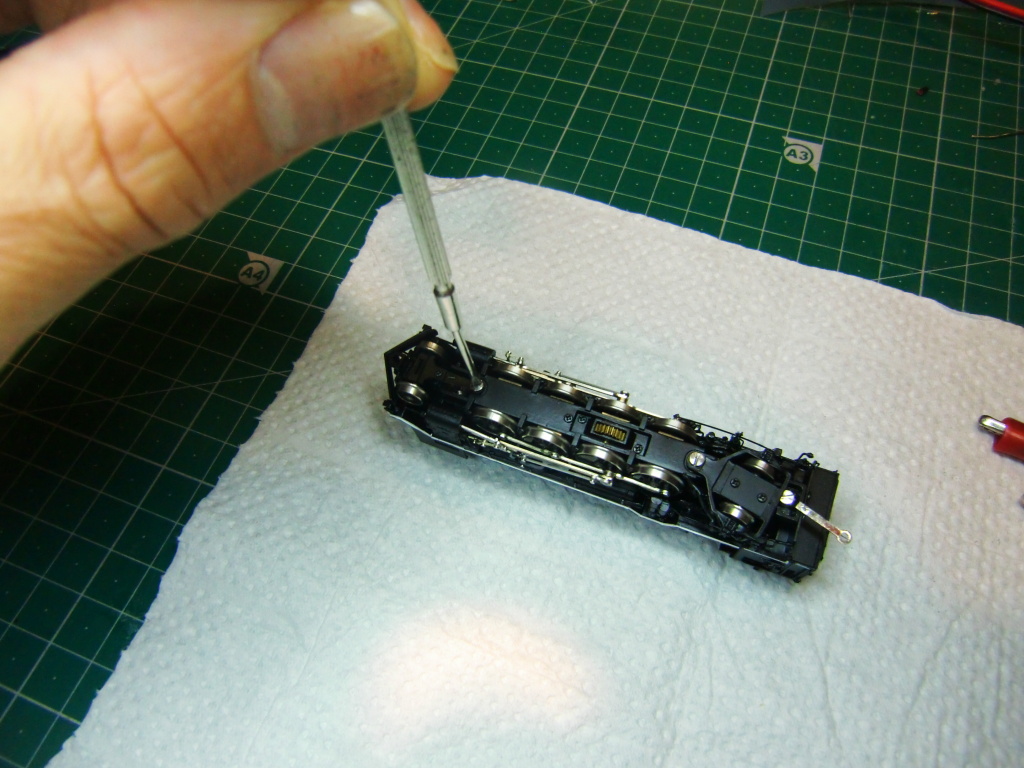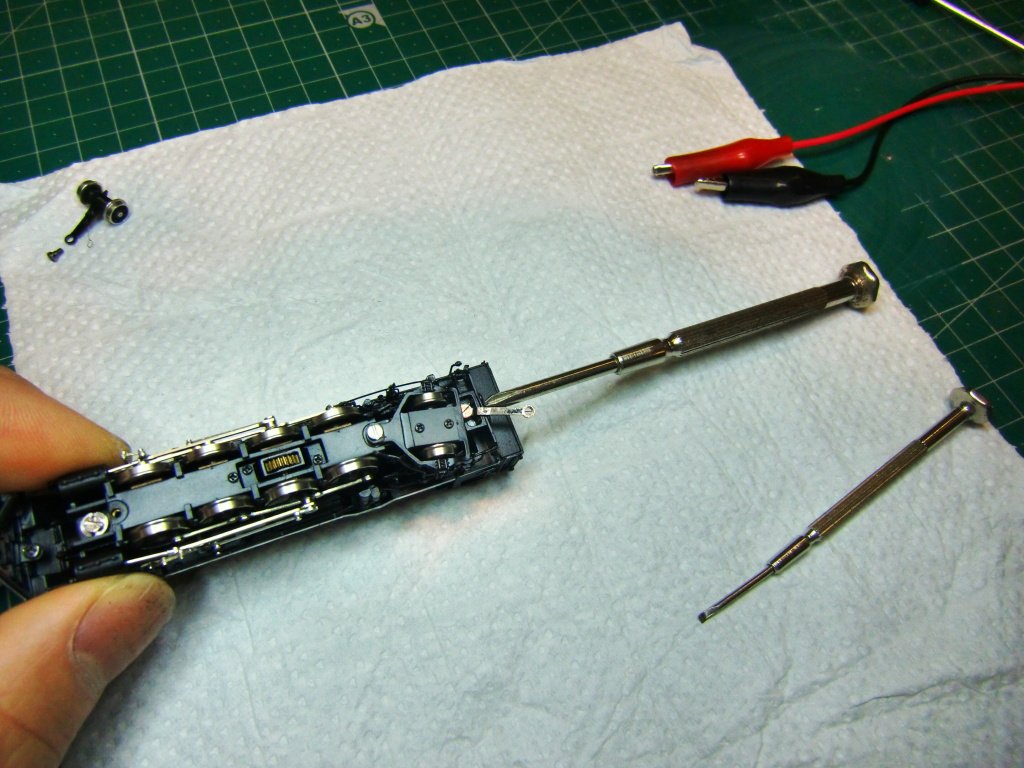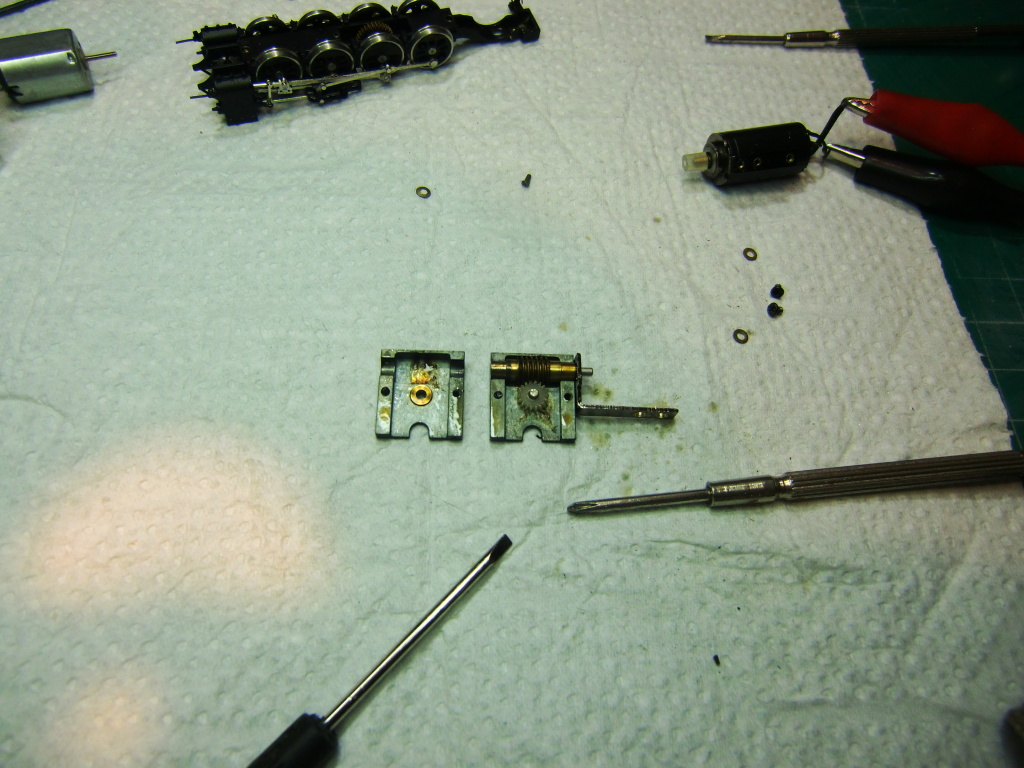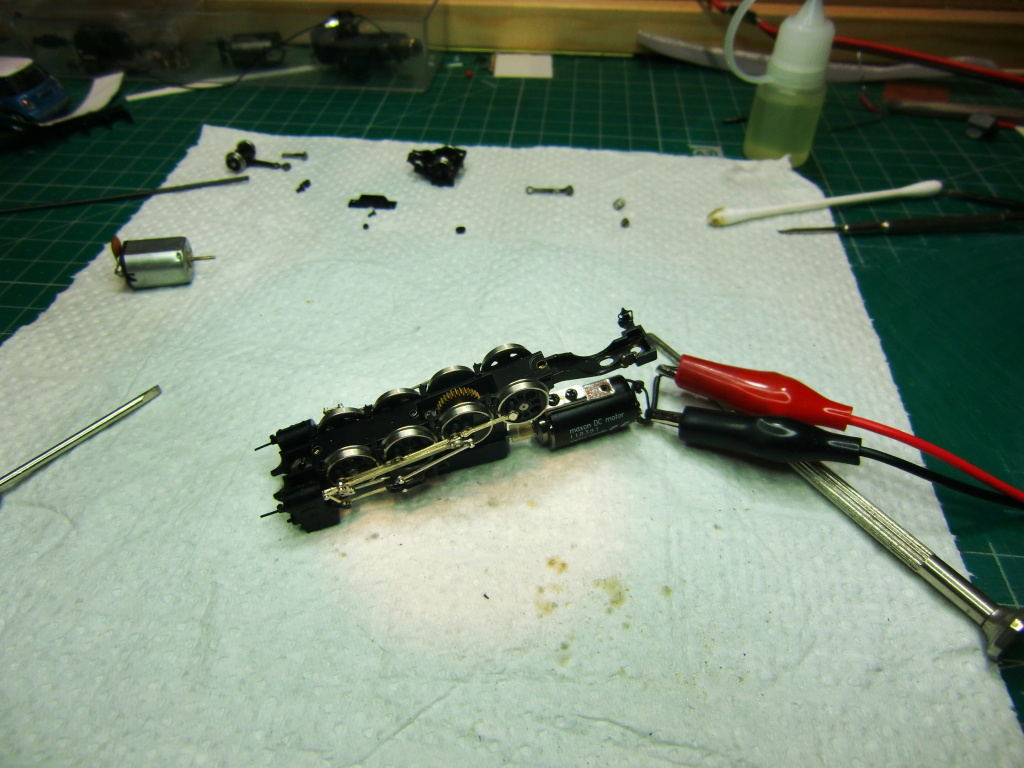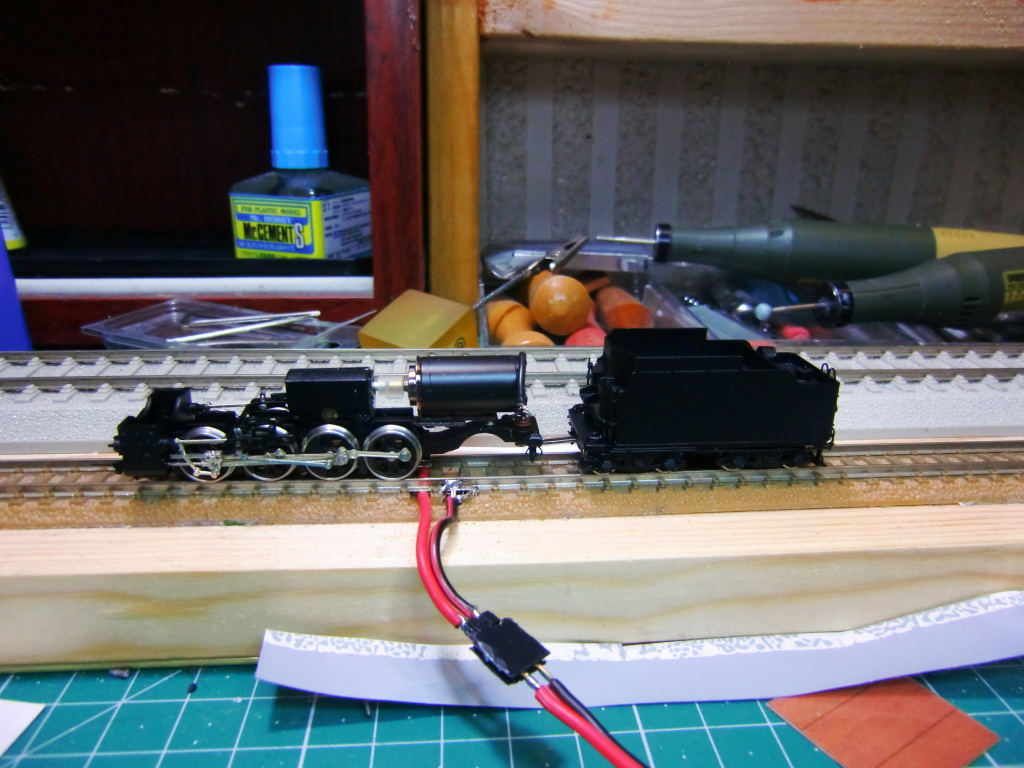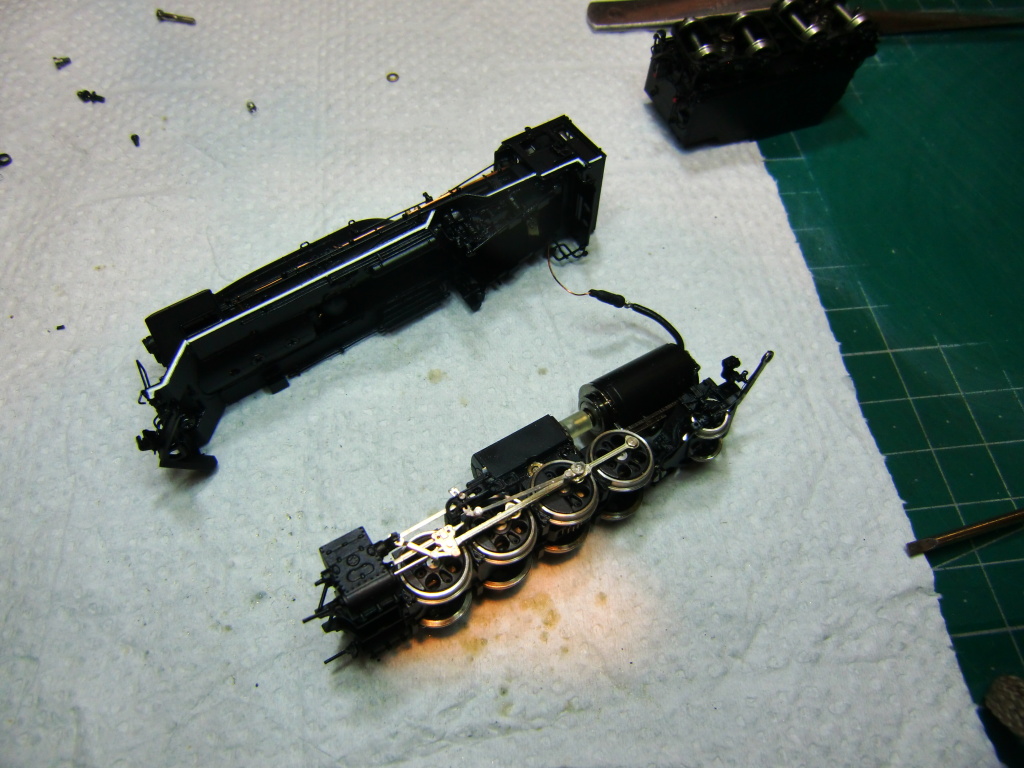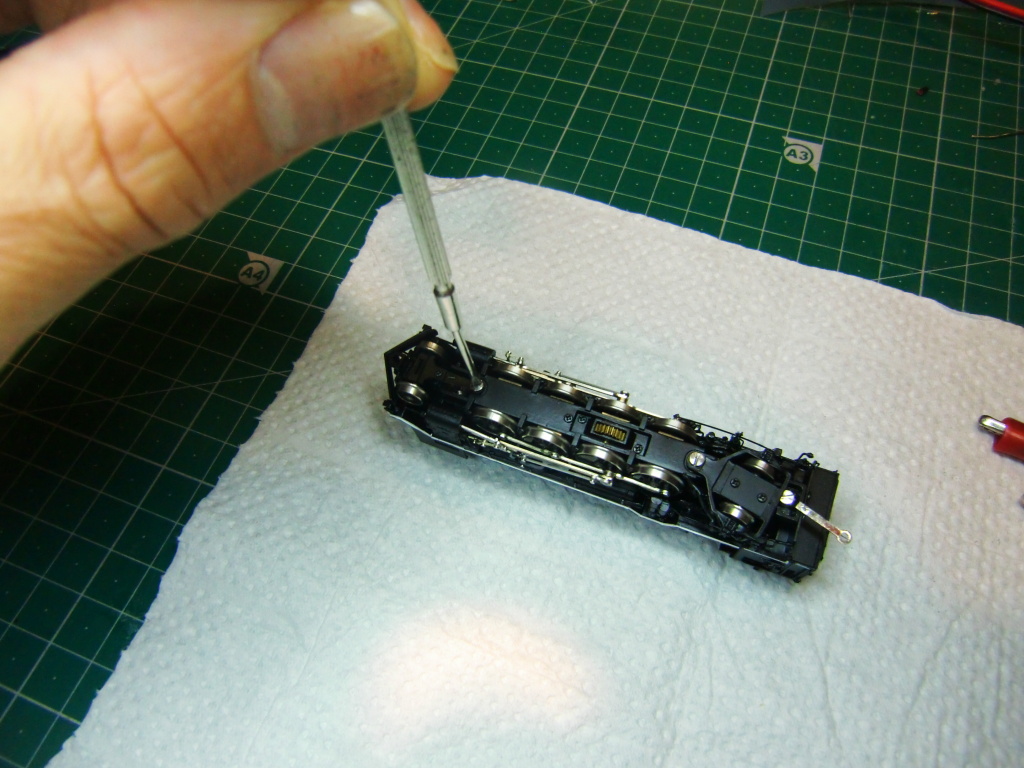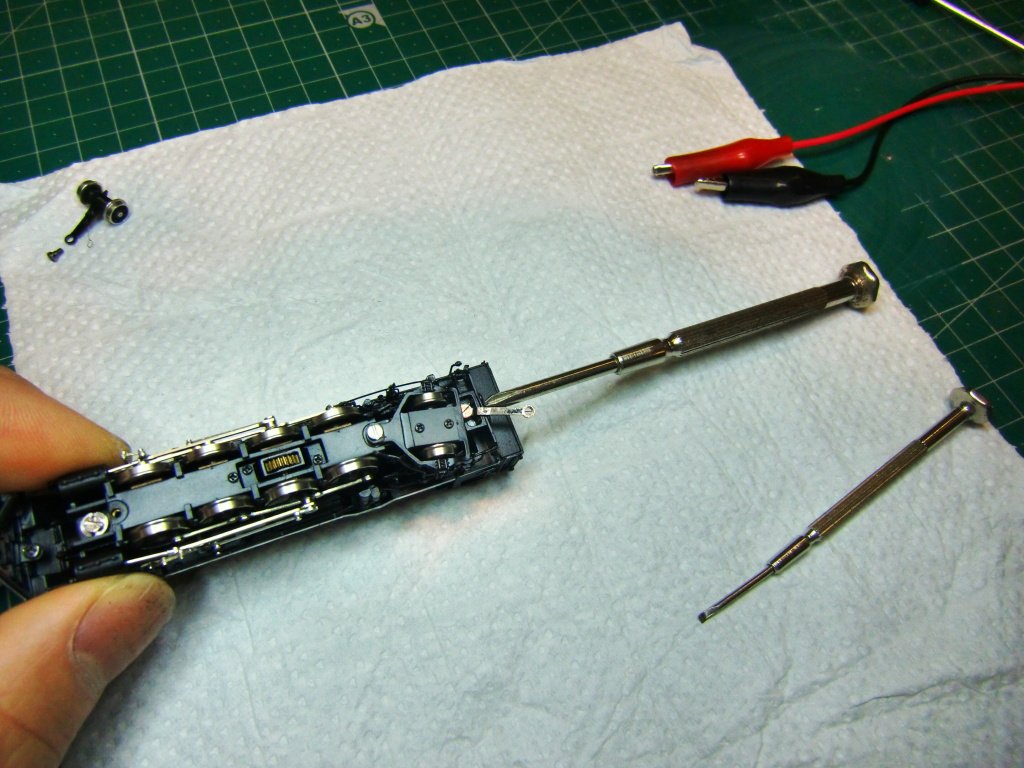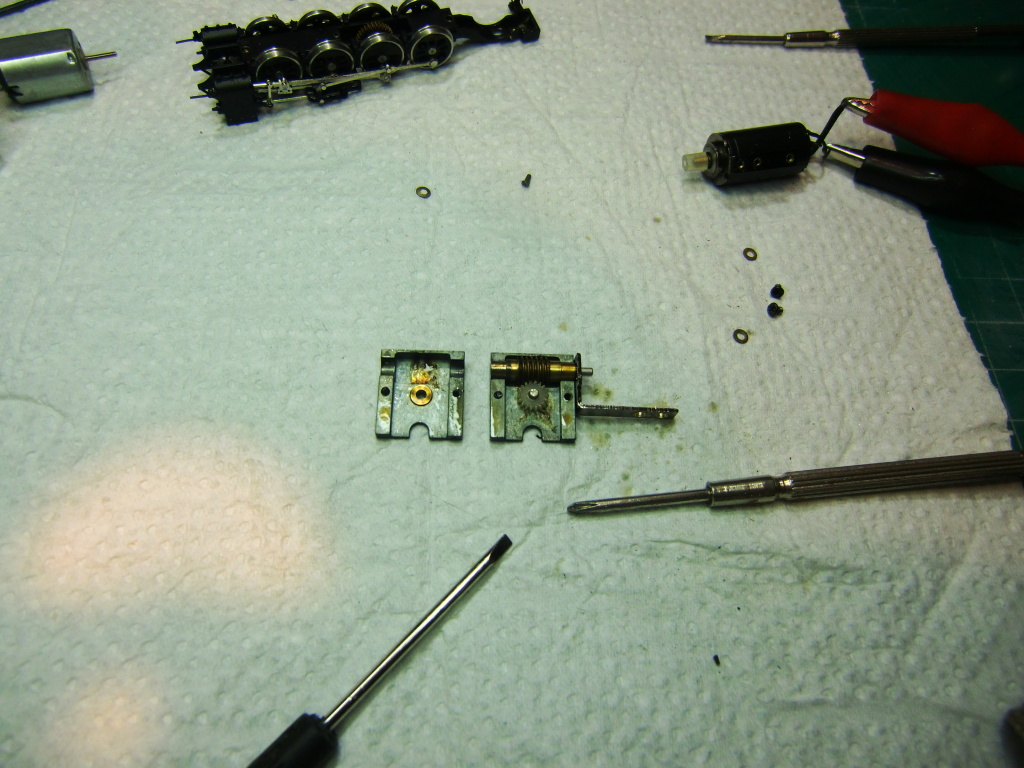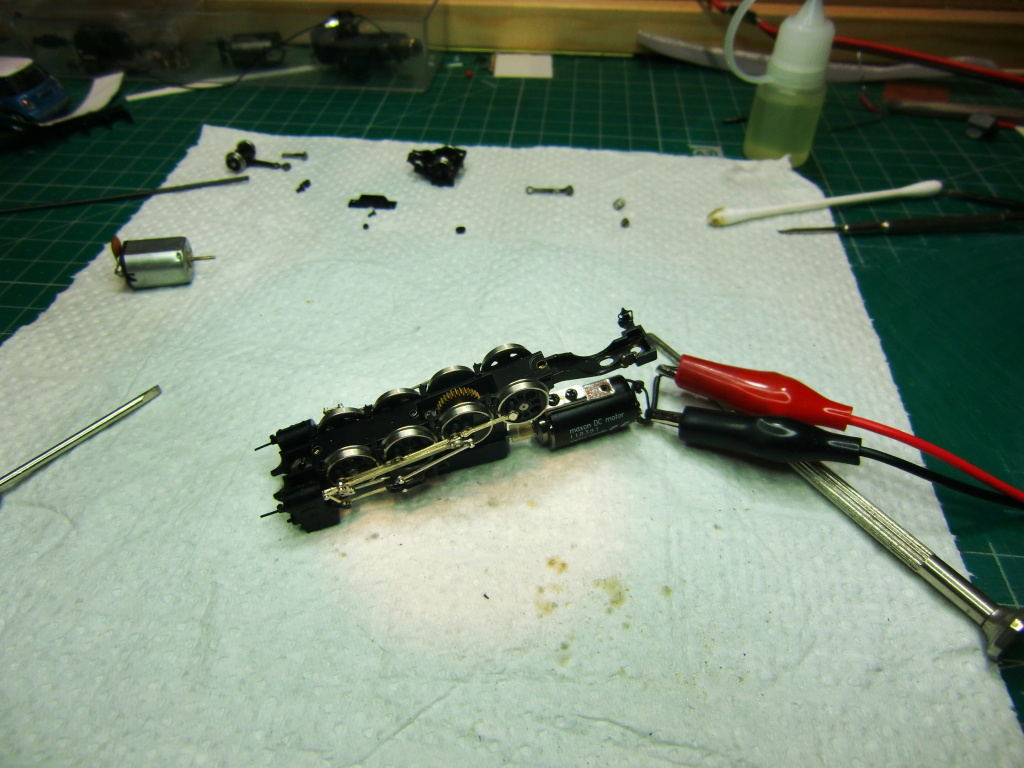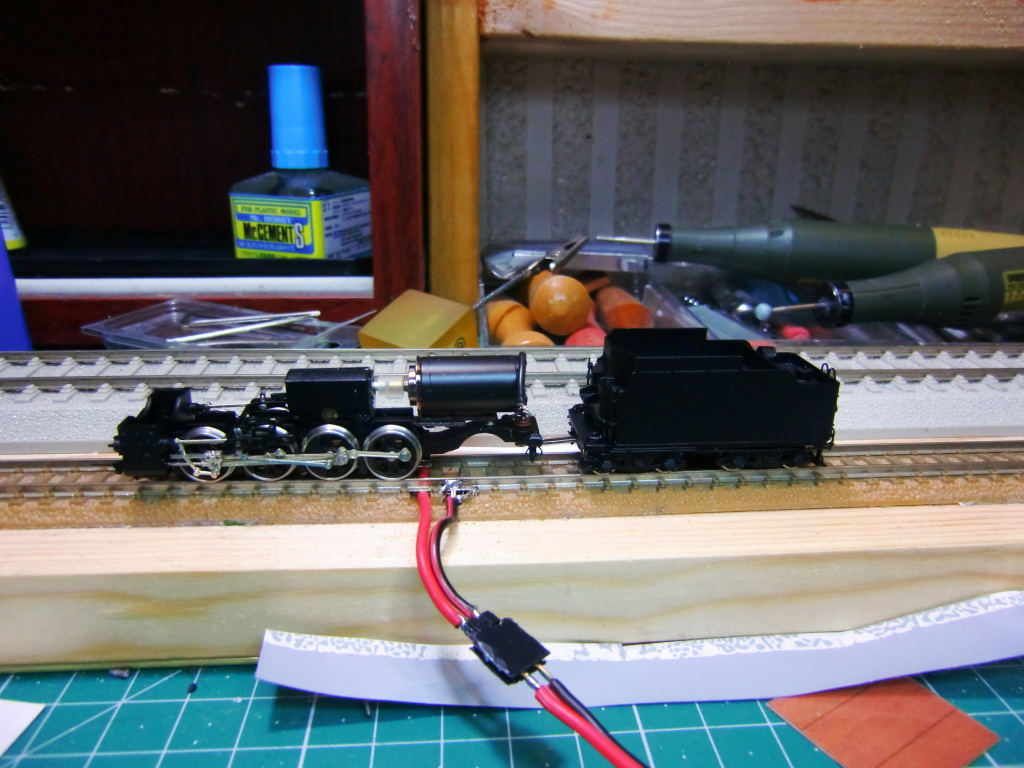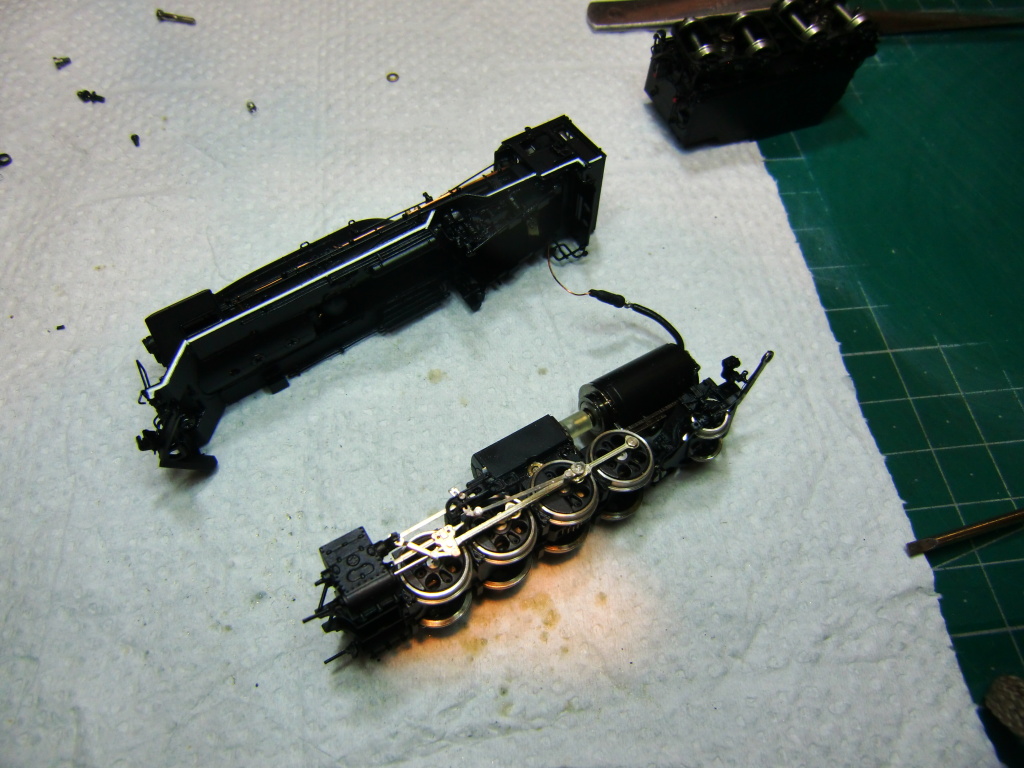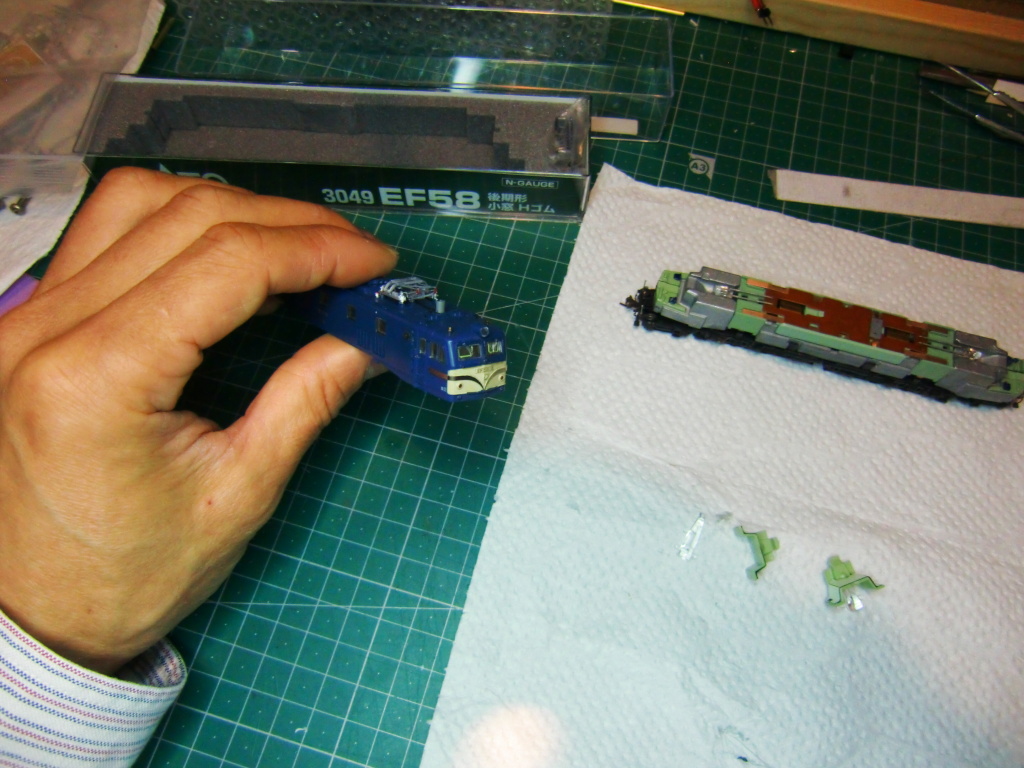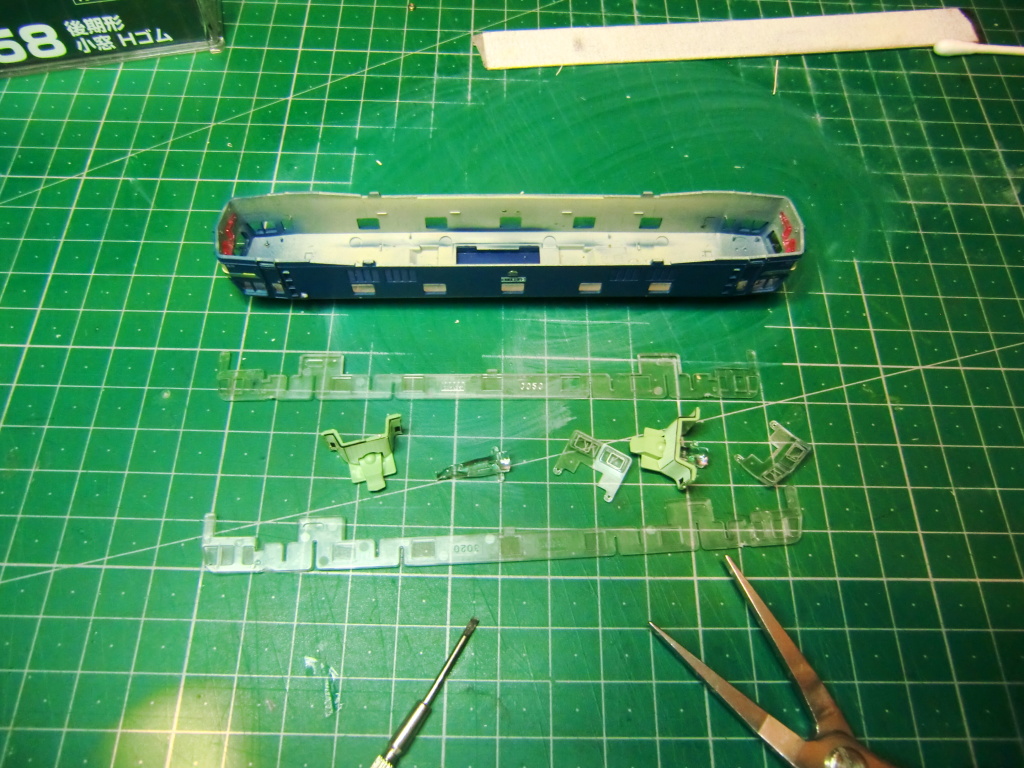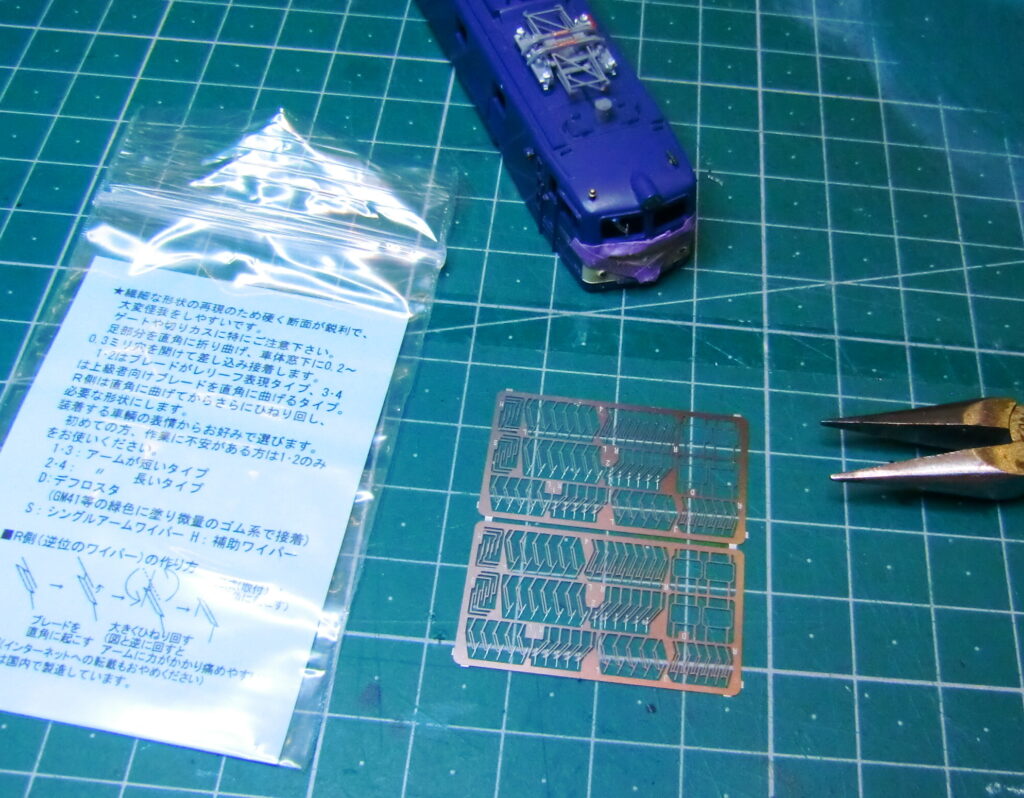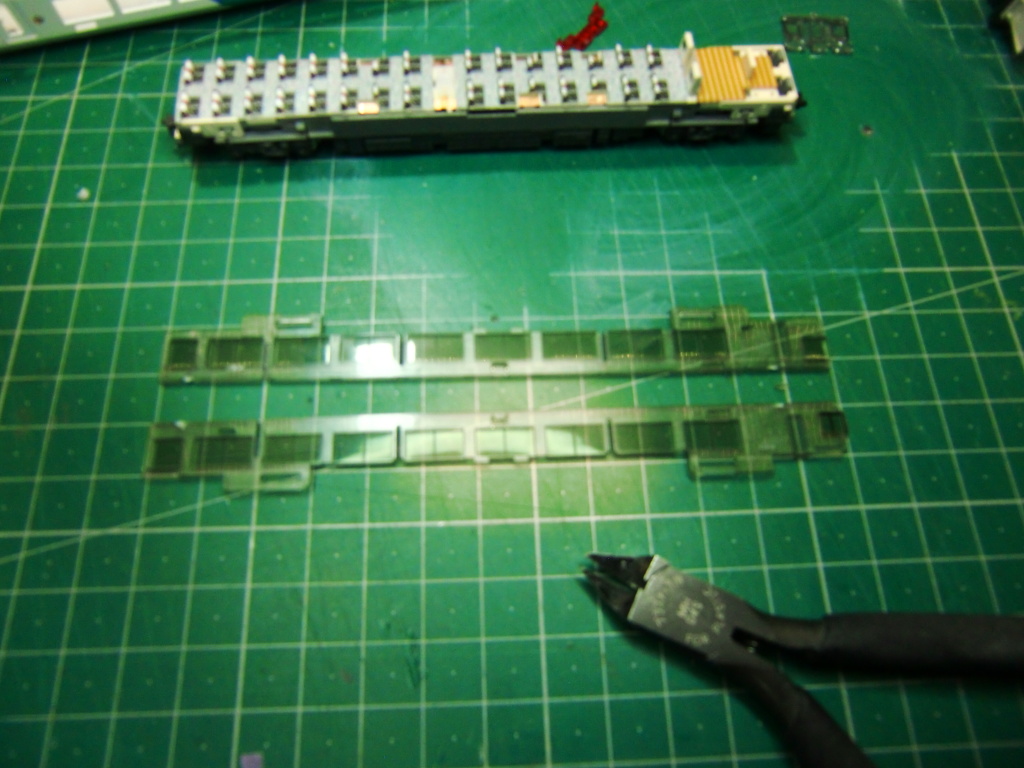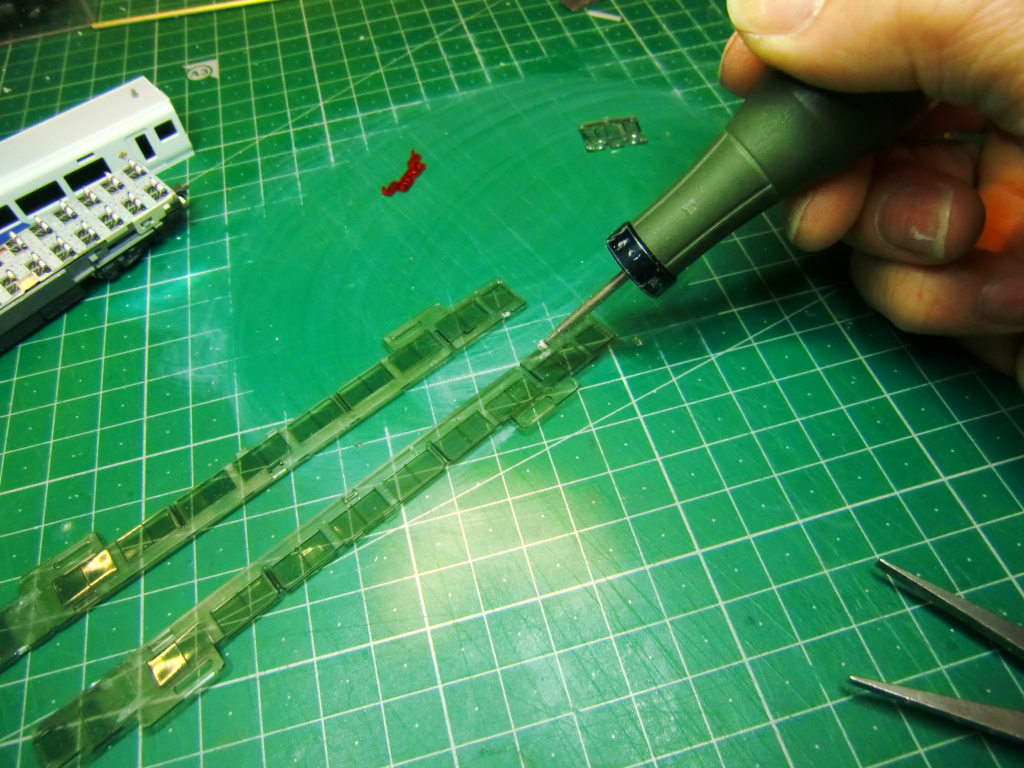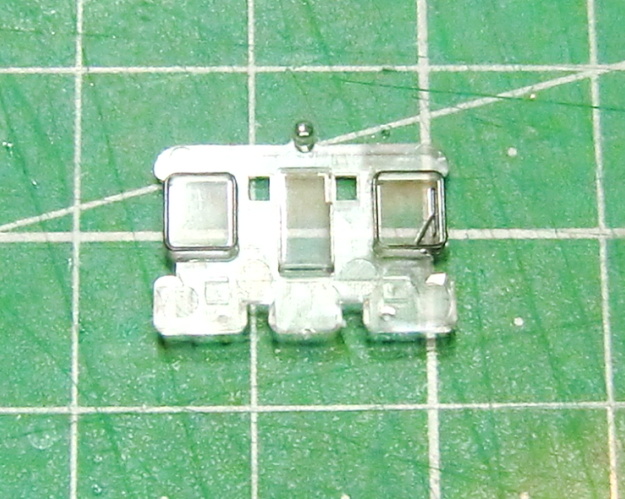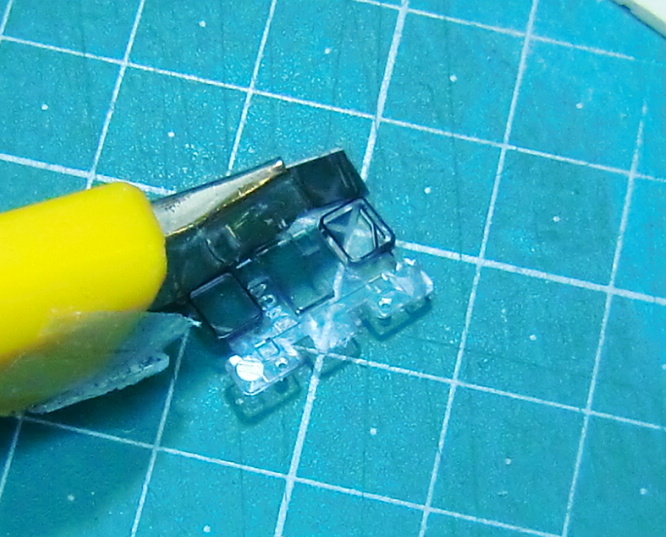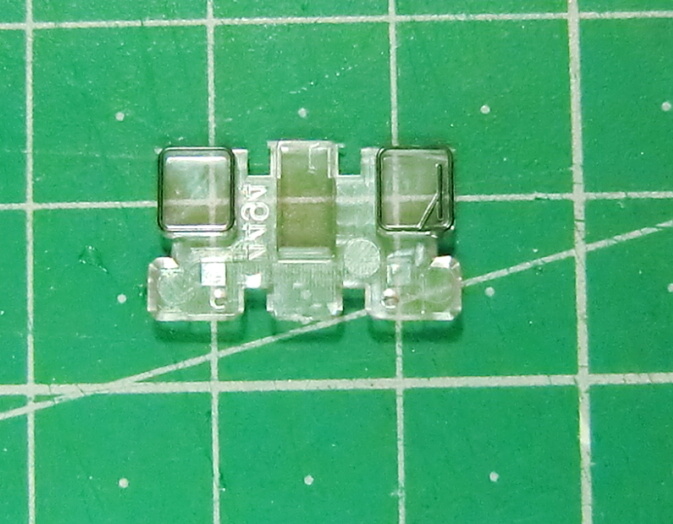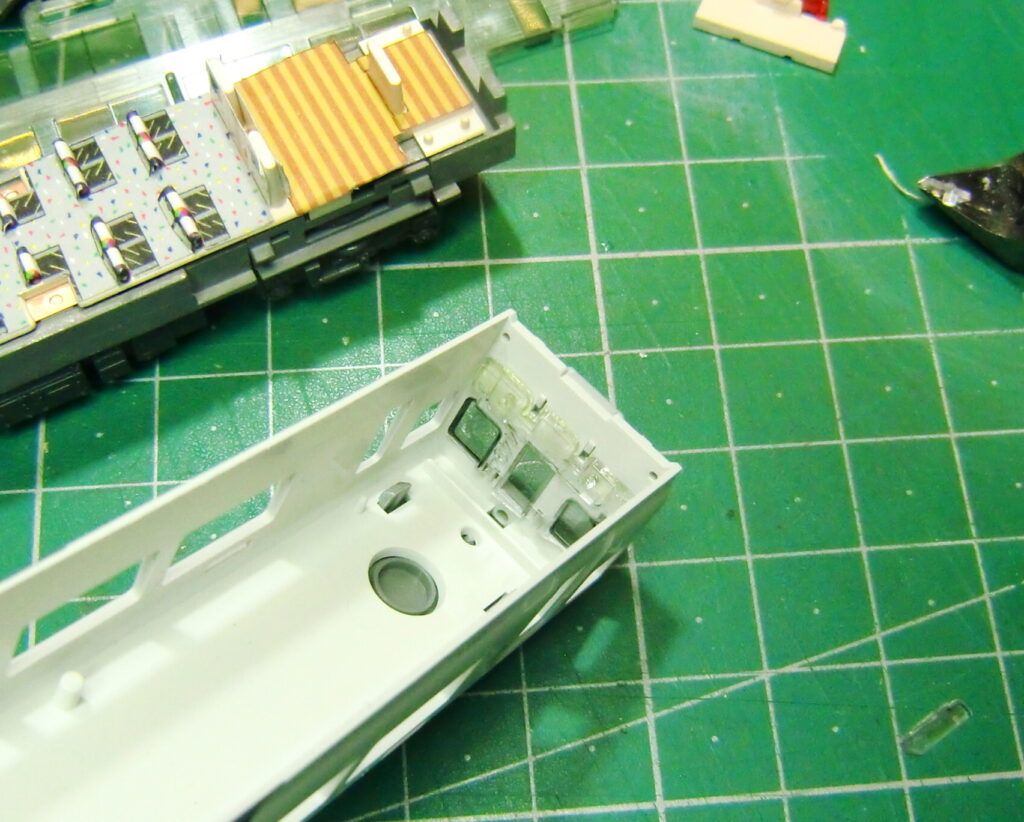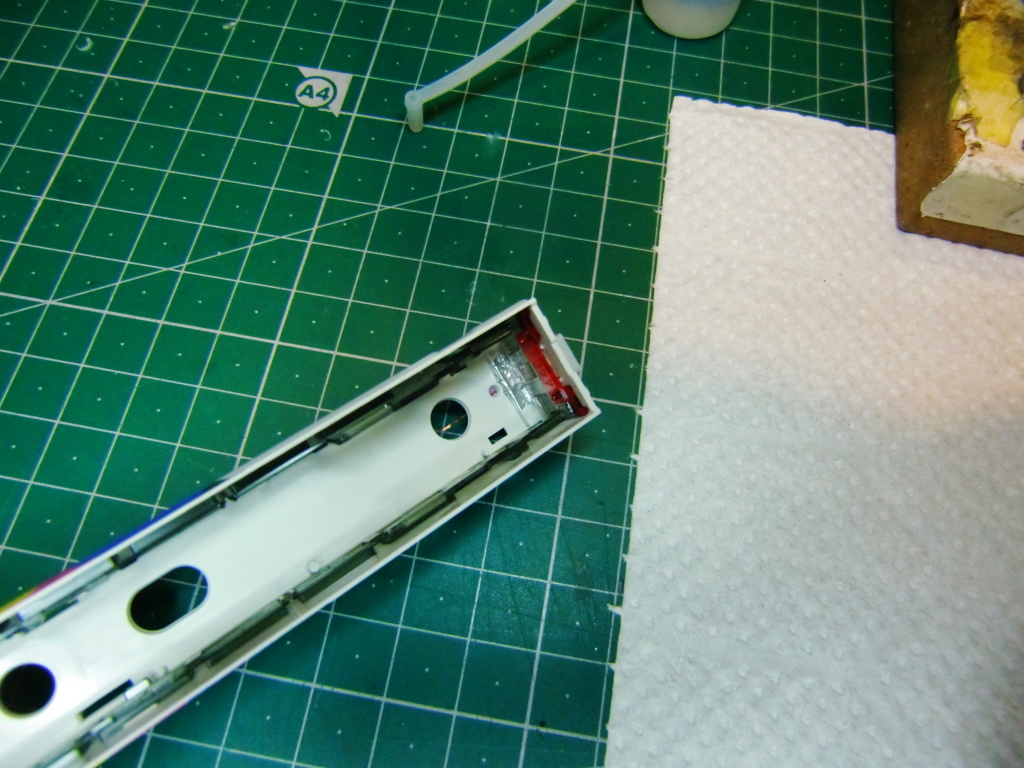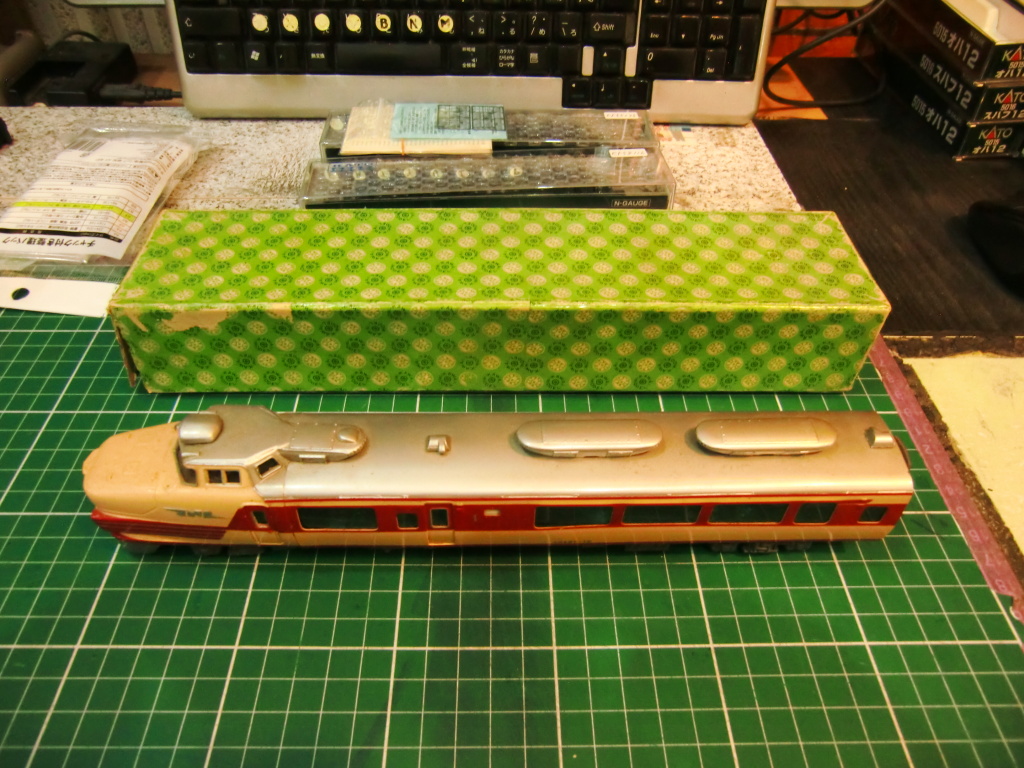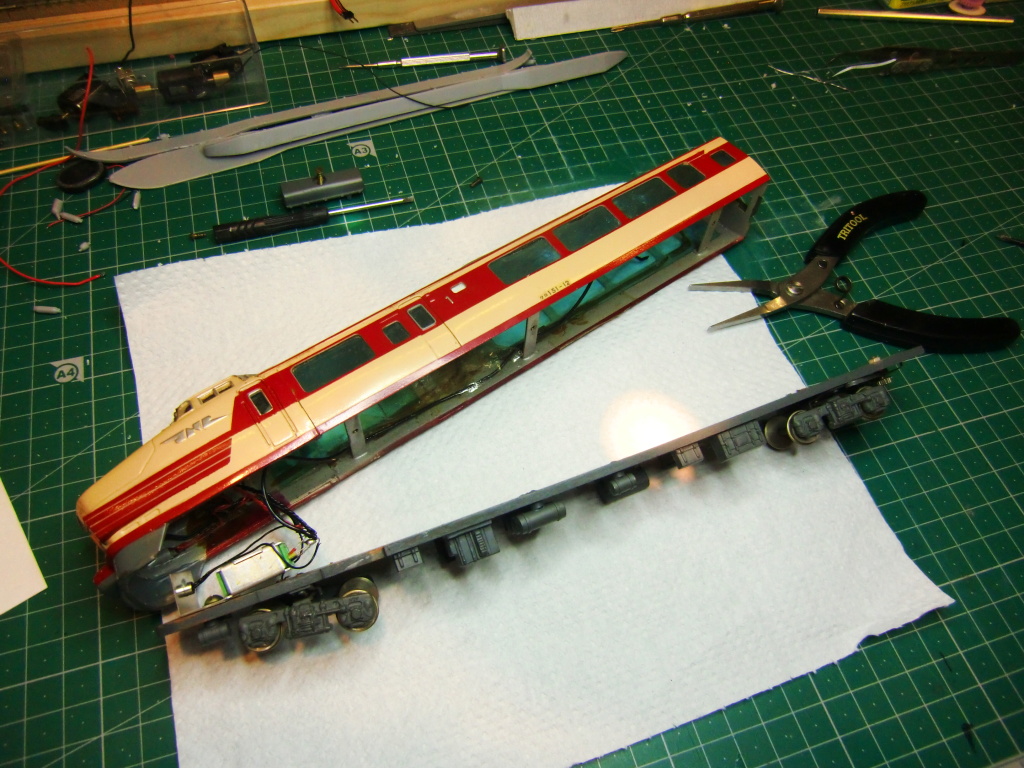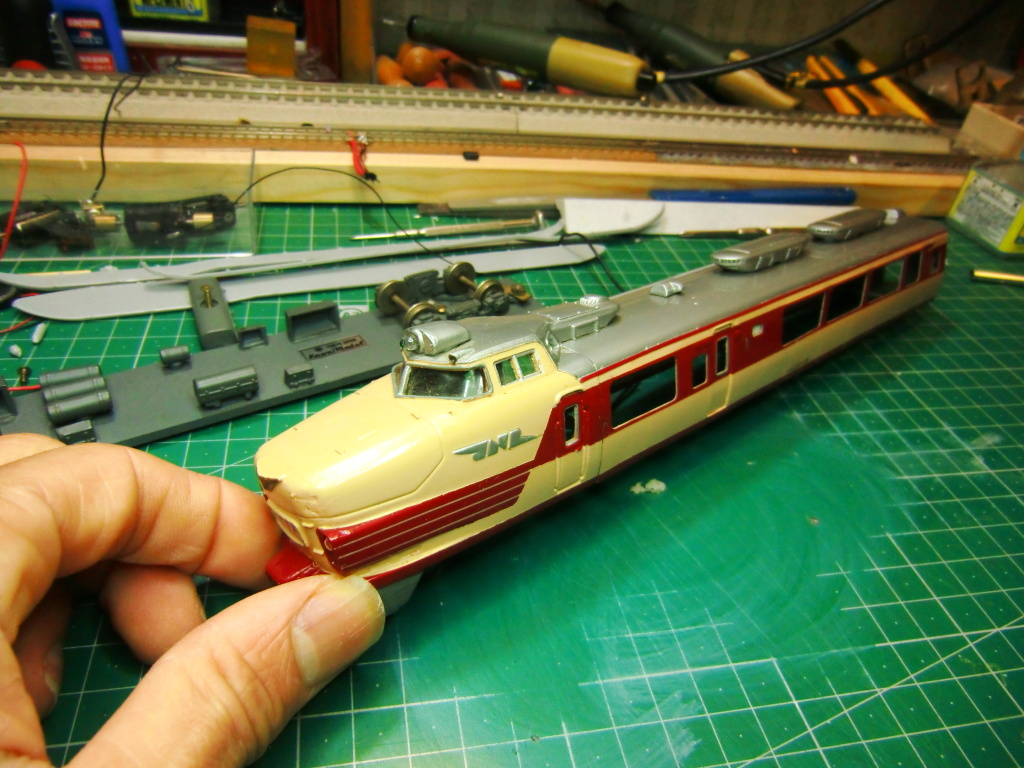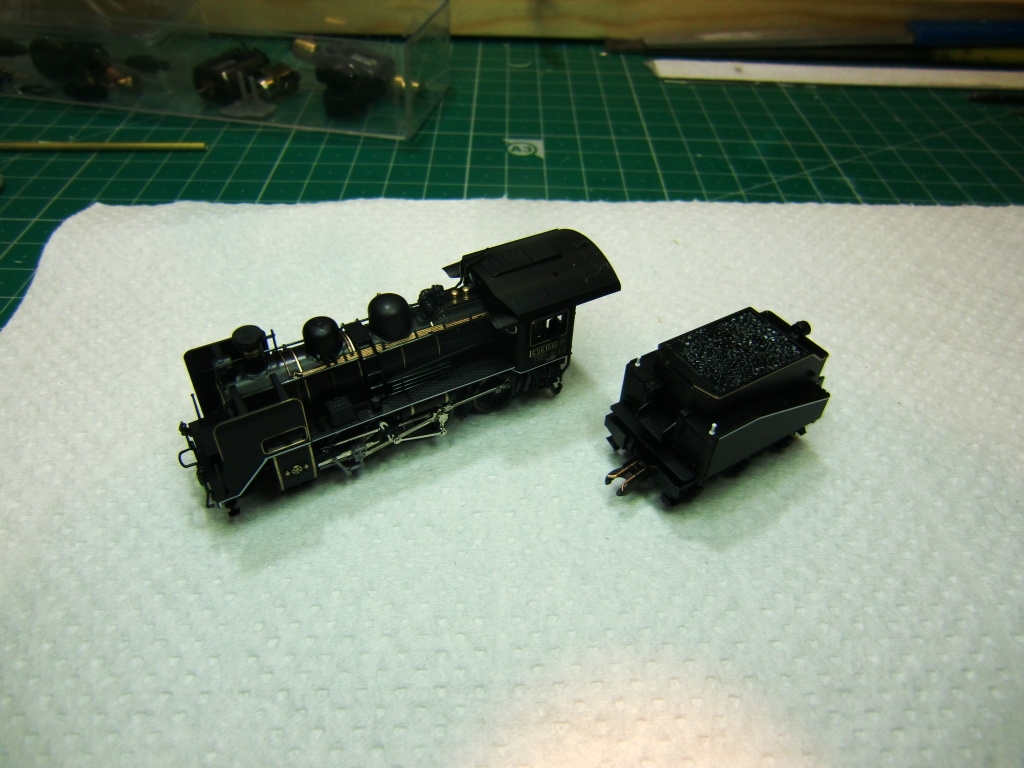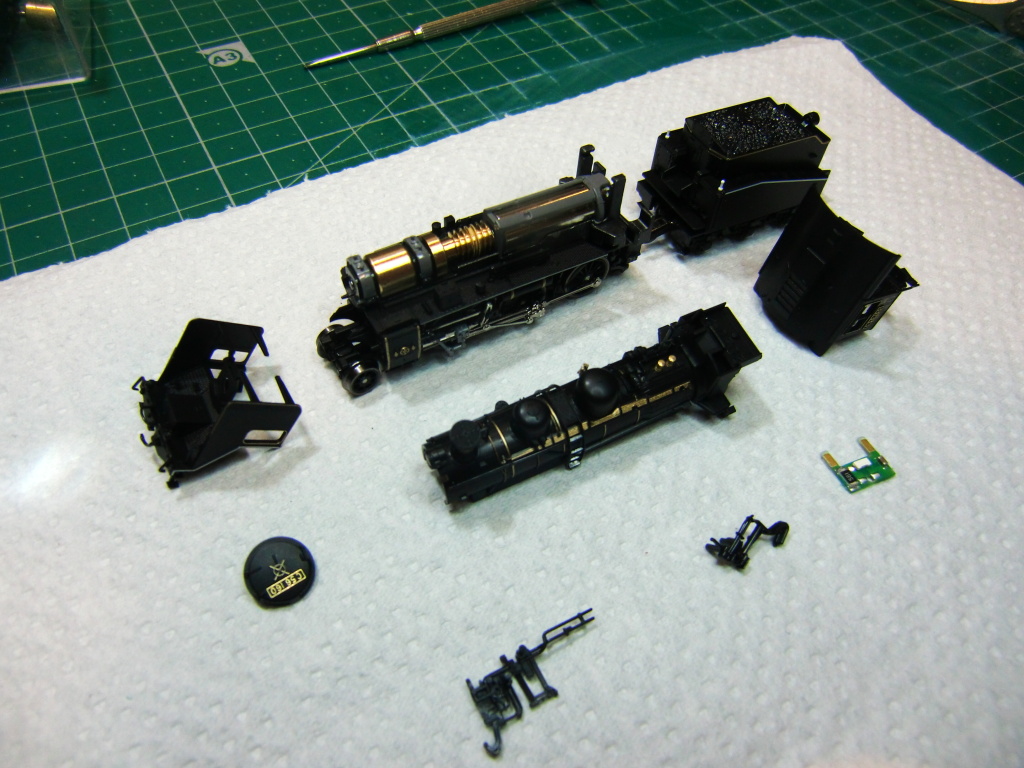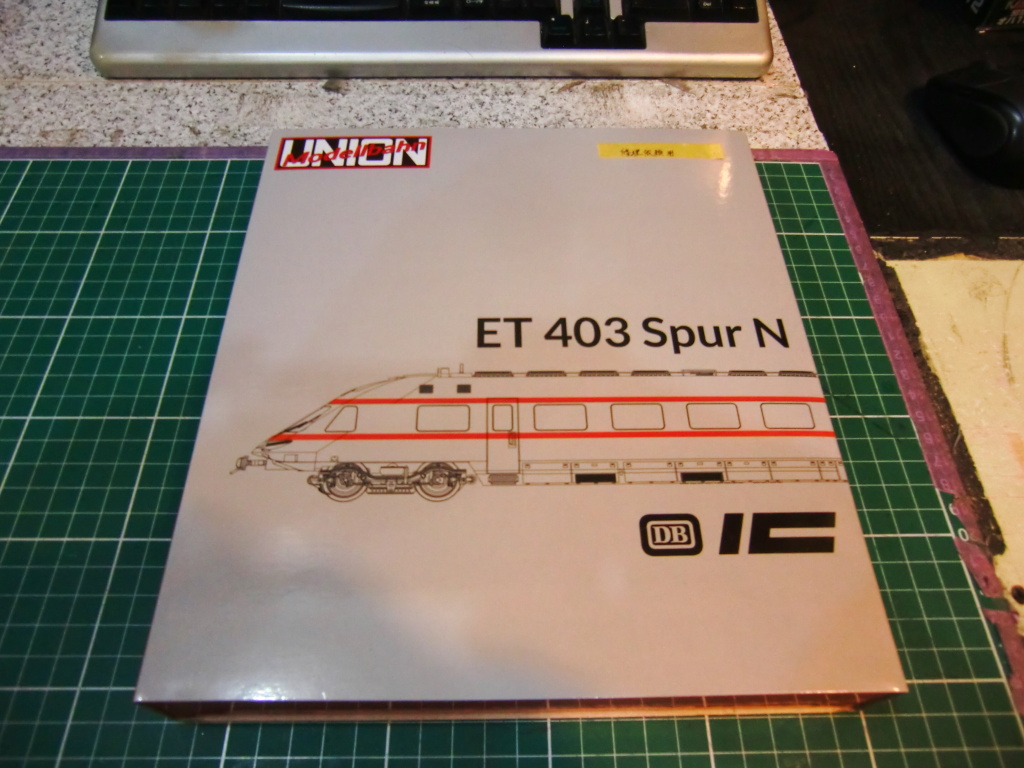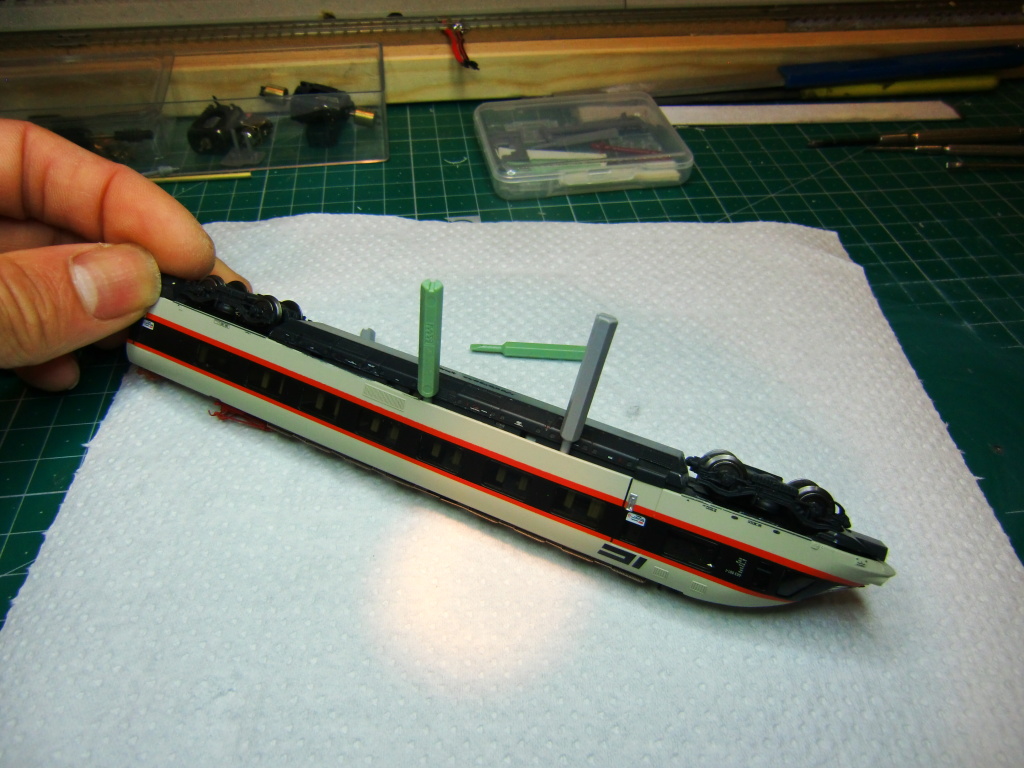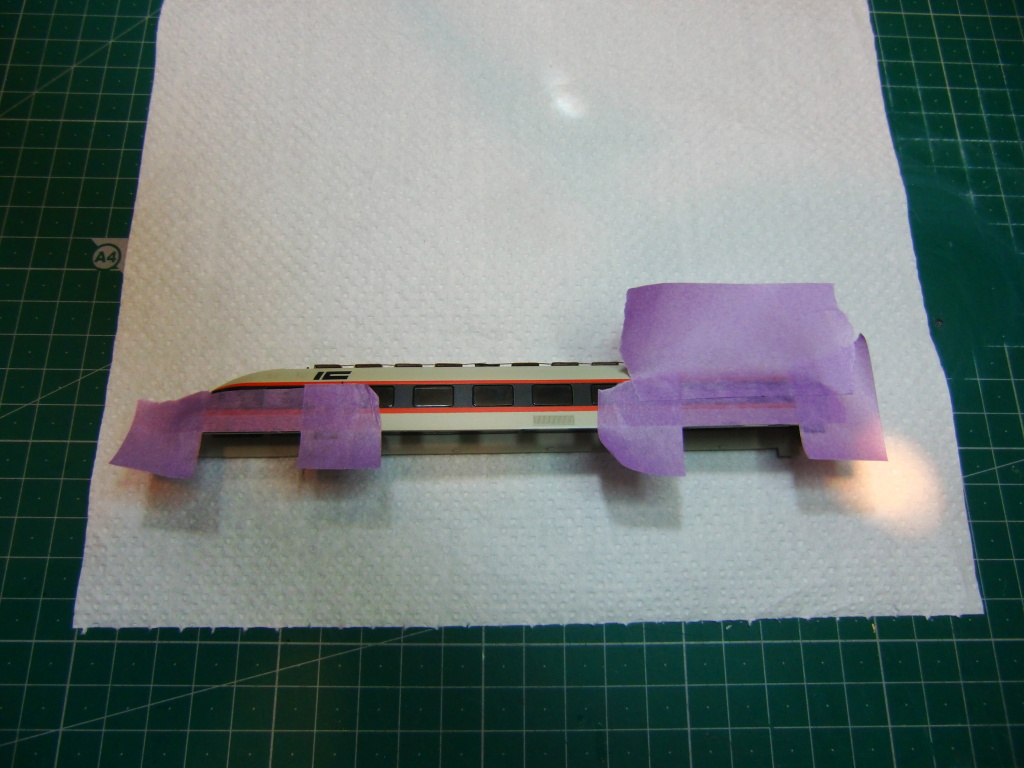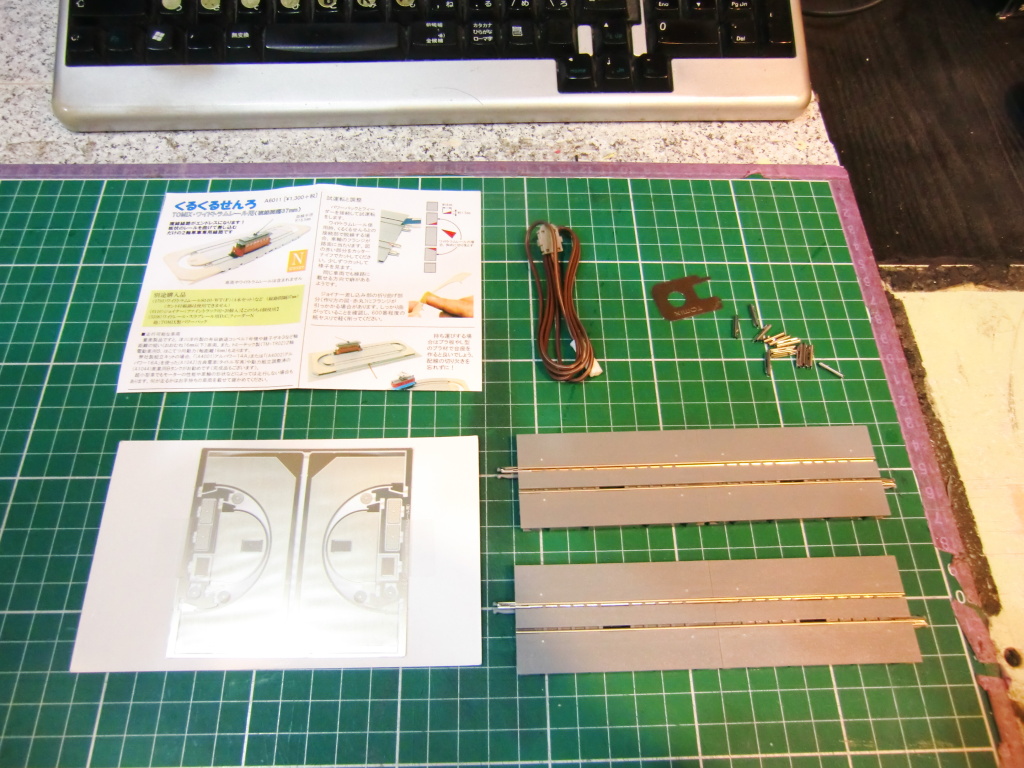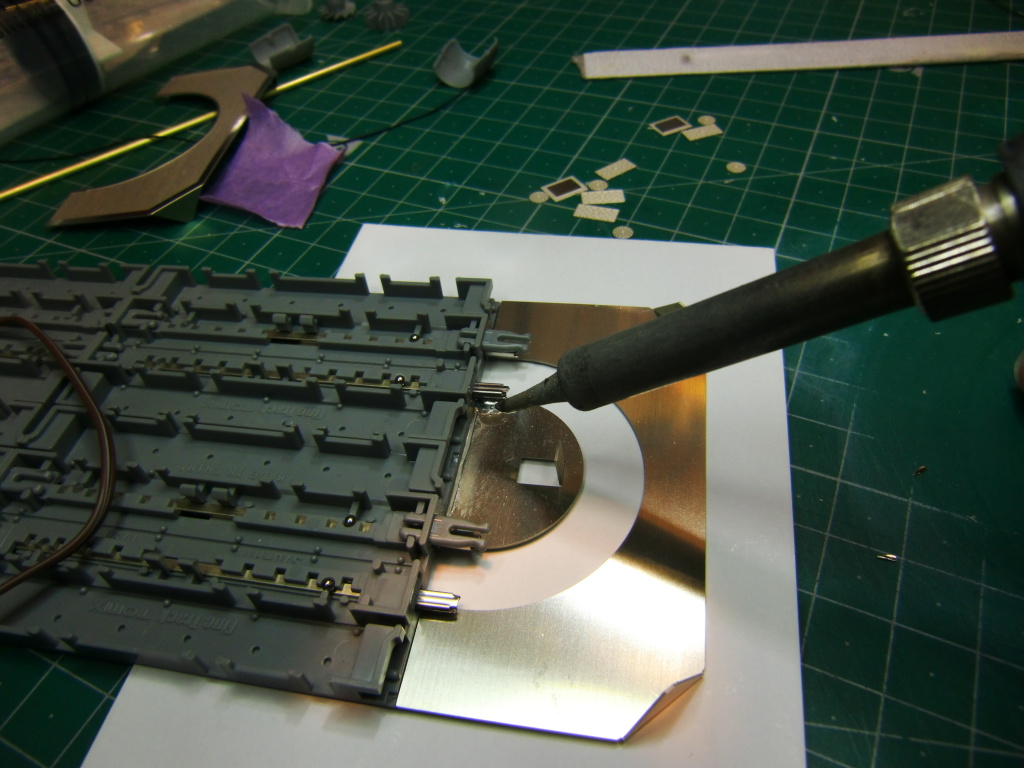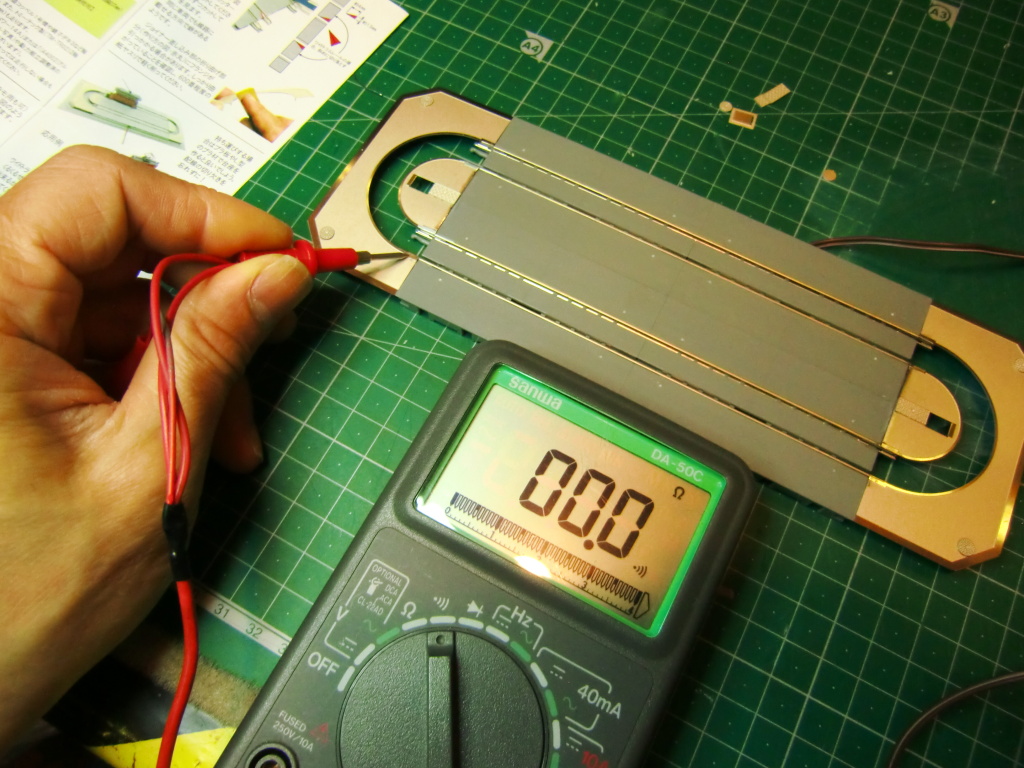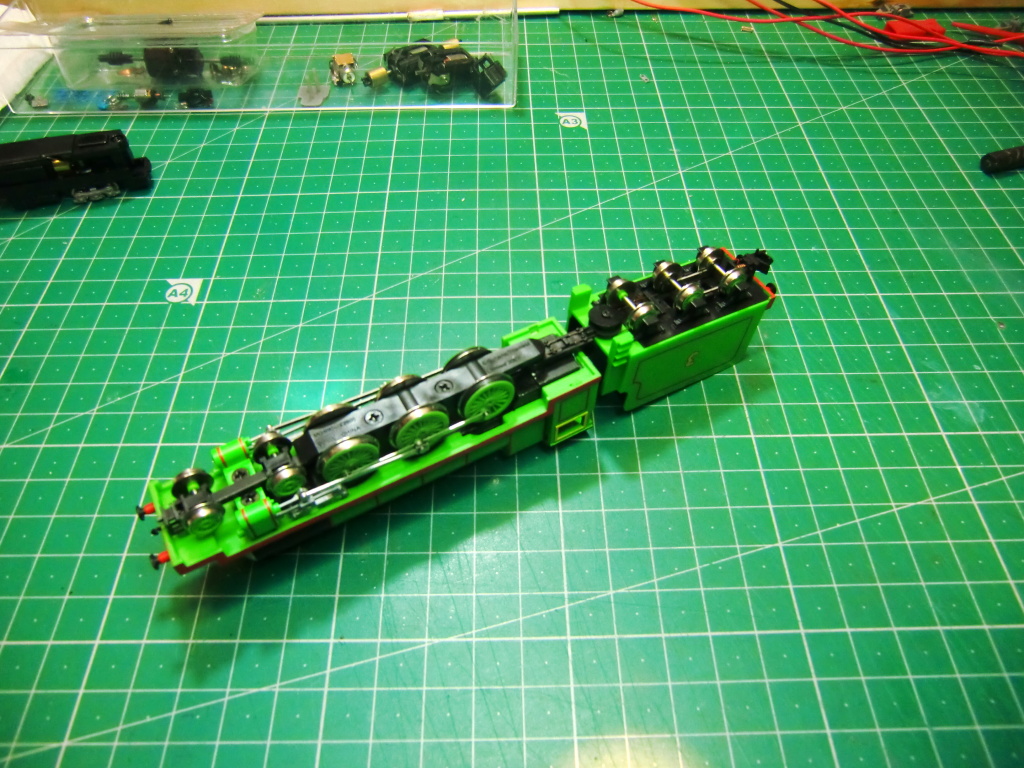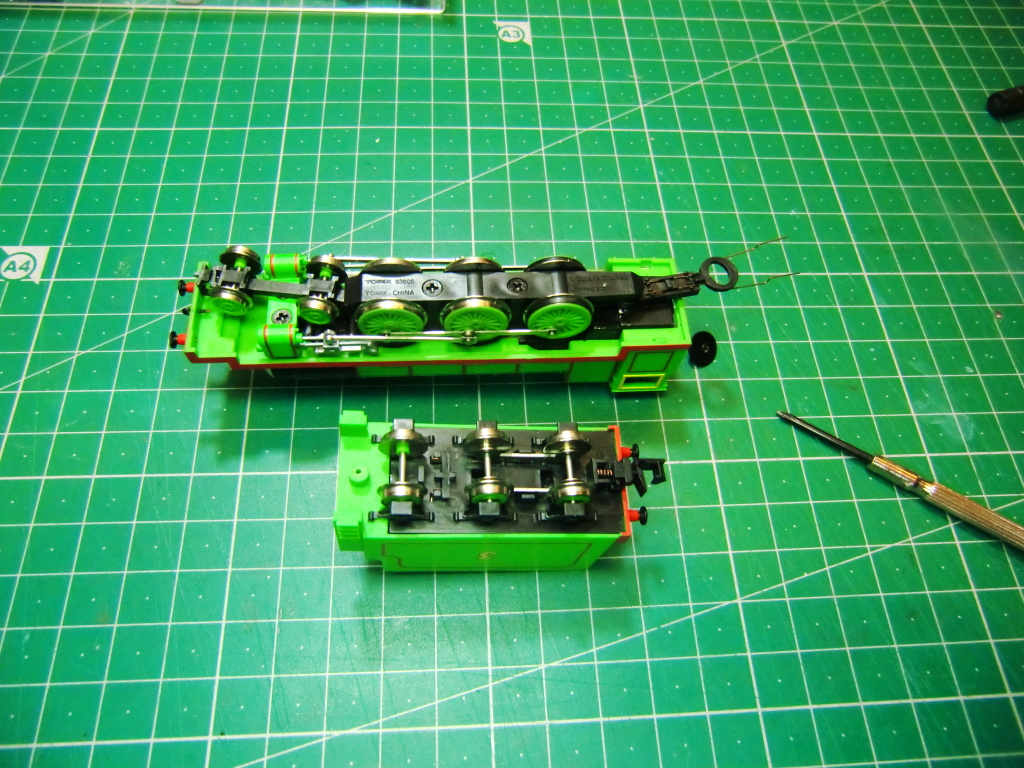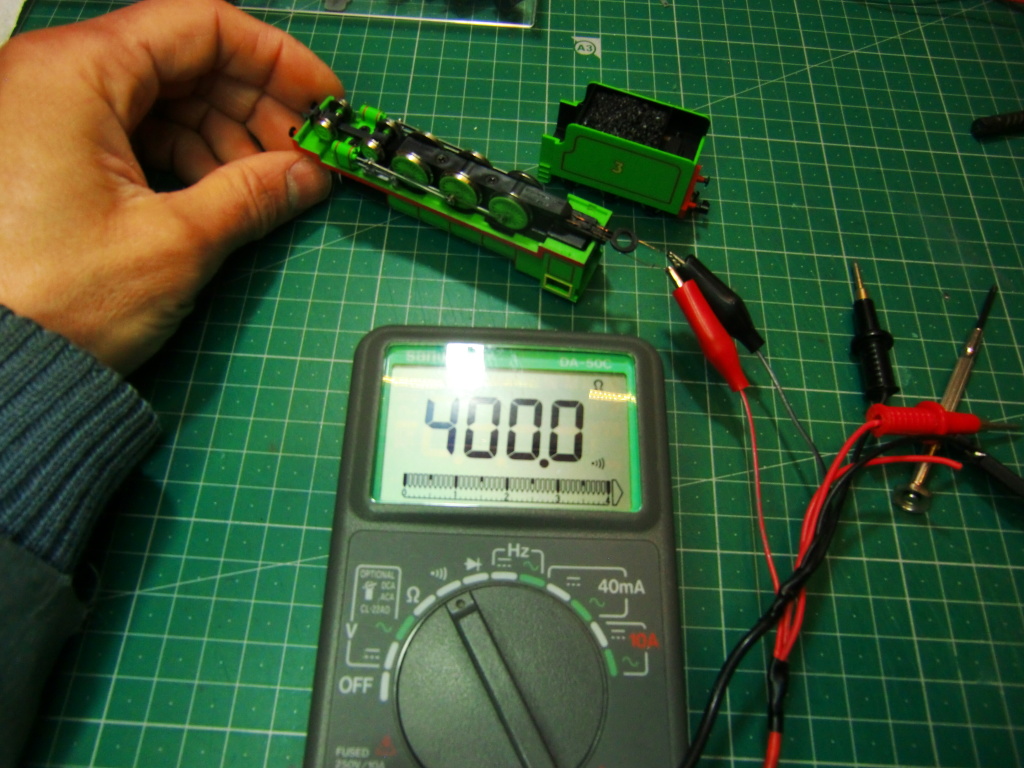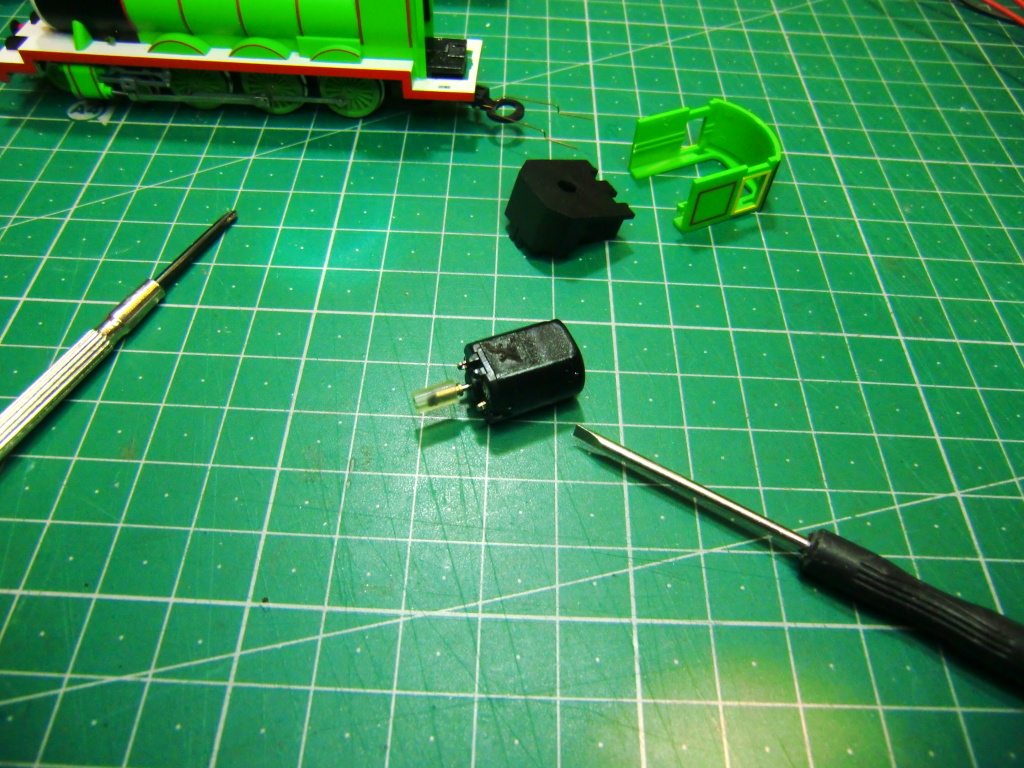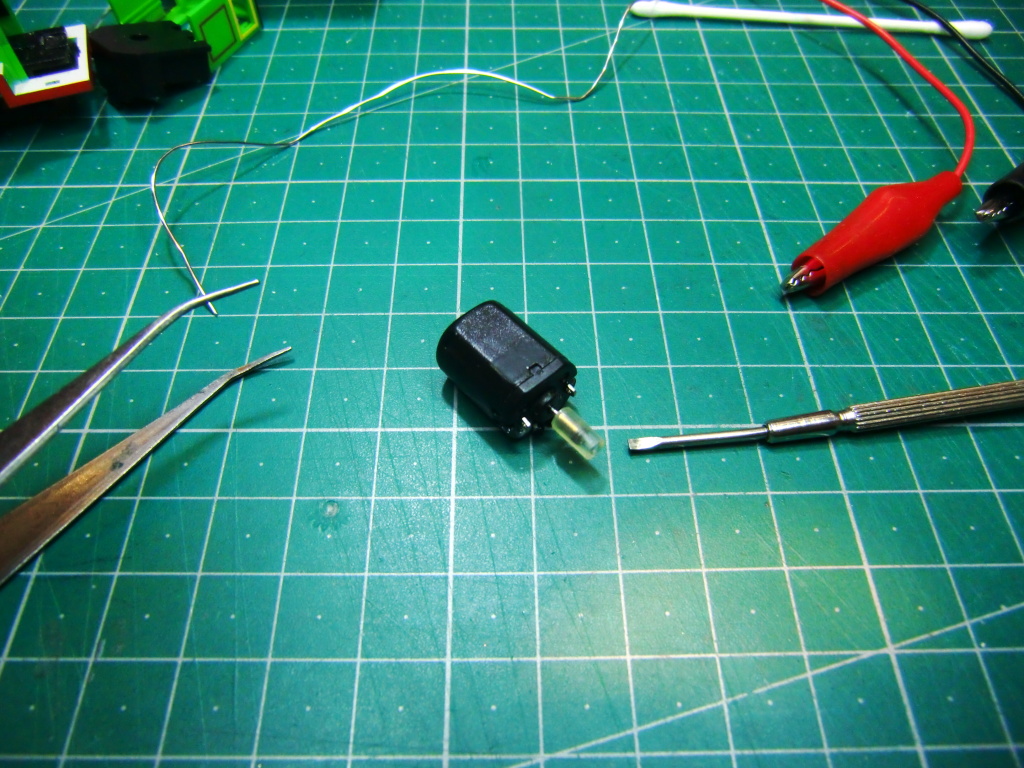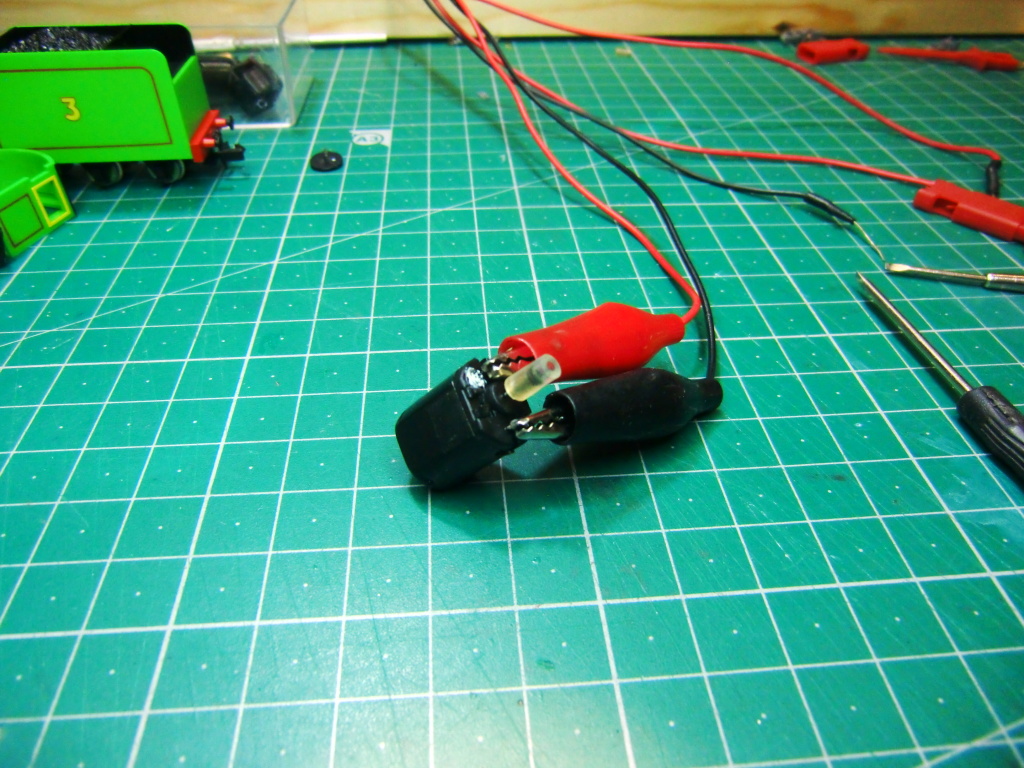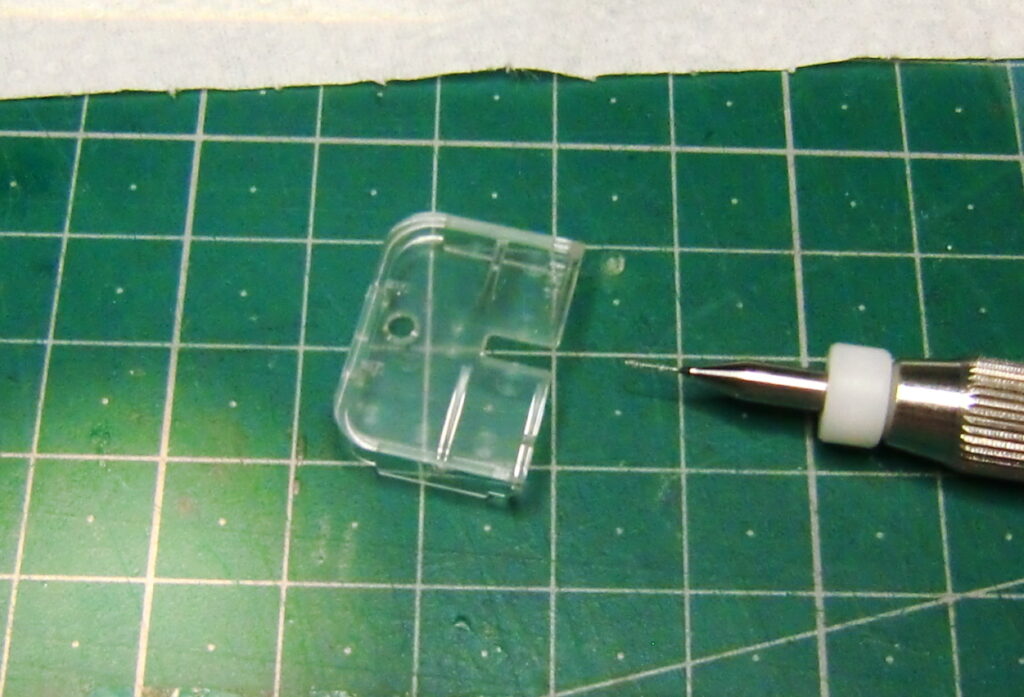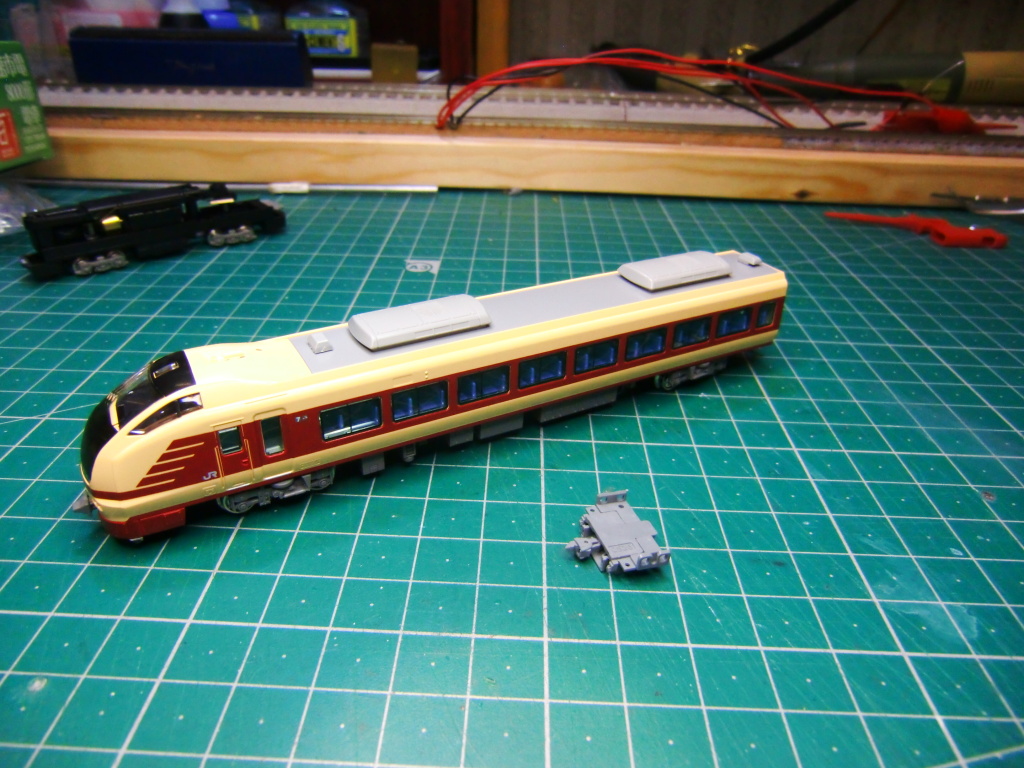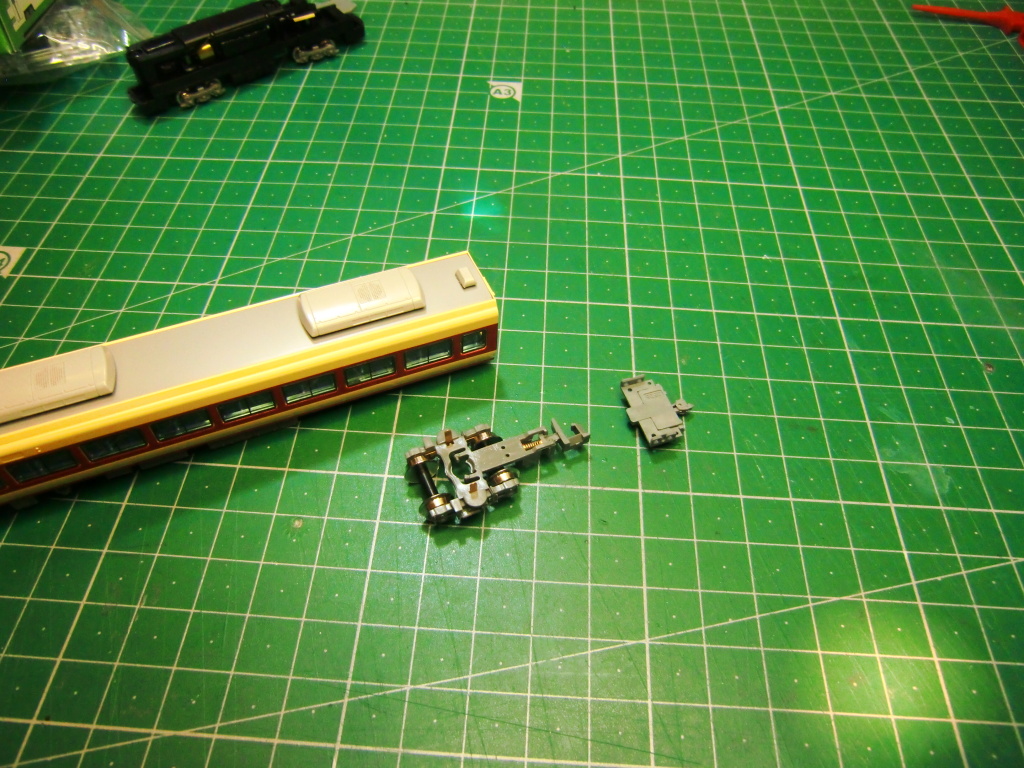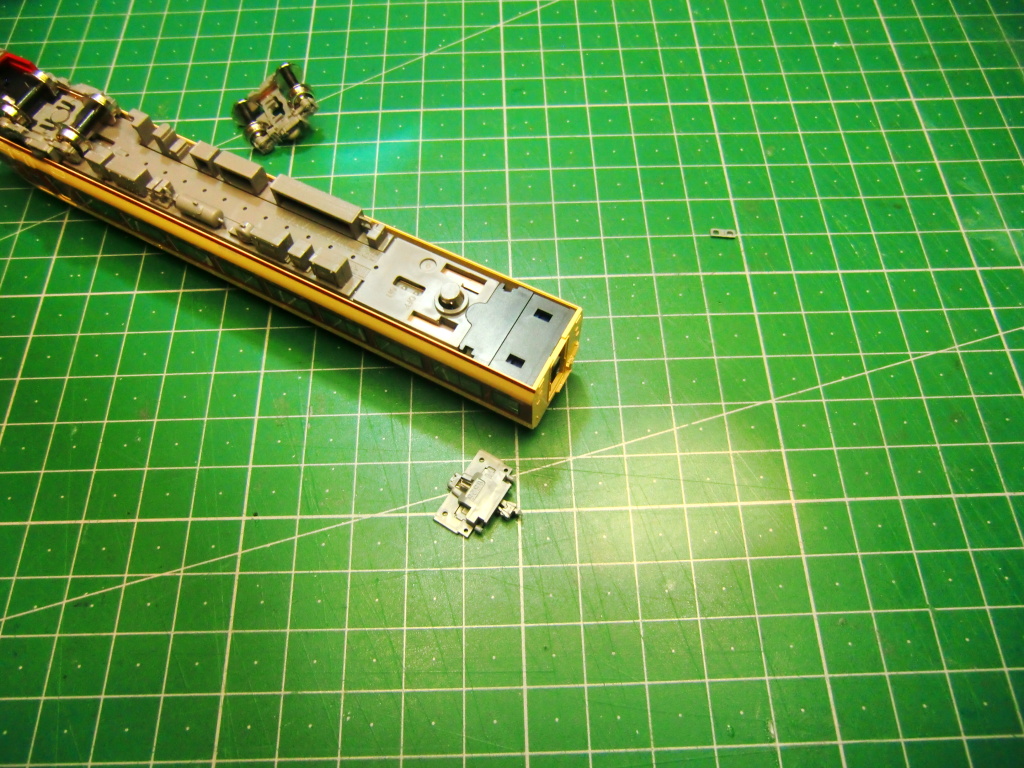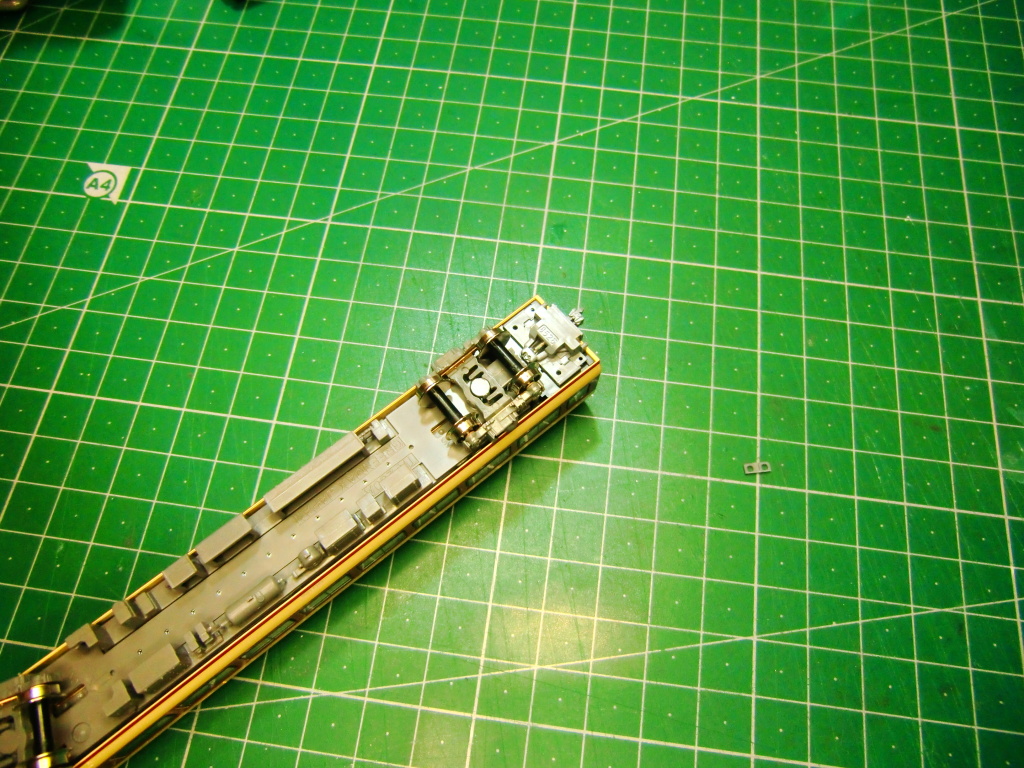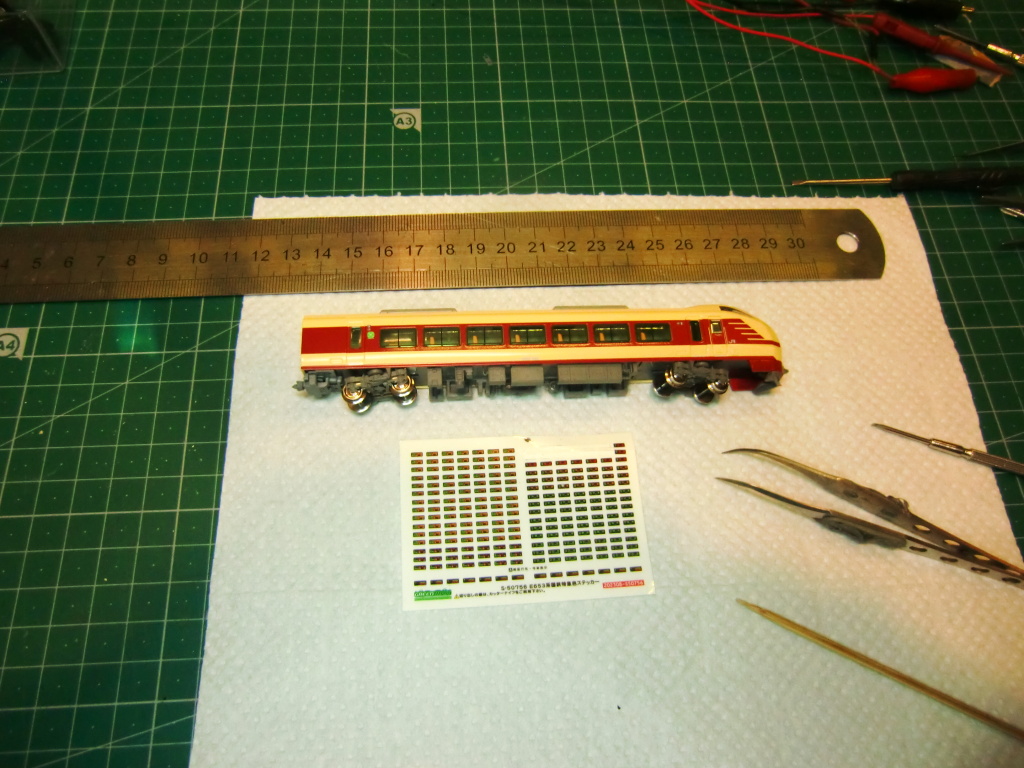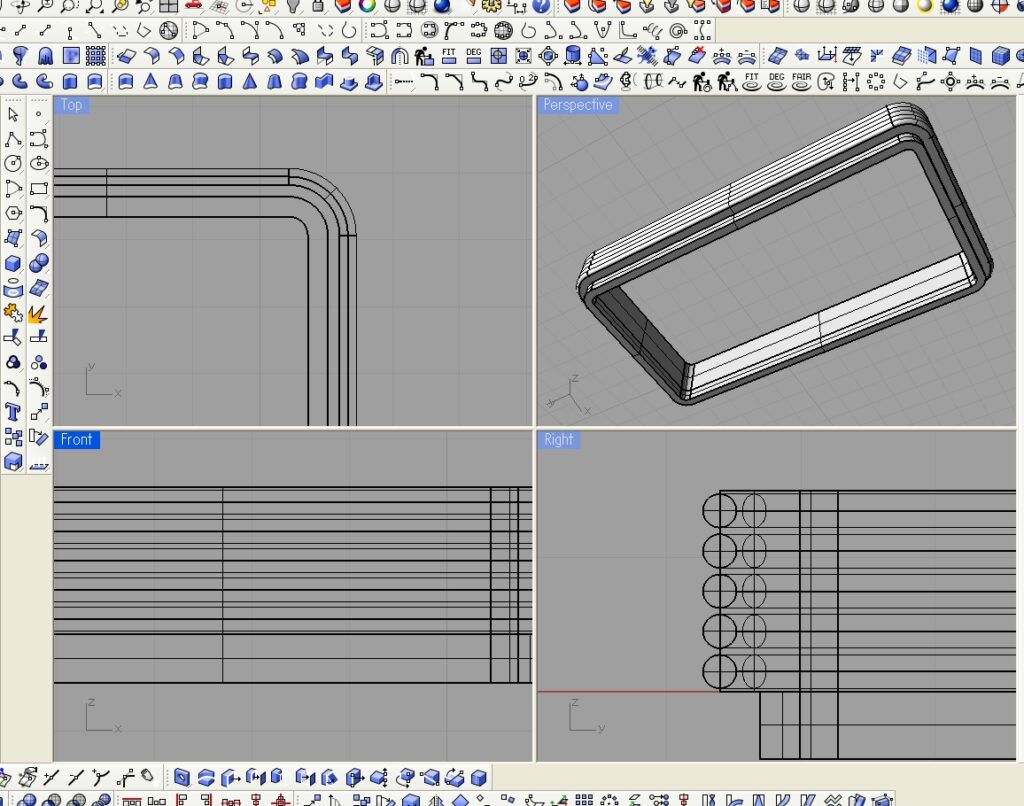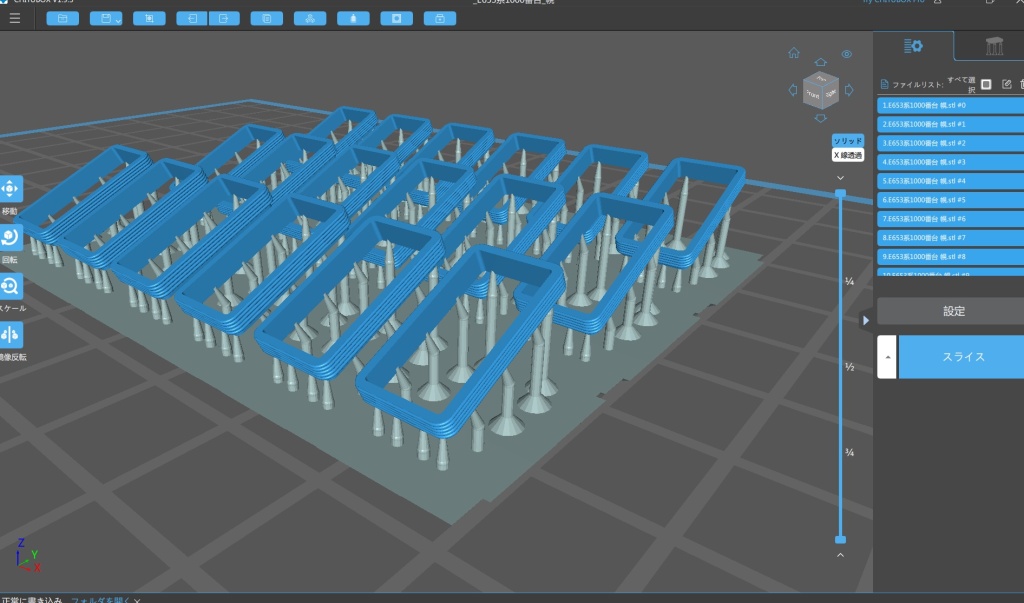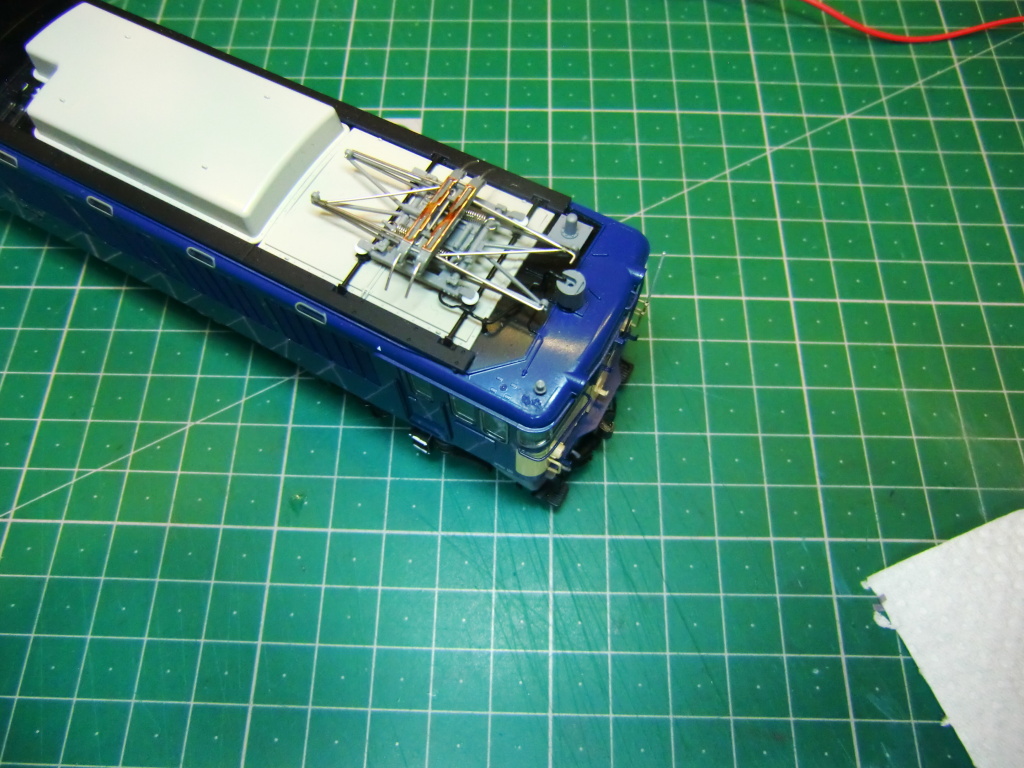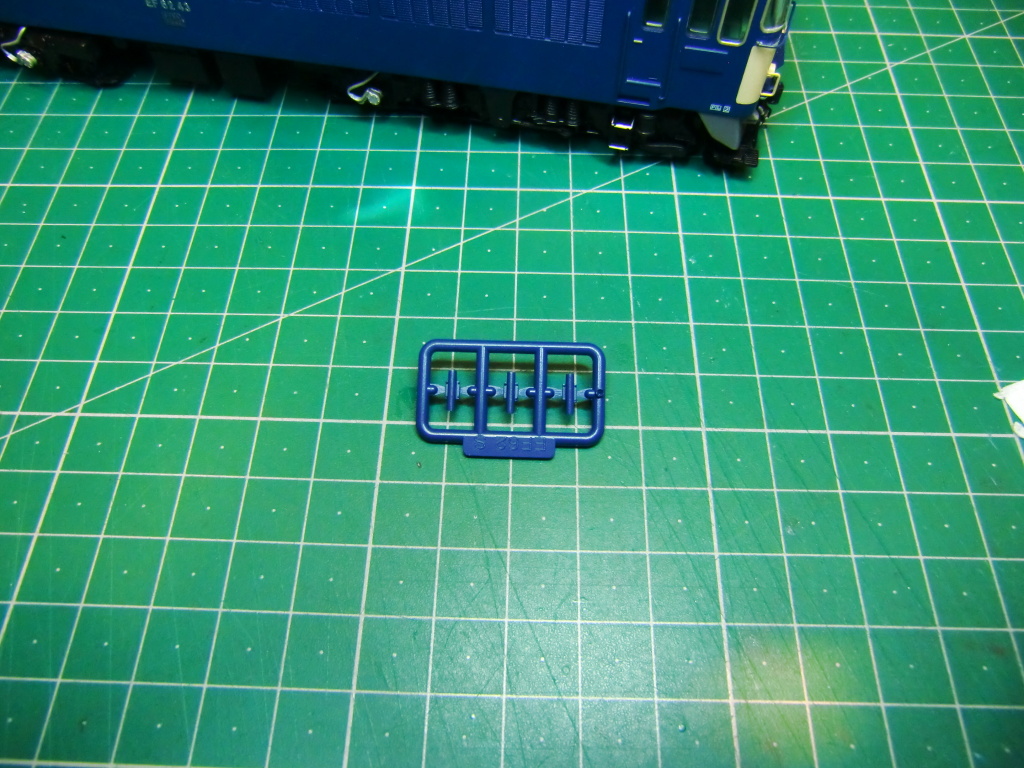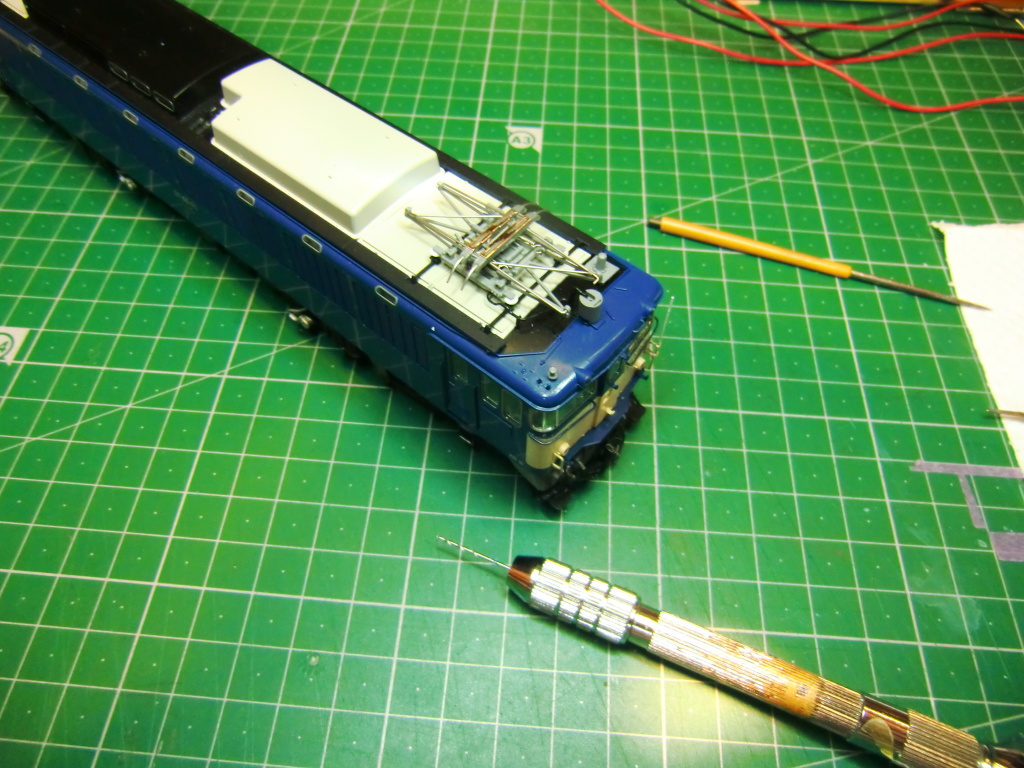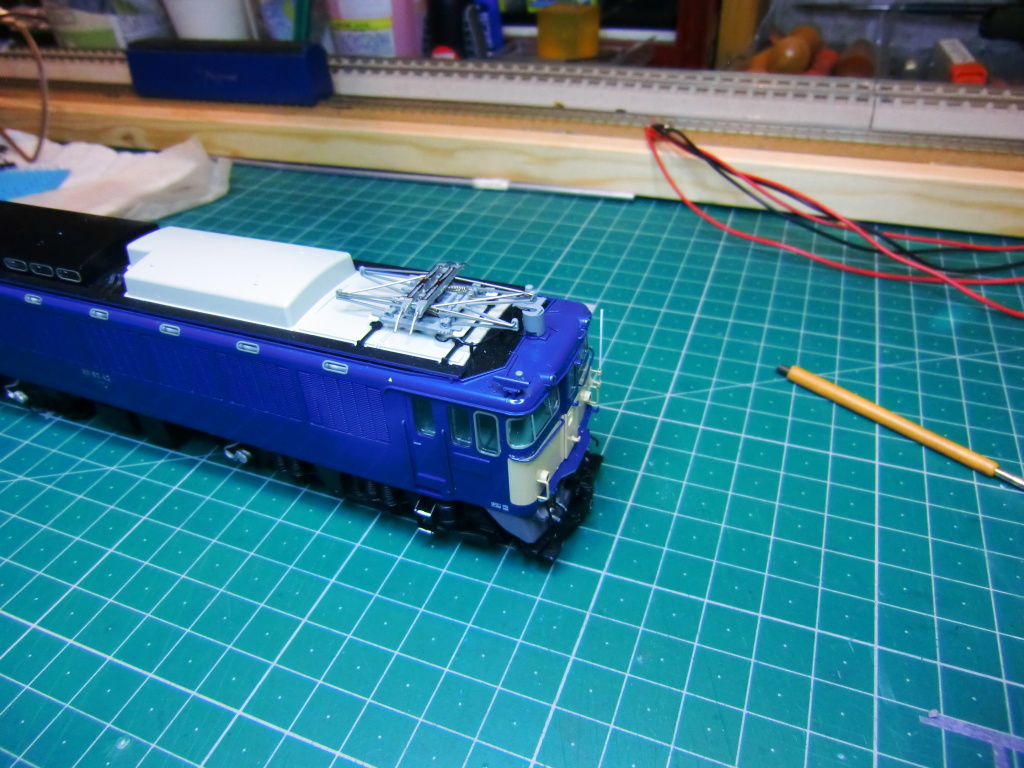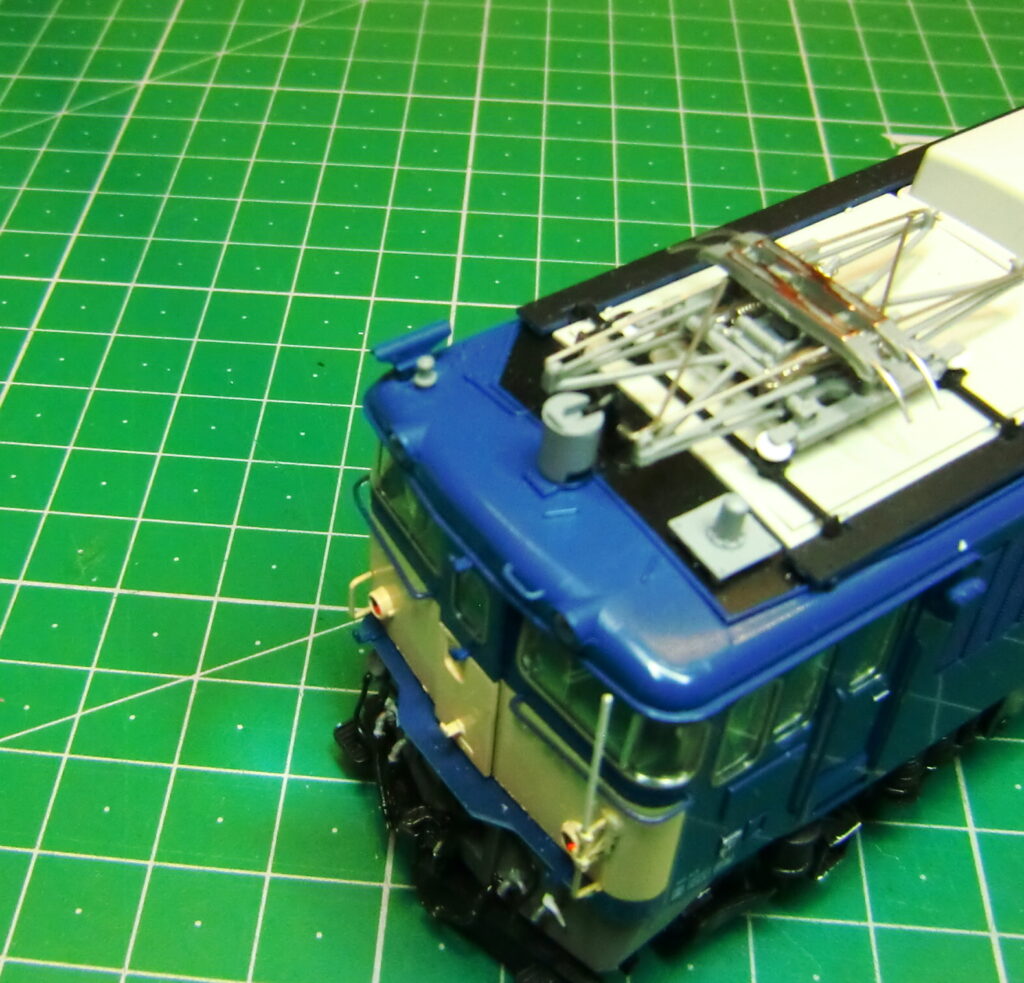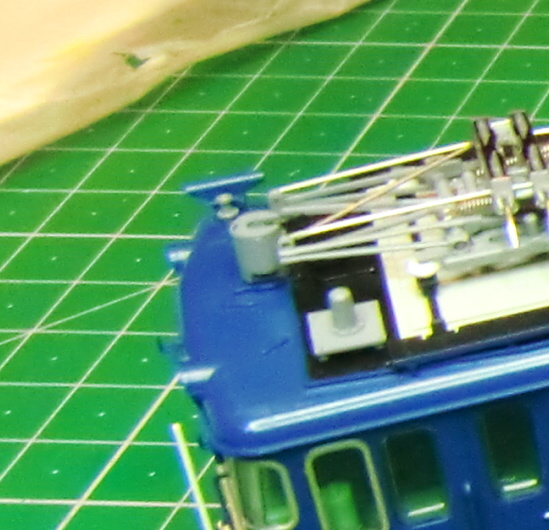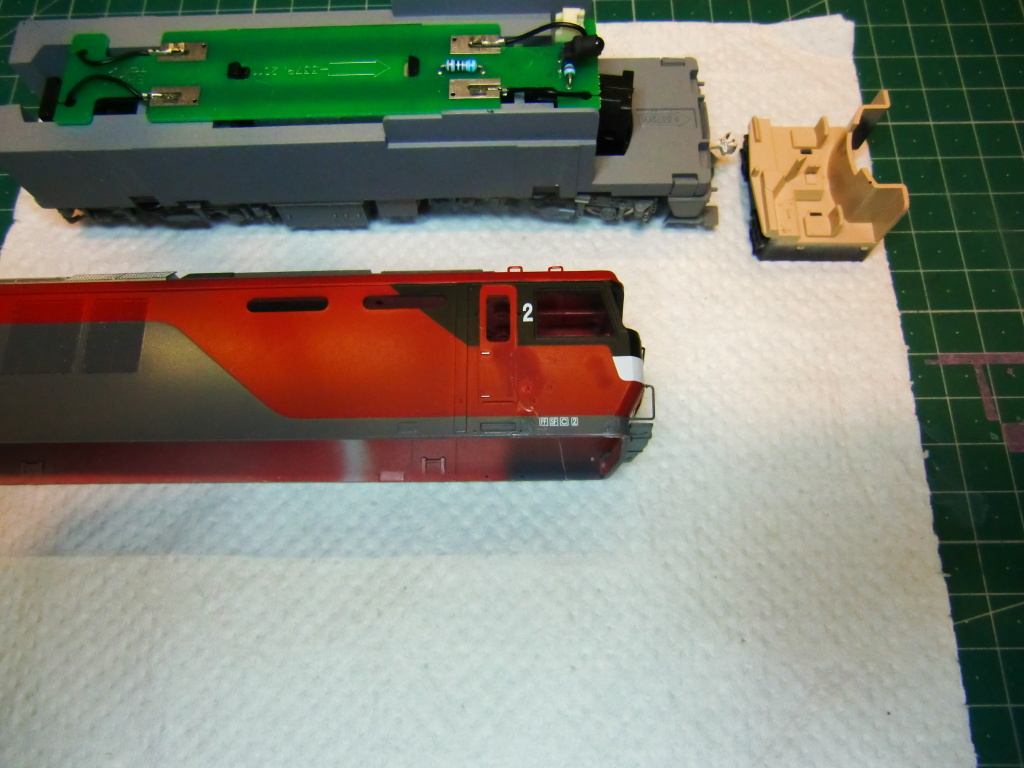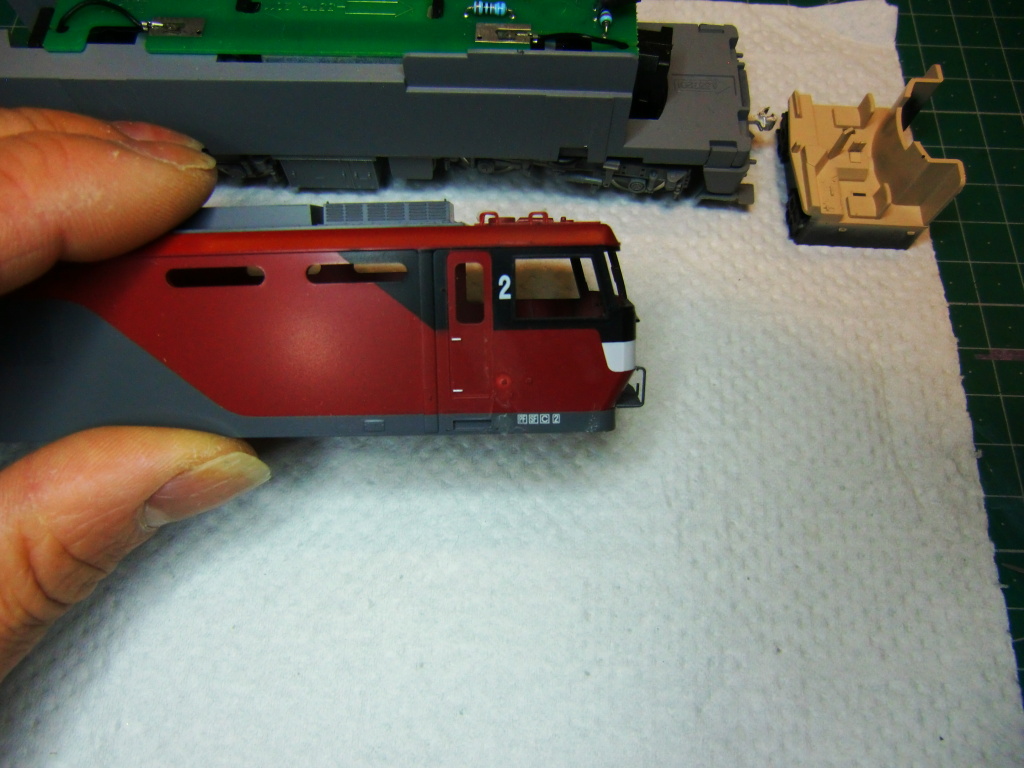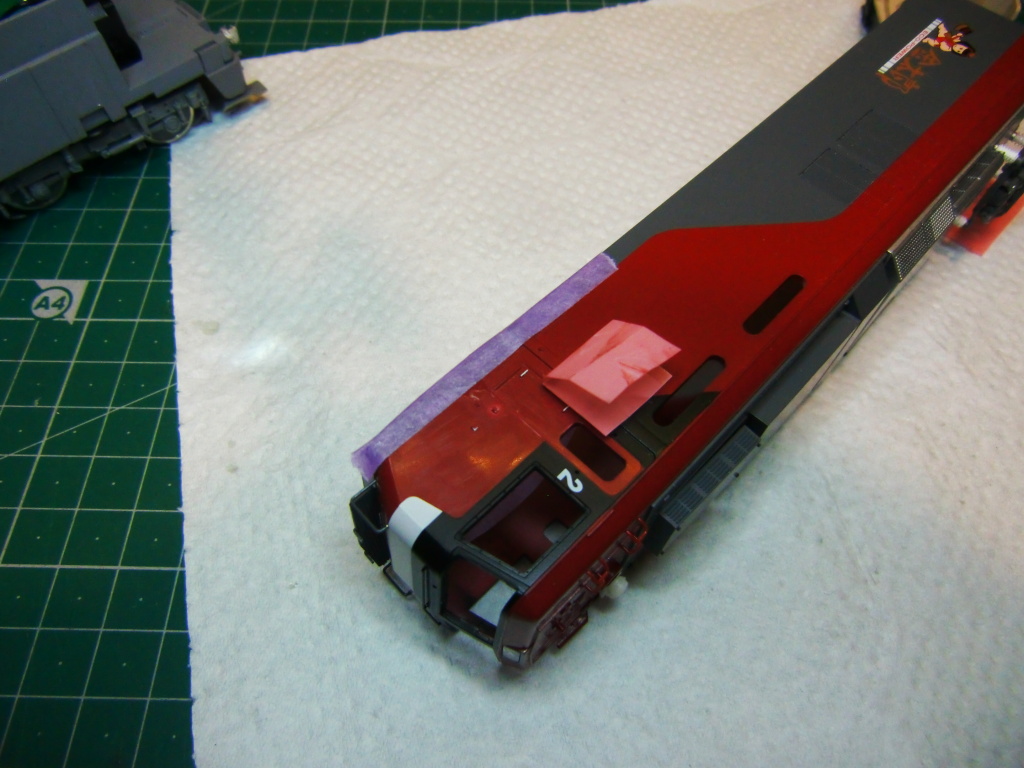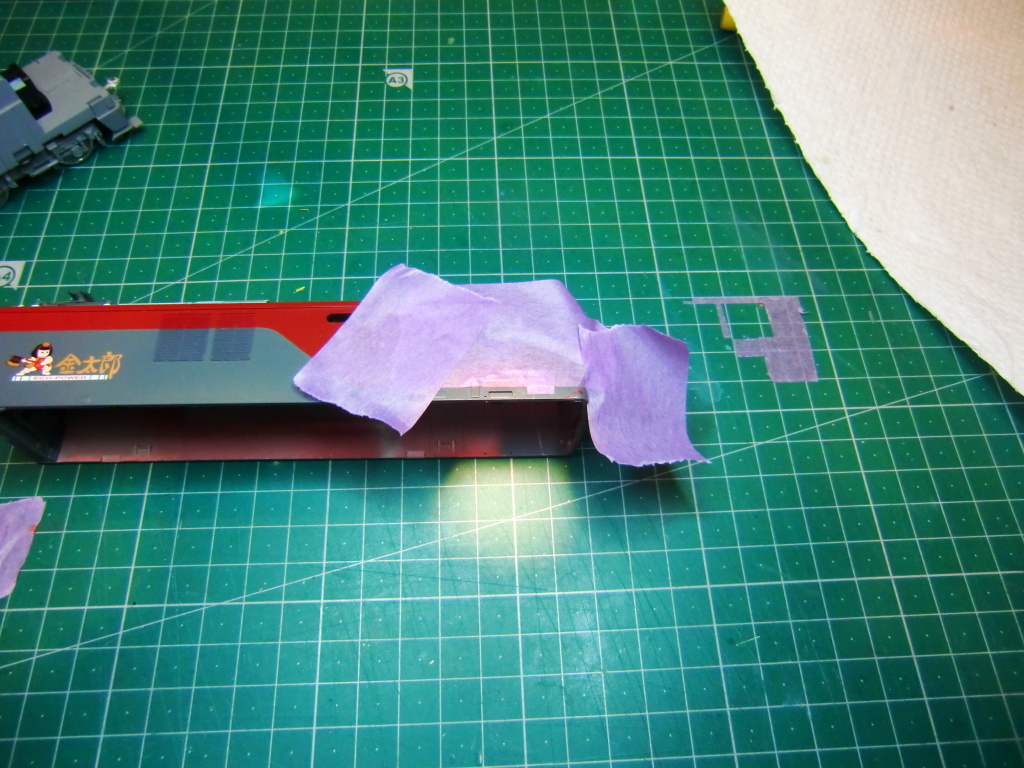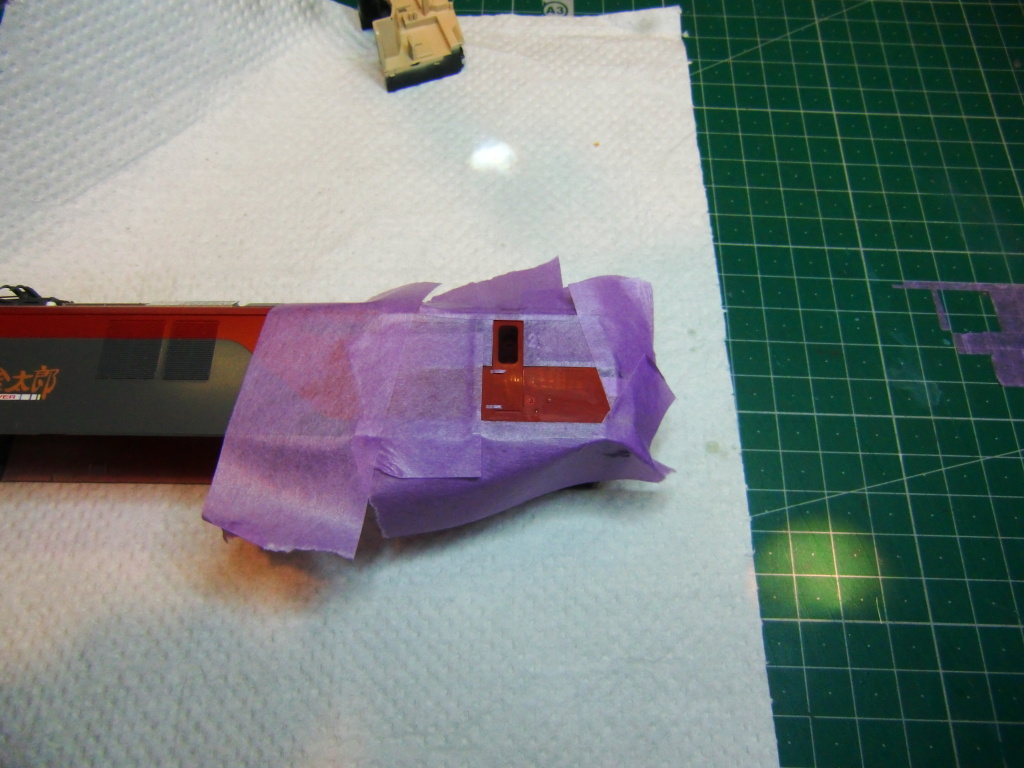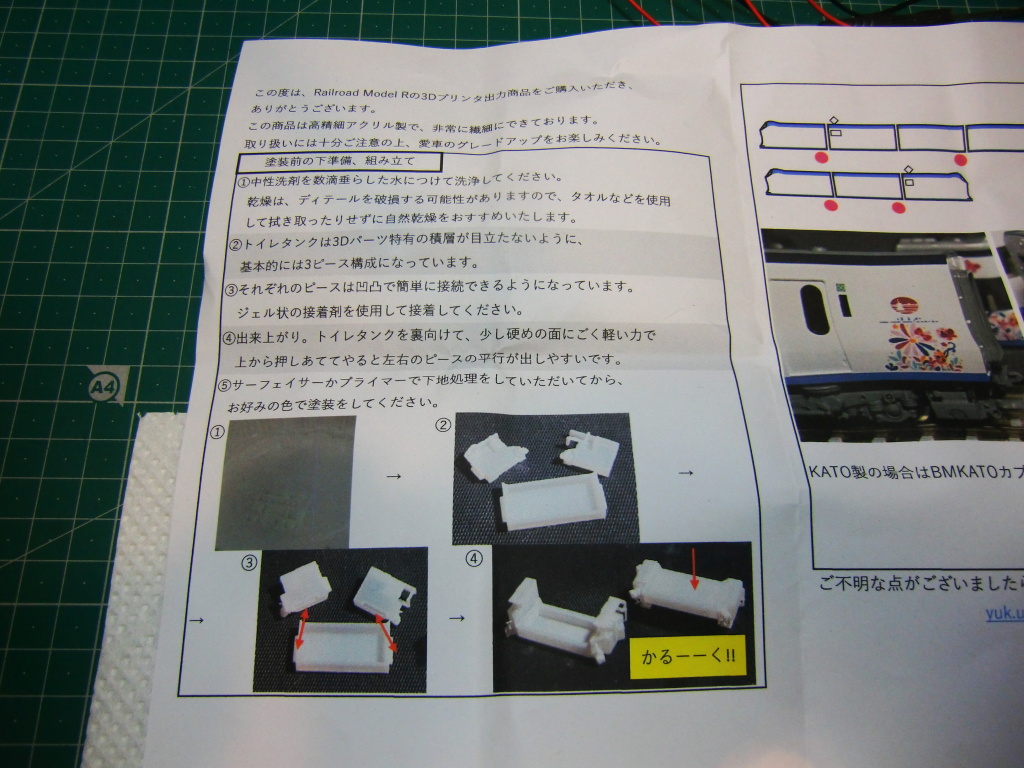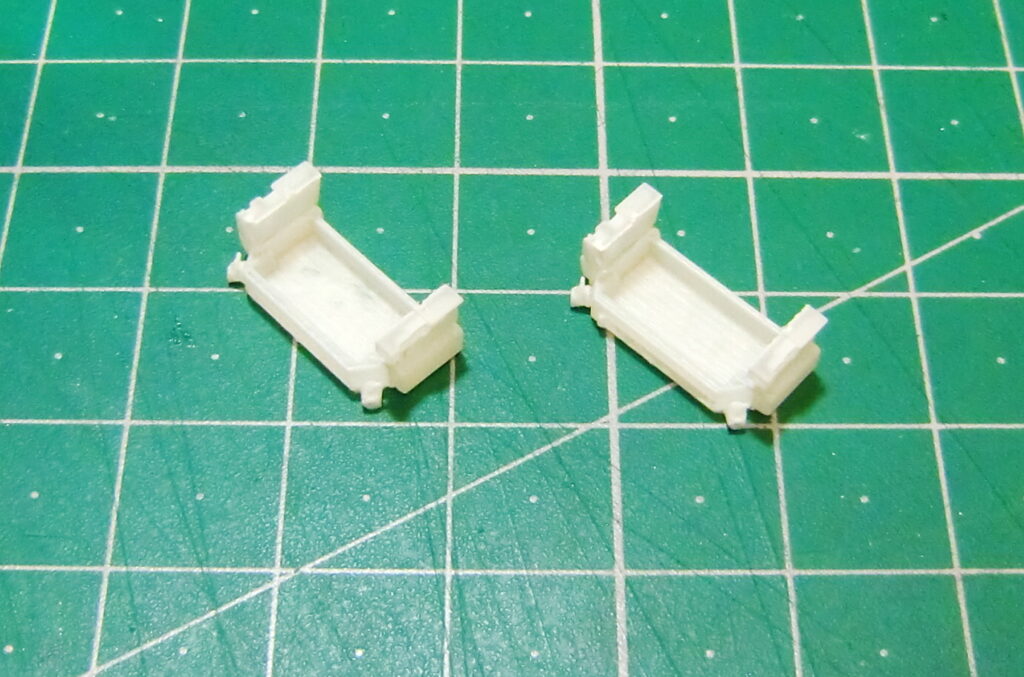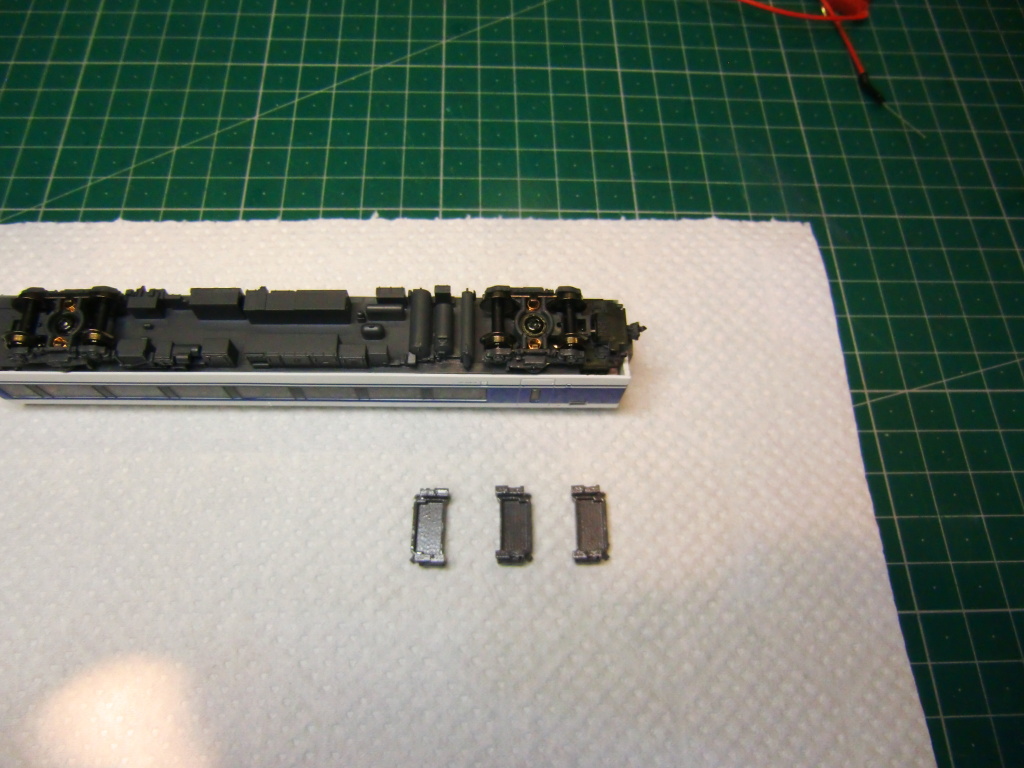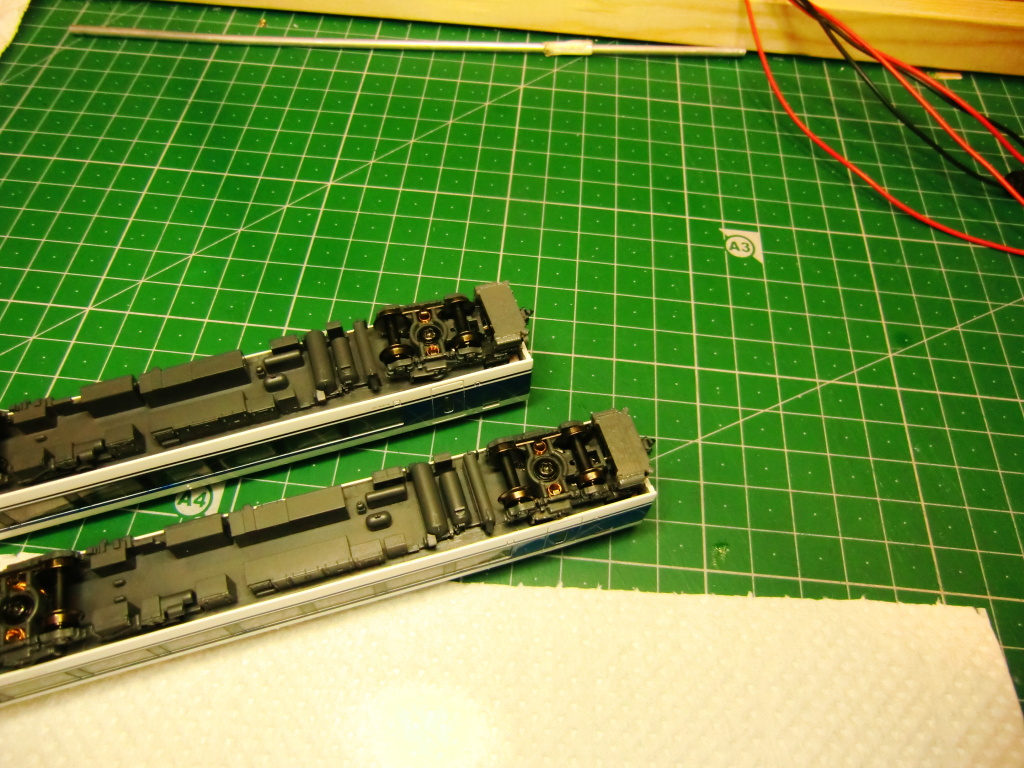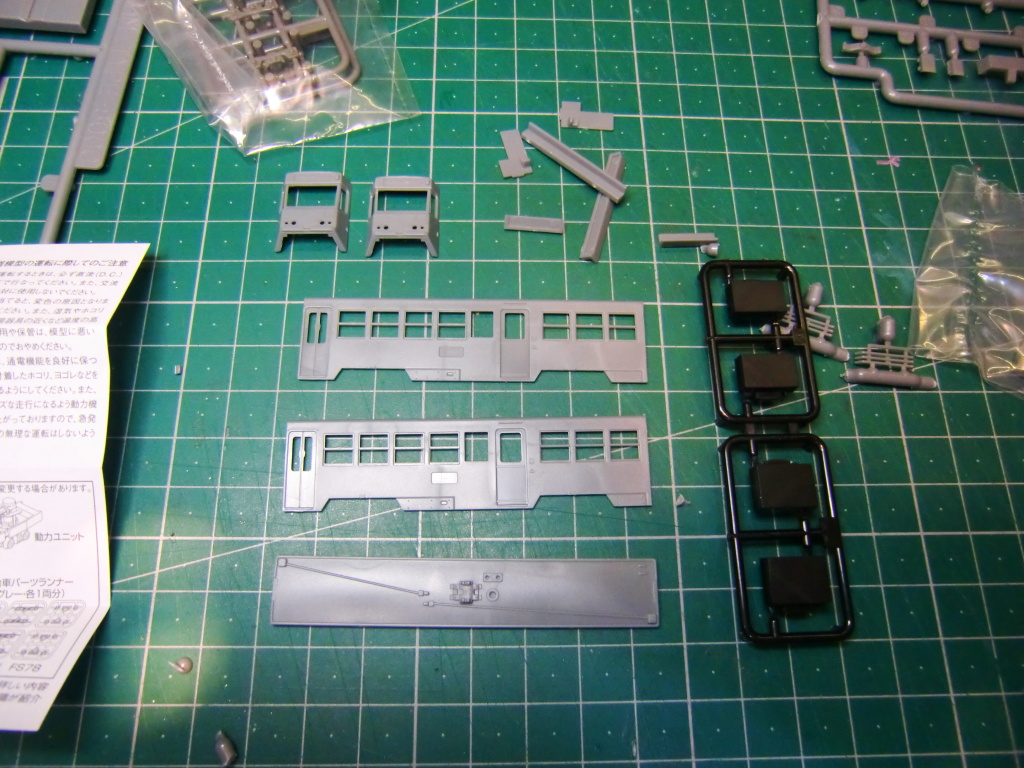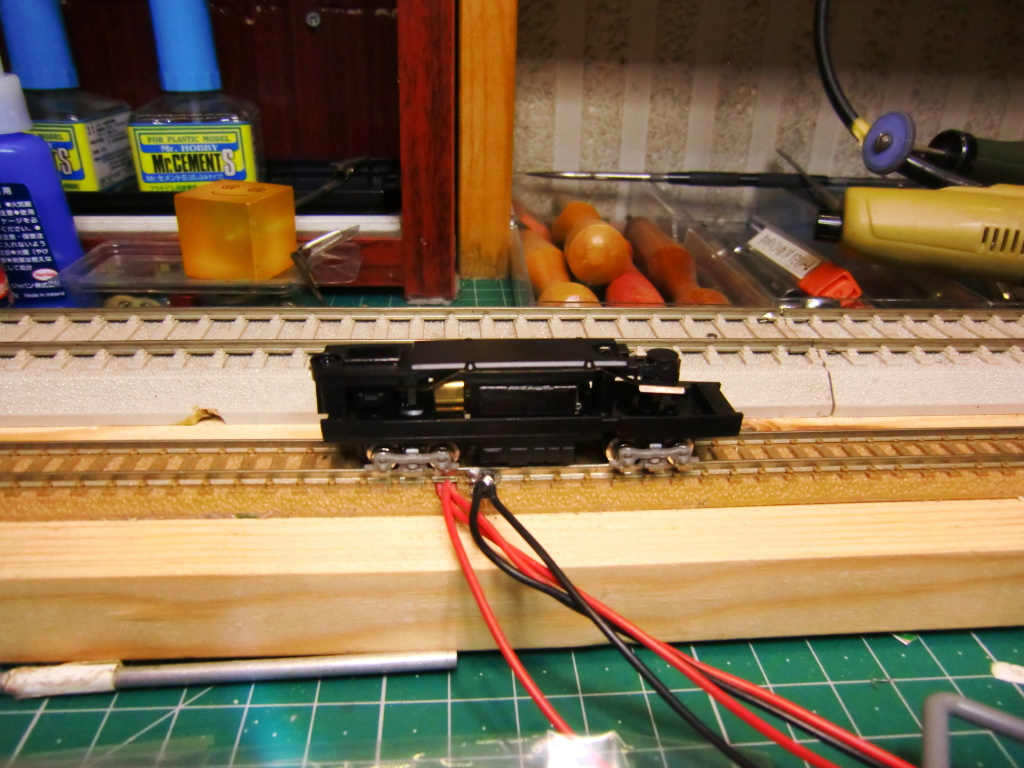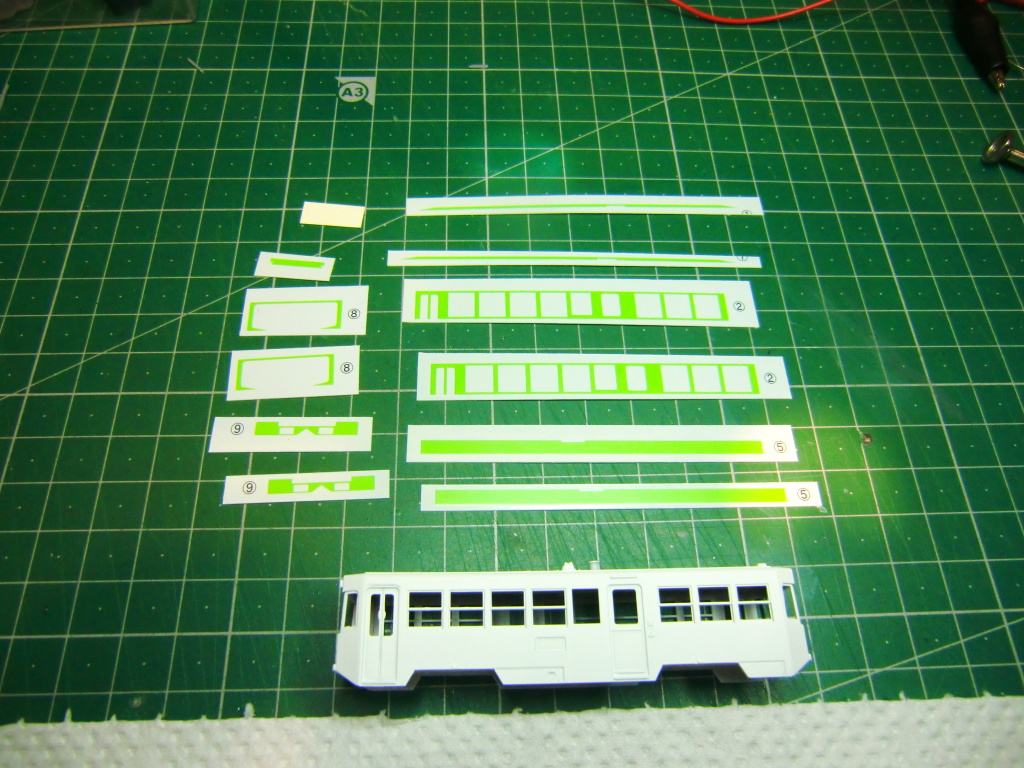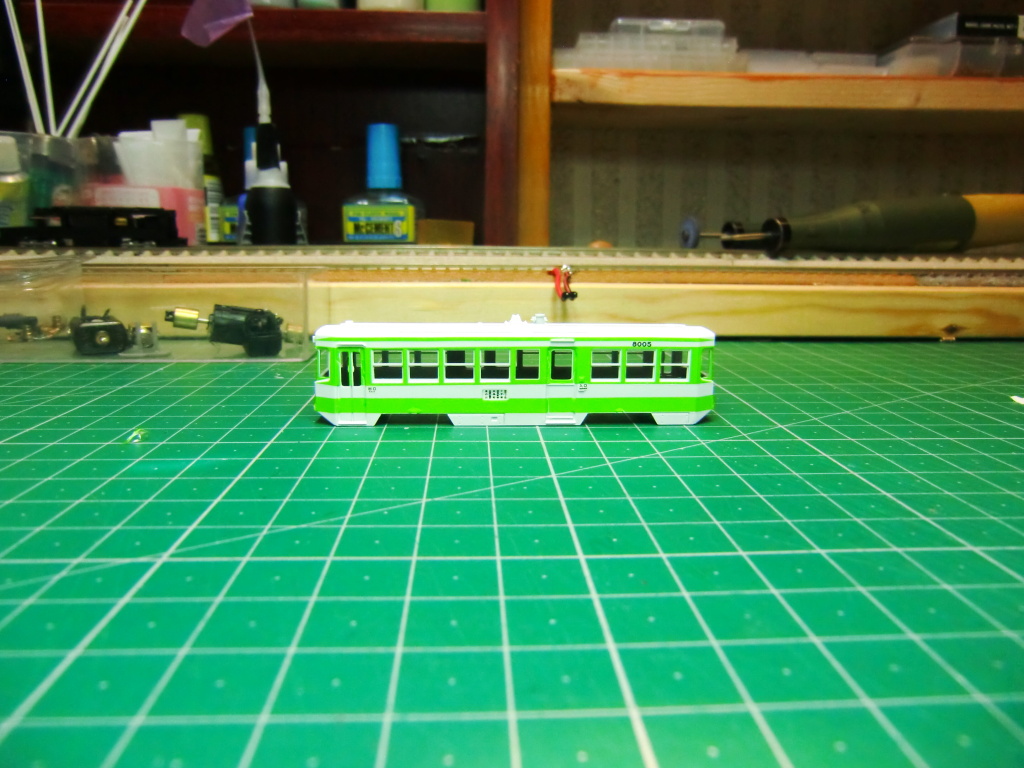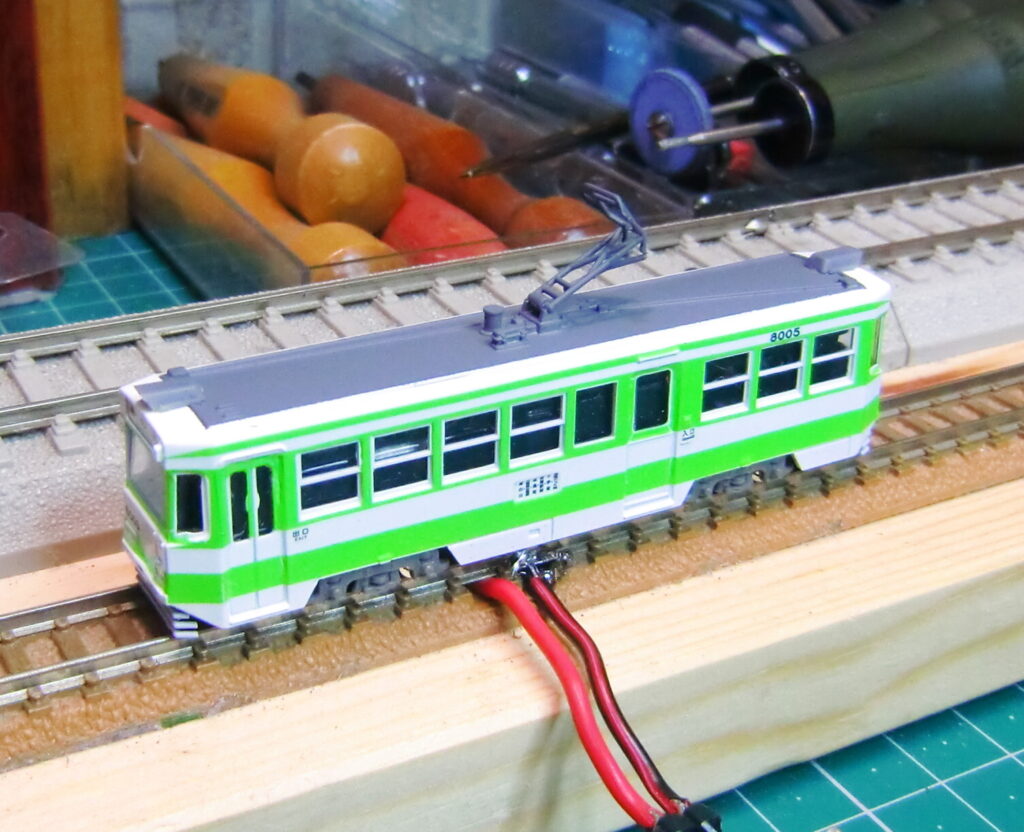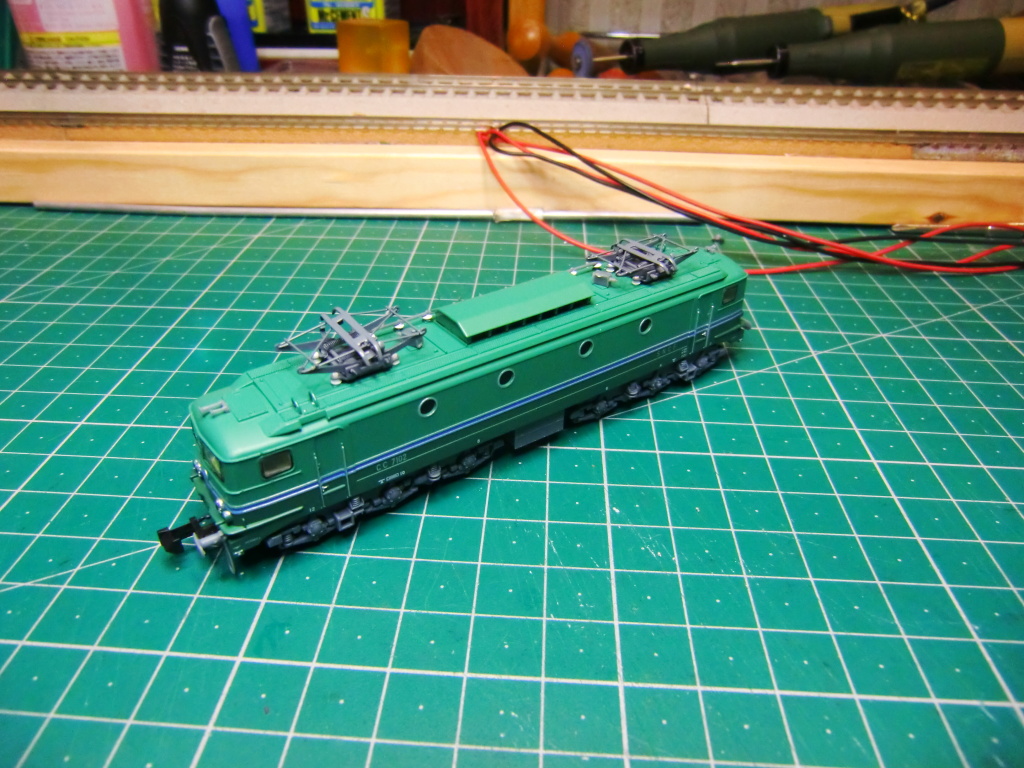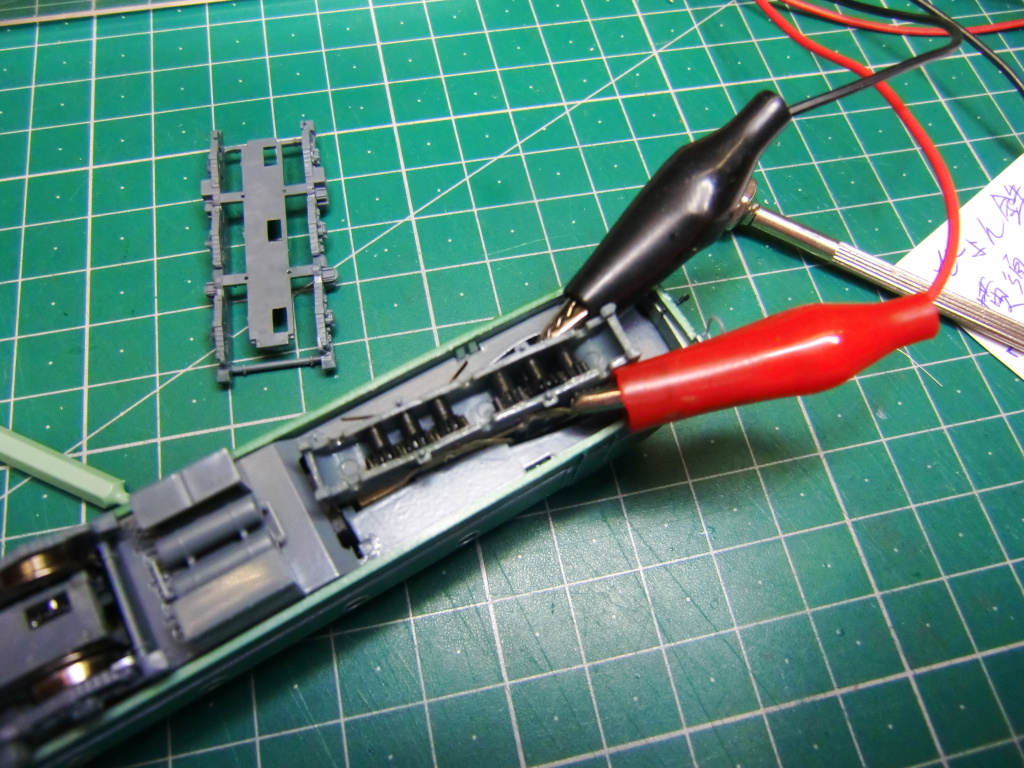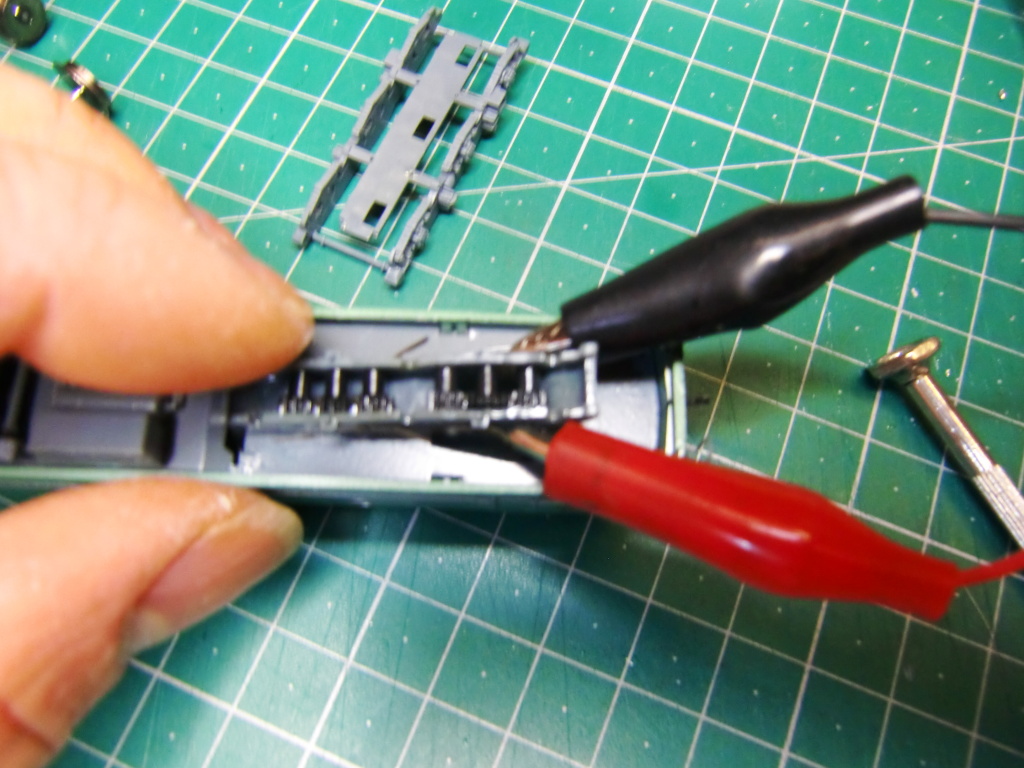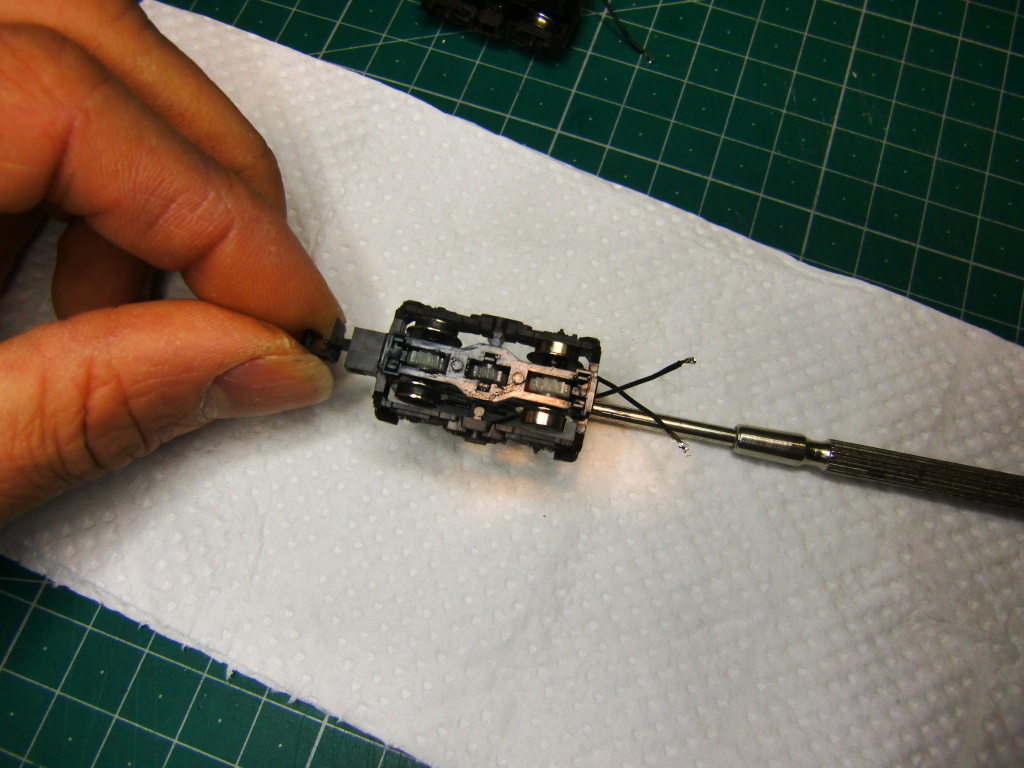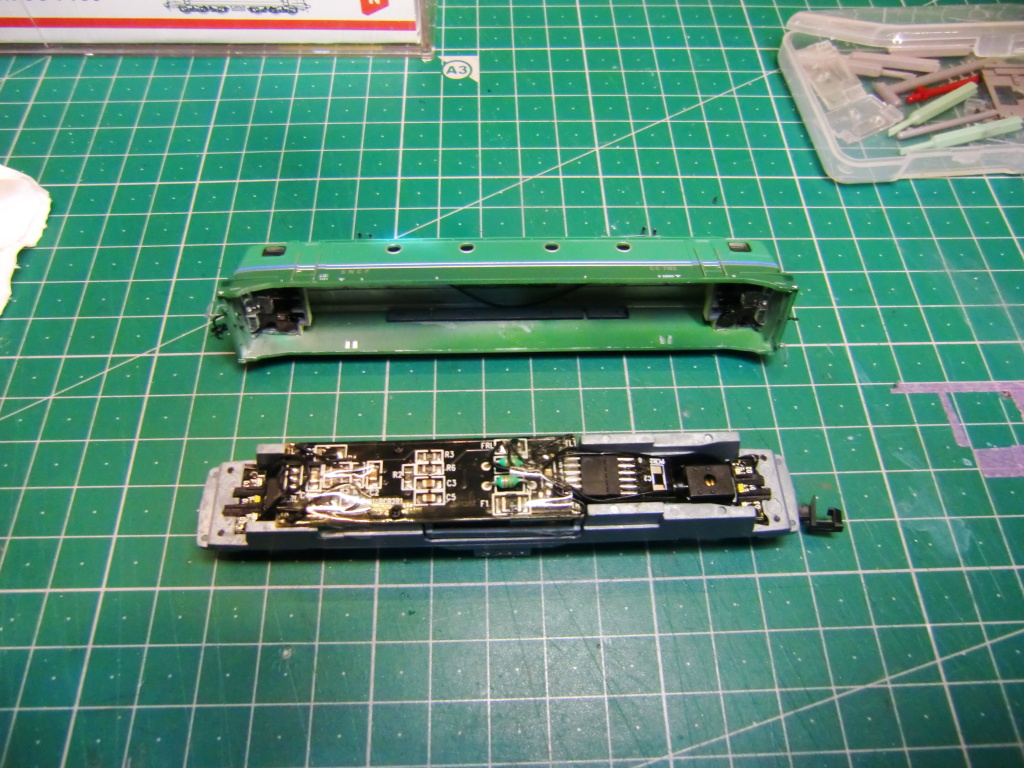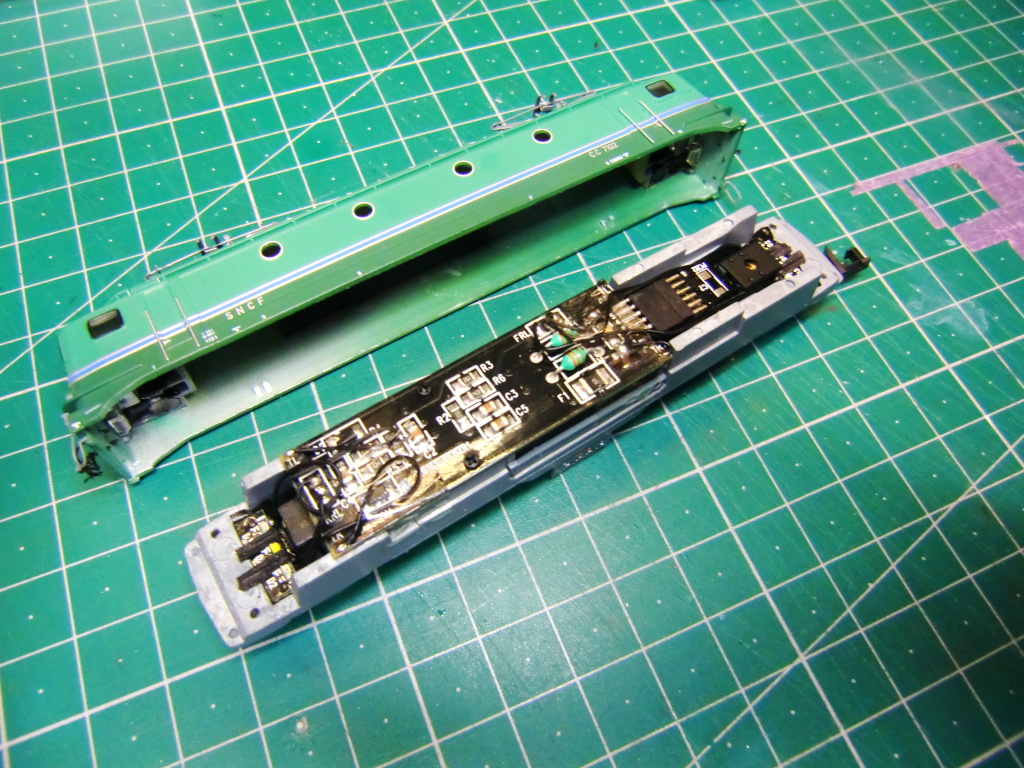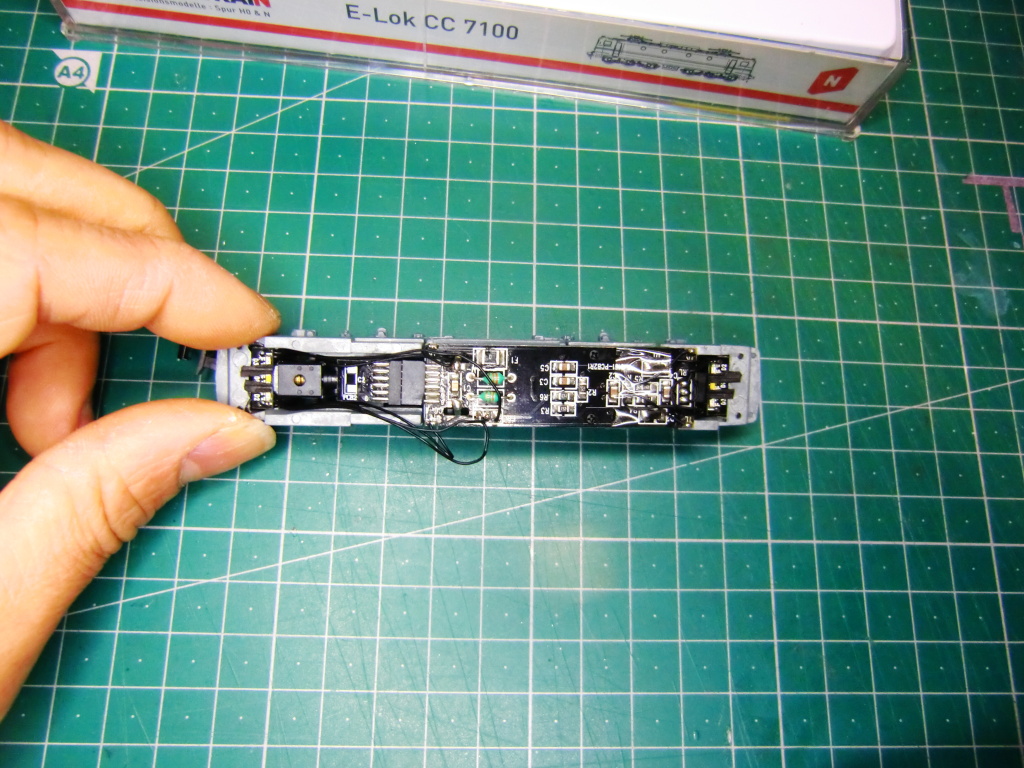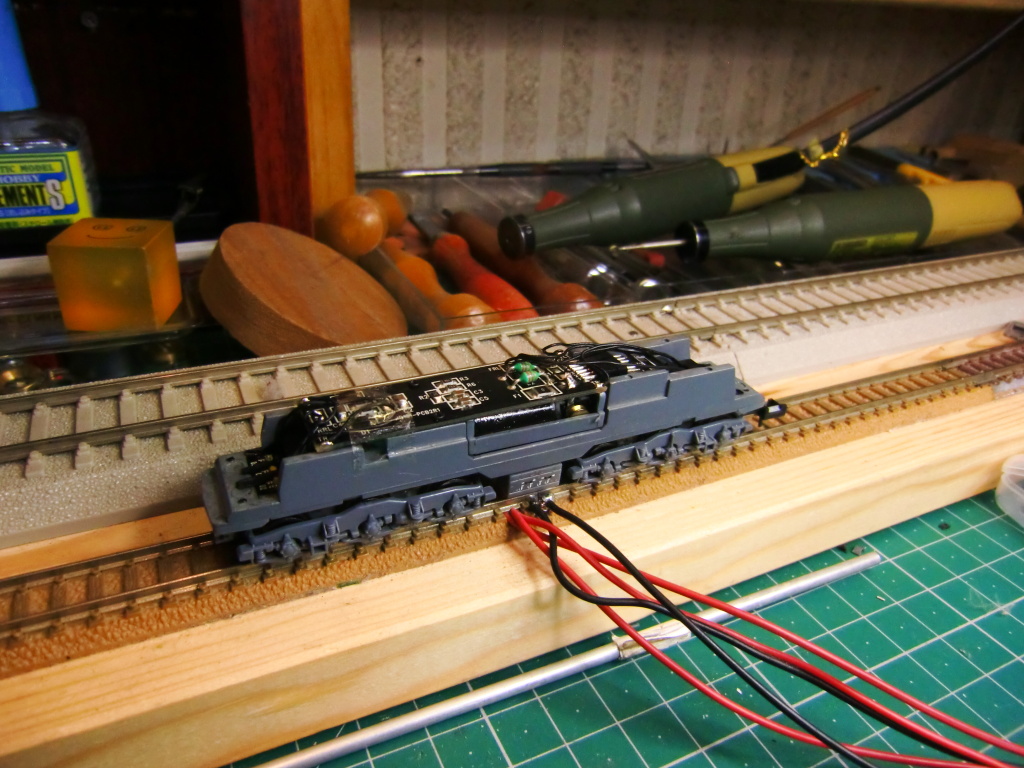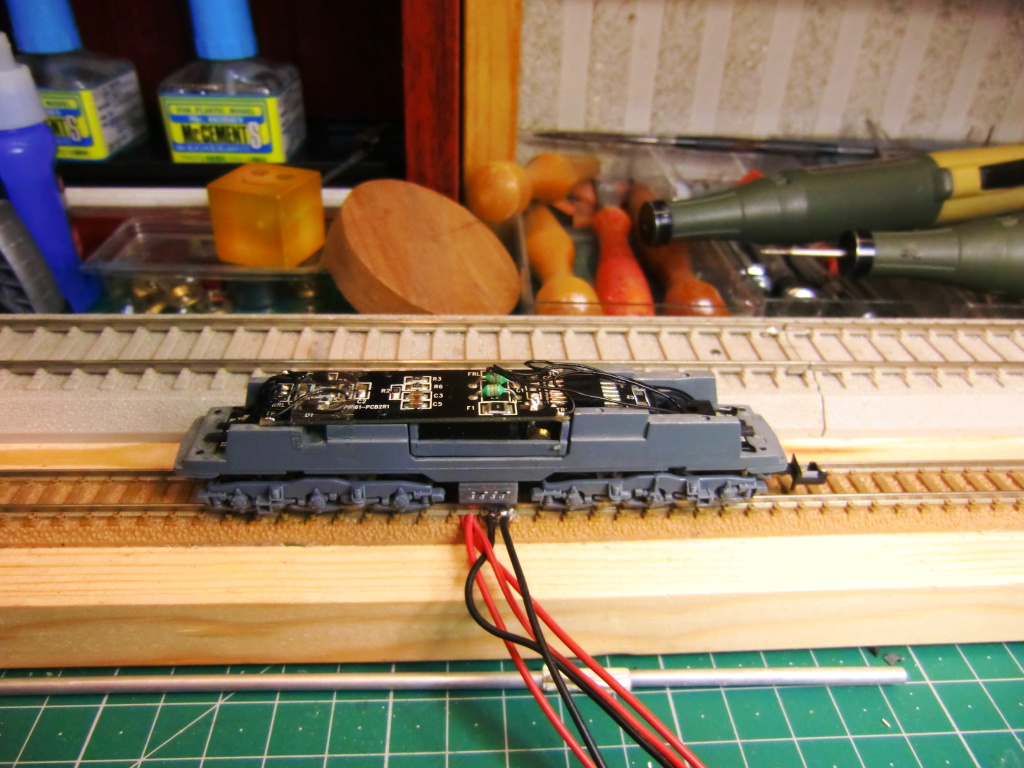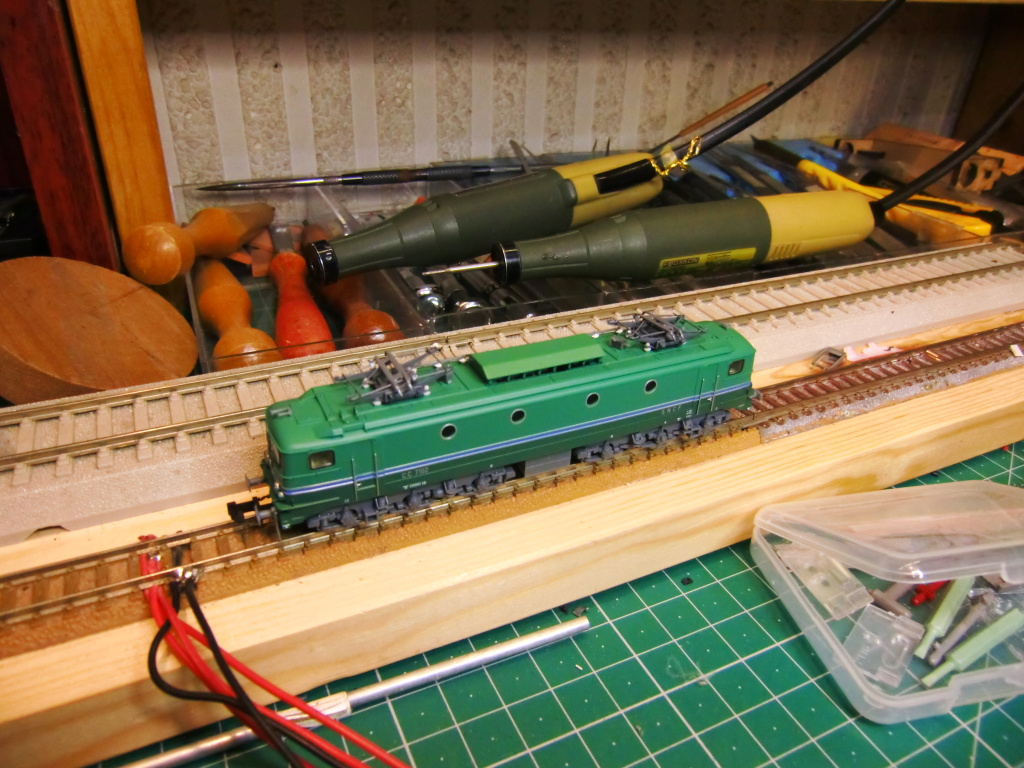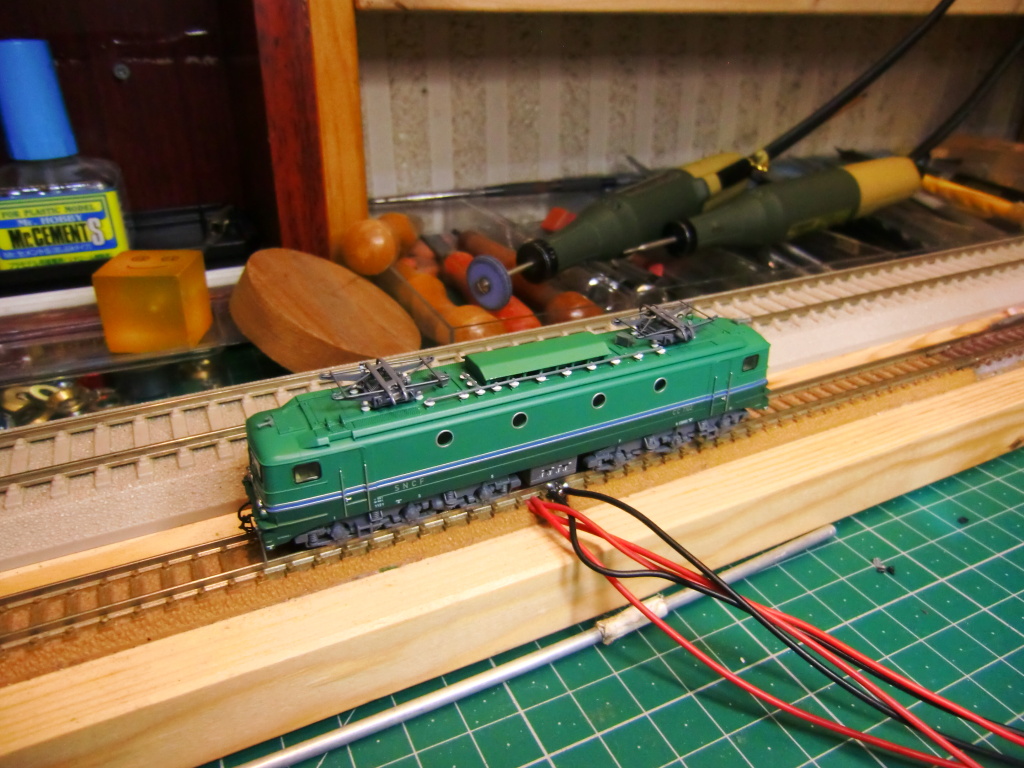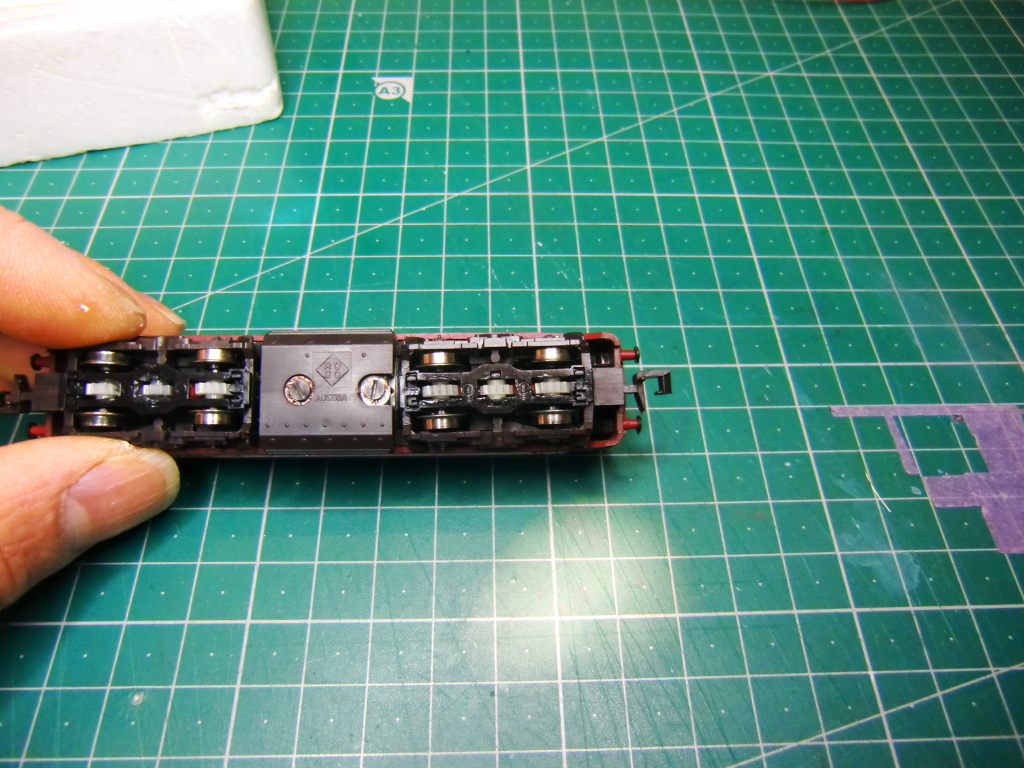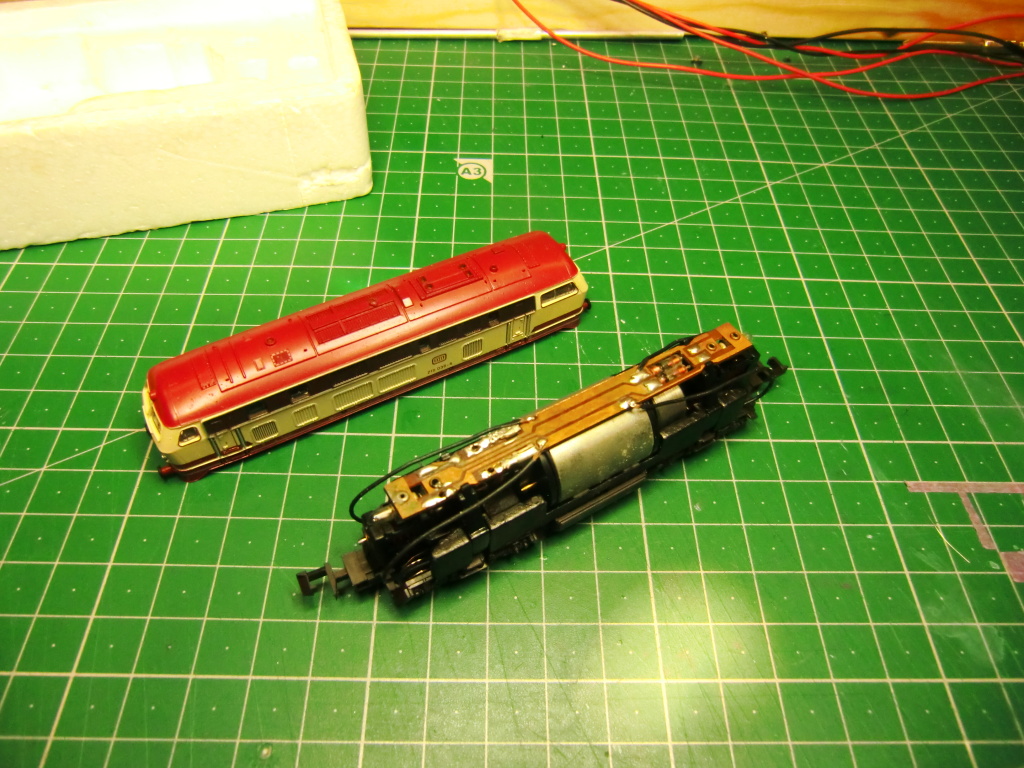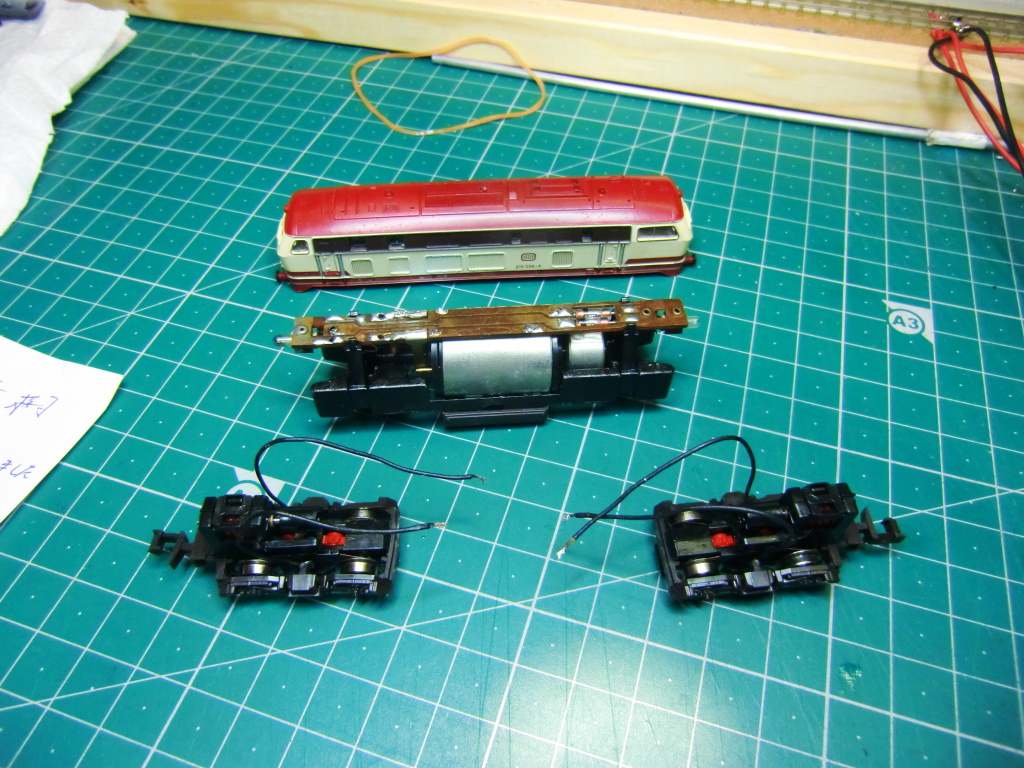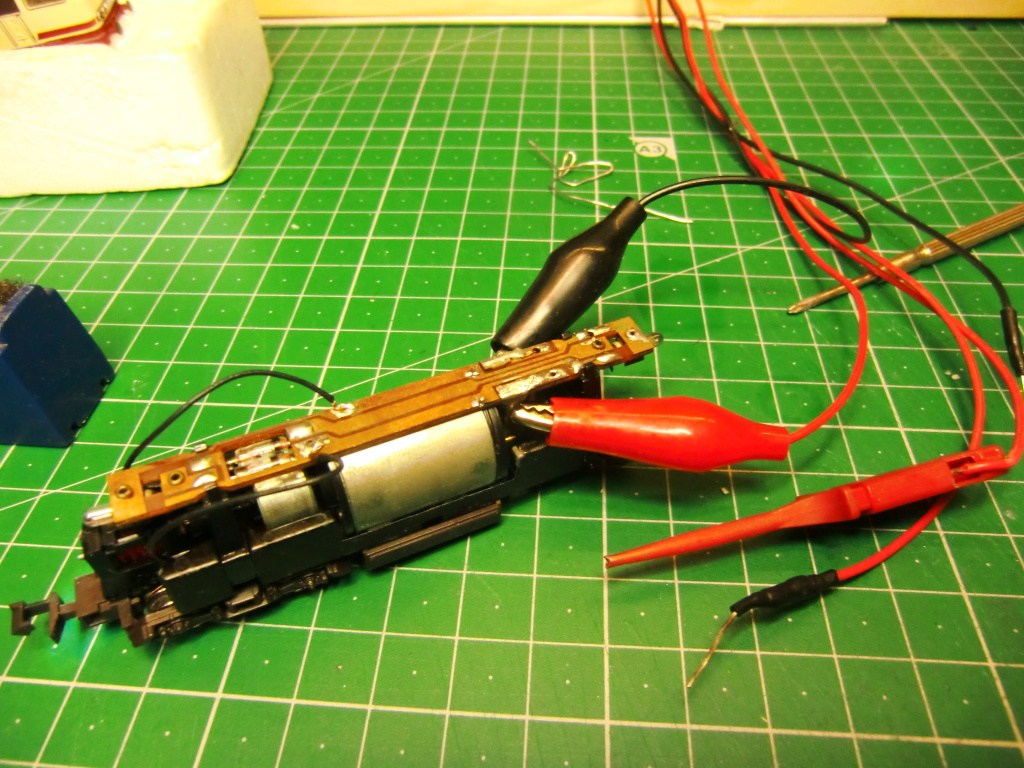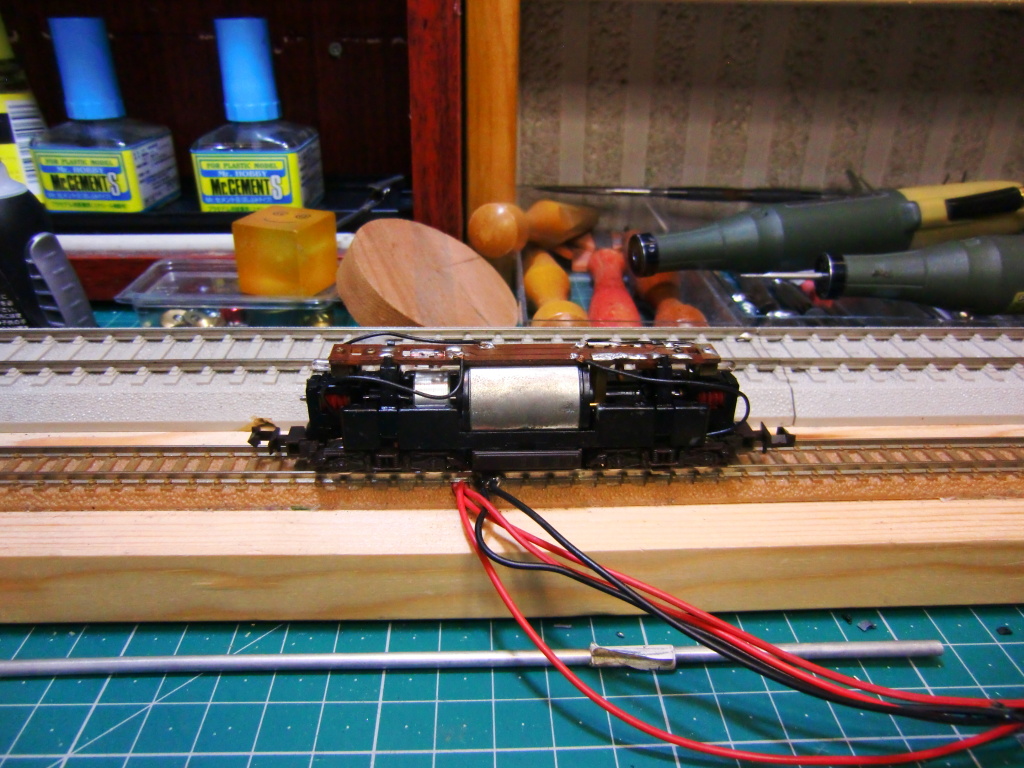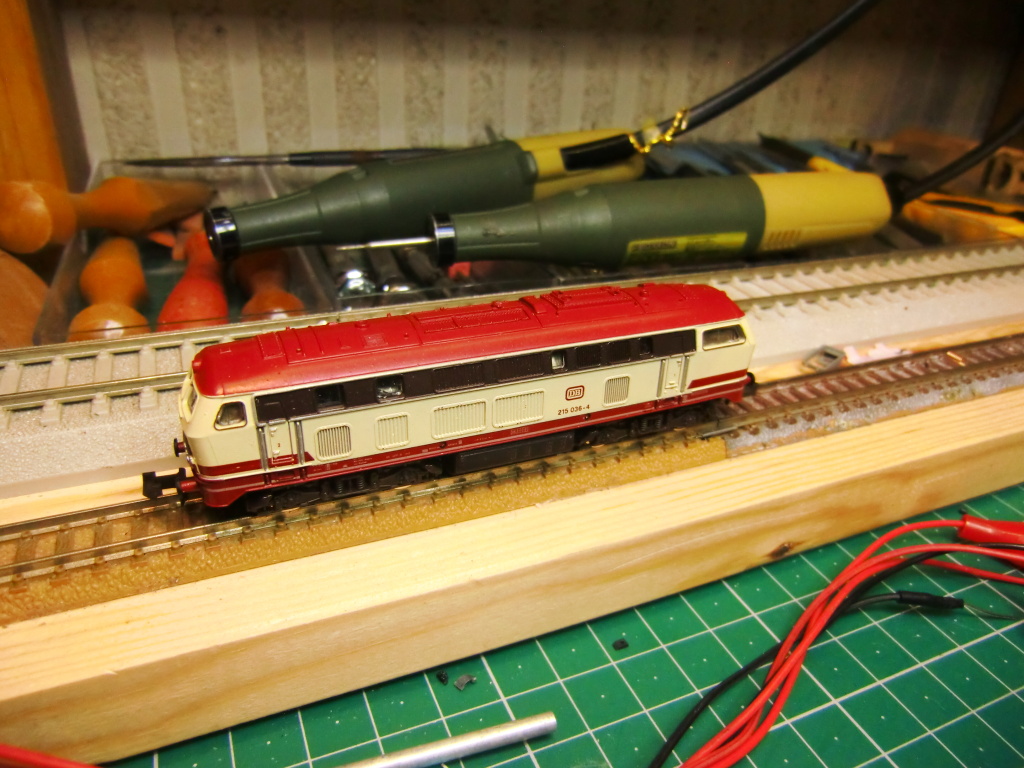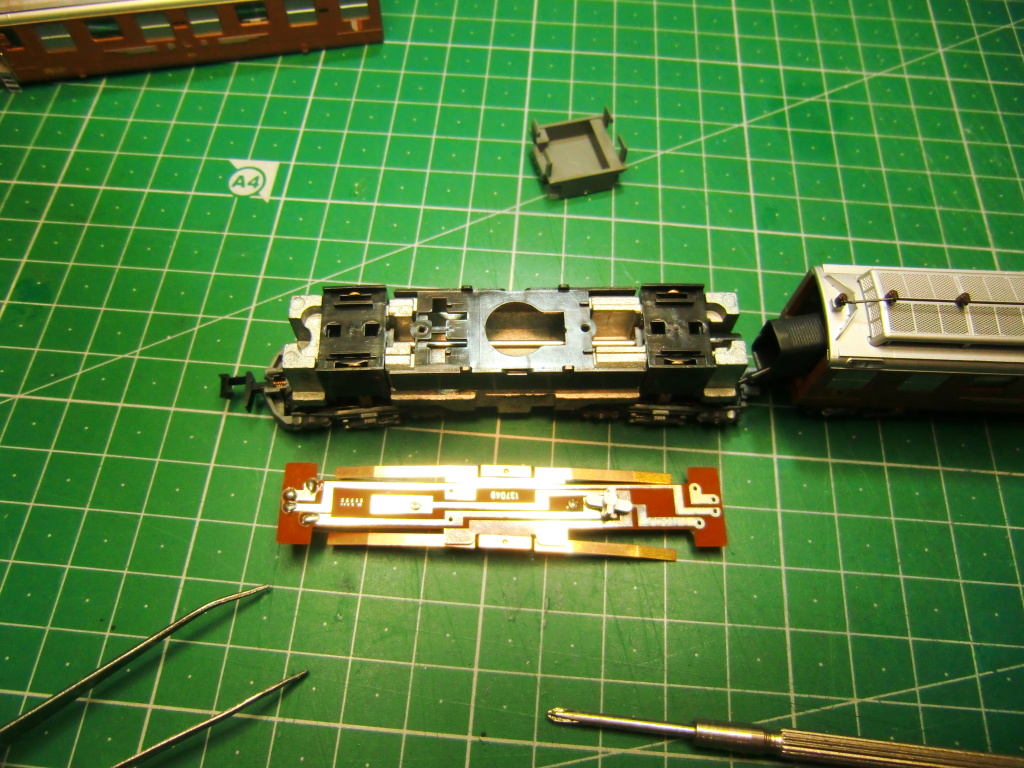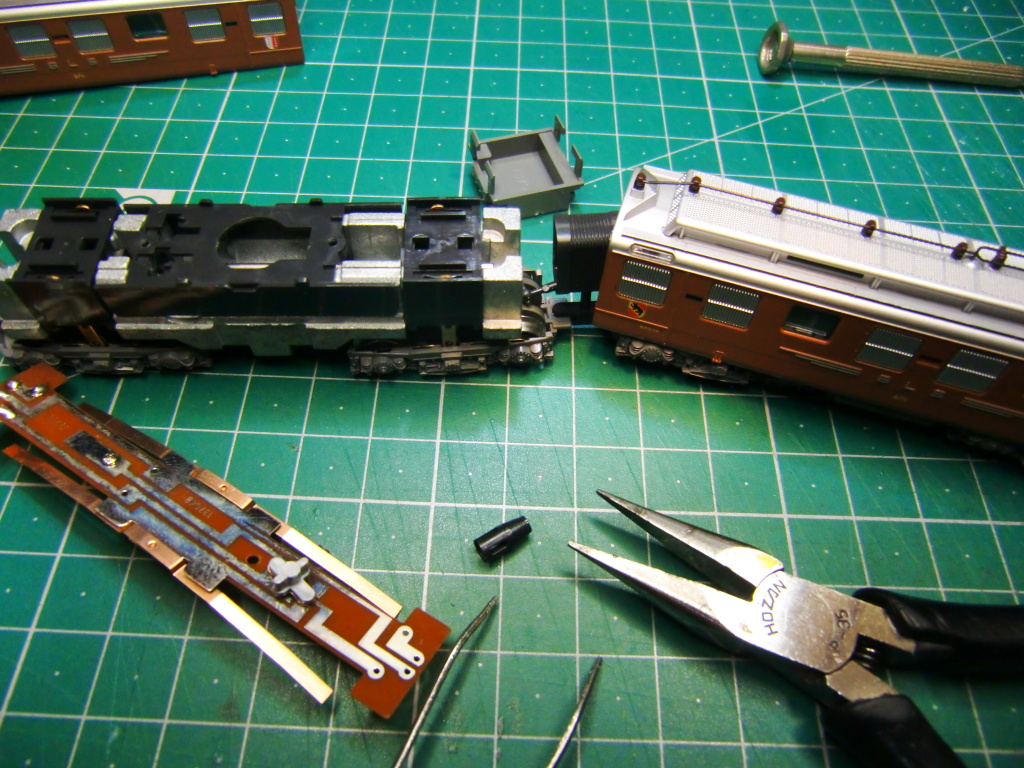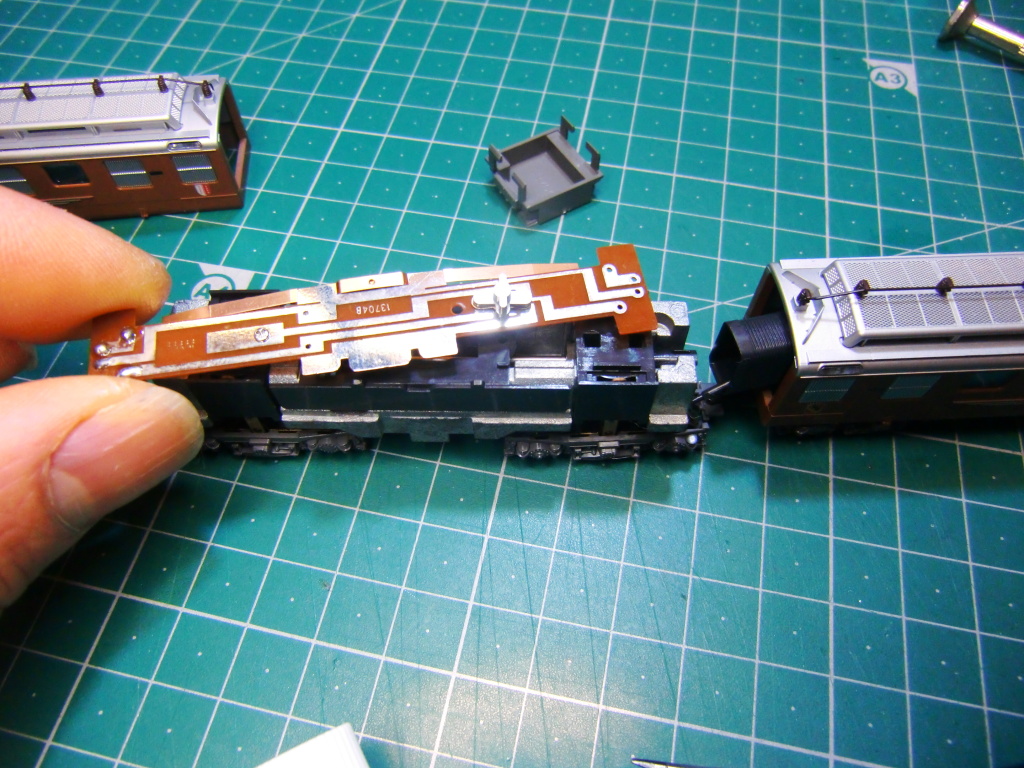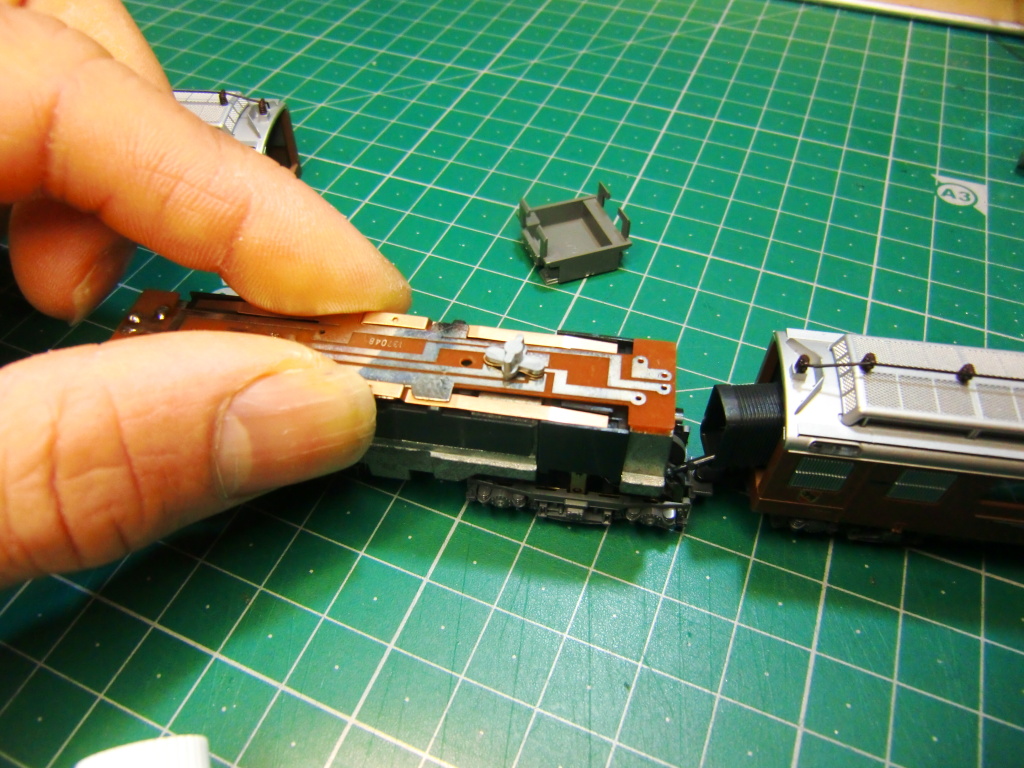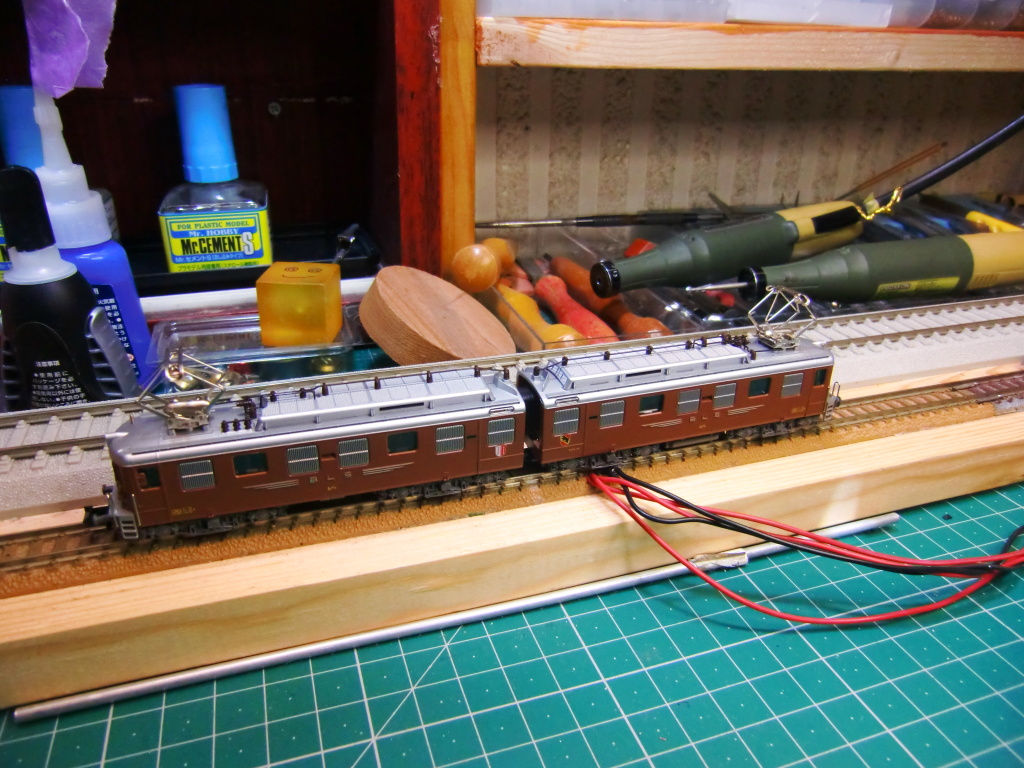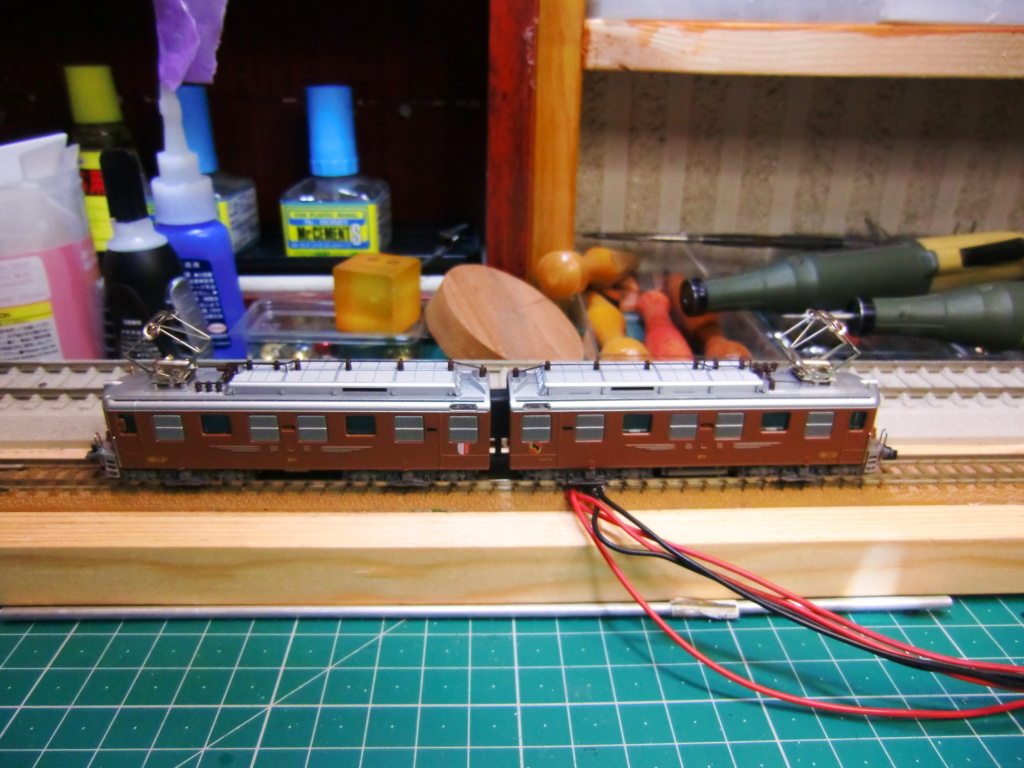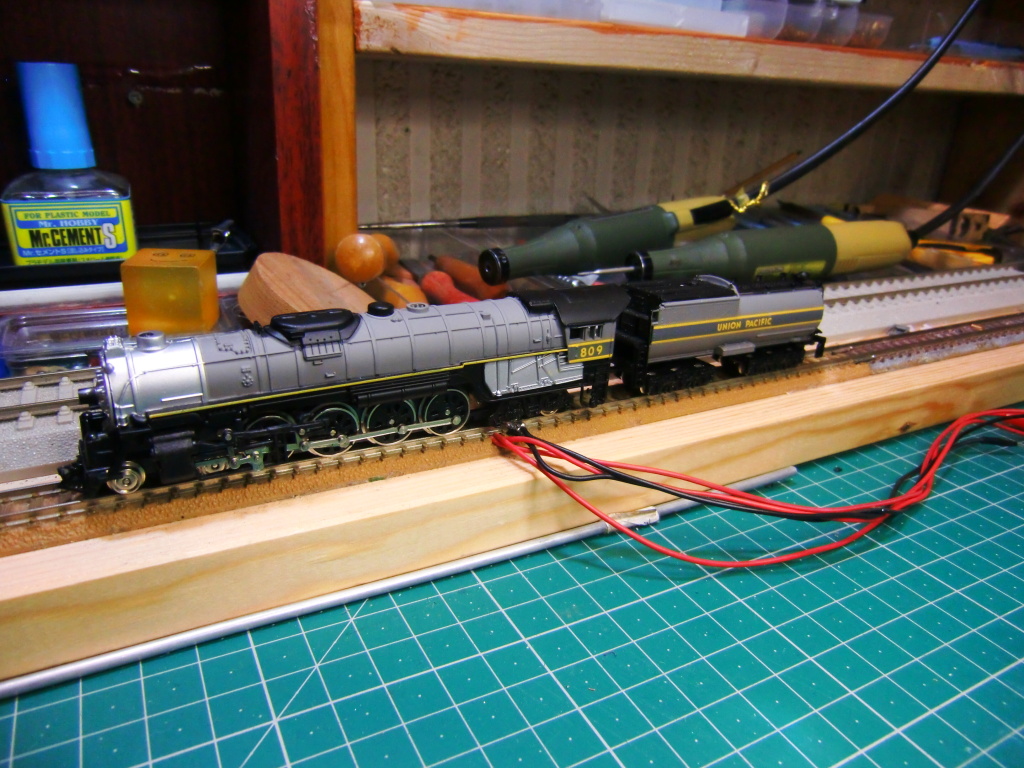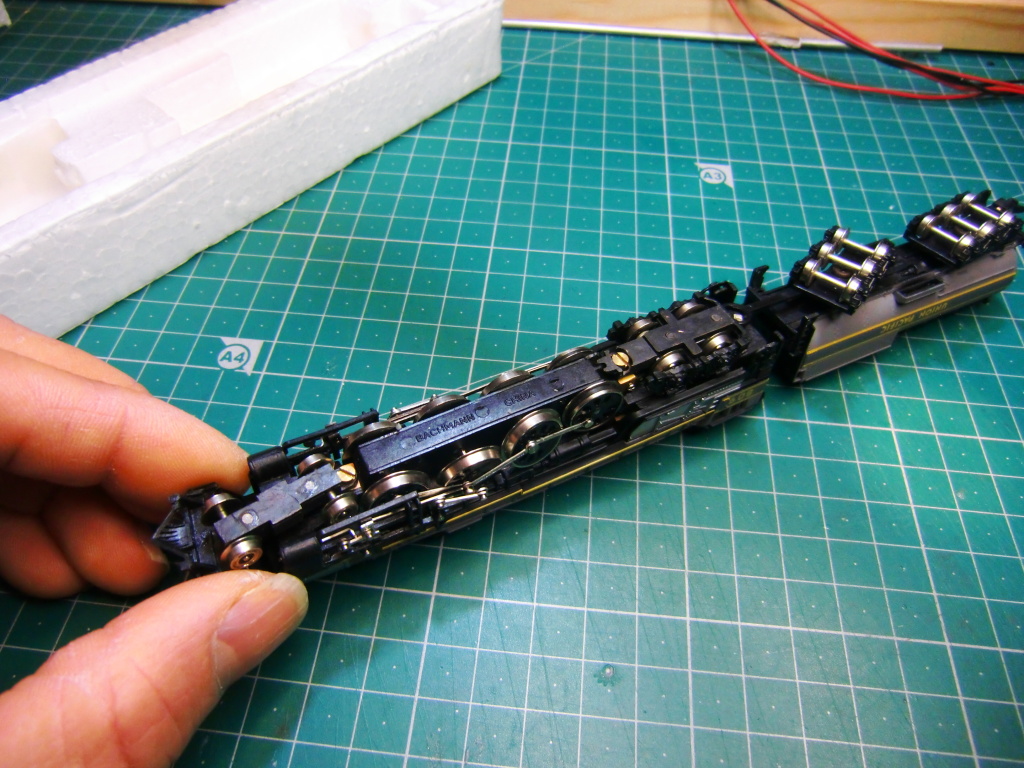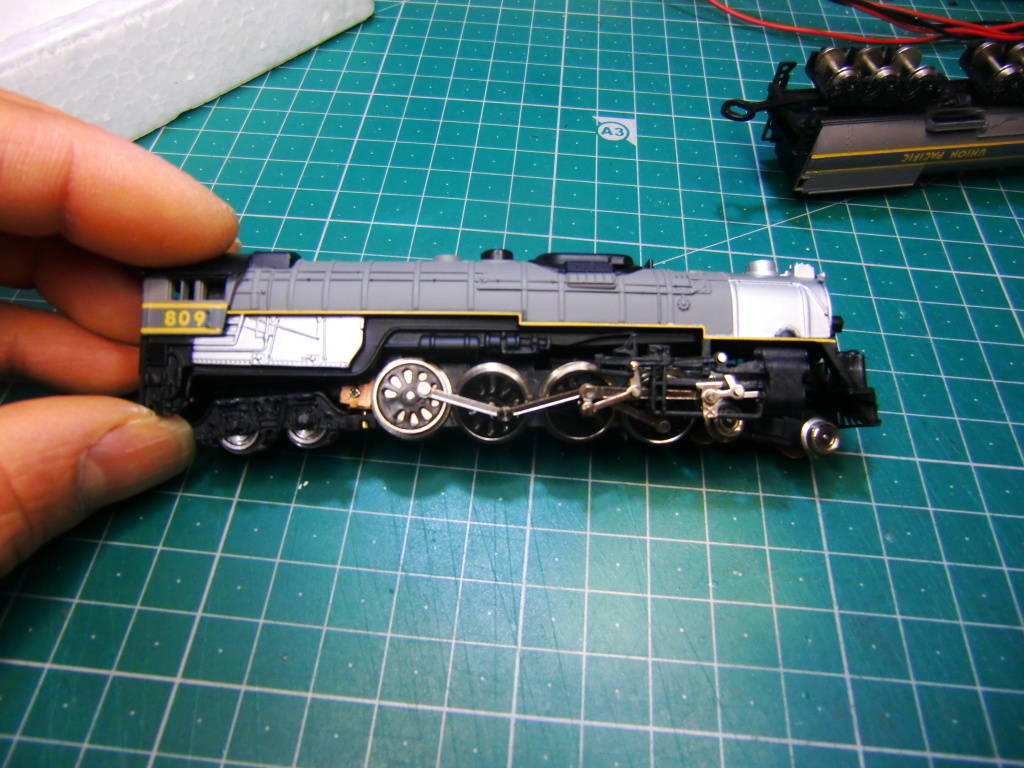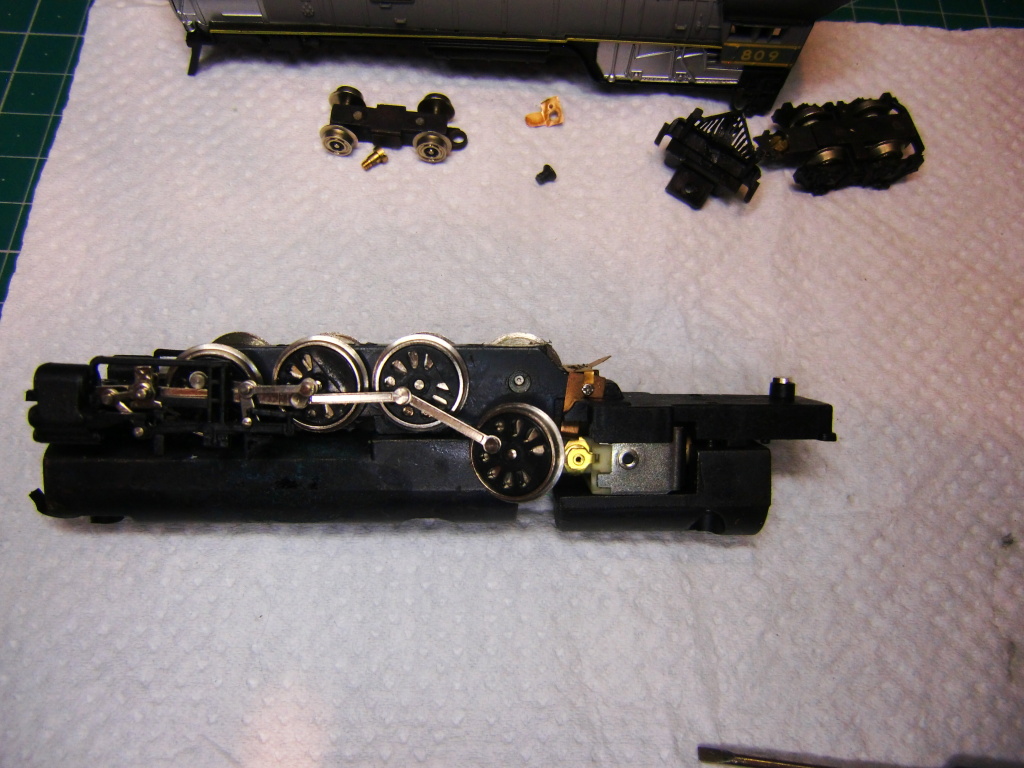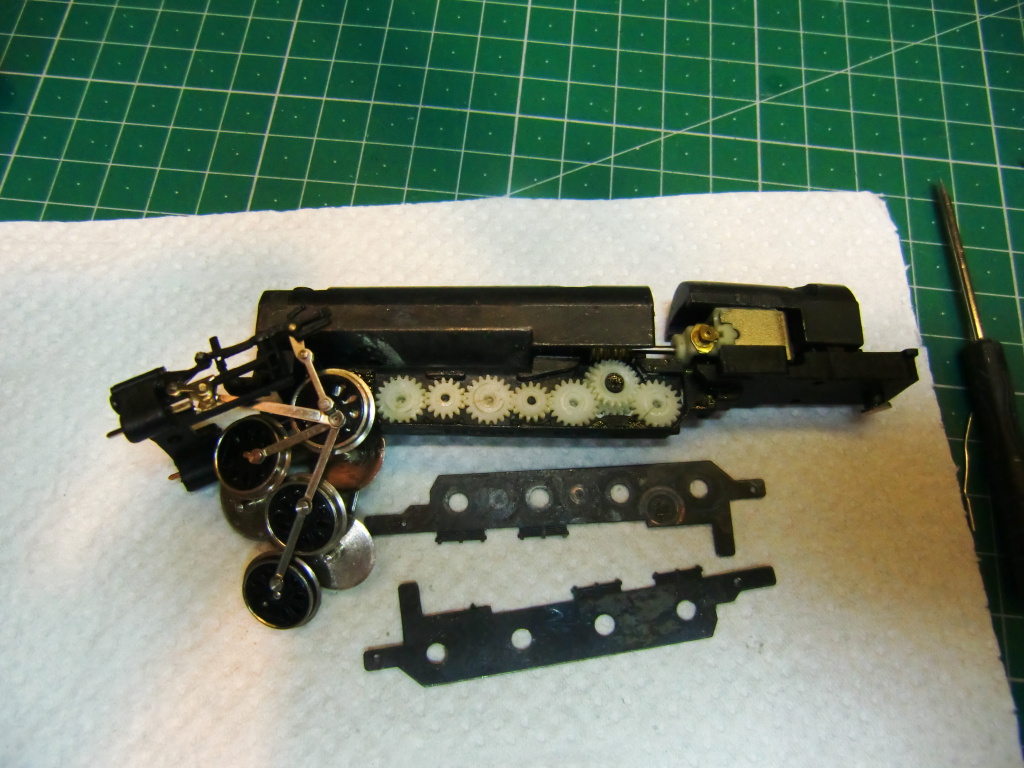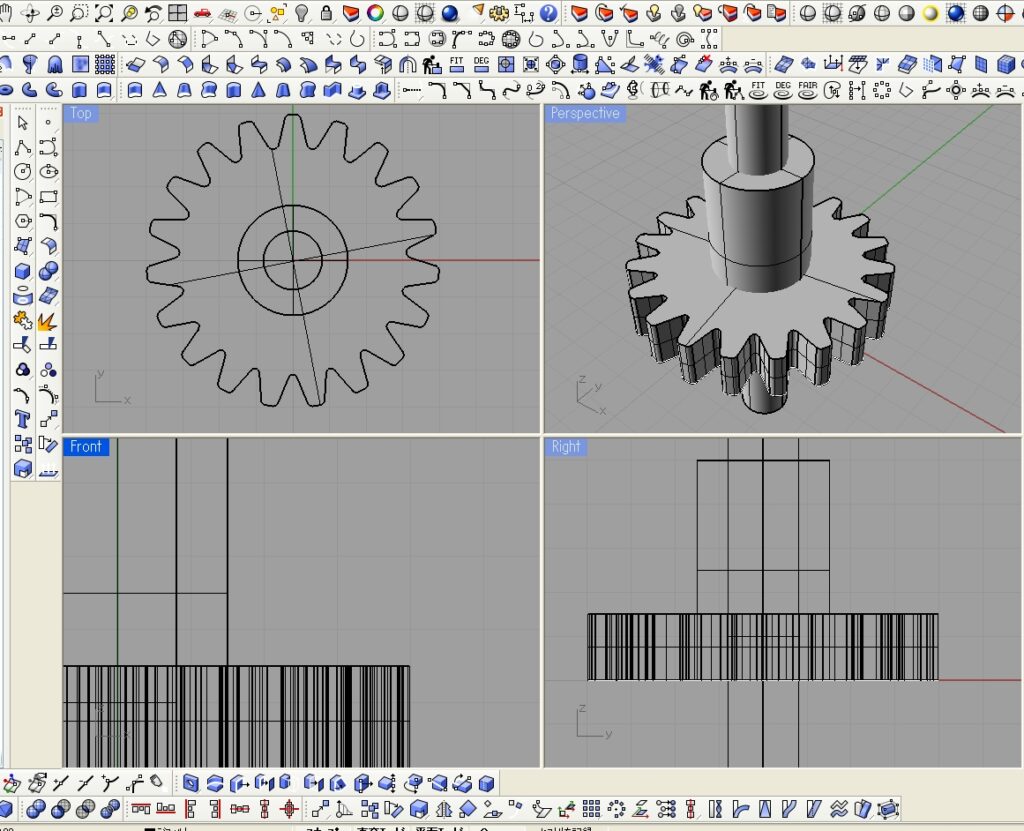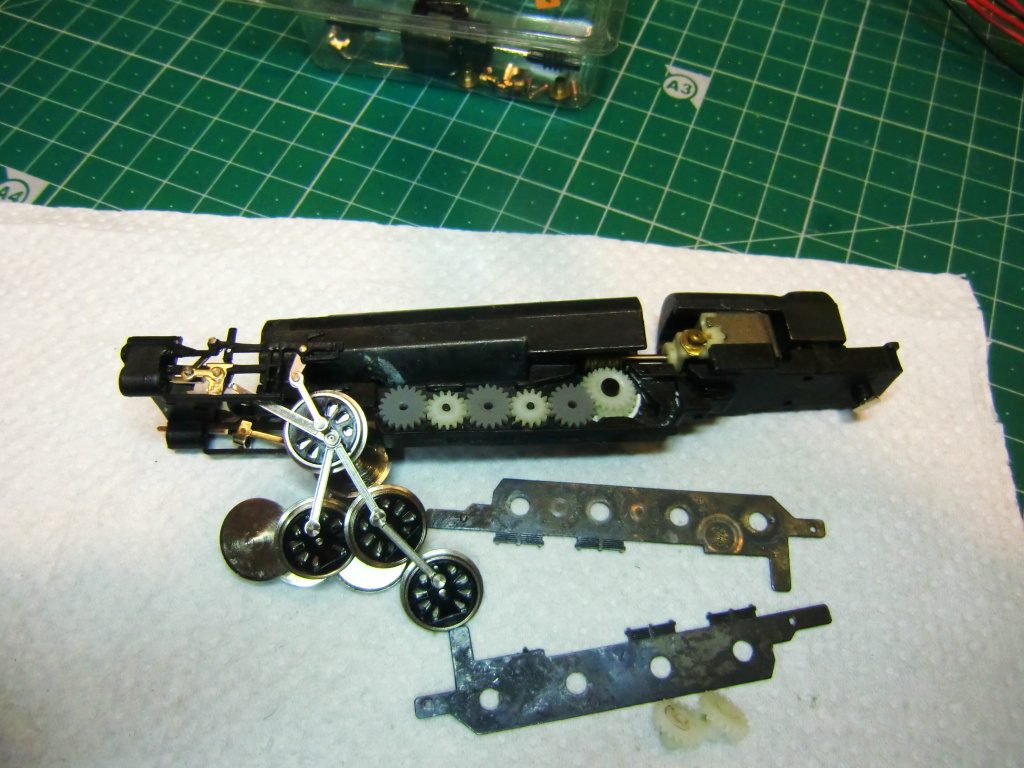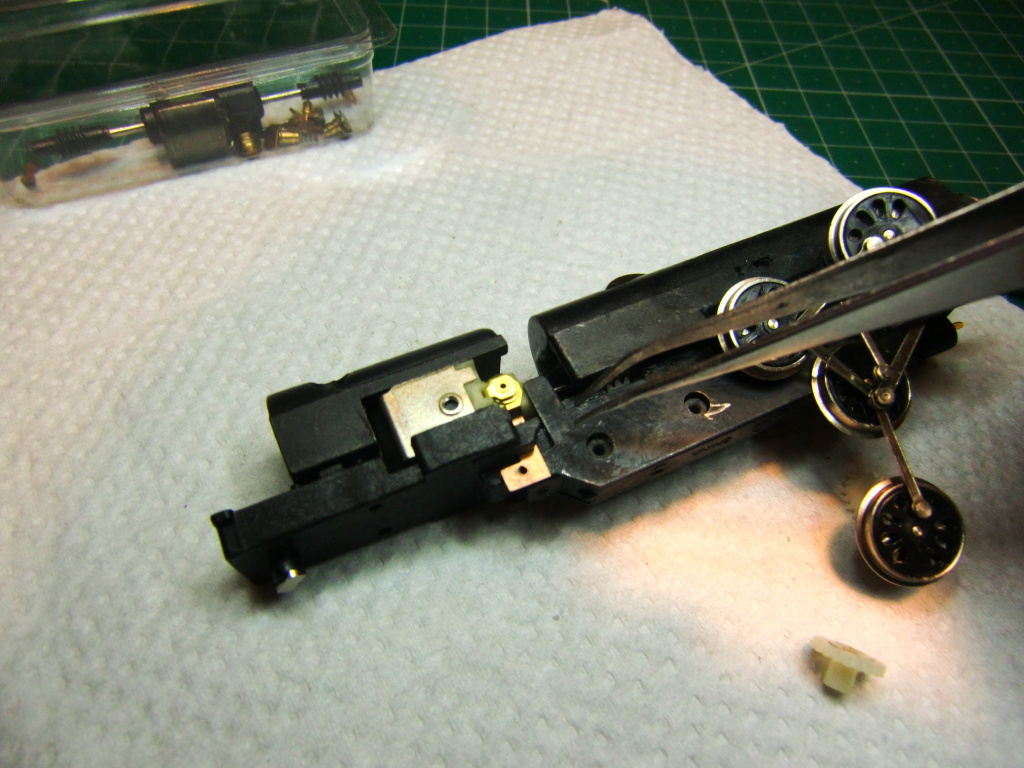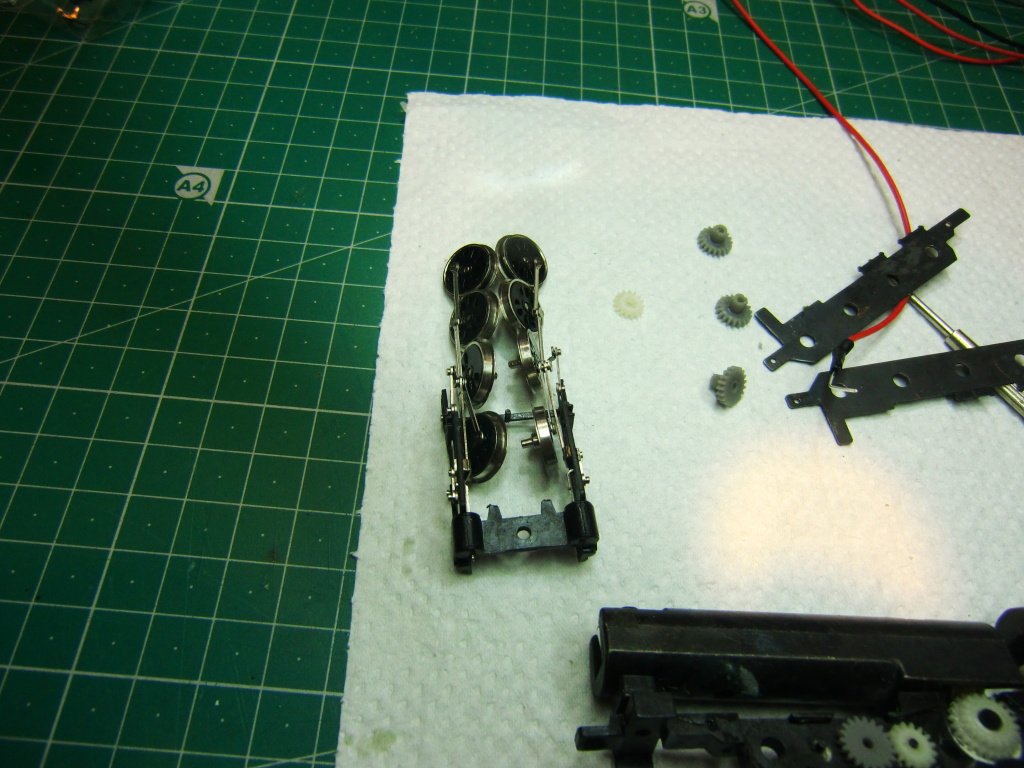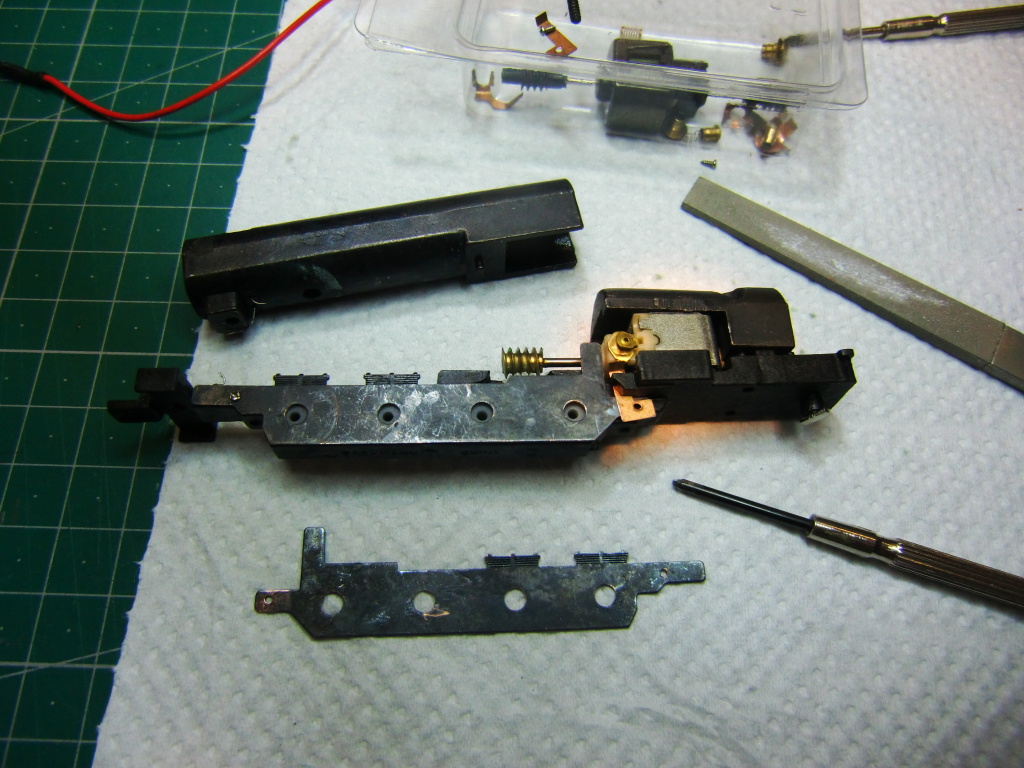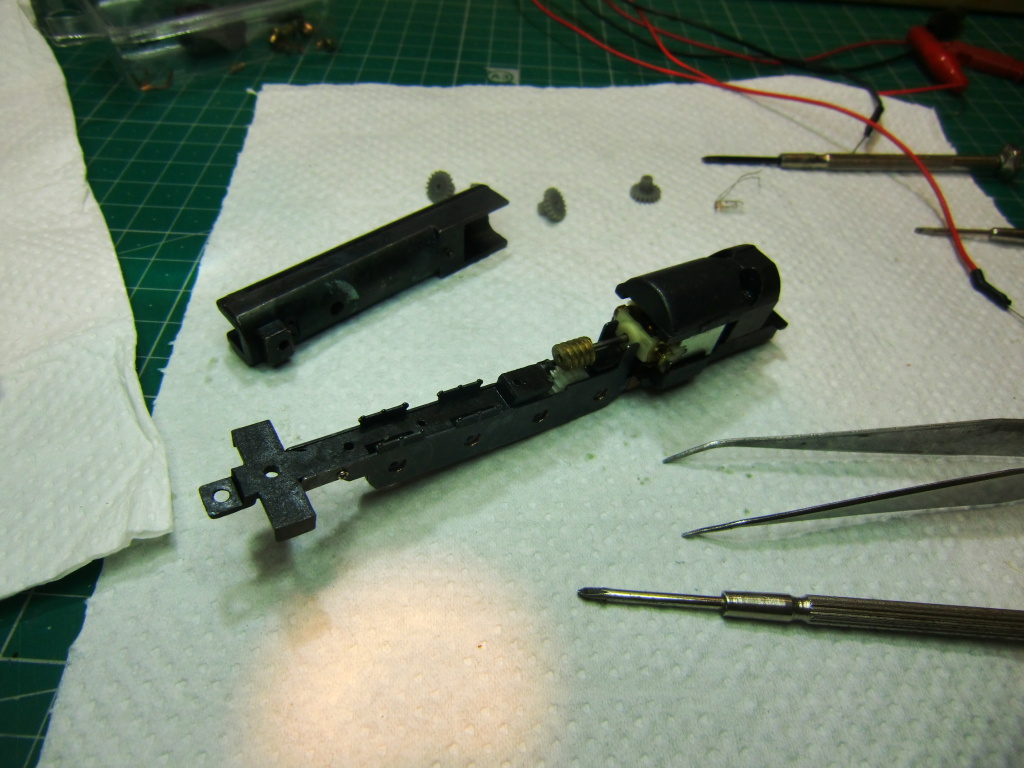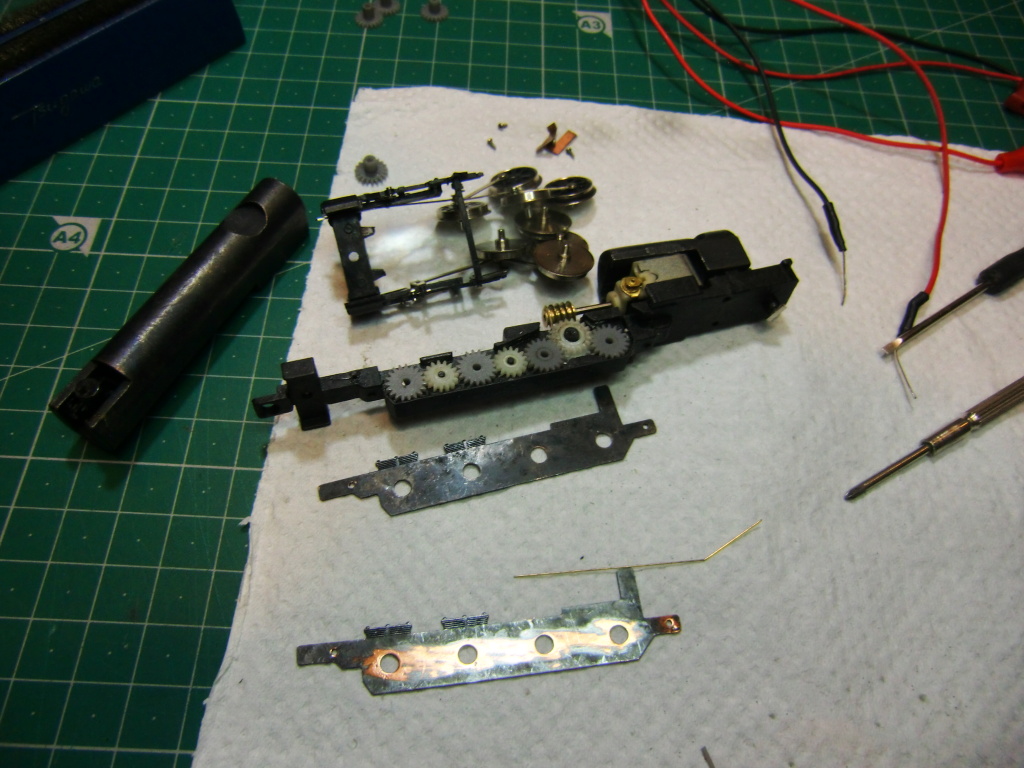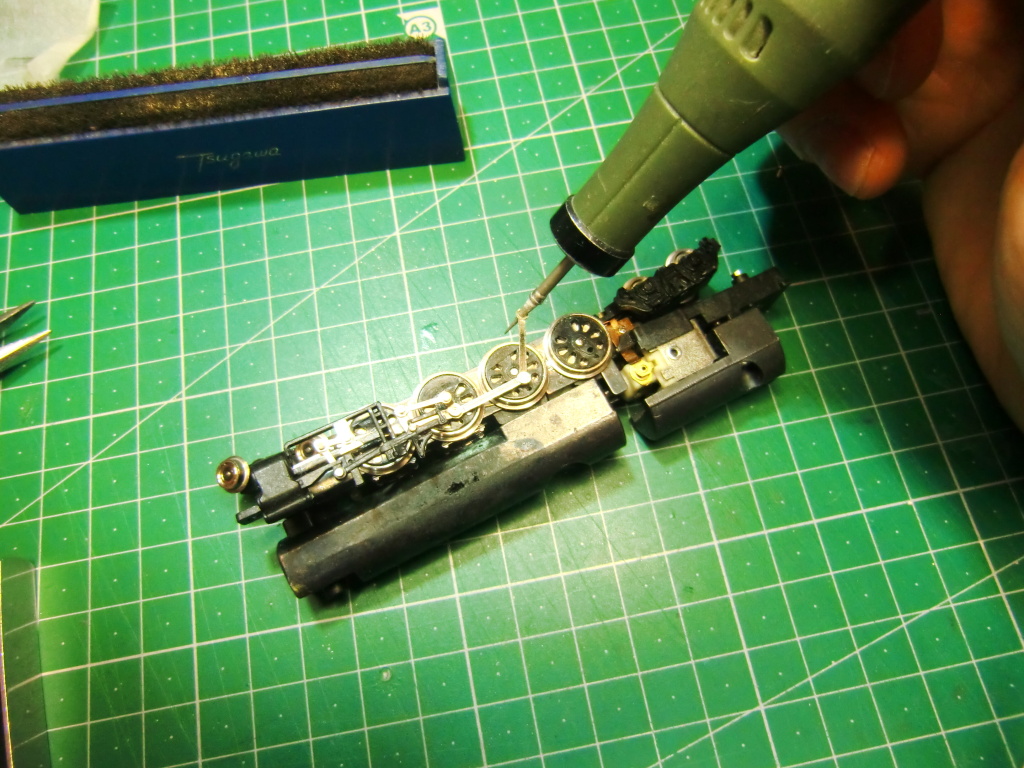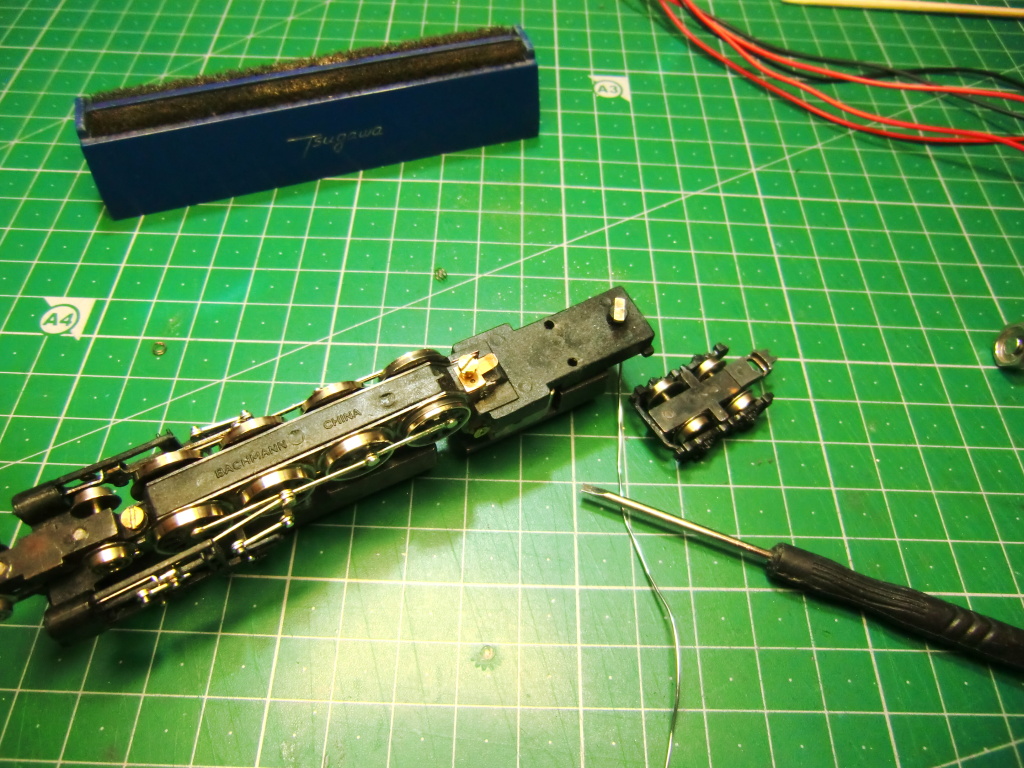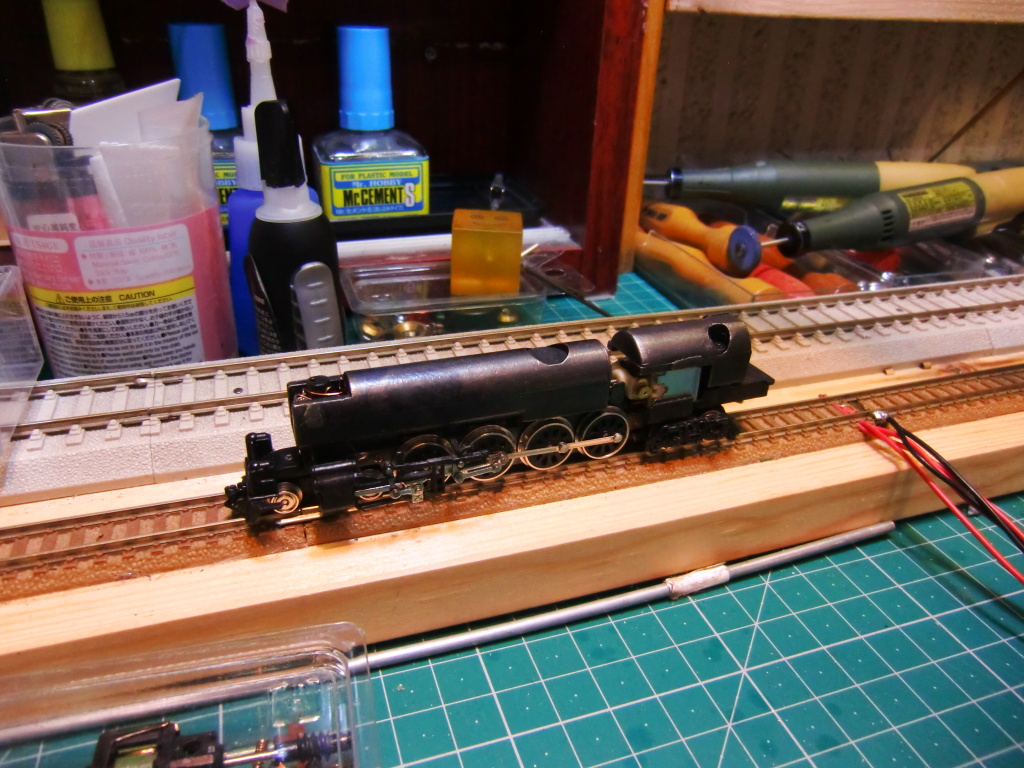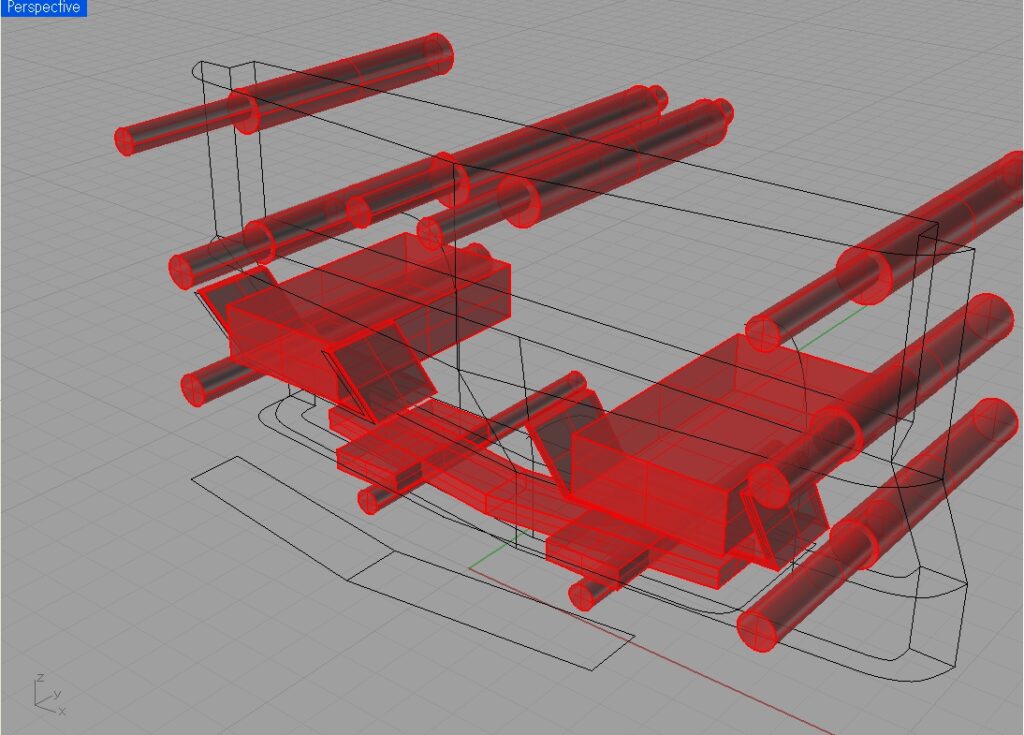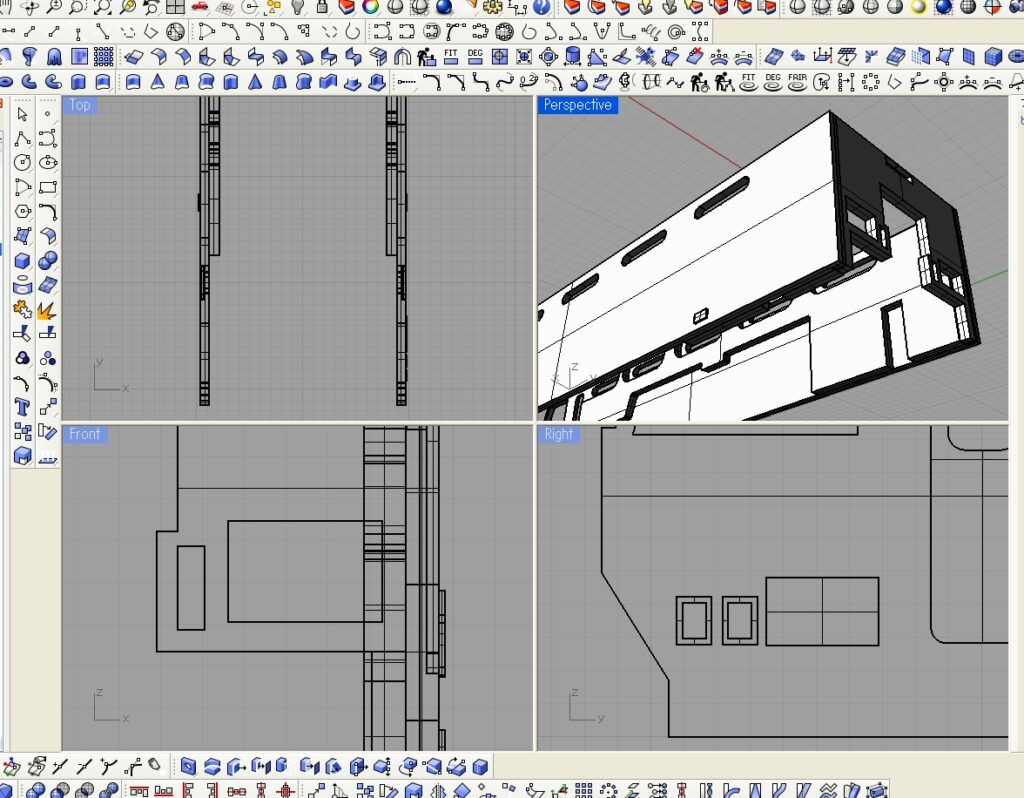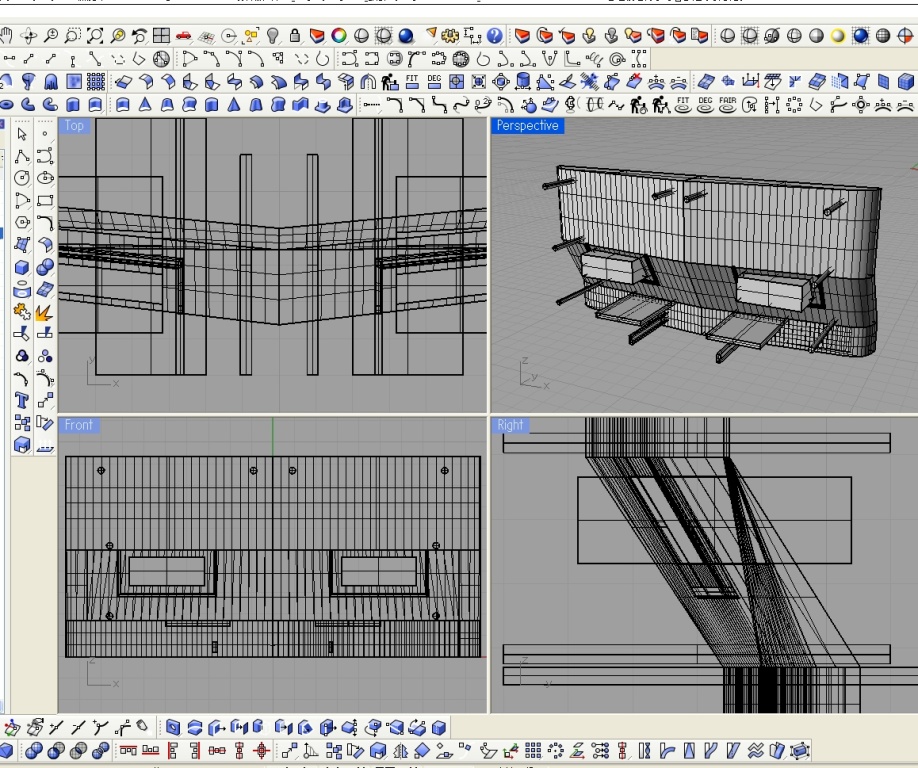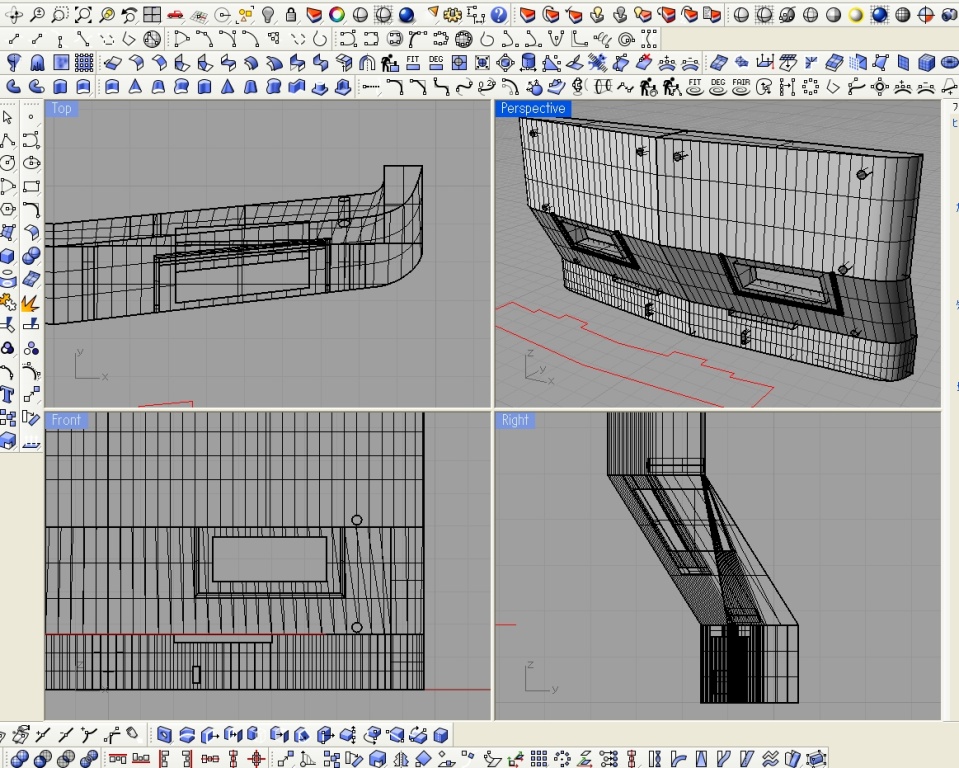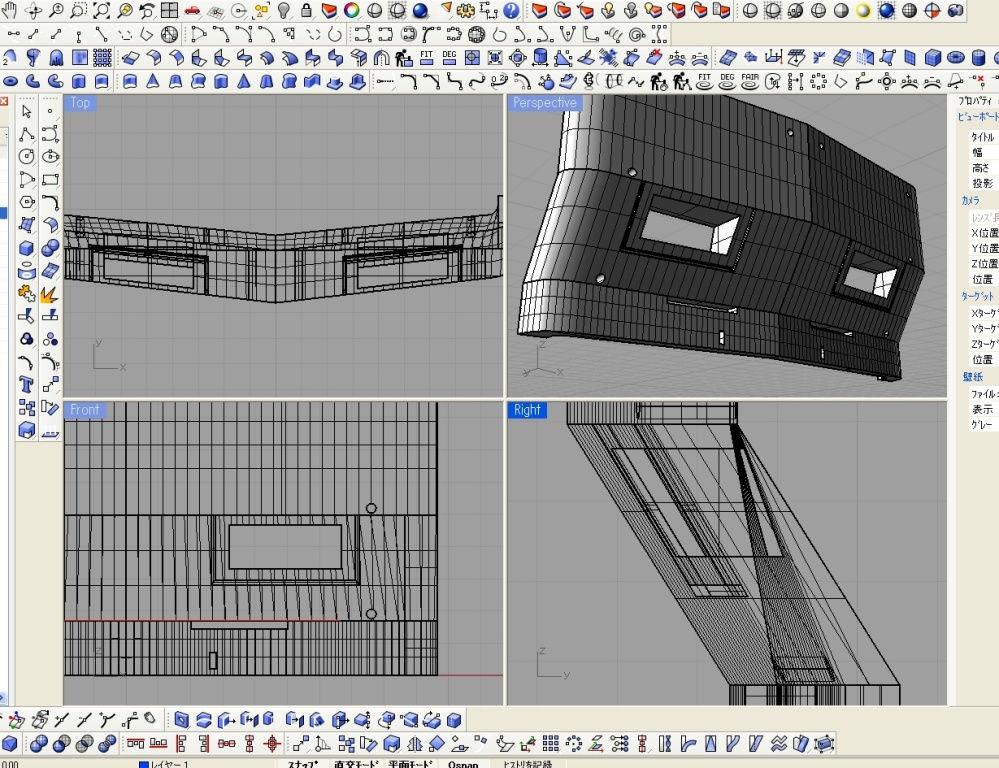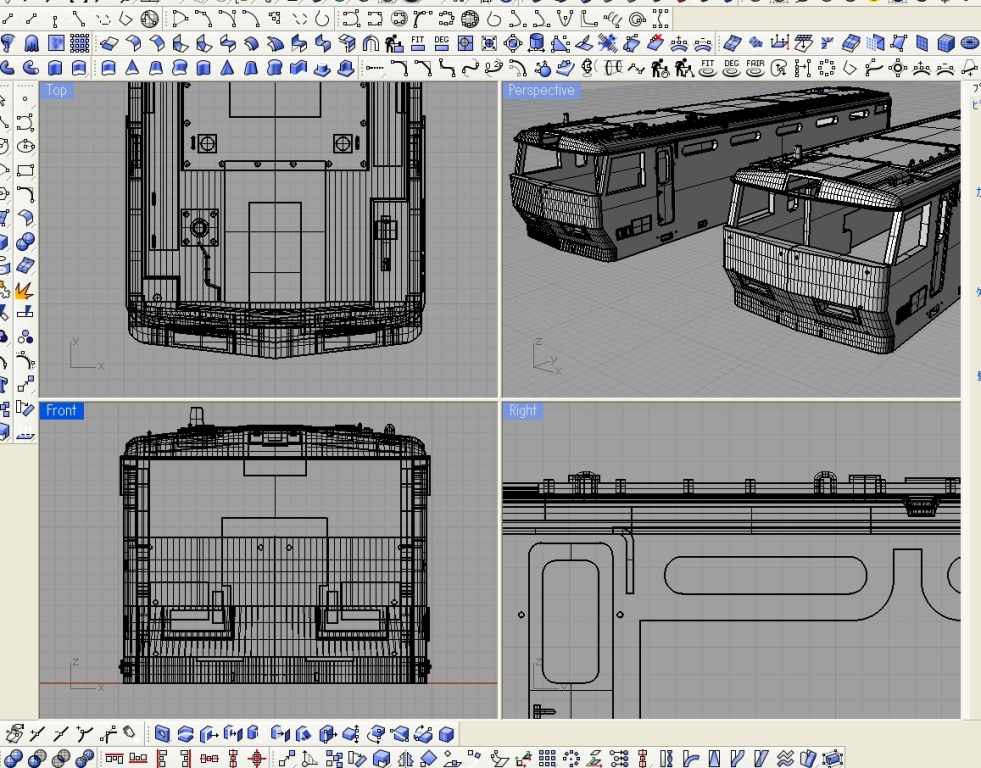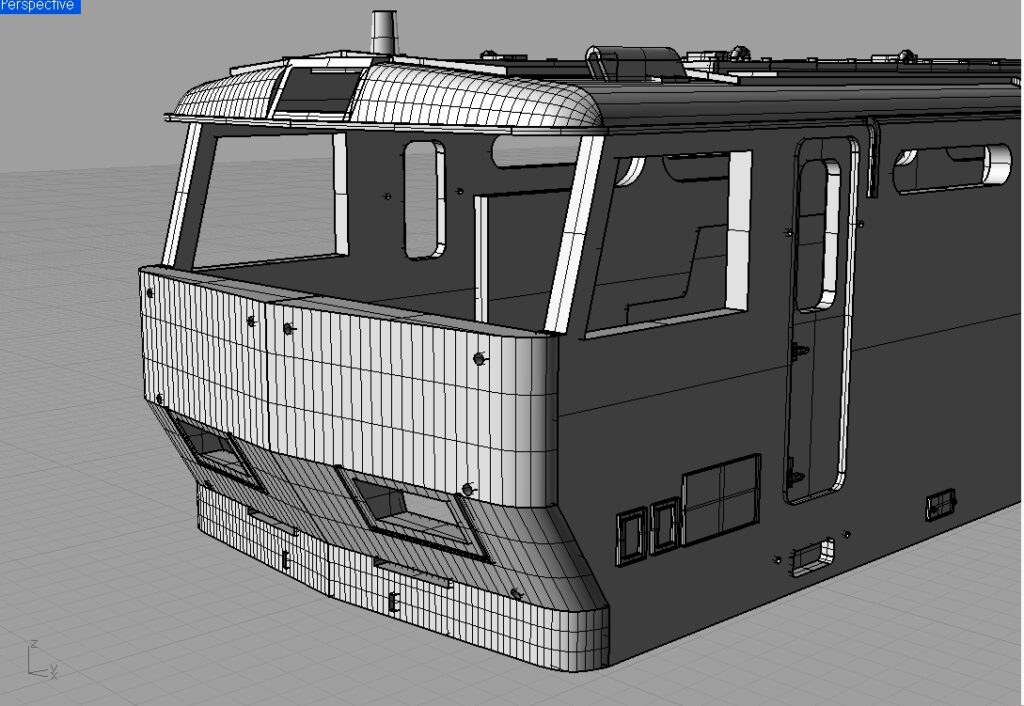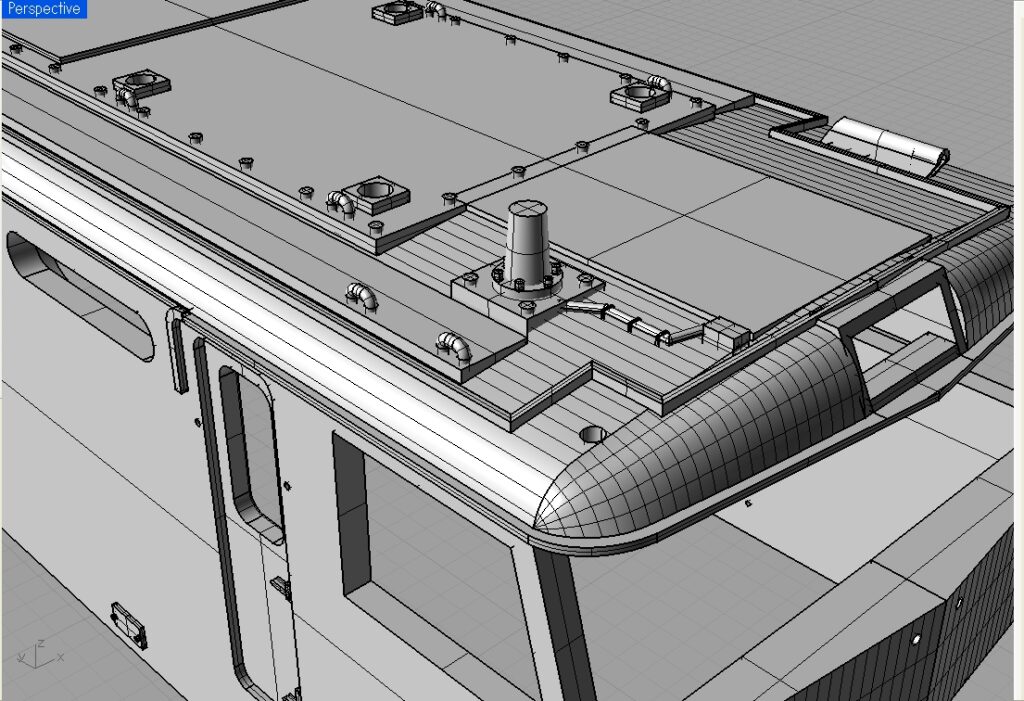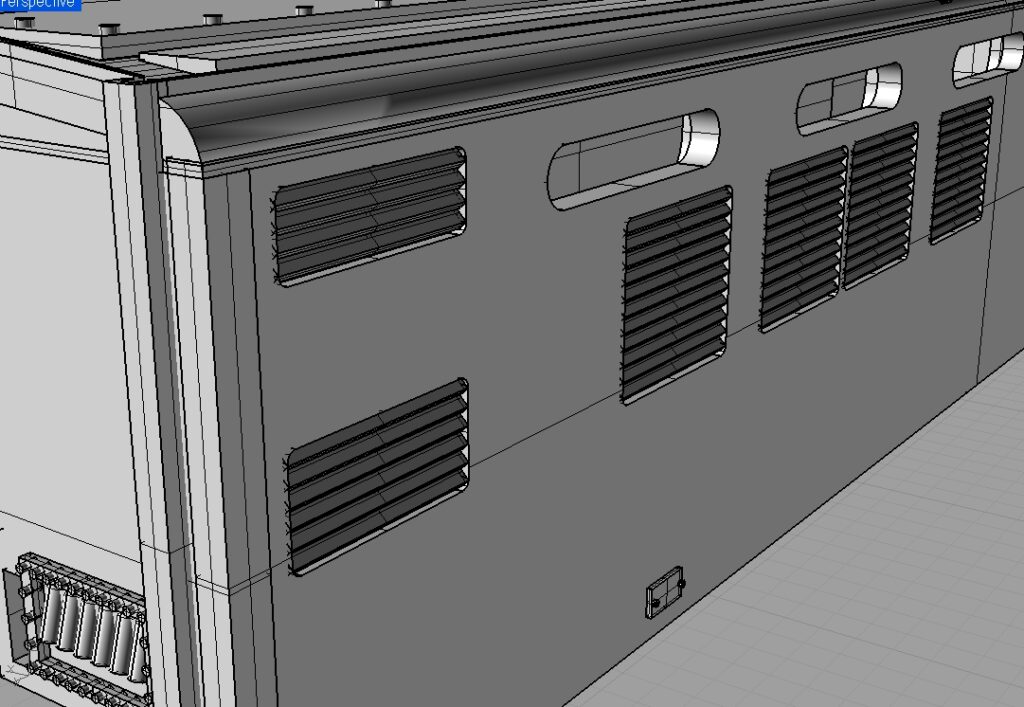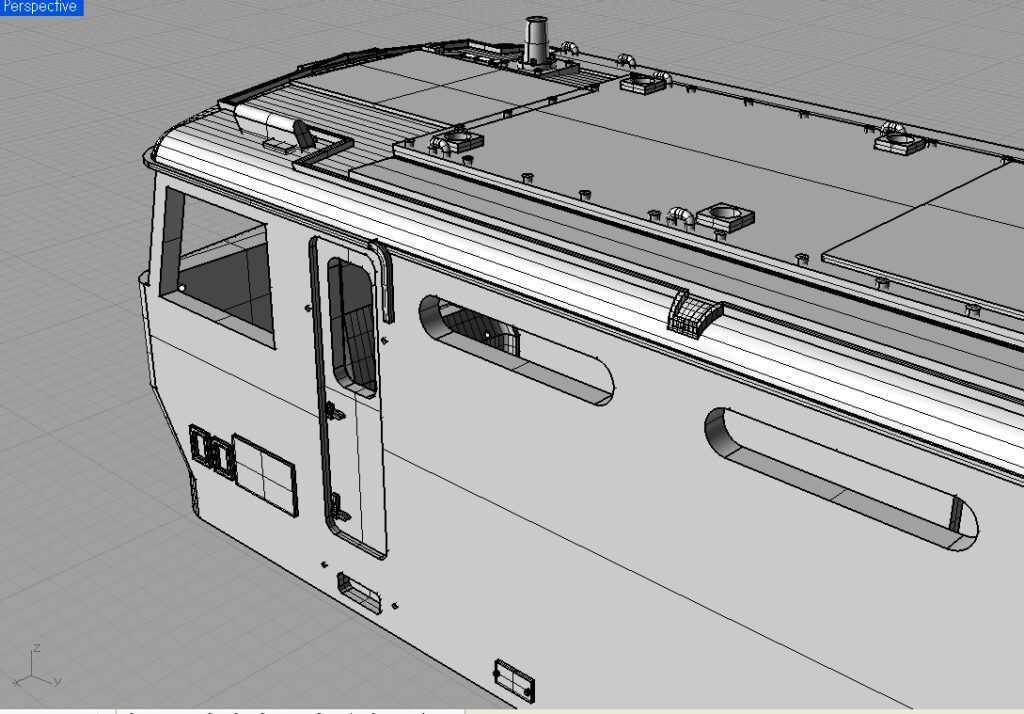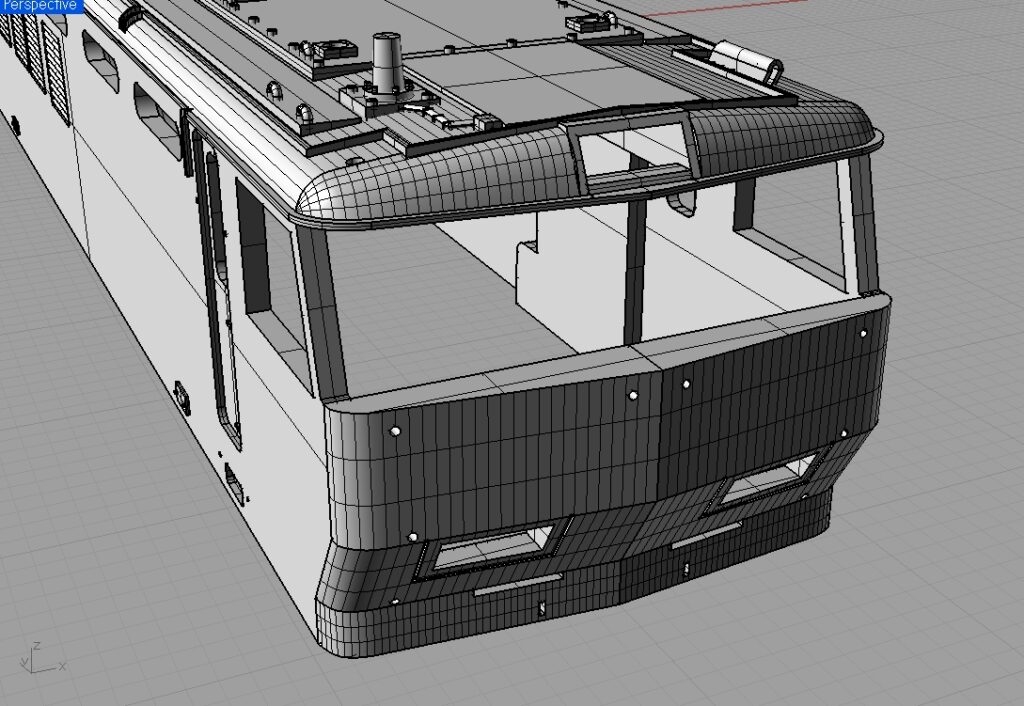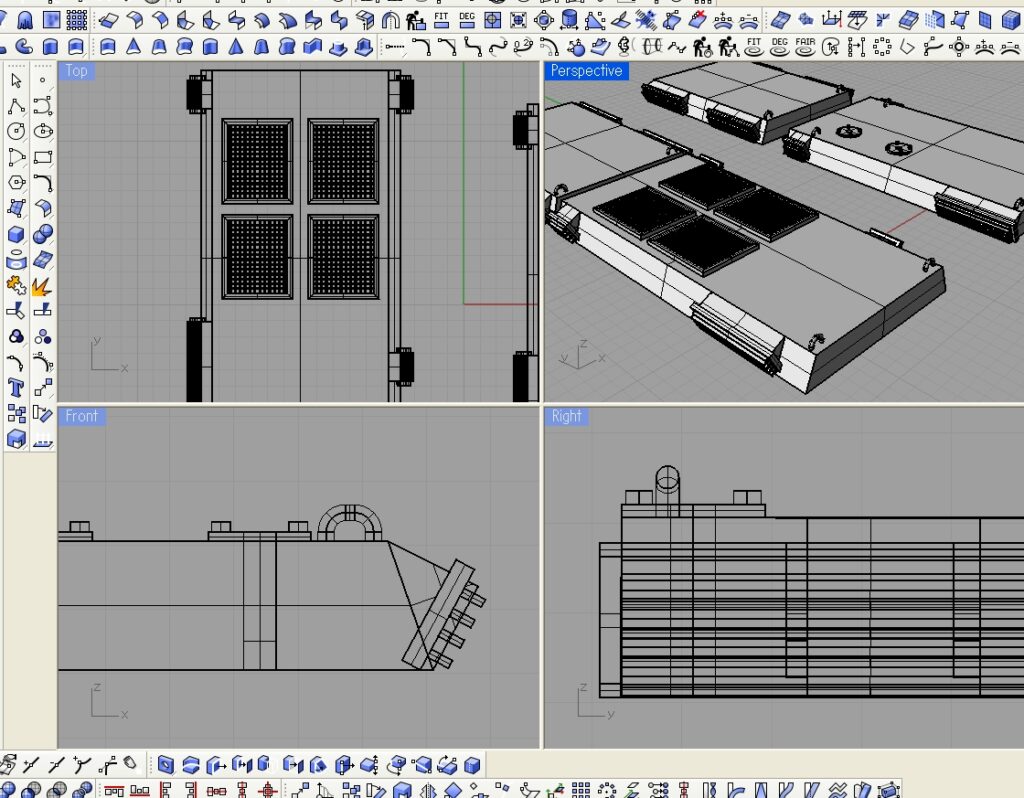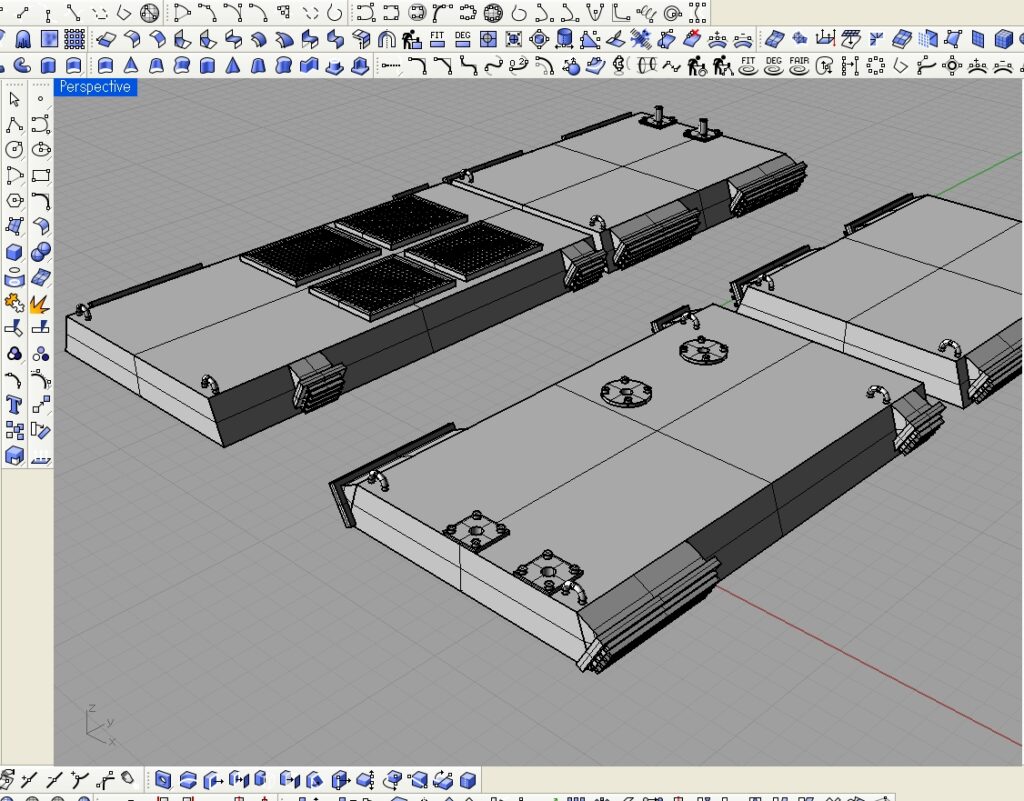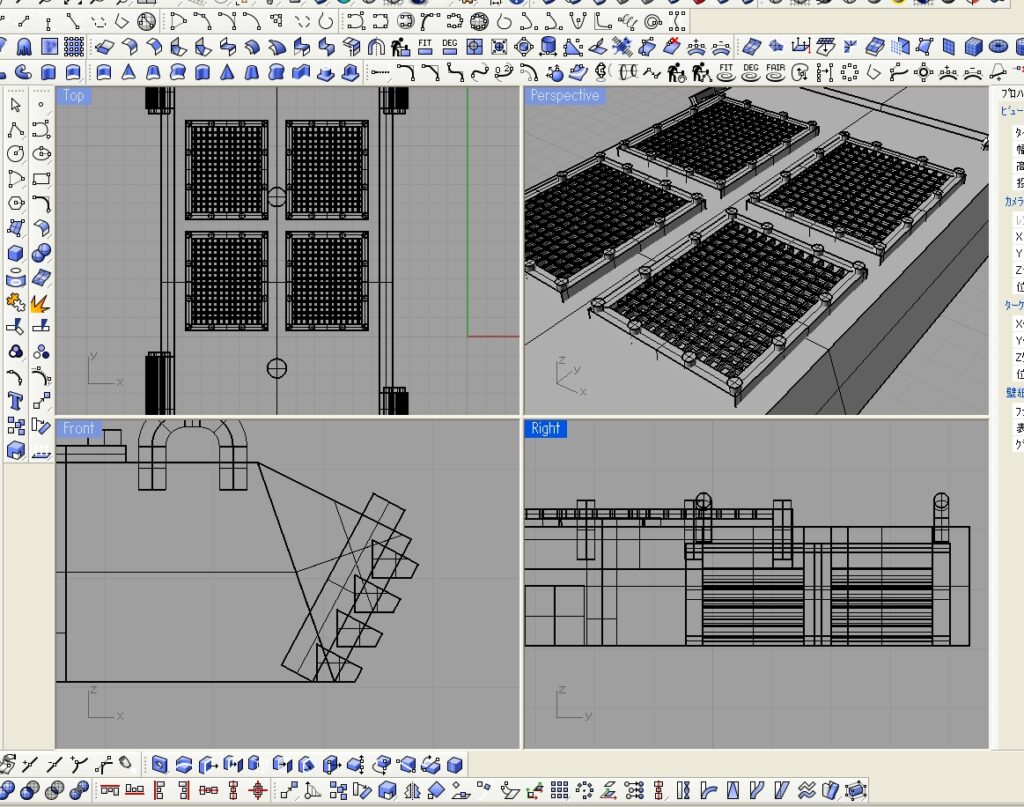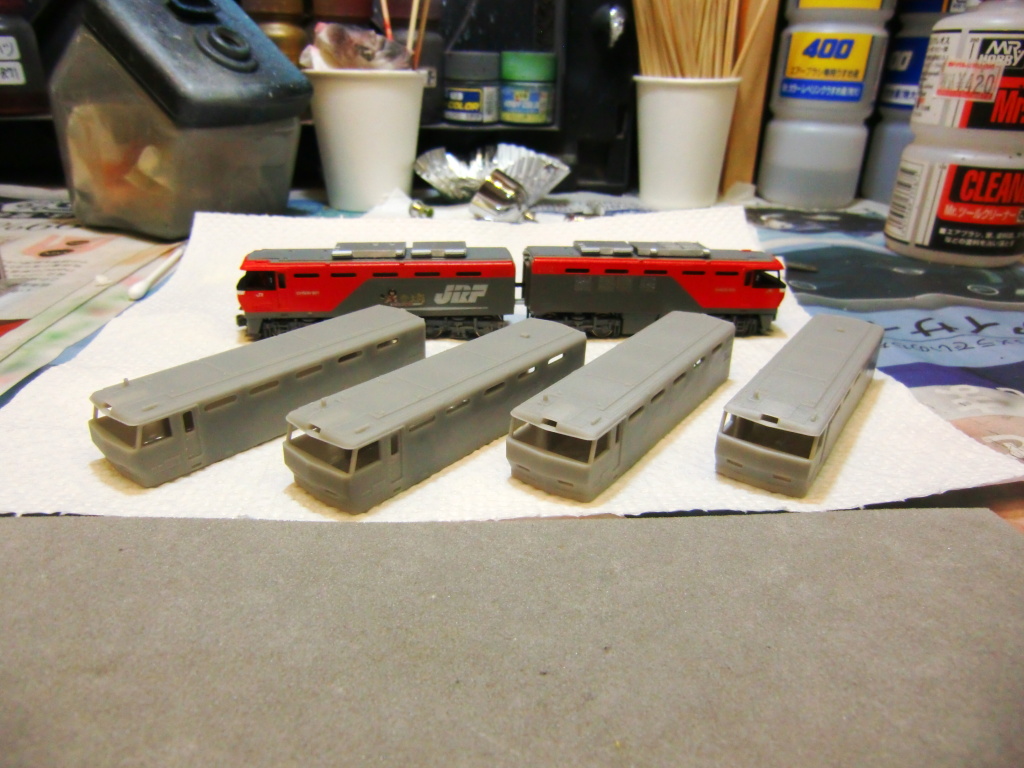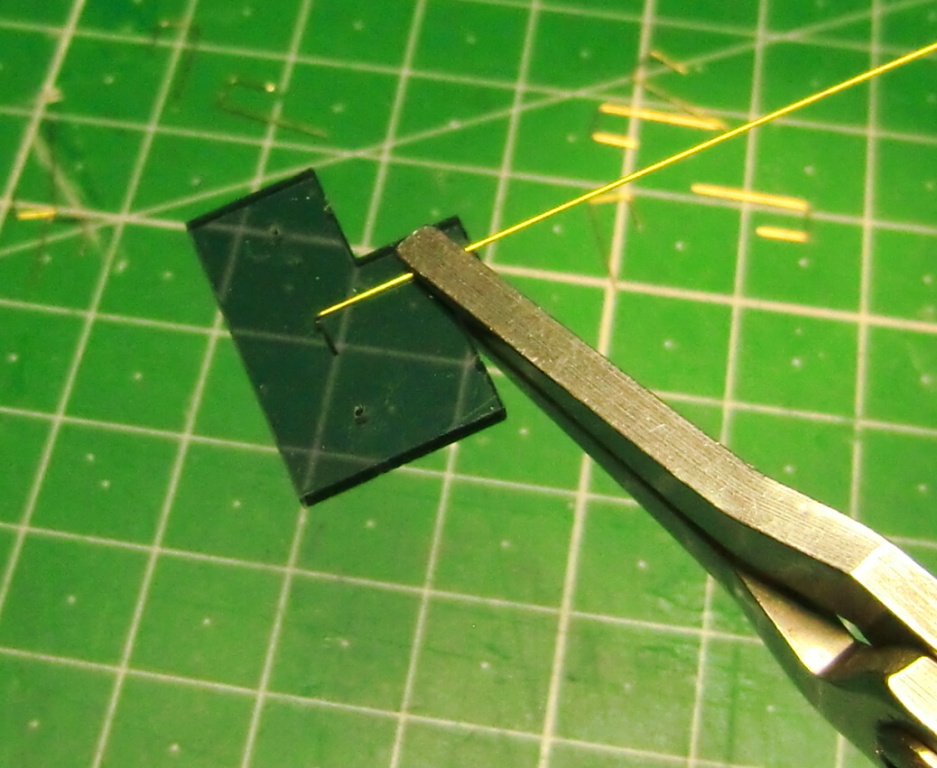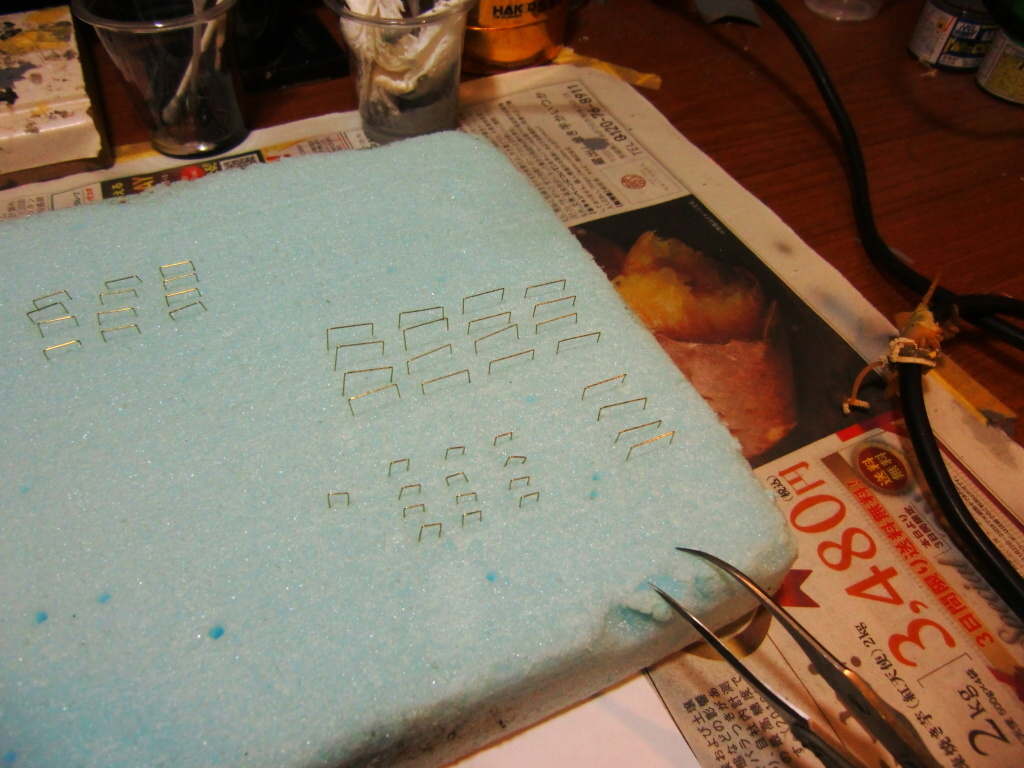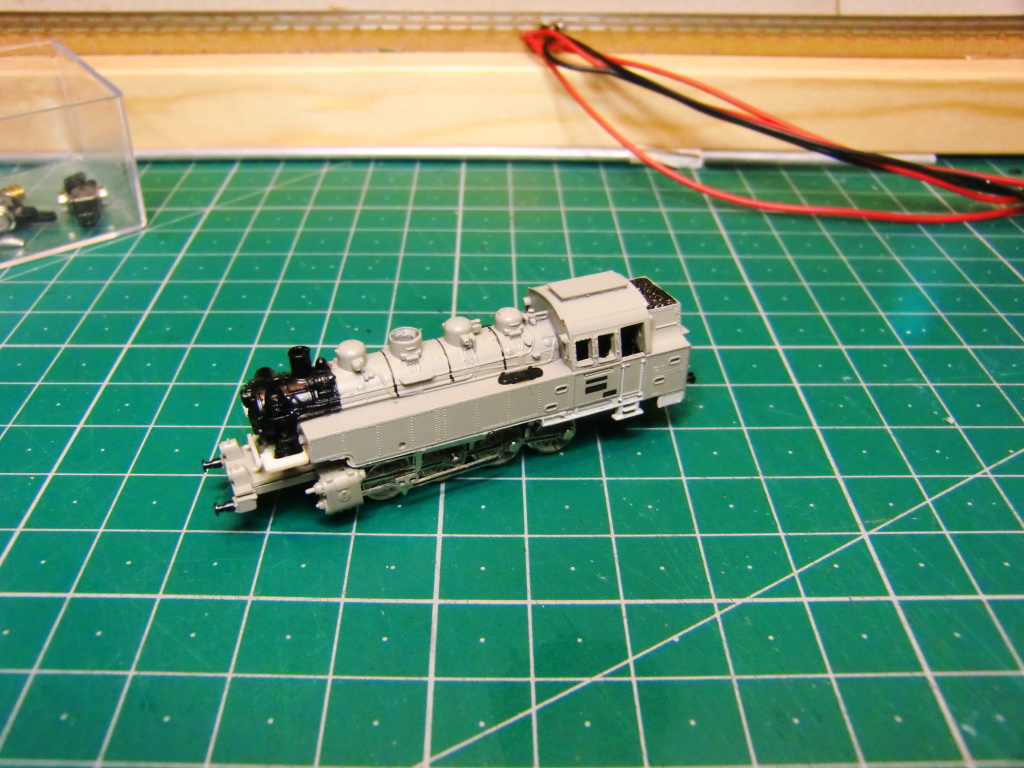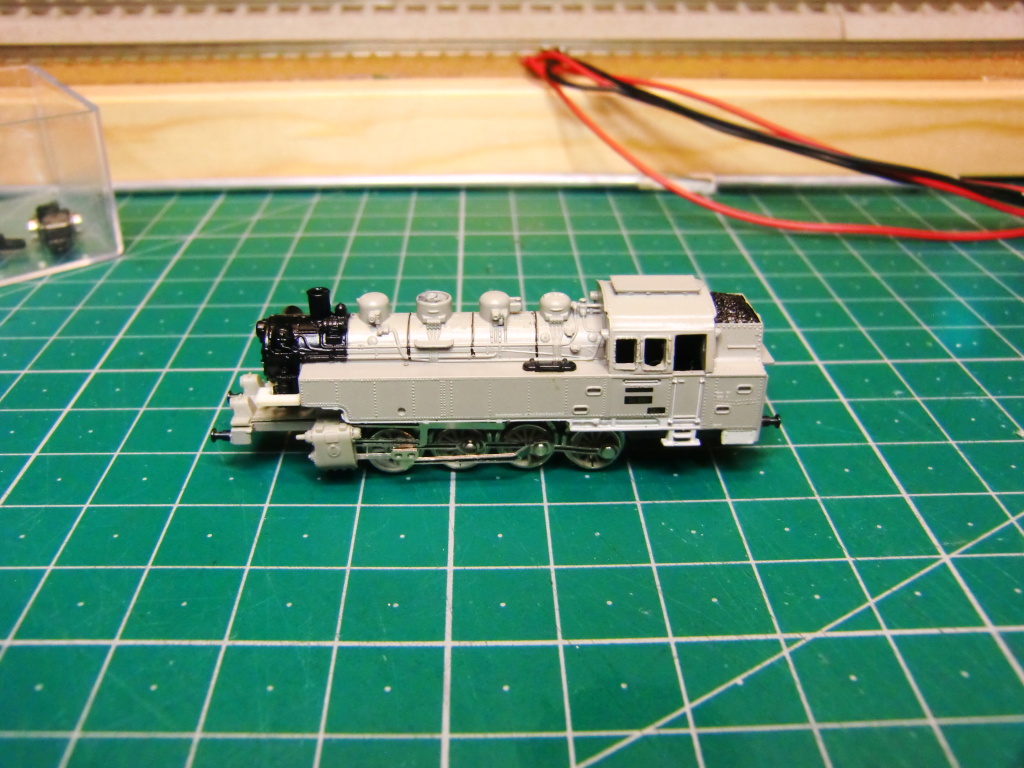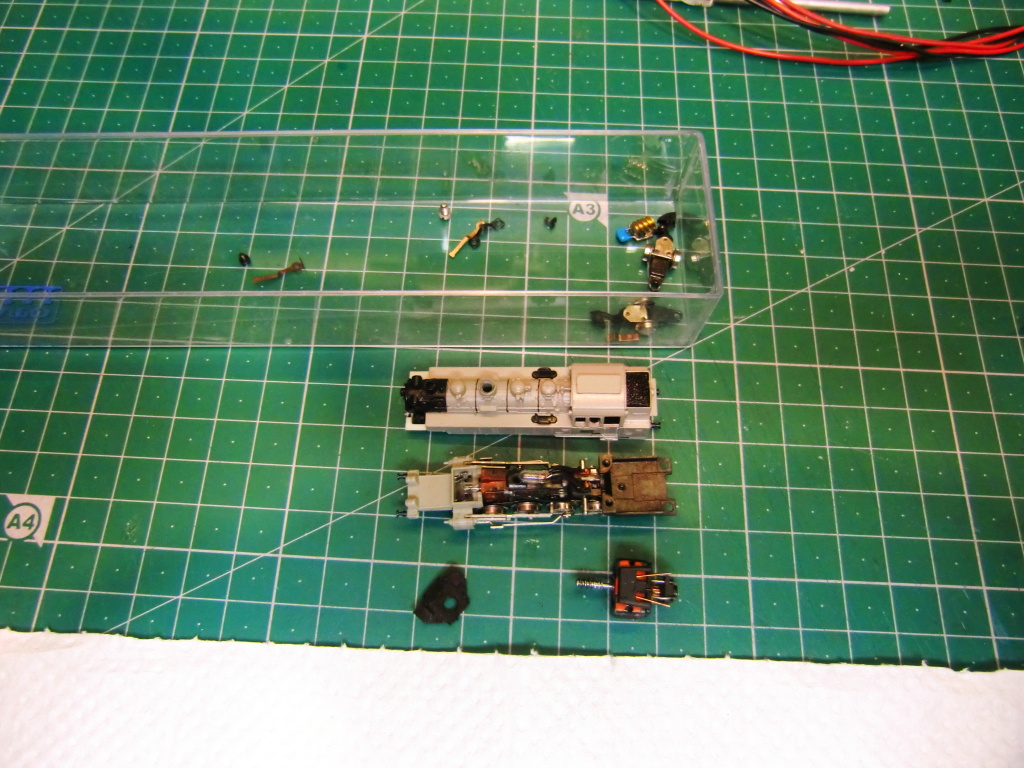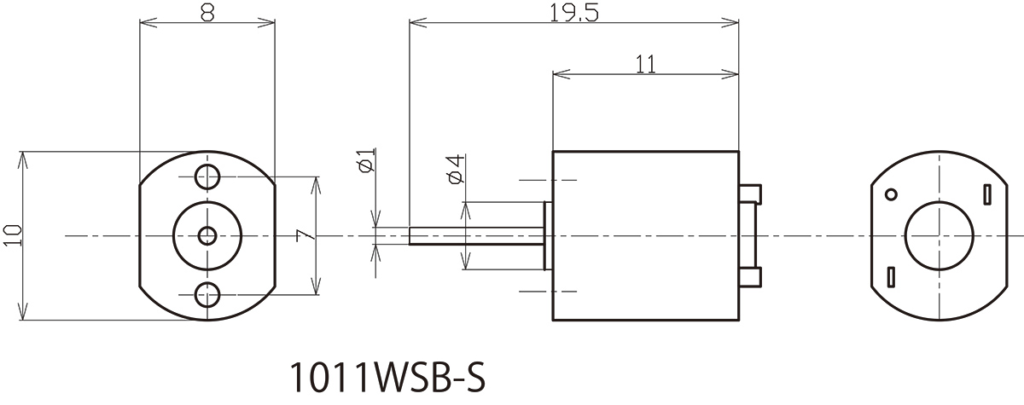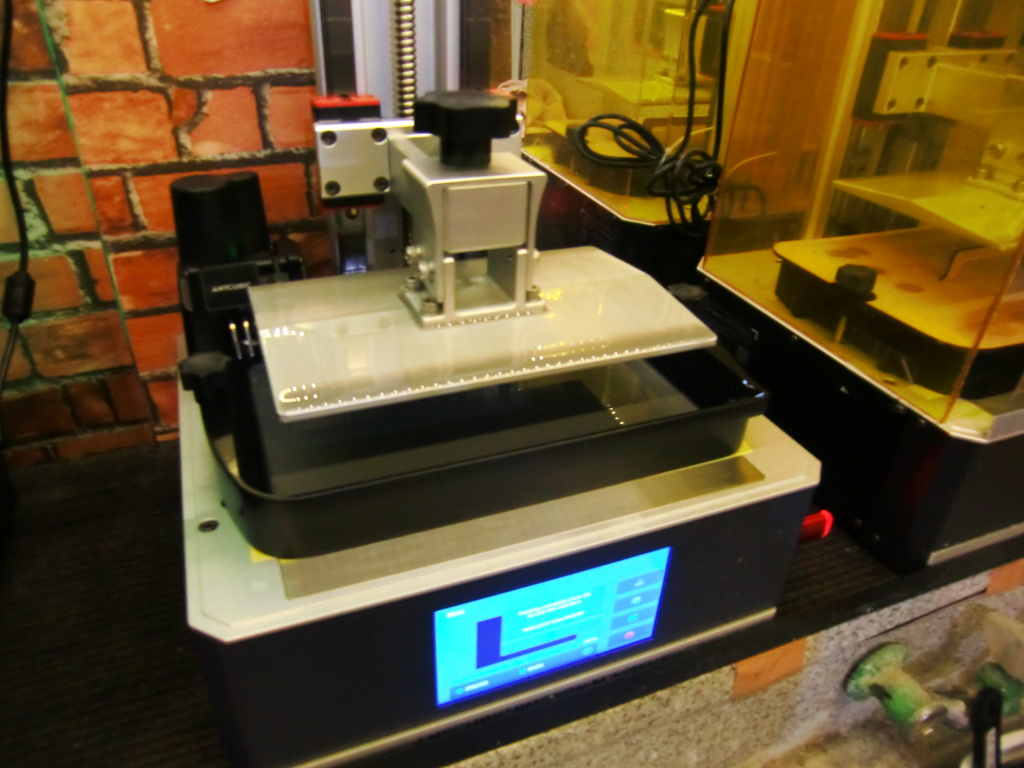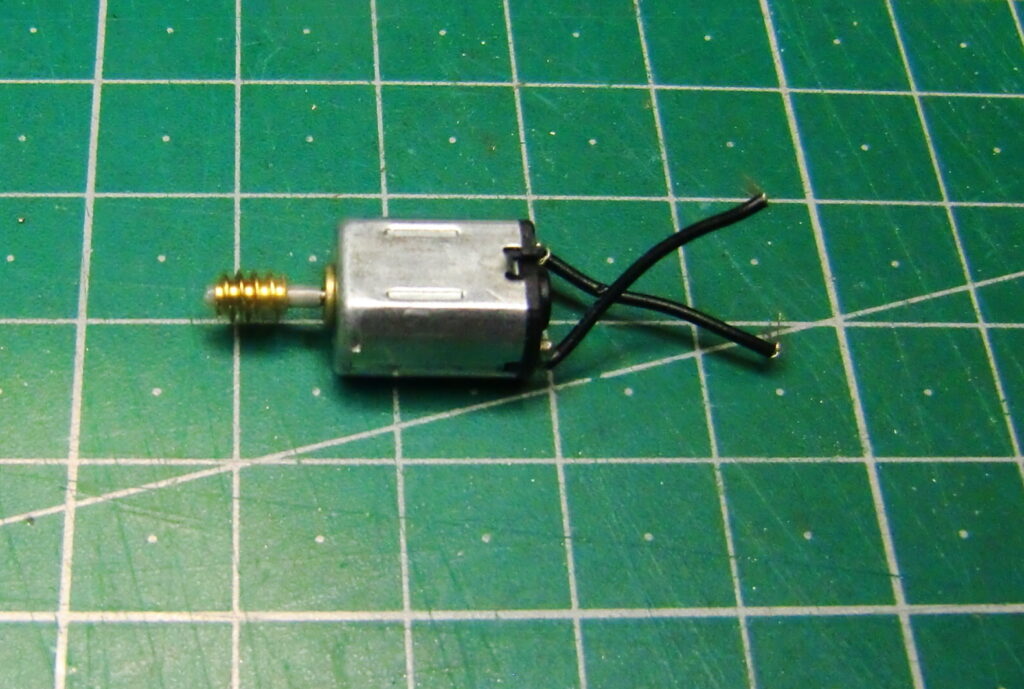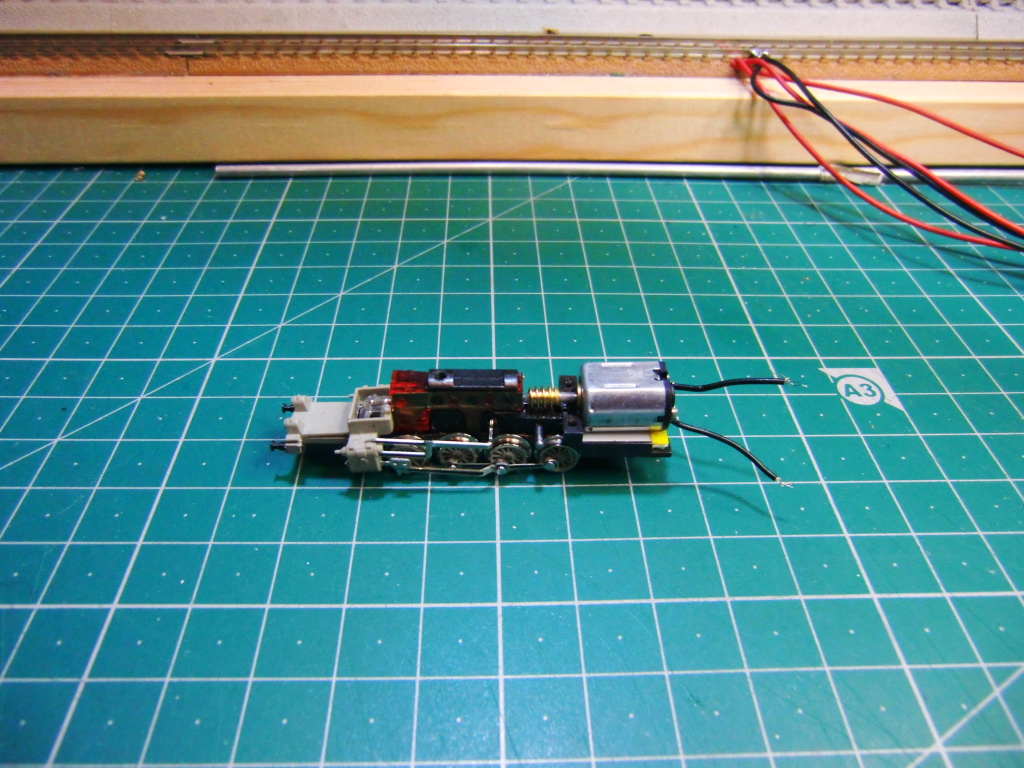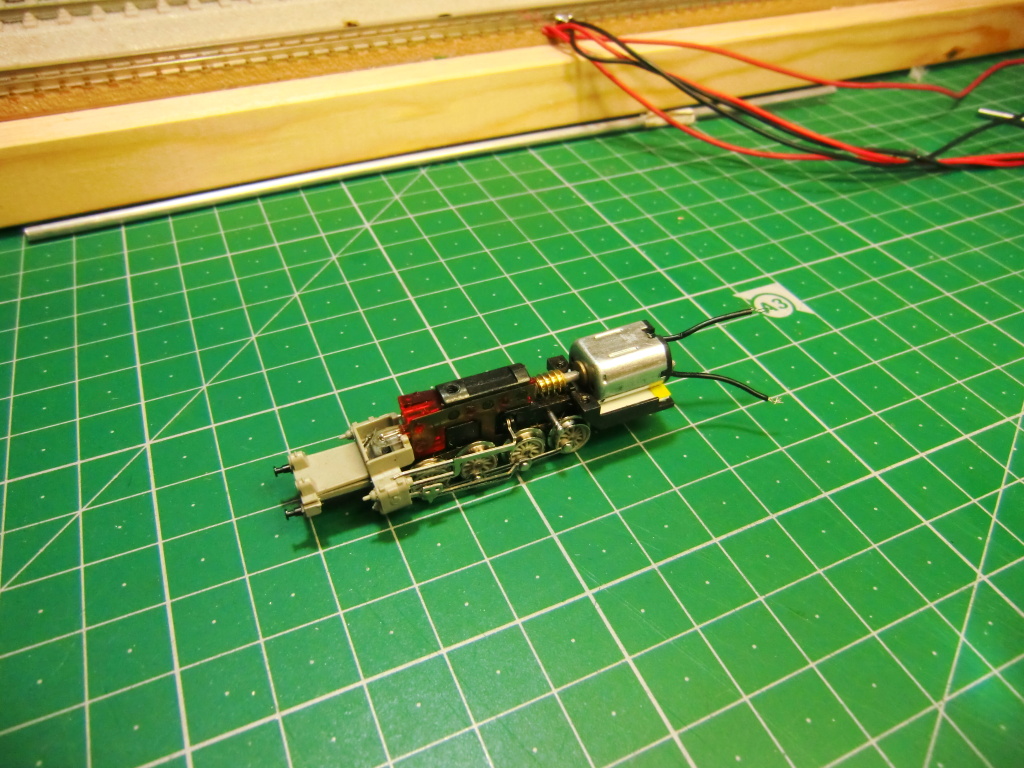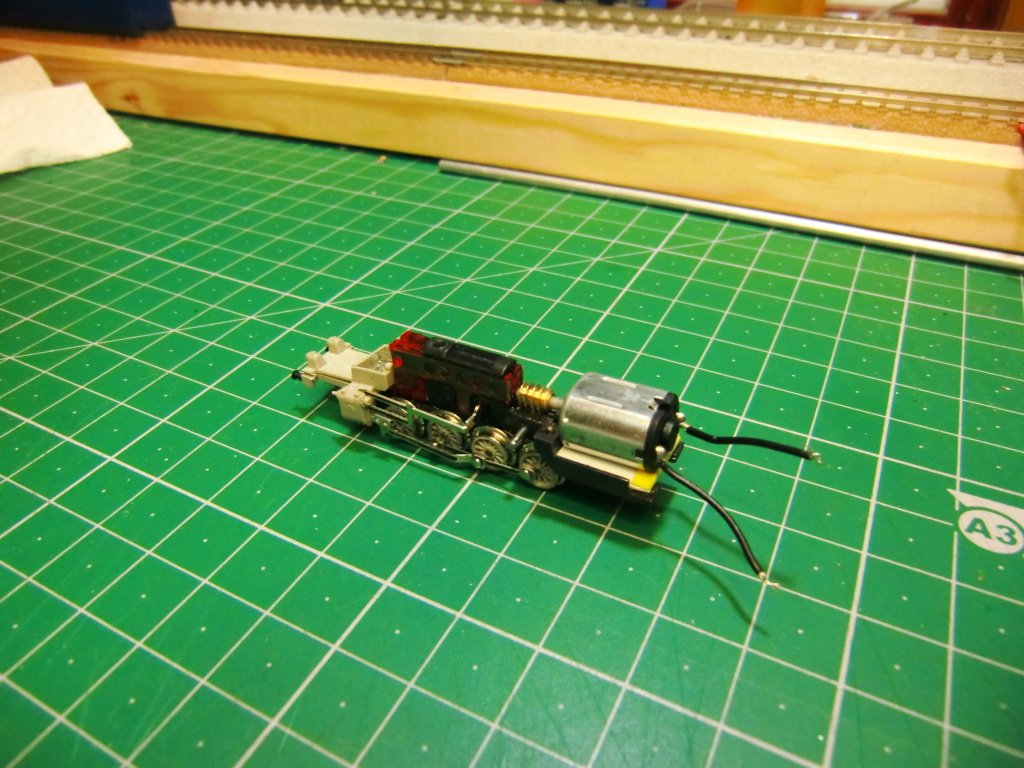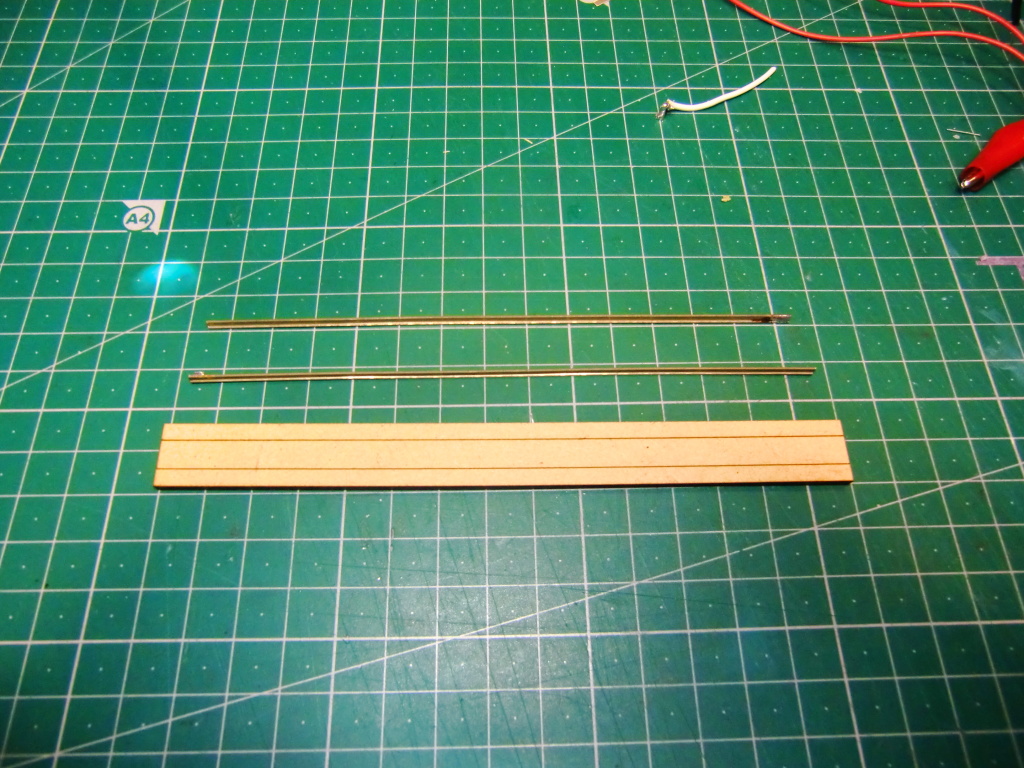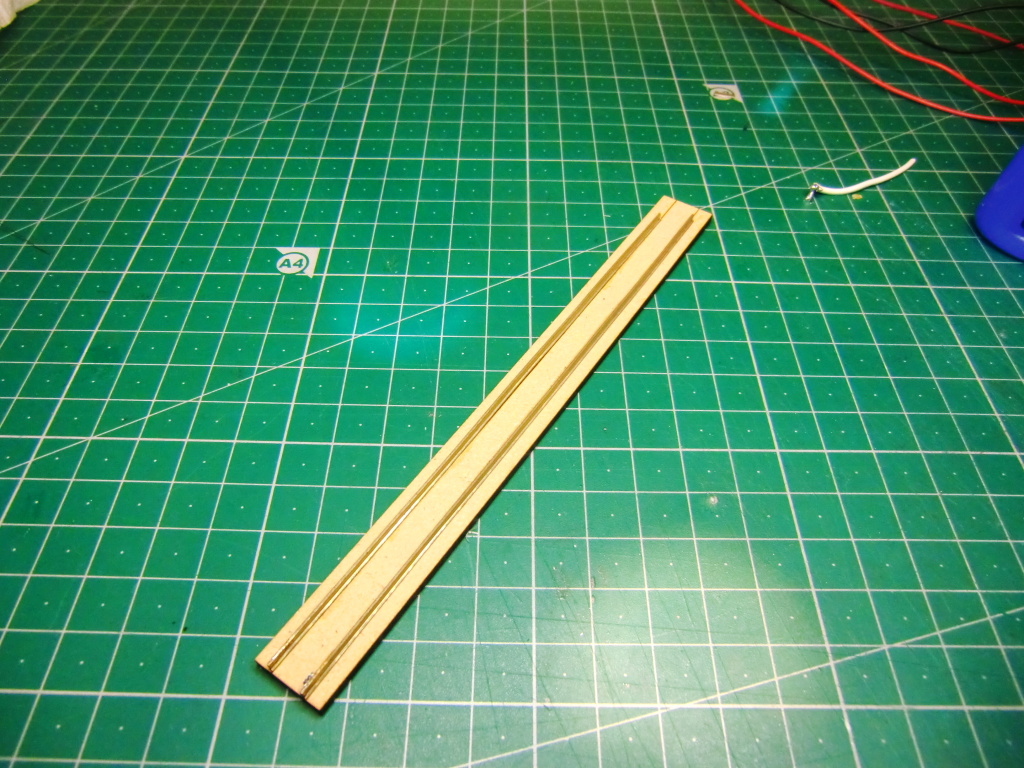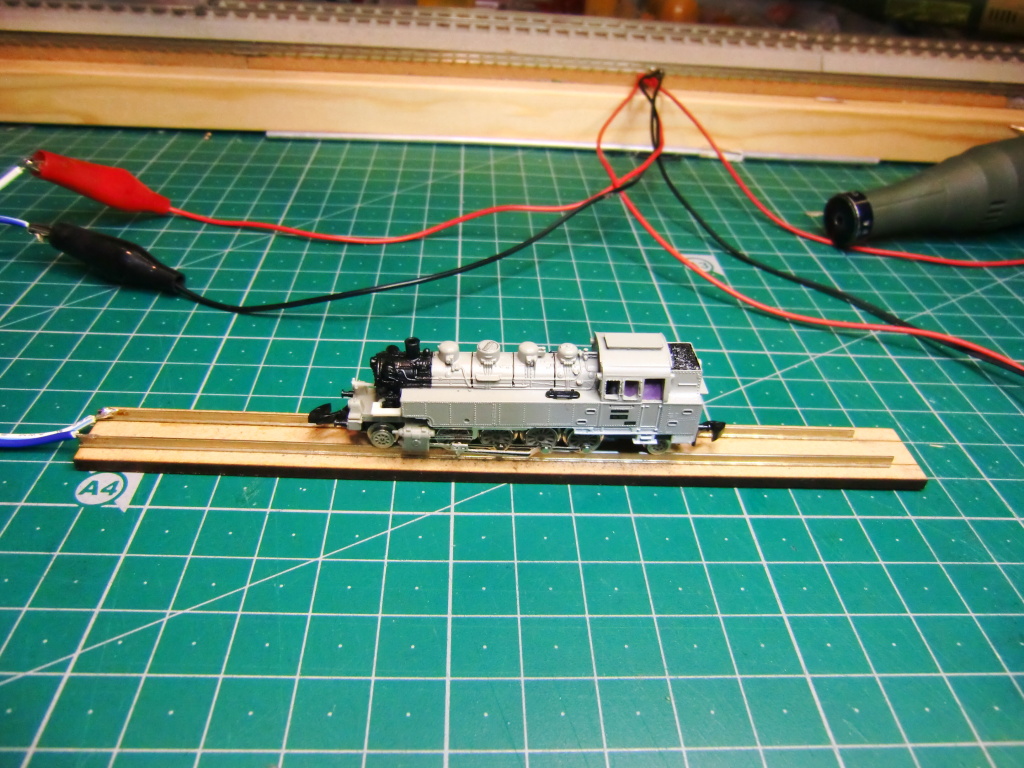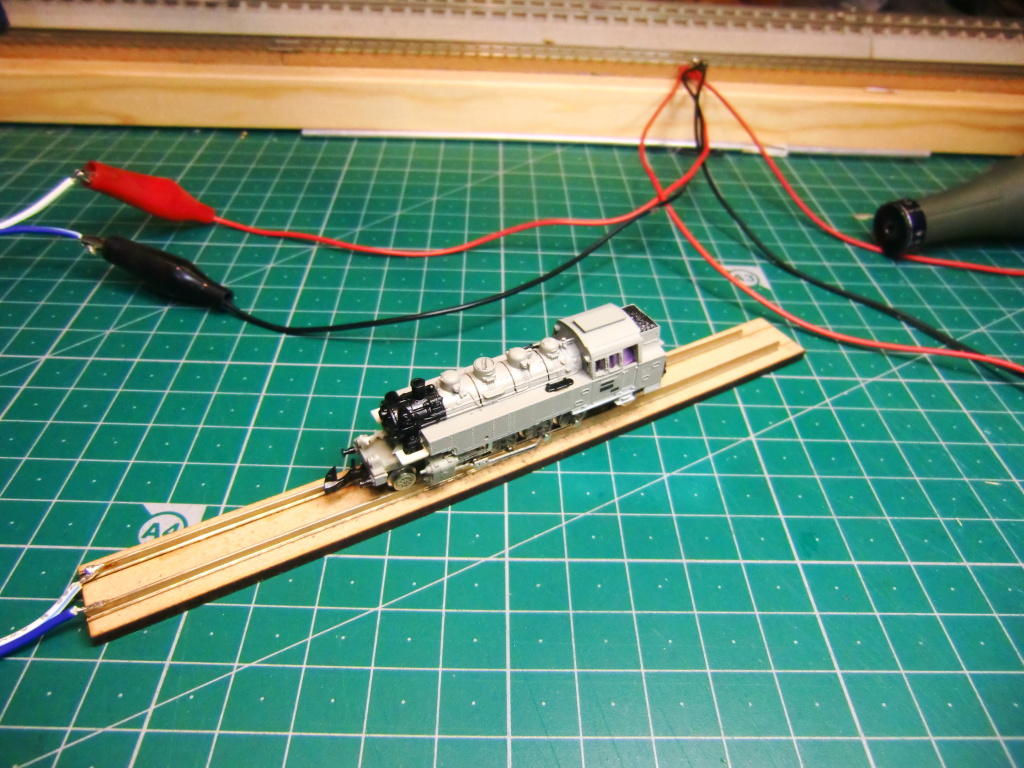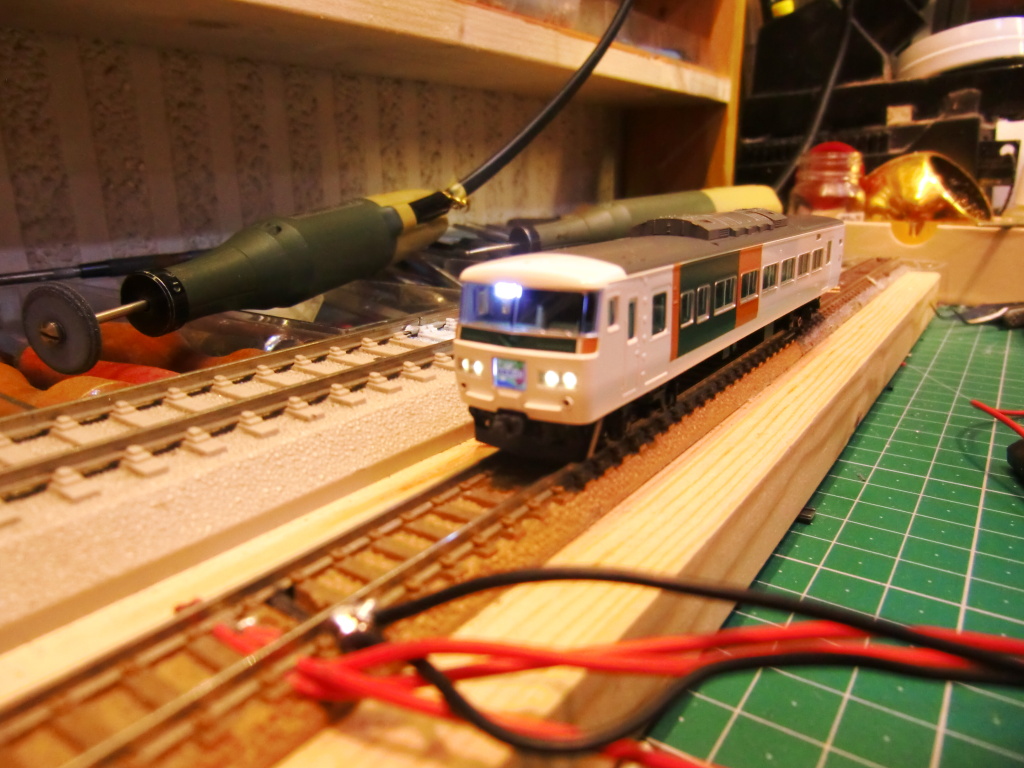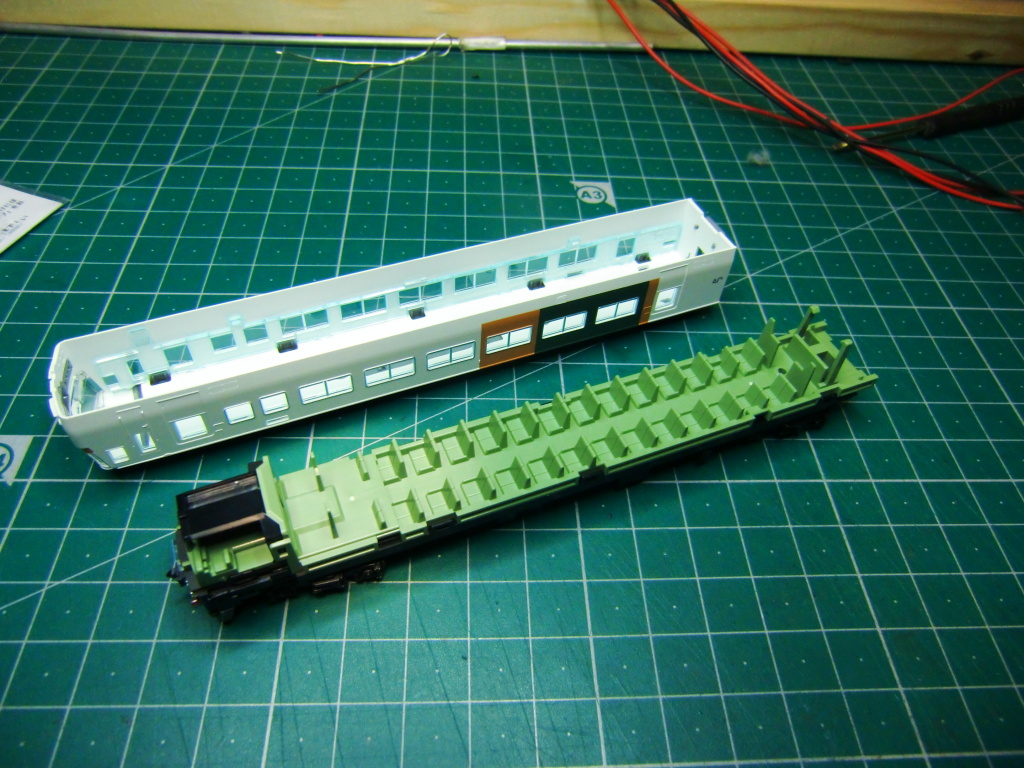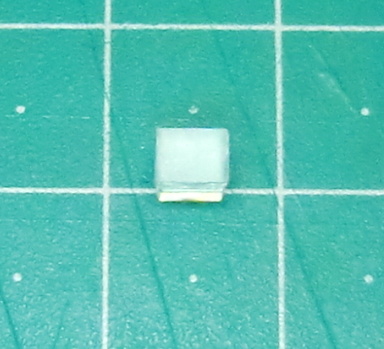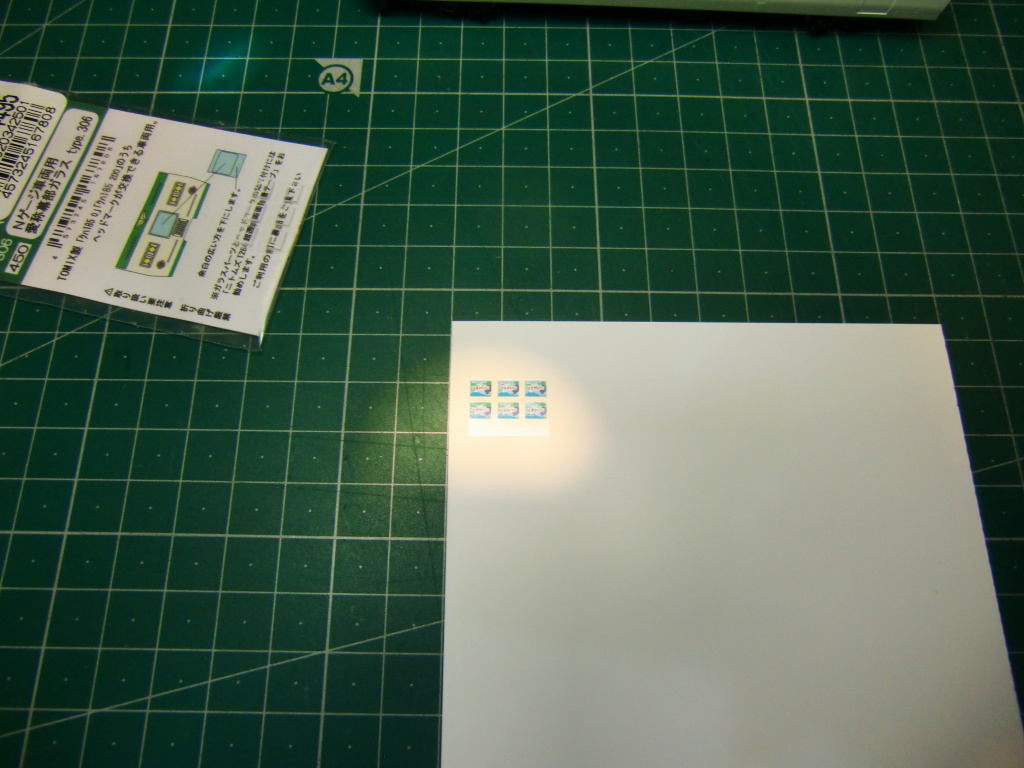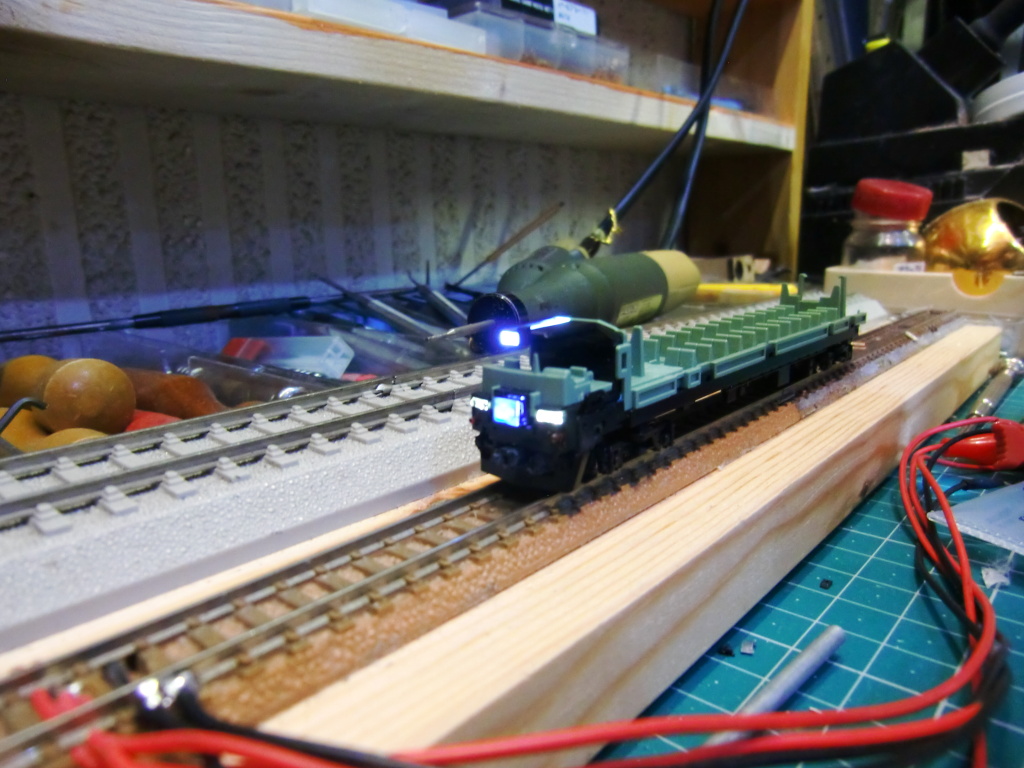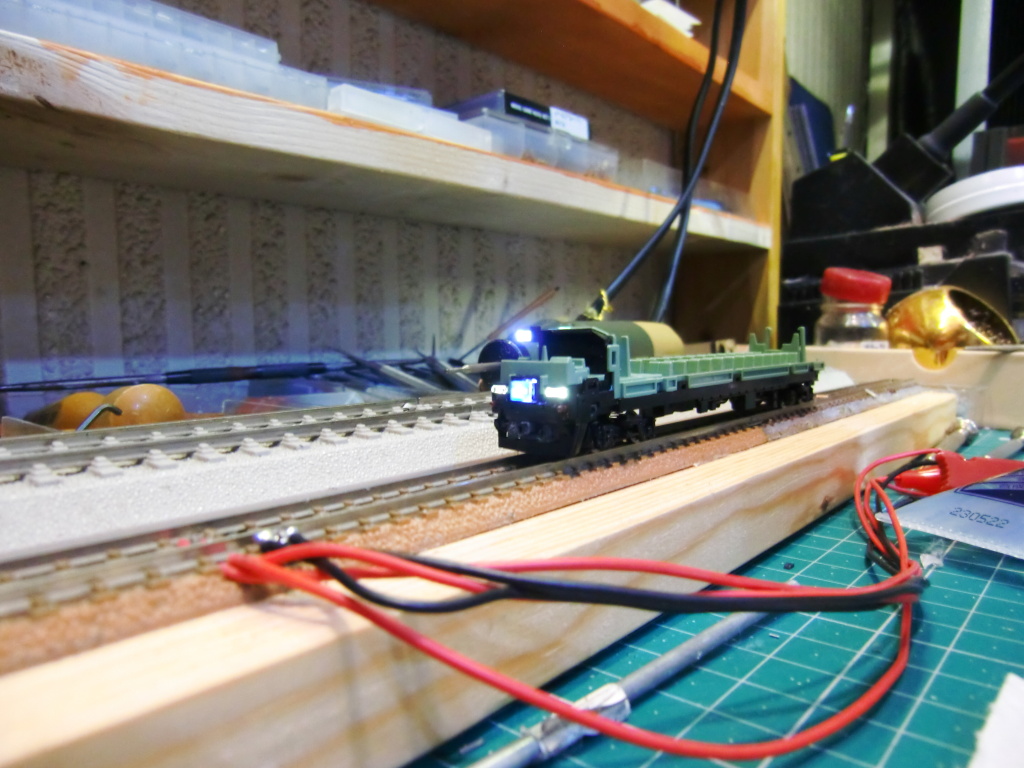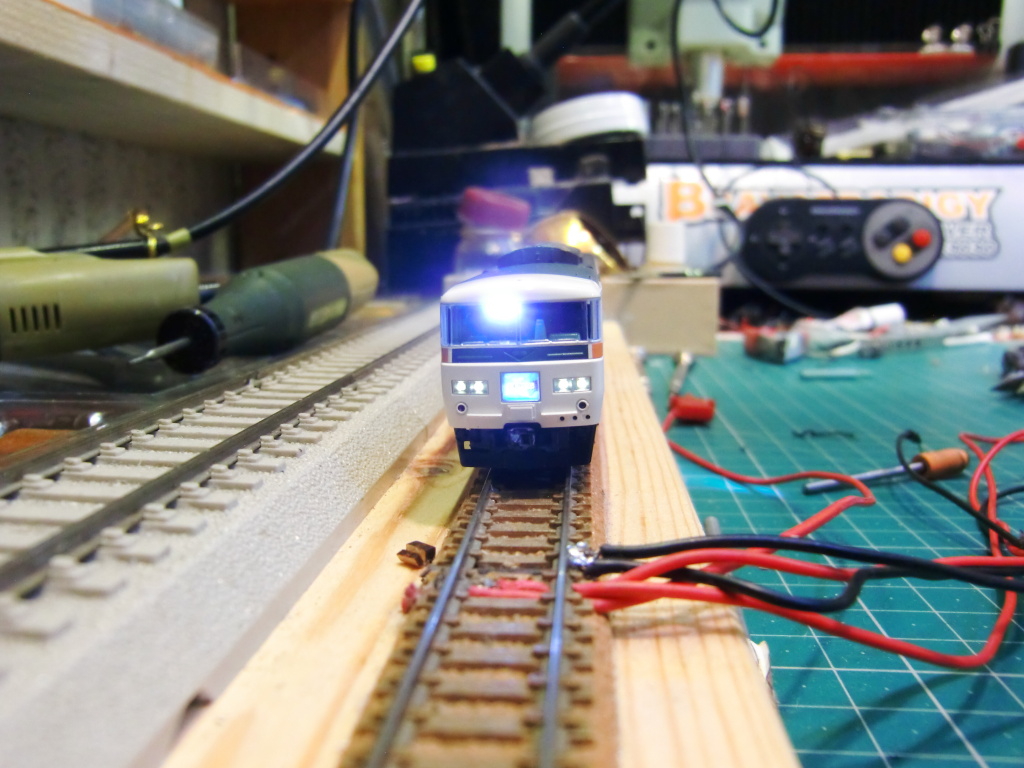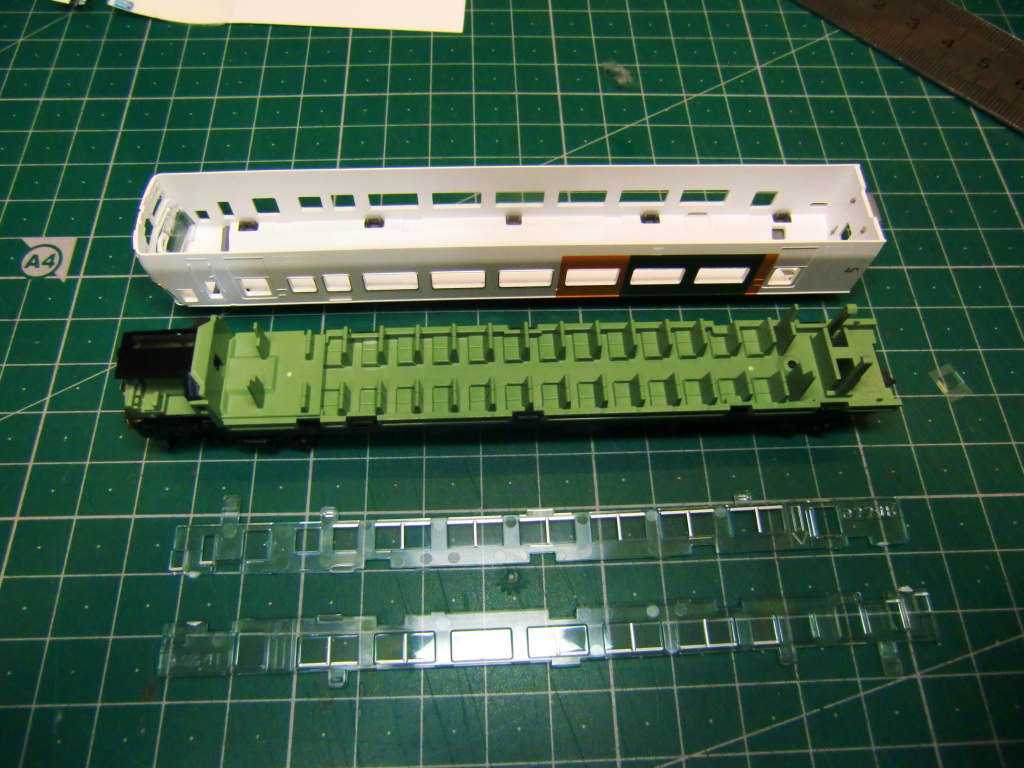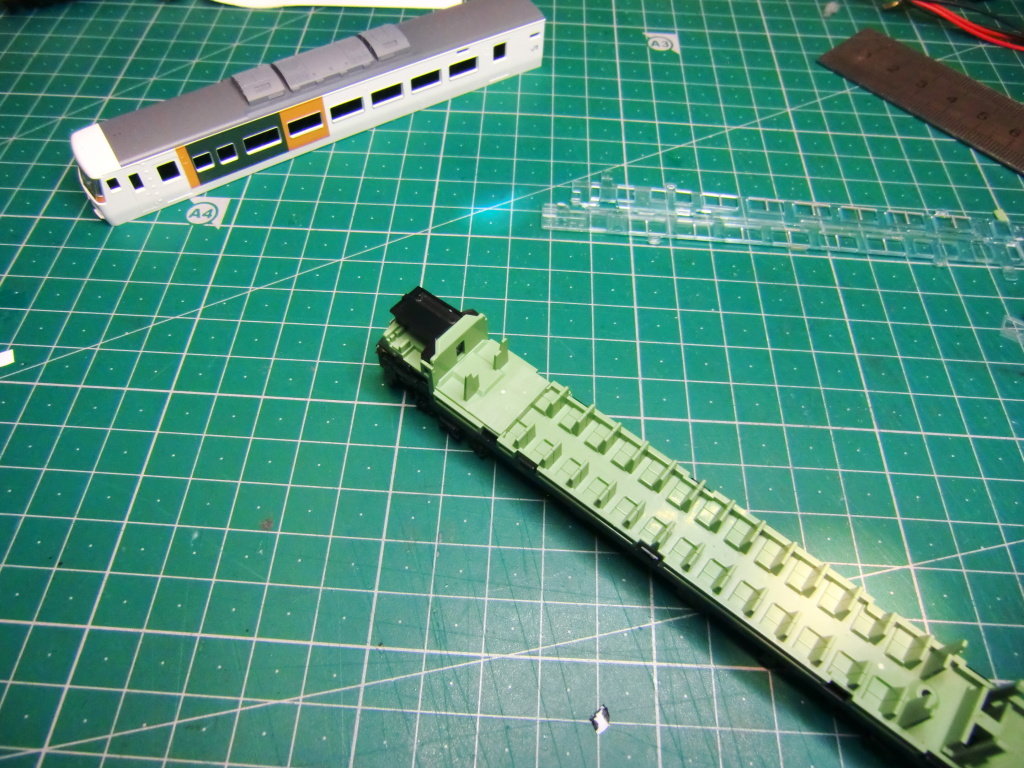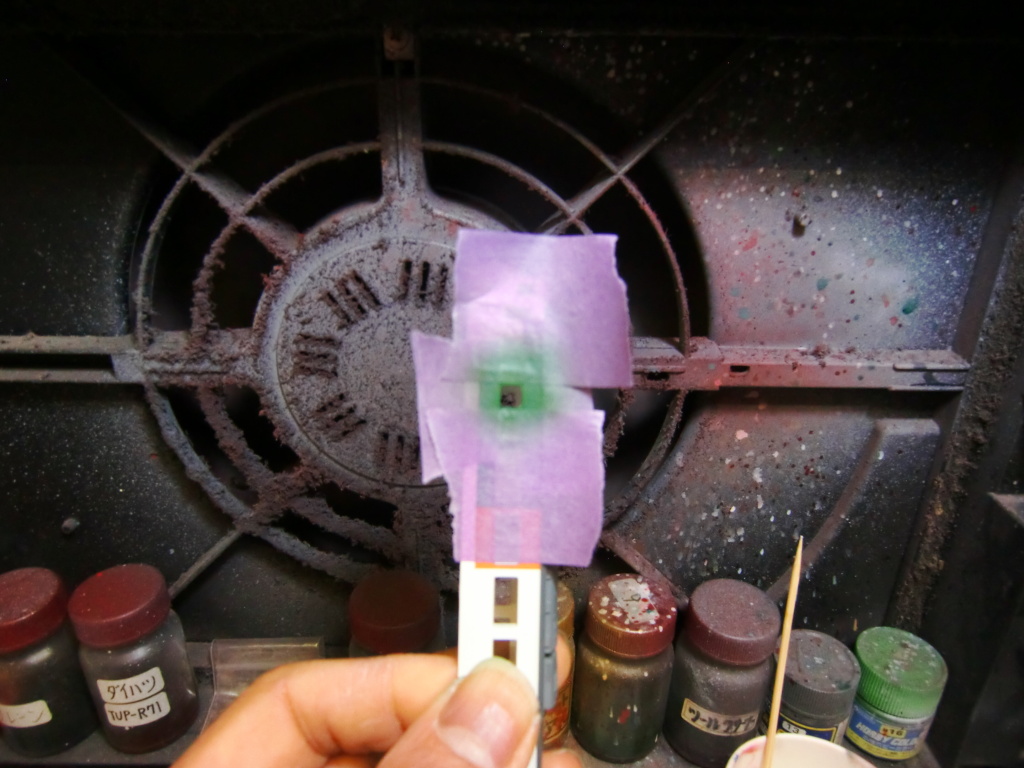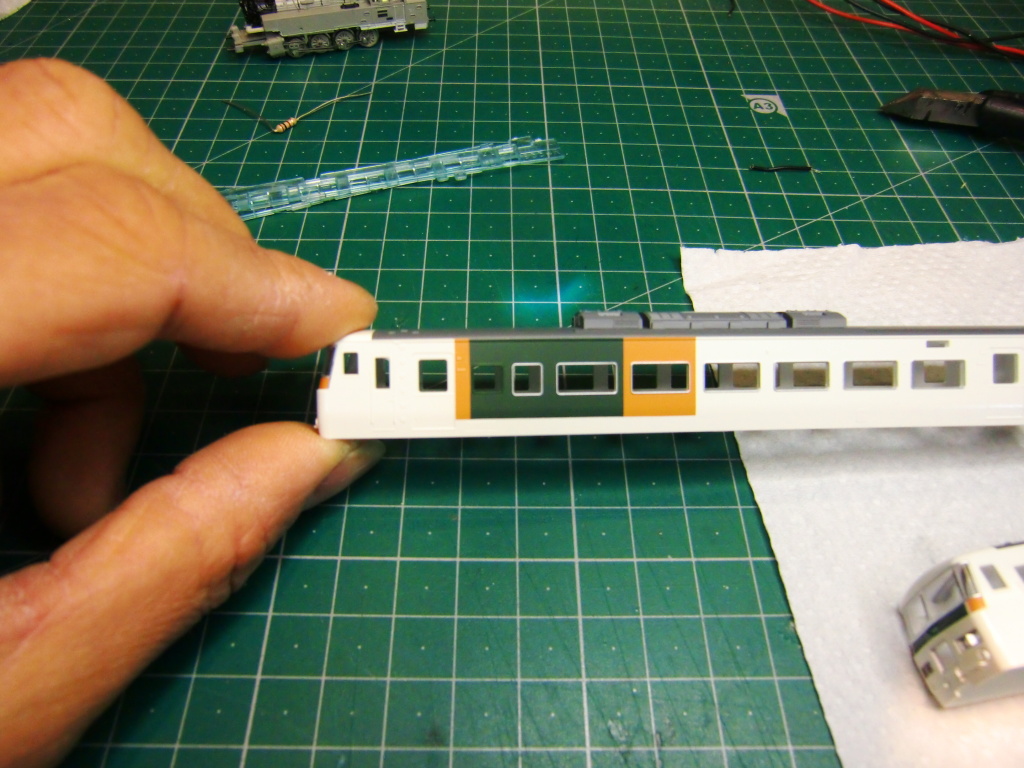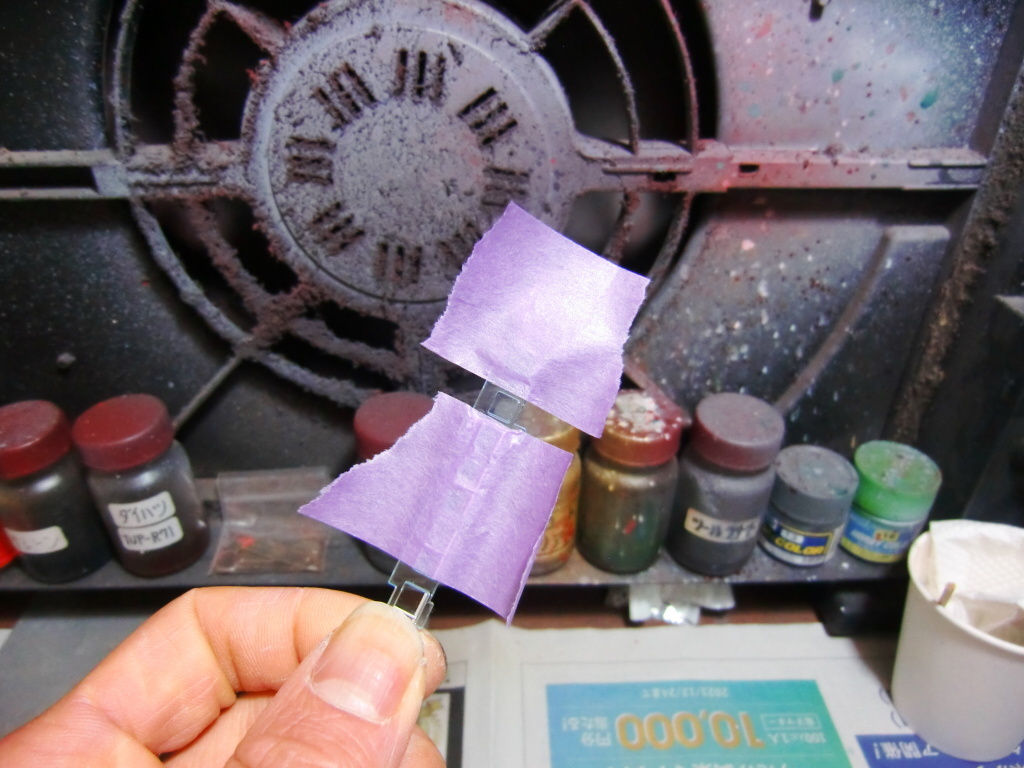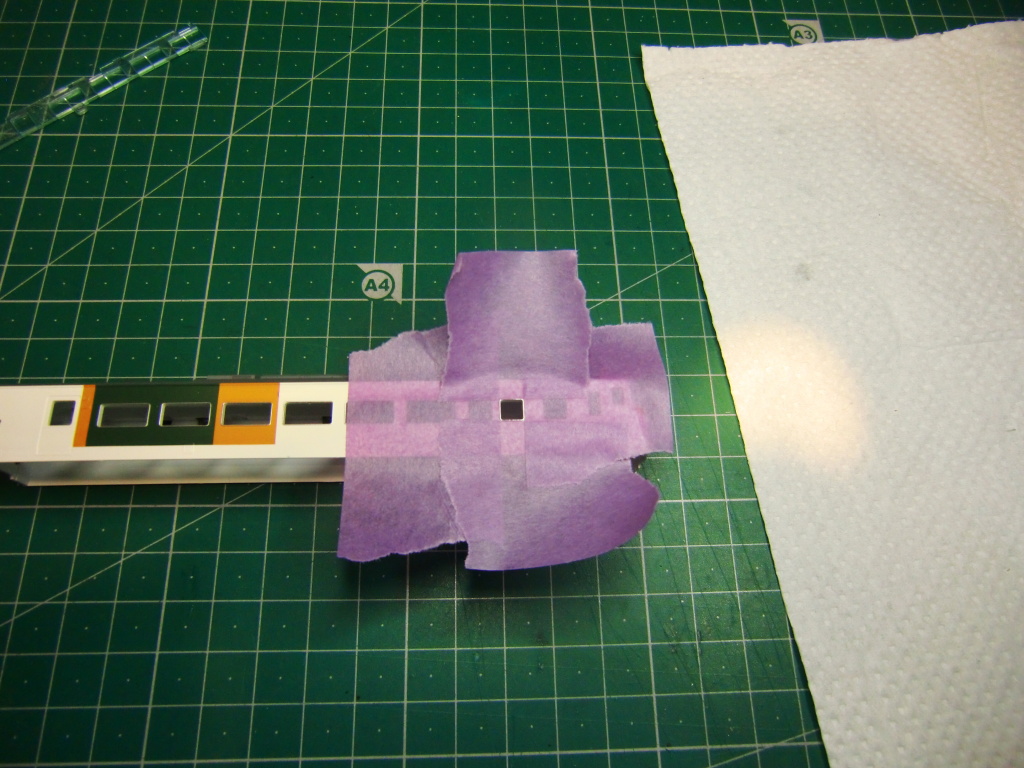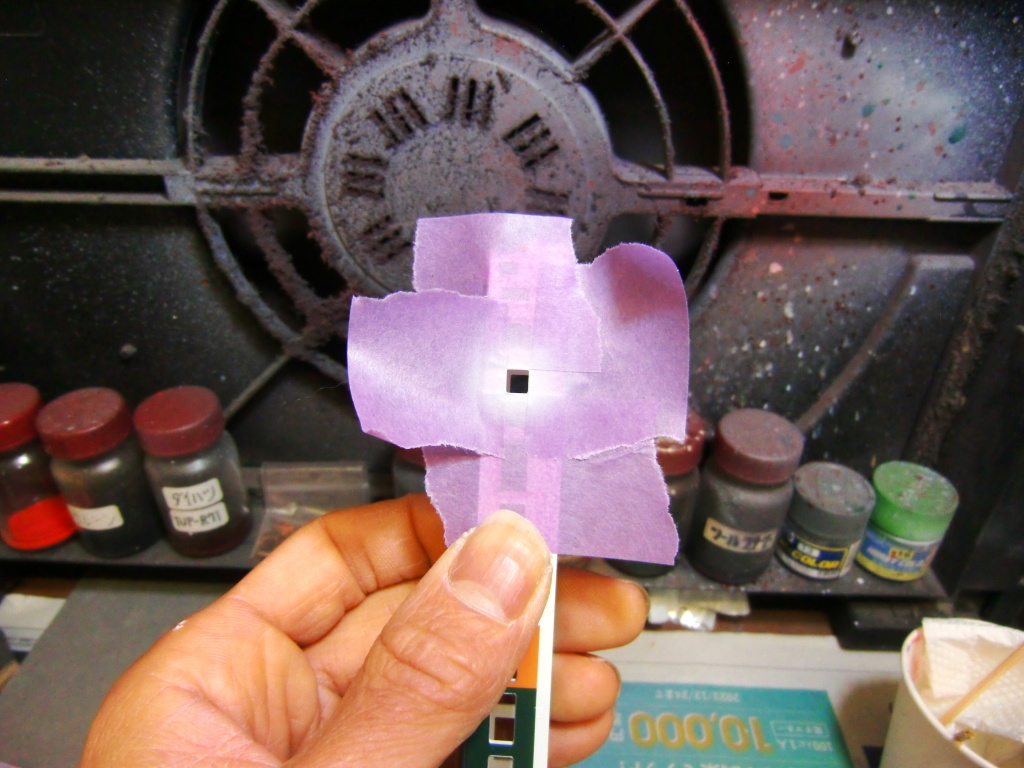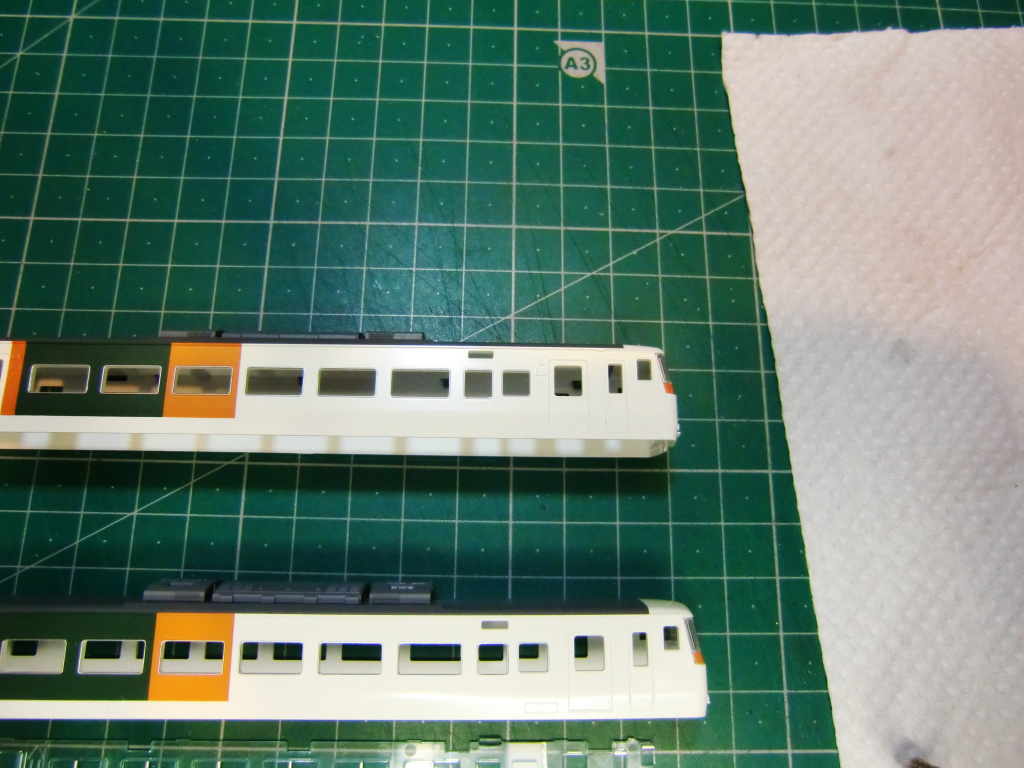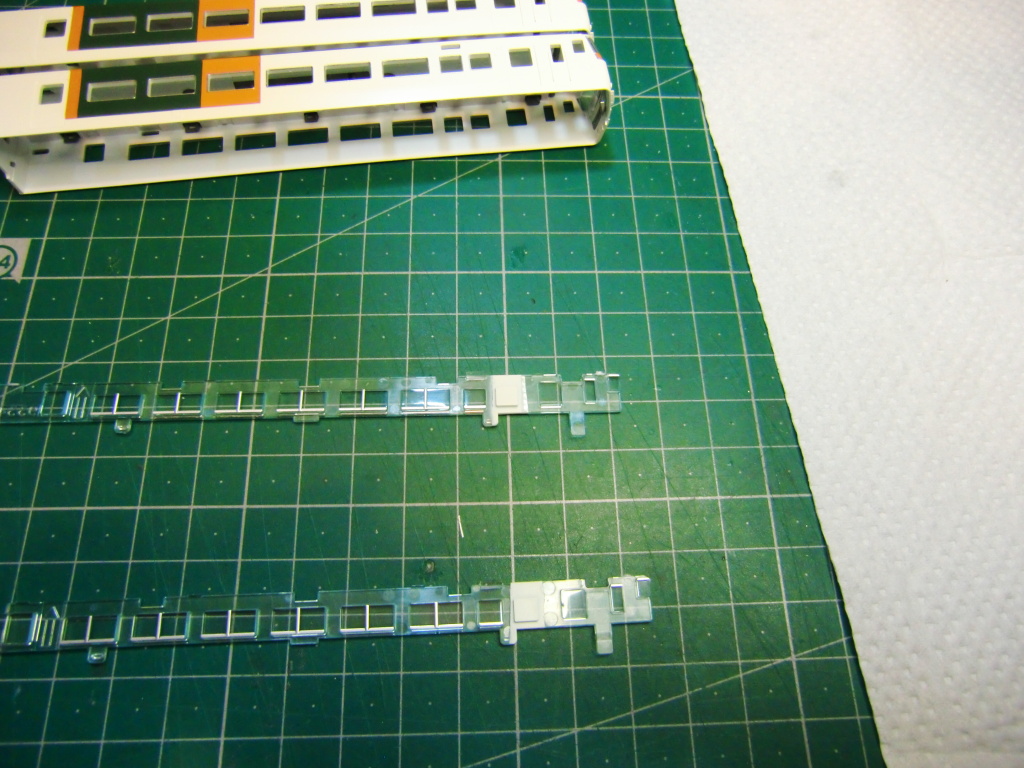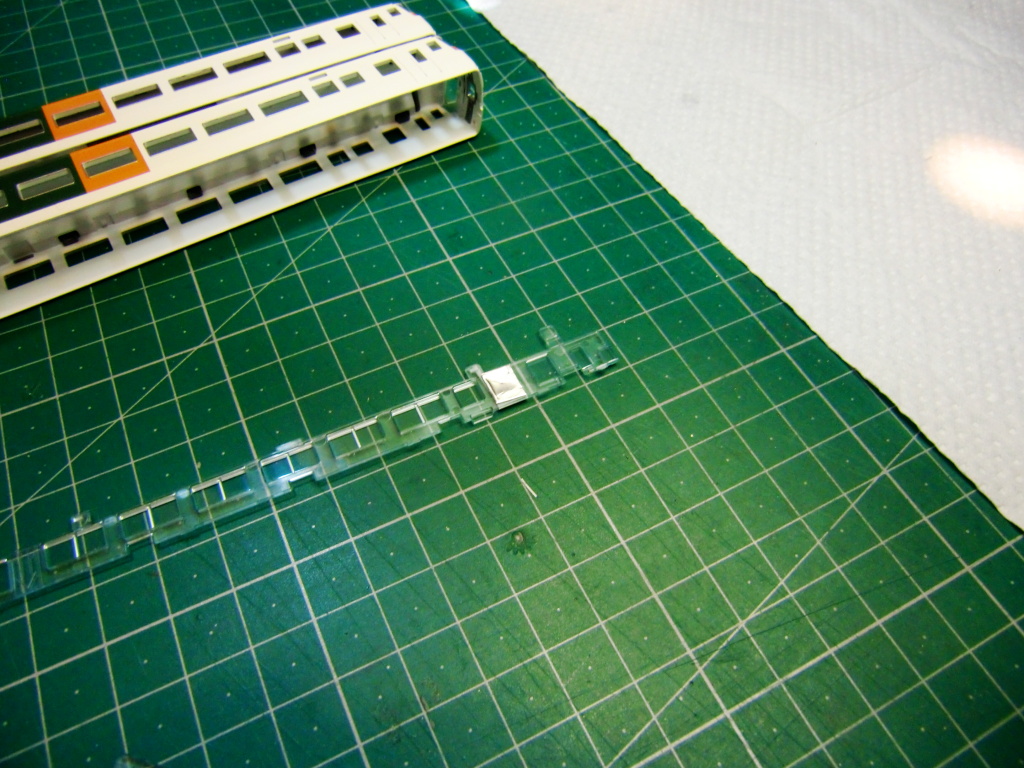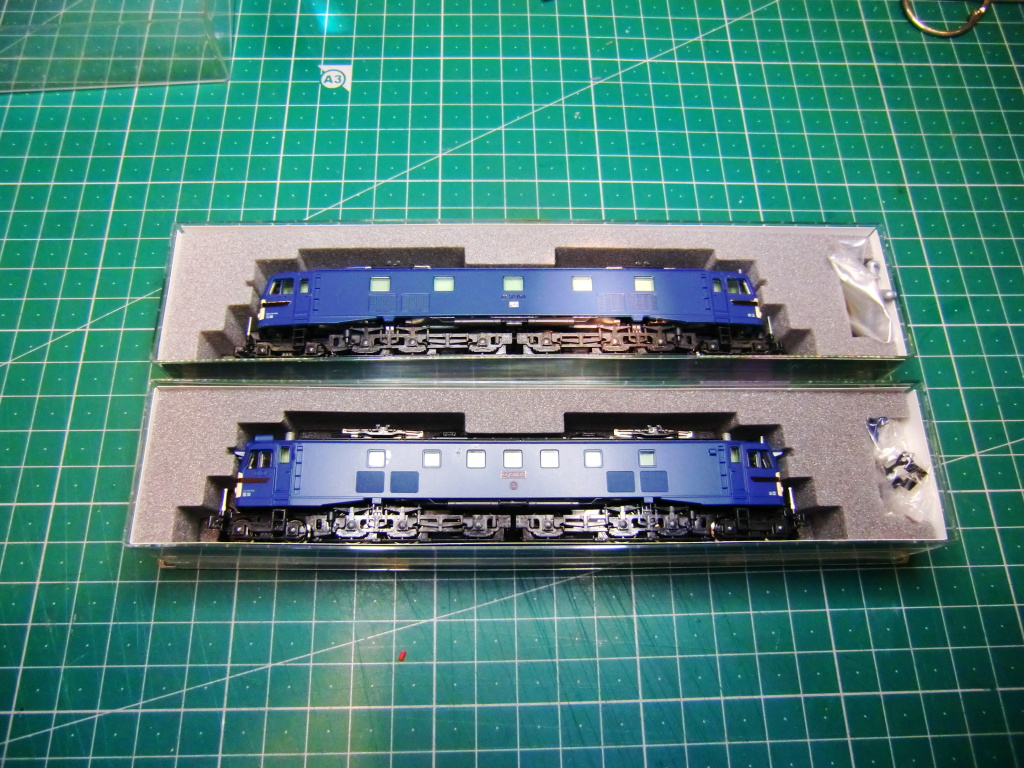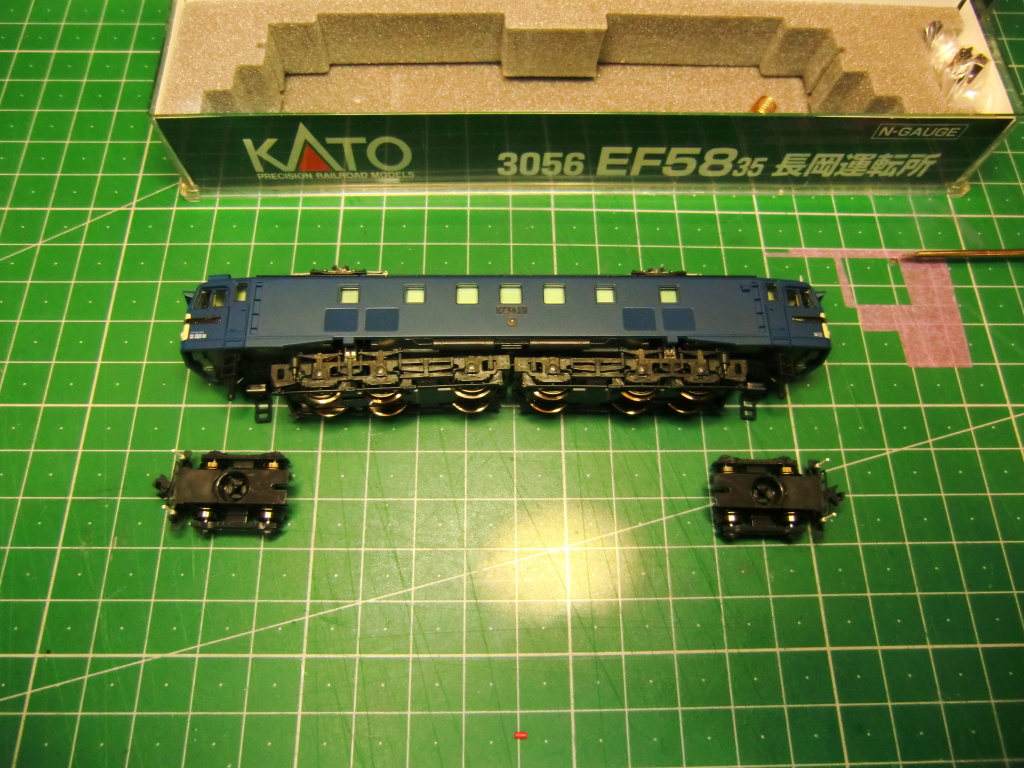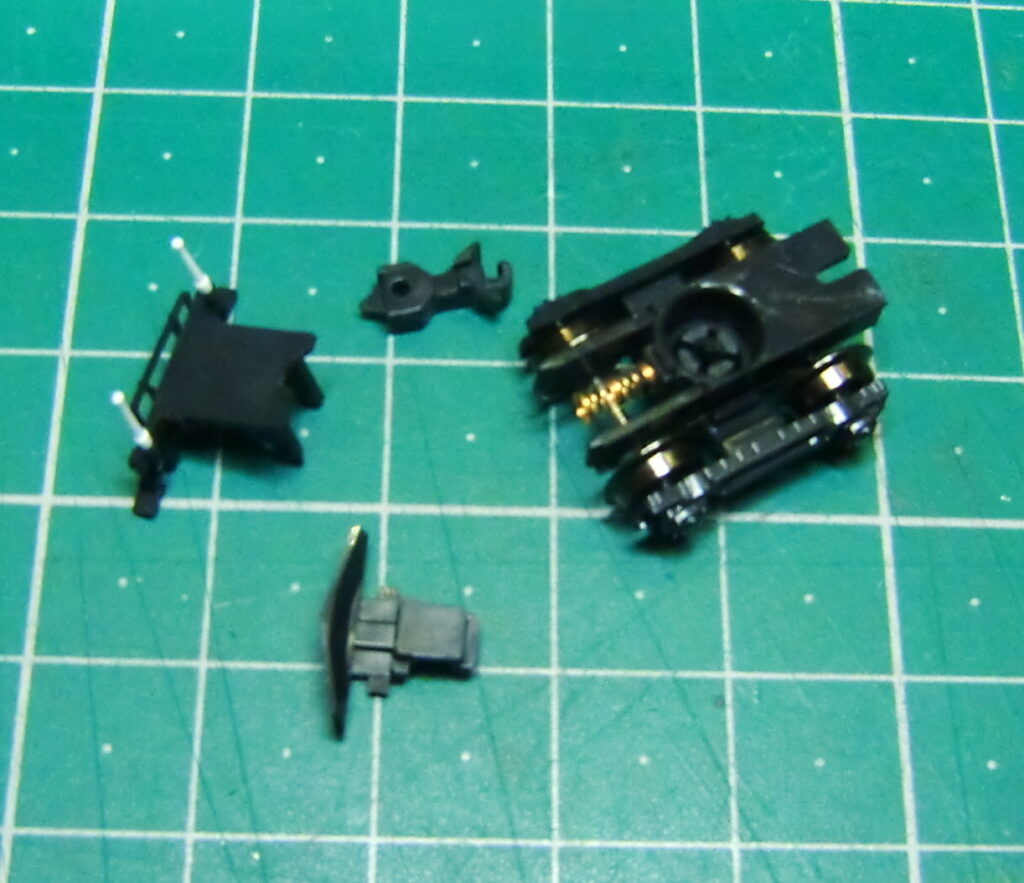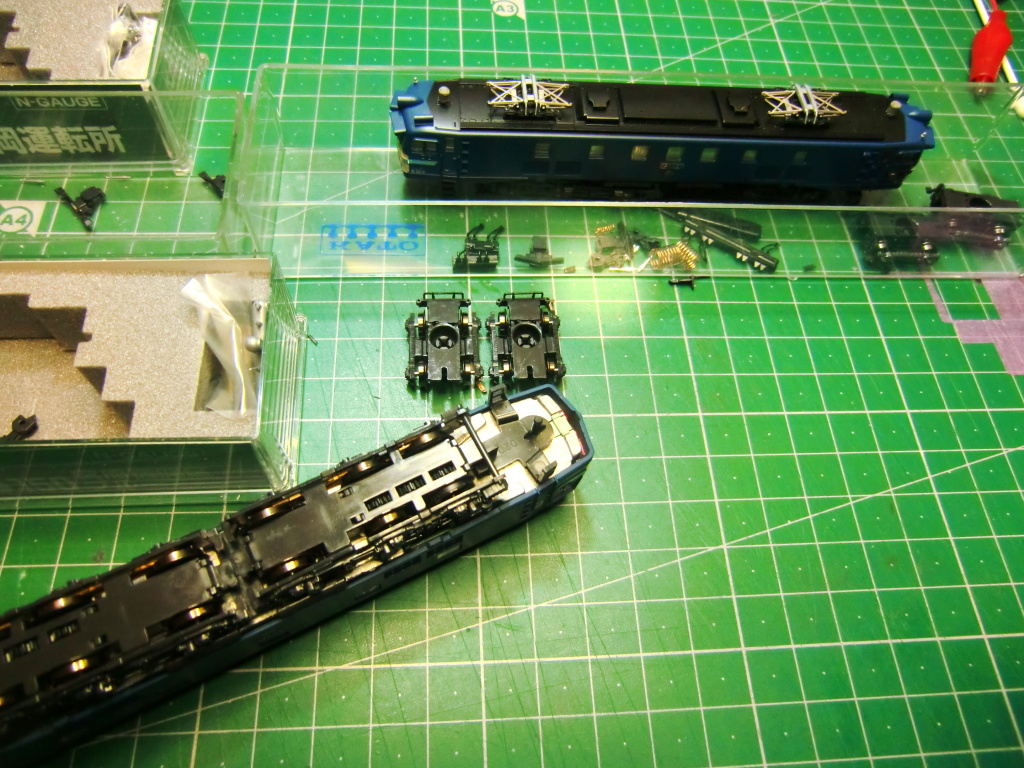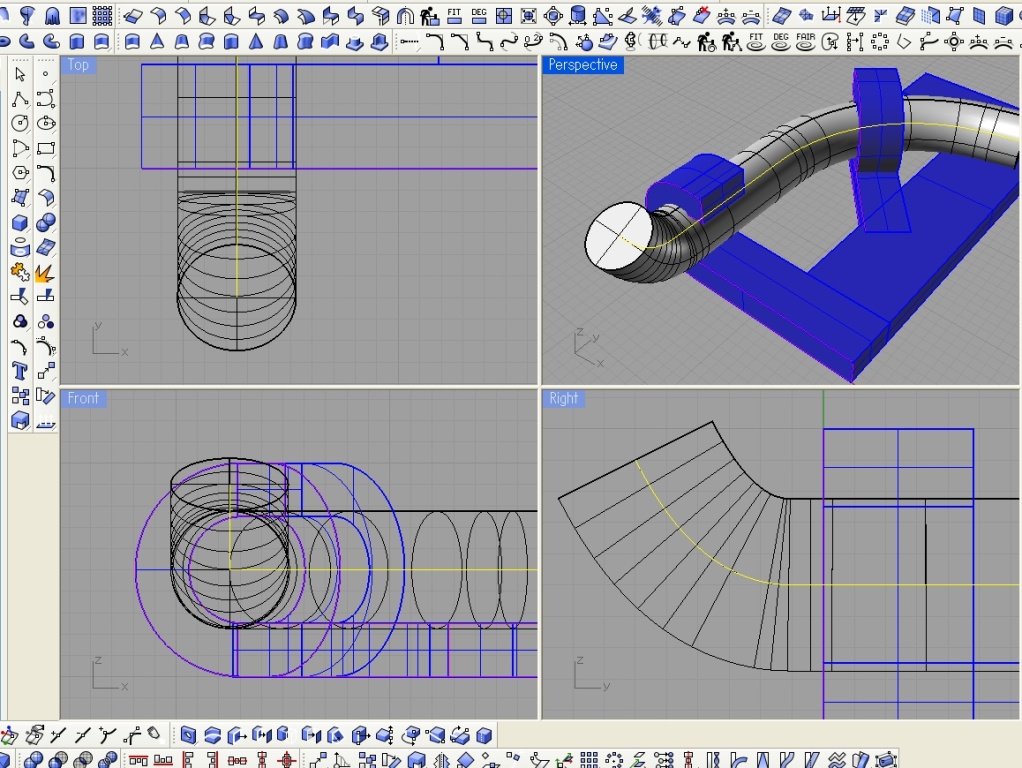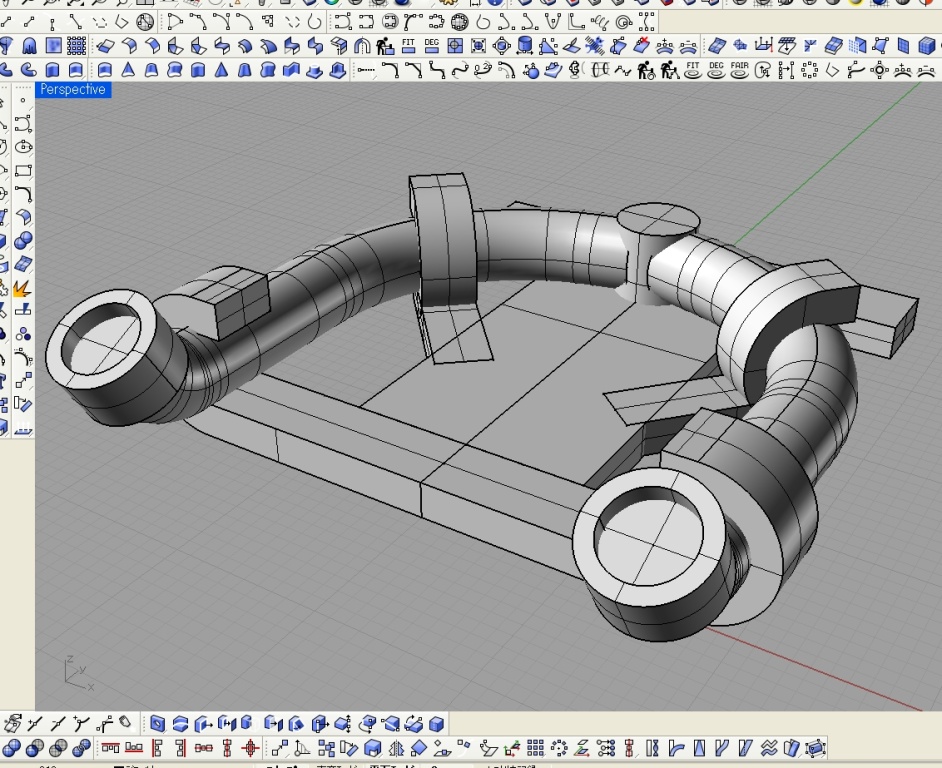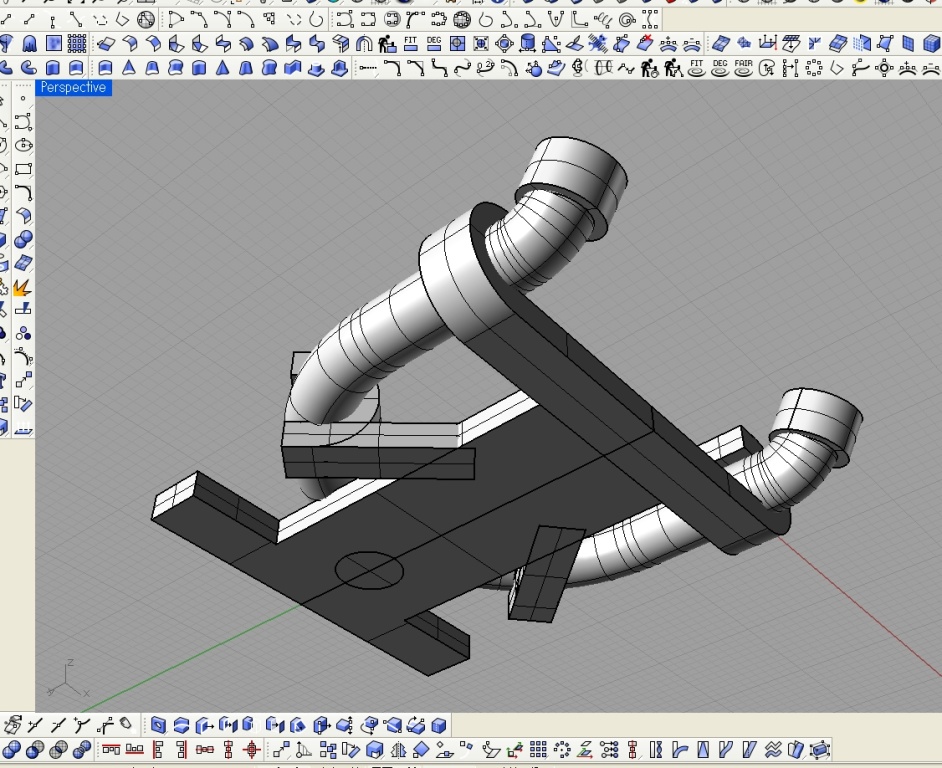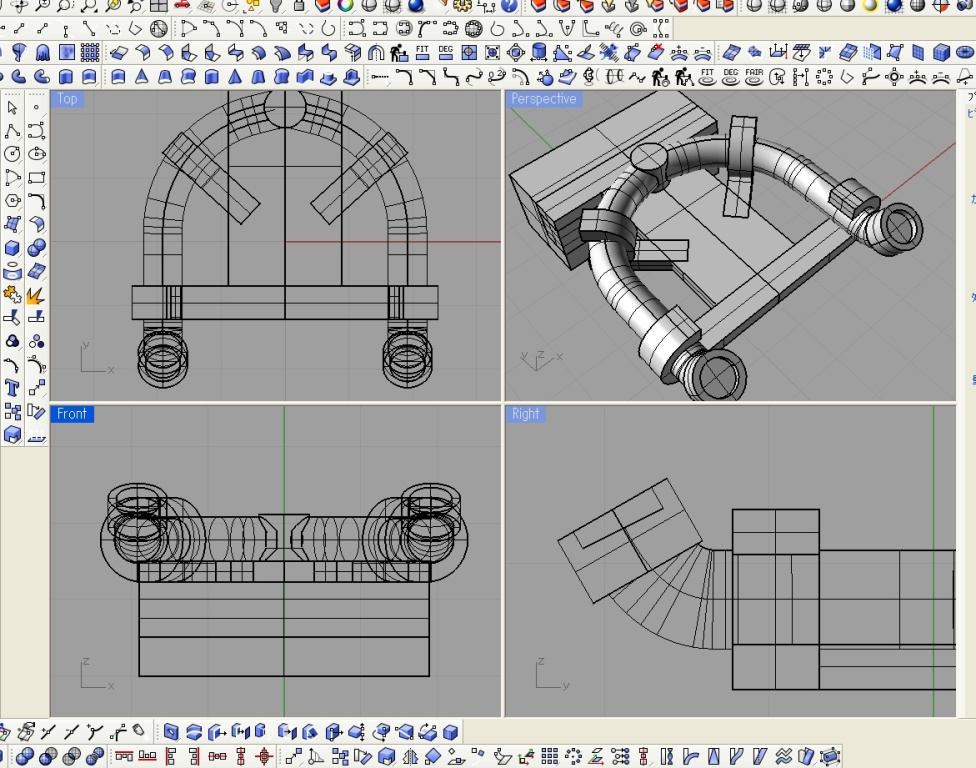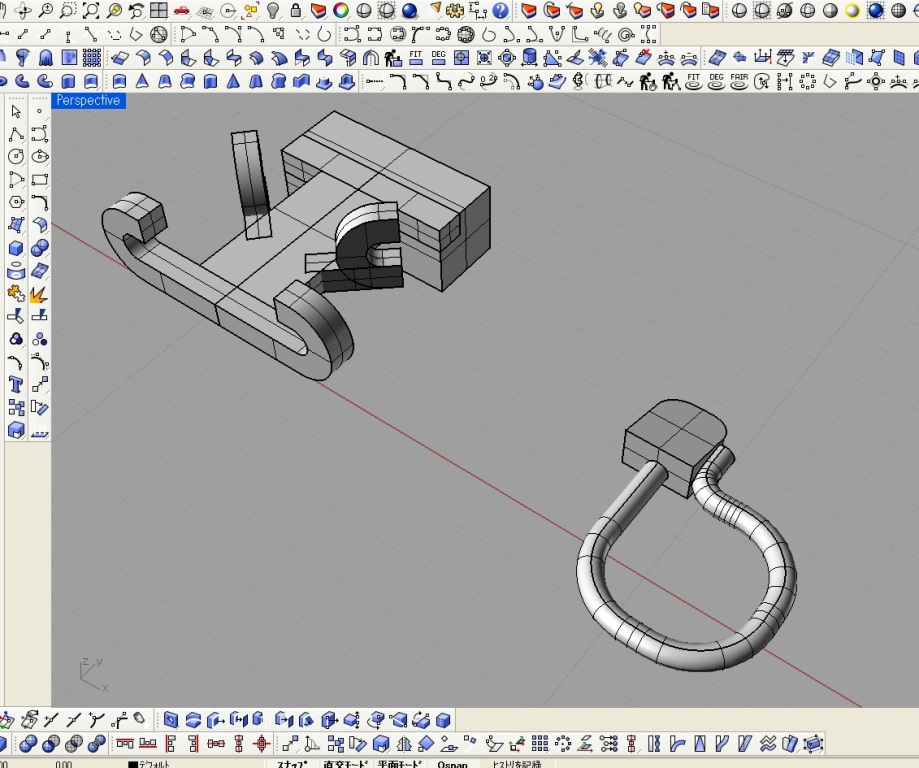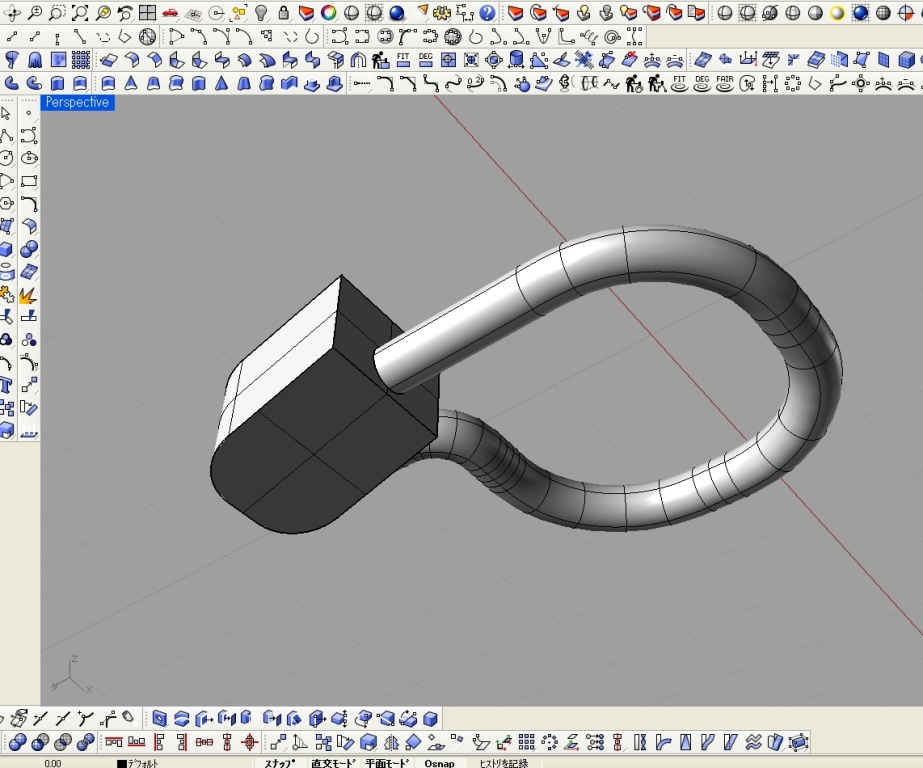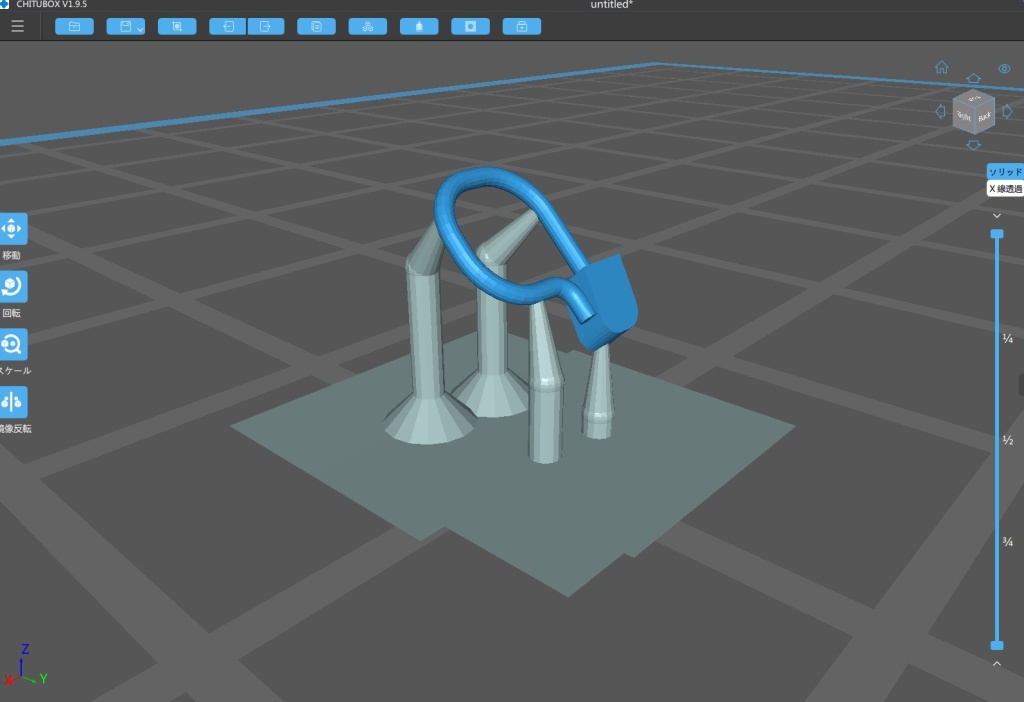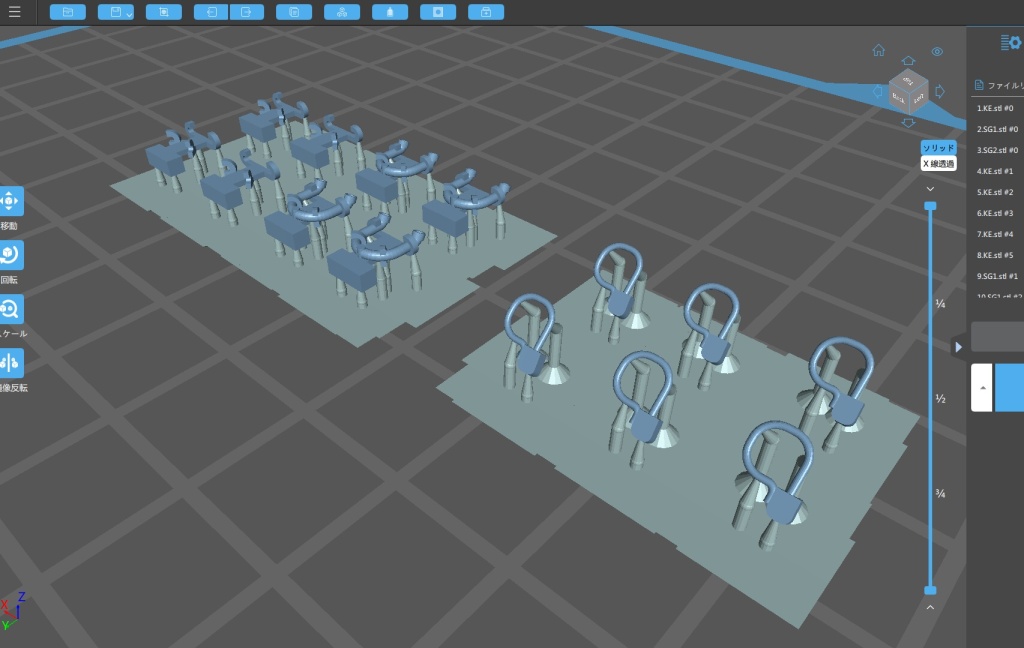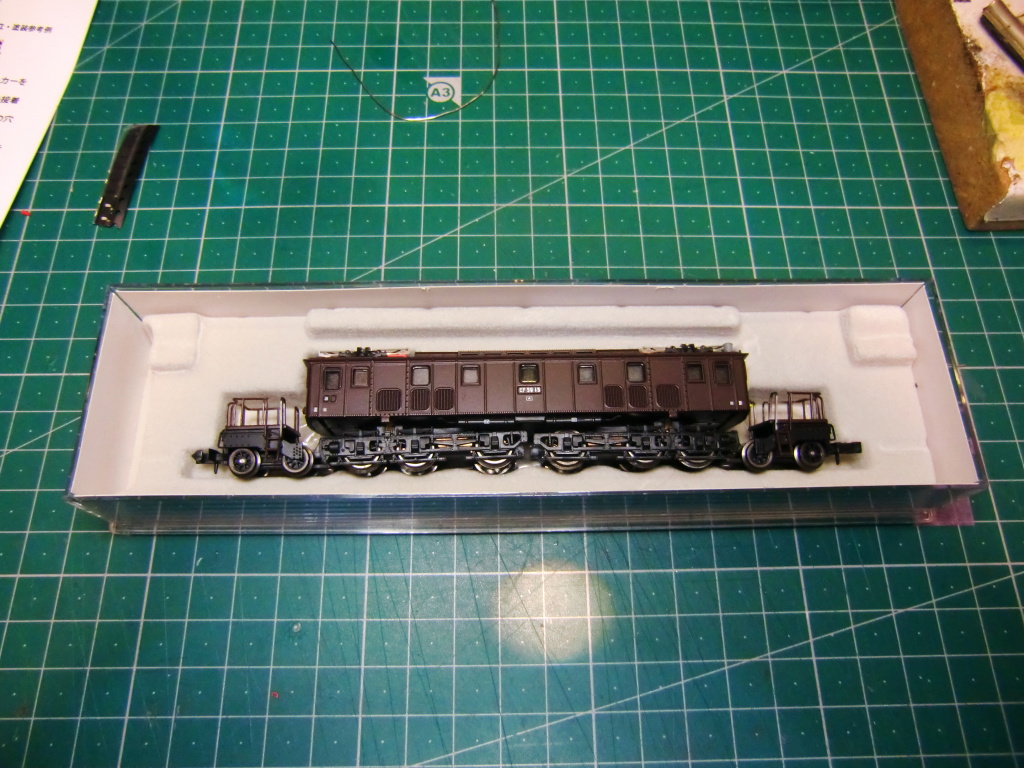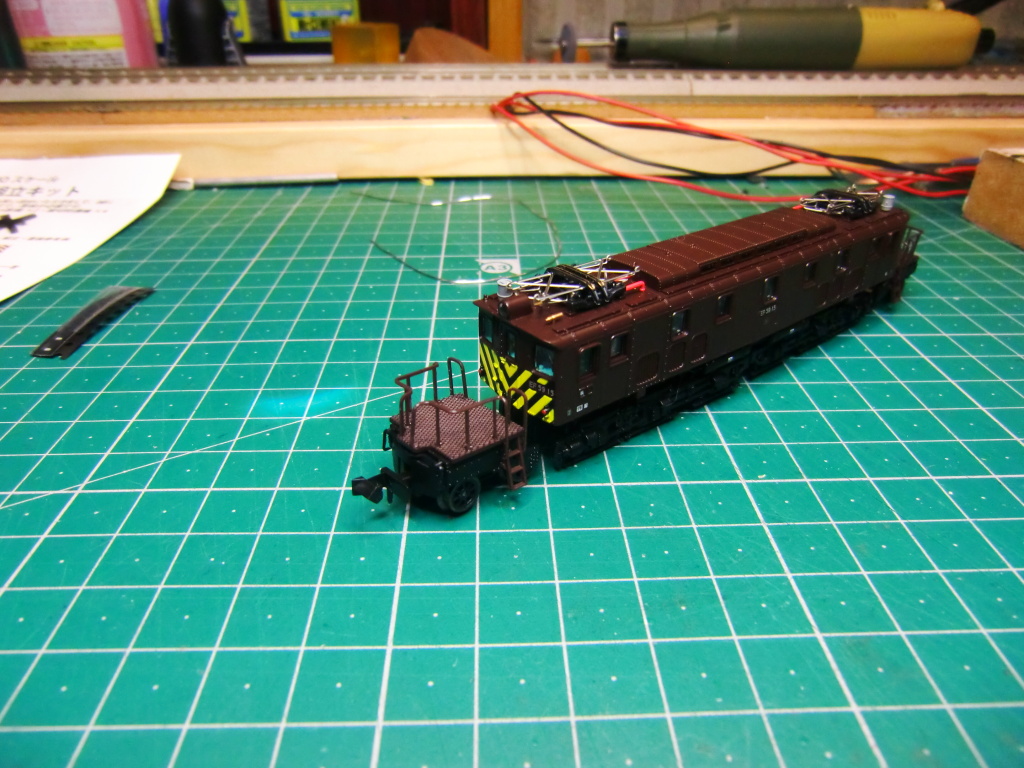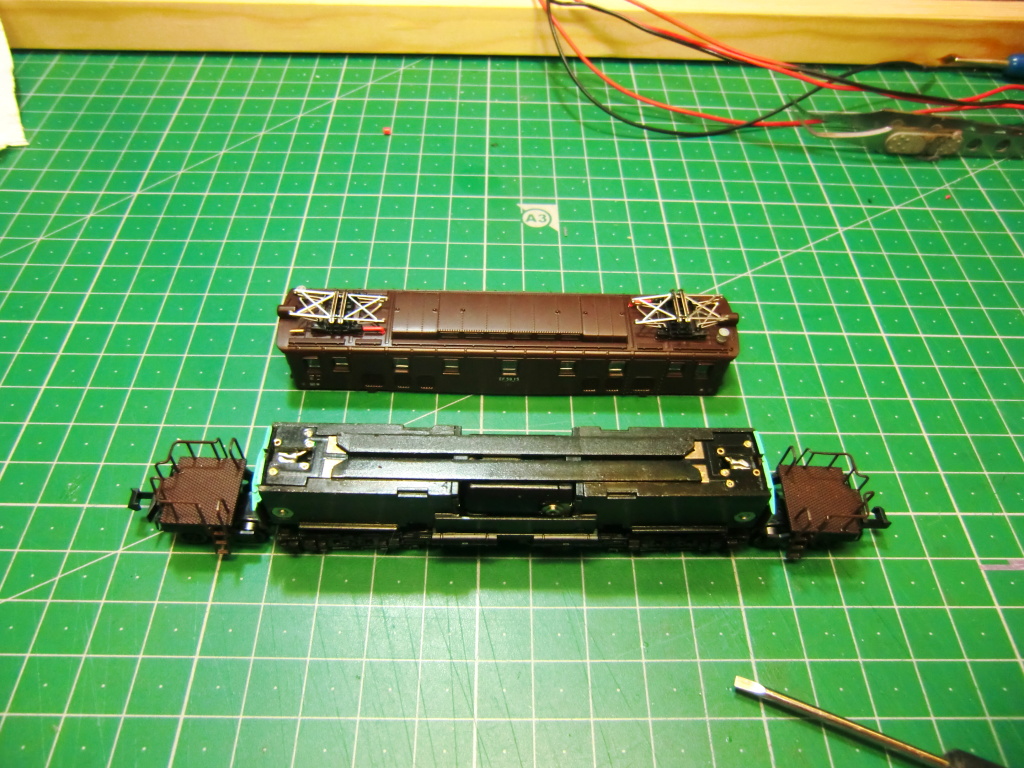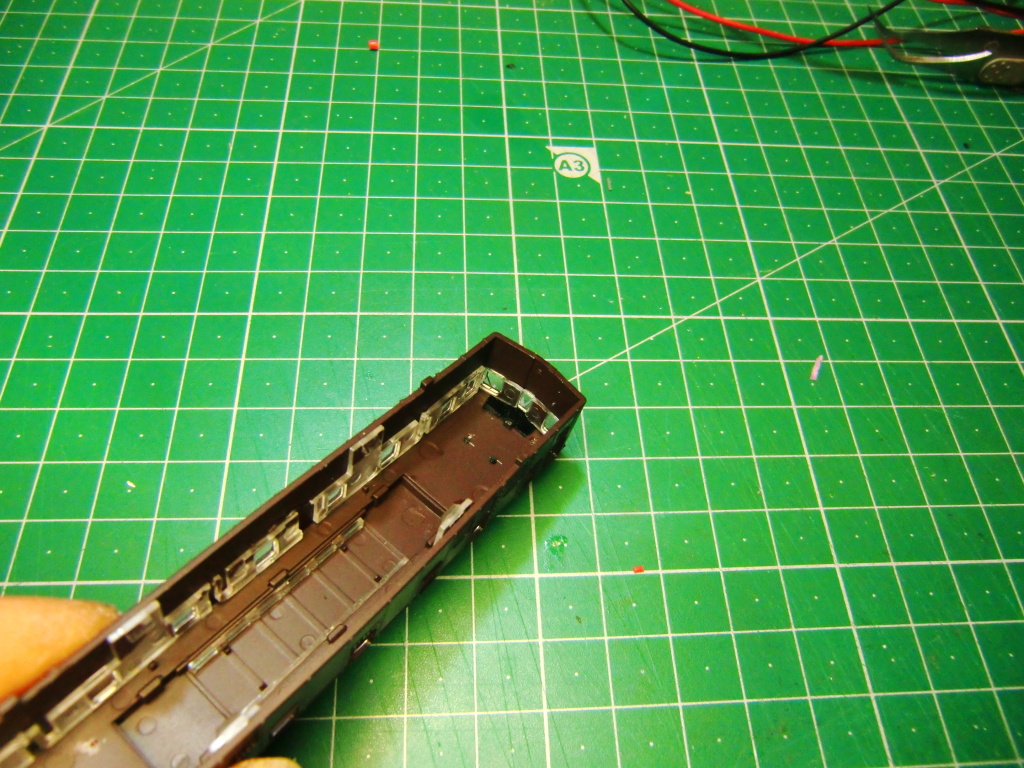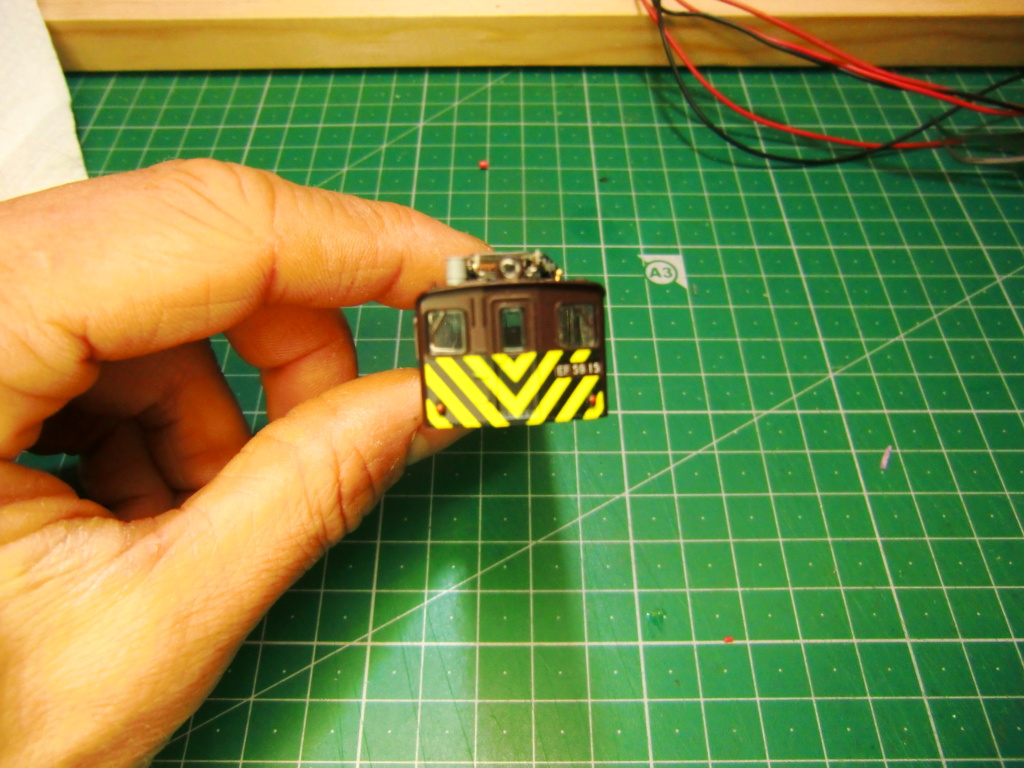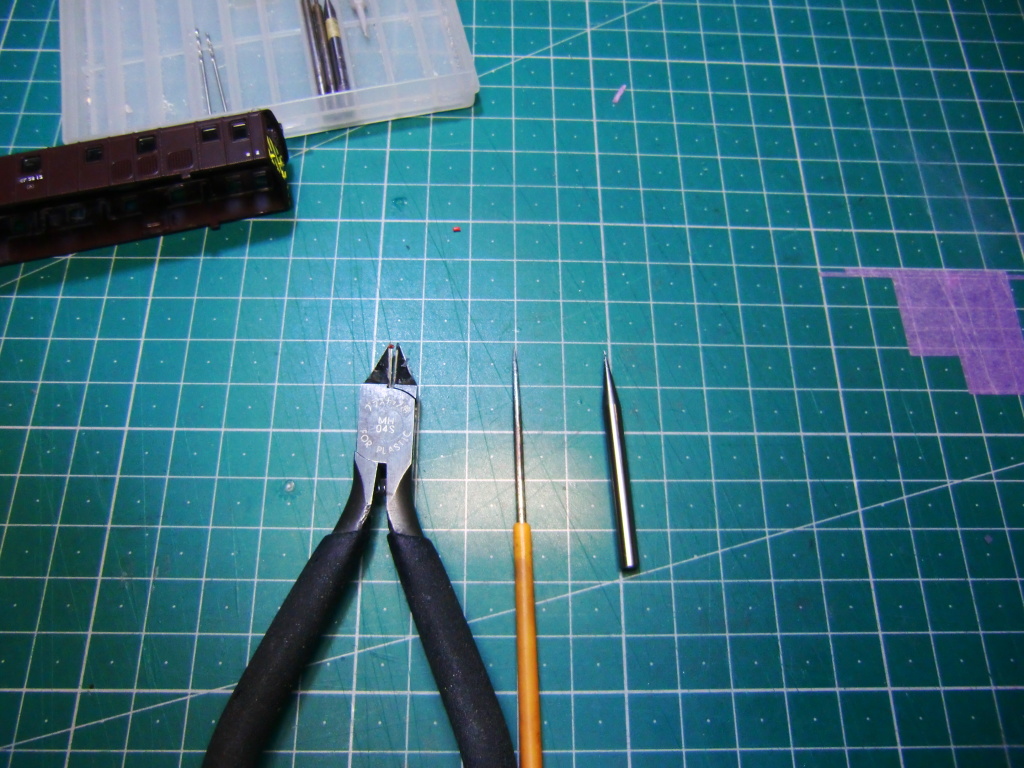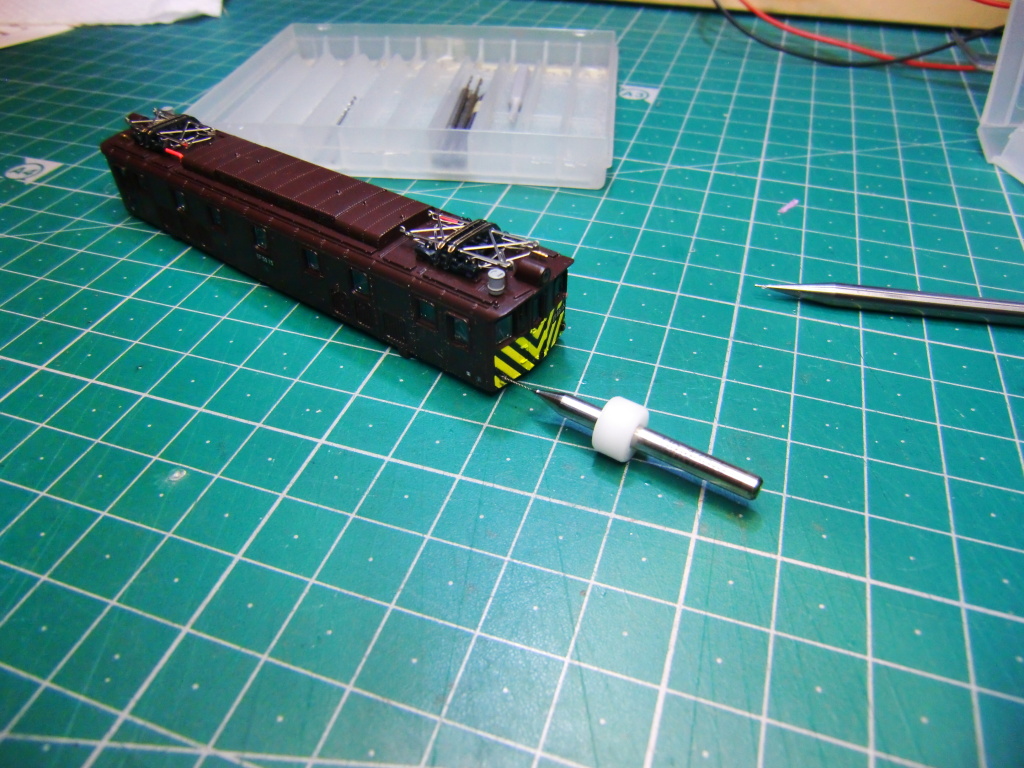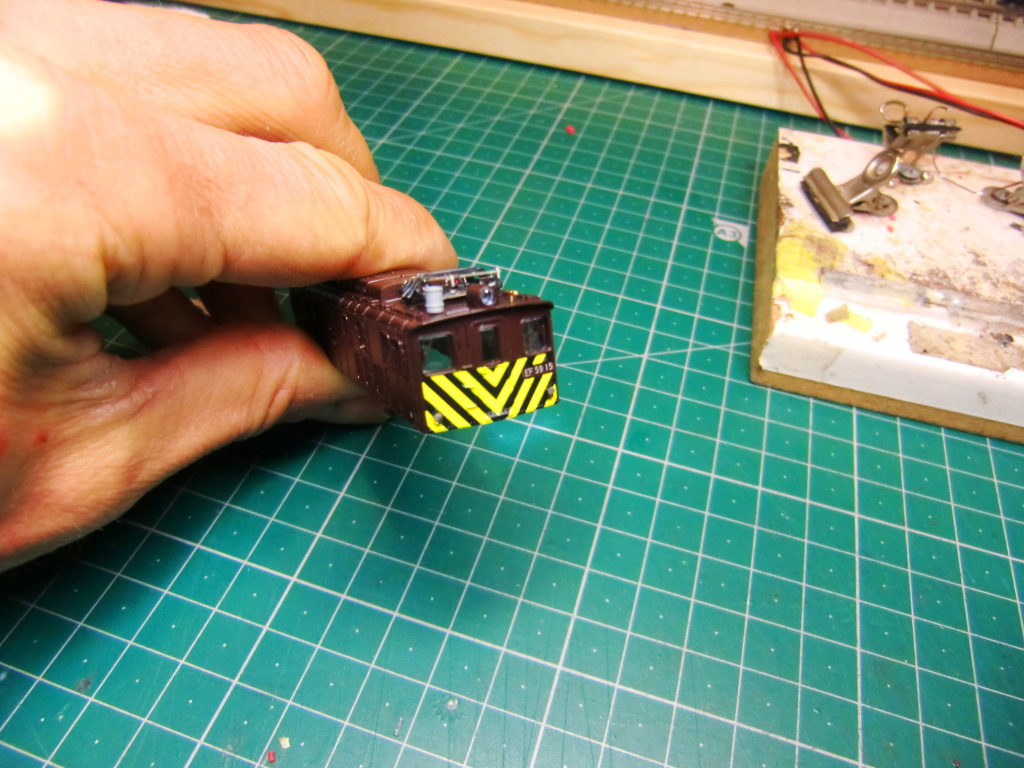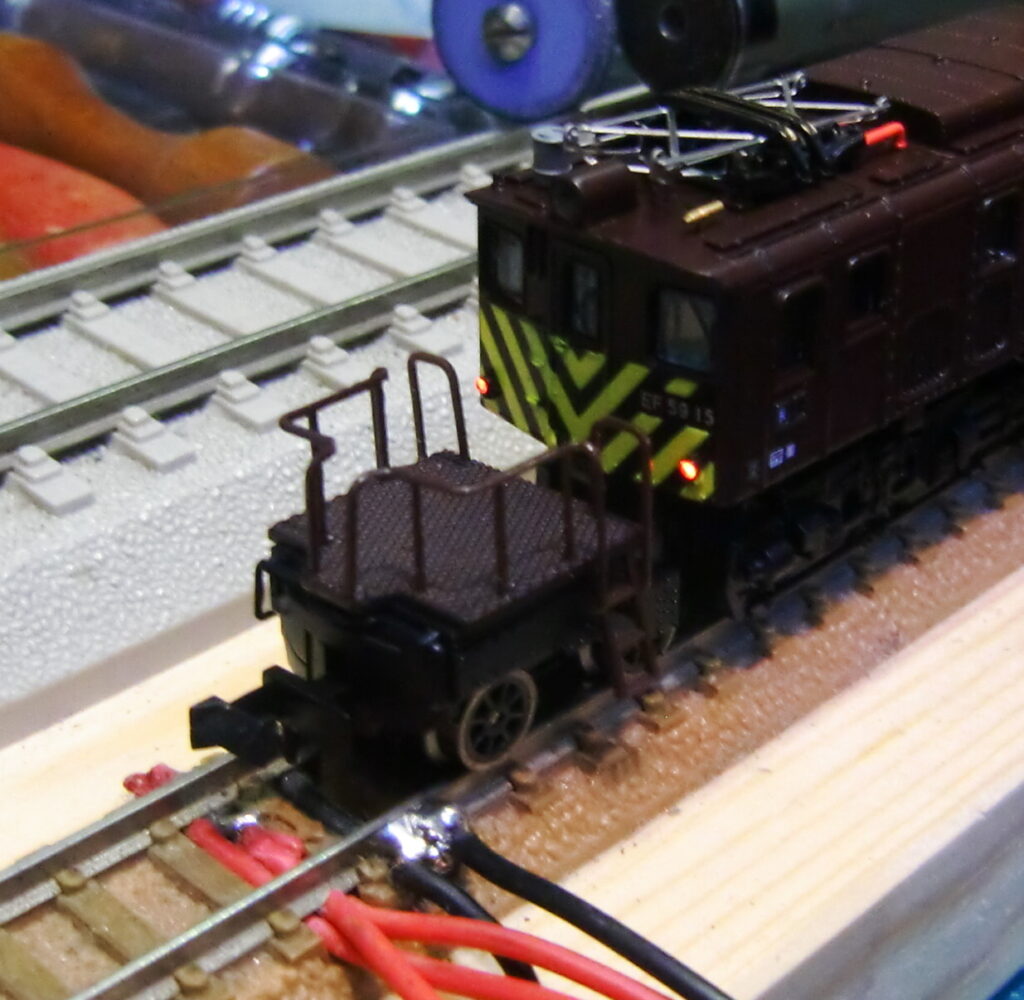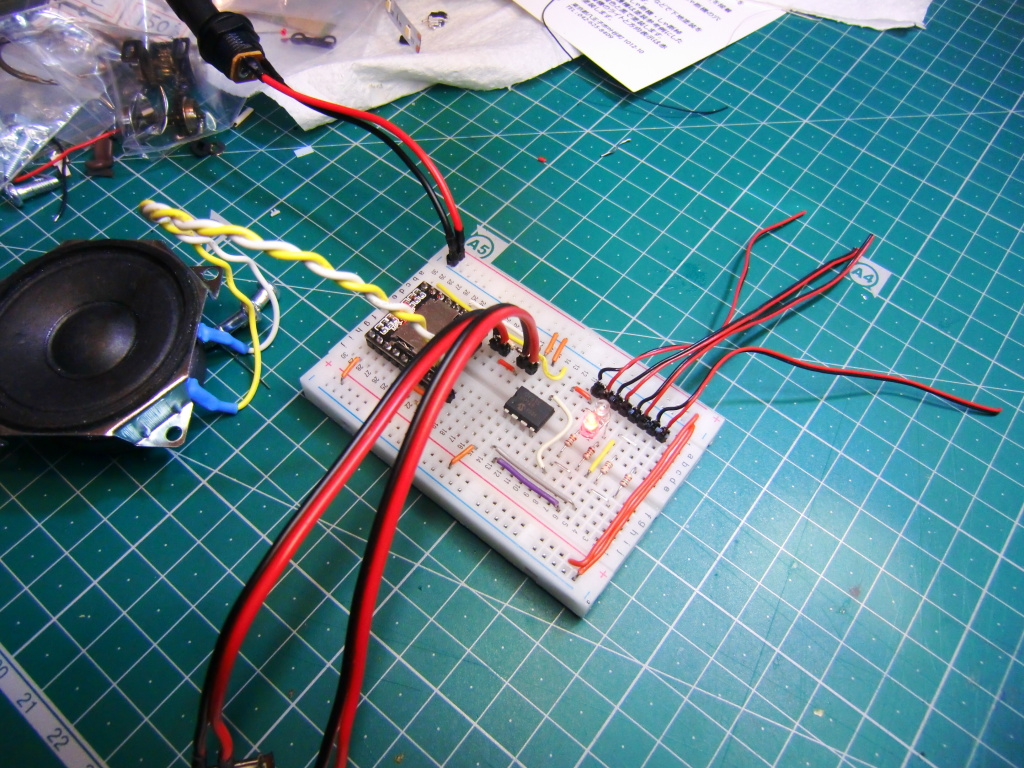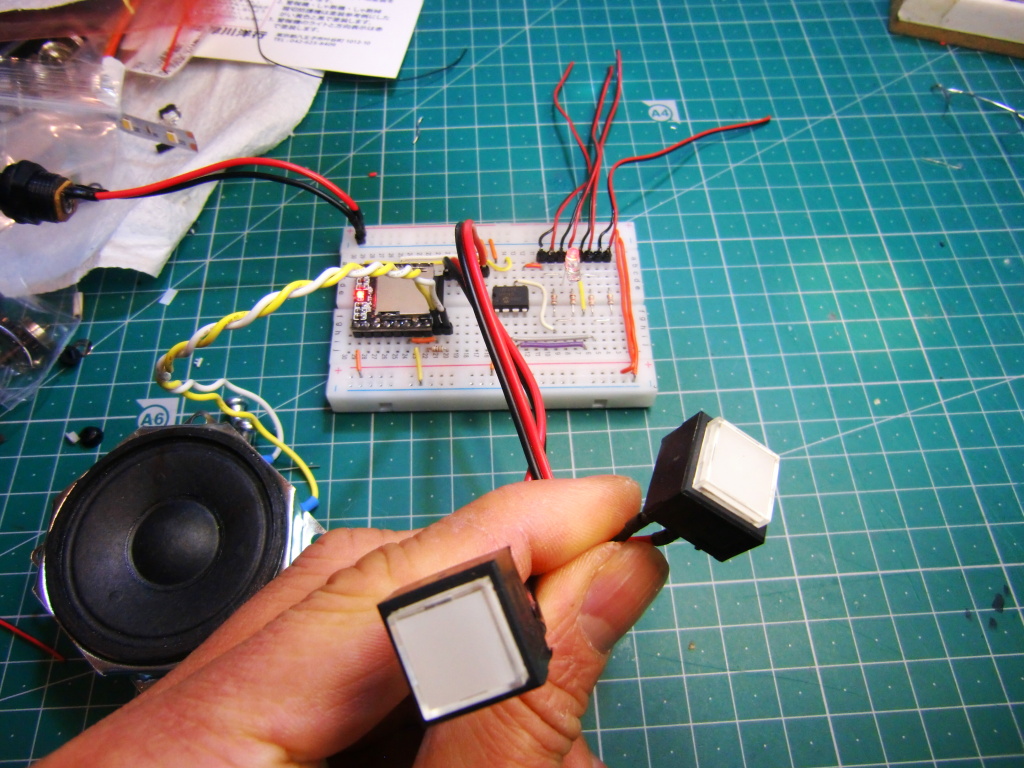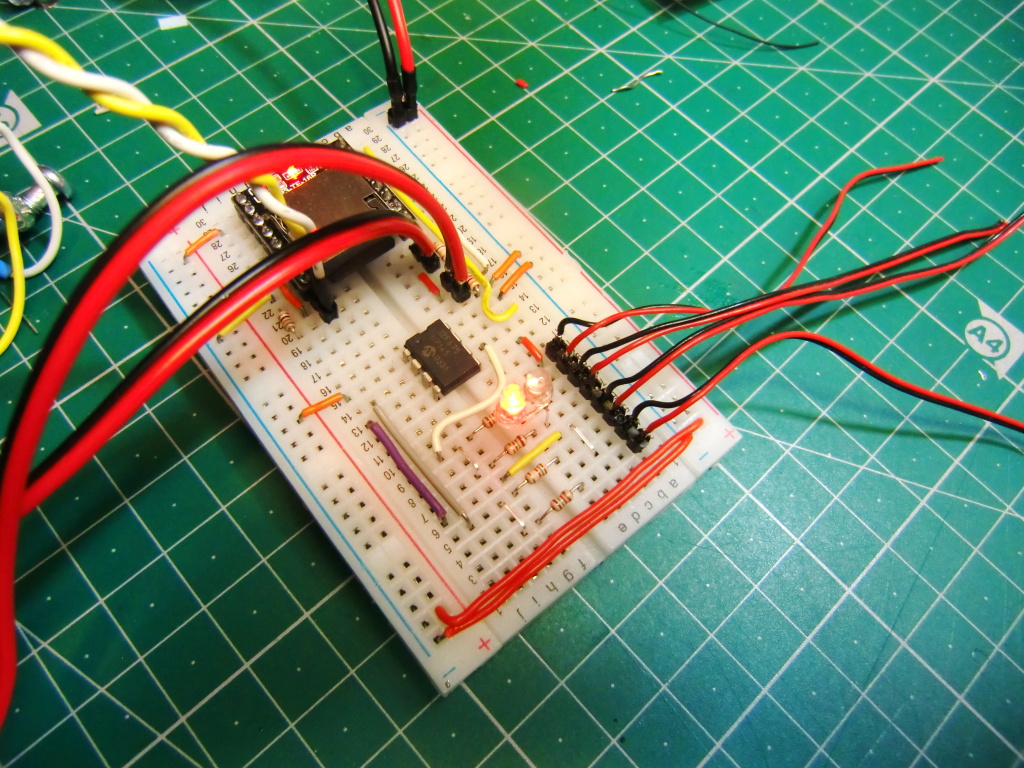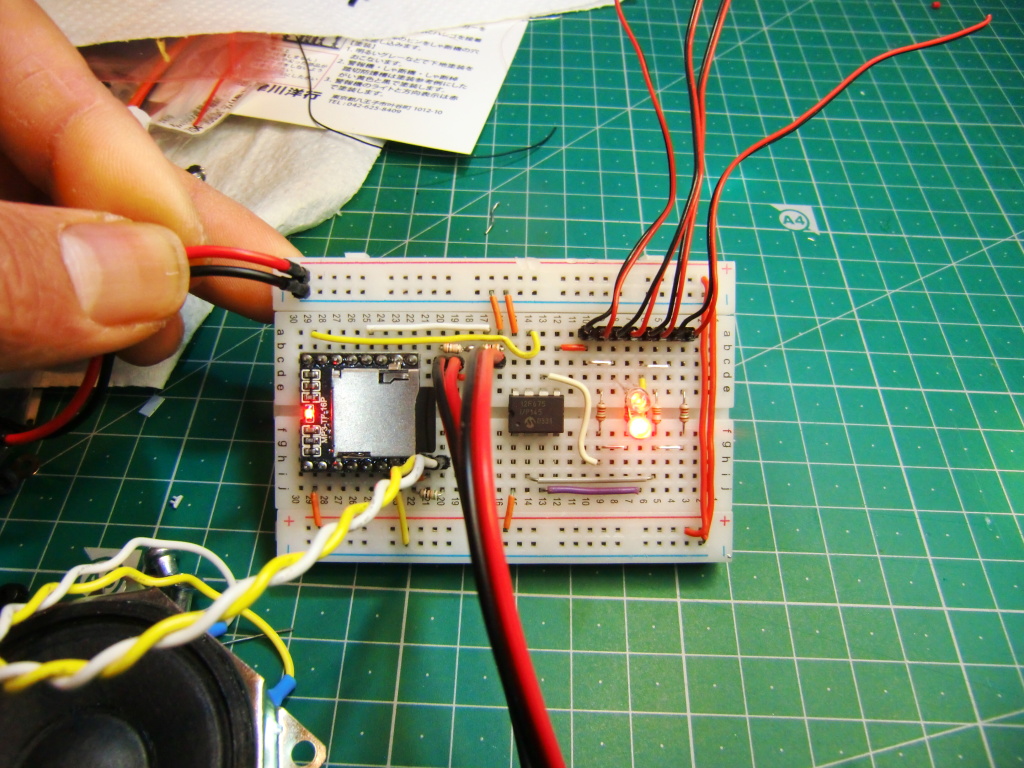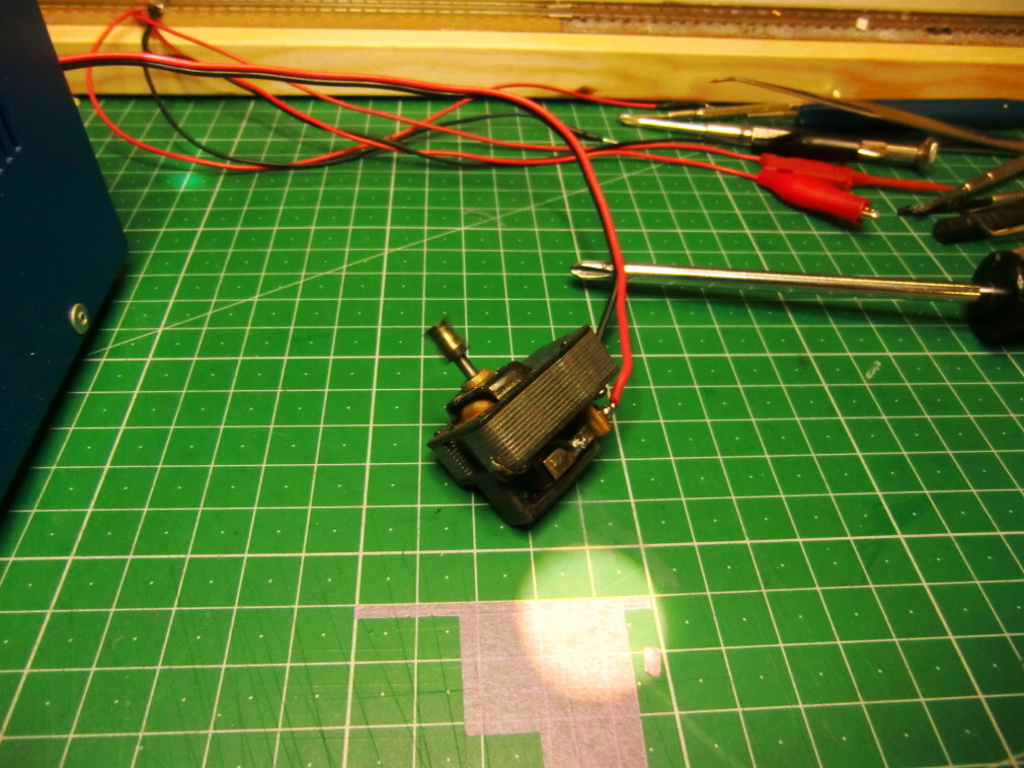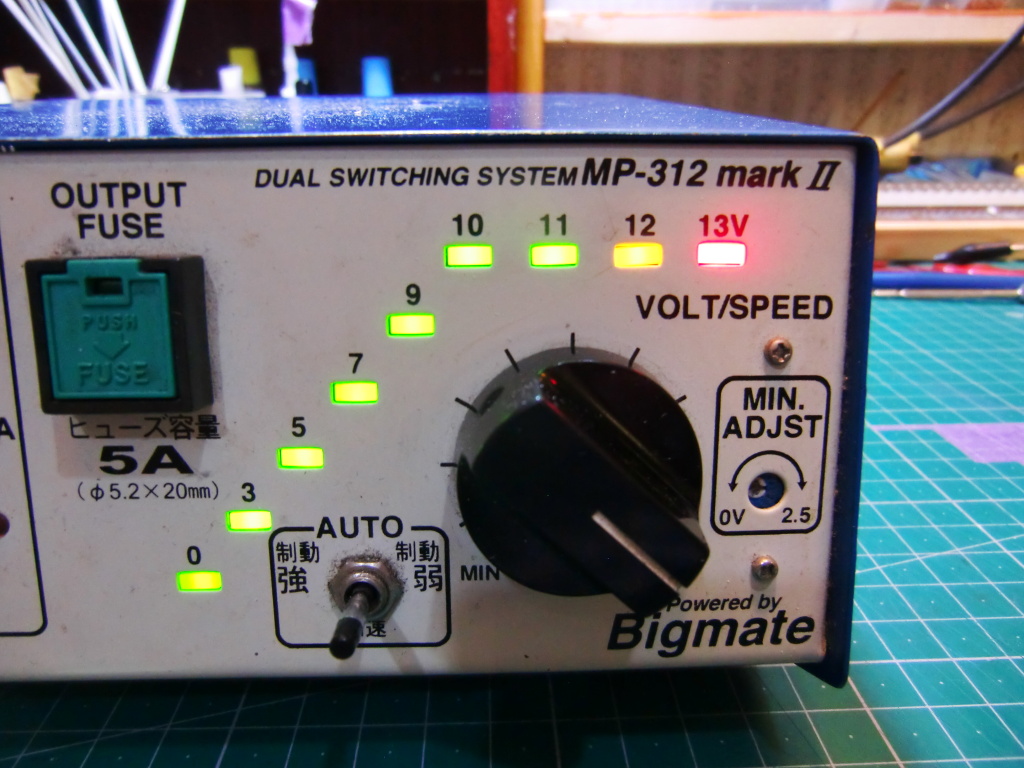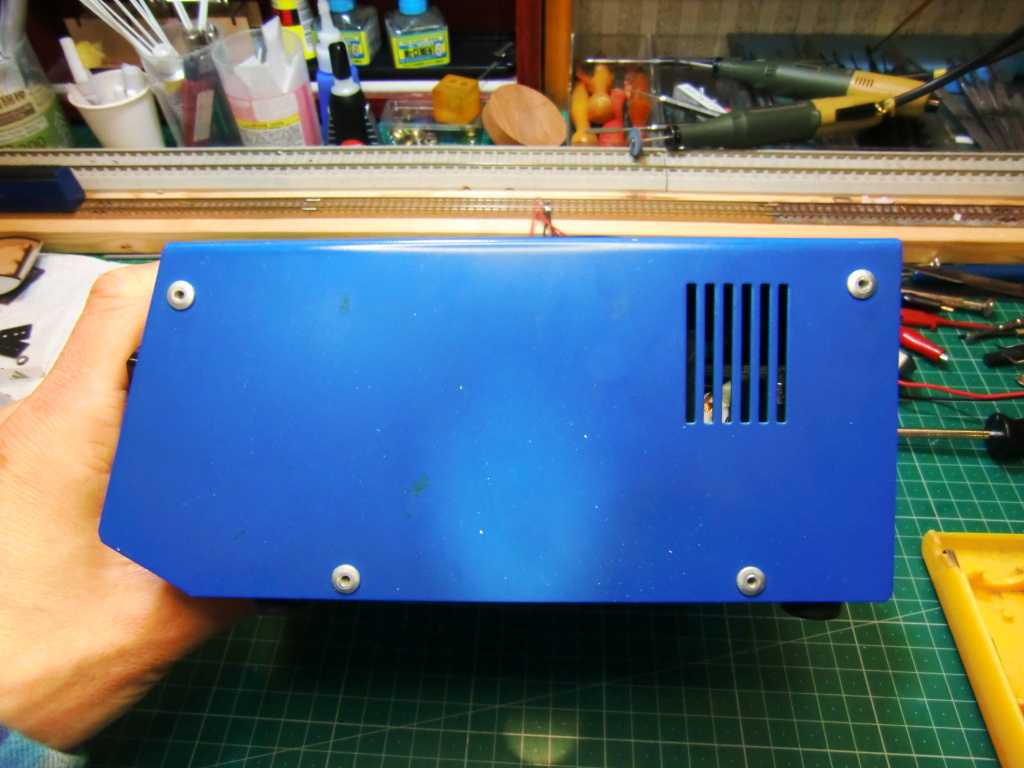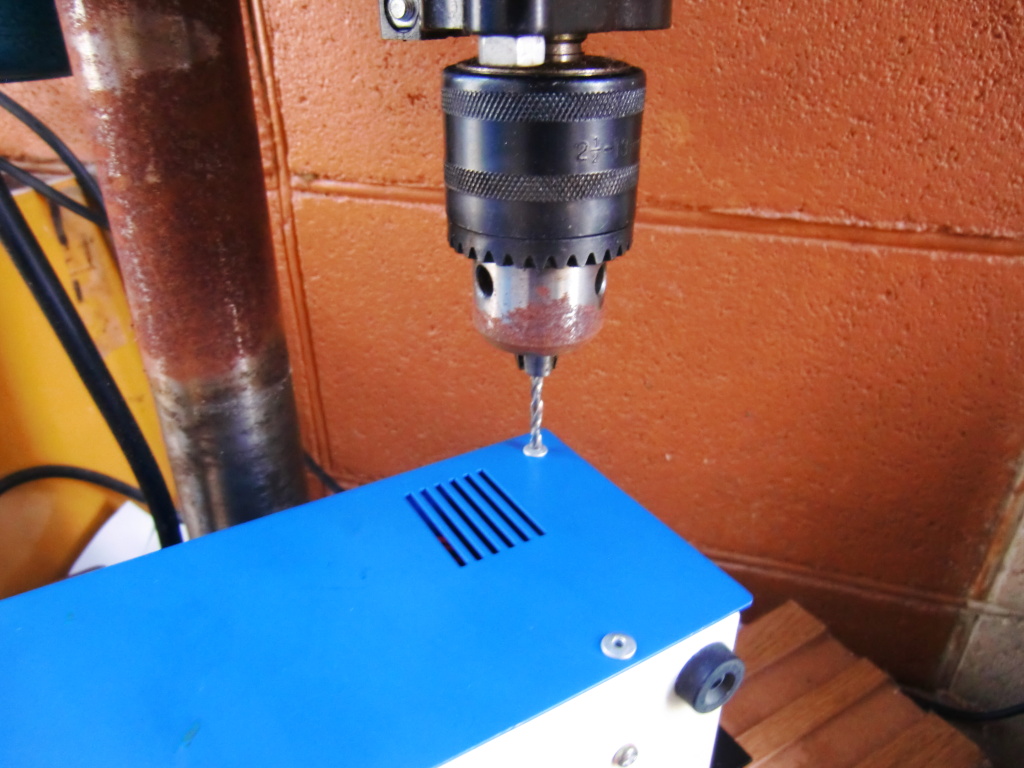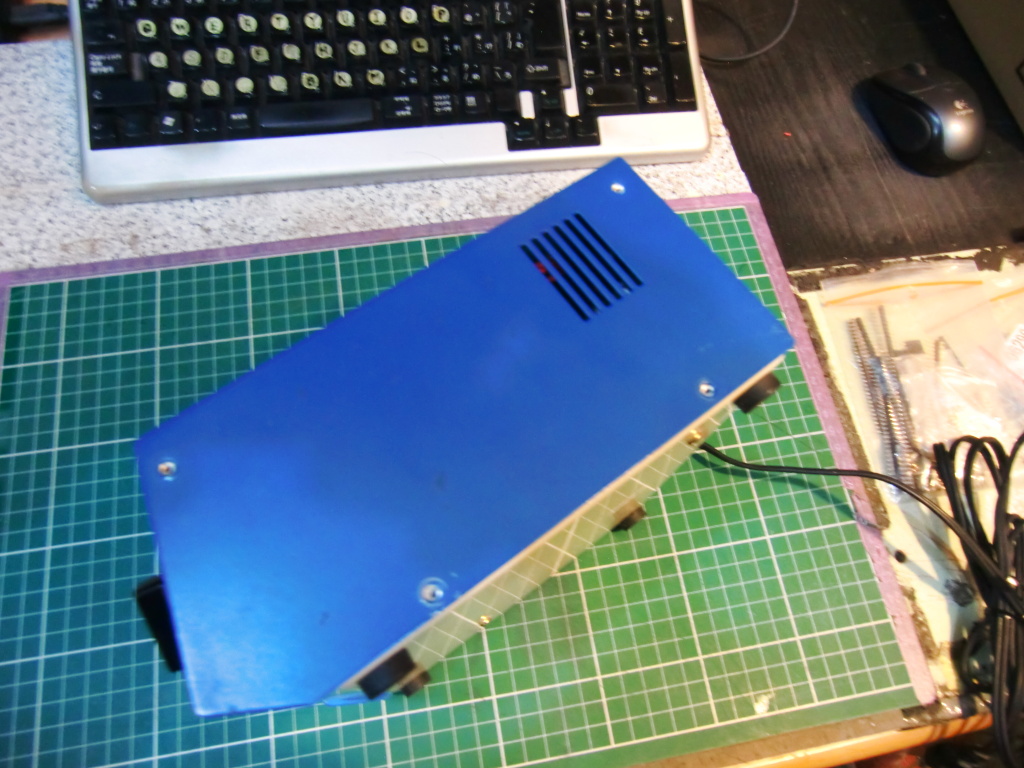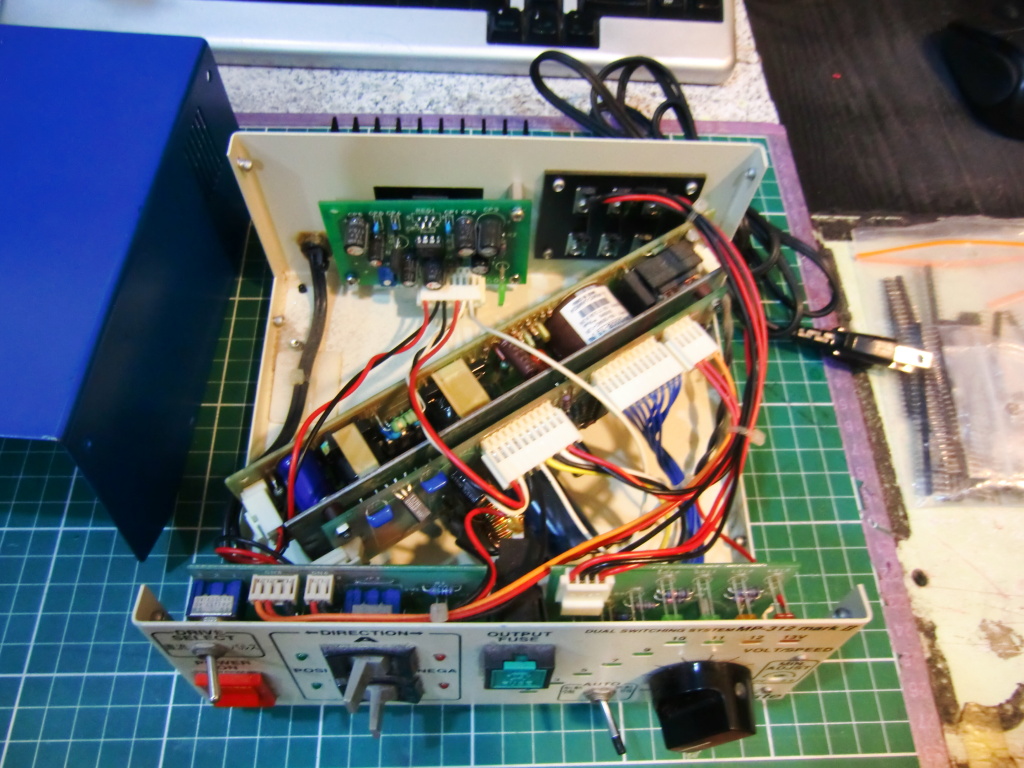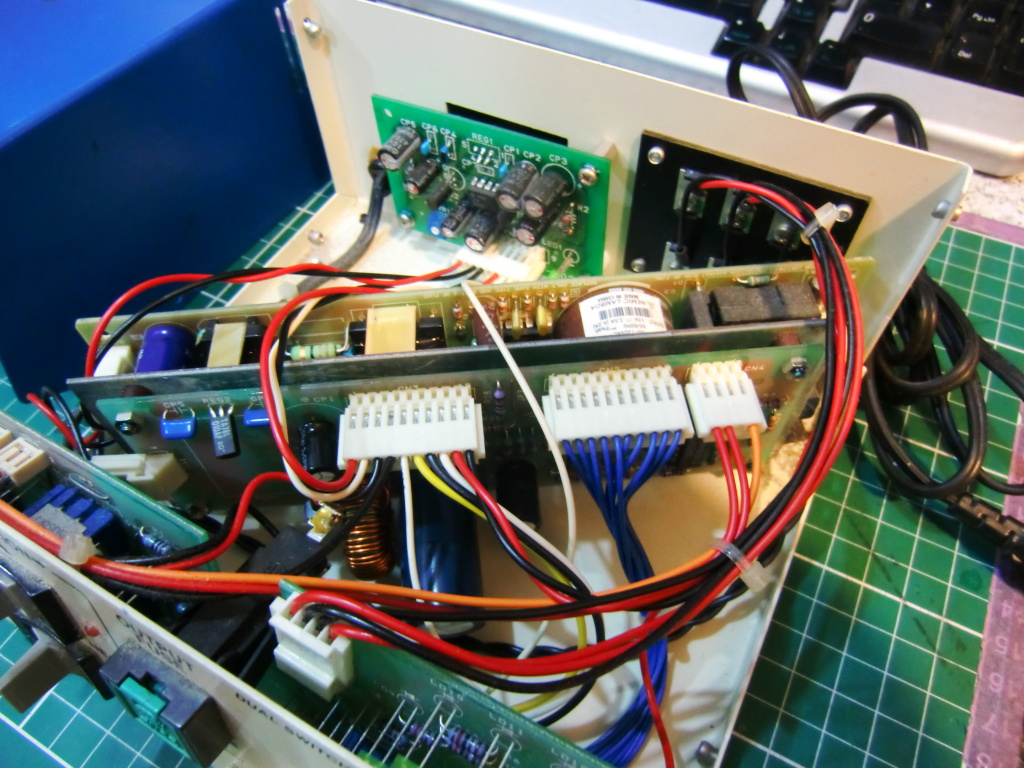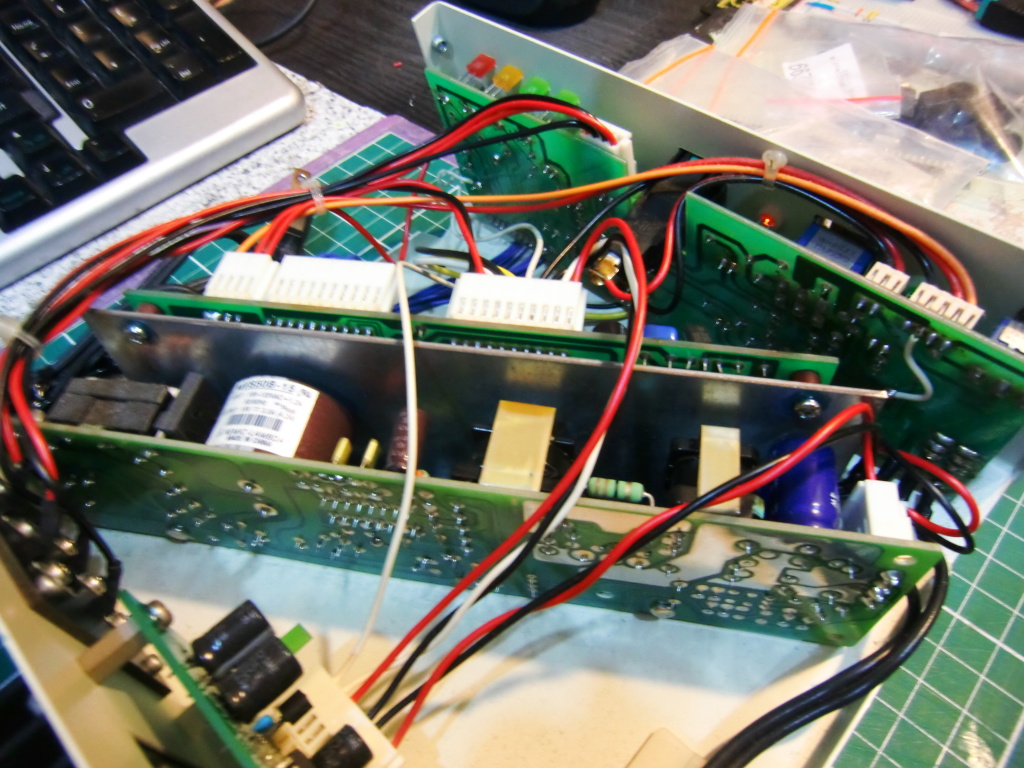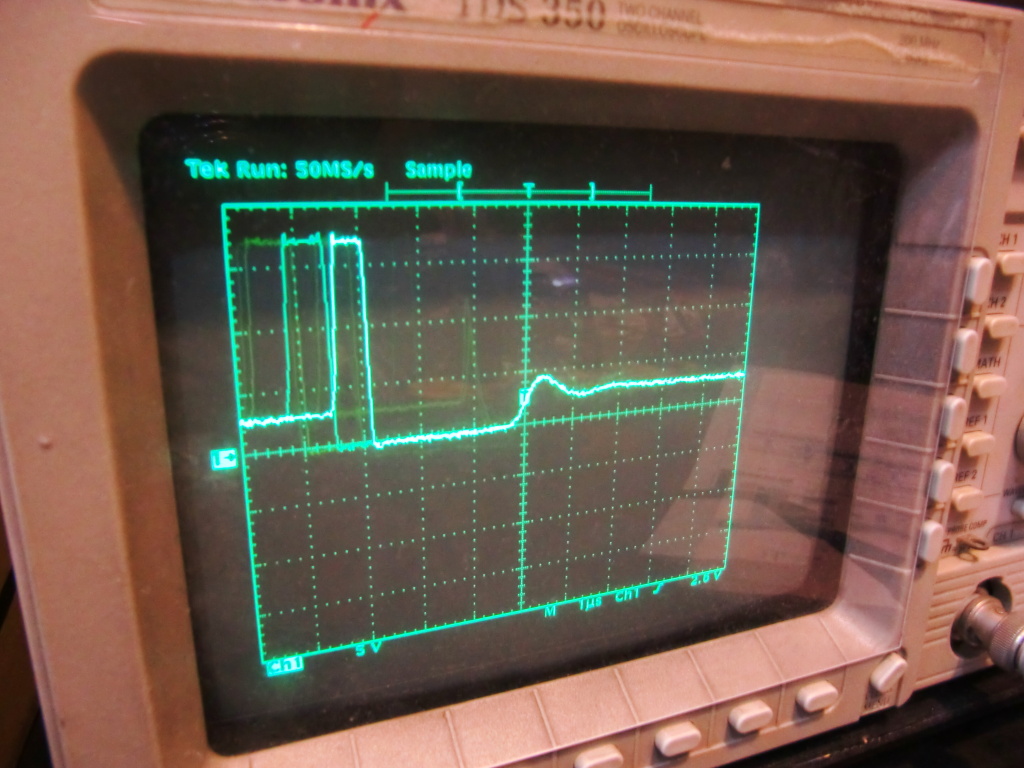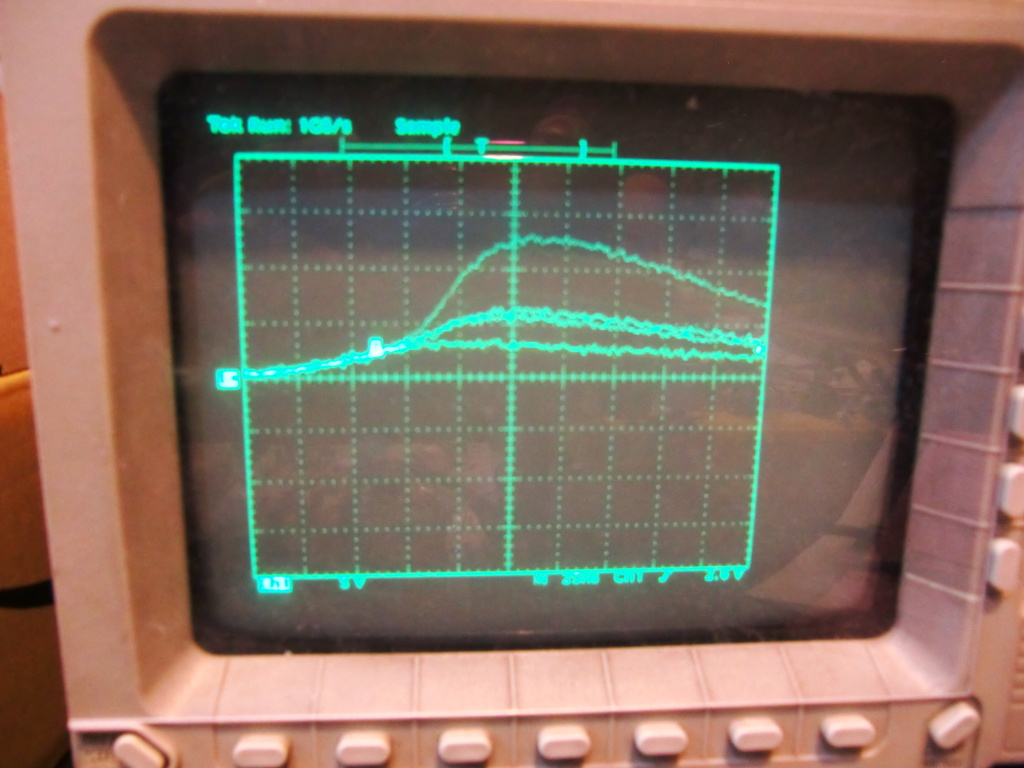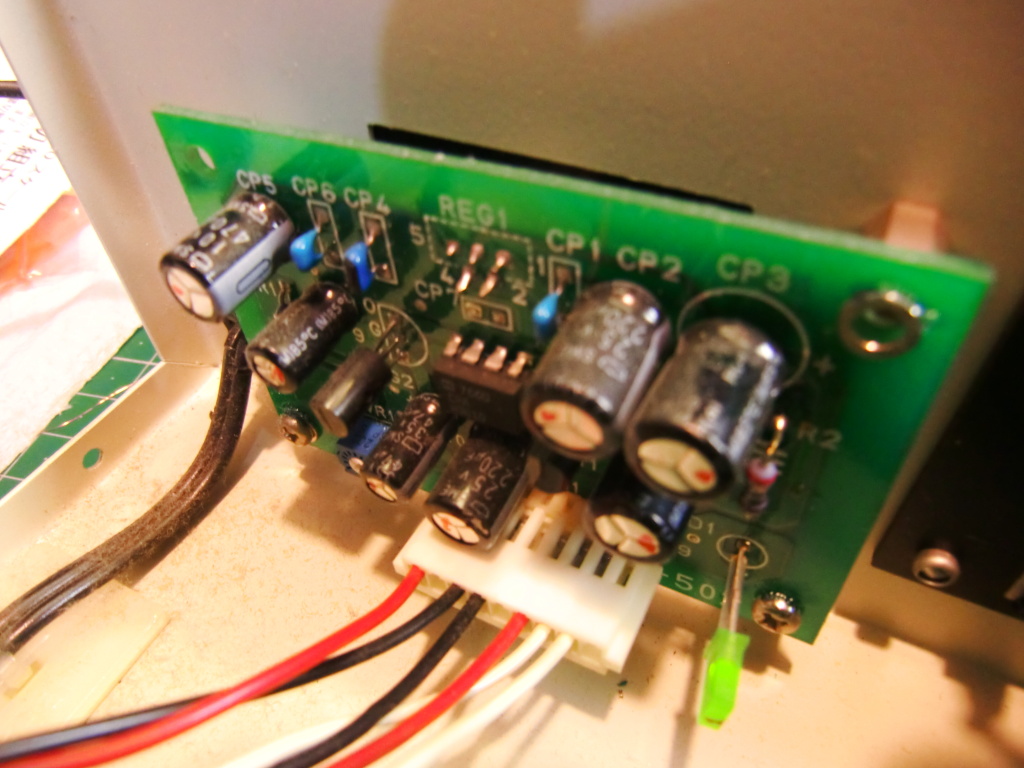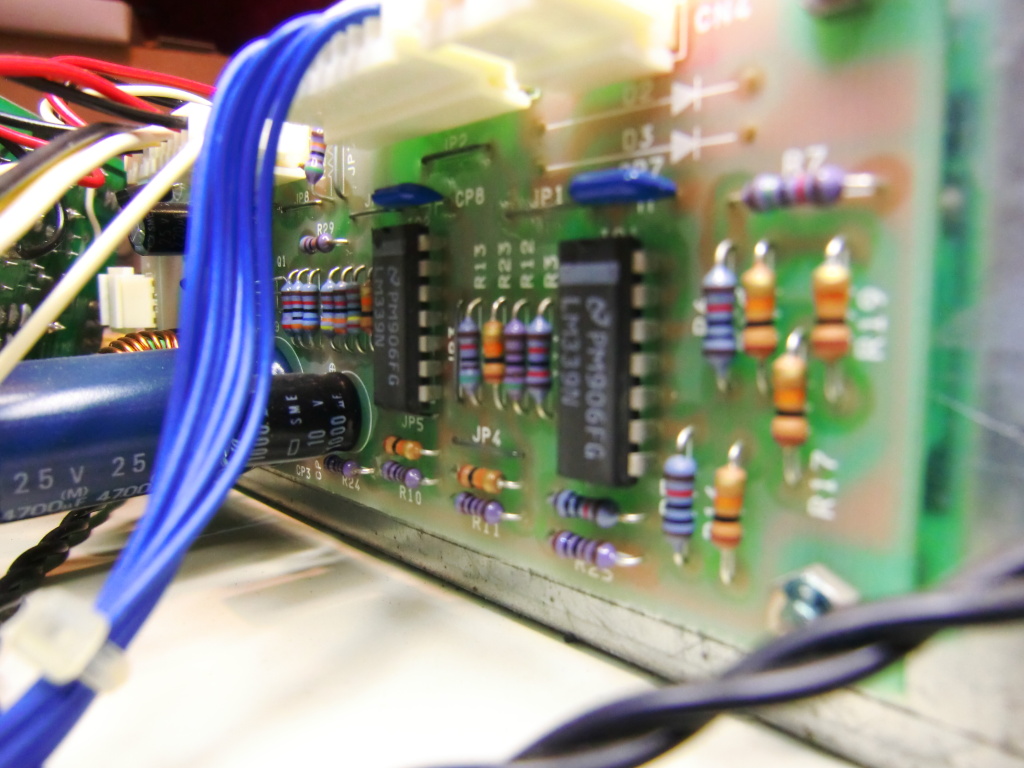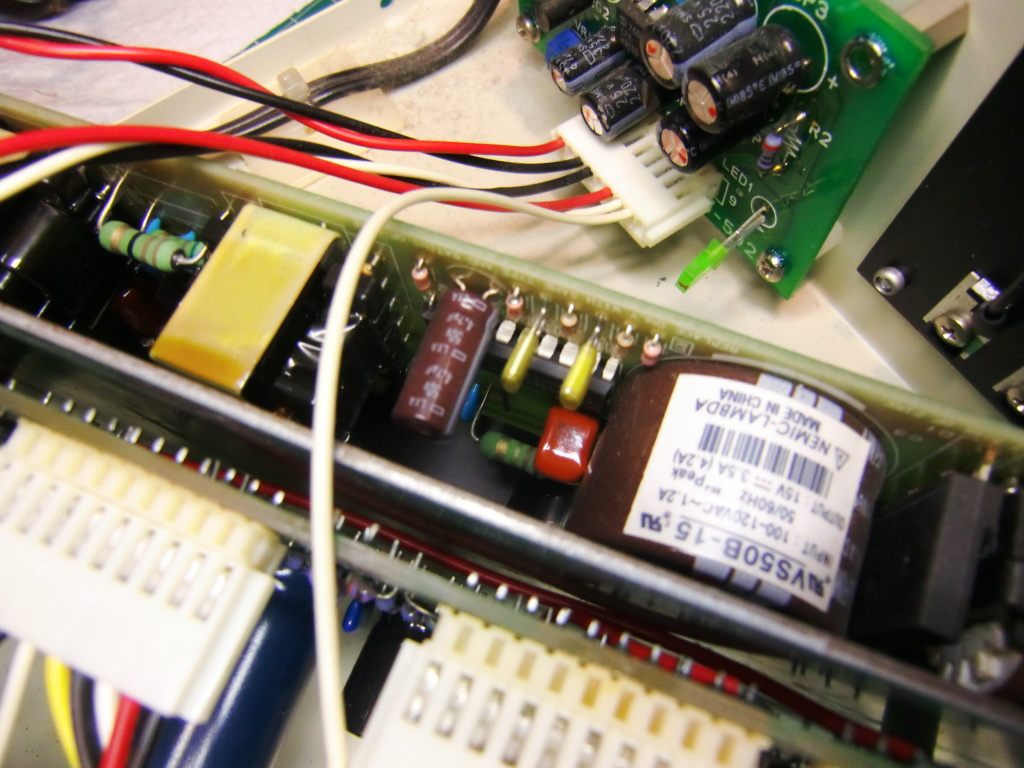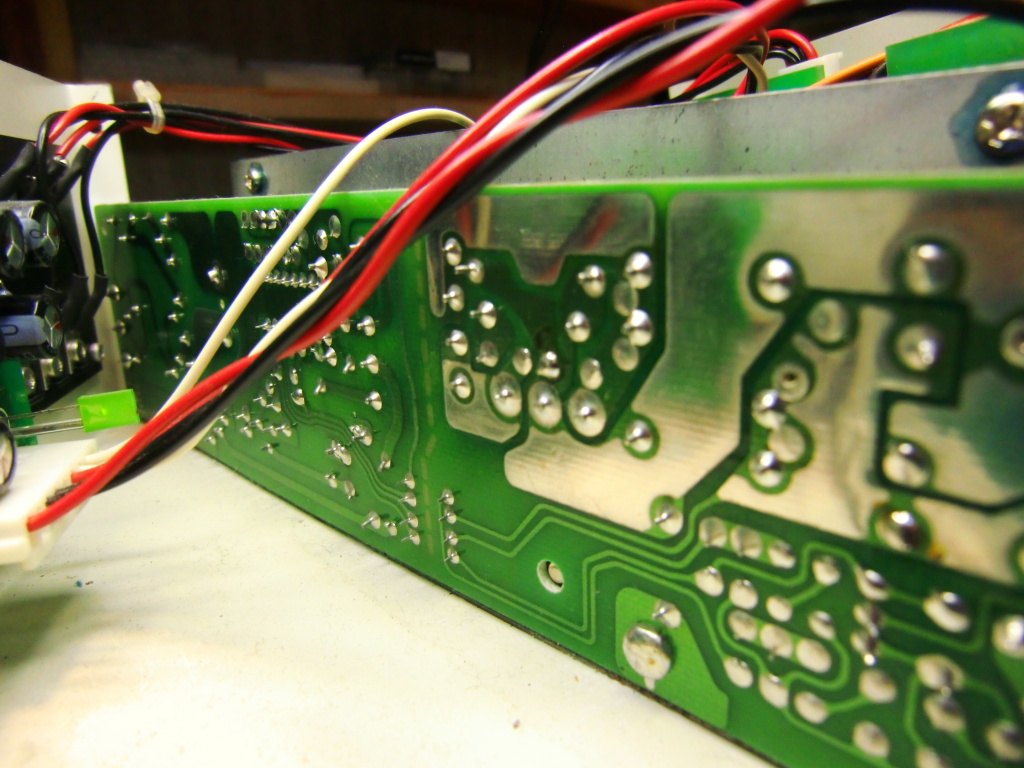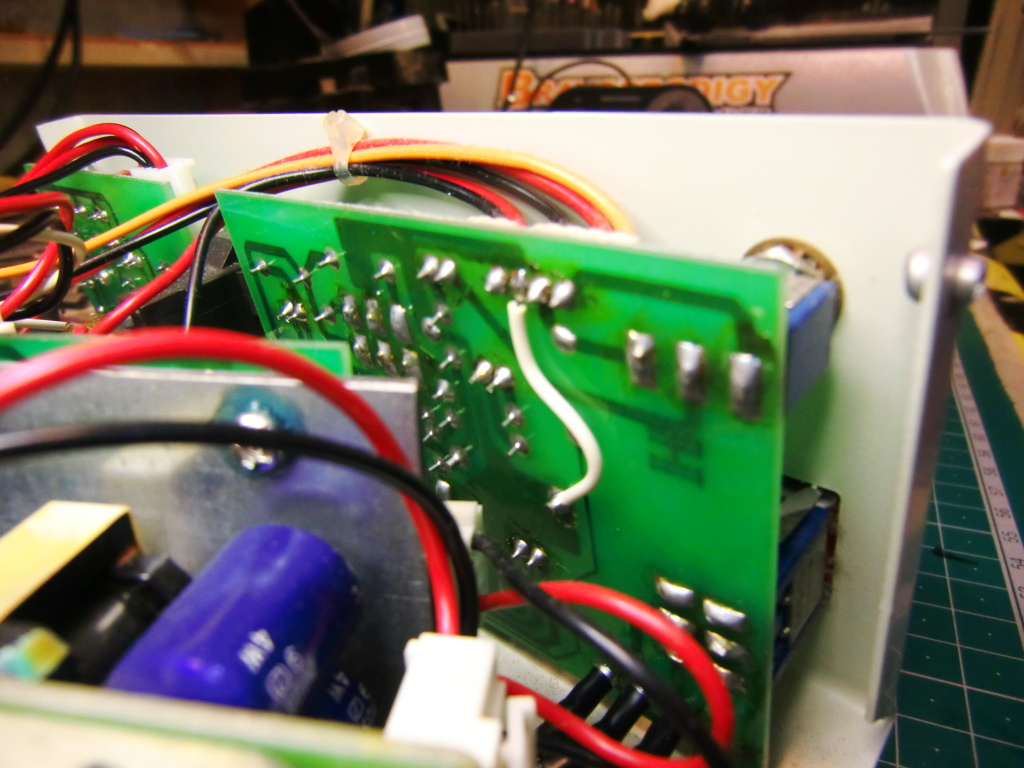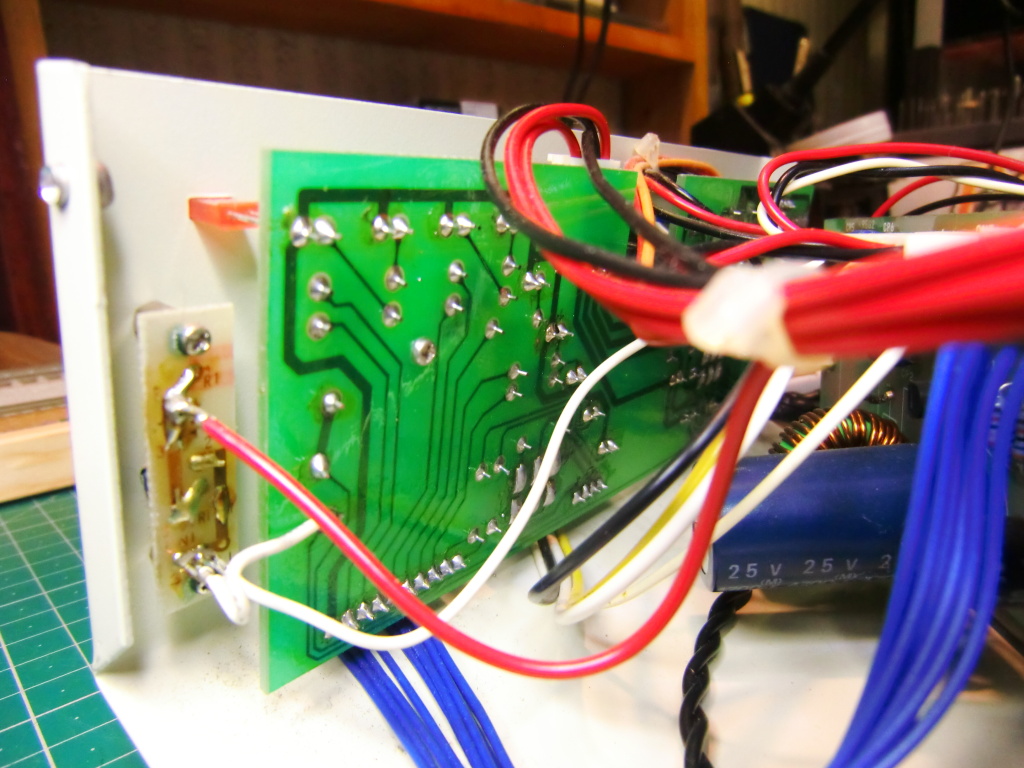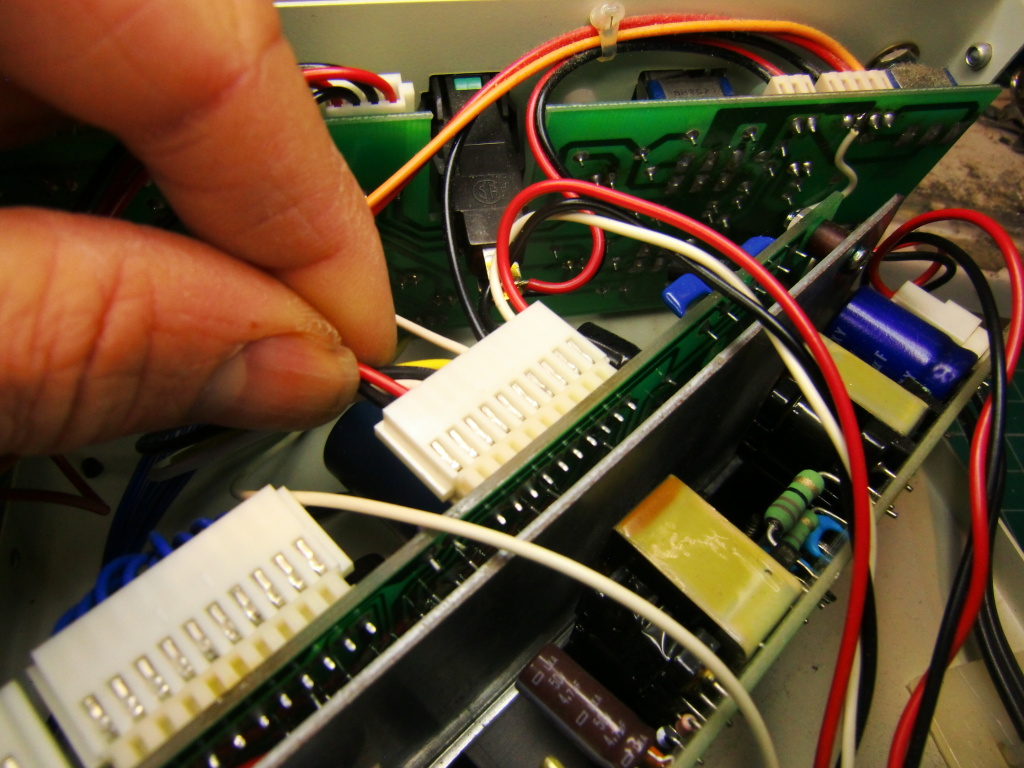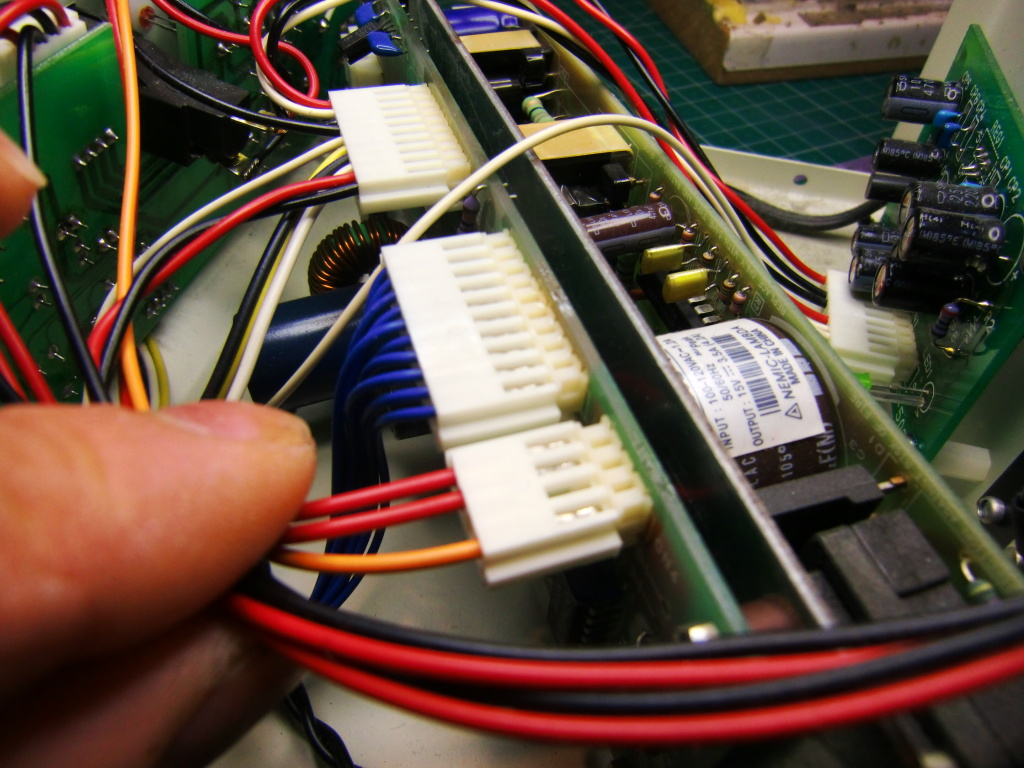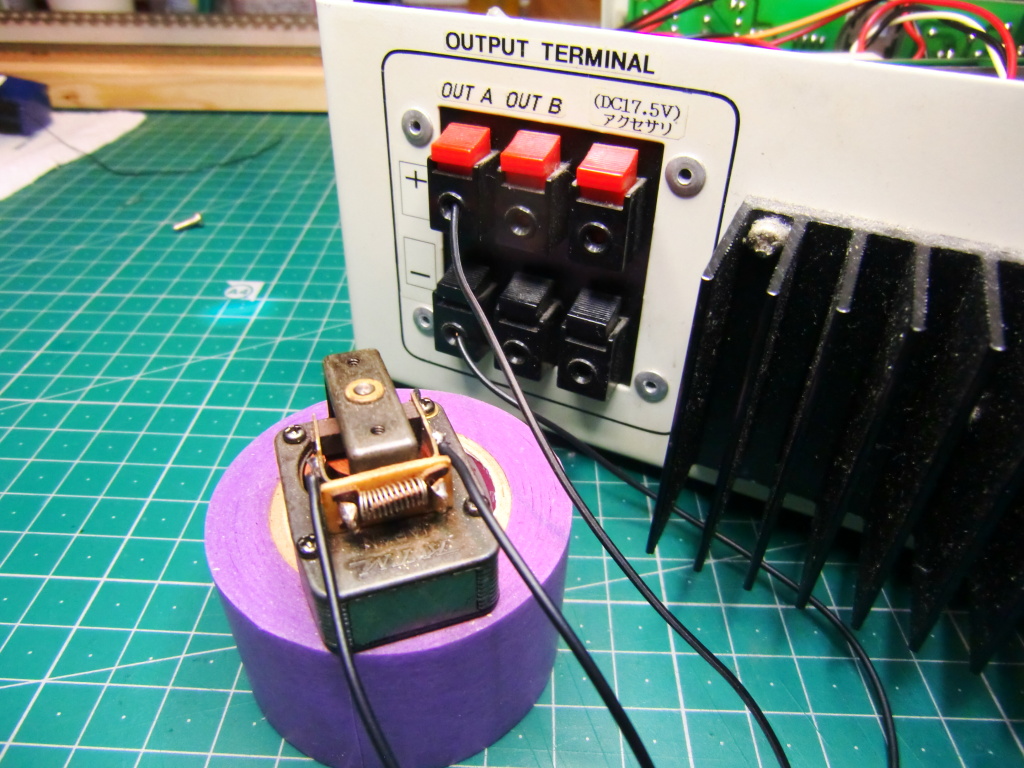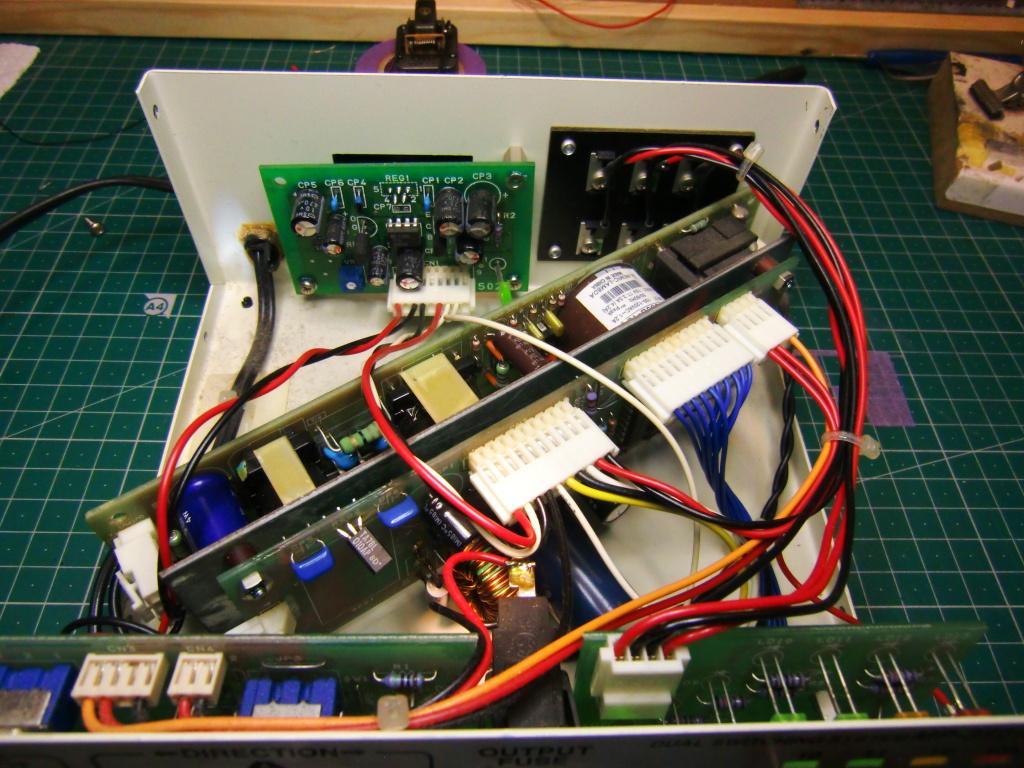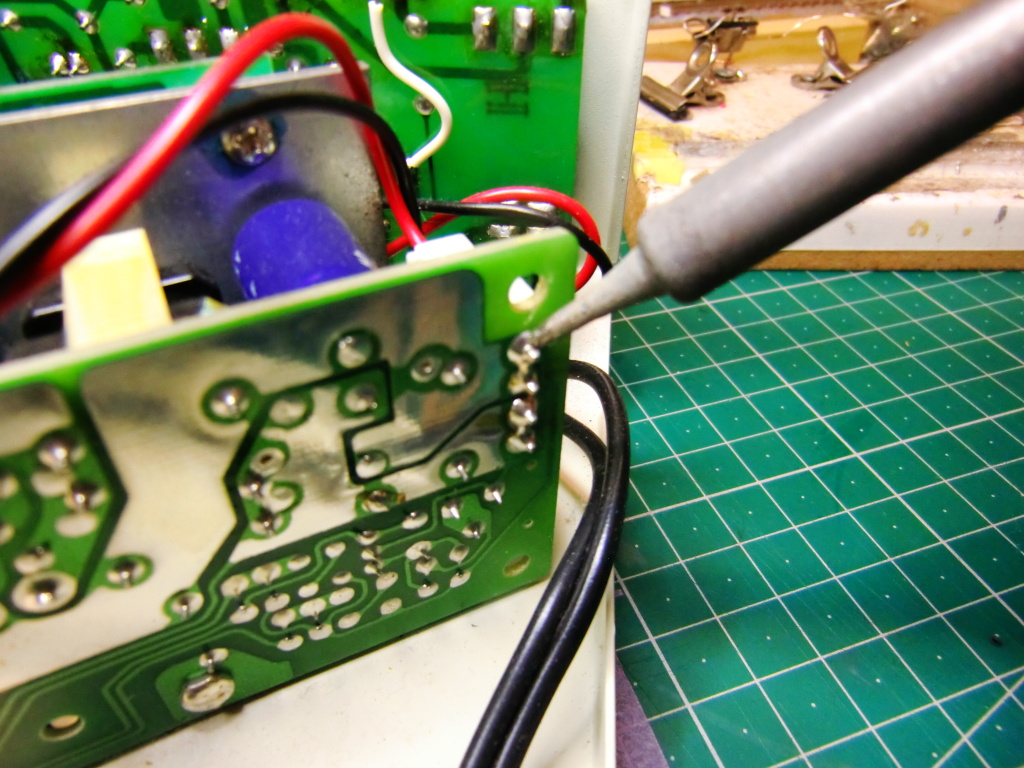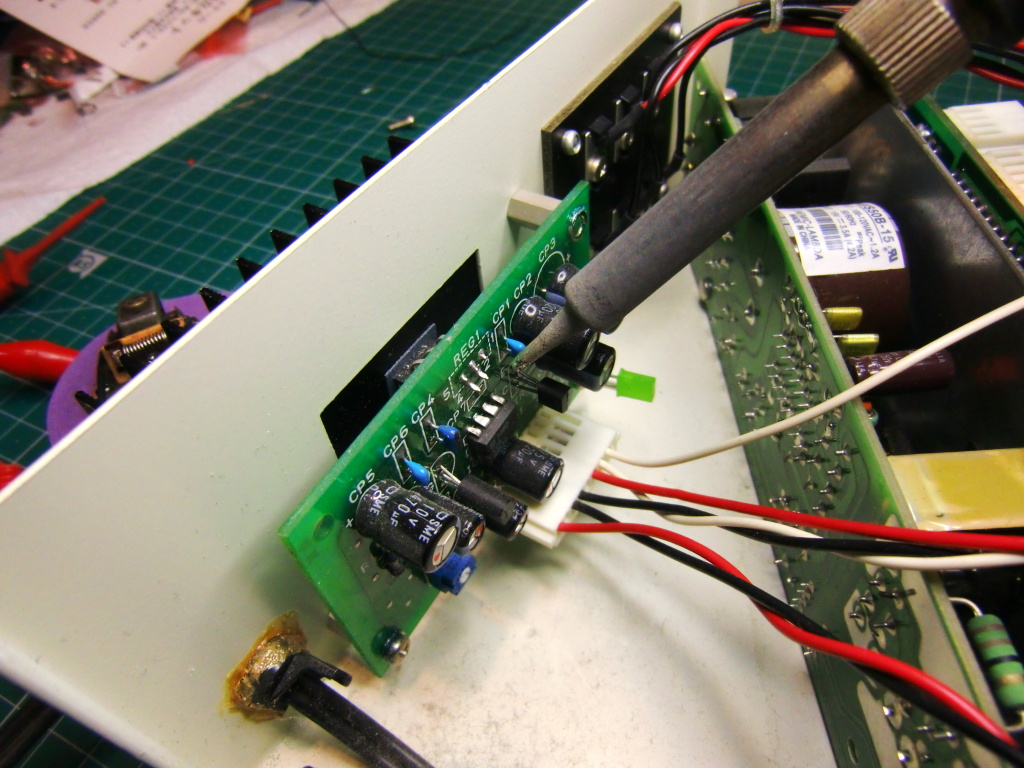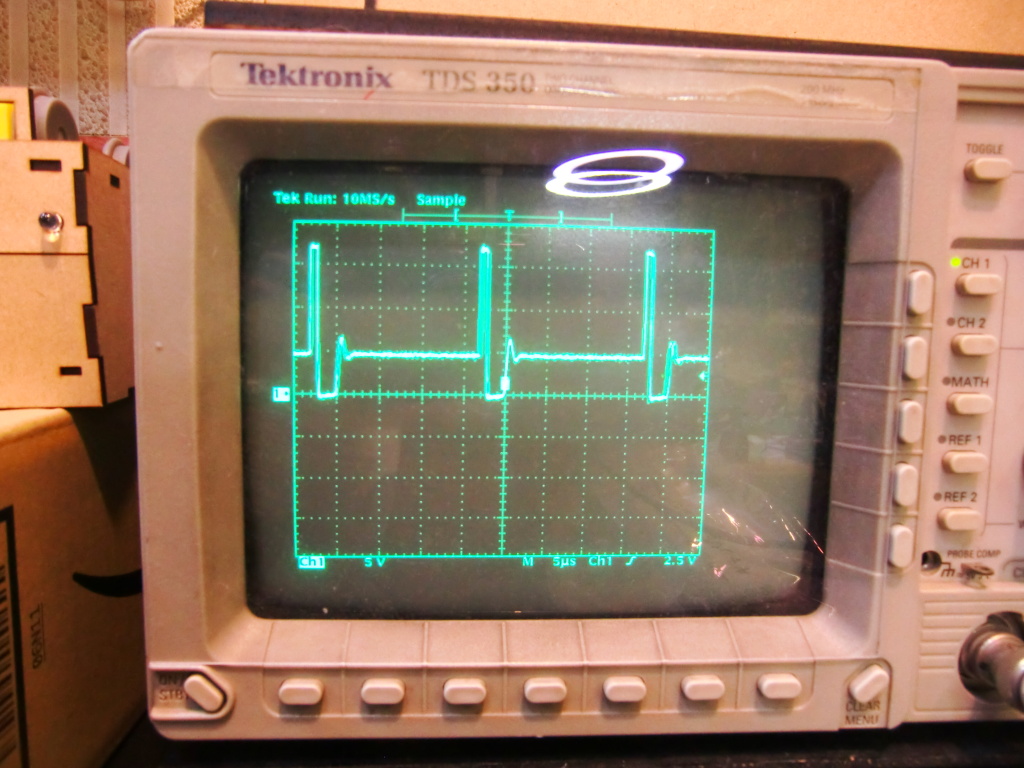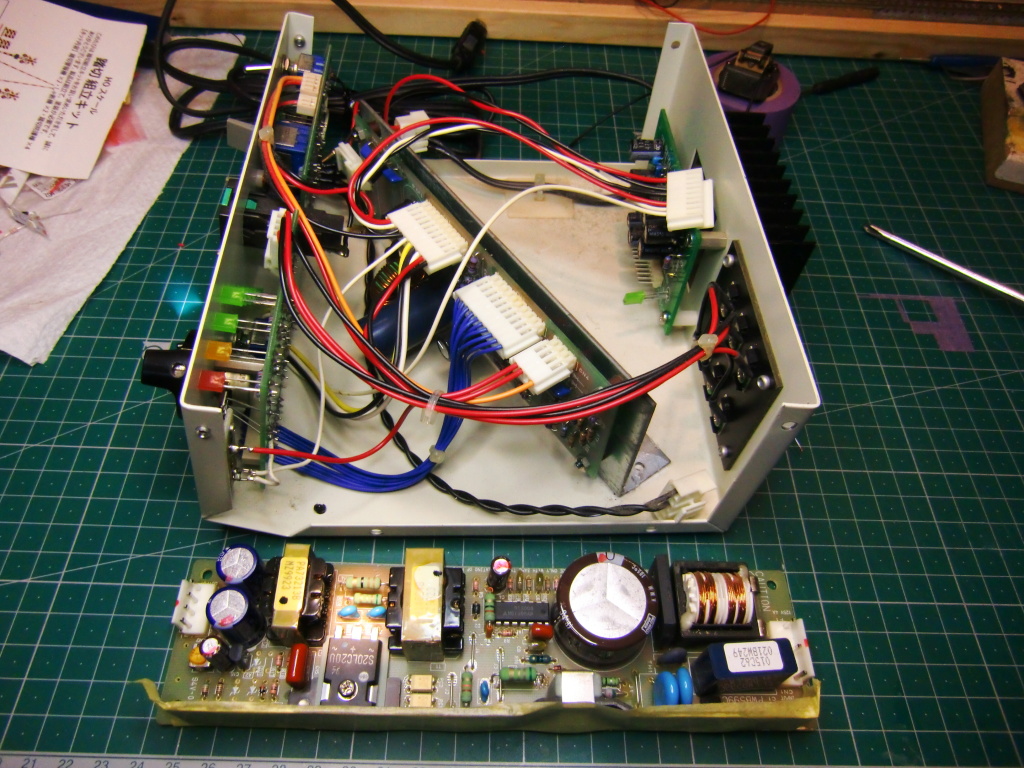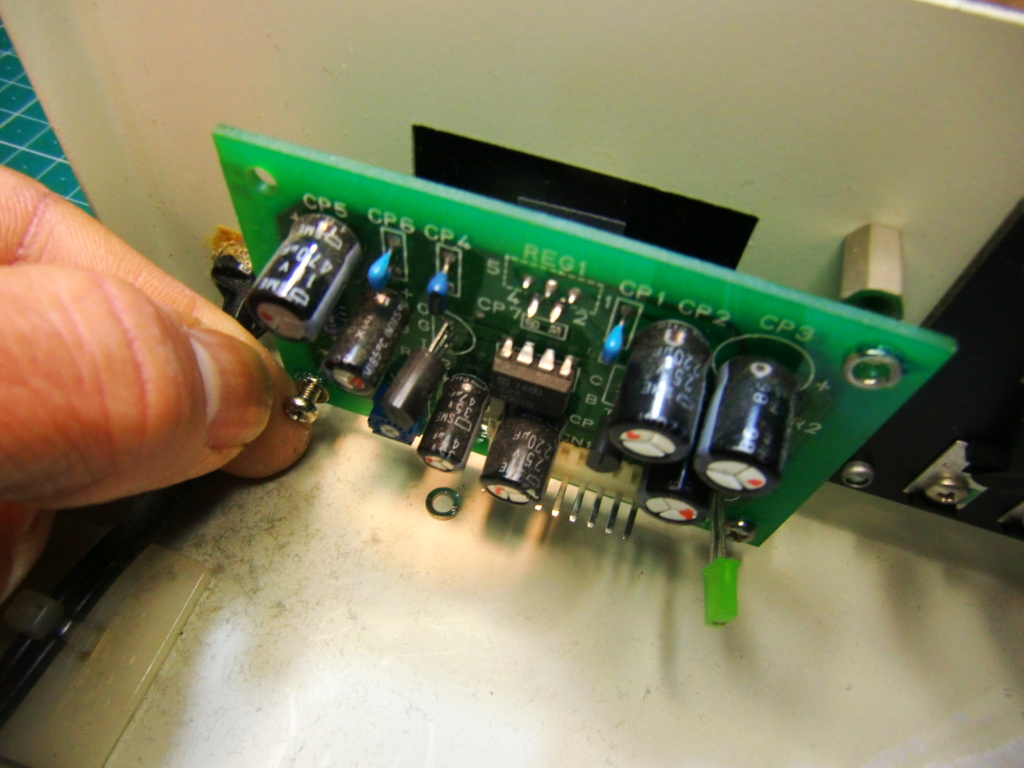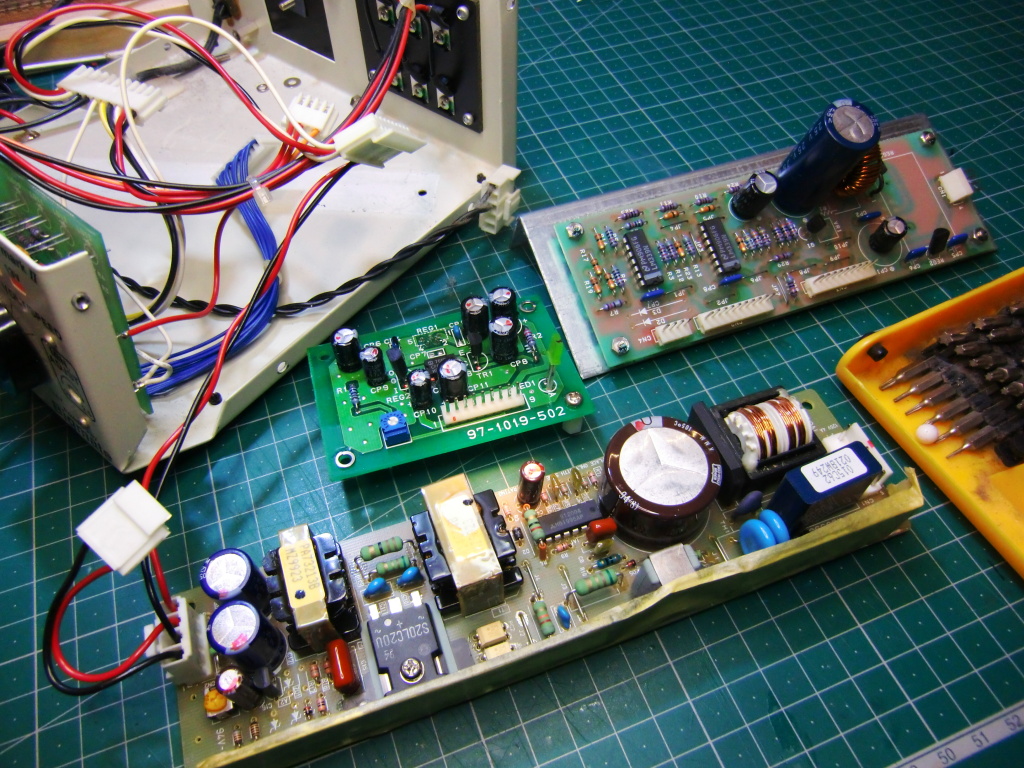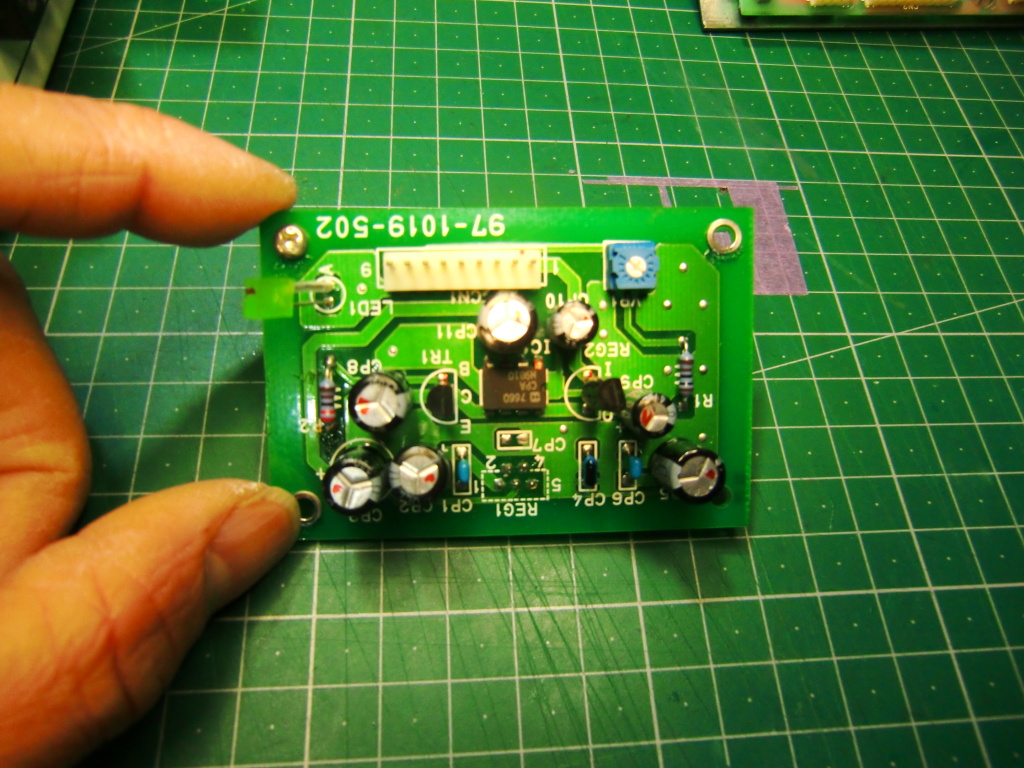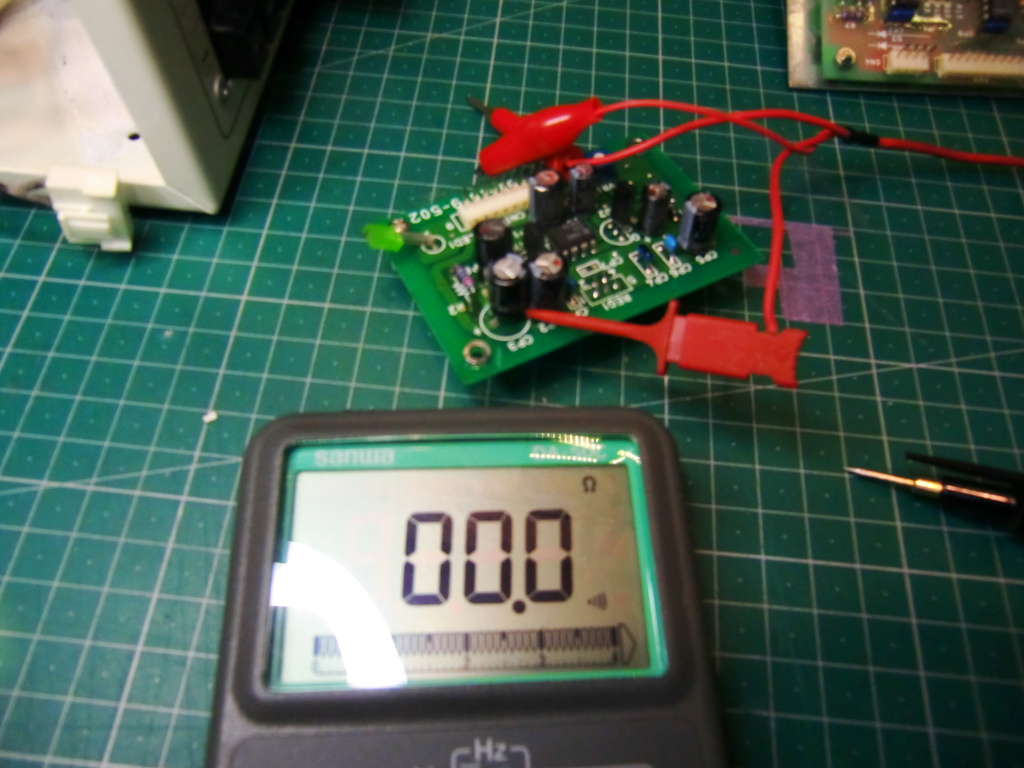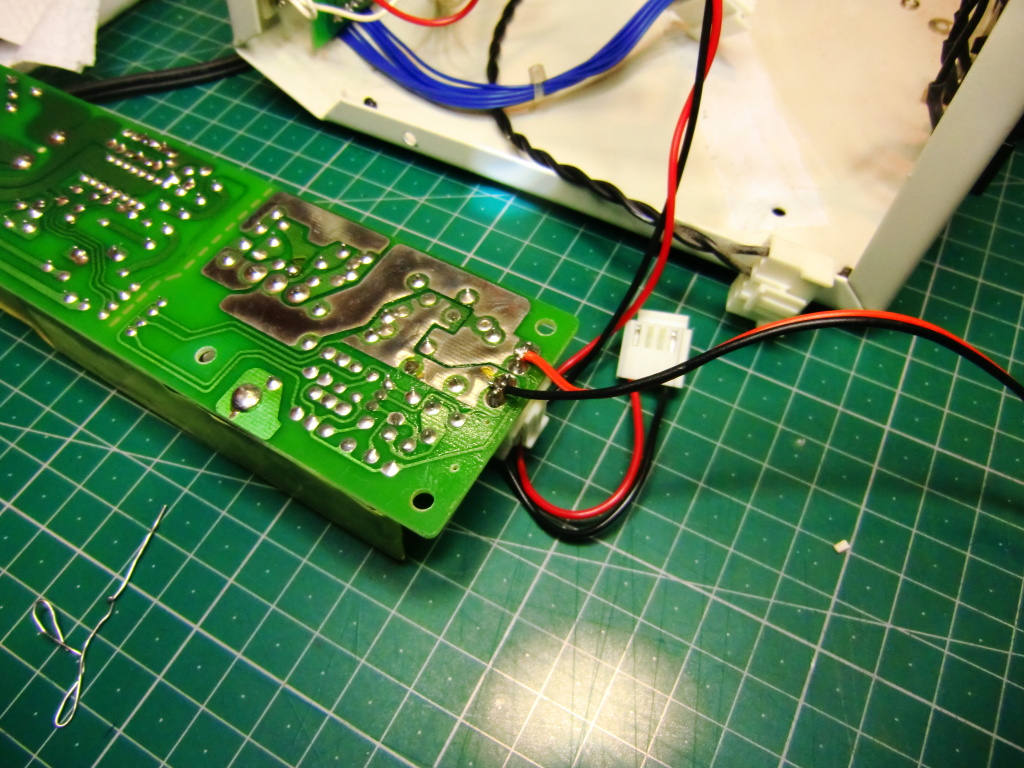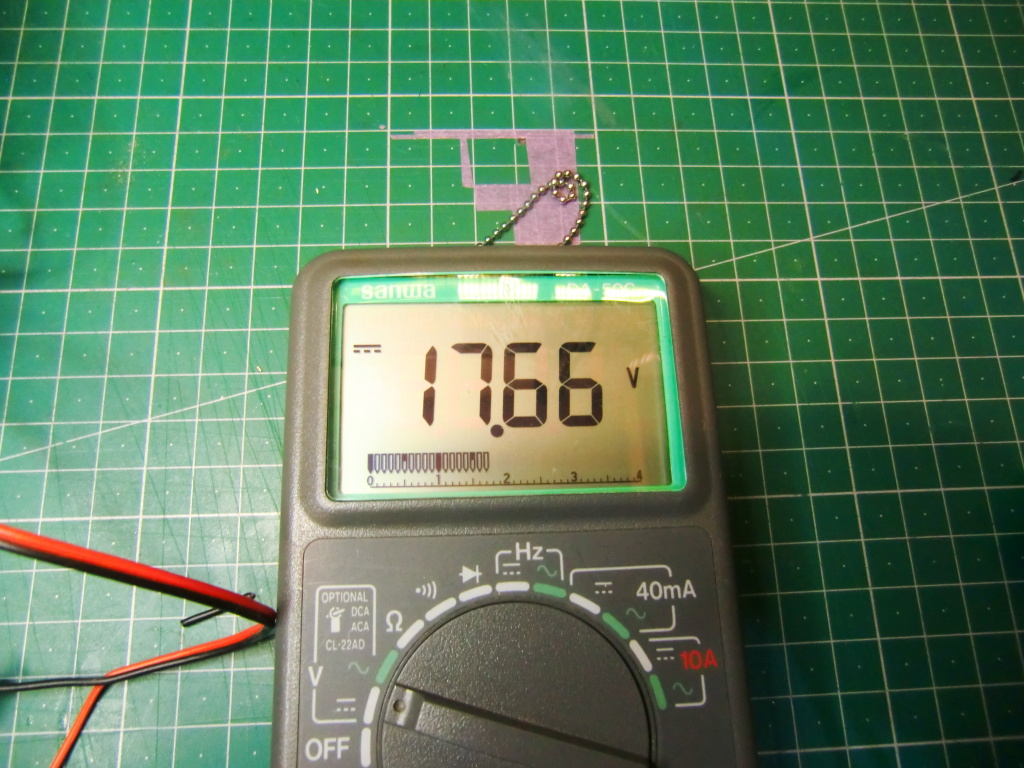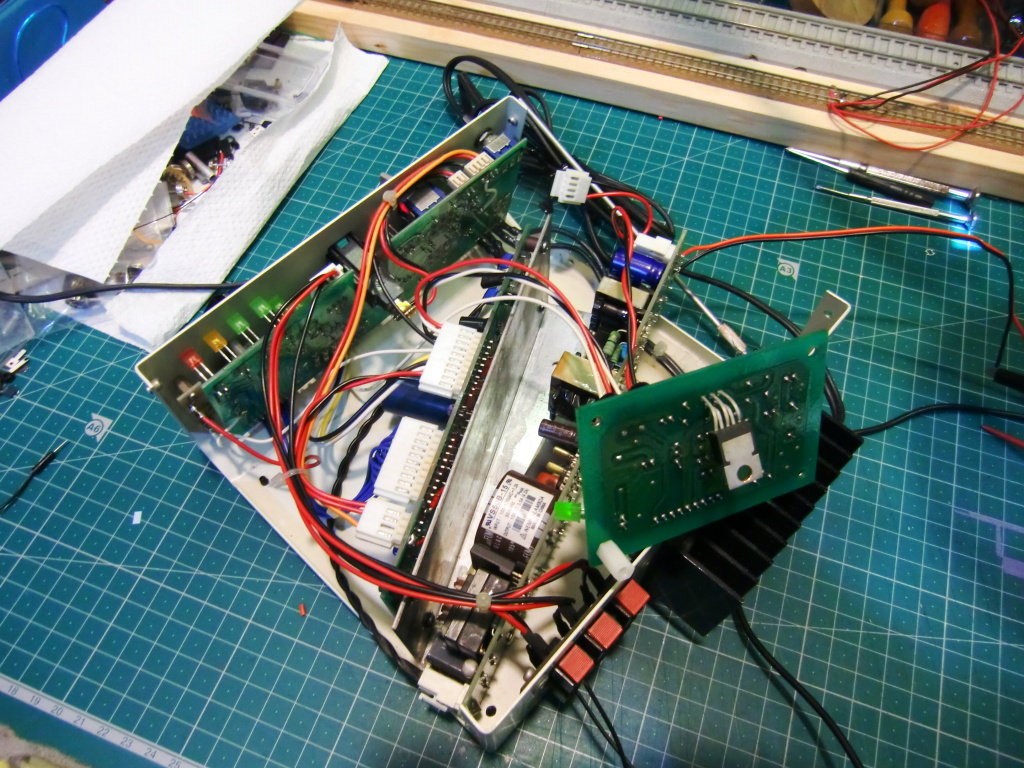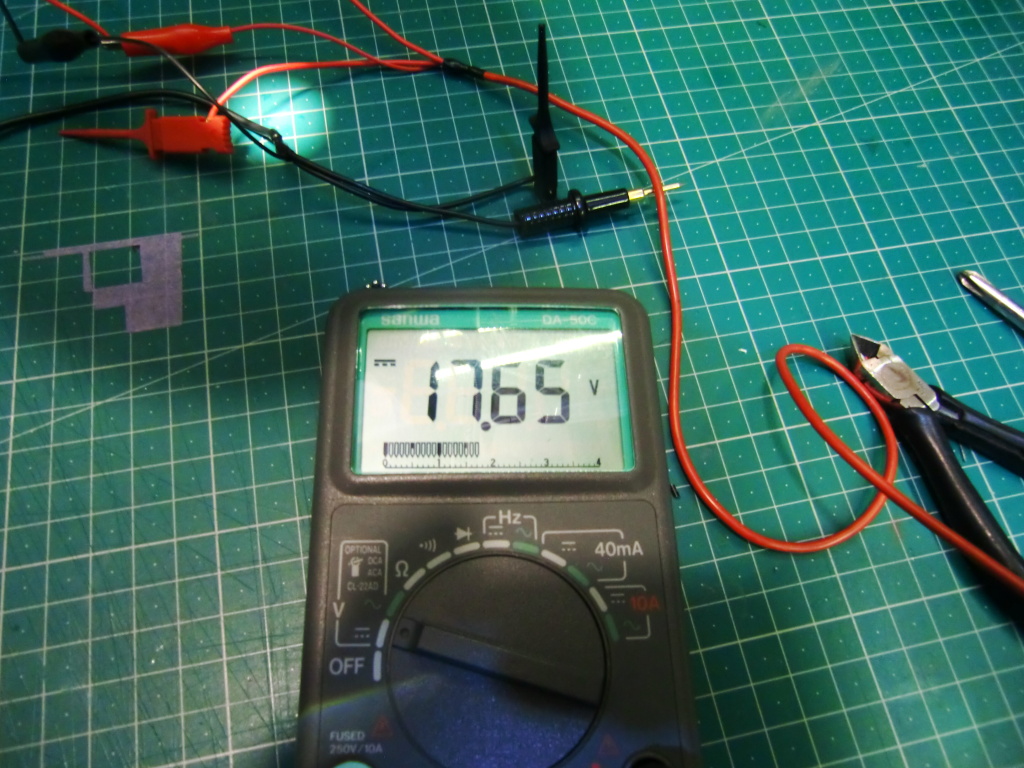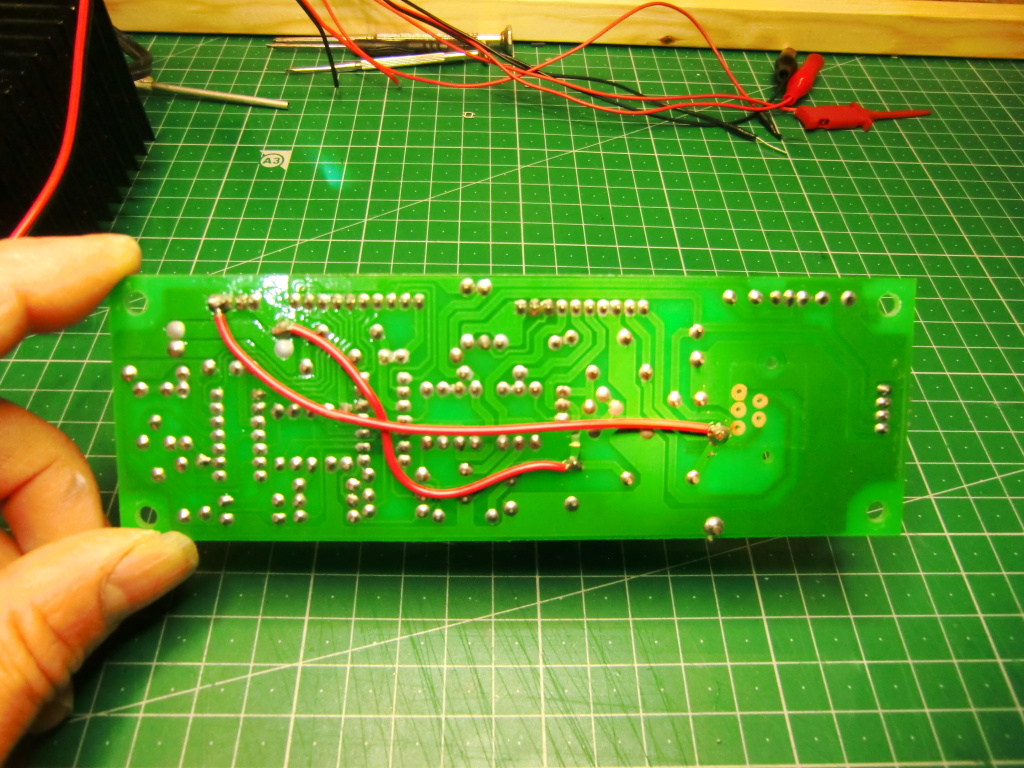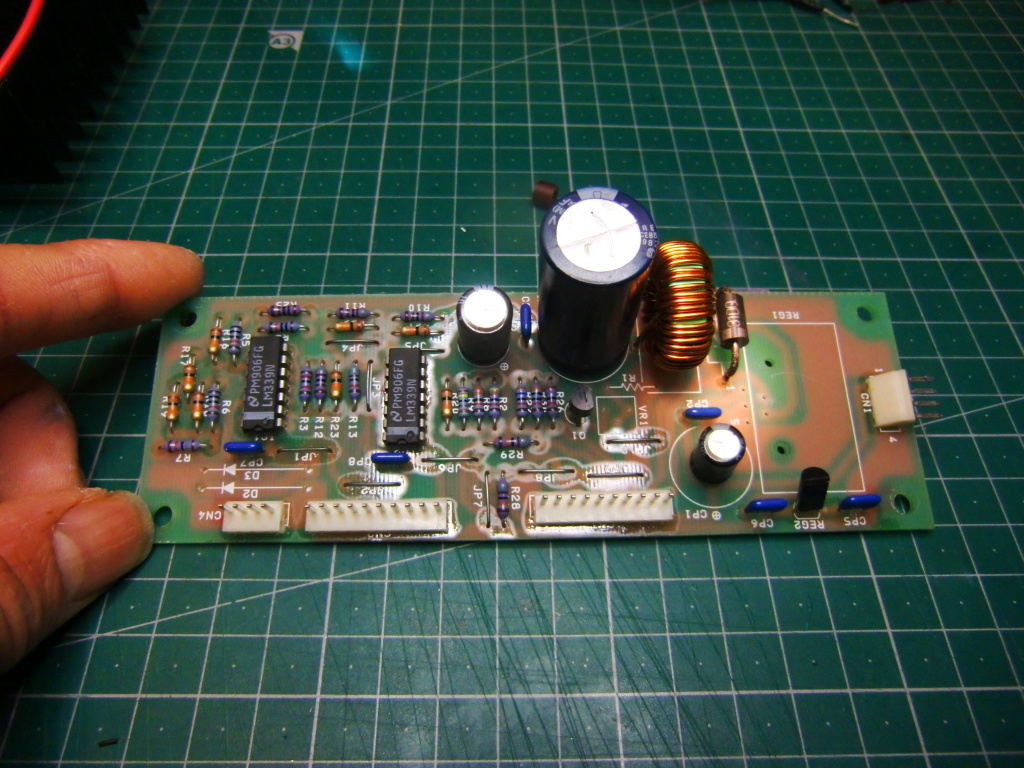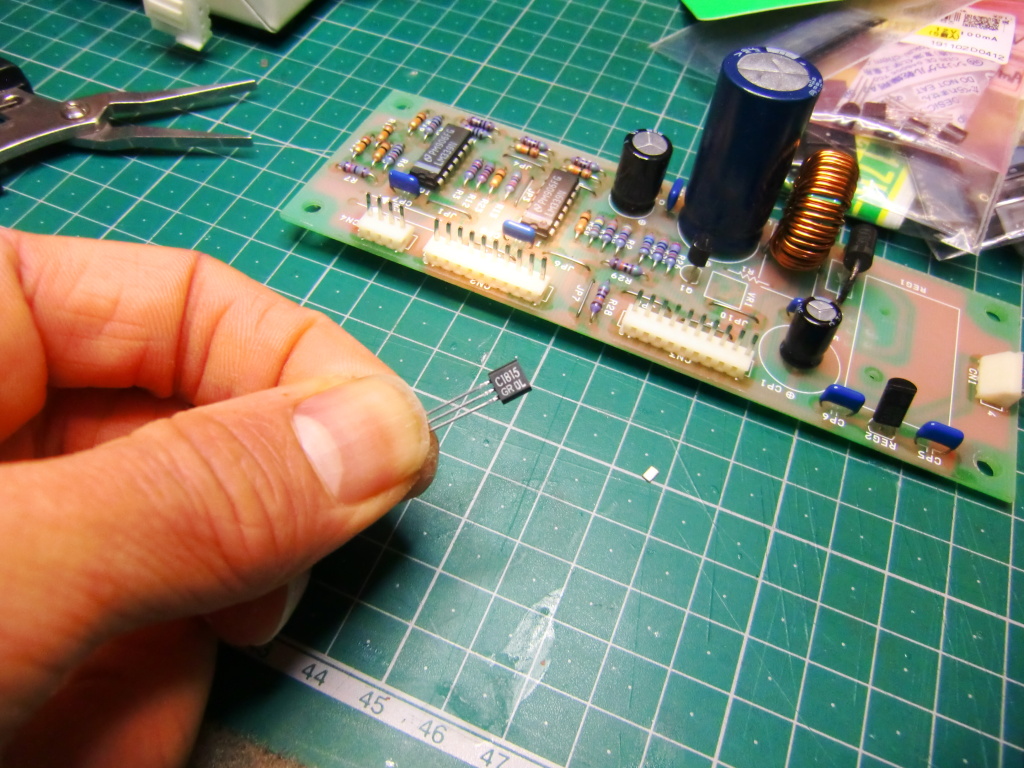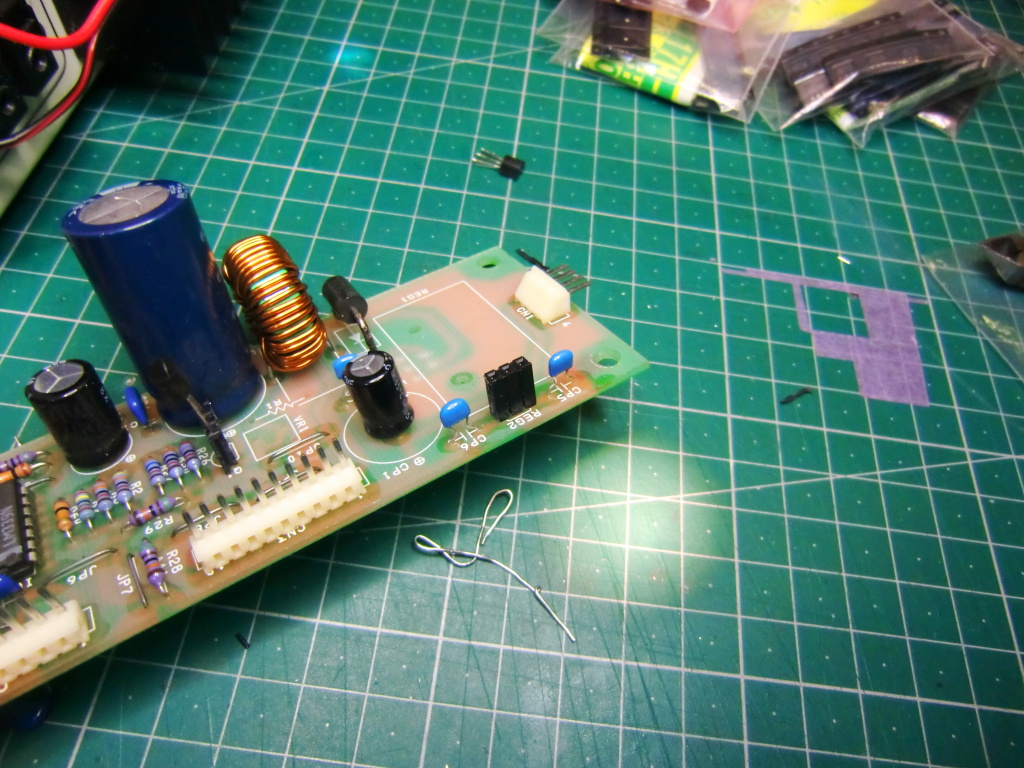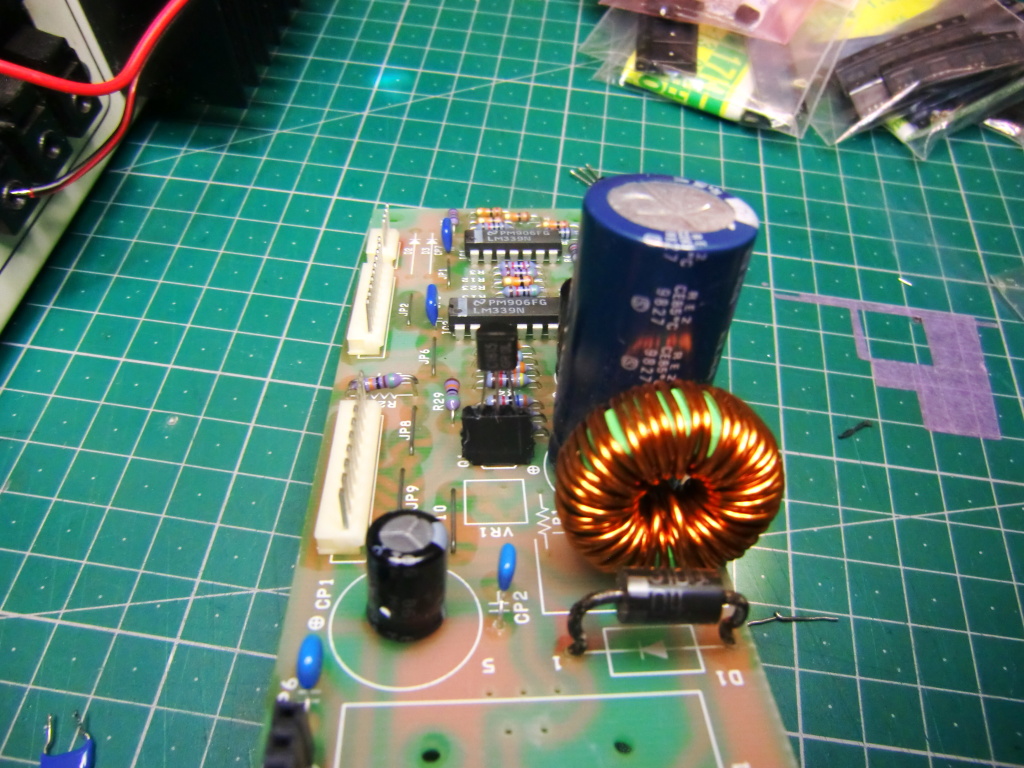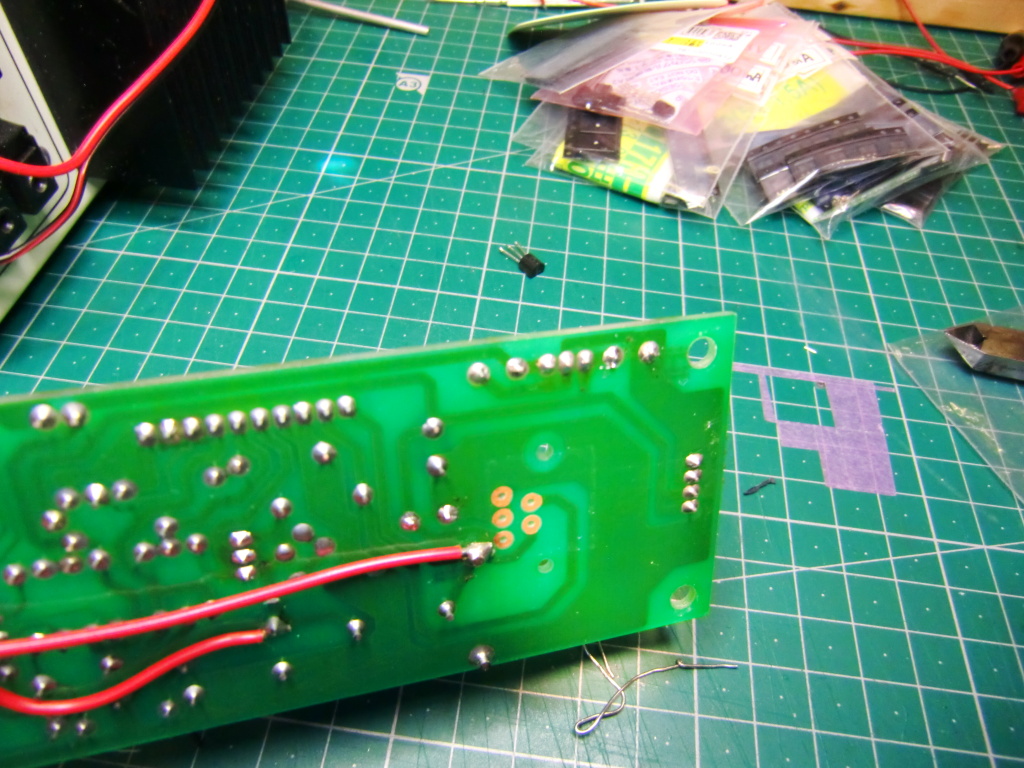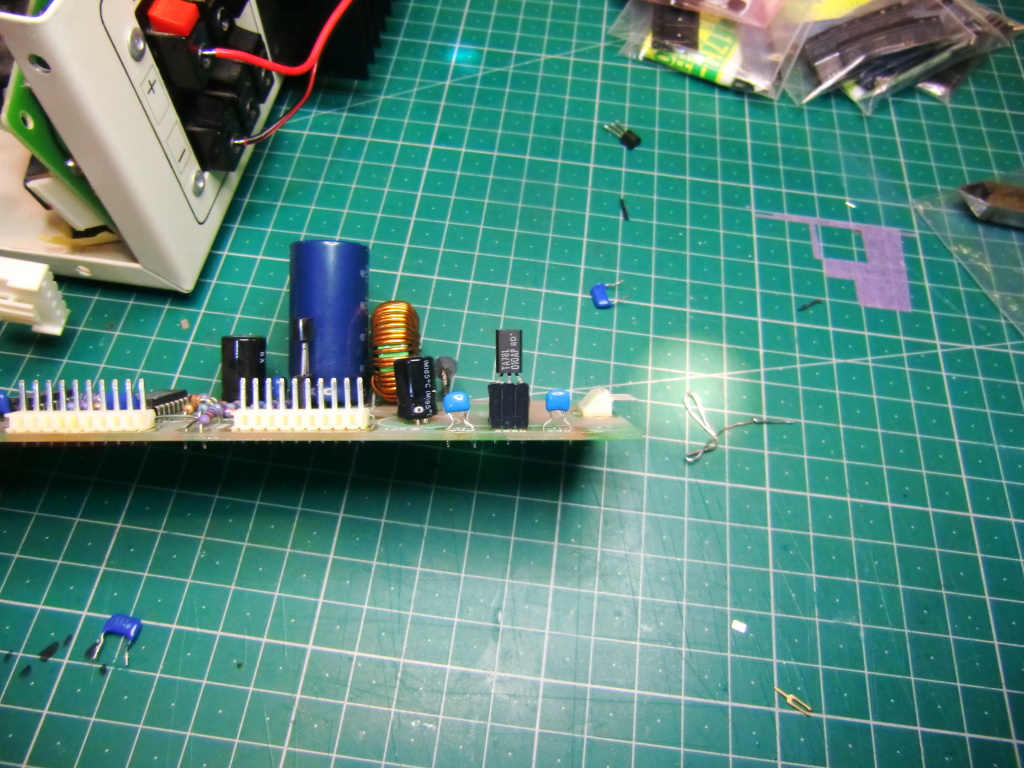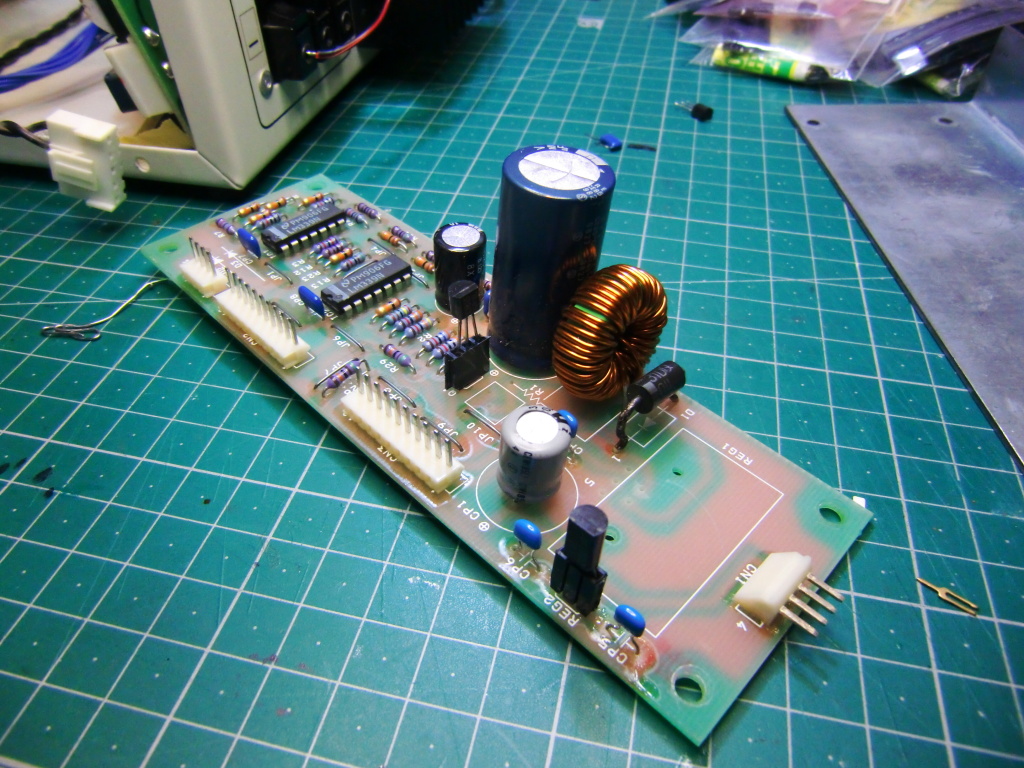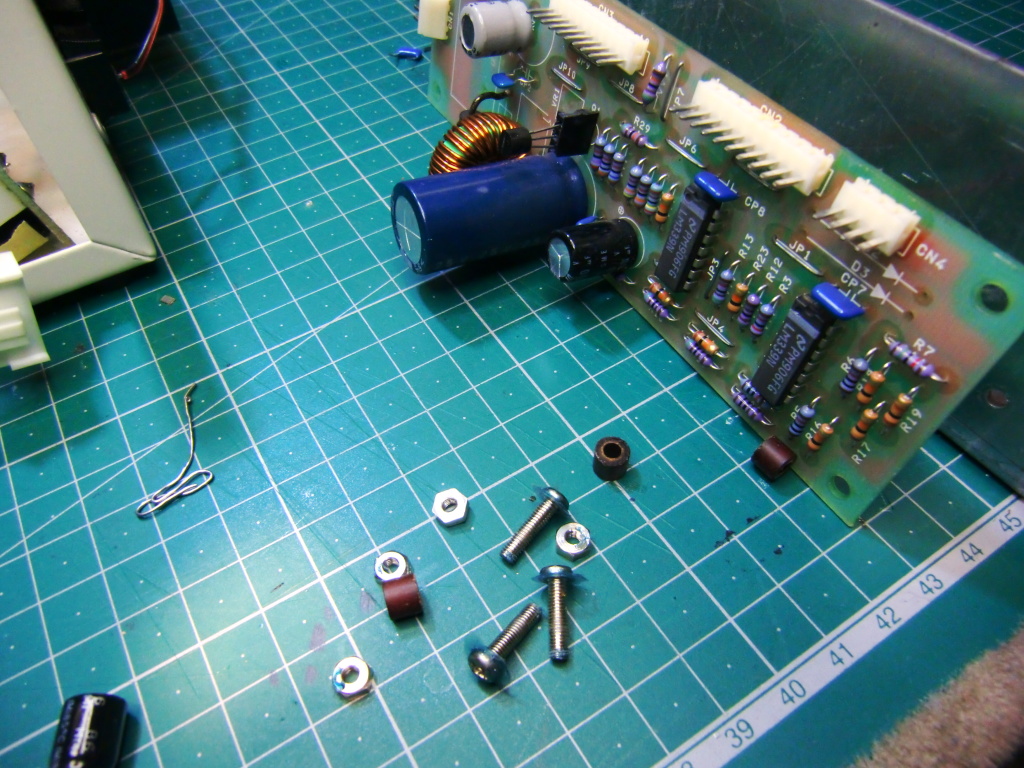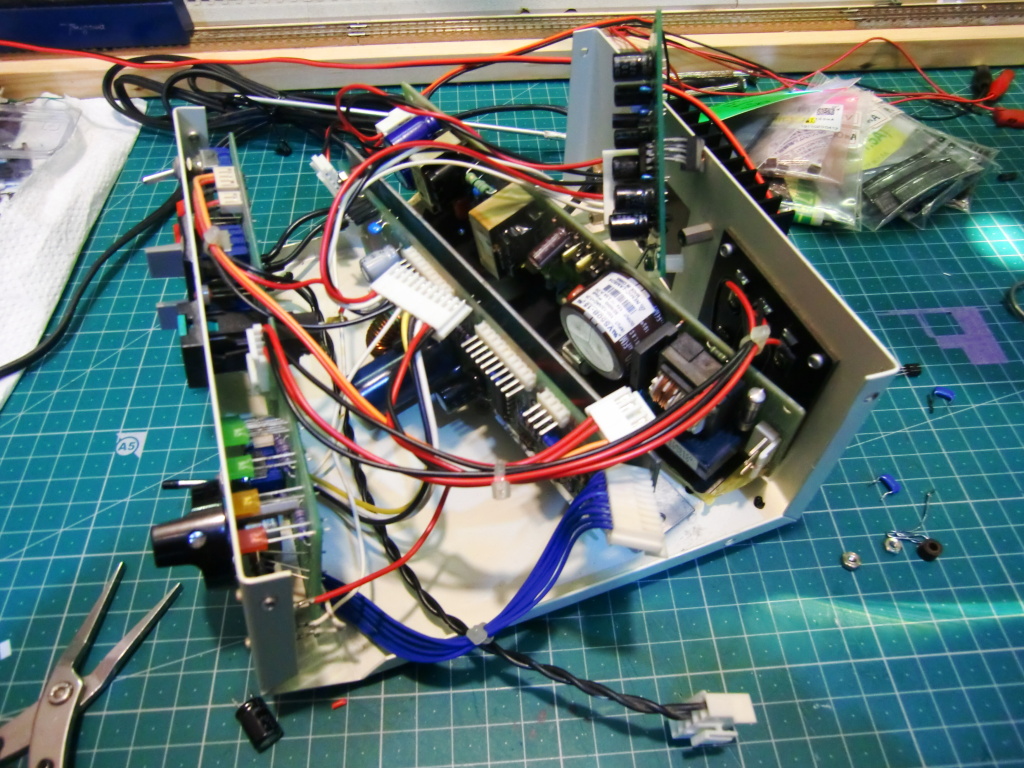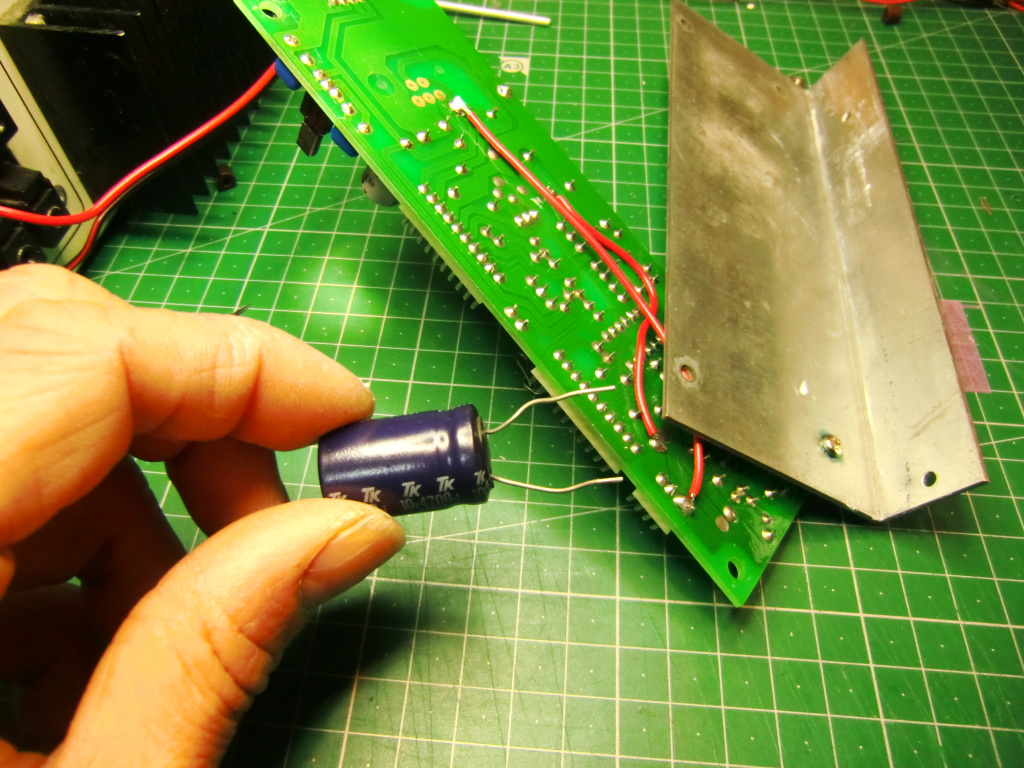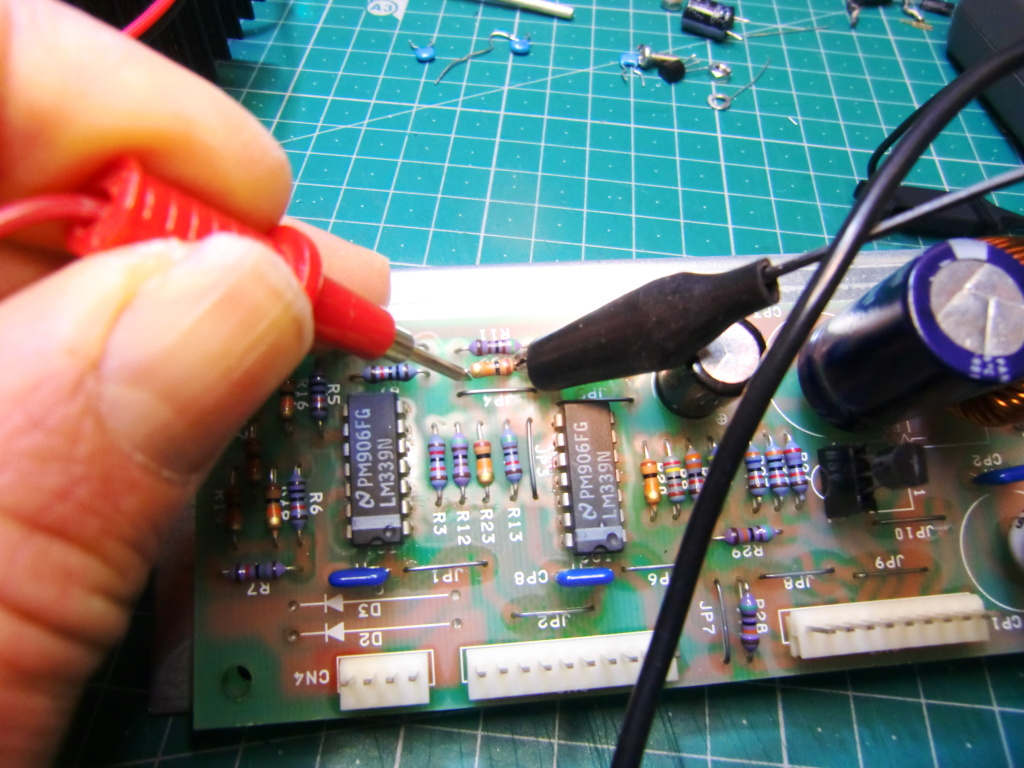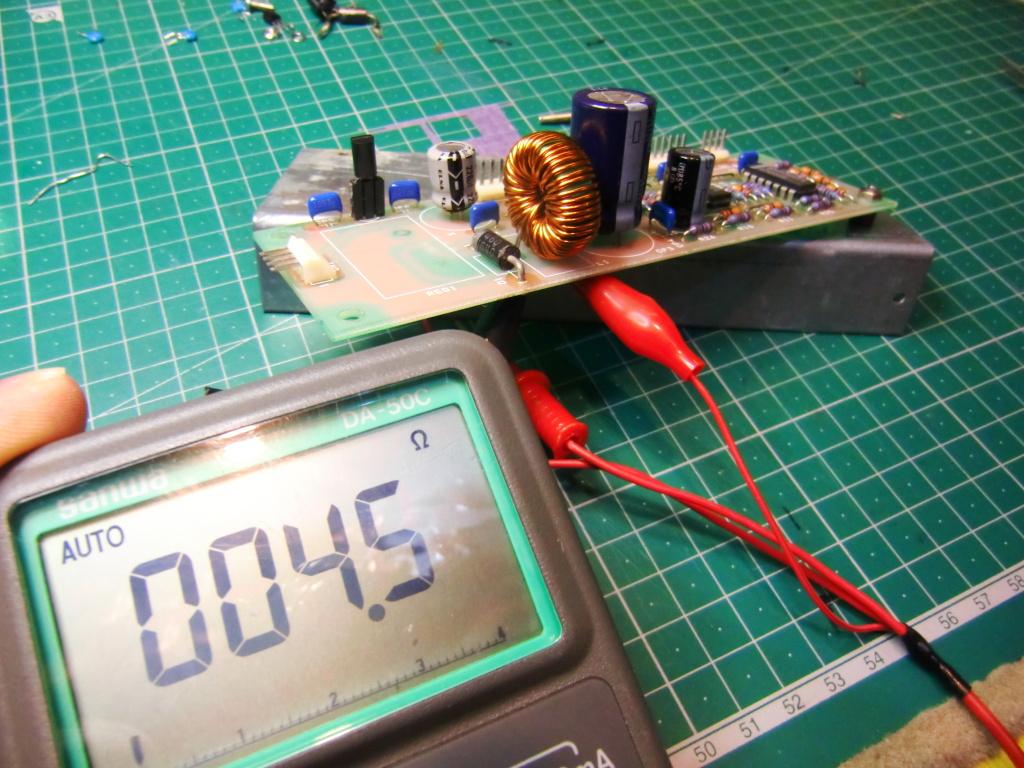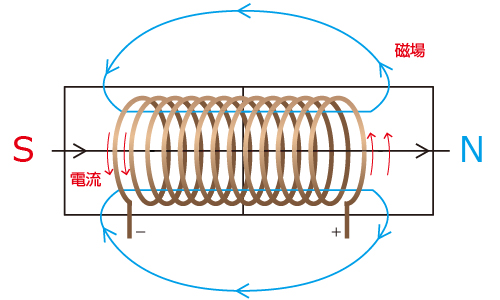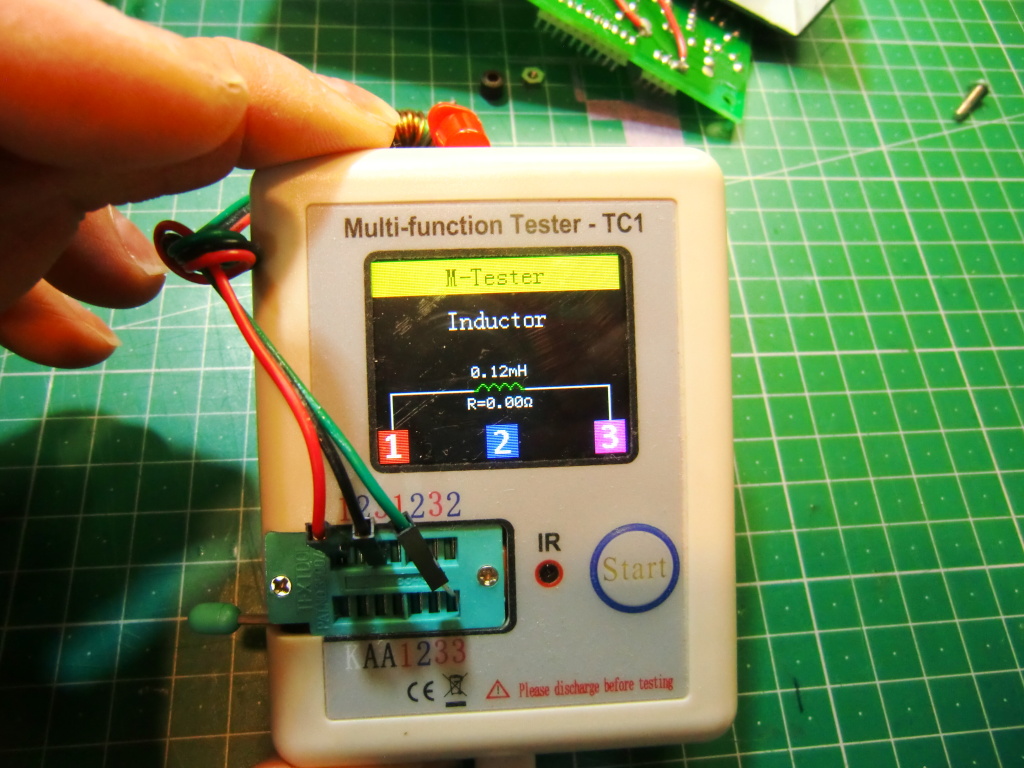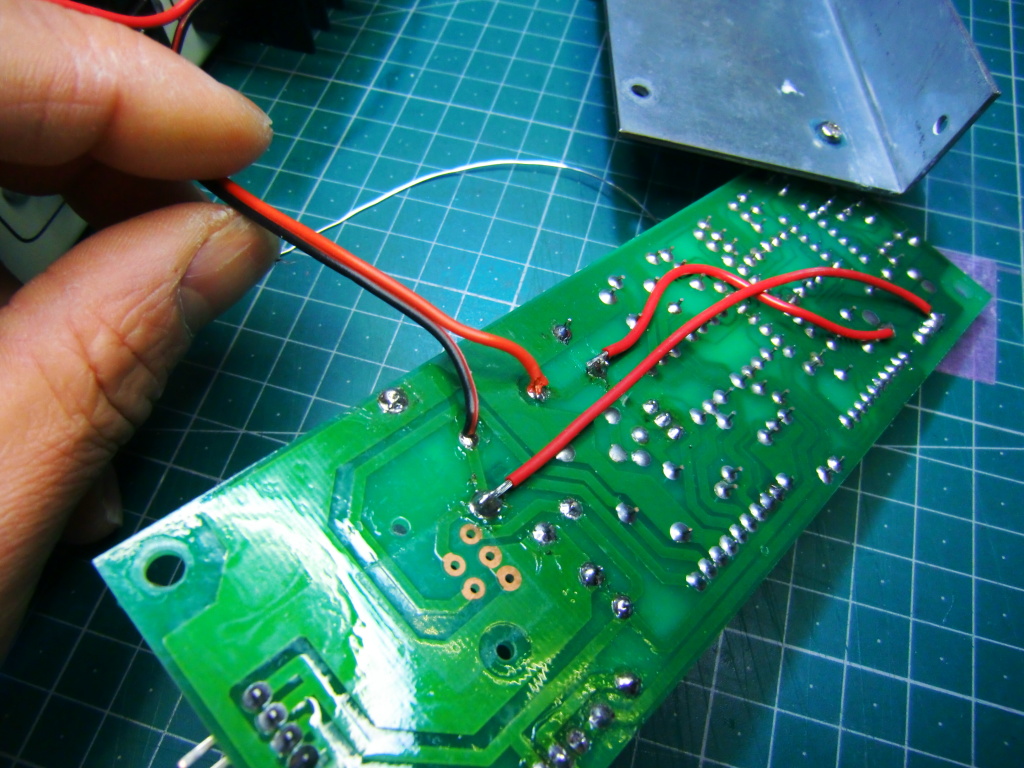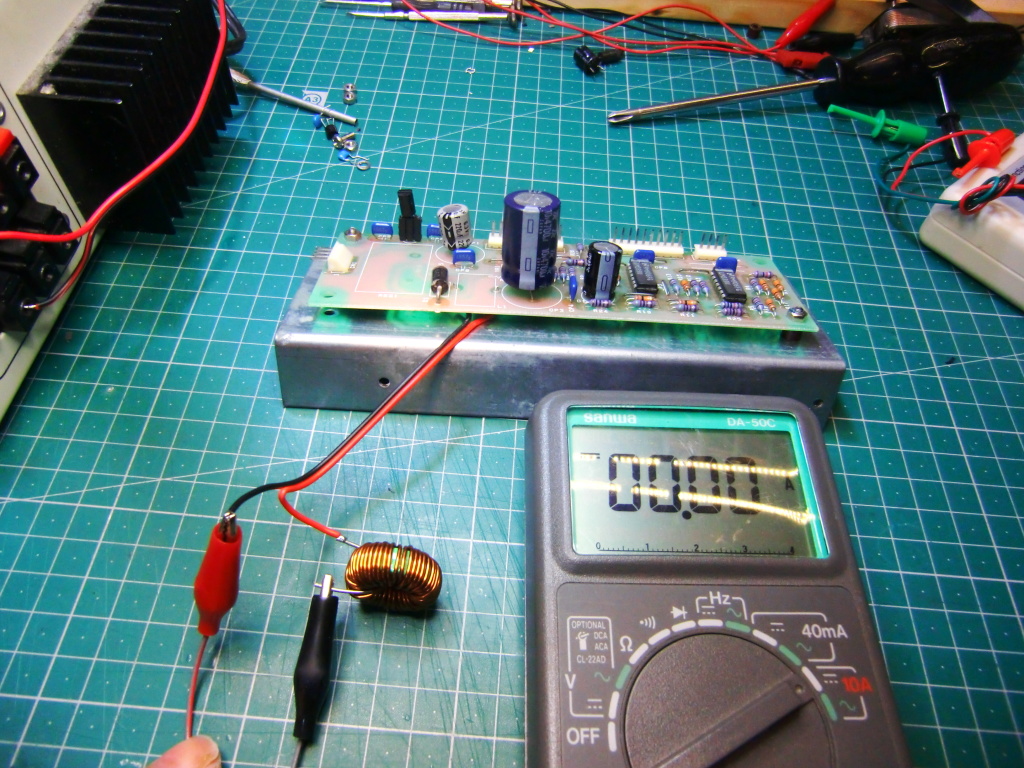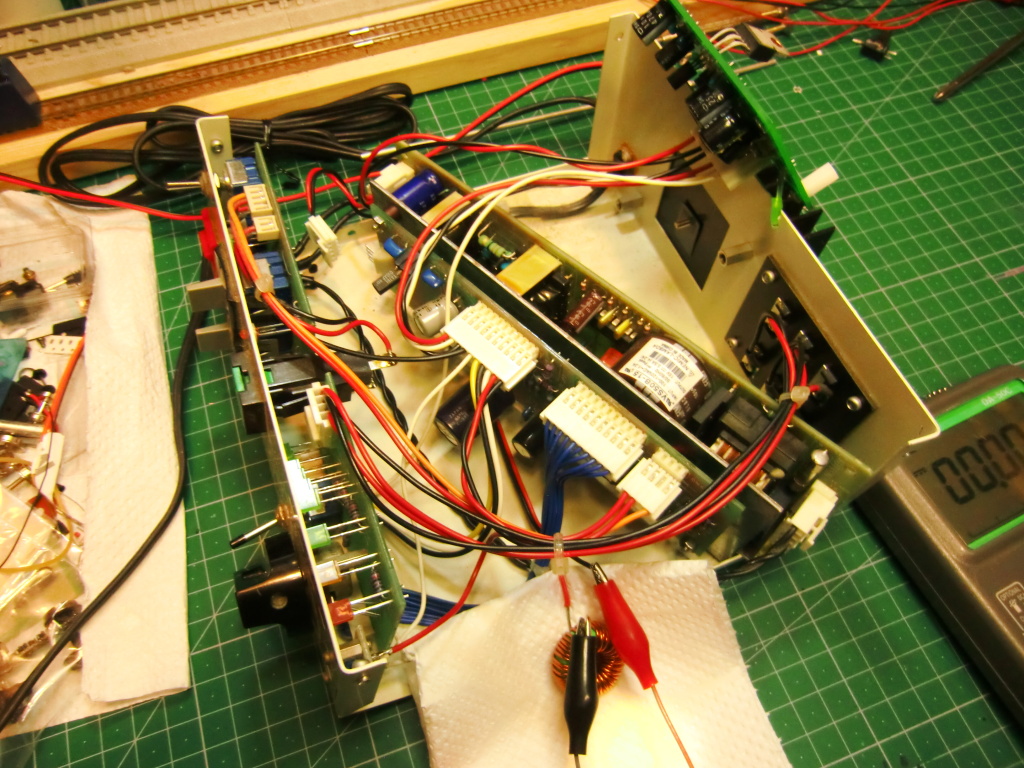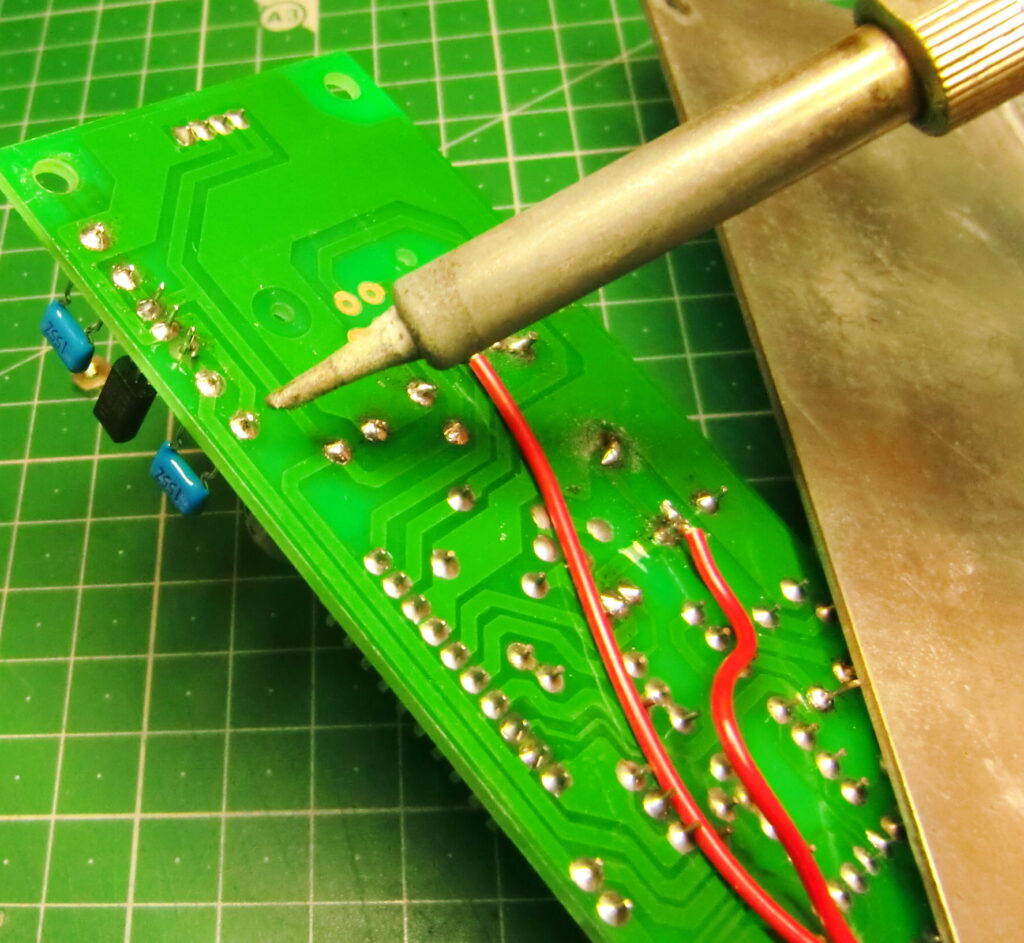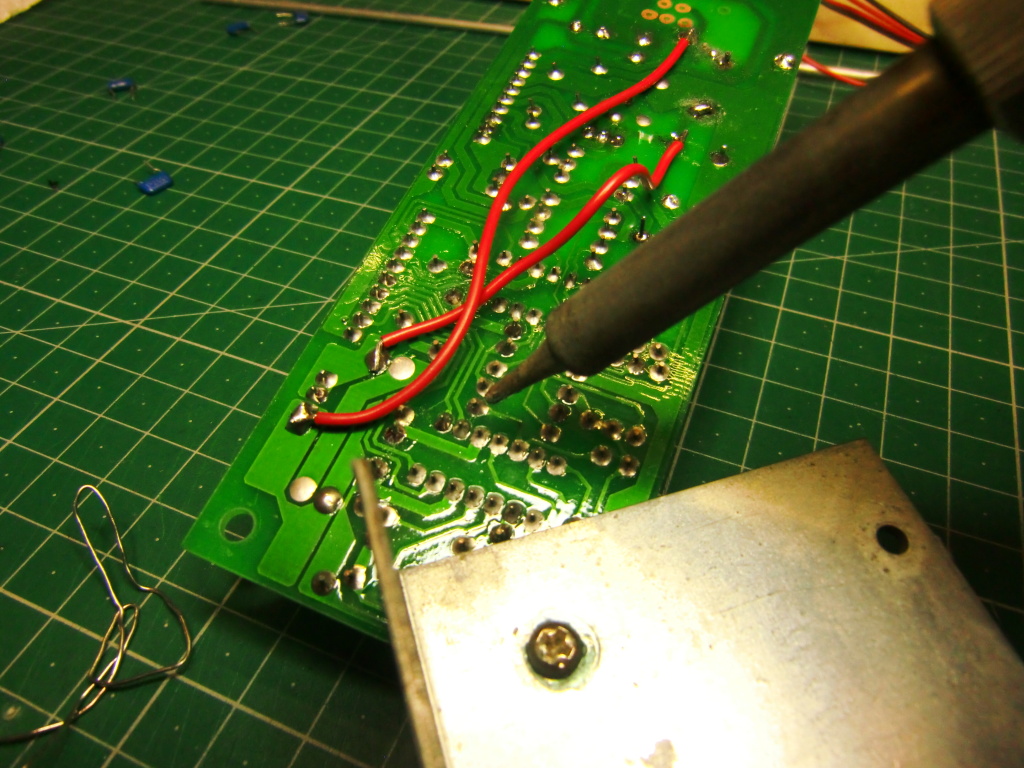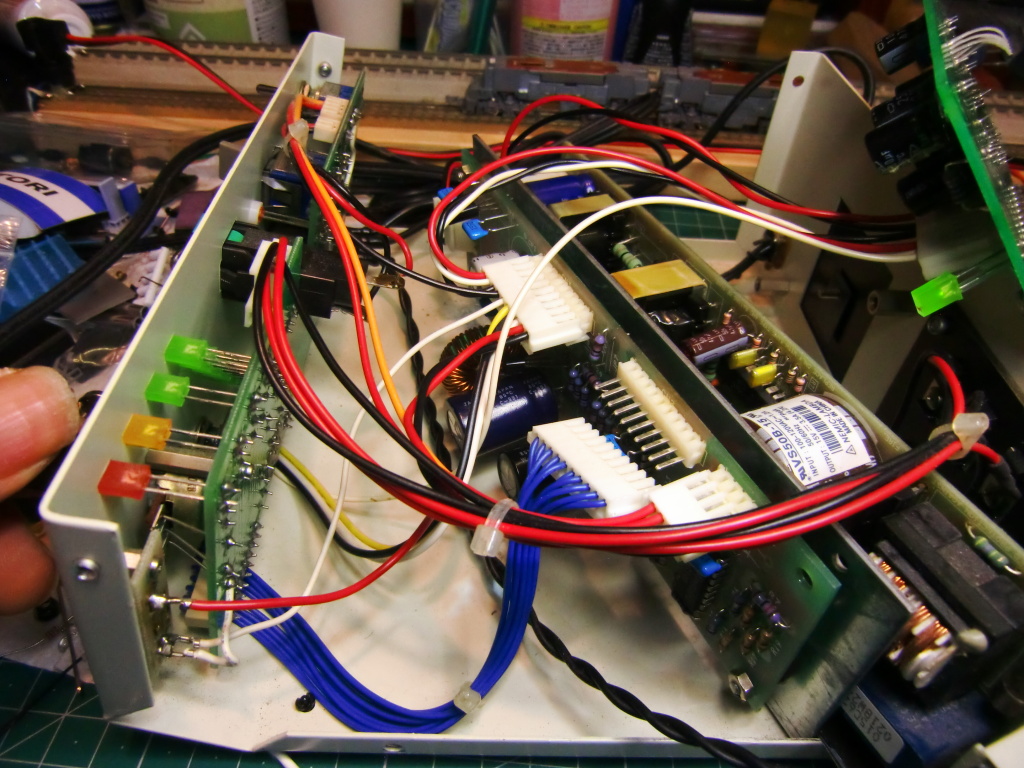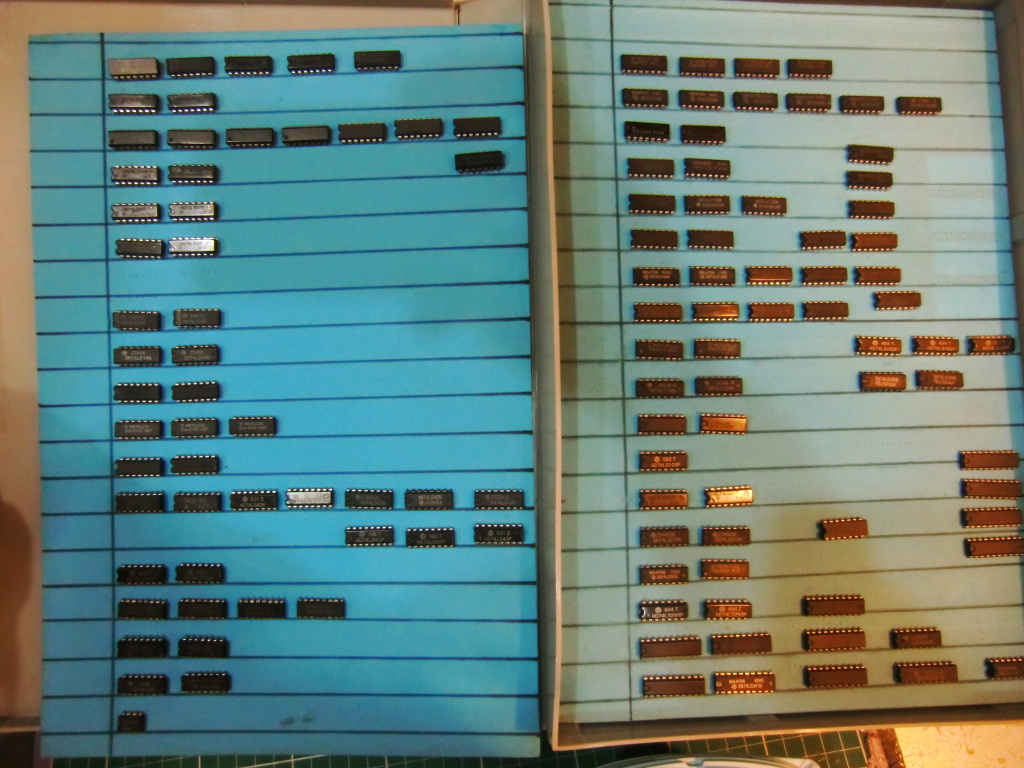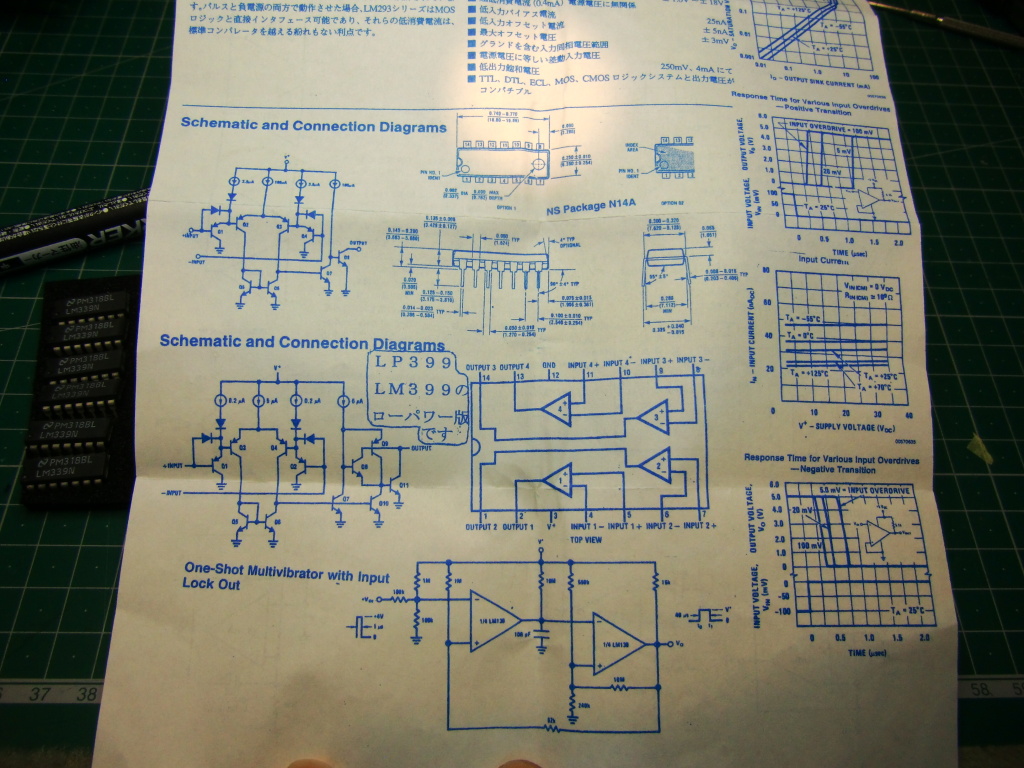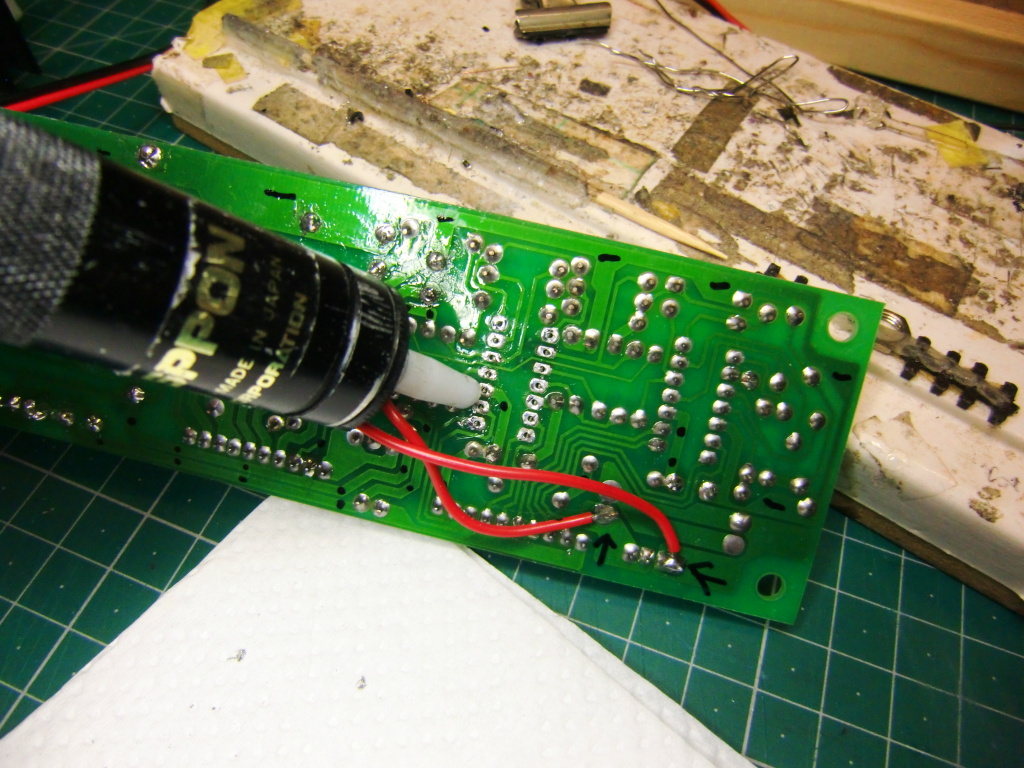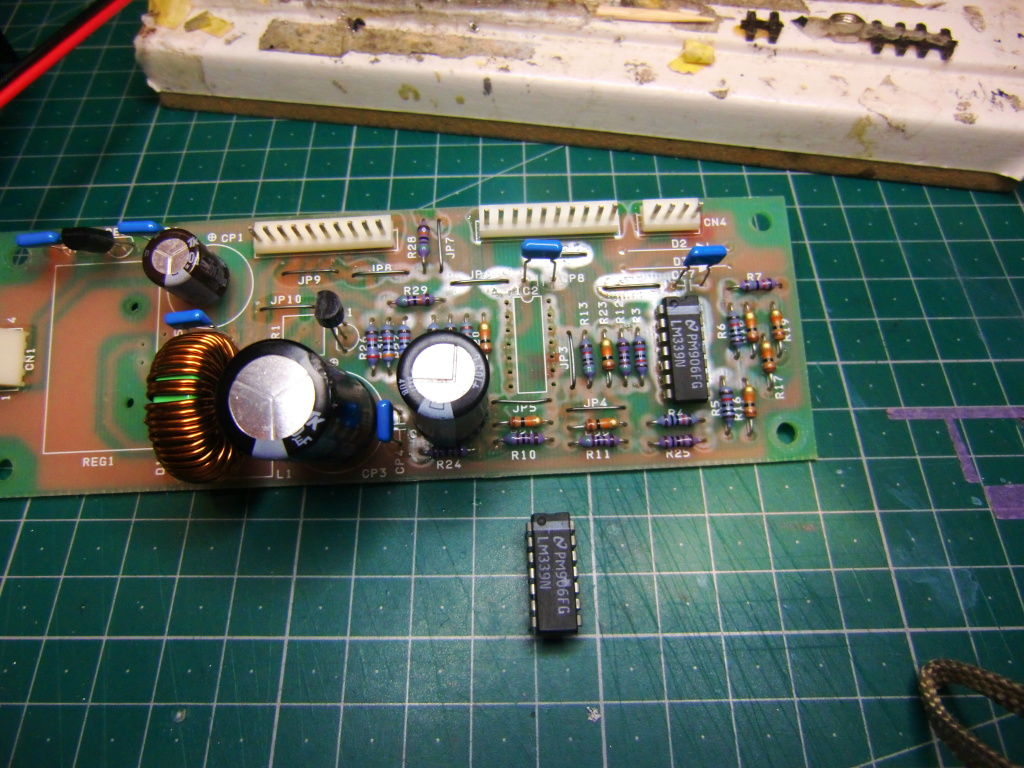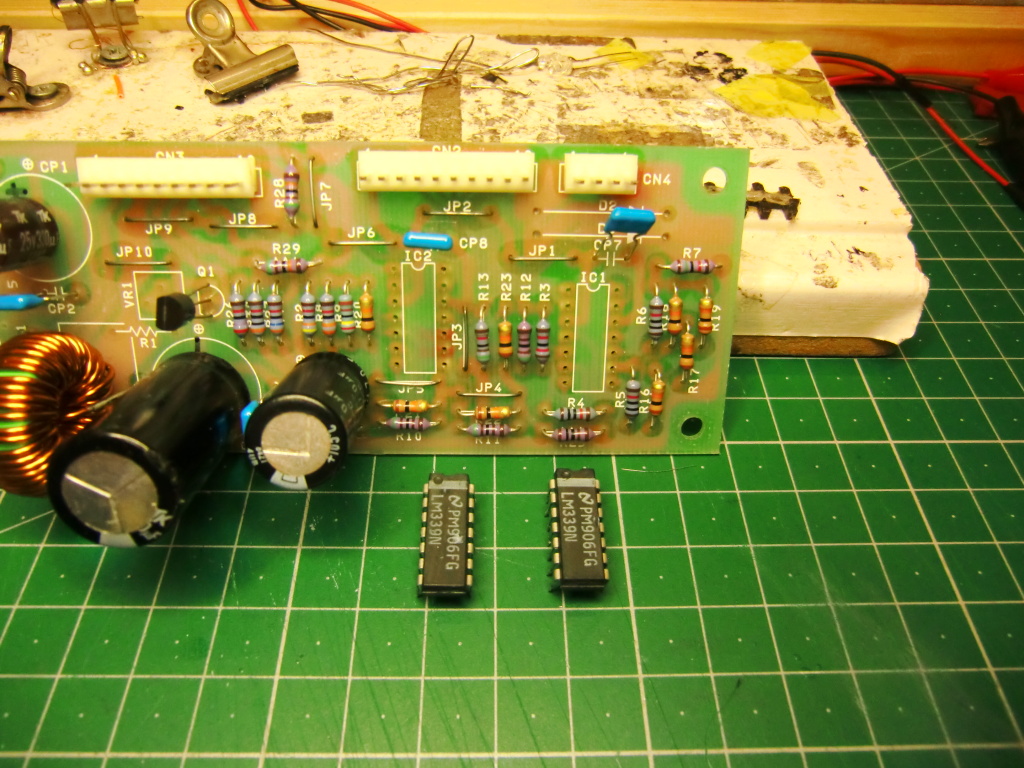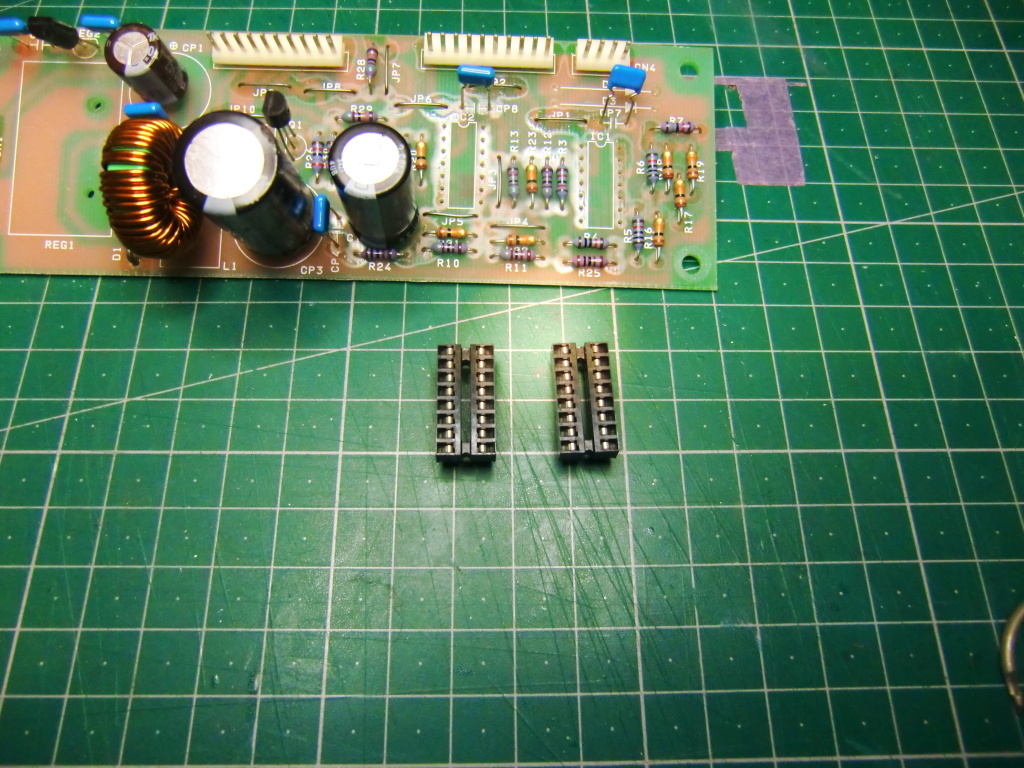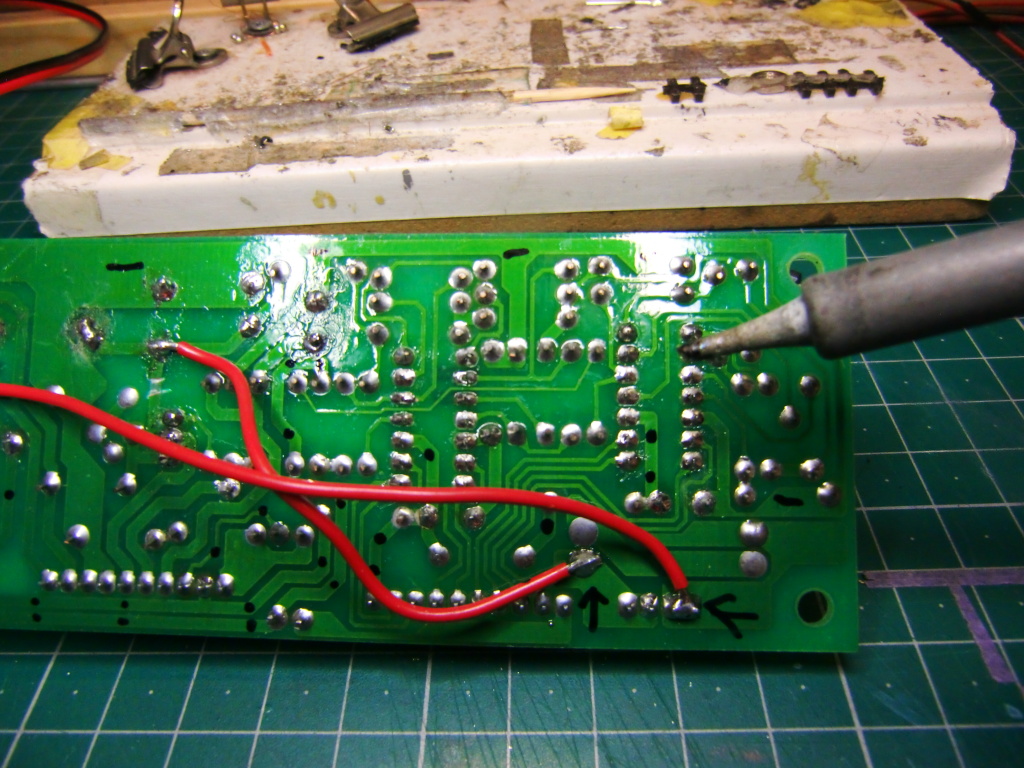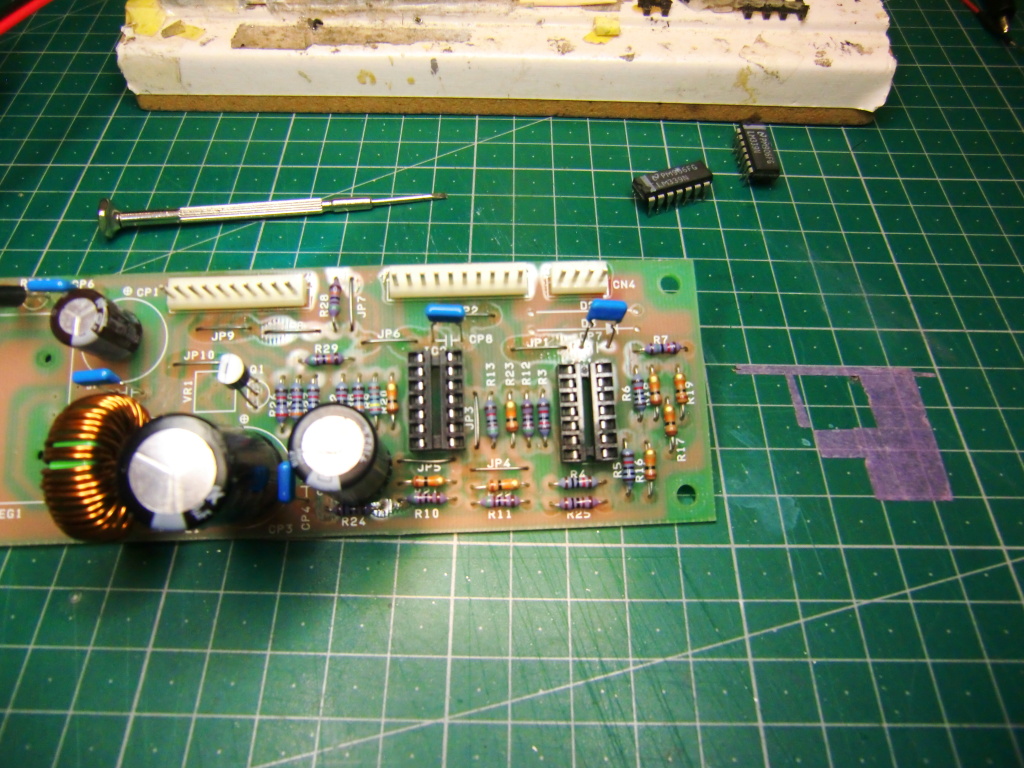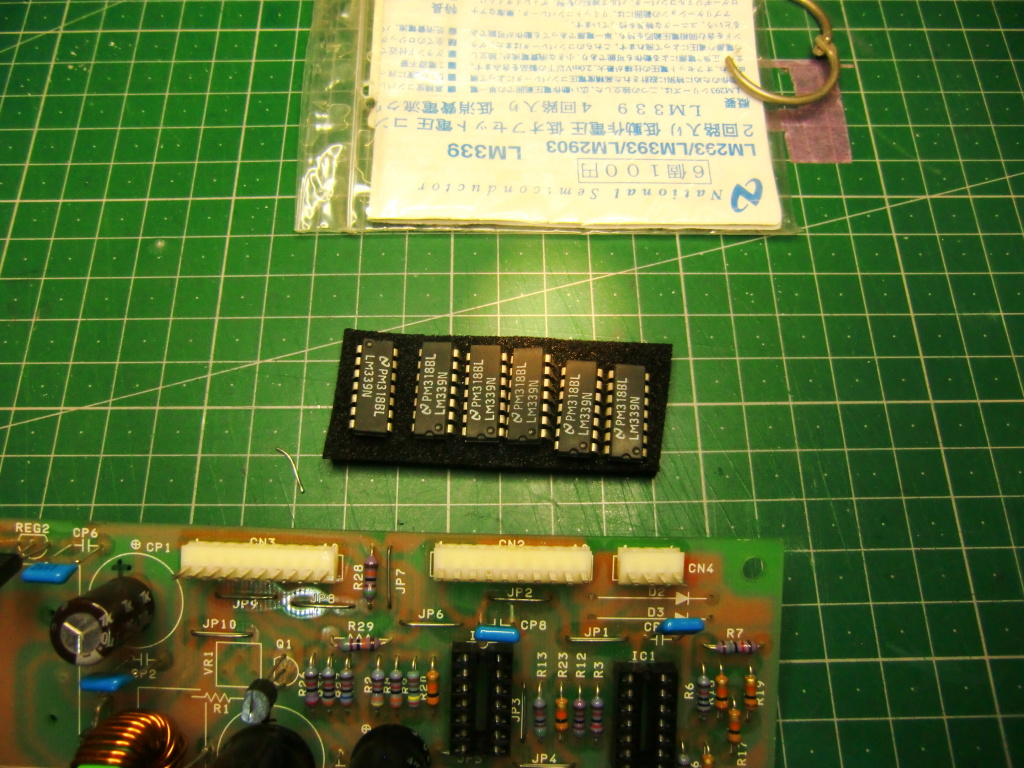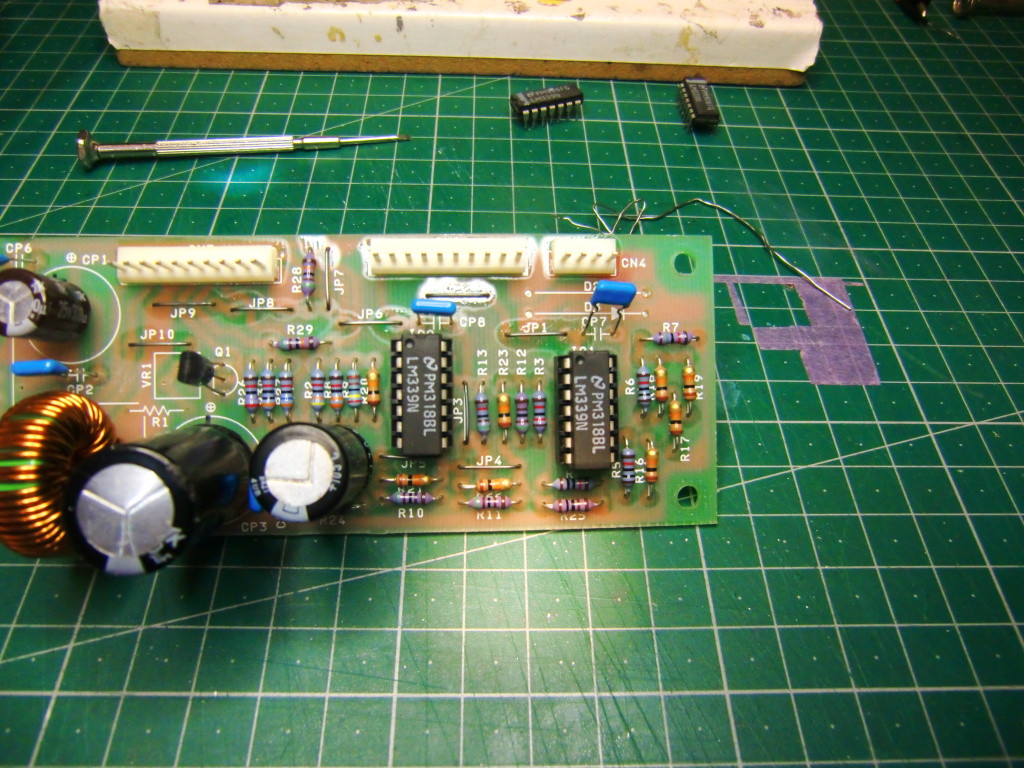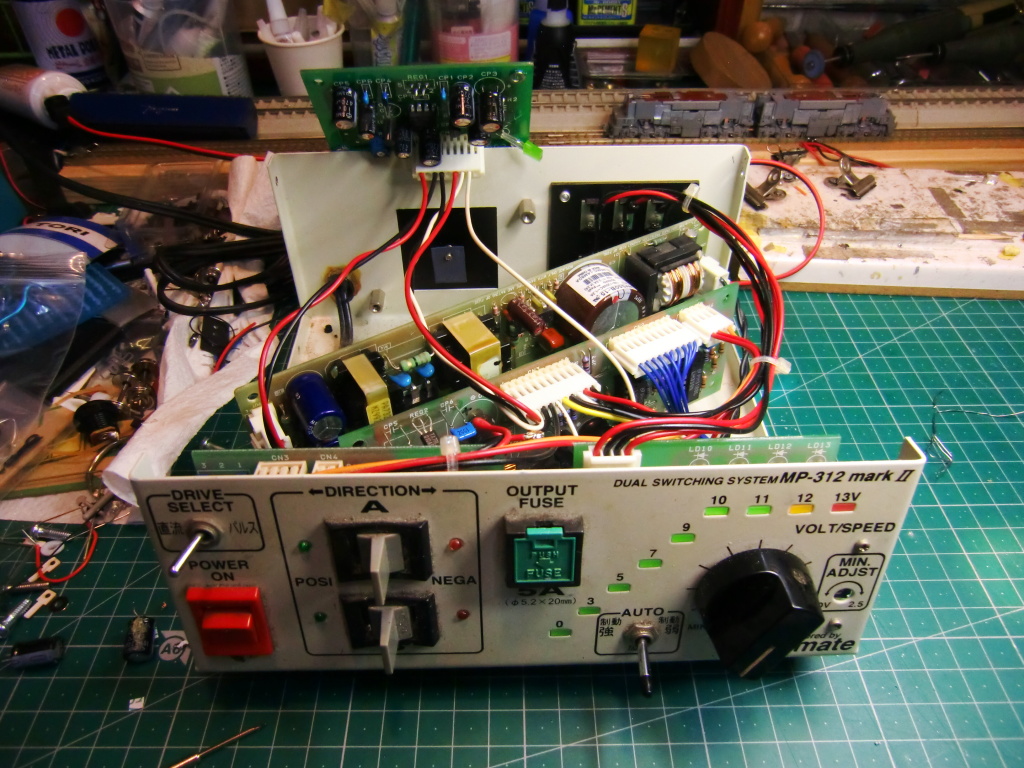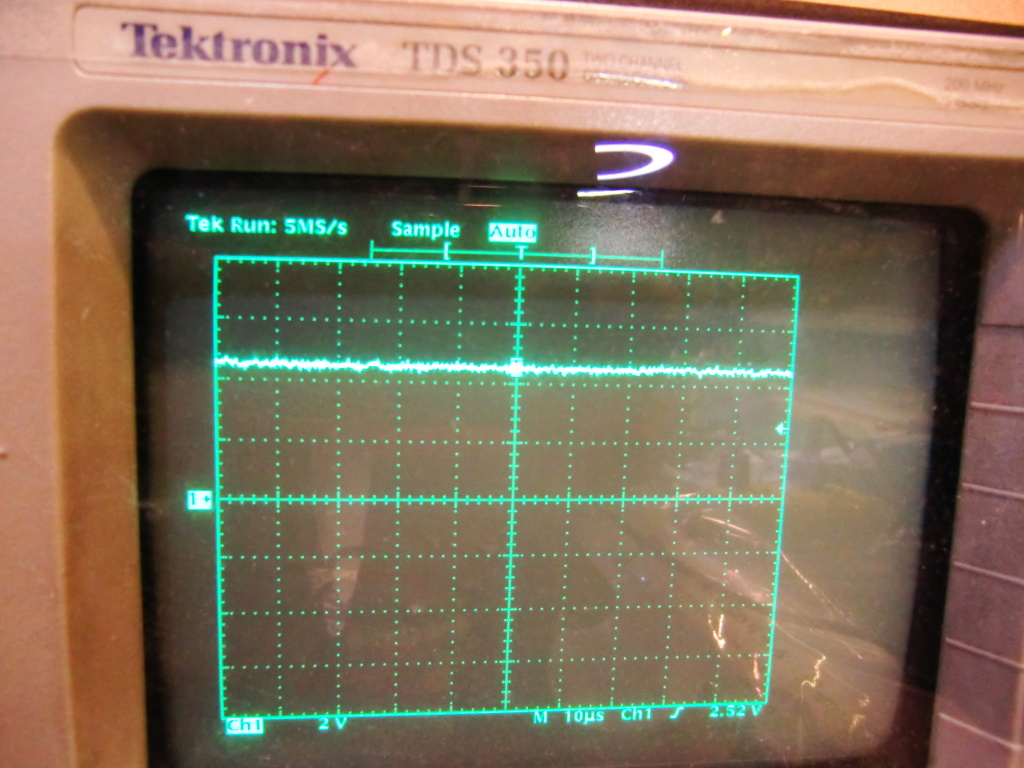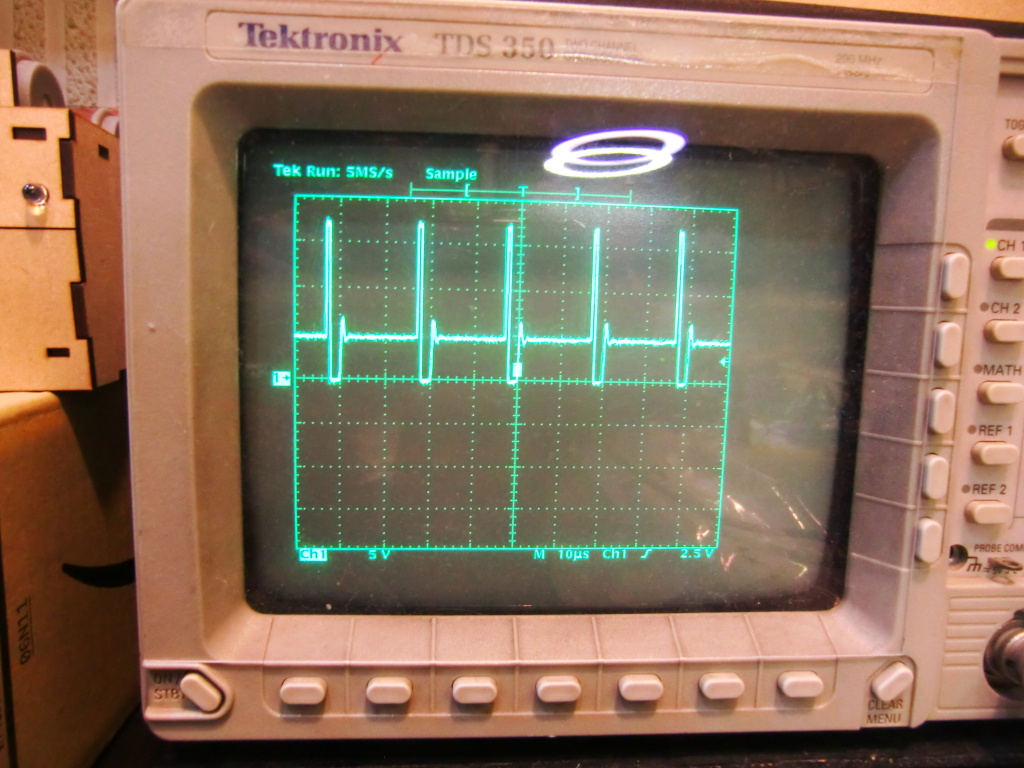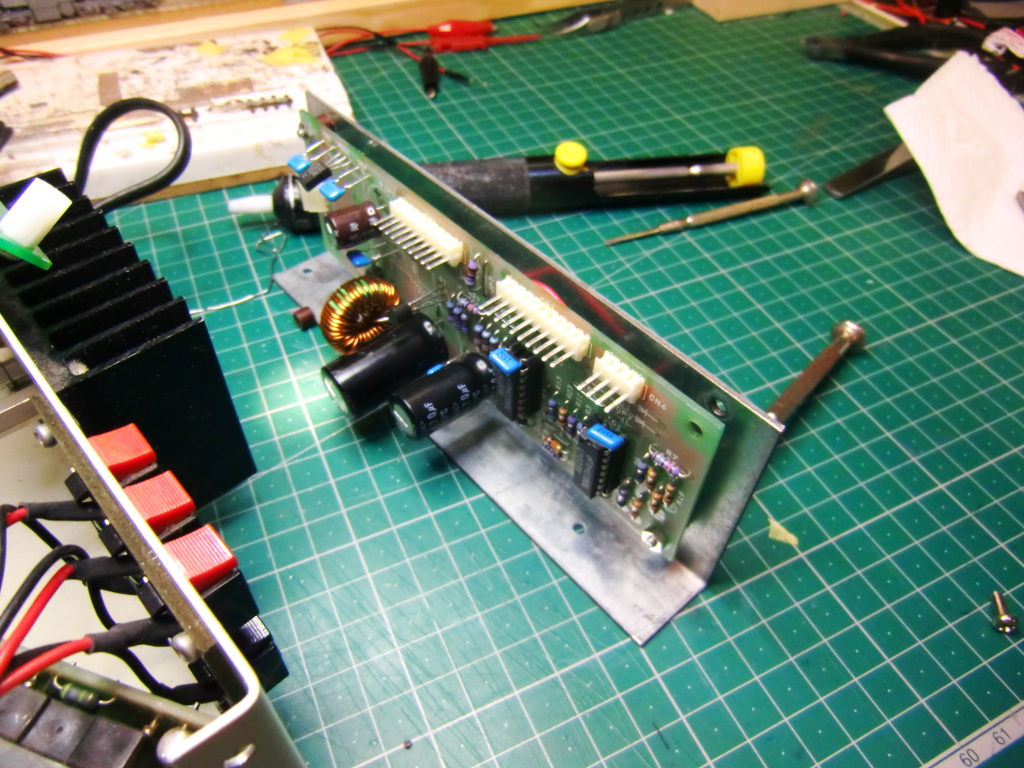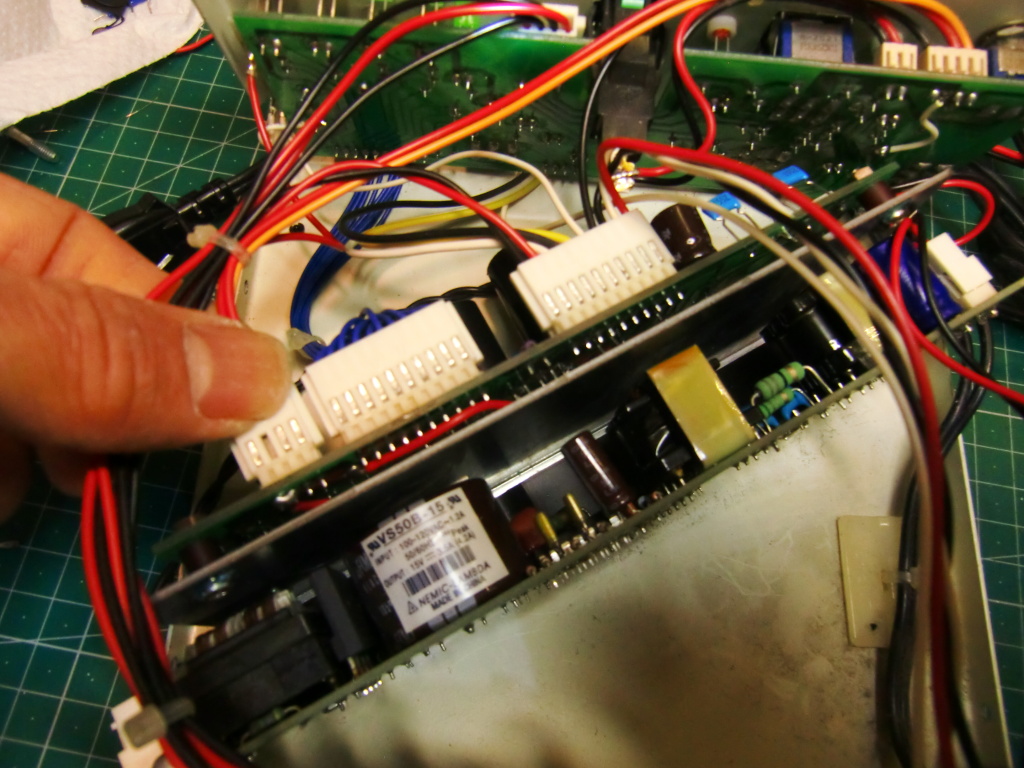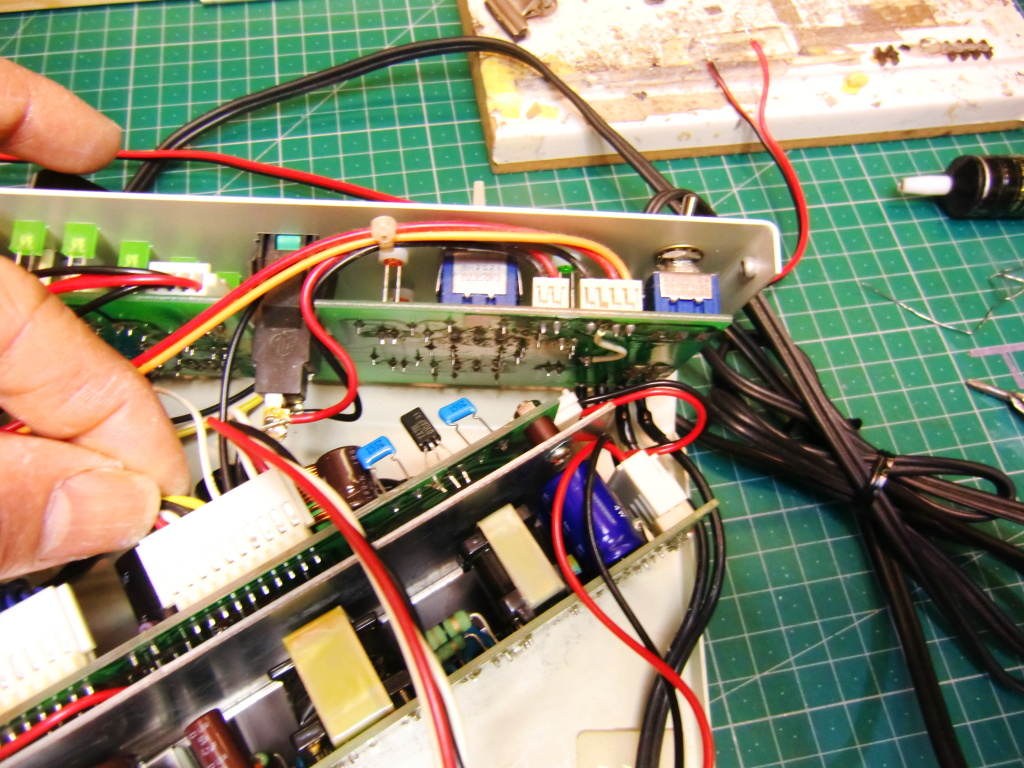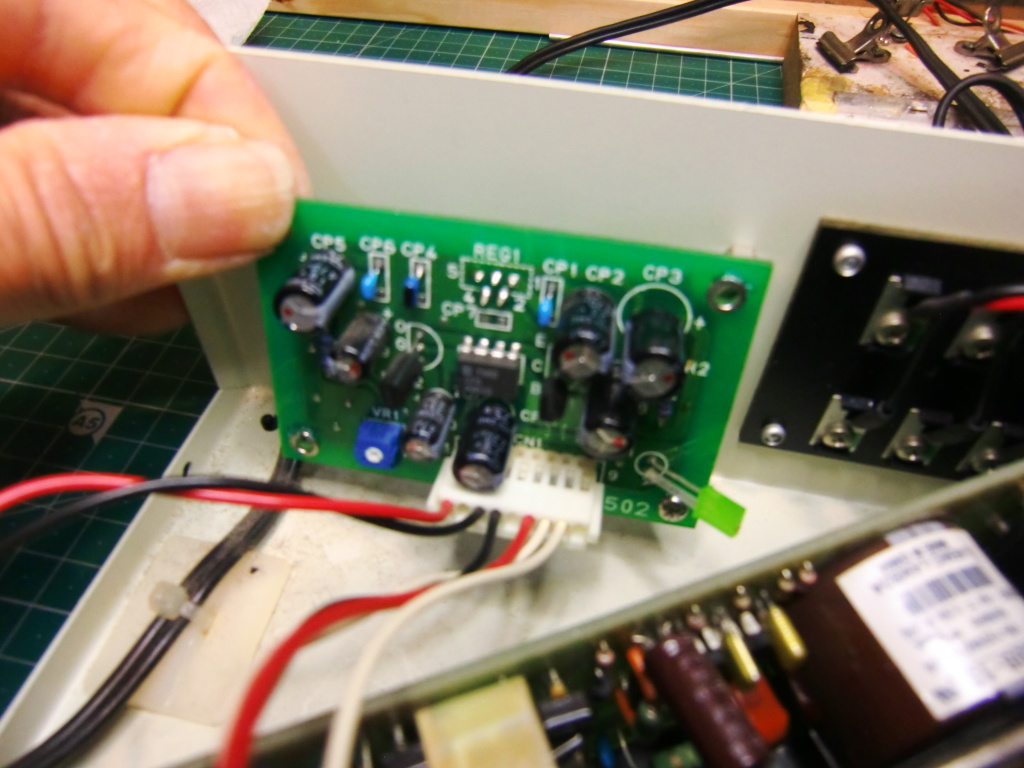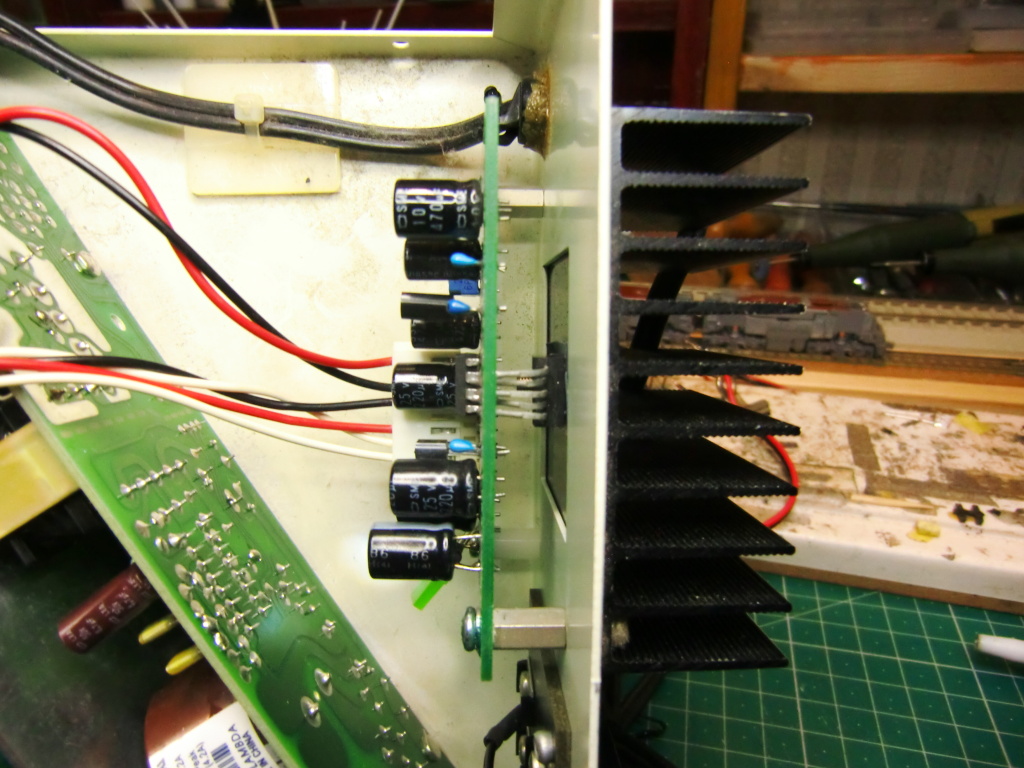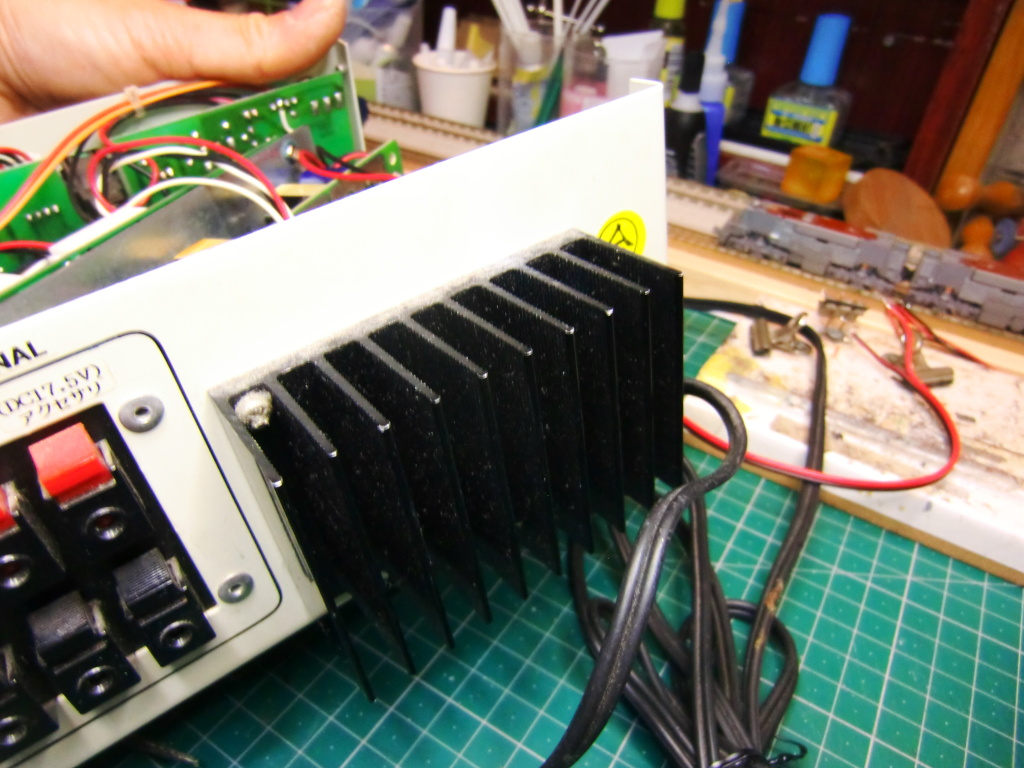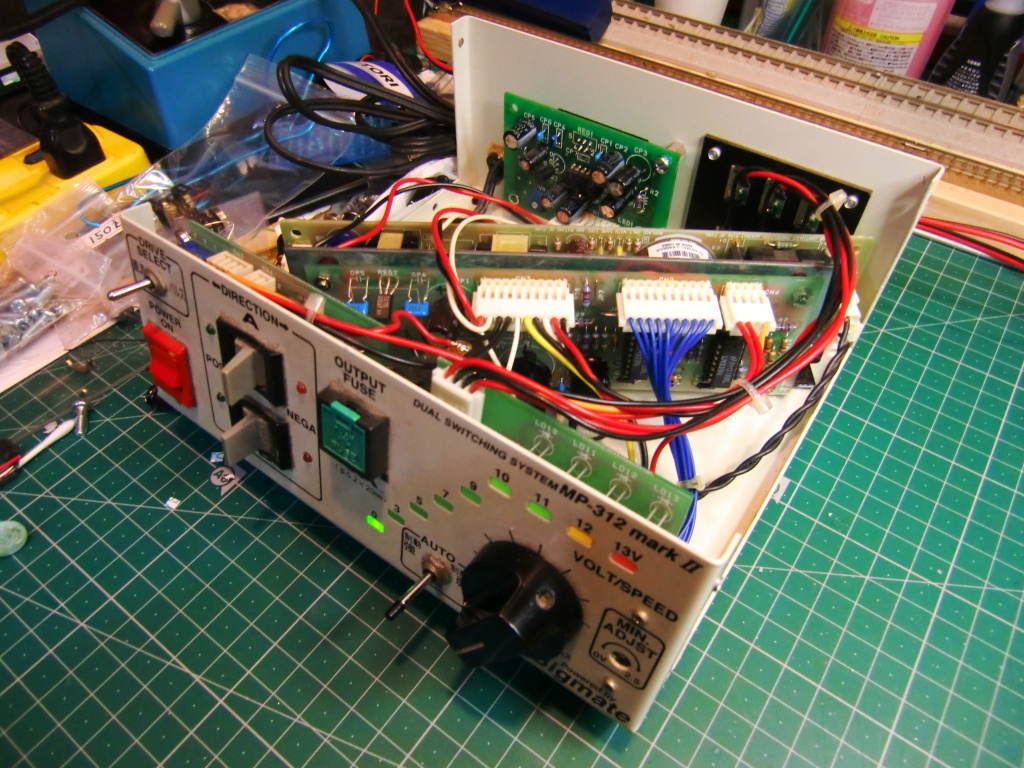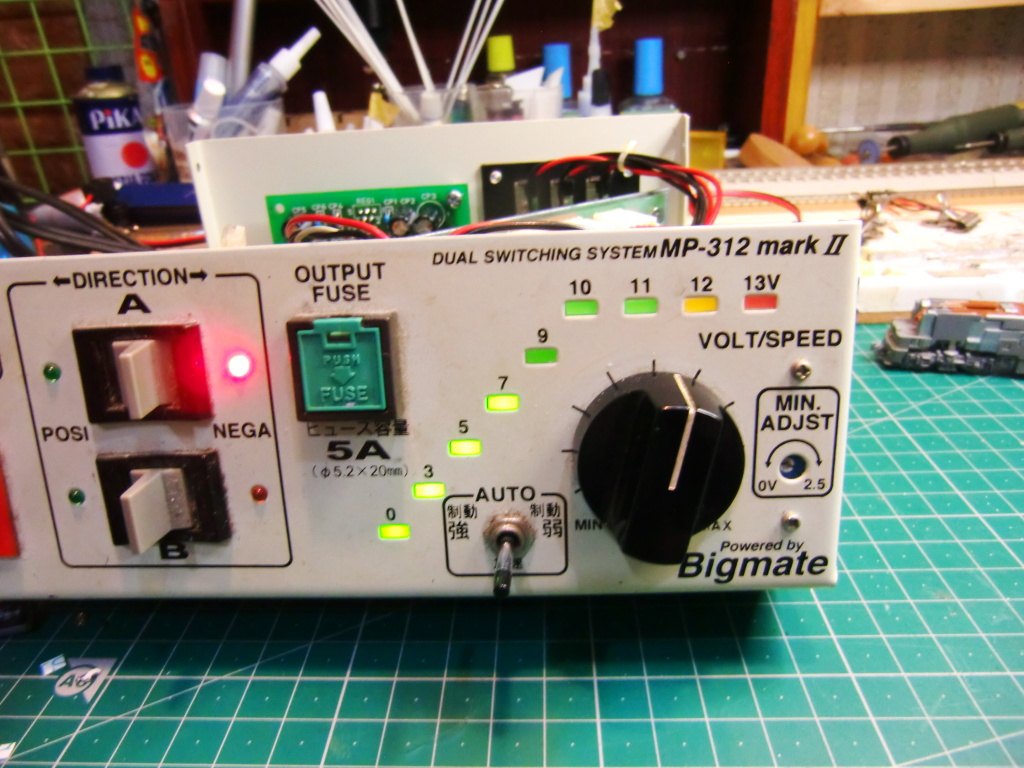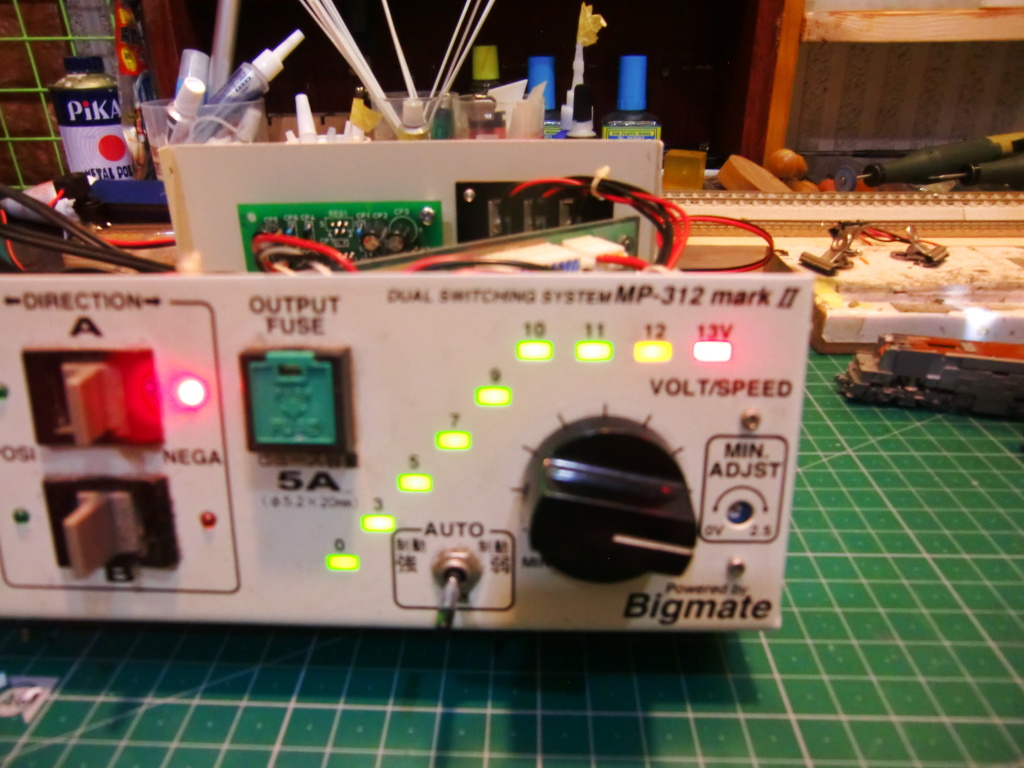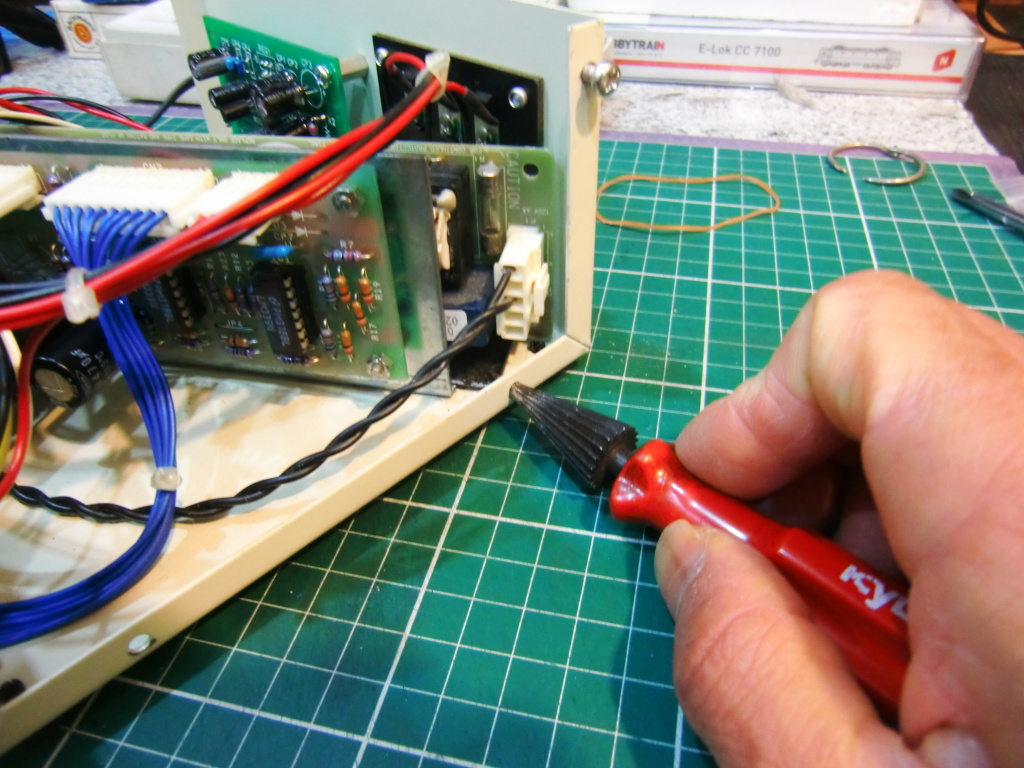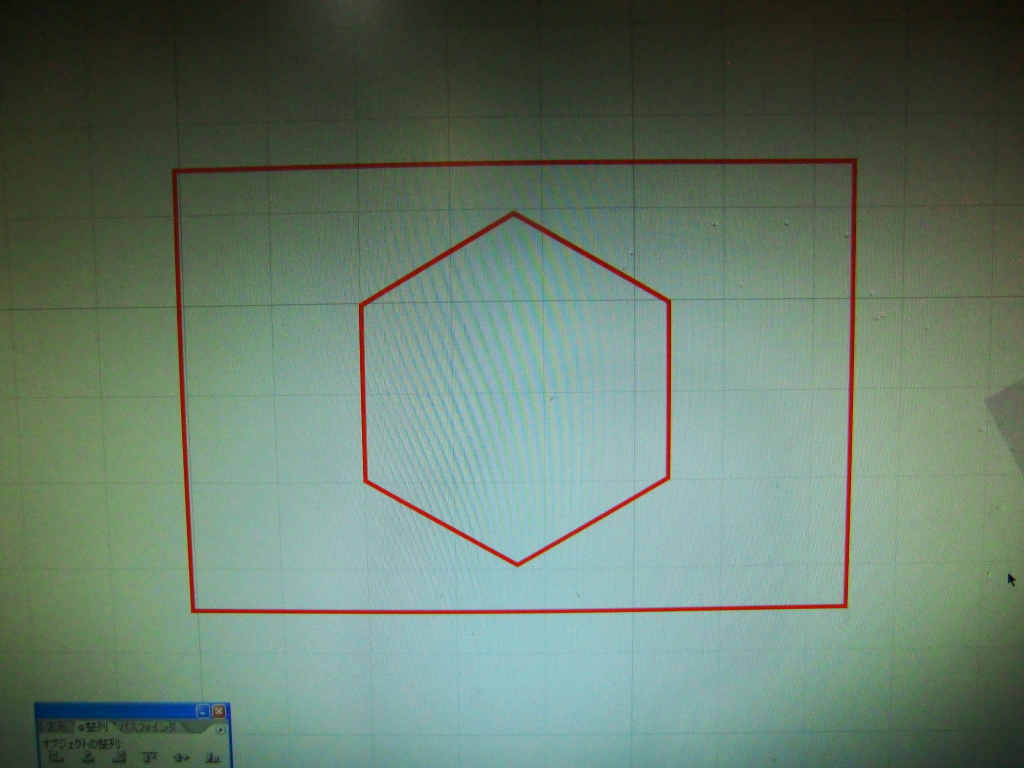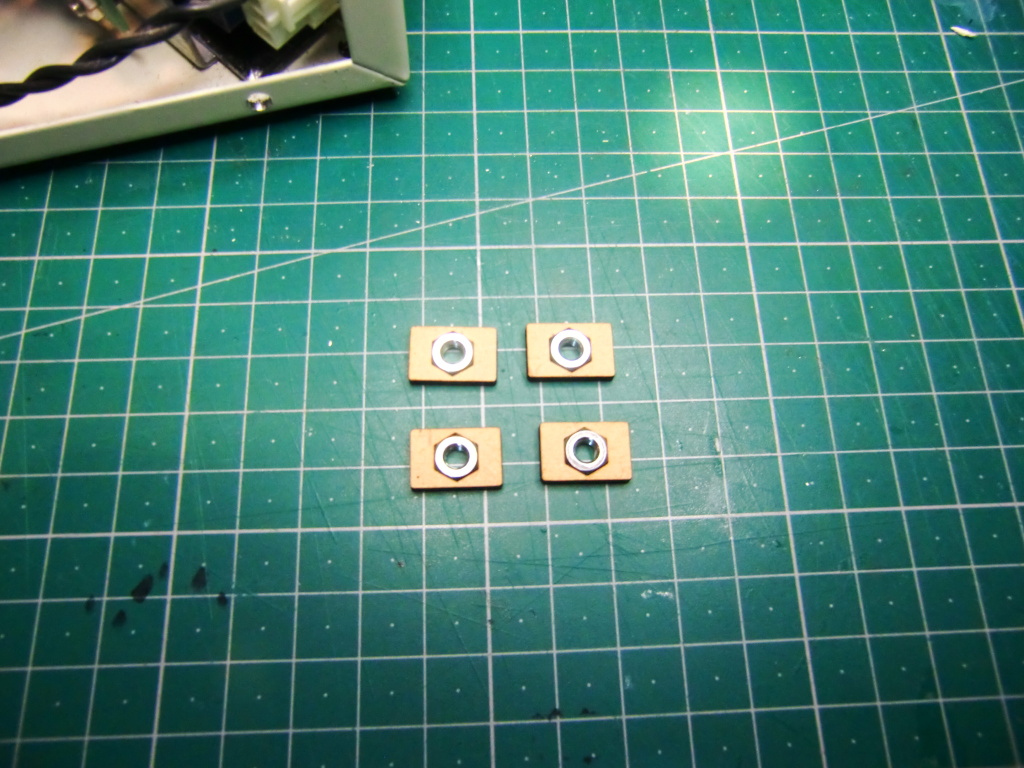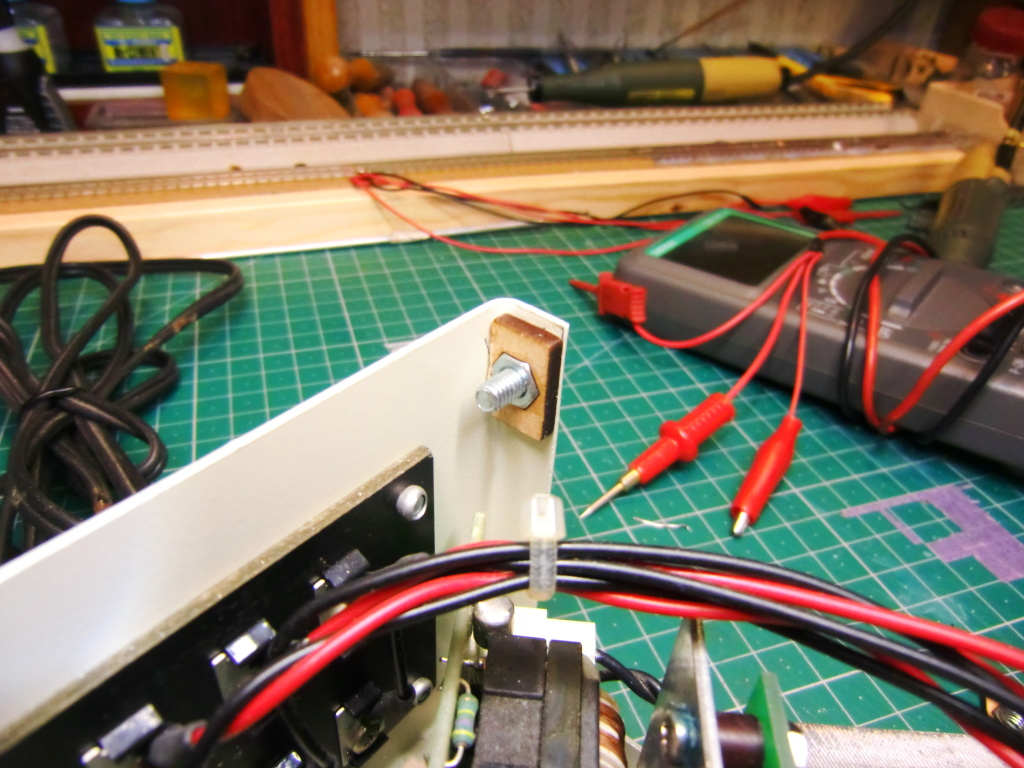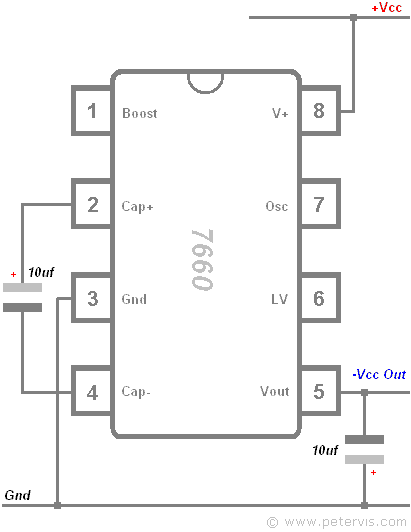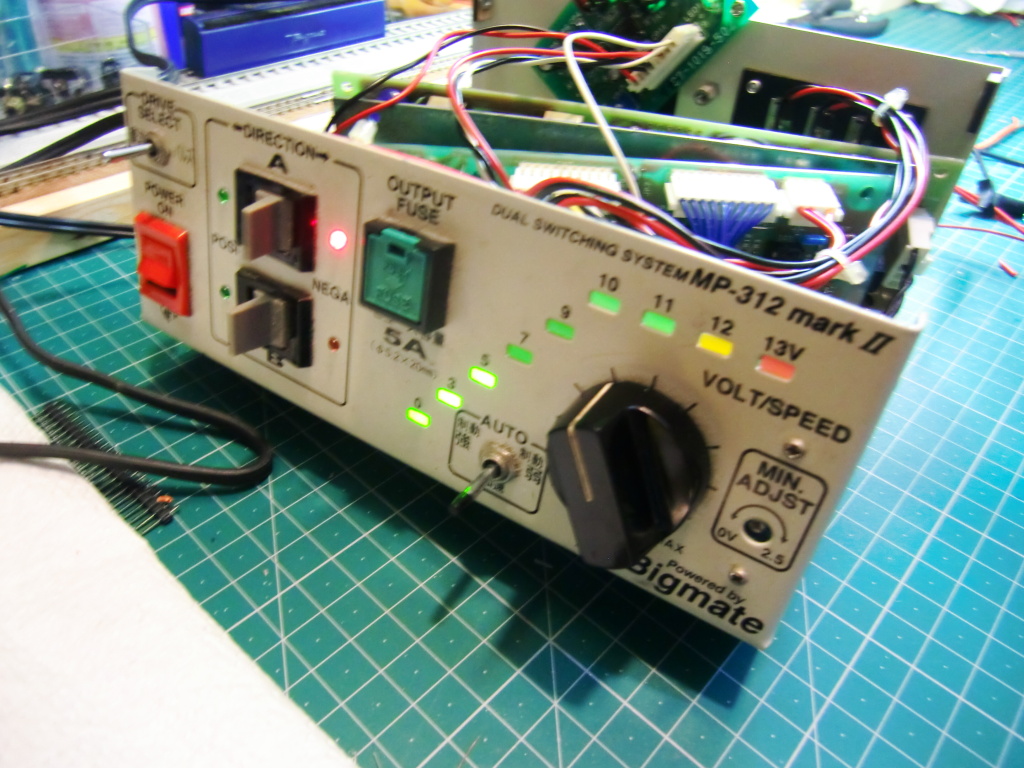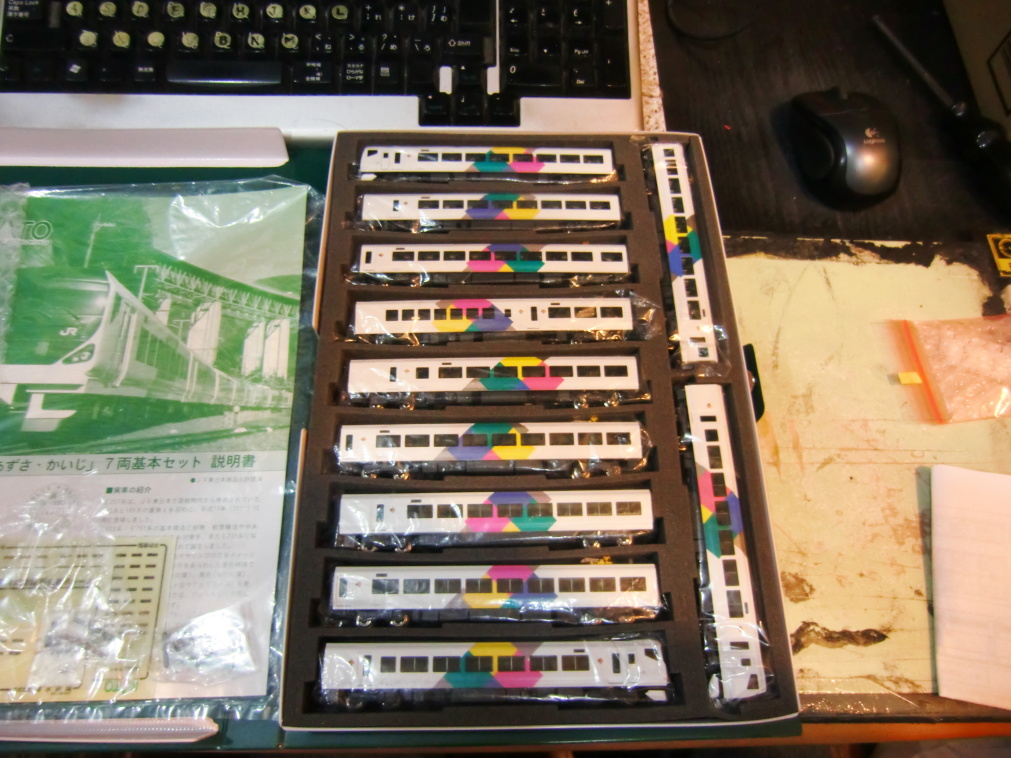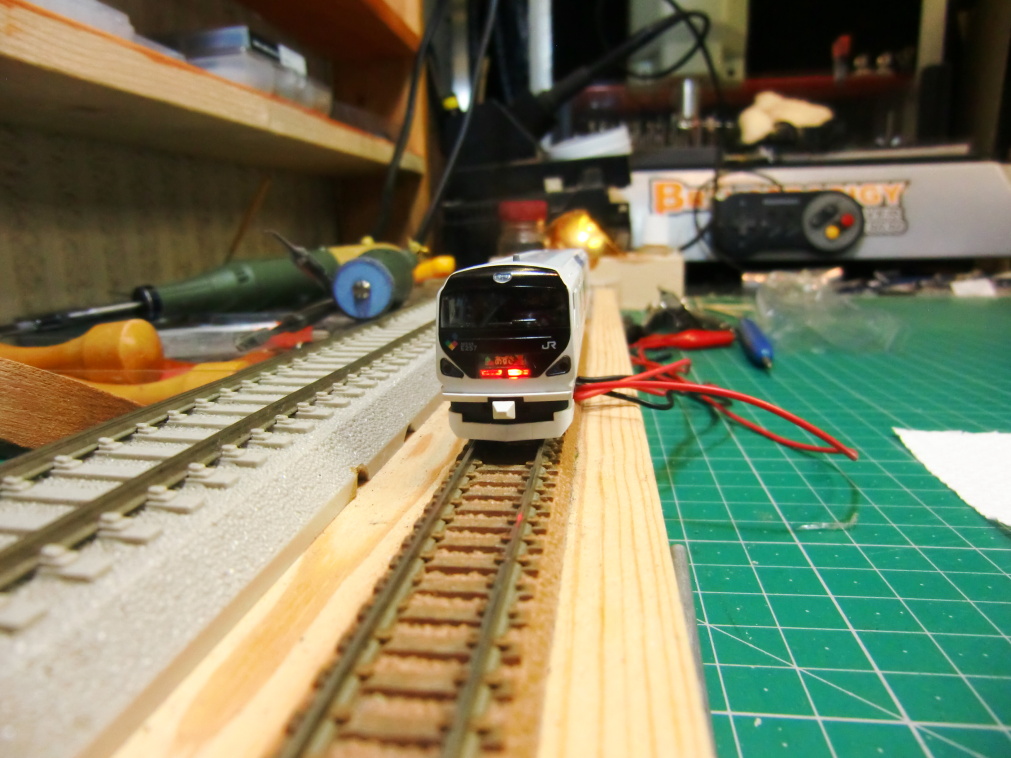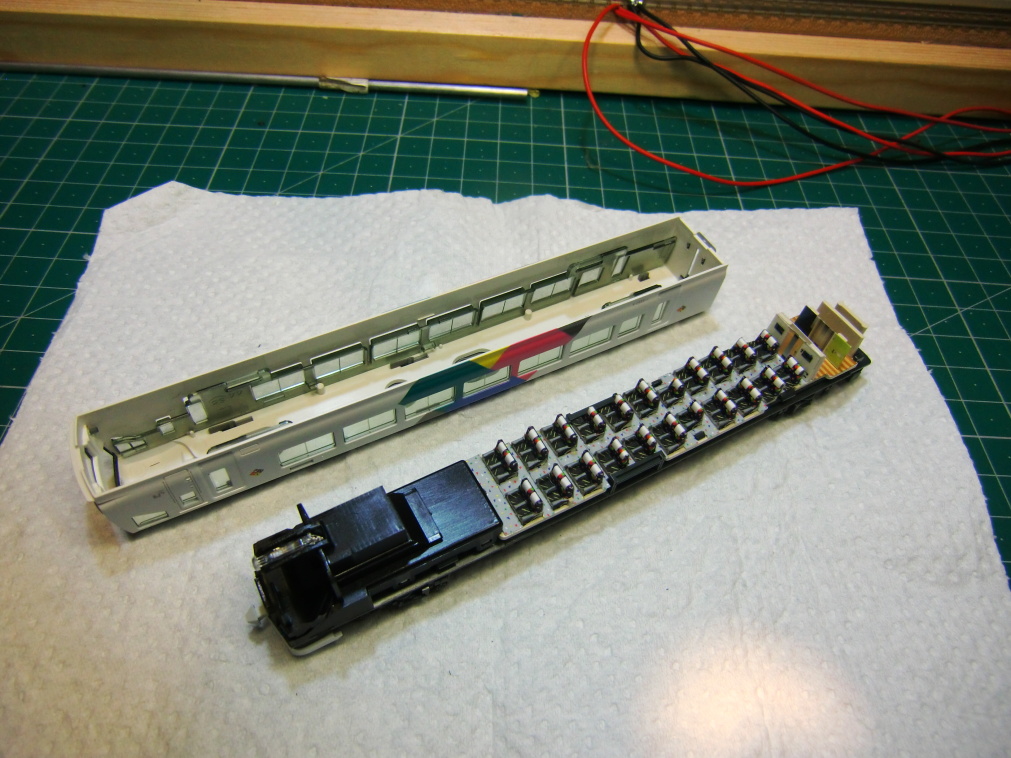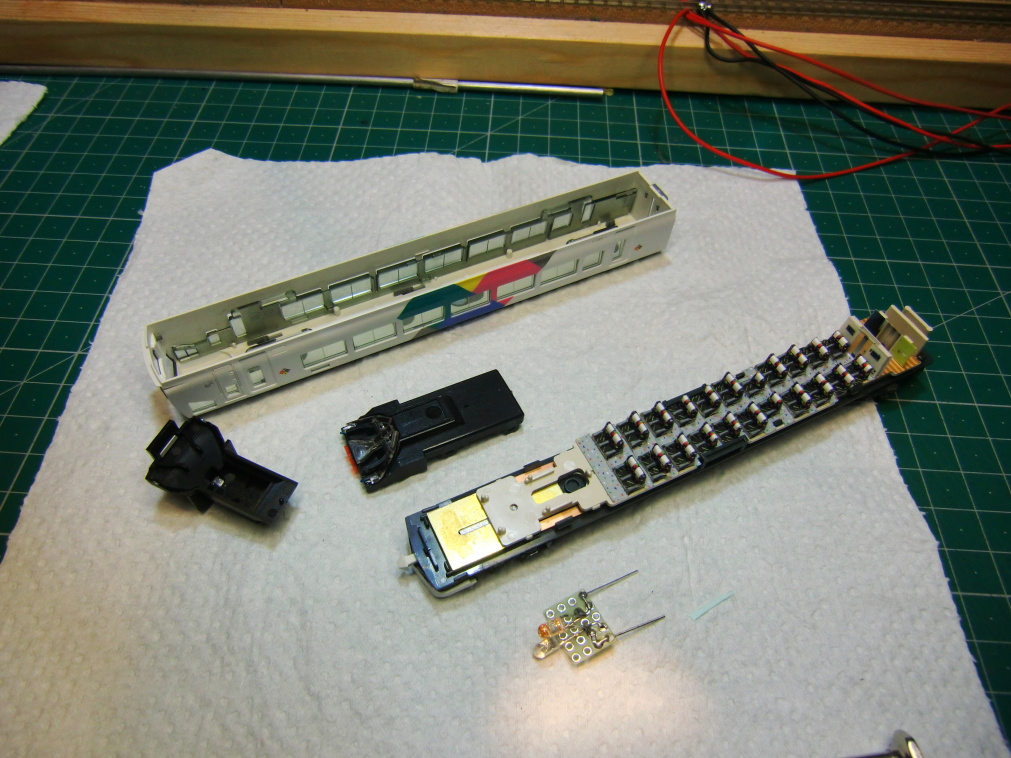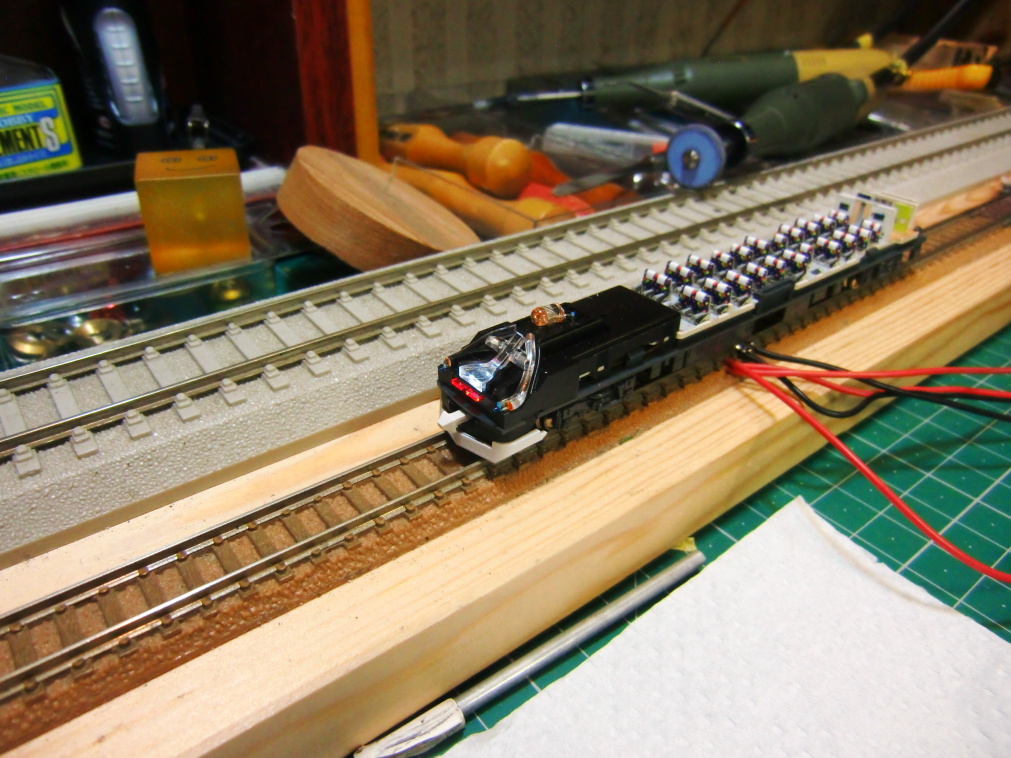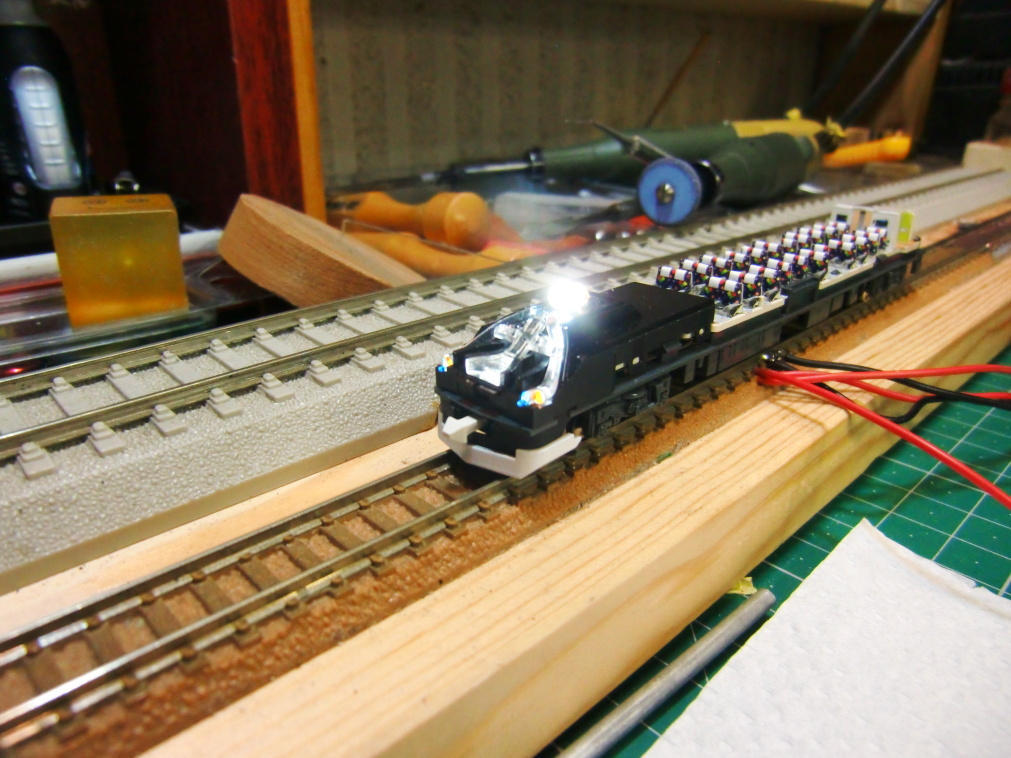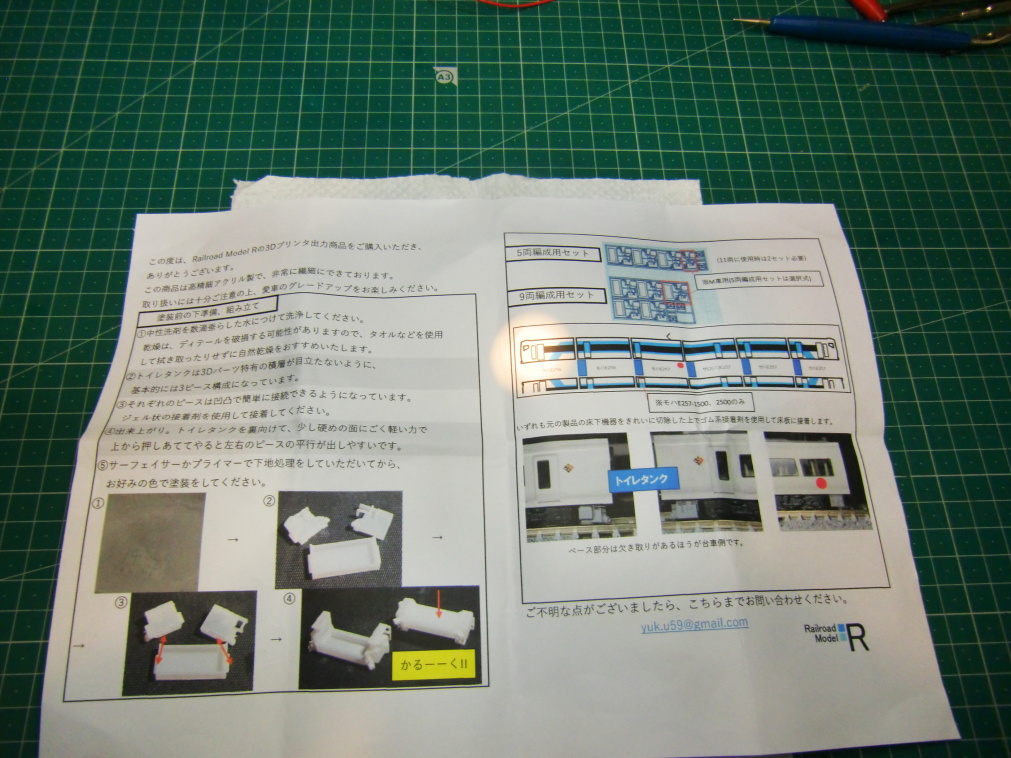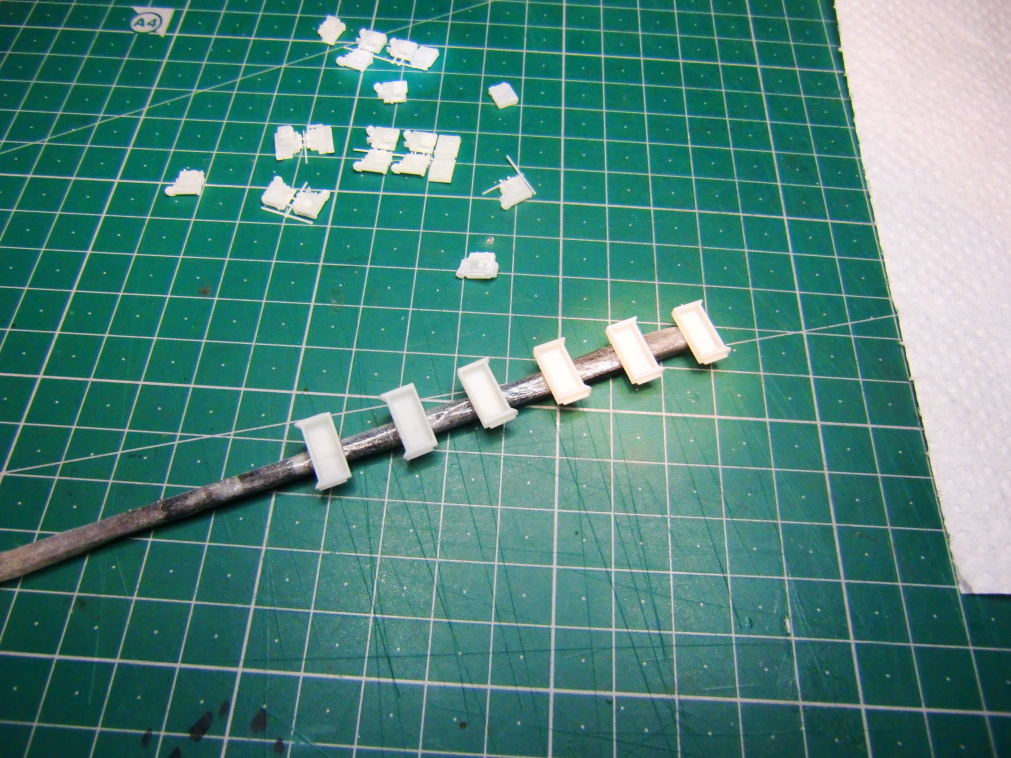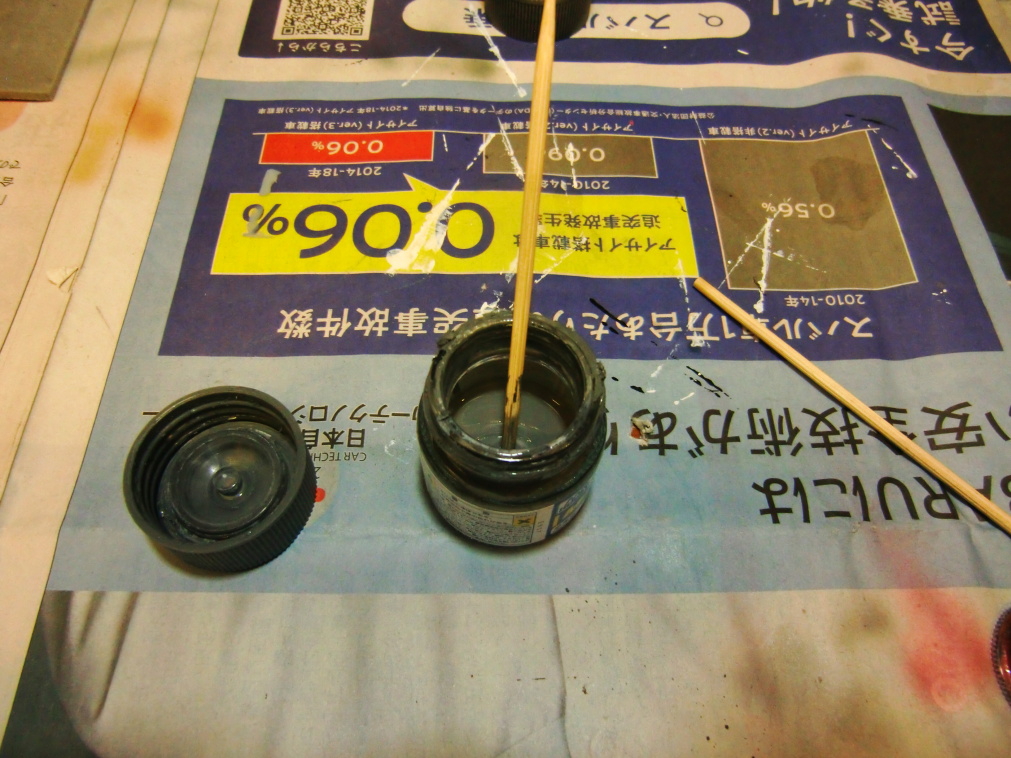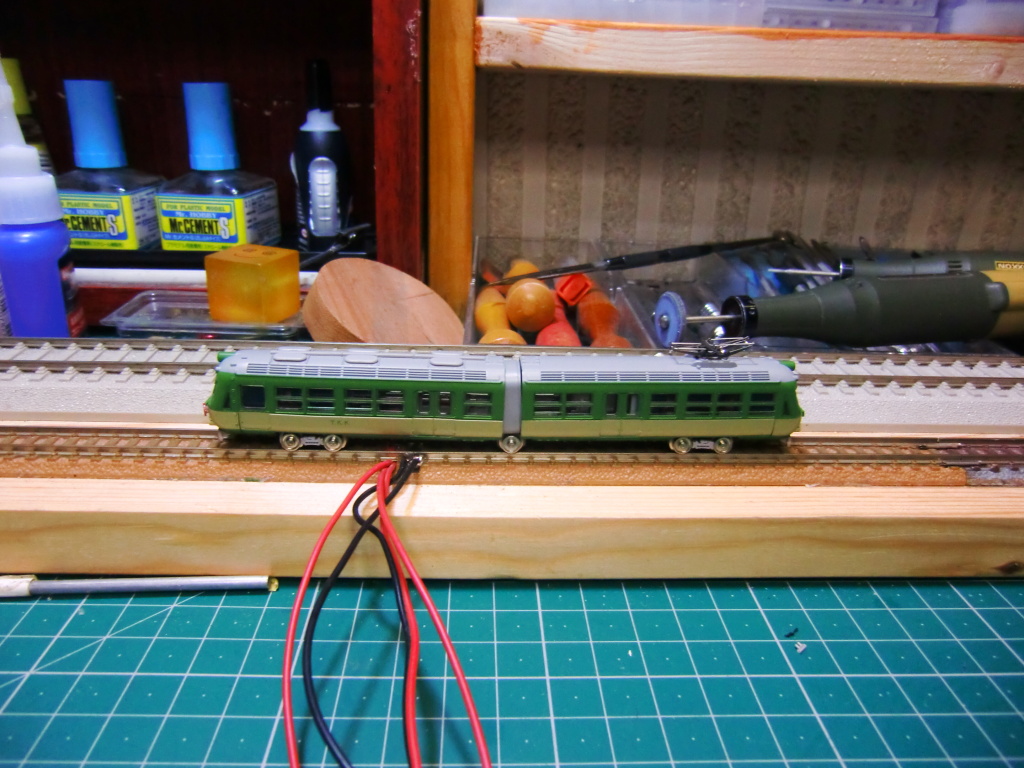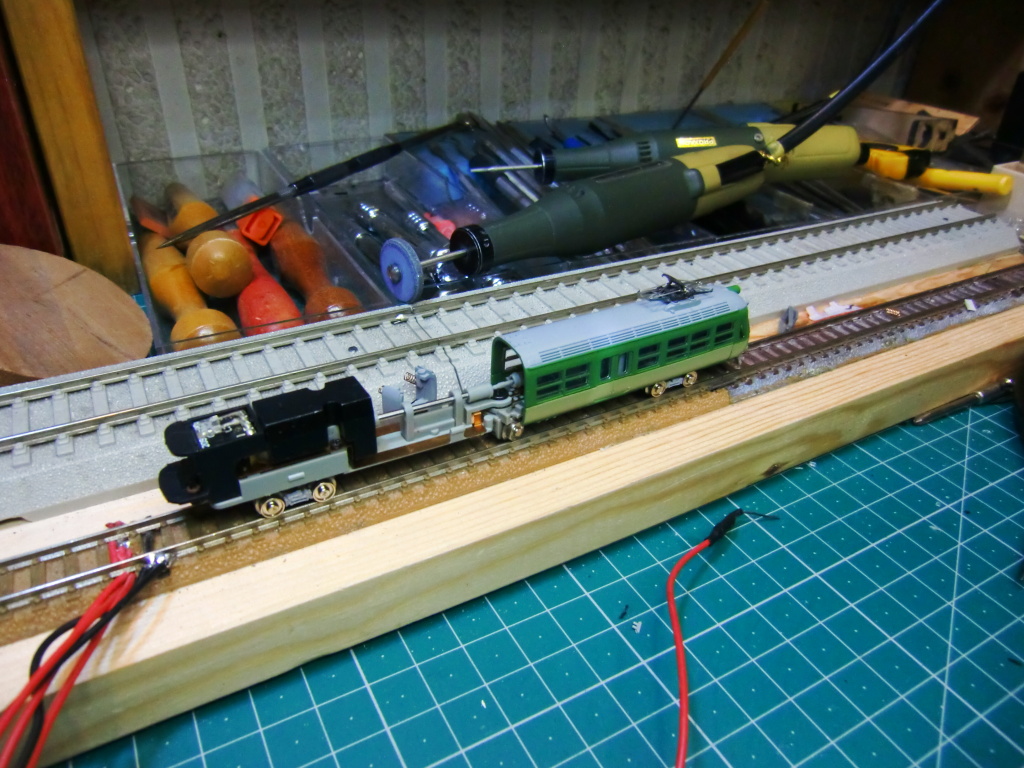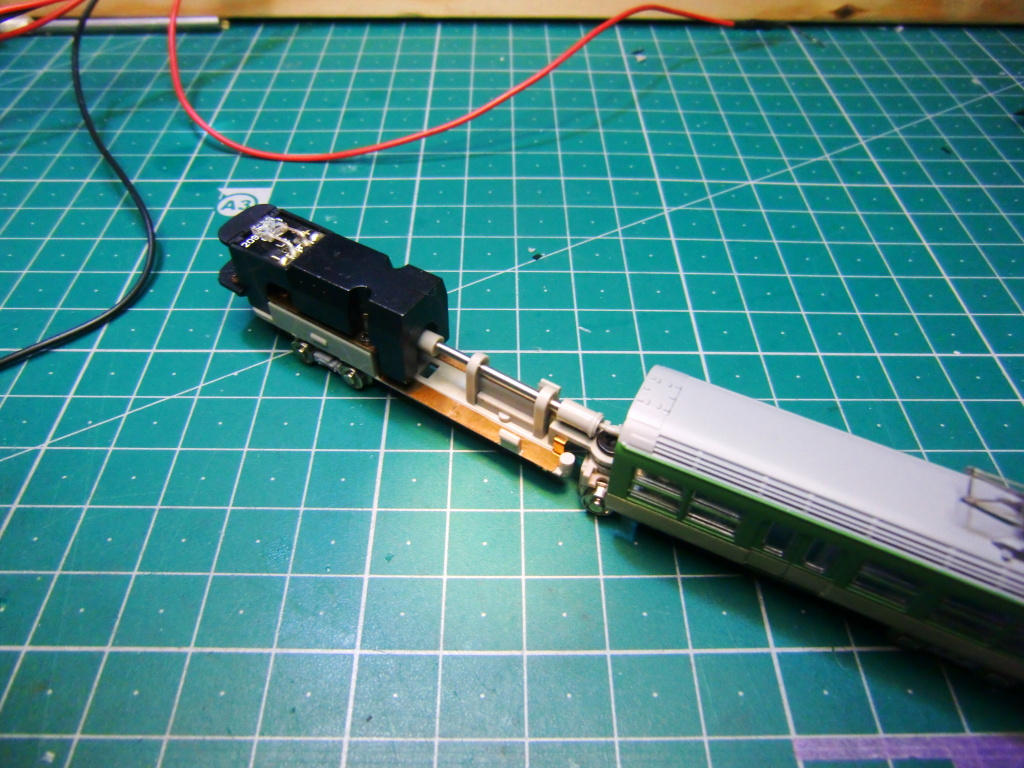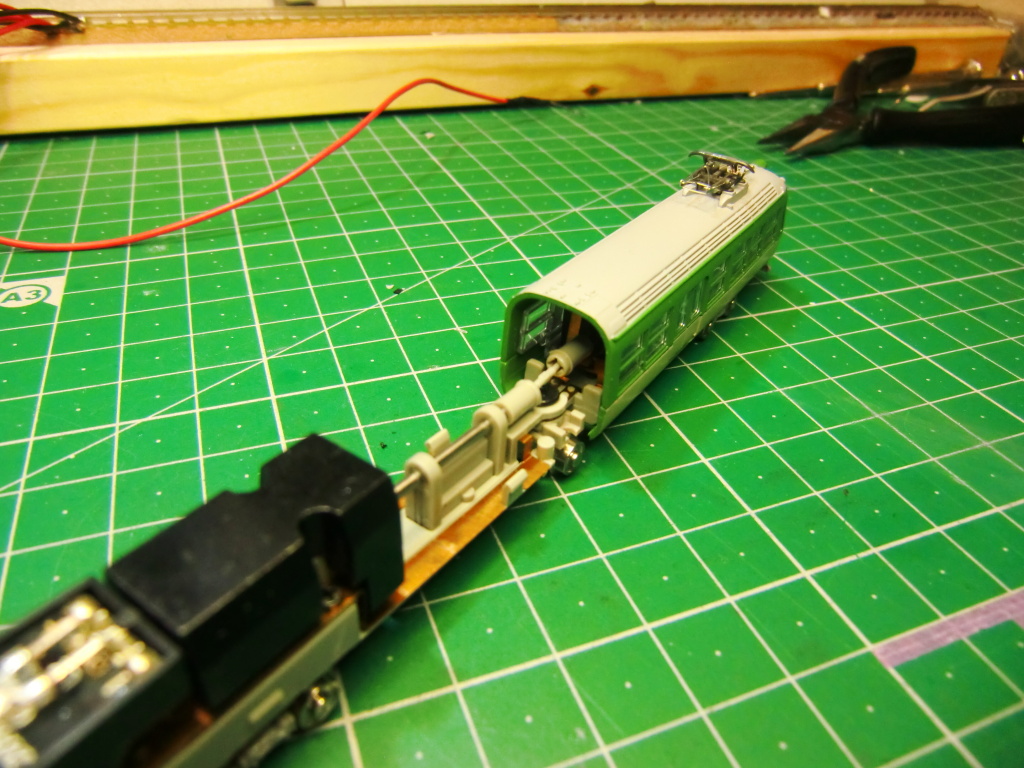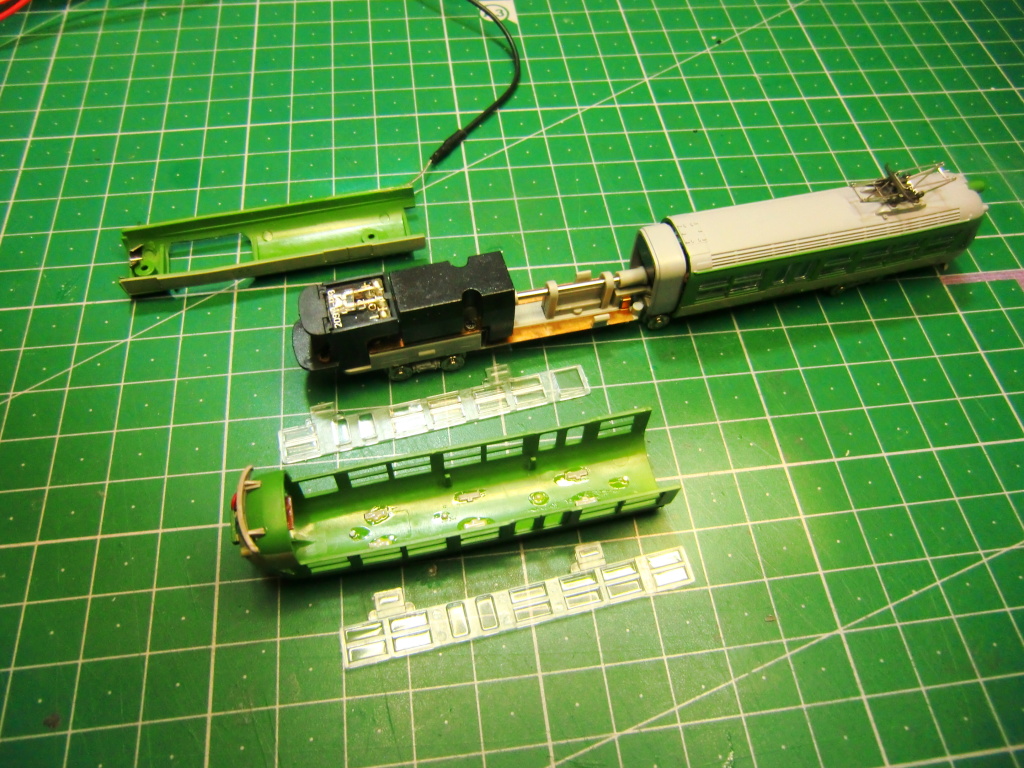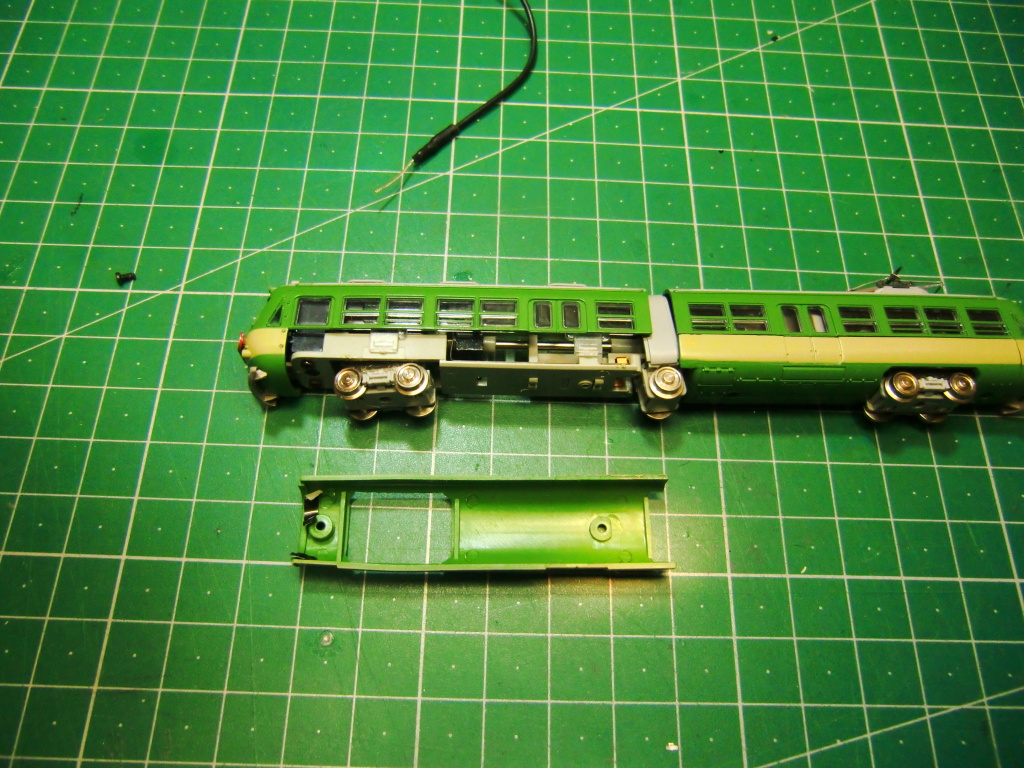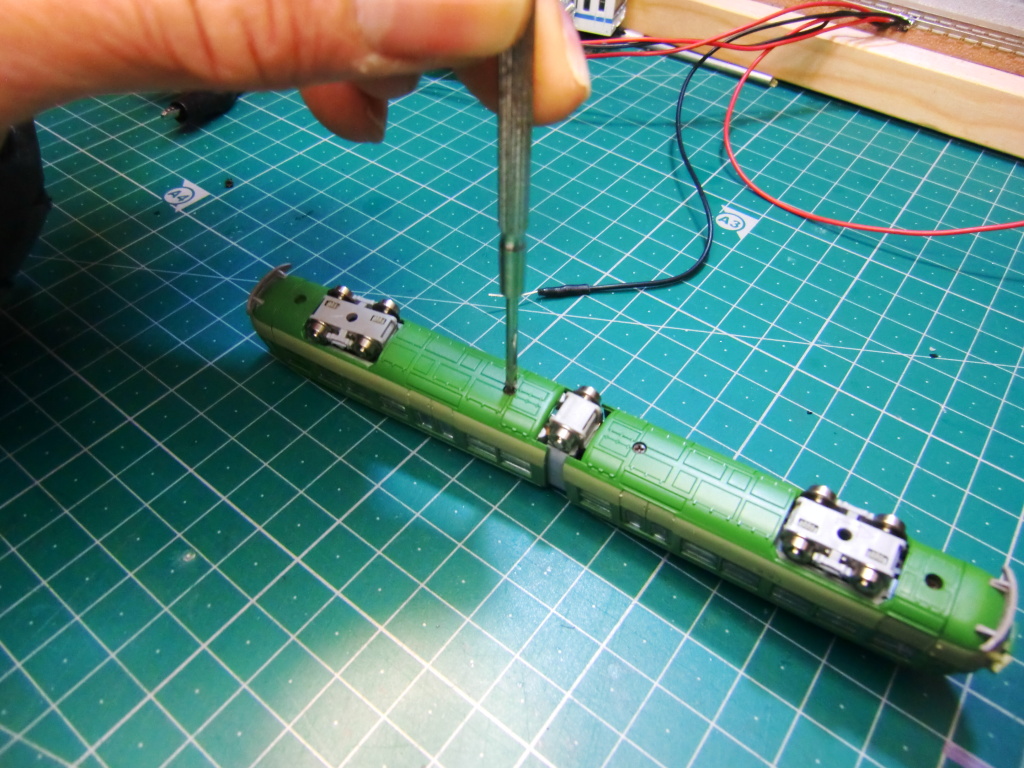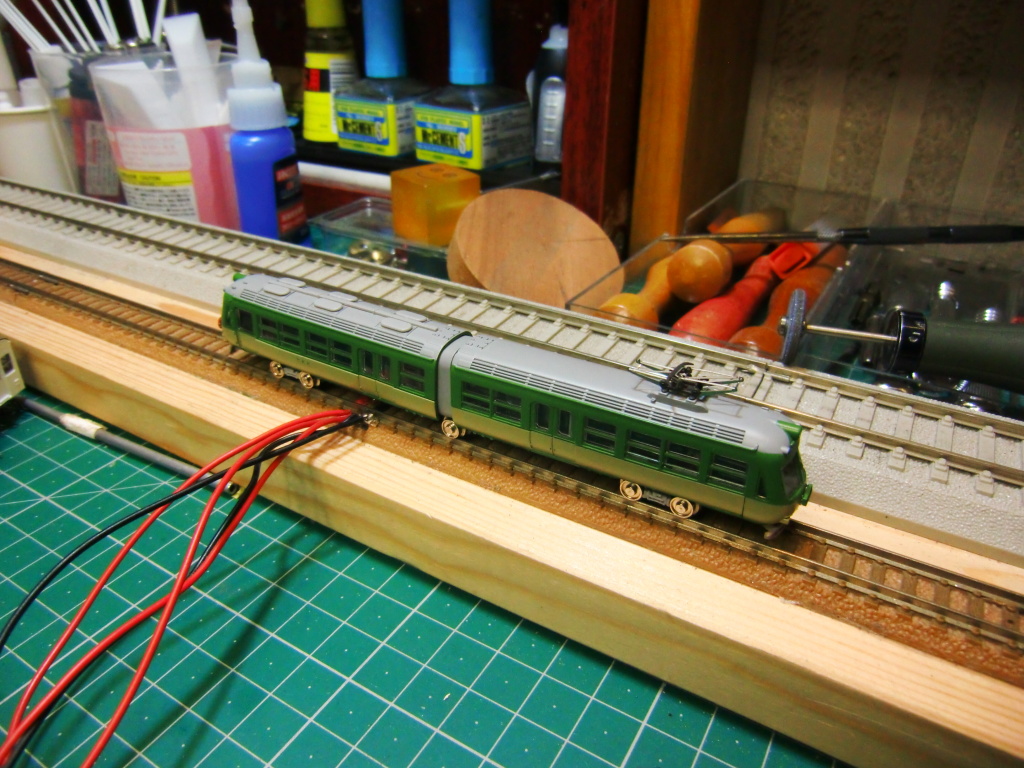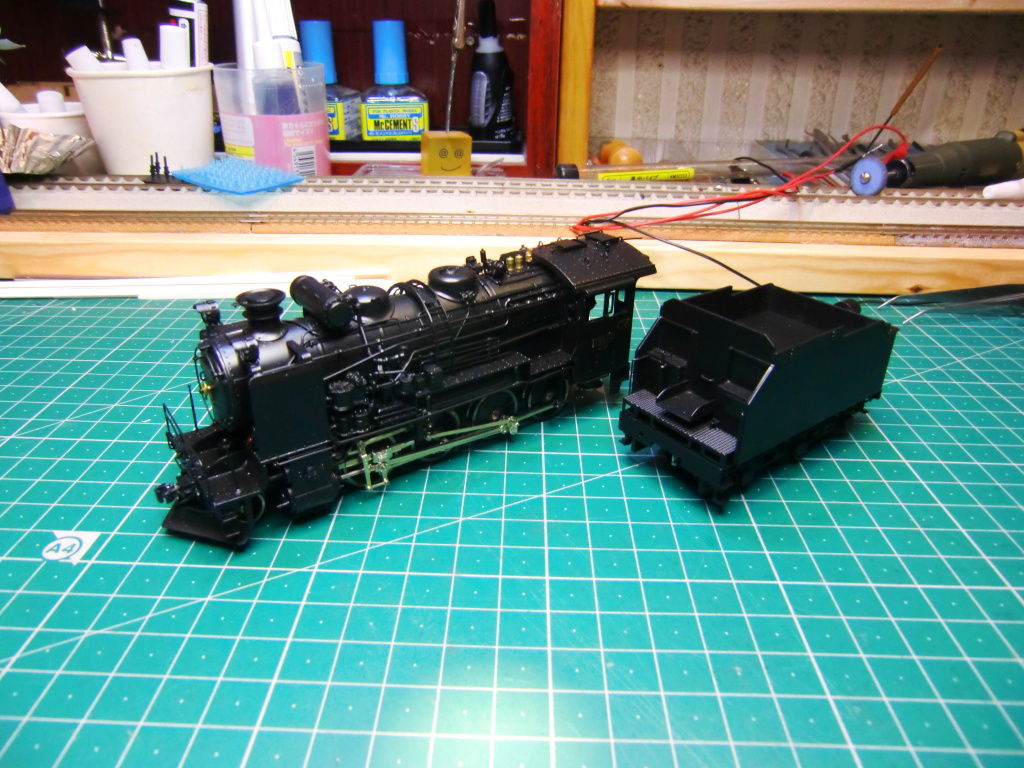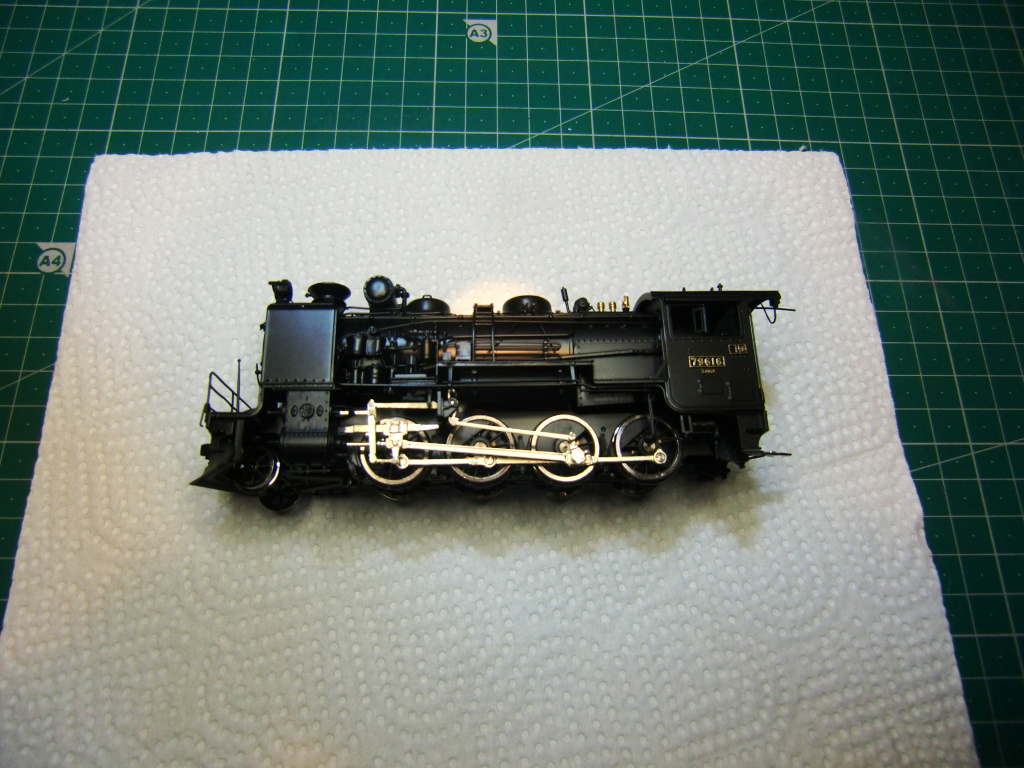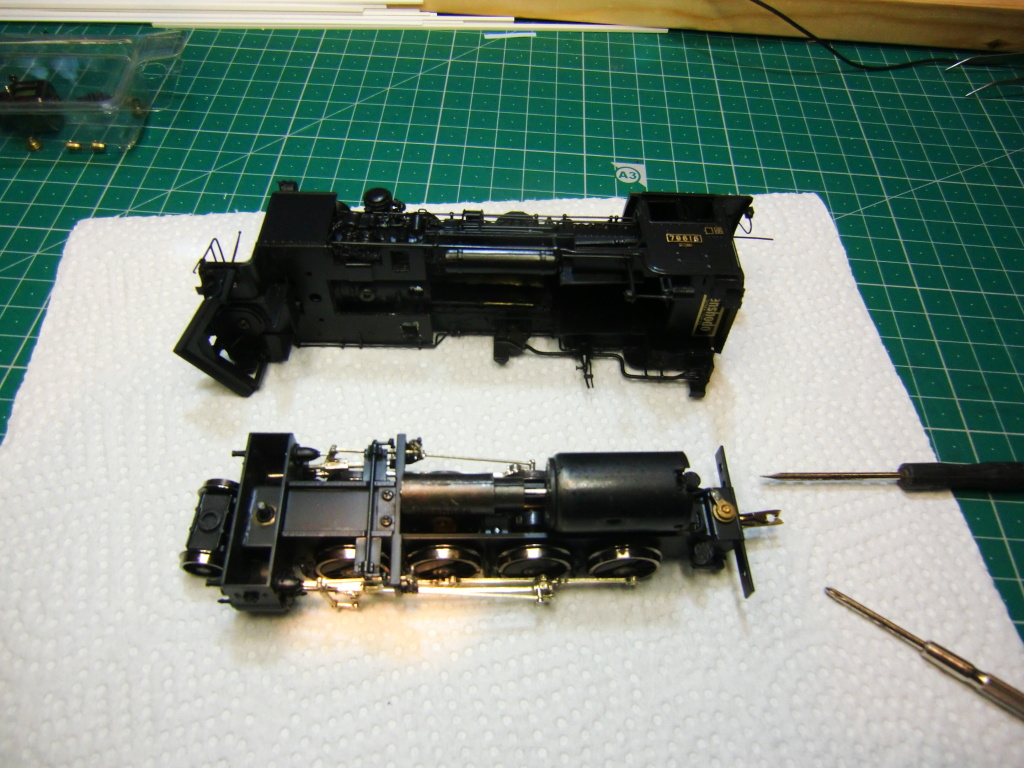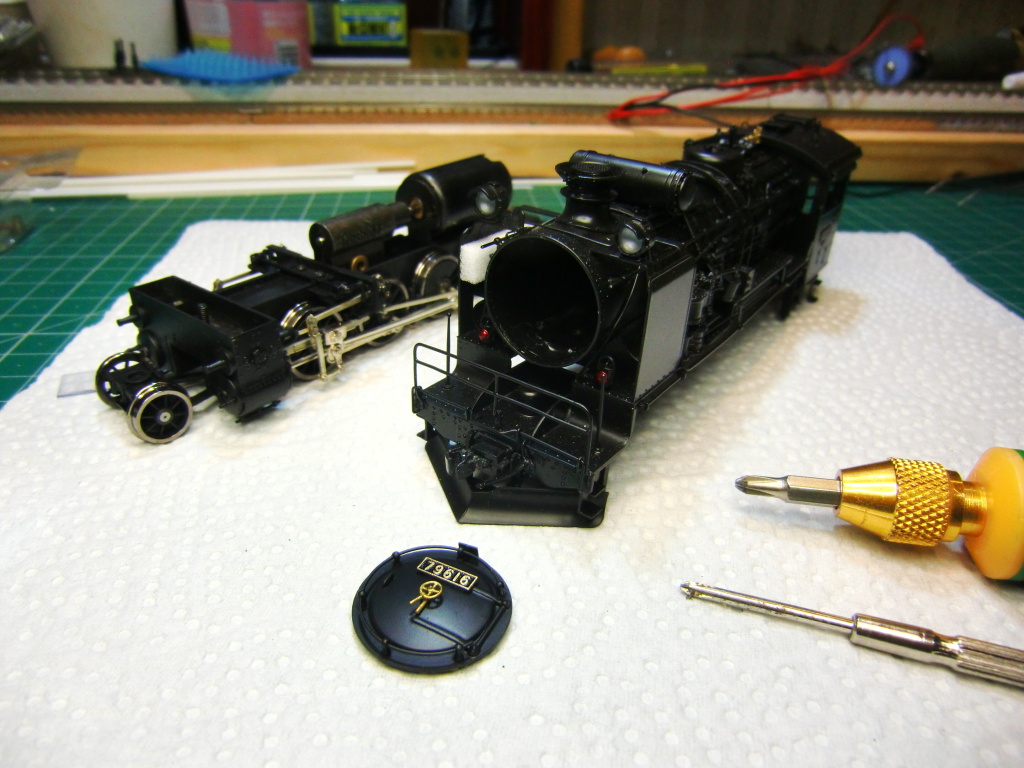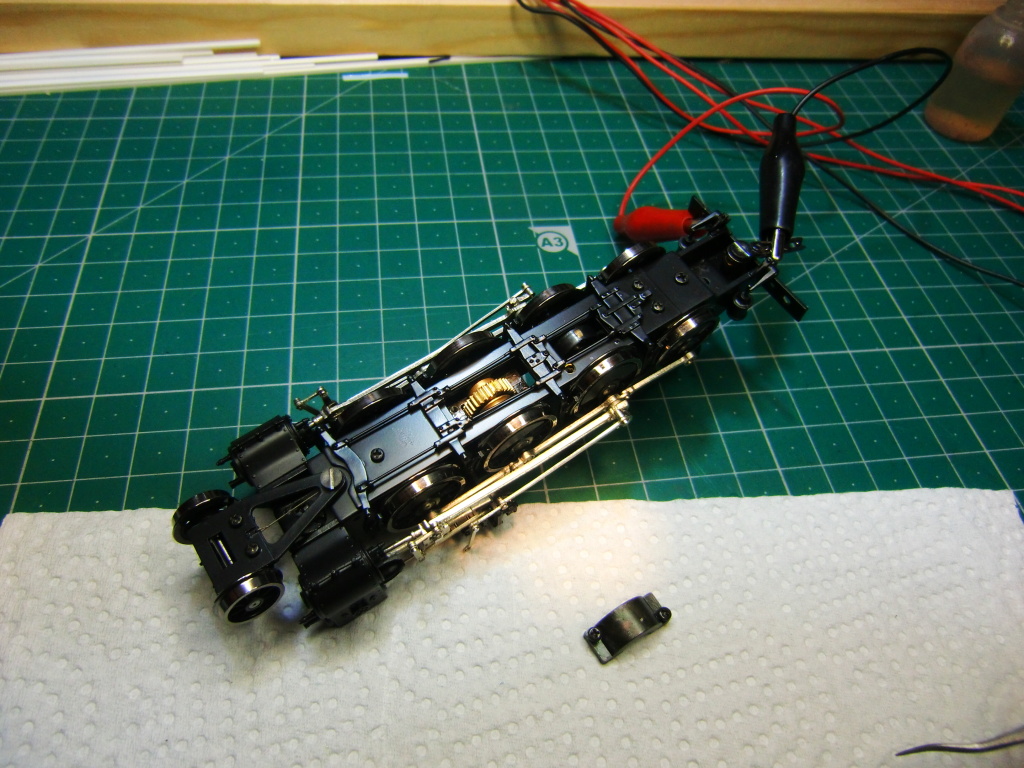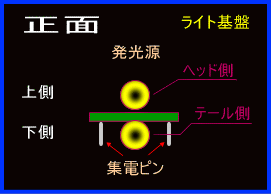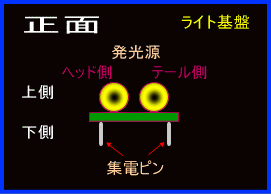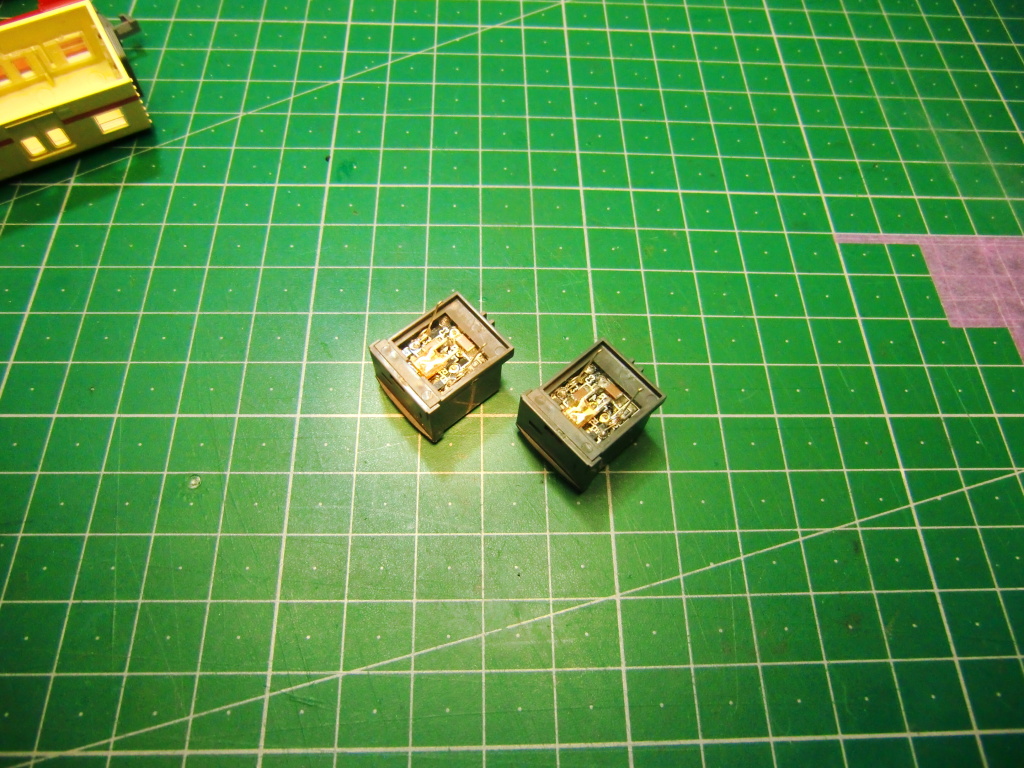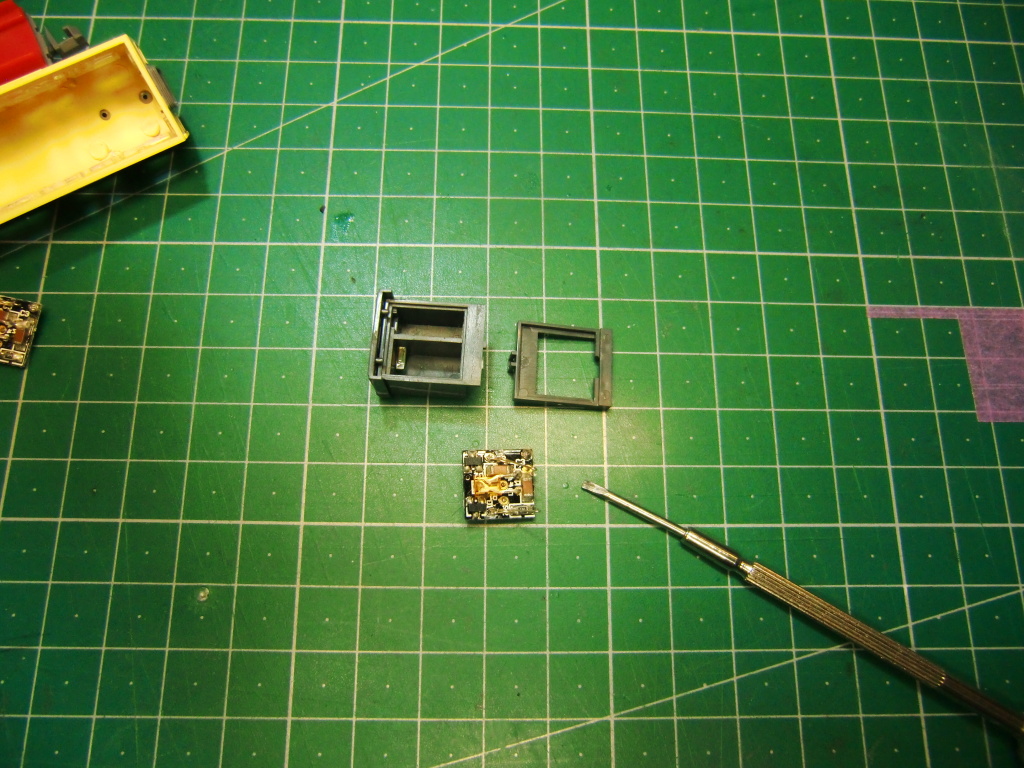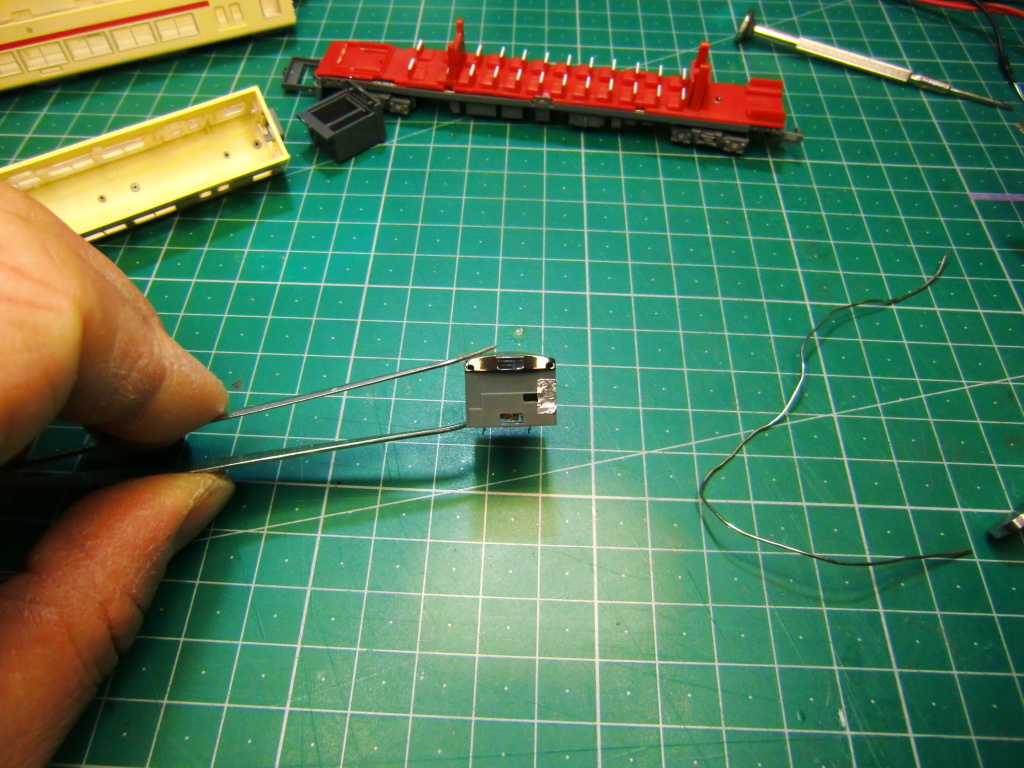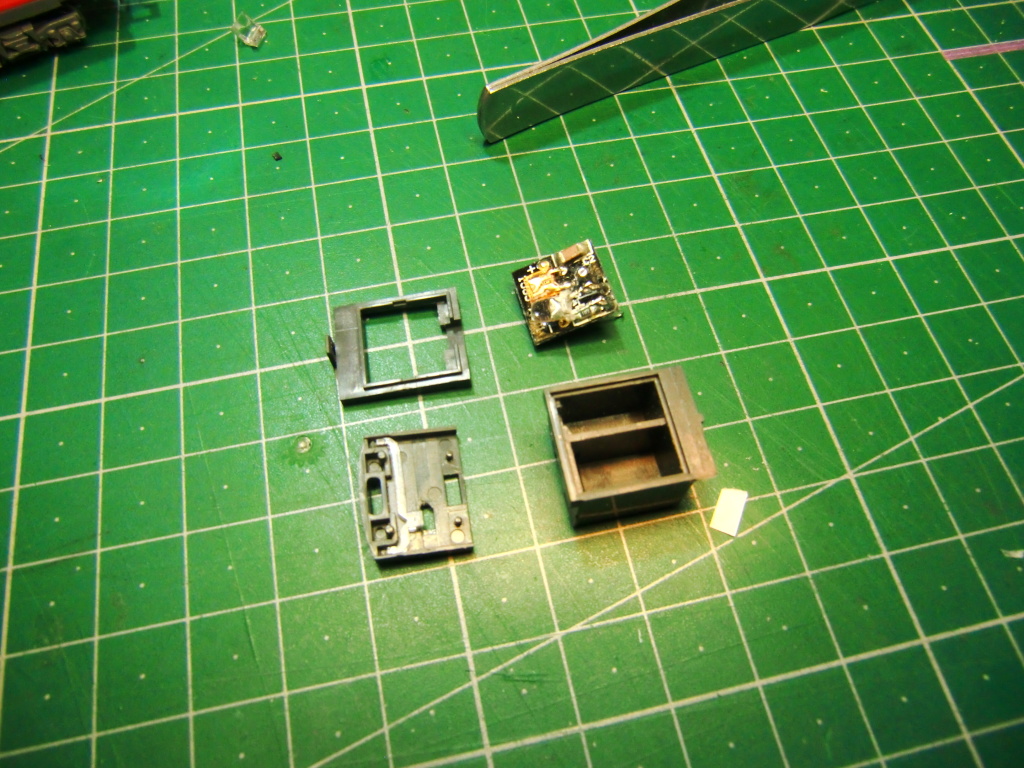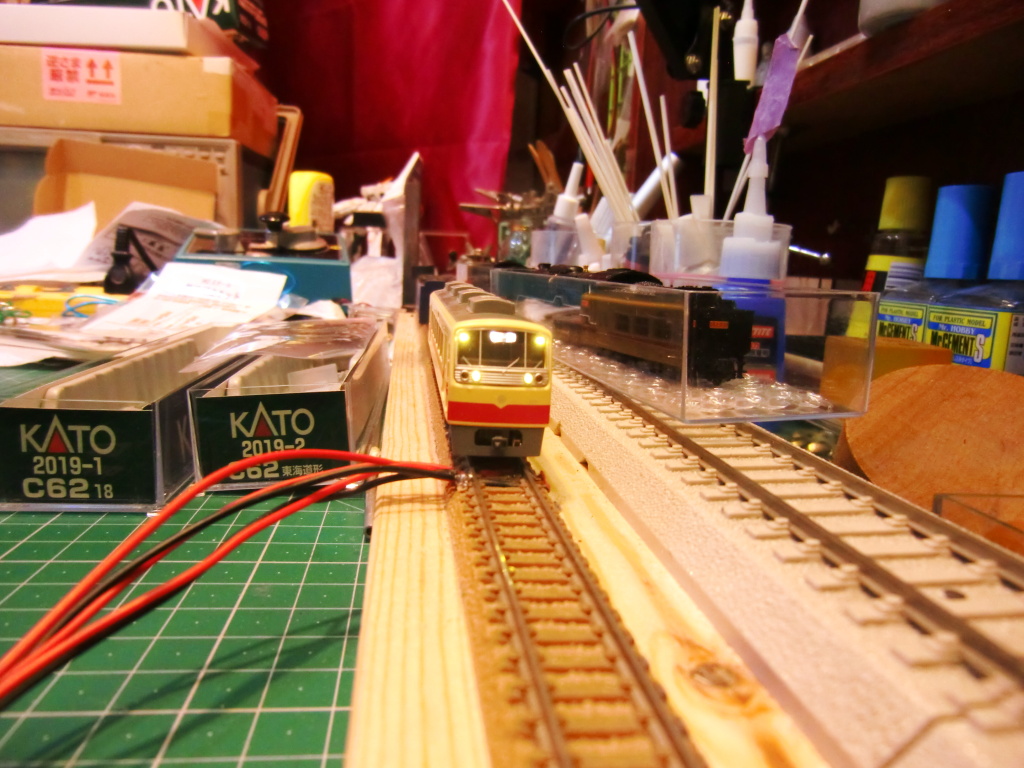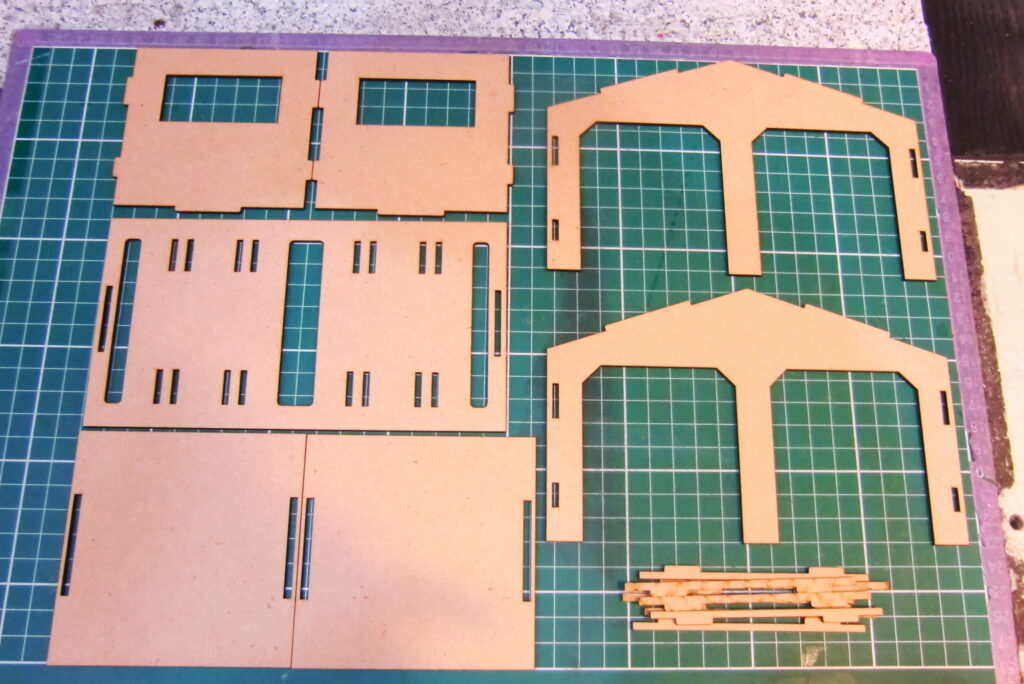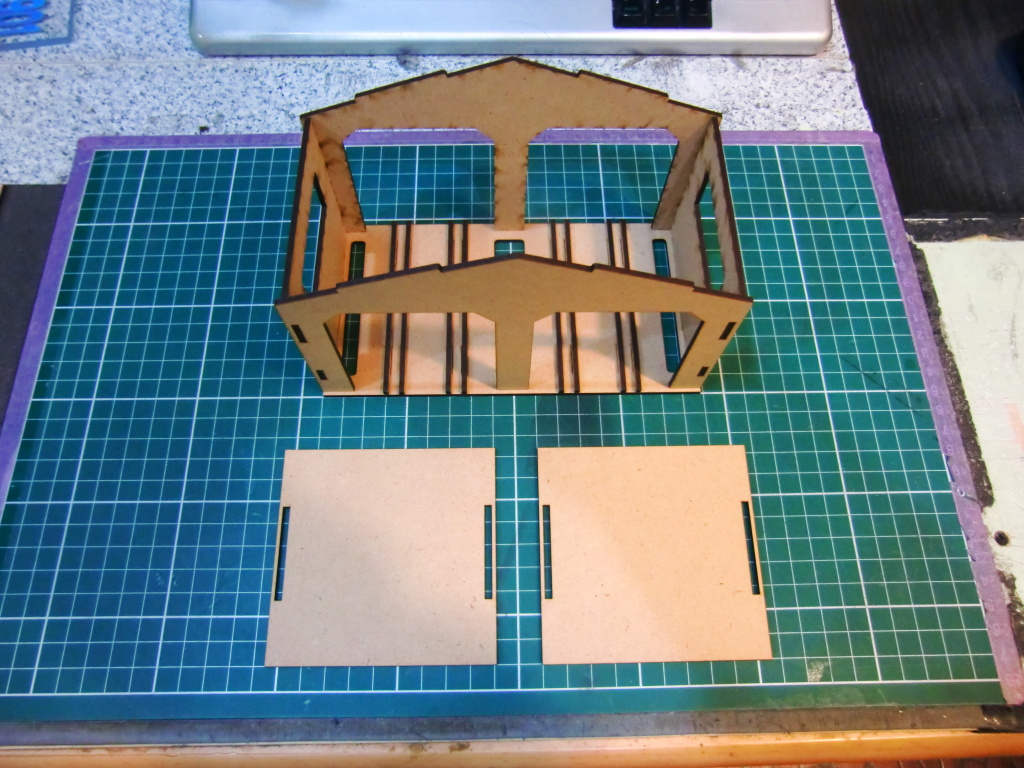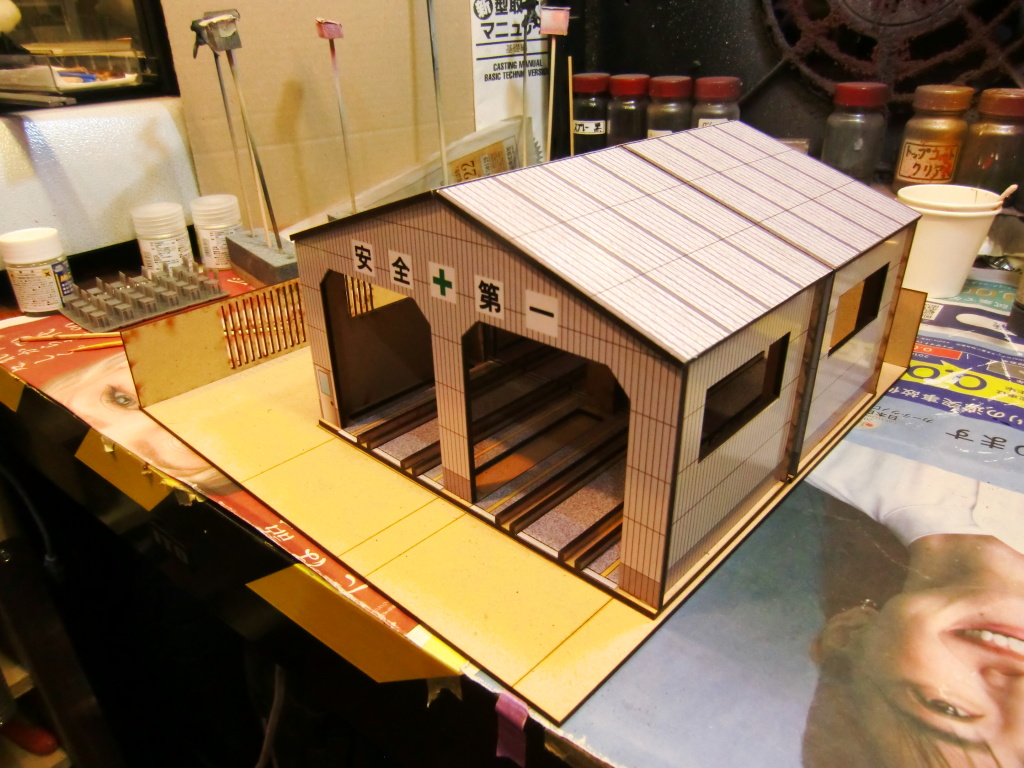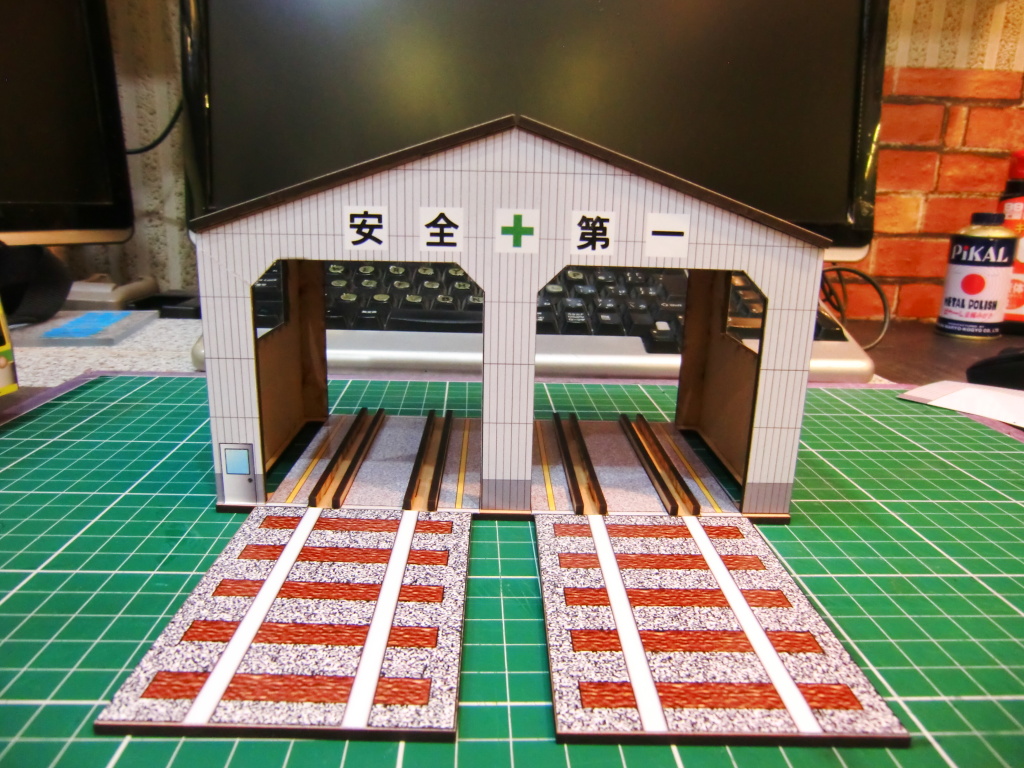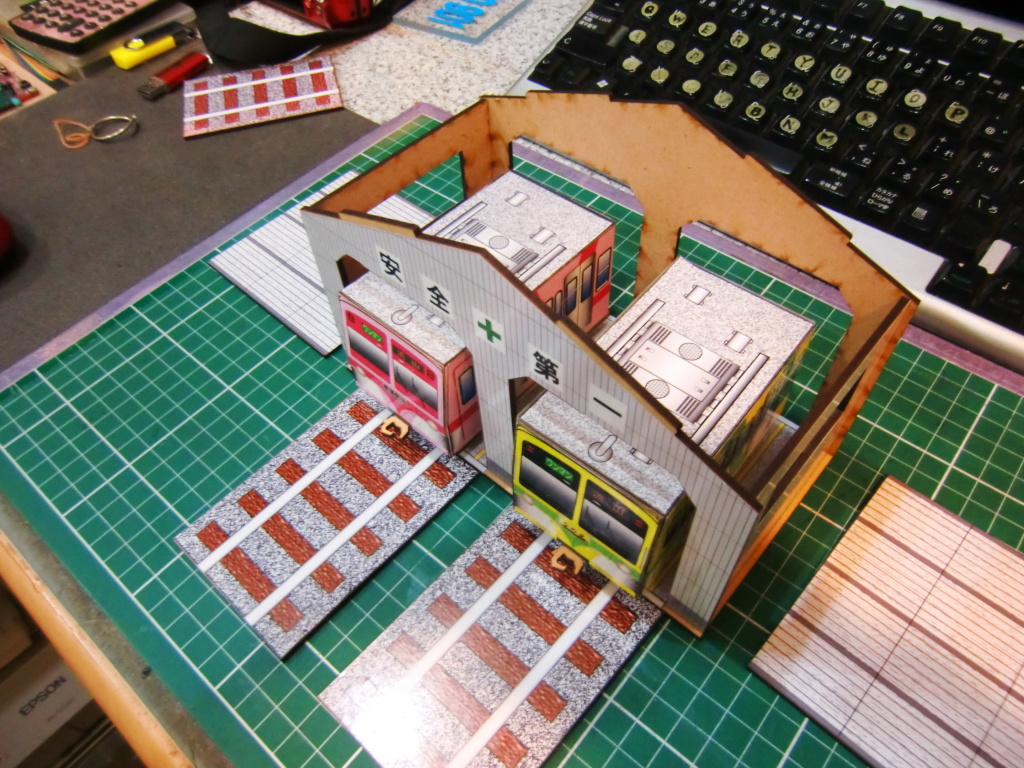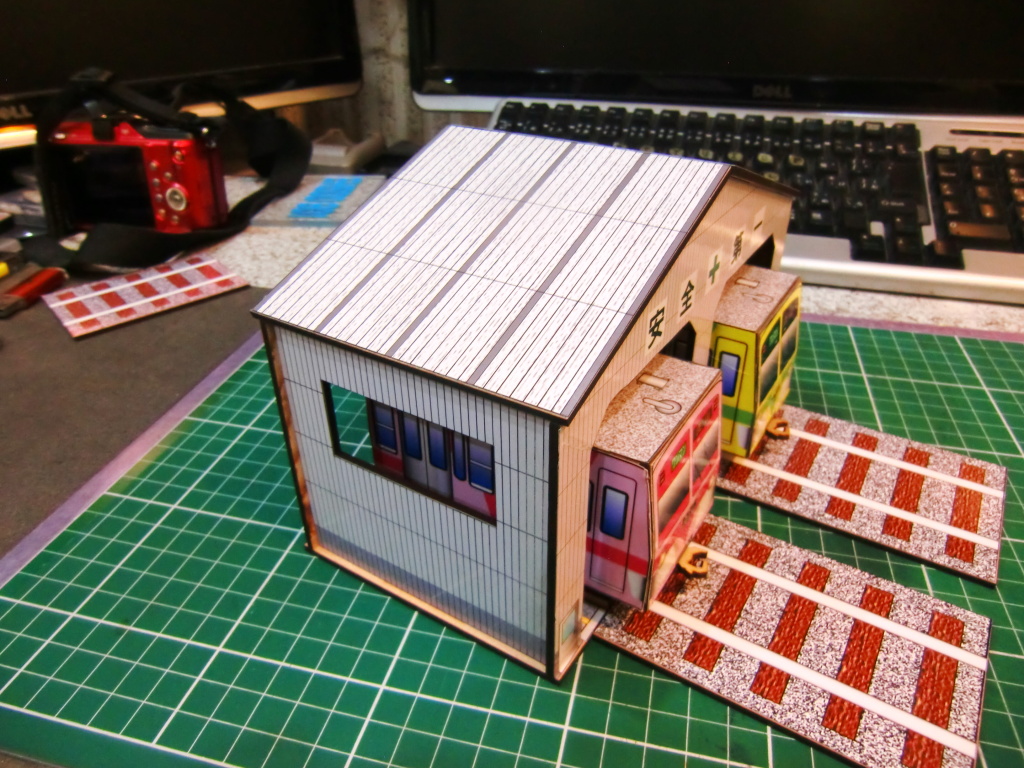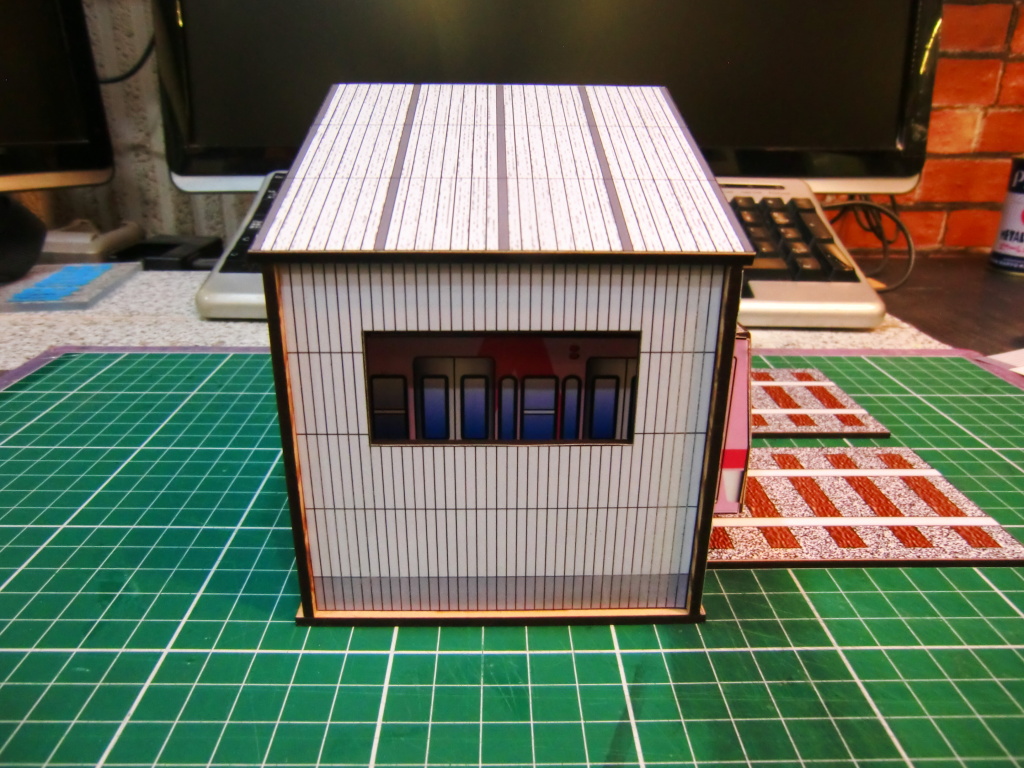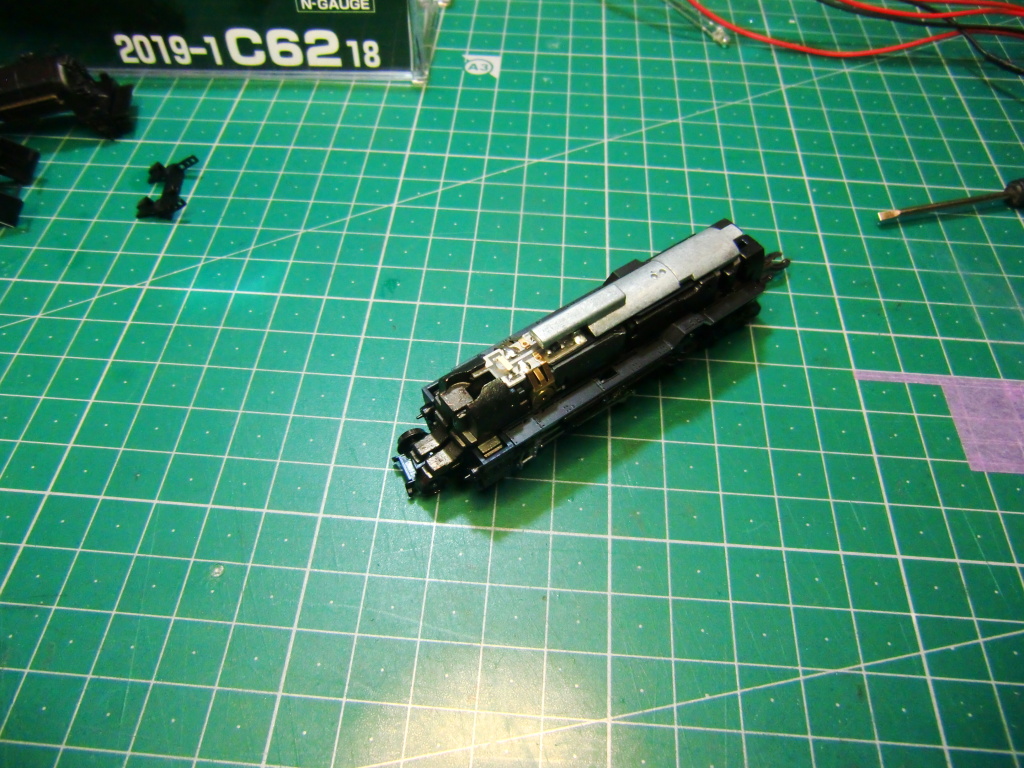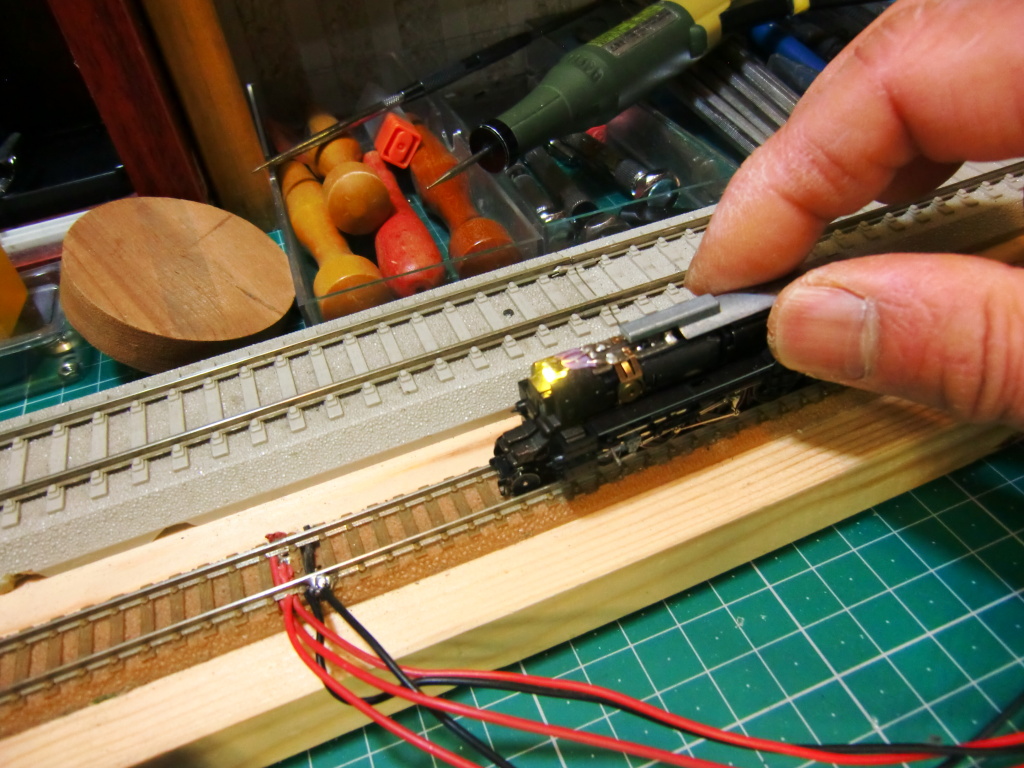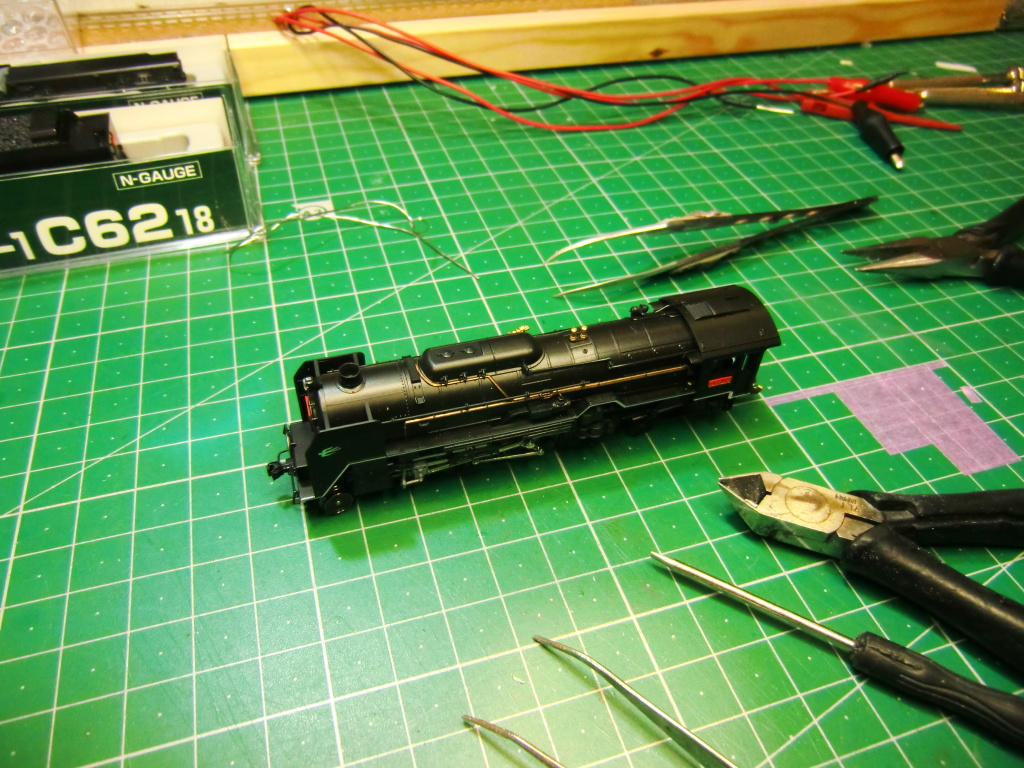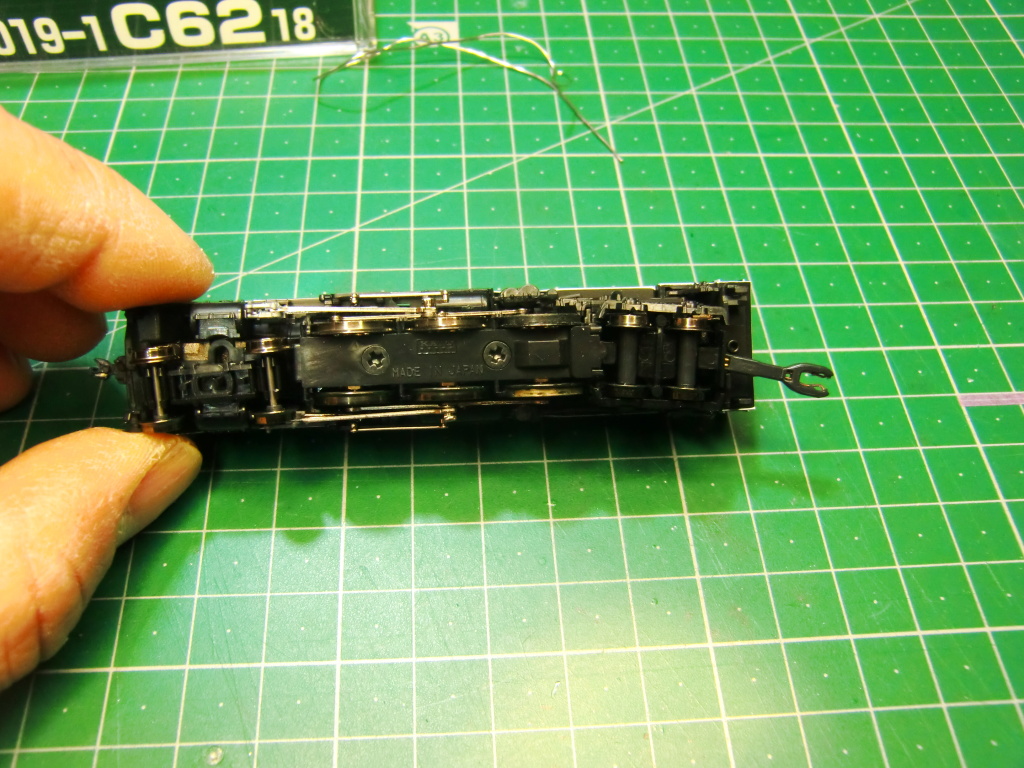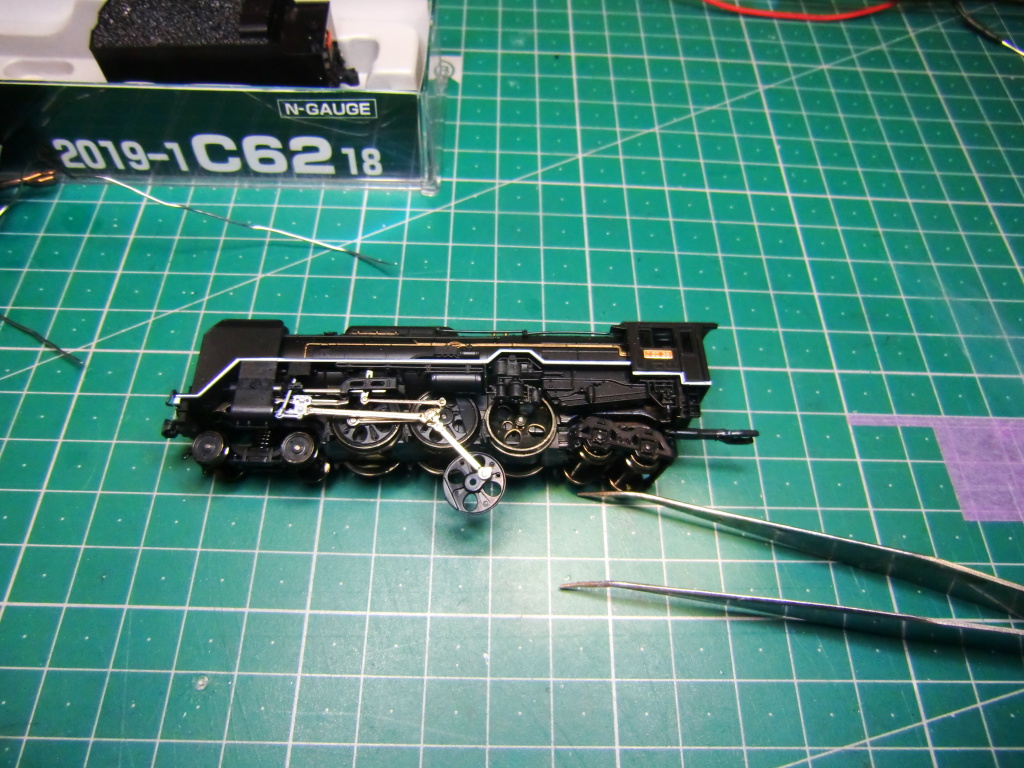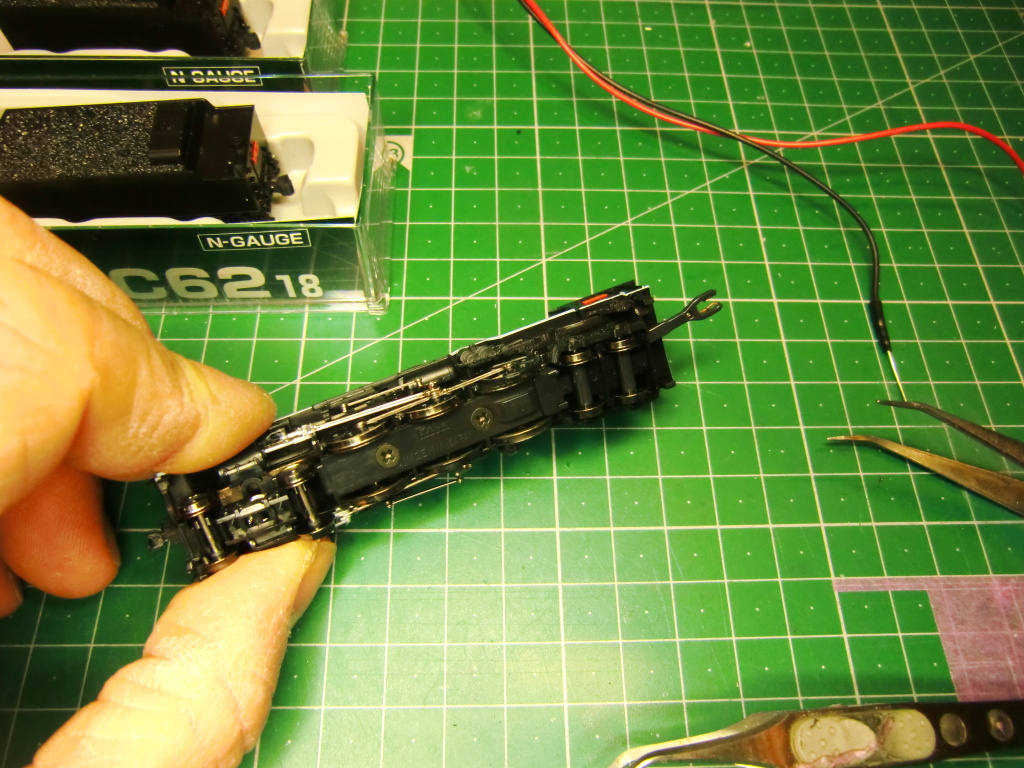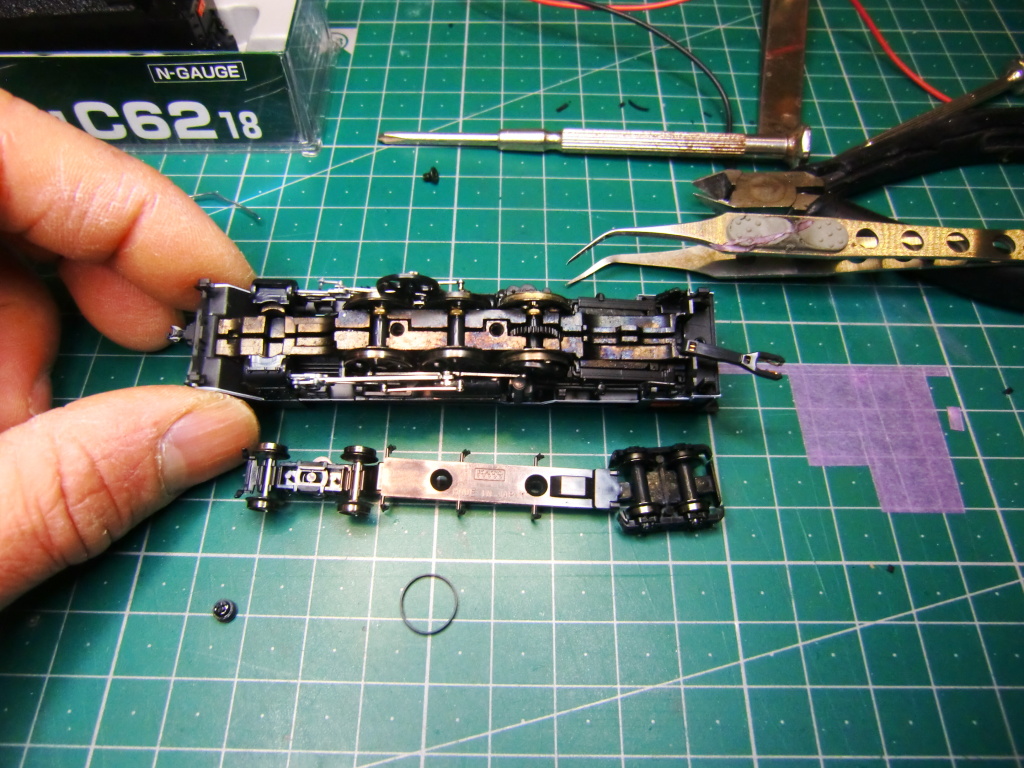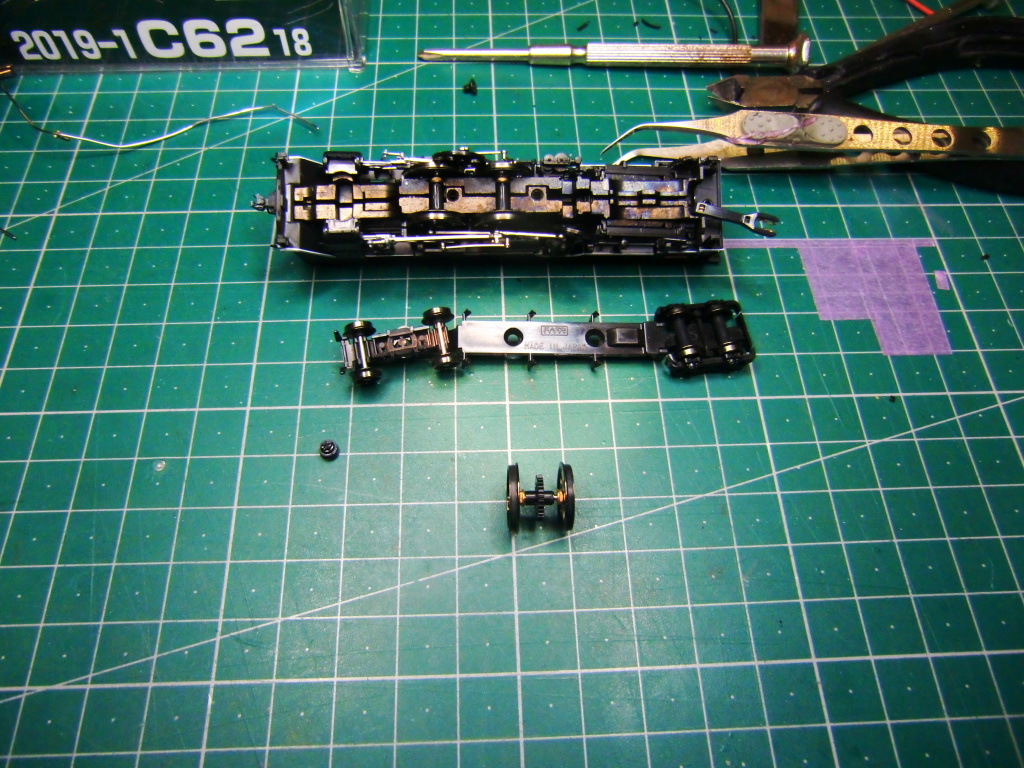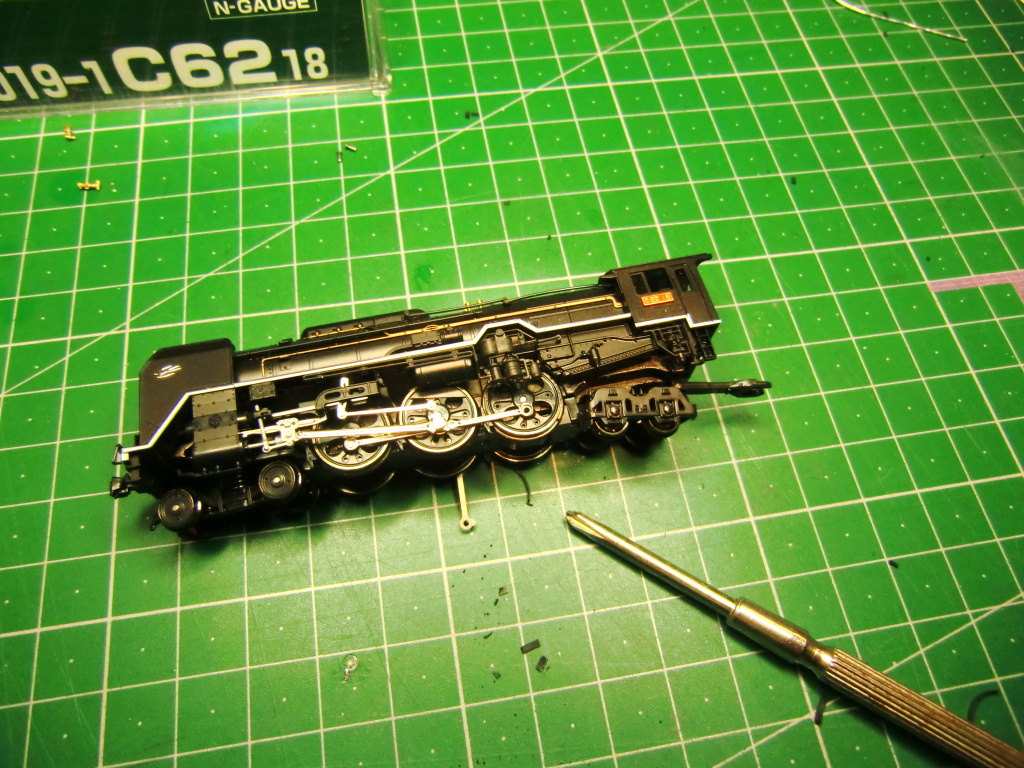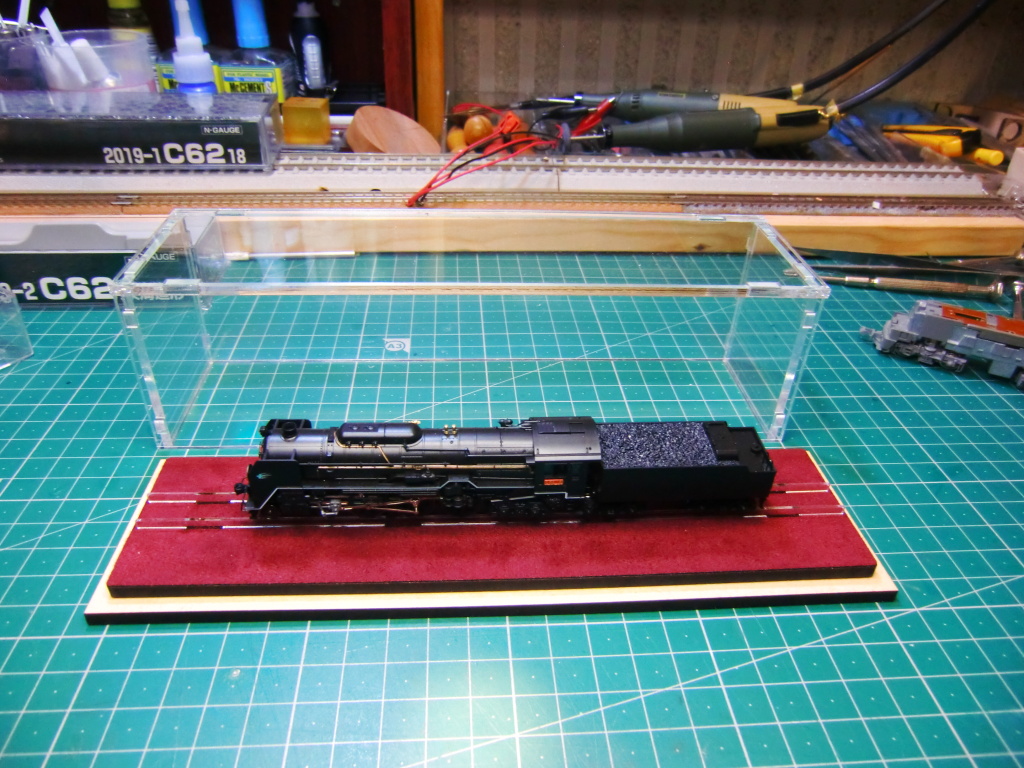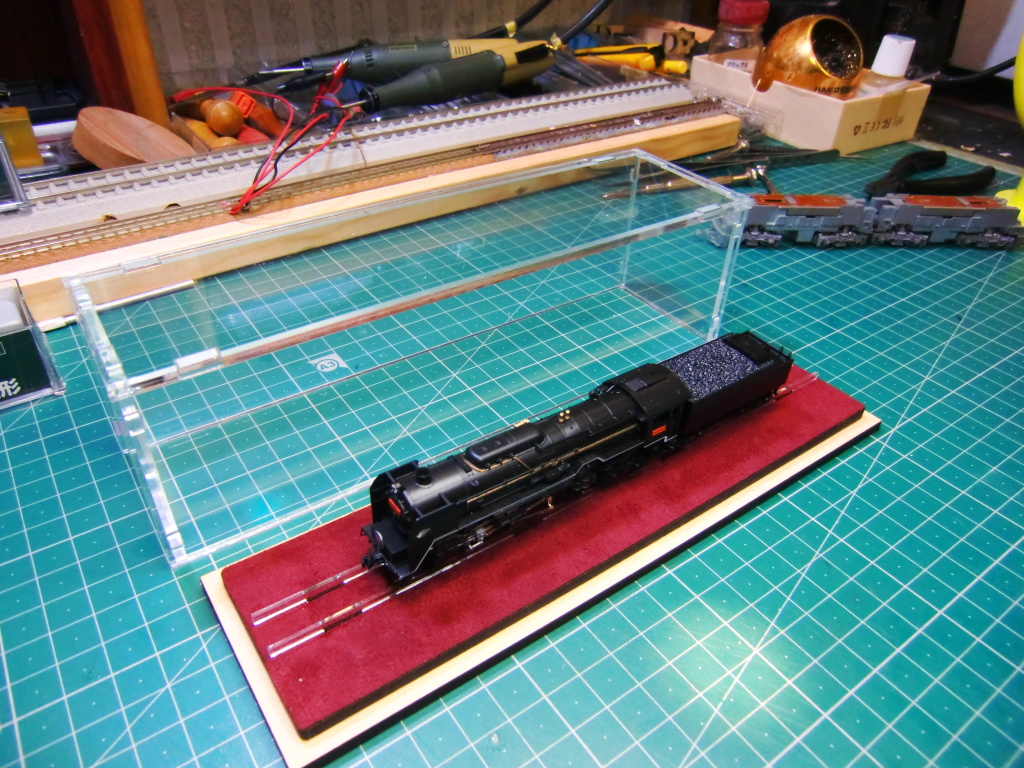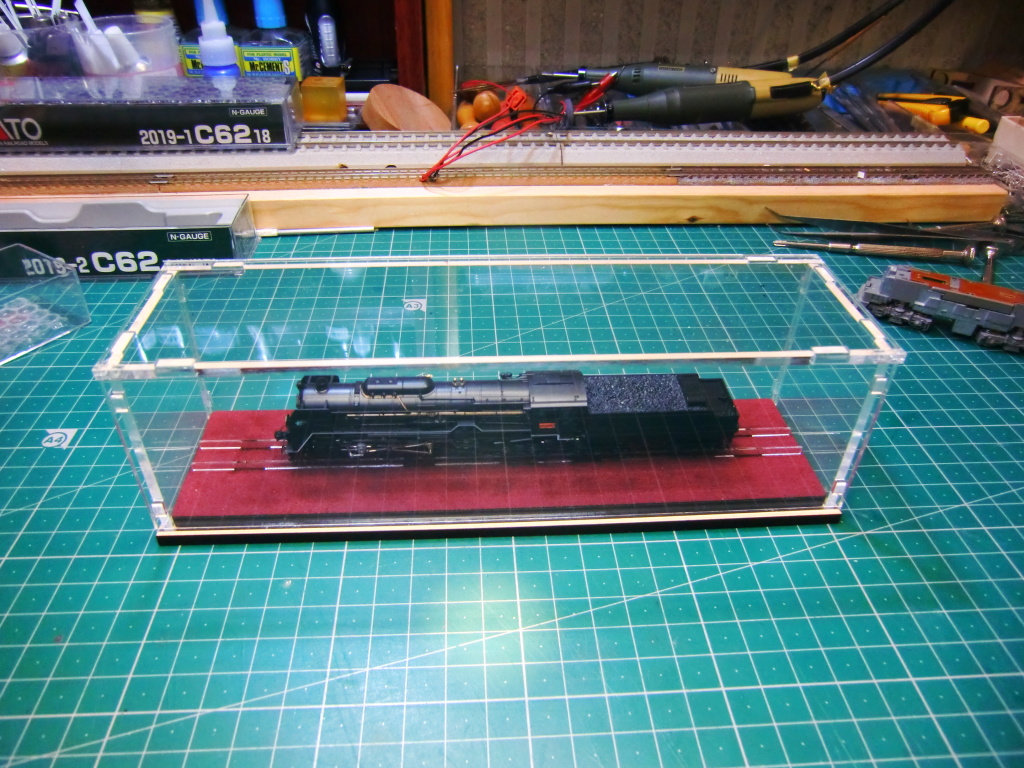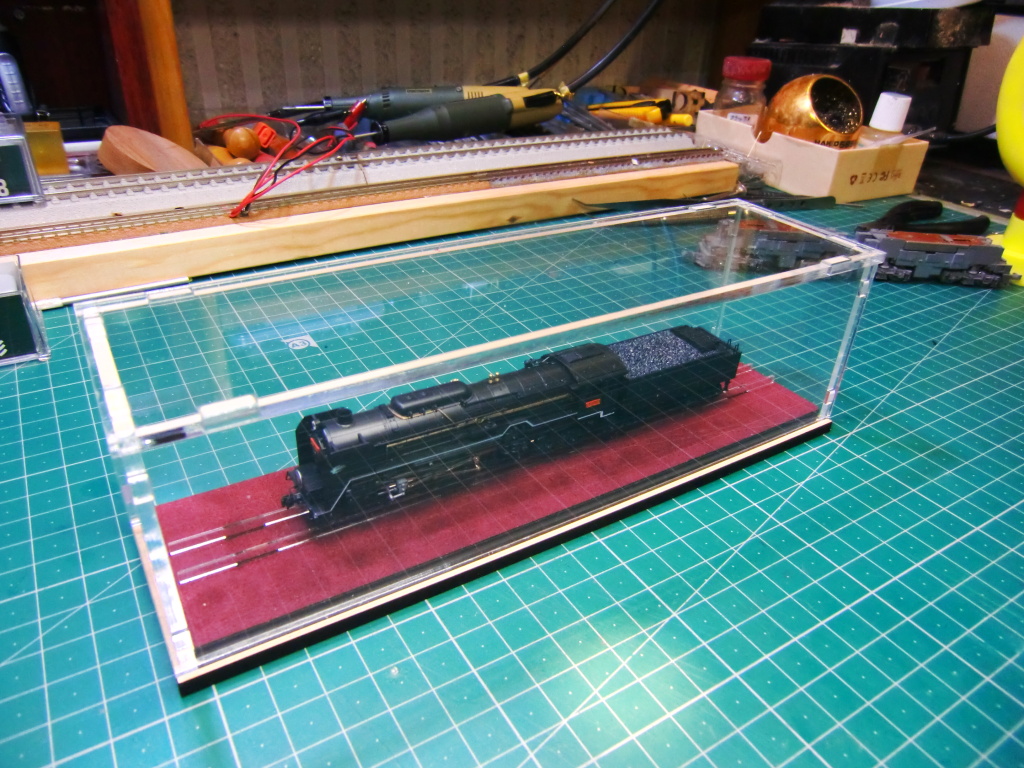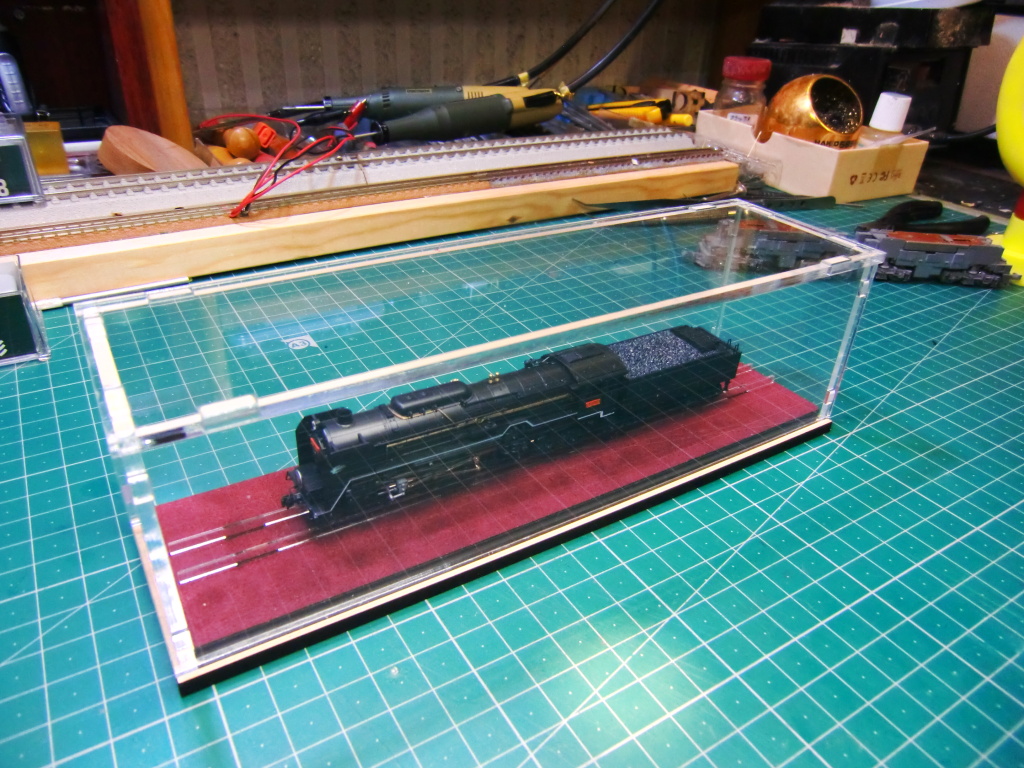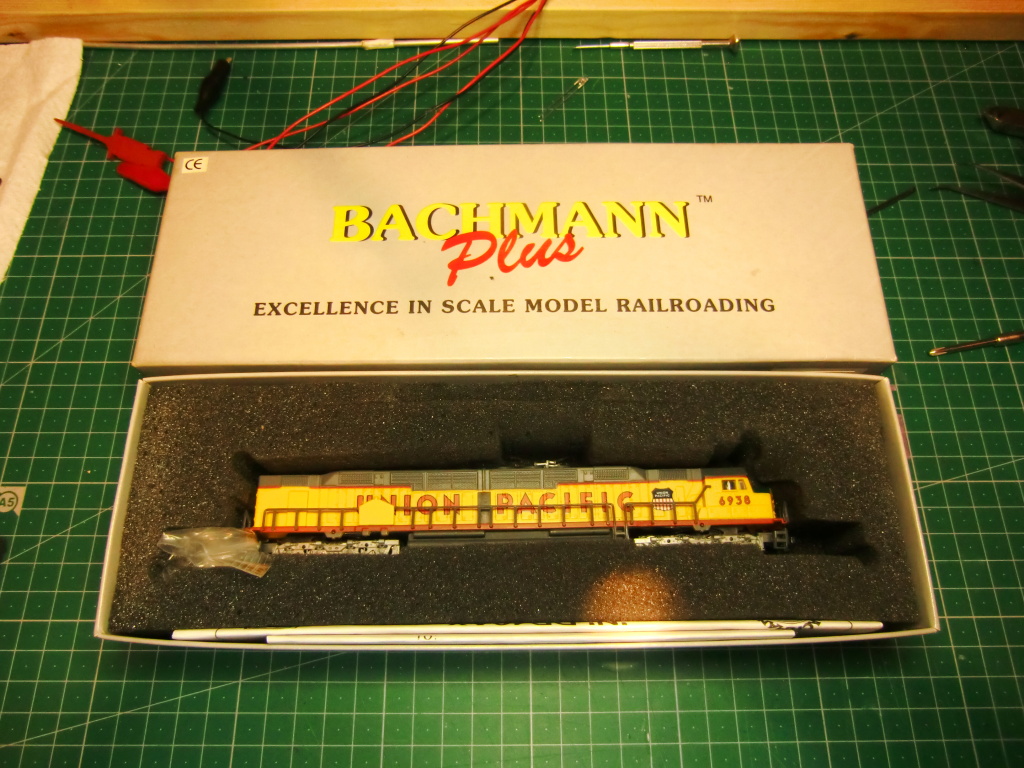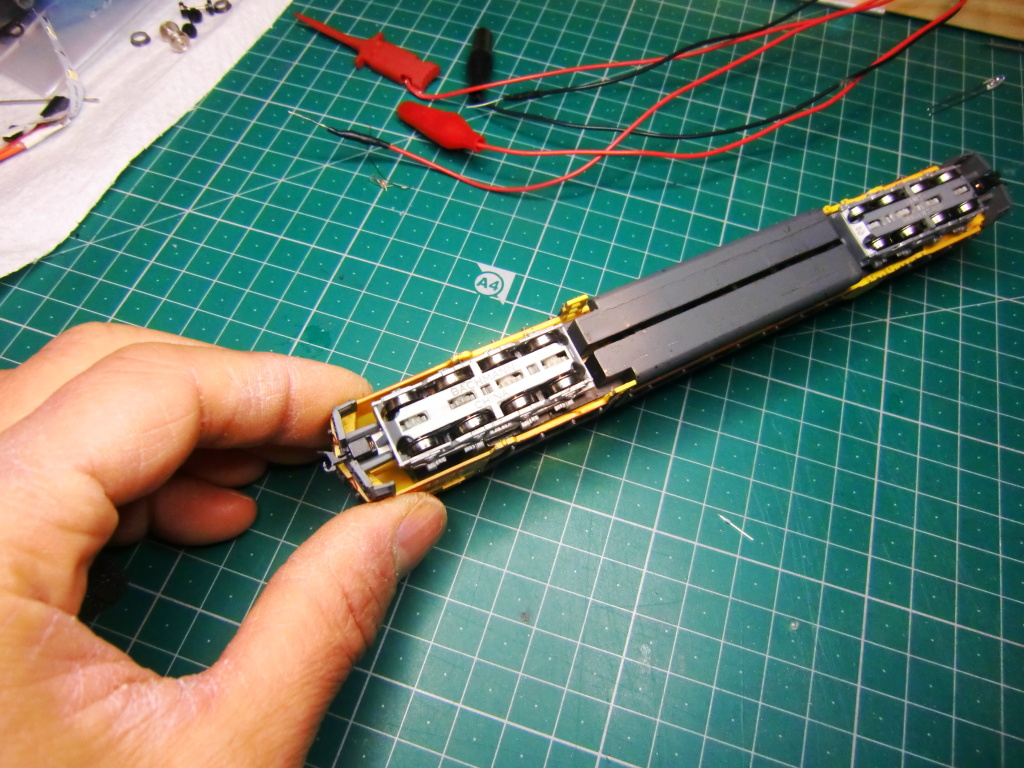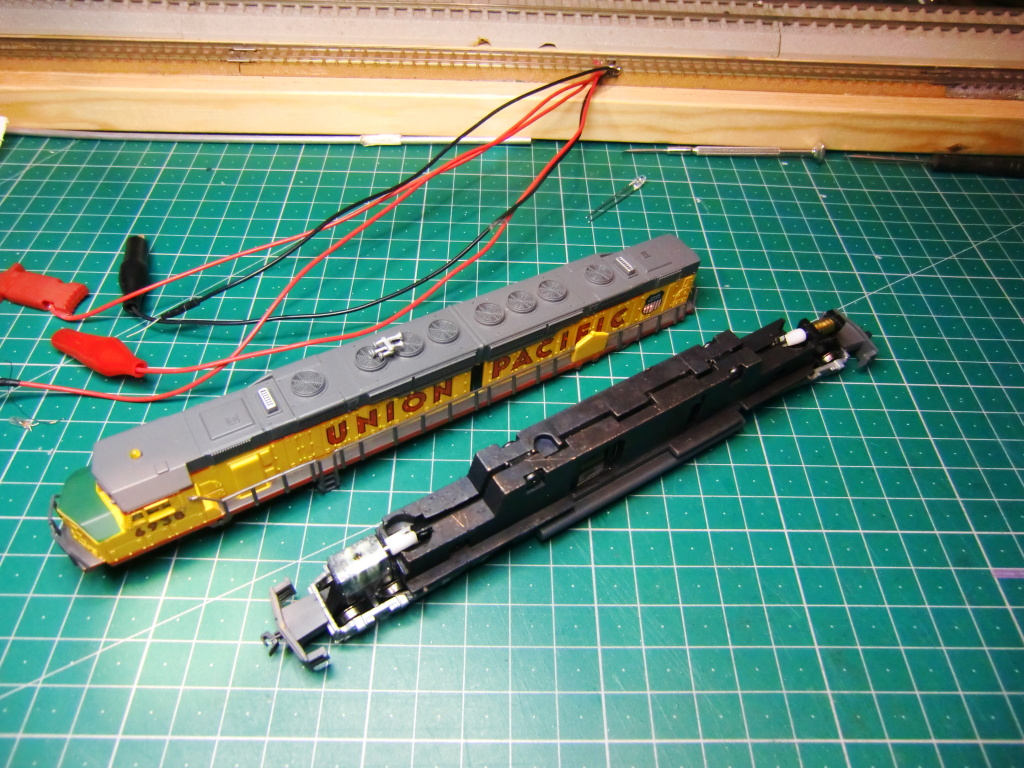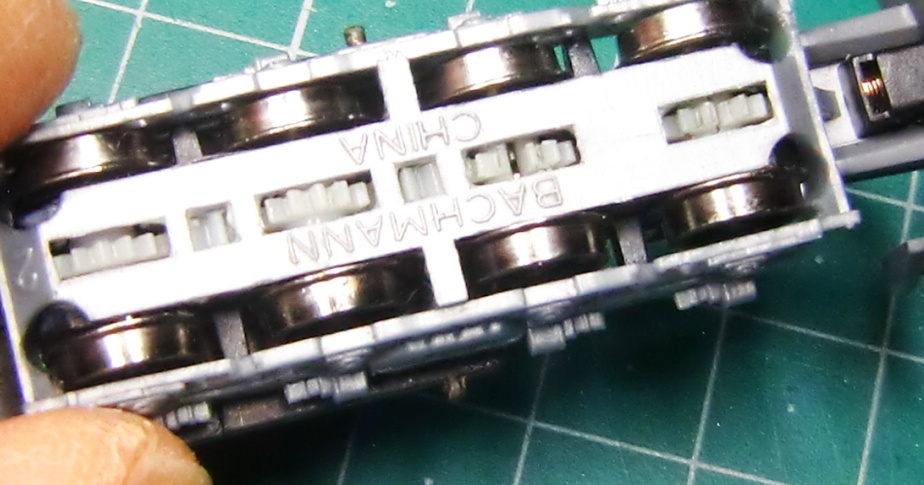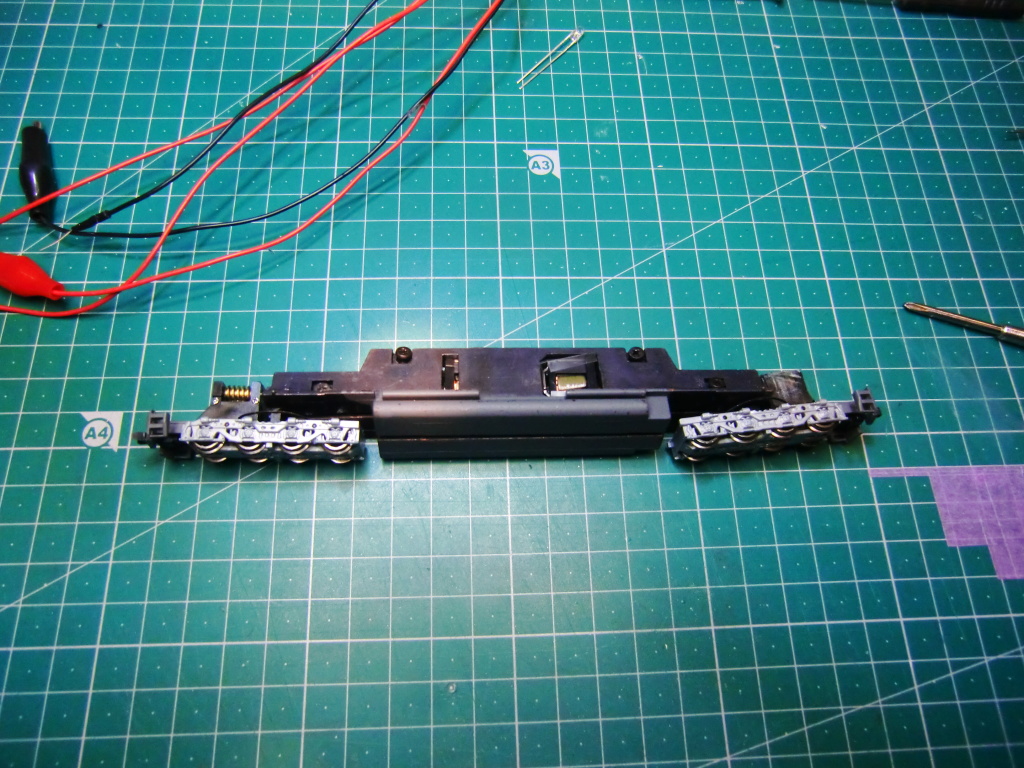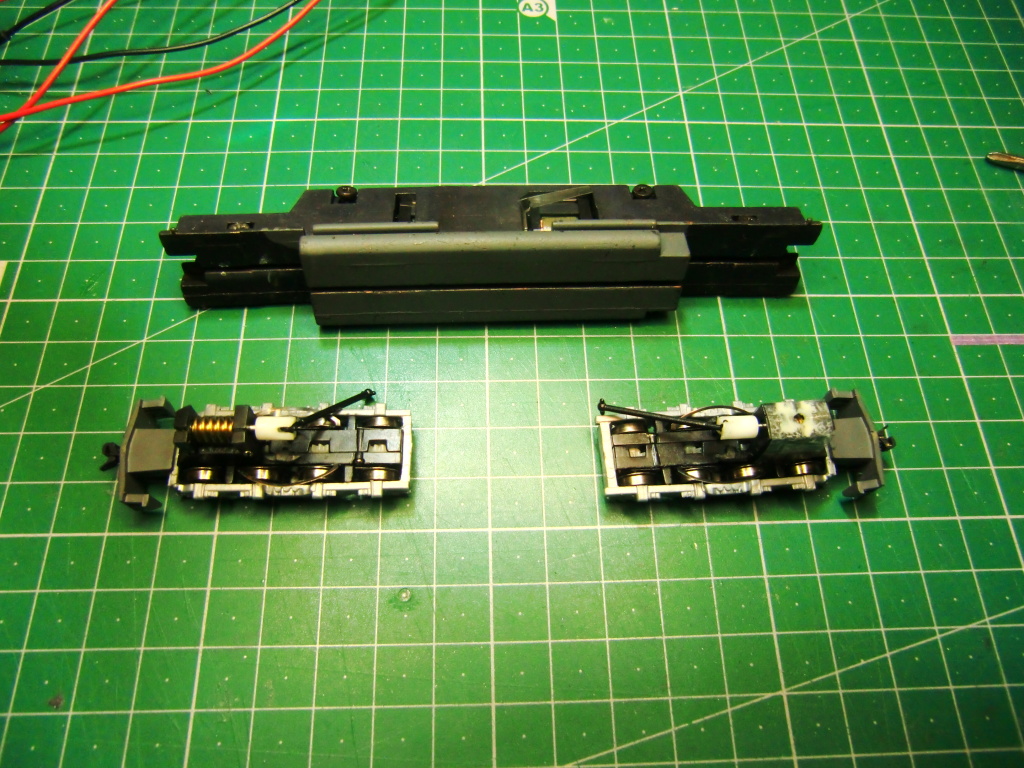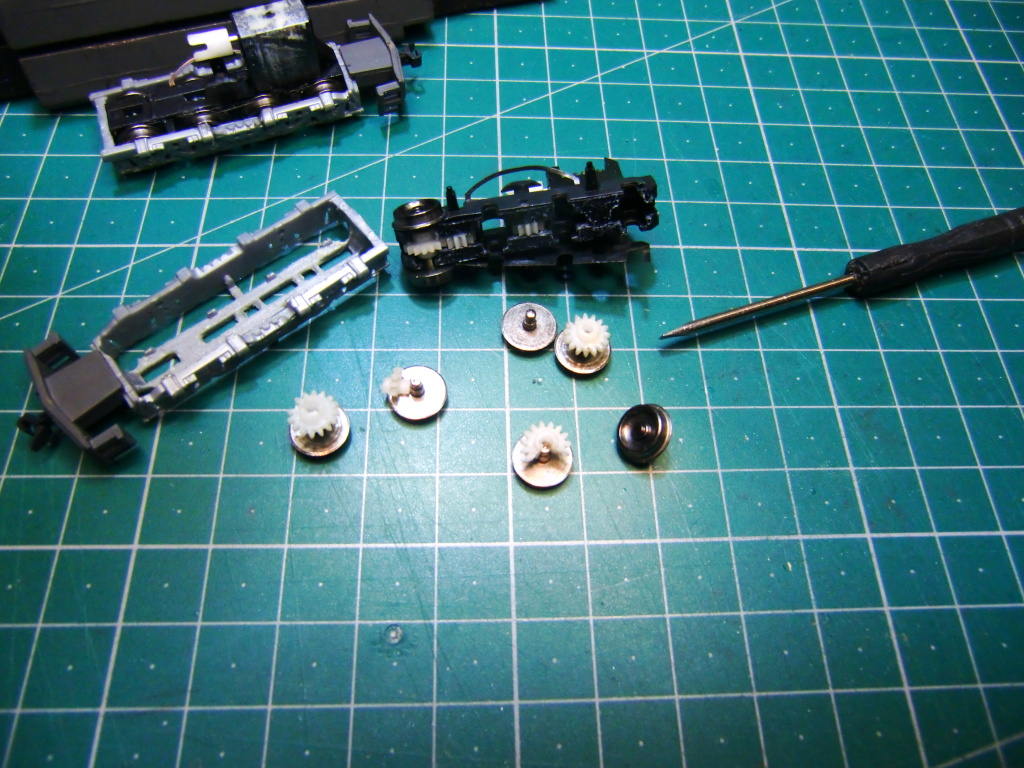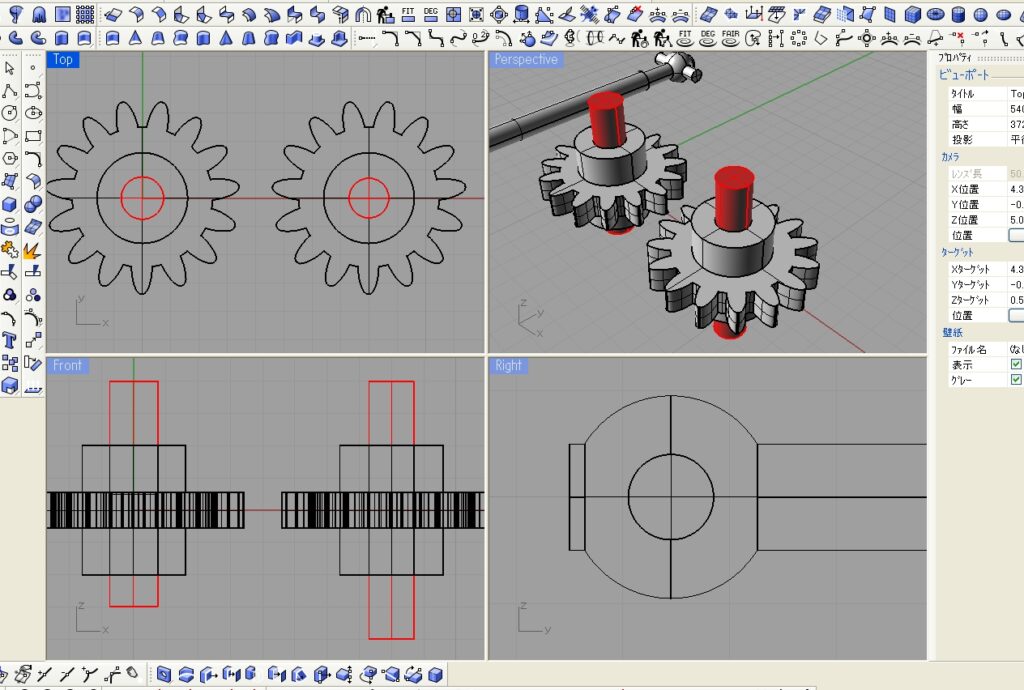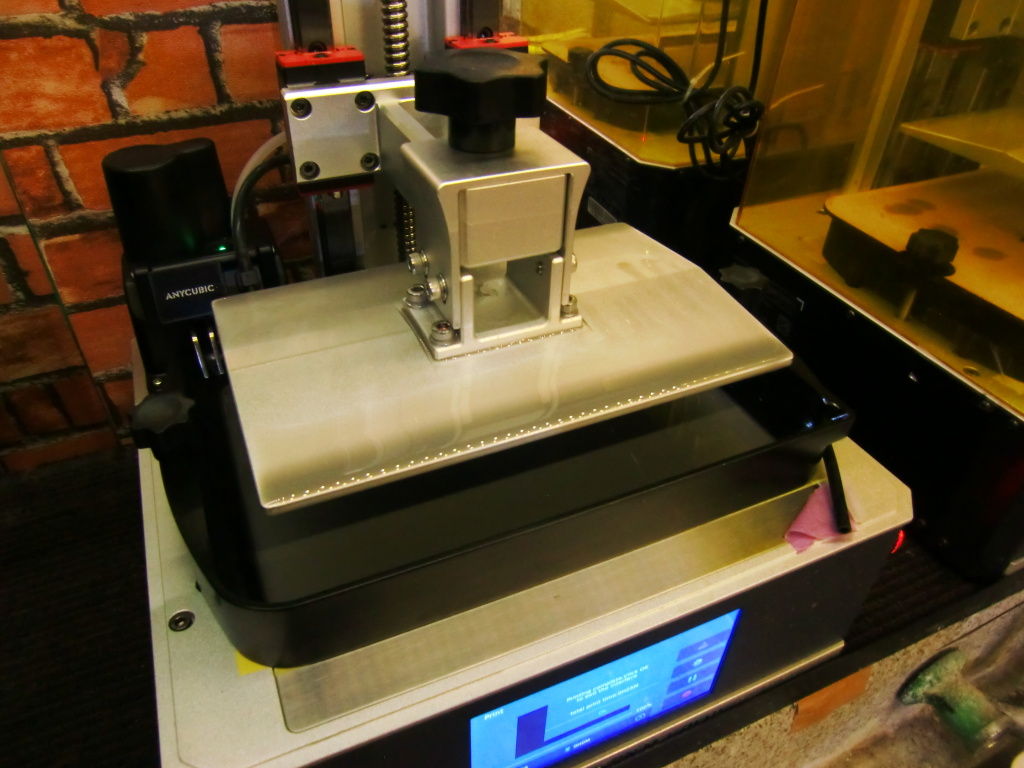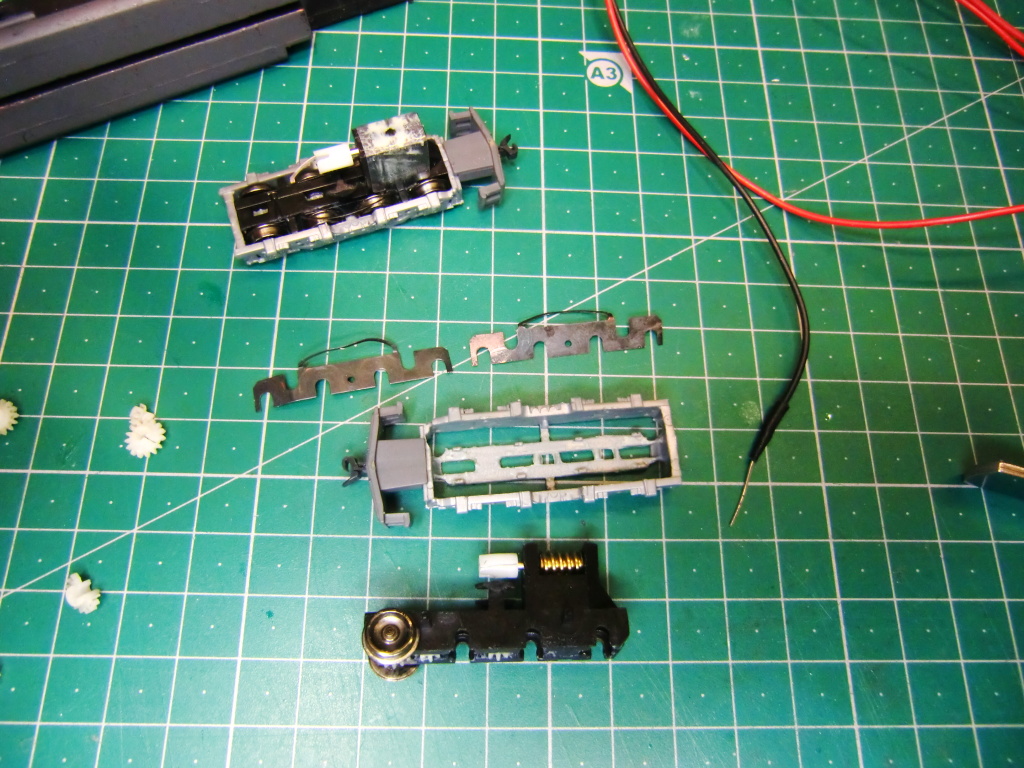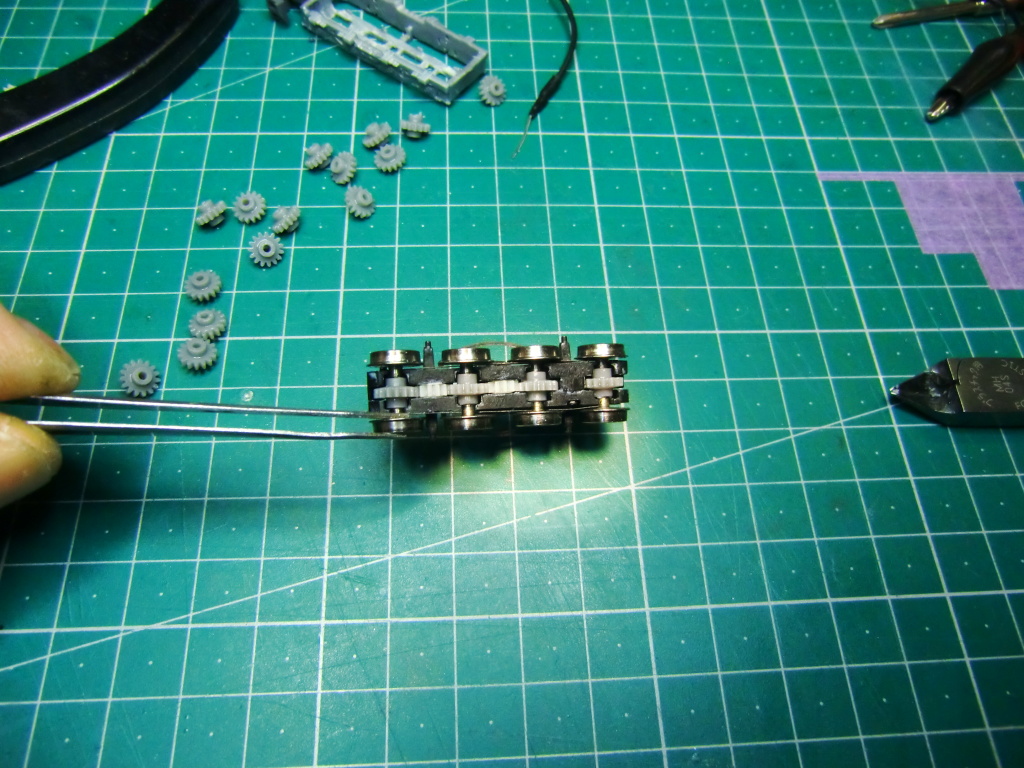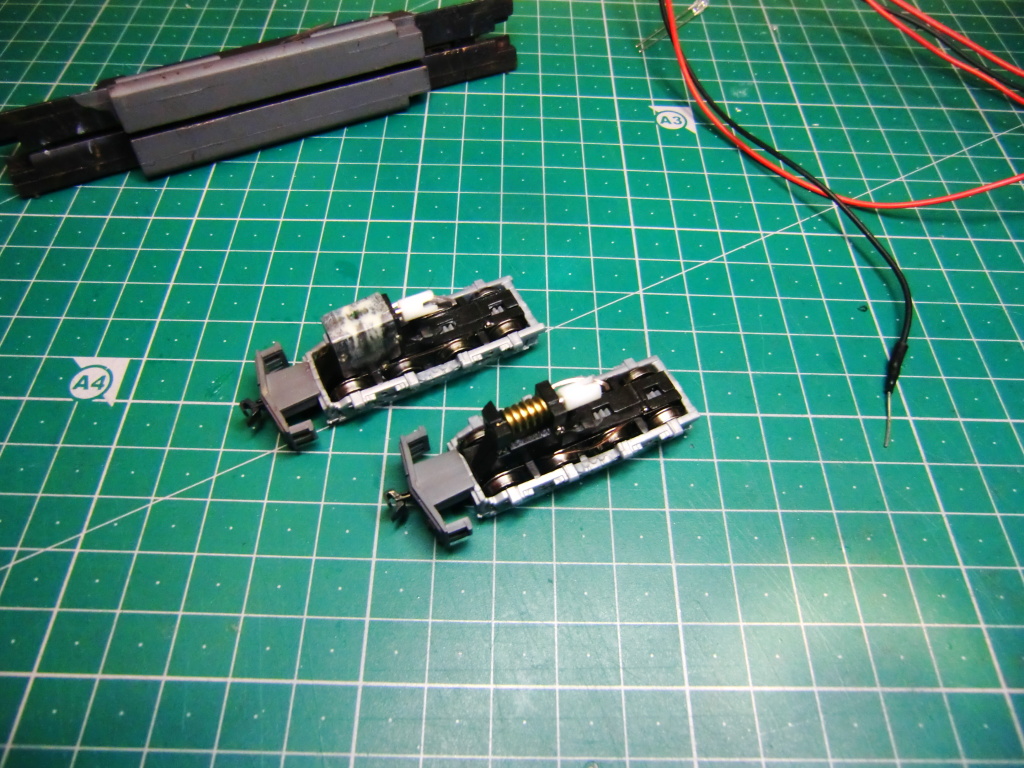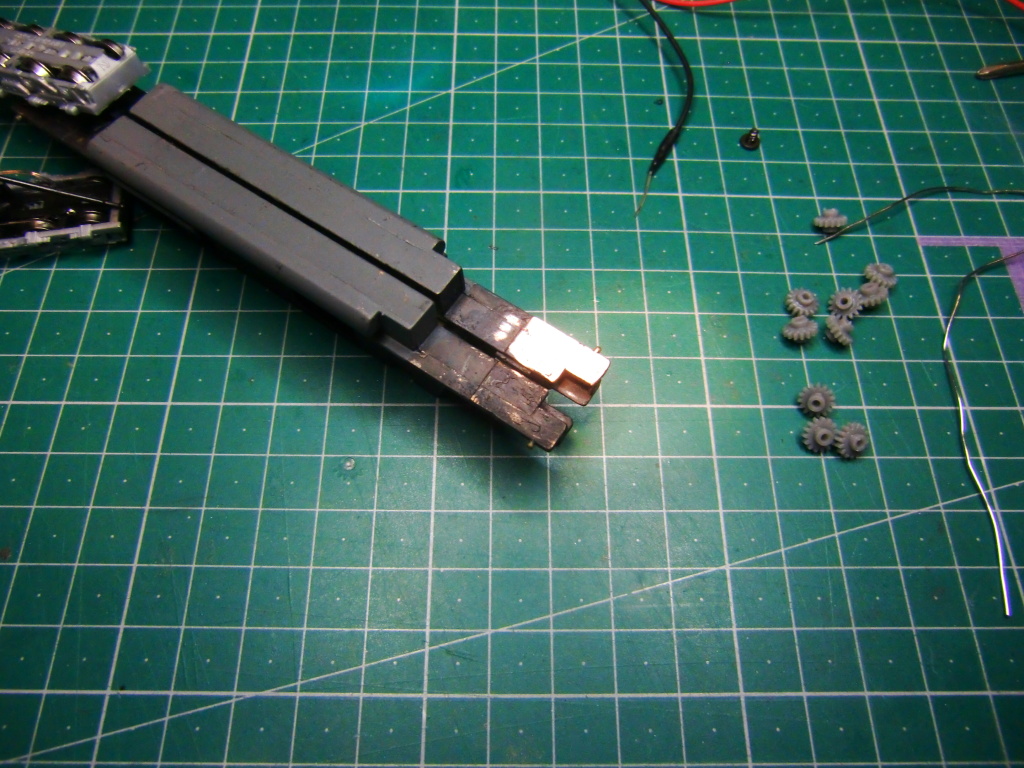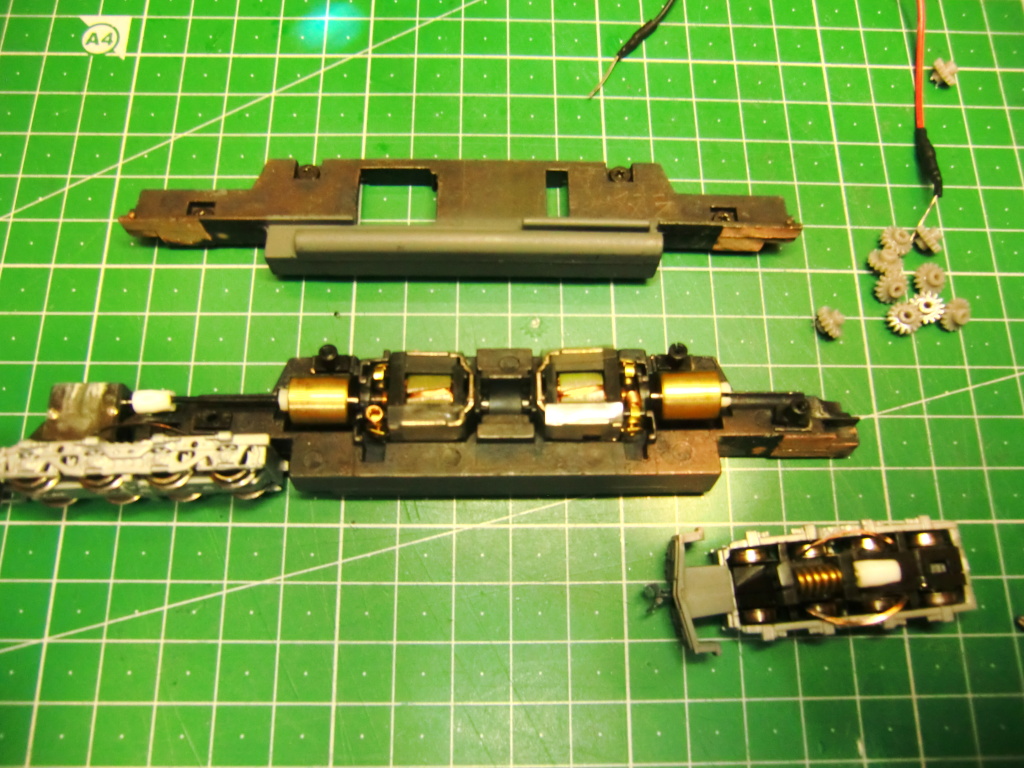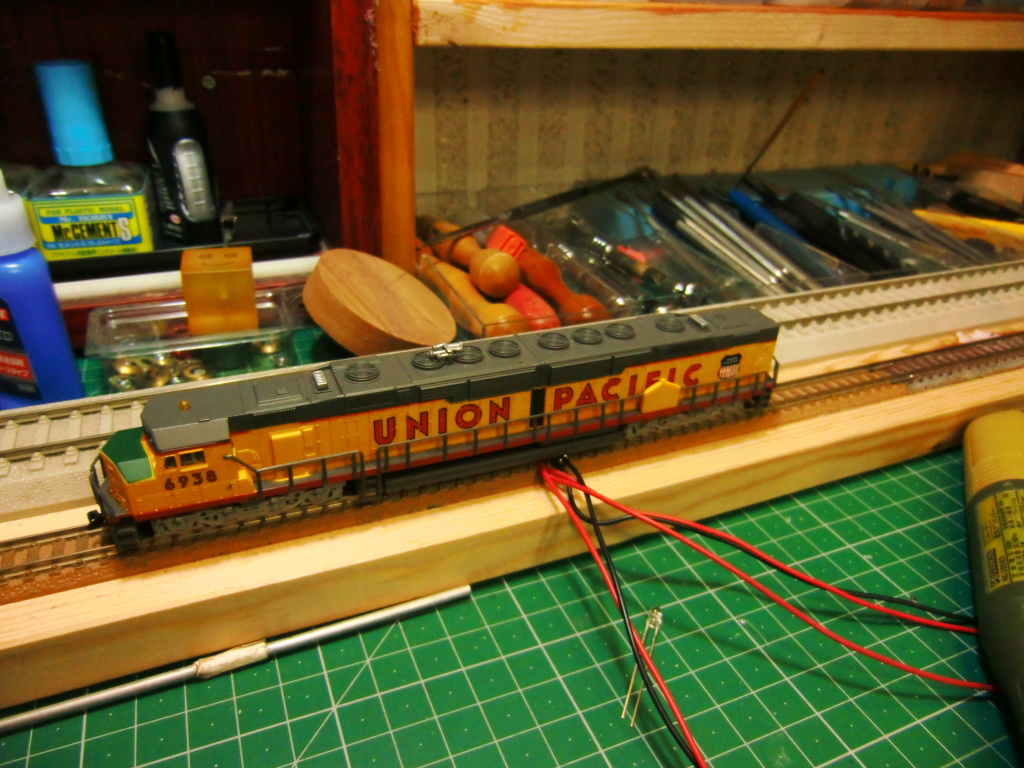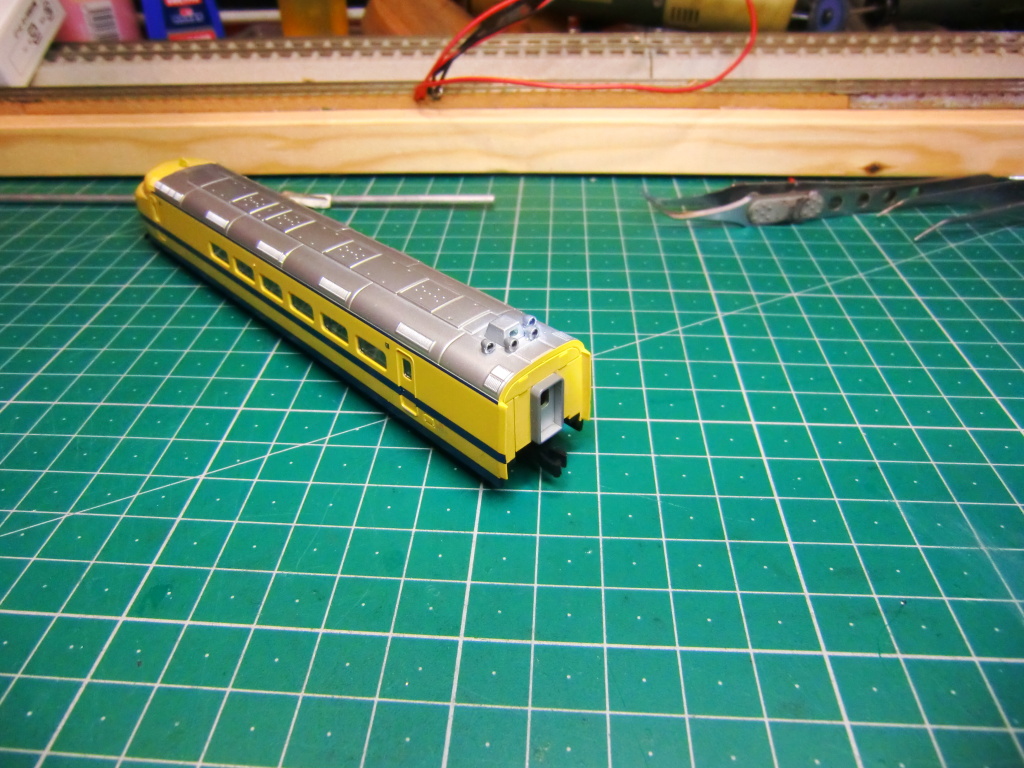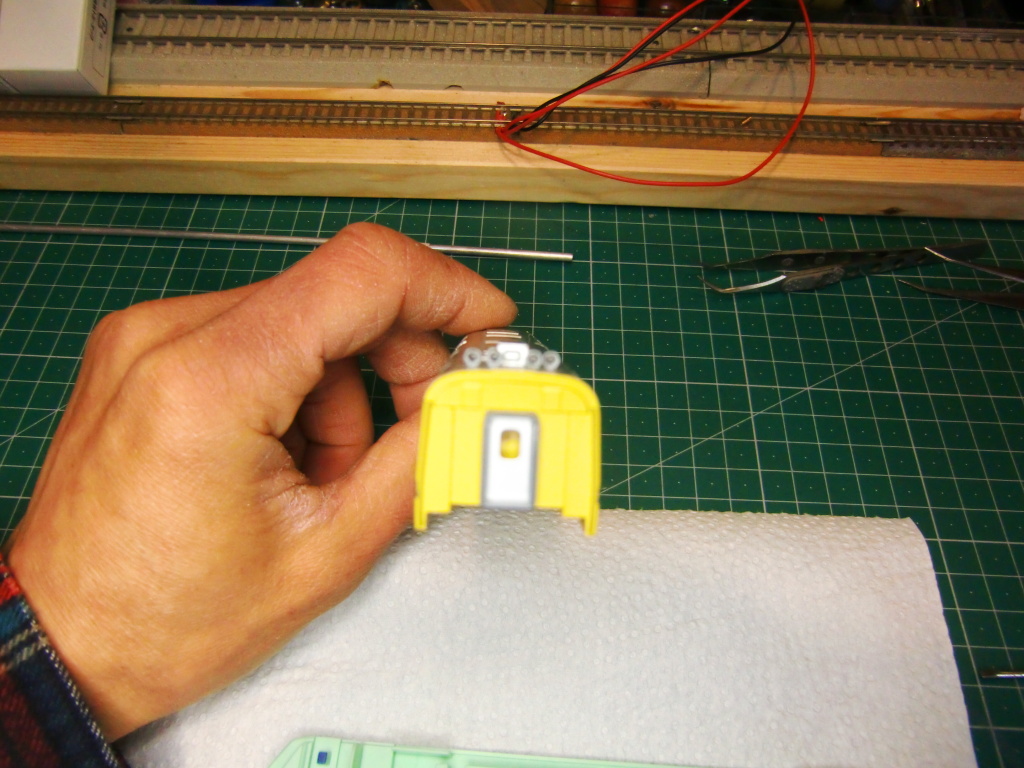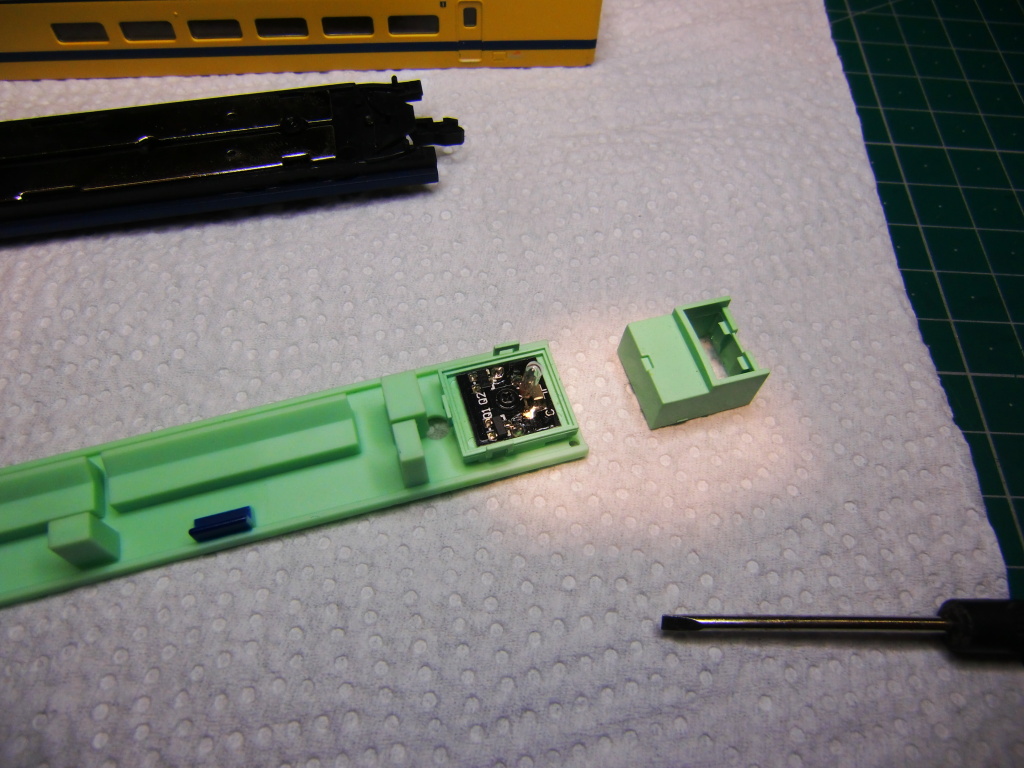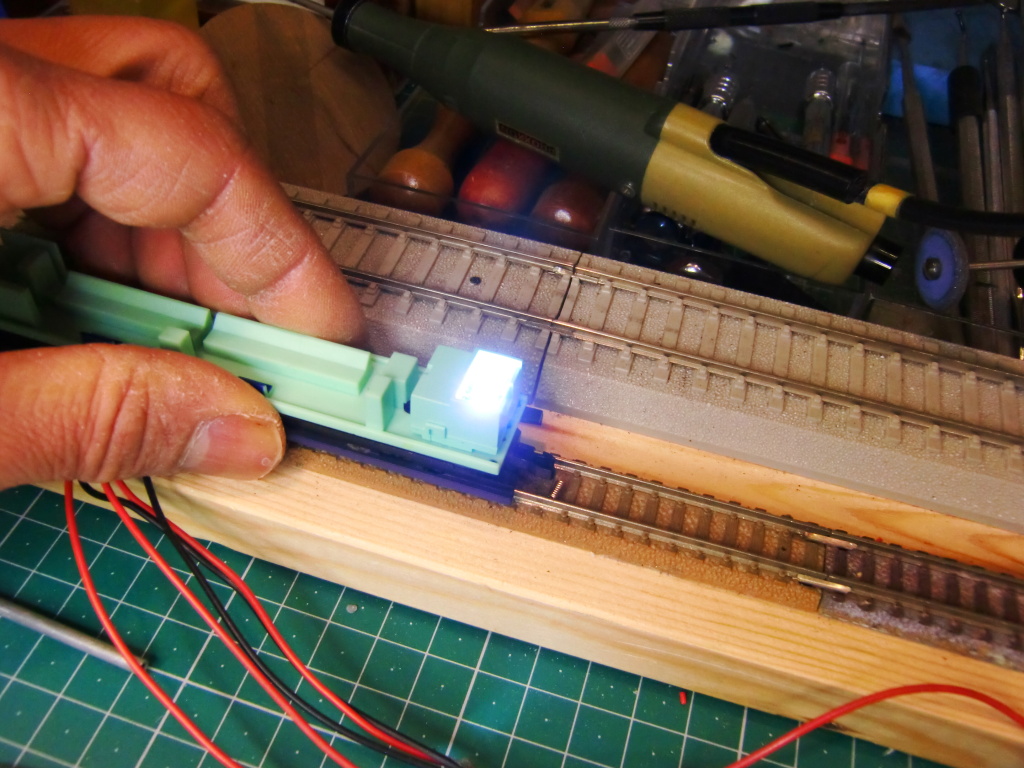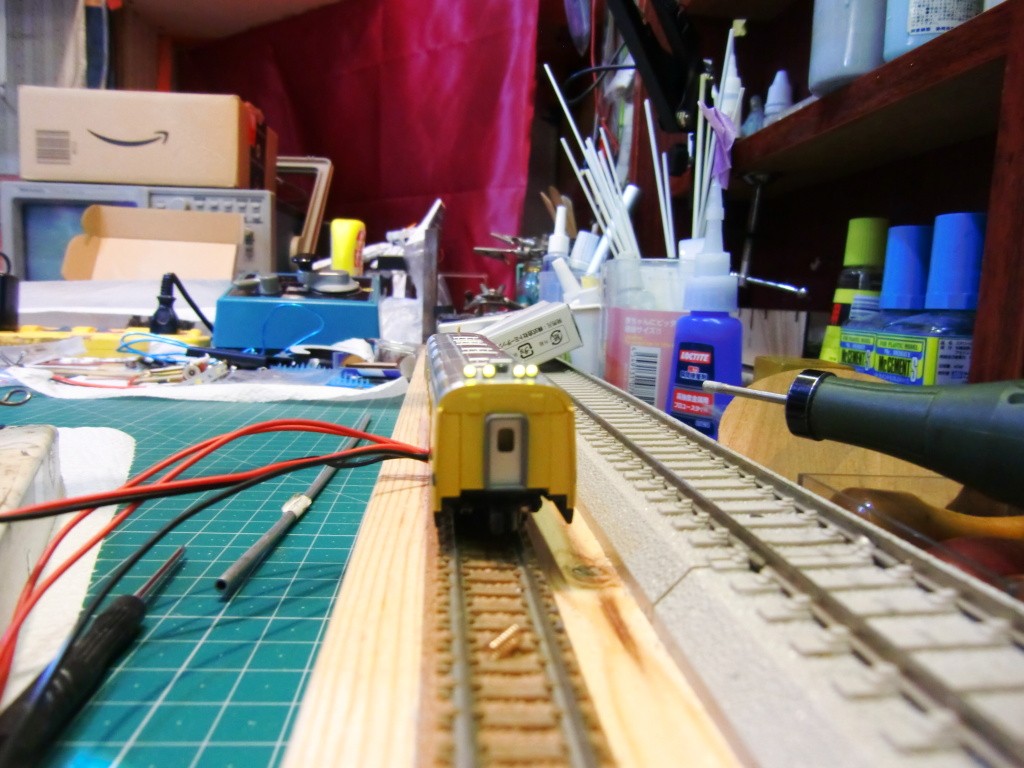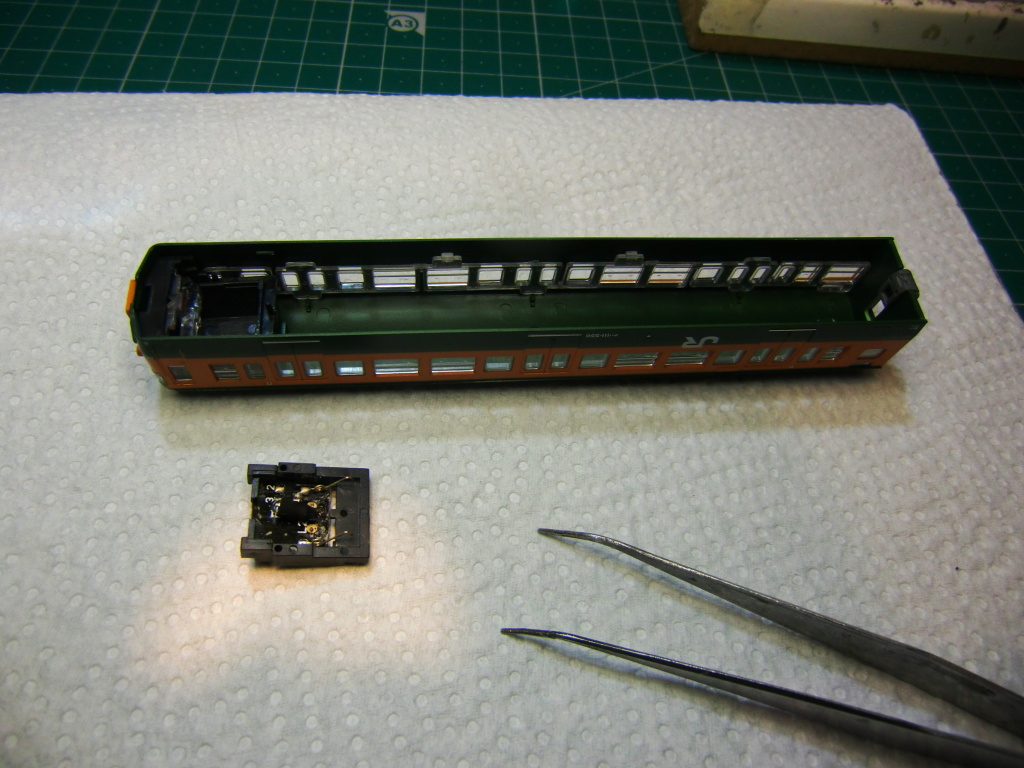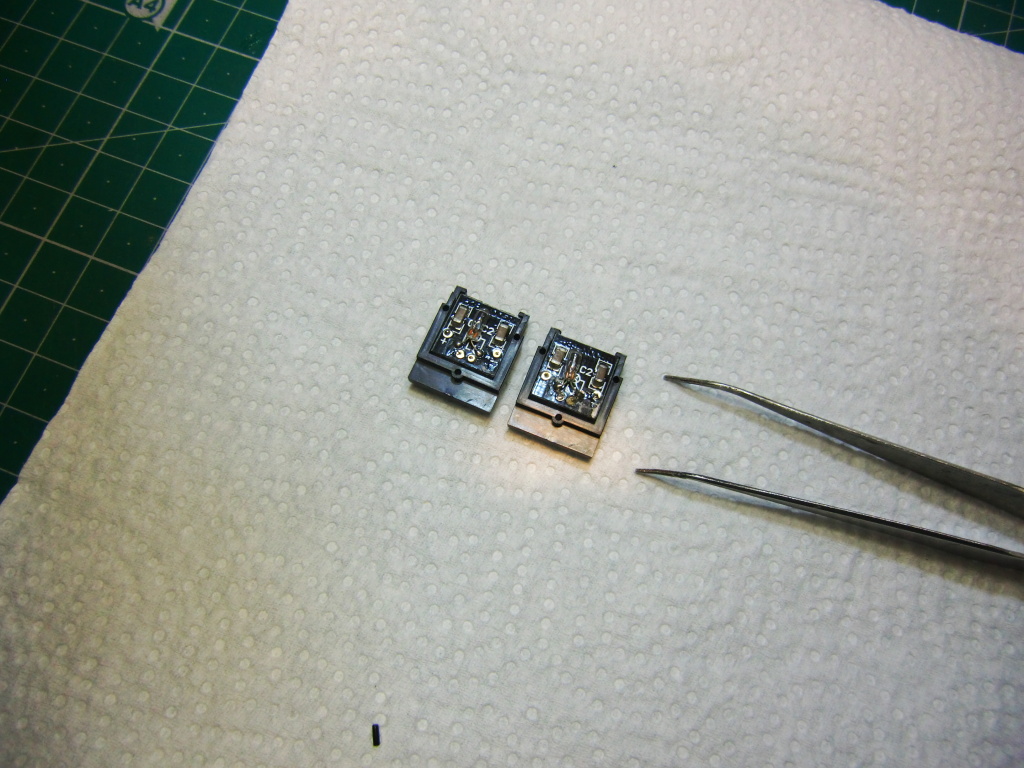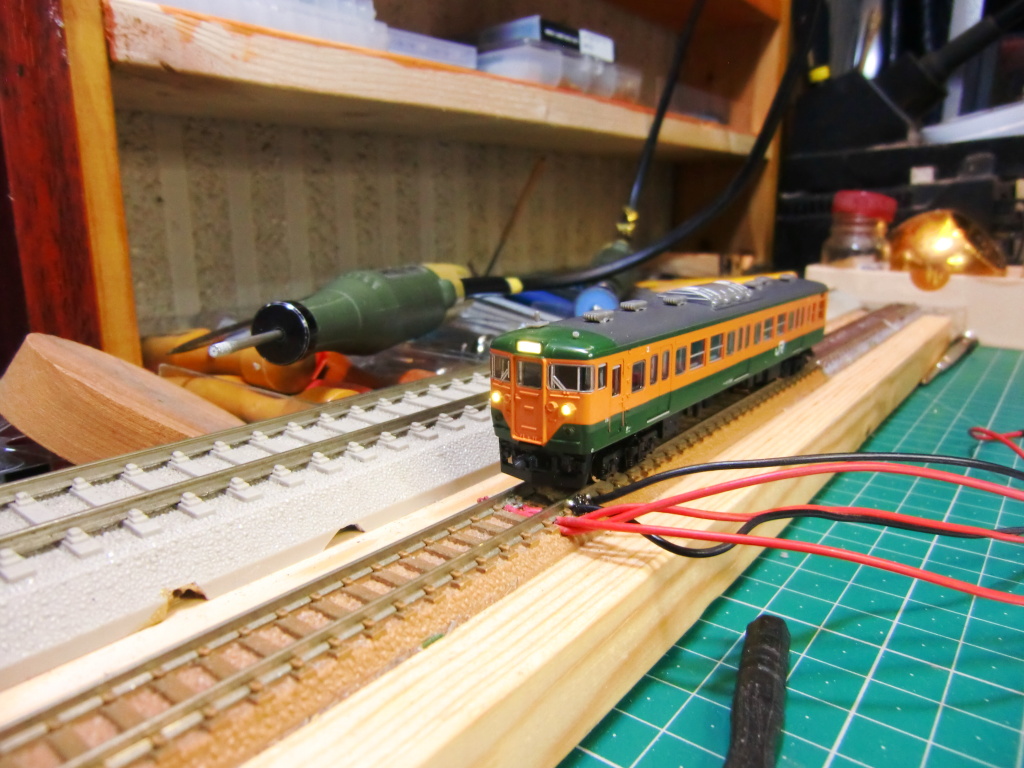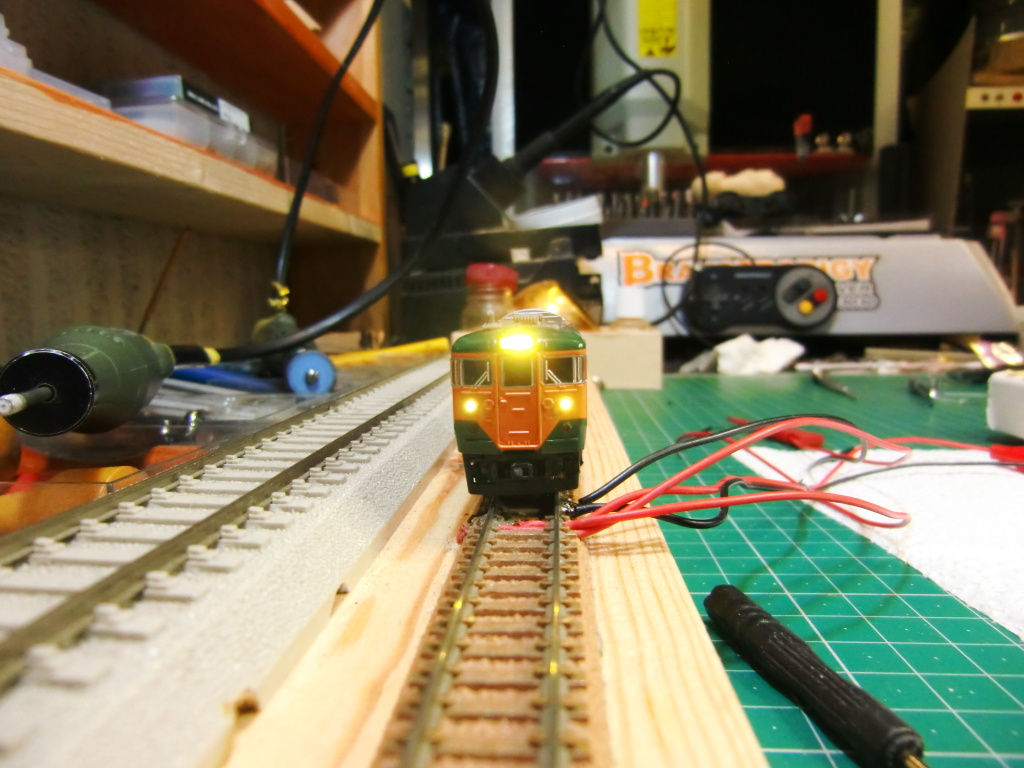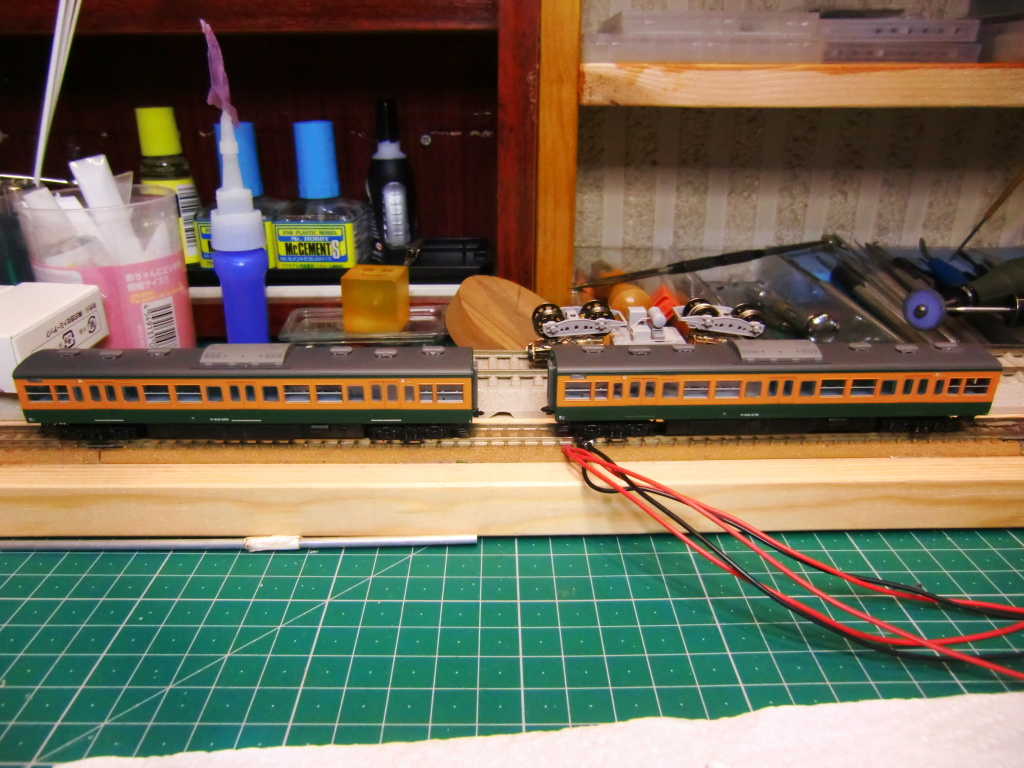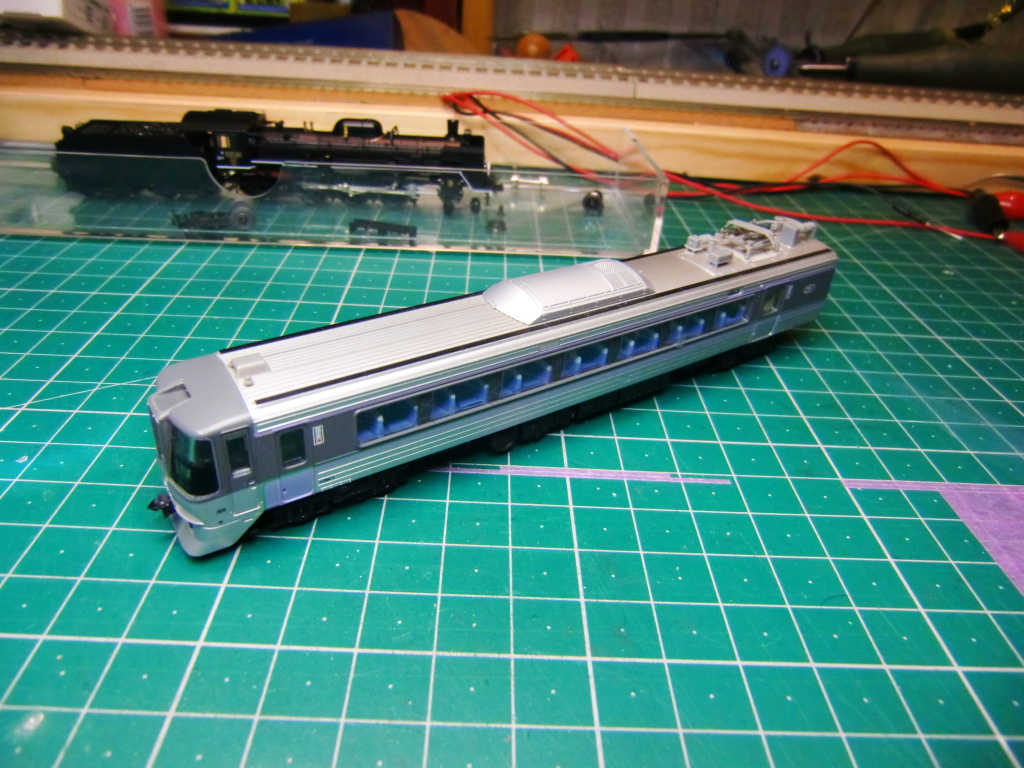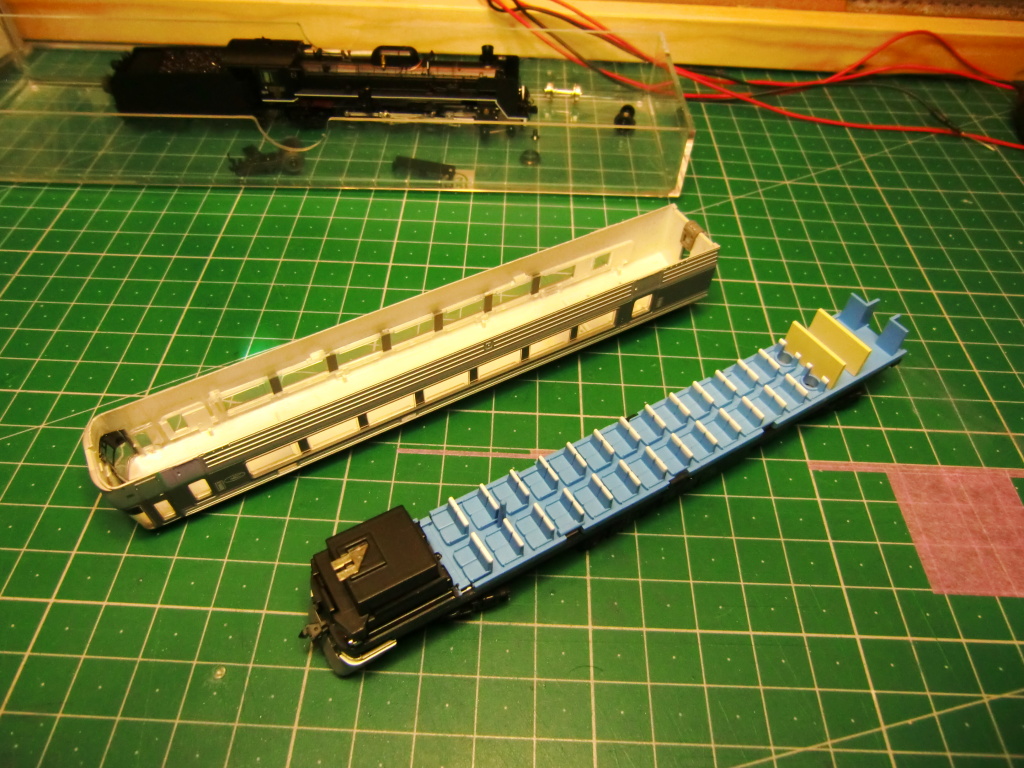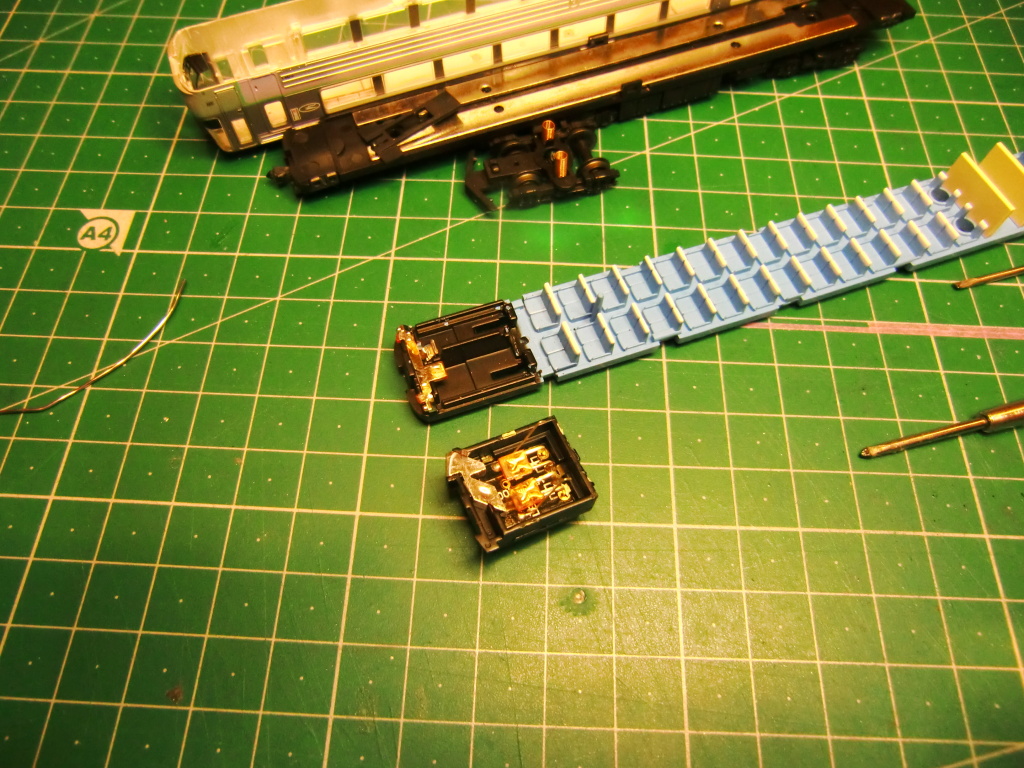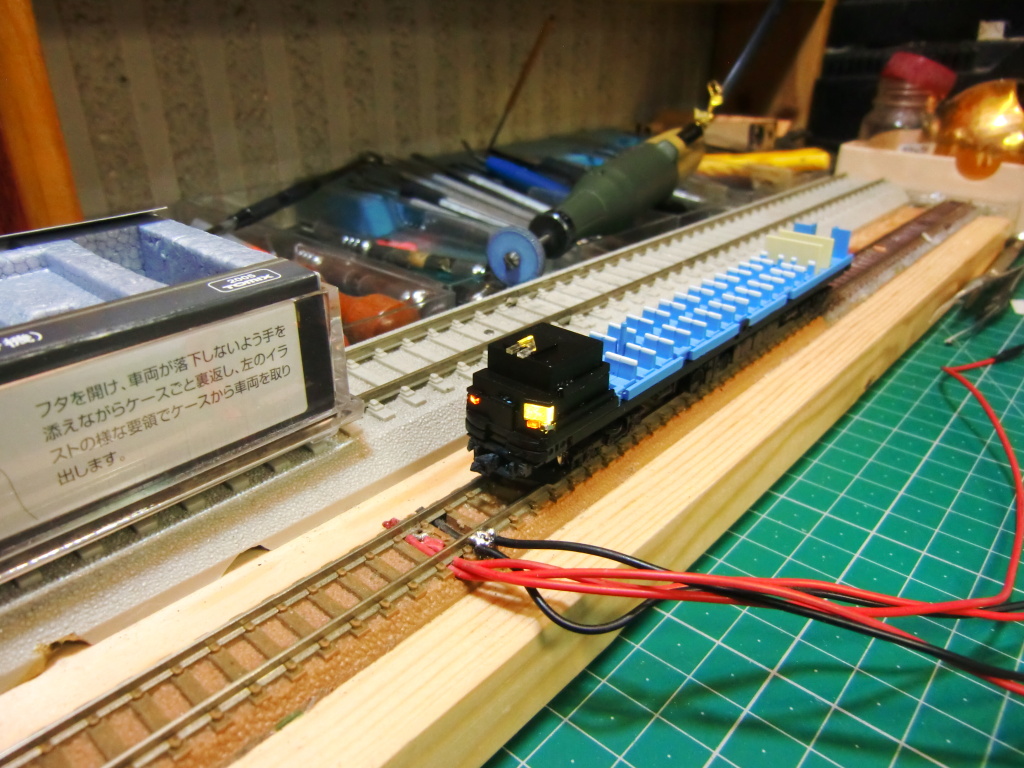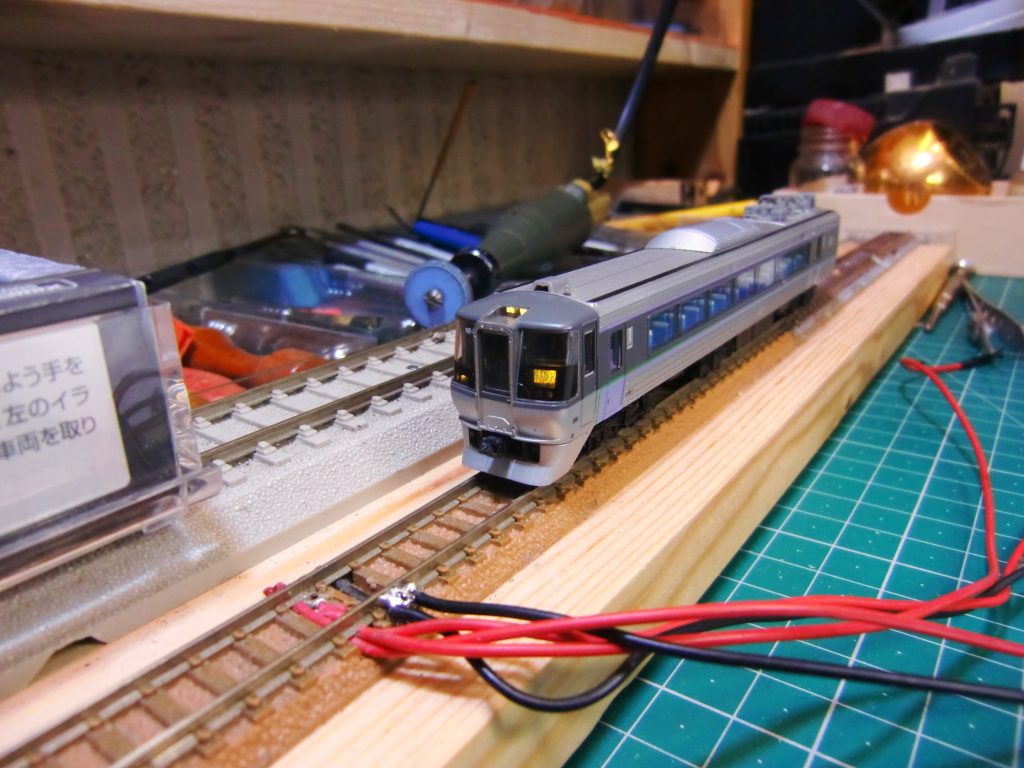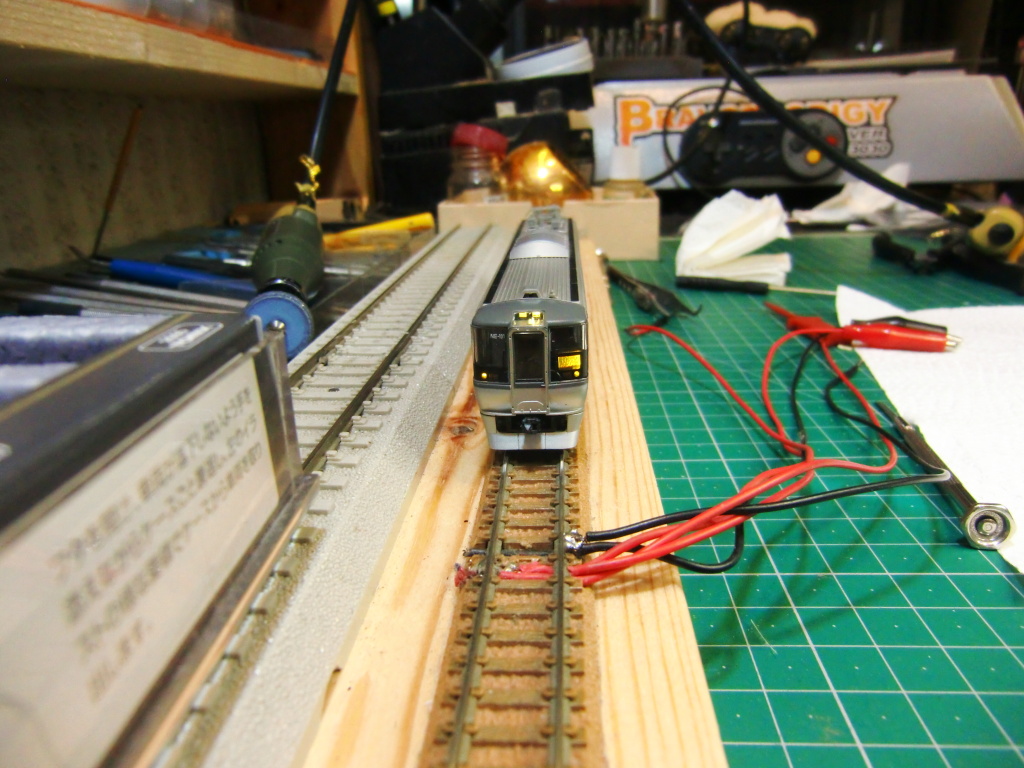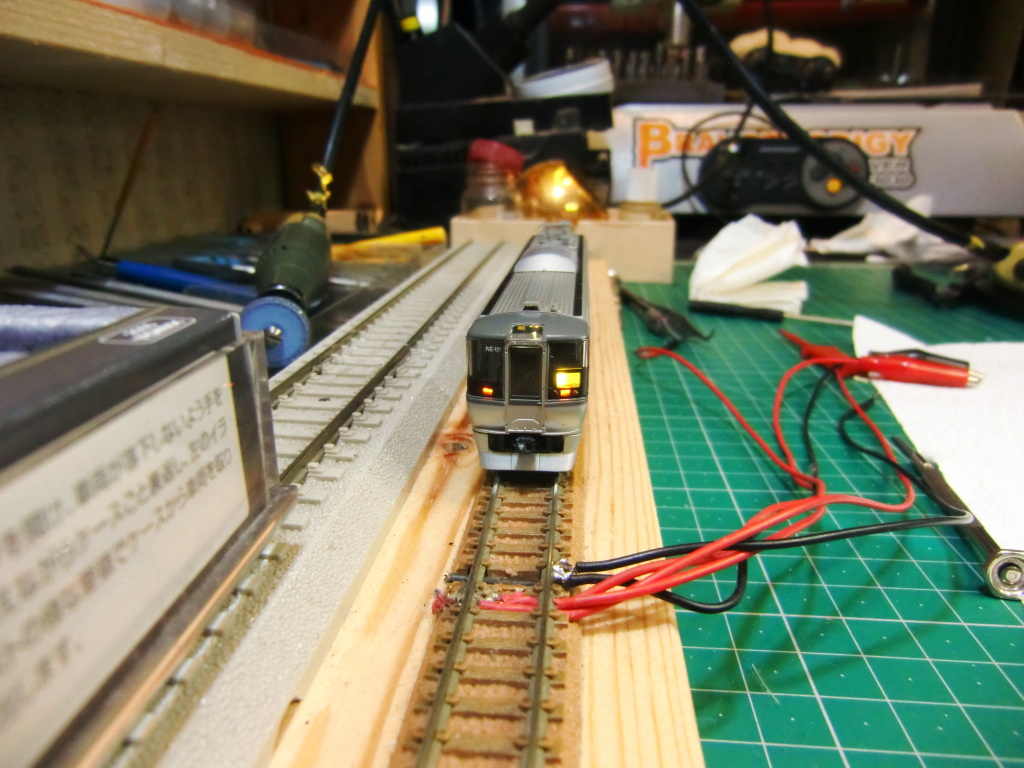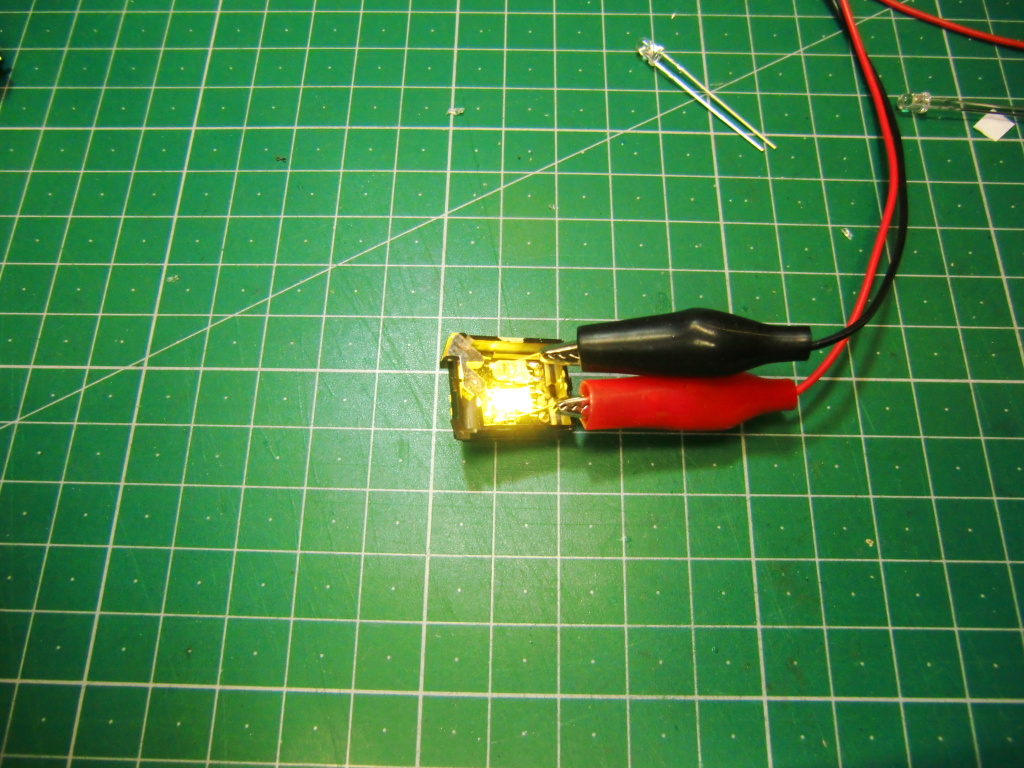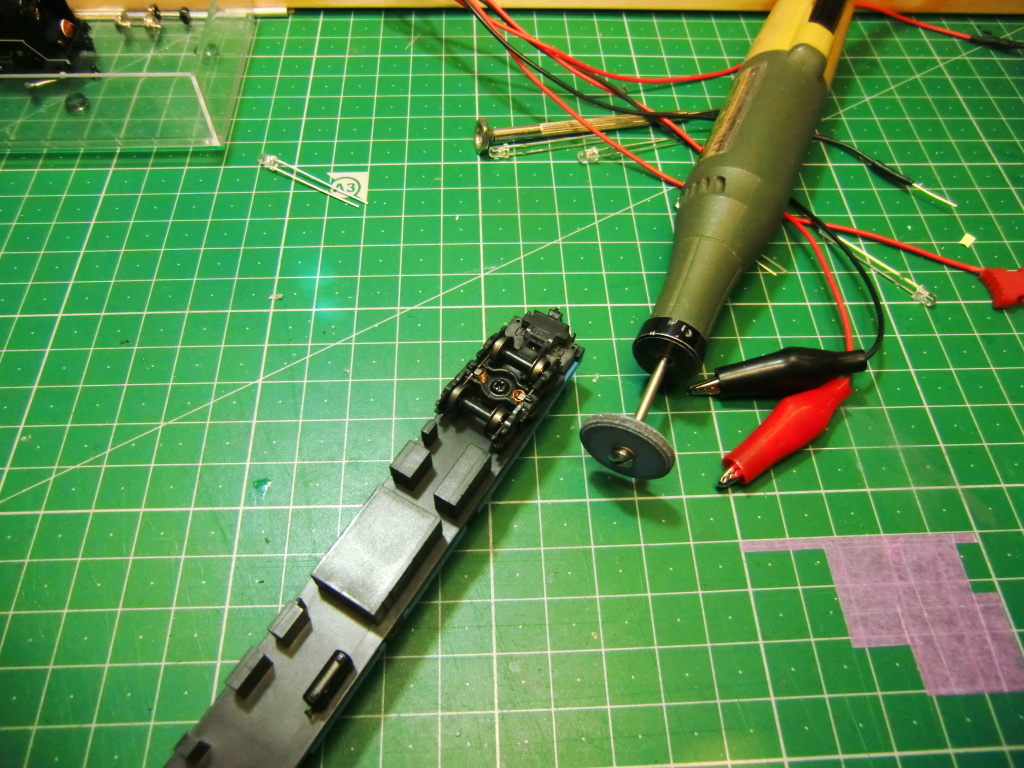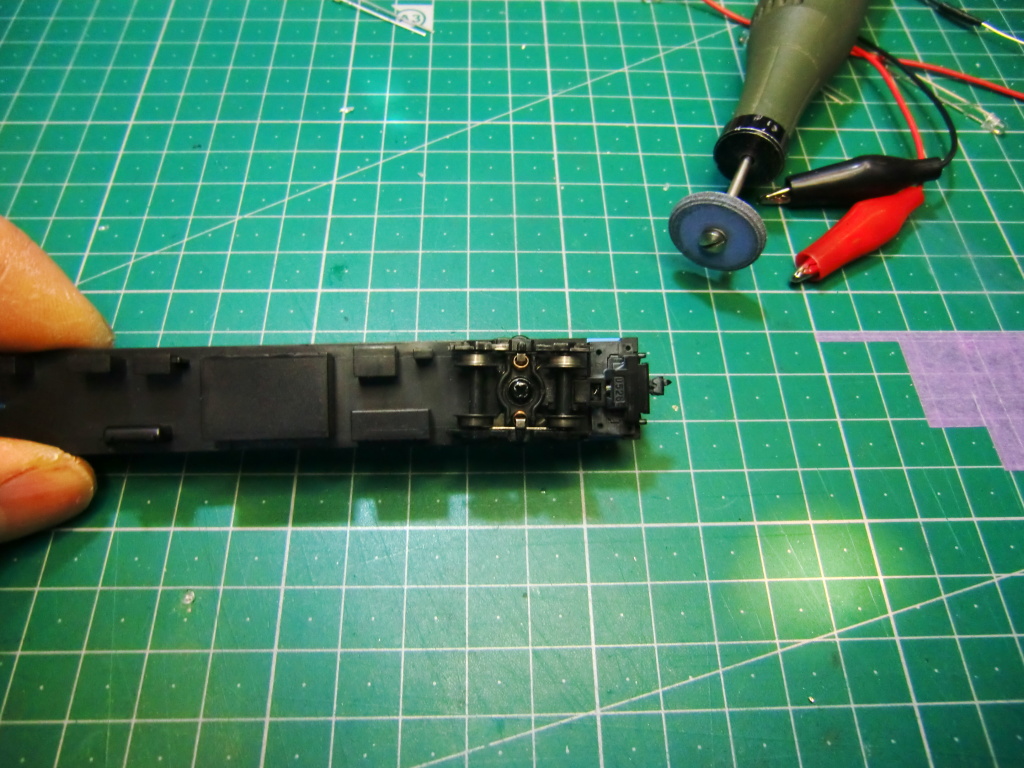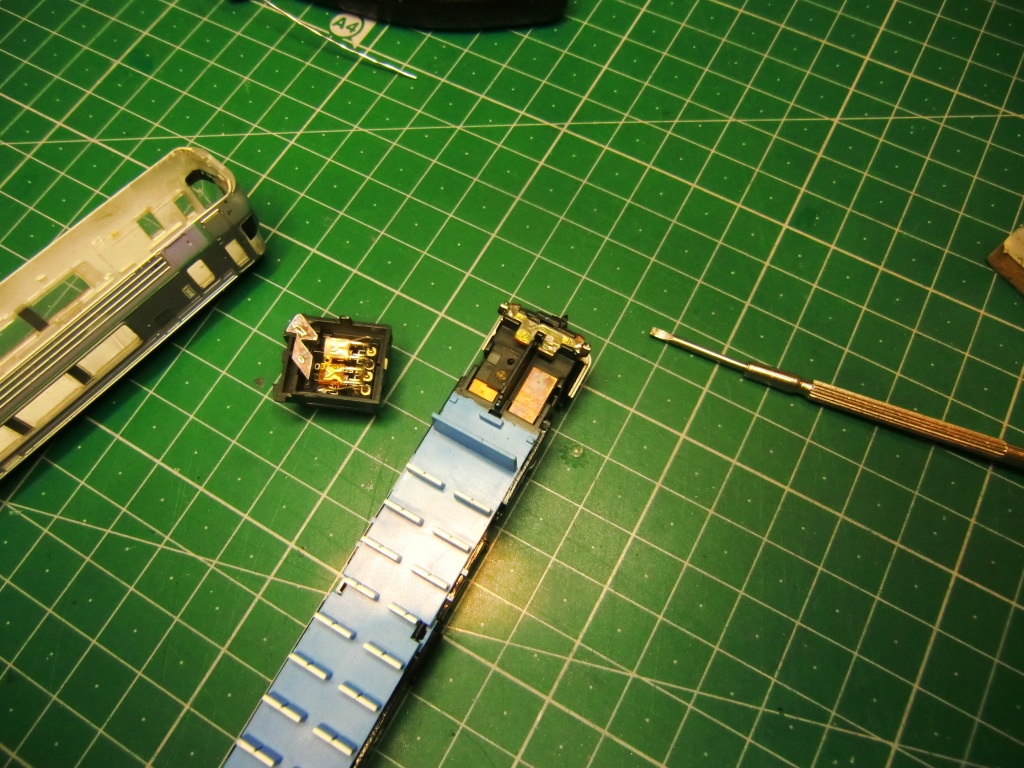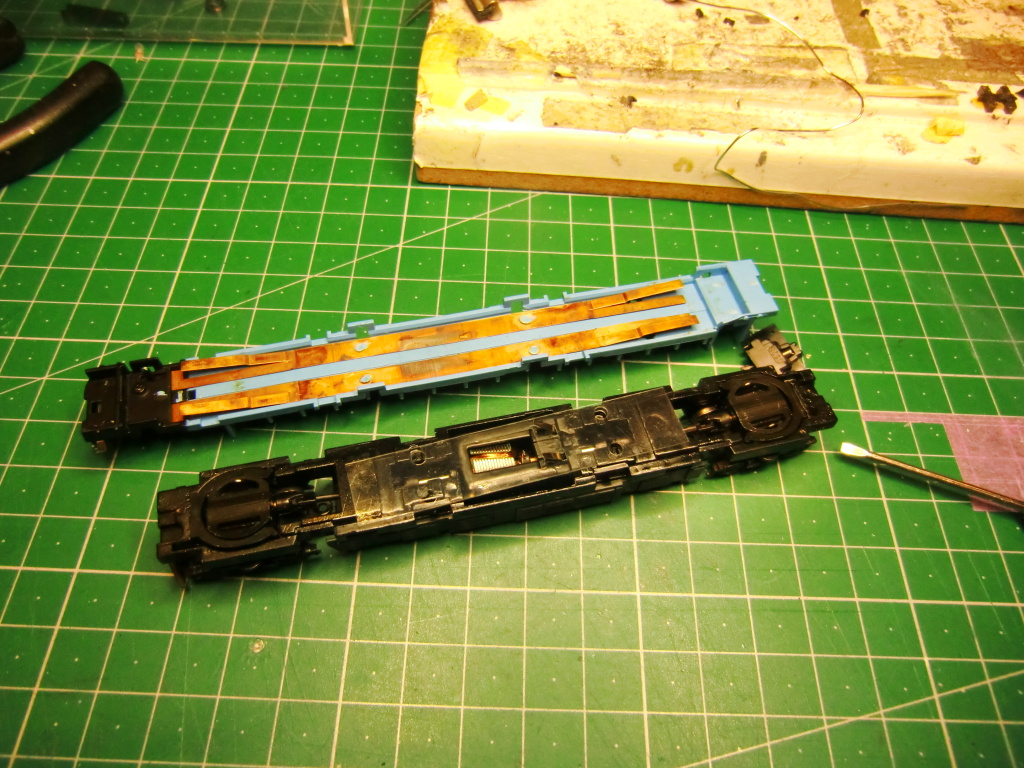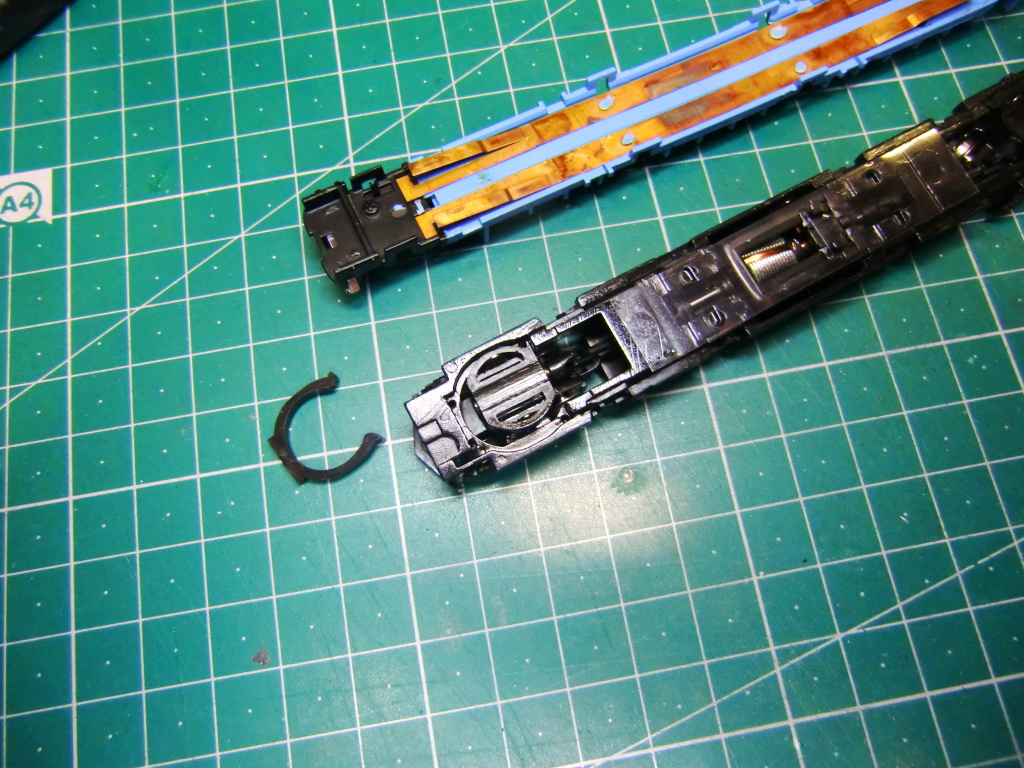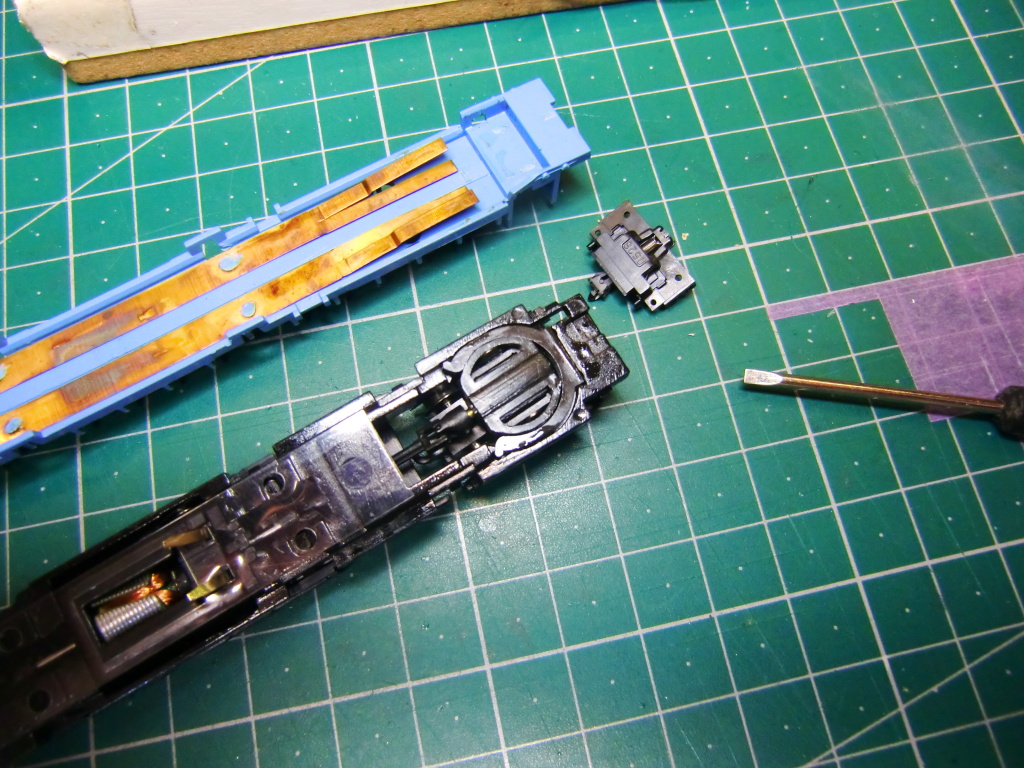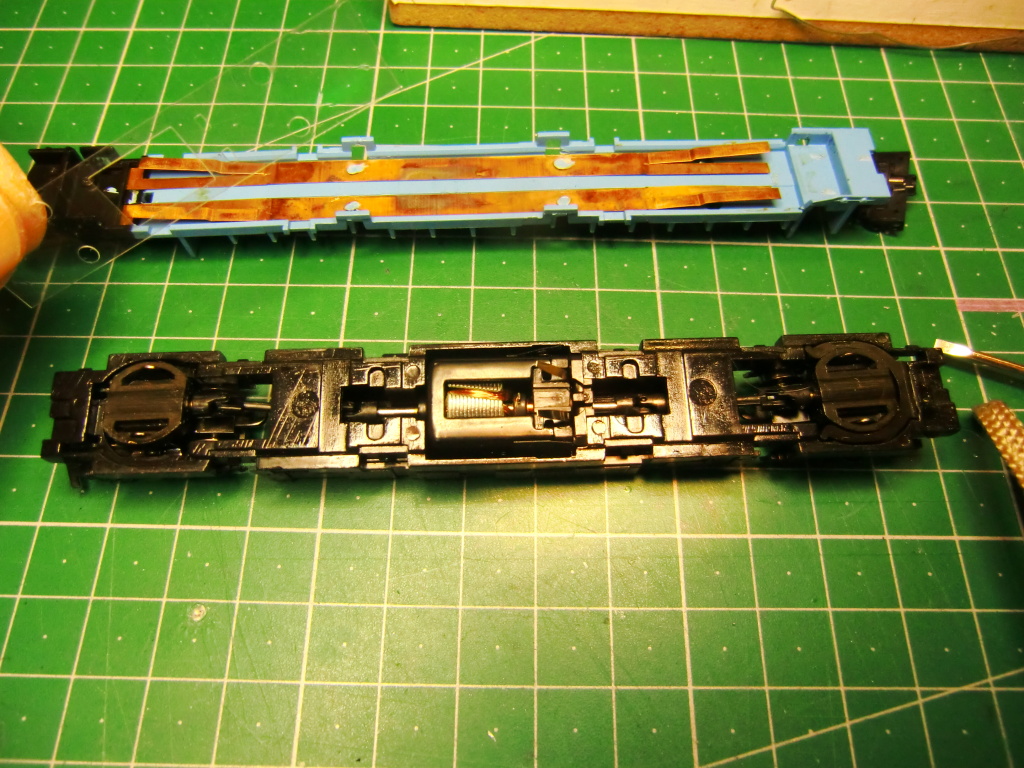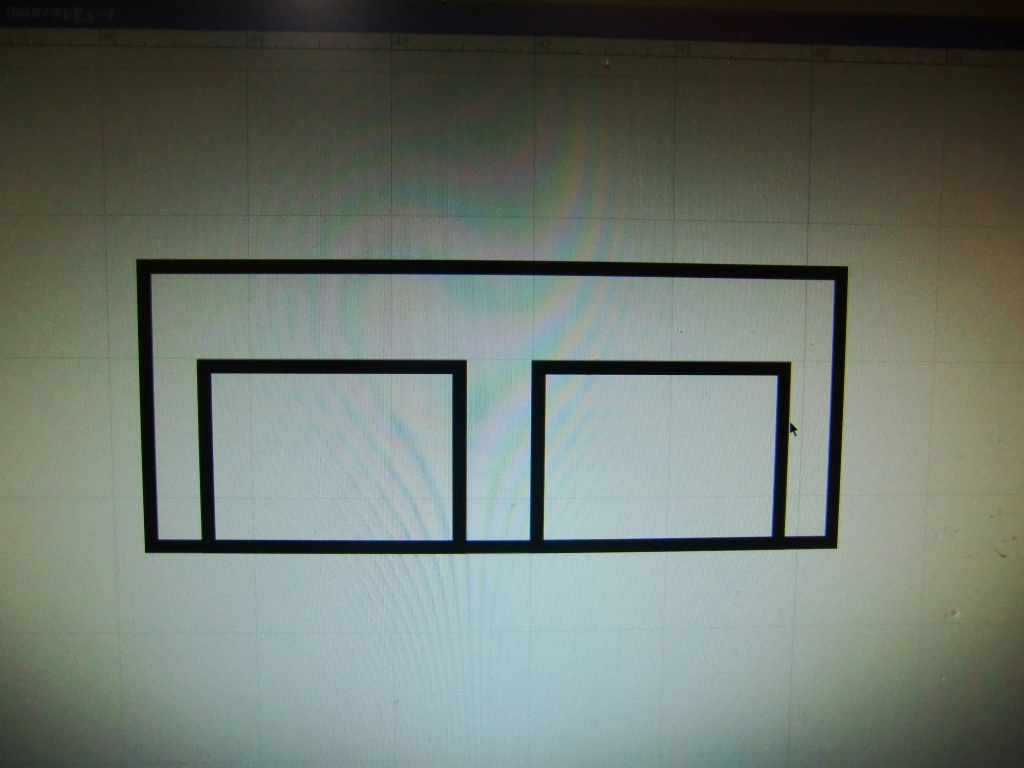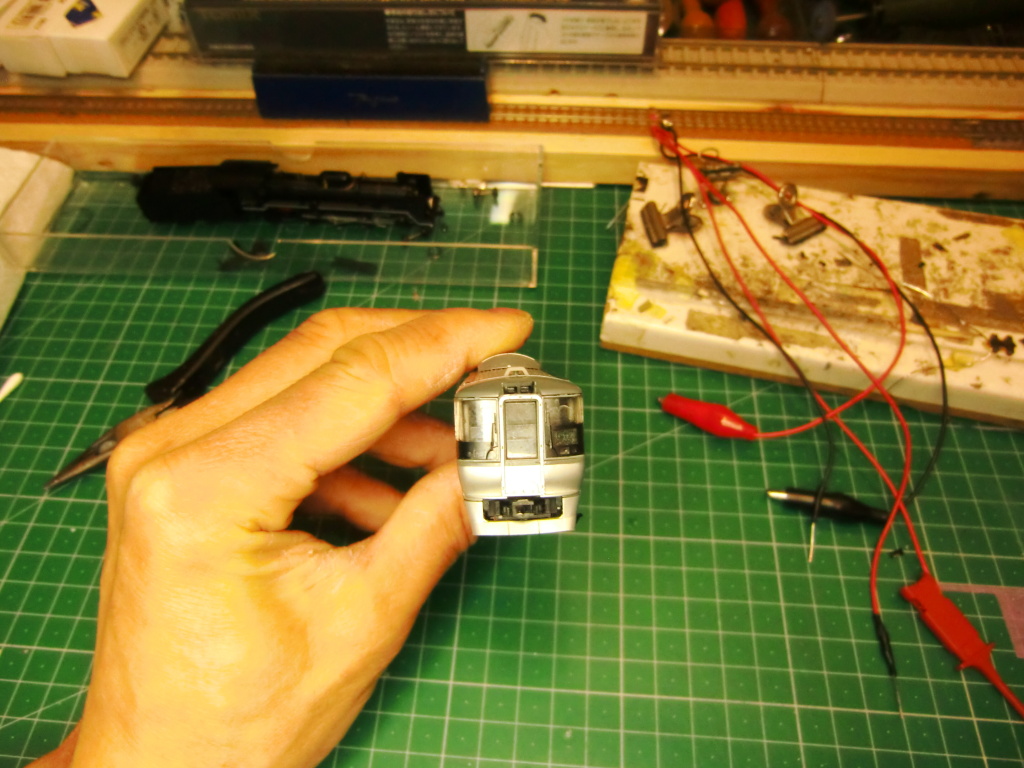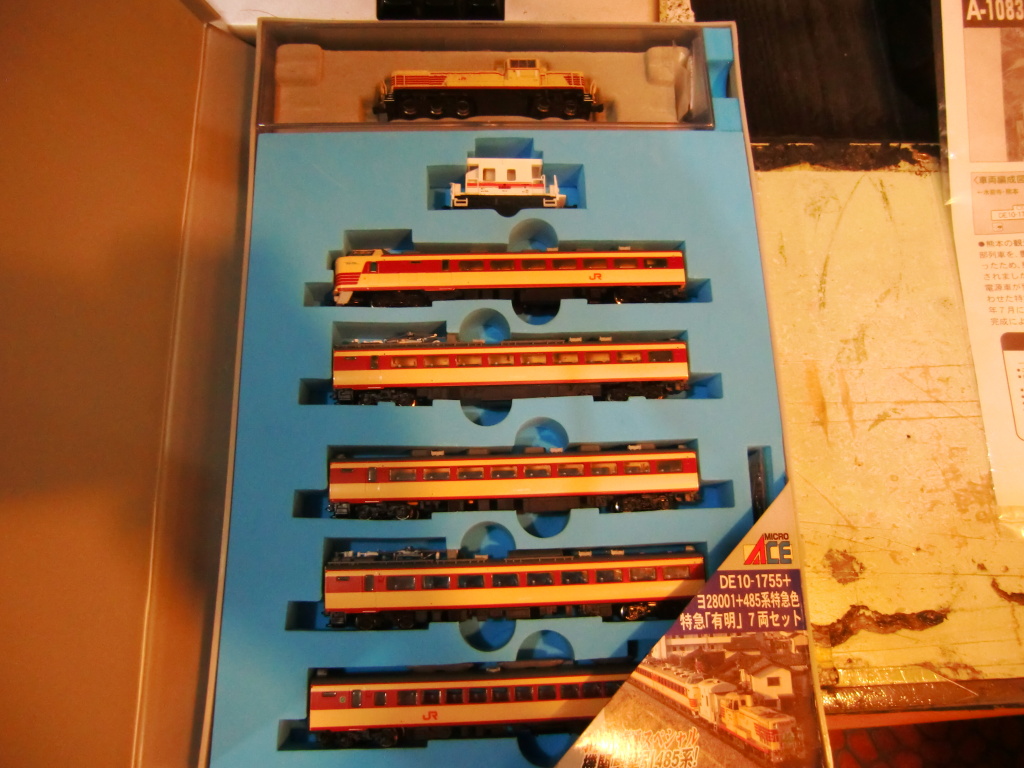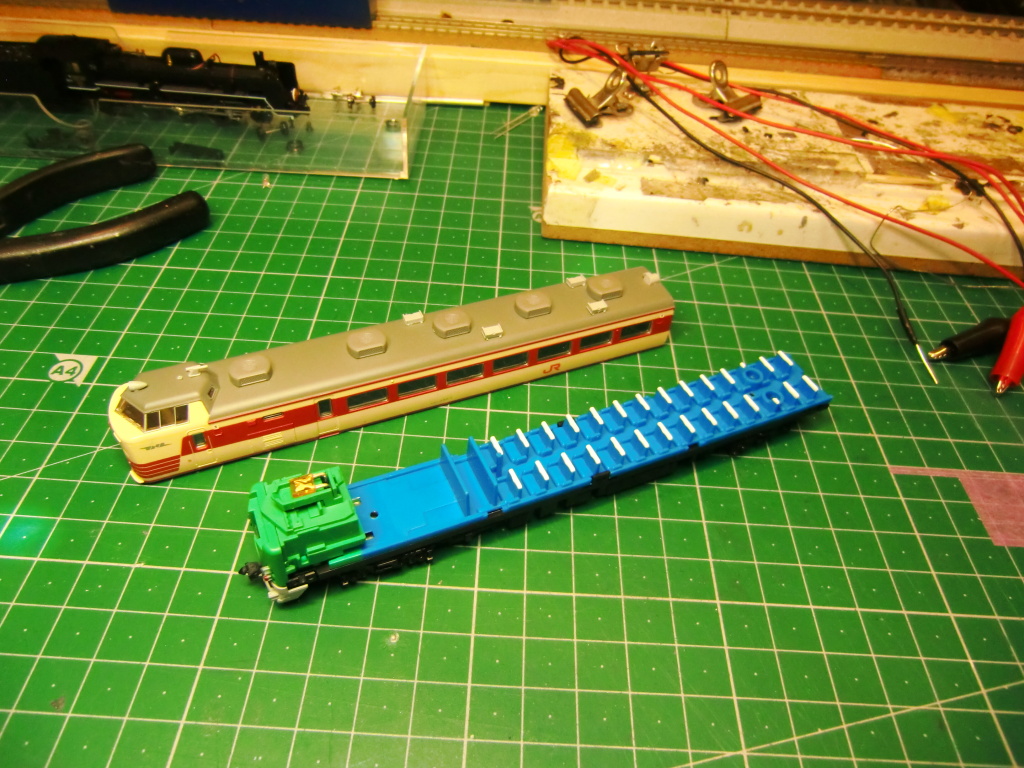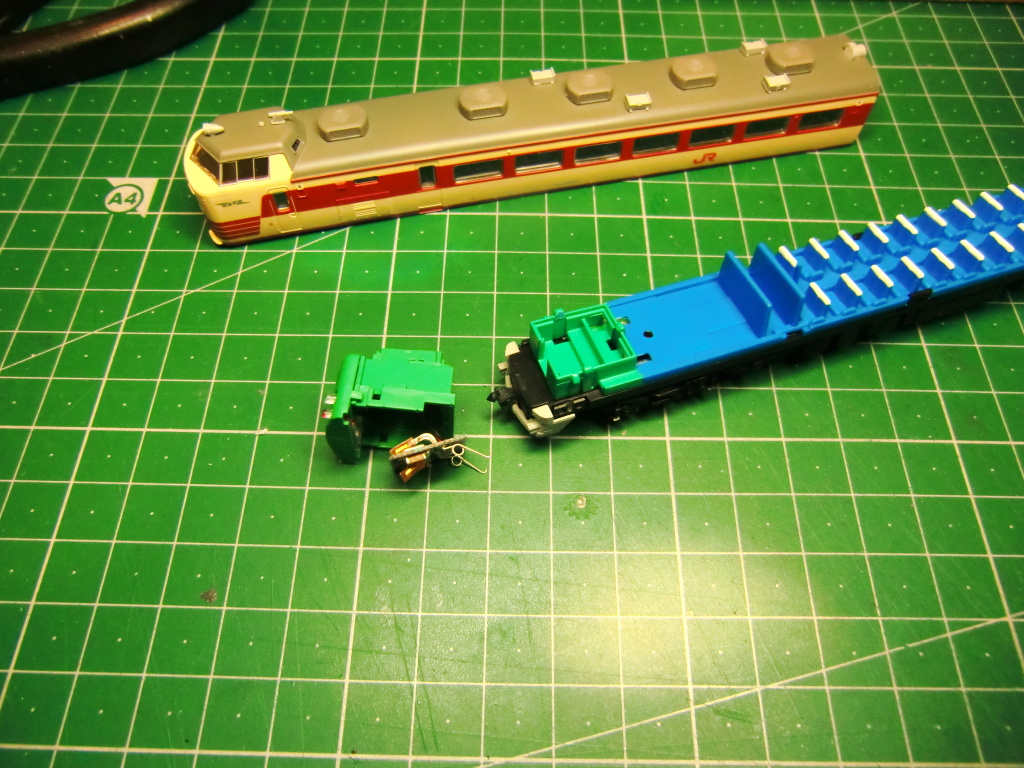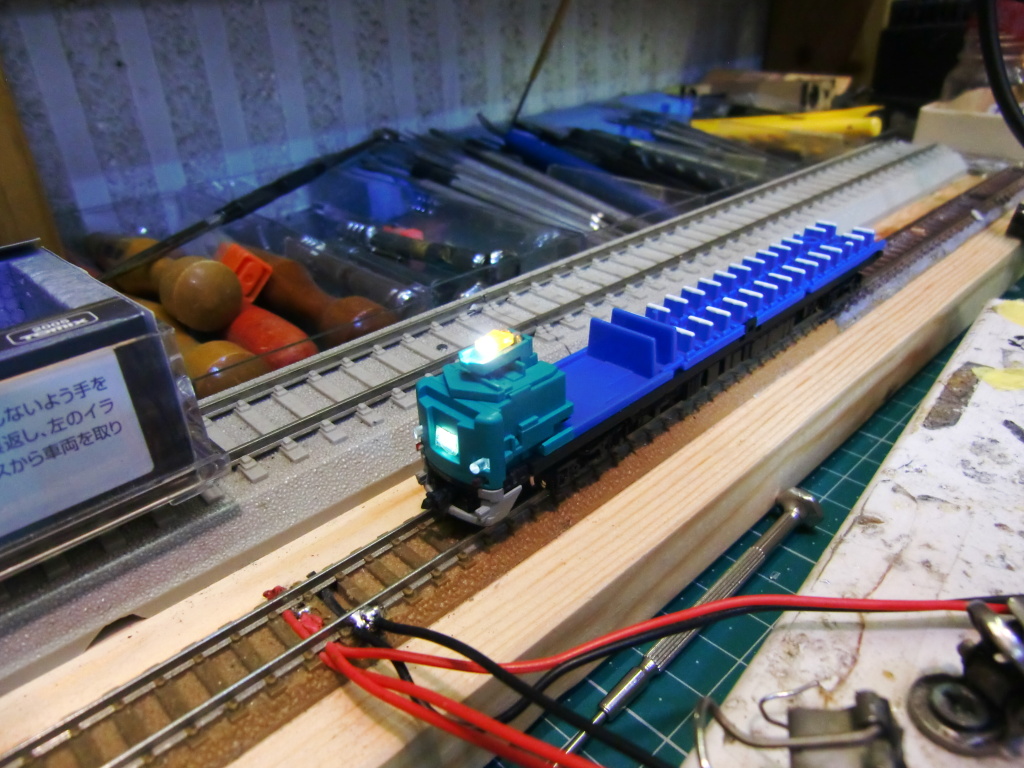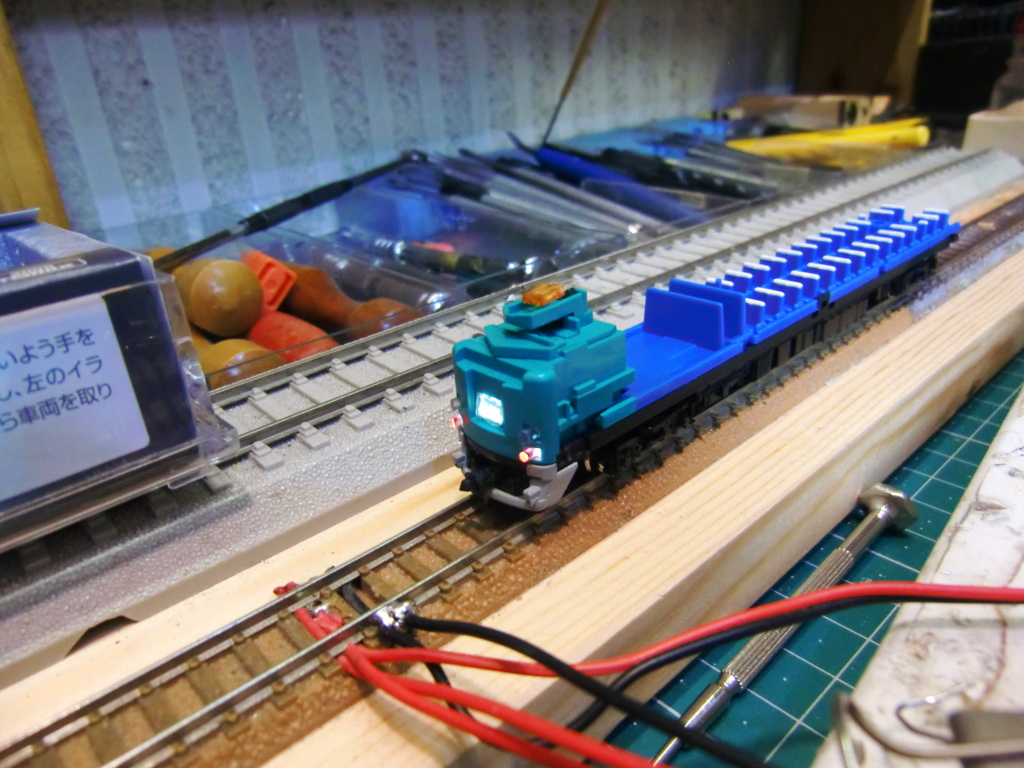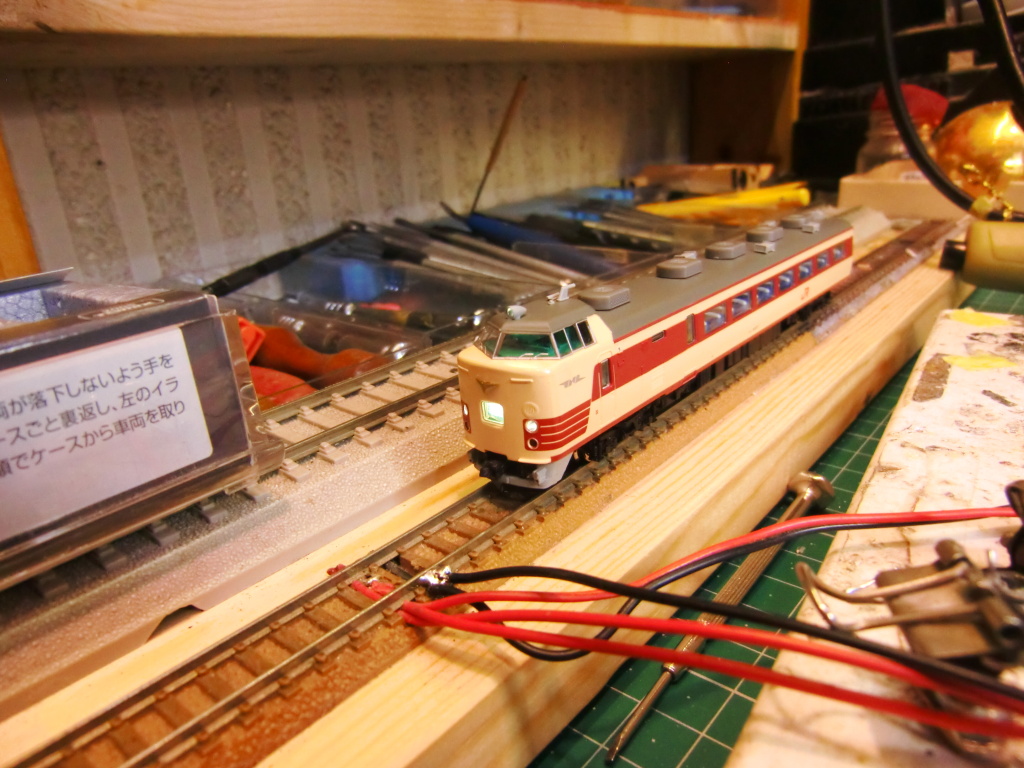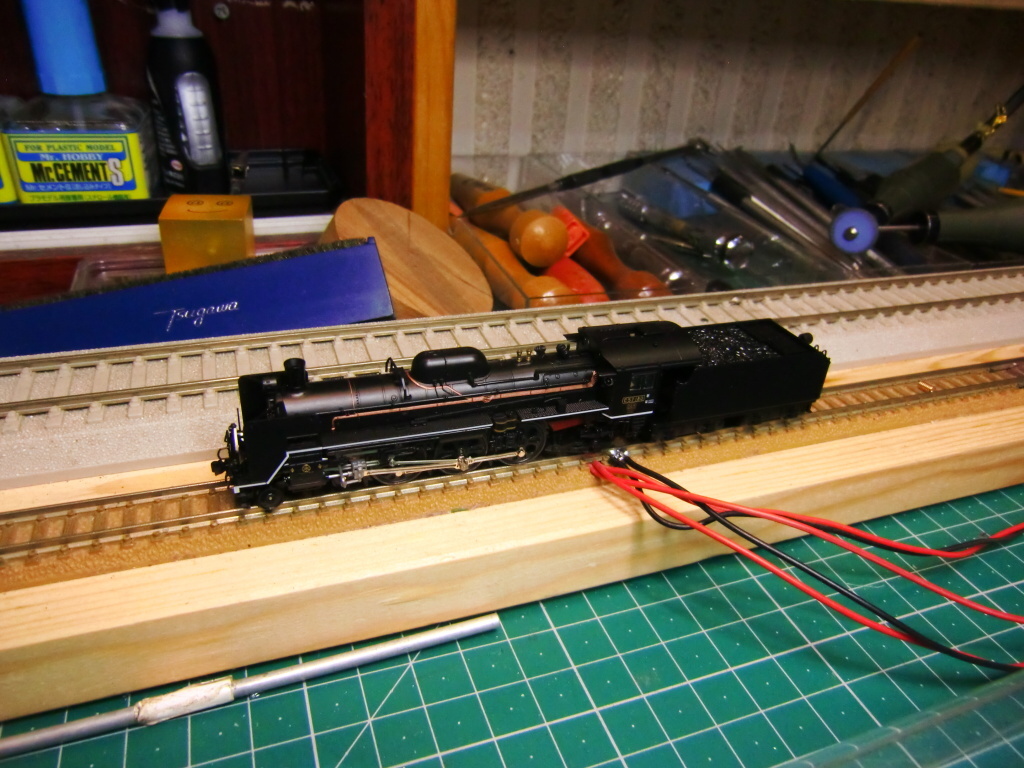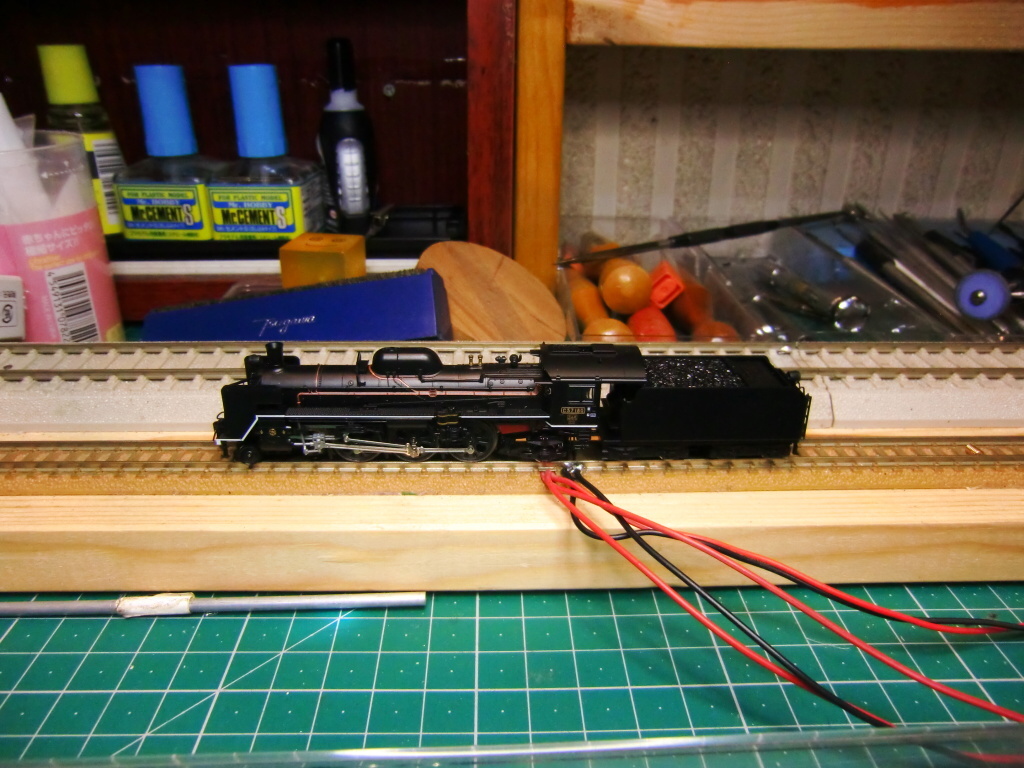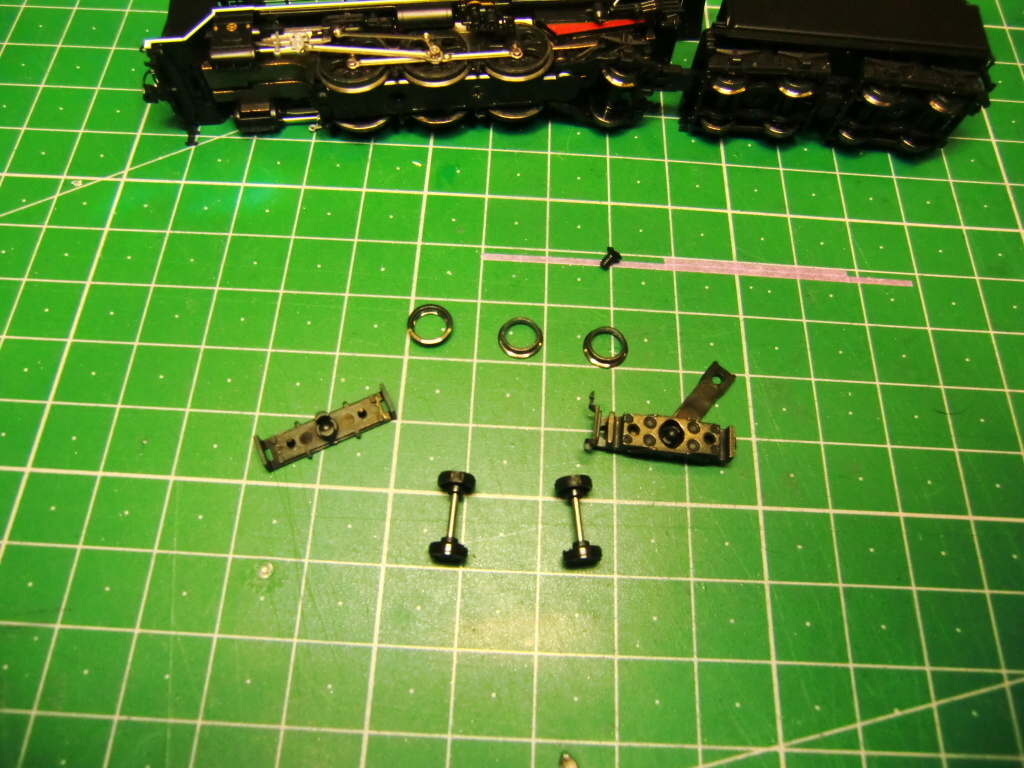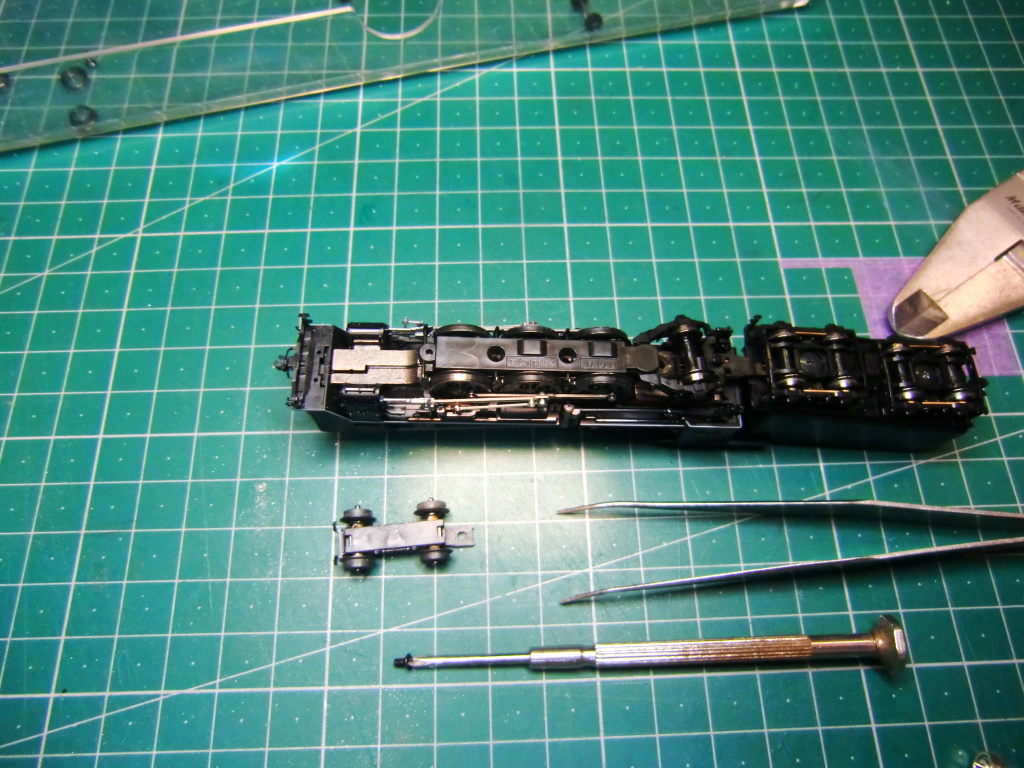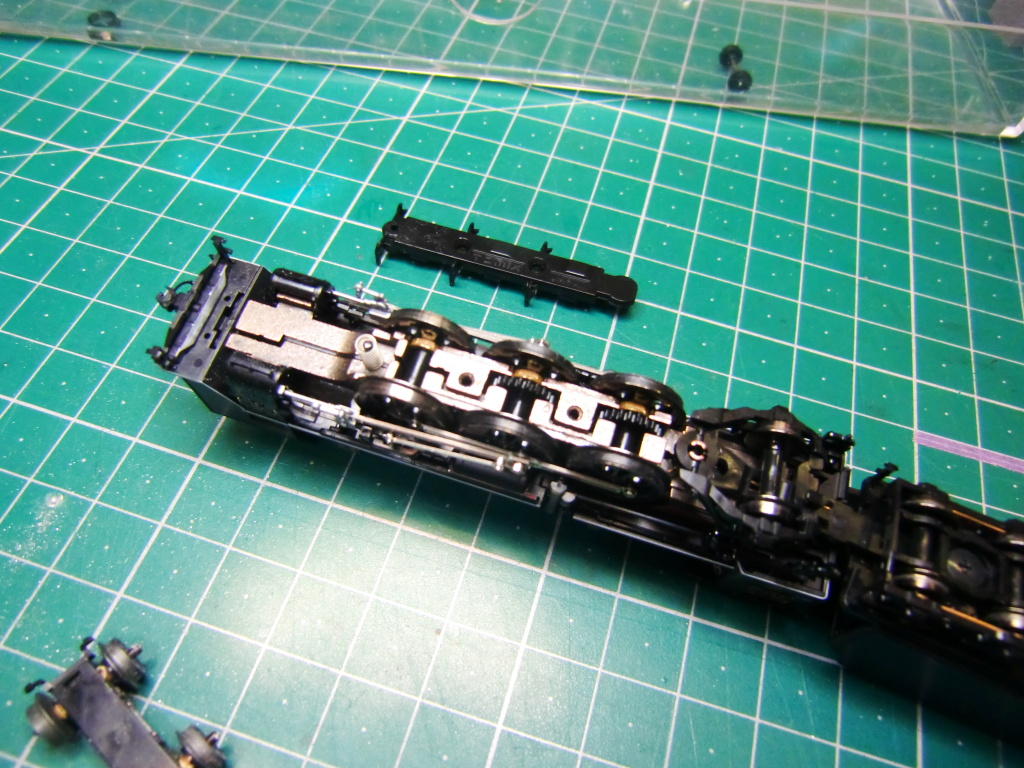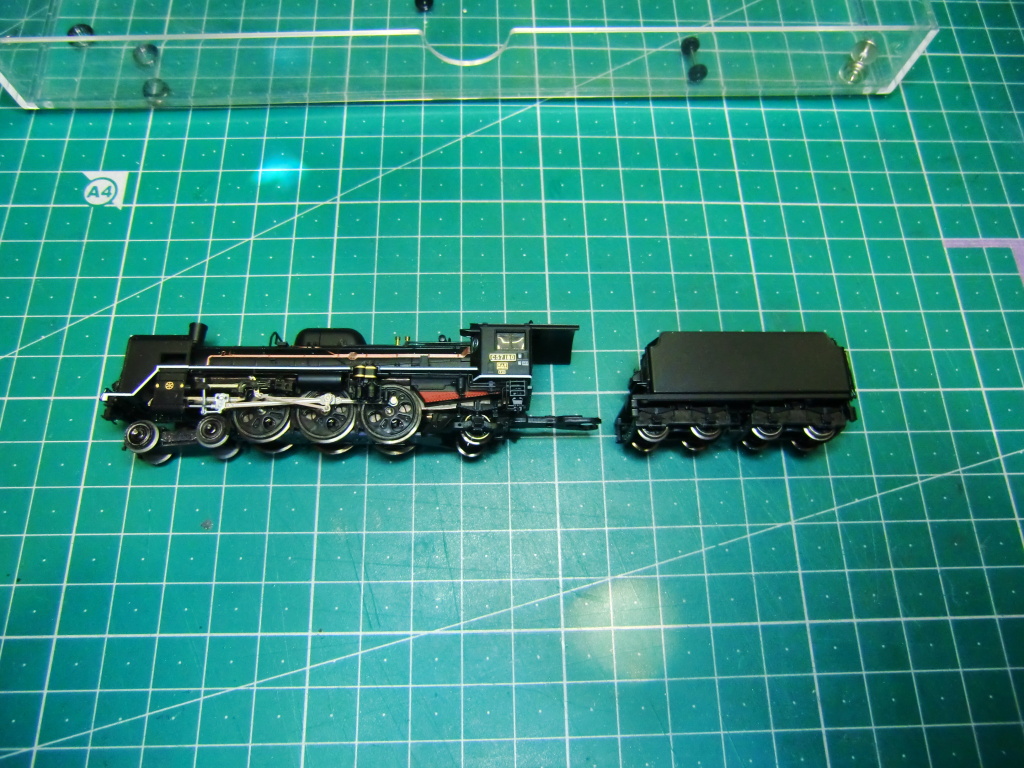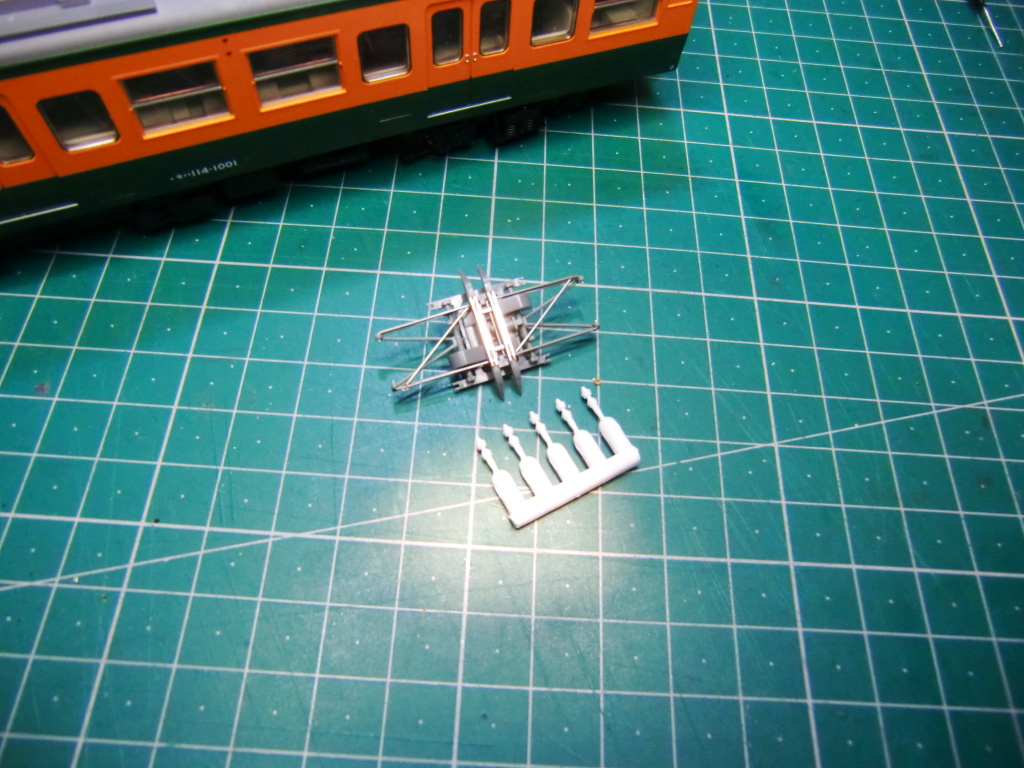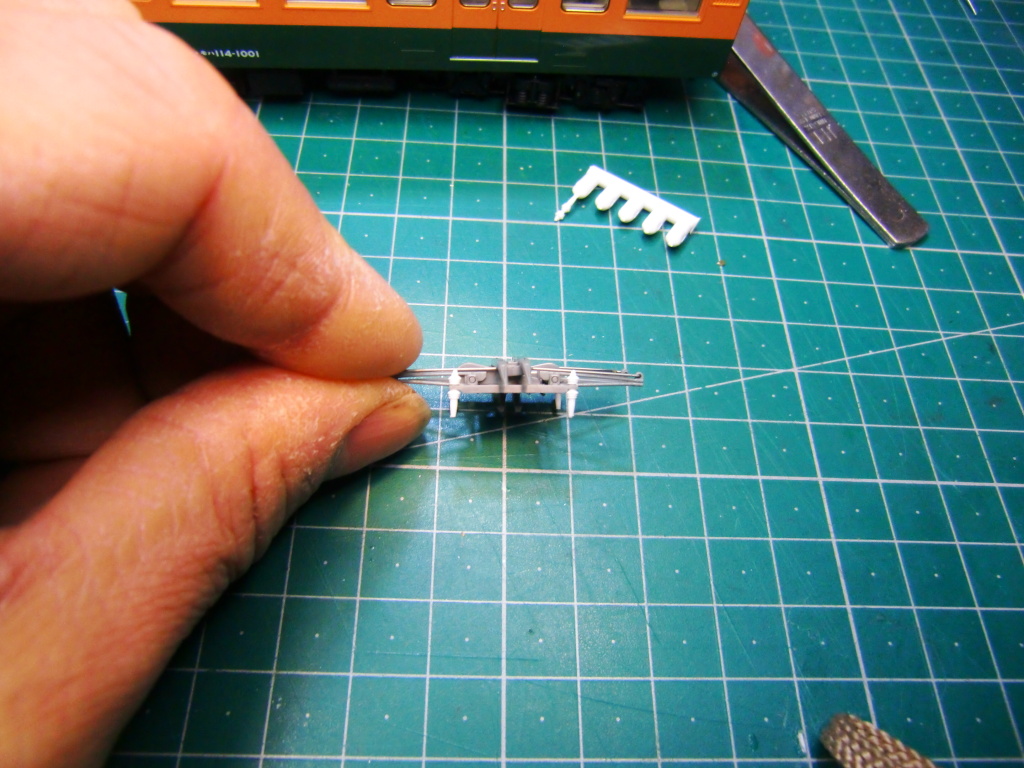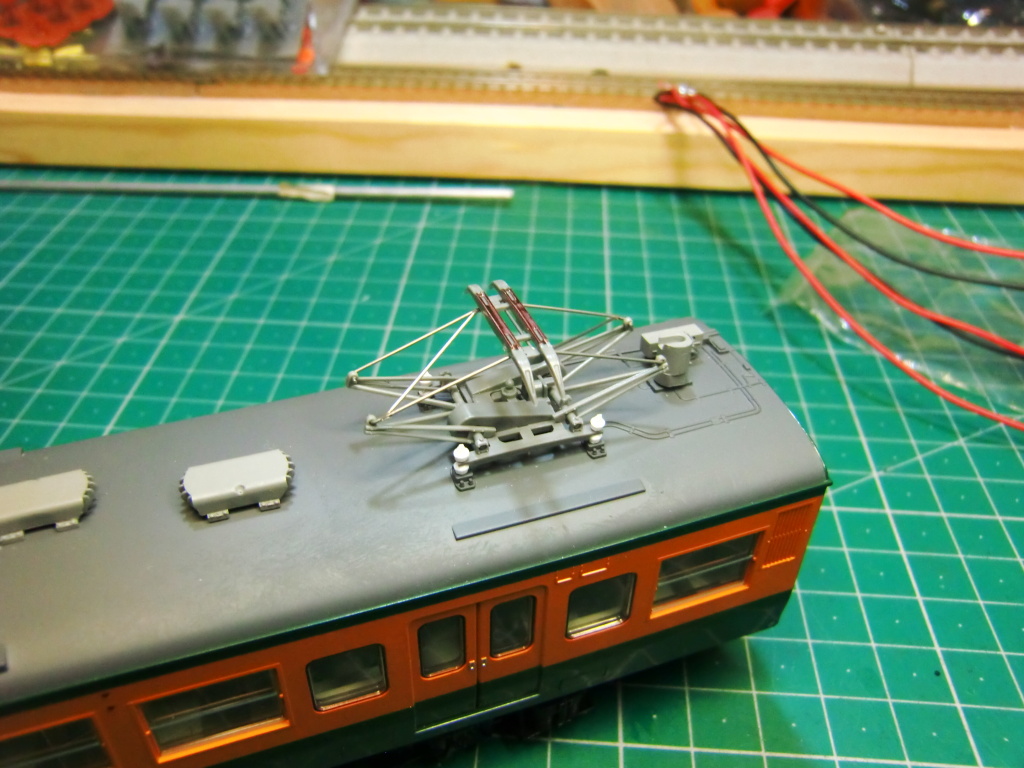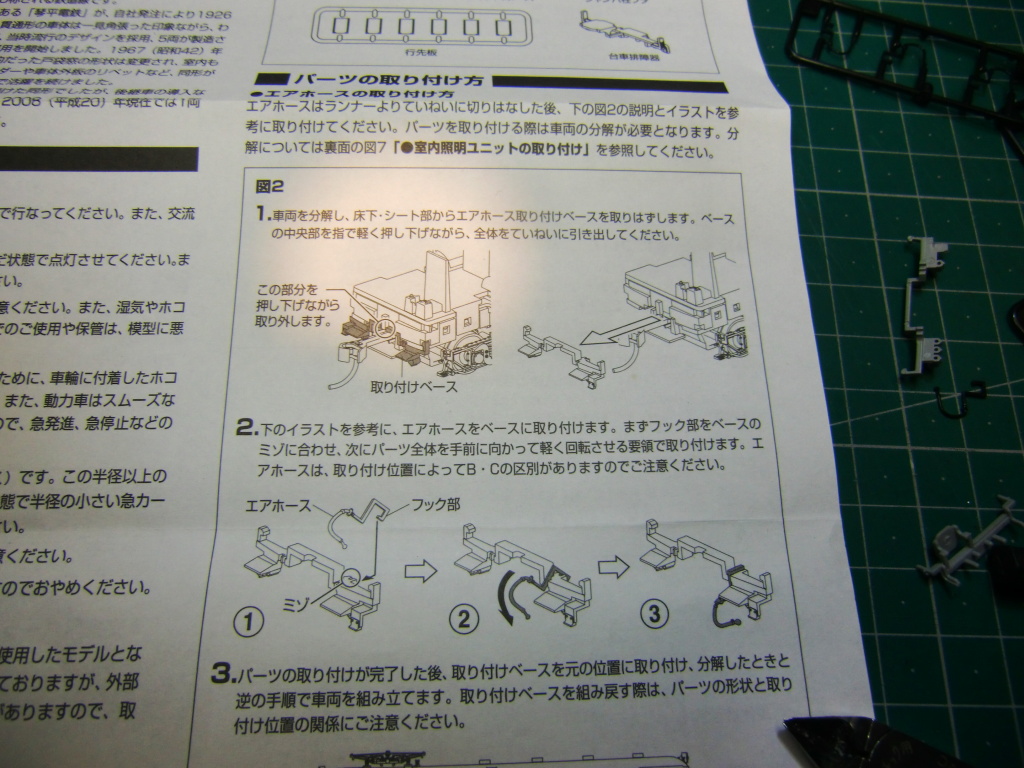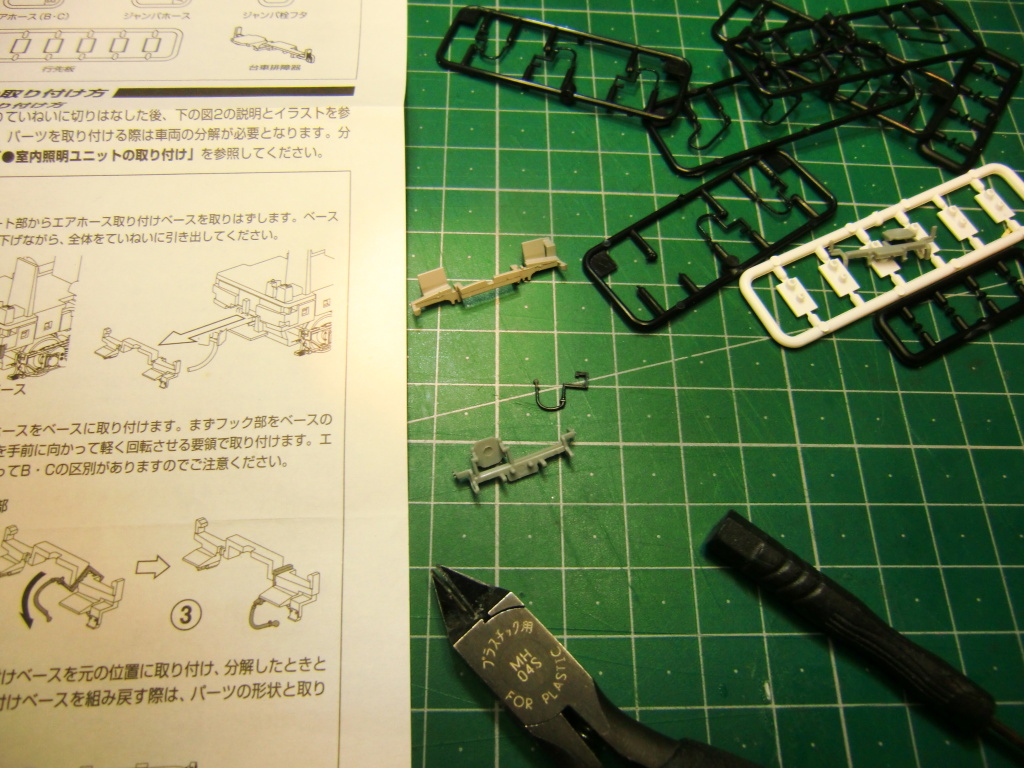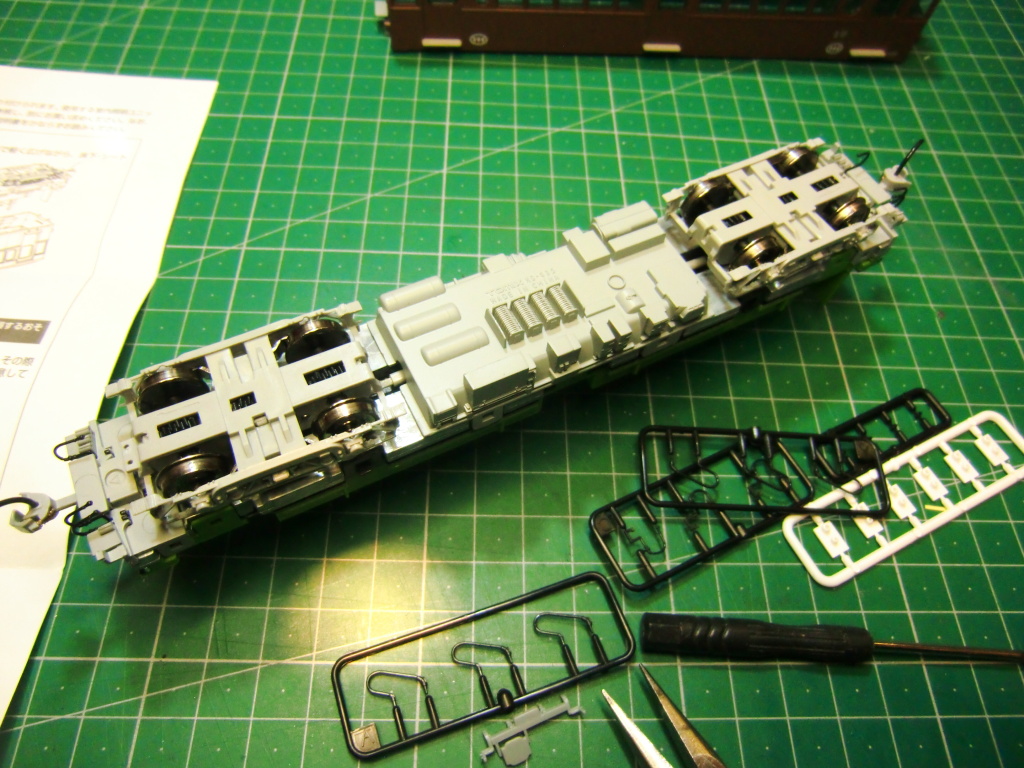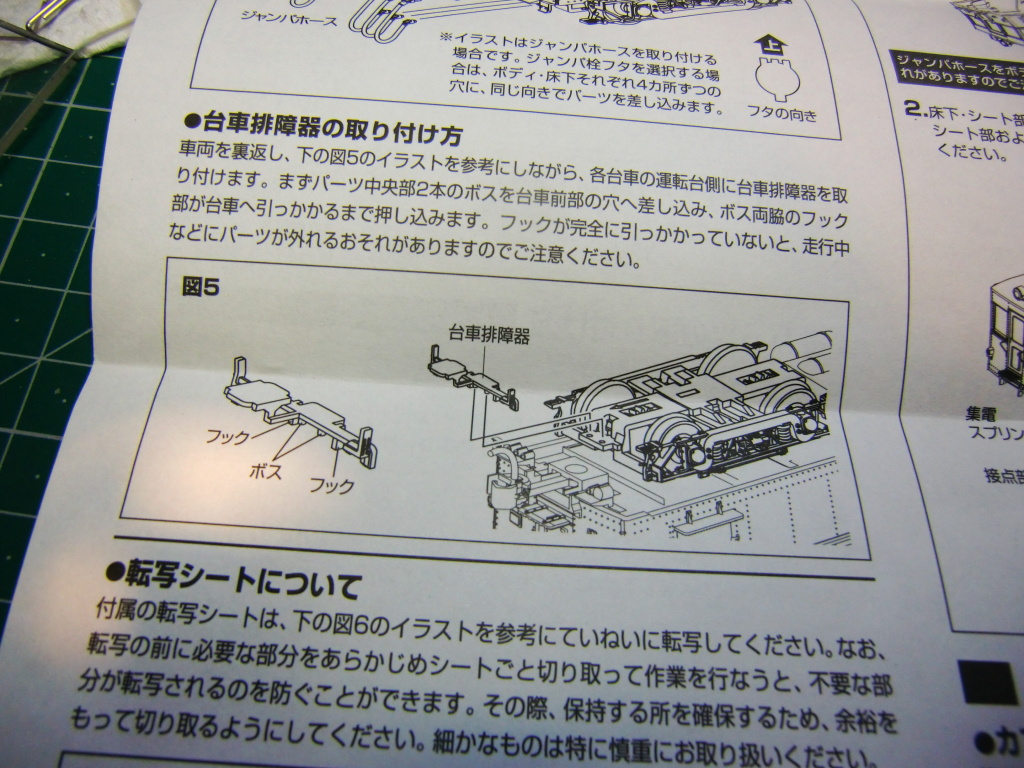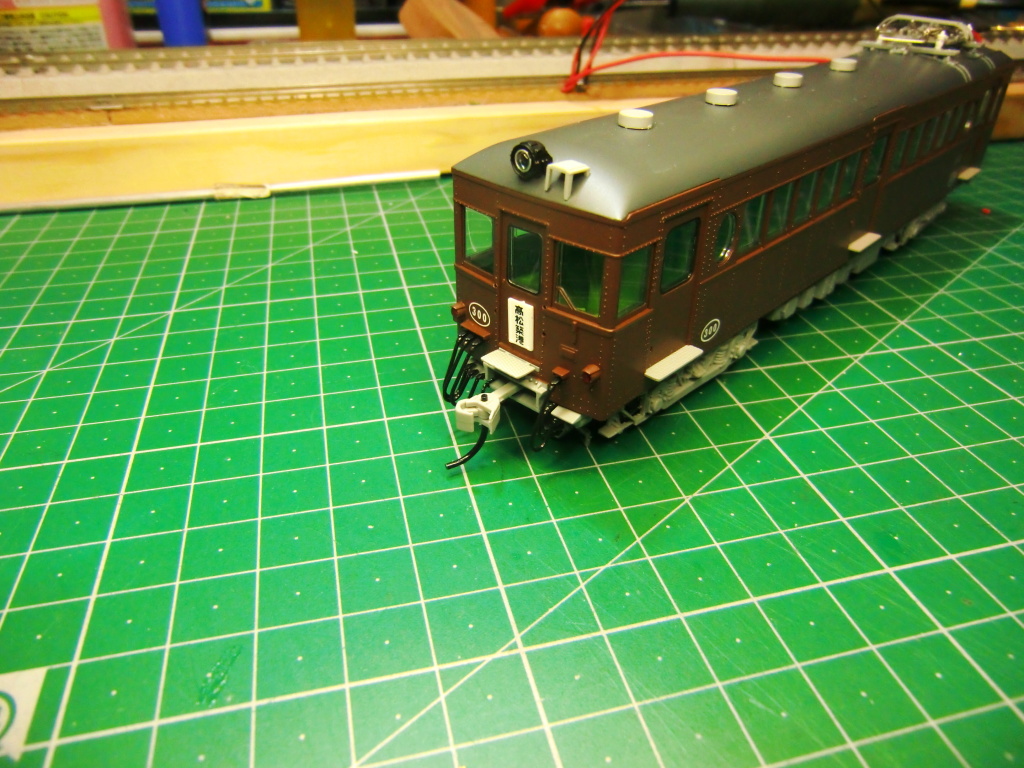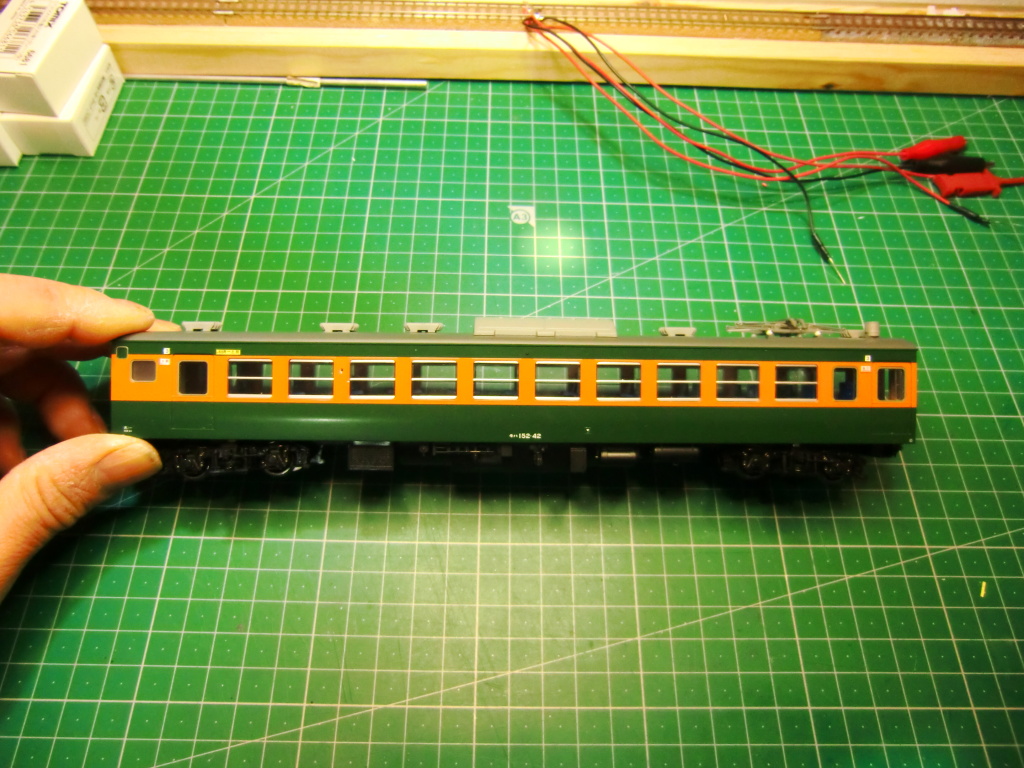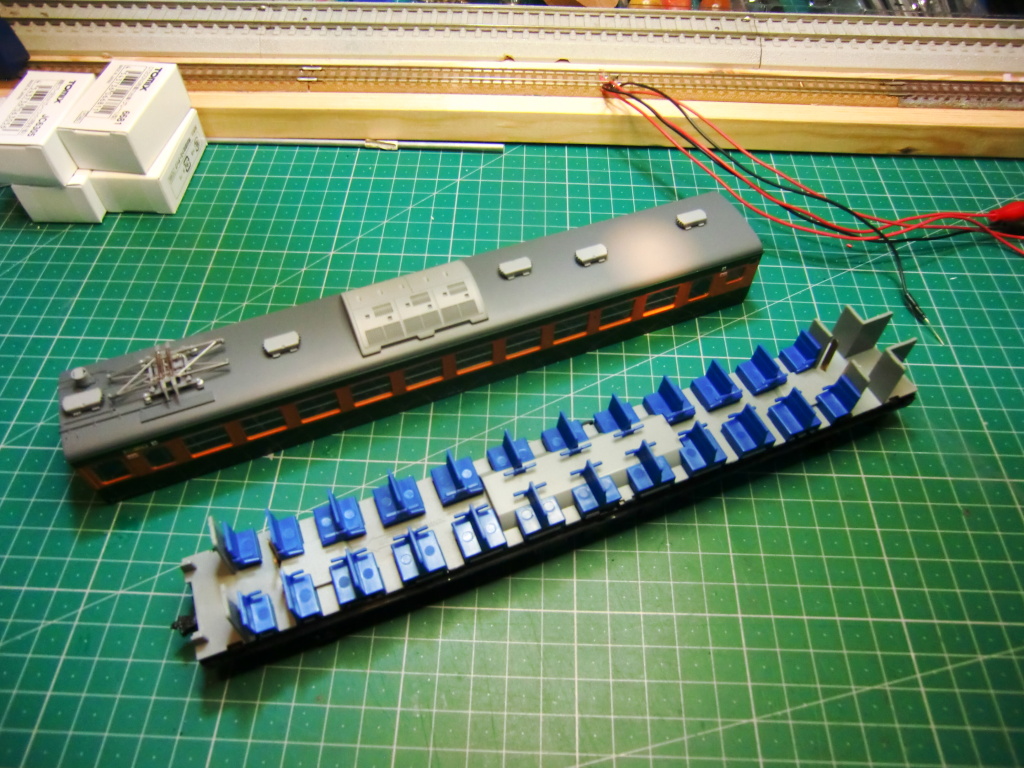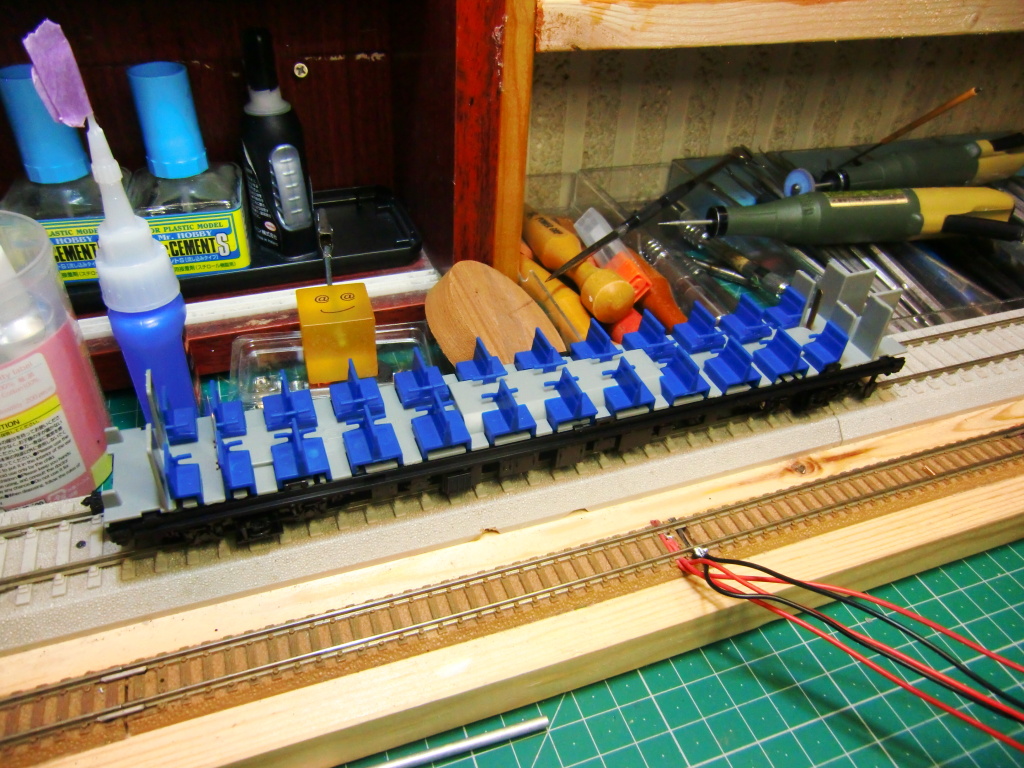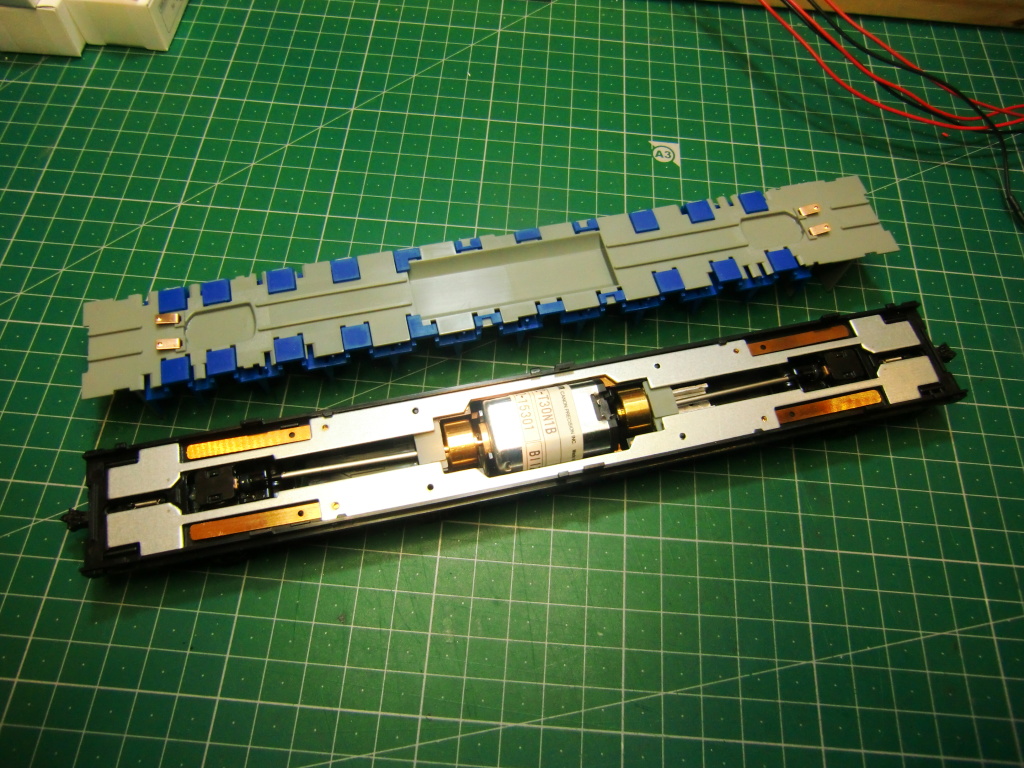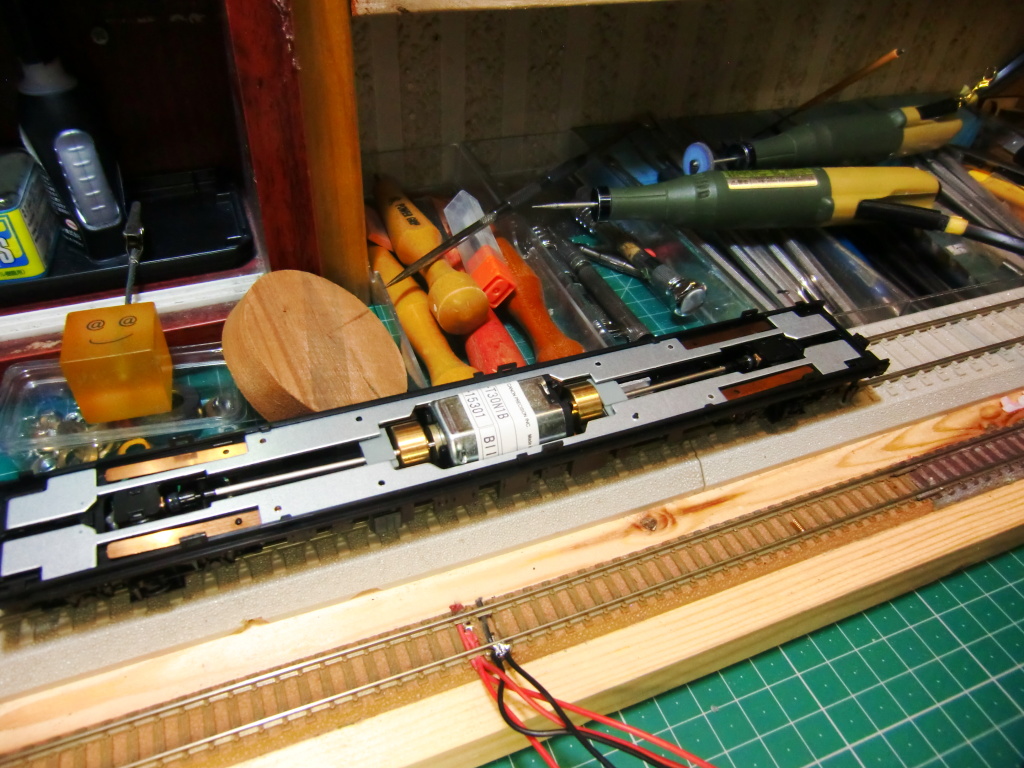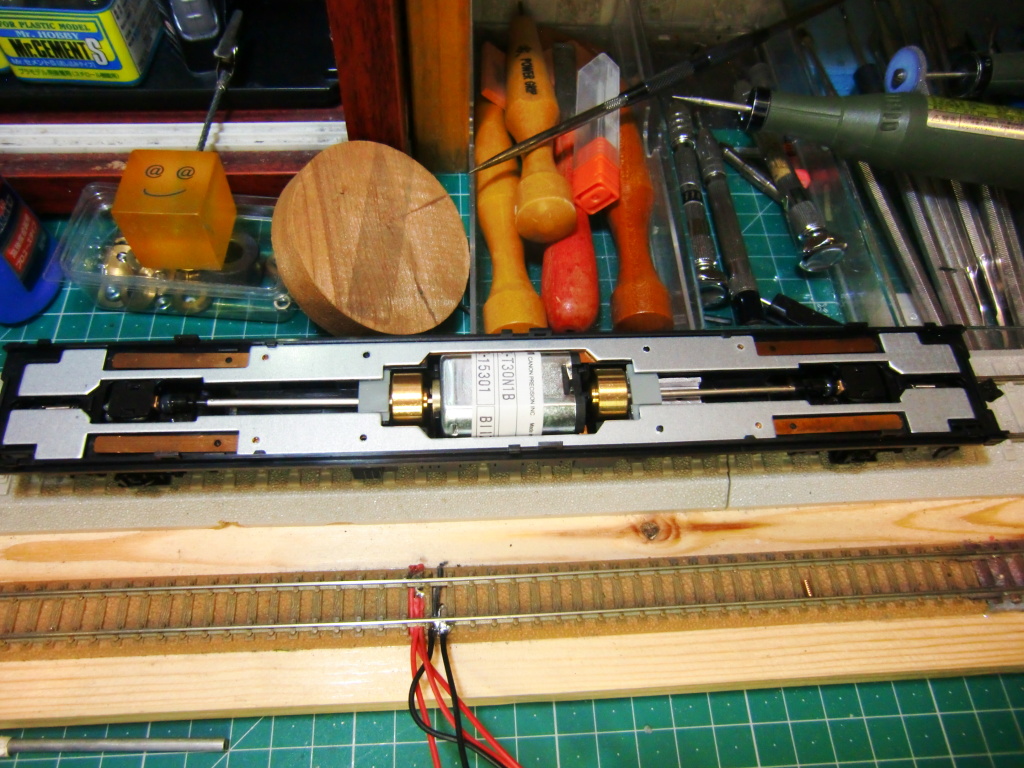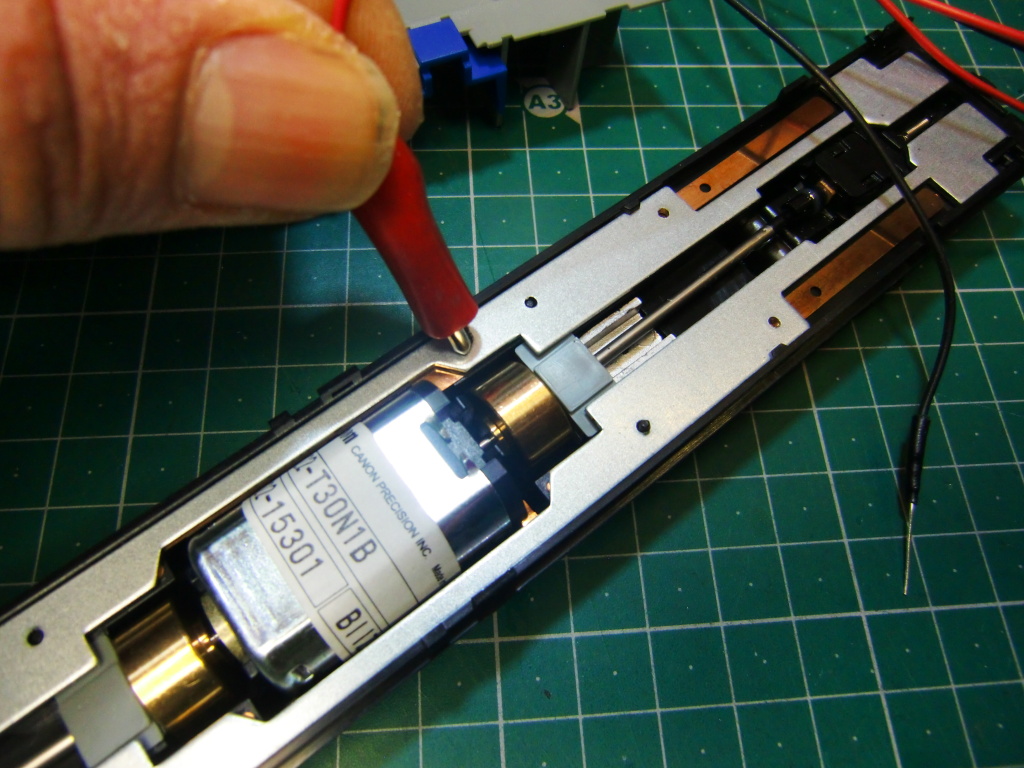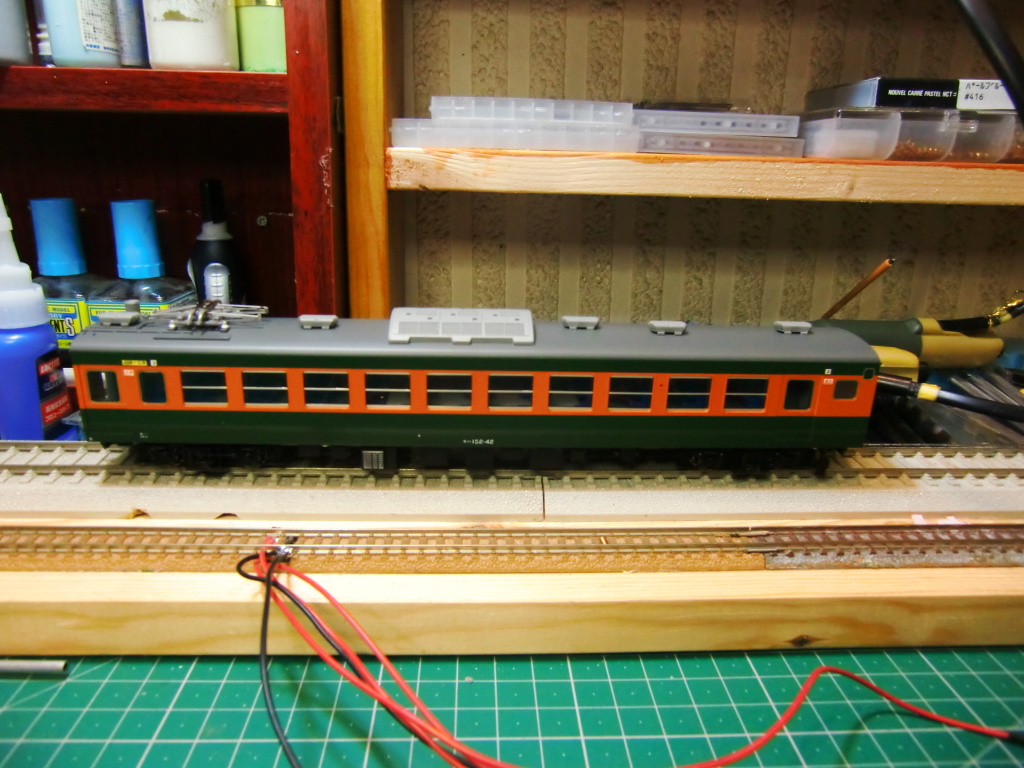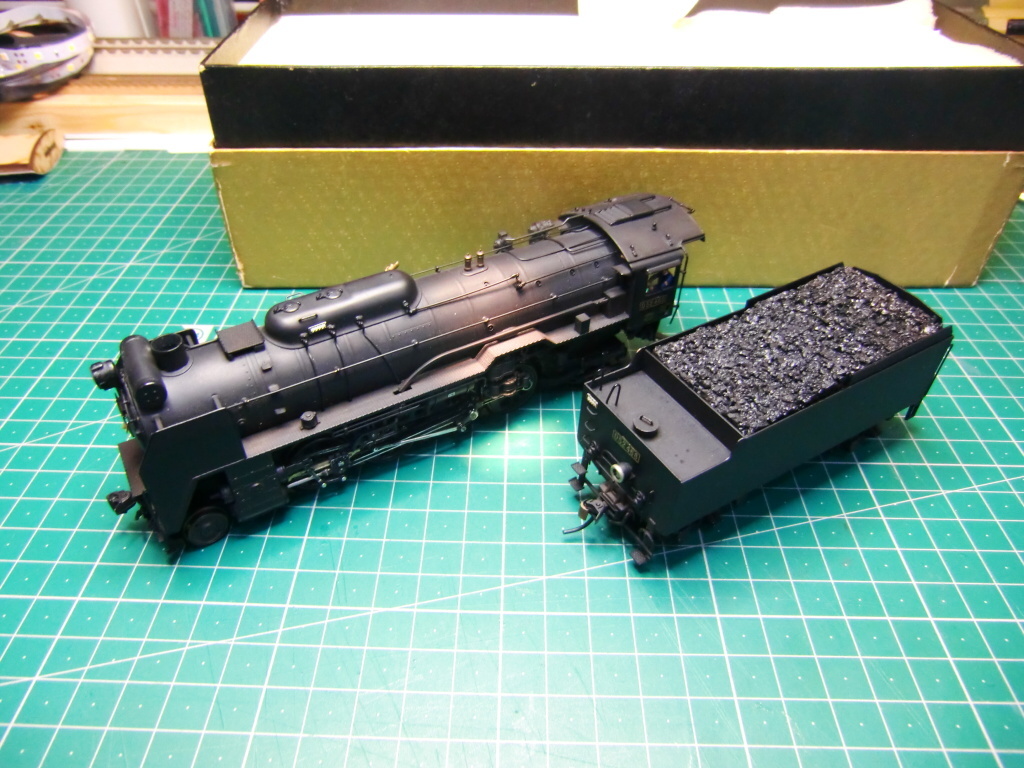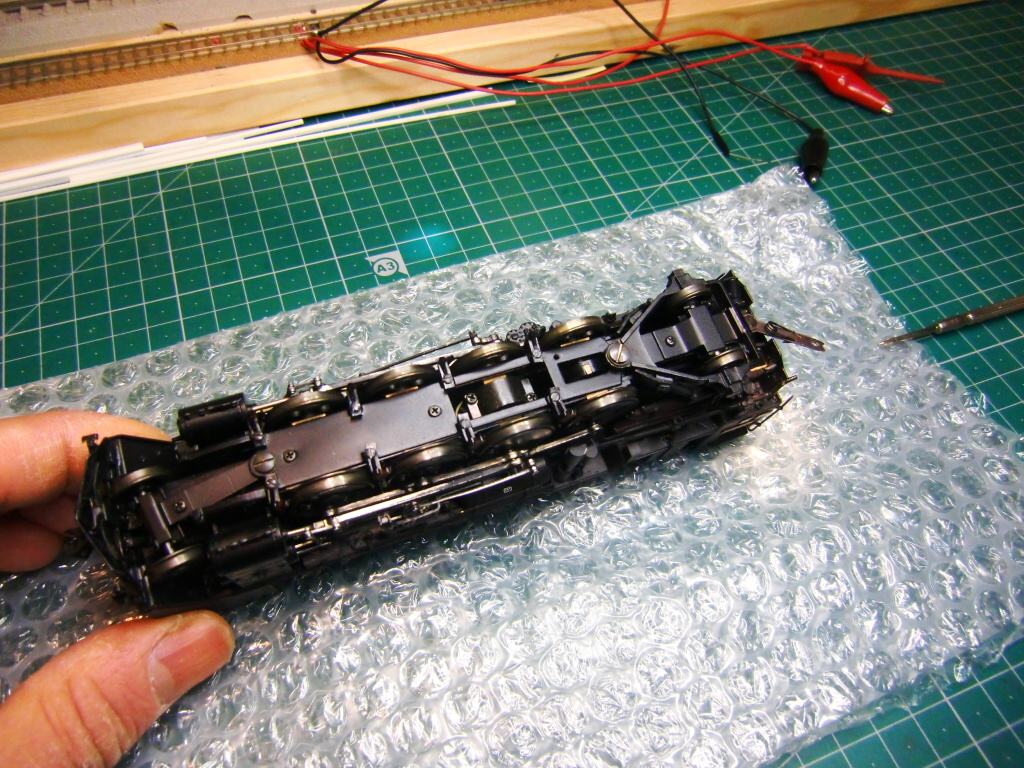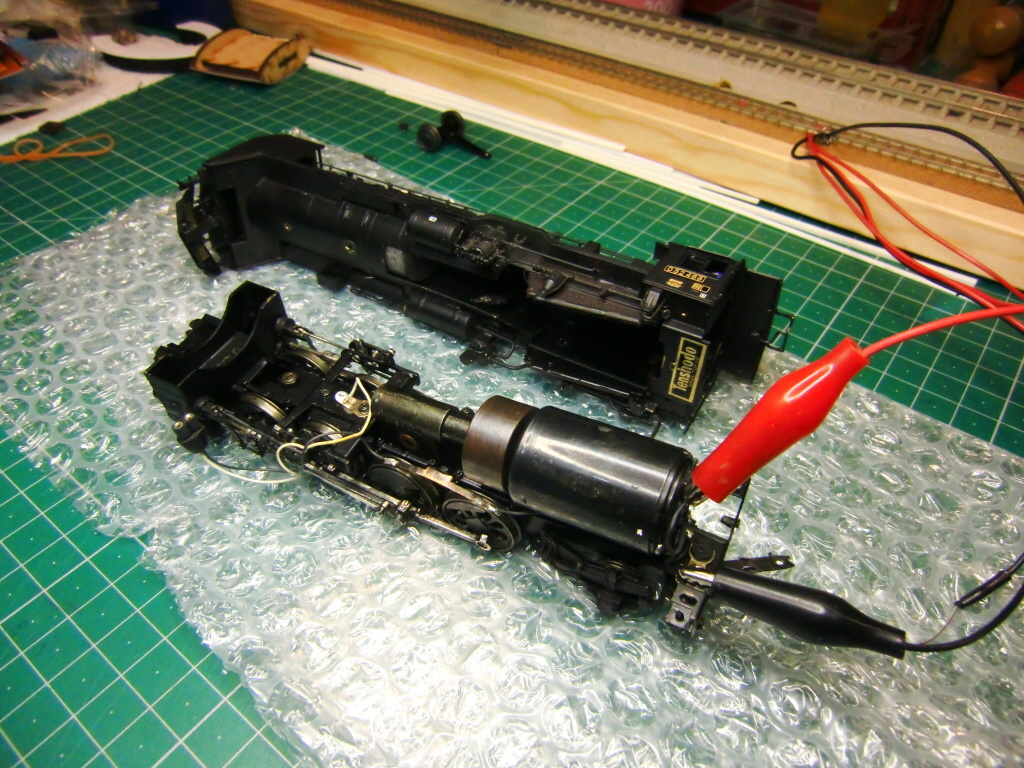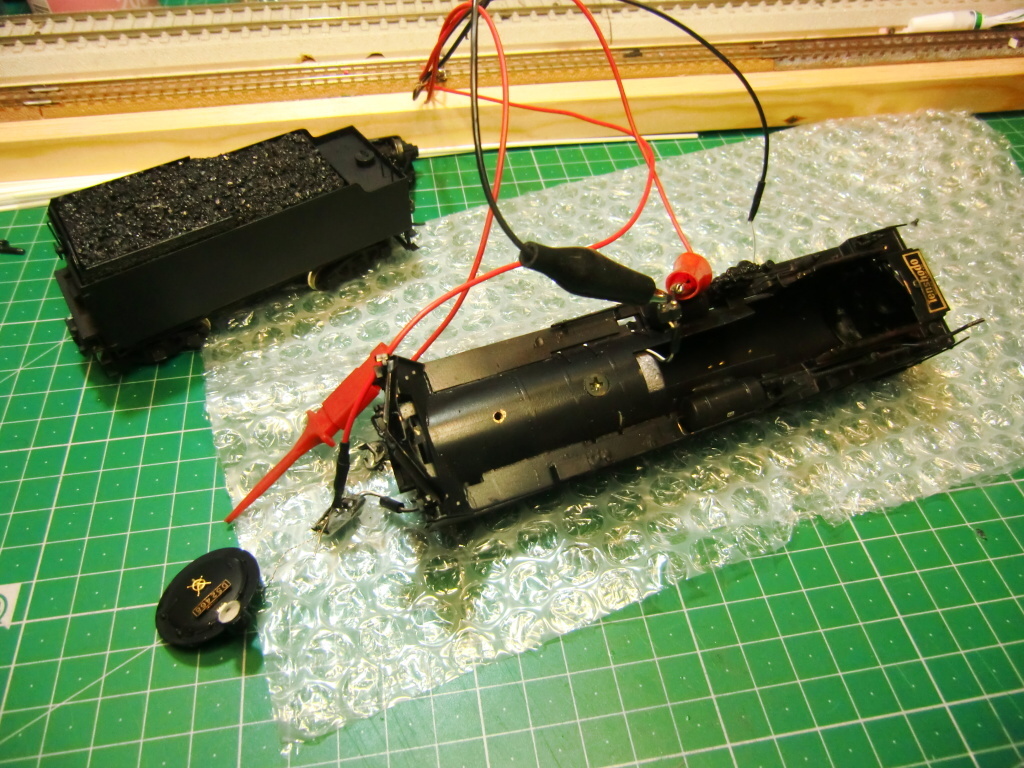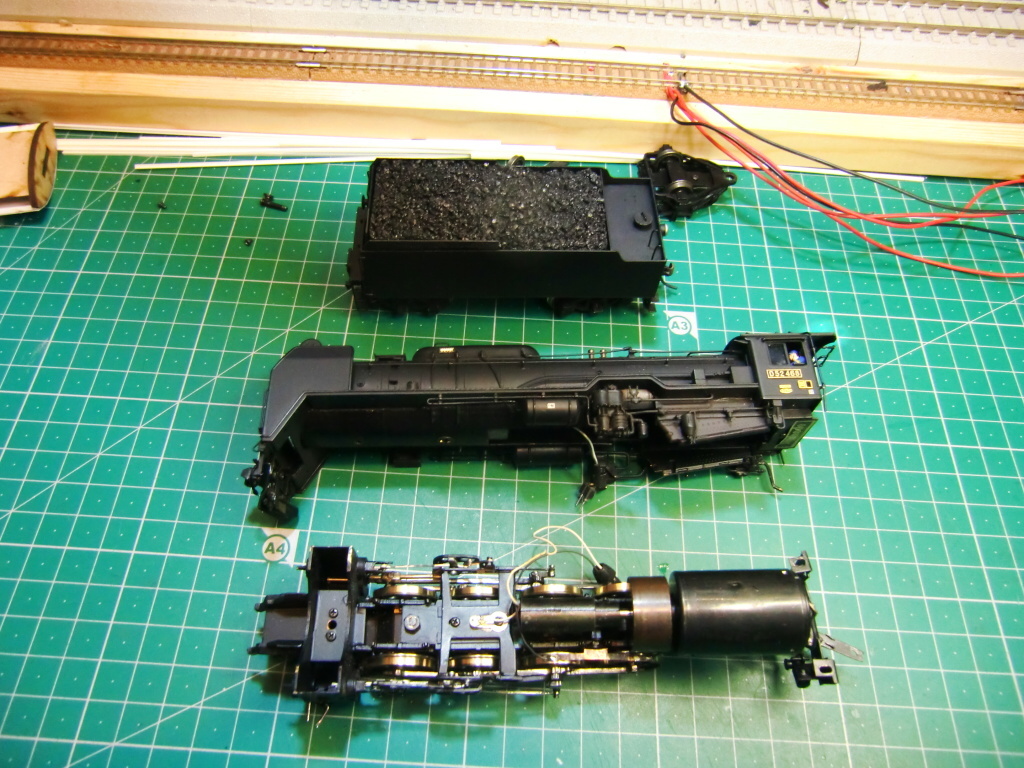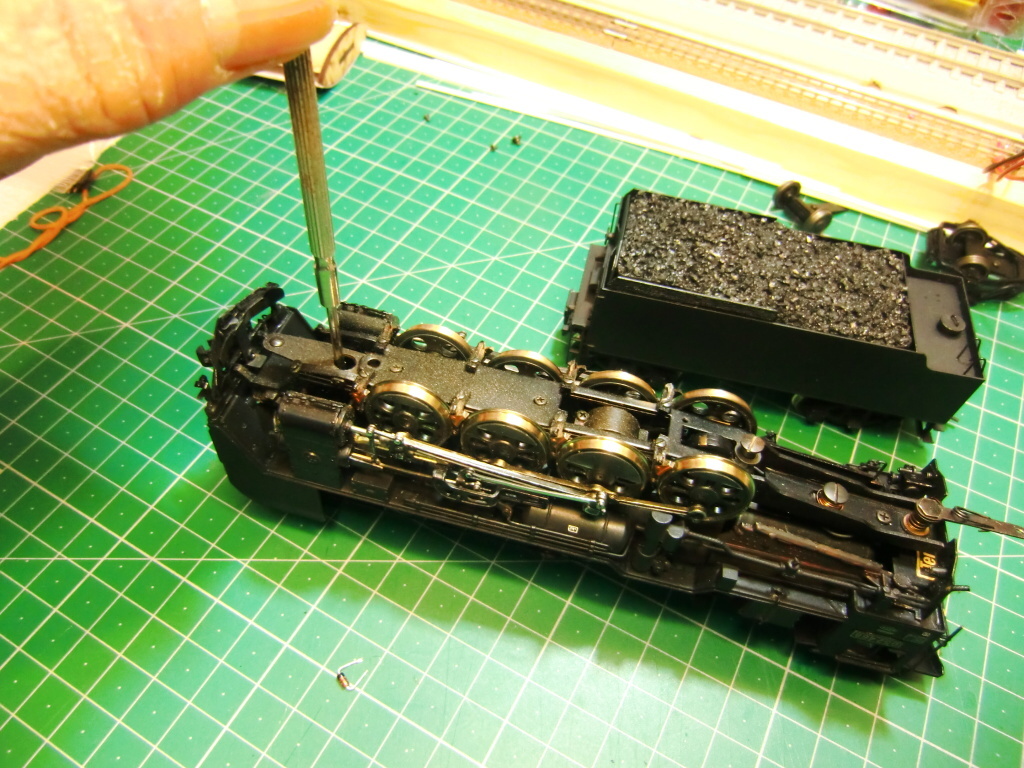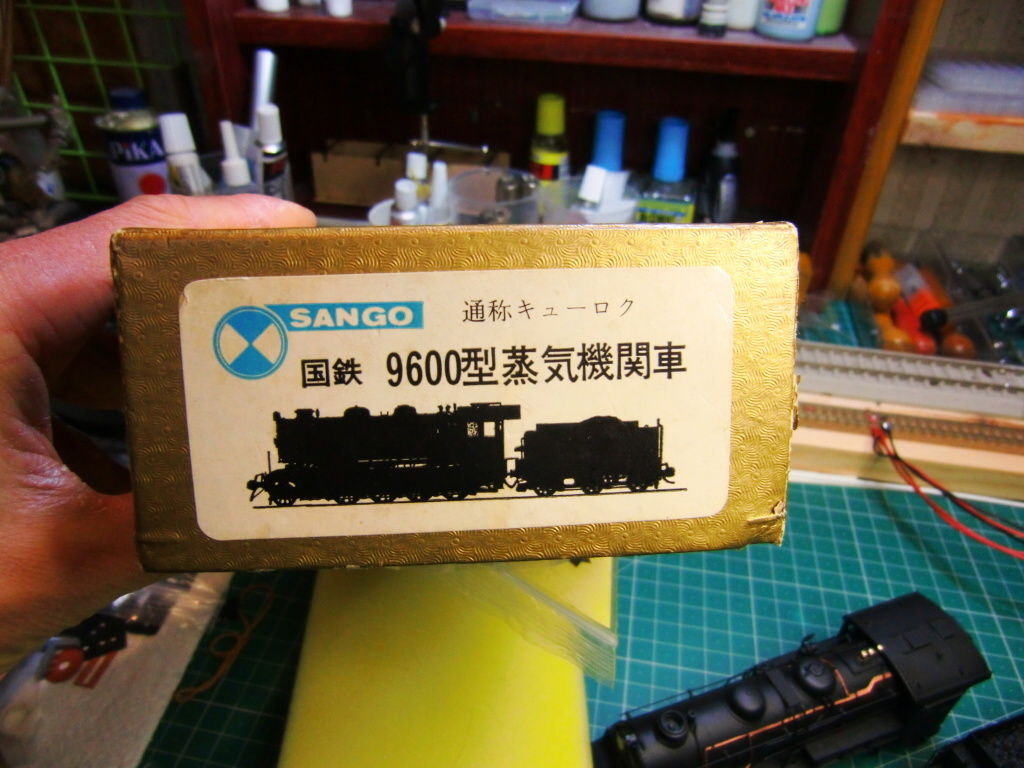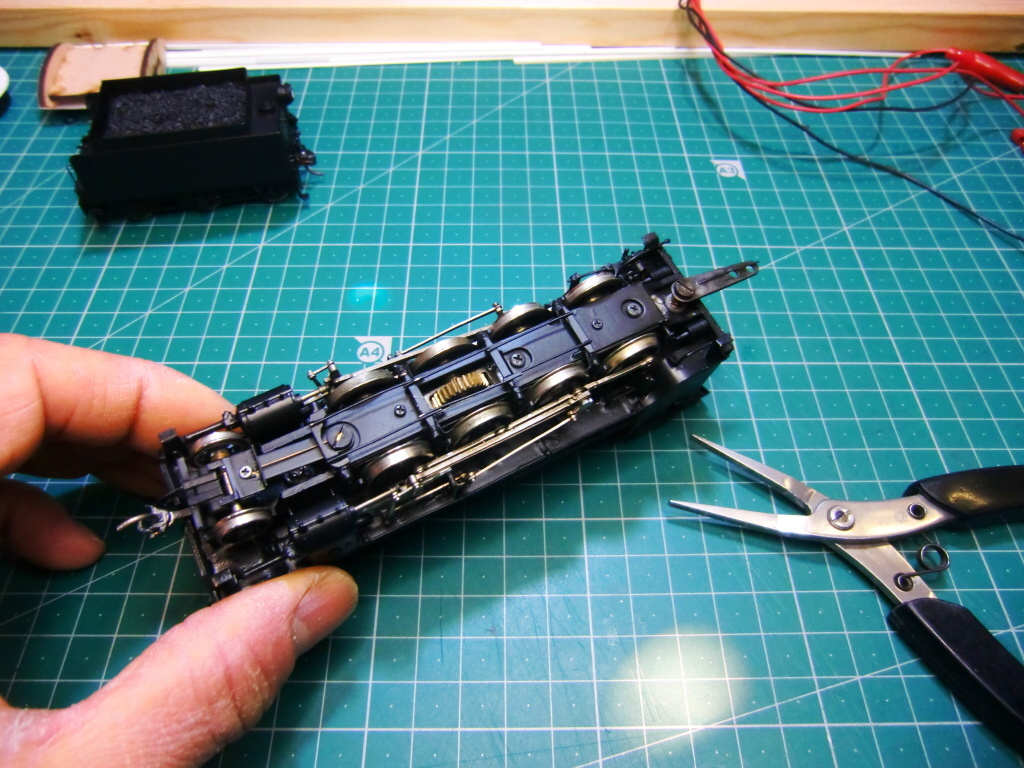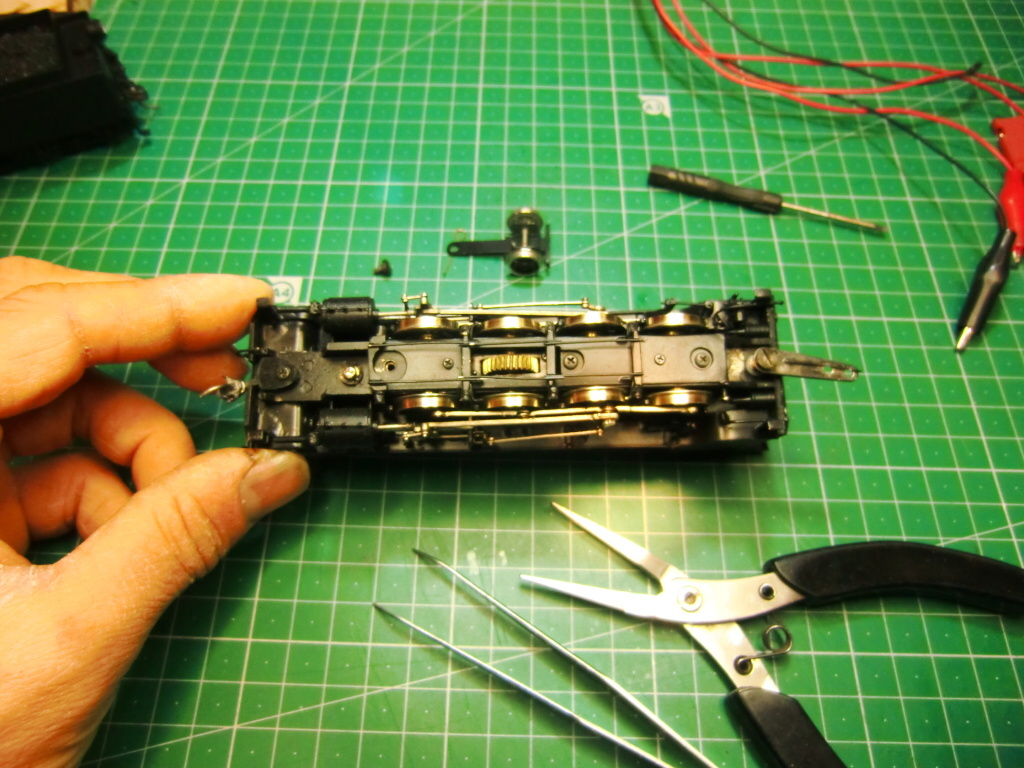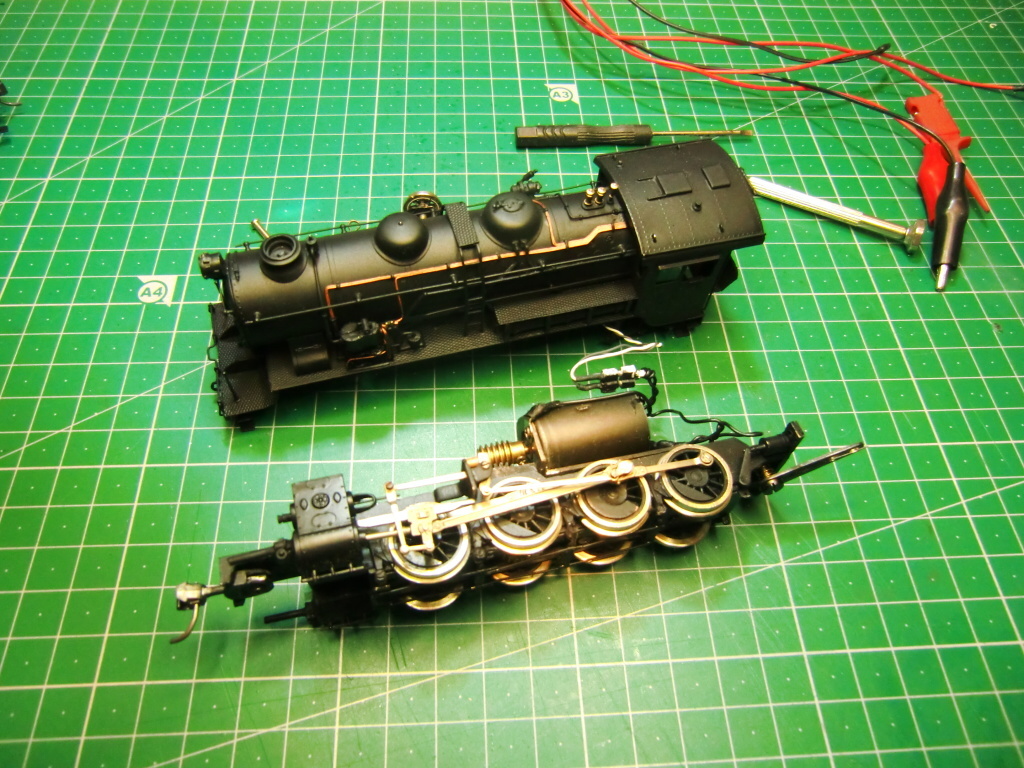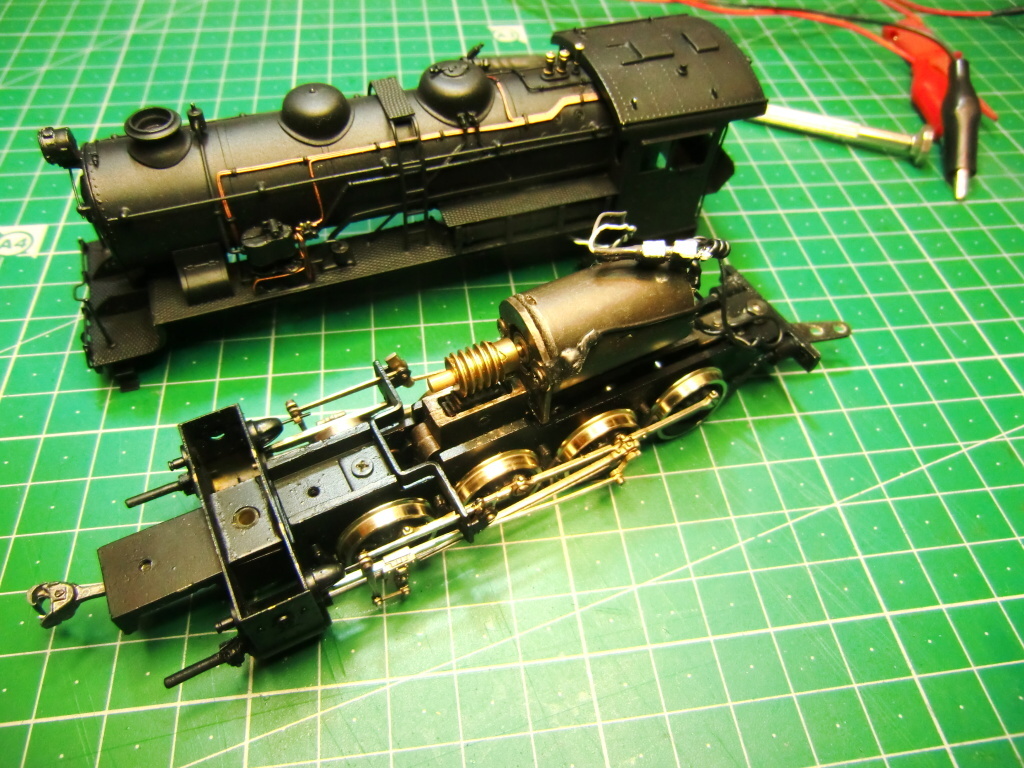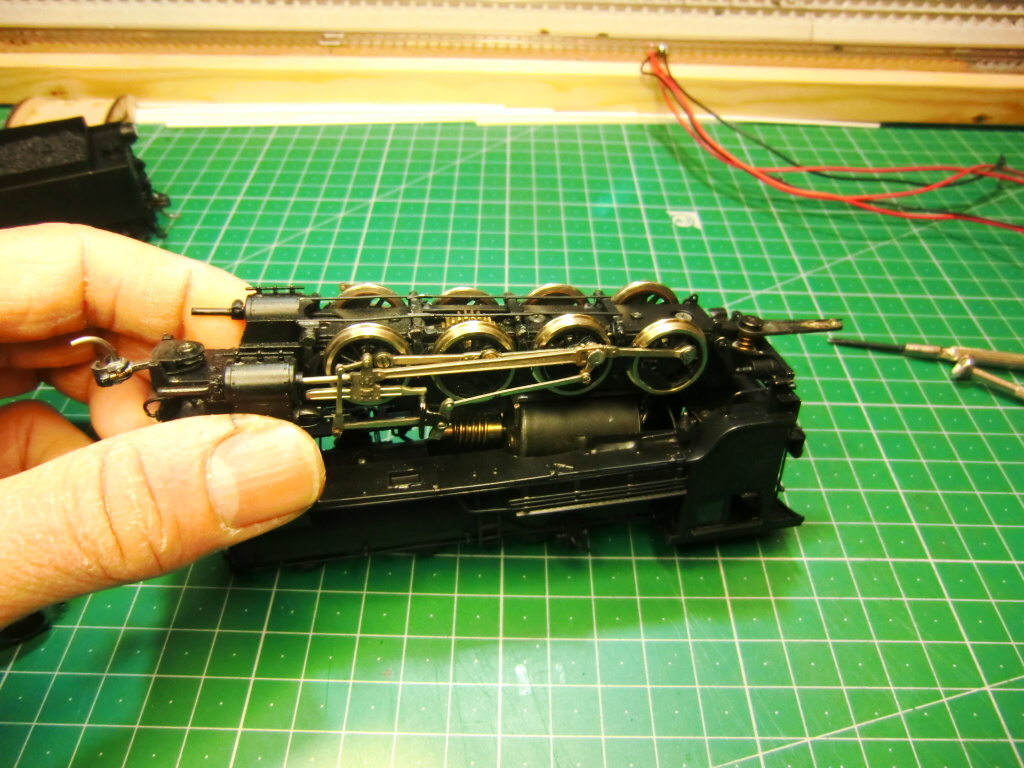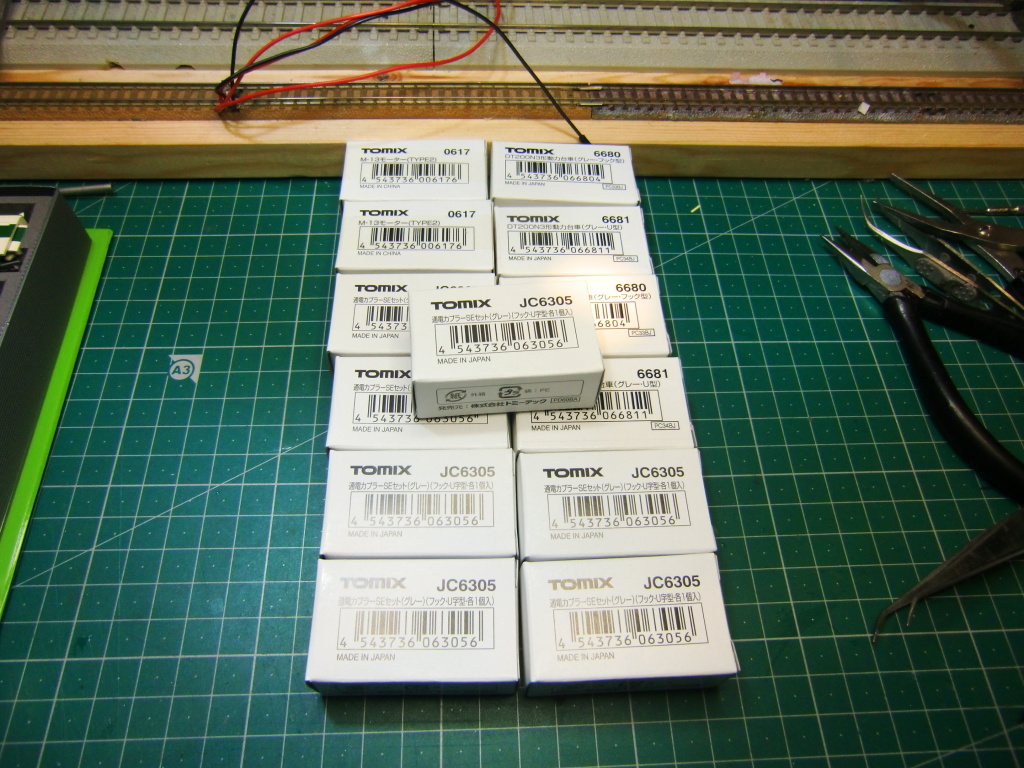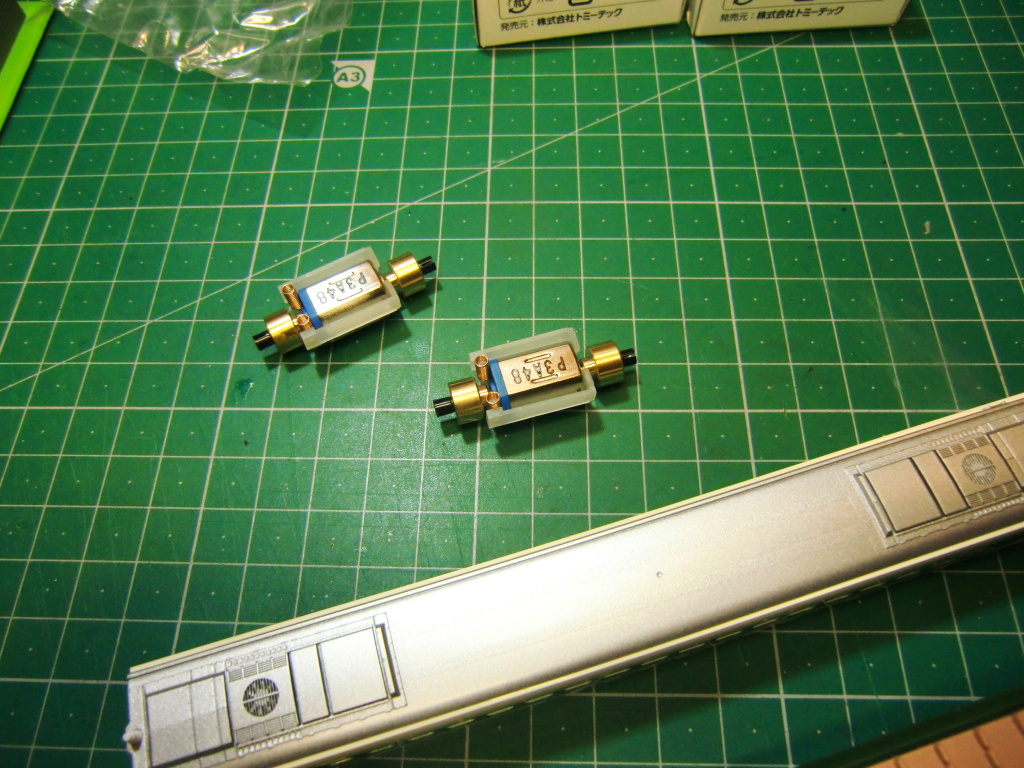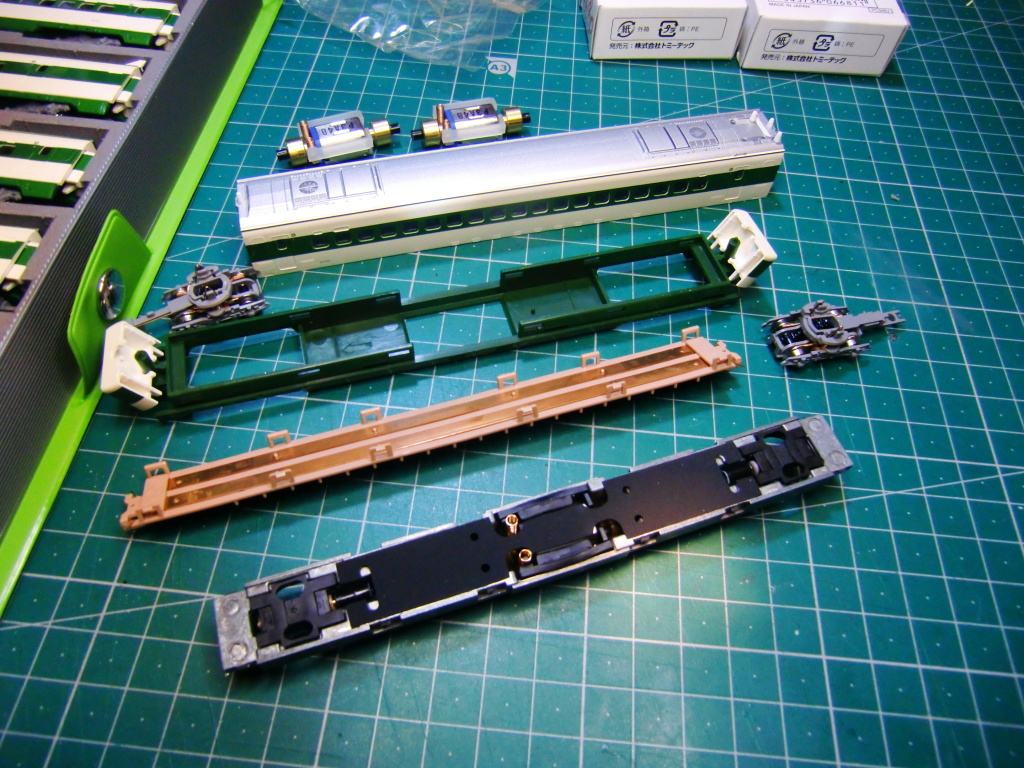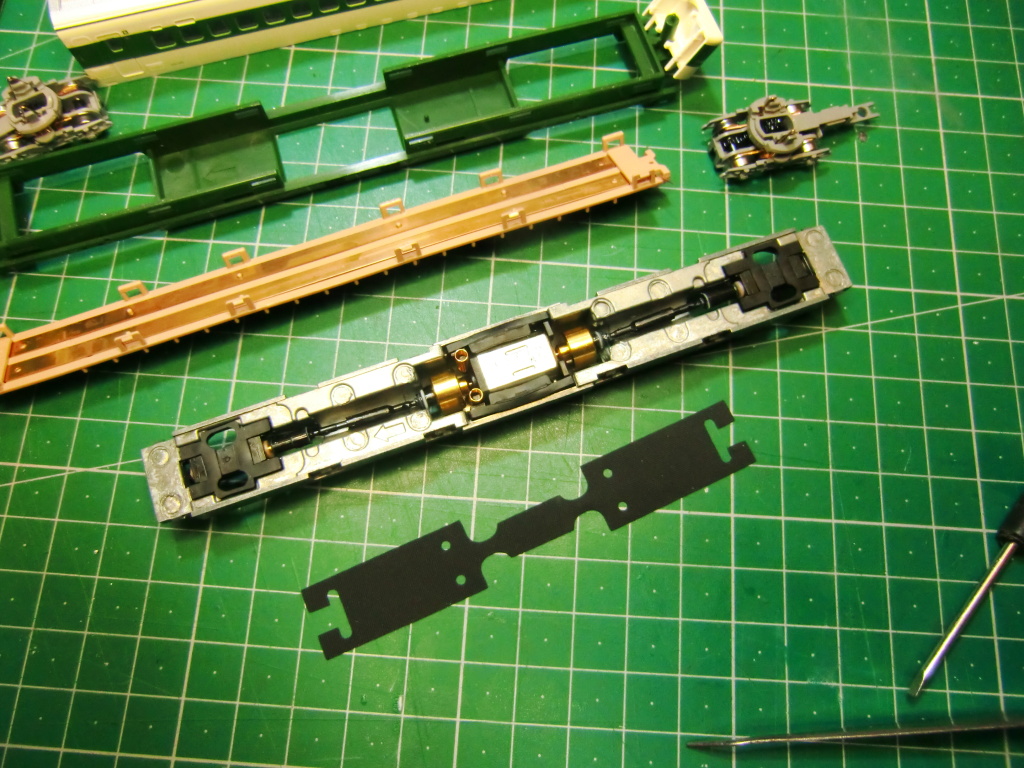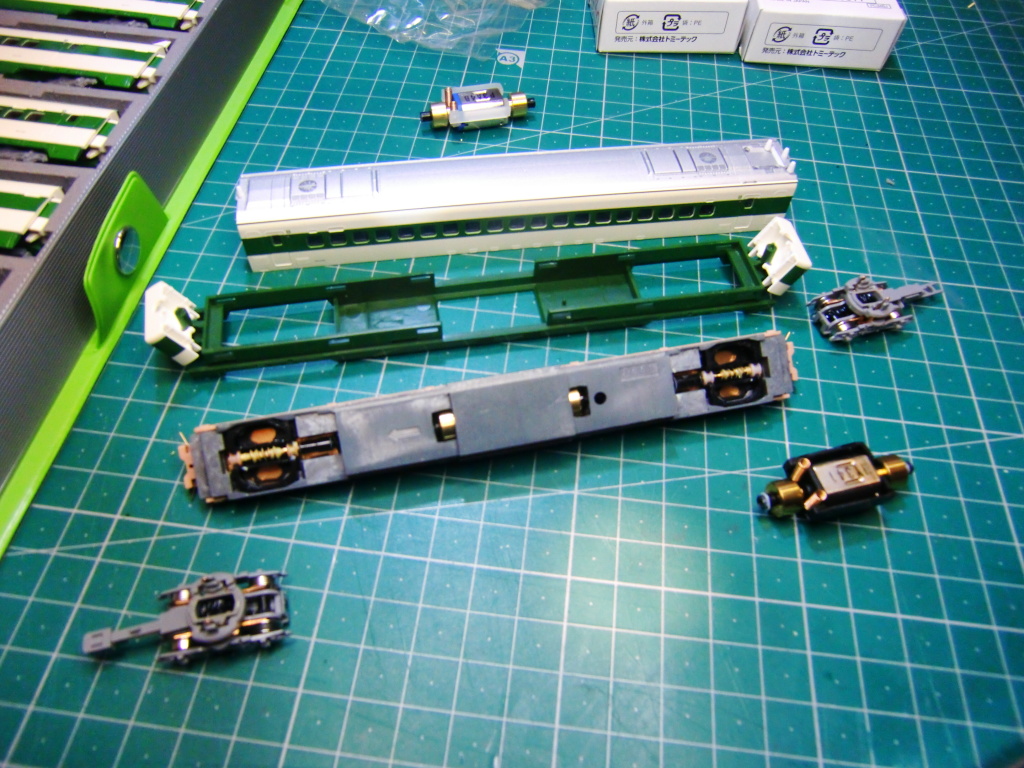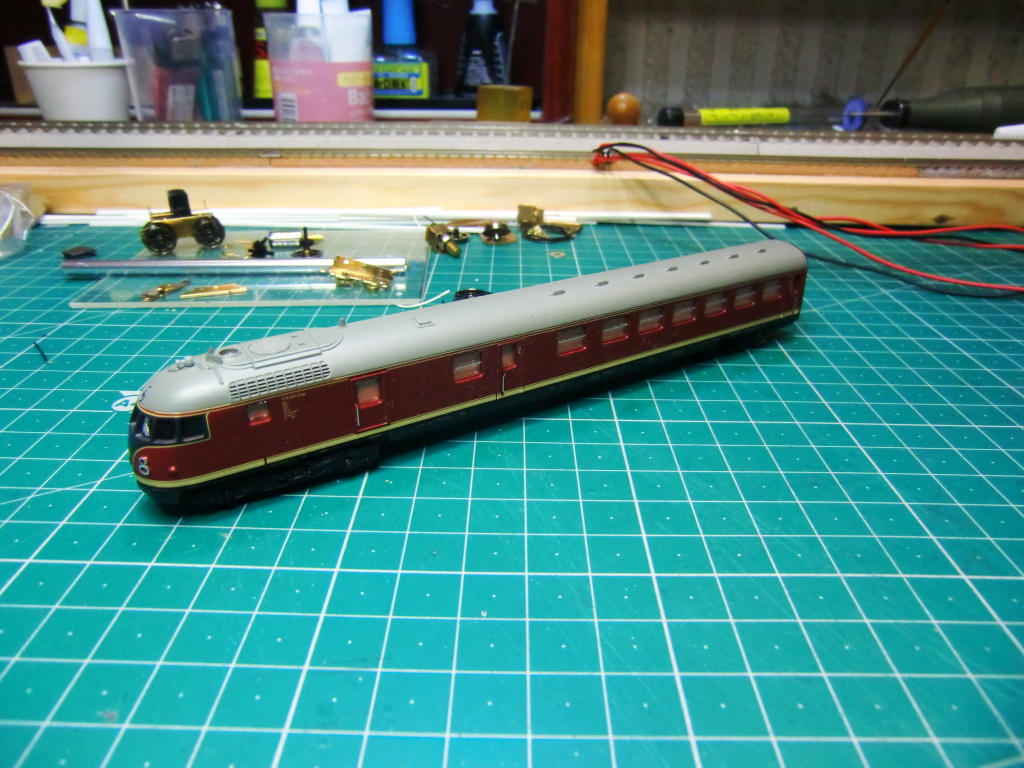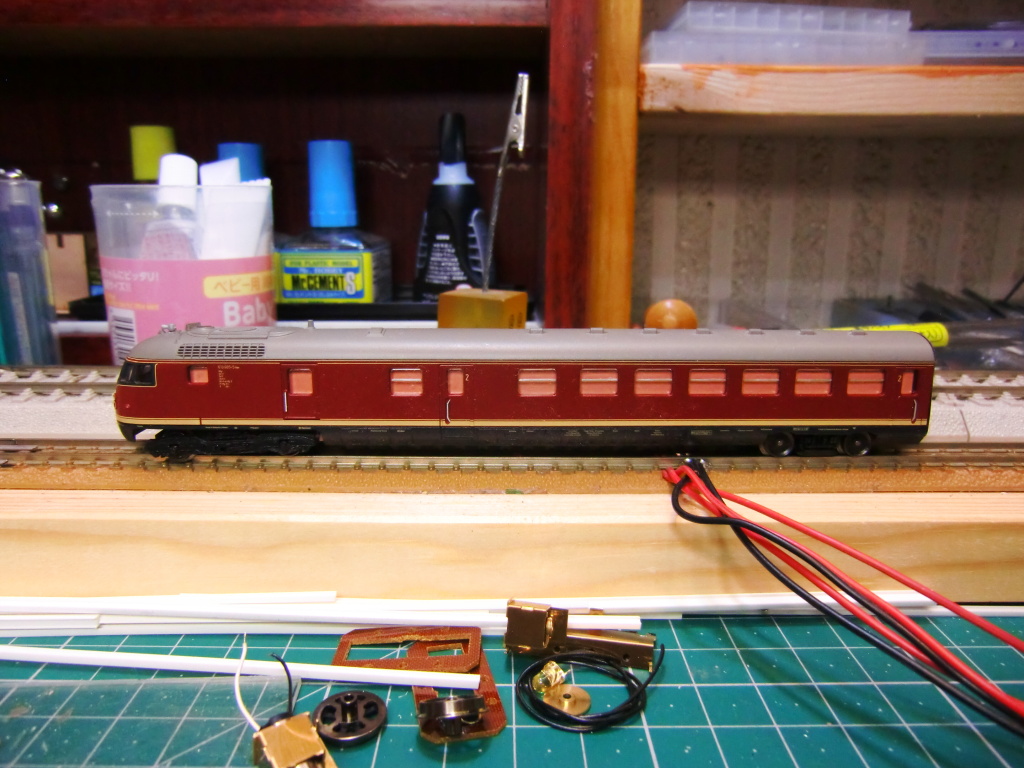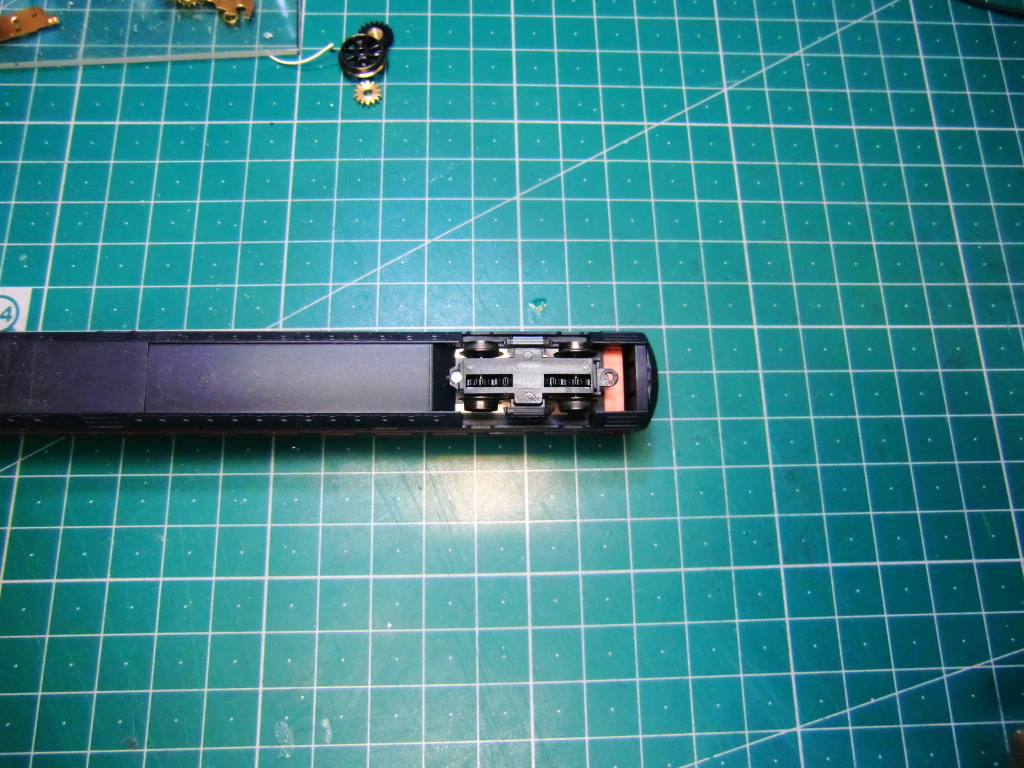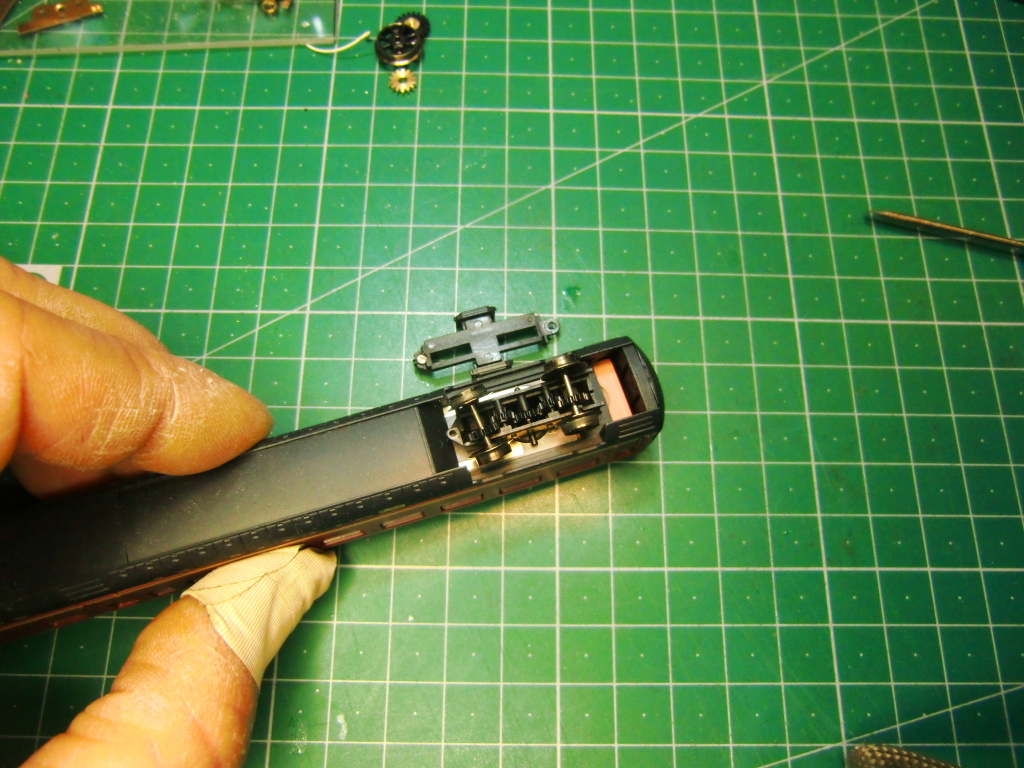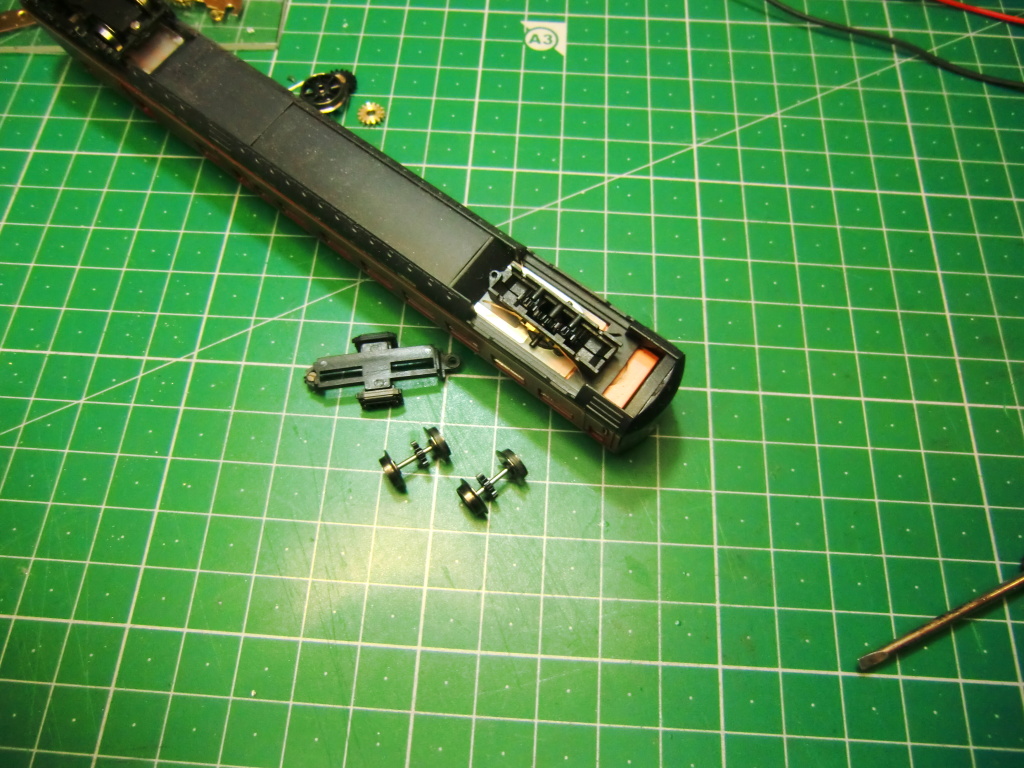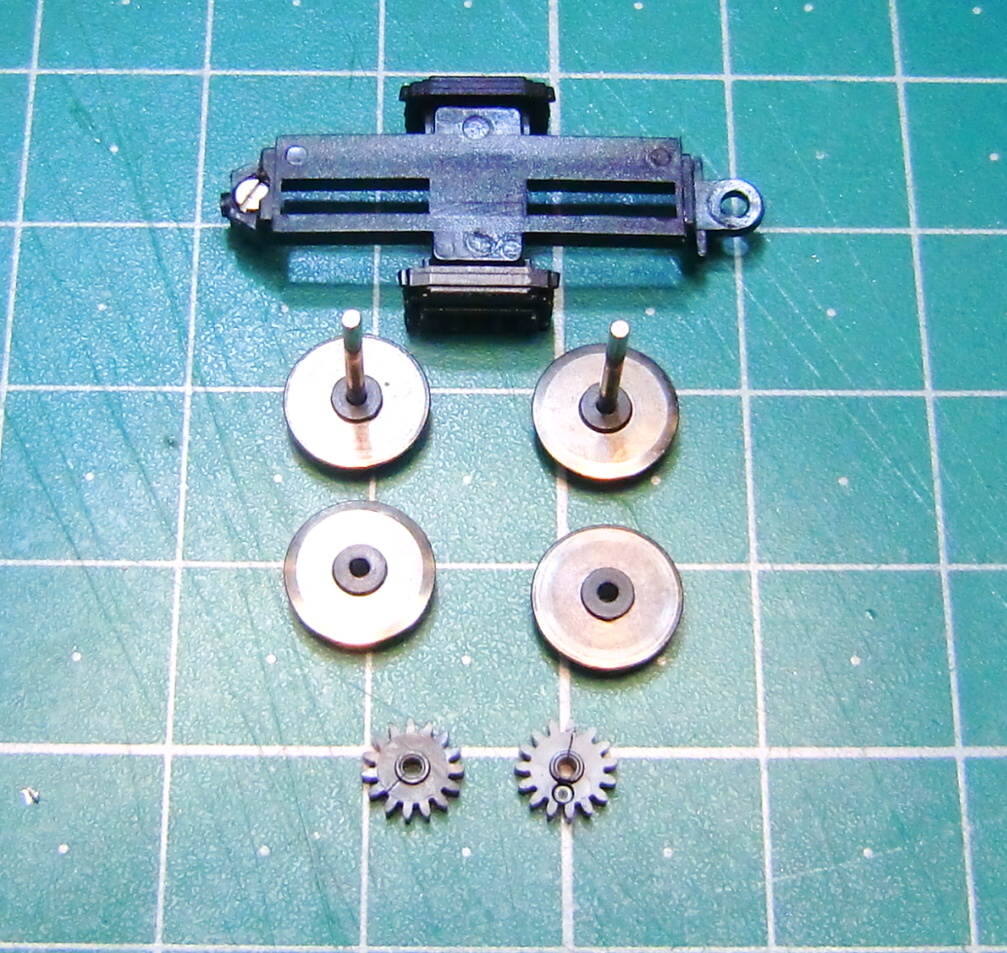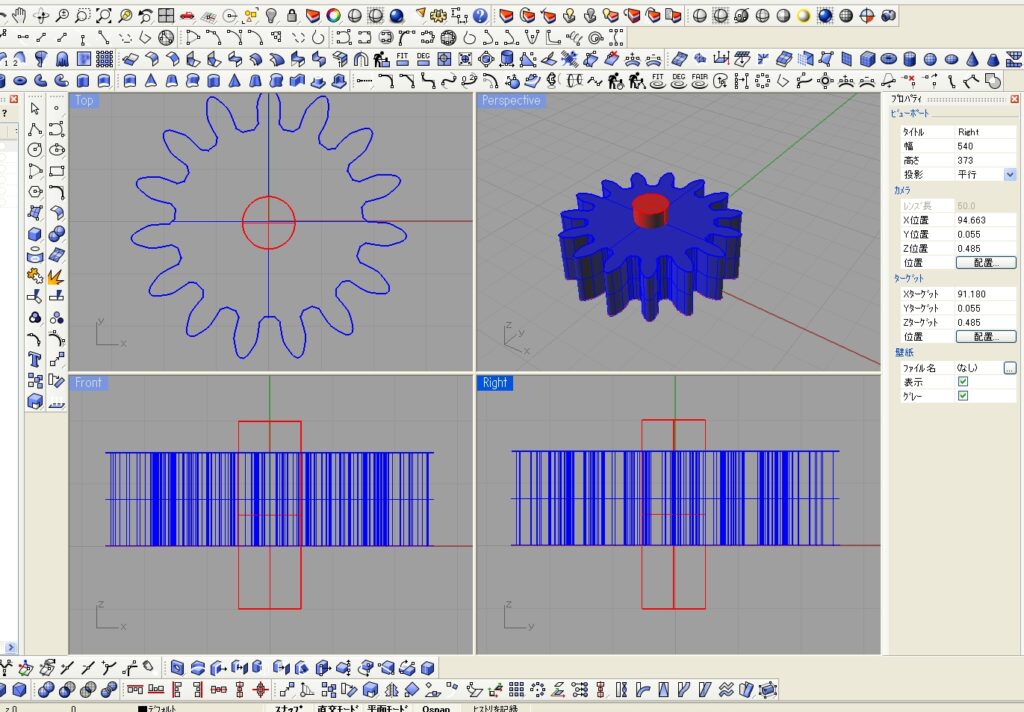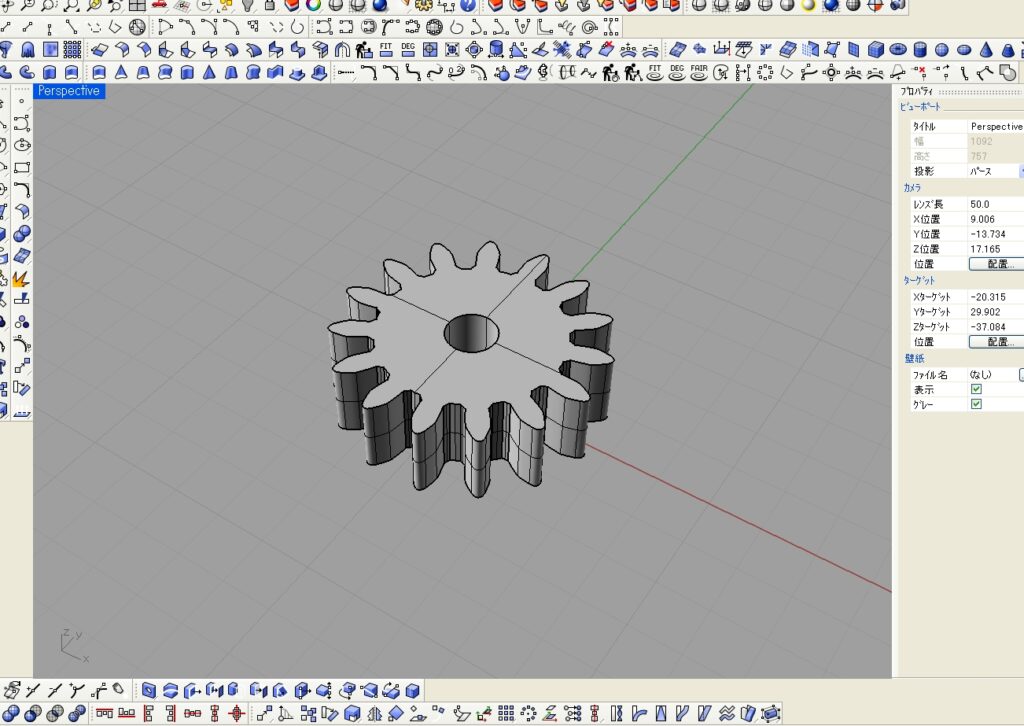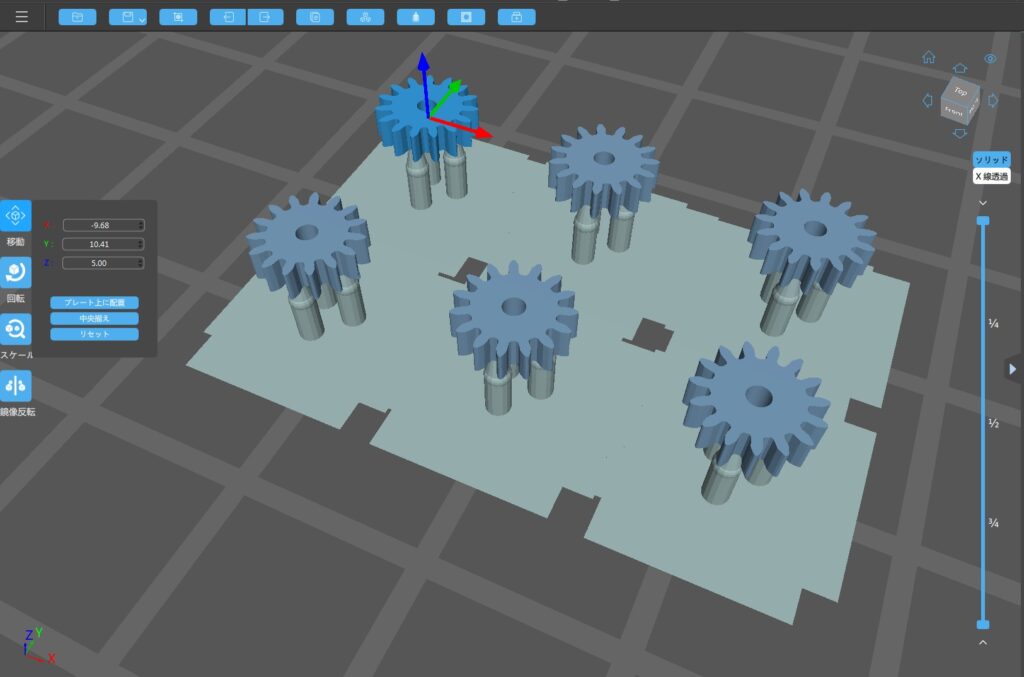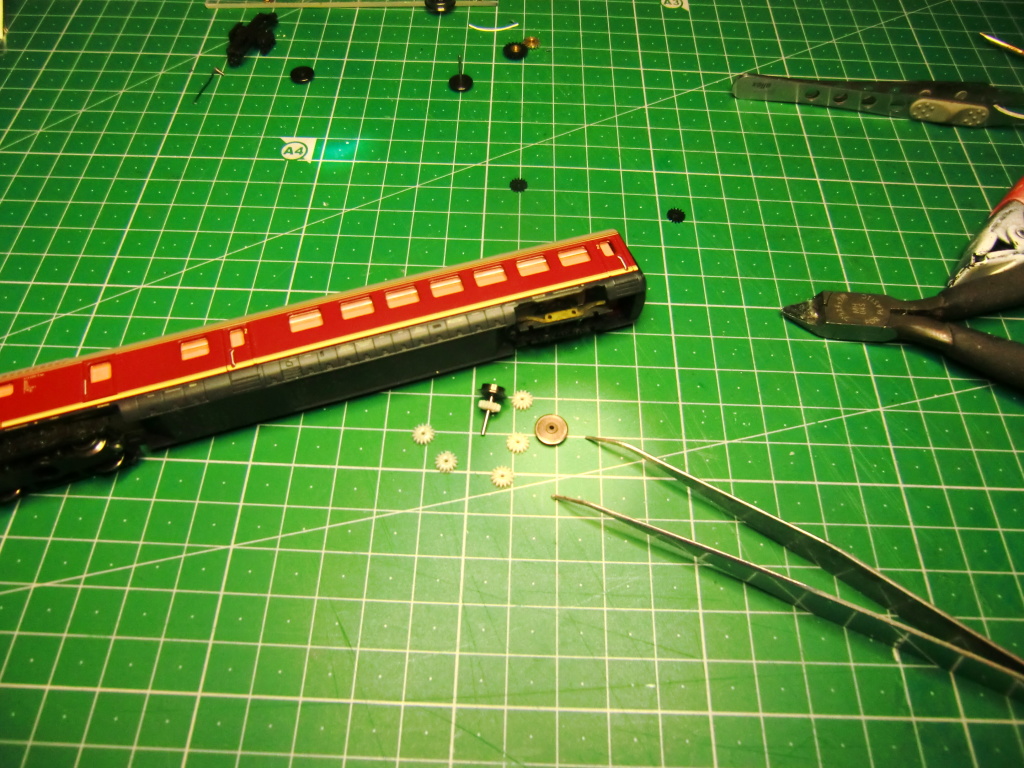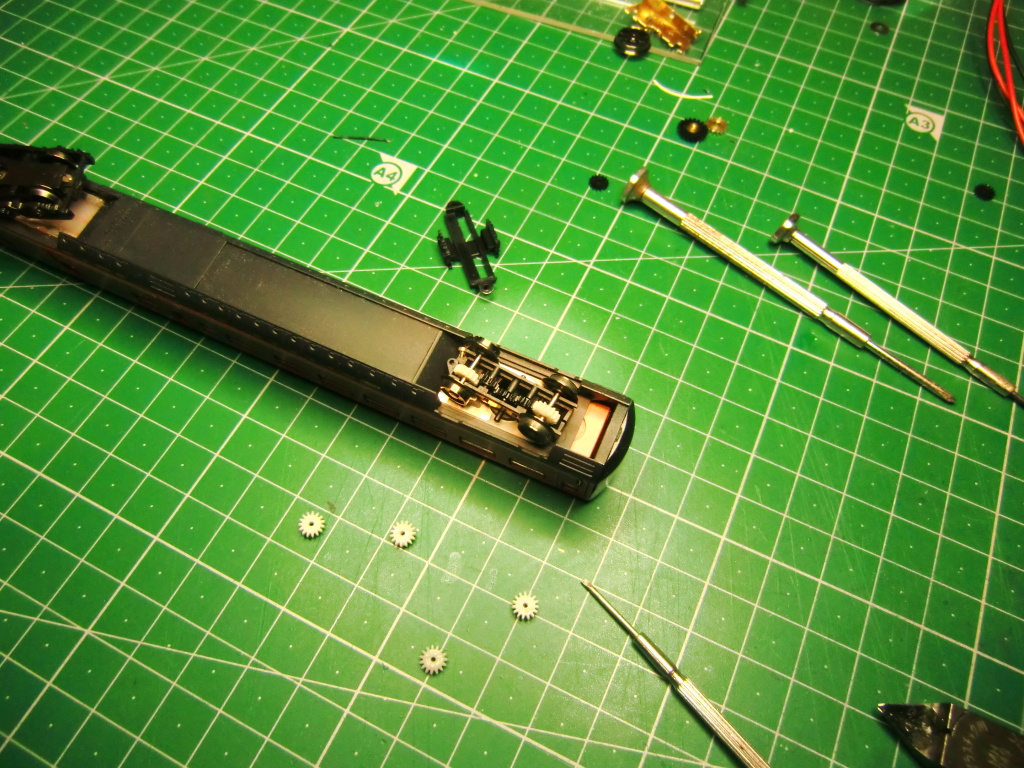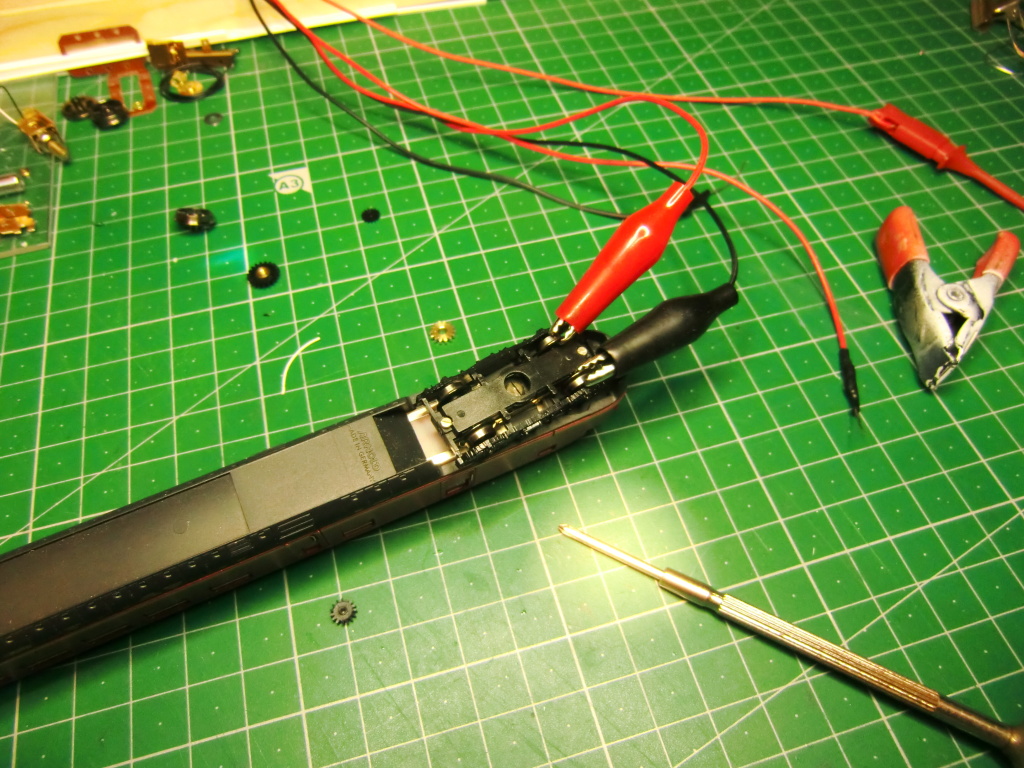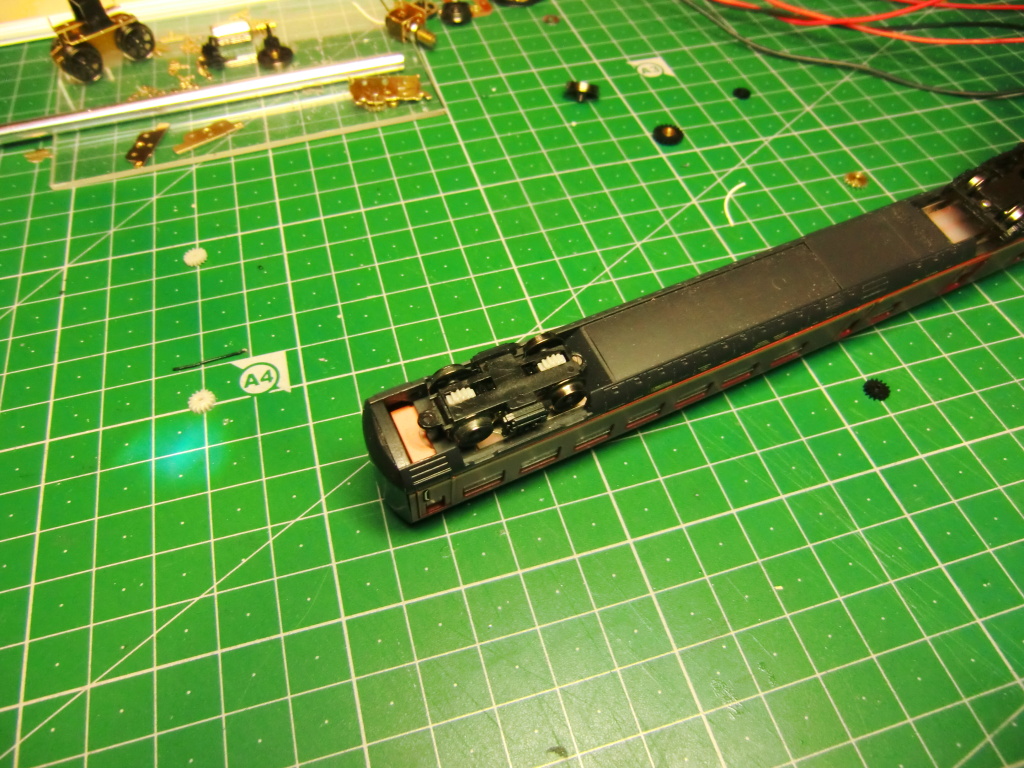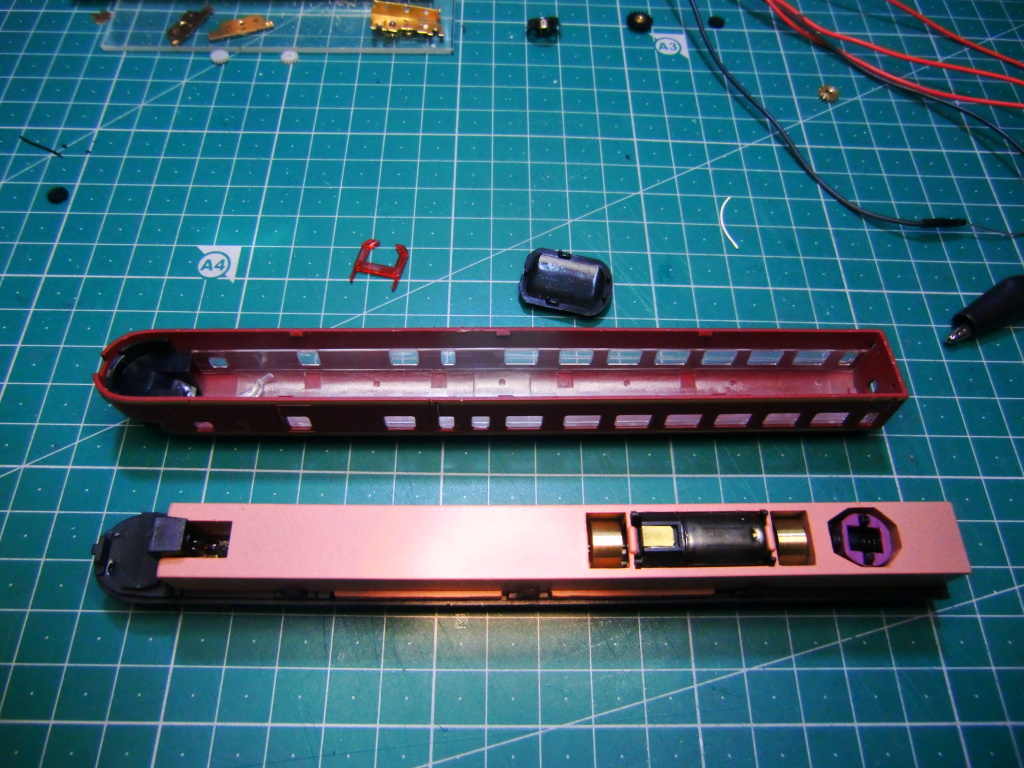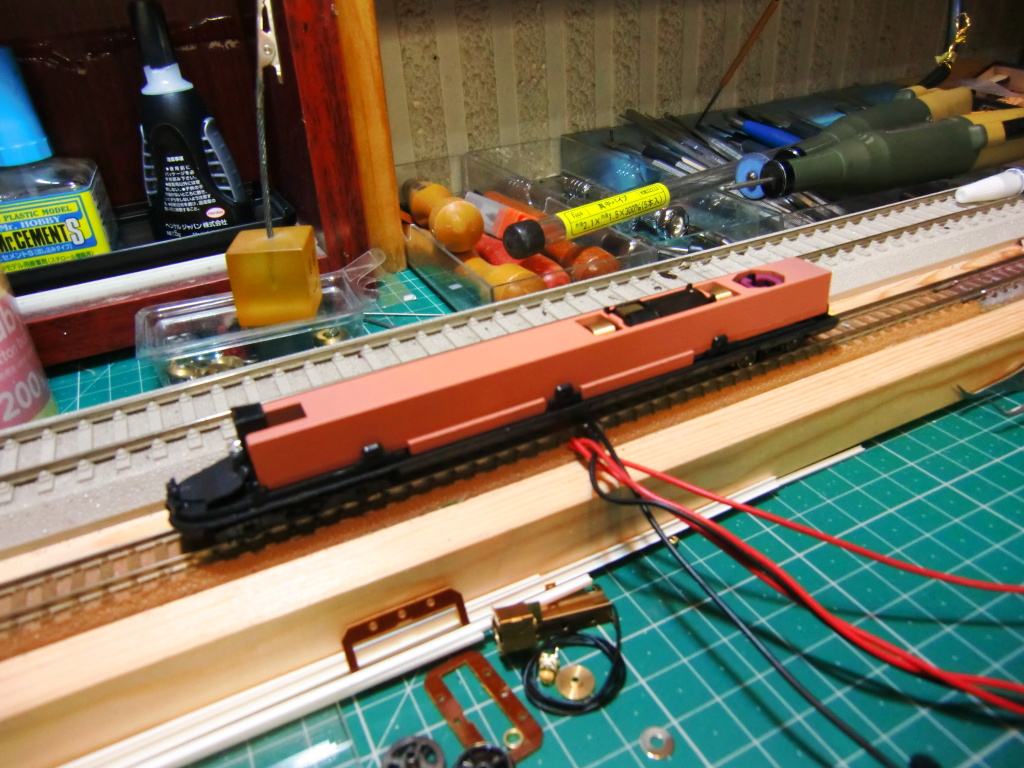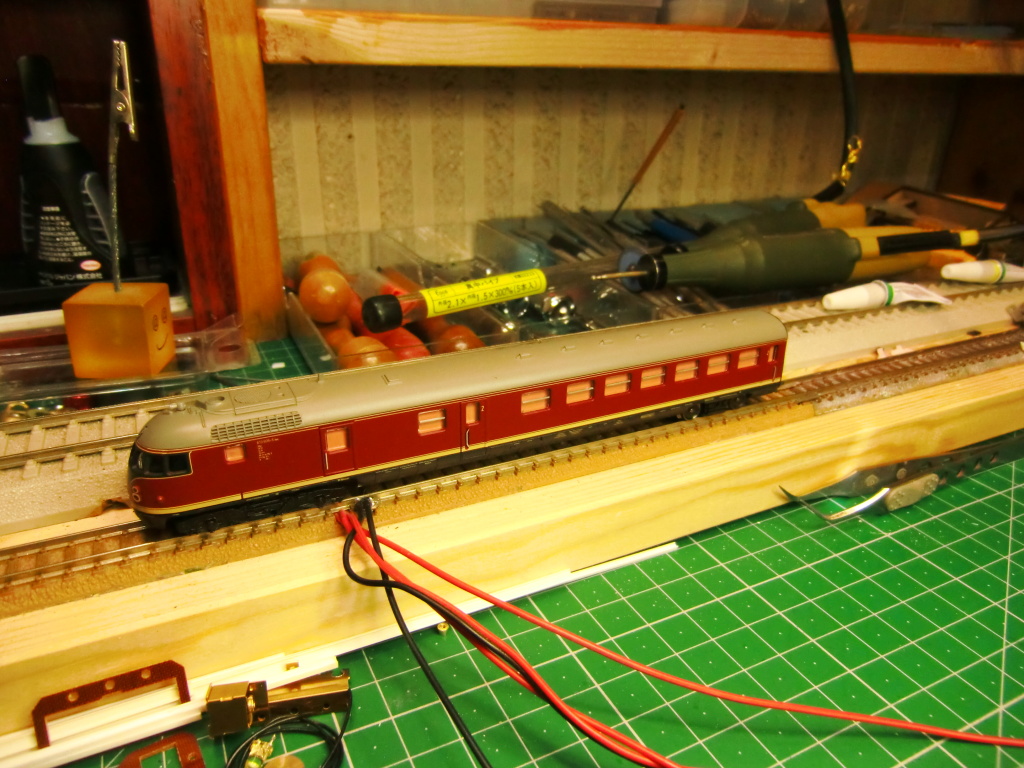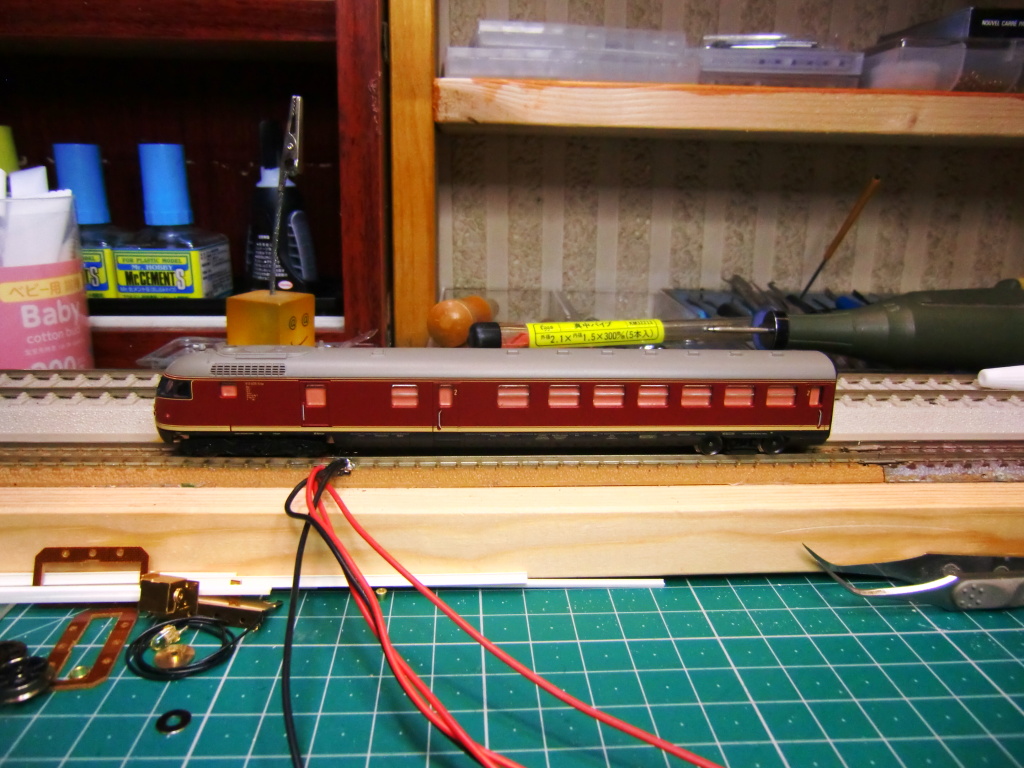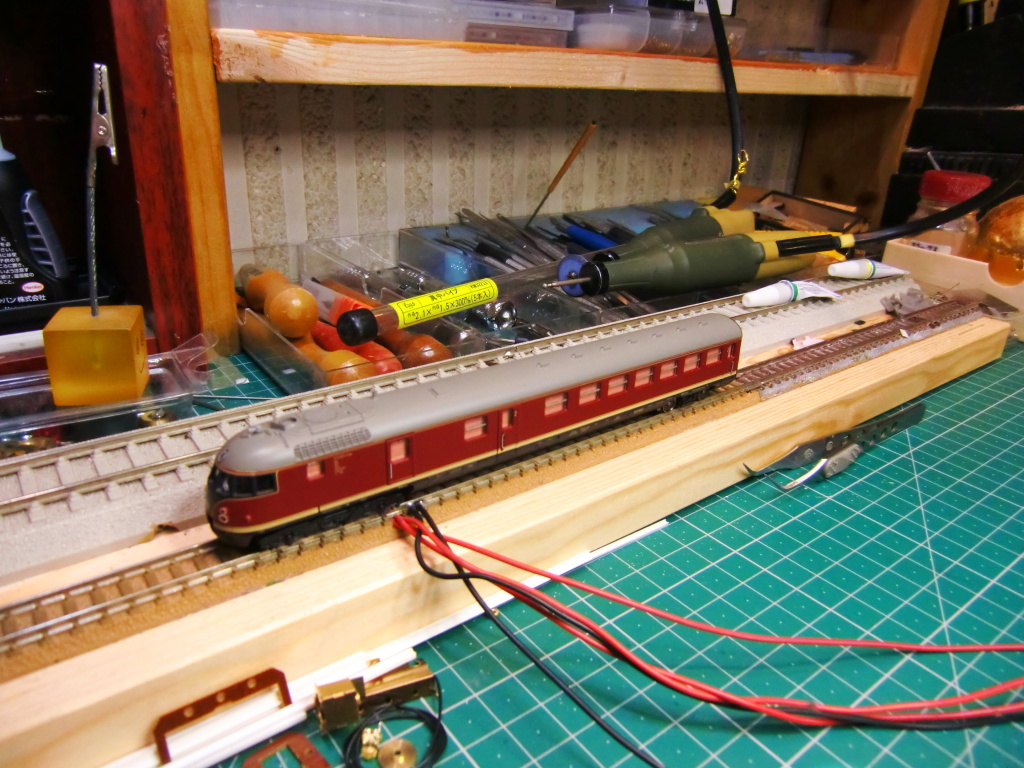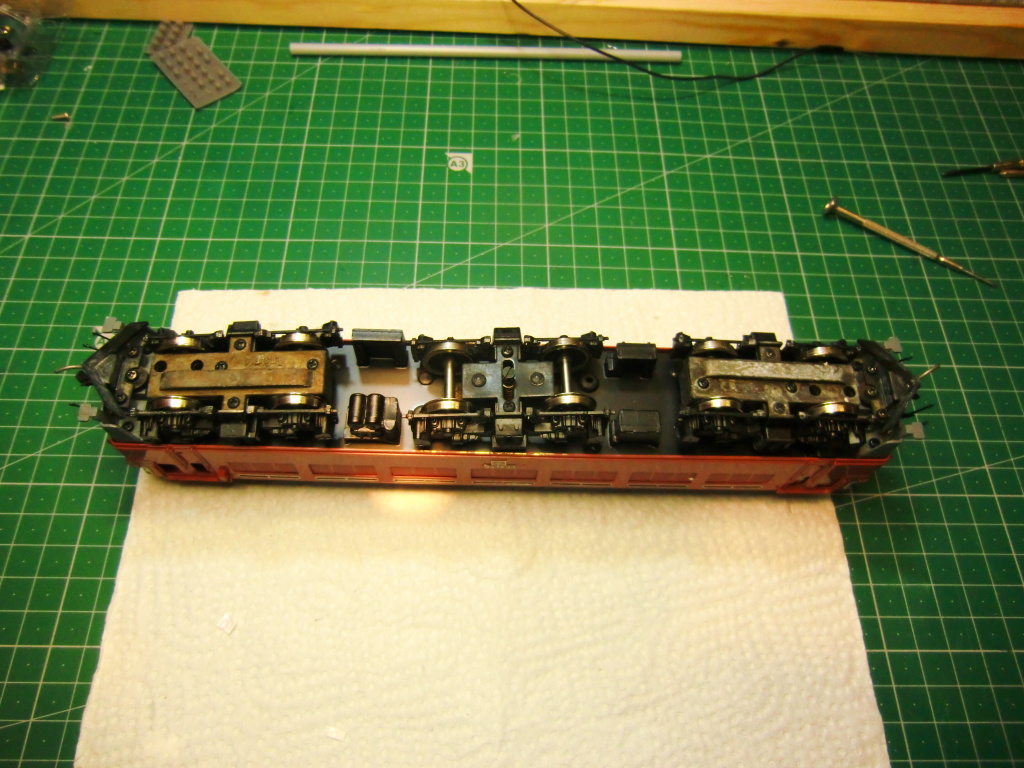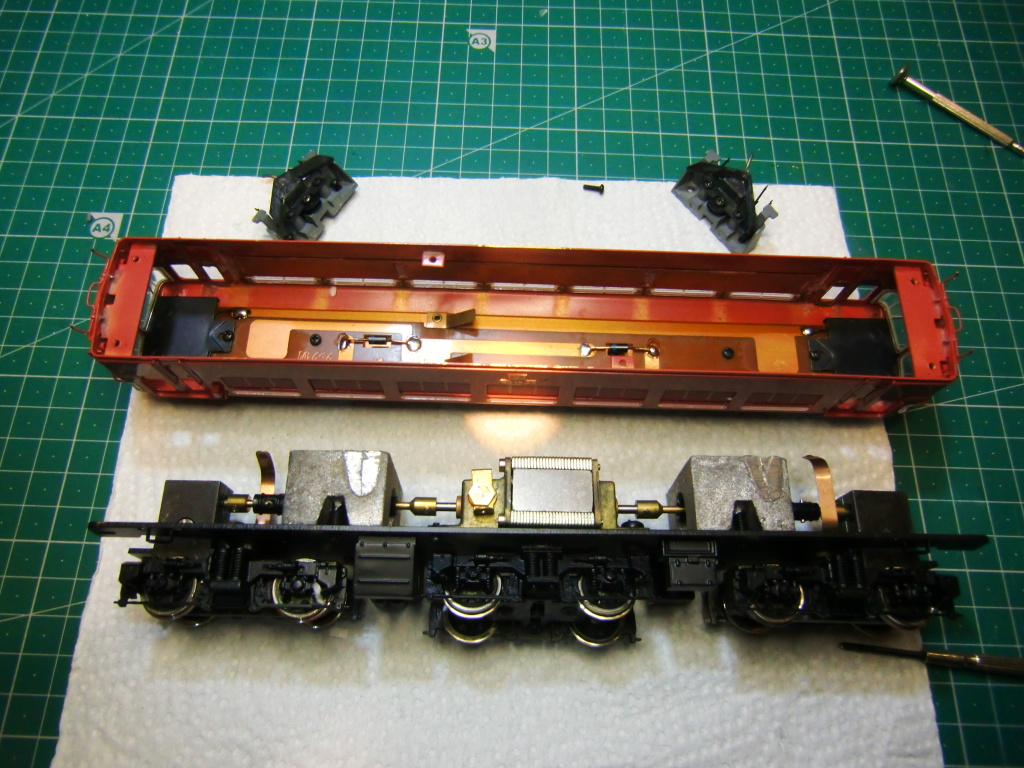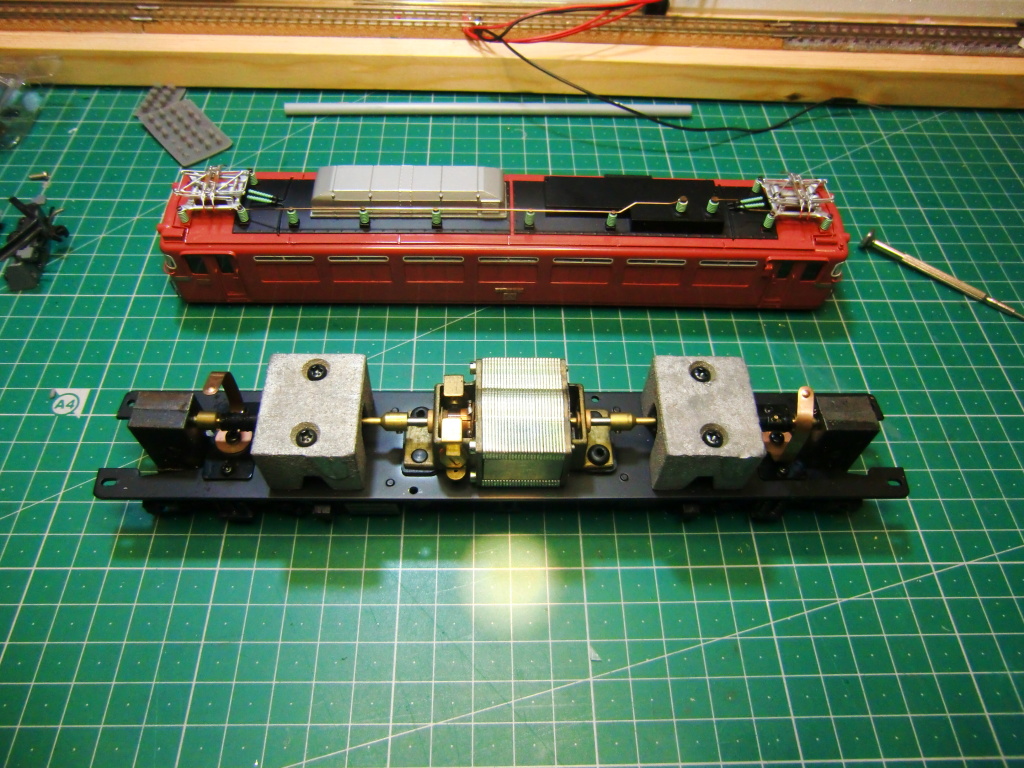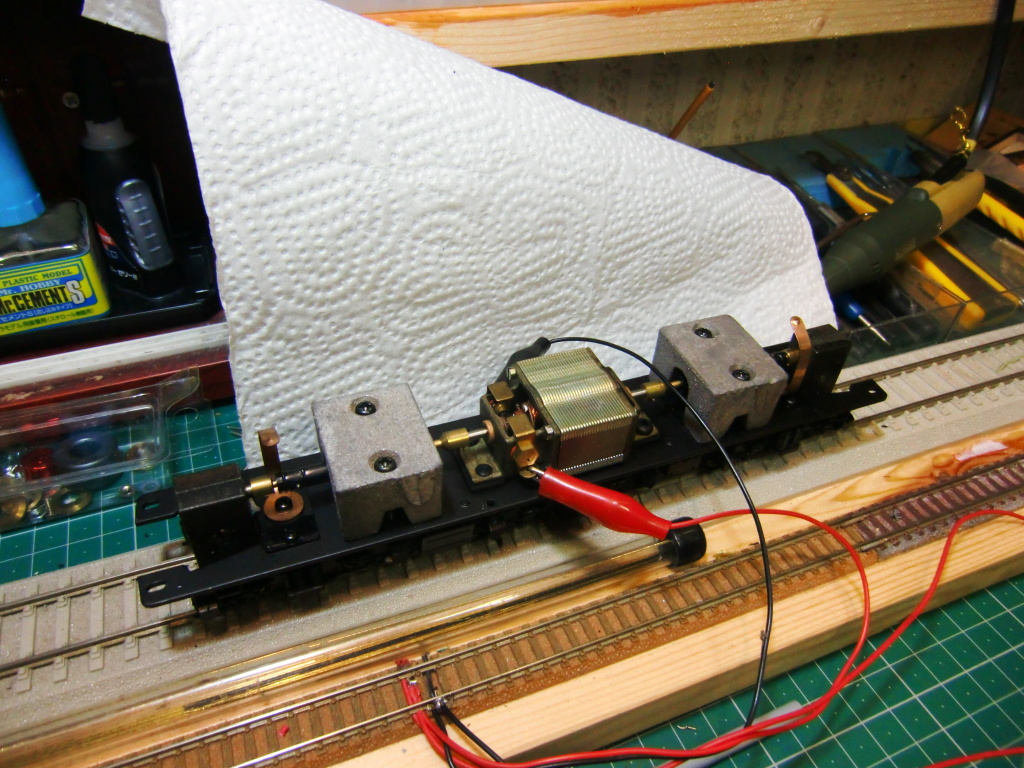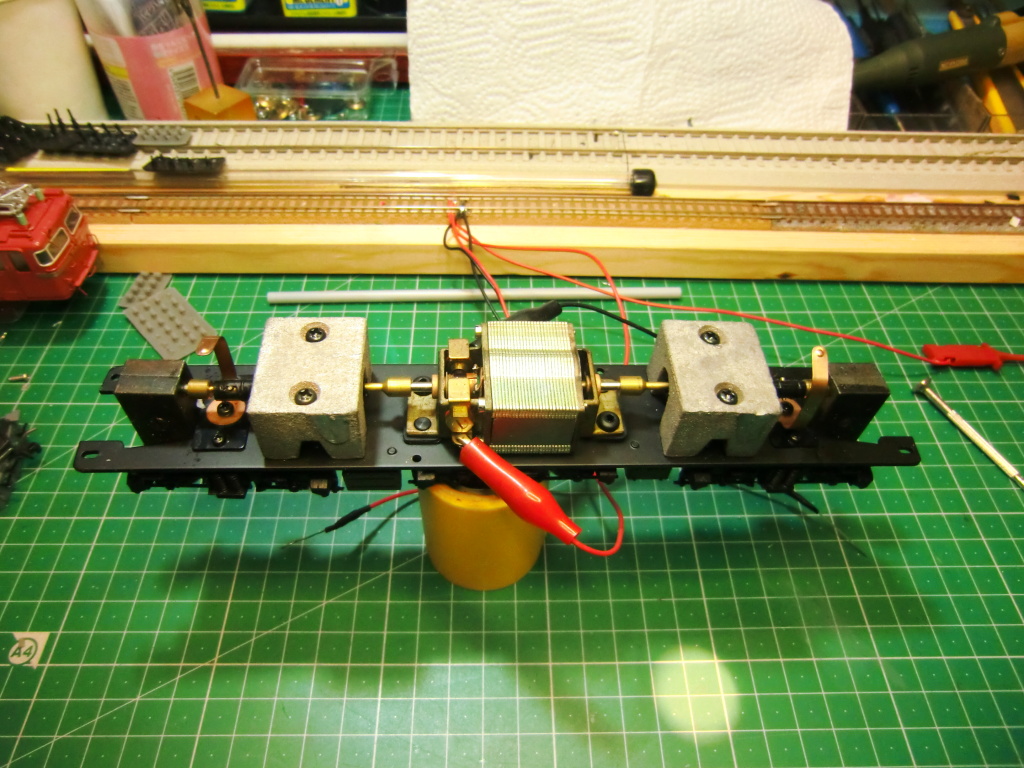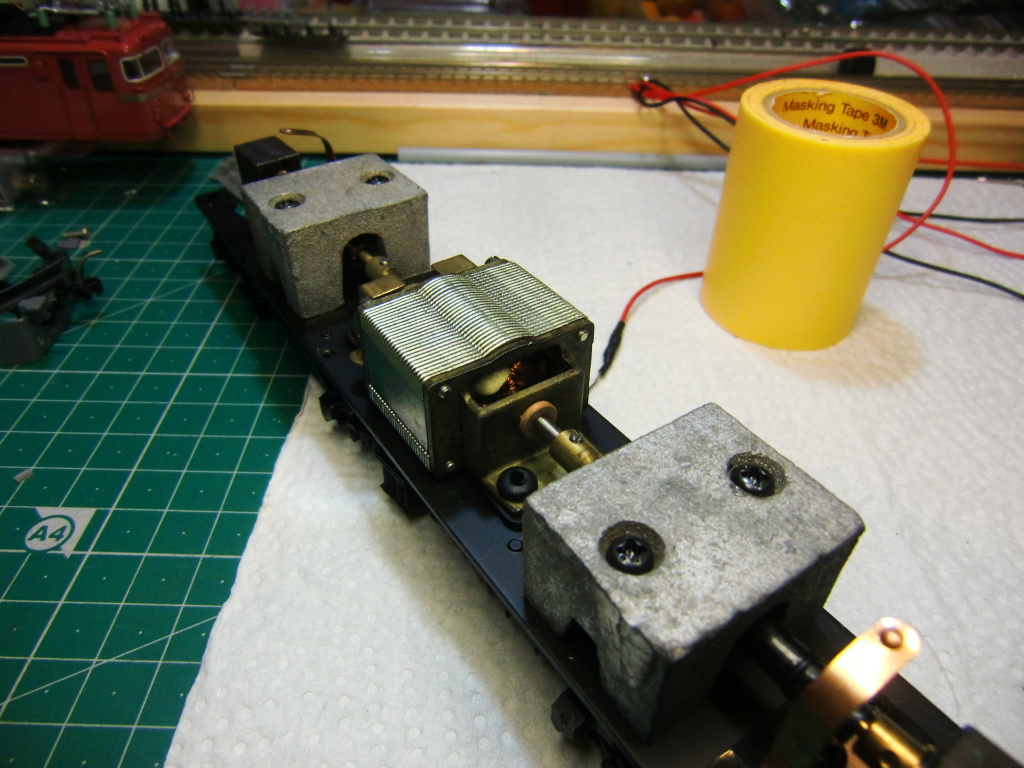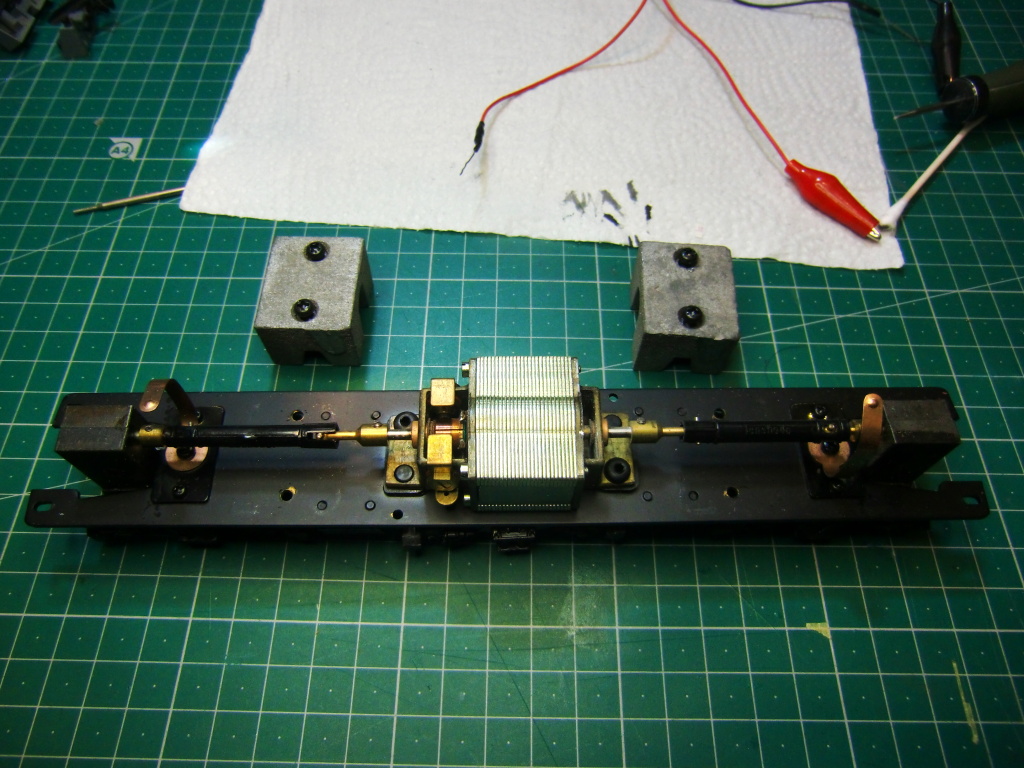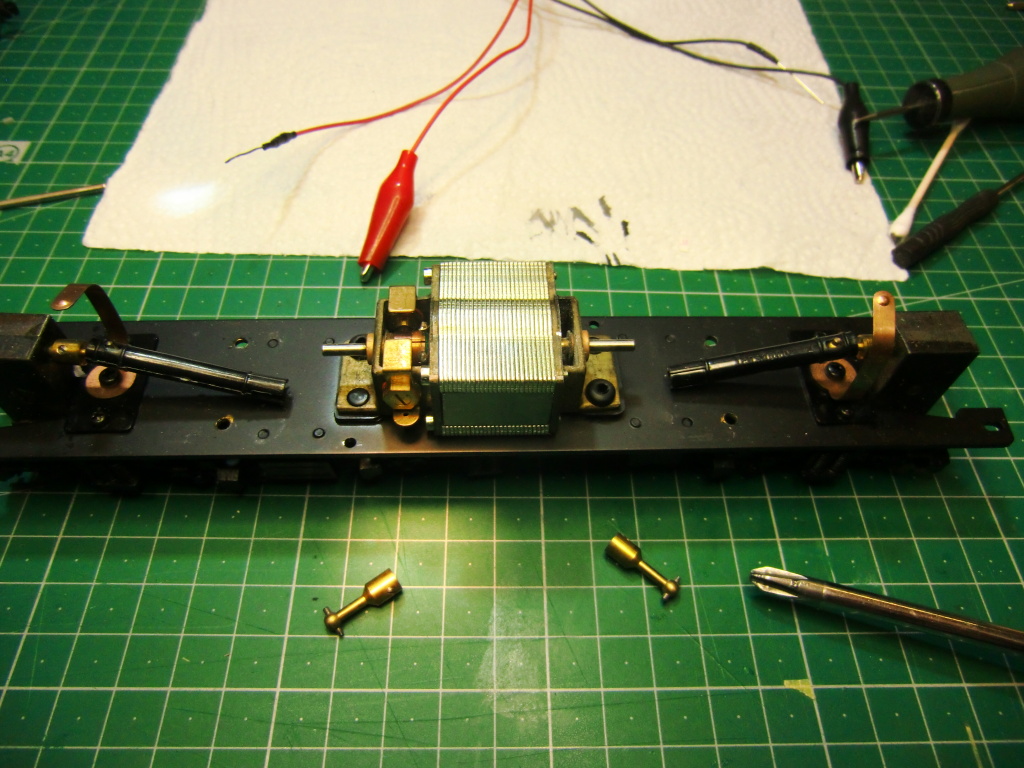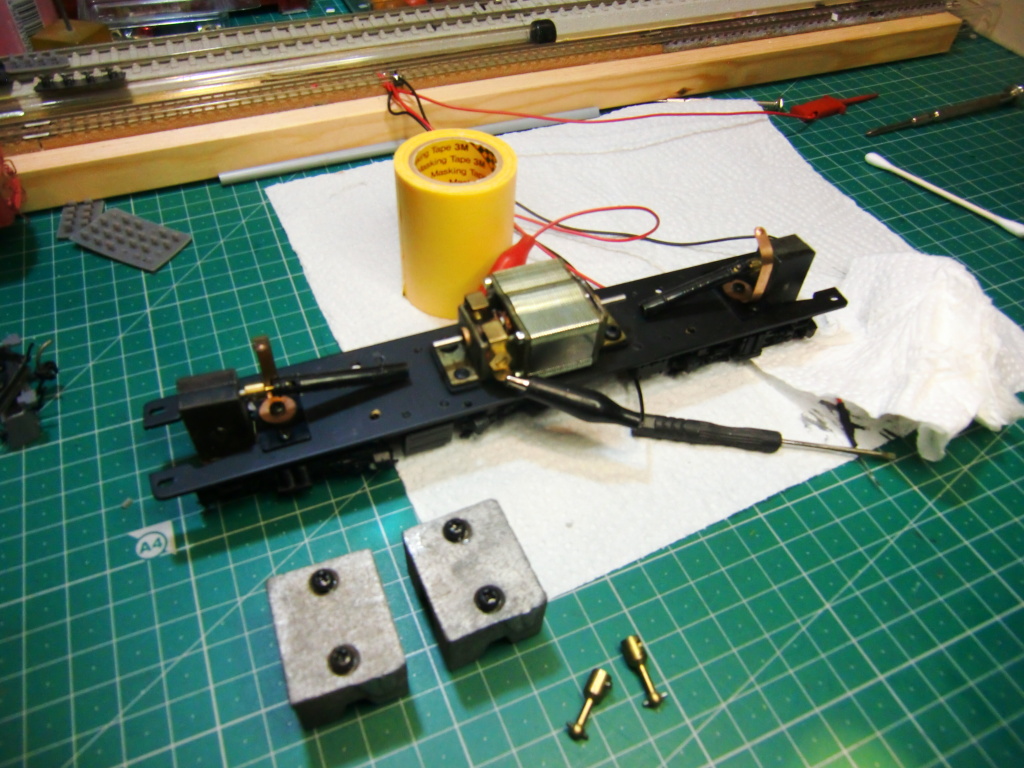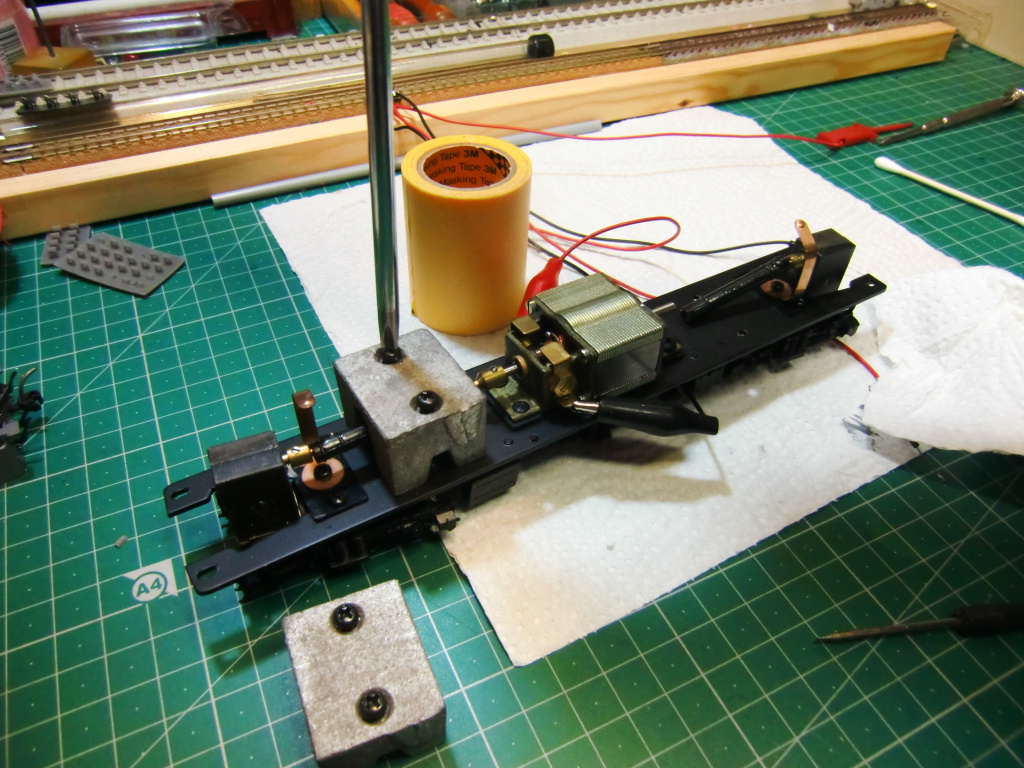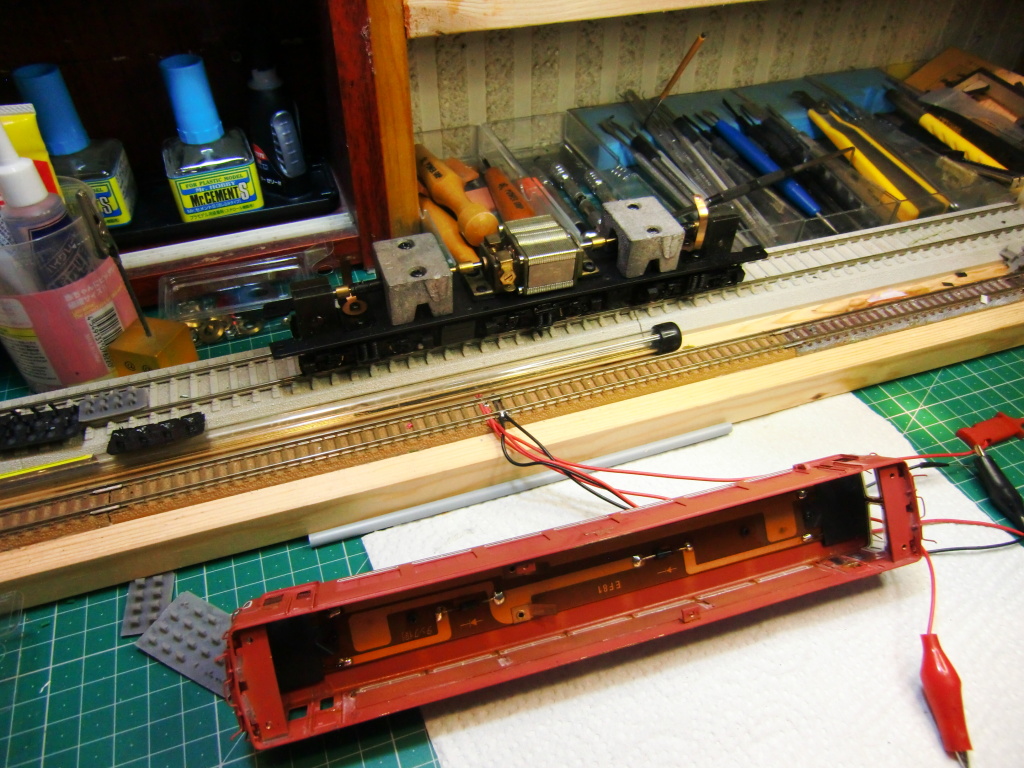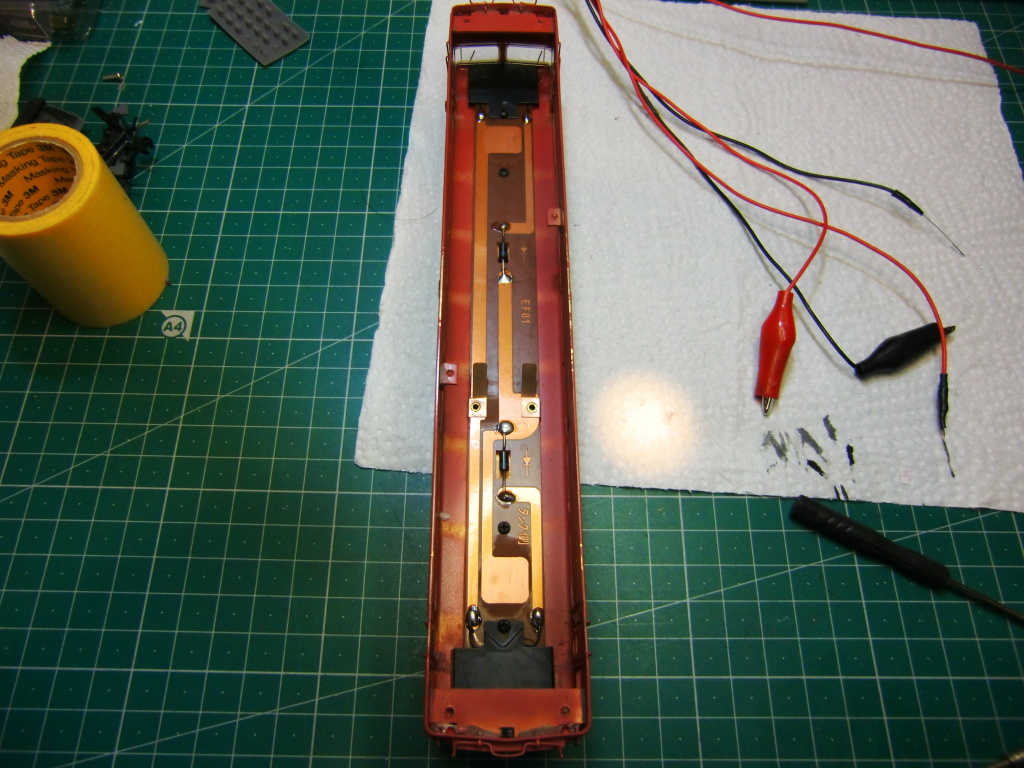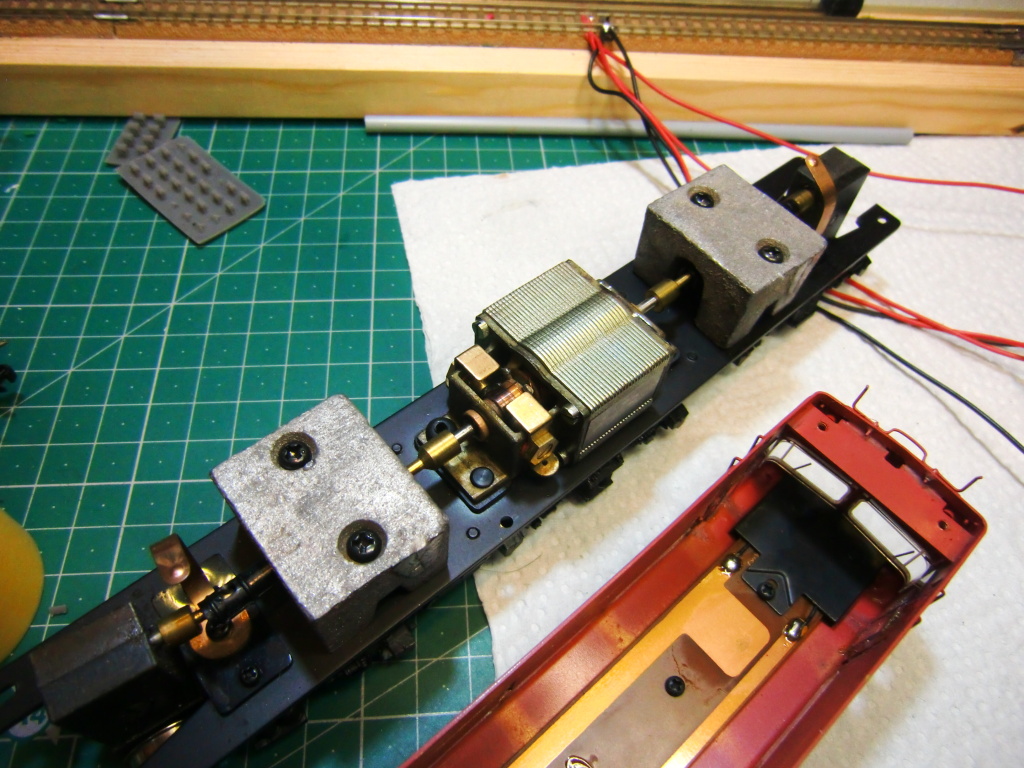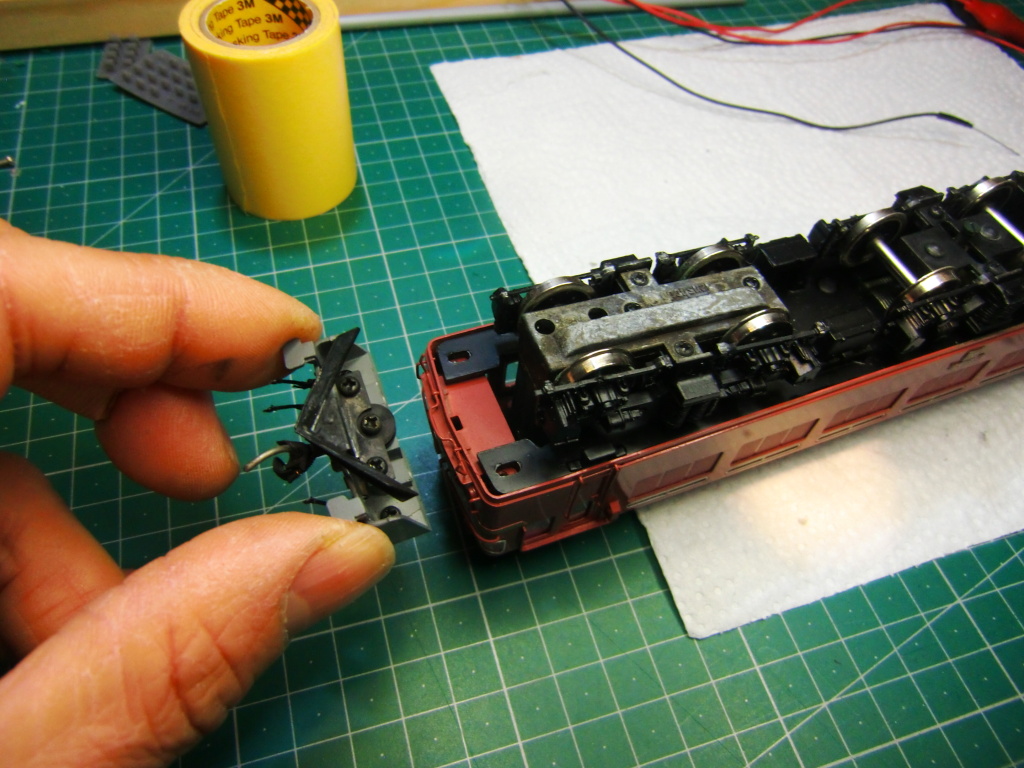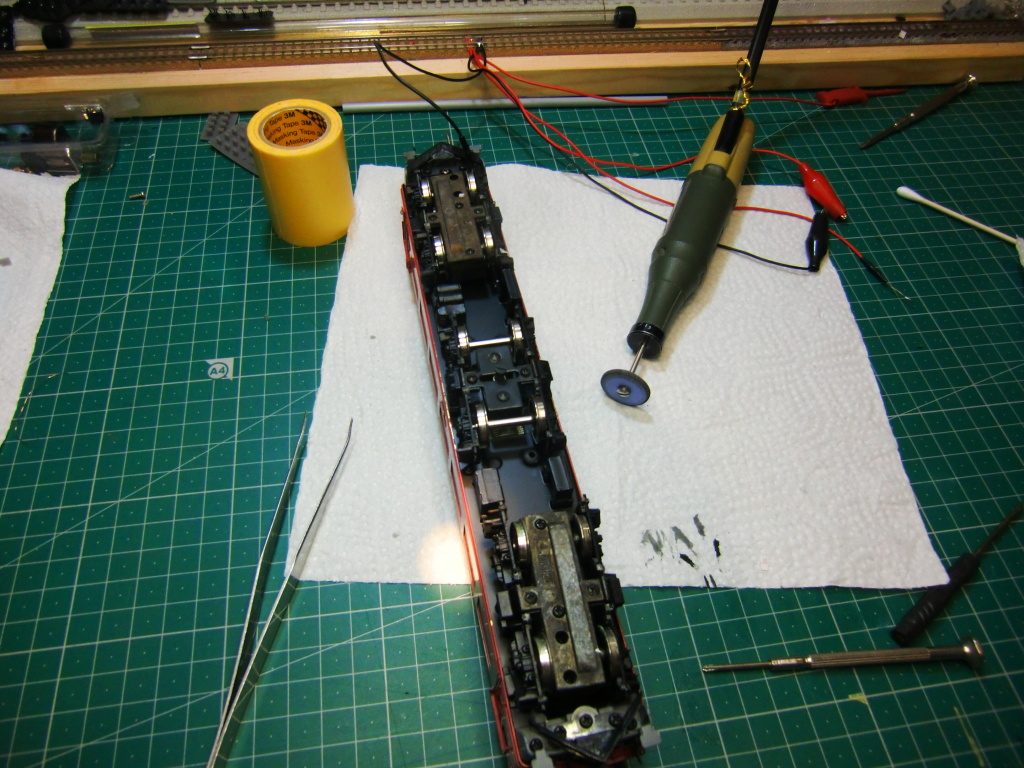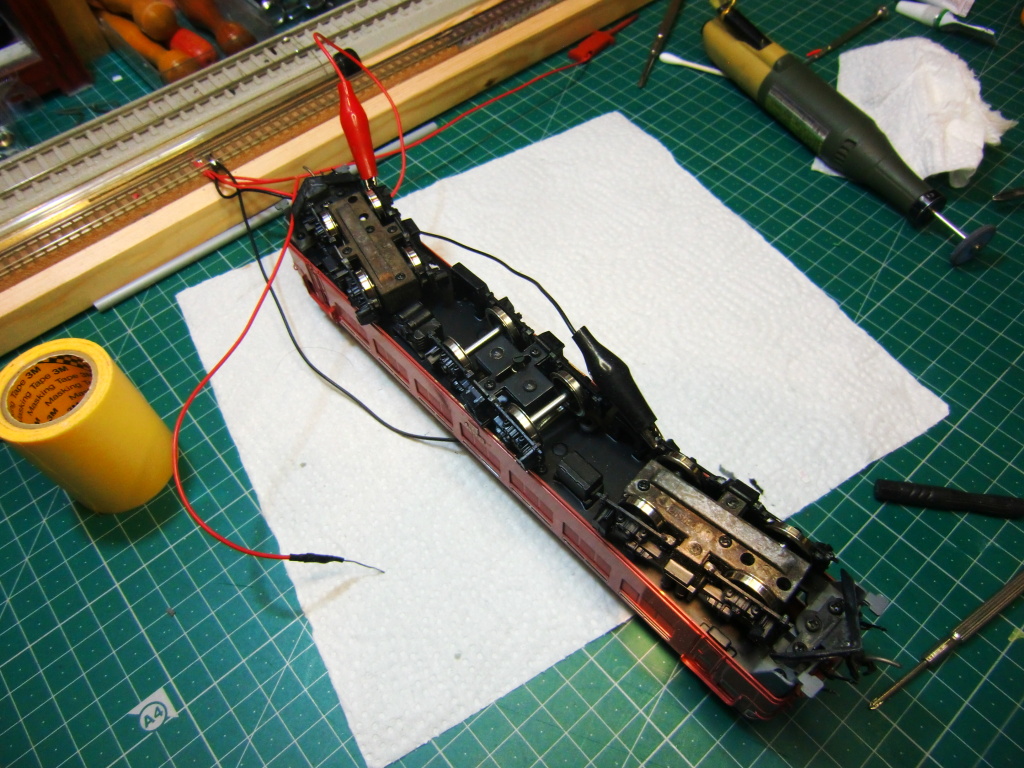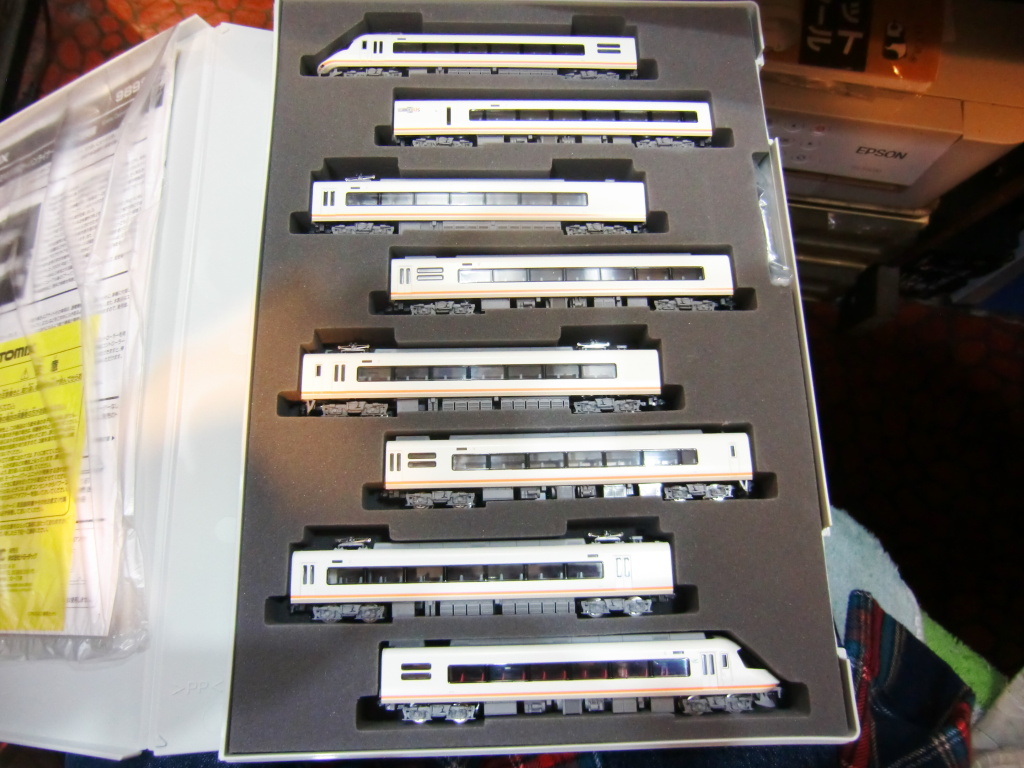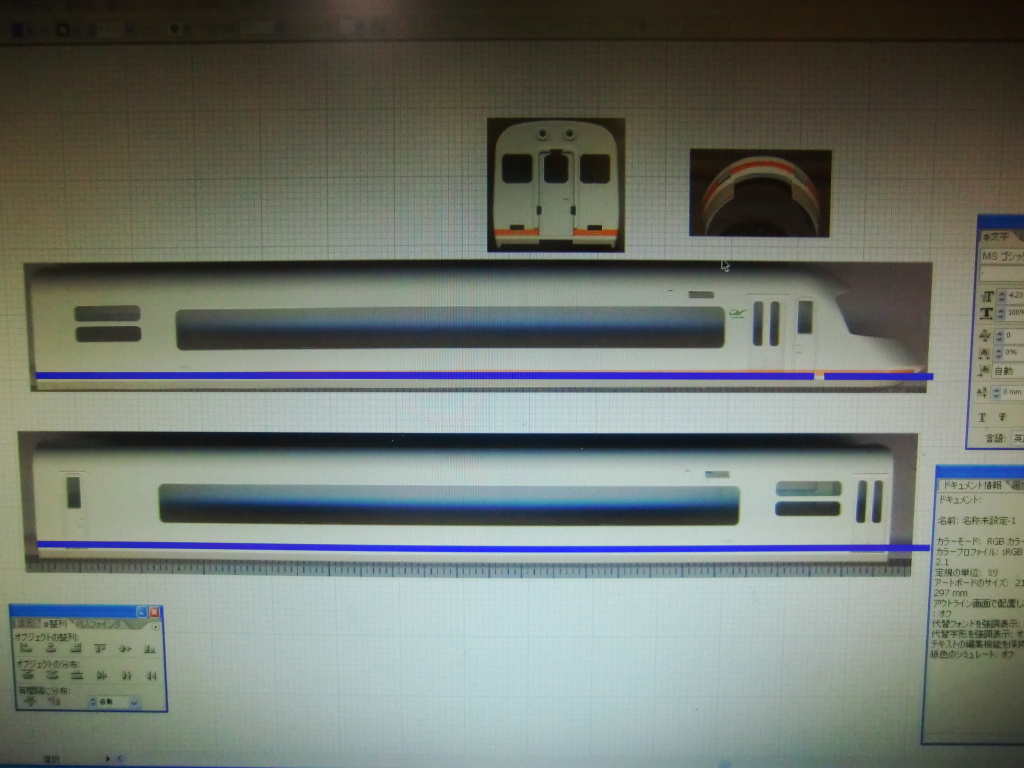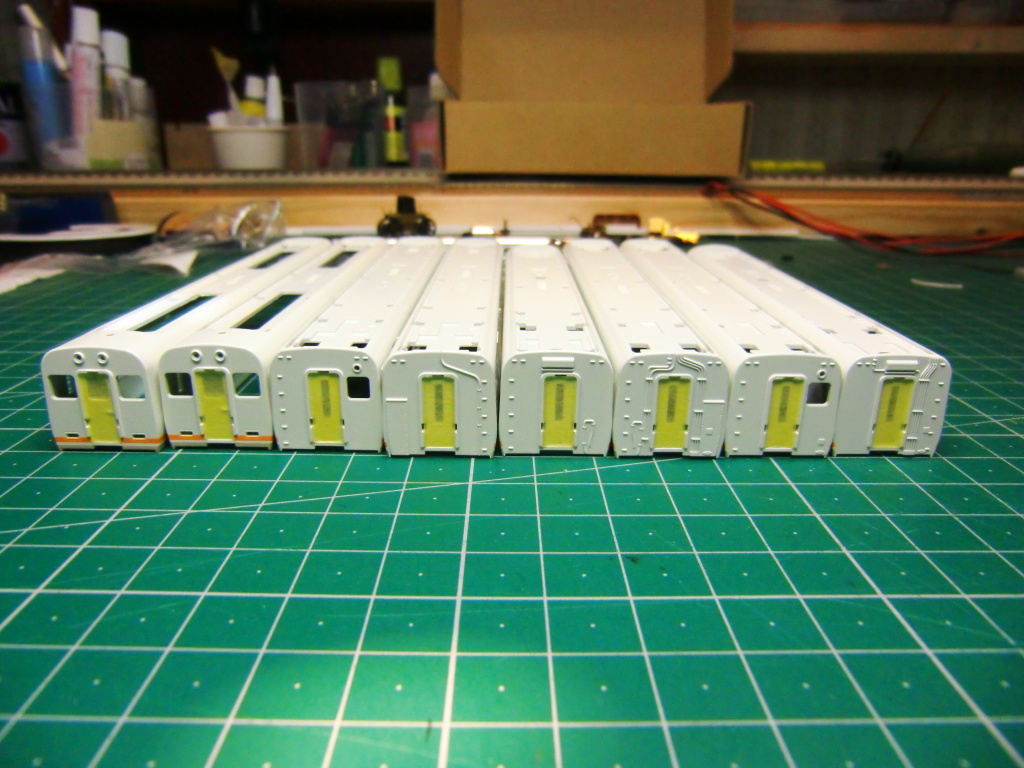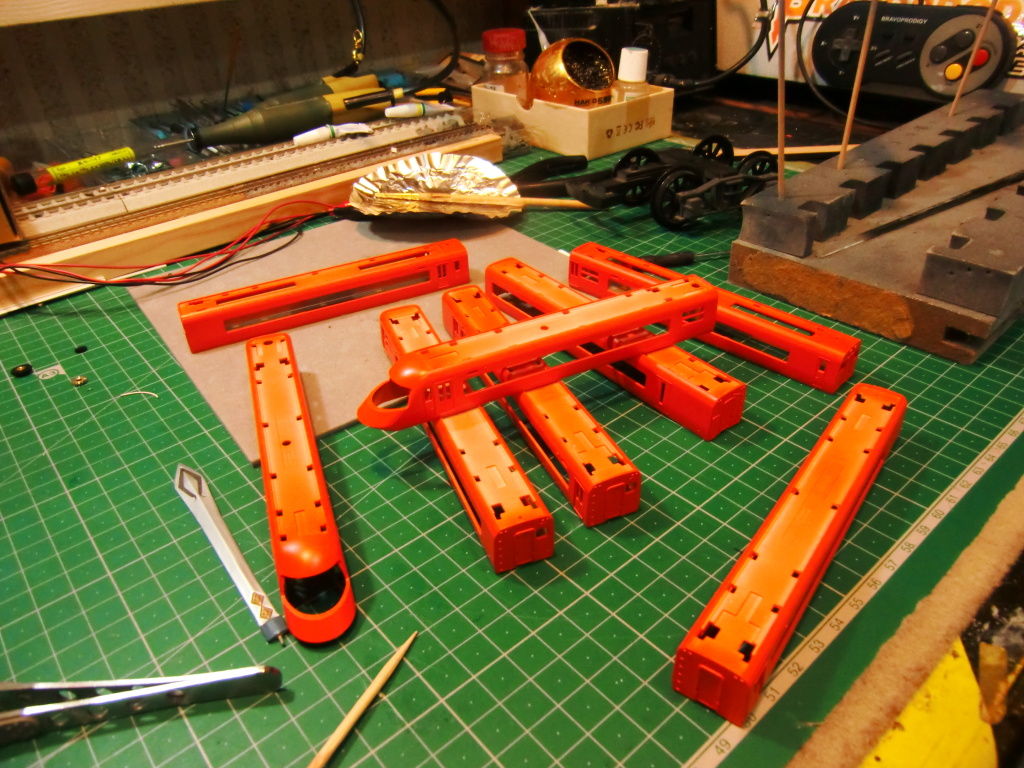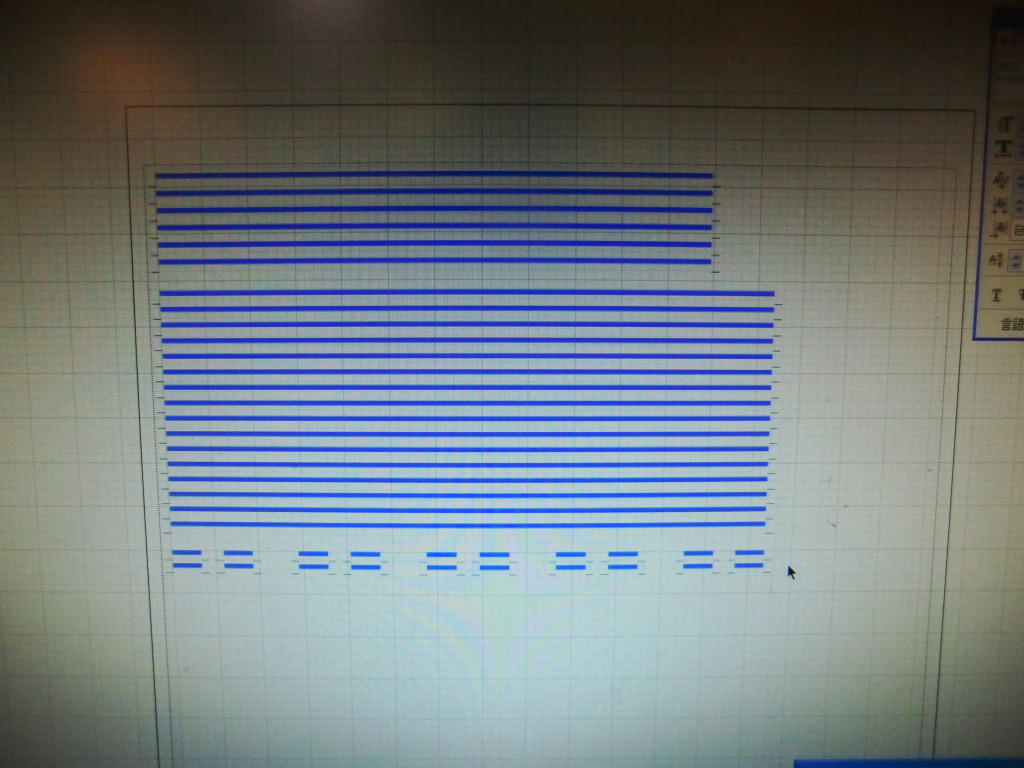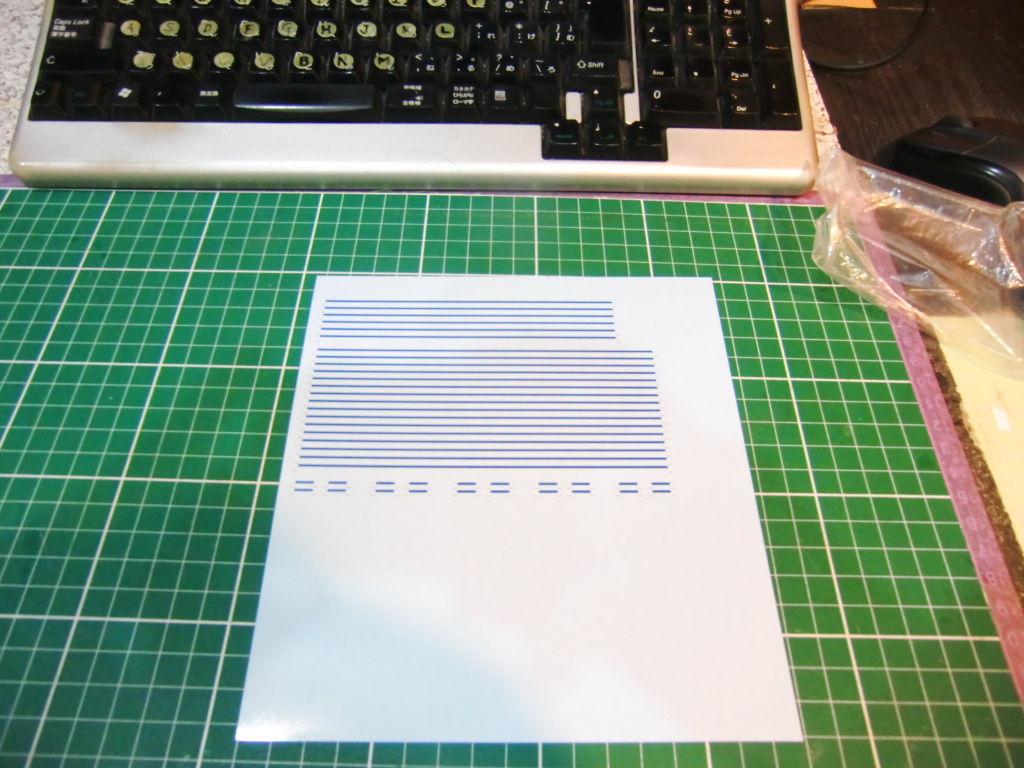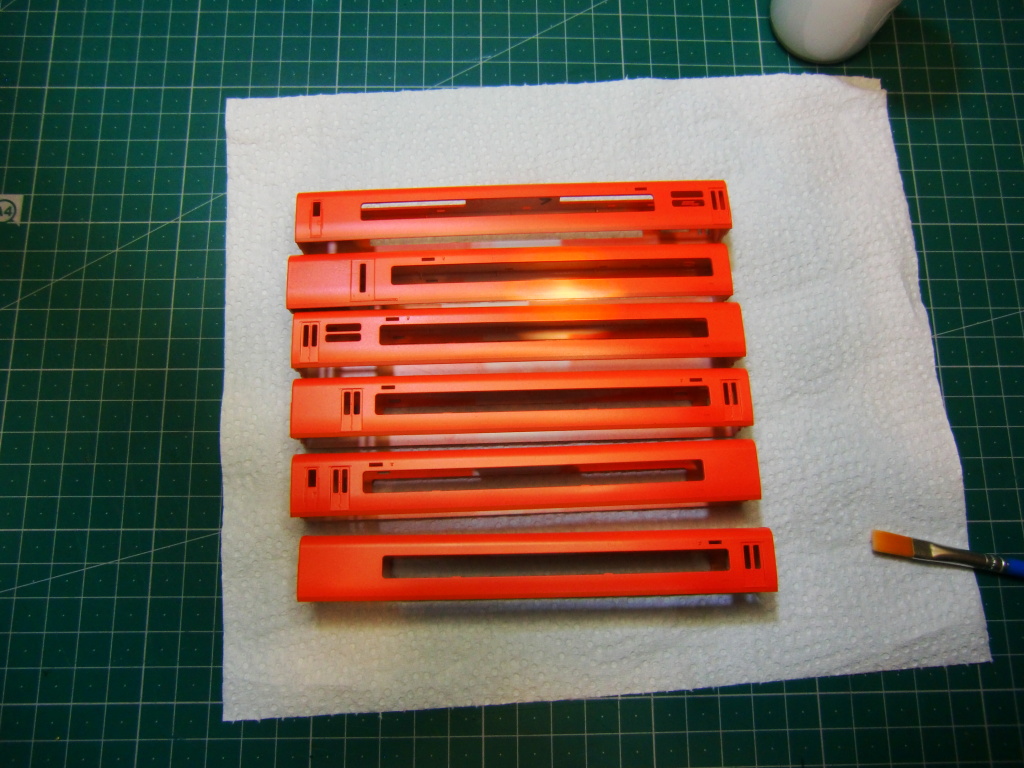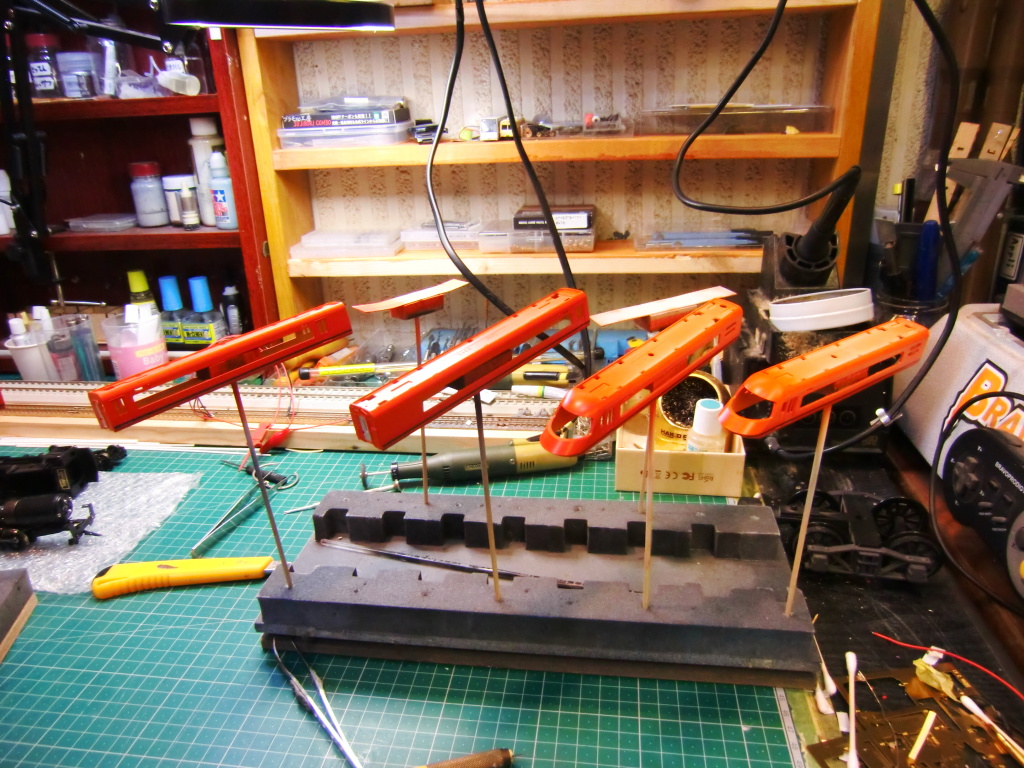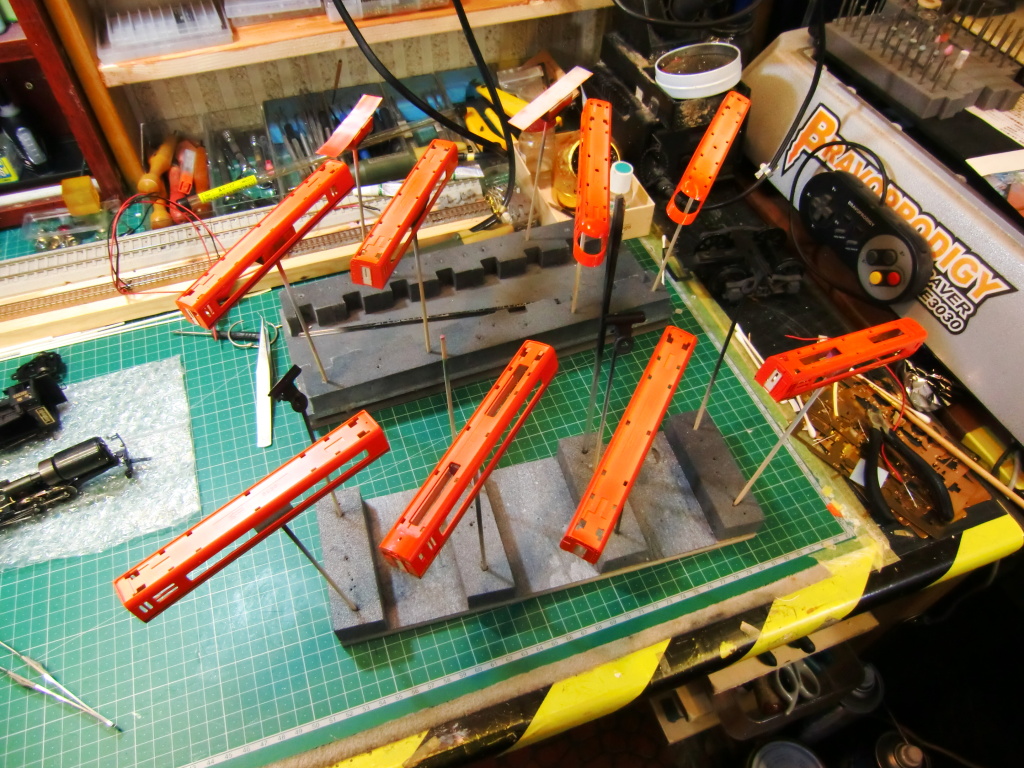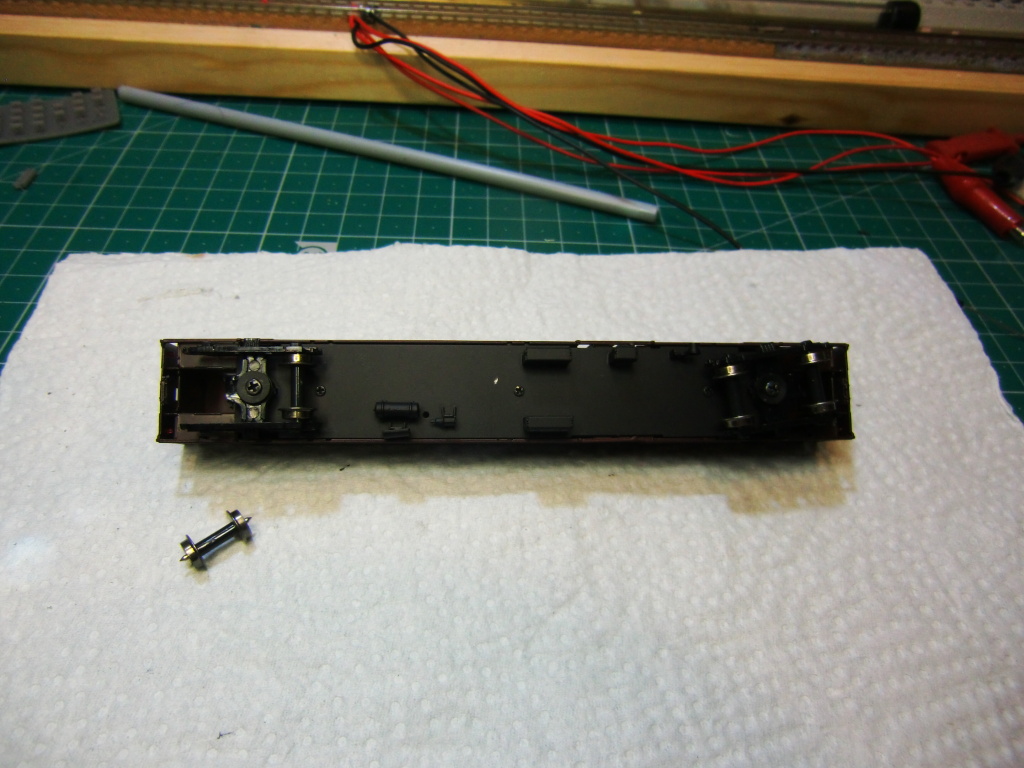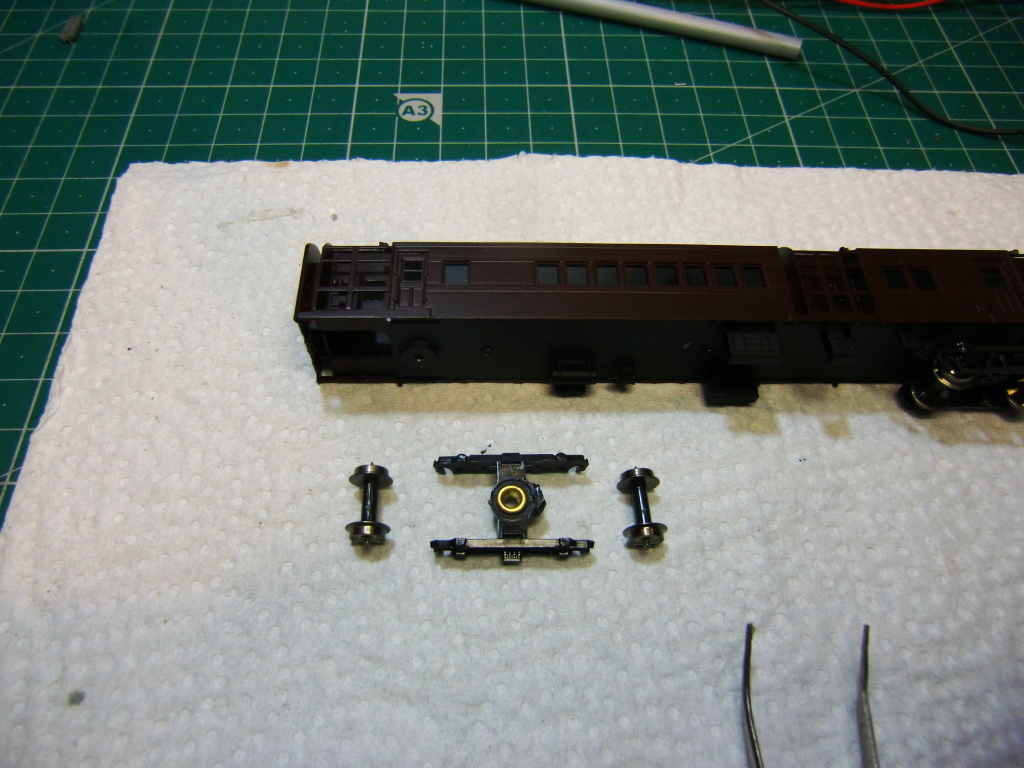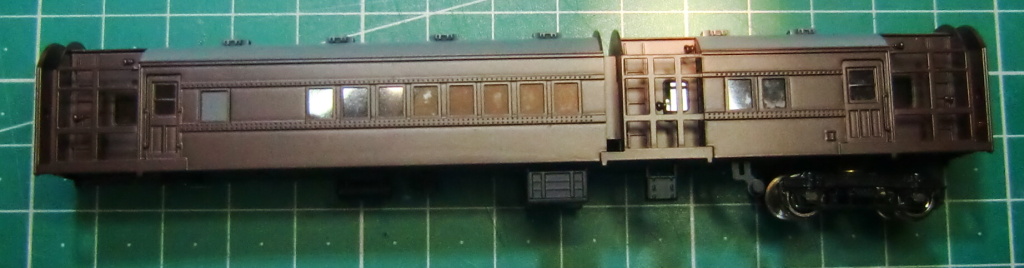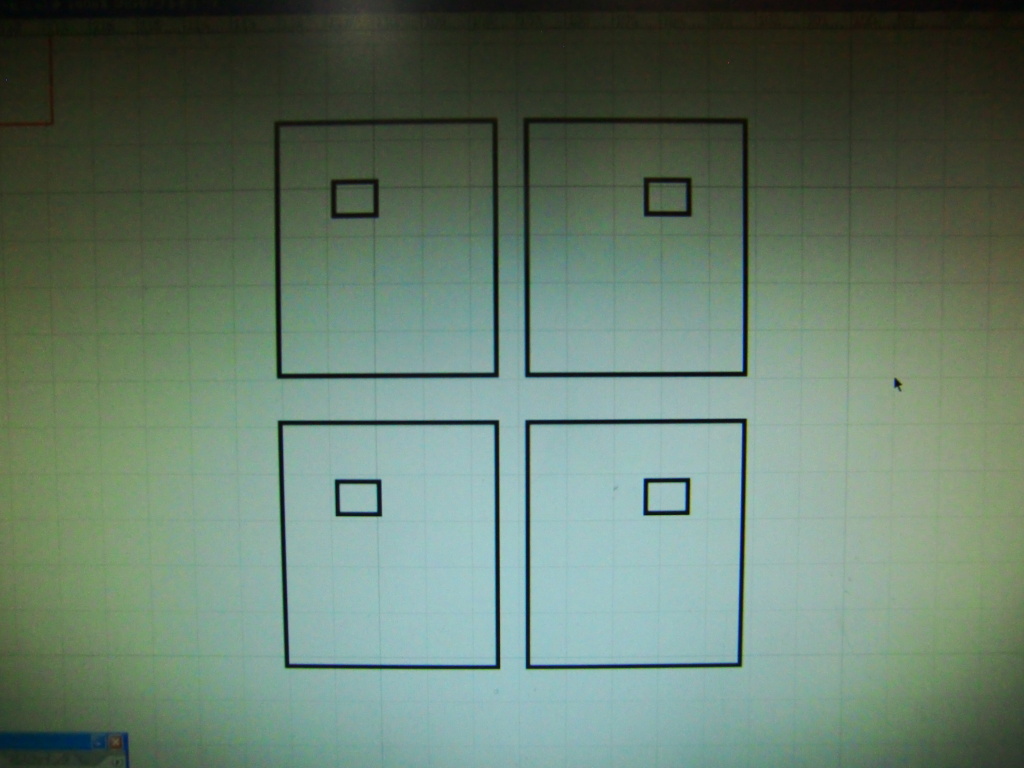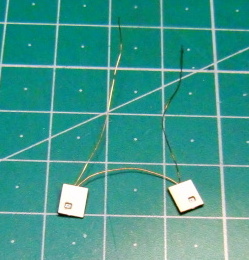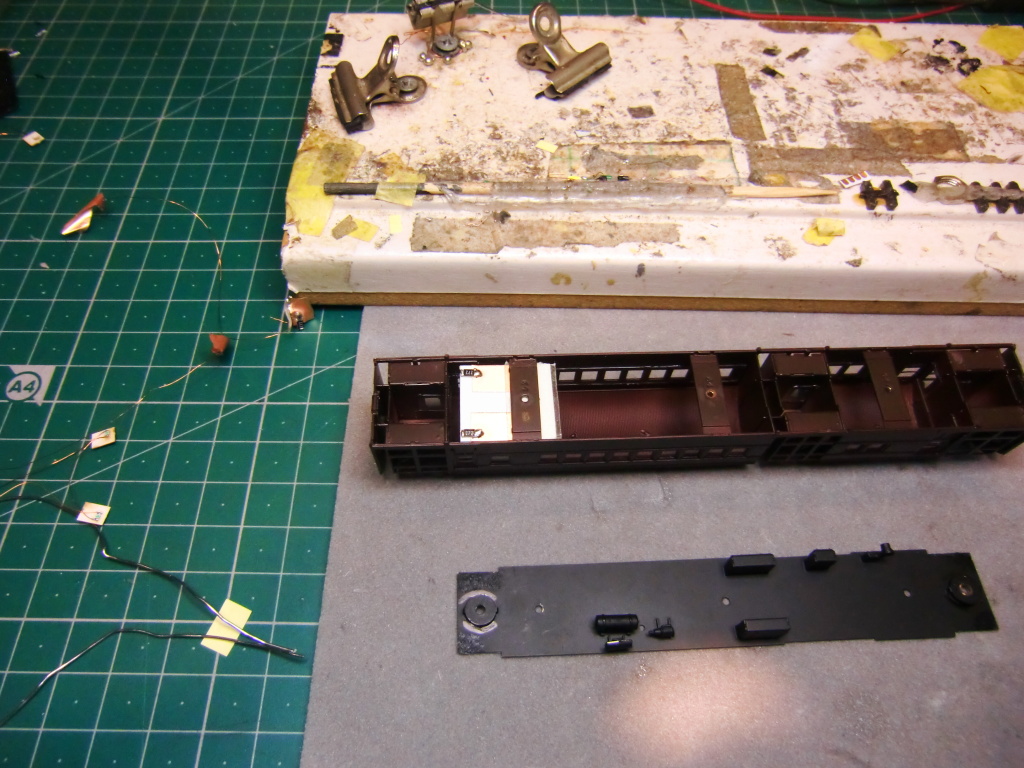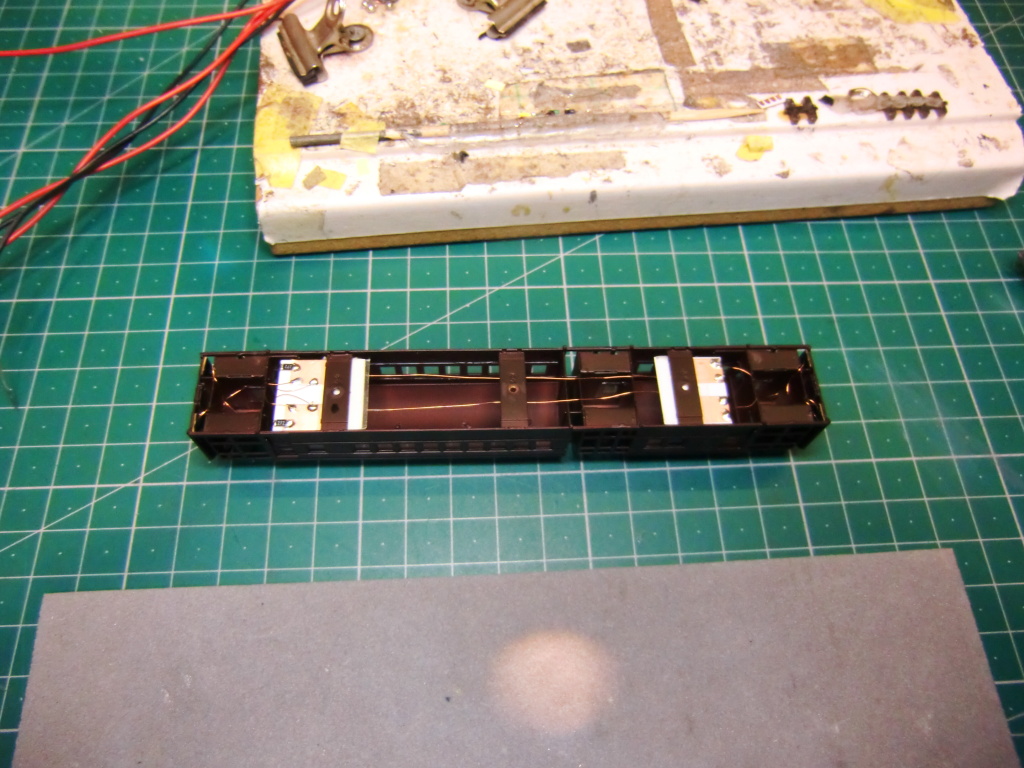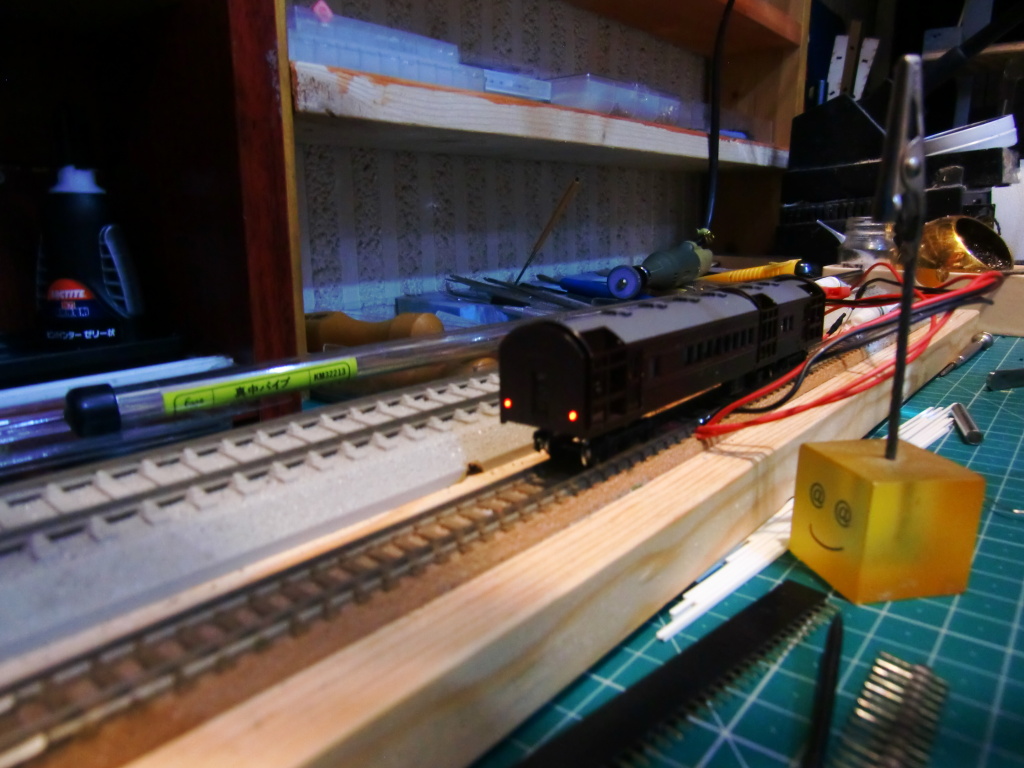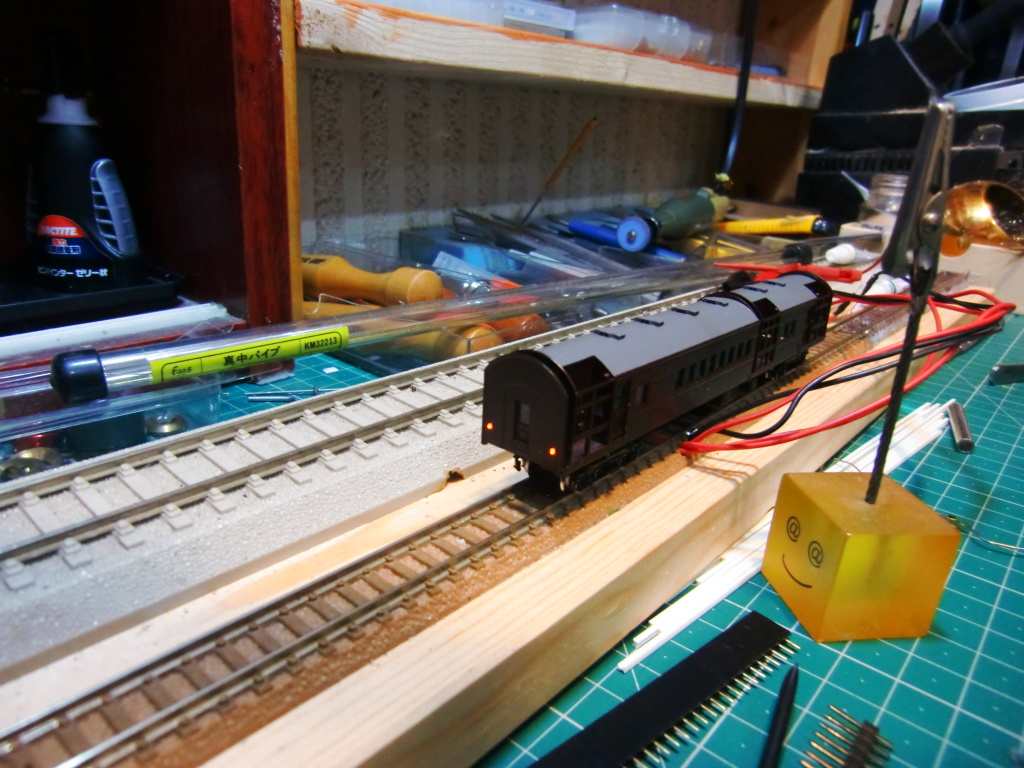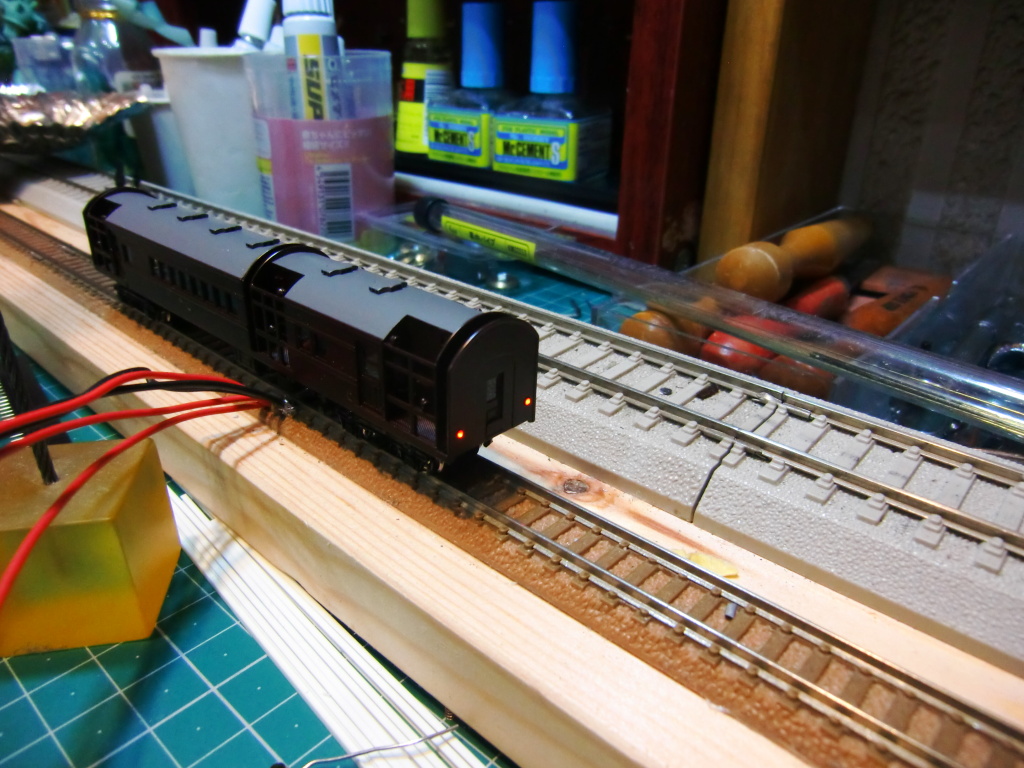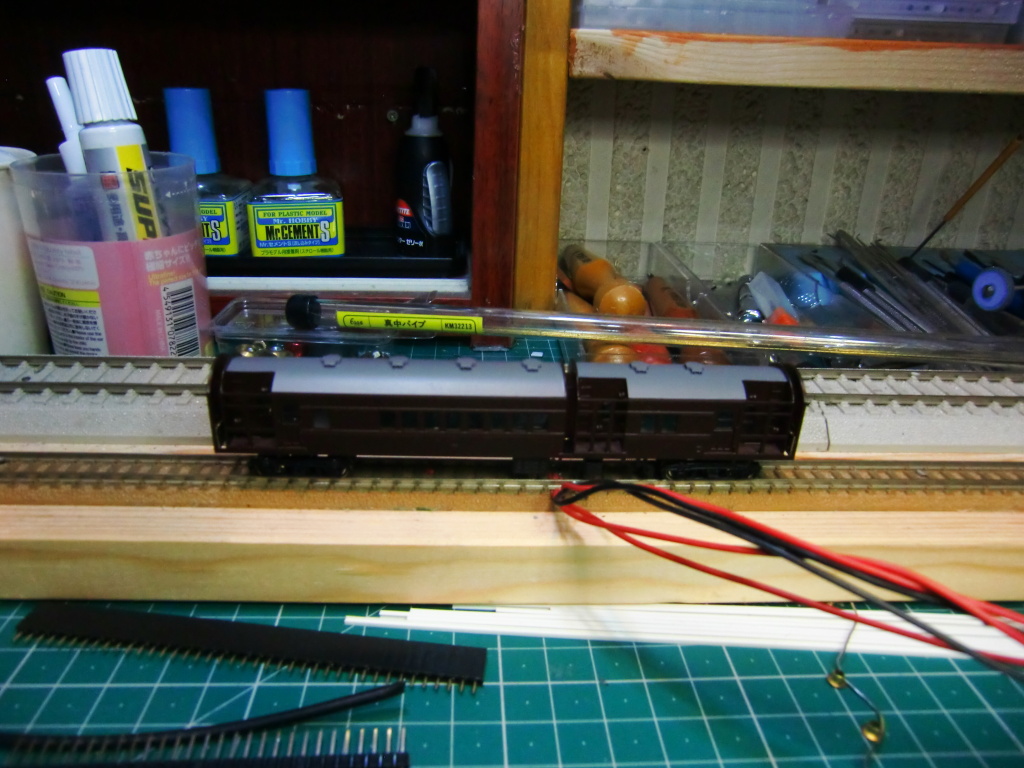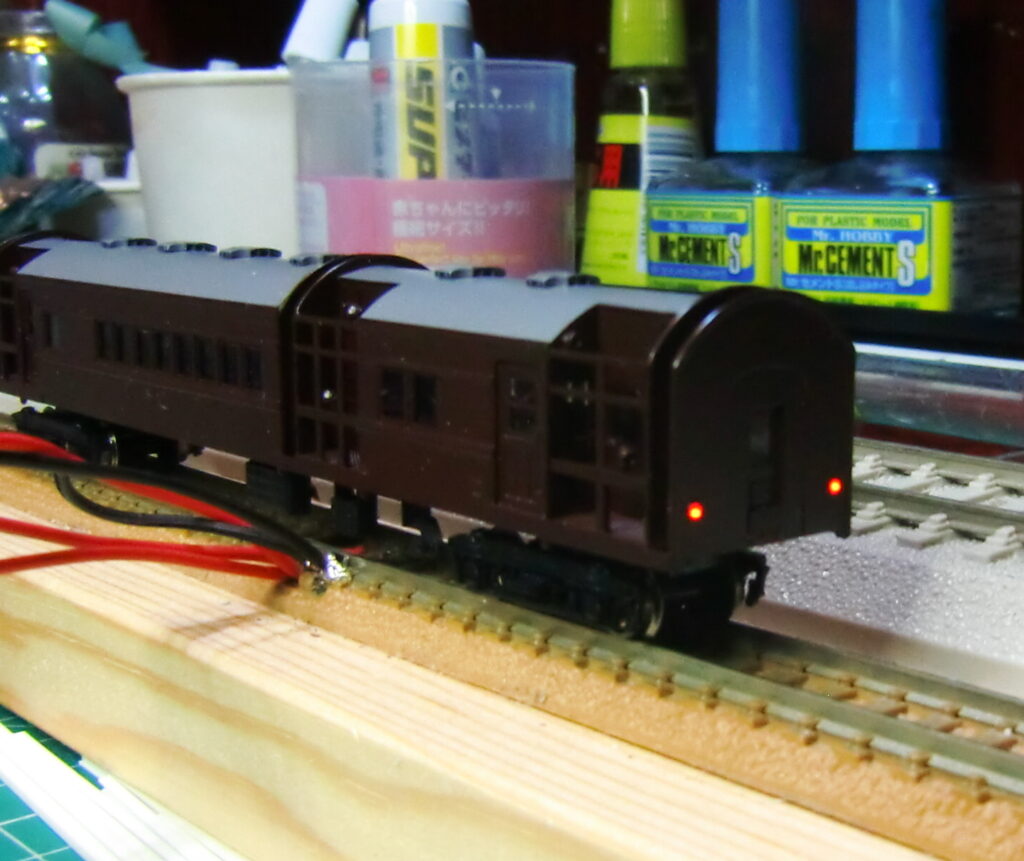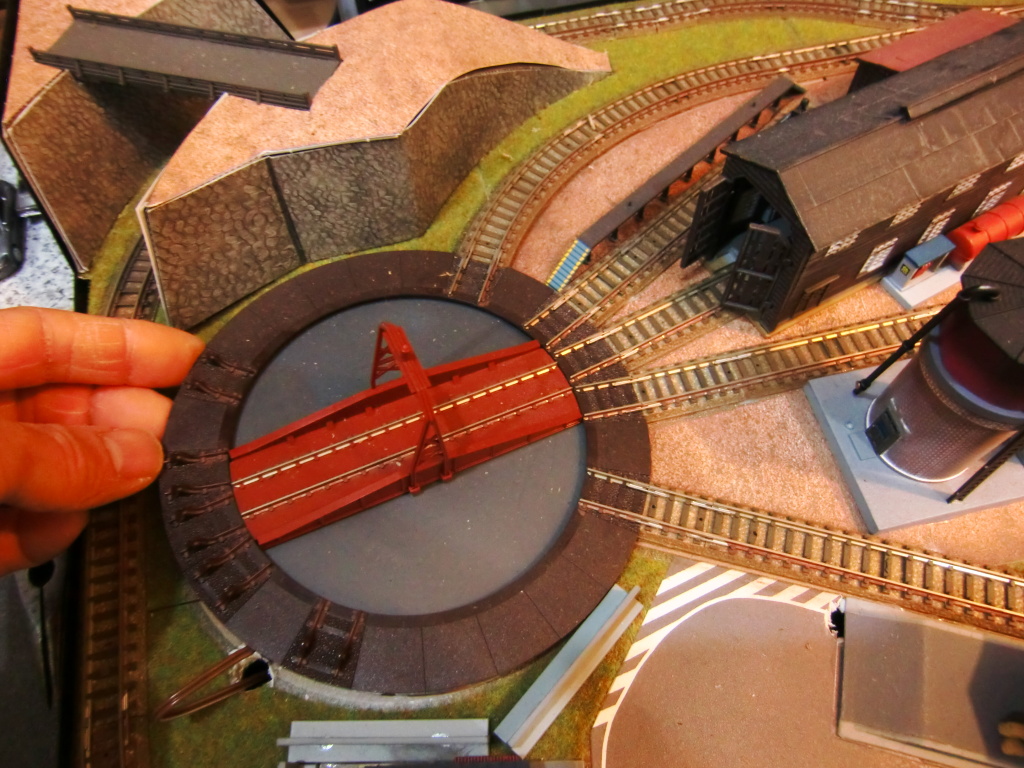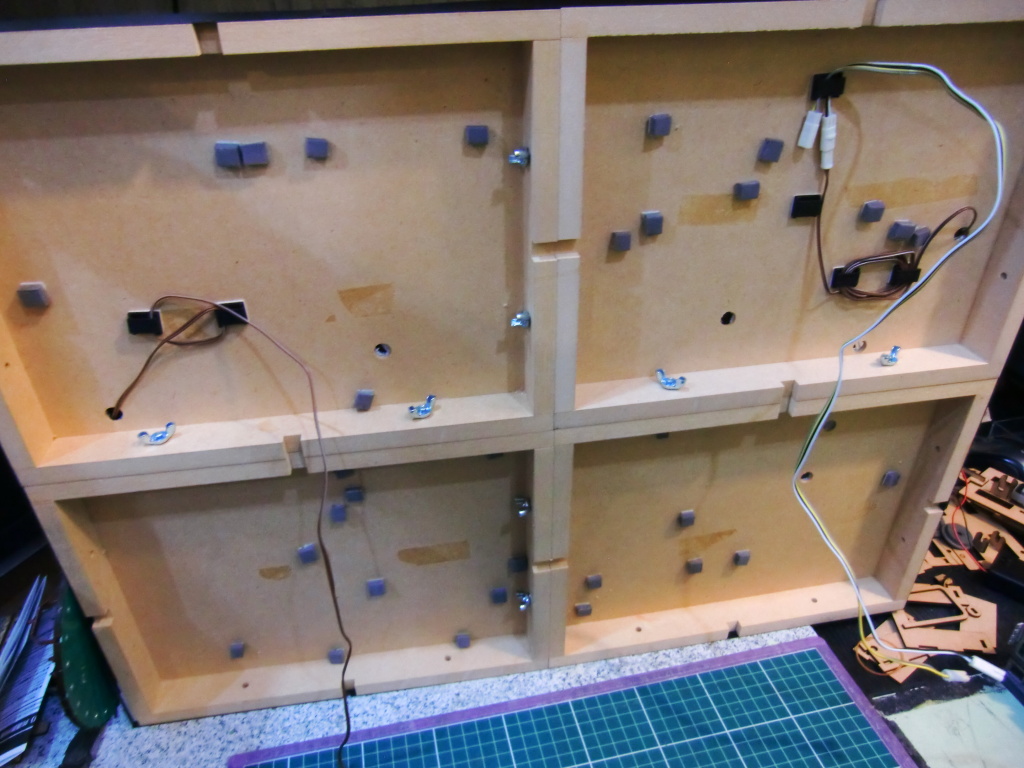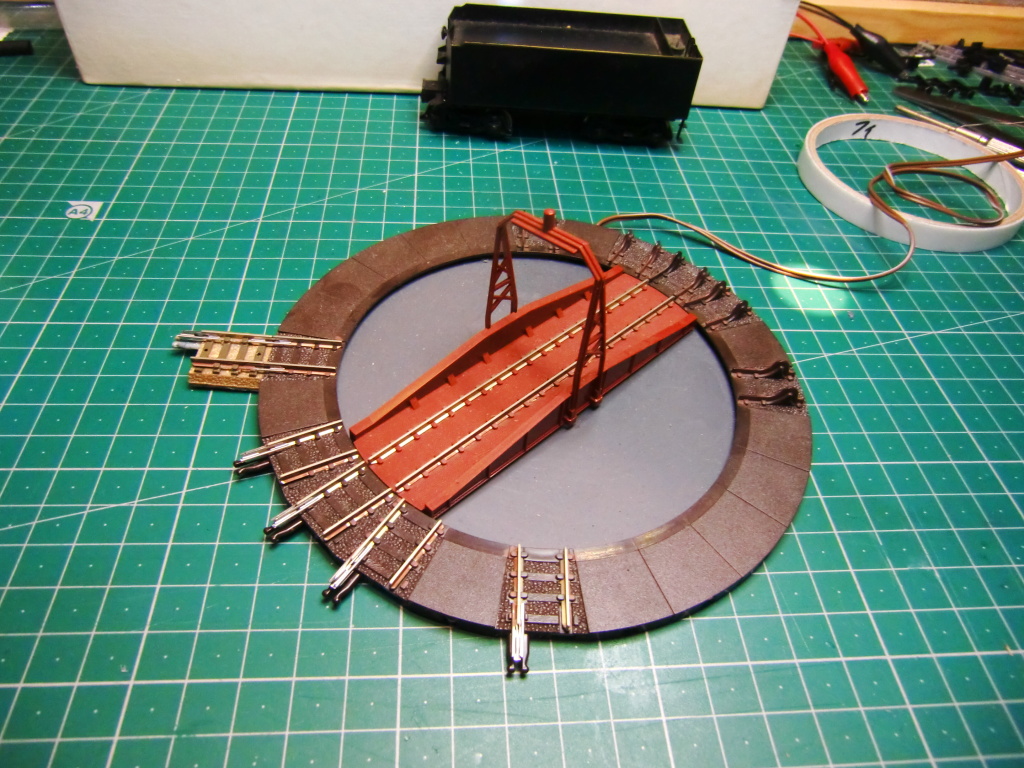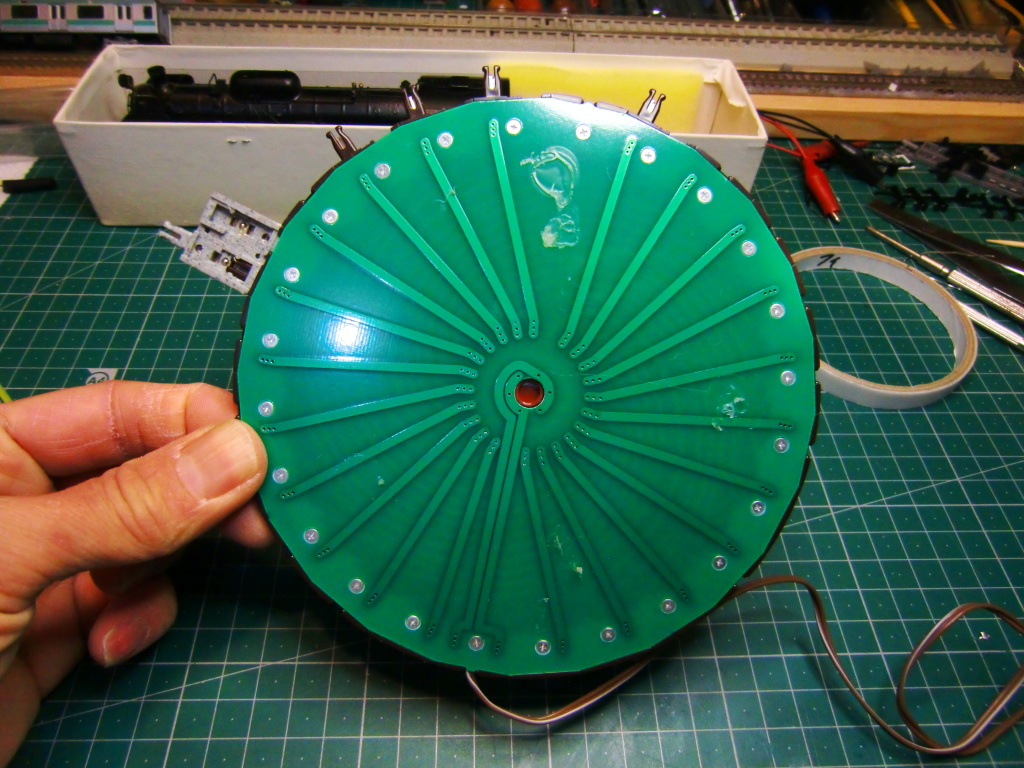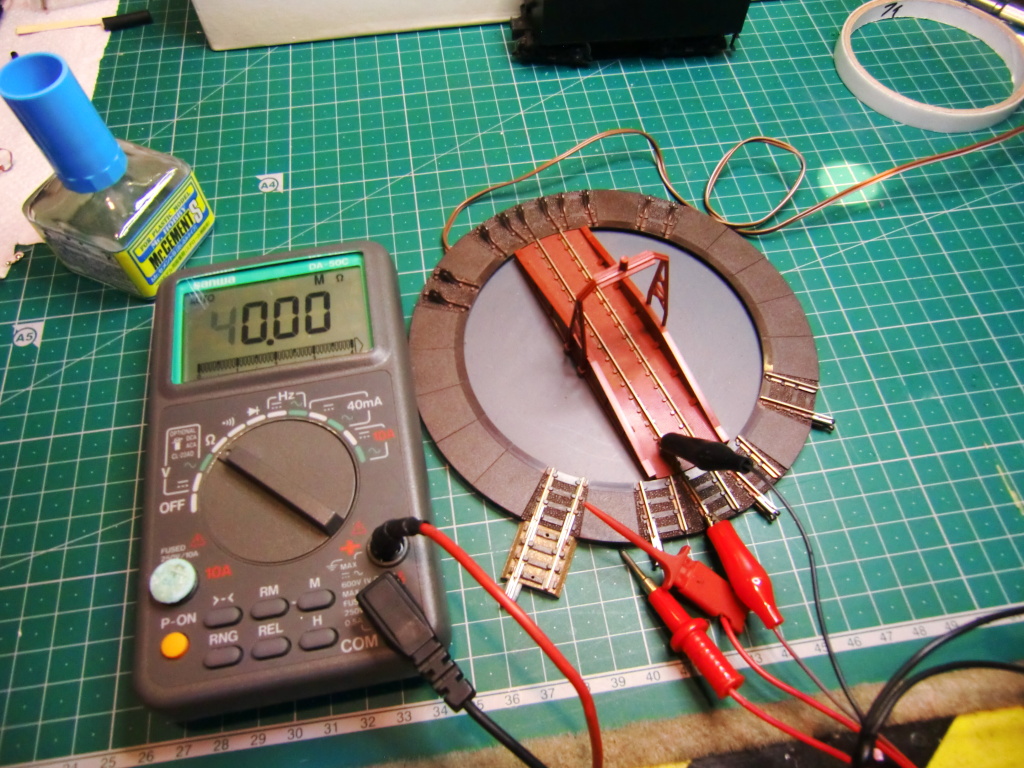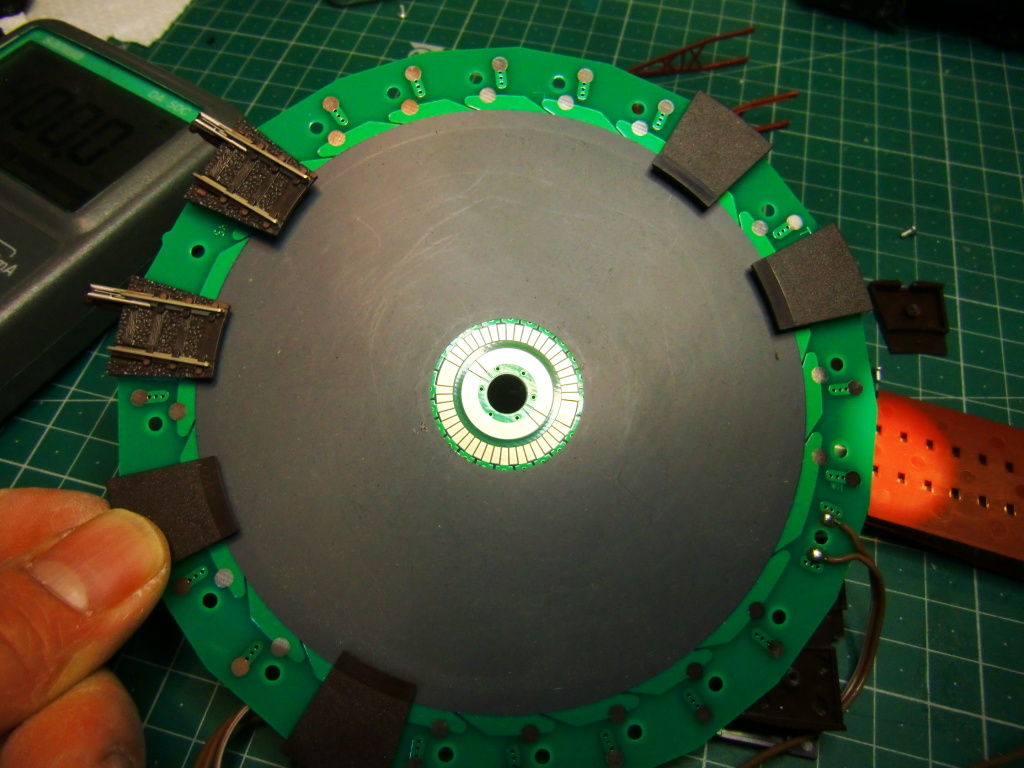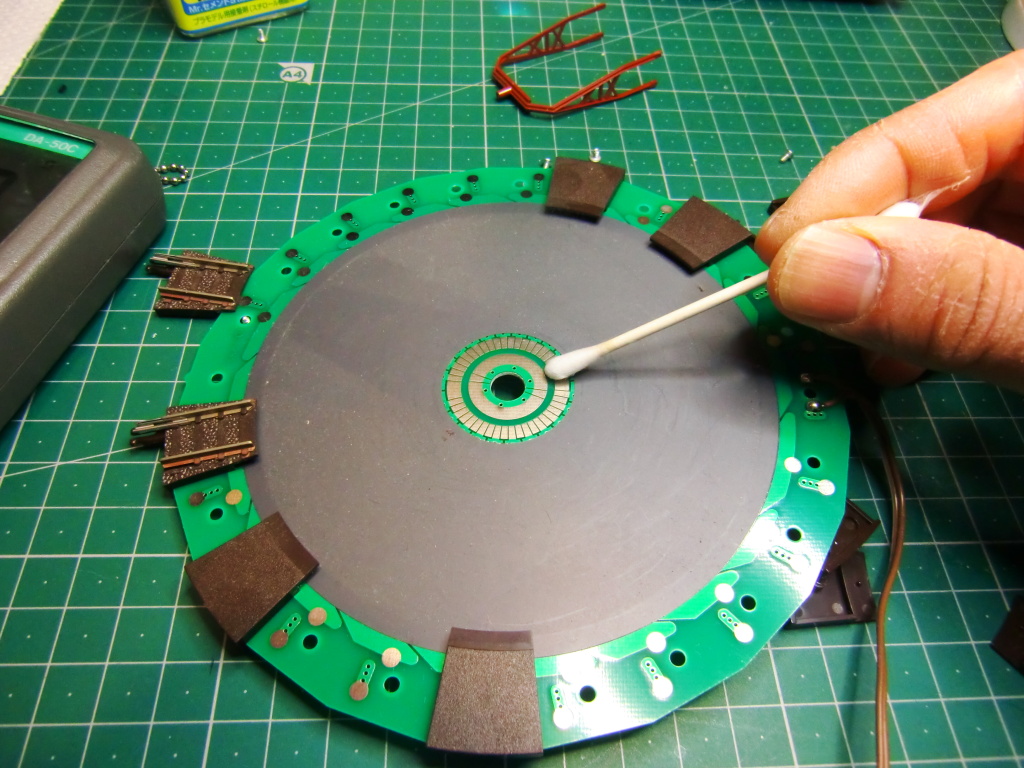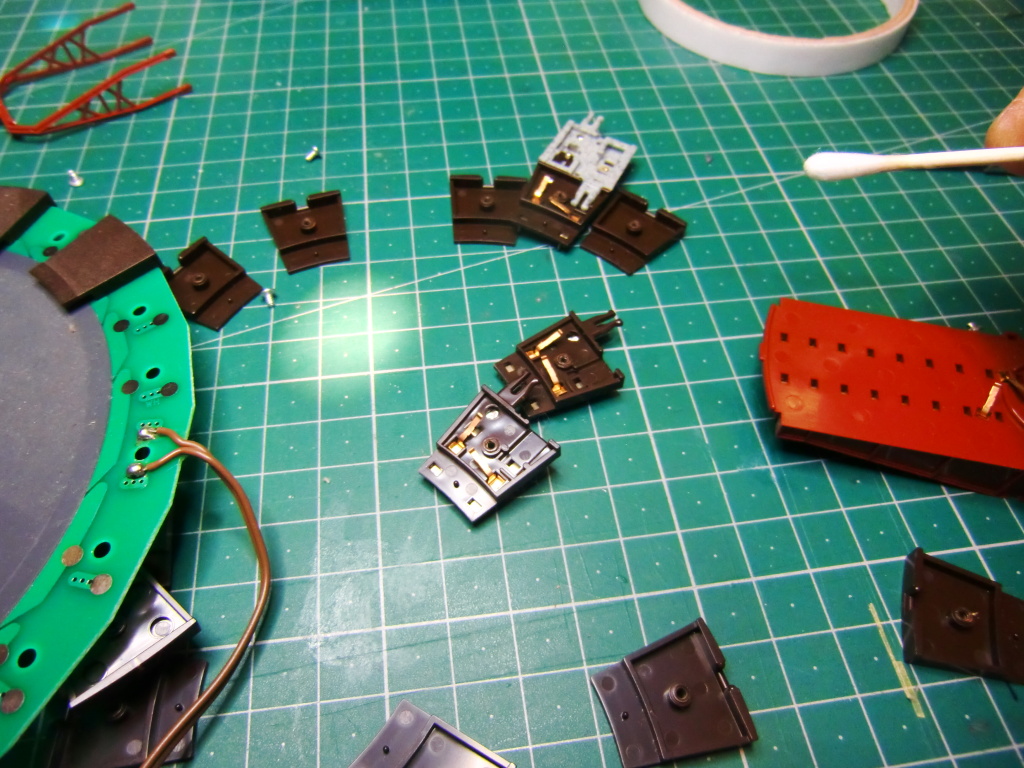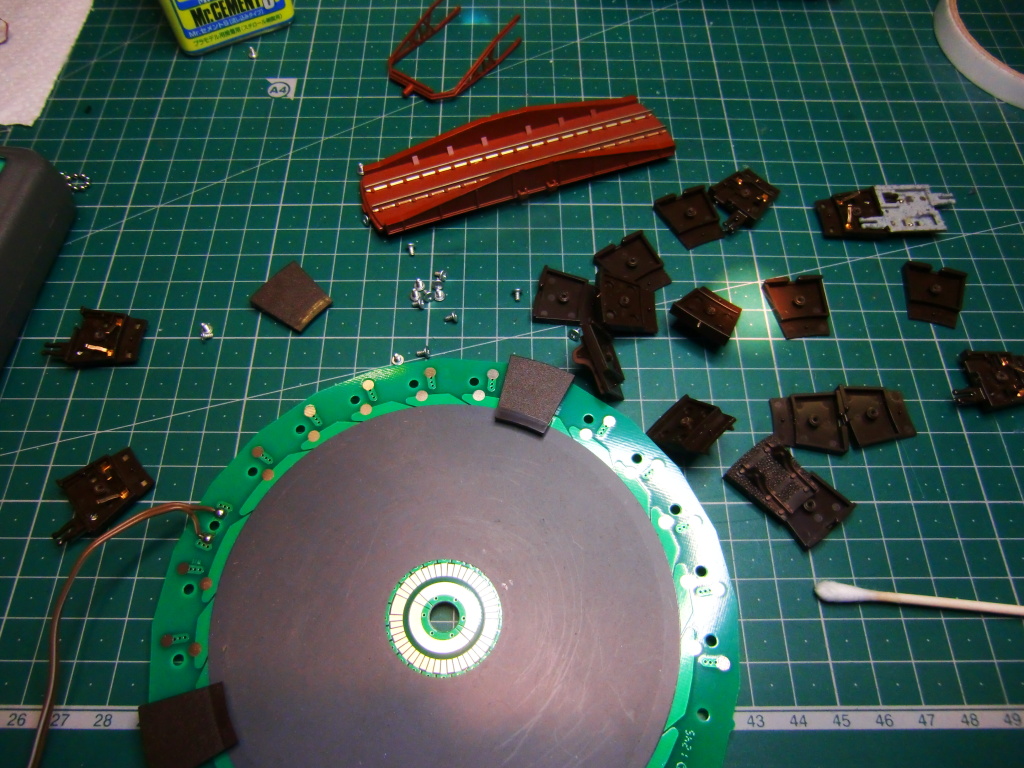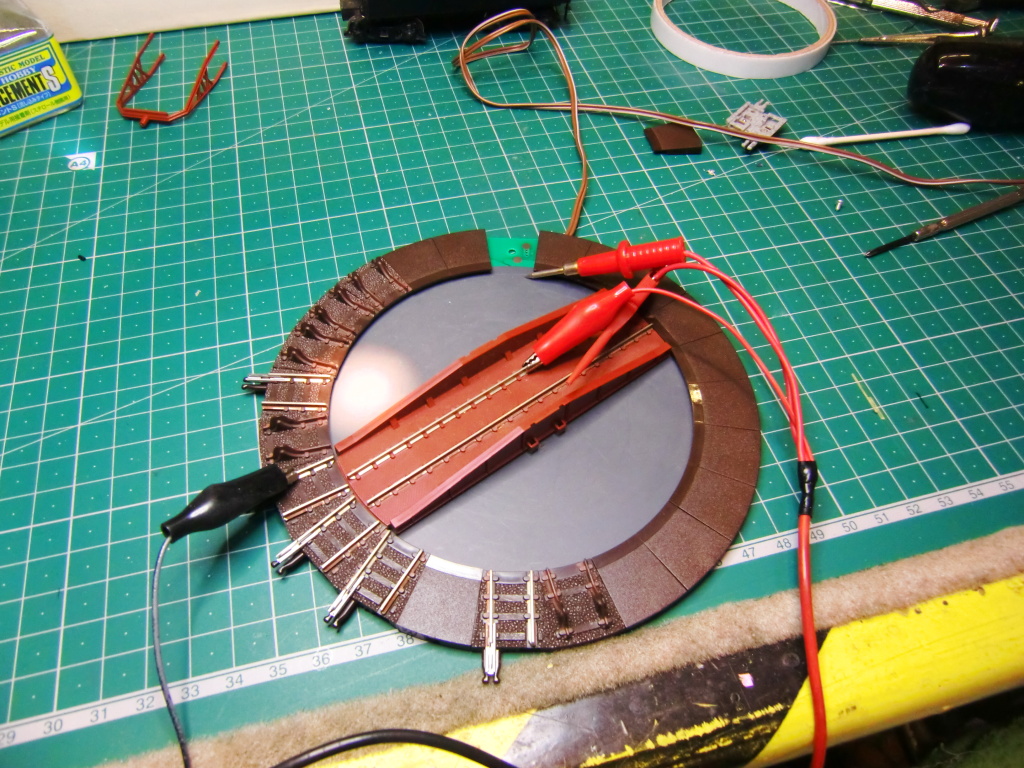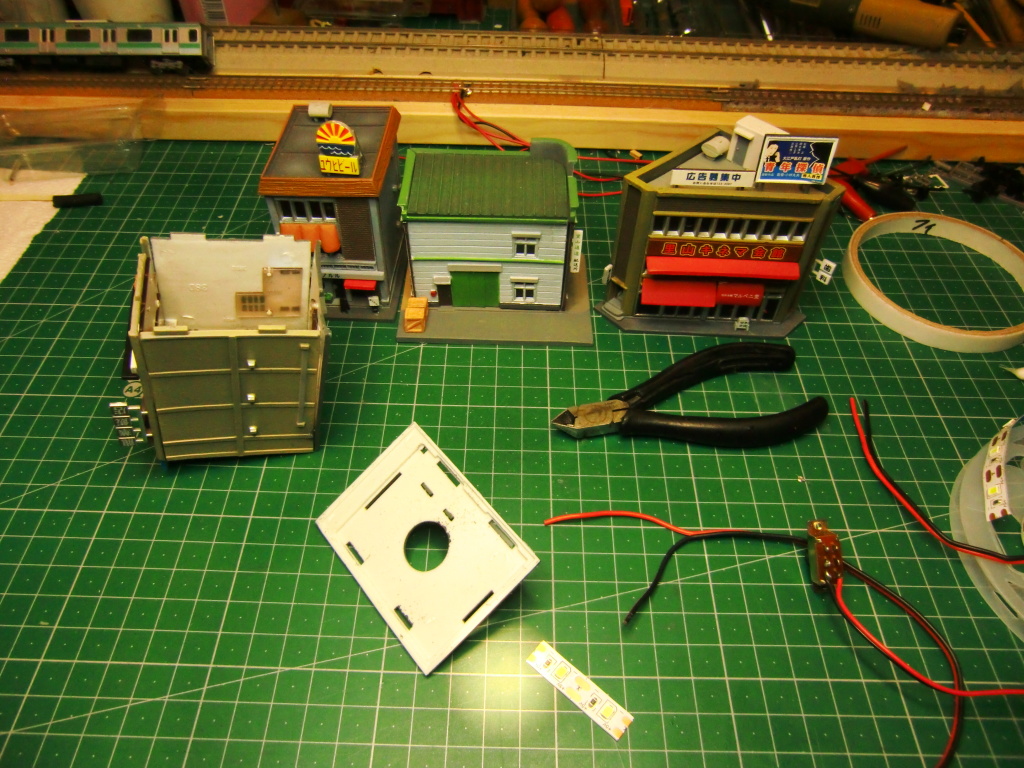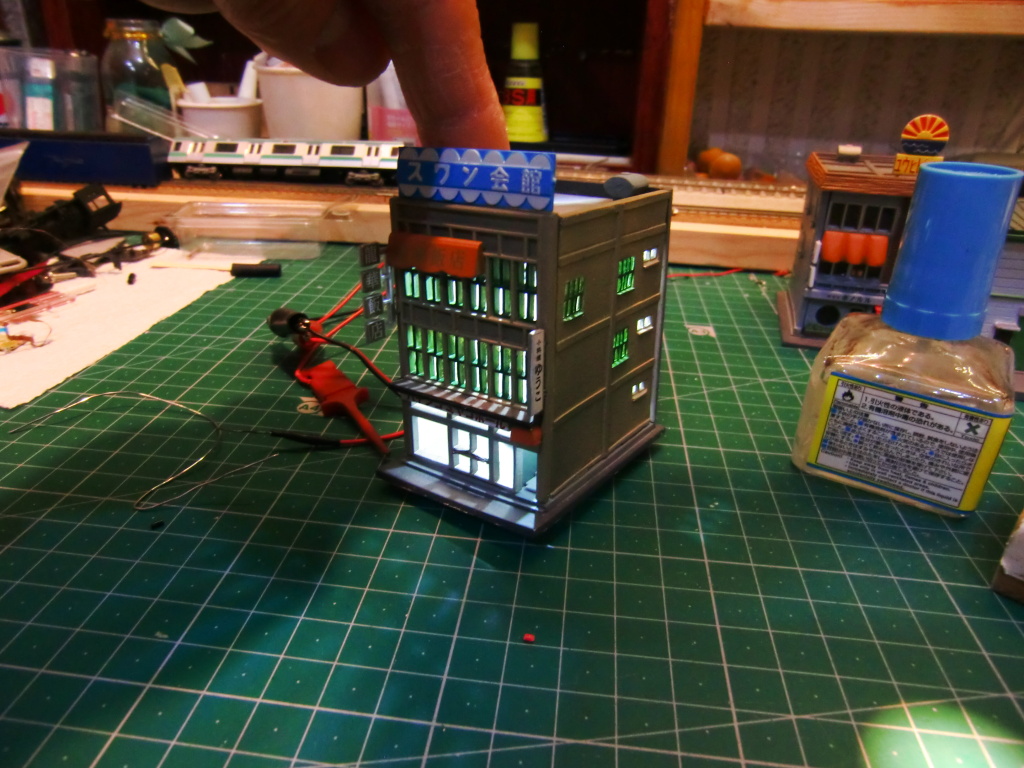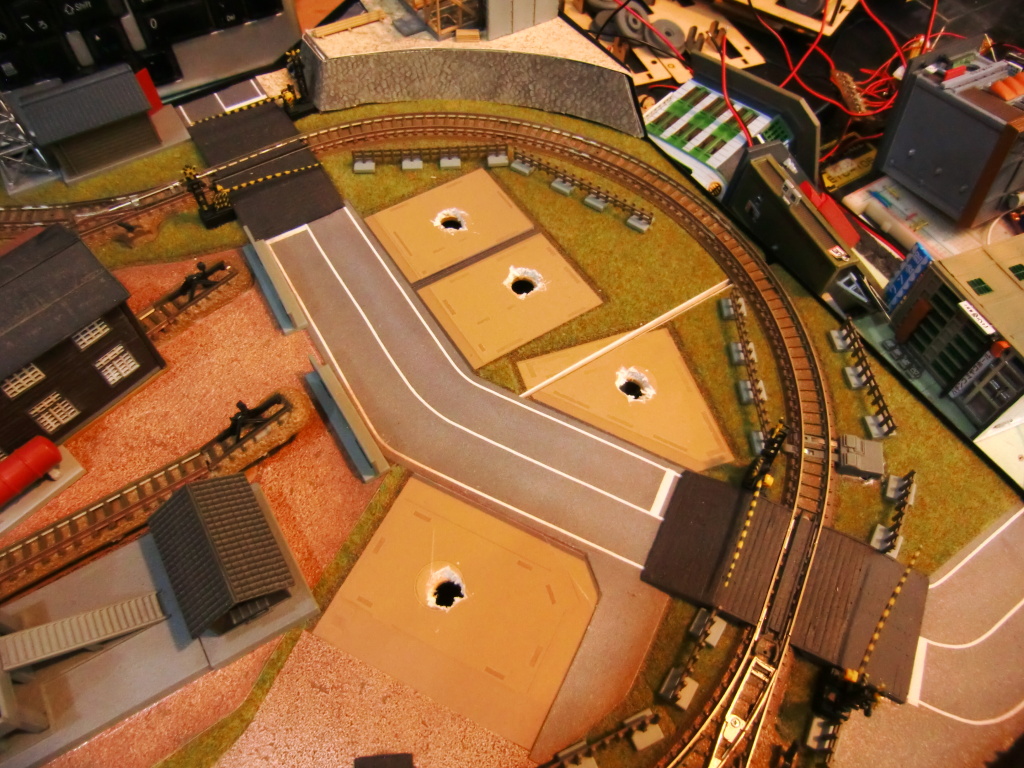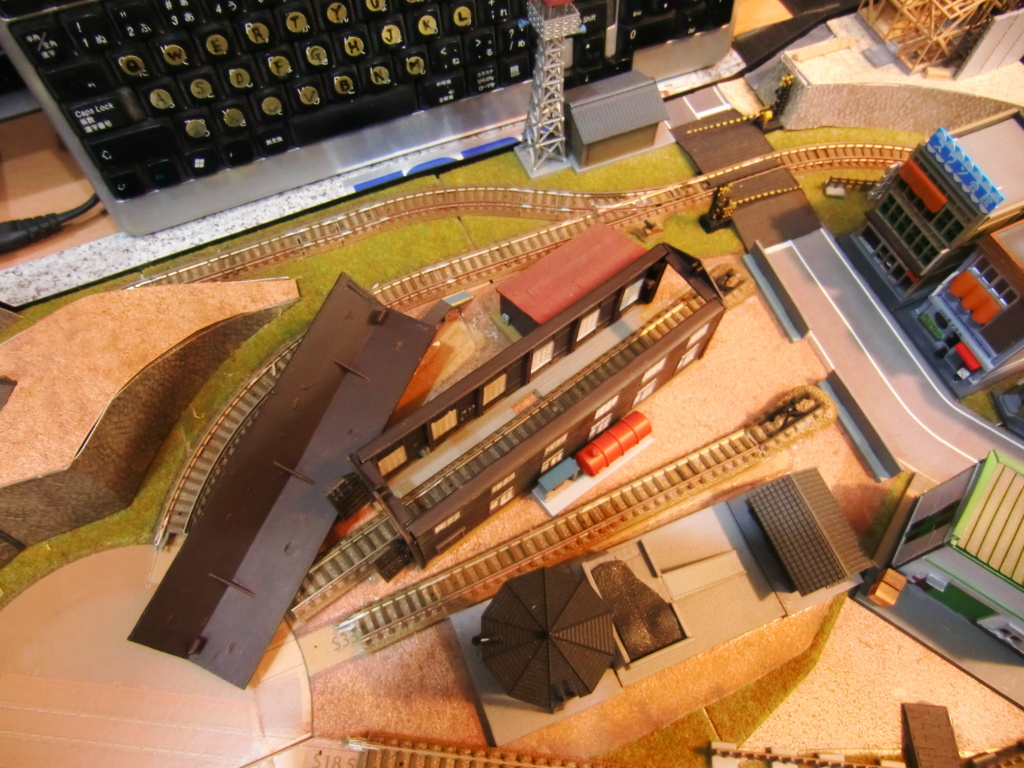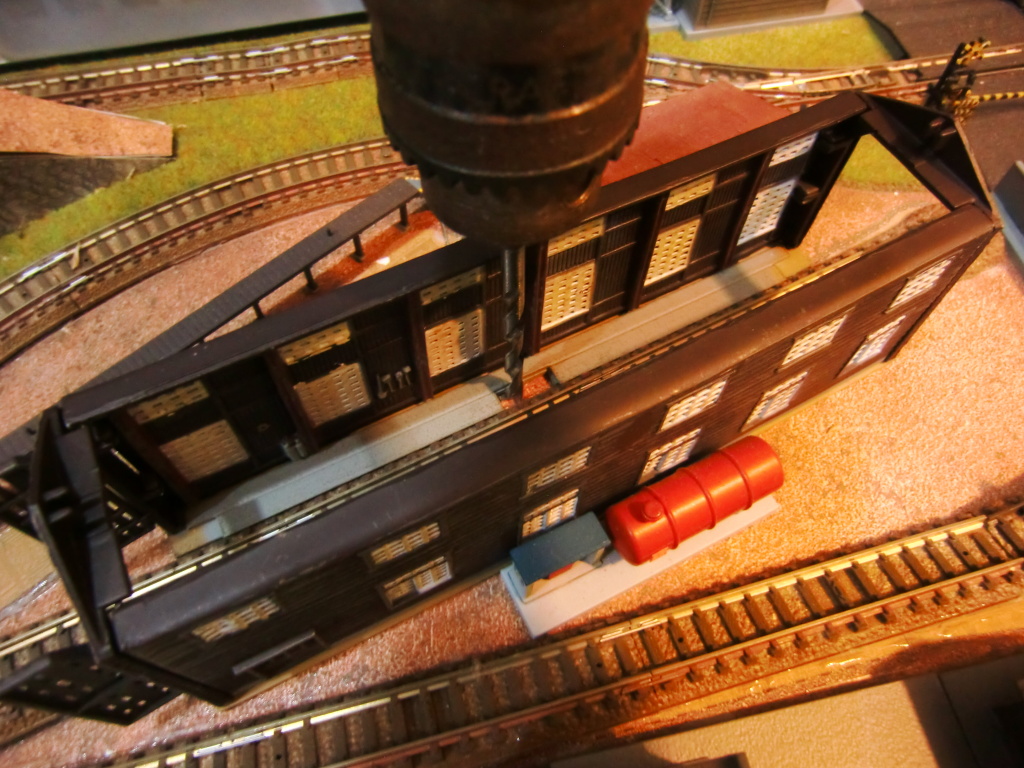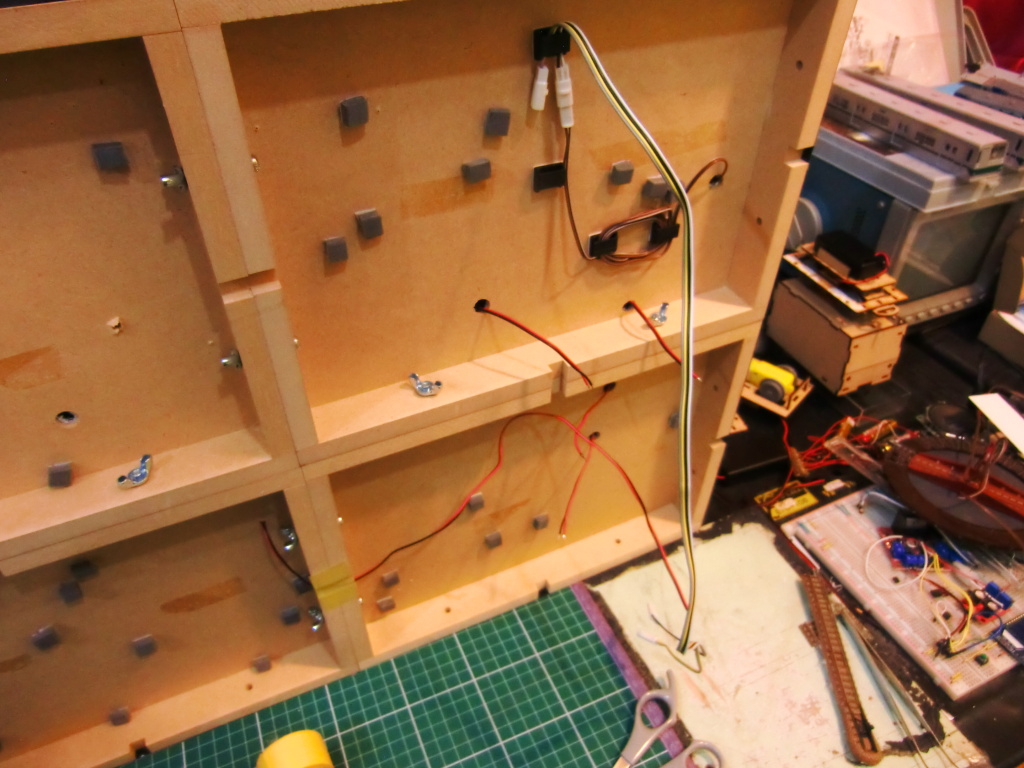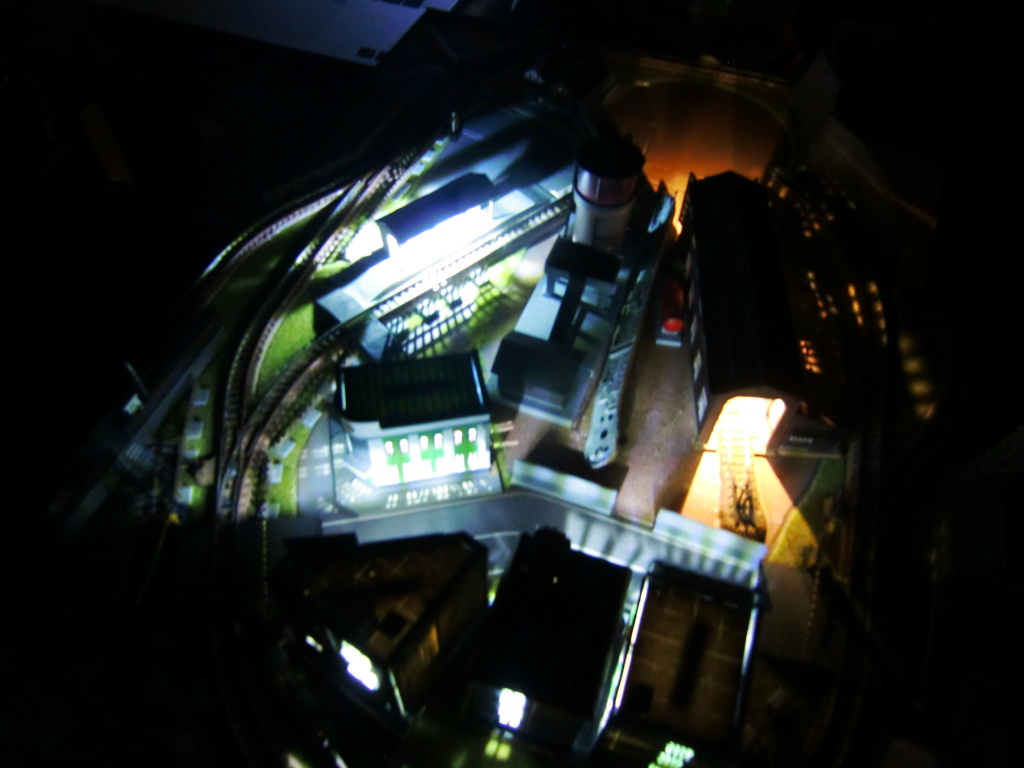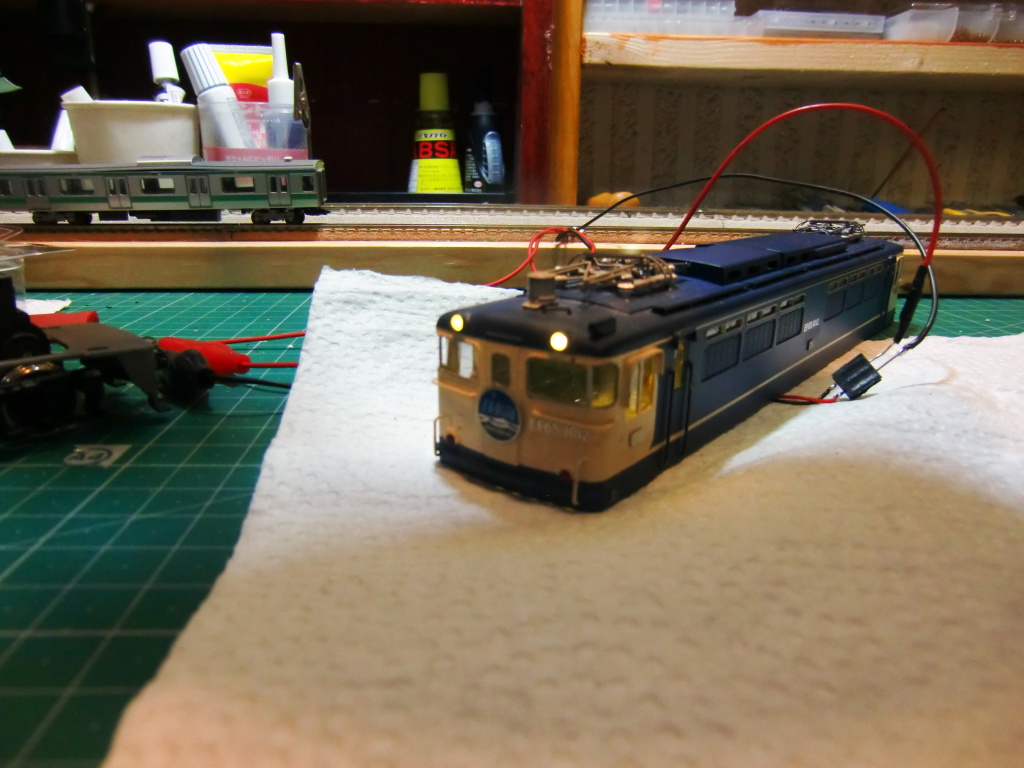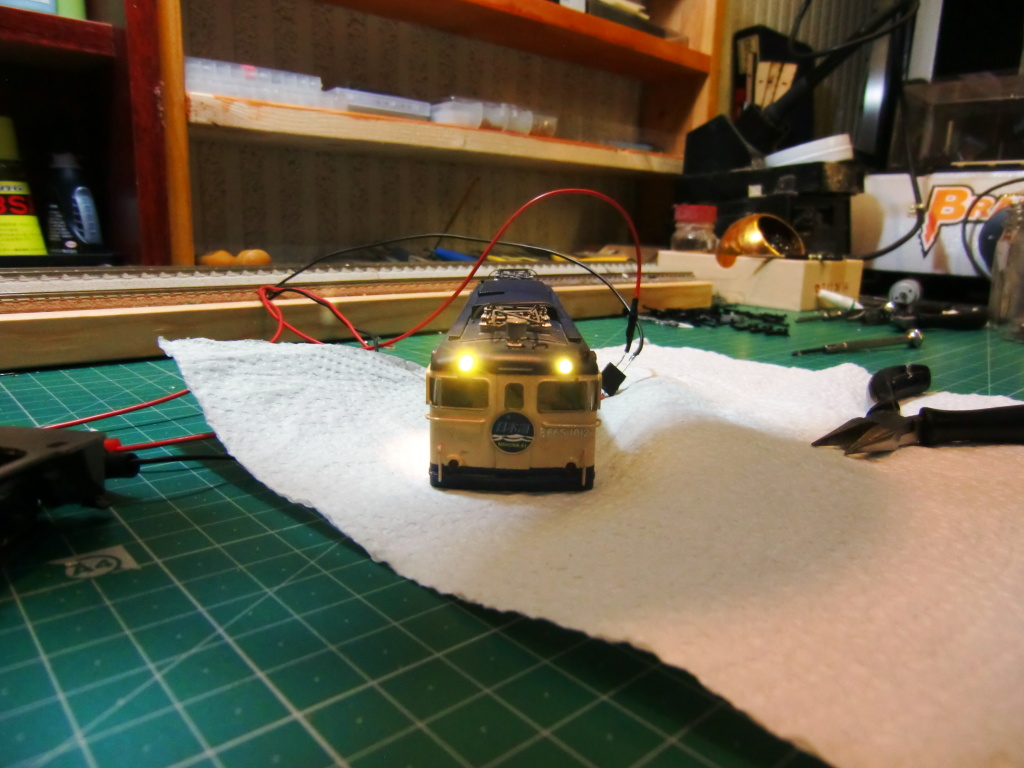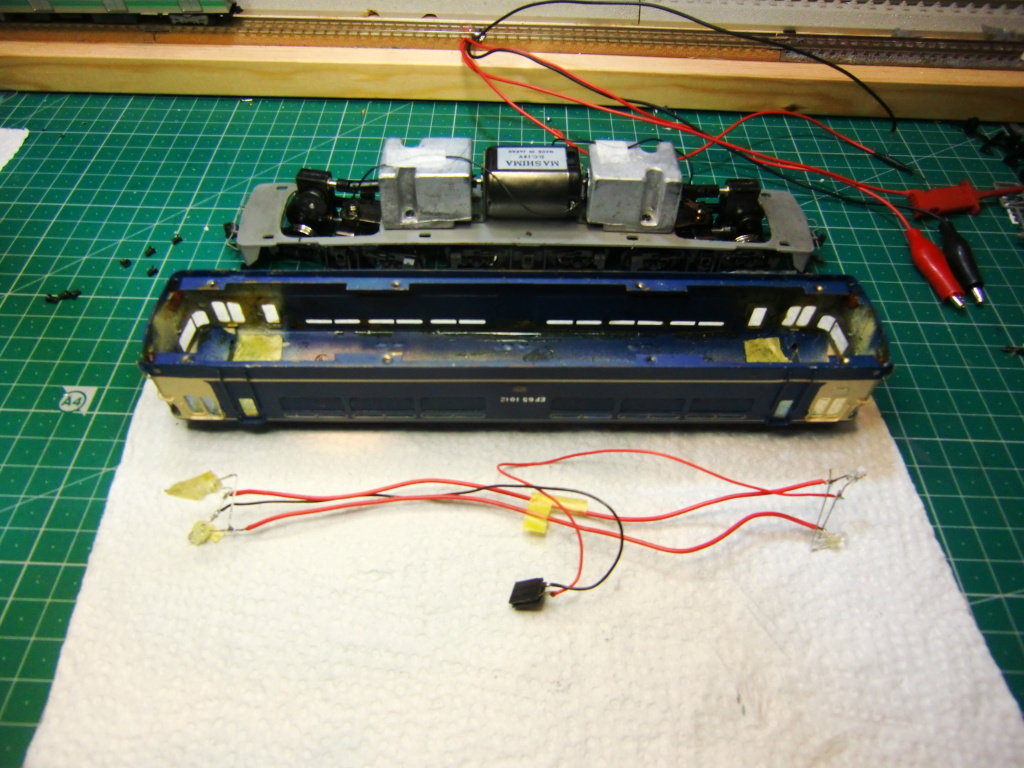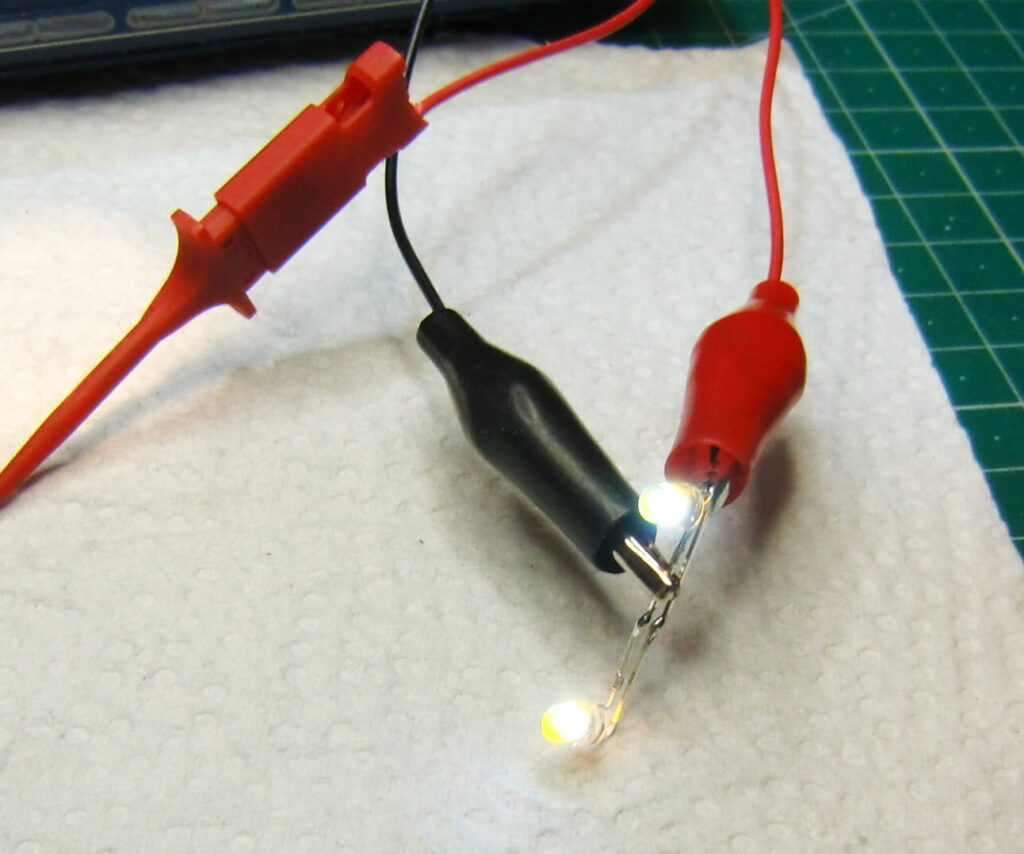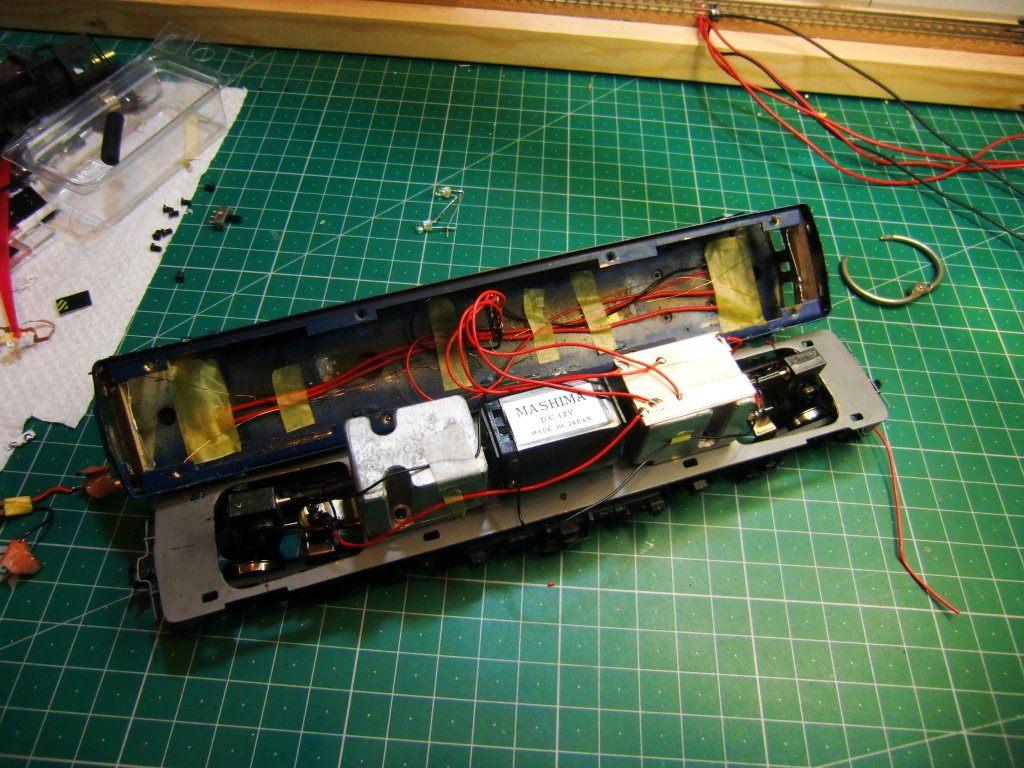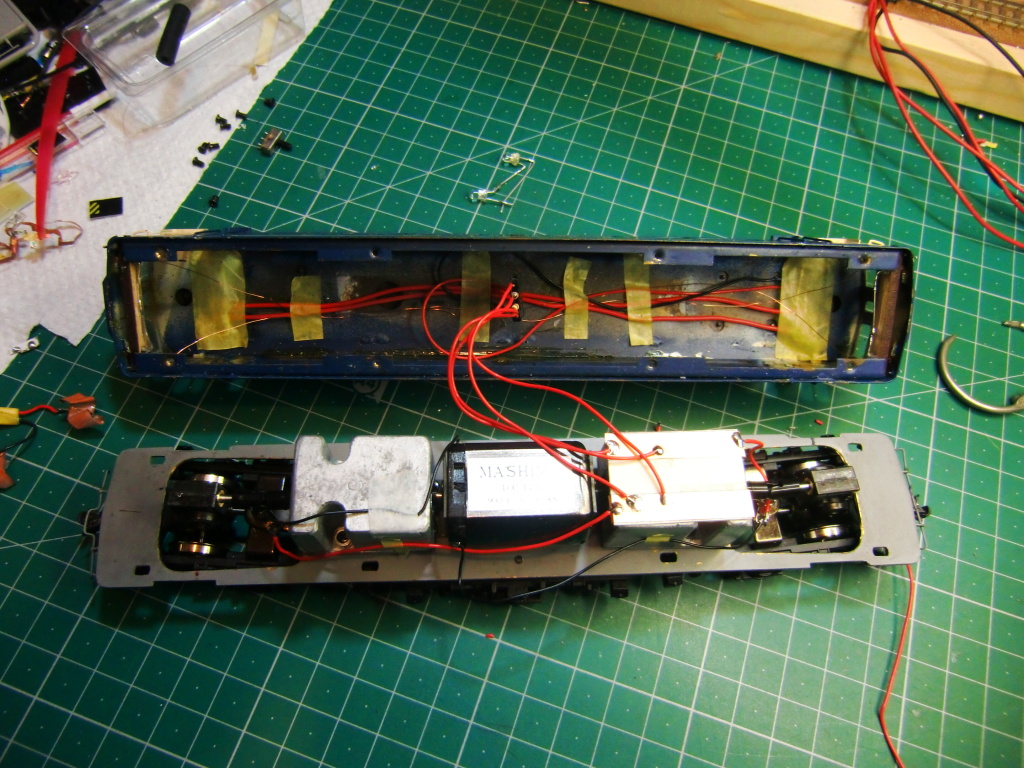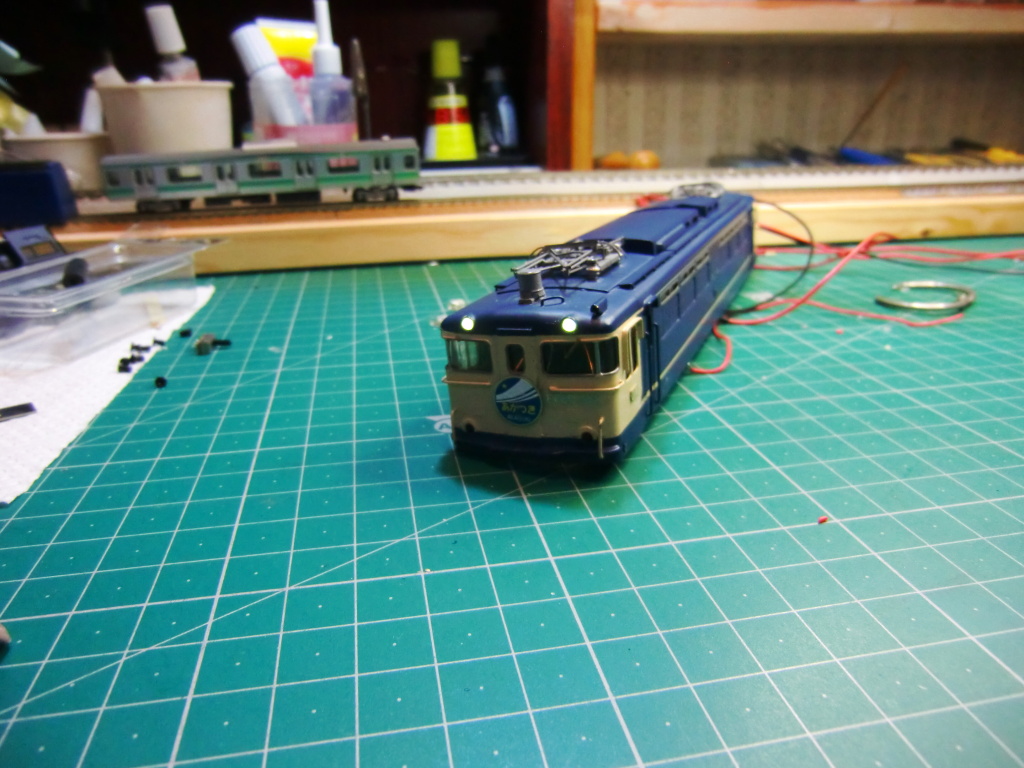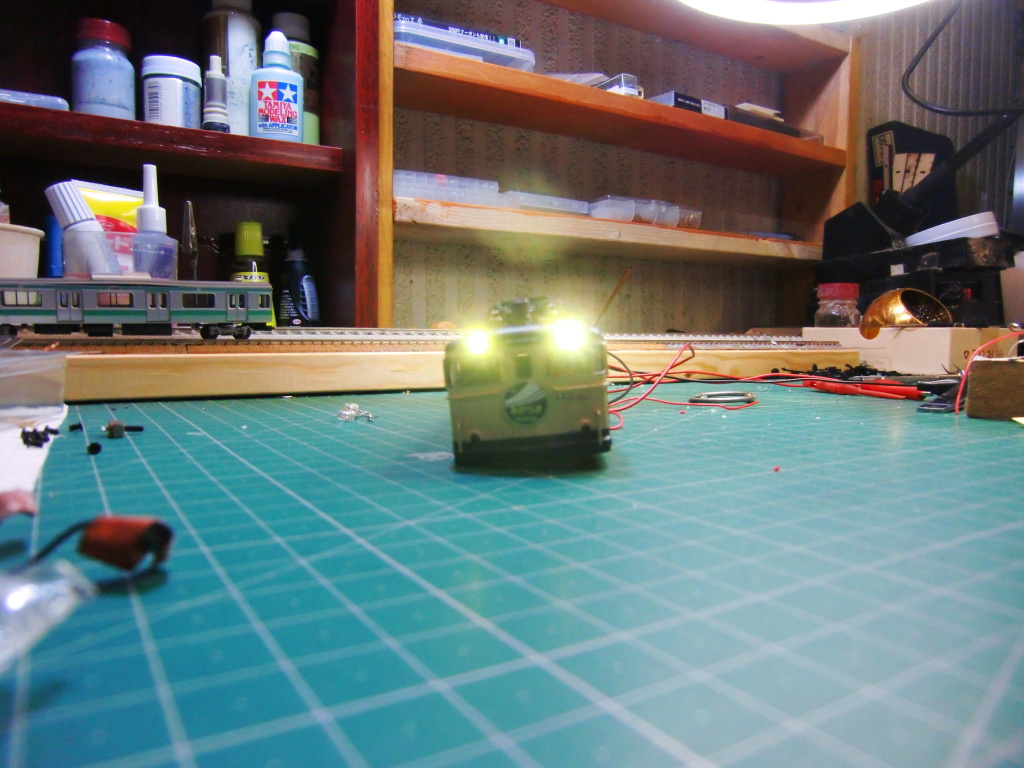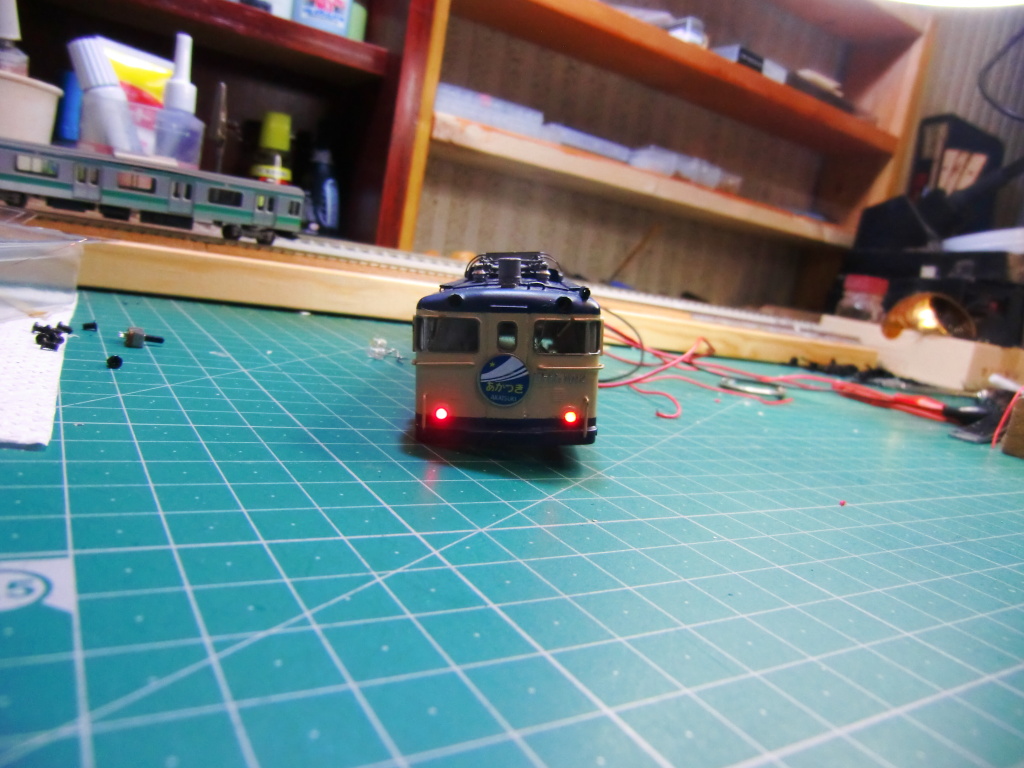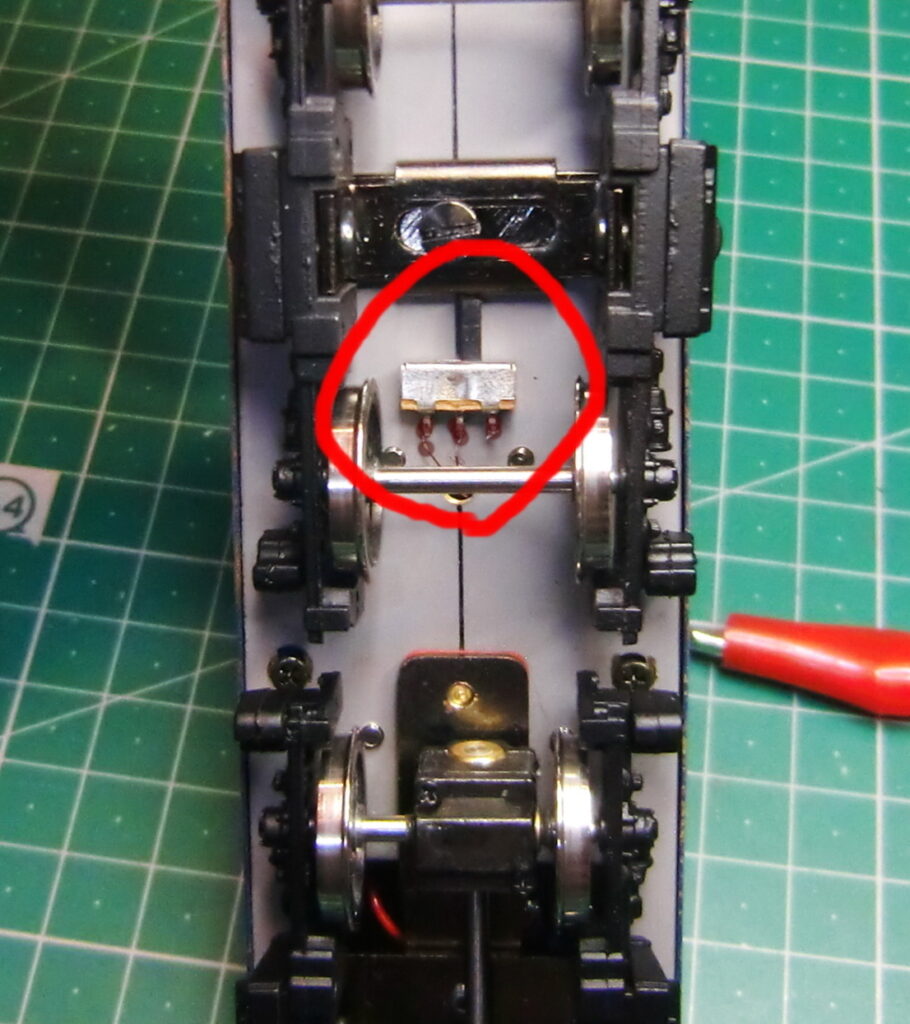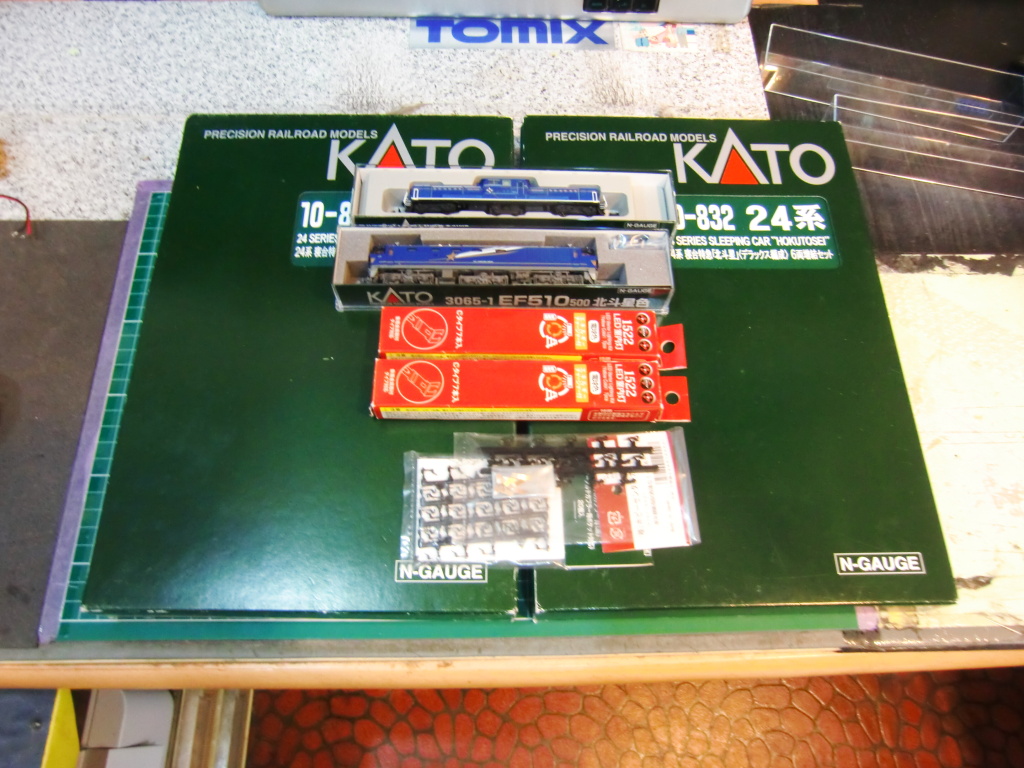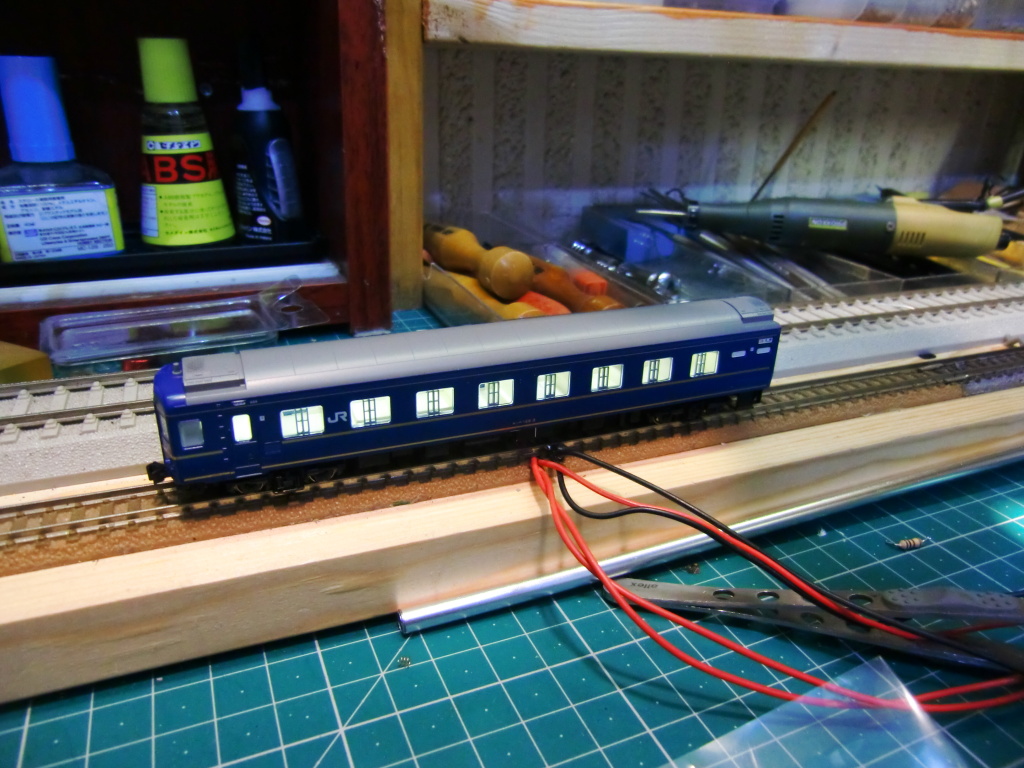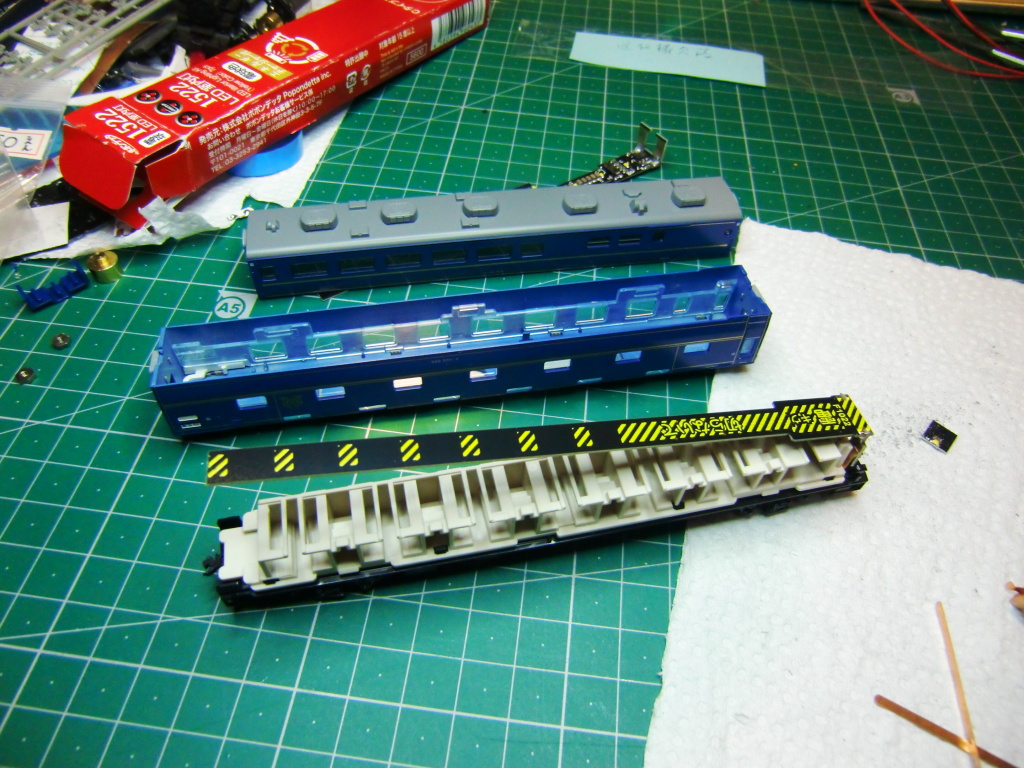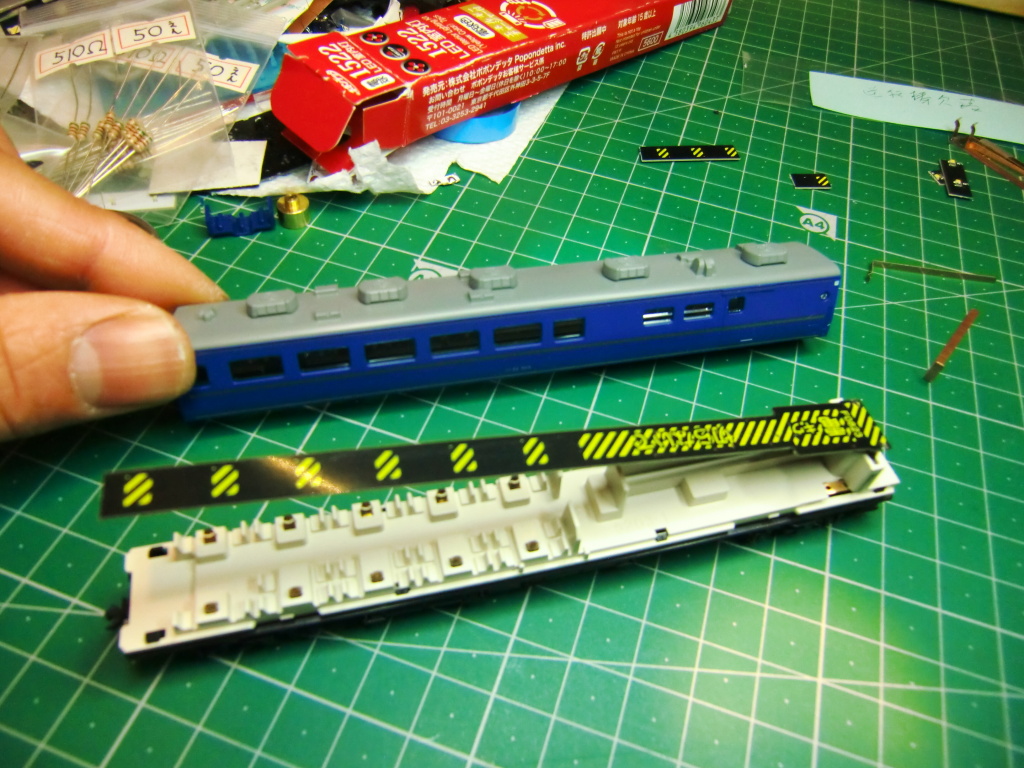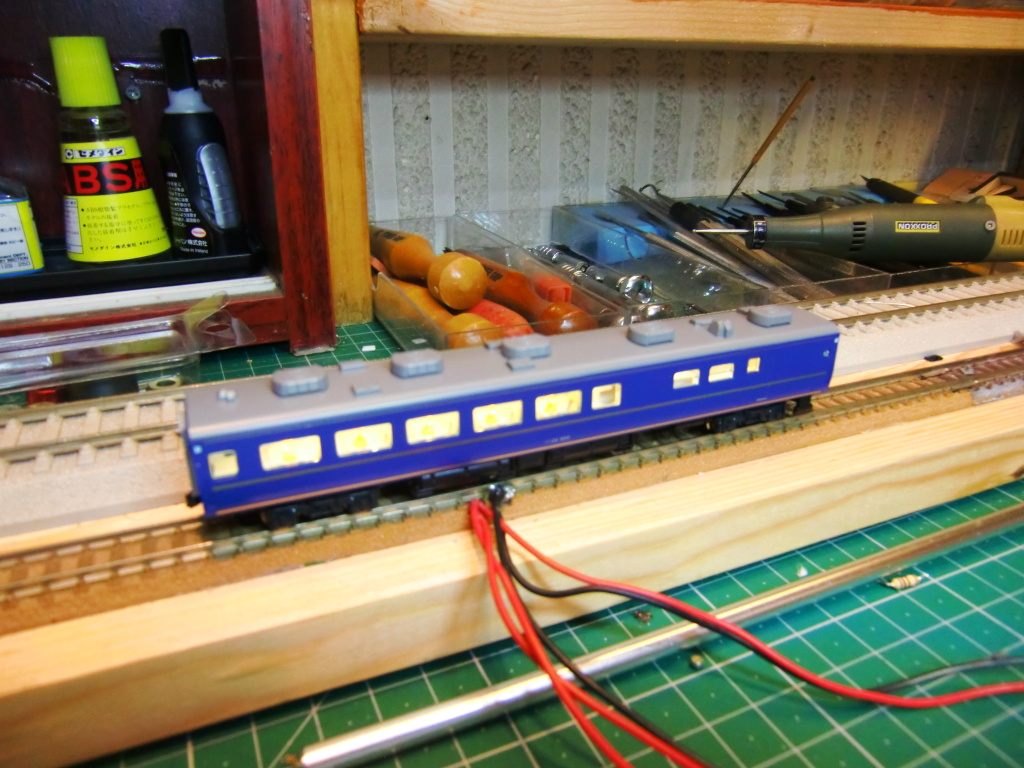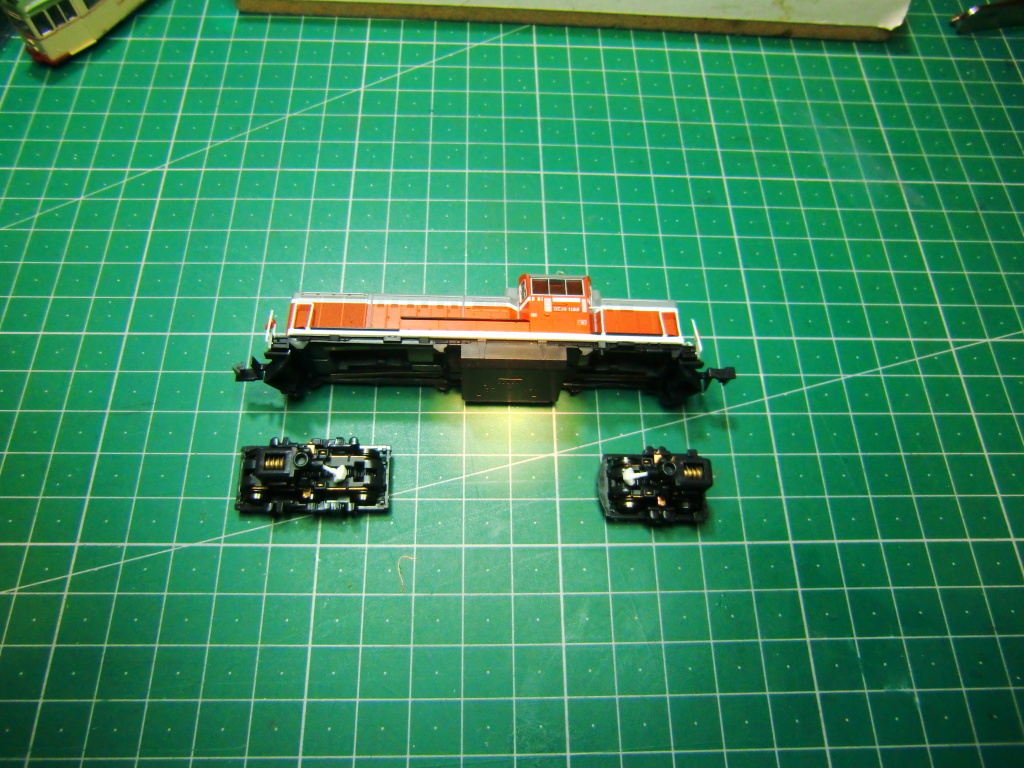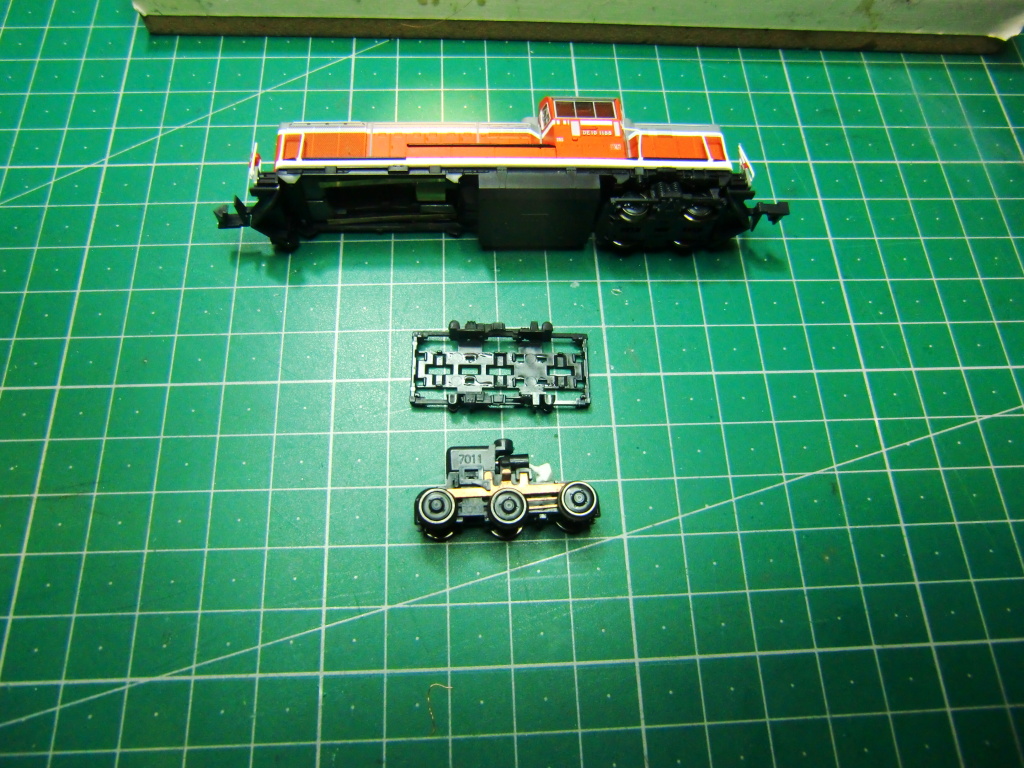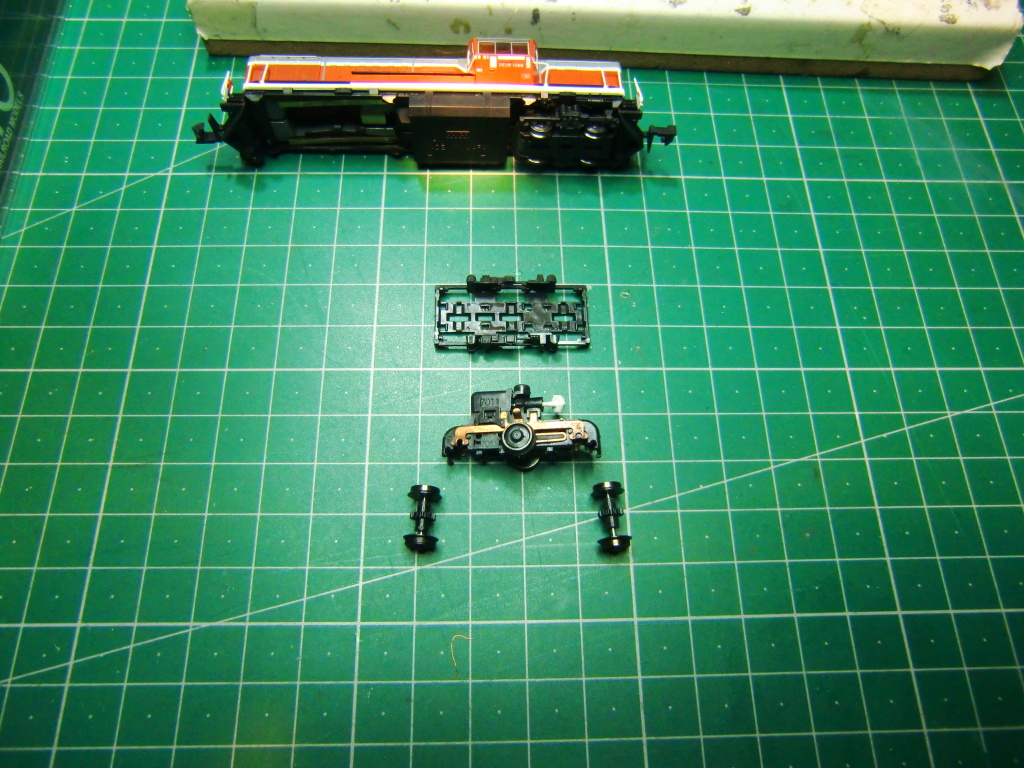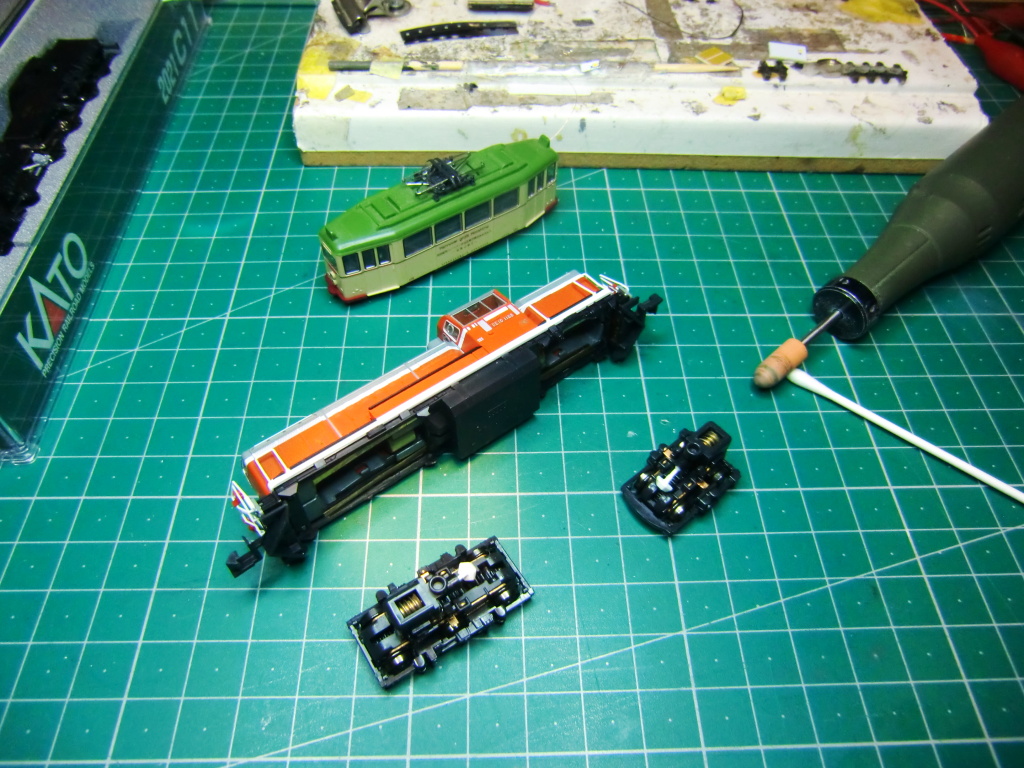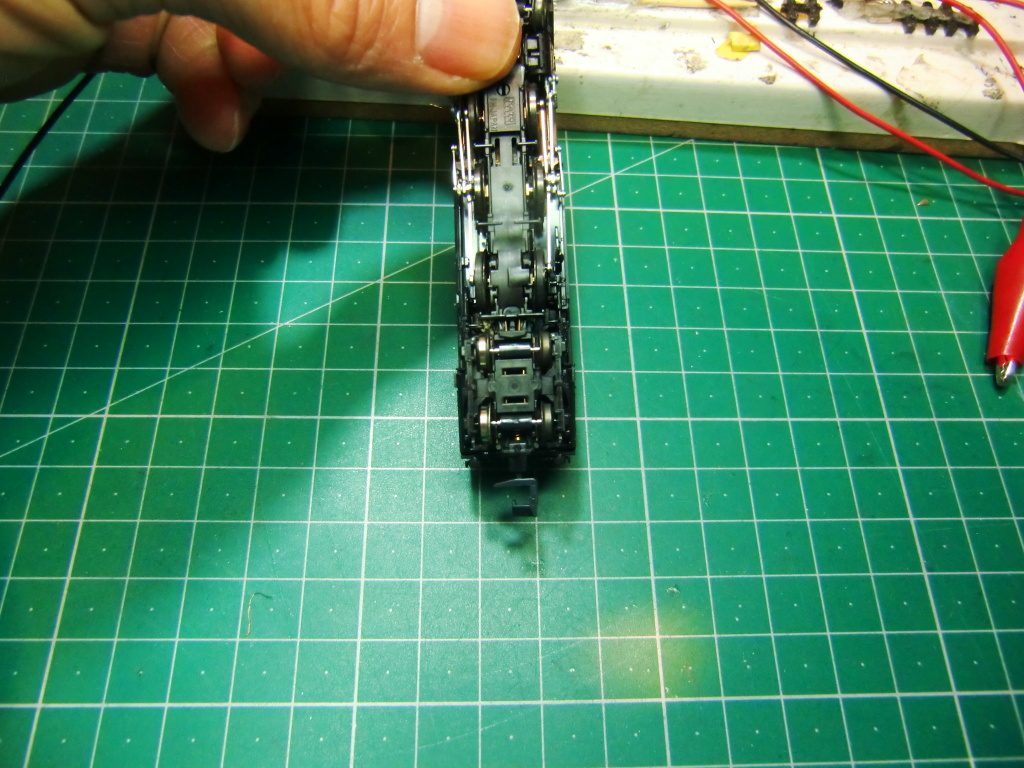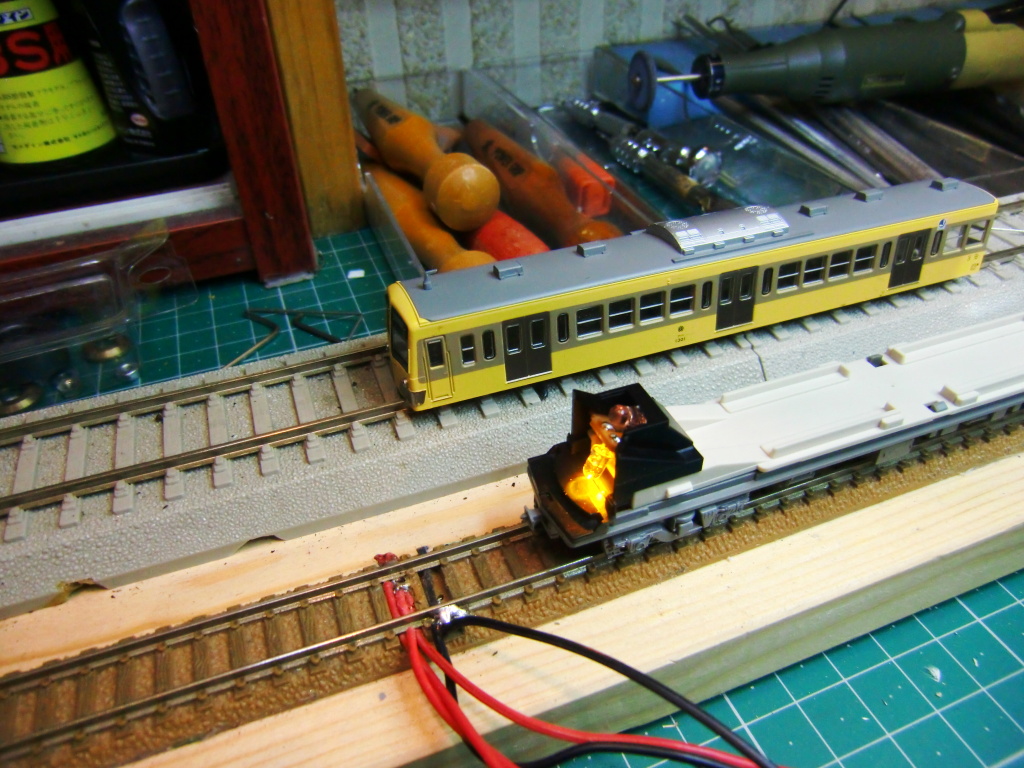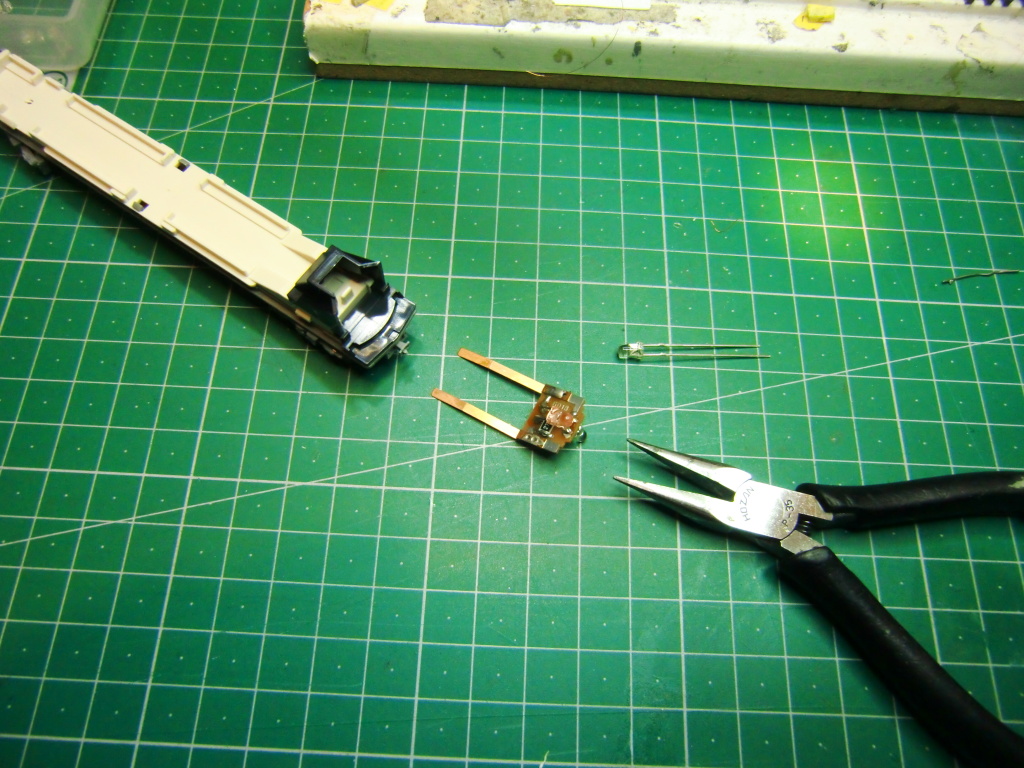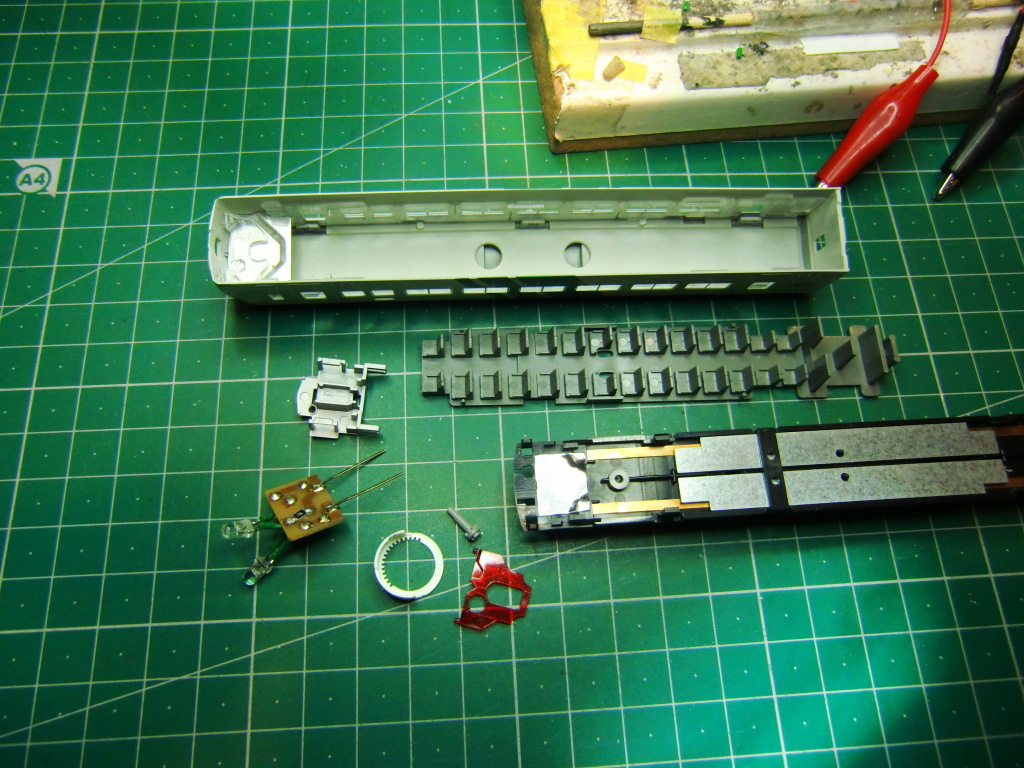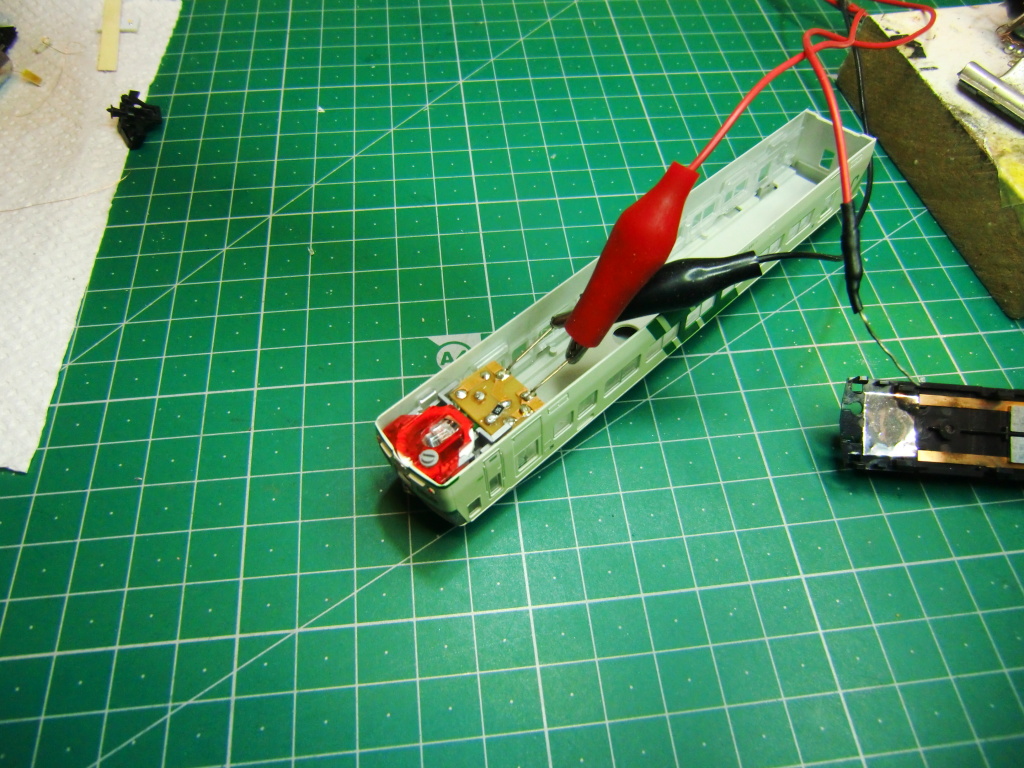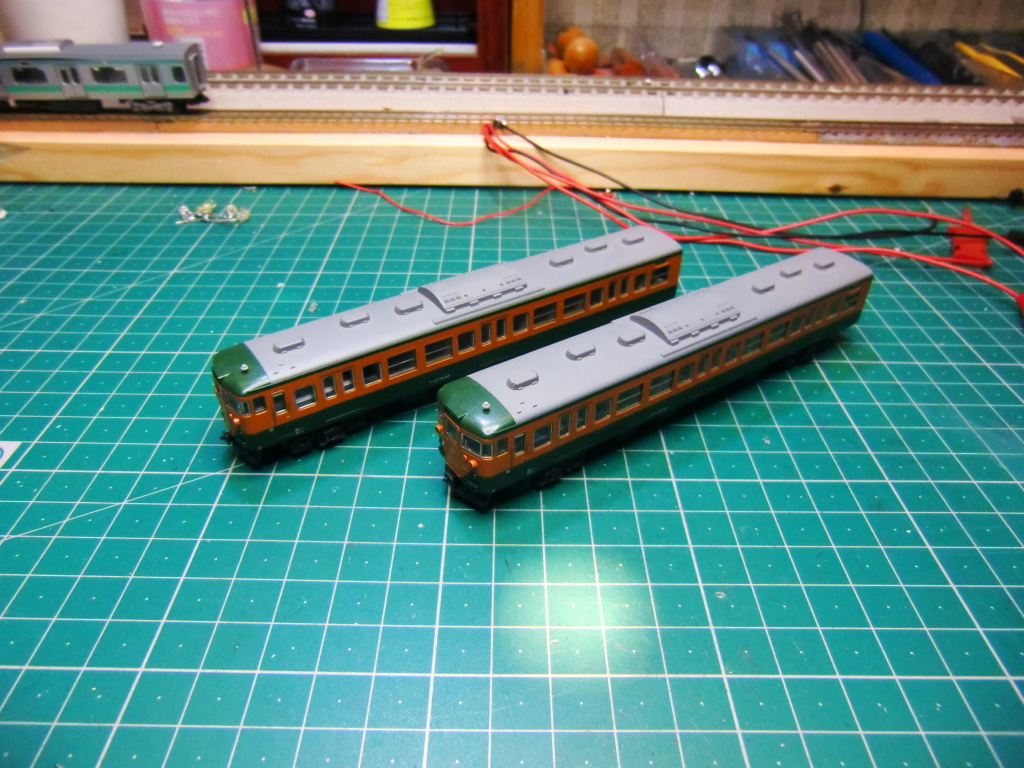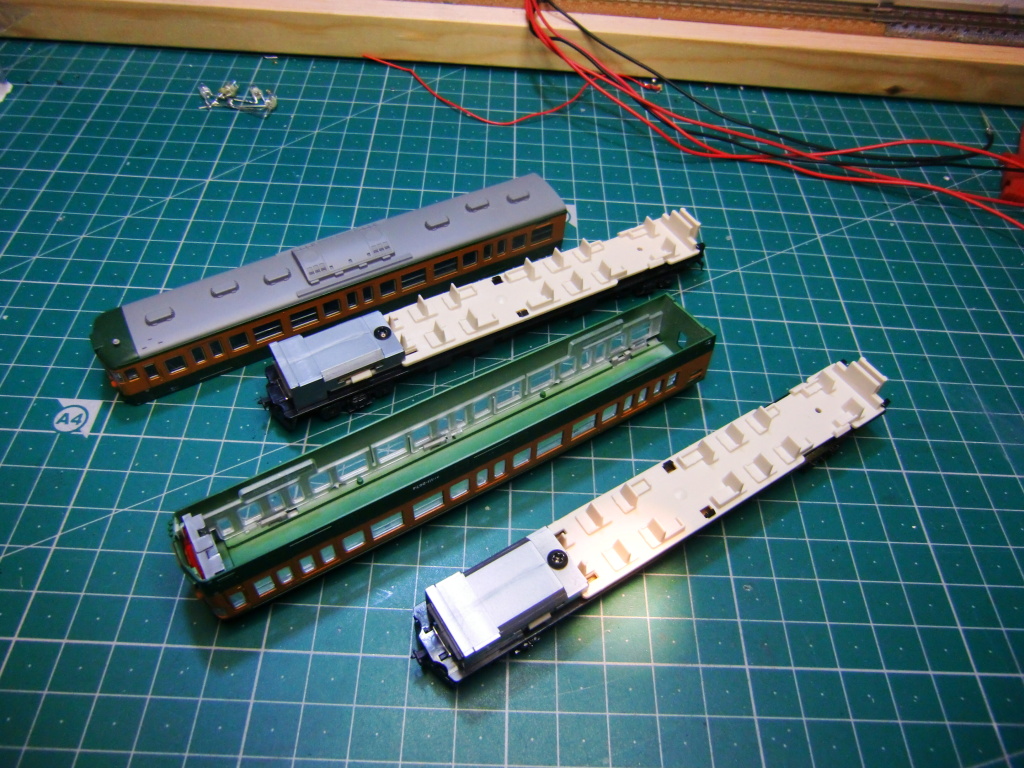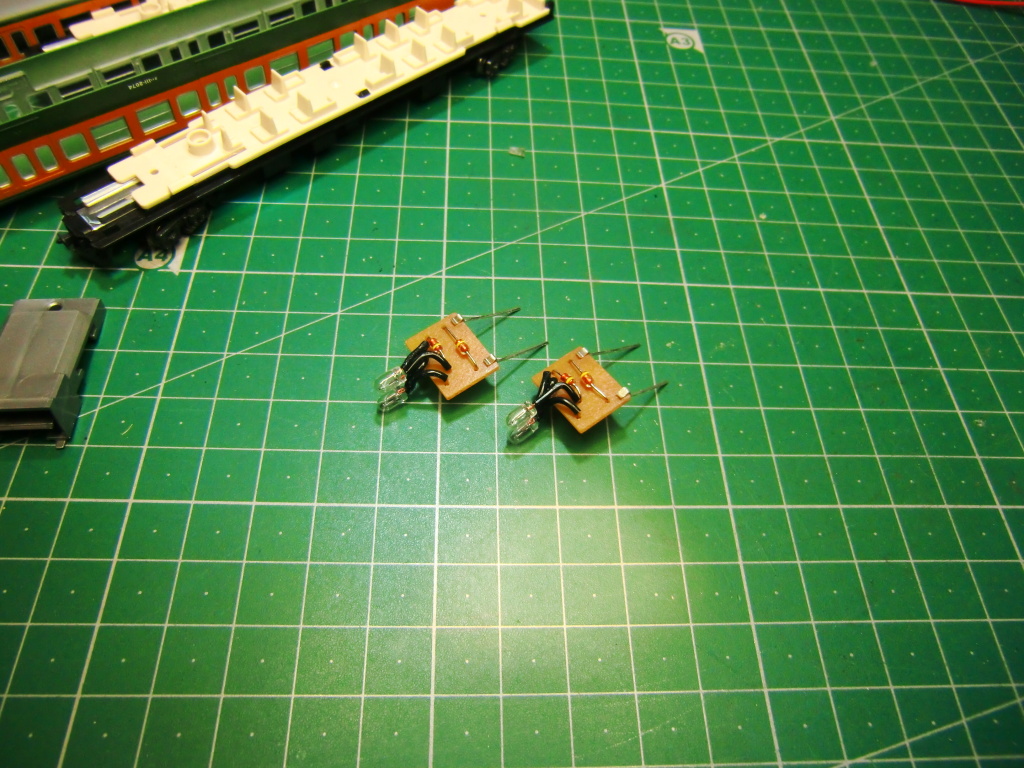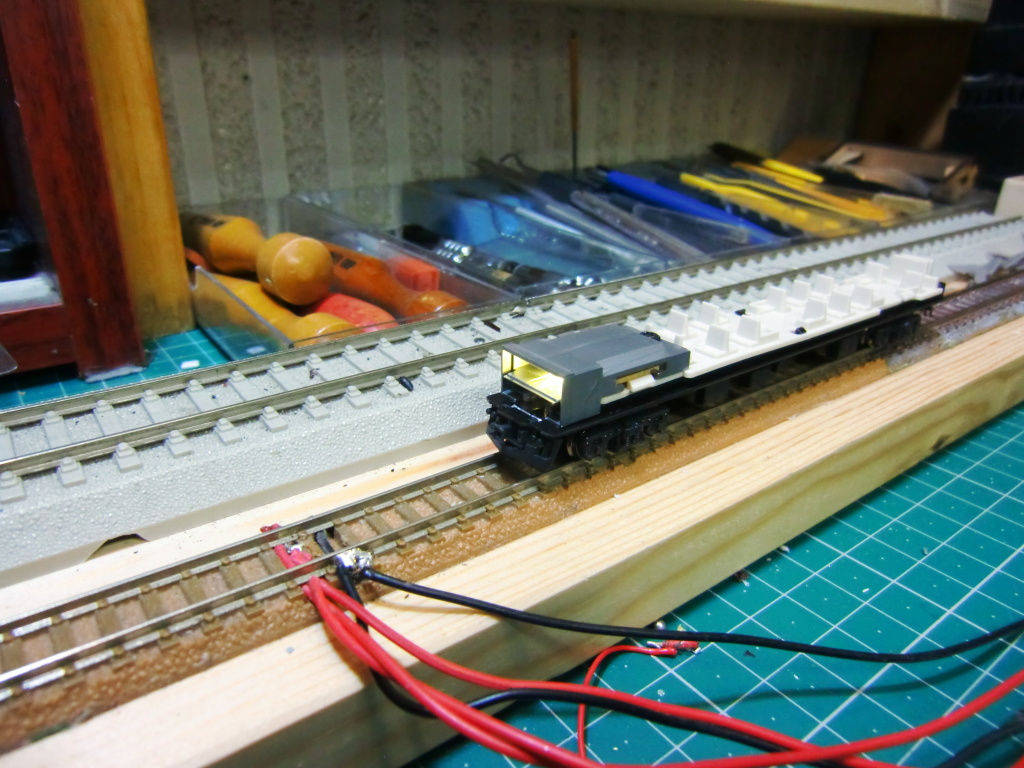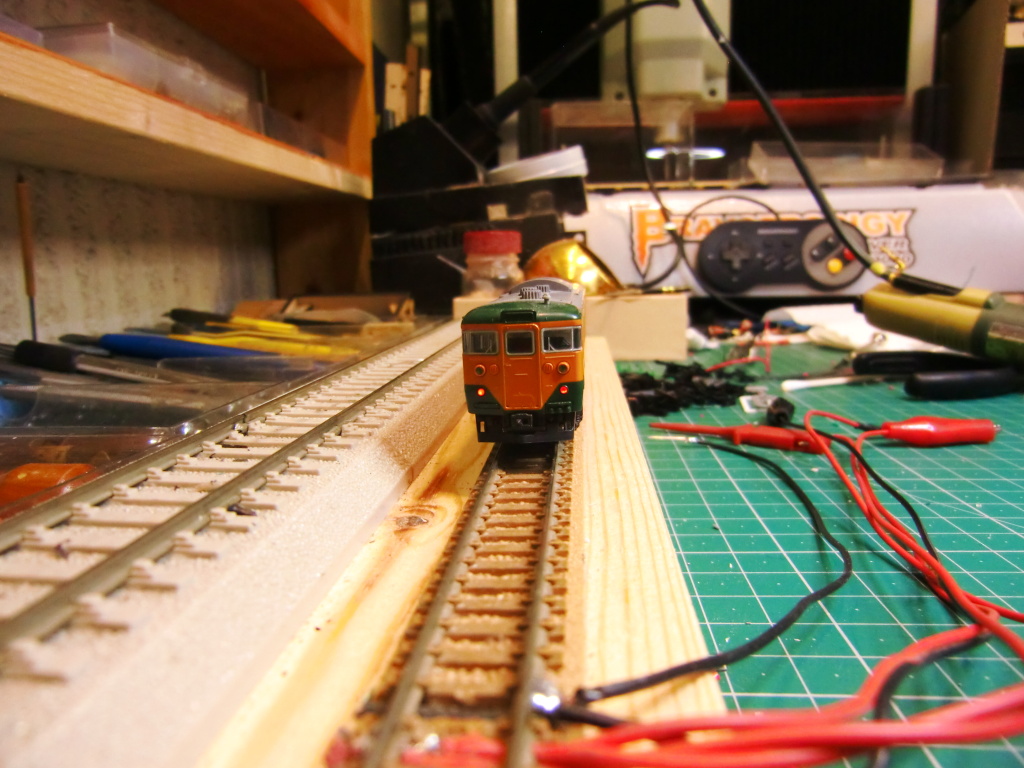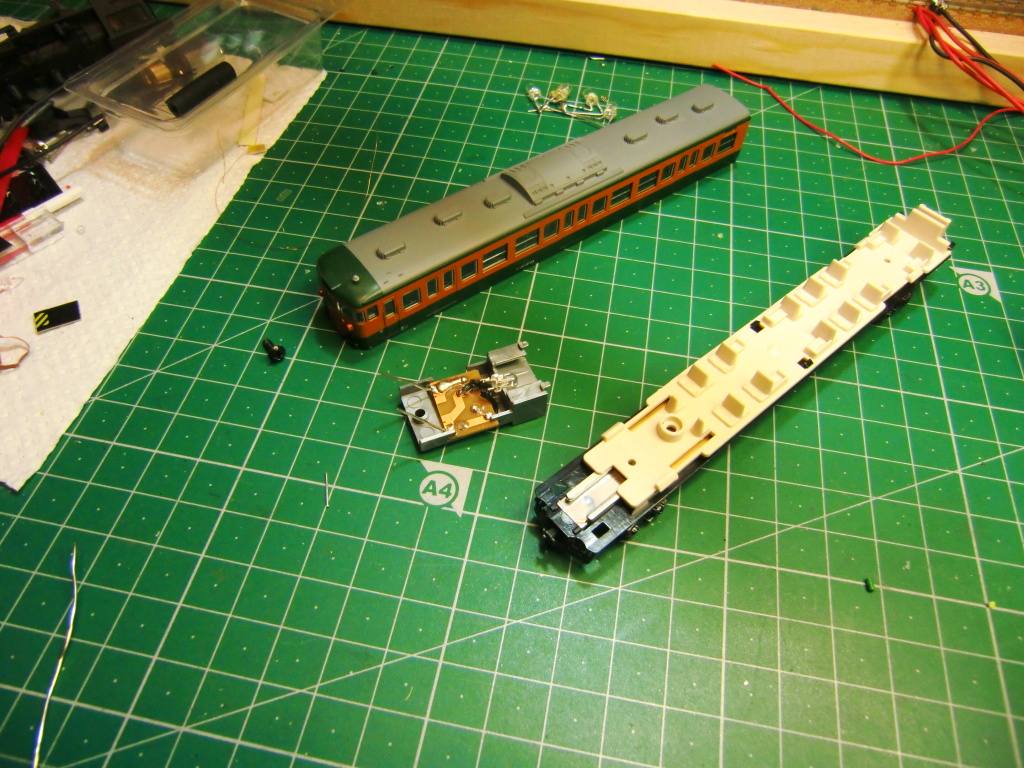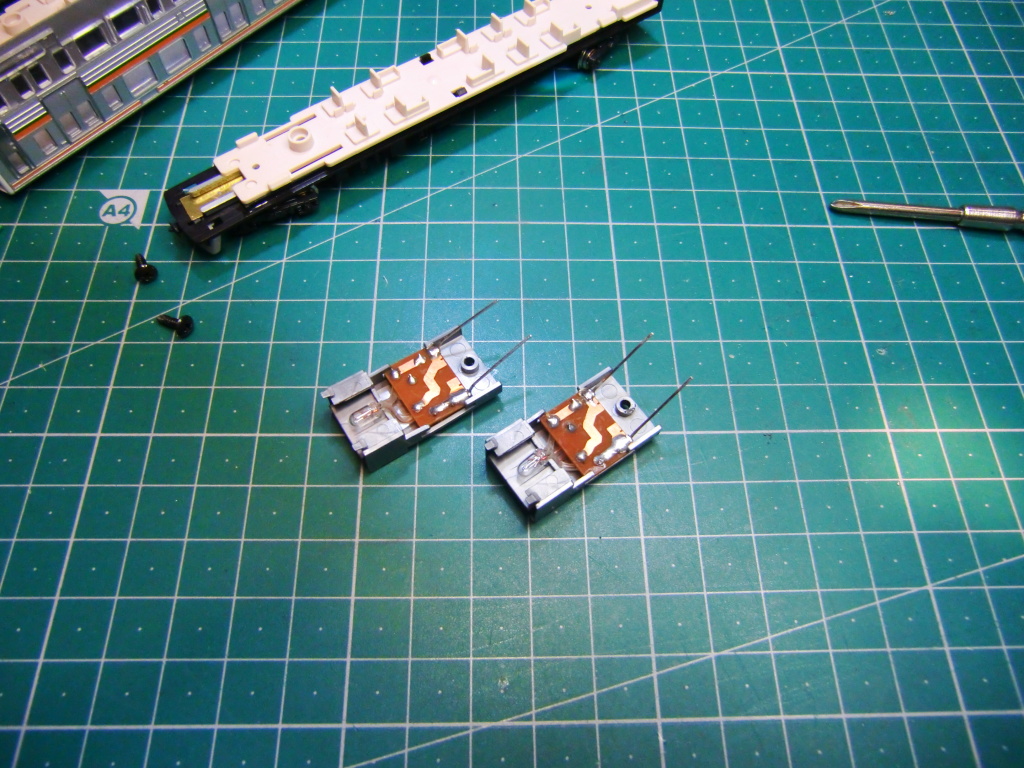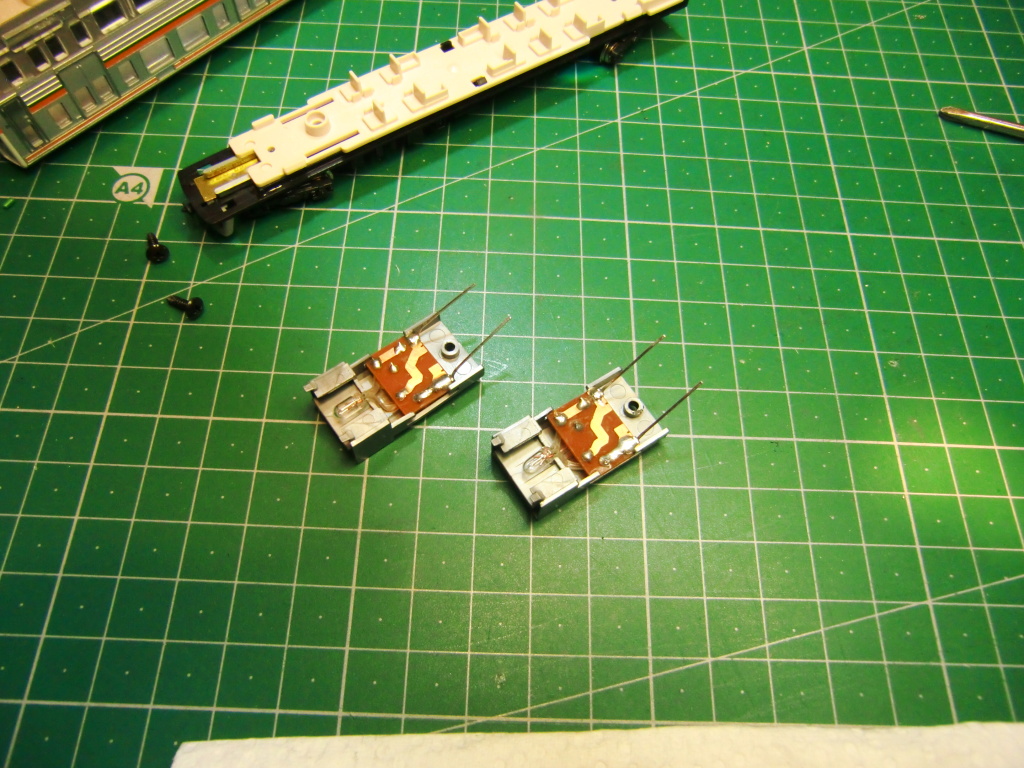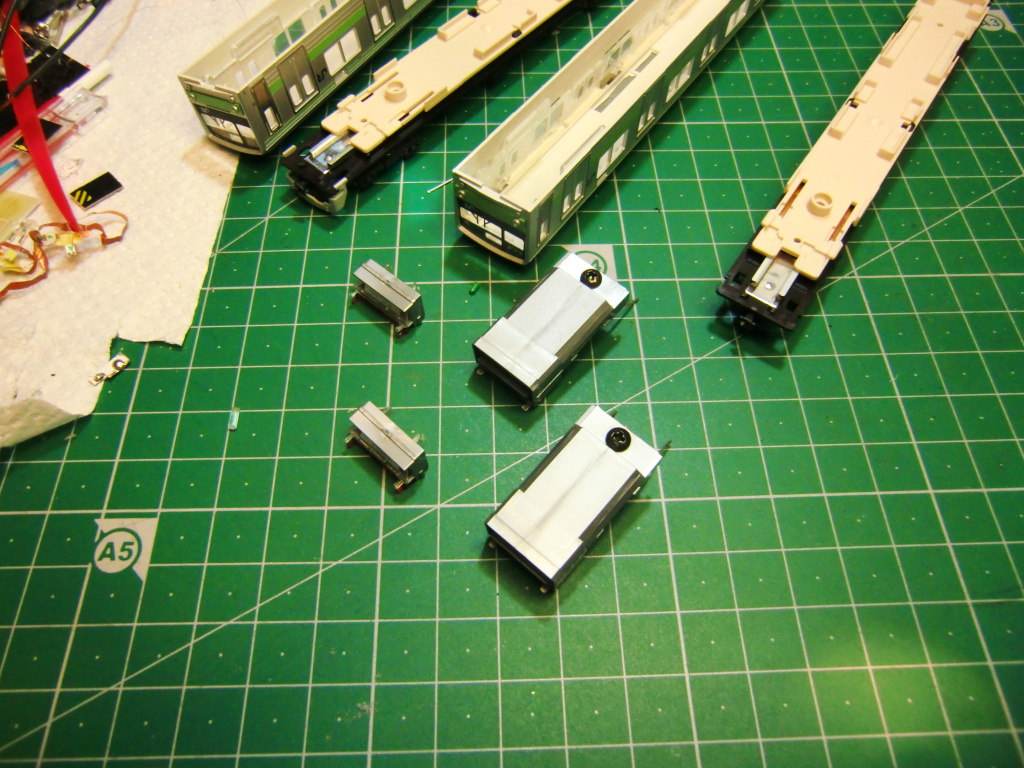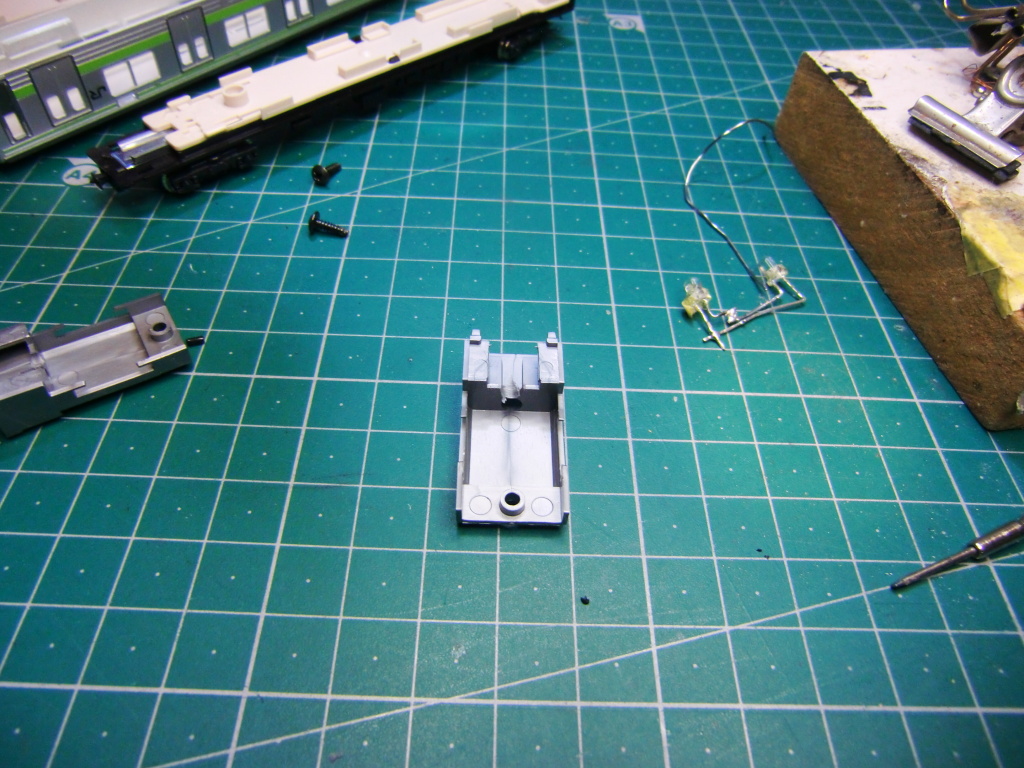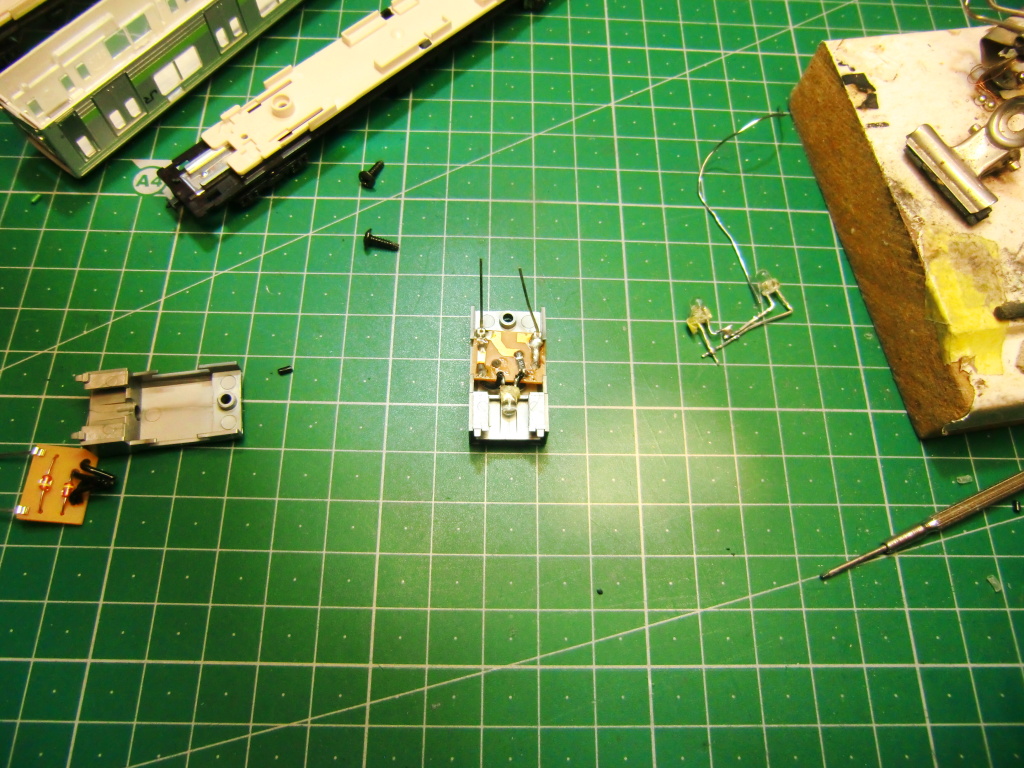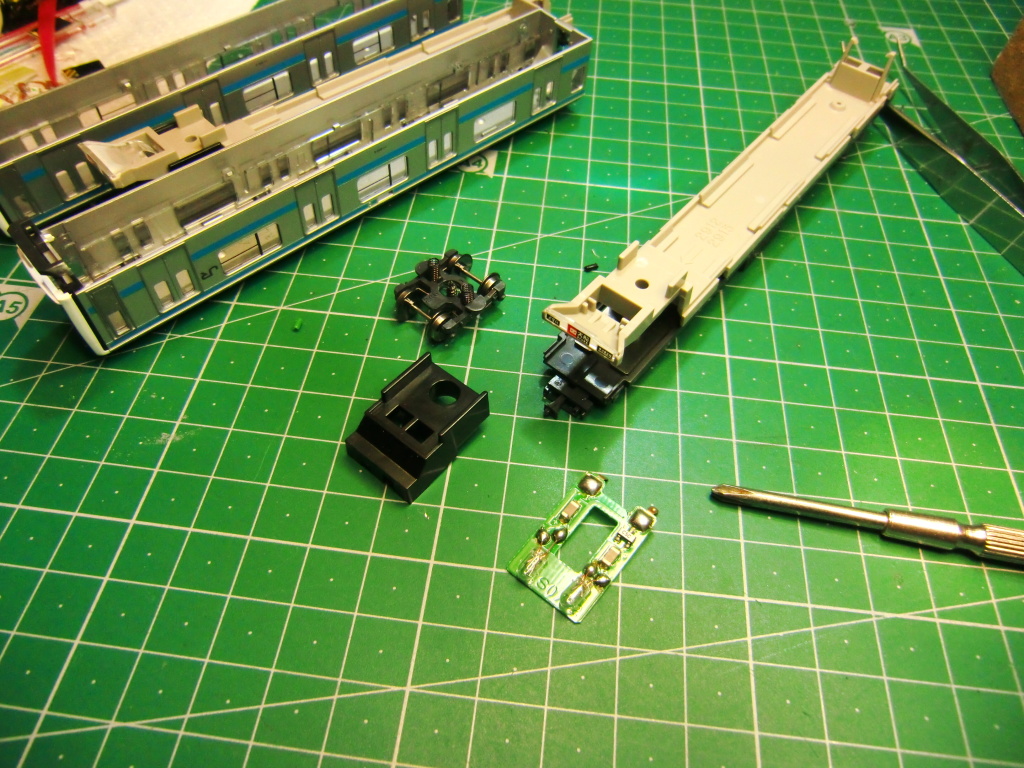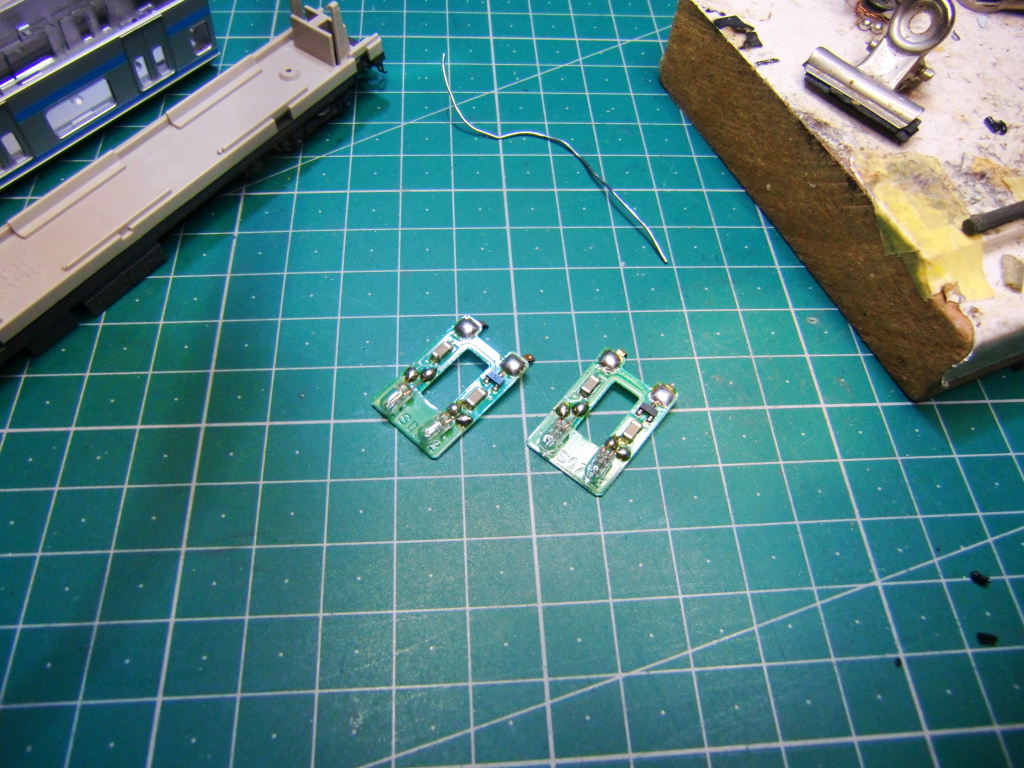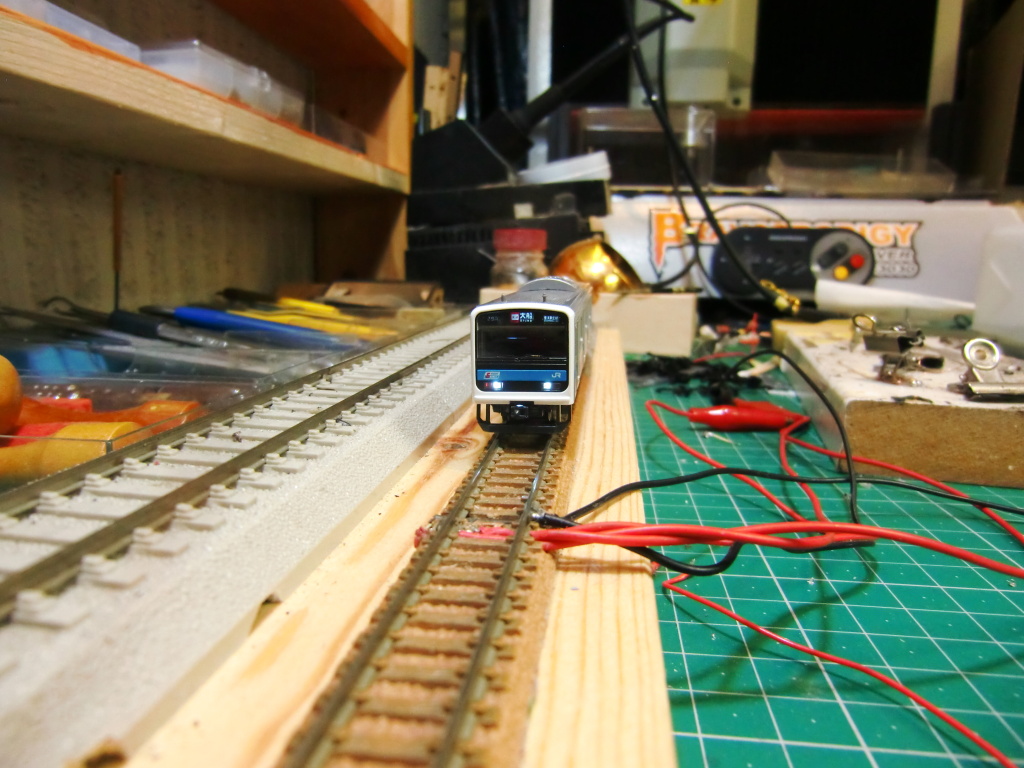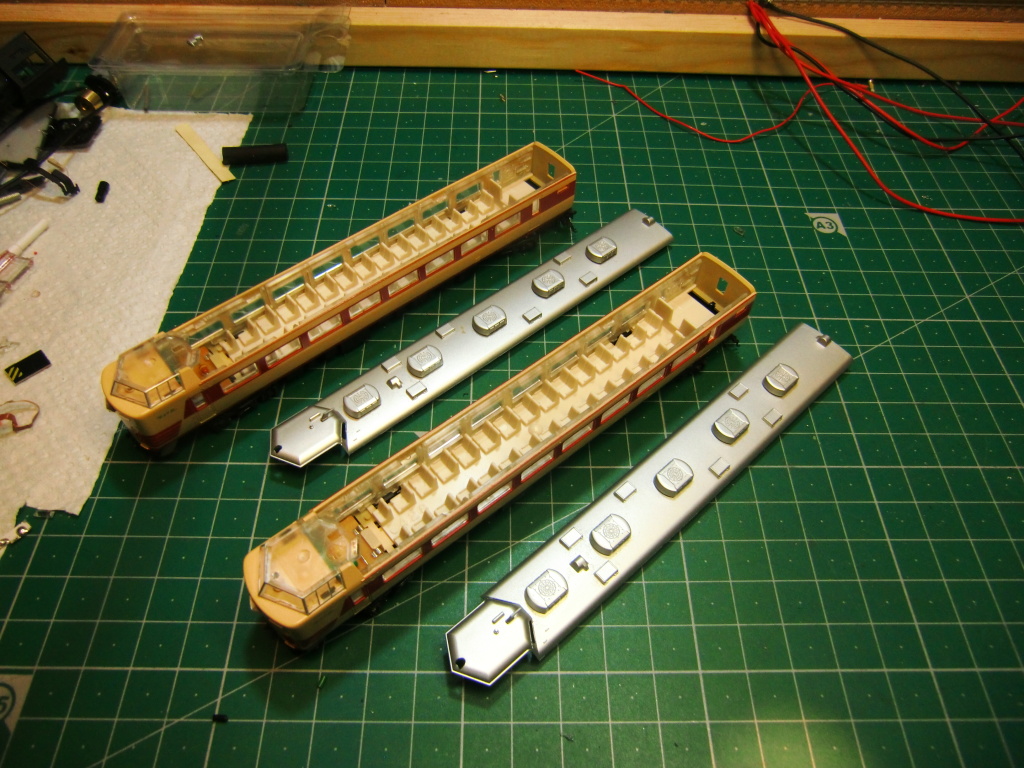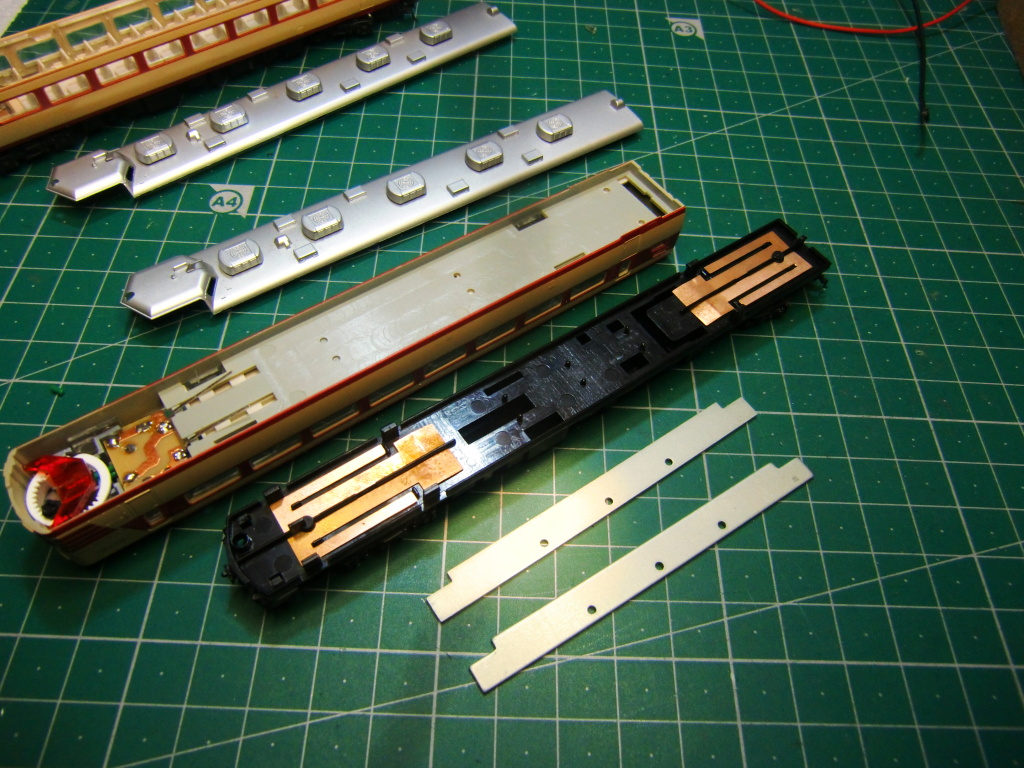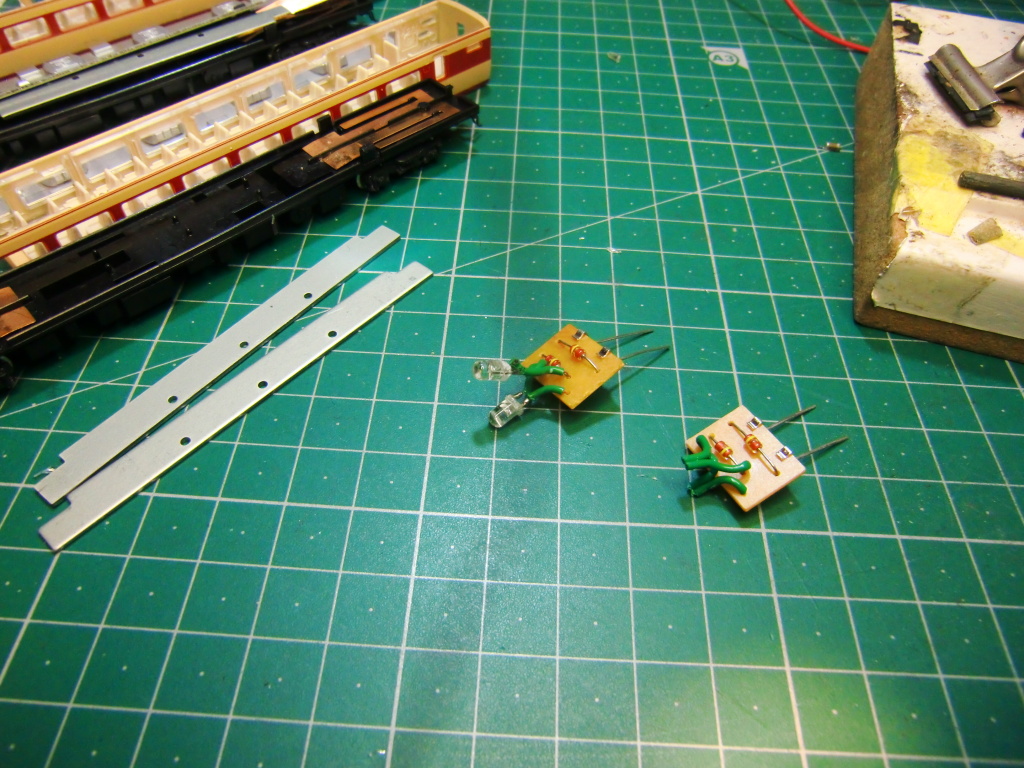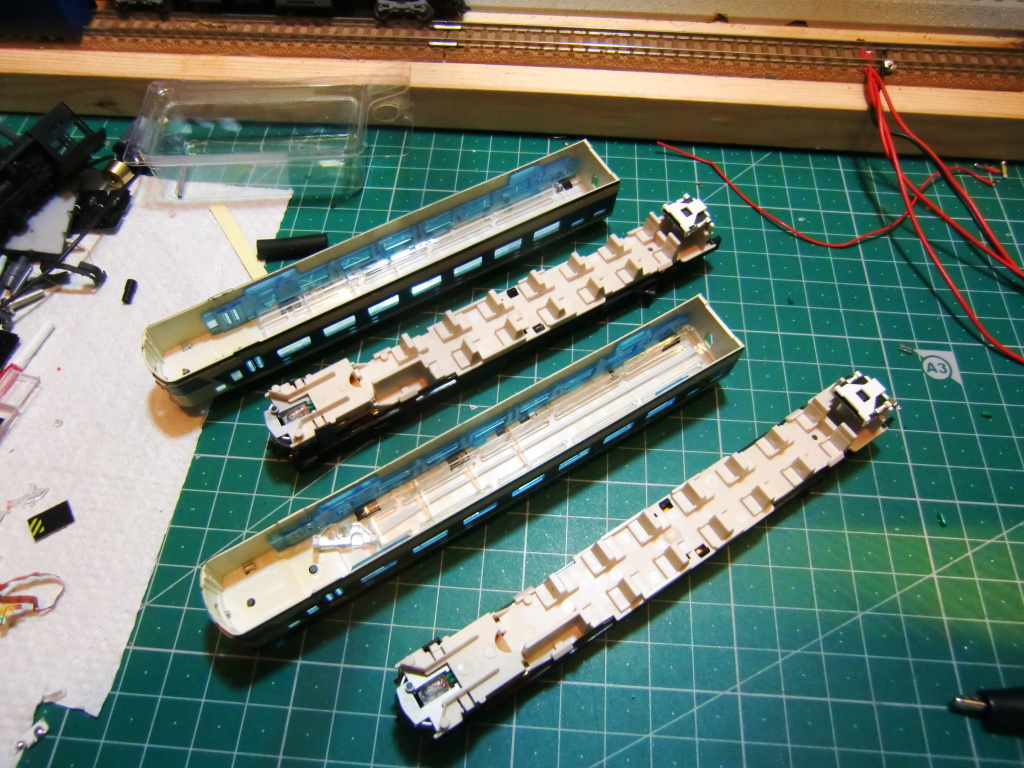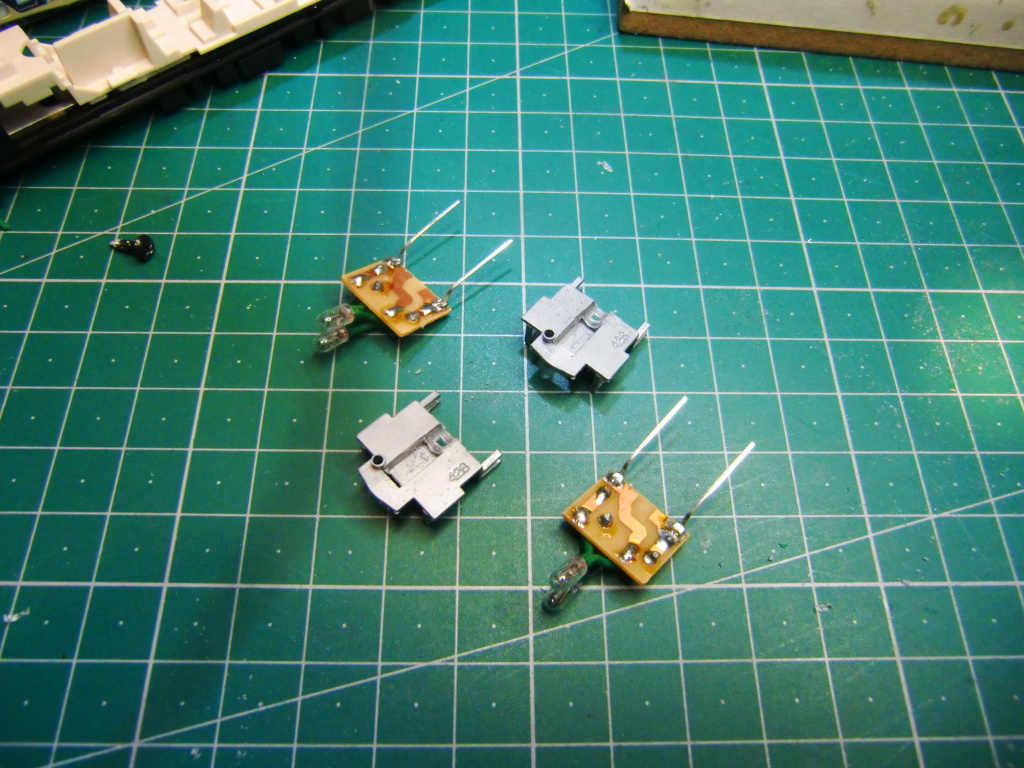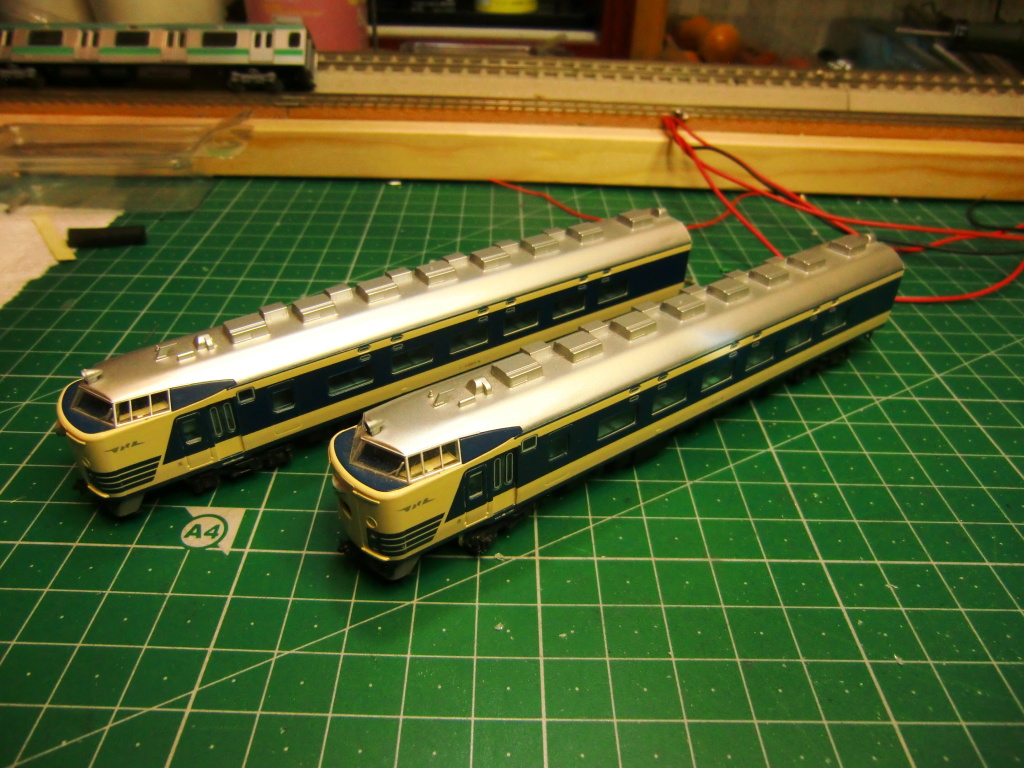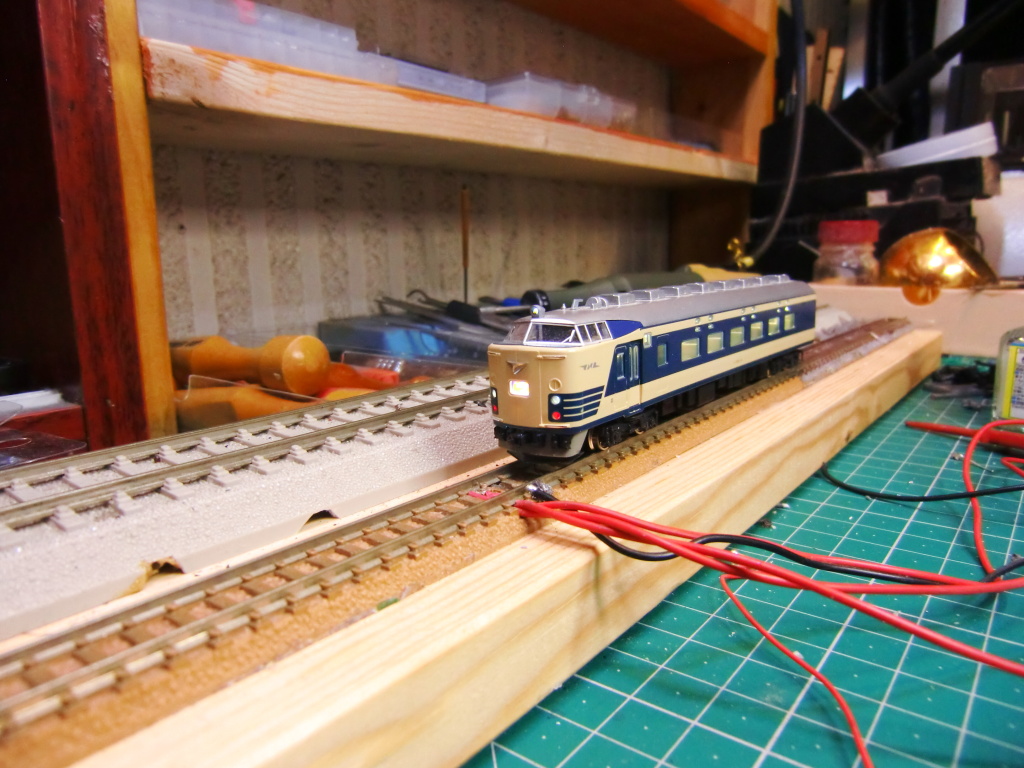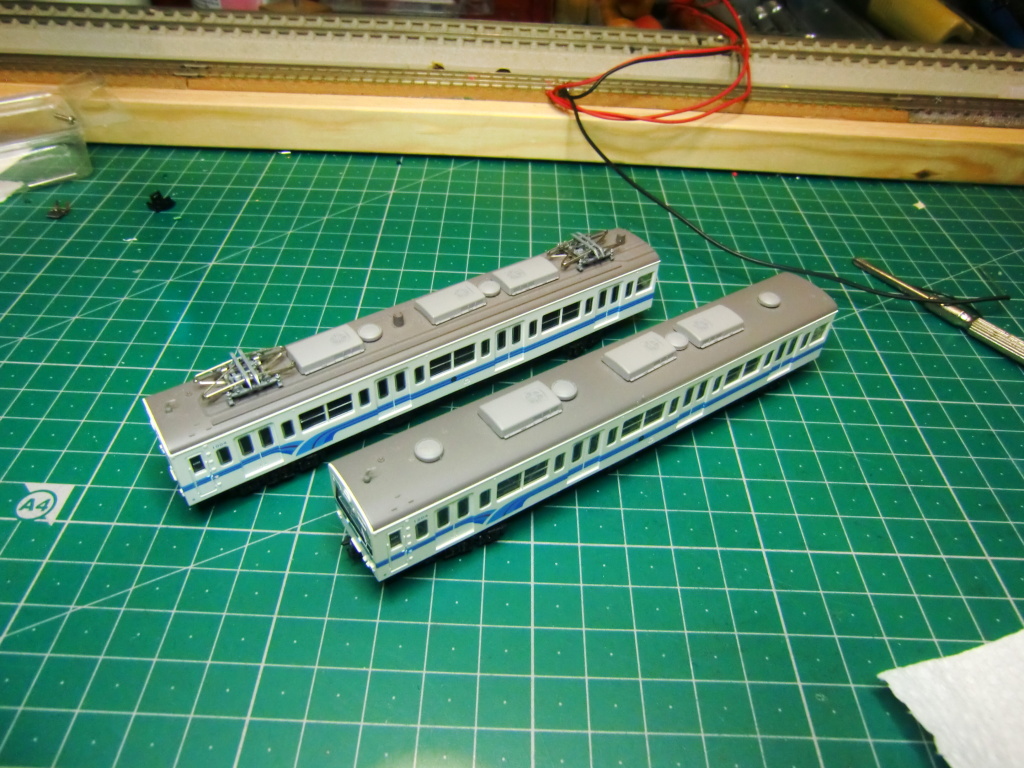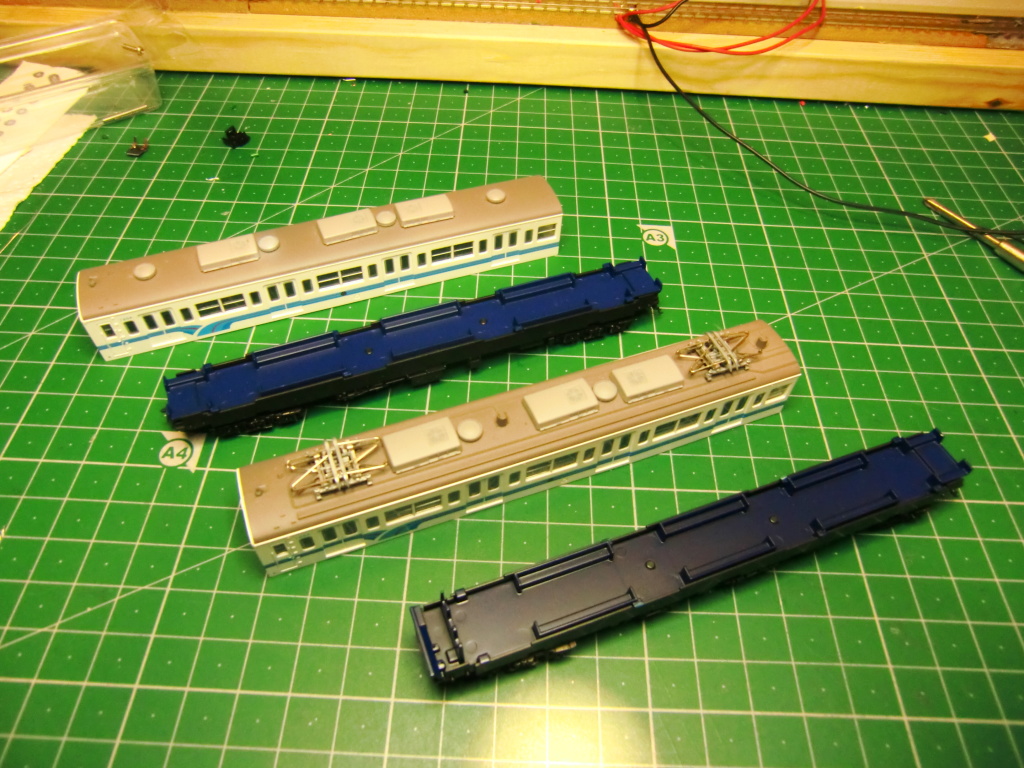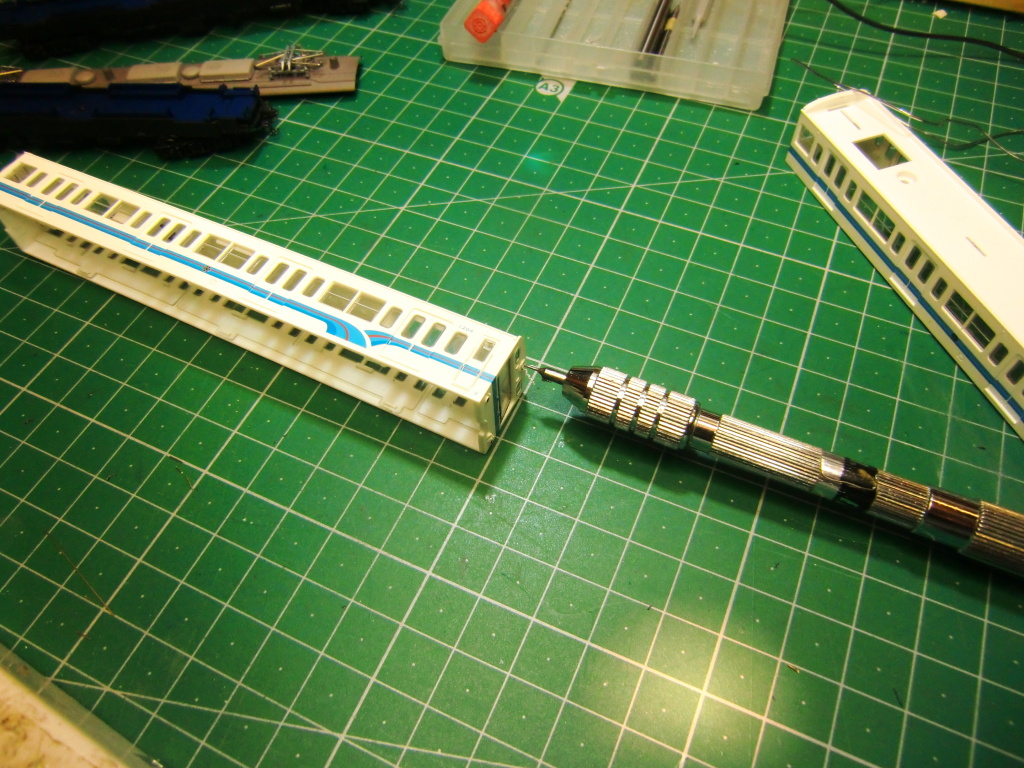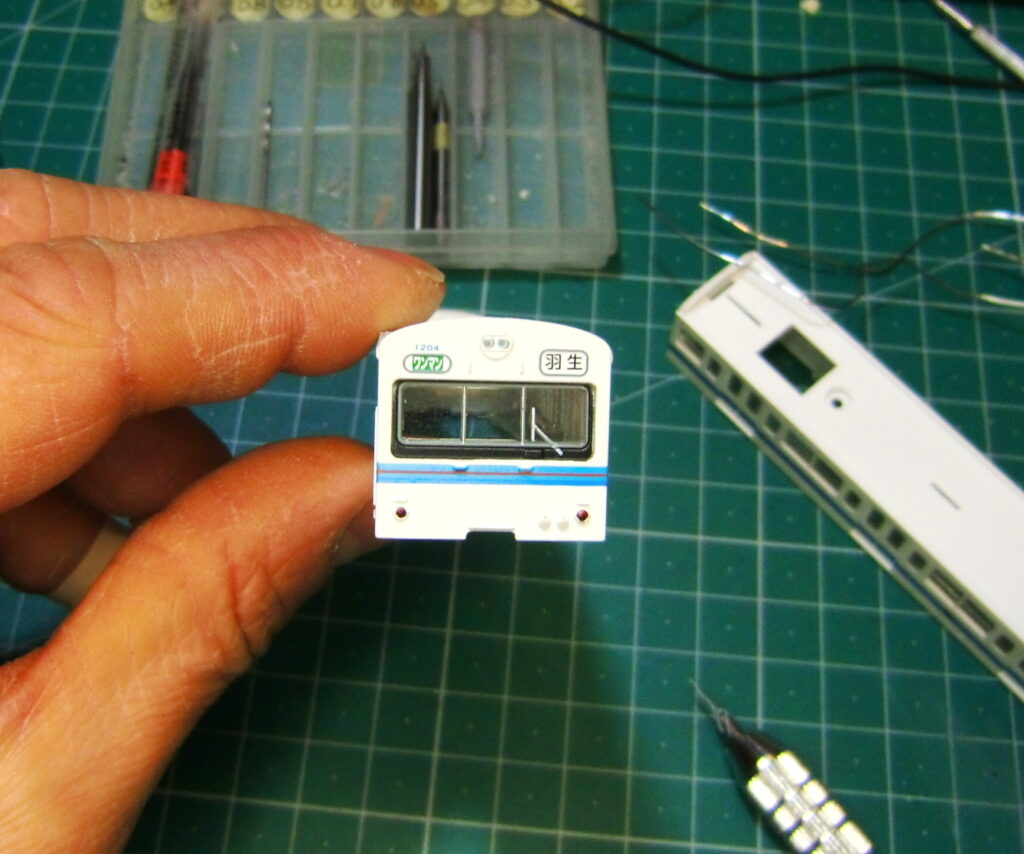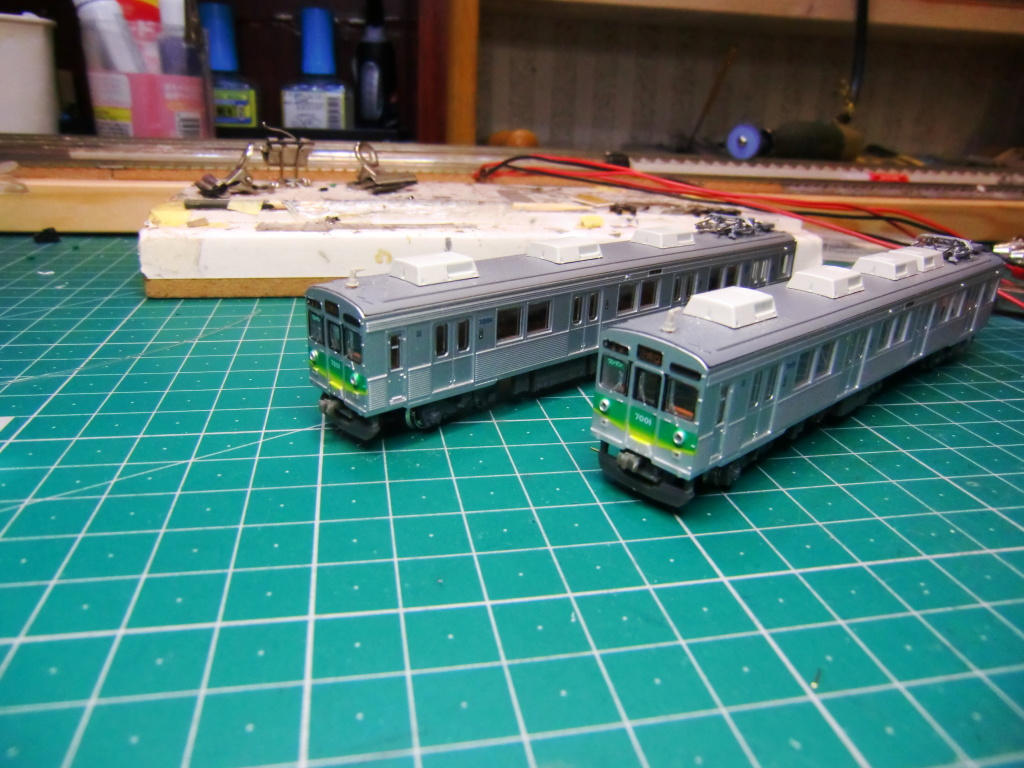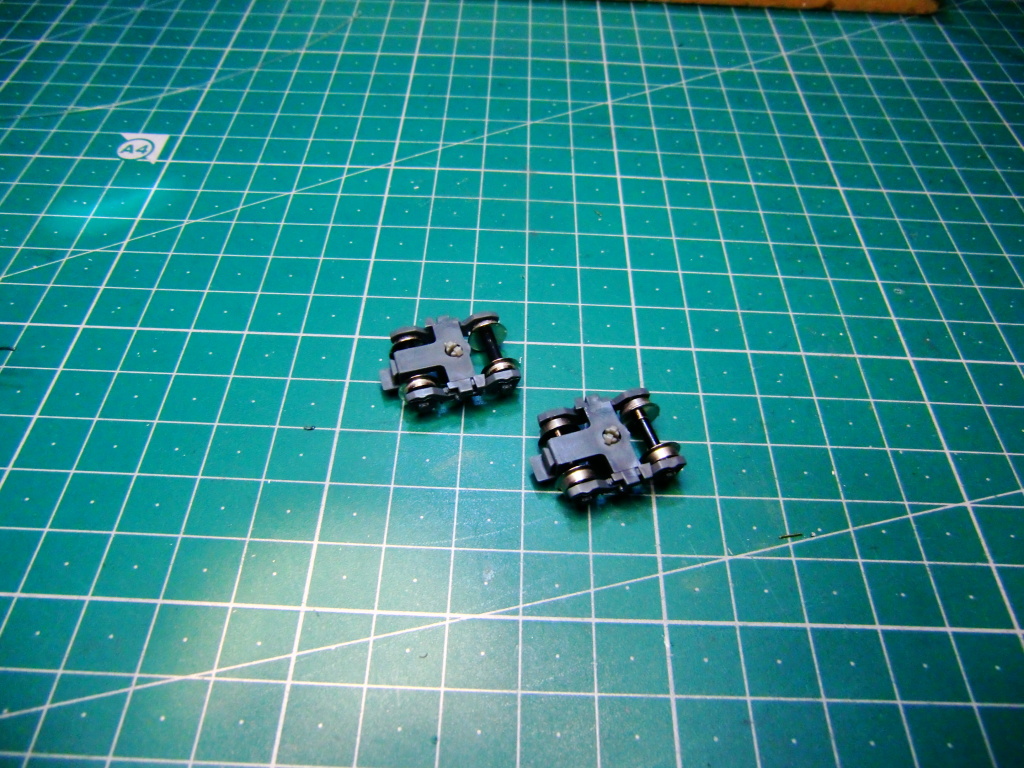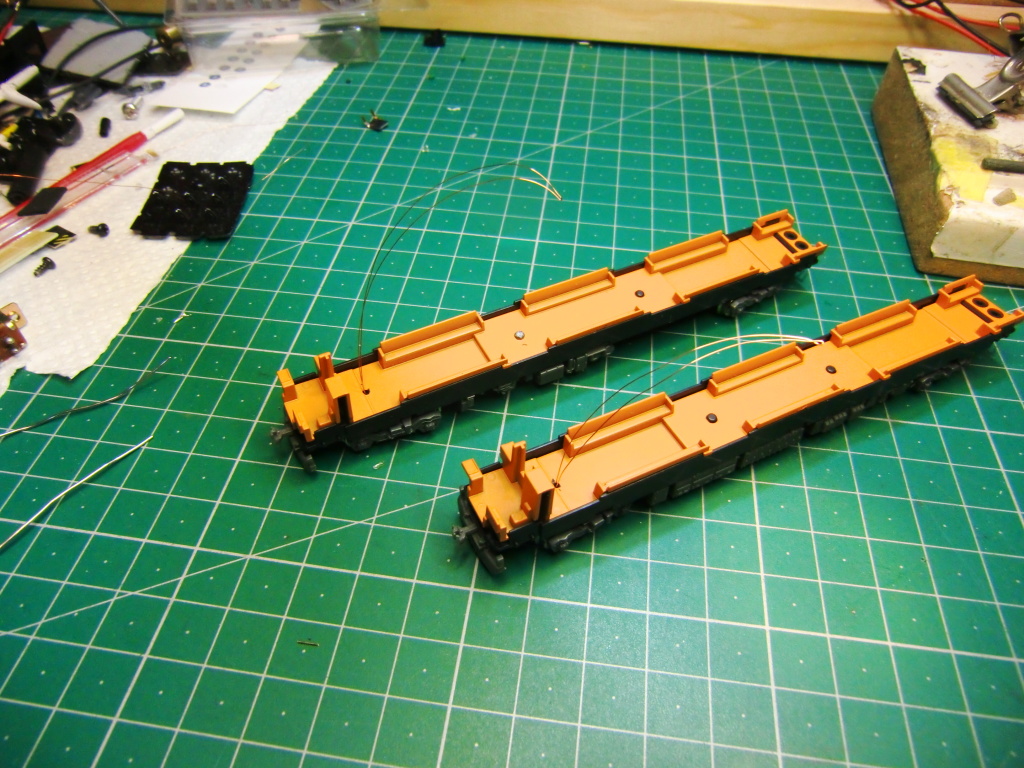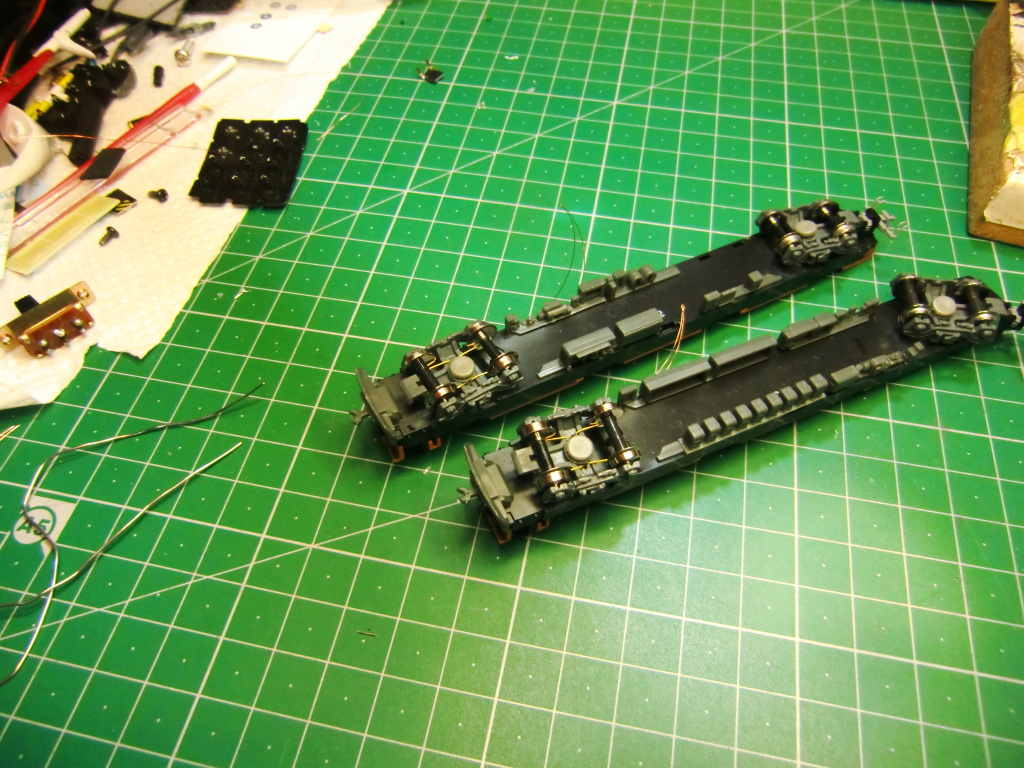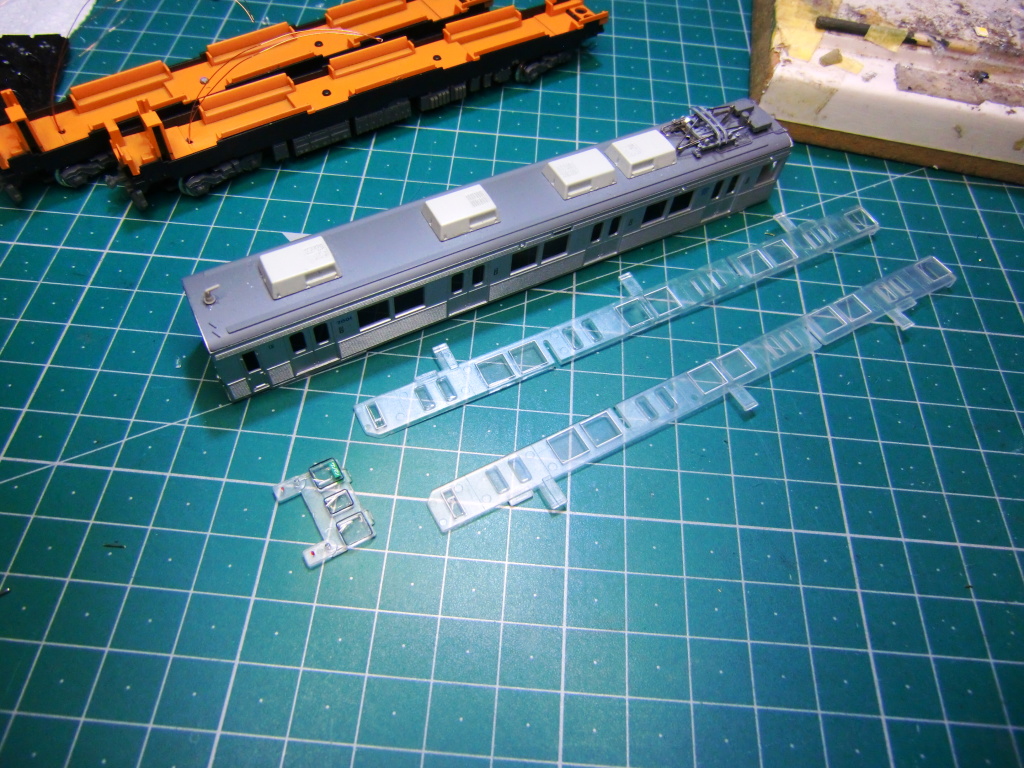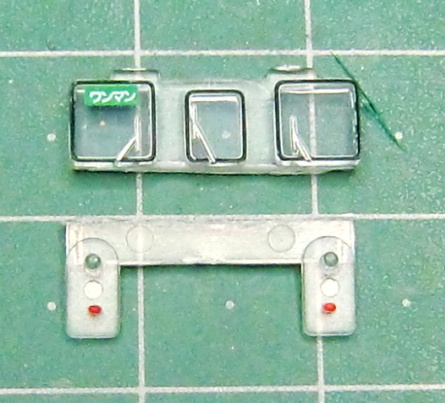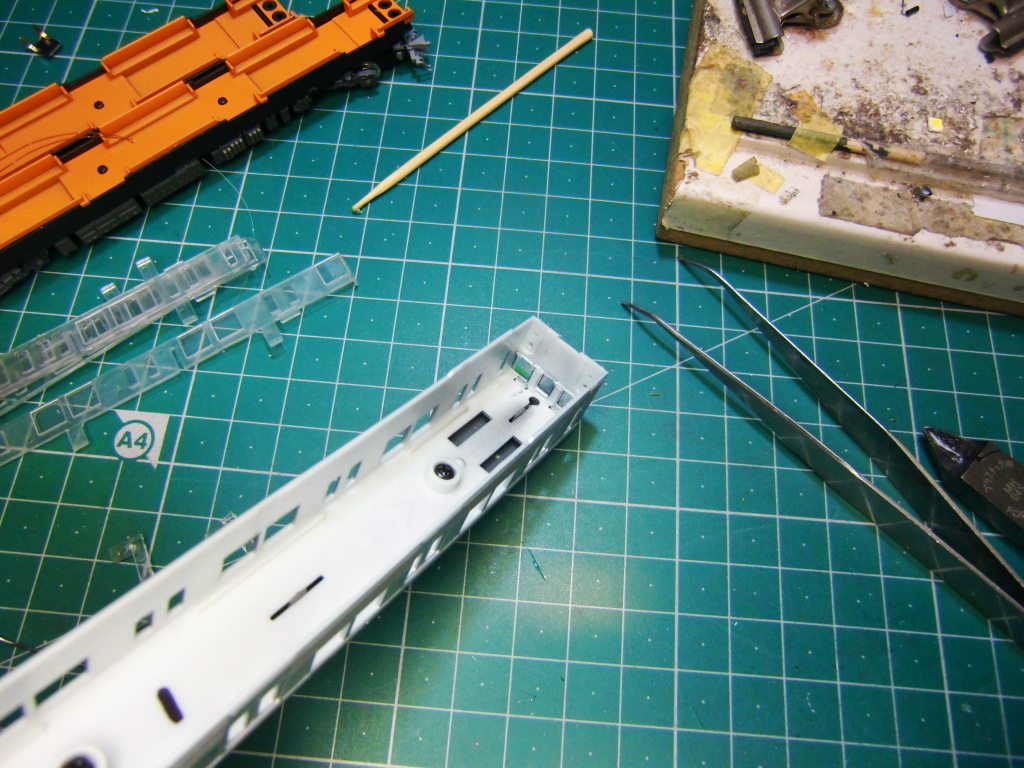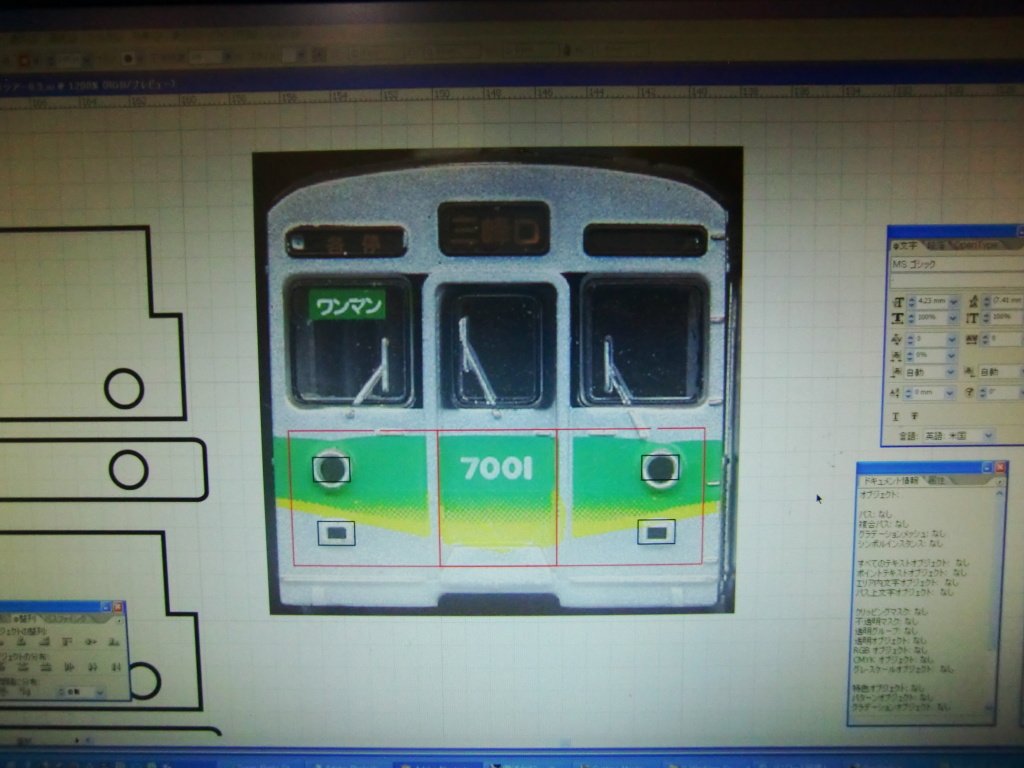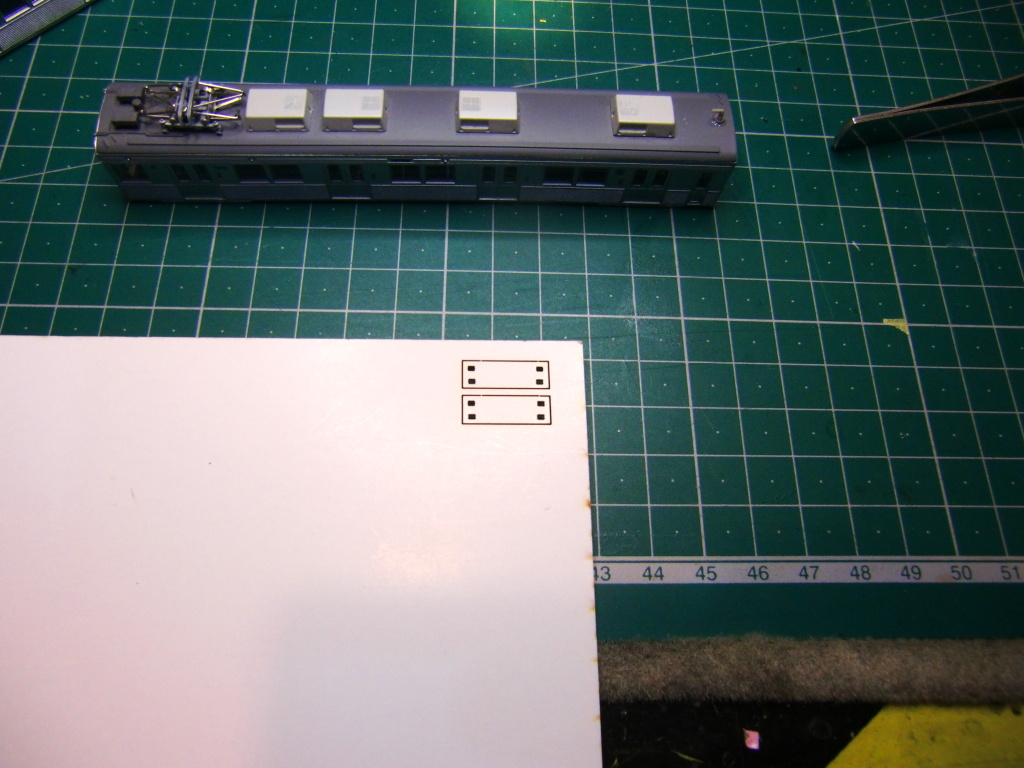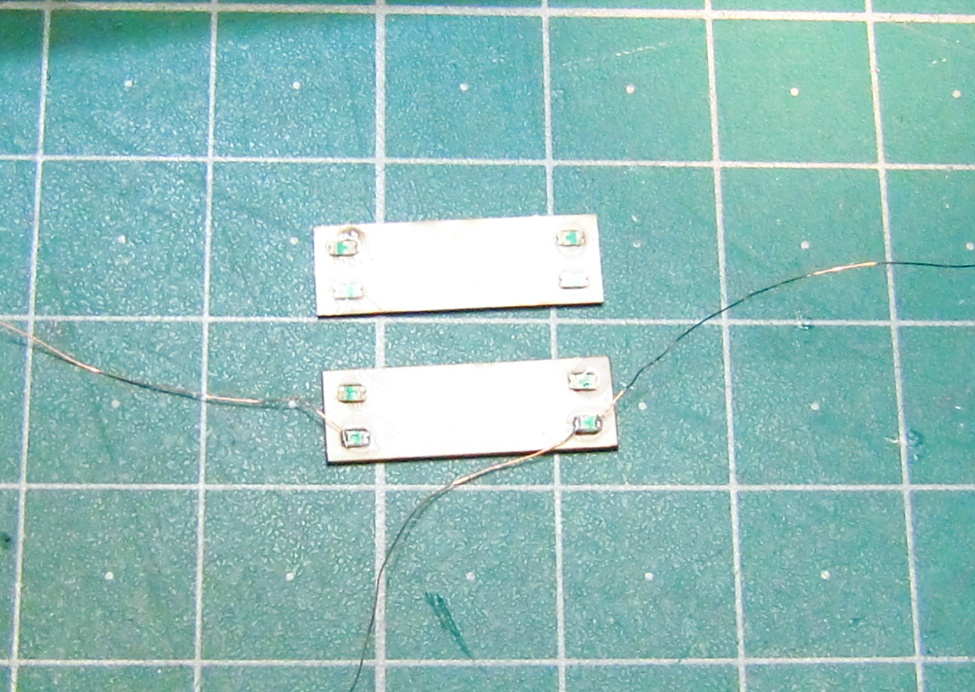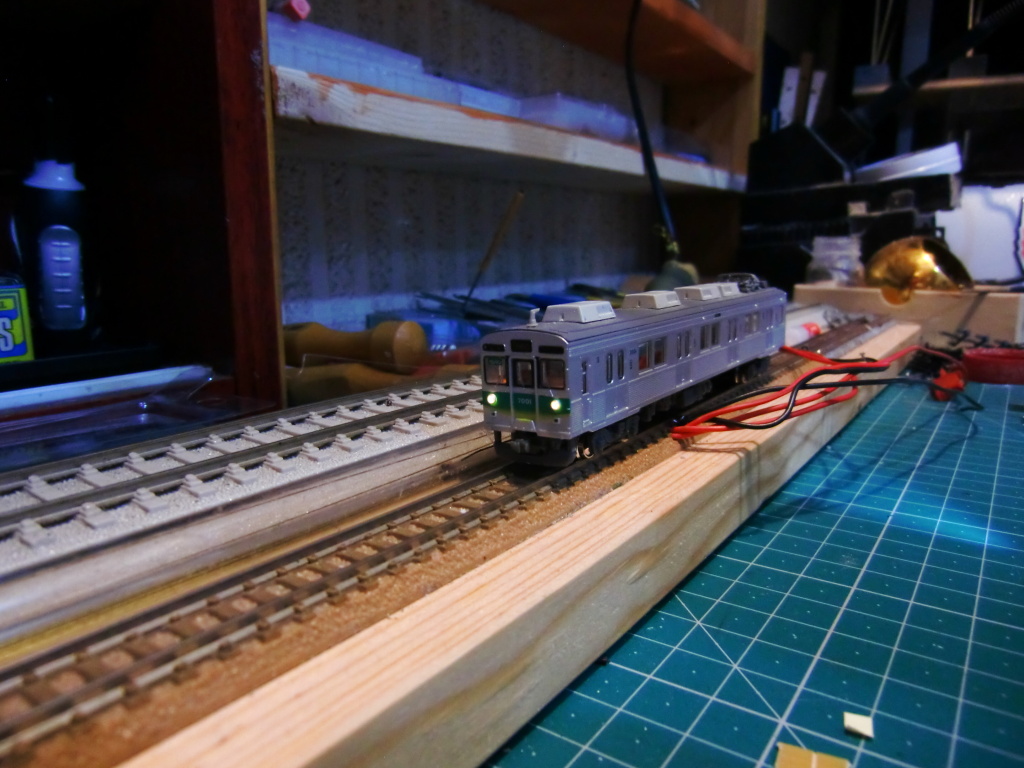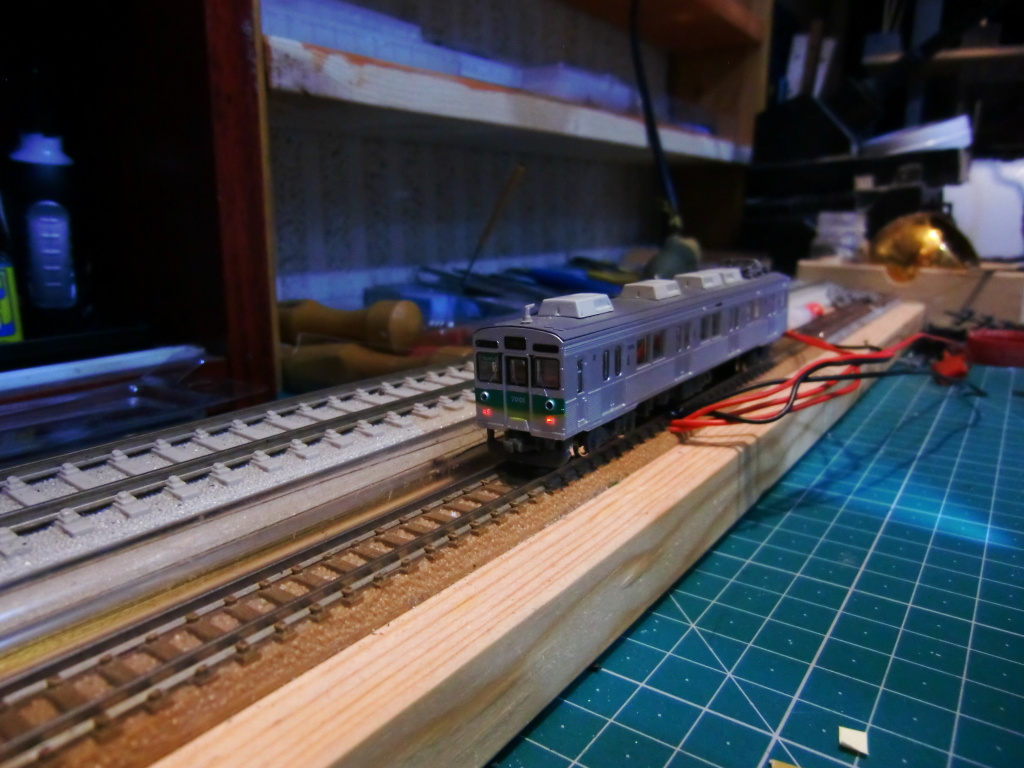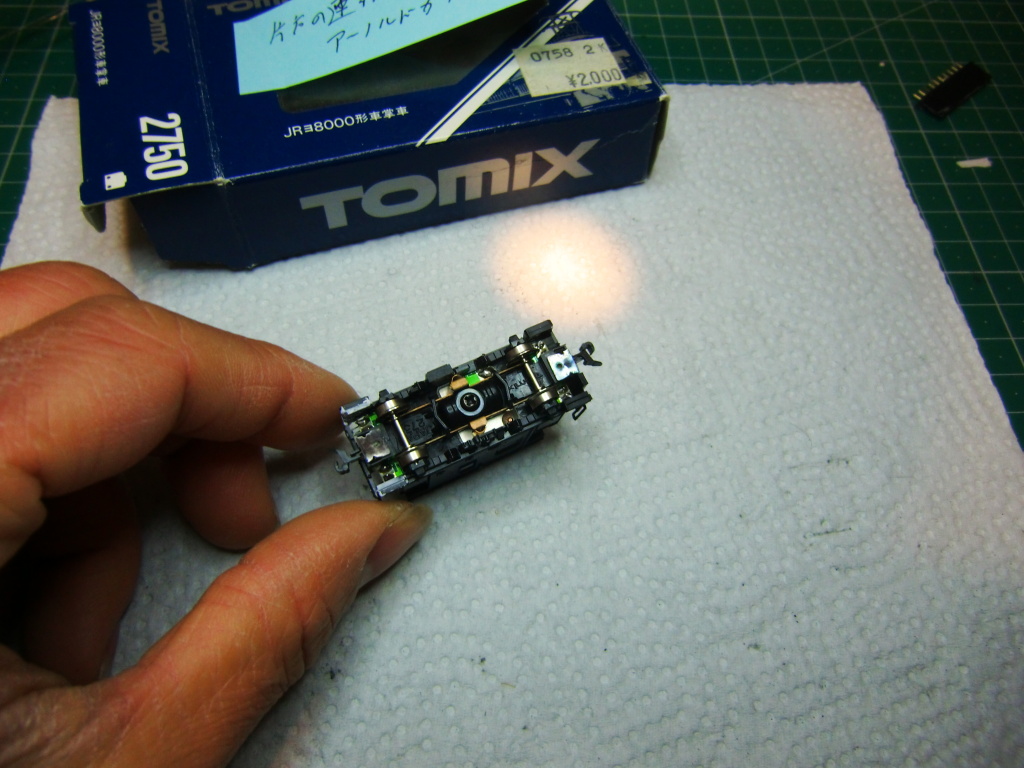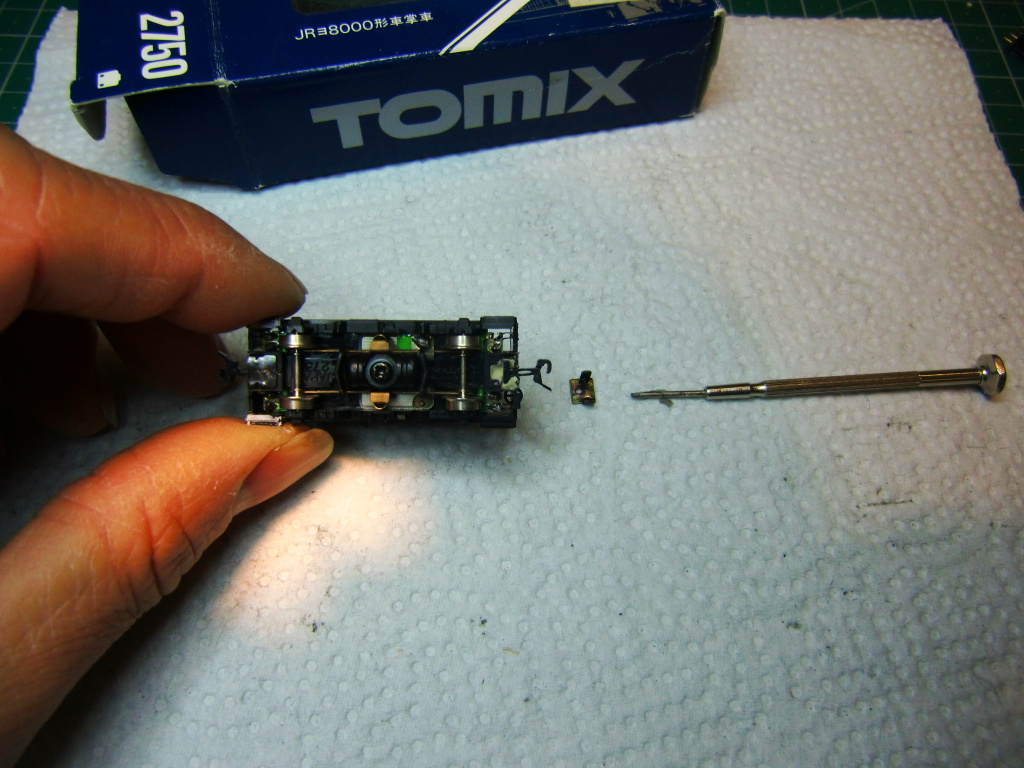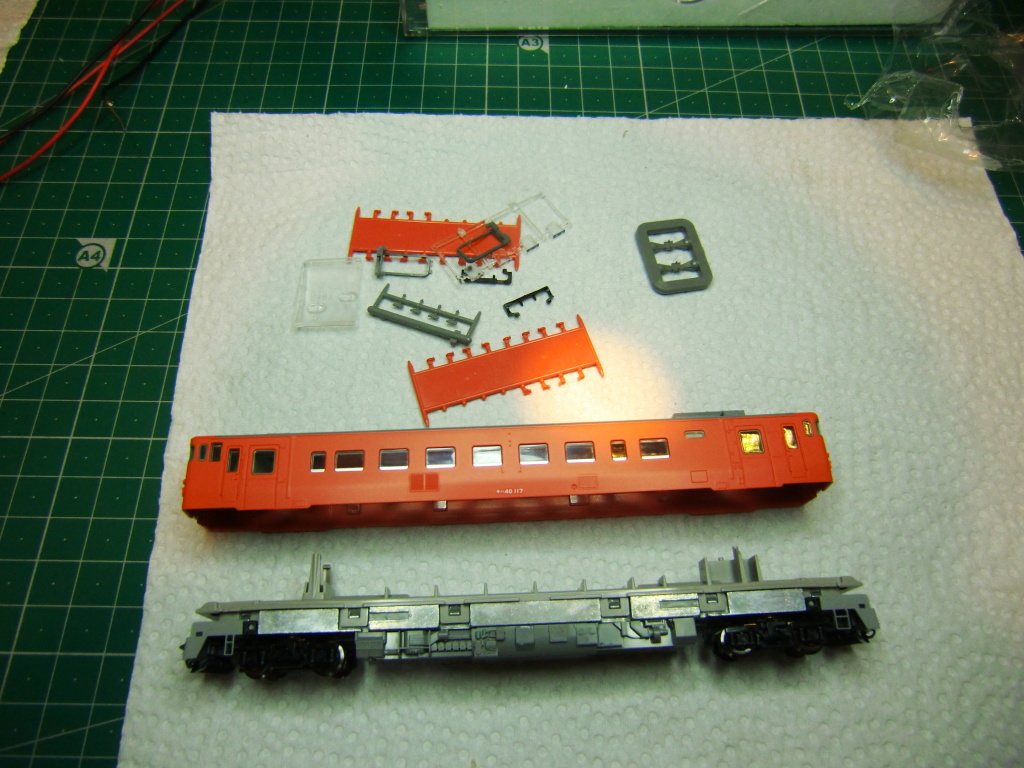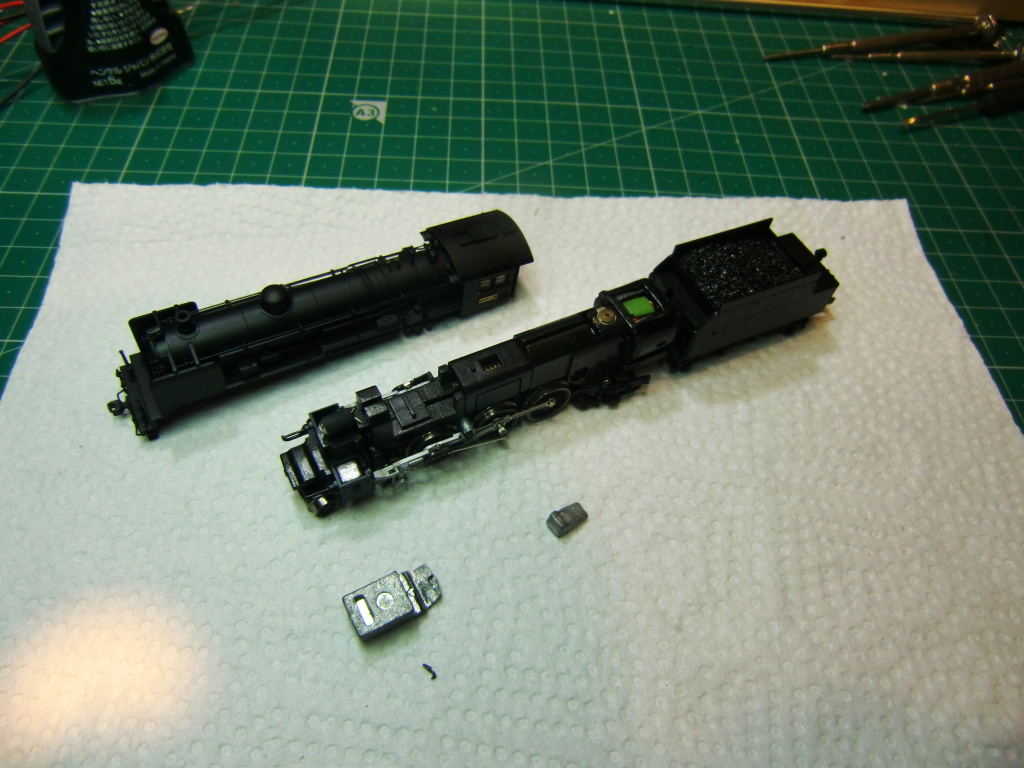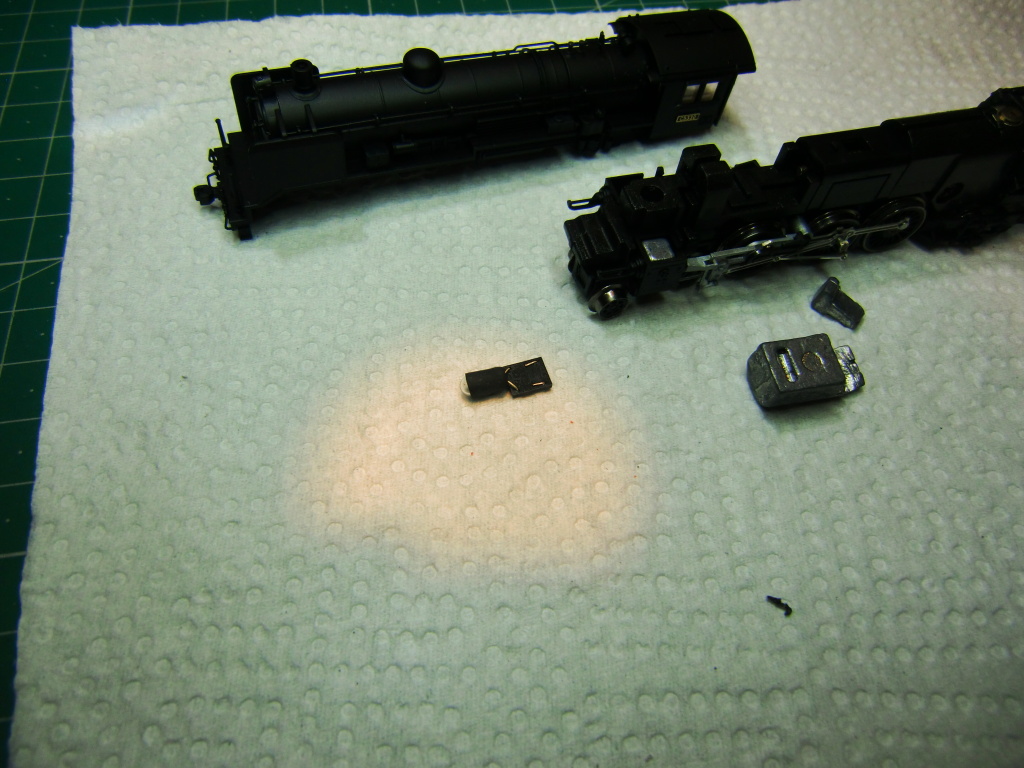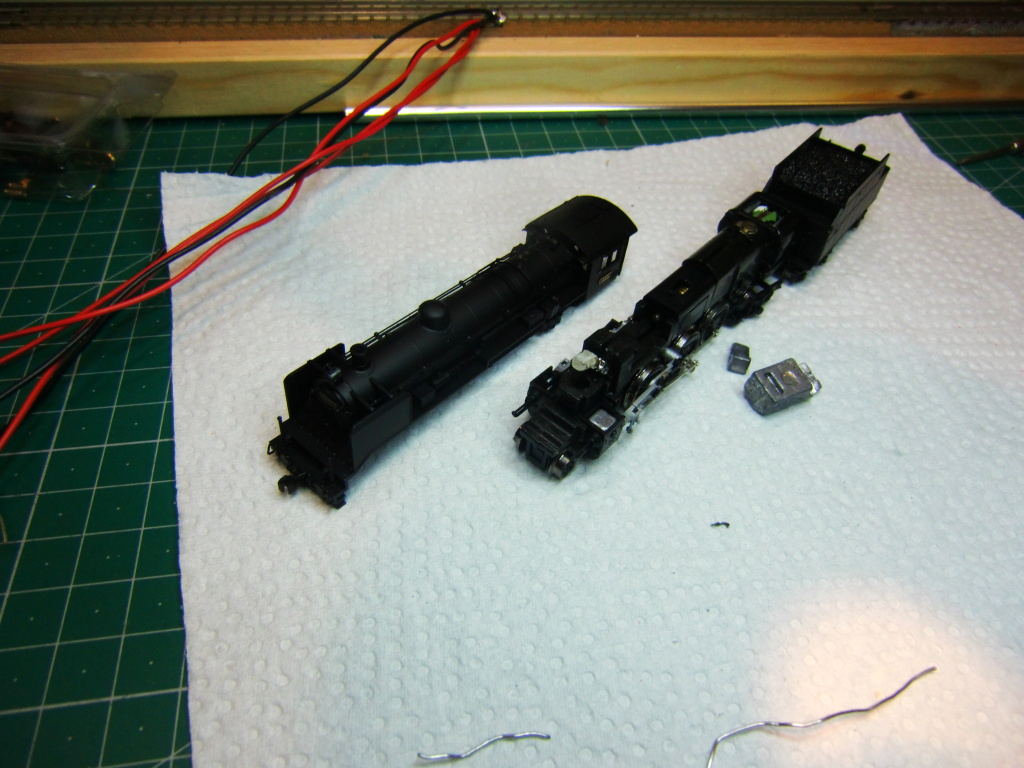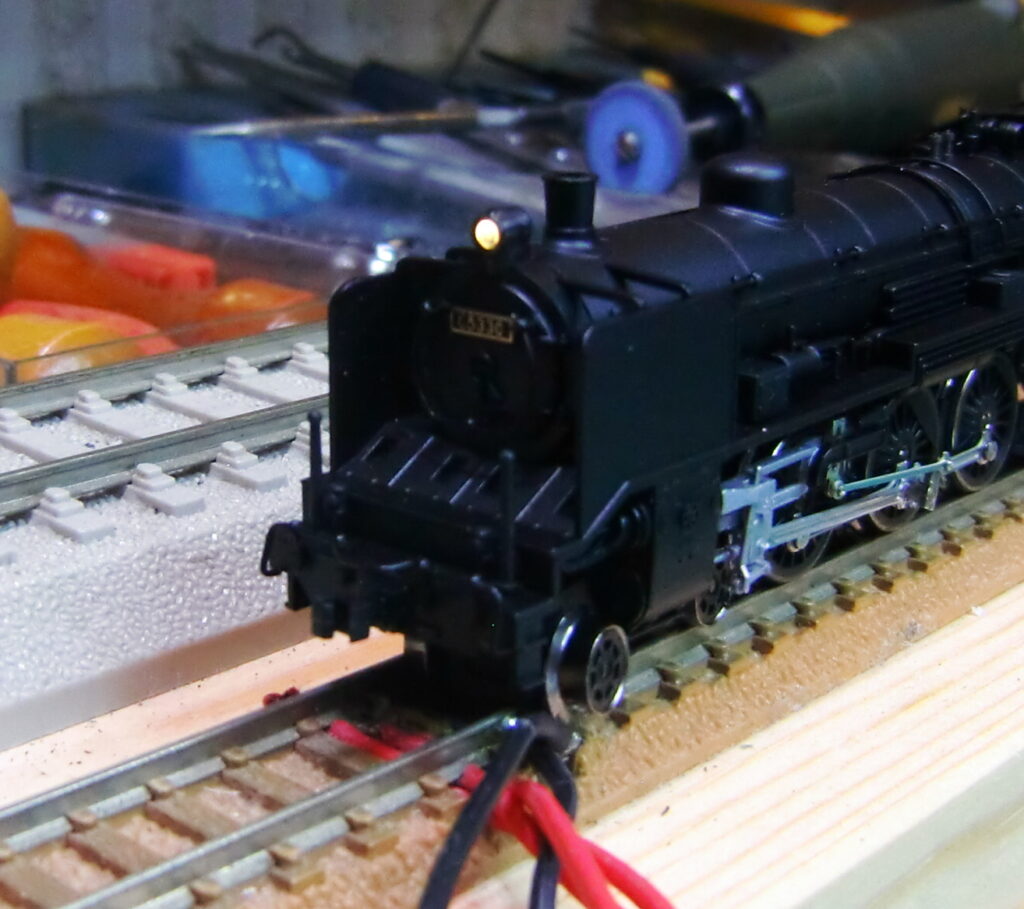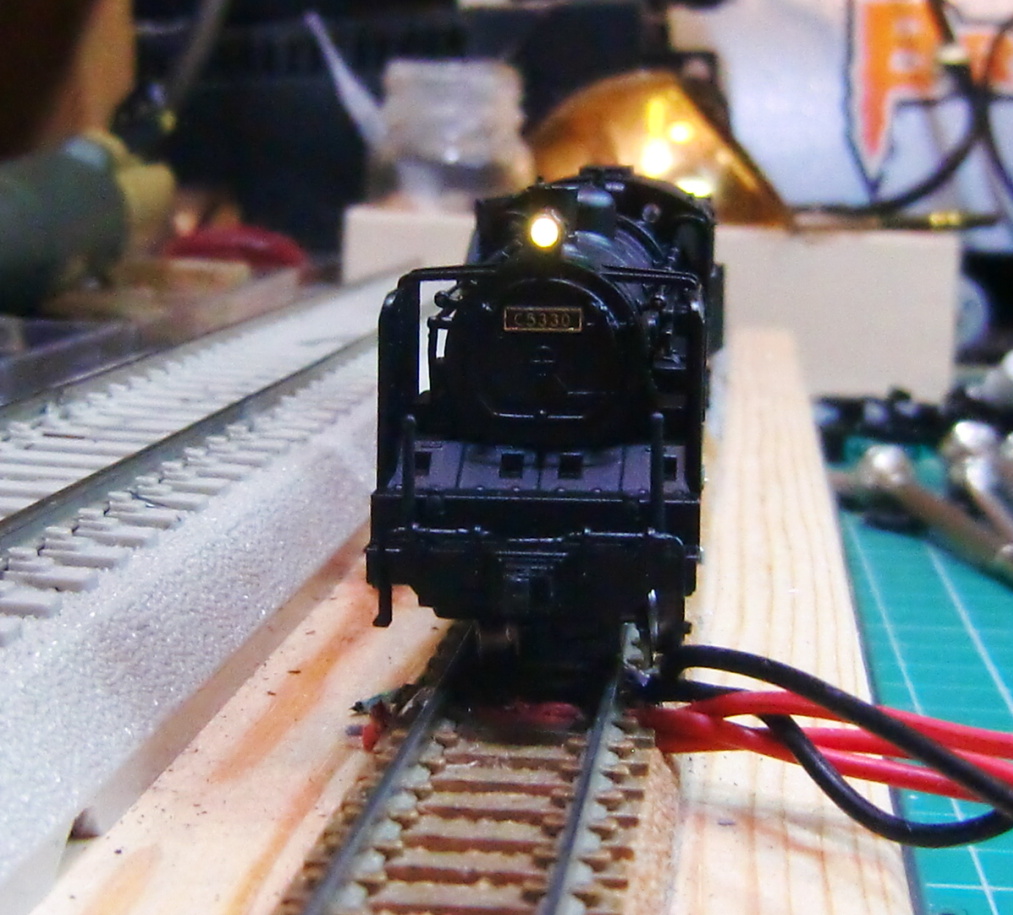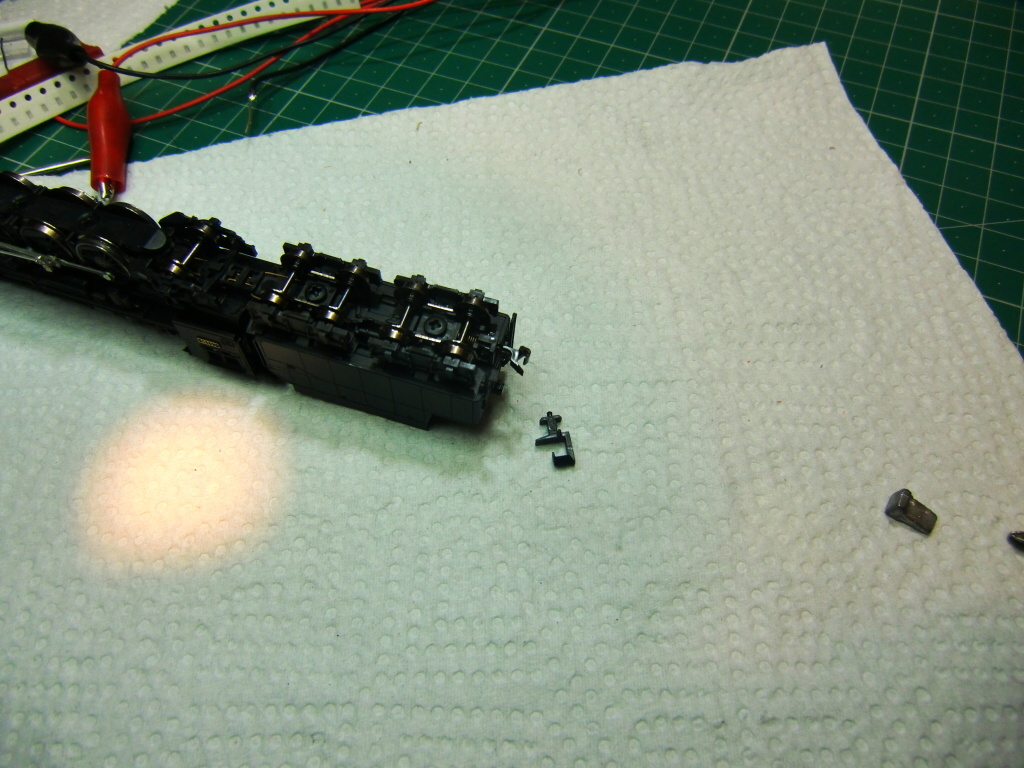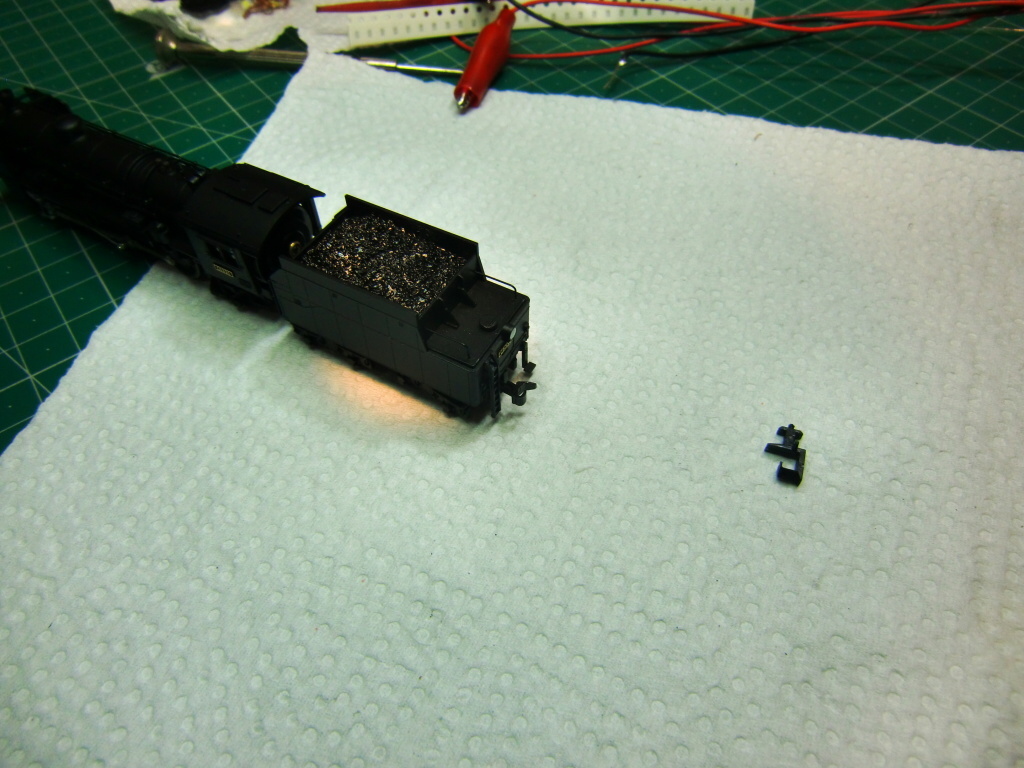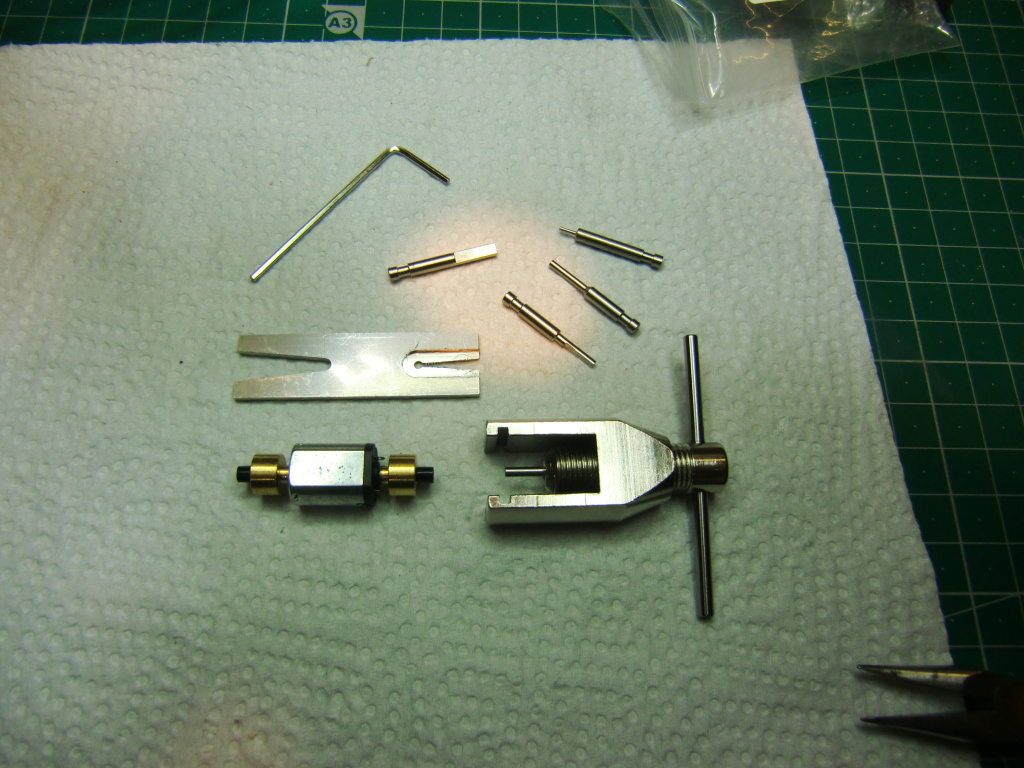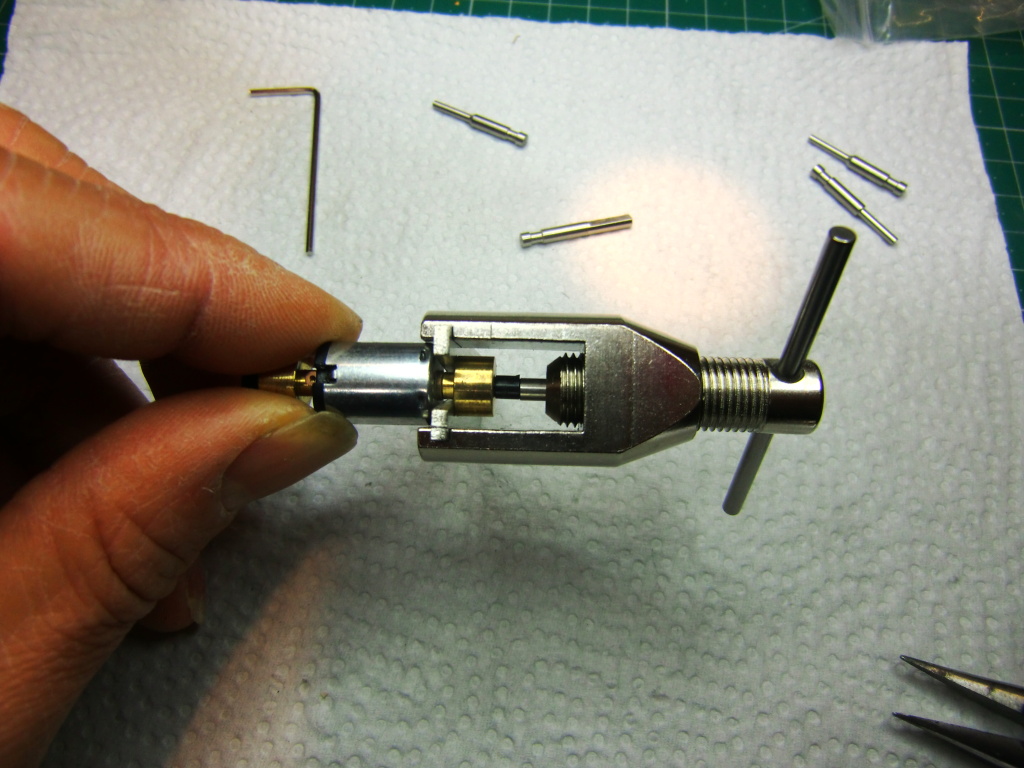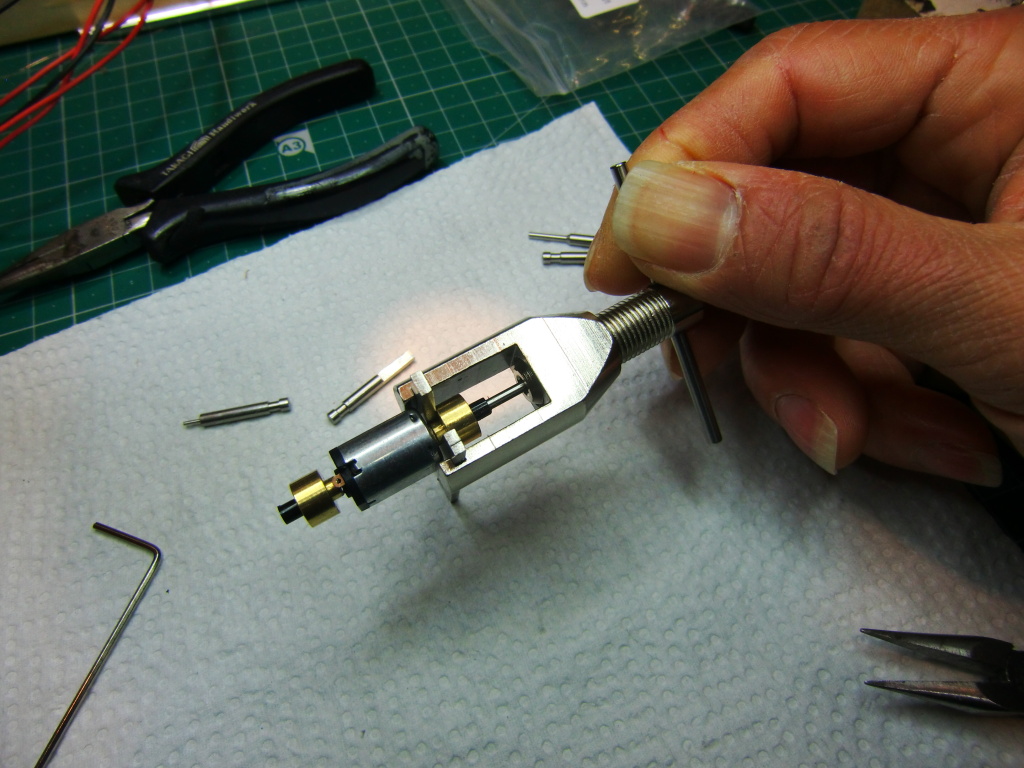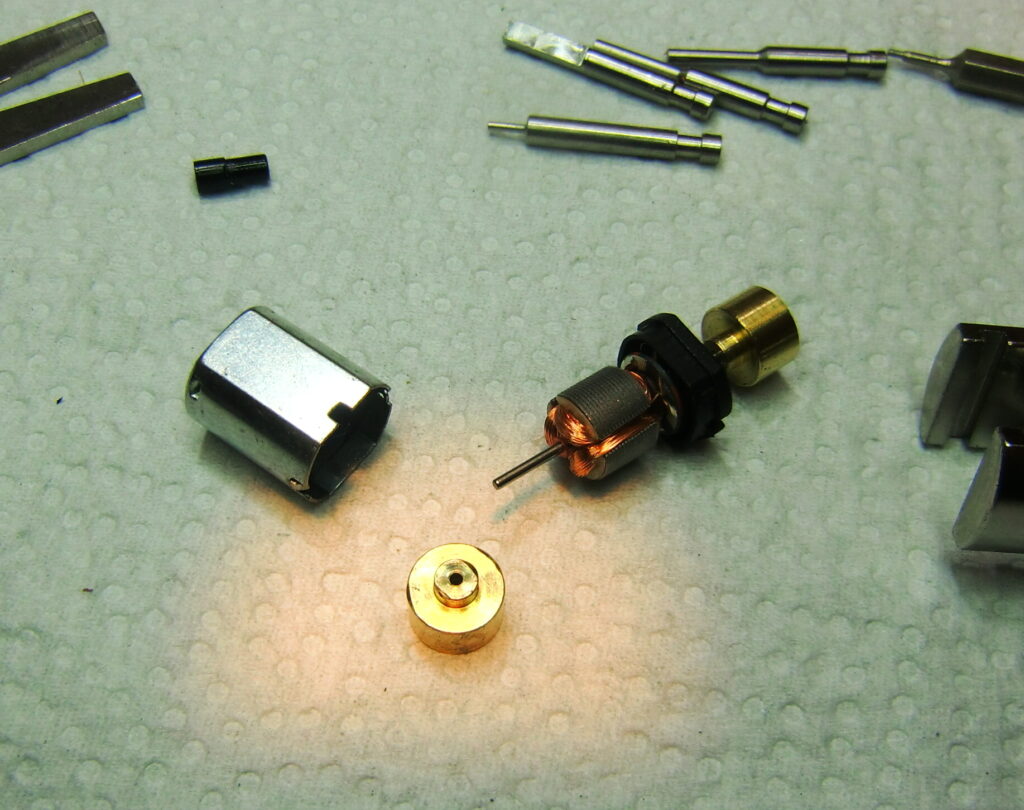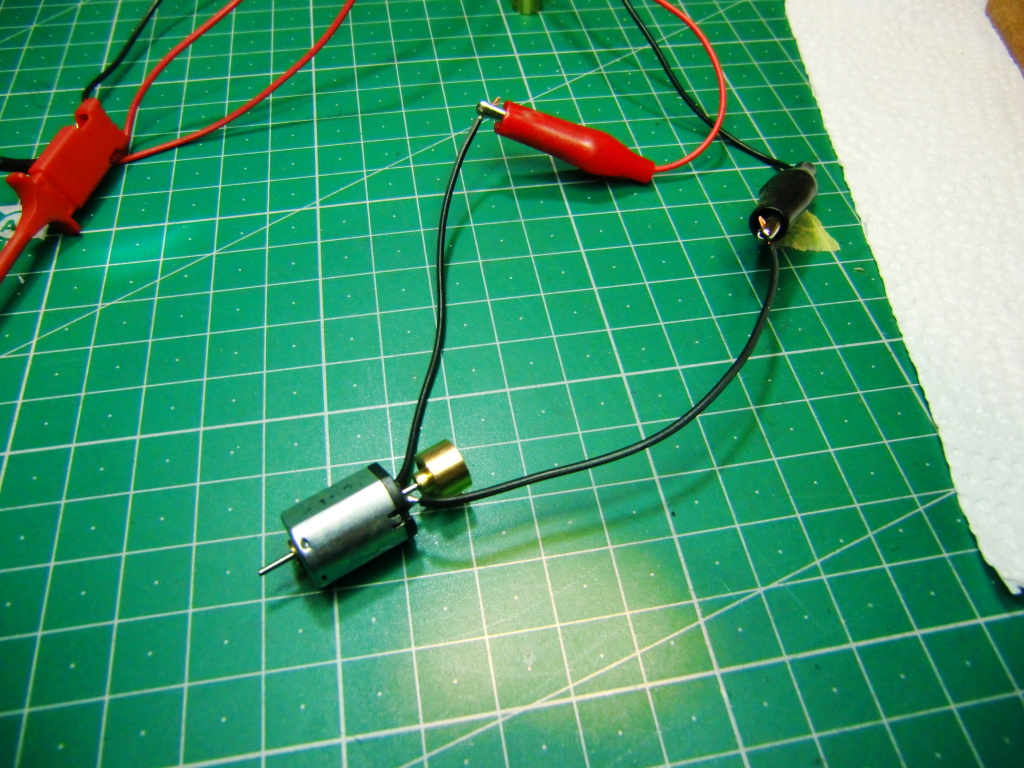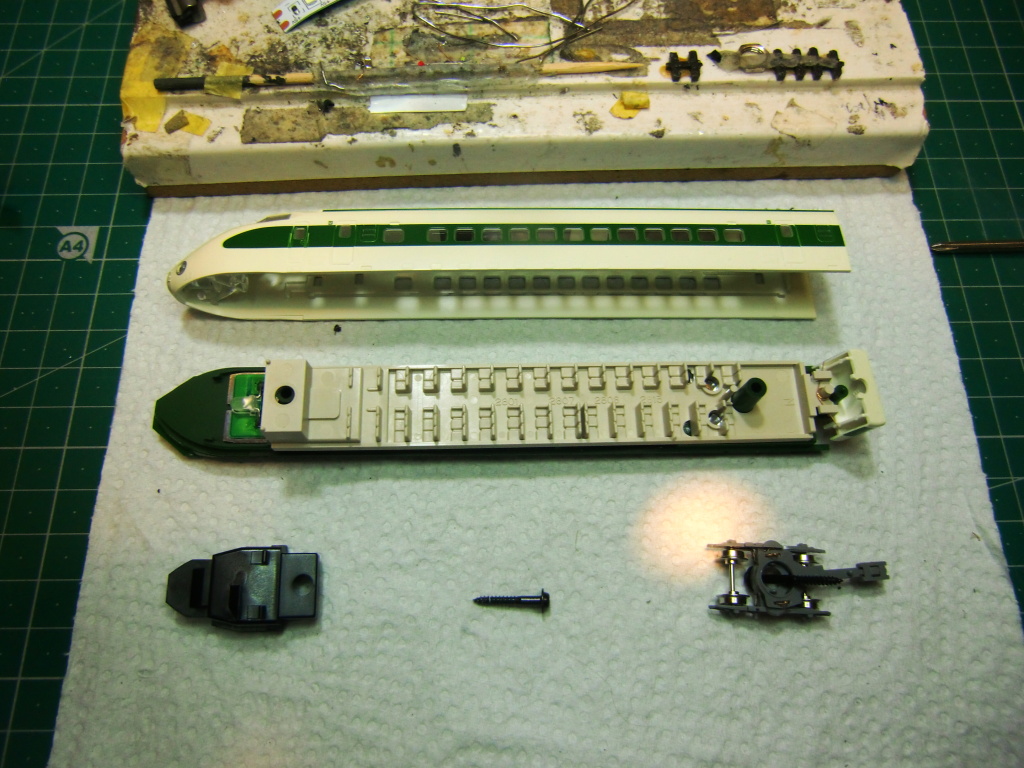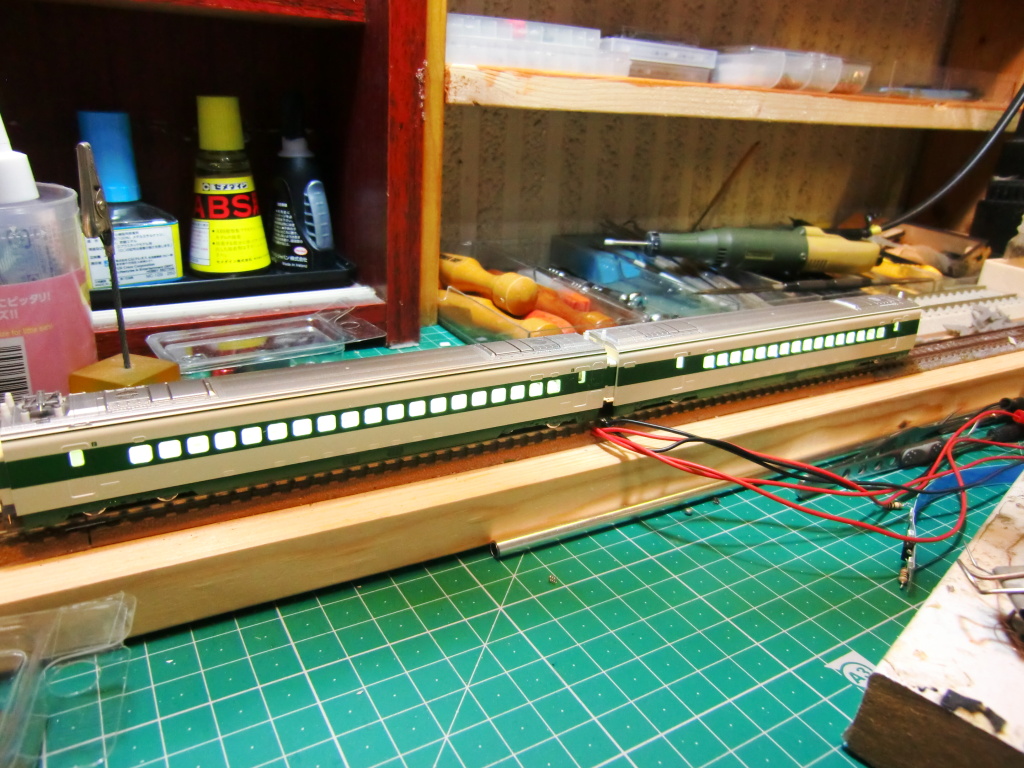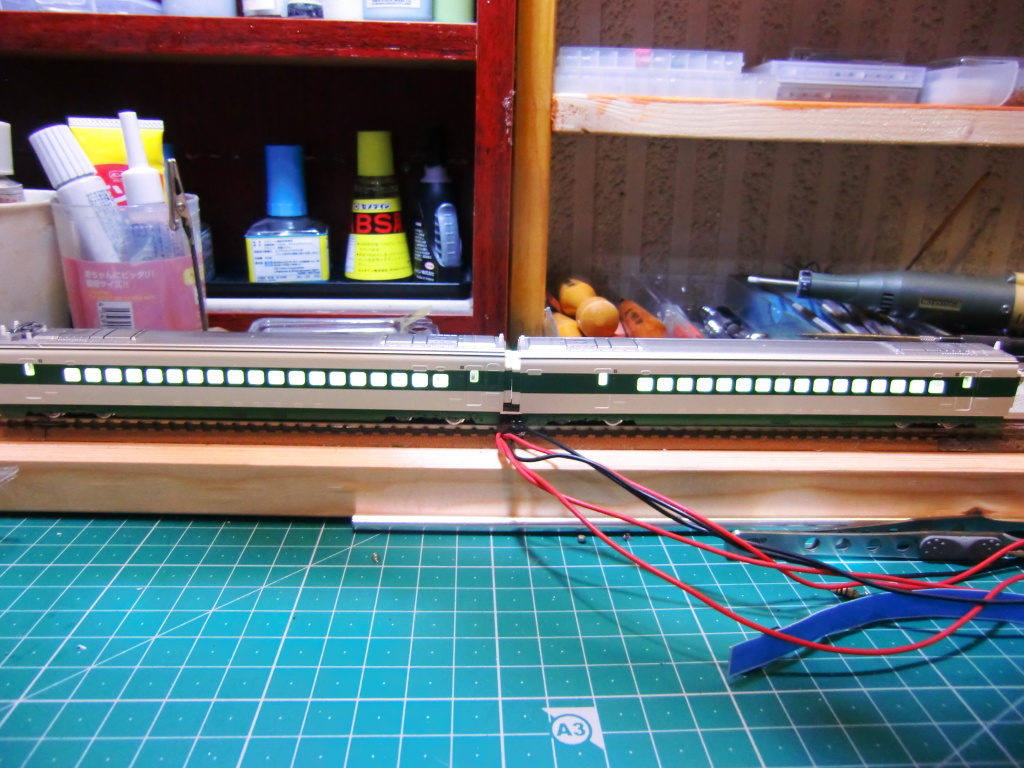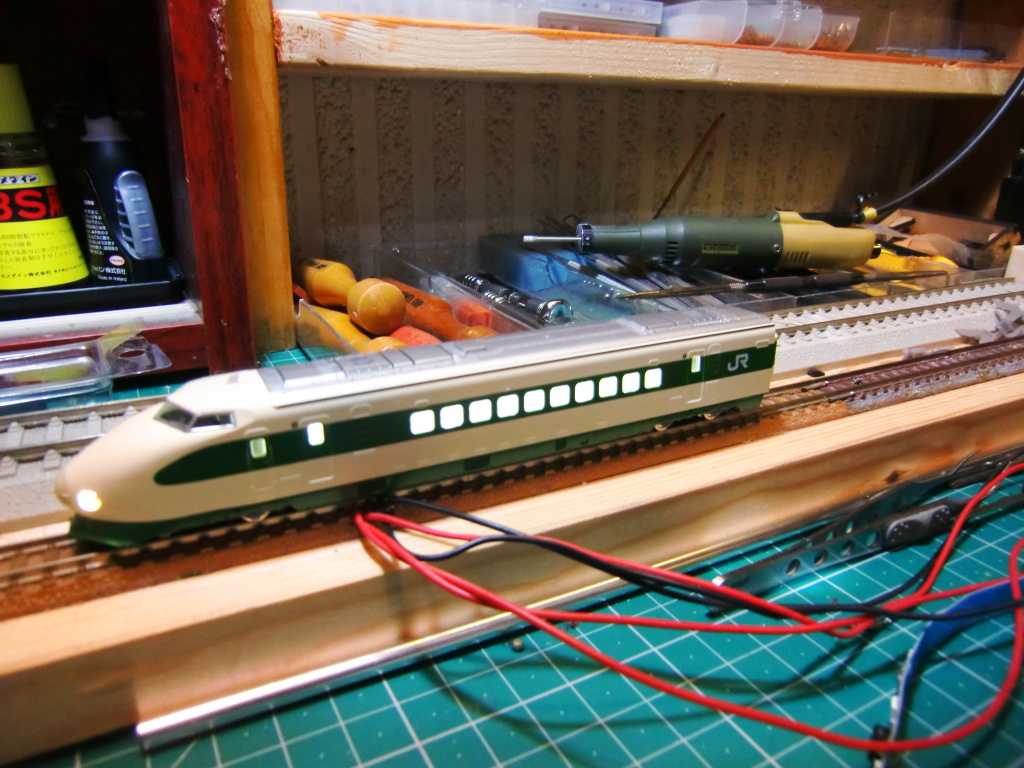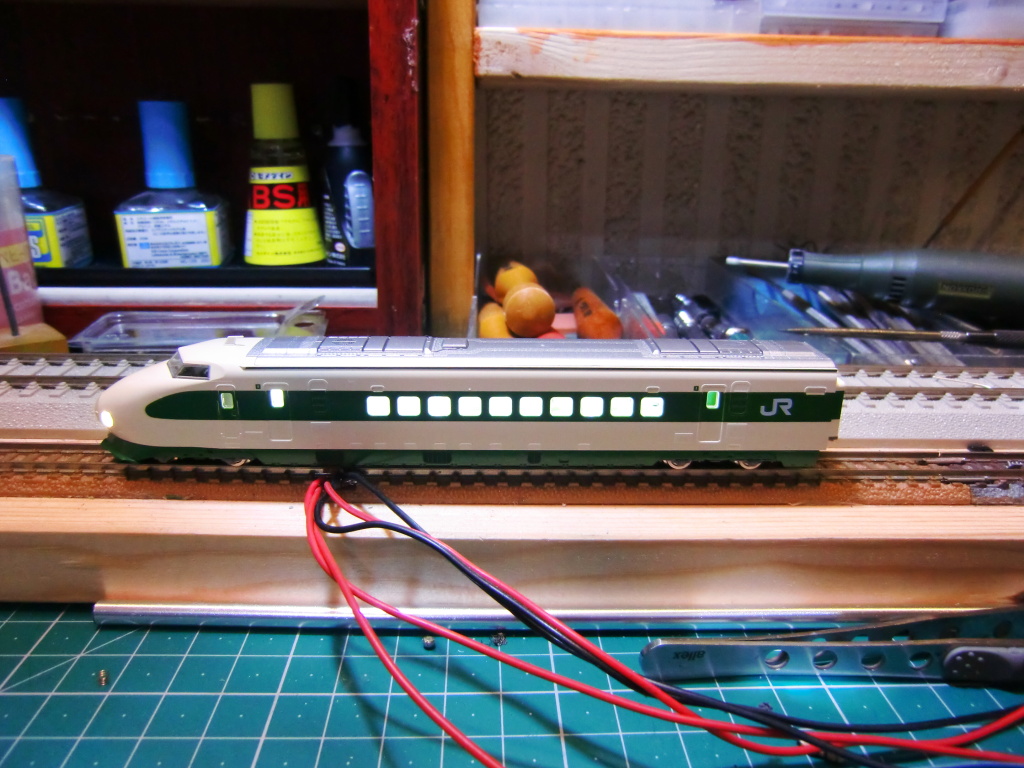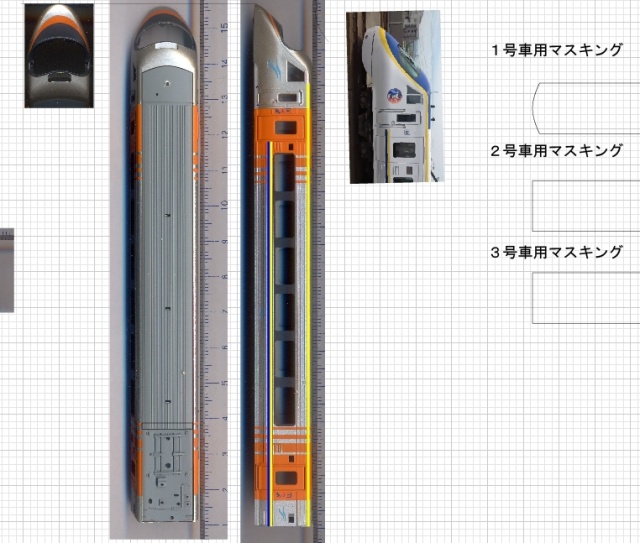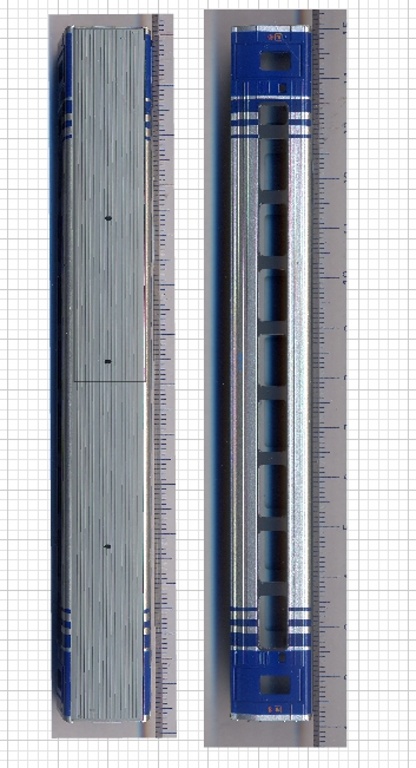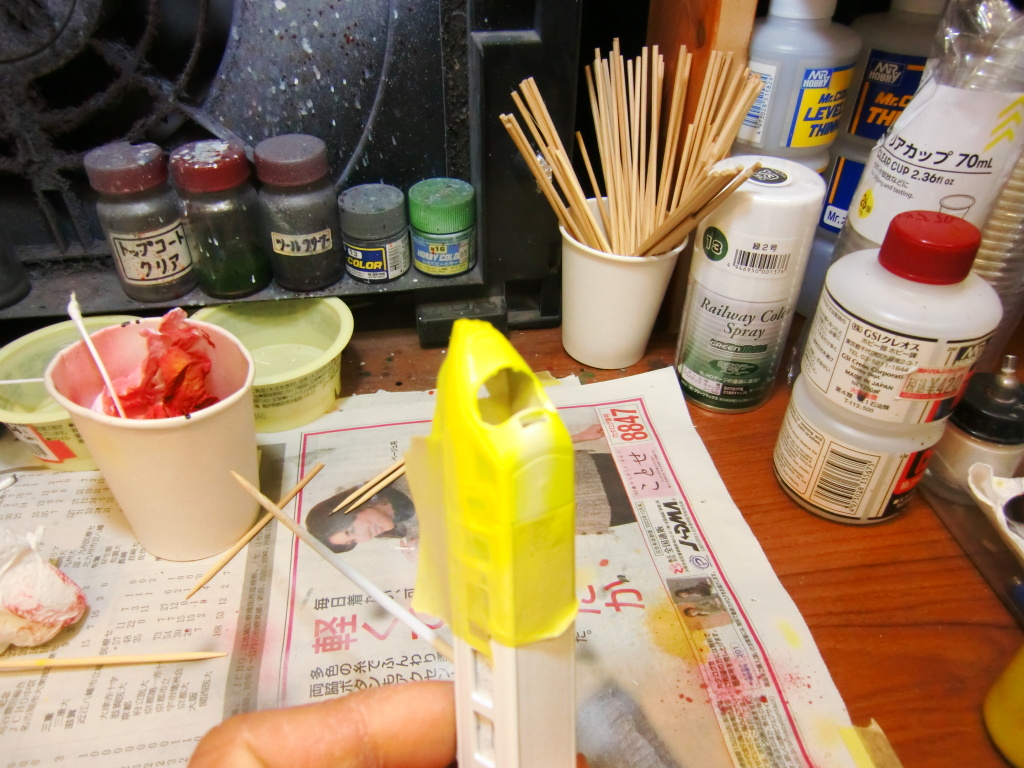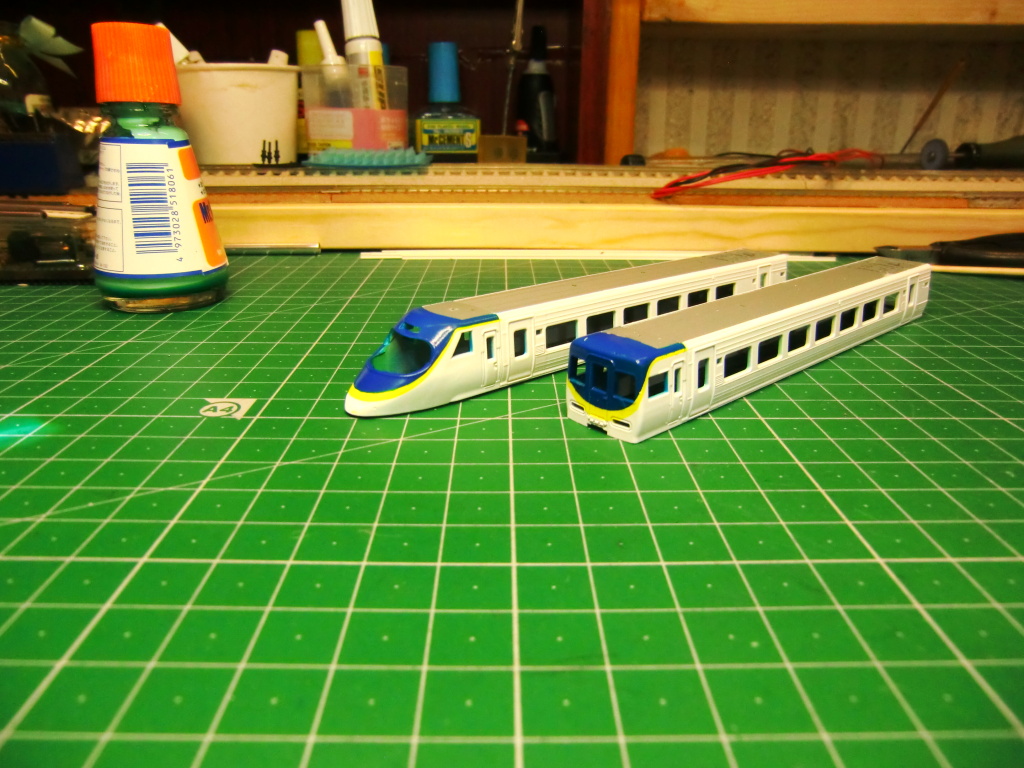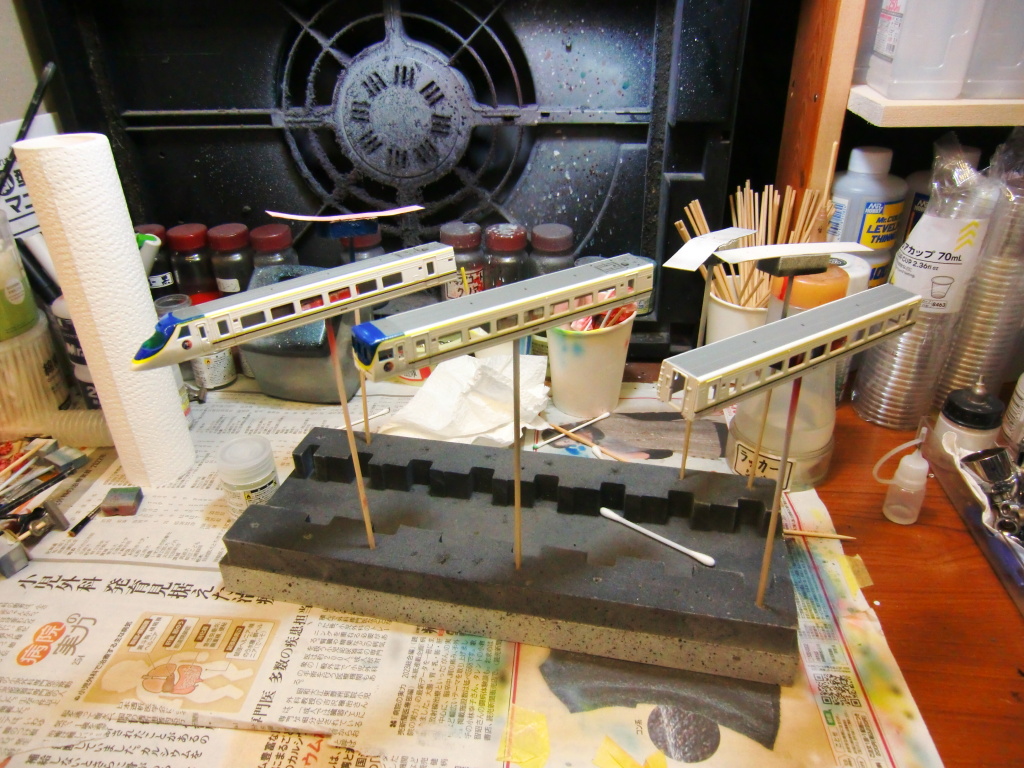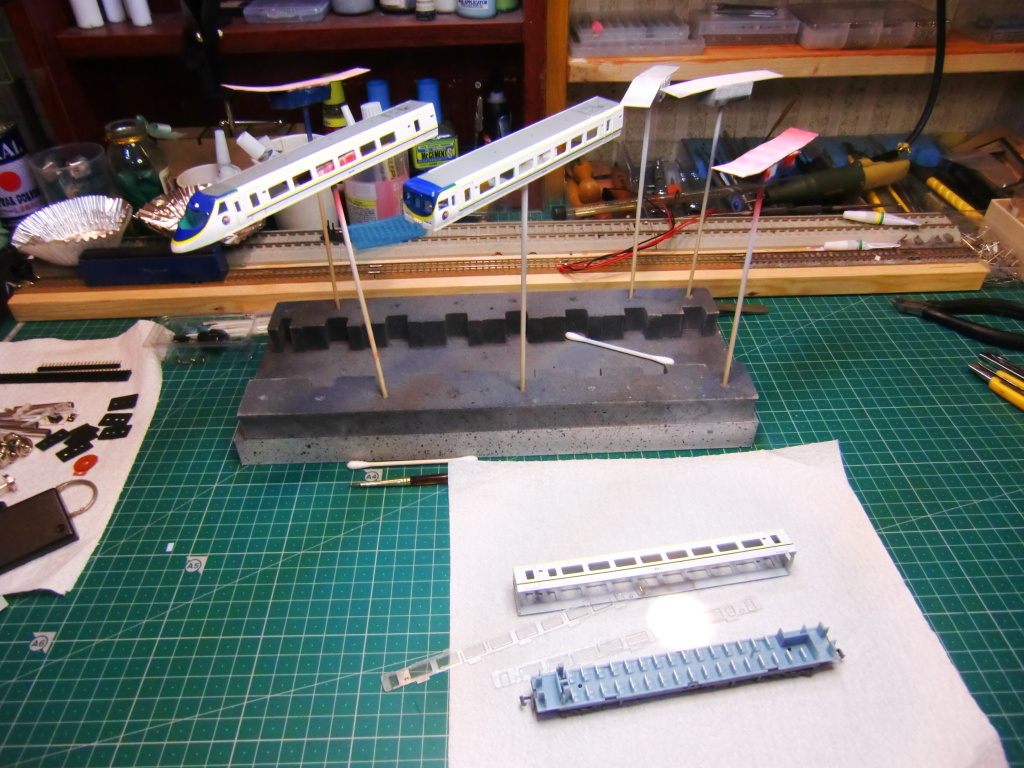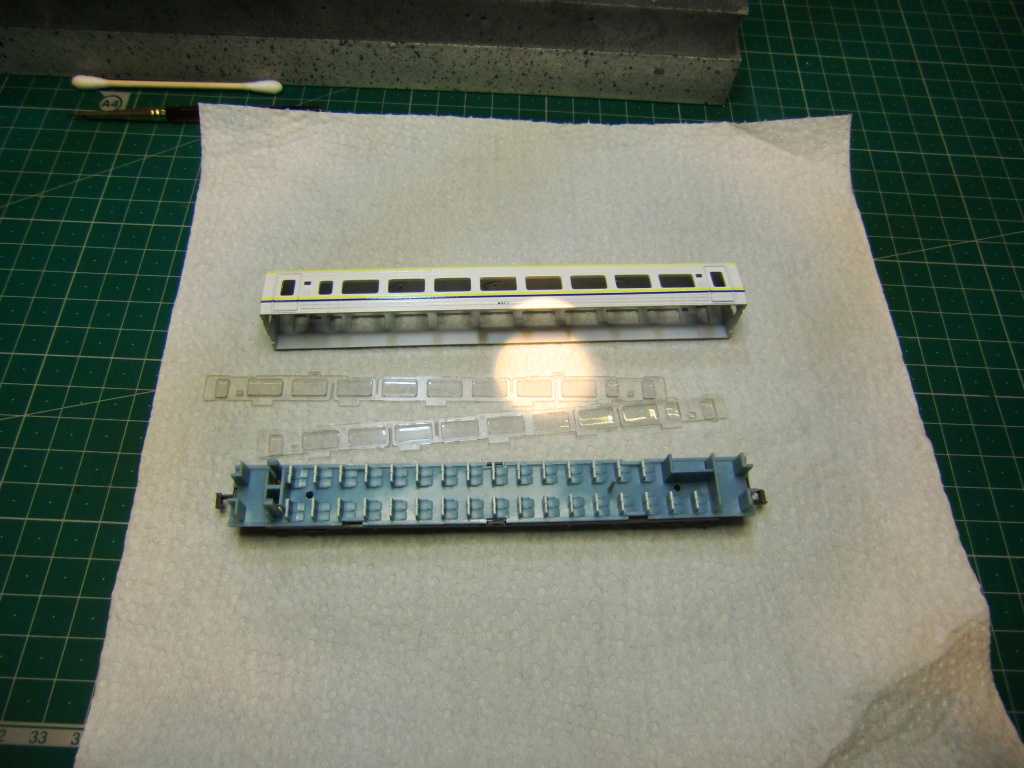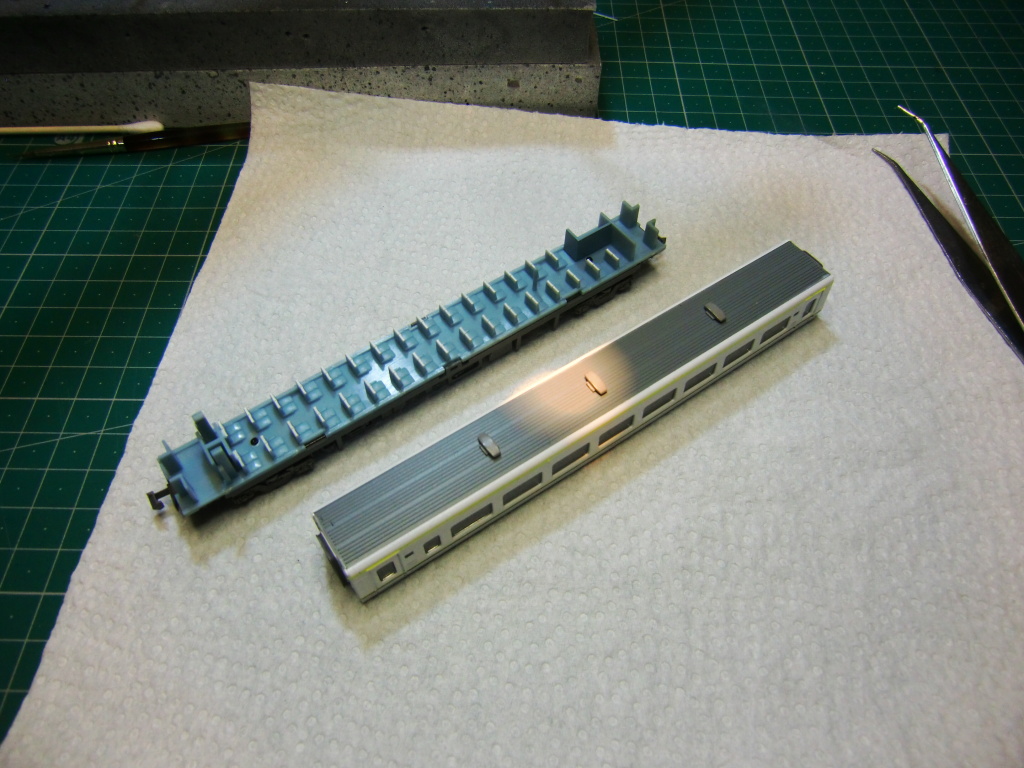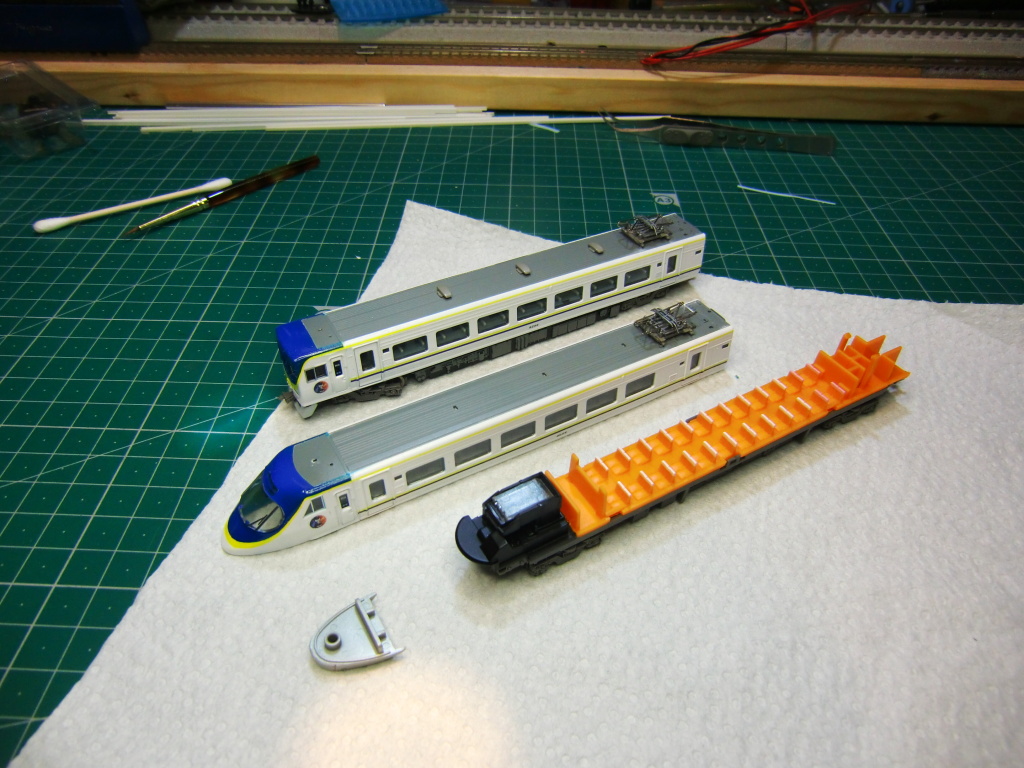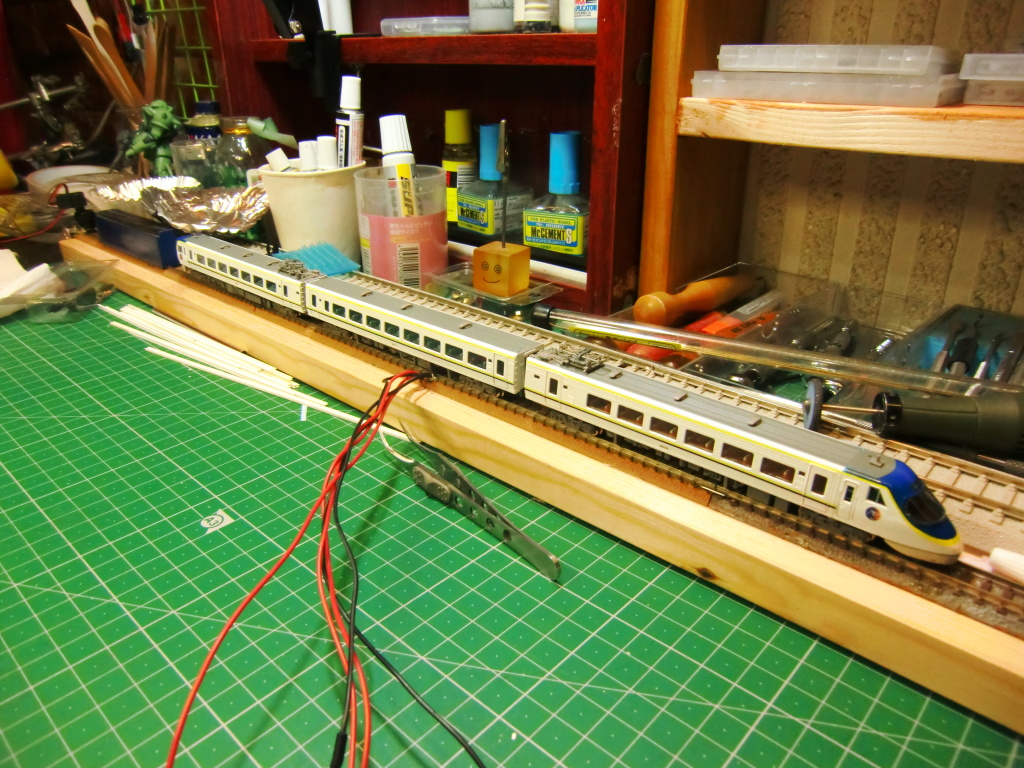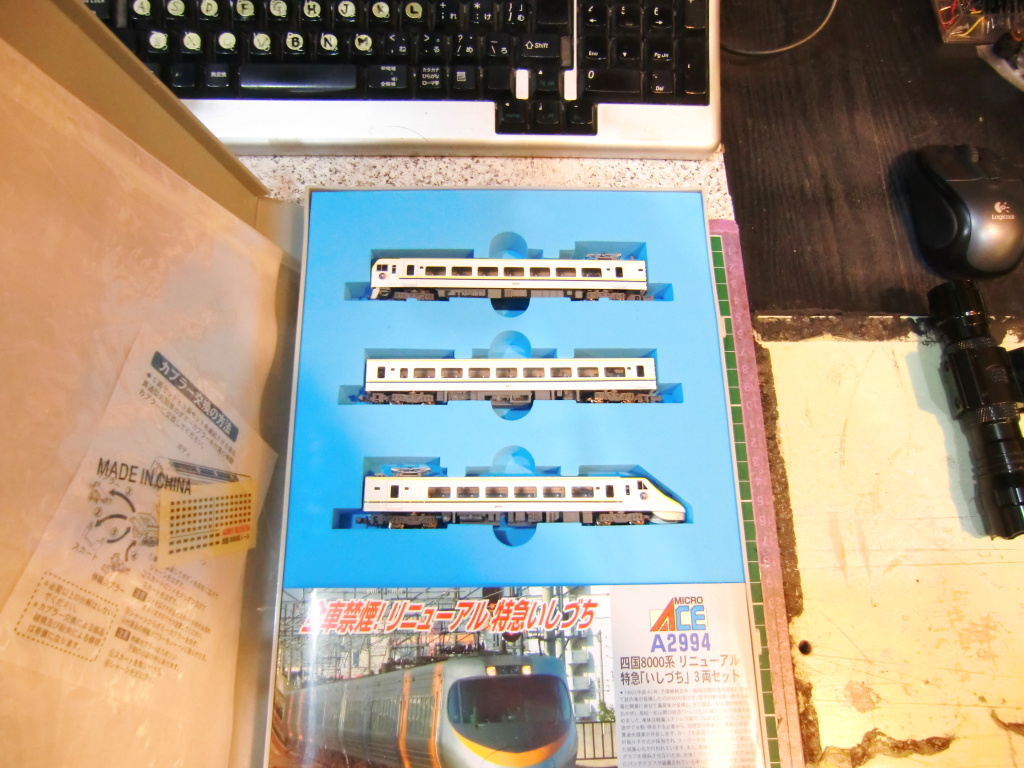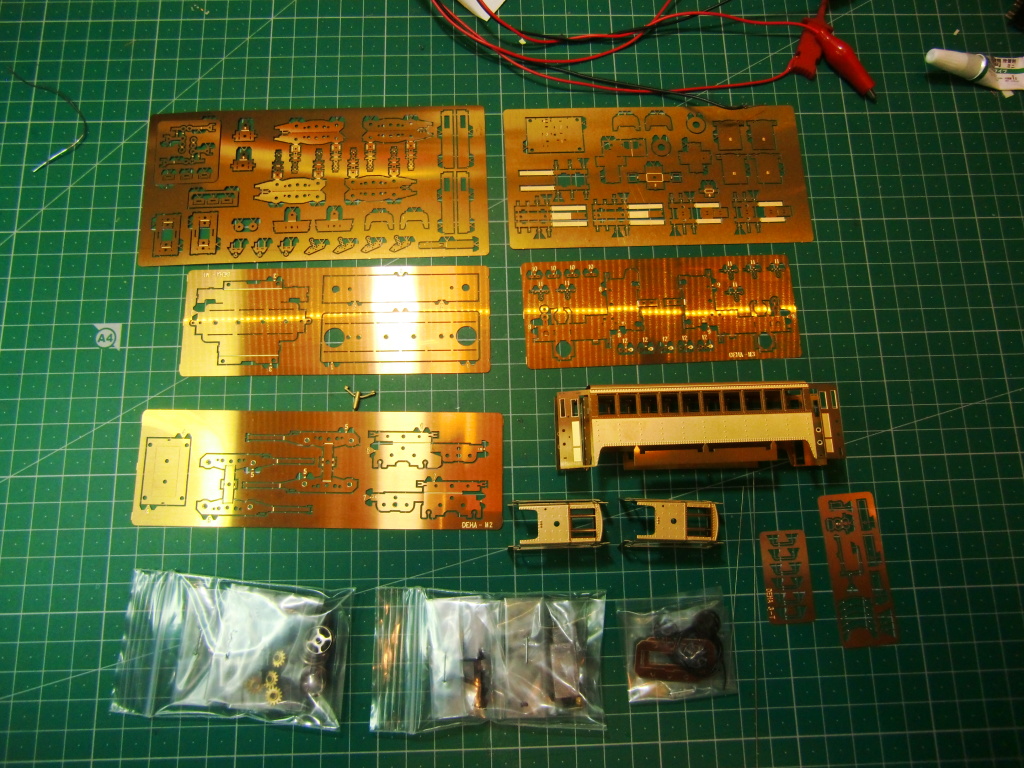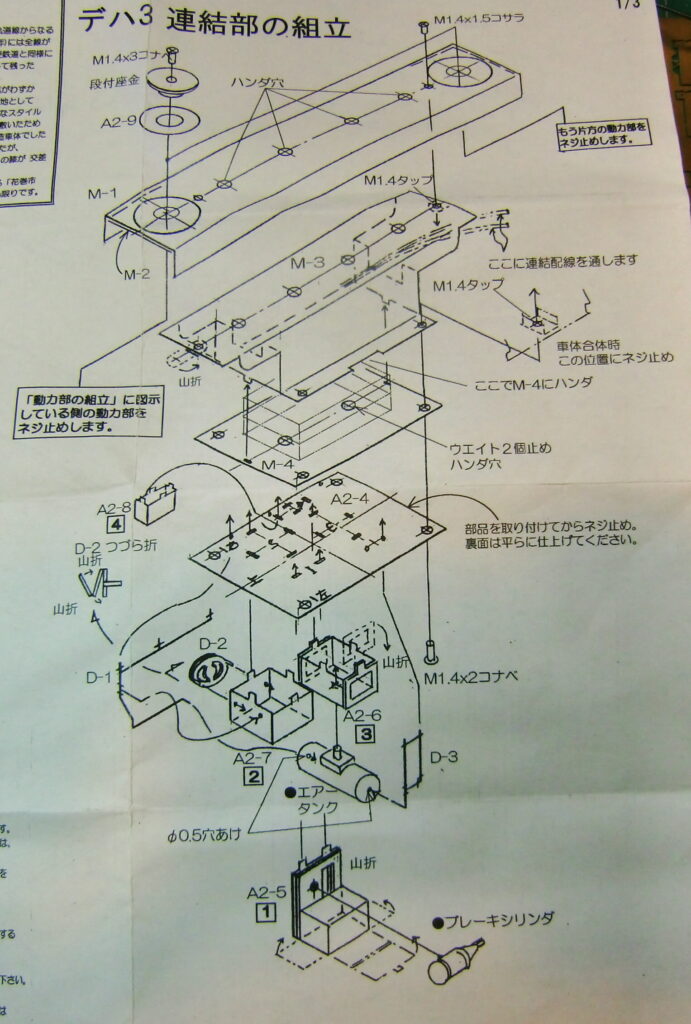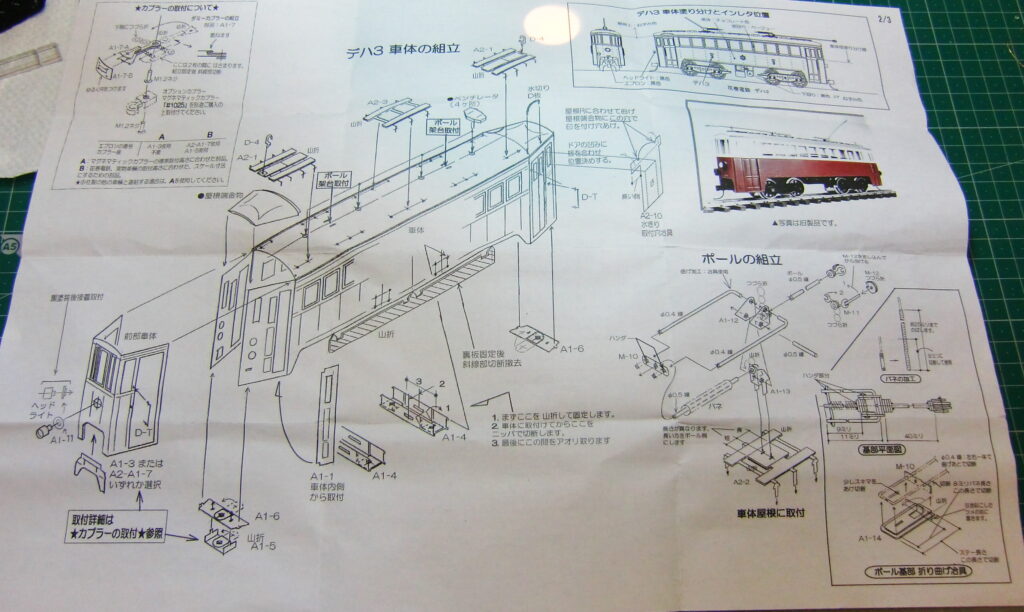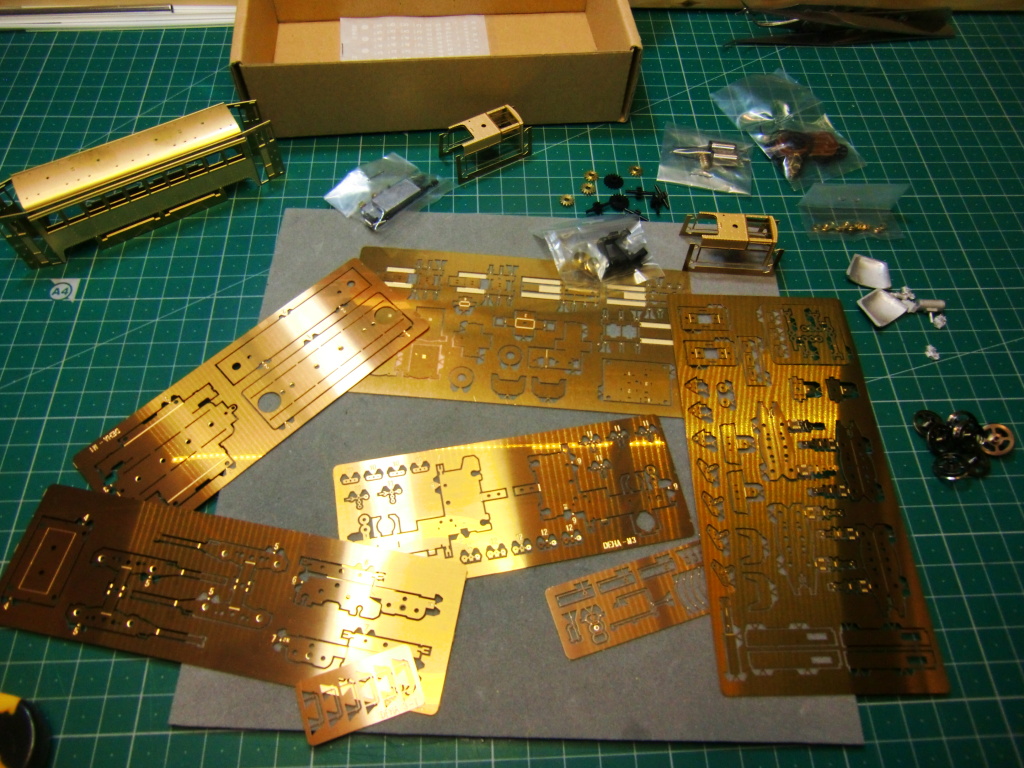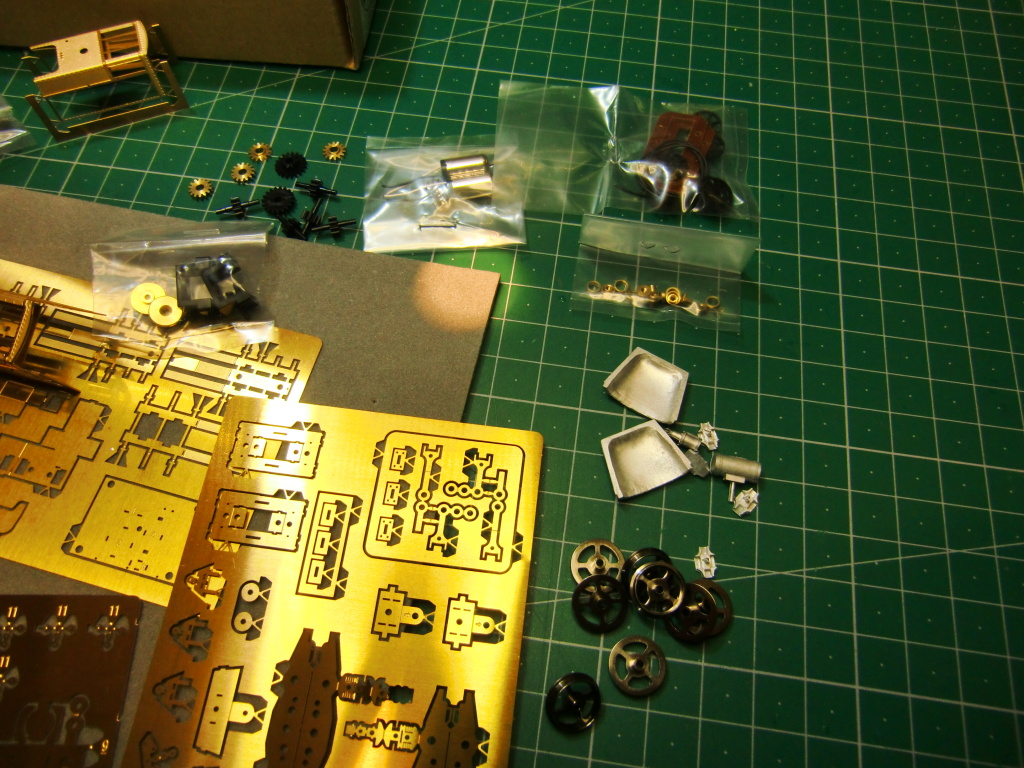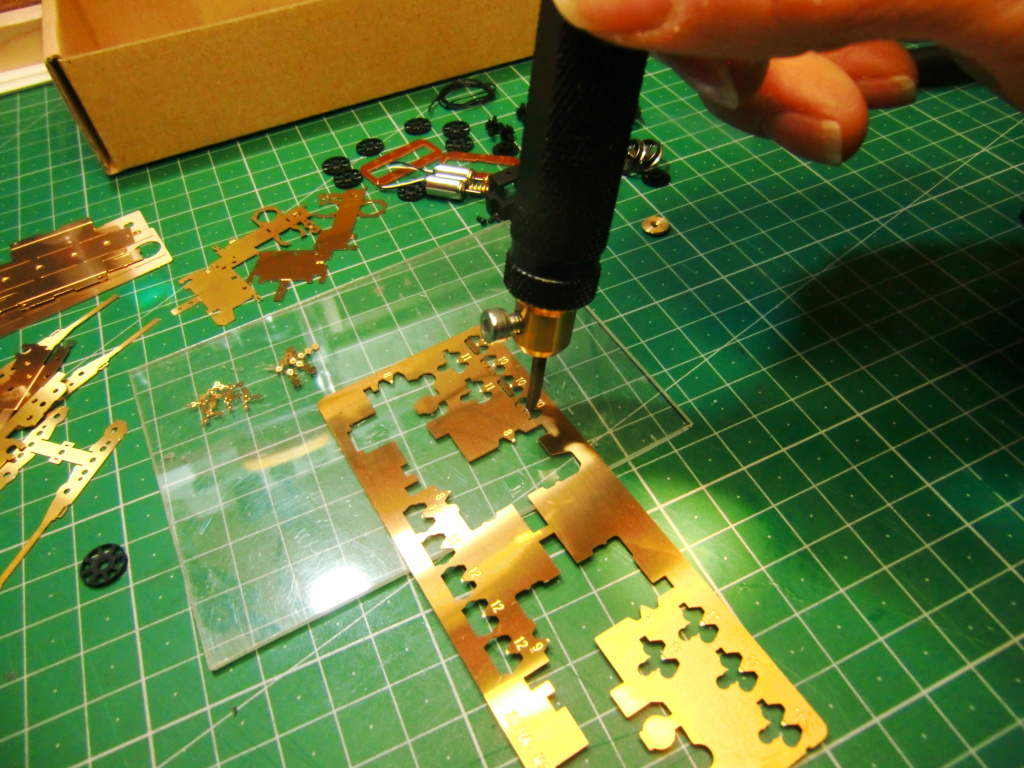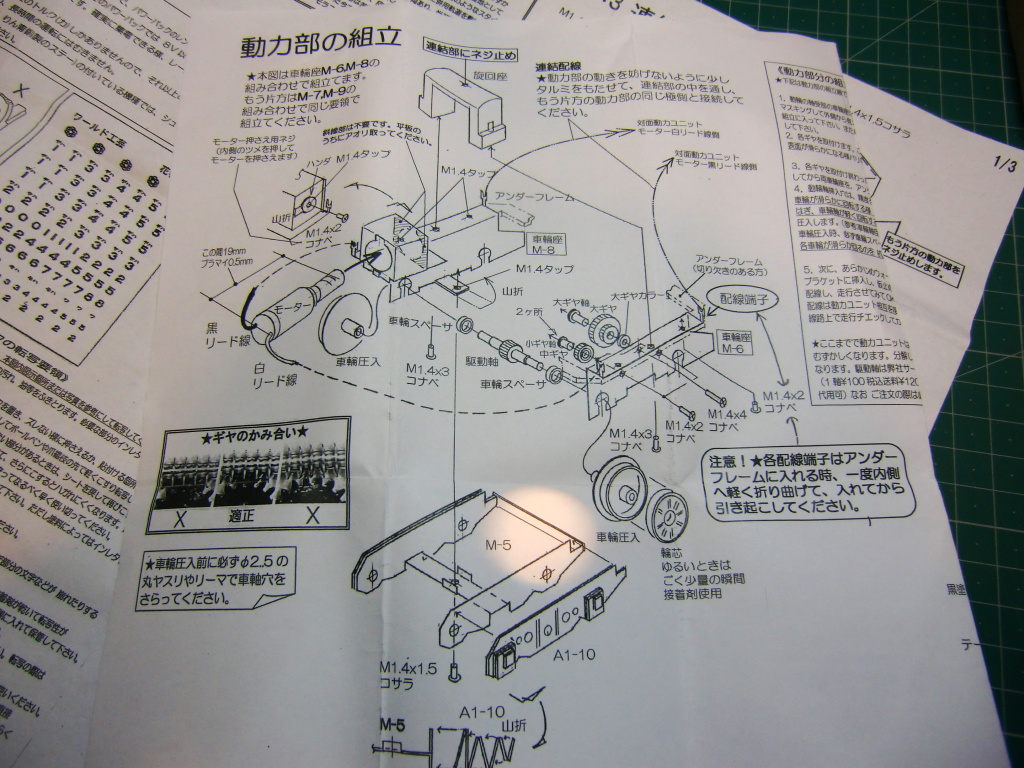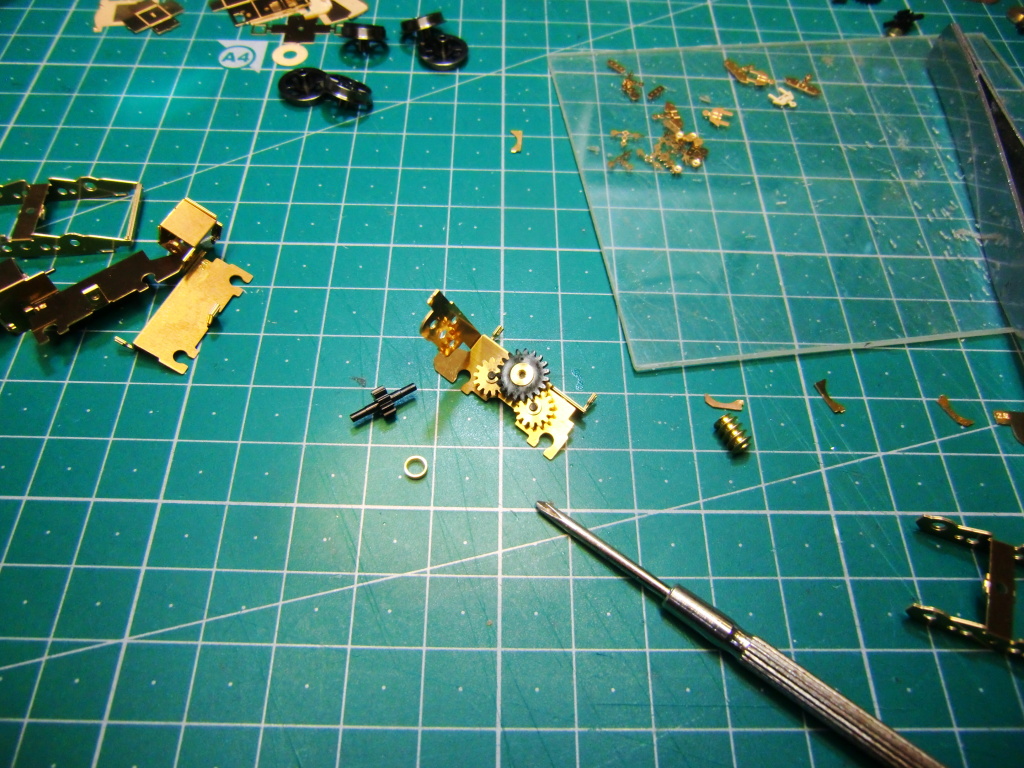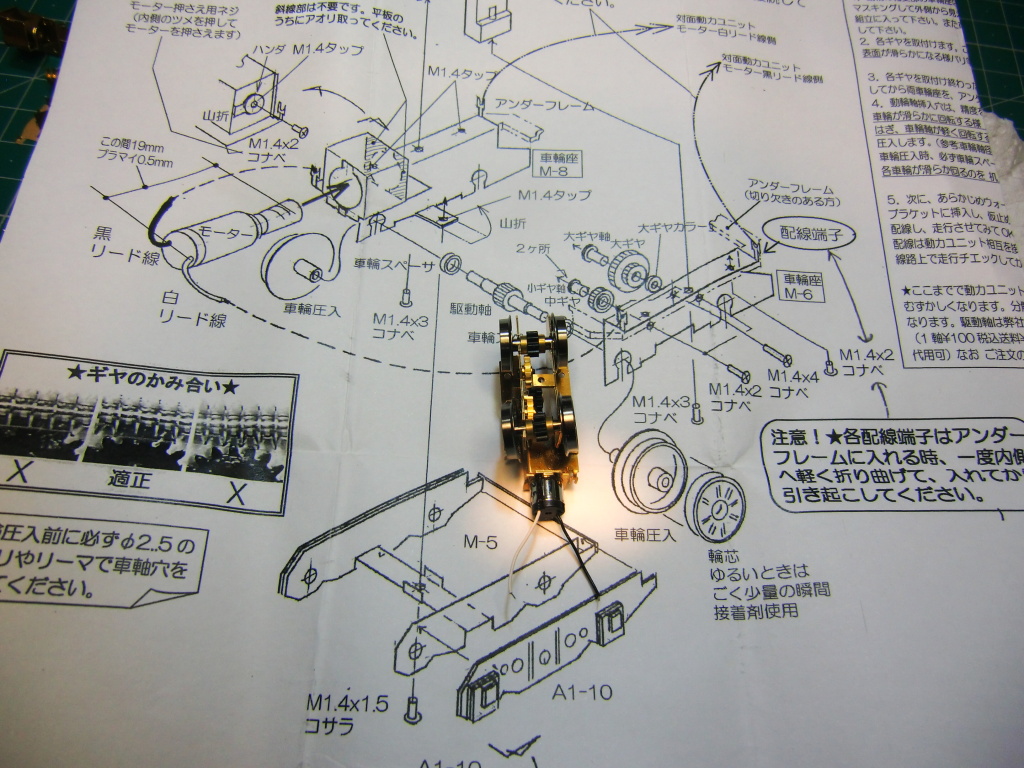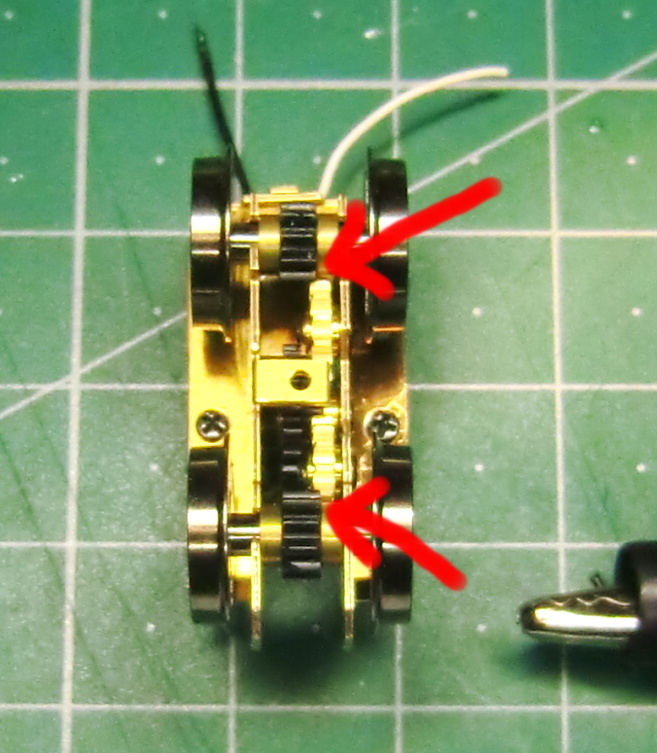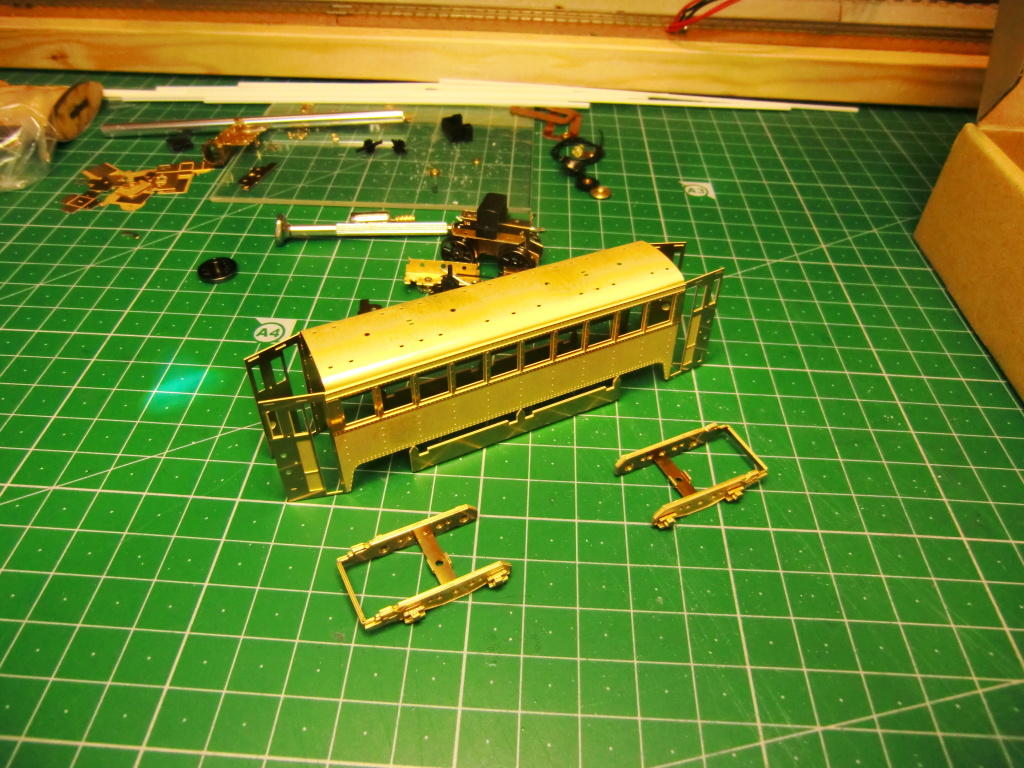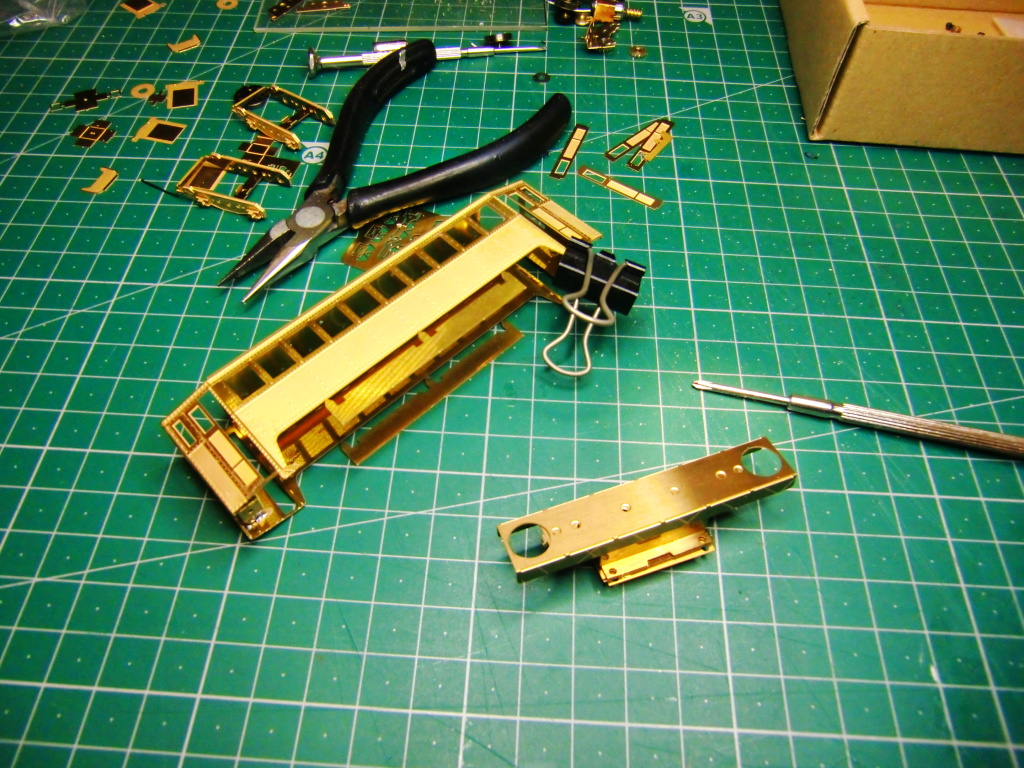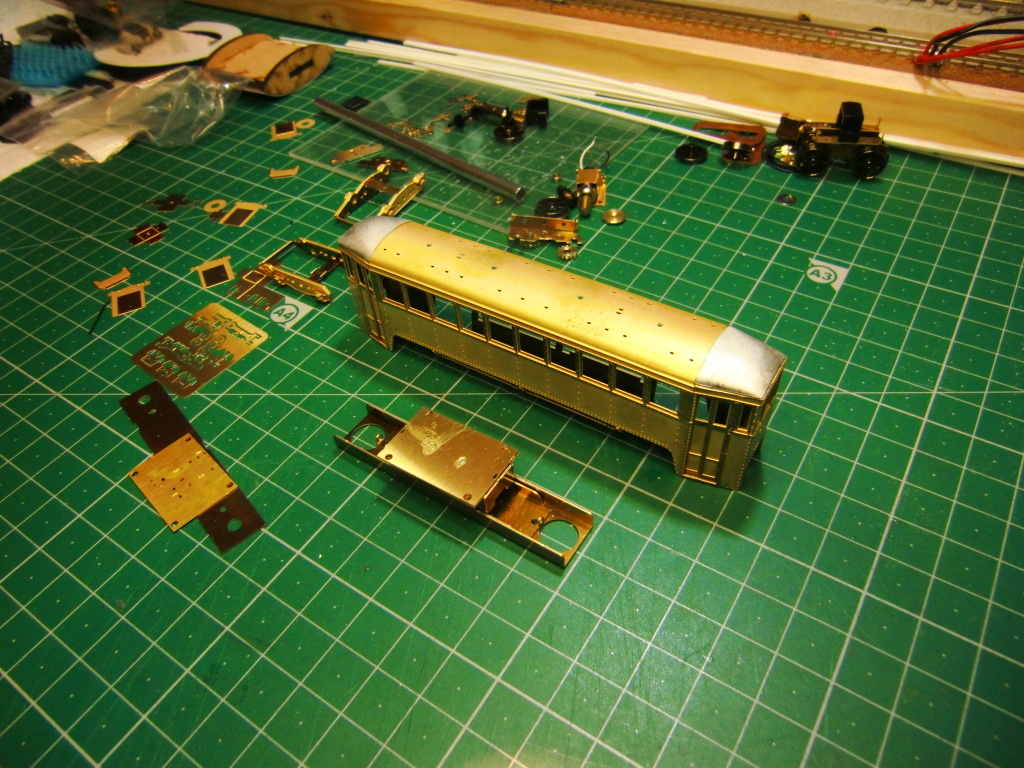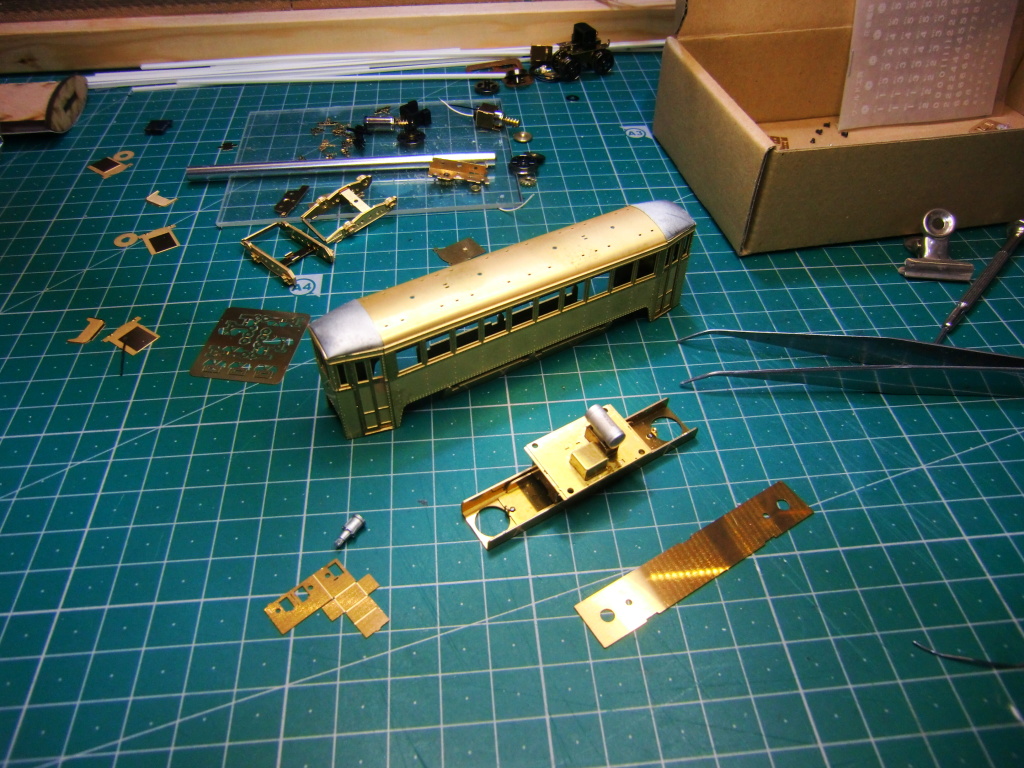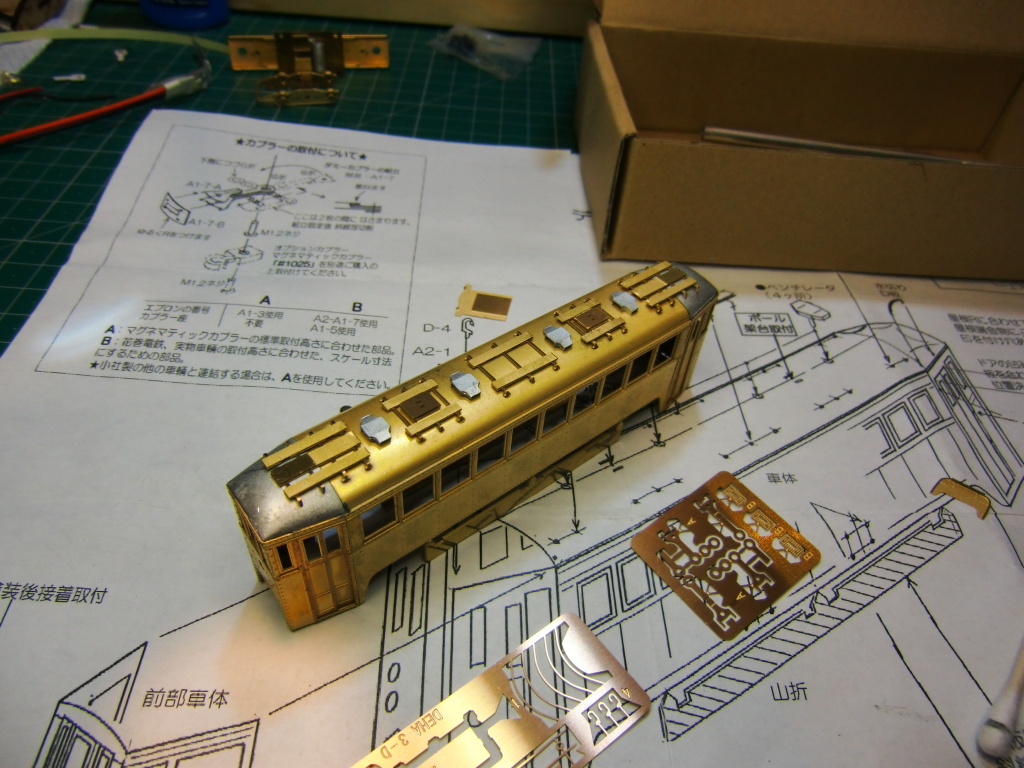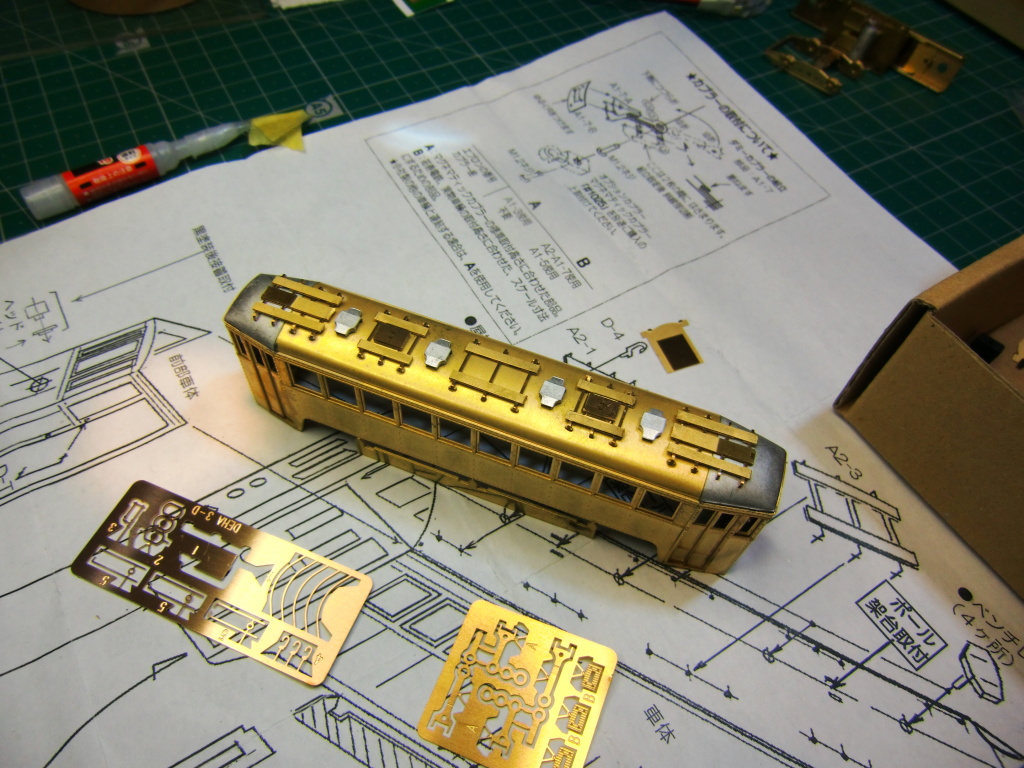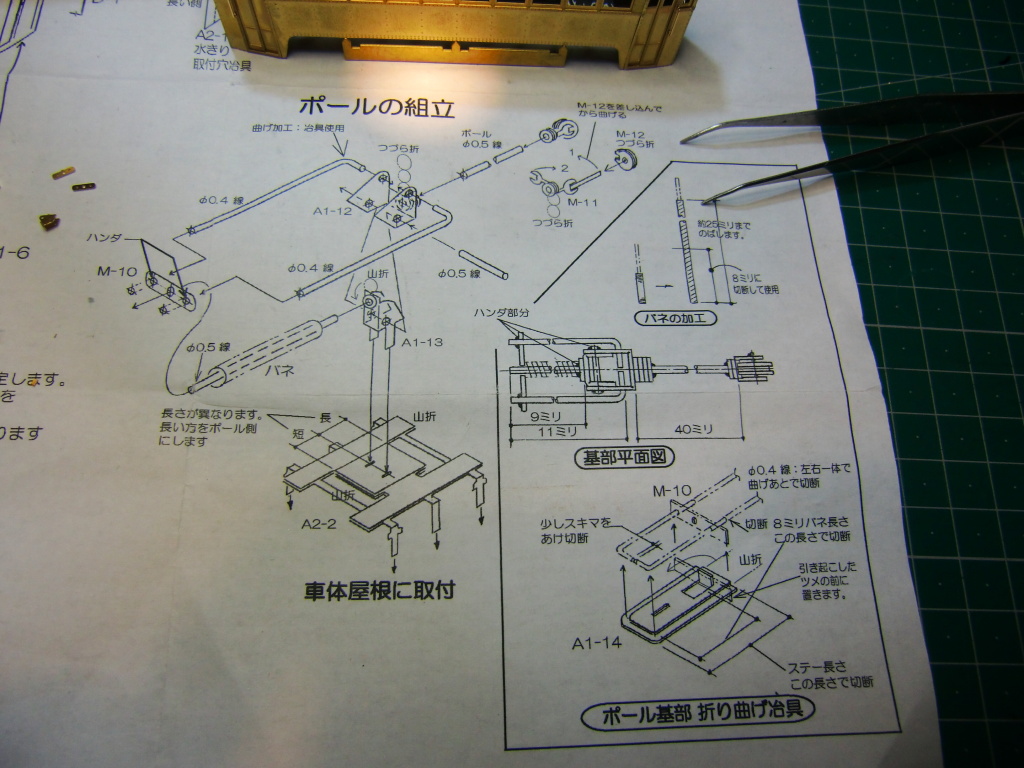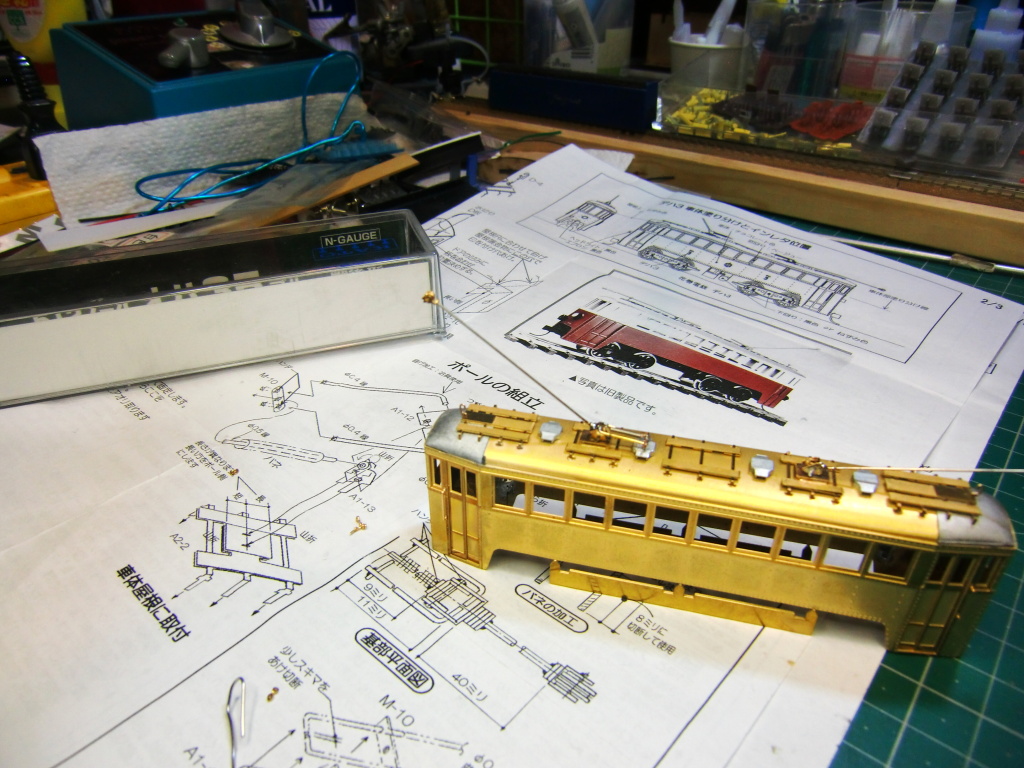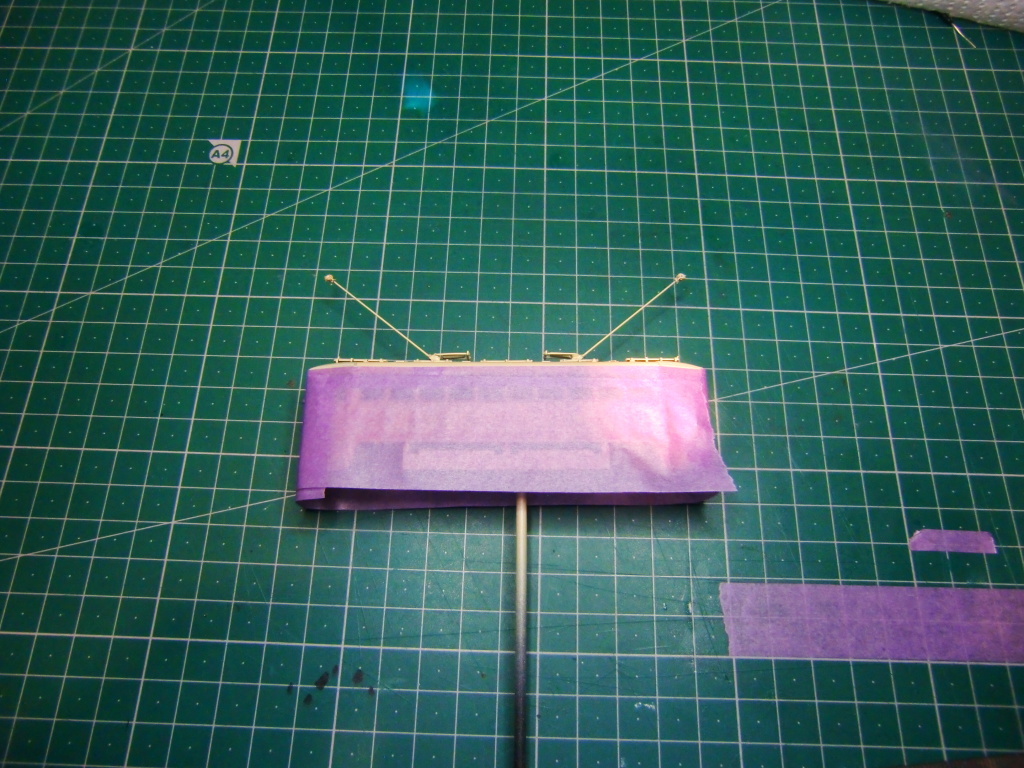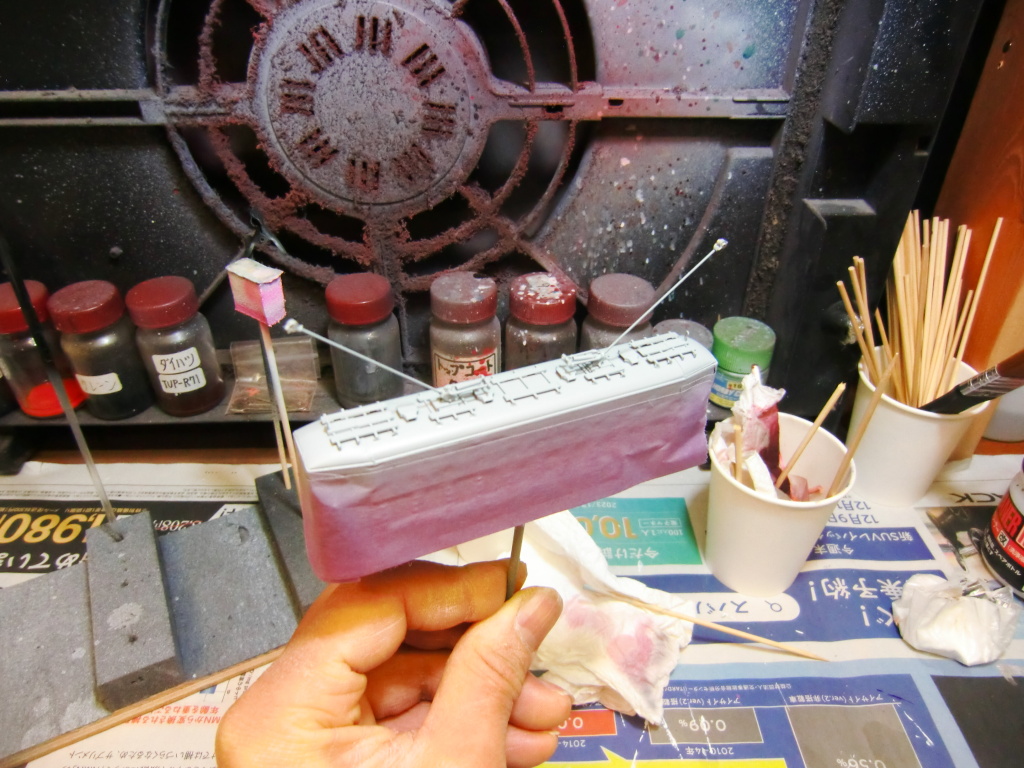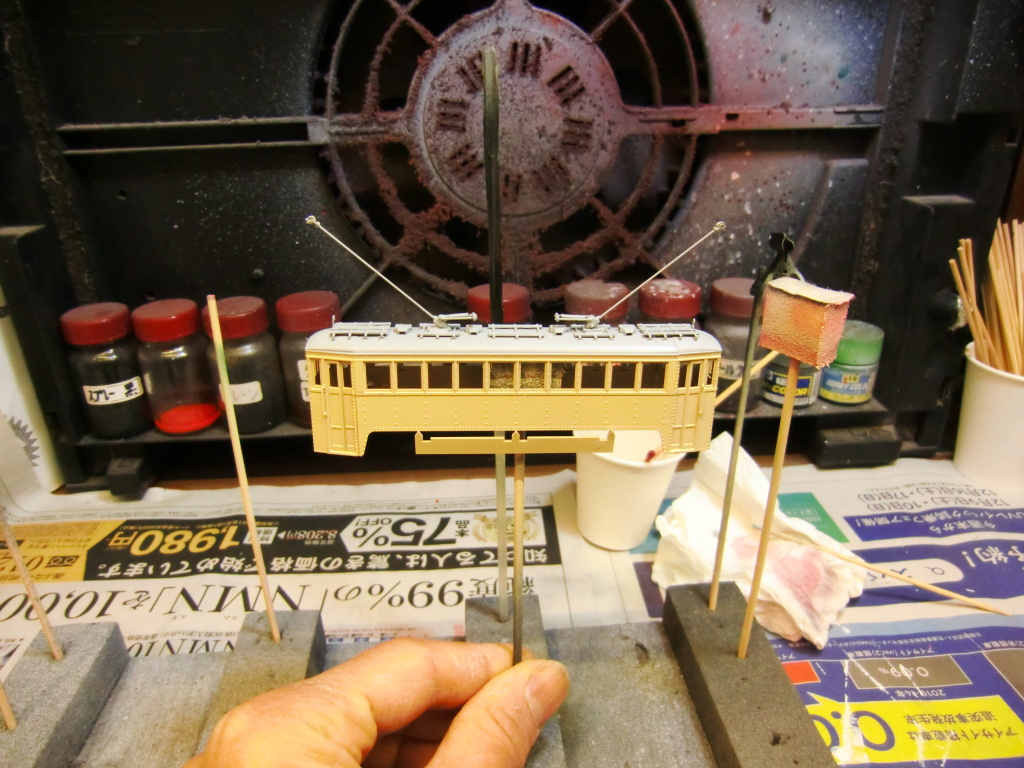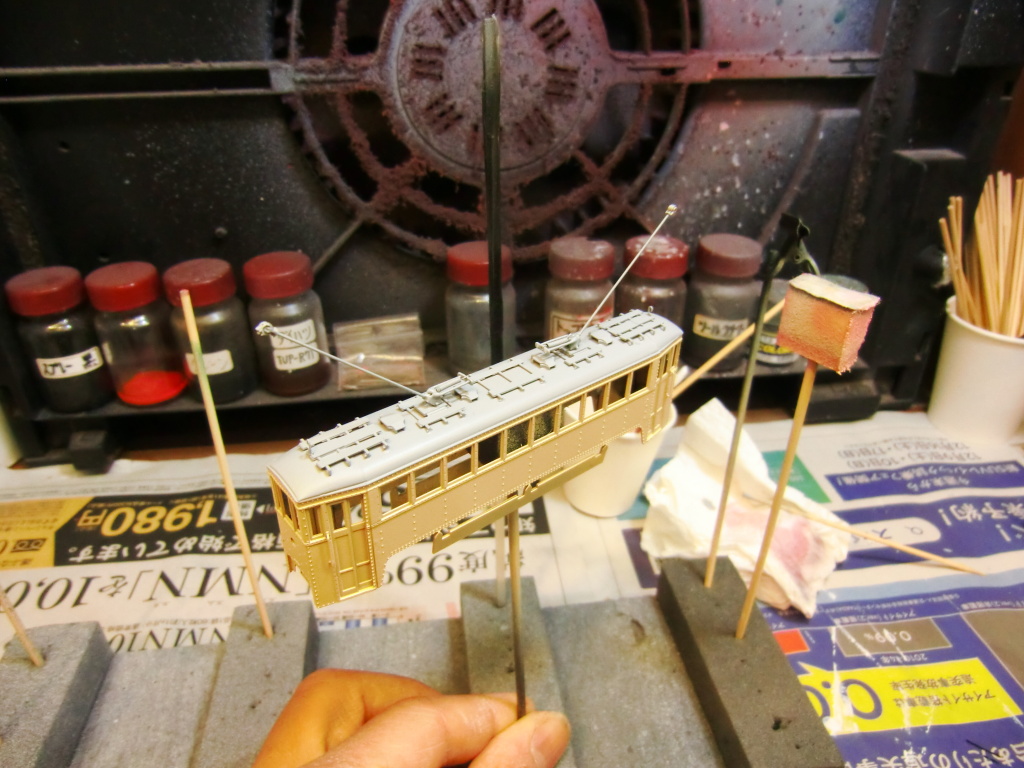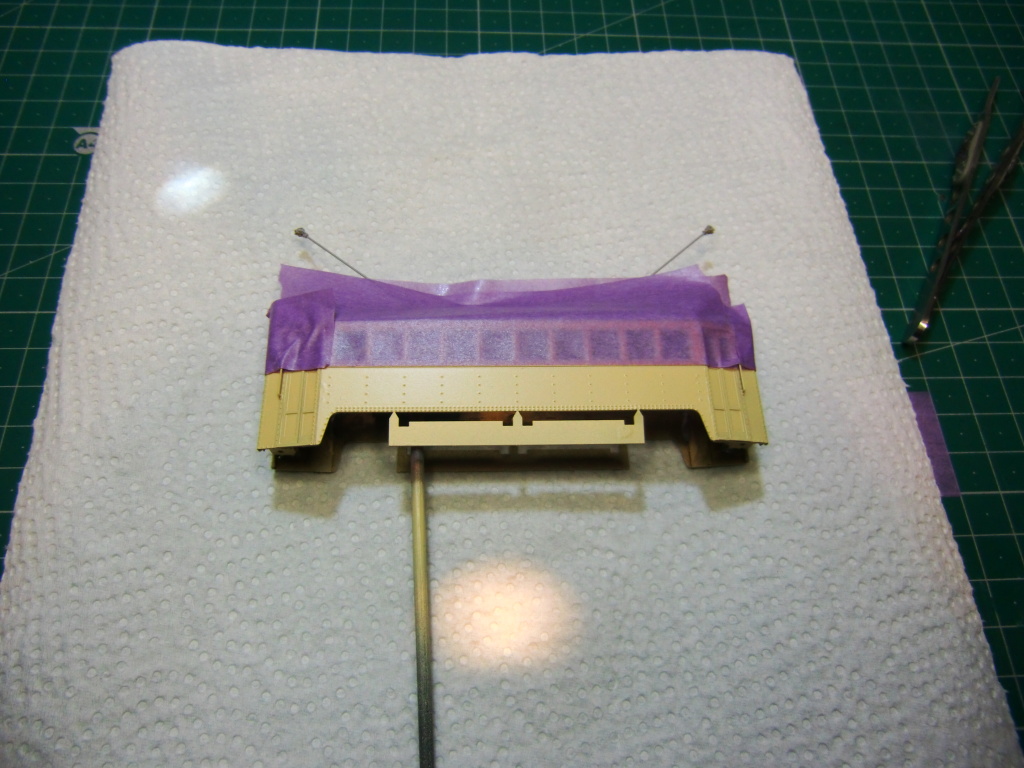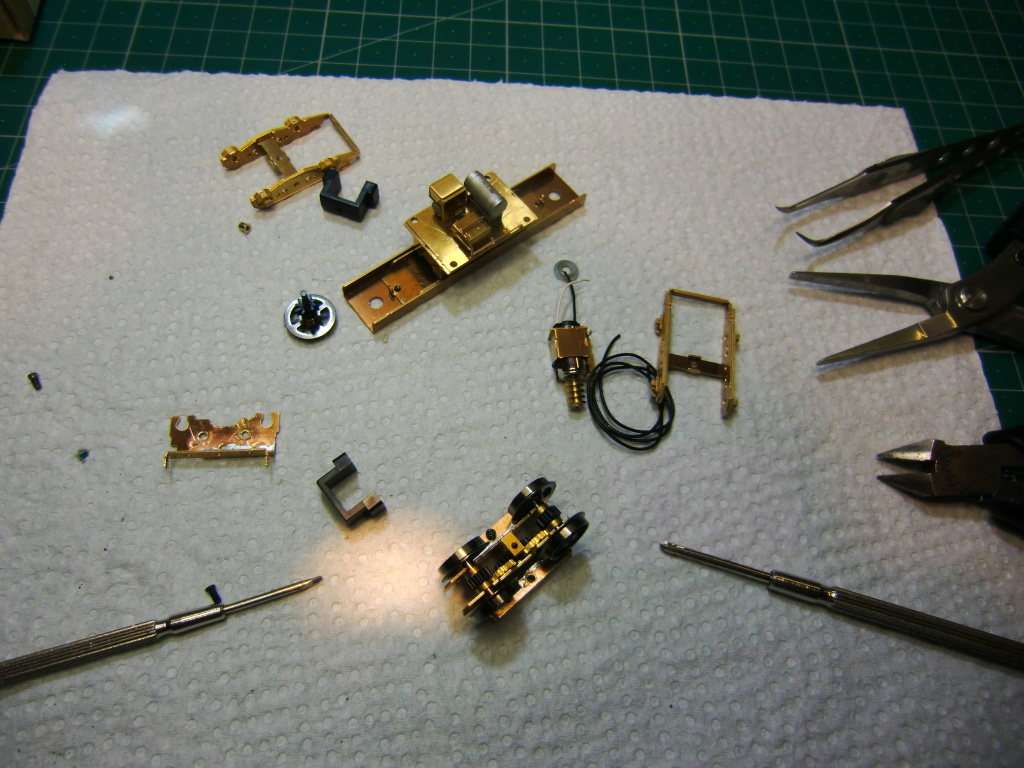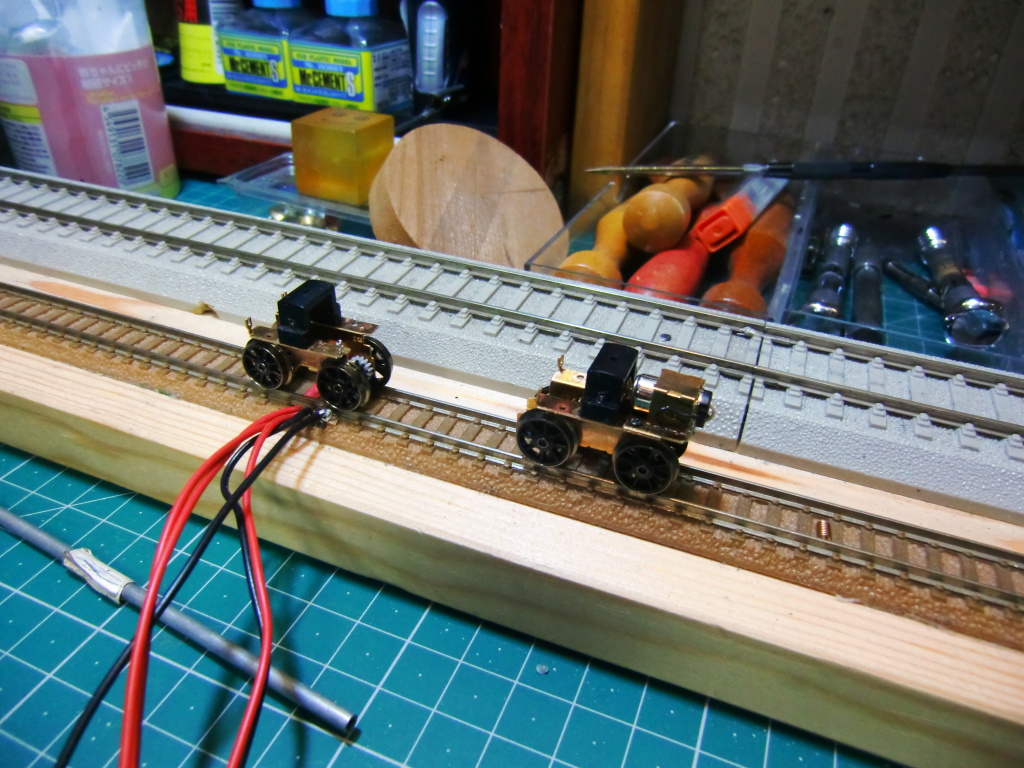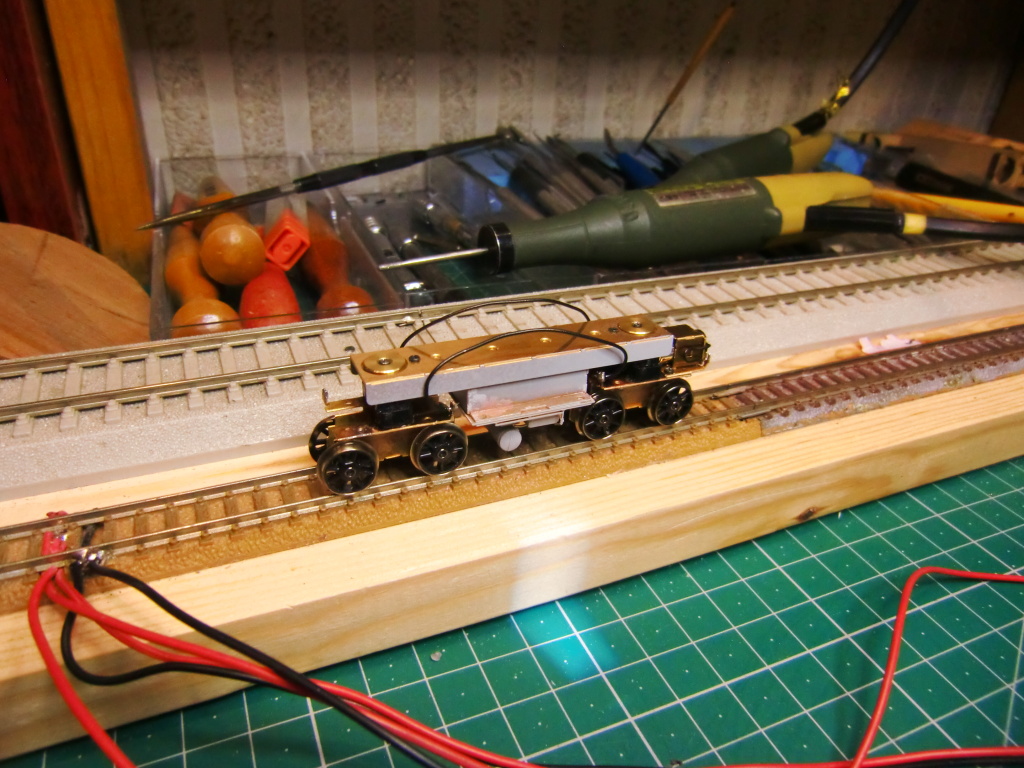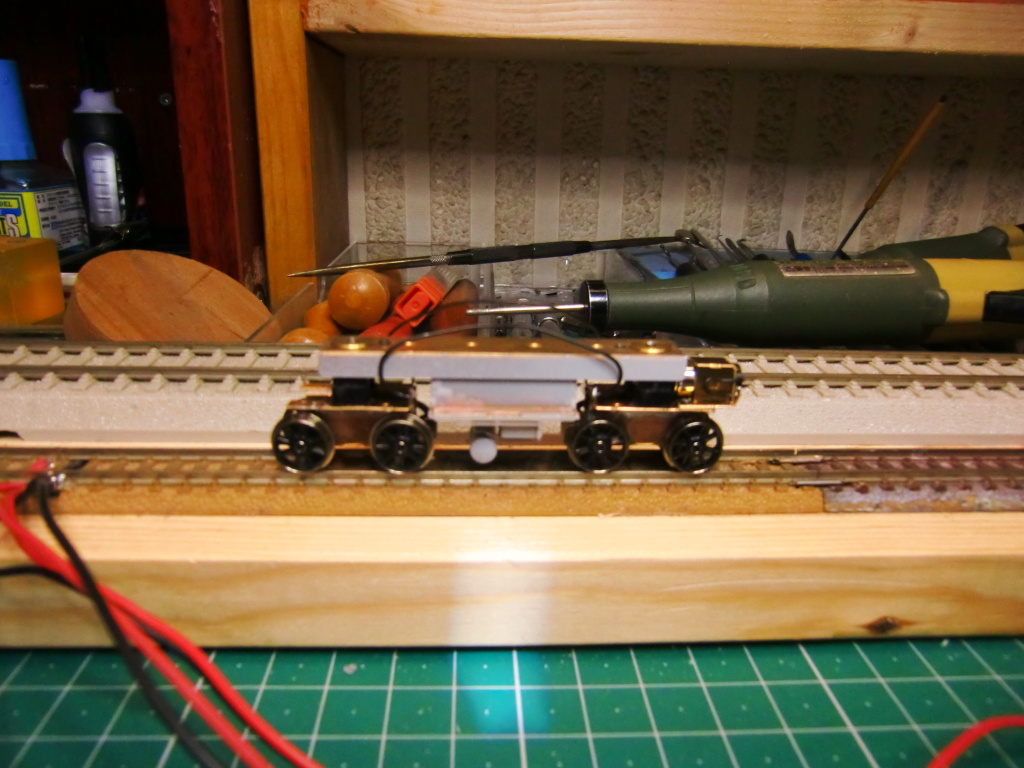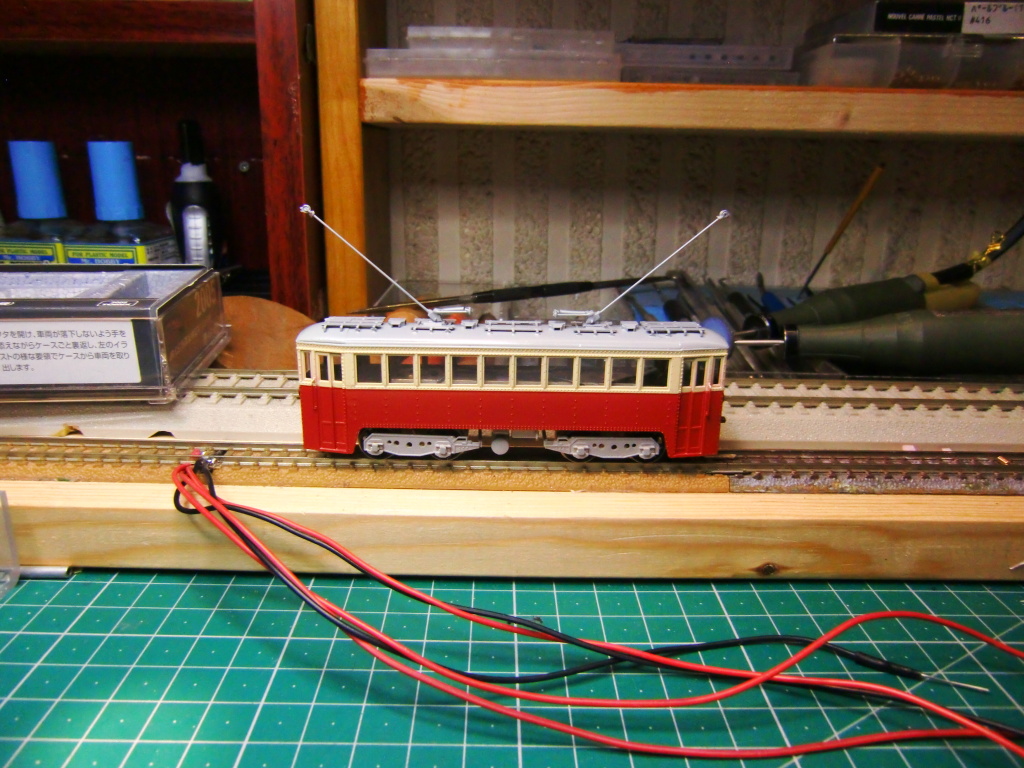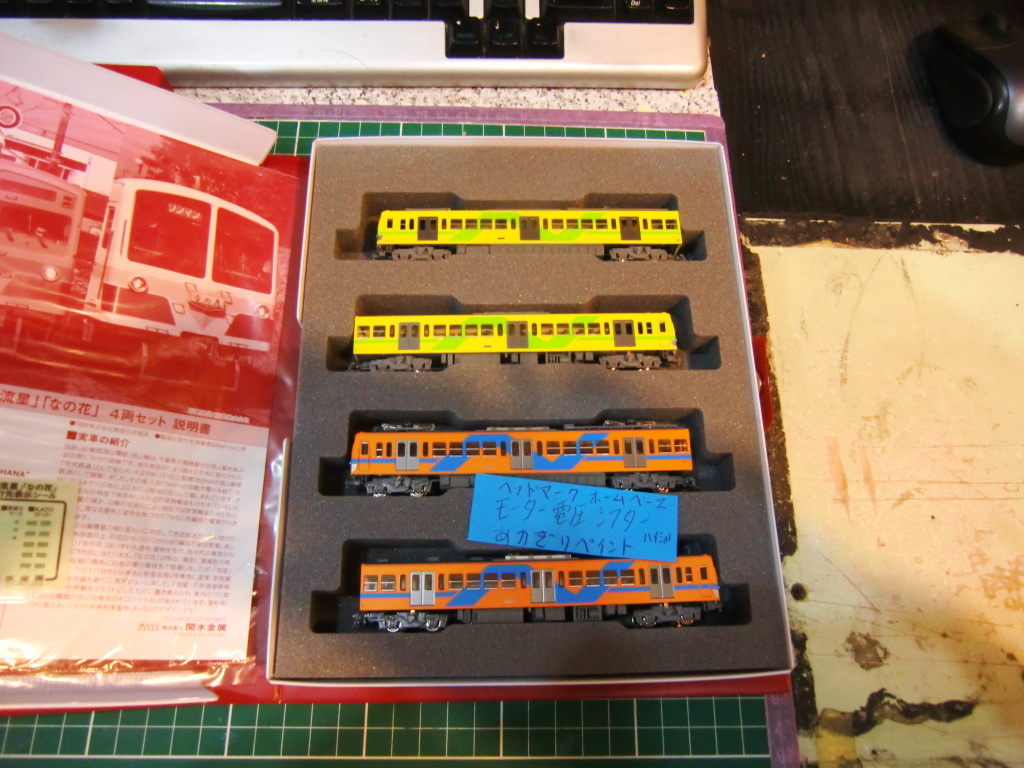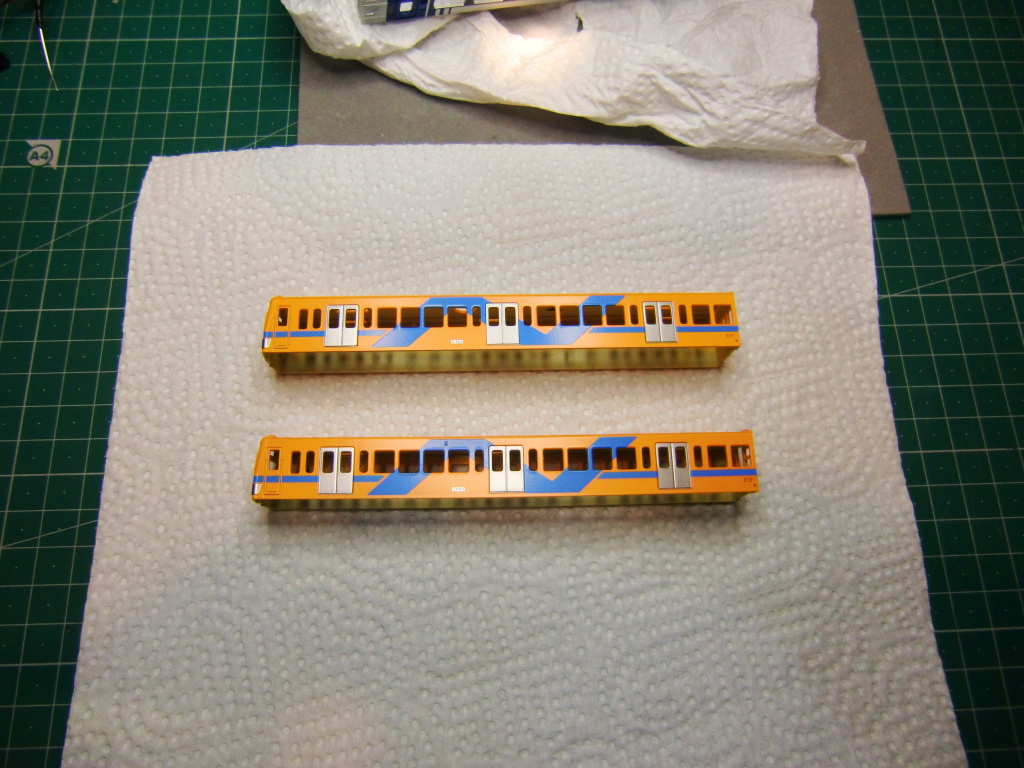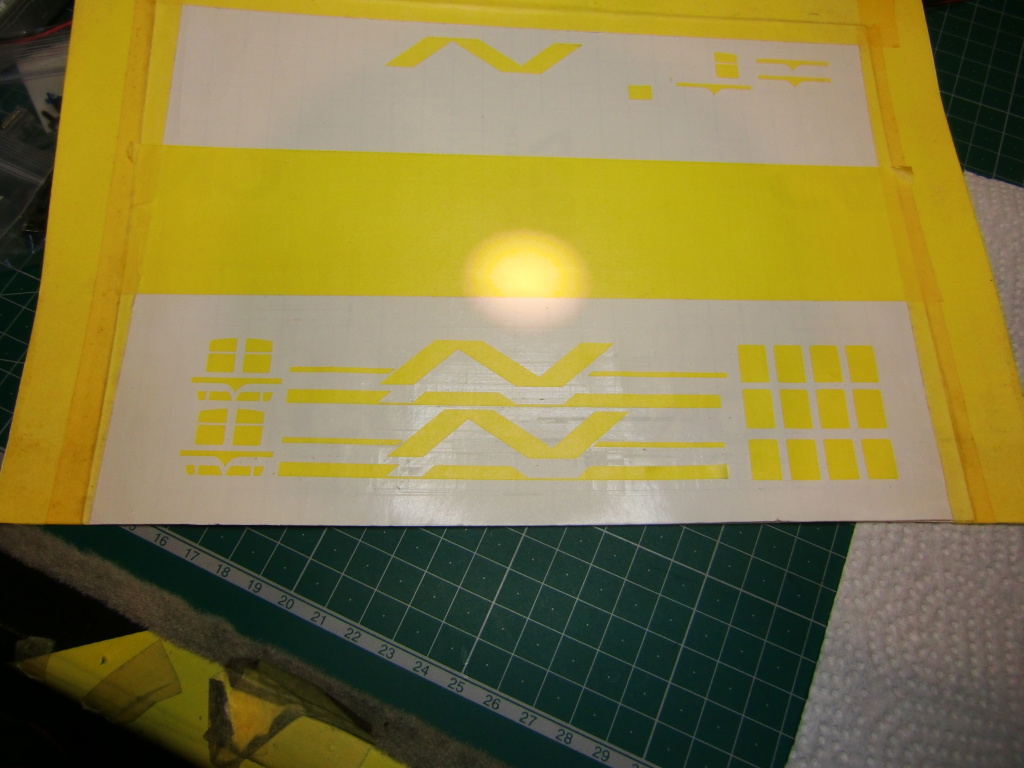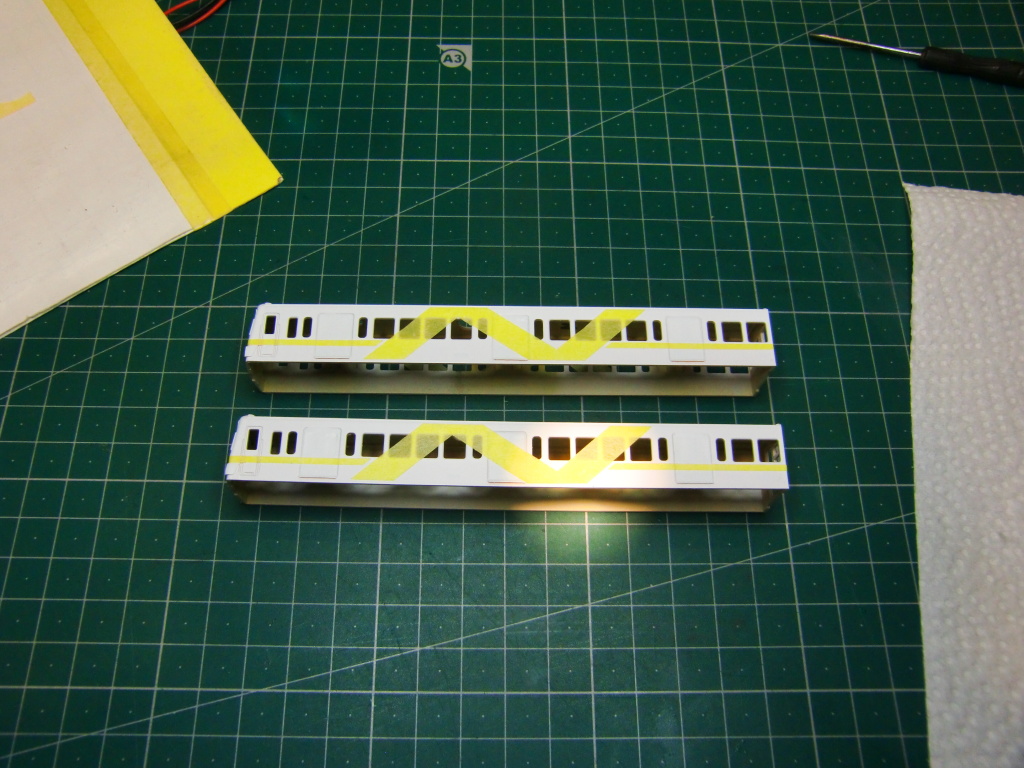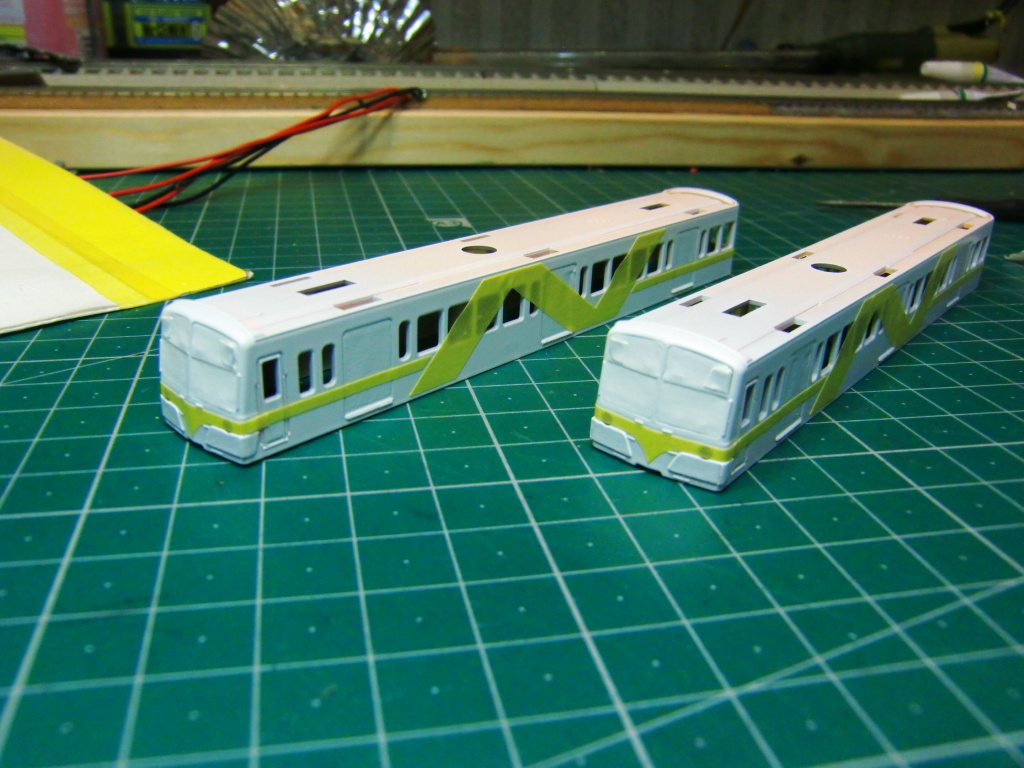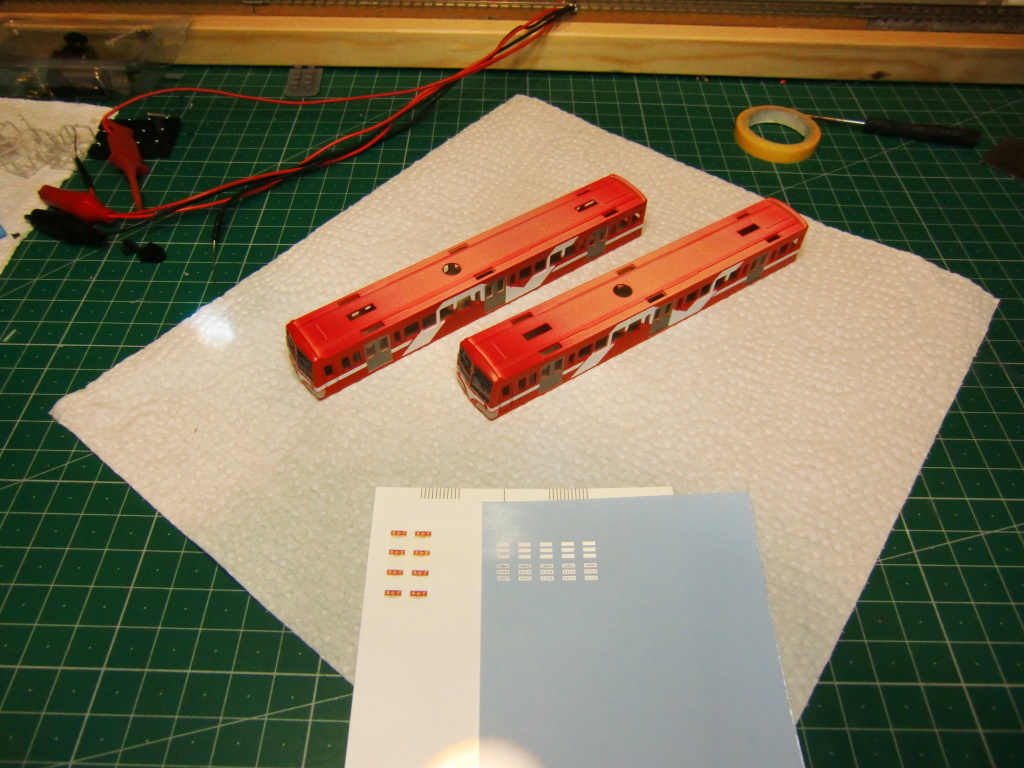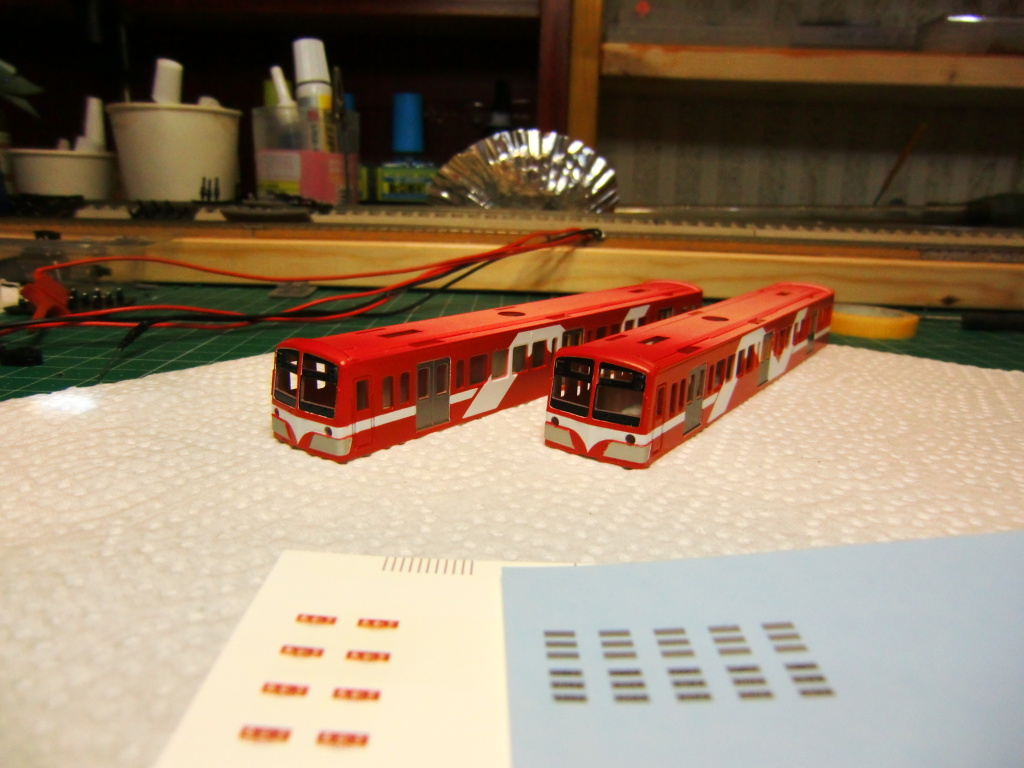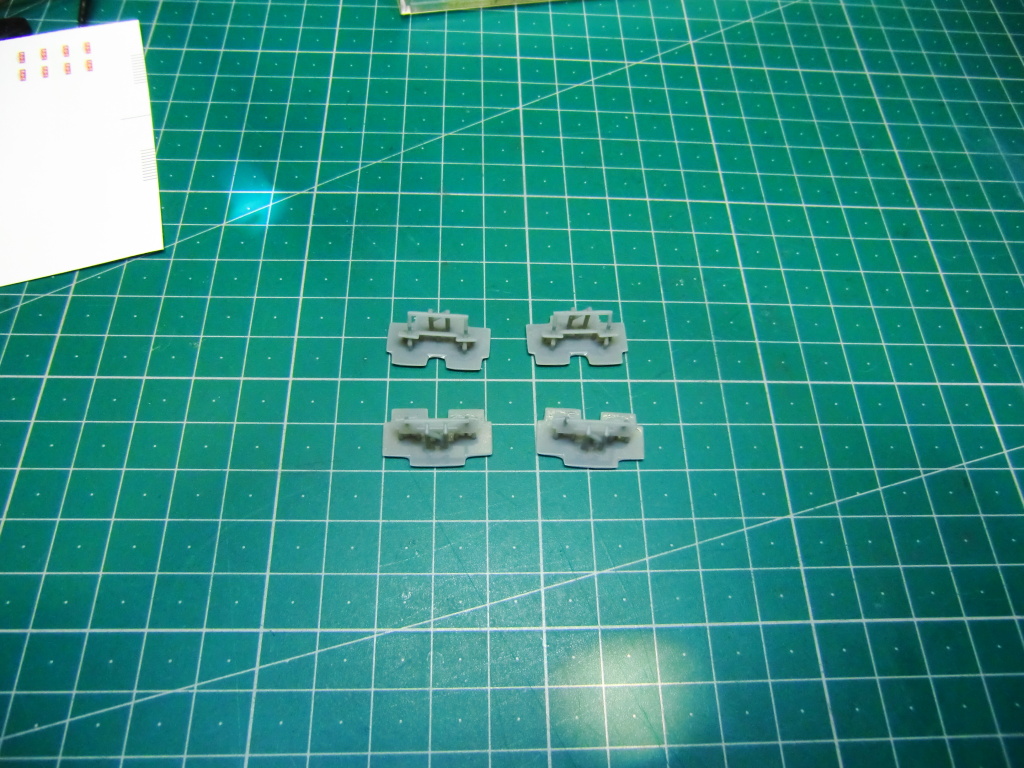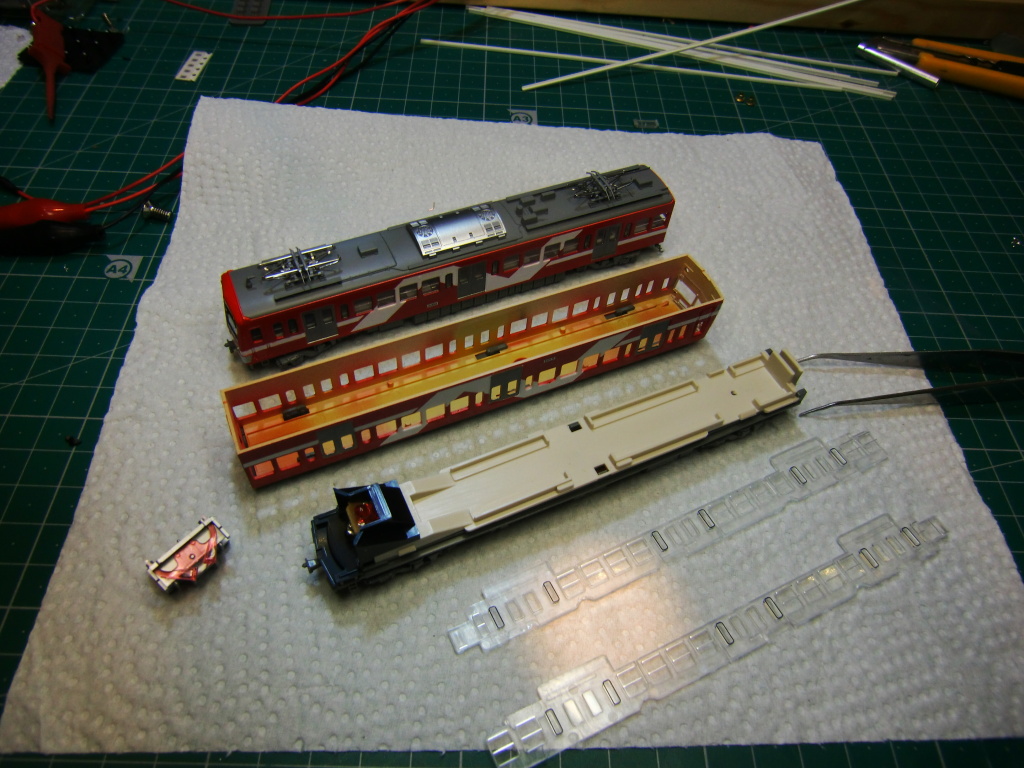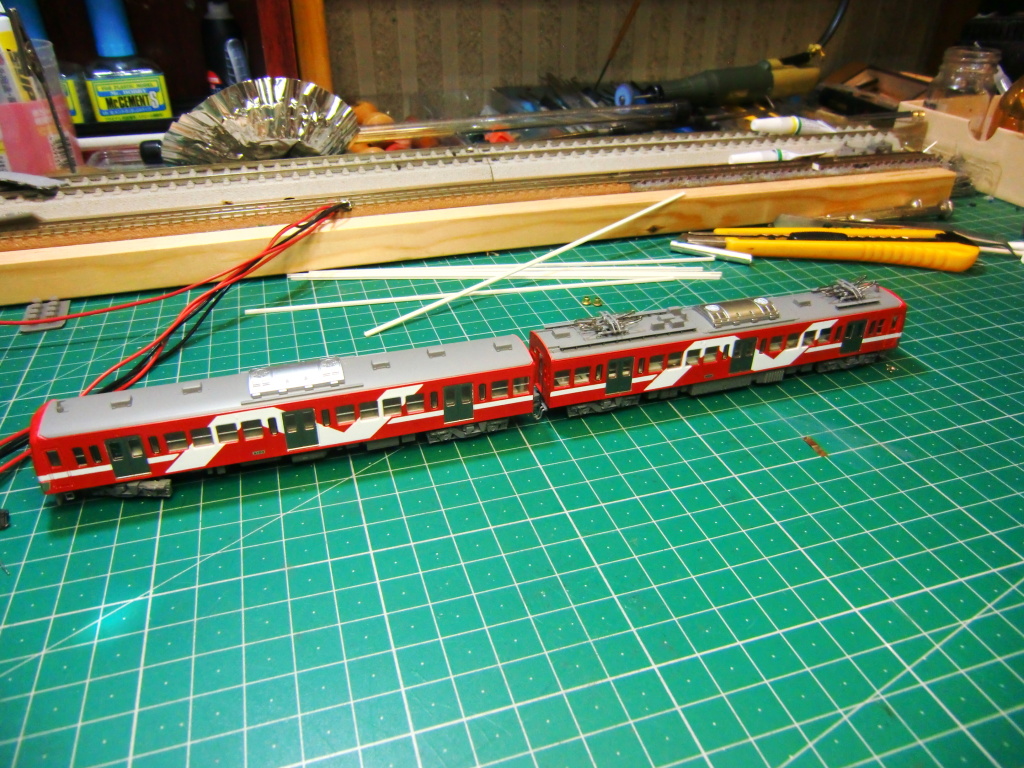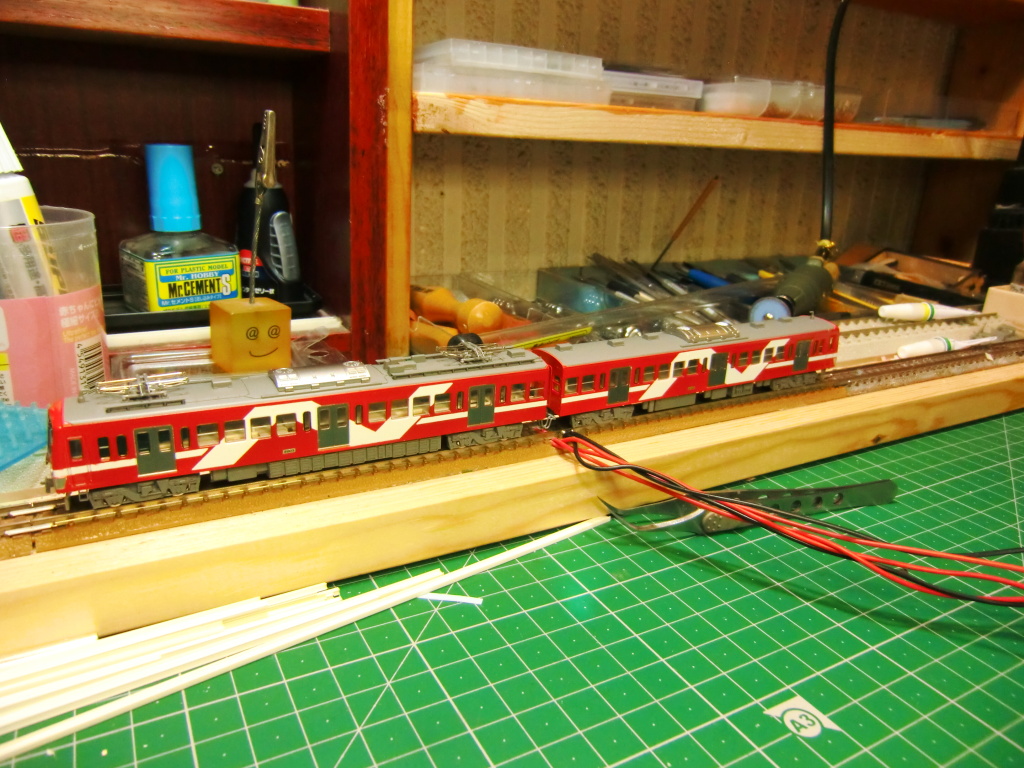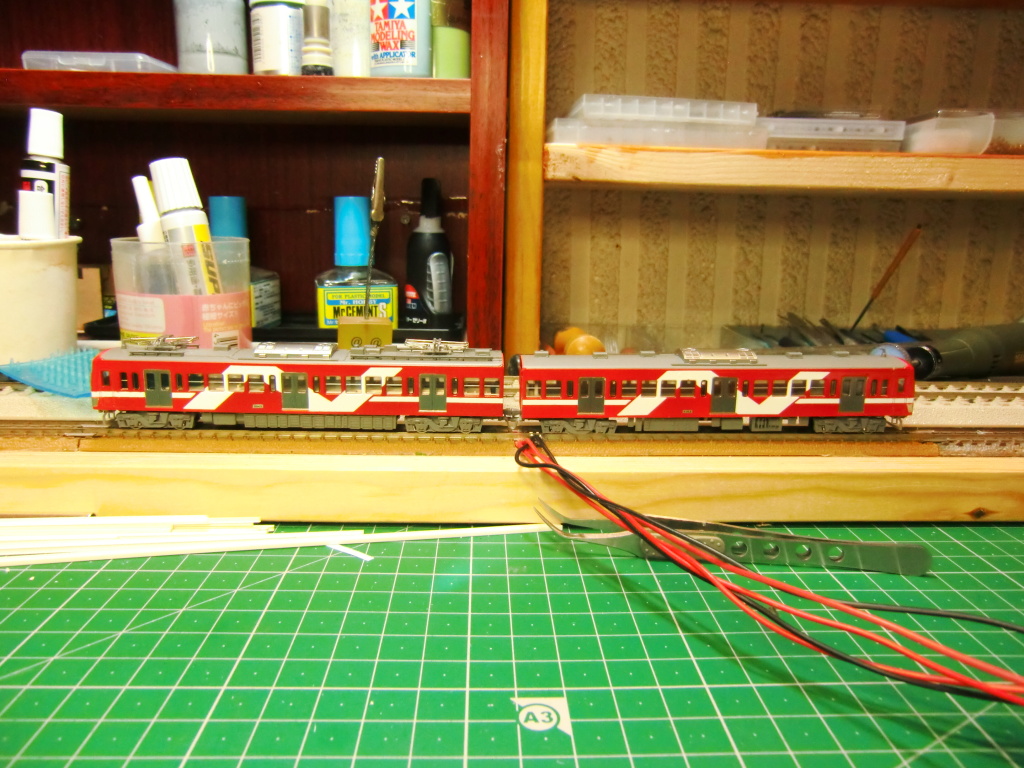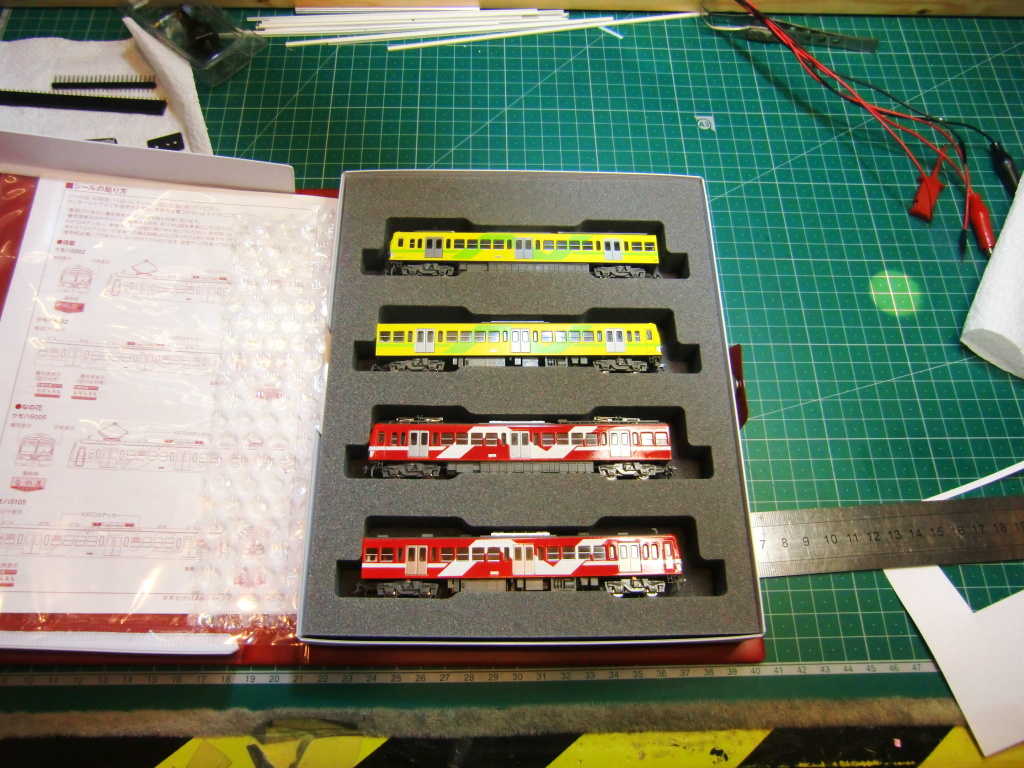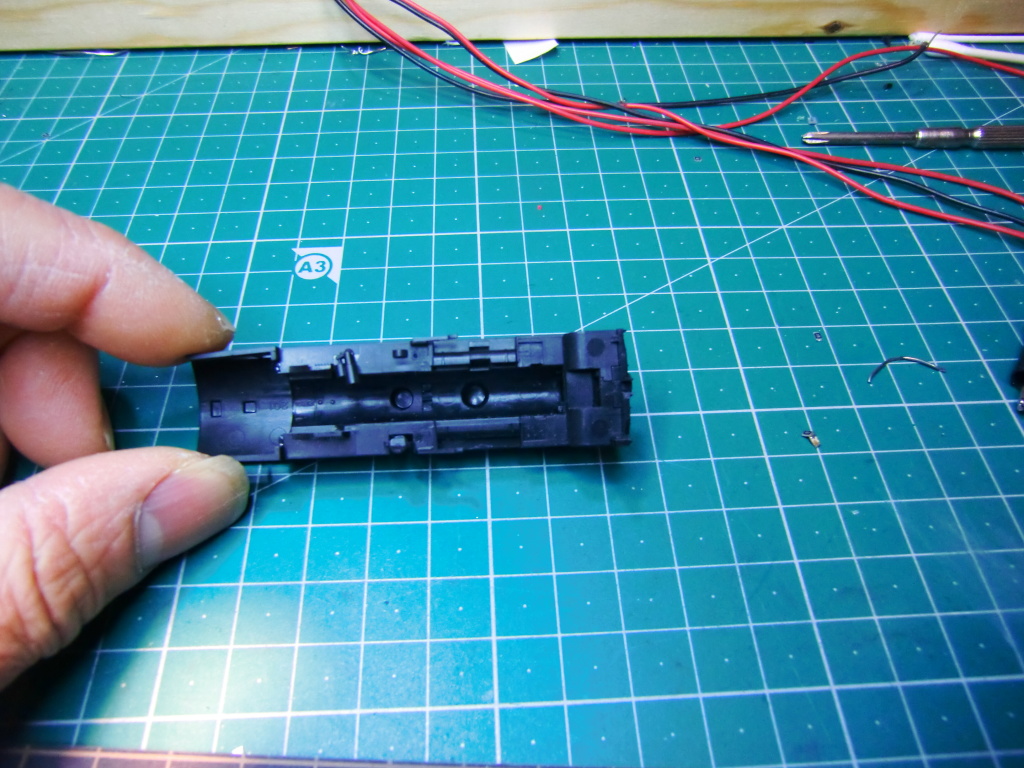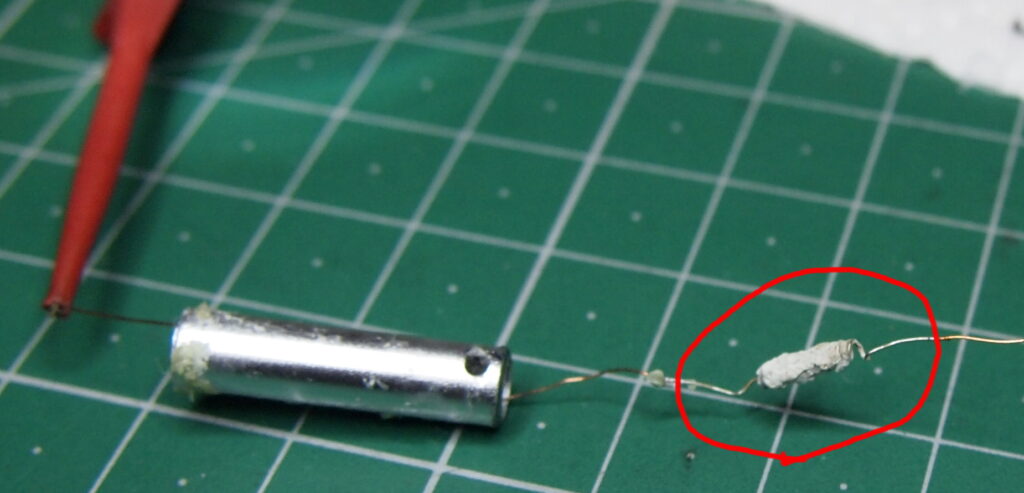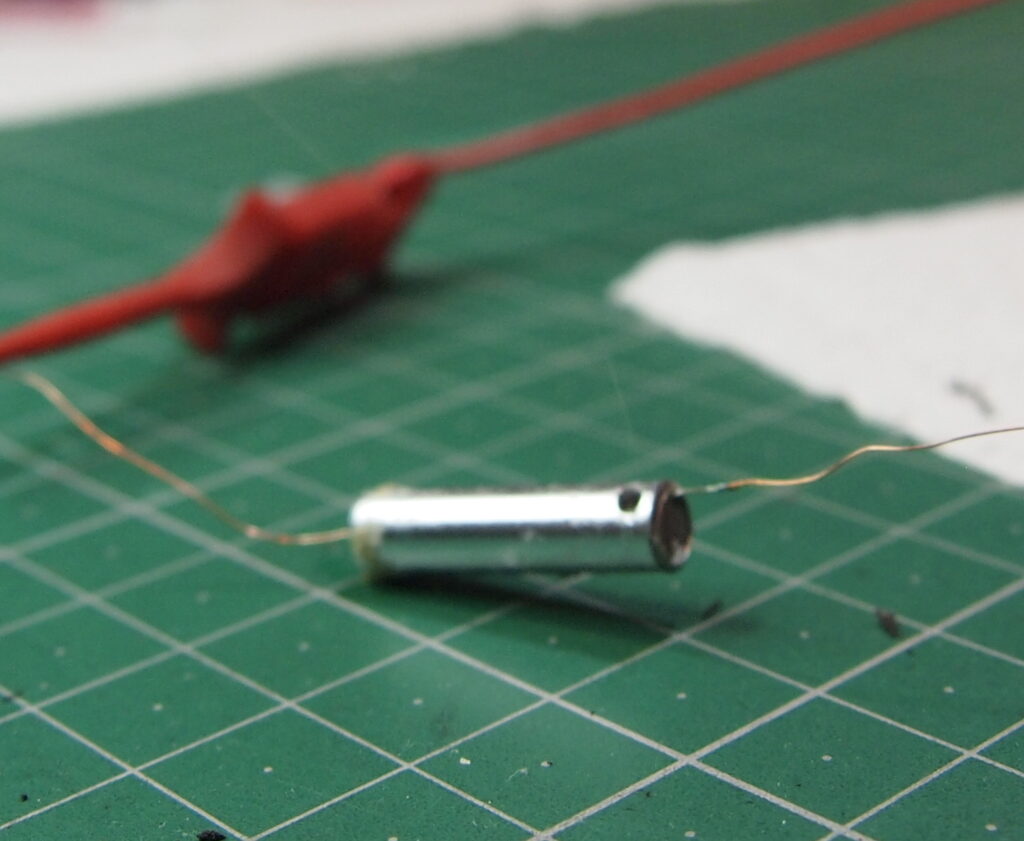今回のご相談では、速度が著しく遅いといったものです。まずは分解して1つ1つ確認していきます。




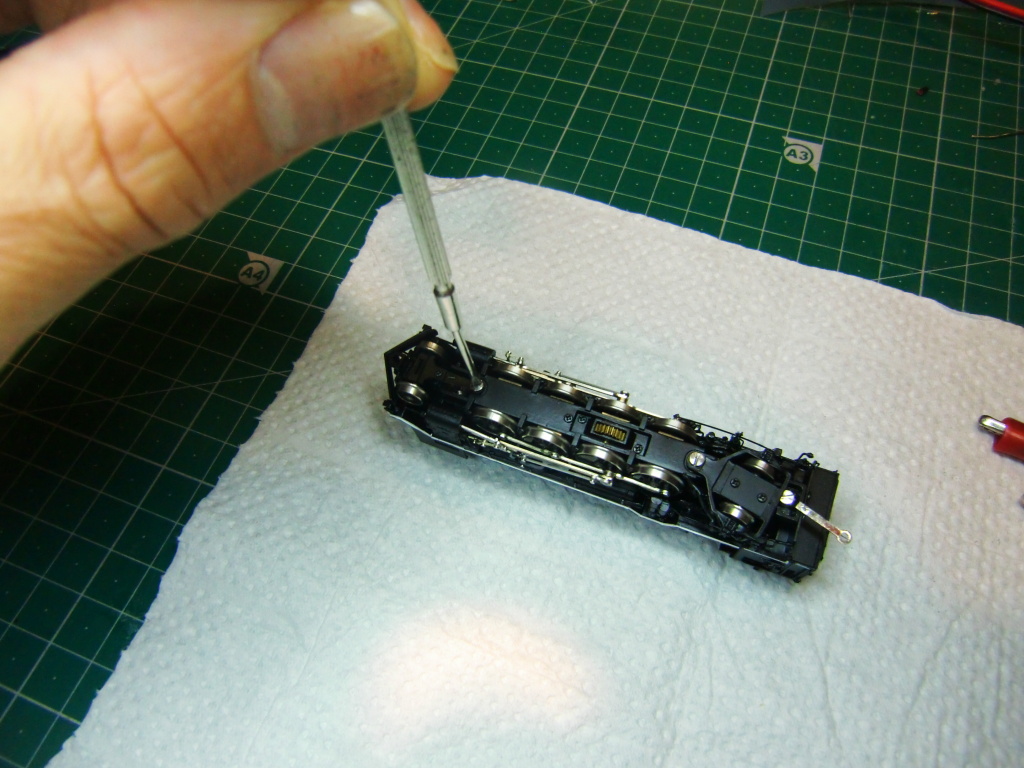

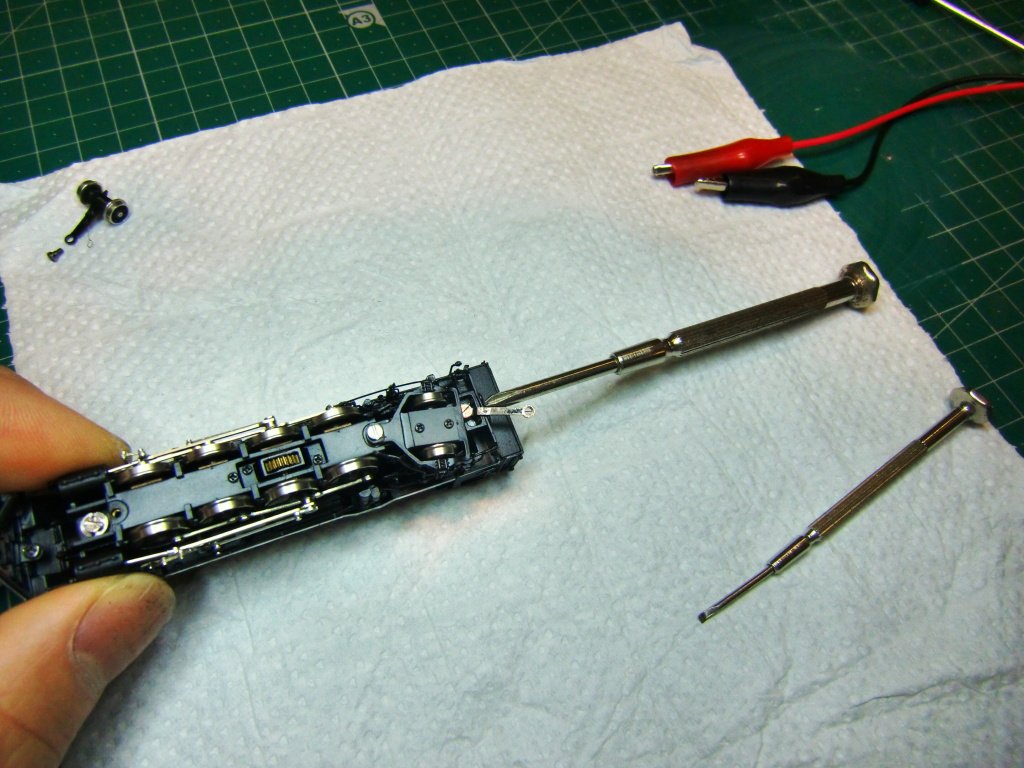
















ルーターで削り穴を広げます。

回転のブレの度合いを見極めながら、最適な位置関係を見つけて微調整を行っていきます。
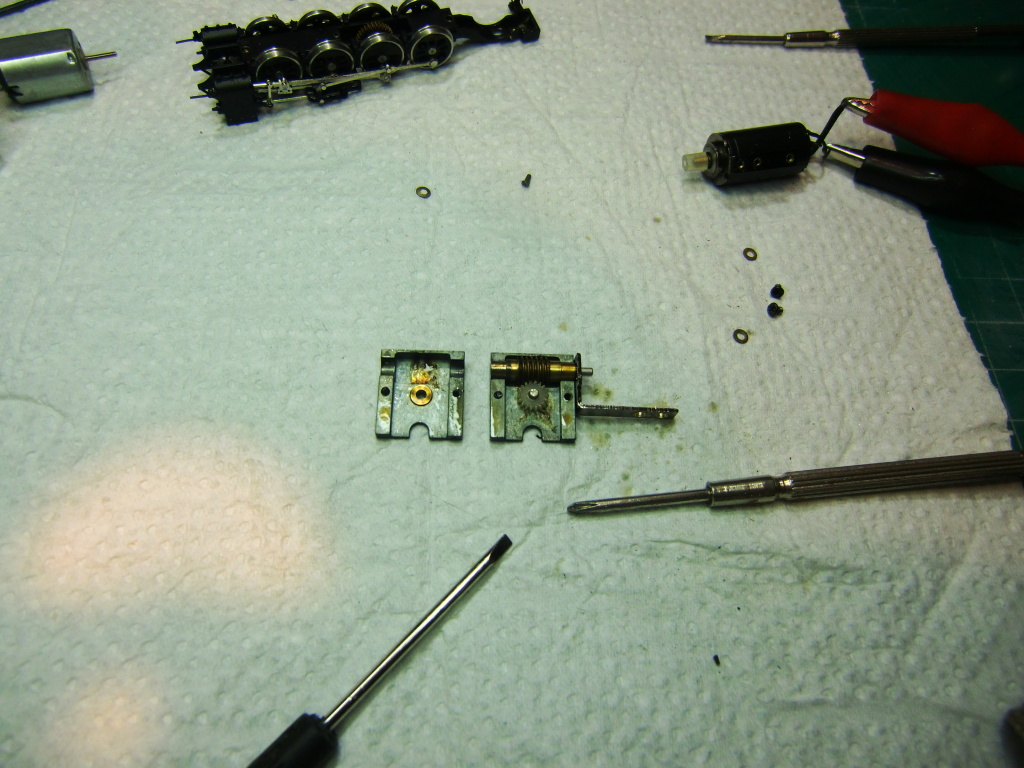
ギア内部の負荷を可能な限り低減させます。
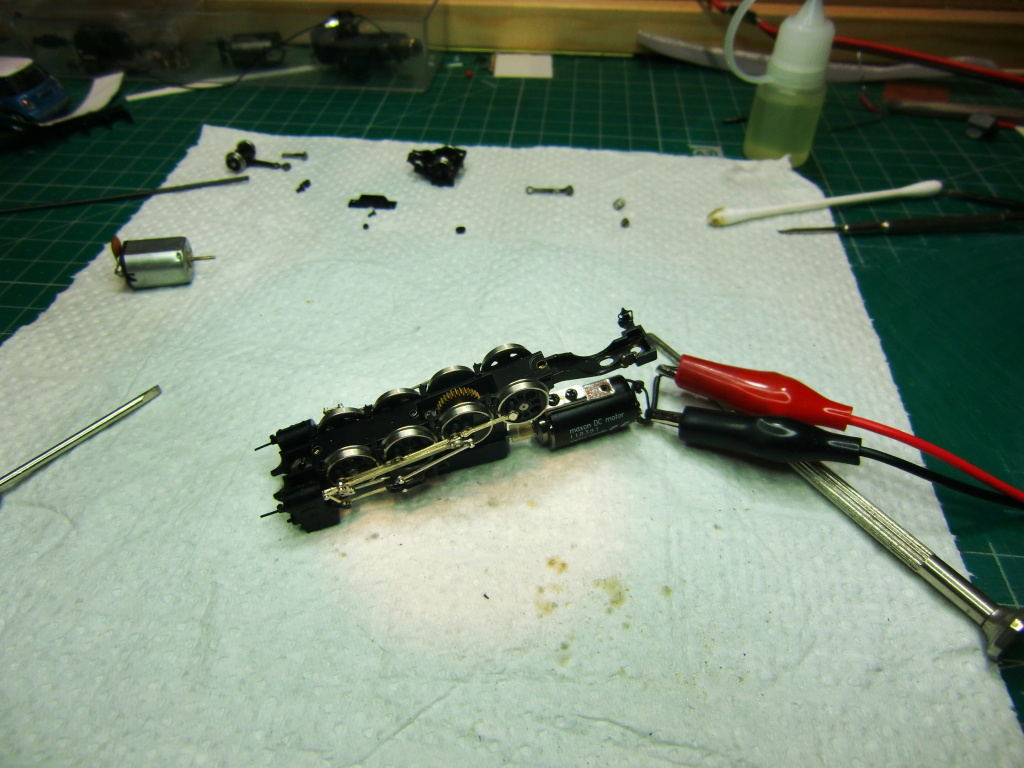



動作確認と微調整をひたすら繰り返します。


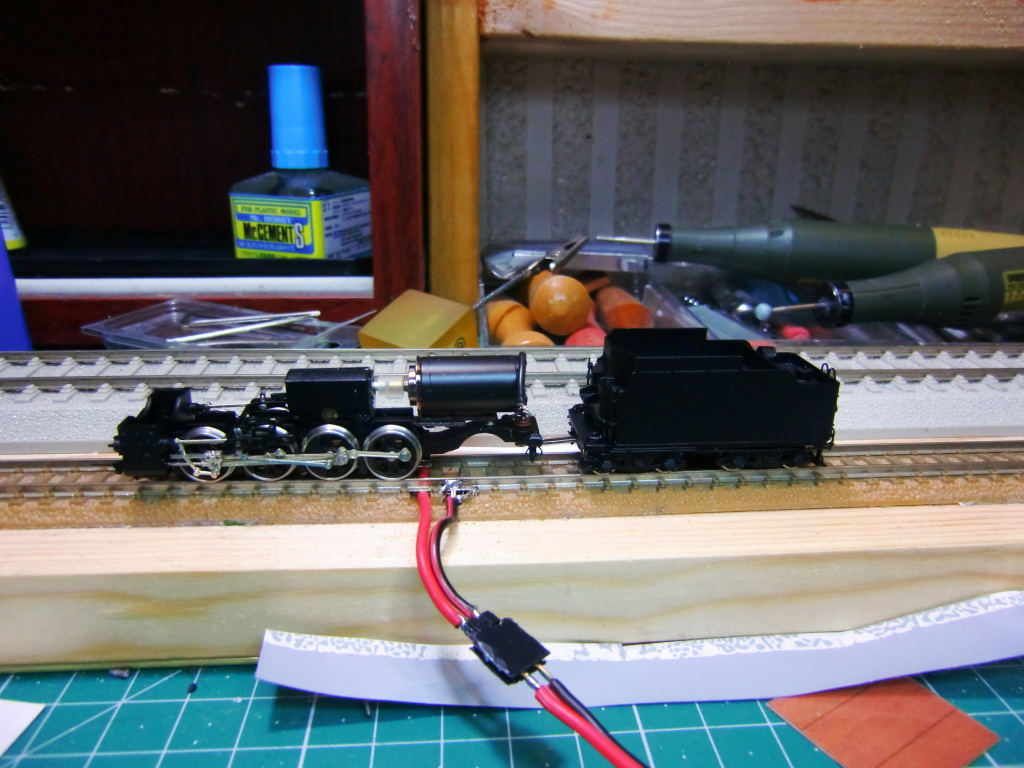

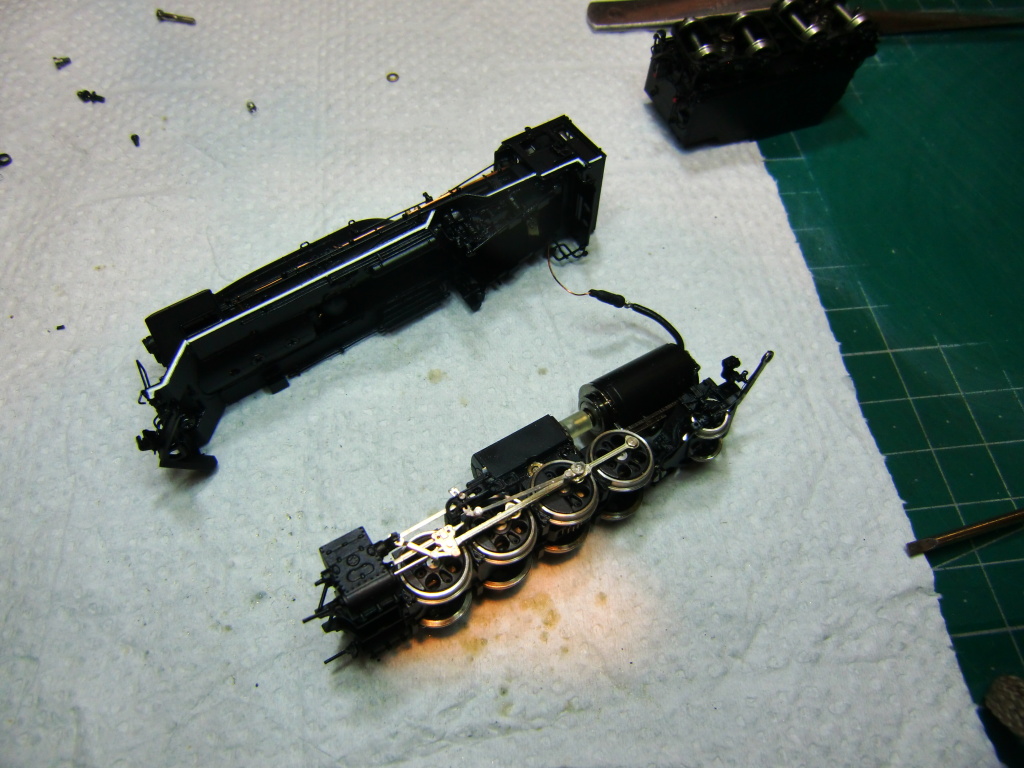

どうもヘッドライトは故障しているらしく、不点灯のようです。今回はあくまでも動力のみの修理依頼でございますので、こちらは保留します。


作業が完了しました。こちらの機関車はもともとそれほど速度が出るようにできてはいないようです。現状からモーターの性能を最大限引き出せるように各部の最善の調整を行いました。
今回もボディーの修復作業でございます。「KATO製EF58 xxx」2台のご依頼です。
▼EF58-116 部分修復

現状はこのような状態でございます。顔の形が変わってしまってい感じですね。今回のご依頼は、ナンバープレート部分の埋め直しと塗装、それとインレタの貼り付けのご依頼となりますことから、気になる個所は多々ありますが、今回はそれ以外の個所の作業を行いません。

作業がしやすいように、ガラスパーツなどはすべてはずします。

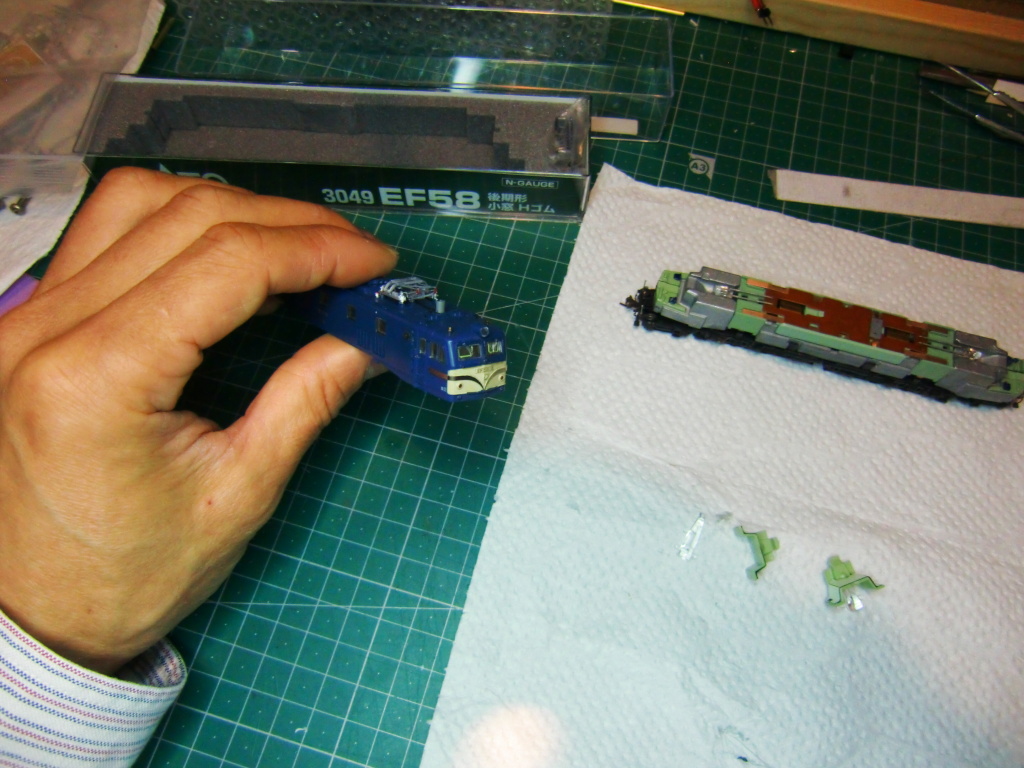
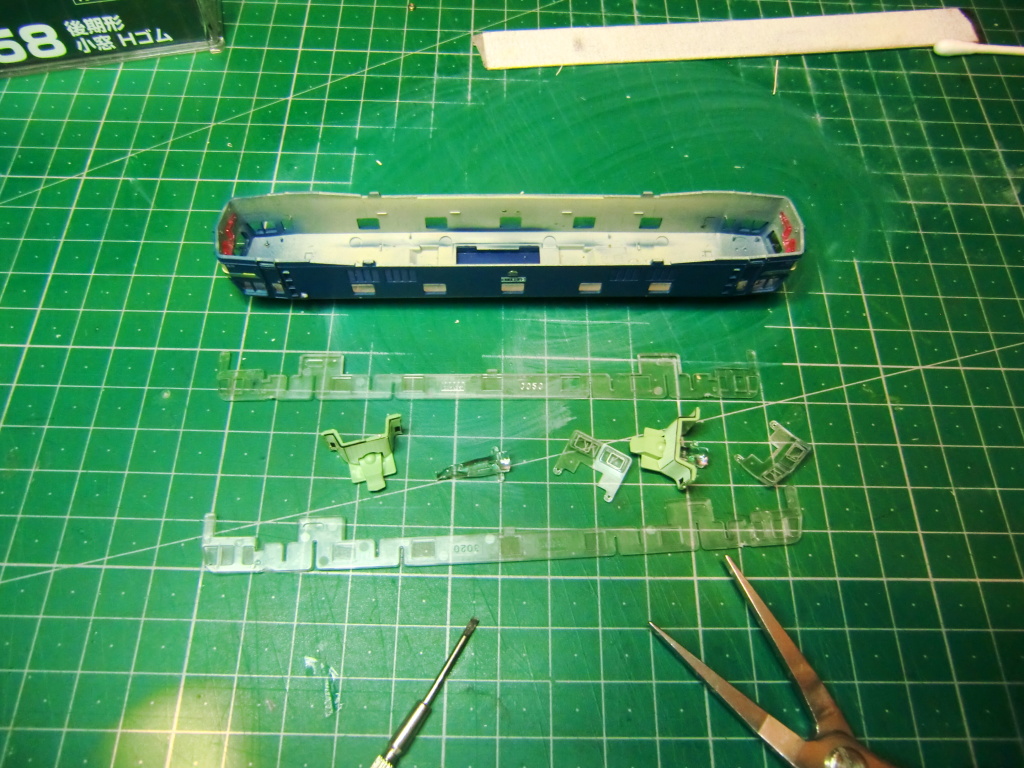

ヘッドマークのフックも表面を削りだす際に邪魔になるので引き抜いておきます。


ナンバーをある程度削り終えたら、パテを塗って隙間を埋めます。先写真のようにマスキングシートを貼り、余分な個所にパテがつかないようにしておきます。パテがある程度乾いた段階で、「#600~800」のペーパーで仕上げていきます。

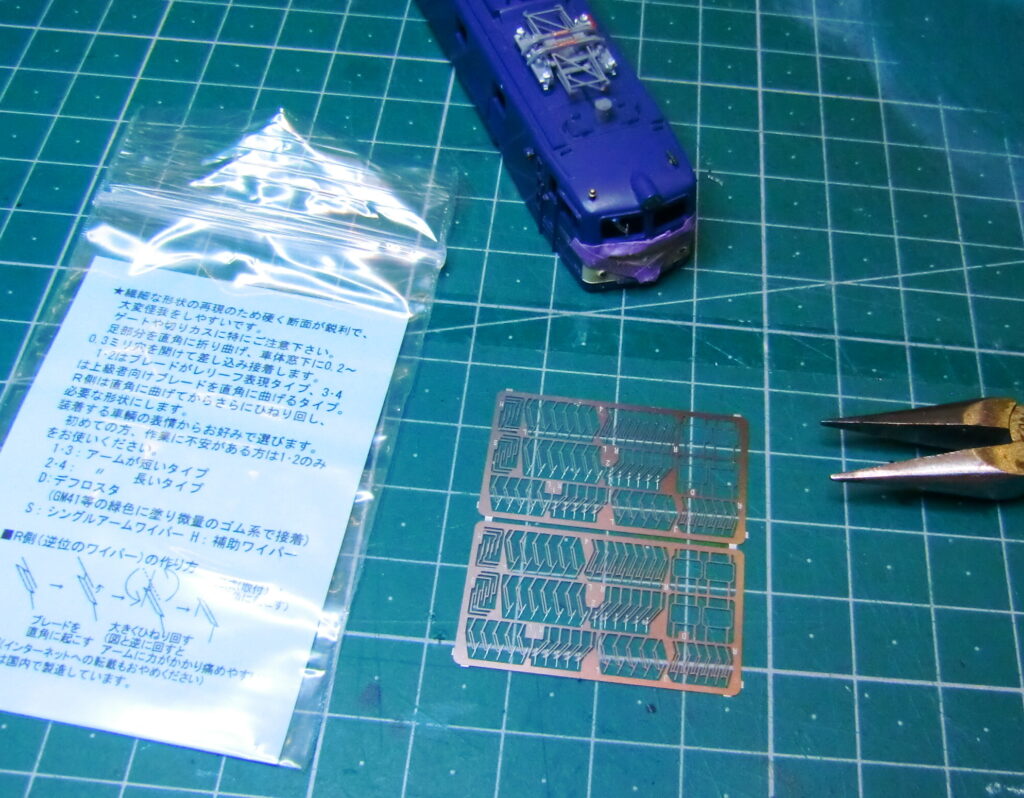

次に凸凹してしまっているヒサシも成型しなおして、形を整えていきます。


可能な限り面を慣らして塗装を終えたところです。あとは細かい箇所の色差しで整えてワイパーとヘッドマークステーを作り直したものを取り付ければ完了です。








可能な範囲で正面の形状を修復いたしました。また、各部のディテールアップパーツが、さわると簡単に取れてしまう個所が随所にありましたので、そちらも固定しなおしました。
作業完了でございます。

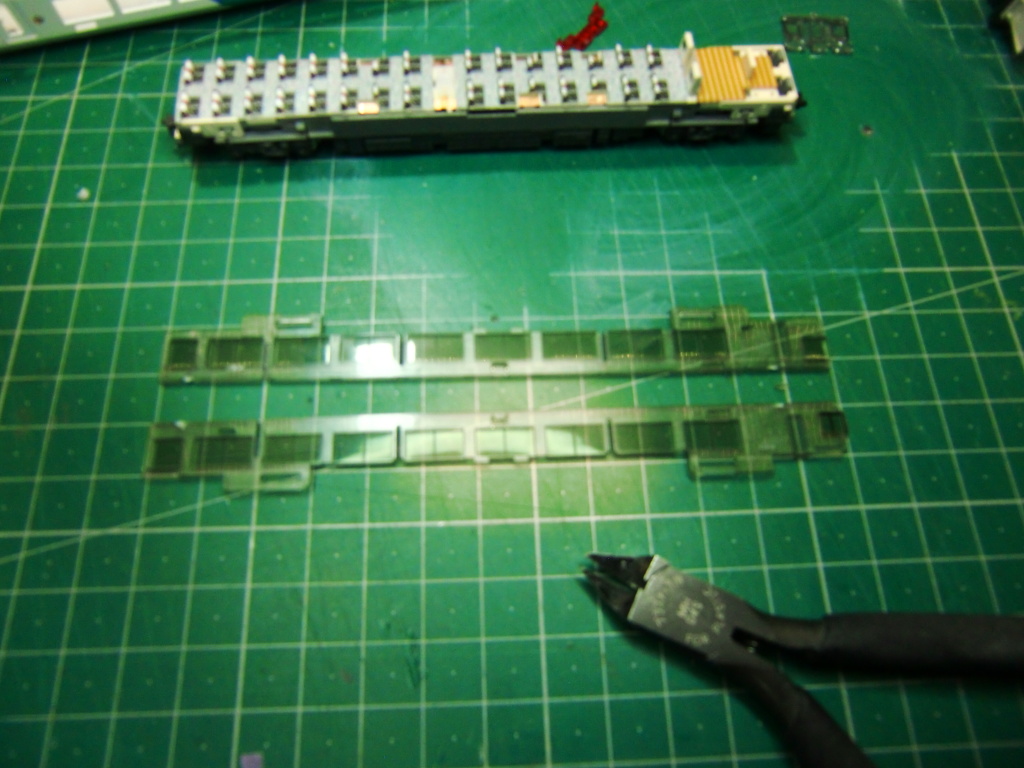

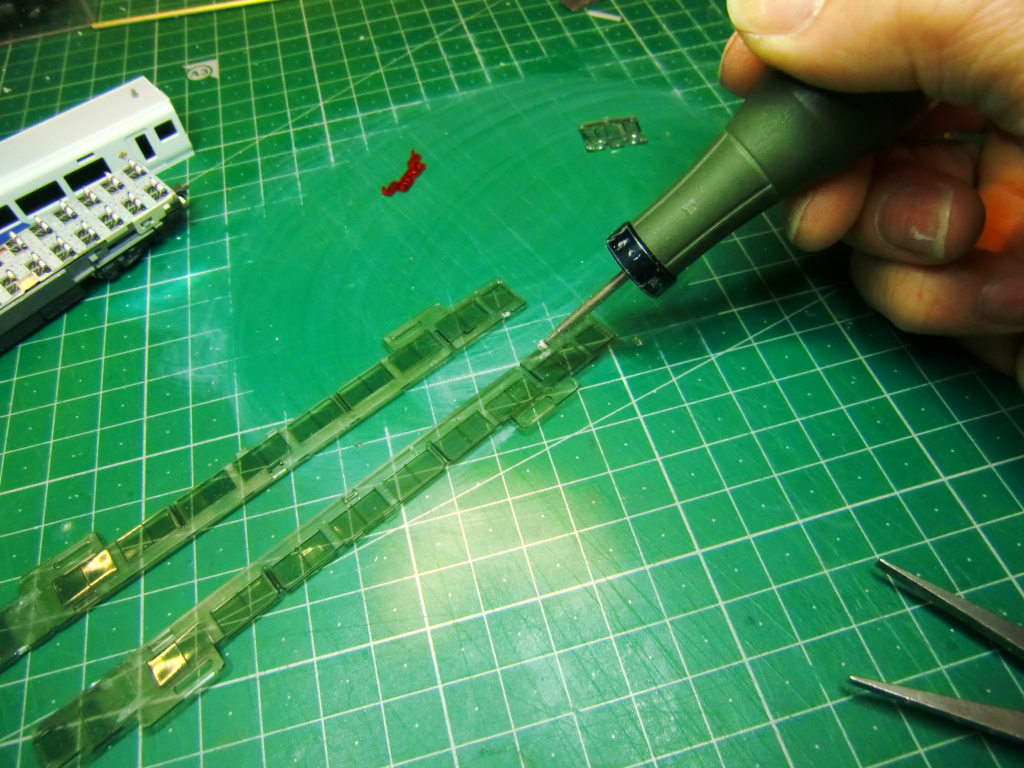


窓ガラスの加工だけではうまく収まらないようです。座席の加工も必要なようですね。

分解して干渉する個所を1つ1つ調整していきます。

座席パーツはこのように加工します。

反対側も加工しておきます。

切り離した面を平らにならします。
加工->調整->確認を繰り返します。

このように外側に膨らむことなく、ぴったりと収まりました。

高さと位置関係もOKです。

▼ライト点灯化改造
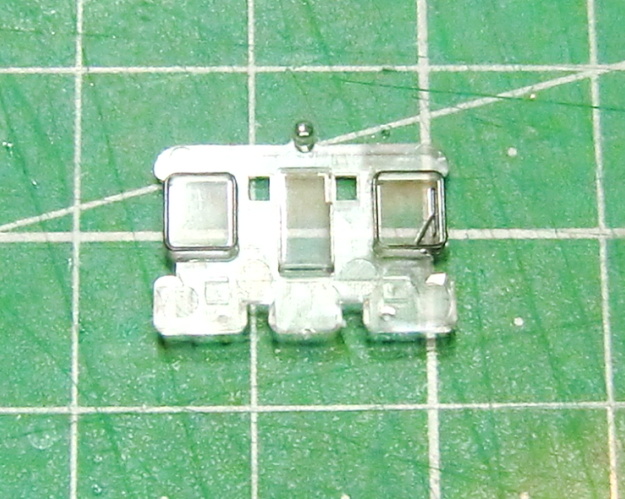
一体化されたパーツを分割します。
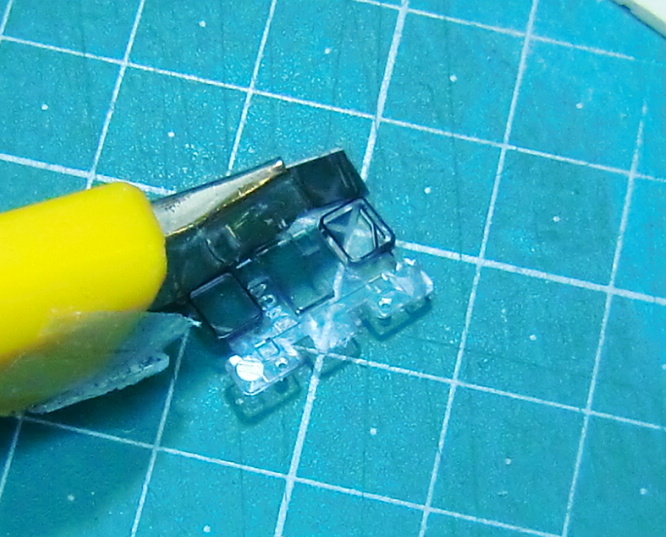
ヘッドライトを切り離します。
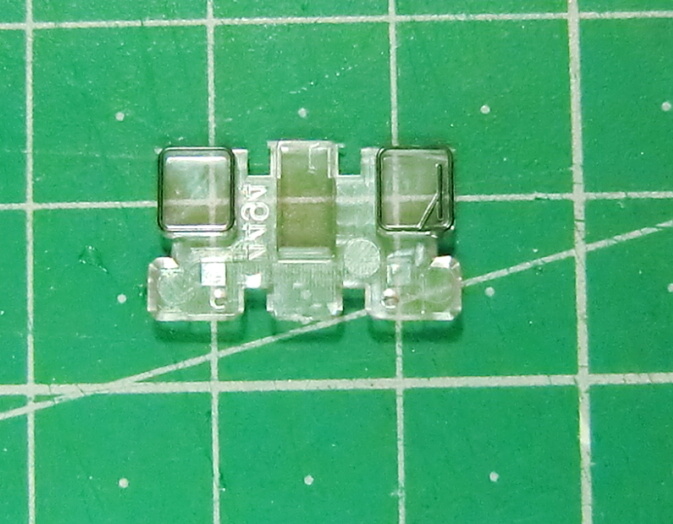
上記のようにギリギリまで切ります。
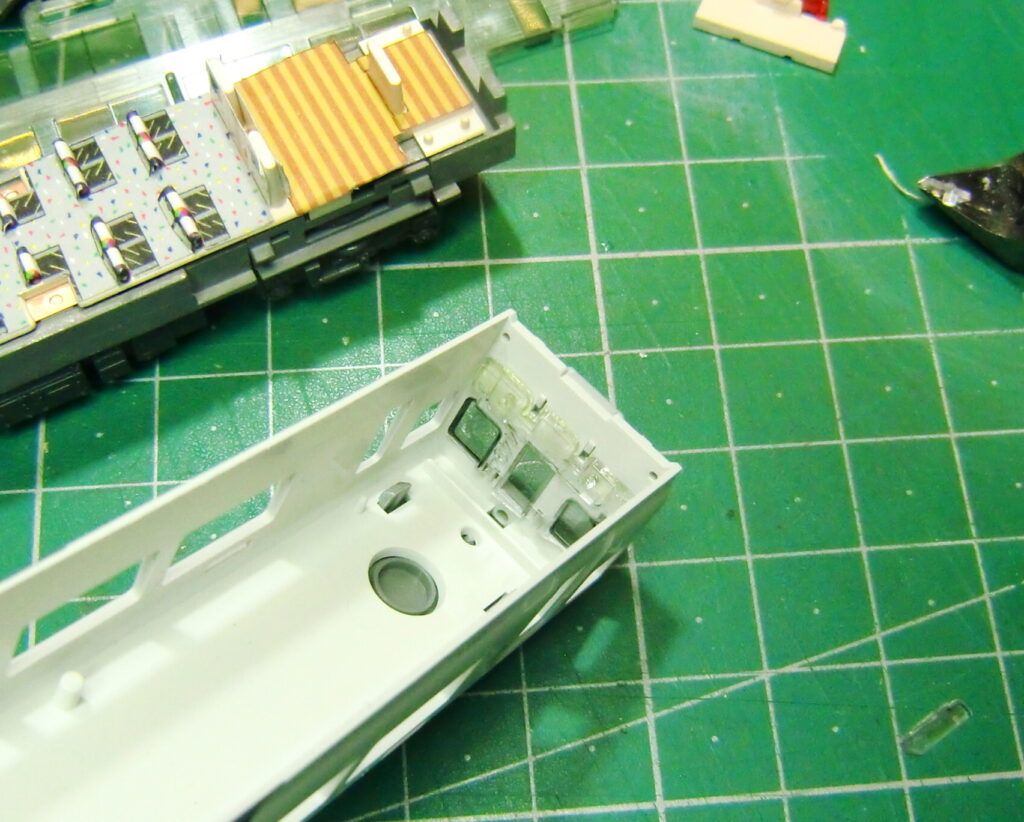
正面のガラスパーツを先に固定してから、切り離したヘッドライトの透明パーツを埋め込みます。

各ライト周りの遮光処理を行います。
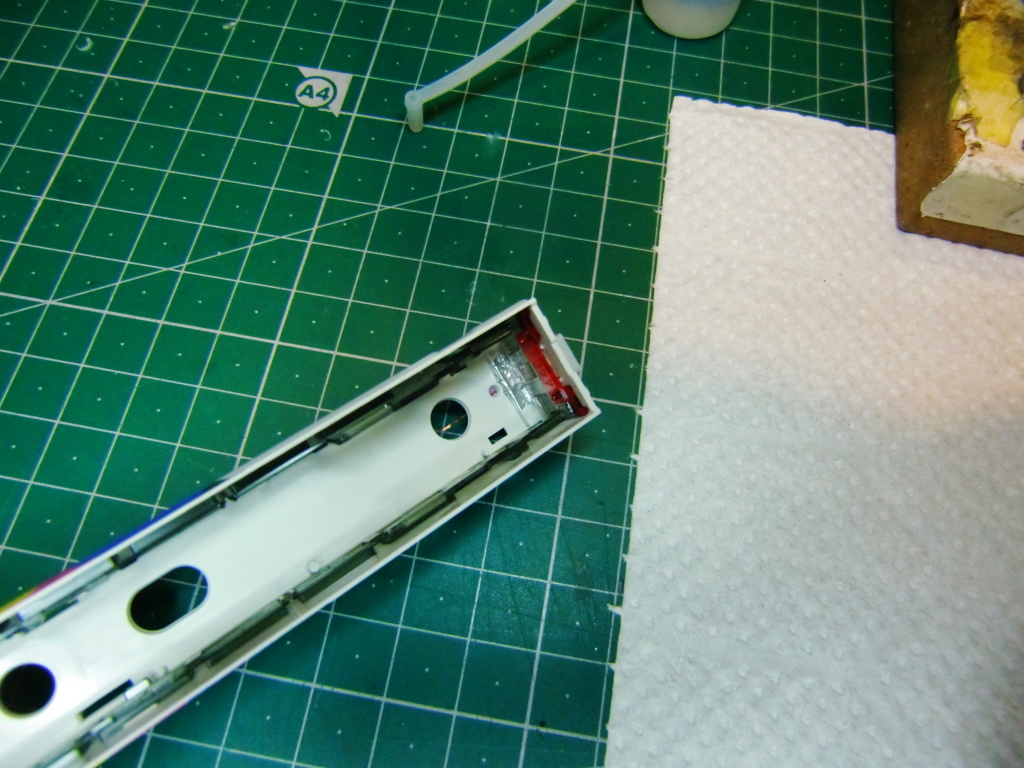


ヘッドライトの点灯テストです。

まずは、ヘッドライトはOKです。次にテールライトに移ります。
テール点灯における制作過程は省略します。

テール点灯加工の作業も完了です。モーターからのノイズ対策を行います。





最後にカプラーを取り付けて作業は完了です。
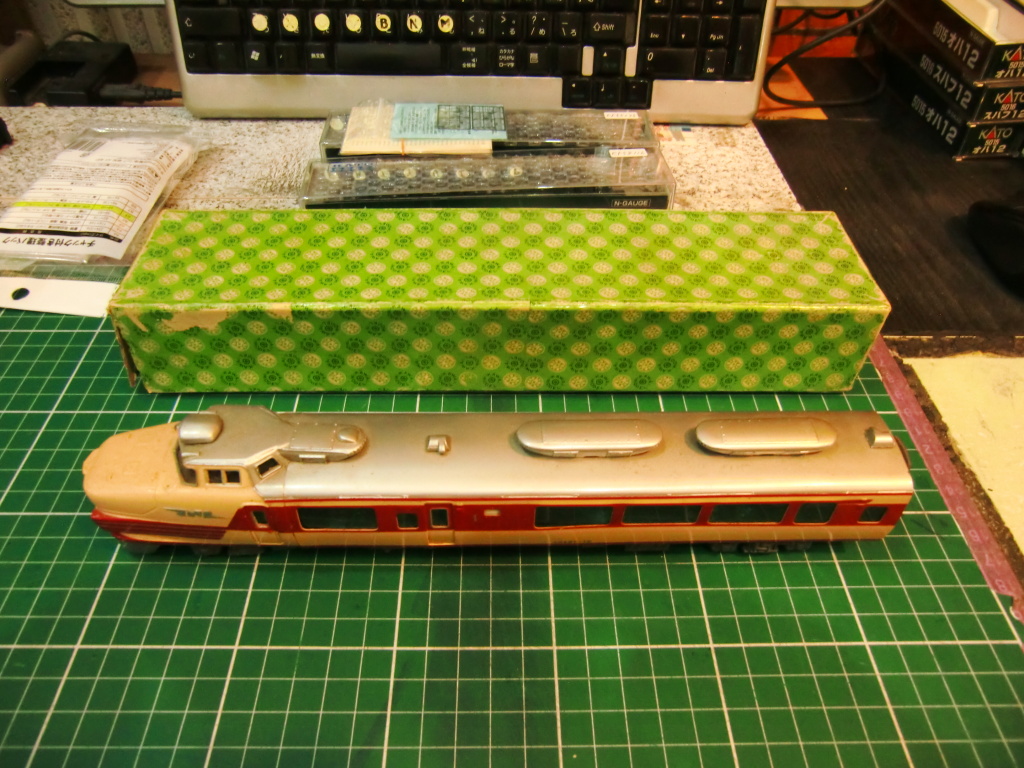



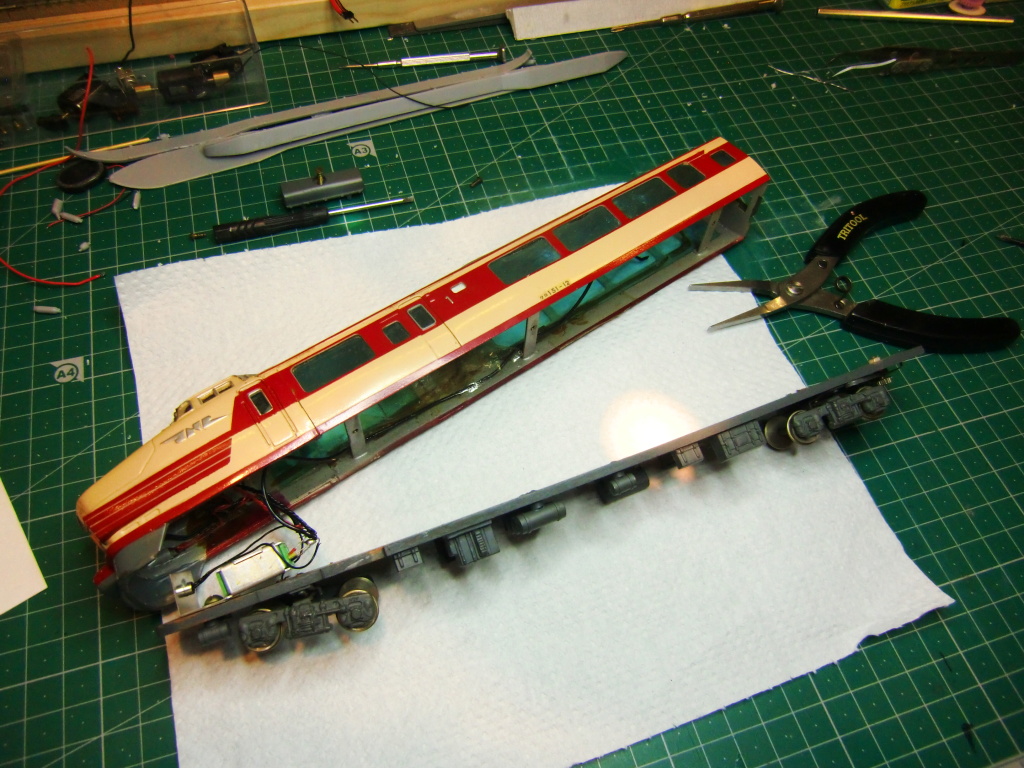

▼ボディー洗浄作業
ボディー表面の汚れなどをきれいに落としていきます。

このようにボディー表面はテカテカに戻りました。

茶っぽい感じだった屋根も本来の光沢が戻りました。
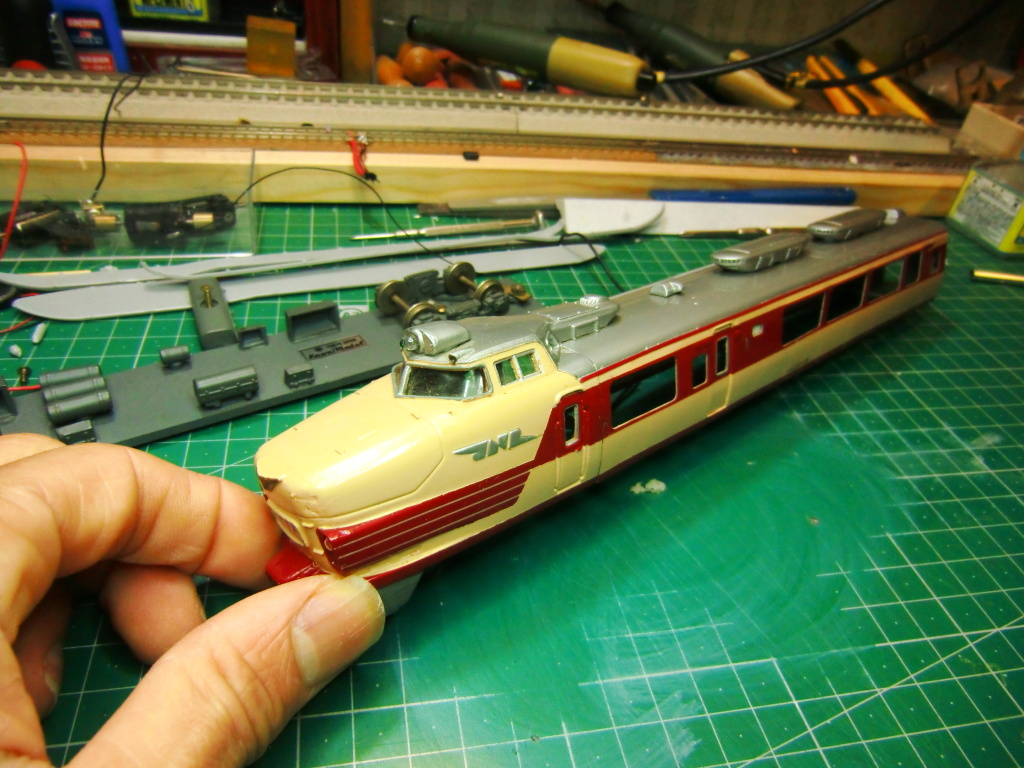
ボンネットもきれいになりました。
▼窓ガラス貼り換え
経年劣化により窓ガラスがぱりぱり状態でした。まずは、裏面に付着したゴム系ボンド跡をきれいに削っていきます。

厚0.2mmの透明プラバンを使います。




ガラスをすべて貼り終えました。


最後に車輪を磨きだして作業は完了いたしました。
停車状態でヘッドライトが点灯できるように、モーター始動電圧をシフトします。


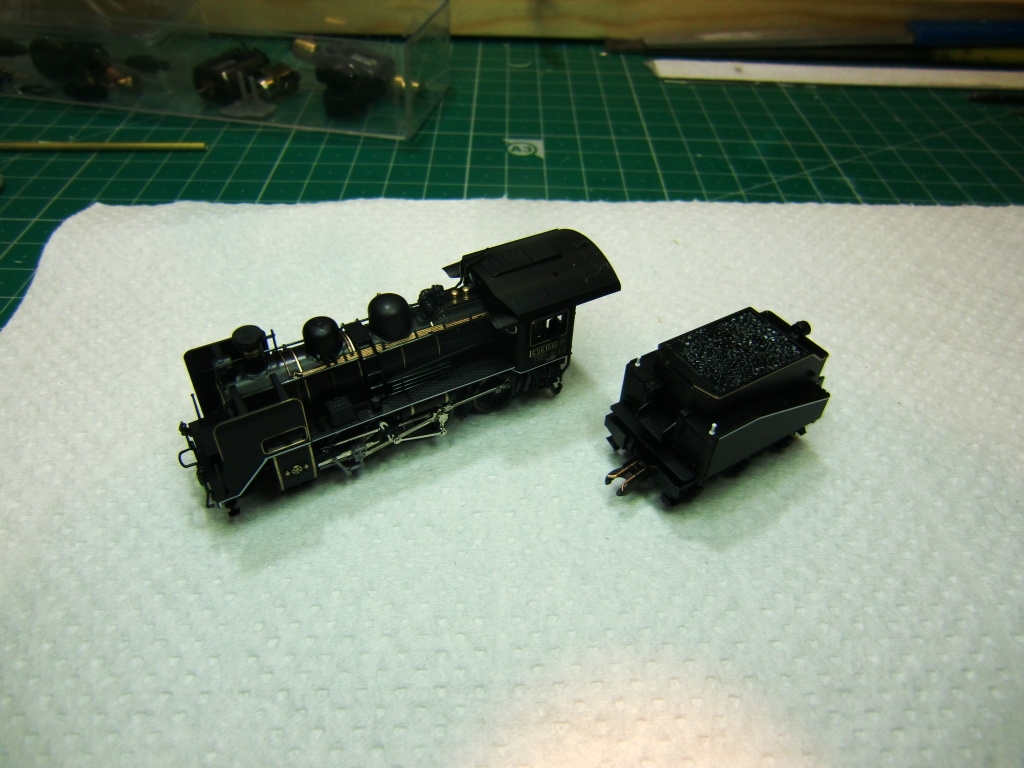

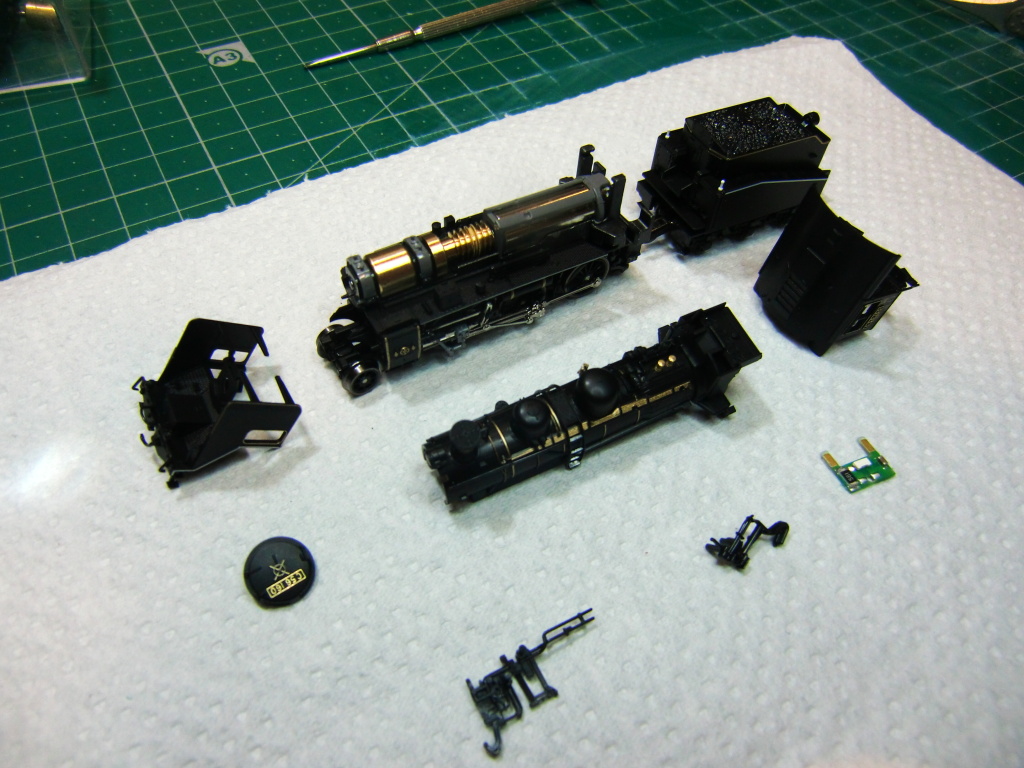


こちらの機関車に搭載されたモーターは非常に高性能で、わずかな電圧をかけただけで動き出してしまいます。LEDライト点灯開始電圧の半分程度でモーターが動き出してしまう感じです。

どうにか試行錯誤しながら、停車状態でギリギリライトが点灯。かなりシビアな調整が続きました。SLで難しいのは内部に回路を組み込むスペースがほとんどないことです。これが作業を一番難しくしている要因です。

作業完了でございます。
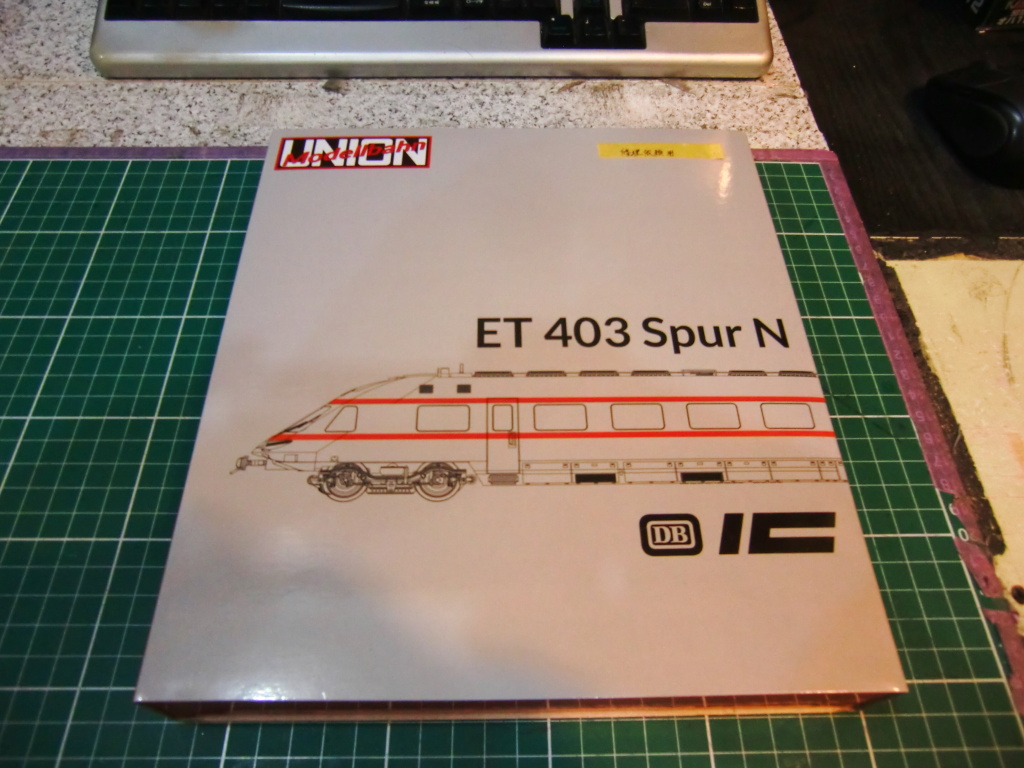



こちらは、先頭車に動力が入ったタイプです。このままでは作業しずらいので分解します。

ボディーの分解にはこちらのヘッドマーク回転用の工具を使います。
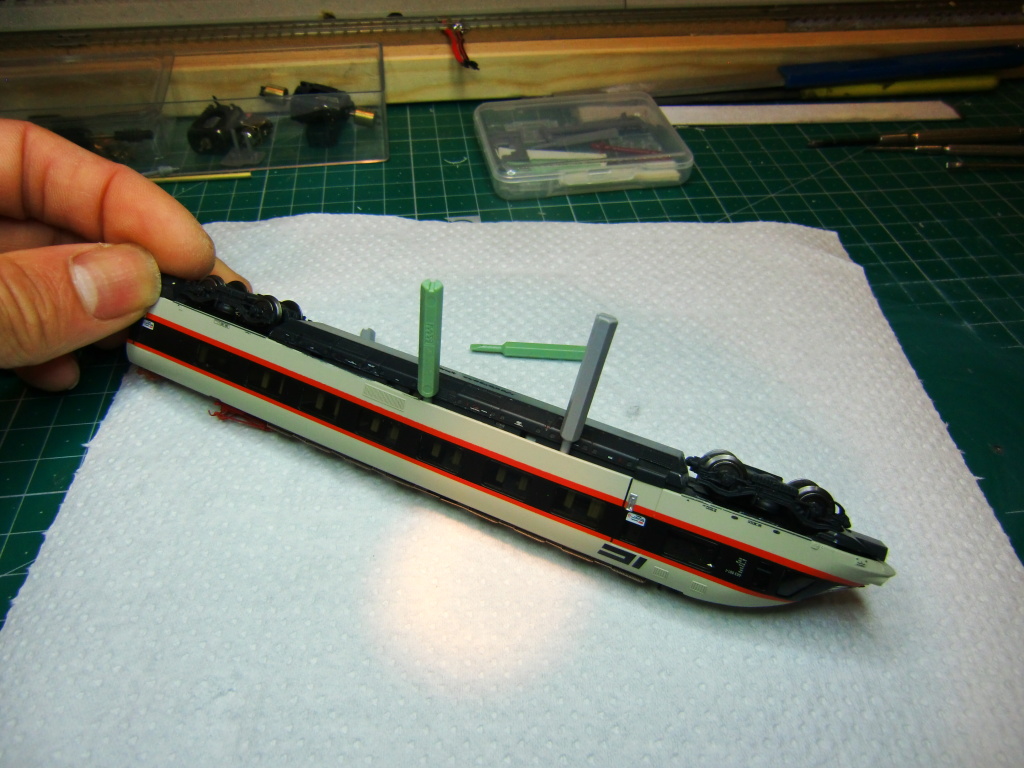
まずは、ボディー内のツメ位置を確認してから上記のように差し込みます。手前を外したら反対側も同様に差し込んで引っ張れば簡単にボディーの分解ができます。ボディー分解でやってはいけないことは、金属製のマイナスドライバーを使ってはいけません。塗装が傷になったりボディーの裾を変形させてしまうことがありますので、プラ製の工具を使います。

海外製の車両に搭載されて基盤は、国内の製品とは違いますね。
まずは、塗装前にボディーの洗浄を先に行います。次に修復に際して本体色を確認してから色を調合します。

本体色のクリーム色ですが、薄いグレーにわずかに茶色味を帯びています。かなり微妙な色合いです。まずは、近似色を用意して調合を繰り返して徐々に色を近づけていきます。この作業だけで数時間を要しました。

ようやく色の調合が終わったところで、塗装にはいります。


基本的にはまったく同じ色とはいきませんので、周辺にぼかし塗装を加えていきます。

次に反対側ですが、こちらの側は少し手間がかかりそうです。何かの溶剤によるものかわかりませんが、表面の色が溶けてやや下地が透けて見えます。また、周辺にわずかに黒く滲んだシミのようなものが見受けられます。


こちらの超精密研磨フィルムで表面を研磨します。

時間をかけて丁寧に研磨します。溶けた面が平らになり黒い滲みもだいたい取れました。この処理をしっかり行わないと、この後の上塗りでグレーに見えてしまいます。

マスキングしなおしてから、こちらも調合してたクリームを薄塗りで複数回に分けて吹き付けていきます。


こちらもぼかし塗装を加えて処理します。
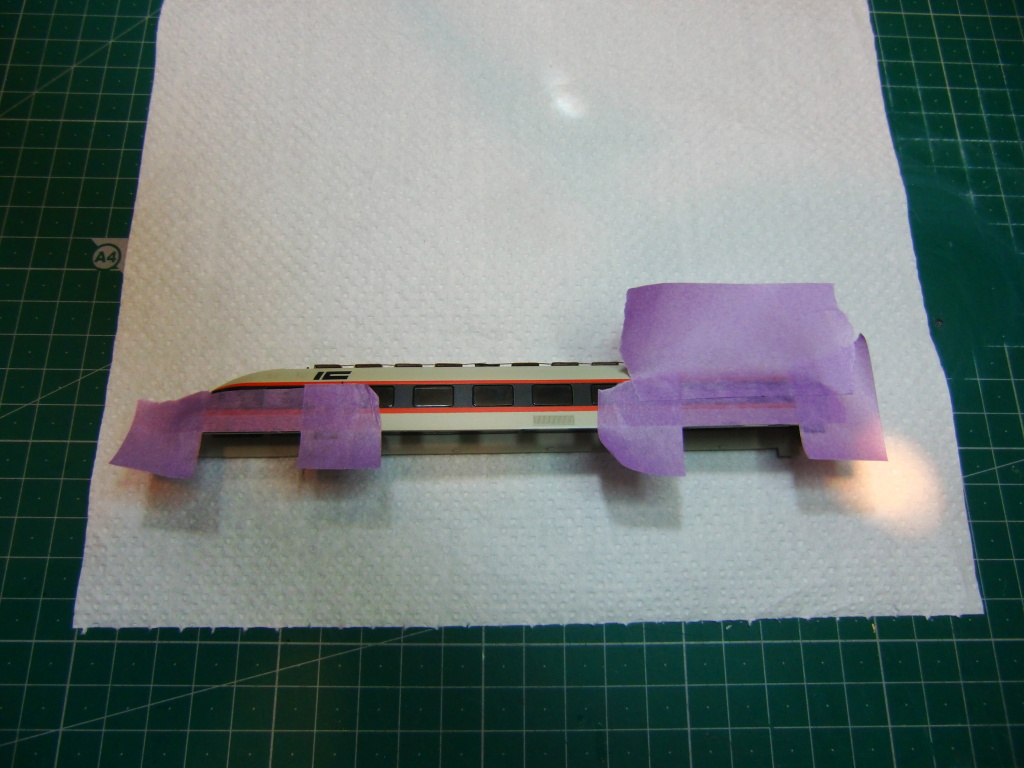
次に「ダークグレー or タイヤブラック」で裾部分を塗装します。


線が細いので拡大しながら作業します。



複数回に分けて色の定着具合を確認しながら作業します。


修復塗装が終わったところで、側面の▼マークの復元を行います。
車体をスキャンしてPCに取り込みます。さすがにここまで小さいと機械でマスクシートを作ることはできませんでした。そこでデカールに置き換えて制作することにします。細かな作業箇所が大変多く、1両修復するだけでもかなりの時間を要します。



作業完了でございます。

こちらの組立のご依頼でございます。
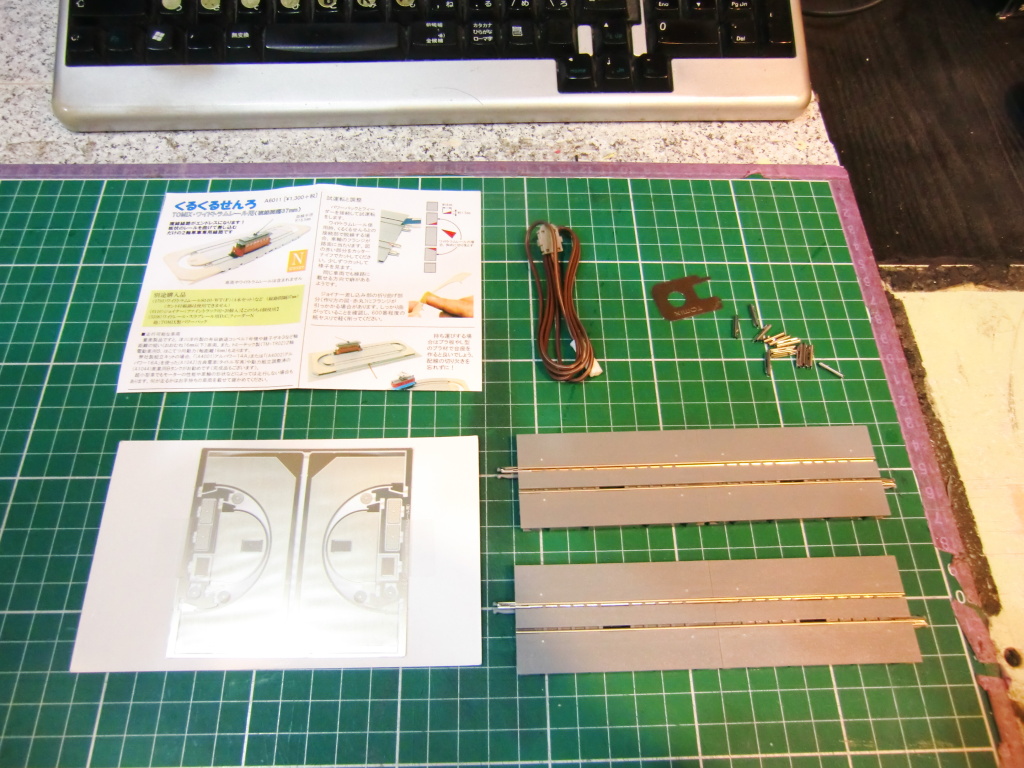

金属部品の切り出しにはタガネを使います。




プライヤーで折り曲げていきます。

まずは仮付けして状態を見ます。



段差となる部分を少し削って平らにします。
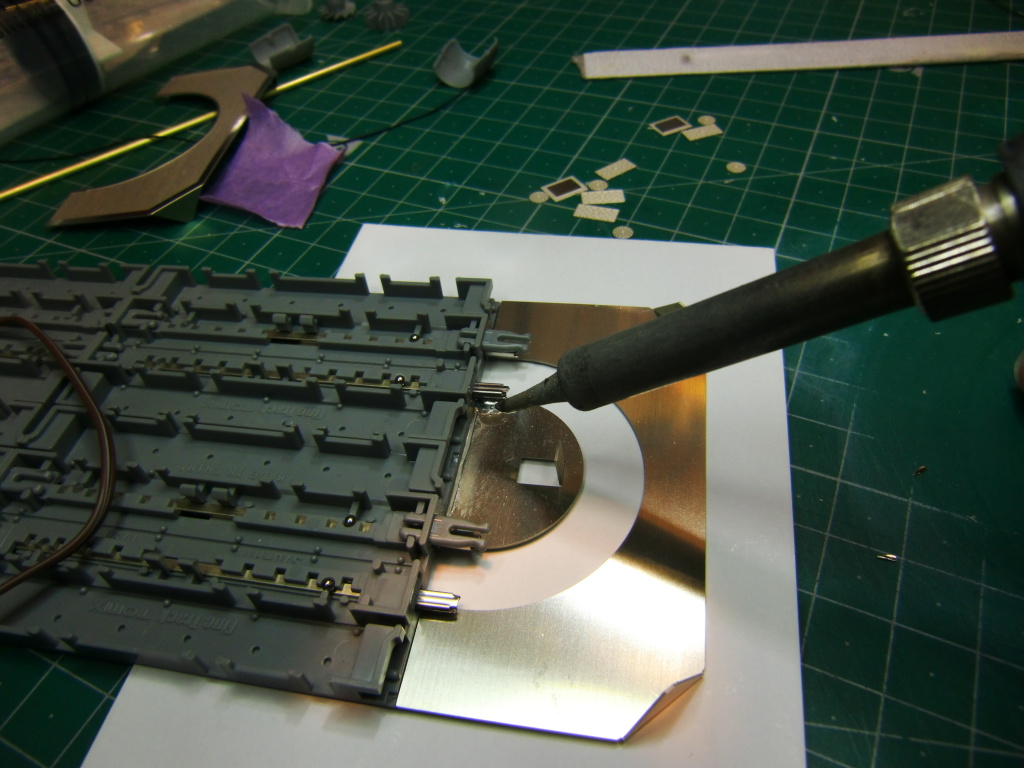
ジョイントとパーツをハンダ付します。

このようになります。

接続部の段差をルーターで削って平らにならしていきます。

マンホールなどの小物を固定していきます。



最後に各部の通電状態をテスターで見ていきます。
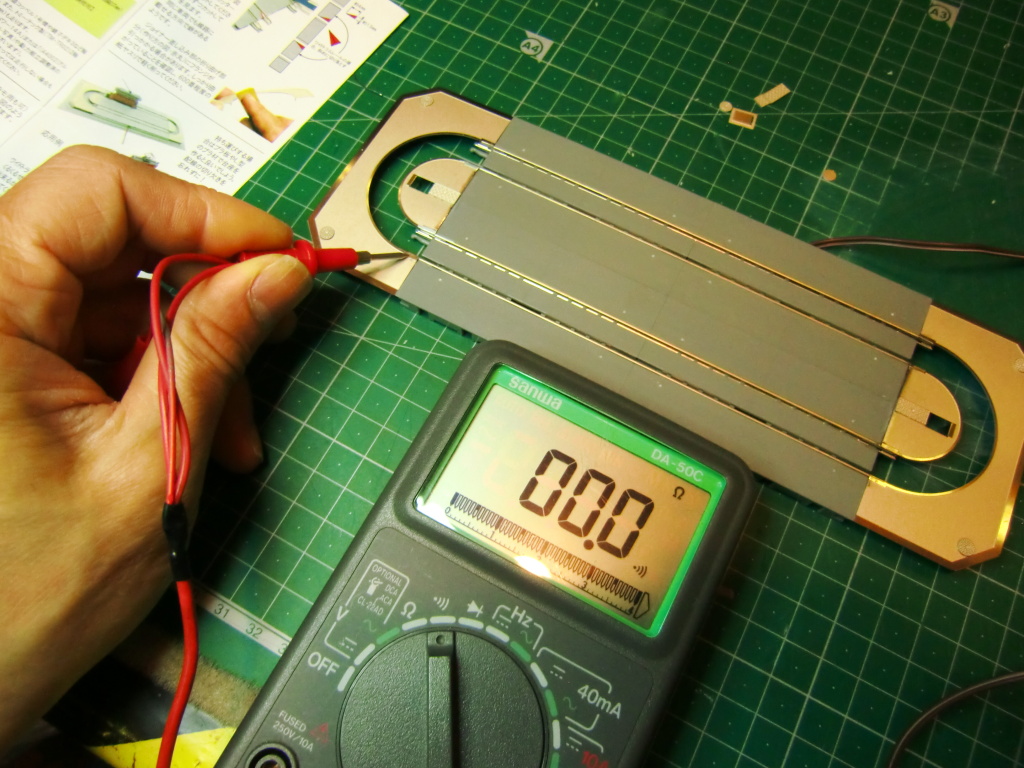
OKです。作業は完了いたしました。


まったく動かないようです。さっそく全分解していくことにします。
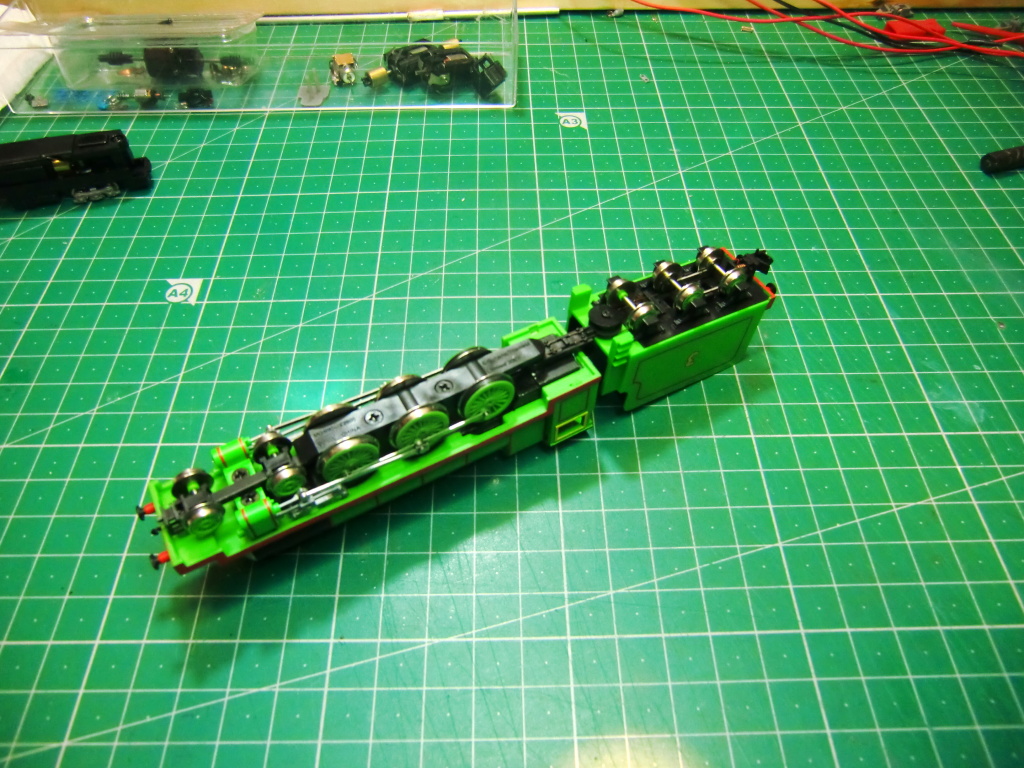
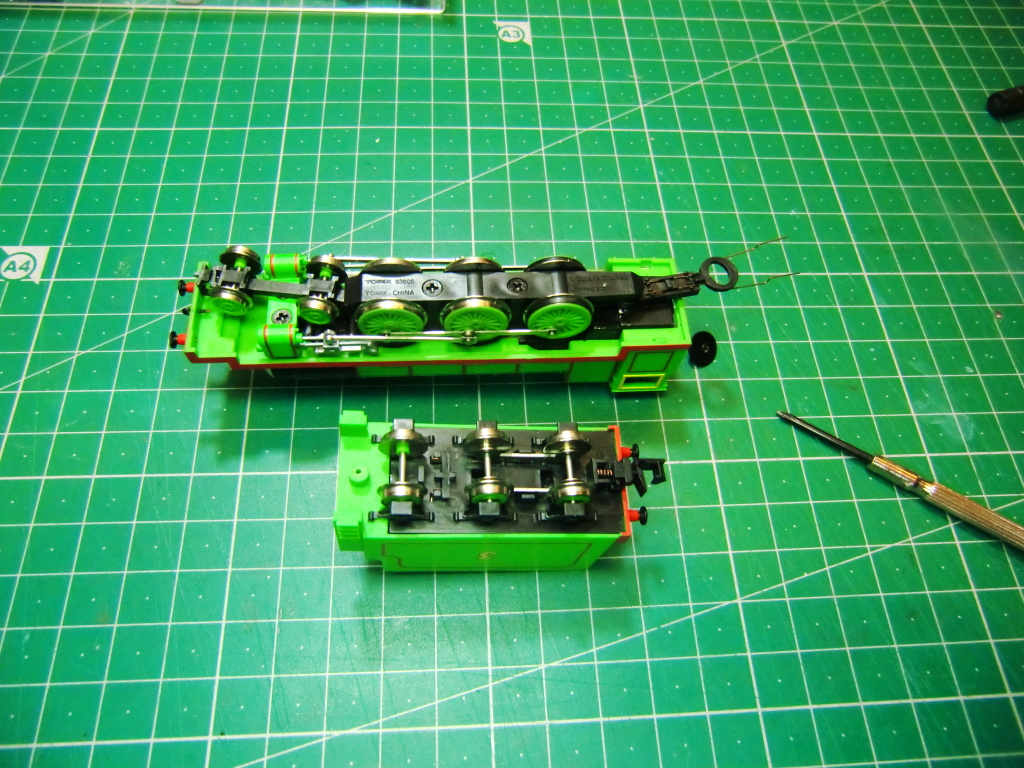
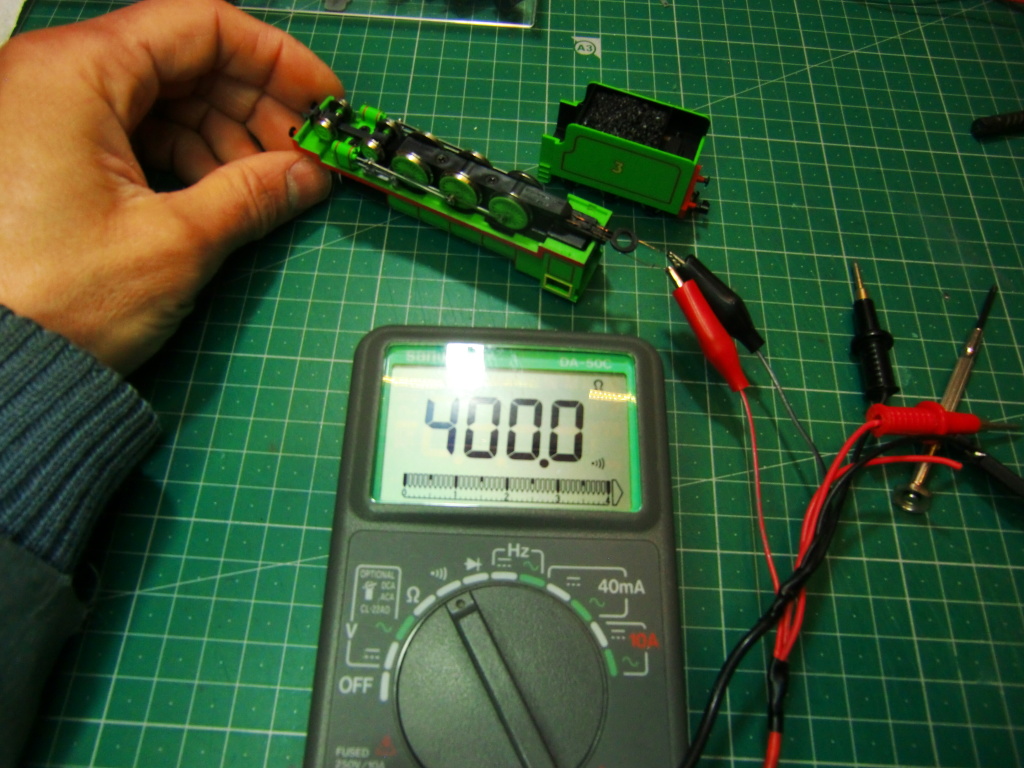

モーターを取り出します。
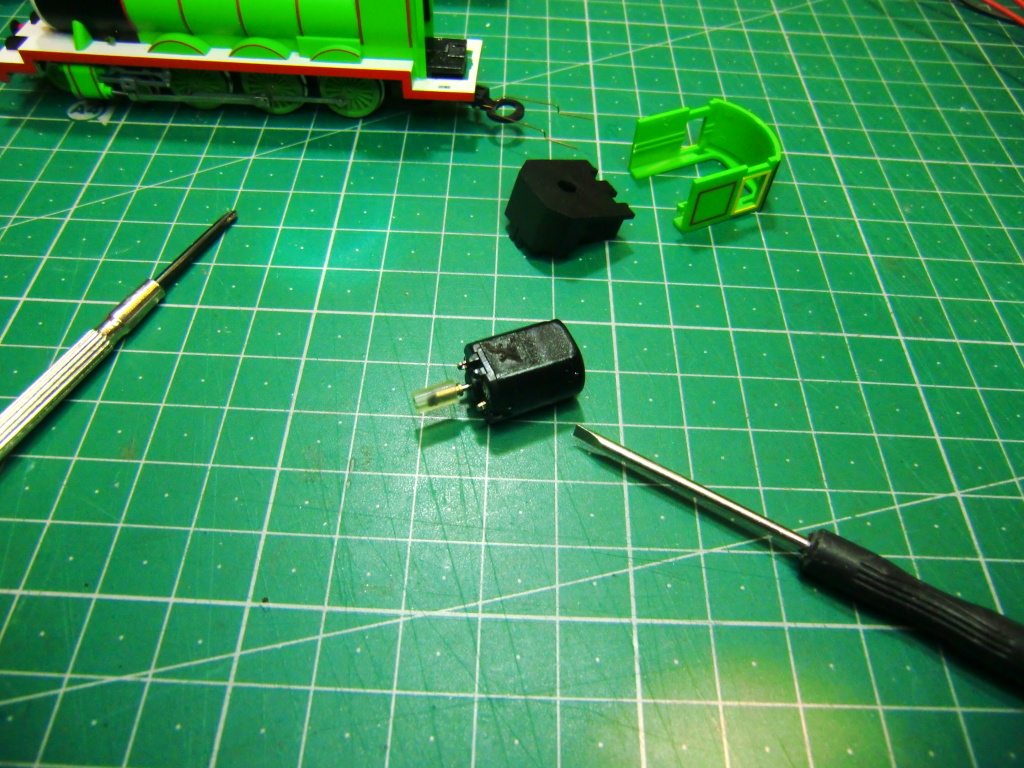

どうやら、モータ自体の故障のようですね。機関車の大きさの割にモーターは比較的小さい目です。

モーターを分解して直していきます。

内部の断線ポイントを見つけて接続しなおします。この作業はすごく難しいです。
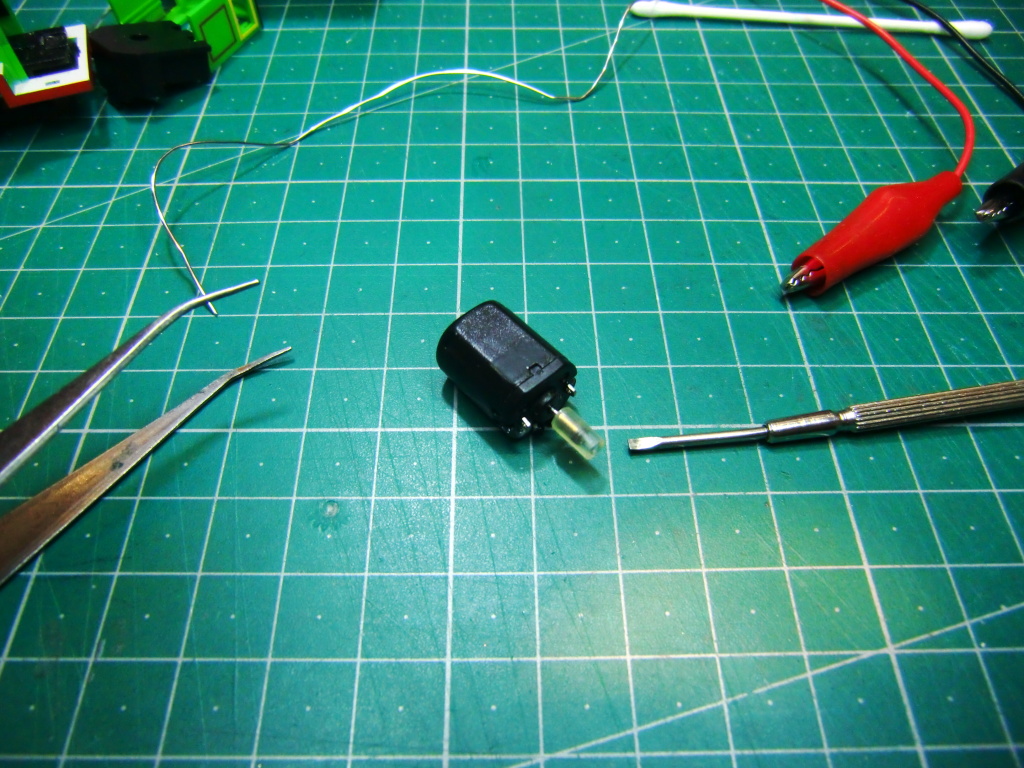
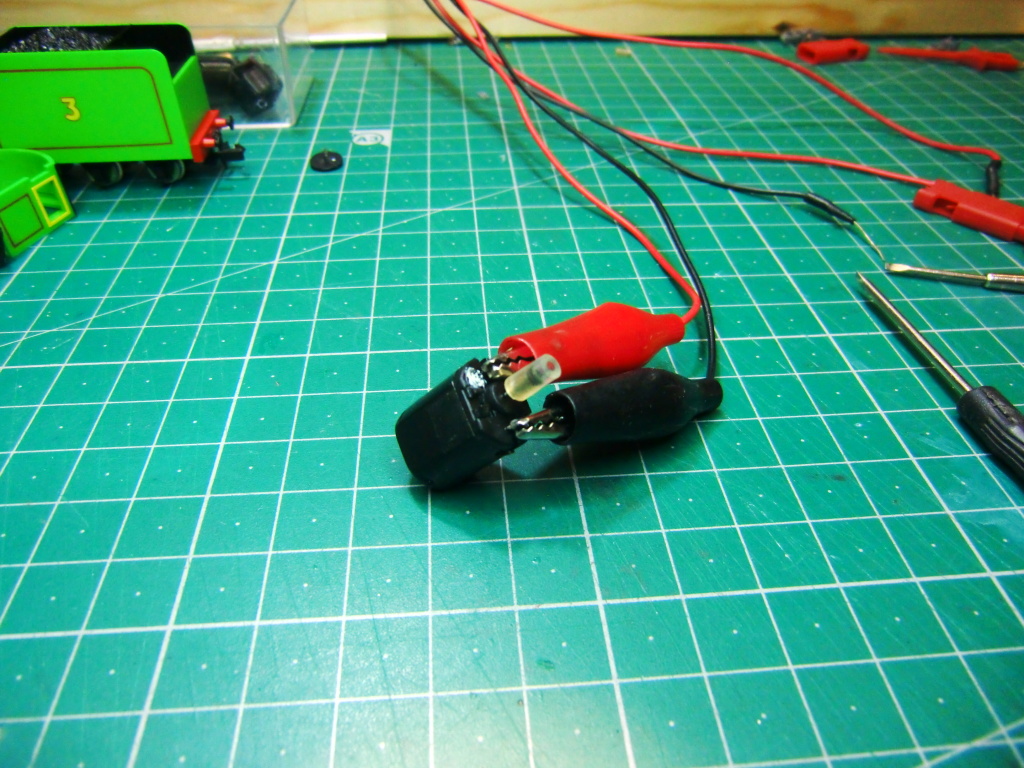
モーター内部の洗浄も念入りに行い、回転が安定するまで待ちます。

こちらにも少々問題があるようですので、見ていきます。



モーター端子に直接配線して本体に固定します。

回転テスト。


テンダー側の集電もいまいちですので、こちらも分解して対応していきます。


動くようになりました、ヘンリーくん復活です。
通常は、付属パーツのお取付に関する内容については、あまり掲載することはあまりありませんが今回は履歴としてアップしてみます。皆様のご参考になればと思います。なお、やり方は人それぞれですので、ご自身でやすい方法で作業を行ってください。


ぴょん鉄ではパーツの取り付けの準備として、まずはすべてのパーツを袋から出して並べます。そこから優先度をつけて重要なパーツから先に作業します。
まずはエンブレムですが、掴むところがなく先端が三角になっているので、そのままピンセットなどで持つと滑って紛失する可能性が非常に高いパーツです。またこのパーツは予備が無いので慎重に作業する必要があります。
まず、ニッパーでパーツを切り離しますが、ここでも注意が必要です。切り出した途端に「ピーン」と、どこかに飛んでいくことが良くあります。それを防ぐために、切り出す方向と反対に指を置いてパーツが飛ばないように抑えながらニッパーでカットします。
次にパーツを実際に車体にはめ込むわけですが、失敗する方の多くがピンセットを使っている場合です。先にも述べましたが、このパーツは持つところに困ります。そこで次の方法で行うとまず失敗しません。

正面が平らな物を使い、先に糊をわずかに付けます。糊は少しべた付く程度にとどめておきます。たくさん付けると車体についてしまい取り除くのにまた手間がかかります。スティックのりが良いでしょう。そこにエンブレムをくっつけて写真のように押し込みます。

その他のパーツも一通り付けました。取り付けるパーツによって工具を変えながら取り付けていきます。失敗するリスクの高いケースは差し込みが固いケースです。無理に差し込もうとすると、パーツが飛んでいきます。ここではジャンパー線の差し込みはちょっときつかったですね。あまり固い場合は、無理に差し込まず先端を尖らすなどパーツを加工して取り付けます。逆に、パーツがグラグラになる場合もあります。こちらの車両でも実際に、ホイッスルはグラグラでした。このようない場合は、少量の接着剤を使用する訳ですが、使い方を誤ると周辺にはみ出してしまうなど汚くなってしまいます。
接着に失敗した経験のある方の多くは、一般的なプラモ用(タミヤの流し込みタイプ/Mr.CEMENT SP/etc)の接着剤を使ってパーツ周辺に想定以上の接着剤がはみ出してしまい、下地の塗装を溶かしてしまったり、テカってしまったとそのような経験をされた方は少なくないと思います。私も過去ありました。また、瞬間接着剤を使ってパーツ周辺が曇ってしまった失敗などもよく見受けられます。基本的に瞬間接着剤の使用はあまりお勧めしませんが、「どうしても瞬着を使いたいんだ~」という方は、ゼリー状の低白化タイプの物をお使いください。
そこで、失敗しないためにも安全な接着剤と使い方をご紹介します。今回の作業の接着にも使用しました。

こちらです。ほど良い粘度で使いやすく乾くまでの時間が確保されます。その間に、はみ出したてしまった場合にも容易にふき取りも可能で下地も溶かしません。安心・安全の接着剤と言えます。この接着剤は小パーツの取り付けに適します。ただしデメリットもあります。それは接着まで時間がかかるのと強度があまりないことです。例えば、この接着剤を使って折れた部品を接着したり、ボディーキットの組立とかには向きません。
良く知られた「Gクリアー」よりも使いやすく、糸引きもないので大変使いやすく大変便利です。
さて、お次は多くの方が苦手意識を感じる上級者パーツの取り付けです。

はい、これですね。付属の治具を当てて、ピンバイスで穴あけを行ってパーツを取付ける作業ですね。
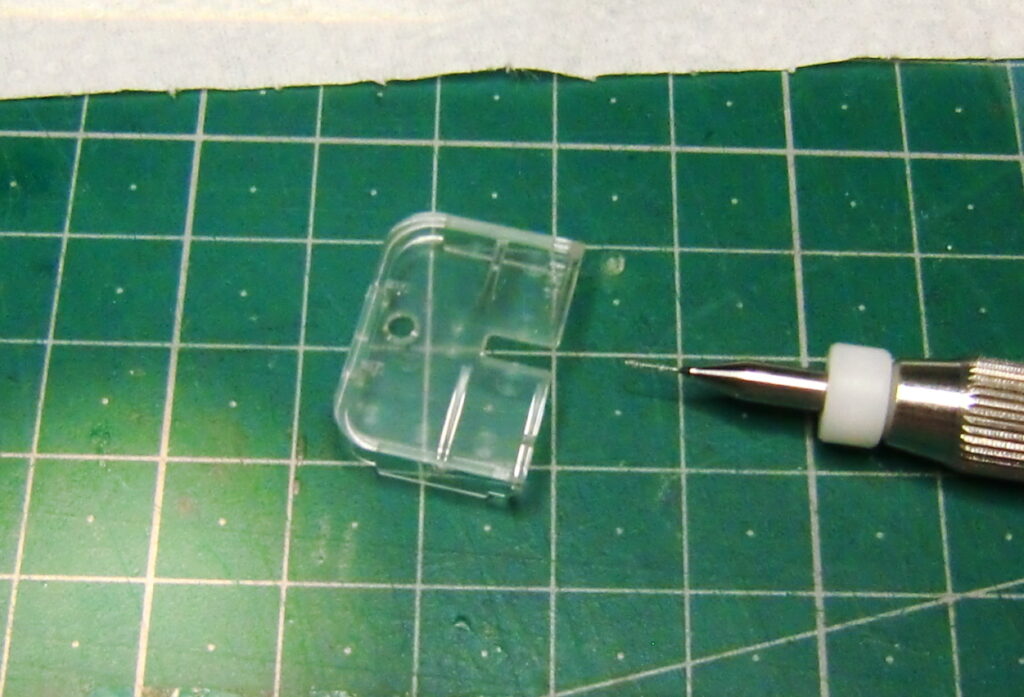
ん?付属の治具ですが、穴が塞がって貫通していないようですね。確かTOMIX付属の治具は貫通していたような気がしたのですが・・・。※写真参照
先に治具の穴あけからです。0.5mmのピンバイスで貫通させます。
ぴょん鉄では次の方法で作業しております。まず、治具を当てて0.4mmのピンバイスで軽くあたりをつけます。

次に治具を外して、0.5mmの手持ちドリルで窪みに合わせてクルクル回転させて貫通させます。
治具から1度に貫通させて良いのですが、以前に穴位置がずれたことがありましたので、穴位置の確認の意味でもこのような方法をとるようになりました。

はい、このように適正な位置への穴あけができました。


はまり具合を確認して、固定します。若干緩めですので、上記で使用した接着剤を少し穴に流しておき、そのあとパーツをはめ込みます。
はい、ここまでが上級者パーツのお取り付けです。一度慣れてしまうとなんてことはありませんので、一度もやったことがない方は挑戦してみてください。穴あけで最も難しいのは、力の入れ方です。刃の太さが0.5mmしかありませんので、穴あけの途中で刃を傾けると簡単に折れます。折れるだけなら良いのですが、折れた刃が車体に刺さった状態となり、これを抜くのが非常に大変です。必ず垂直にして穴あけを行うようにすることで失敗のリスクを減らせることができます。また、刃が長すぎるものは避けてください。刃が長すぎると、さらに折れやすくなります。
ここでまた1つおすすめアイテムをご紹介します。
▼ライト付き スタンドルーペ スタンド

特に細かい作業にはあると大変便利です。ぴょん鉄でも使ってます。軽量コンパクト、移動も楽々でライト付き。
お次は、インレタ貼りの工程に移ります。

さて、インレタの貼り付けですが、実際のところ苦手に感じている方も多いと思います。それもそのはず、インレタ貼りは難しいです。私もあまり得意とは言えません。一概にインレタと言っても転写する場所によっても難易度が大きく異なります。比較的広い面積への転写(側面など)への貼り付けは容易ですが、正面や妻面または狭い窪みに転写する場合は、非常に難しくなります。また、いくらこすってもまったくインレタが食いつかないことも良くあります。ようやく転写できても曲がっていたりするとかっこ悪いですからね。まっすぐ適正な位置に貼るのが難しいのです。
インレタはメーカーによってそれぞれ癖があります。それらを理解したうえで、それにあった貼り方とコツをつかむ必要があります。
同一メーカーであっても保管方法、ロットや時期によっても異なります。
インレタ貼りのご依頼はよくありますが、最も緊張するのがこのインレタ貼りだったりします。つかないのは本当につきません。何度か失敗するうちにストックを使い切ってしまうこともたまにあります。こうした場合はデカールに置き換えることも時々あります。
今回の作業では、トミックス付属のインレタとなりますが、糊の強さは比較的弱めの部類に入ります。そのため、シートを切り分けせずに直接転写ができます。
▼最後にシールの貼り付け
シール貼りの難しさは、貼ることより切り出しです。対象がすごく小さいので切りすぎたり、余白が大きく残ってしまい、「シール貼ってますよ~」みたいになってしまいます。これを防ぐには刃先を常に最善の状態を保つのとと、一度で切らずに1回目は軽く筋を入れてから2回目で切り出す形にします。ここでのポイントは下紙を完全に切らないことです。上のシールのみを切り出すのがポイントです。力の加減がちょっと難しいですが、手先の感覚で慣れるしかありません。完全に切り出してしまうとバラバラになったり、切り出し中に対象が動いてしい、うまく切れなくなってしまいます。

さて、一通りご依頼の作業も終わりました。

作業完了でございます。

今回の作業は、上記車両にTNカプラーを取り付けのご依頼ででございます。そのままでお取り付けできませんので、各種車両への加工を施していきます。
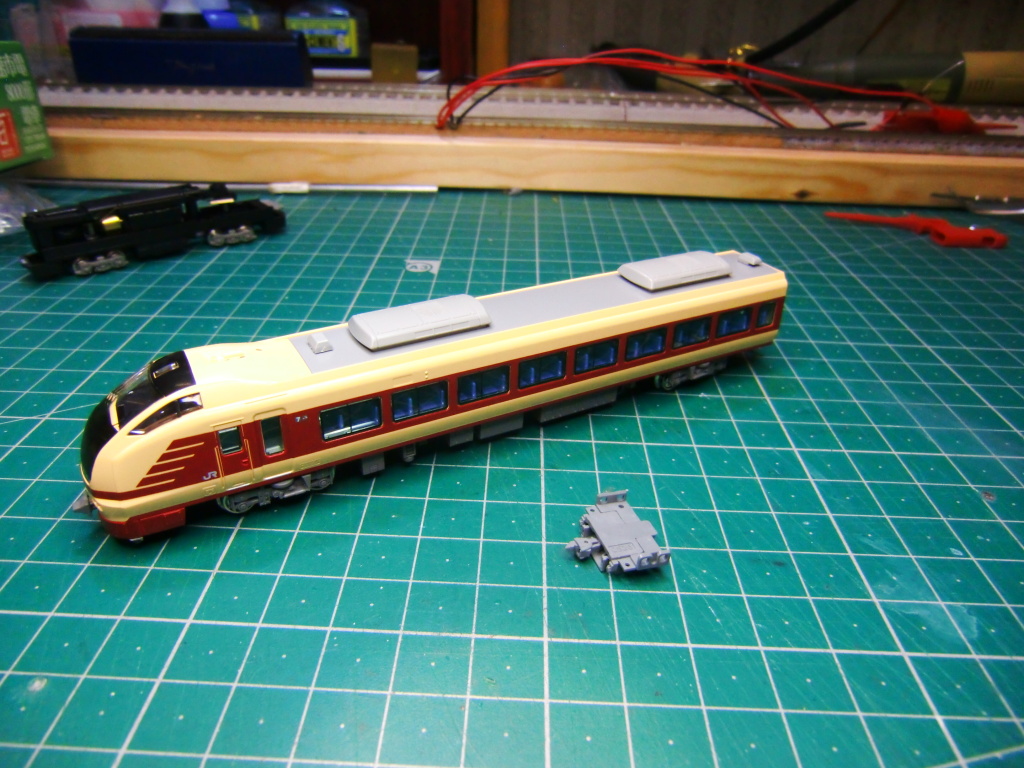

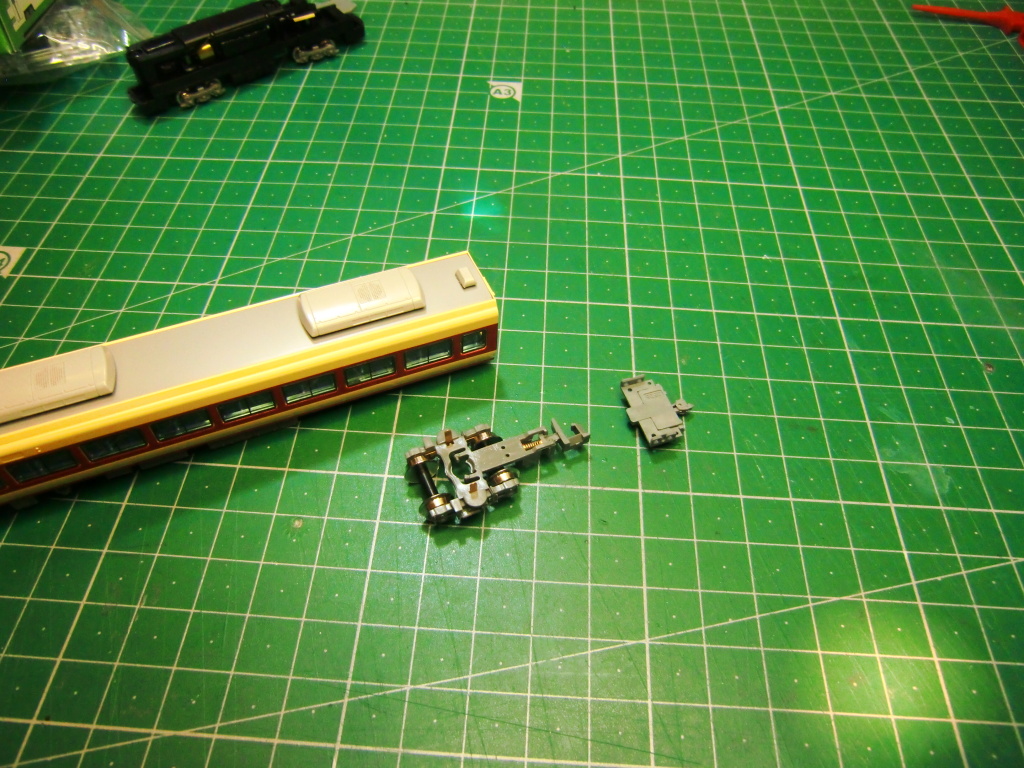


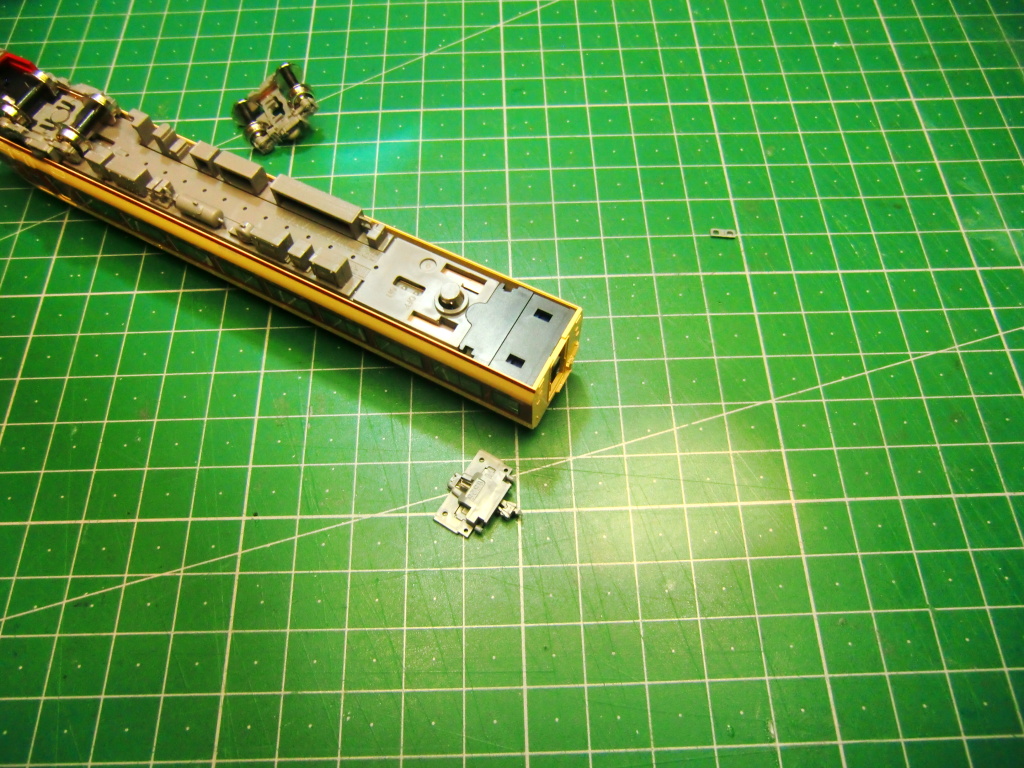

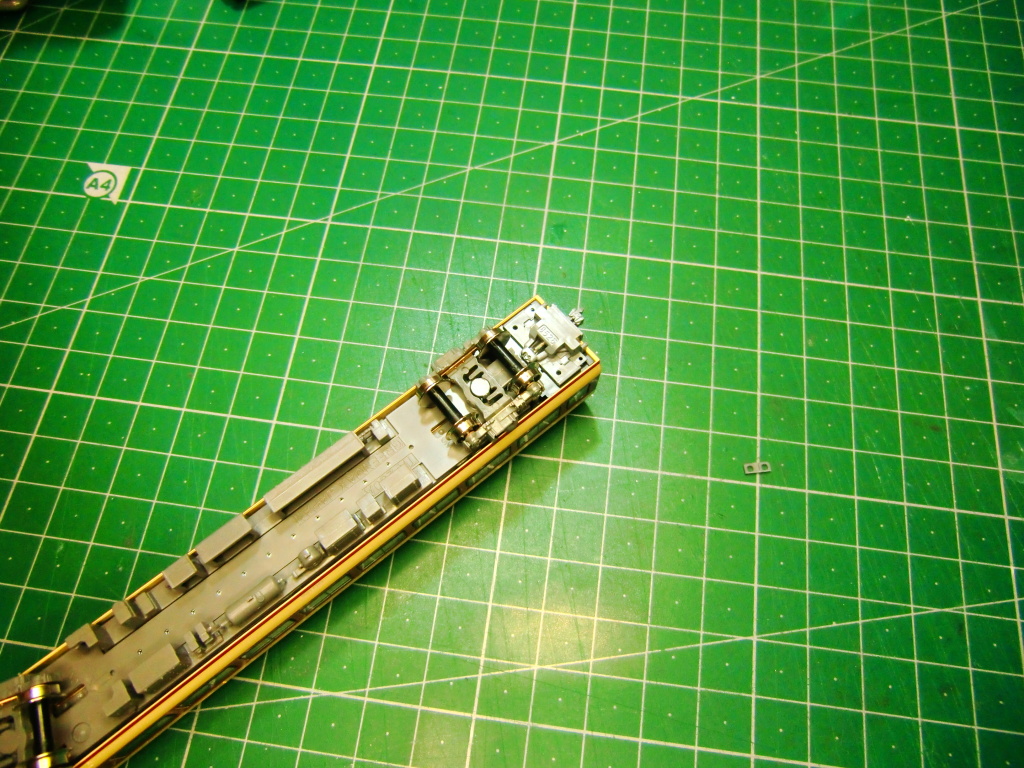

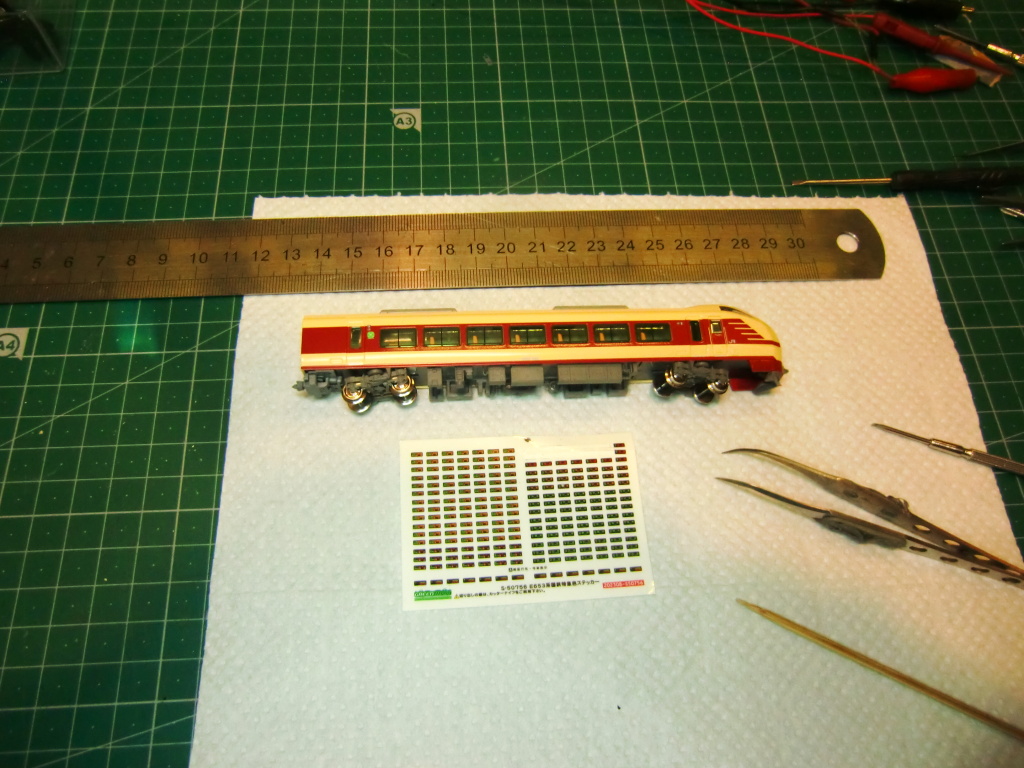
側面行先シール貼り:特急(号車)※全7両

▼幌の制作と取付
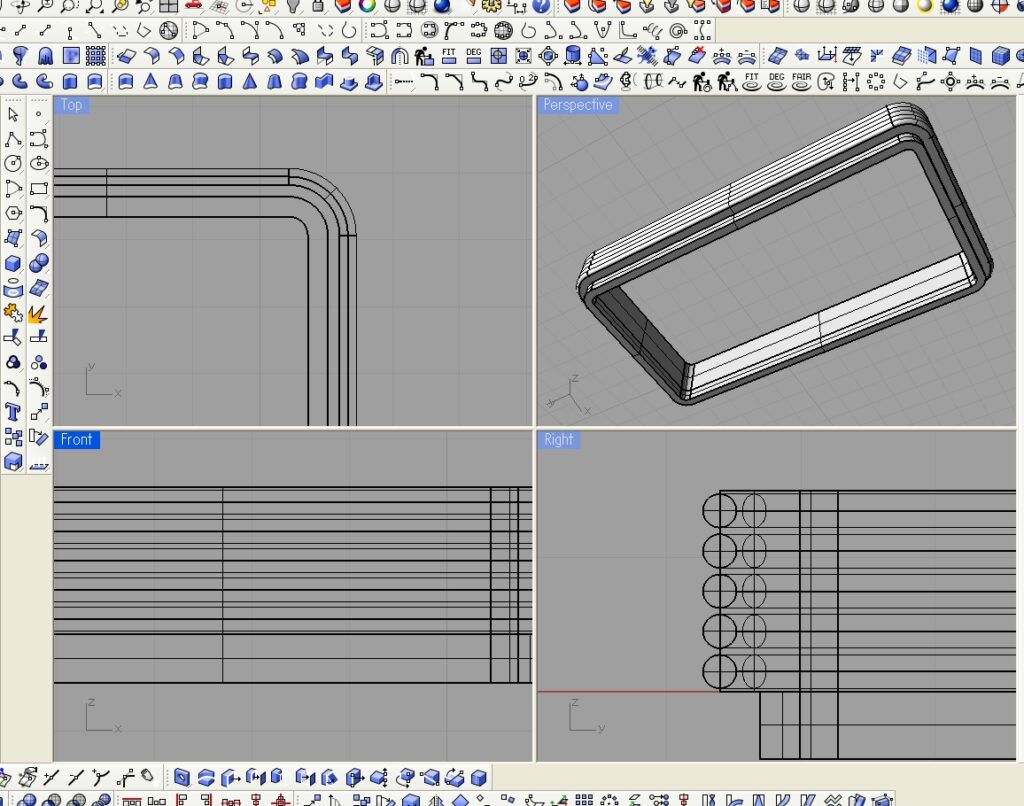
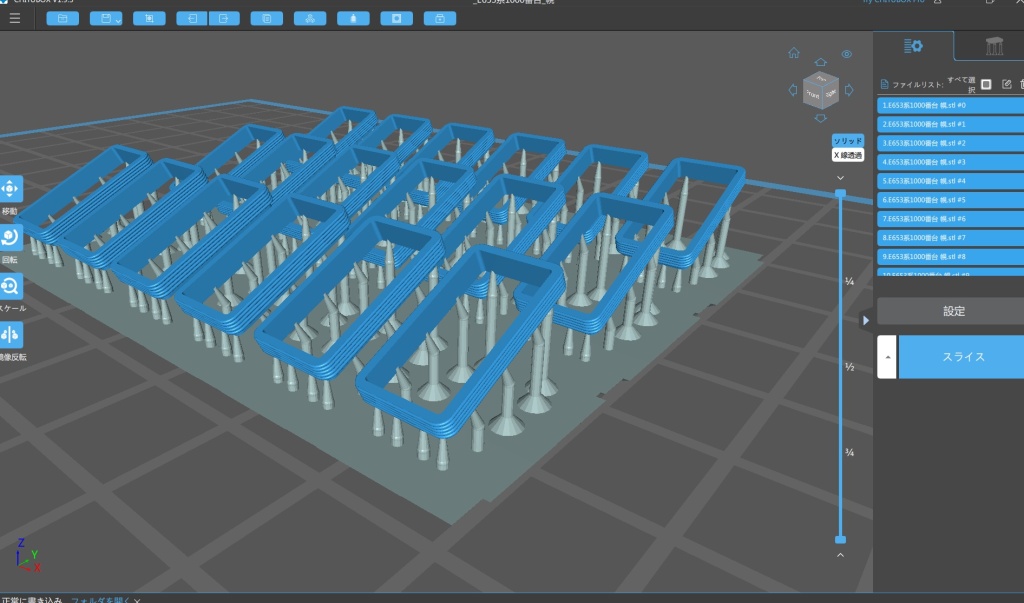







幌パーツが付いたことで、そのままではケースに車両が入りません。幌がぶつかる個所のウレタンをすべてカットして収まるように加工します。

車両がすべて収まりました。作業完了でございます。
EF62のホイッスルの修理から始めます。

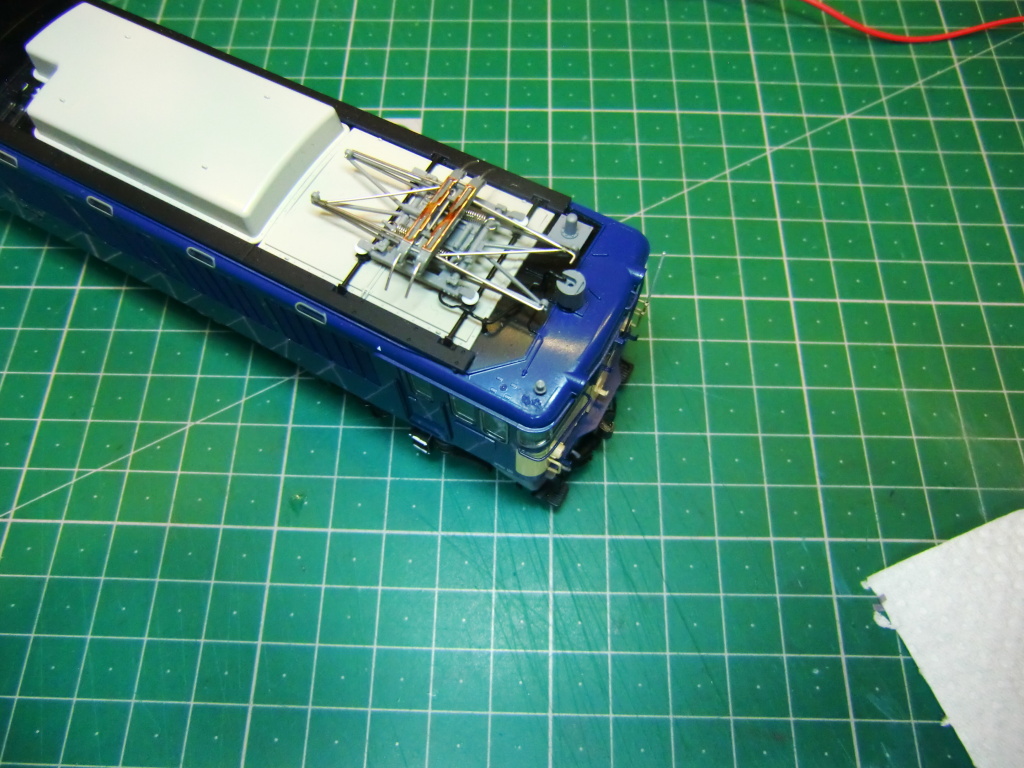
現状このような具合です。
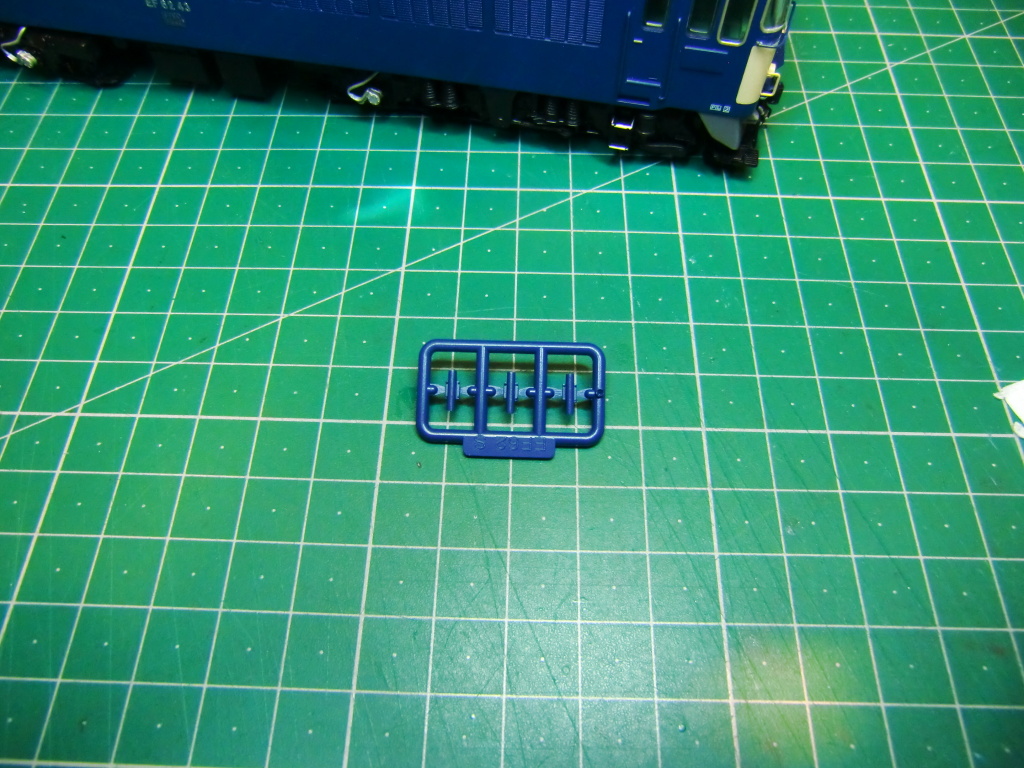
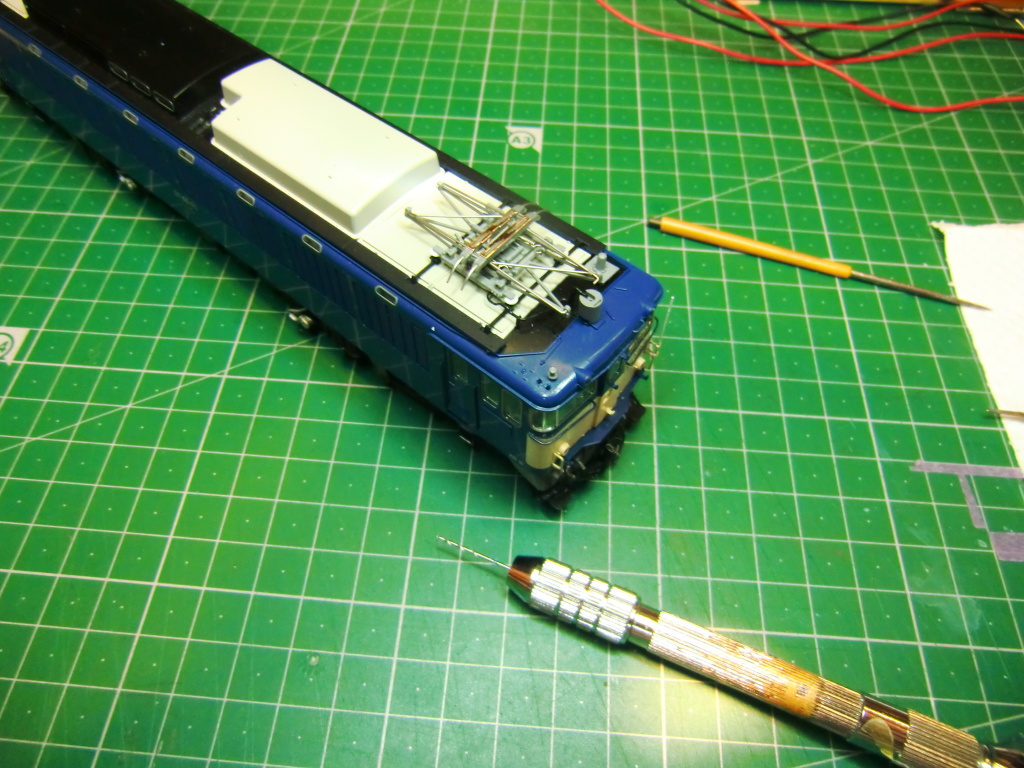
表面を慣らしてから適正な位置に穴あけを行います。
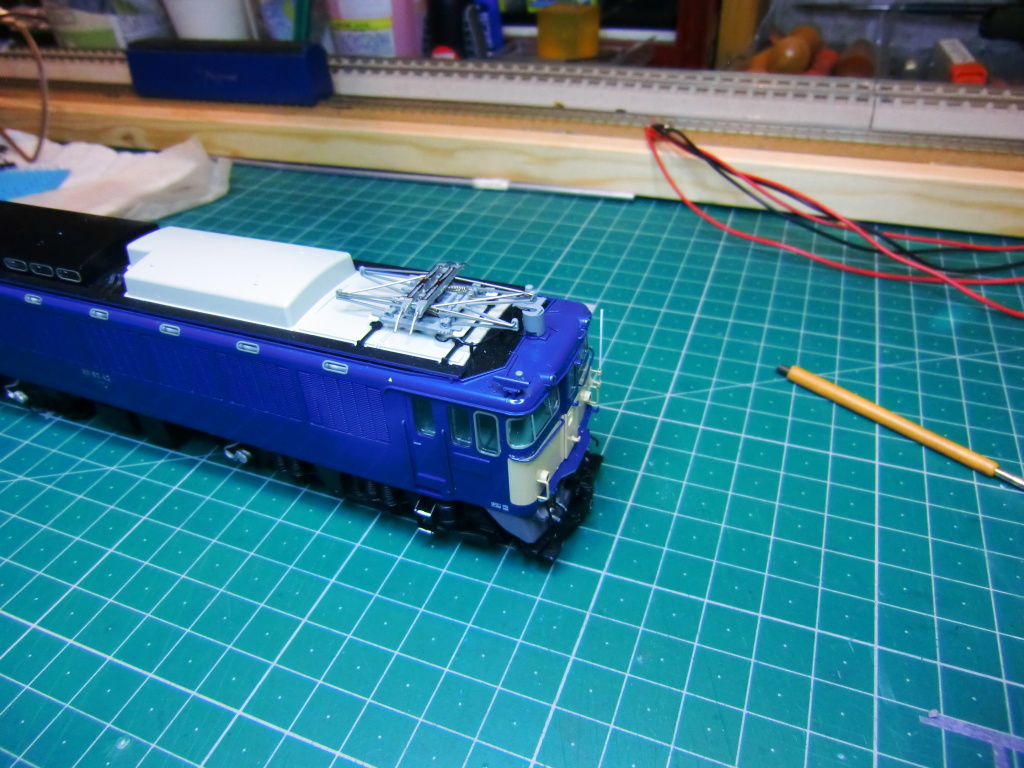
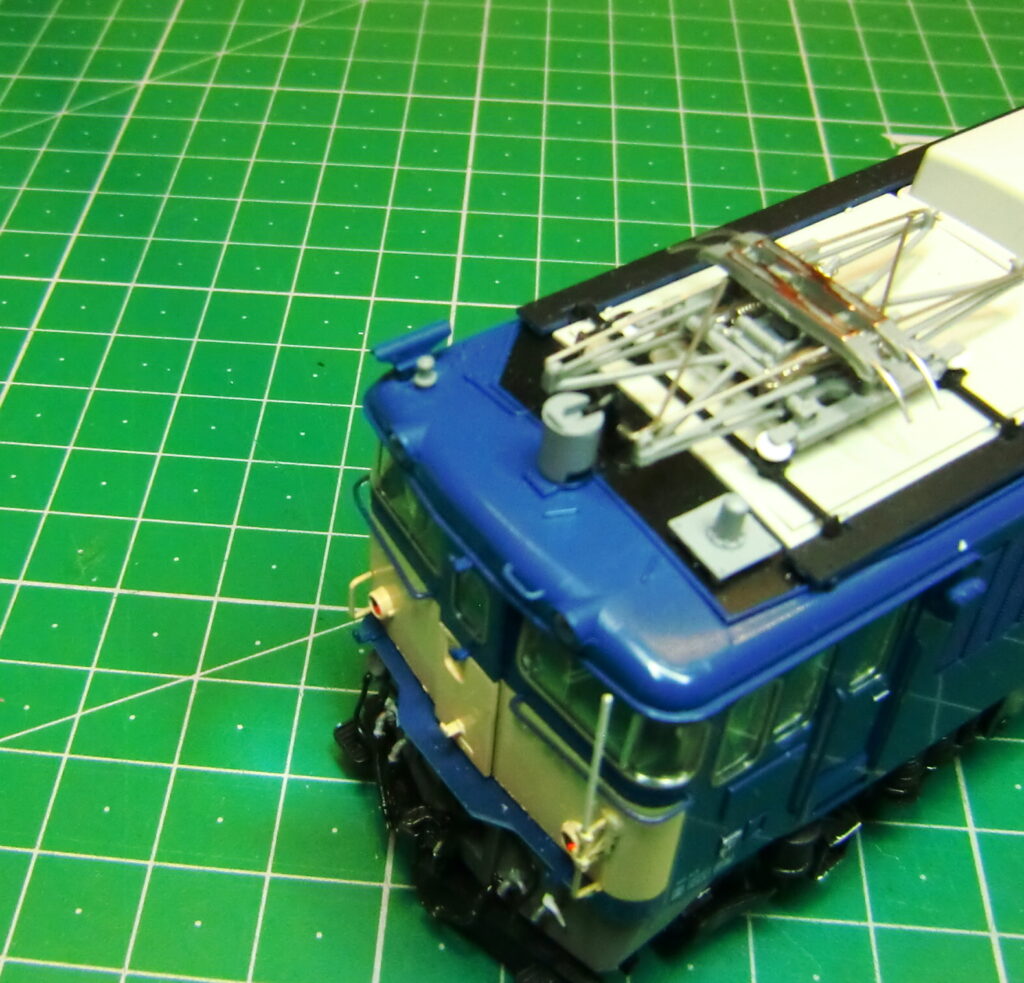
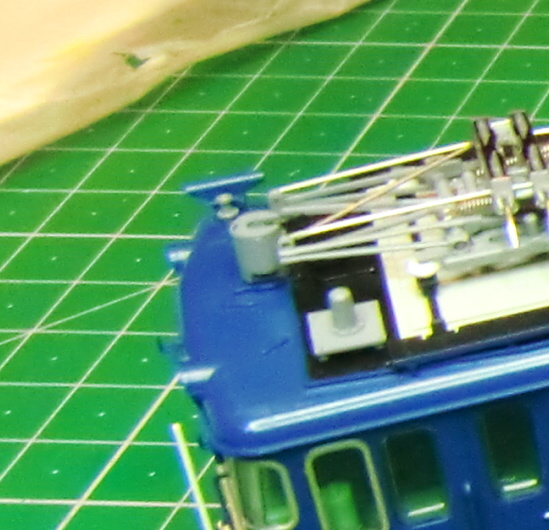
まずは、ホイッスルの修理は完了です。
お次はCアンテナの修理です。


このように修復いたしました。


パーツ洗浄をしっかりおこなってから、下塗り(ガイアマルチプラーマー)を塗ってから白を塗装します。


▼EH500 ボディ損傷による復元作業
お次の作業では、なかなか時間はかかりそうです。

ボディが溶剤のようなもので溶けて変形している感じです。現物をよく見ると修復はかなり大変そうです。
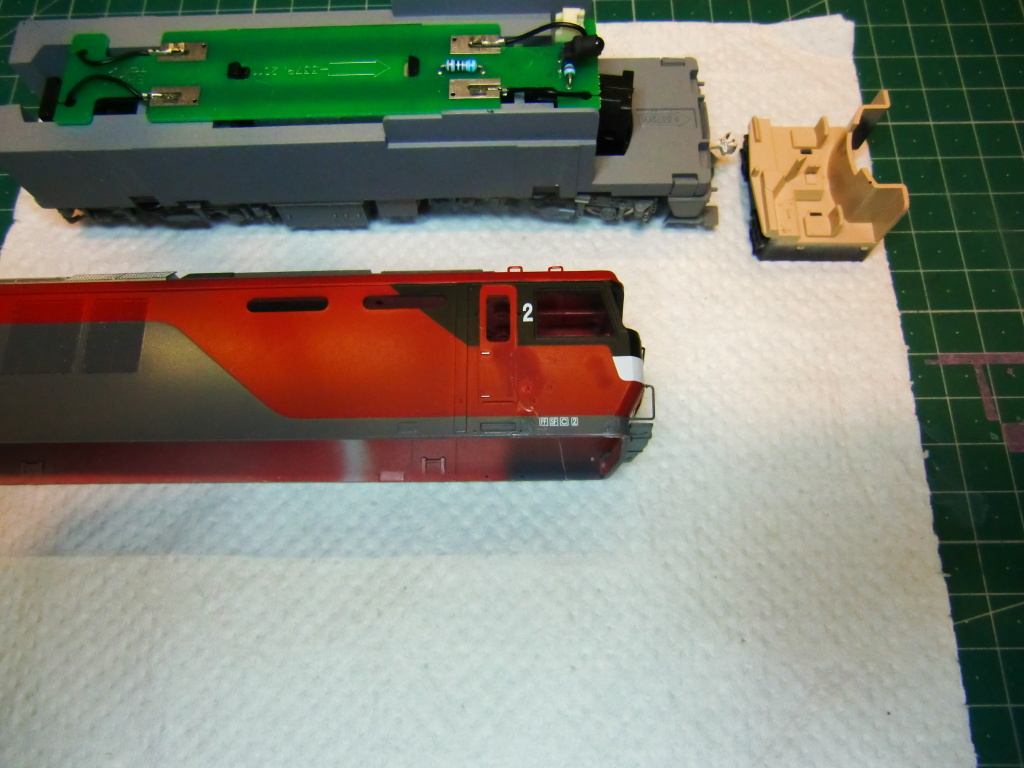
まずは、埋めてからペーパーヤスリ(#1000)を使い、他まで削ってしまわないように慎重に研ぎ出しを行い、ある程度平らになった段階で表面の仕上げ処理を行います。
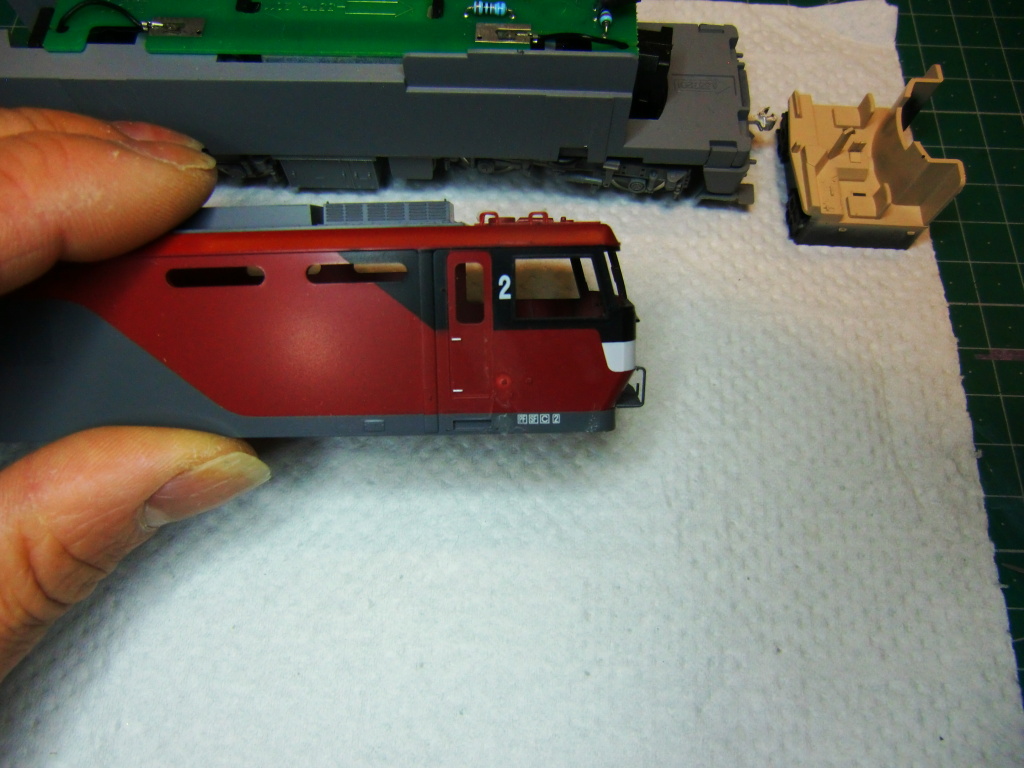
精密ヤスリ(#4000)に切り替えて、またひたすら研ぎ出しです。
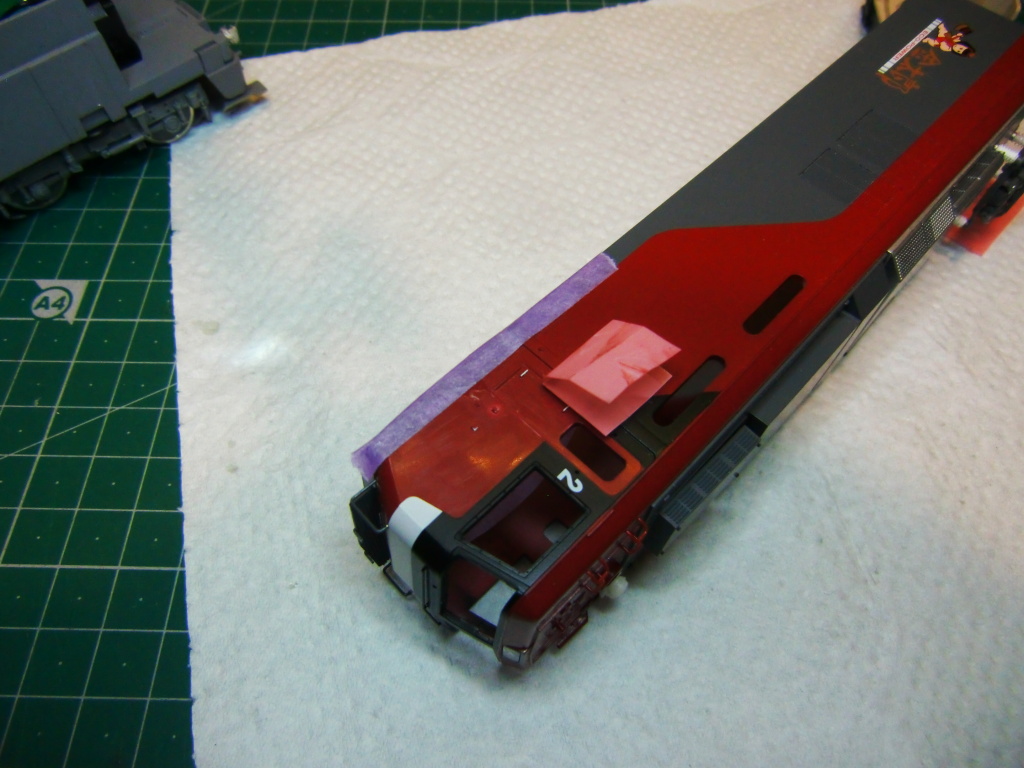
さらに時間をしっかりかけて作業を進めます。ドアなどの凹みは特に慎重作業します。

ようやく塗装工程へと移ることができます。
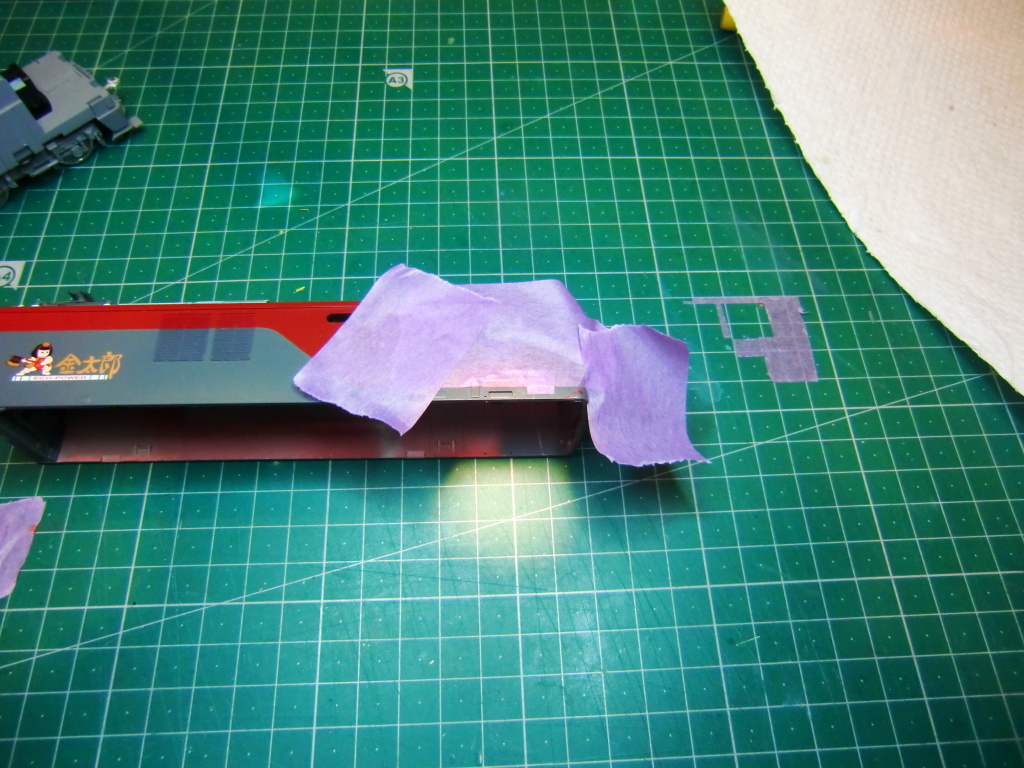
まずはグレー部分です。マスキングシートを一定区間貼り、部分塗装していきます。


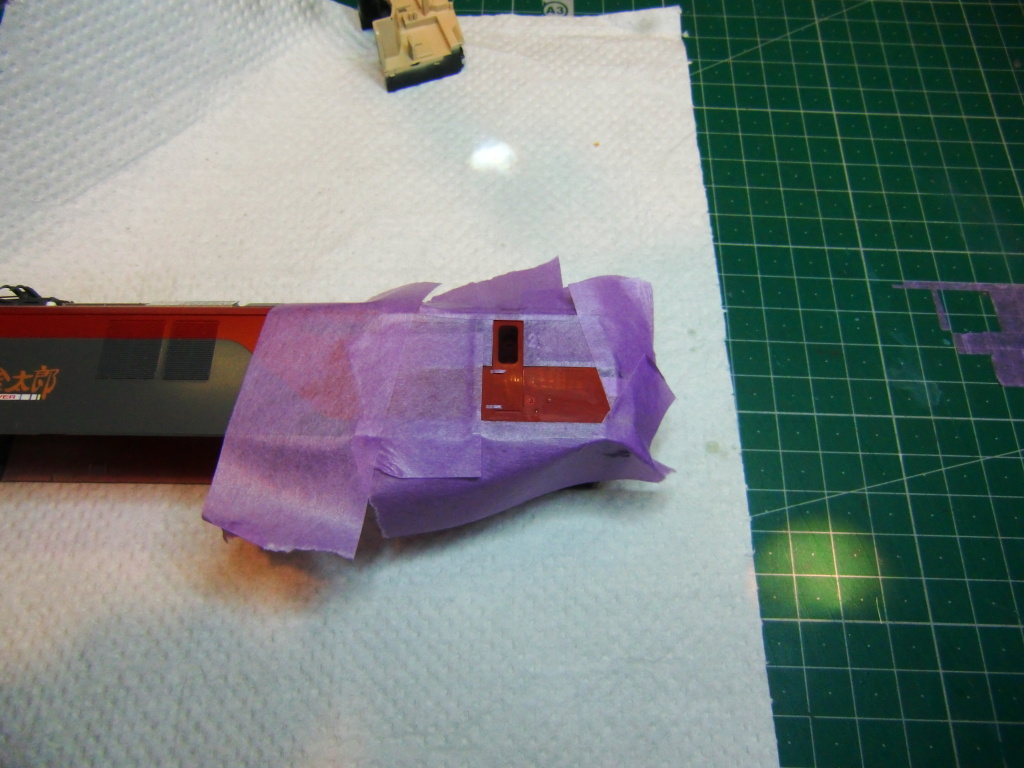
次に研ぎ出した赤の部分をマスキングします。


可能な限り近い色となるようにしましたが、完全に同じというわけにはいきません。


ここまで修復ができました。作業完了でございます。

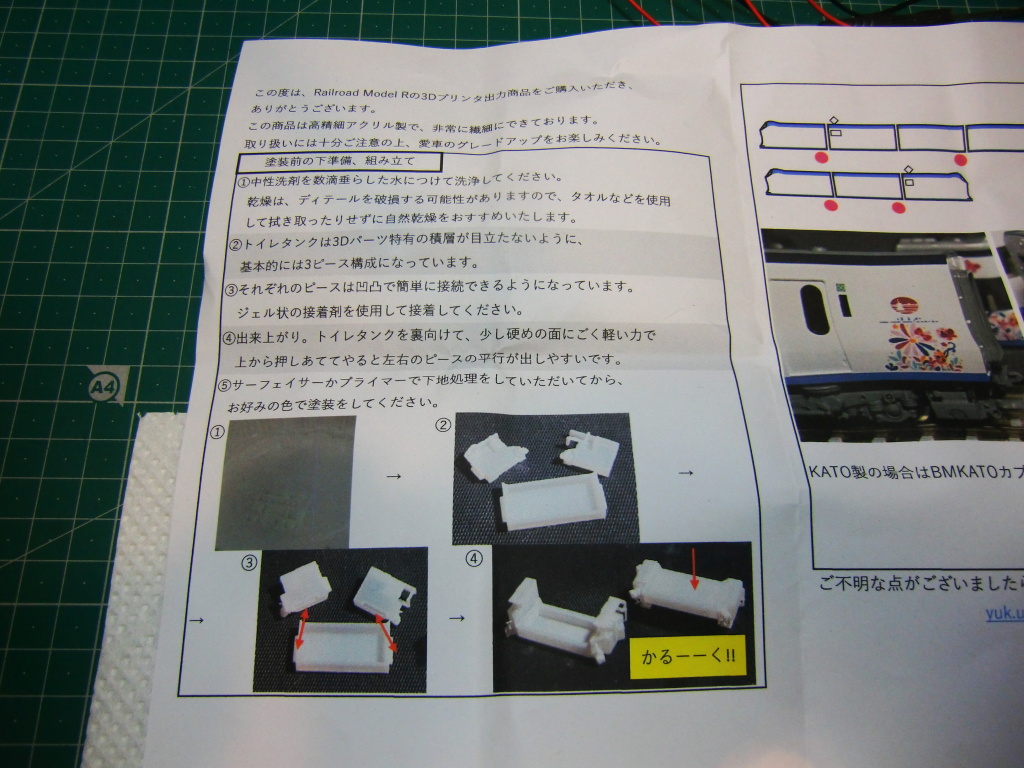
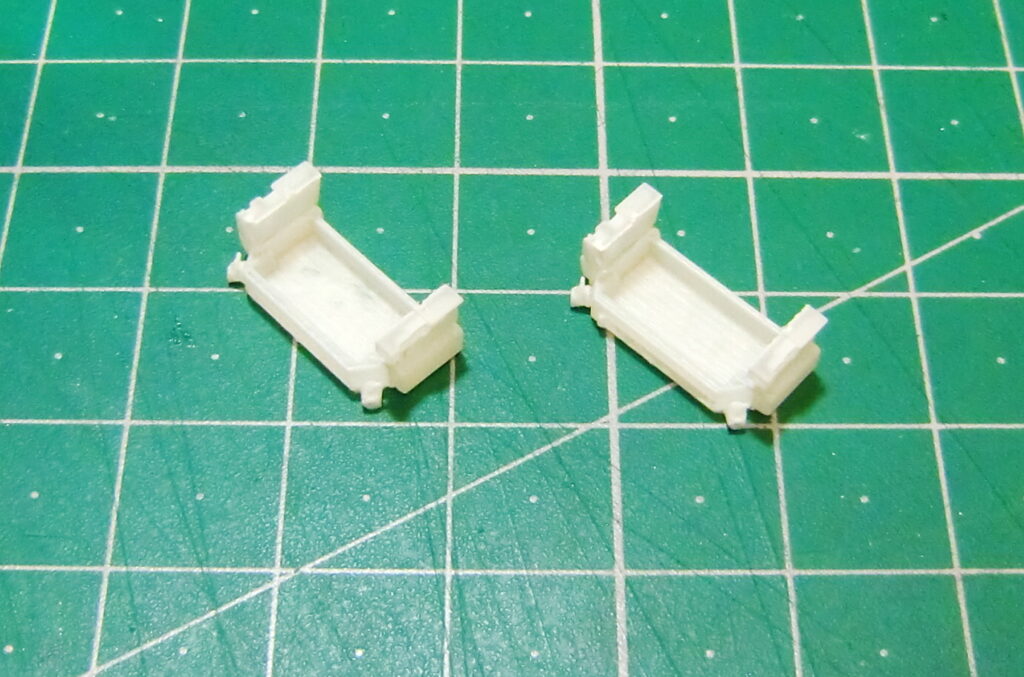
パーツ組立(写真右)、このあと塗装作業に移ります。

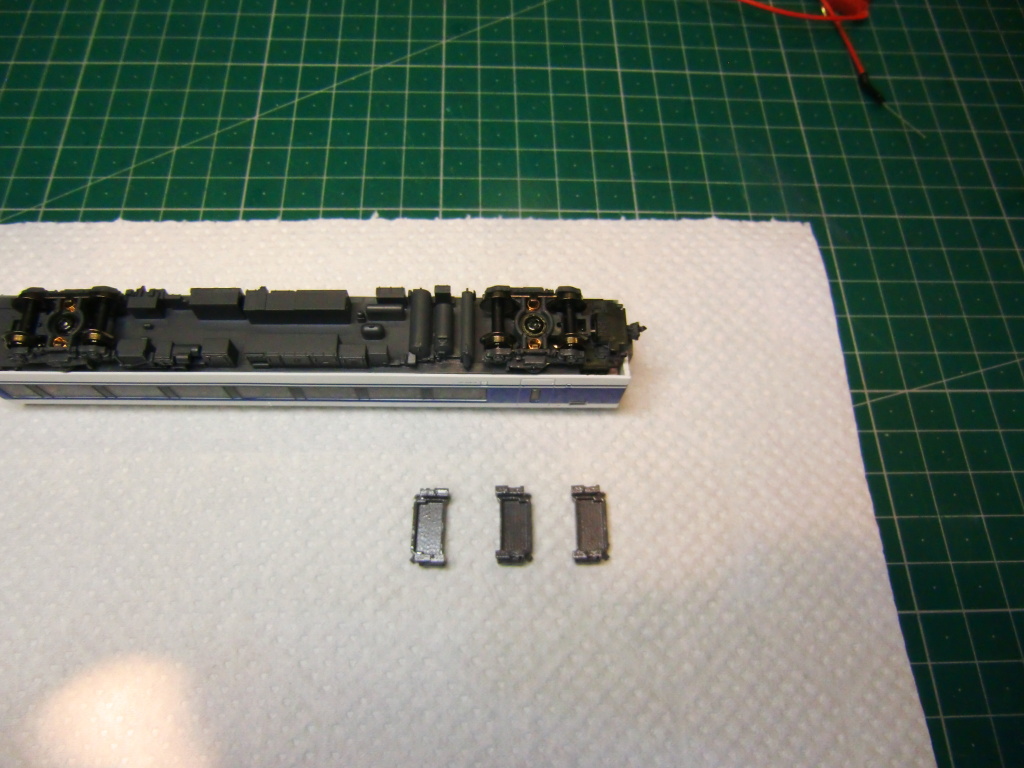
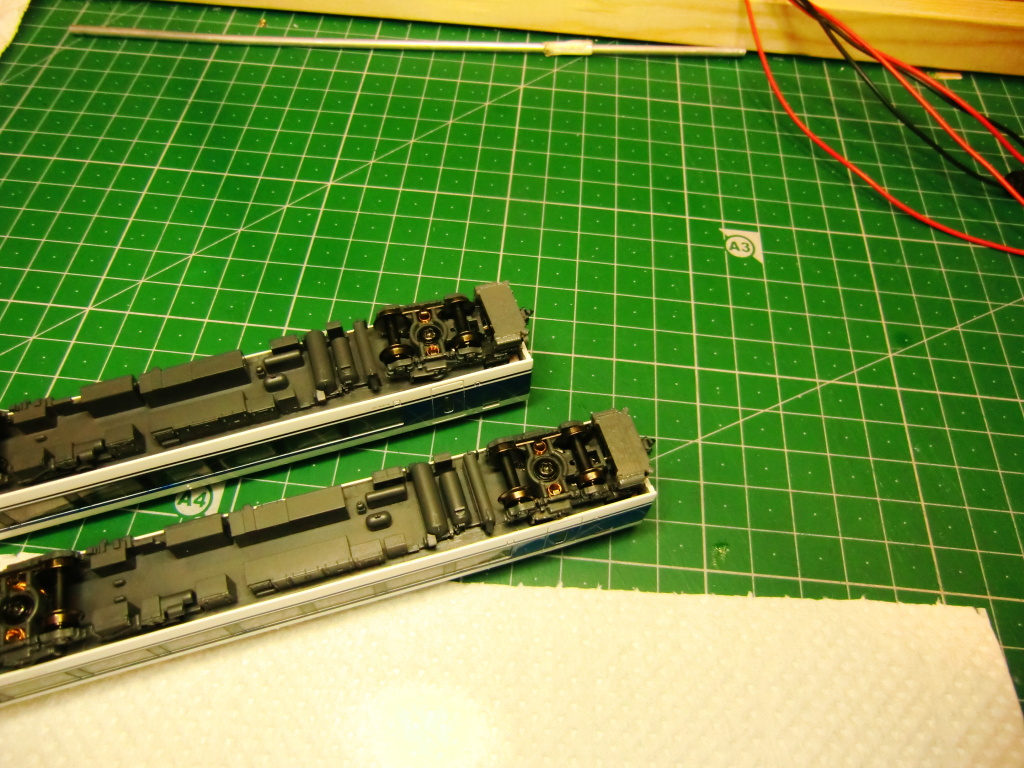



お取り付け作業完了でございます。


▼函館市電8000形 組立塗装+ライト遮光
まずは、「グレイスモデル 函館市電8000形」の制作から始めます。ライトは後ほど点灯させることを前提とした遮光処理を施しておきます。
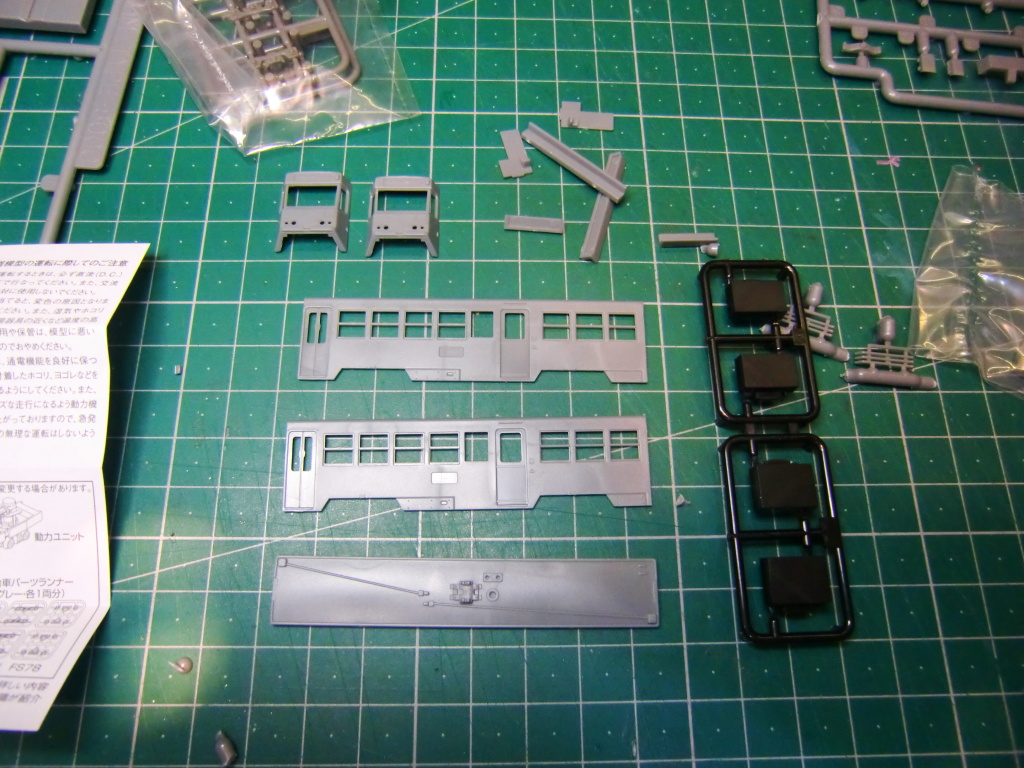
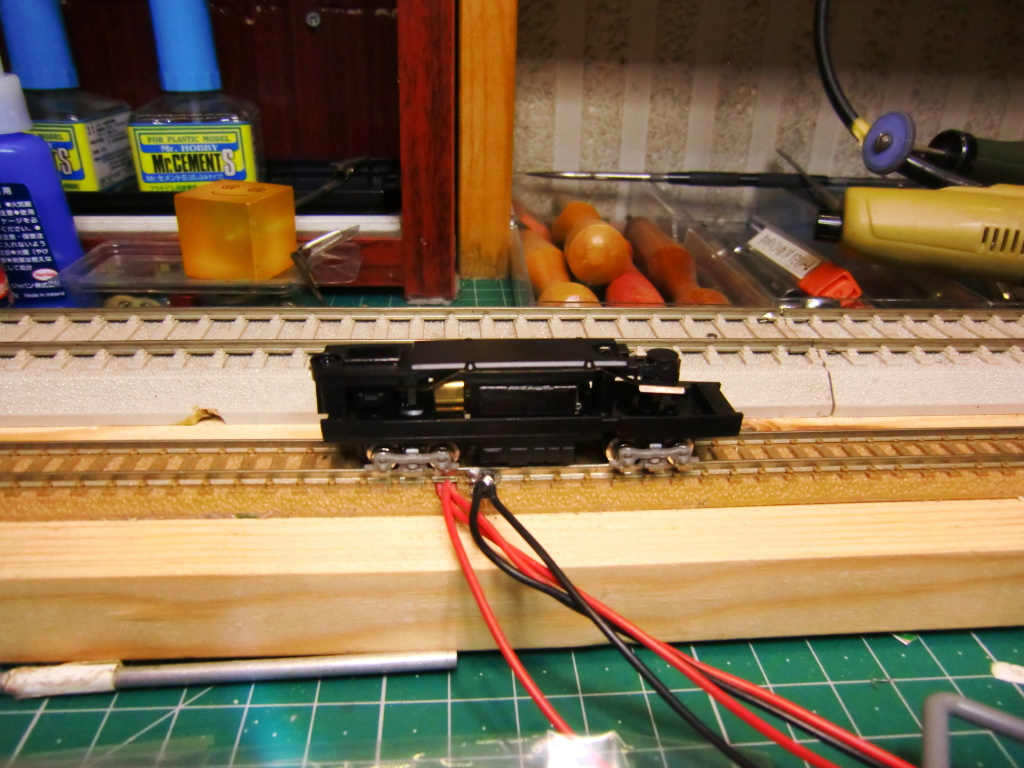




組立後にボディー洗浄 > サーフェイサー > 基本塗装 の順に行いました。
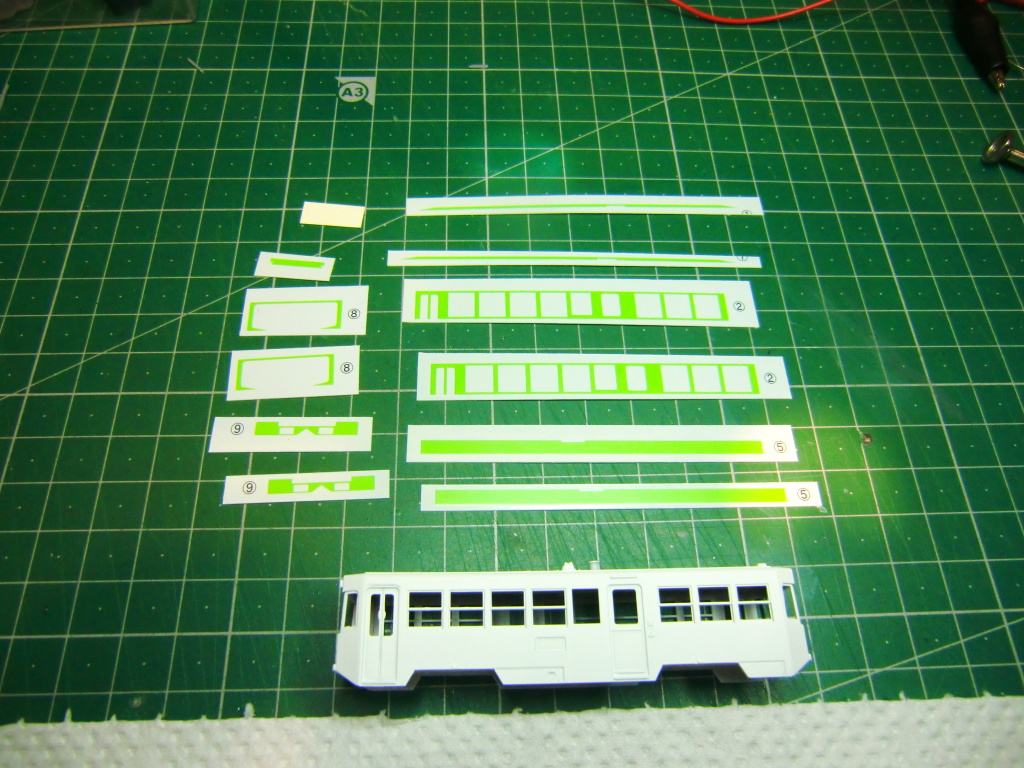
デカールを切り分けます。


完全乾燥したのち窓の切り抜き(デカール)を行います。


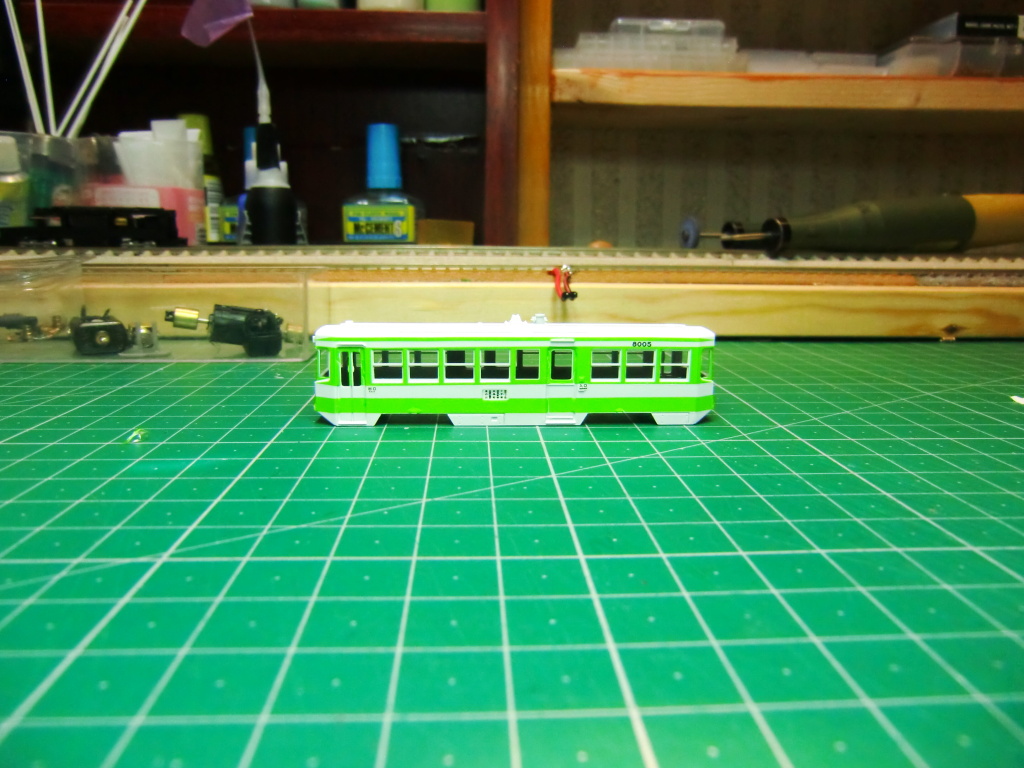
▼クリアコート

▼屋根塗装



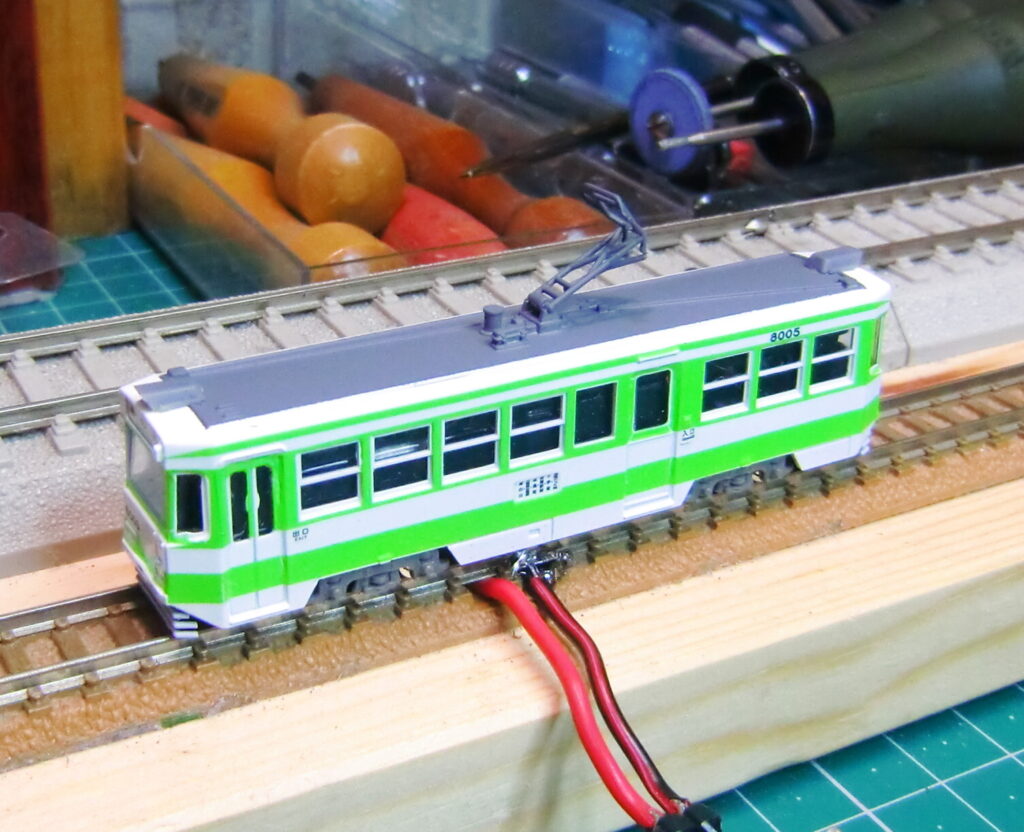


作業完了でございます。
まずは、こちらの車両から作業を開始します。
現状ですがまったく速度が出ません。

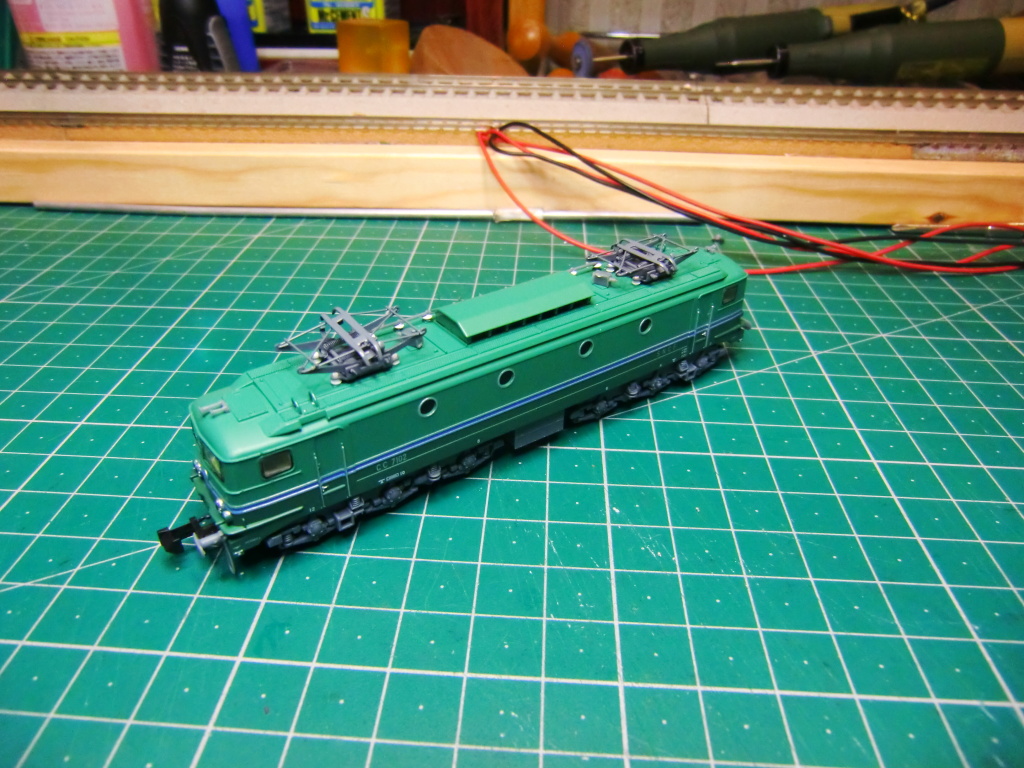


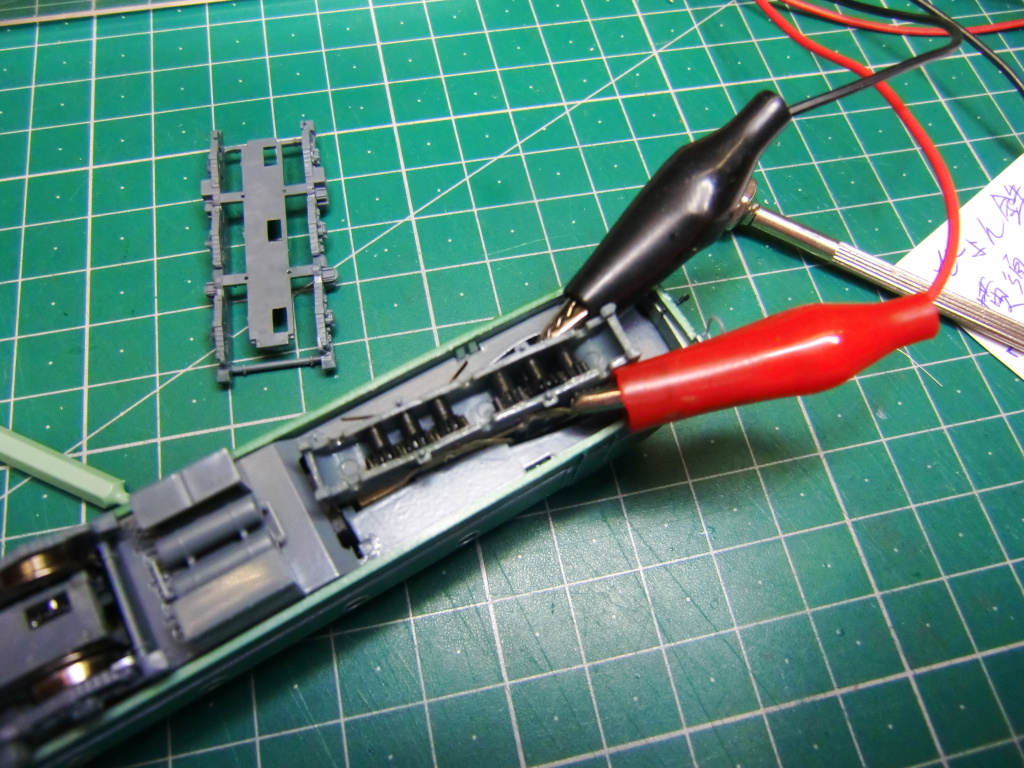
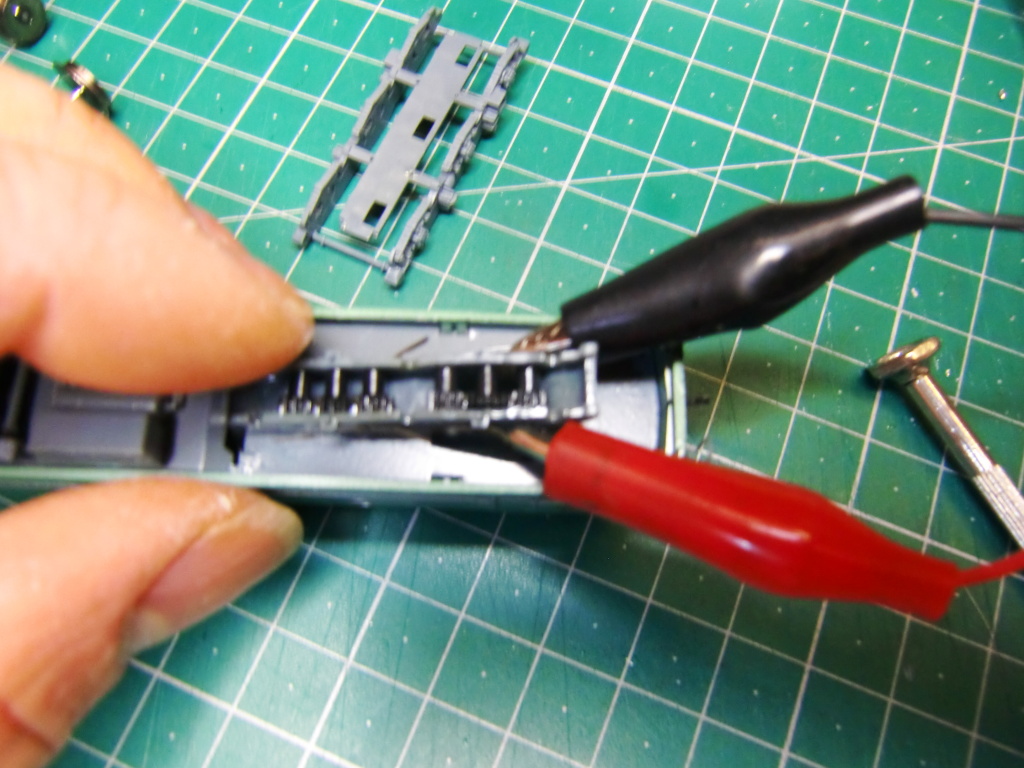
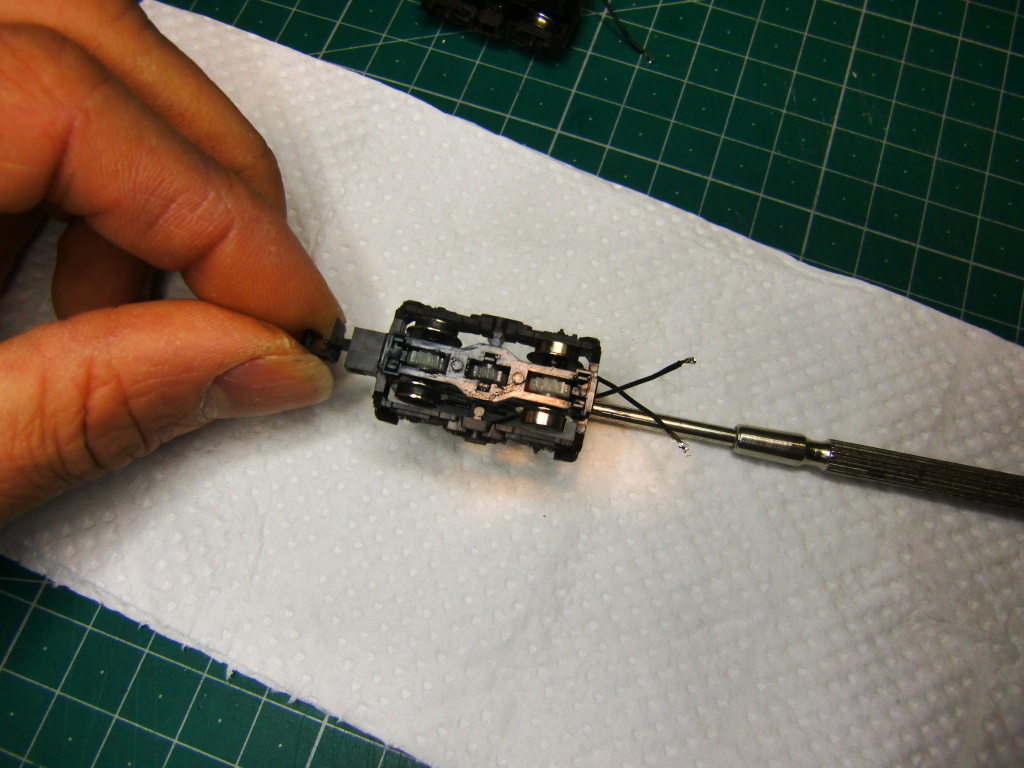
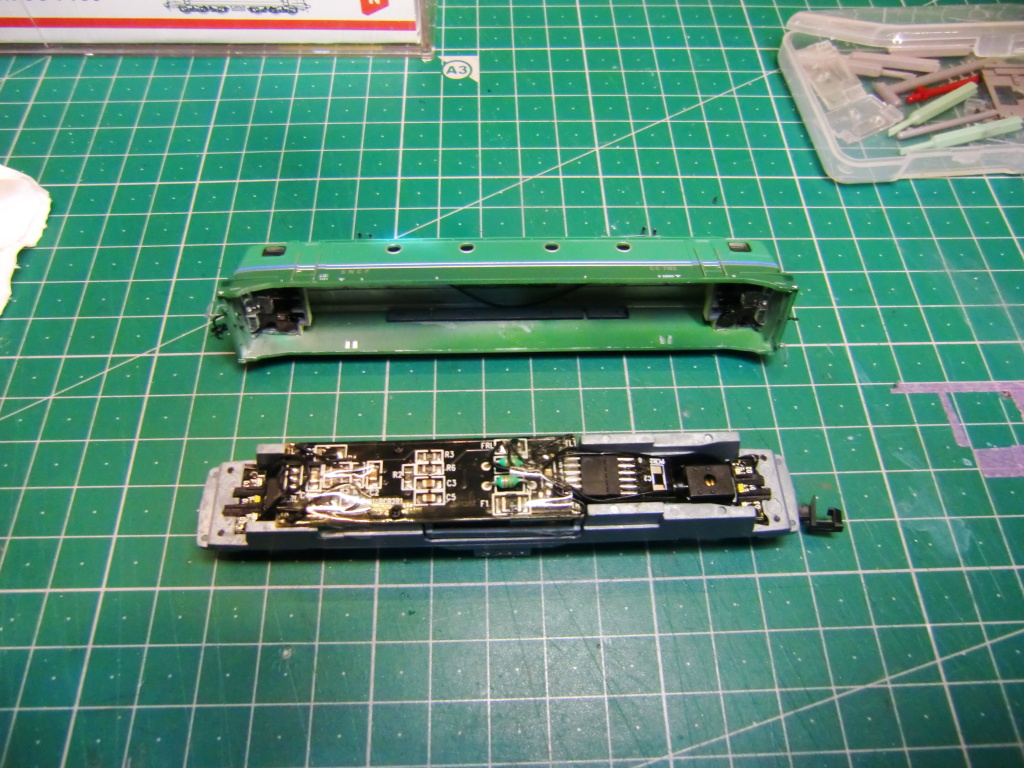
こちらの車体、とにかくボディーが開きませんでした。これ以上は車体を破損させてしまう心配がありましたので、あきらめかけたところ、最後にトライしてようやく分解できました。
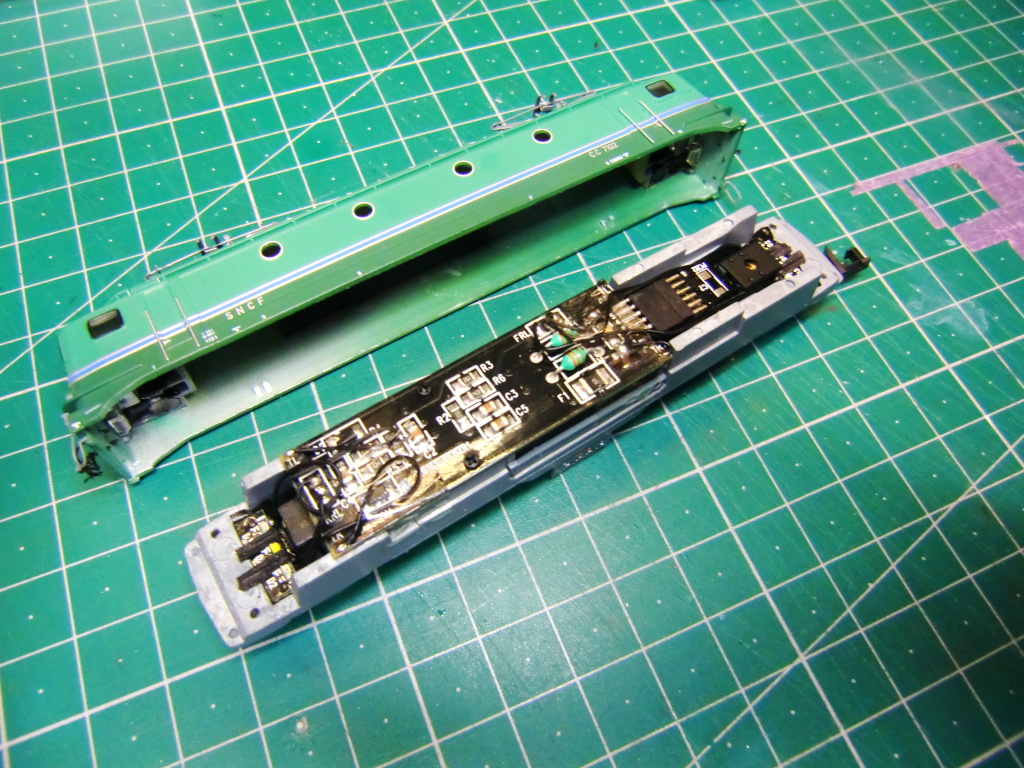
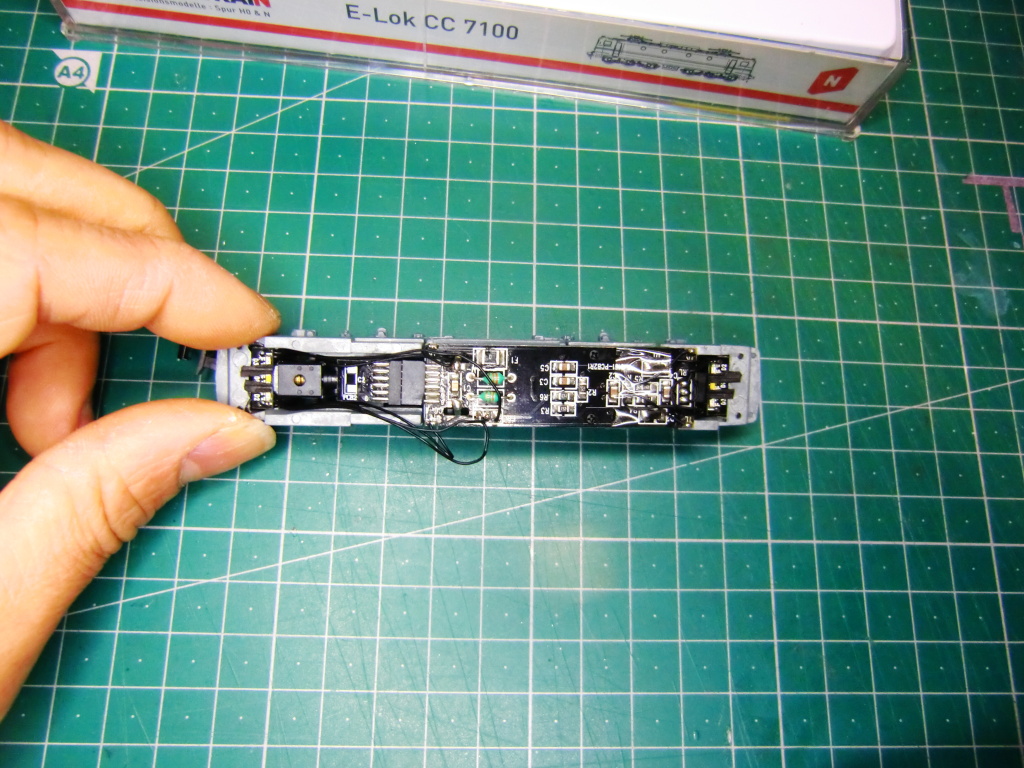
国内メーカーの基盤とは根本的に違う並びですね。基盤およびモーターなどもすべてを一旦取り外して個別にテストを行い問題個所を特定していきます。
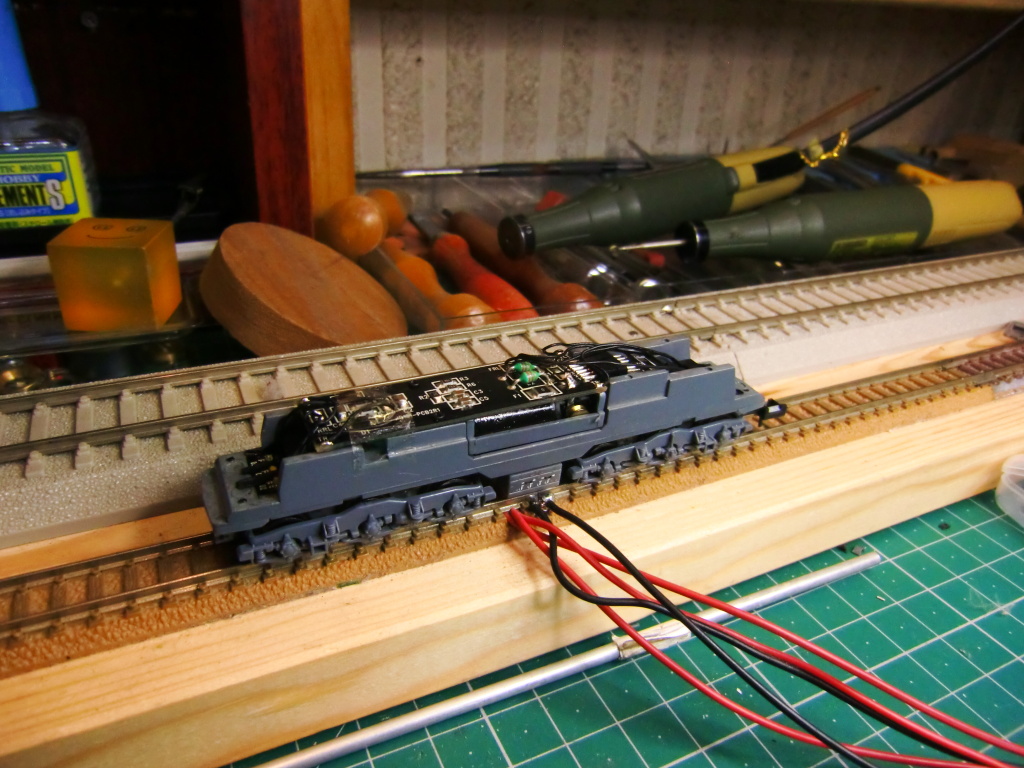
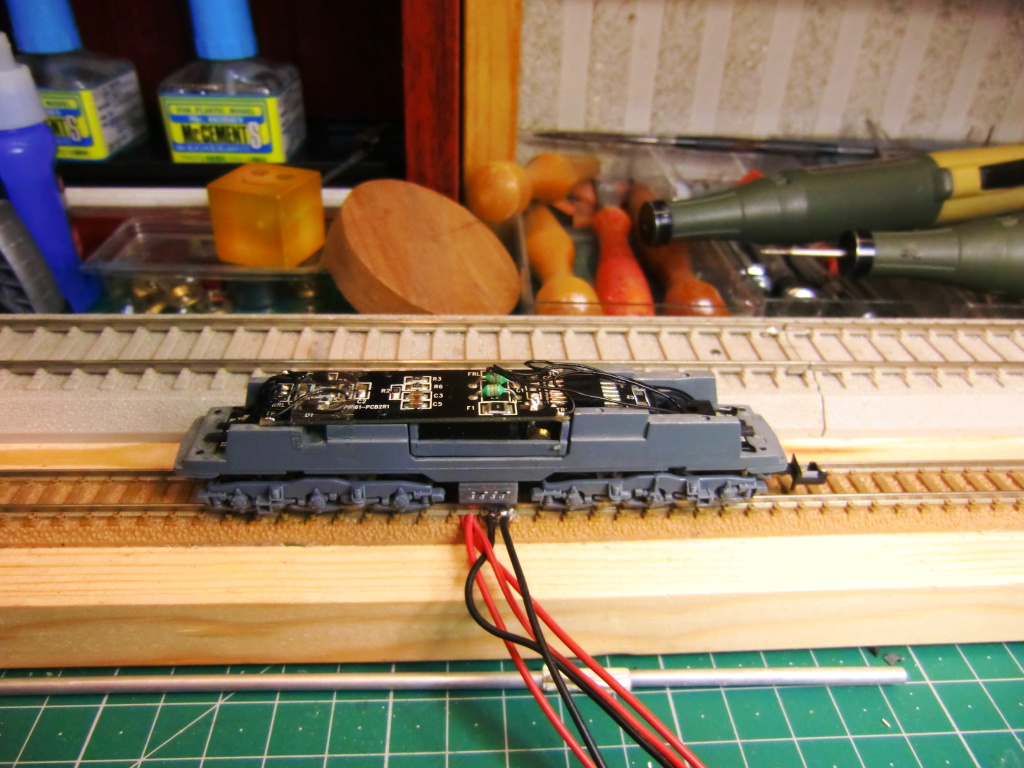
調整と走行テストを繰り返し行います。
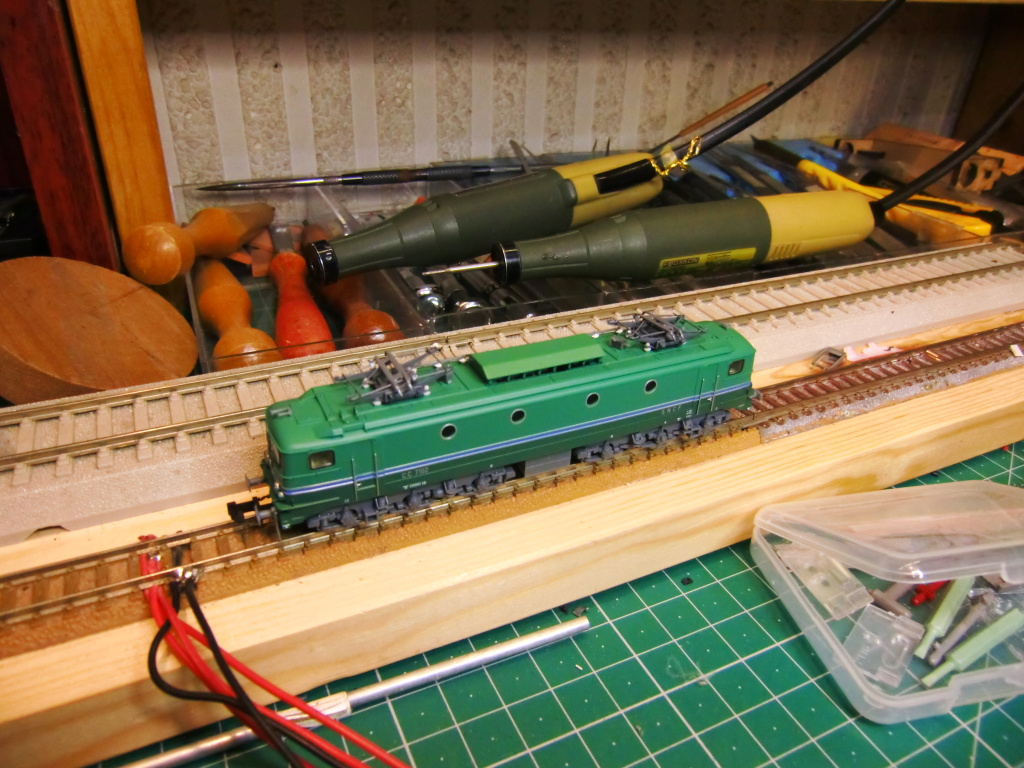
ボディーの分解をしやすくなるように、内側を加工しておきます。
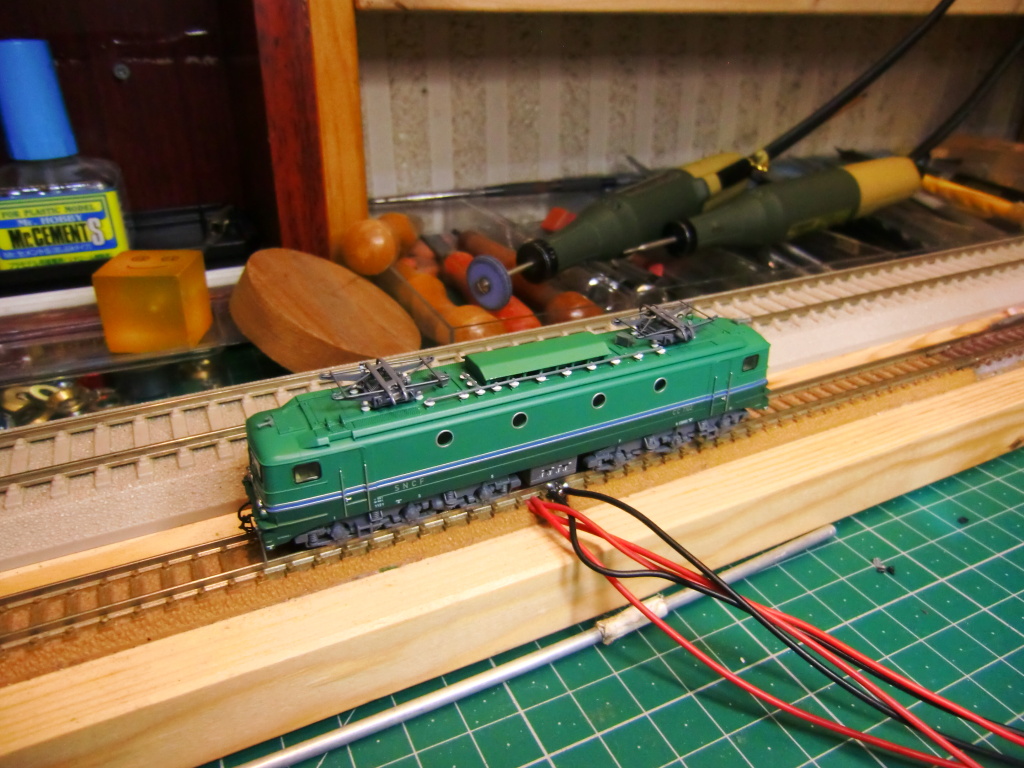

最後にボディーを被せて走行テストを行い作業は完了です。次に進みます。

次にこちらの機関車ですが、大きな振動とゴトゴト音がかなり出ます。

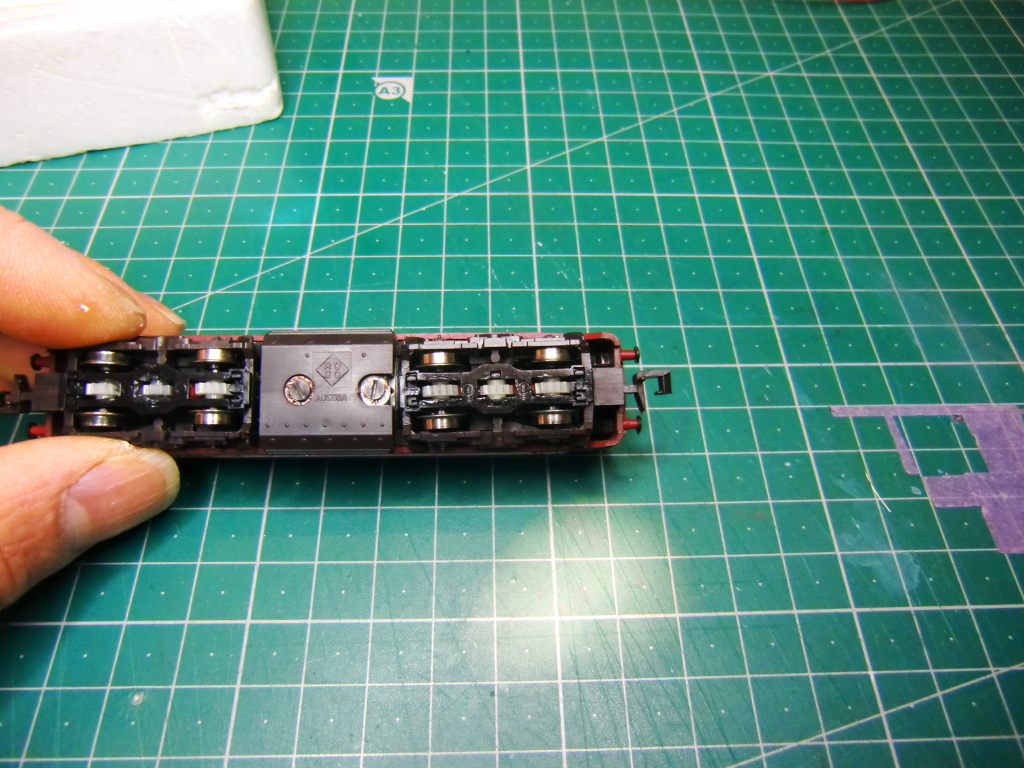
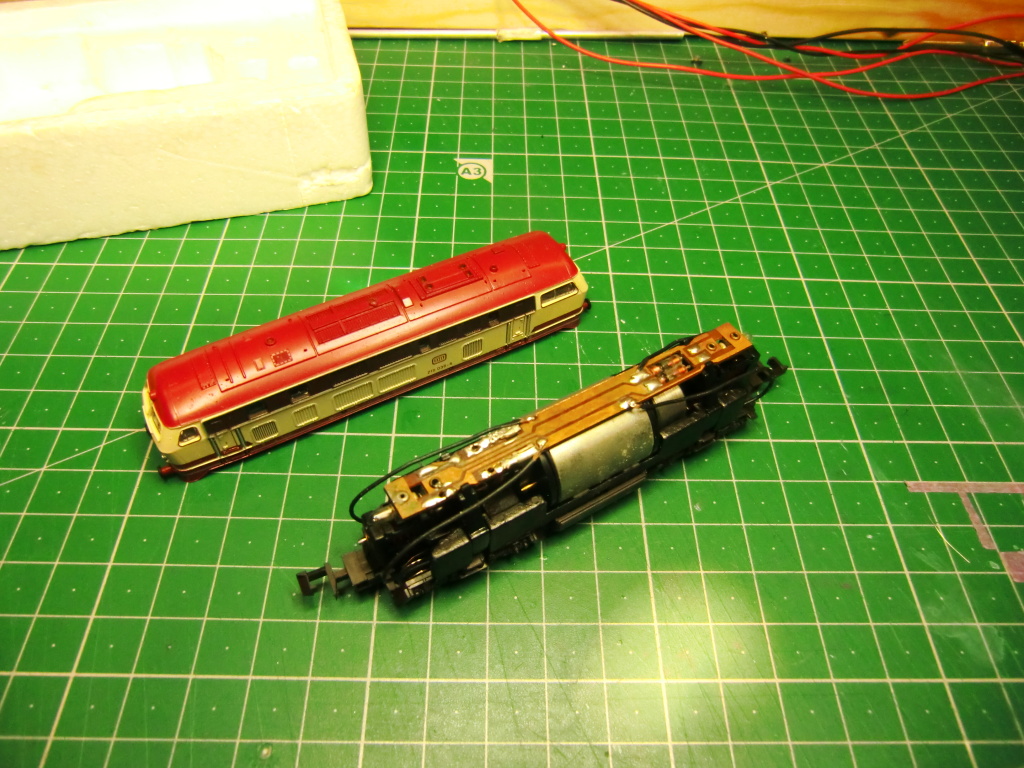
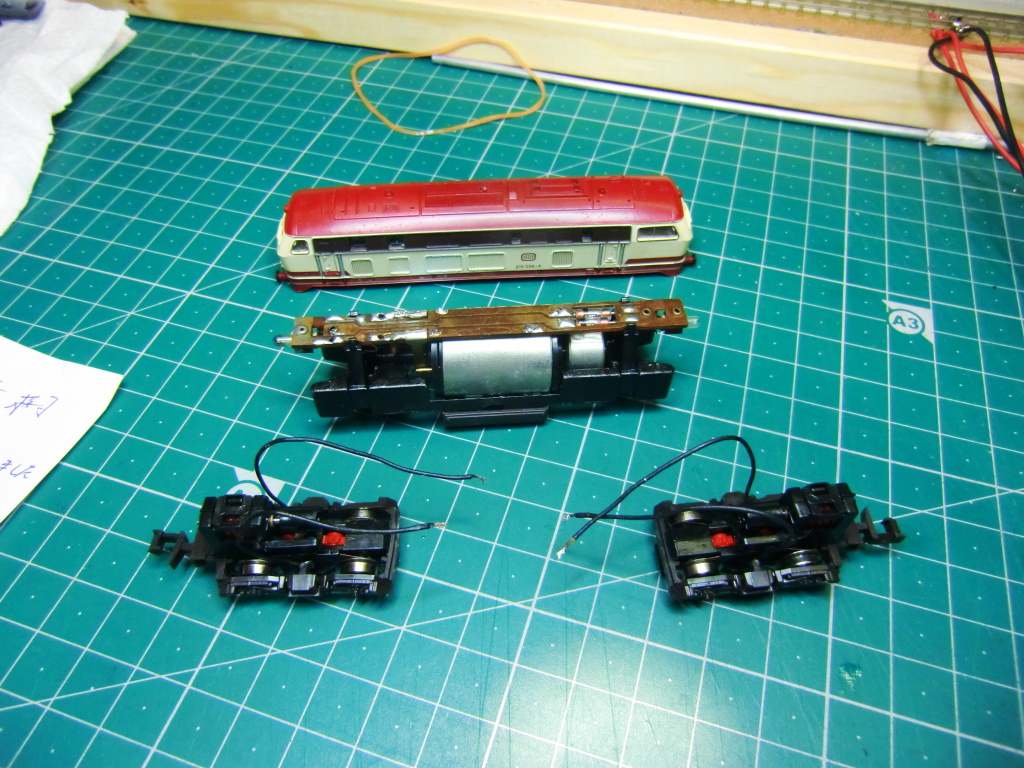

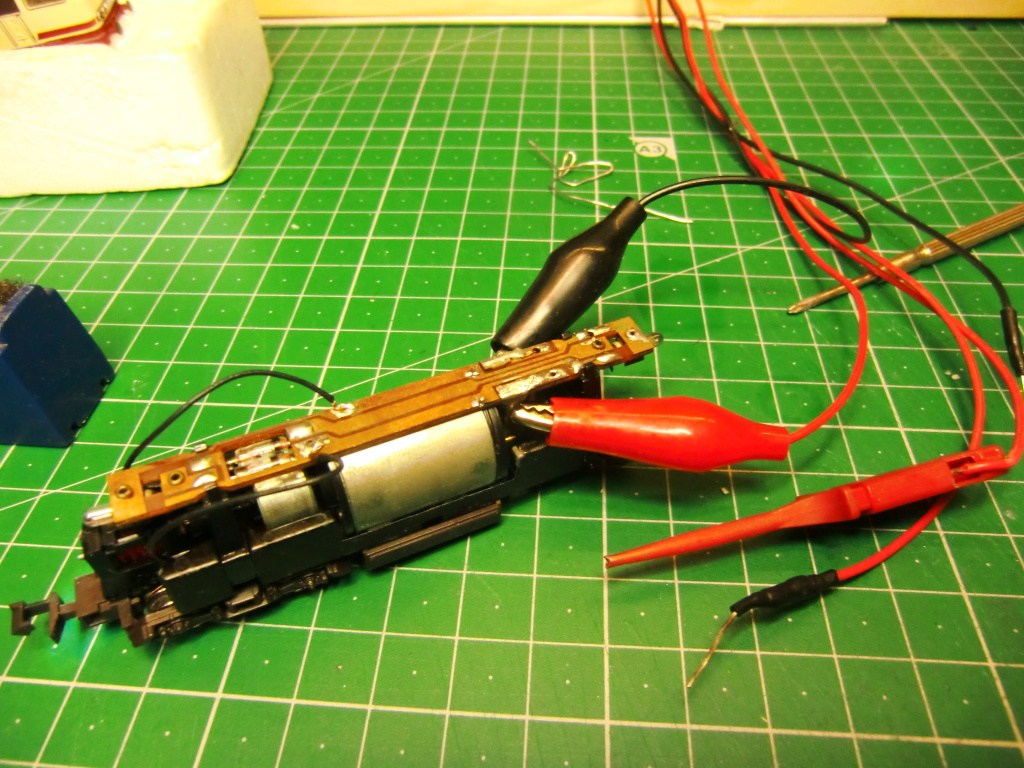

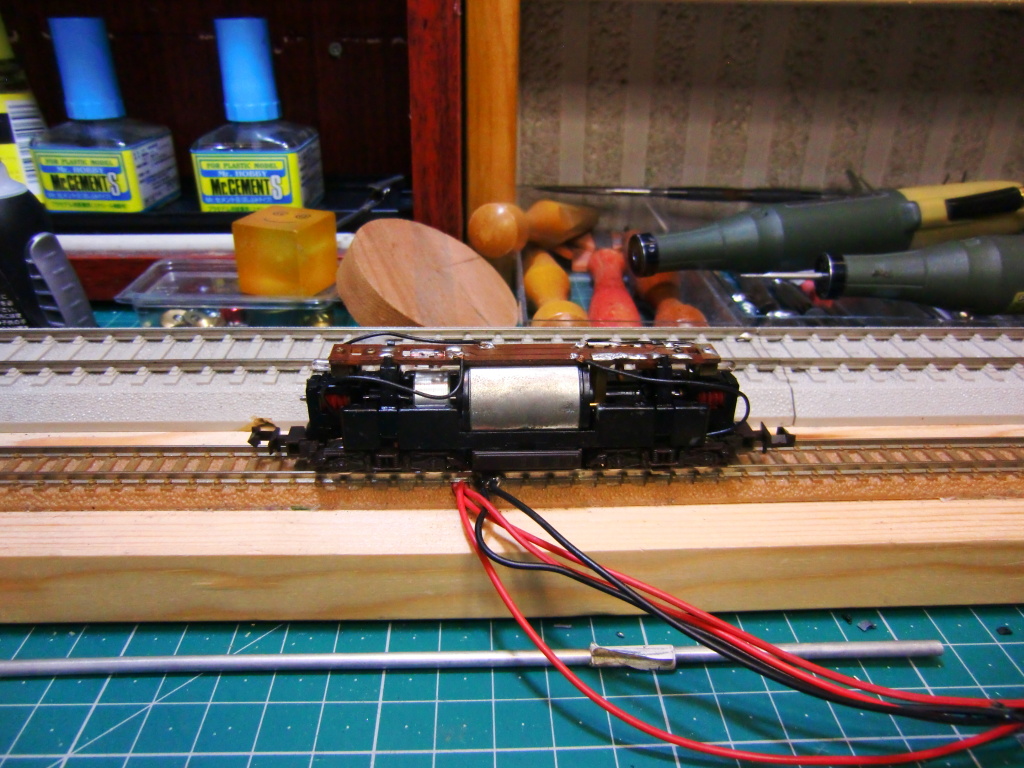
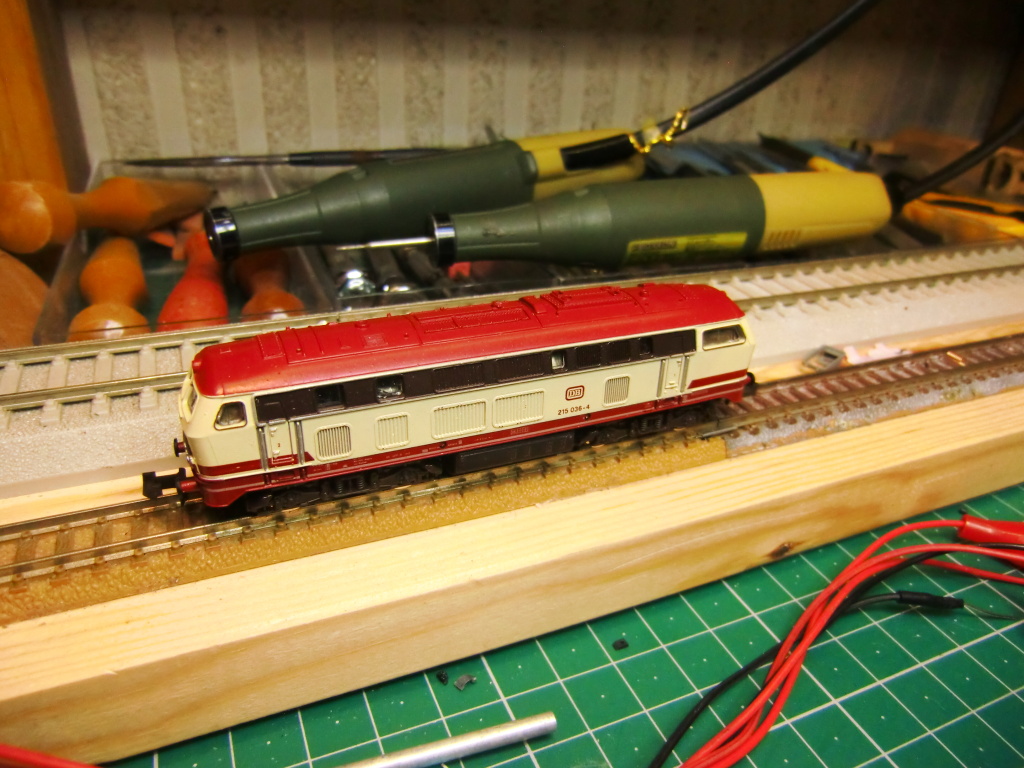







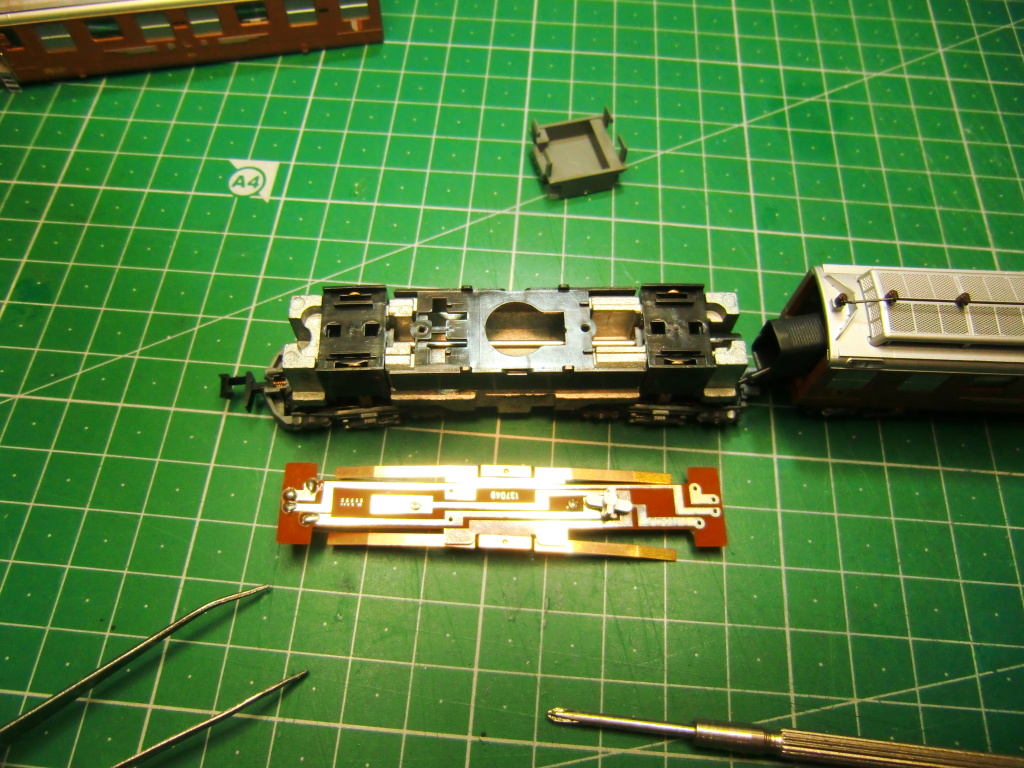
部品が損傷しているため直していきます。
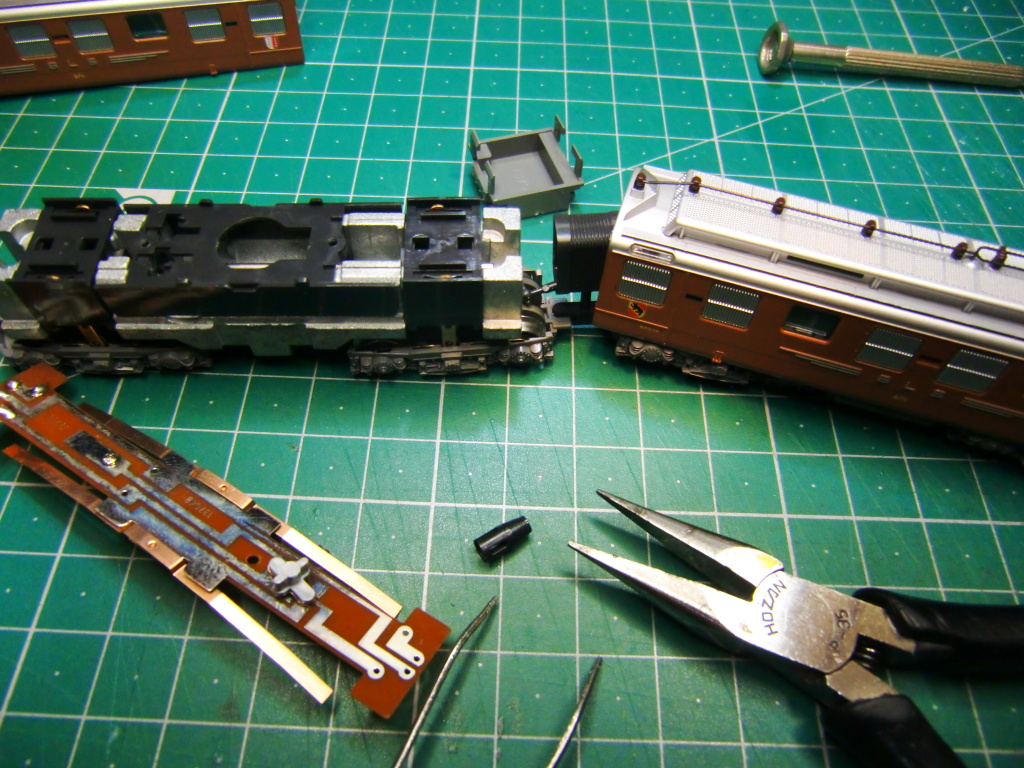
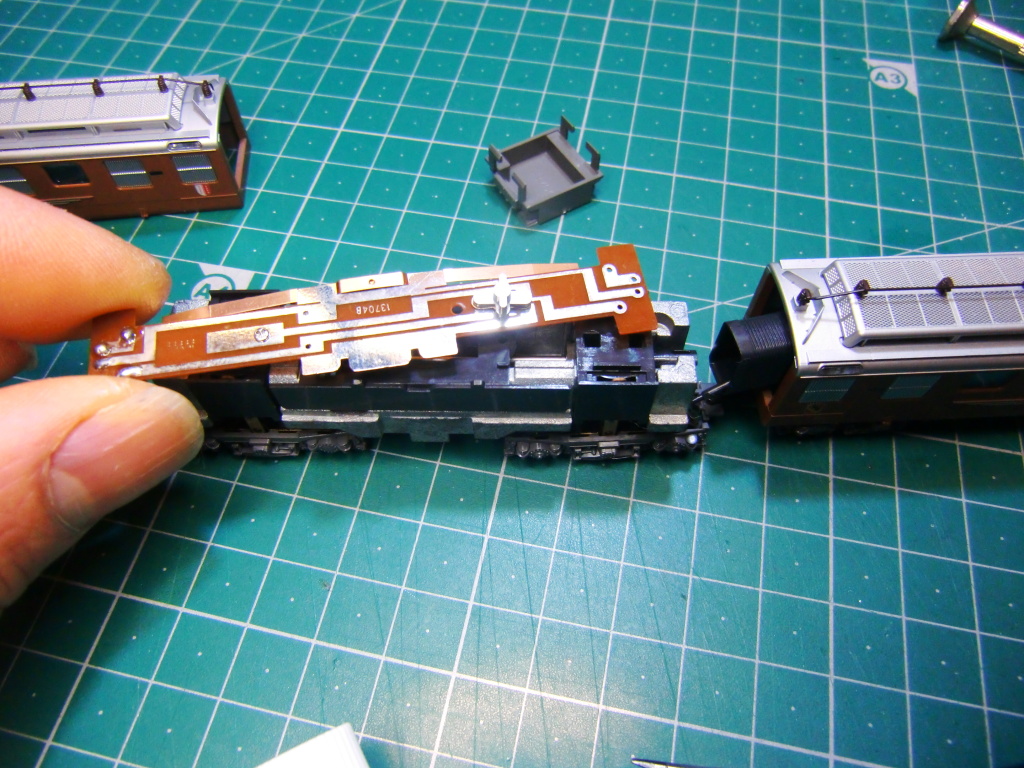
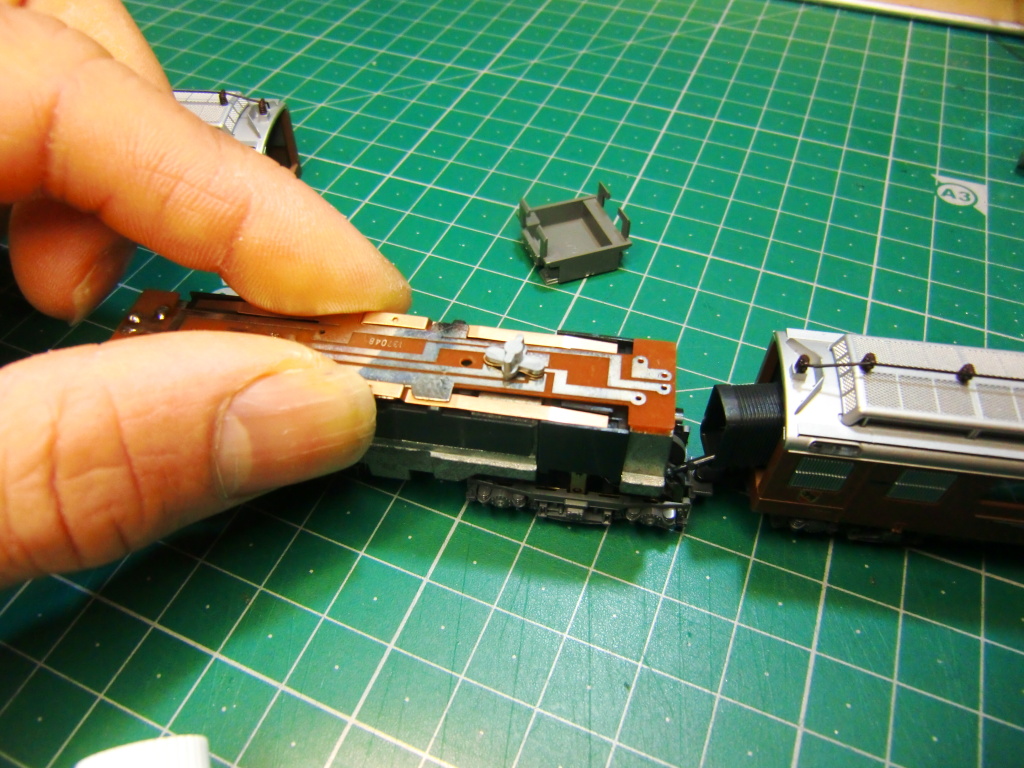
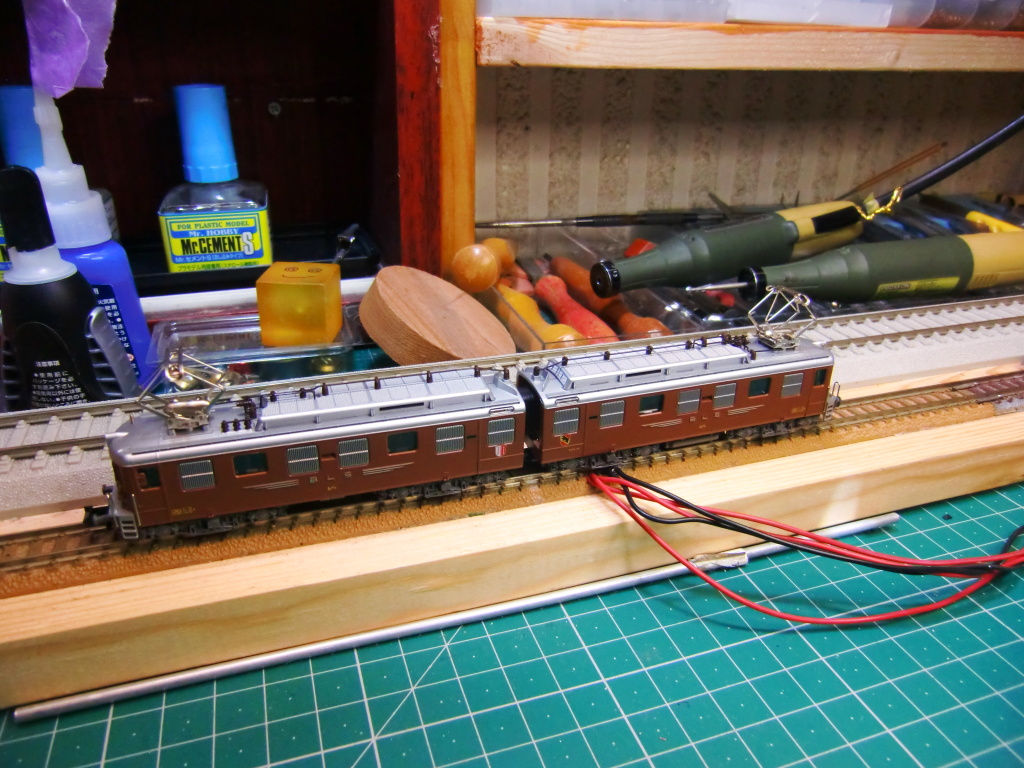
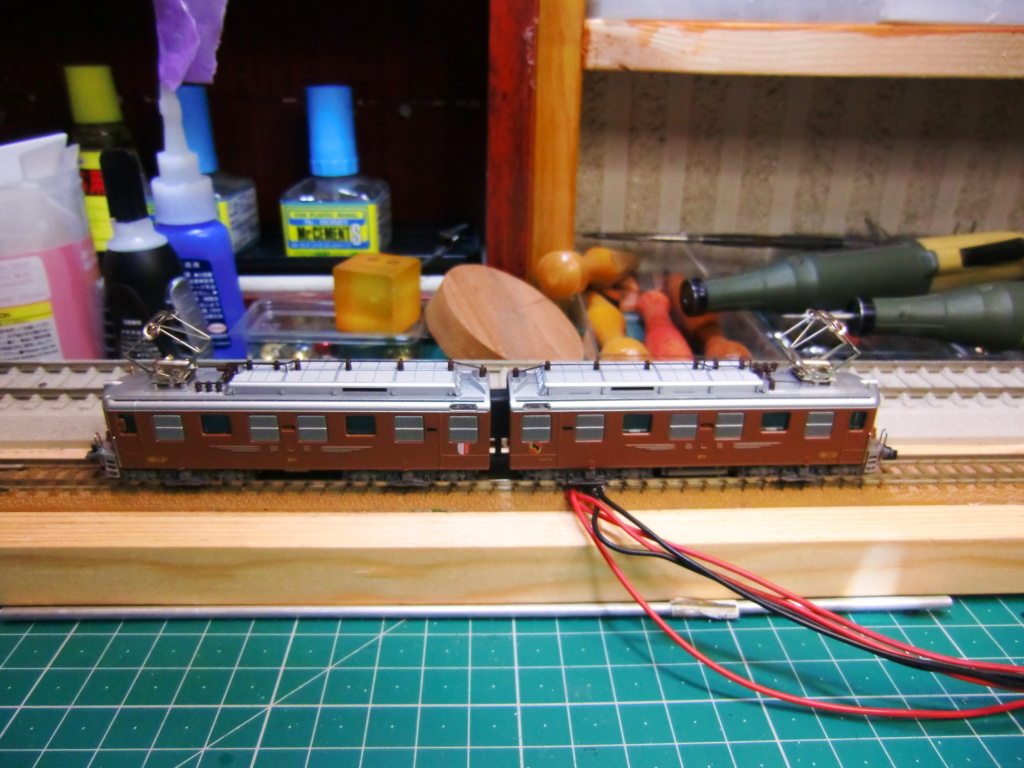




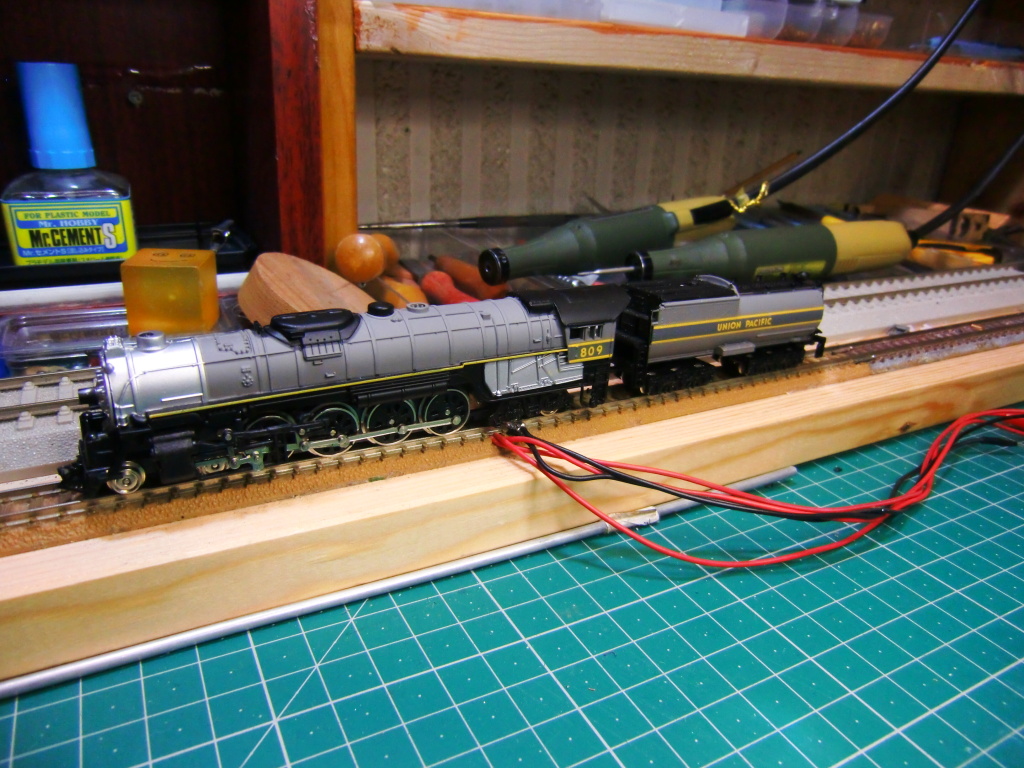

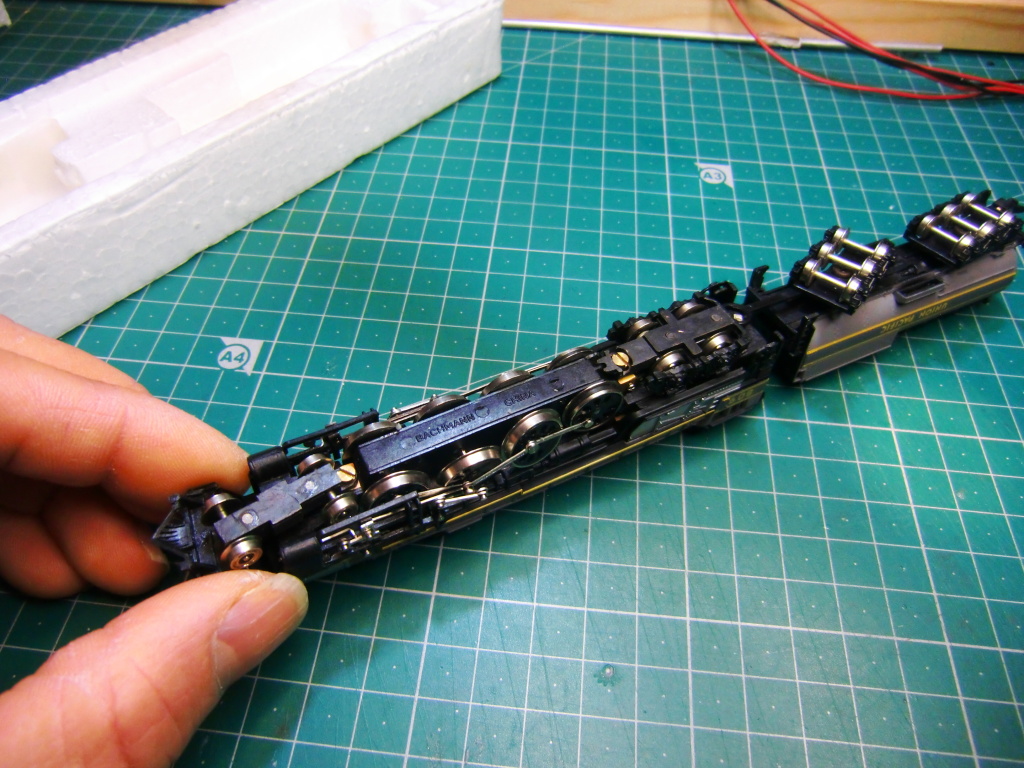
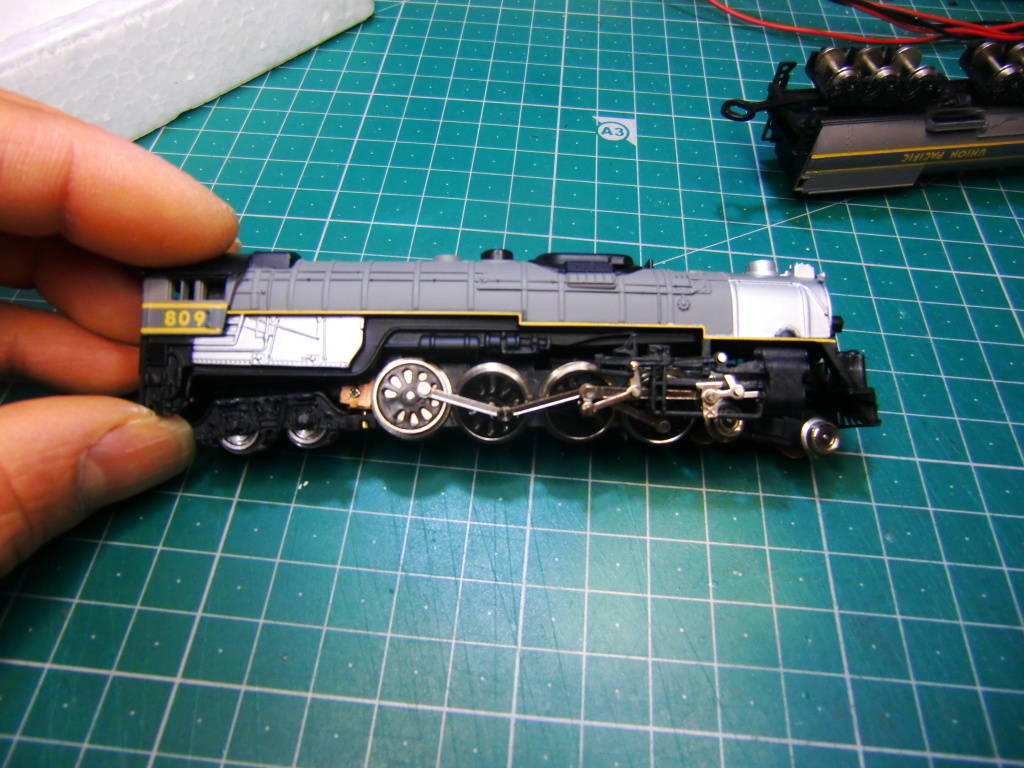

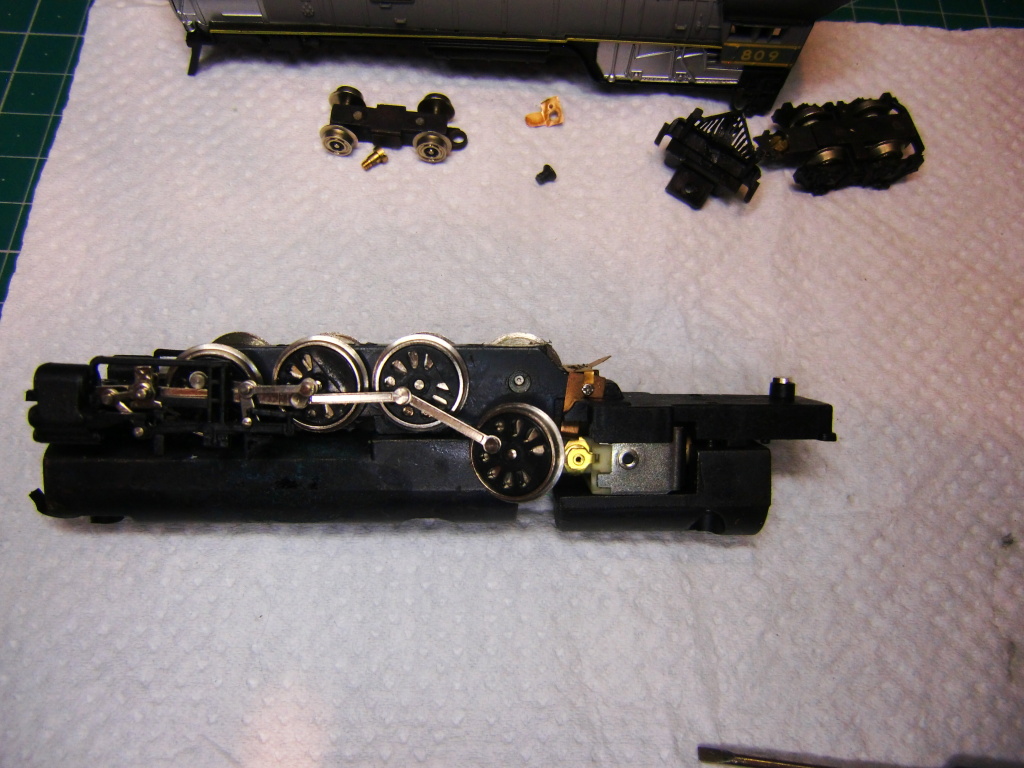
内部のギアがすべて割れていて車輪がすっぽ抜けてしまう状態です。これは非常に難しい修理となりそうです。SLはロッド調整が非常に難しいので集中して作業にあたります。
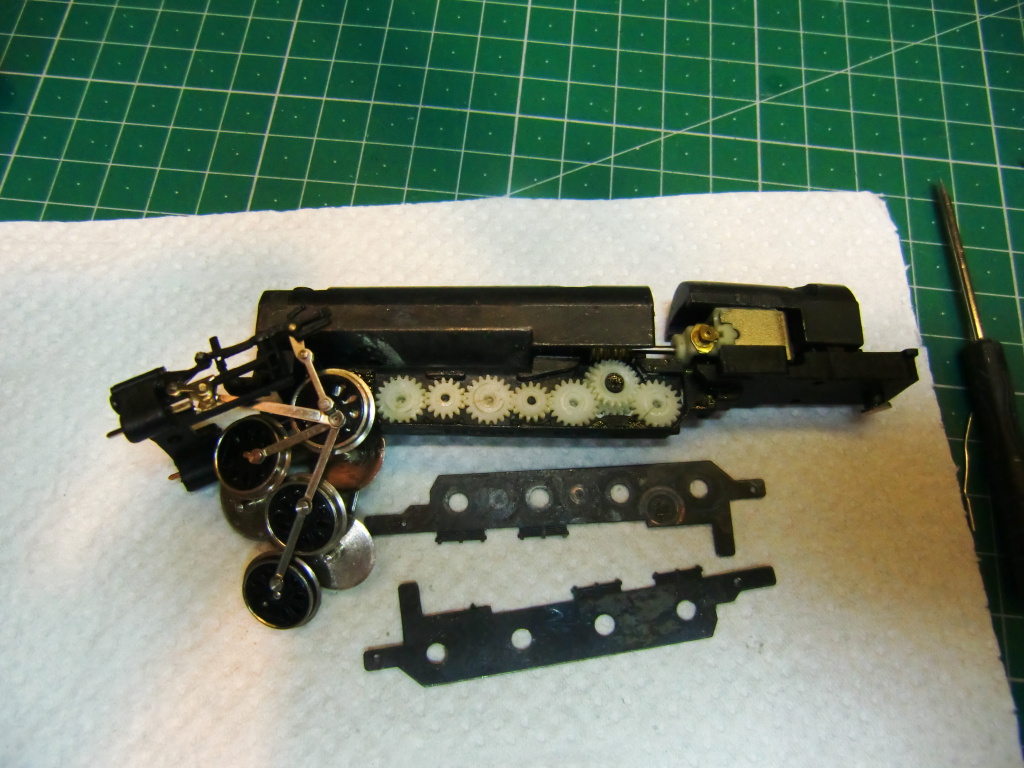


個別ギアのデータを取り、ギア自体を制作していきます。
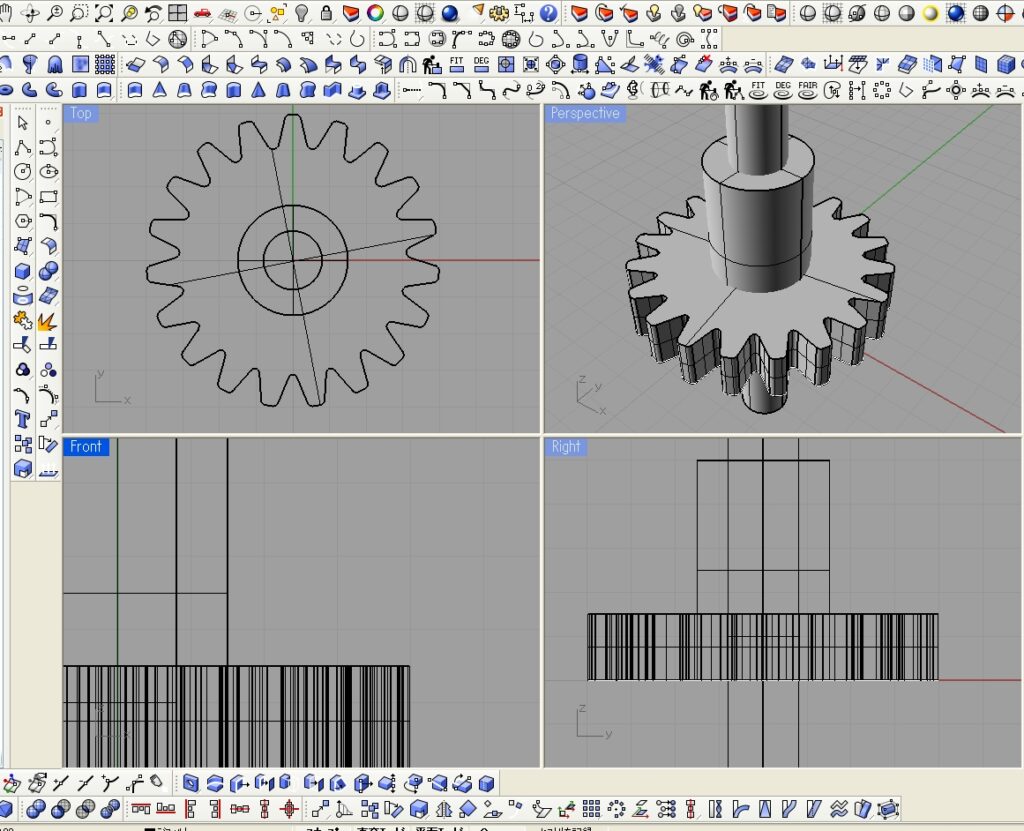

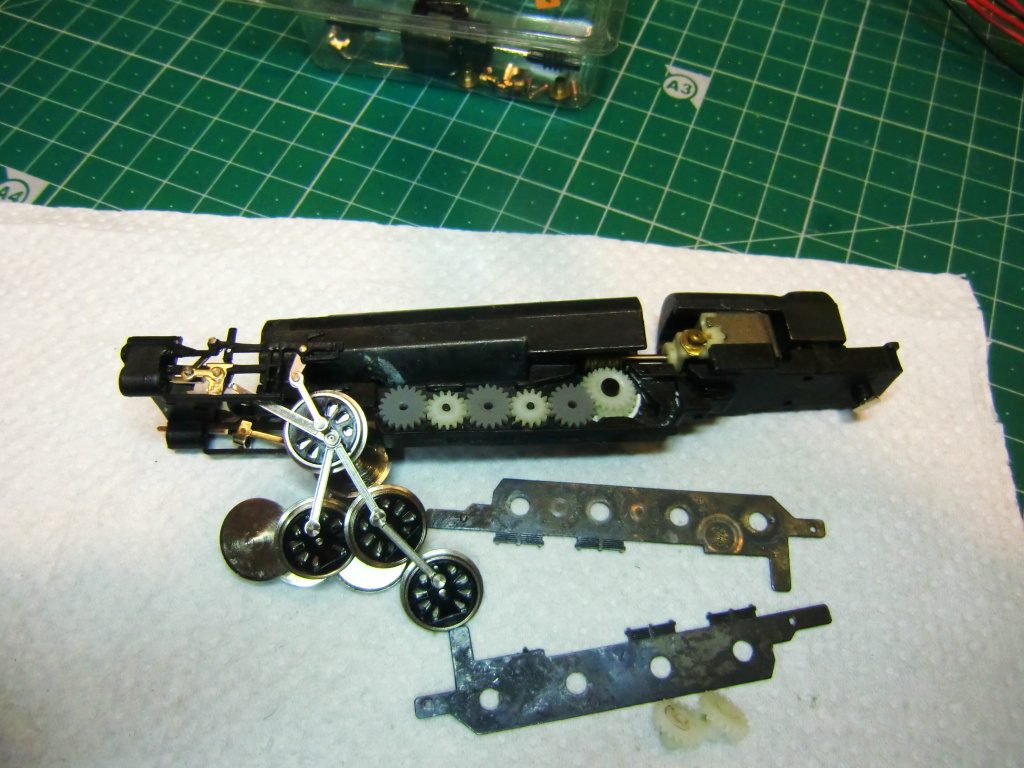

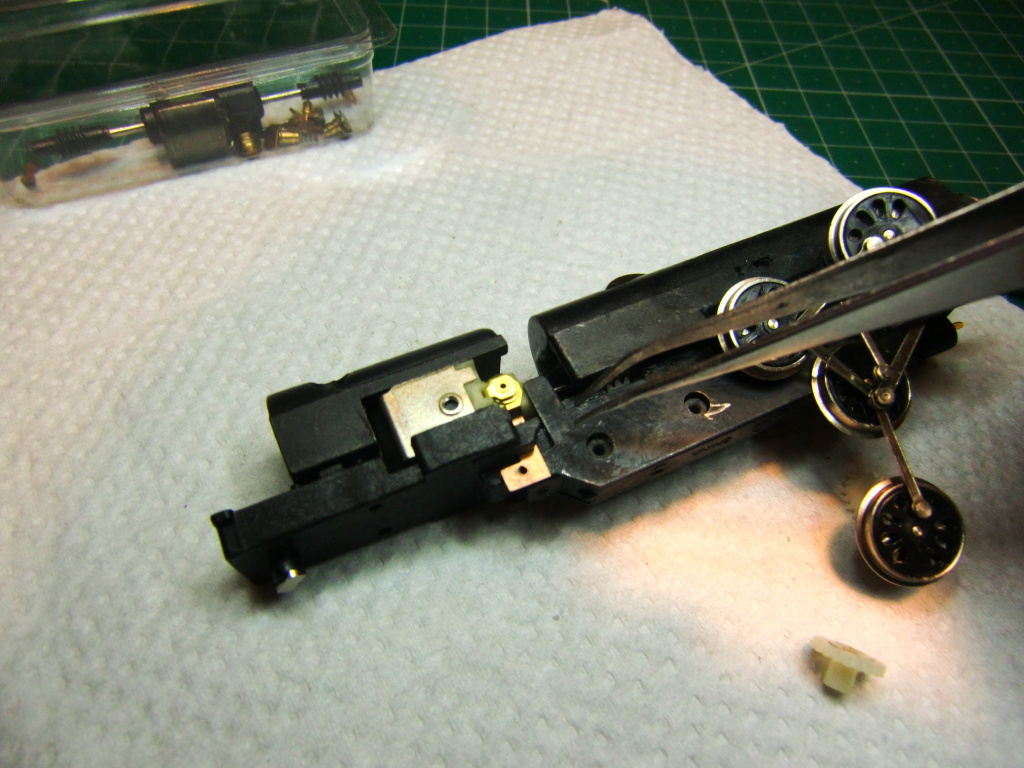

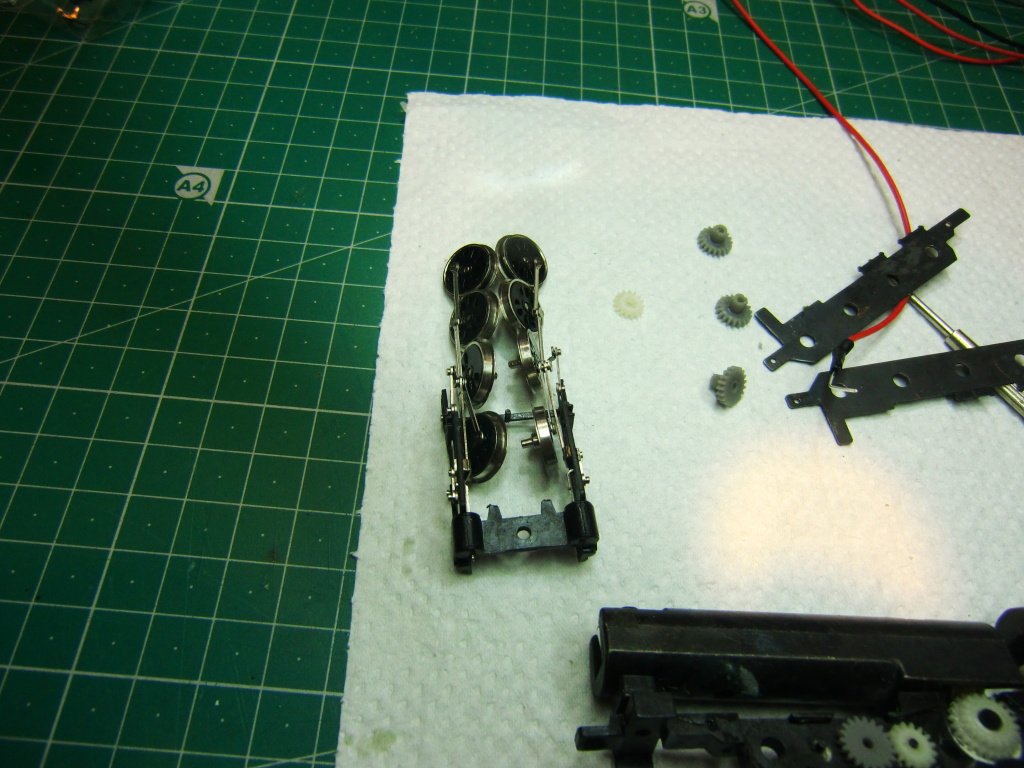
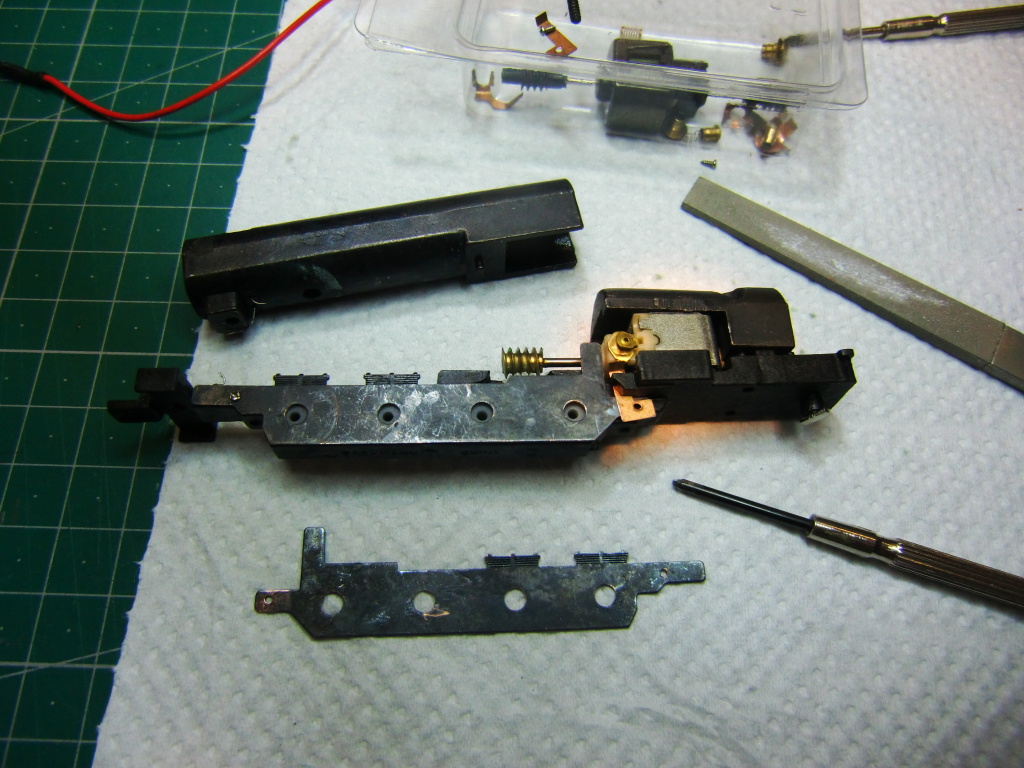
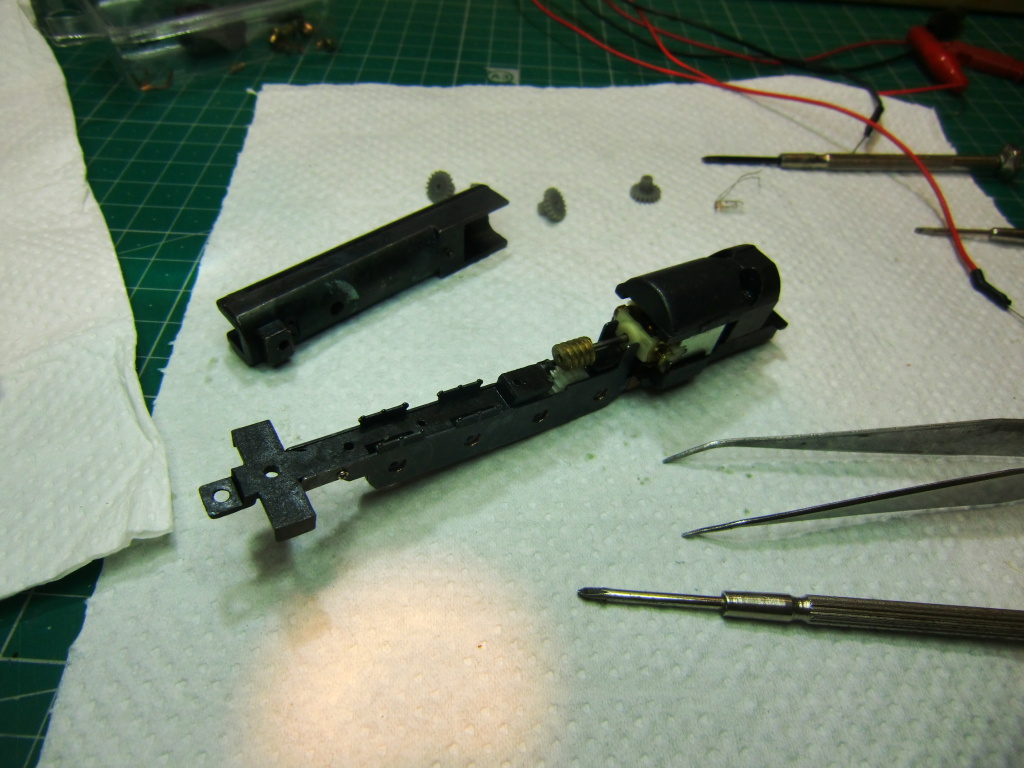
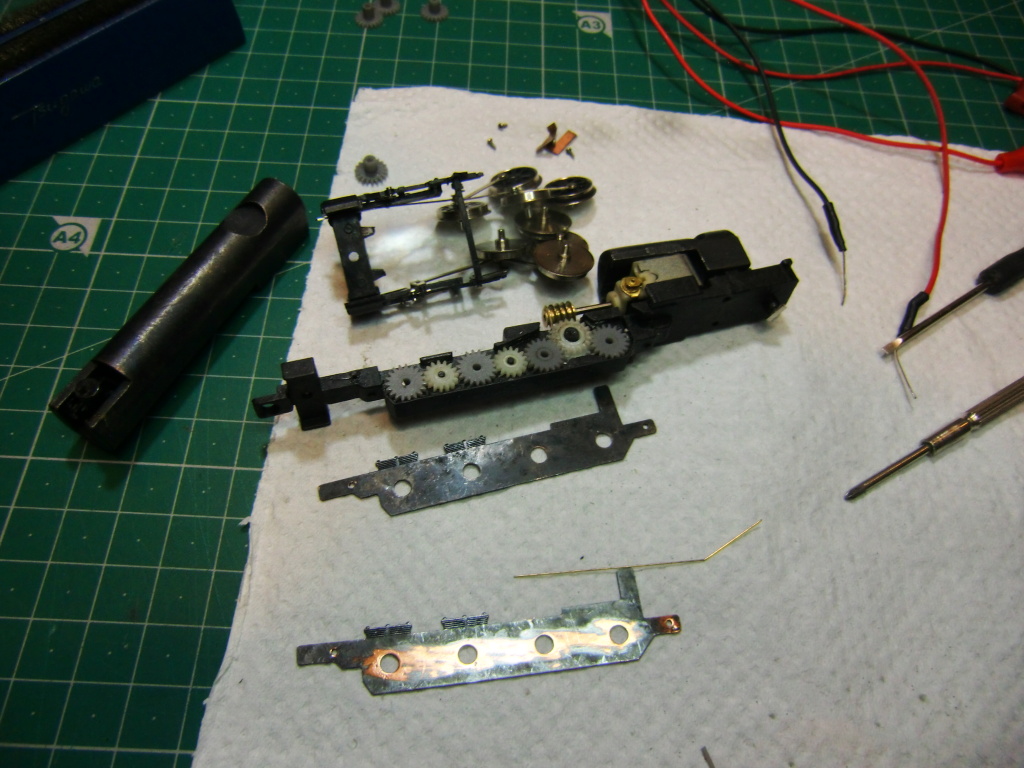
作業はかなり難航。ギアを作り直すこと4回、またその他にも問題となっているパーツがいくつかあり、調整もすごく難しい。全分解とテストを何度行ったかも覚えていない。既にこの車両に4日以上費やしているが、泥沼に入った予感。

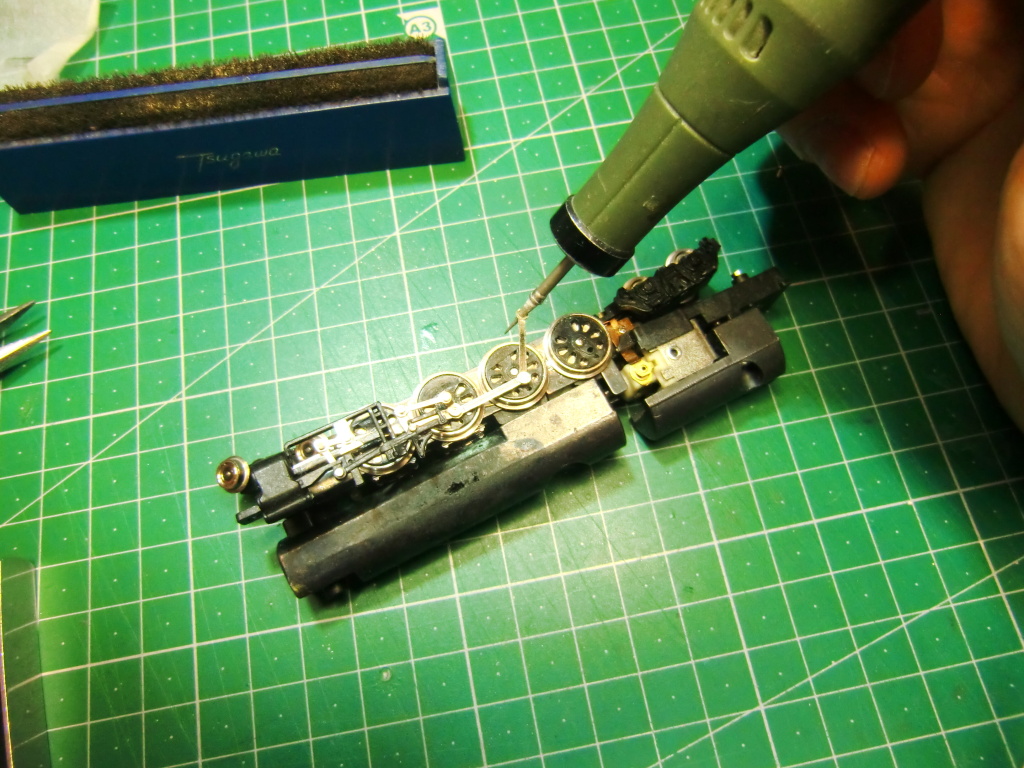
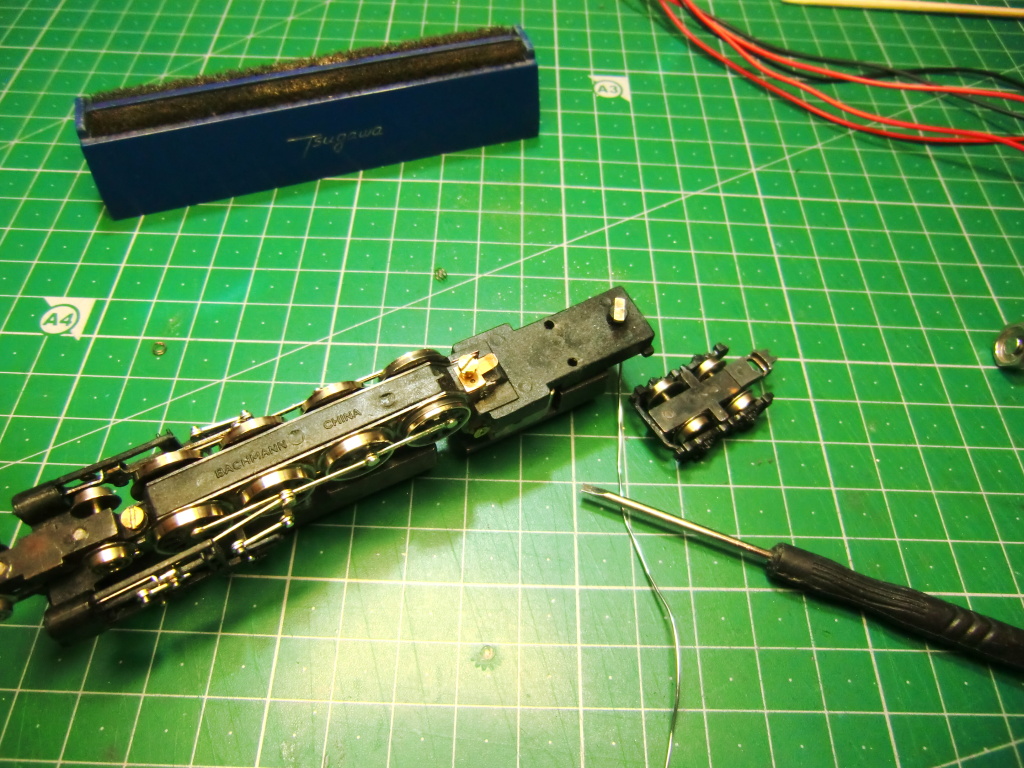

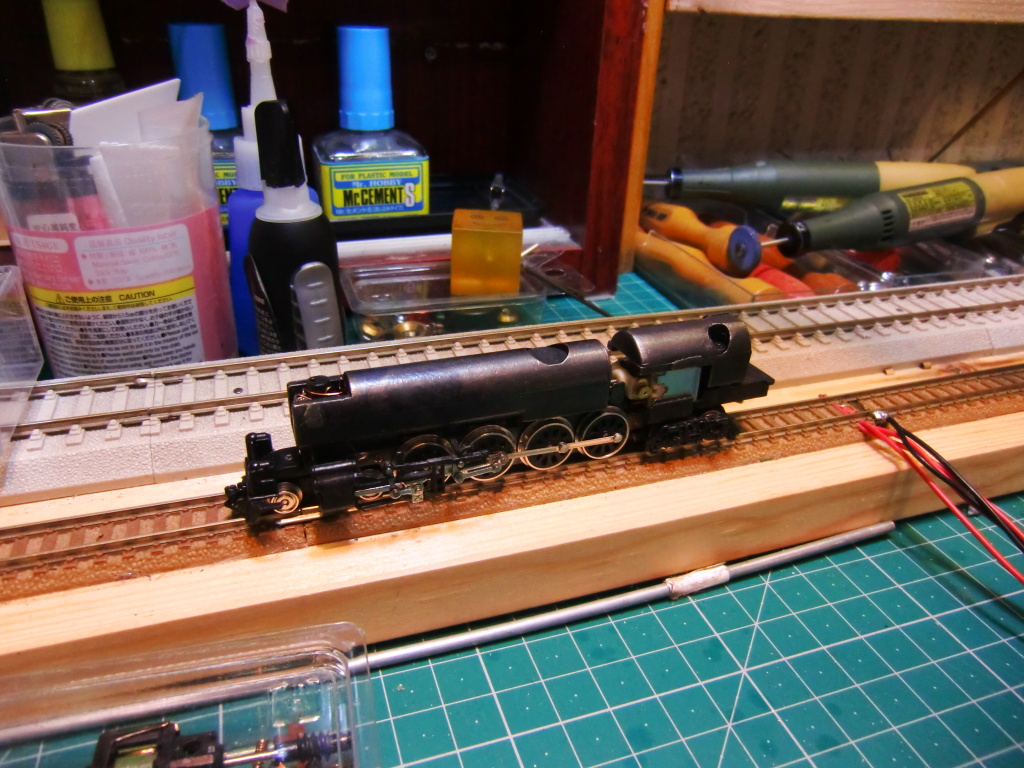

ようやく、走行できるまでに至りました。今回の作業では、破損したギアを交換すれば完了といった単純なものではありませんでした。
それ以外のパーツも歪みが出ていることで、回転が不安定となりこの歪み対策に難儀しました。そこで歪み分を吸収できるように各車輪に特殊な加工を施して、回転テストを何度も繰り返すことで、ようやく走行できるまでに至りました。ここまで難航することは珍しく、過去の作業でもあまり例がありません。神調整が必要な車体でした。



長期戦となってしまいましたが、ようやく作業完了でございます。従来の修理内容とは大きく異なり、大変勉強になる車両でございました。今後の修理作業に活かせる濃い内容の作業でした。
Zゲージの修理依頼は初めてとなります。とにかく小さいので難易度はNの比ではありません。しかもメルクリンの蒸気機関車です。
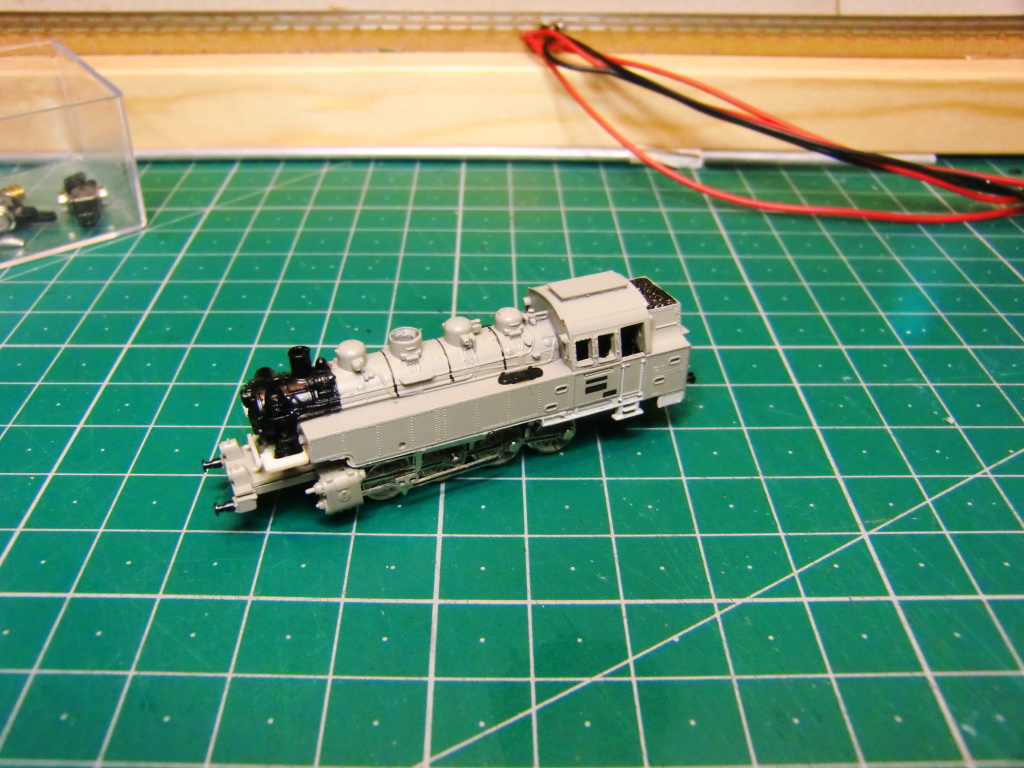
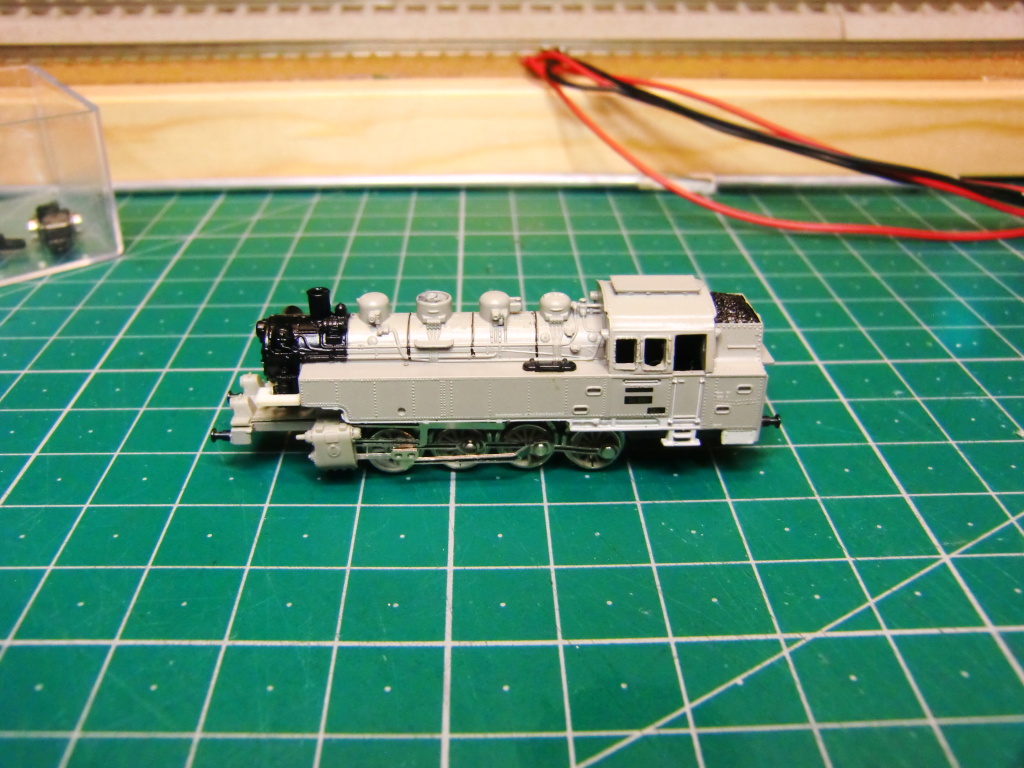
まず、現状ですがモーターが回りません。さらに分解していくといくつかの問題を抱えていることがわかりました。
まずモーターを取り出して単体でテストを行いましたが、どうやら内部で断線しているようです。このモーターはもう使えません。
また、分解することを想定していないため内部のローターを取り出すことができません。
次に、動輪の回転テストですが所々ひっかります。そこでギアすべて取り出して、確認してみたところモーター側に伝達する中間ギアの形状が変わっていることが確認できました。そこで、全分解して問題のギアを取り出し、精密ヤスリを使ってピッチを研ぎ直してスムーズに回るまでこの作業をひたすら繰り返します。ちなみにギア自体も非常に小さいため、至難の業です。
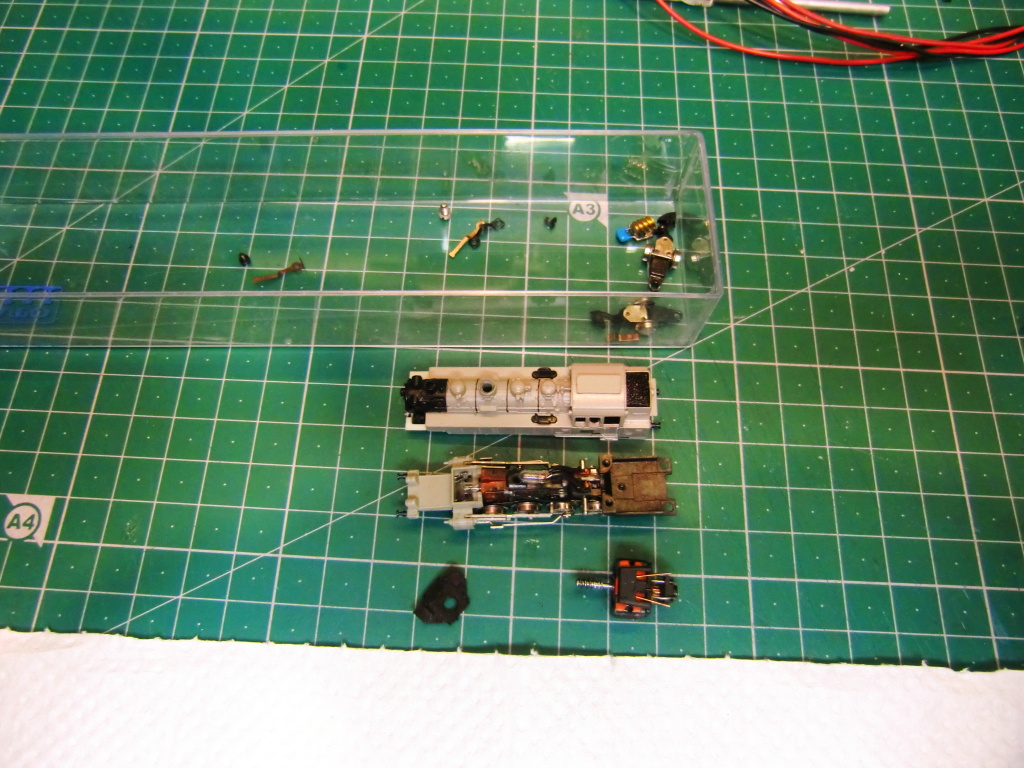
この作業だけで、半日を要しました。そして、各動輪のバランスとりに数時間。ようやく、すべての動輪がすべてスムーズに回るようになりました。
恐らく、これが原因となって車輪がロックした状態で、高い電圧をモーターにかけたことで大きな負荷がかかり、内部のコイルが焼けたのだと思われます。
次はモーターですが、復活不能で既にモータはお亡くなりになってますので、代用できそうなモーターを探して組み込むわけですが、当然そのままでは取り付けできません。
まずは、肝心のモーターですが12V仕様の超小型モーターが1つ出てきたので、これが使えるか試してみます。サイズ的には問題ありませんが、トルクがどこまであるかです。
▼軸径の変換
モーターシャフトとウォームギア内径の変換パイプを作る必要があります。「軸径:1.0 -> 1.5」
▼もう一つの選択
超小型モーターを調べる中で、ワールド工芸「#1011WSB-S」がサイズ的には入りそうです。上記のモーターが難しい場合は、こちらのモーターも選択肢に入れておきます。
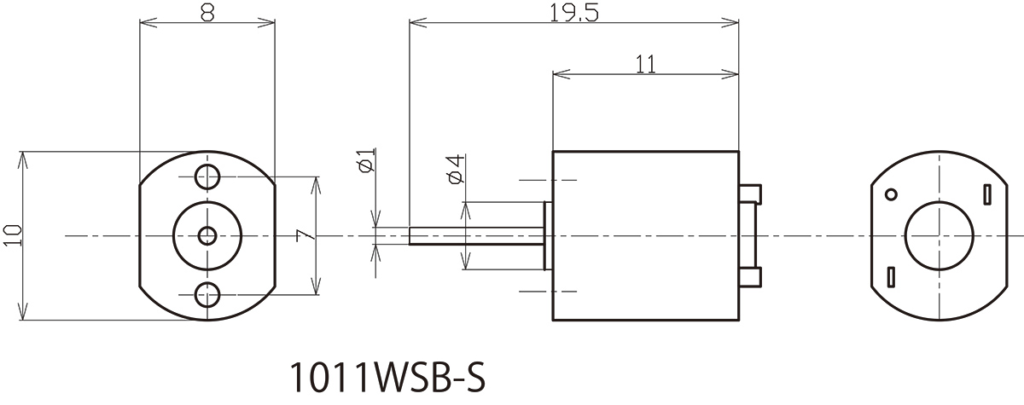
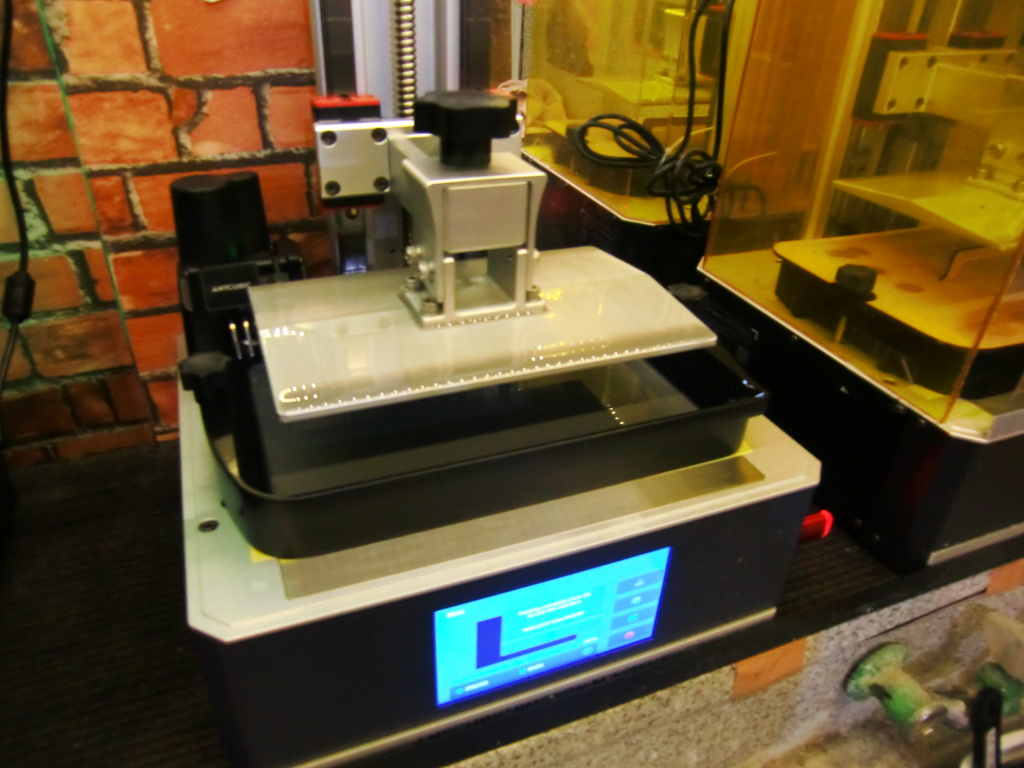
3Dプリンターで「外形:1.5mm/内径:1mm」のパイプを作ります。

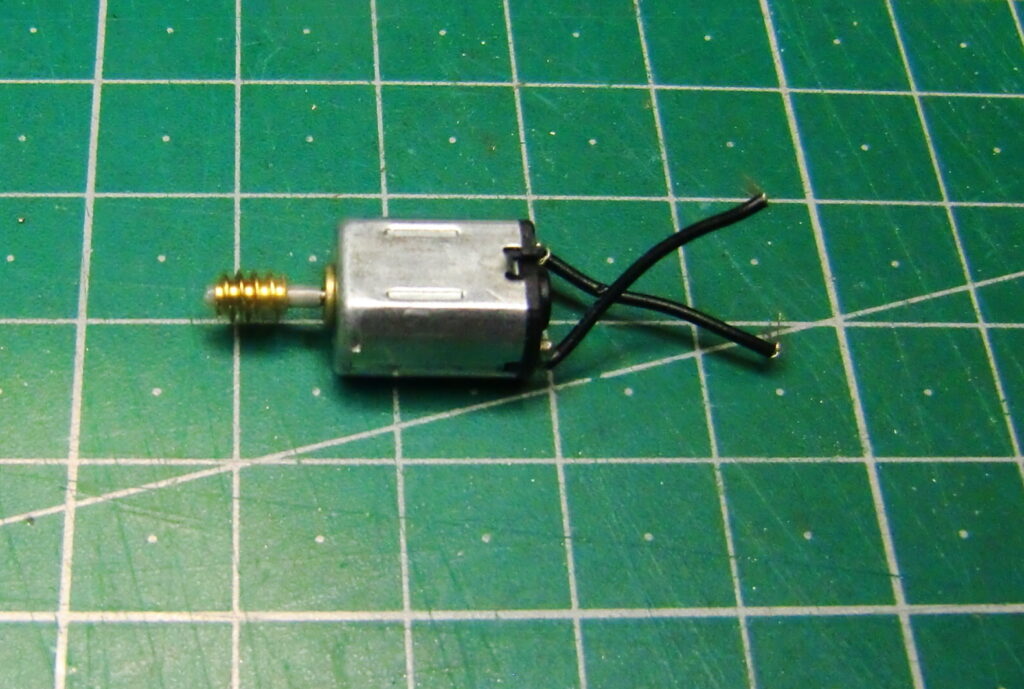
なお、ここまで小さいウォームギアは当店のストックにはなかったため、知り合いのお店さんより数個ほど分けていただきました。モーターについては、ワールド工芸と同等サイズのものが1つ見つかりましたので、そちらを使います。それでは早速組み込んでテストしてみます。
中間の伝達ギアとの絶妙な高さ調整が求められます。わずかにずれると抵抗が大きくなりスムーズに回らなくなるので、ここでもしっかり時間をかけていきます。
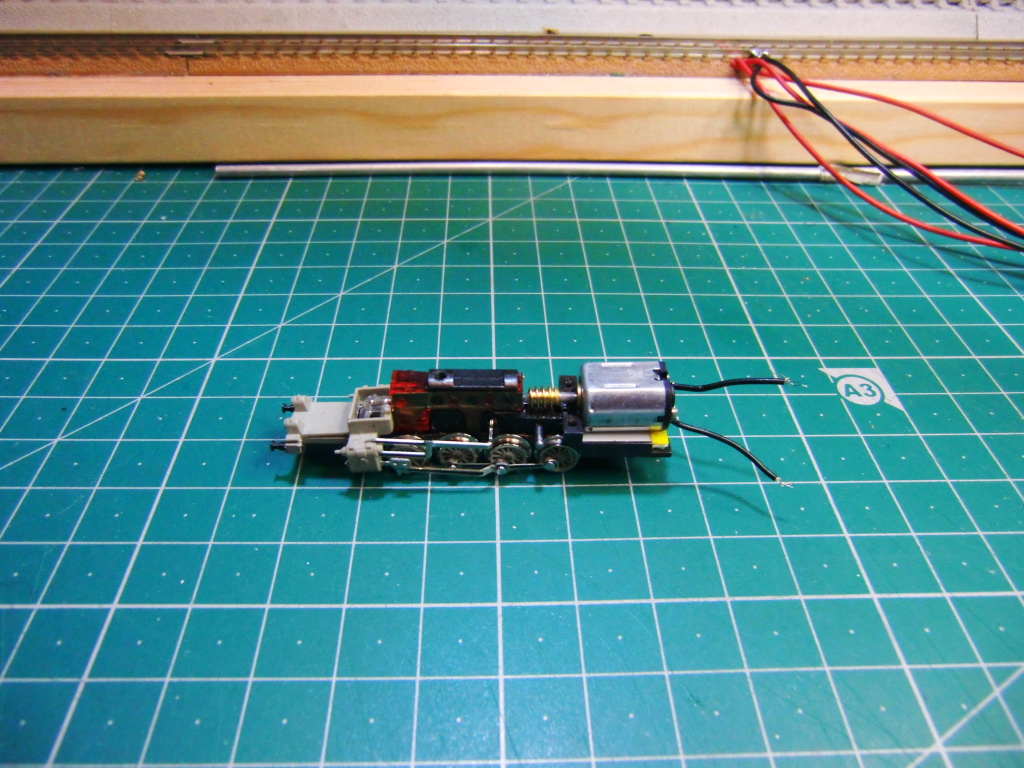
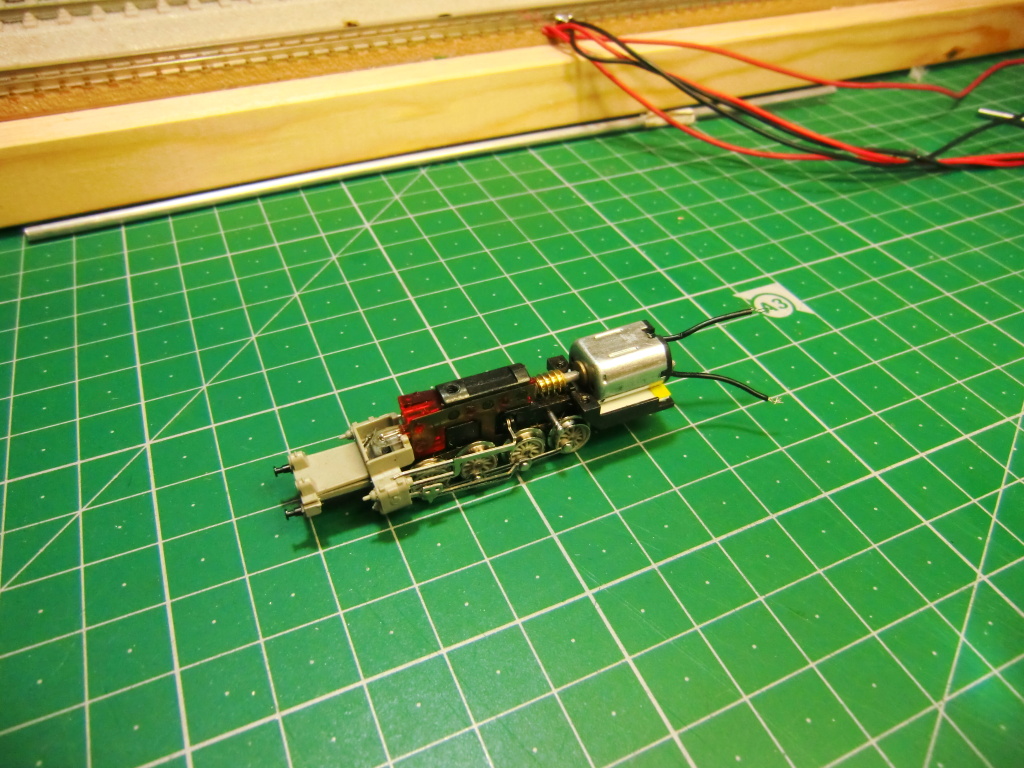
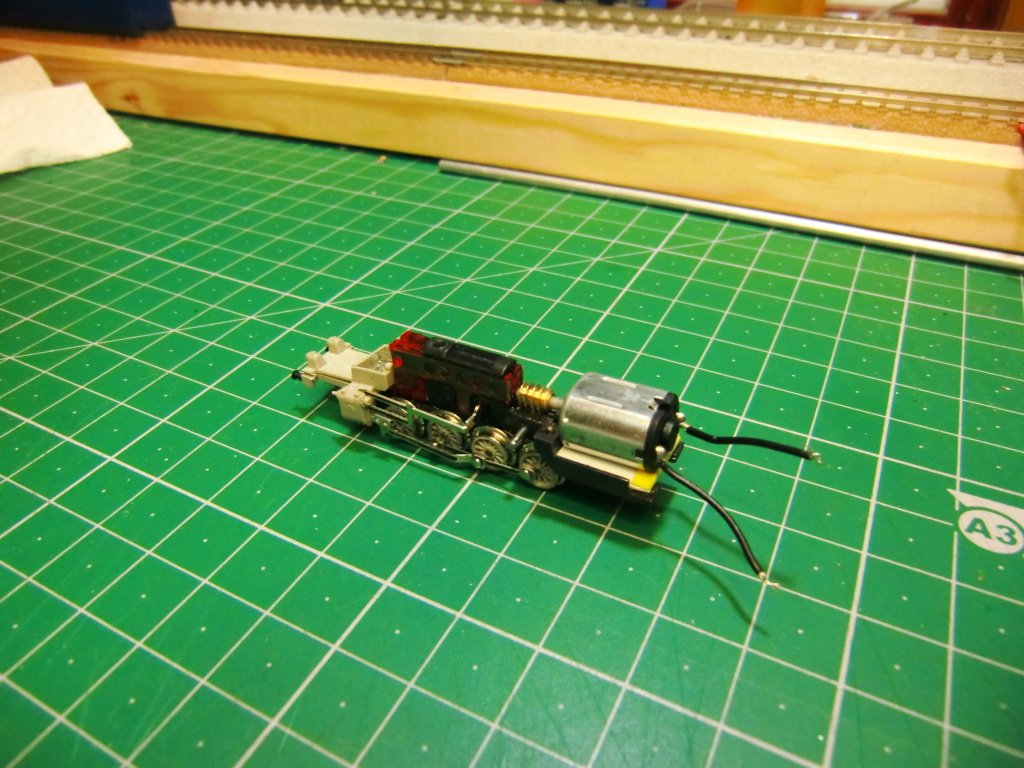

高さ調整のため、t1.0のプラバンを下に置き、後部にt0.3のプラバンを配置して絶妙な位置で固定します。回転テストでは大変スムーズな車輪の回転を確認できました。次に抵抗を接続して電流量を調整します。
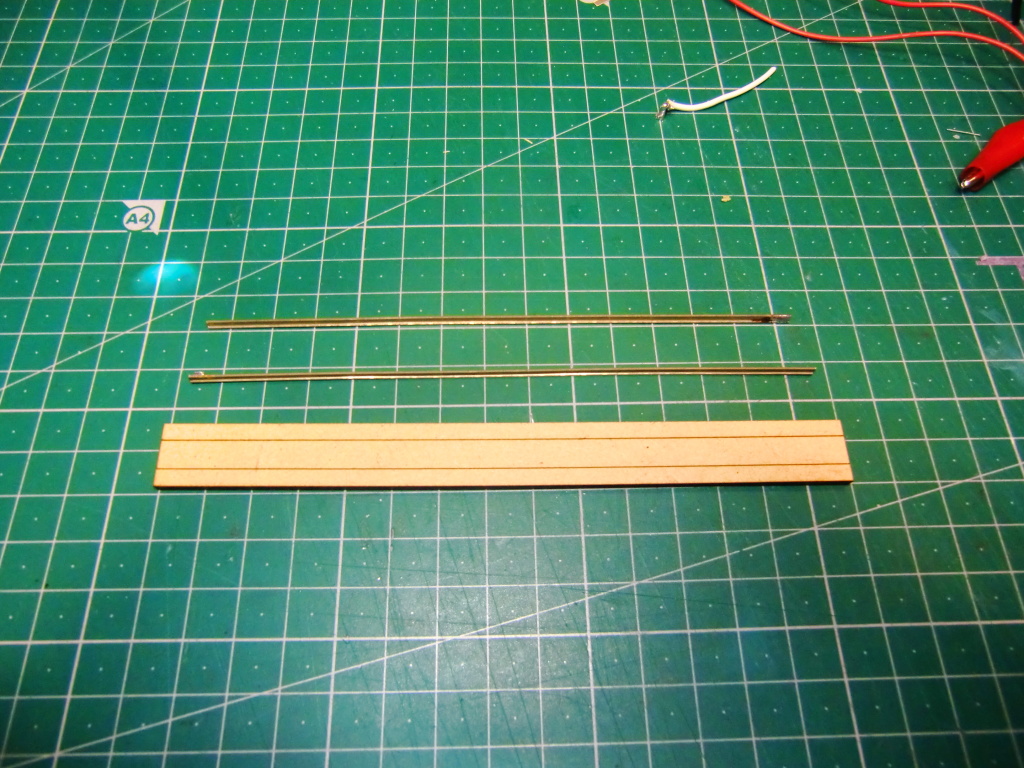
Zゲージ(軌間:6.5mm)のレールが無いため、急遽N用フレキ線路を加工してテストレールを作ります。
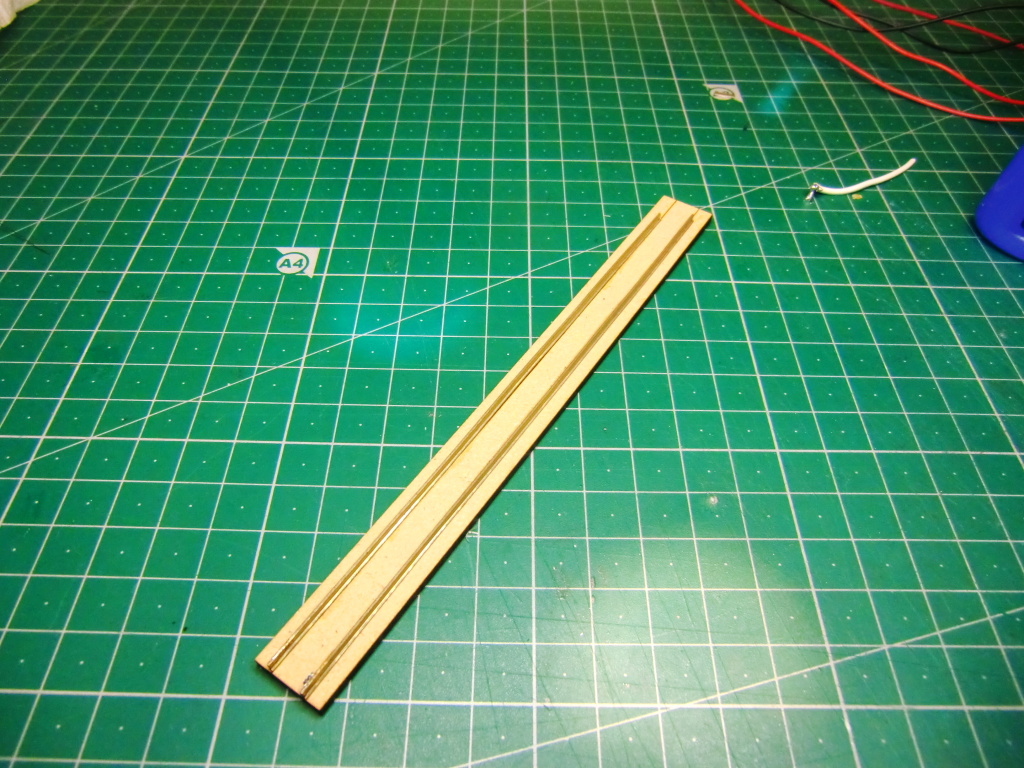
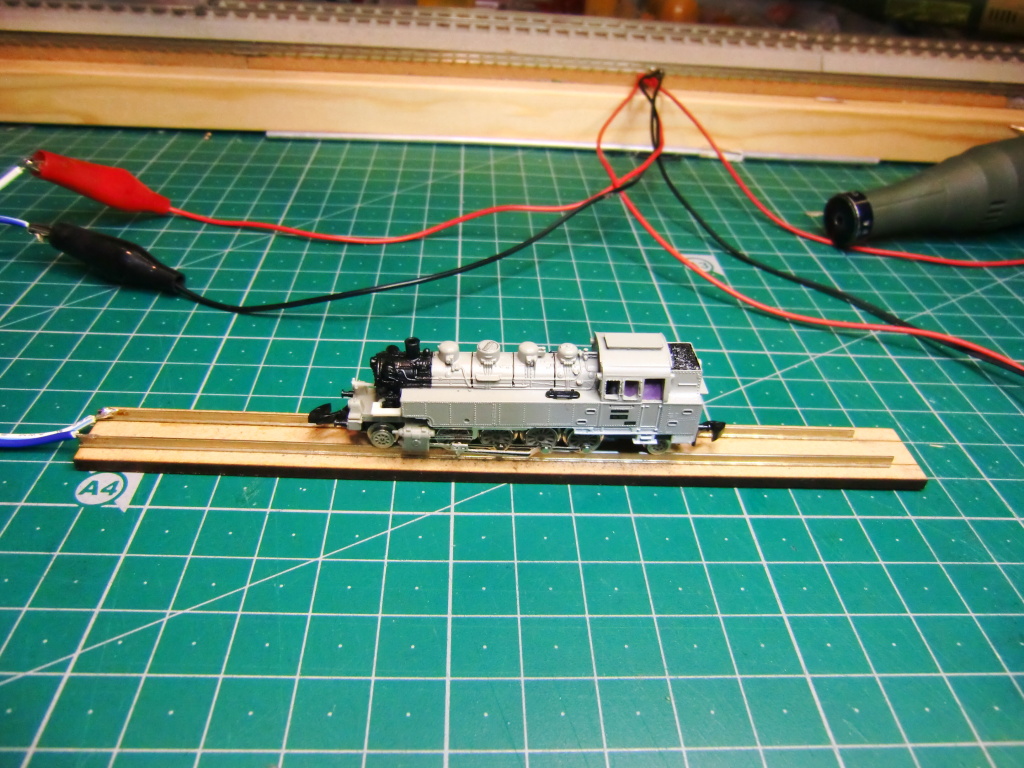
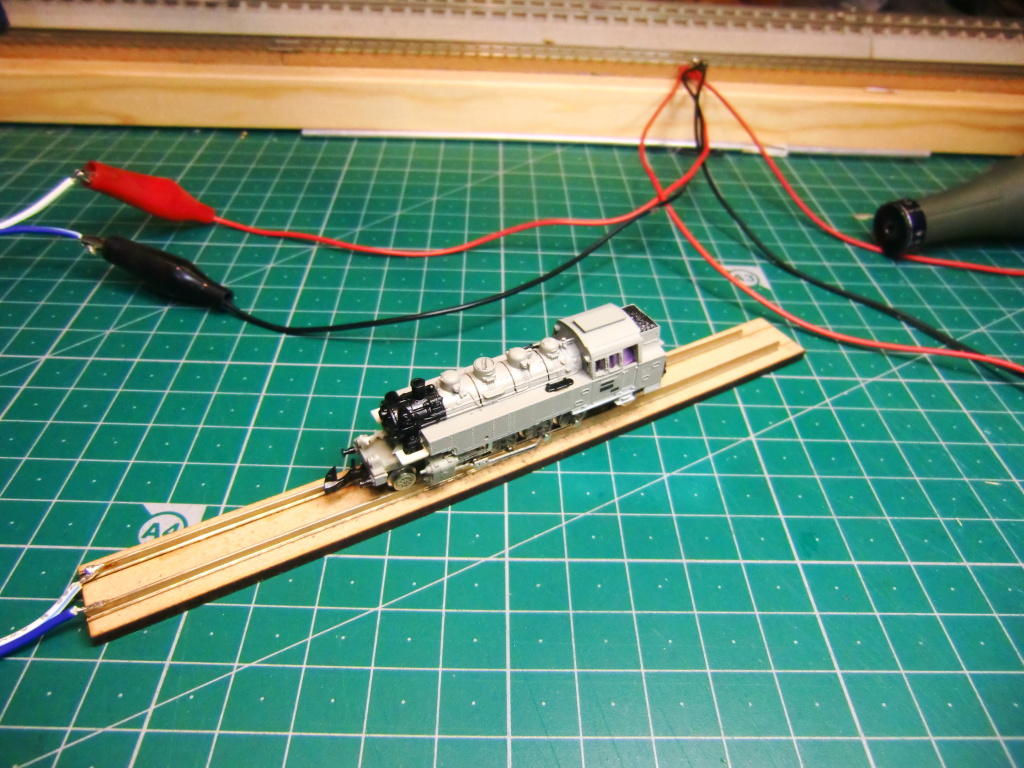
調整とテスト走行を幾度となく重ねて、ようやく動きました。ライトもLED化され、低速時でも明るく点灯します。作業完了でございます。

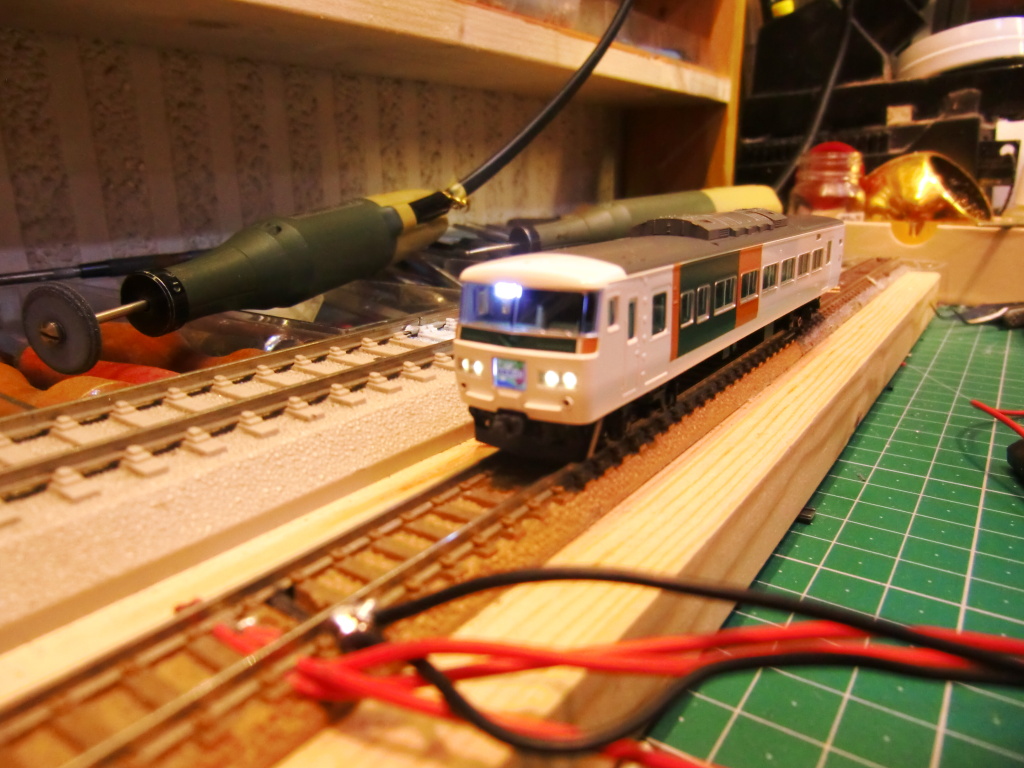
現状はかなり暗くなっているようです。
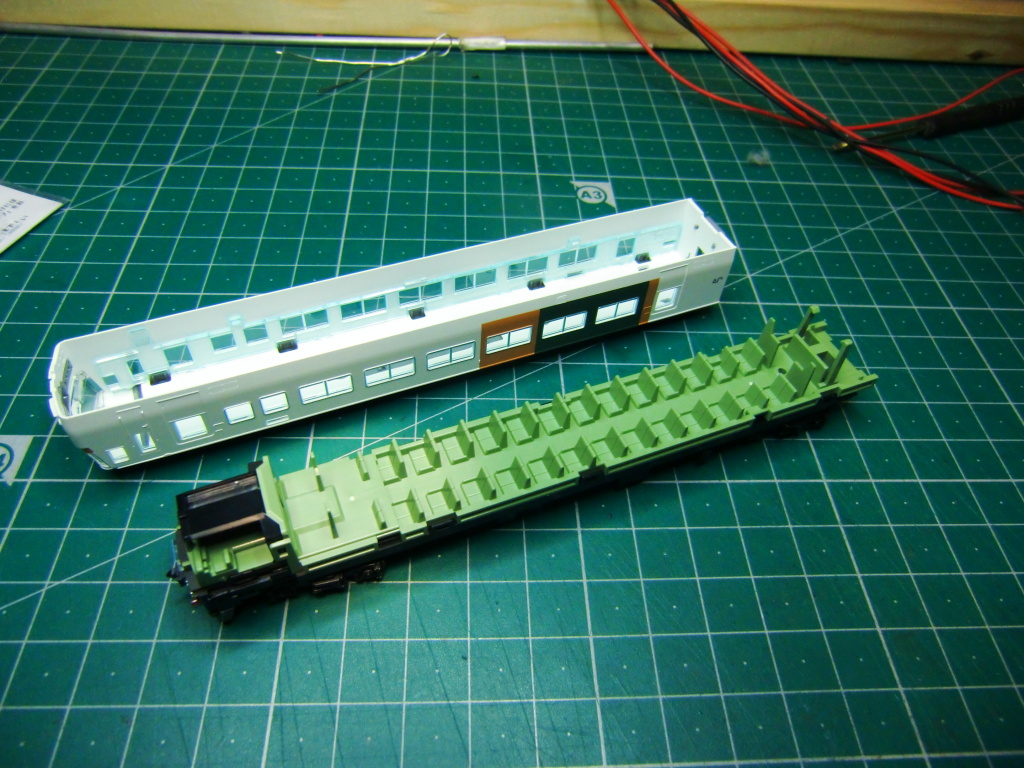

ヘッドマークの部品を取り出して、印刷された部分を削ります。

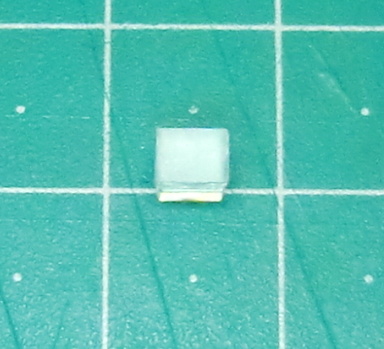
右が削ったあとです。

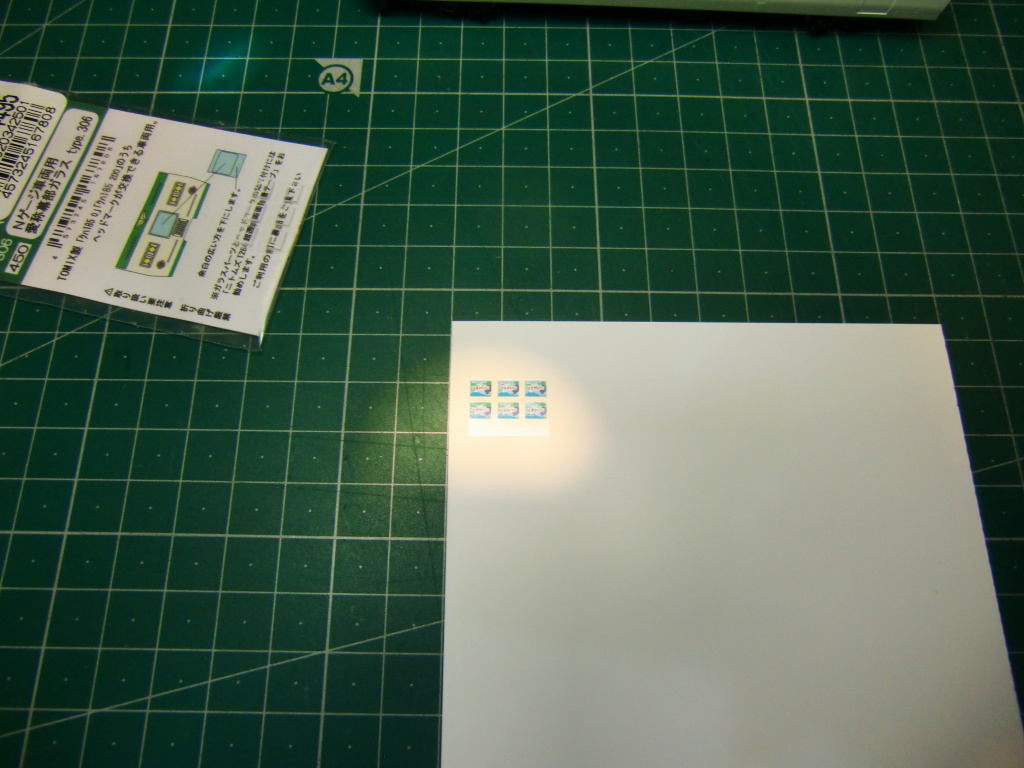
今となっては非常に入手の難しい貴重なシールに印刷を行い、さらに表面に特殊な処理を施して、高光沢仕上げとしております。

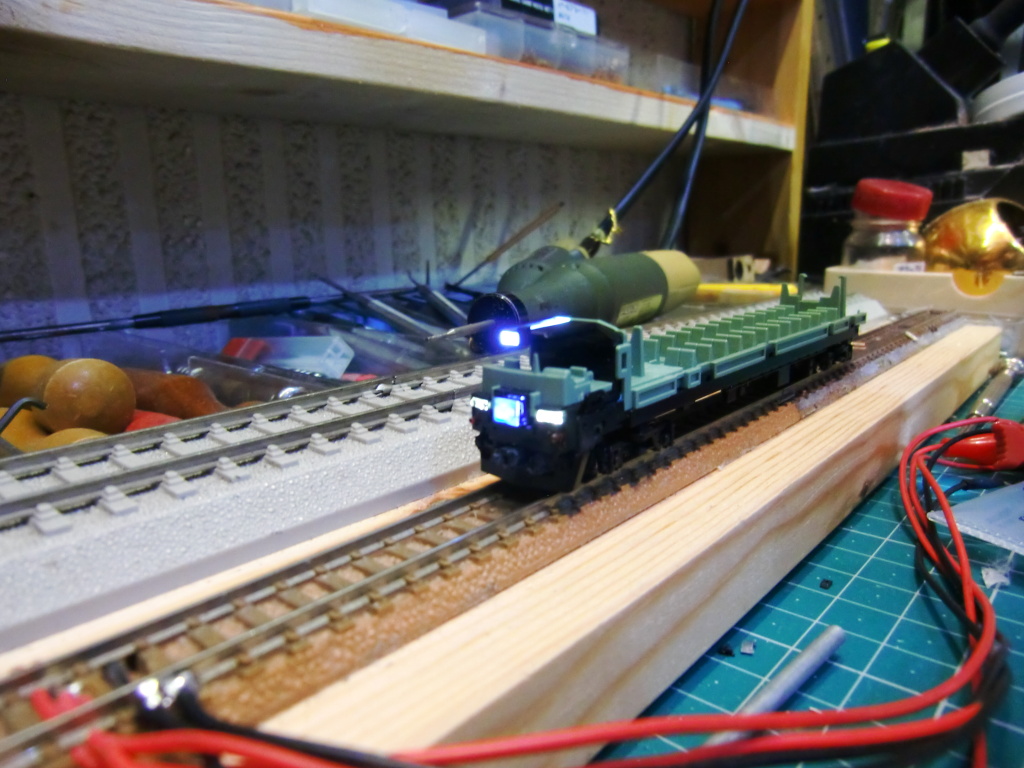
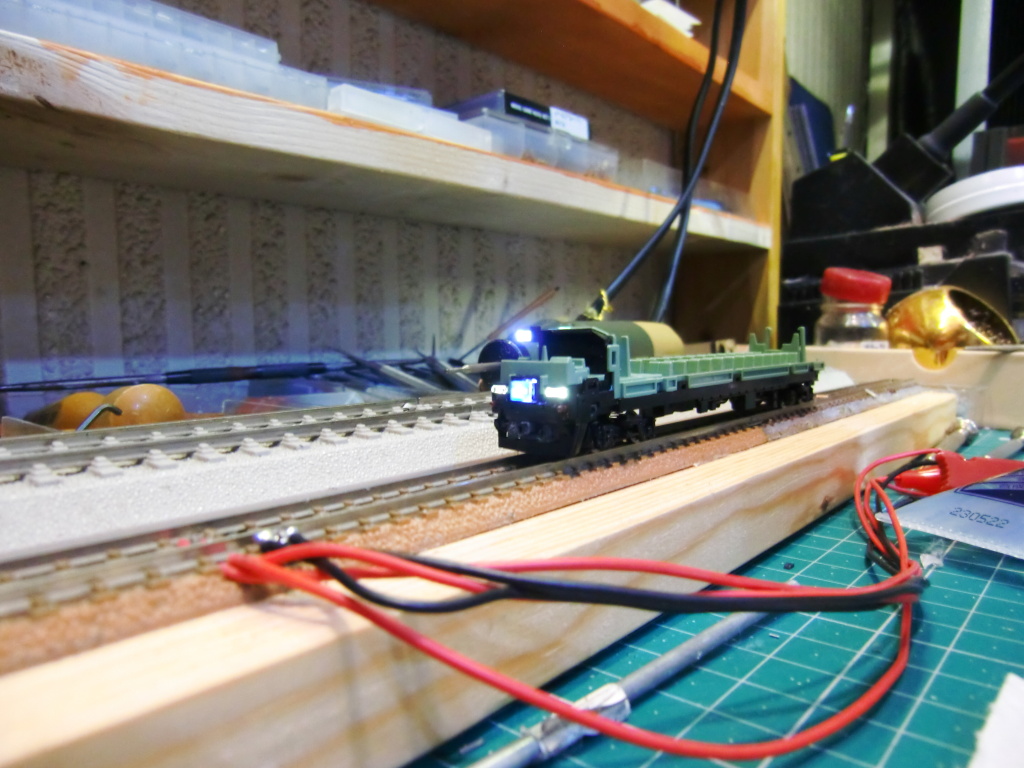

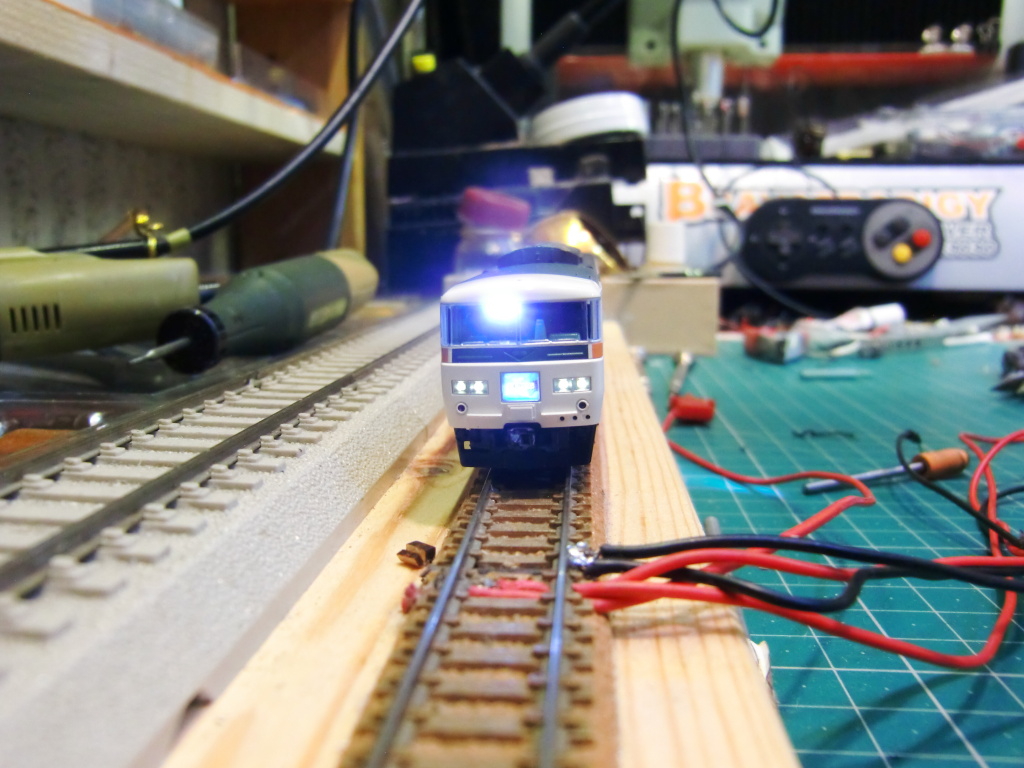
▼窓埋めと座席撤去
今回は、窓のパテ埋め処理ではなく塗装のみで行います。まずは車内の座席を撤去するための加工を行います。
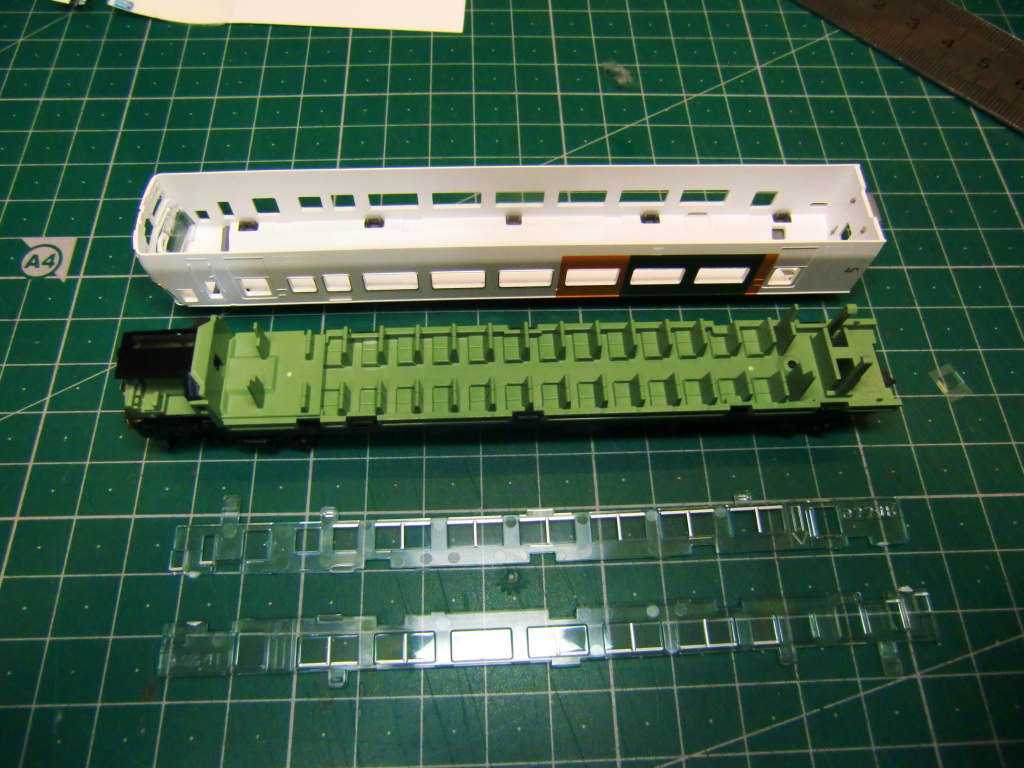
最前列の座席をカットしていきます。
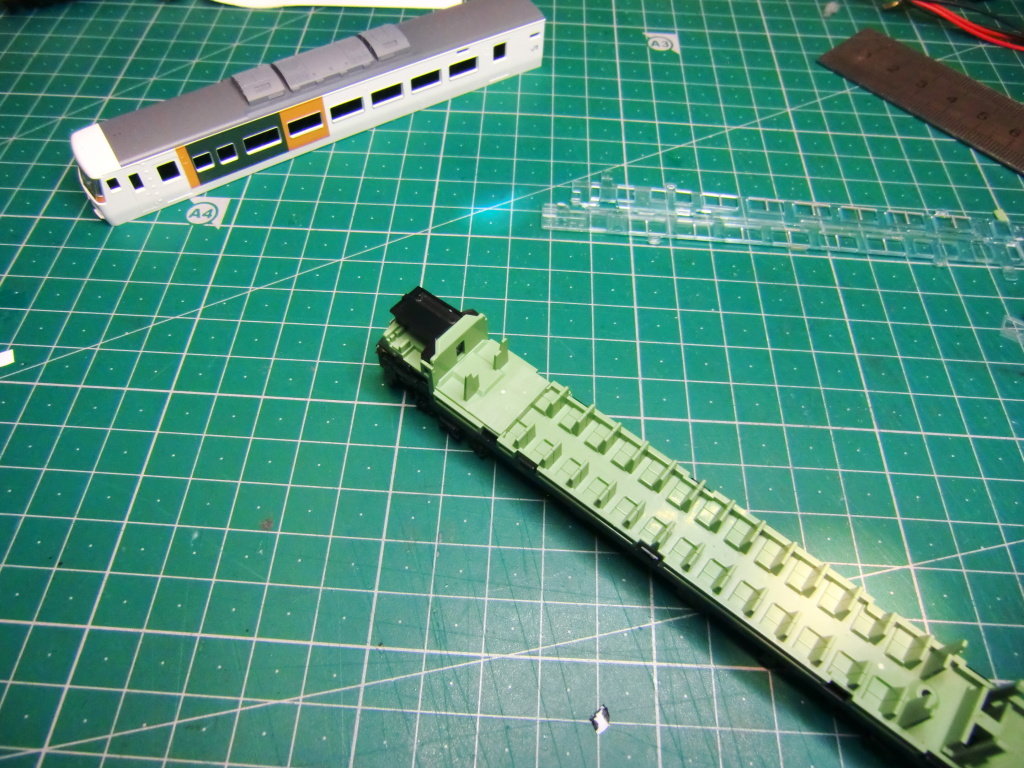
まずはニッパーでカットした後、ルーターで処理を行い最後に1500番ペーパーで丁寧に仕上げていきます。
次に窓なし風の加工ですが、埋め処理による方法ではなく塗装のみで再現します。まずは、窓枠のシルバーを本体色に塗装します。



窓ガラスと塗装します。


次に窓枠のシルバーを塗装します。
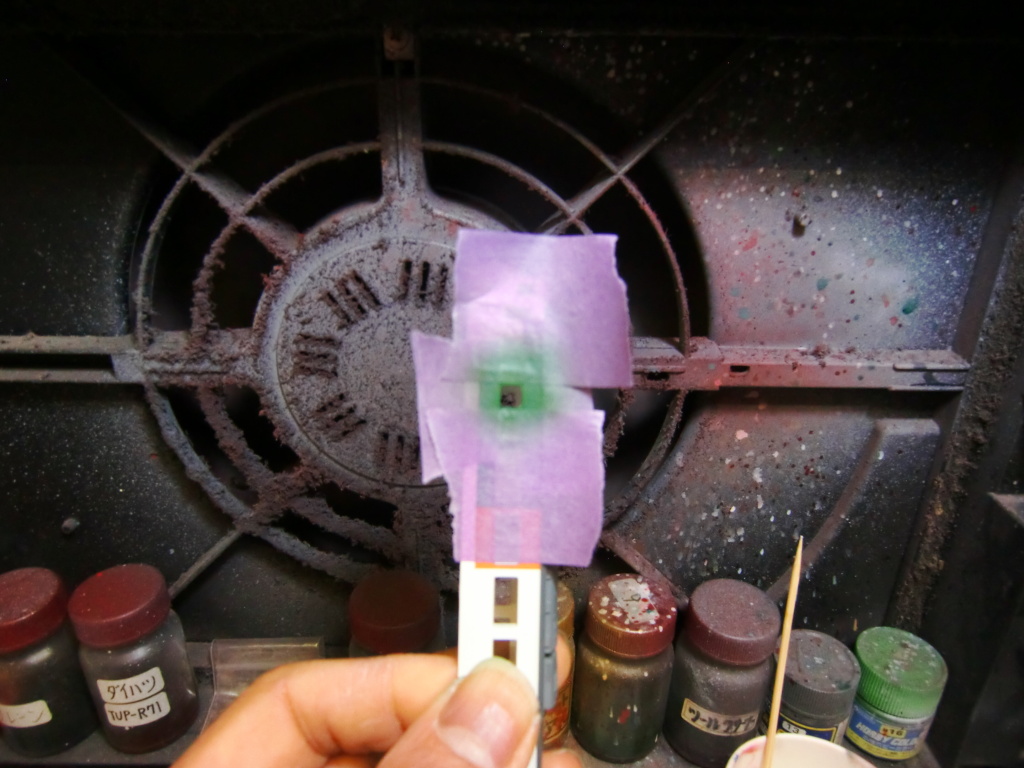
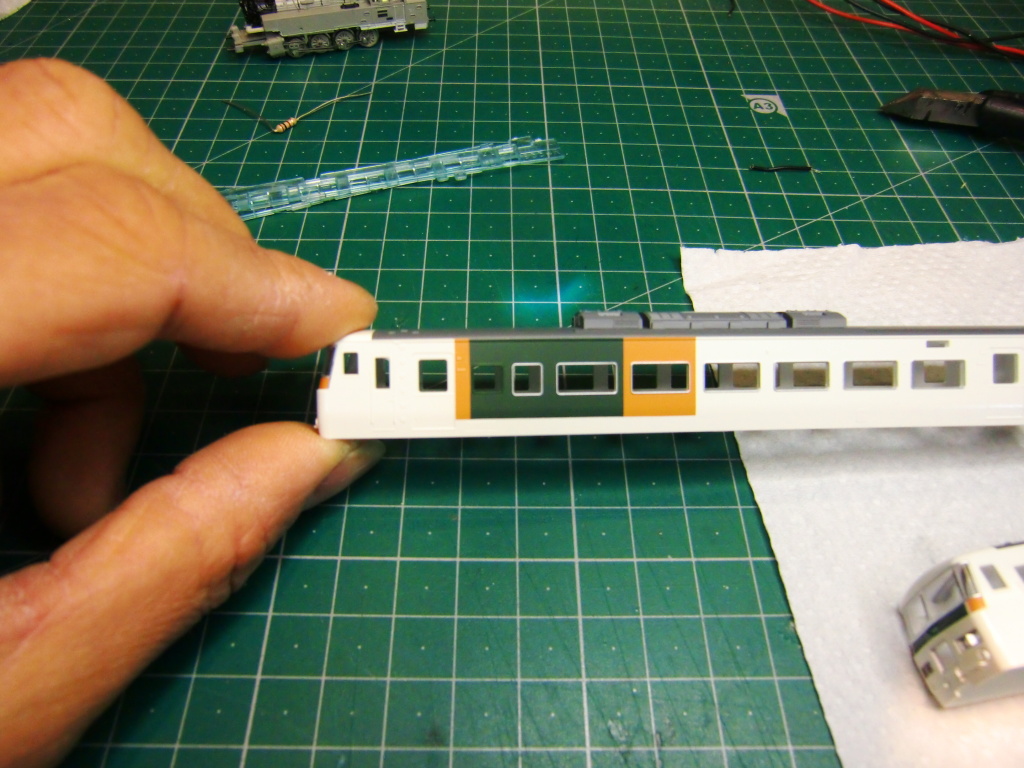
右窓と比較すると、窓枠の塗装前と後の違いがよく判ります。
次に反対面です。こちらは白ですが、若干黄色味を帯びているので、調合して近似色を作ります。

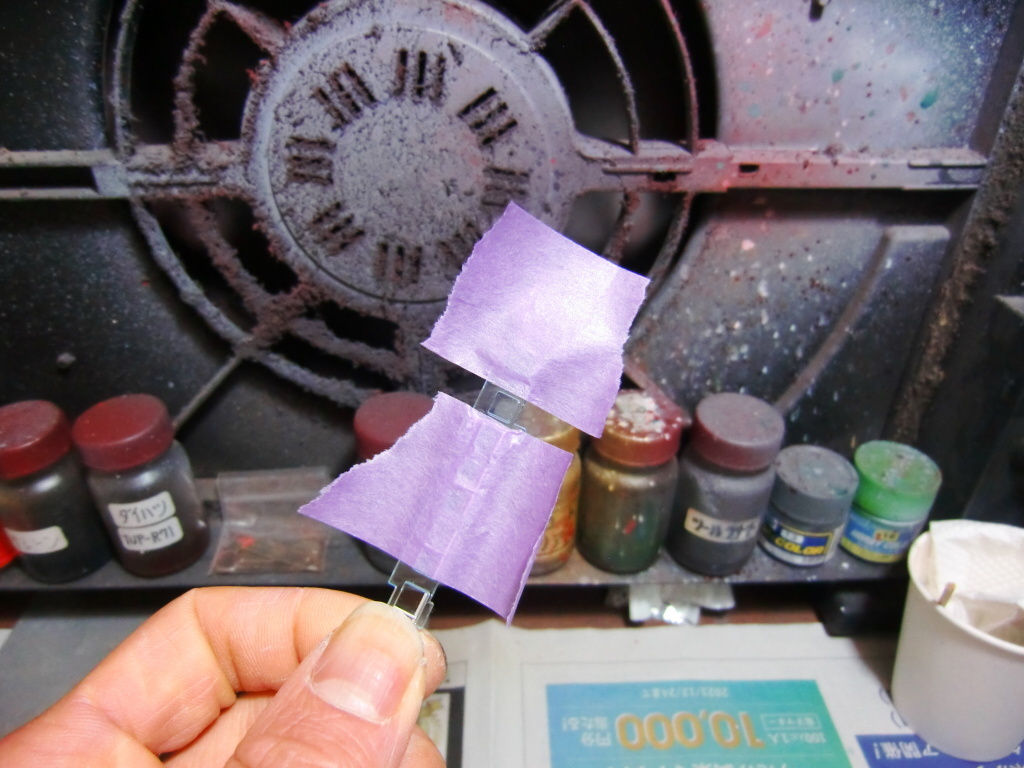
まずは、窓からです。

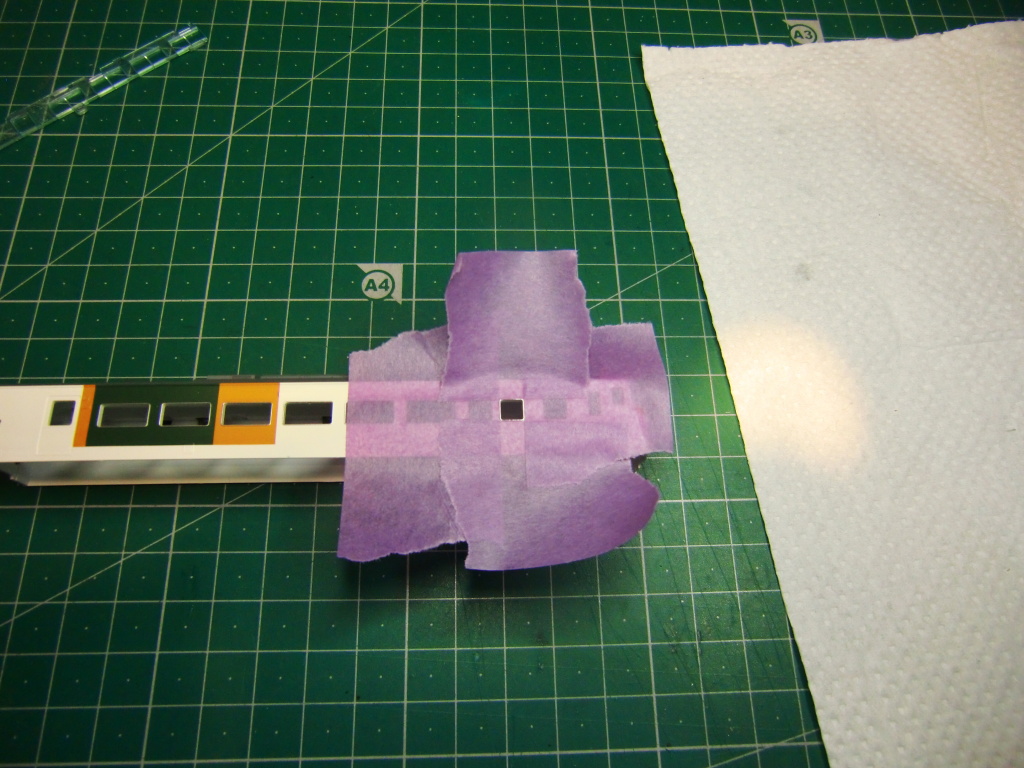
続いて、窓枠を塗装します。
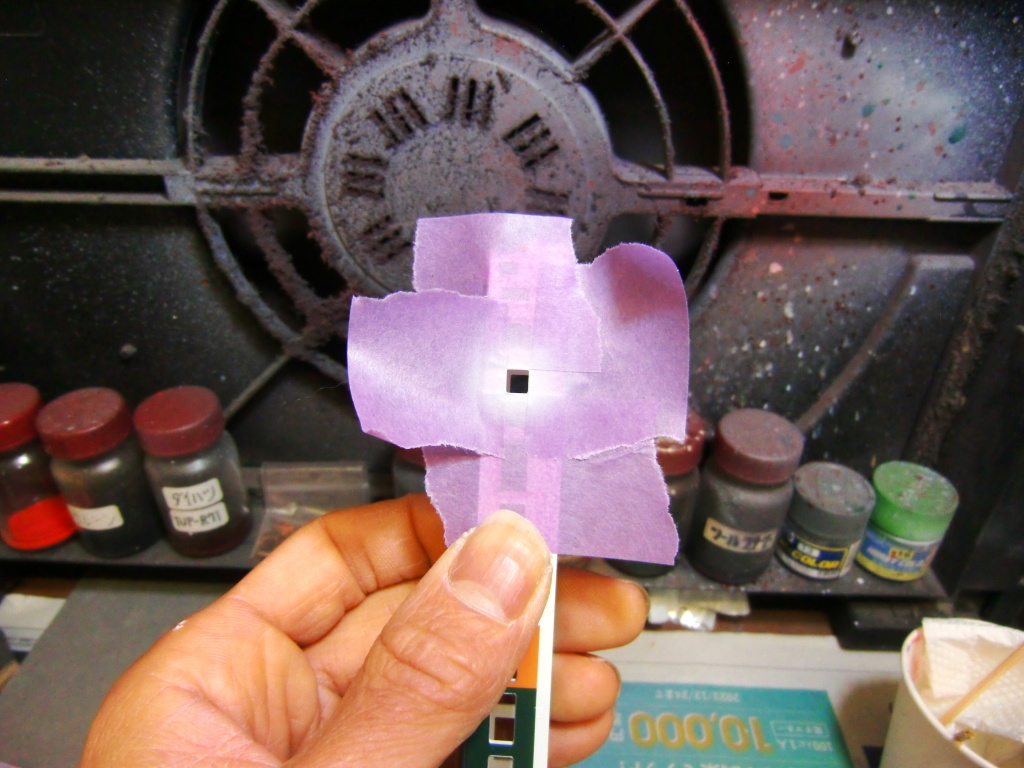

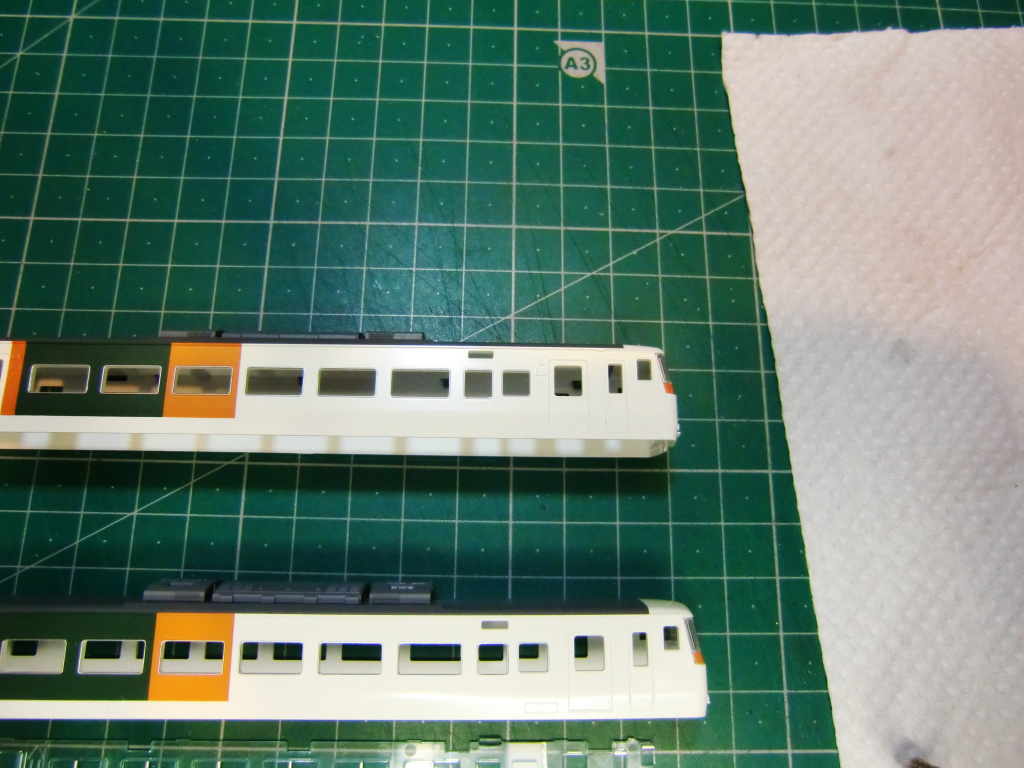
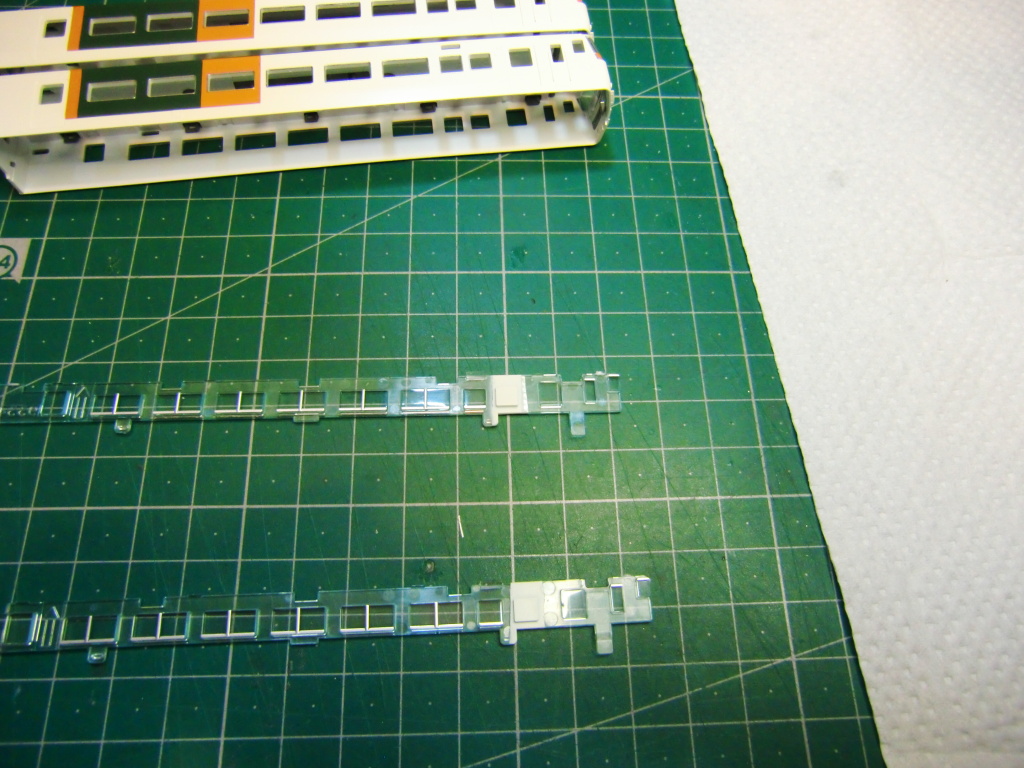
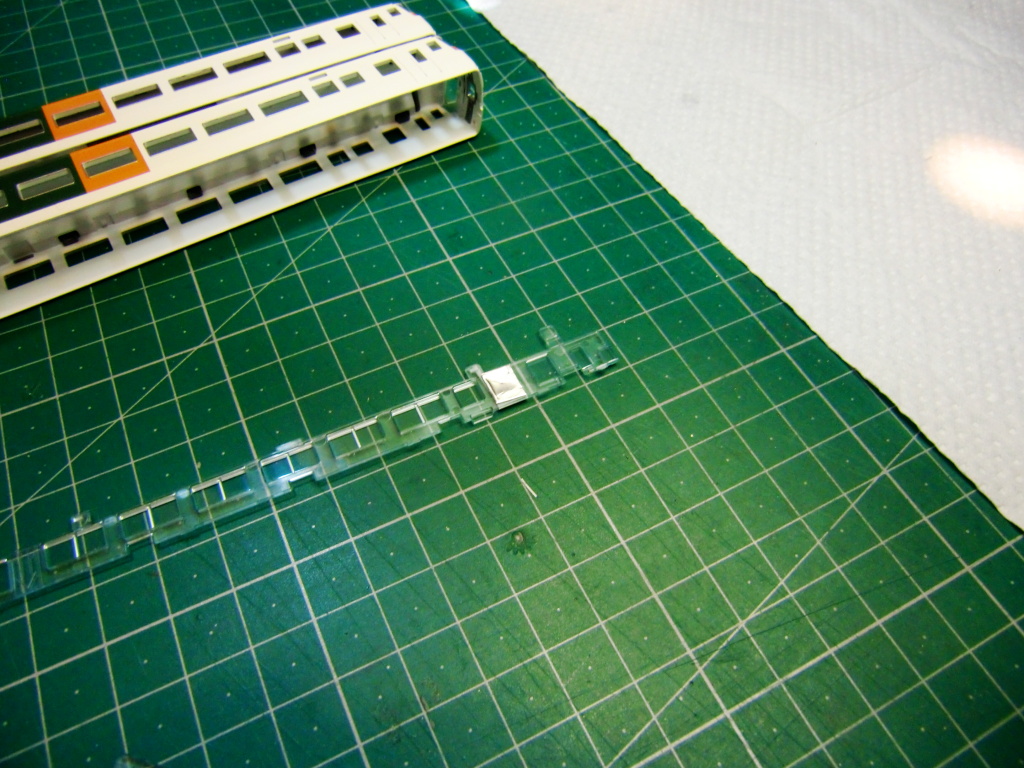
裏面にアルミテープを貼って遮光します。



作業完了でございます。
アクリル製、大型ディスプレイケース高架橋タイプ・・予定価格:165,000円(税込) ※主に新幹線車両を飾るのに適します。
サイズ:幅:750~800? x 奥行:200~300? x 高さ:350? /(mm)
詳細につきましては、今後お知らせしてまいります。
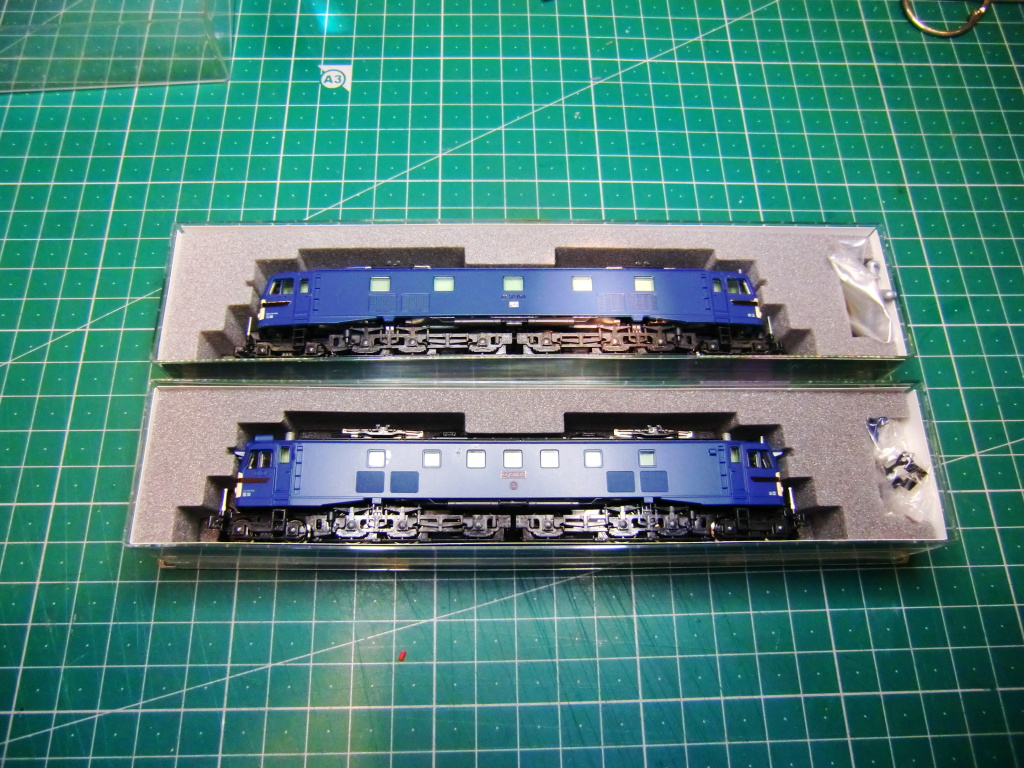
▼先台車短縮加工 ※35/150号機
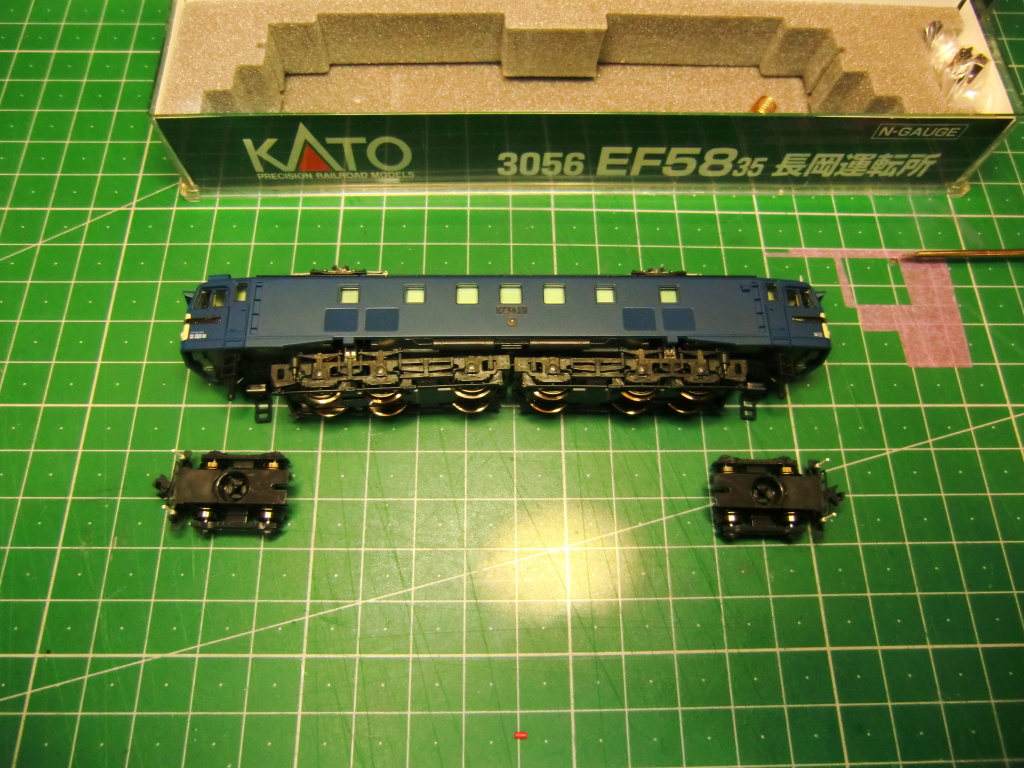
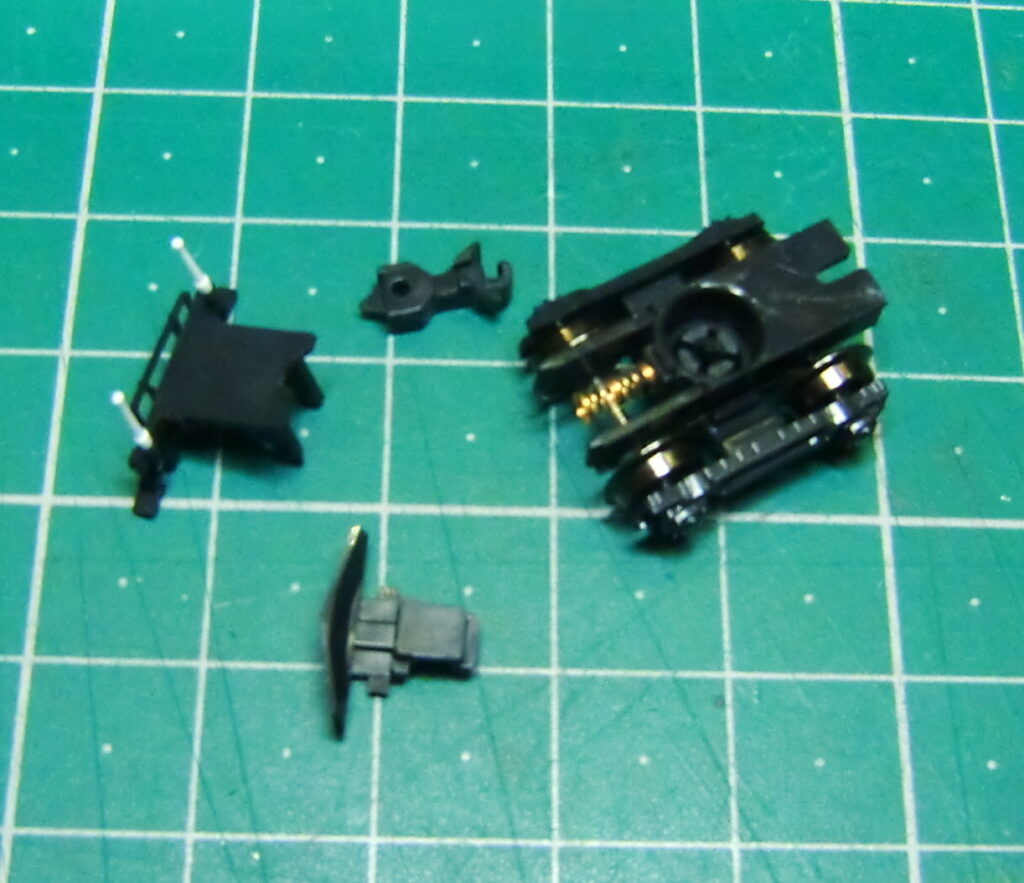

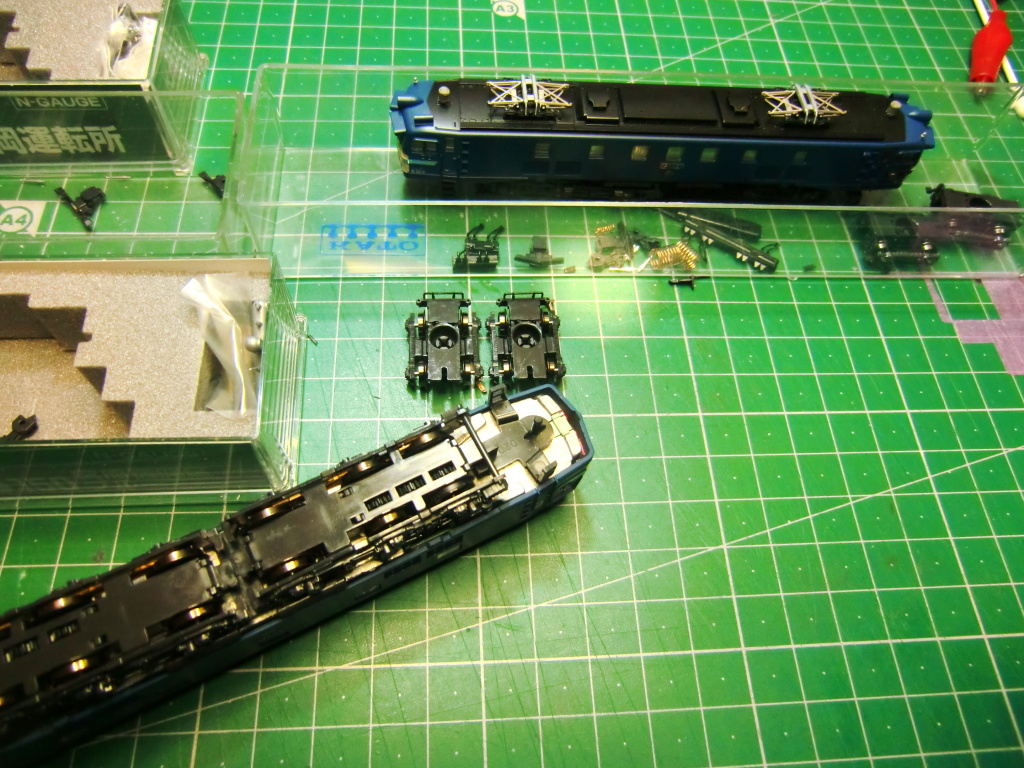
台車の短縮加工が2台とも完了。
▼デフロスター制作+取り付け ※35号機

▼屋根ルーフ裏面加工 ※35/150号機


「内径:幅:22.4mm/高さ:1.0mm」に合わせて透明プラバンを切り出して、裏から固定します。※透明プラ t0.15

▼SGホース設計+取り付け ※150号機
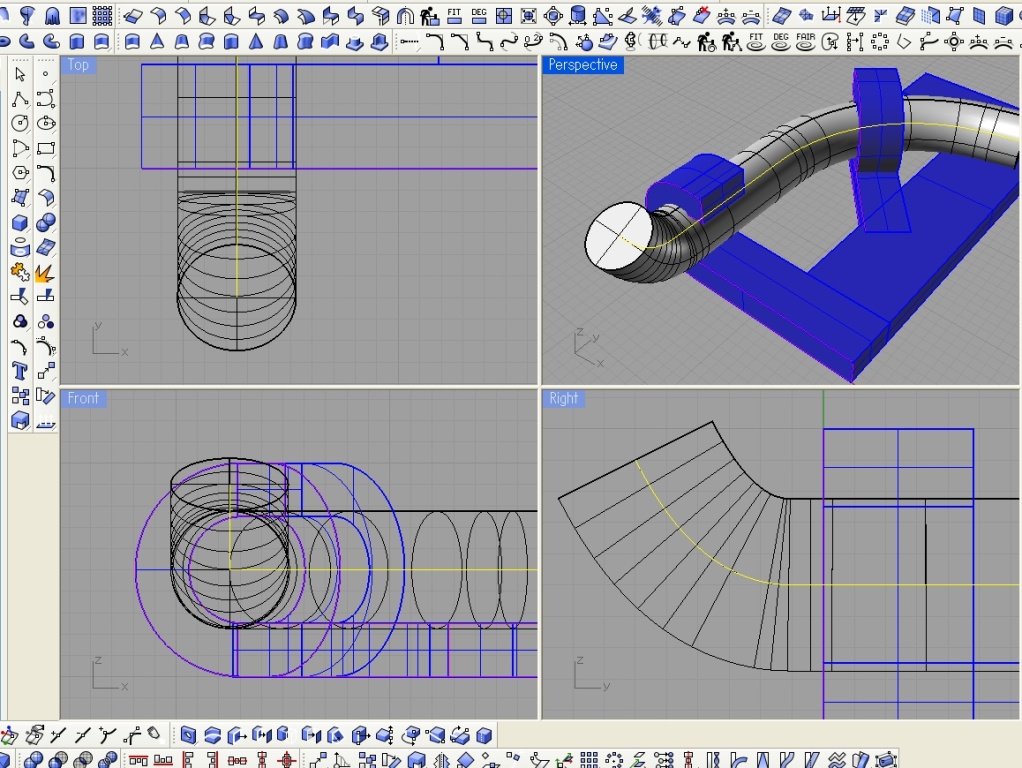
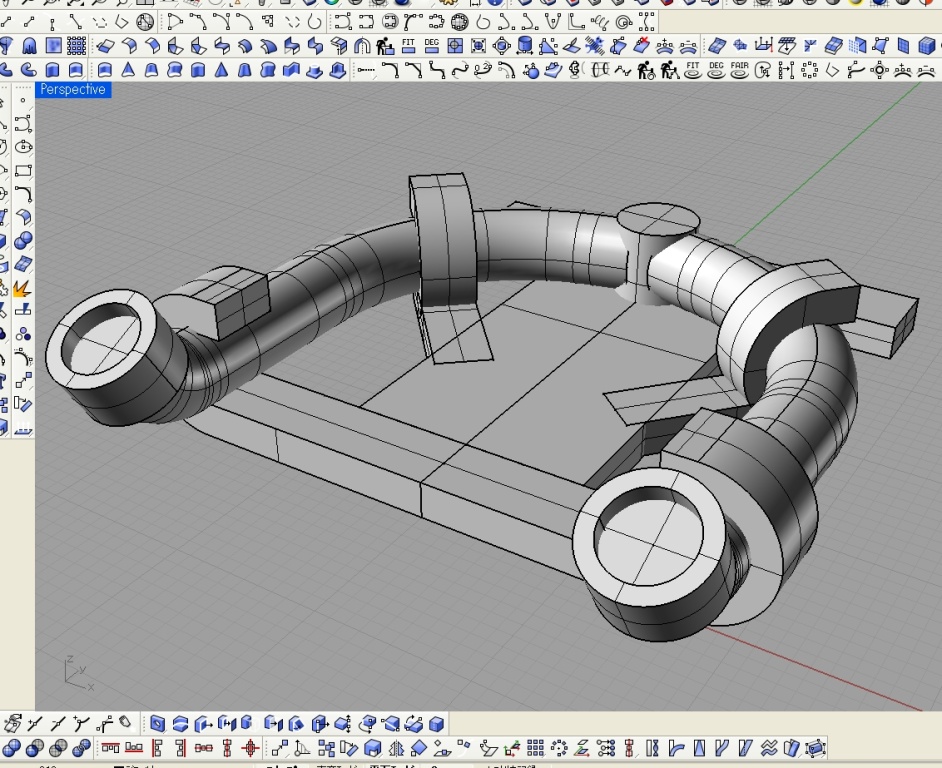
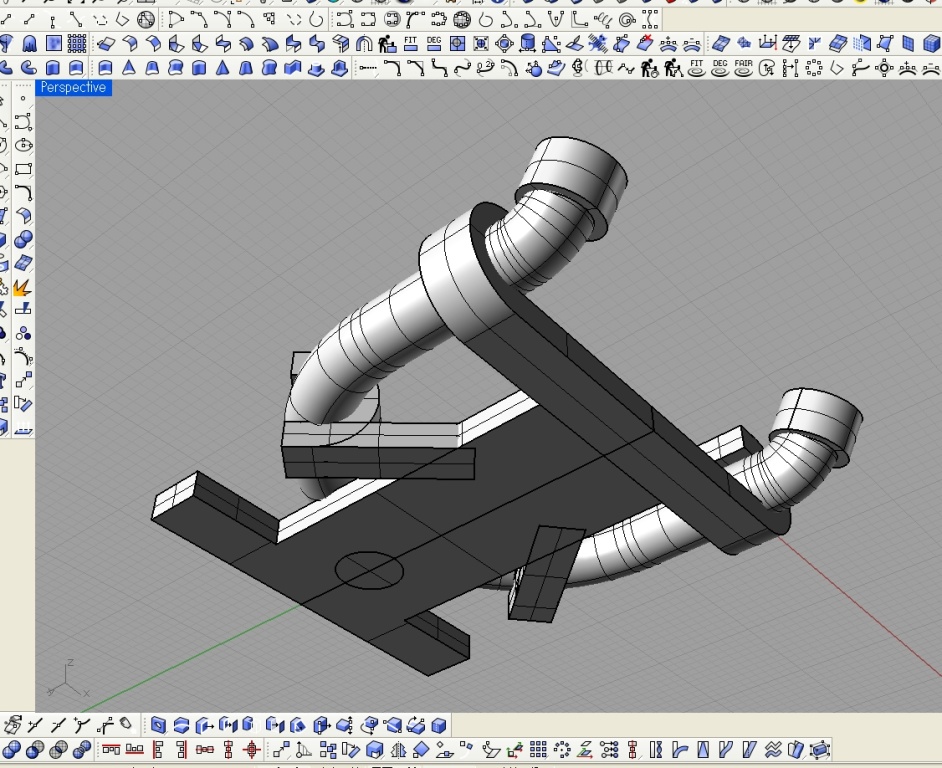
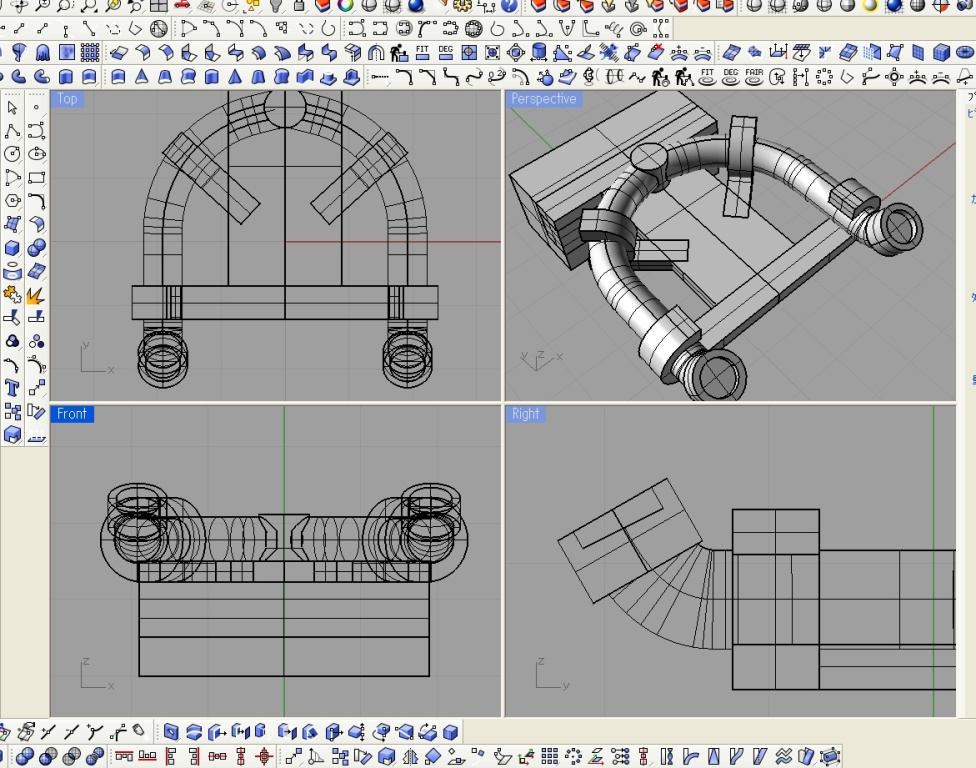
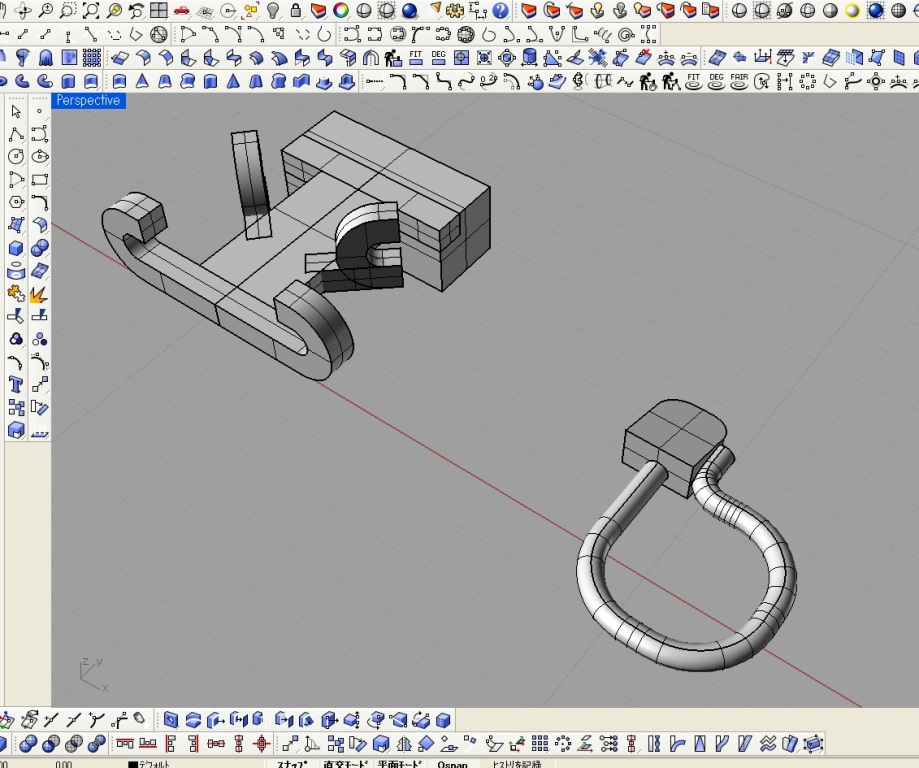
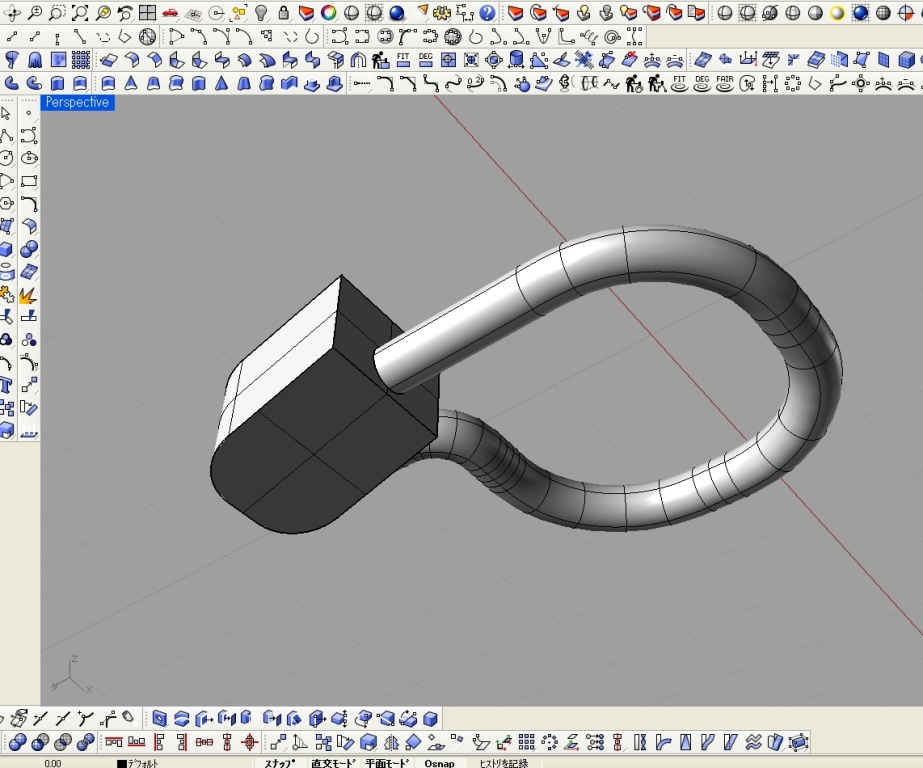
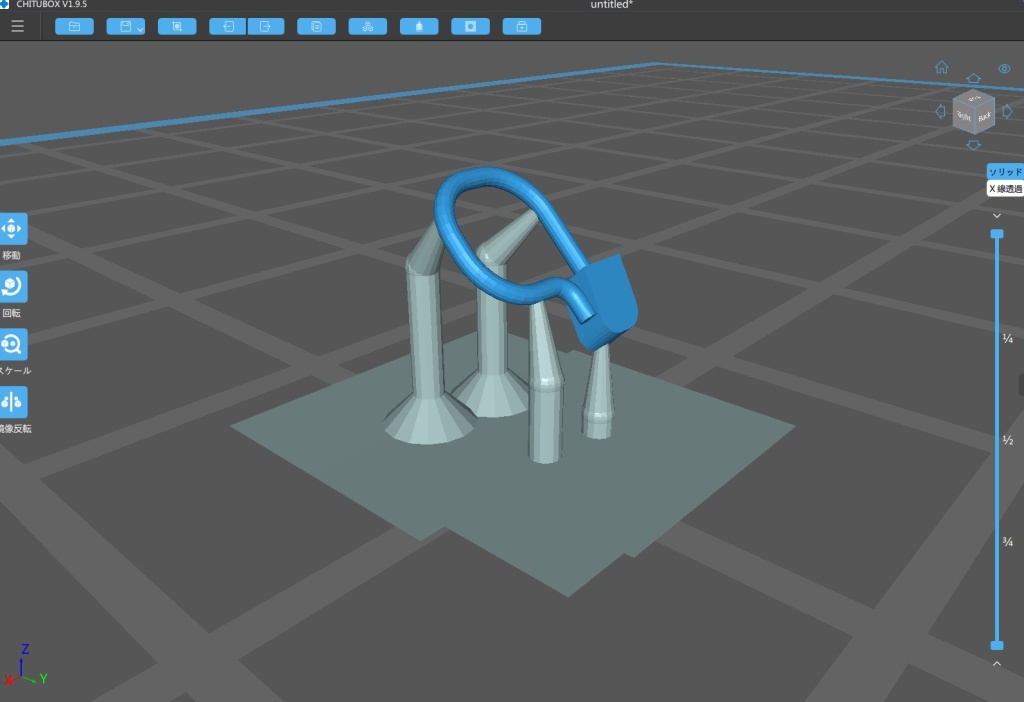
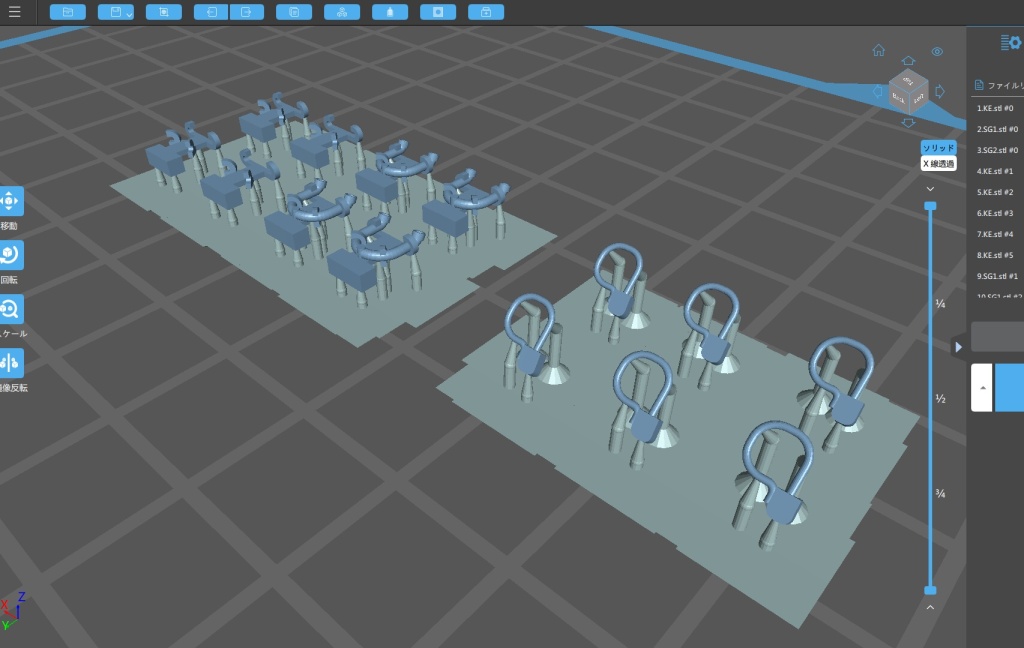
データが出来上がったところで、3Dプリンターで出力します。


2側にも同様の加工が施されております。


少々見づらいですが、はしご横に制作したパーツが取り付けされています。2側にも同様の加工が施されております。
作業はすべて完了でございます。
マイクロ製電気機関車のテール点灯改造でございます。2004年ごろに発売された製品です。
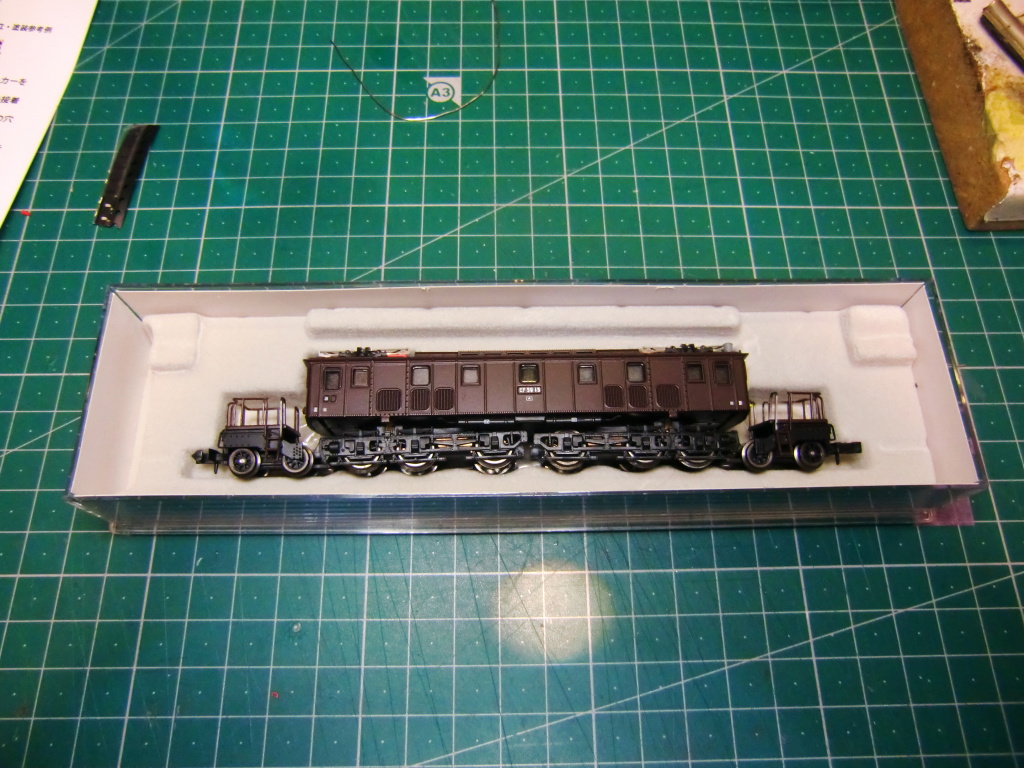
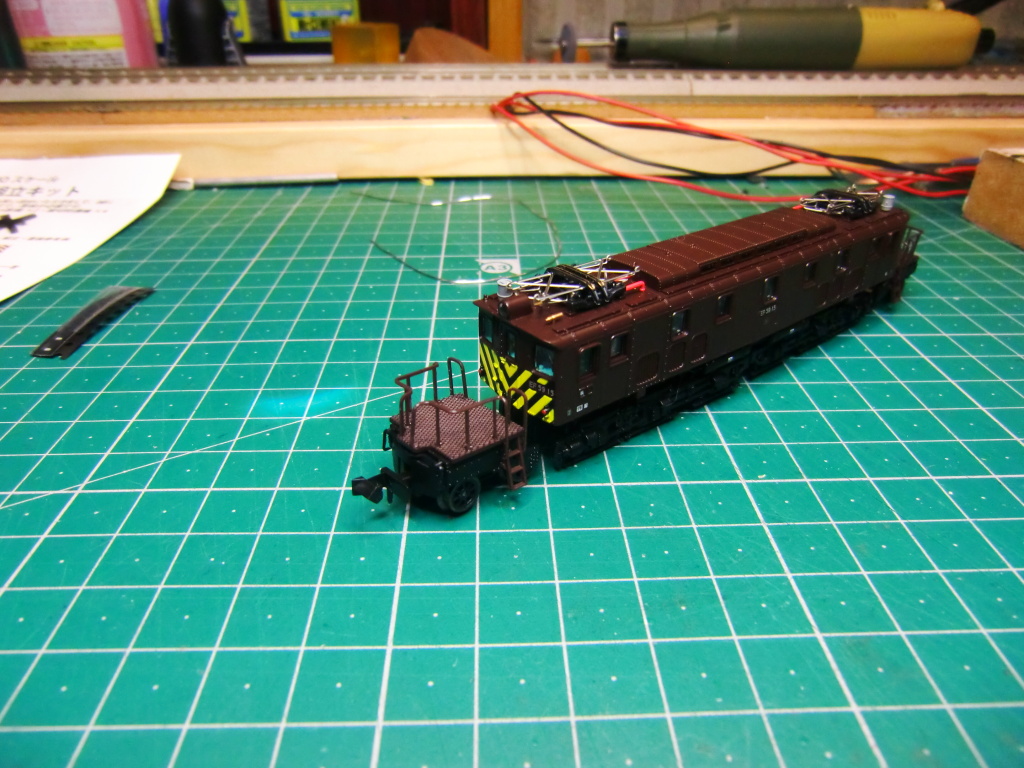
こちら側を点灯ご希望ということでございますので、そのように加工いたします。

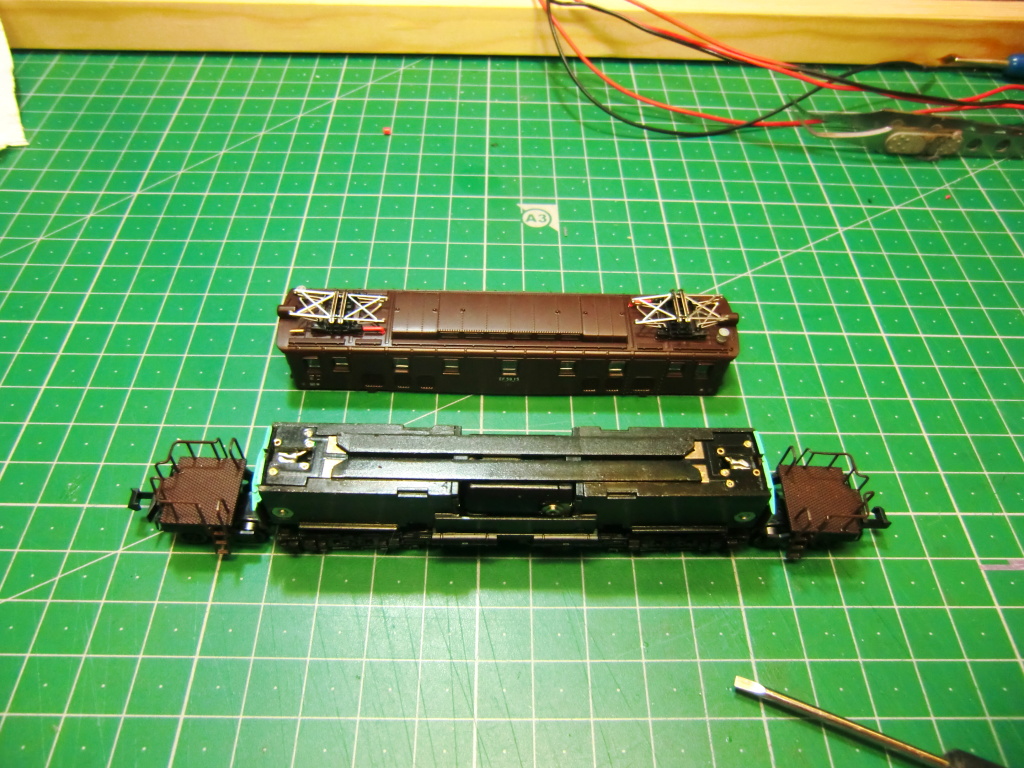
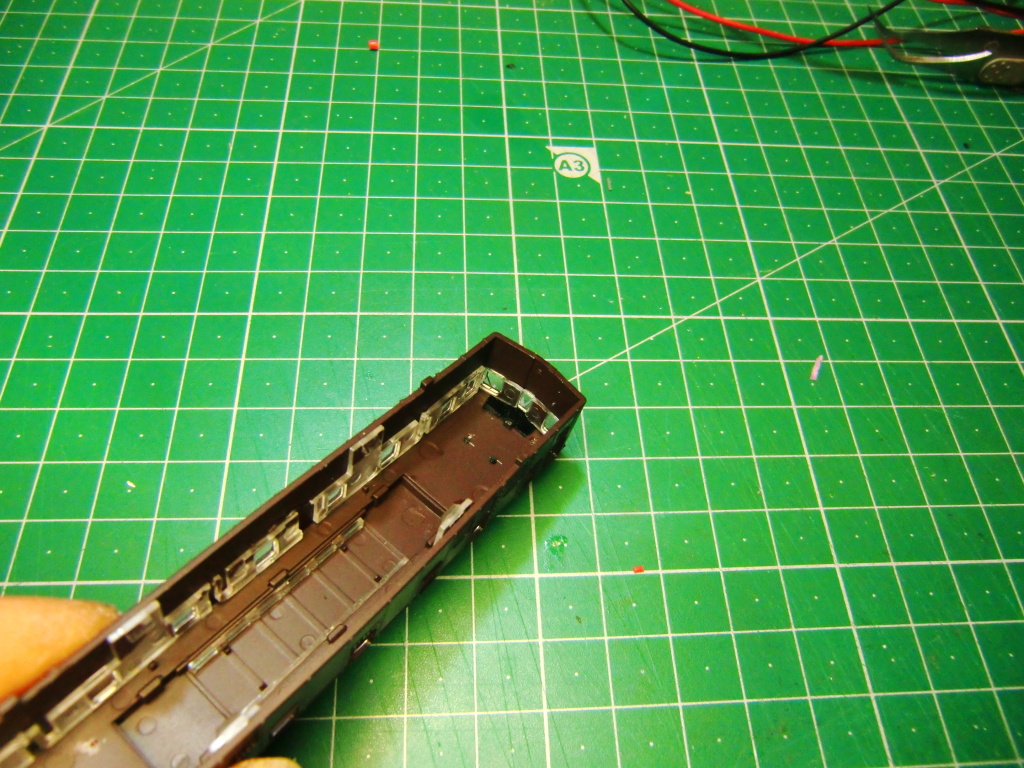
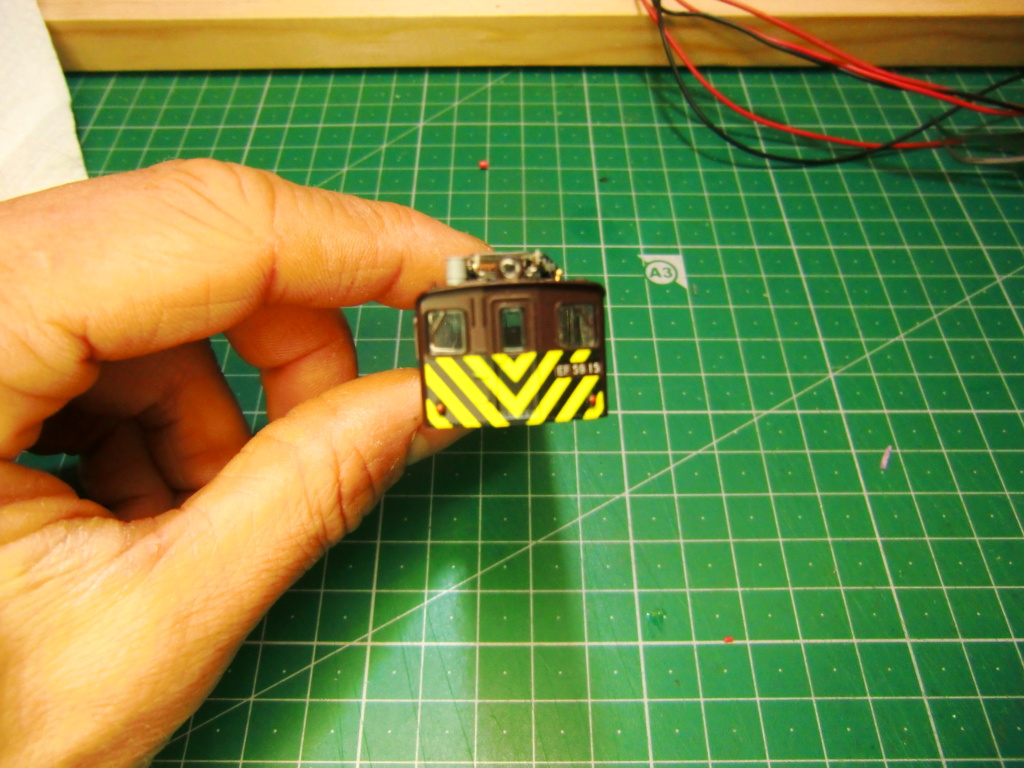
作業の中で最も難しいのが、テール中心への穴あけ作業です。特にこちらの製品では、出っ張りとライト面が小さいので、難易度が高いです。
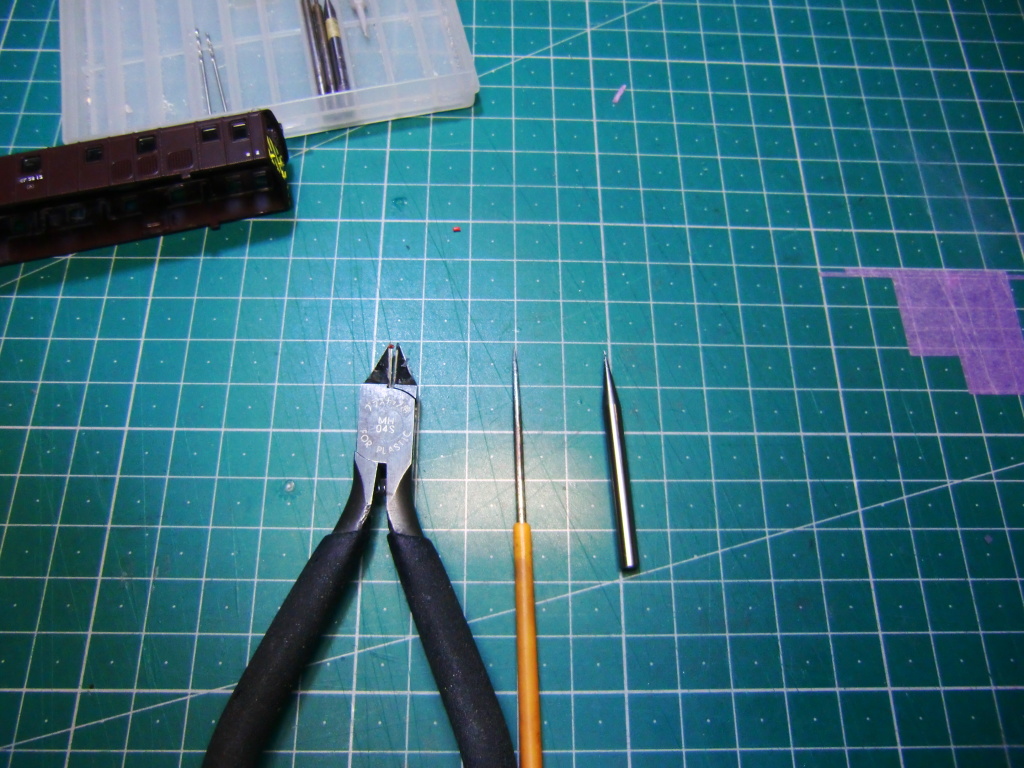
左から順に使用していきます。まずは、現状のテールの出っ張りをニッパーでカットします。次にセンターにあたりを入れます。(最も重要)。
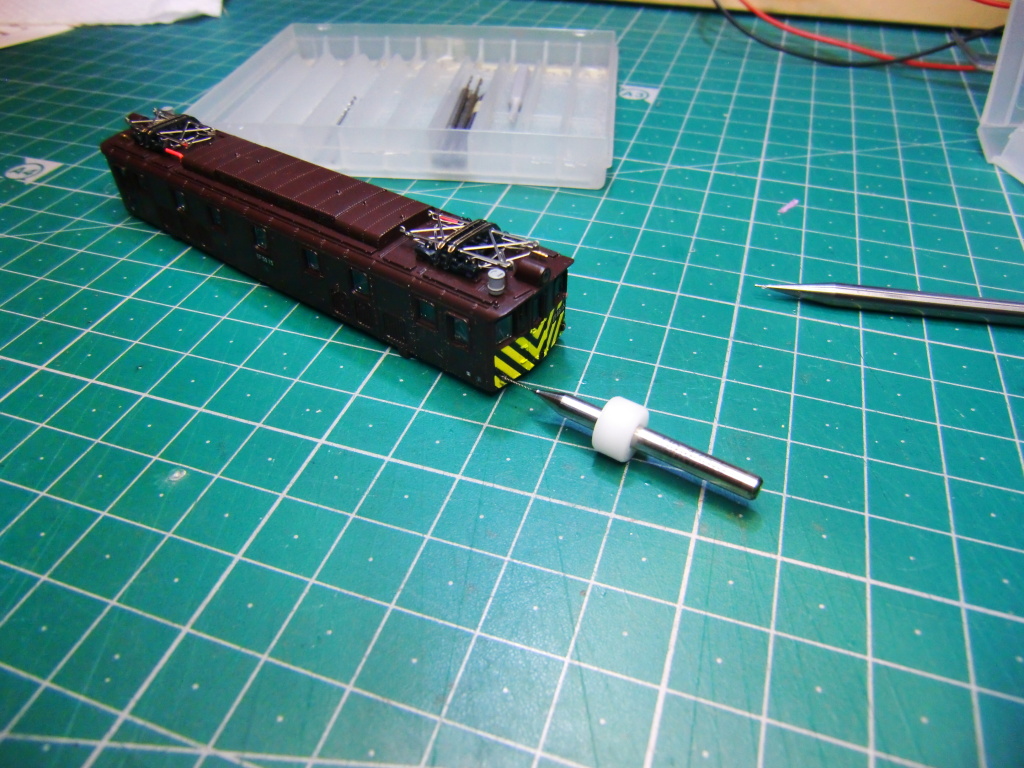
まずは、0.3mmのドリルで貫通させます。力の加減を誤るとすぐにドリルが折れるので、慎重に進めていきます。貫通したのち、0.5mmのドリルに交換して径を広げます。
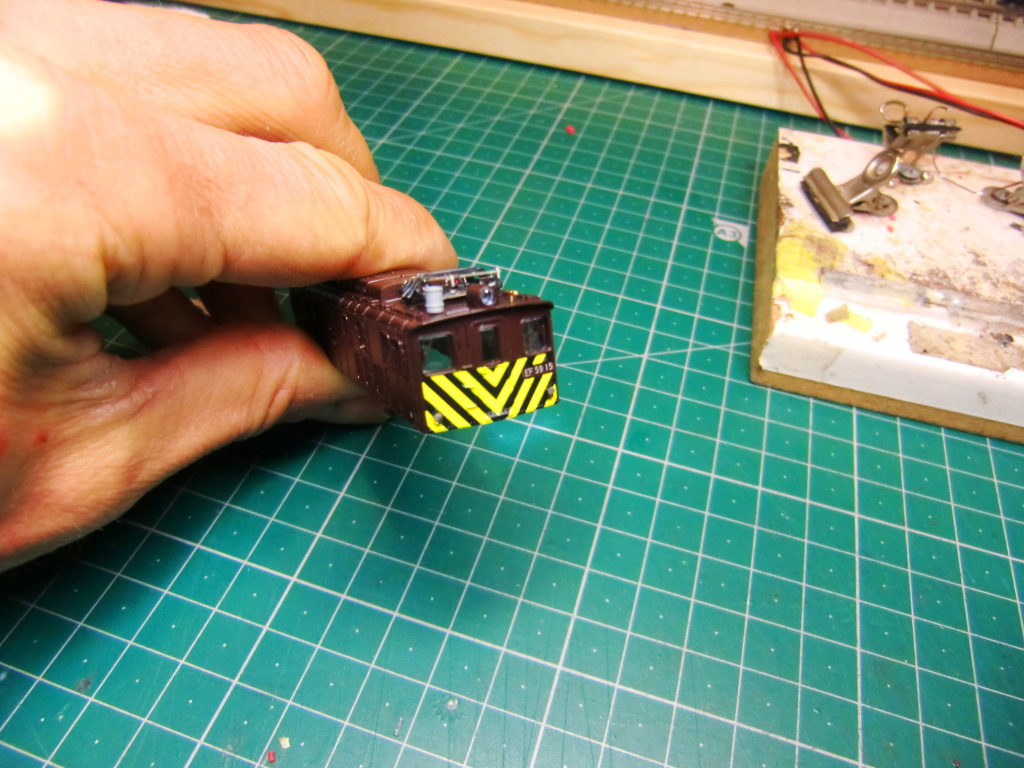
0.5mmの光ファイバーを埋め込み断面をドーム状に加工します。

「1608赤色チップLED」を直列で繋ぎ、テールの位置と合うように配置します。次に基盤に接続しますが、抵抗値をやや高めにして配線します。

テスト点灯させてみます。

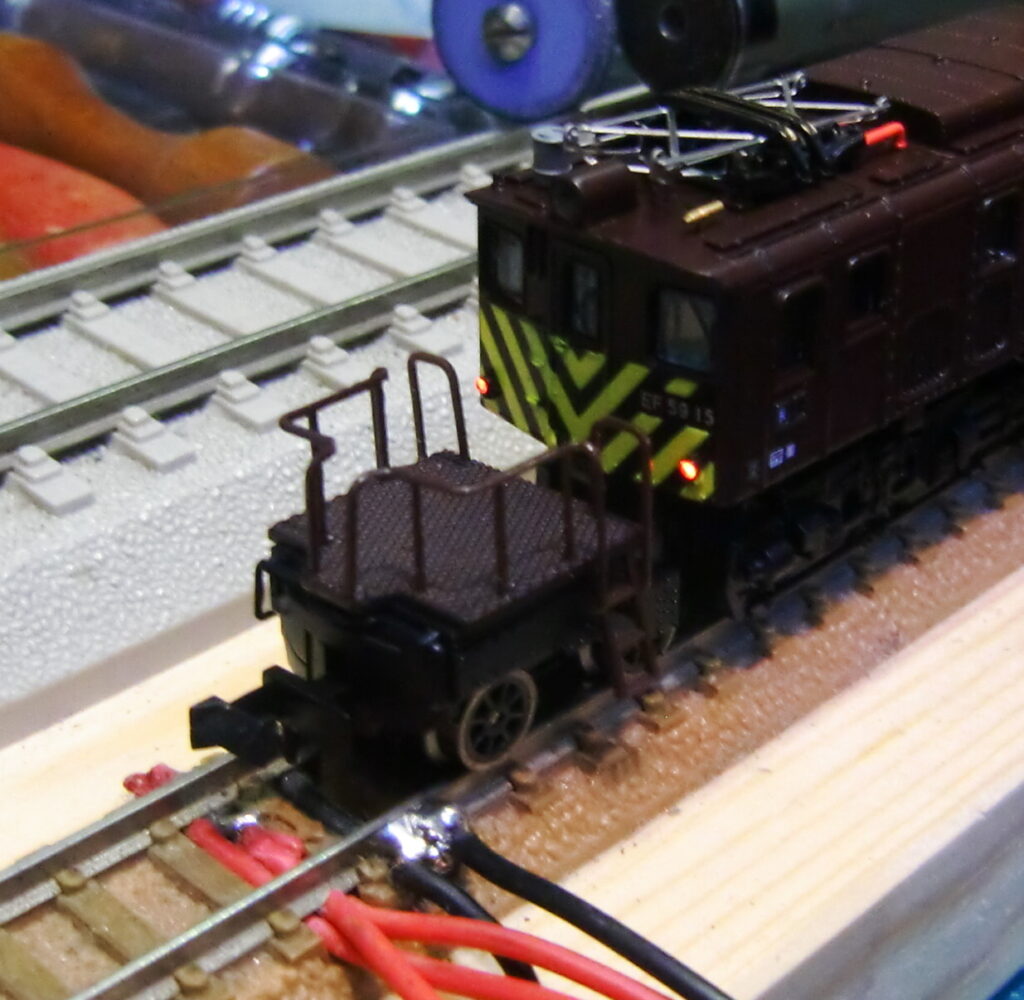
LEDの配置などの微調整を何度か行い、明るさのバランスがとれたところで、作業は無事完了いたしました。
今回のご依頼は、踏切の点滅とサウンドを再現したいとのことで、遮断機の上げ下げなどのギミックはなくて構わないそうです。
それでは作業を進めていきます。

持ち込まれた加工対象となる「津川洋行製 踏切セット」ですね。こちらに組み込んでいきます。
まずは、チップLED(赤)をそれぞれ埋め込んでいきます。
配線は2線となるように、極性変わることで左右の点滅を変えるように配線します。極性の制御はマイコンに行わせます。
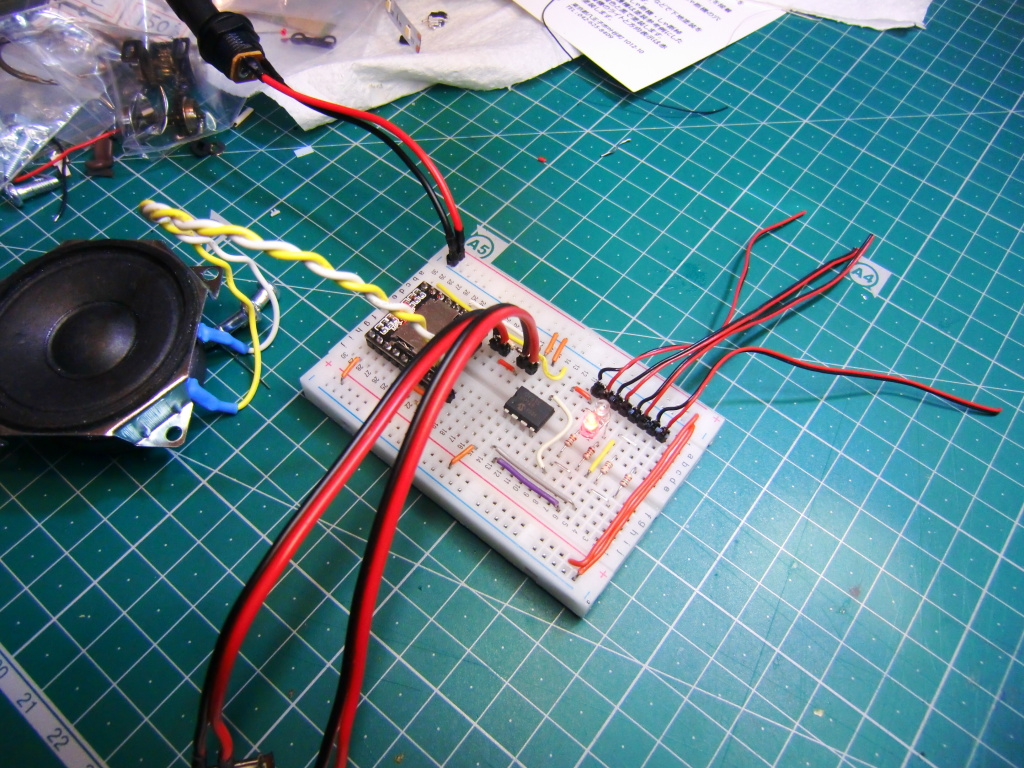
比較的シンプルな回路でございますので、作業時間短縮のためブレッドボードにそのまま配置します。
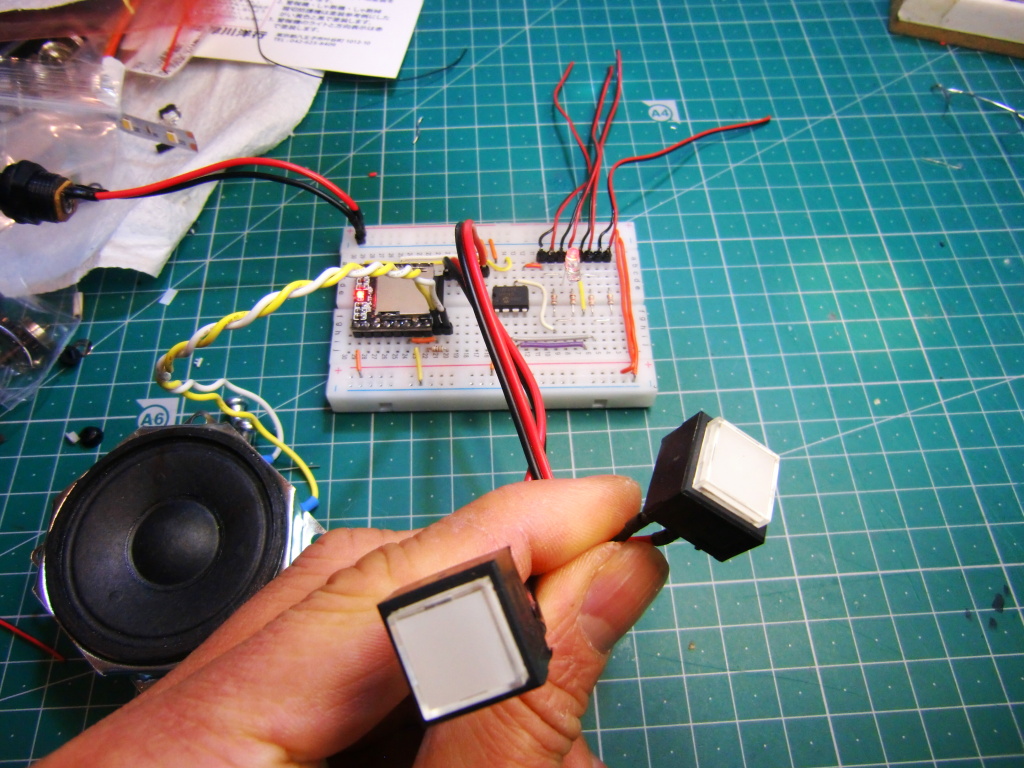
ボタンを押すと点滅と踏切音が鳴ります。
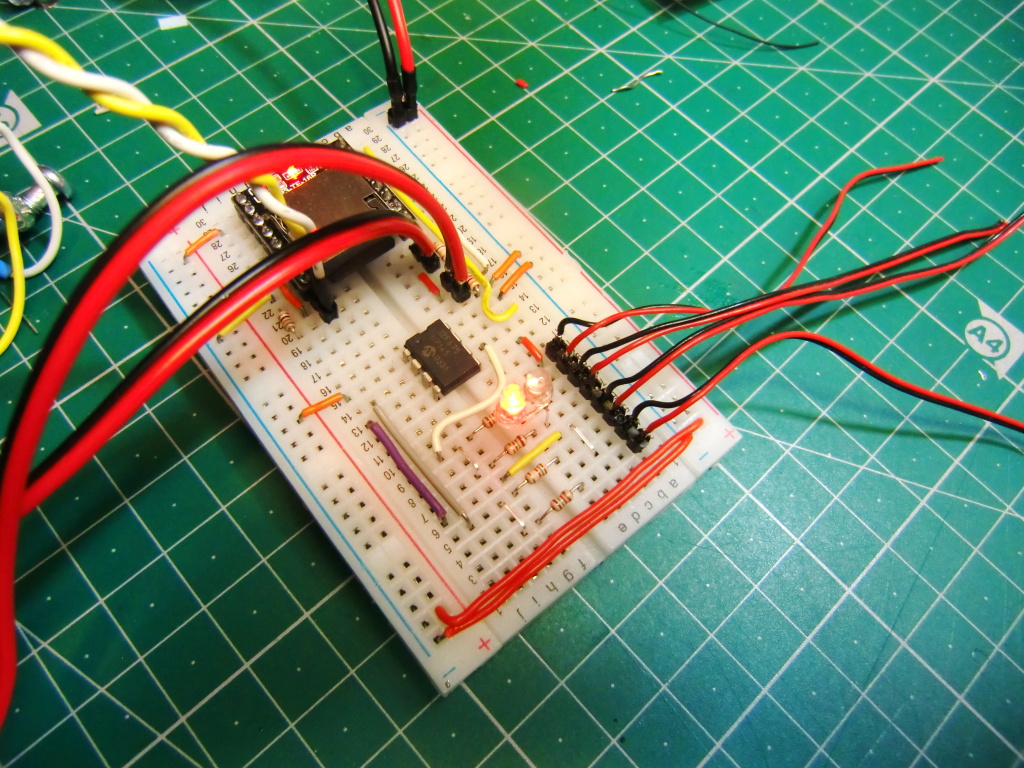
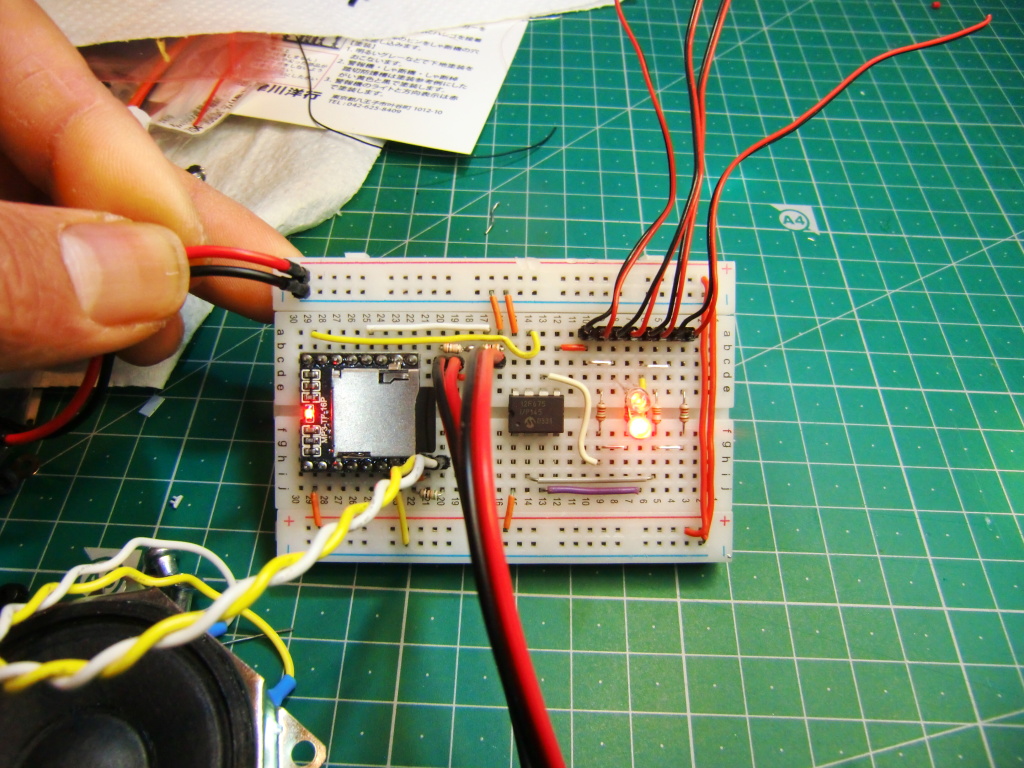
各種ハンダ付けと配線は、お客様ご自身で作業されるとのことですので、作業はここまでとなります。

まずは現状確認のため、走らせてみます。
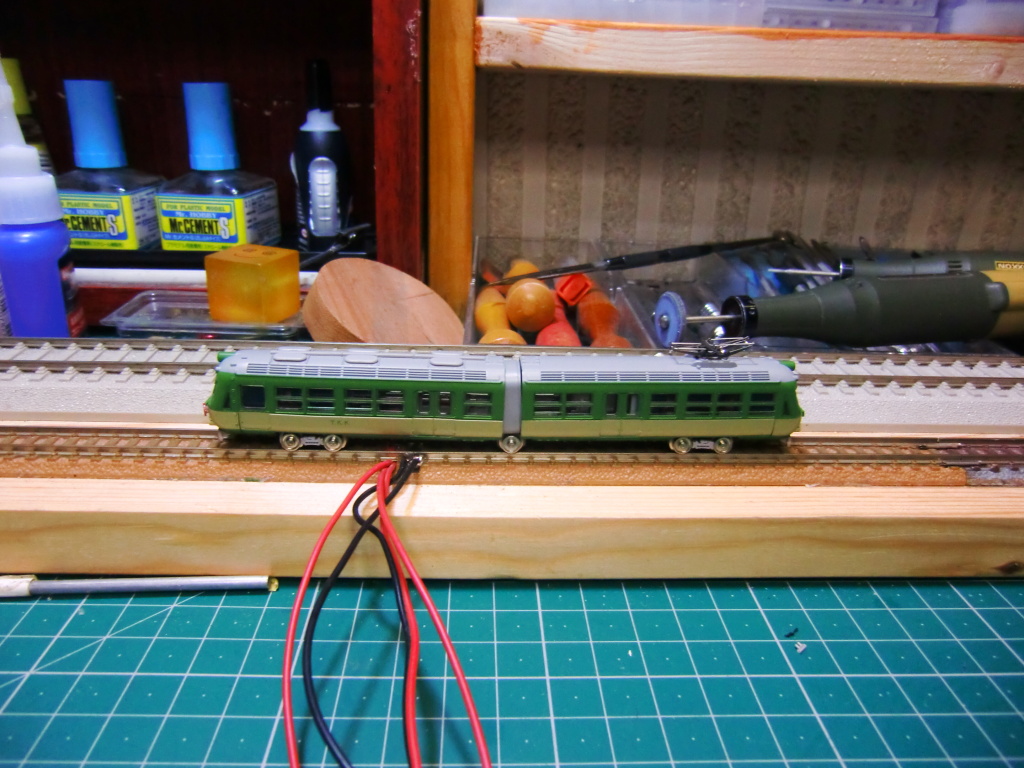
片側の台車が回っていないようです。内部でガラガラ音がします。

分解して直してきます。

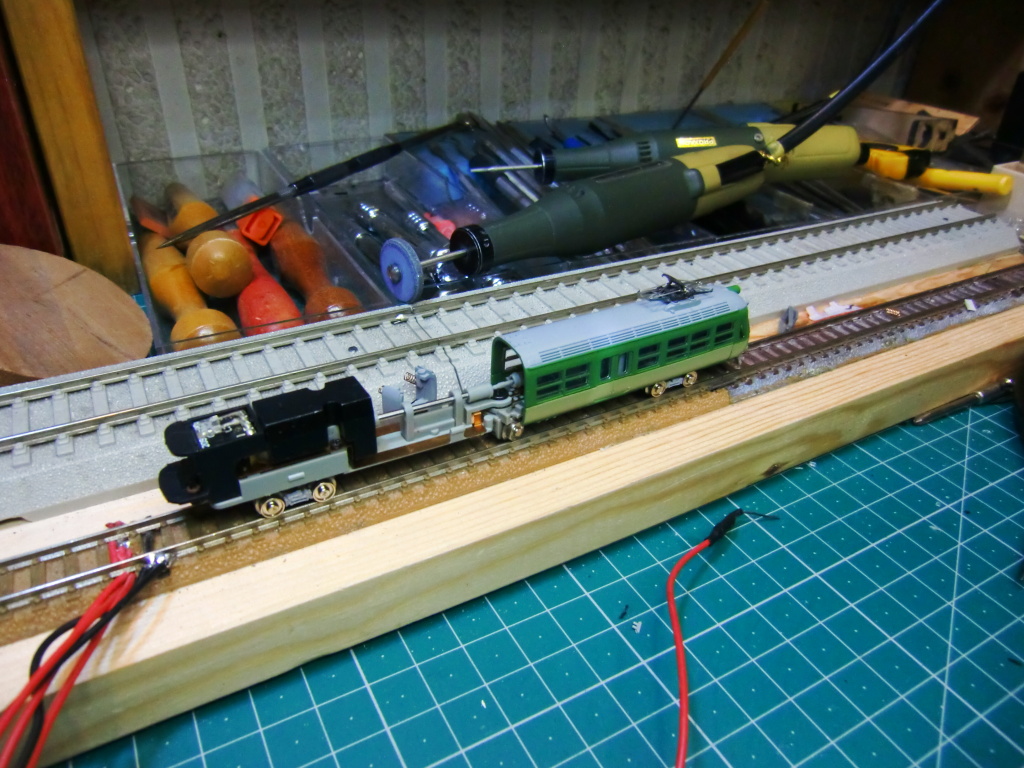
確認と調整を繰り返していきます。

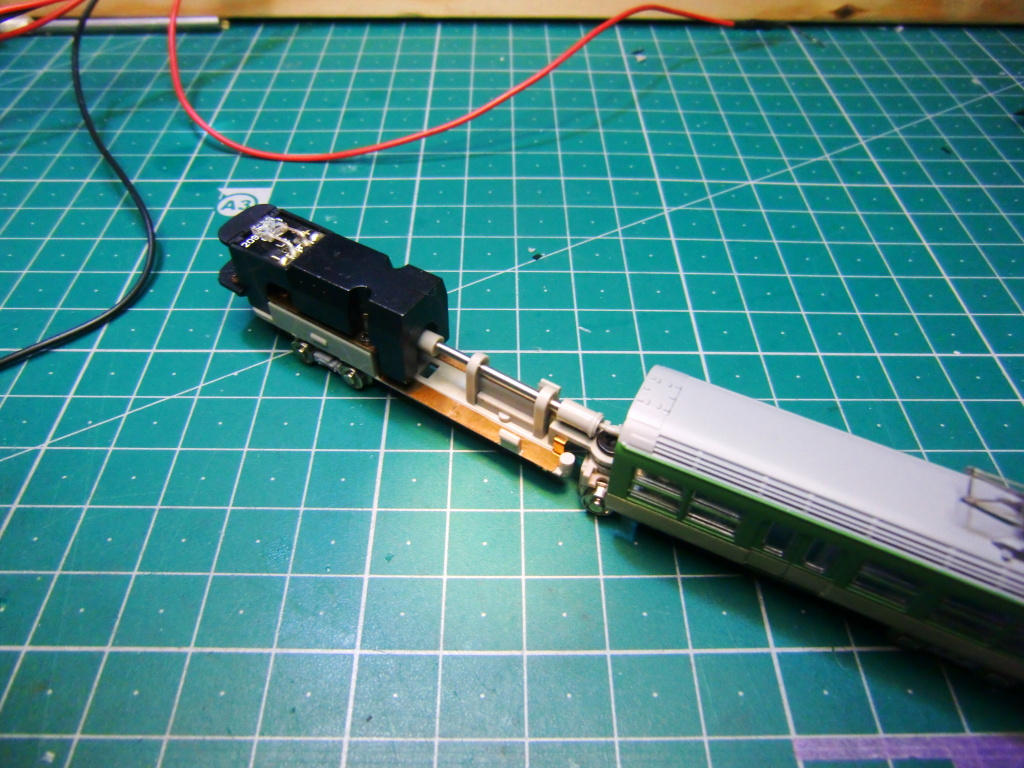
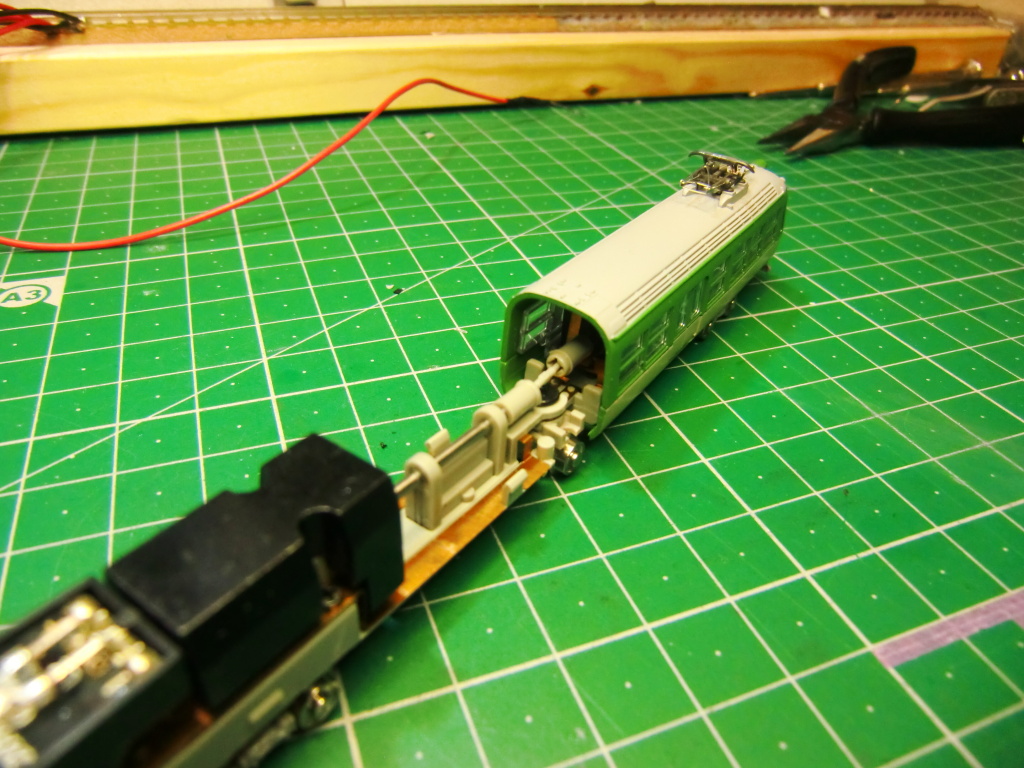
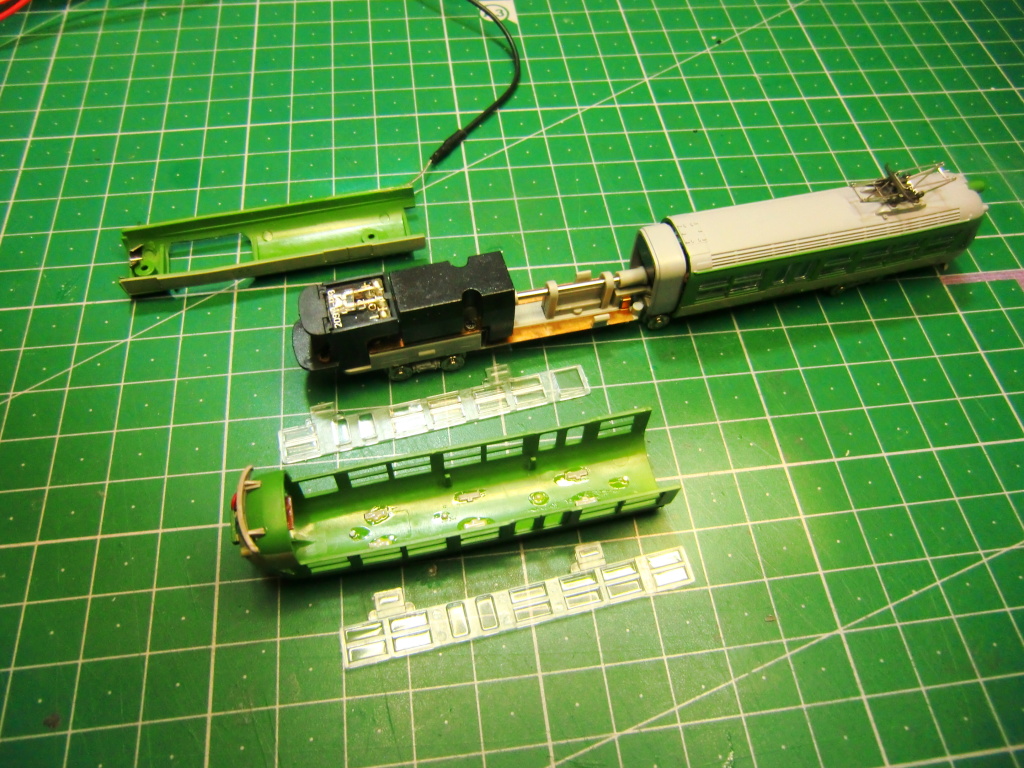
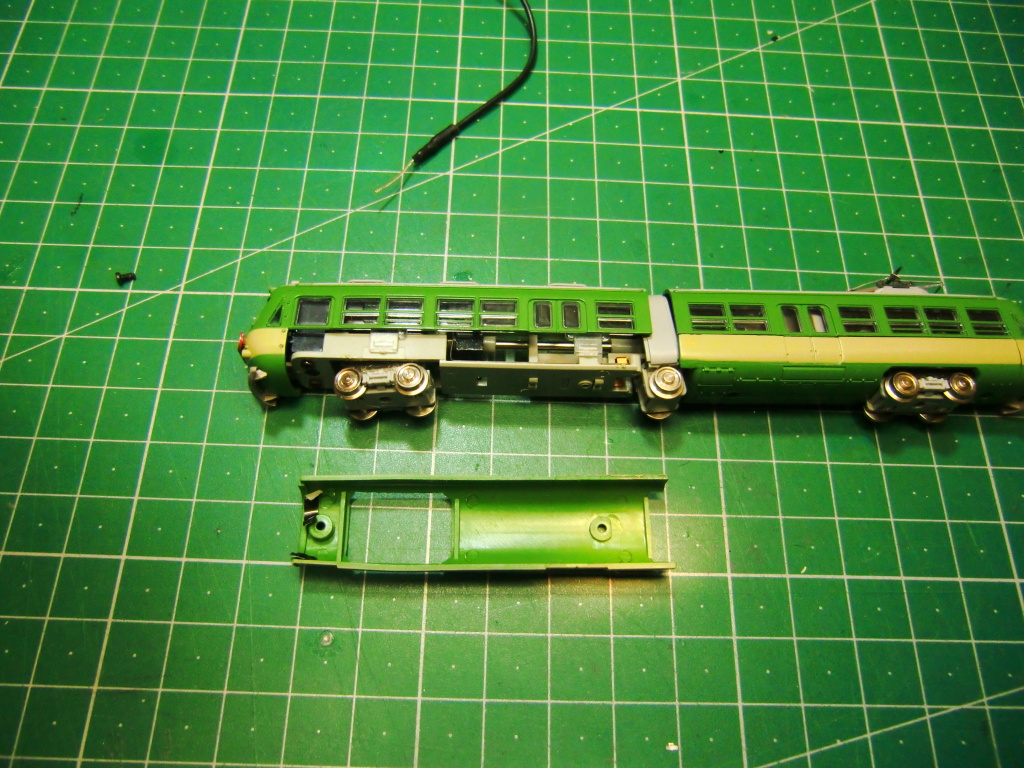
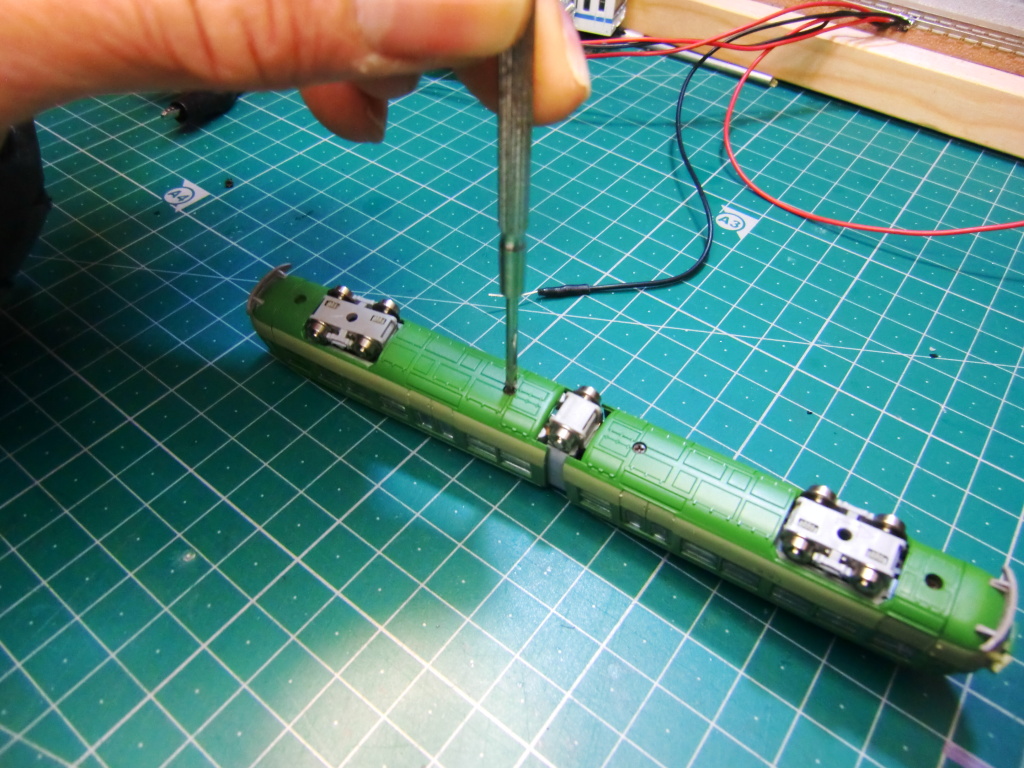
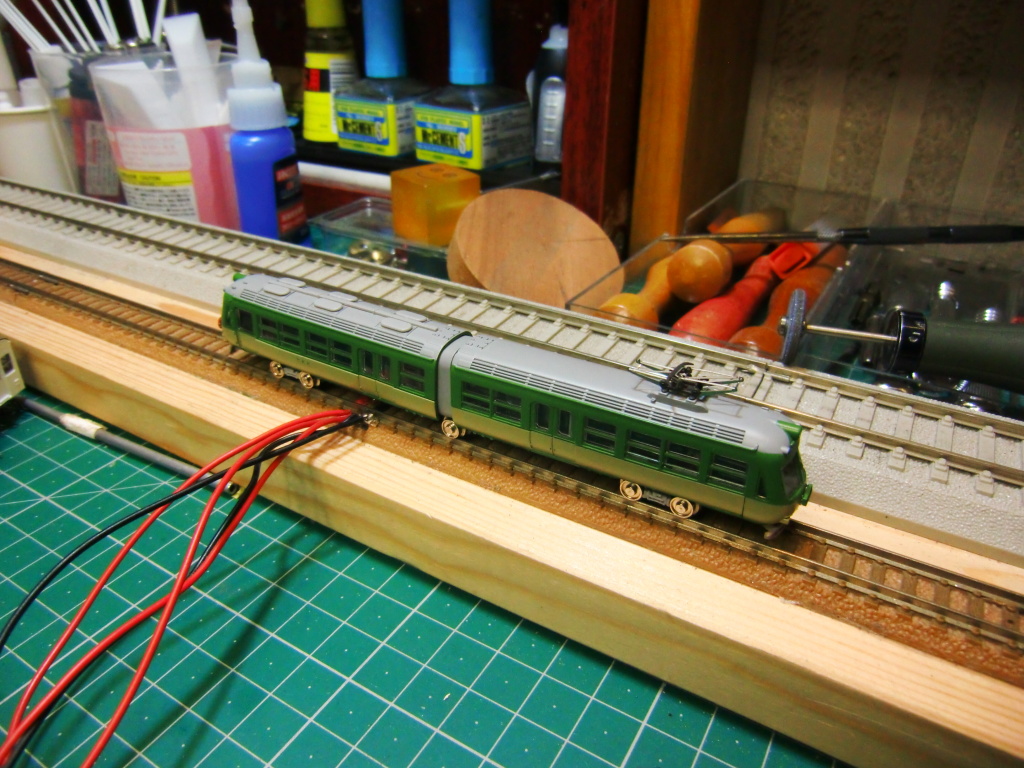

作業完了でございます。
当時のマイクロ製品で、よく見られる左右の明るさの違い(左が明るく右が暗い)を調整していきます。作業方法は、車種ごとにやや異なりますが、基本的な考え方は一緒です。
まず、なぜ左右で明るさが違ってしまうのかについて簡単にご説明いたします。
まずは、こちらの図をご覧ください。
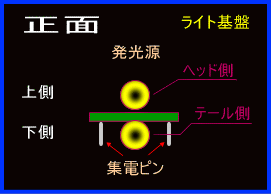
光源が中心に配置されている基盤です。この場合、左右のライトの明るさは同じとなります。主にTOMIX/KATOでは、このスタイルとなっていることが多く、左右の明るさが極端に違うことはあまり見られません。次に
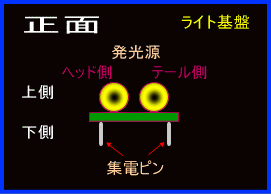
こちらの図では、光源が左右に配置されている基盤です。この場合、左右のライトの明るさが違って見えることがよくあります。これは、発光面までの距離が異なるためです。上図では左がヘッドライトとなりますが、左面のライト発光面までの距離が短く、逆に右面までの距離が遠くなります。この差が明るさに影響します。しかしながら、すべてこのような症状となるわけではありません。光源が電球?LED?、プリズムの透明度、大きさや形状の違いなども関係するため、影響が少ない車種もあるのも事実です。



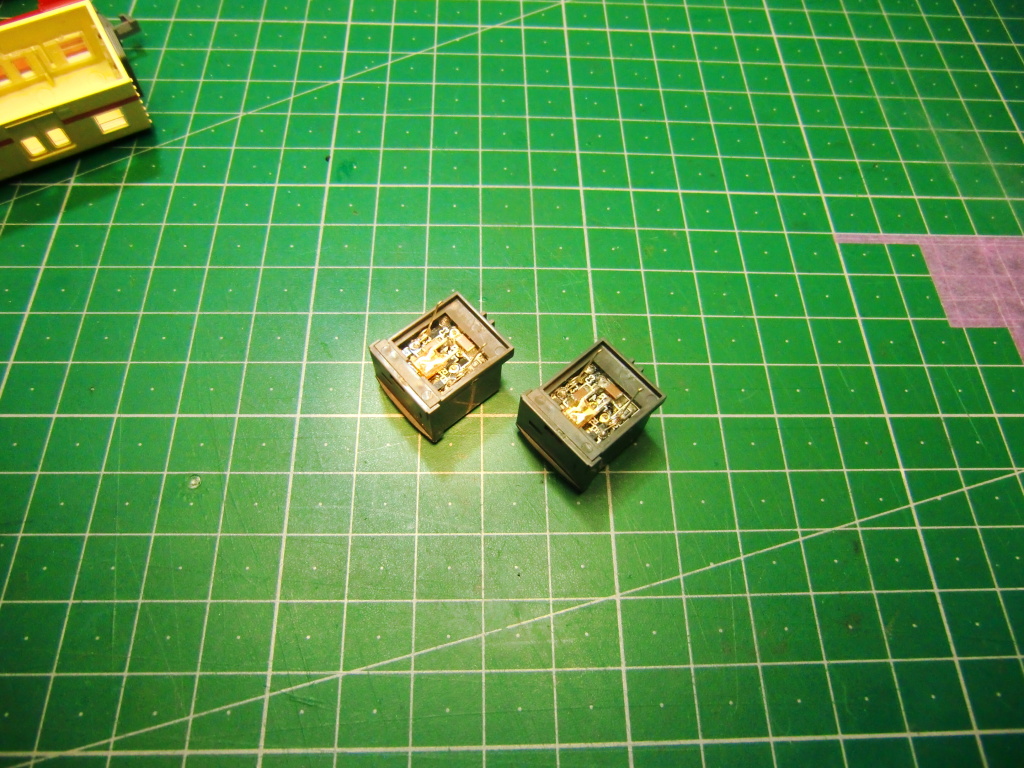
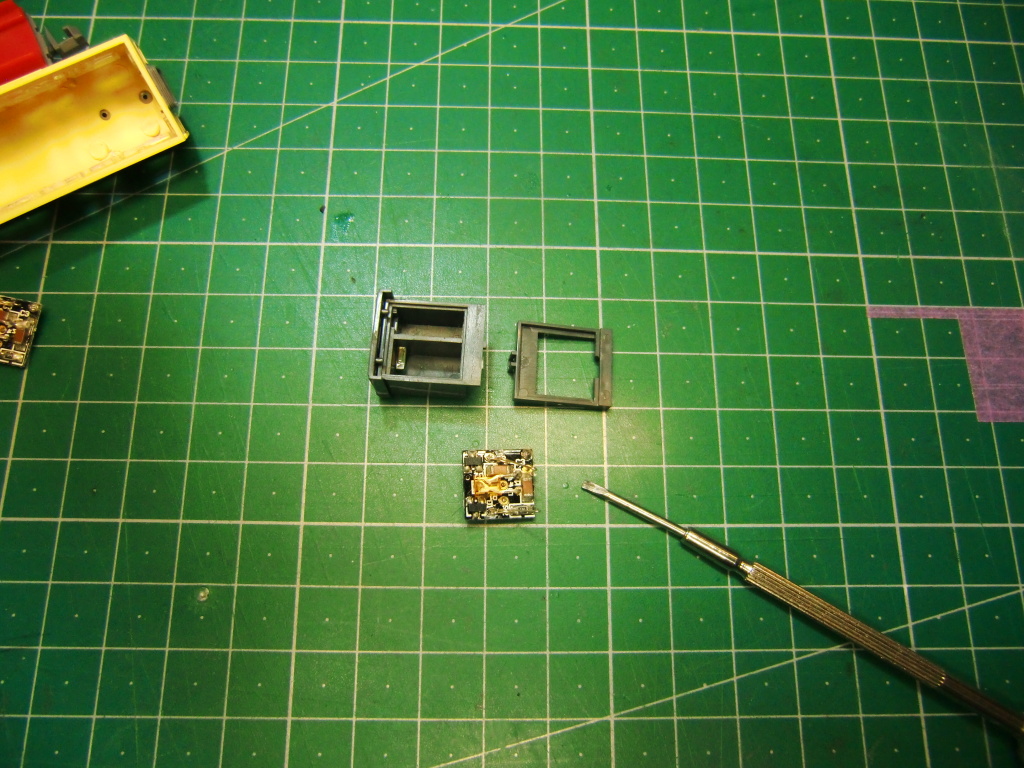
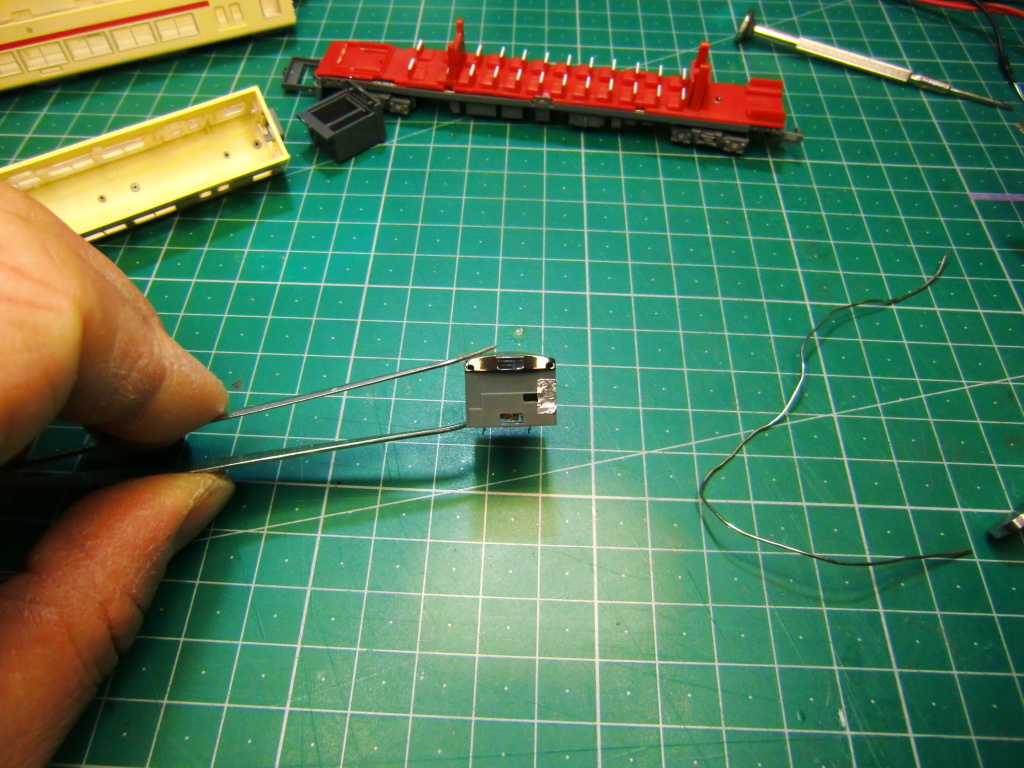


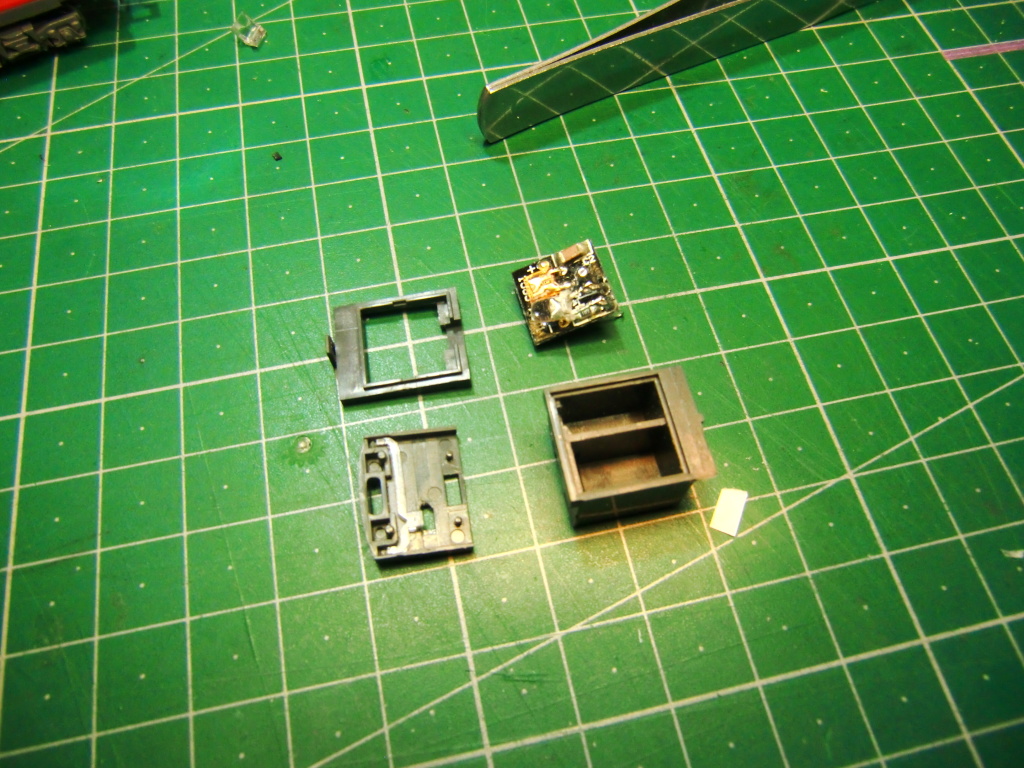

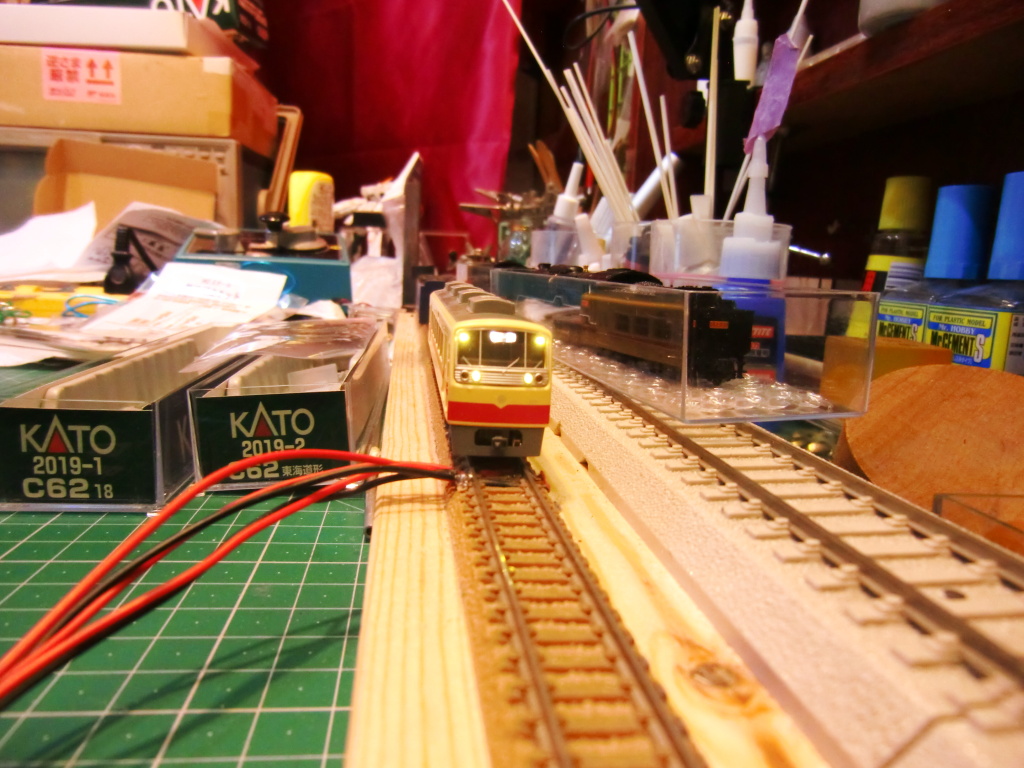




先にテンダーとキャブを外してから、写真の位置で持ち上げるとボディーが外れます。その際に正面のパーツも引き抜きます。

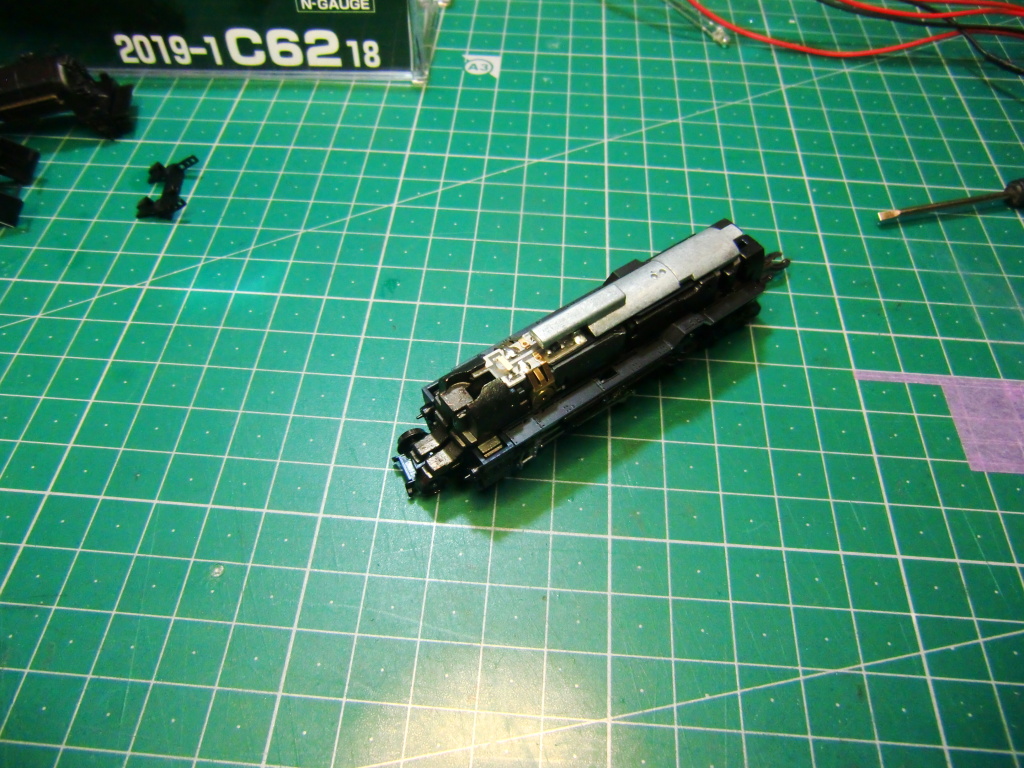

3mmのLEDを削り込んで埋め込みます。削った面は黒で遮光します。
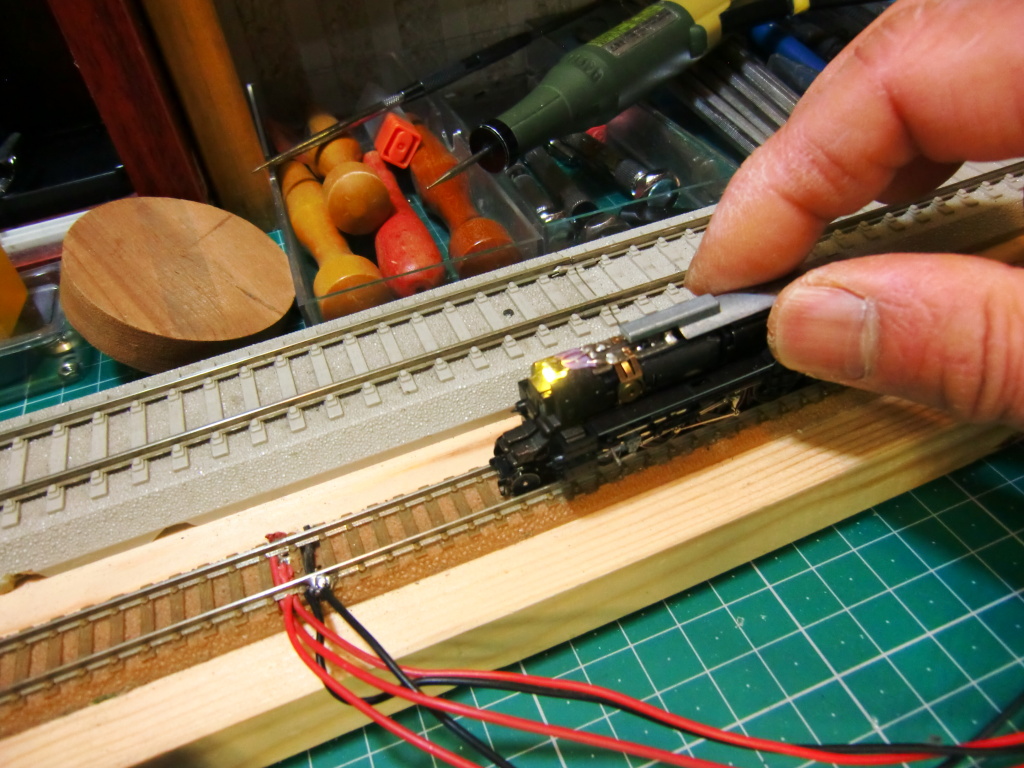
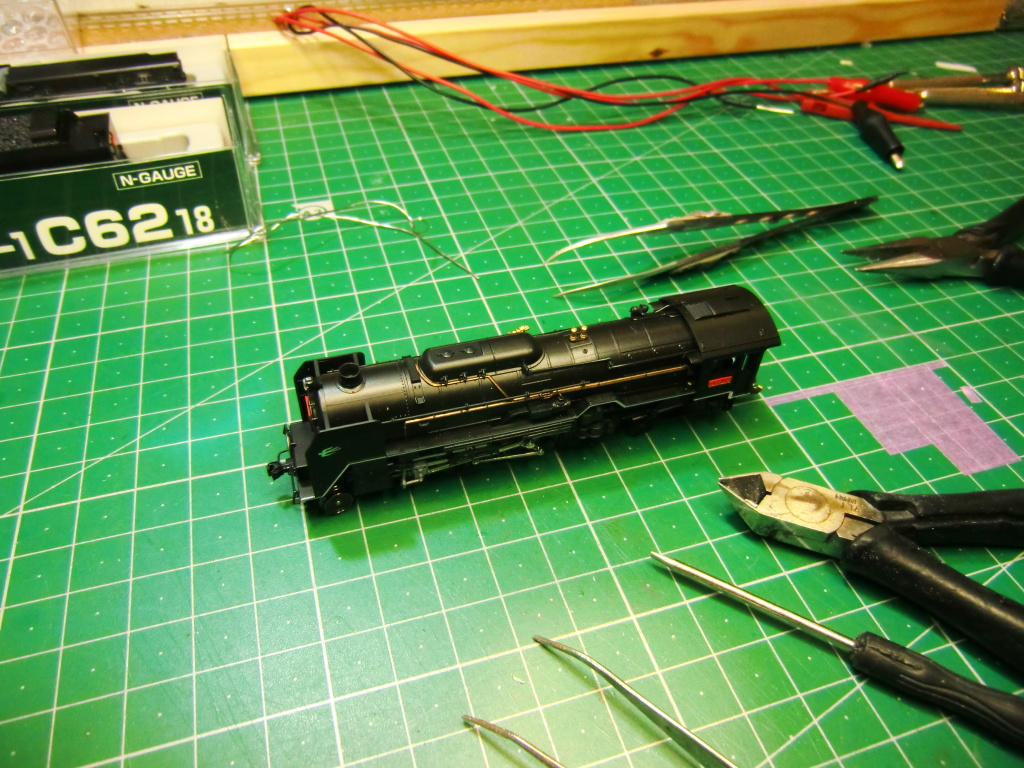

on/off機能は解除して、常時点灯モードとなります。
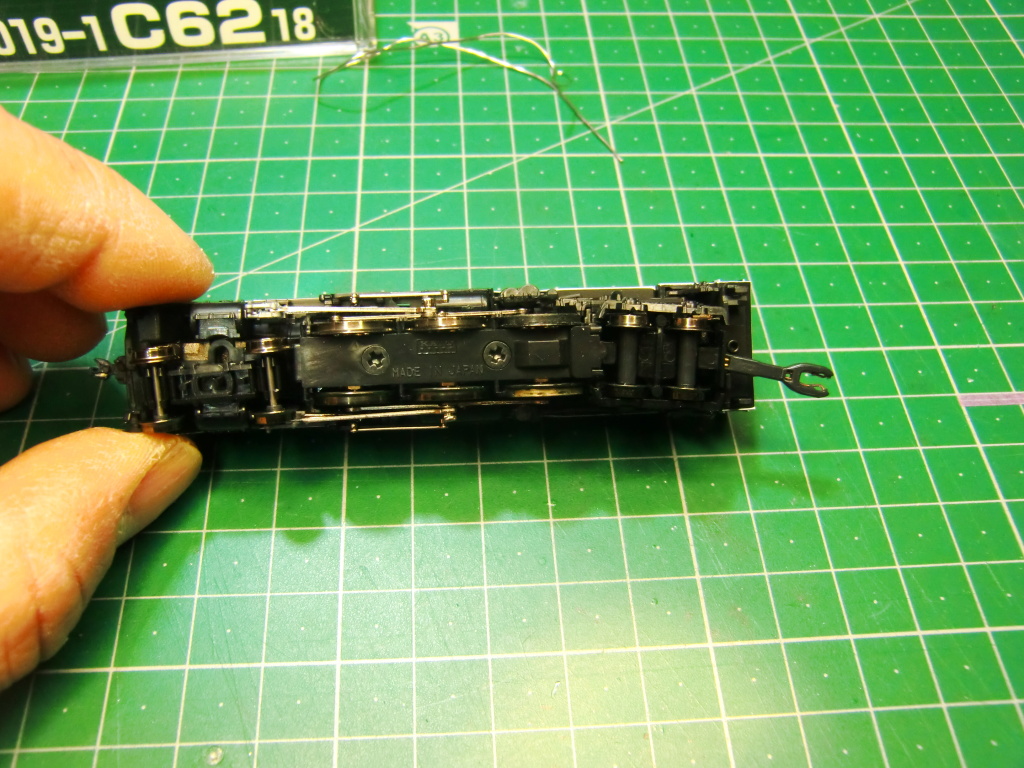
次にトラクションタイヤの交換ですが、ピンセットで剝がそうにも車輪にこびり付いており剥がれません。

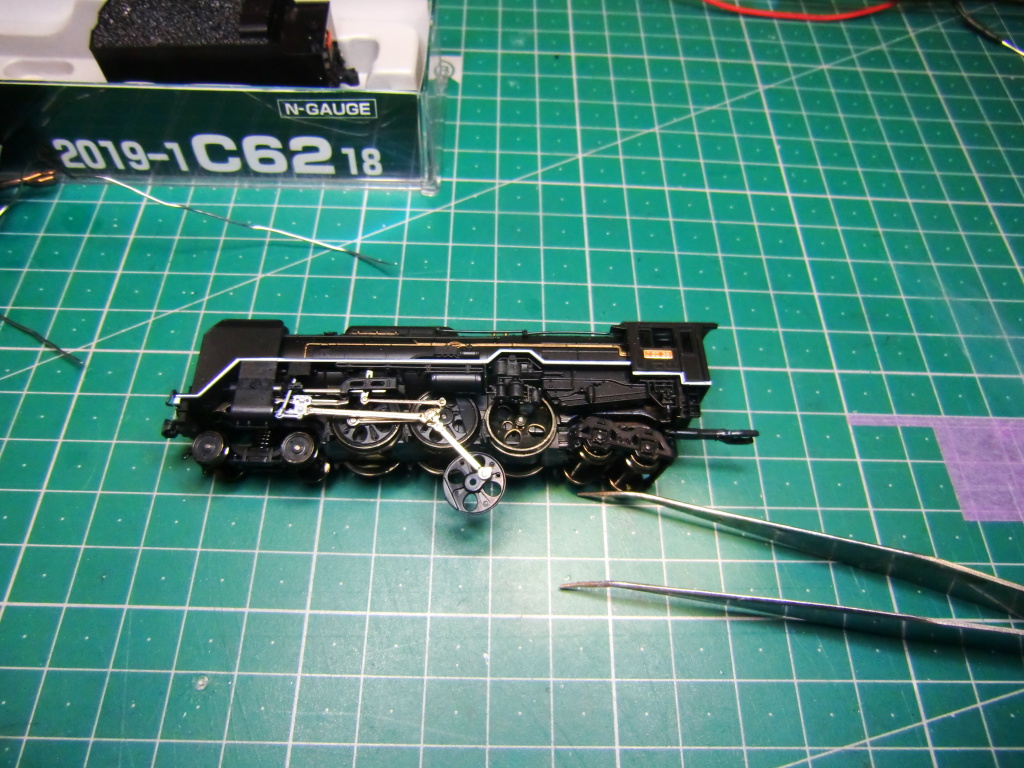
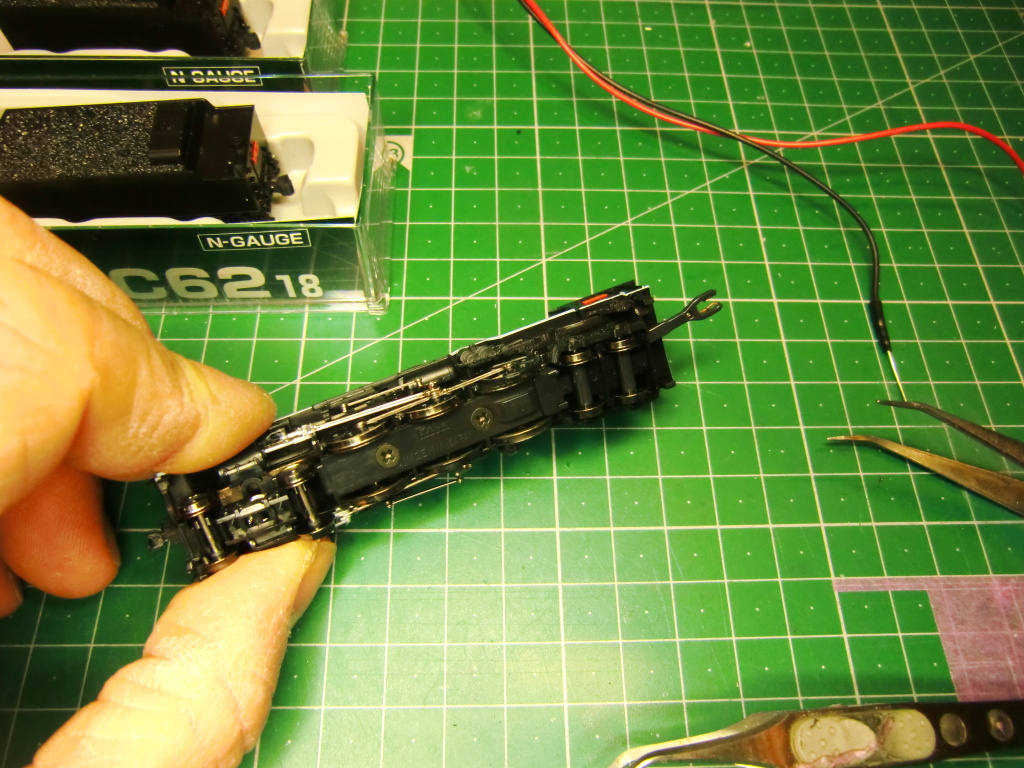
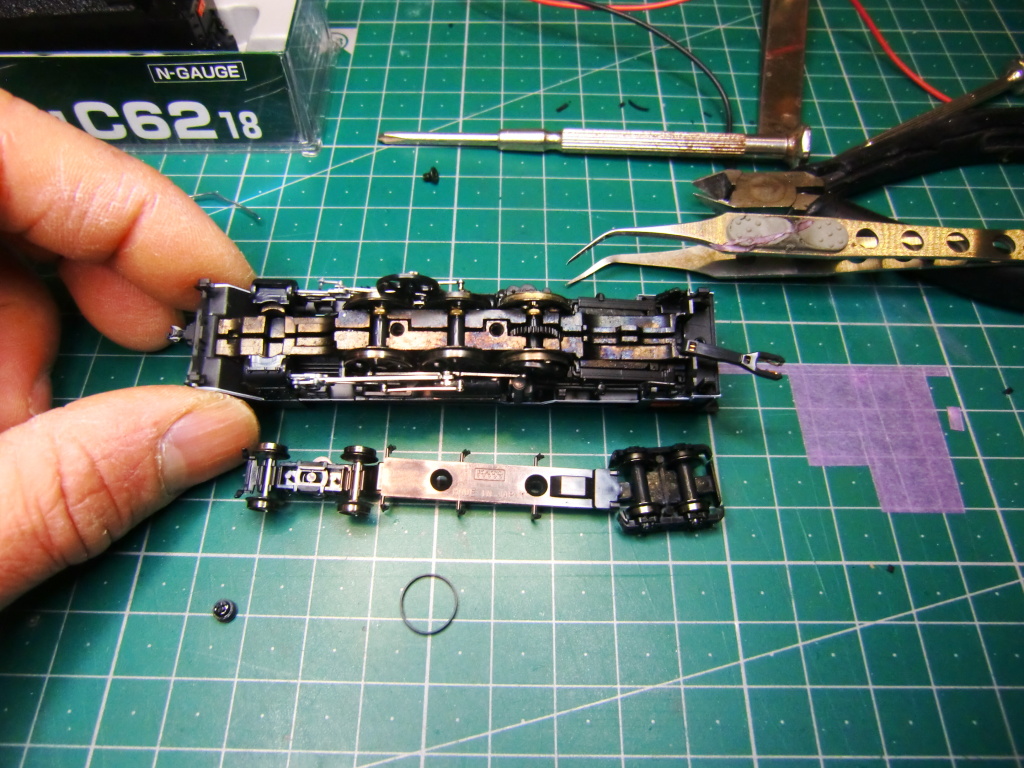
やもえないので、すべて分解して車輪にこびりついた古いトラクションゴムを削り落とすところから作業する必要があります。
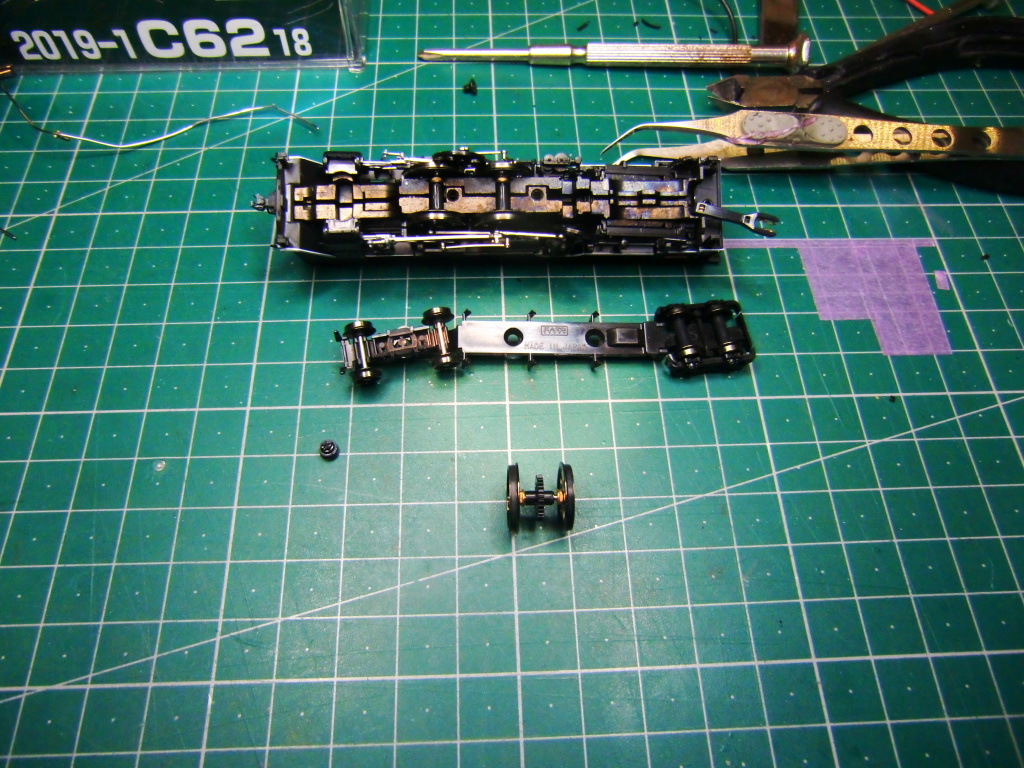
車輪を取り出して磨きだしを先に行います。


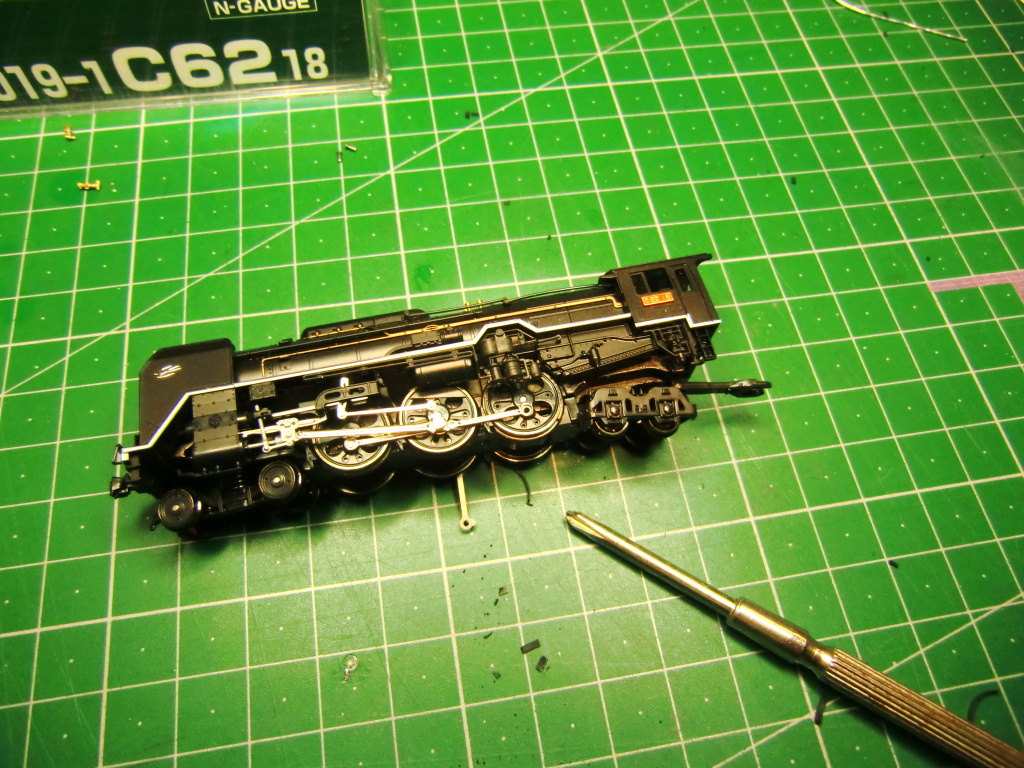



作業完了でございます。
アクリル製ディスプレイケースのご案内です。主に機関車を飾ることを目的として制作いたしました。素材は、3mm厚の透明度の高いアクリルを採用しております。ベースはアルカンターラー調マットを使い、レールはアクリルを使用しております。
アクリル樹脂の特徴は、透明度が高く厚みによる曇りが少ないく丈夫な素材ではありますが高価なため、安価なディスプレイケースの場合、「ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリカーボネート」などの素材が使用されることが多いようです。
▼ディスプレイケースの重要性について
ディスプレイケースの重要性は、展示物の魅力を最大限引き出す上で大変重要なアイテムの一つです。また、照明効果とアククリル素材の相性も良く、高級感のある演出効果も期待できます。
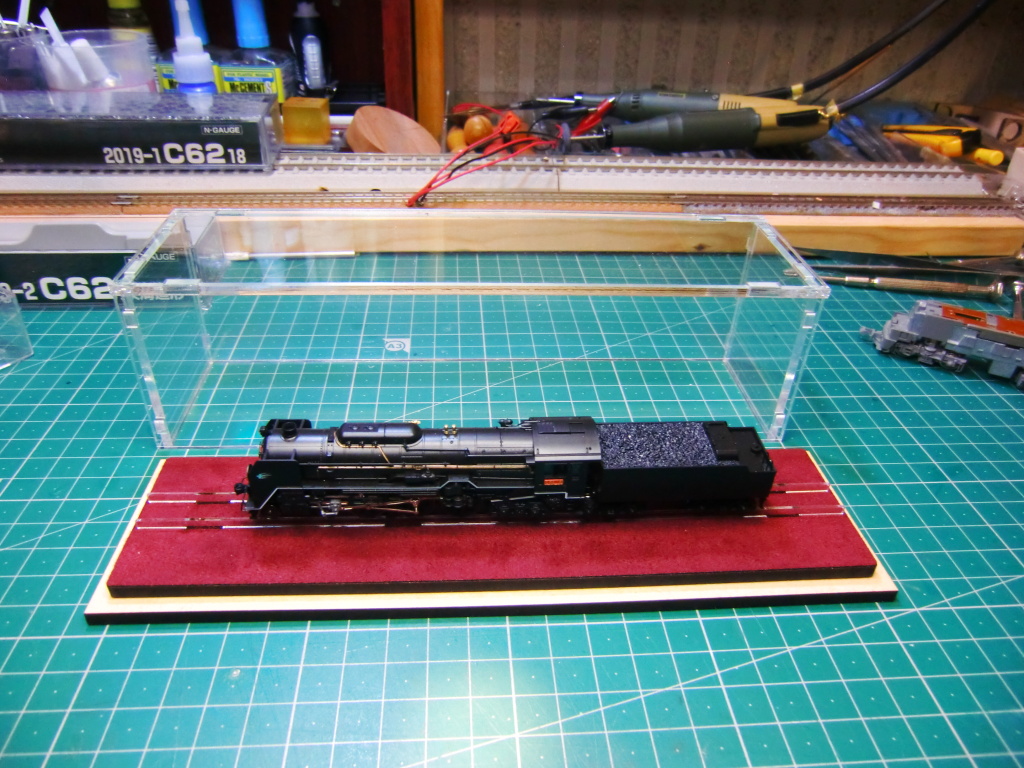
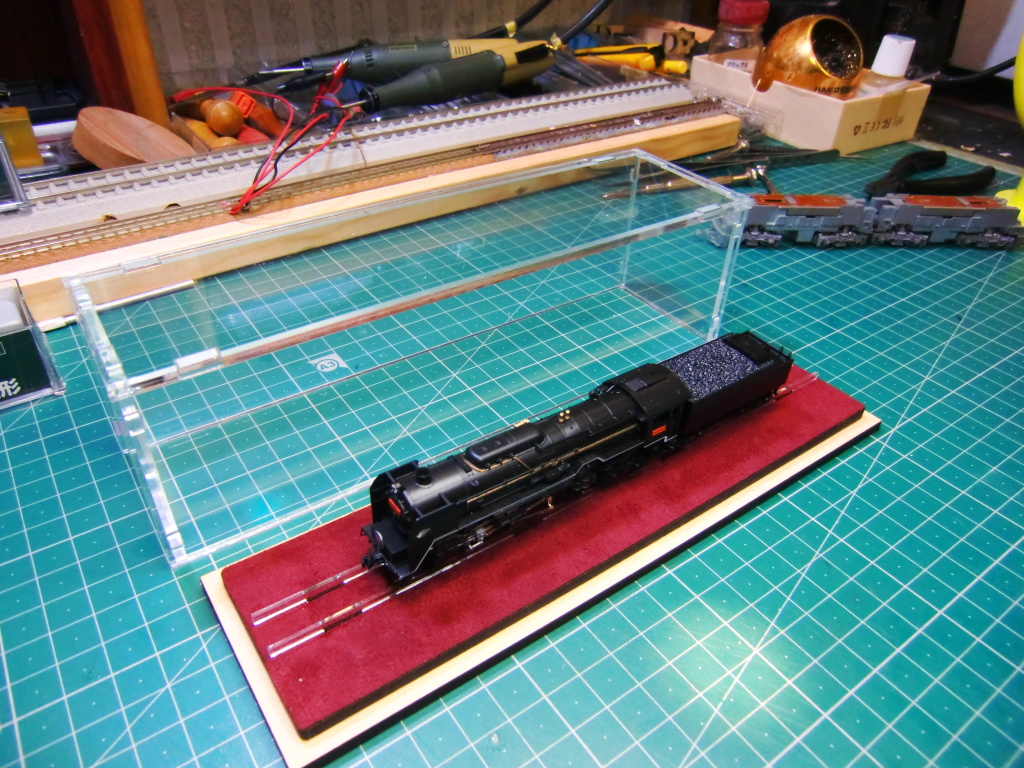
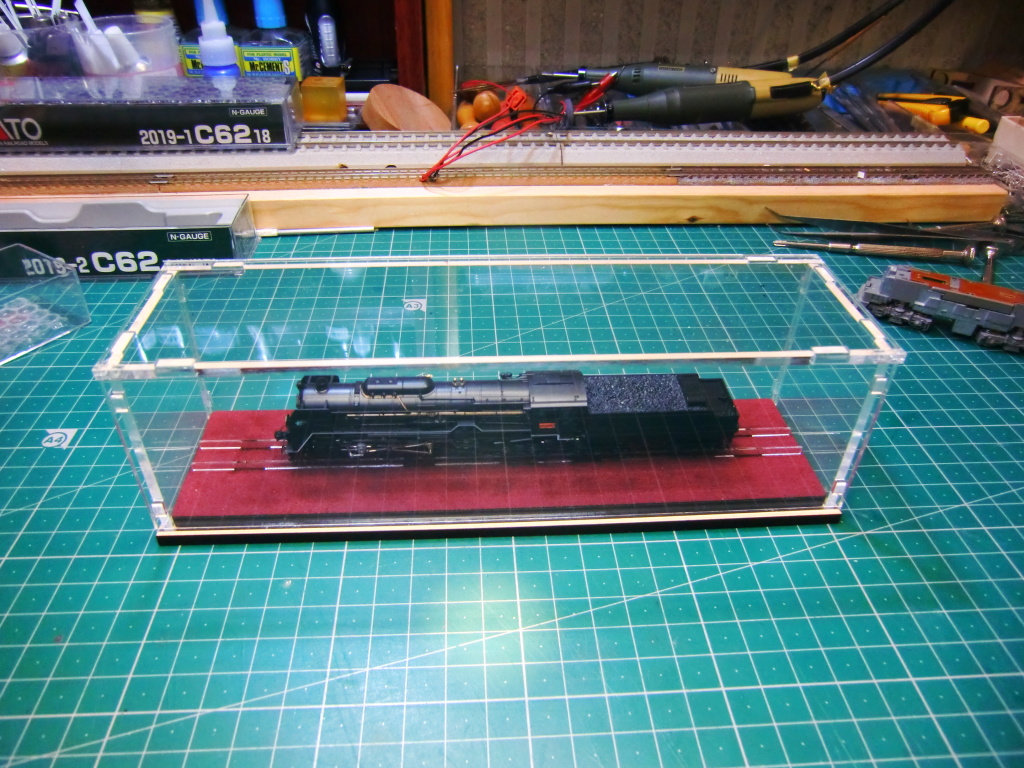
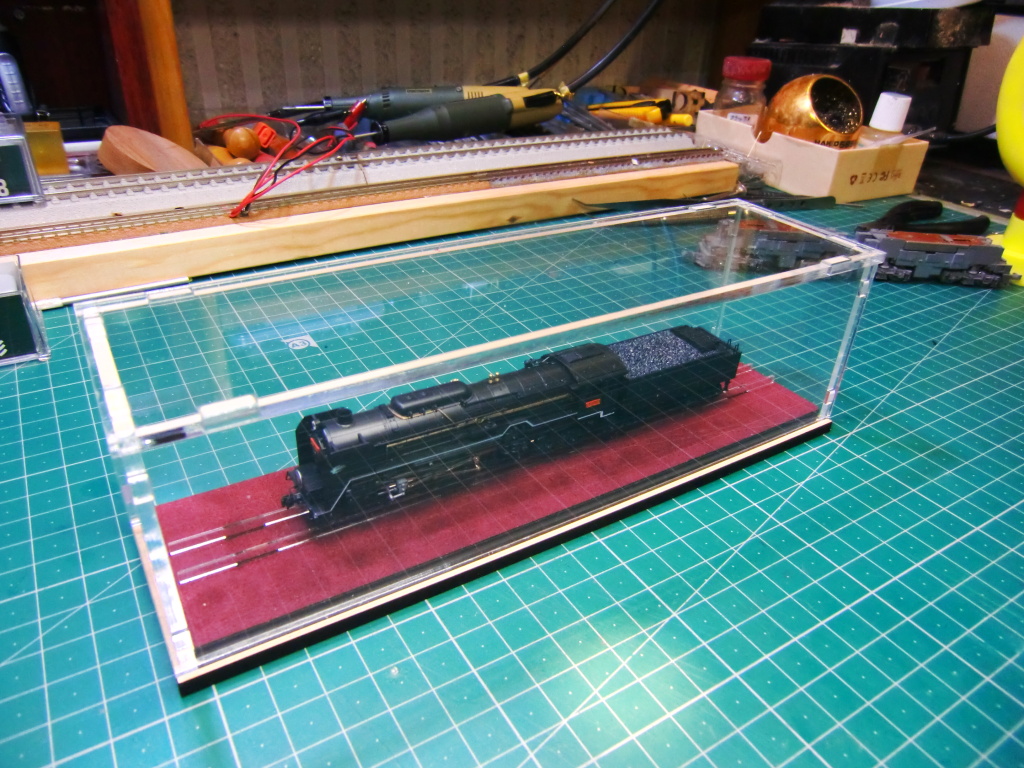

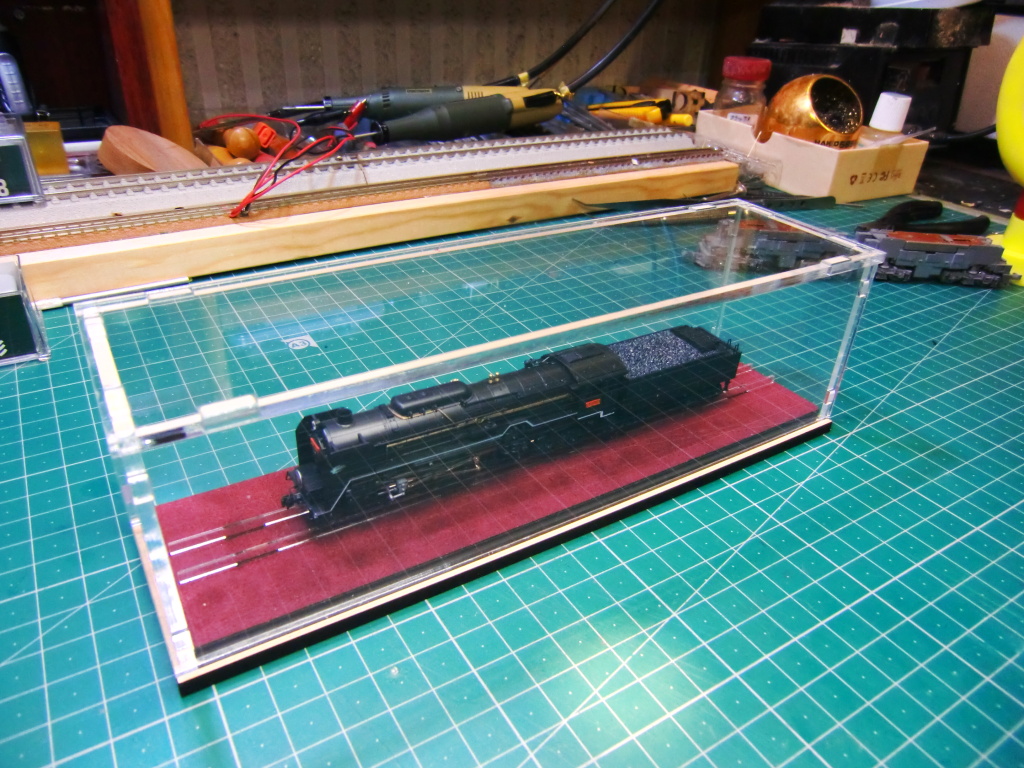
▼HO/16番用は受注生産 ※Nは在庫ストック
N以外のスケールは、ご注文を受けてからの制作となります。
▼[Nゲージ用]アクリル製ディスプレイケース「外形:210mm/レール長:198mm」・・2,200円(税込)
▼[HO/16番]アクリル製ディスプレイケース「外形:300mm/レール長:288mm」・・4,180円(税込)
※一般的な機関車の展示に最適なサイズでございます。
▼HO/16番 アクリル製・ディスプレイケースW「外形:350mm/レール長:338mm」・・5,280円(税込)
※上記のレール長に収まらない場合は、こちらのワイドサイズをご用意しました。EH-xxなど2連機関車に対応可能です。
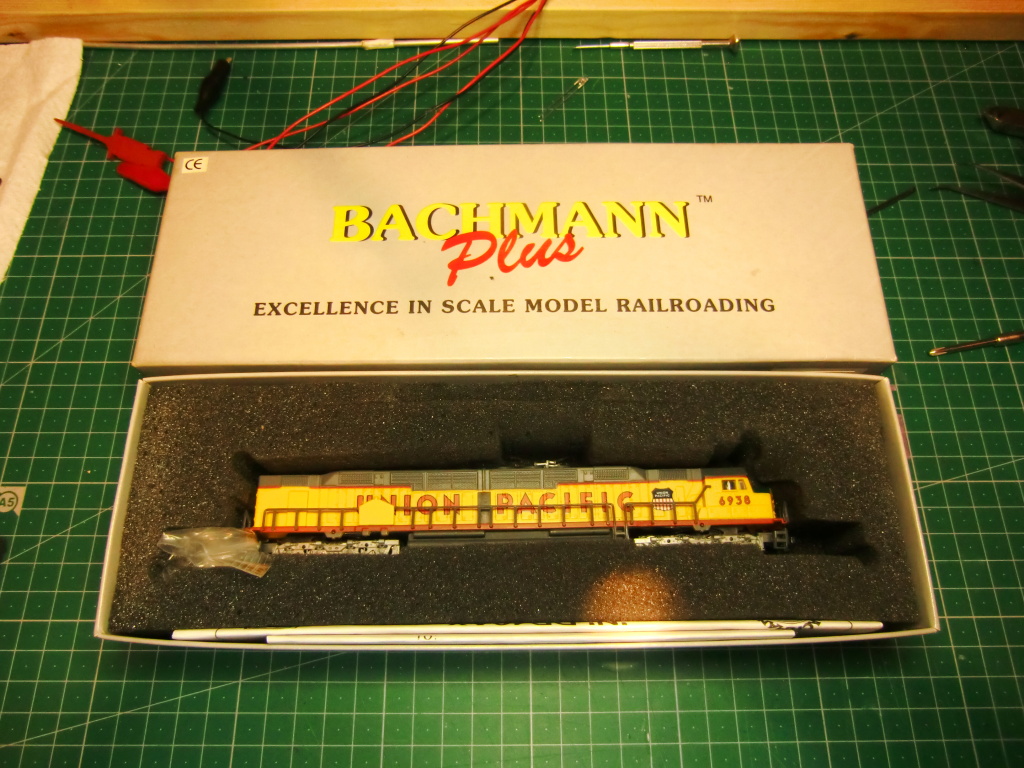


現状を確認します。

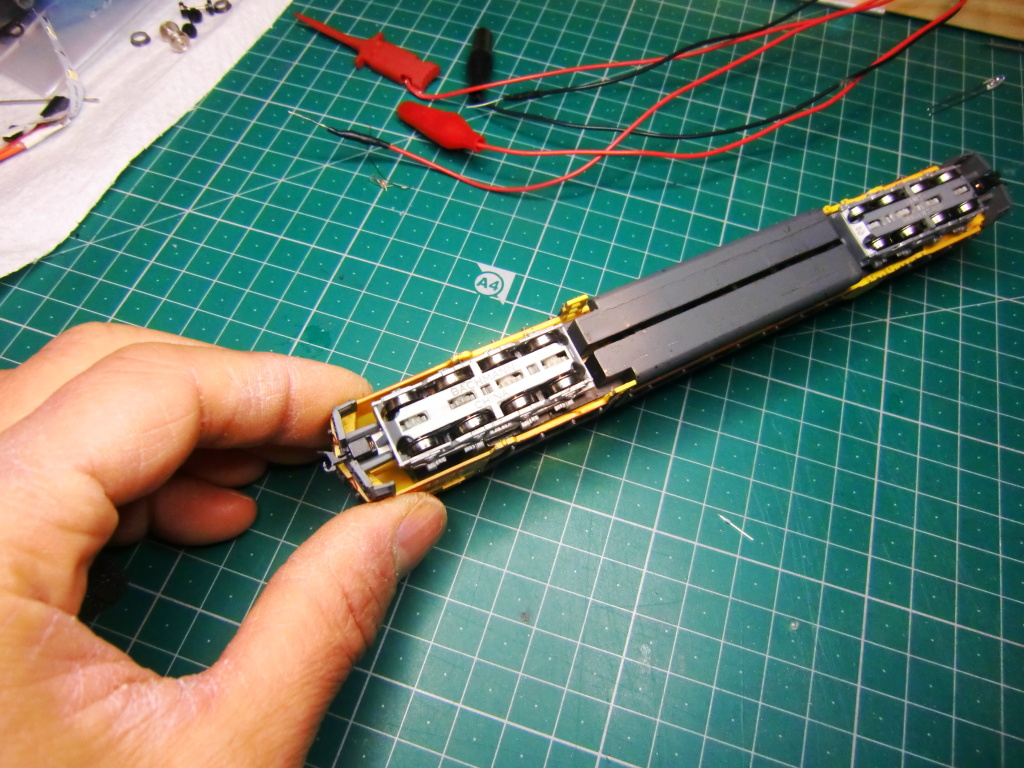
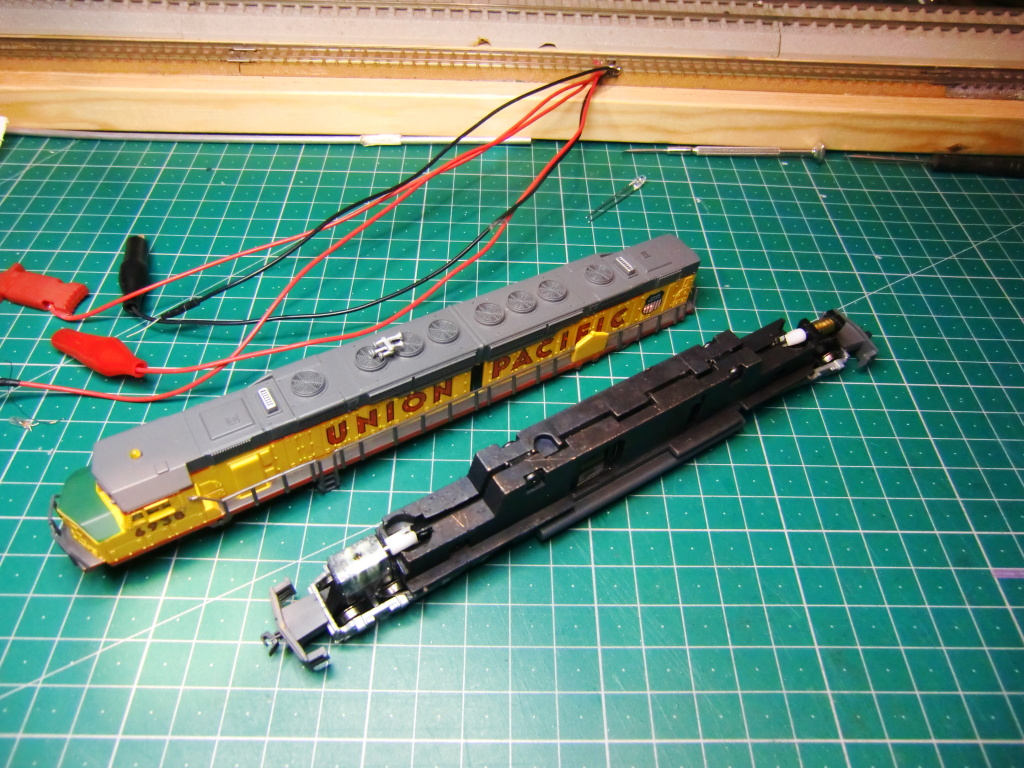
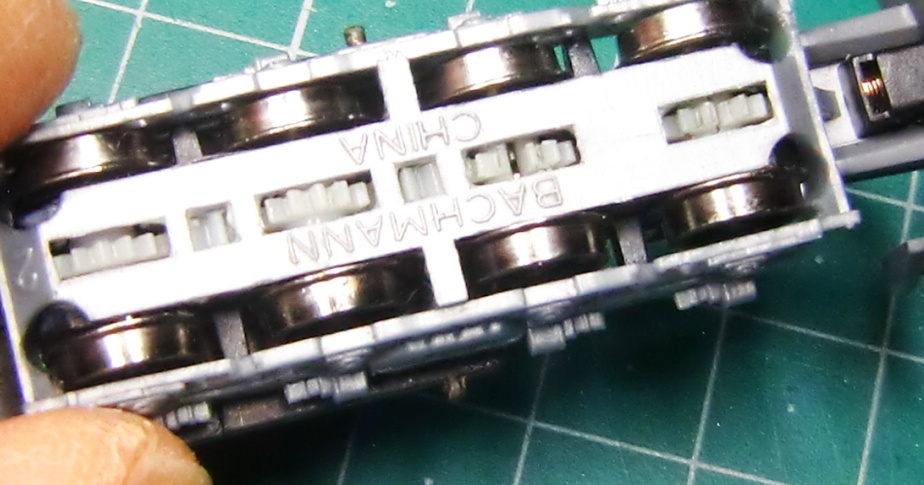
ギアが割れてしまっています。すべてのギアを作り直します。
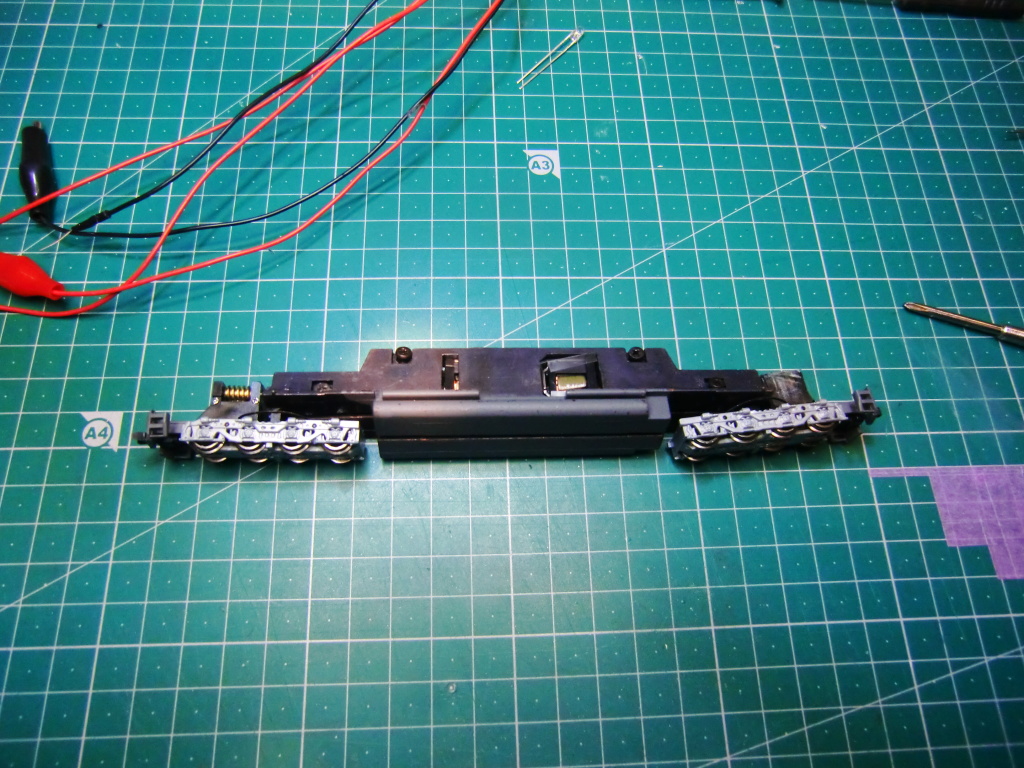
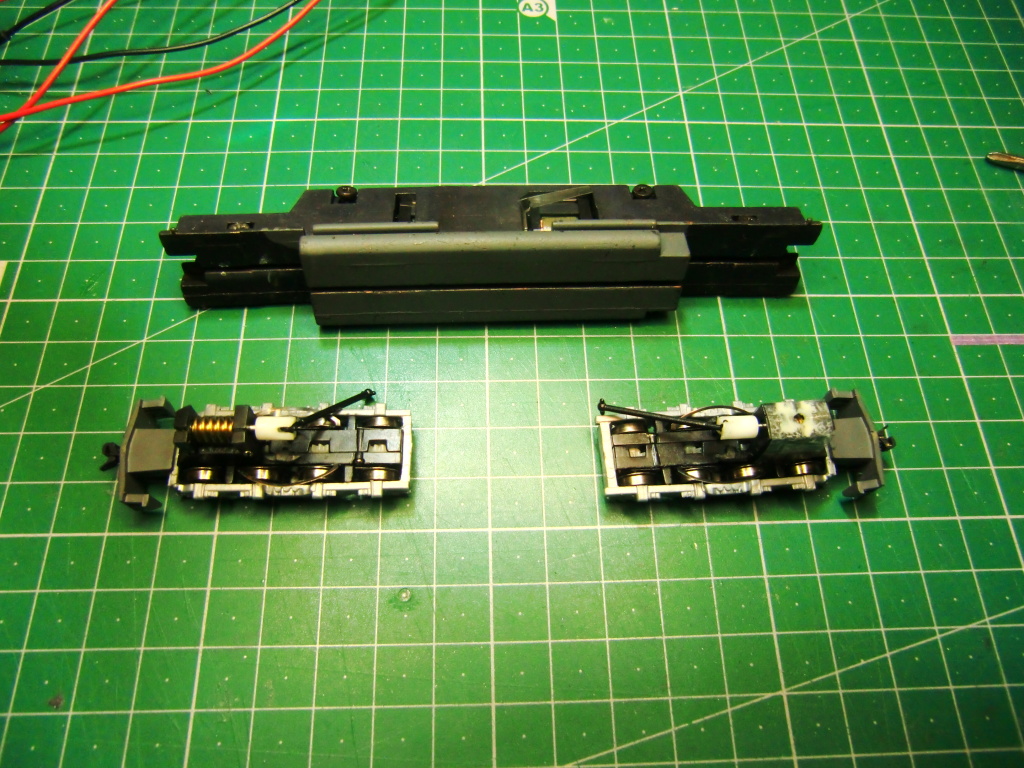
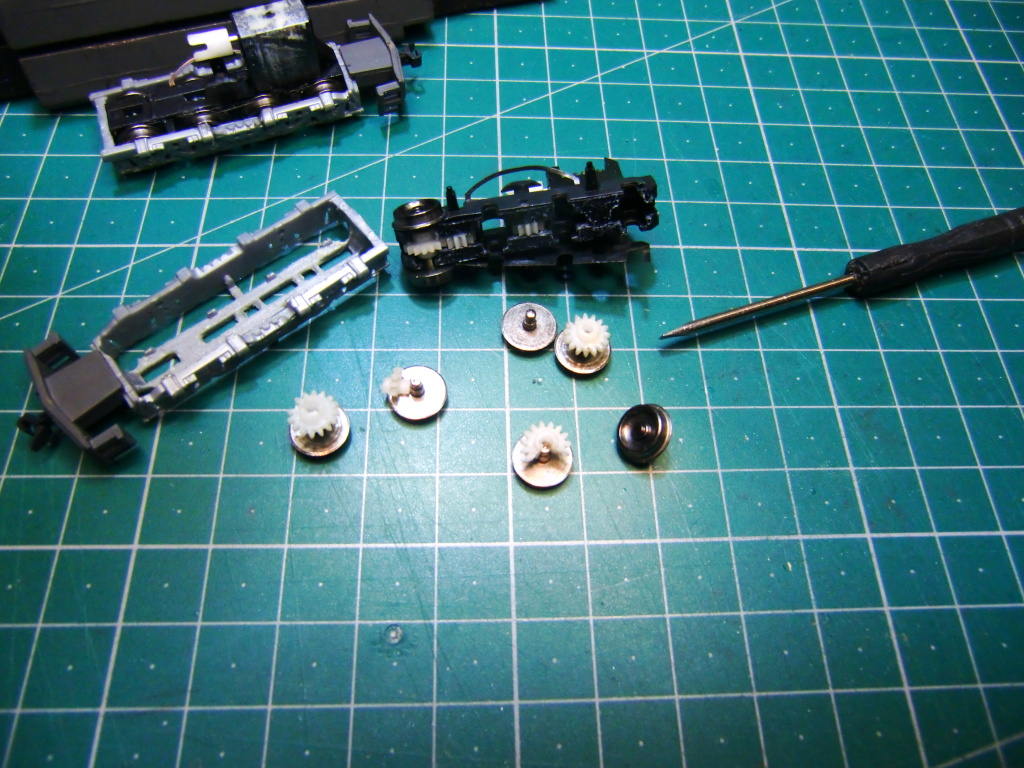

すべて割れています。
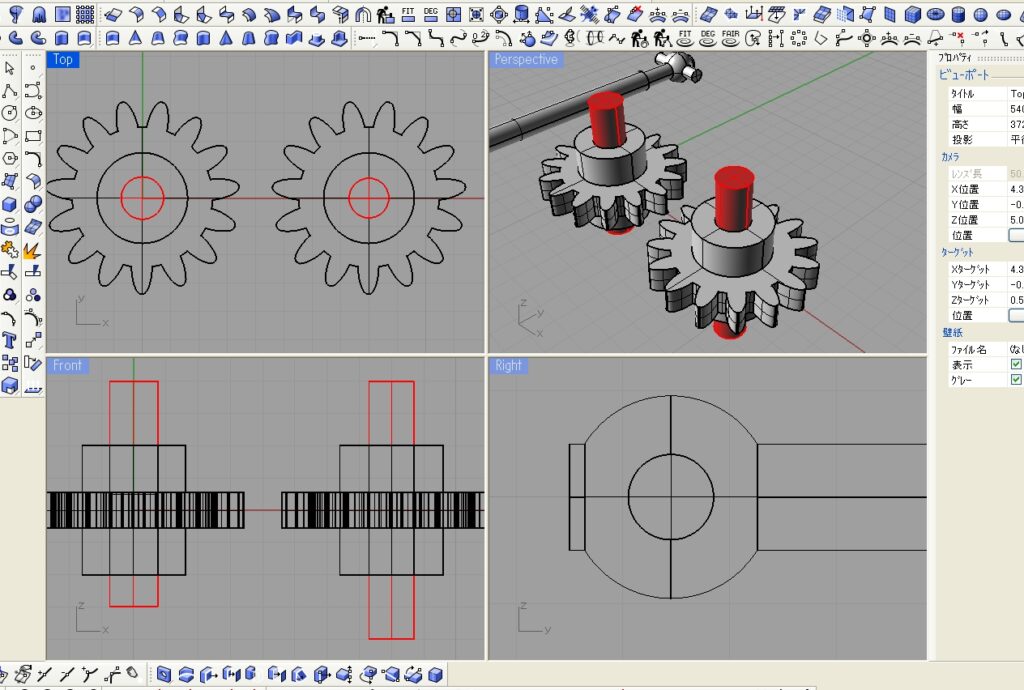
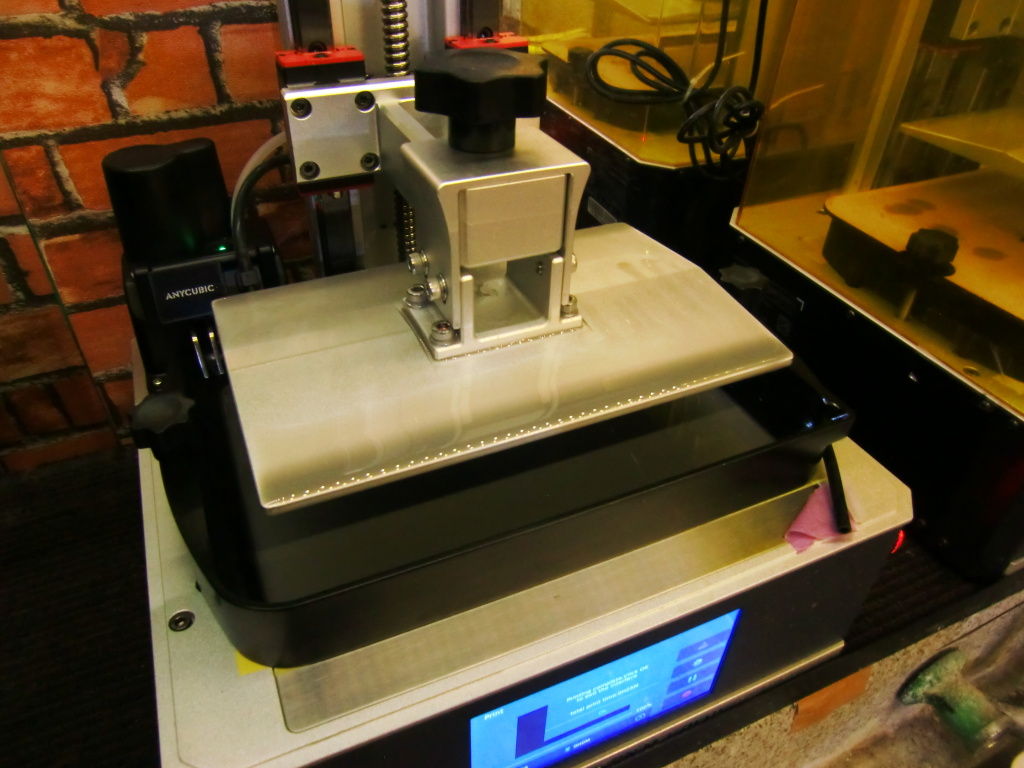


ギアが出来上がったので、実際に組み込んで嚙み合いを調整していきます。
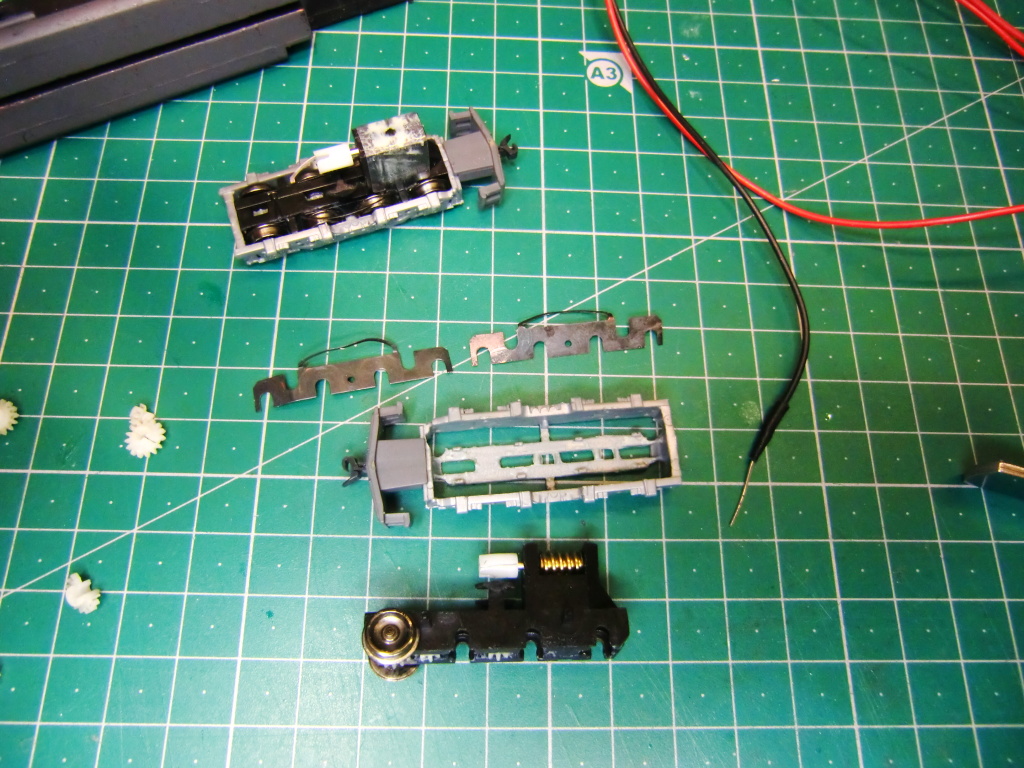
集電部も真っ黒ですので、一通りメンテを行っていきます。




スムーズに回転するまで、ピッチの調整を行います。
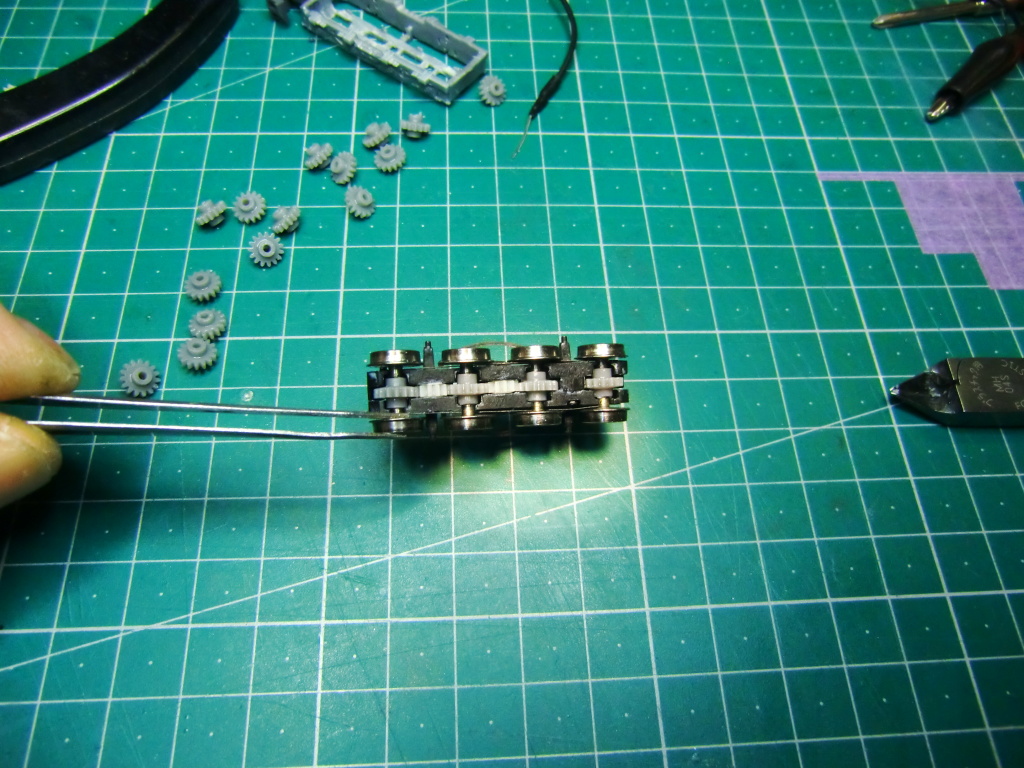
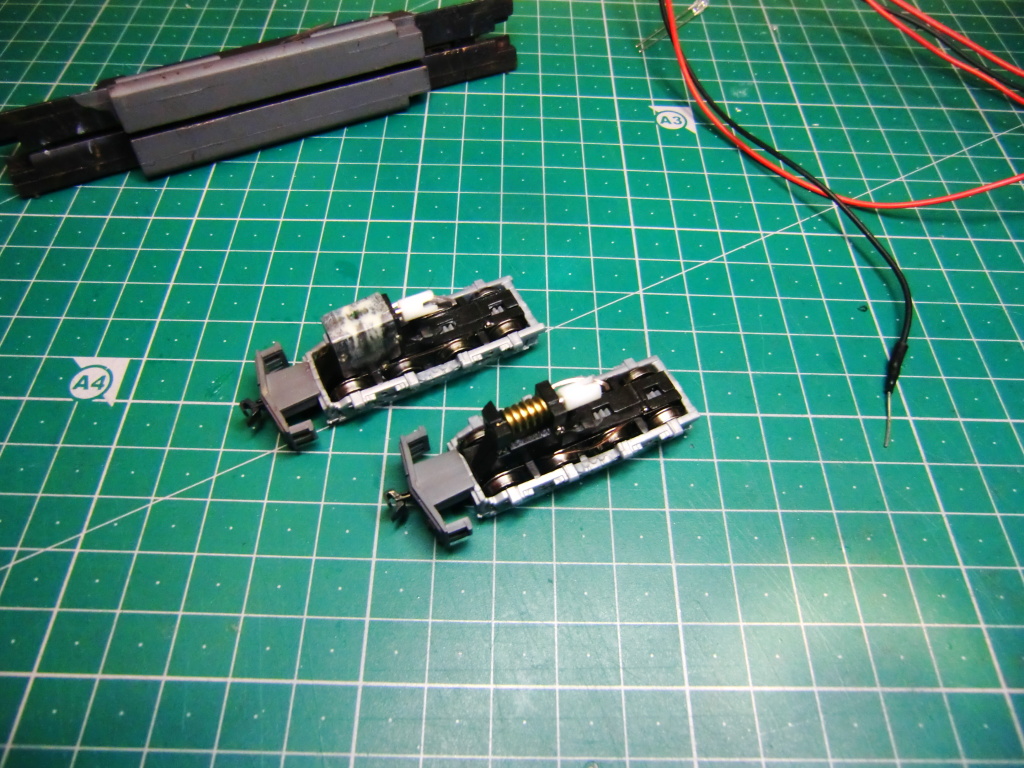
すべてのギアを制作して入れ替えました。
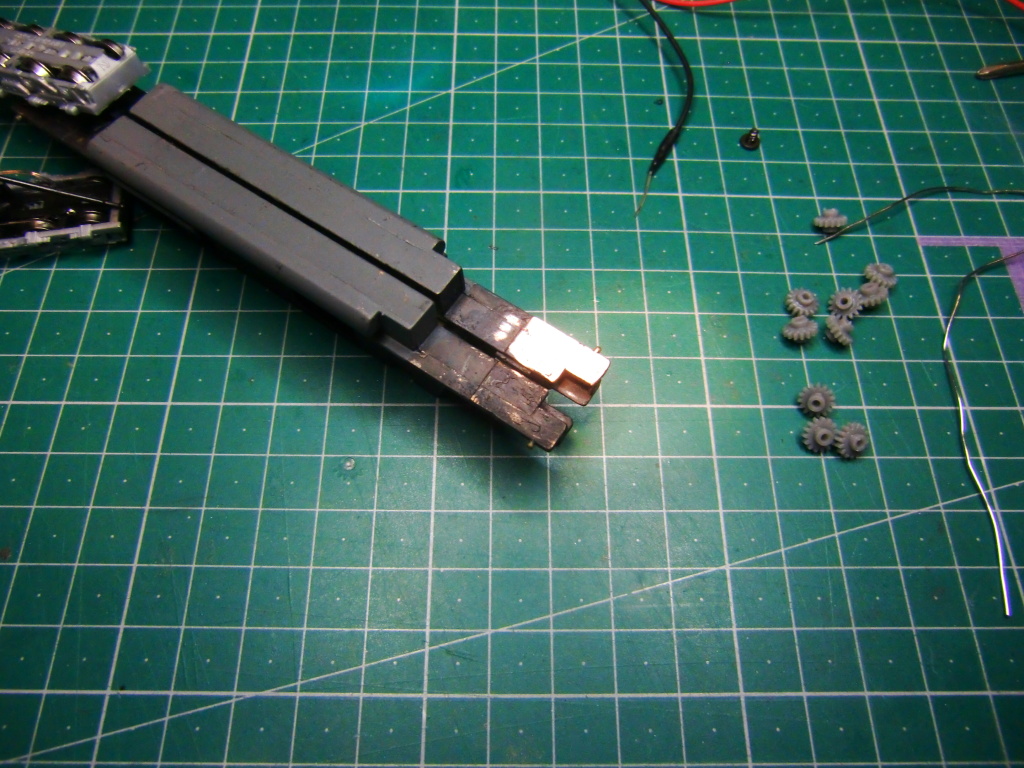
本体側の接点部も汚れとグリスで真っ黒でベタベタしてますので、こちらもメンテします。上がメンテ後の接点です。残りもすべて研ぎ出します。
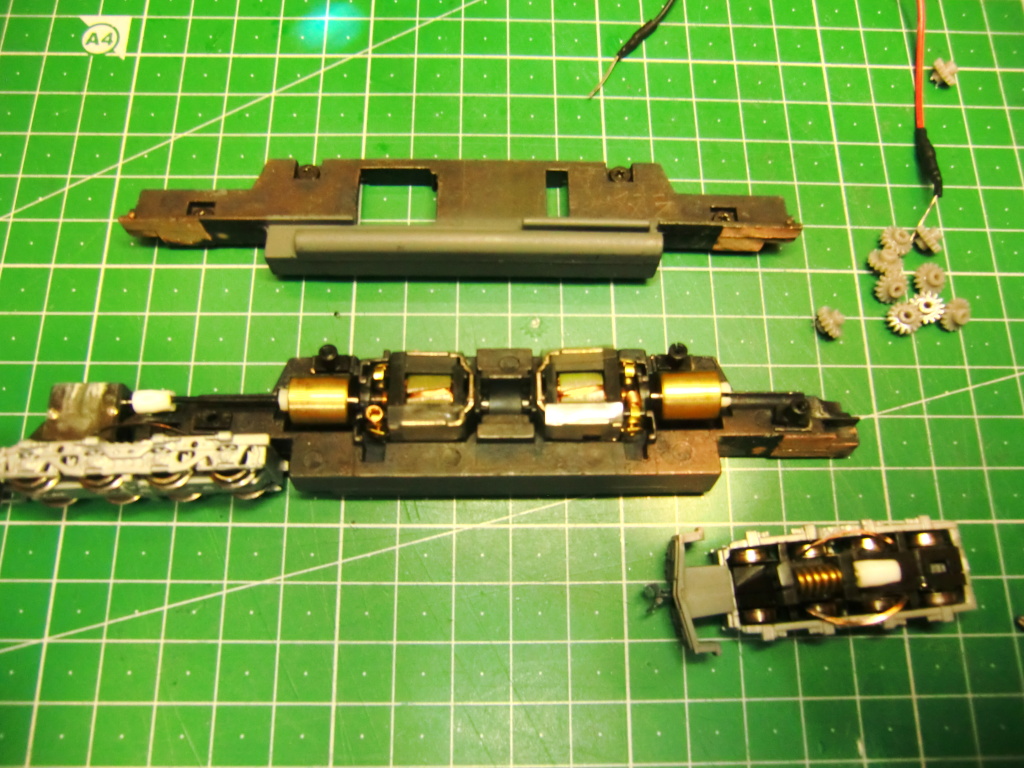
続いて、片側のモーターの回転が不安定のようです。いったんすべて分解して調整を行います。

一通り問題となっていた個所の修理が終わったところで、テスト走行して様子を見ます。

よさそうです。
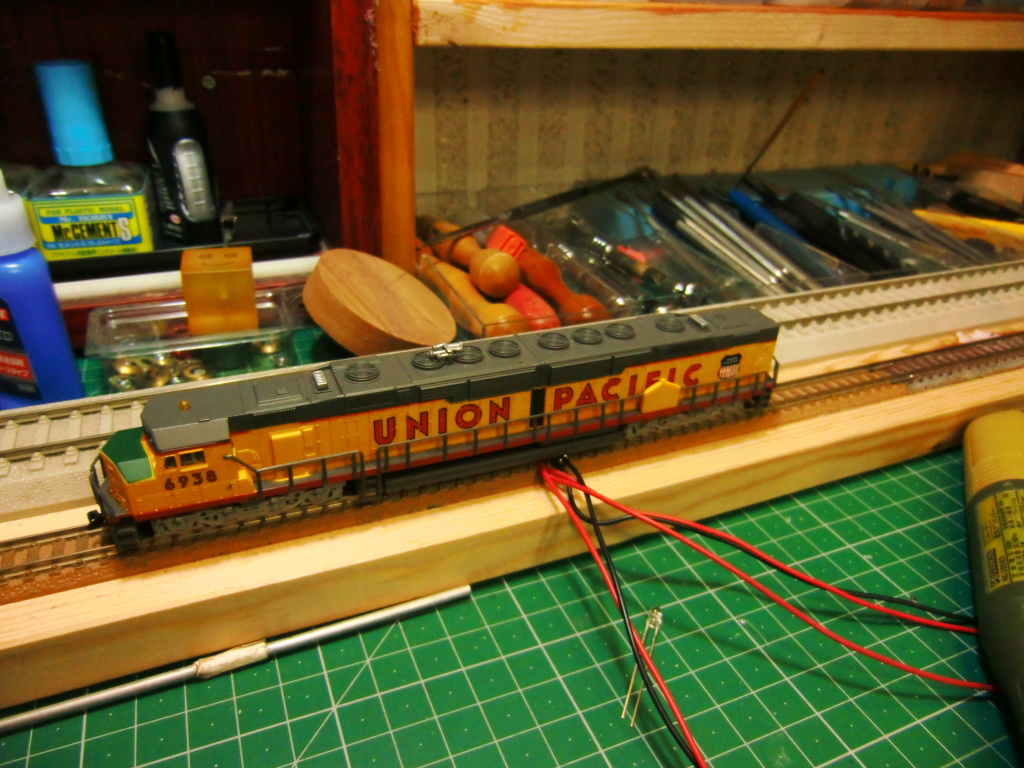
ボディーを被せて、さらに15分程度往復運転を行ってから問題なければ修理は完了となります。

最後にギアに少量の注油を行って、作業は無事完了しました。

▼A0496 922形サーチライト修理

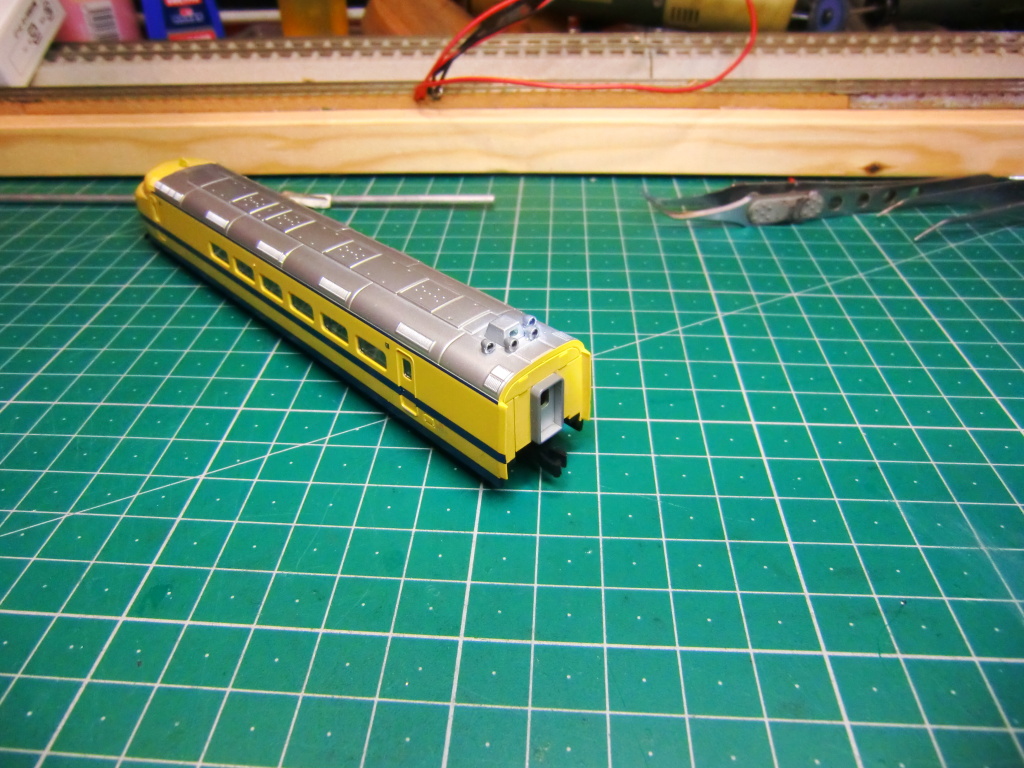

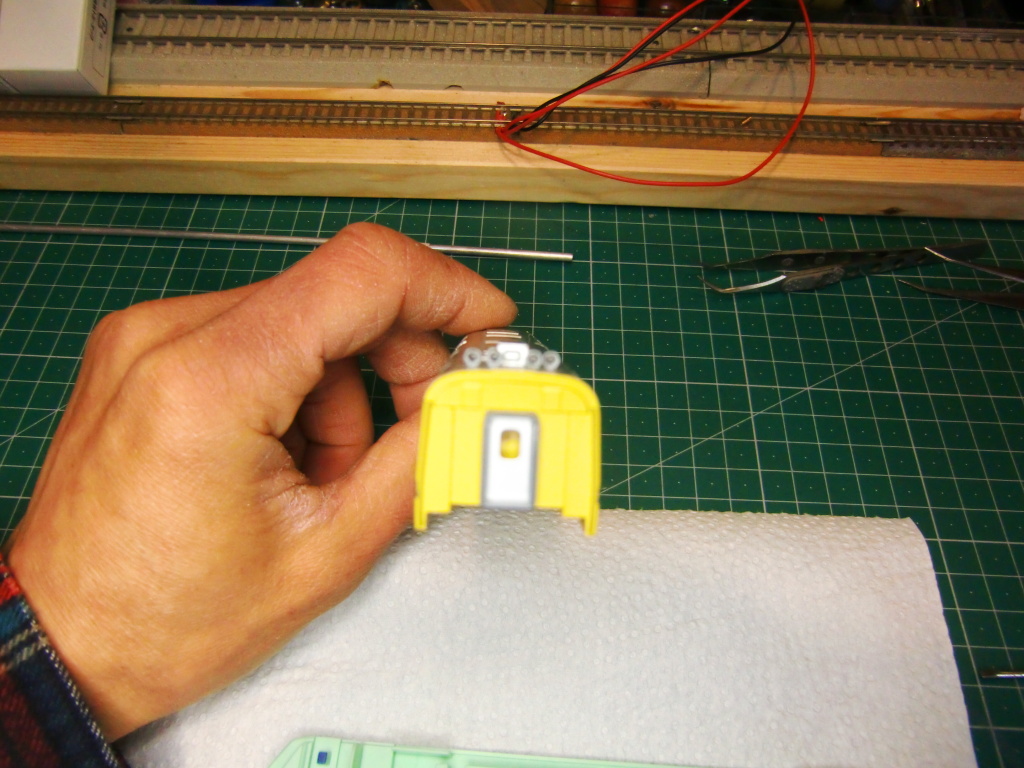
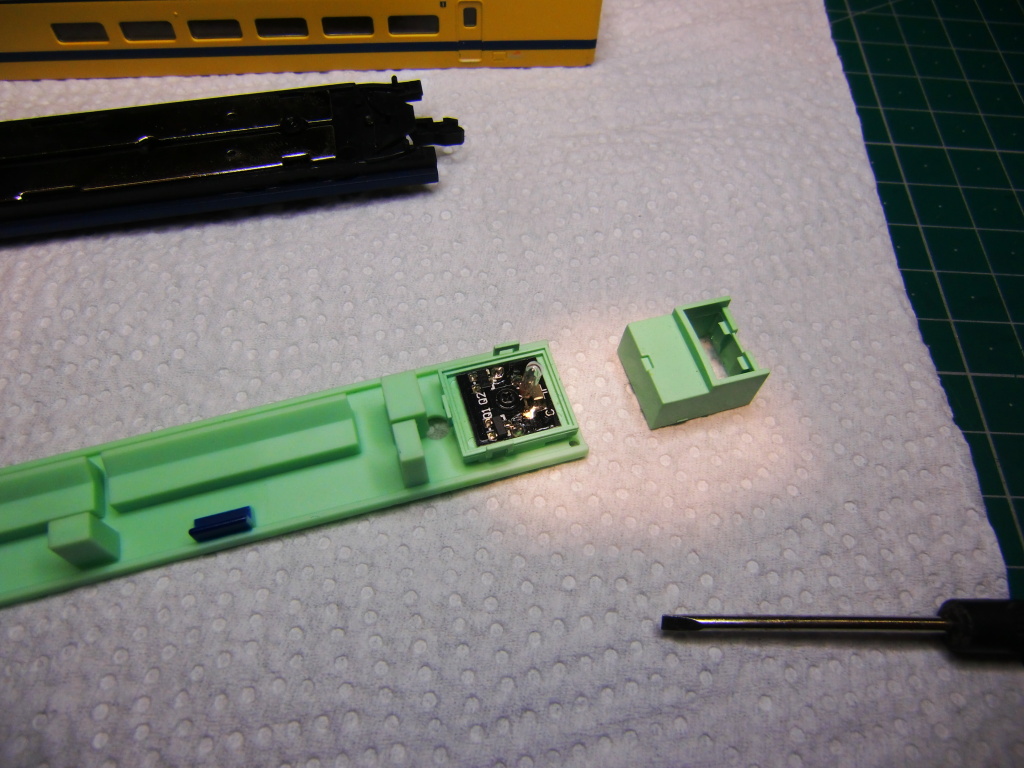
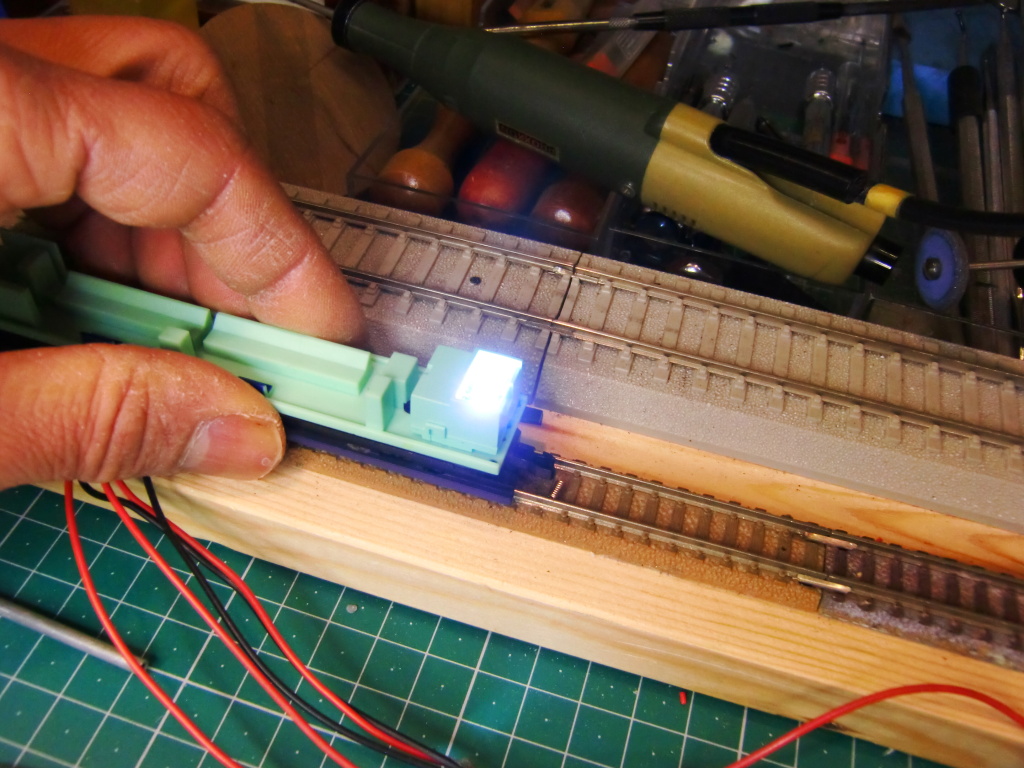

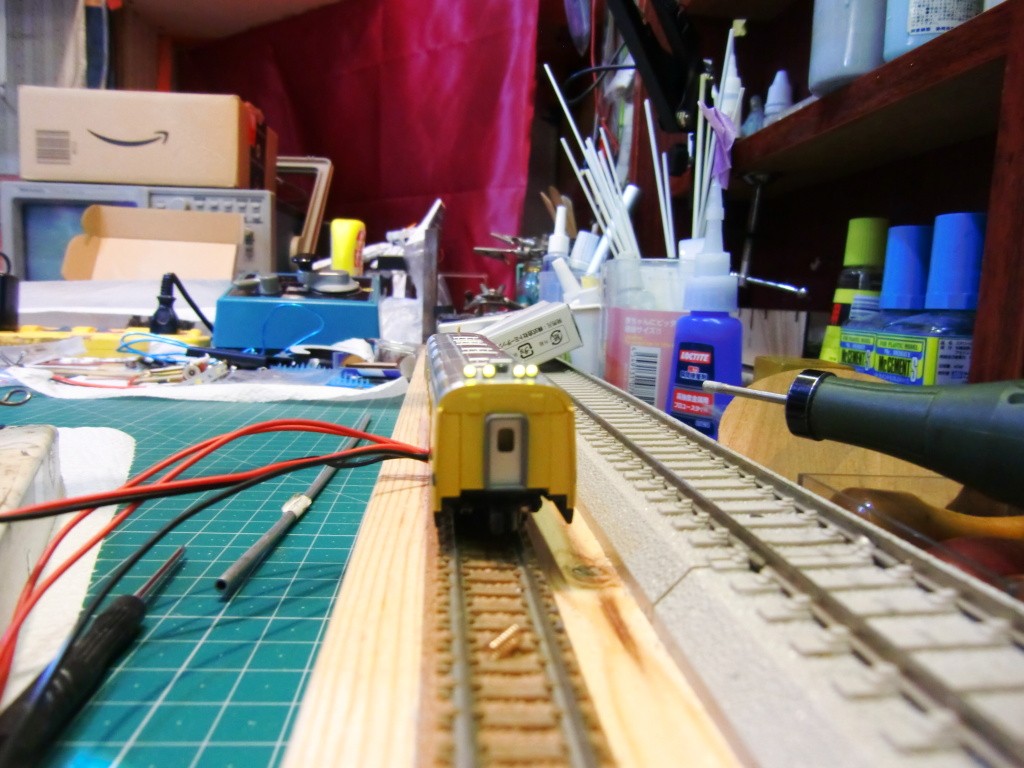
▼A0614-6 113系LED加工+M車同調




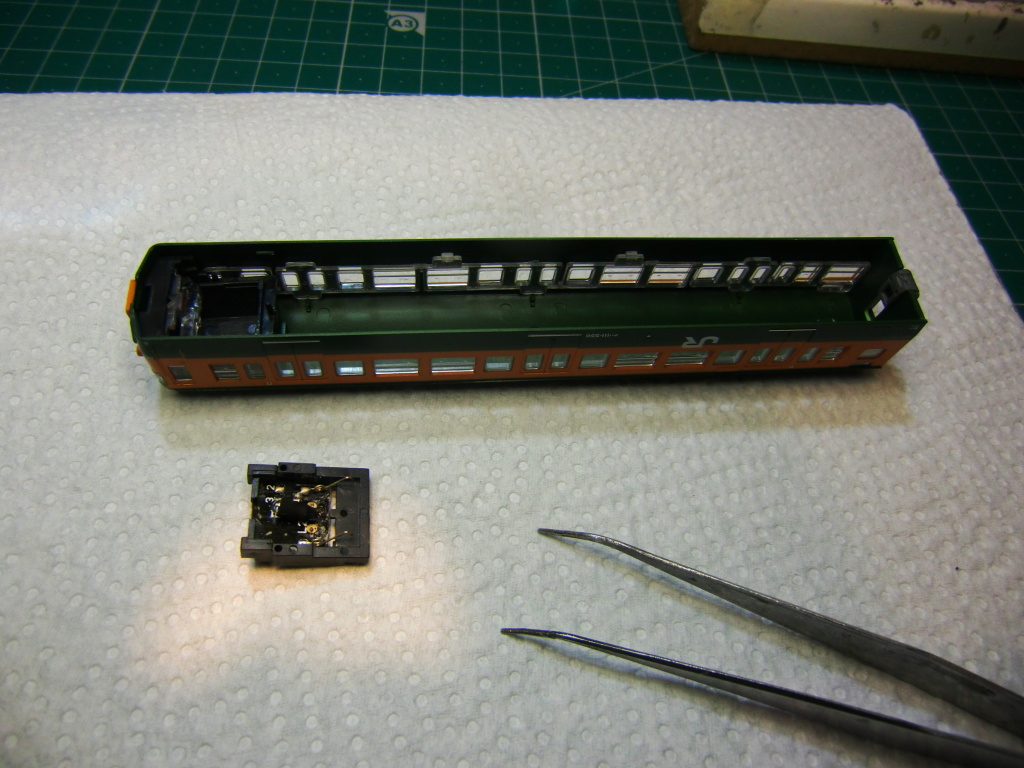
こちらの製品は旧製品ということで、電球が使用されていますのですべてLEDへ置き換えます。
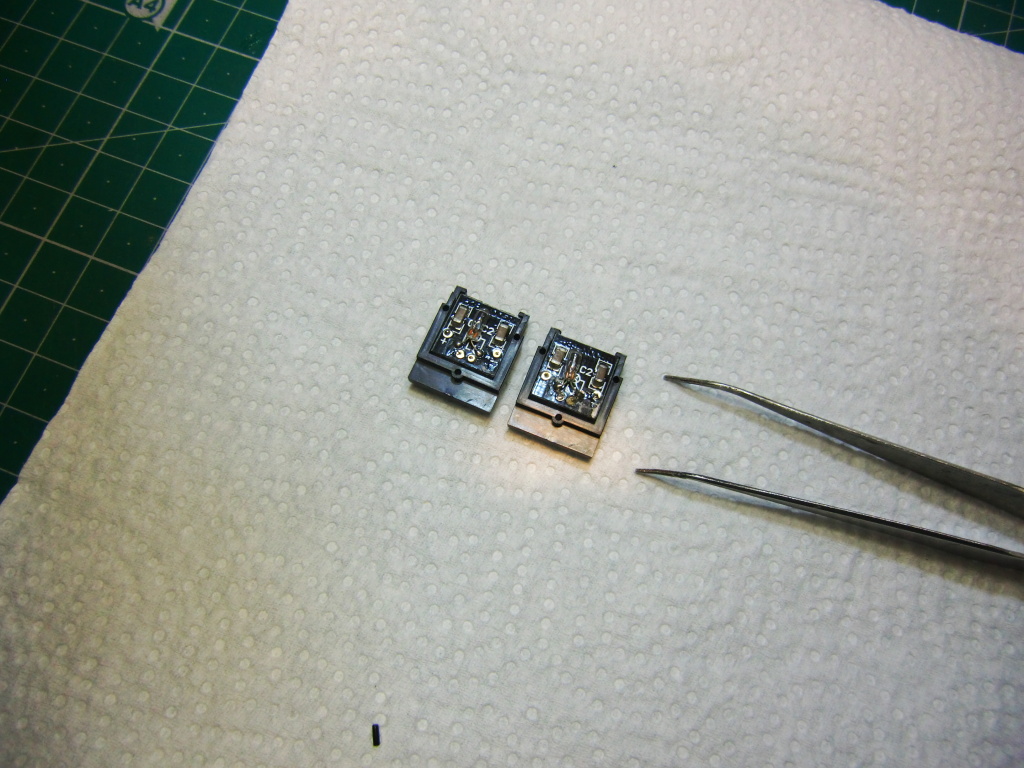
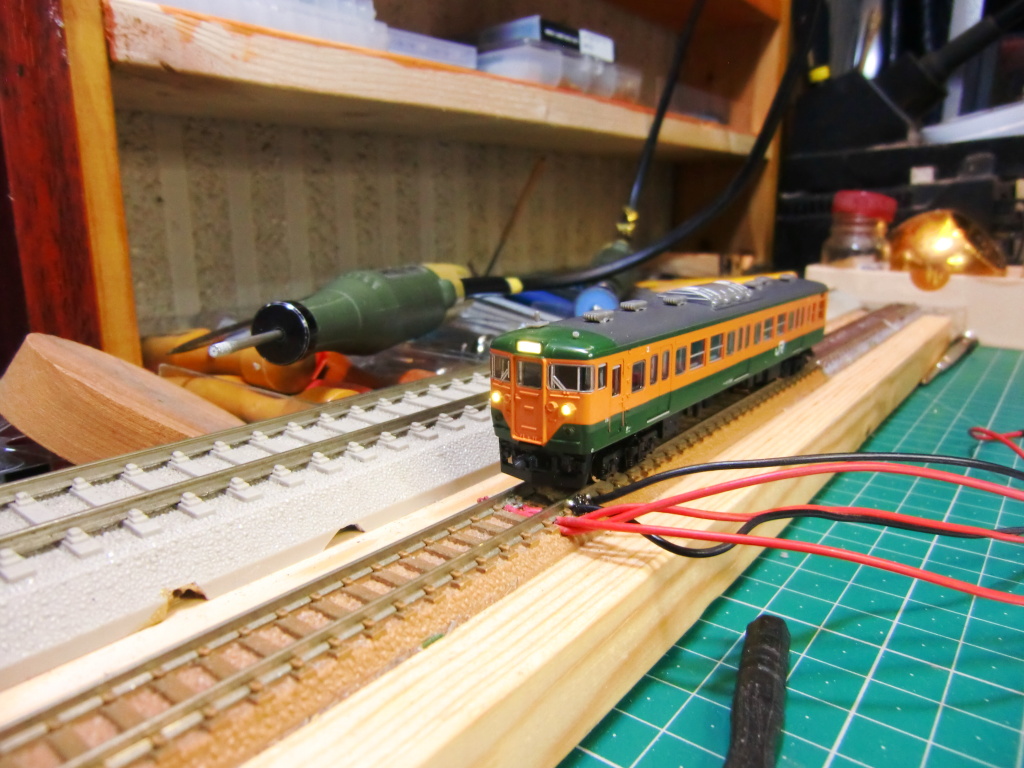
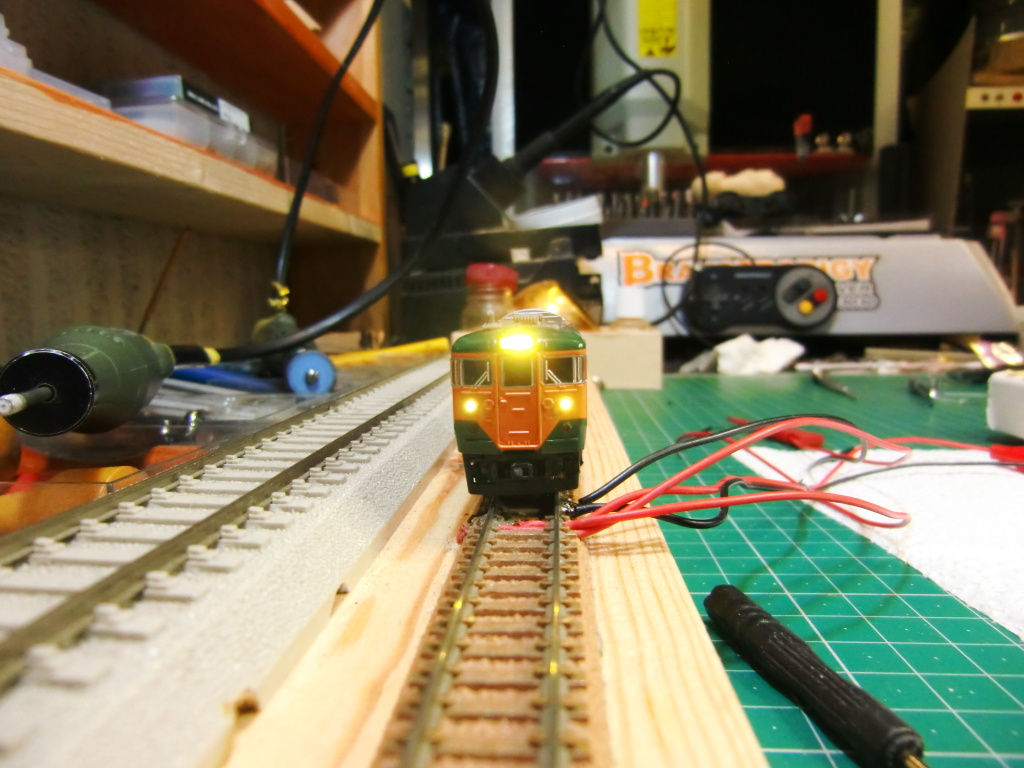

M車2両の速度差を確認して、どのように処理するか考えます。
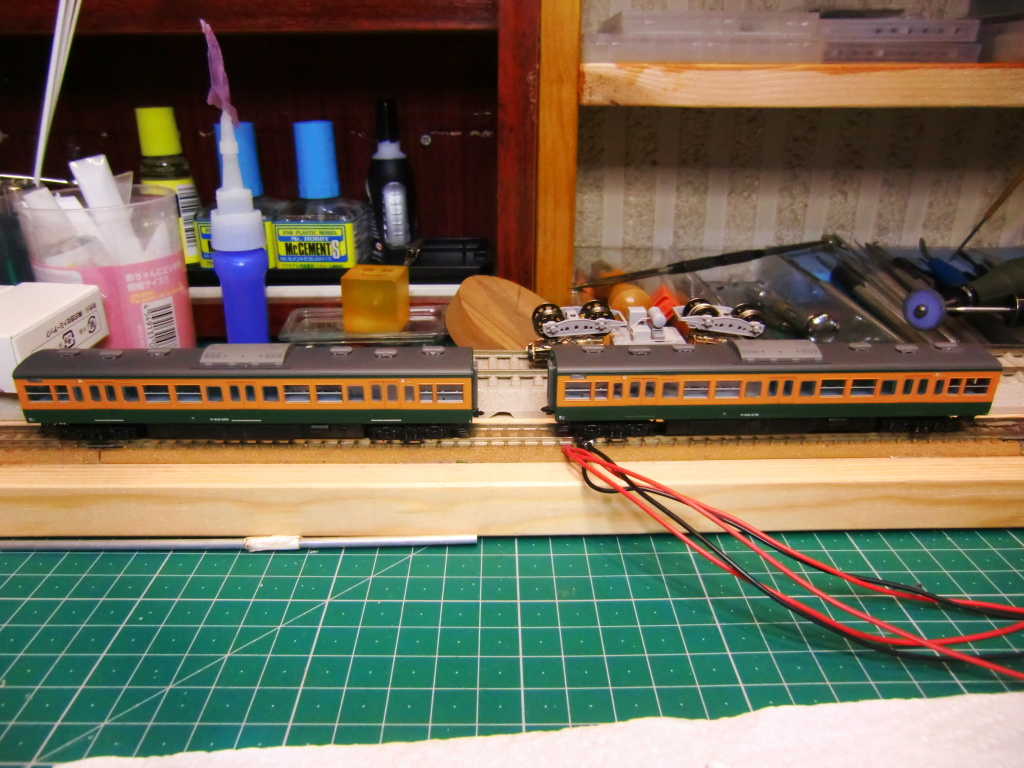
分解と各種調整を何度か繰り返しながら出来るだけ近い速度になるように調整していきます。
▼A0980 785系ライラック LED加工+M調整+ヘッドライトパーツ製作

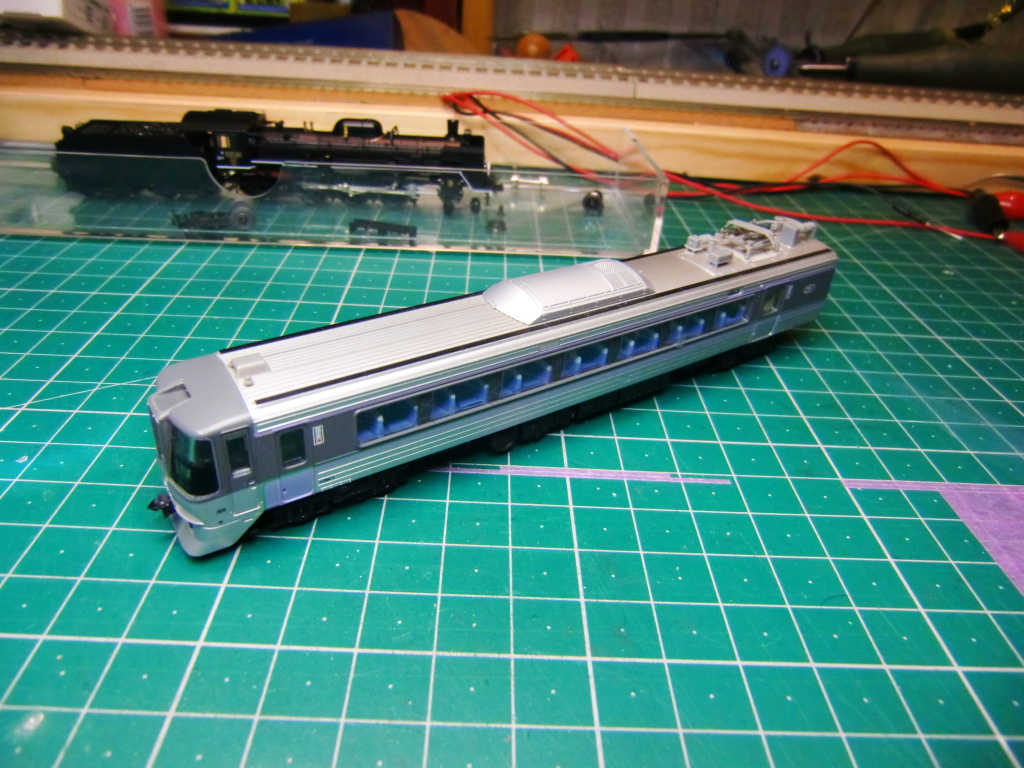
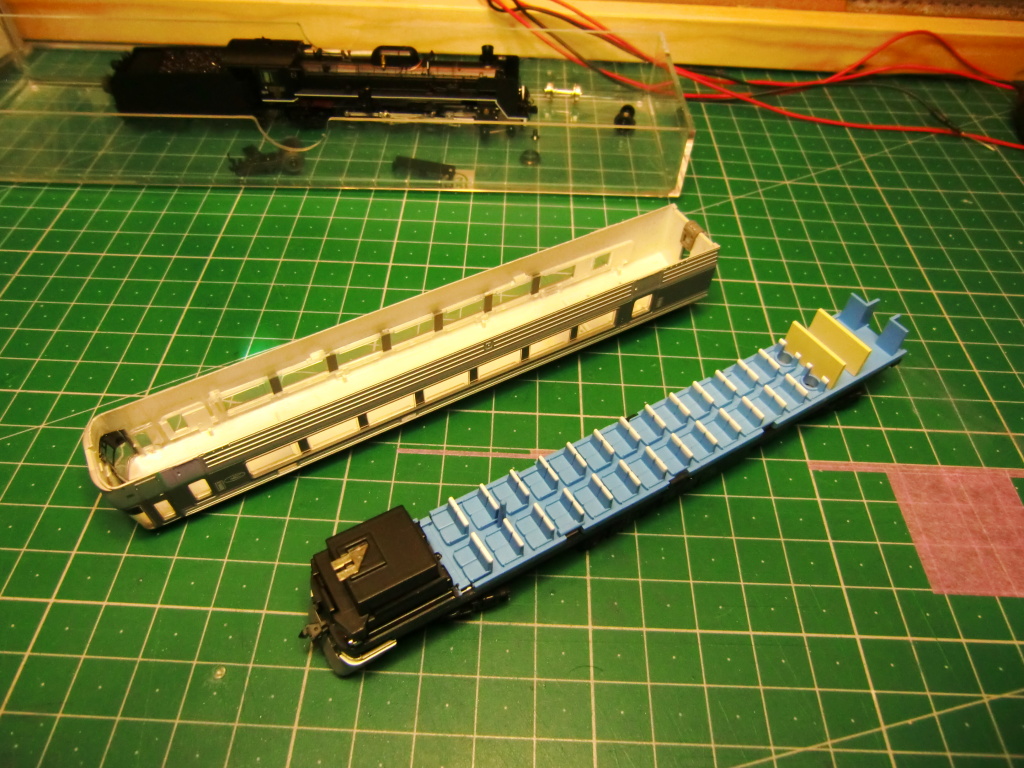
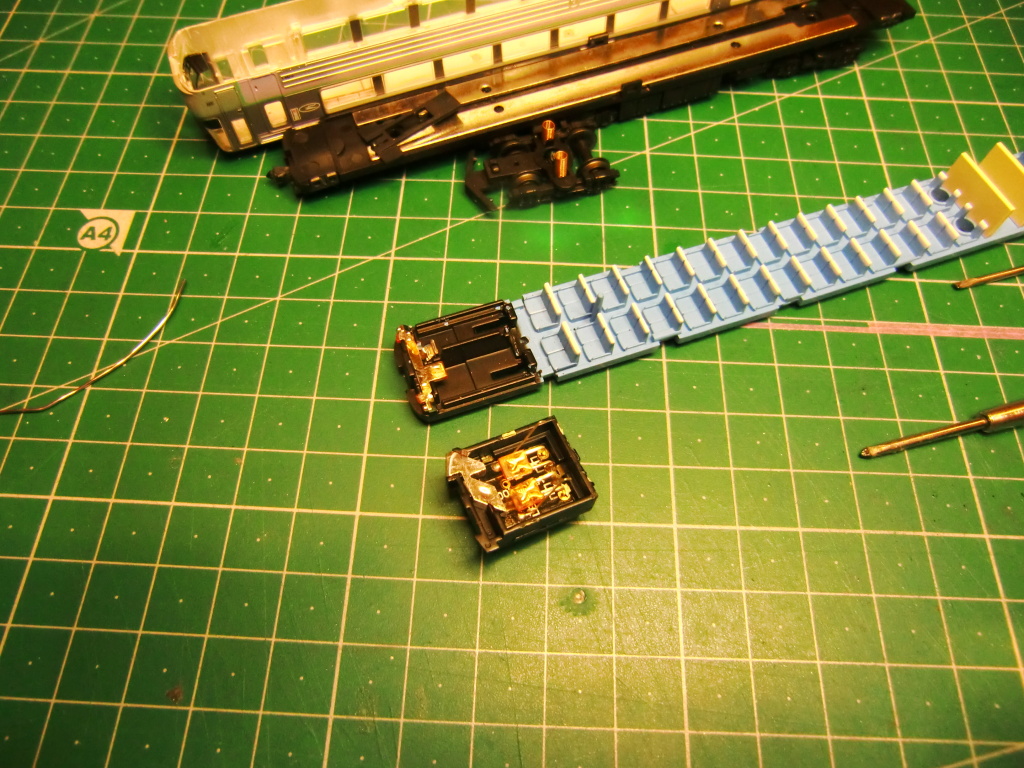

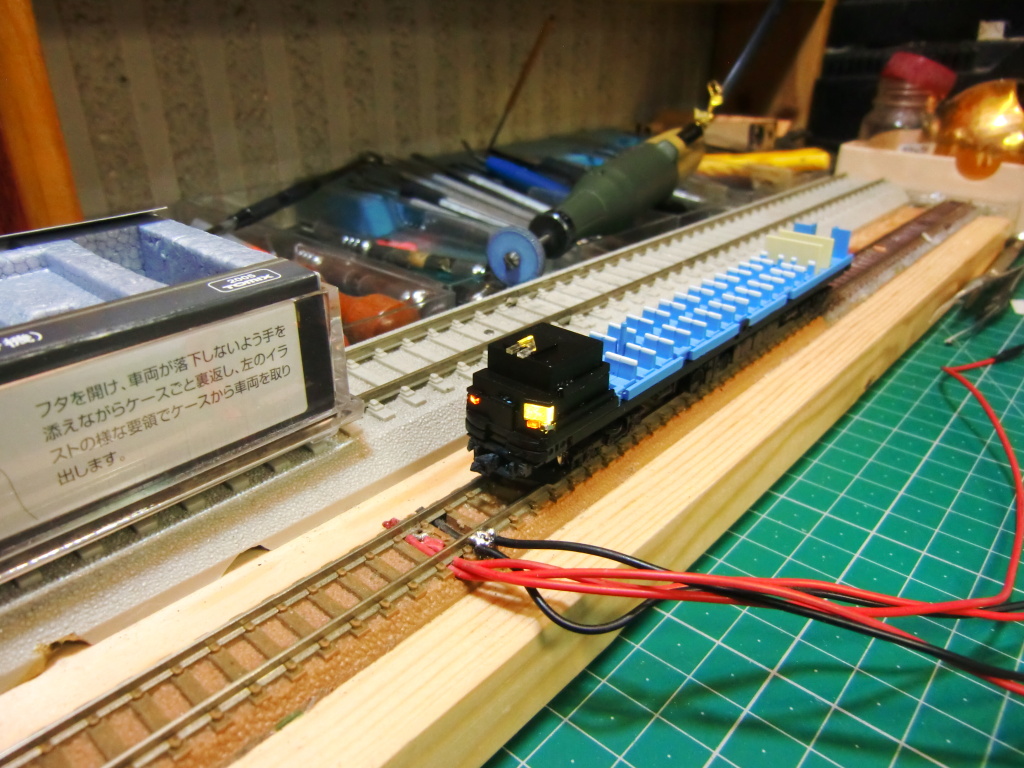
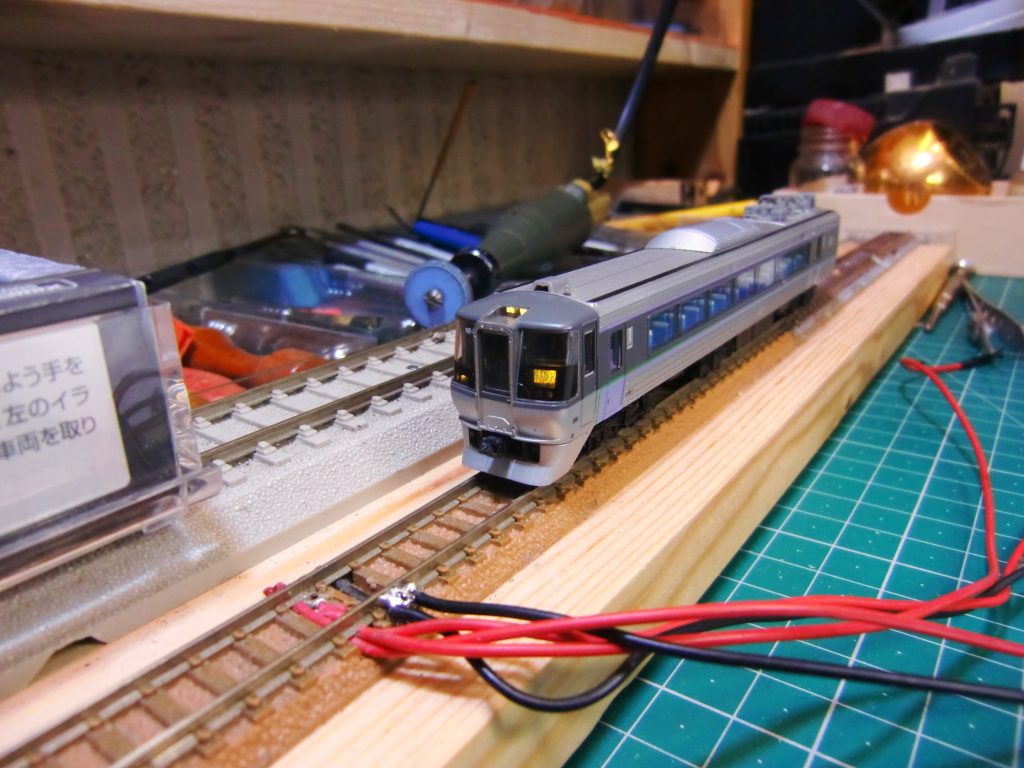
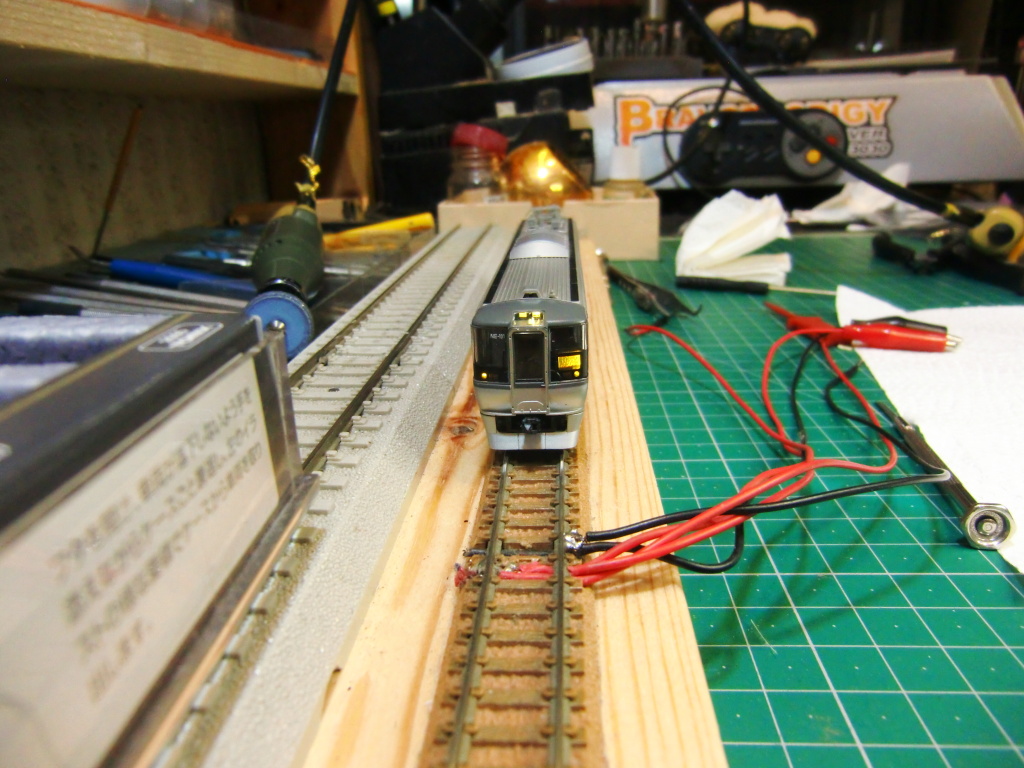

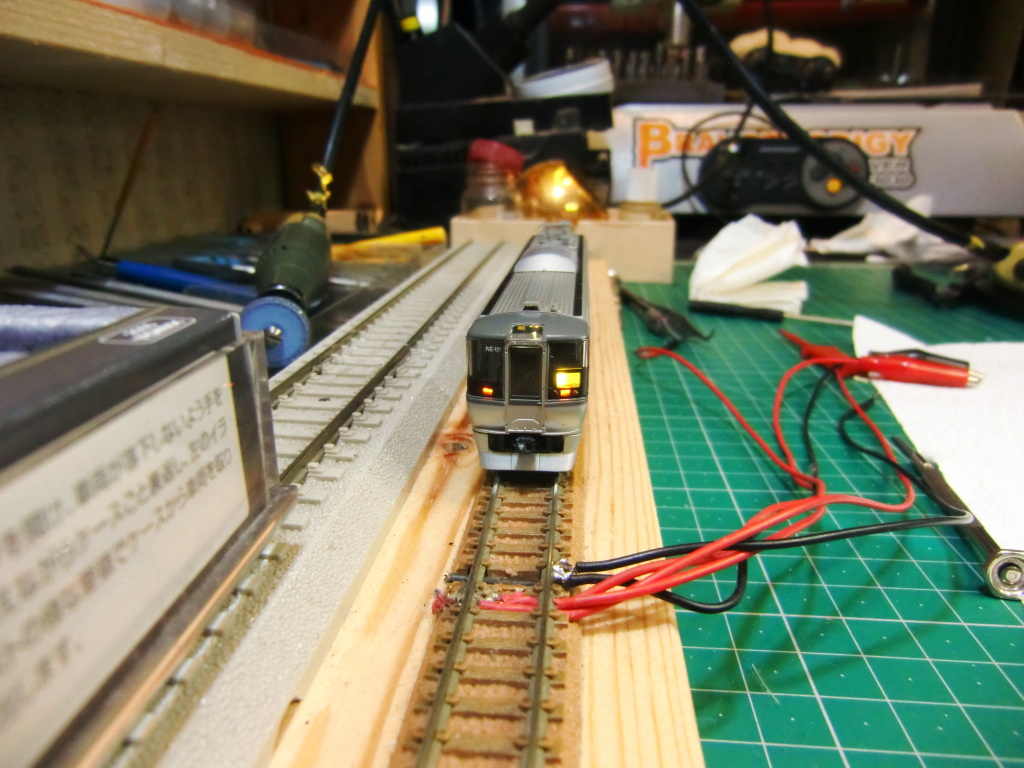
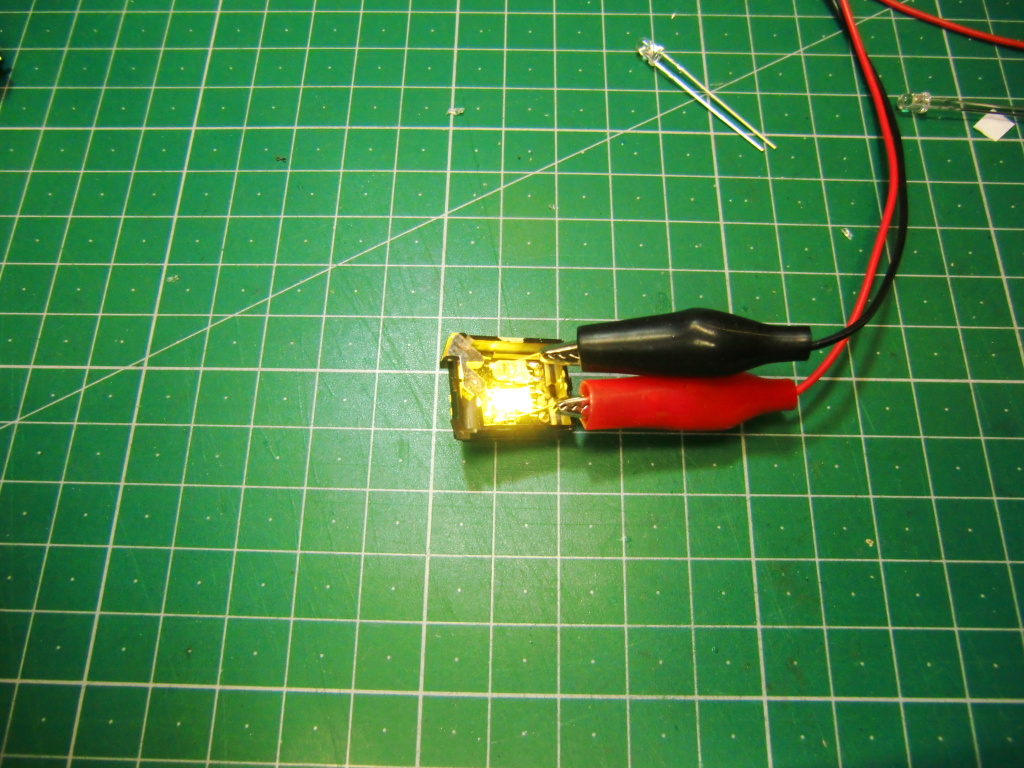
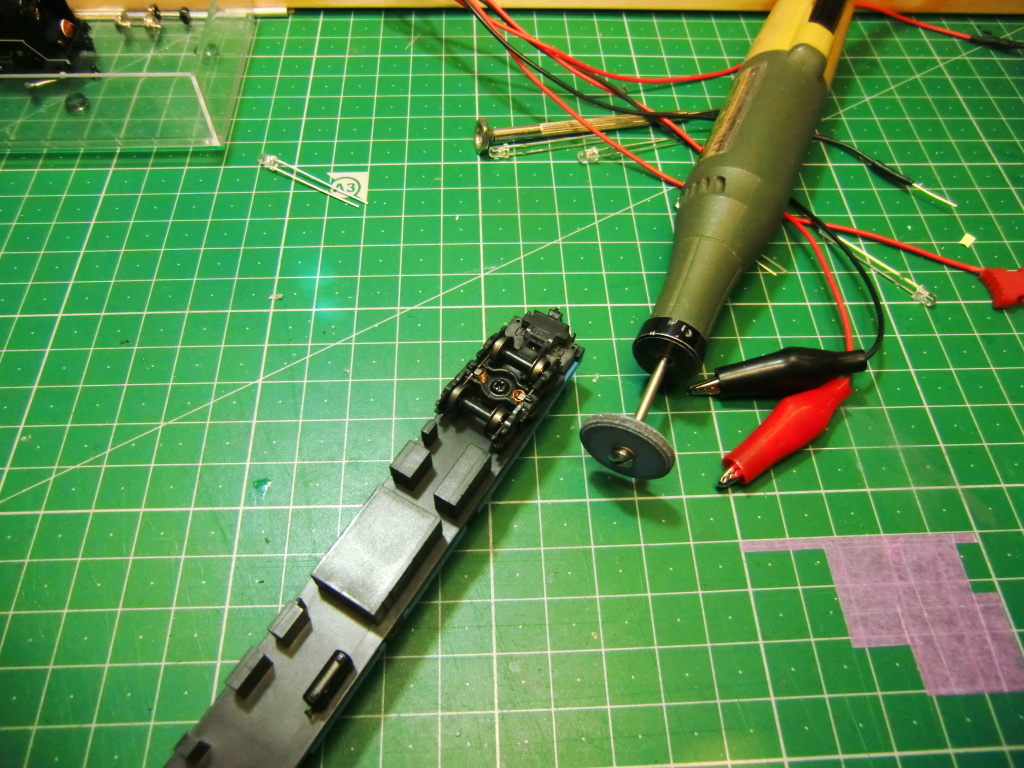
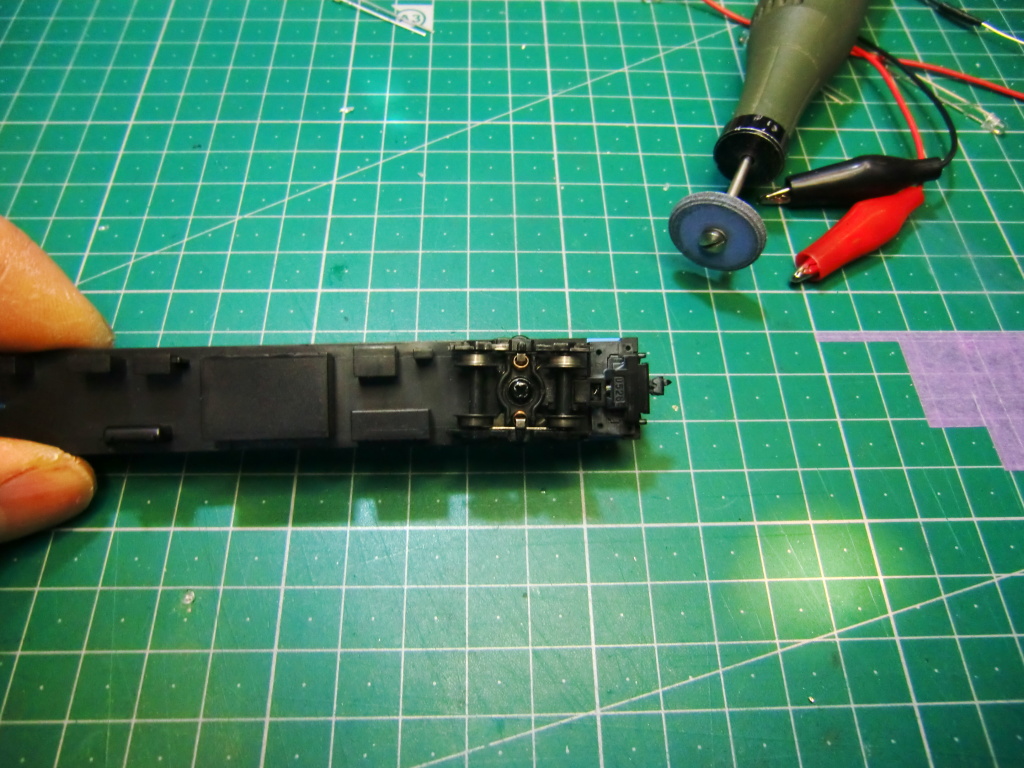
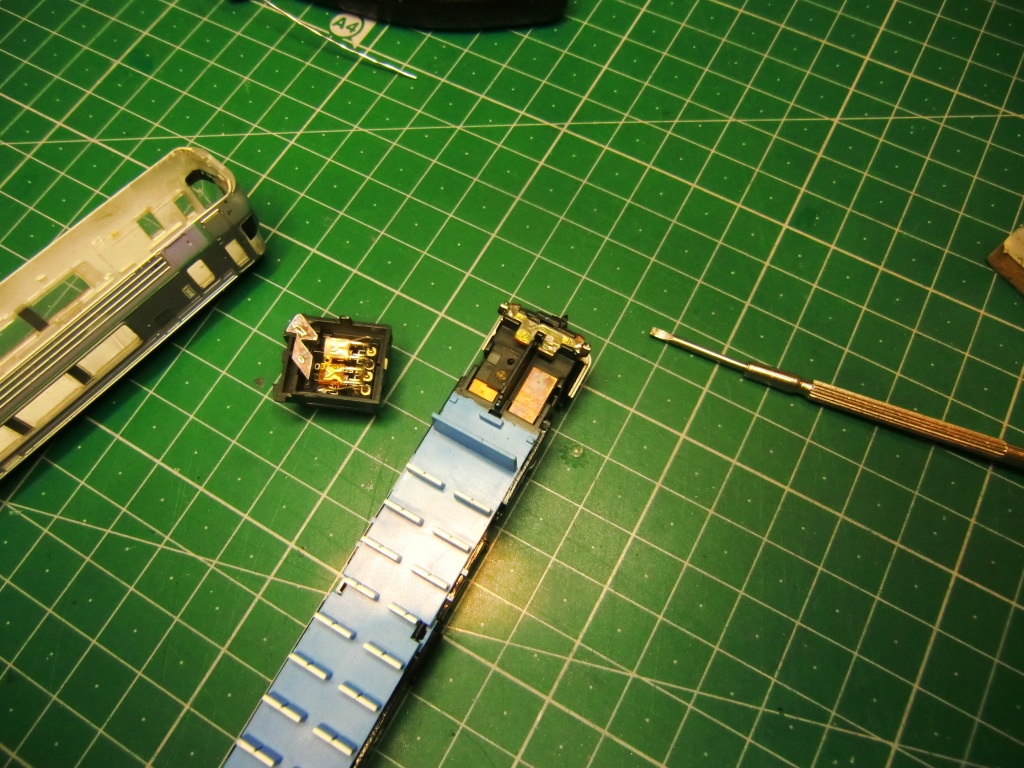
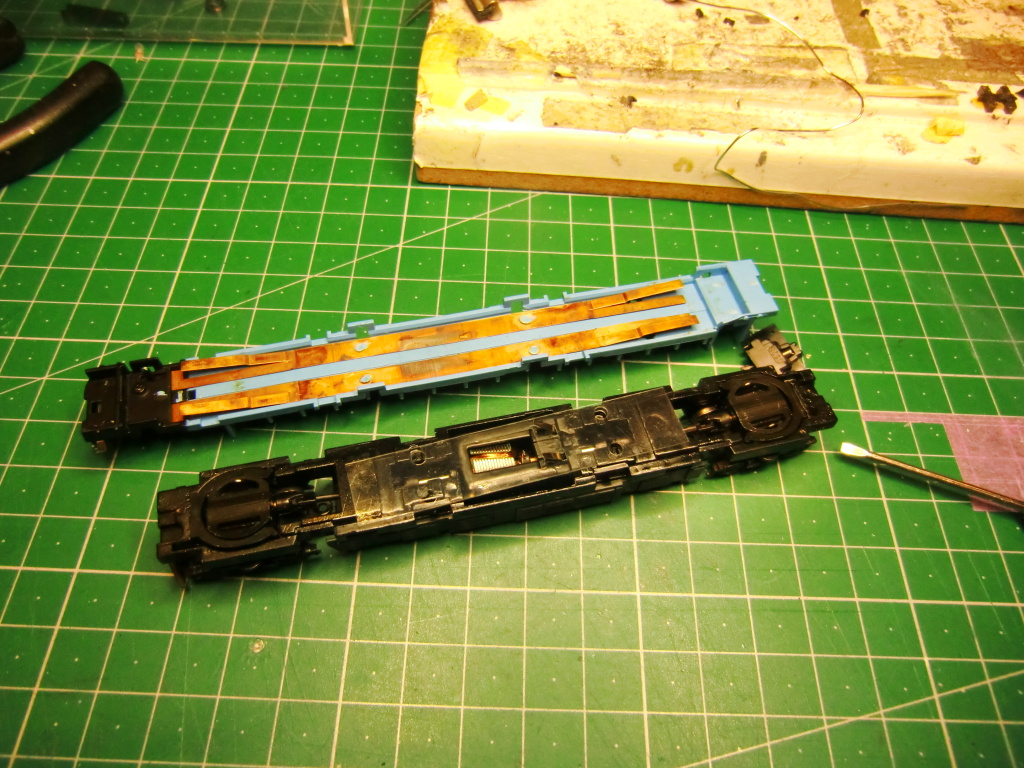
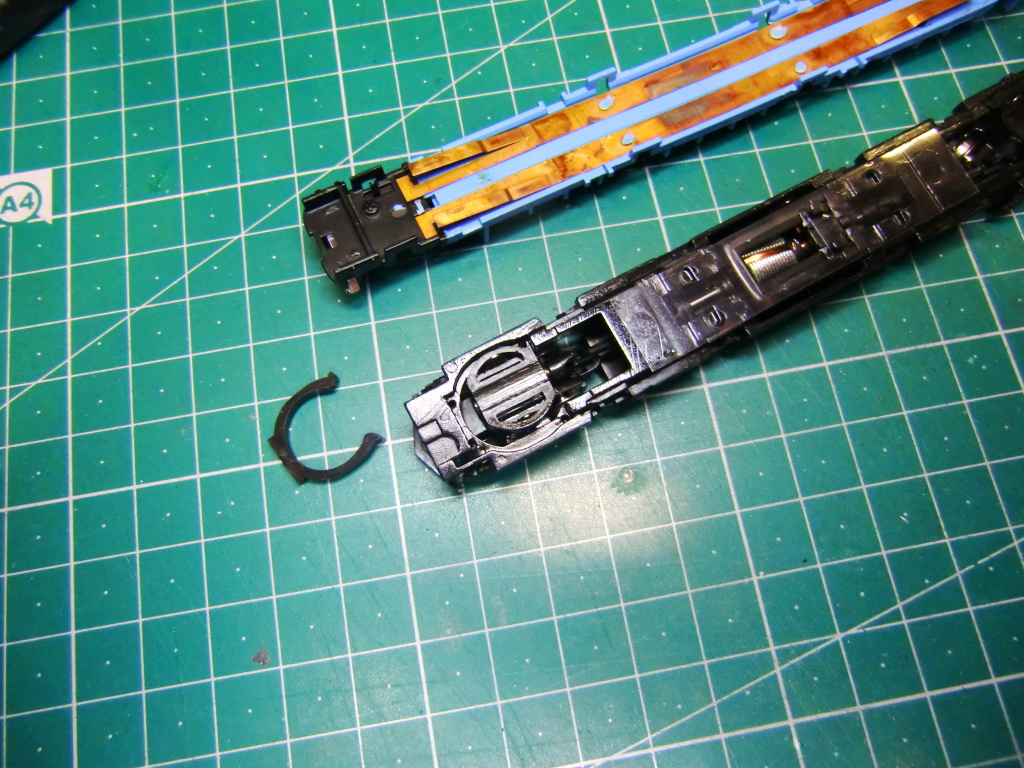
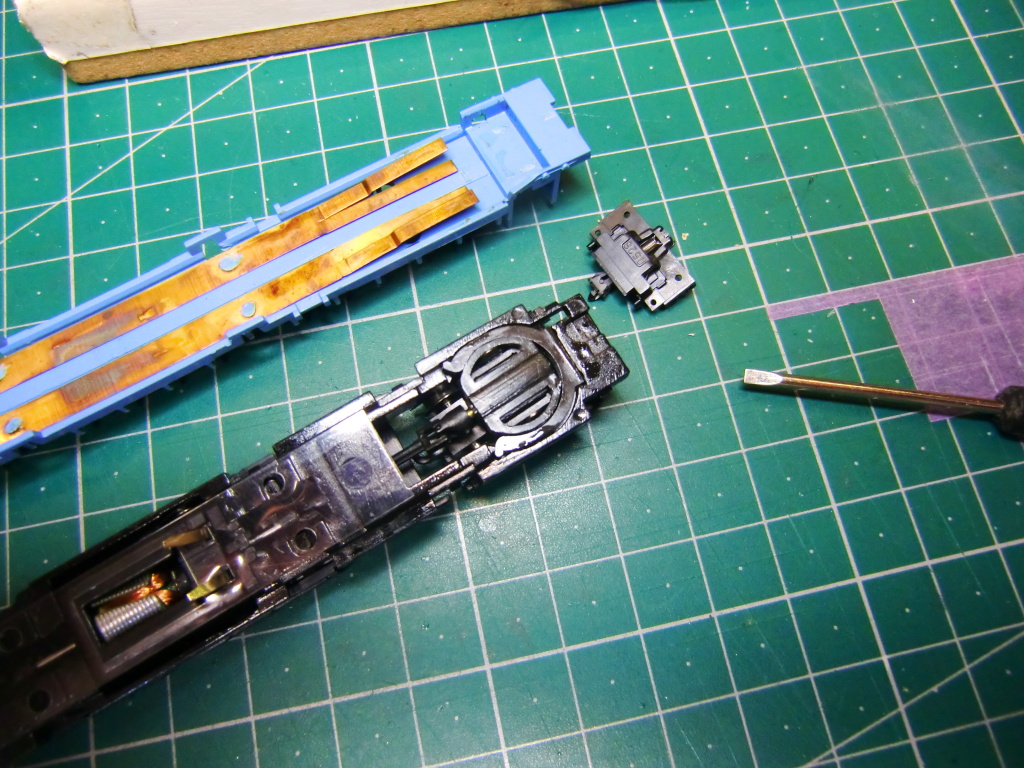
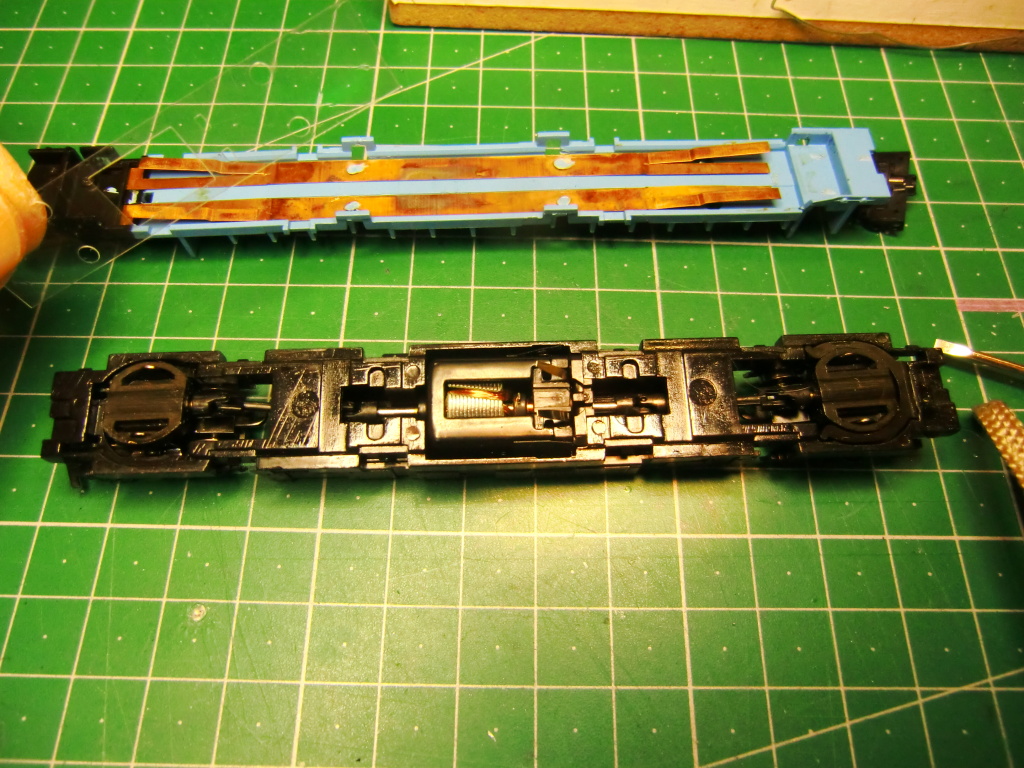

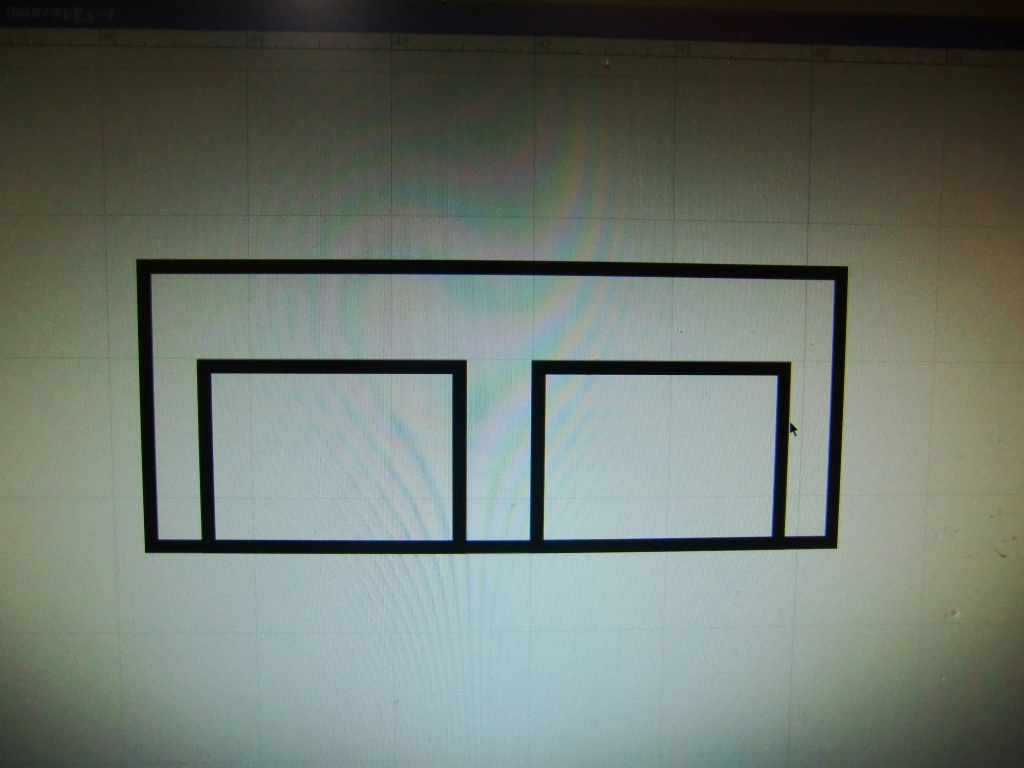
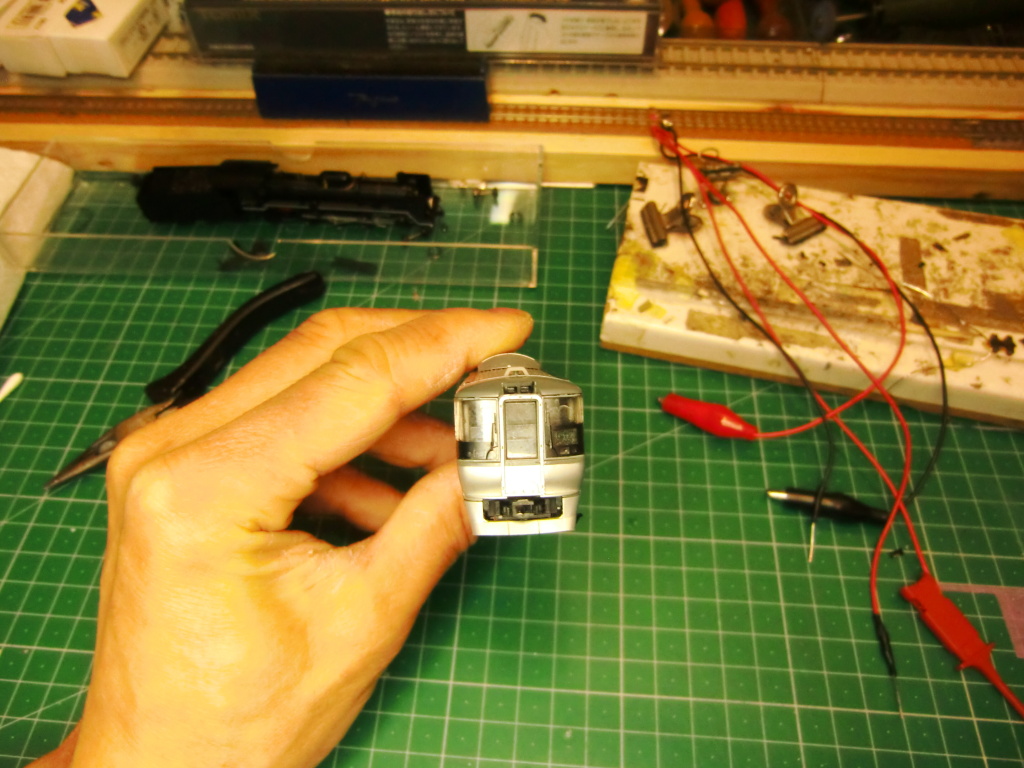
▼
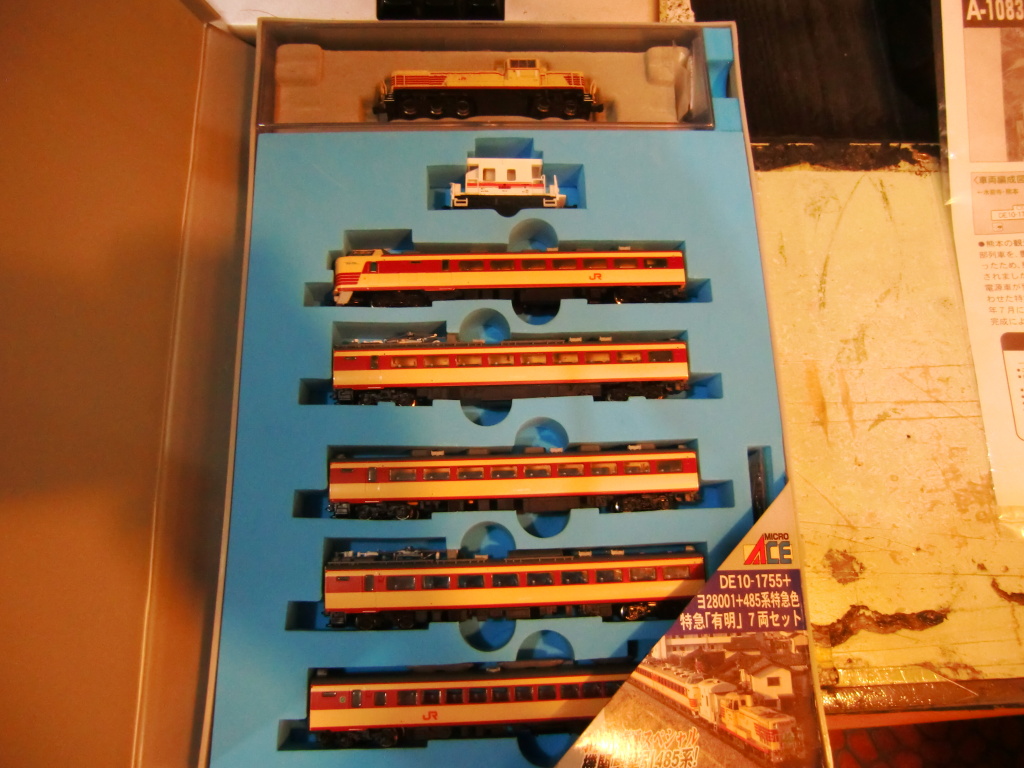

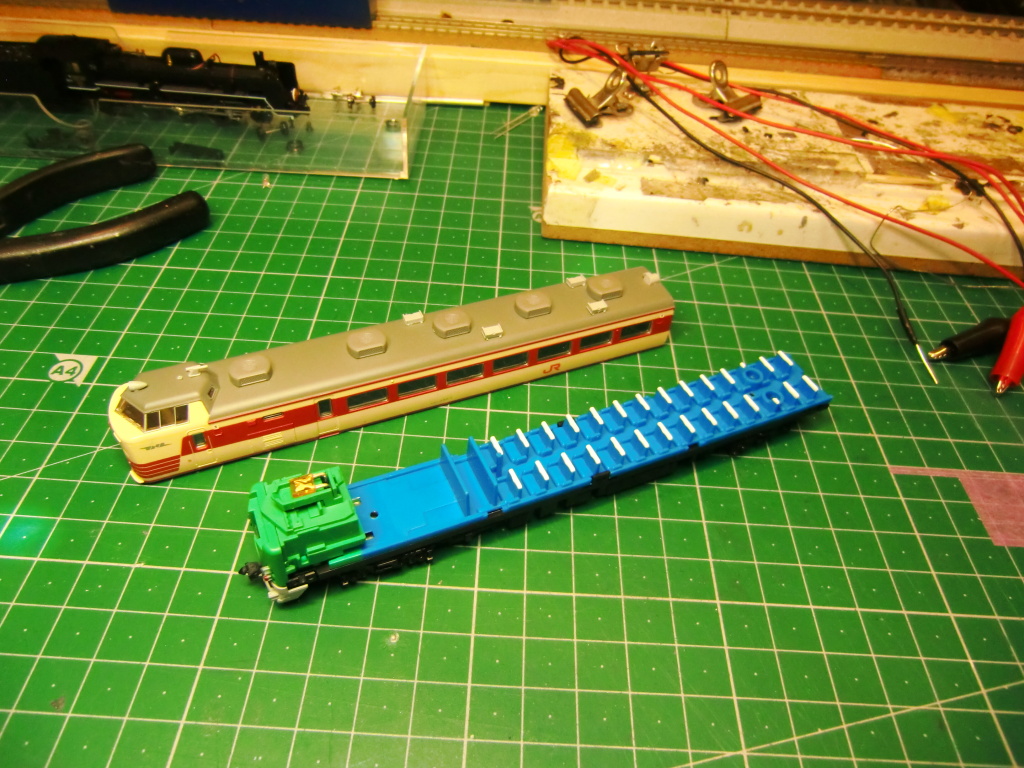
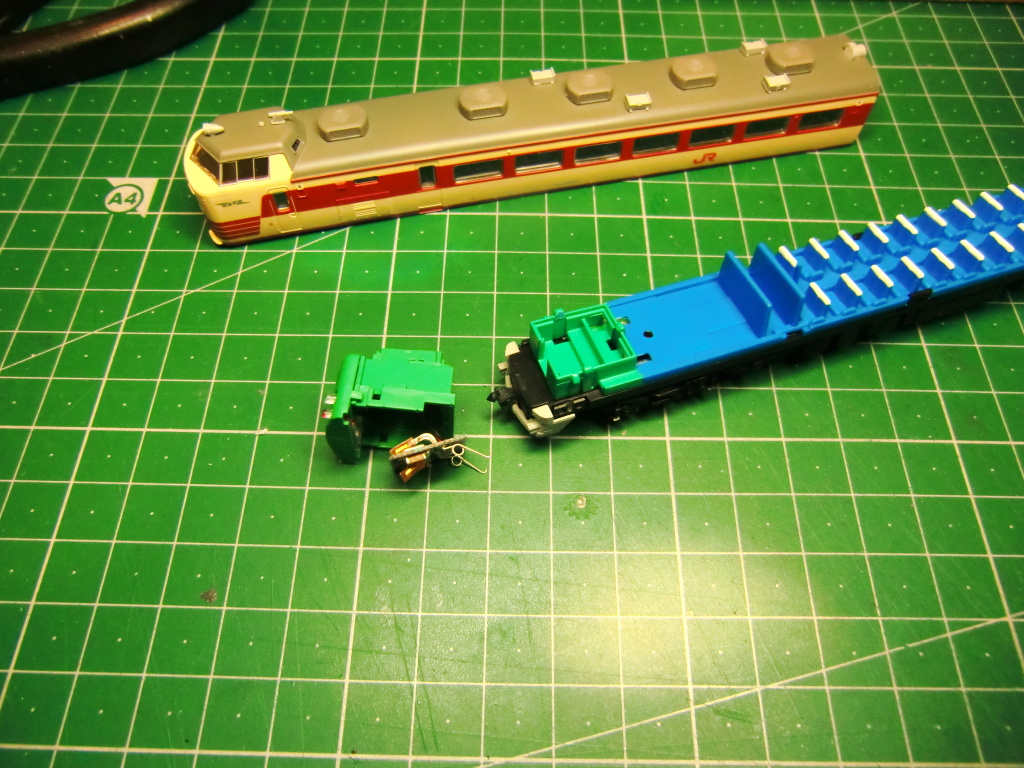
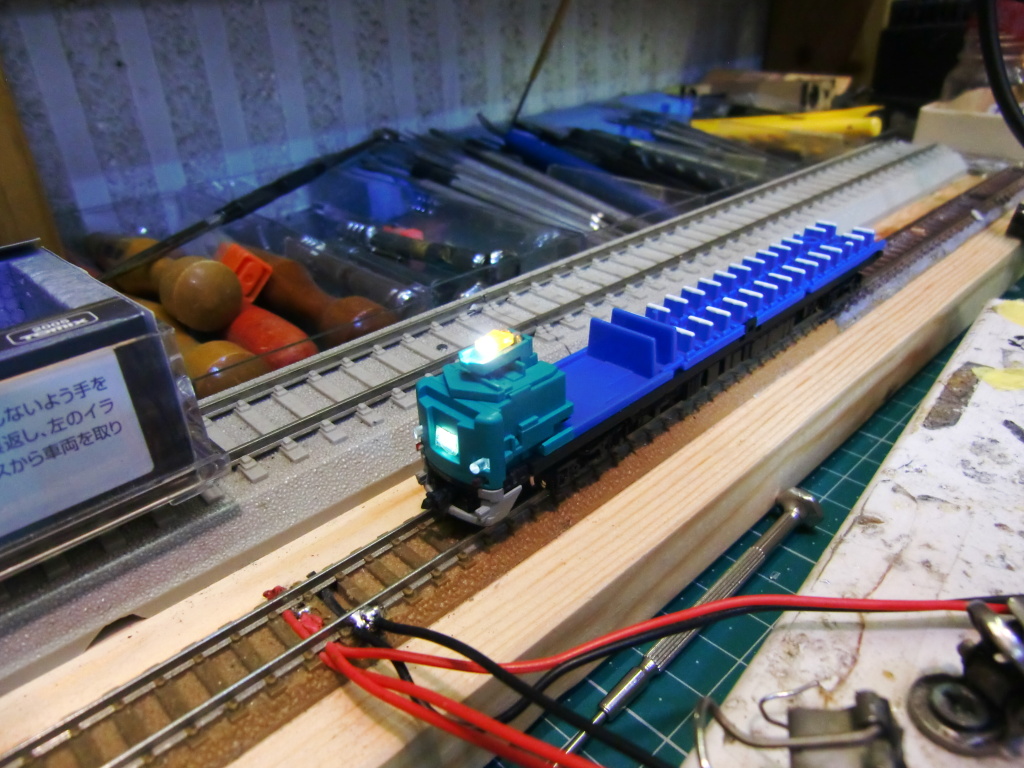
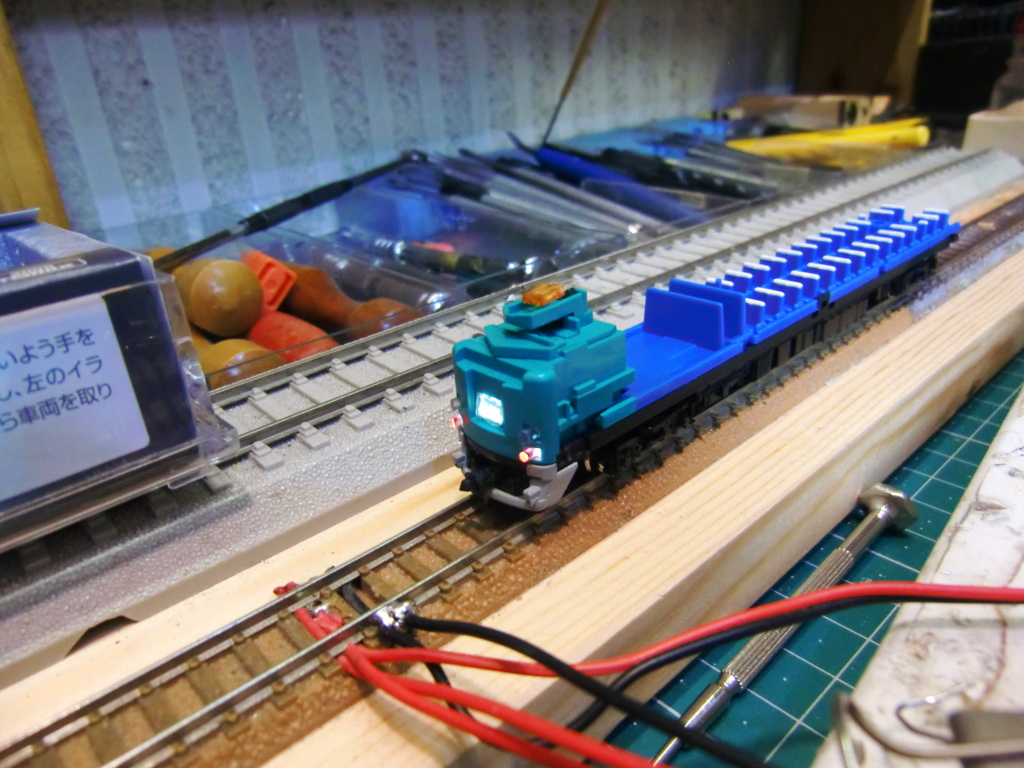
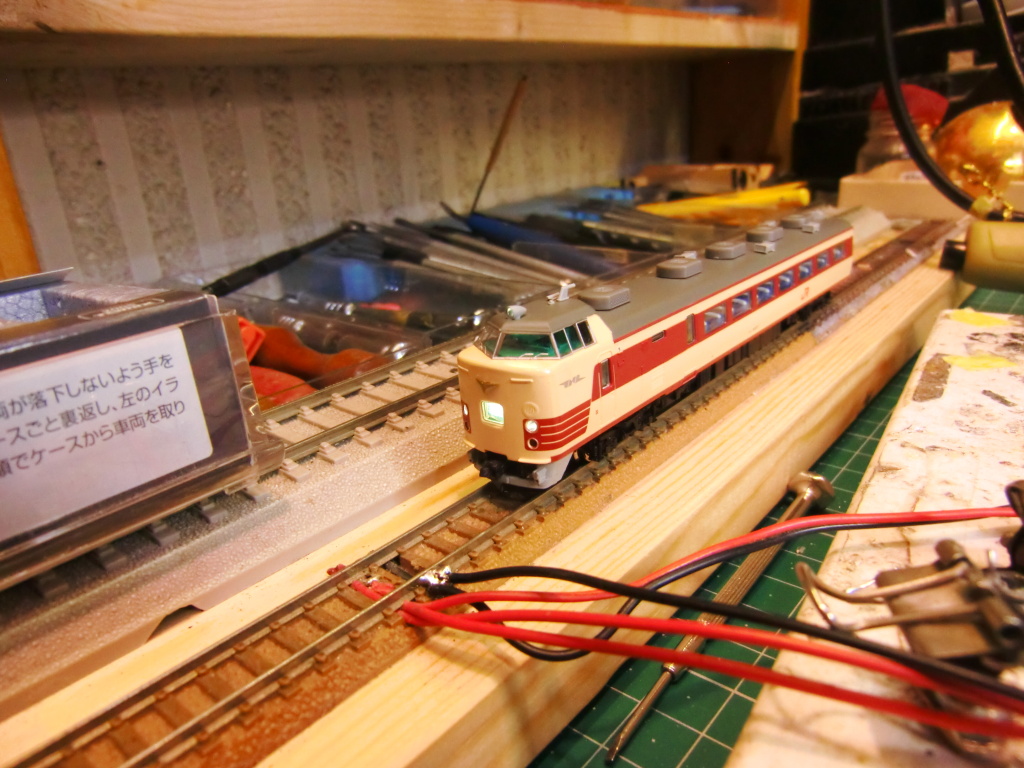


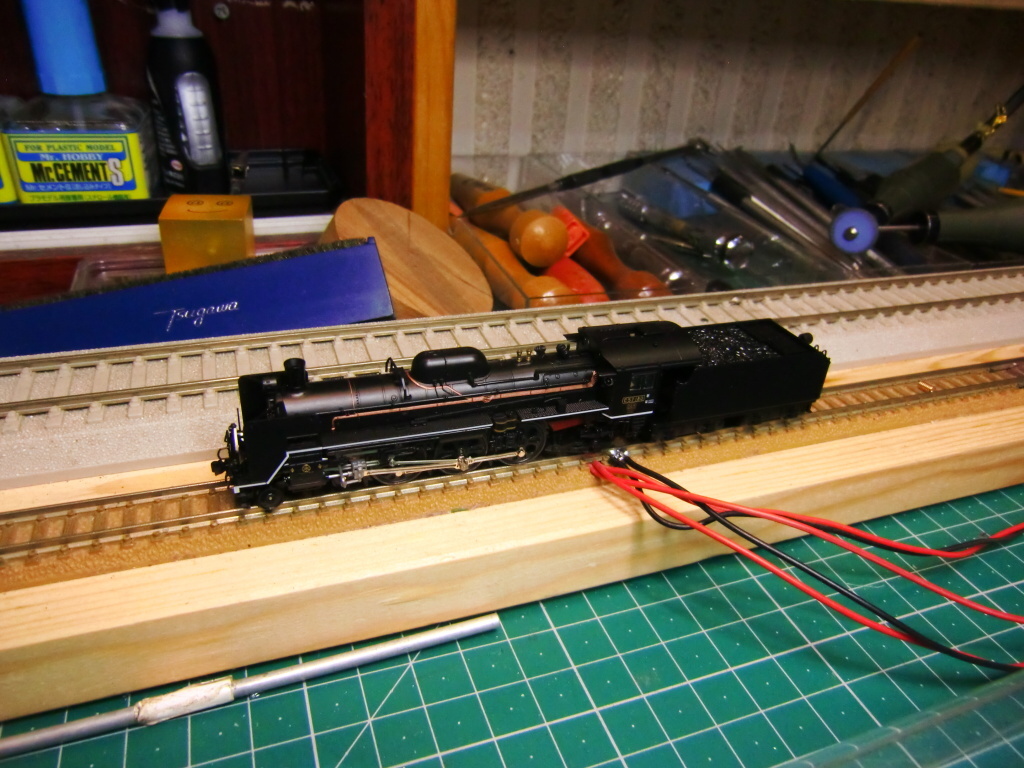
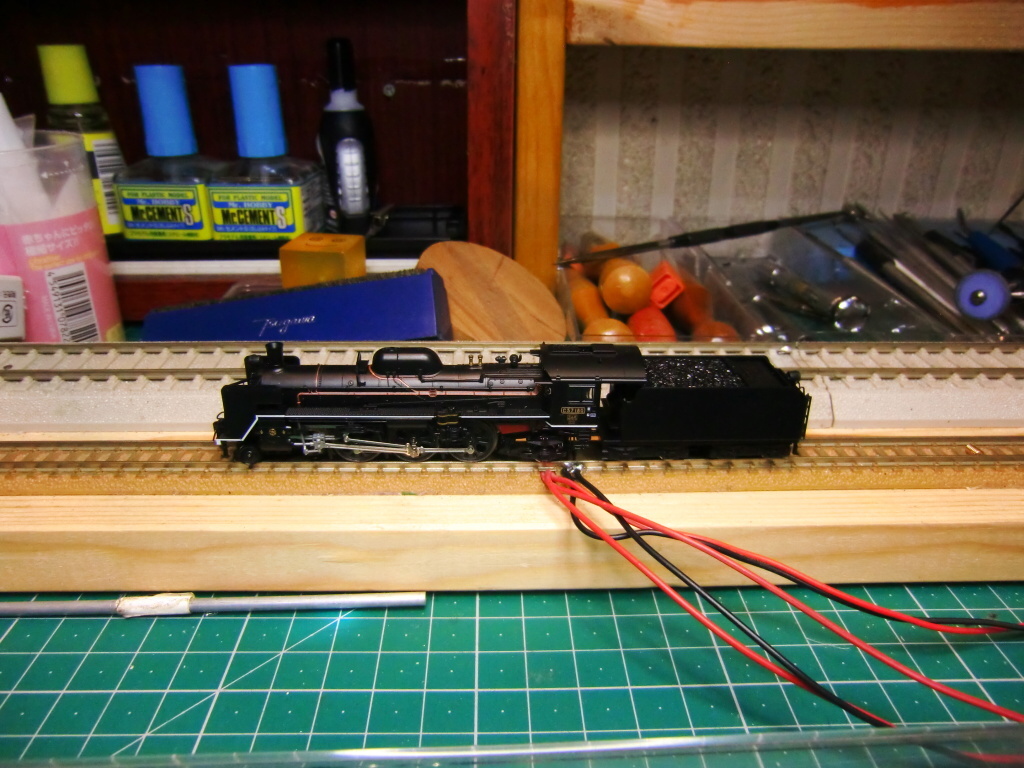
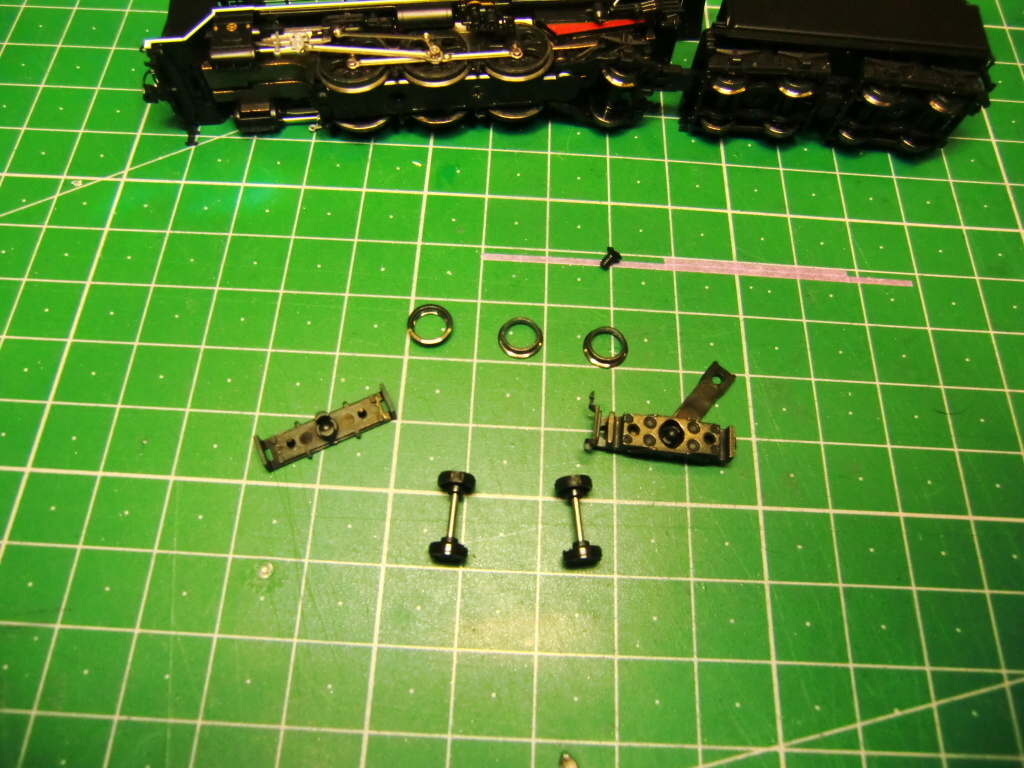

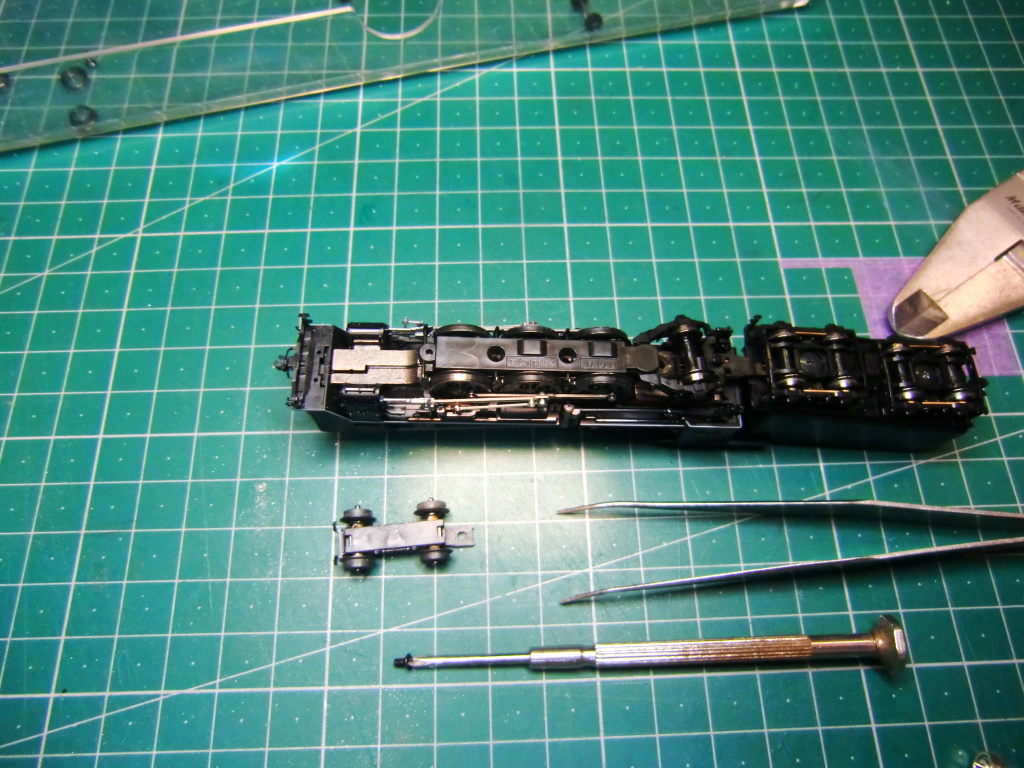
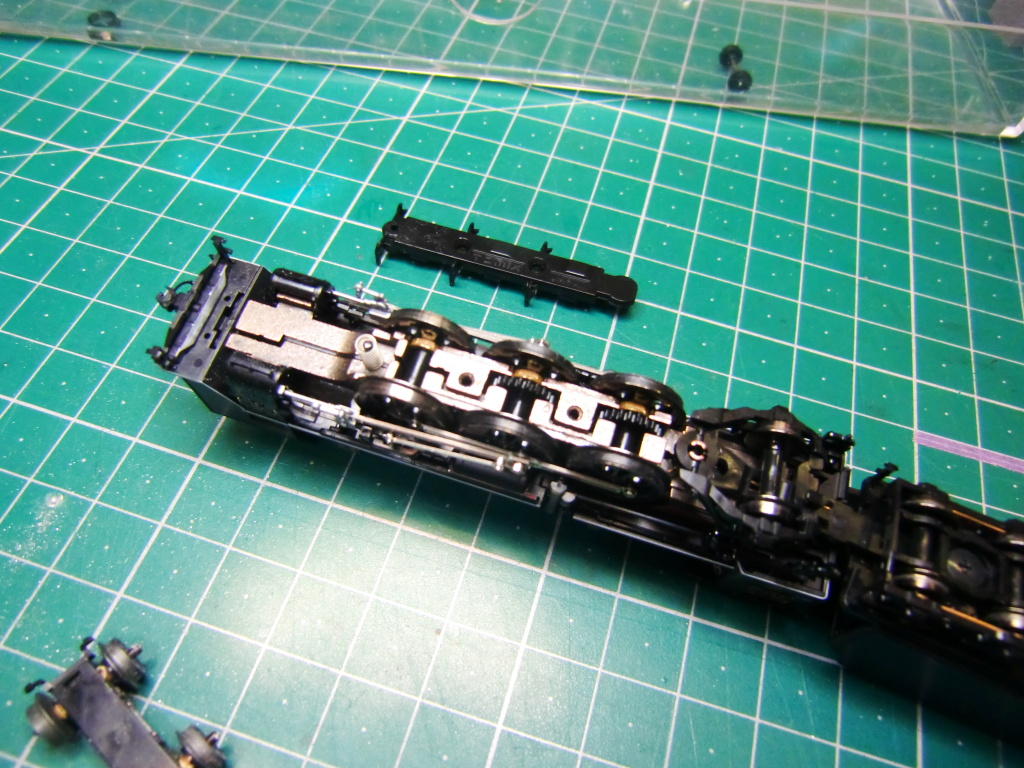
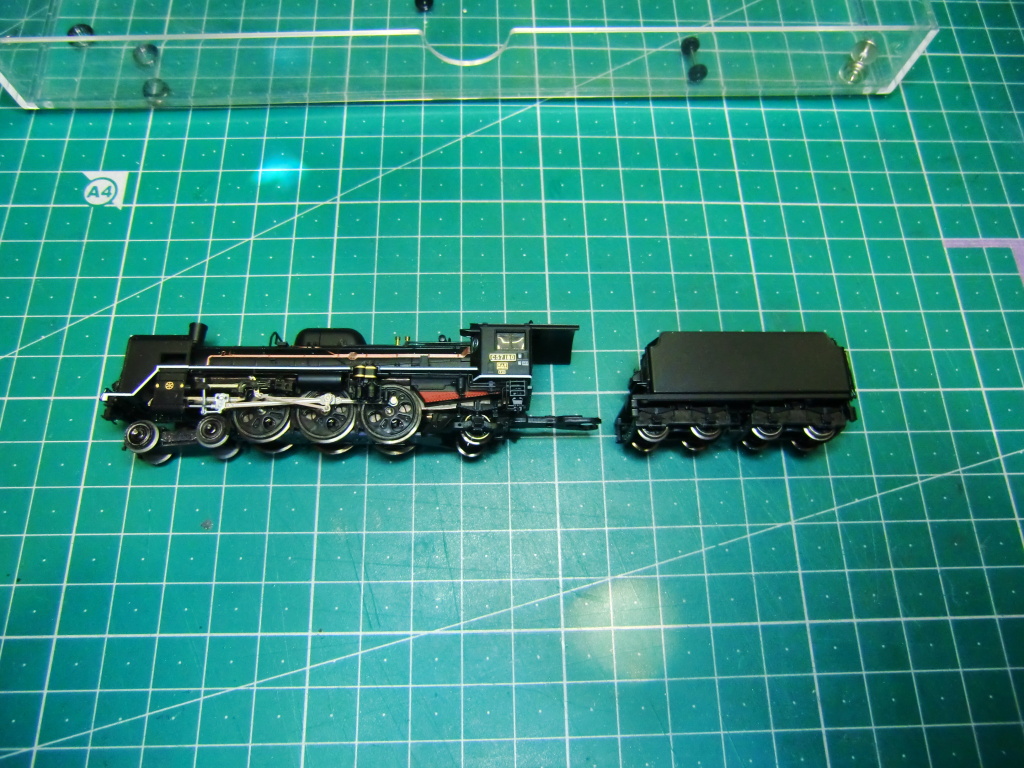
破損したシングルパンタをPS16形パンタへ交換します。


碍子を1ずつ持ち上げてパンタ本体を取り外します。

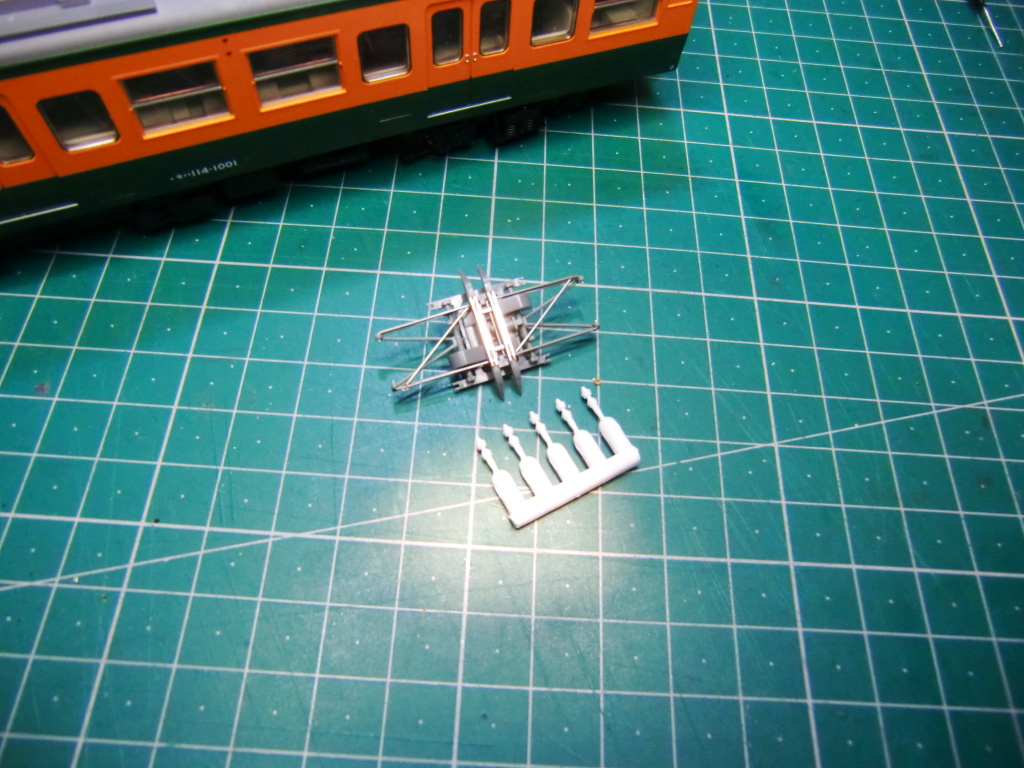
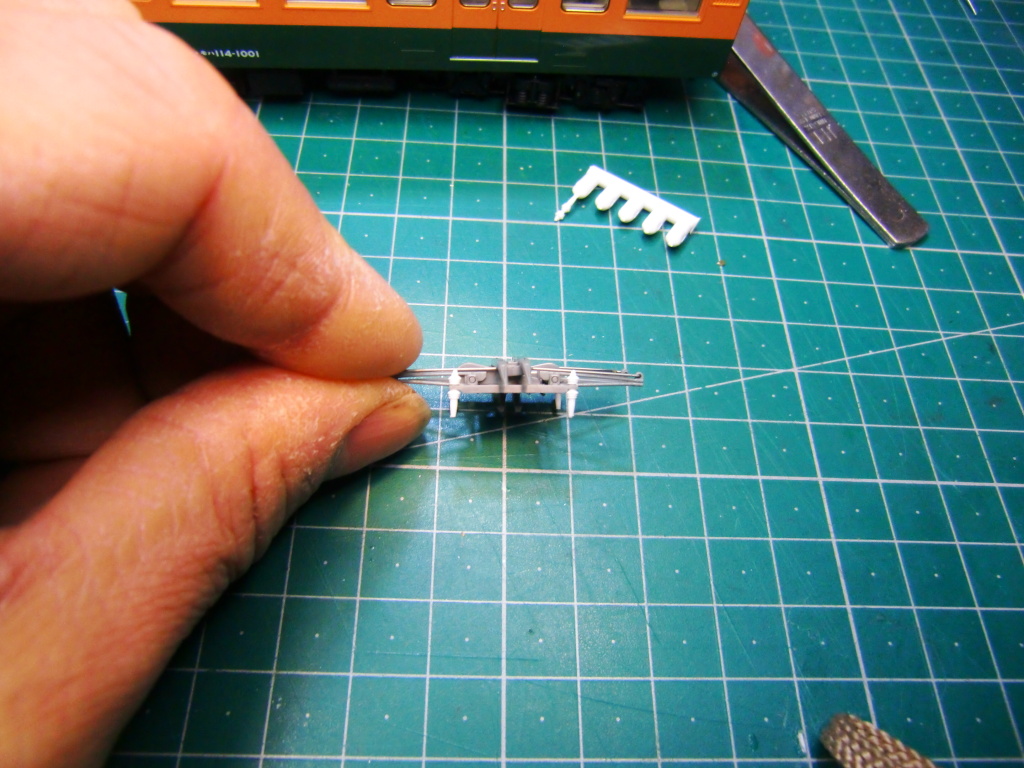
碍子を取り付けます。
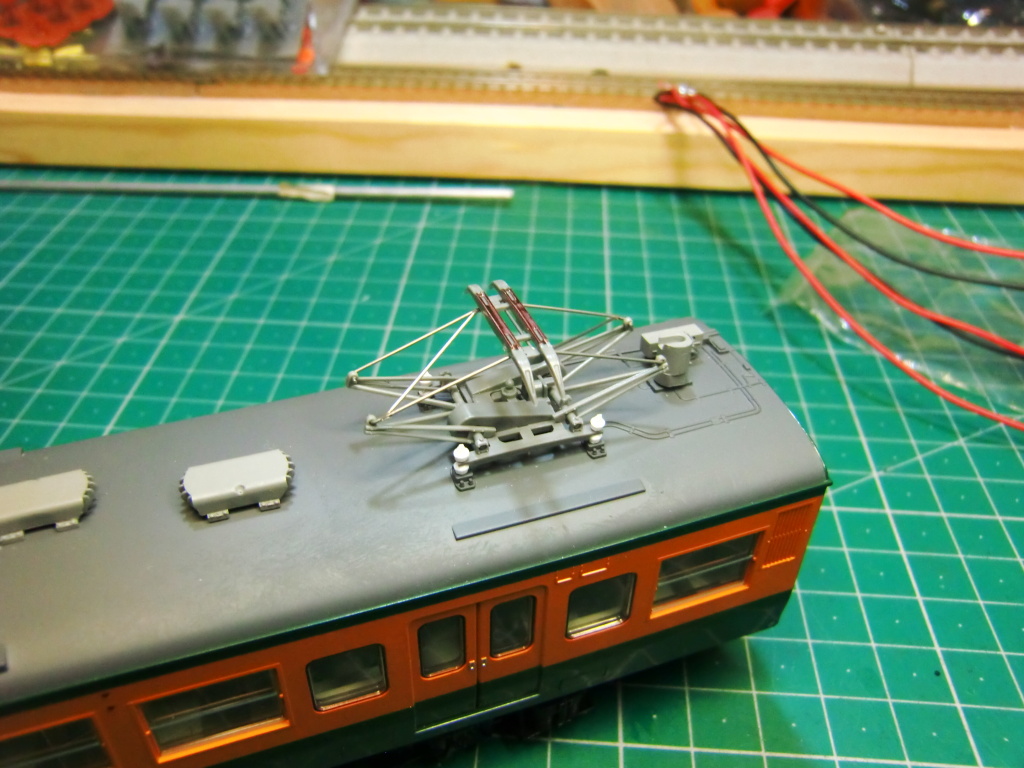
碍子を1本ずつ上から慎重に押し込んでいきます。少しコツがいります。


▼付属パーツ取付

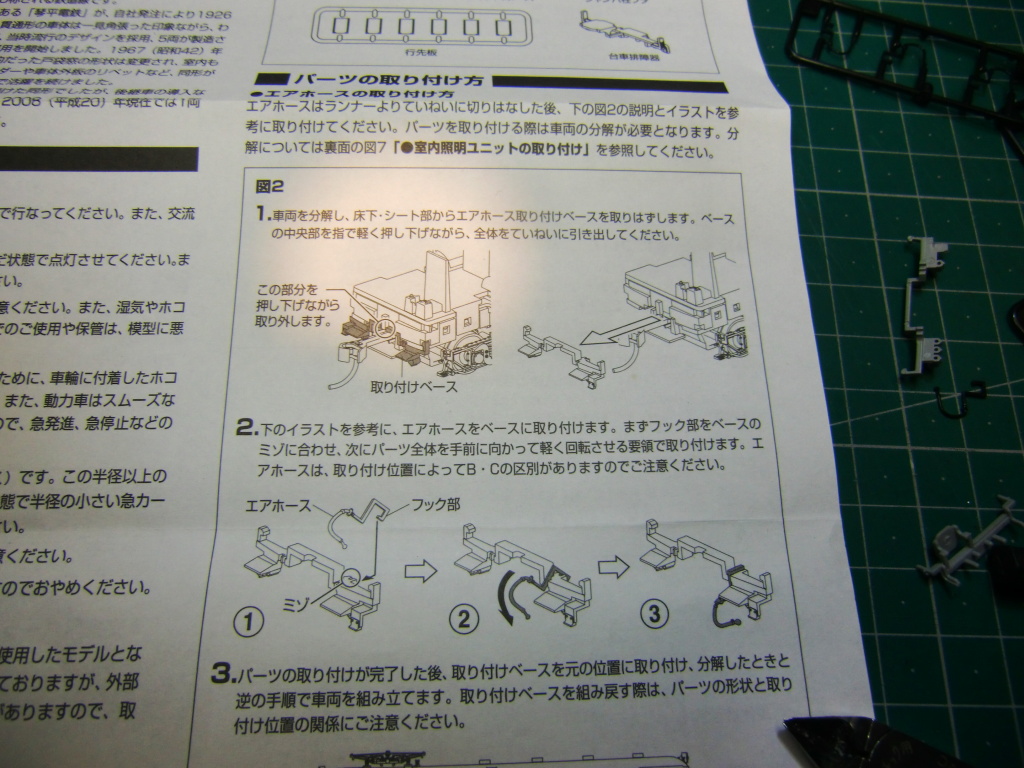
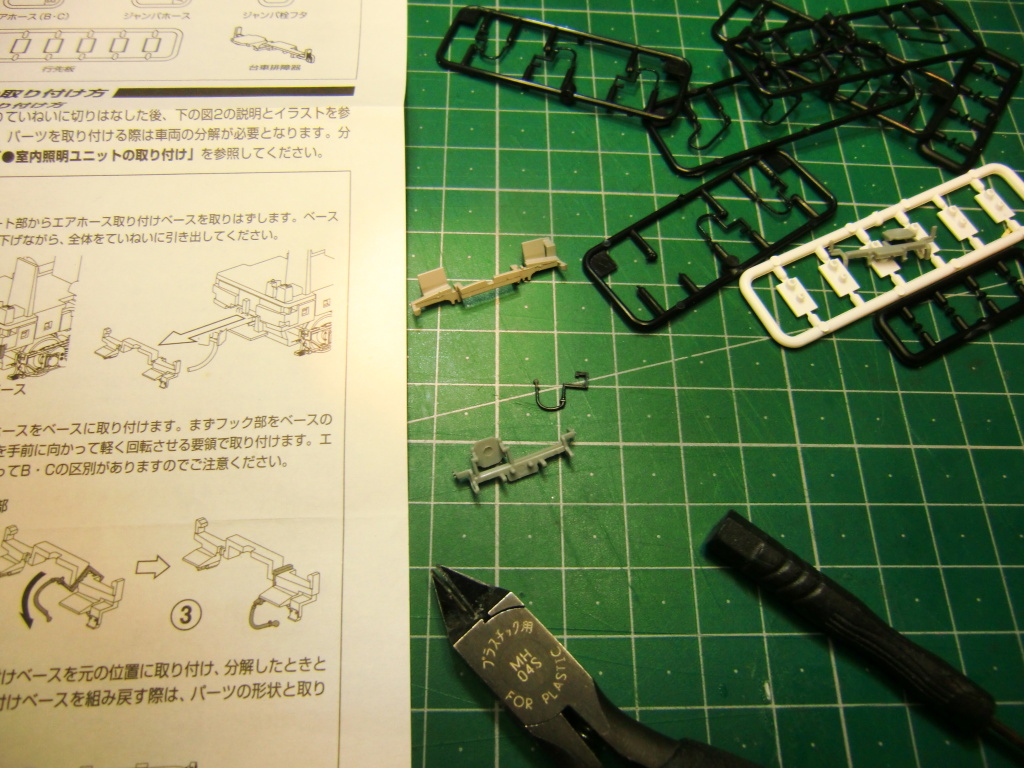

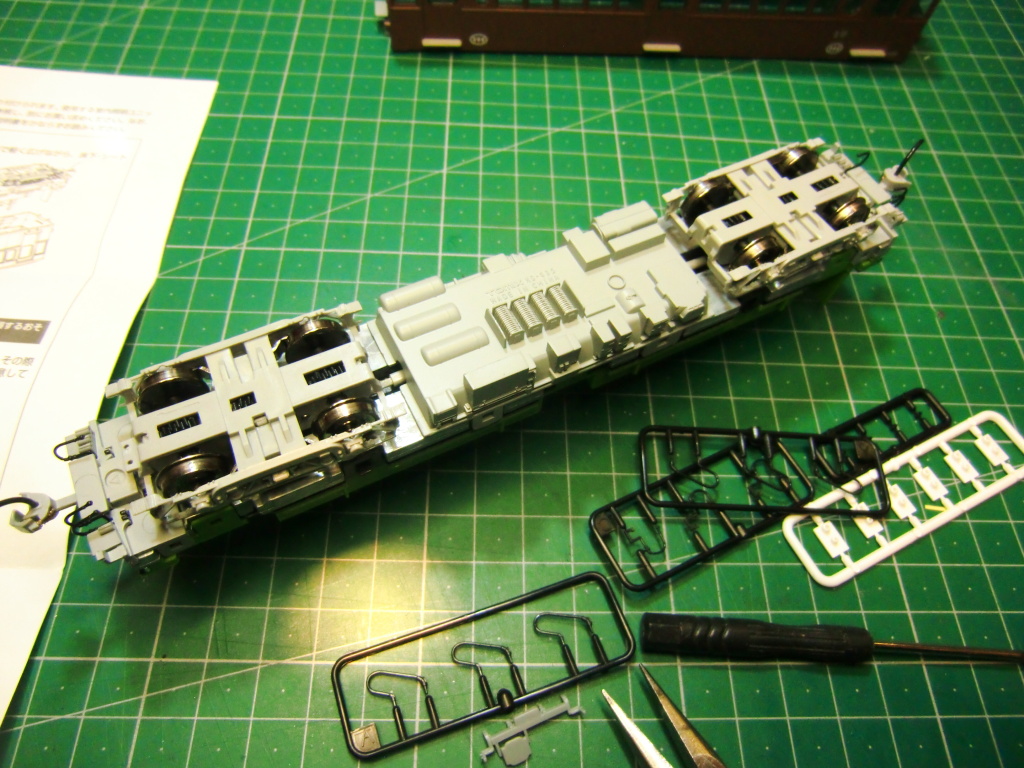
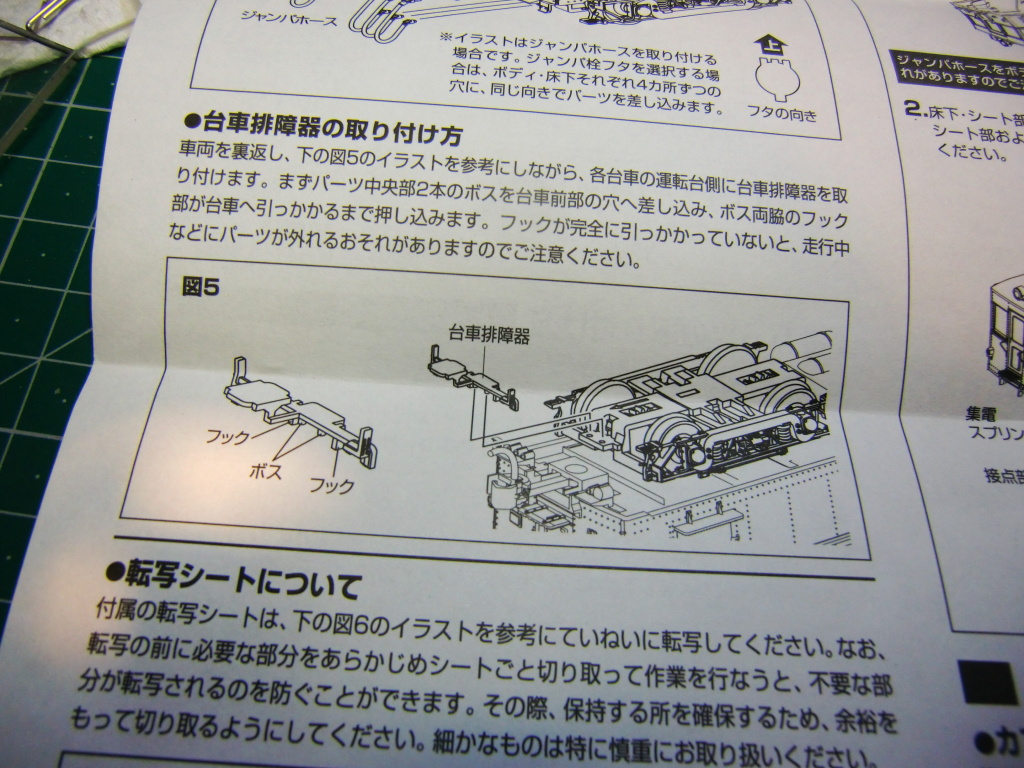
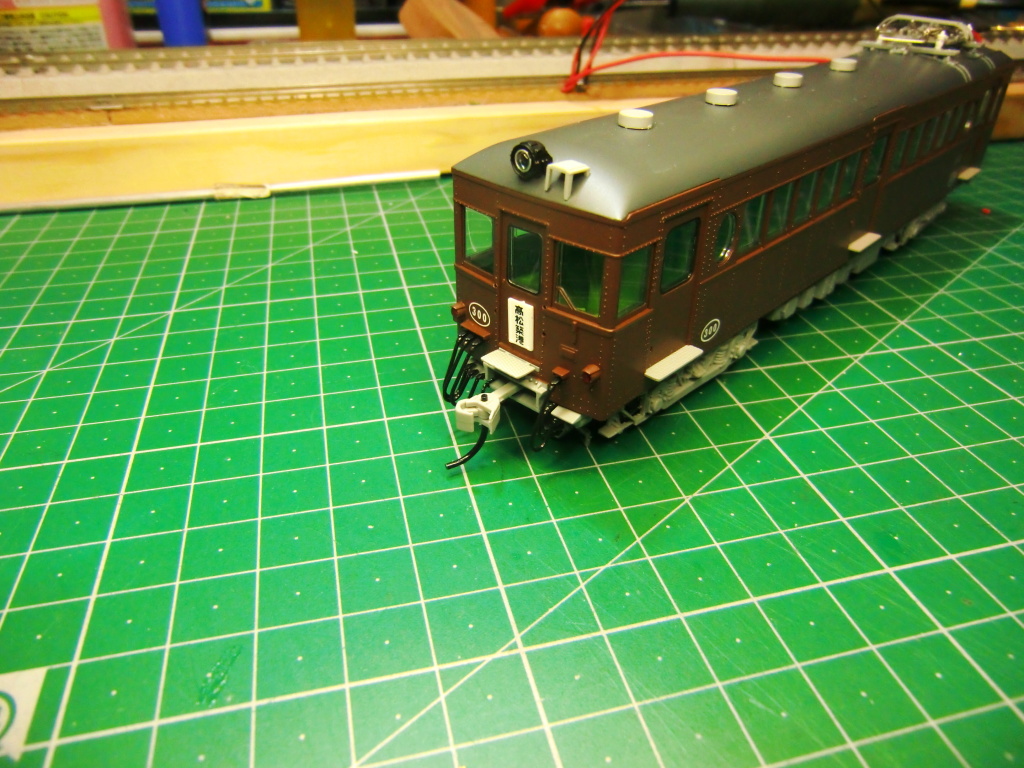



▼M車不動修理
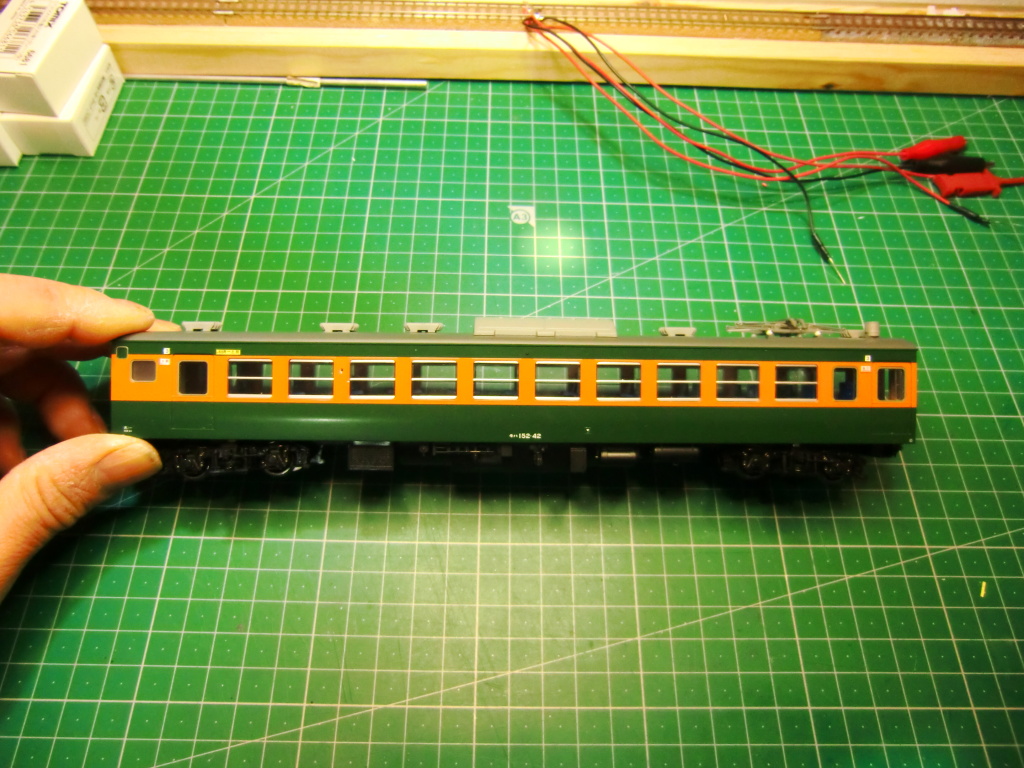
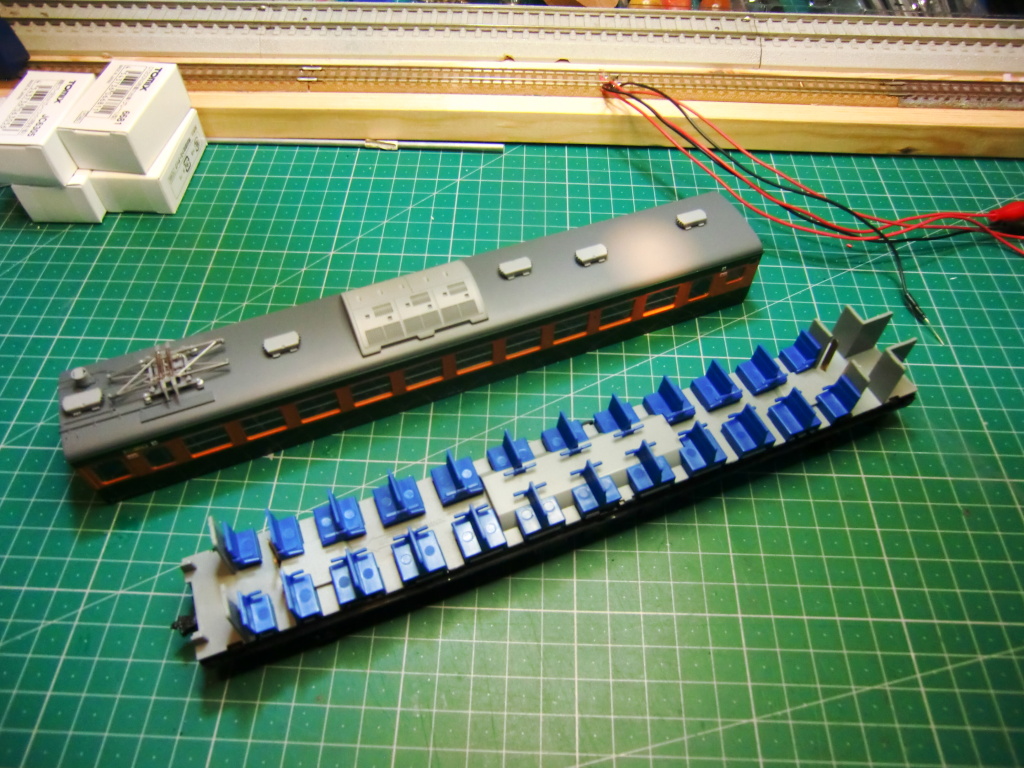
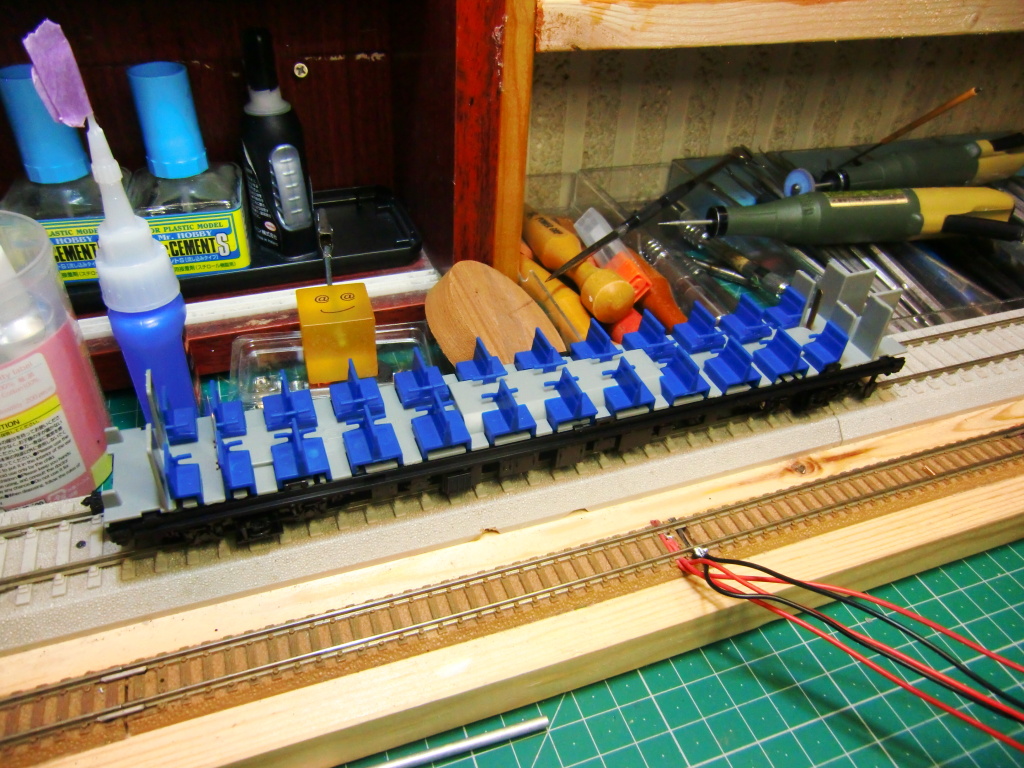
ピクリとも動きません。
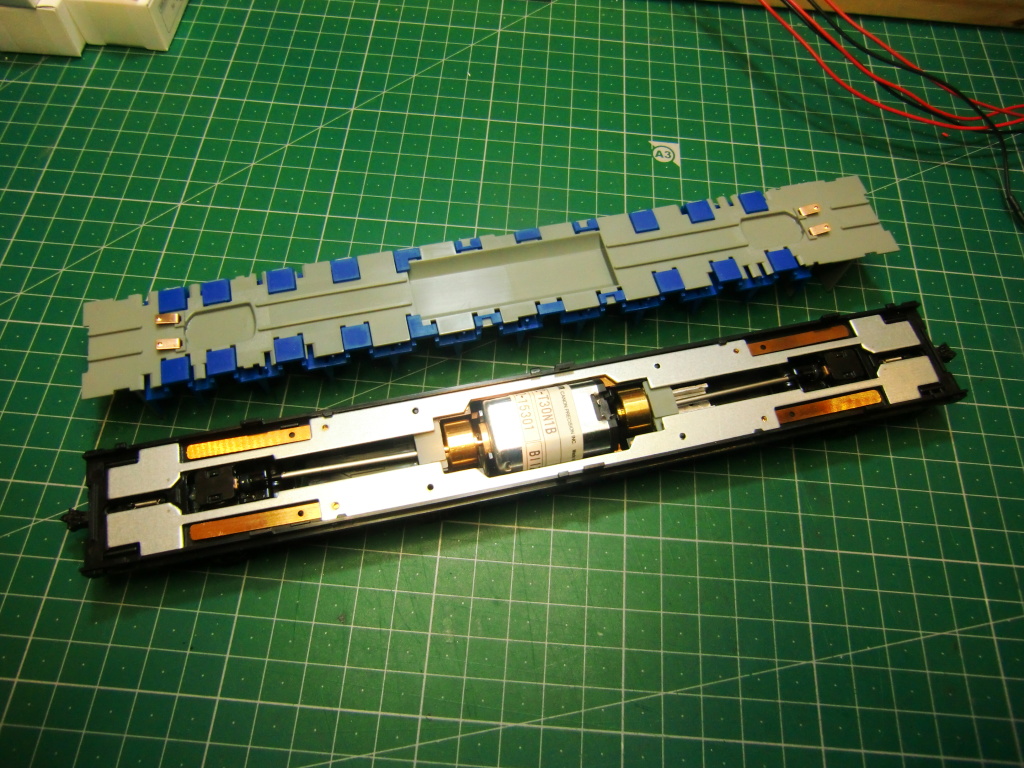
分解して1つ1つ確認して問題となっている個所を特定していきます。
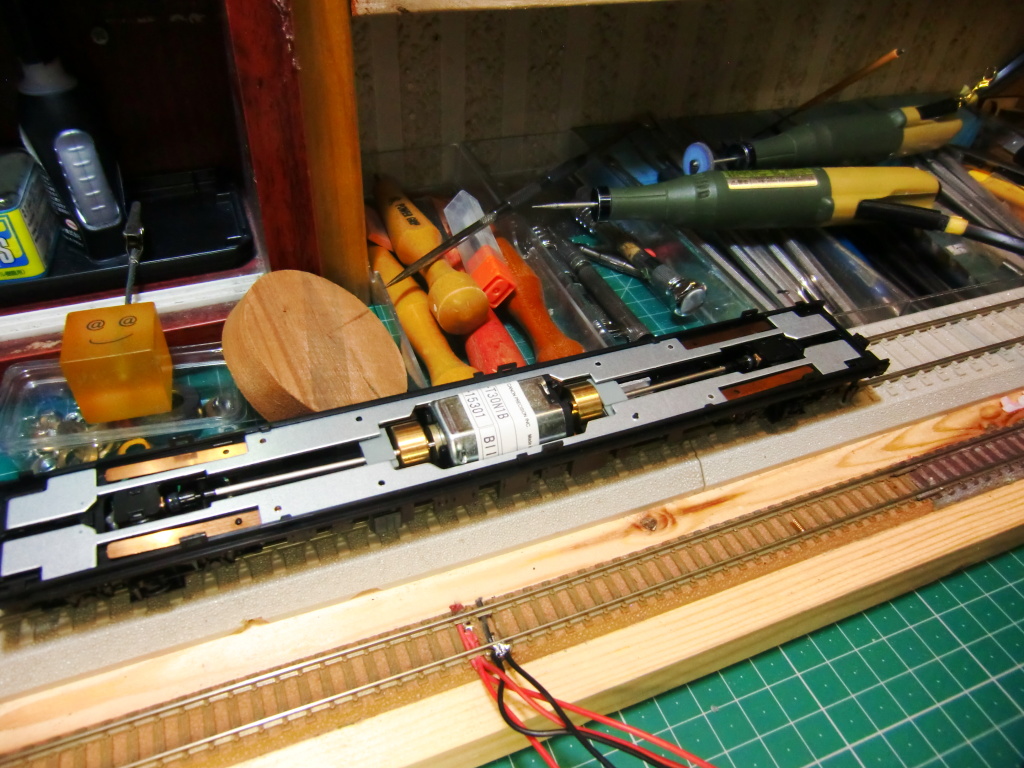
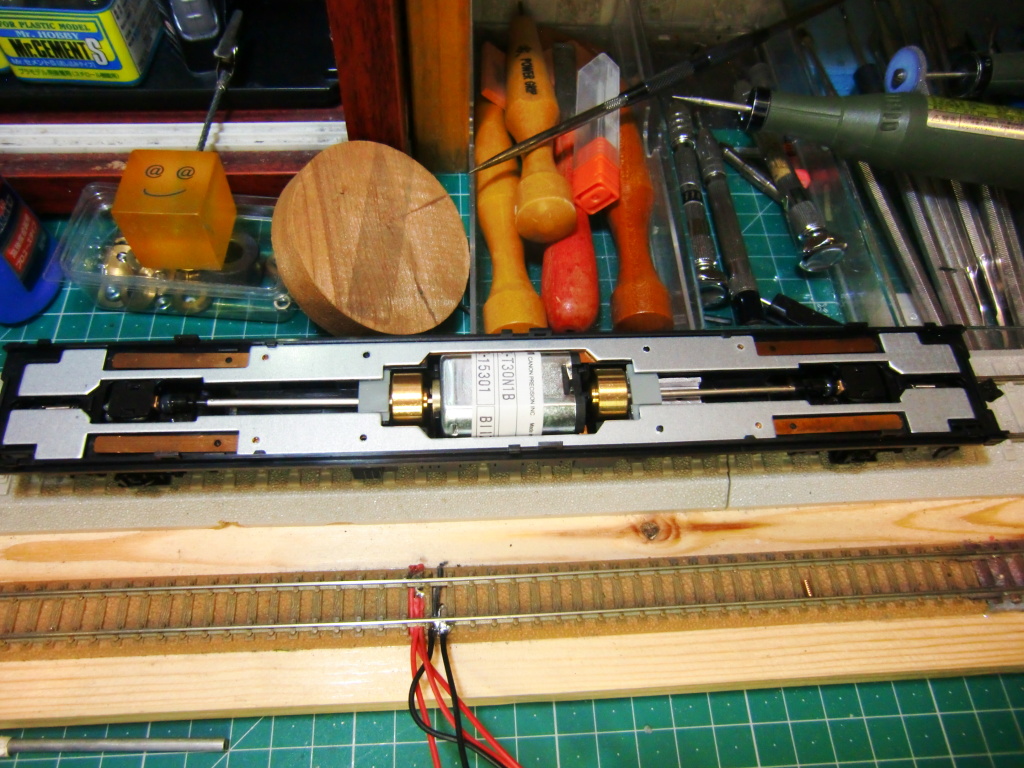
モータ本体がまったく回っていませんので、いったんすべて取り出して各種接点を始め、モーターの単体テストと各種調整と確認を繰り返します。
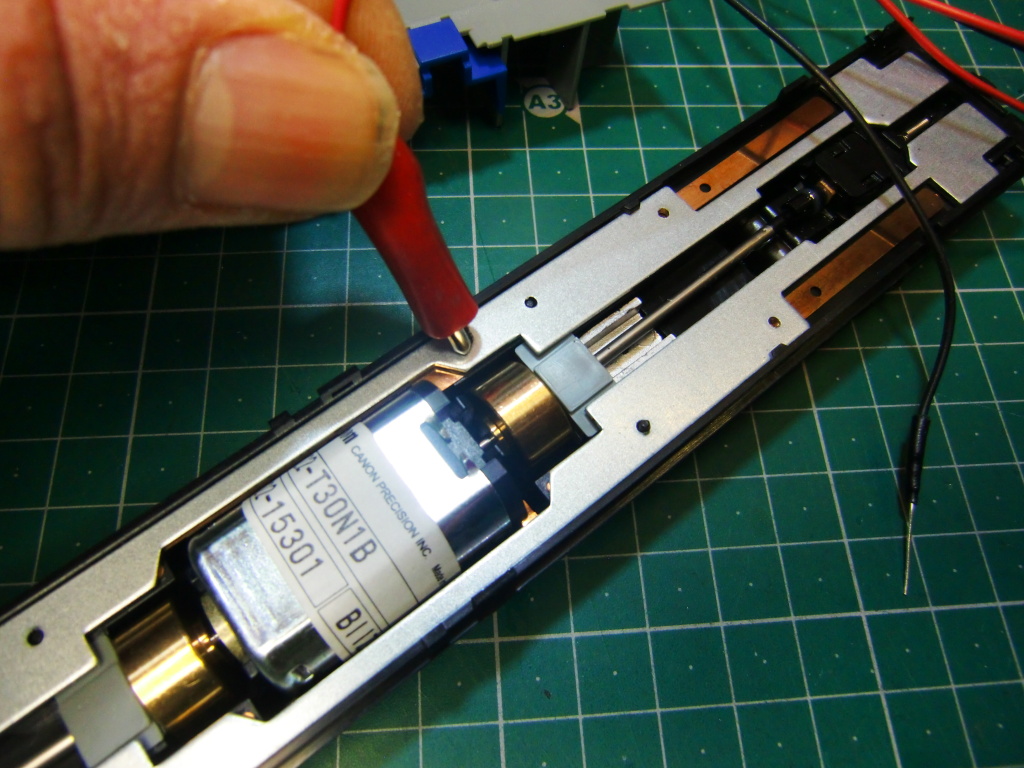



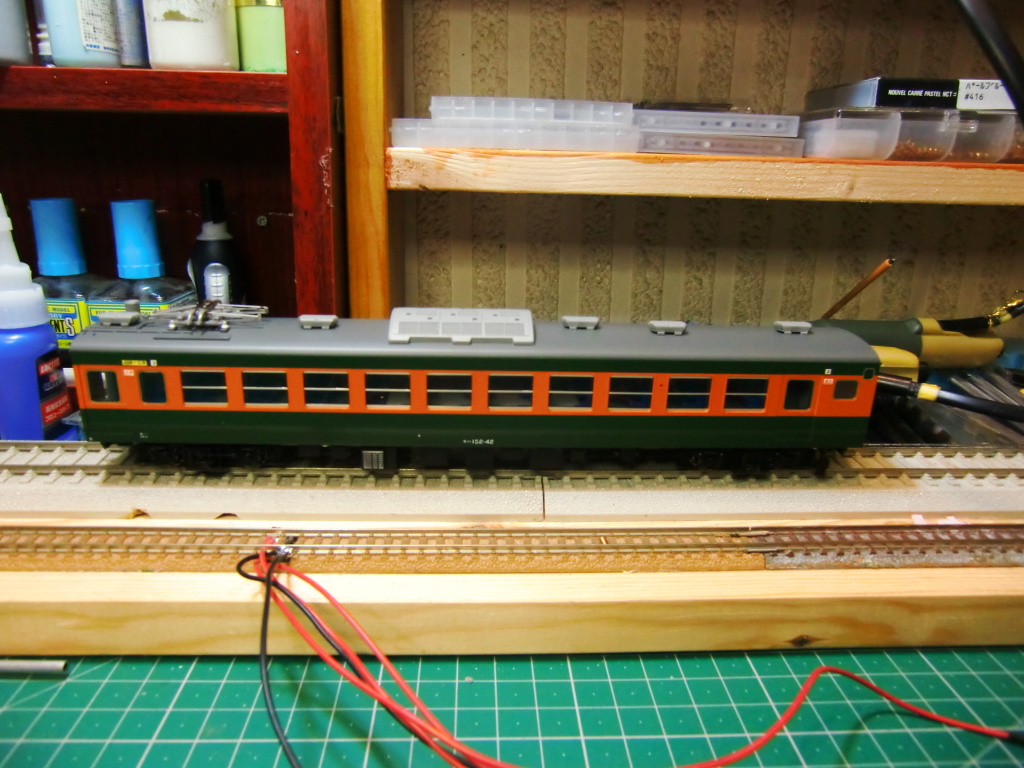
作業は少々手間取りましたが、無事に安定した走行を確認できました。作業完了でございます。
今回の作業では、モータの換装(2台)とカプラー全交換の作業でございます。

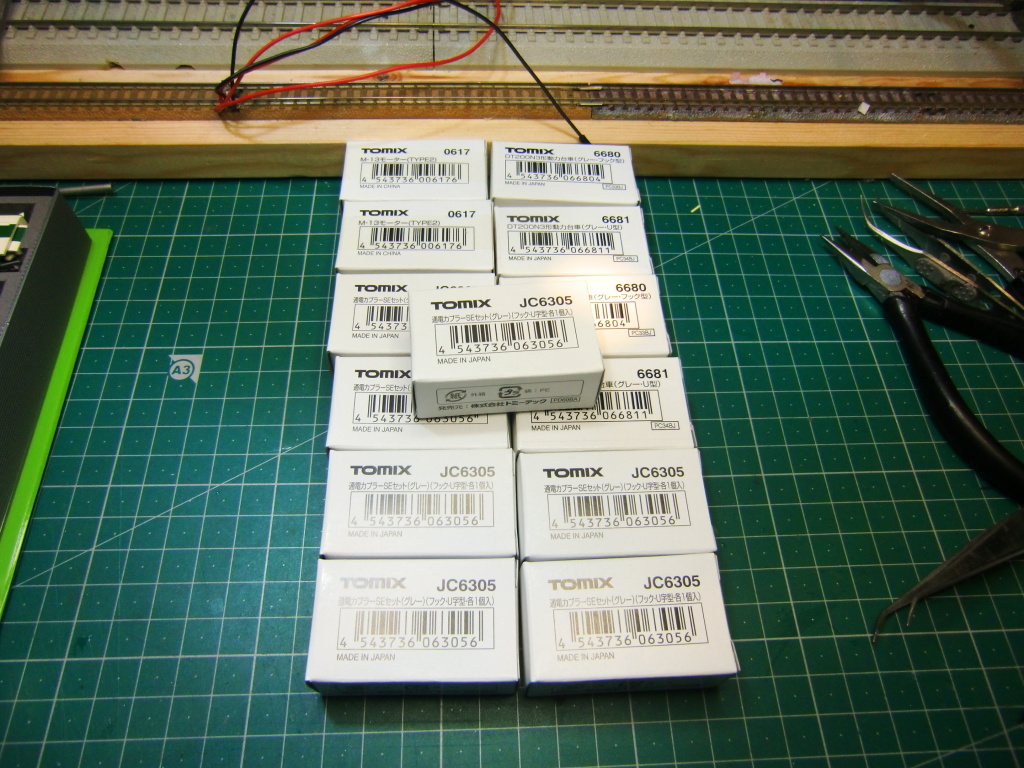

取り付けには、台車をいったん外す必要があります。
▼モーター換装

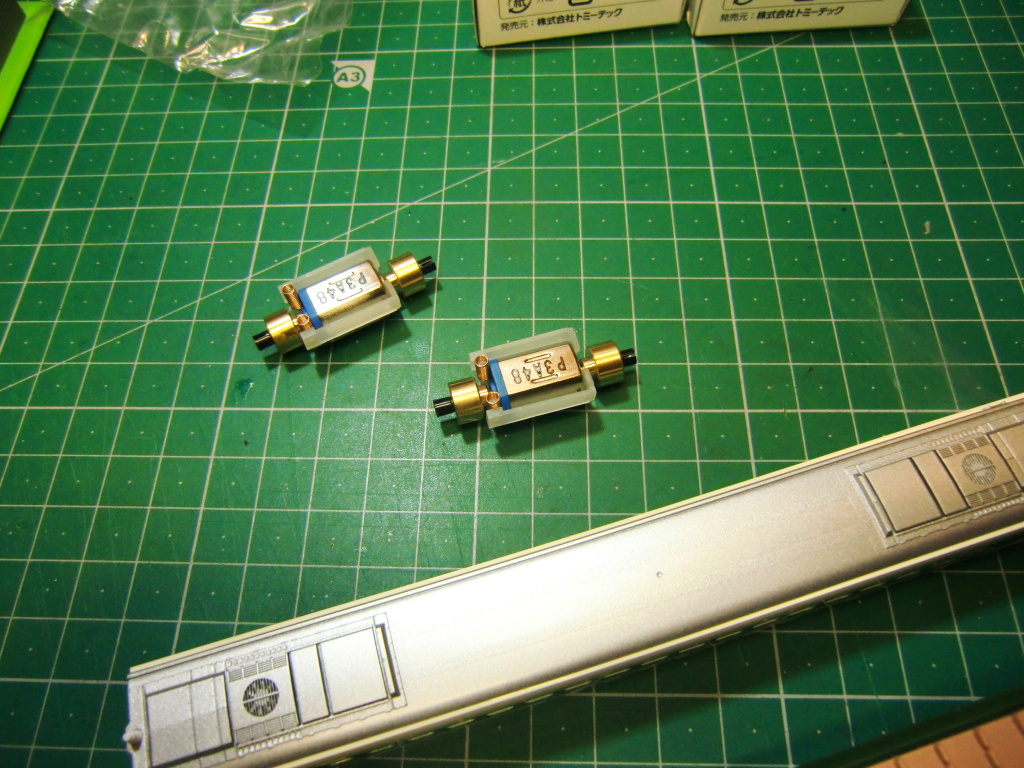
こちらがの入れ替えるモーターです。
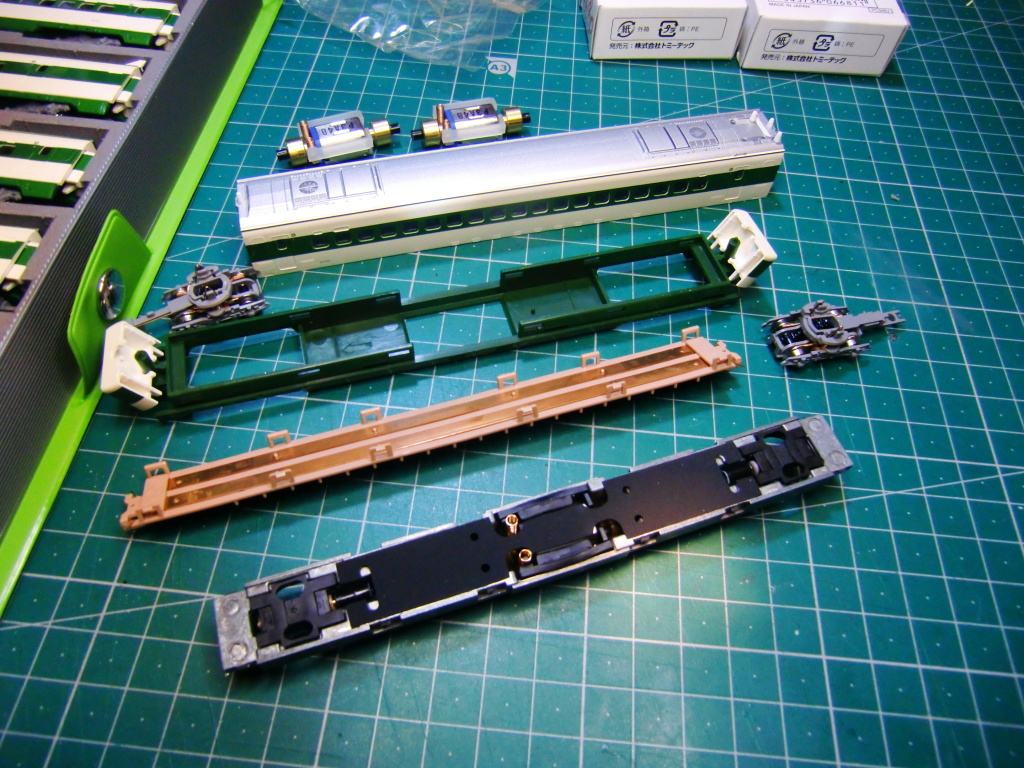
換装にはすべて分解する必要が生じます。
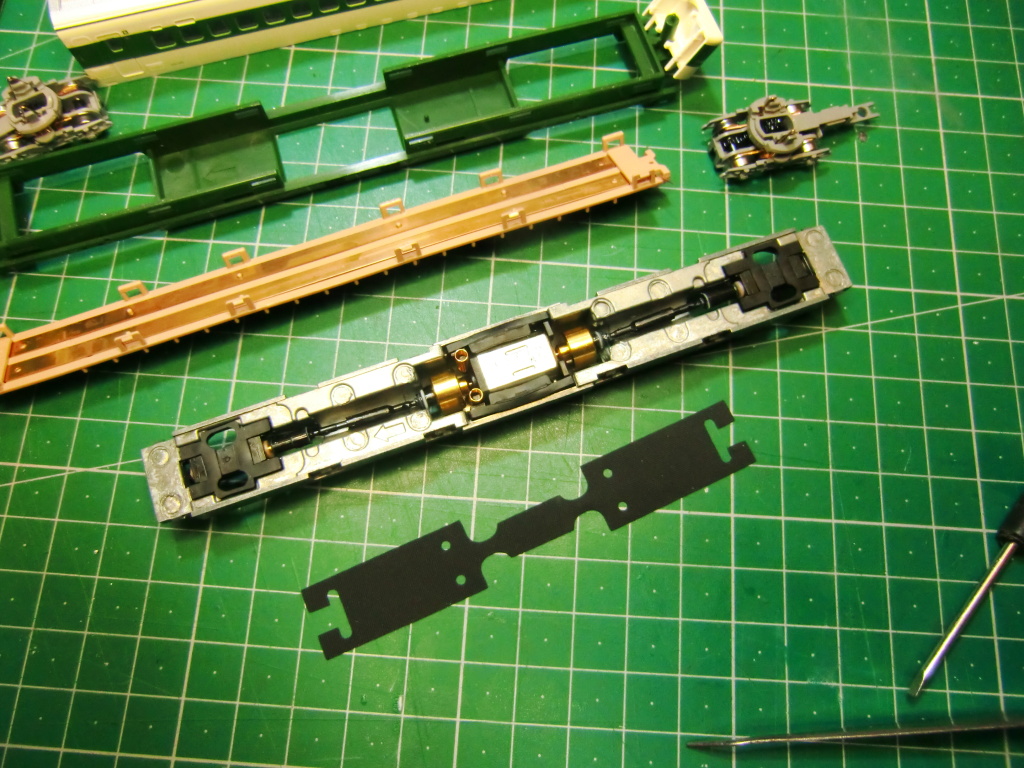
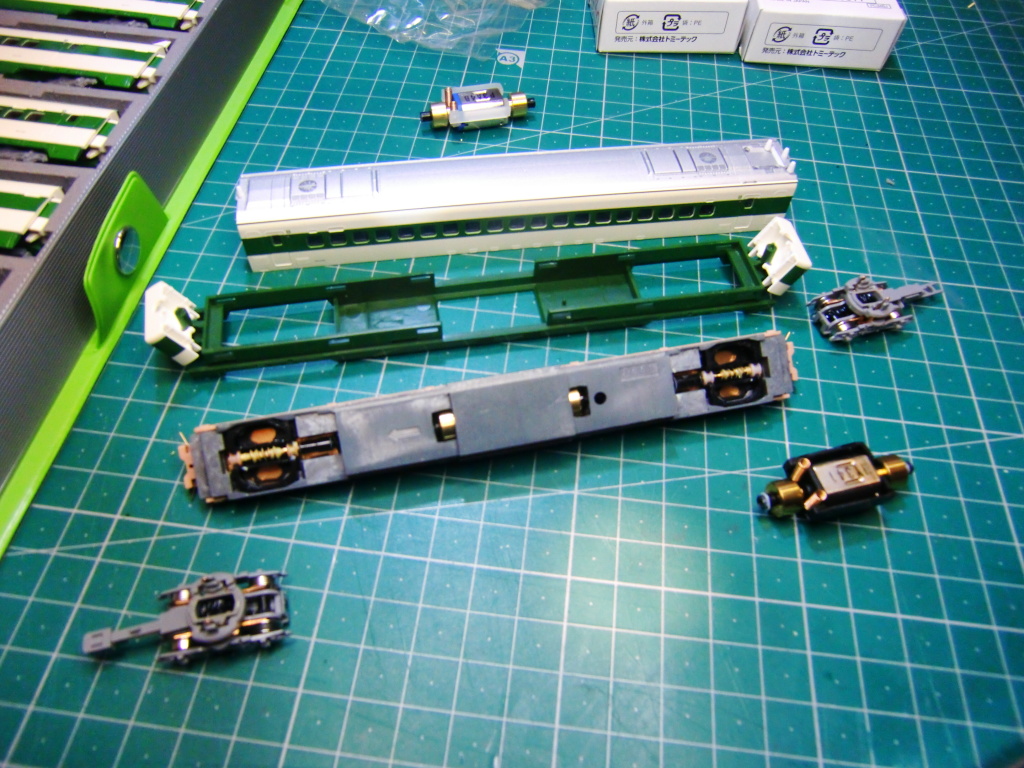
組込み後の調整なども行います。一方の車体から異音が出ているため、こちらの調整にはやや苦慮しましたが、作業は完了です。

モーター換装および、カプラーの全交換の作業は完了しました。
外国製車両の修理となります。まずは、現状確認を行ってみたところ、ギアからの異音と空回り台車集電不良など簡易テストの時点でいくつかの問題点が確認されました。異音と空回りは、恐らくギアd損傷による症状と思われます。
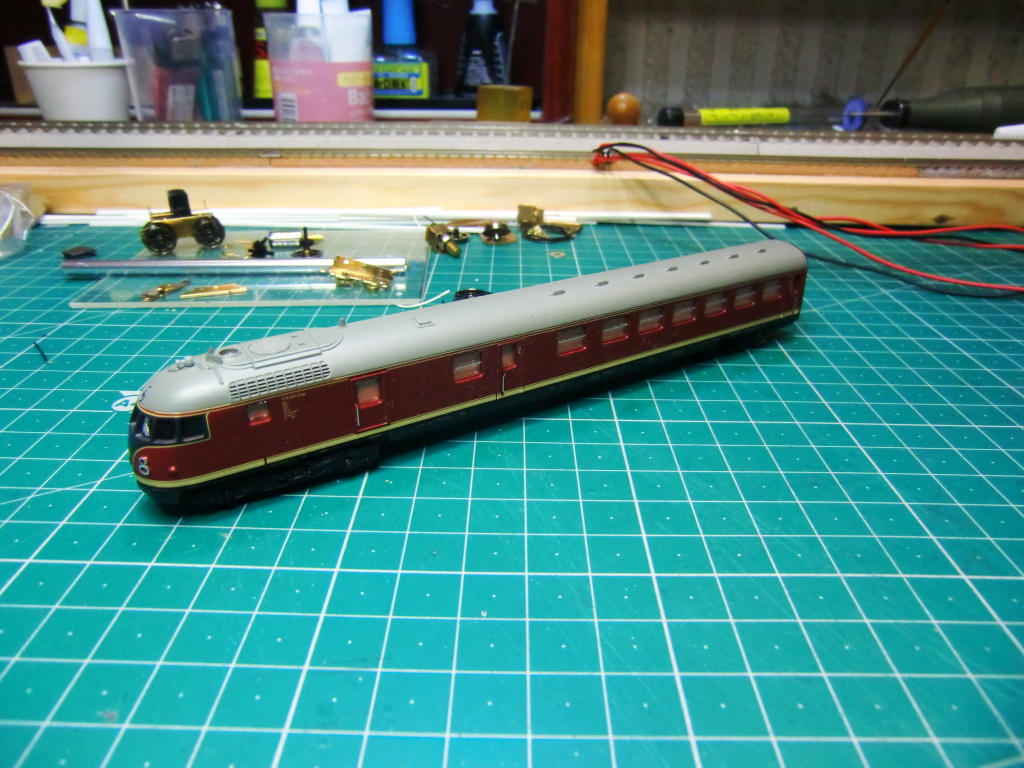
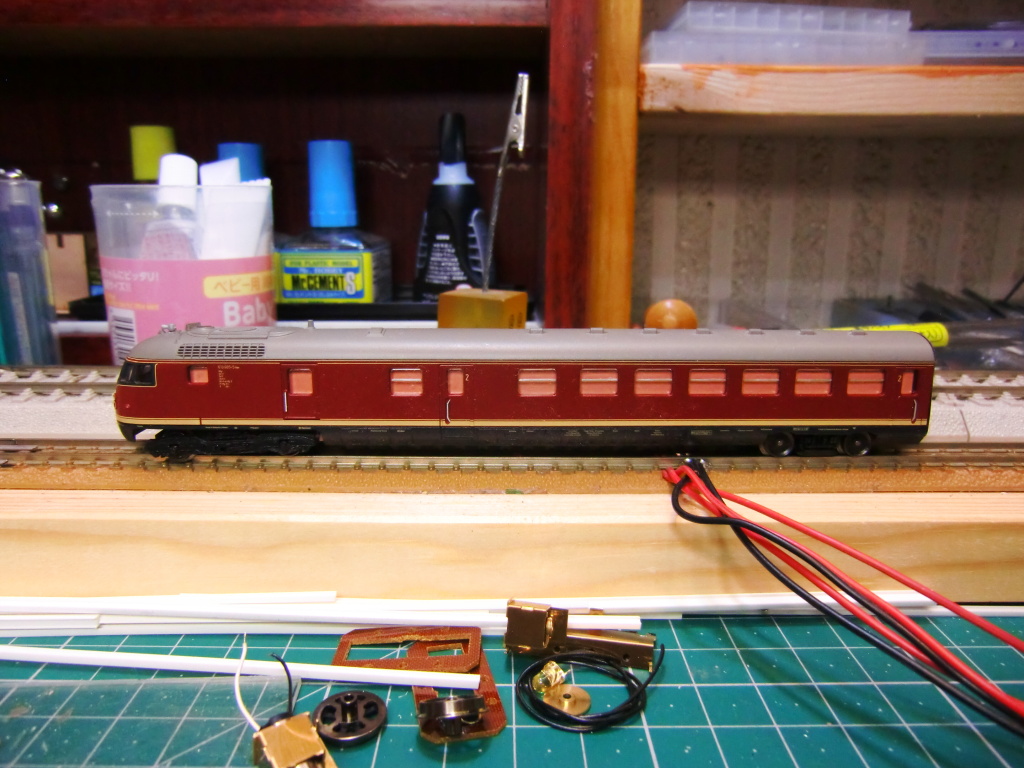
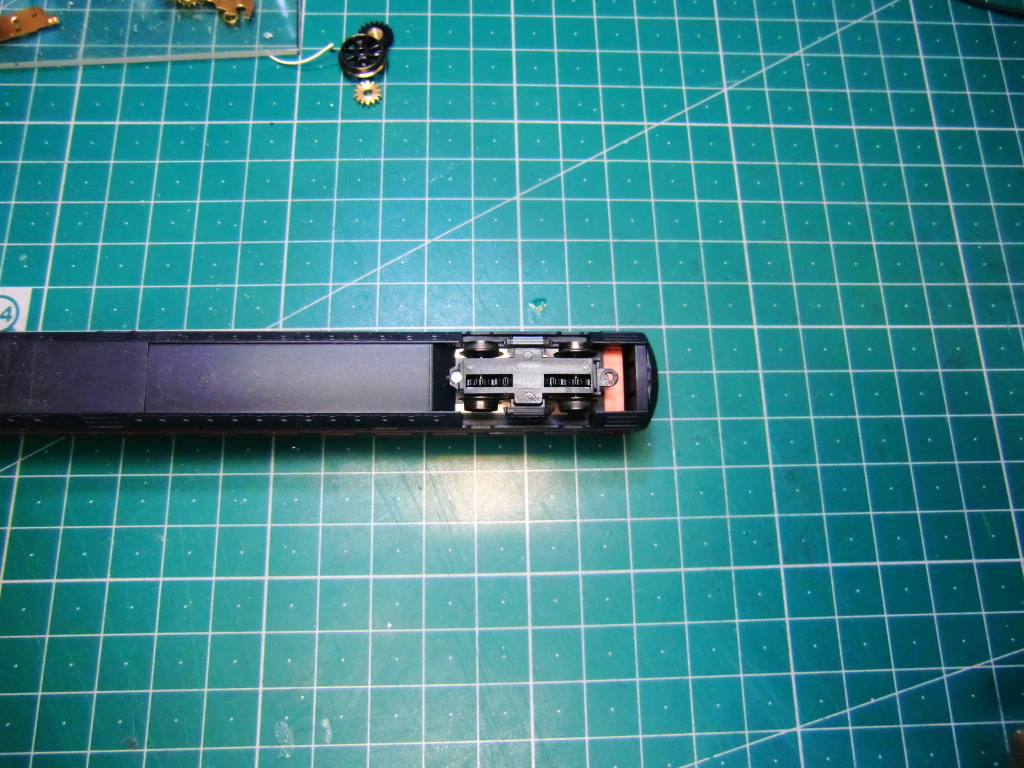
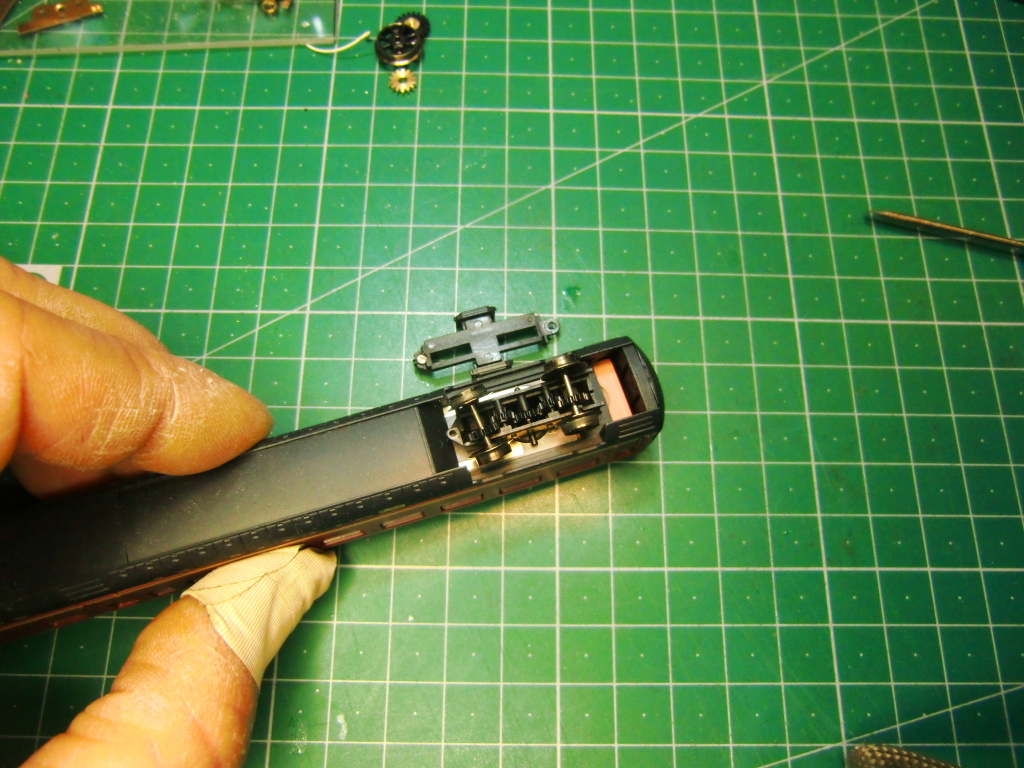
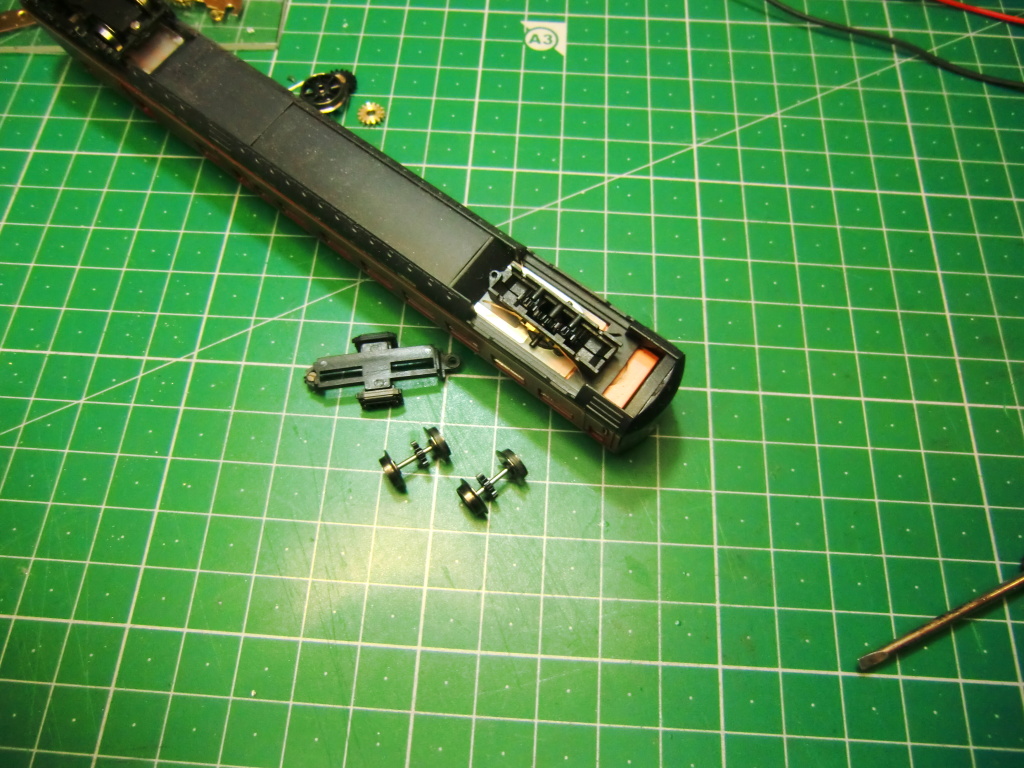
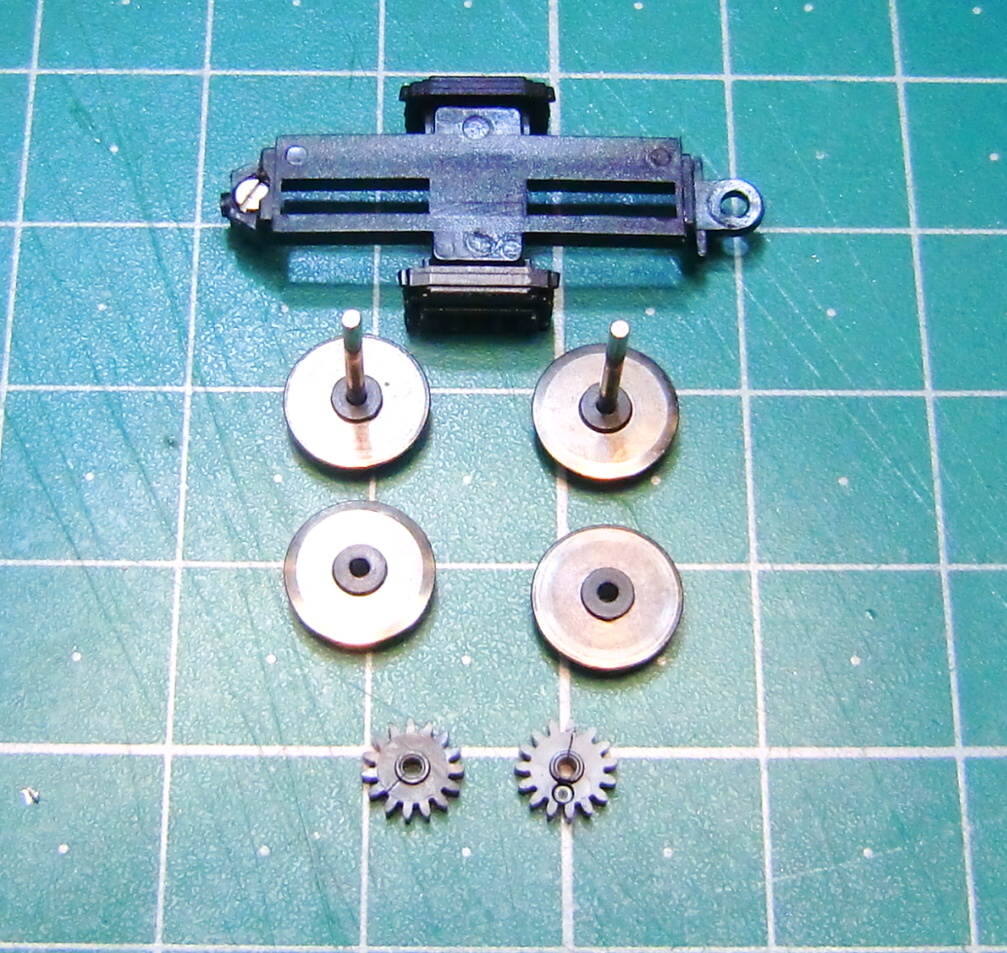
写真からもおわかりの通りう、ギアが経年劣化により割れてピッチがずれてしまっています。ギアにつきましては新規に作るほかありません。
▼現物スキャンとデータ制作

スキャナーで細部までしっかりと取り込むため、「1200dpi」で読み取ります。
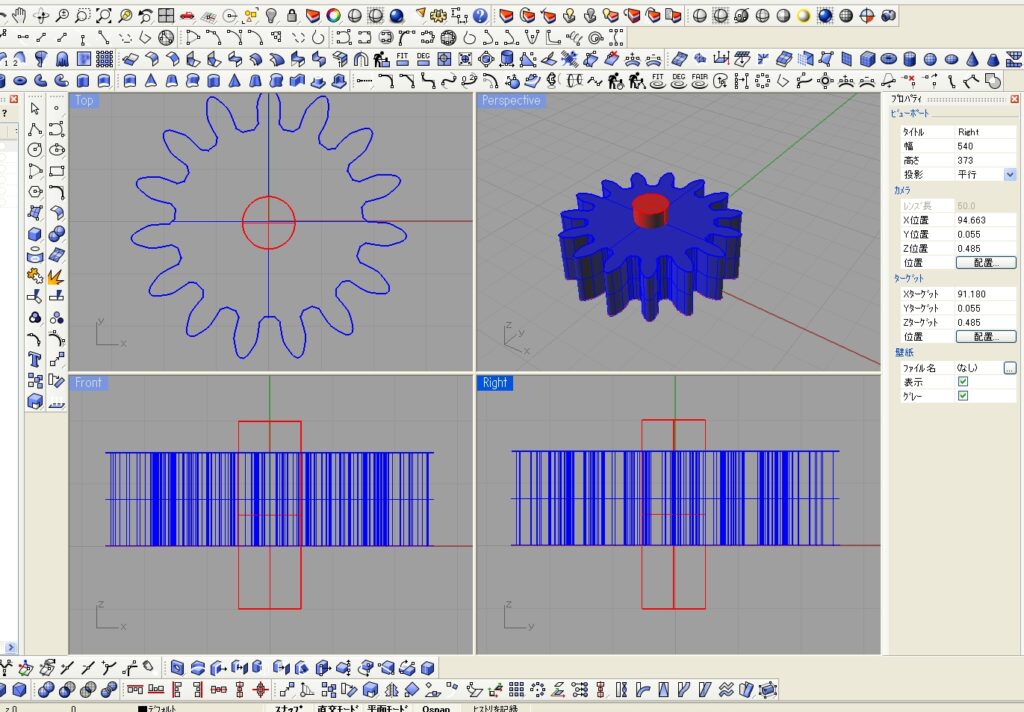
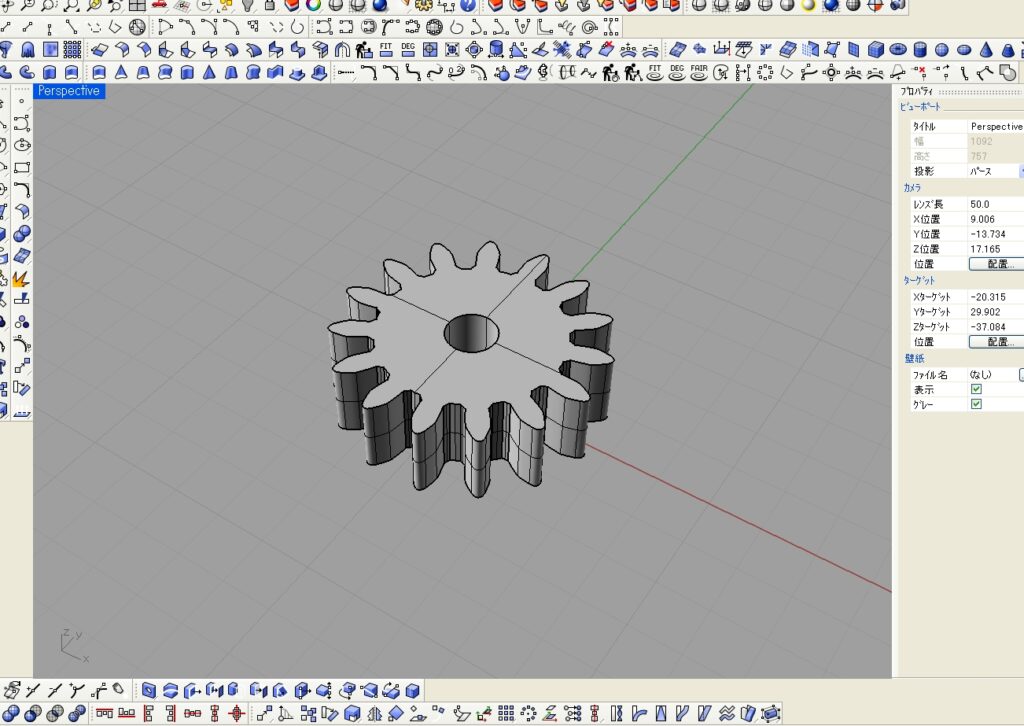
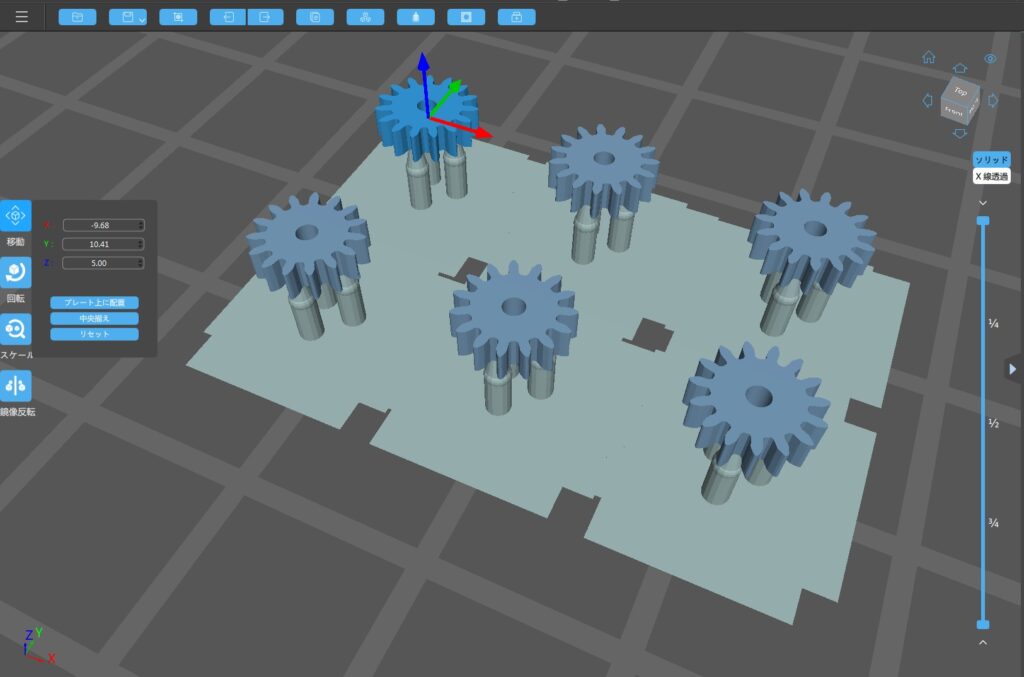
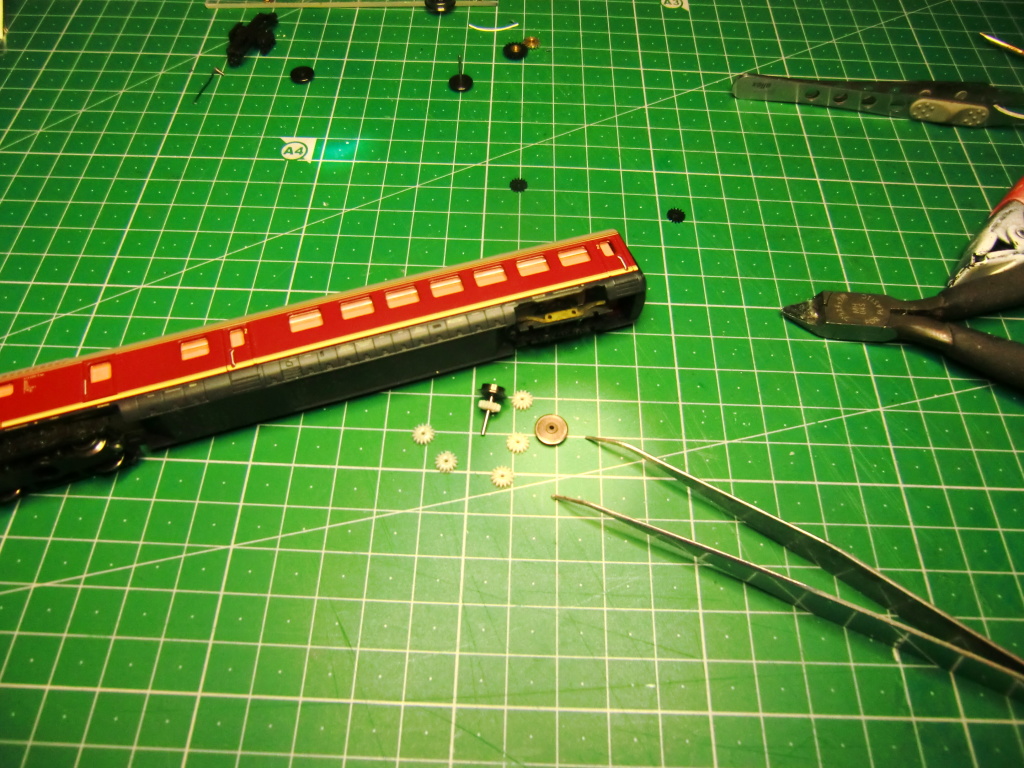
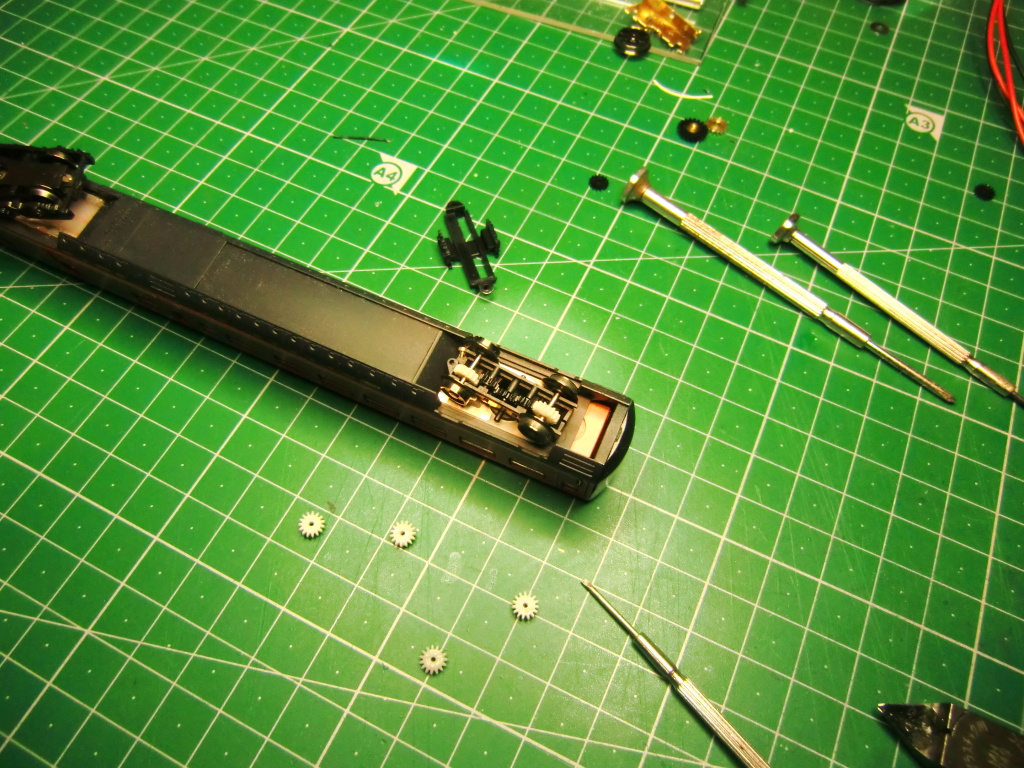
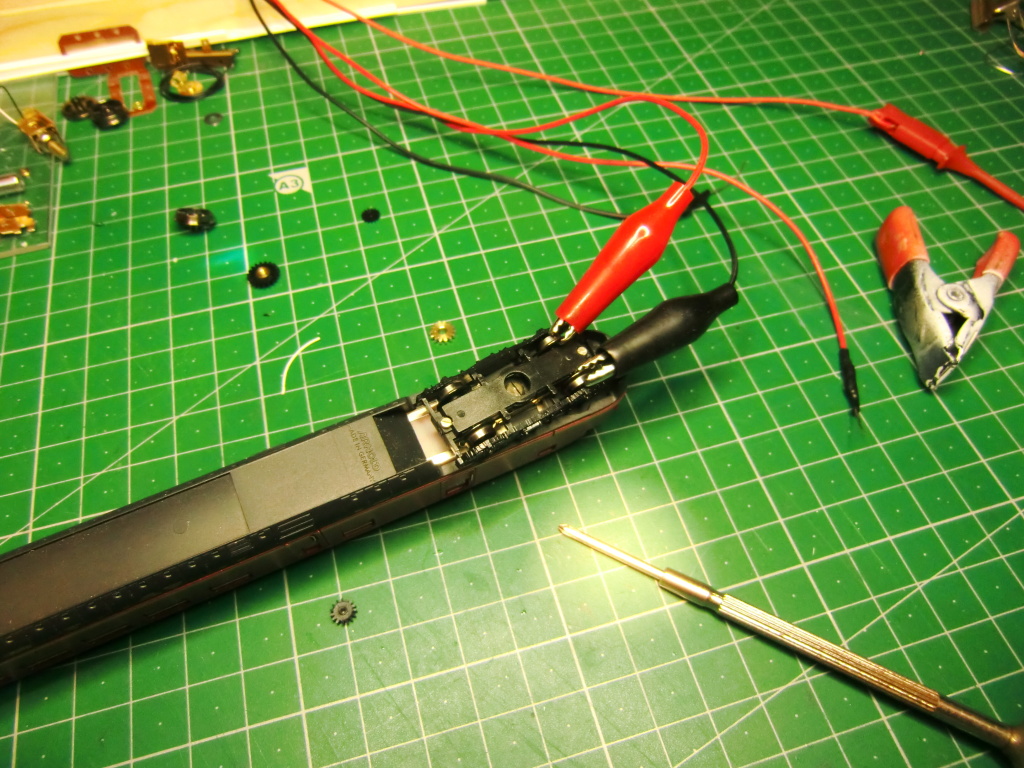
制作したギアに問題がないかを回転テストと調整を繰り返し行い、ピッチを手作業で削り仕上げていきます。
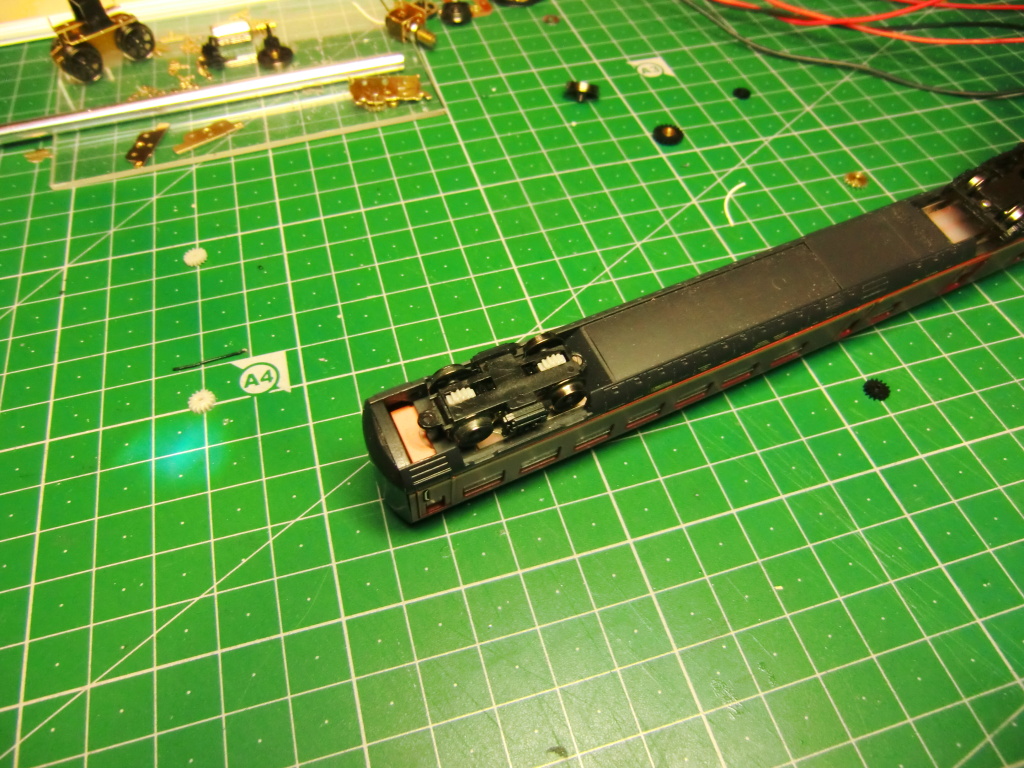
ようやくギアが完成して組込み完了です。次に集電系を一通り見ていきます。

上回りもすべて分解し、モーターを取り出し単体テストを行い確認と調整を行います。
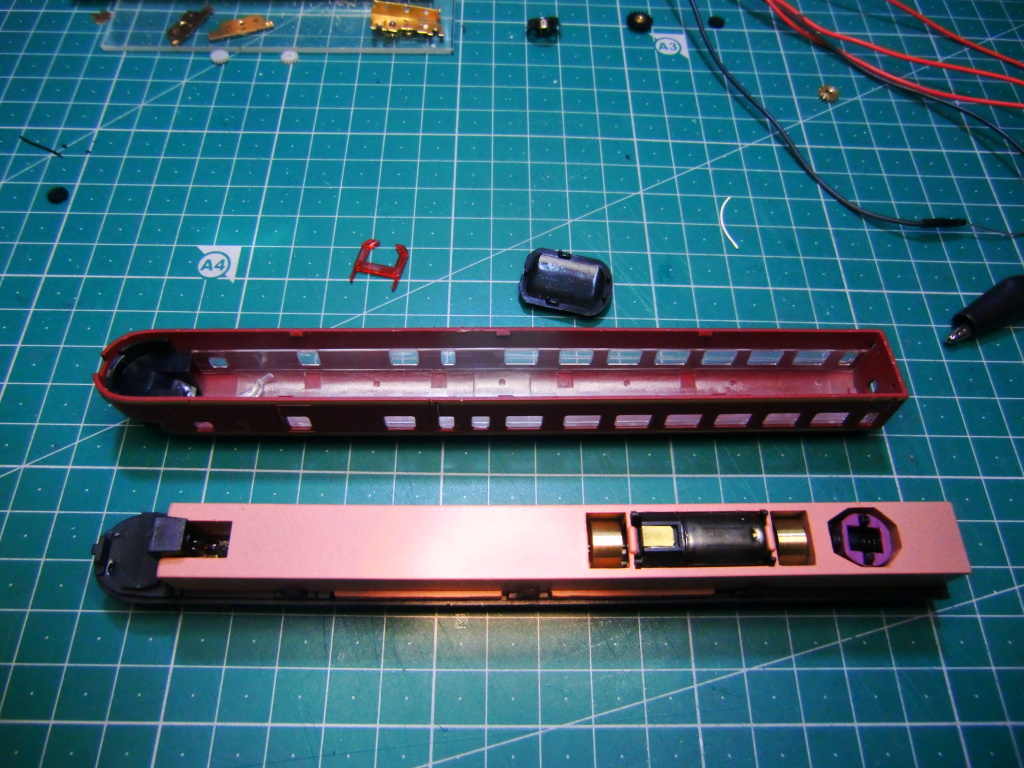
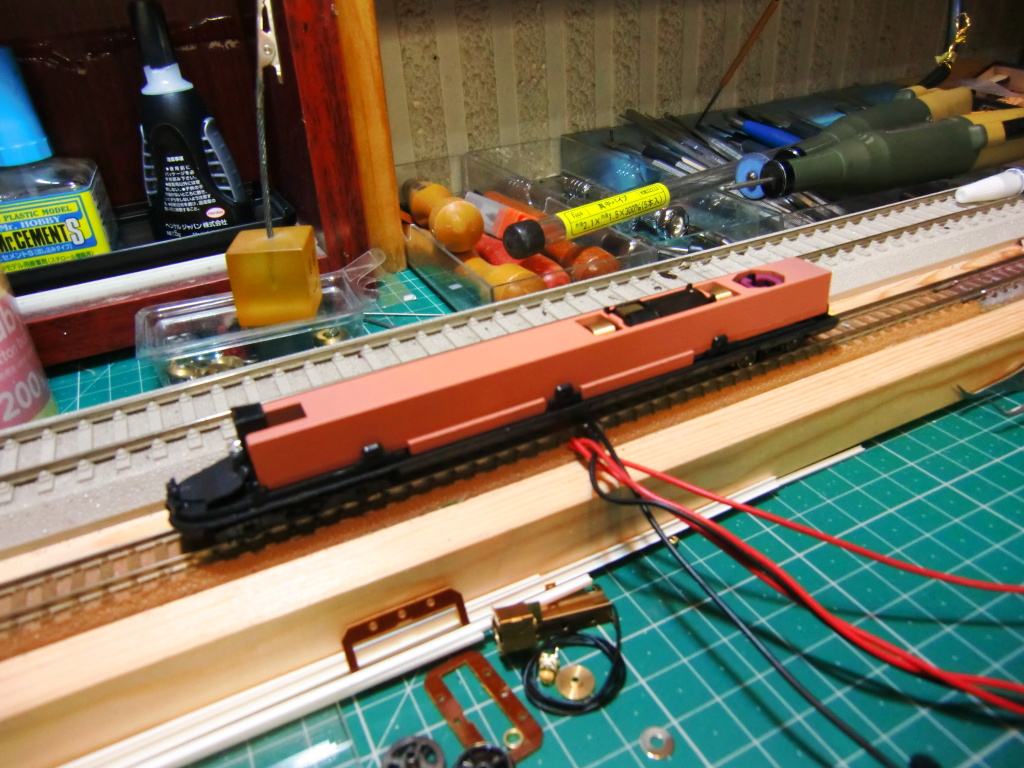
走行テストと調整を繰り返します。問題がなければボディーを戻していきます。
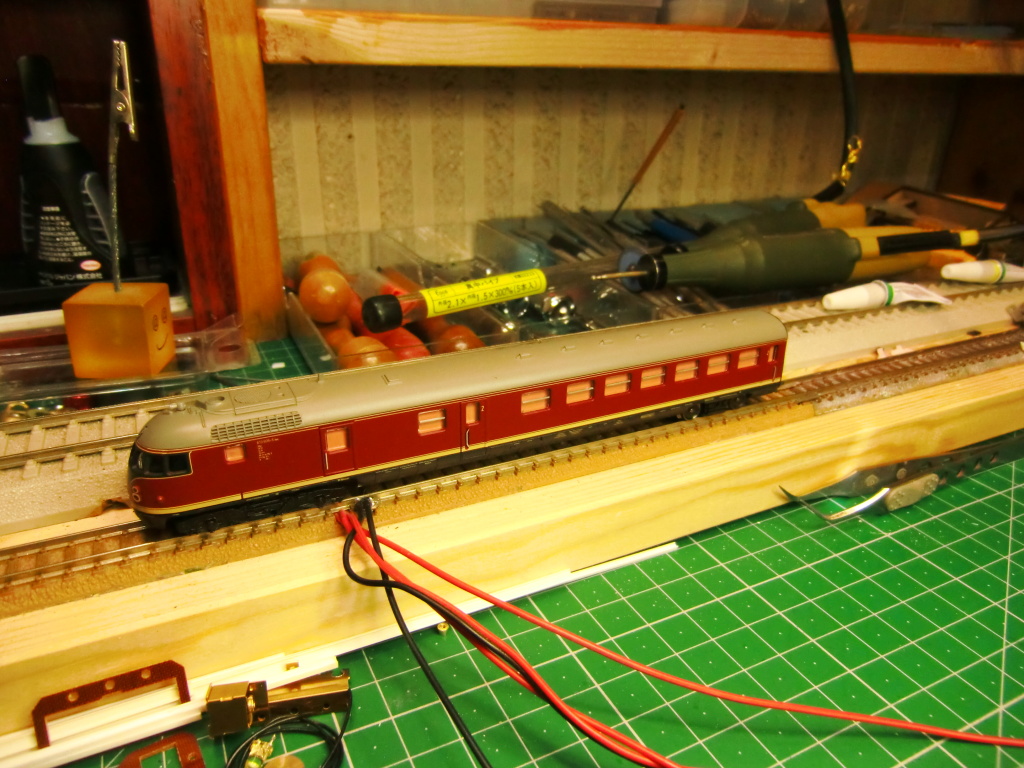
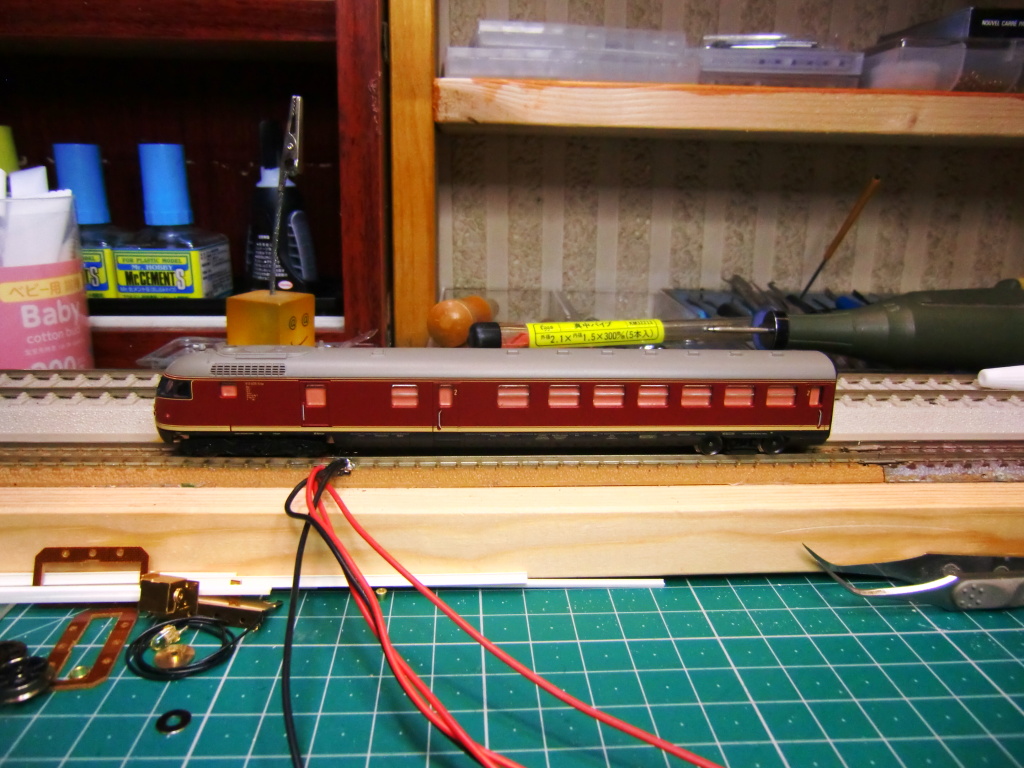
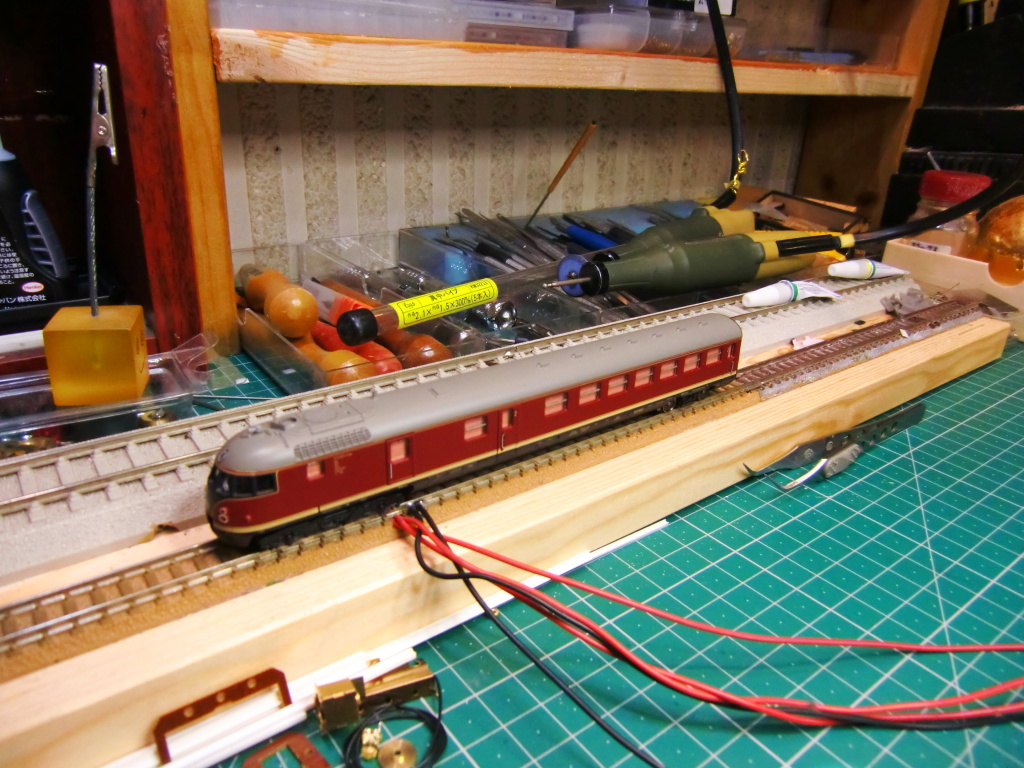
作業完了でございます。
モーターの回転が非常に不安定で音と振動があります。



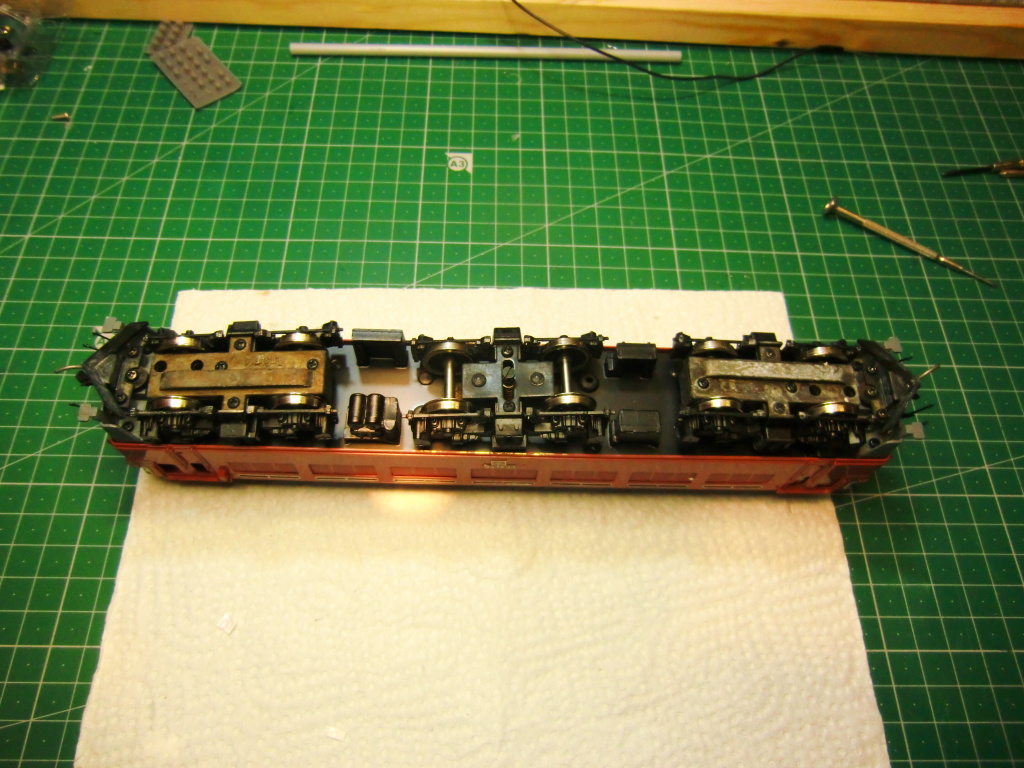
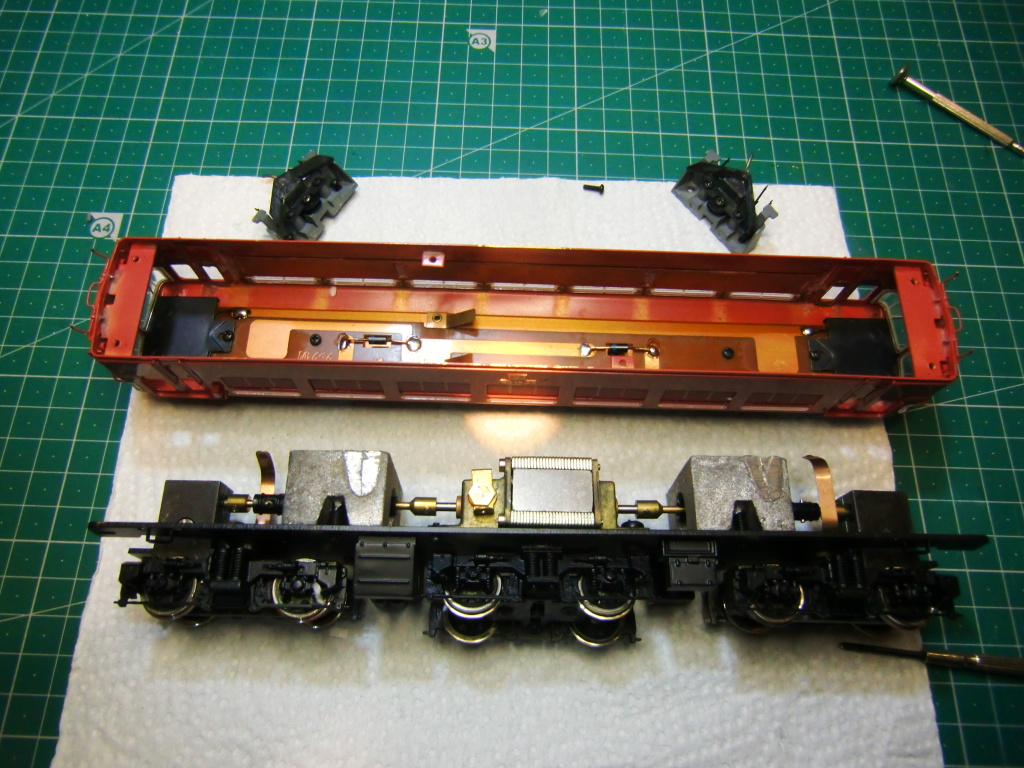
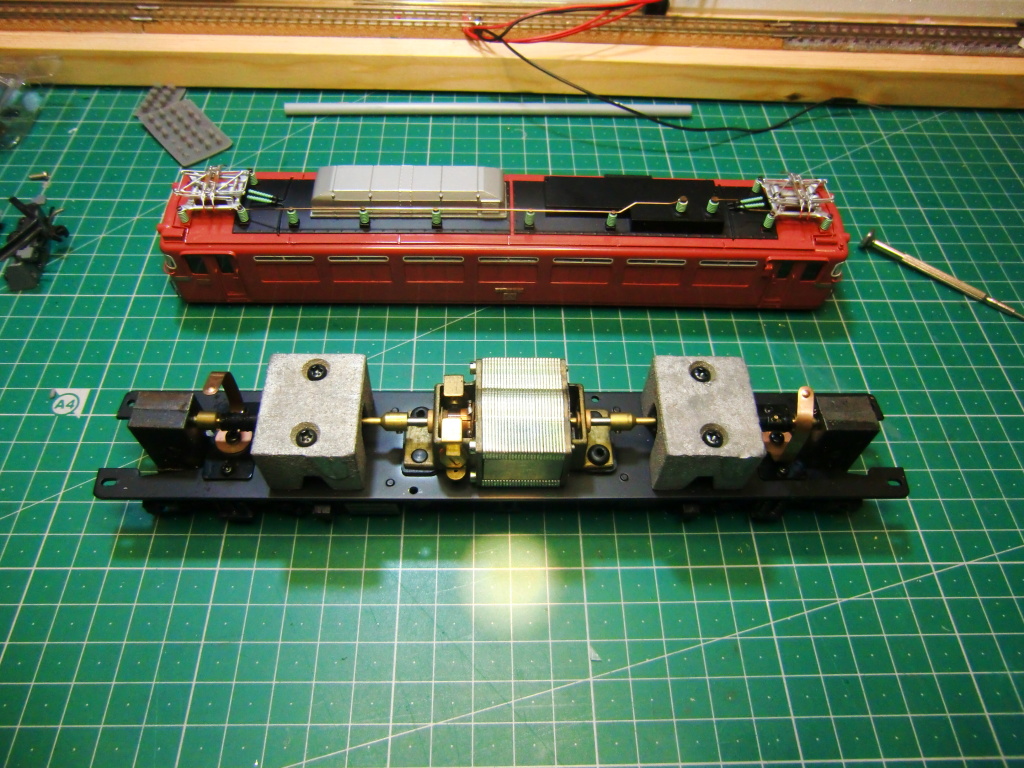
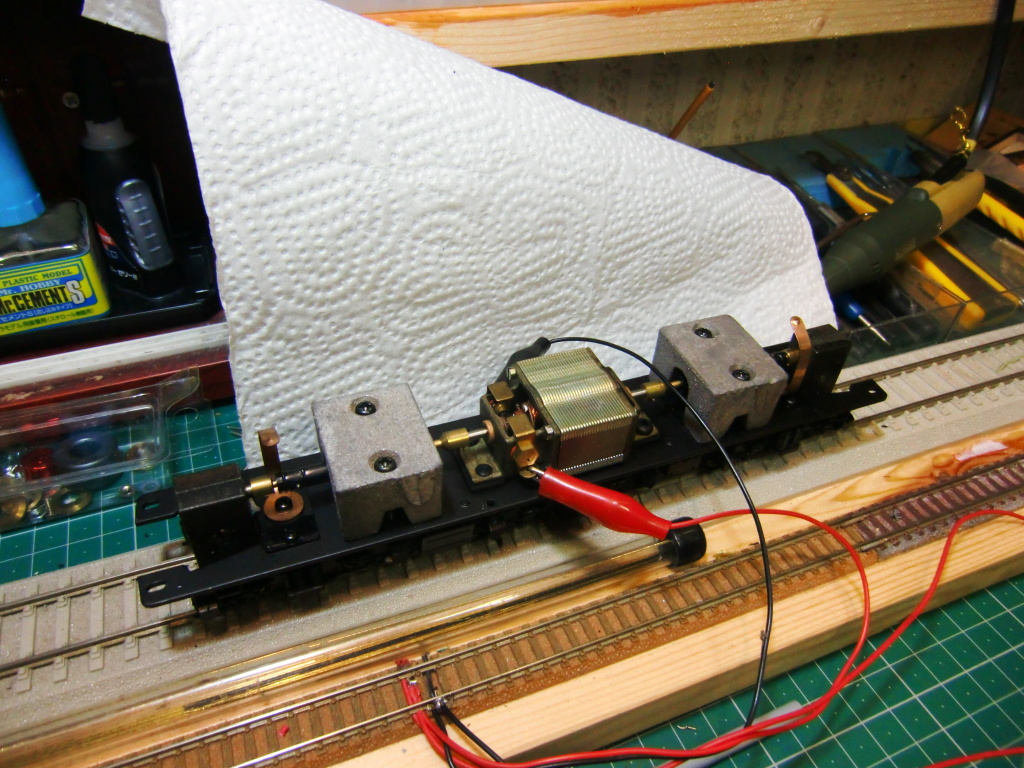
モーターそのものに問題をかかえているようです。
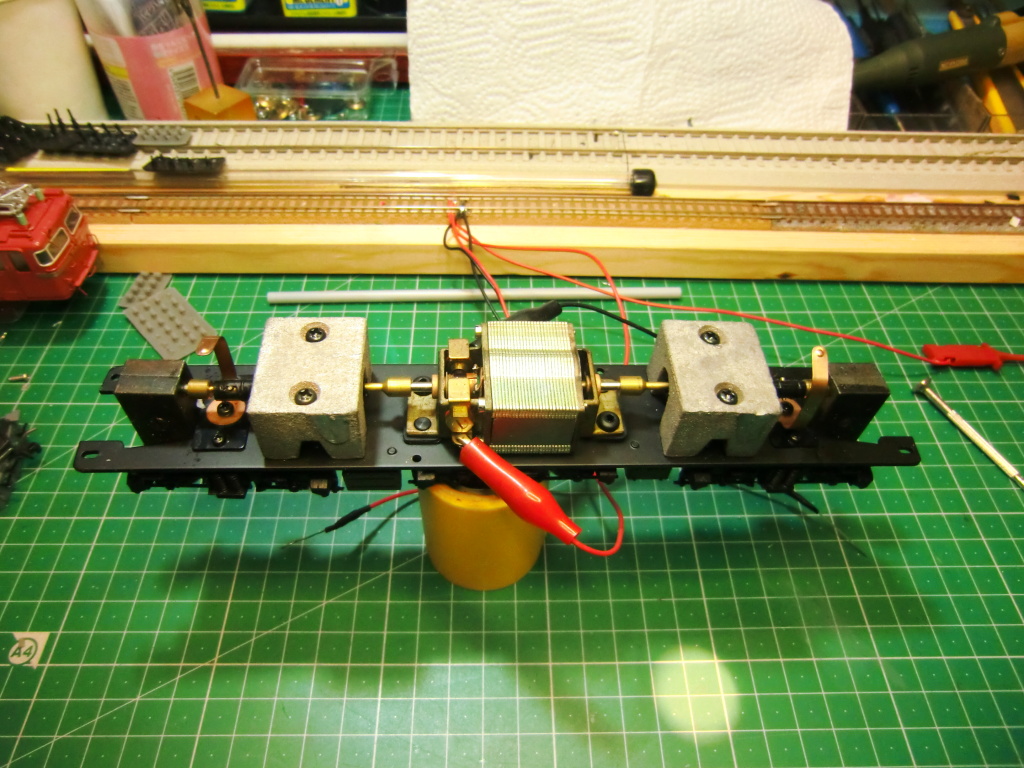
回転のブレが大変大きいです。
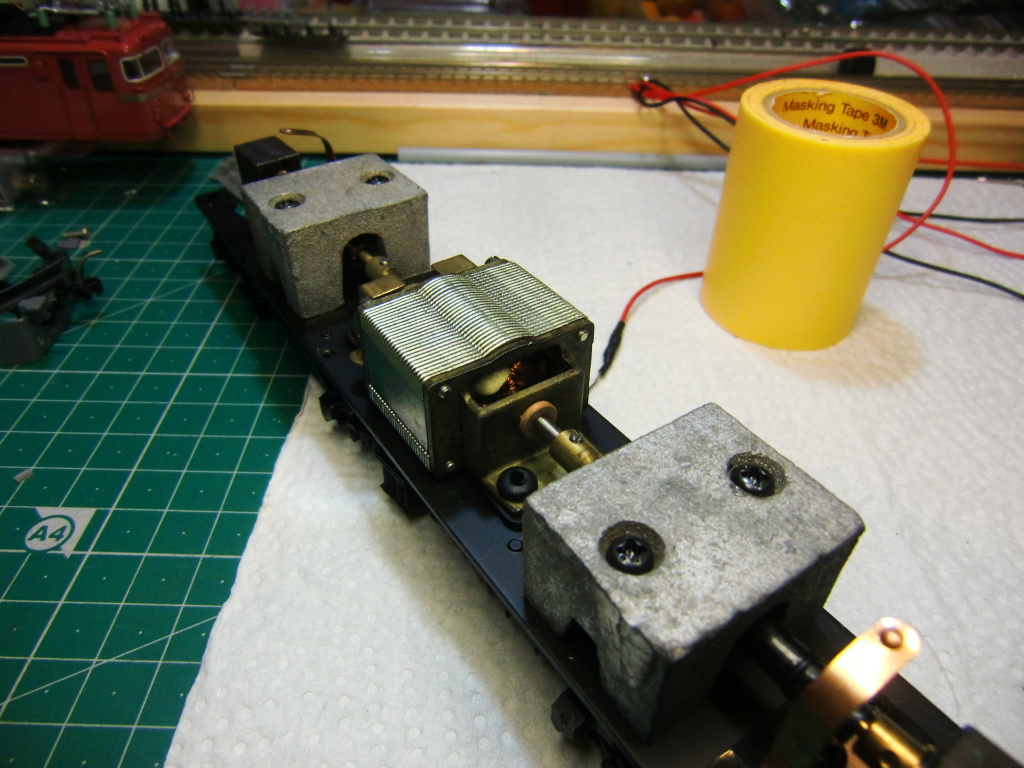
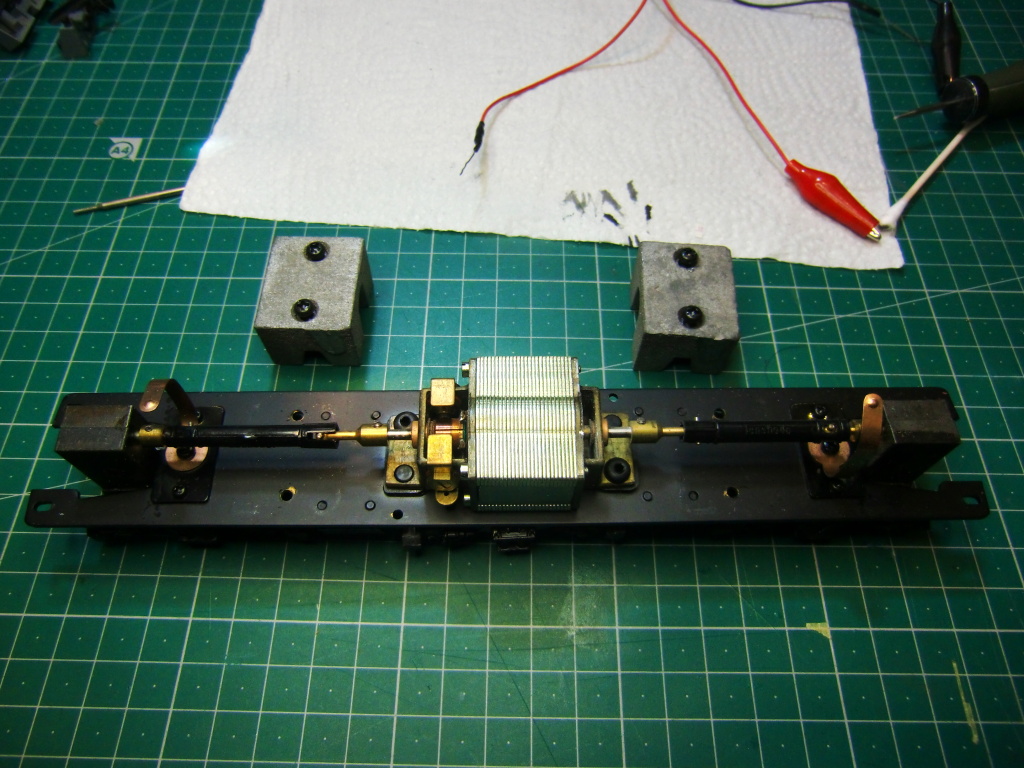
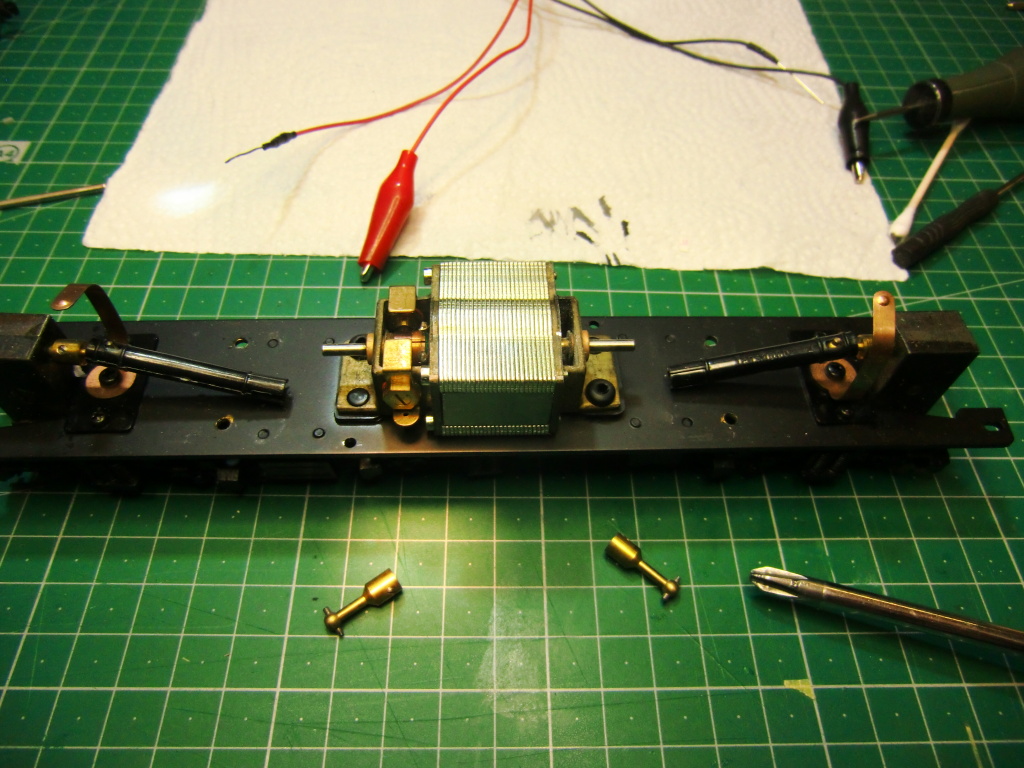
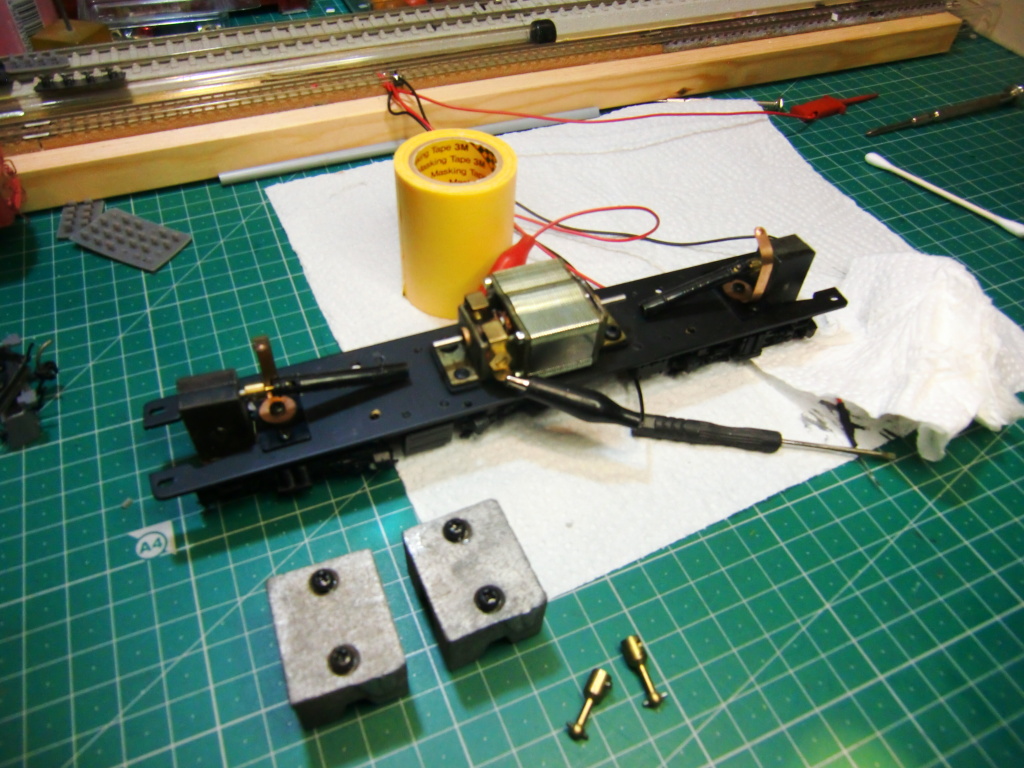
周りのパーツも外してより詳細に見ていきます。
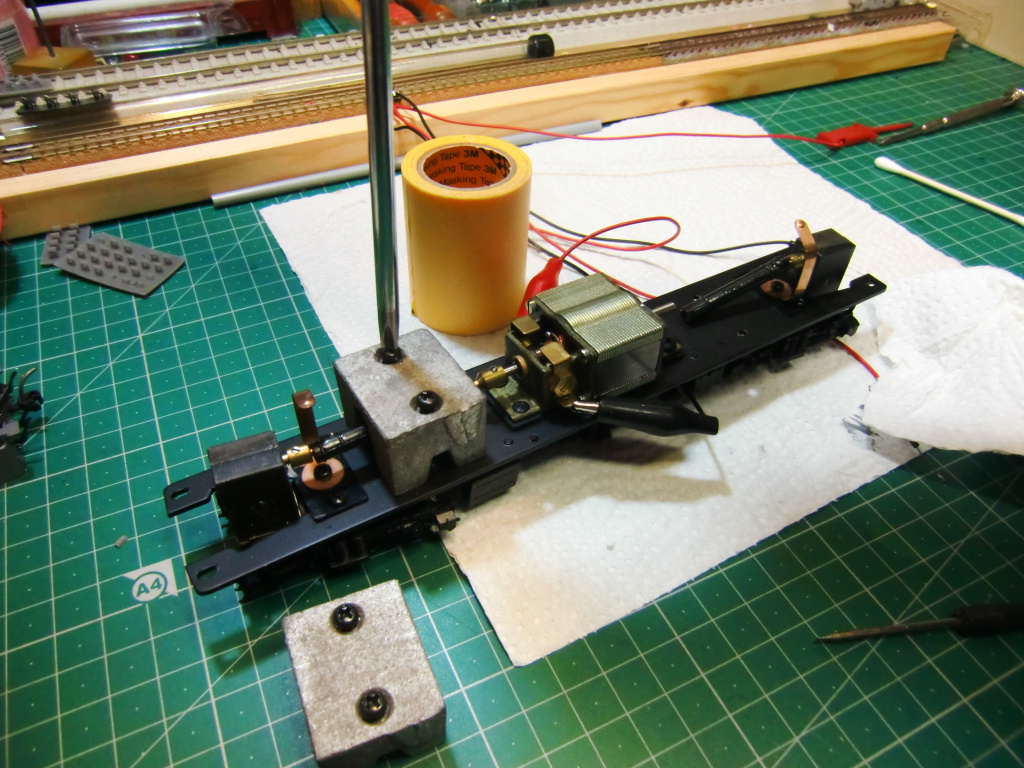
モーターの回転がだいぶ安定したところで戻します。
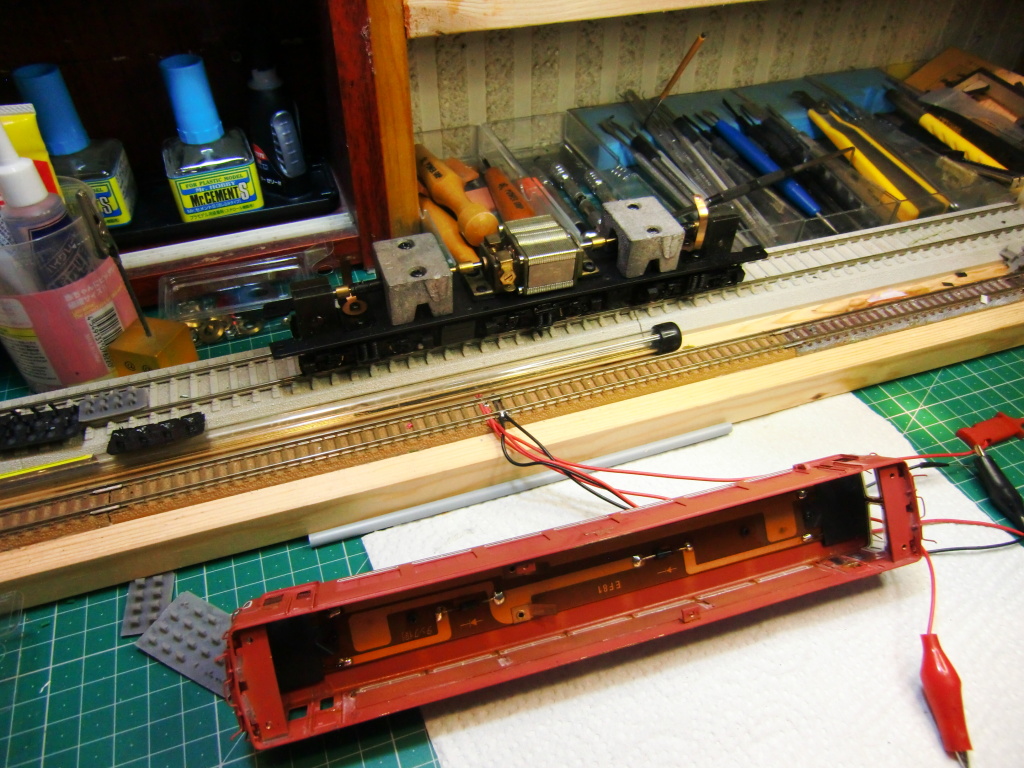
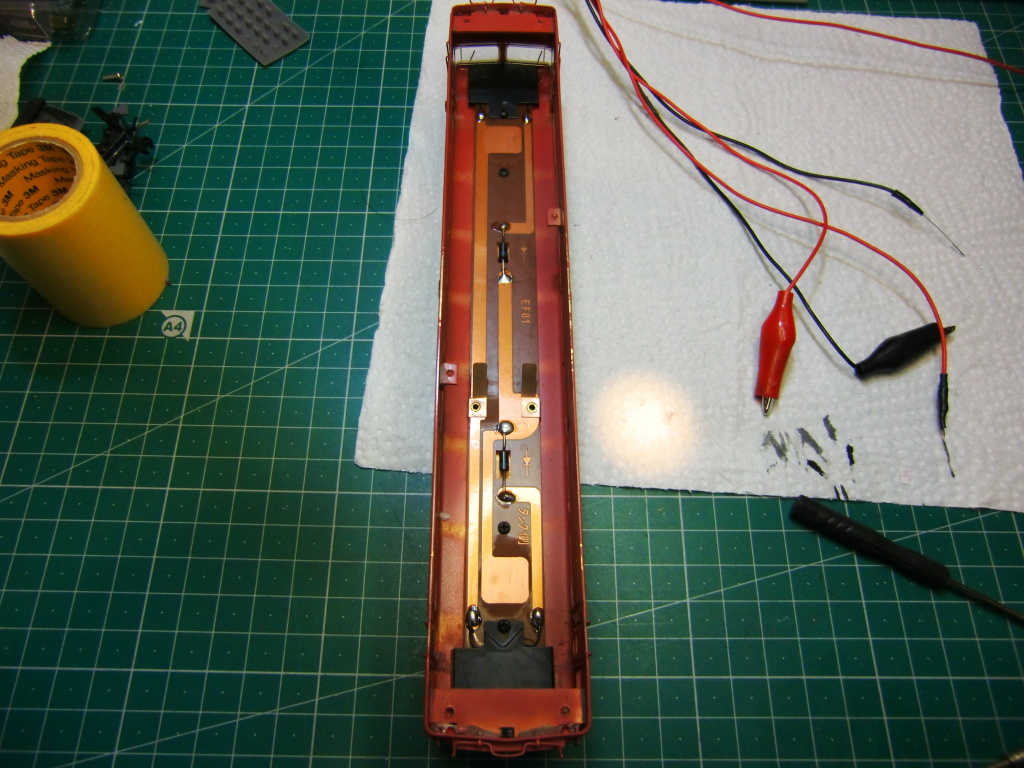
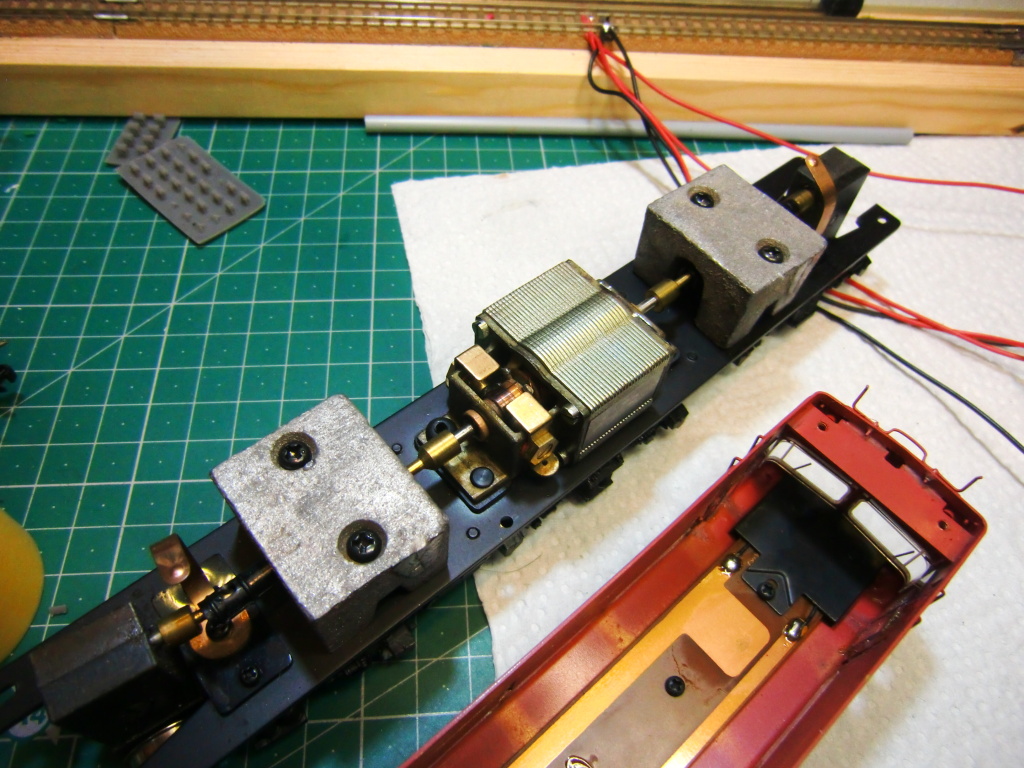
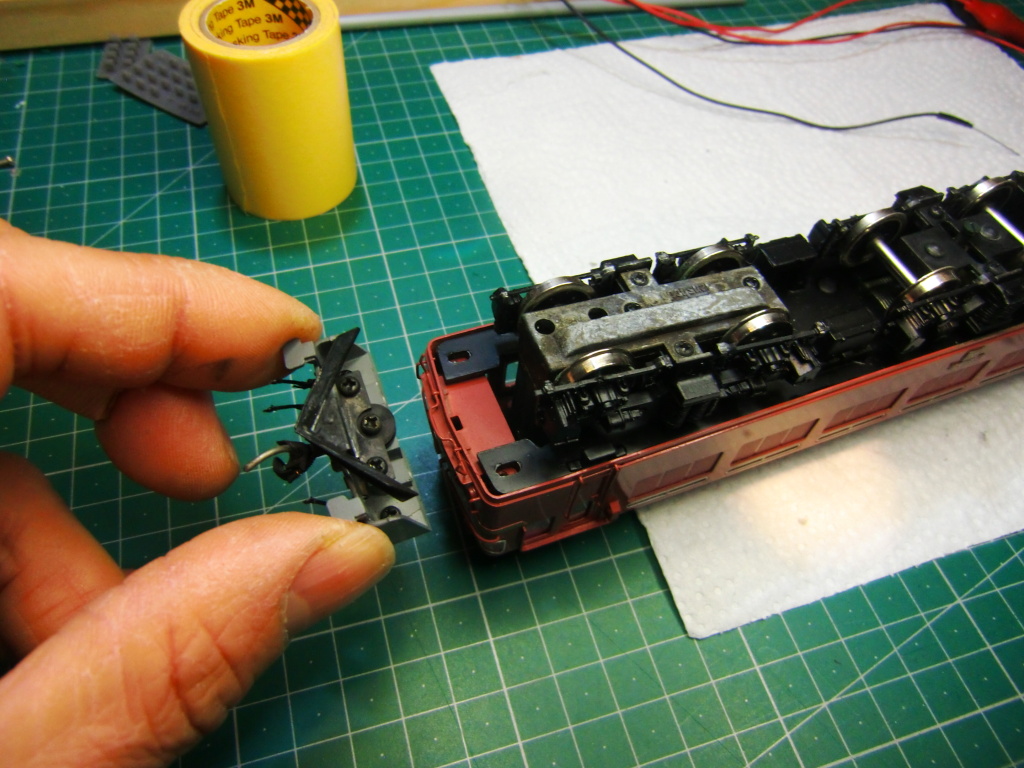
カプラー加工へと移ります。
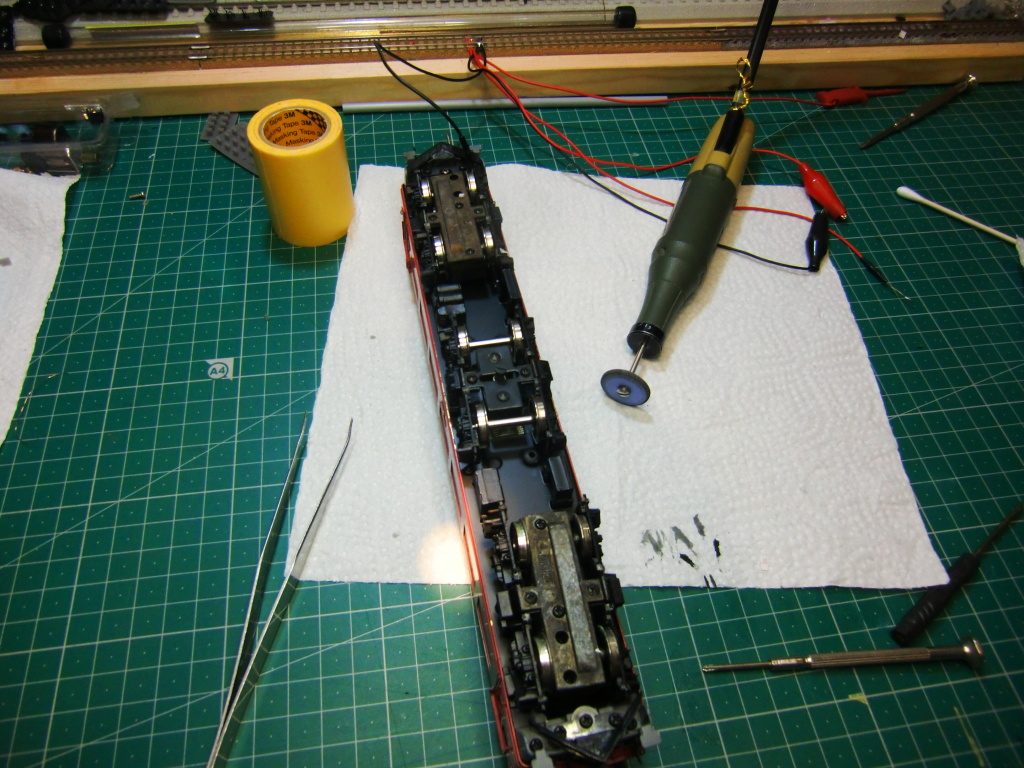
最後に車輪を磨きだして作業は完了となります。
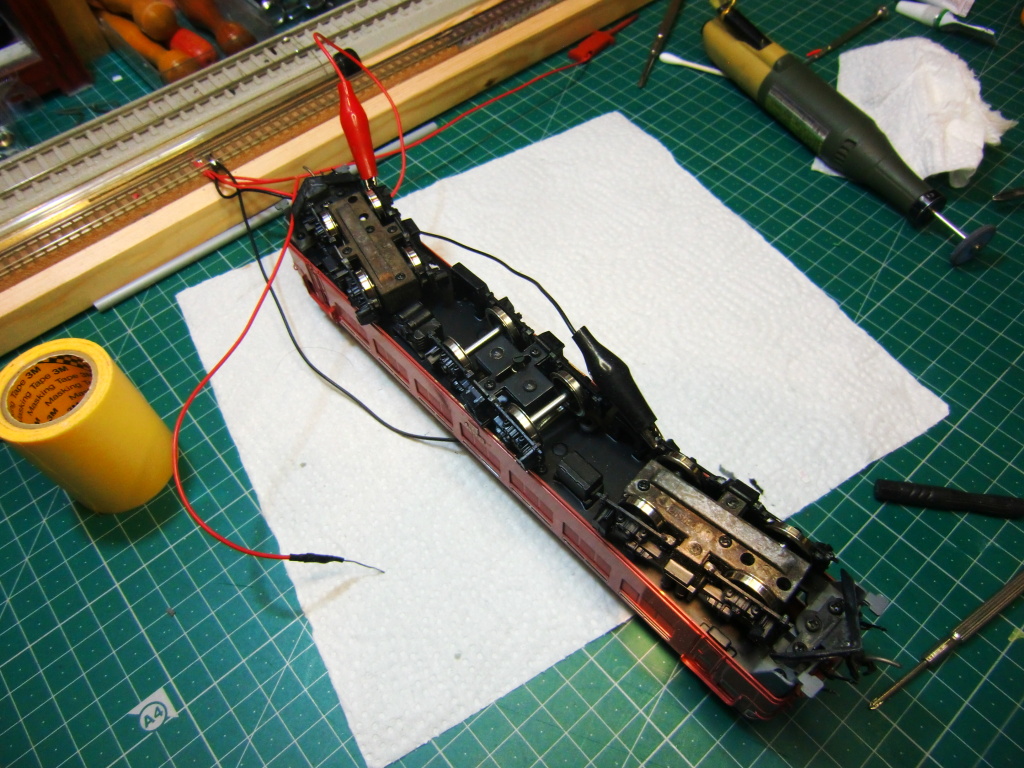



走行テストOKです。作業完了です。
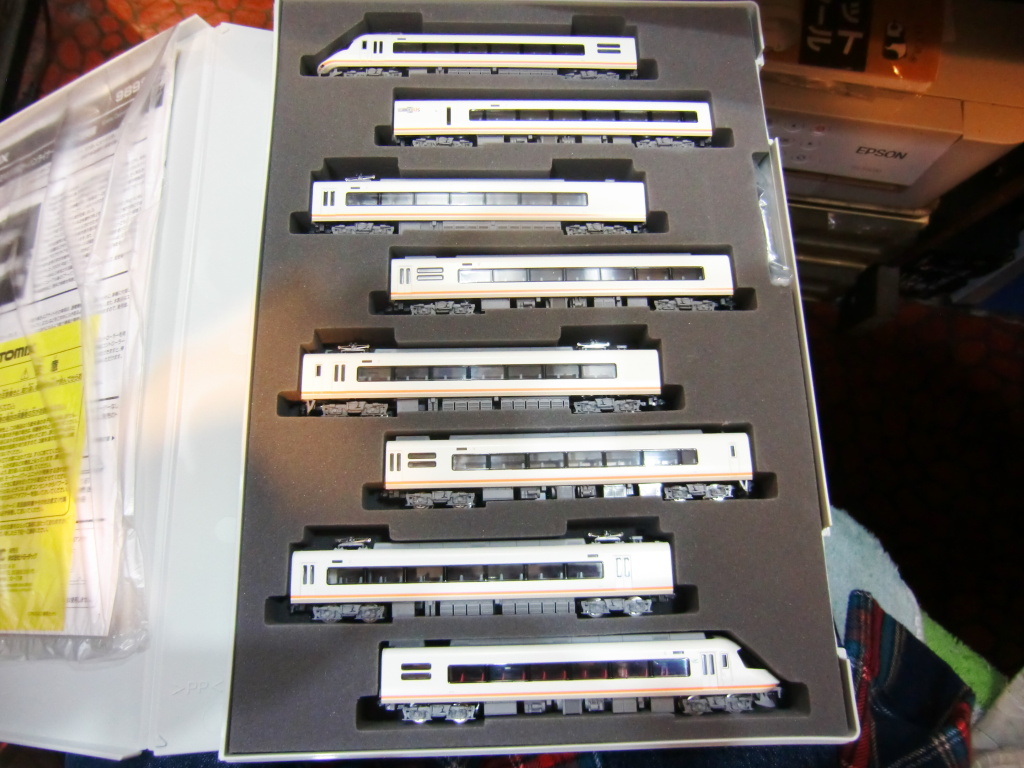
まずは、車体を分解します。



屋根もすべて外します。
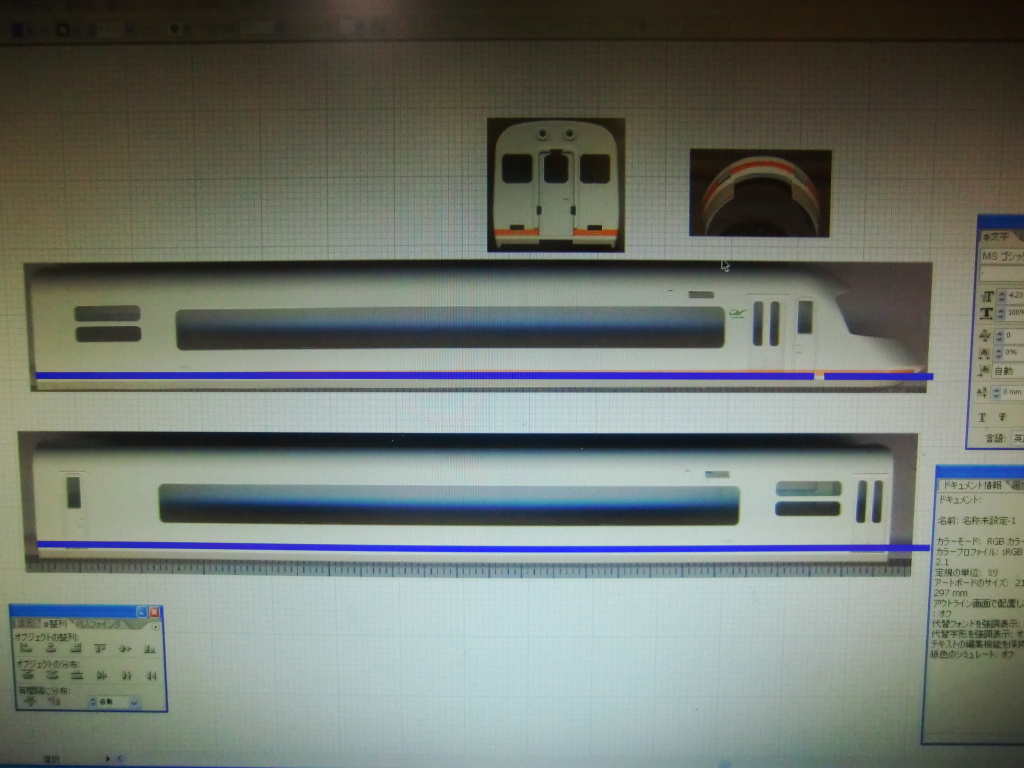
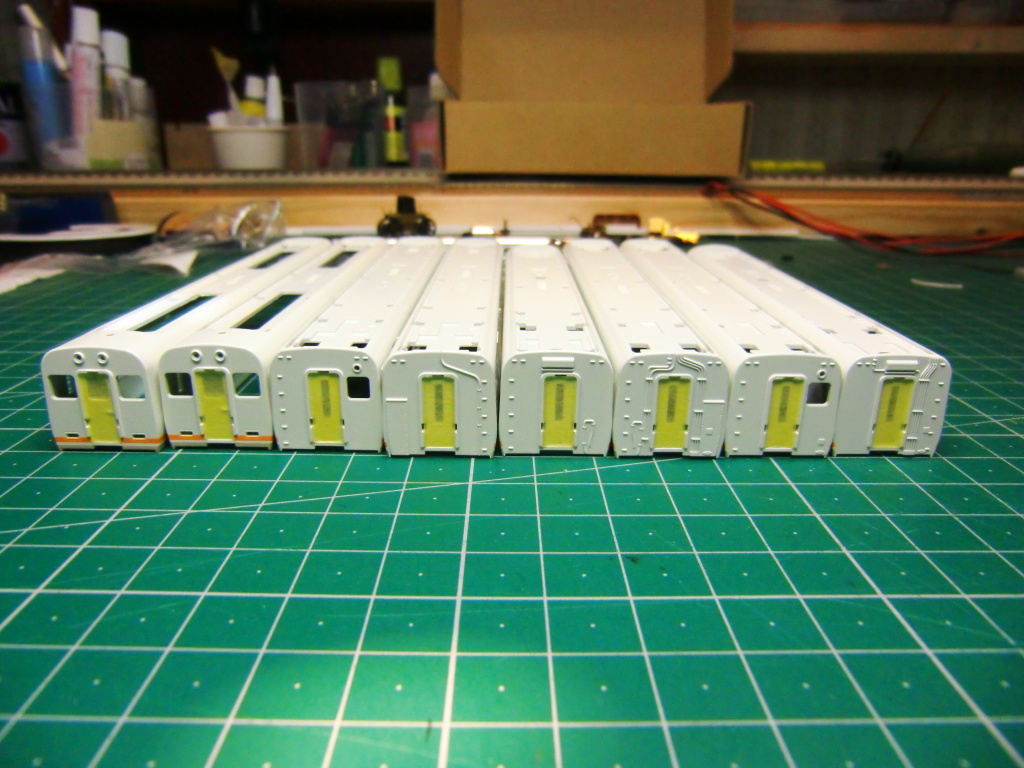

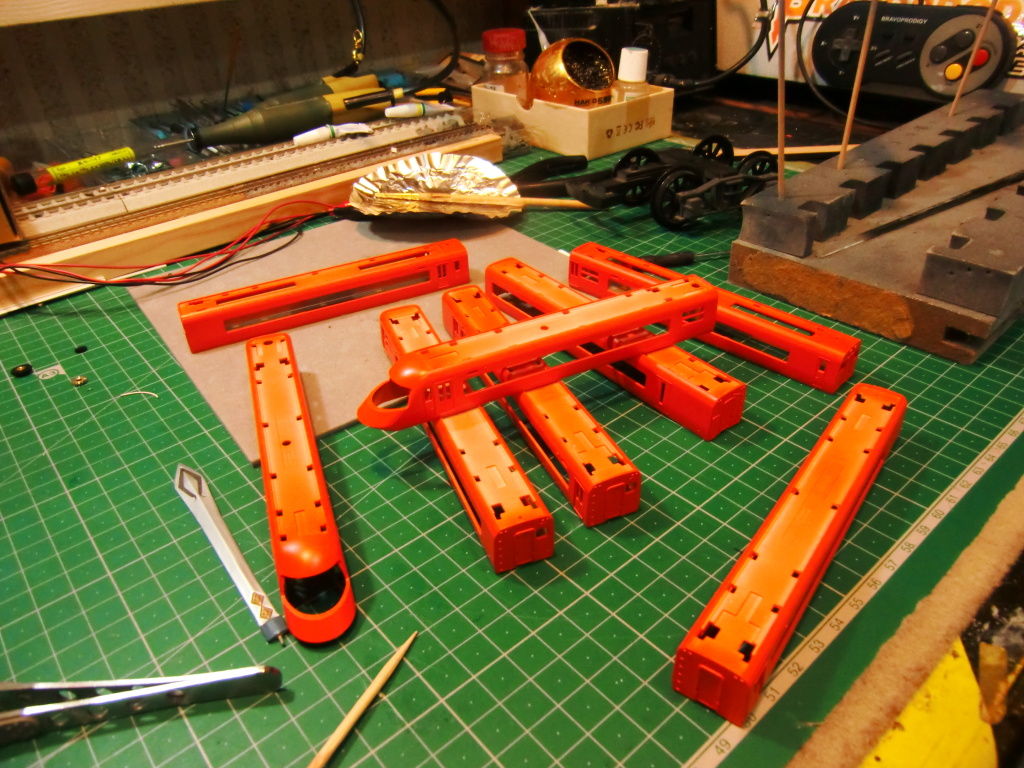
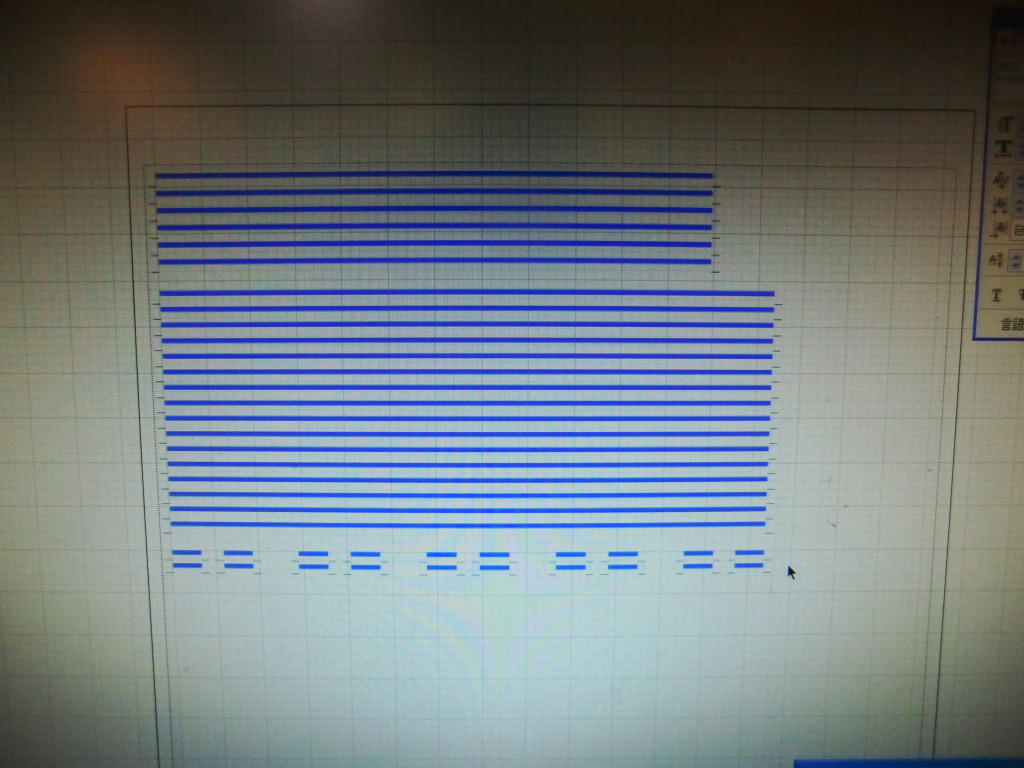
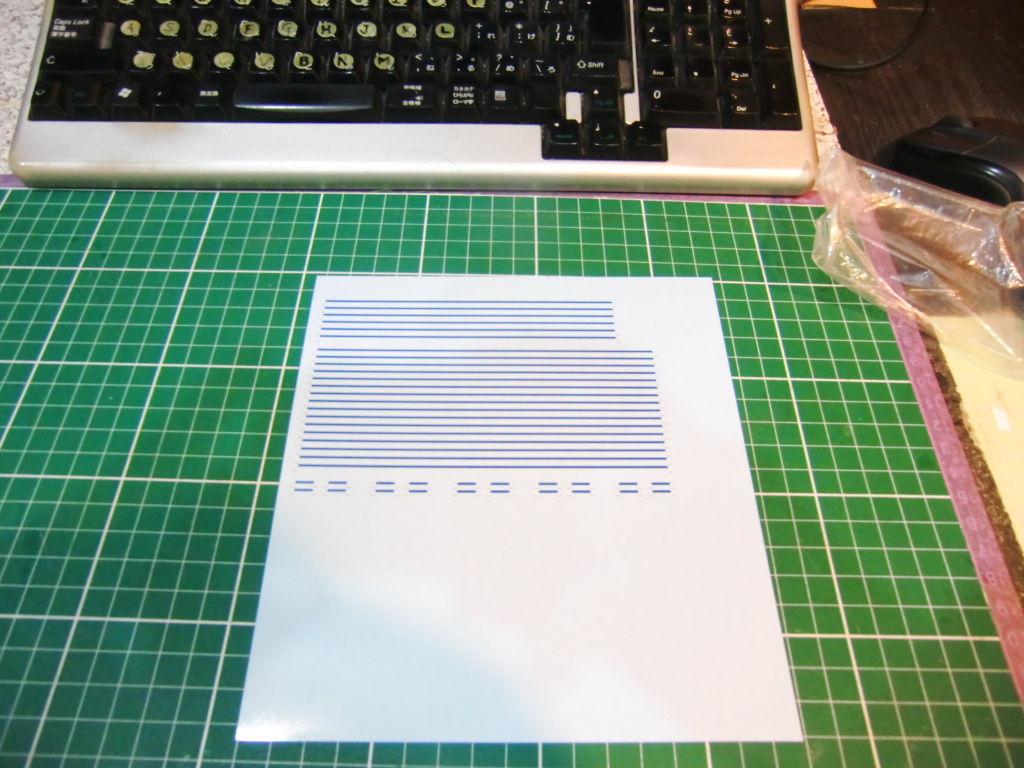
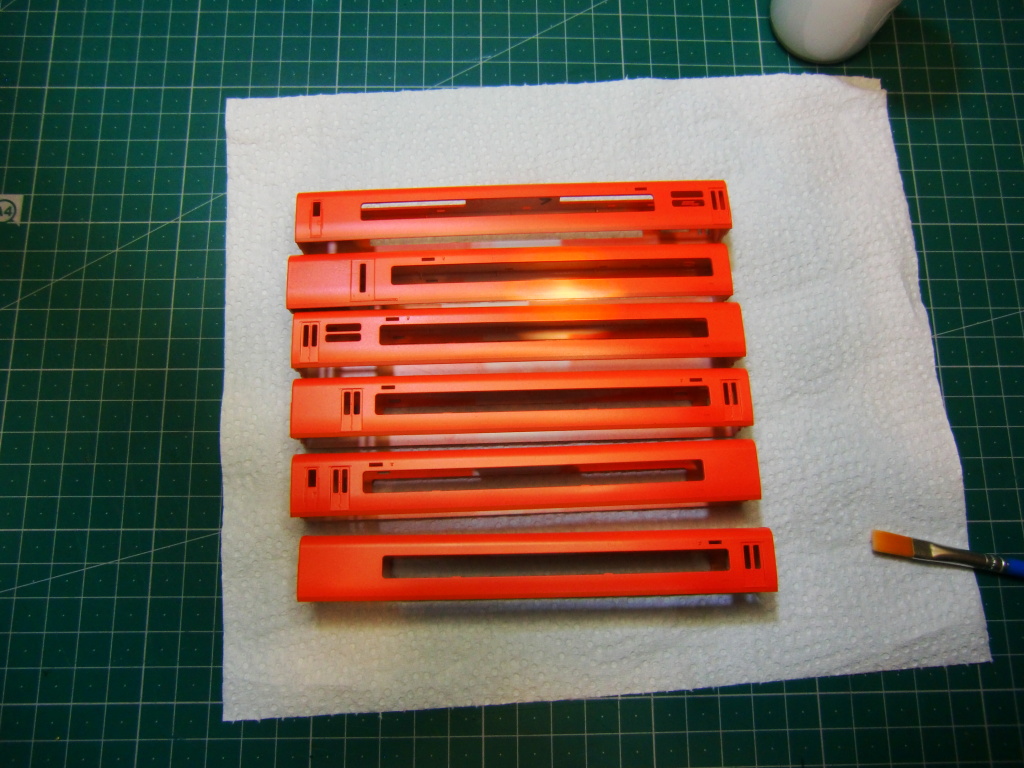



24時間乾燥させてから、仕上げとして「UVクリアーコート」を車体全体に3~5回に分けて重ねていきます。
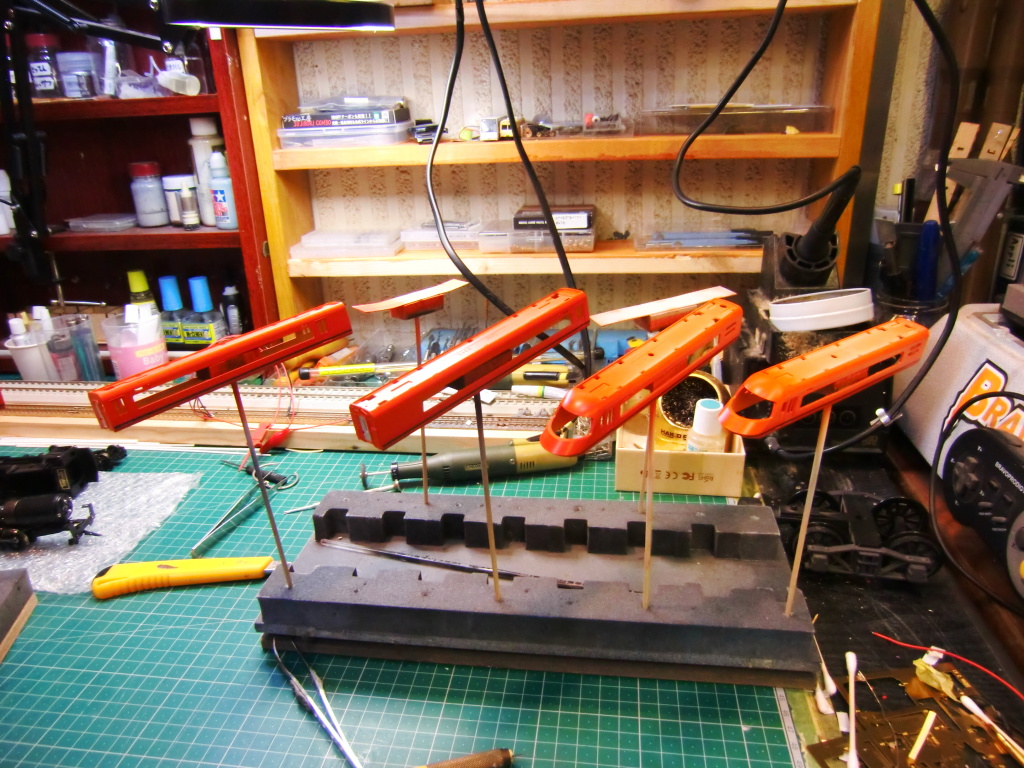

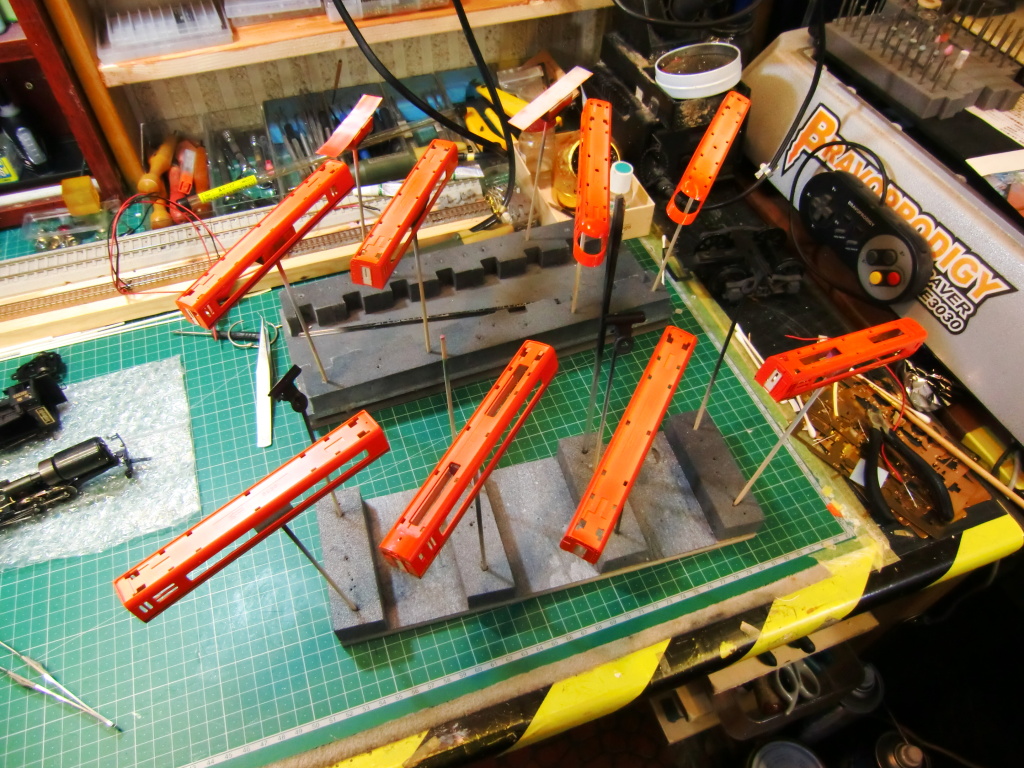
「UVクリアコート」作業が完了です。6時間ほど自然乾燥させてから、車体を組み戻して作業は完了となります。



作業完了でございます。


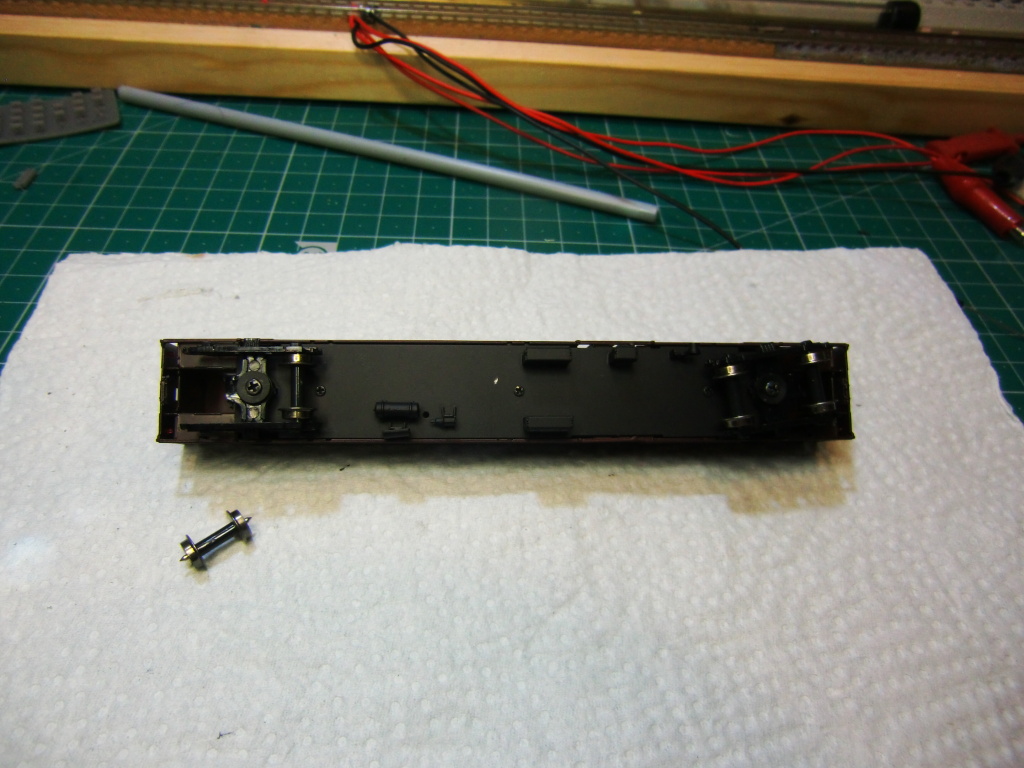
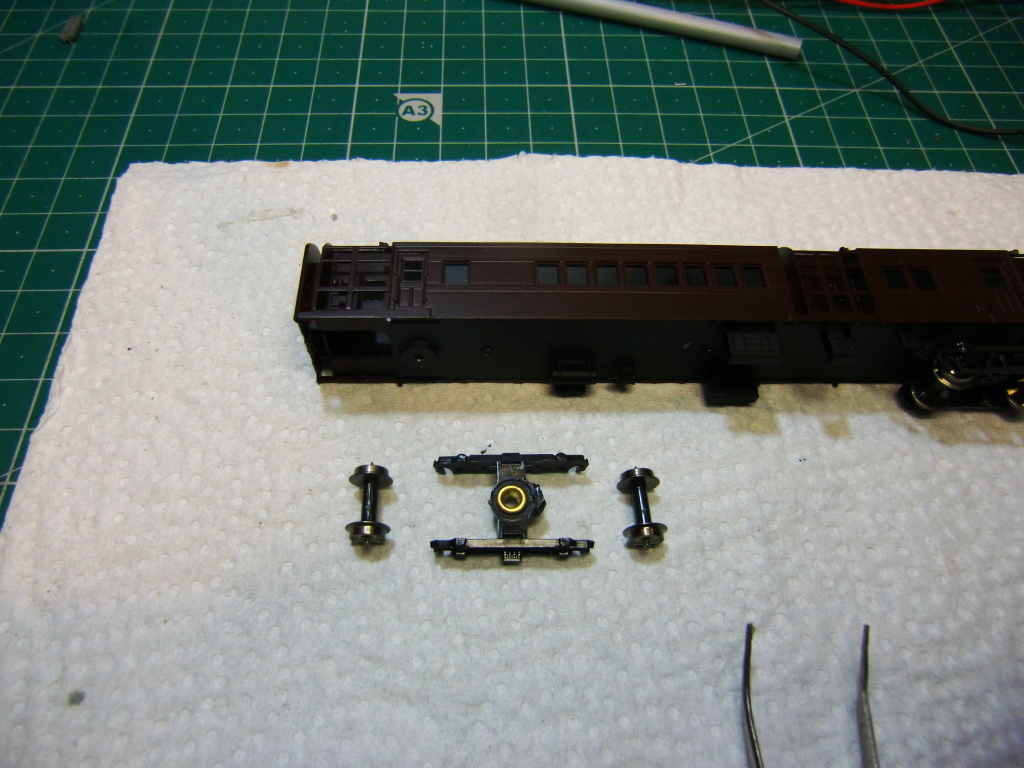

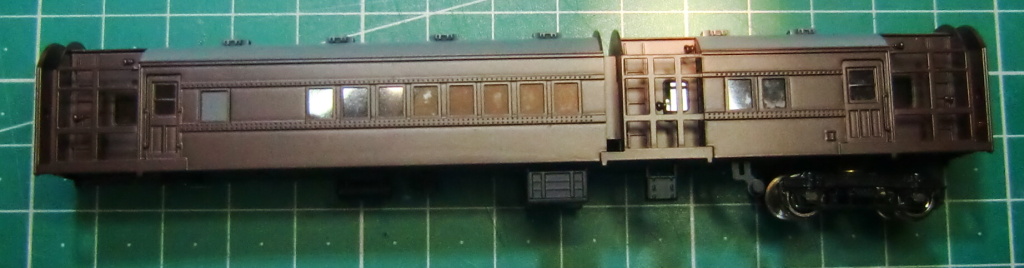
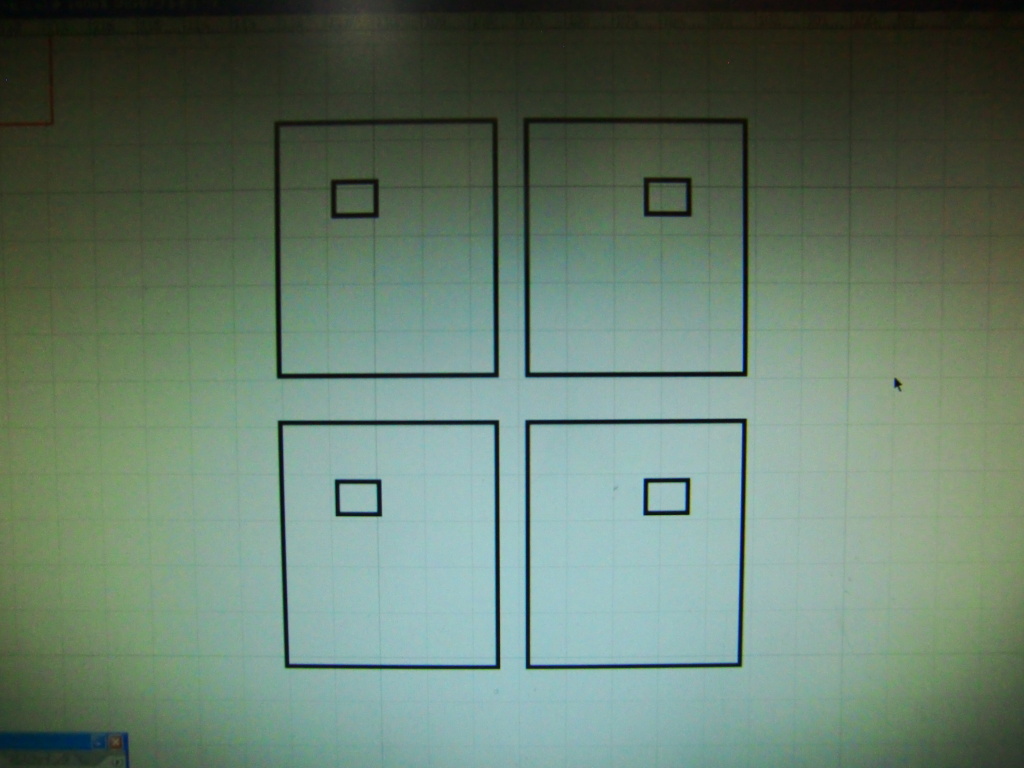
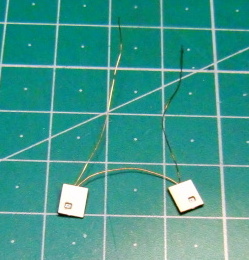
このようにチップLEDを組み込みます。
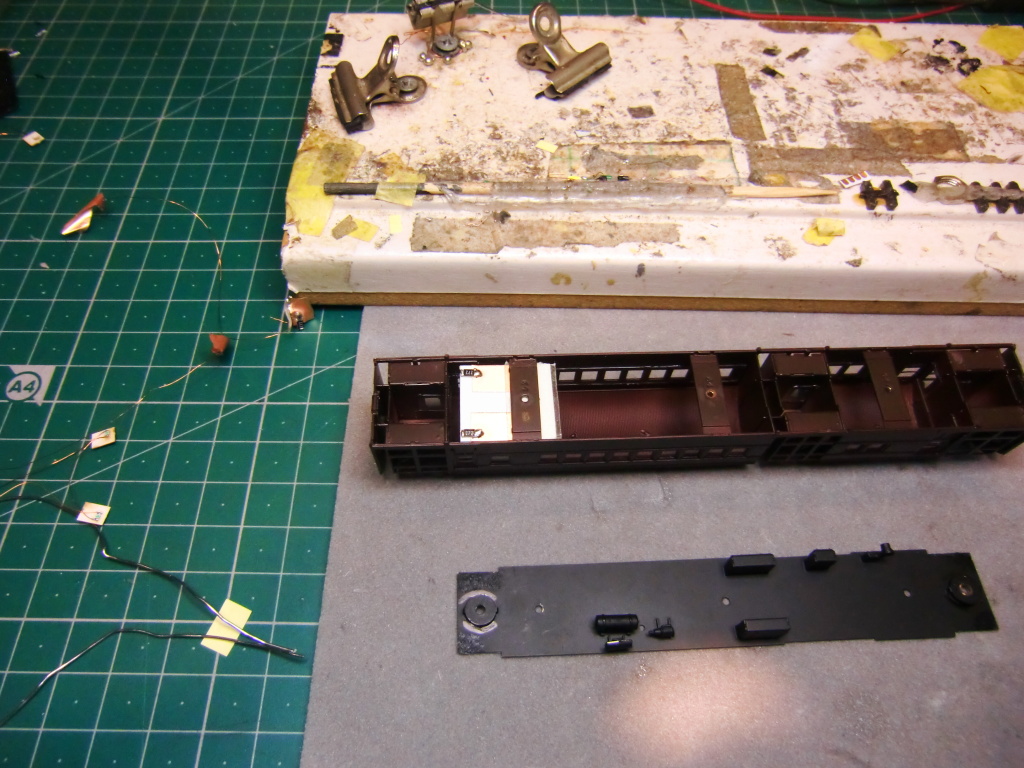
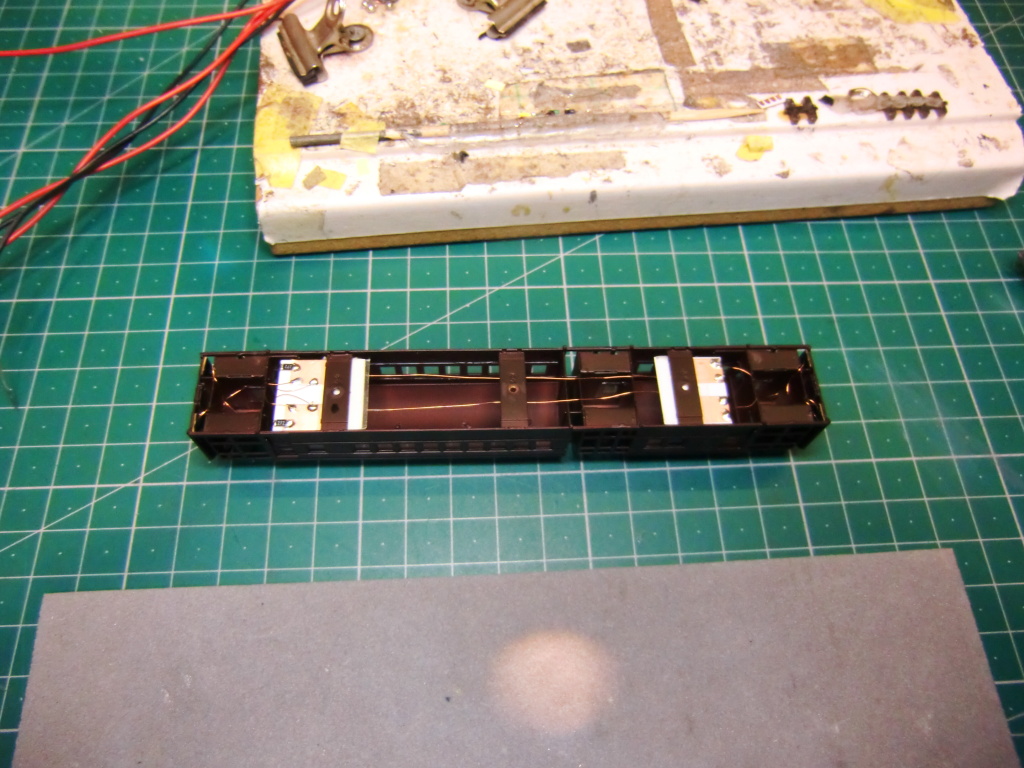
両サイドに集電用のターミナルを配置します。
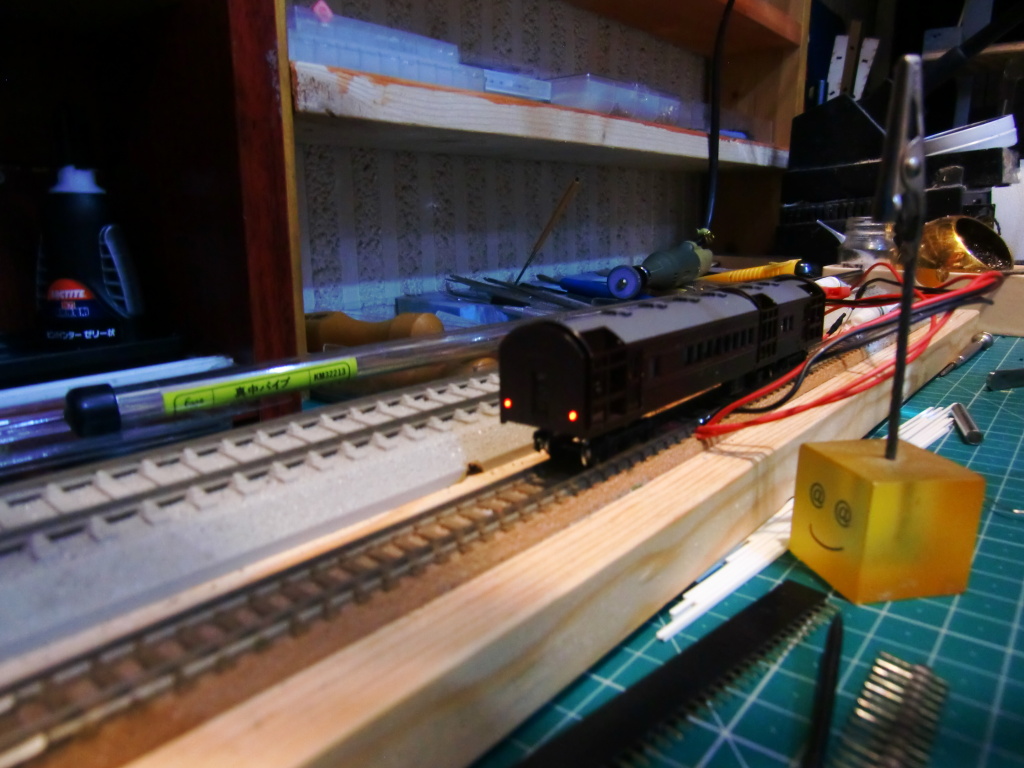

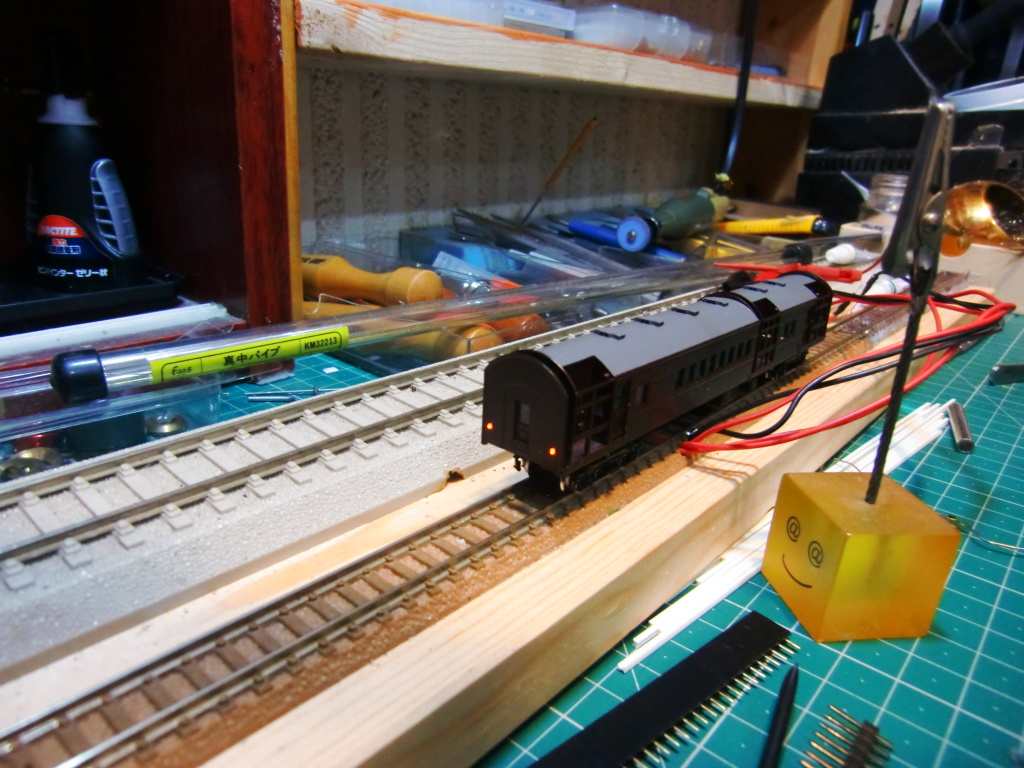
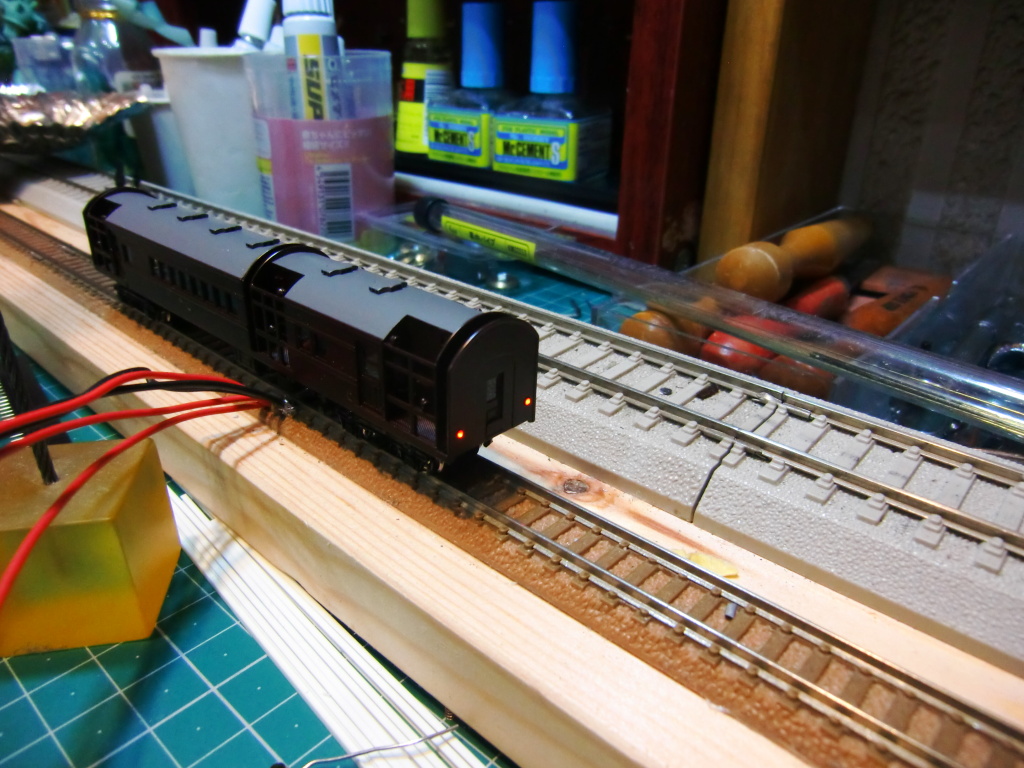
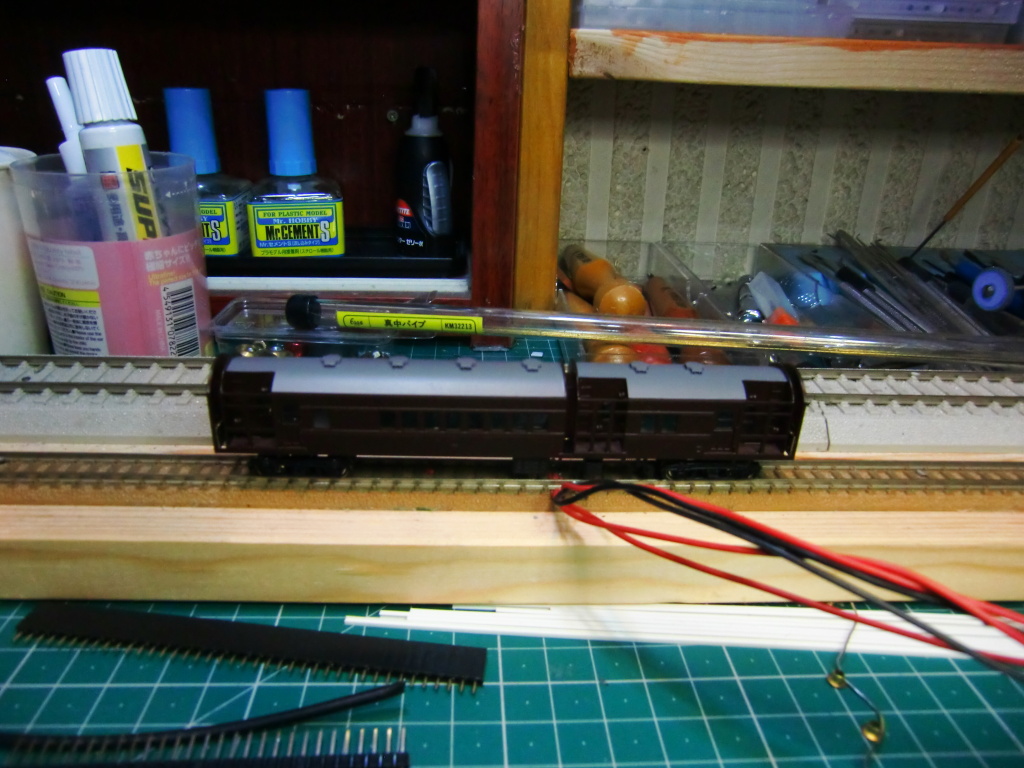
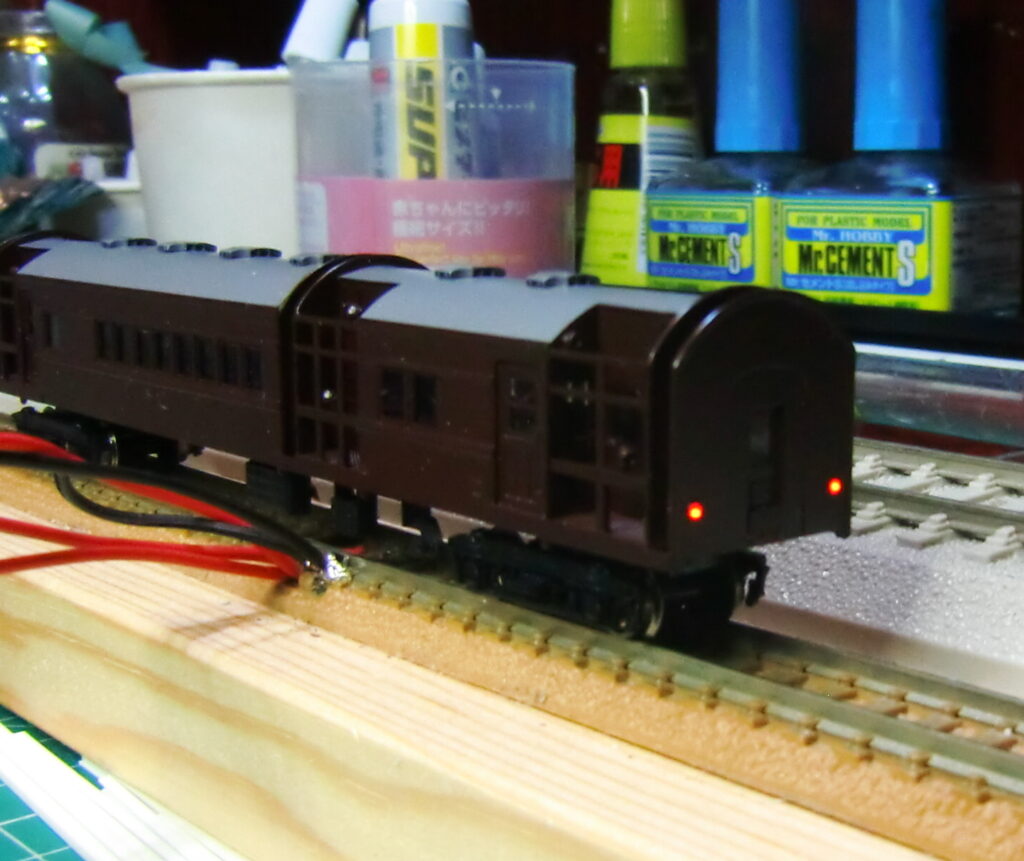

作業完了でございます。
今回の作業では、ミニレイアウトのターンテーブル通電不良における修理と建物への電飾化のご依頼でございます。

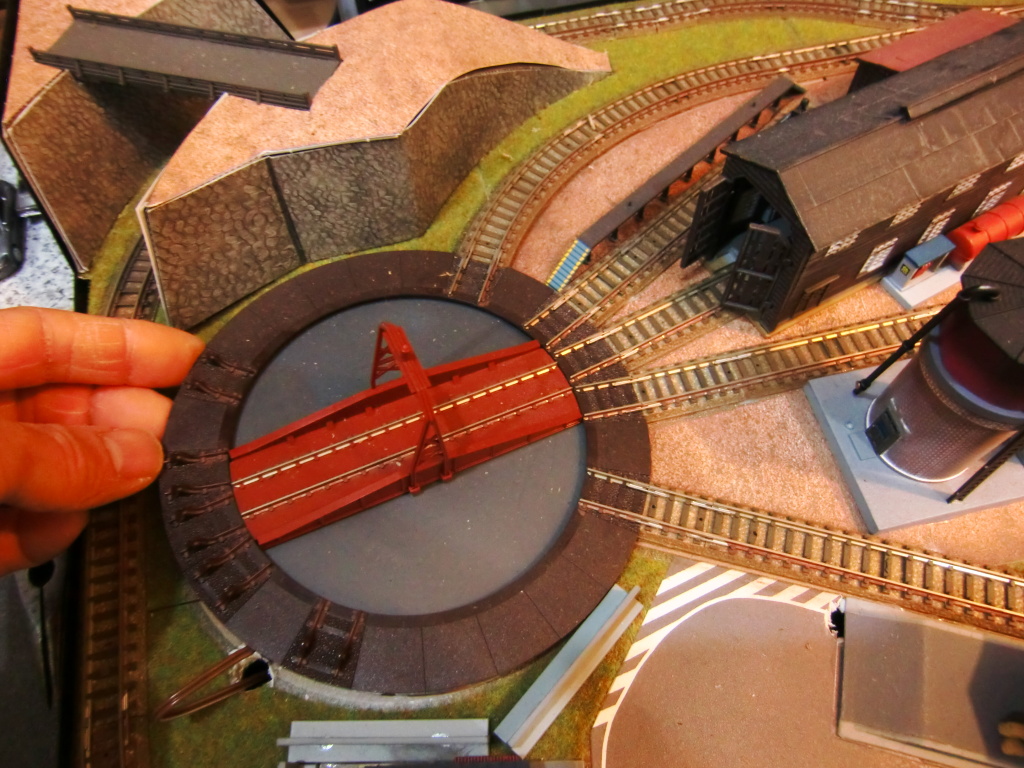

釘をすべて抜いてから線路の接着をはがして、ようやく外れました。
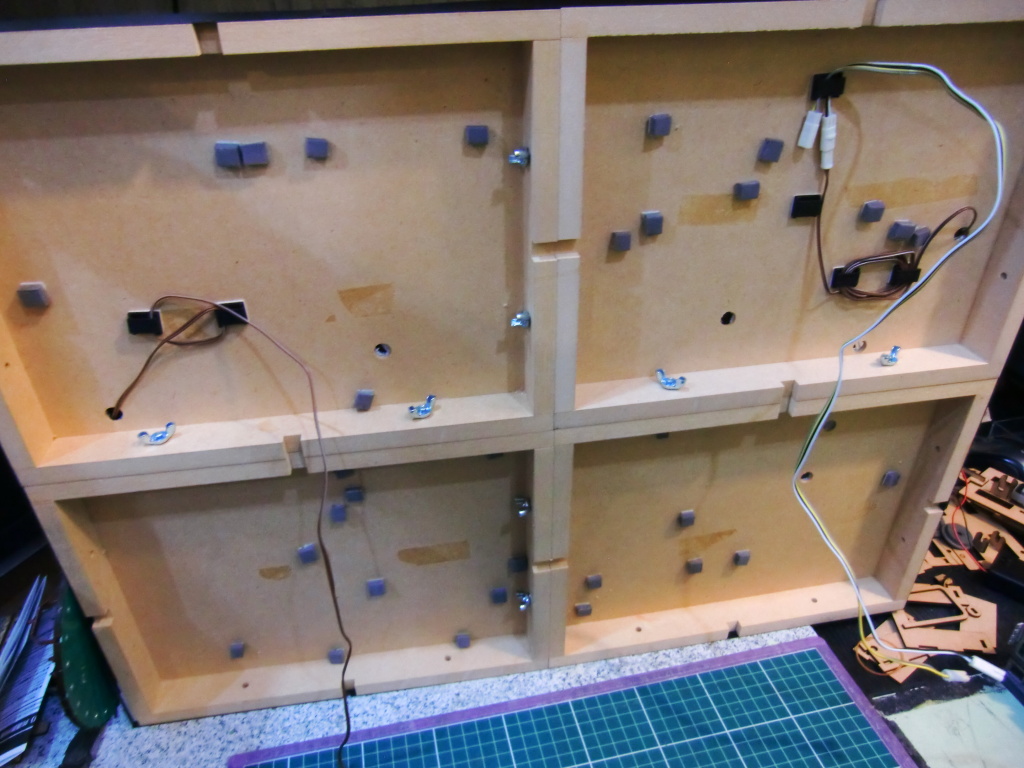
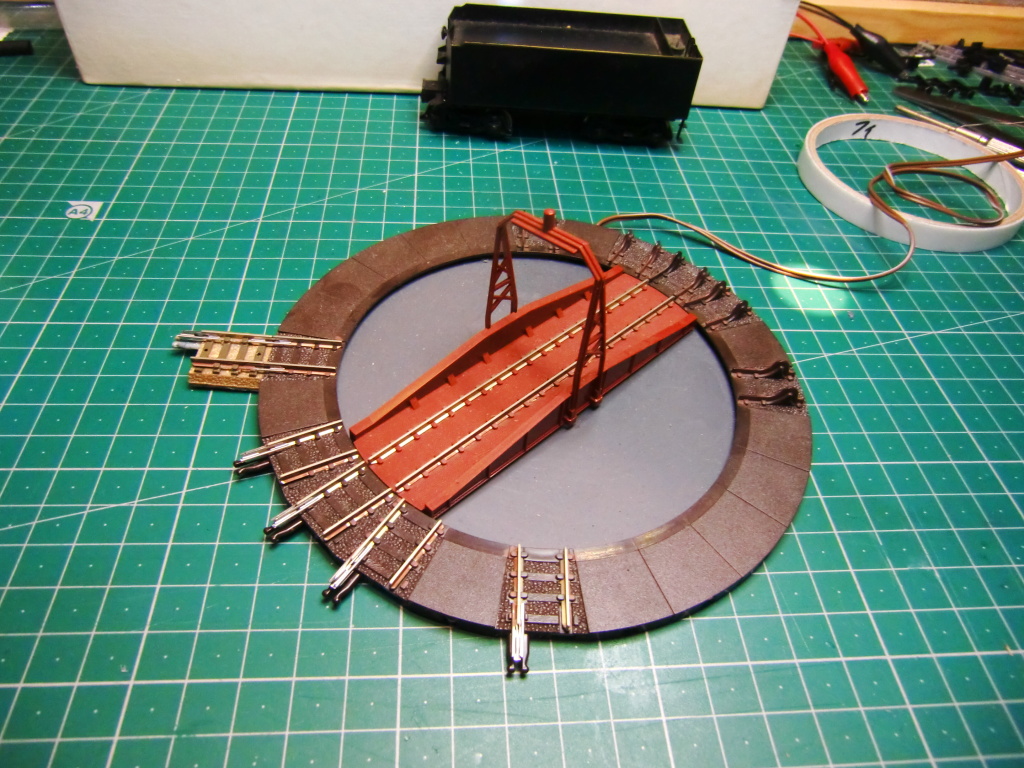
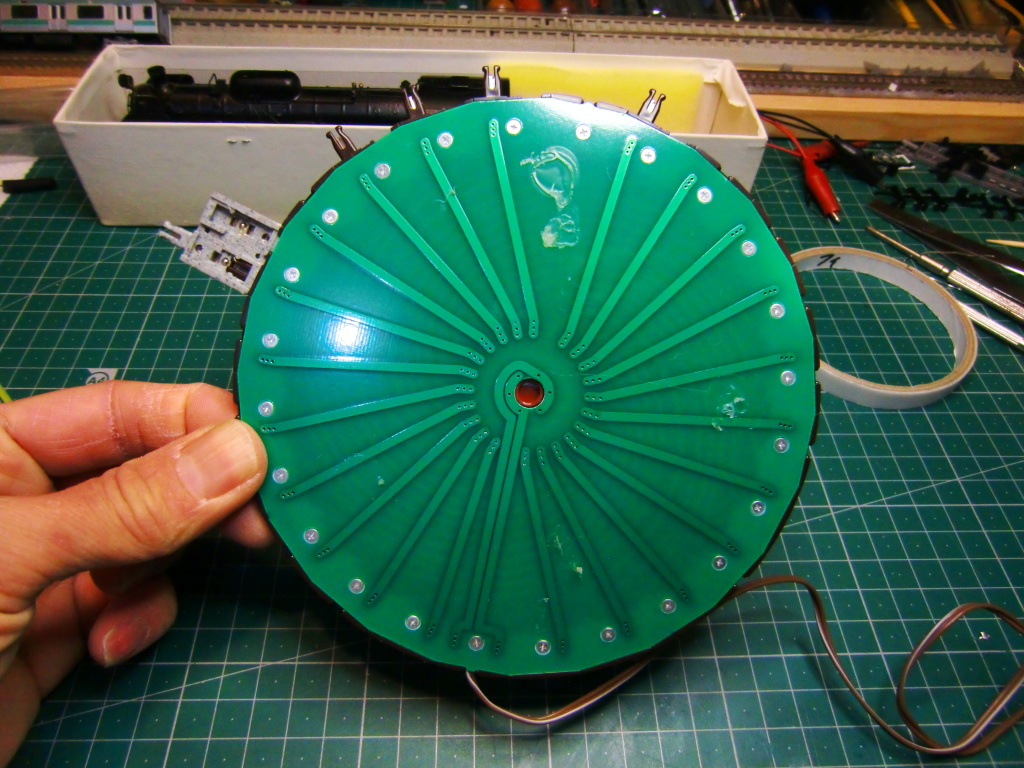
裏はこんな感じです。
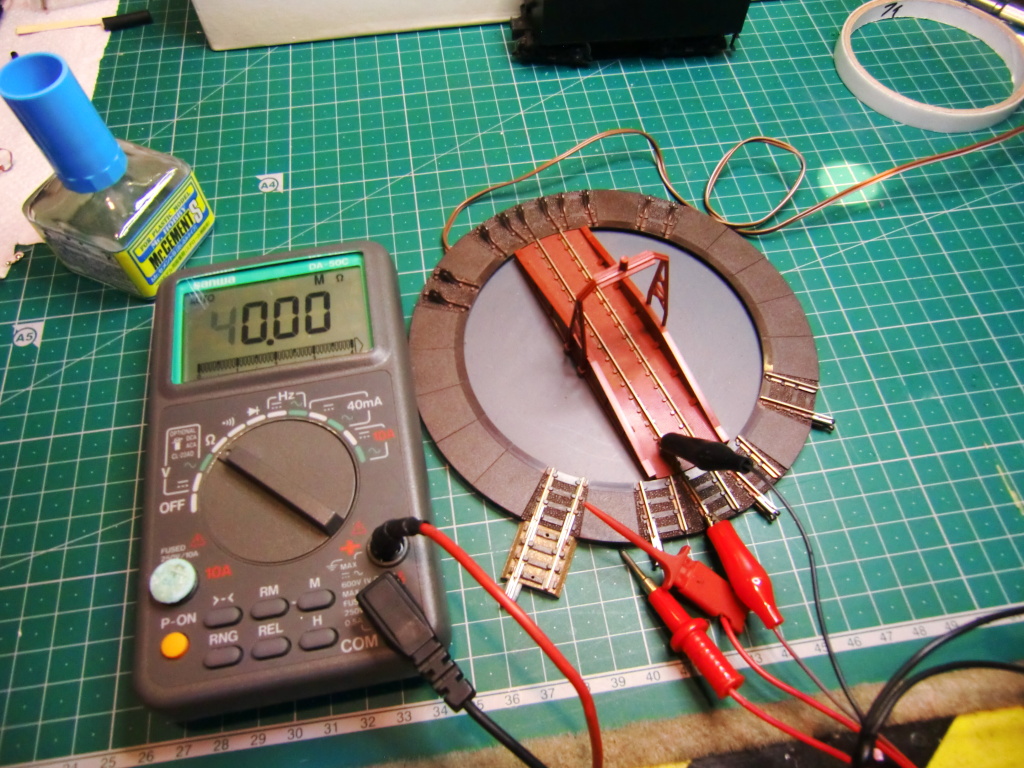
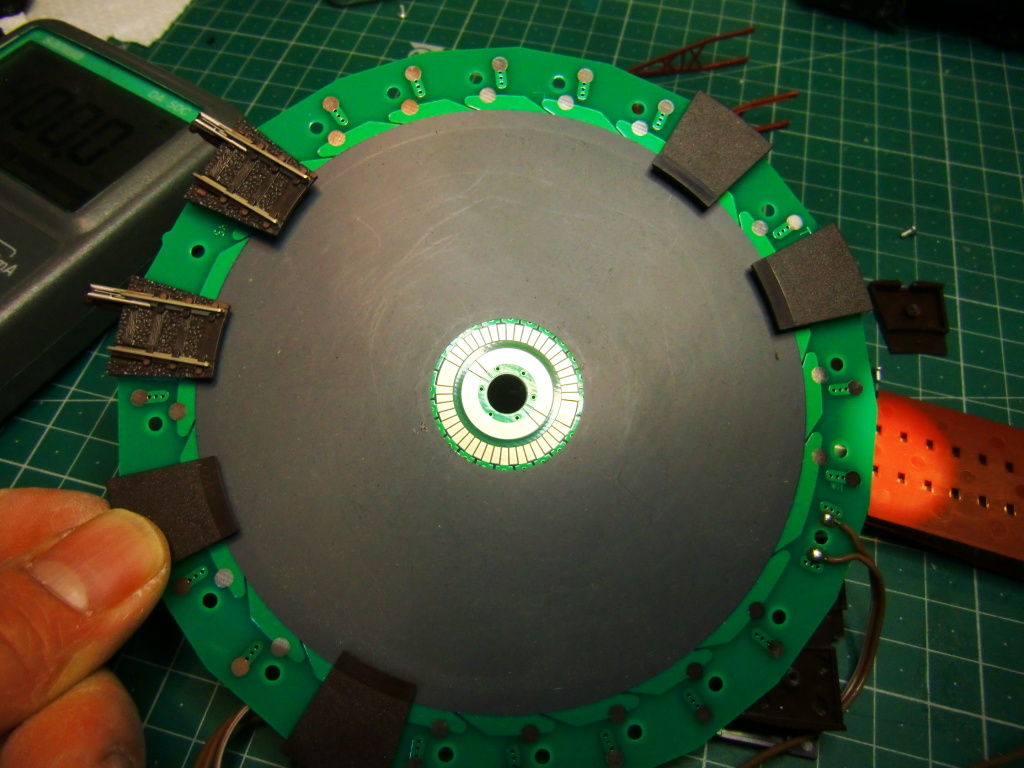
すべてのネジを外して分解します。
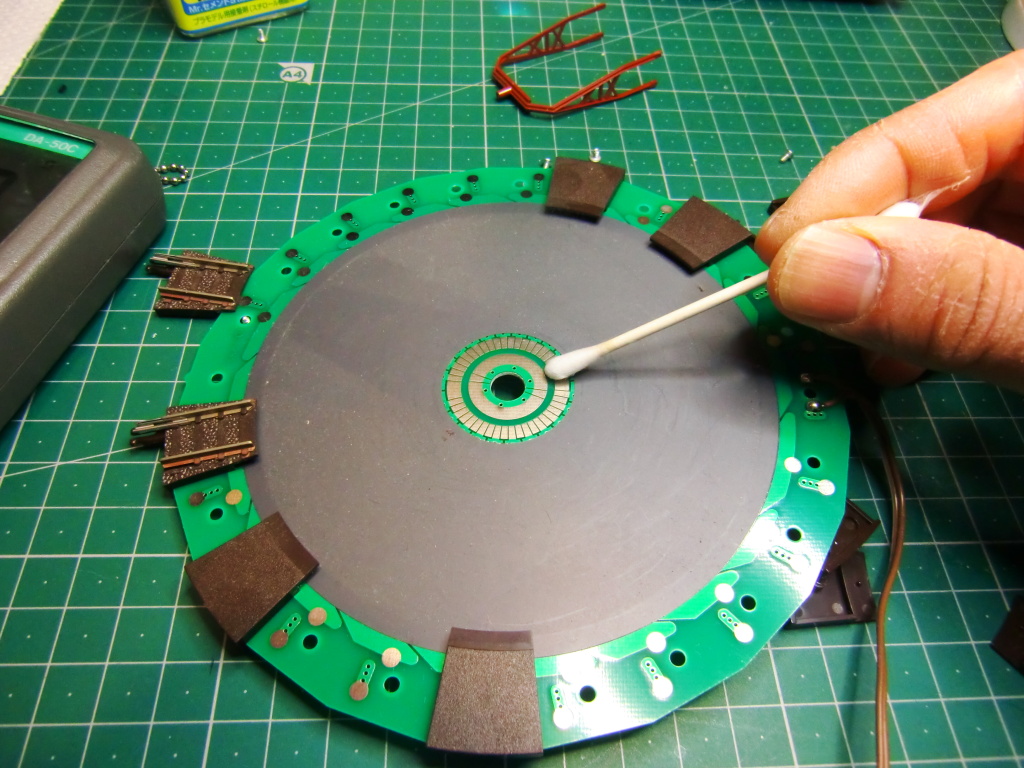
まずは接点のメンテと各種調整を行います。
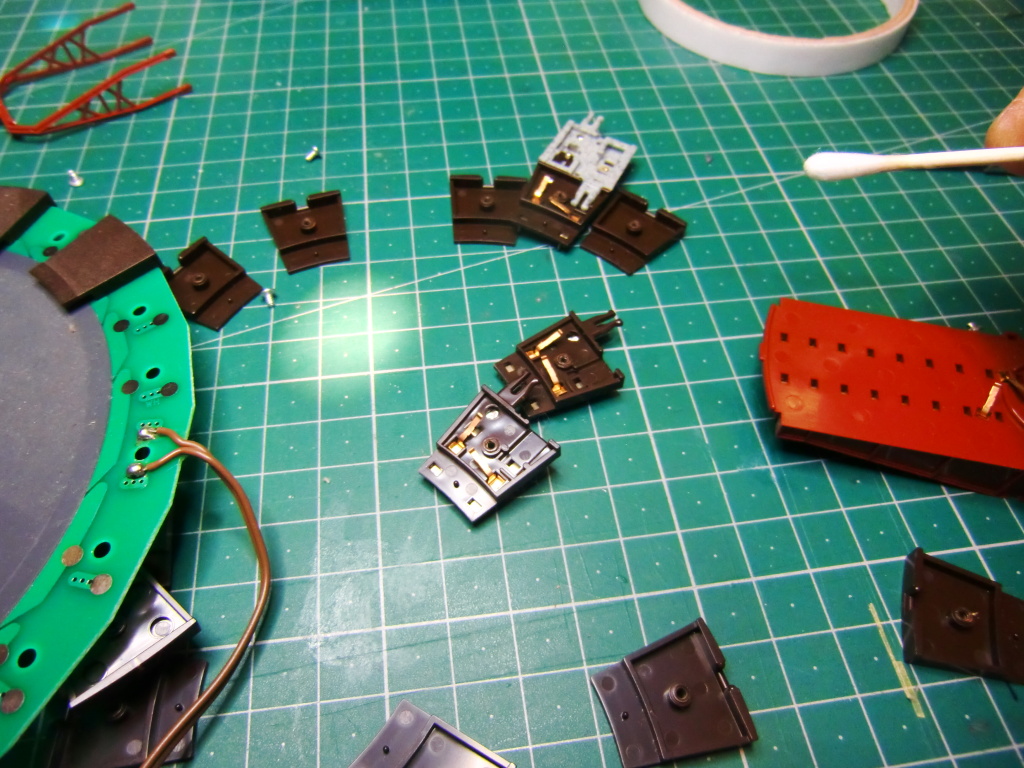
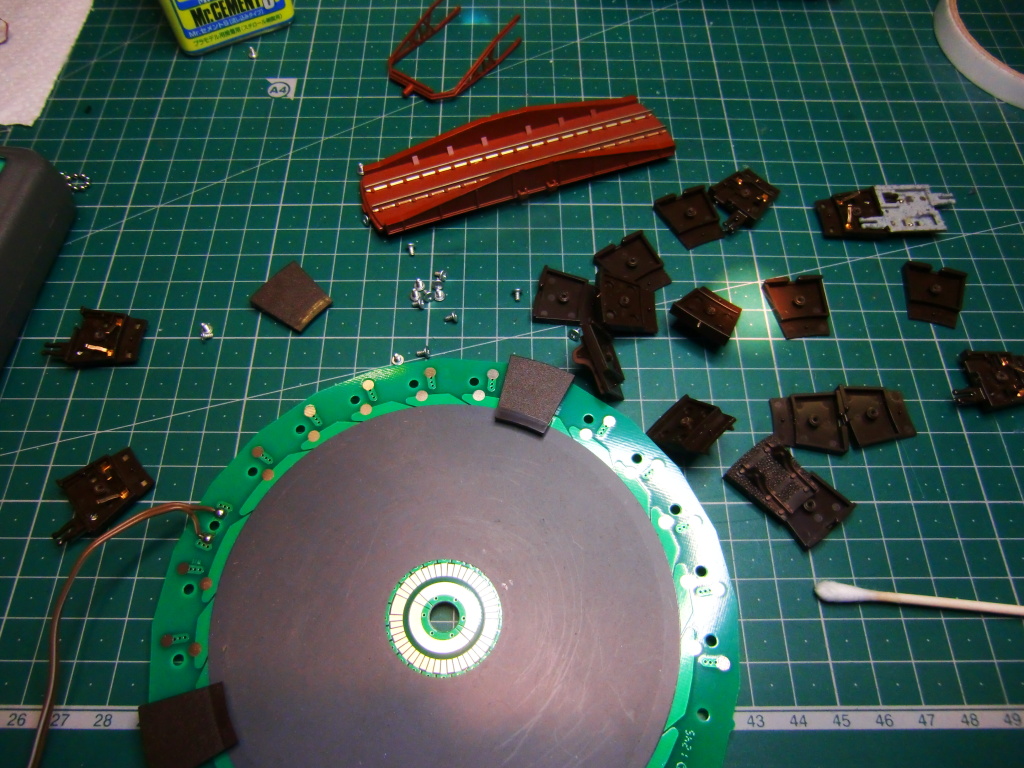

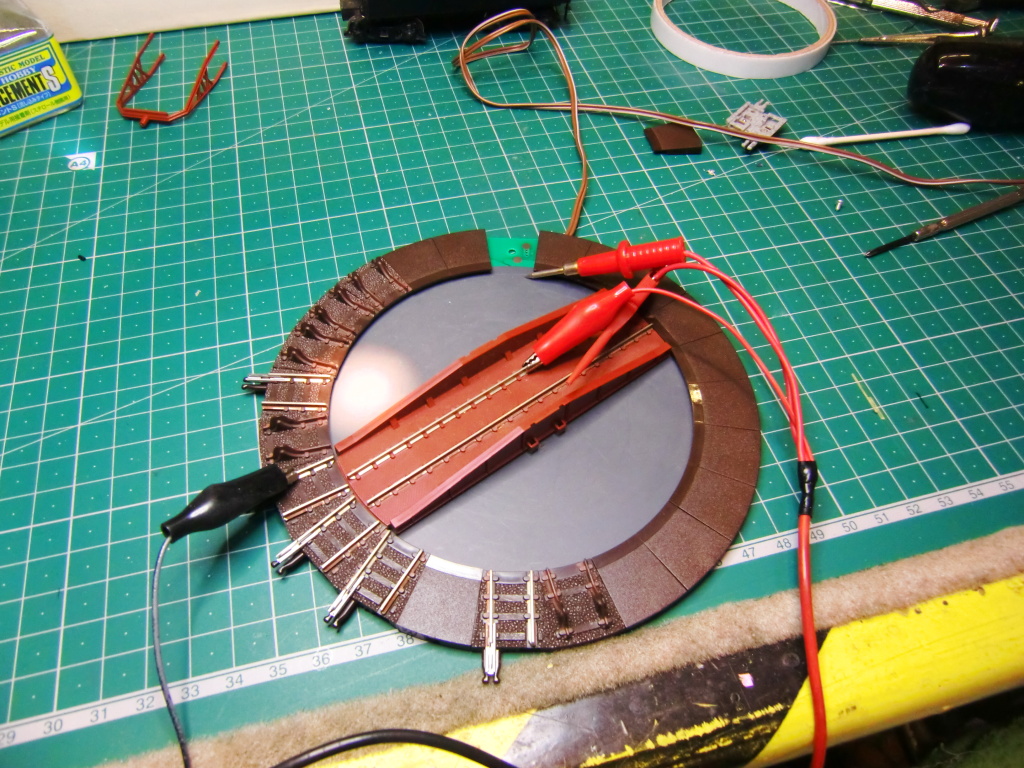
最後にすべてのセクションの通電確認を行い問題がなければ次に進みます。
▼電飾加工

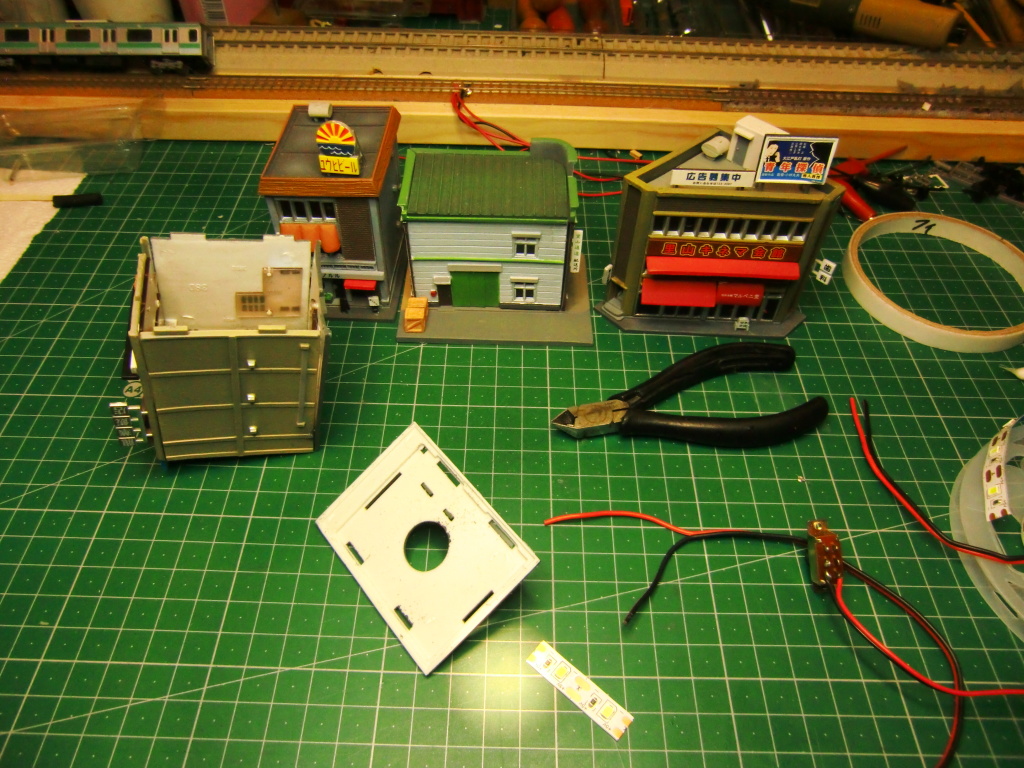
「電源・電圧」を5Vに設定して、各建物に電飾を埋め込んでいきます。
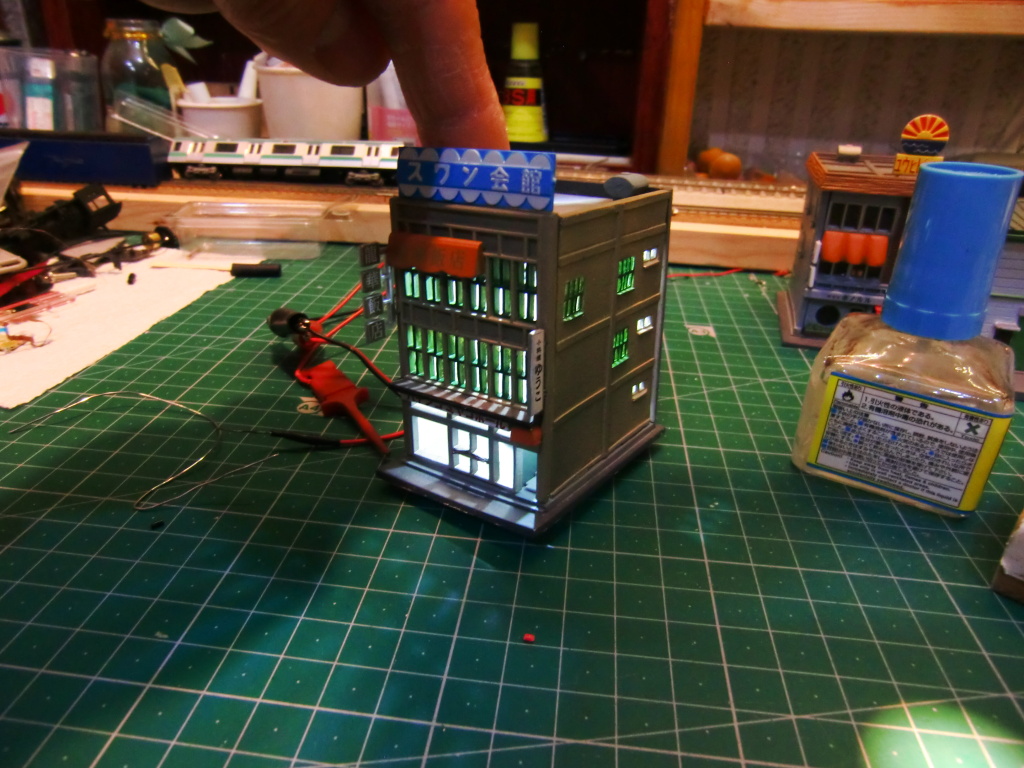
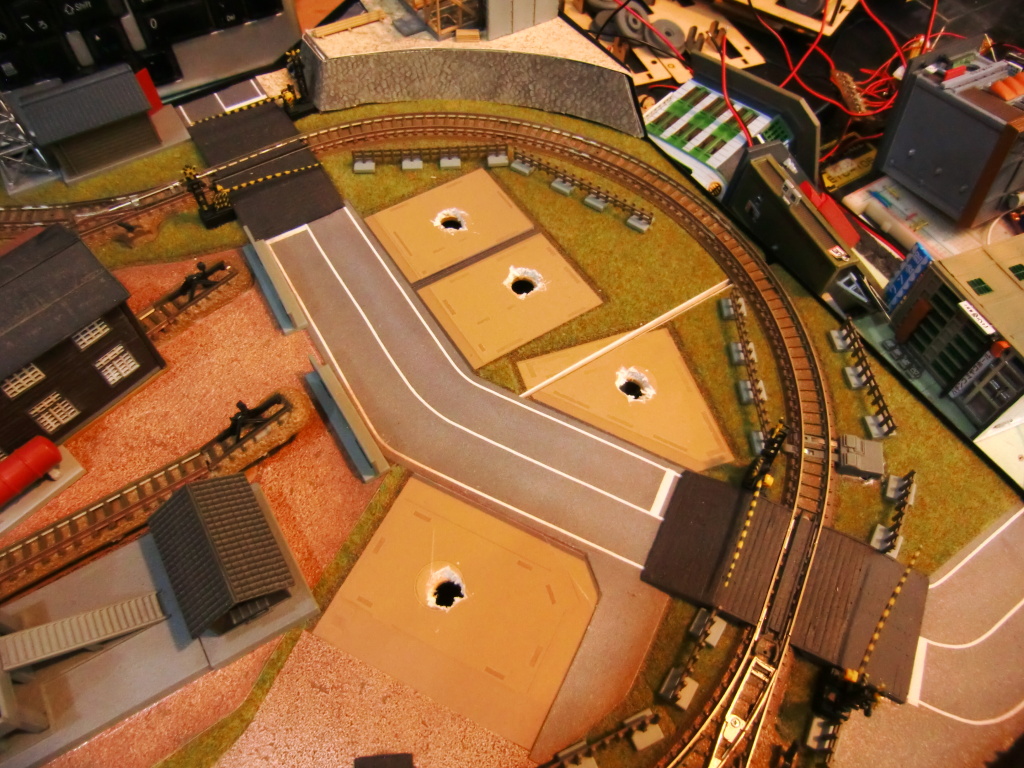
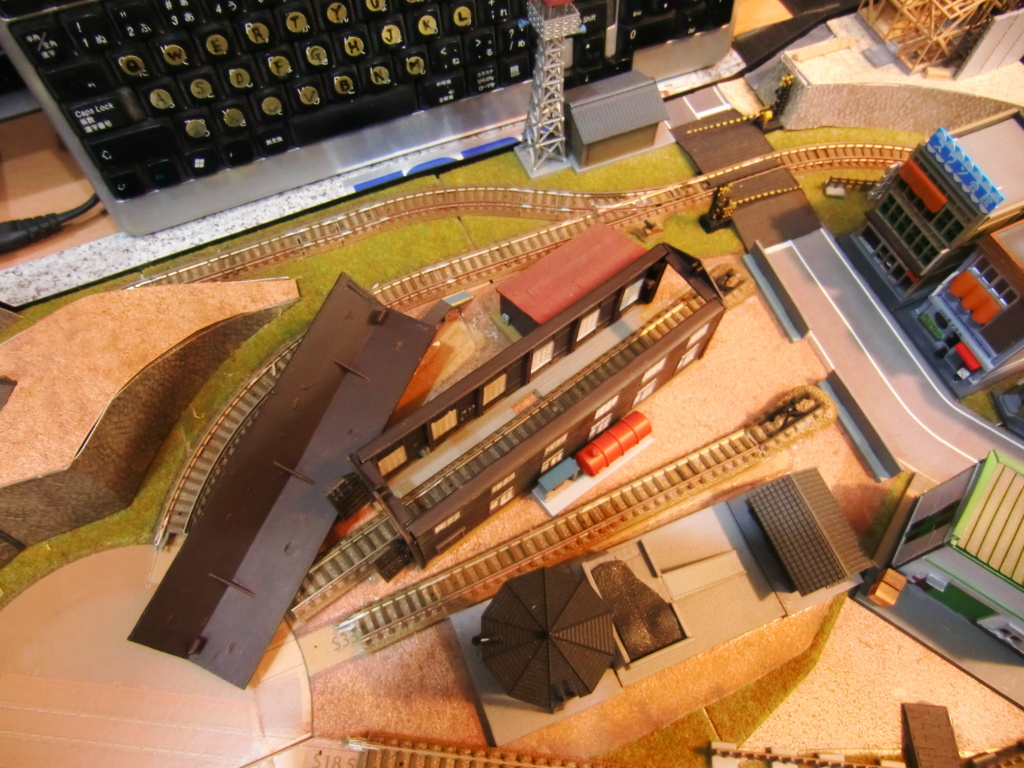

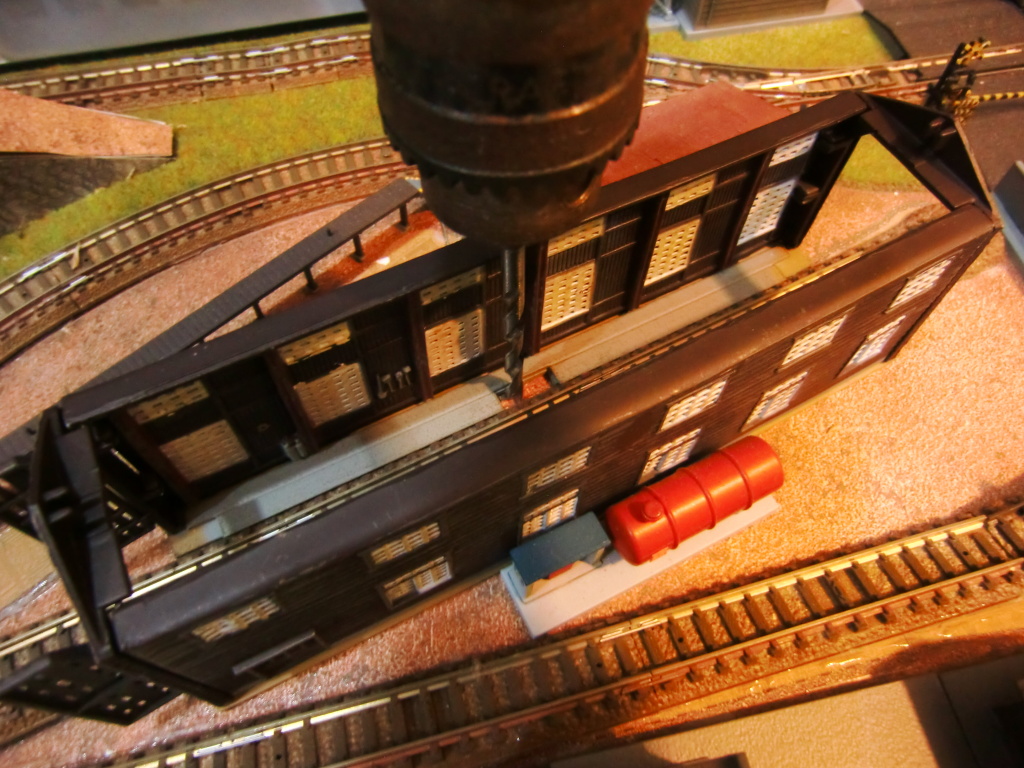
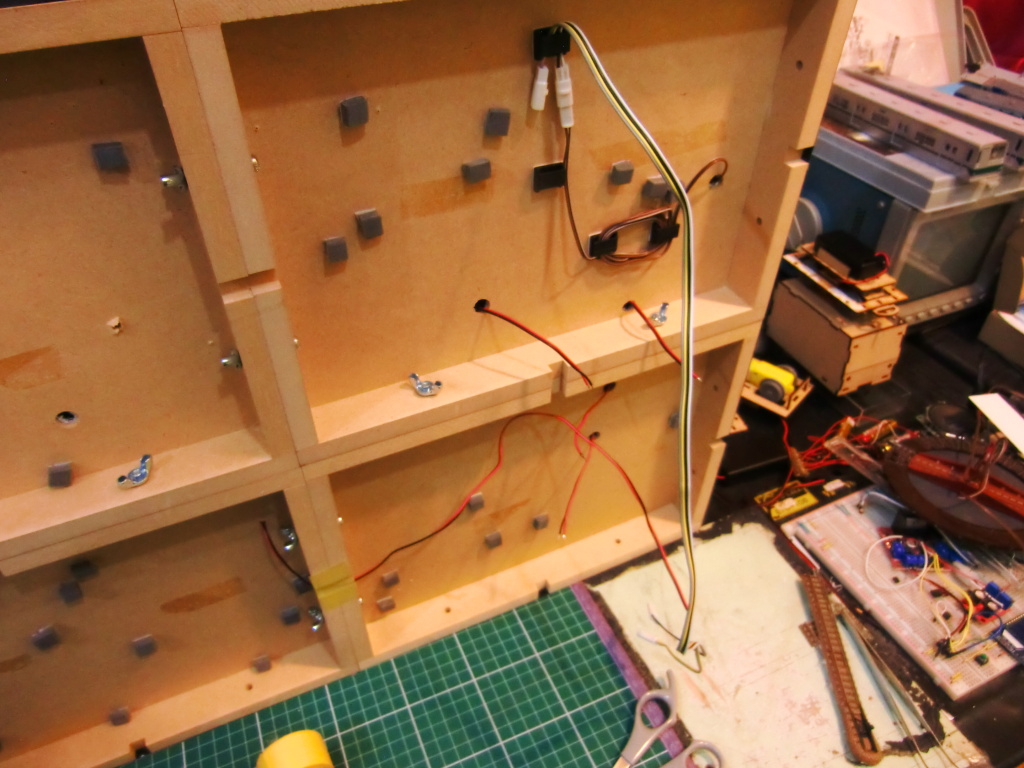


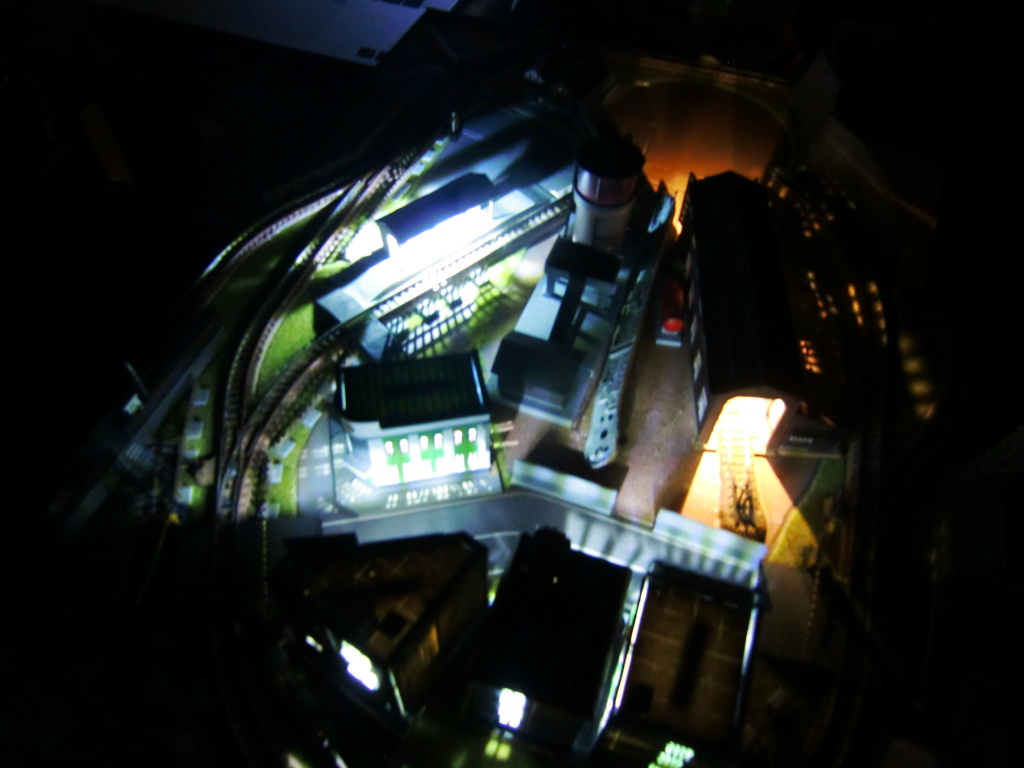



作業完了でございます。


まず、ヘッドライトの色合いをより白系に近い電球色ご希望とのことです。
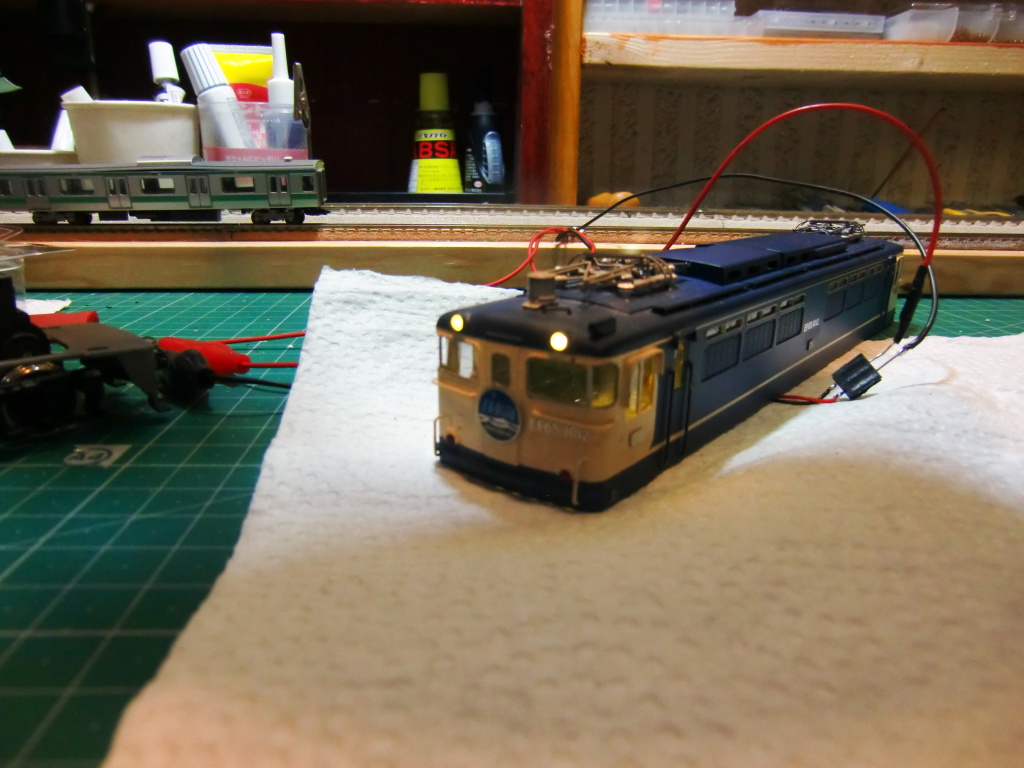
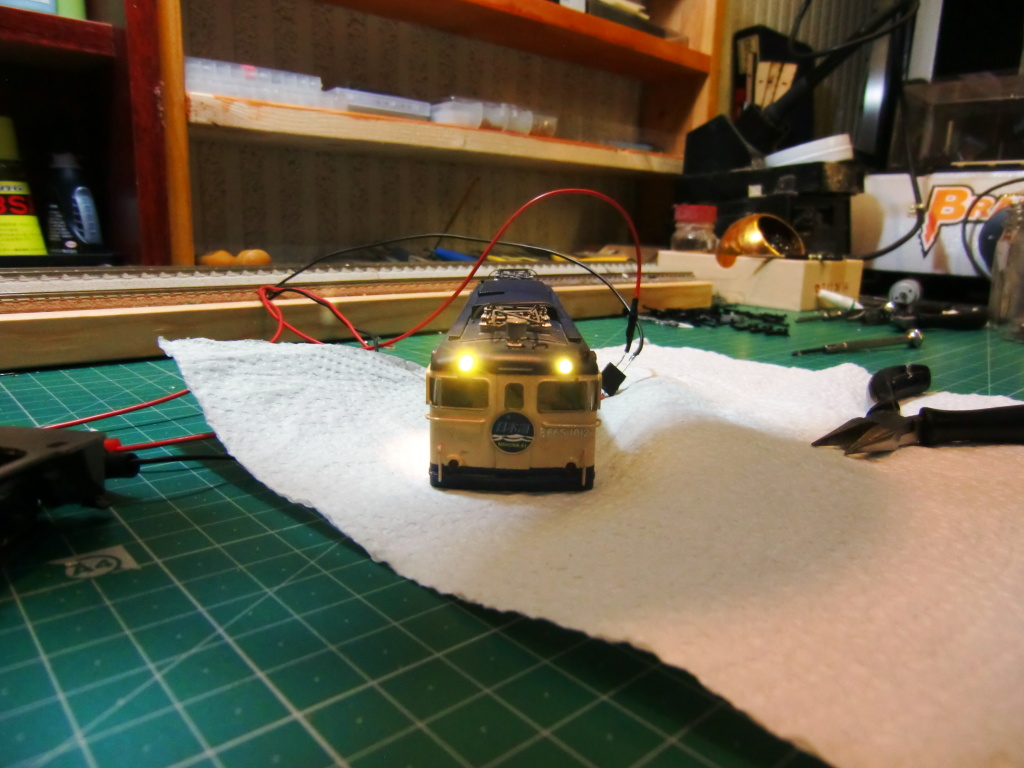
現状の電球色としては問題ないレベルの色合いではありますが、「より白っぽい感じで」とのご希望でございますので、すべて作り変えます。
色合いにつきましては、個人の好みにもよりますので難しところです。電球色の範囲としては以下の通りとなります。今回の作業では、白色LEDを使い、色合いを調整しながら埋め込むかたちとなります。今回は4,000K(かなり白っぽい感じ)となるようにしてみます。

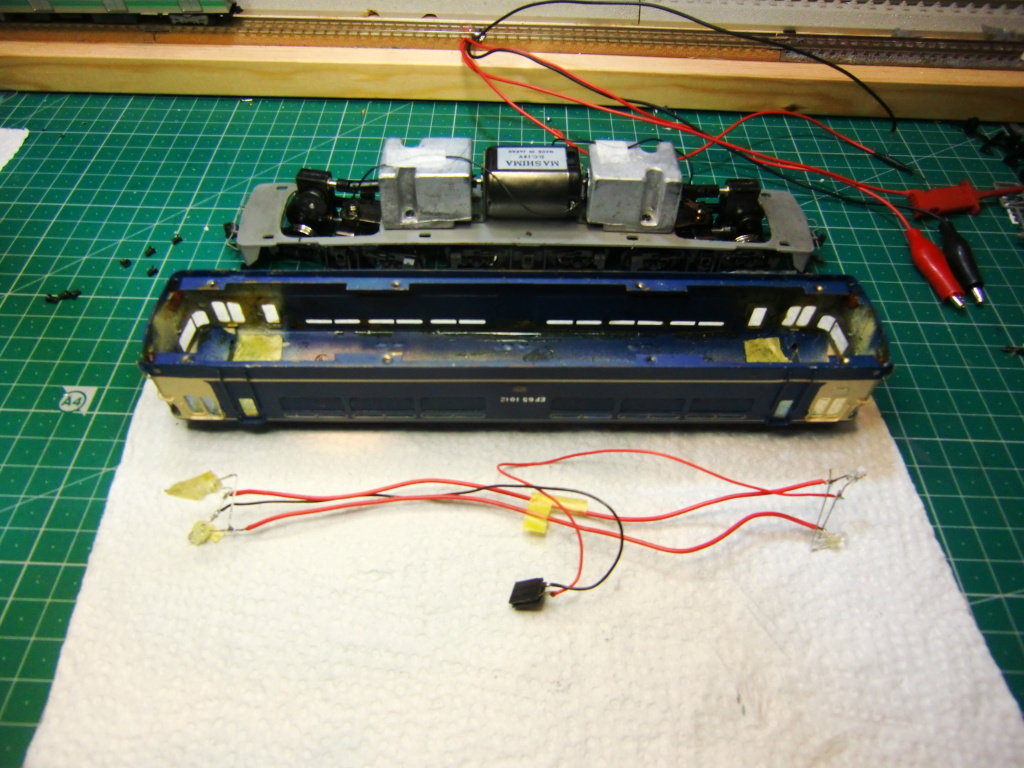
まず、ヘッドライト用の配線をすべて取り外して再構成します。

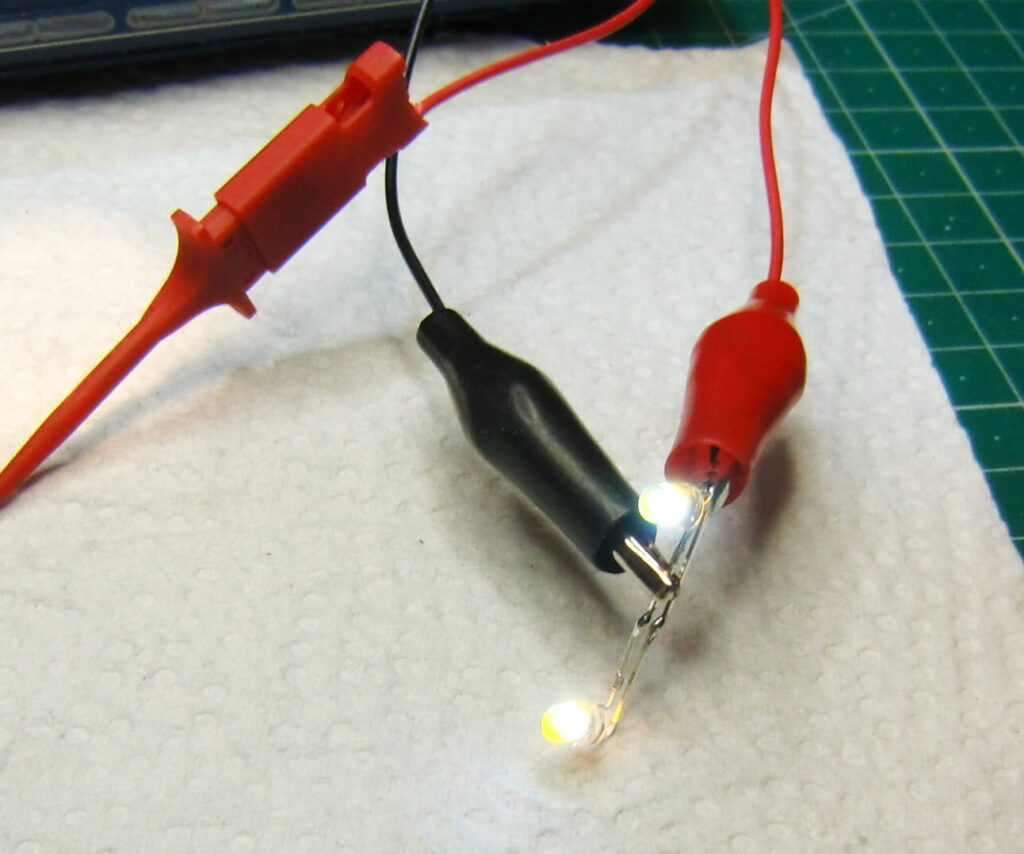
薄くクリアオレンジを重ねて、目的の色になるまで点灯と確認を繰り返していきます。

目的の色合いになったところで、車体に組み込んで配線していきます。ヘッドライトが終わったところで、次はテールライトに作業は移ります。
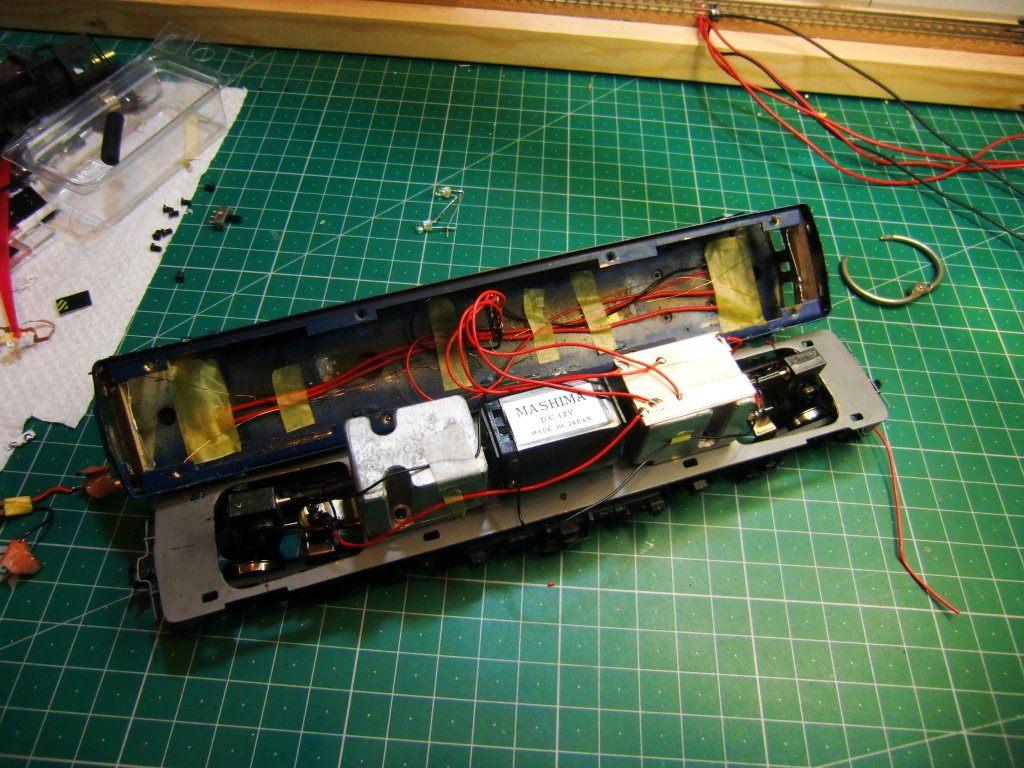
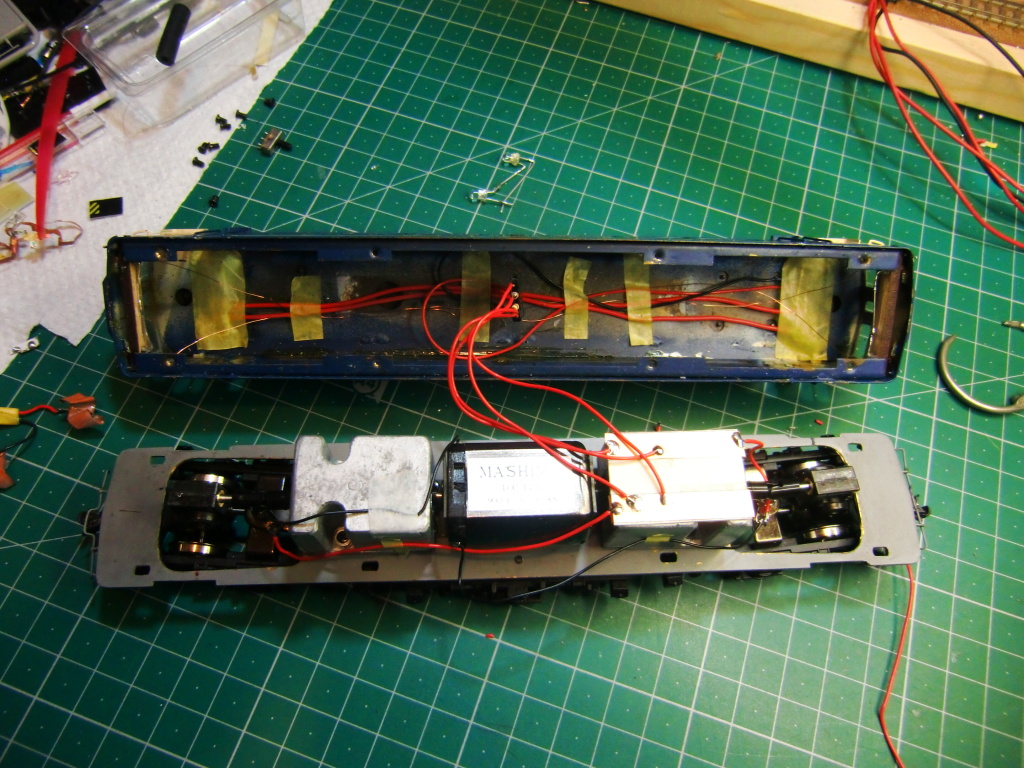
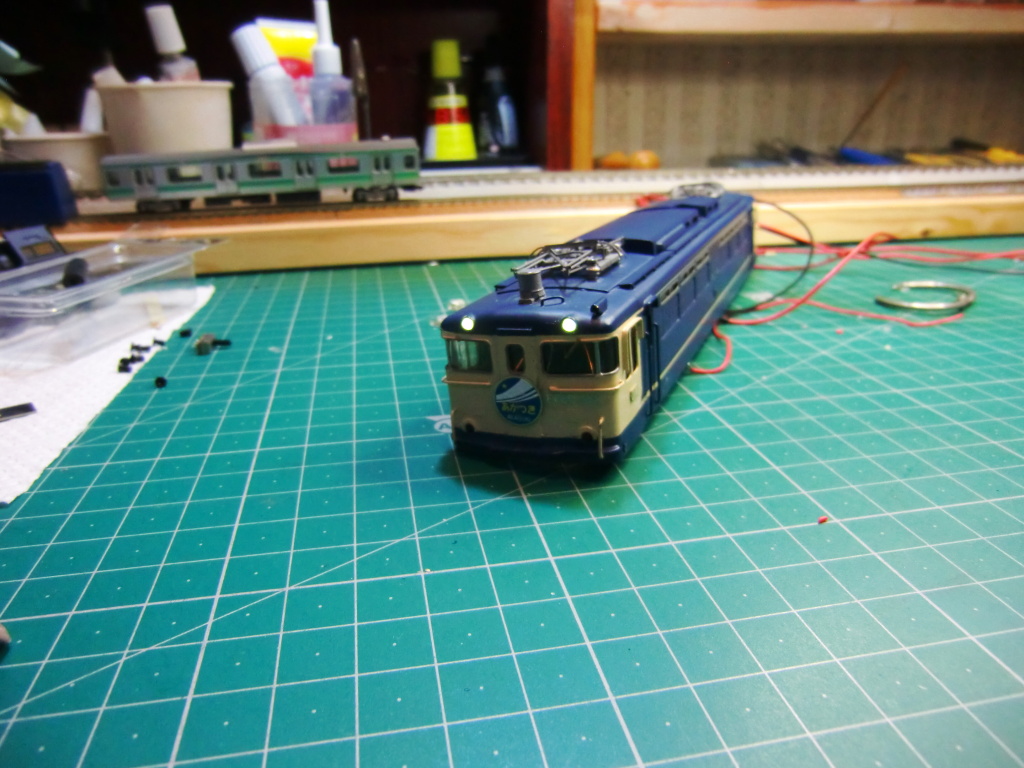
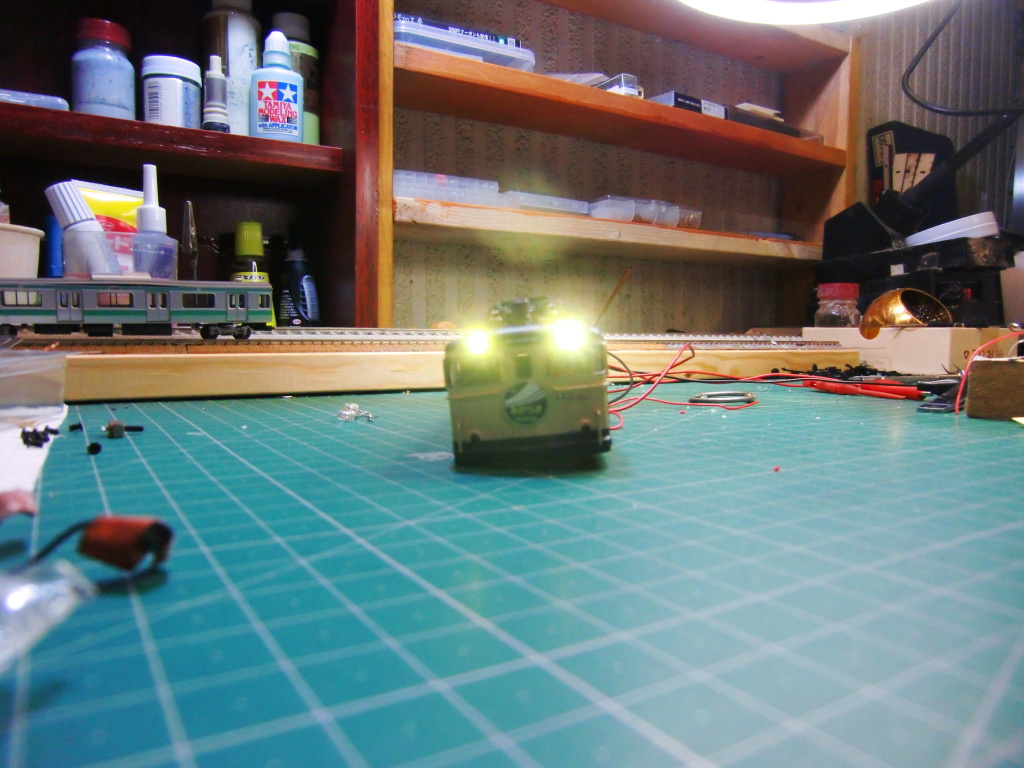
写真で見るよりさらに白っぽい感じで光ります。

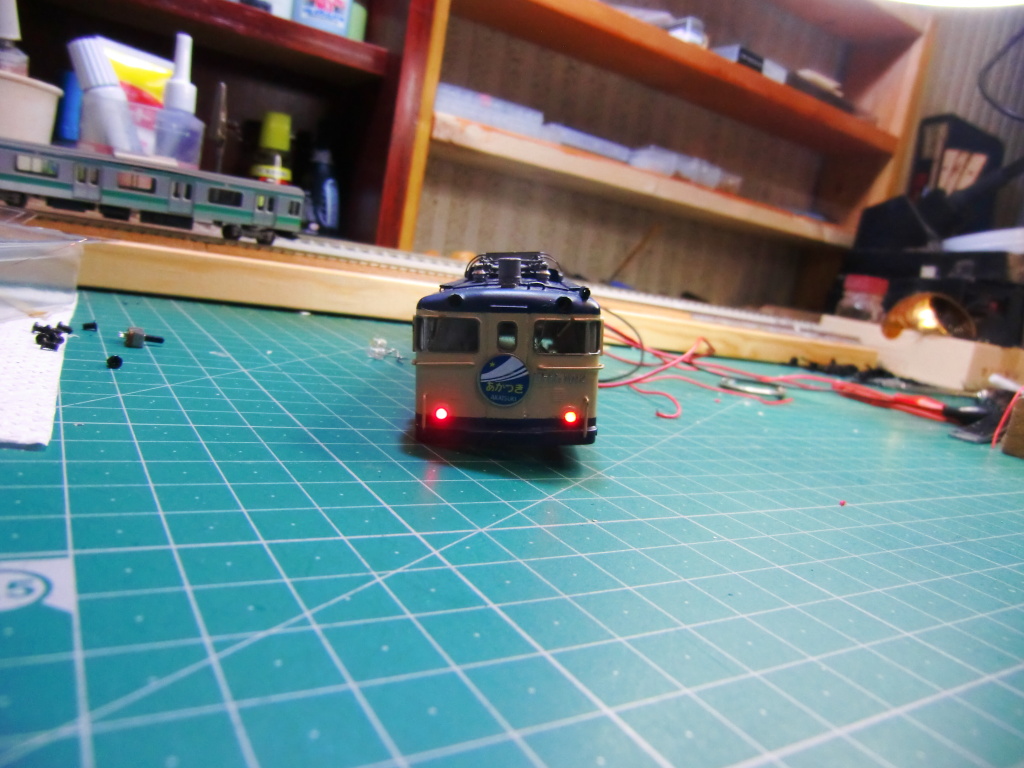
テールもばっちり点灯しているのがわかります。テールライトの固定するマウントはレーザーで作り、3mmLEDを埋め込んで適正な位置に固定しました。
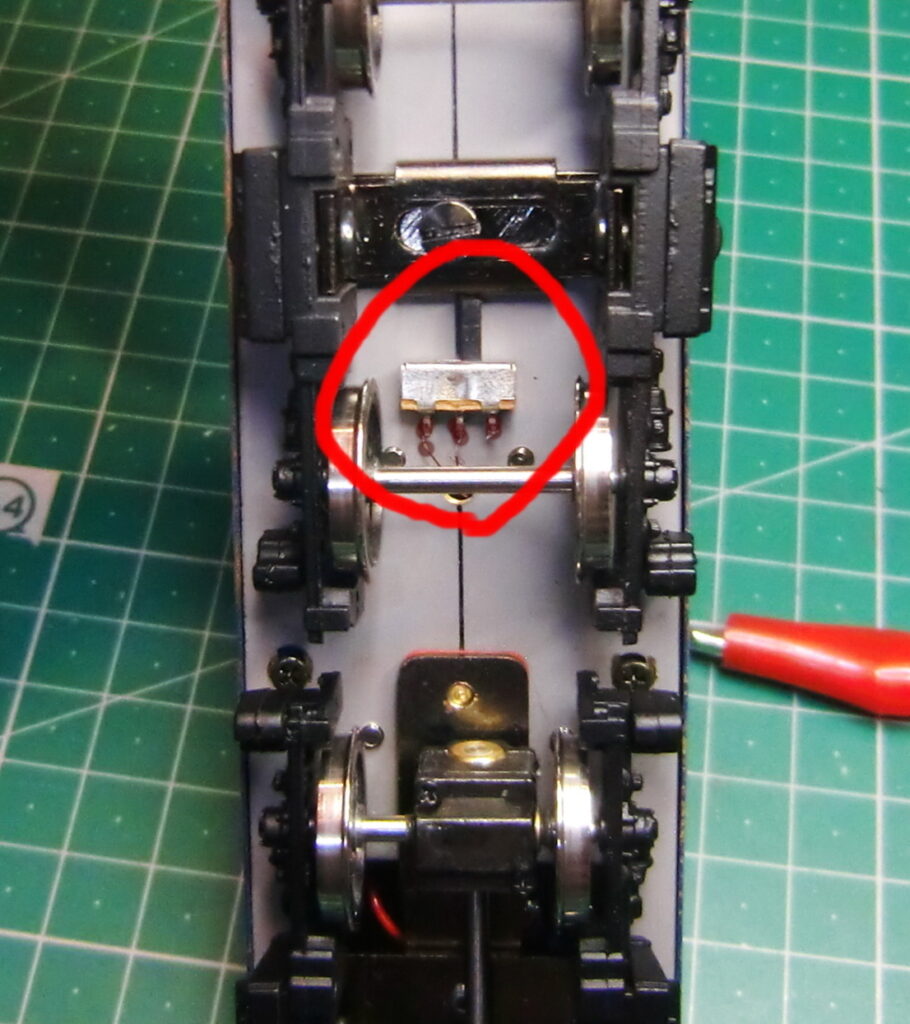
「ON/OFF」スイッチはこの位置に取り付けました。ピンセットまたなどで、横方向に動かすことで操作できます。


最後にすべての動作確認を行って作業は完了いたしました。
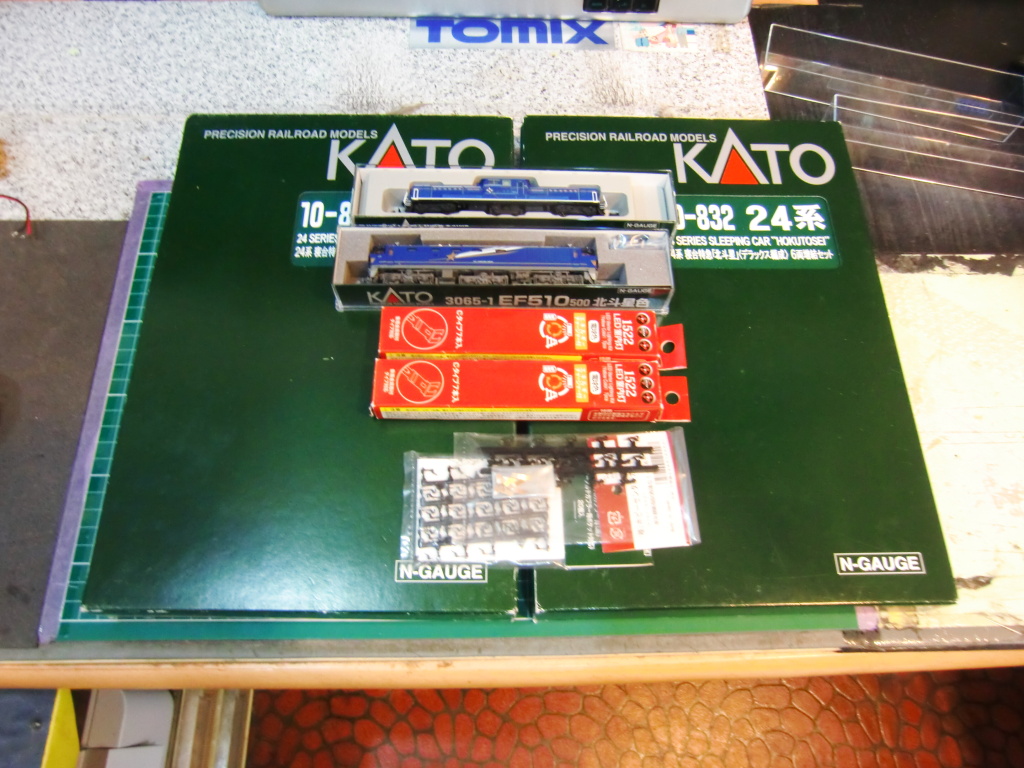


順に組み込んでいきます。車体のサイズに合わせてユニットカットしていきます。
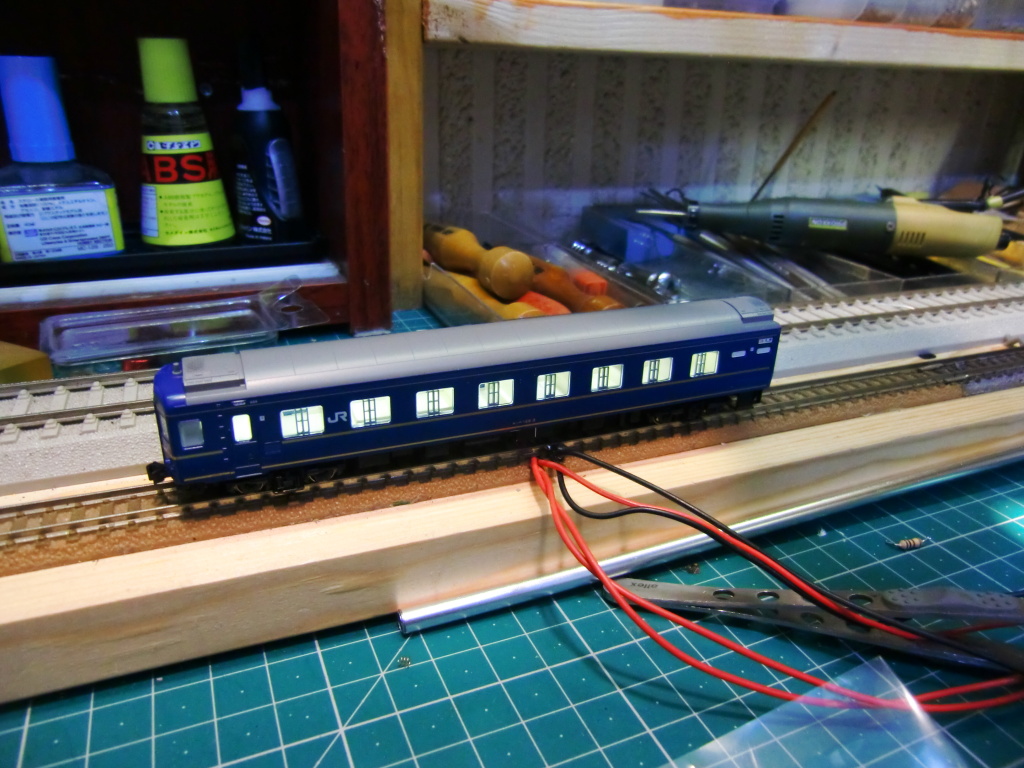

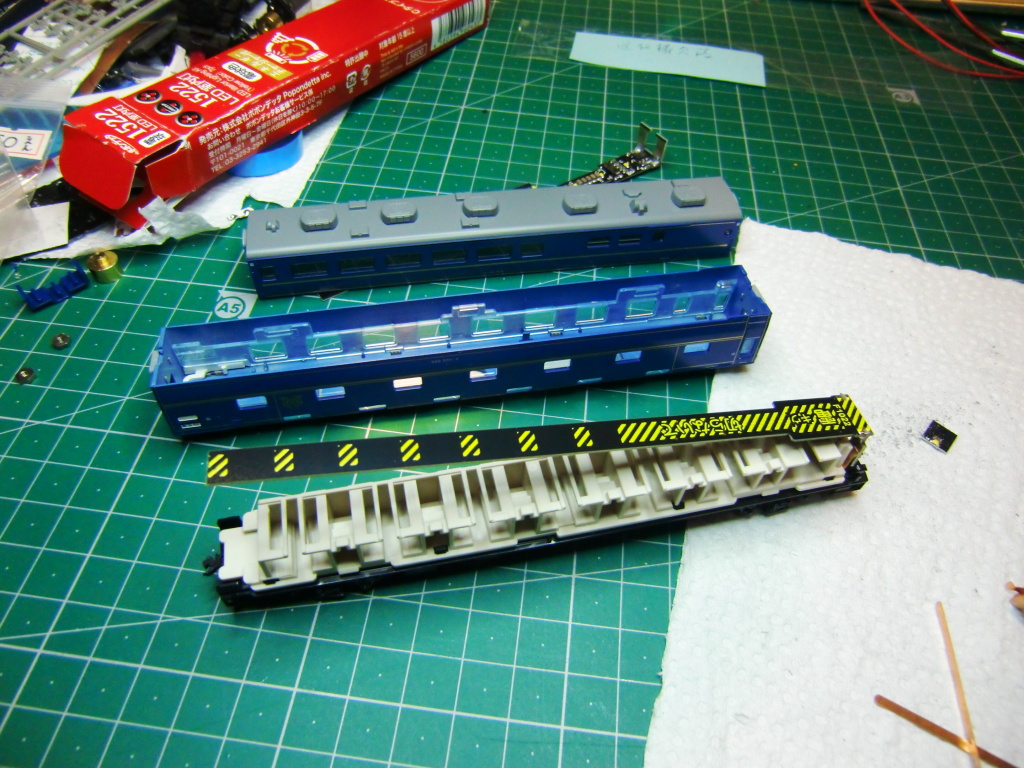

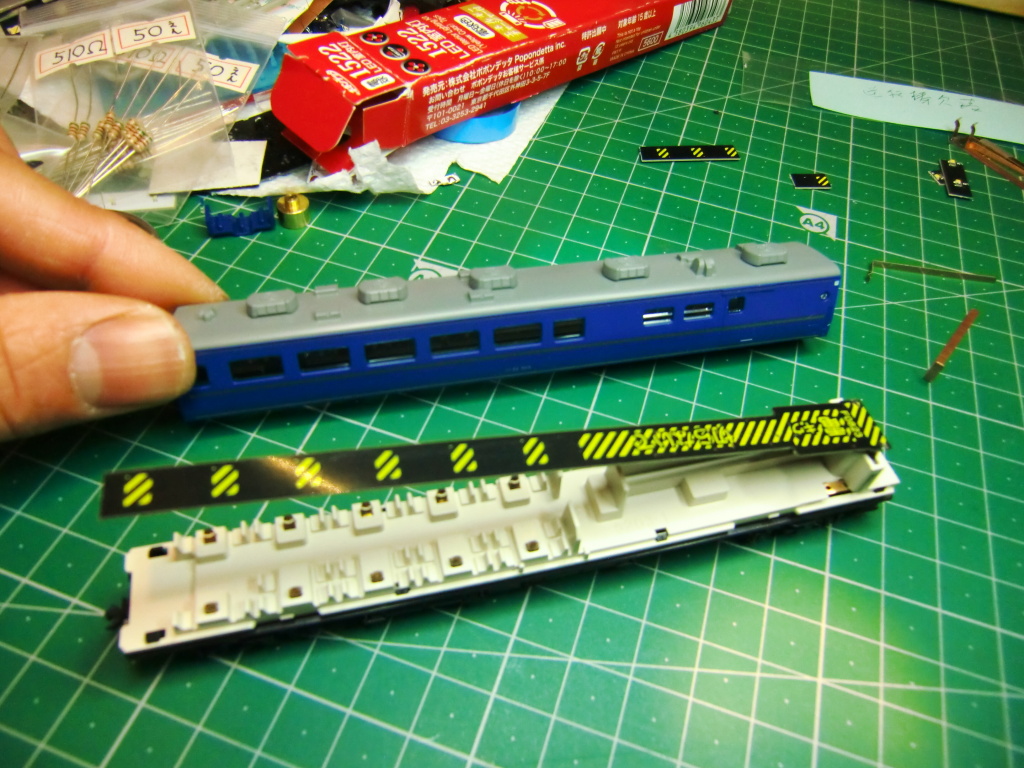
こちらの車両には、そのままでは入りませんので、まずユニットの集電部を撤去して薄型に入れ替え加工します。次に、コンデンサーなどの出っ張りと干渉する個所を加工していきます。編成中で最も難しい車体となります。
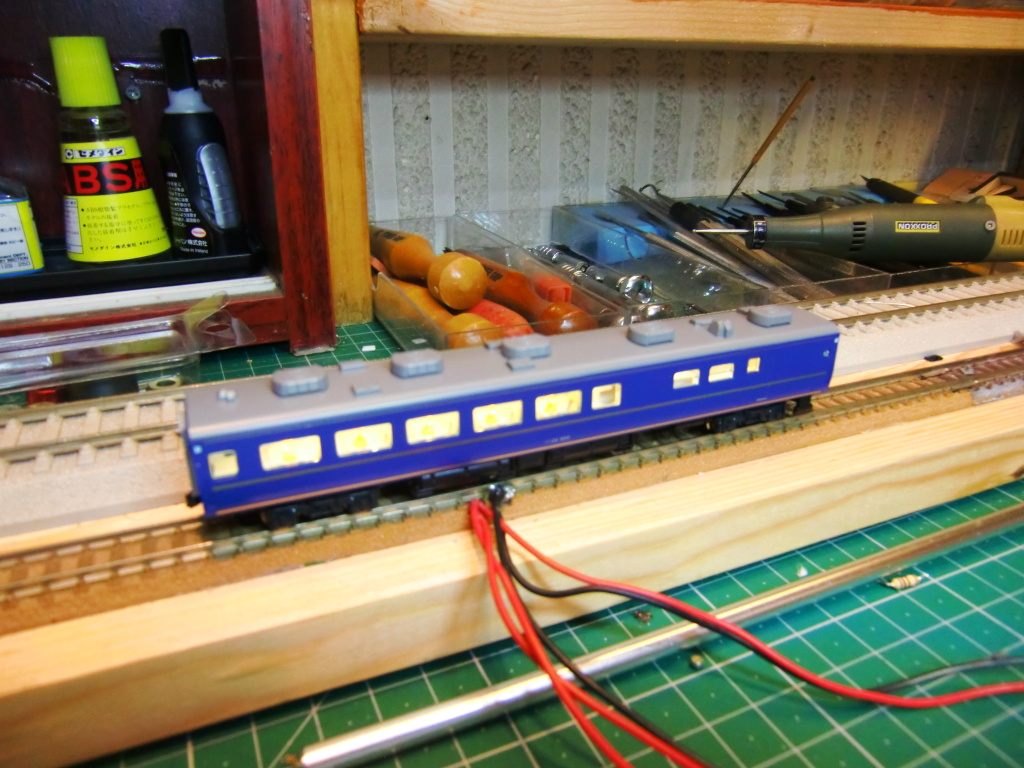









すべての作業が完了いたしました。


鉄コレのライト点灯化改造を始め、主にライト加工が中心のご依頼でございます。こちらも順次作業を進めていきます。
▼機関車各種のメンテナンス
主に集電パーツのメンテが中心となります。

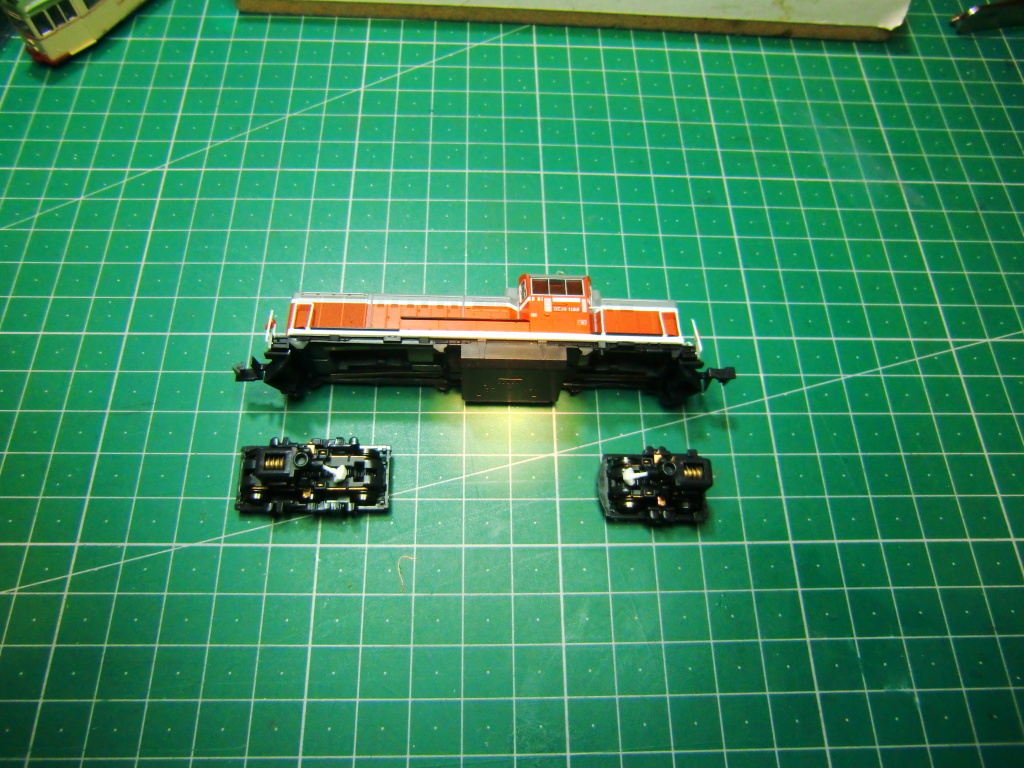
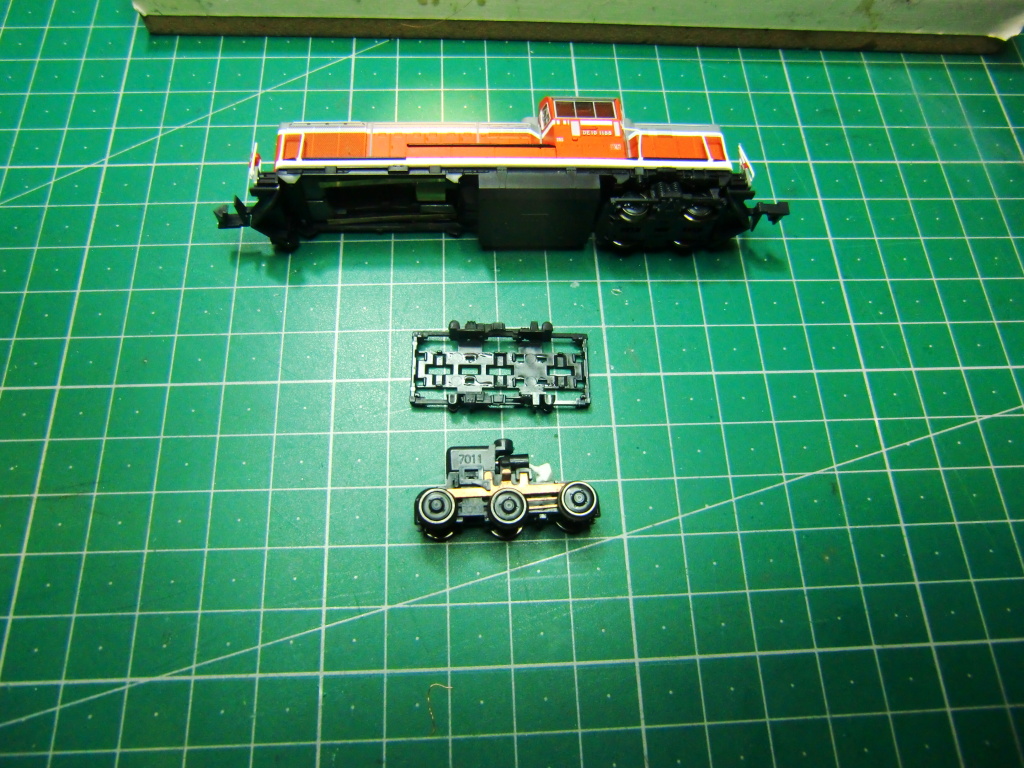
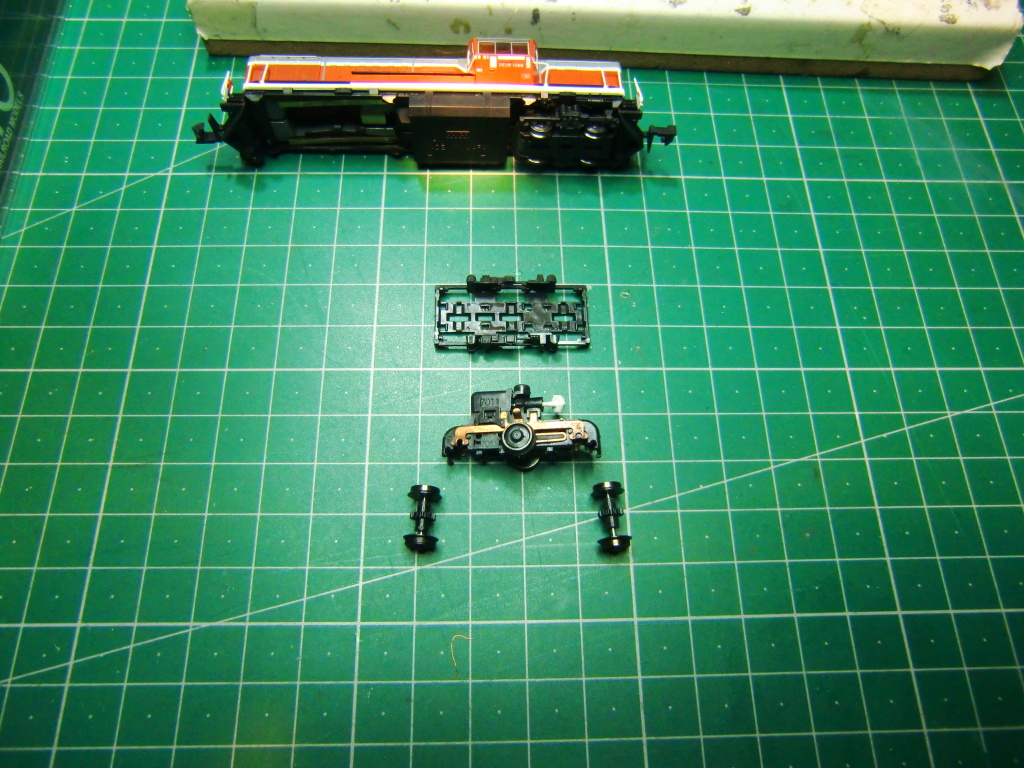
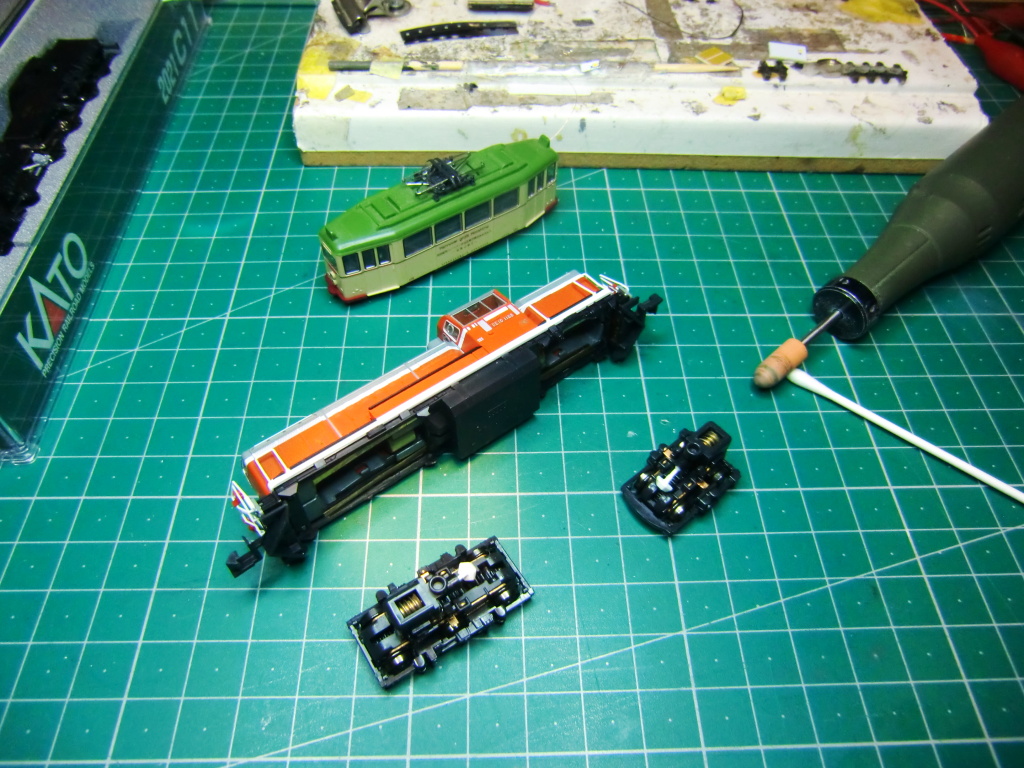


その他の機関車類も基本的に集電パーツのメンテが中心となるため、作業写真のアップは省略します。・・・・・
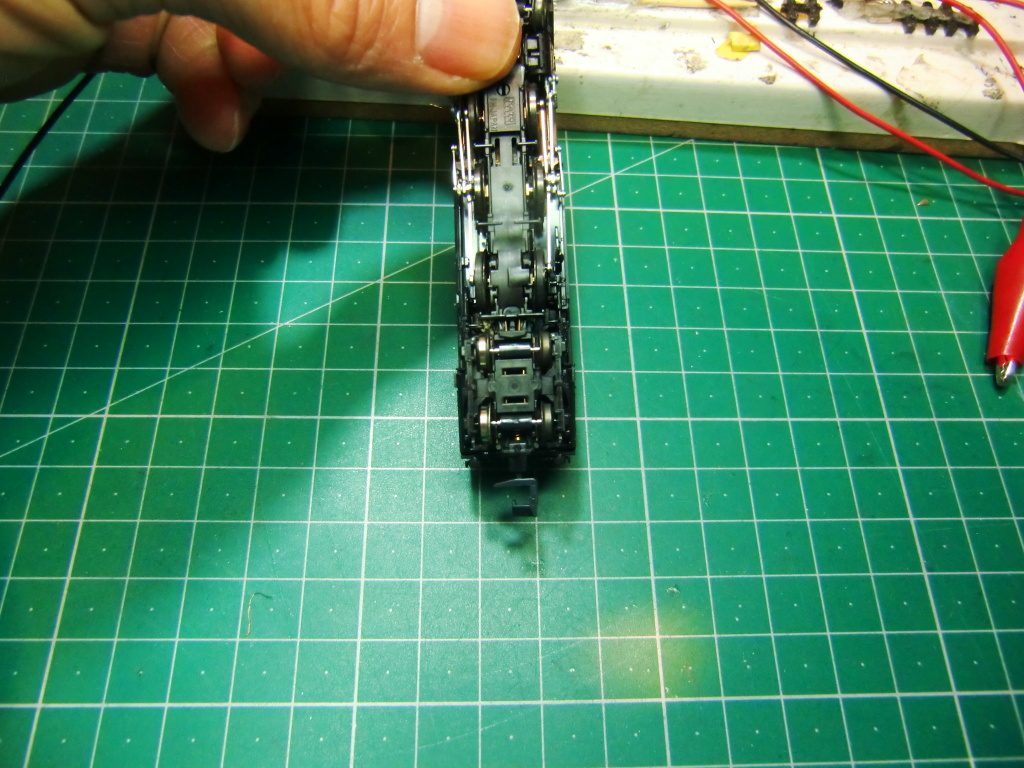

低速でもスムーズな走行が可能となりました。
▼各種ライト加工

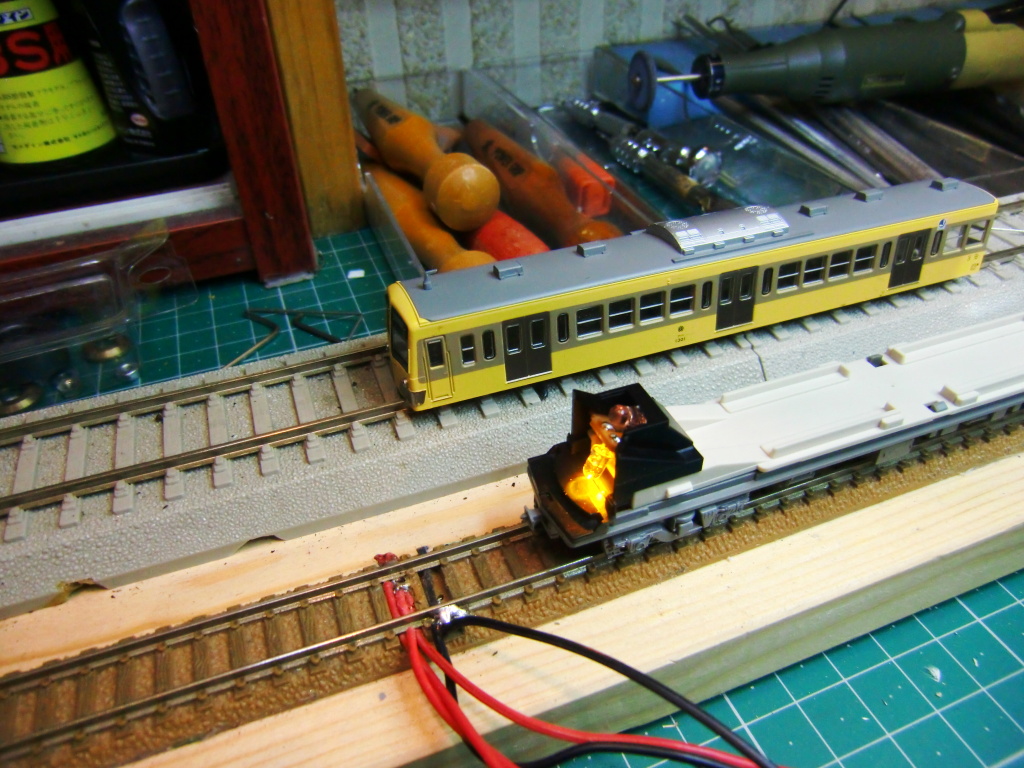
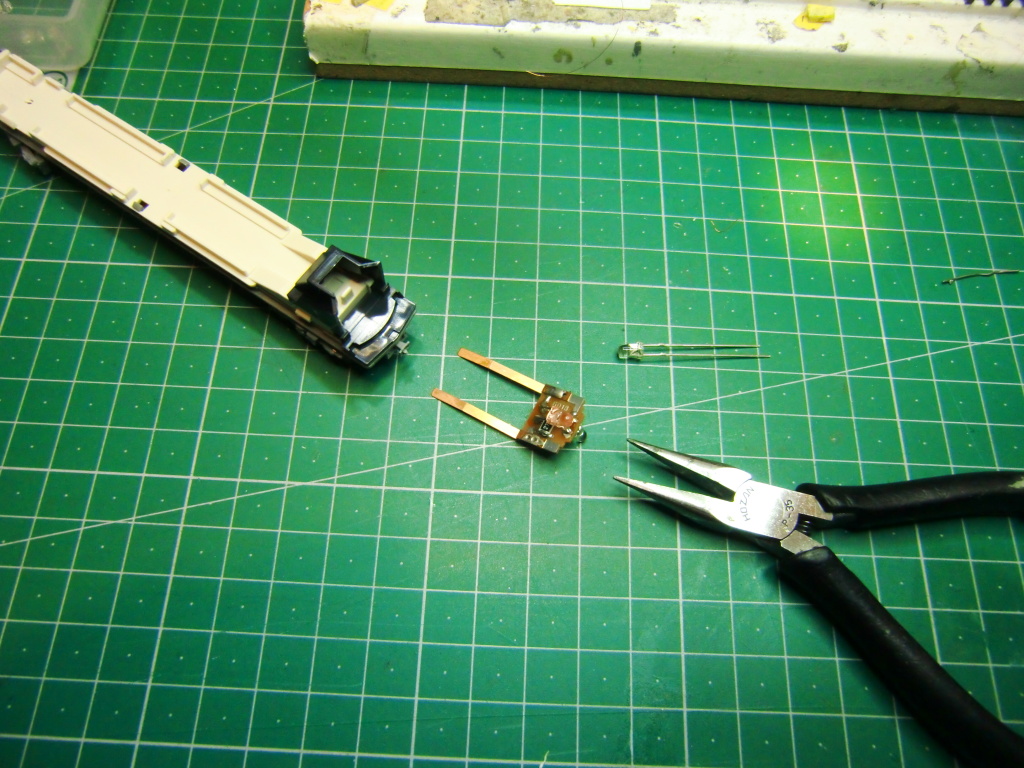
ヘッドとテール用にLEDを交換していきます。






電球のタイプです。
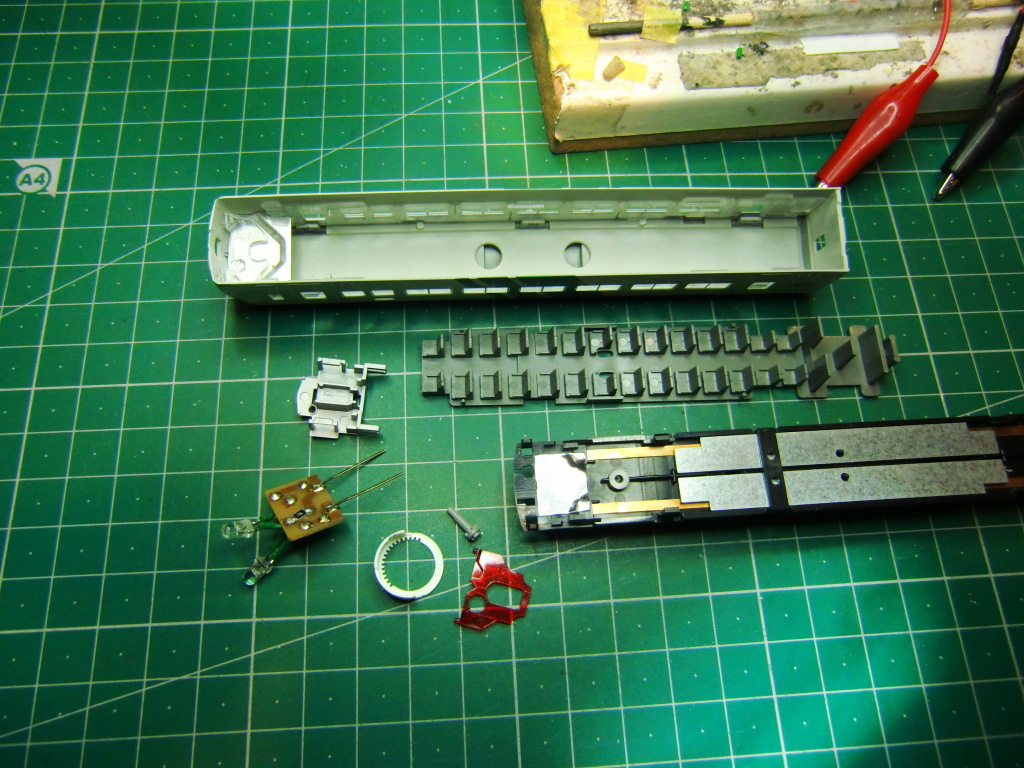
LEDへ置き換えます。このユニットへの組込みは少々コツがいります。
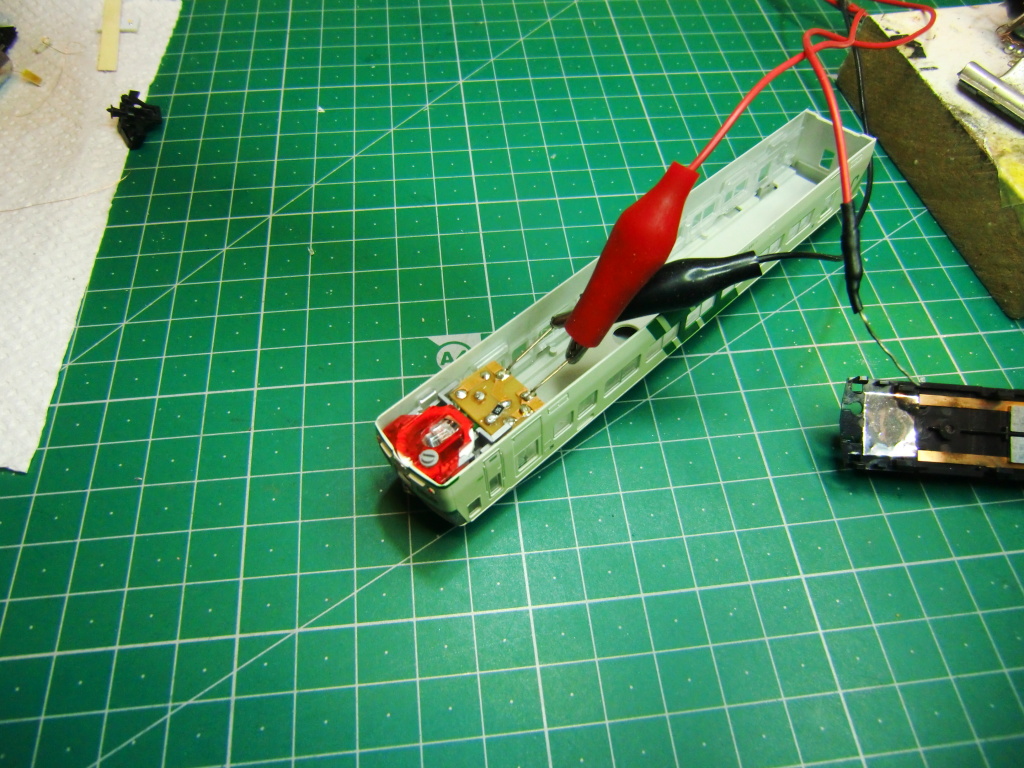

ヘッドマークは白色、ヘッドライトは電球色風に点灯。


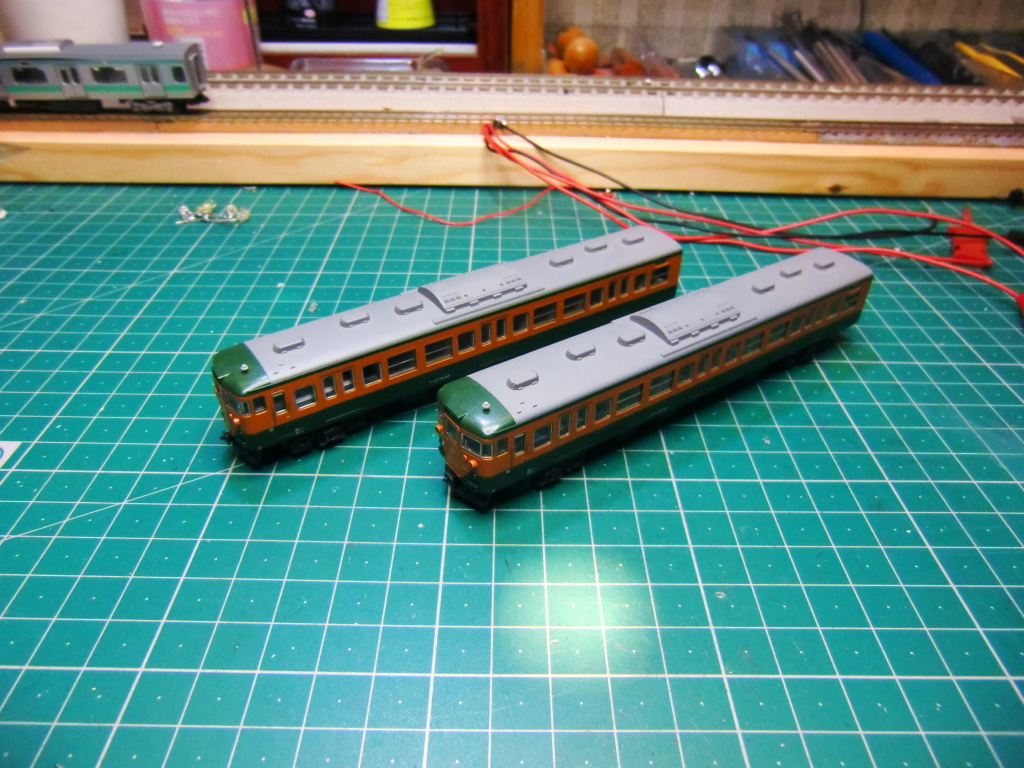
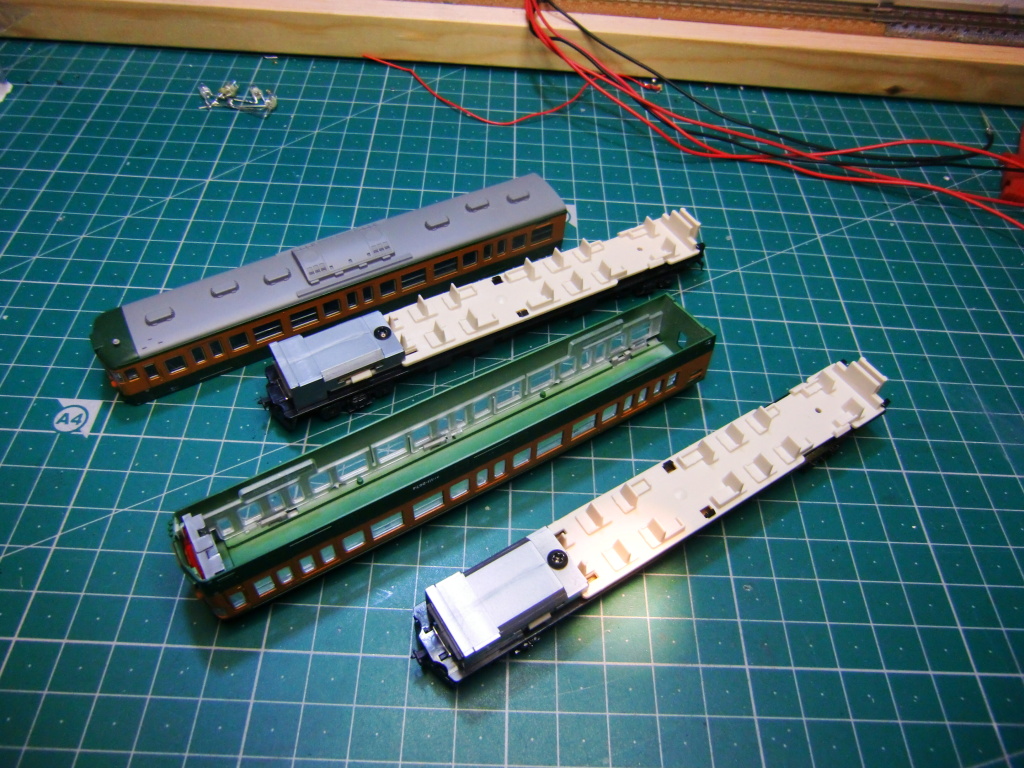
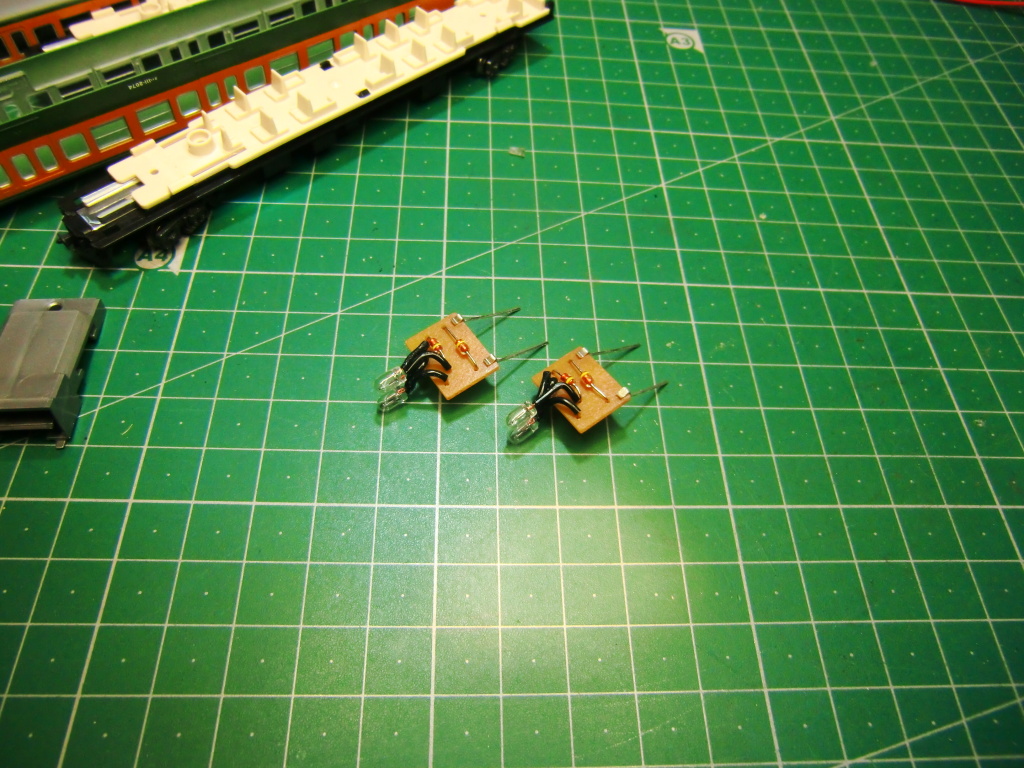
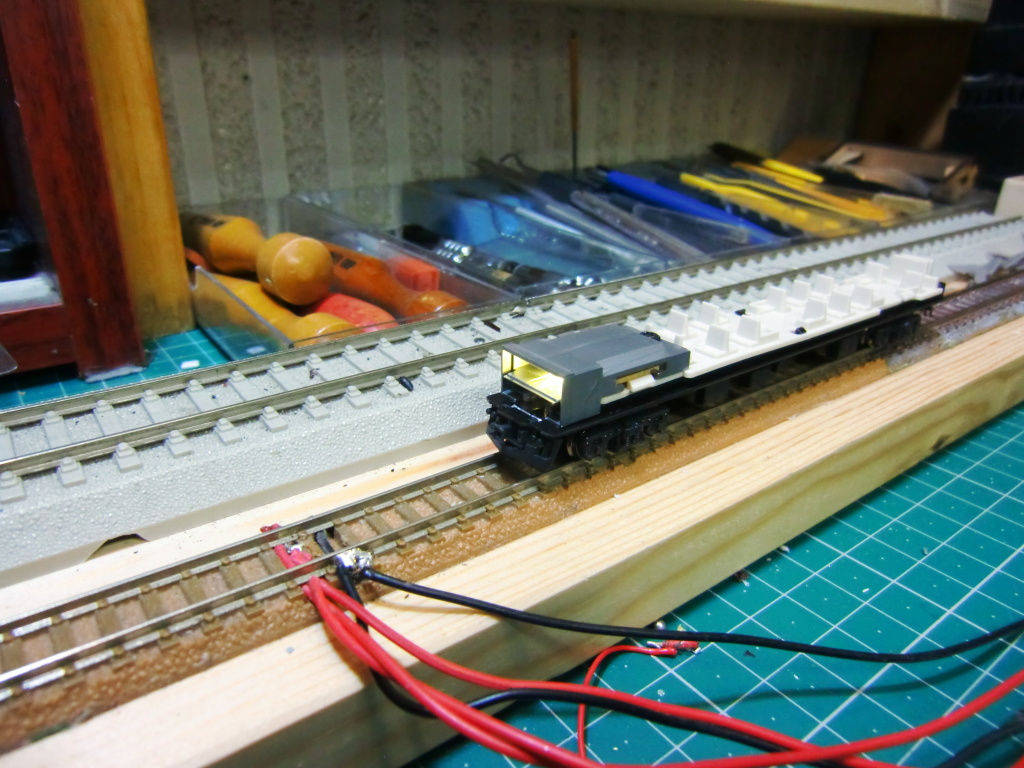


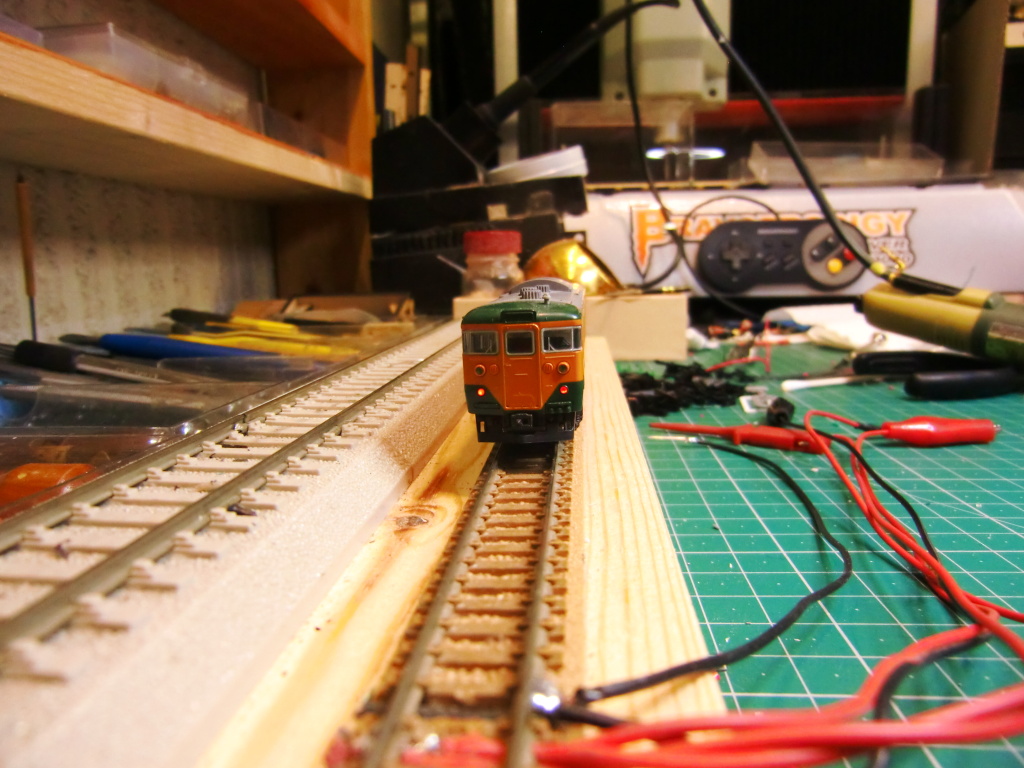
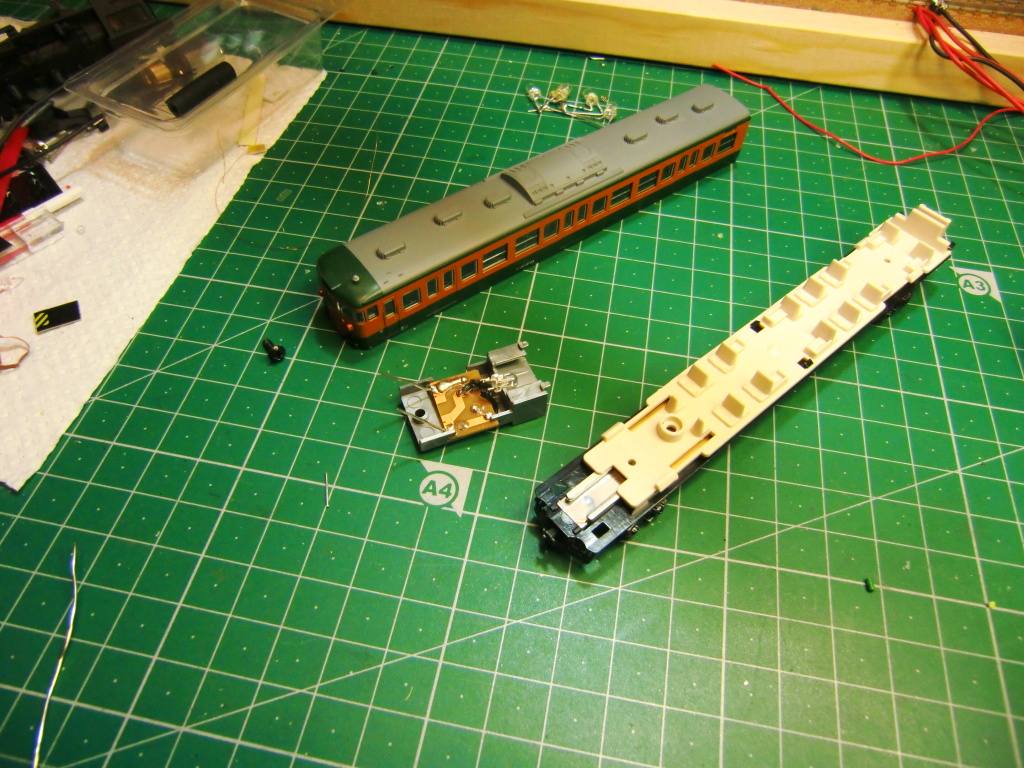


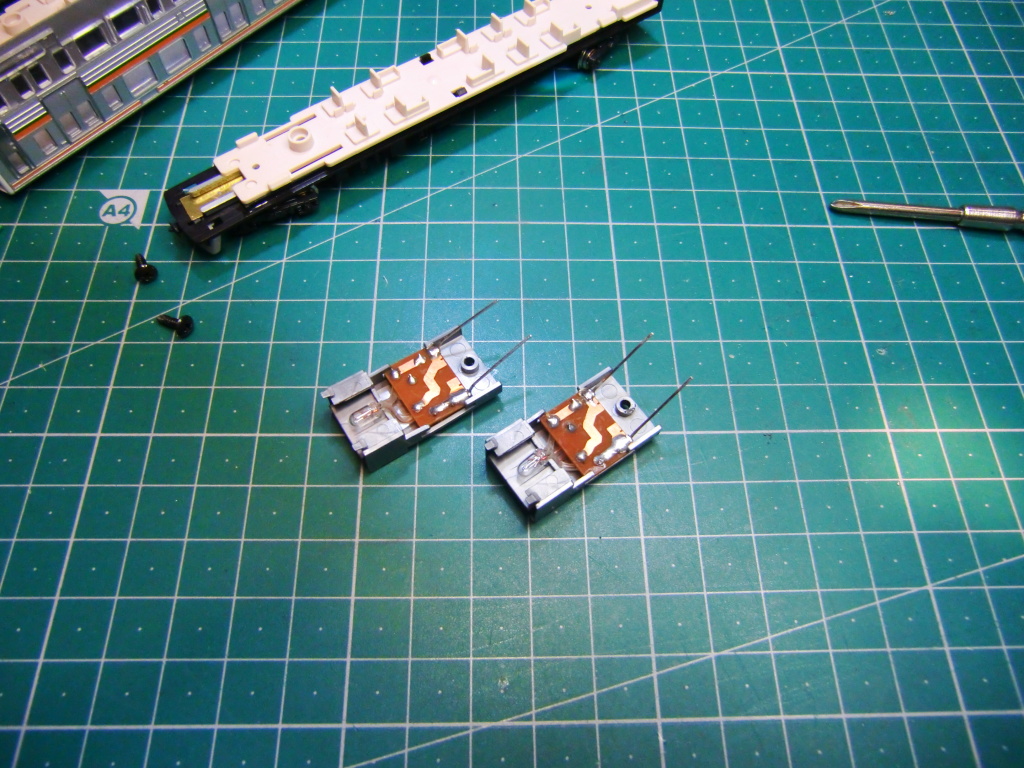
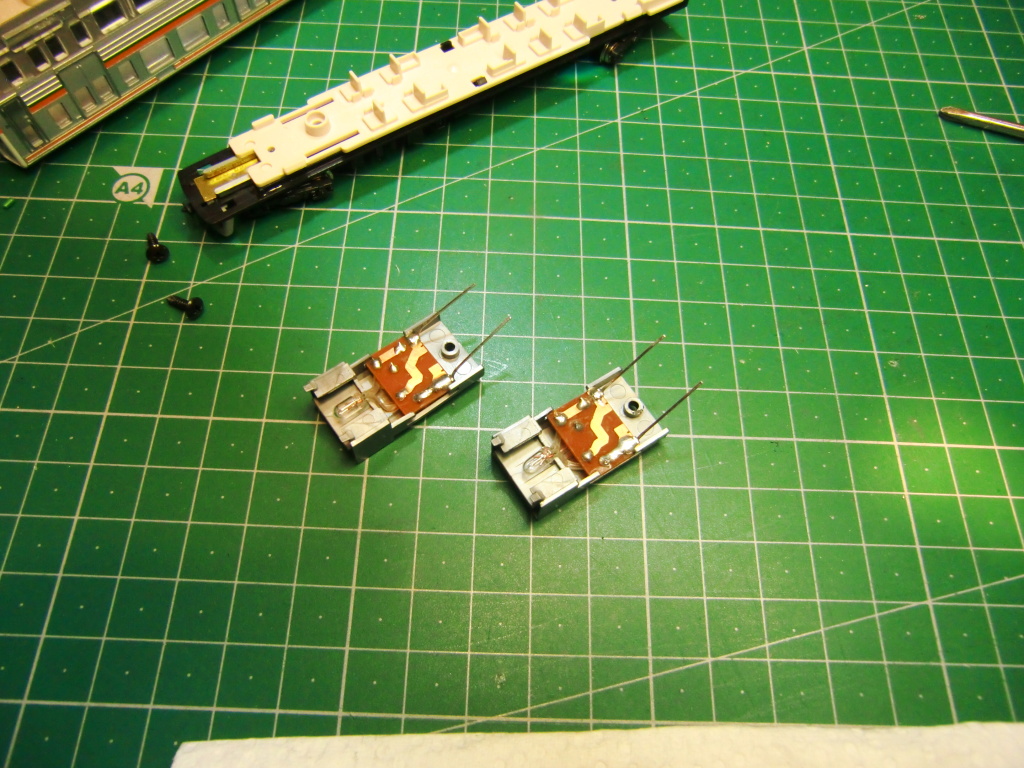




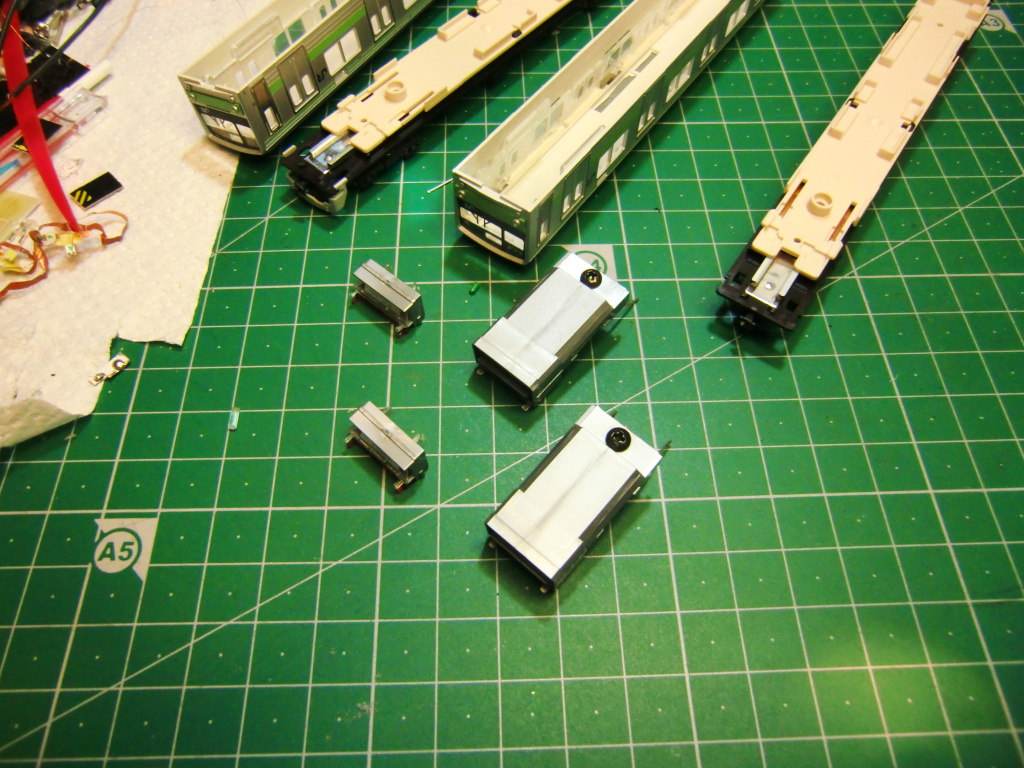
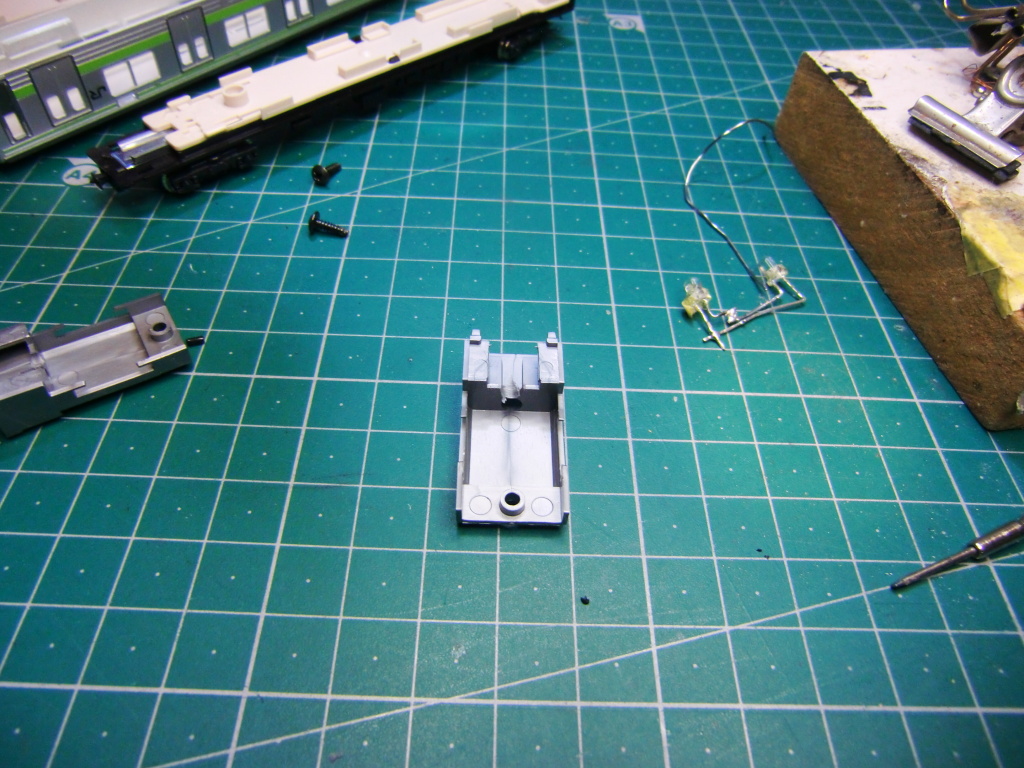
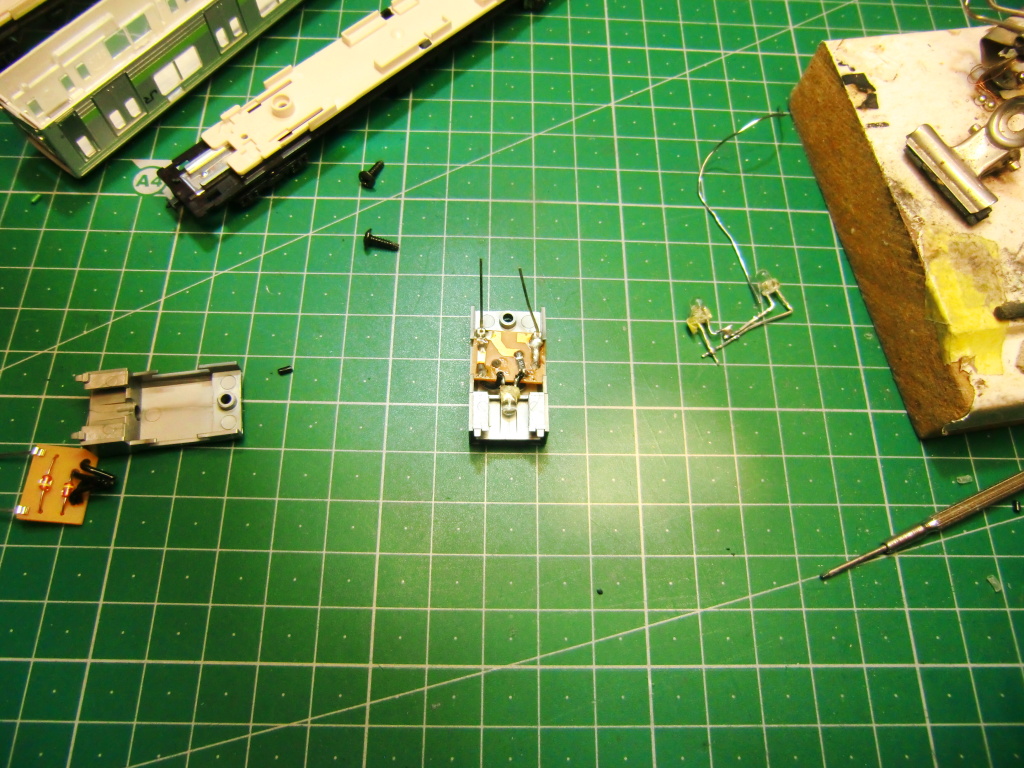



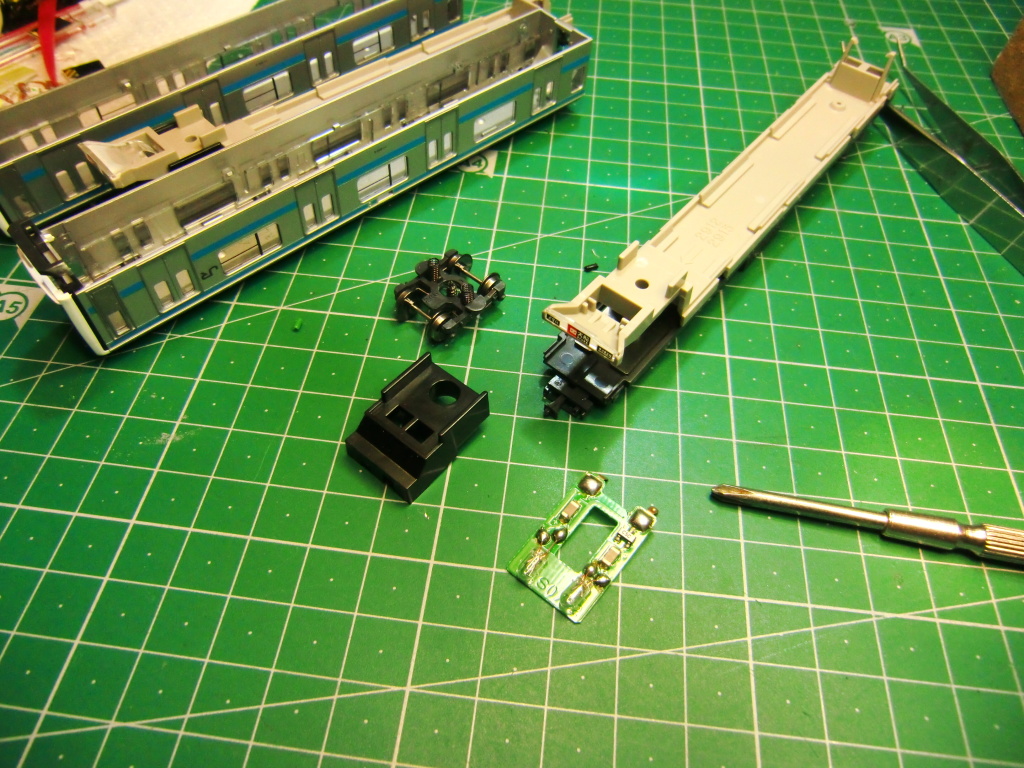
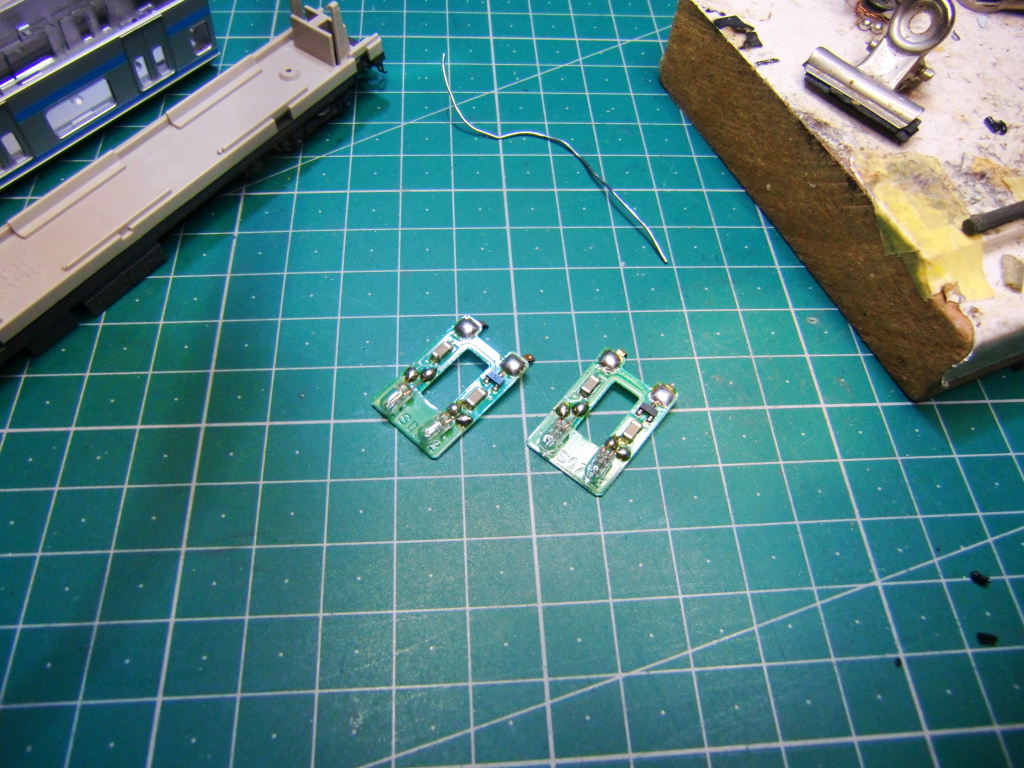

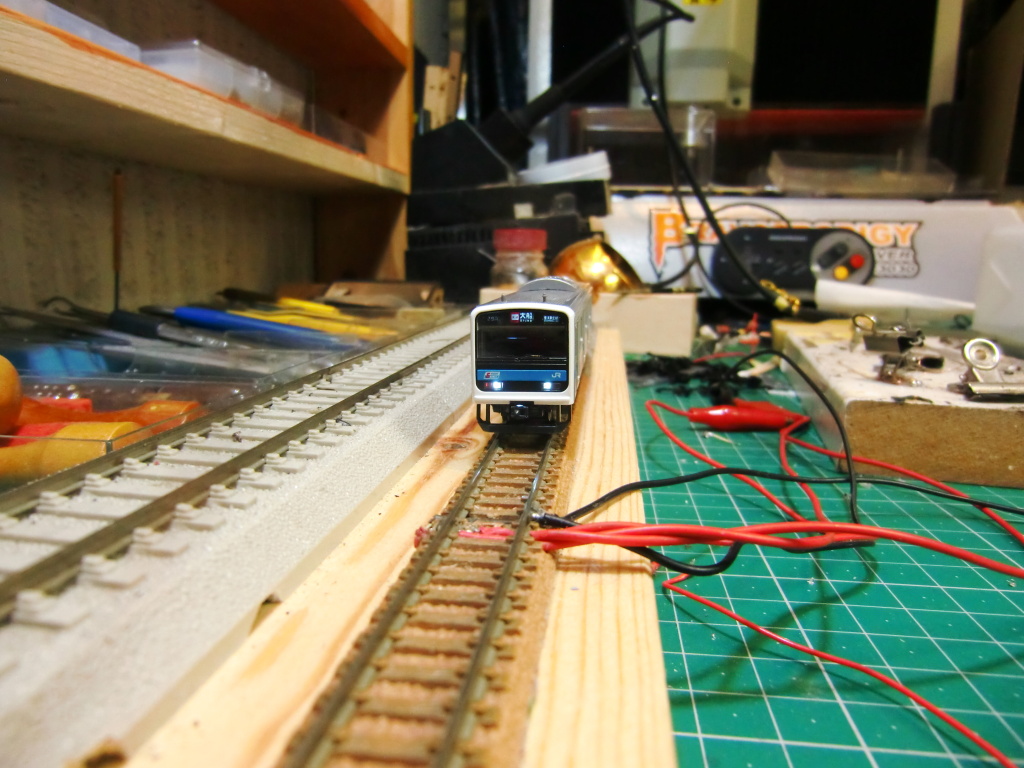


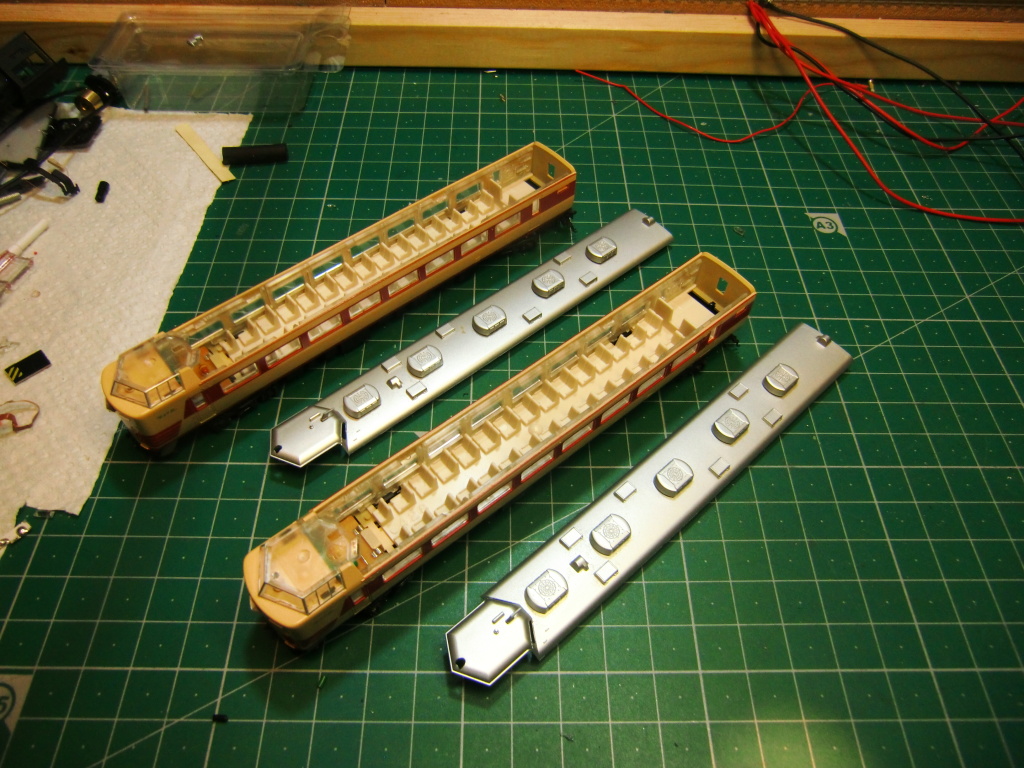
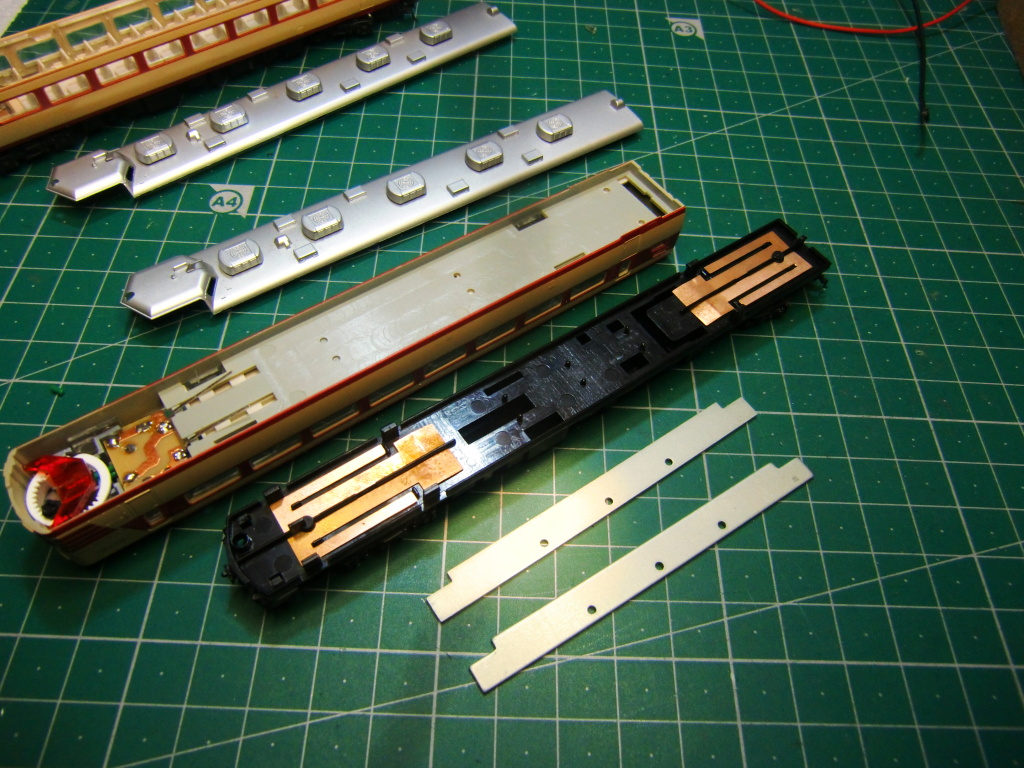

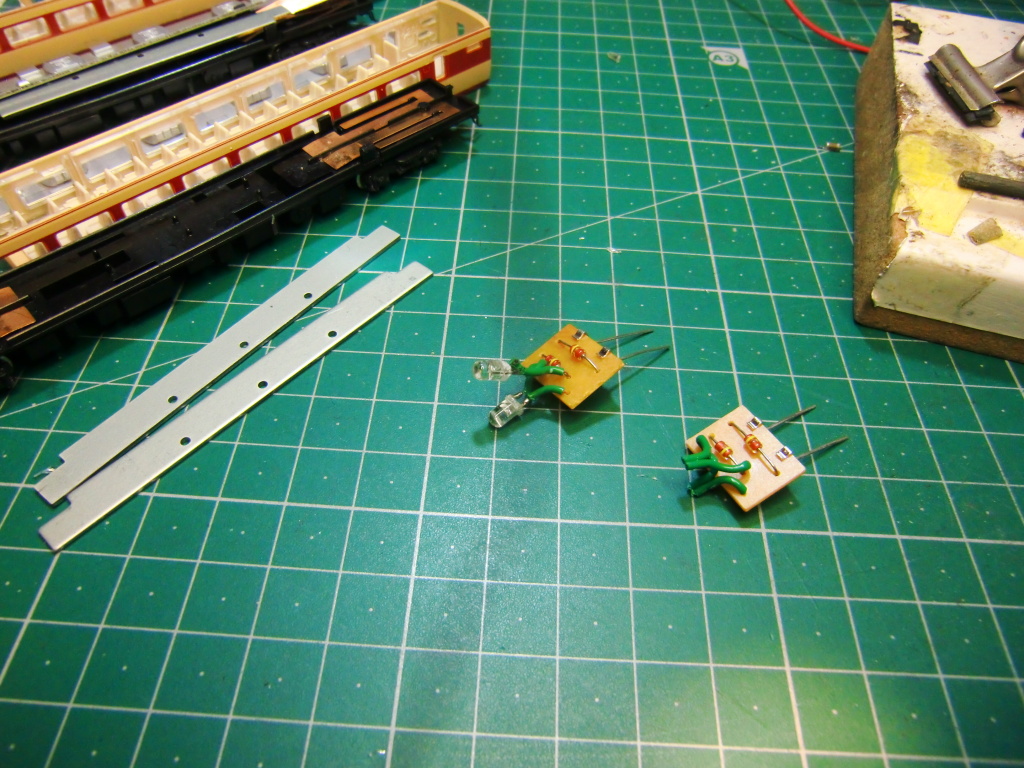


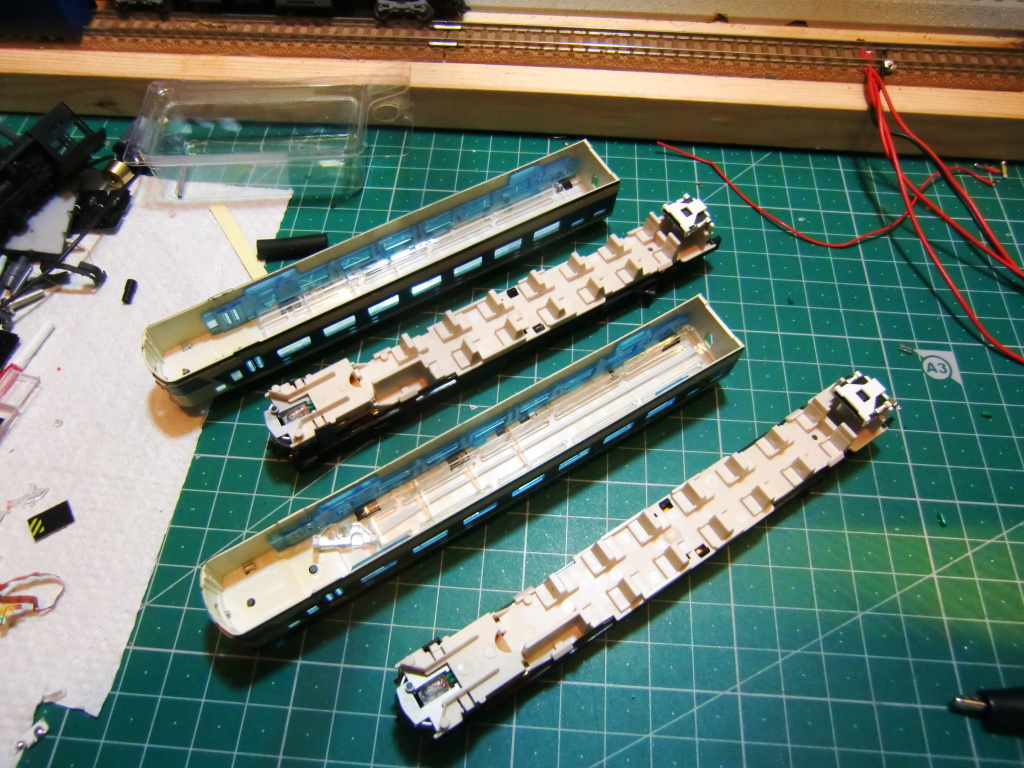
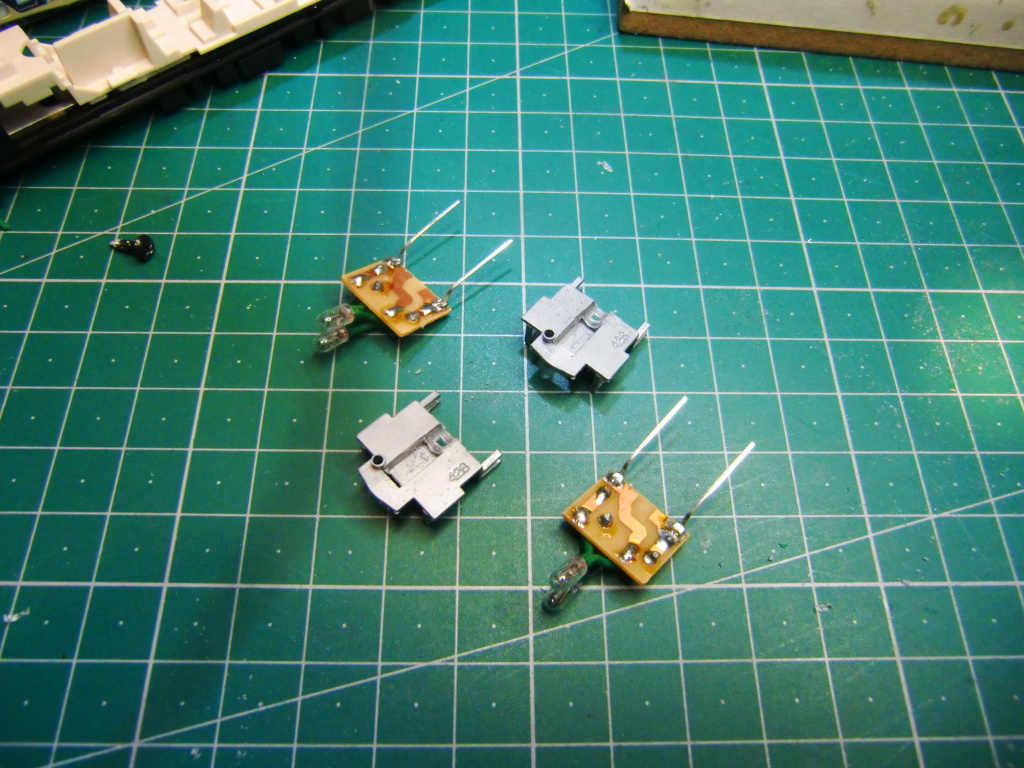
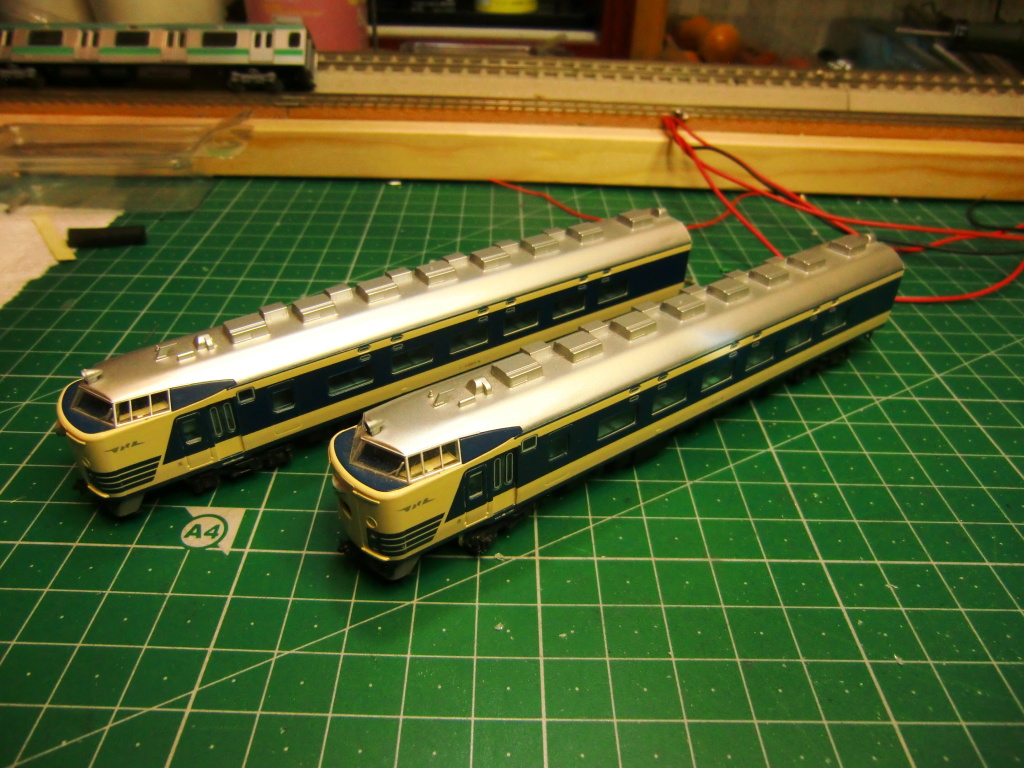

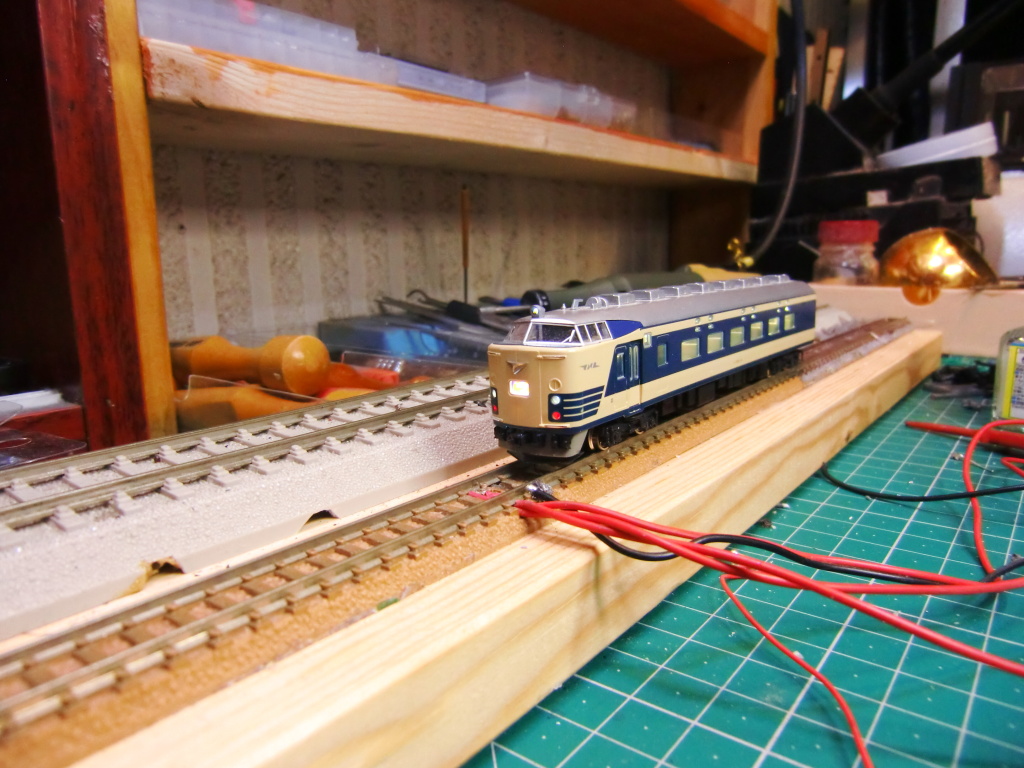

こちらもすべて完了です。
▼鉄道コレクション ライト点灯化改造

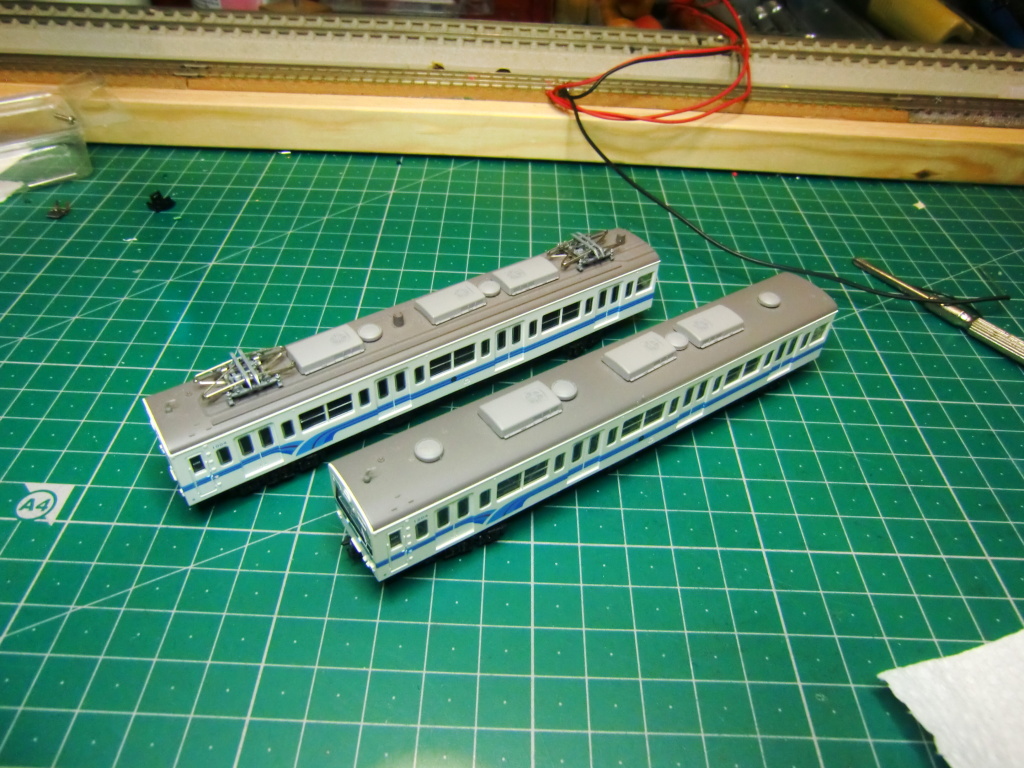
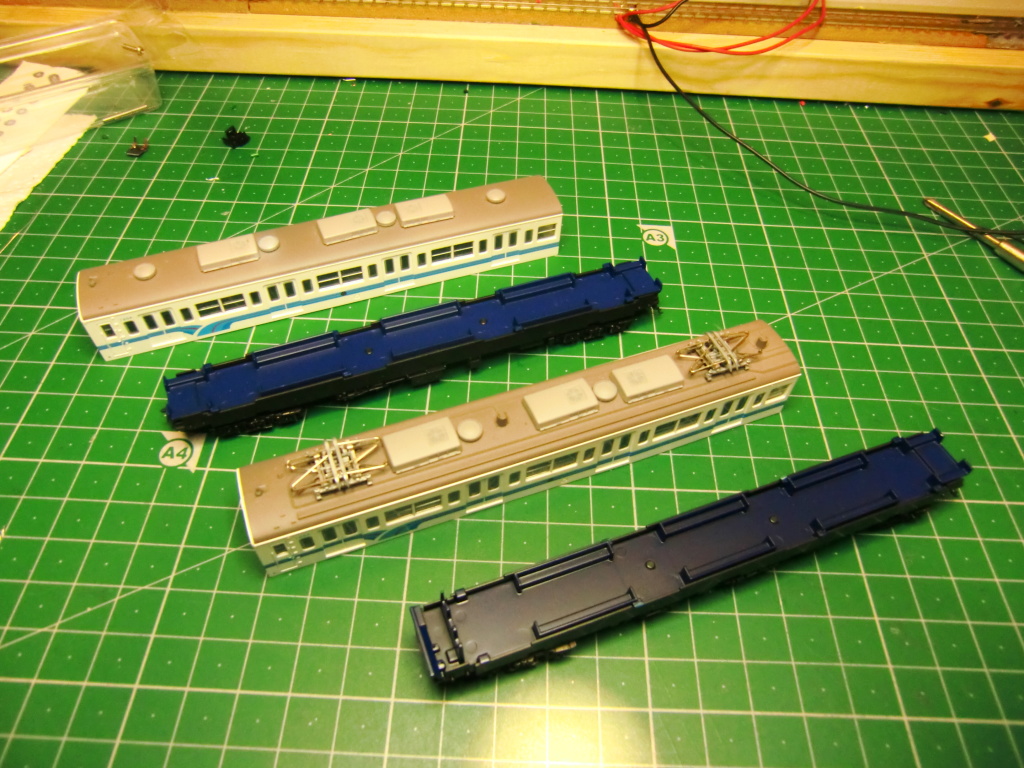


真鍮線を加工して、台車に集電機構を作ります。

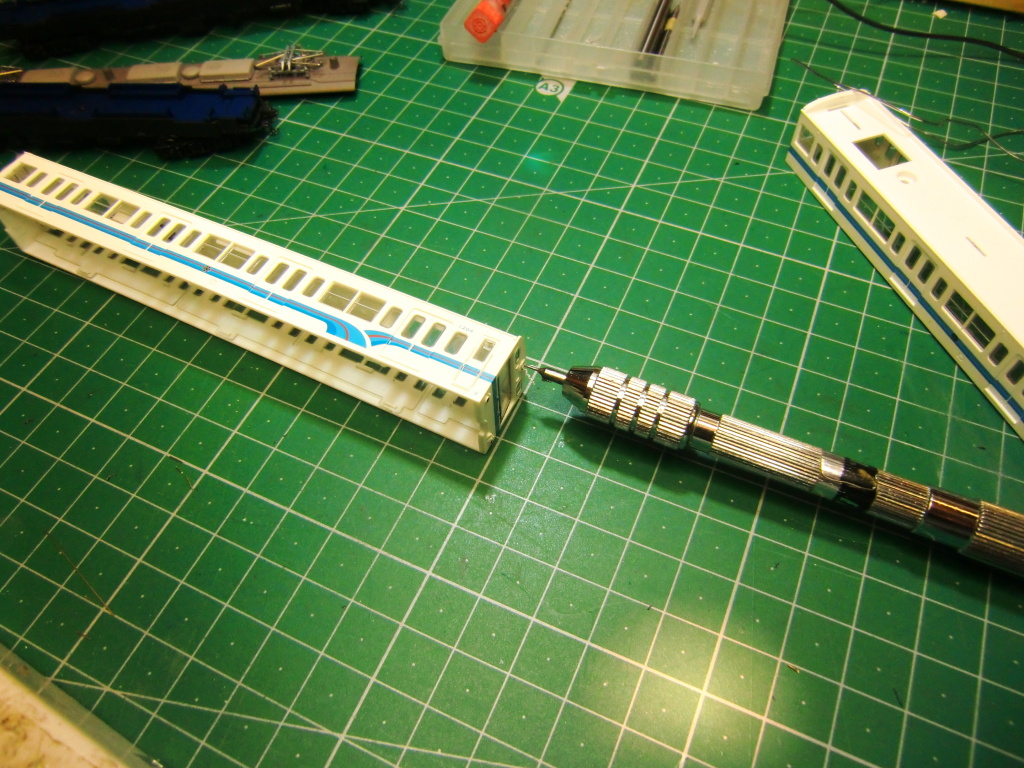
ヘッドライトの穴あけを行います。
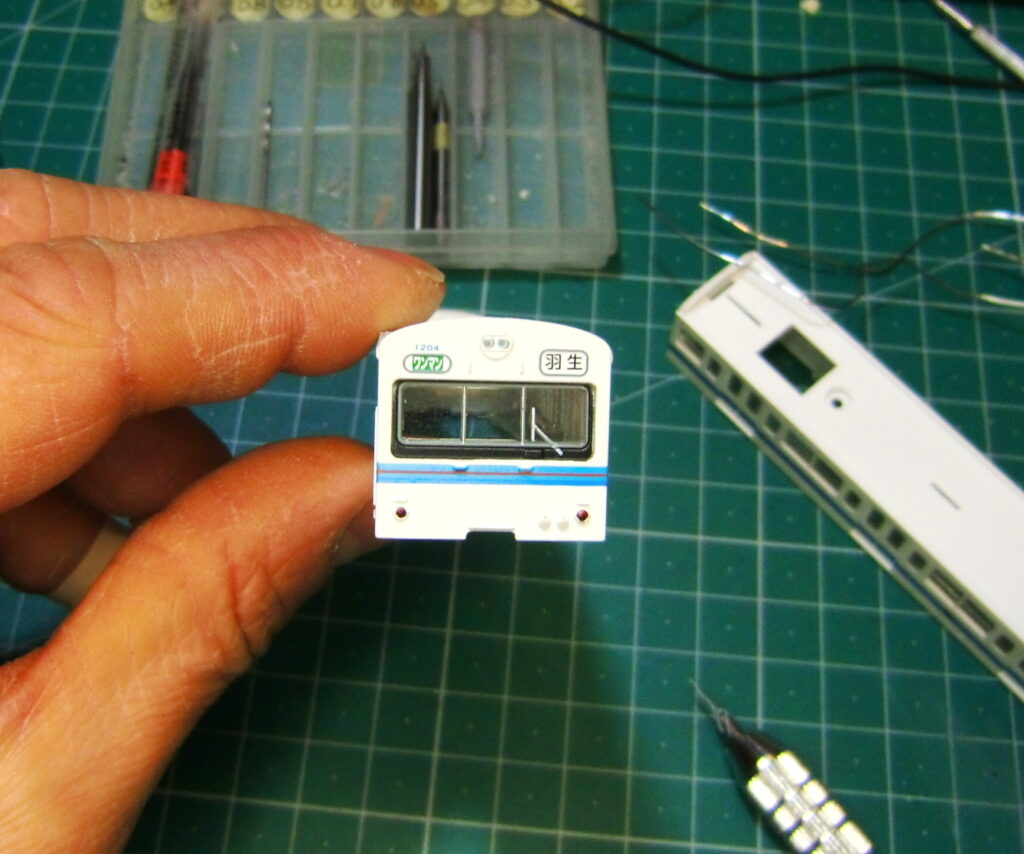
続いて、「光ファイバー」を埋め込んでいきます。




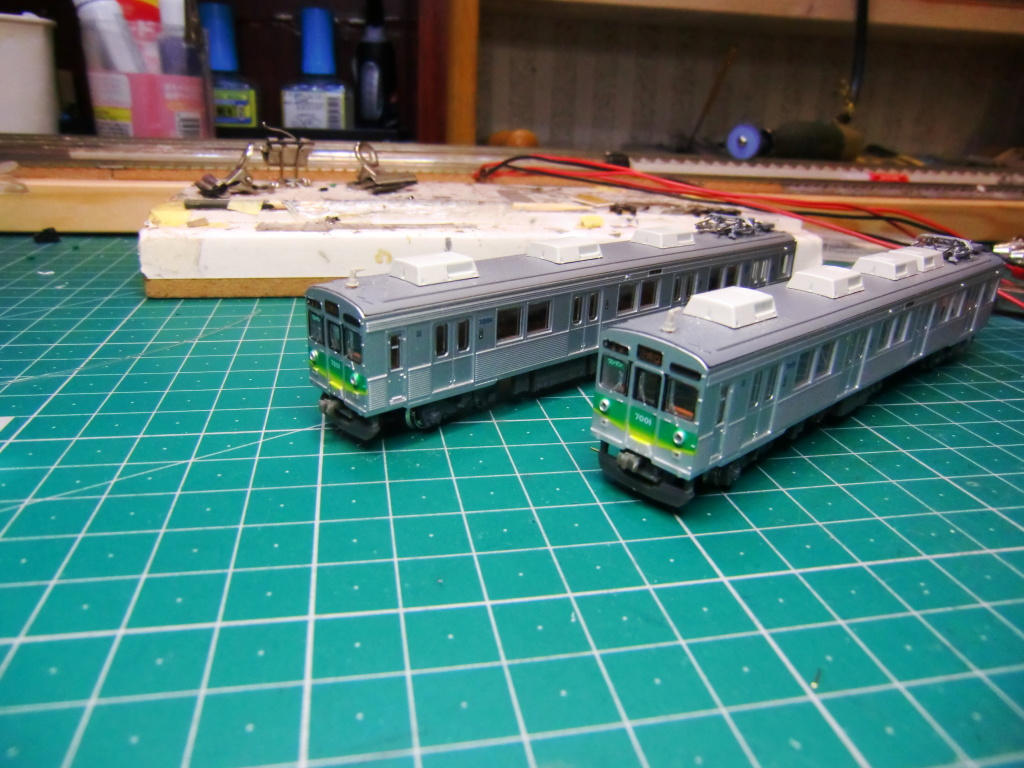

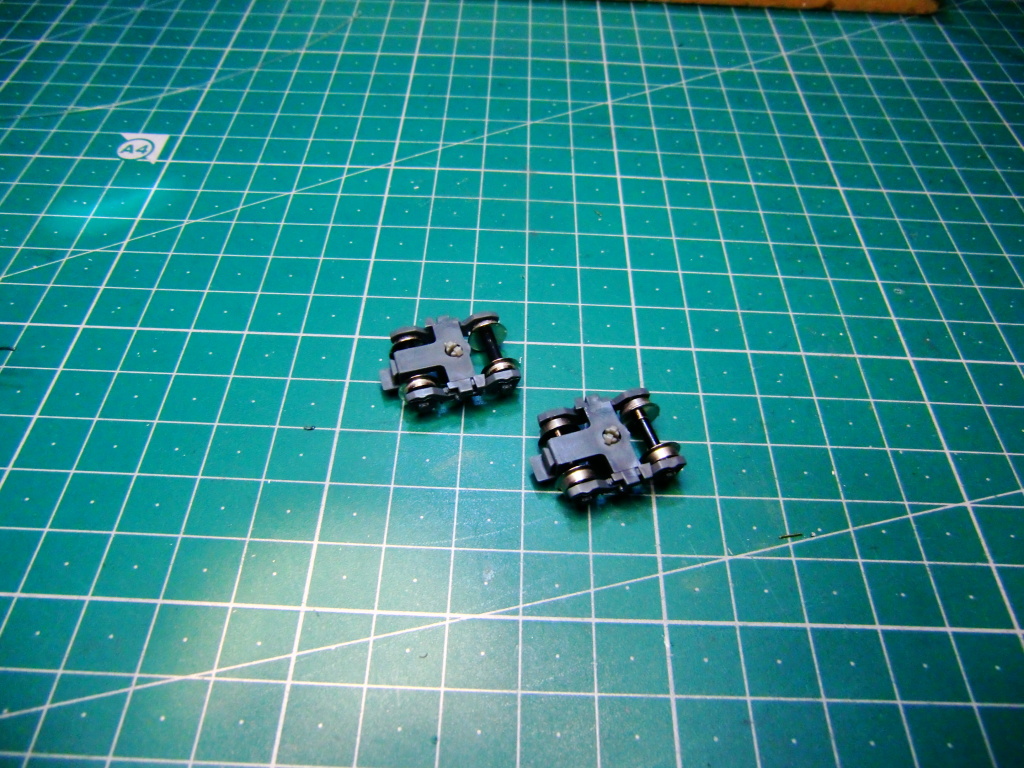
こちらも台車集電機構を作ります。
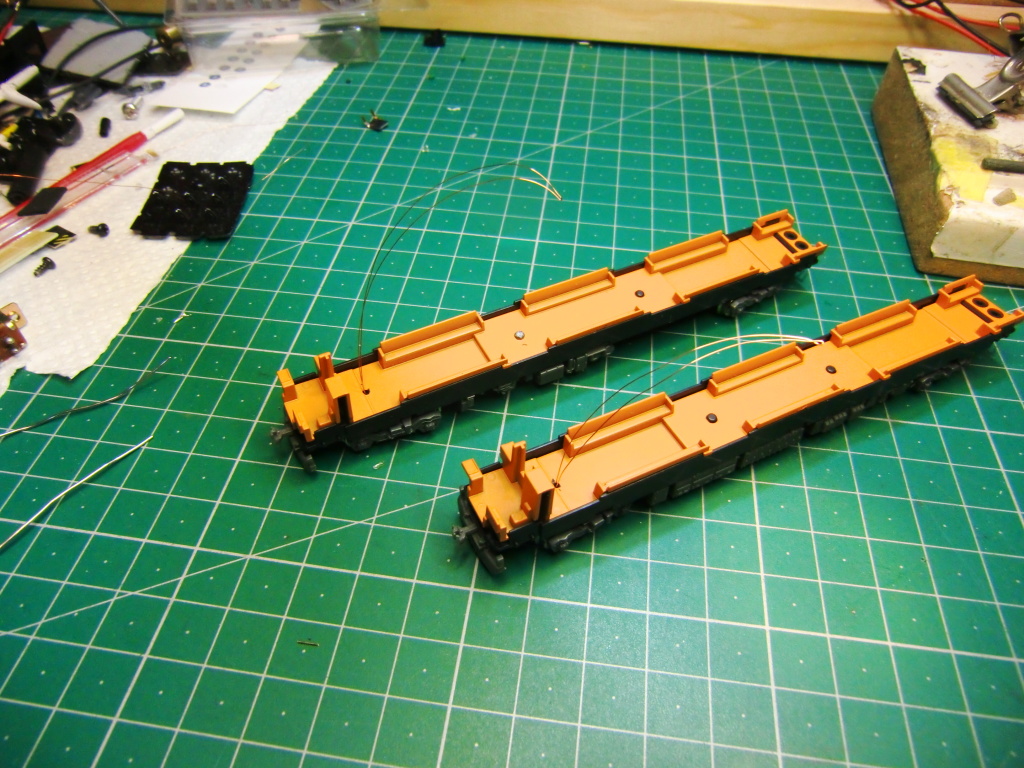
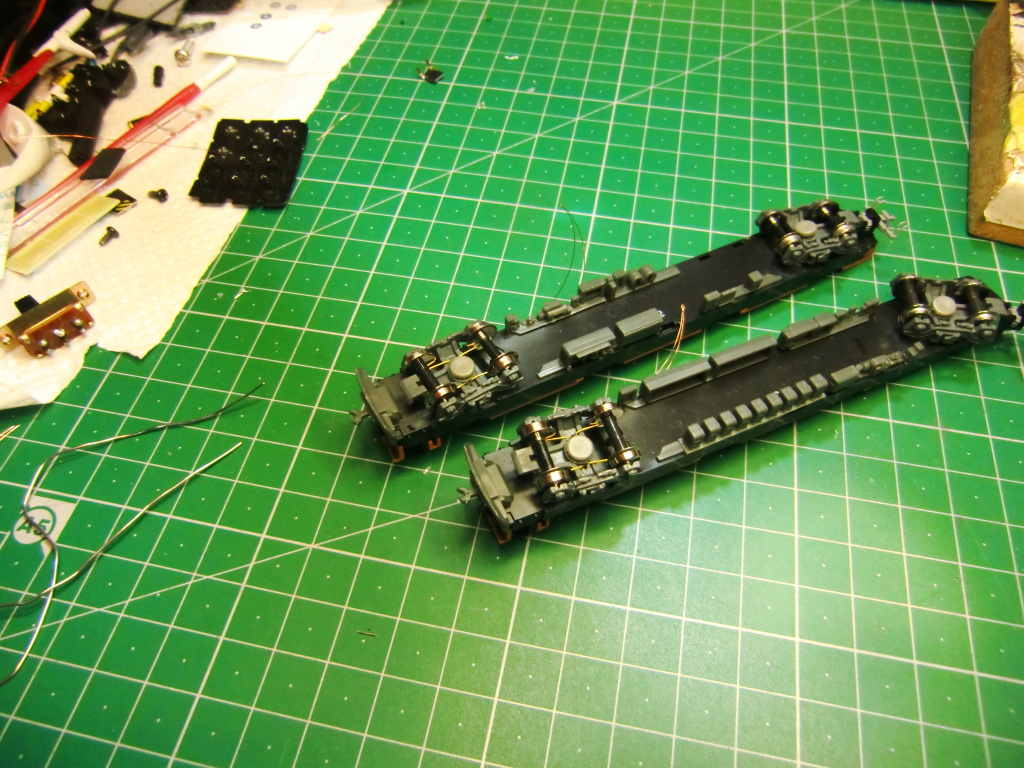

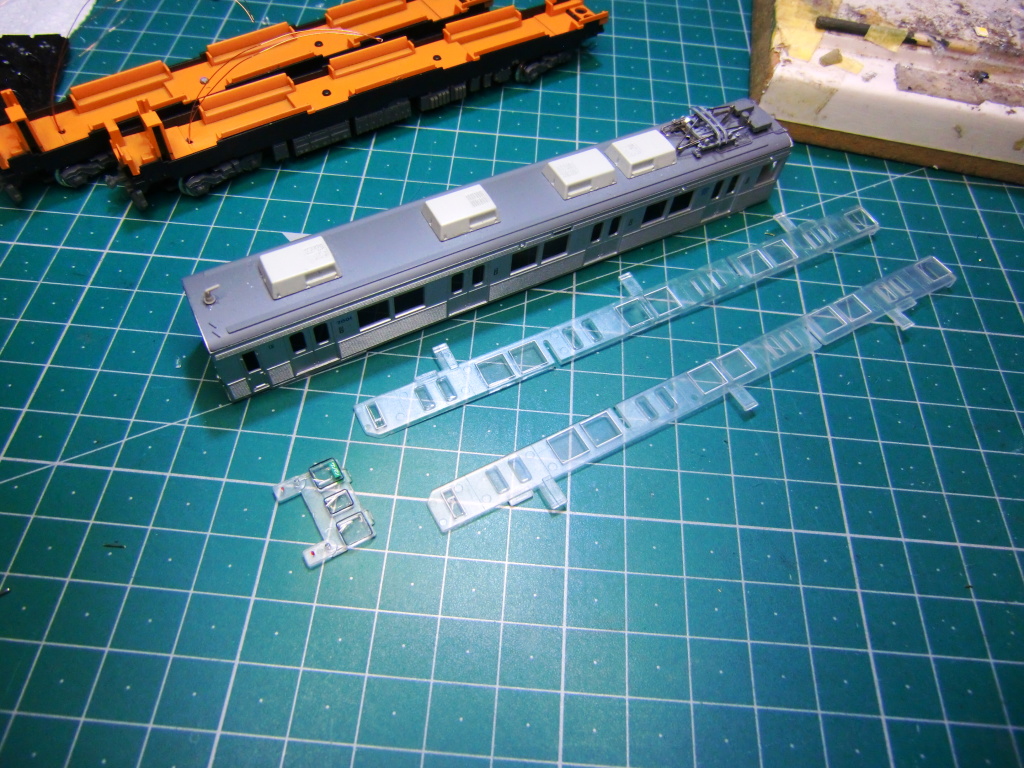
続いて、内部パーツをすべて外して加工します。

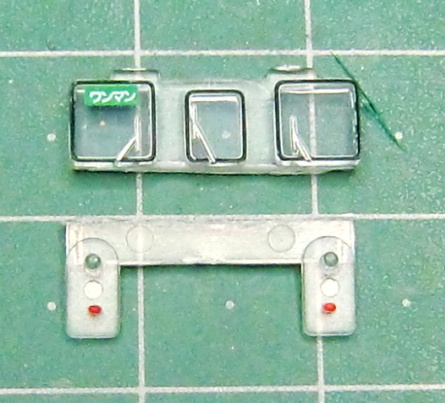
正面のパーツを分離させます。※右写真
次に、ヘッドライトとテールライトのパーツも分割します。
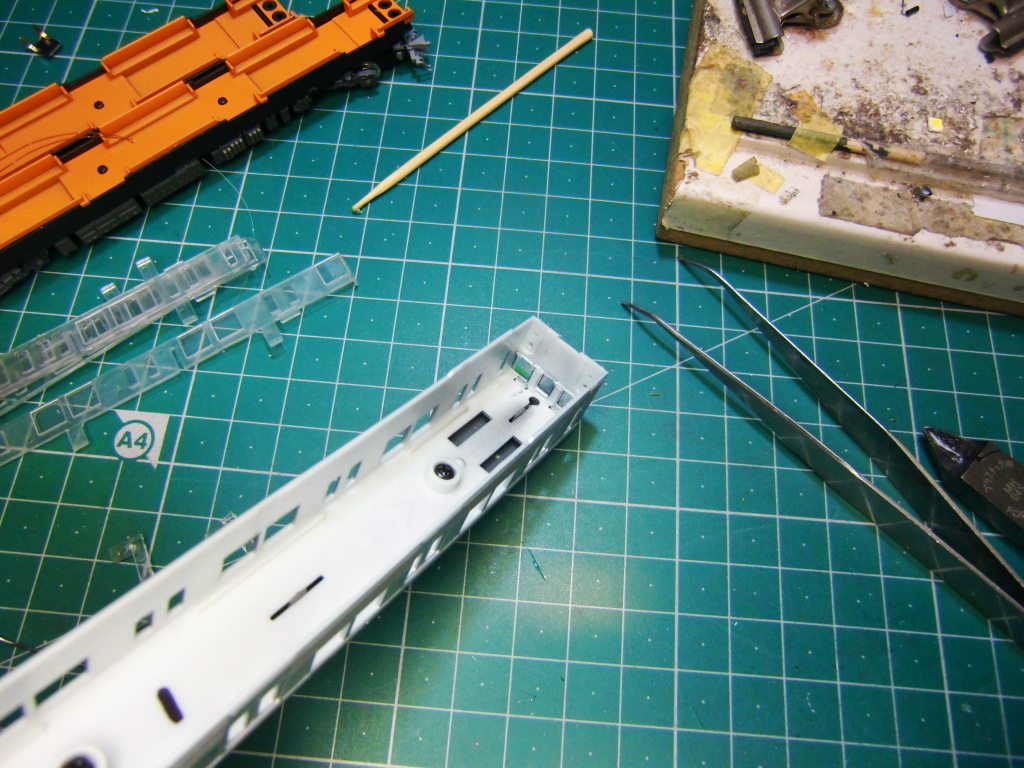

次に、ボディー裏面を黒で塗装してボディーが透けないように遮光します。※2度塗りしています。

塗装が乾いた段階で、分割したクリアパーツ(ヘッドライト用・テールライト用)を組み込んでいきます。
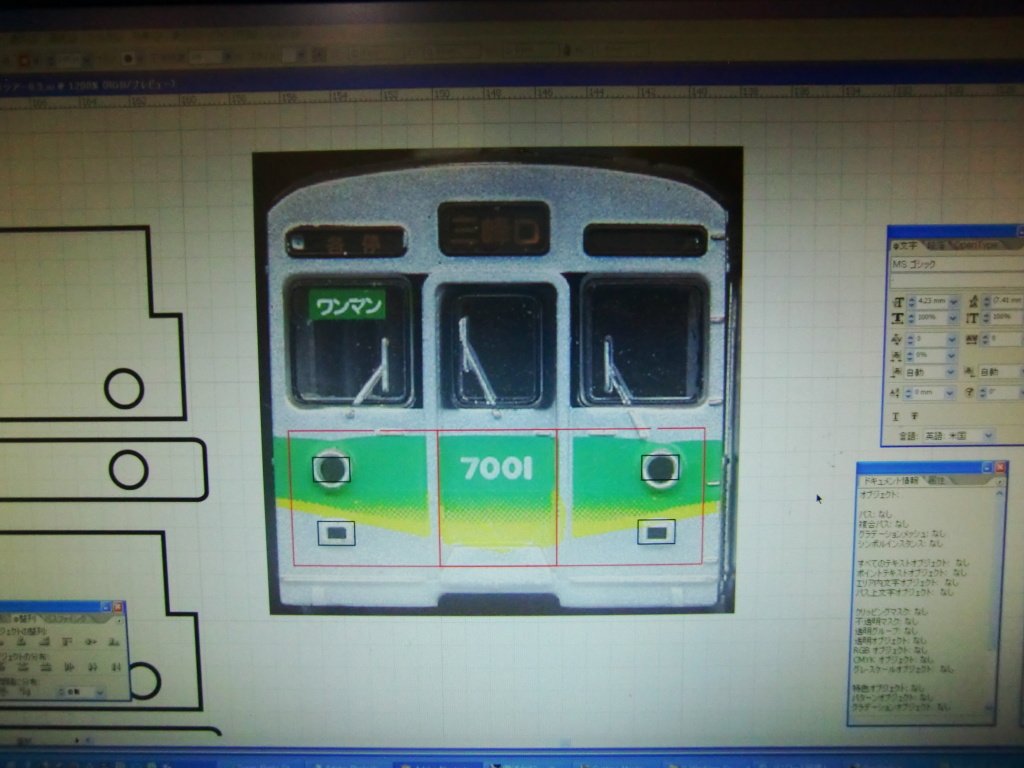
車体正面をスキャンしてライト位置に合わせたパーツを作ります。
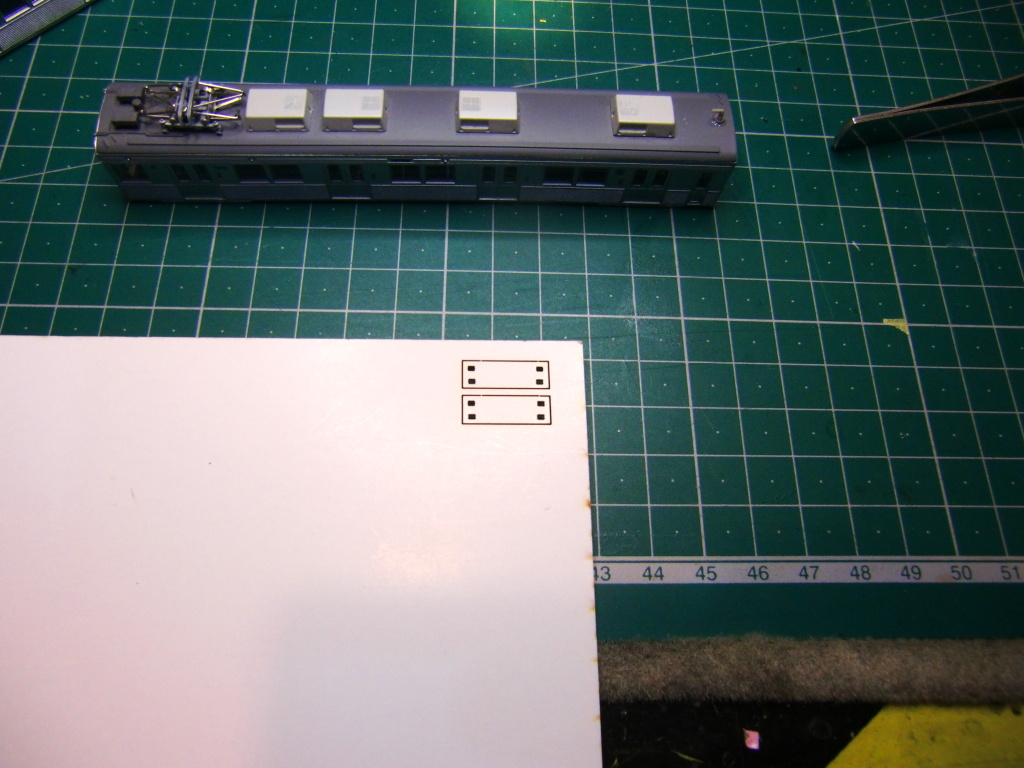
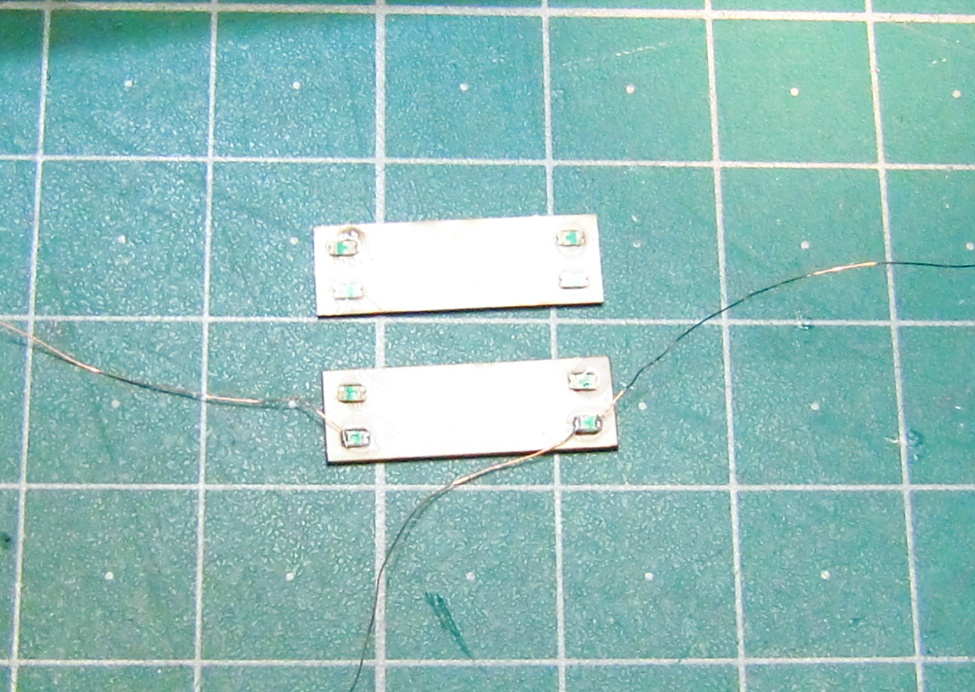
制作したパーツの穴位置に、チップLEDを埋め込んでいきます。あとは、1つ1つ配線を行ってから点灯テストです。
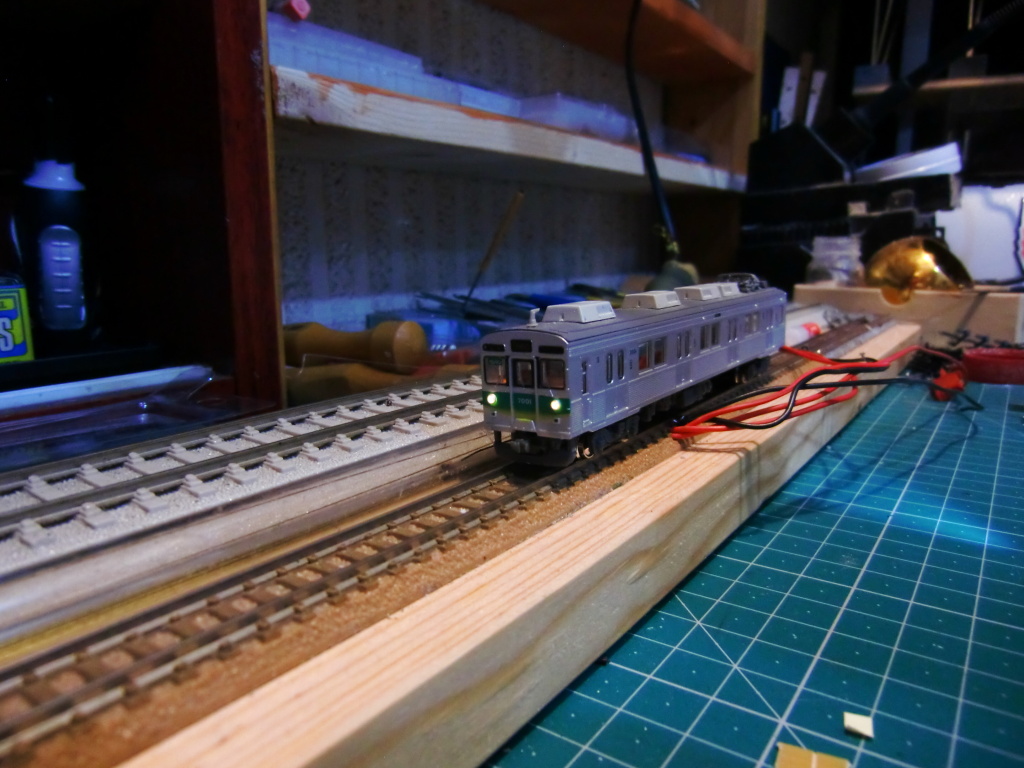
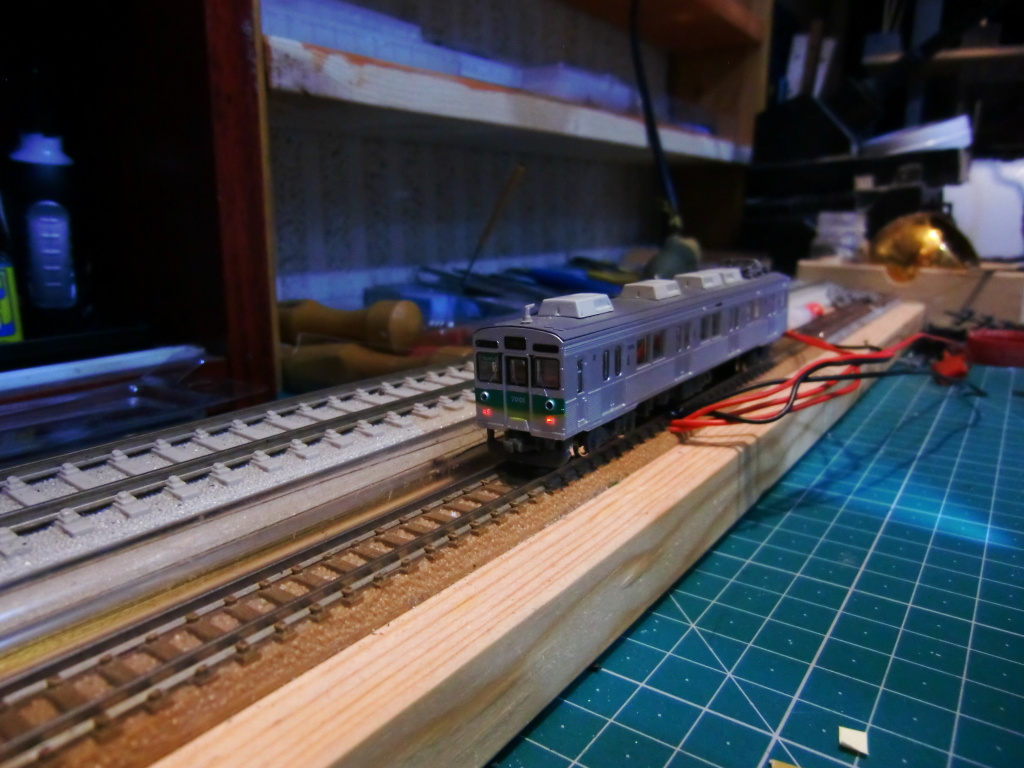
作業はすべて完了いたしました。

制作にあたっての資料集めに少し手間取りましたが、ようやく制作に必要な資料がすべて揃いました。特に時間がかかったのは、各車両ごとの車番です。公開されている動画を1つ1つ確認しながら、再生と停止を繰り返しながら、ようやくすべての車番がわりました。

車体をすべて分解して塗装前の準備を進めます。
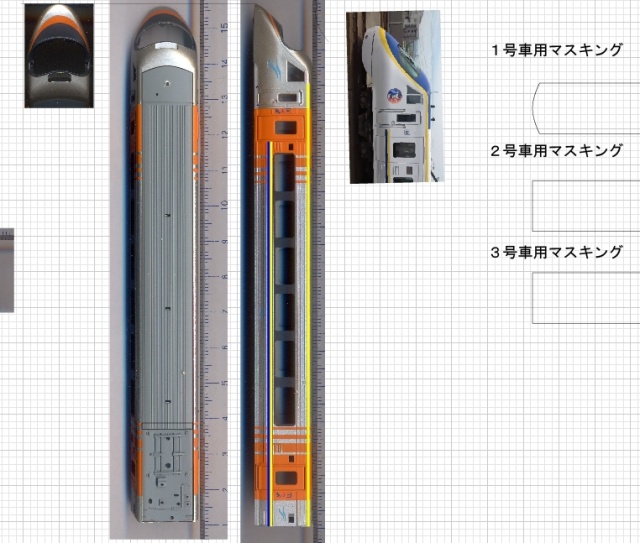
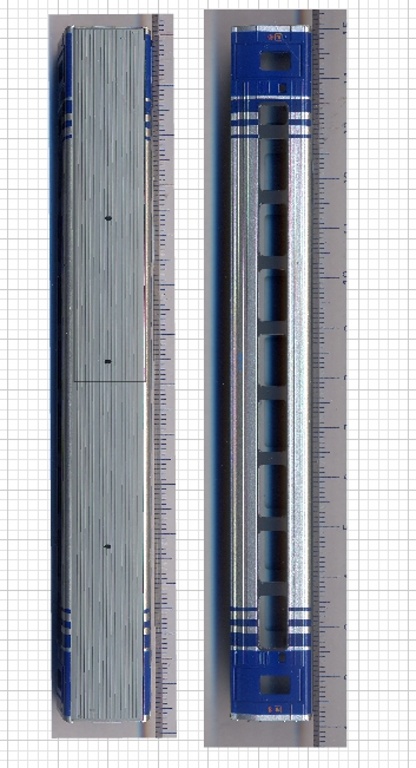

車体をスキャンを行い、各種車両ごとの「マスキング・データ」を制作していきます。データ制作にあたり、1枚の目の写真のように実写と模型を横並びにして正確な帯位置を割り出します。



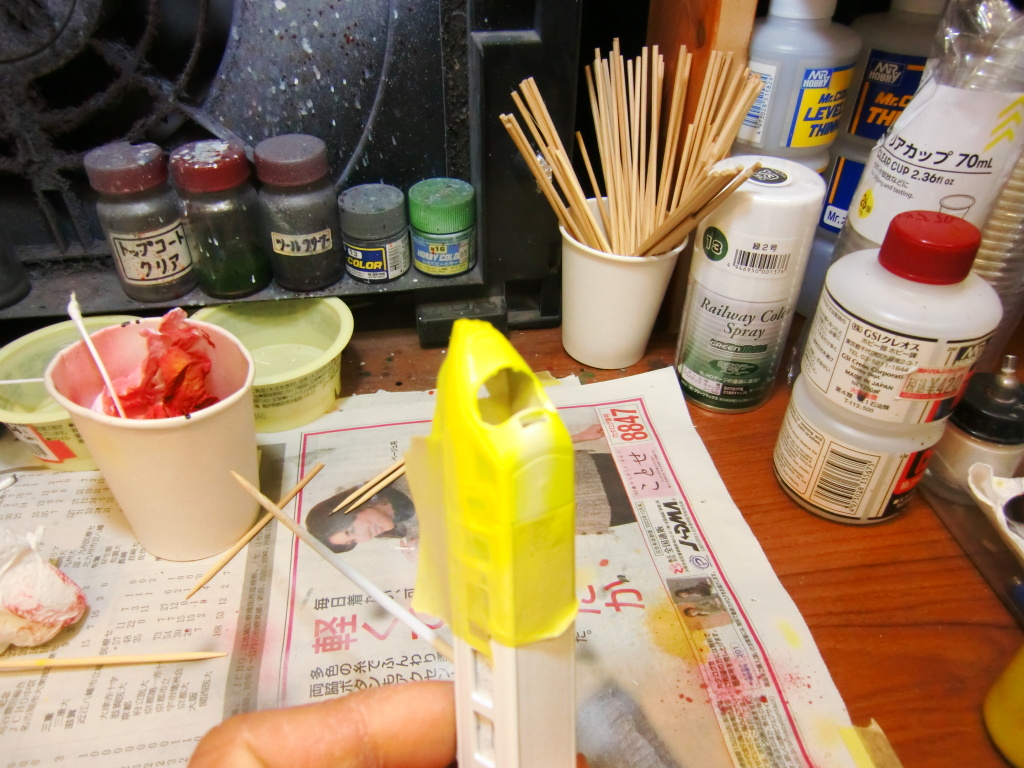



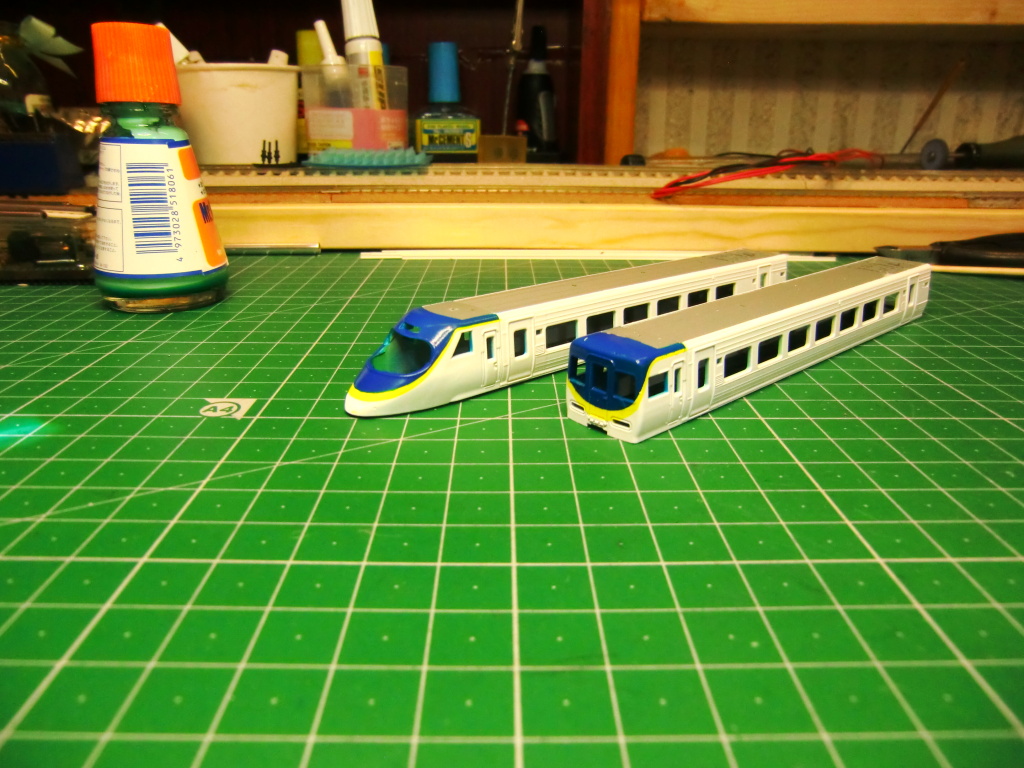

「UVクリアーコート」工程
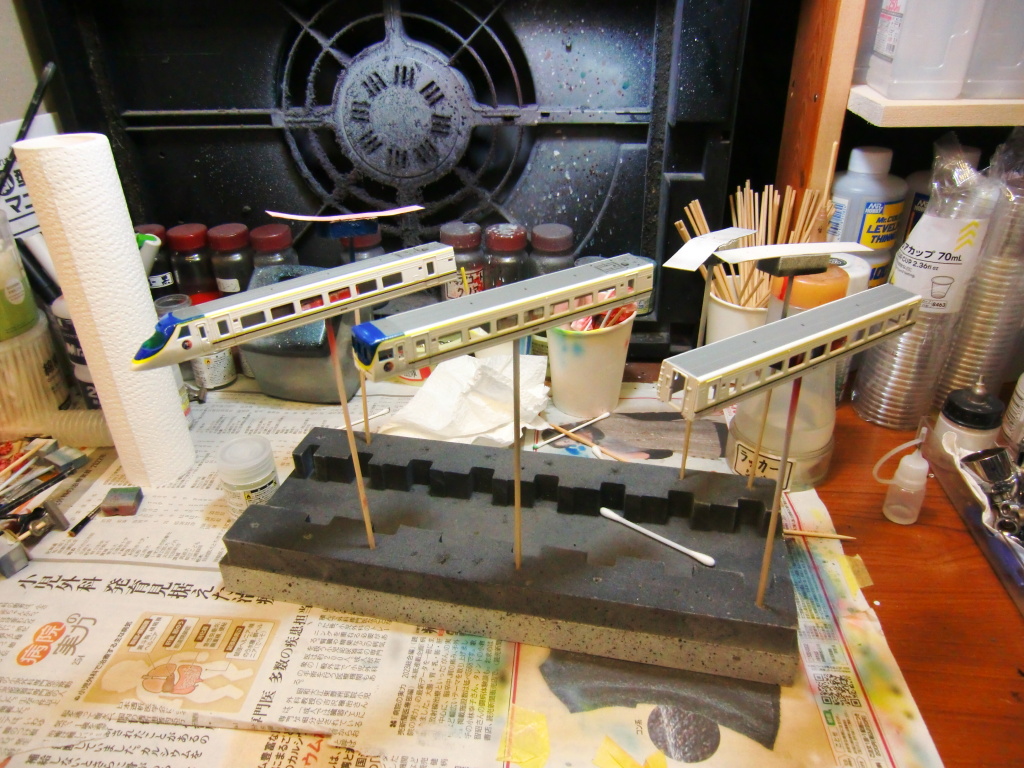
クリアーコート乾燥まで12時間置きます。
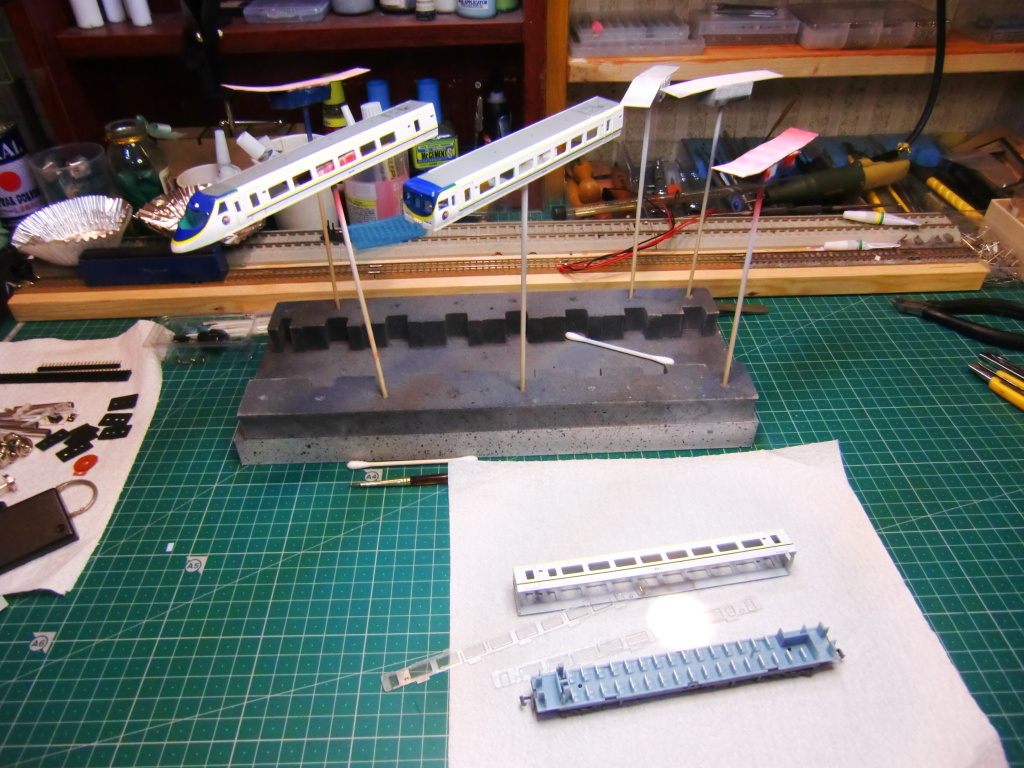
完全に乾燥したところで、ボディーを組み戻して完了となります。
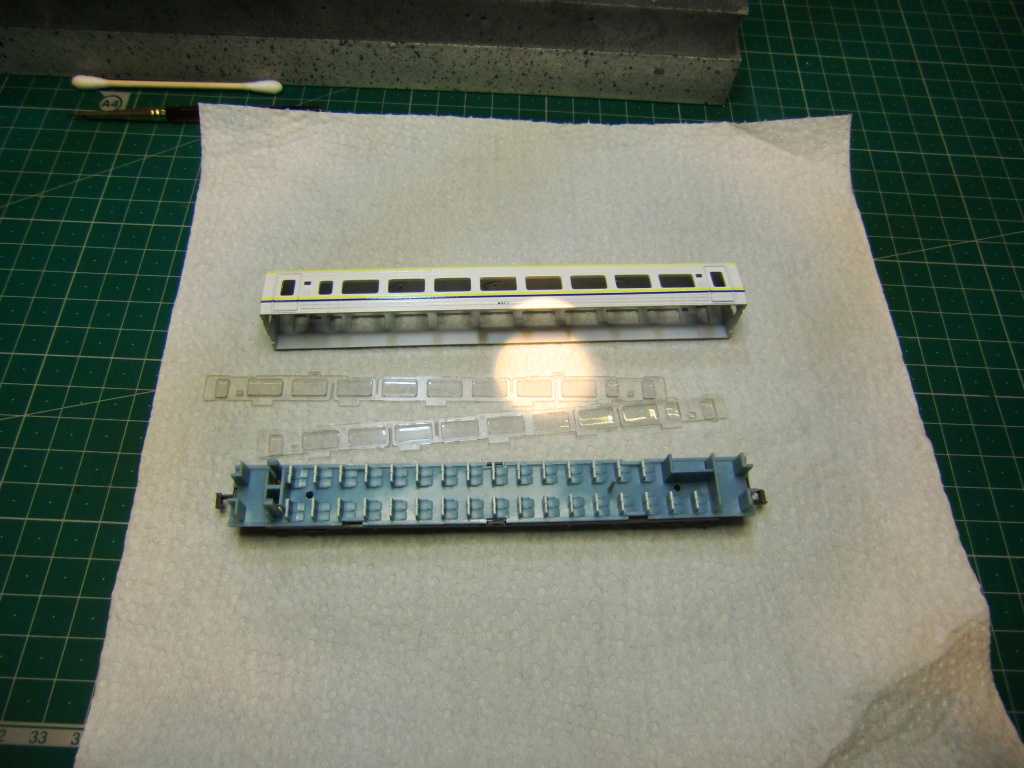
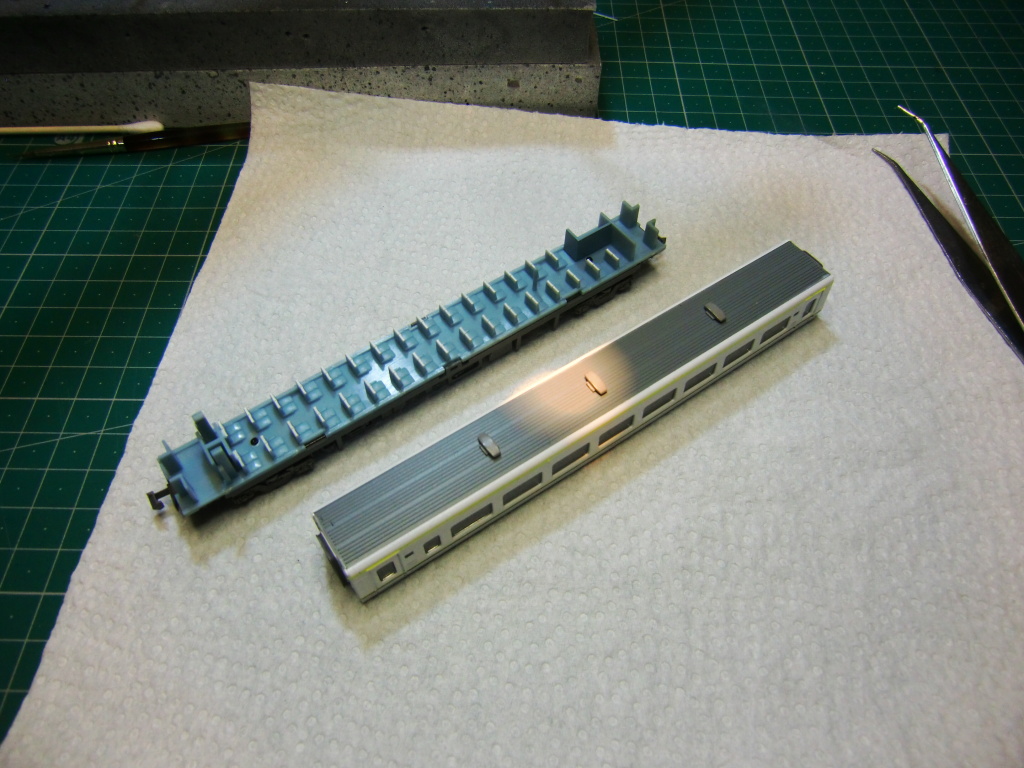
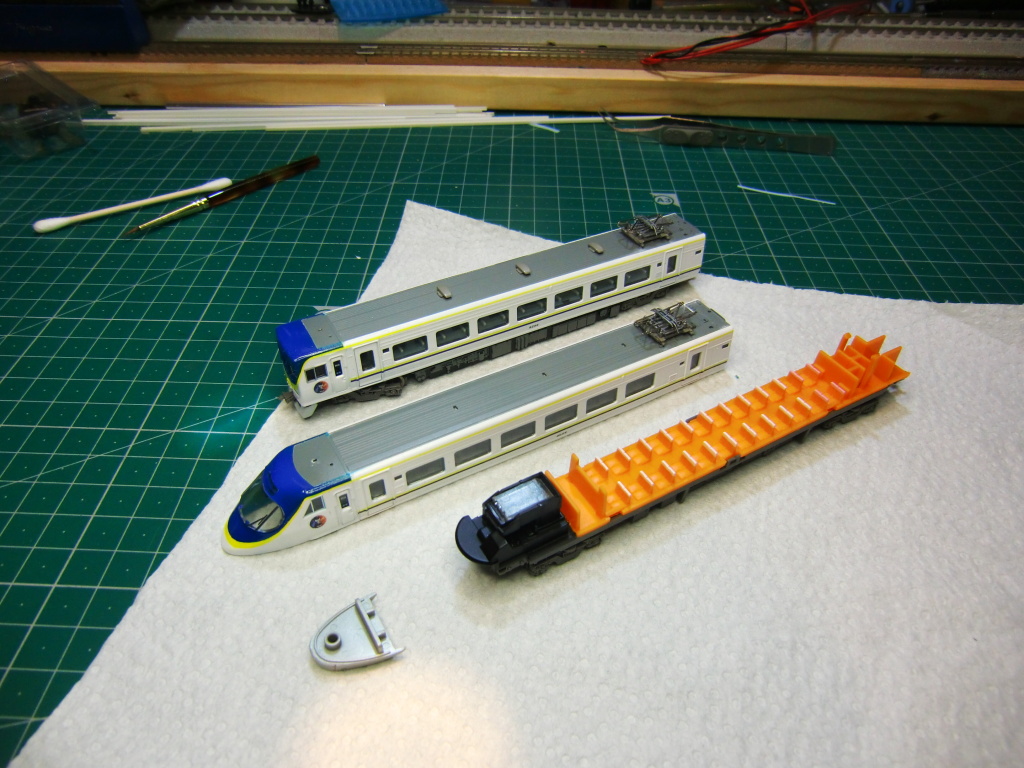








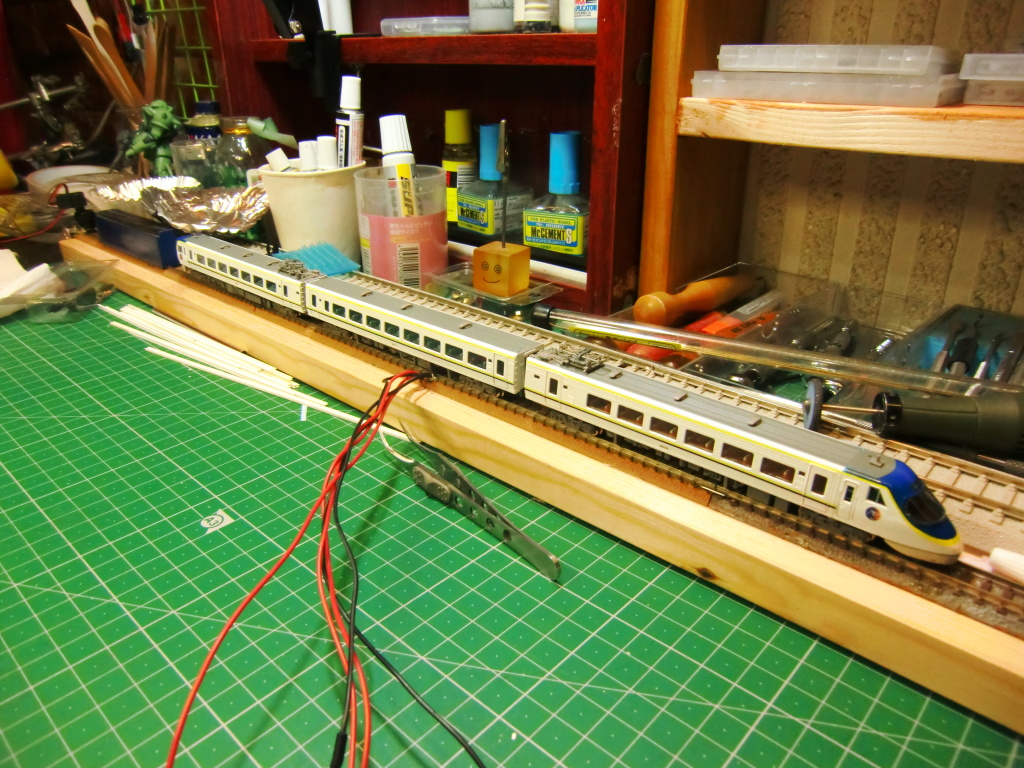
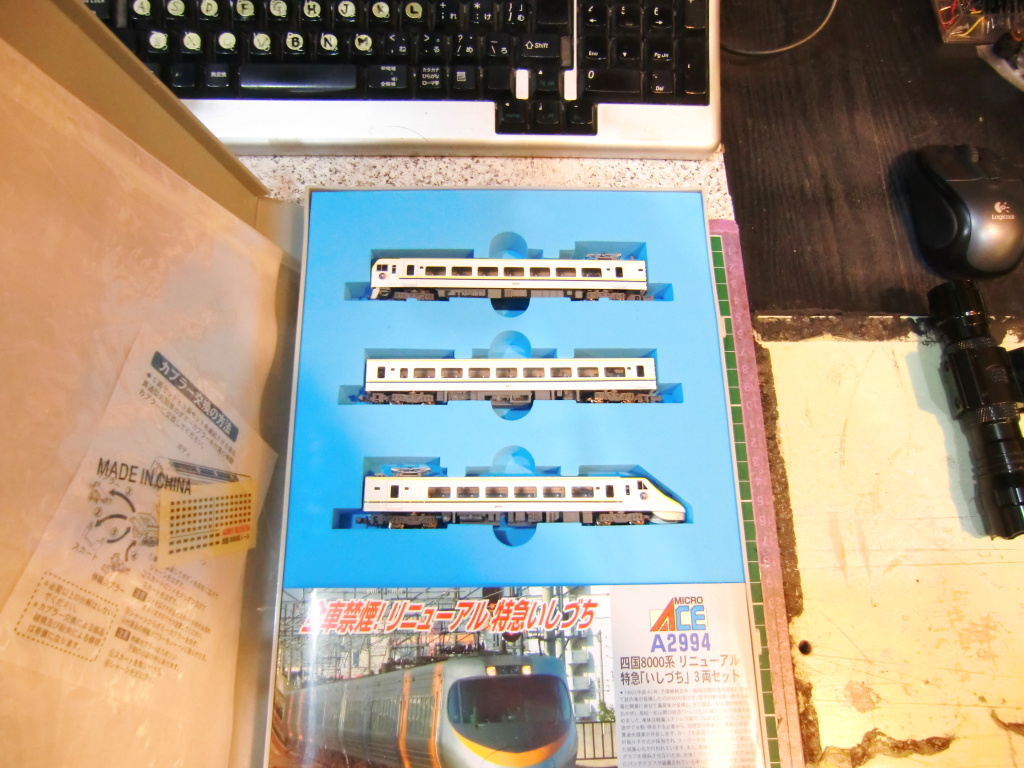
作業完了でございます。


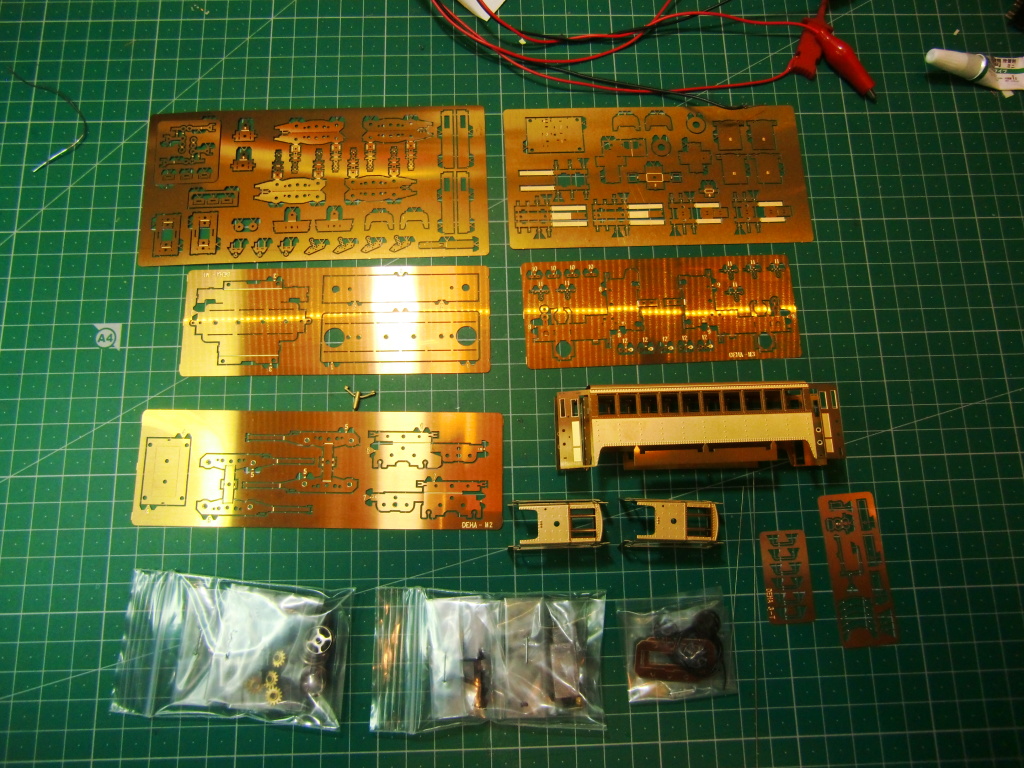
かなりの部品点数です。
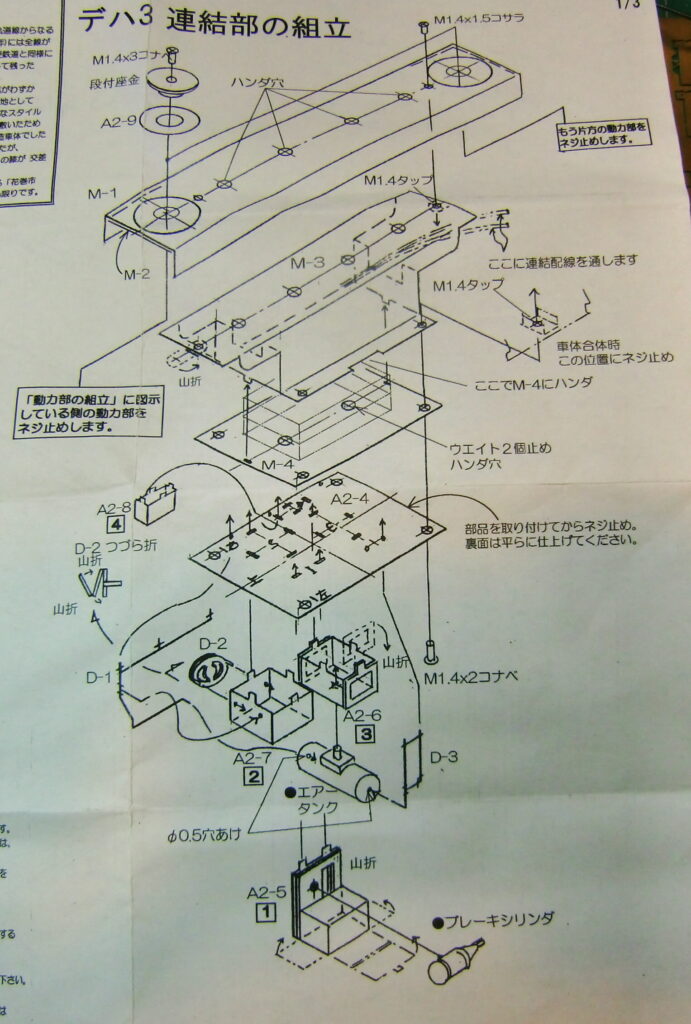
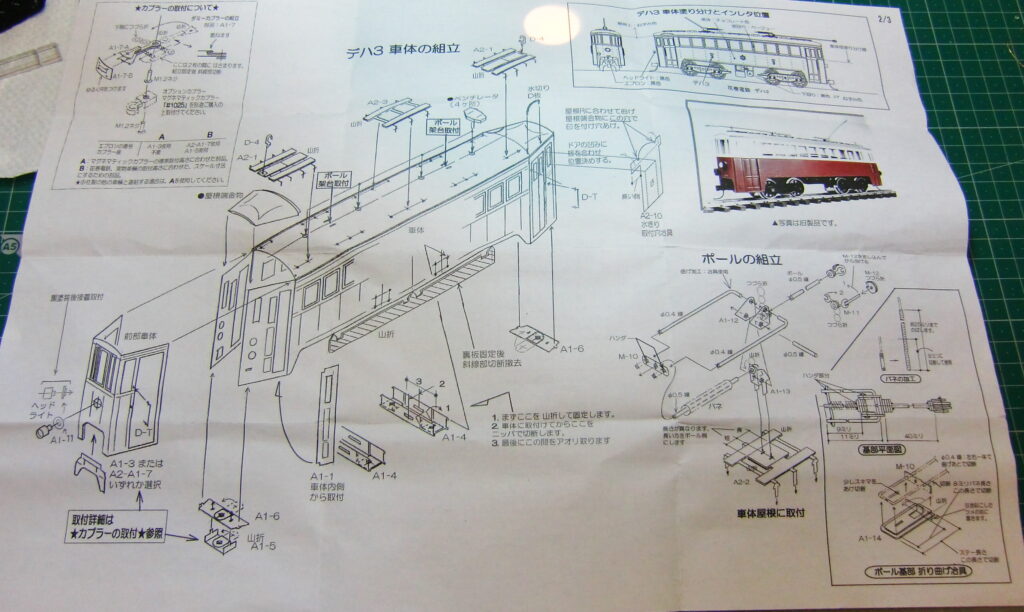
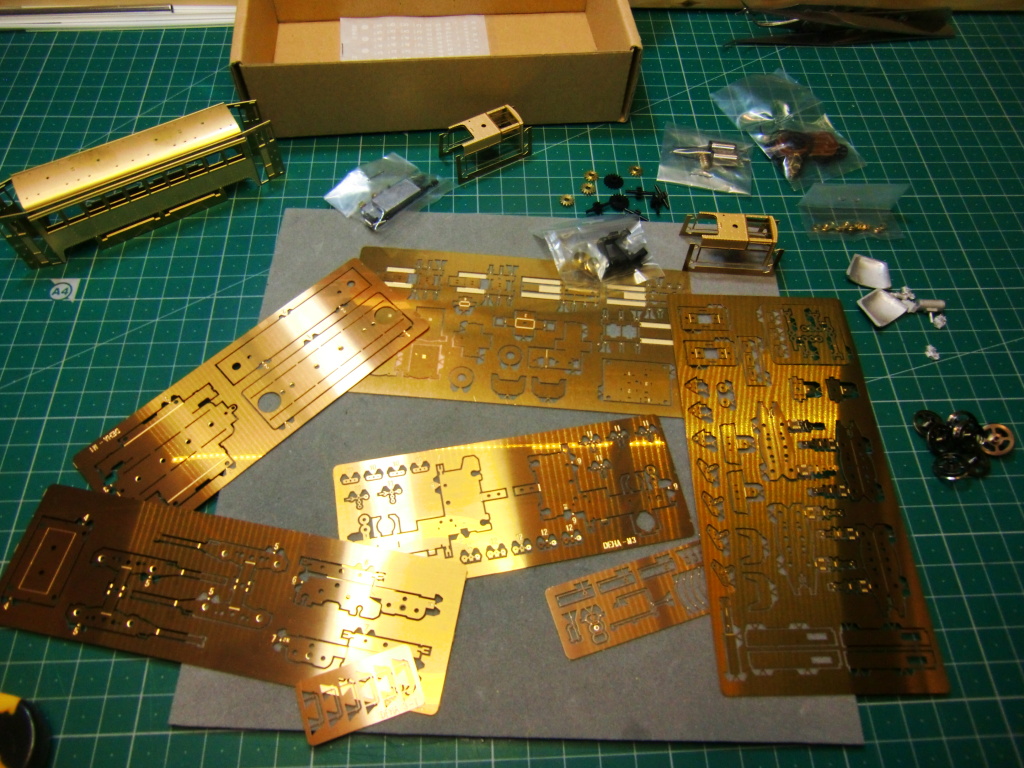
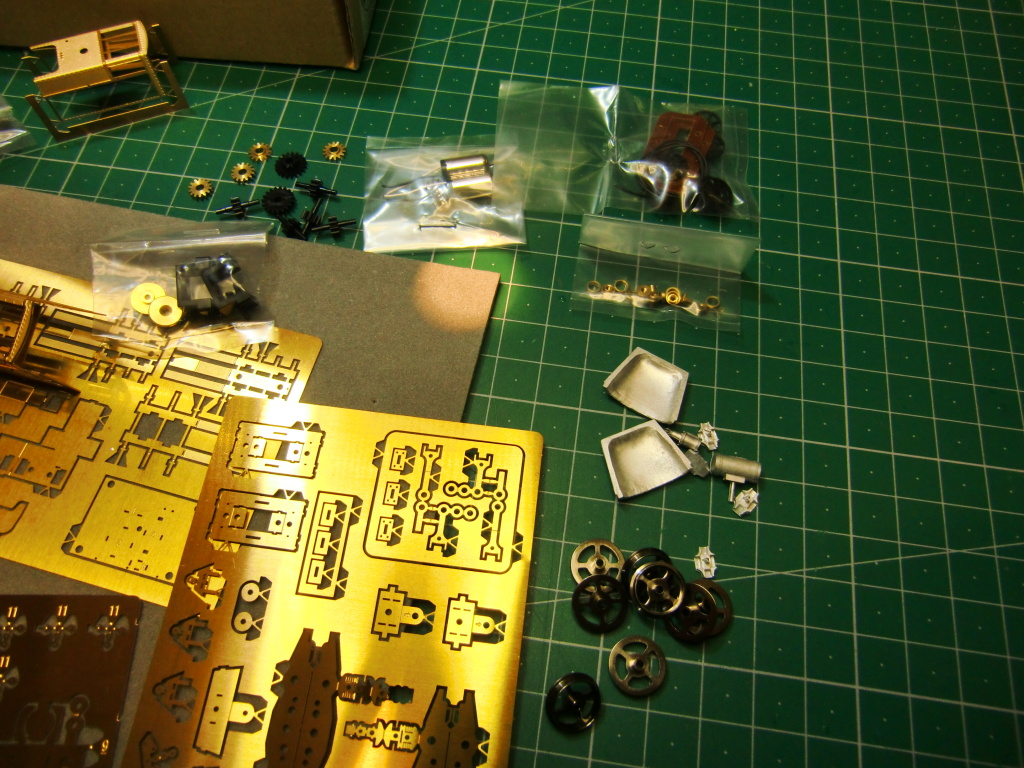

市販のプラモデルキットとは違い、金属キットでは組立工程が大きく異なり時間も大変かかります。事前に説明書をしっかりと理解して組立工程を考えながら進めていかなくてはなりません。
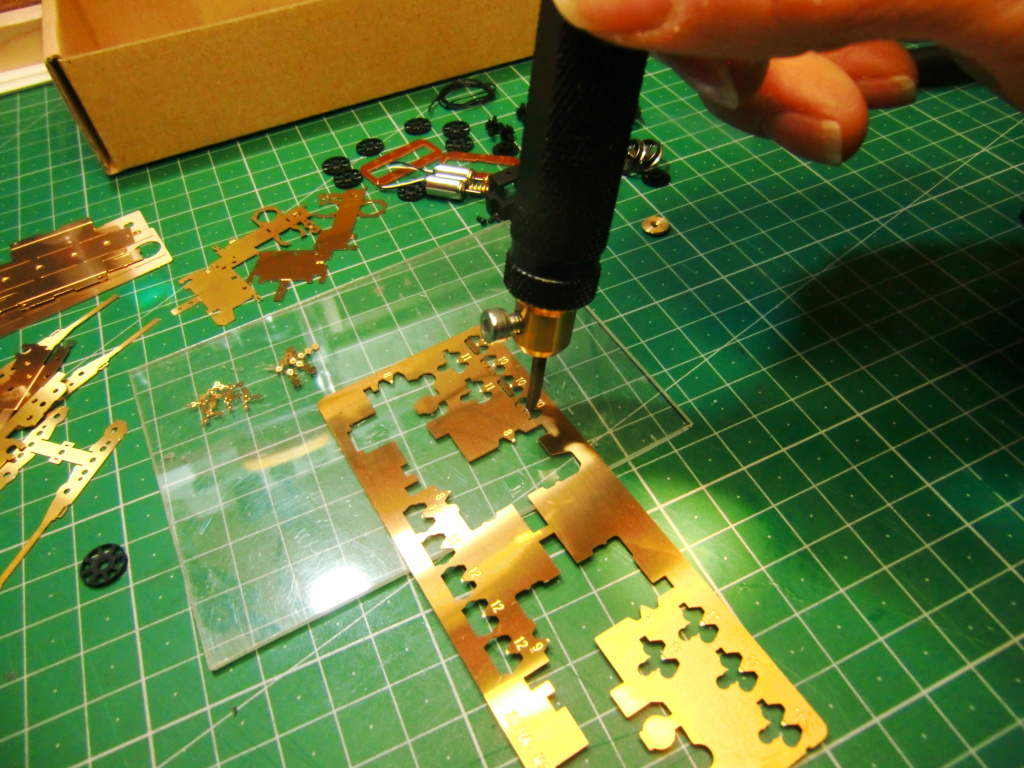
パーツを切り出しにはタガネを使います。


▼動力部の組立
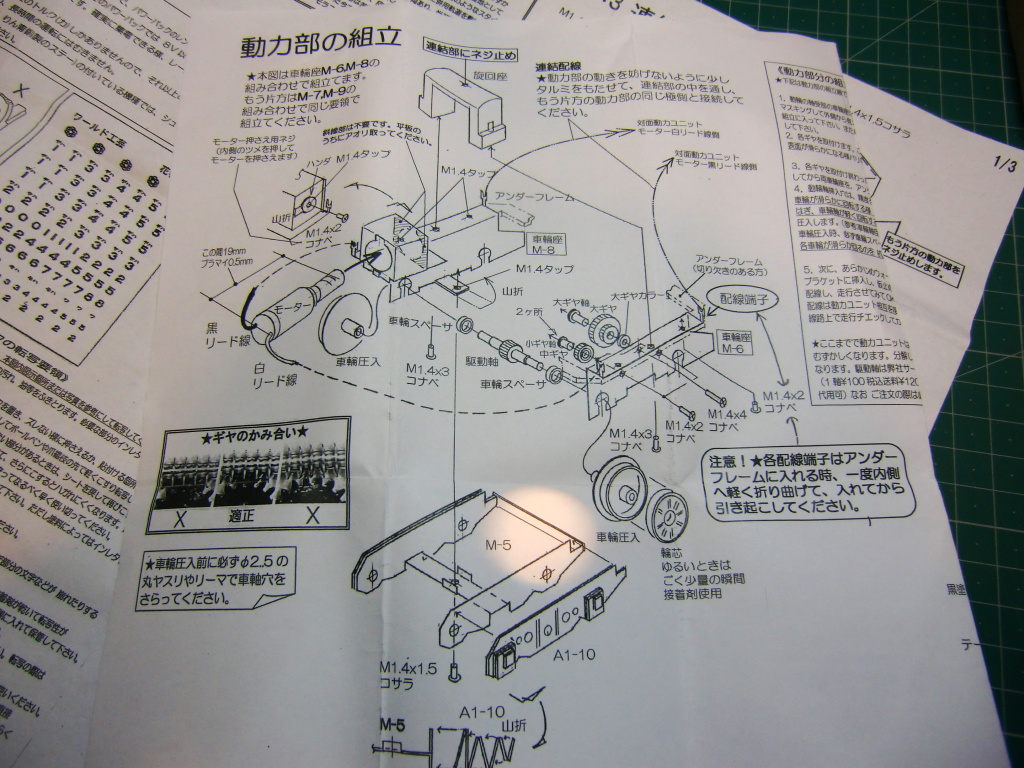


特に頭を悩ませたのがこのパーツです。
試行錯誤しながらようやく形になりましたが、何度も曲げ加工が必要なパーツは、手順などをしっかりと書かなくては混乱のもとになります。その説明がすっぽり抜け落ちている感じですね。


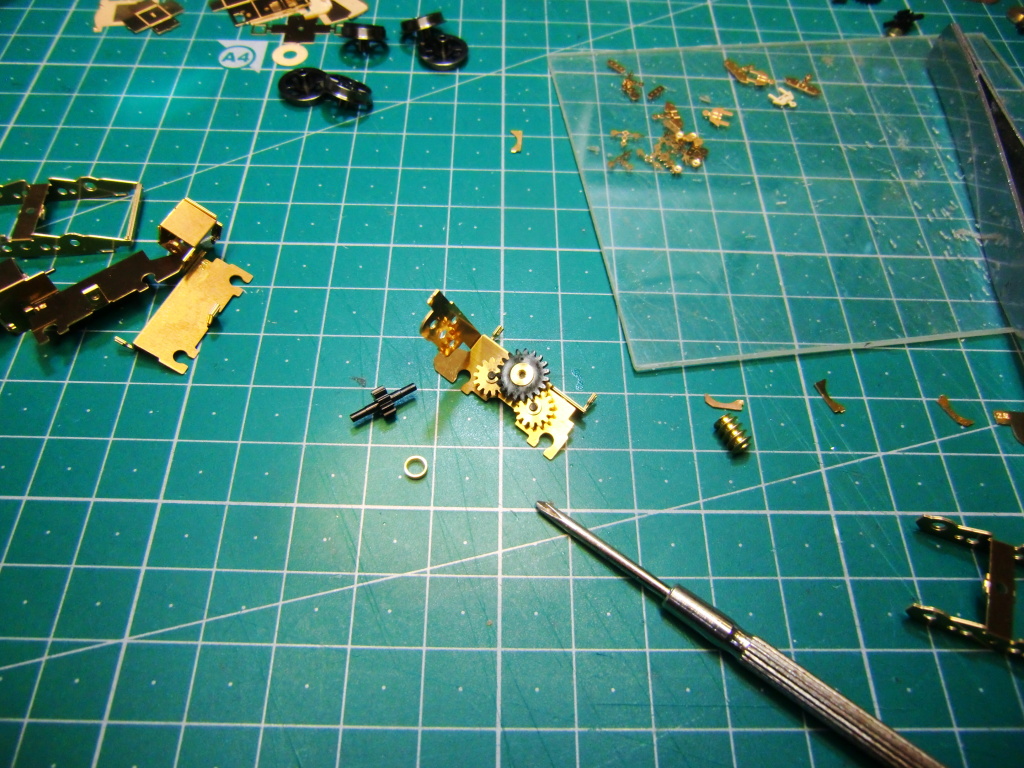
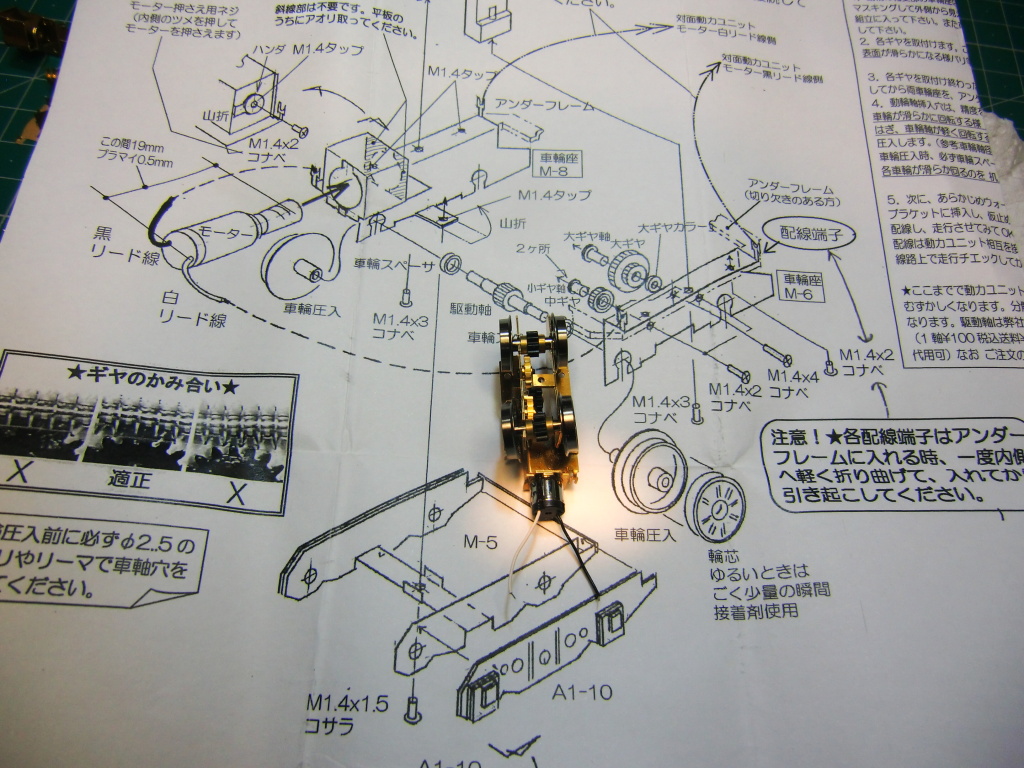
車輪を差し込む内径が狭いようでして、そのままでは入りませんでした。そこで、ルーターで車輪が入るまで内側を削りました。
次に、モーターシャフトにウォームギアをはめ込んでも固定されません。そこで、瞬着を少量流して固定しました。後部のネジは何のため?と疑問が出てきます。
車輪に伝達するギアのかみ合う面積も小さく、かろうじてギアにかみ合っている程度です。この辺は、なぜぞうなっているかわかりません。
組み方が間違っているのかな?と確認したいとこですが、その図がありません。駆動系は大変重要な個所となりまので、ここは説明書に詳細に書くことが望ましいと思われますね。
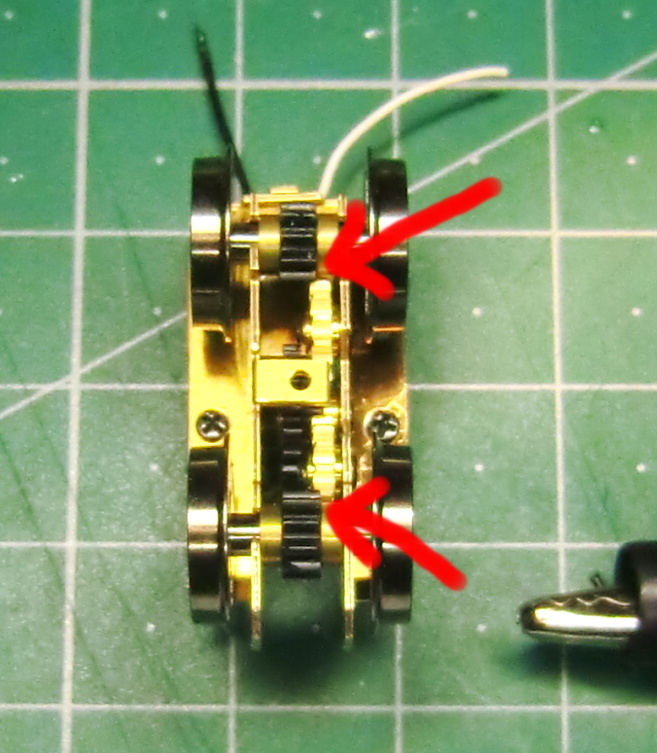
少し時間をかけて作業を進めていくことといたします。
駆動系は後回しにして、それ以外の作業を順次進めていきます。
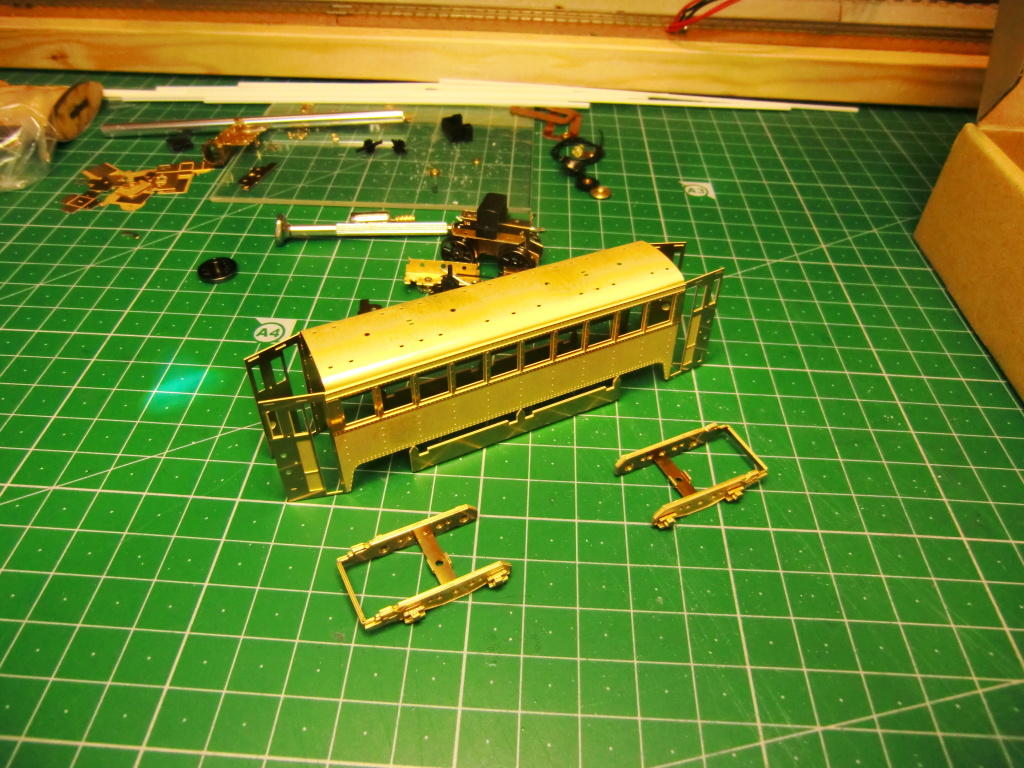


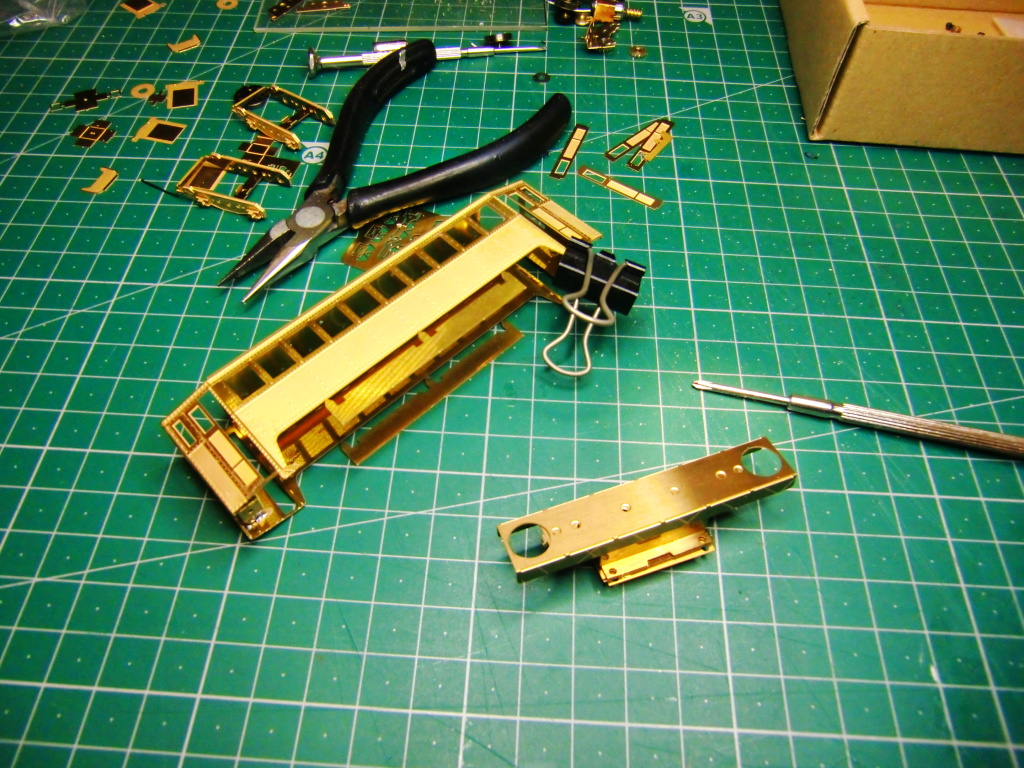

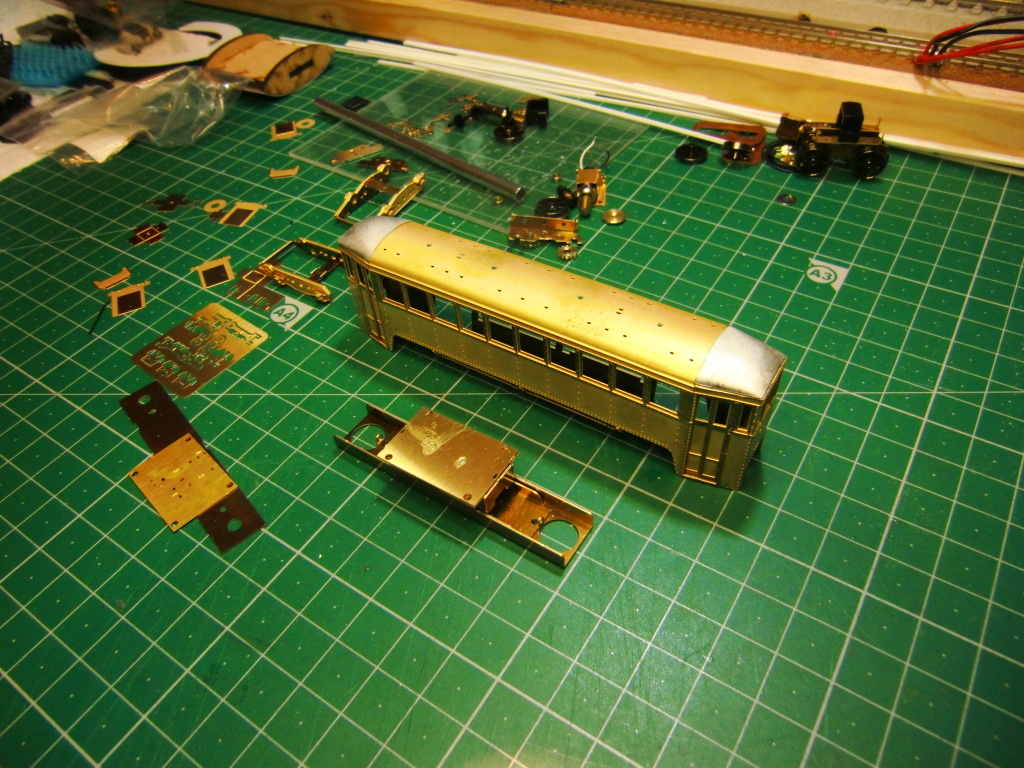
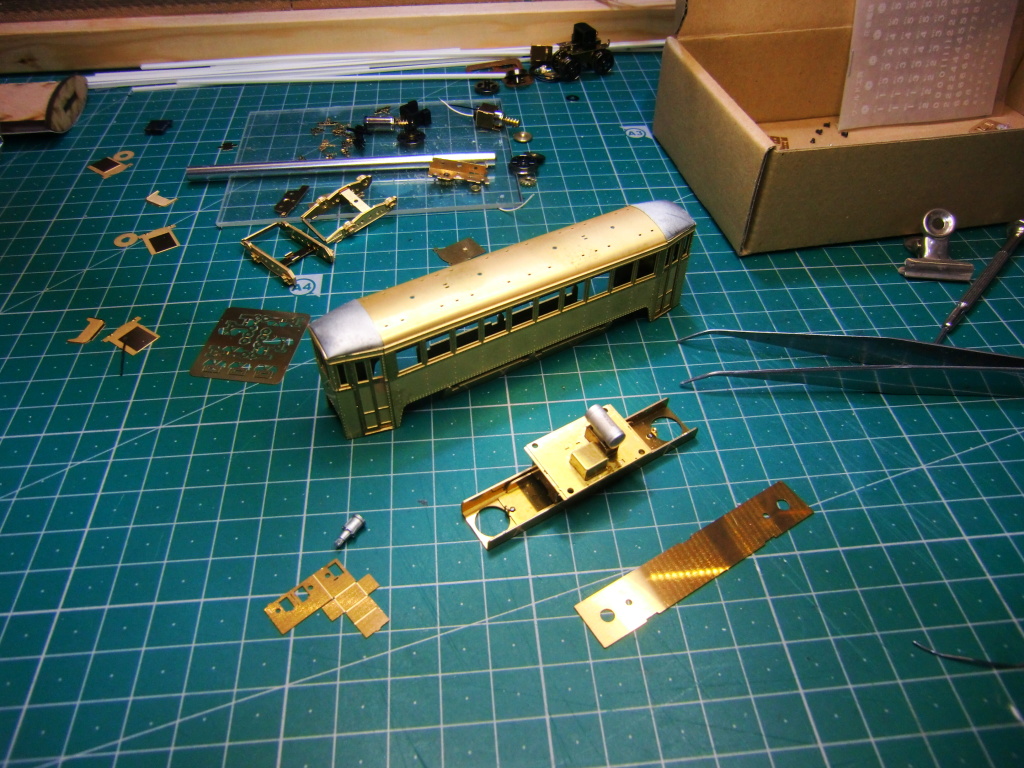
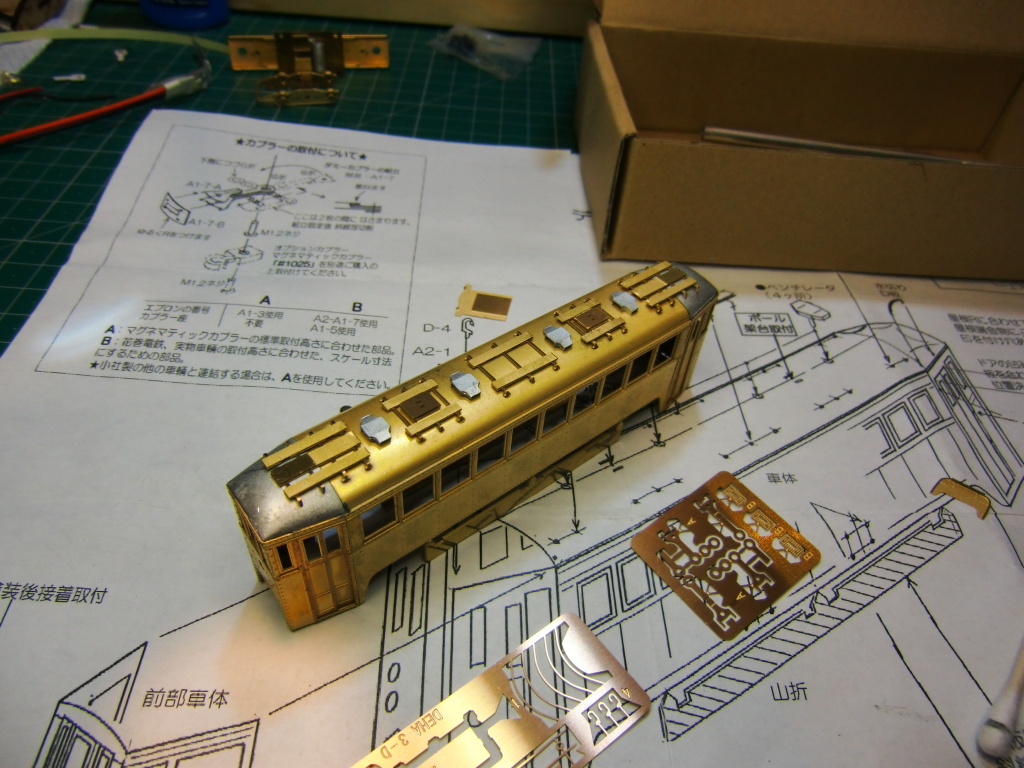
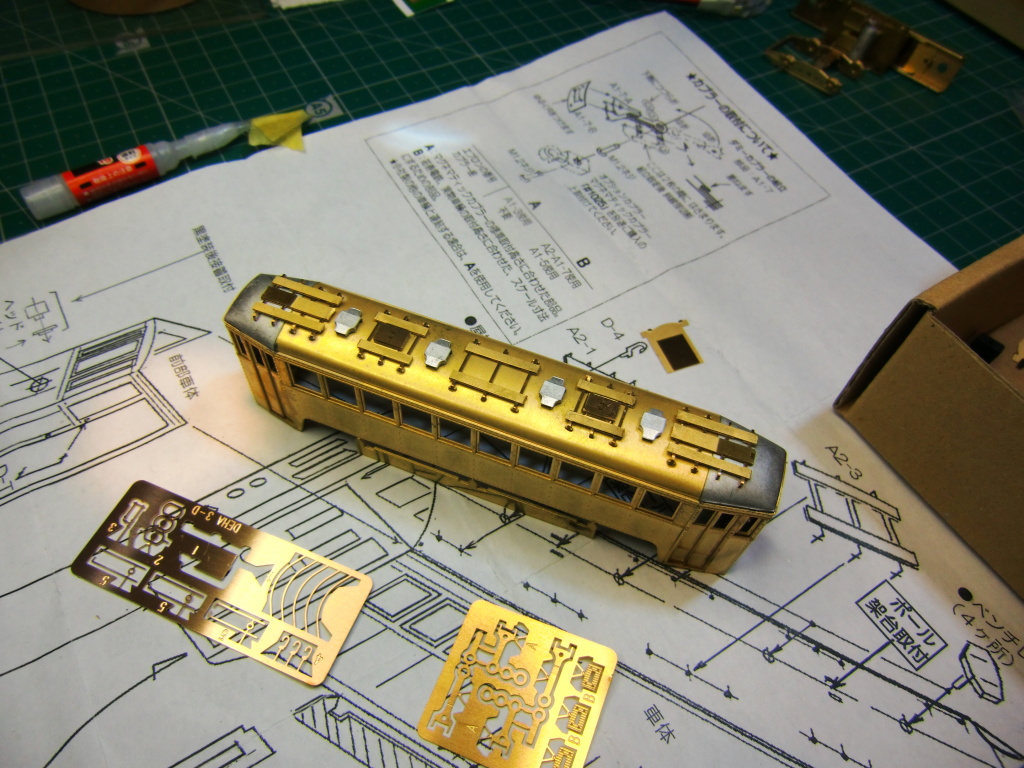
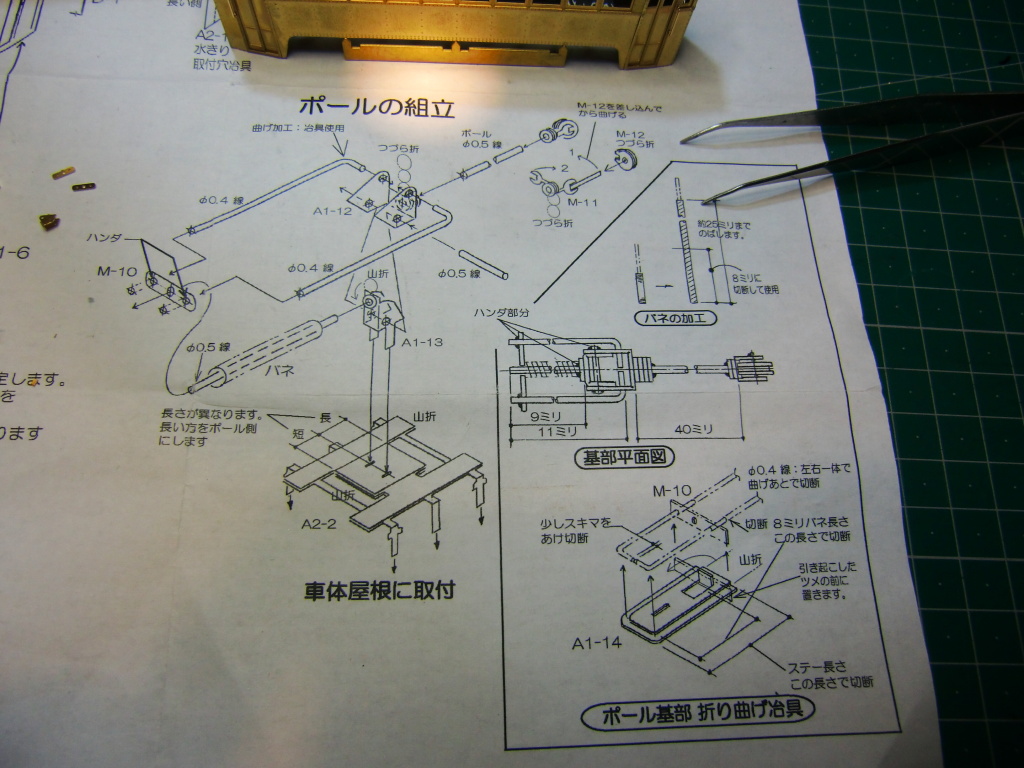

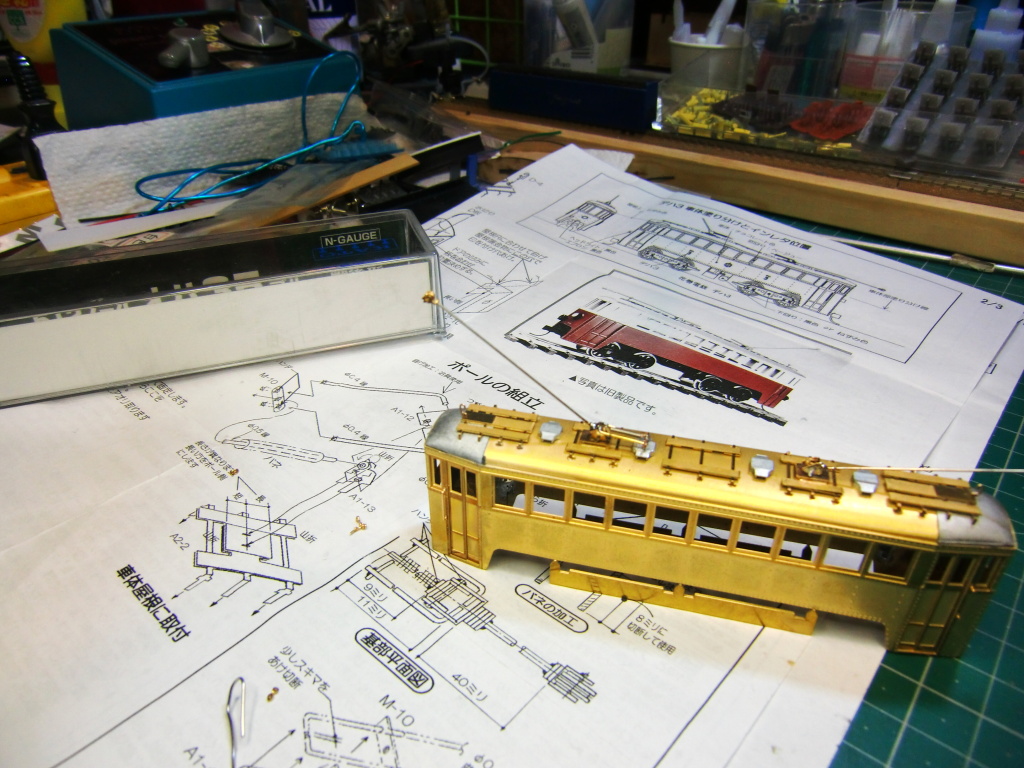

▼塗装工程
ボディーの脱脂を念入りに行ってから金属プライマーを車体に吹き付けます。

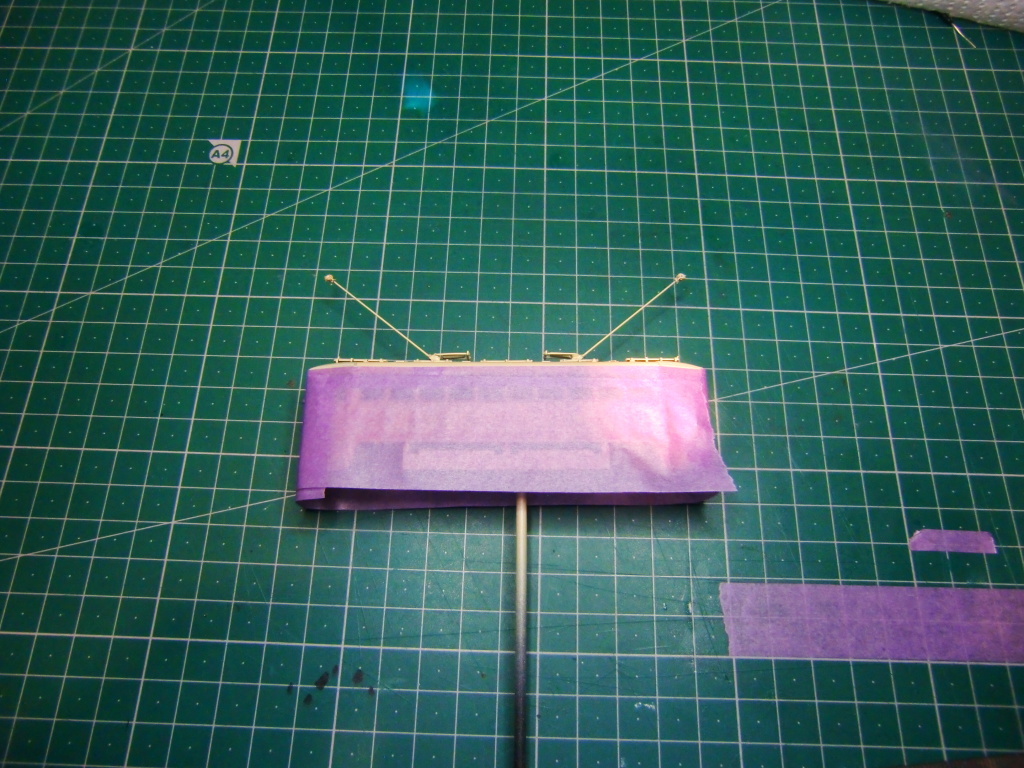
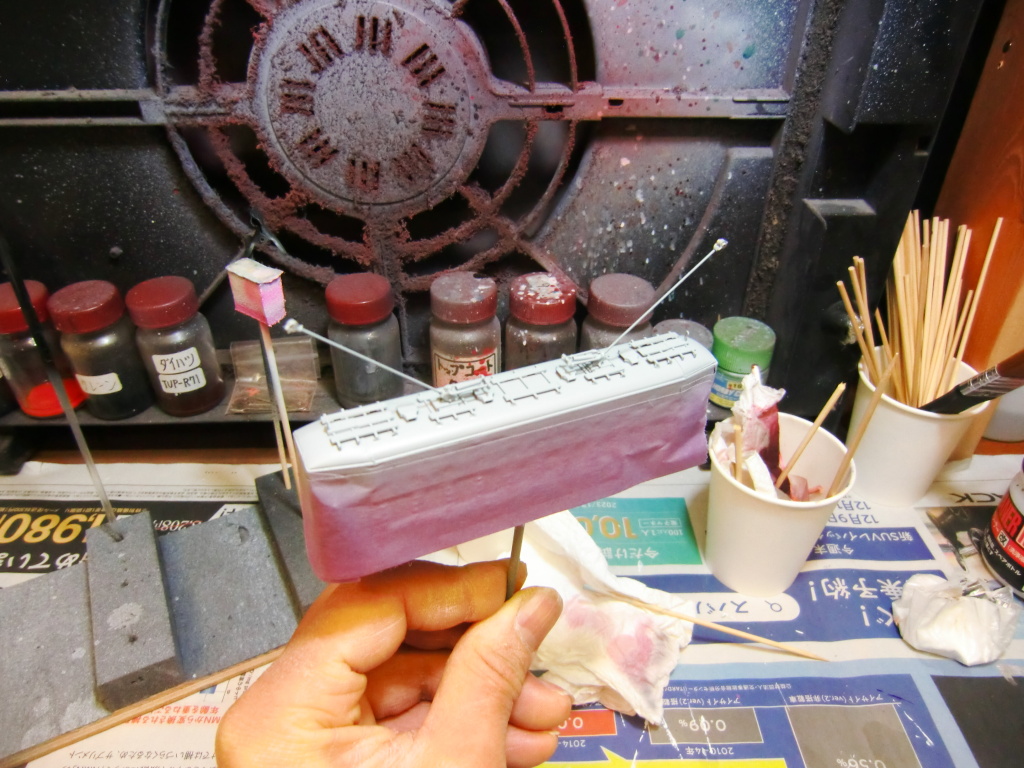

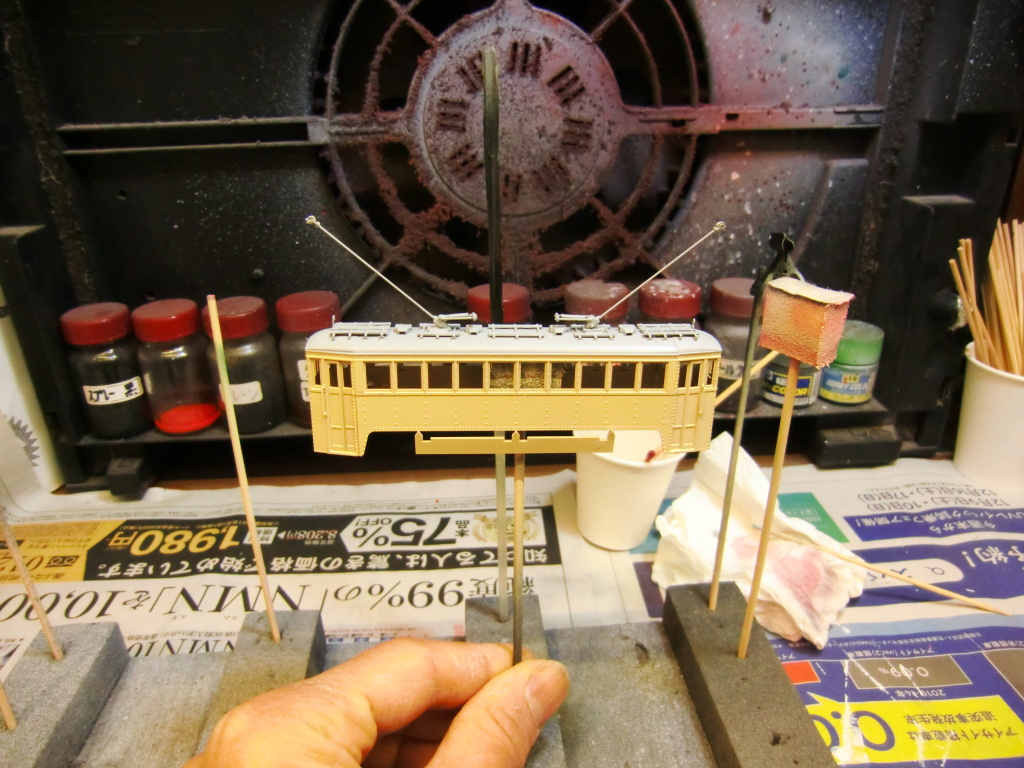
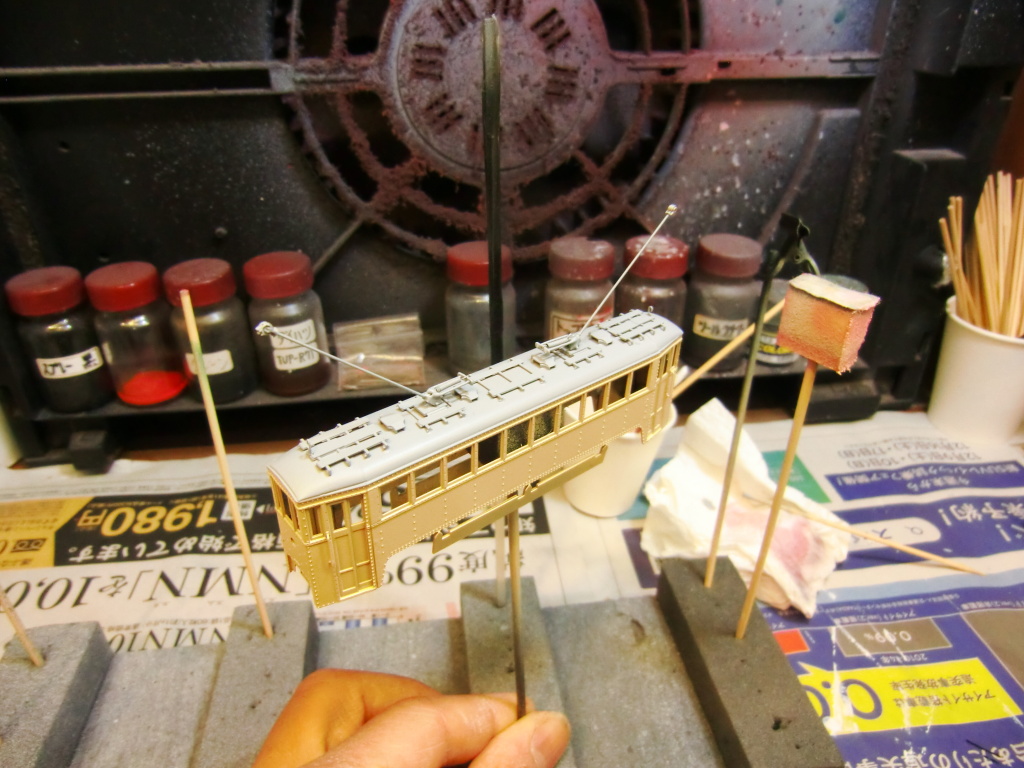
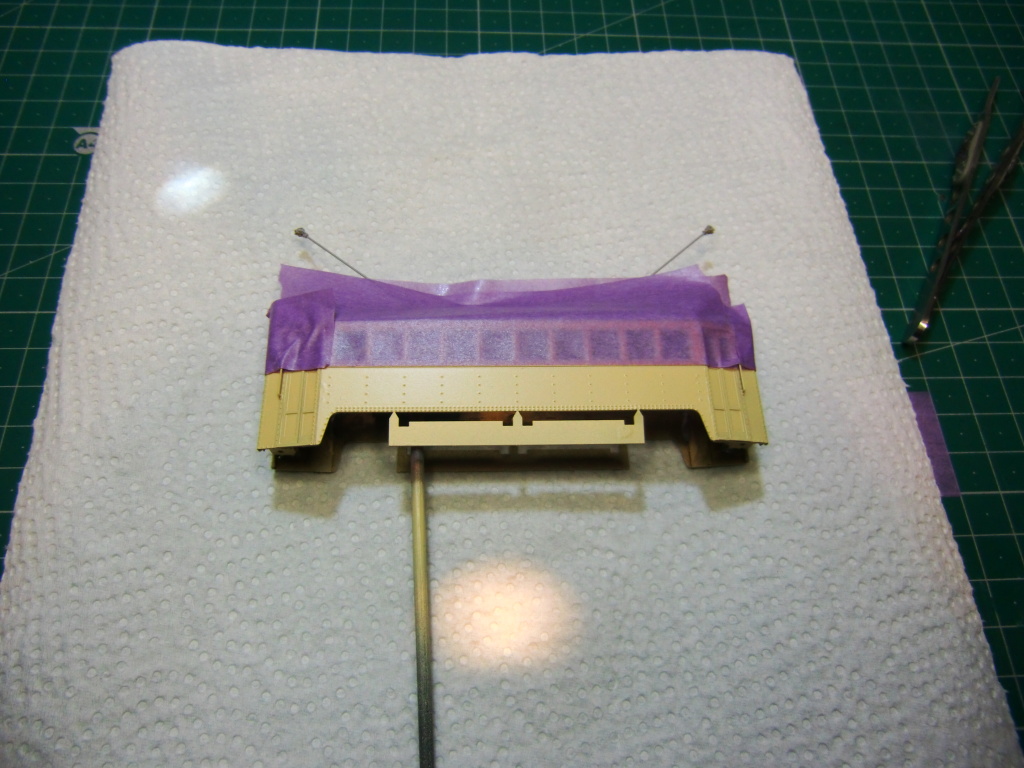



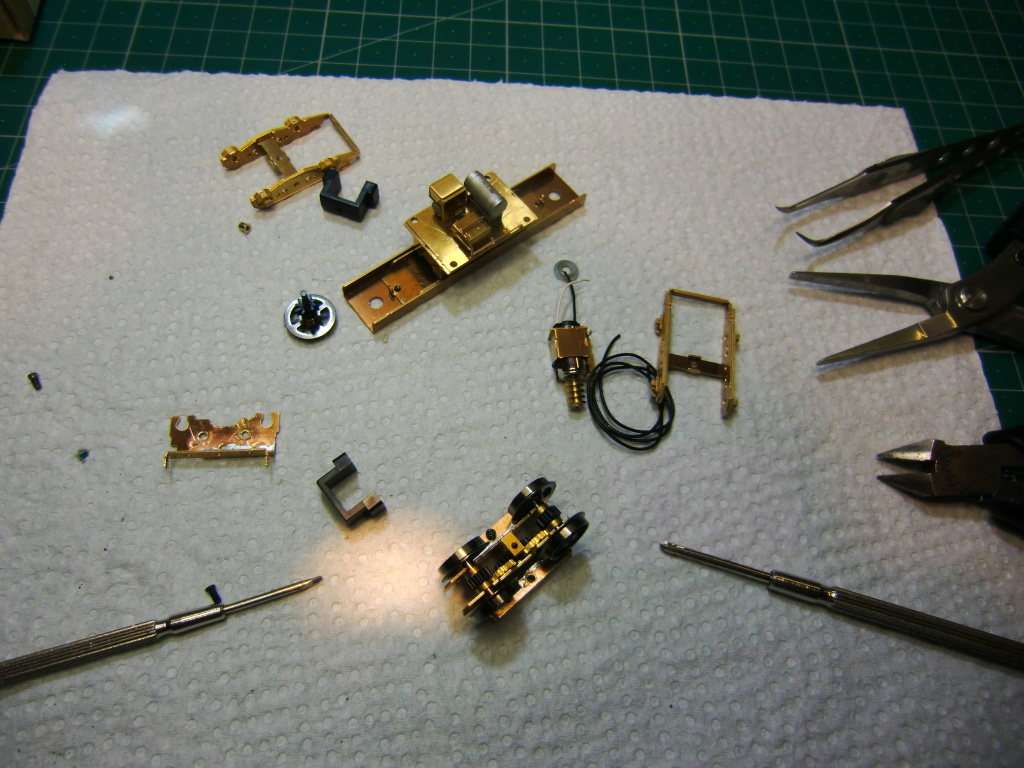

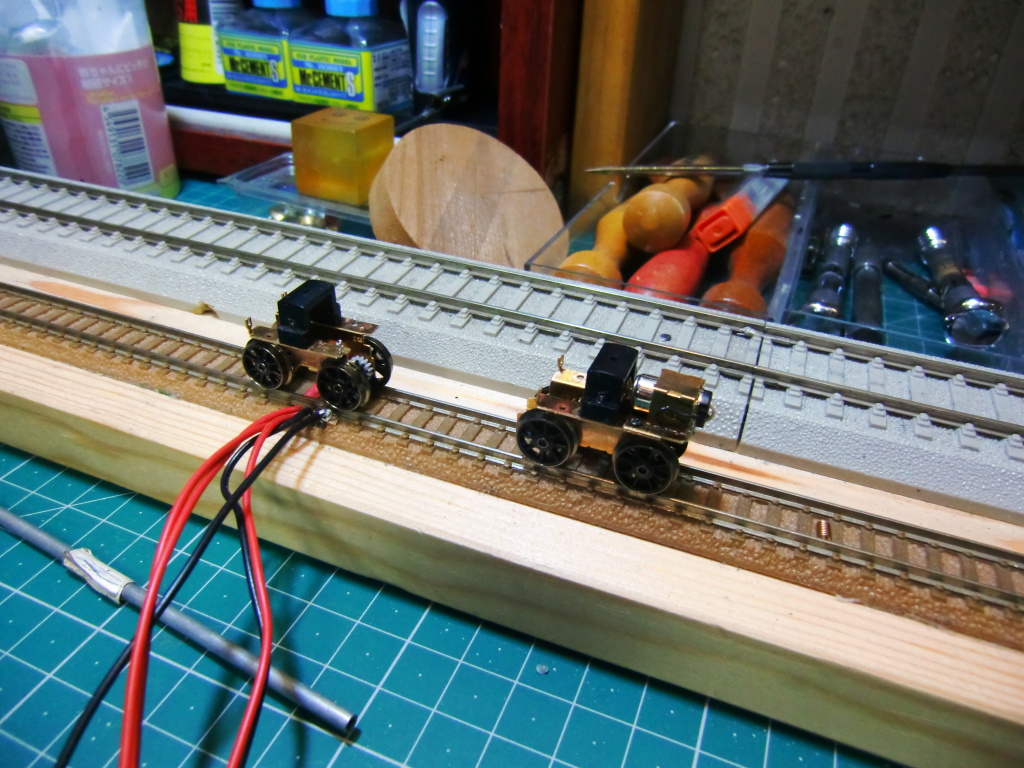
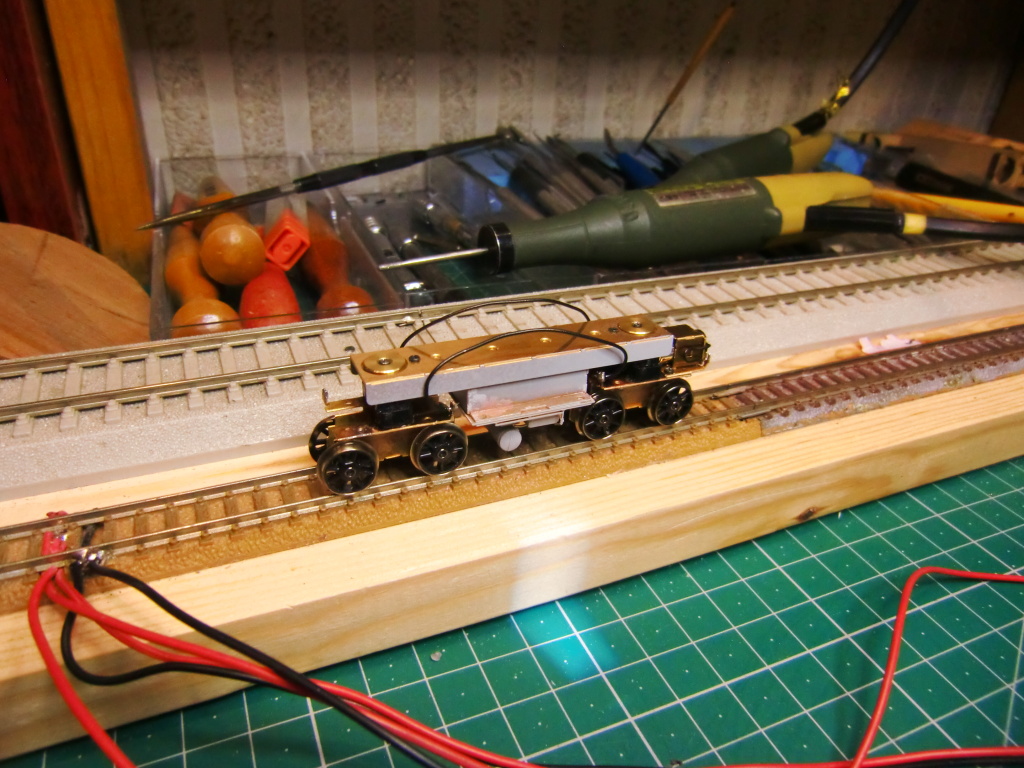
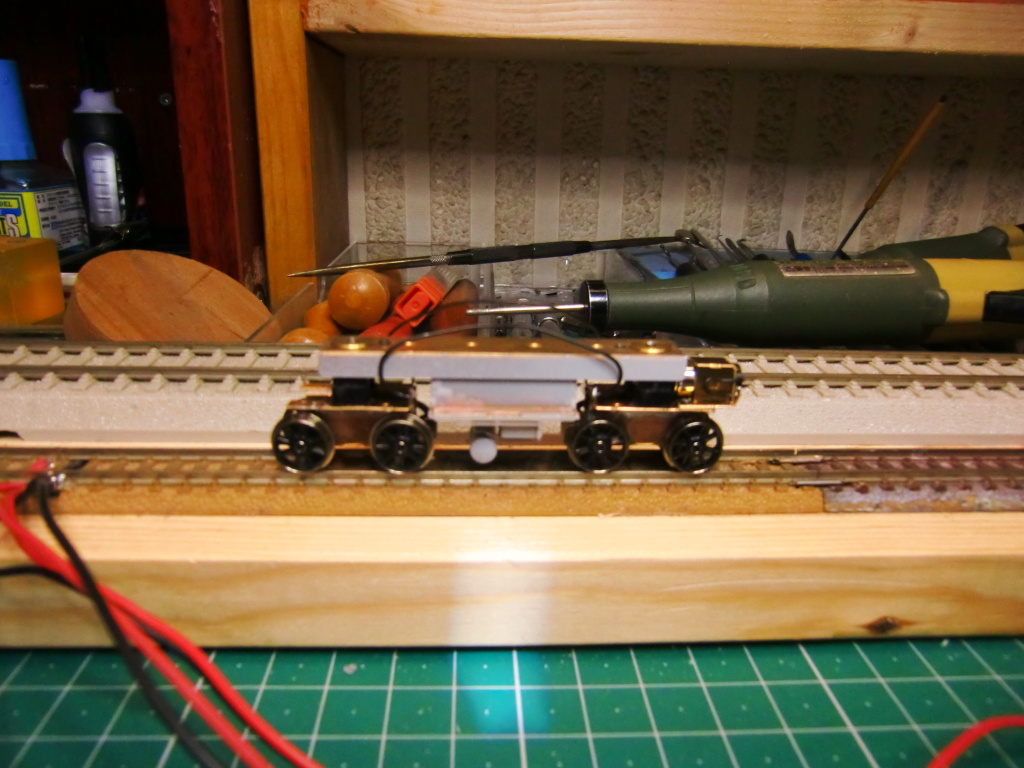

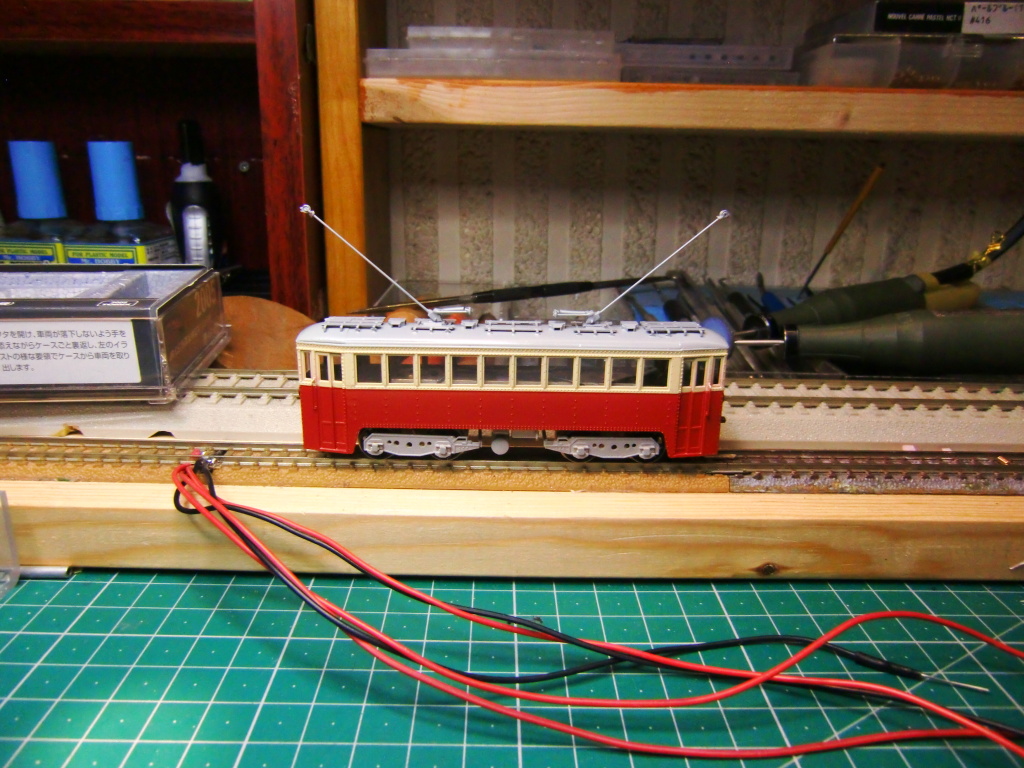
大変難航したキットでございました。まず、このキットの最大の難点は、組立に関する説明図があまりに少ないことです。どのようにしたら目的の形状になるのかな?といった感じでその手順がすっぽり抜けている個所が随所に見られます。やはり組立説明書で見やすいのは、テキスト文章の多さよりも図の多さだと思わらます。
特に苦労したのは駆動系です。そのまま組んでみましたが動きません。その後、何か組立にミスがあったのではと思い、幾度となく分解と組み立てを繰り返しましたが、やはりスムーズに回りません。そこでじっくり検証してみると、問題となっている個所が随所に見えてきました。ここですべて書くと長くなるので省略します。
そこで、問題となっているパーツに加工を施してから、組立と調整を何度か繰り返しながら、どうにか回るようになりました。絶妙なセッティングができないと回りません。特に駆動系は重要な個所でもありますので、誰でも容易に作れる設計が求められると思われます。また素材の特性上、補強部分が足りていないところが見られます。
なにかと苦労しましたが、どうにか作業は完了です。
前回の「さくら号」制作に続き、次は「あかぎ号」の制作となります。
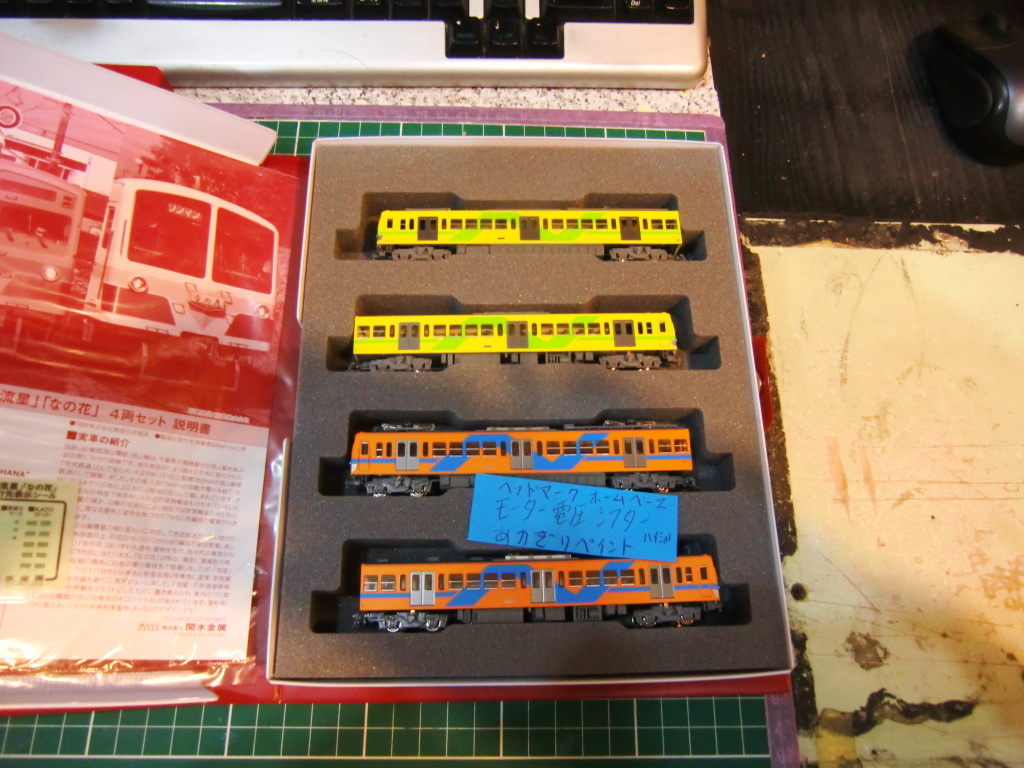

それでは分解していきます。

ボディー側の部品はすべて外します。

分解が終わったところで、M車に電圧シフト加工を施します。最近のモーターは性能が良く、LEDが点灯する前に動き出してしまいます。そこで、モーターが動き出すタイミングを後ろにシフトすることで、LEDが点灯が点灯する前に動き出すことのないようにできます。特にあとから電球色LEDまたは、白色LEDに交換した際にこの現象が多く発生します。
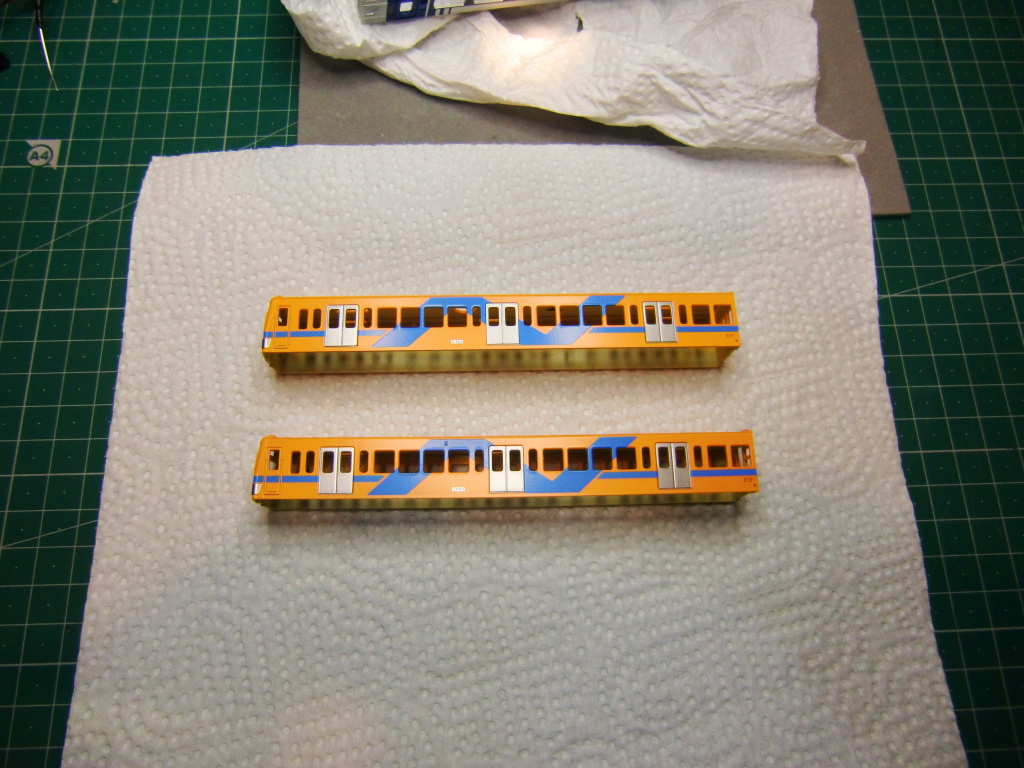
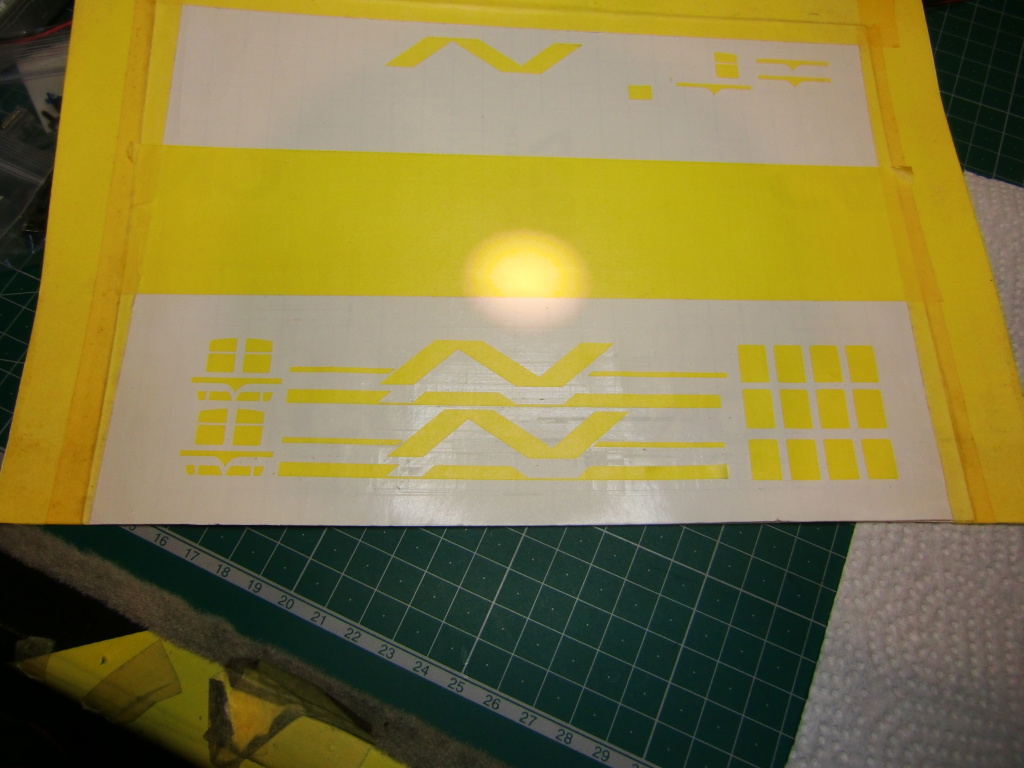



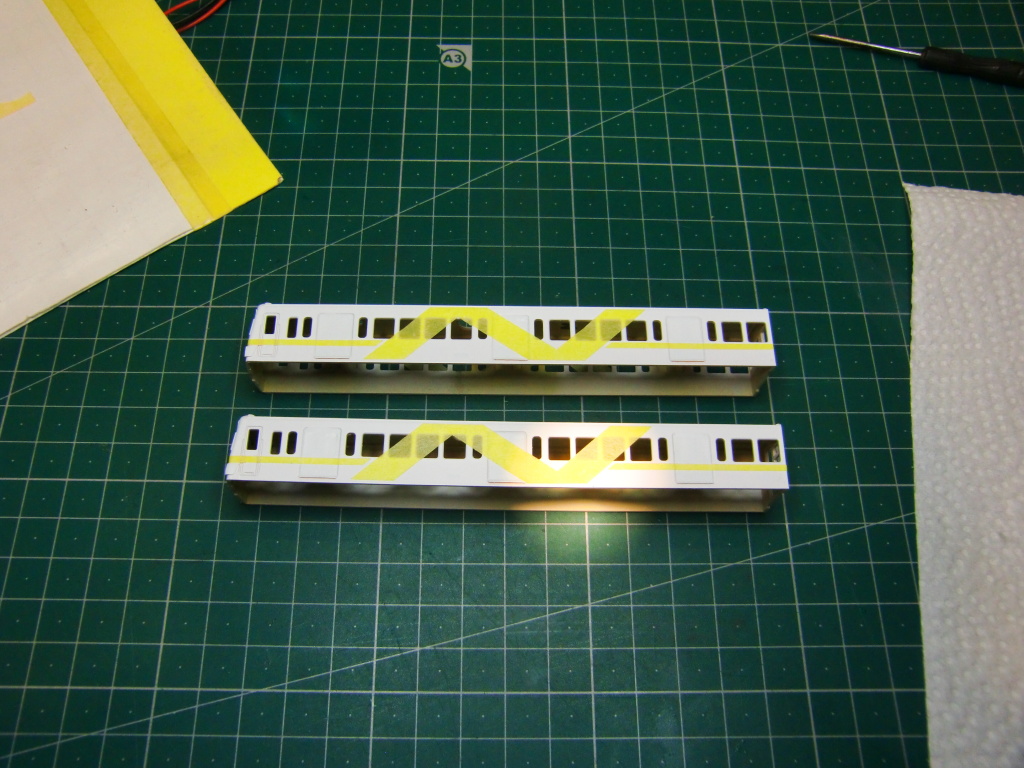
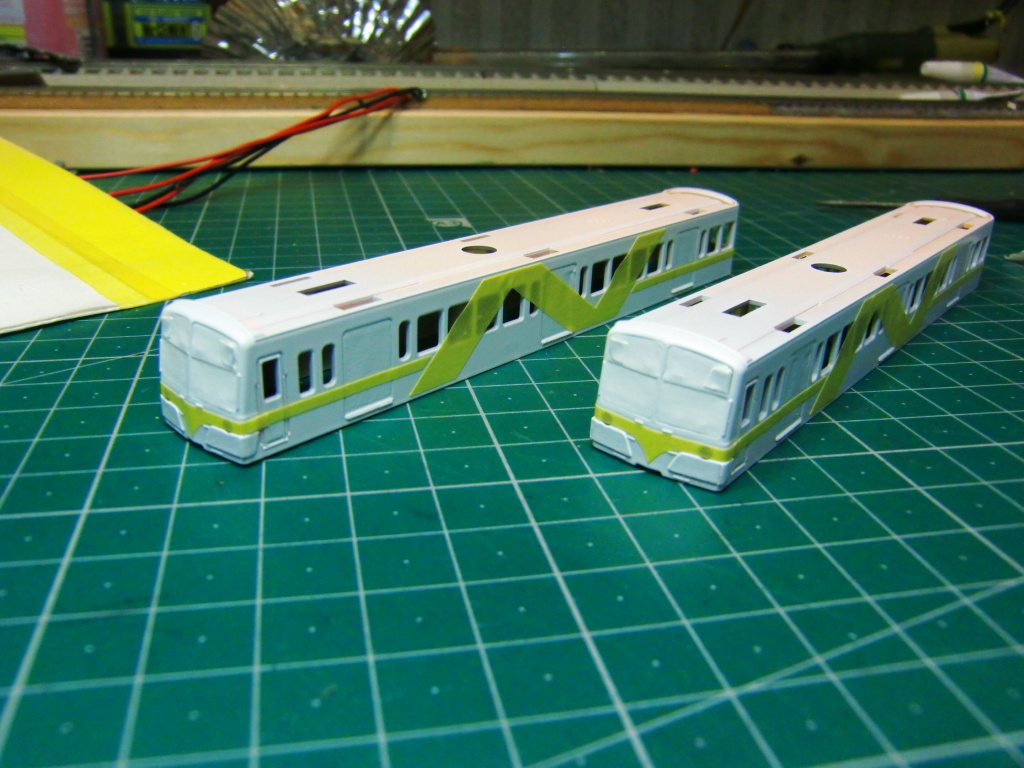



まもなく完成。
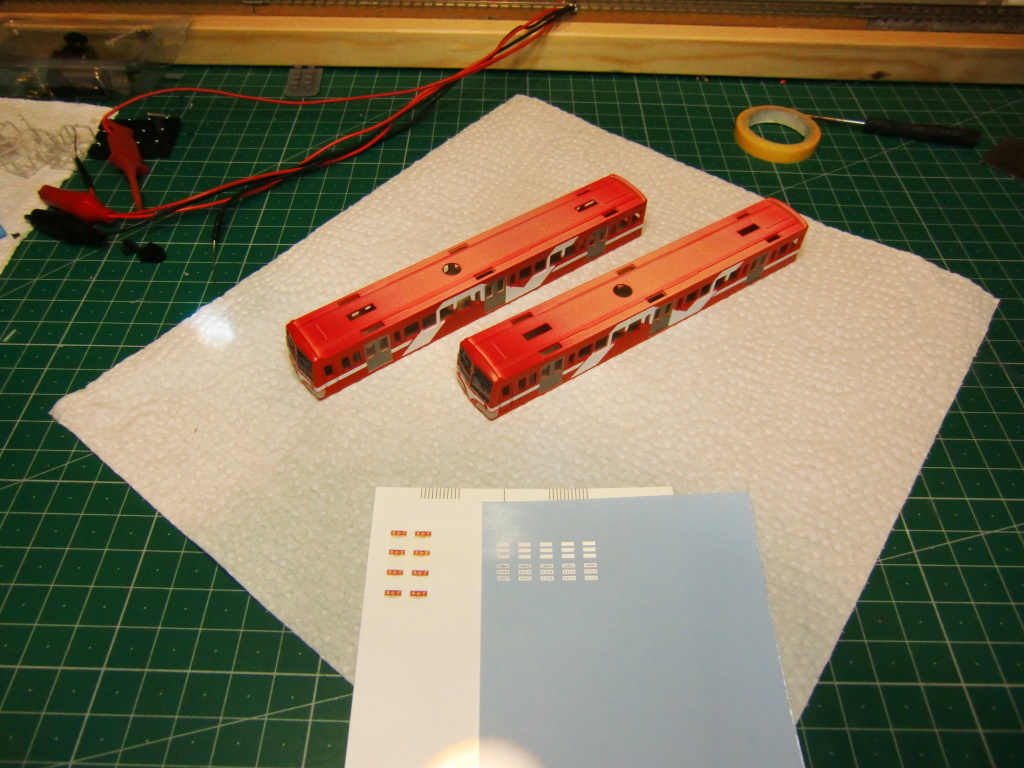

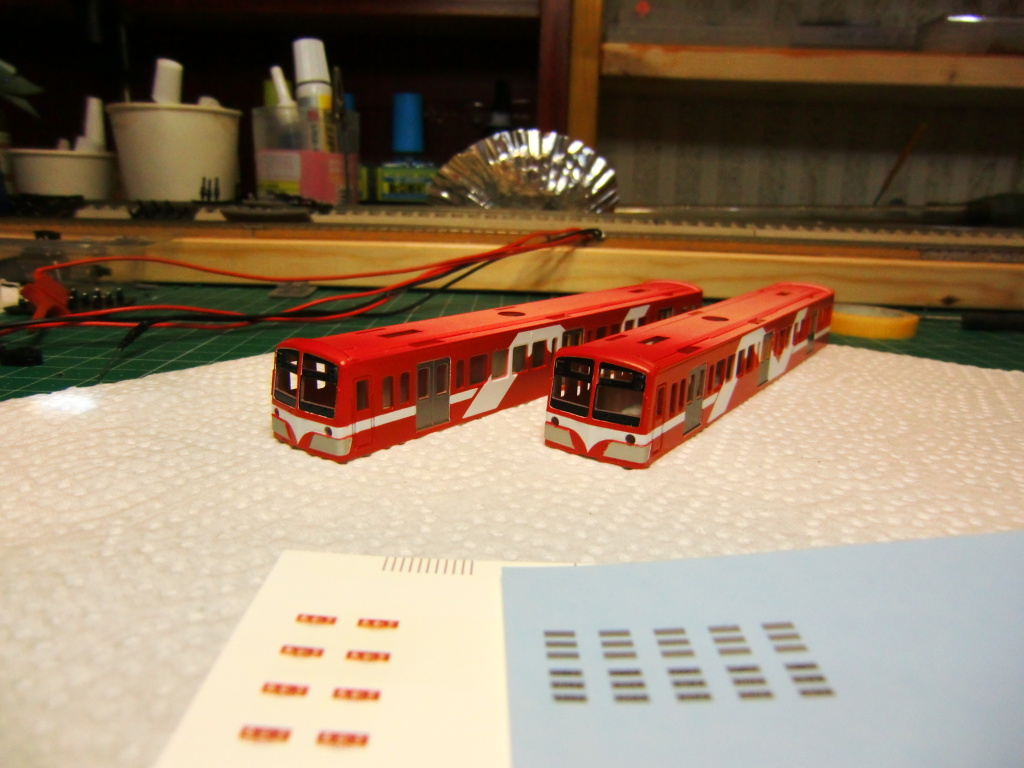
最後に車番とヘッドマークを取り付けて、車体全体をクリアコートして完成となります。


UVクリアーコートを終えて、12時間ほど自然乾燥させて完了となります。
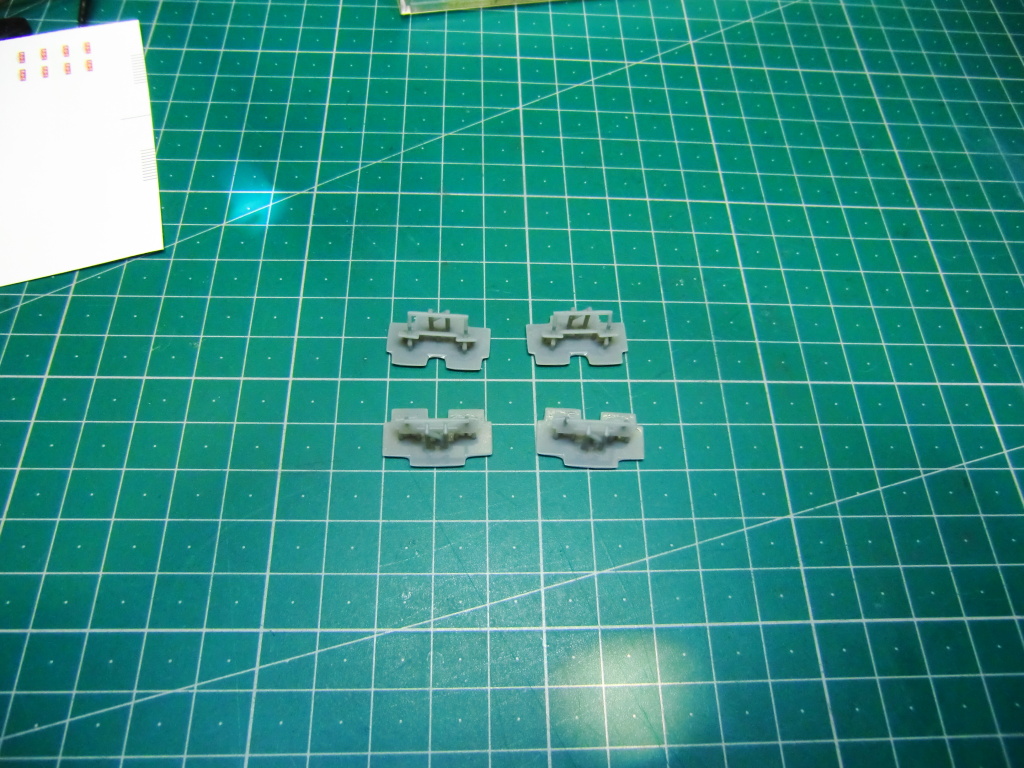
排障装置の取り付け
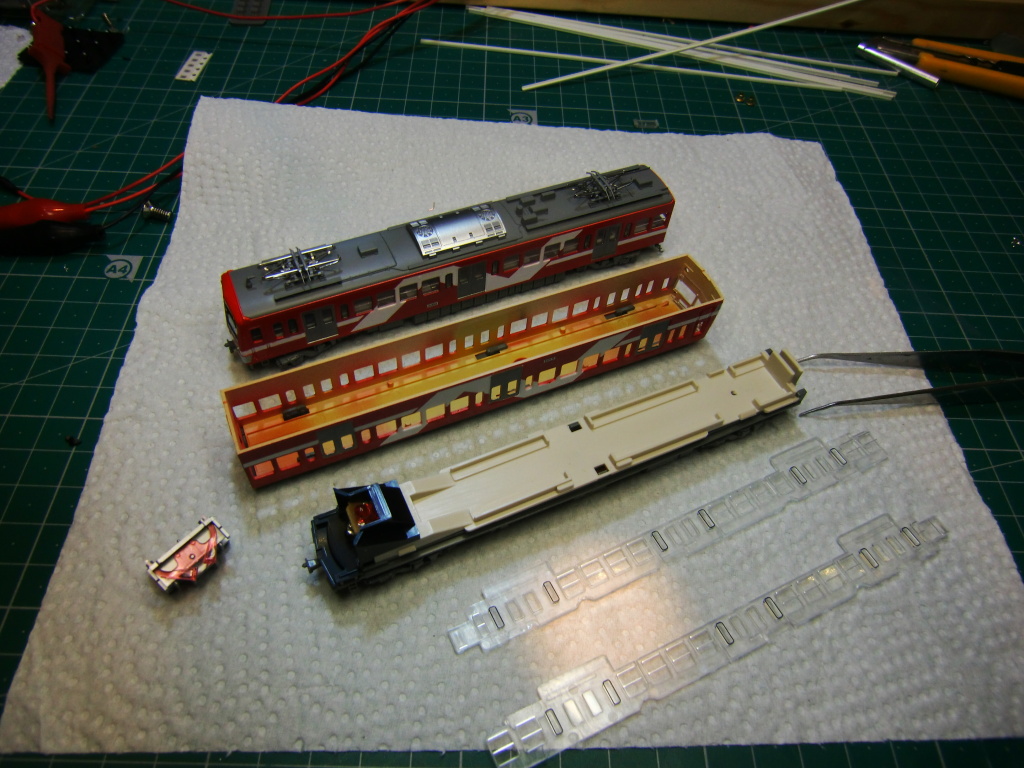
車両を組み戻して完成となります。
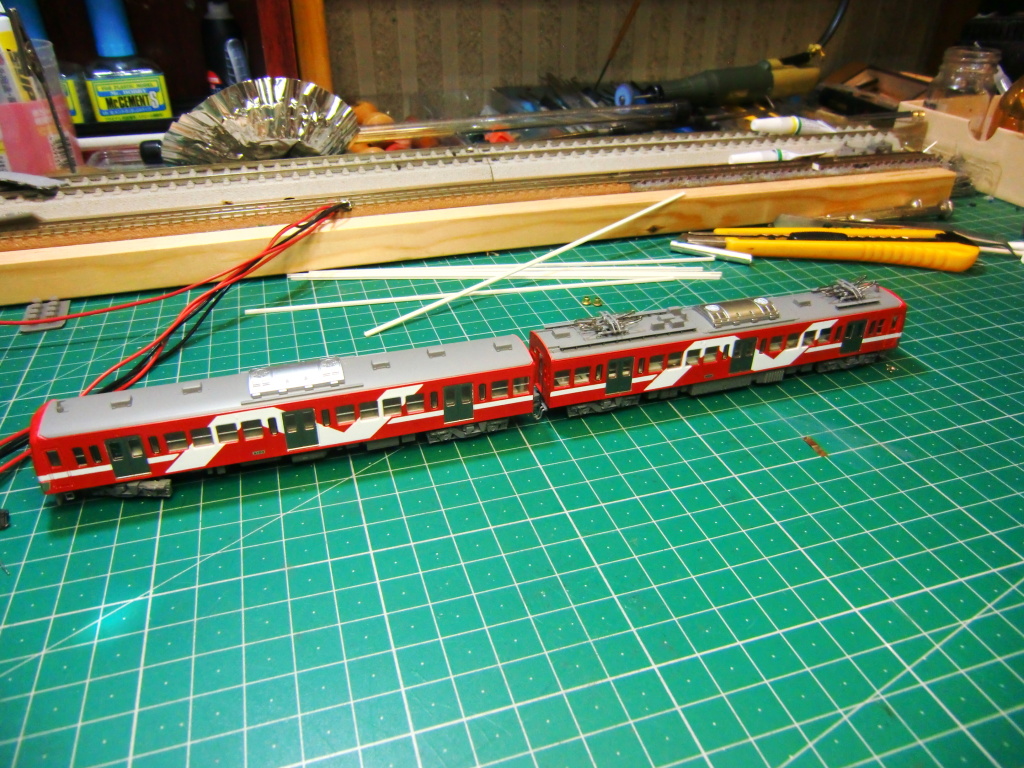




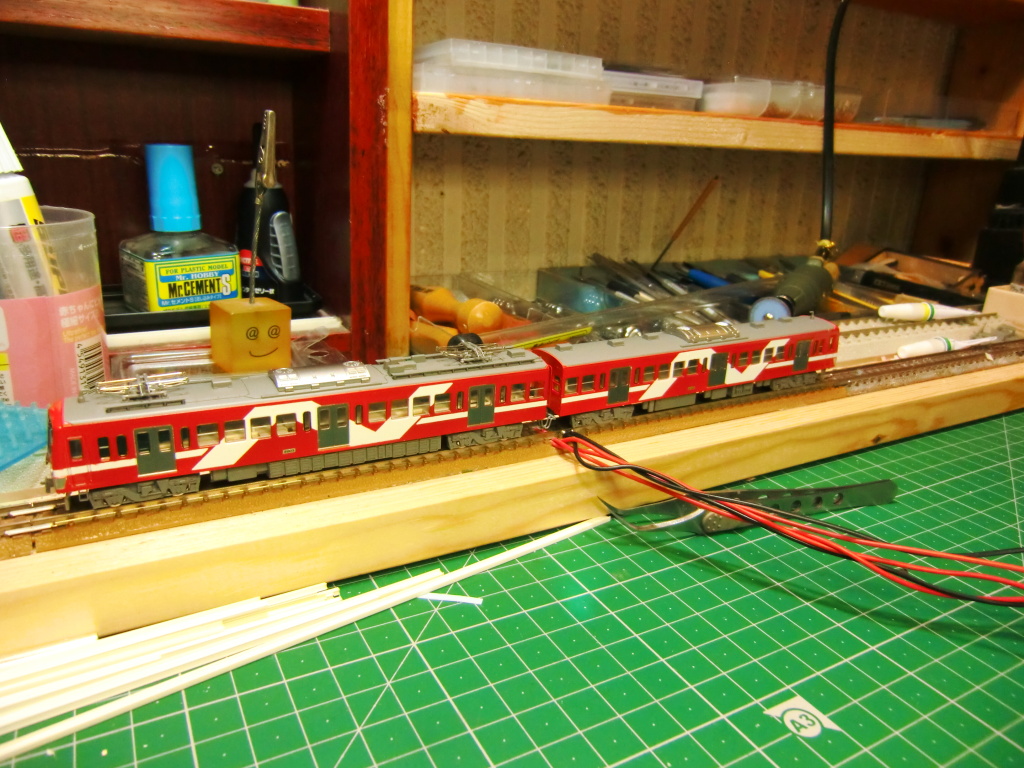
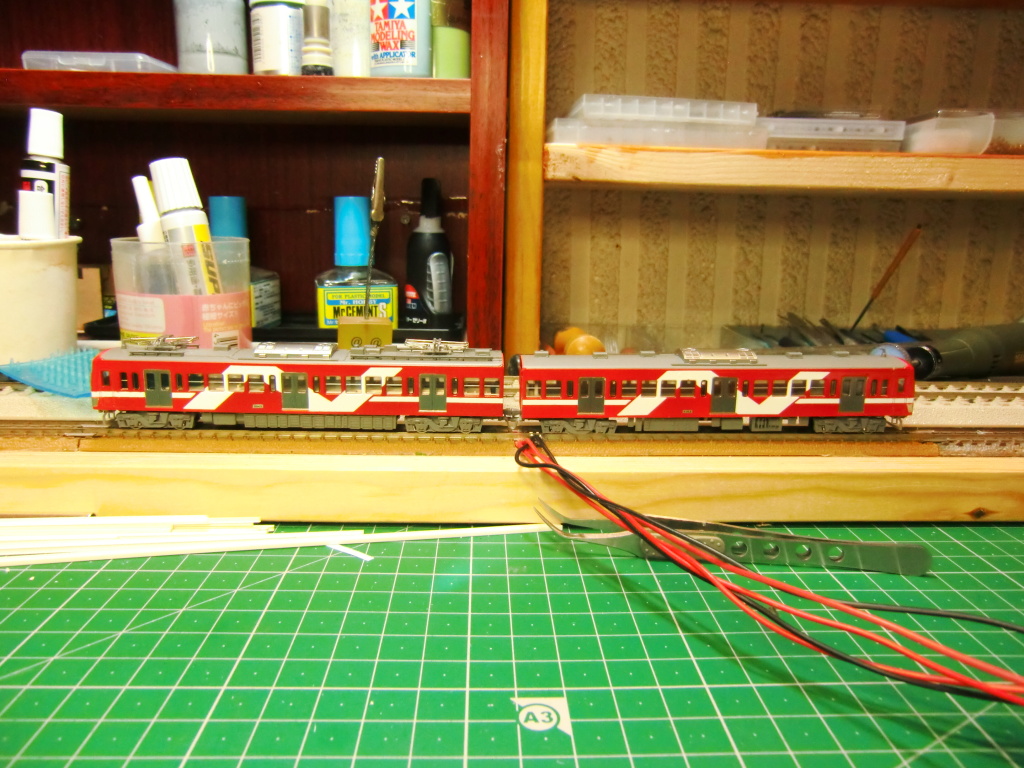
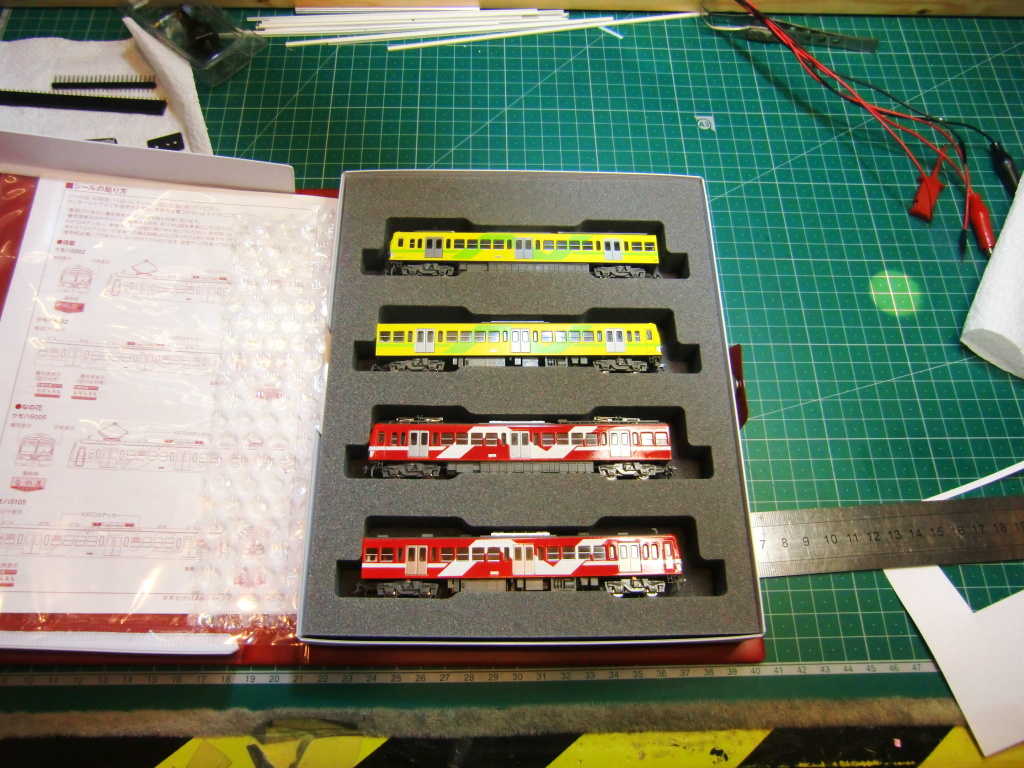
すべての作業が完了でございます。完成!
まずは試作を作るところから始めます。発煙する仕組み自体は単純ですが、Nゲージにユニットを組み込むには、車体内部を大幅に加工しない限り組み込むことが困難となります。いかにユニットを小型化できるかが大きな課題となりますが、当然ながらユニットが小さくなれば、連続して発煙できる時間が短くなります。
今回は、身近にあったKATO製蒸気機関車C11のボディーを使って実際に組み込めるかをテストしてみます。

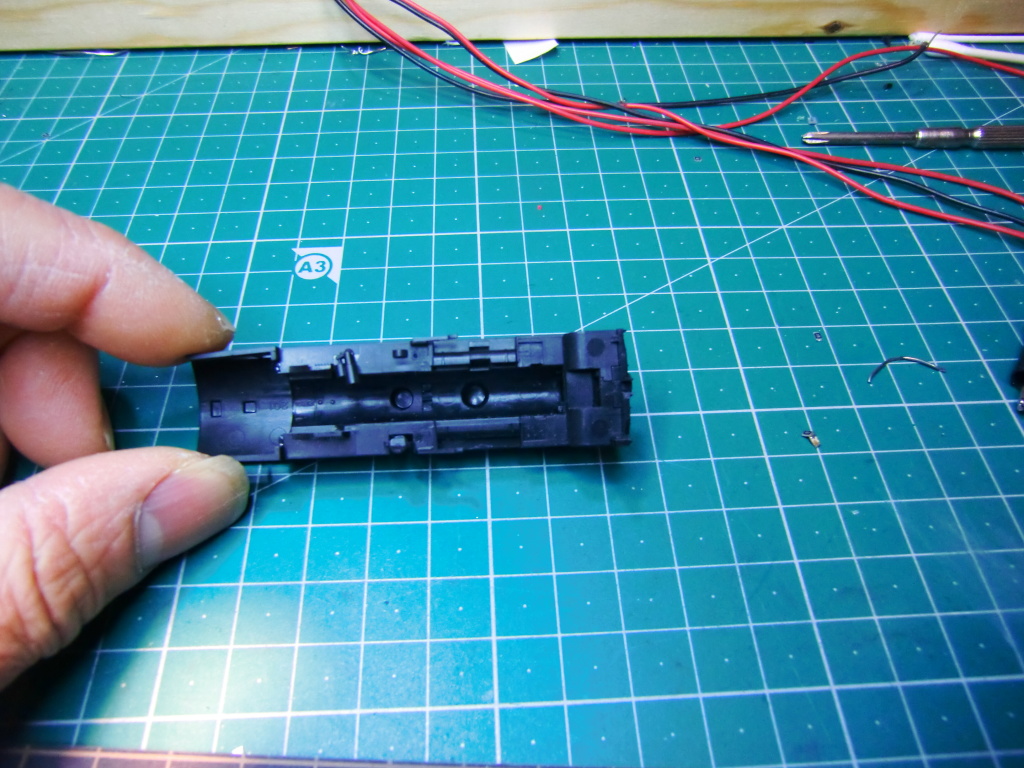
それでは、発煙装置に必要な素材を入手するところから始めます。
◆ニクロム線(ニッケルクロム1種) 0.2mm
| ・線径 | :0.2m |
| ・条長 | :5m |
| ・最高使用温度 | :1100℃ |
| ・導体抵抗 | :34.3Ω/m (許容差±8) |
ニクロム線にかける電圧による発煙の違い
20mmを巻線にして実際に電圧をかけて発煙具合を見てみました。
3.5V付近から発煙開始が確認できました。細い線状に煙が上がり始めた程度です。そこから4.5V付近まで上げると発煙量はかなり増えてきました。7V付近になるとモクモクと煙を上げ始め、充分な発煙が確認できました。それ以上は必要ないと考え、3.5~7Vあたりで回路を制作していきます。
ニクロム線2次加工
ニクロム線に身近にあった素材を巻き付けて発煙状態を確認してみました。不燃綿、不燃ペーパー、その他・・・。不燃な吸収素材であれば何でも構いませんが、内径5mmの筒状に適正な位置に配置するのは少し難しいですね。
いろいろ試している中で、たまたま近くにあった物がニクロム線に触れて溶けて固形化。これが偶然の産物として発煙効果を上げることになりました。この固形化した物質は、発煙剤を適度に吸収する効果もあるようで、持続的な発煙が見られます。
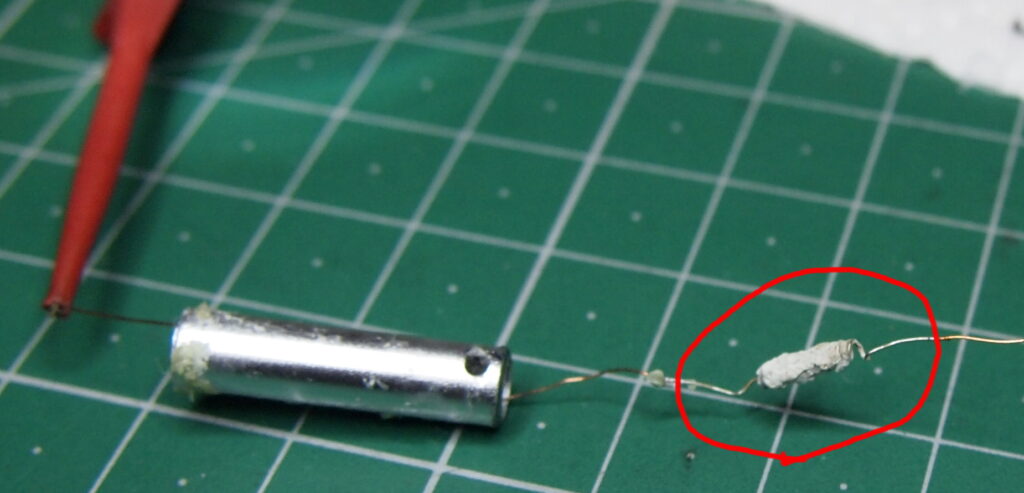
数分の連続した発煙テストでは、焦げることなく安定した発煙を確認できました。もう少し様子を見てから本当に適した素材なのかを見極めていきます。
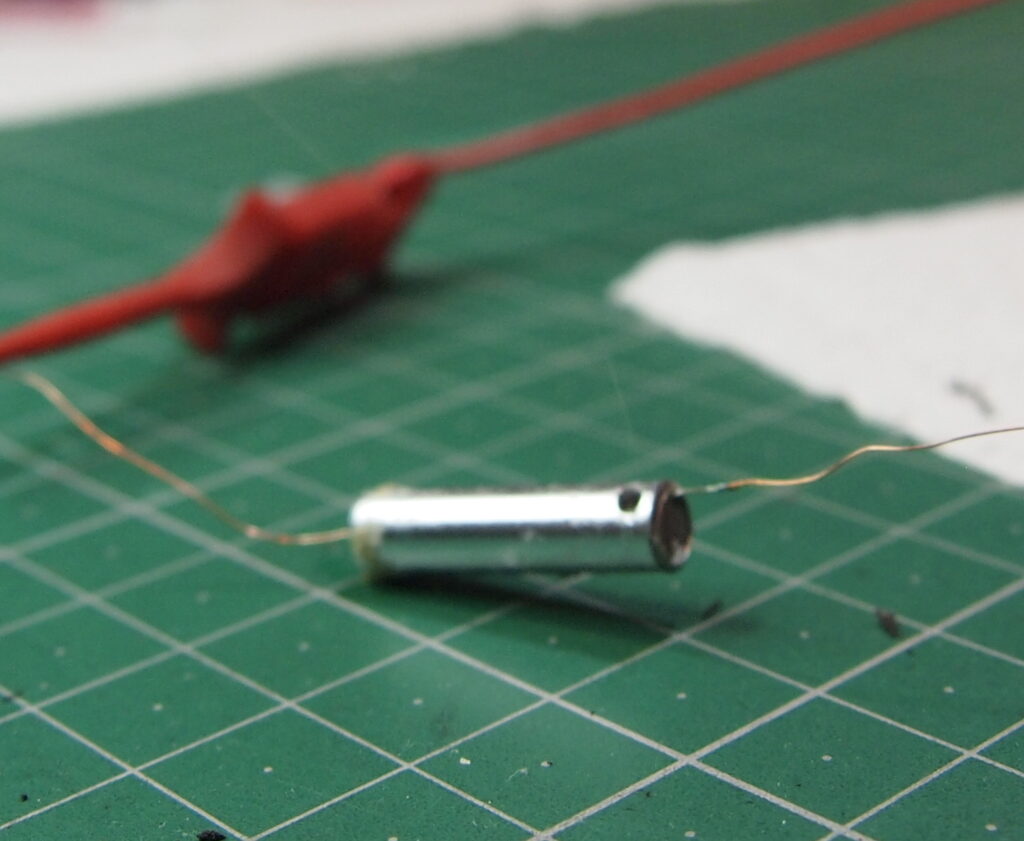
低い電圧でも煙が上がっていきます。
それでは発煙ユニットを形にして、実際に機関車に組み込んでみることにします。
「長さ:20mm/幅:6mm/高さ:5mm」でユニットが形になれば理想ですが、そううまくはいかないでしょうね。