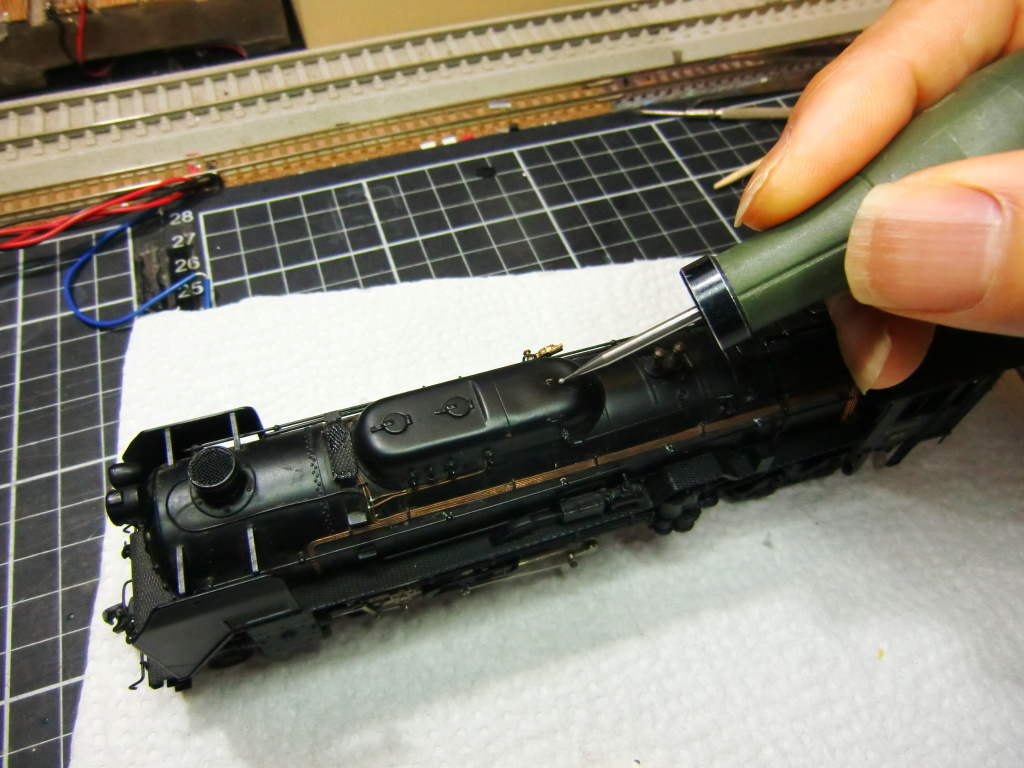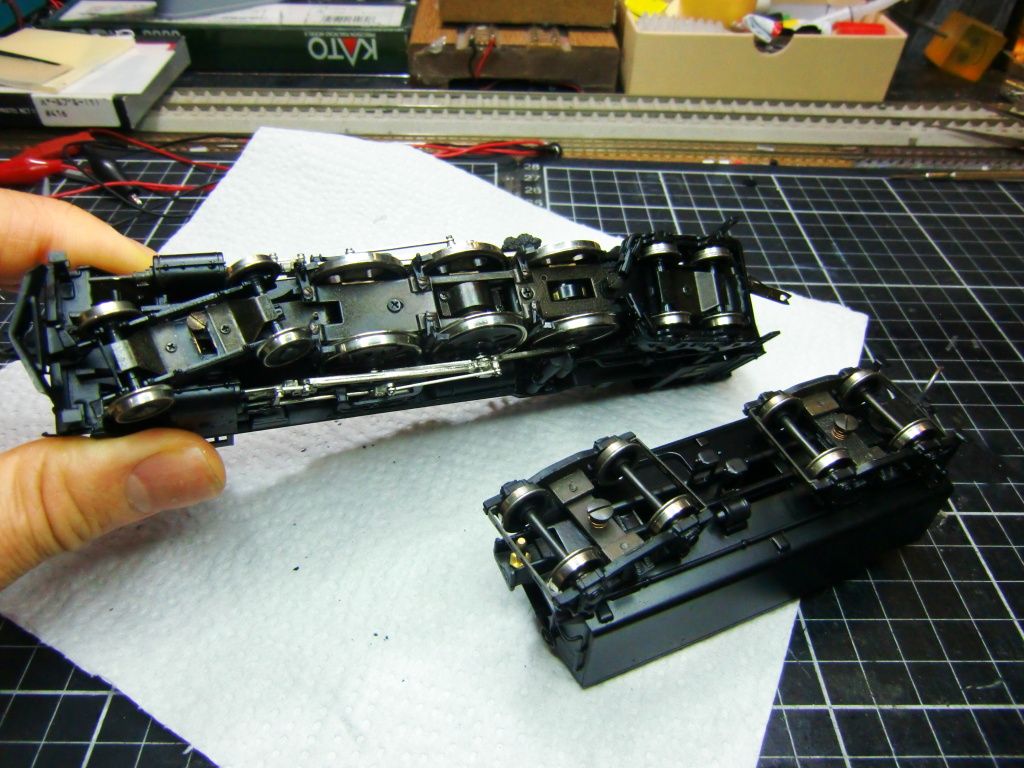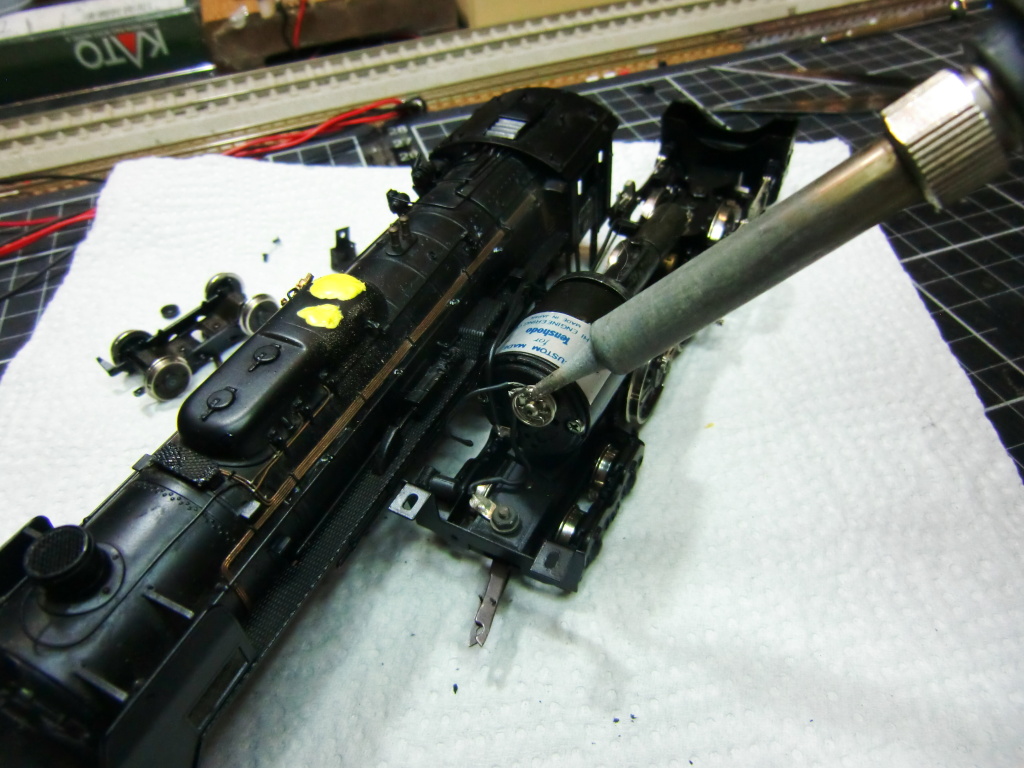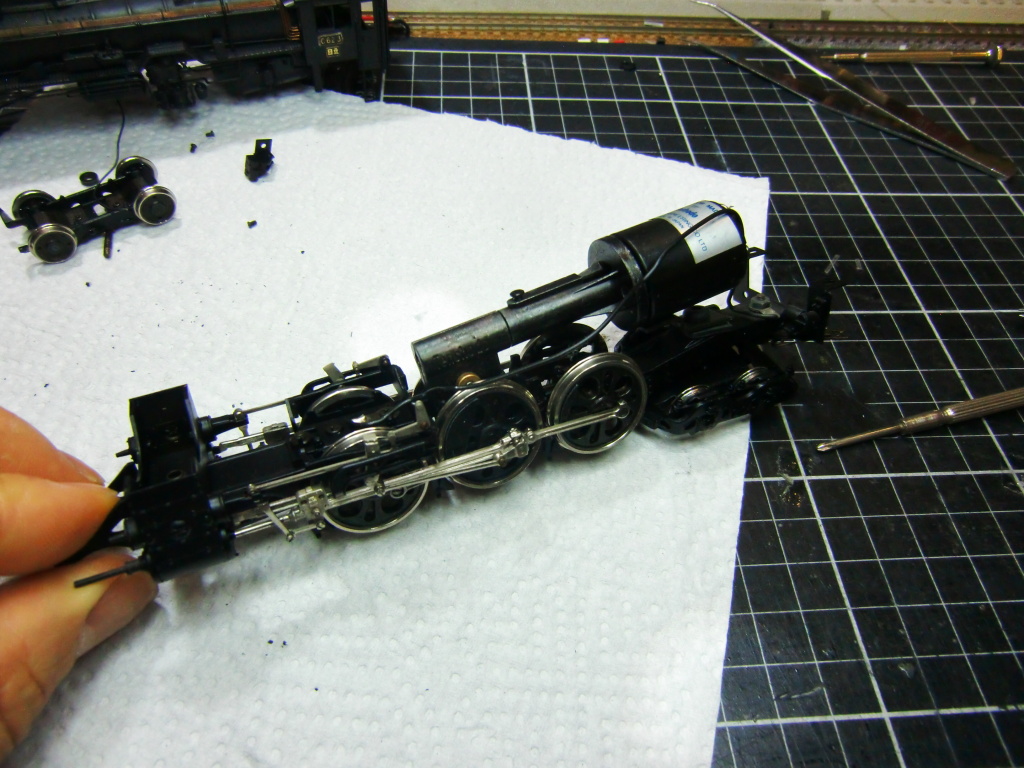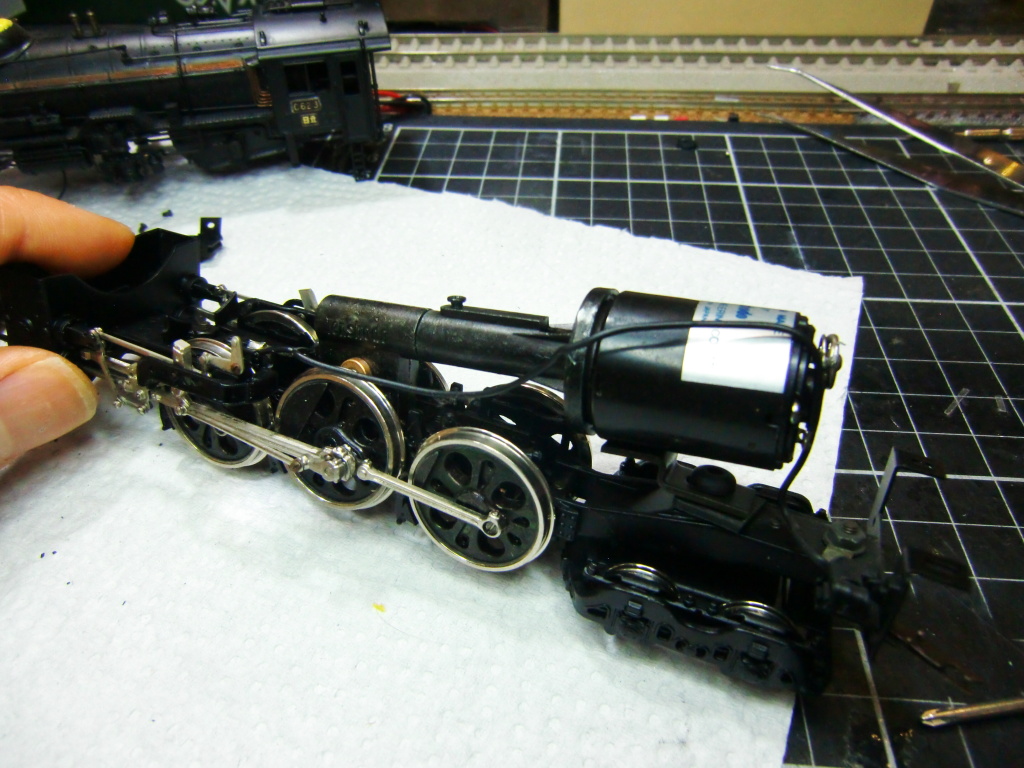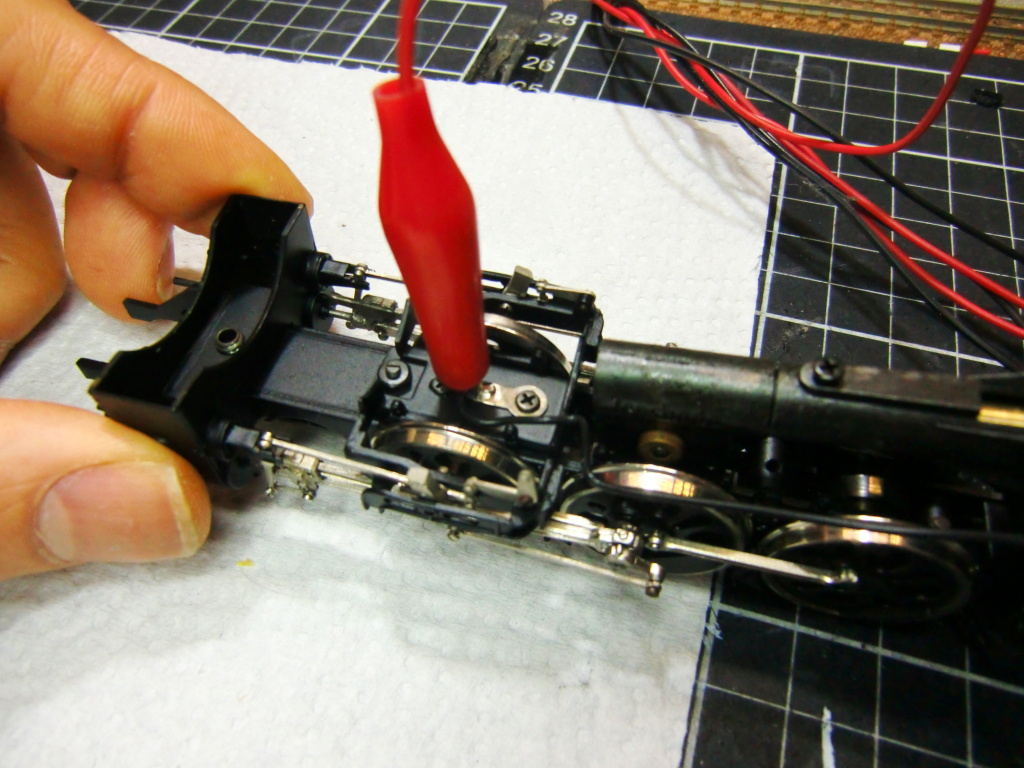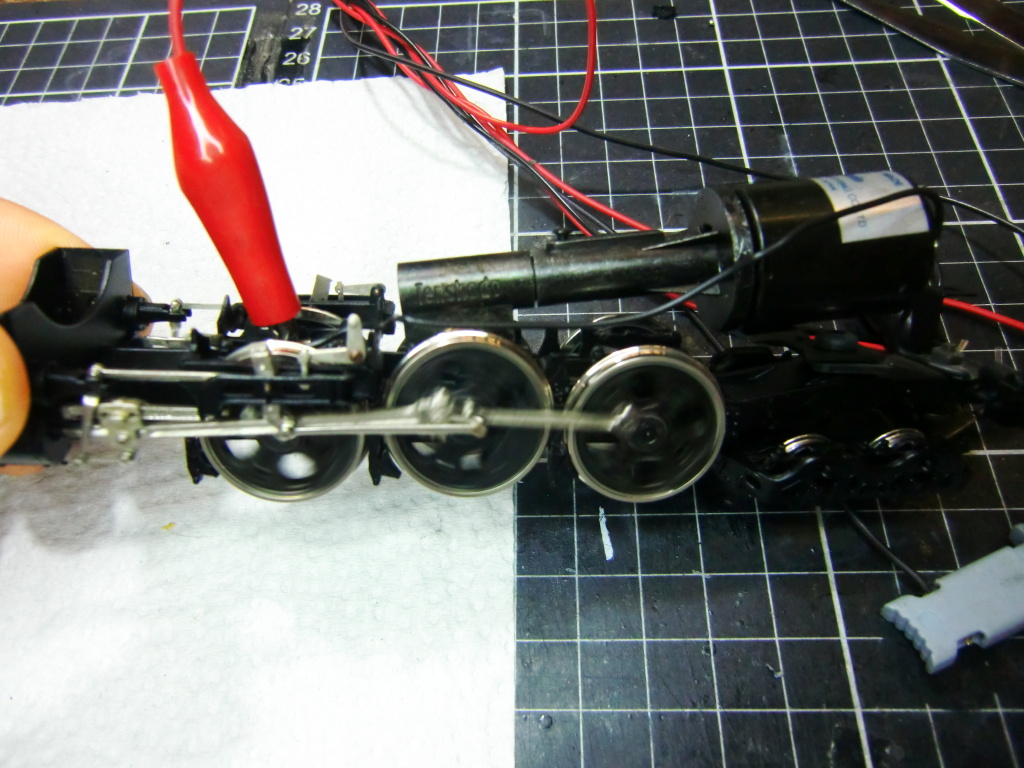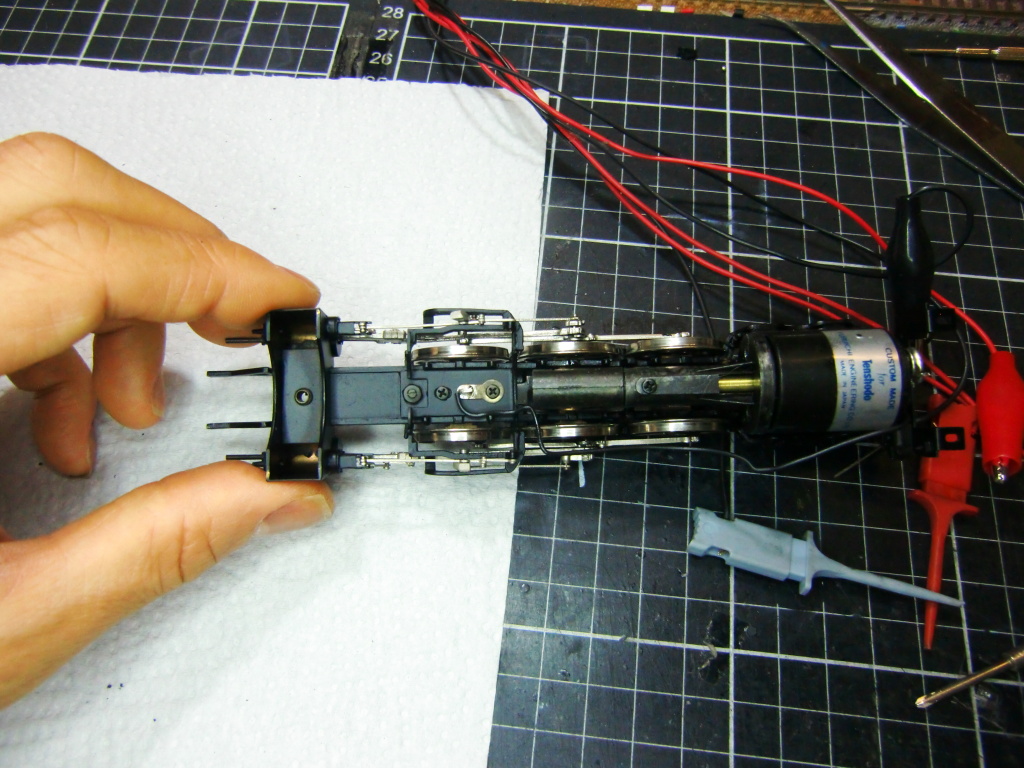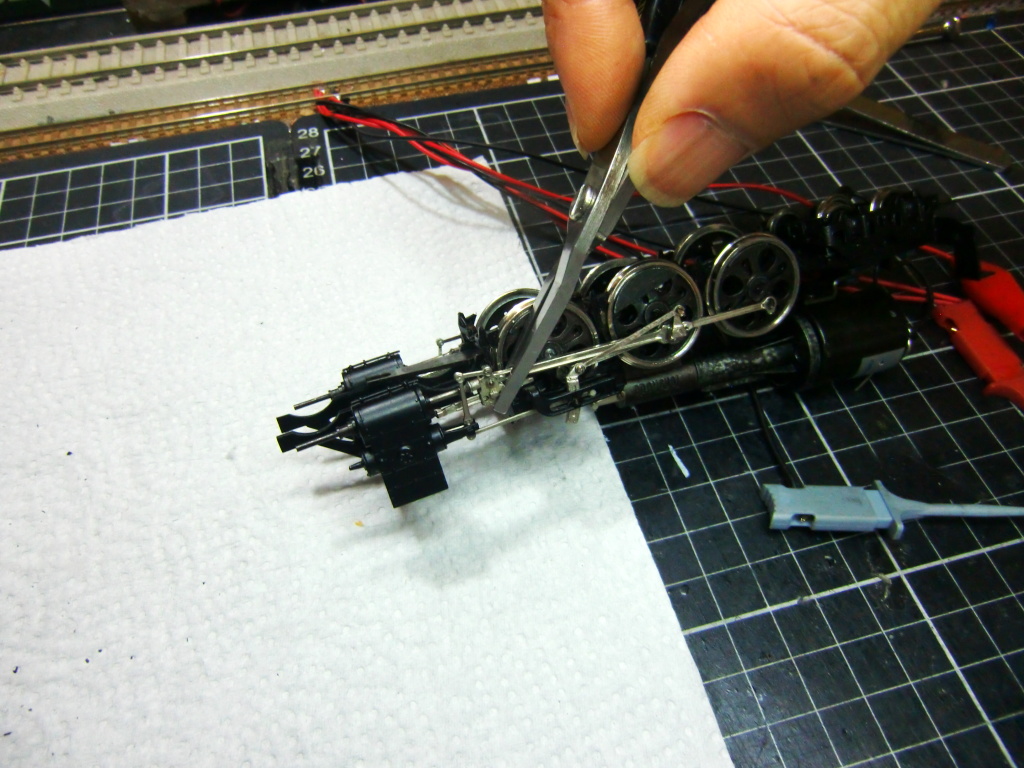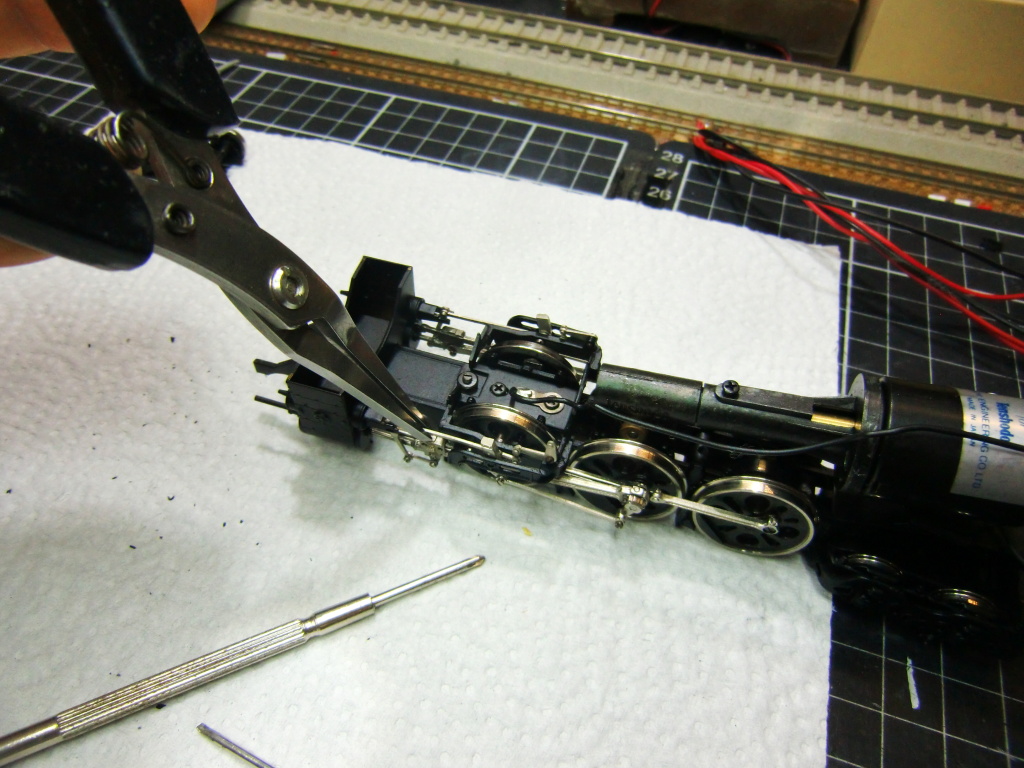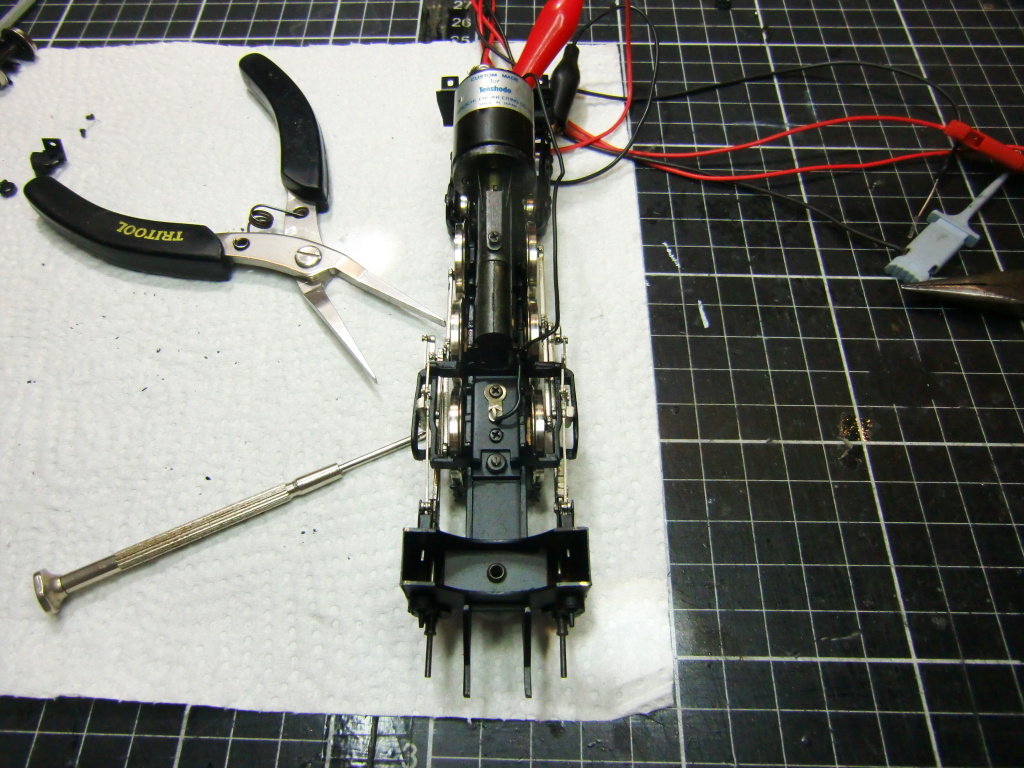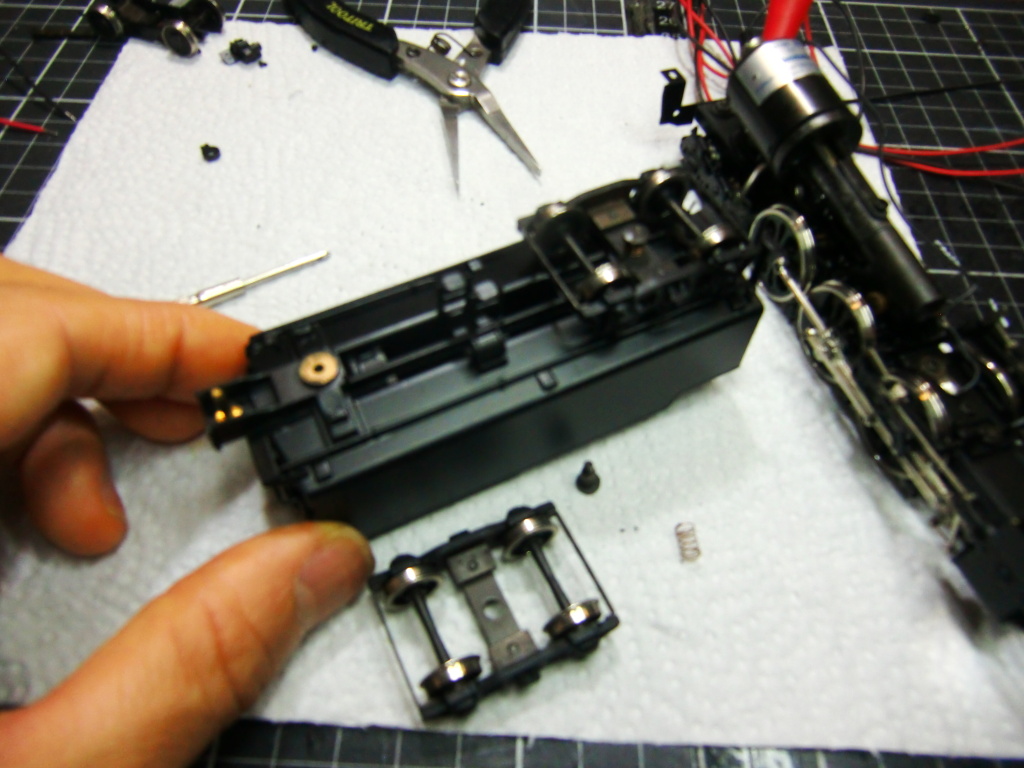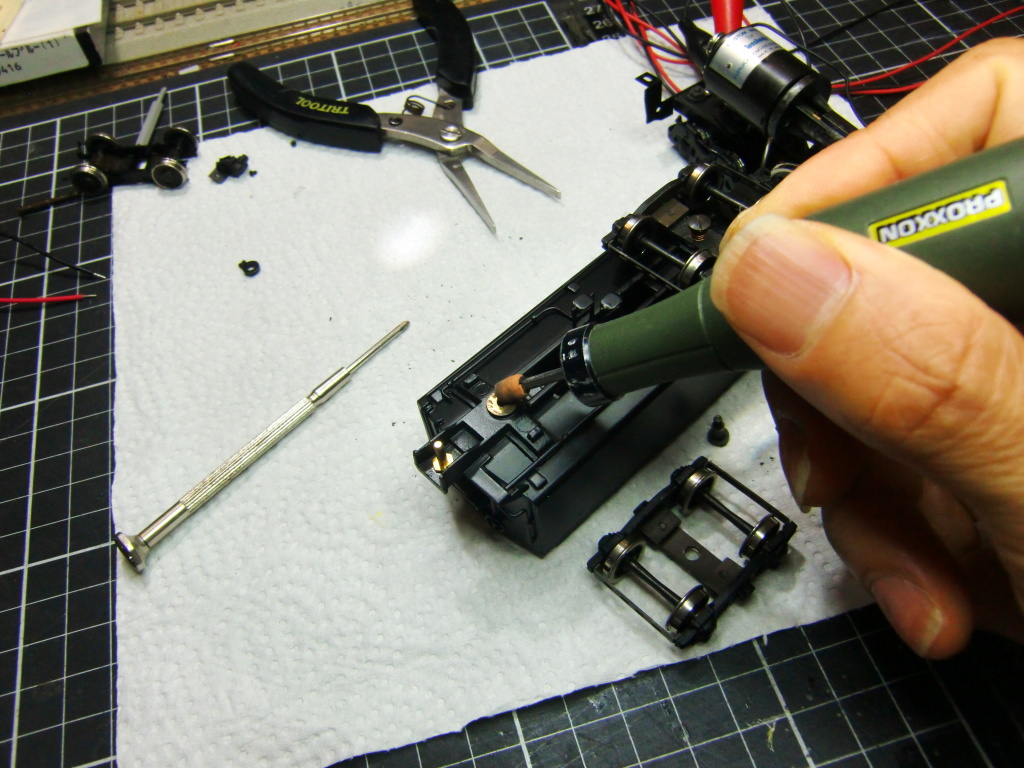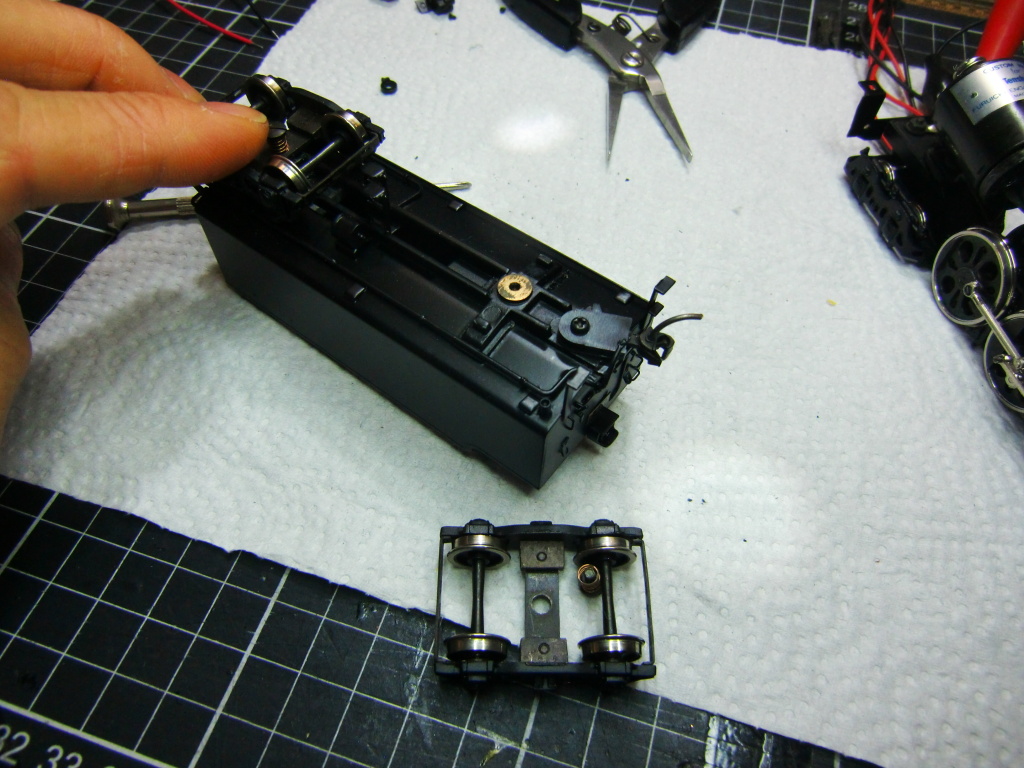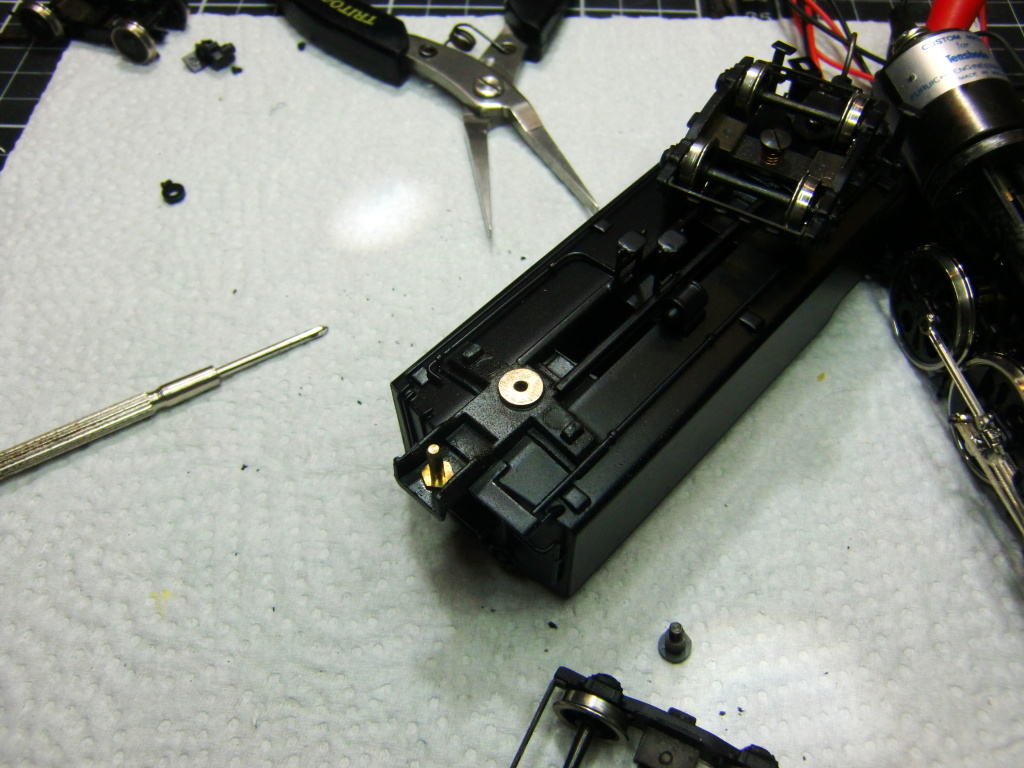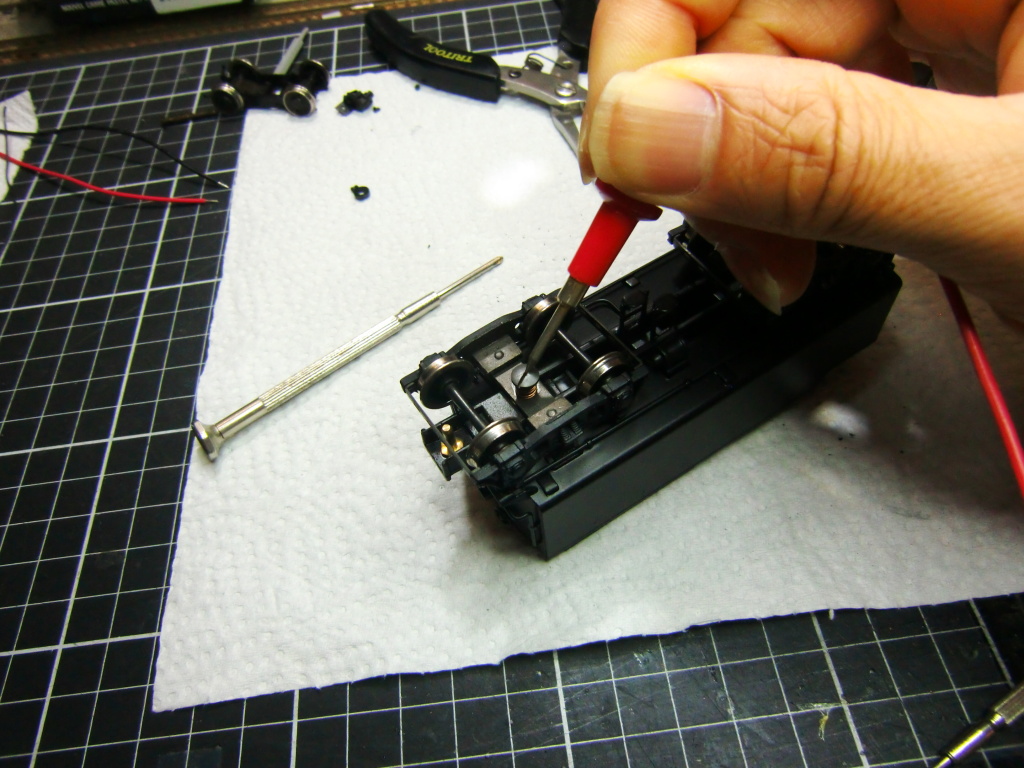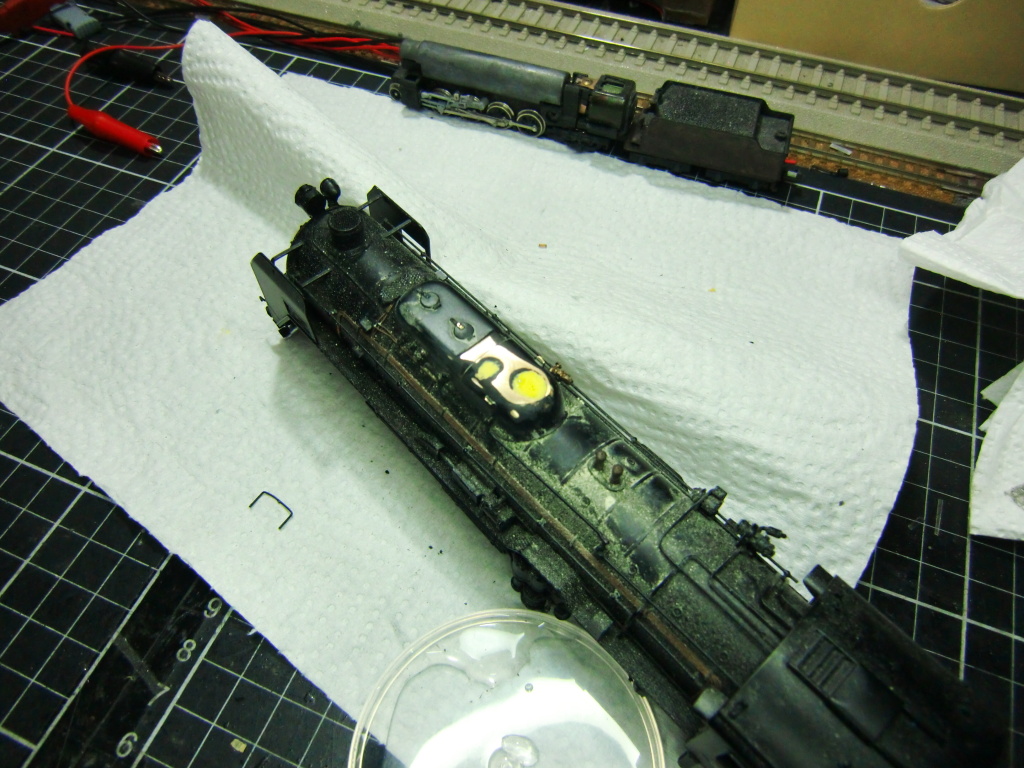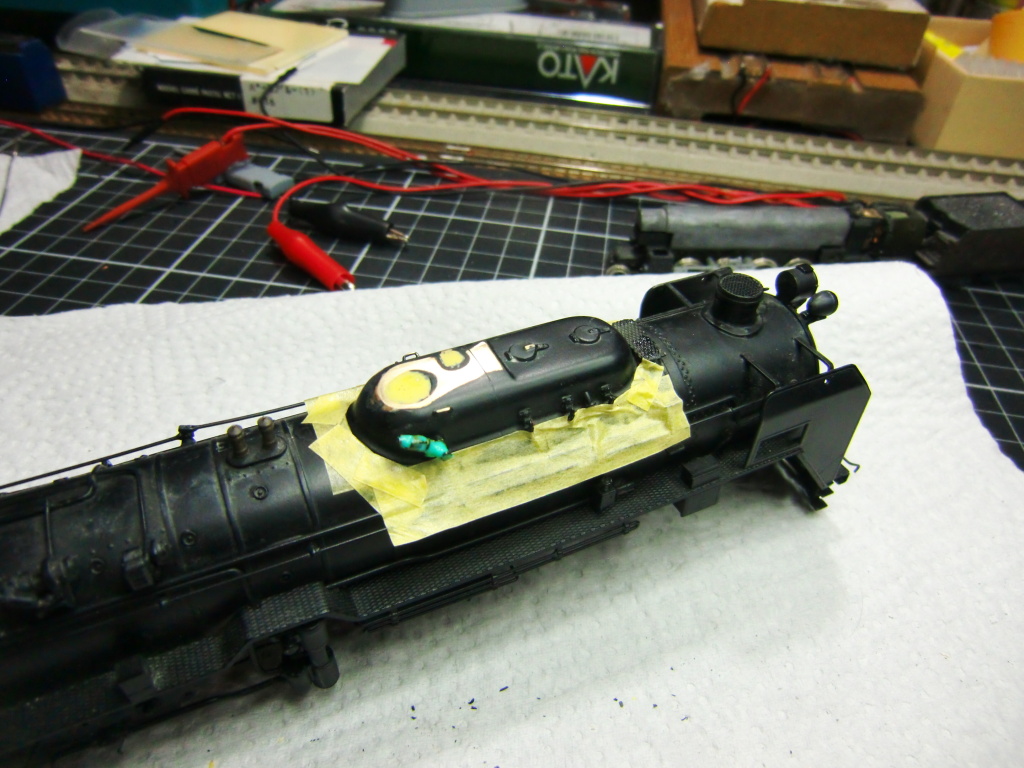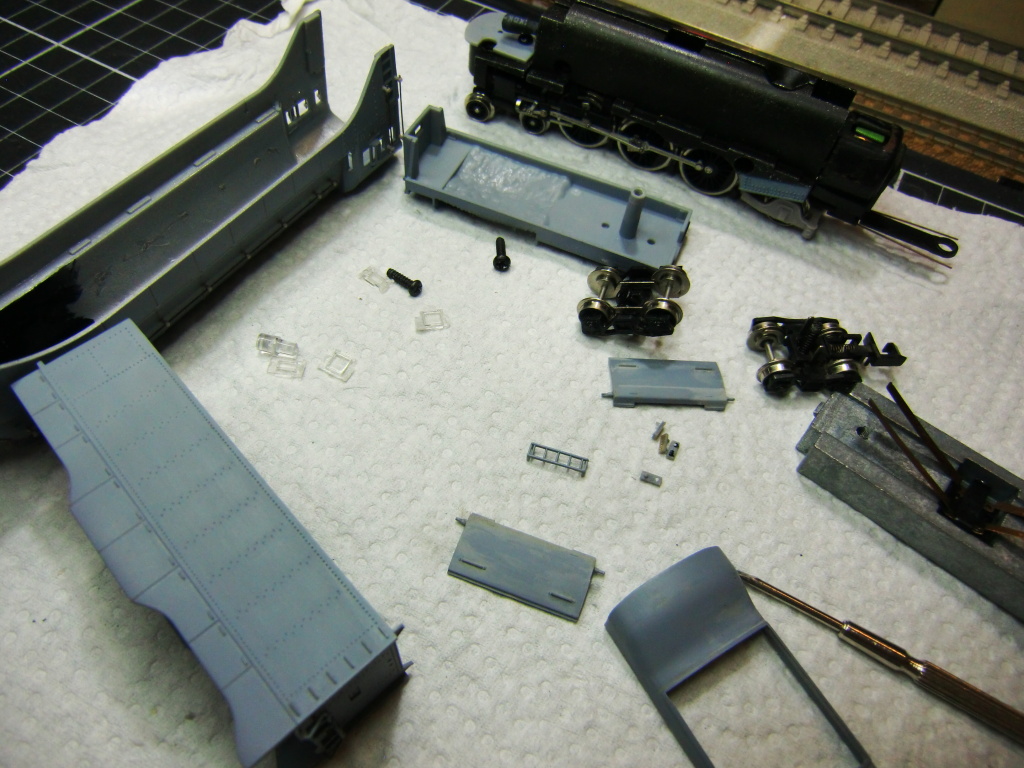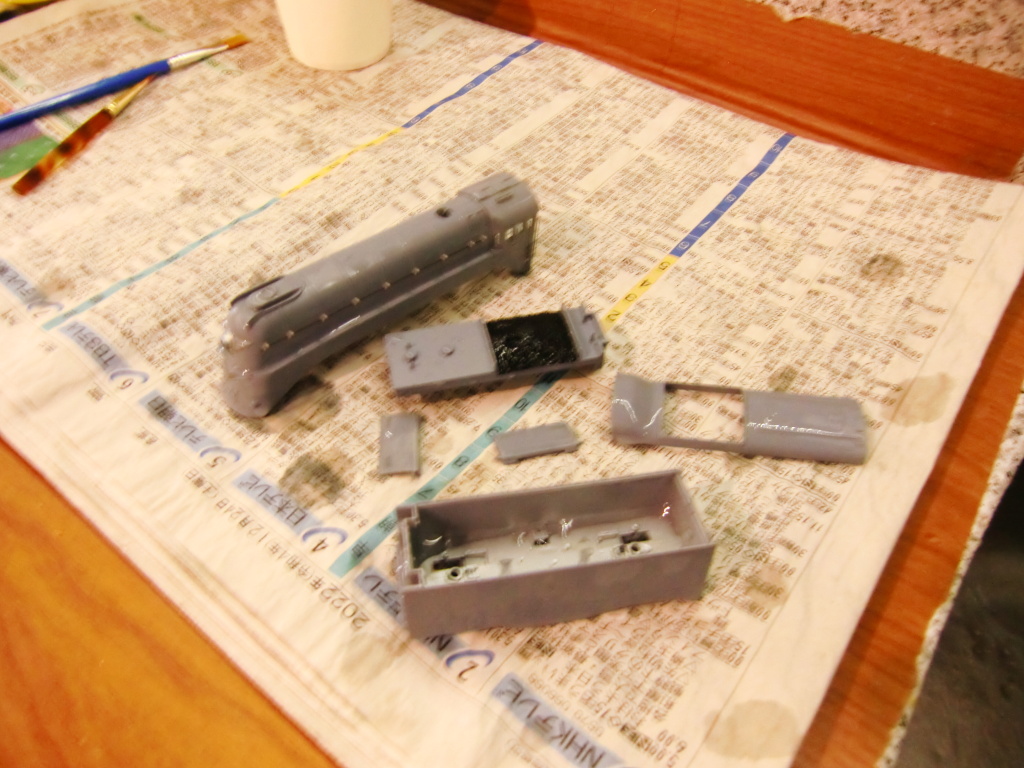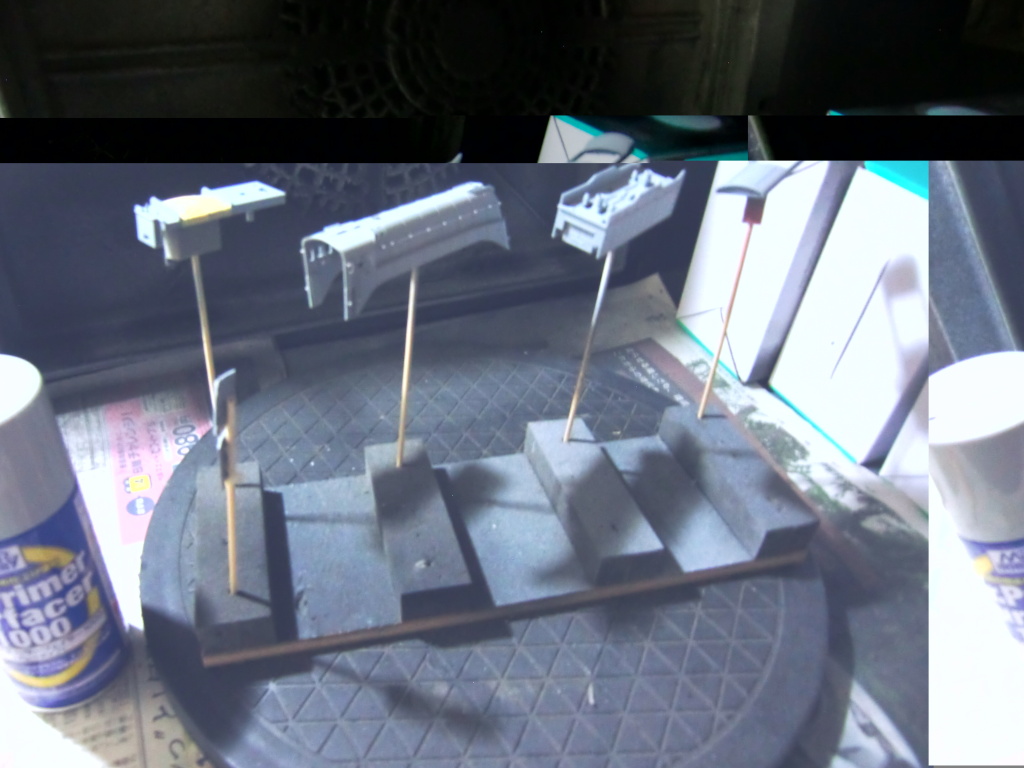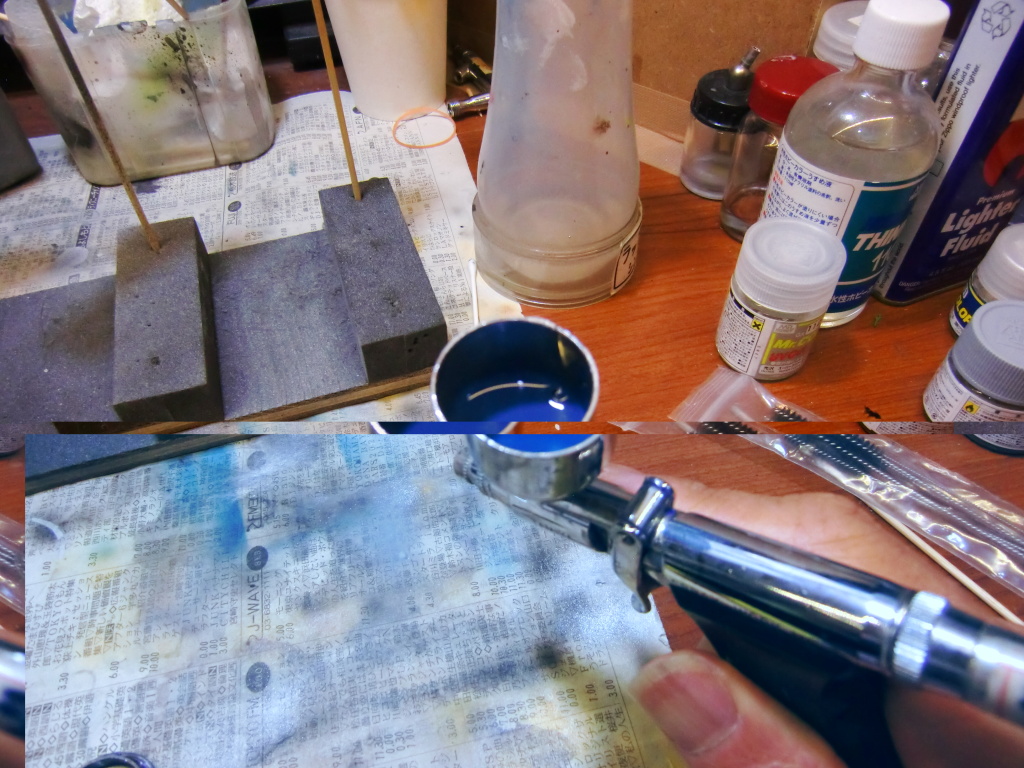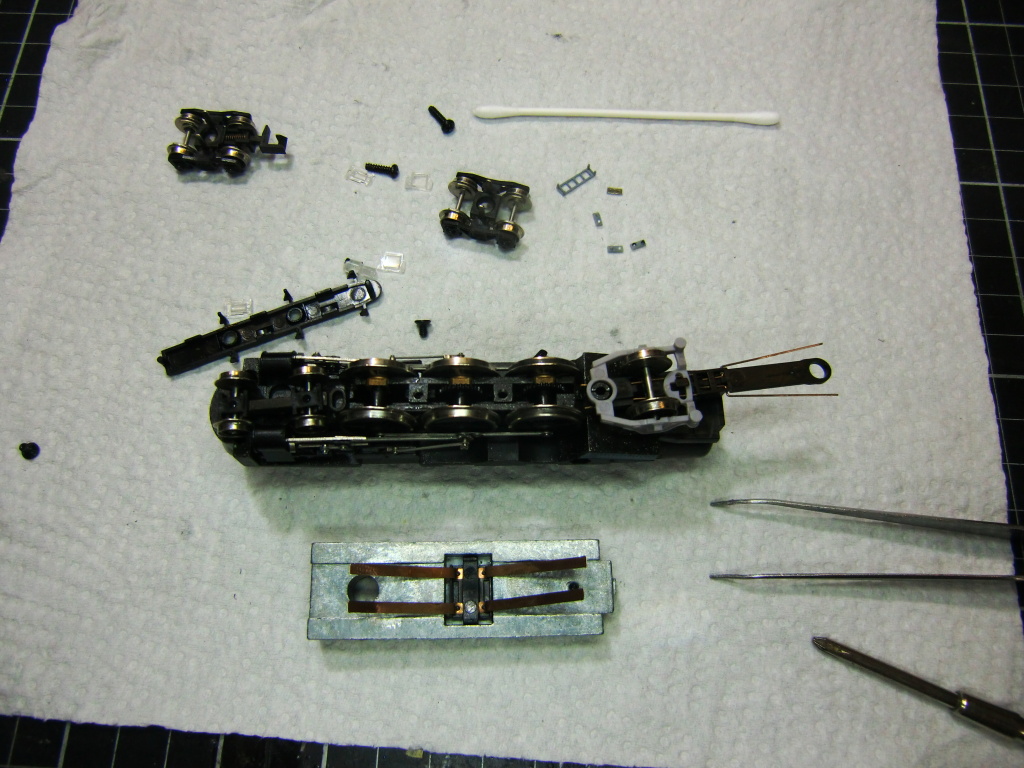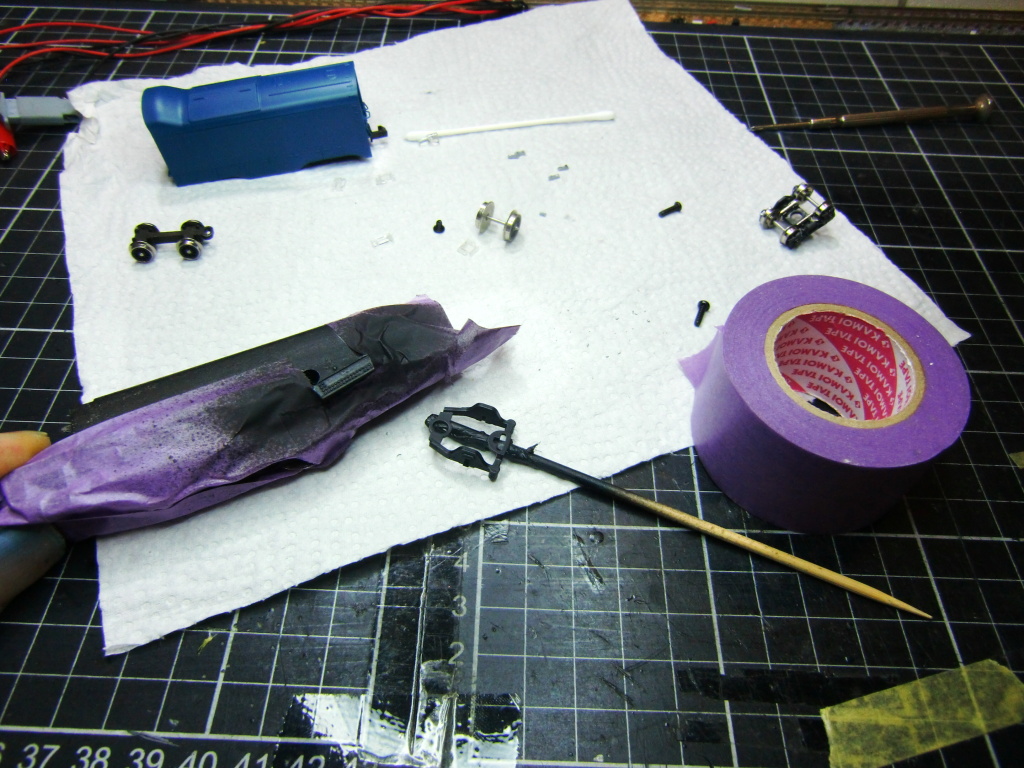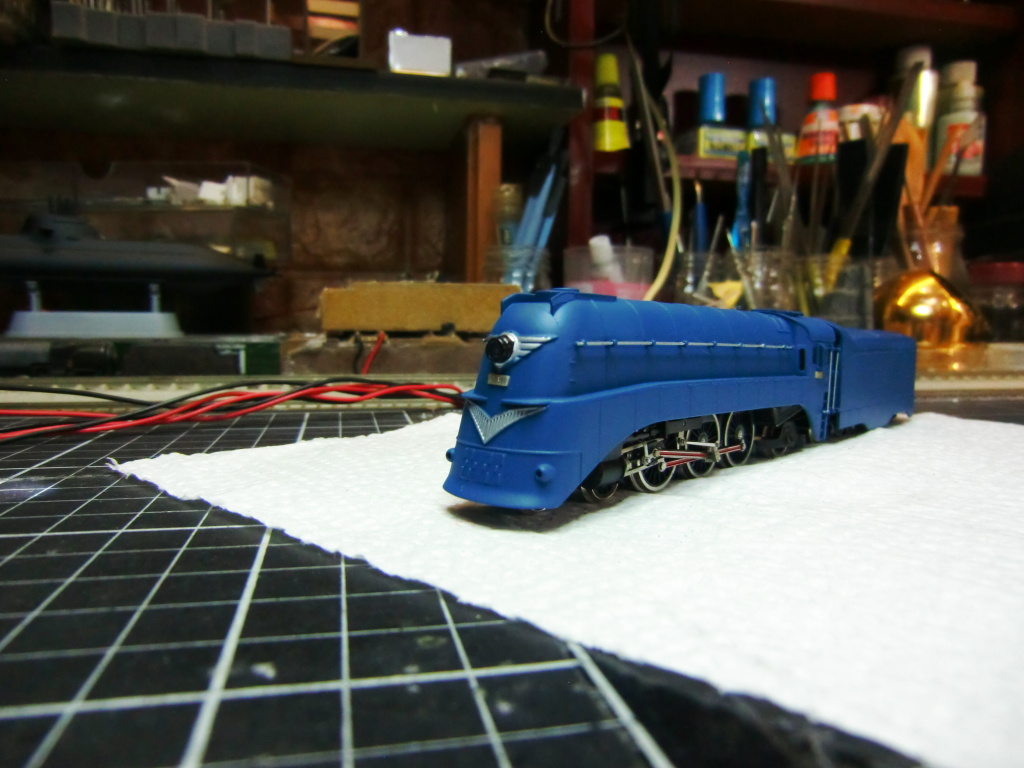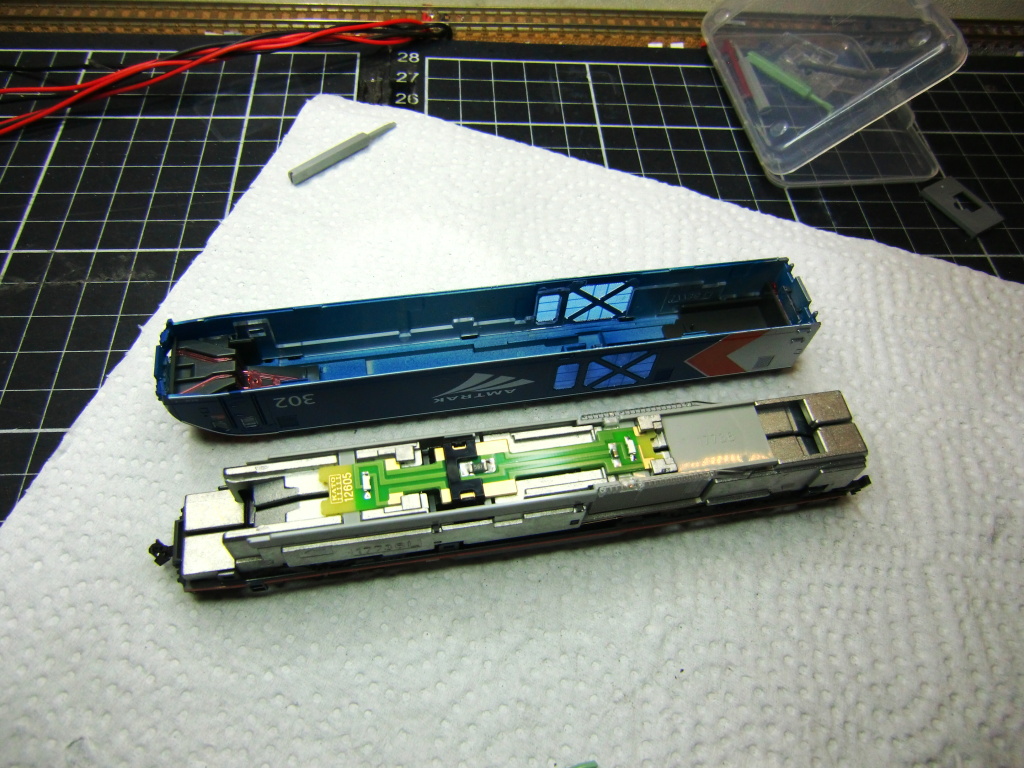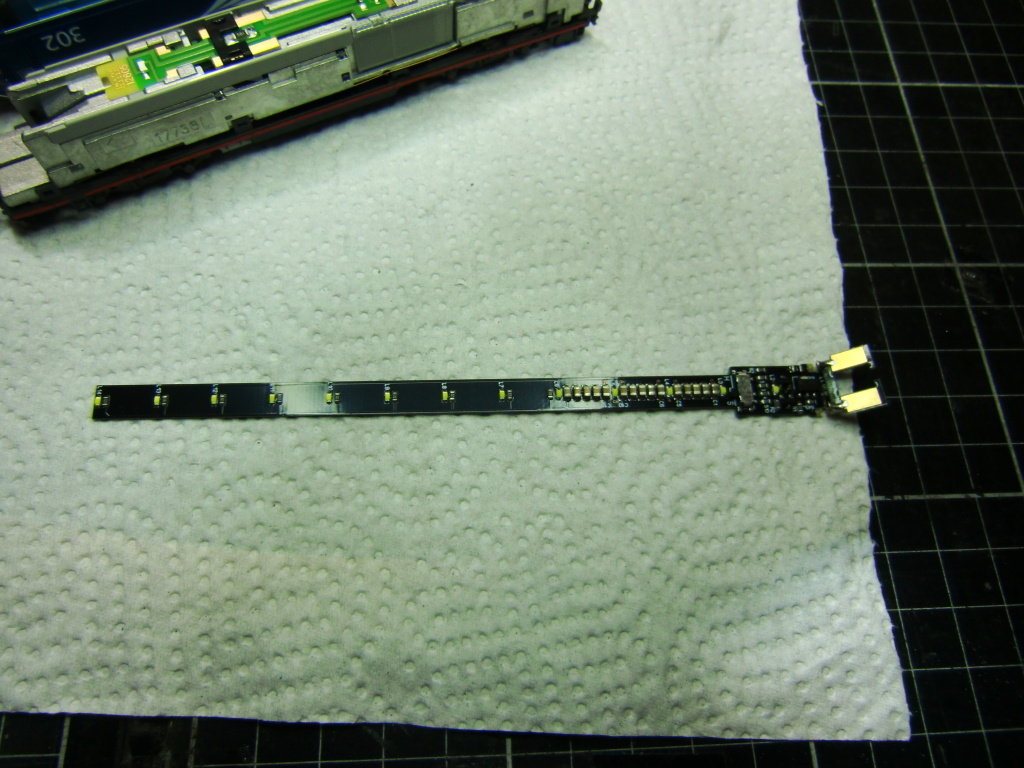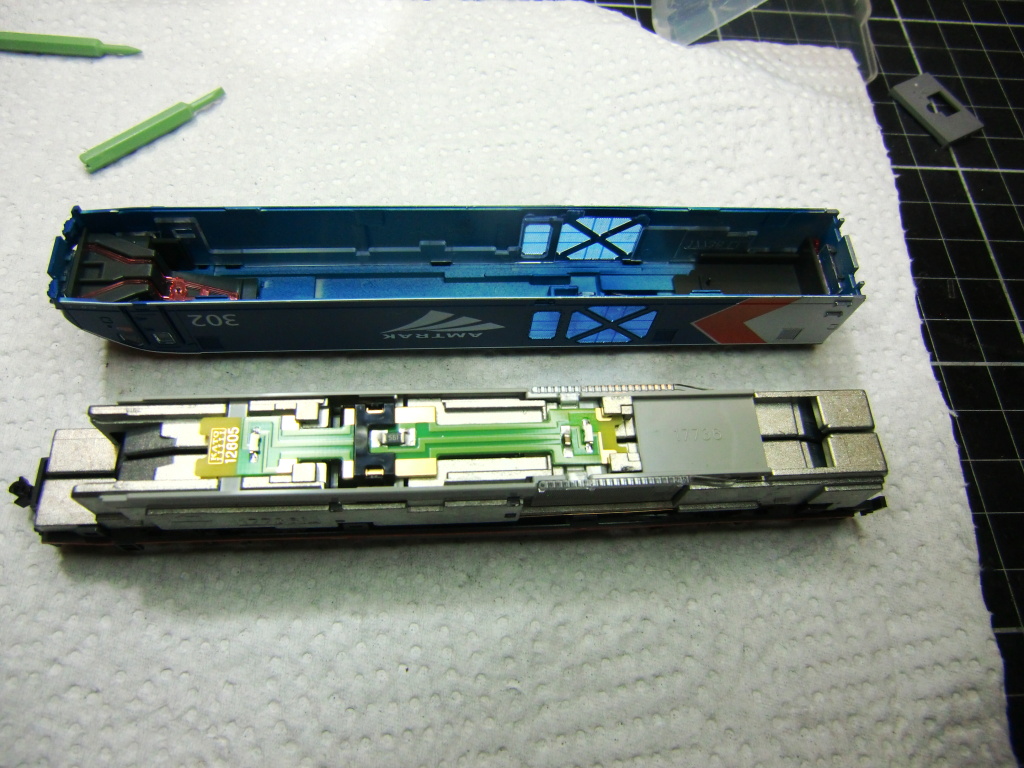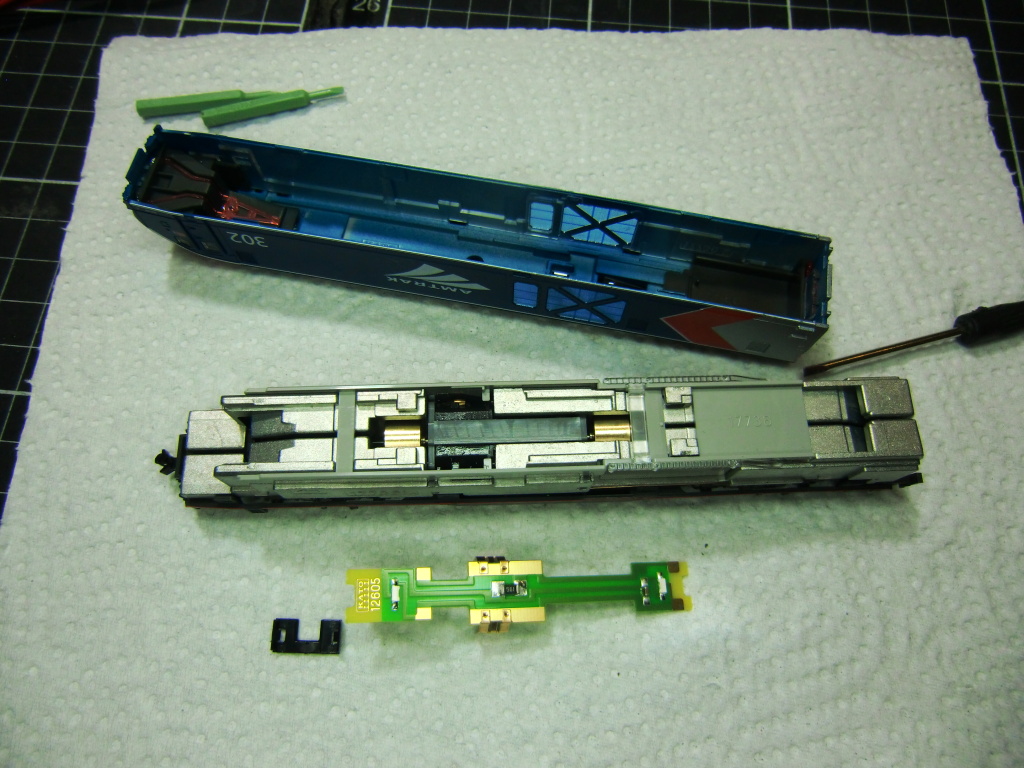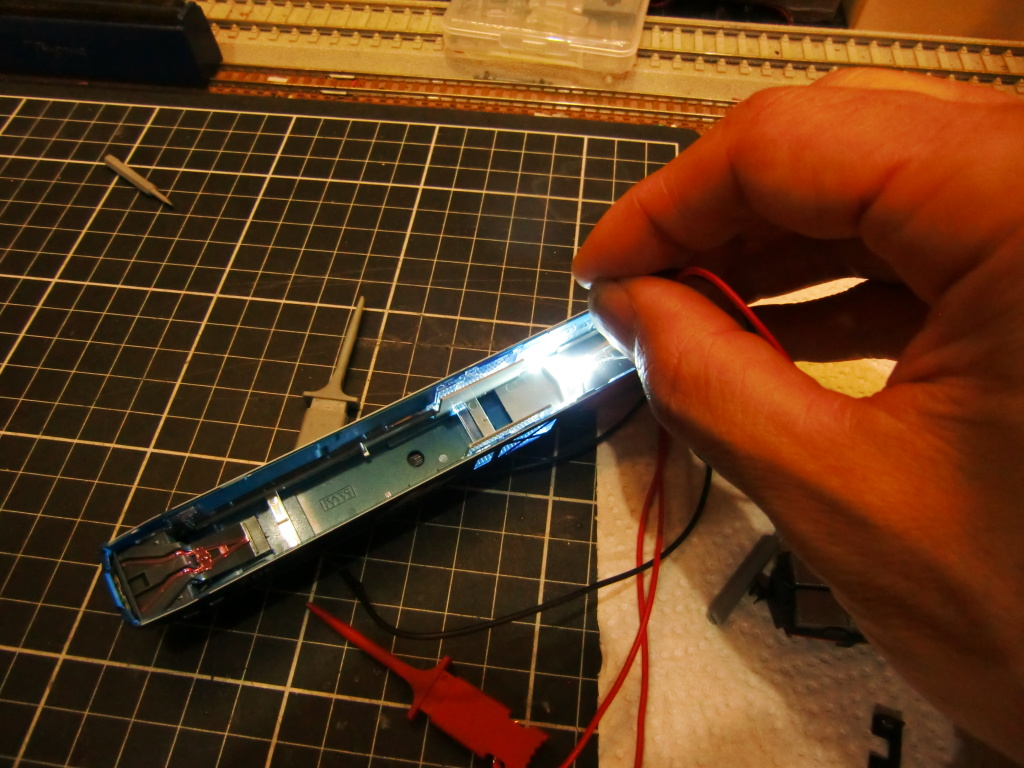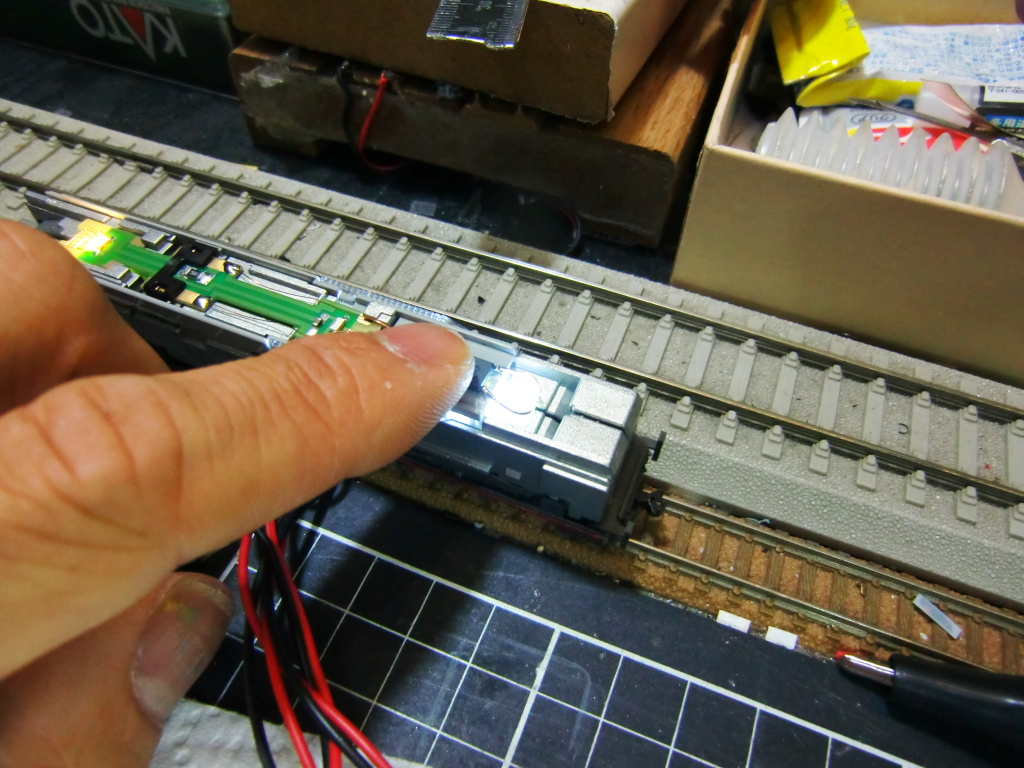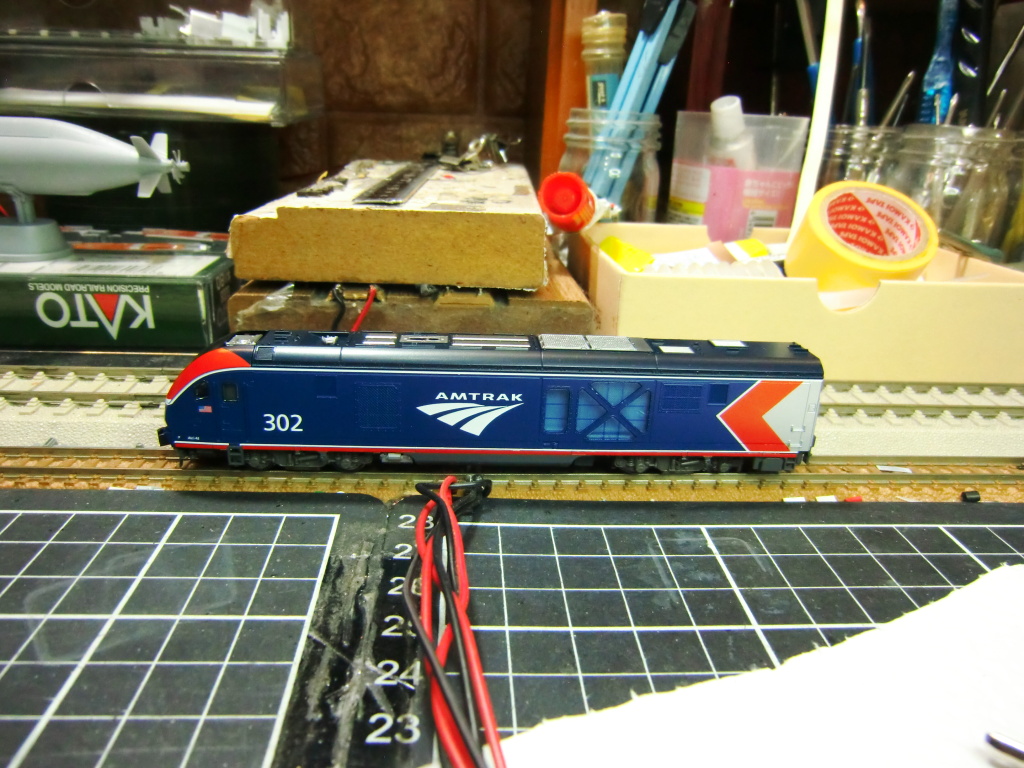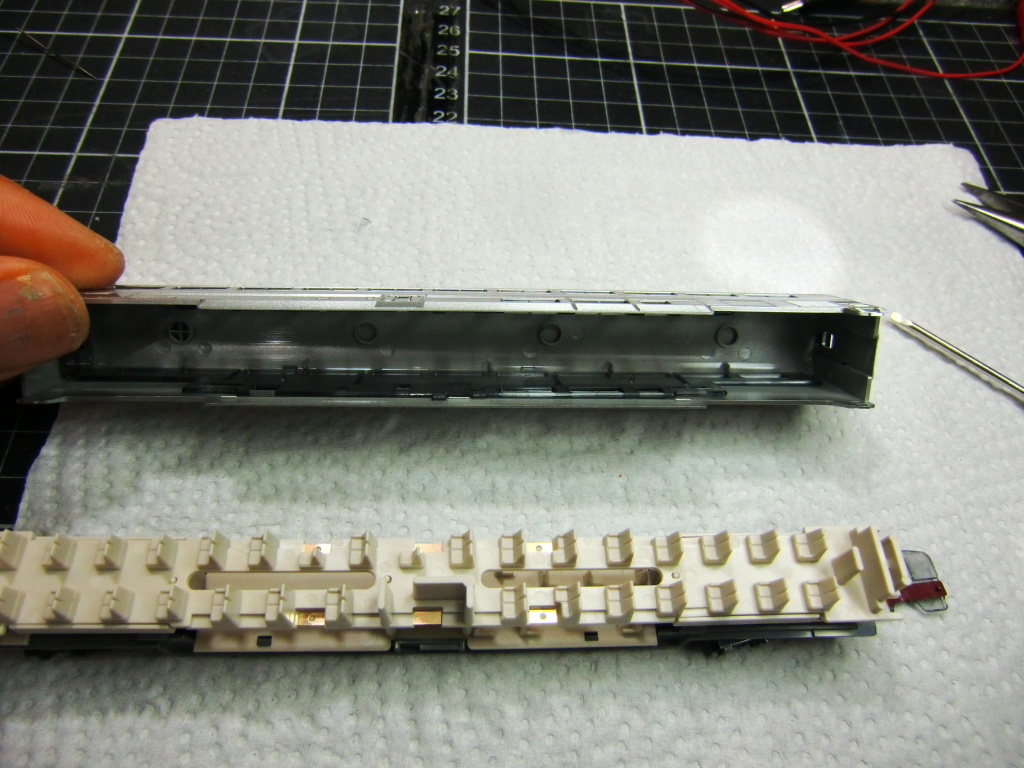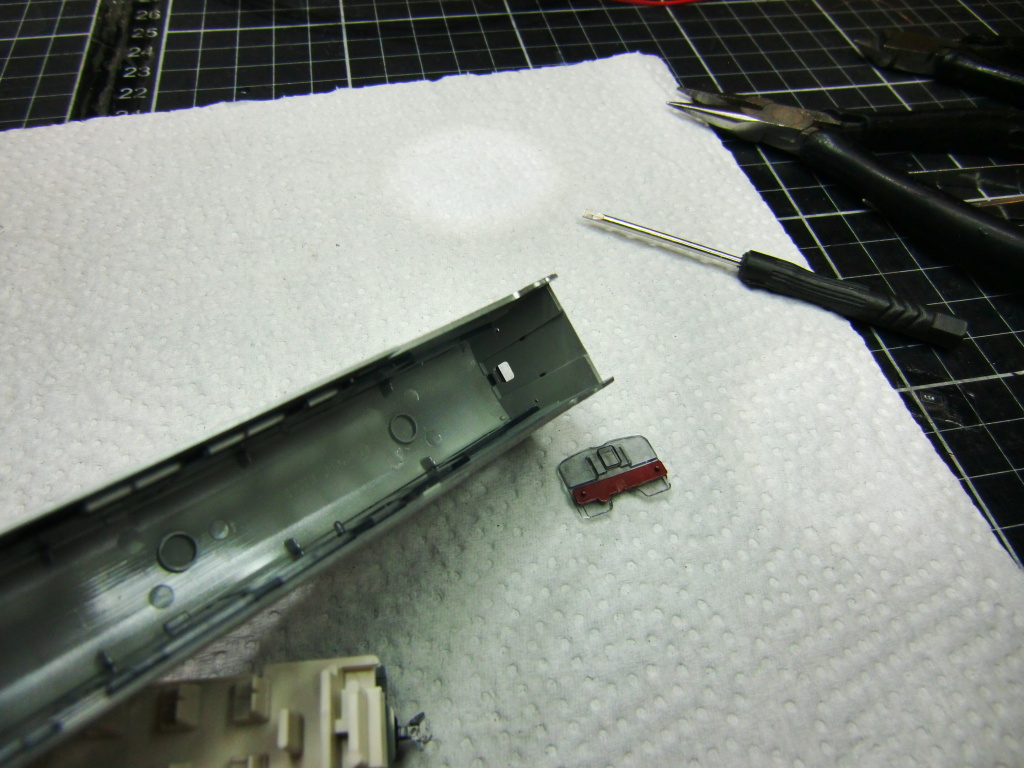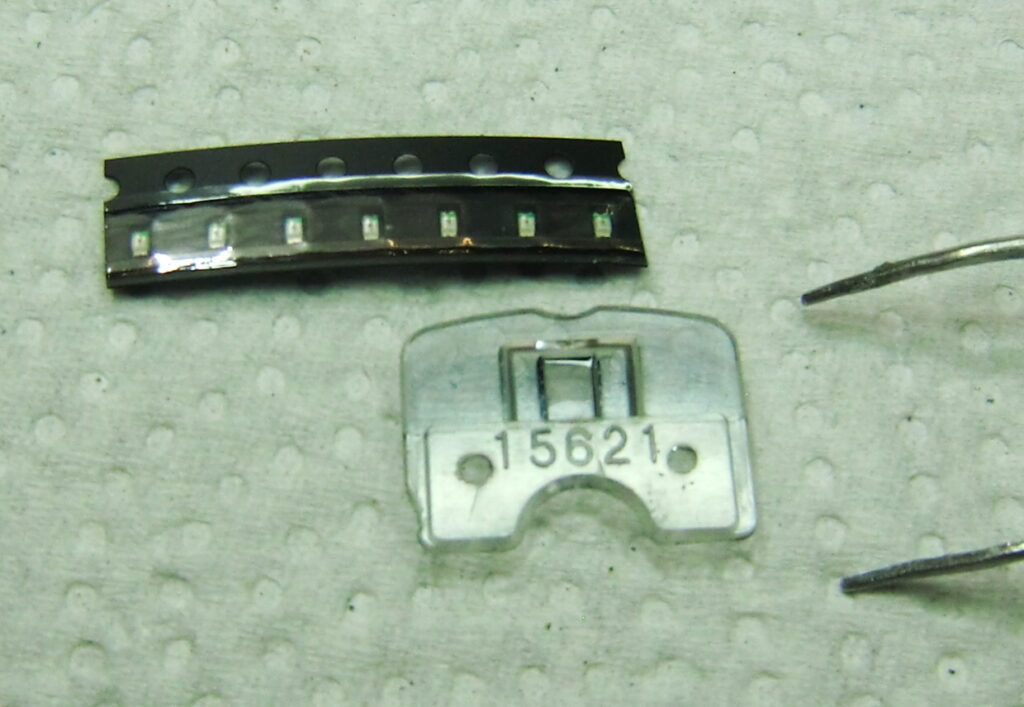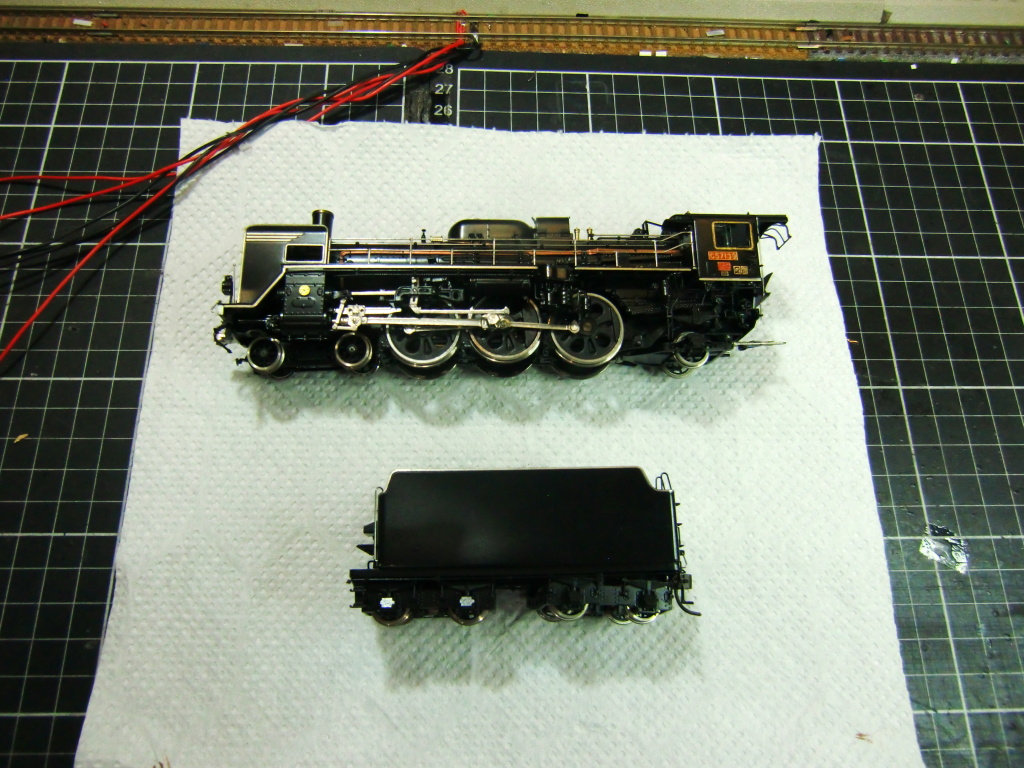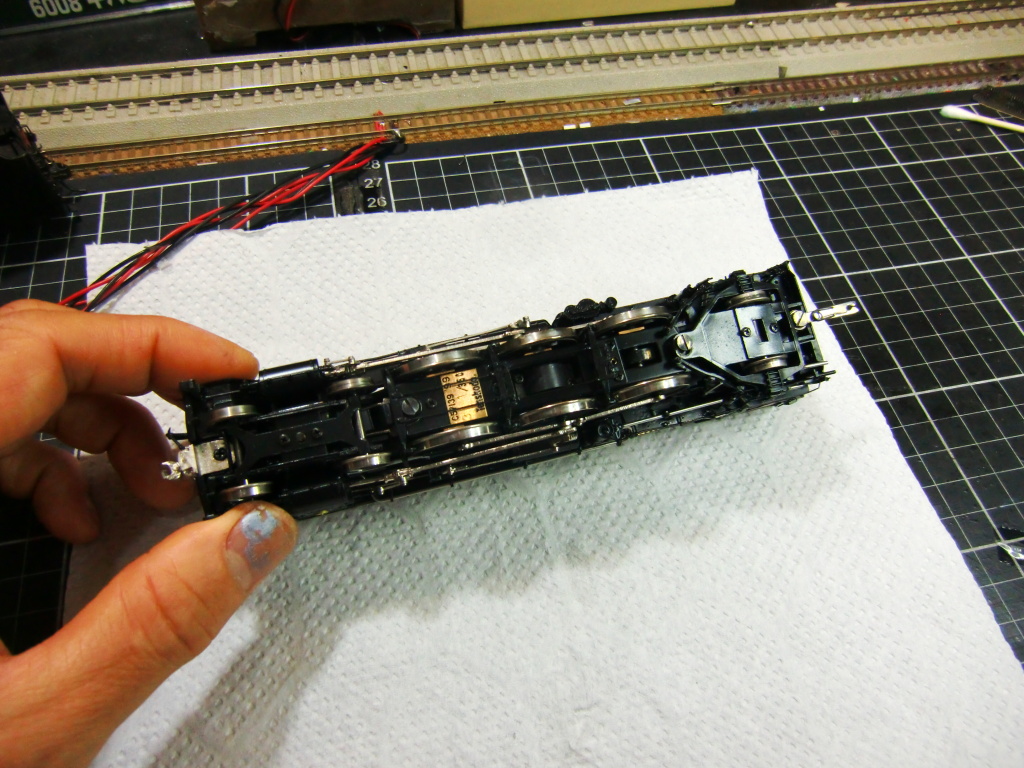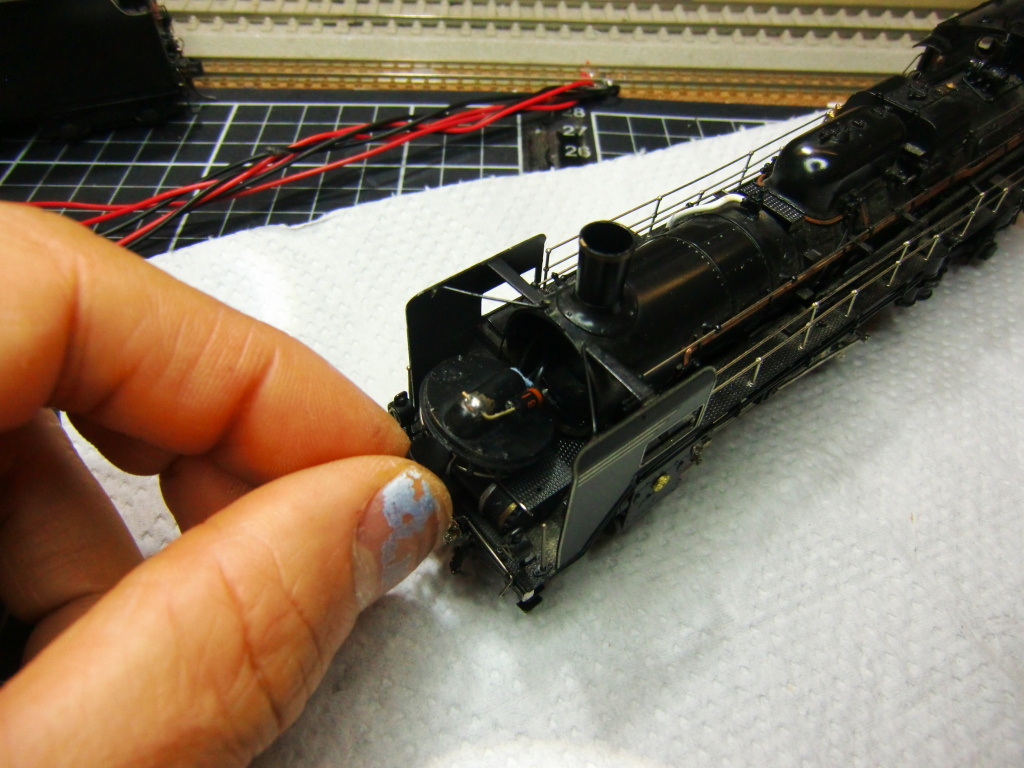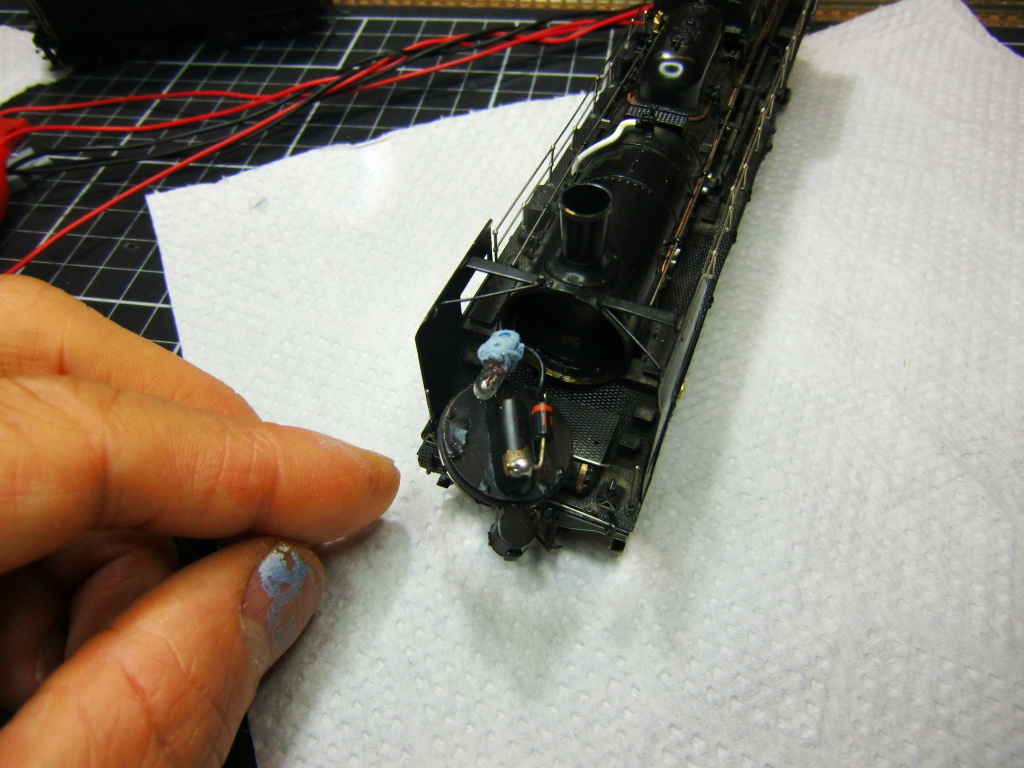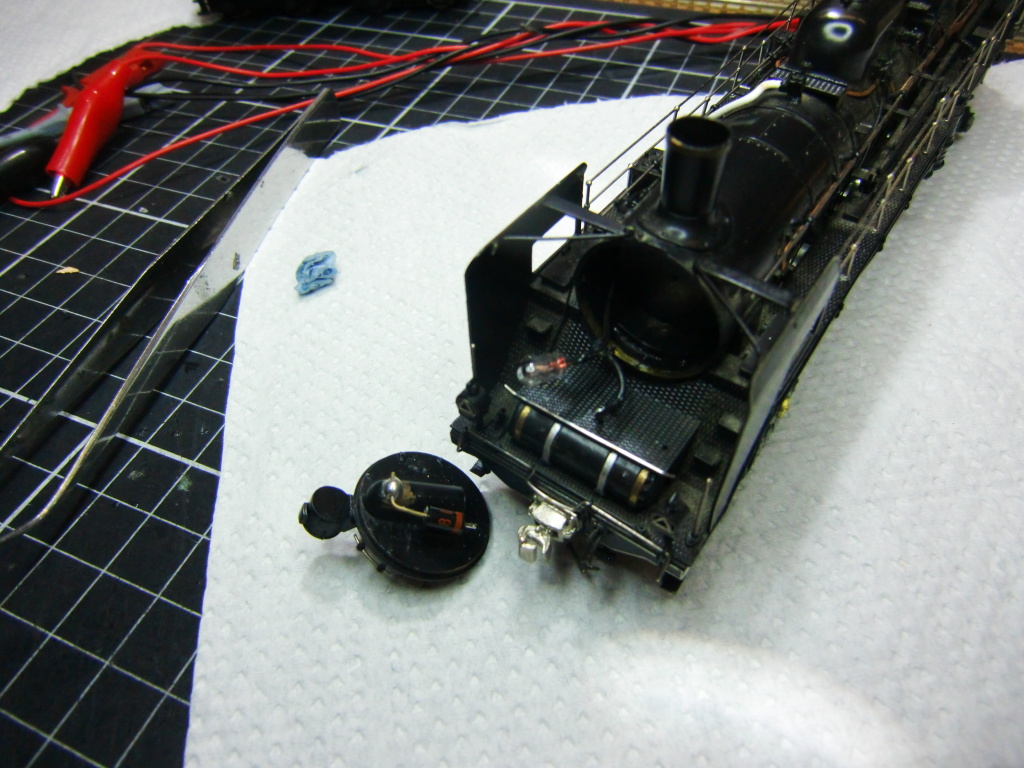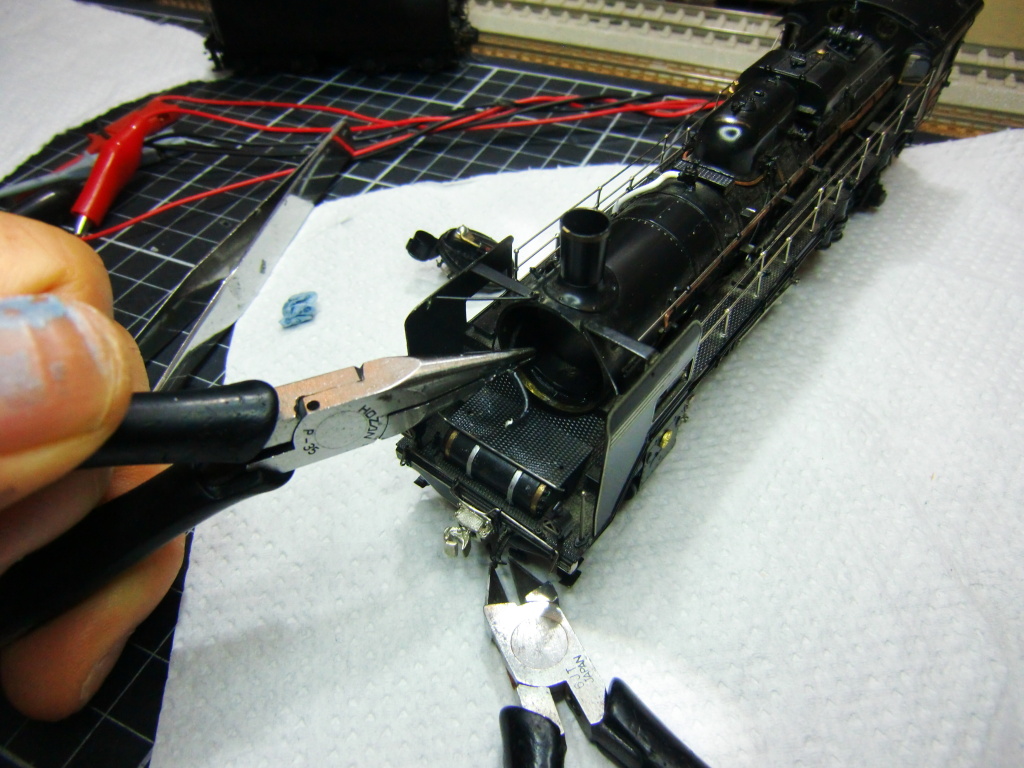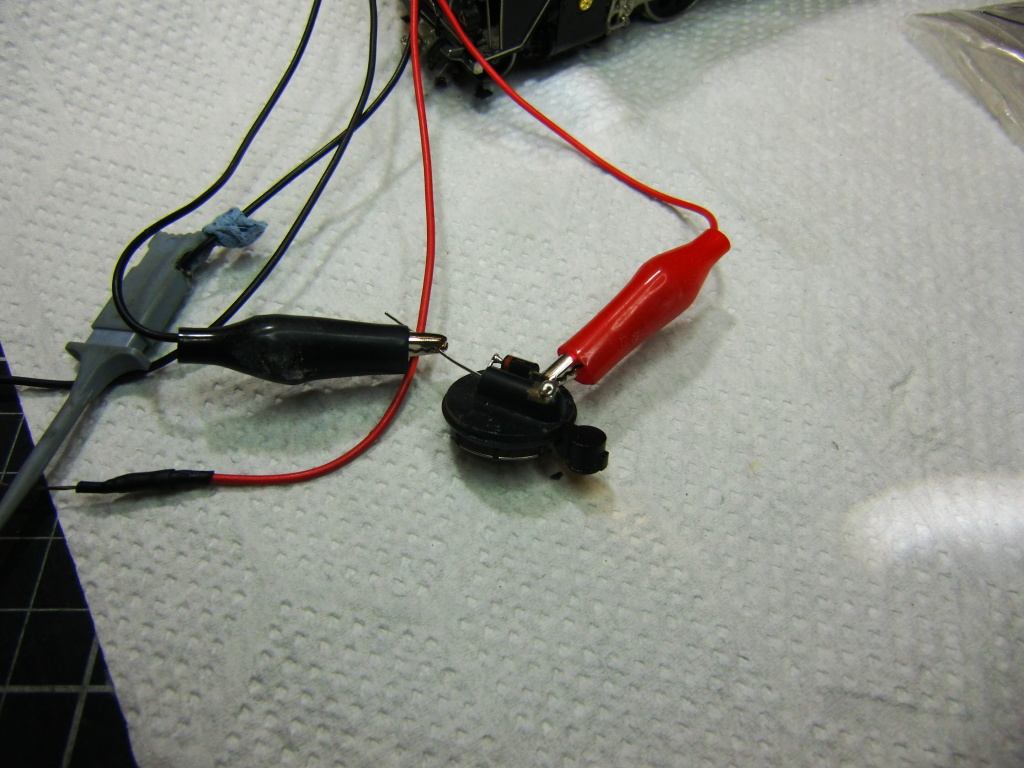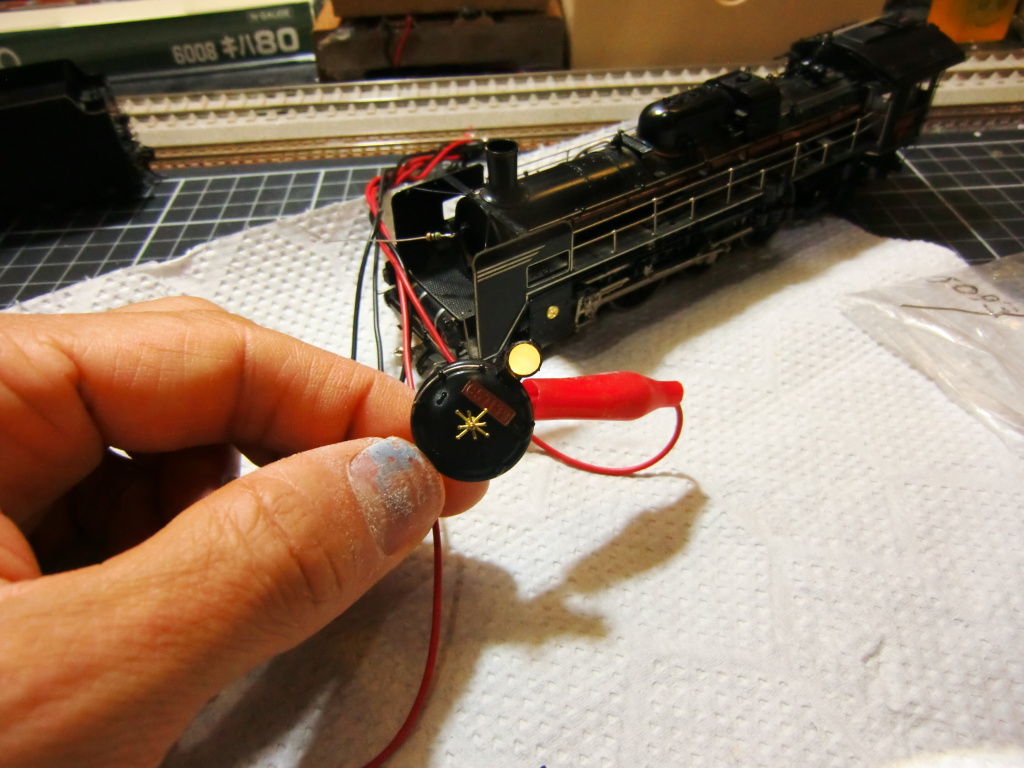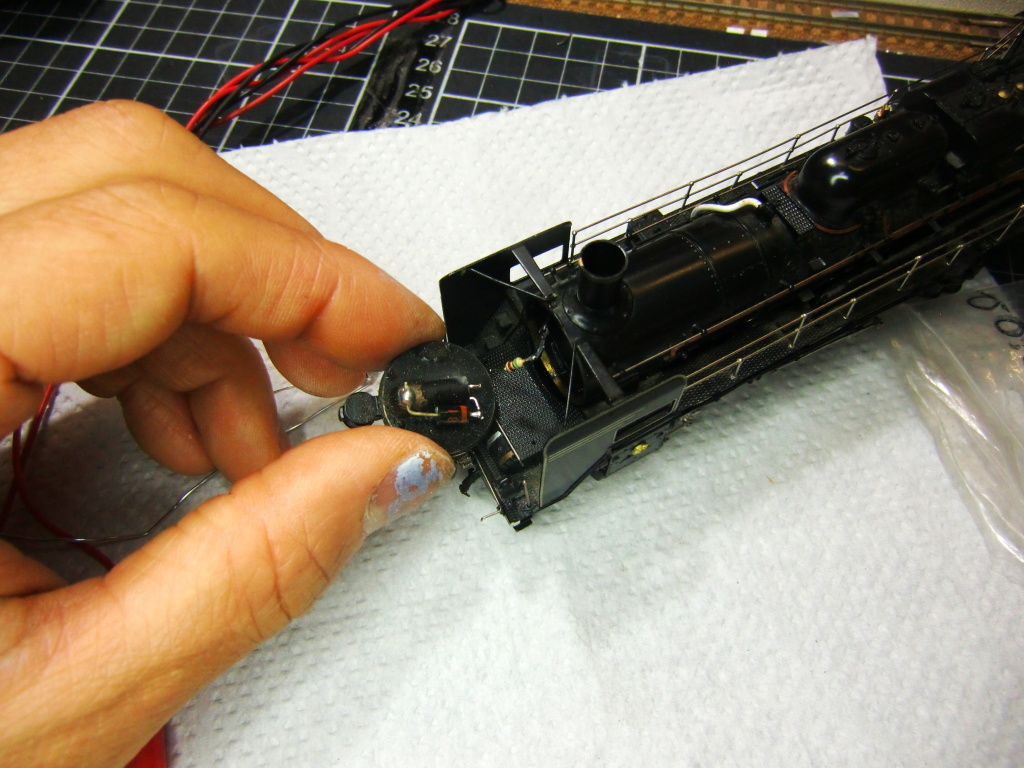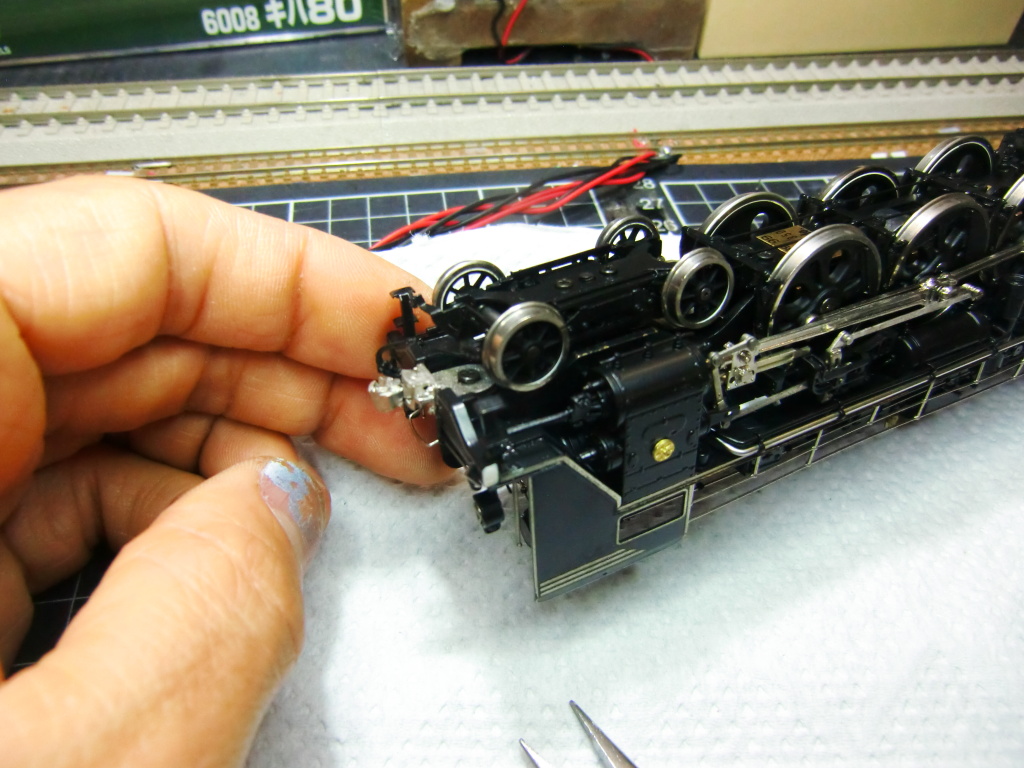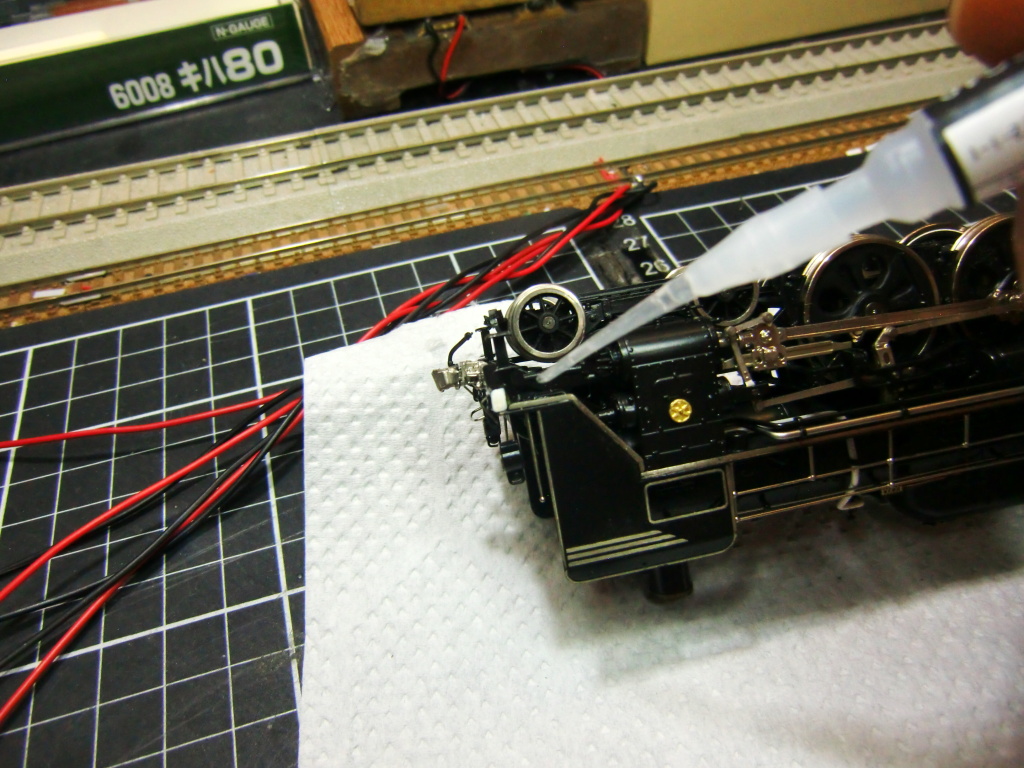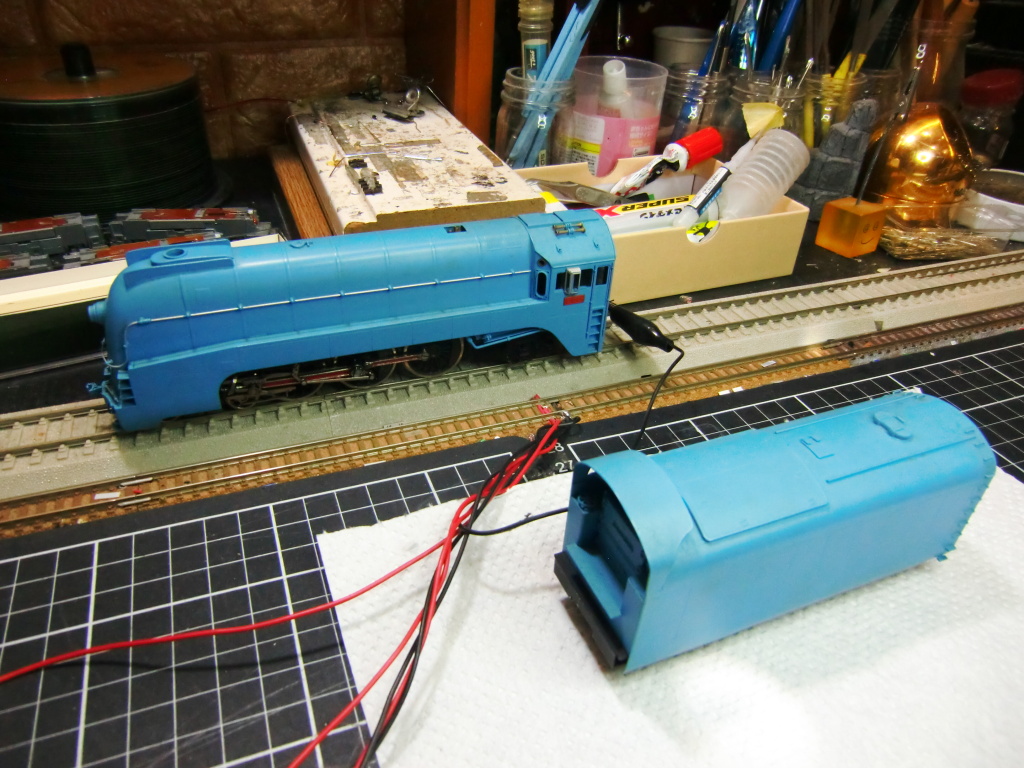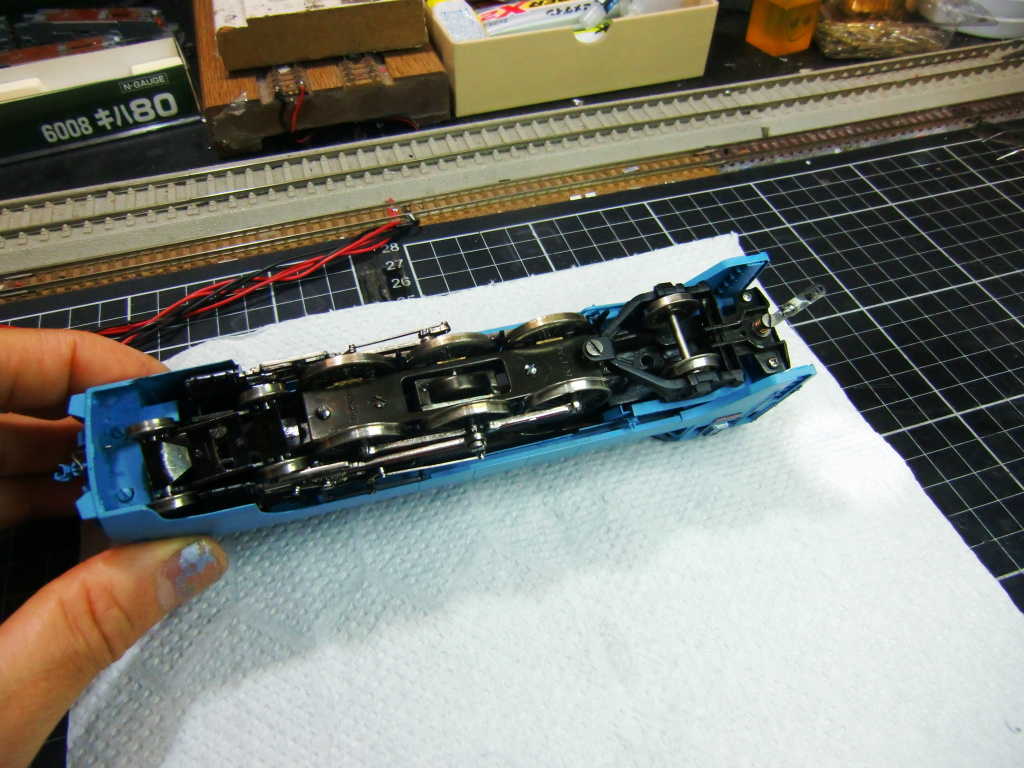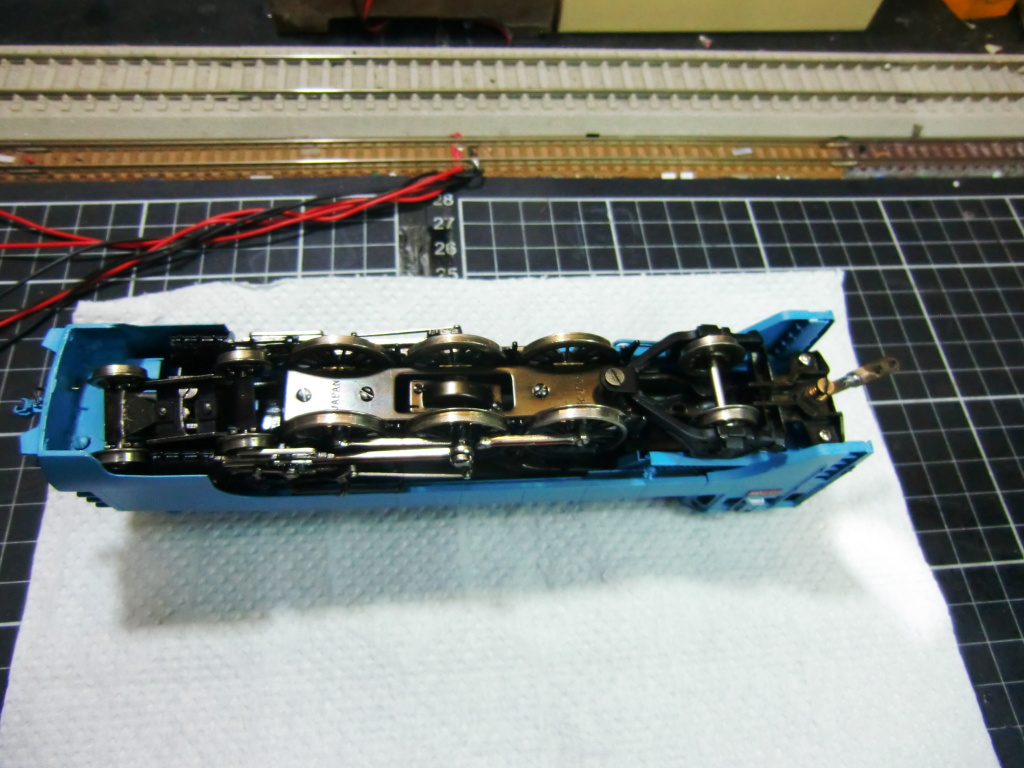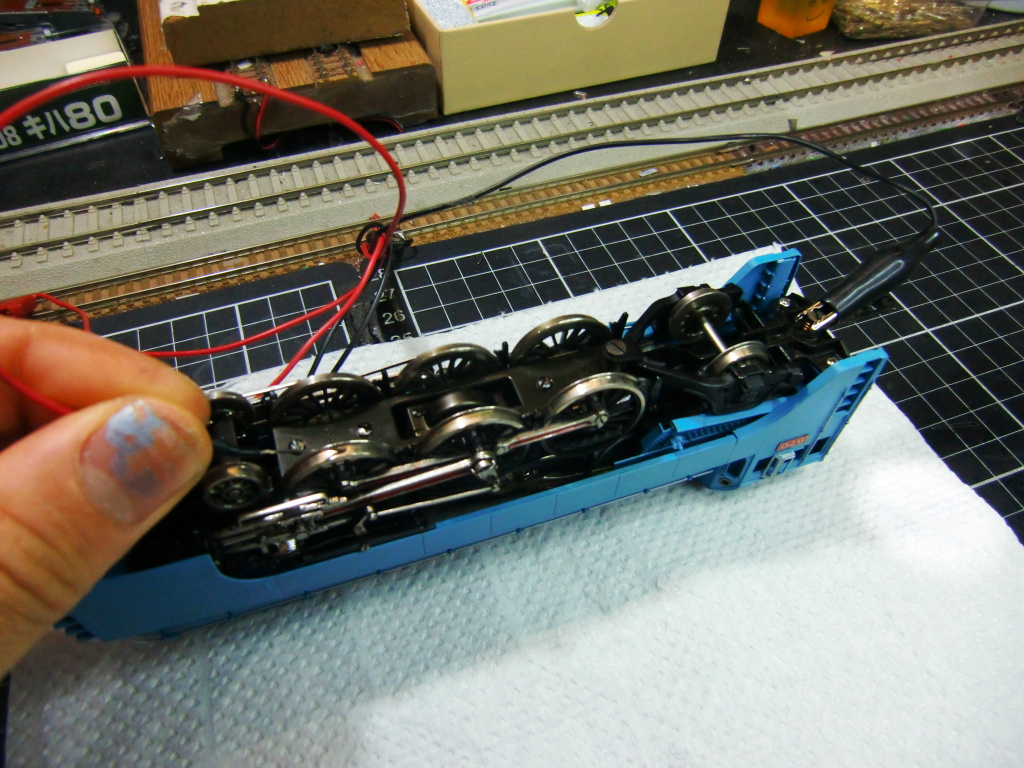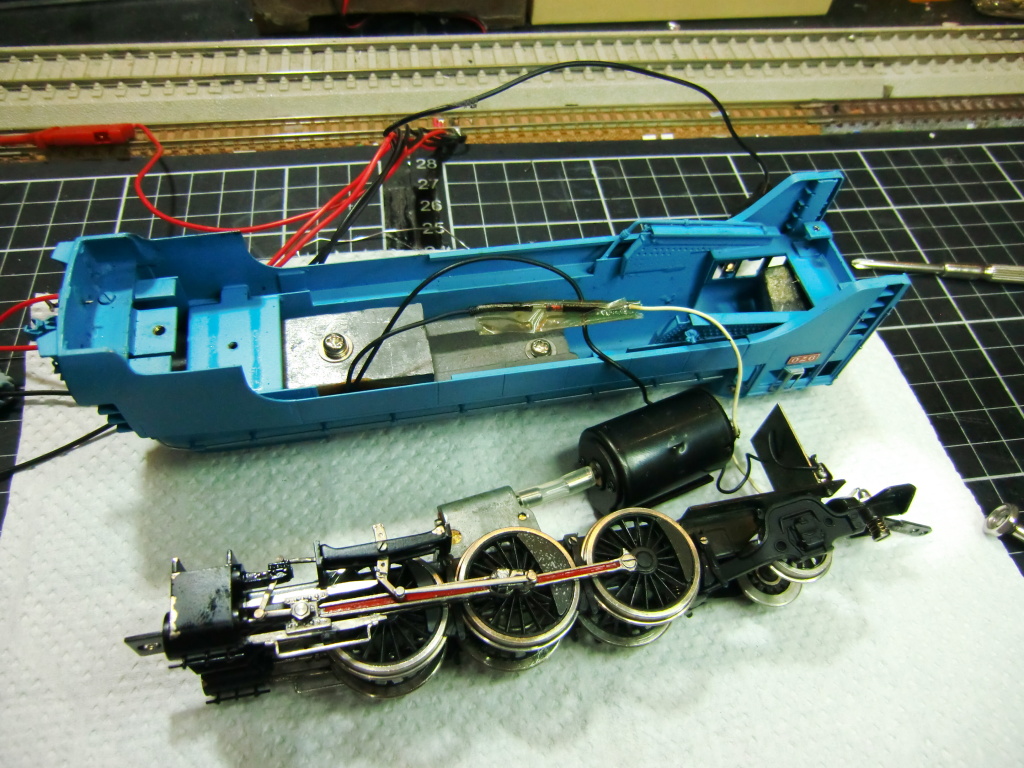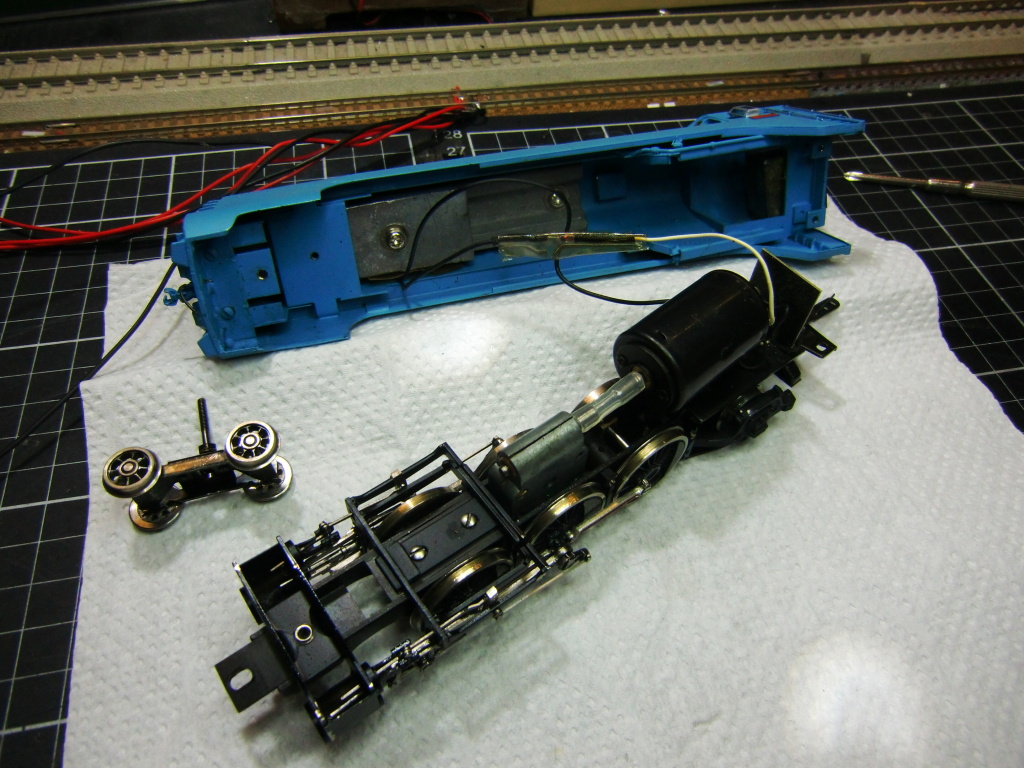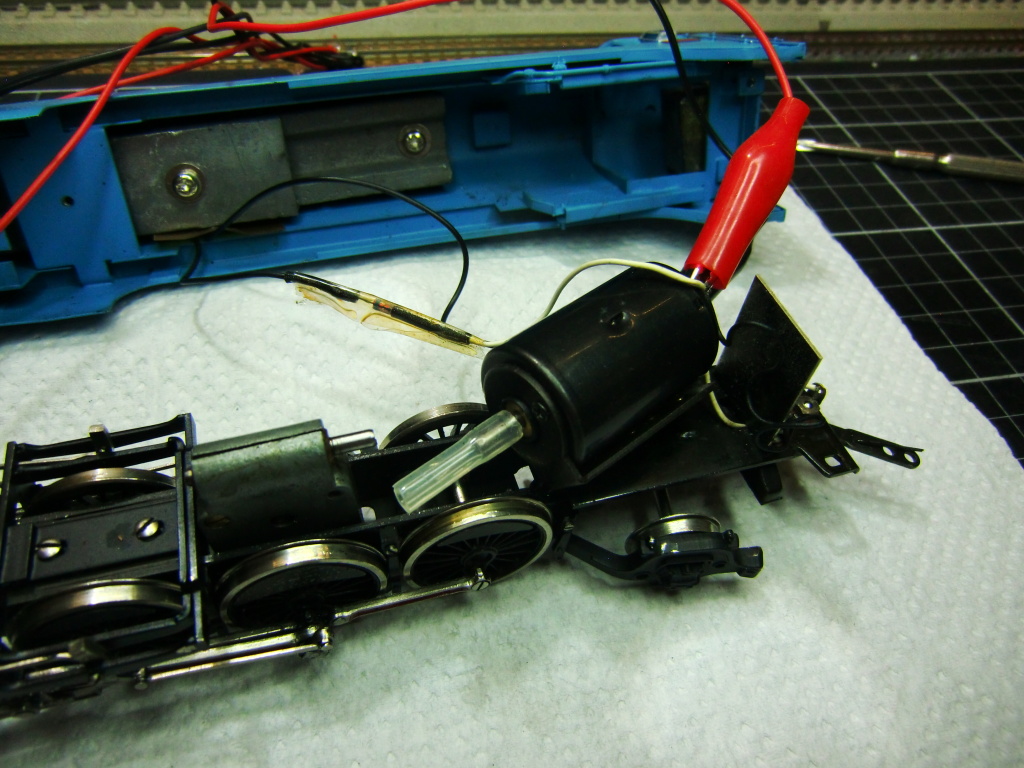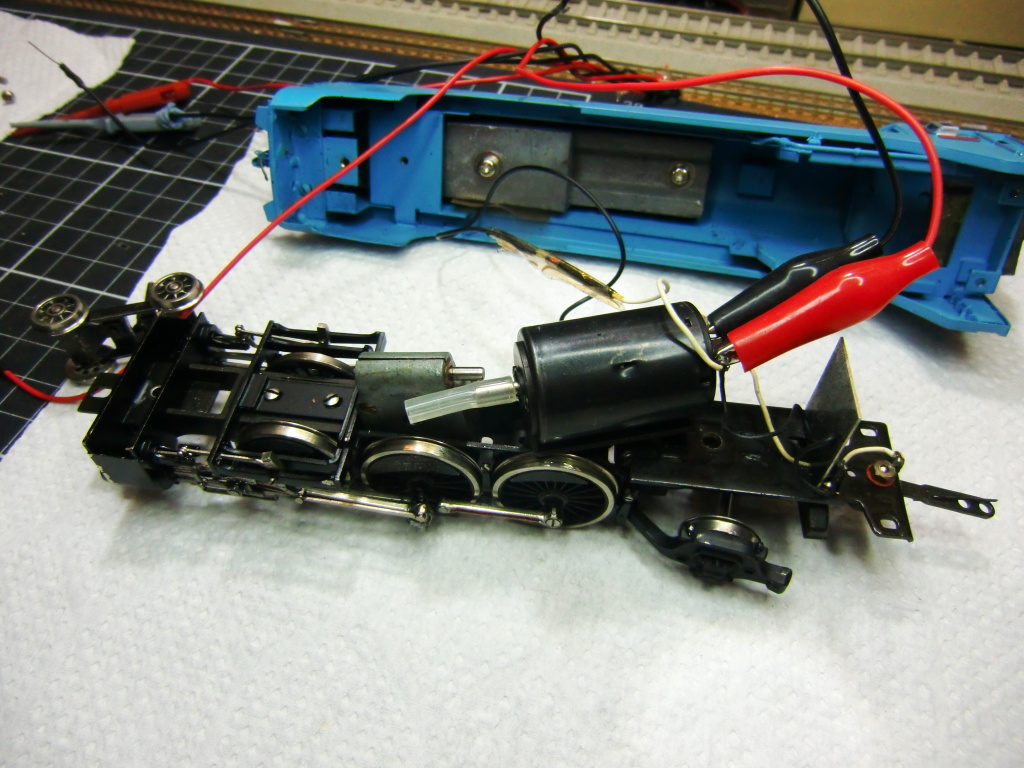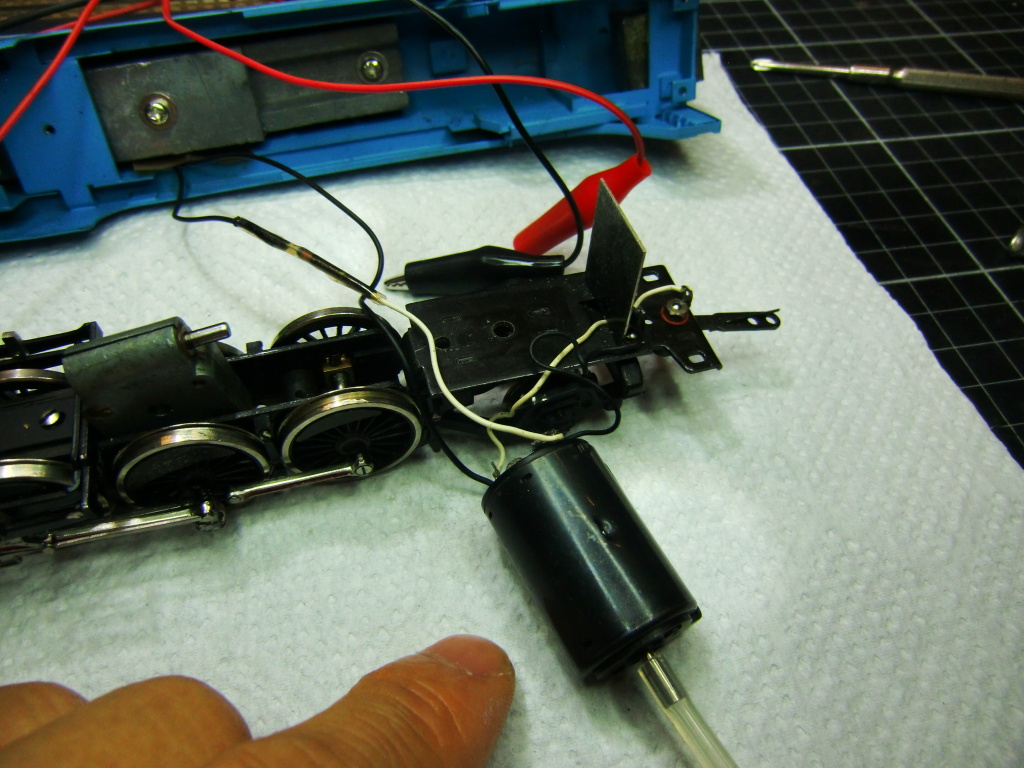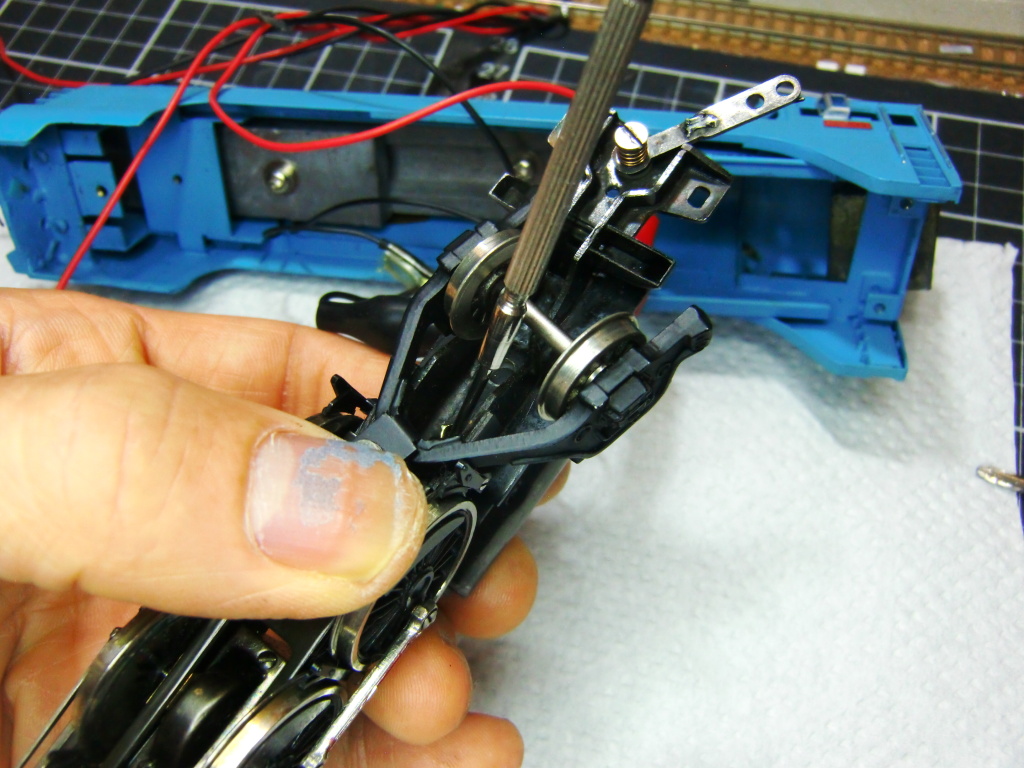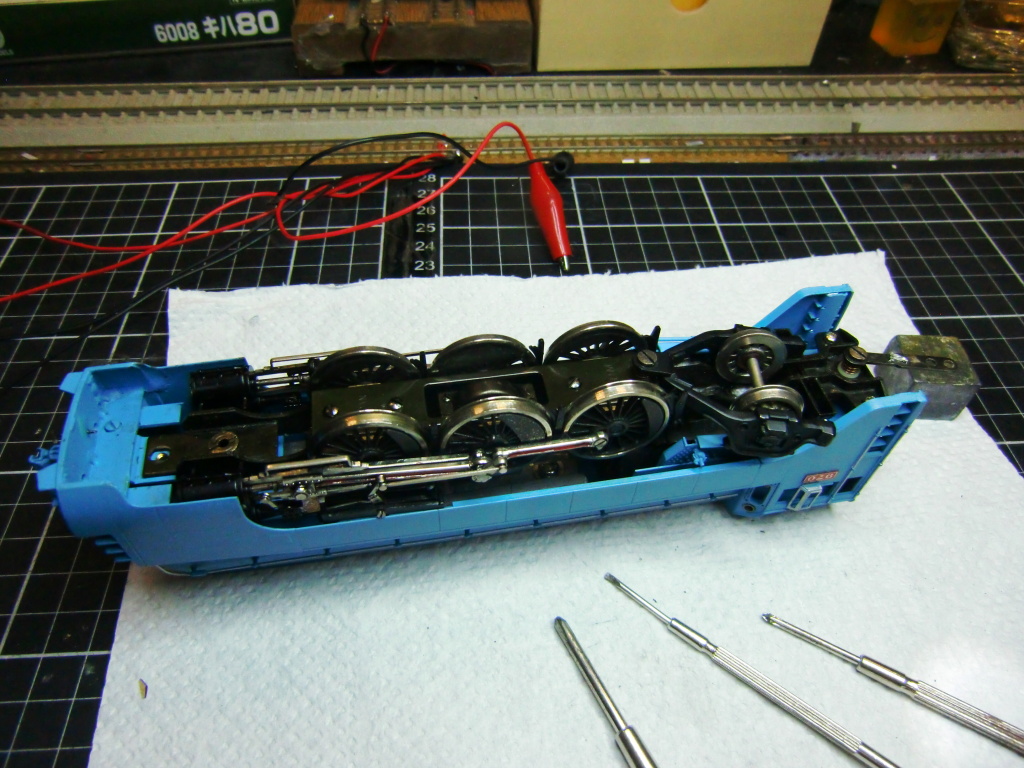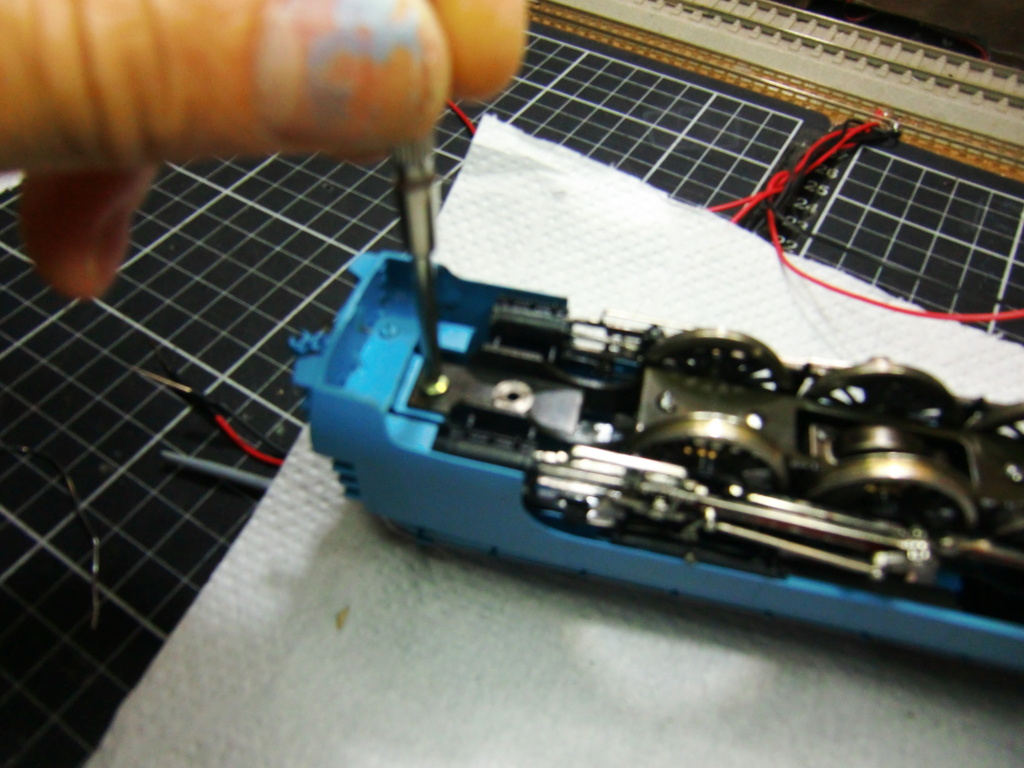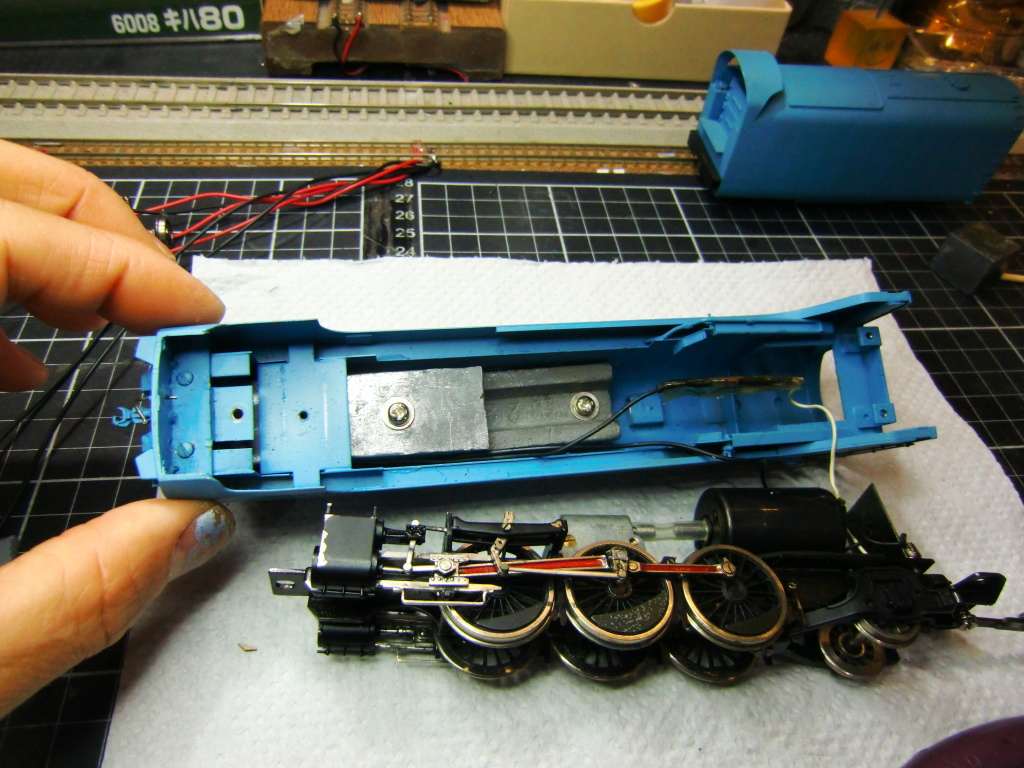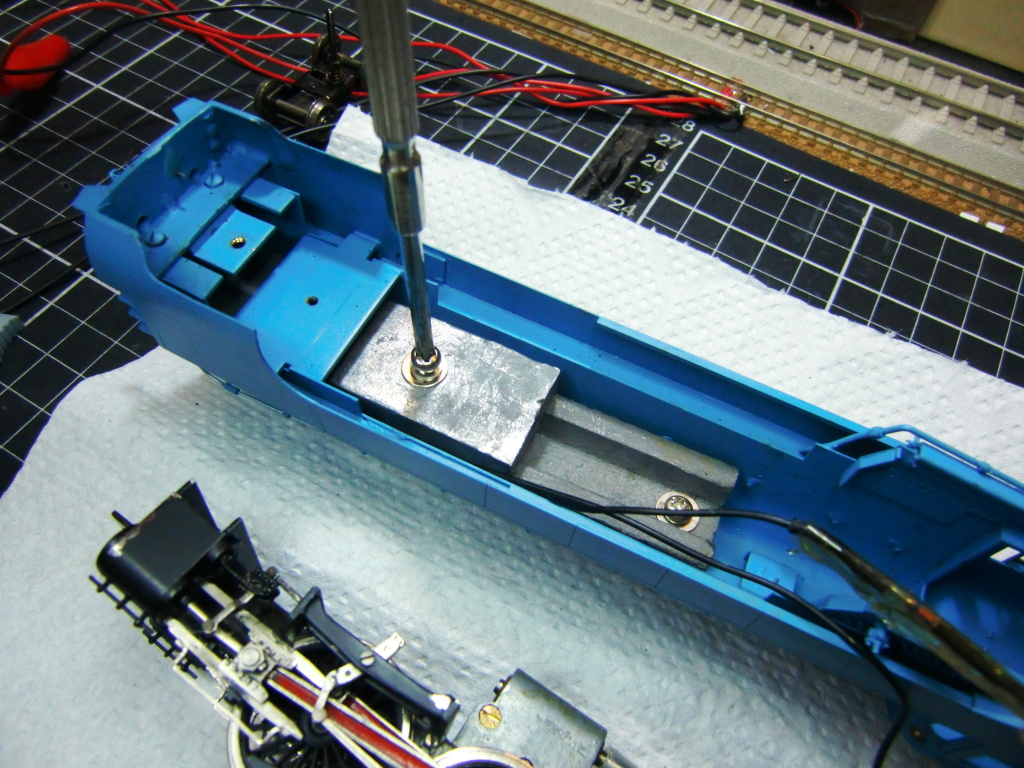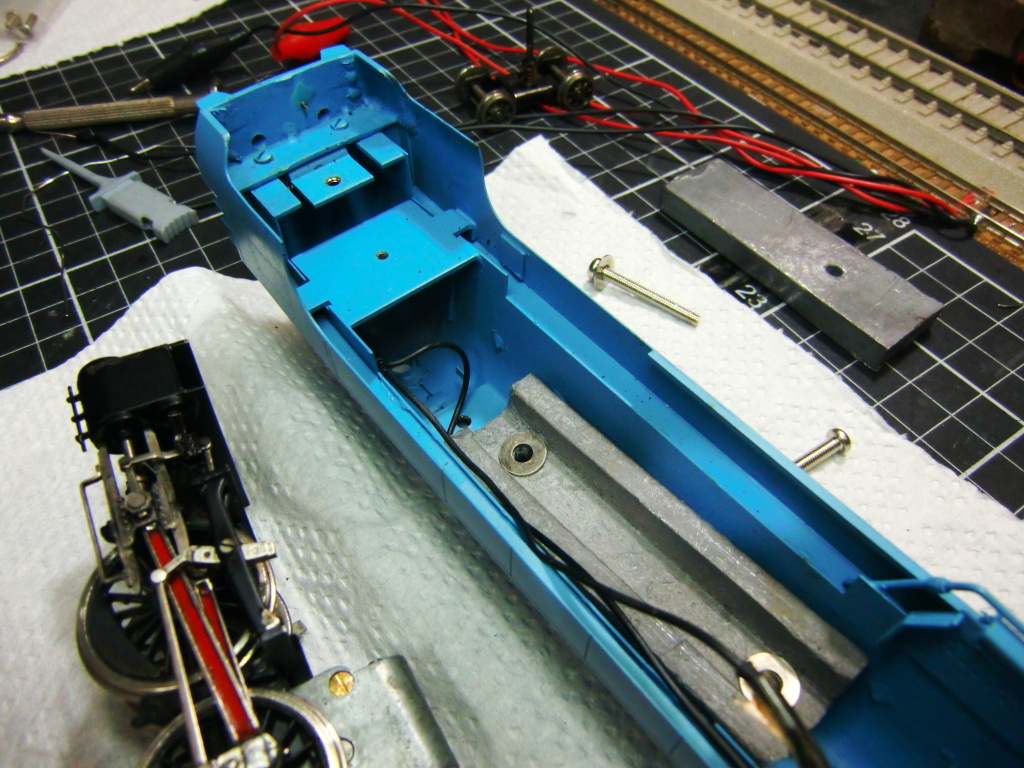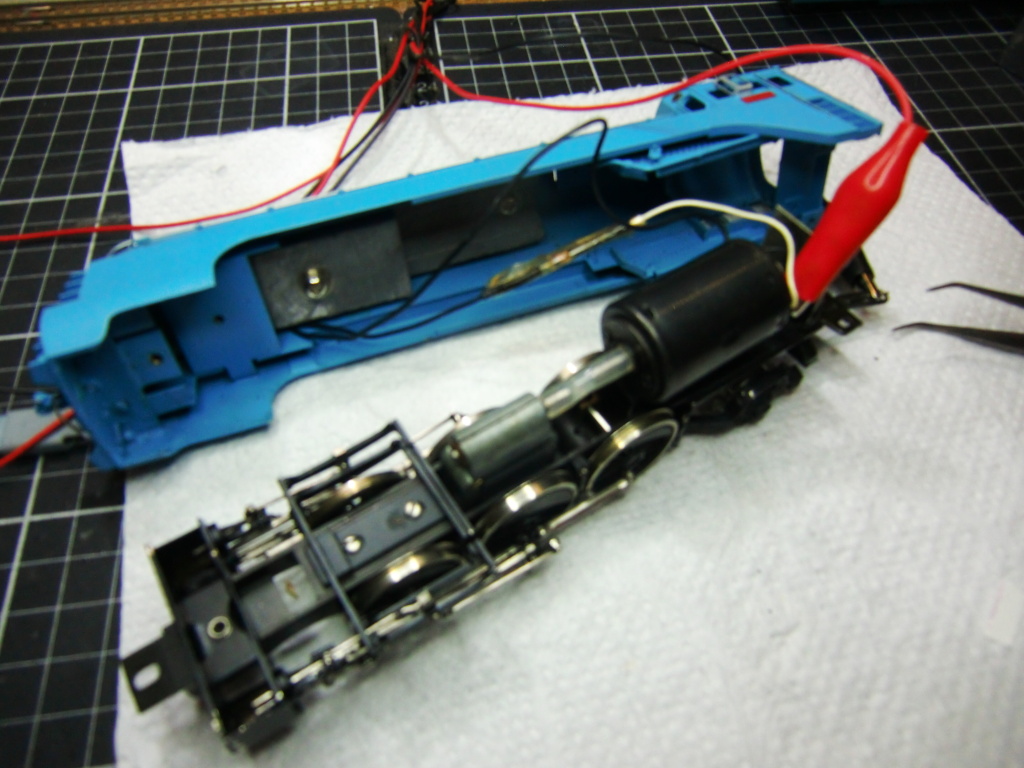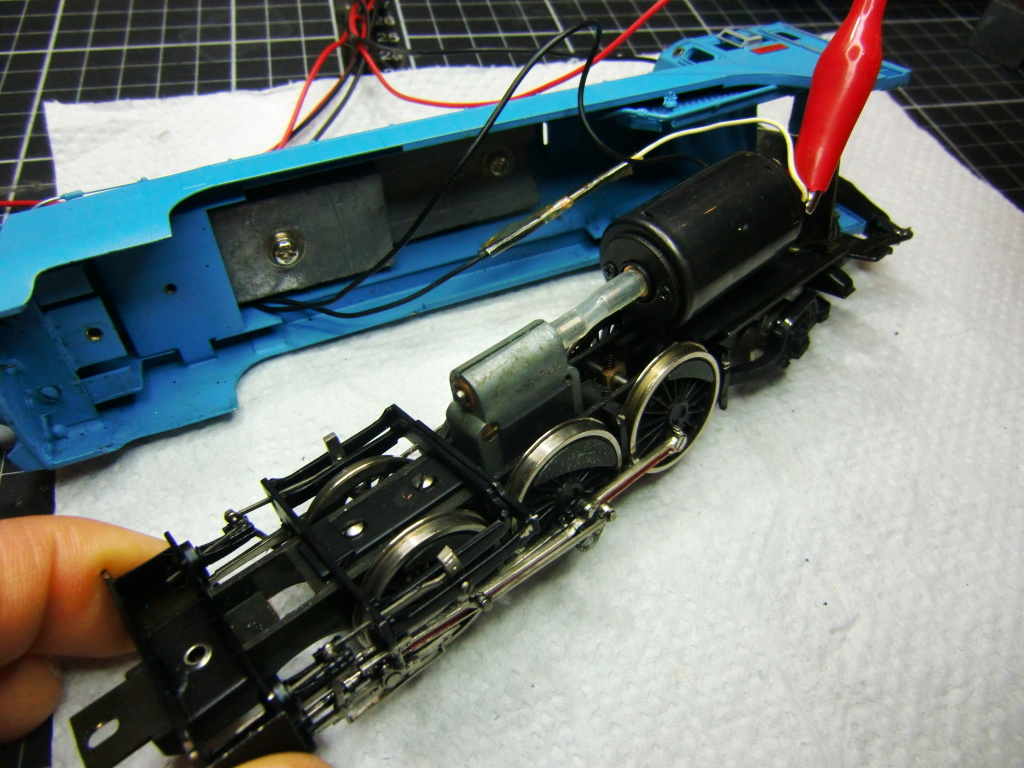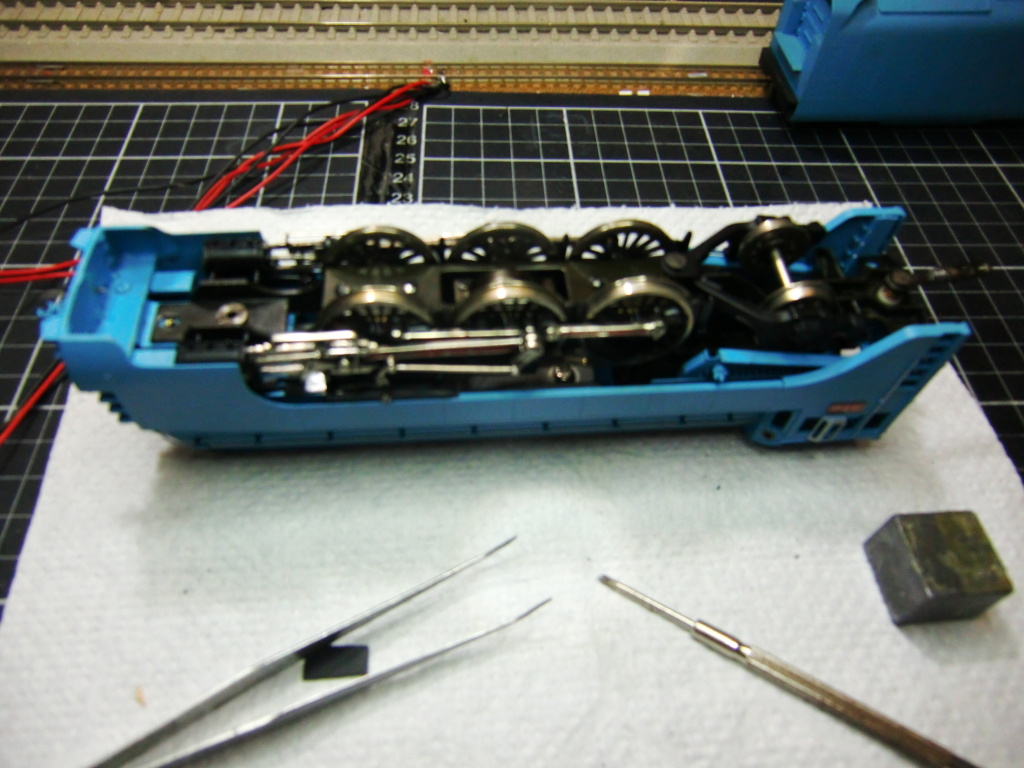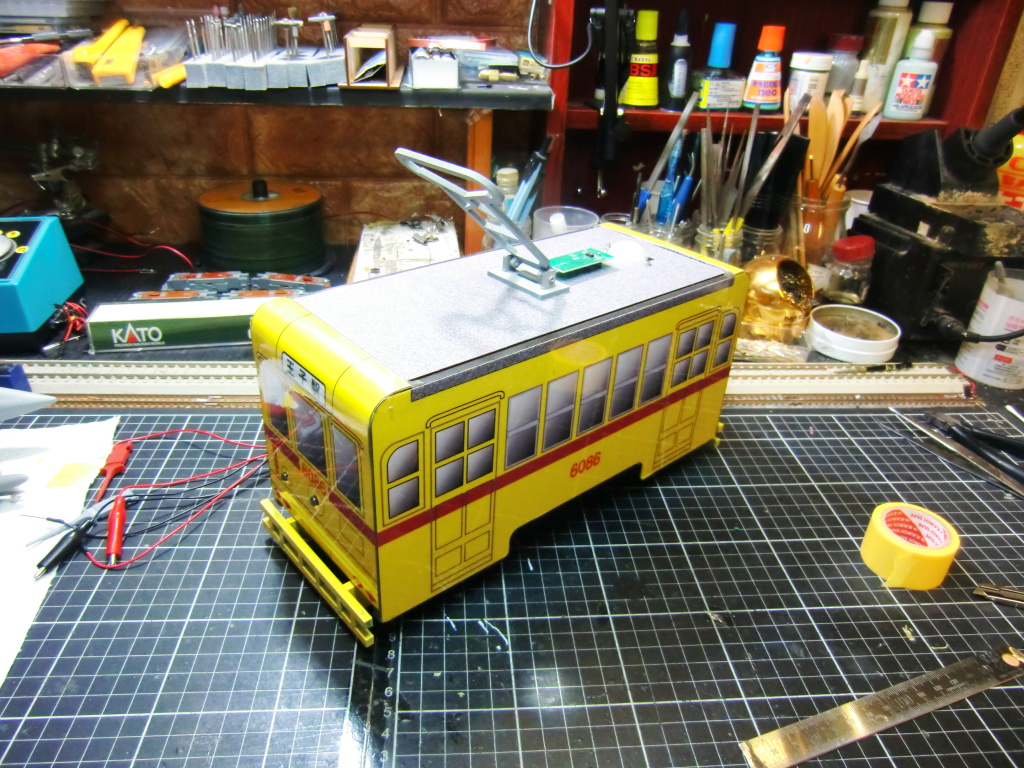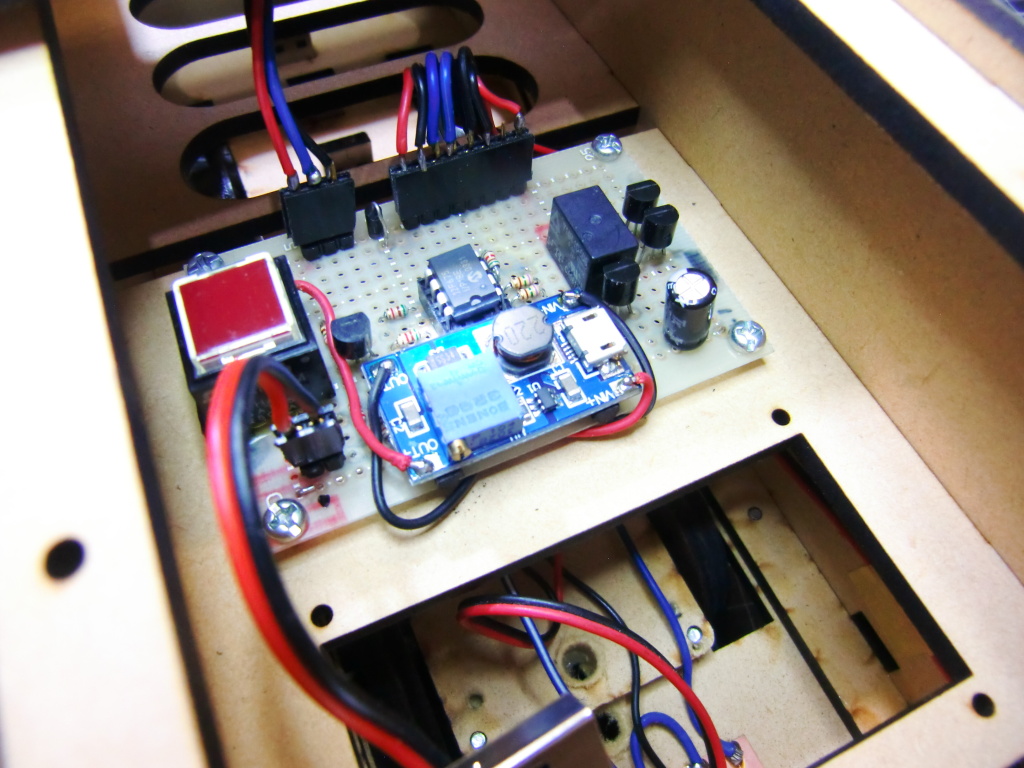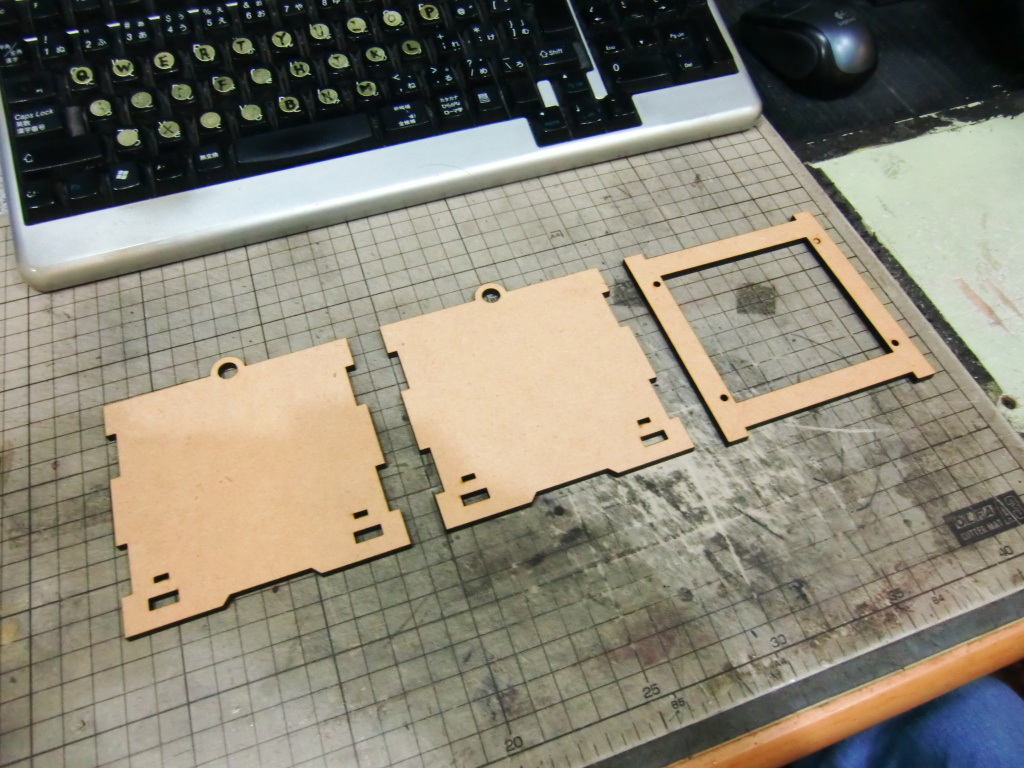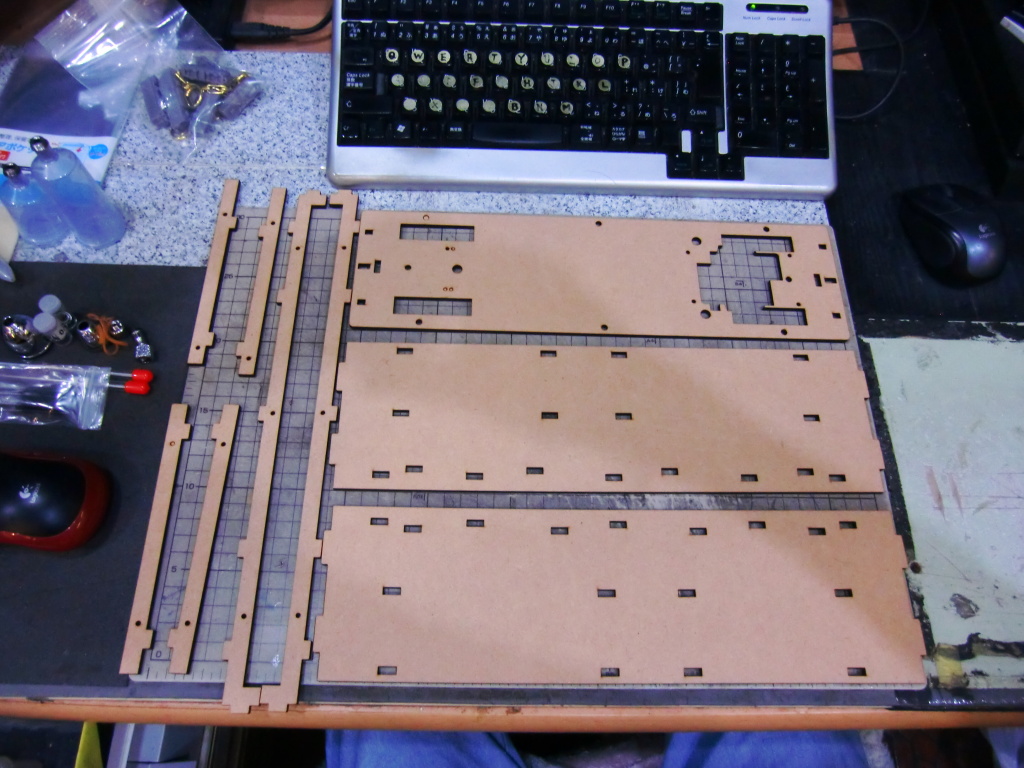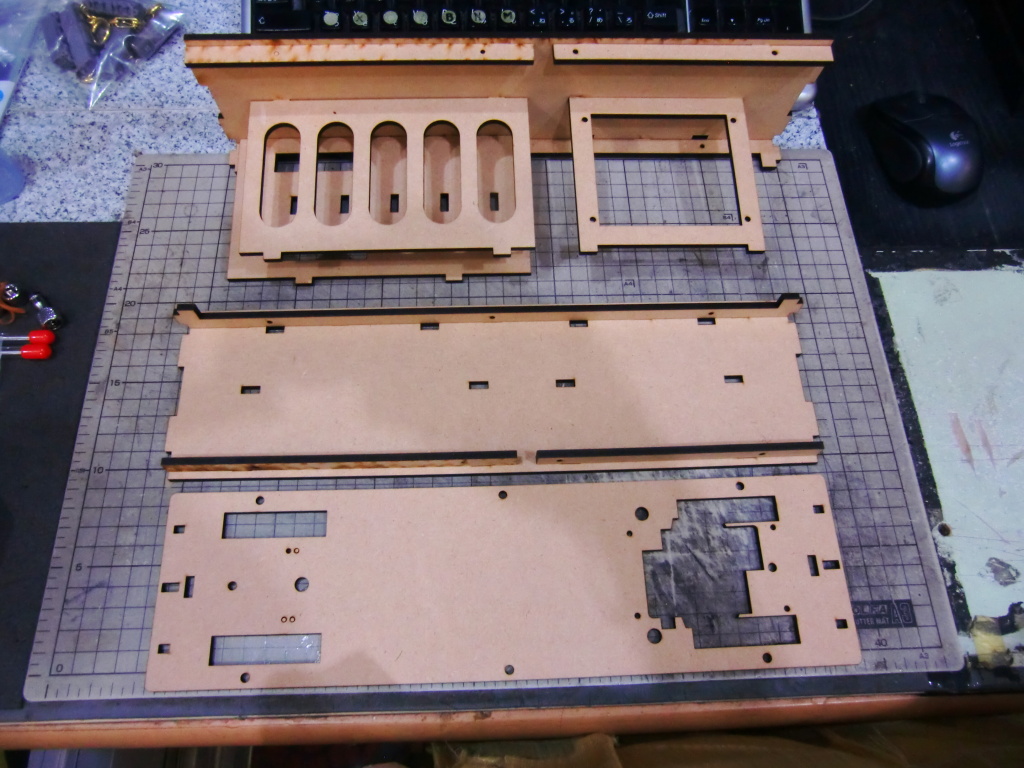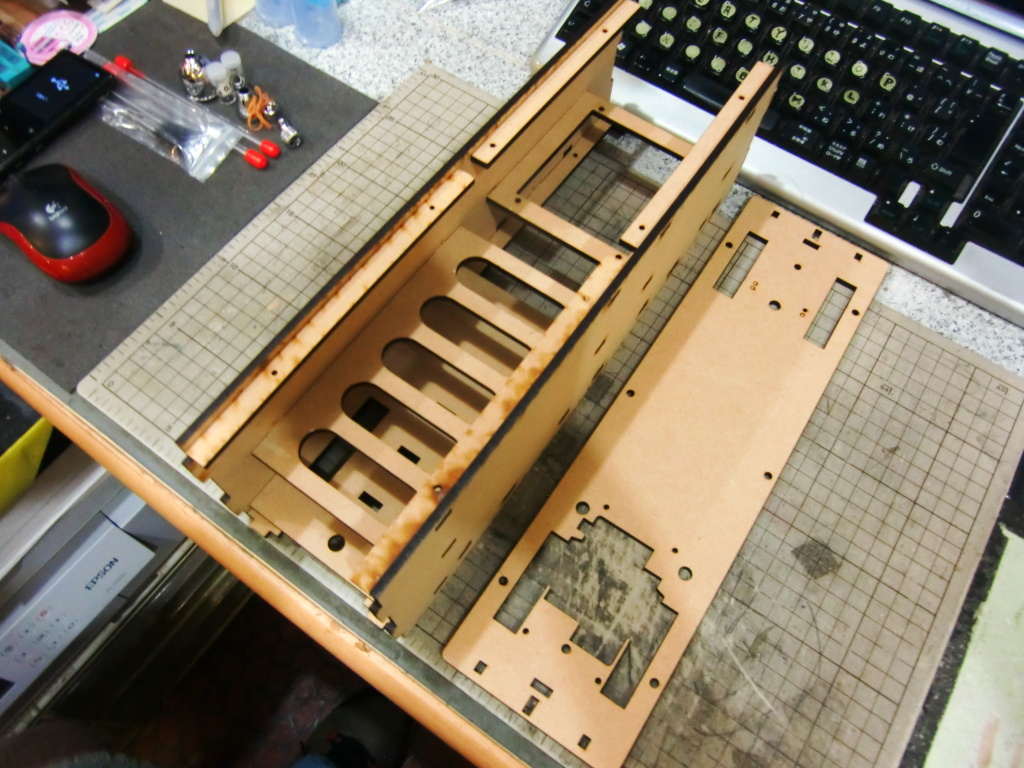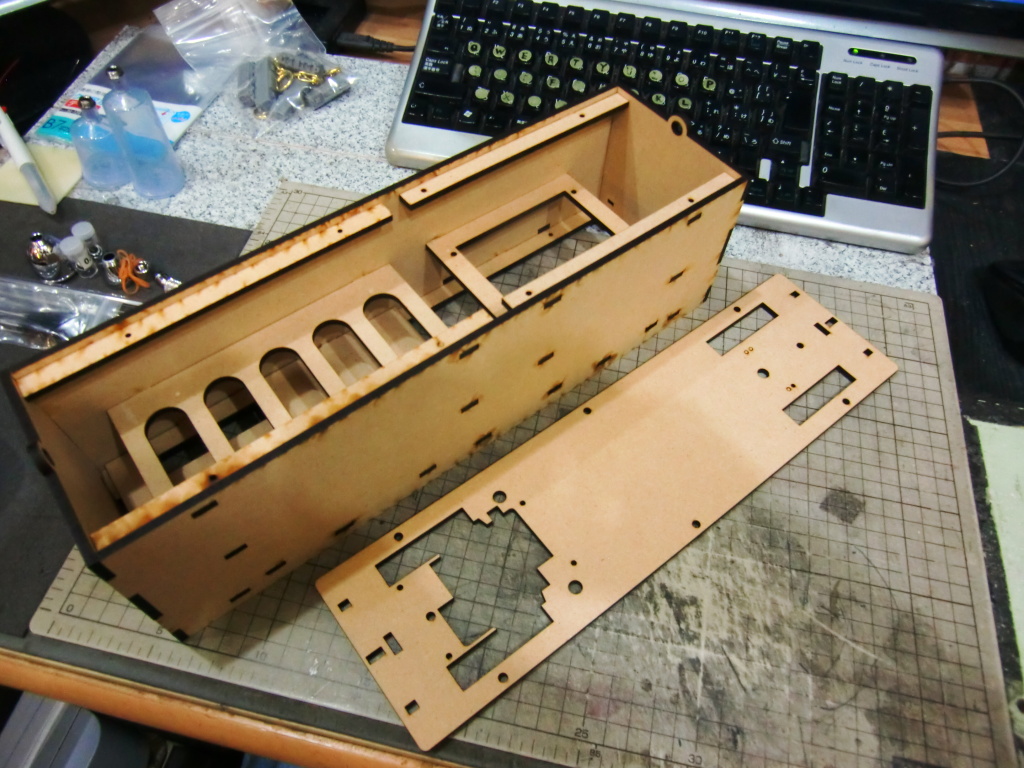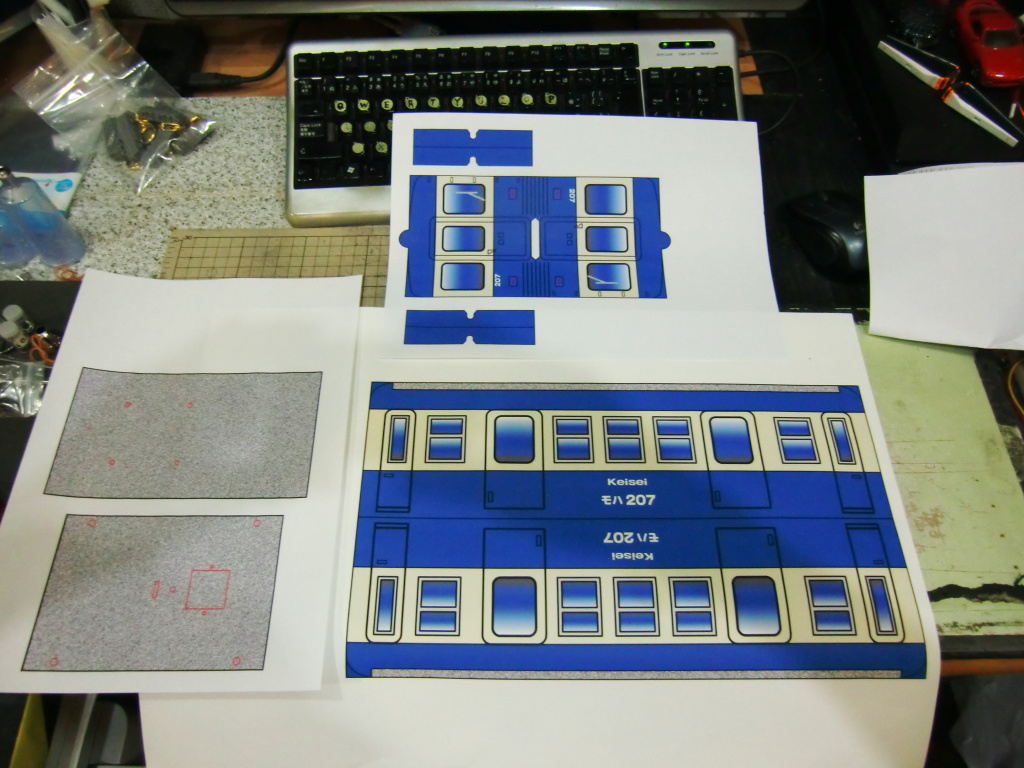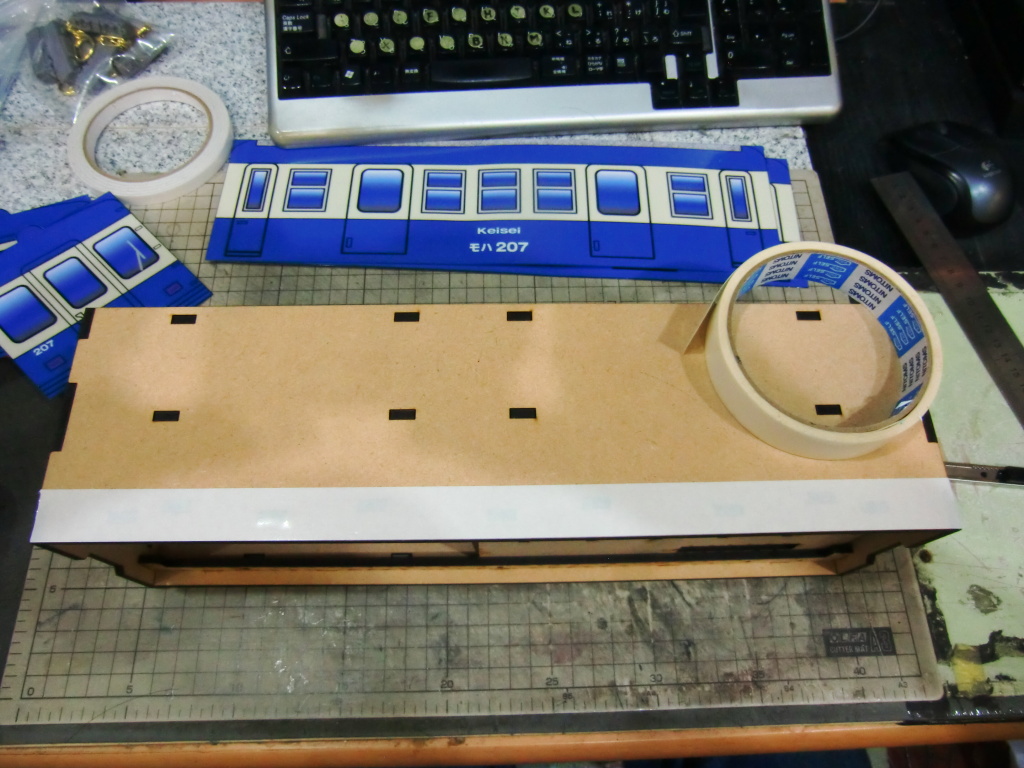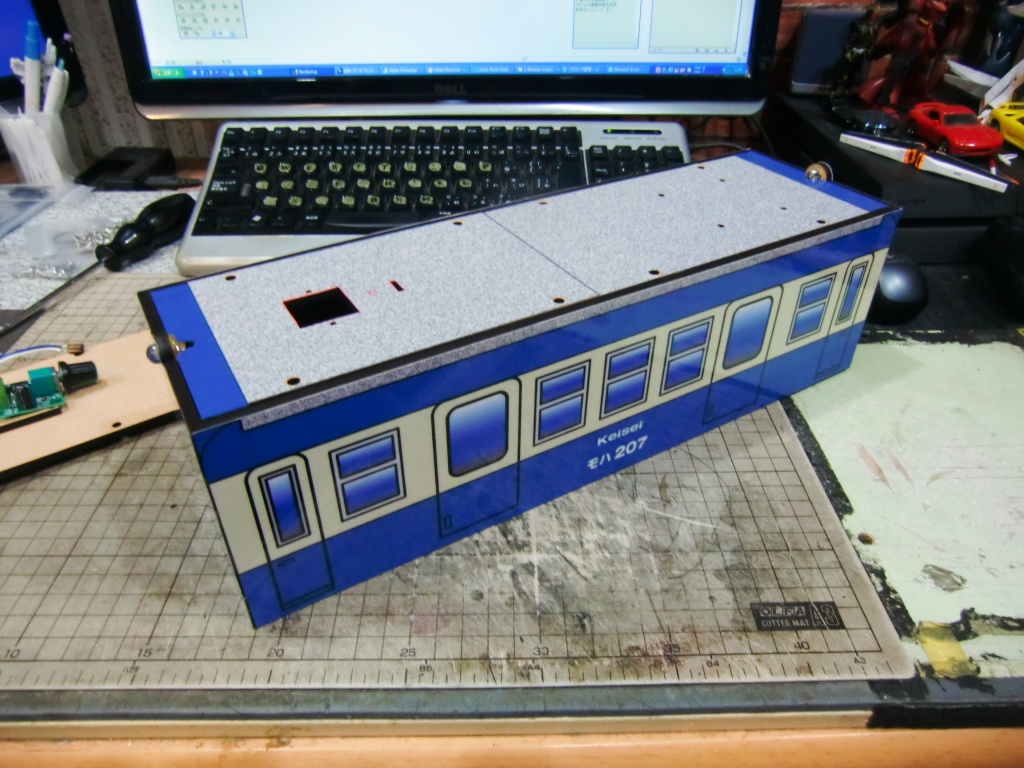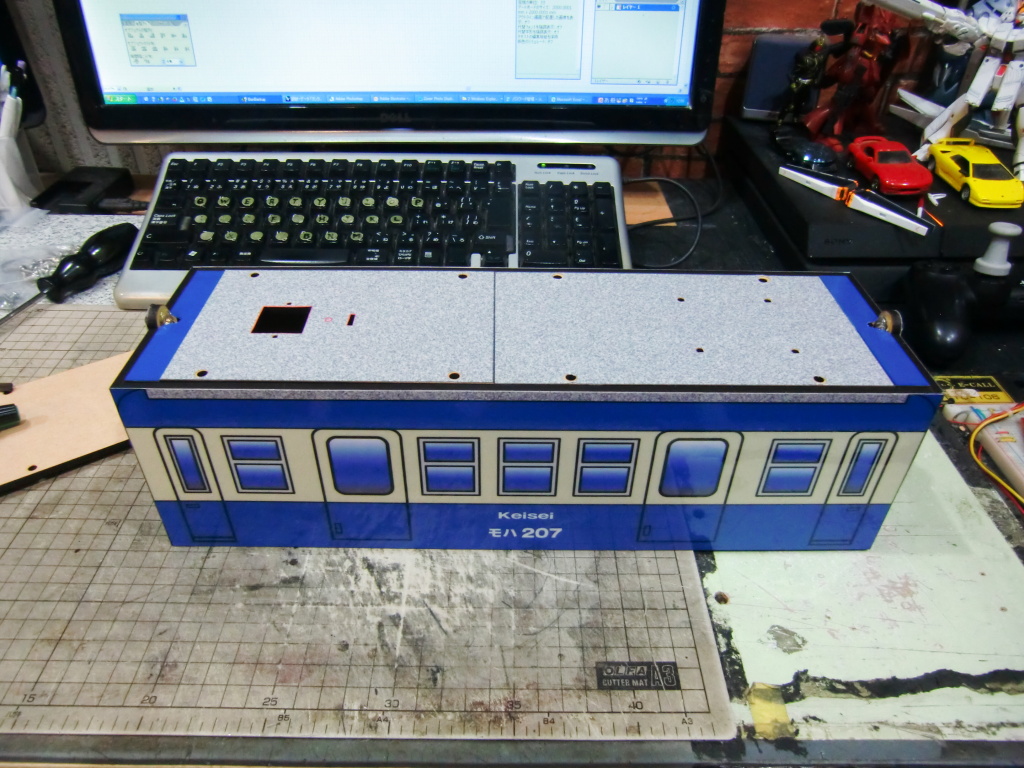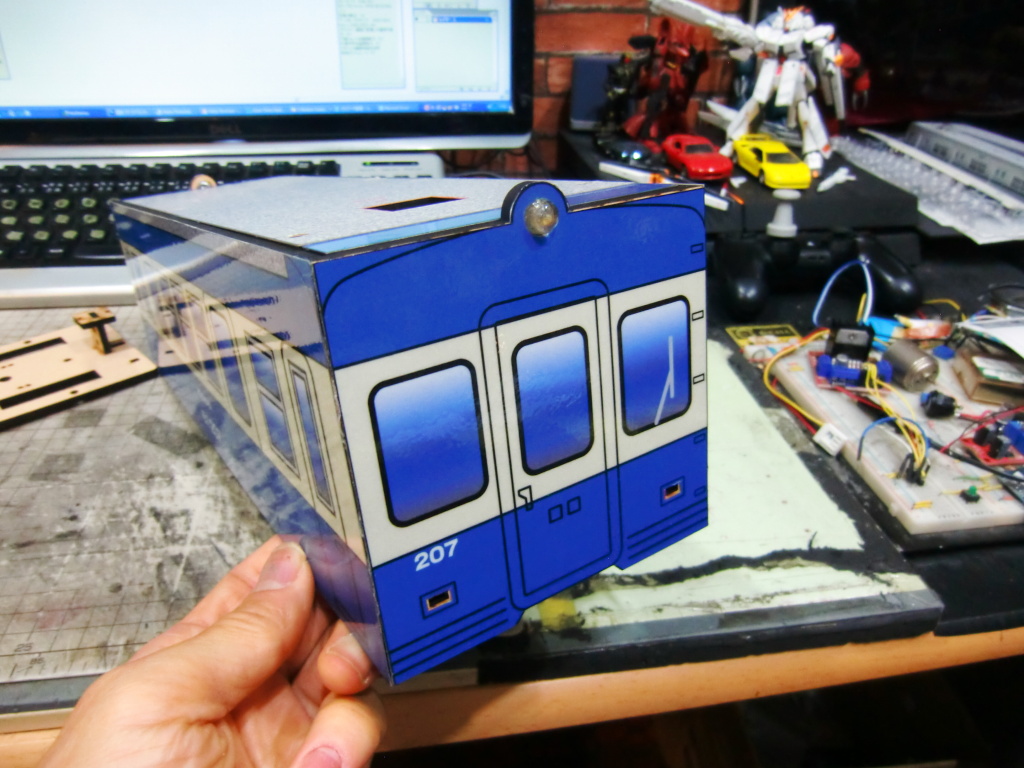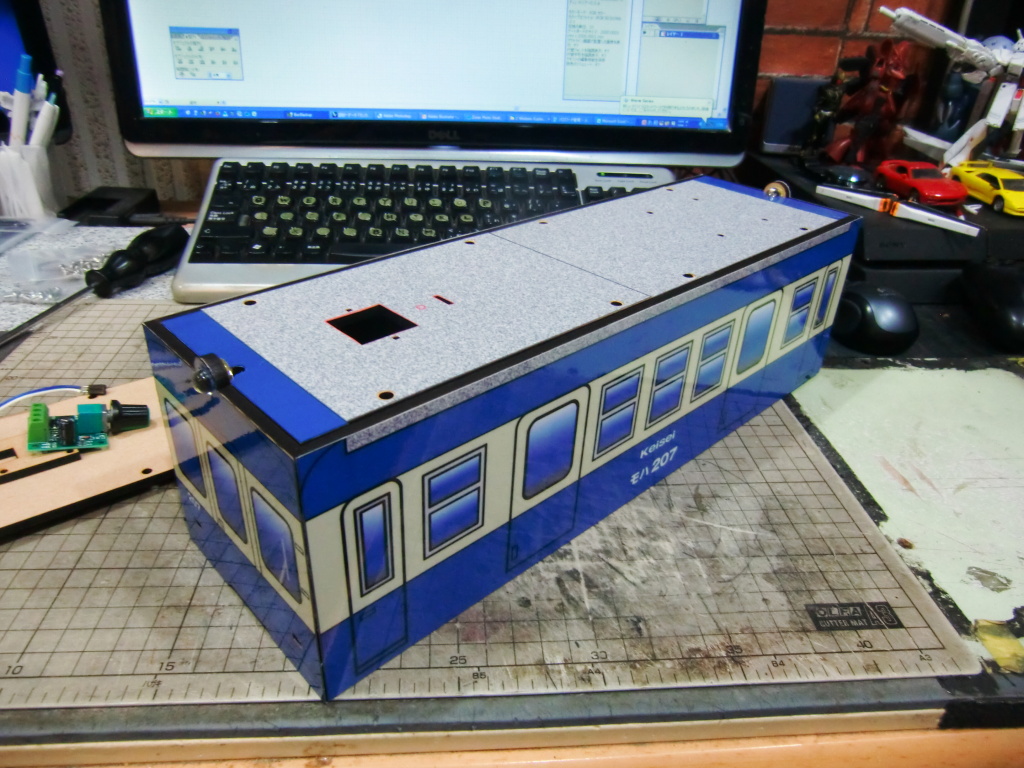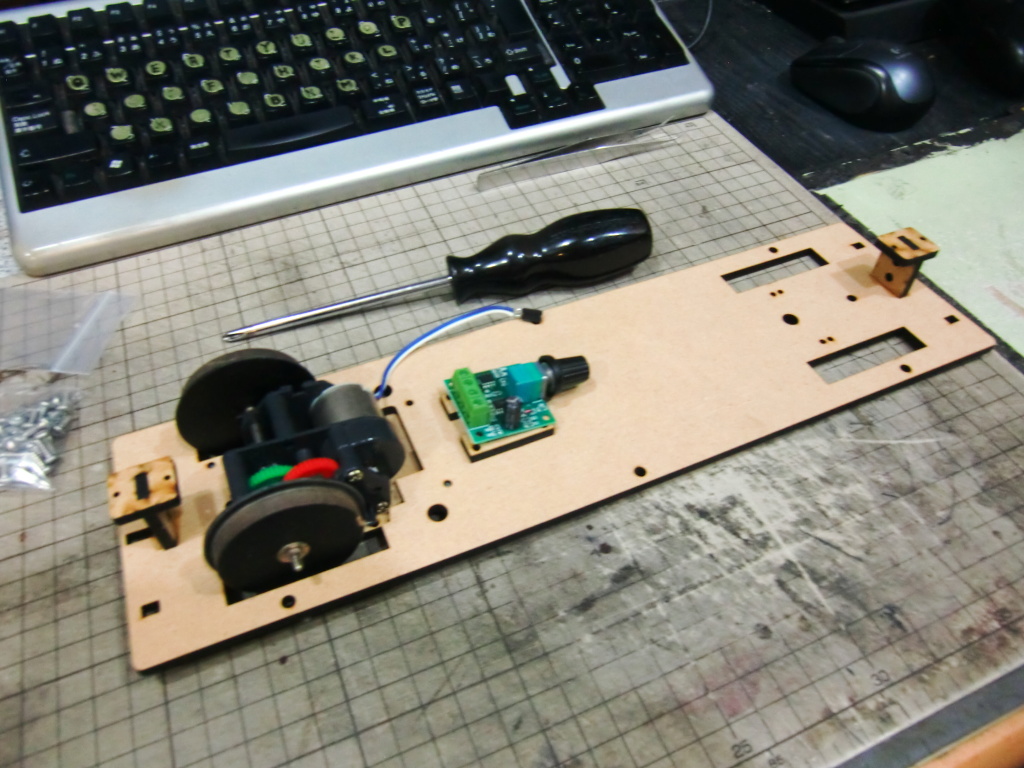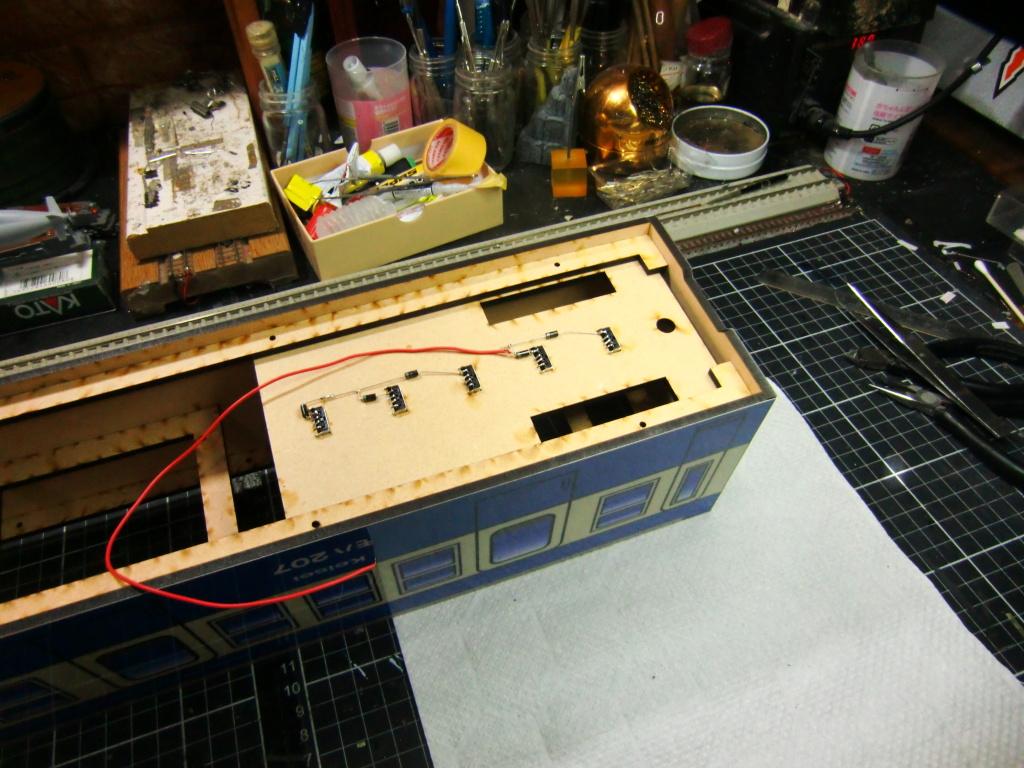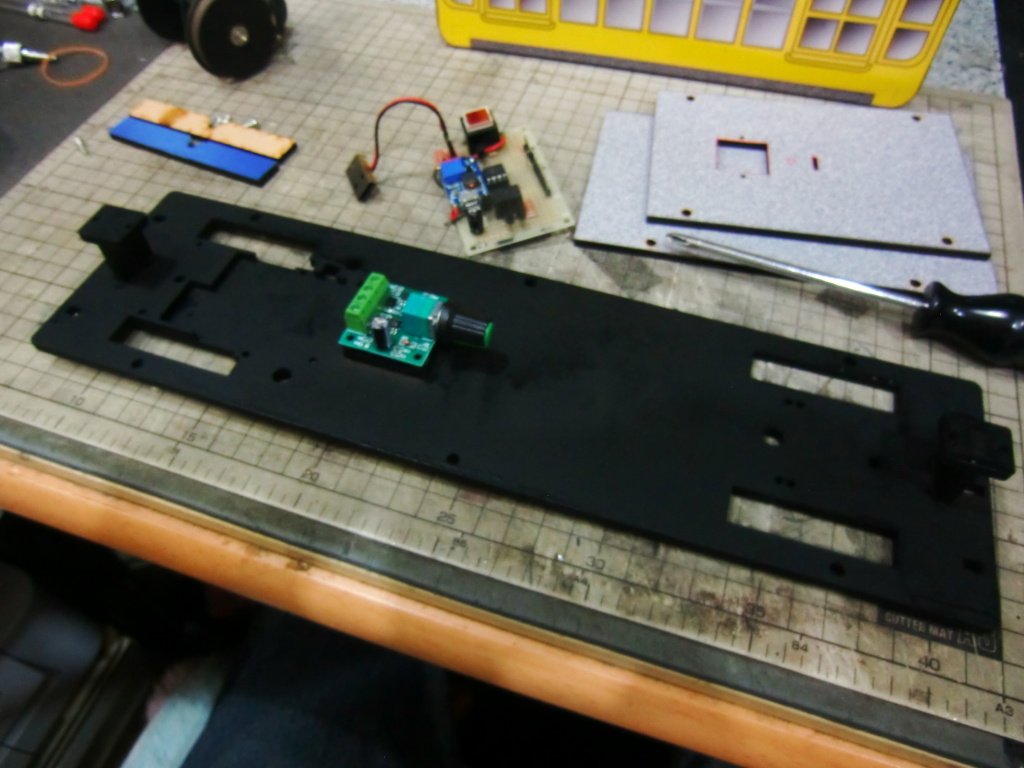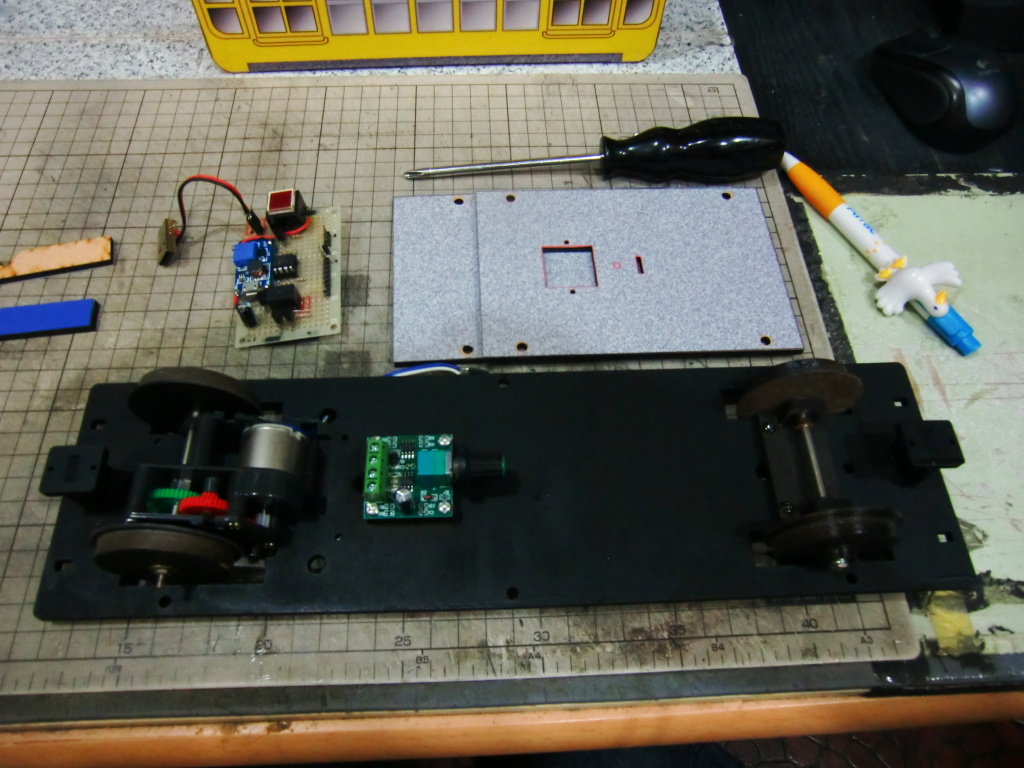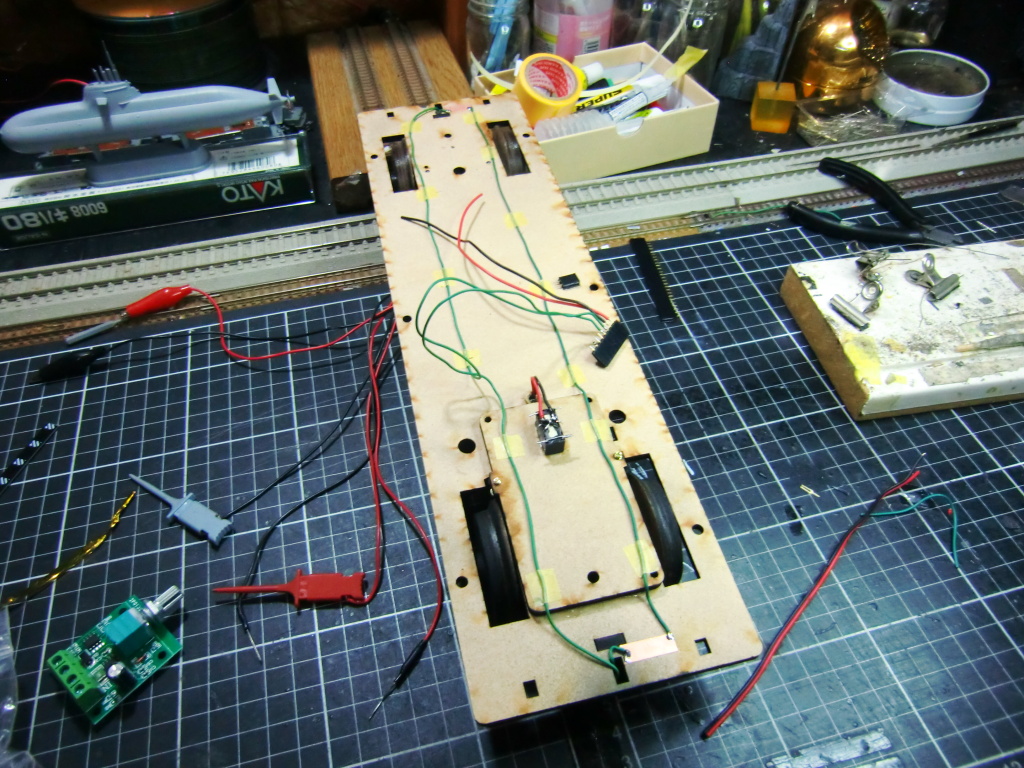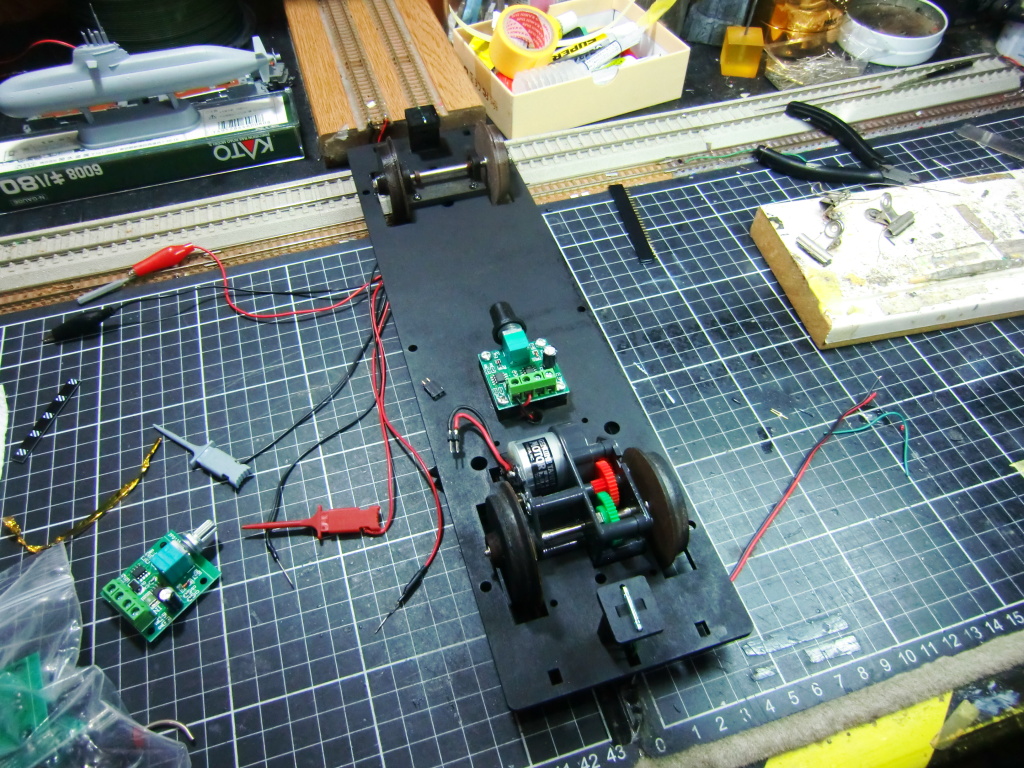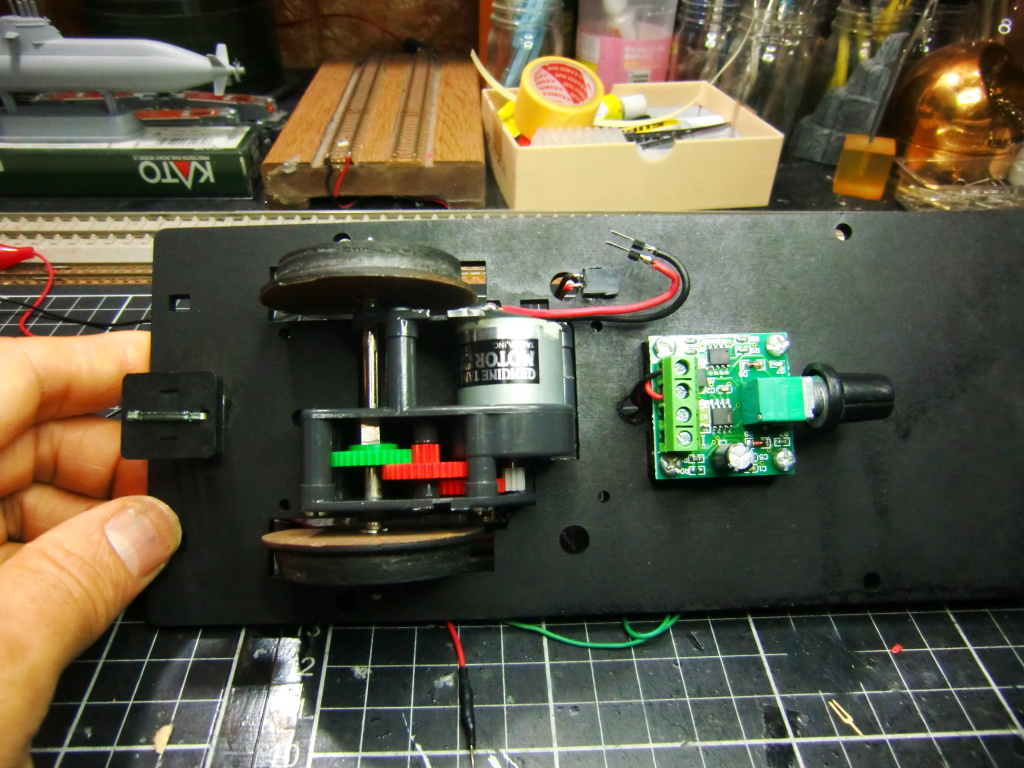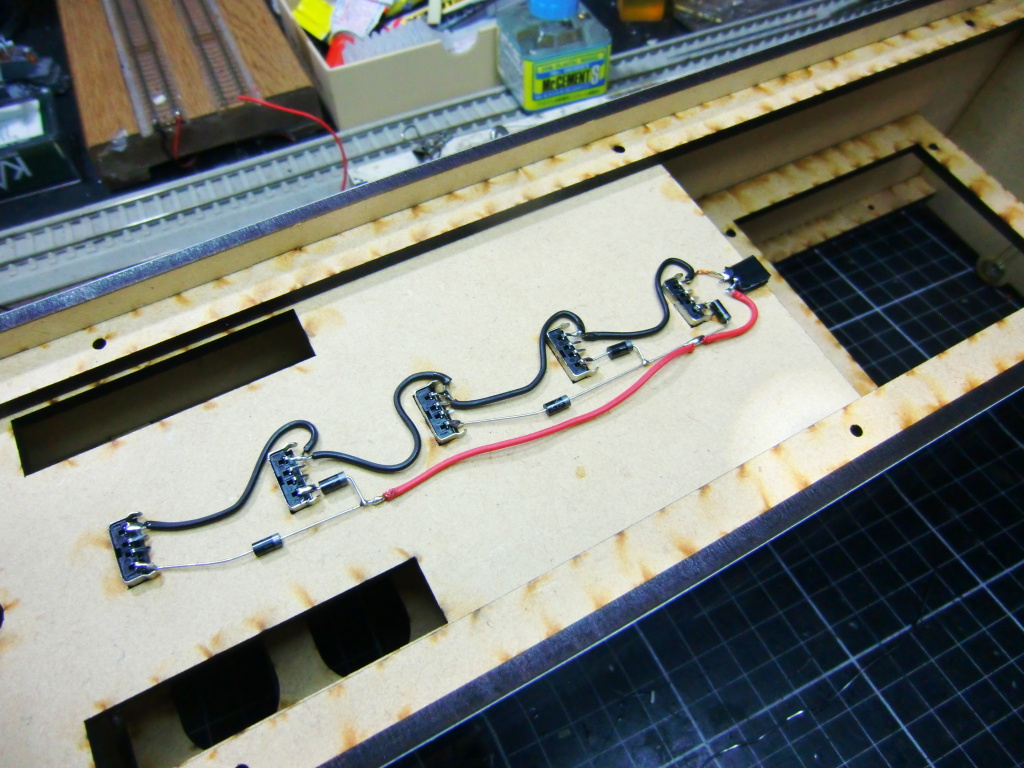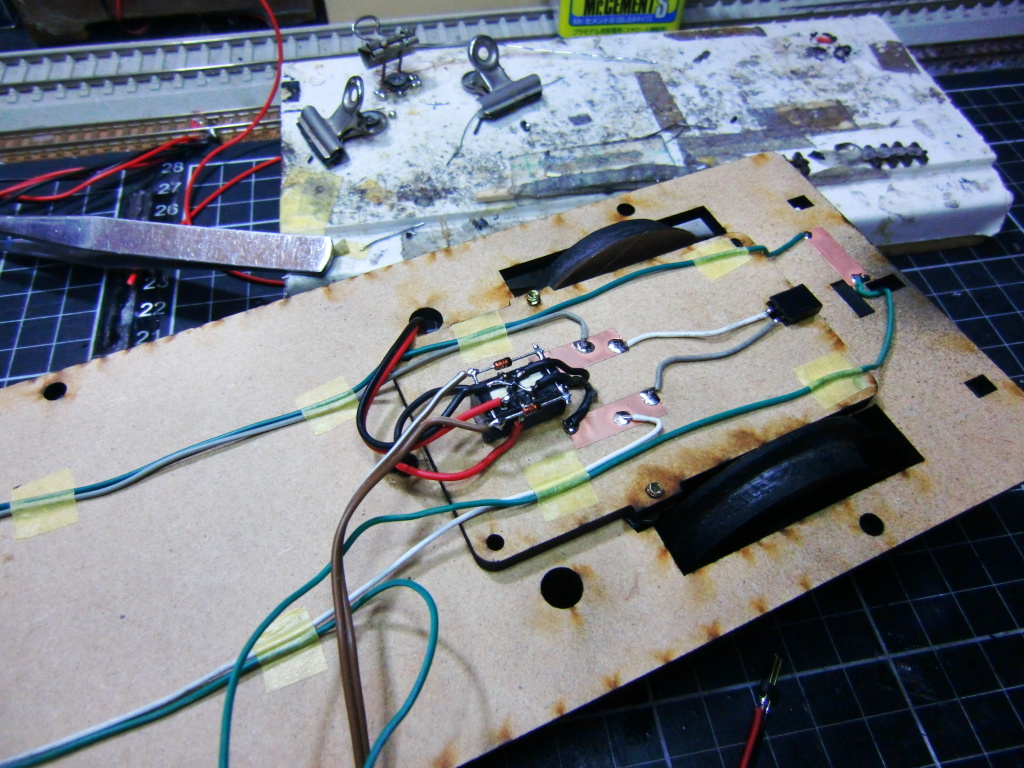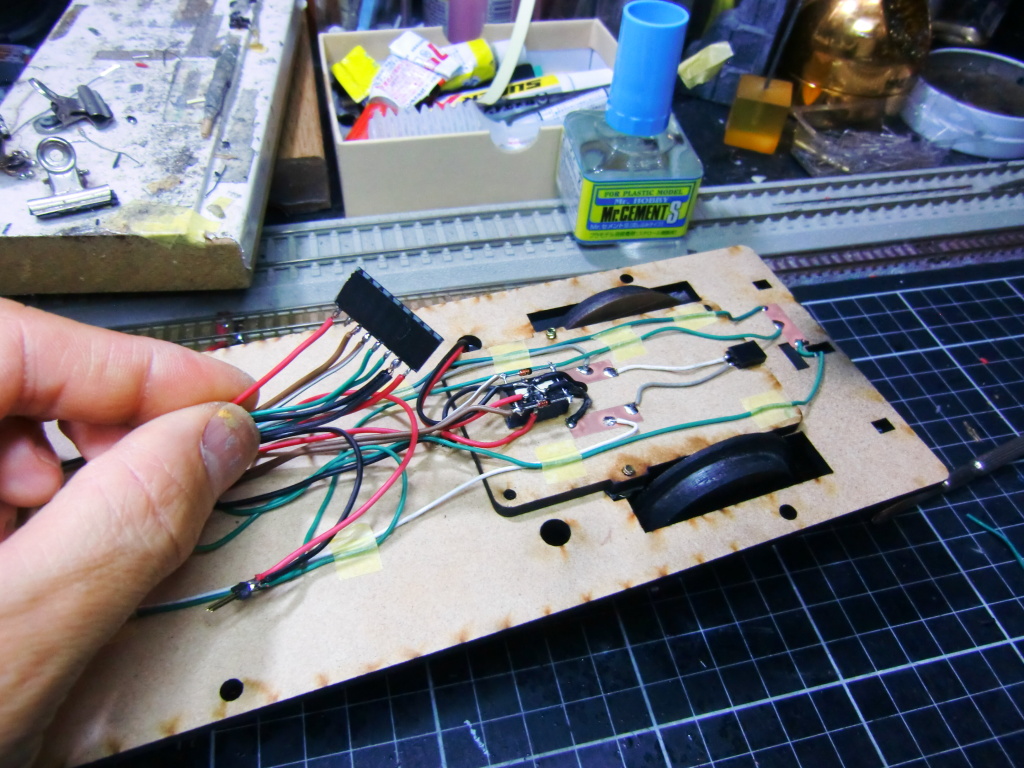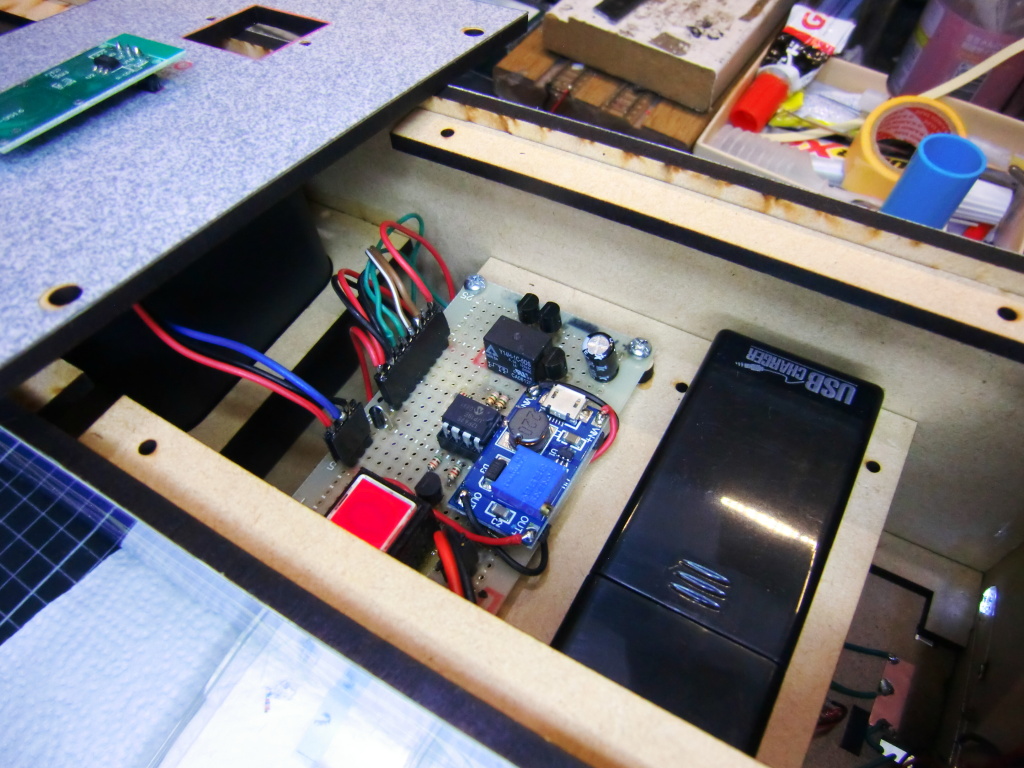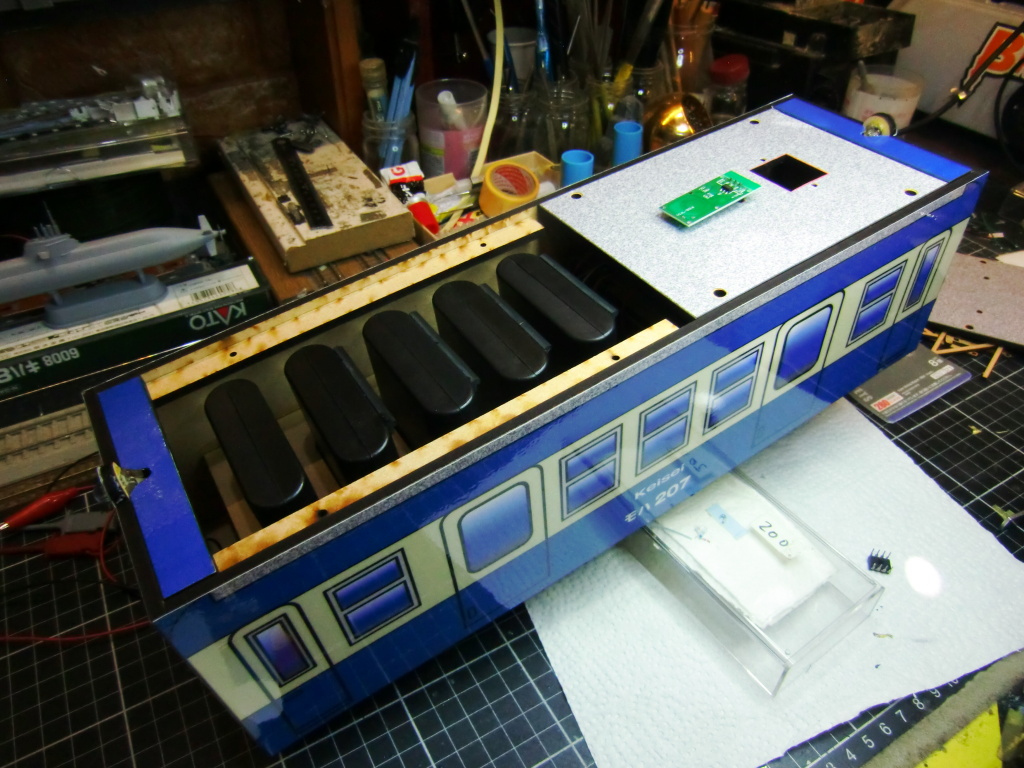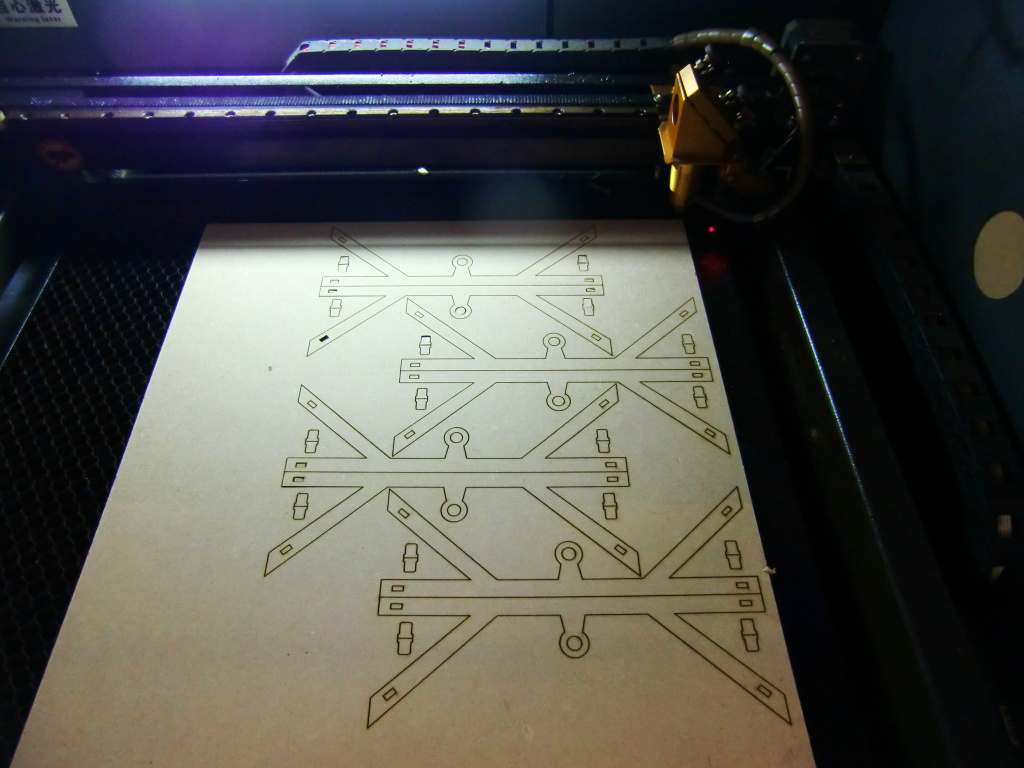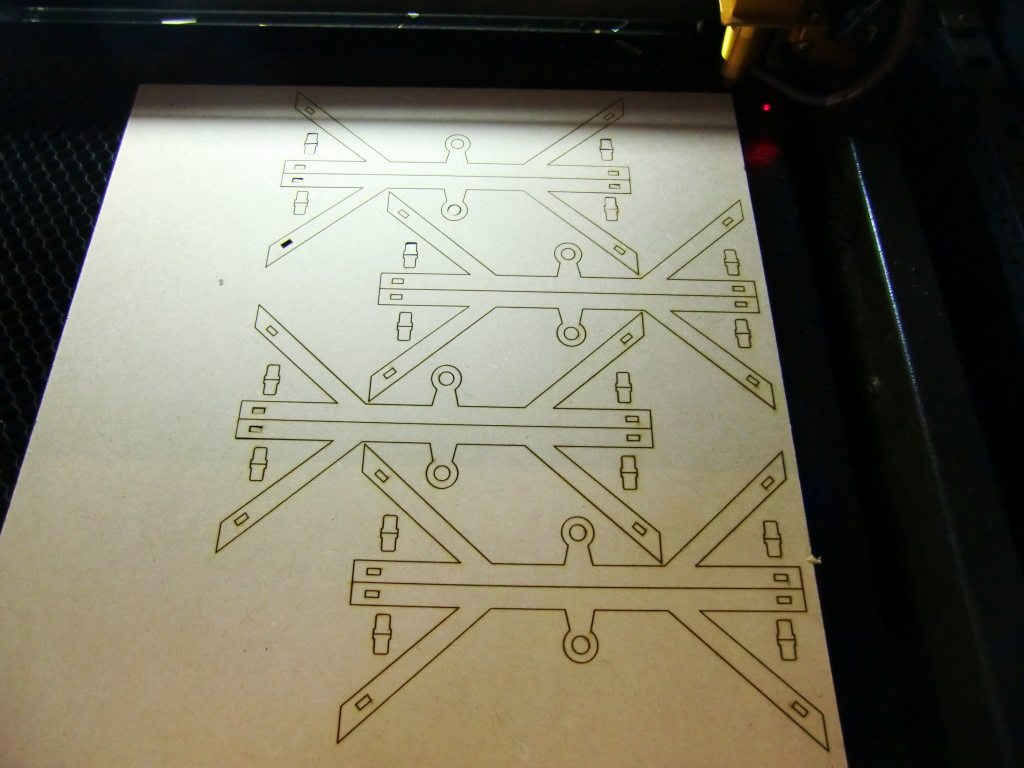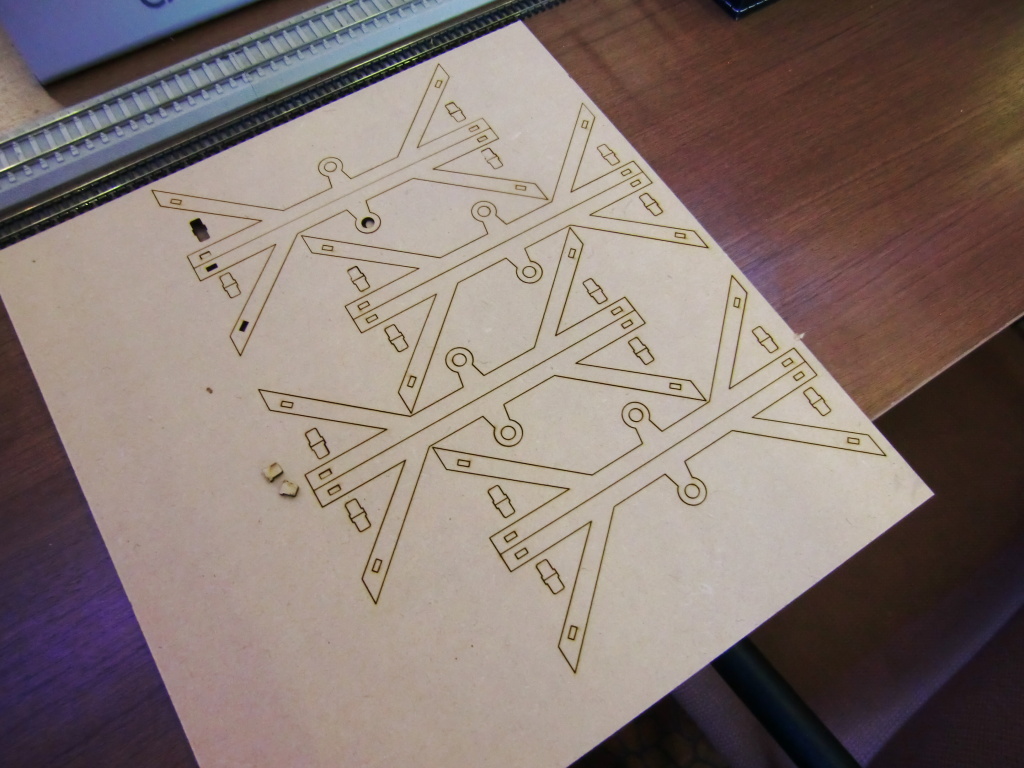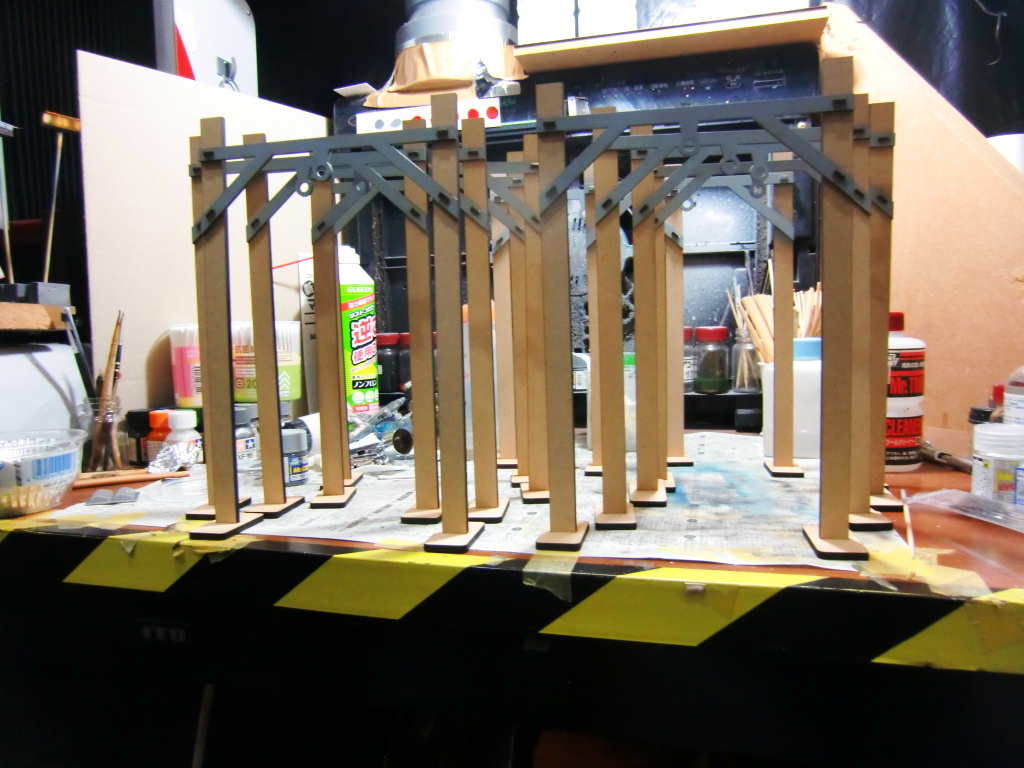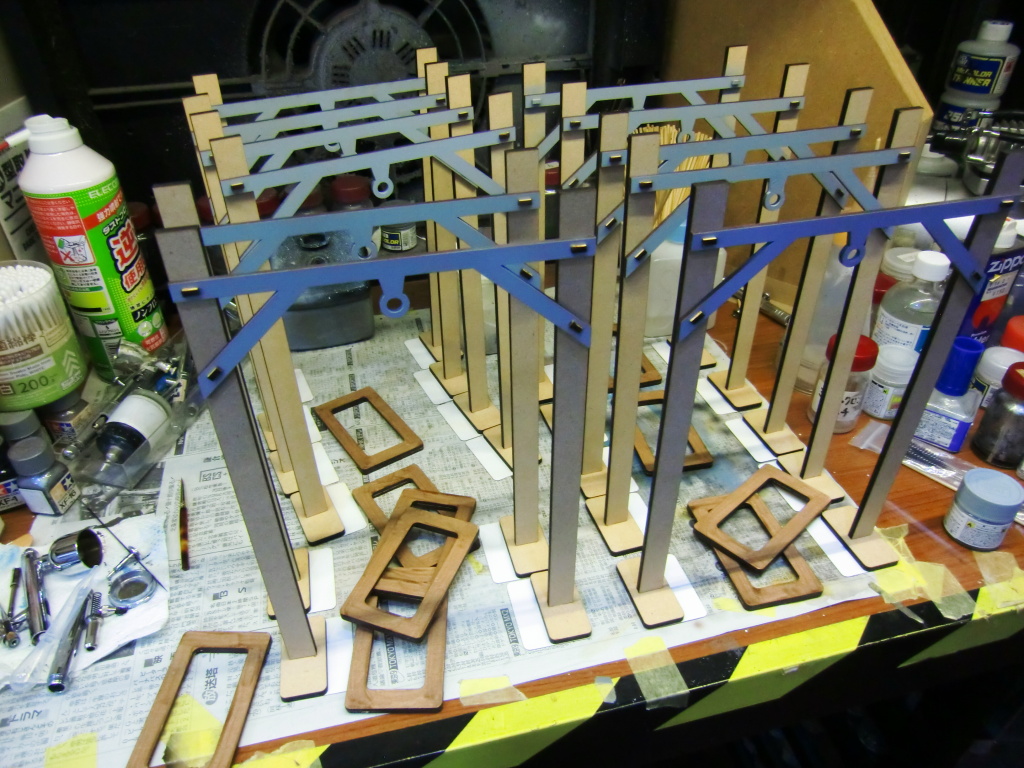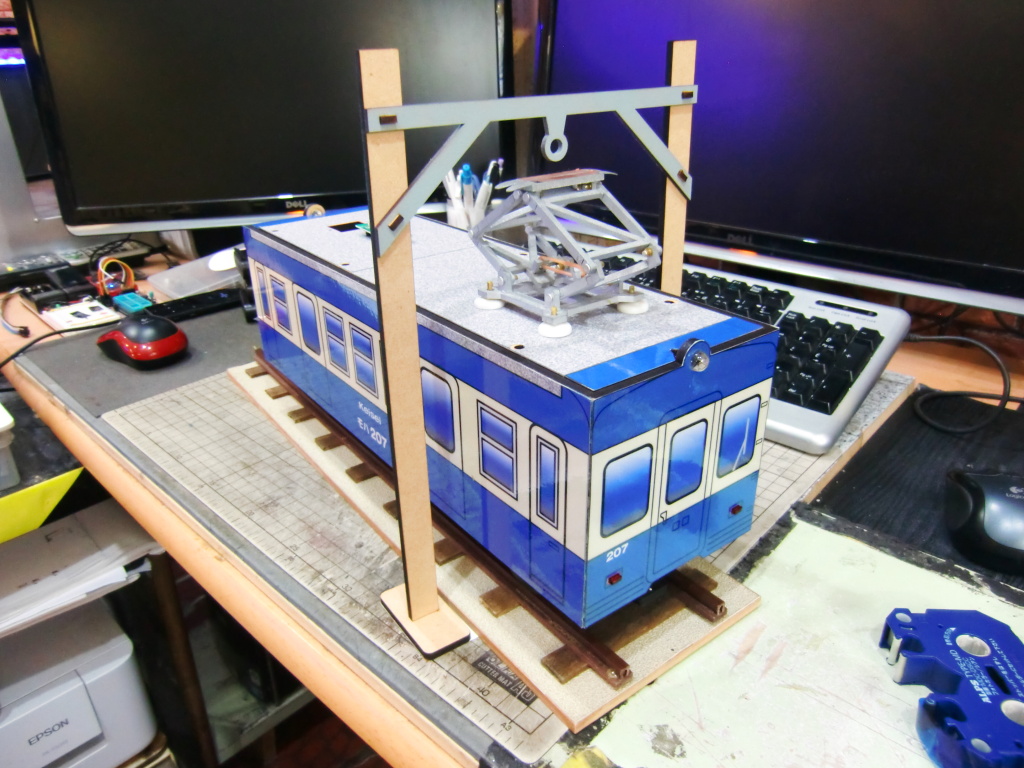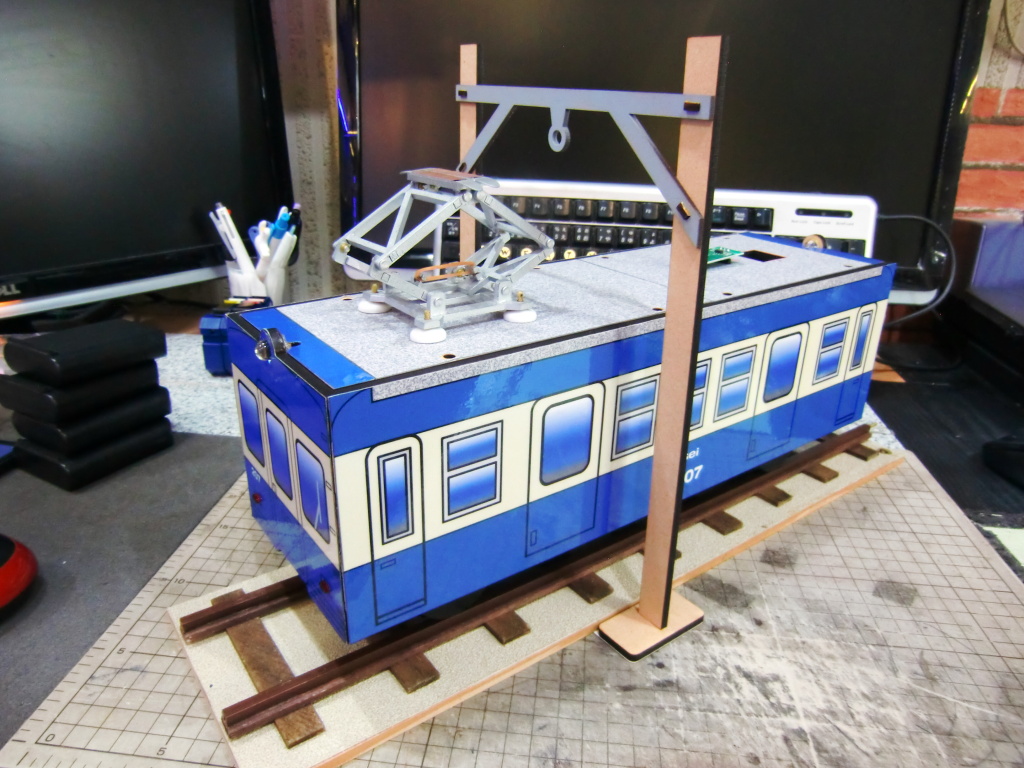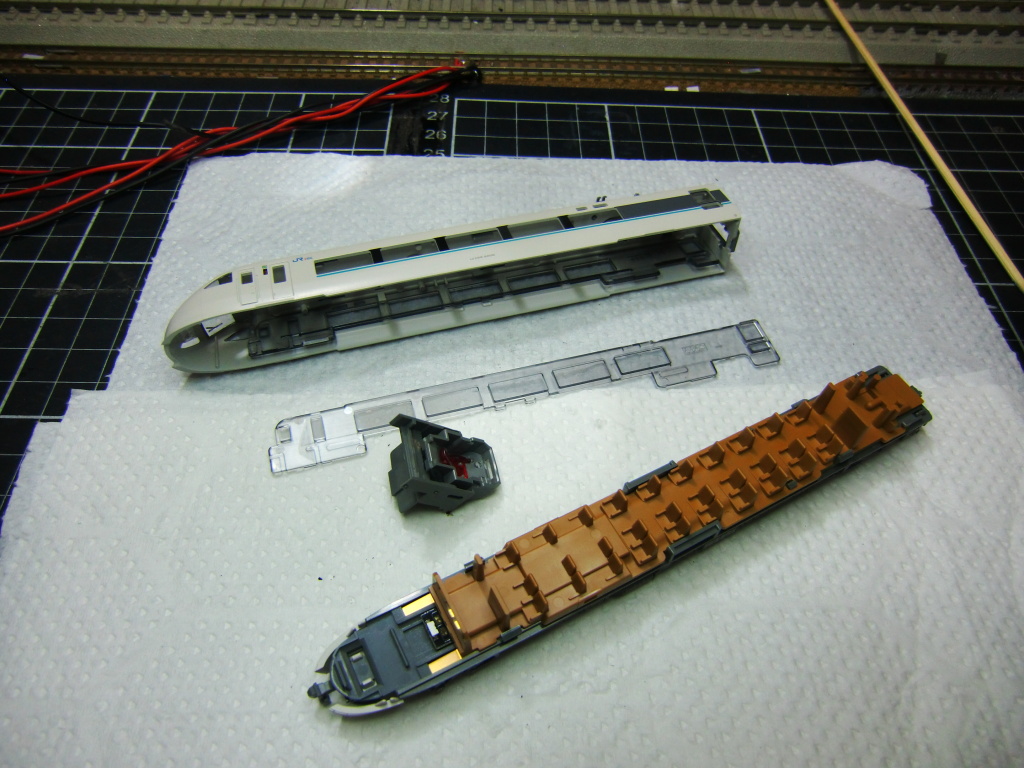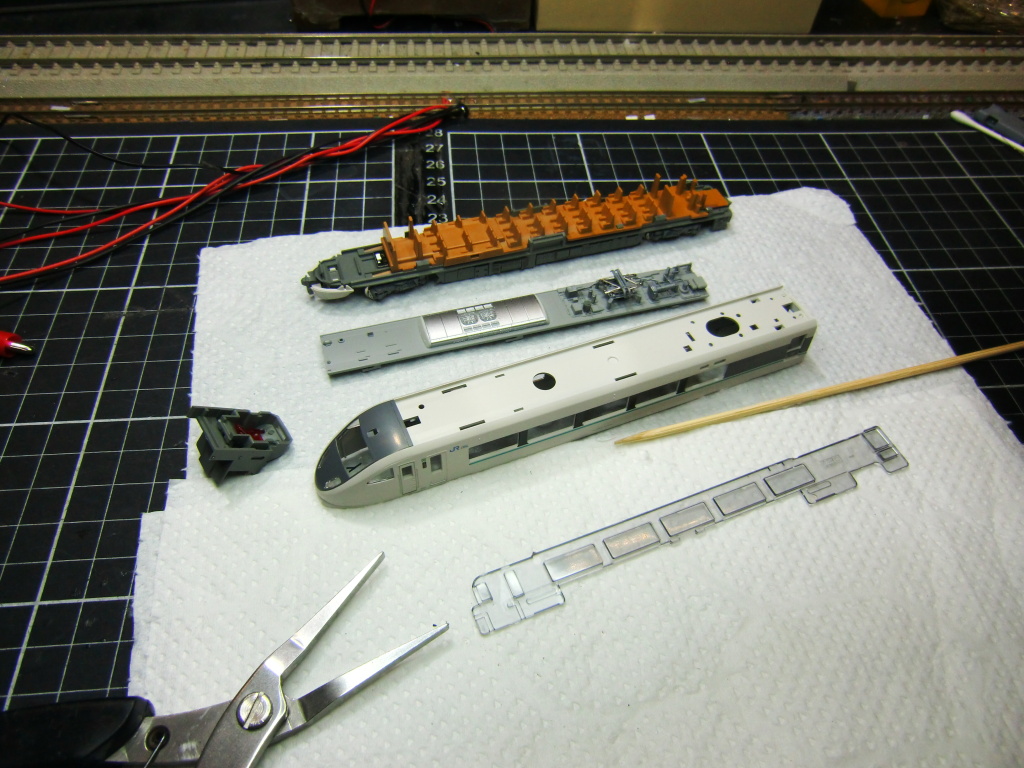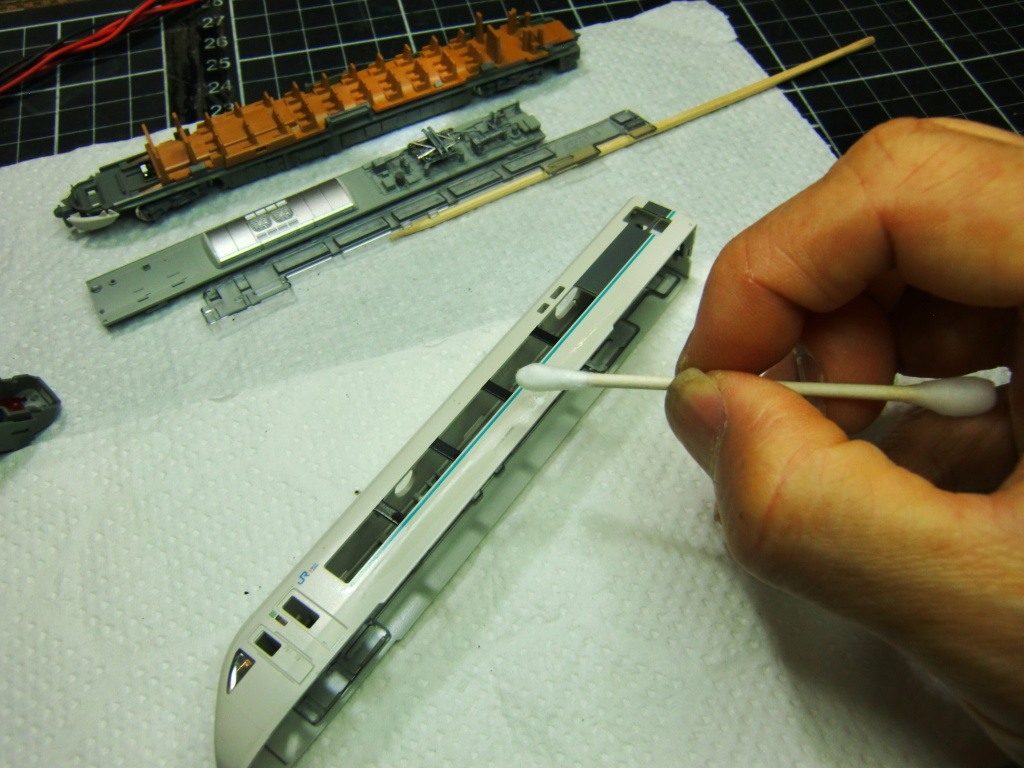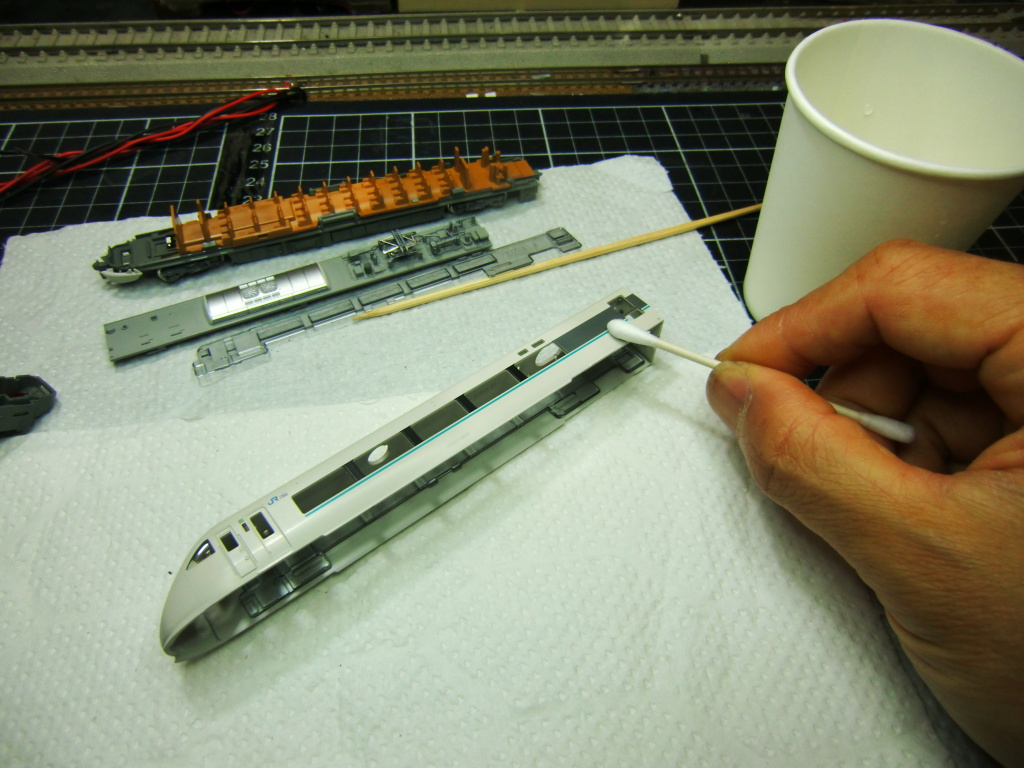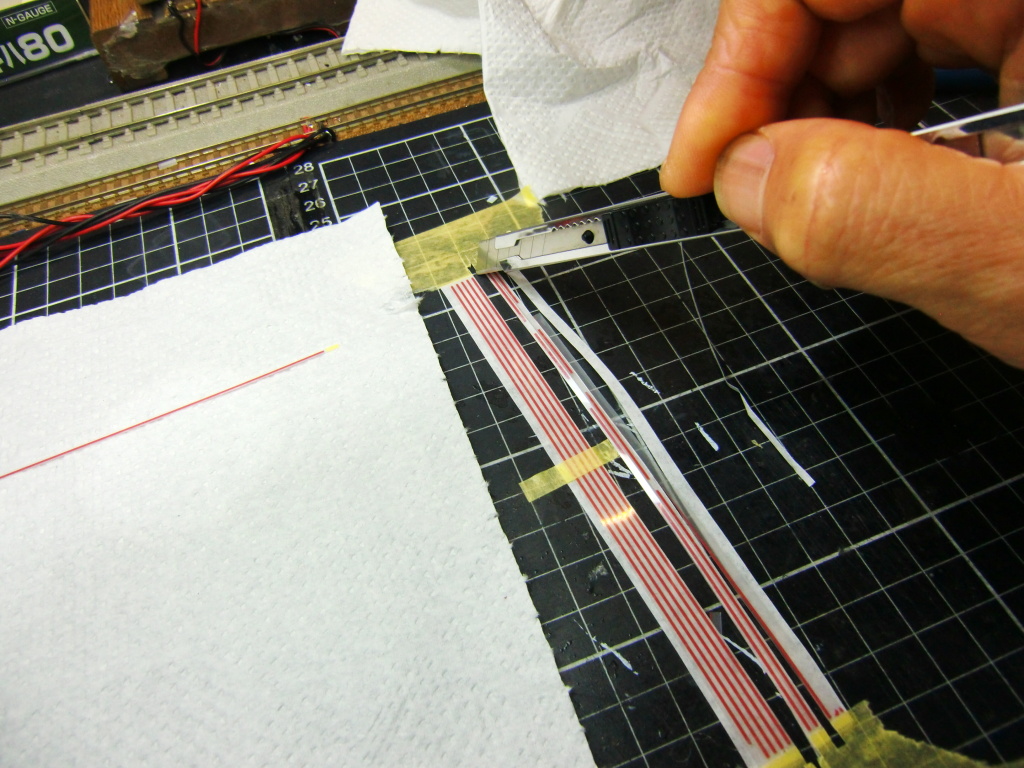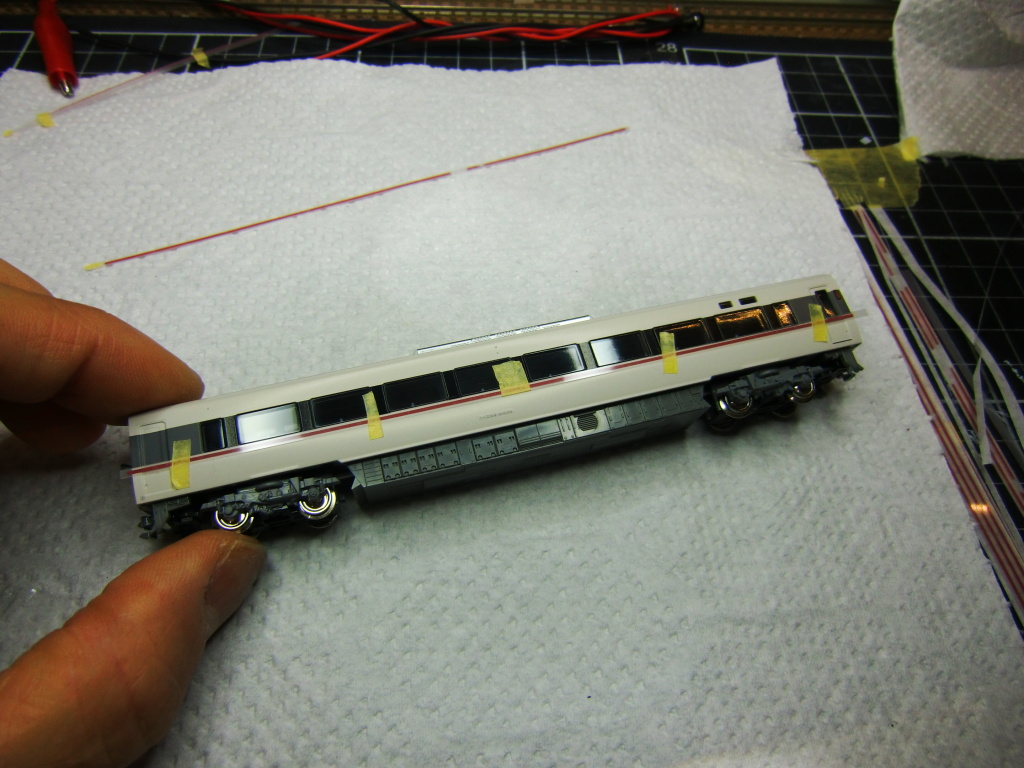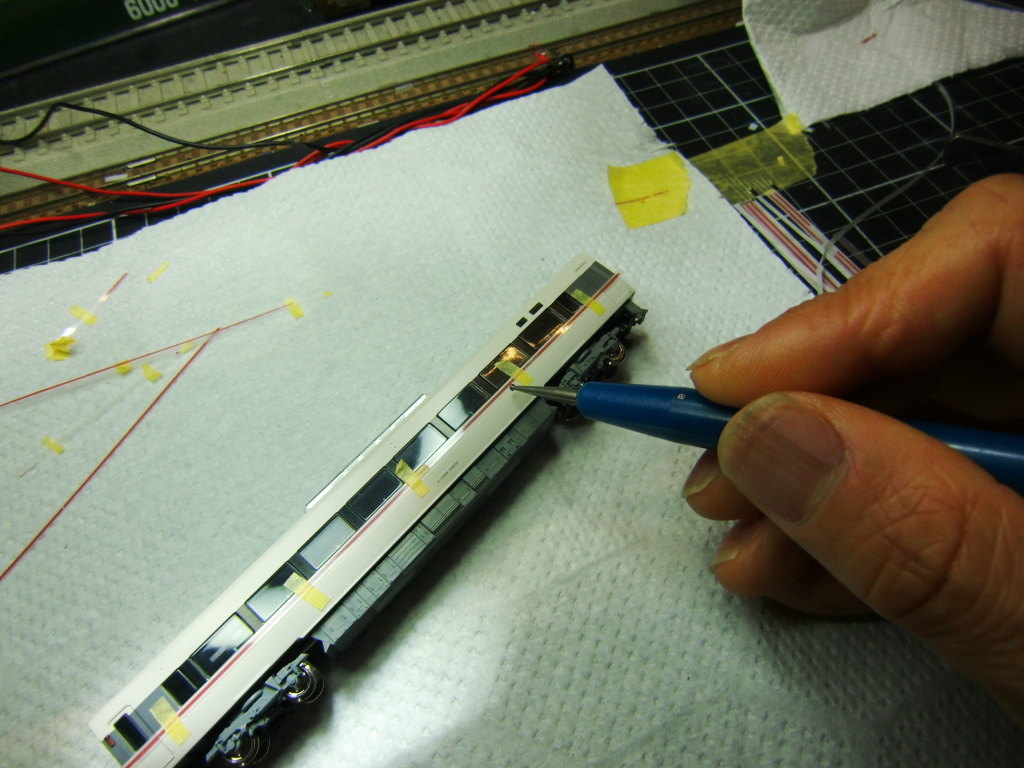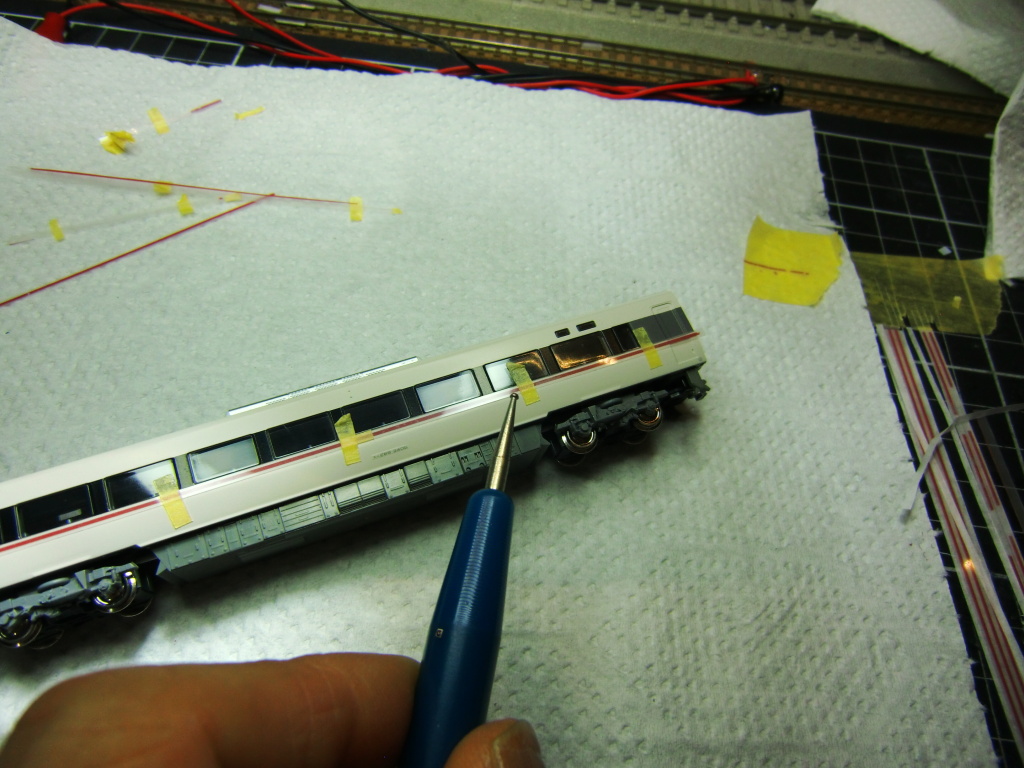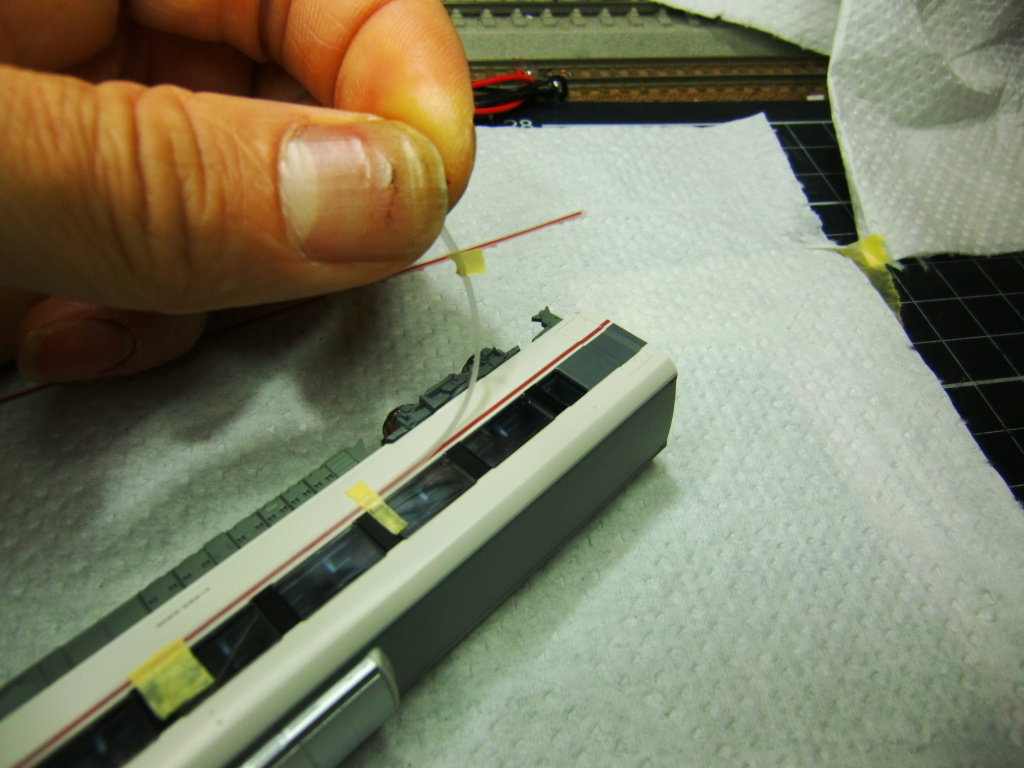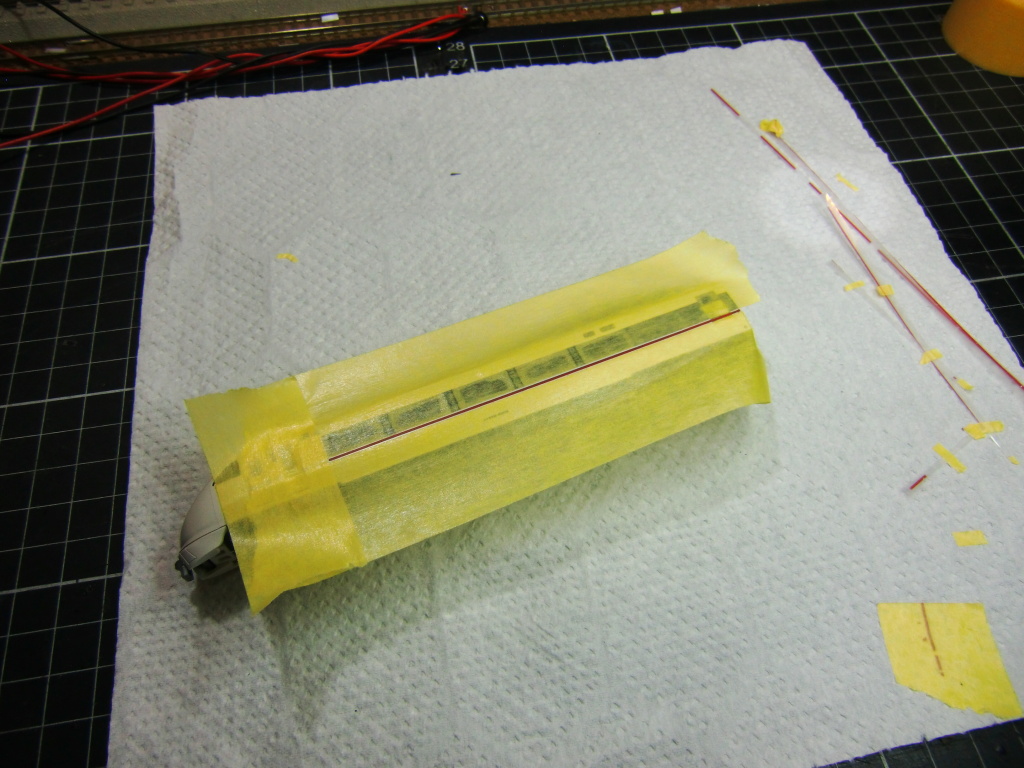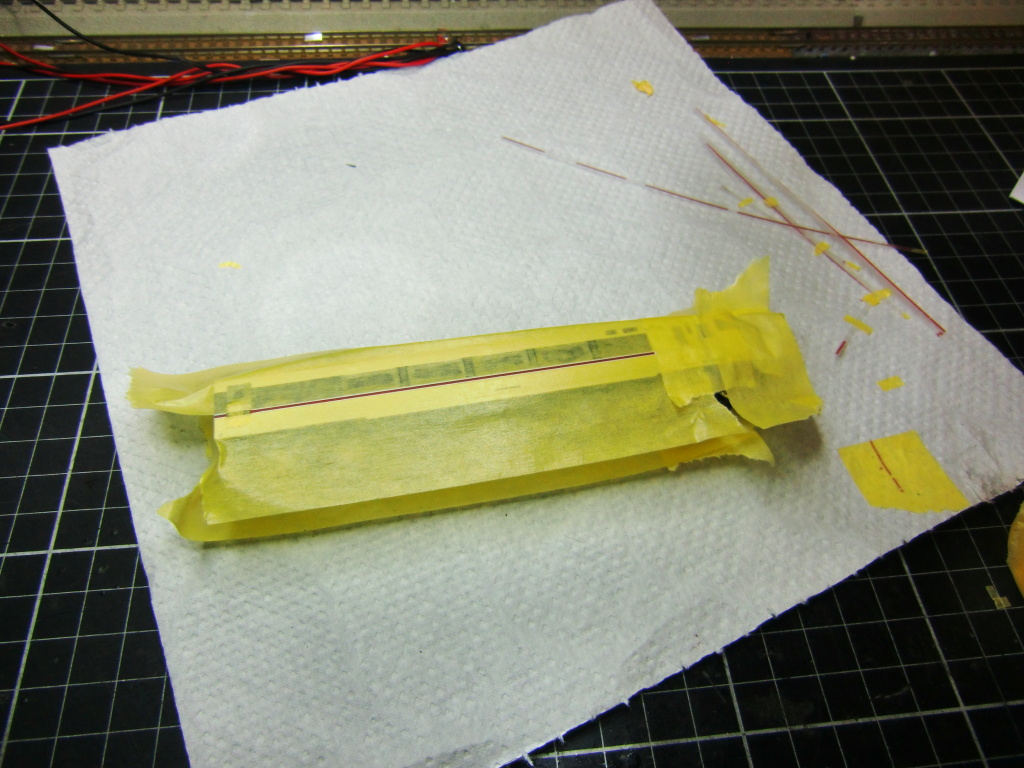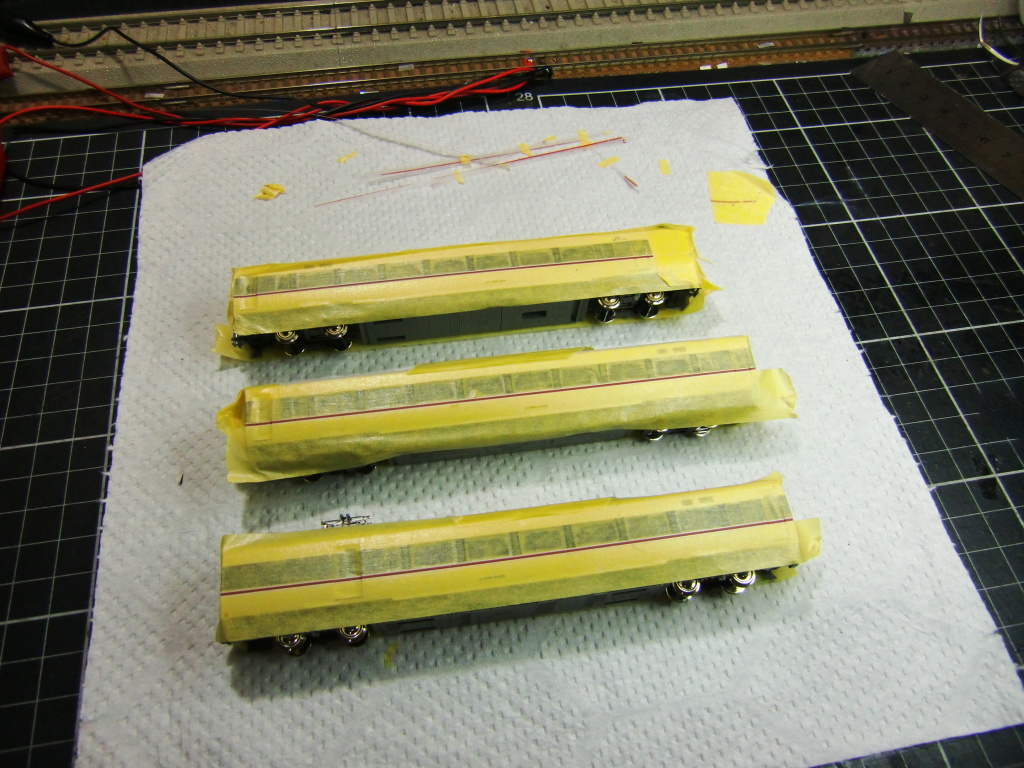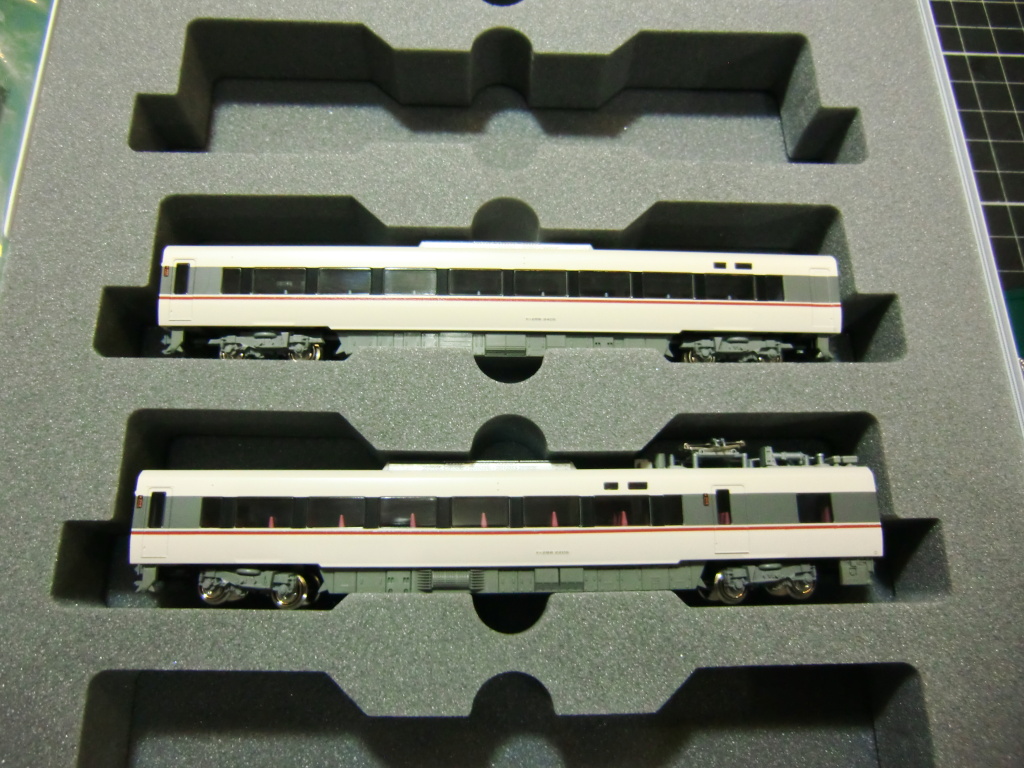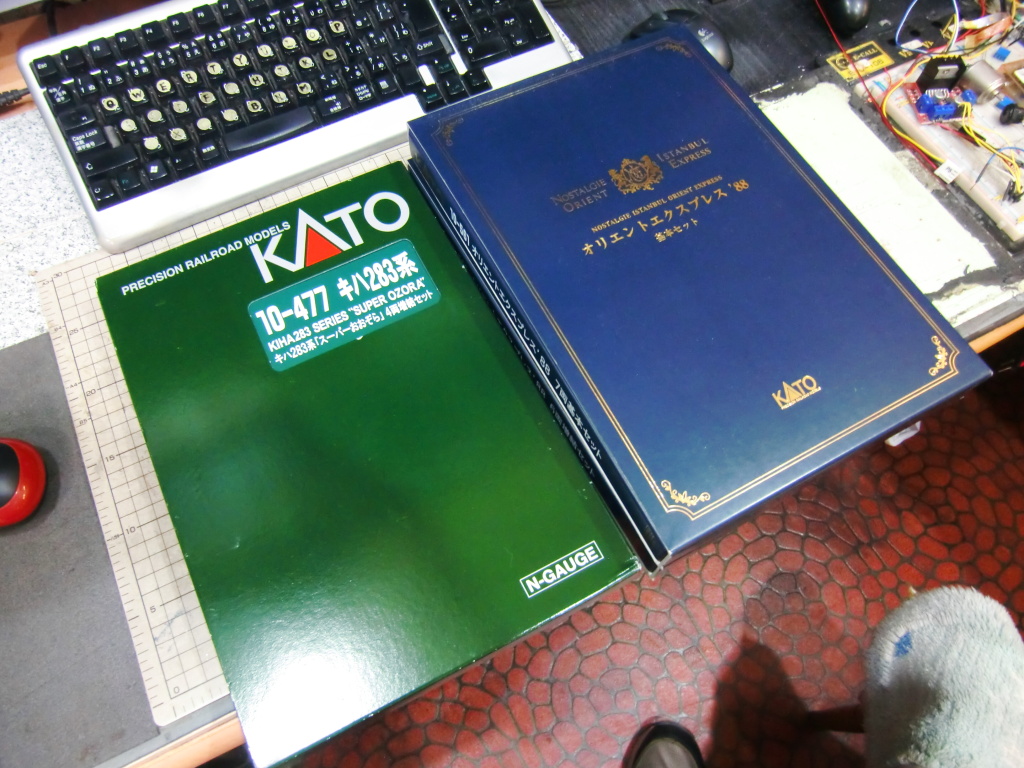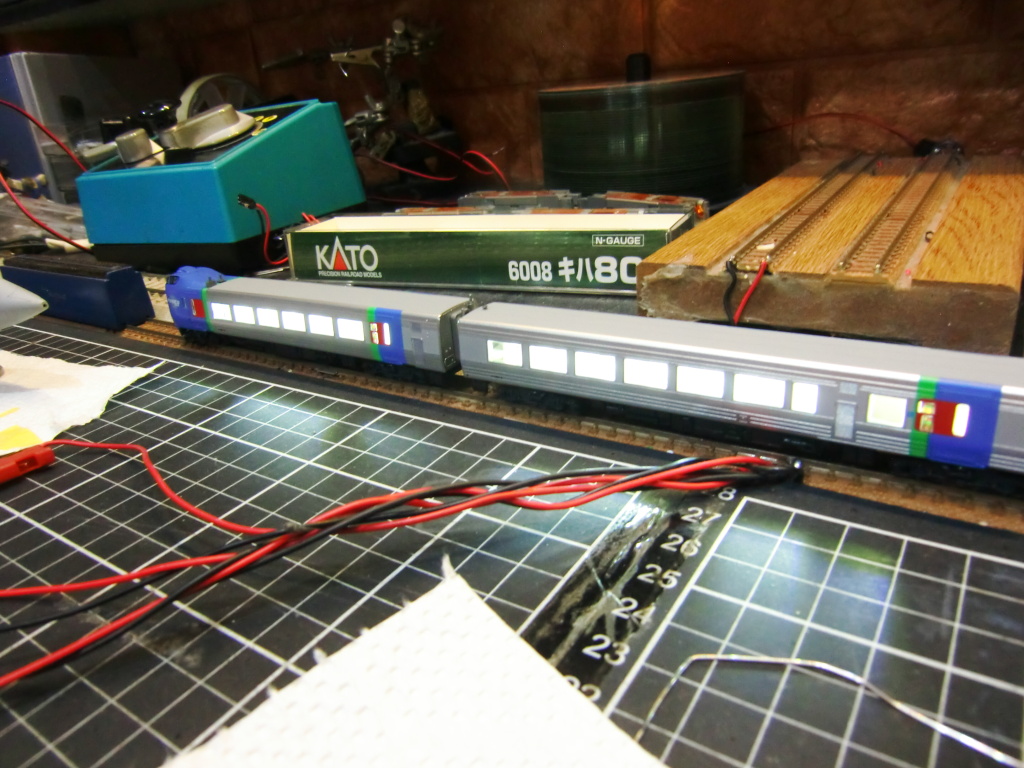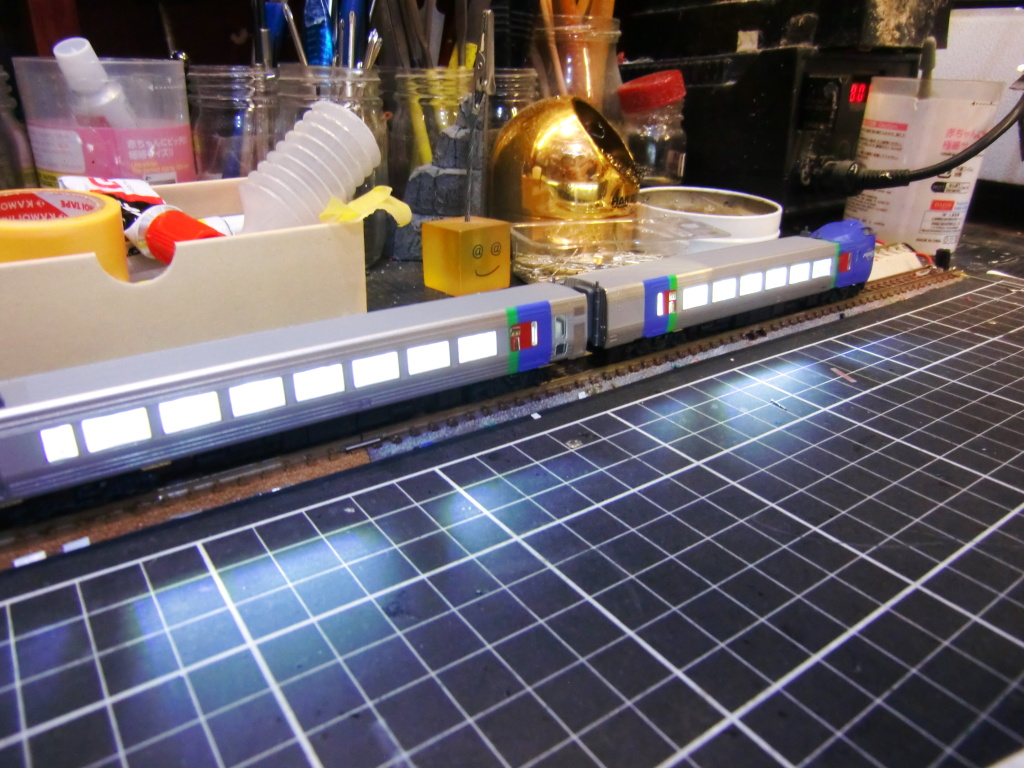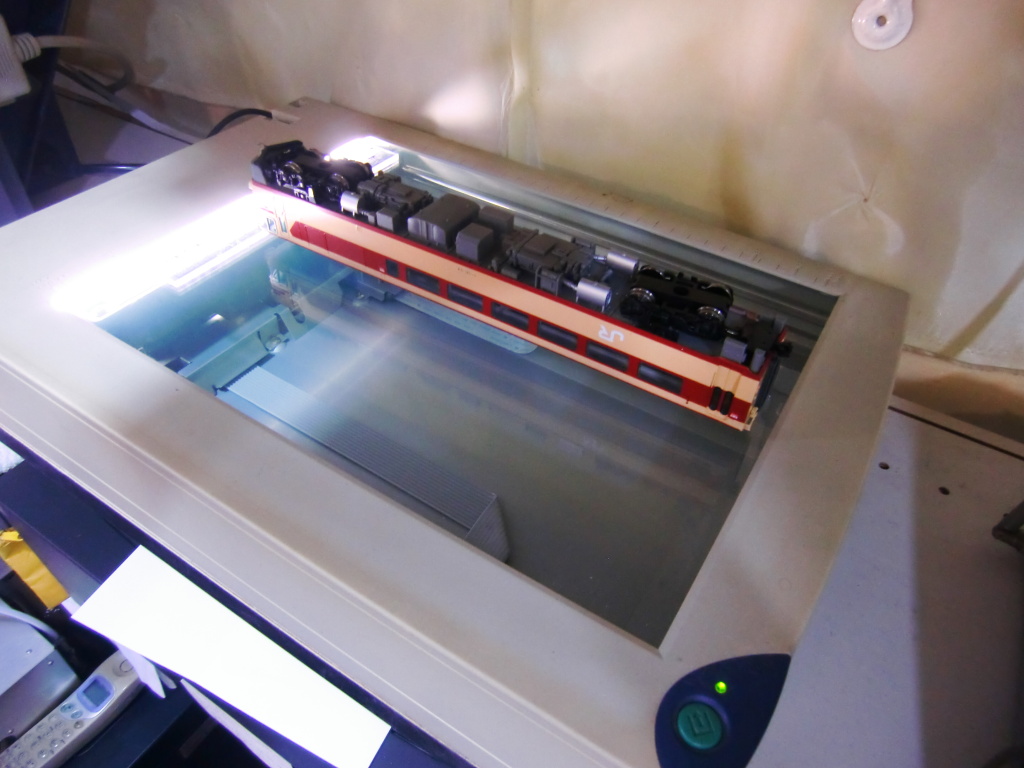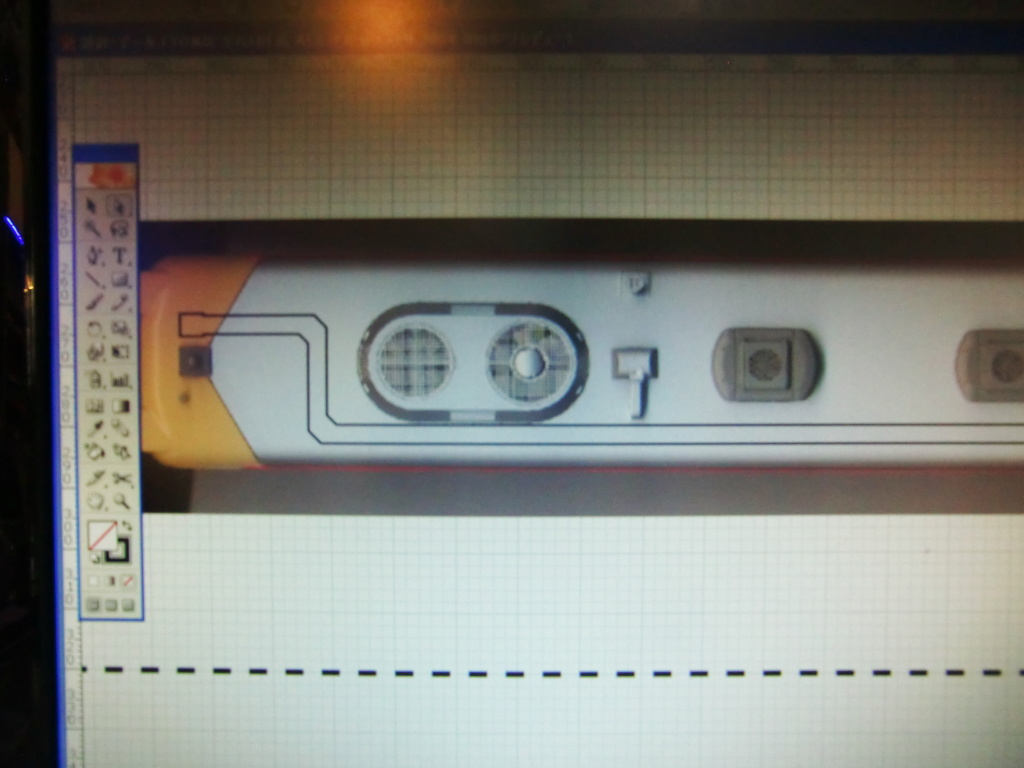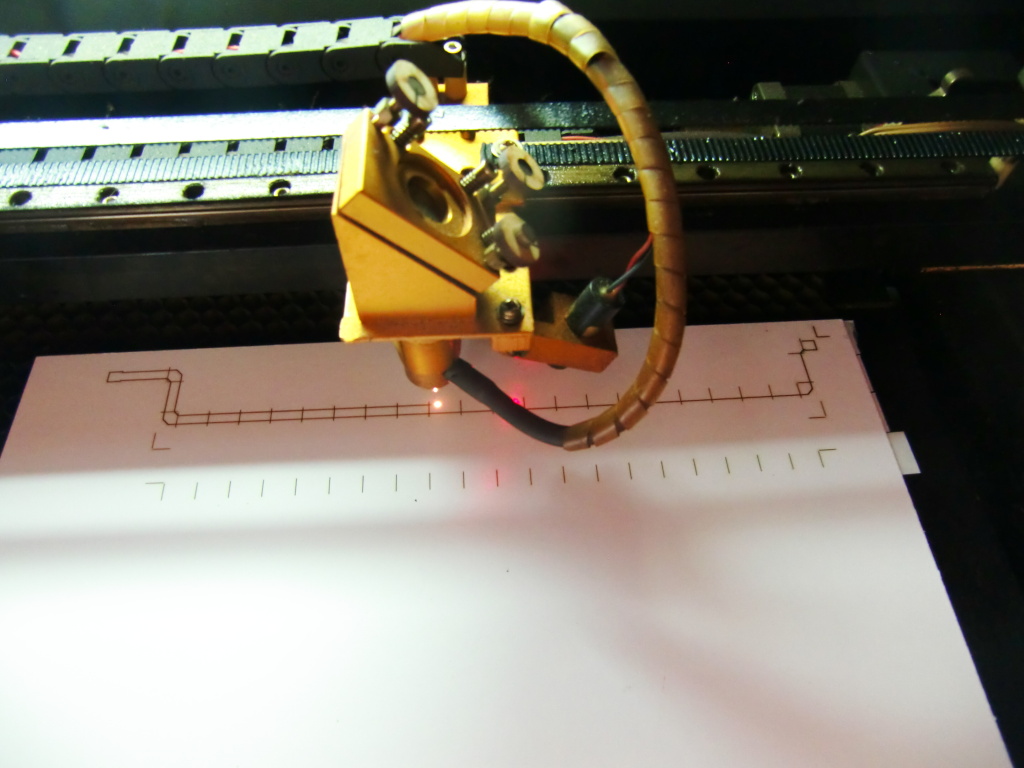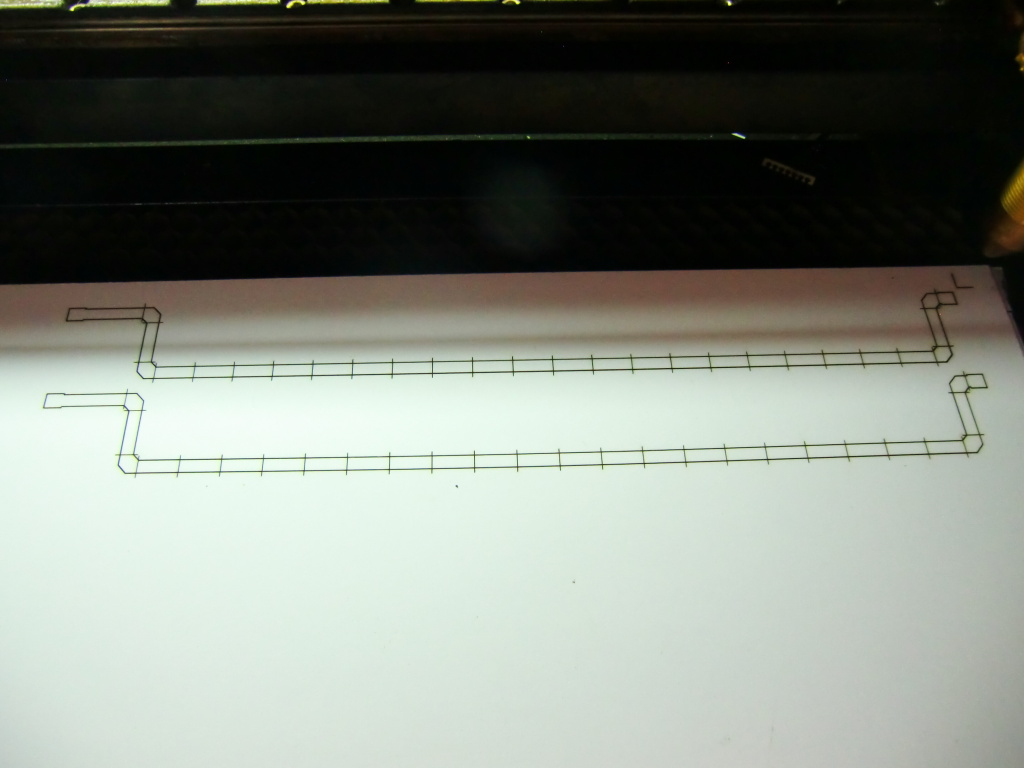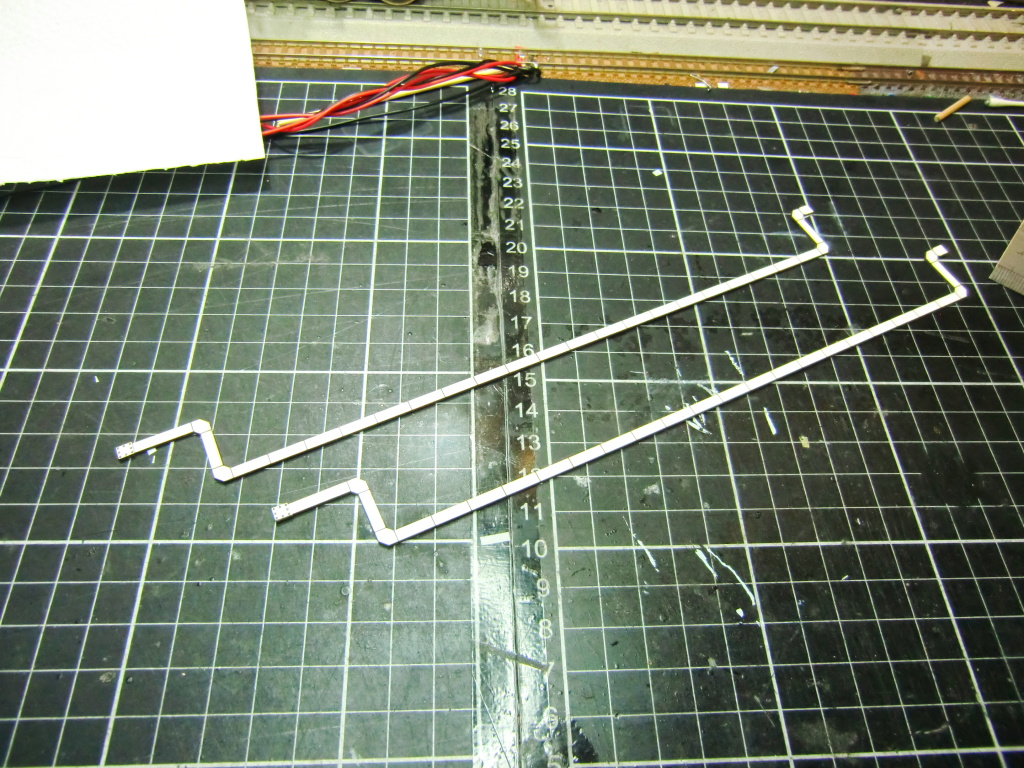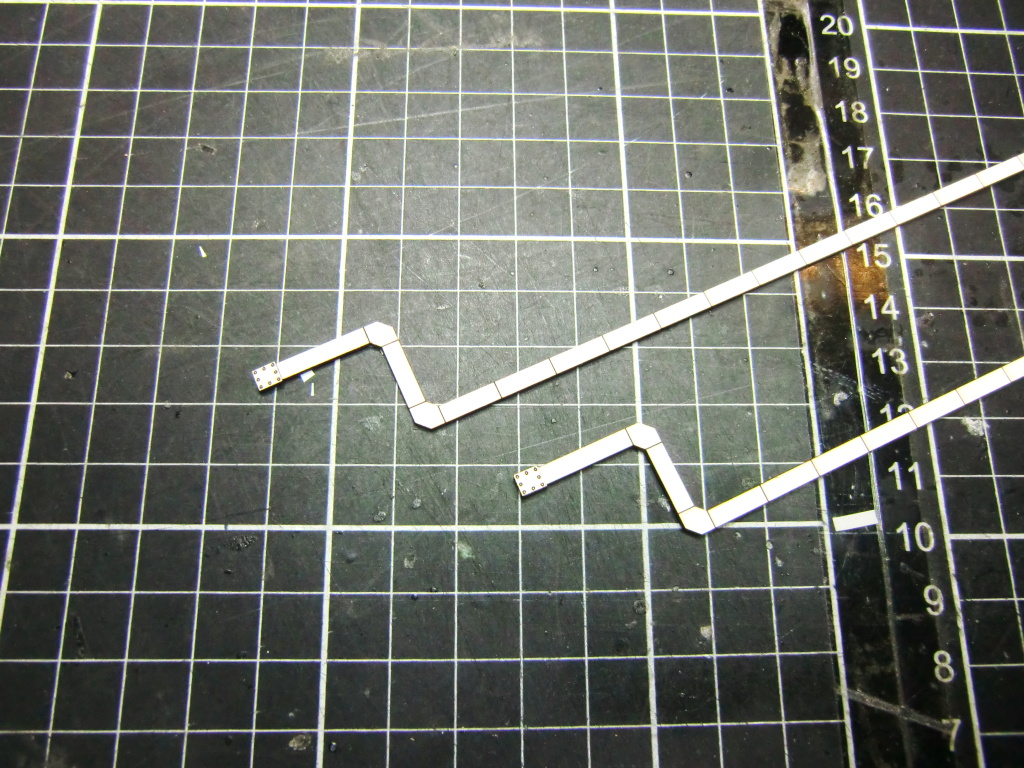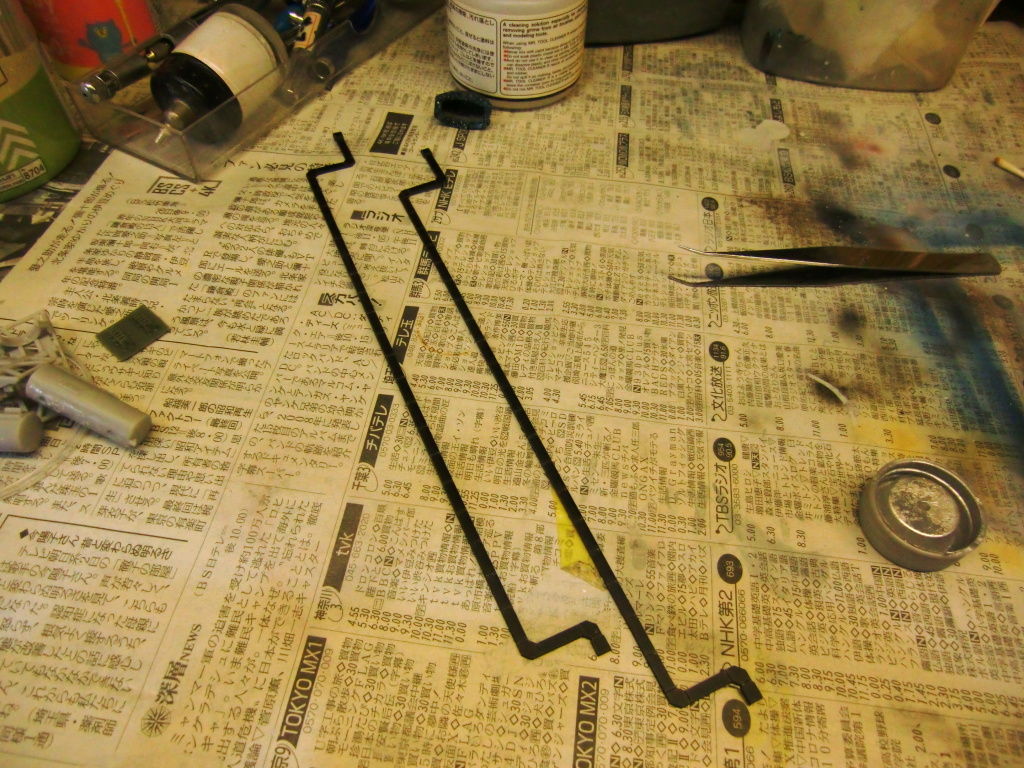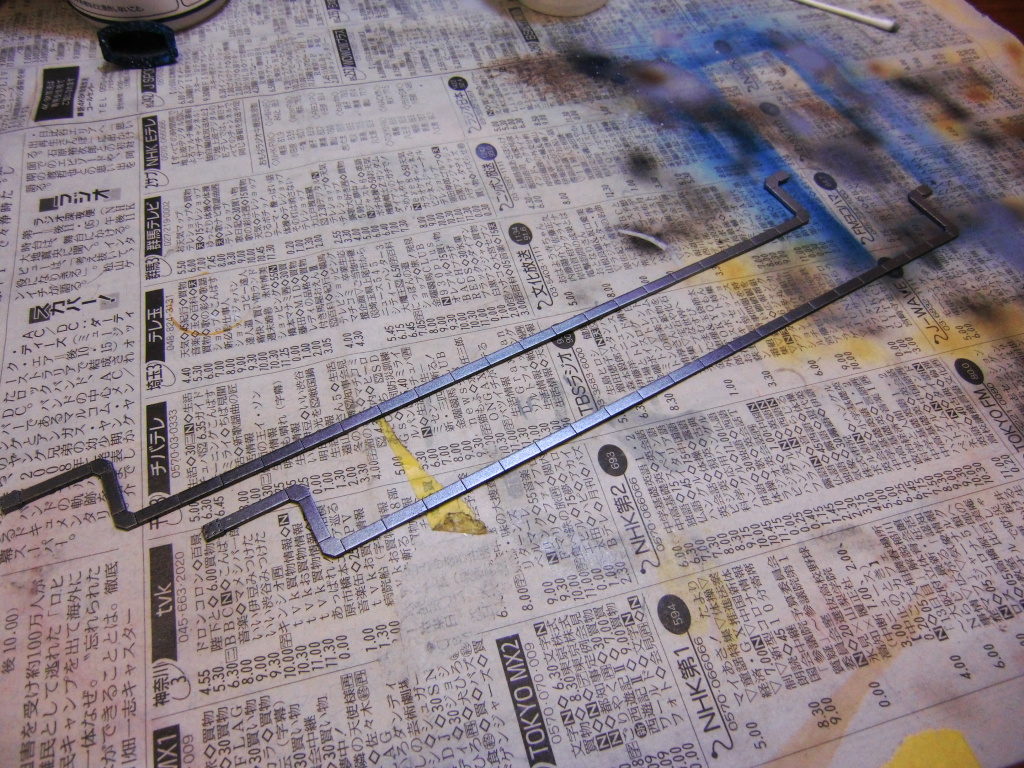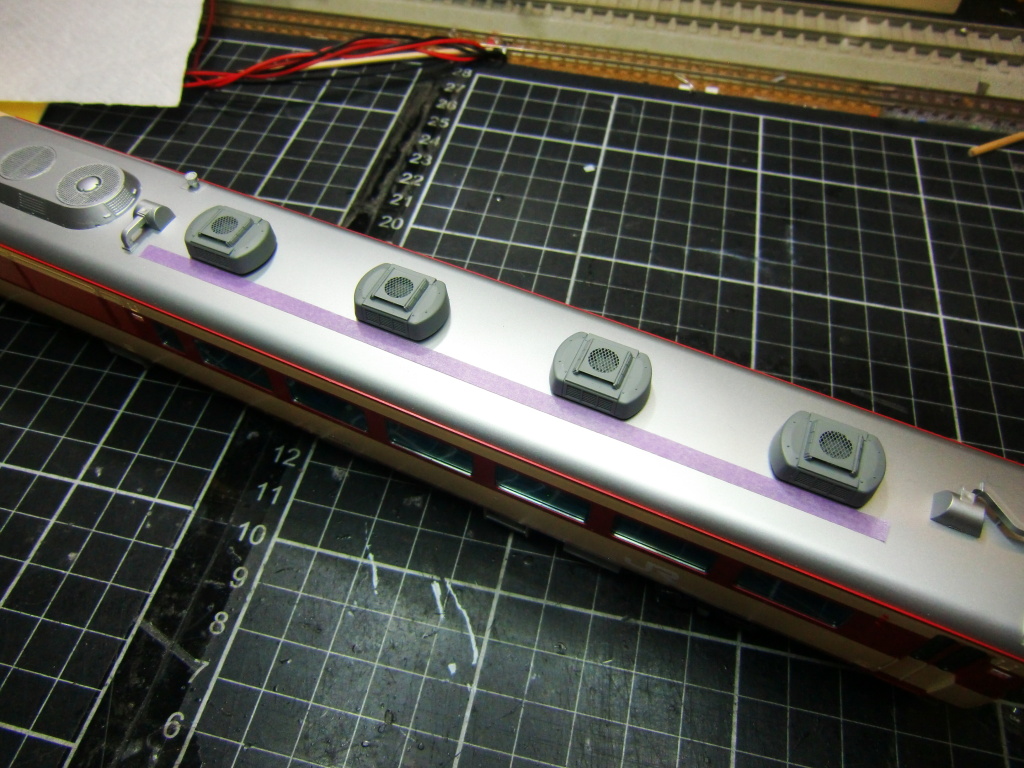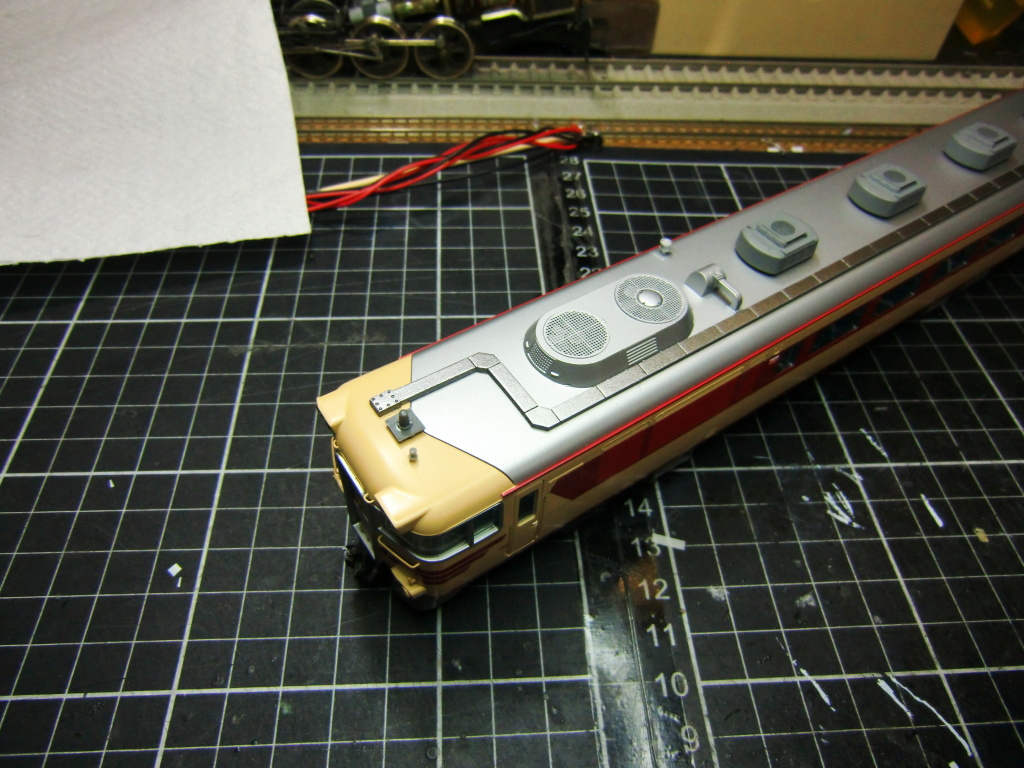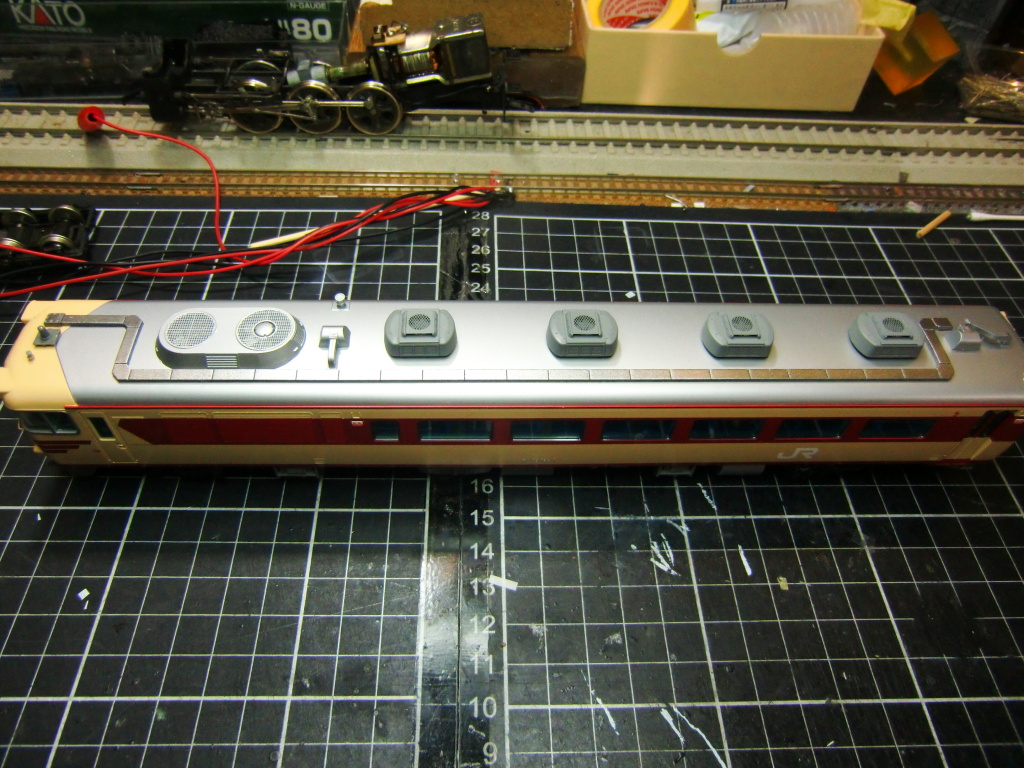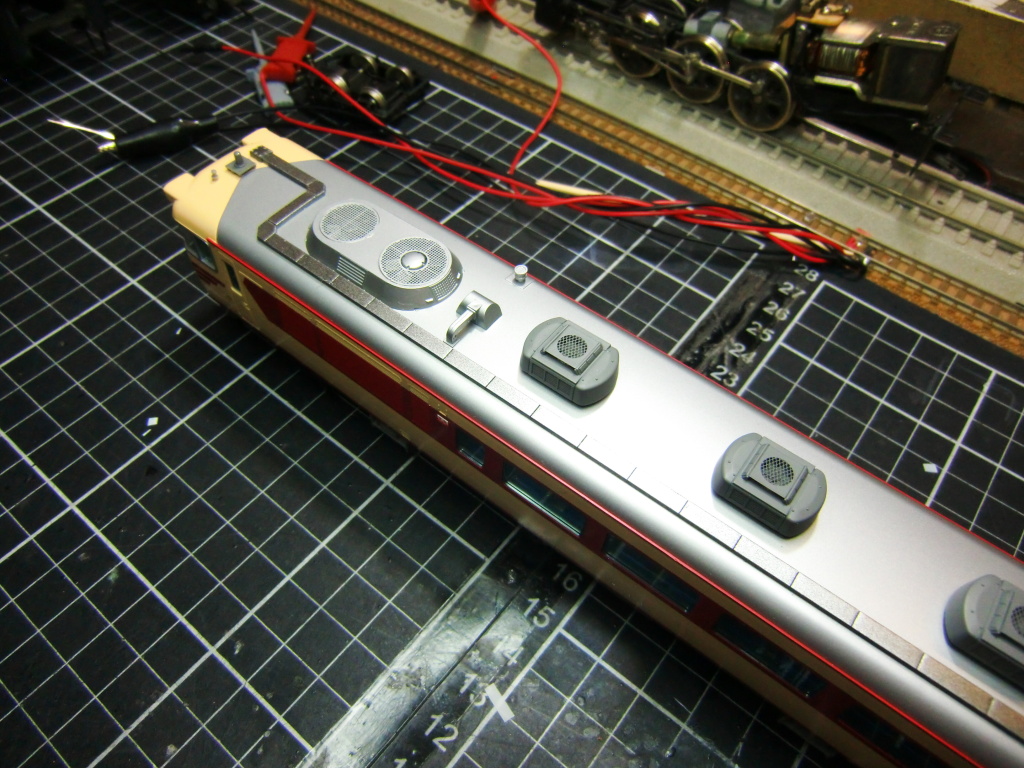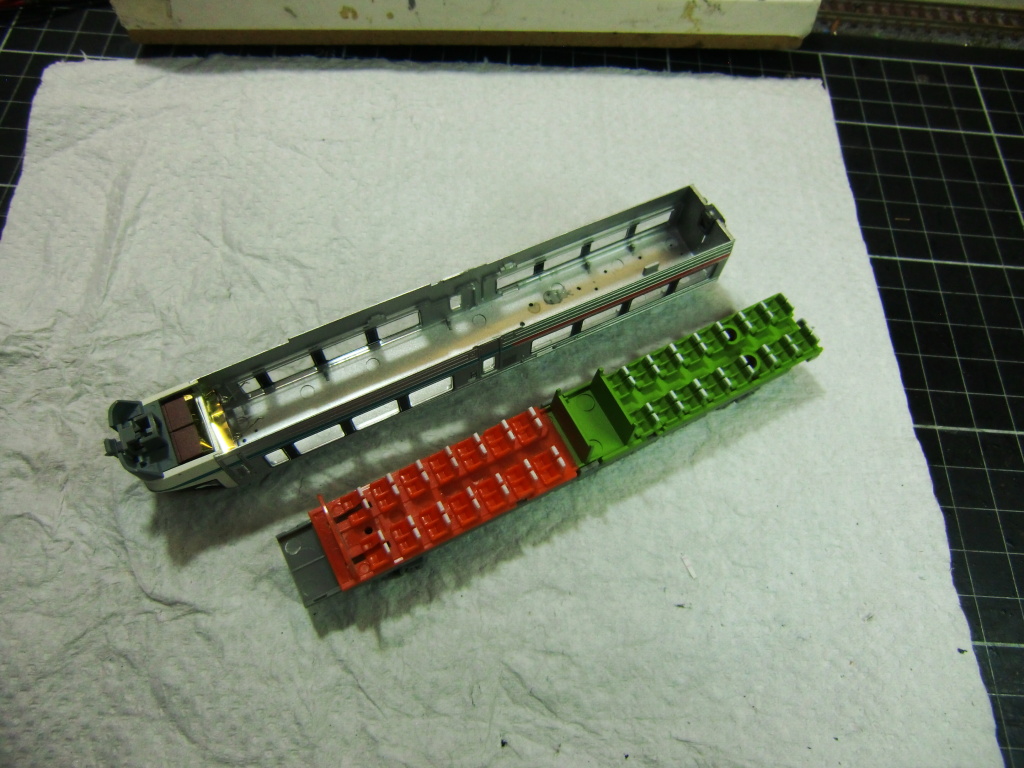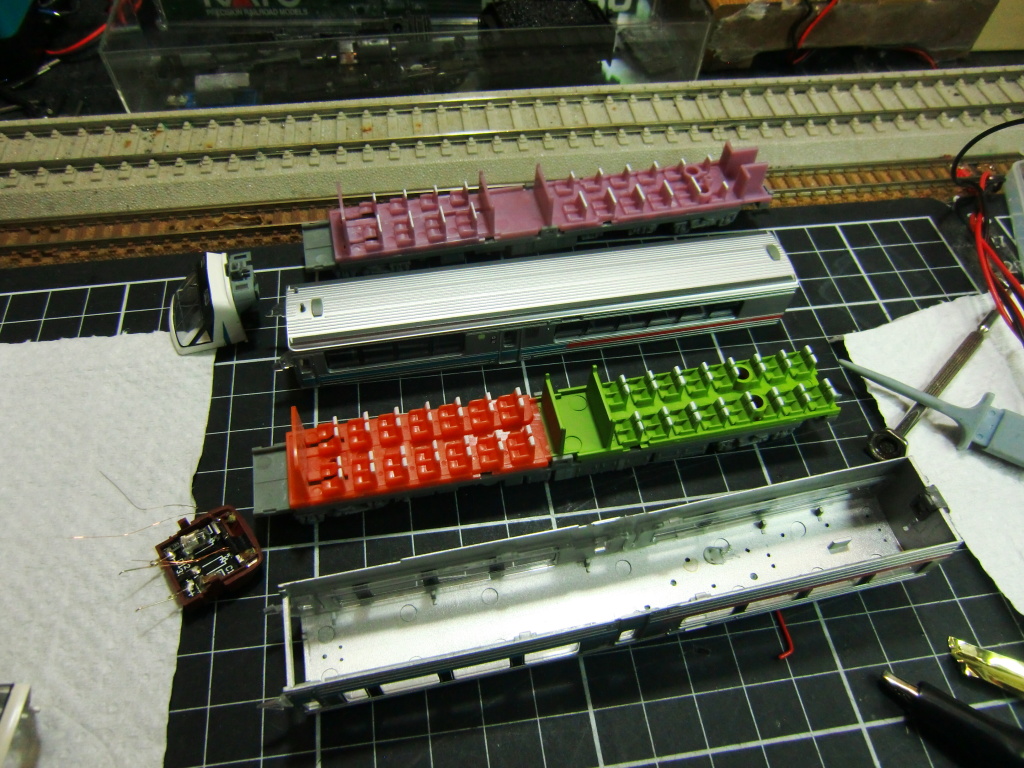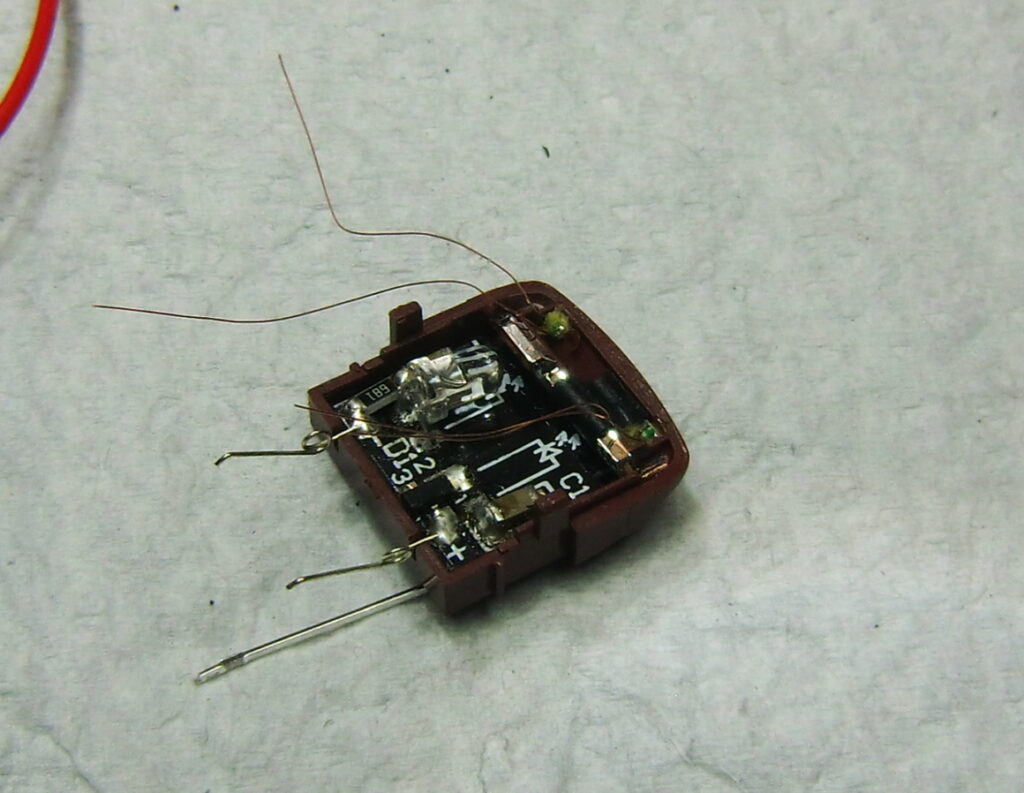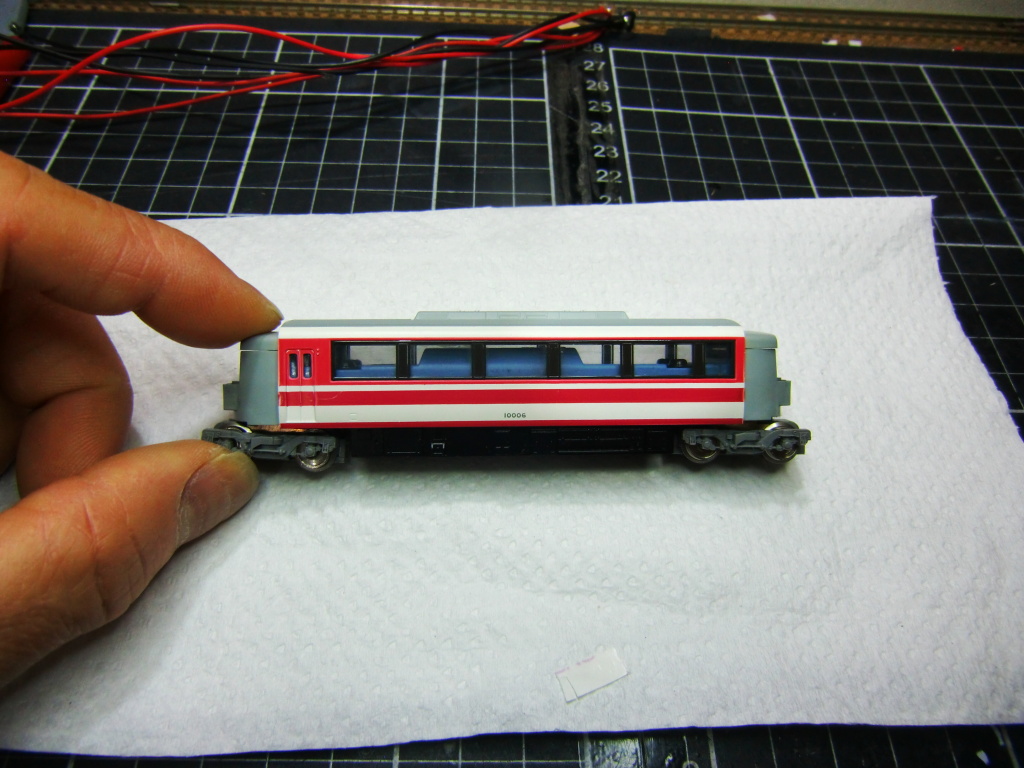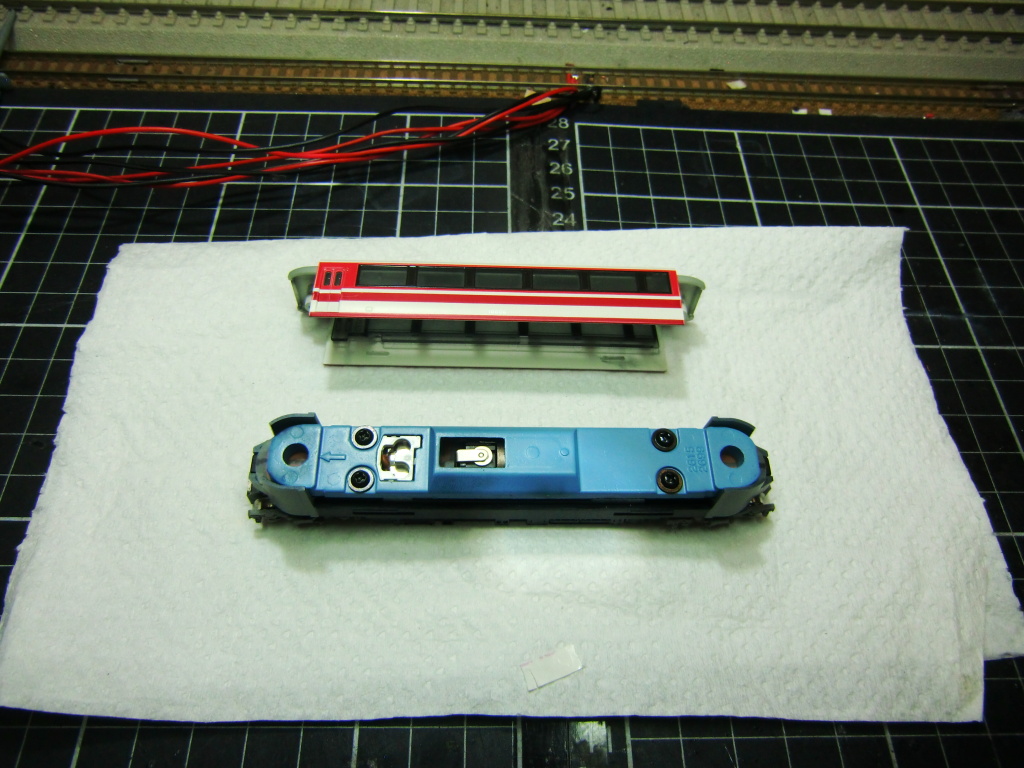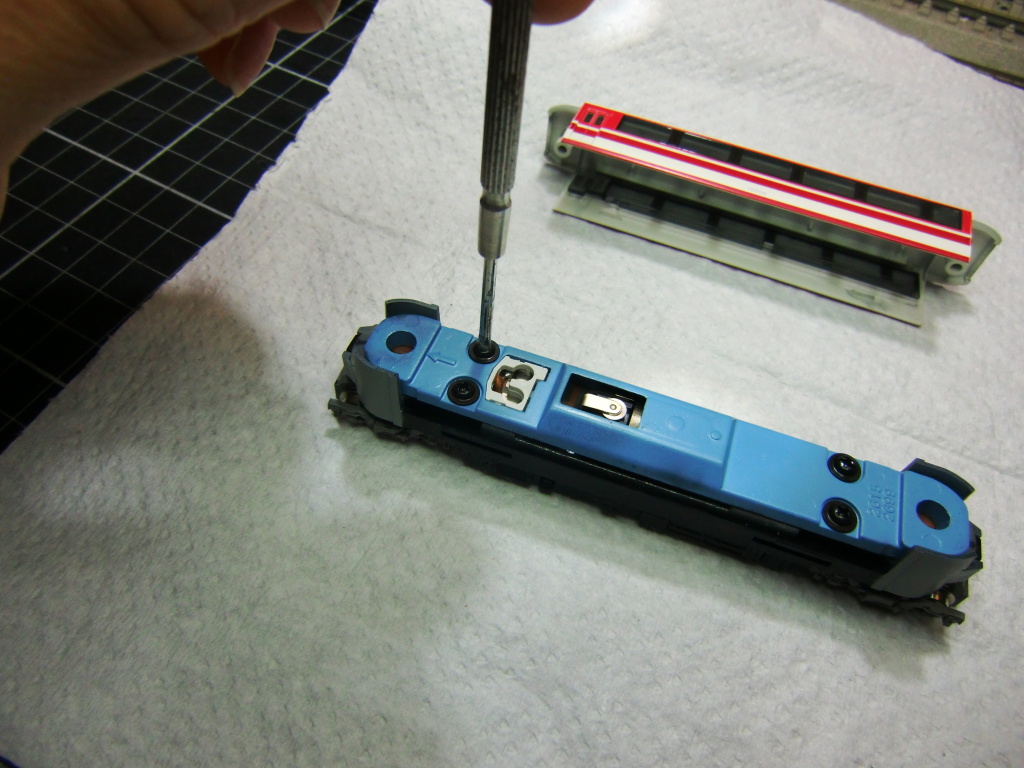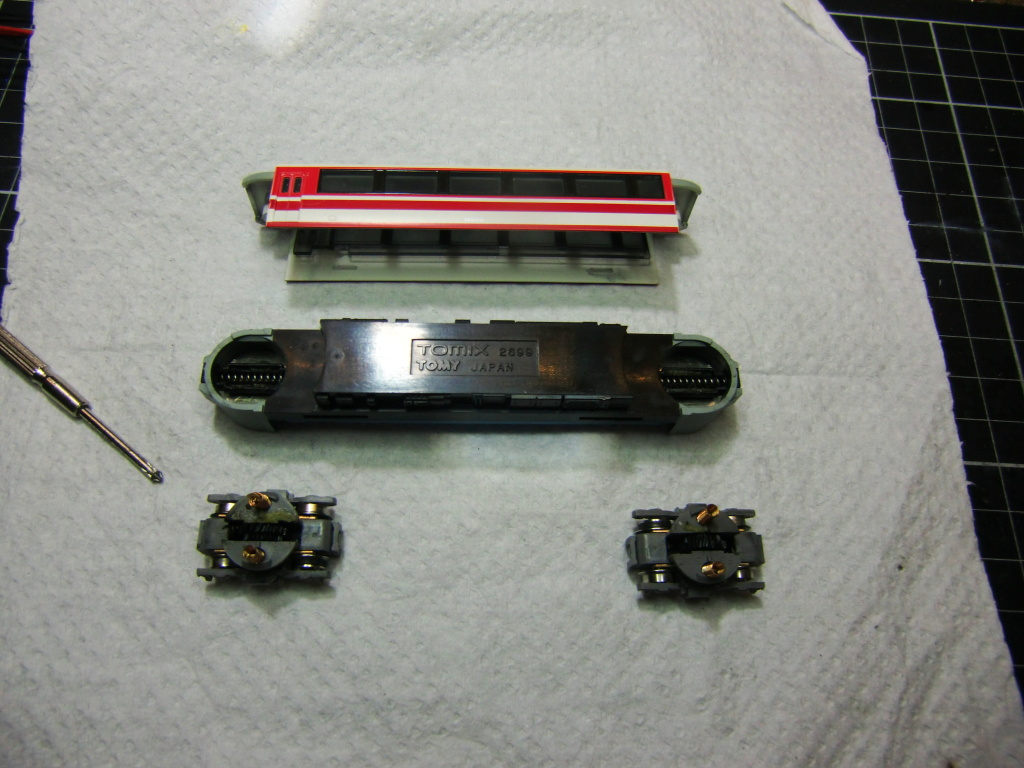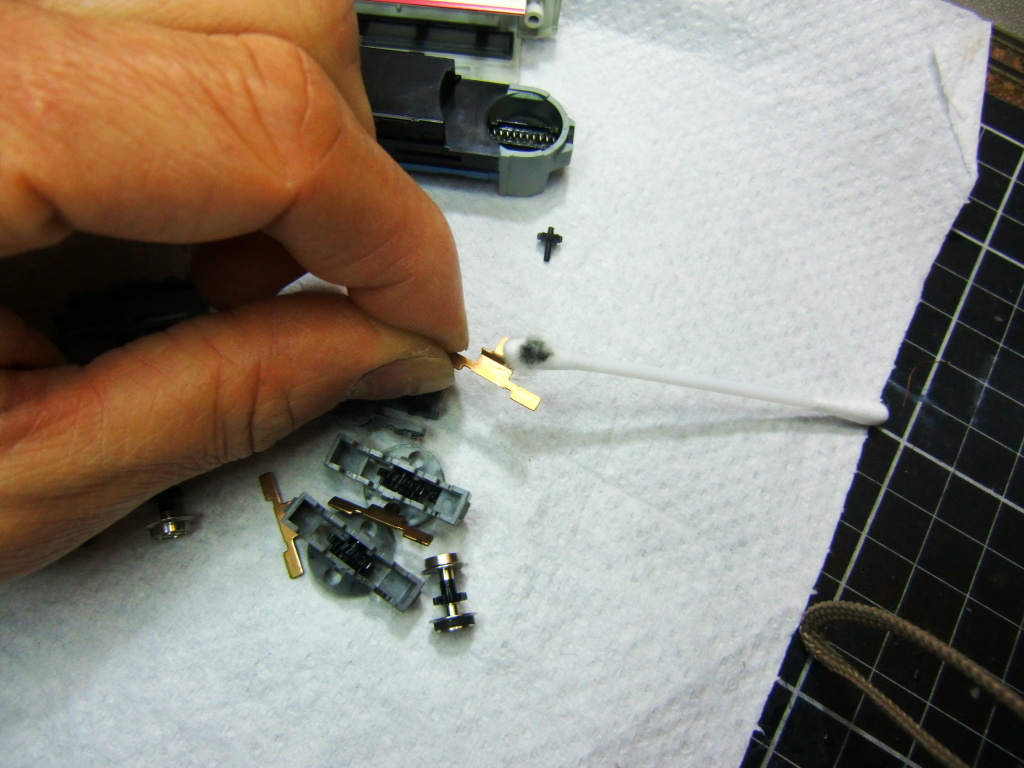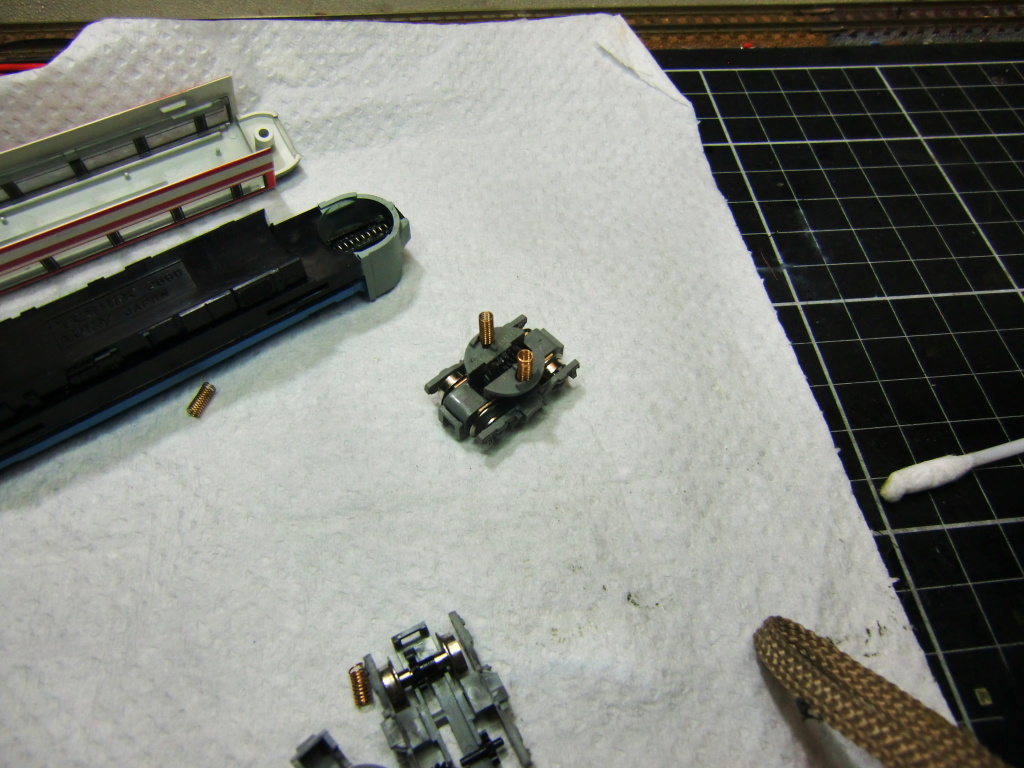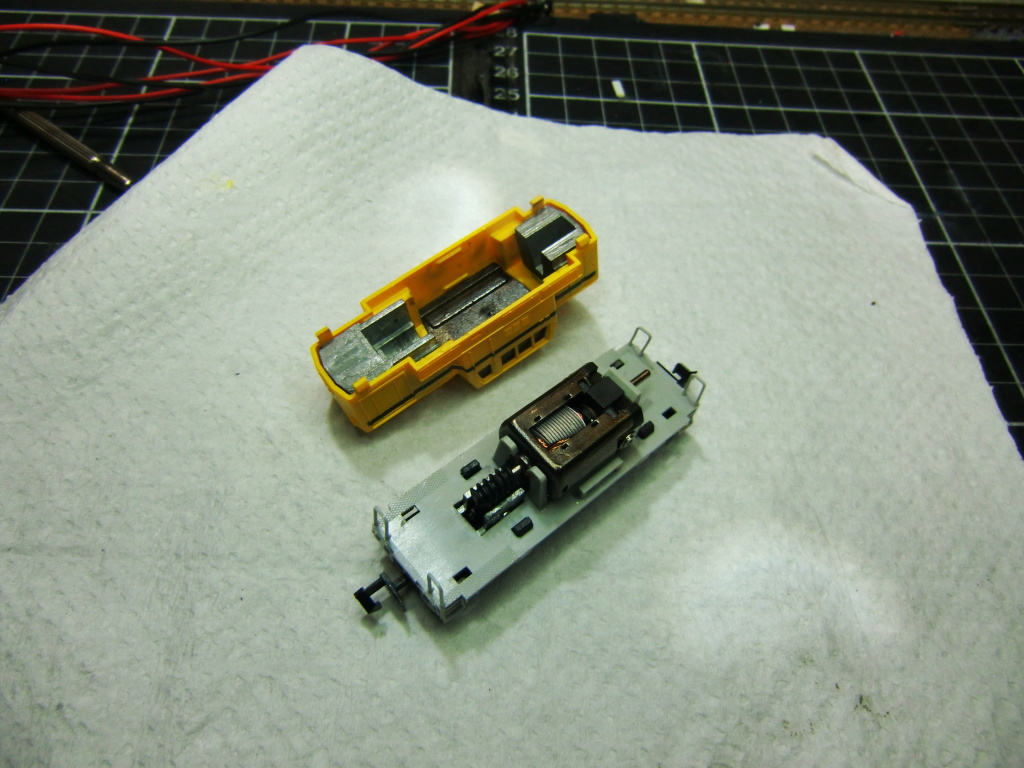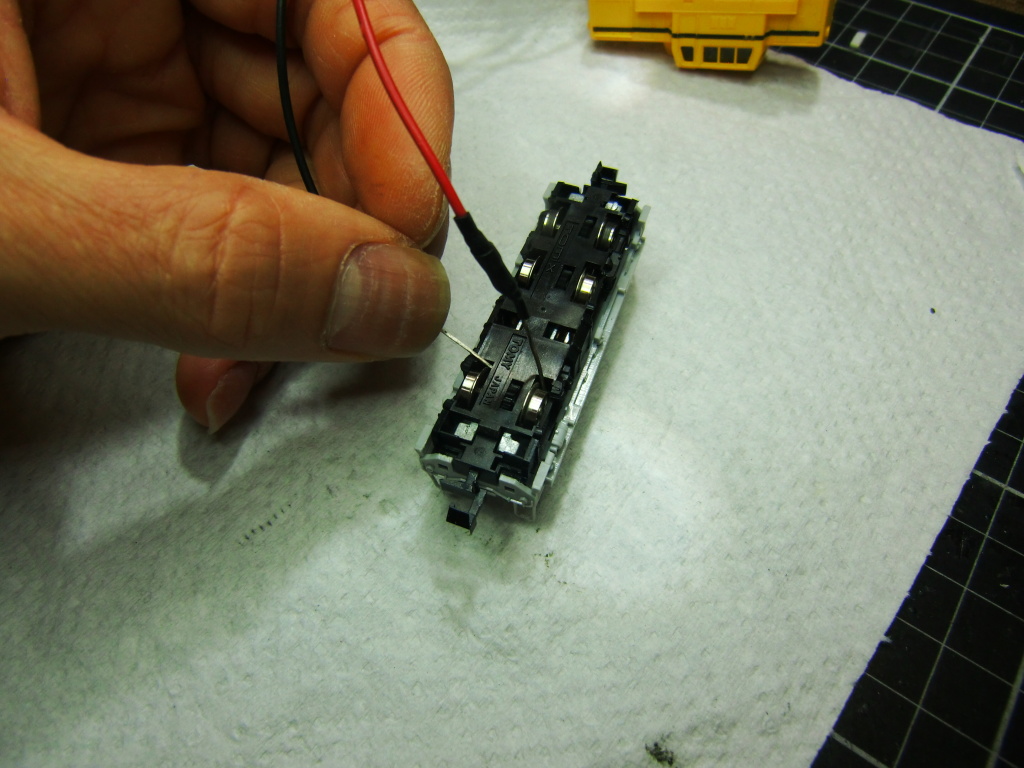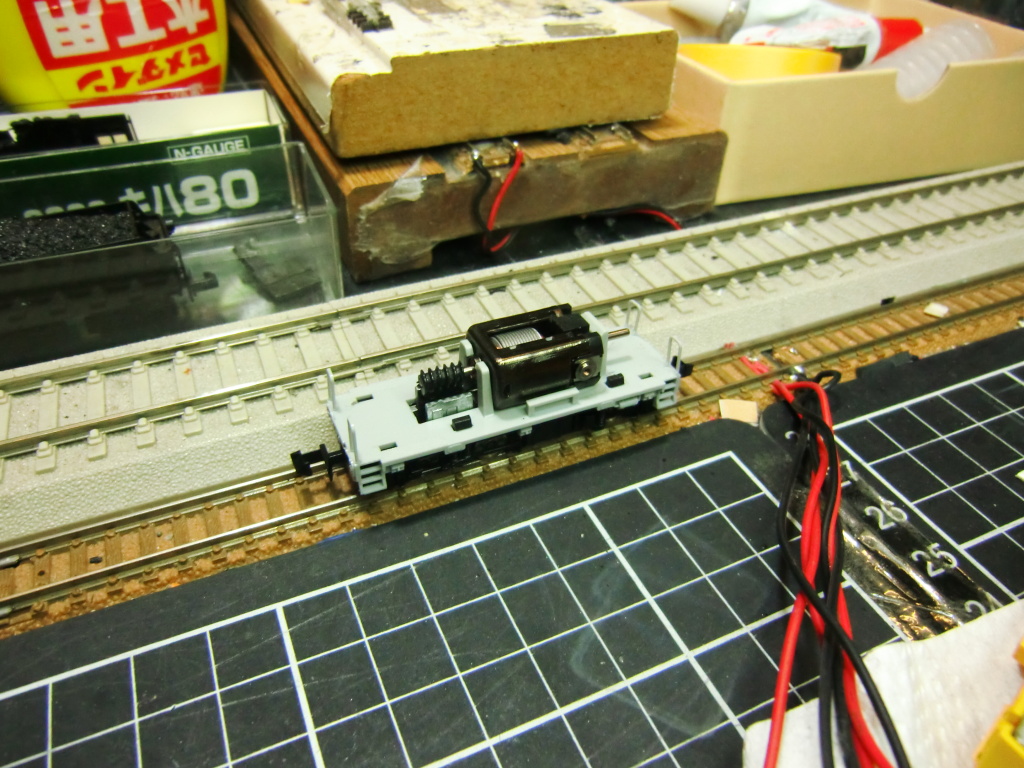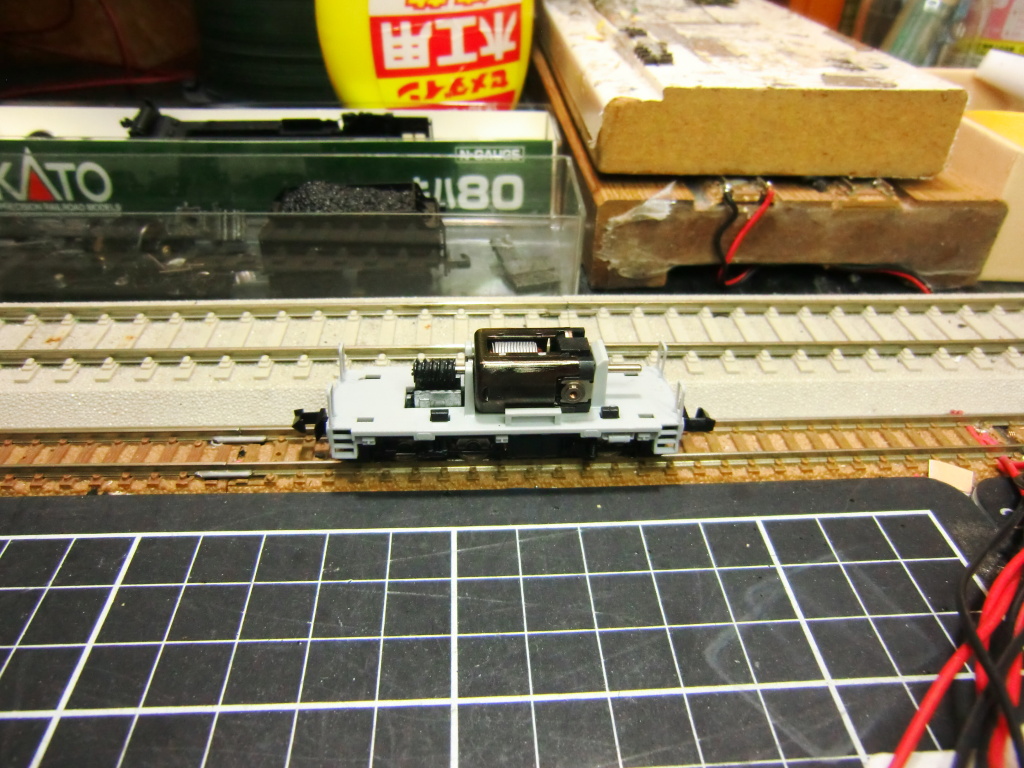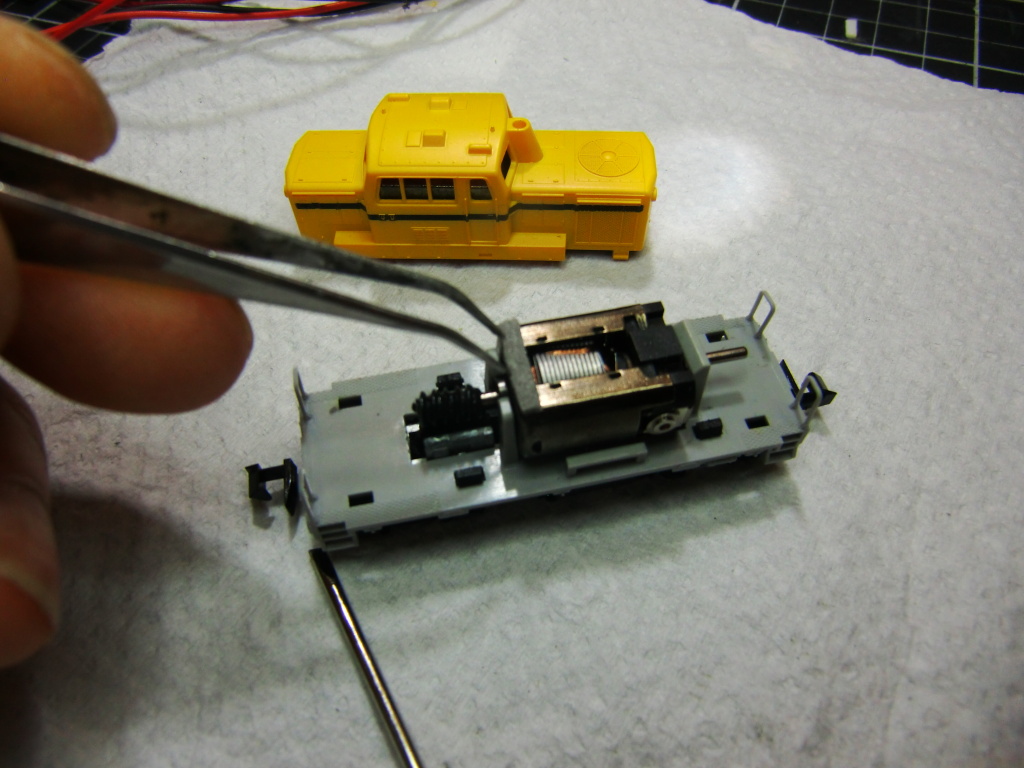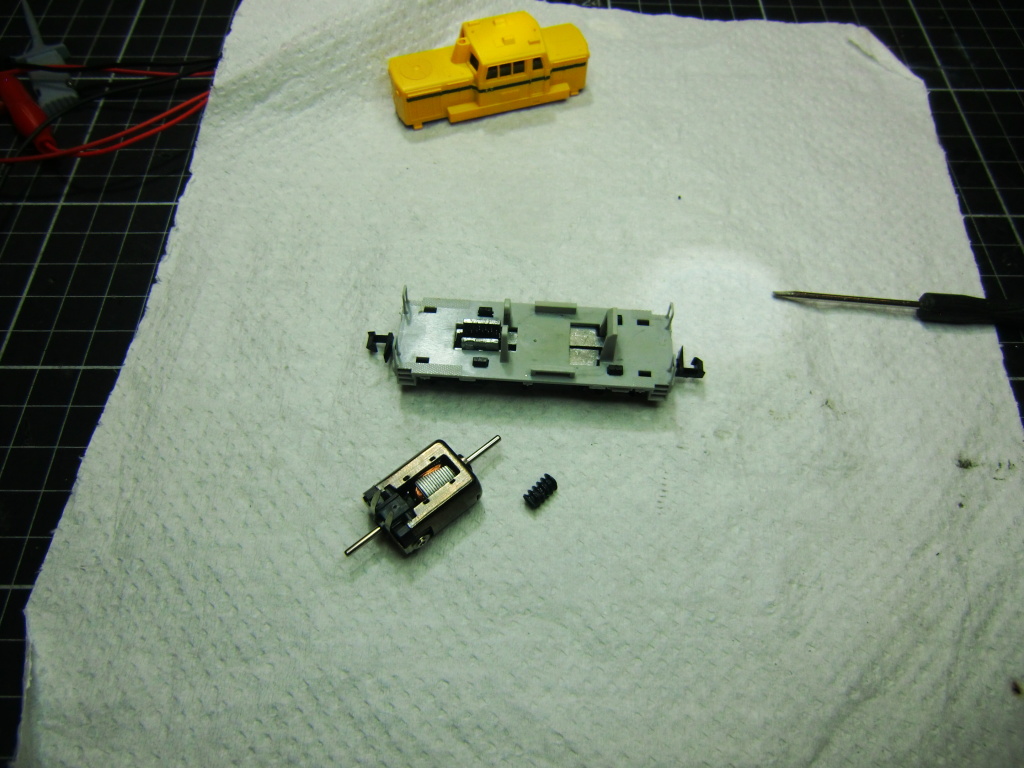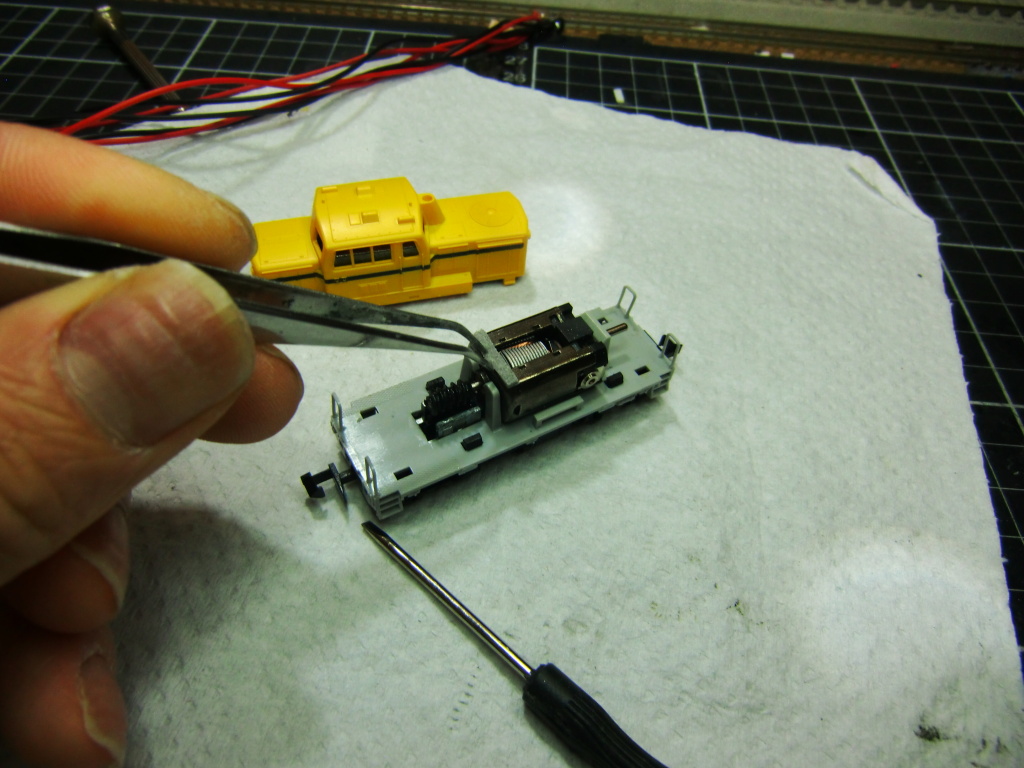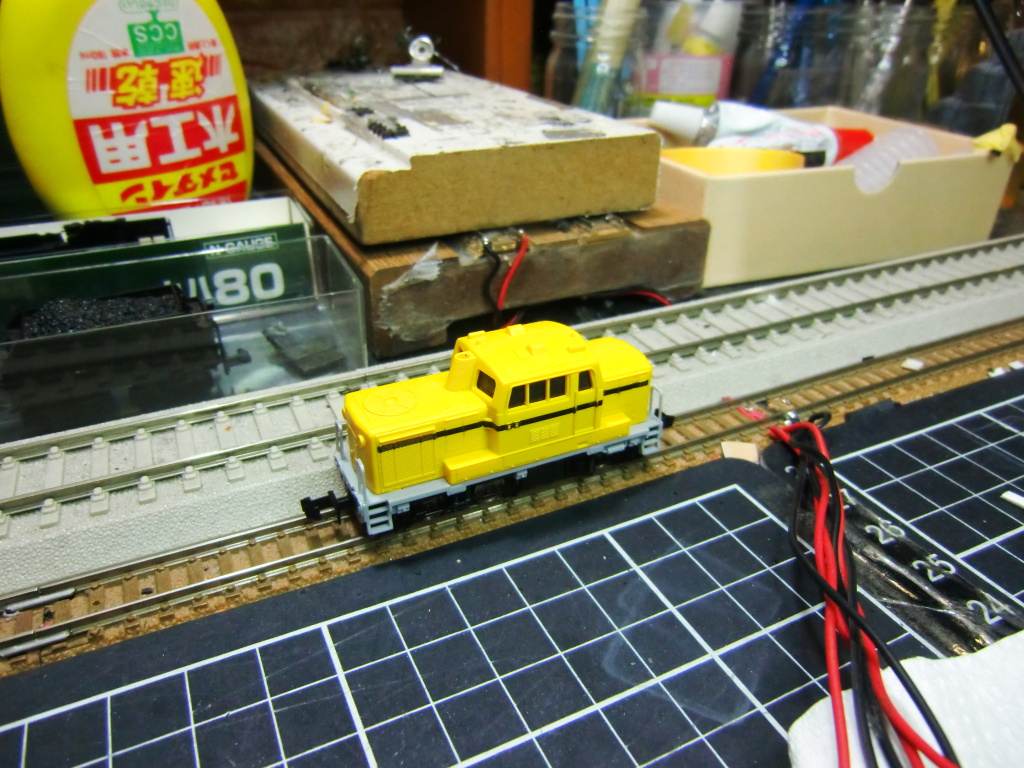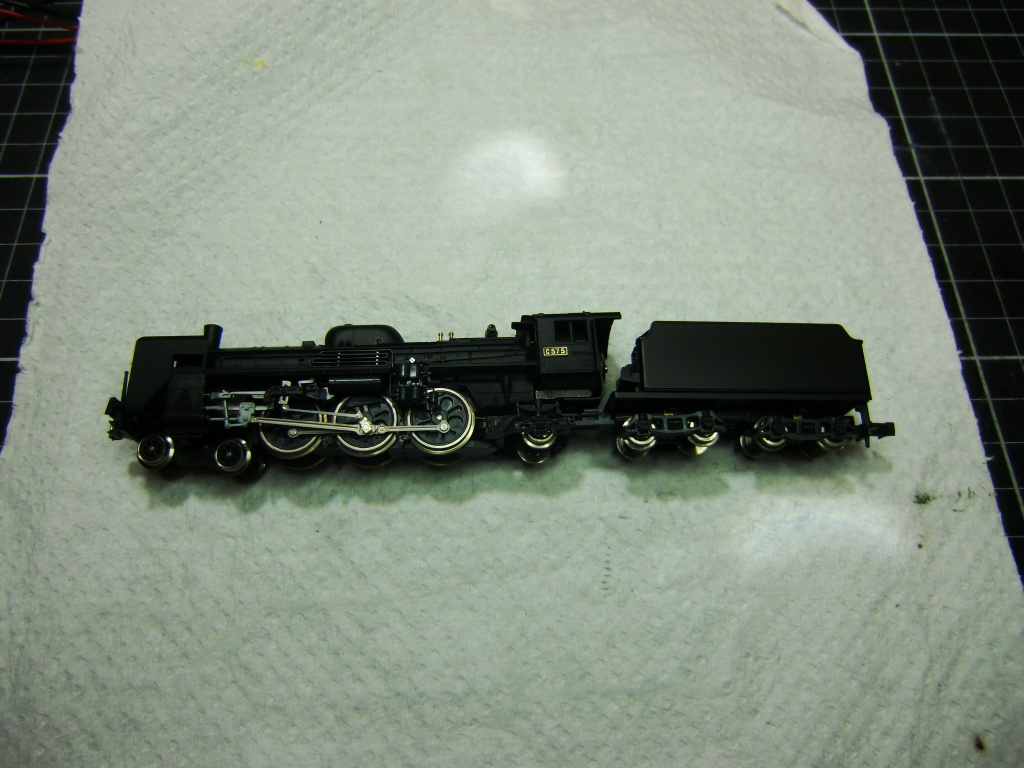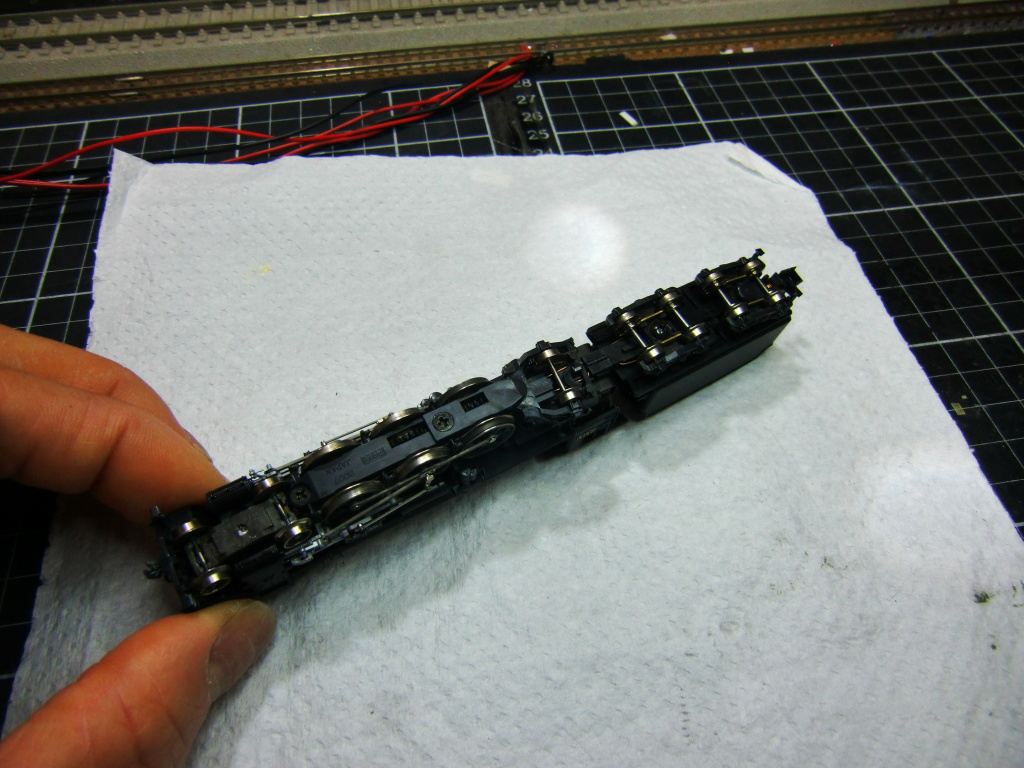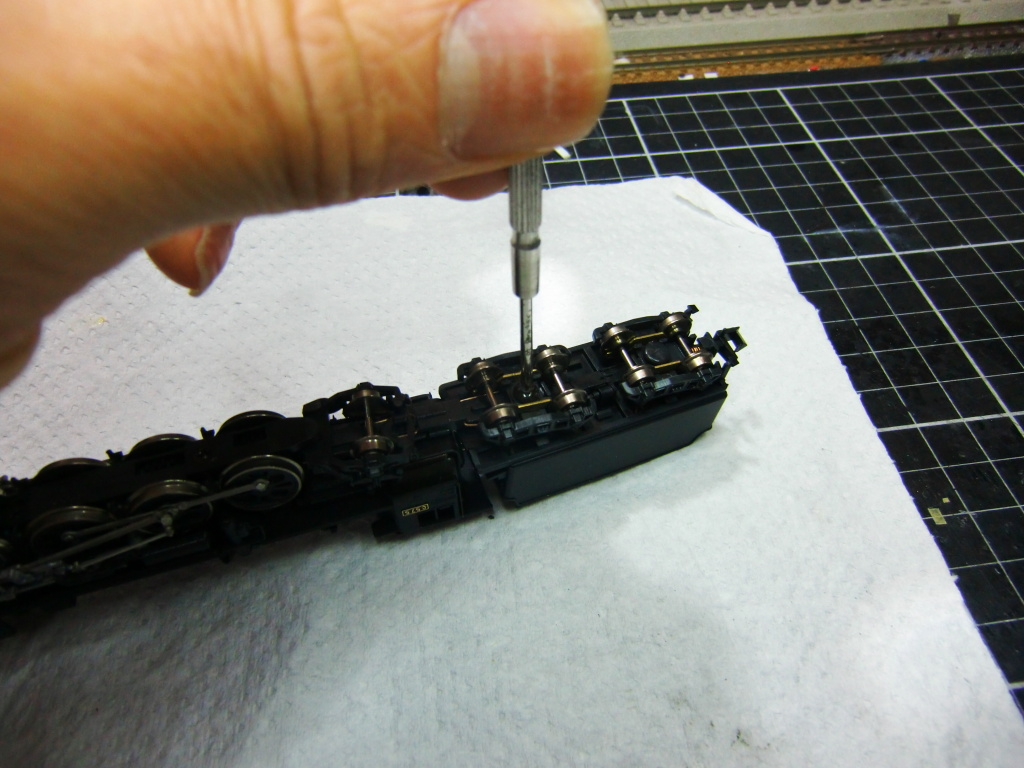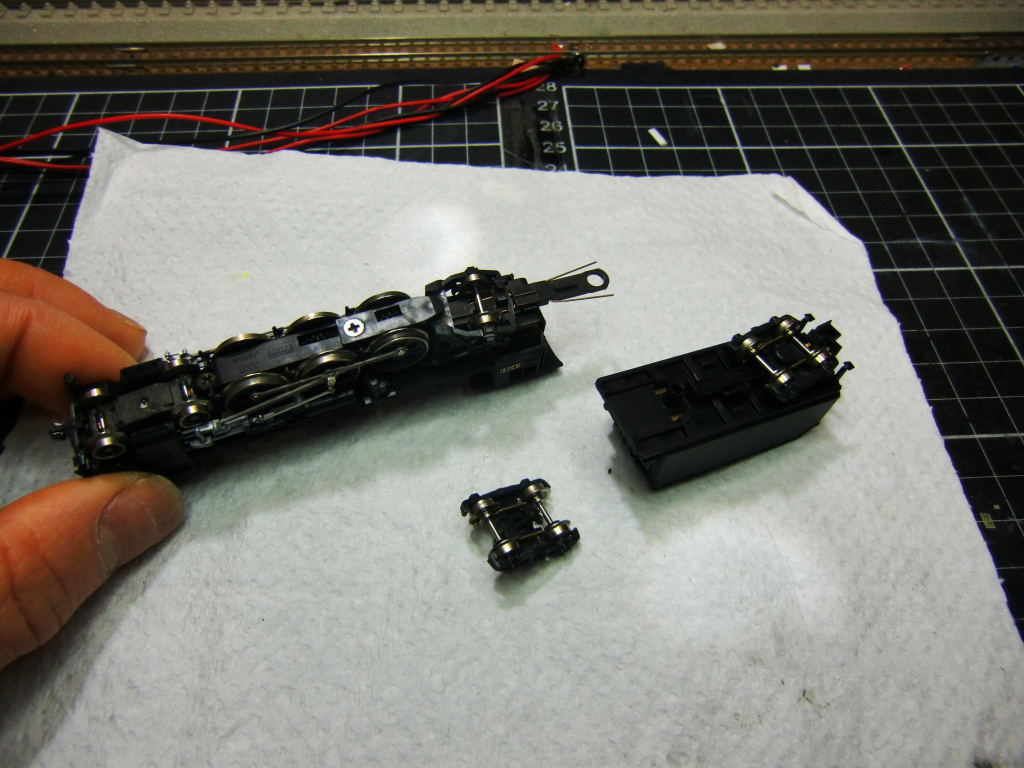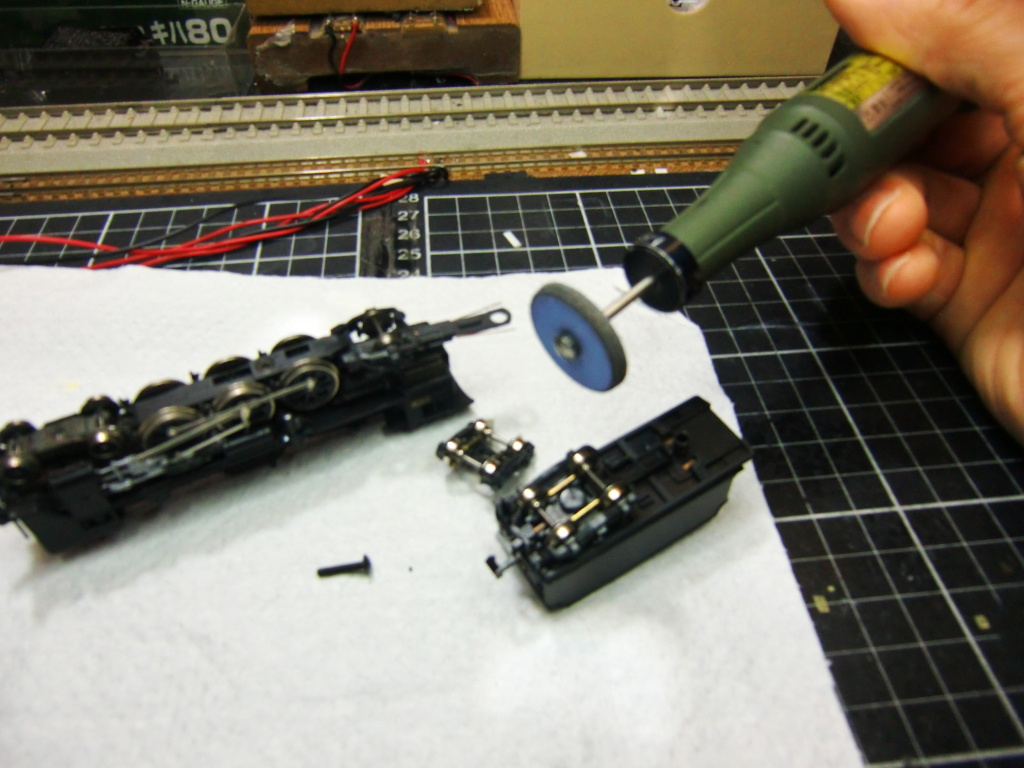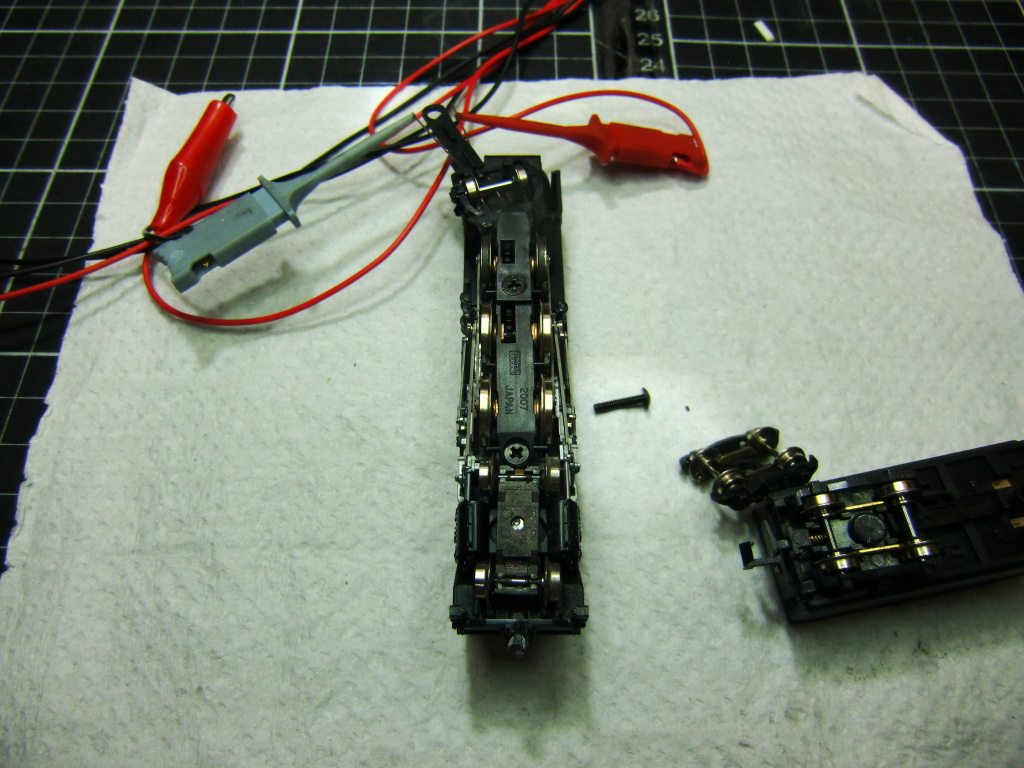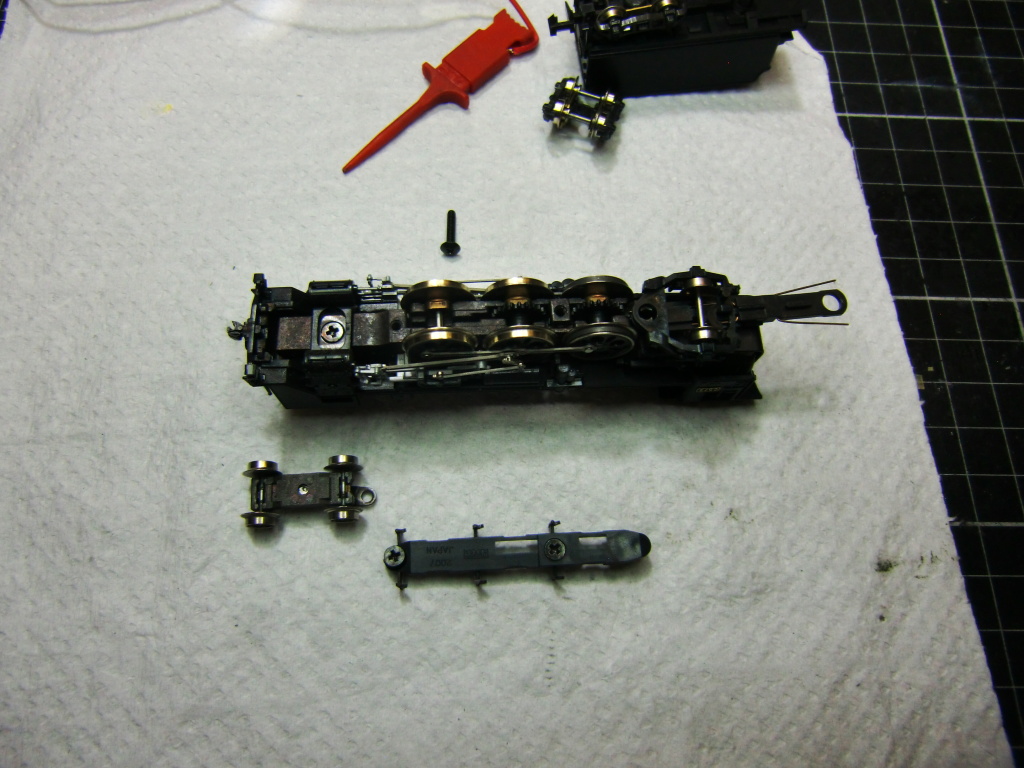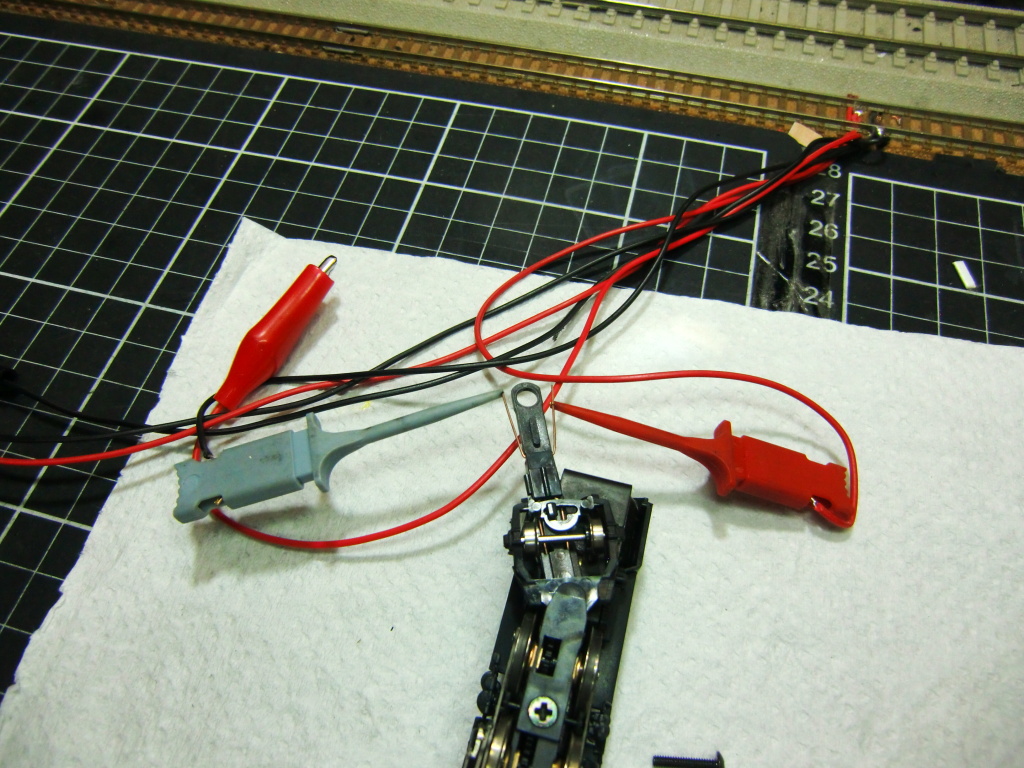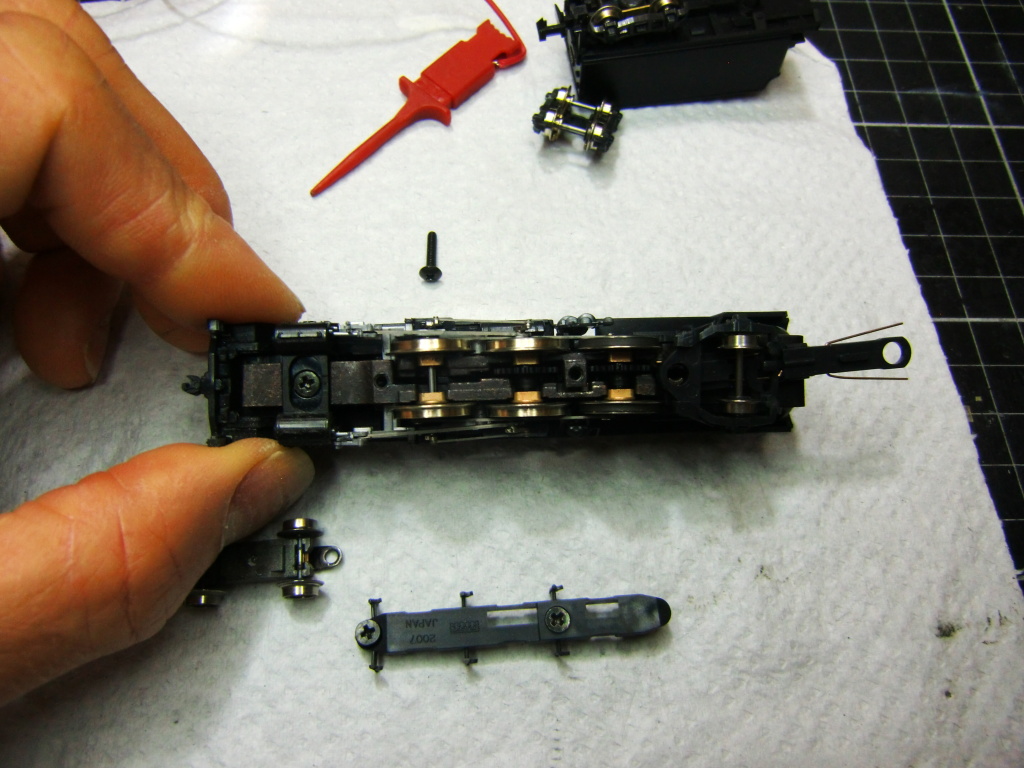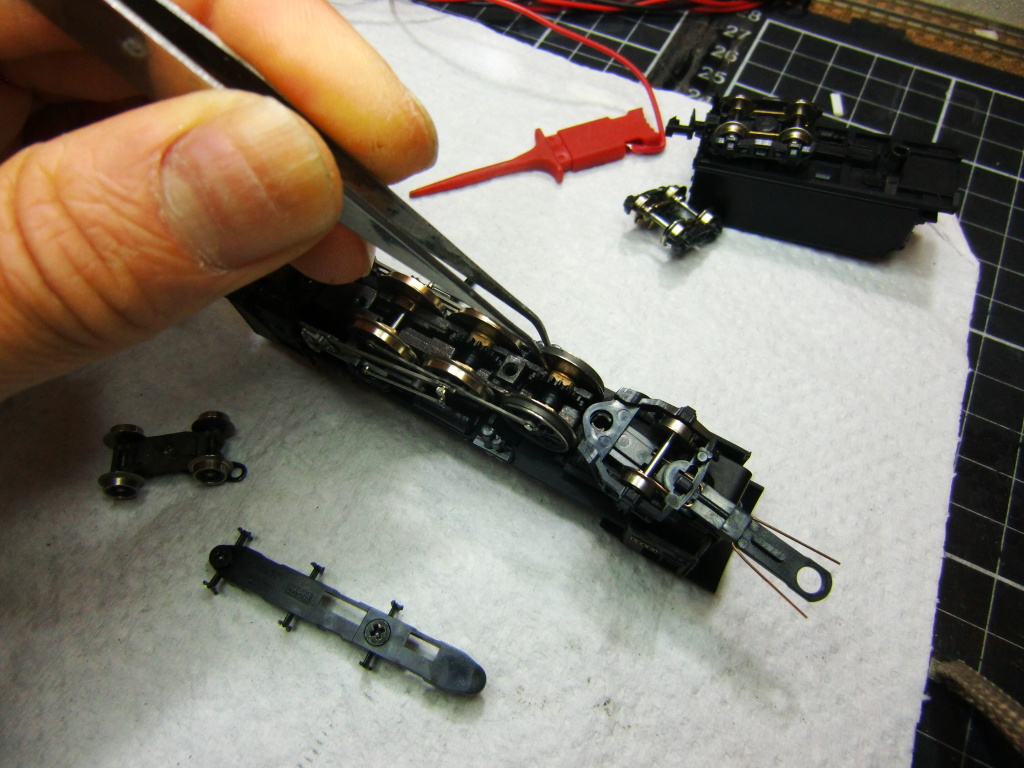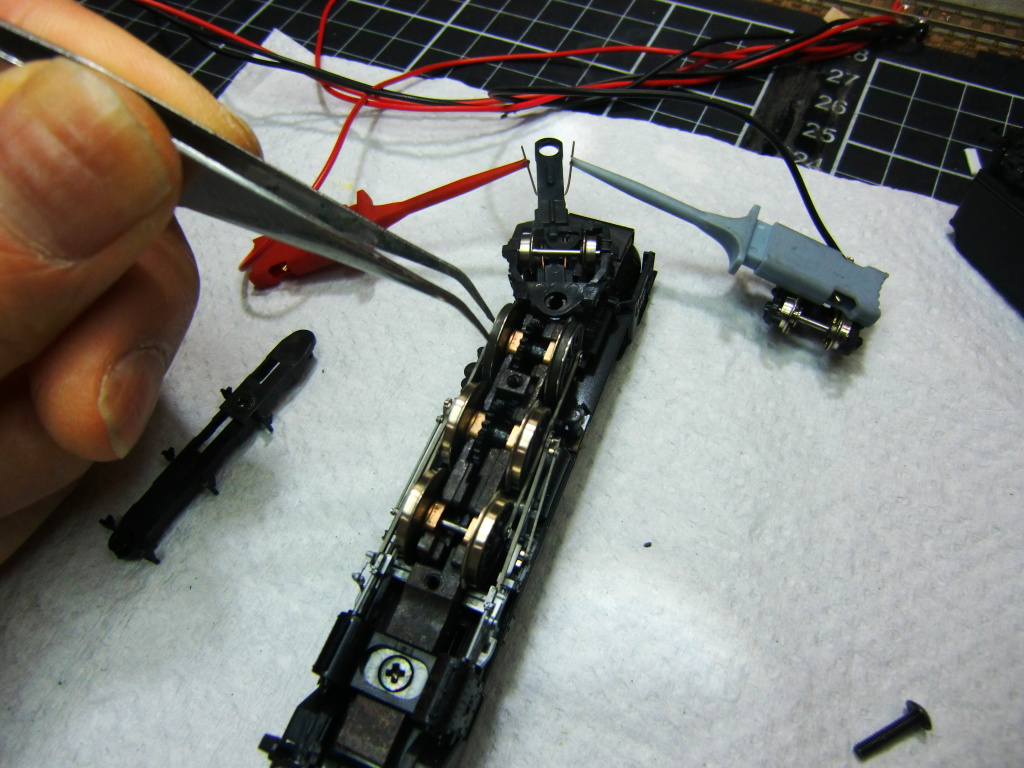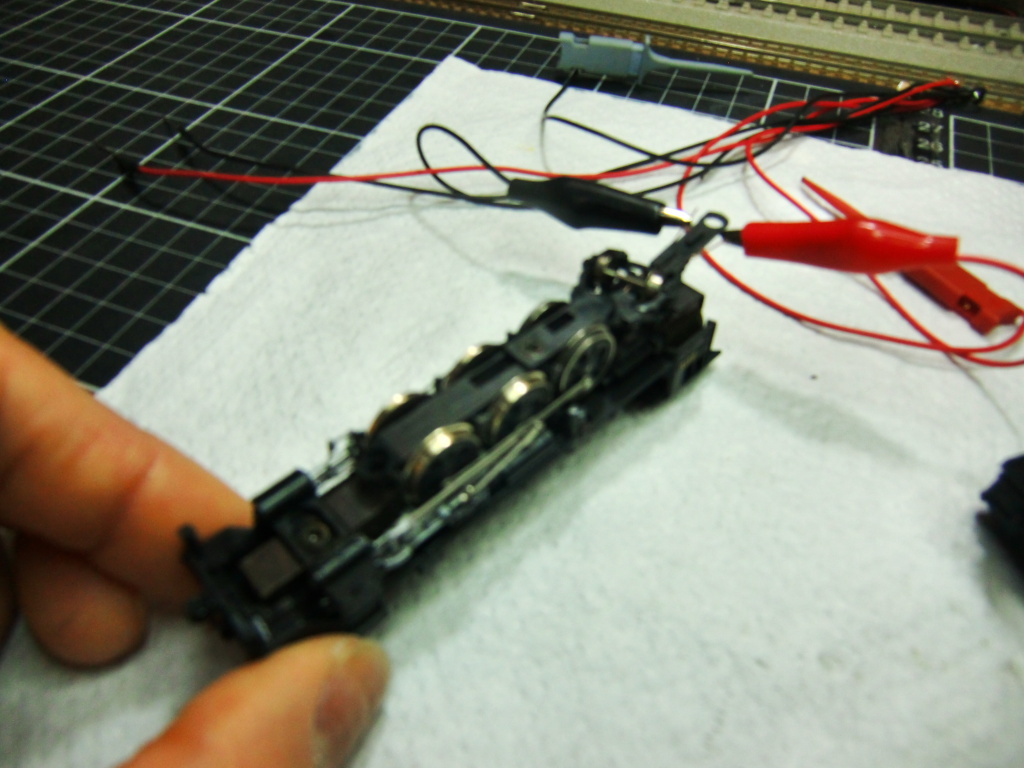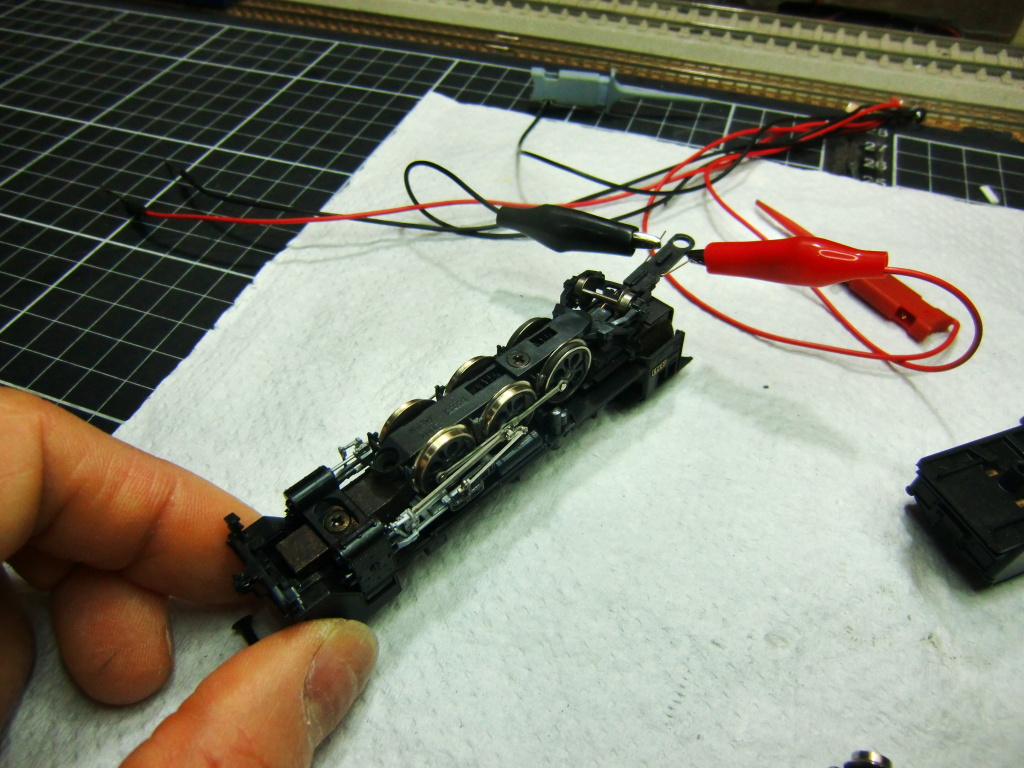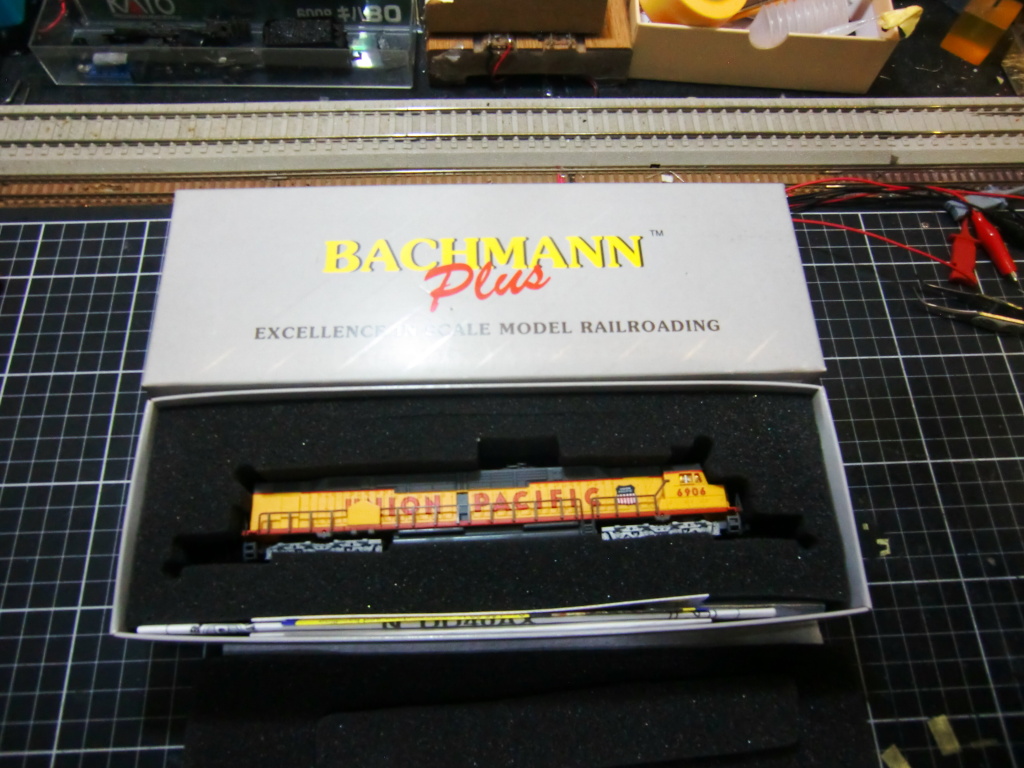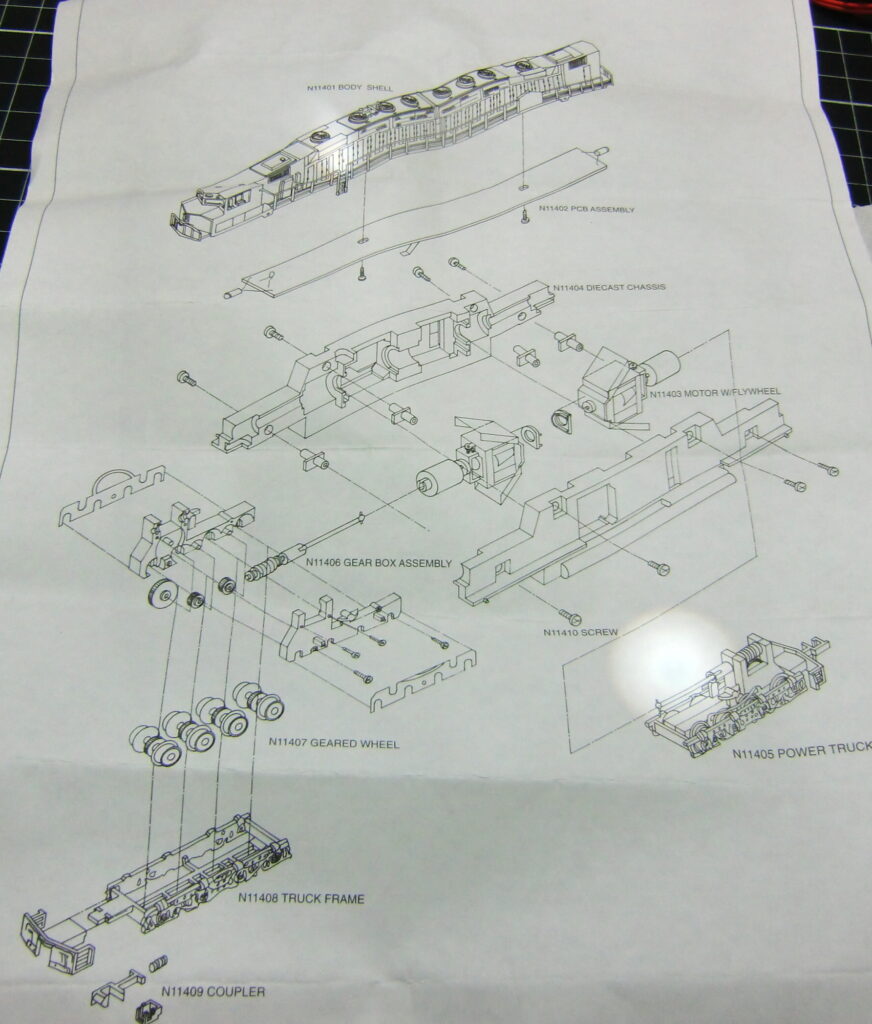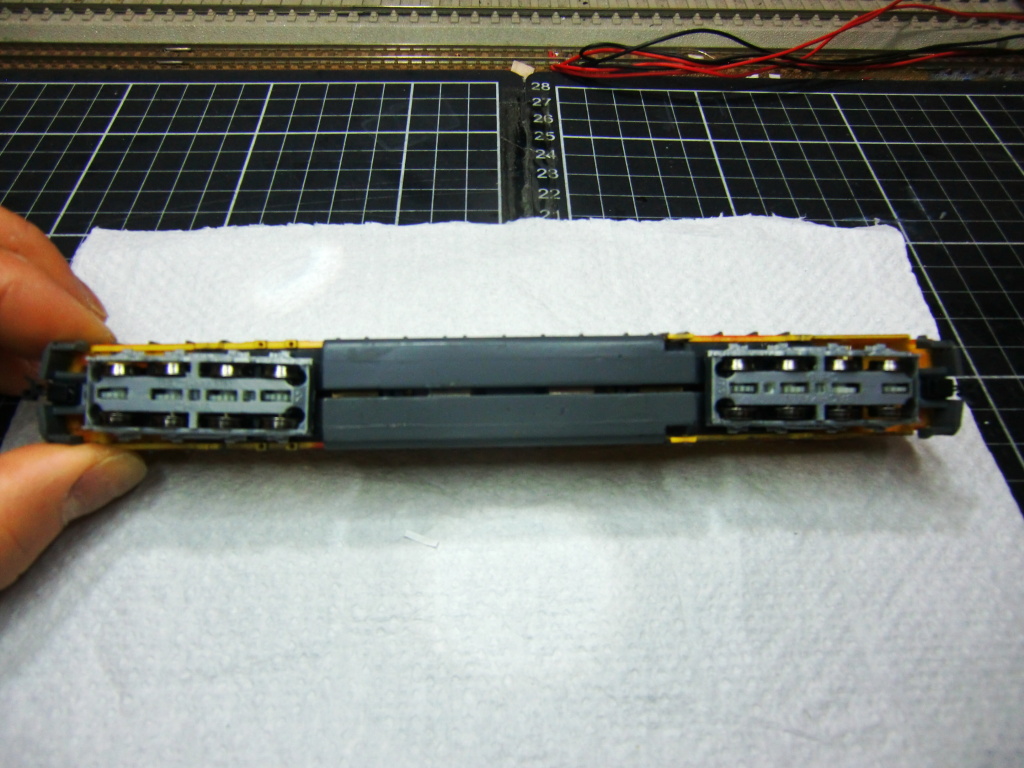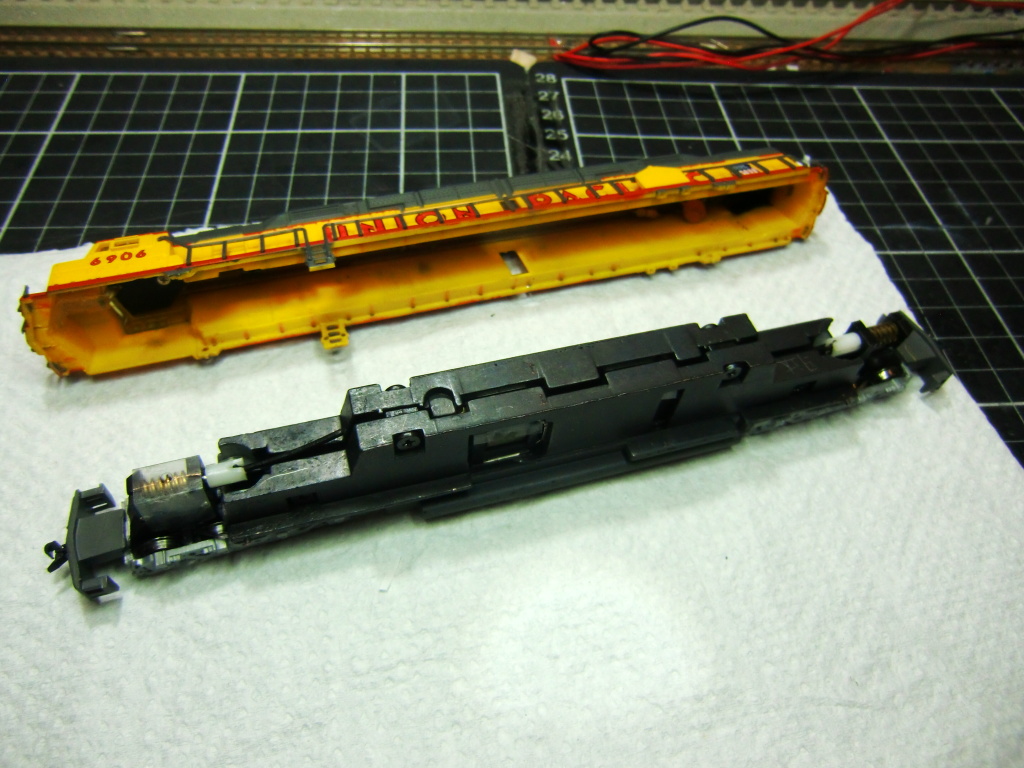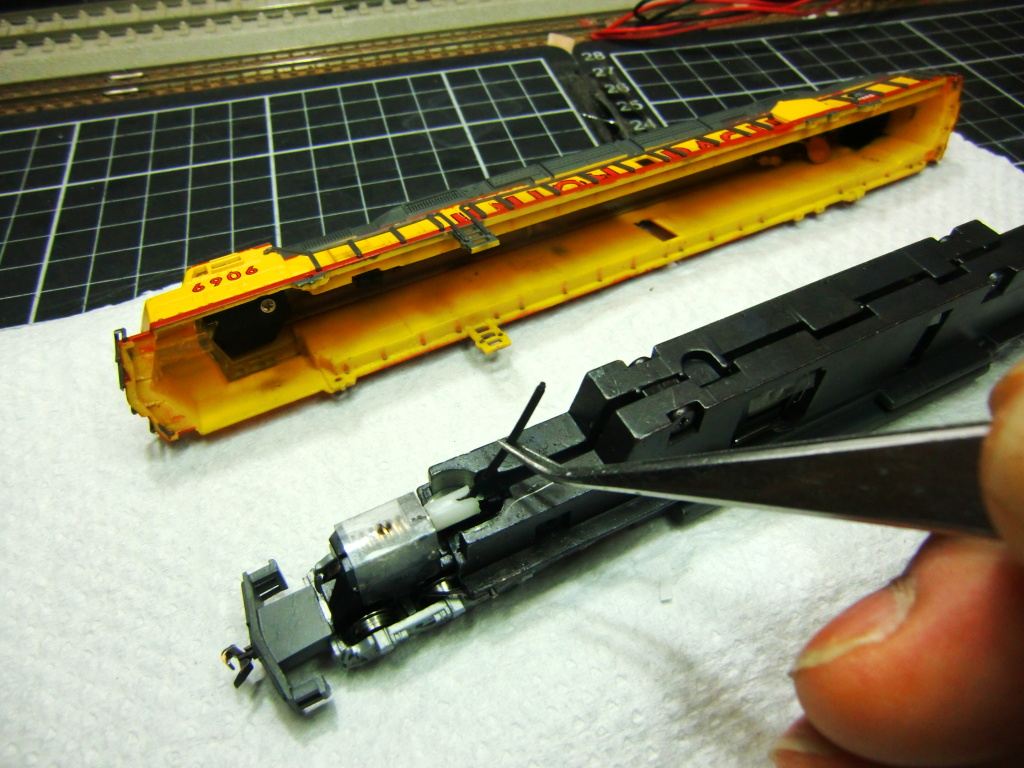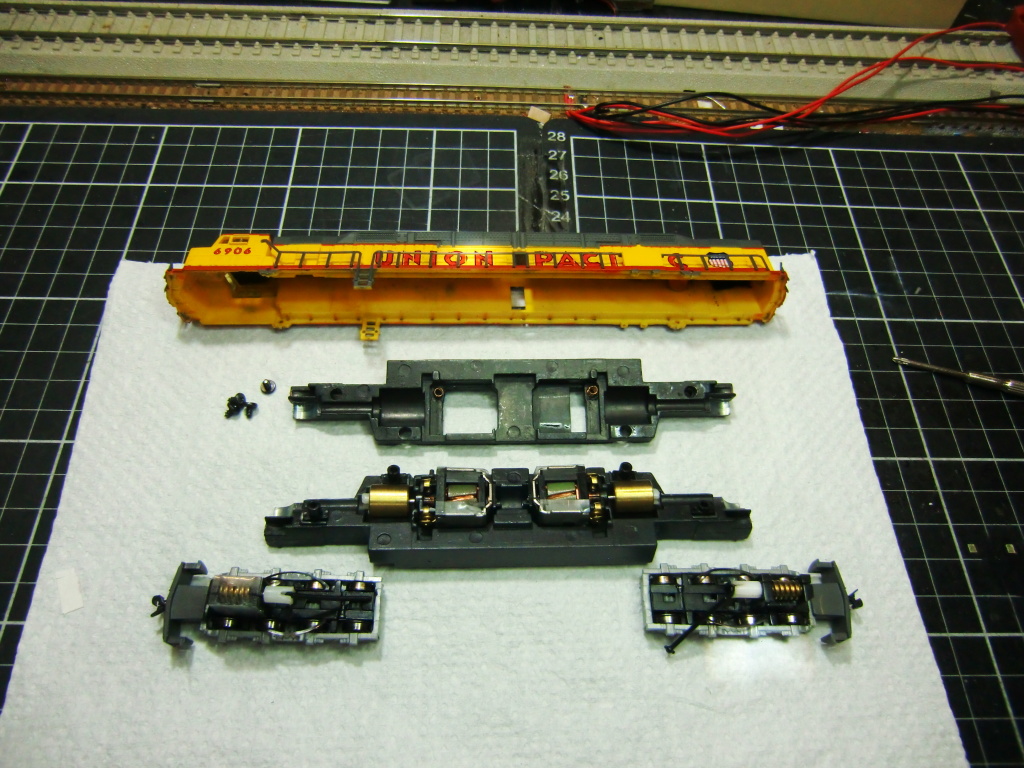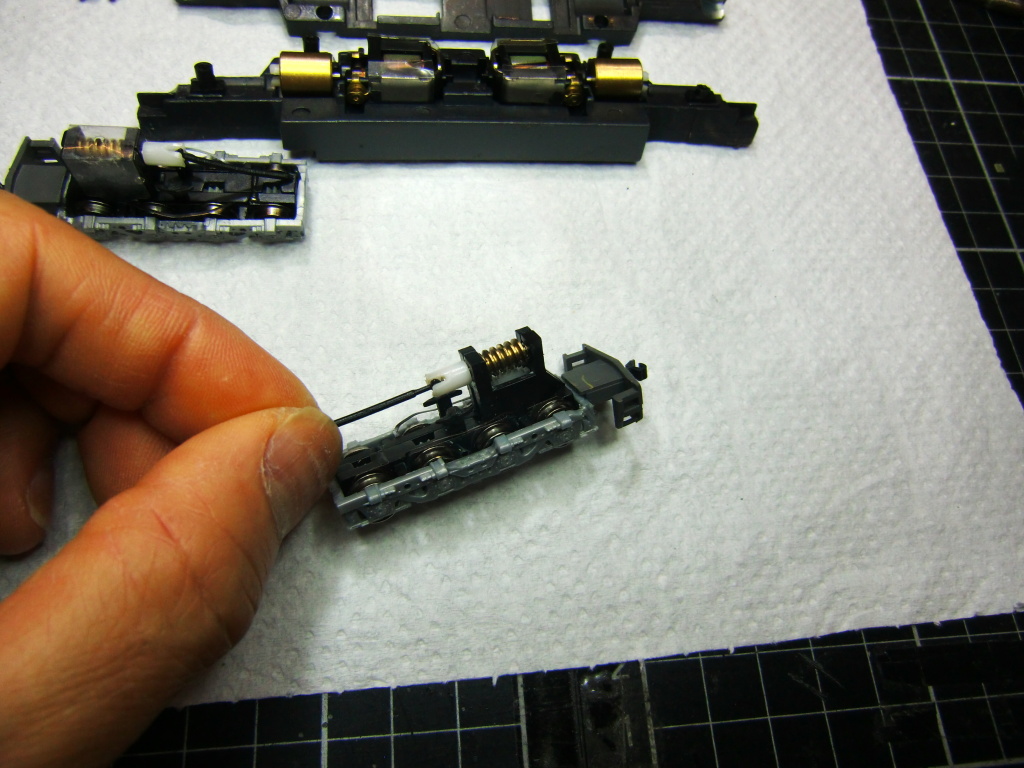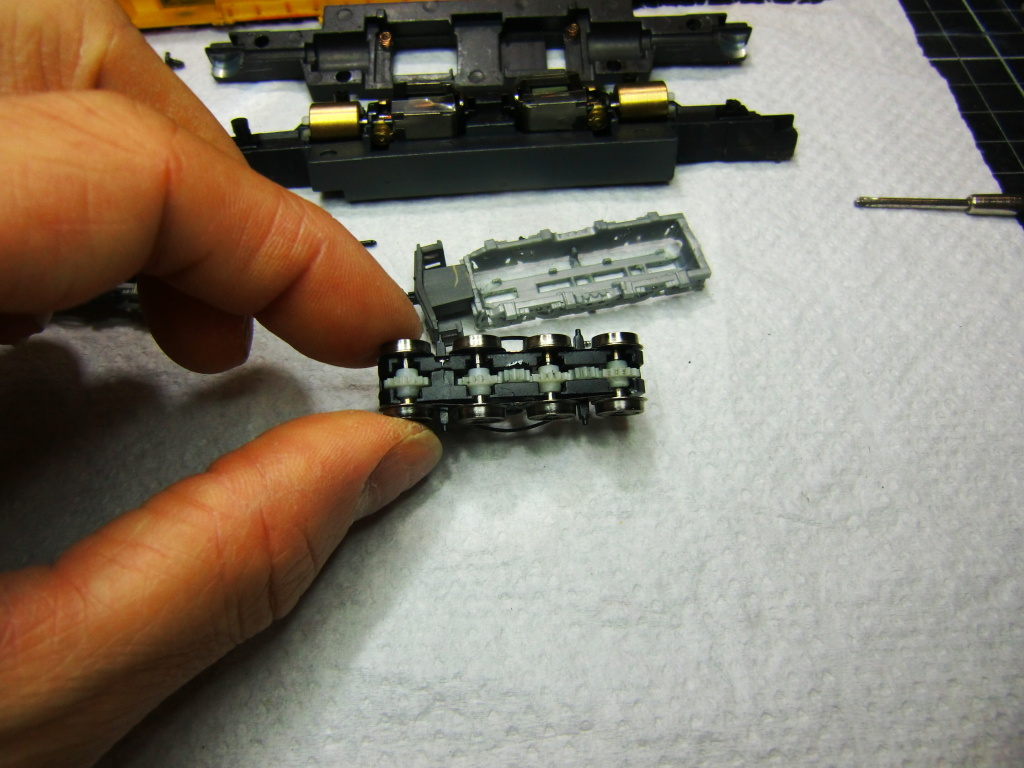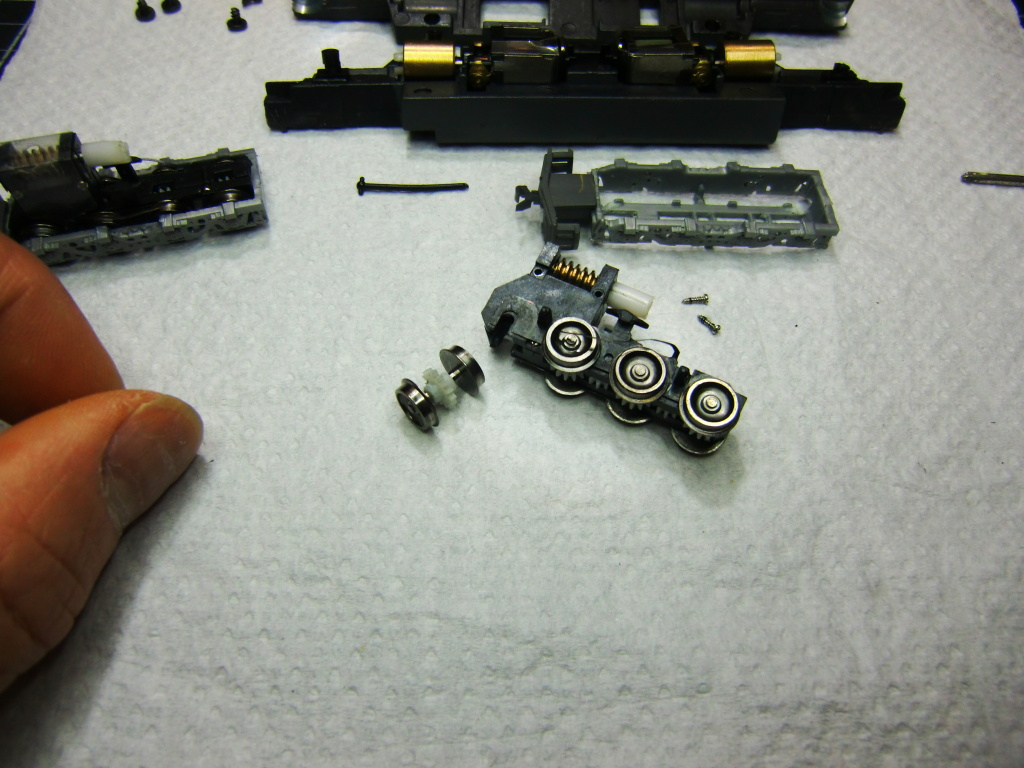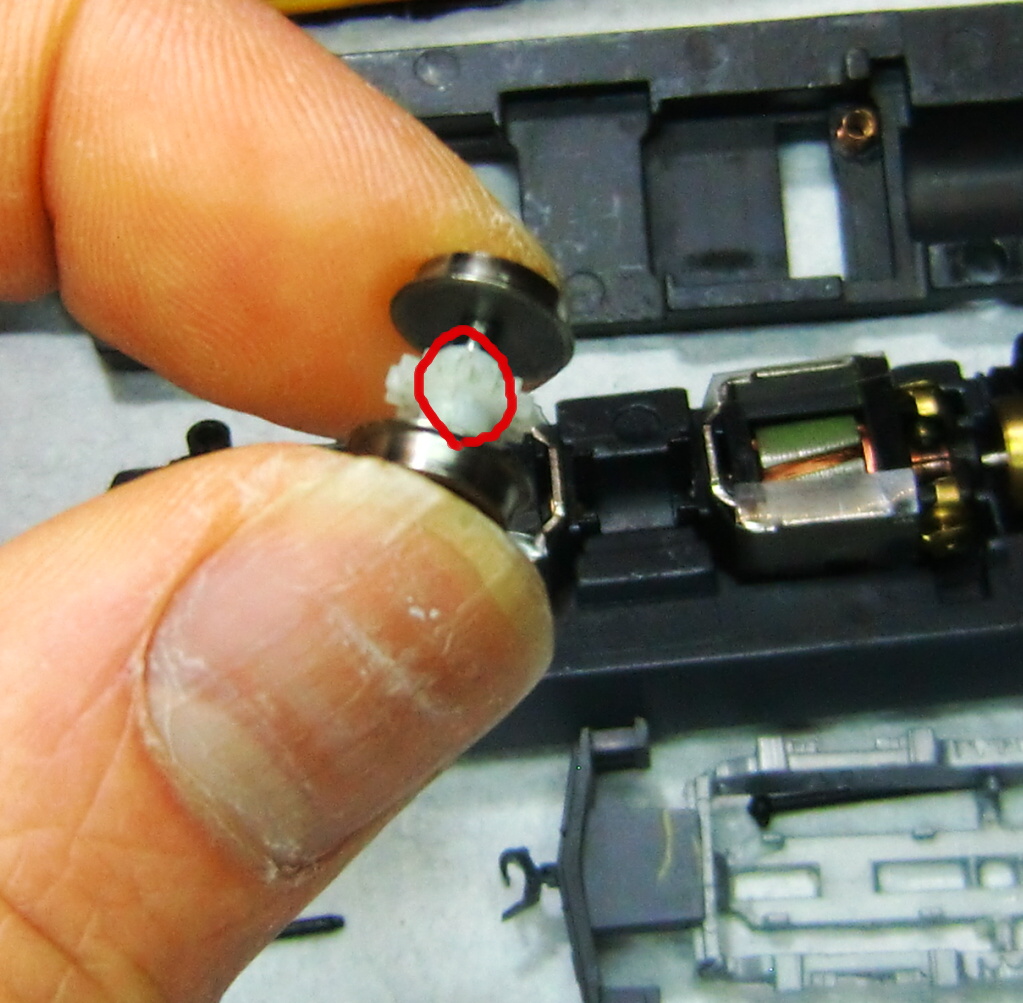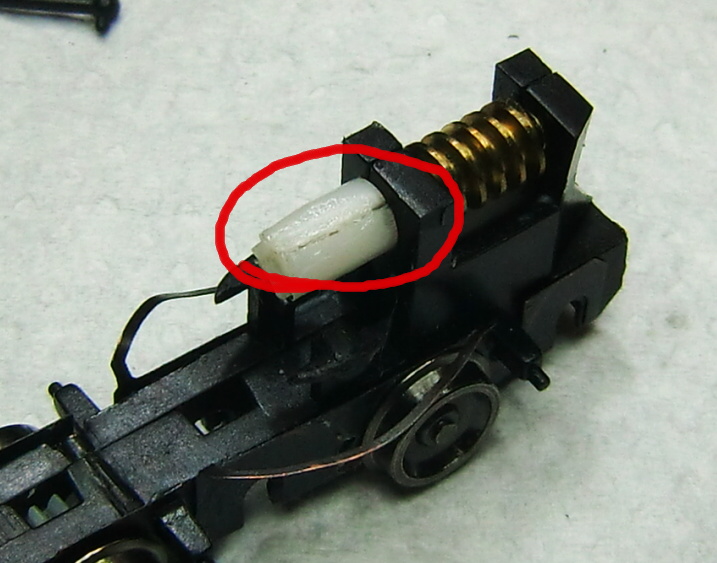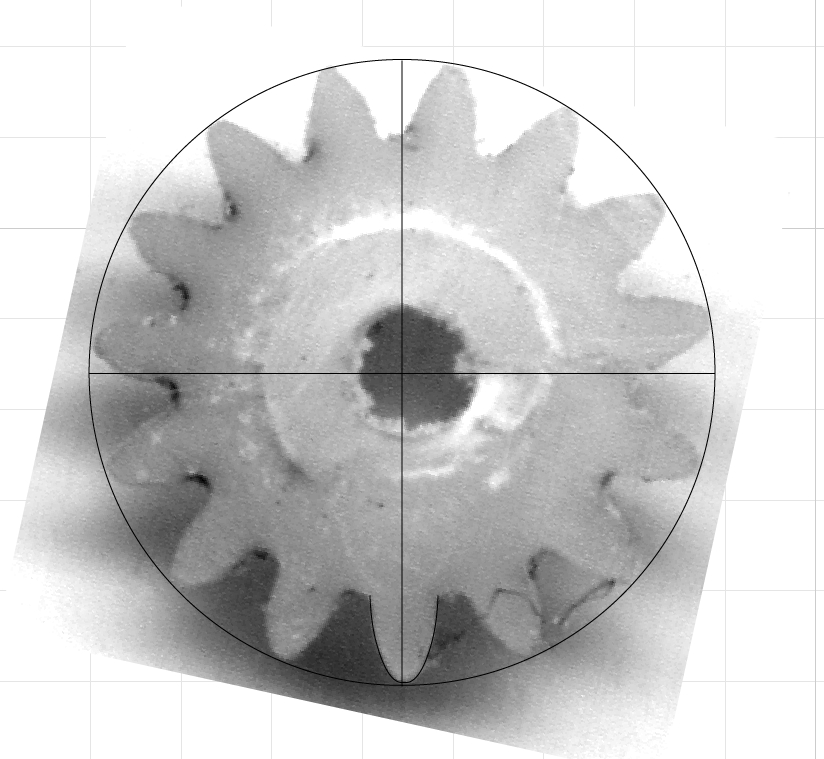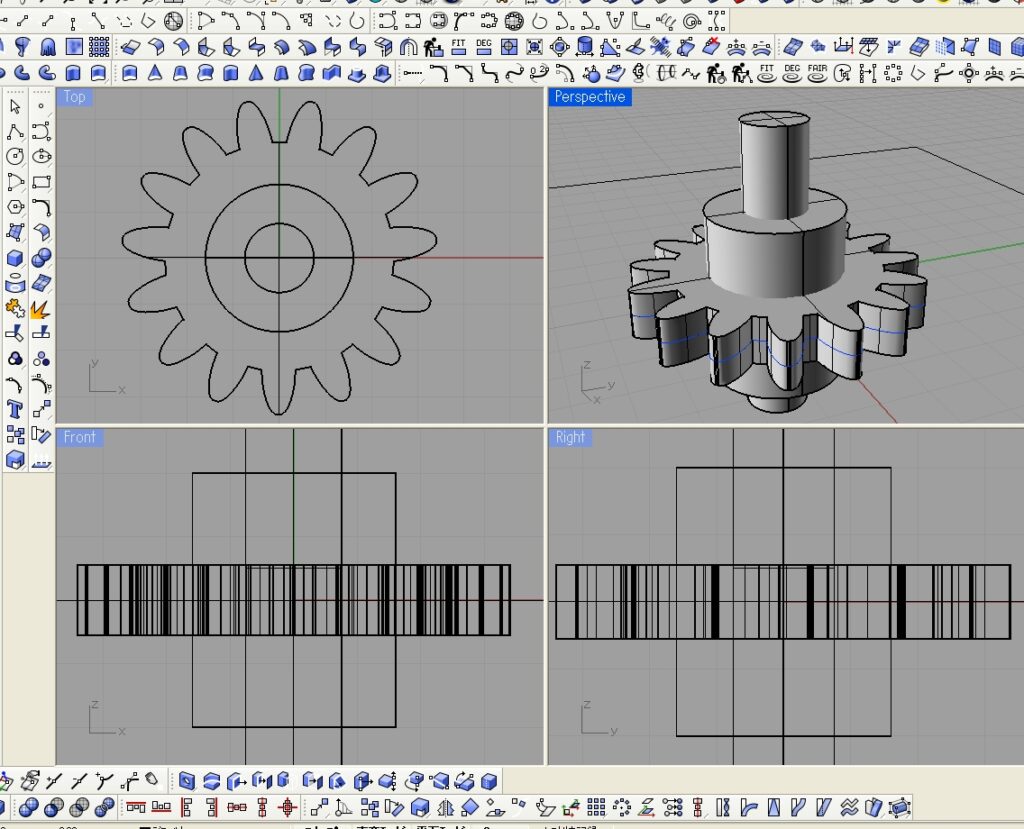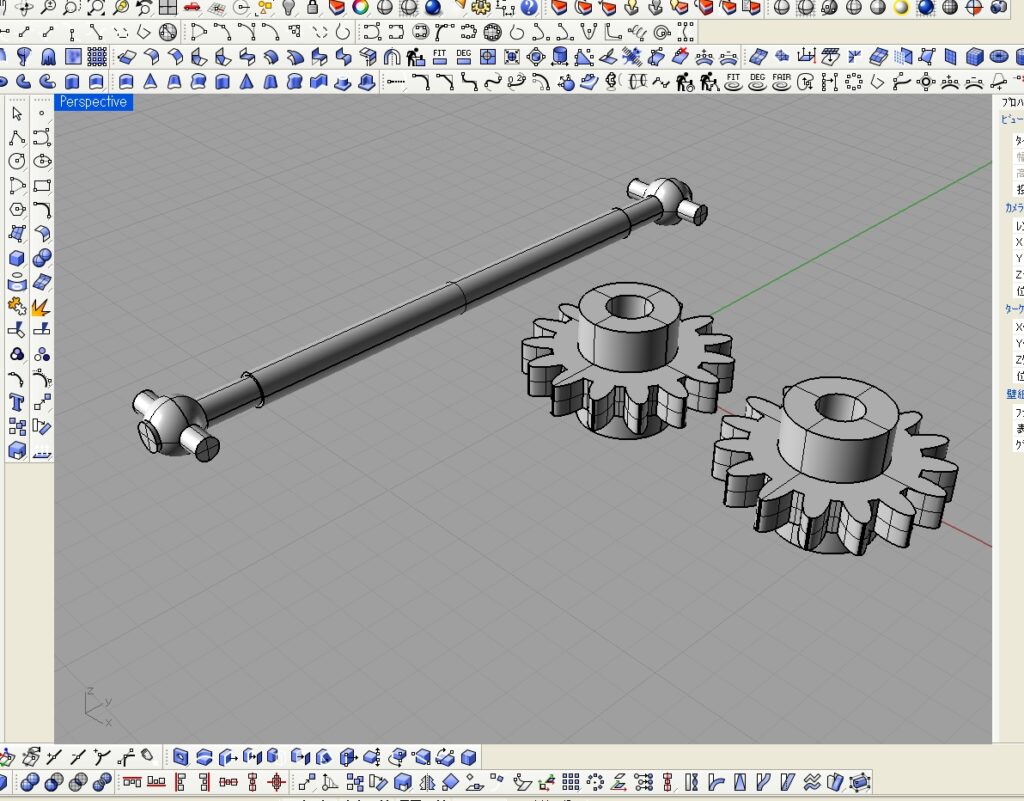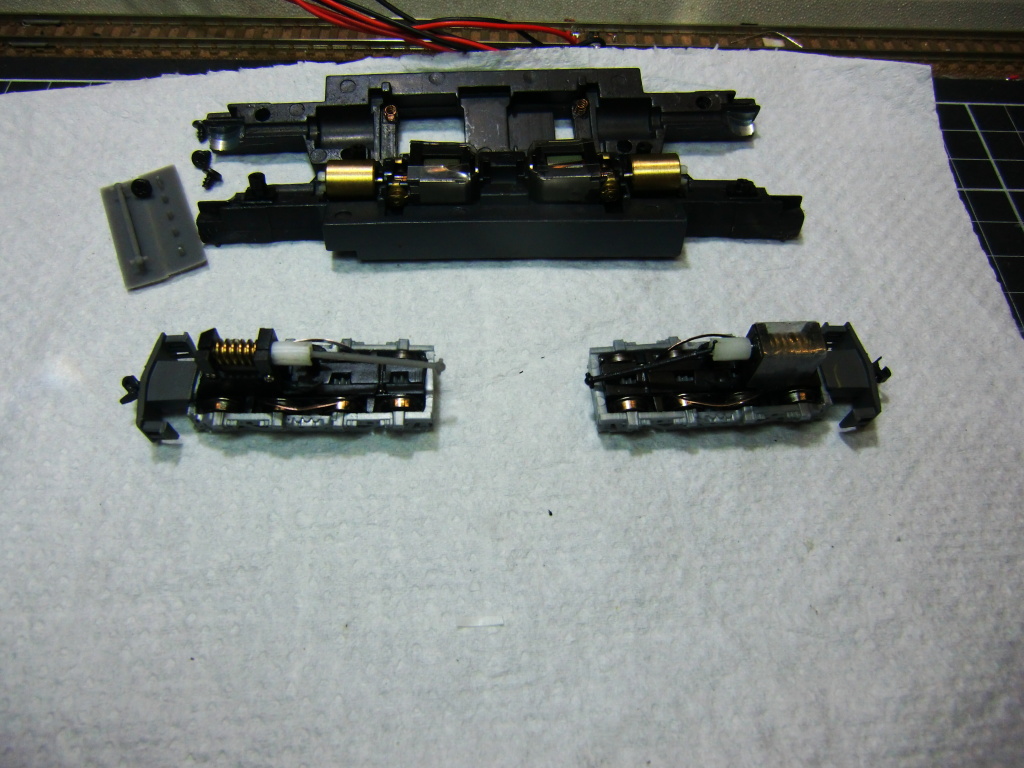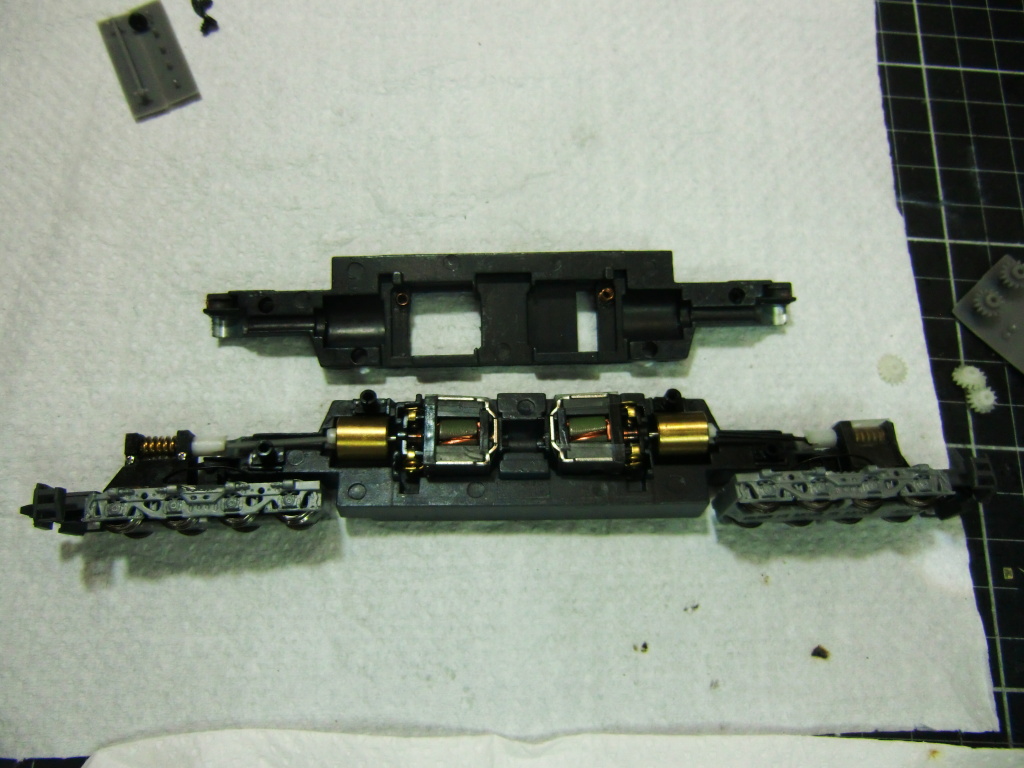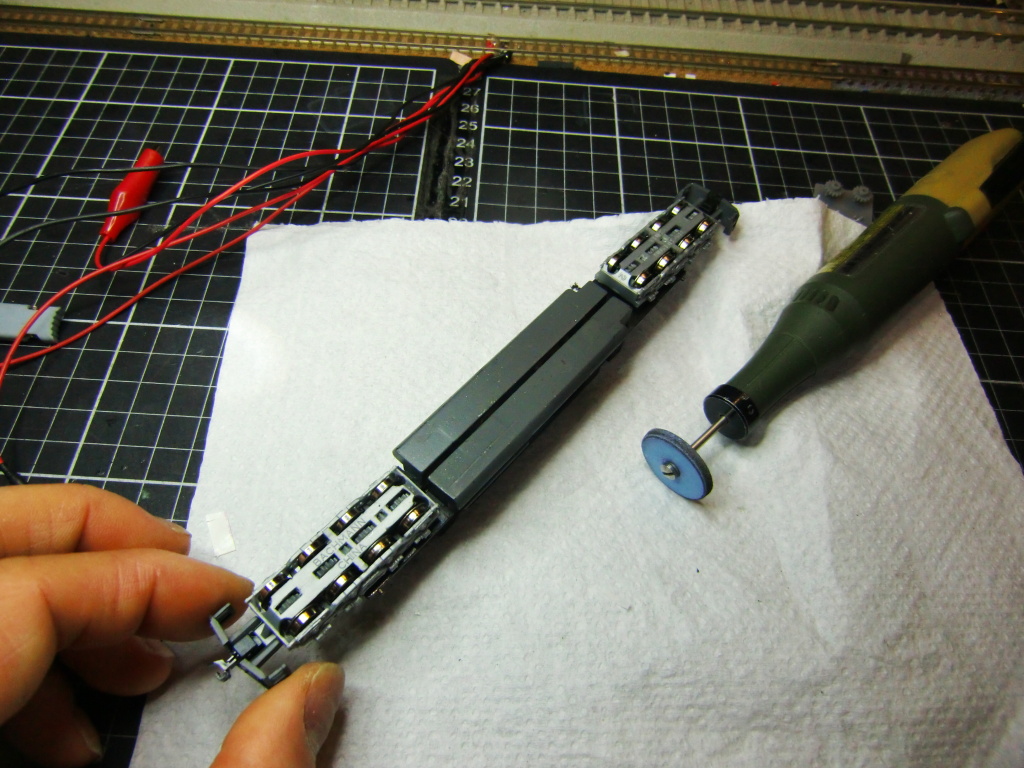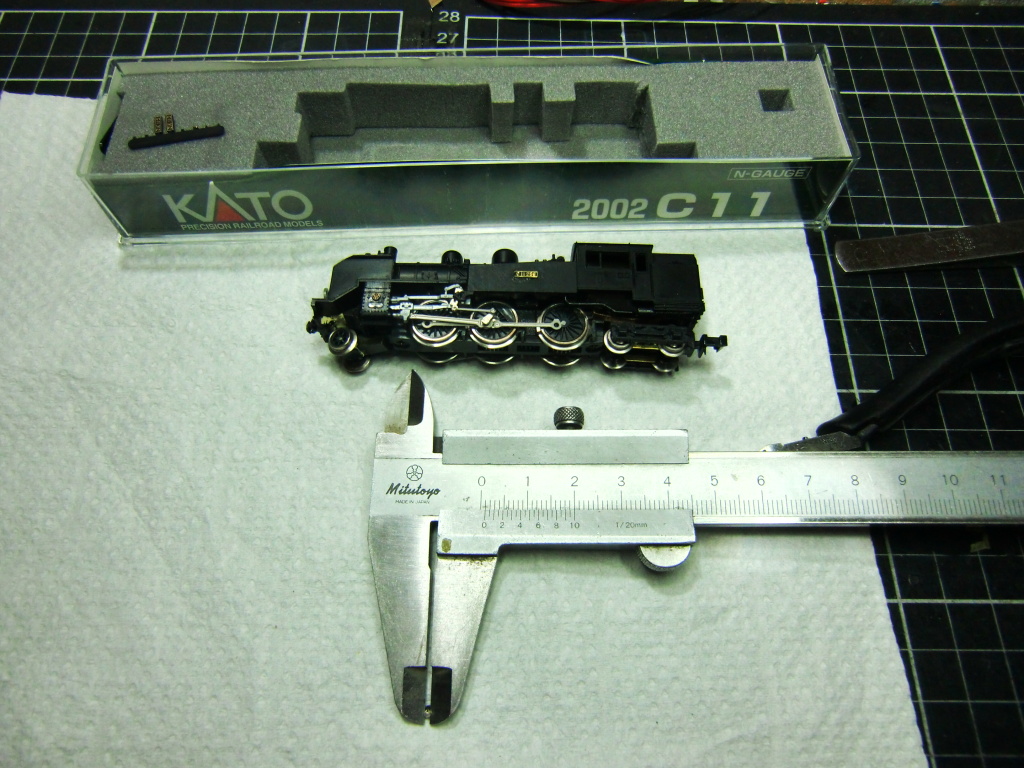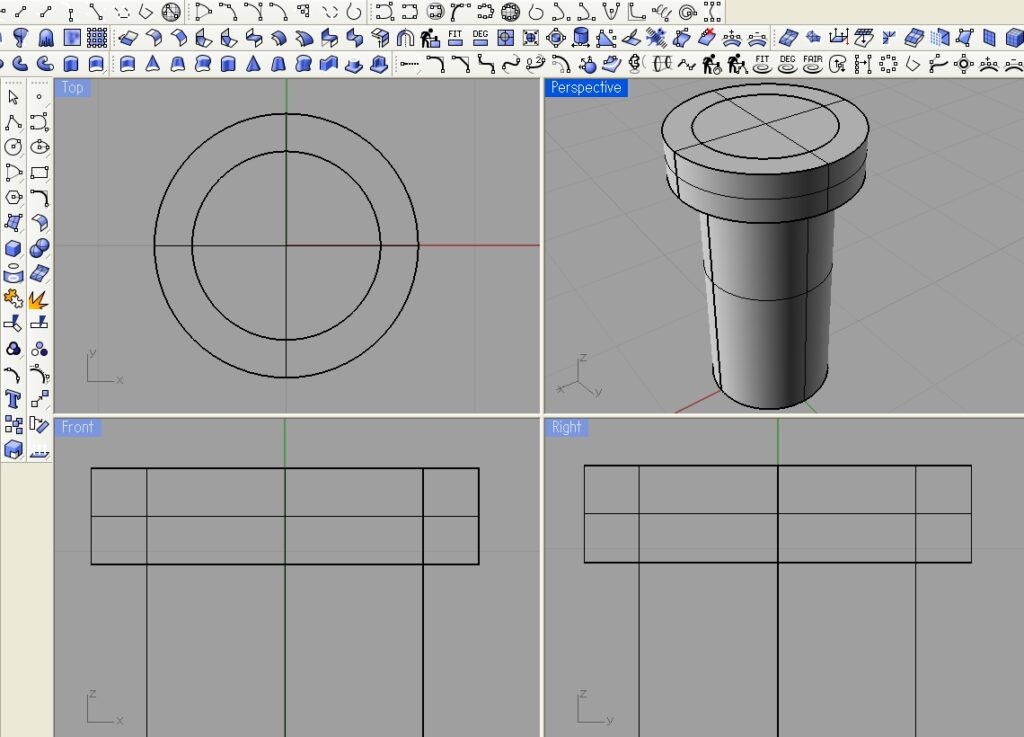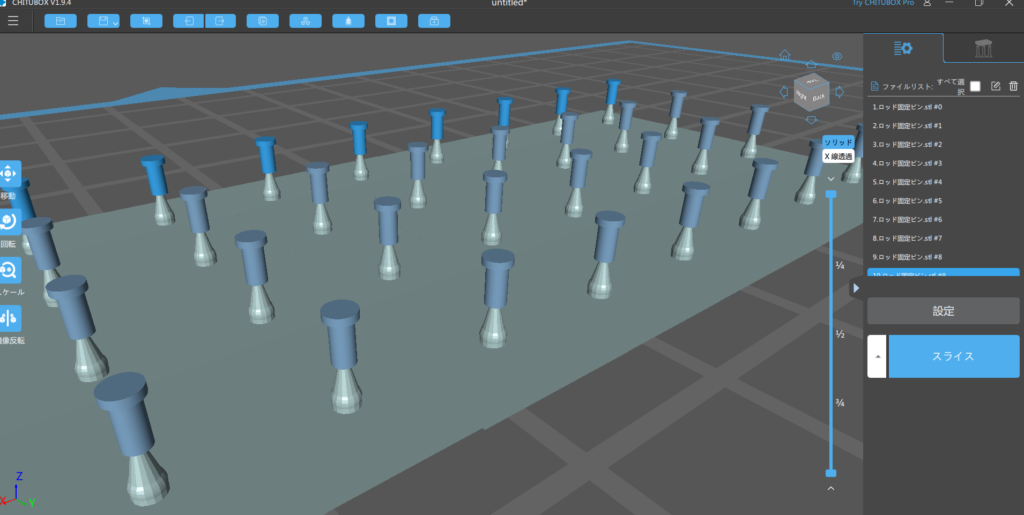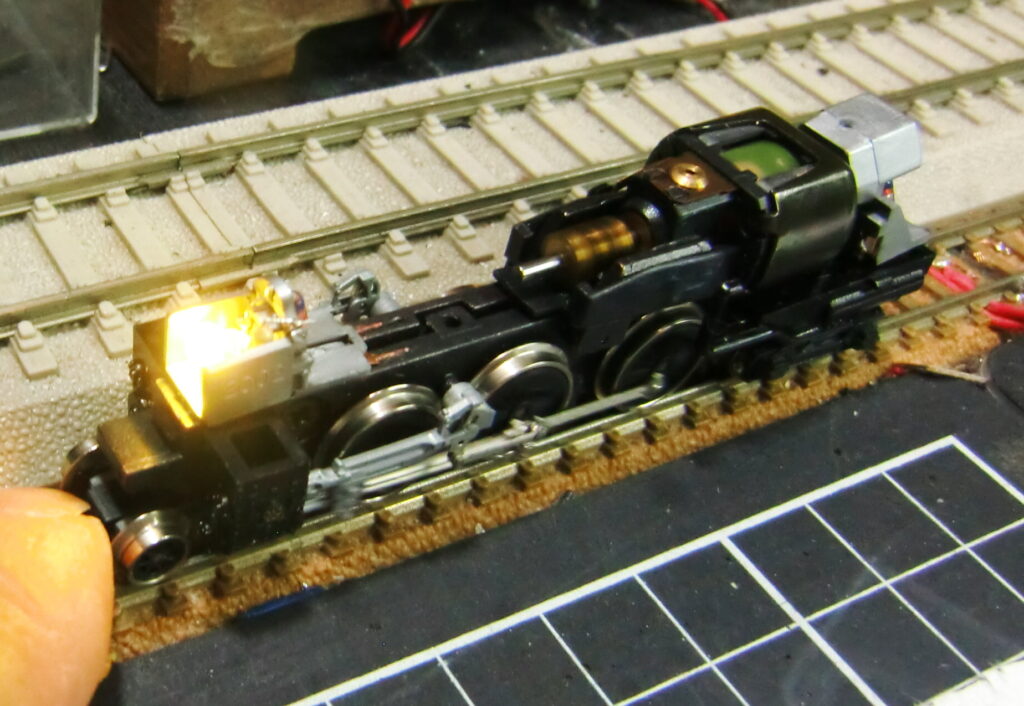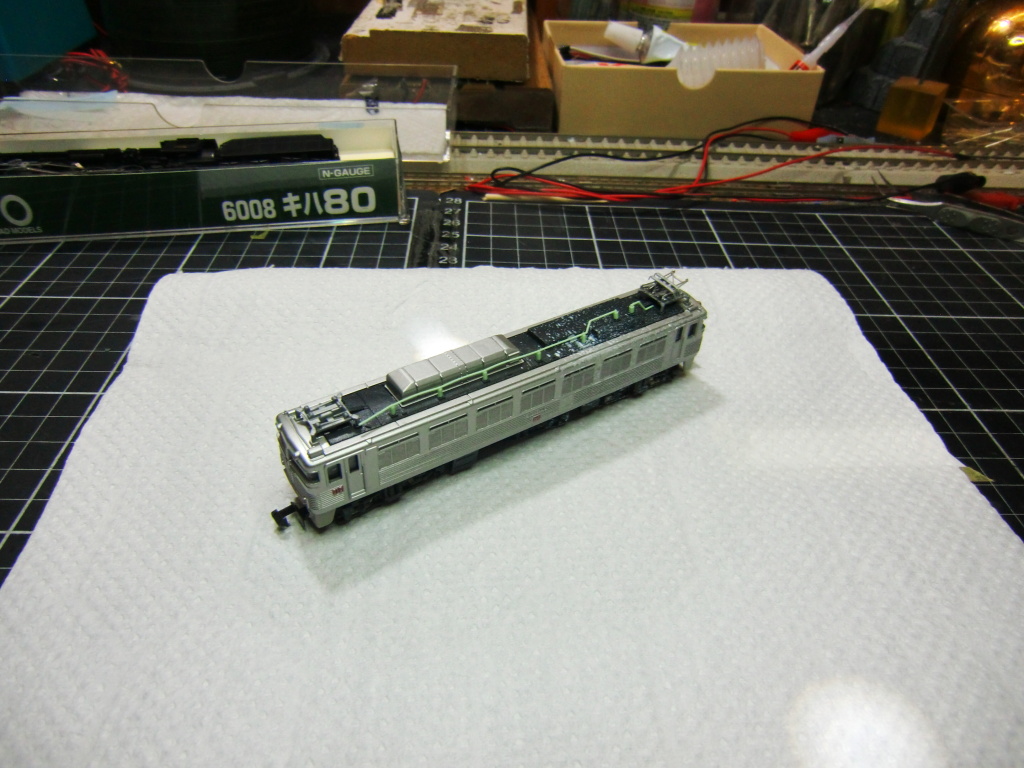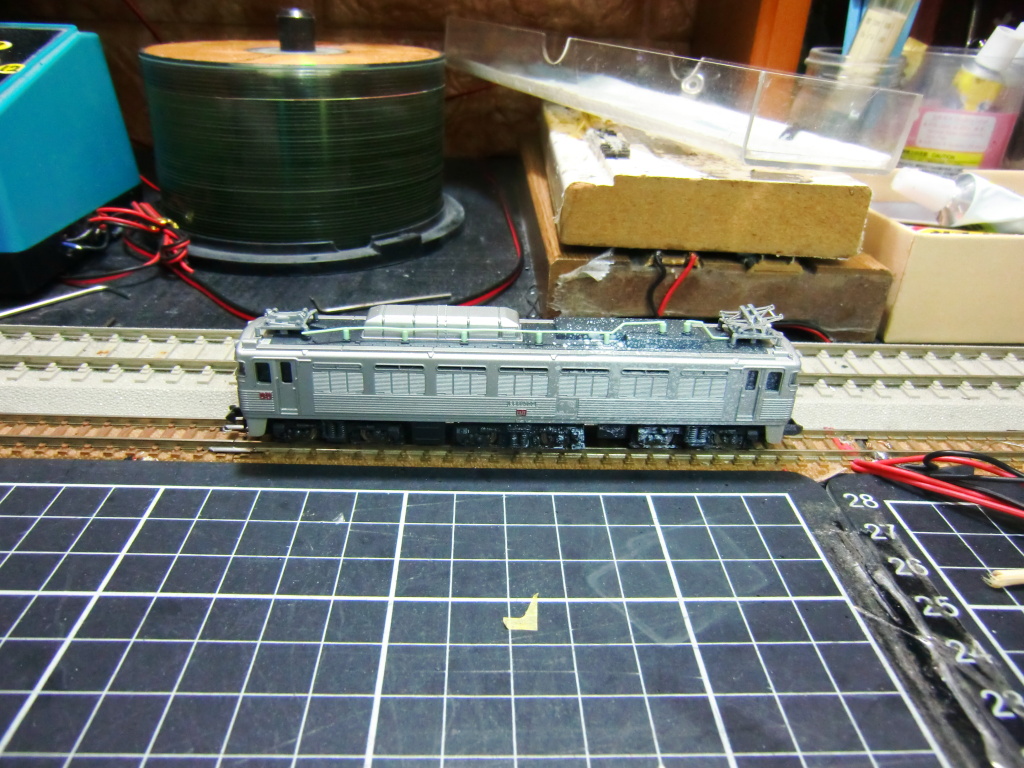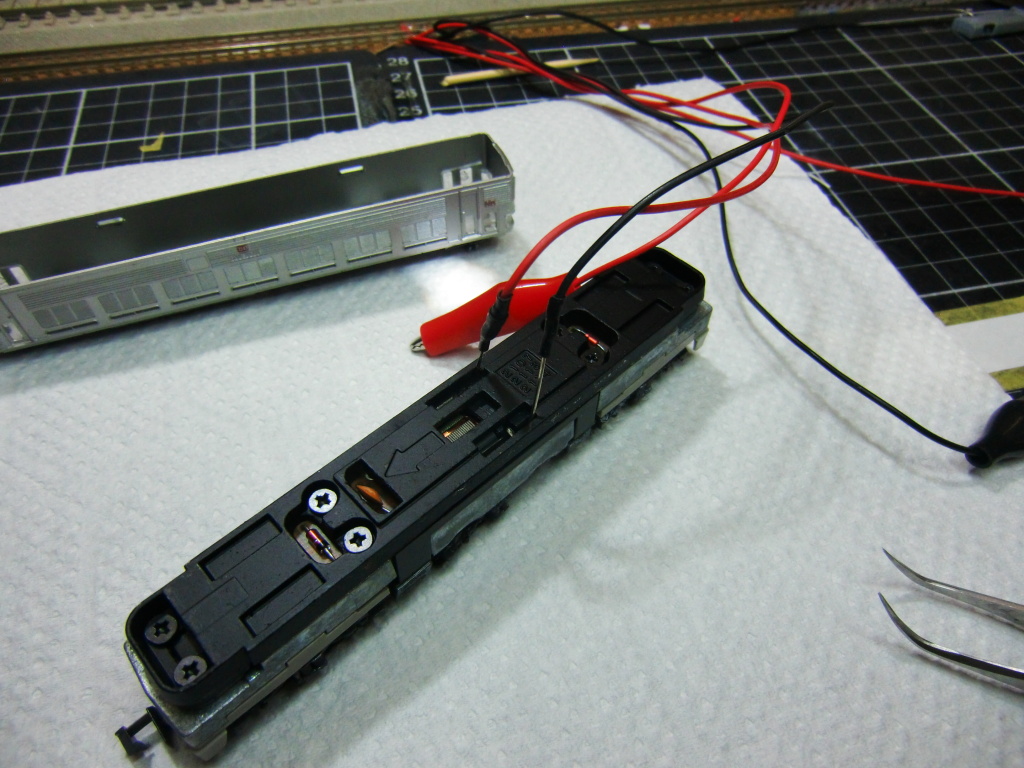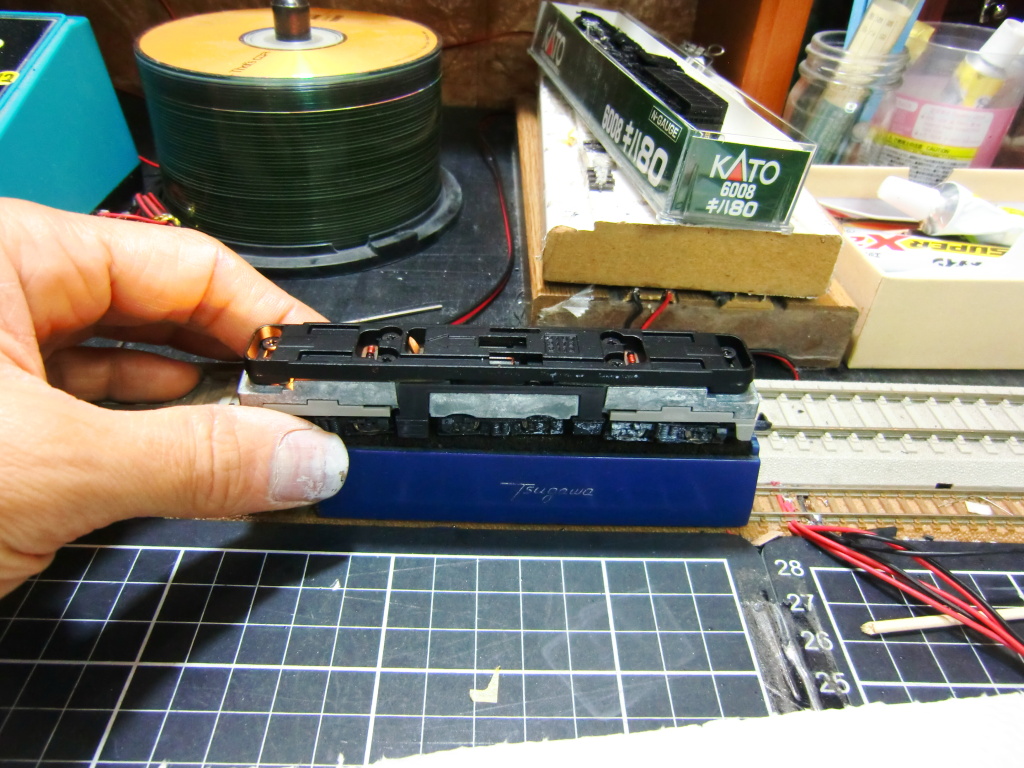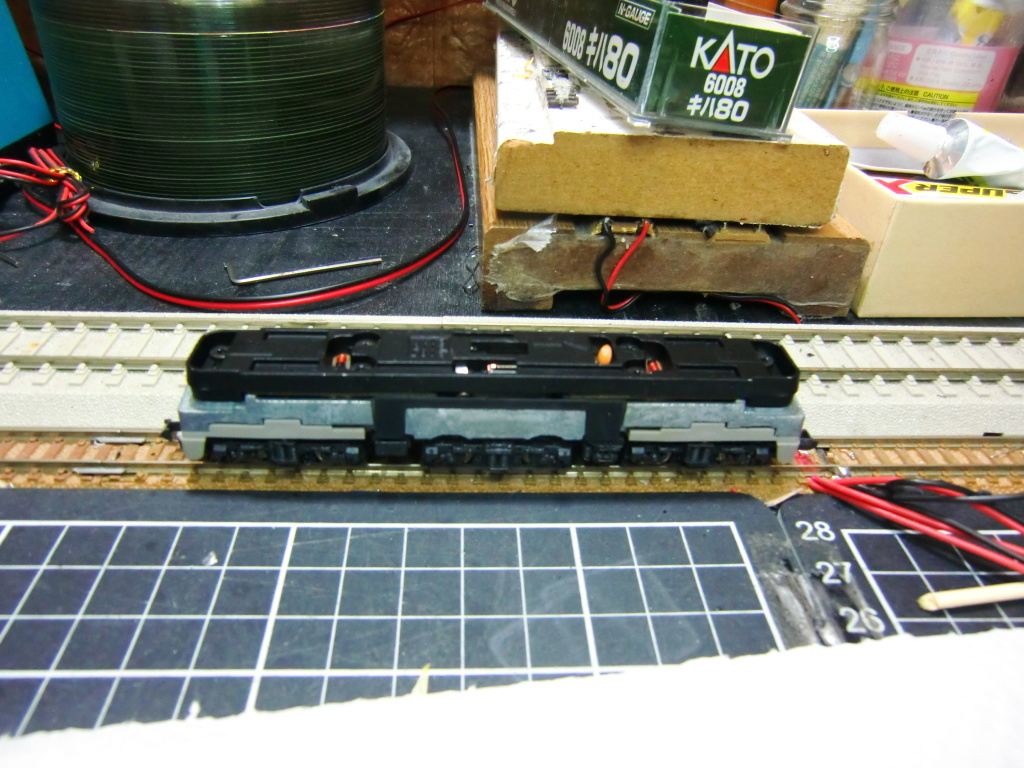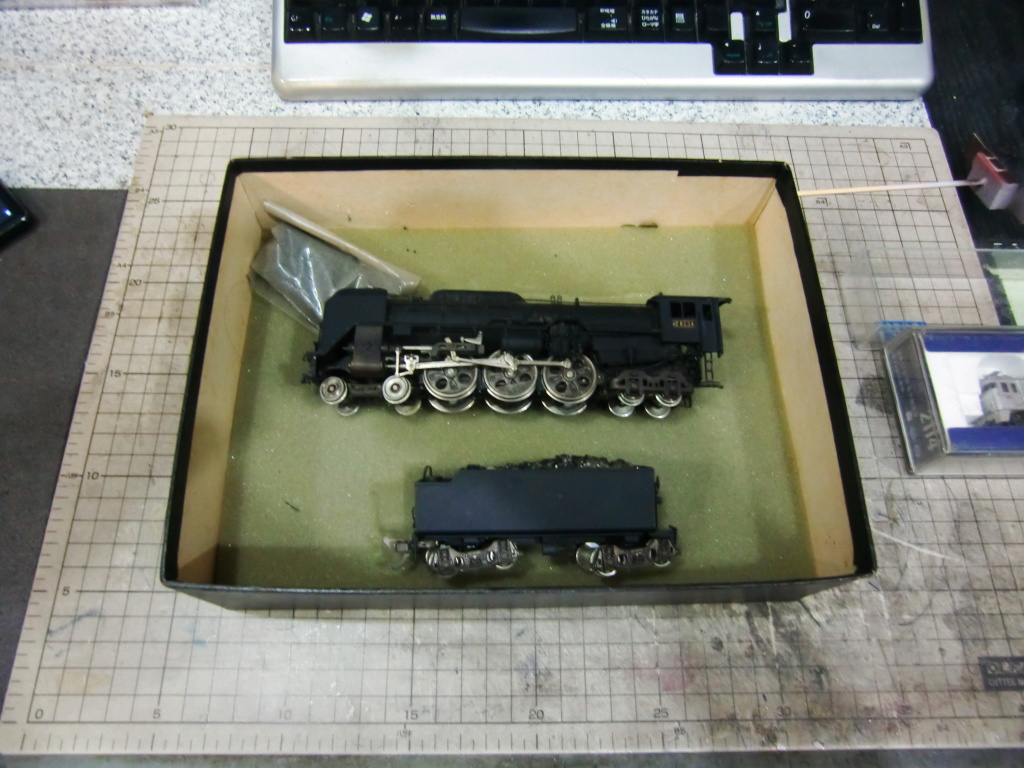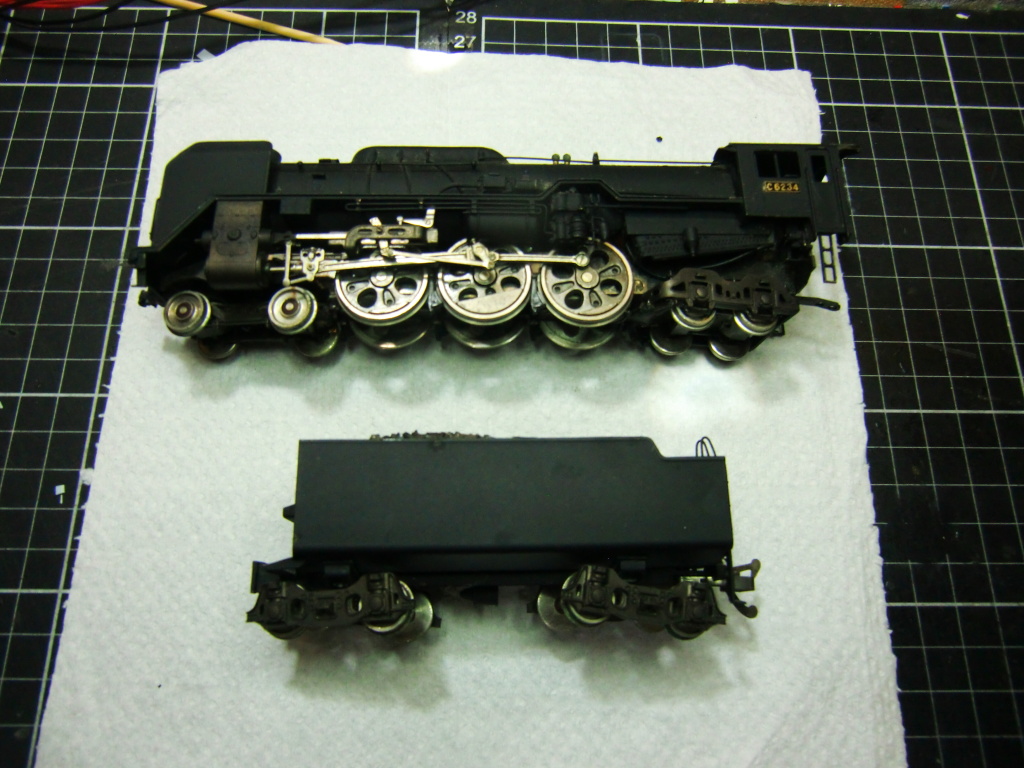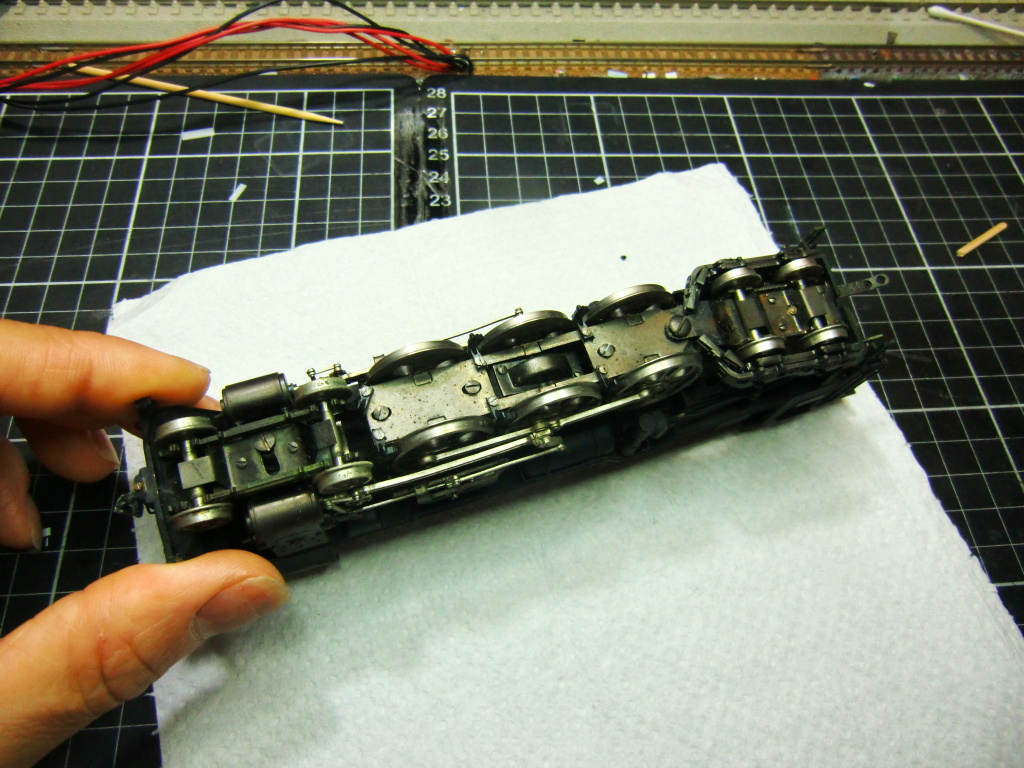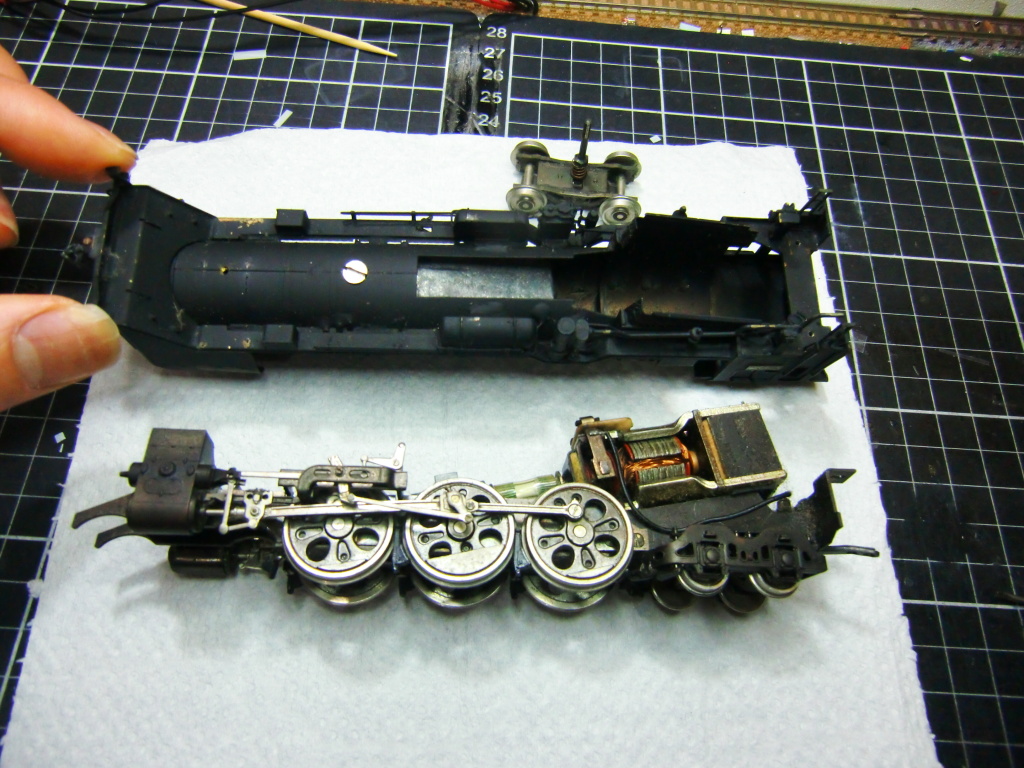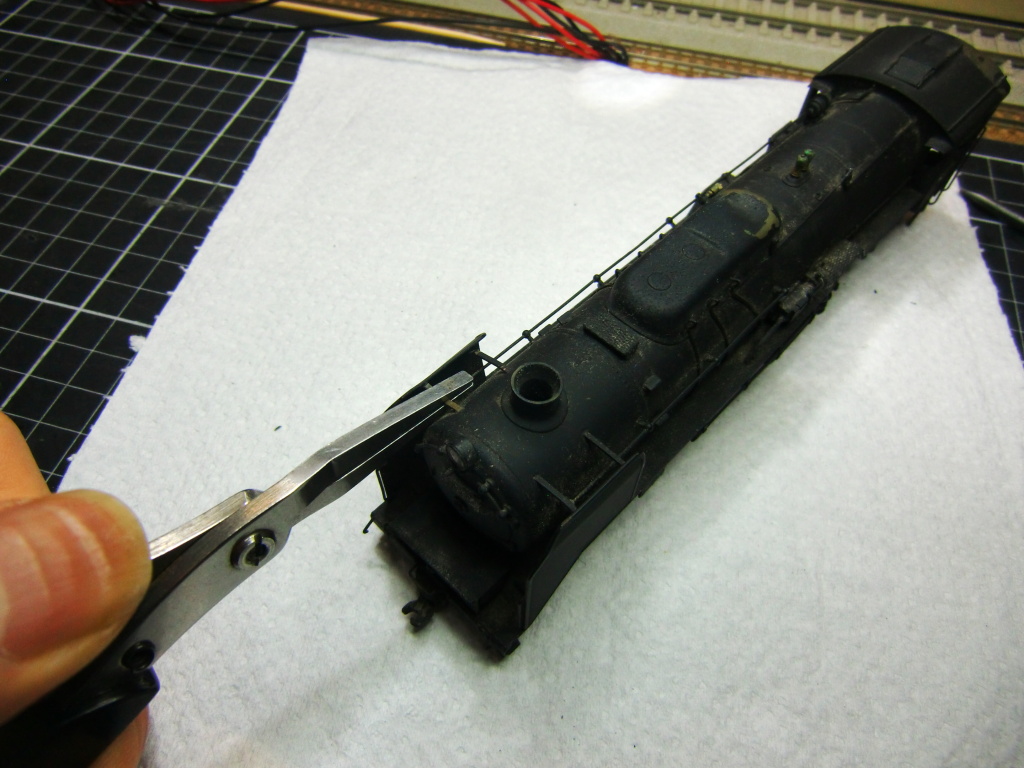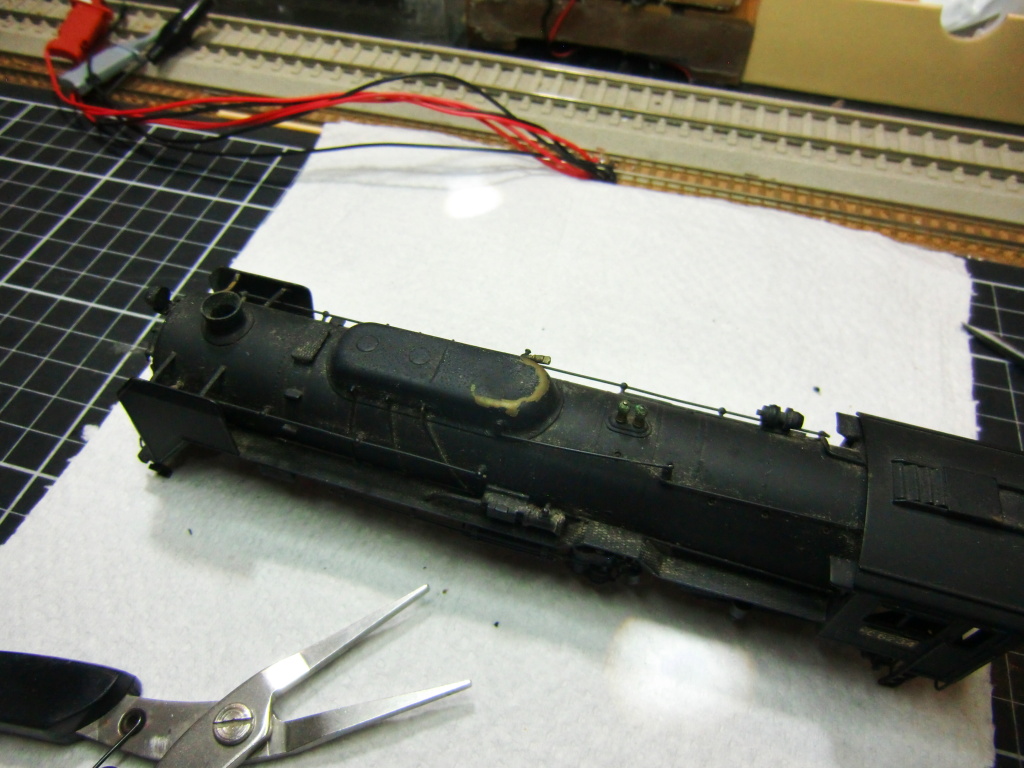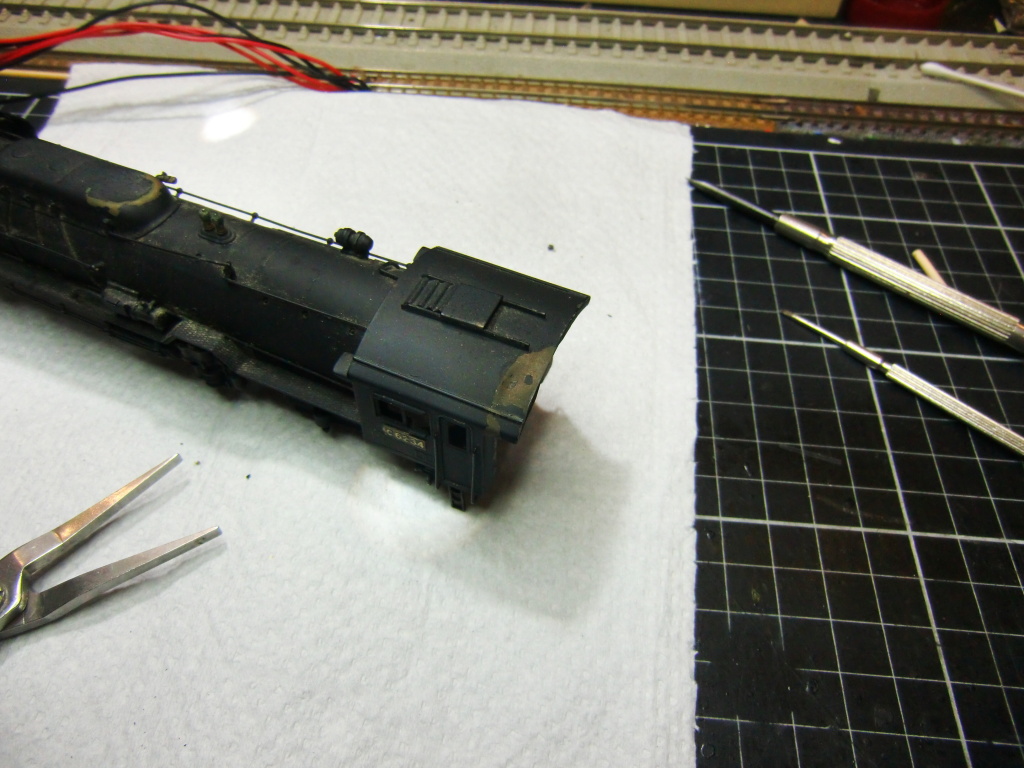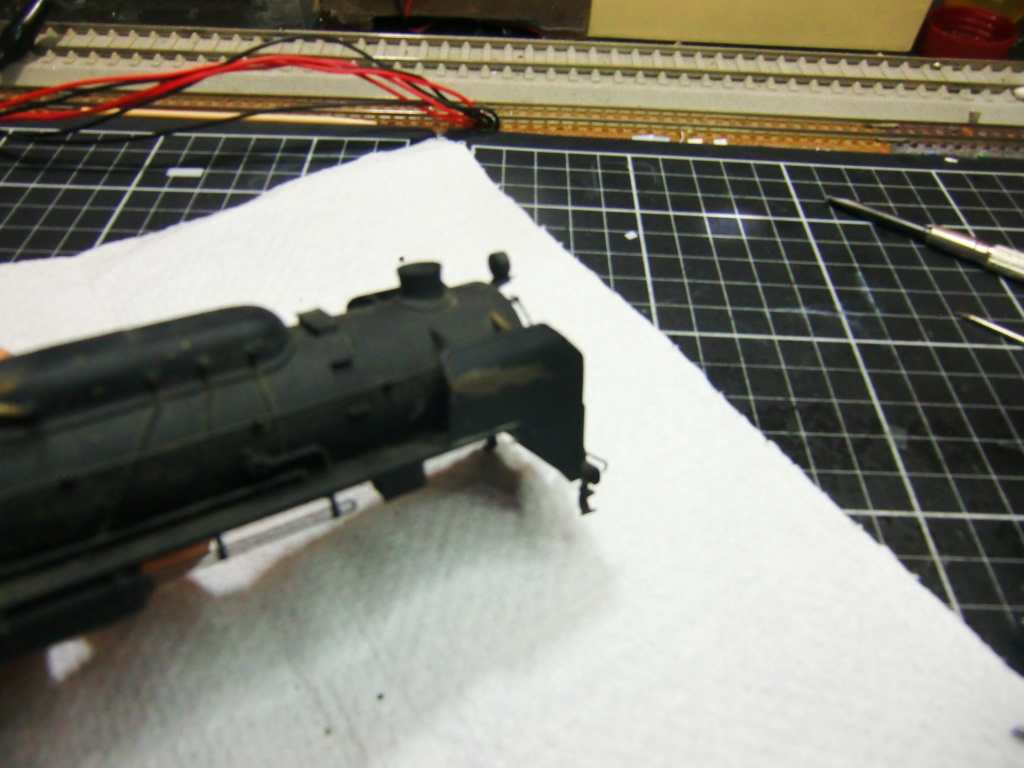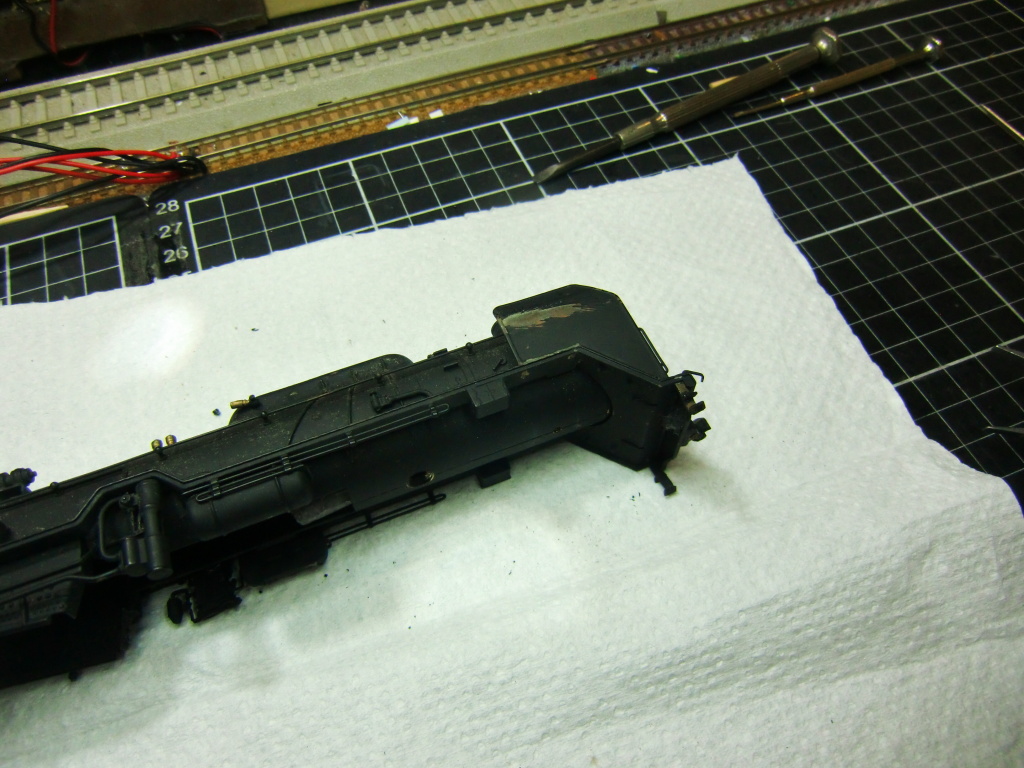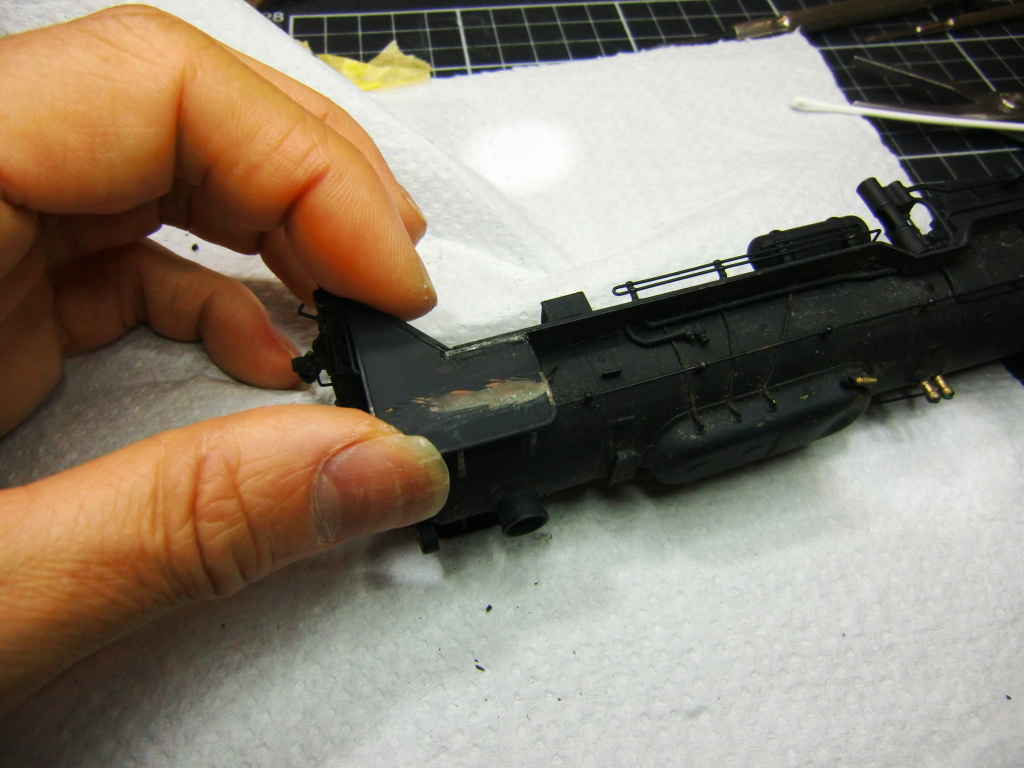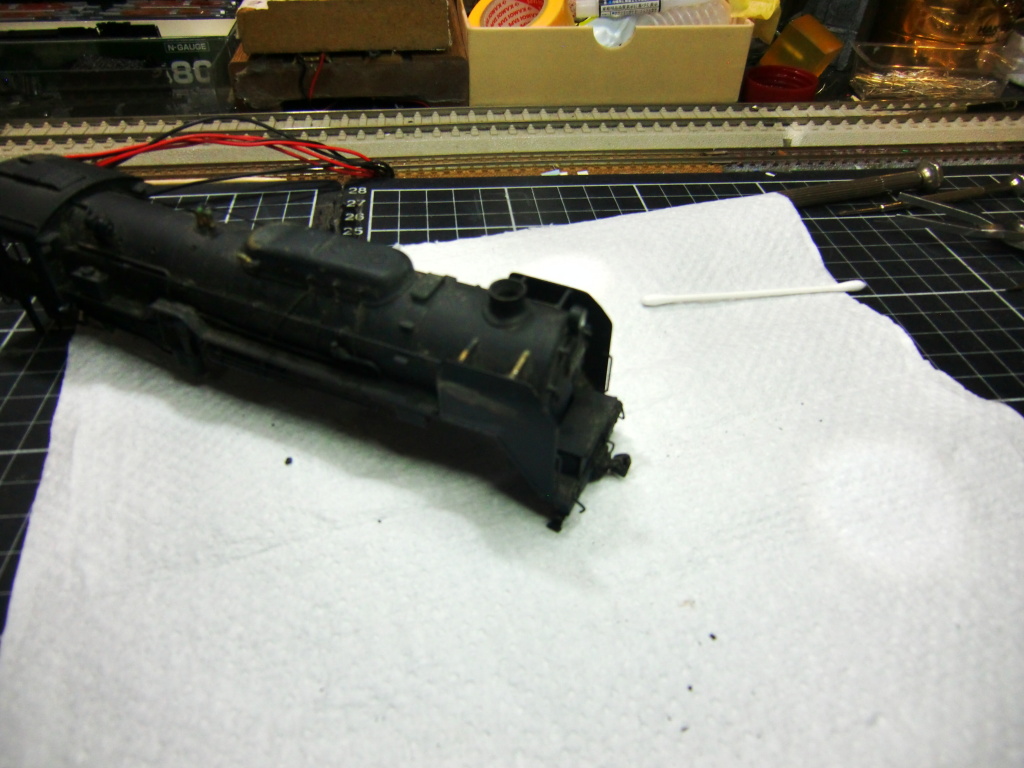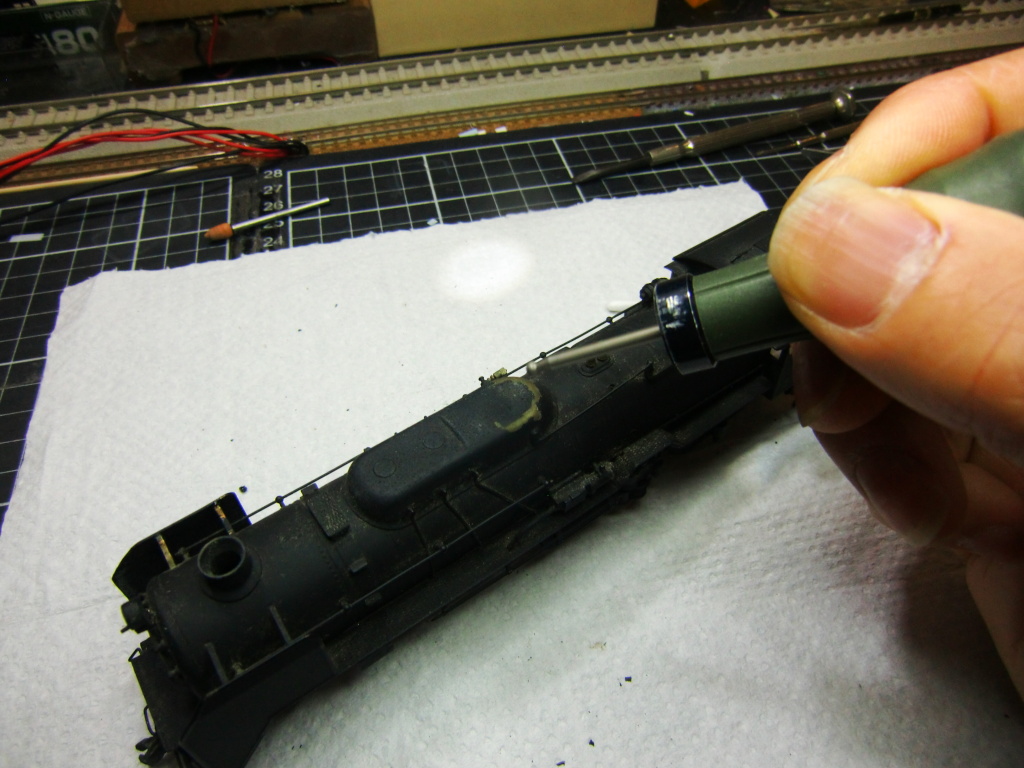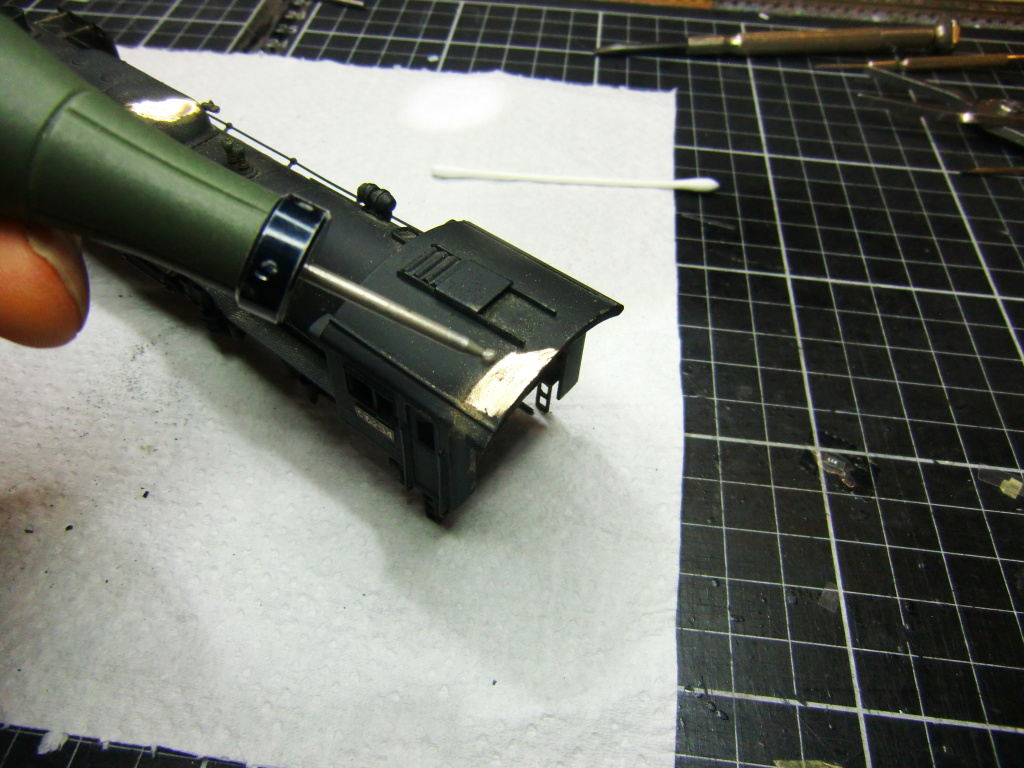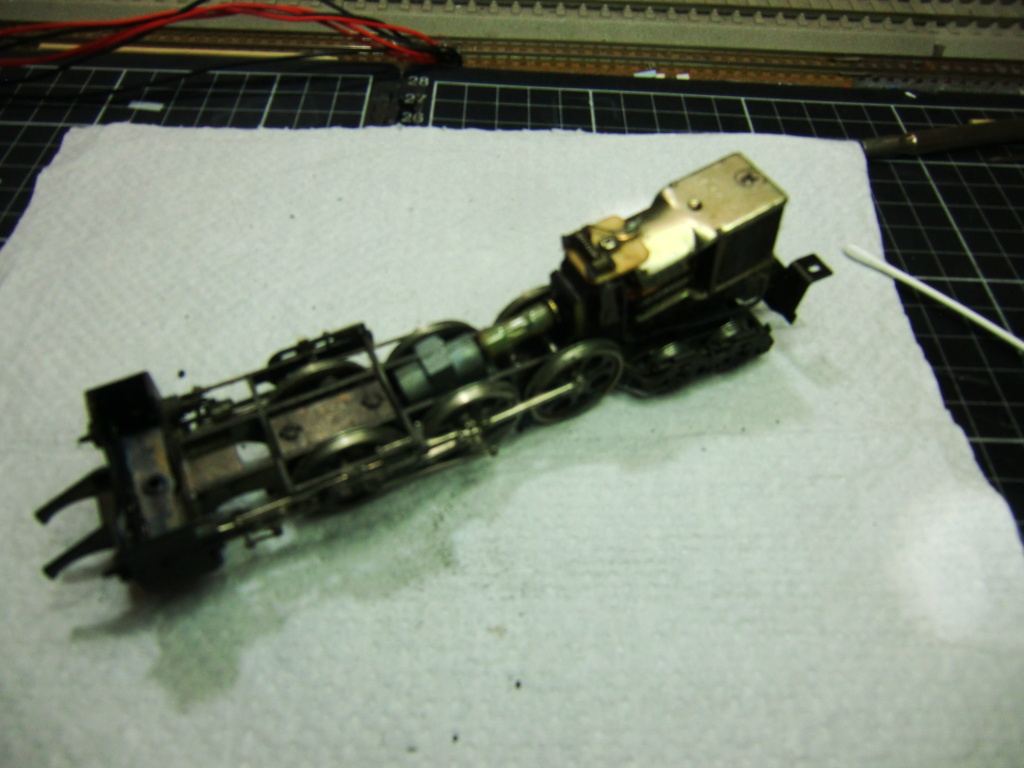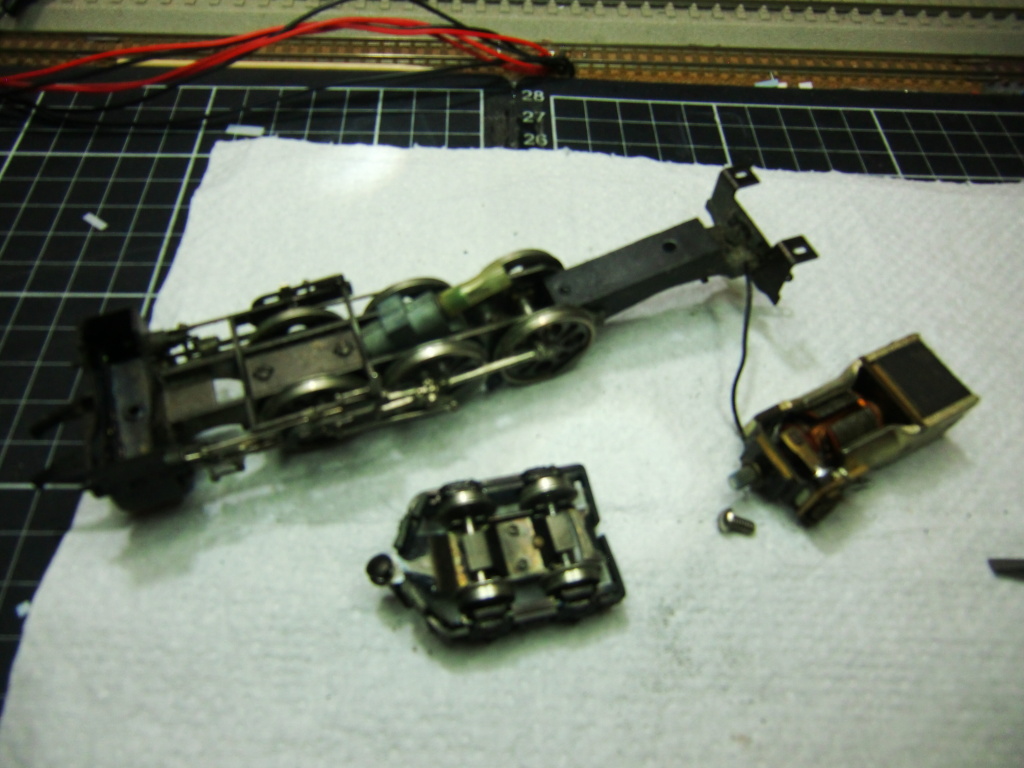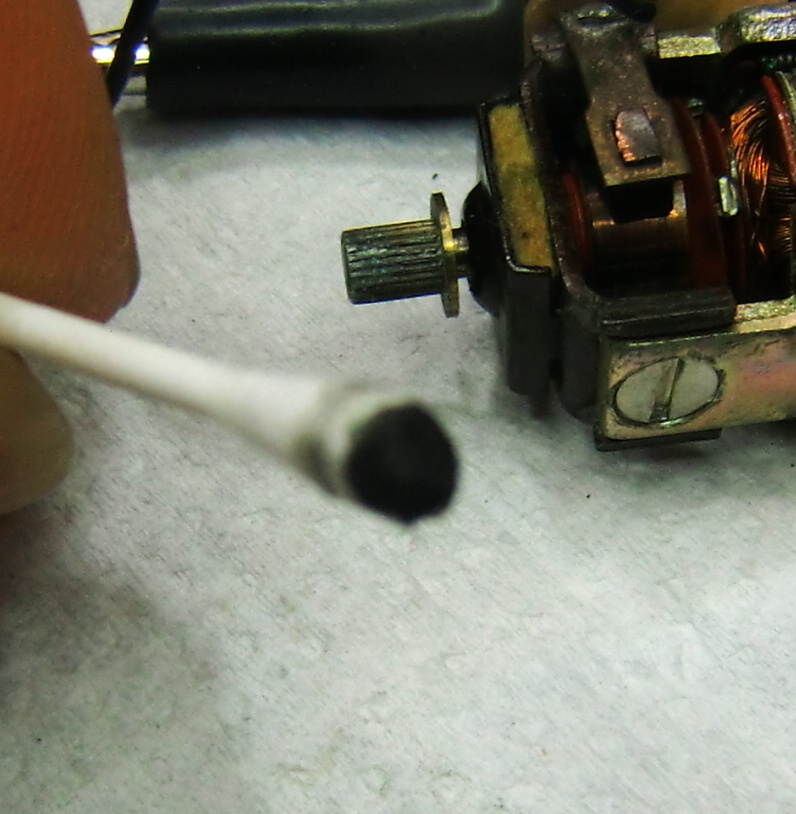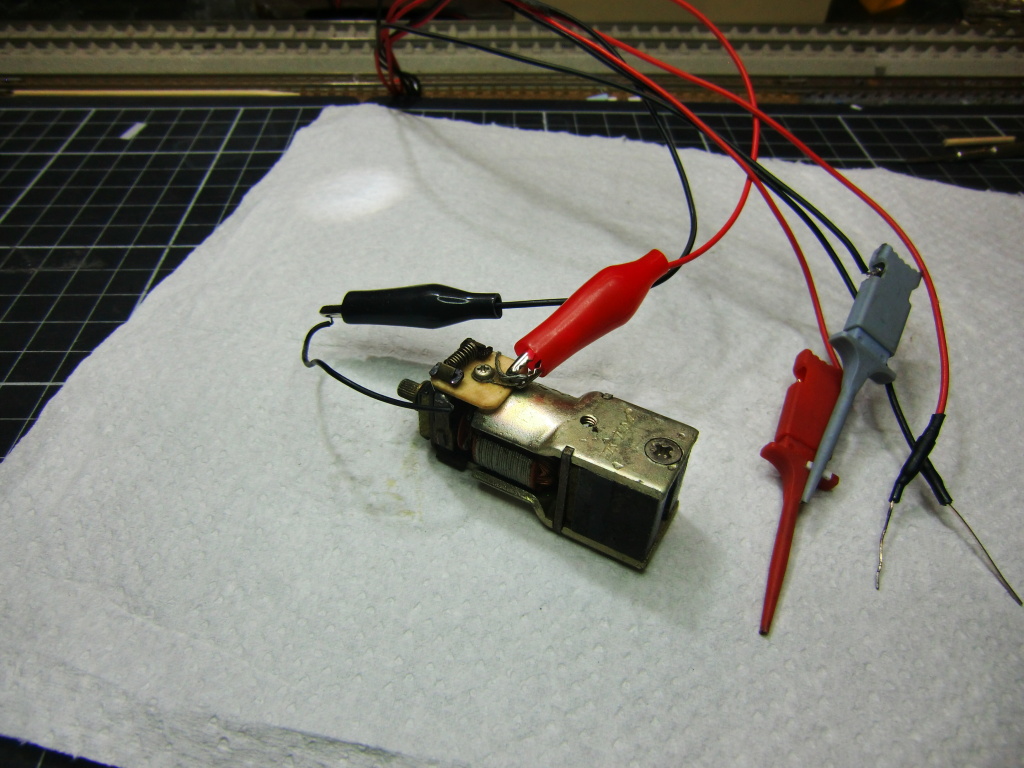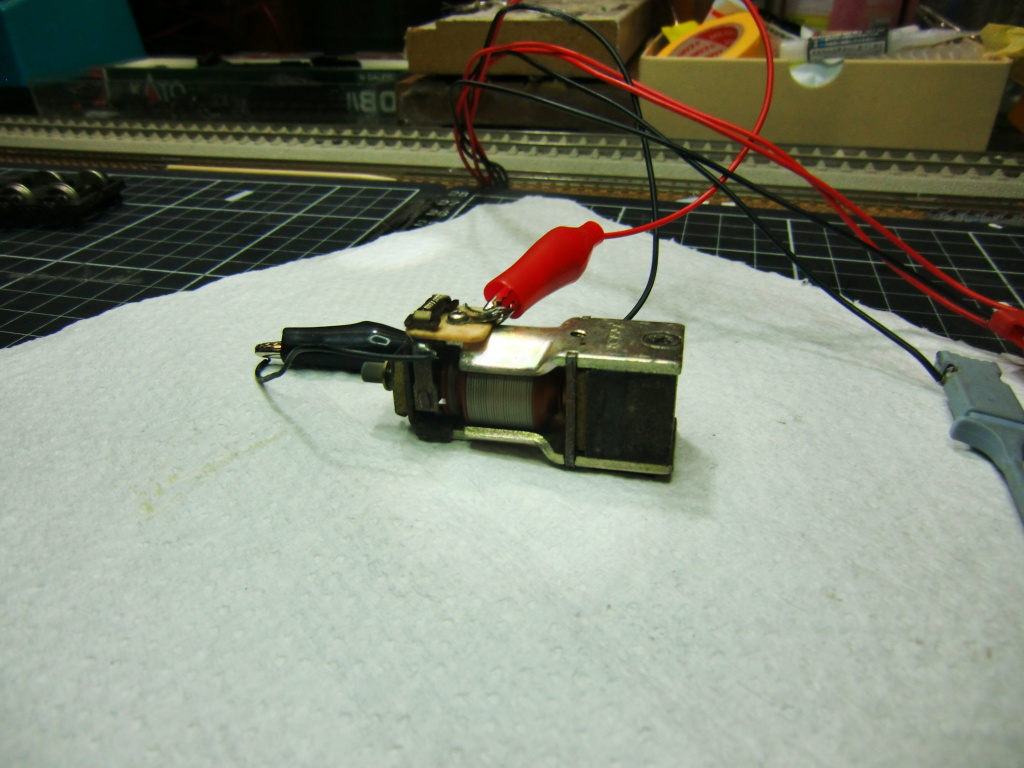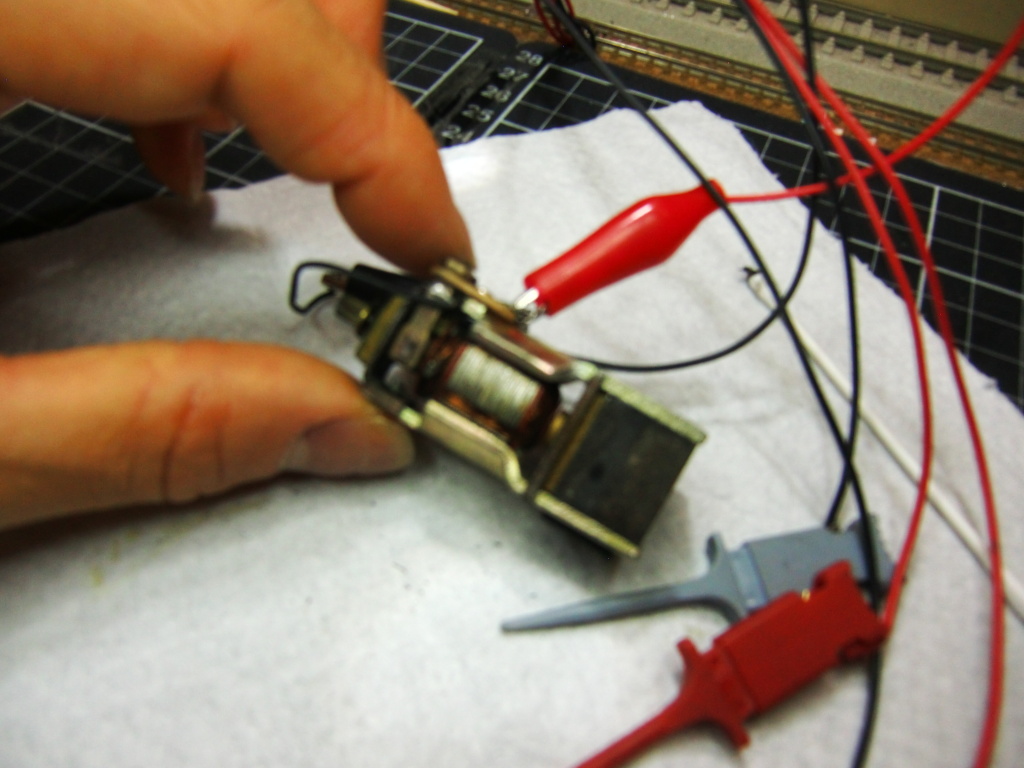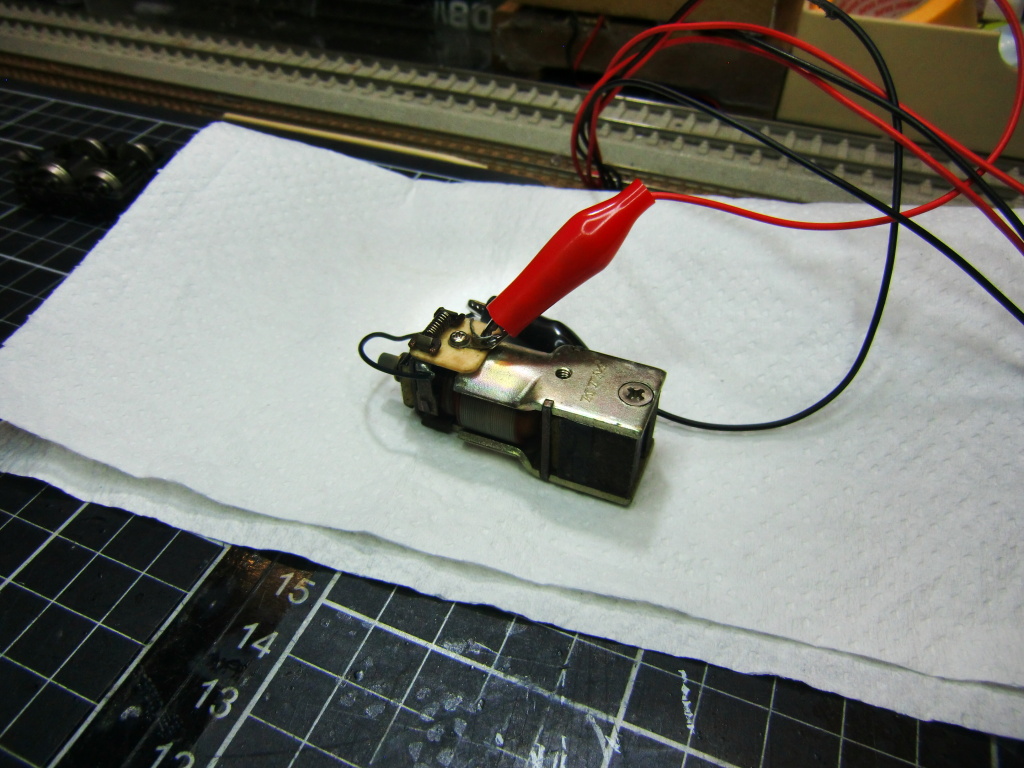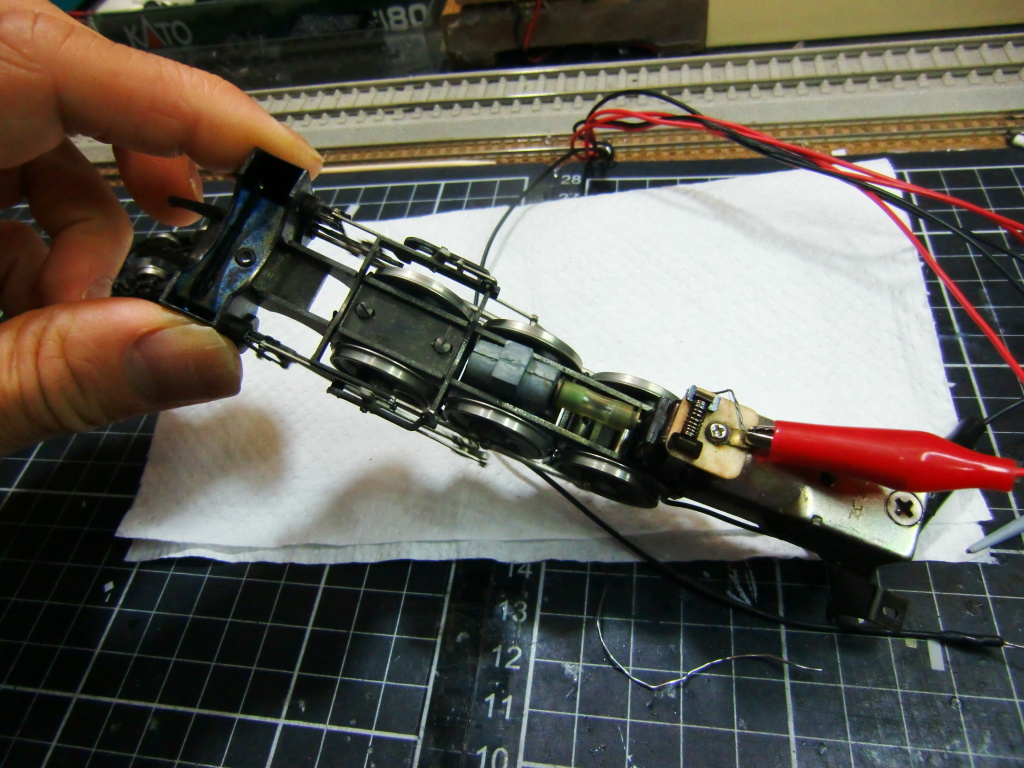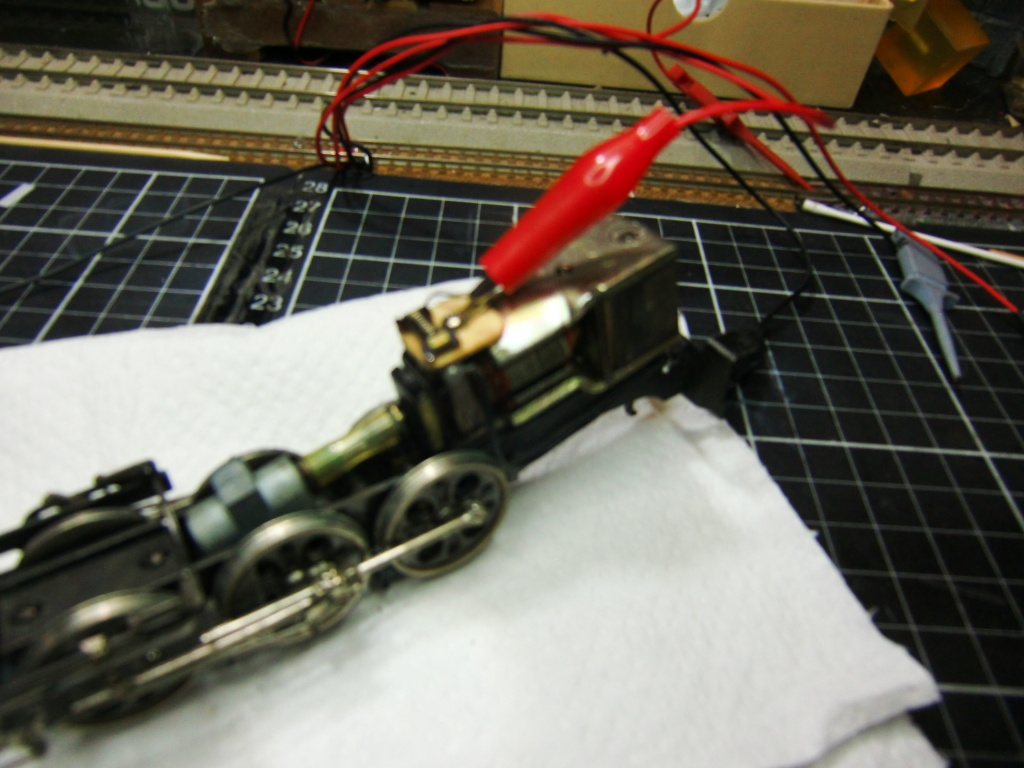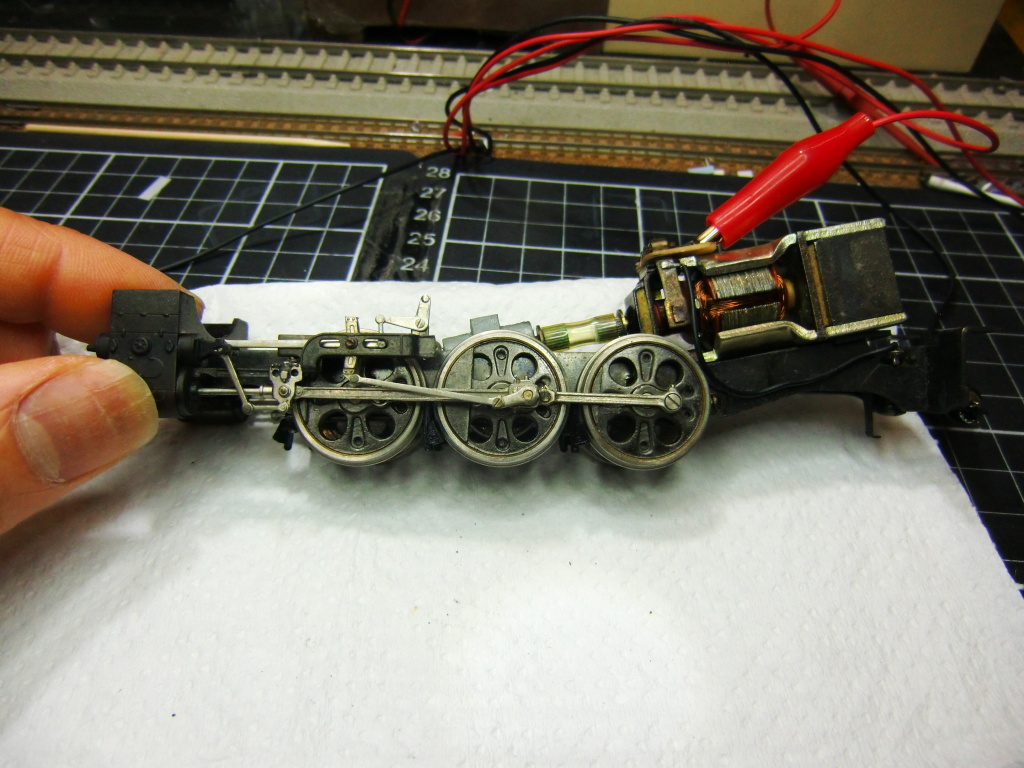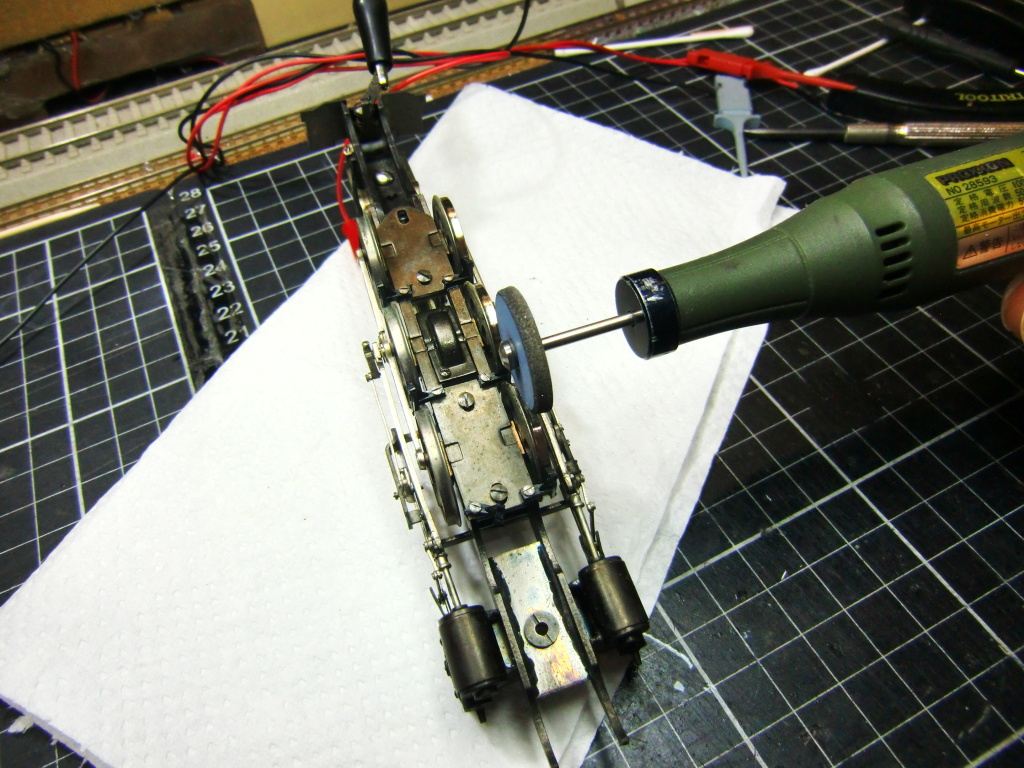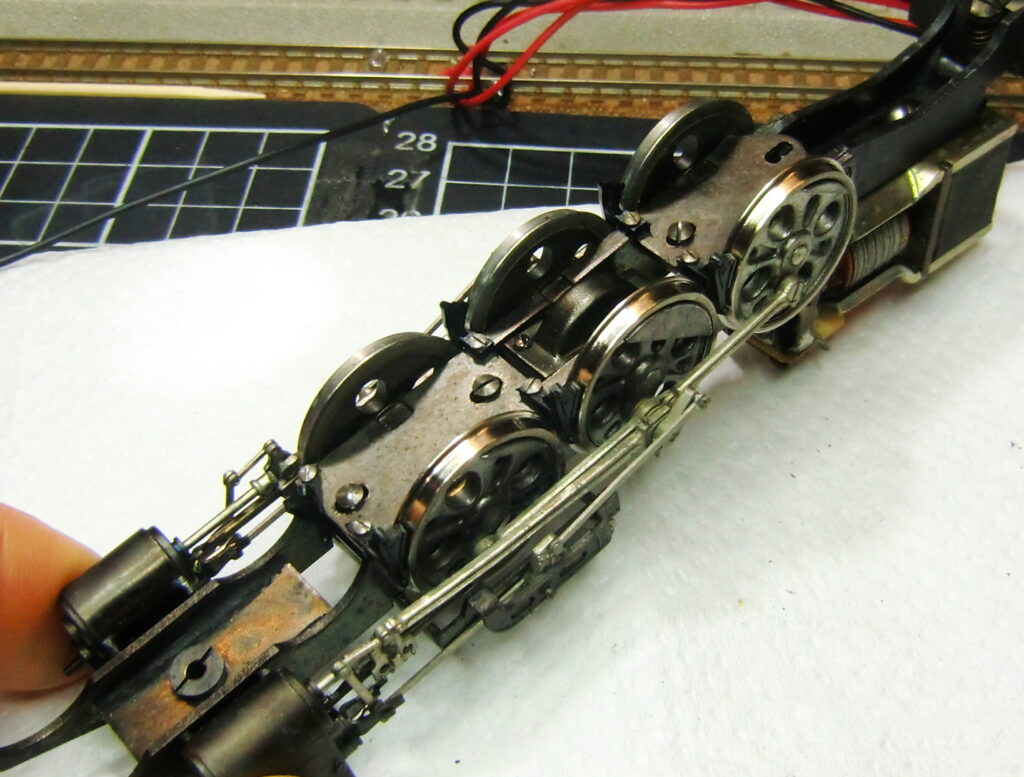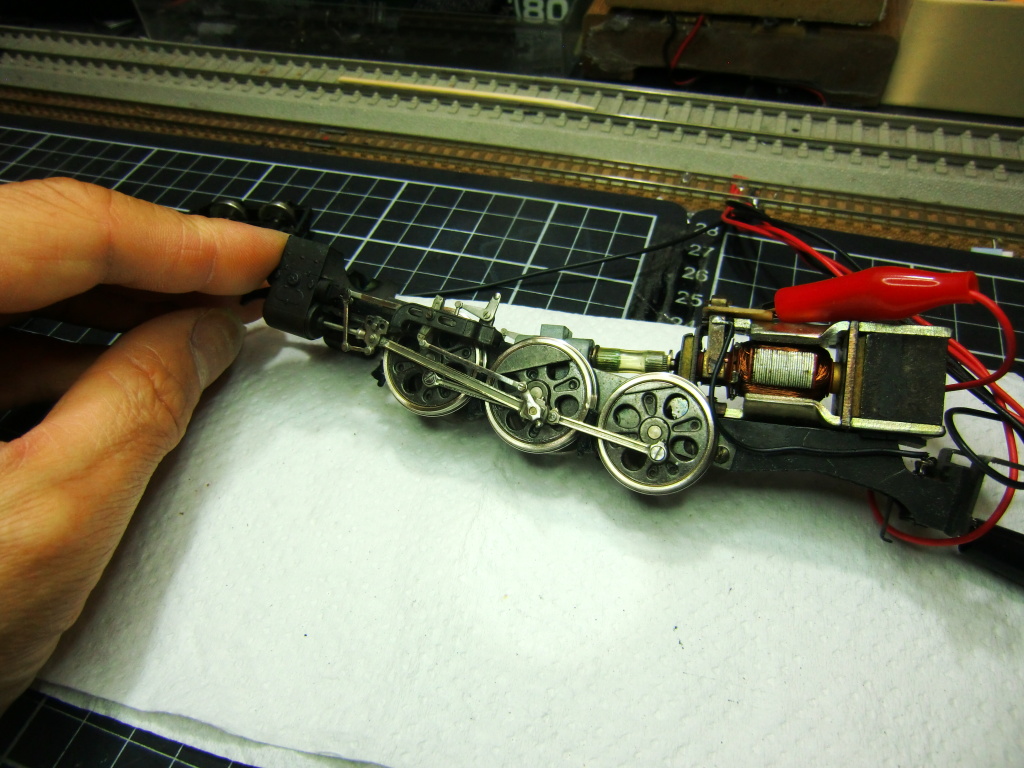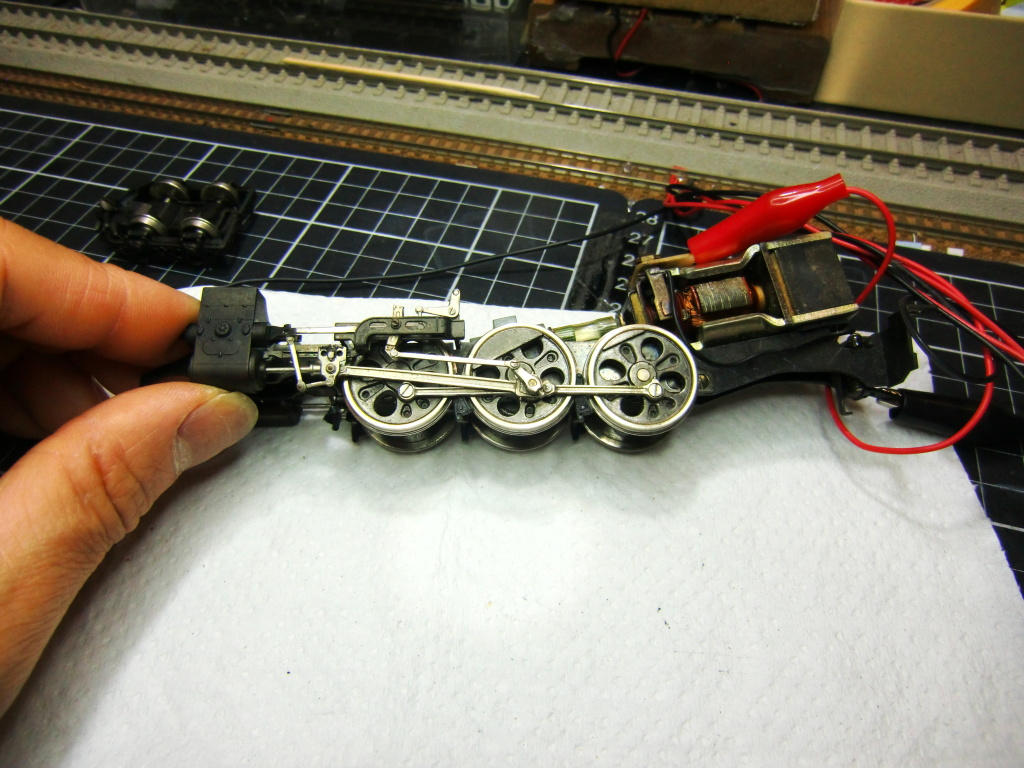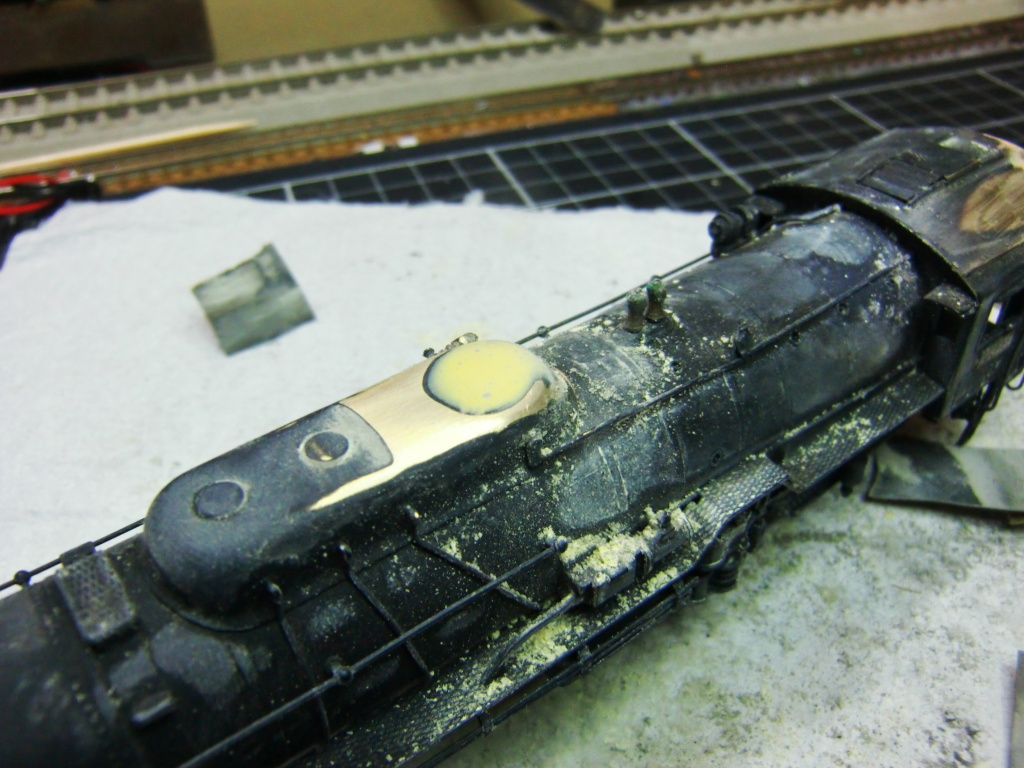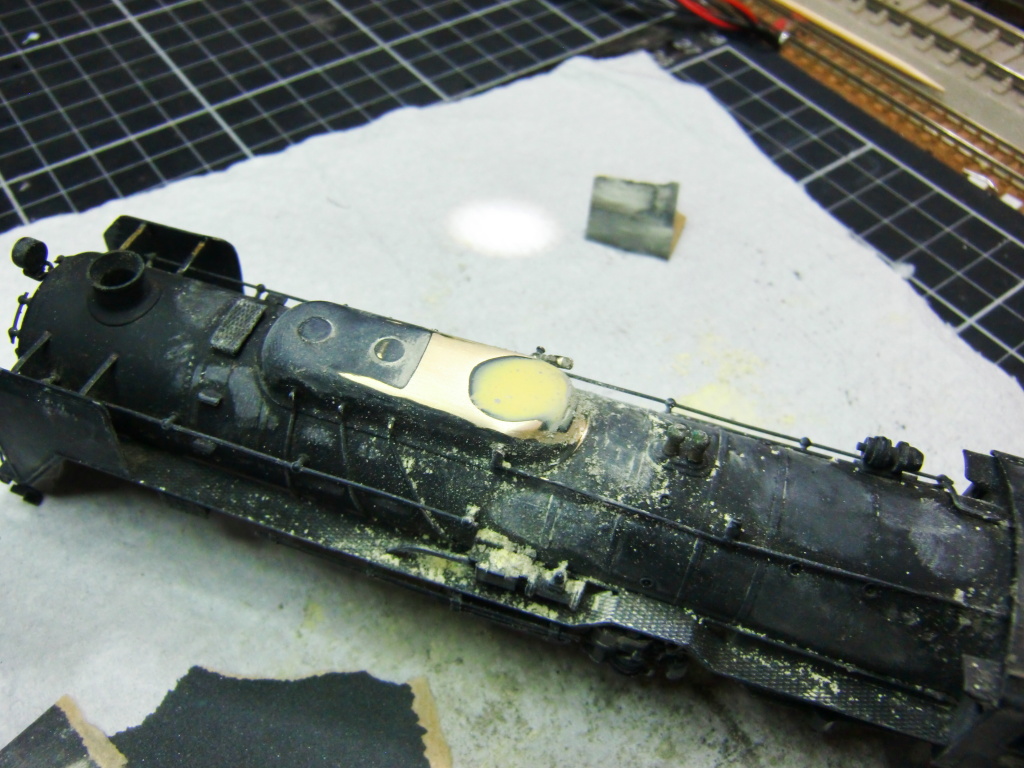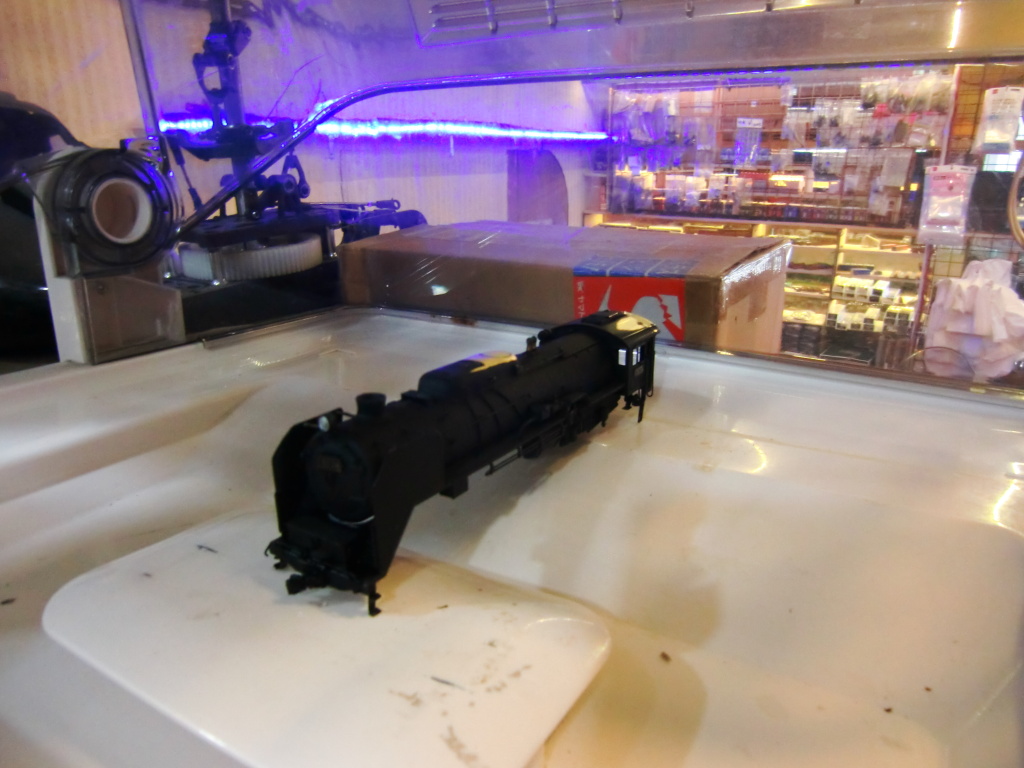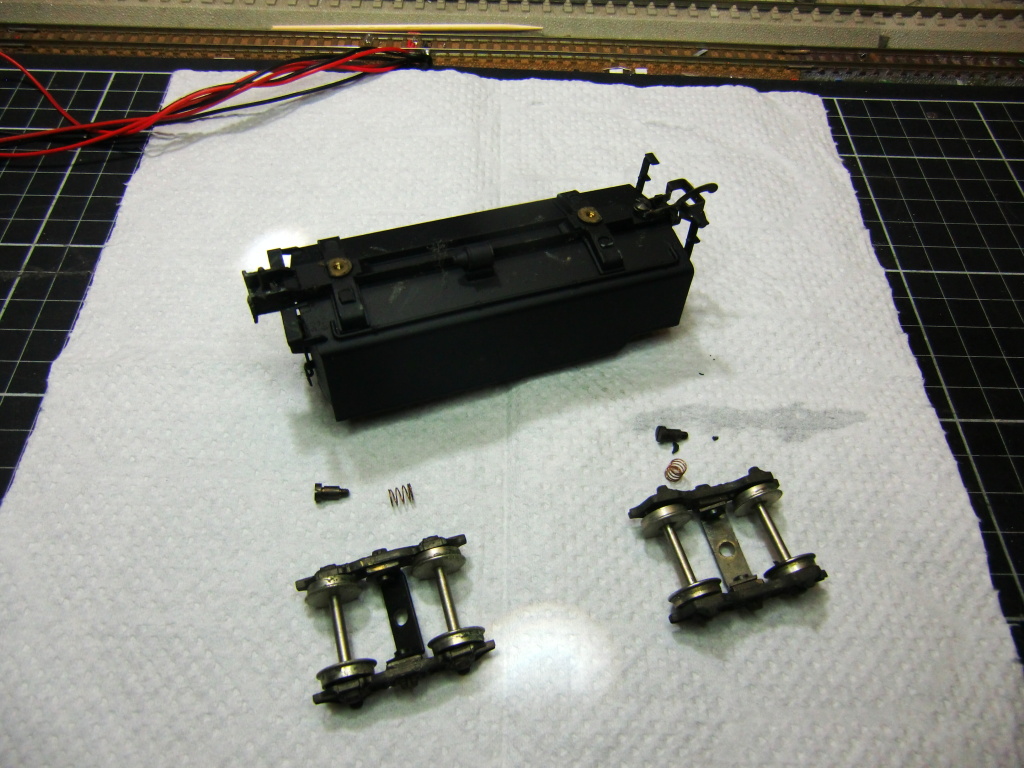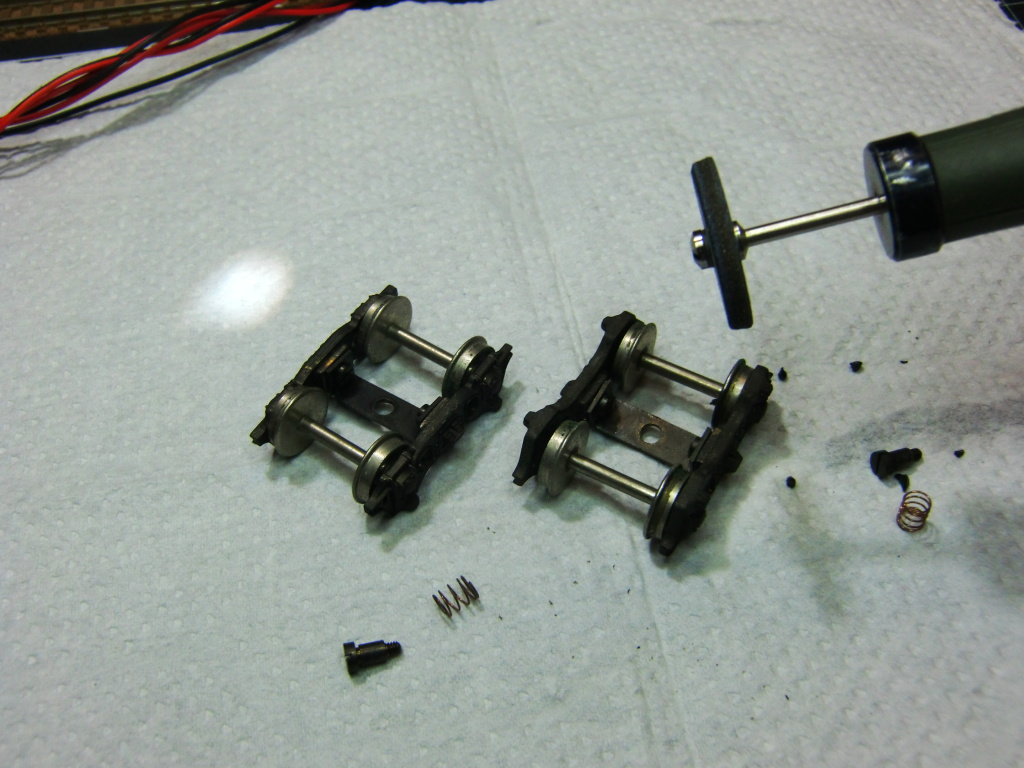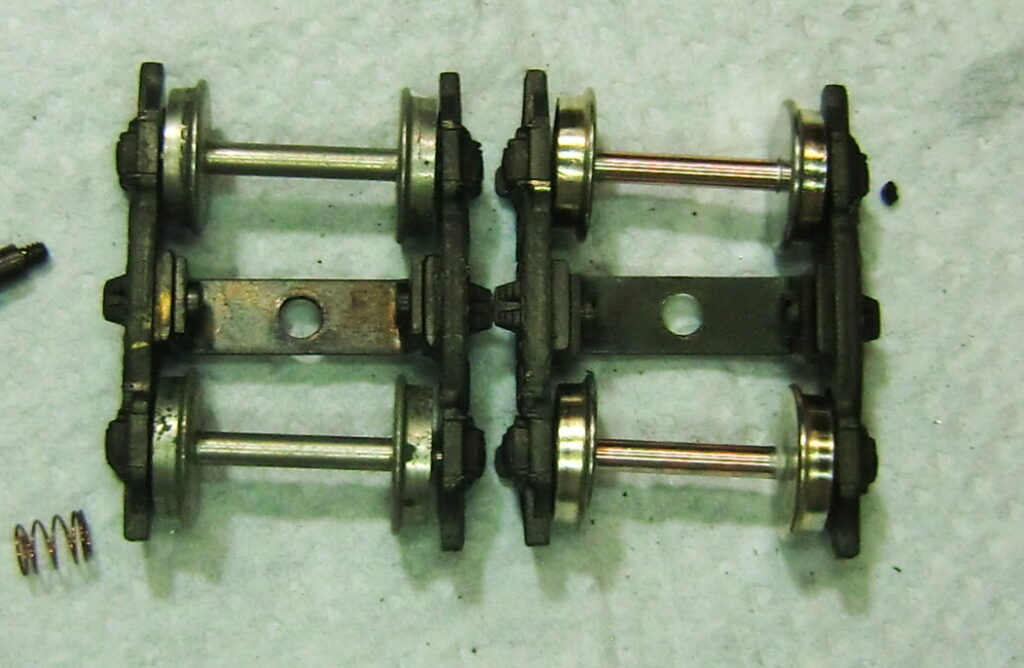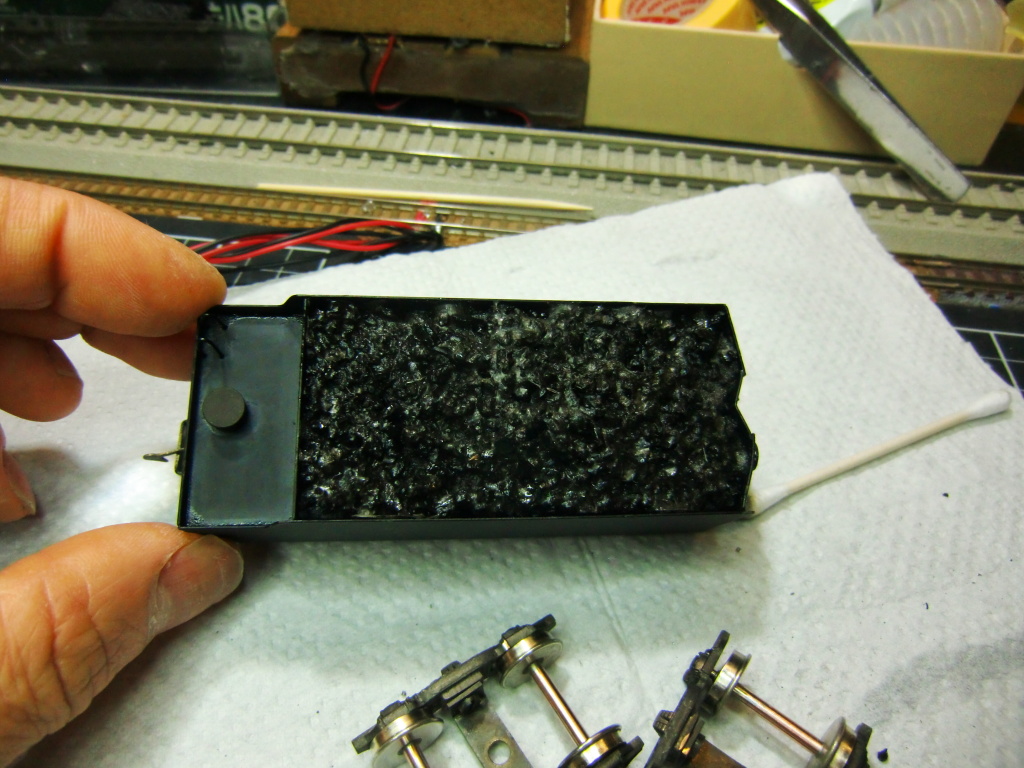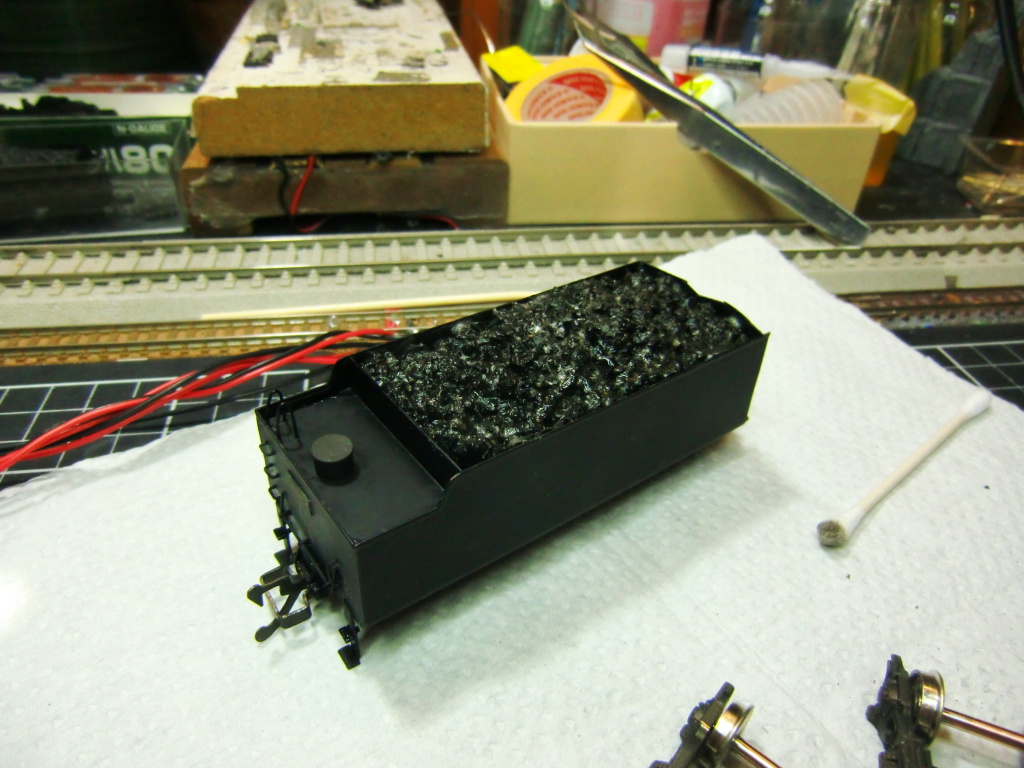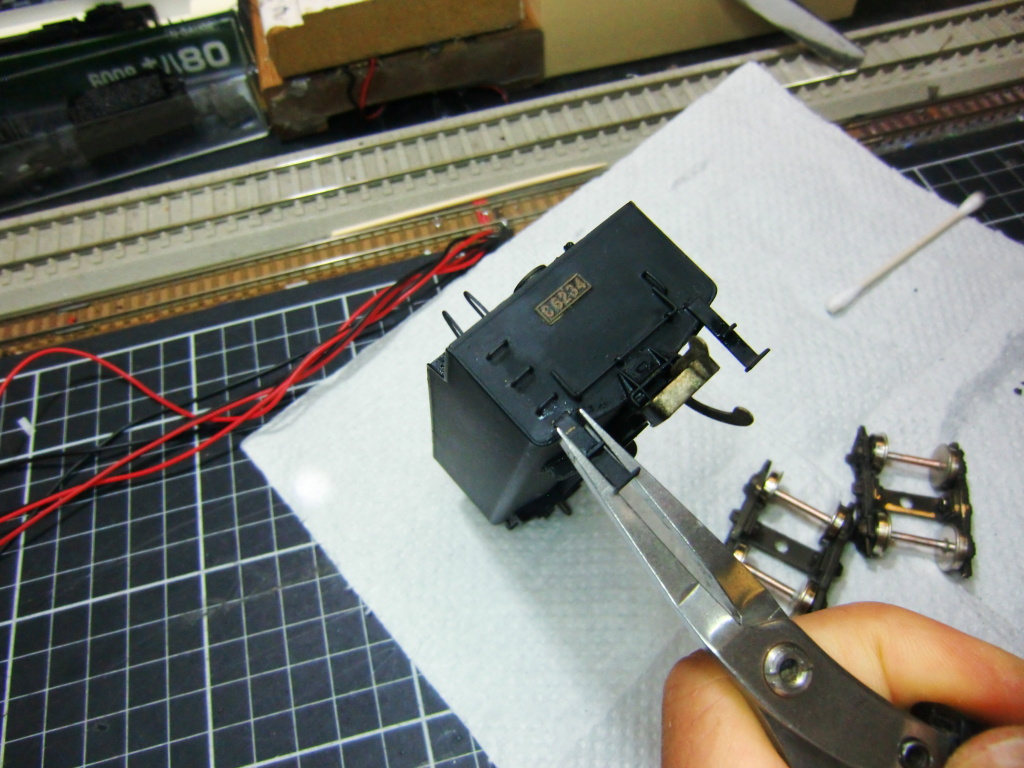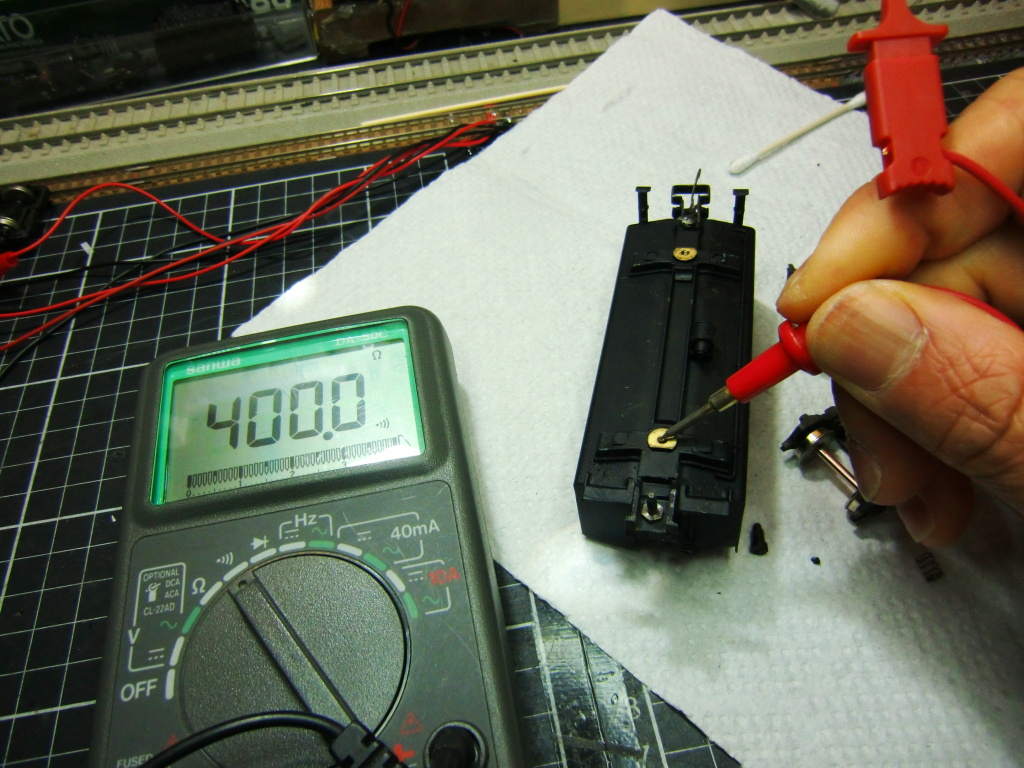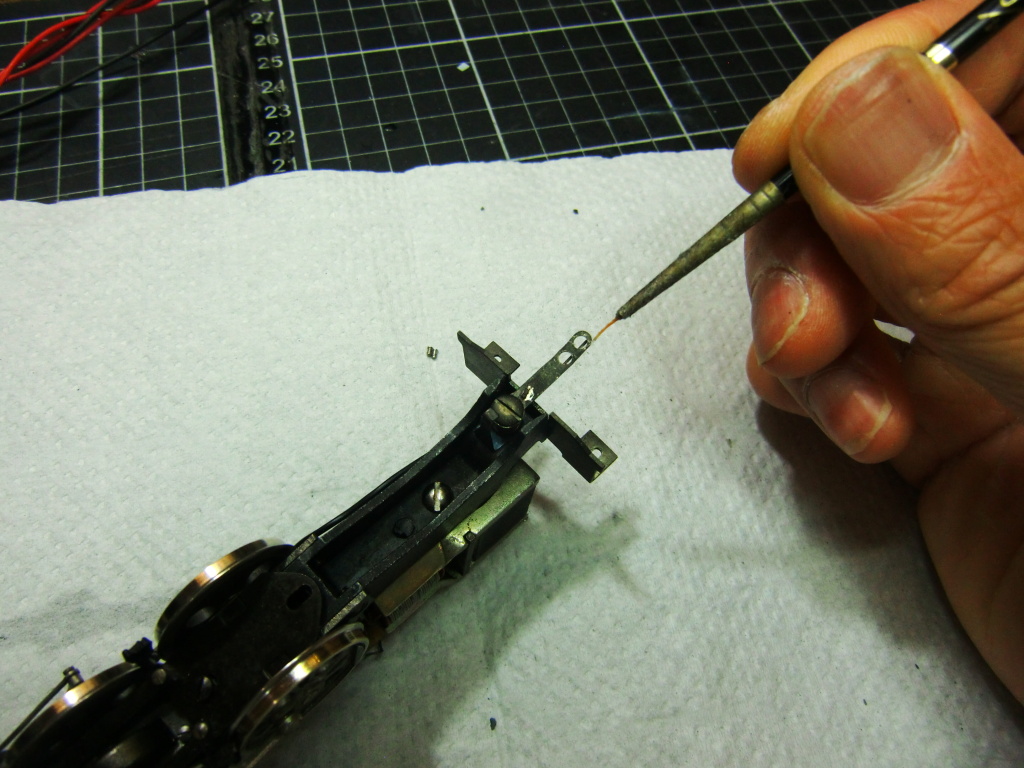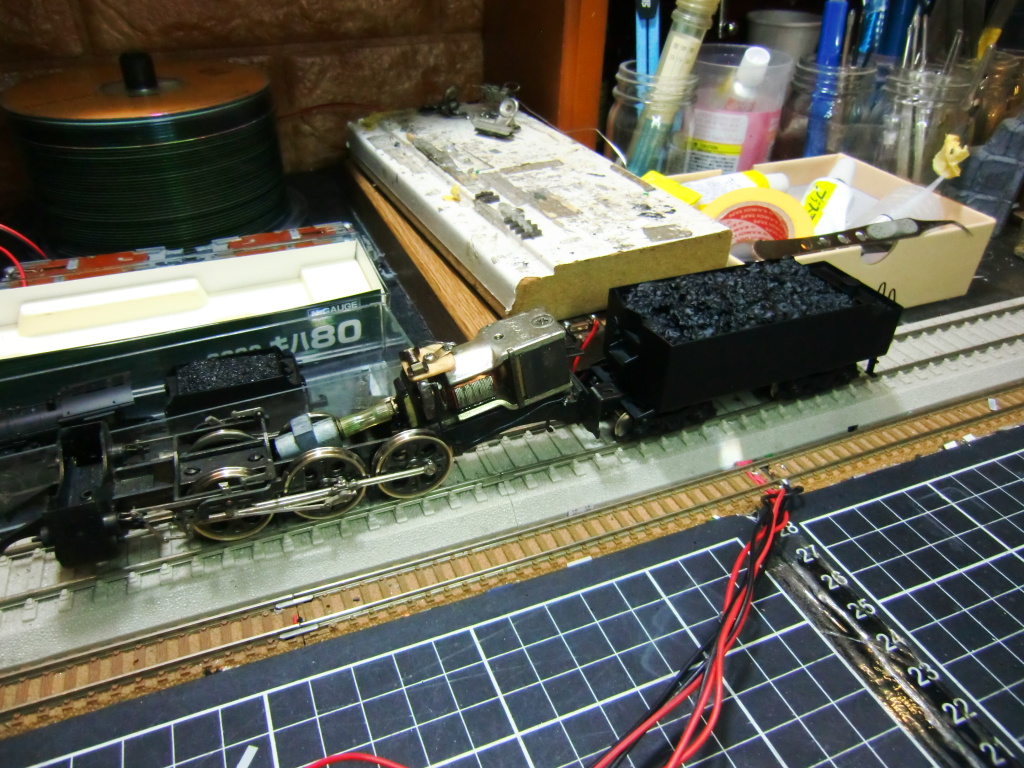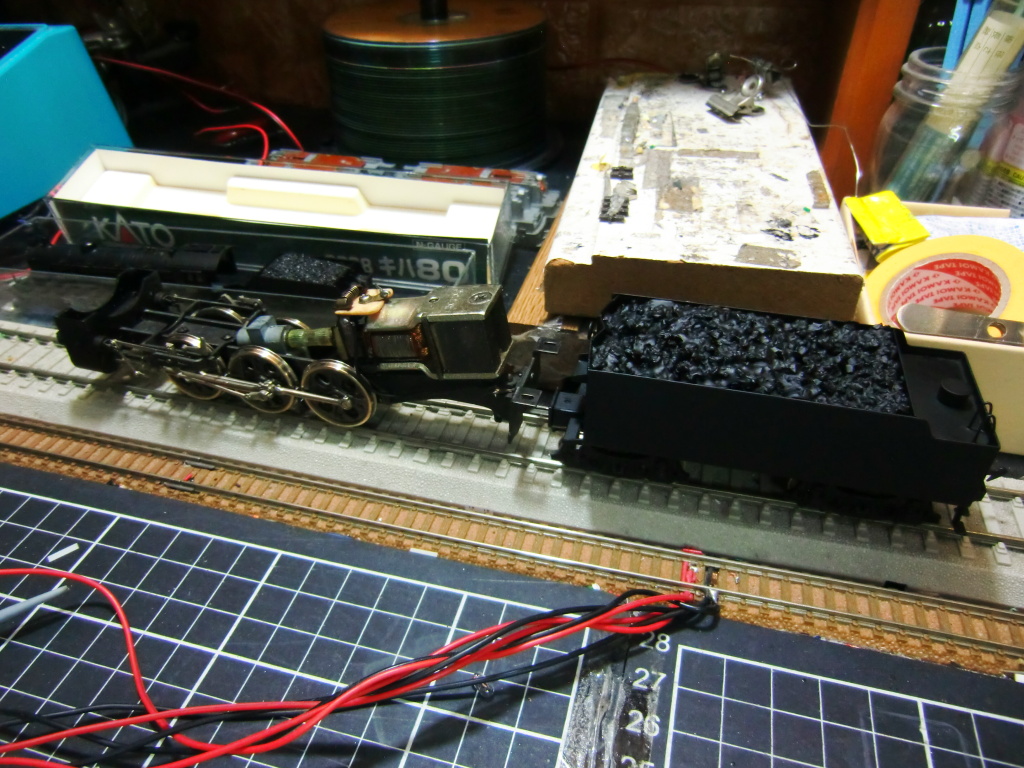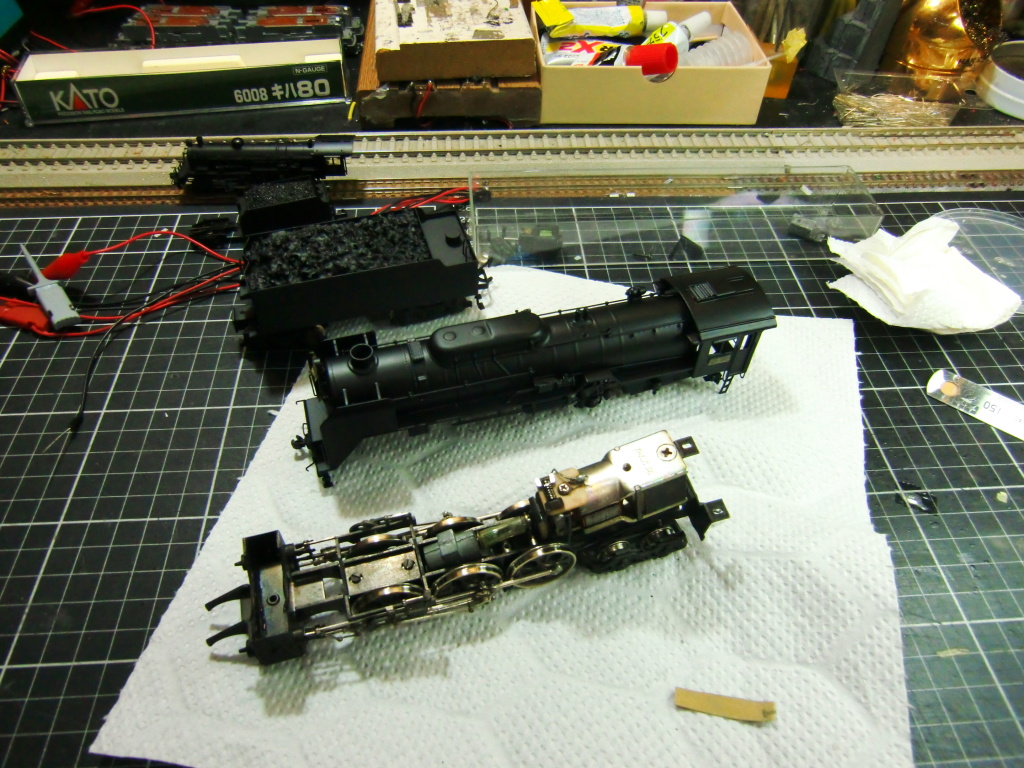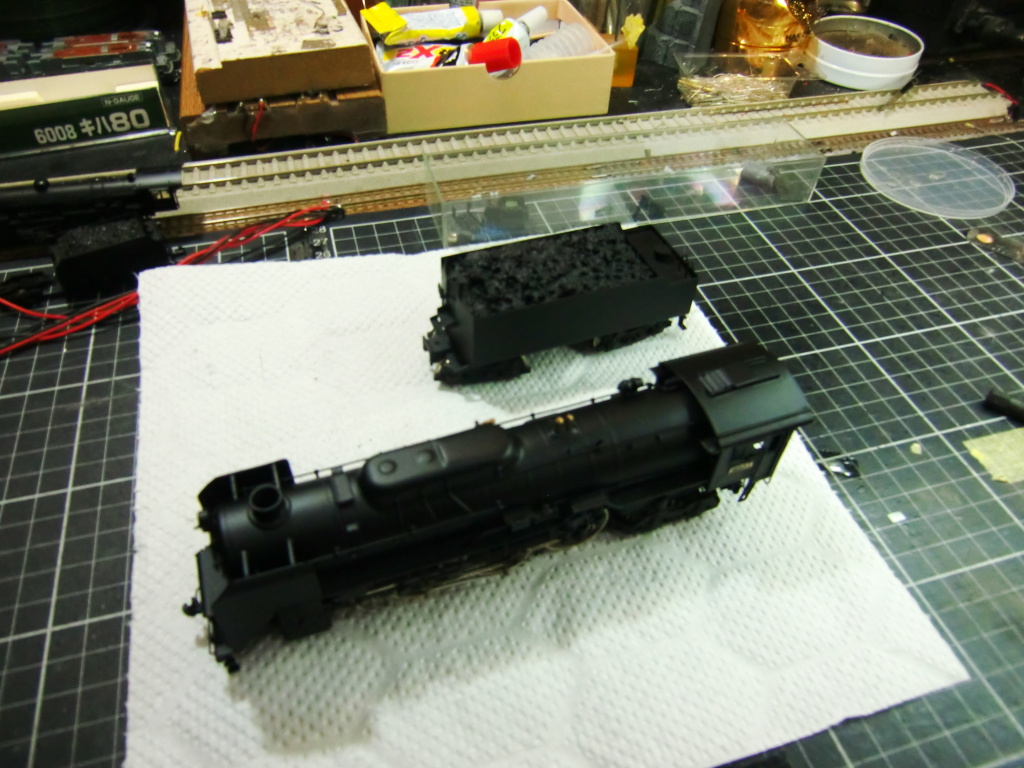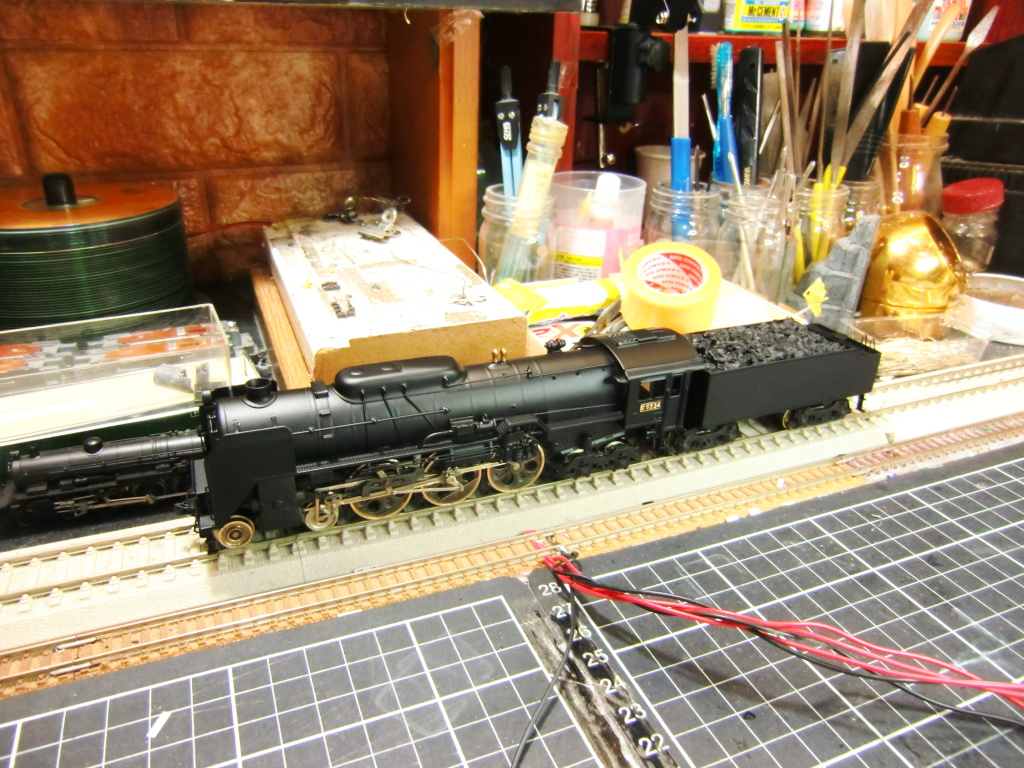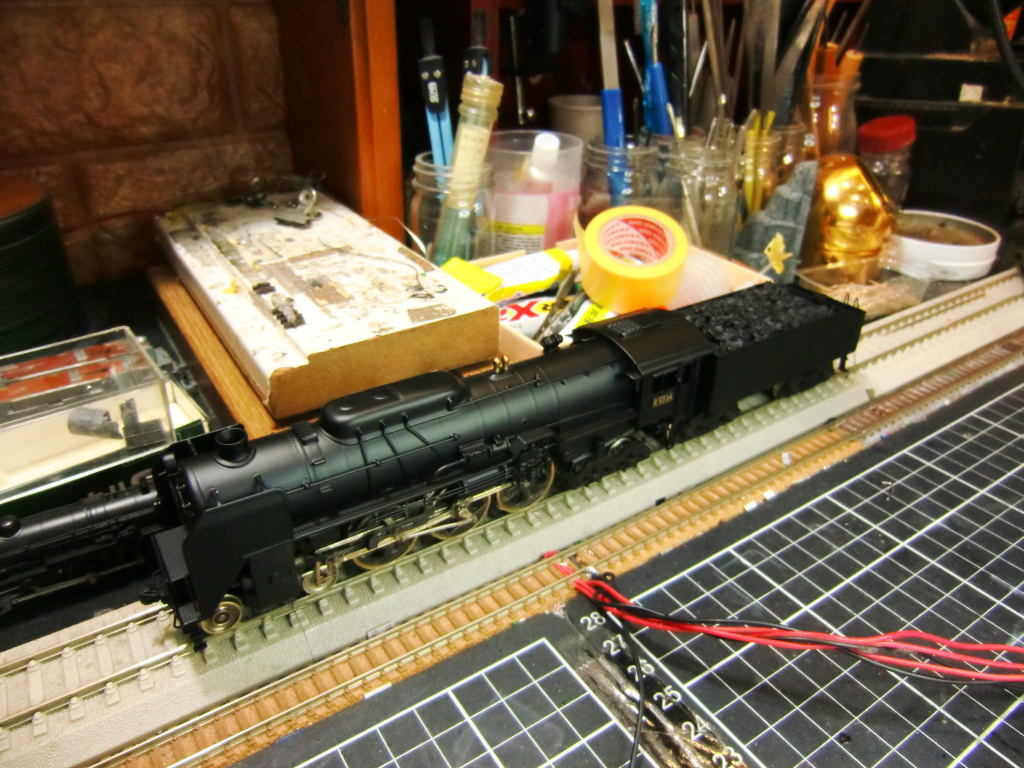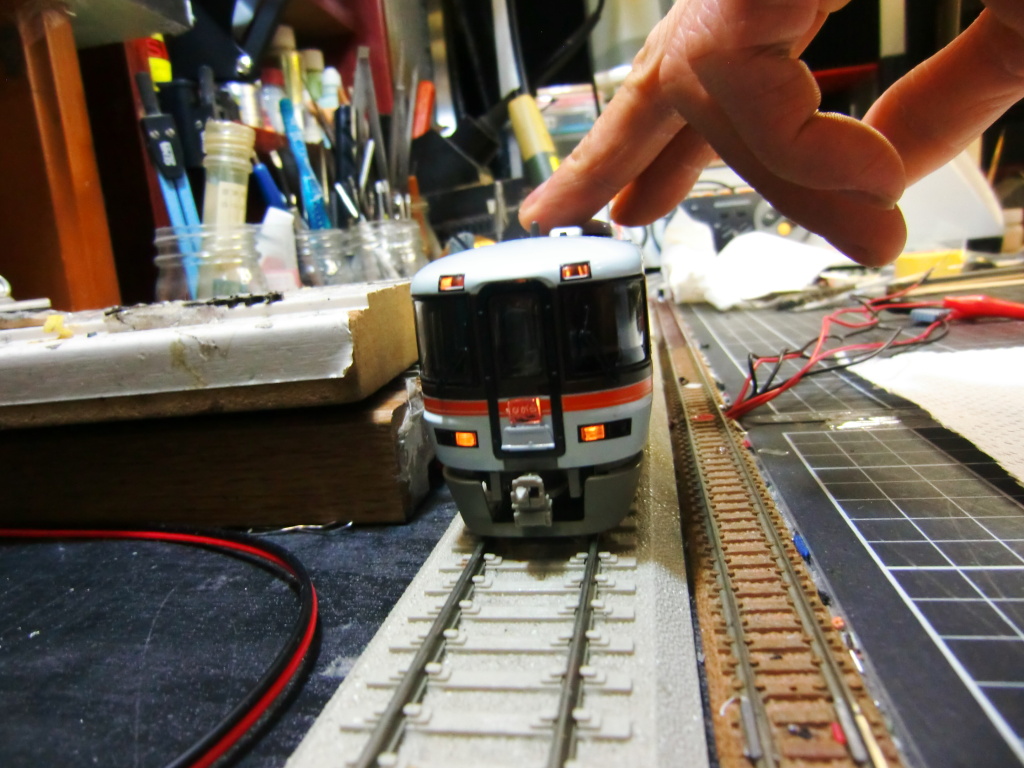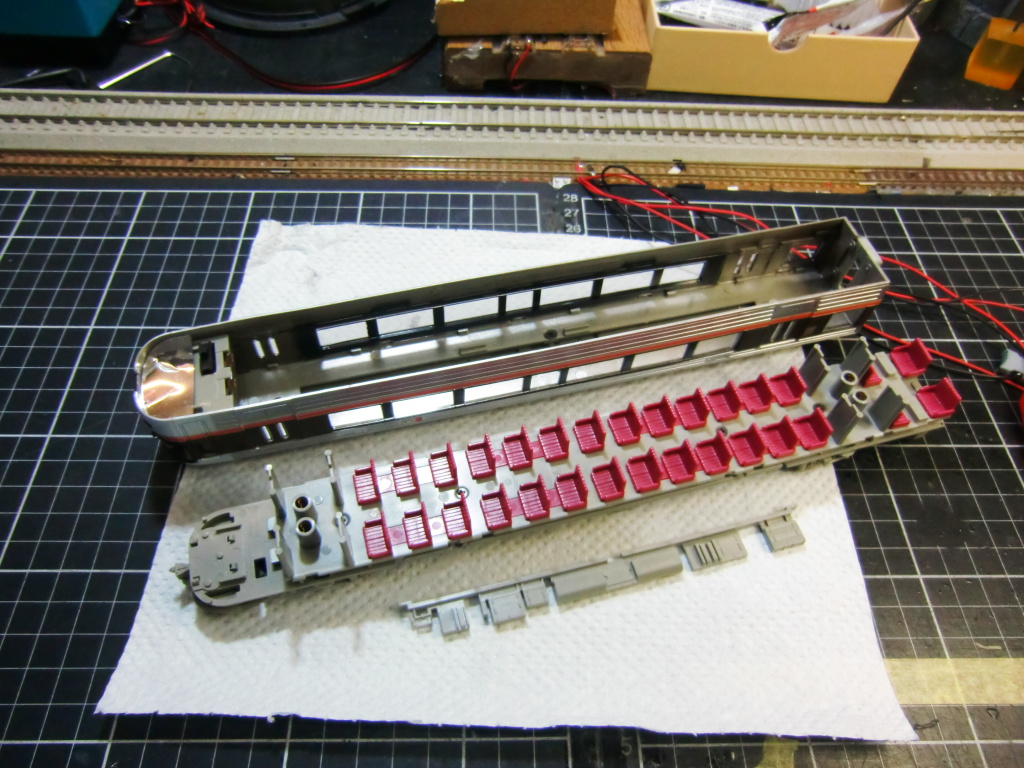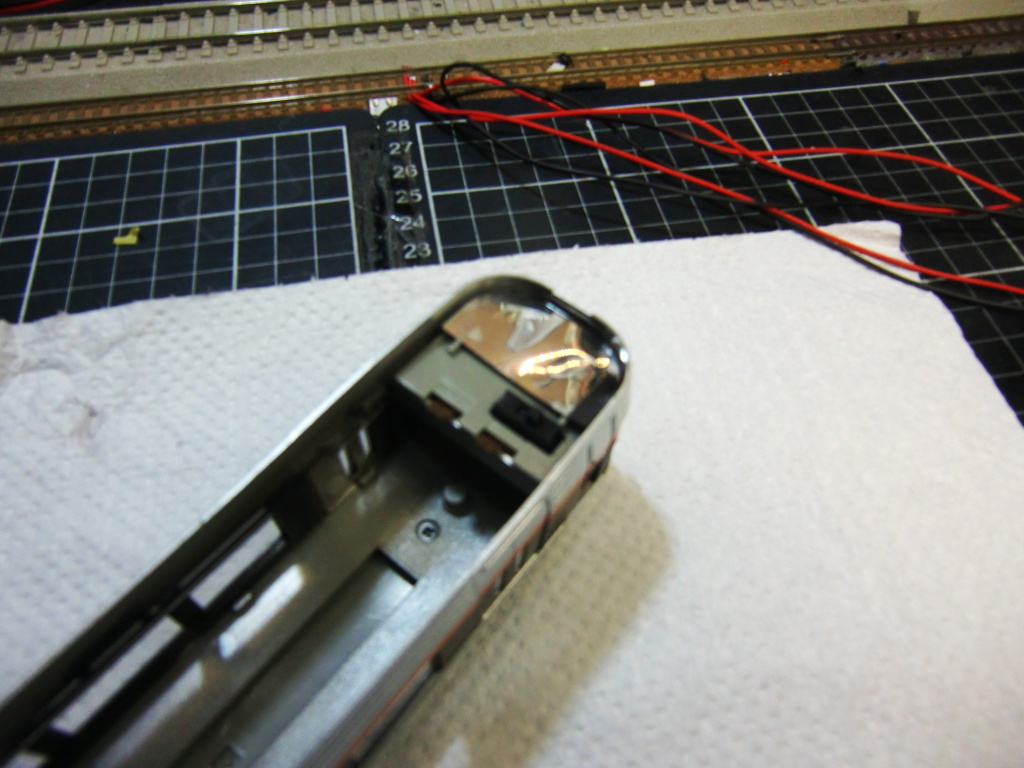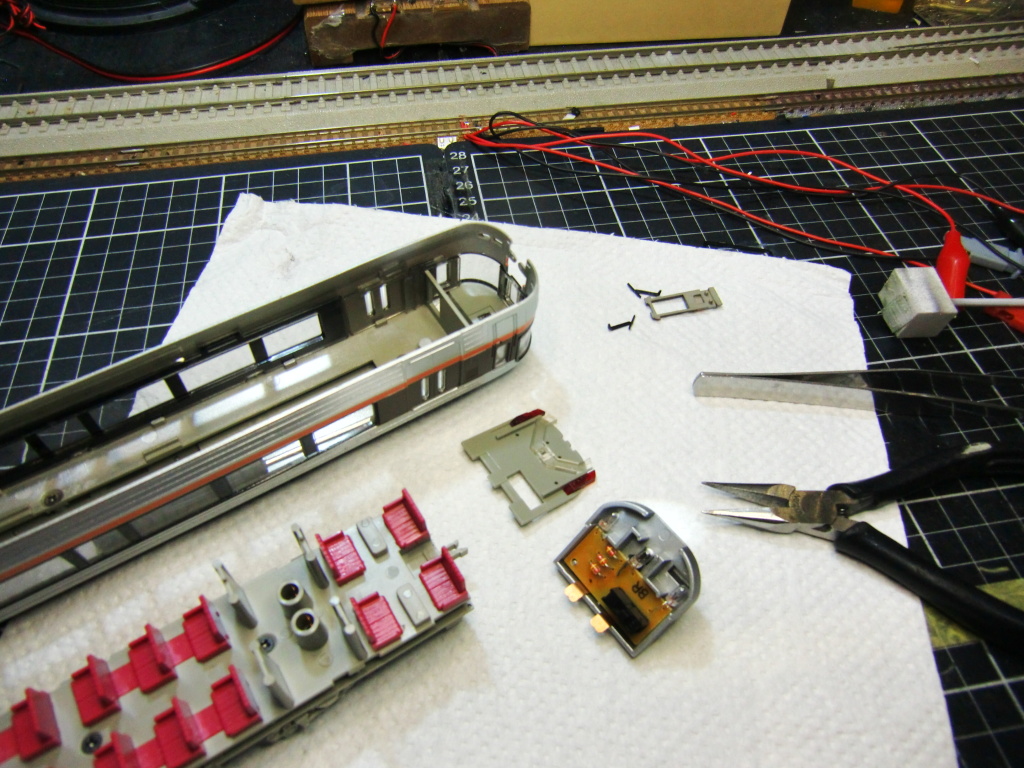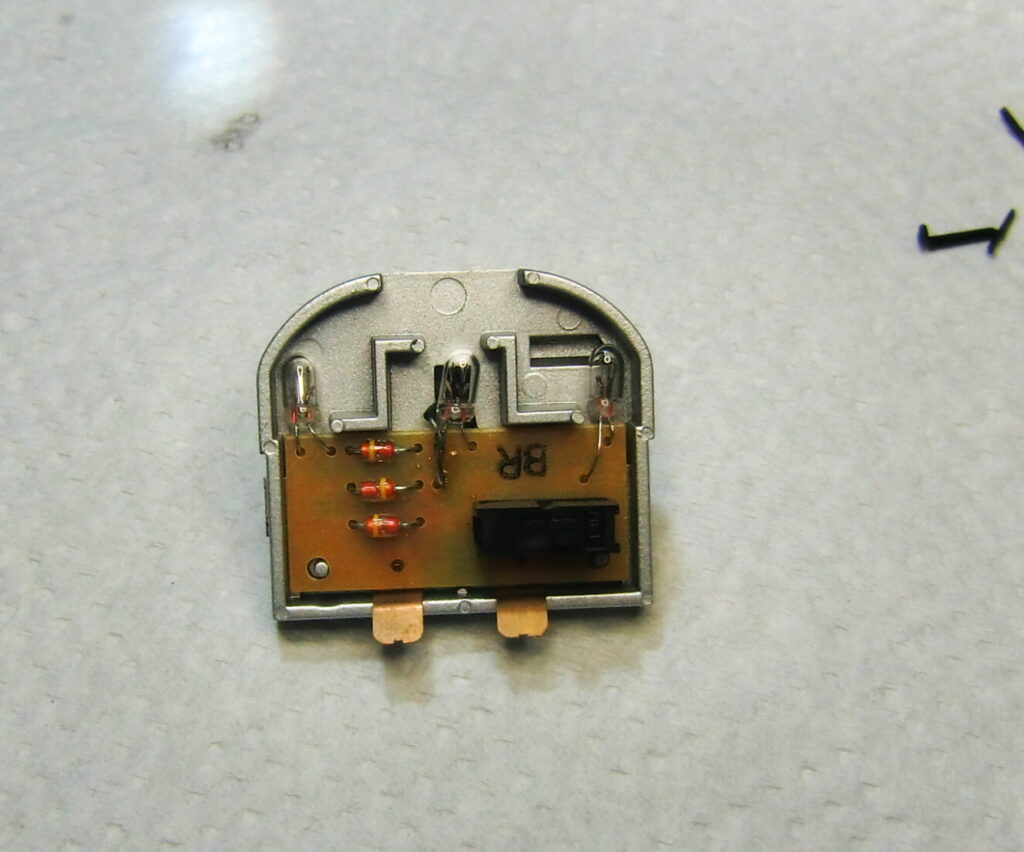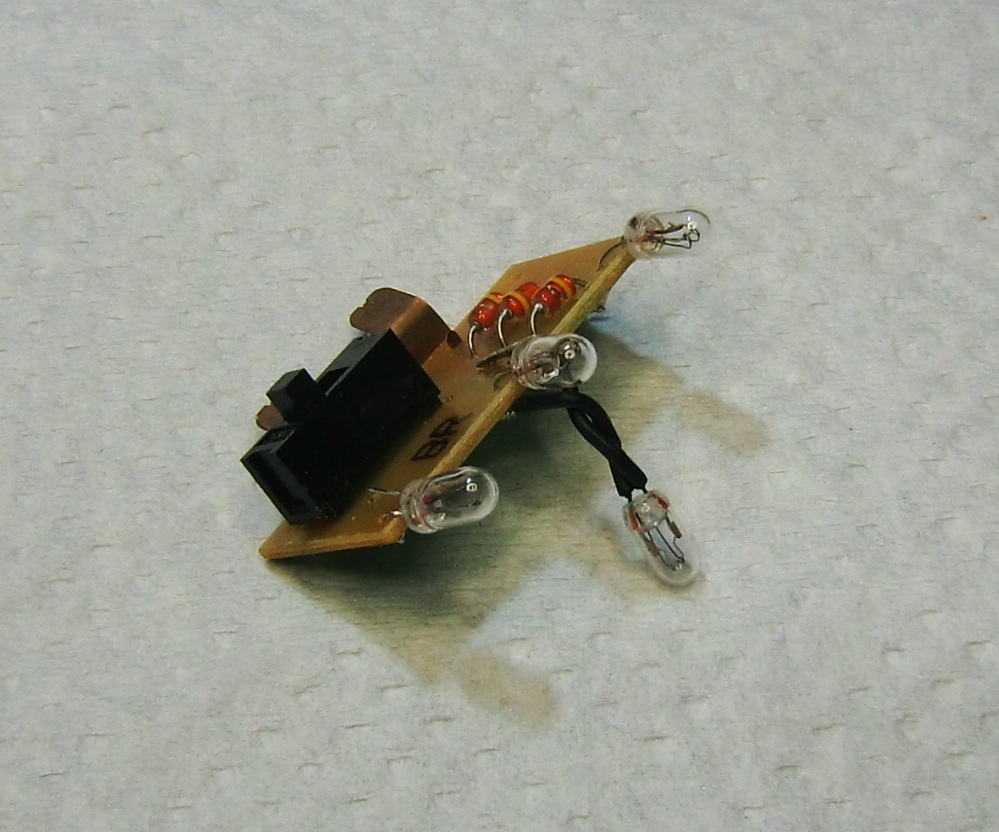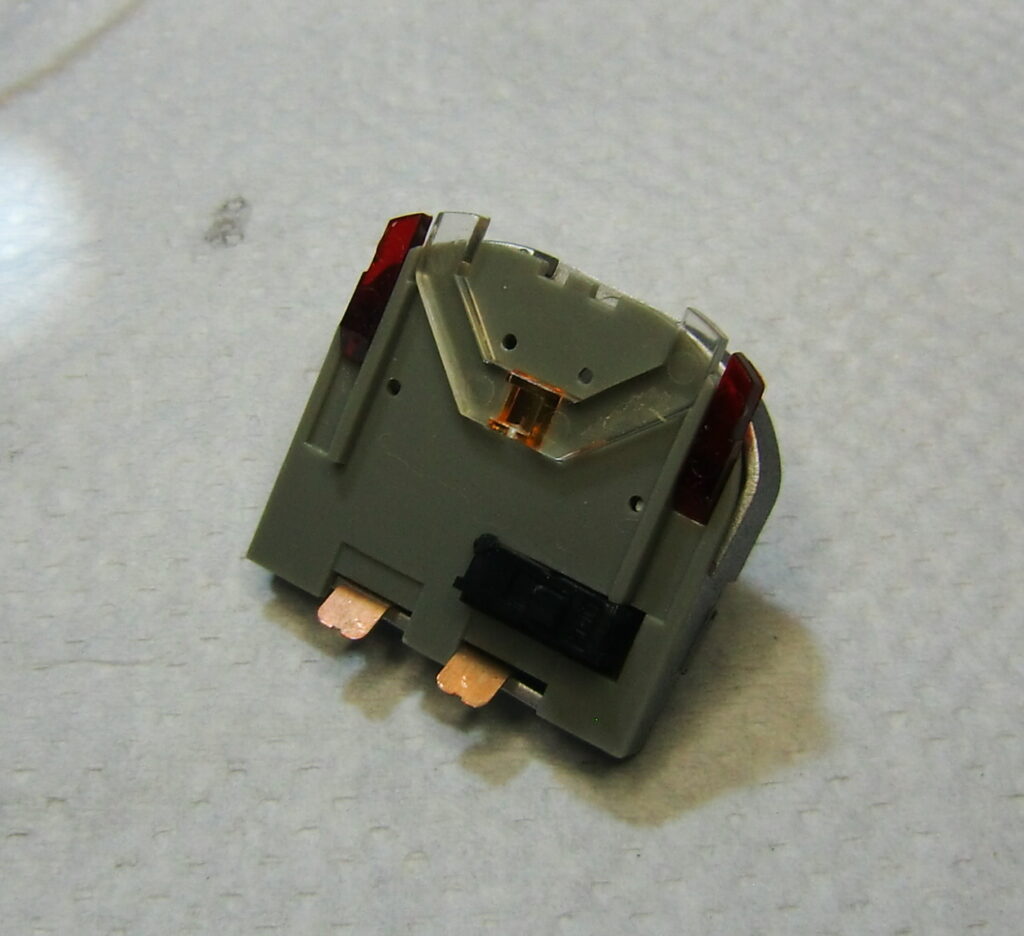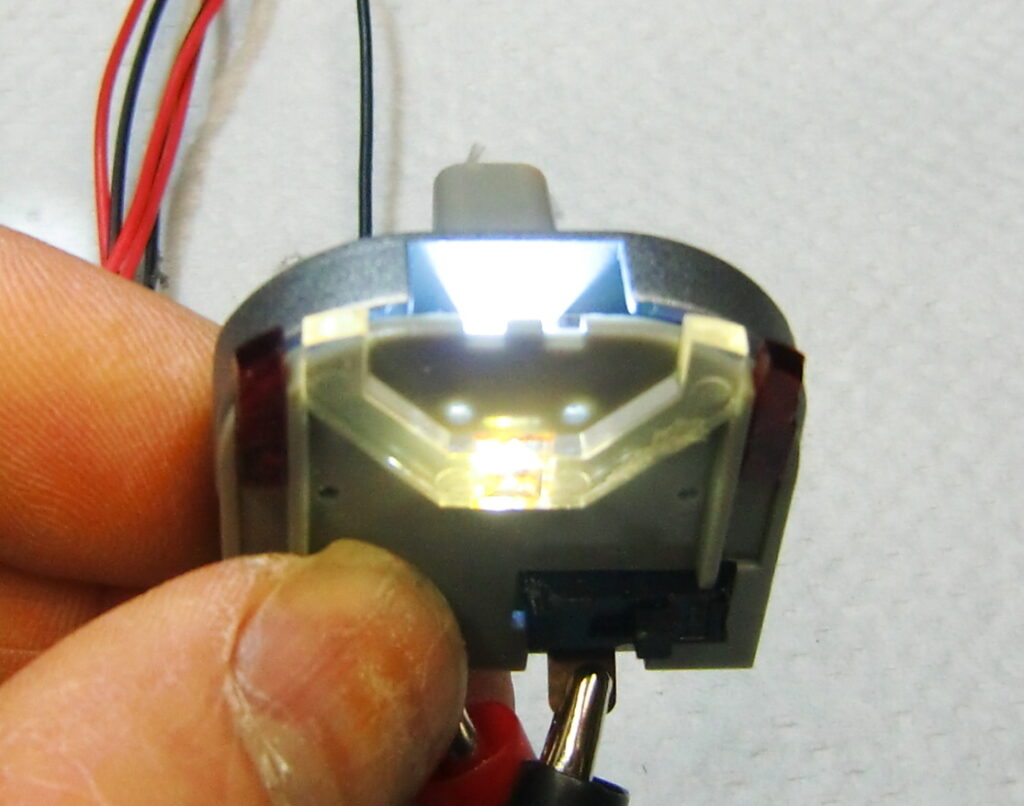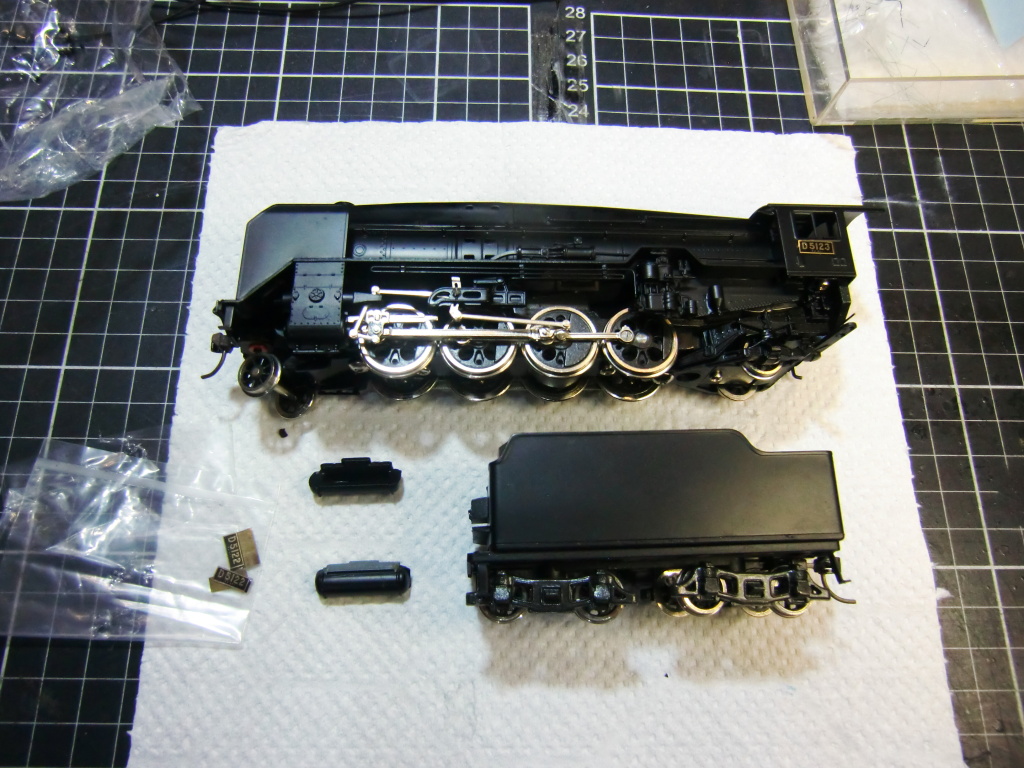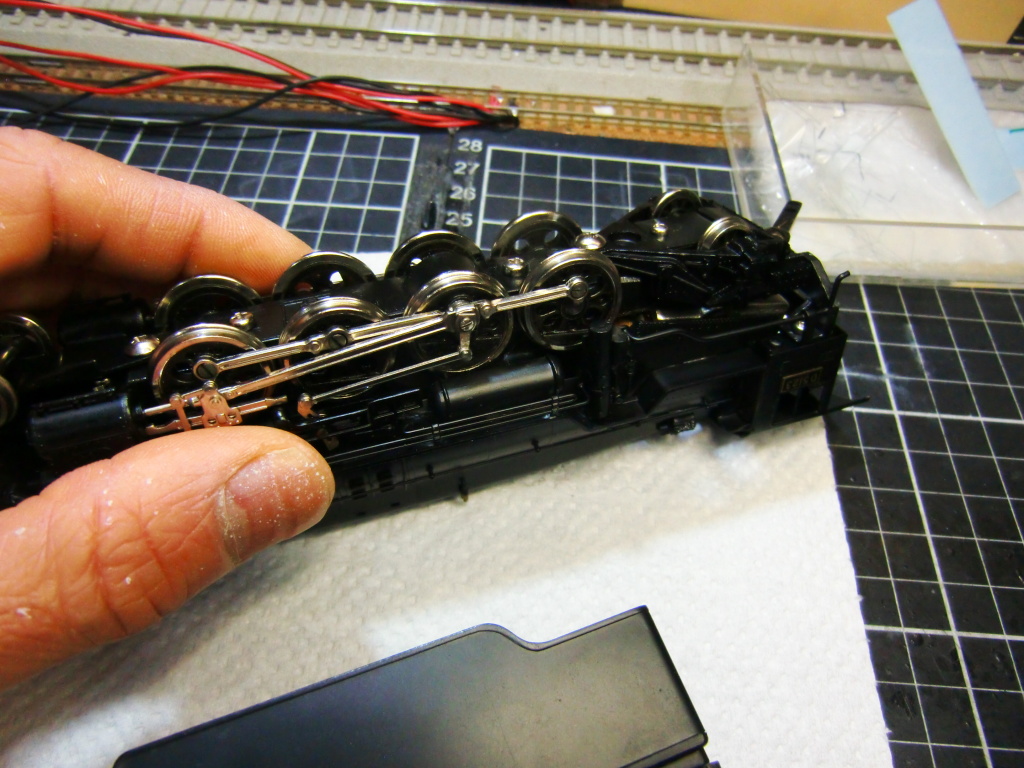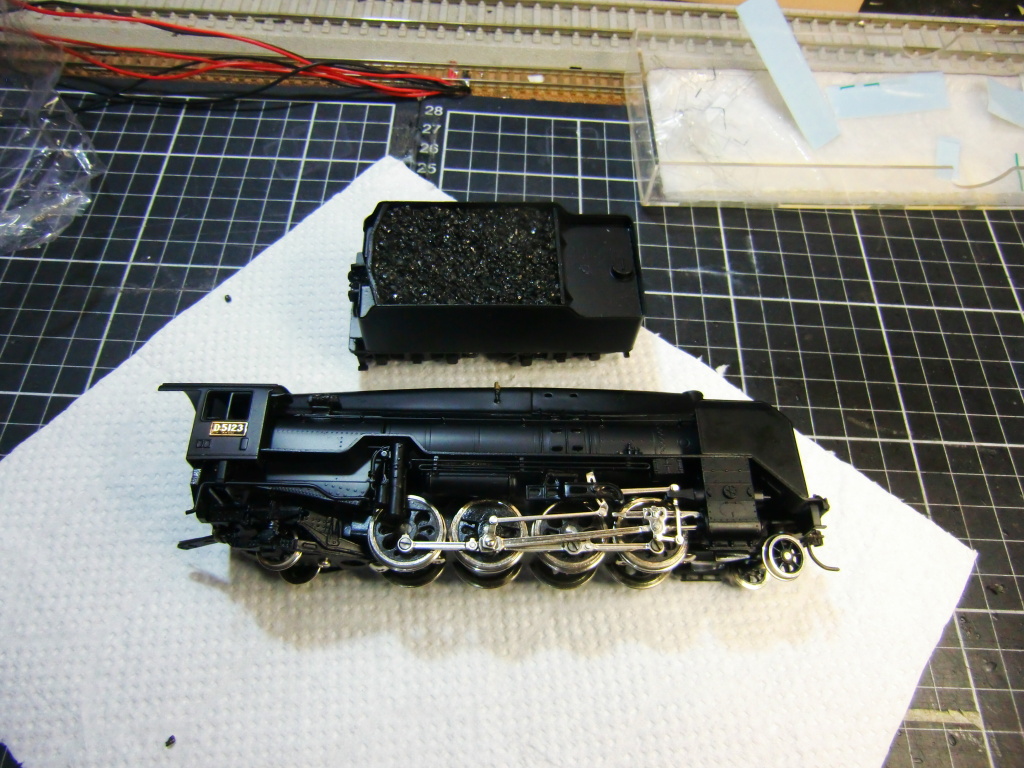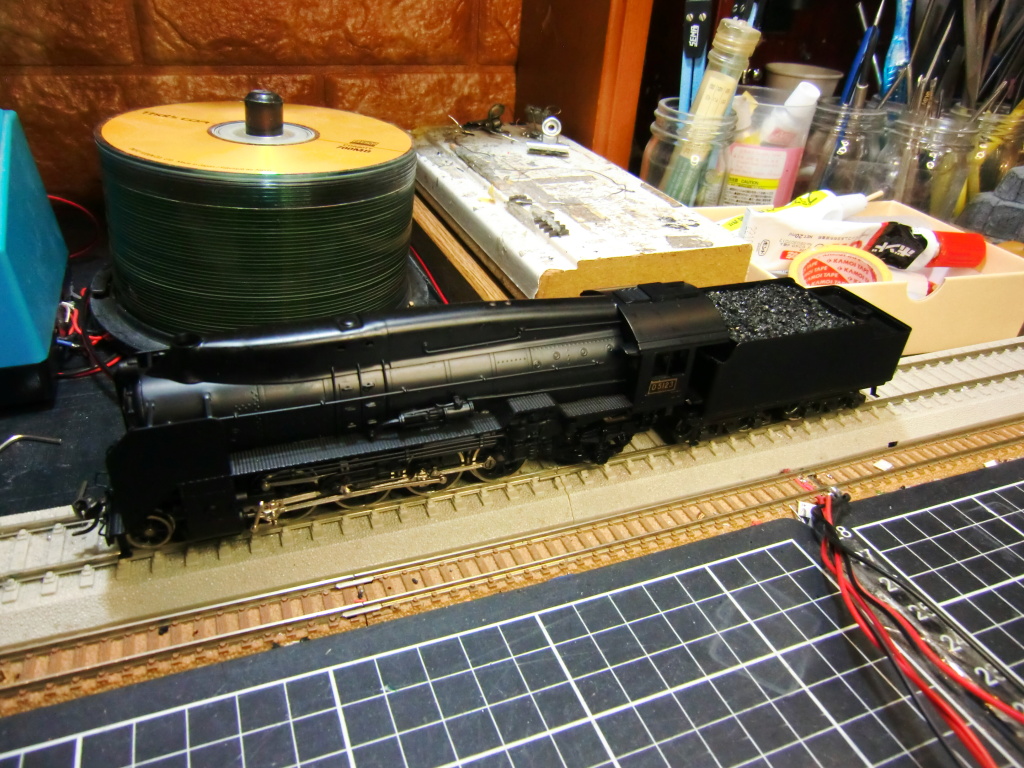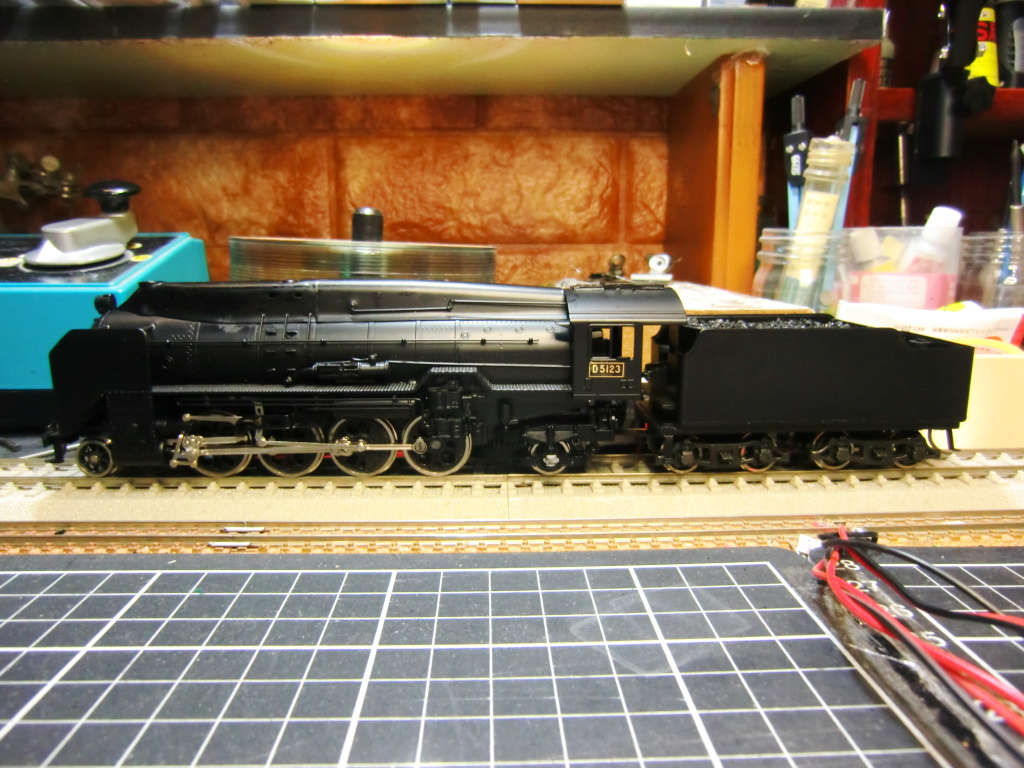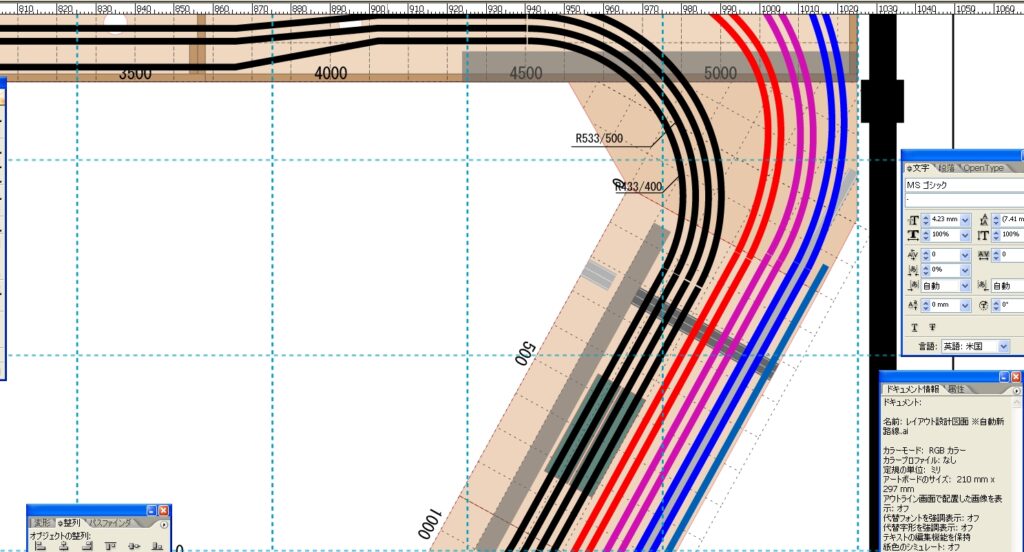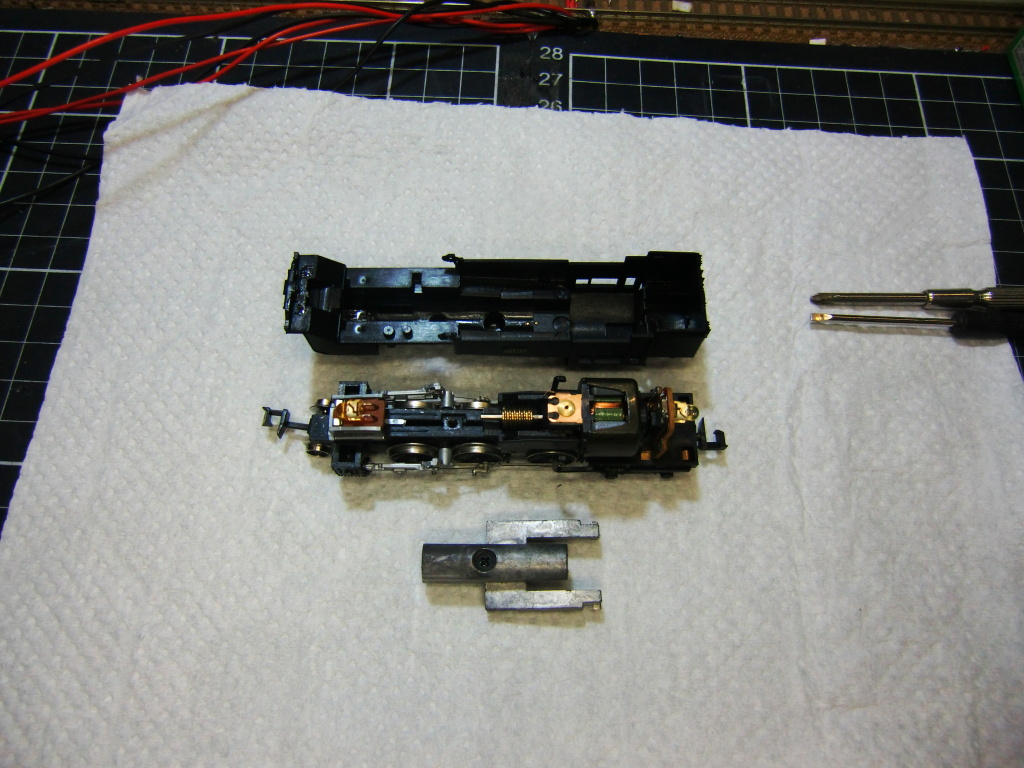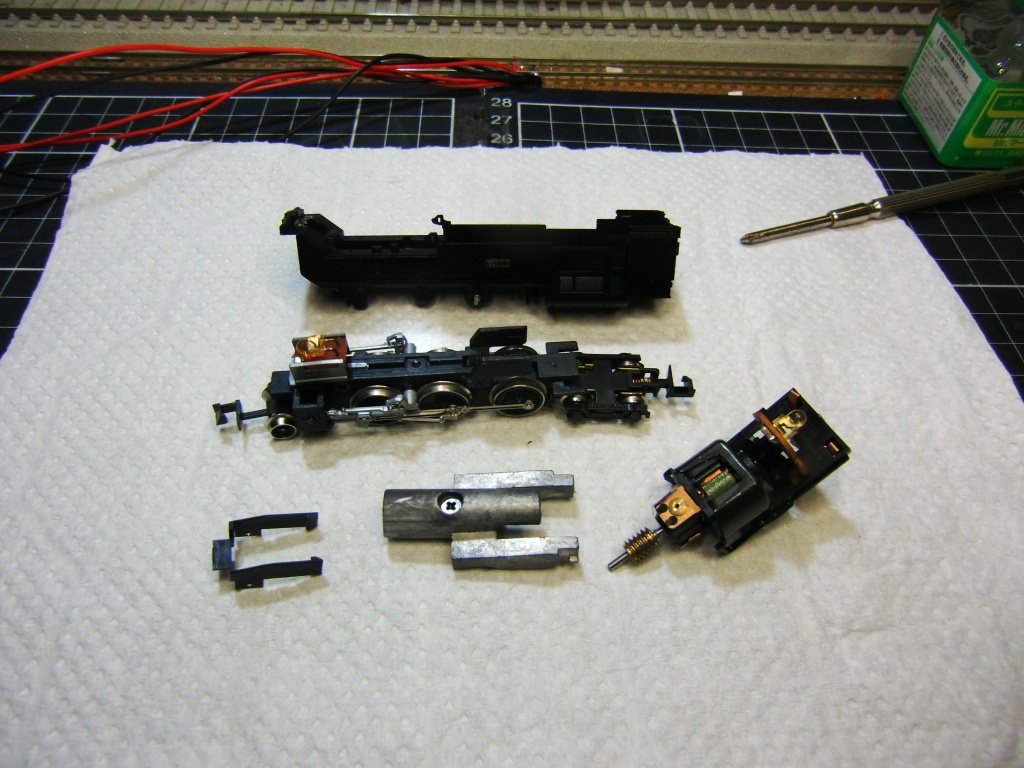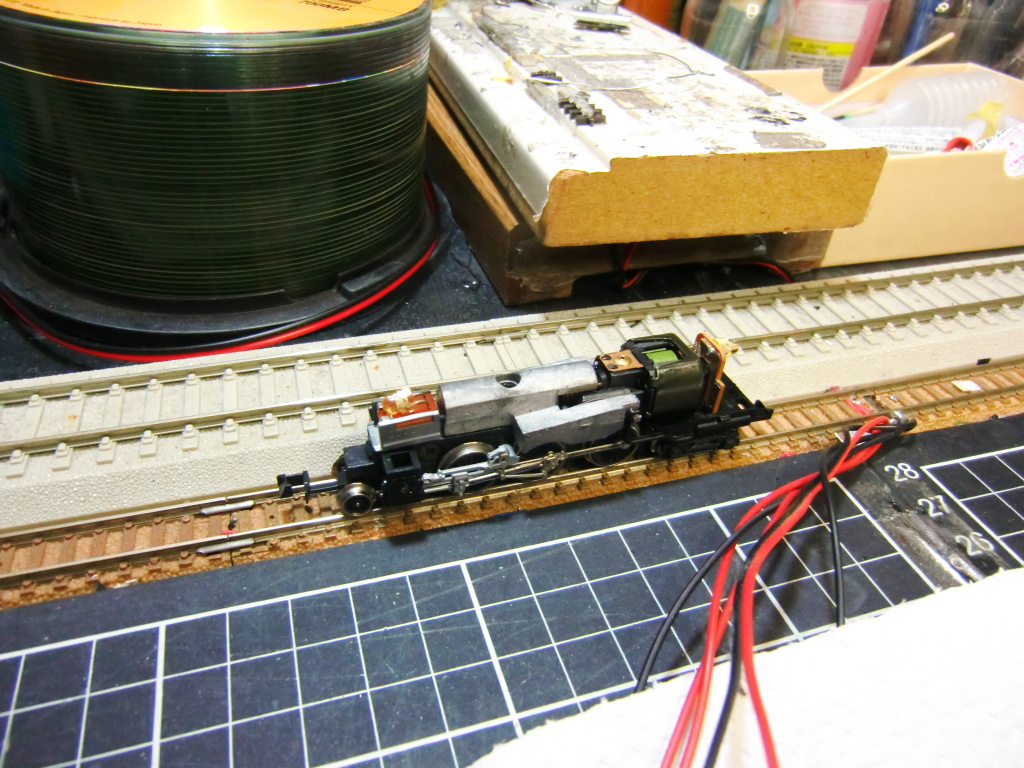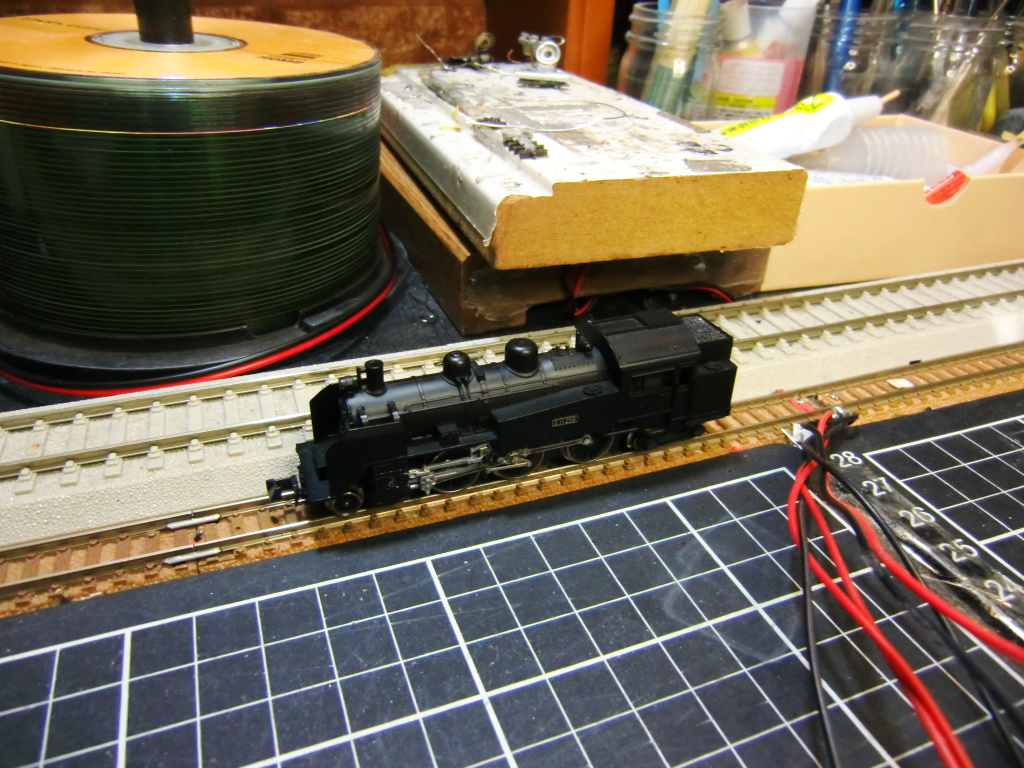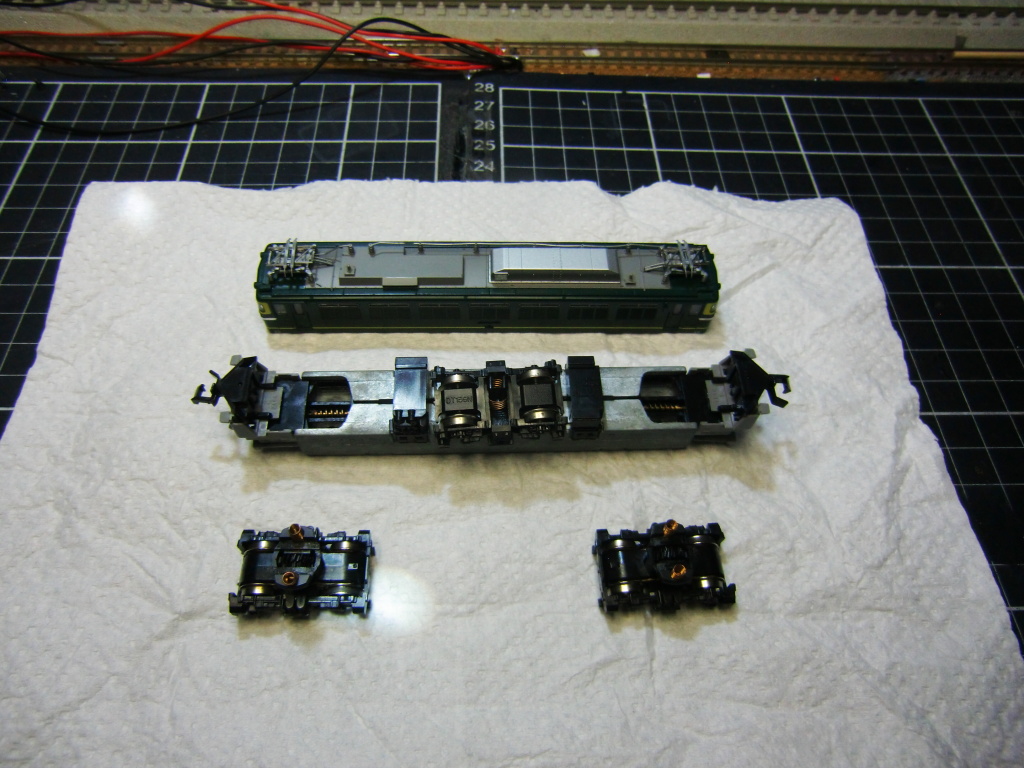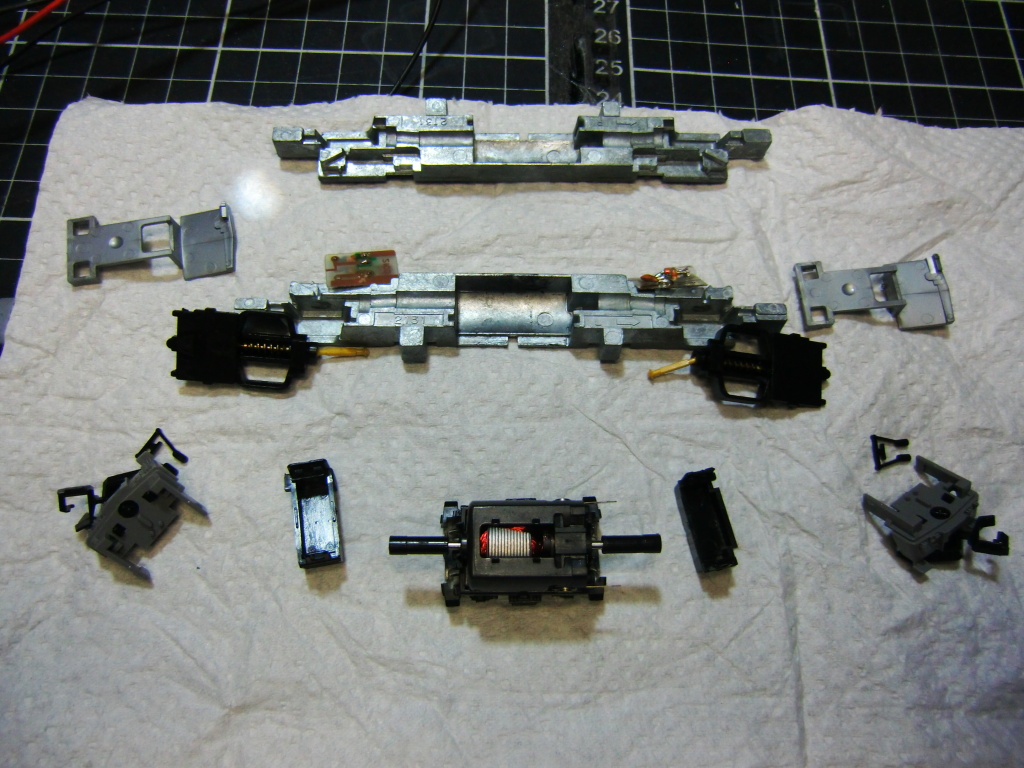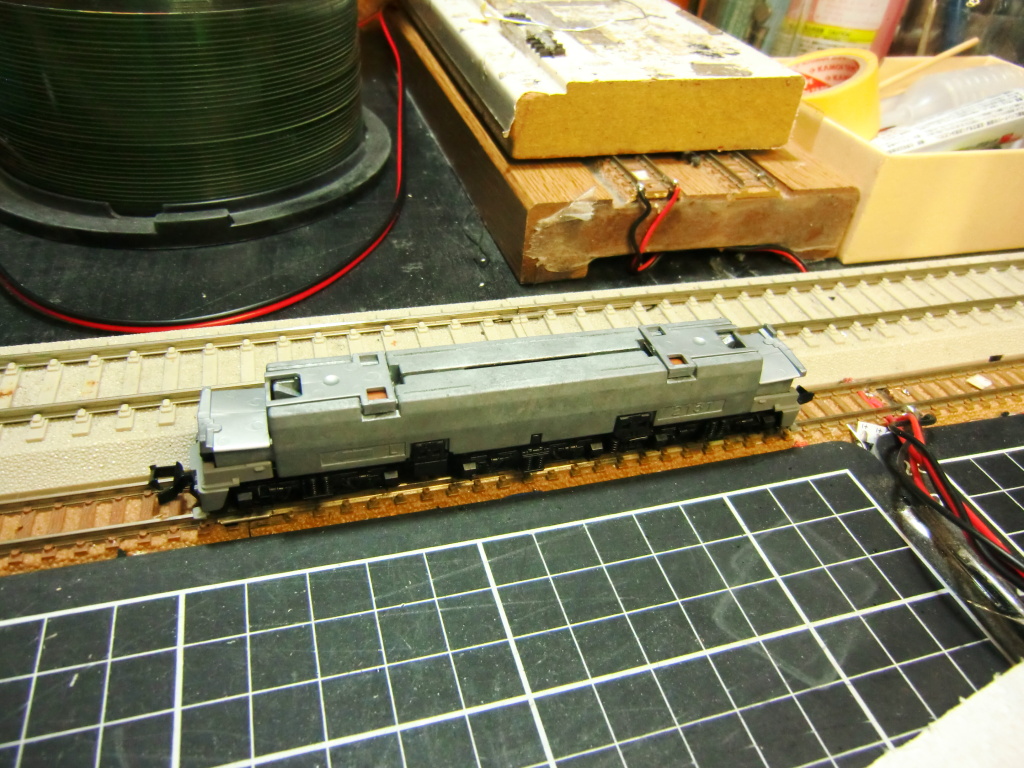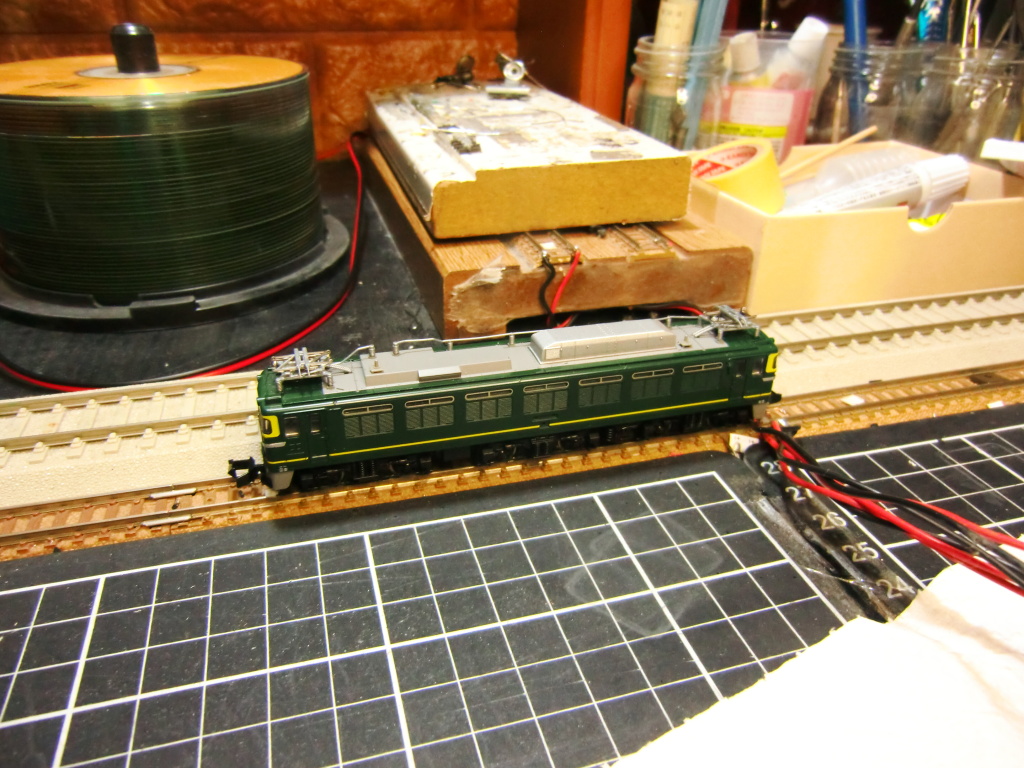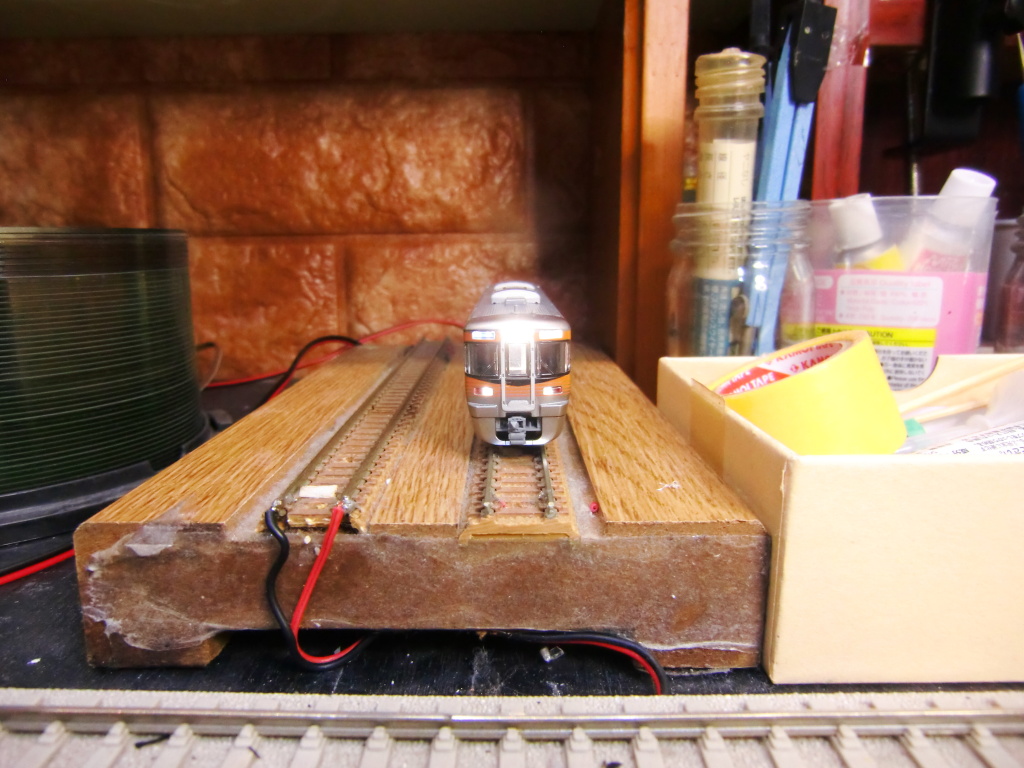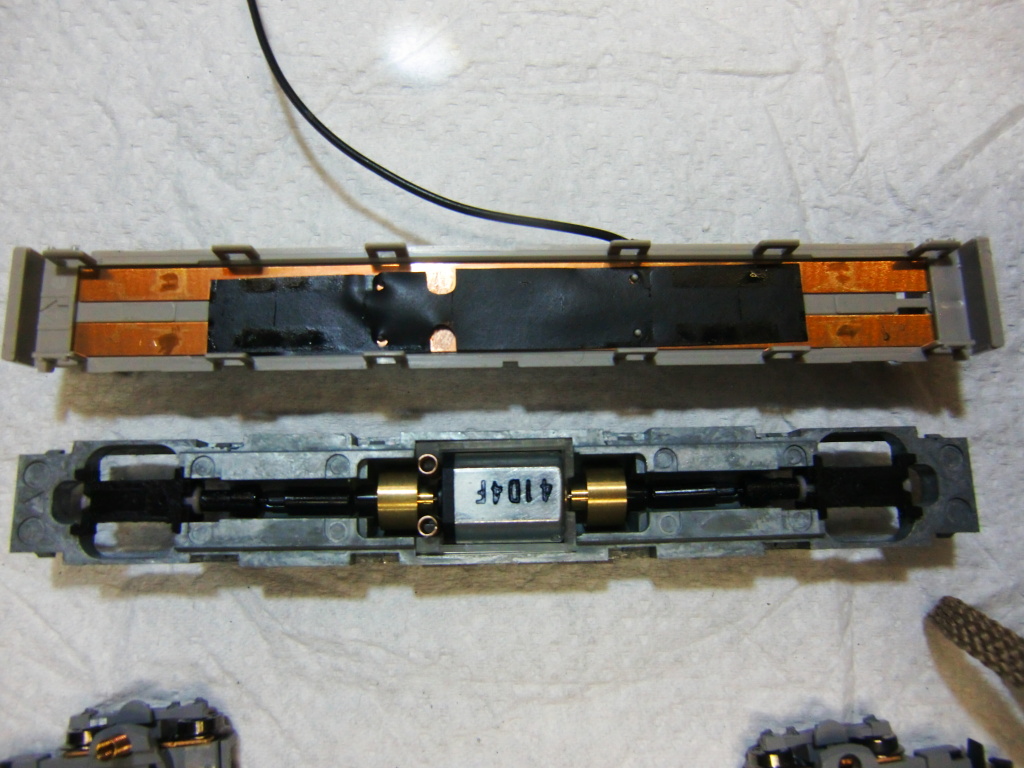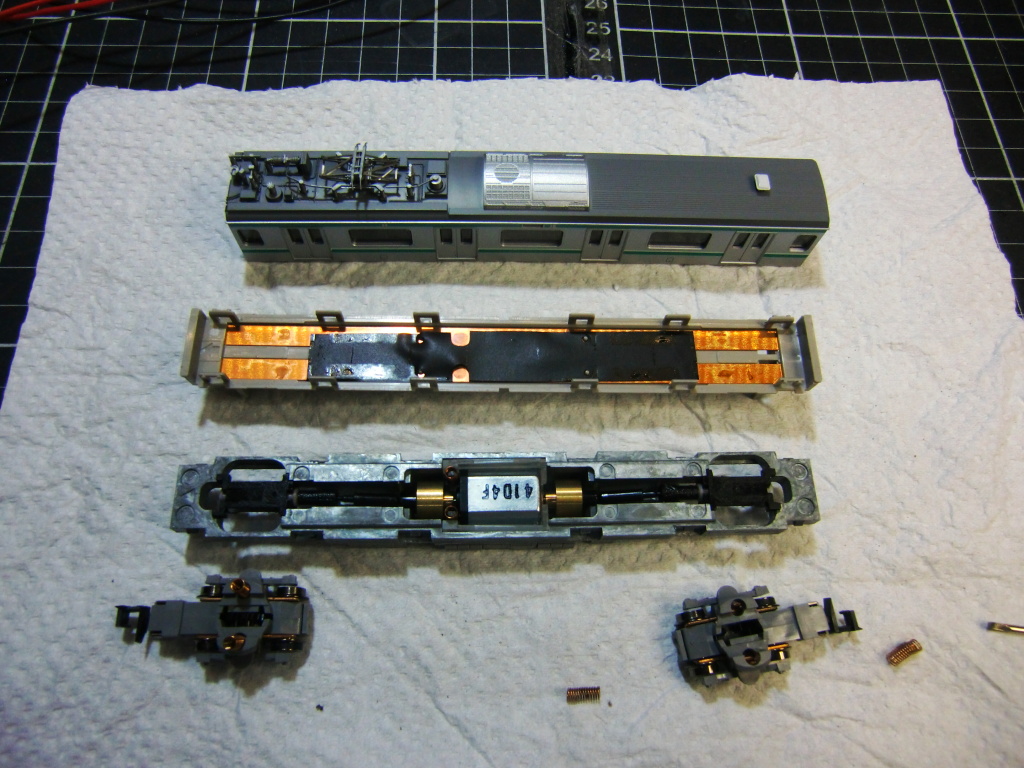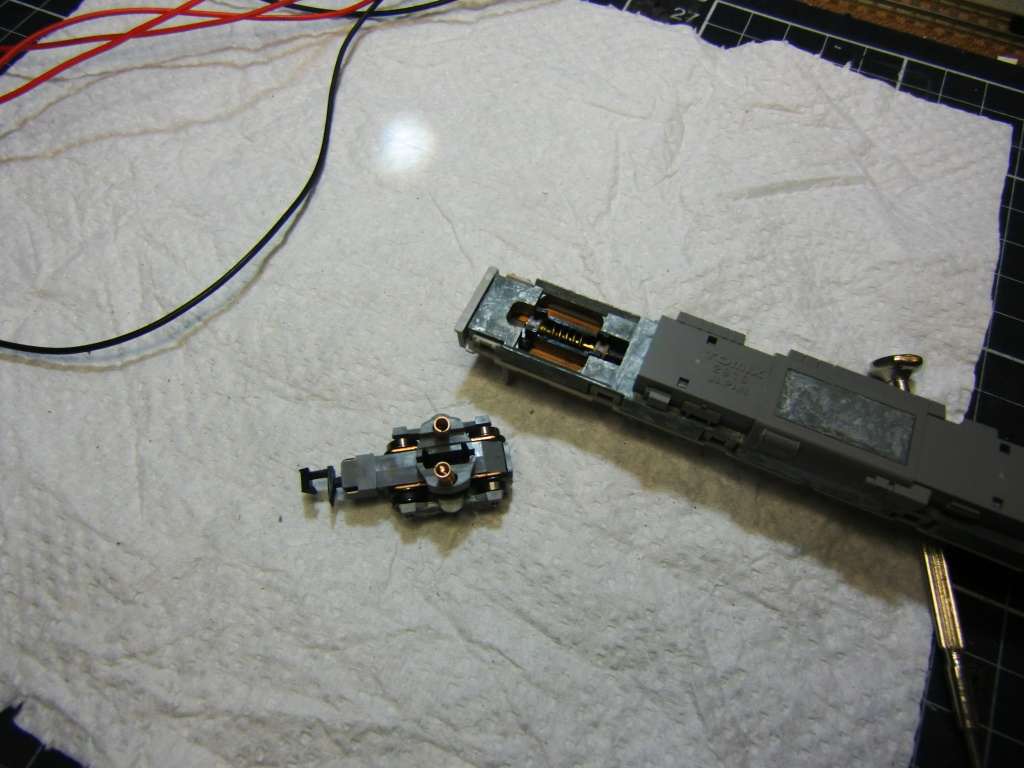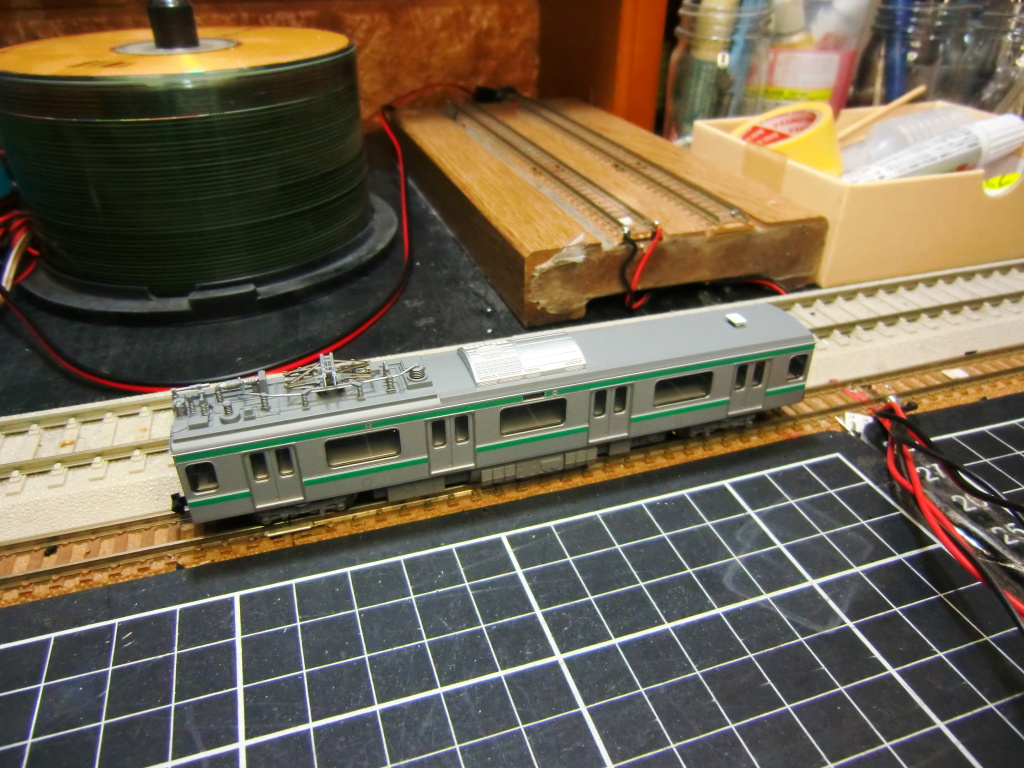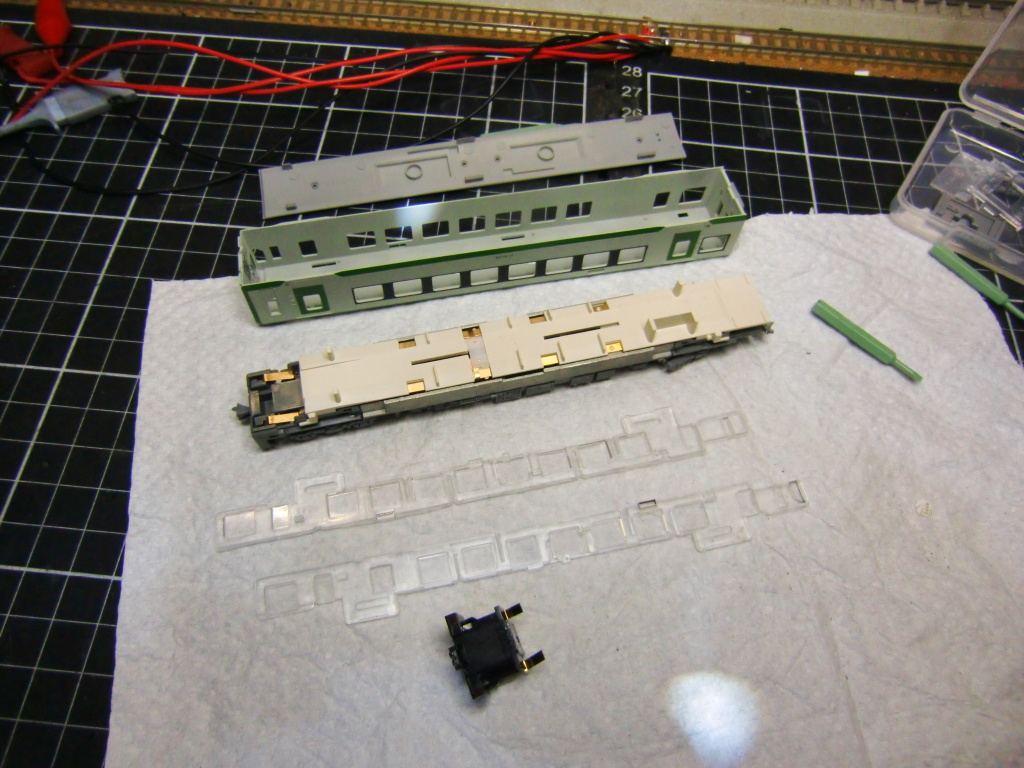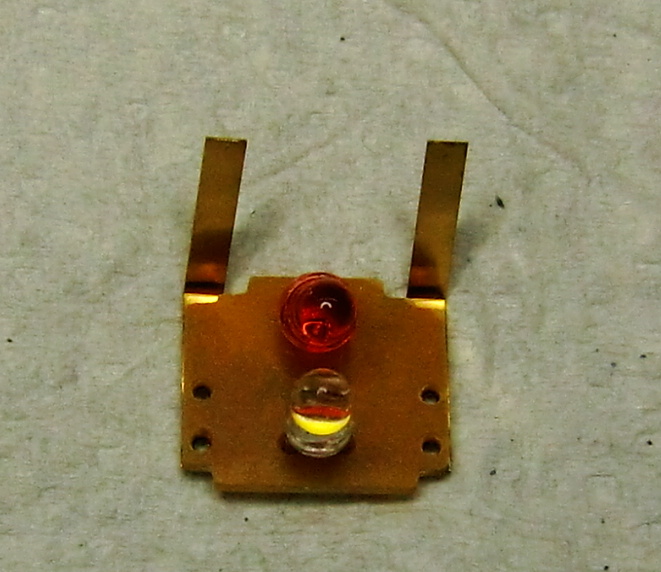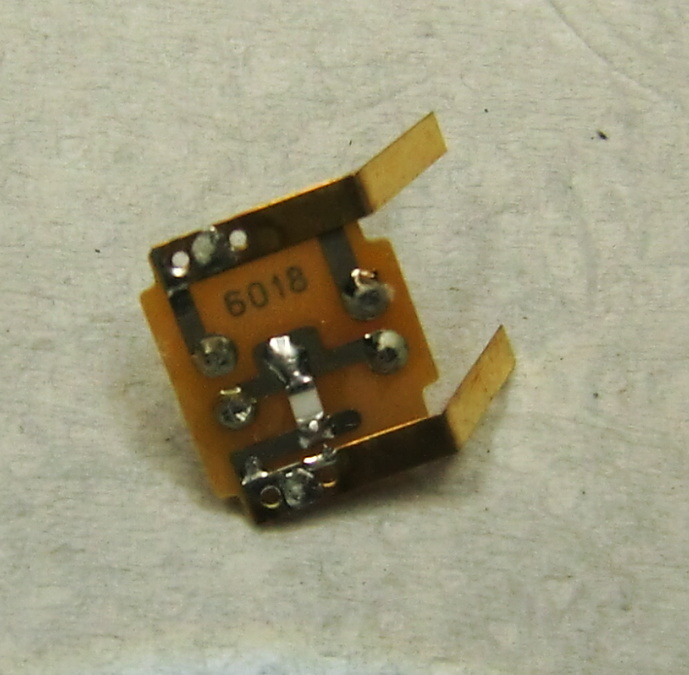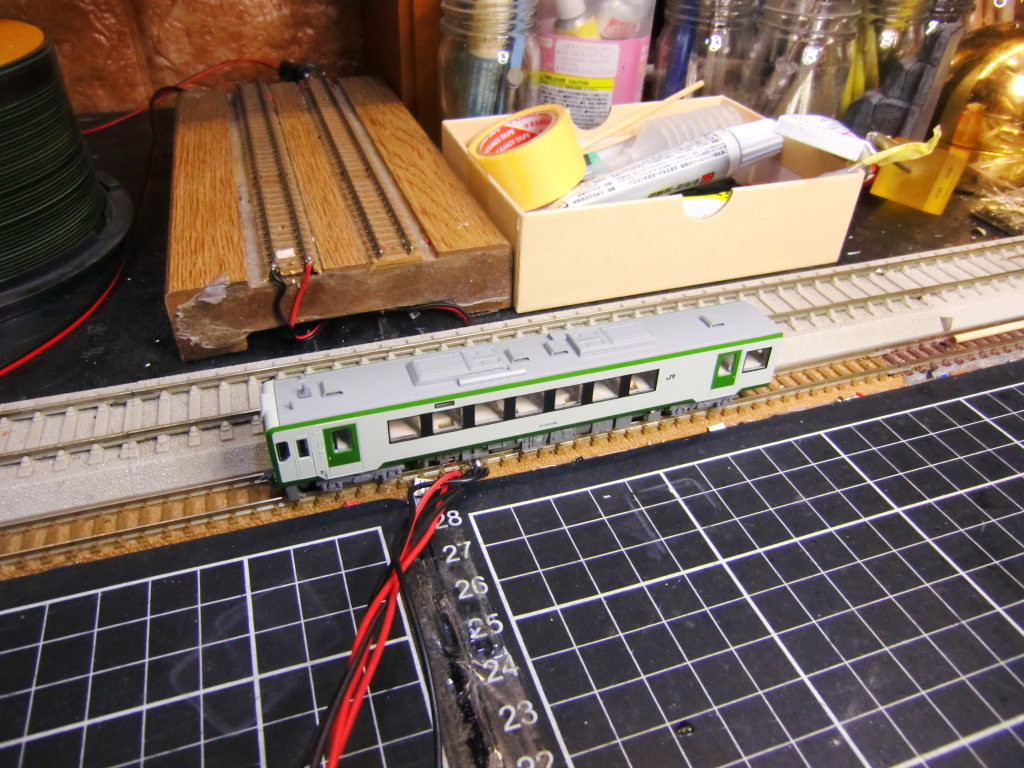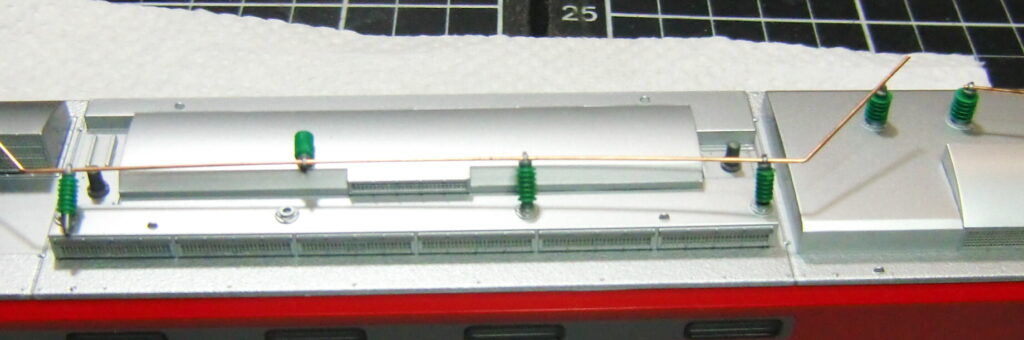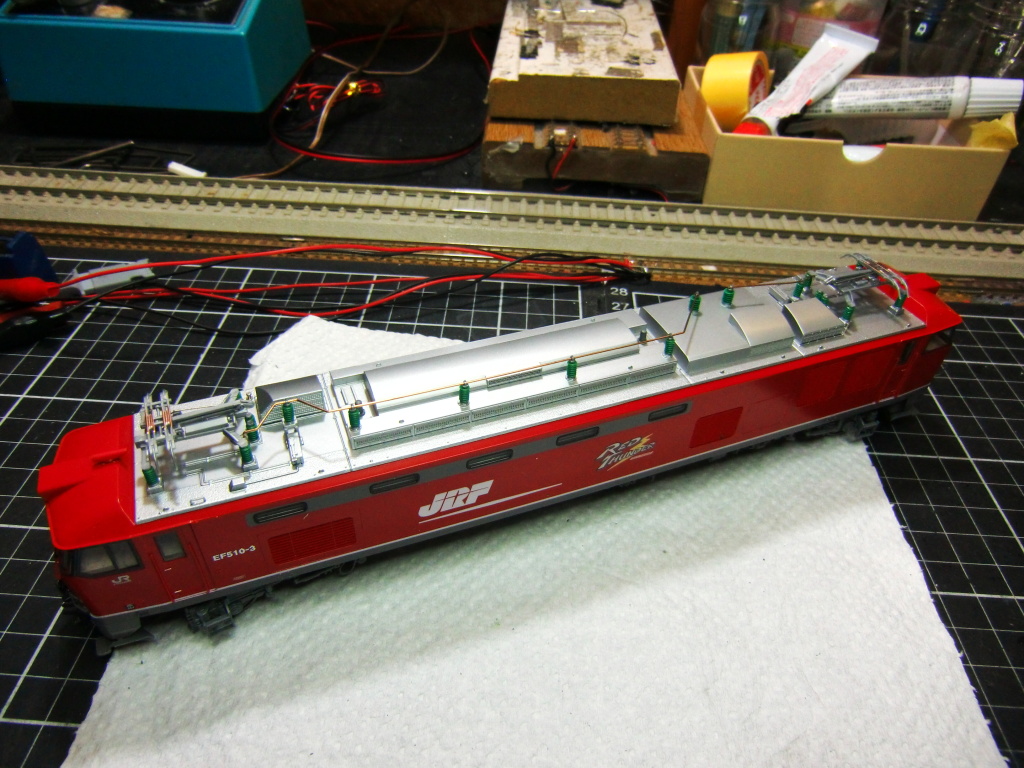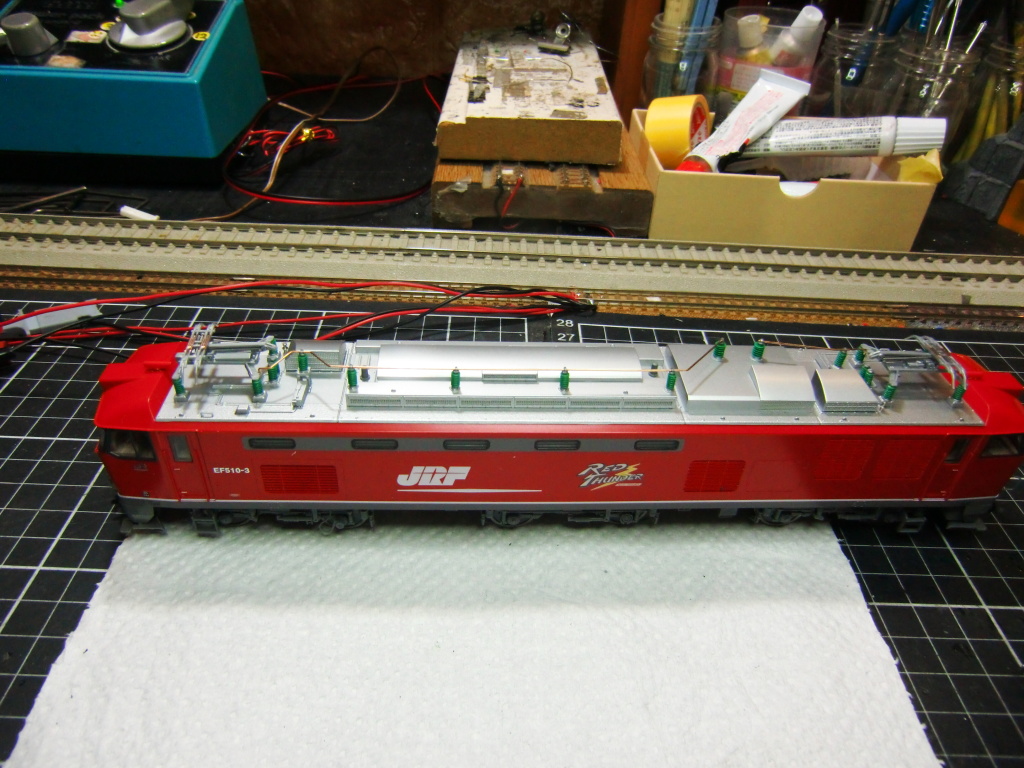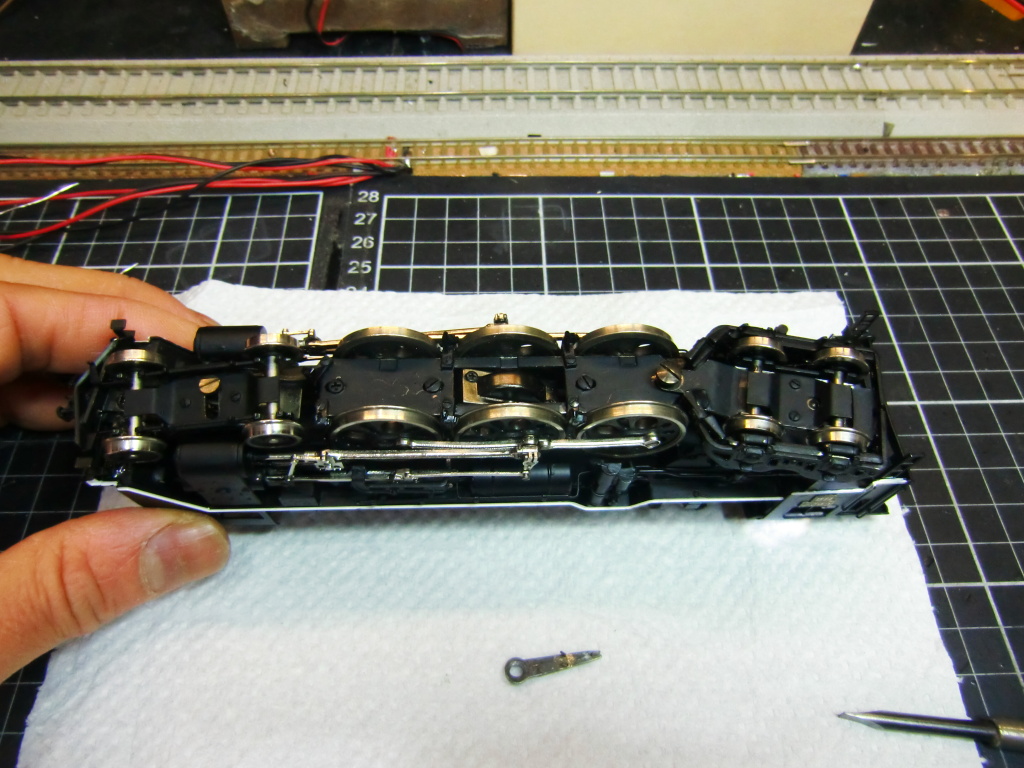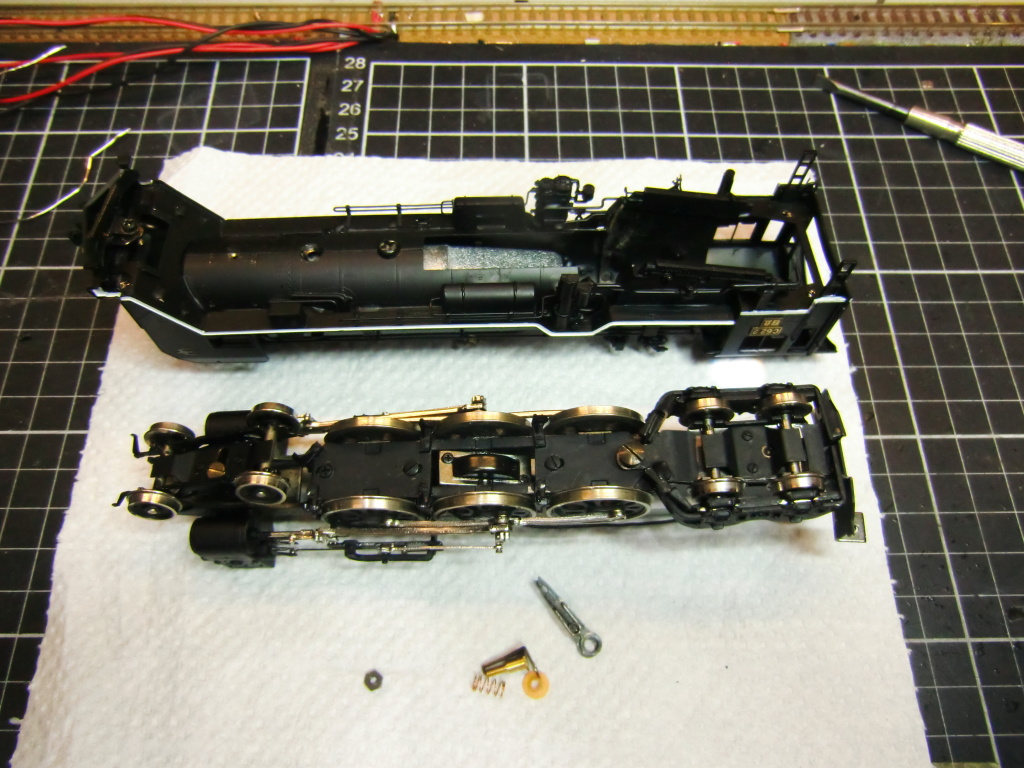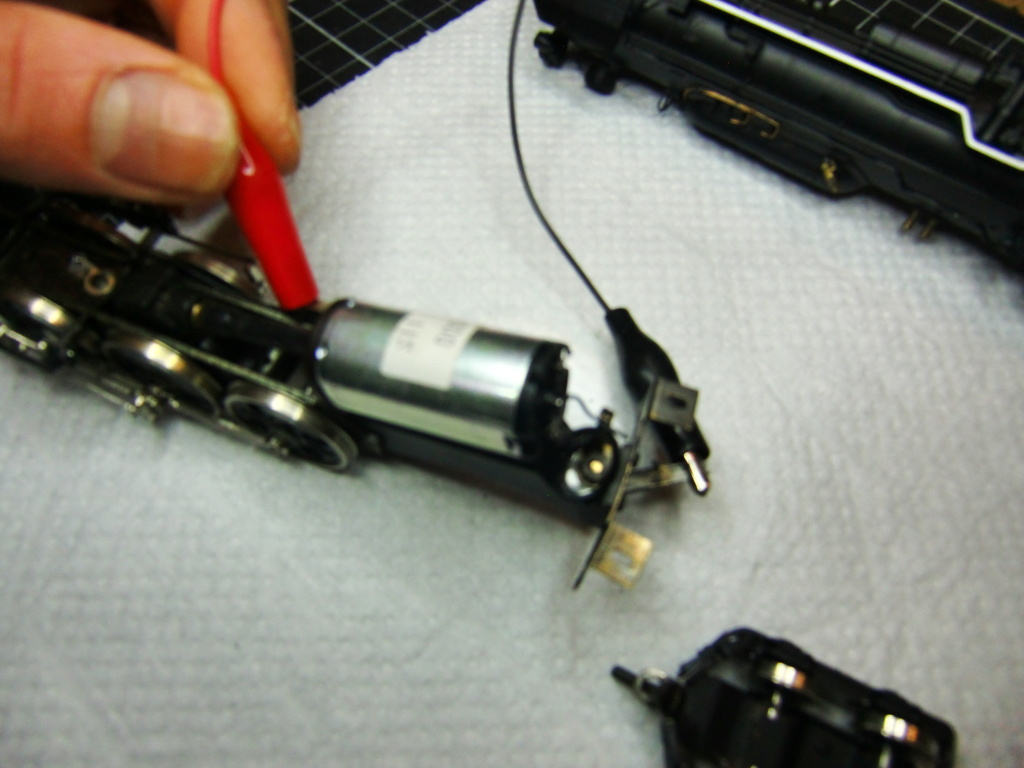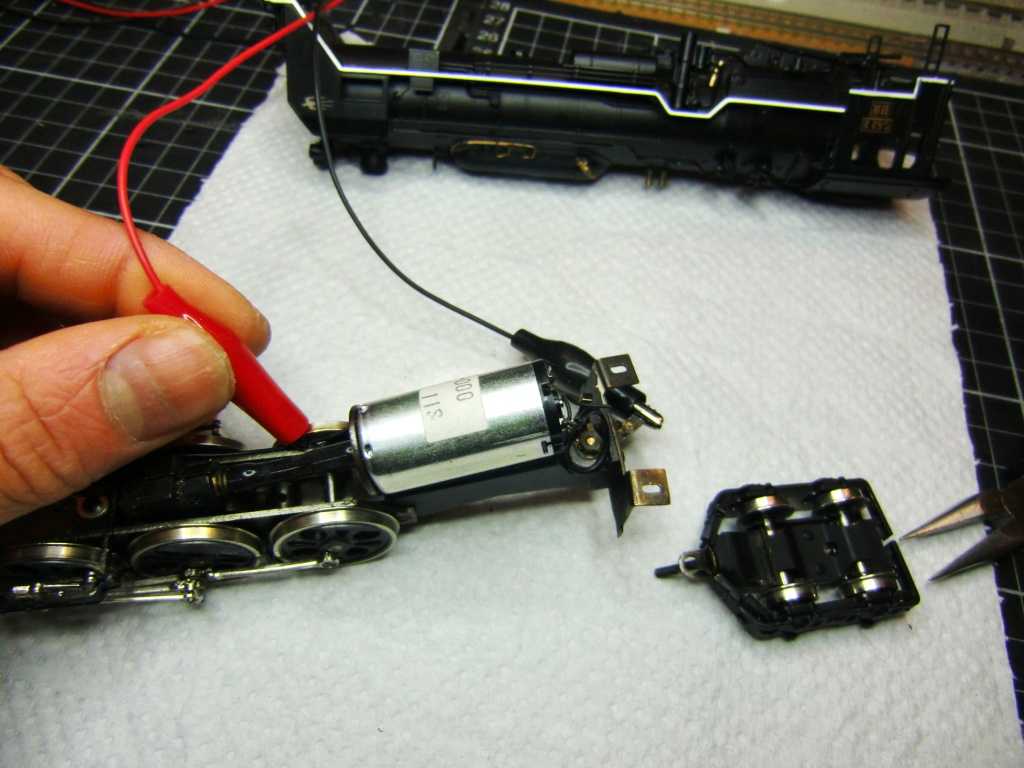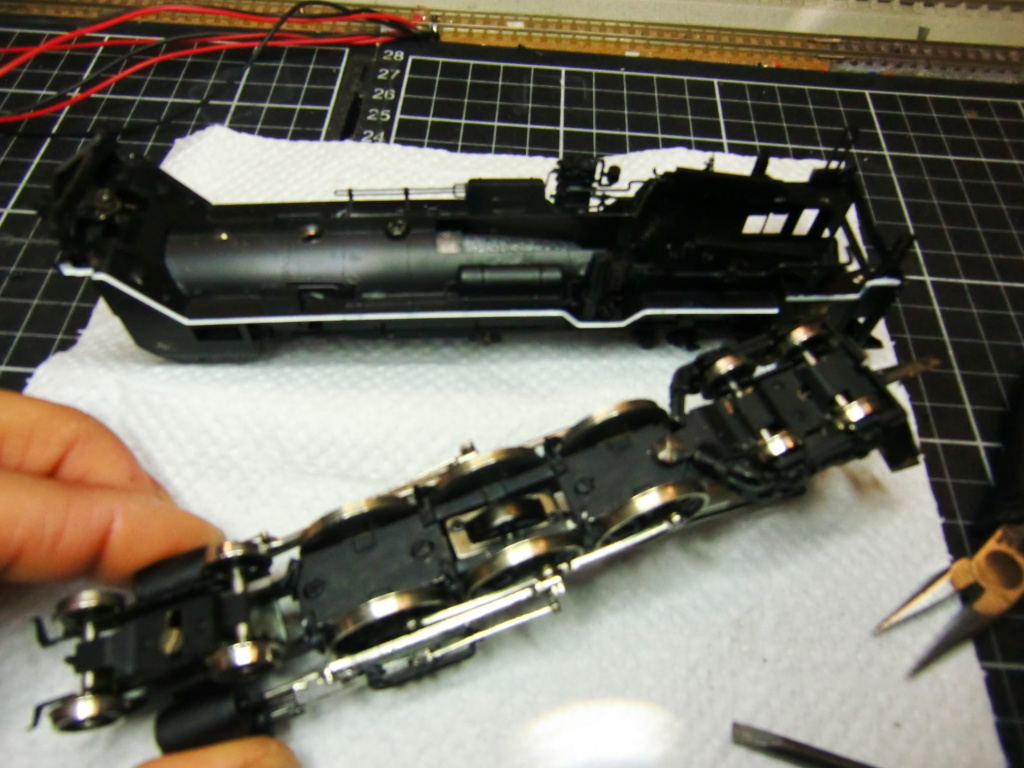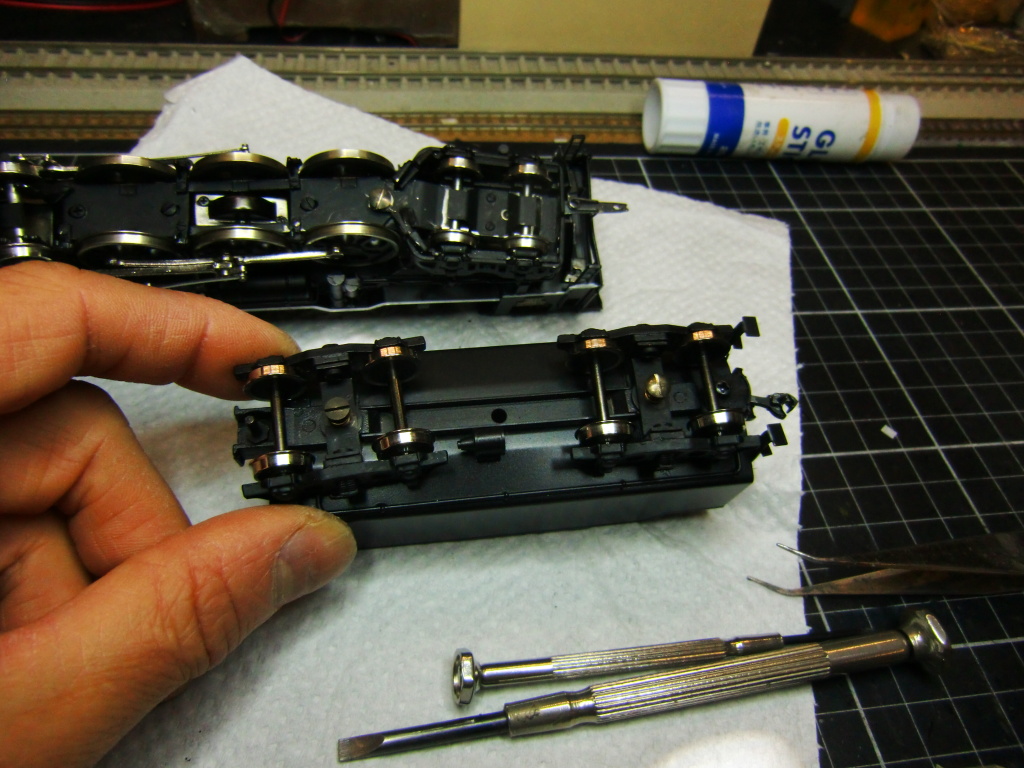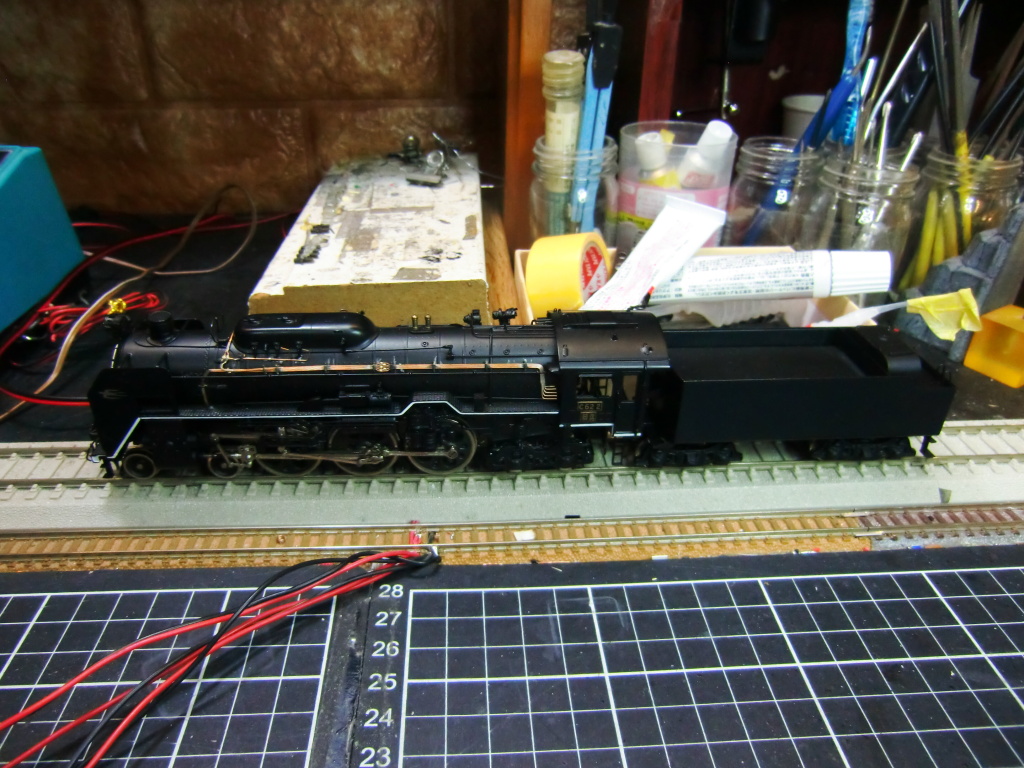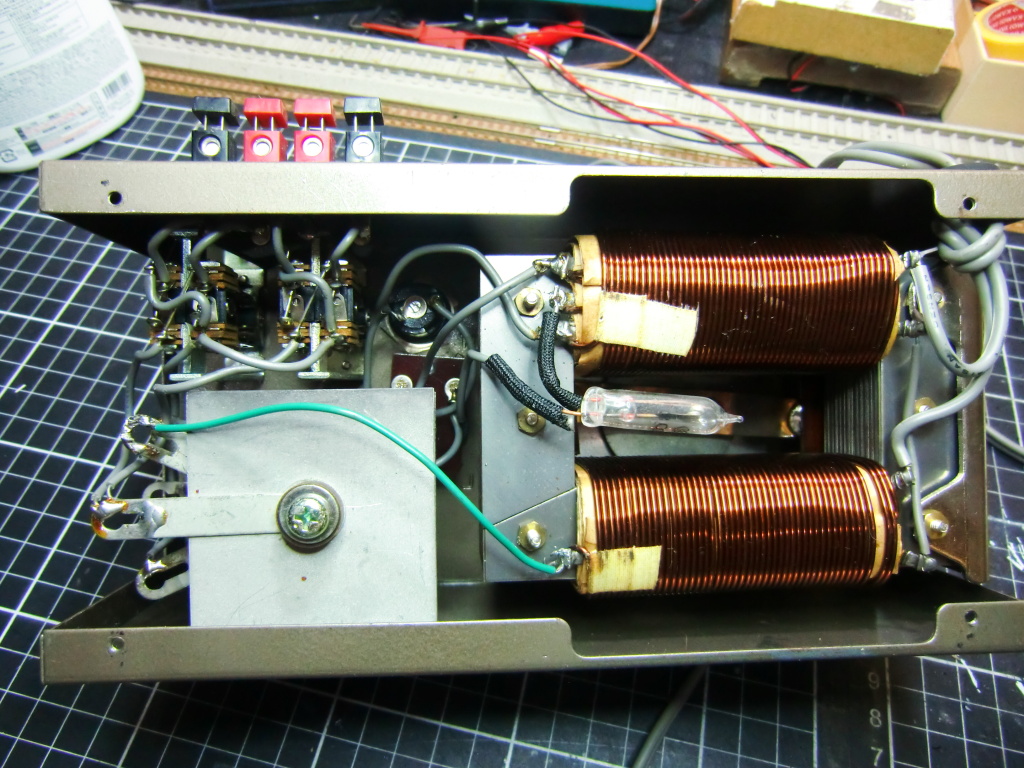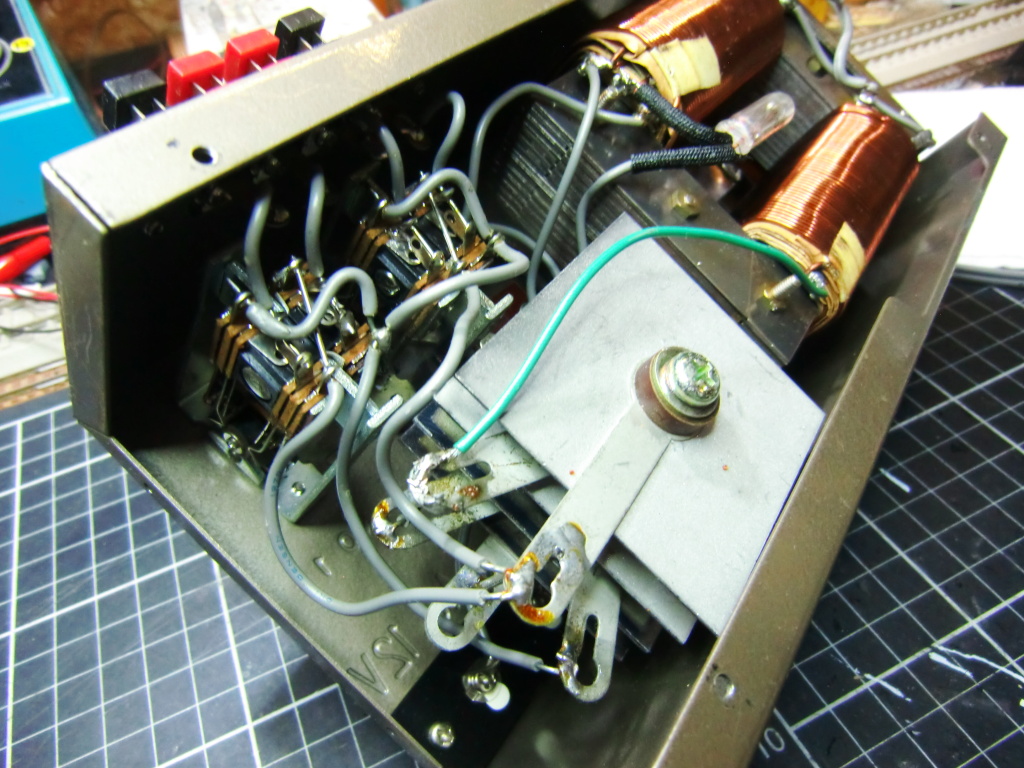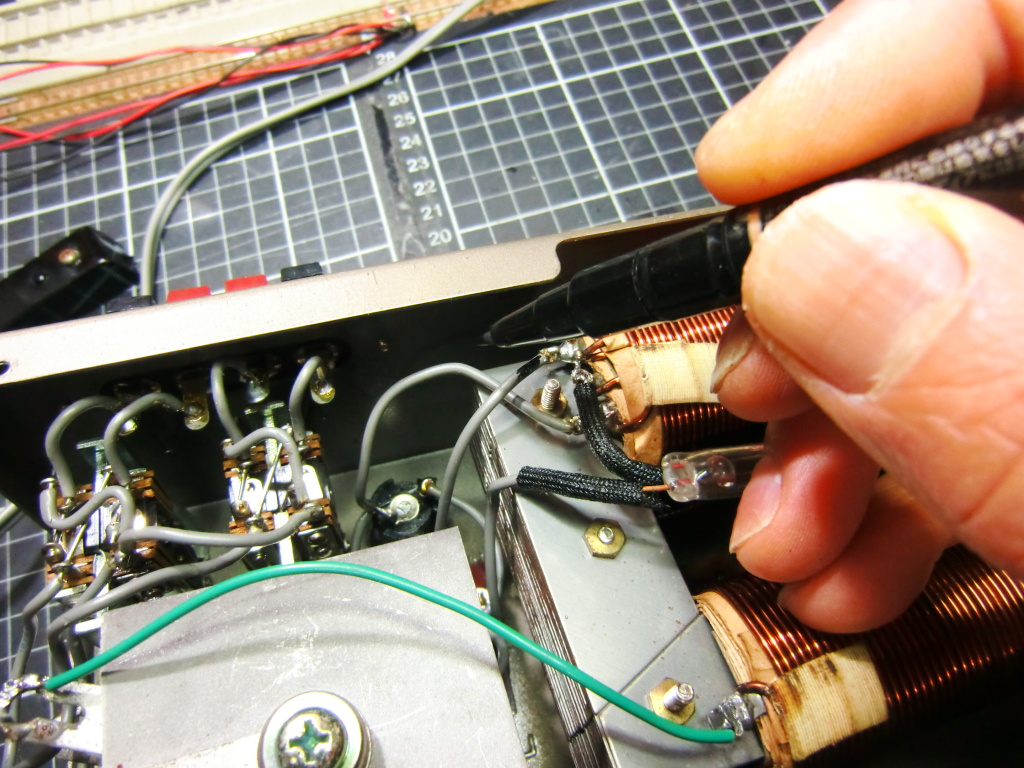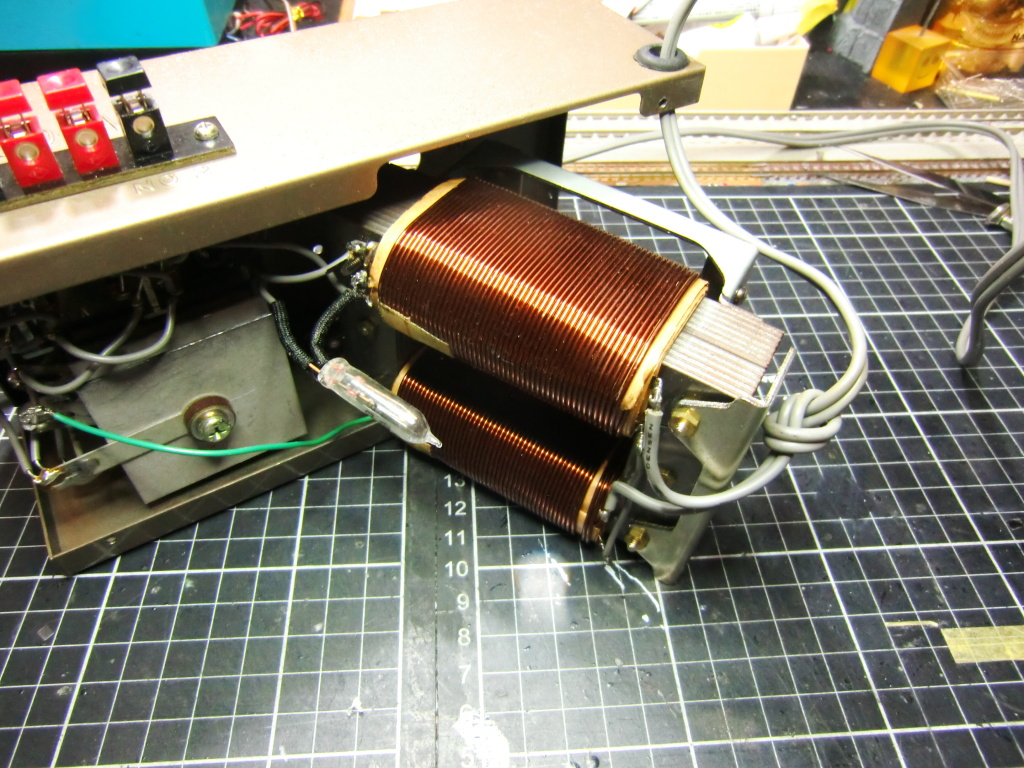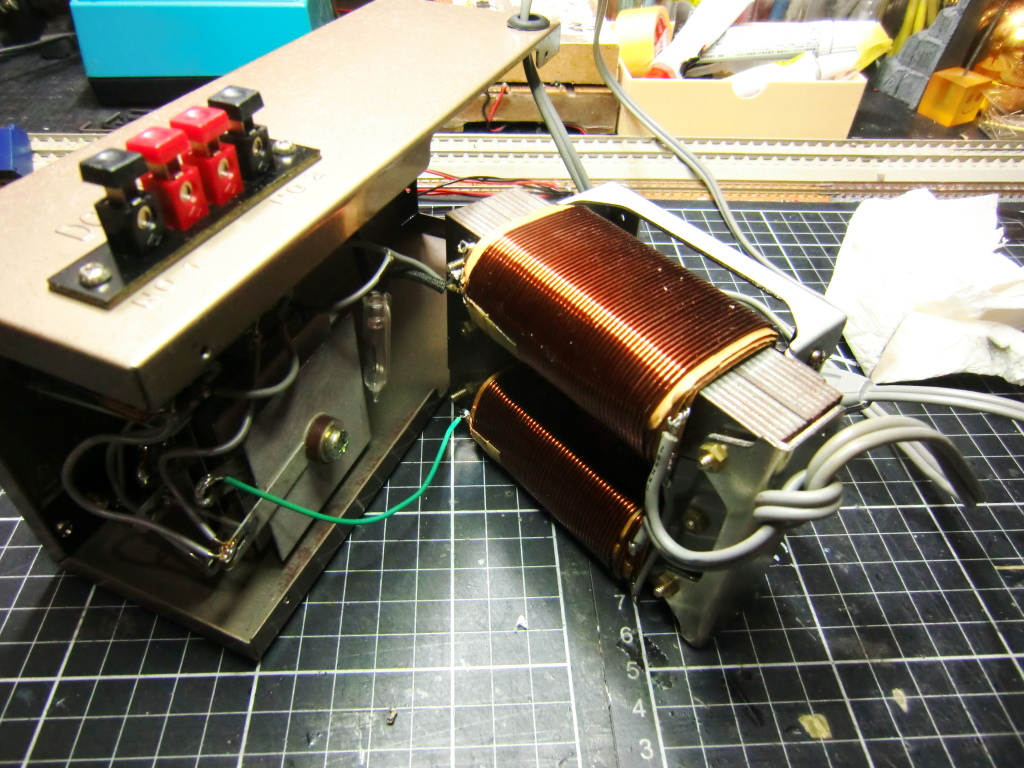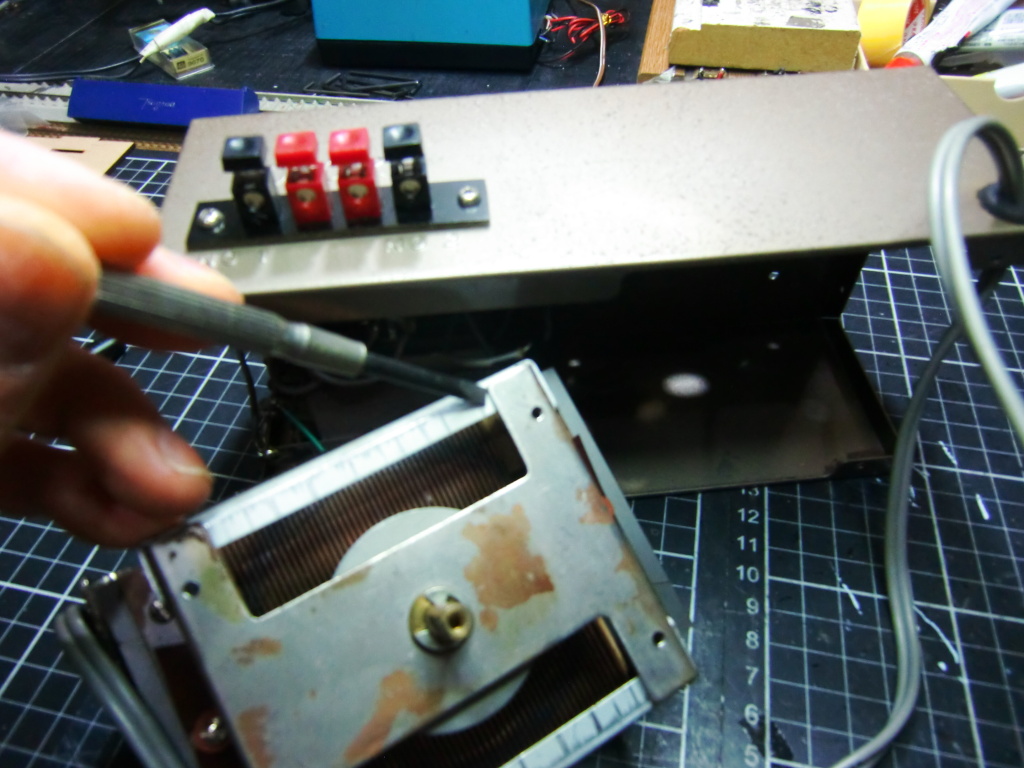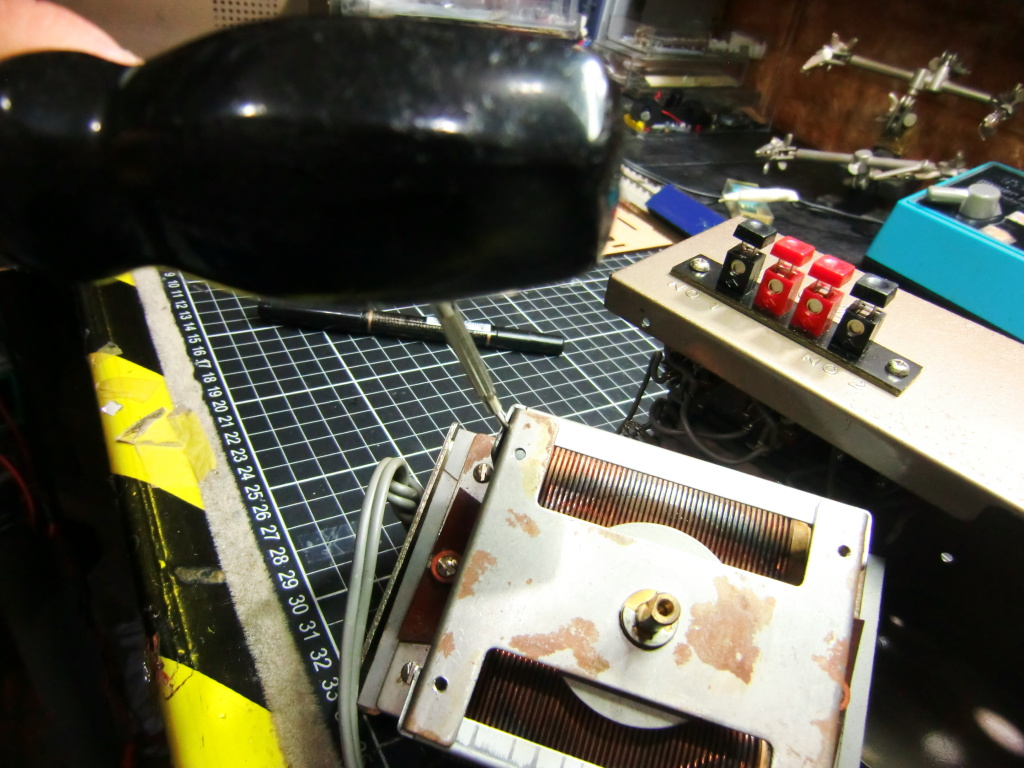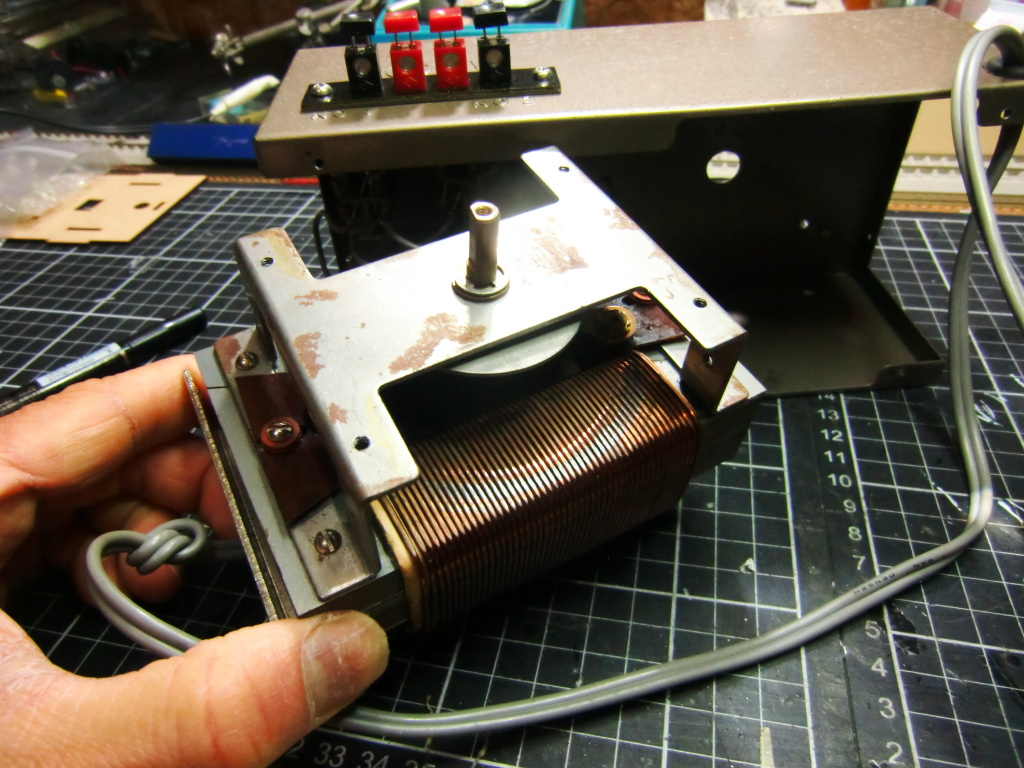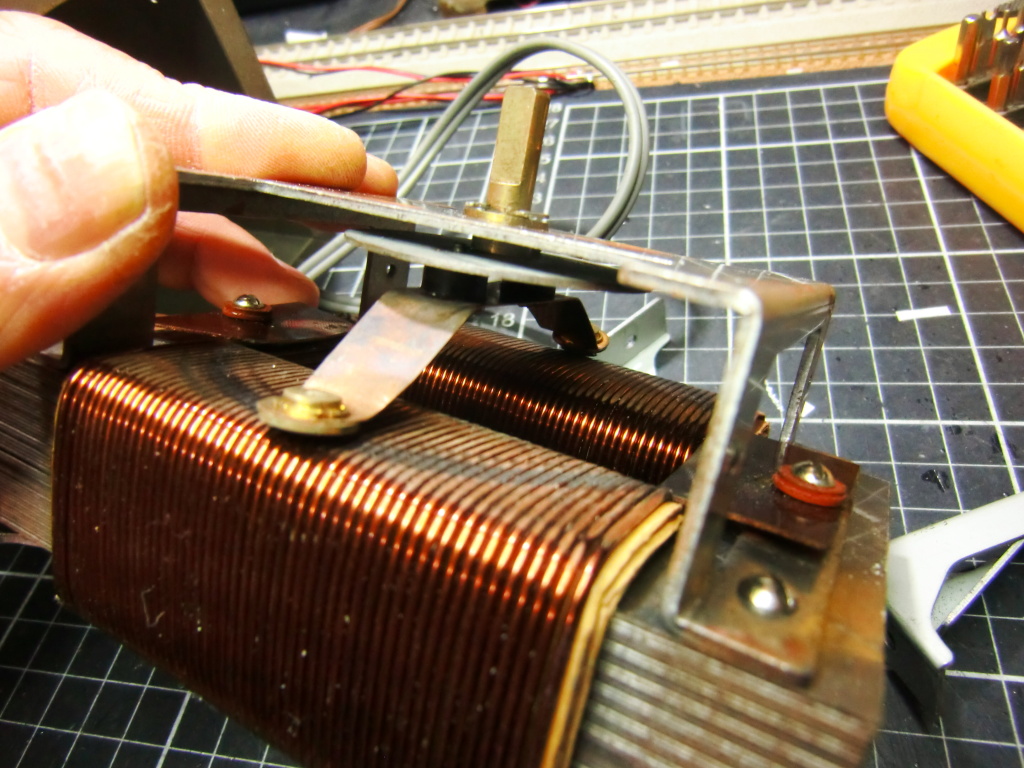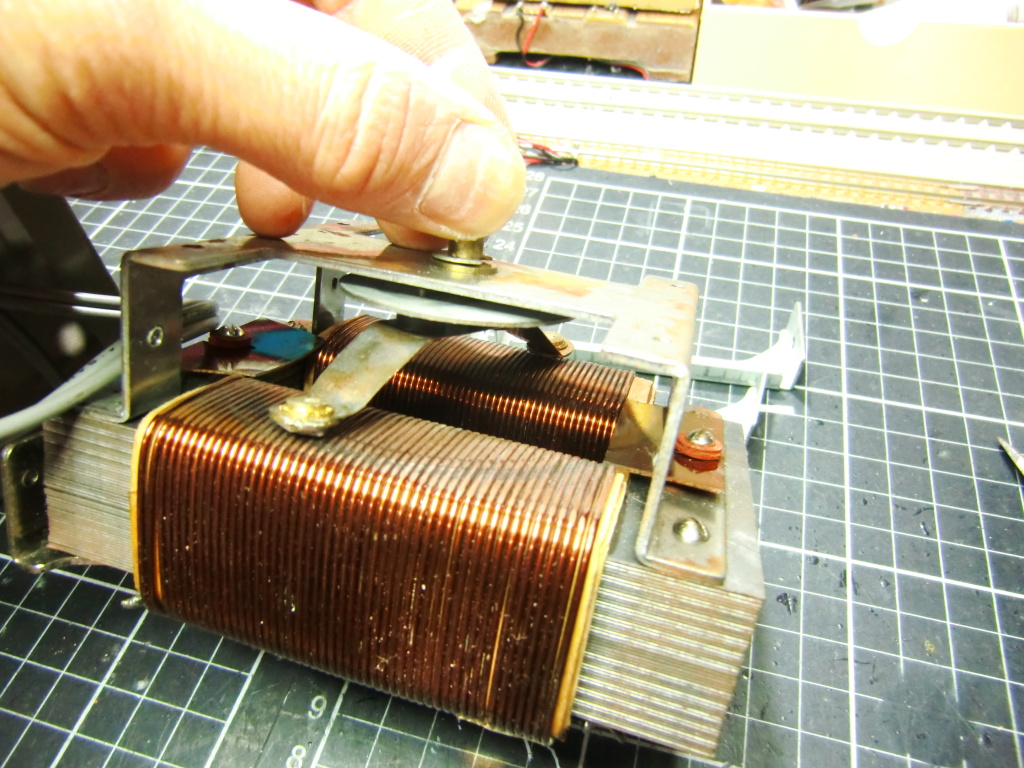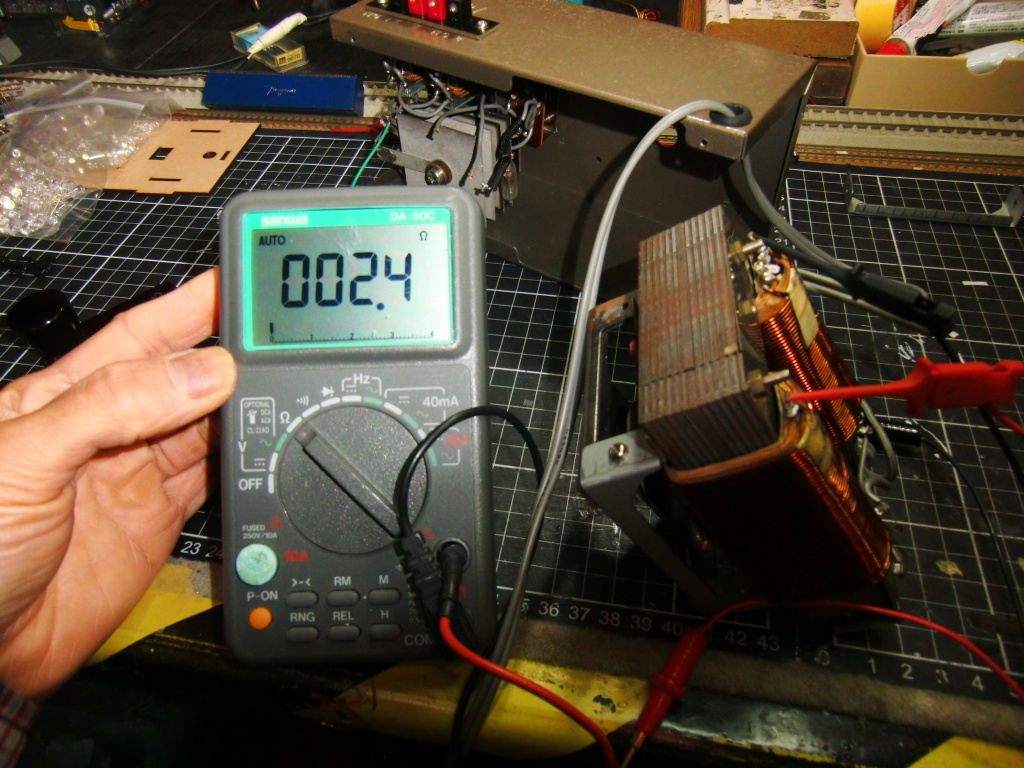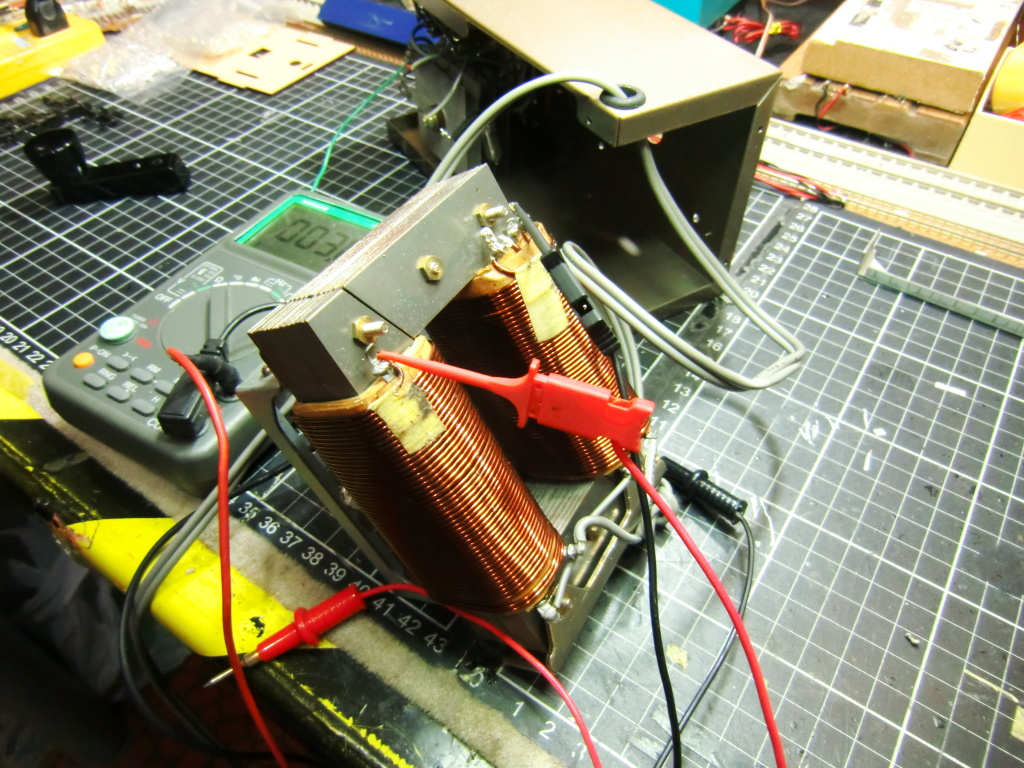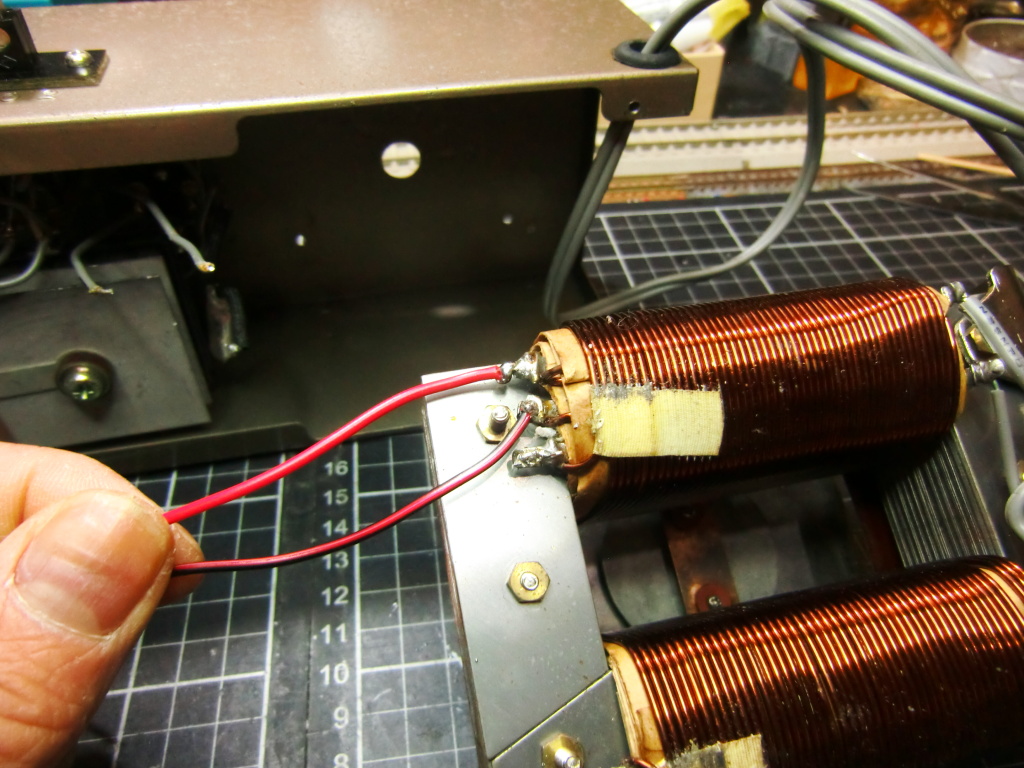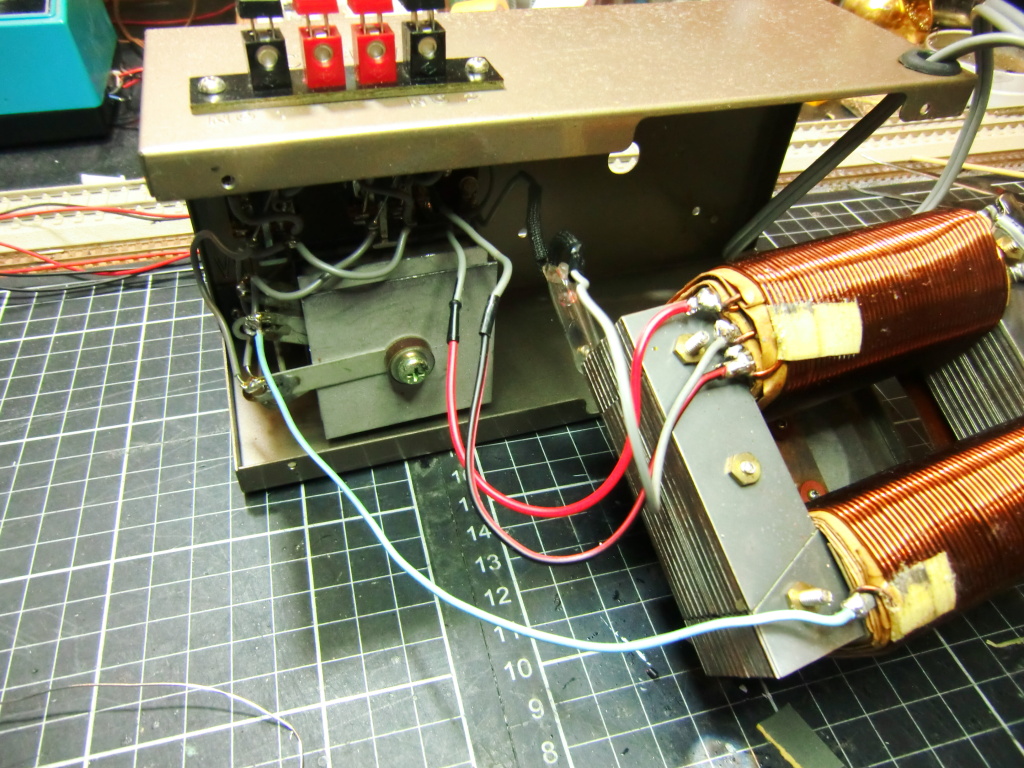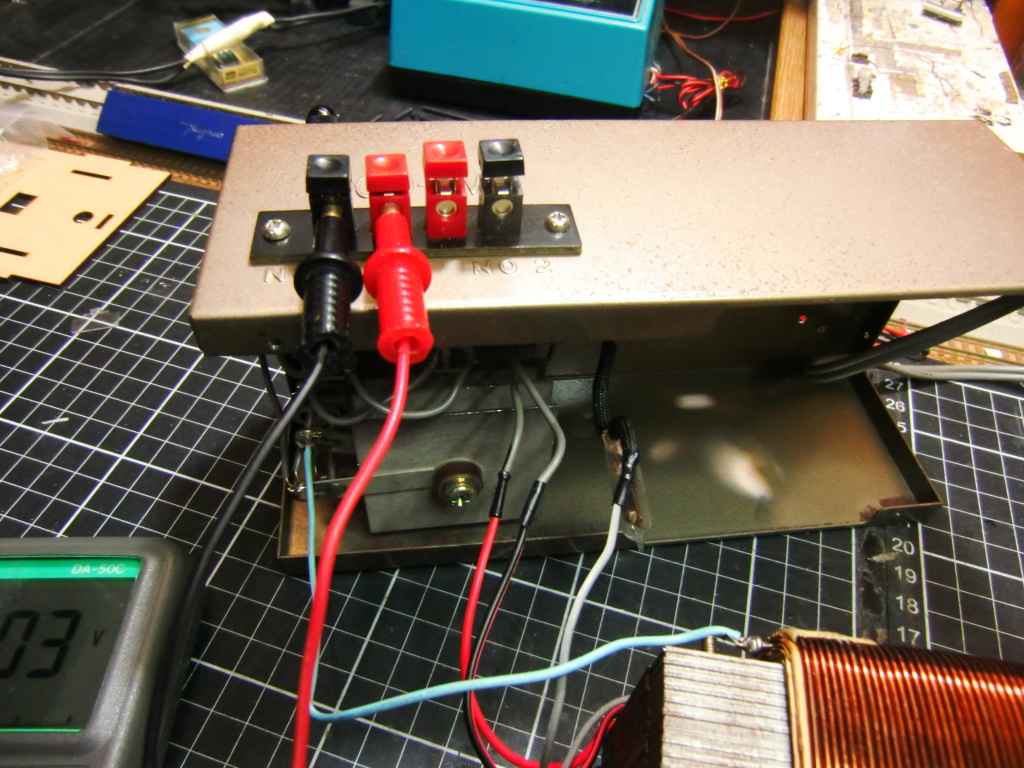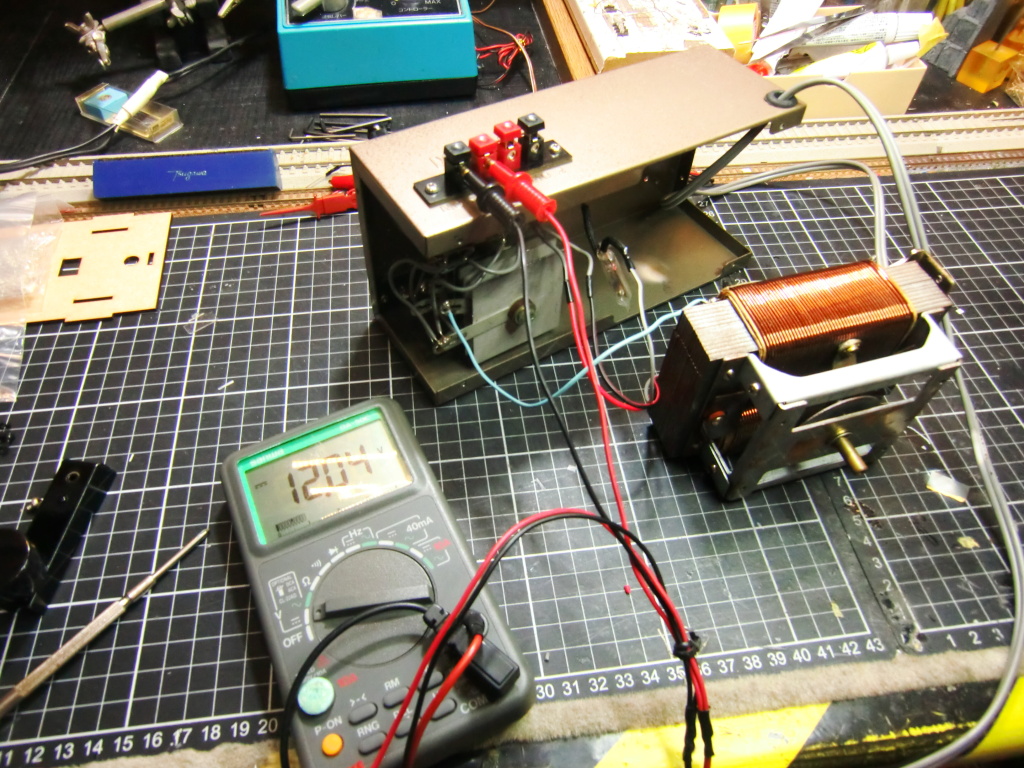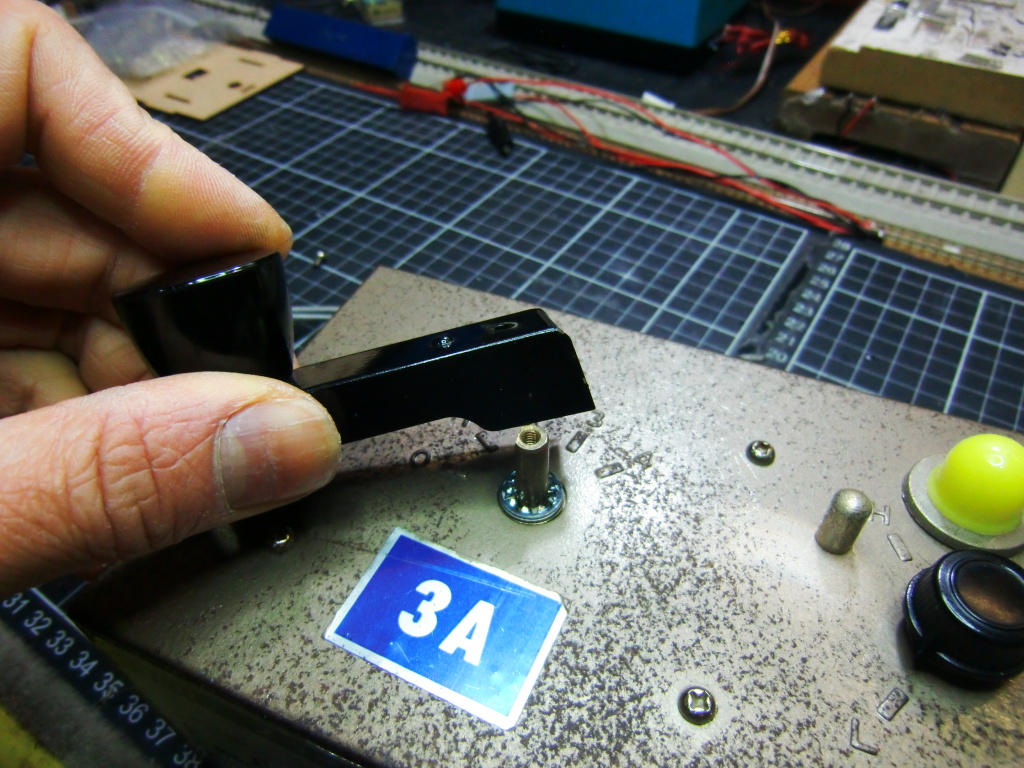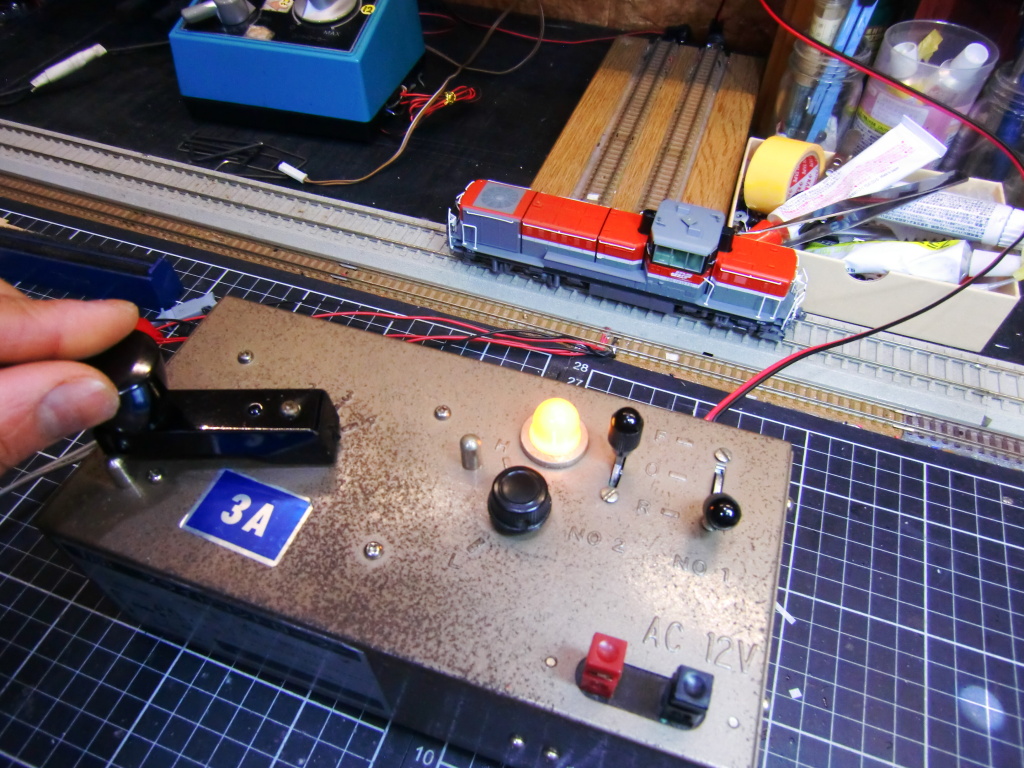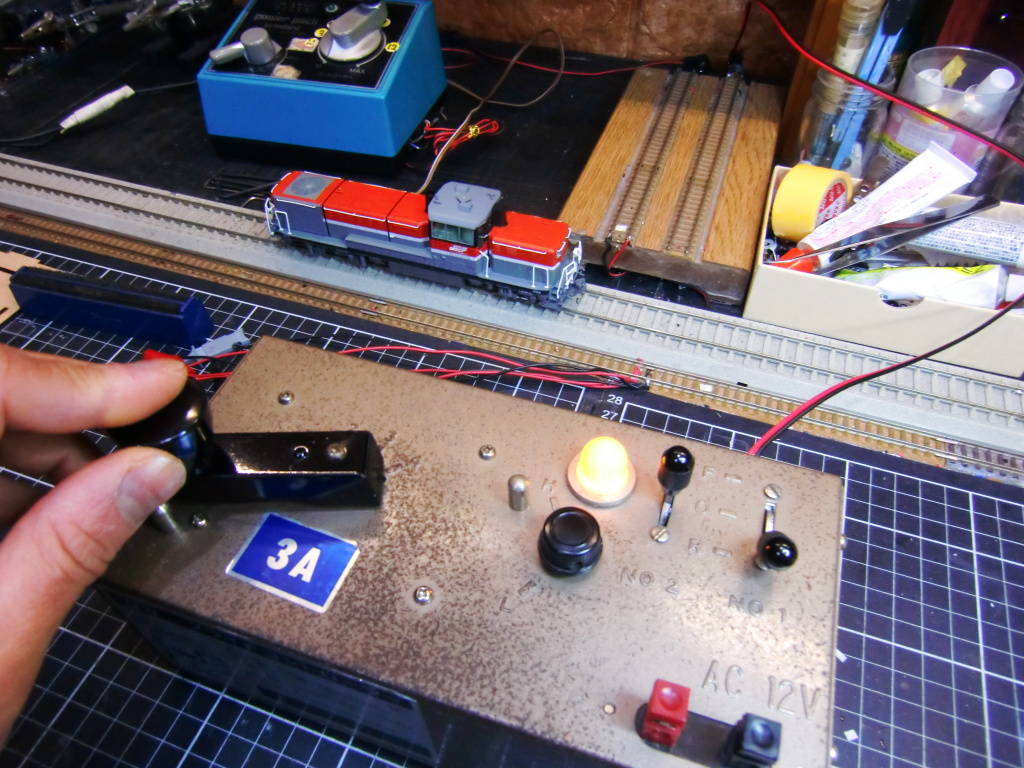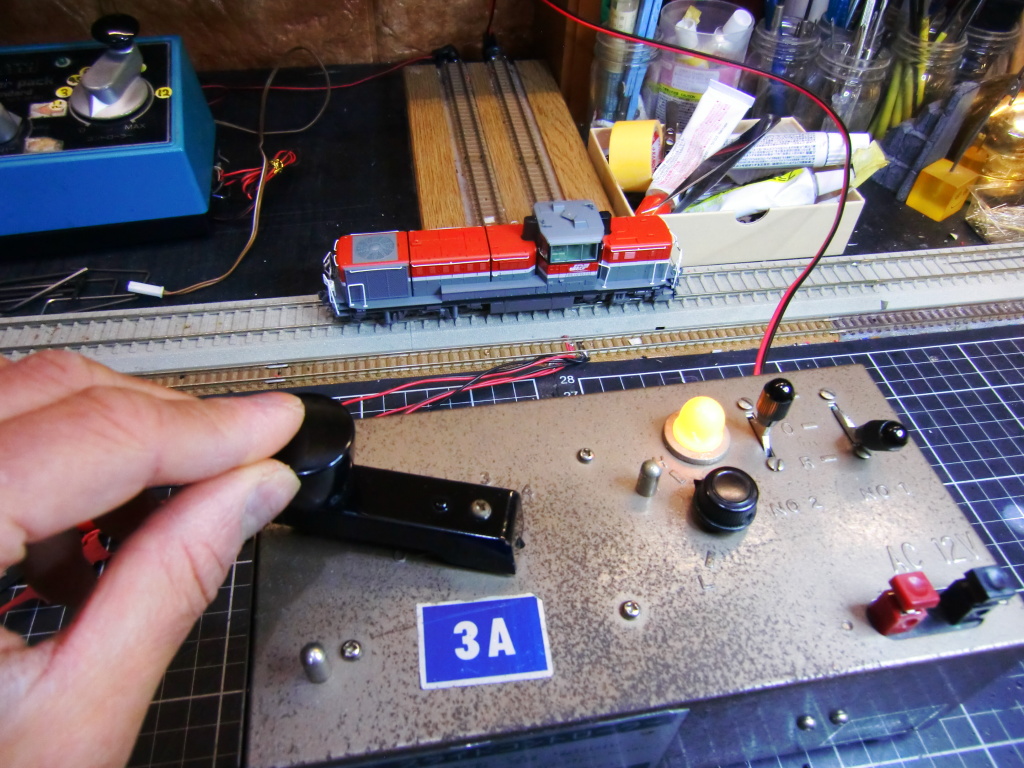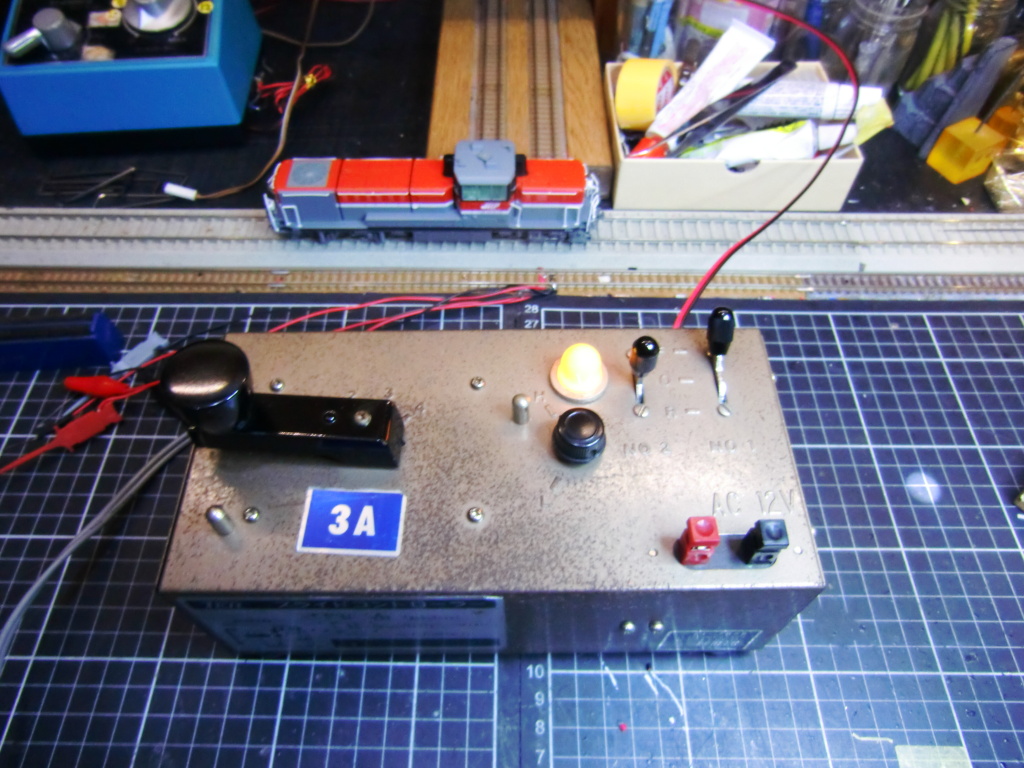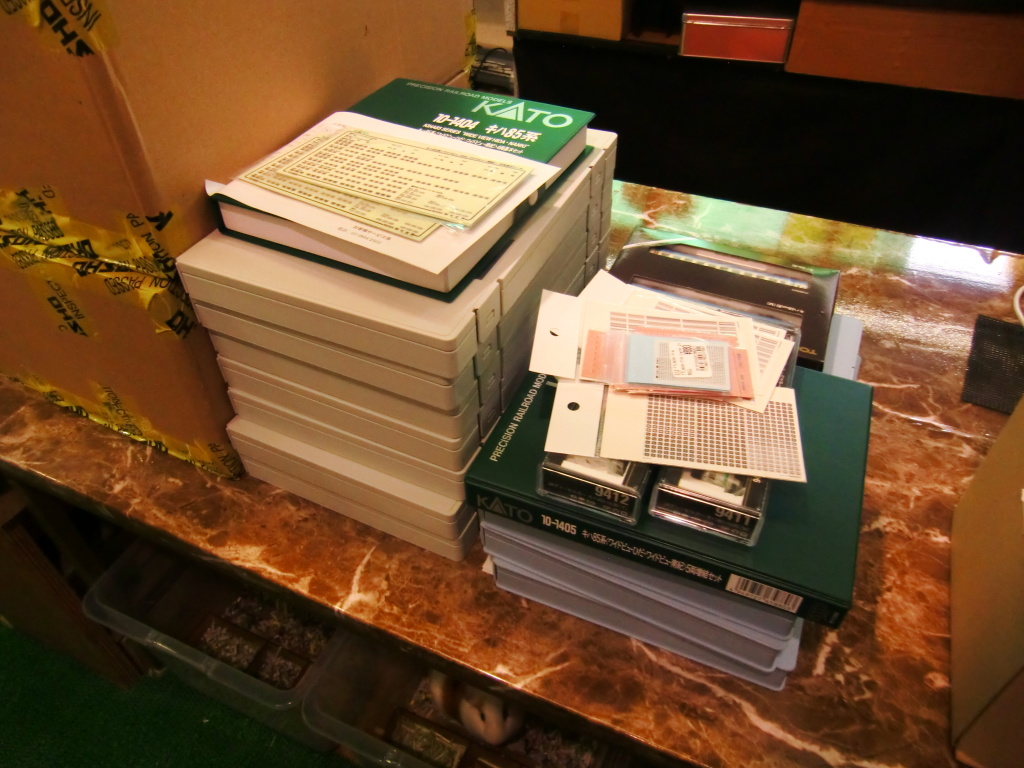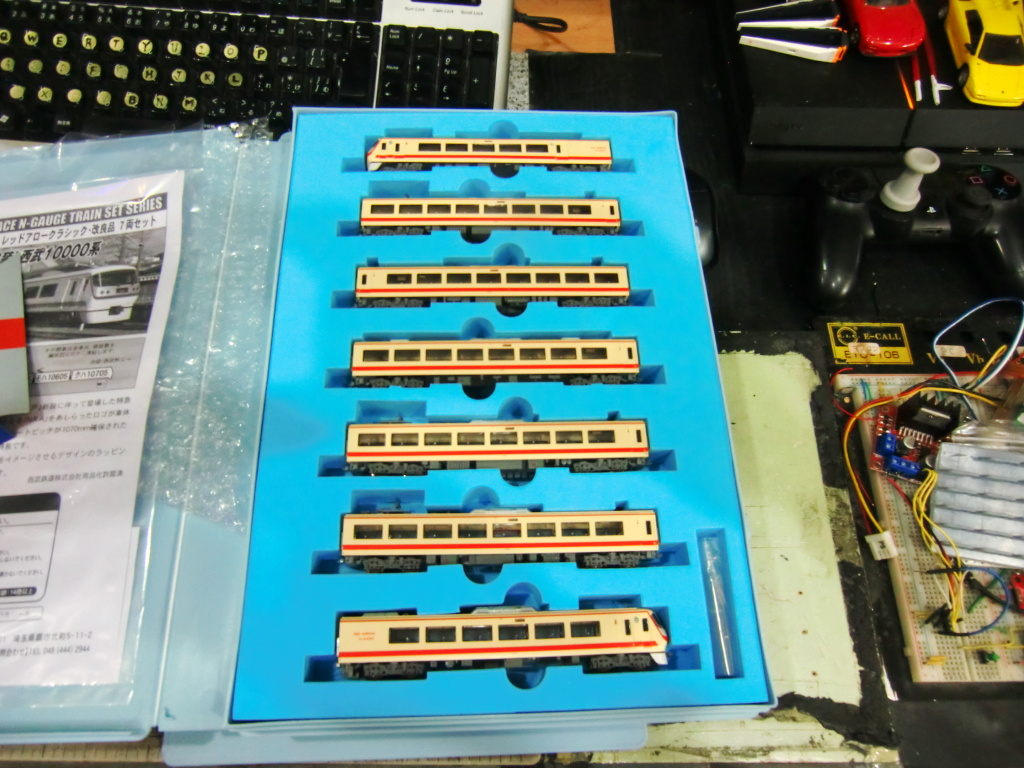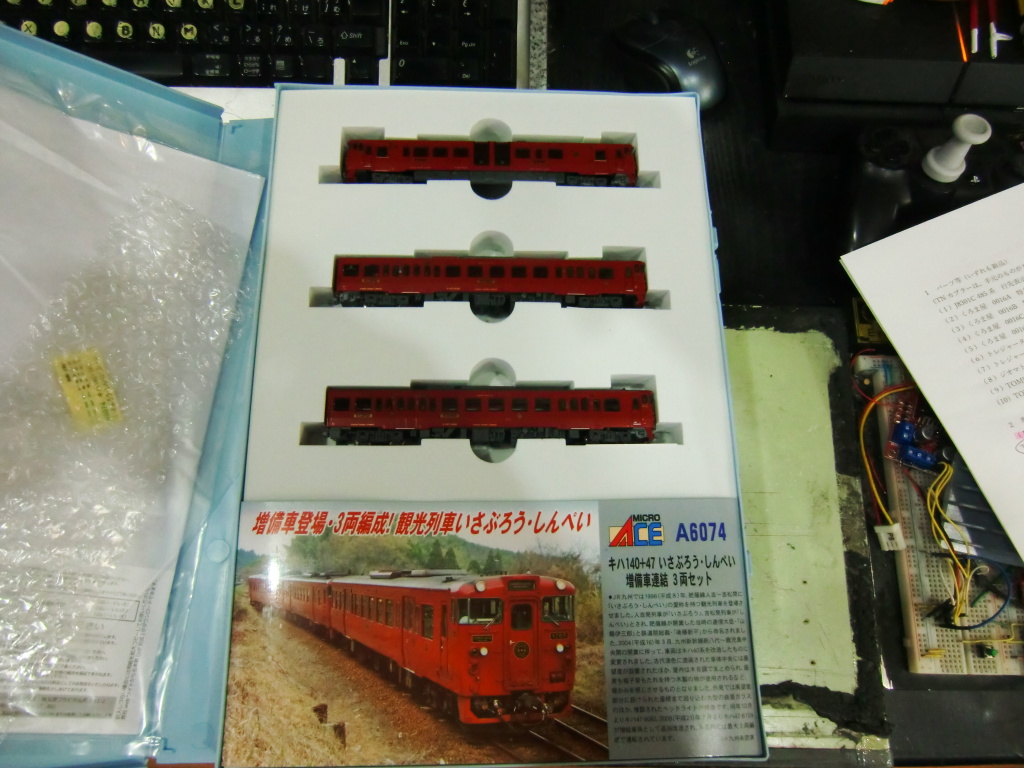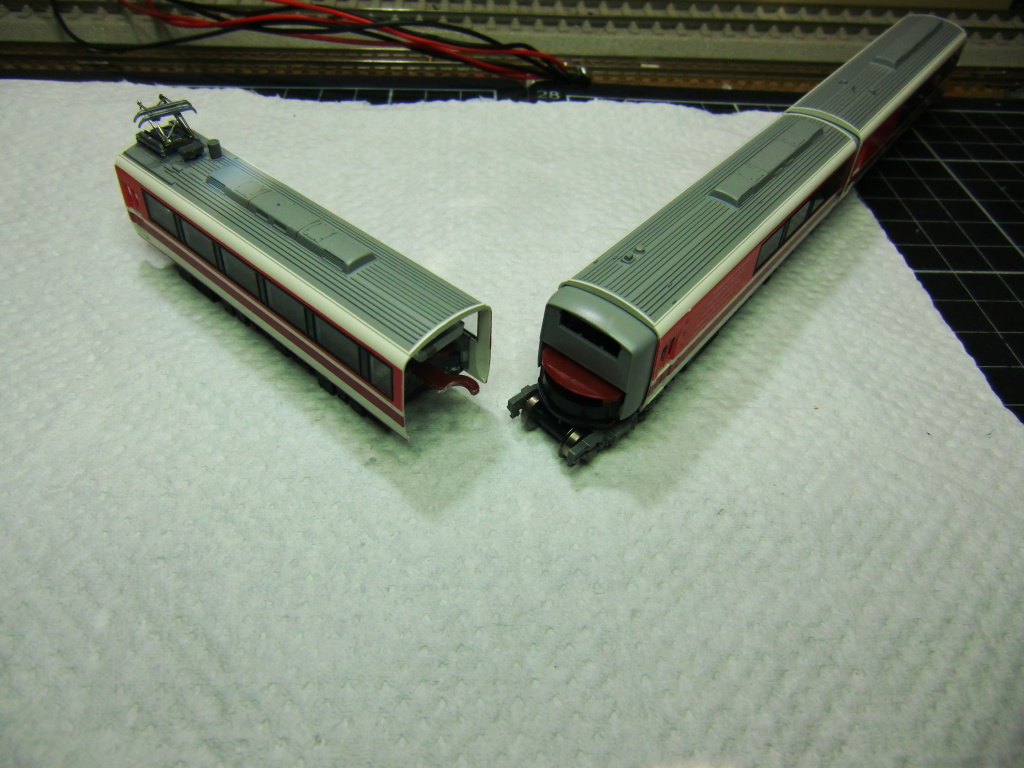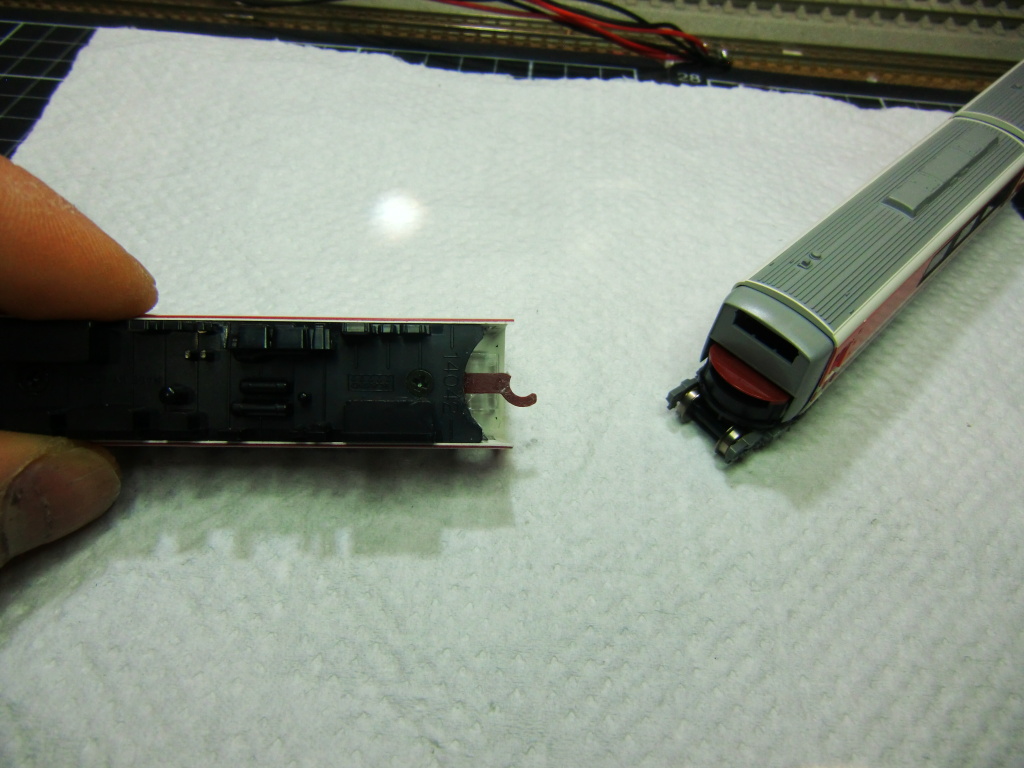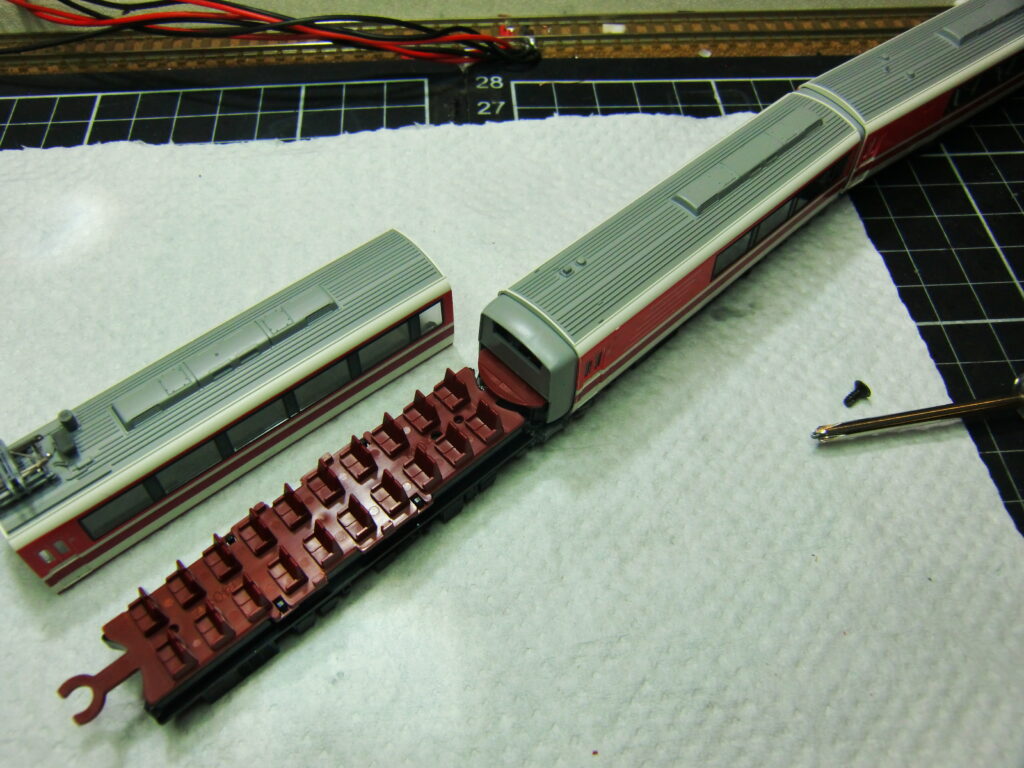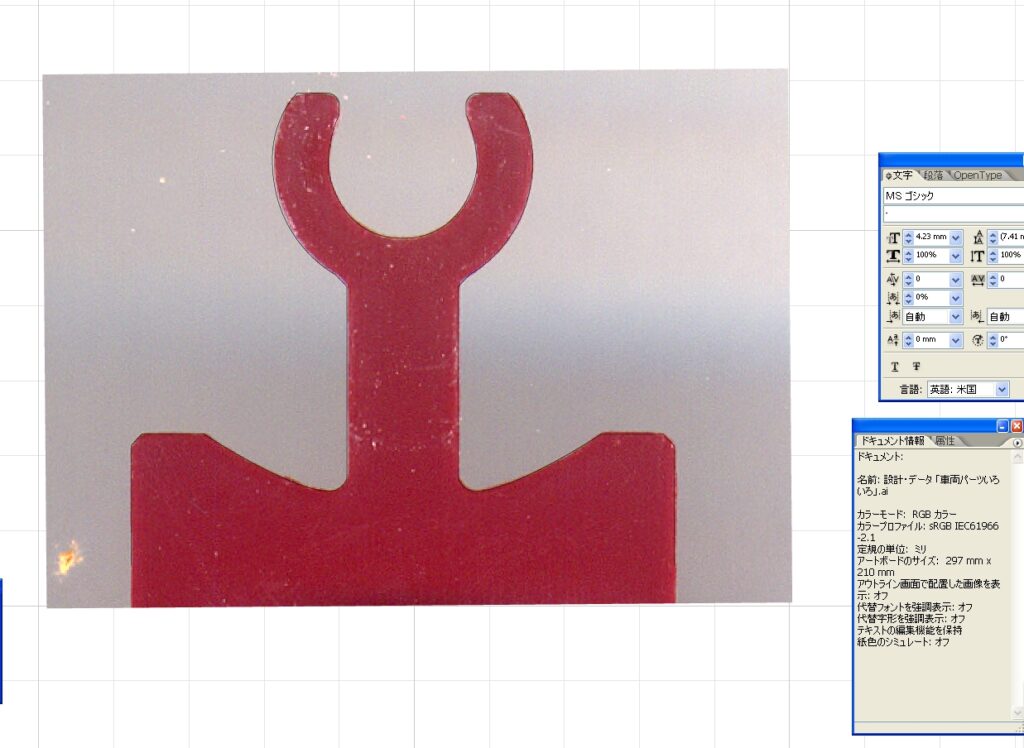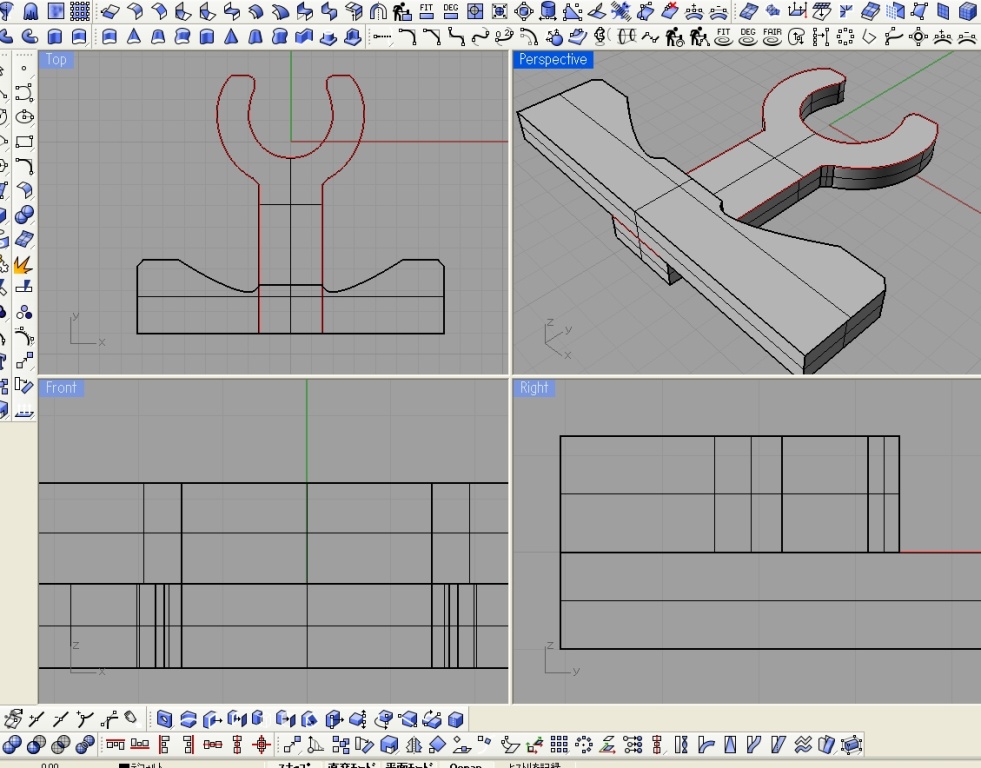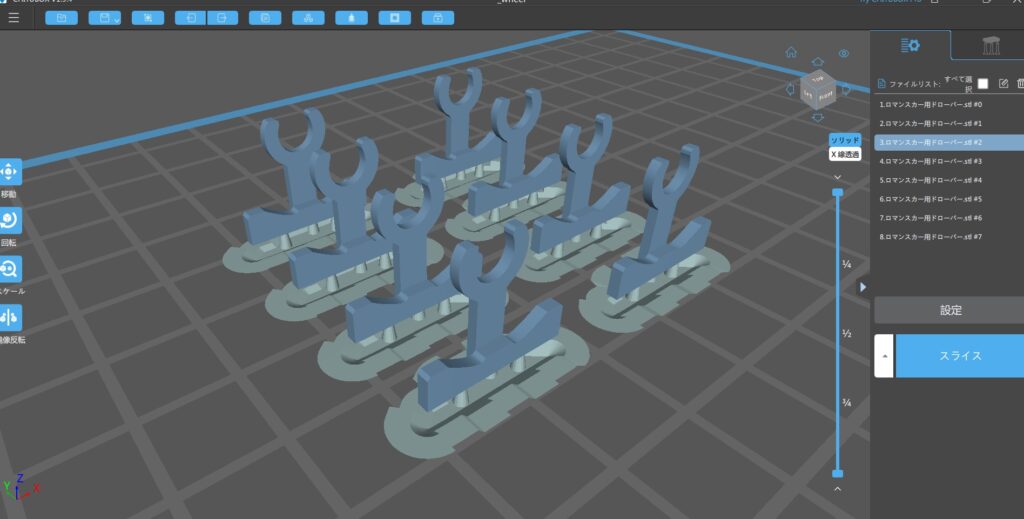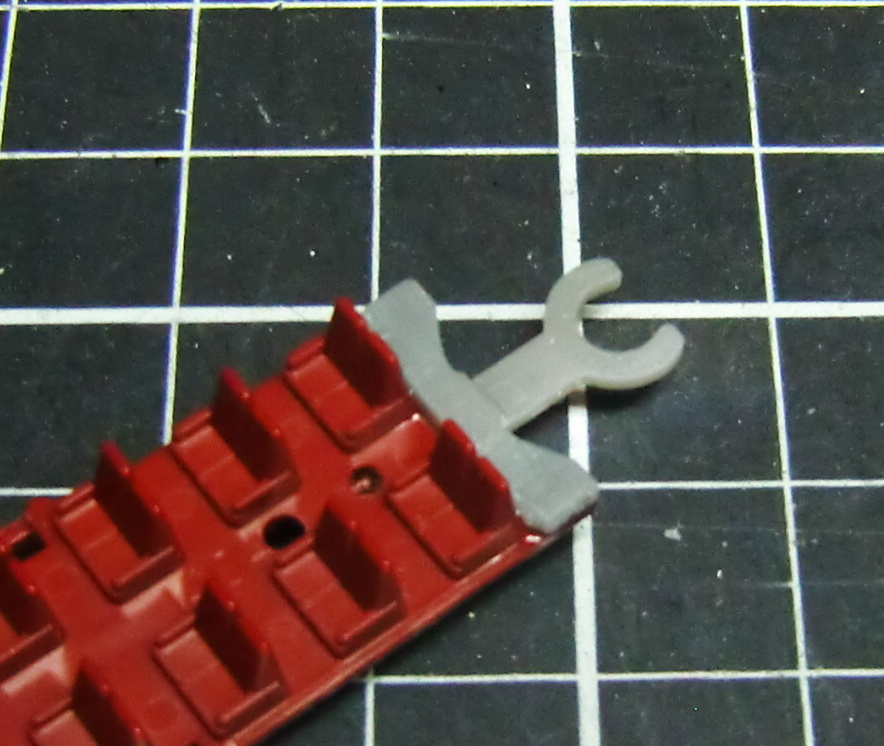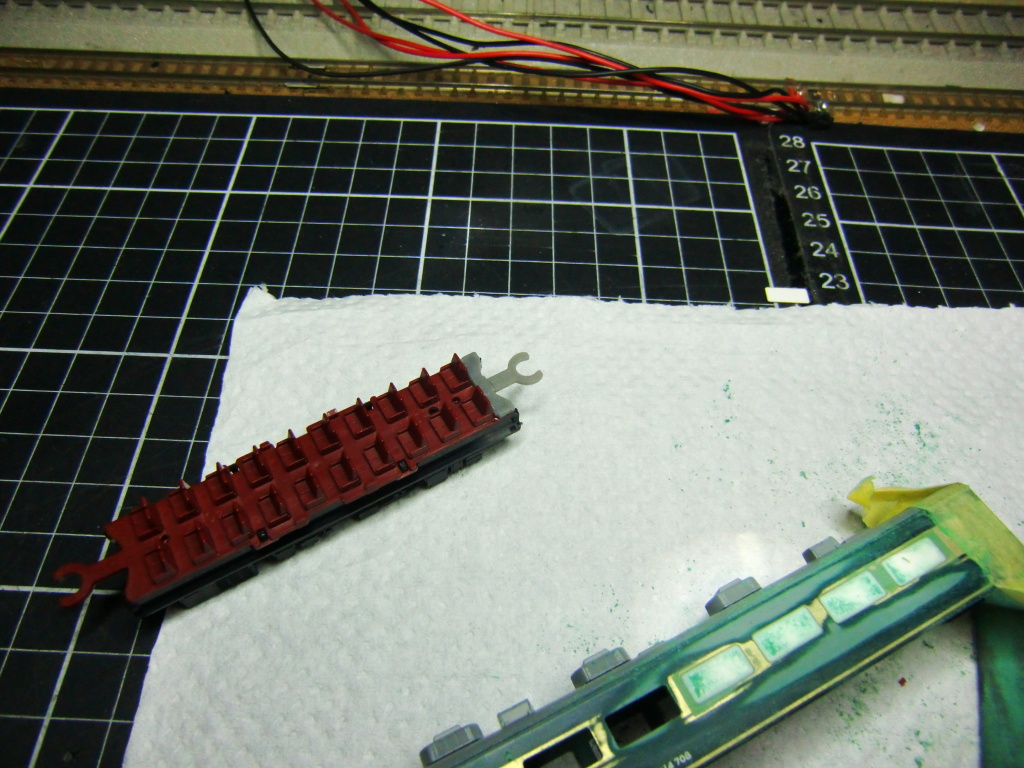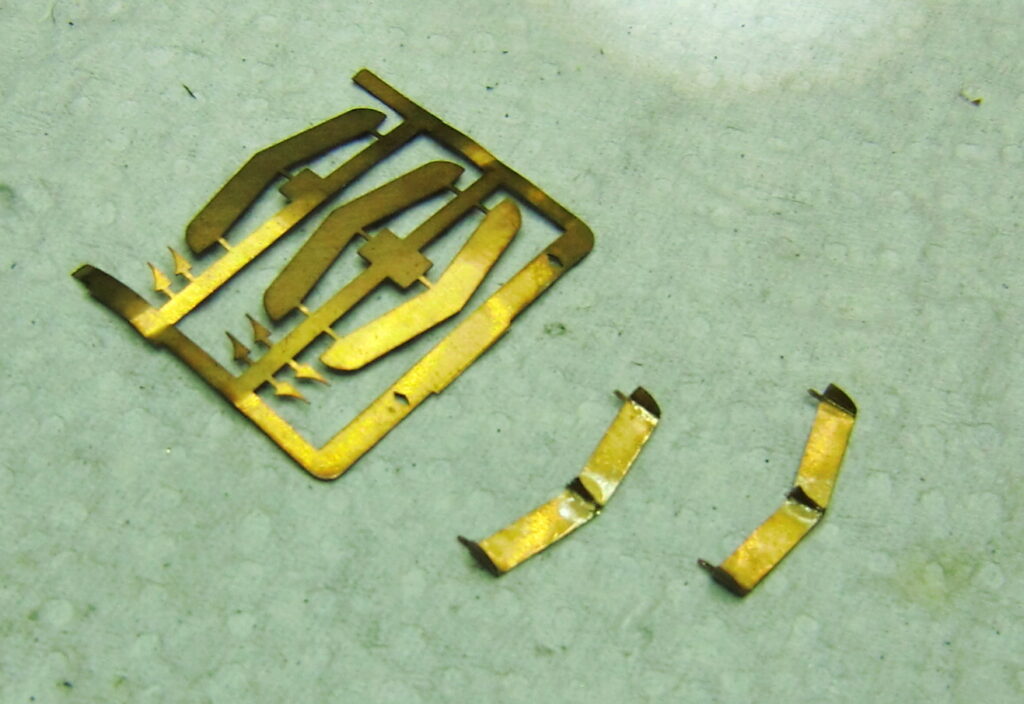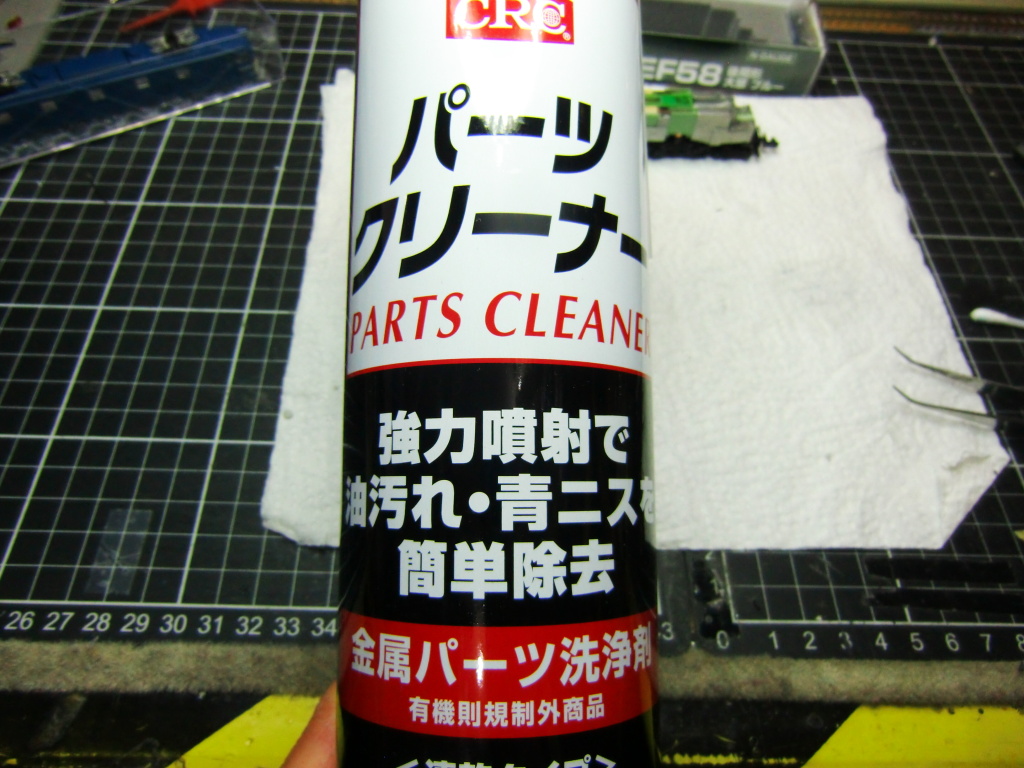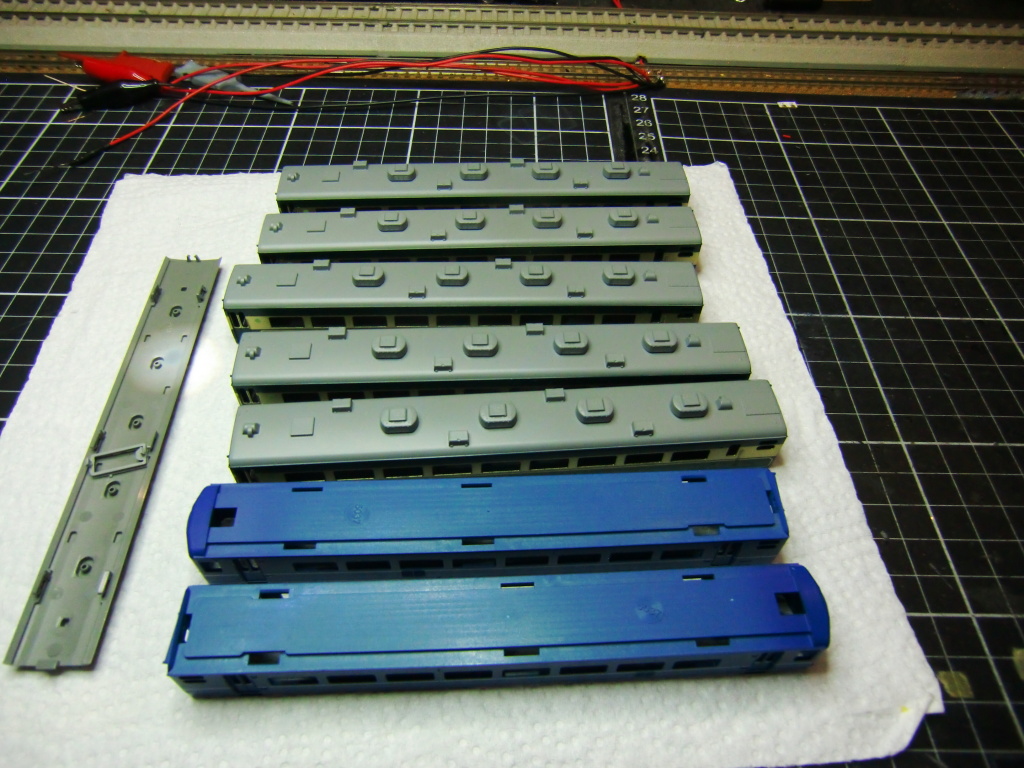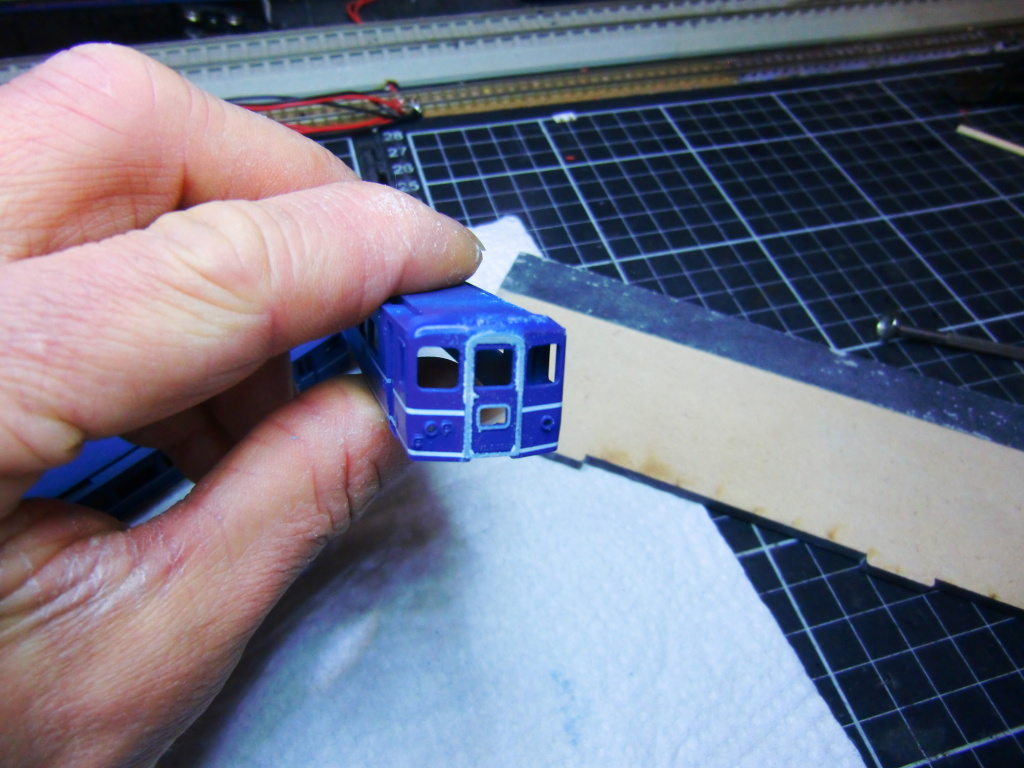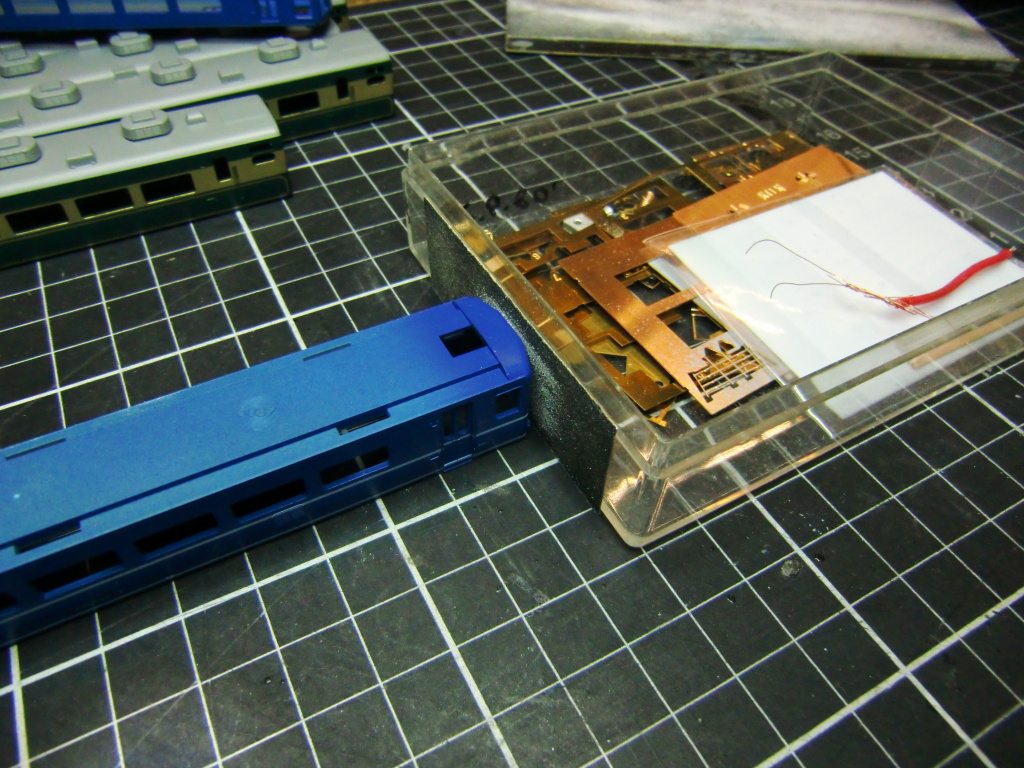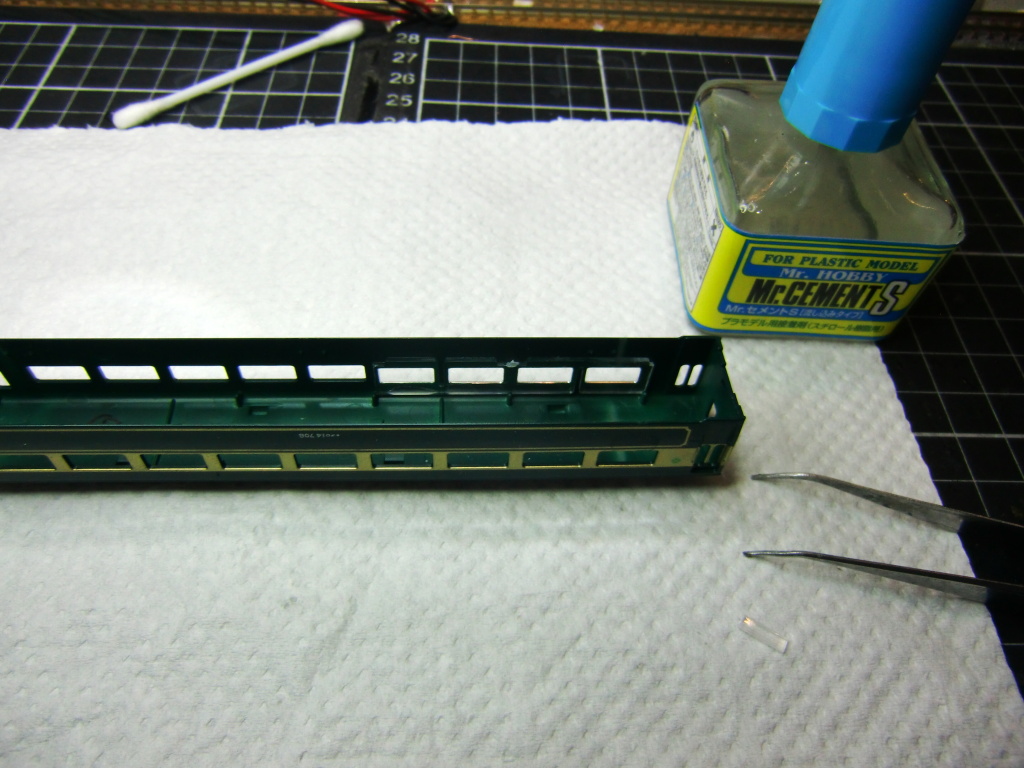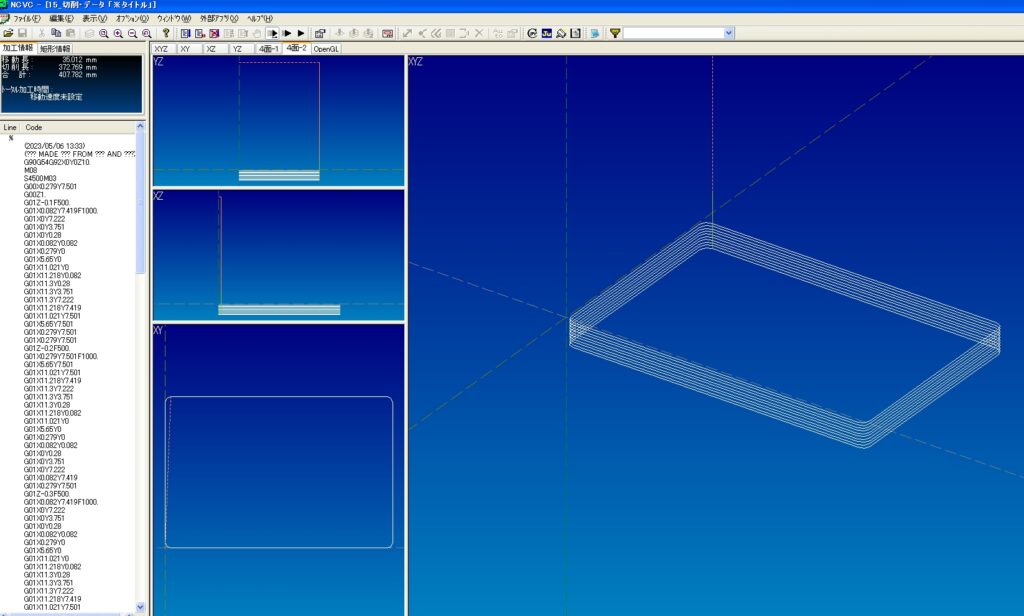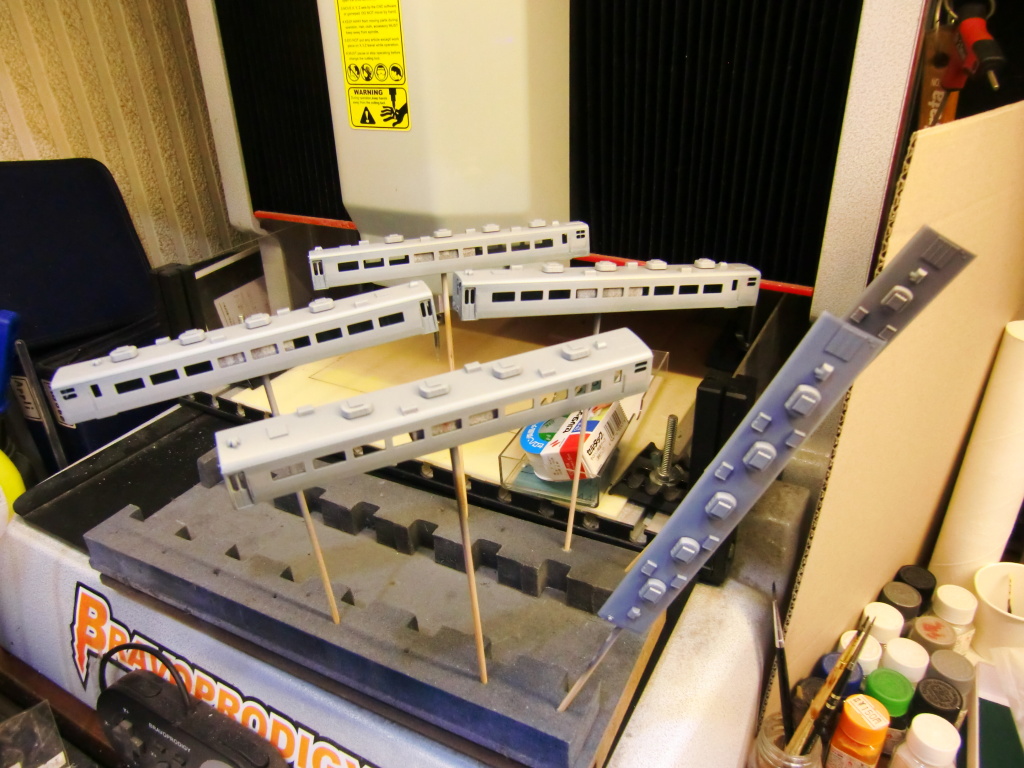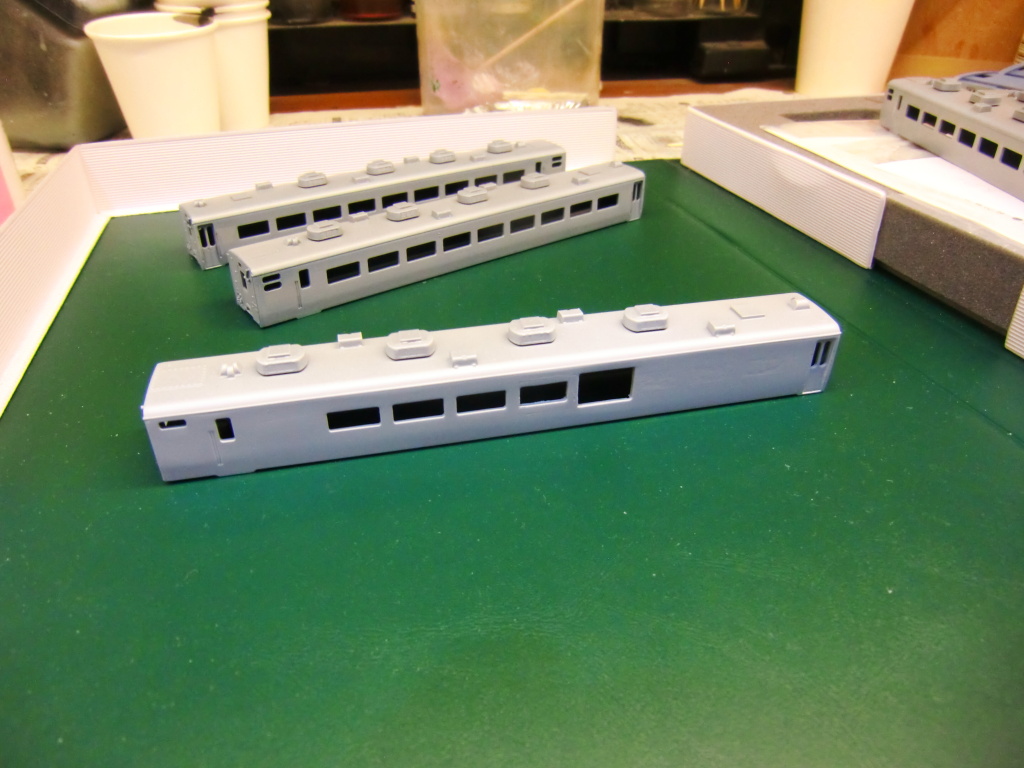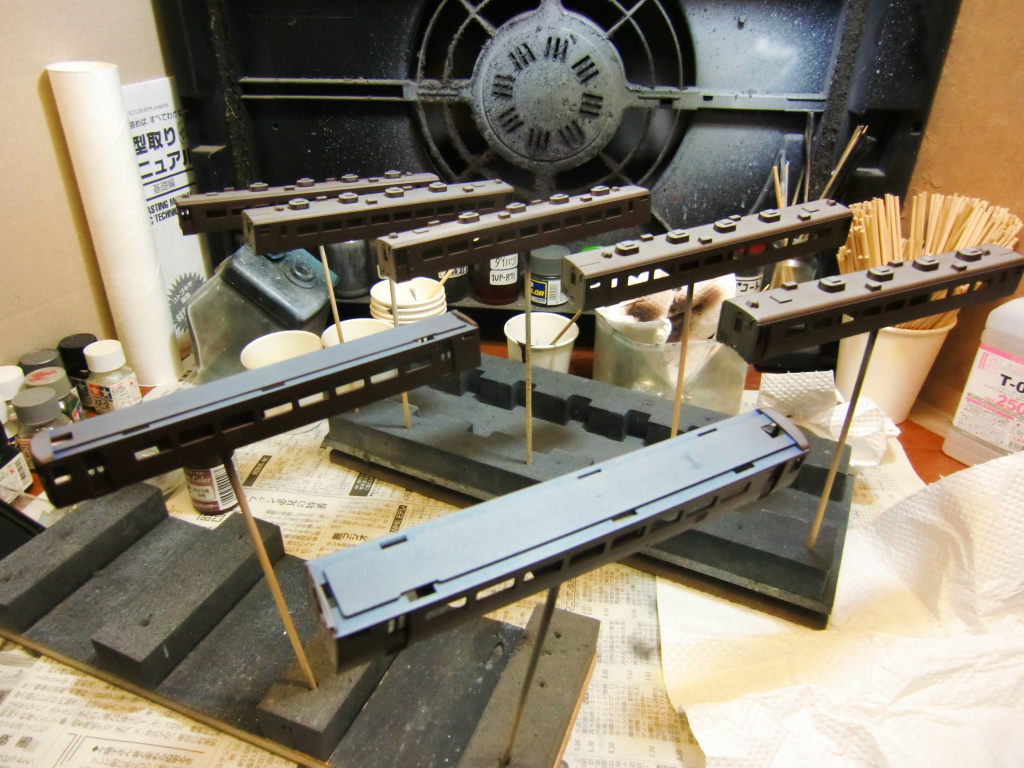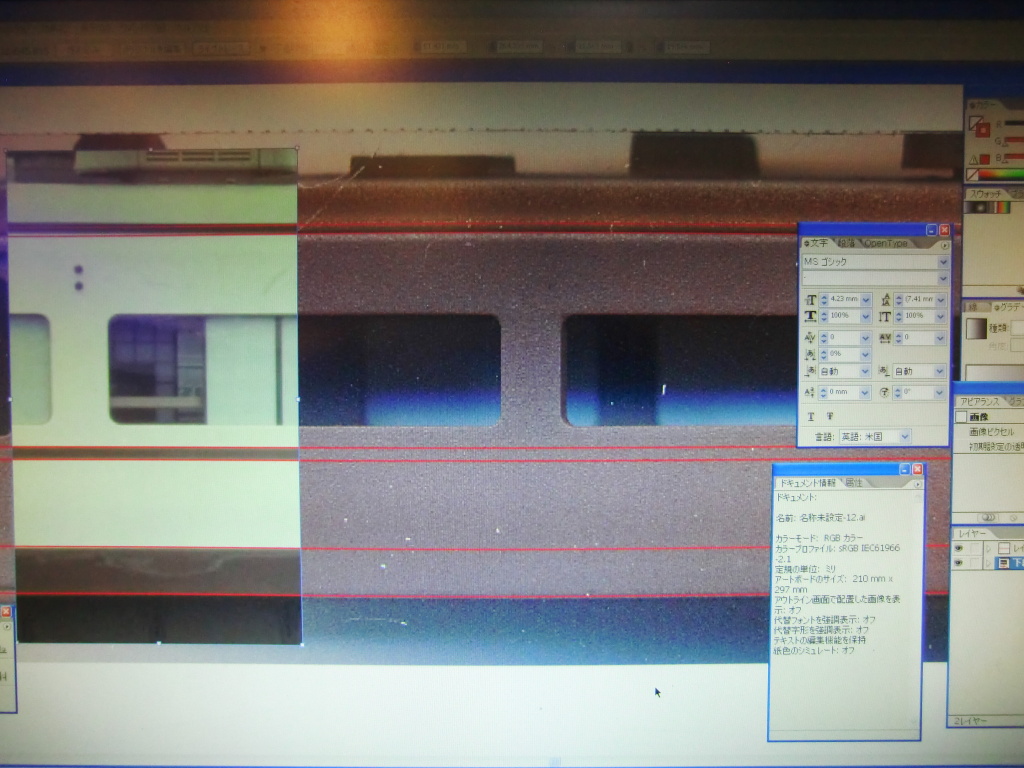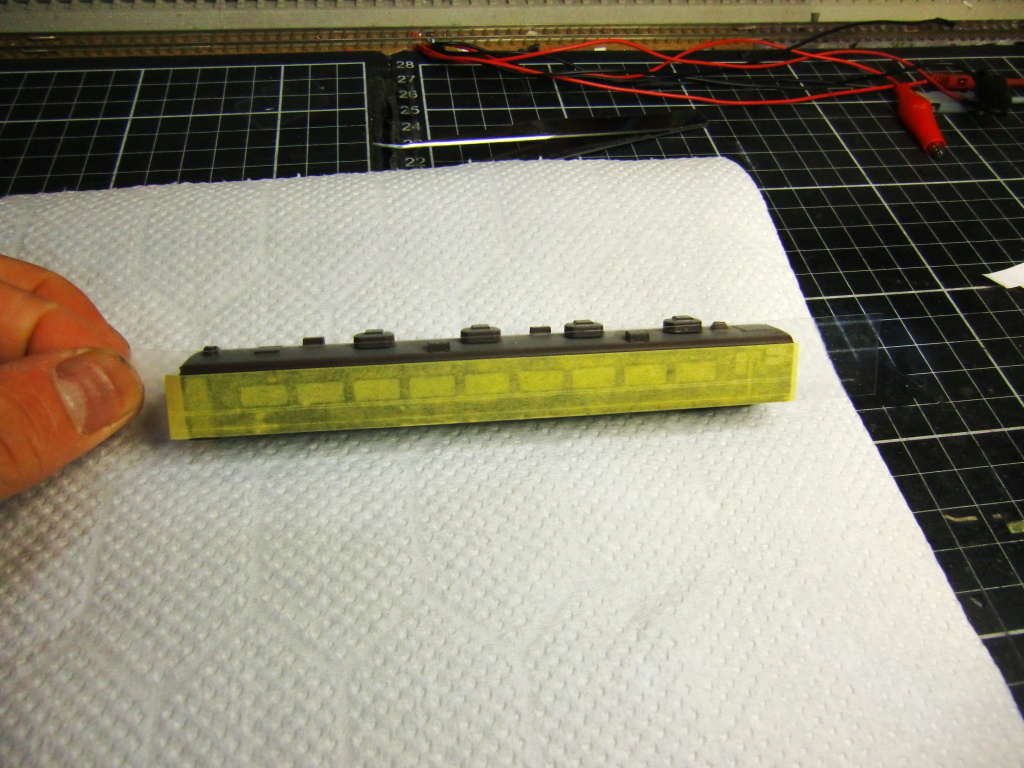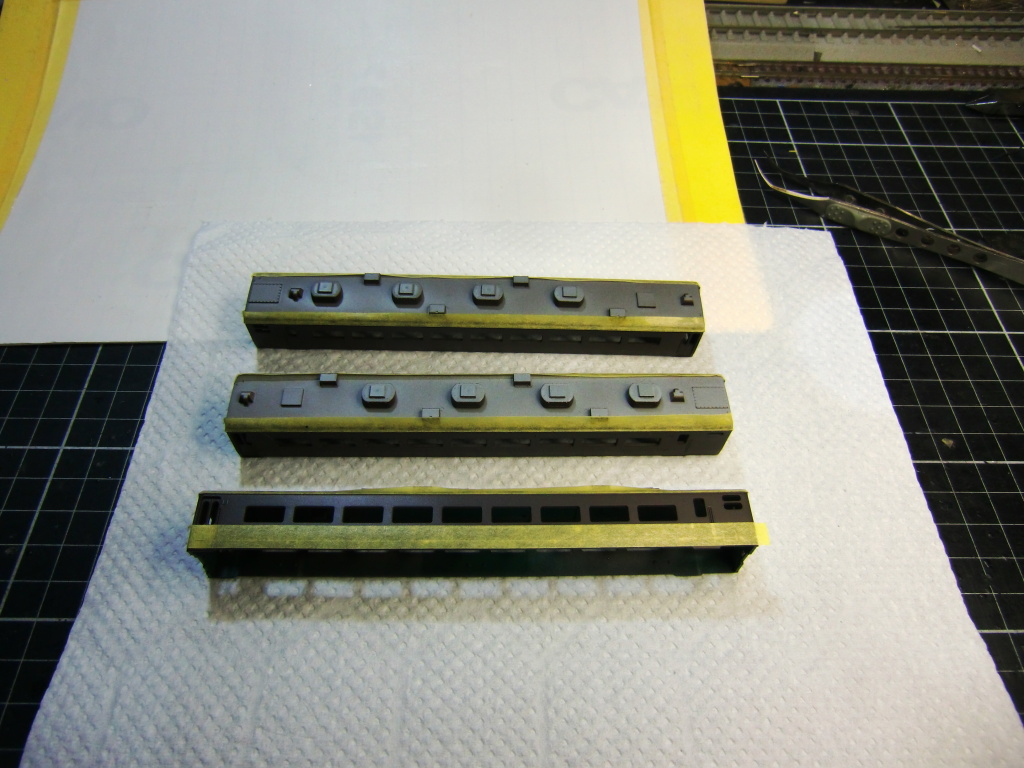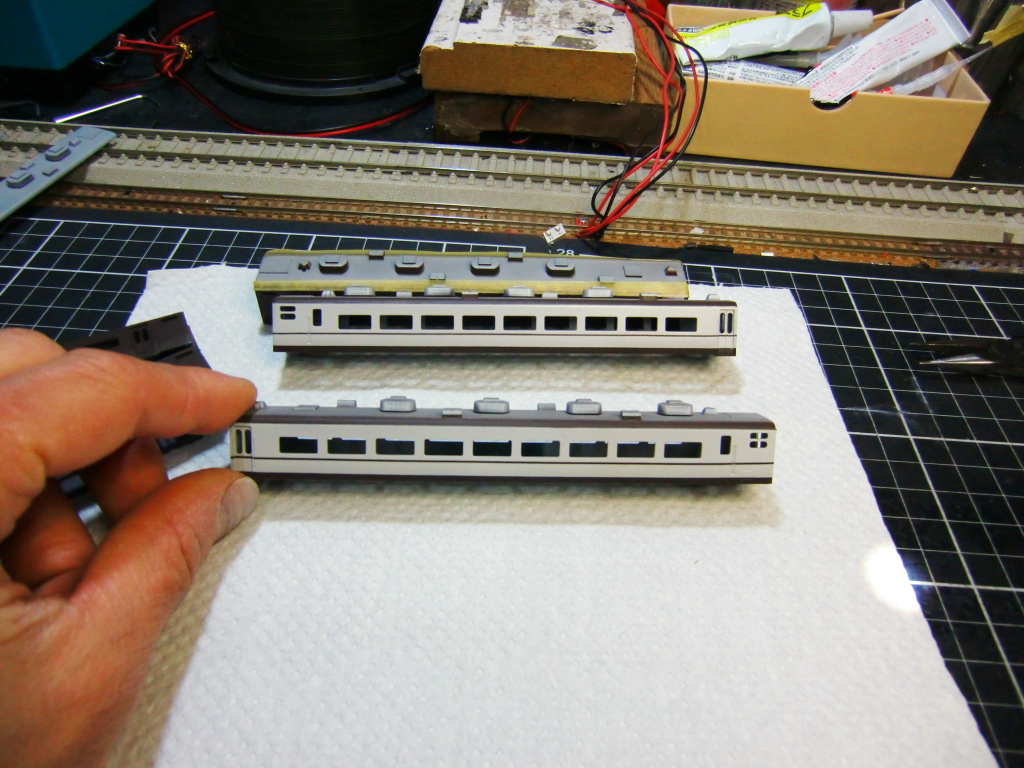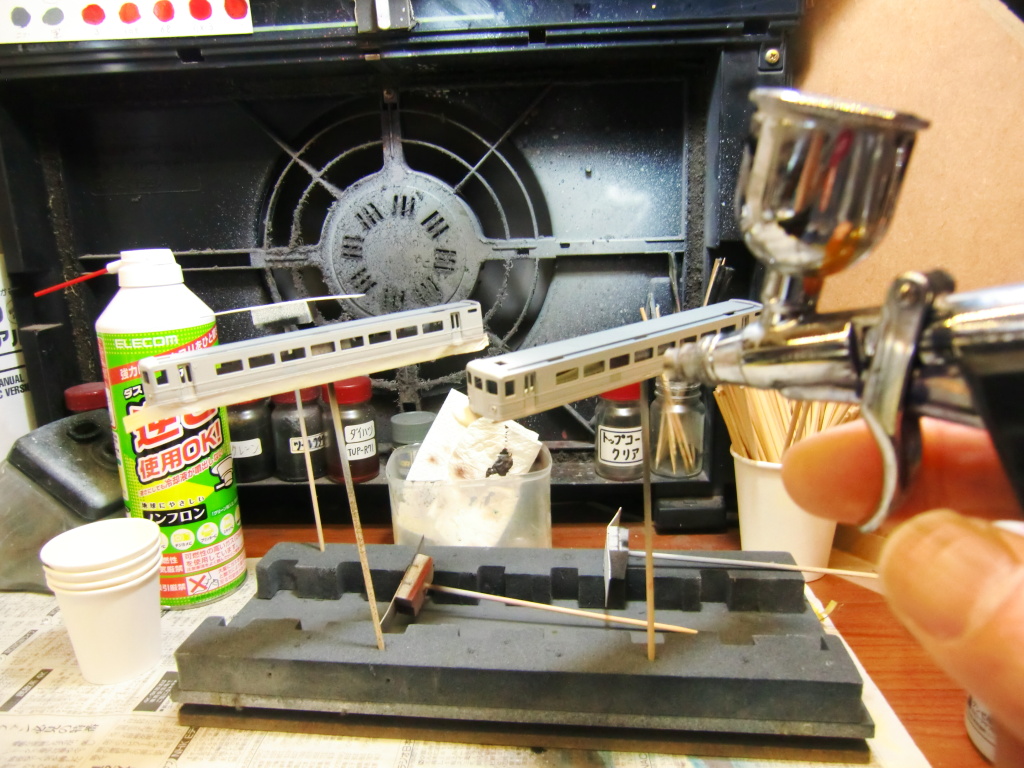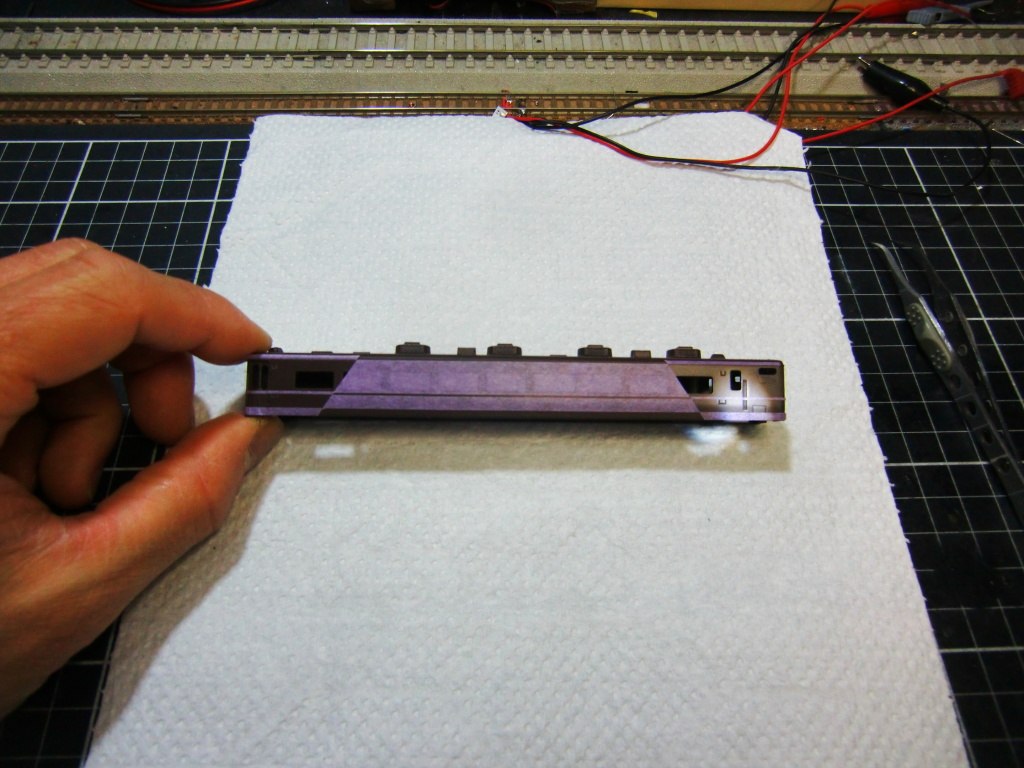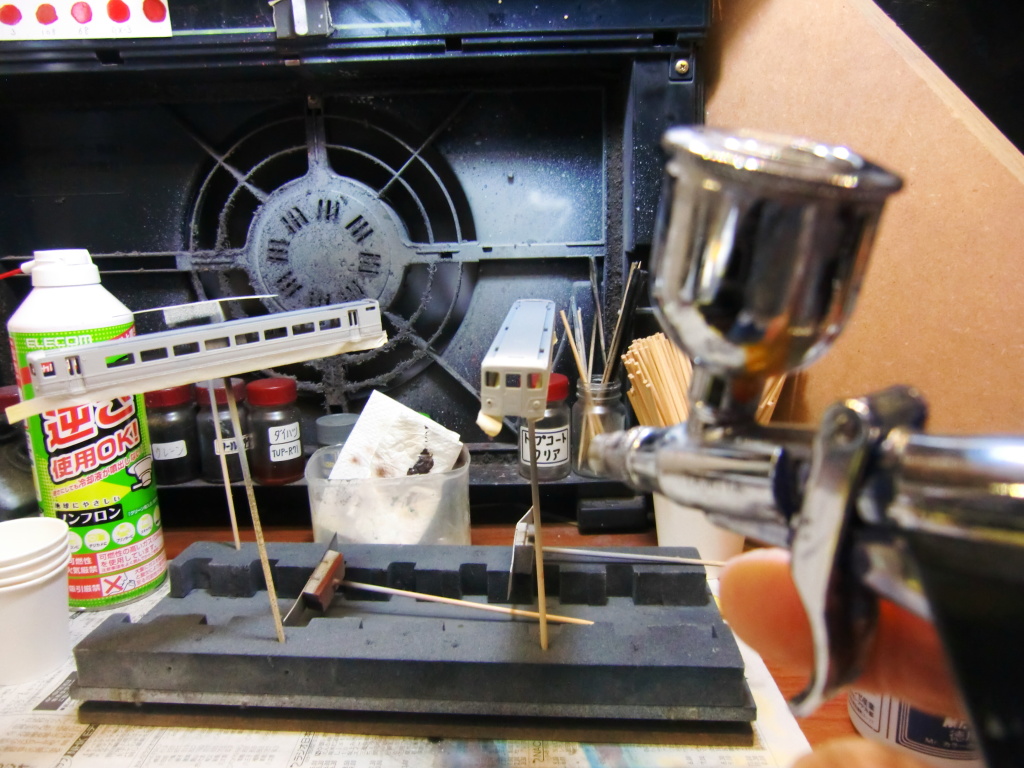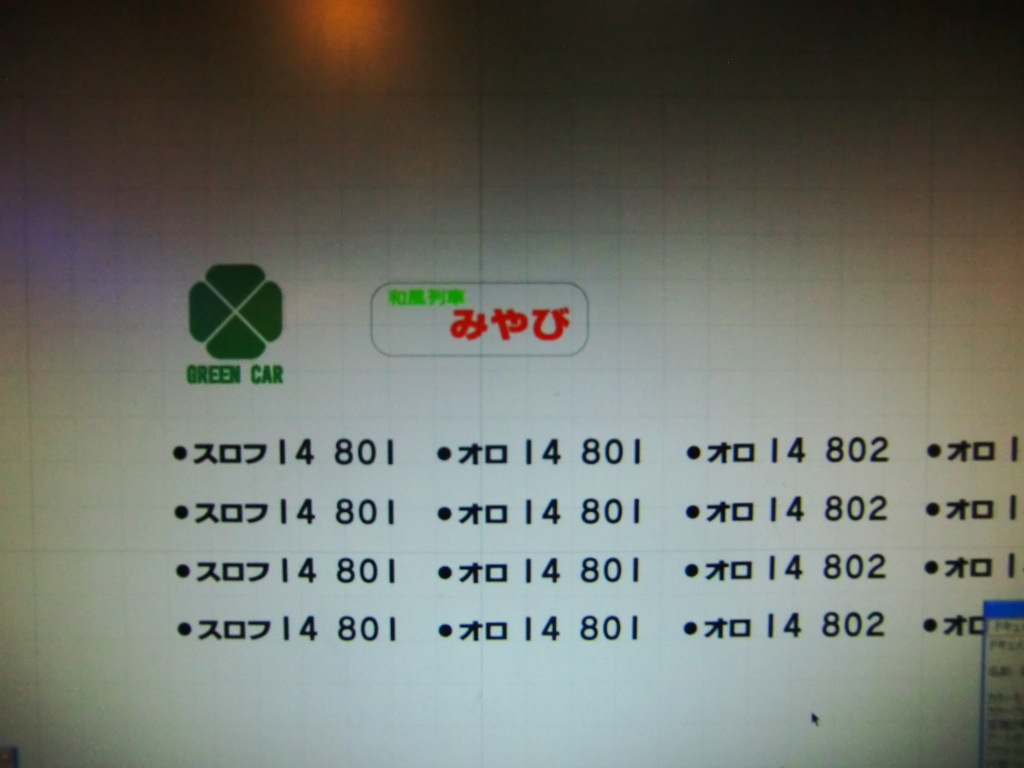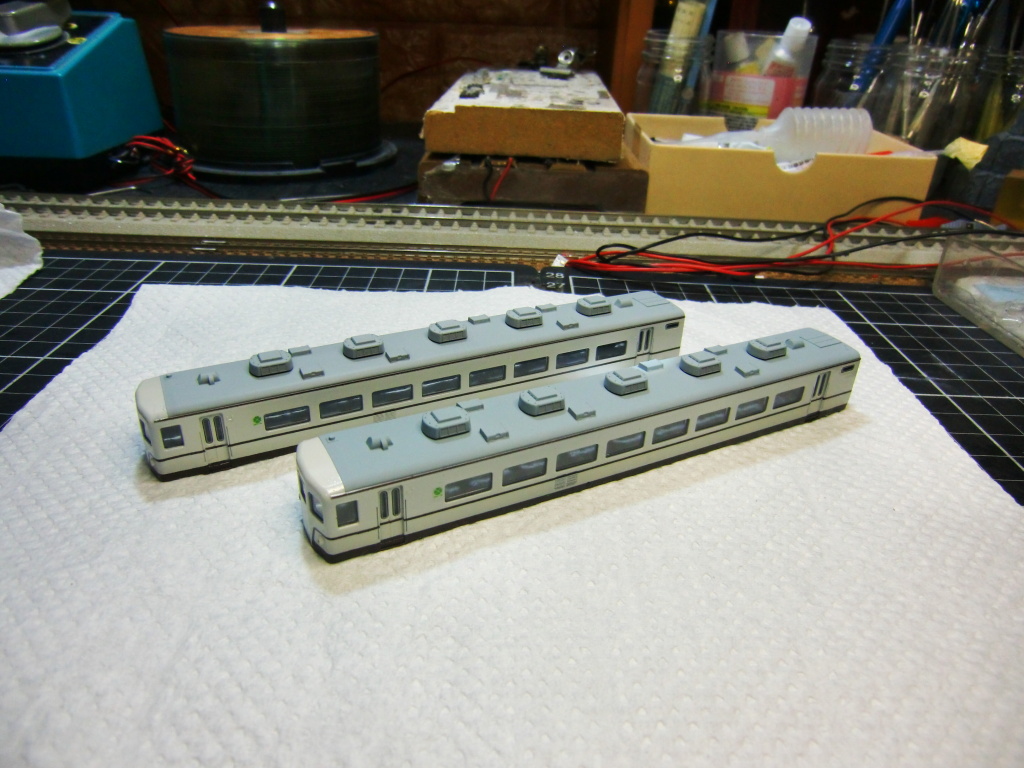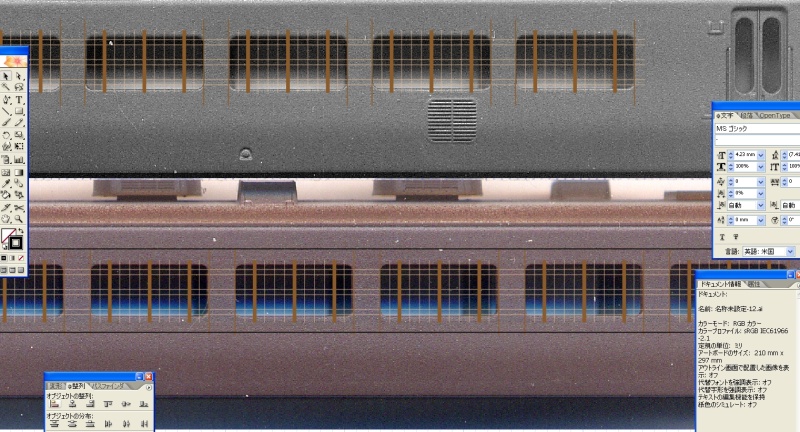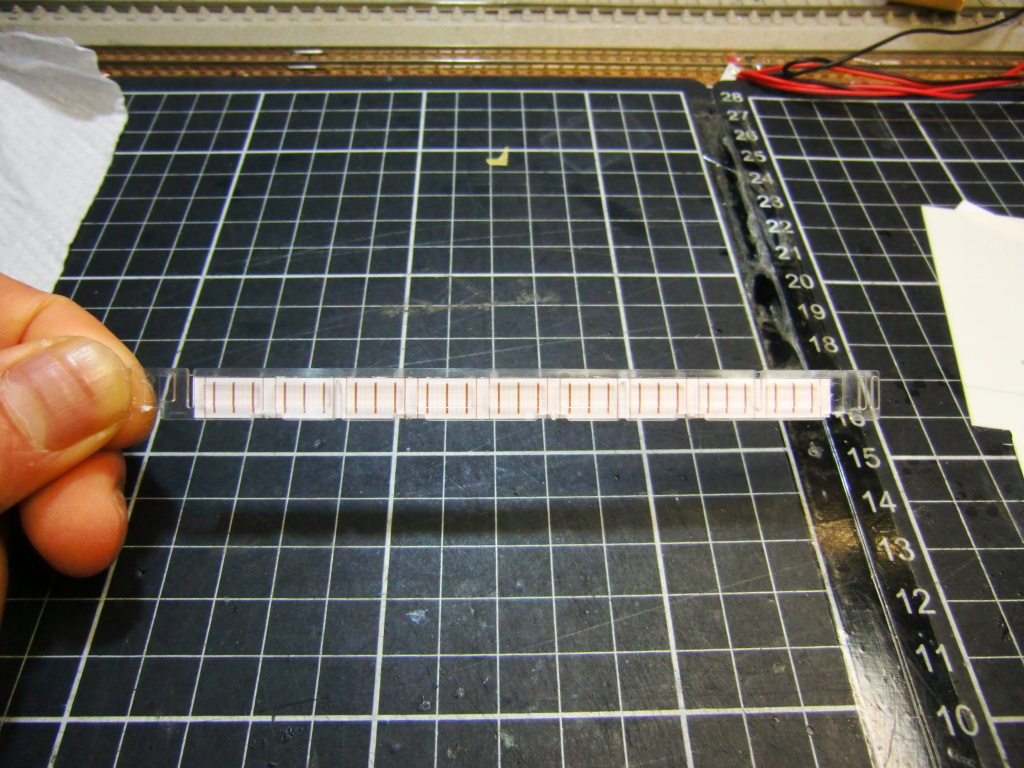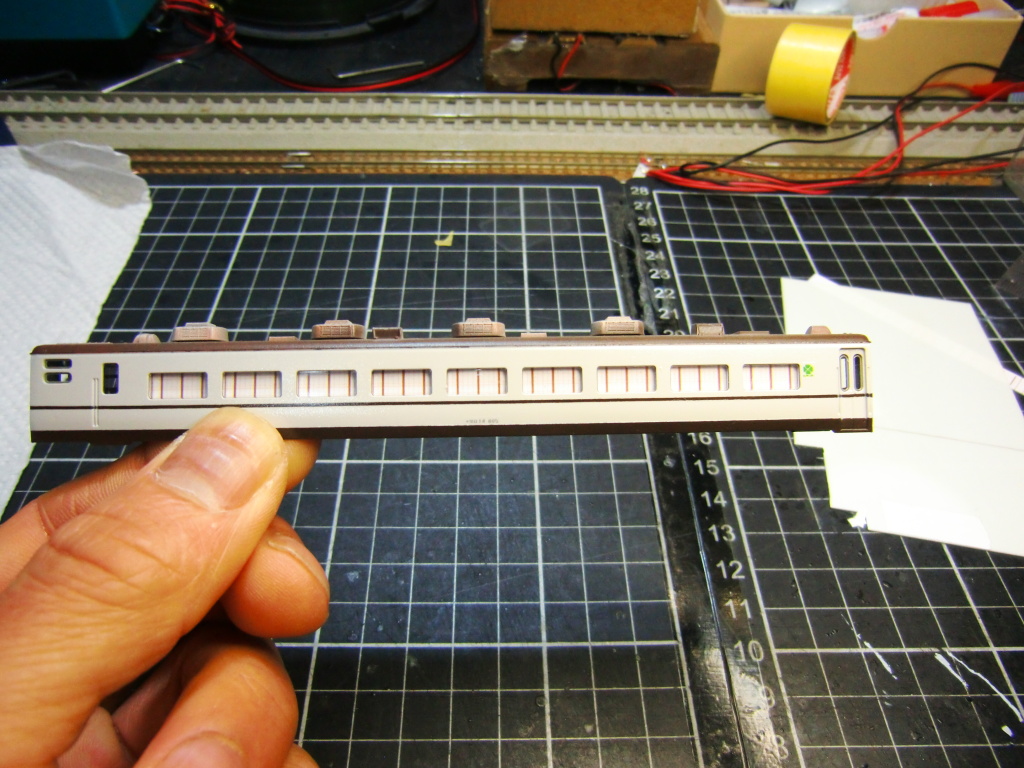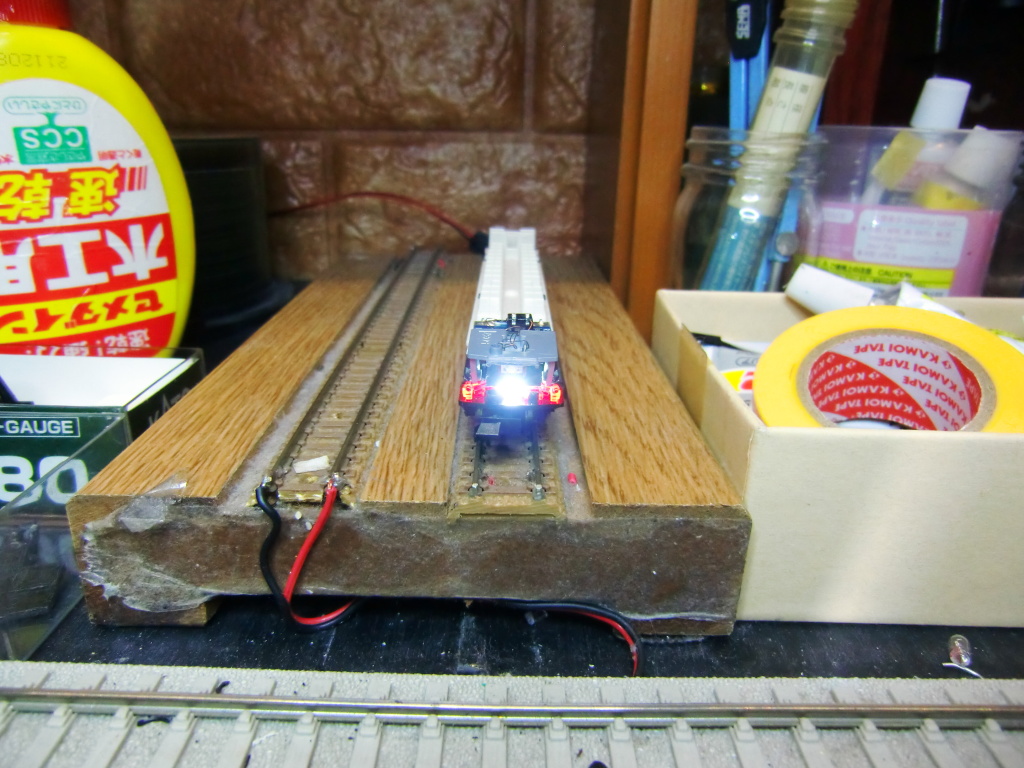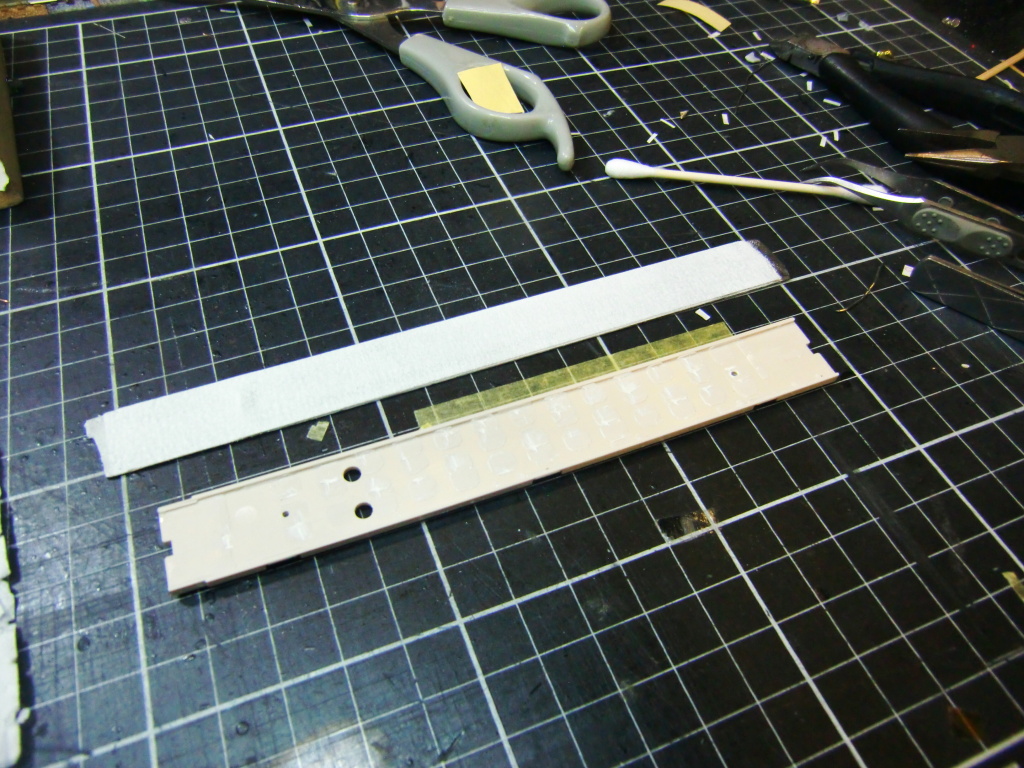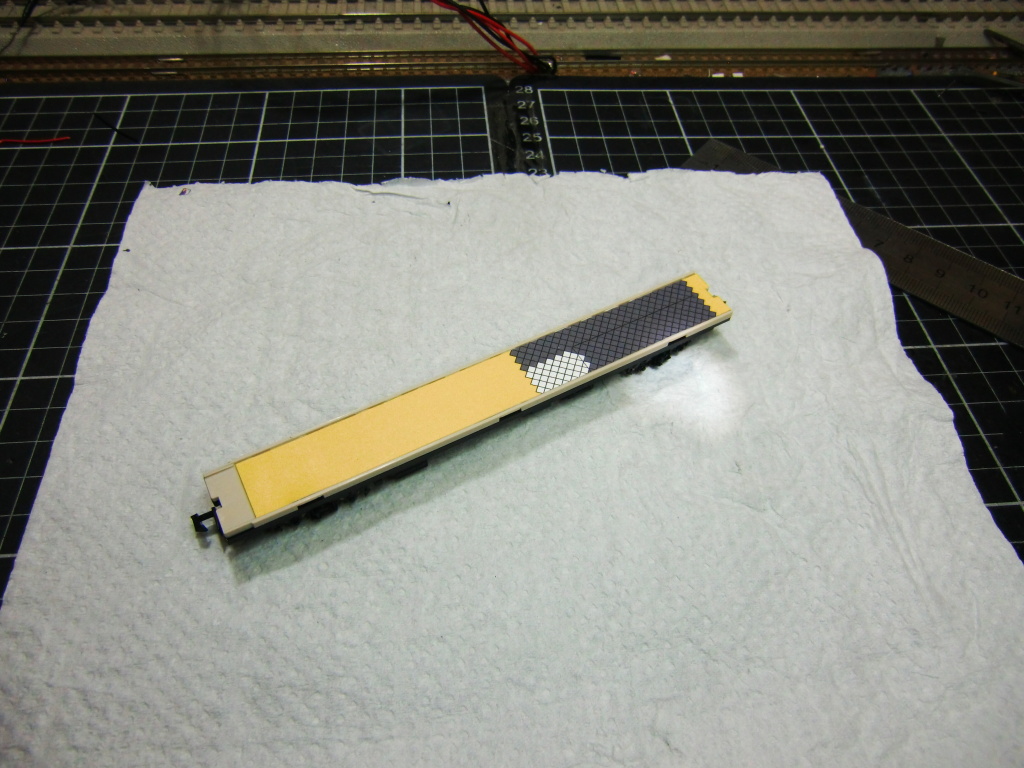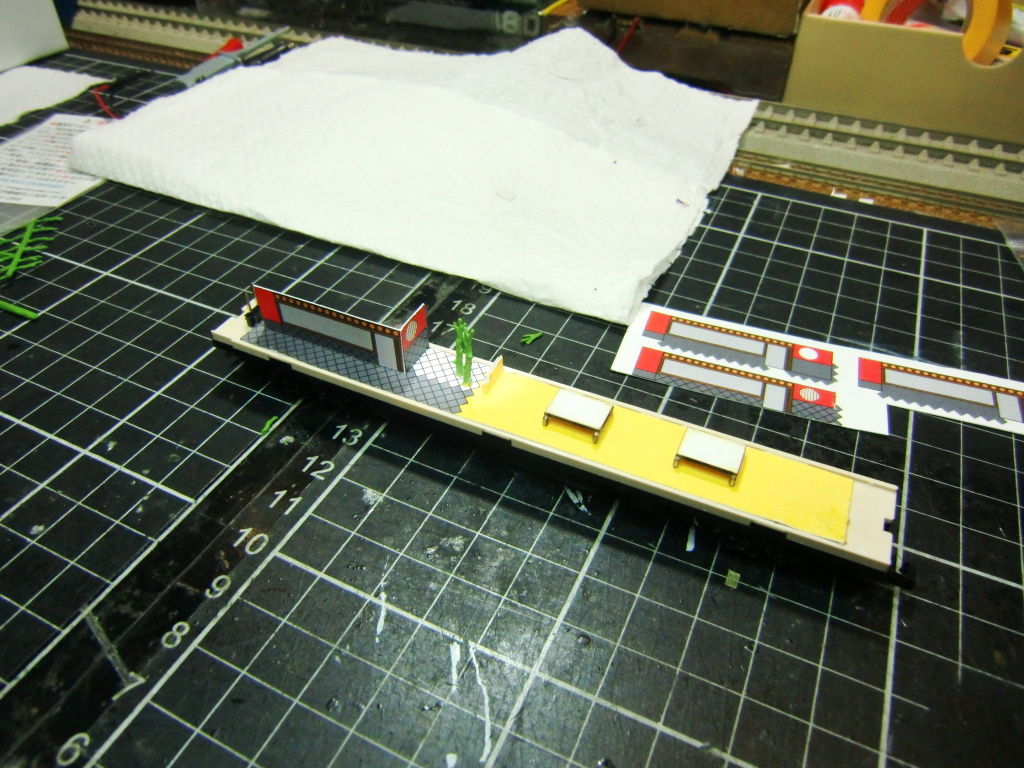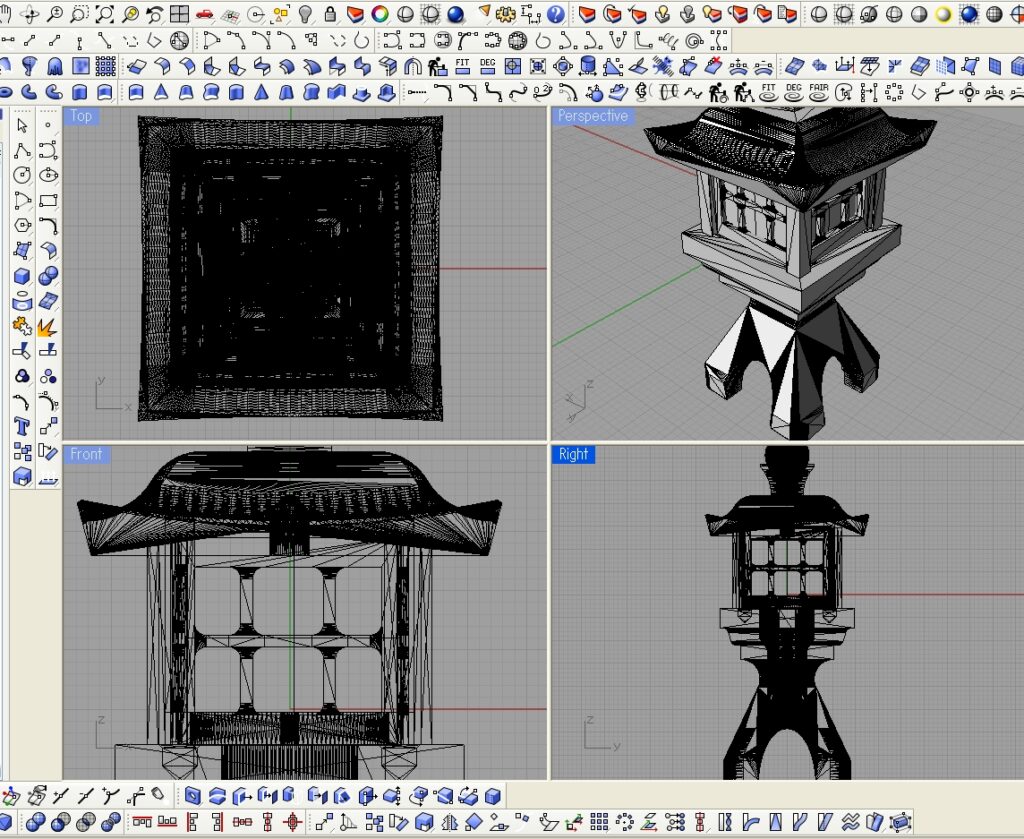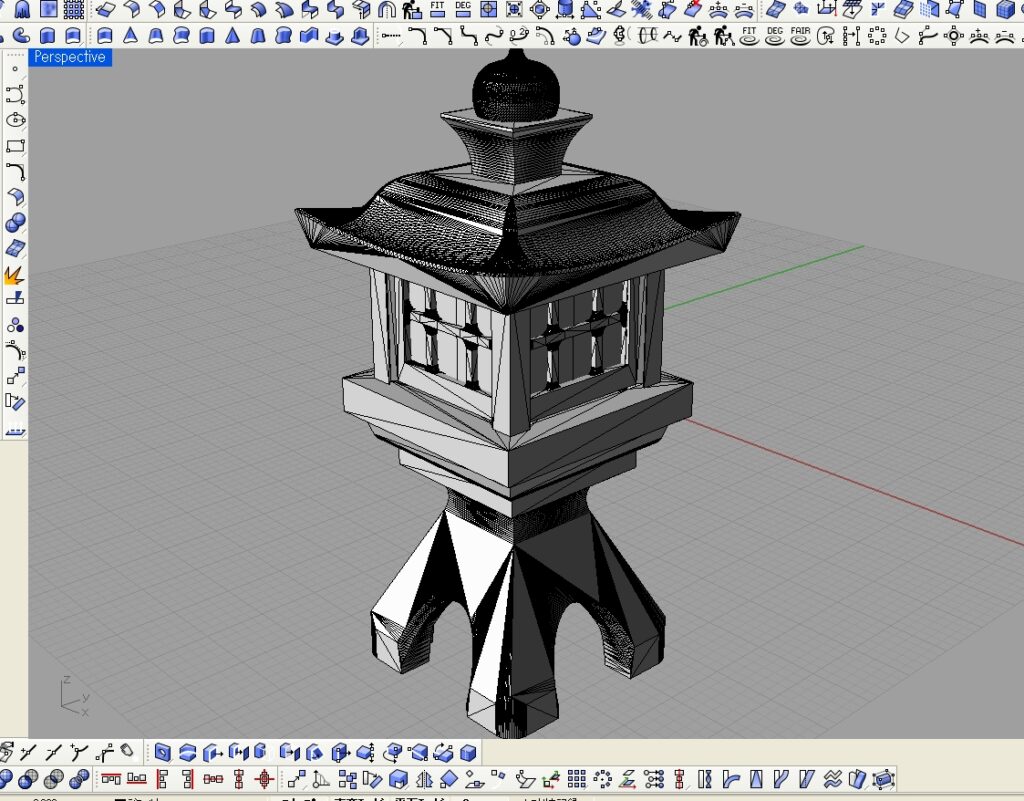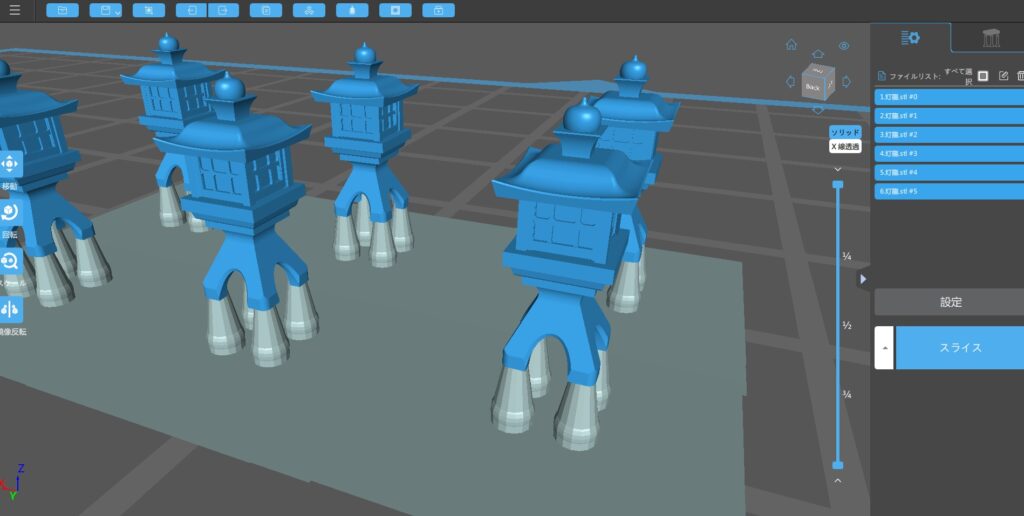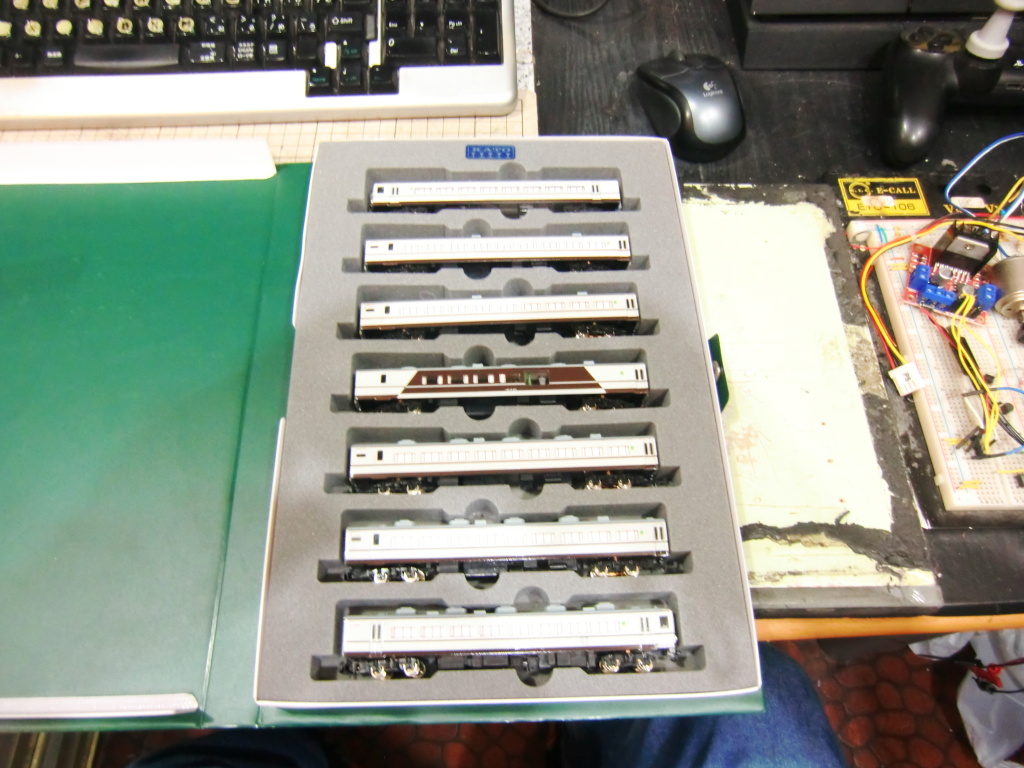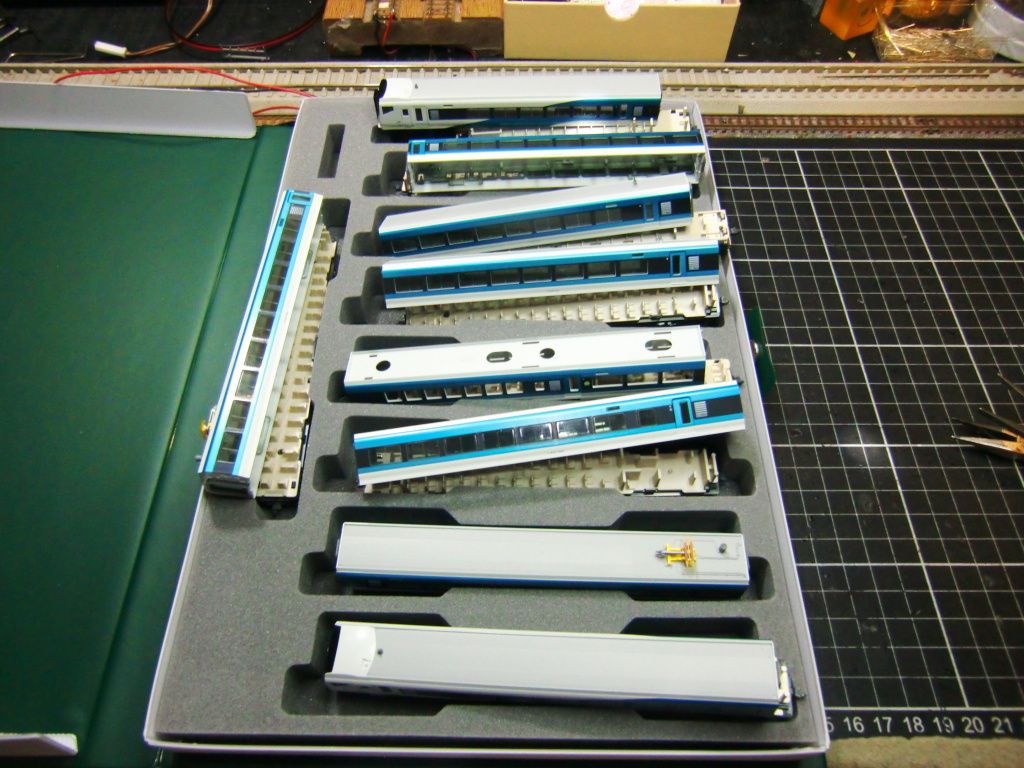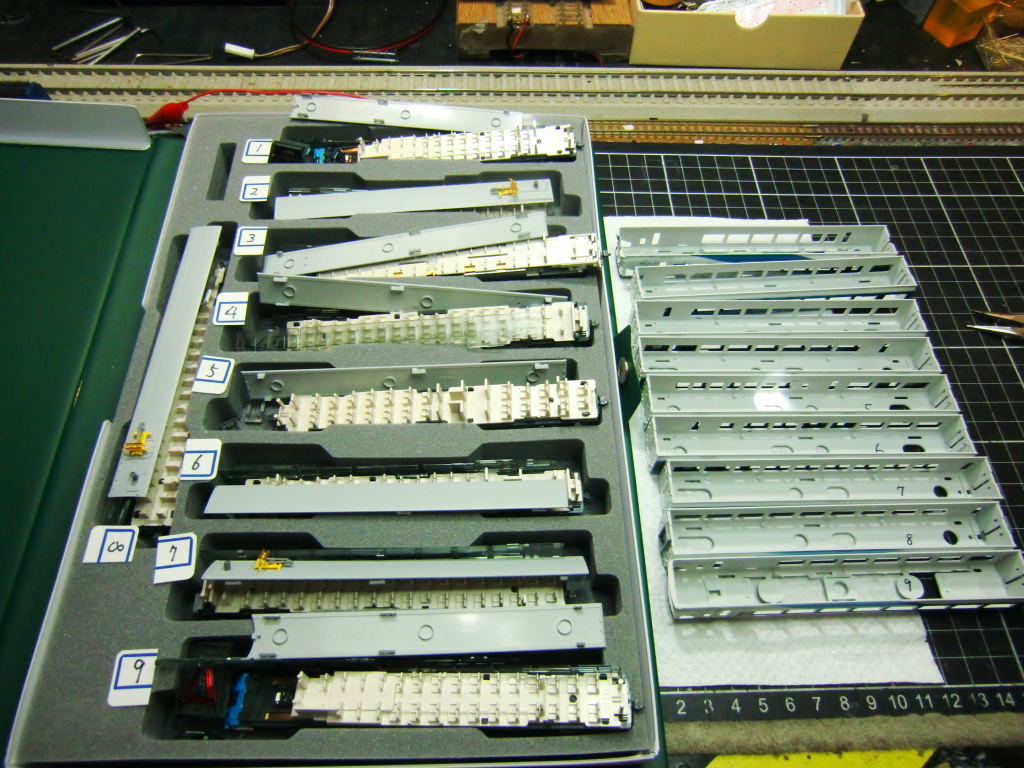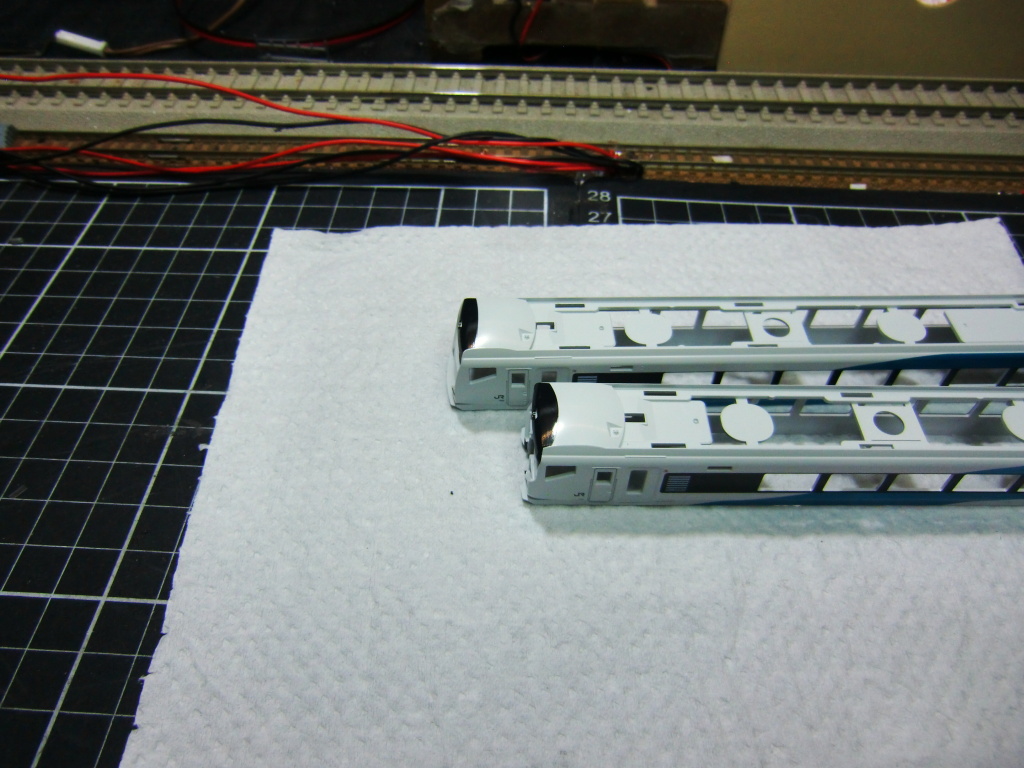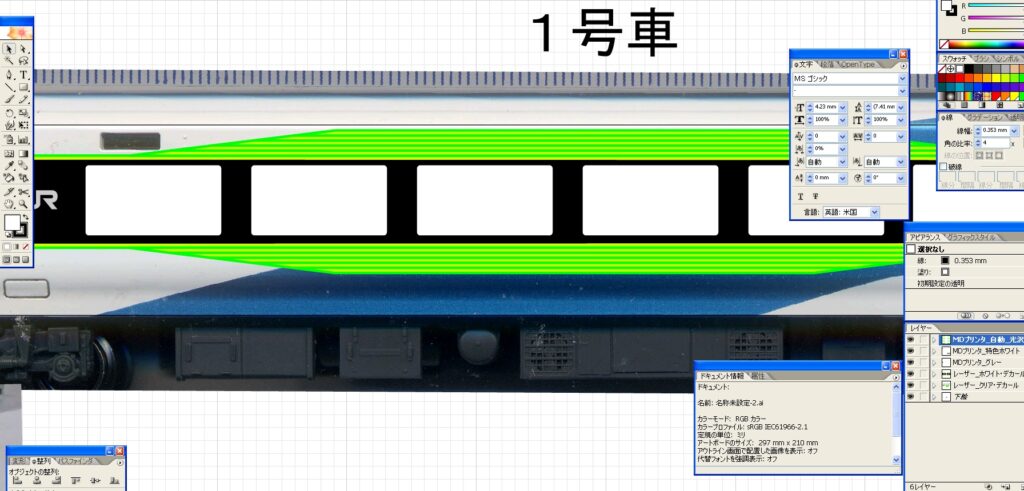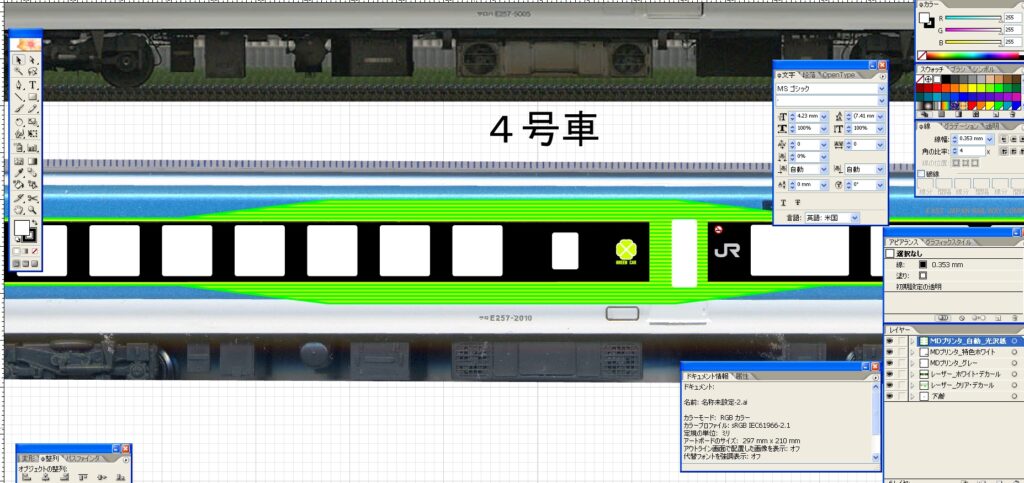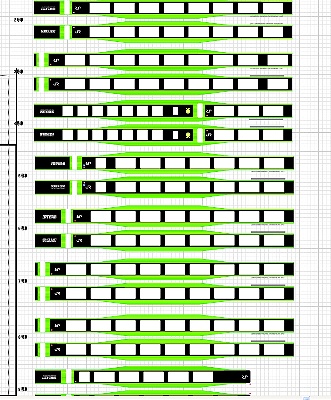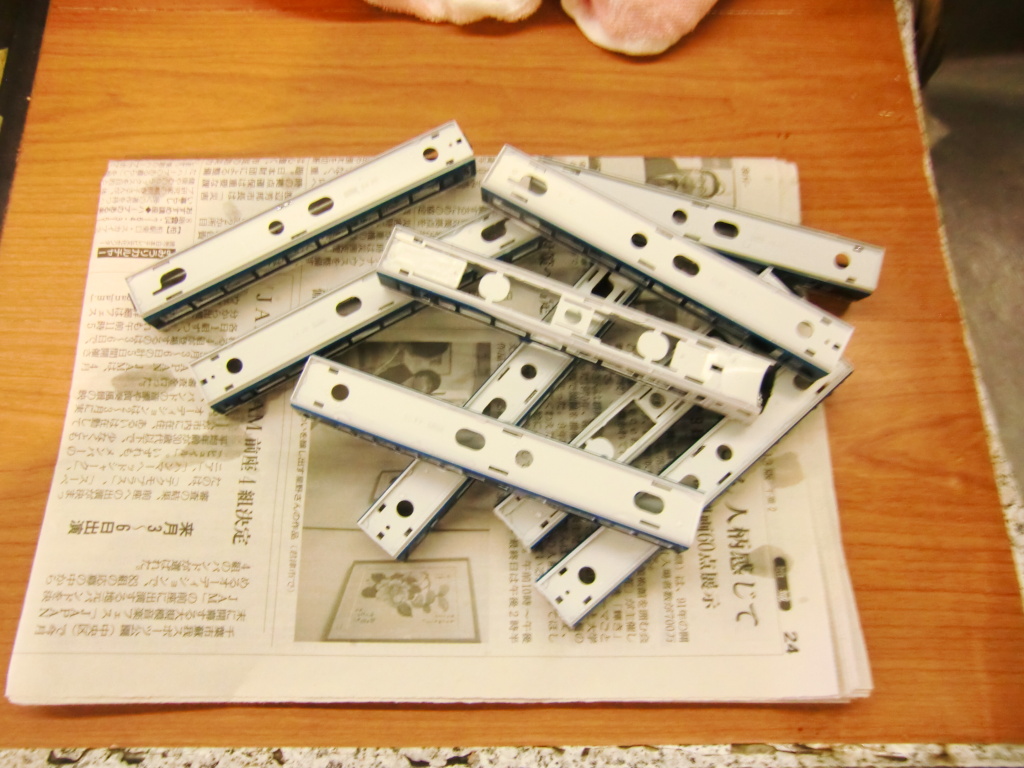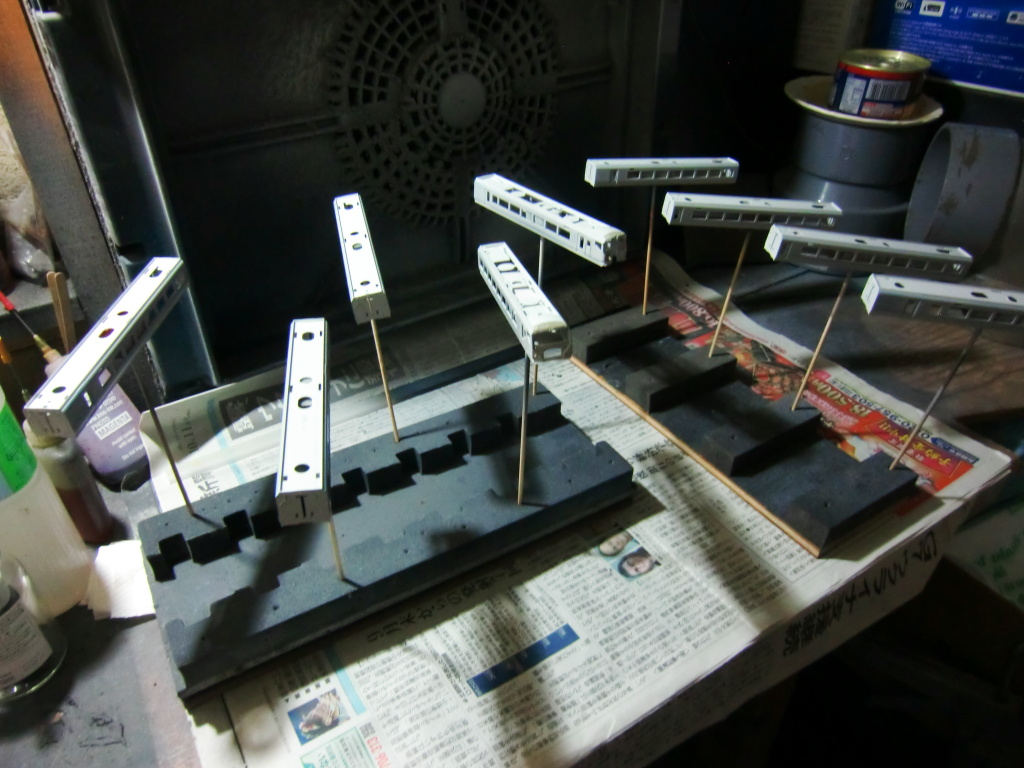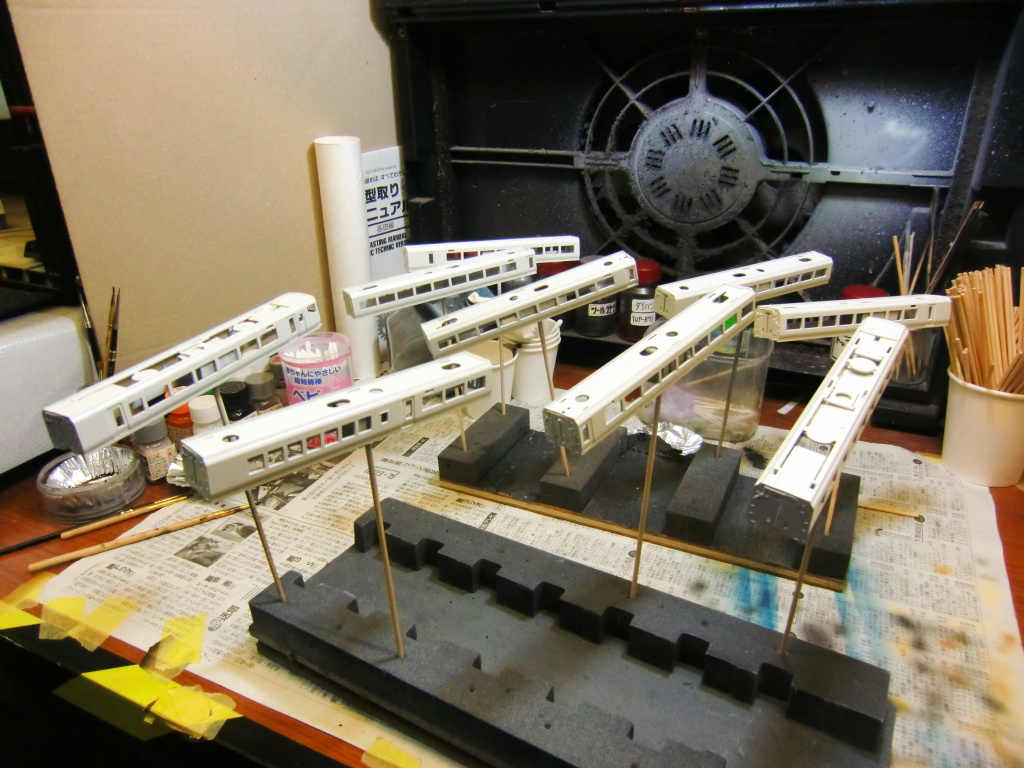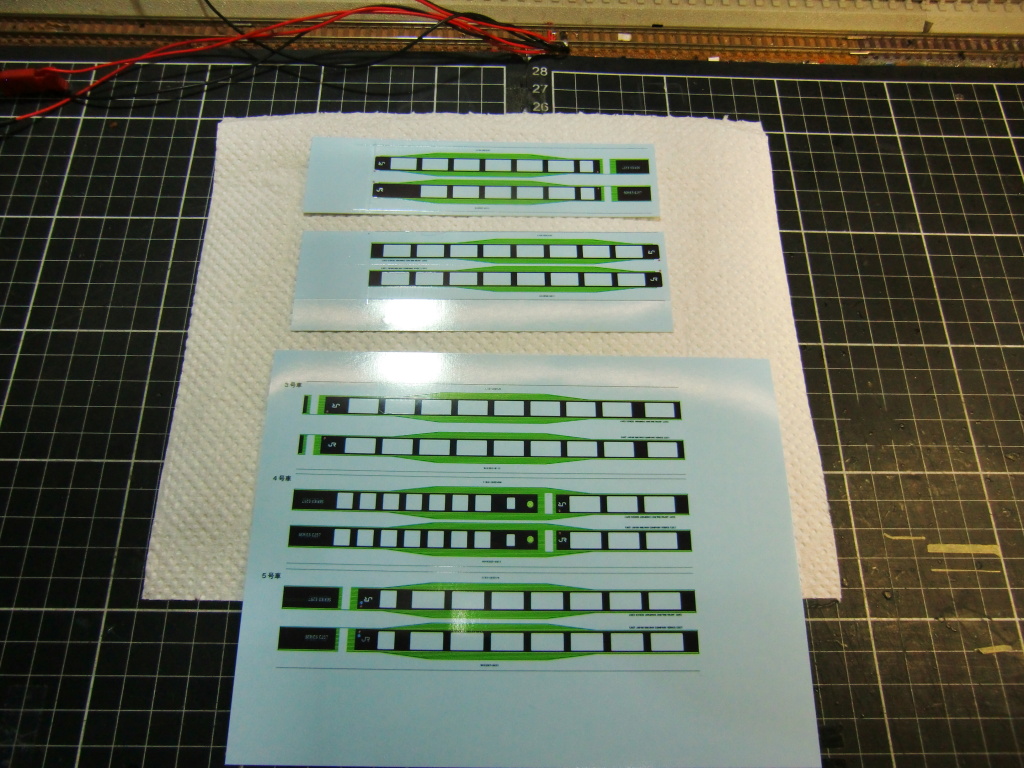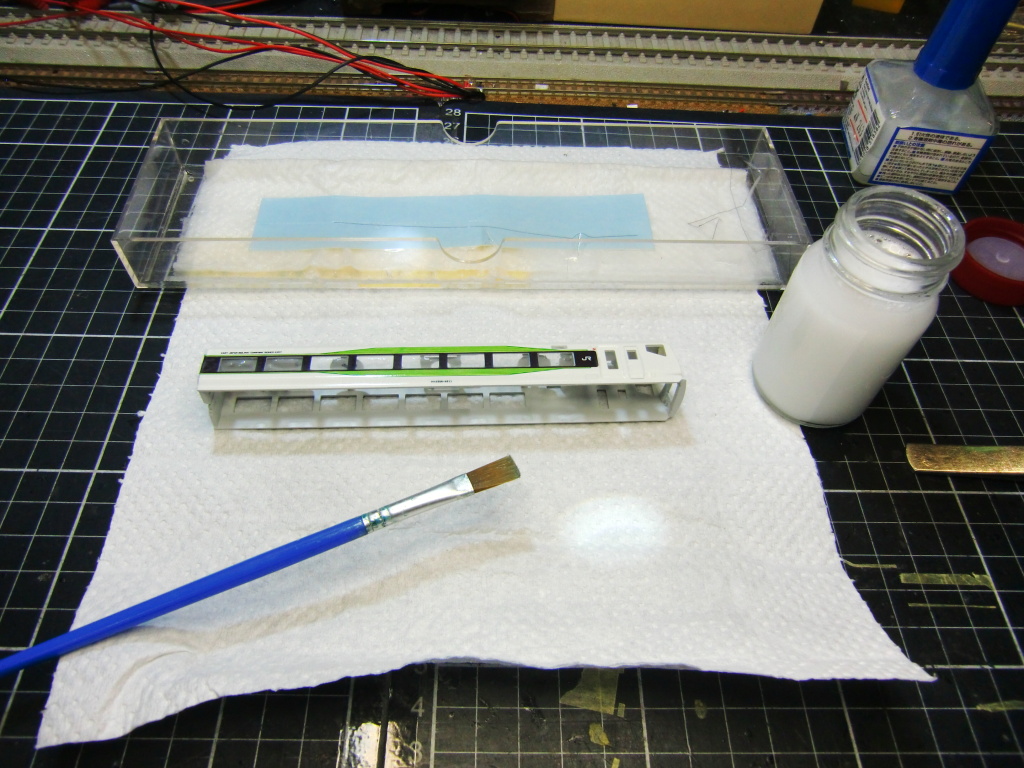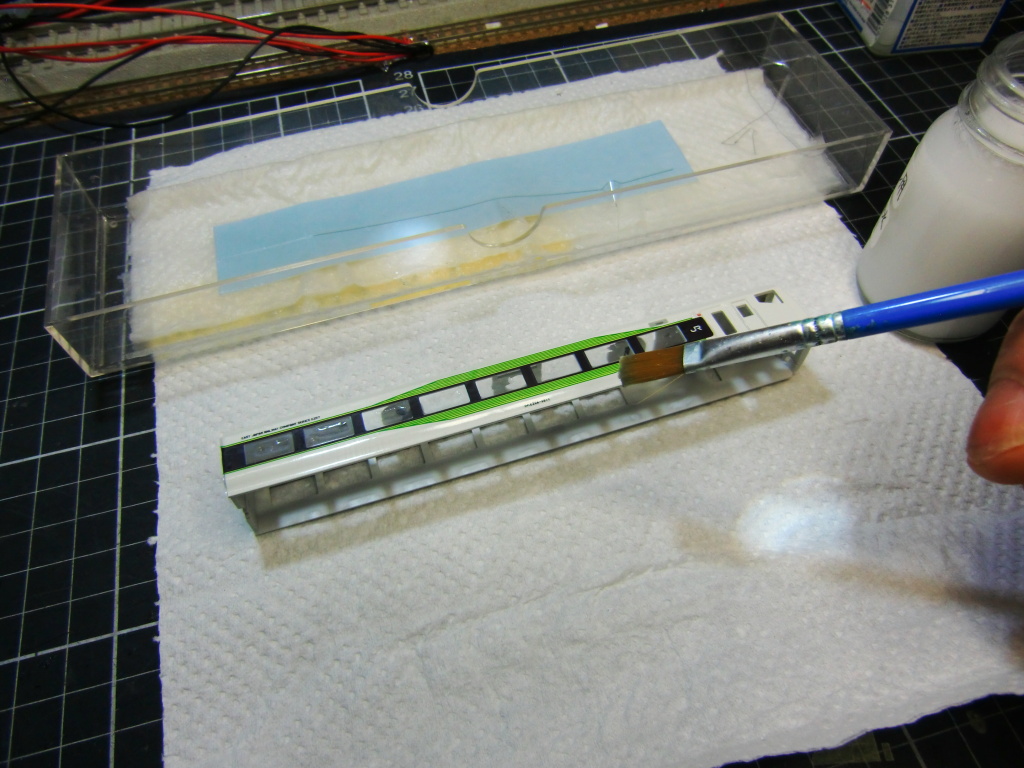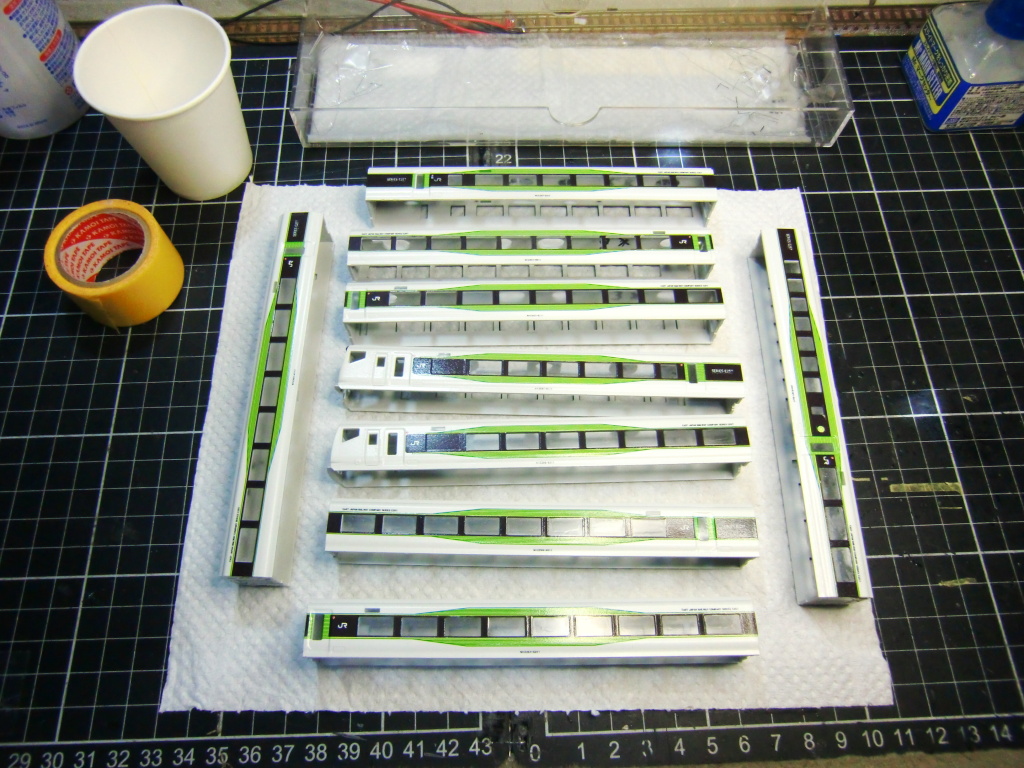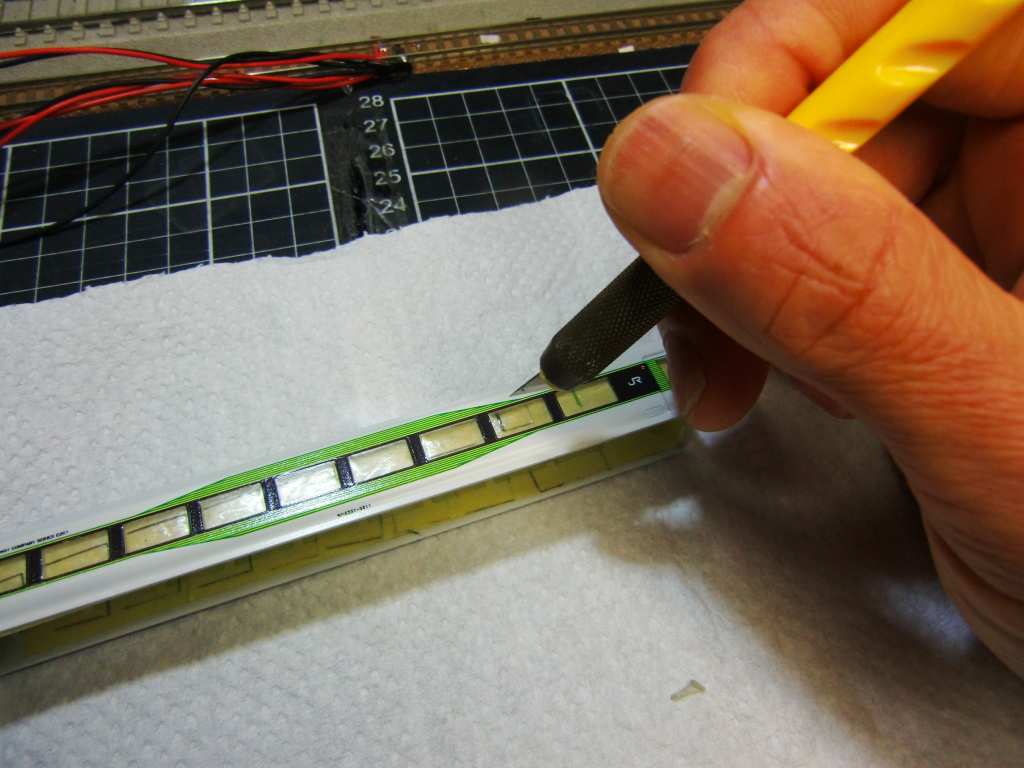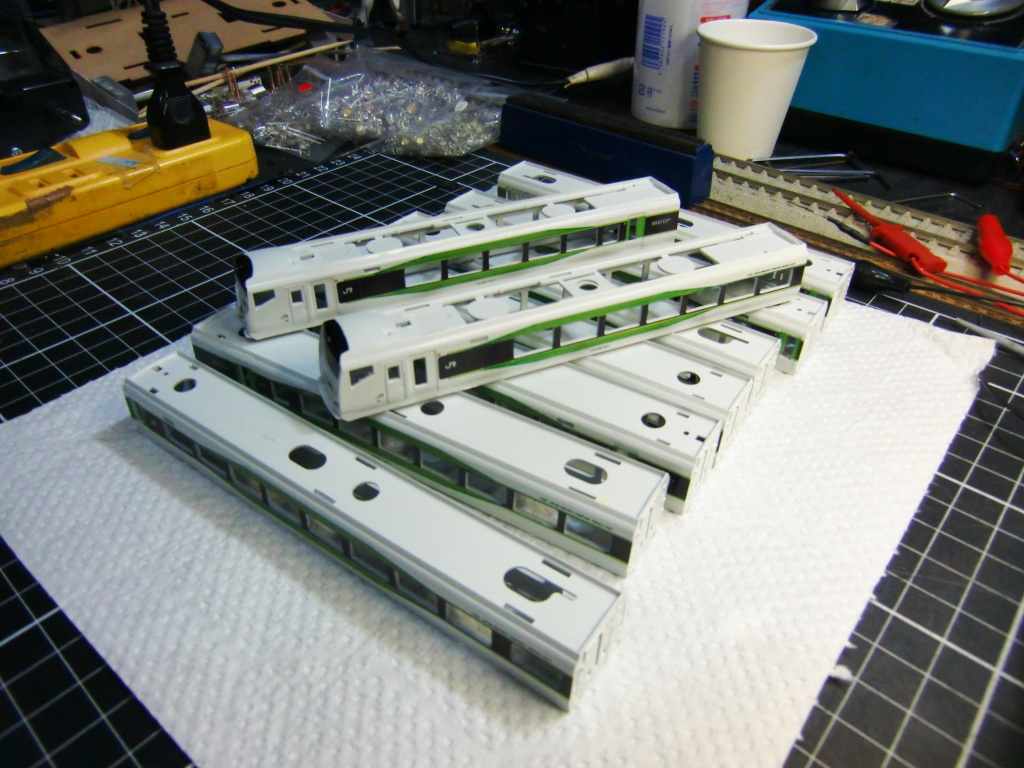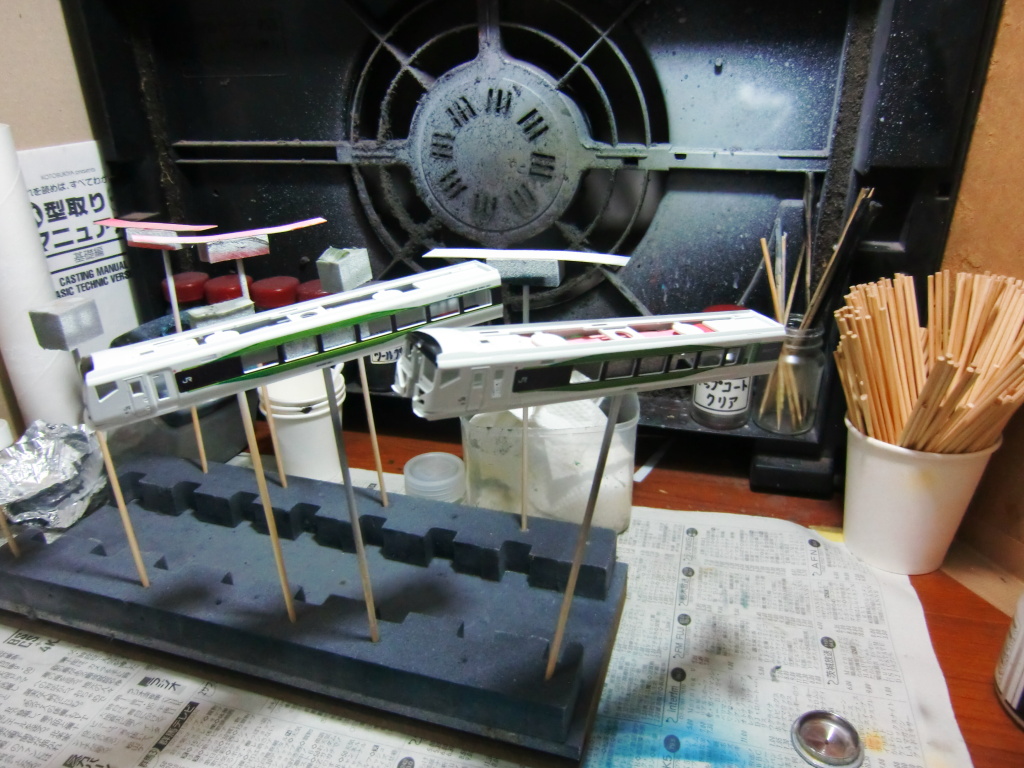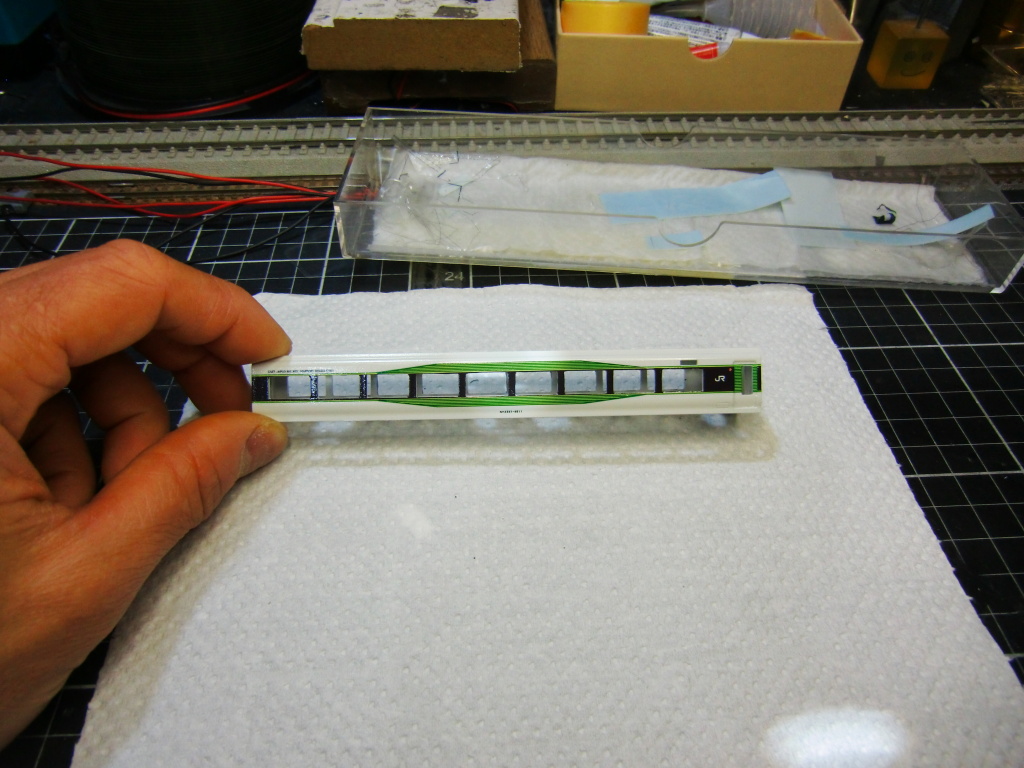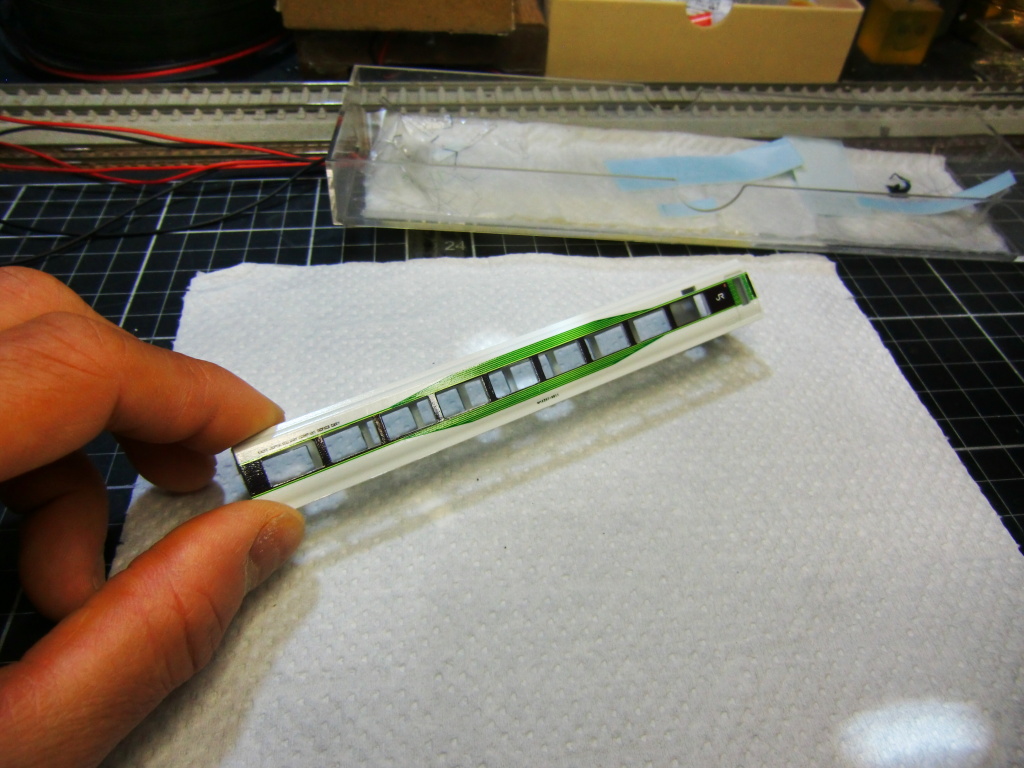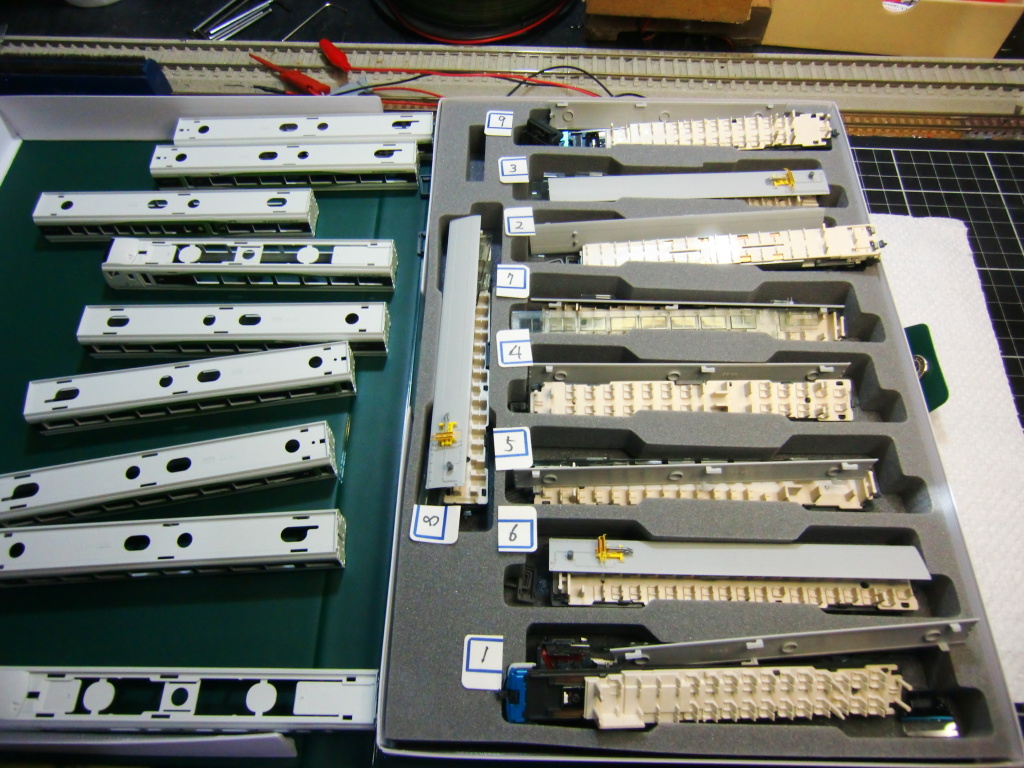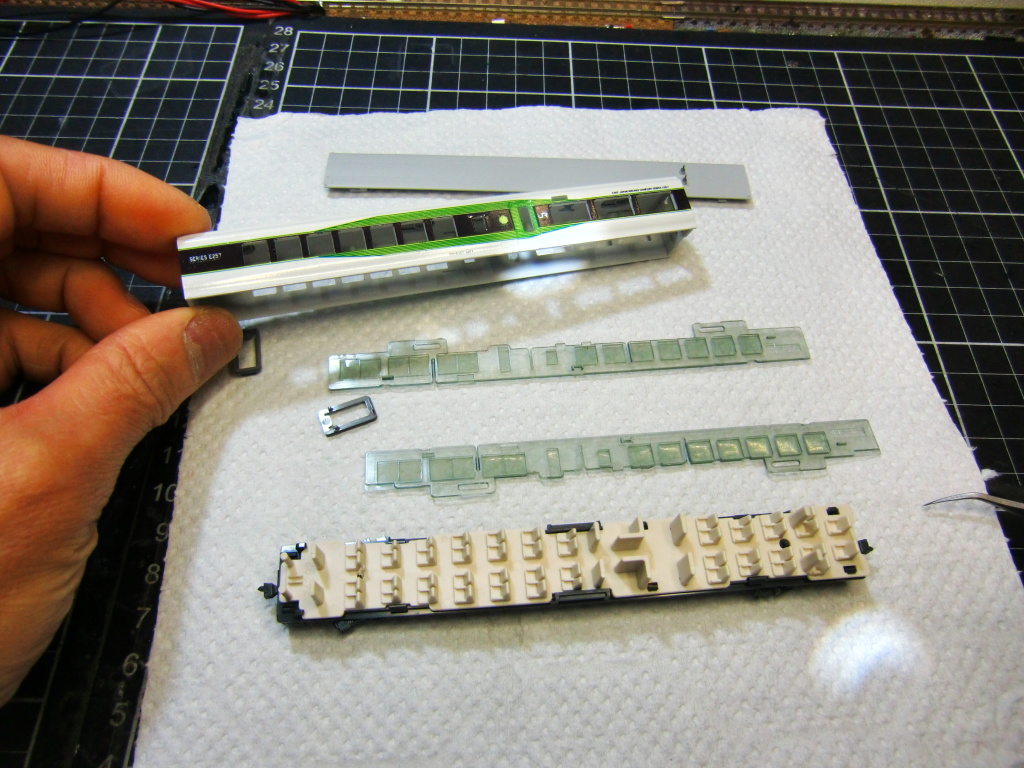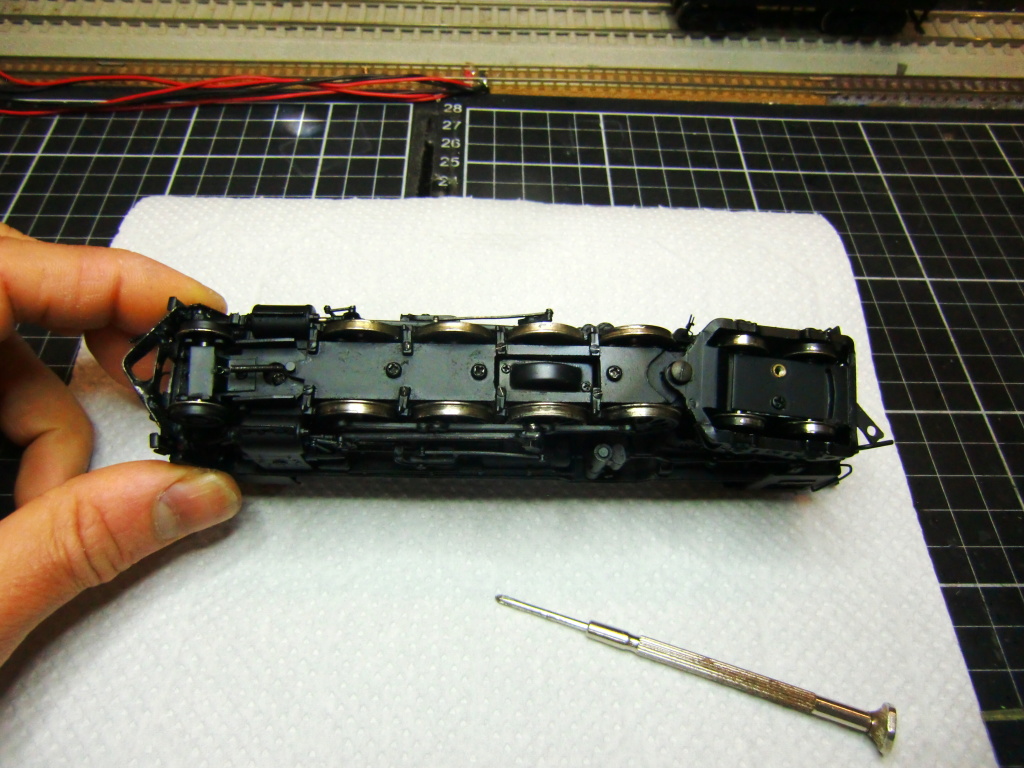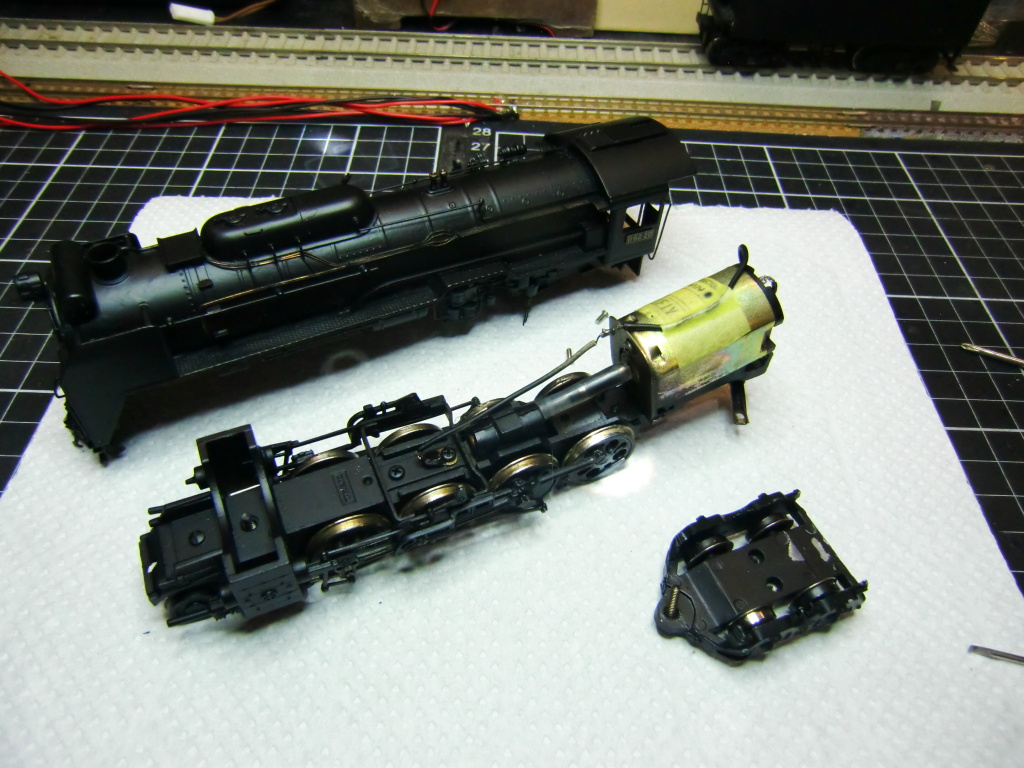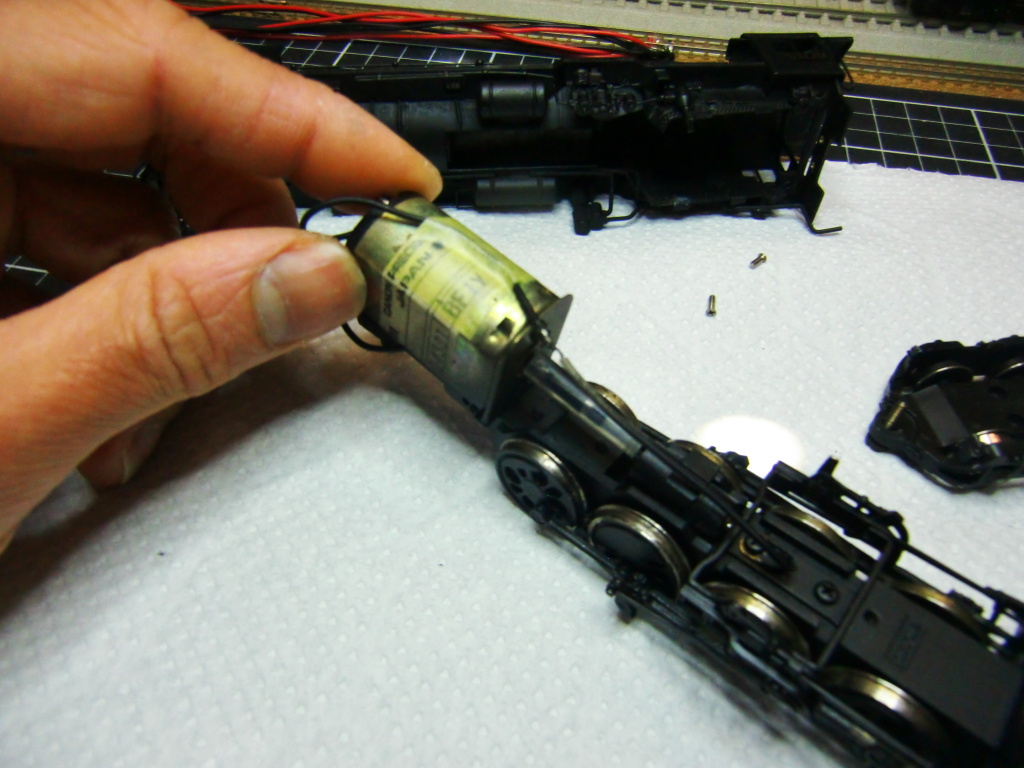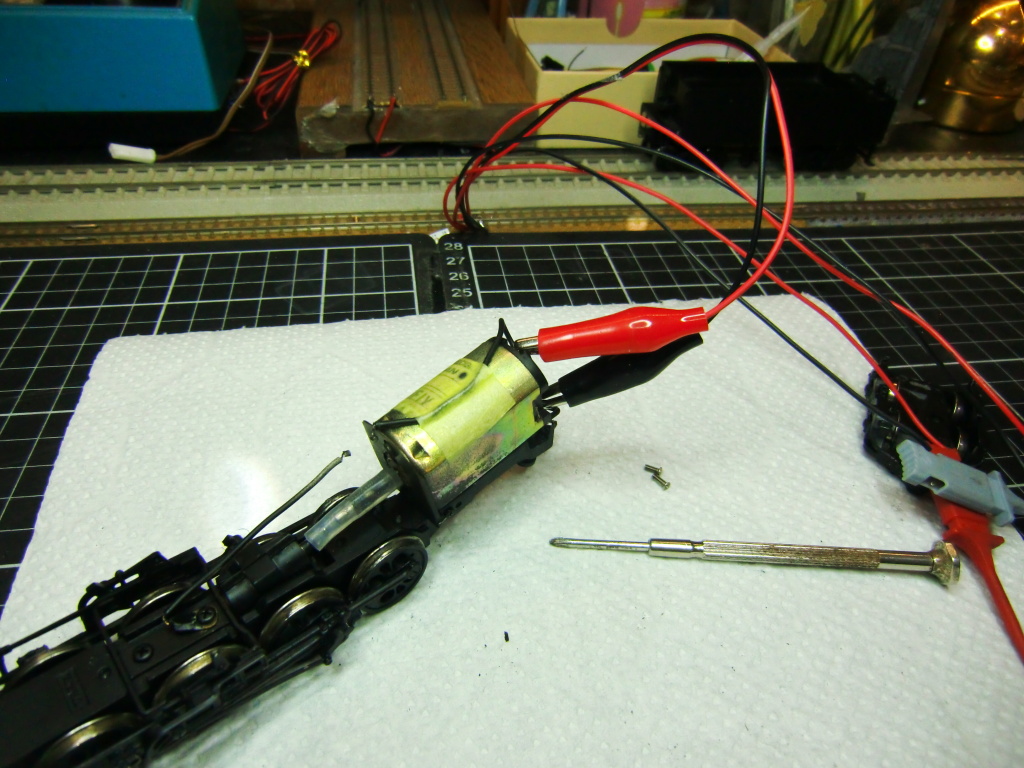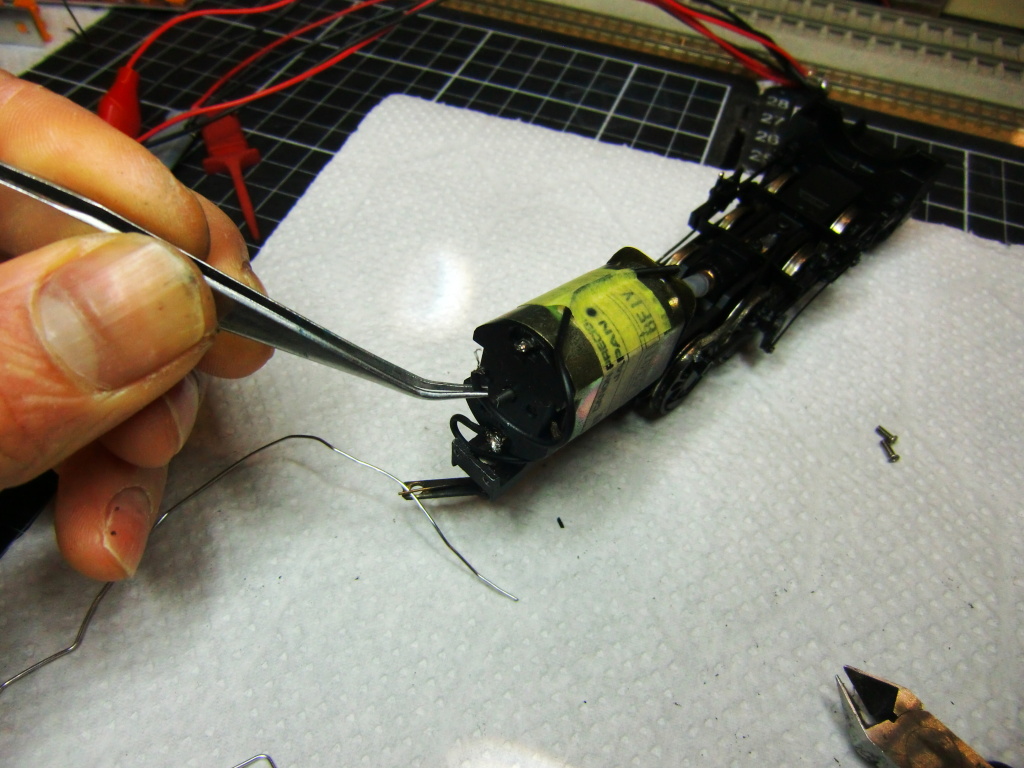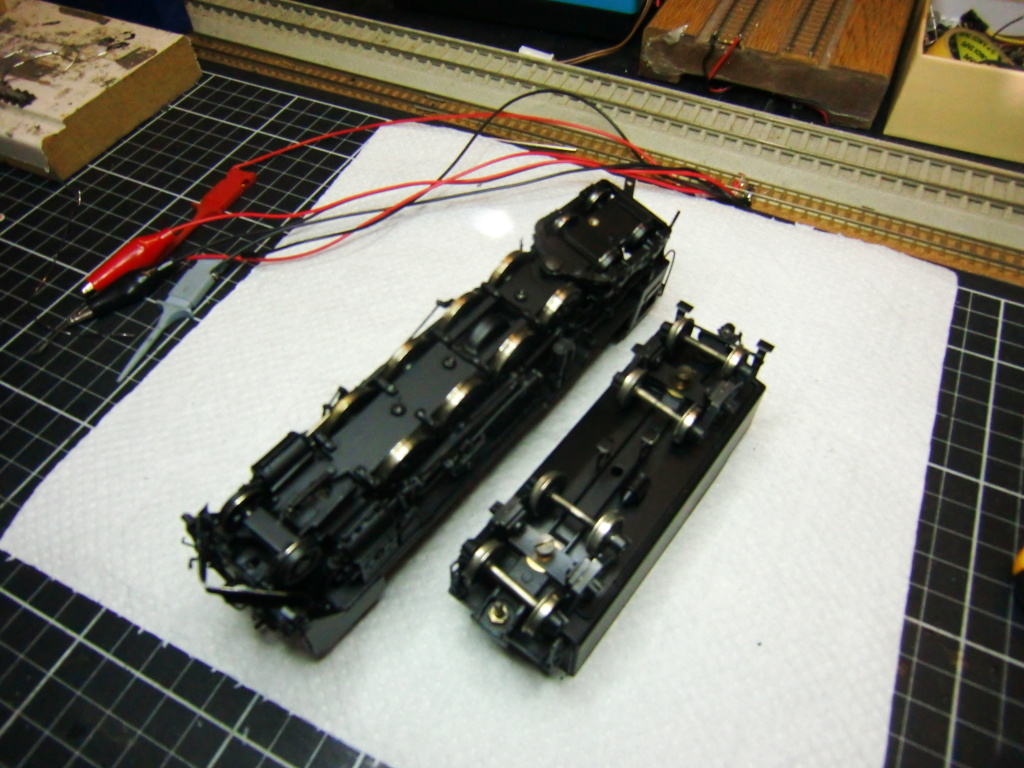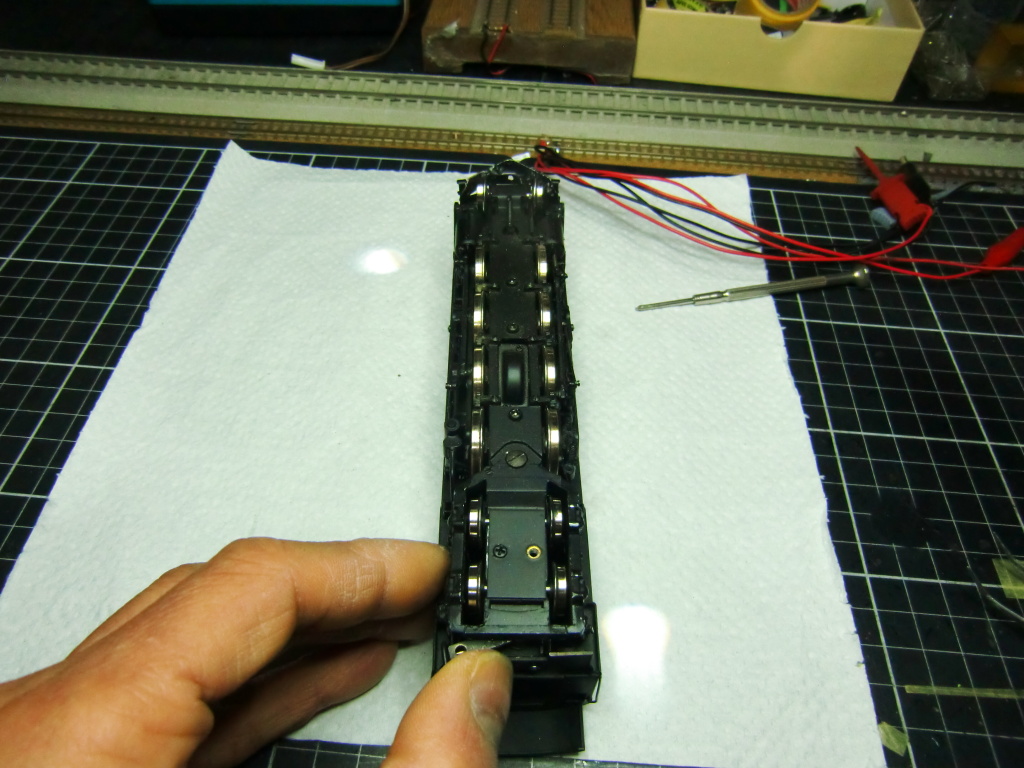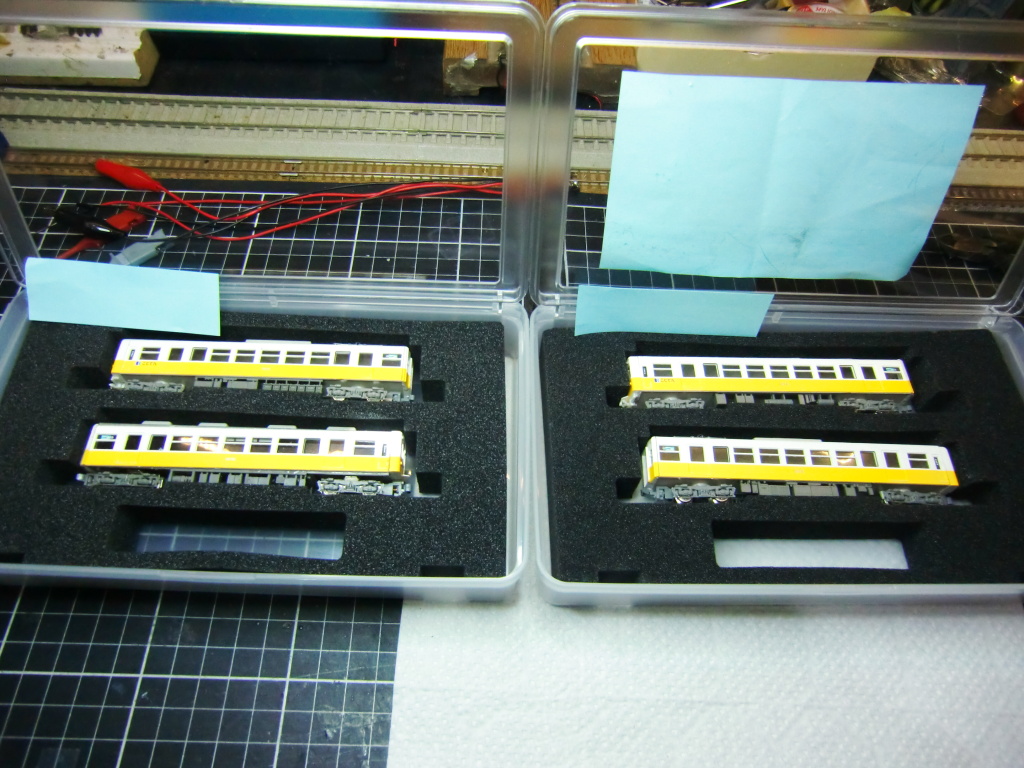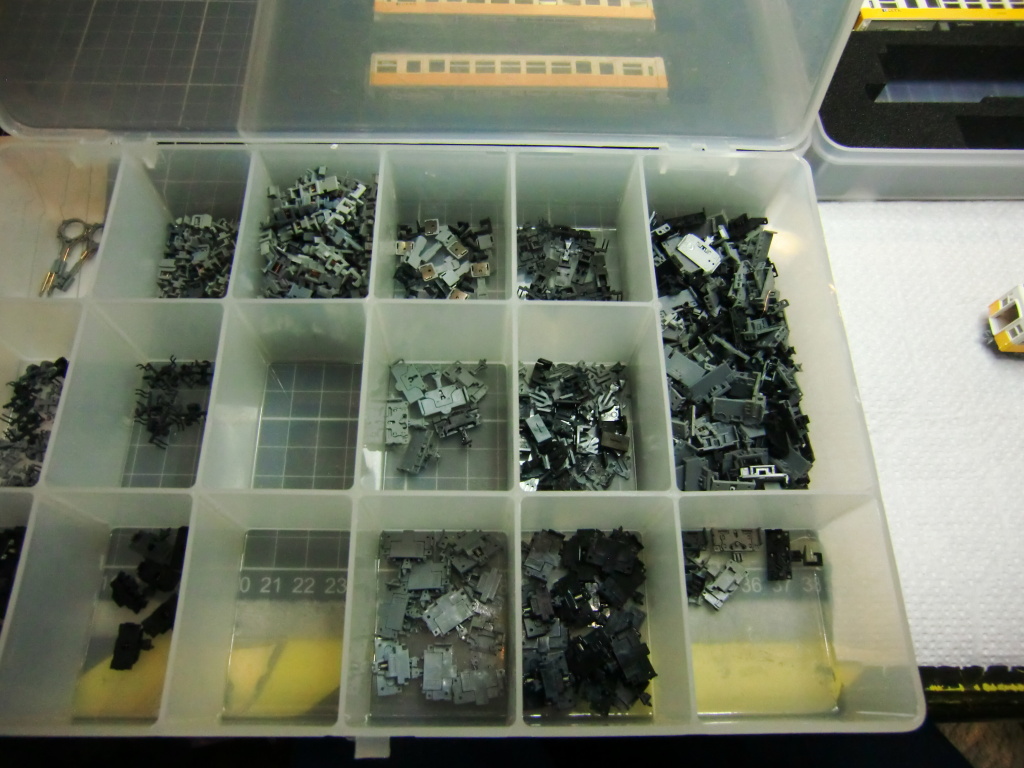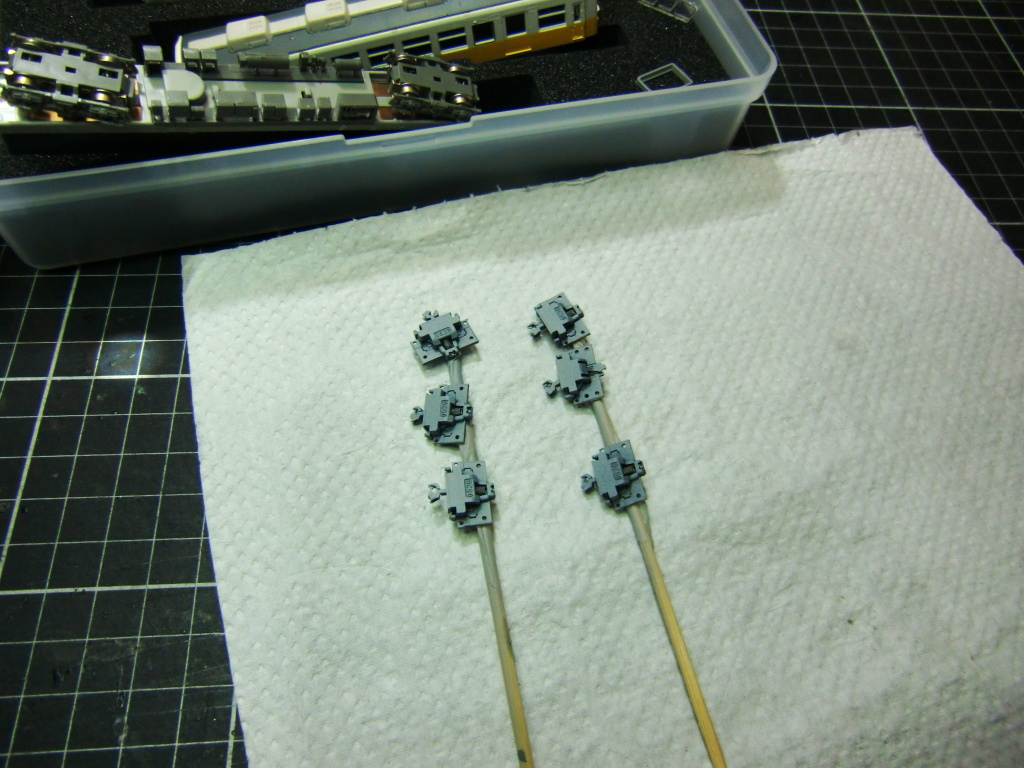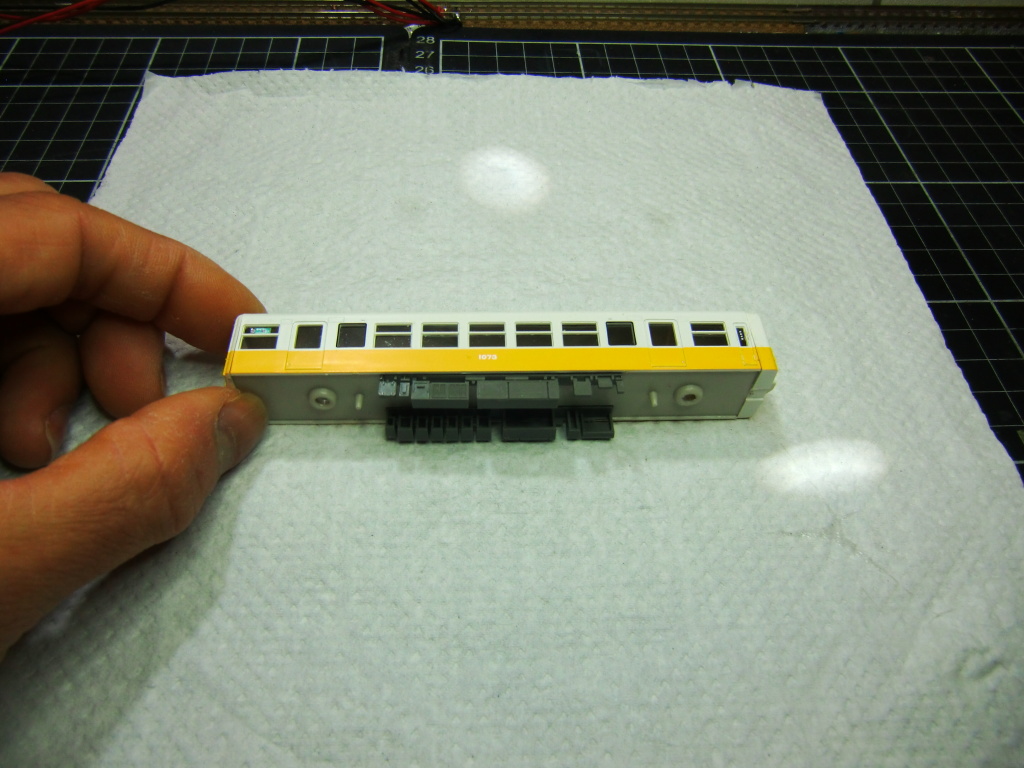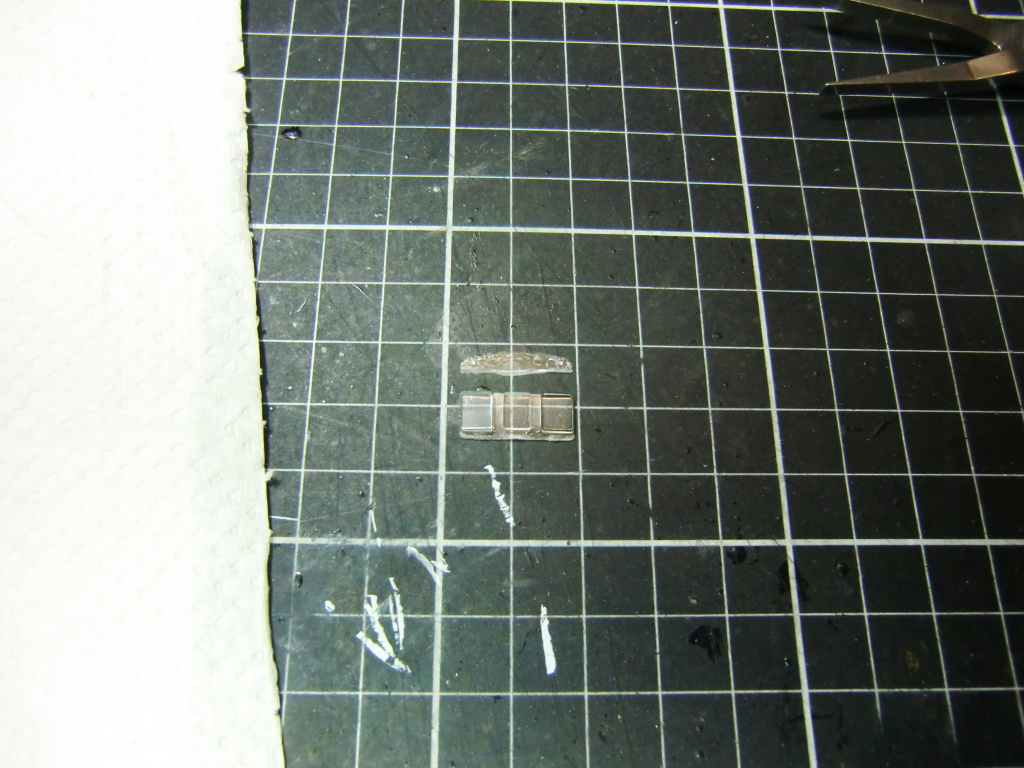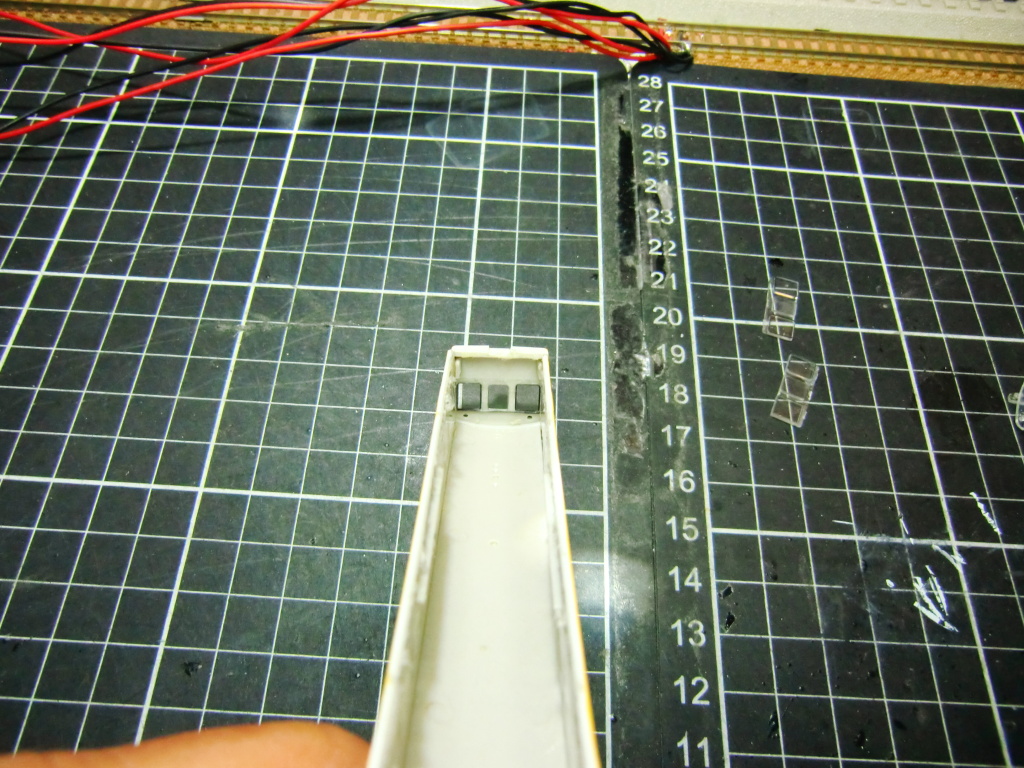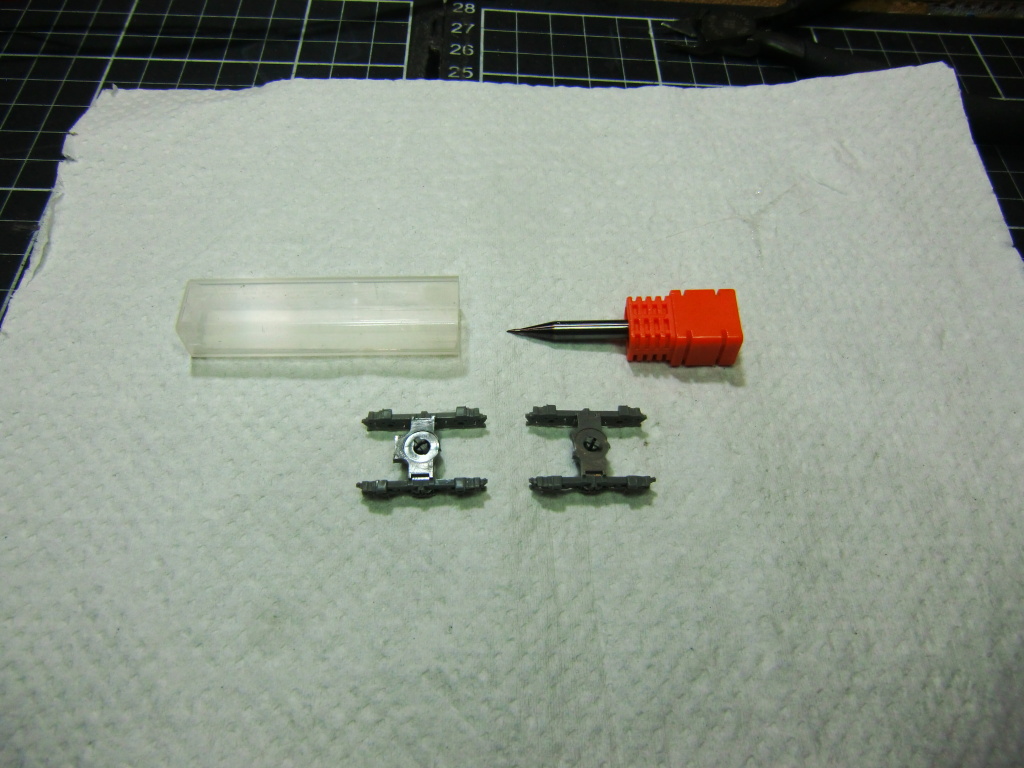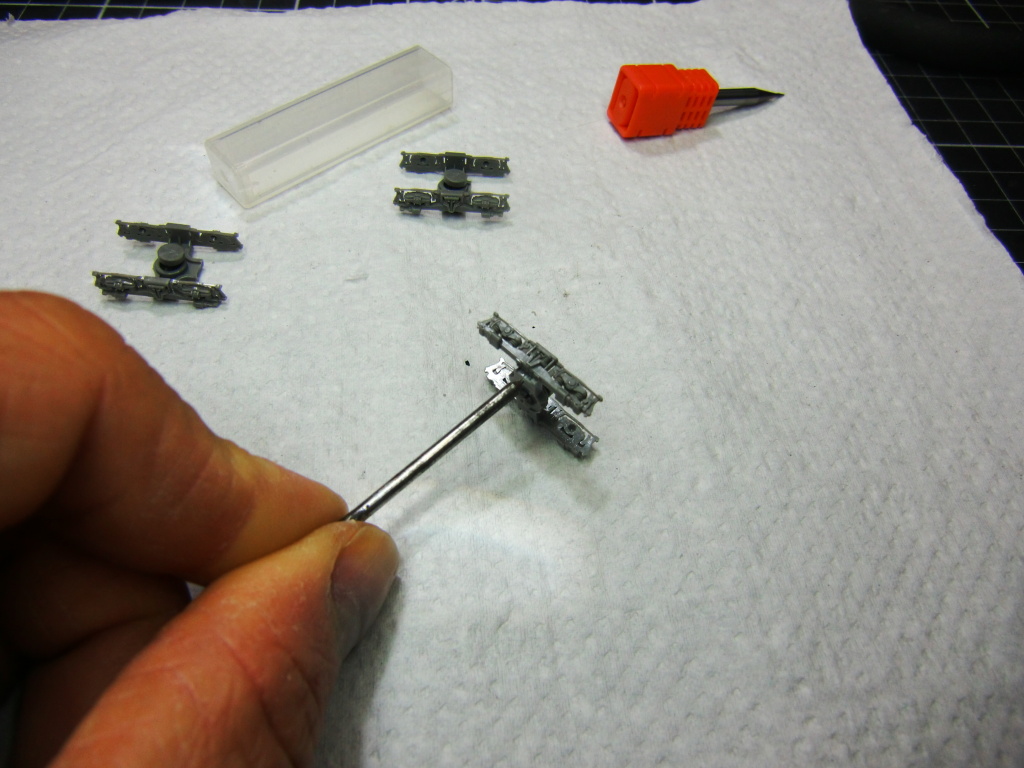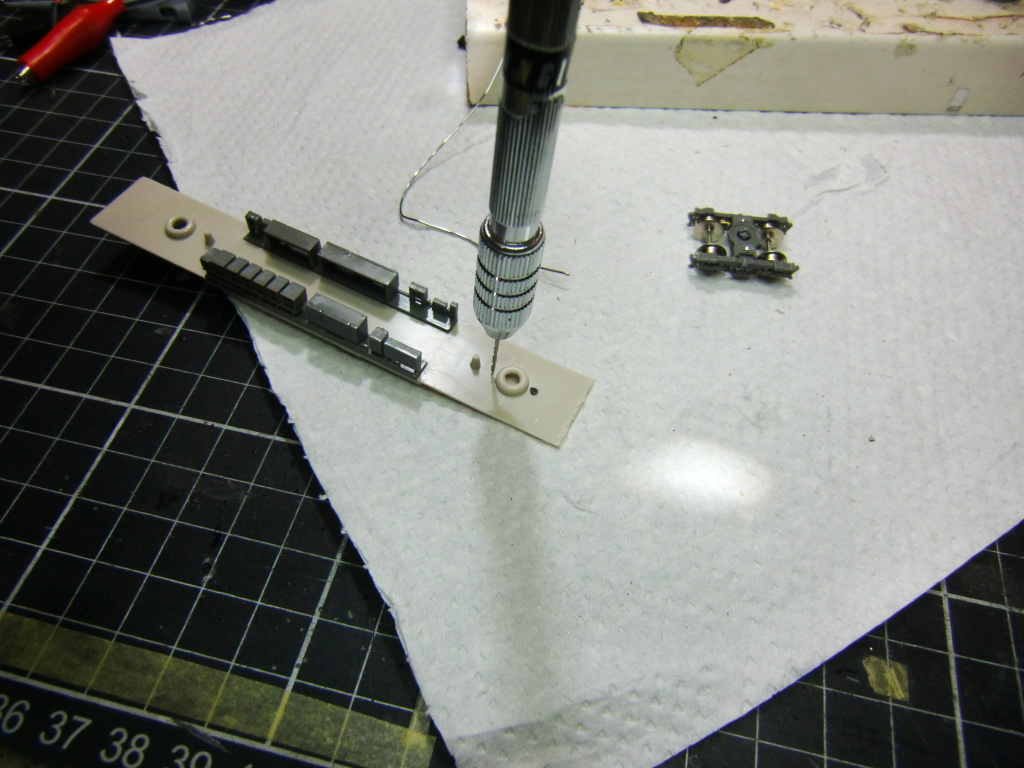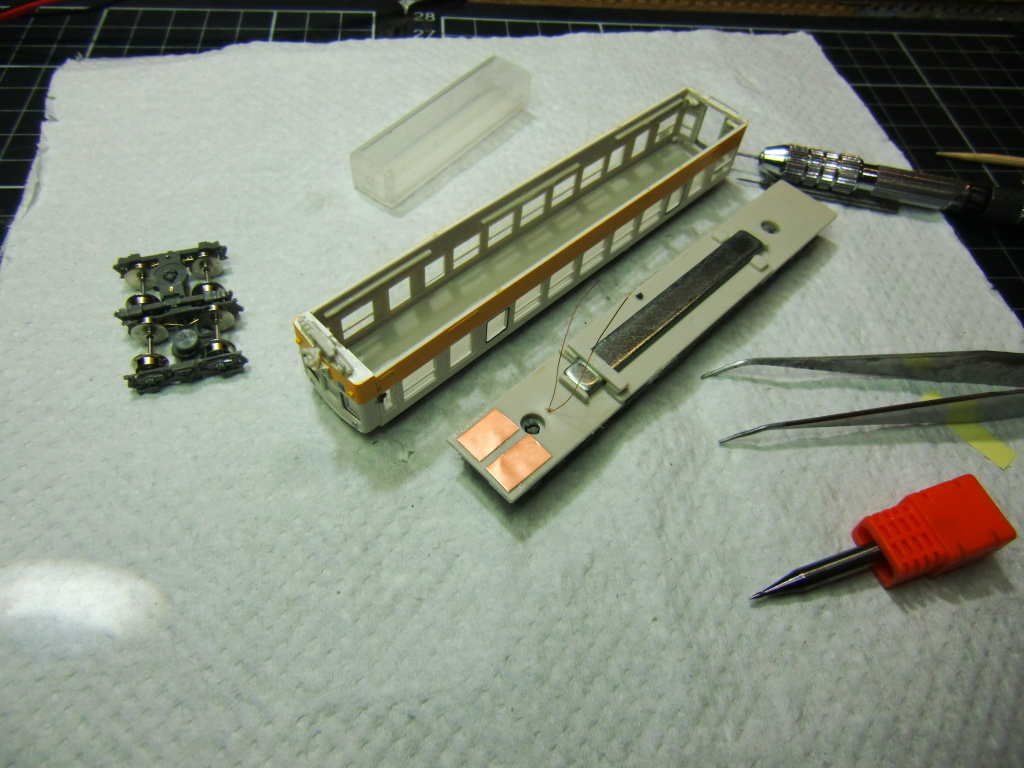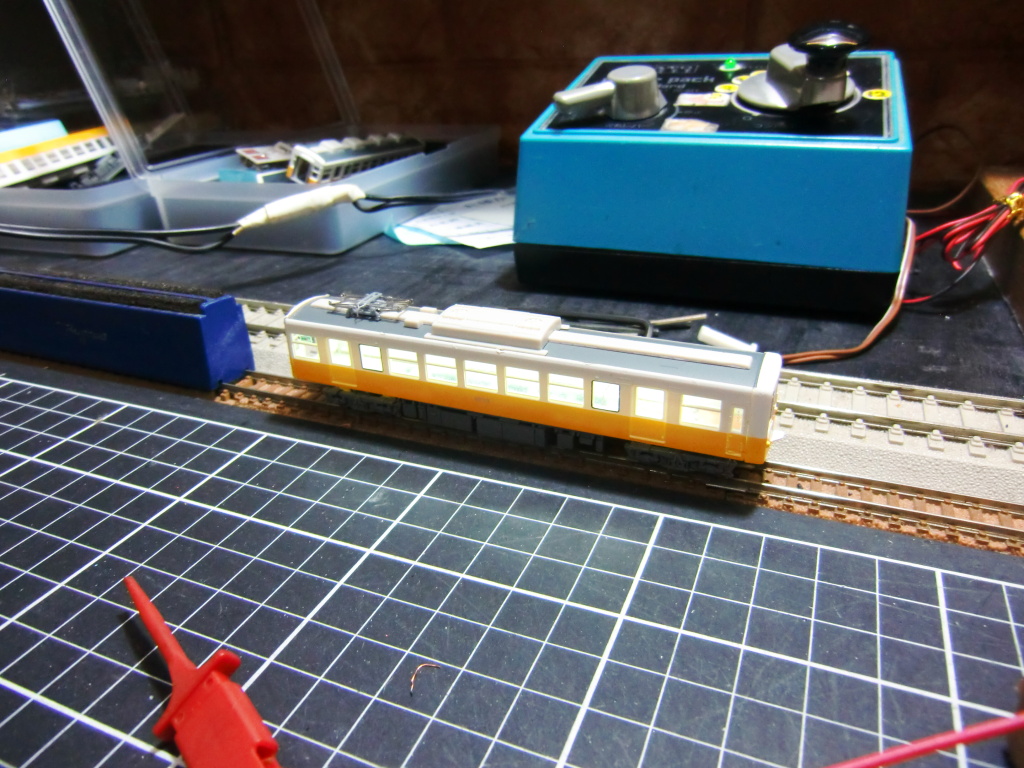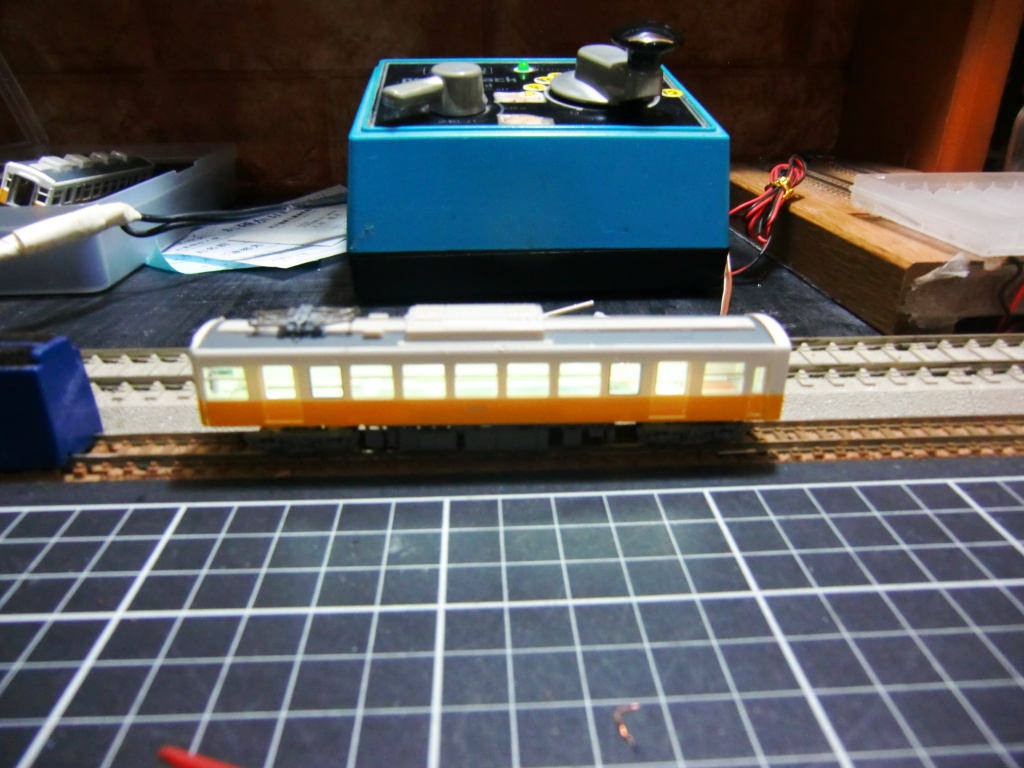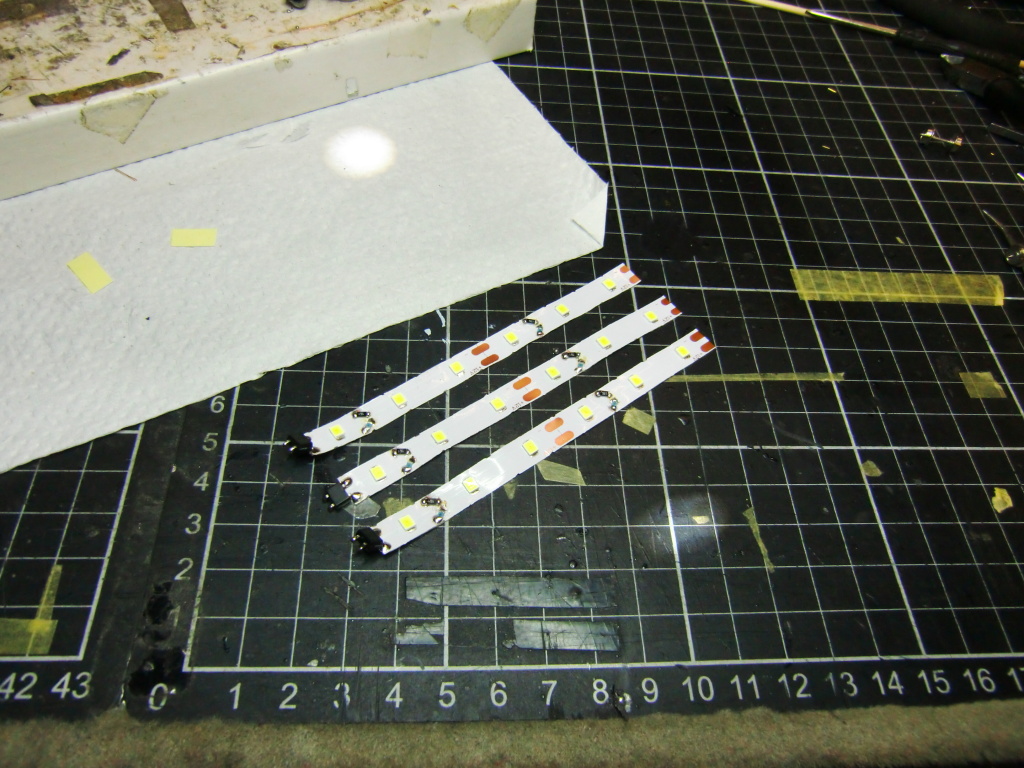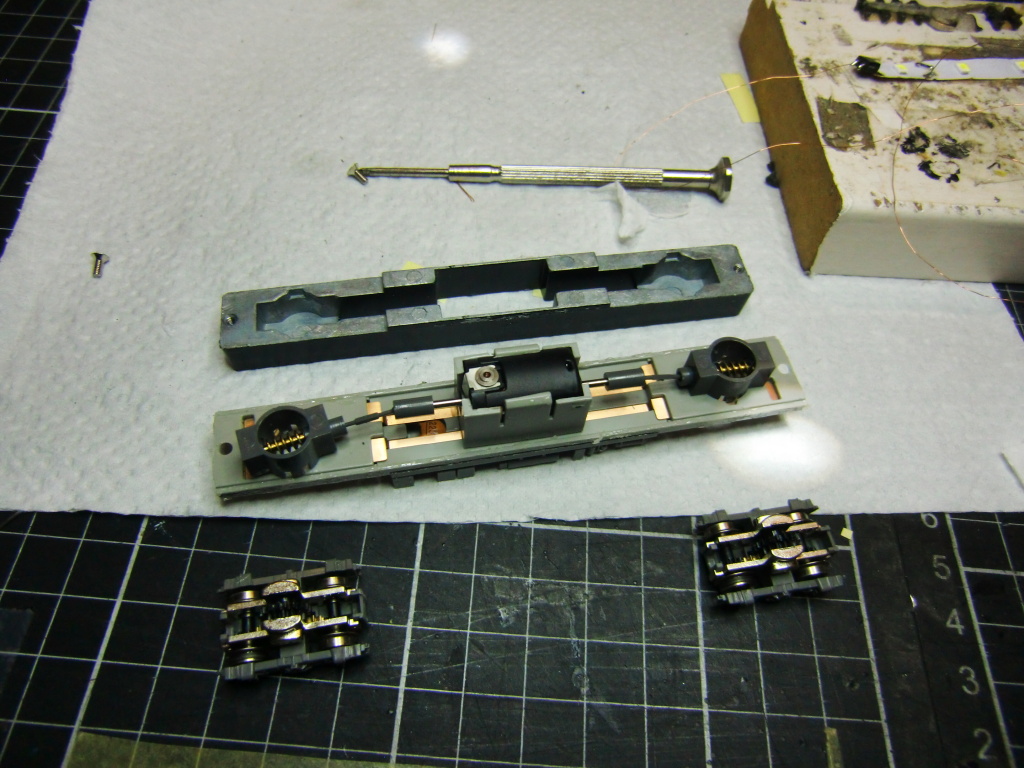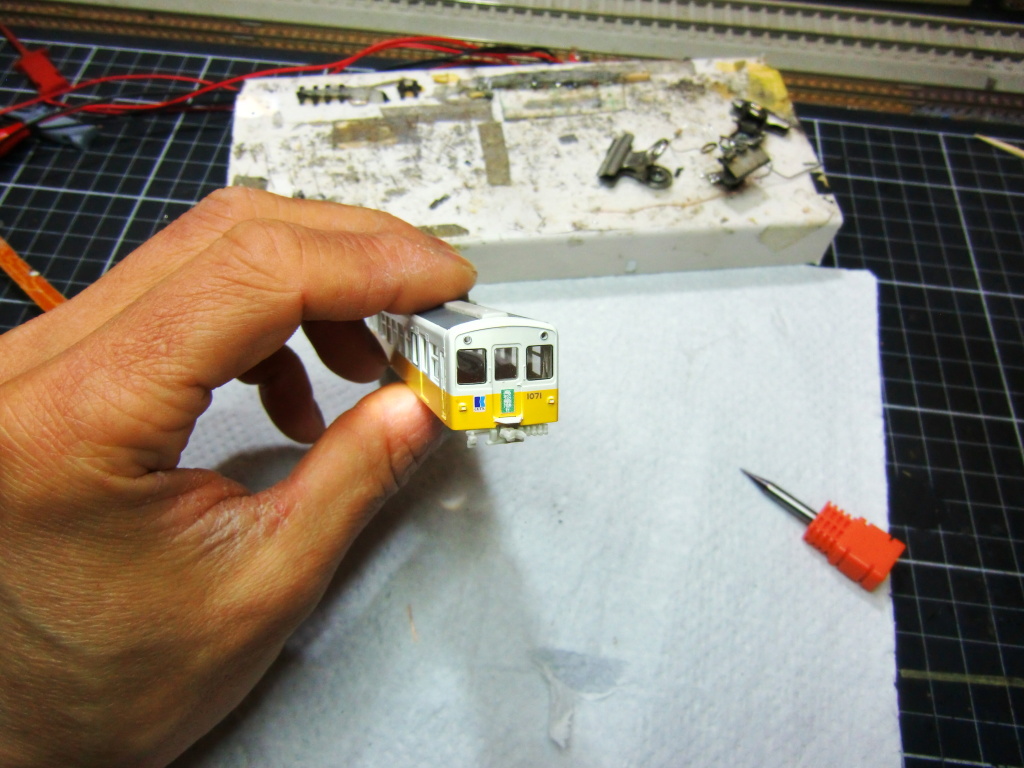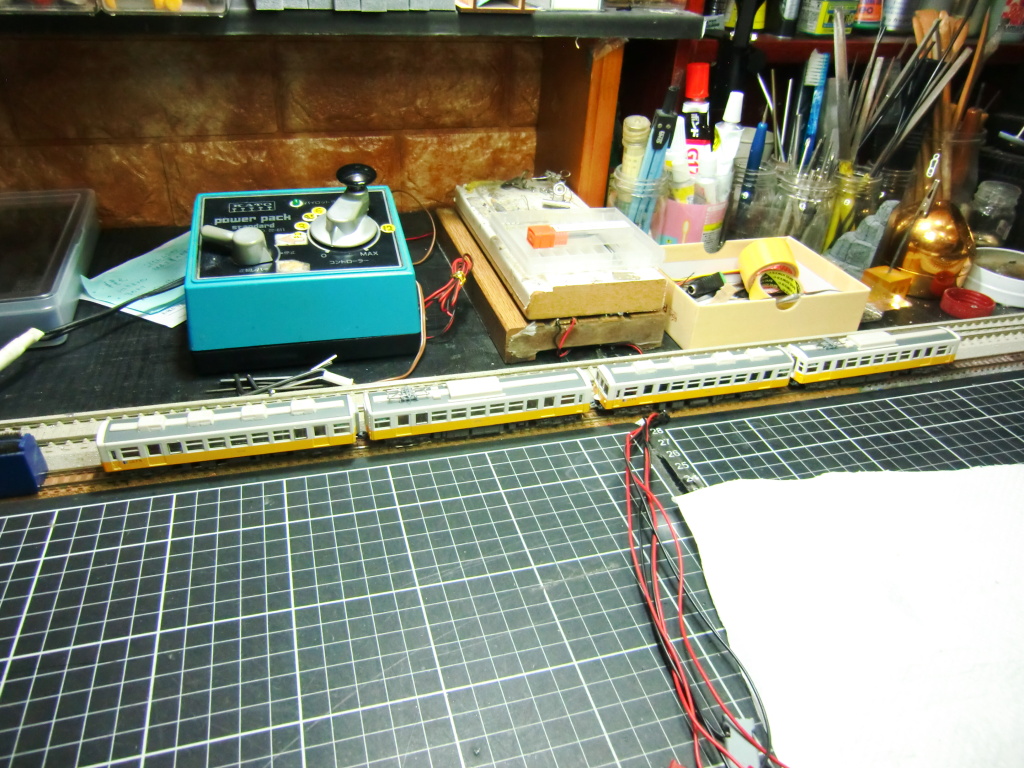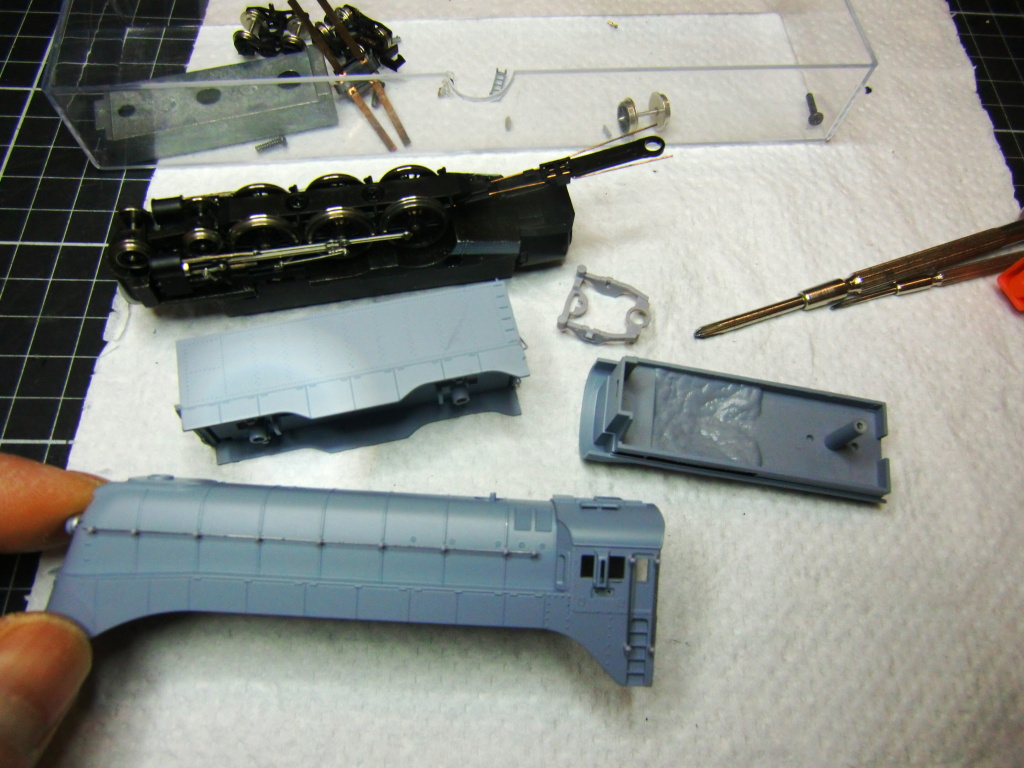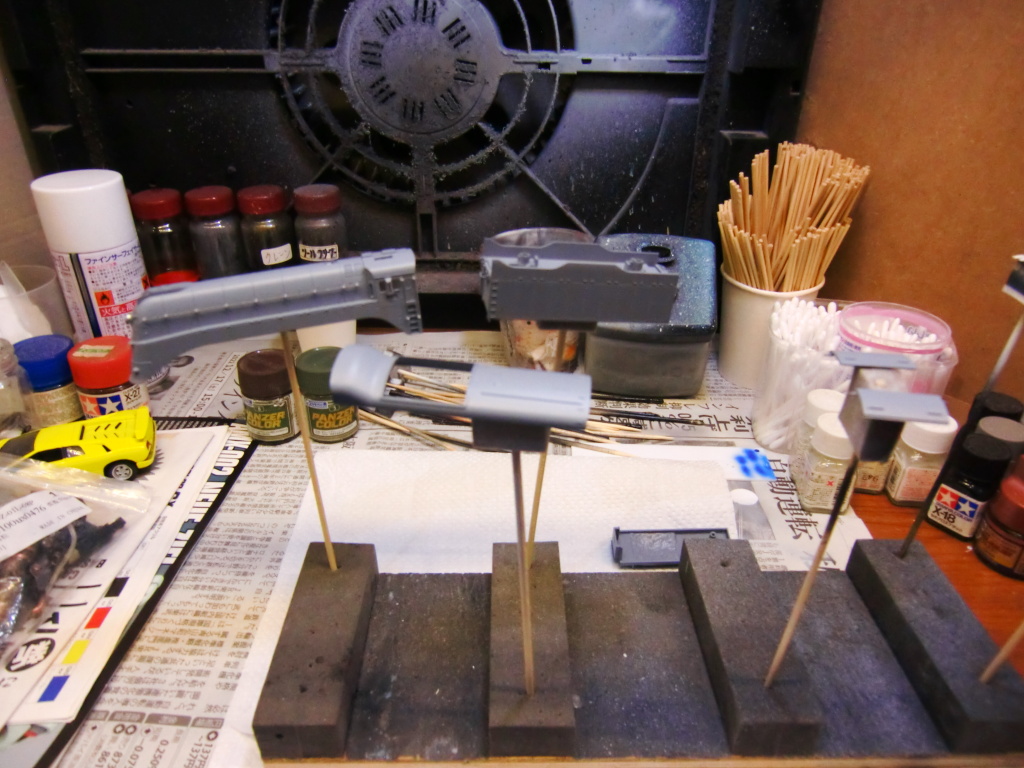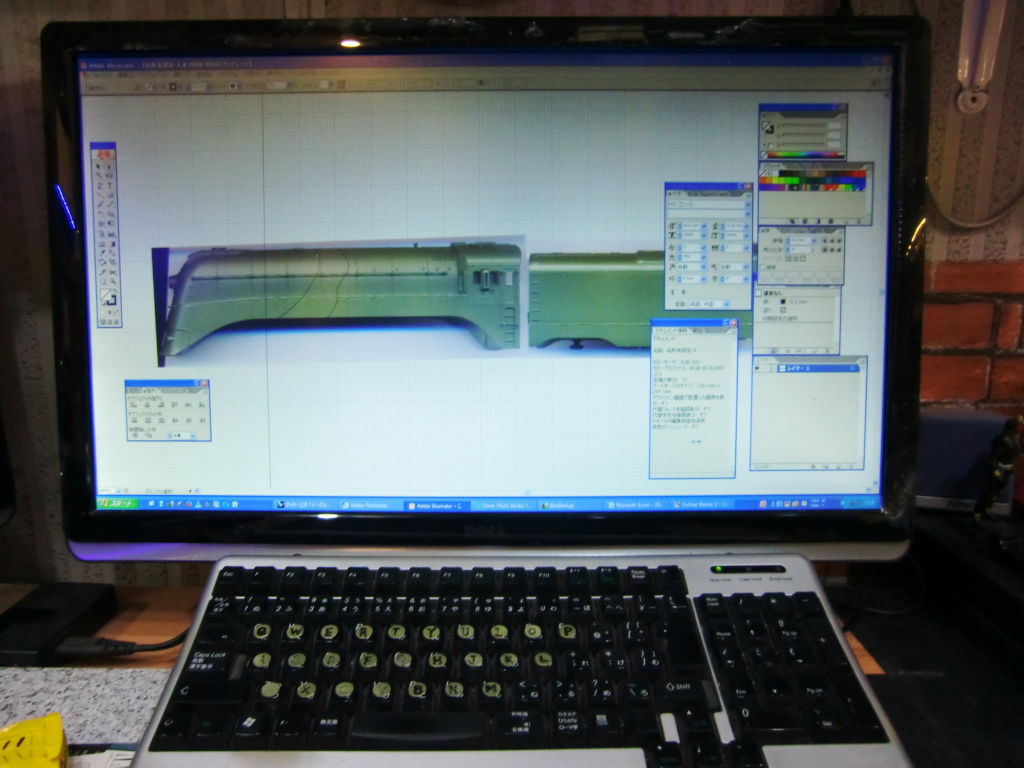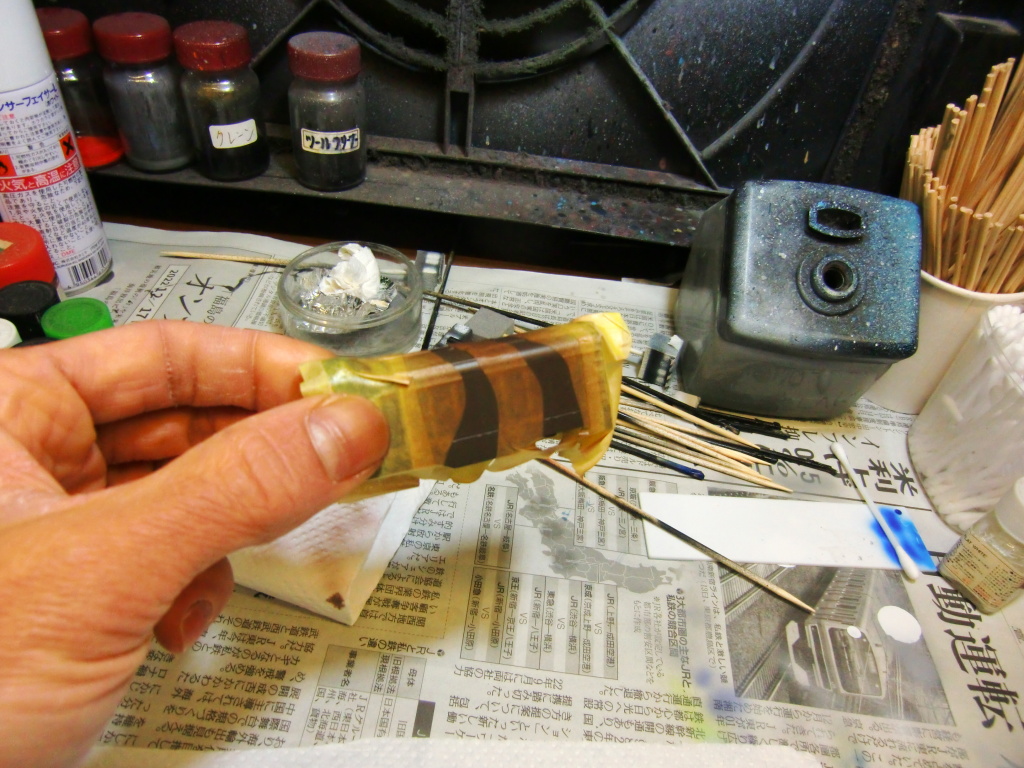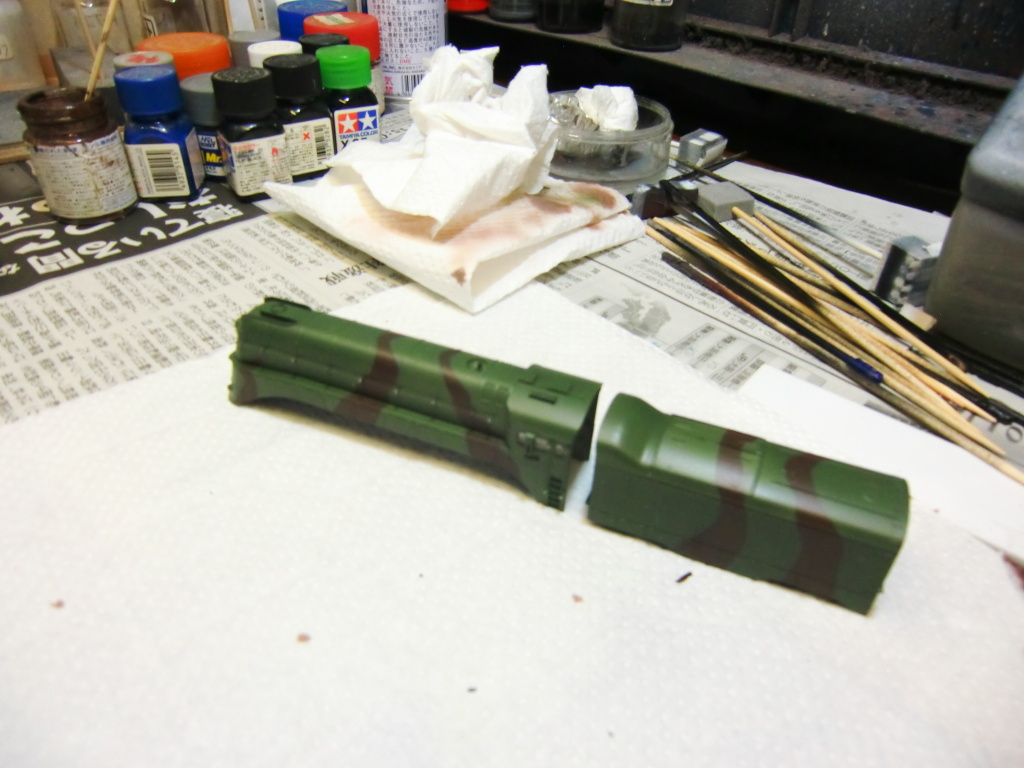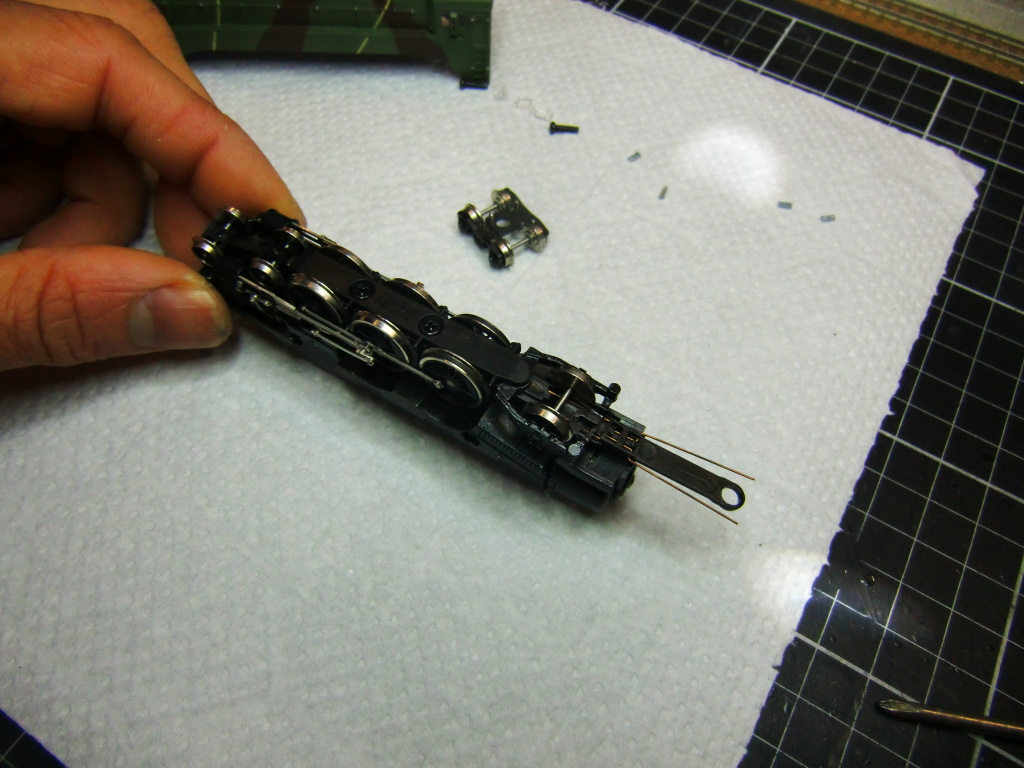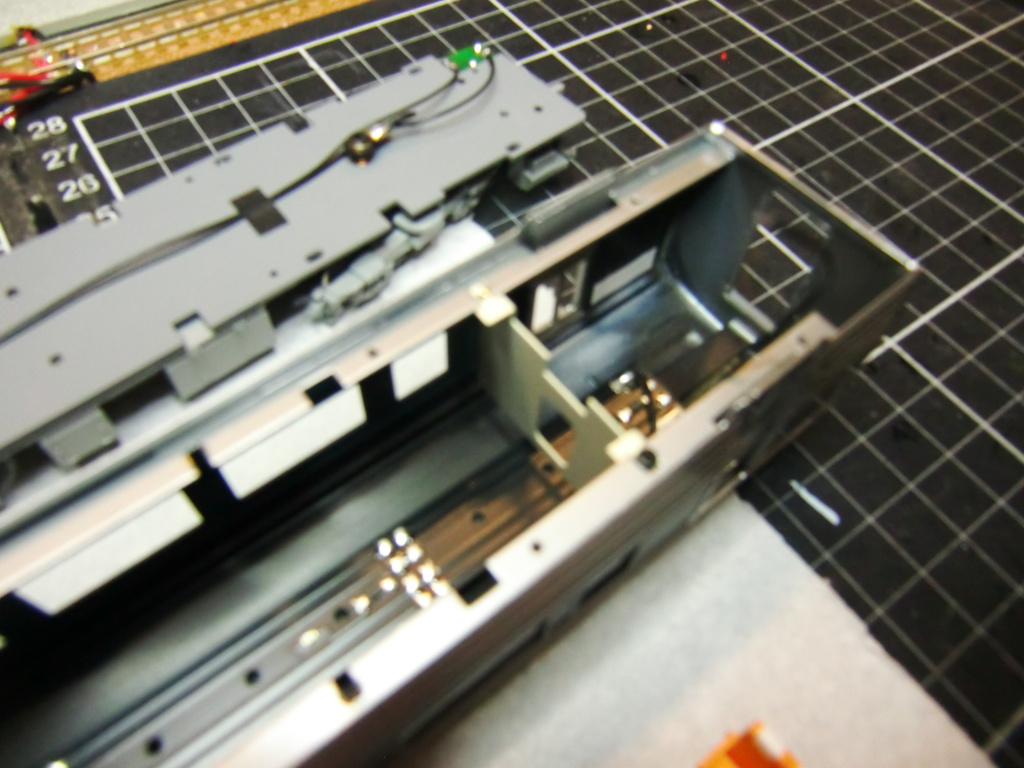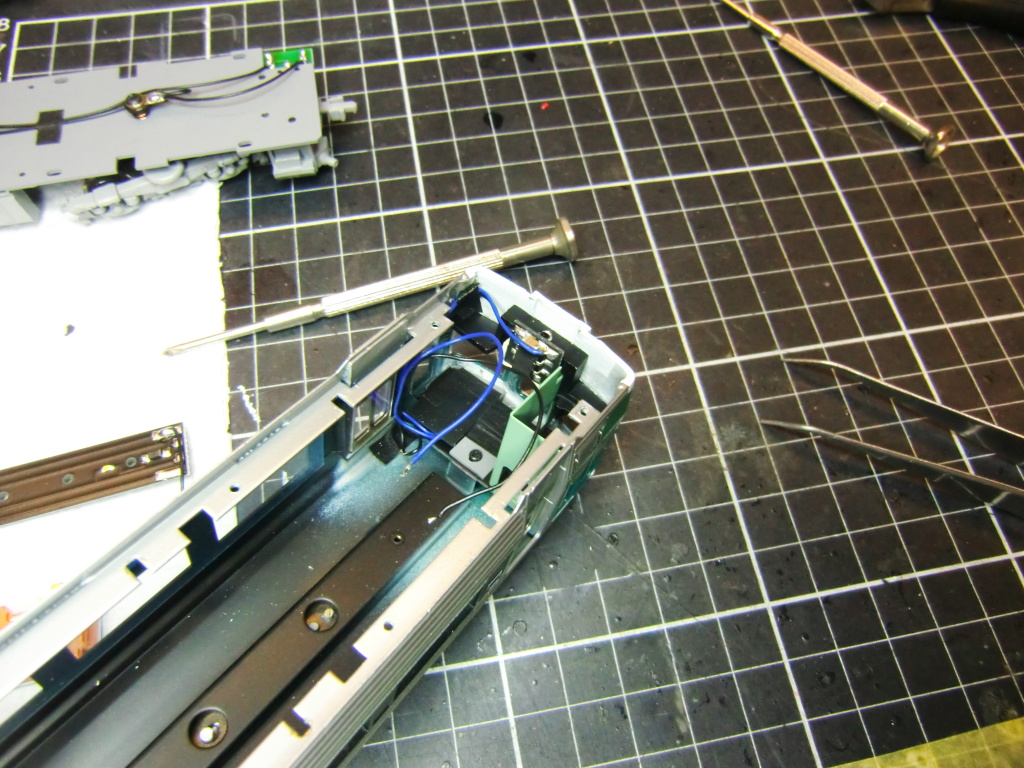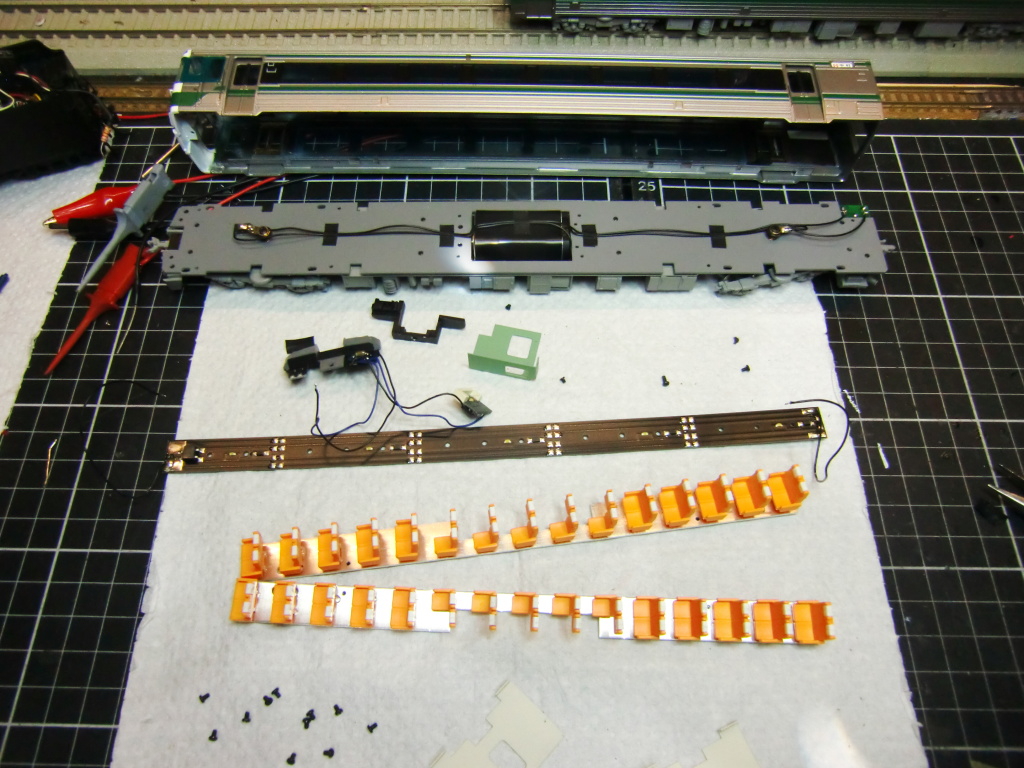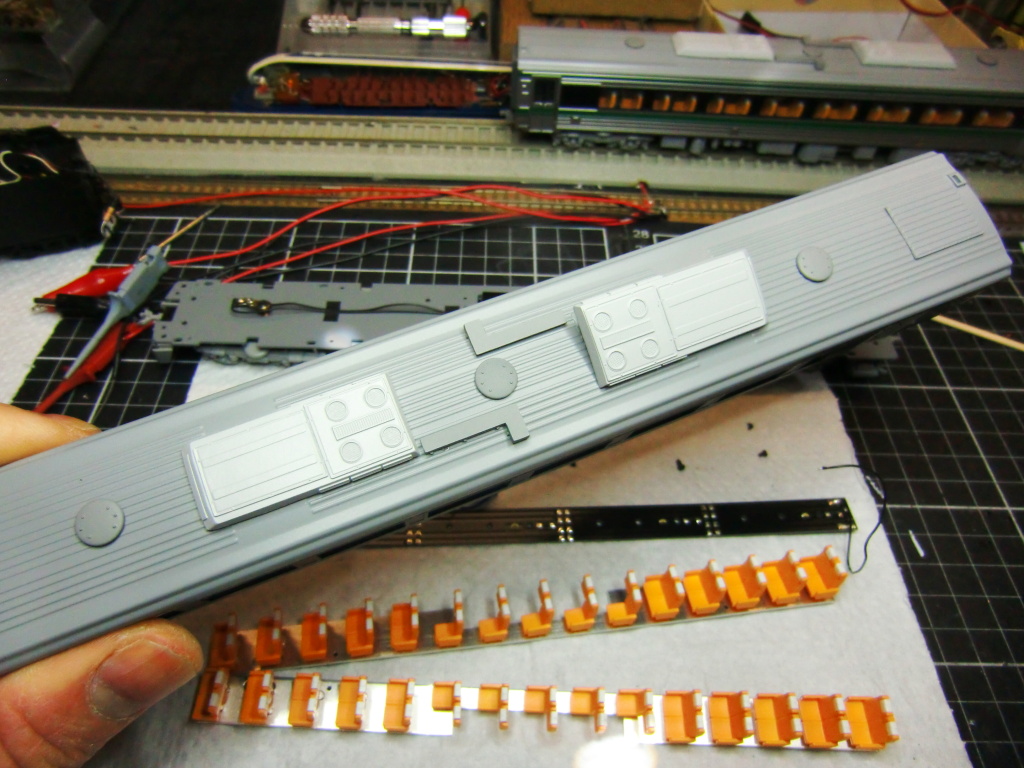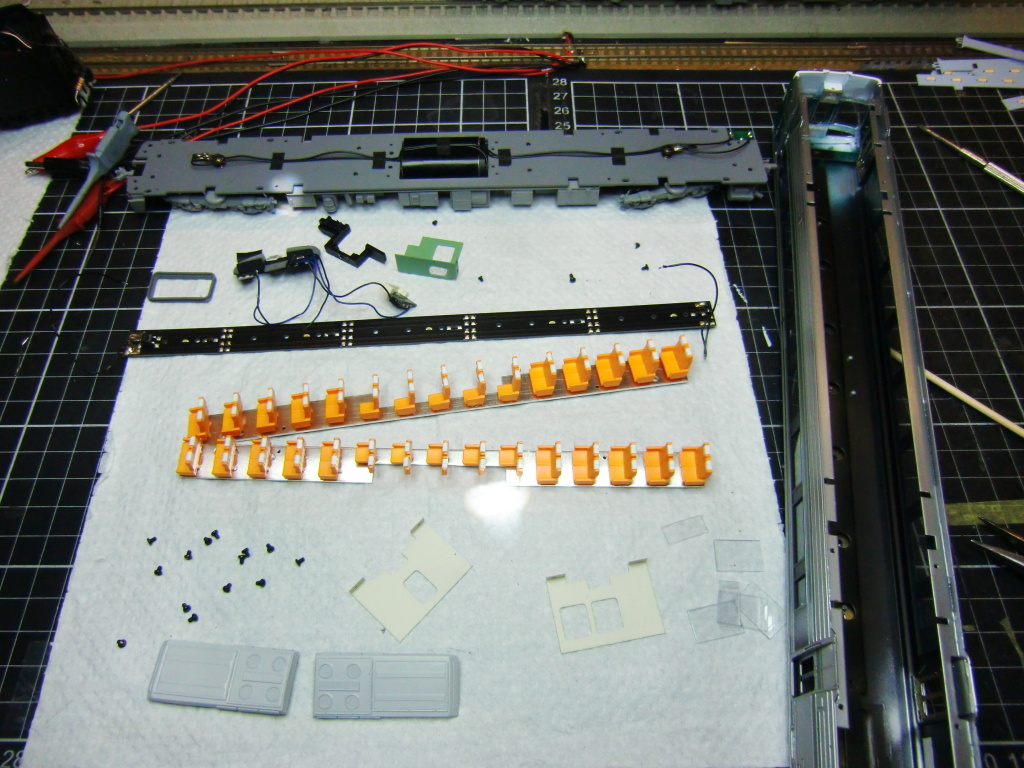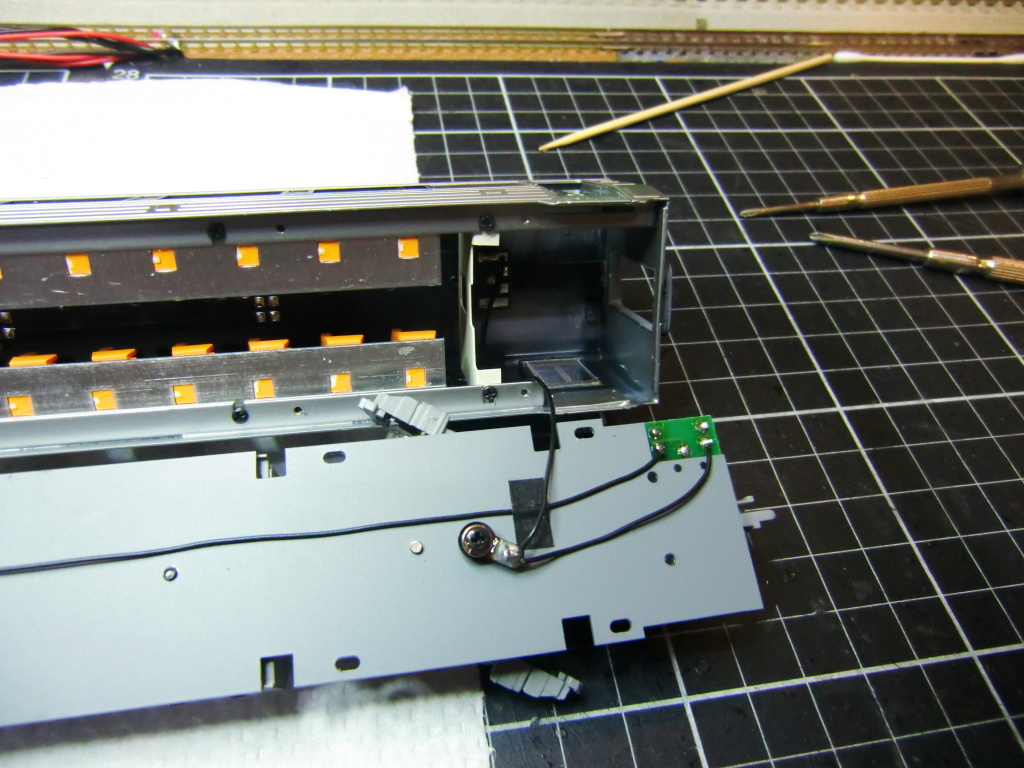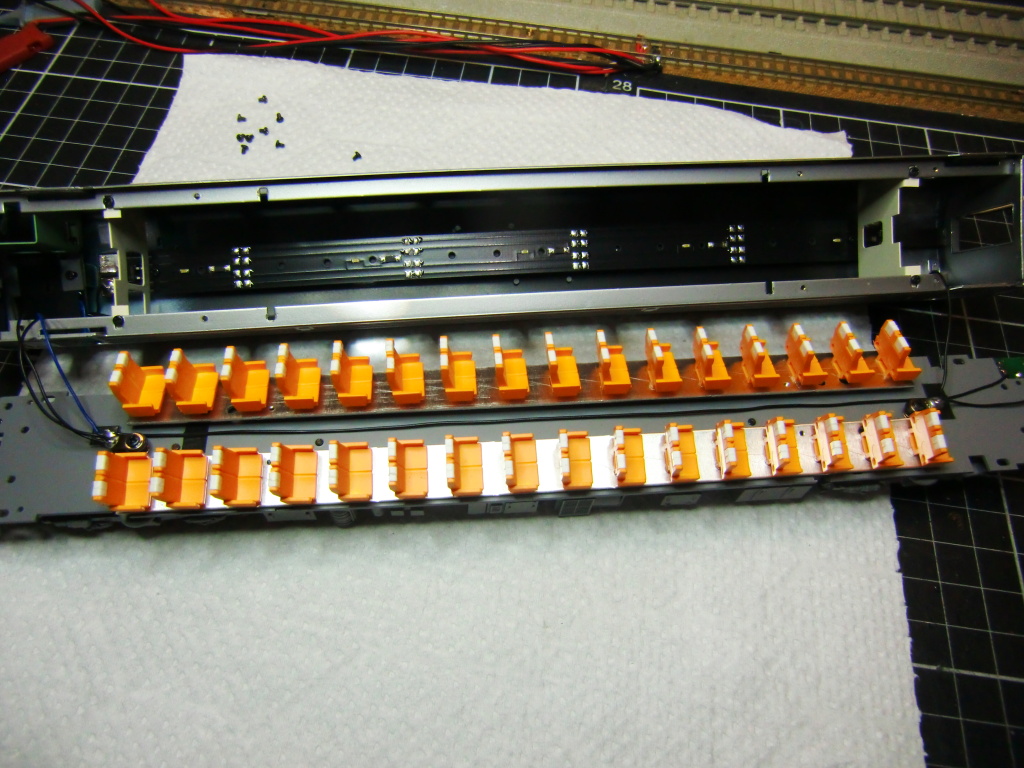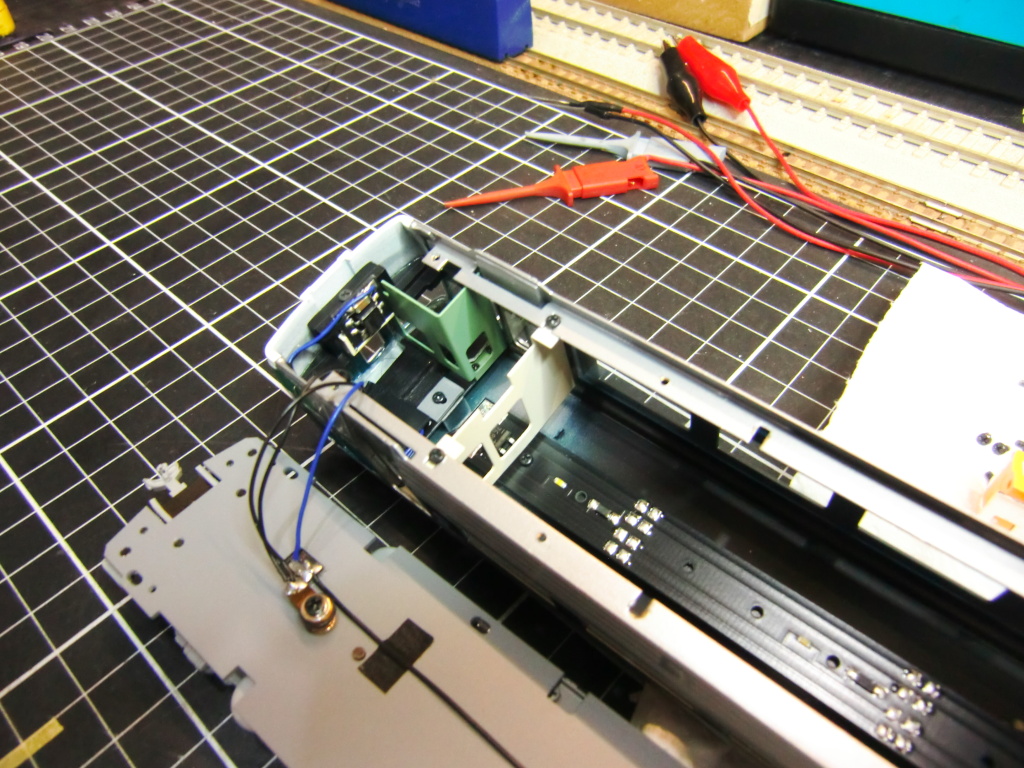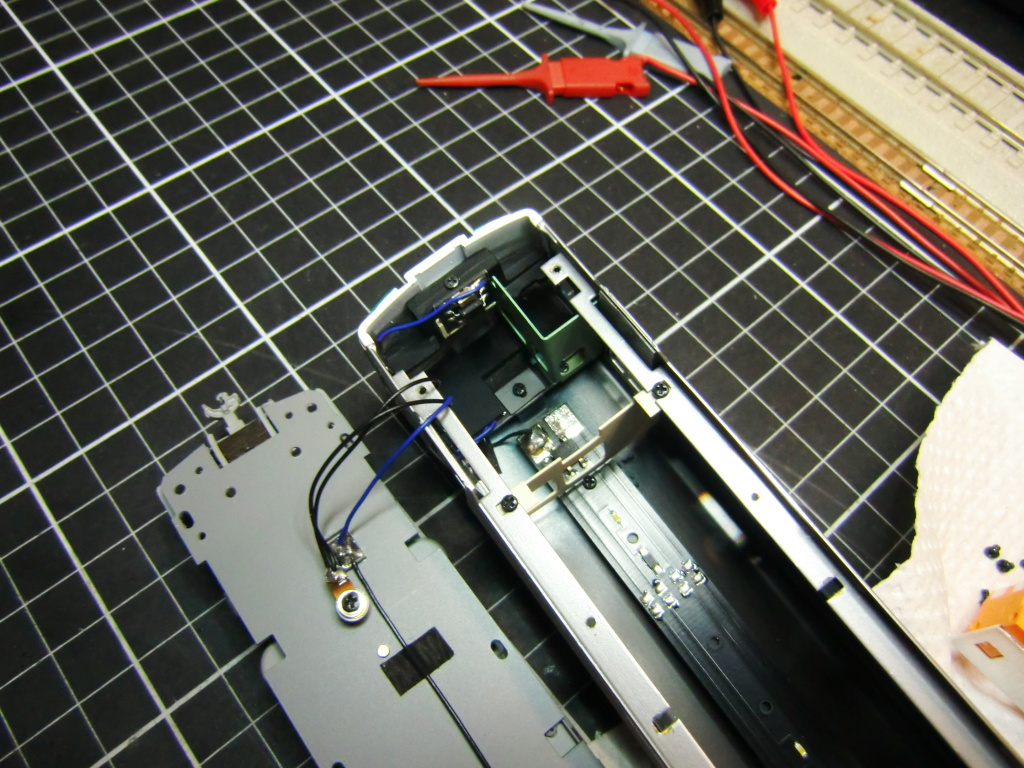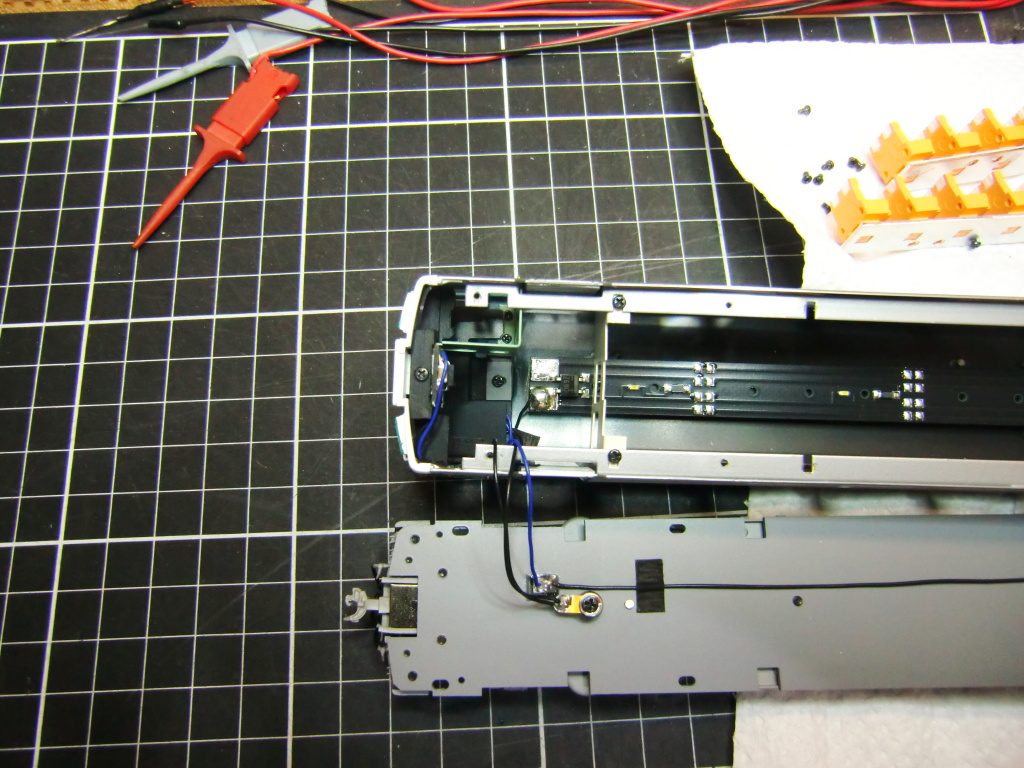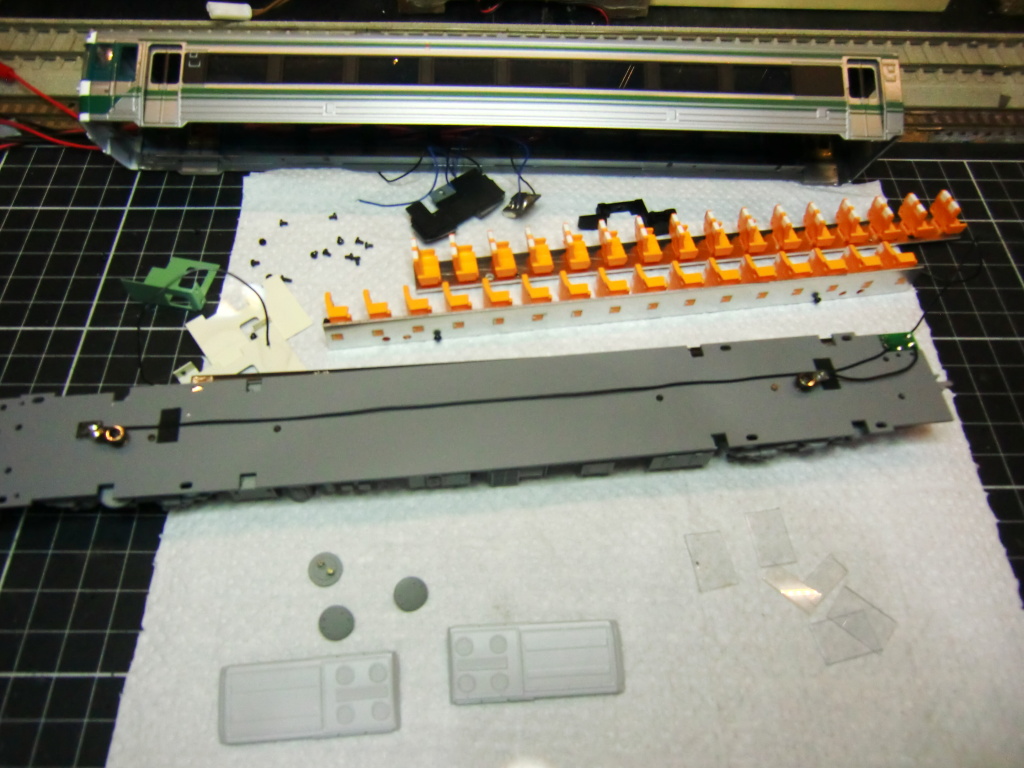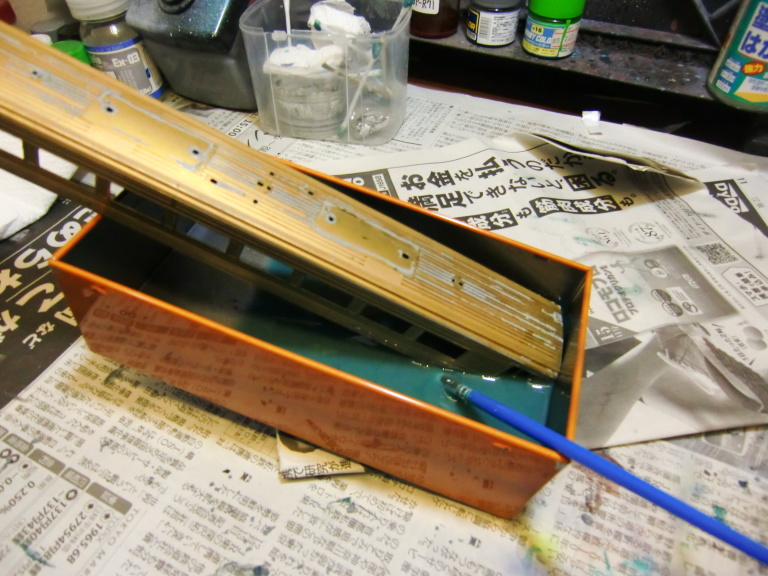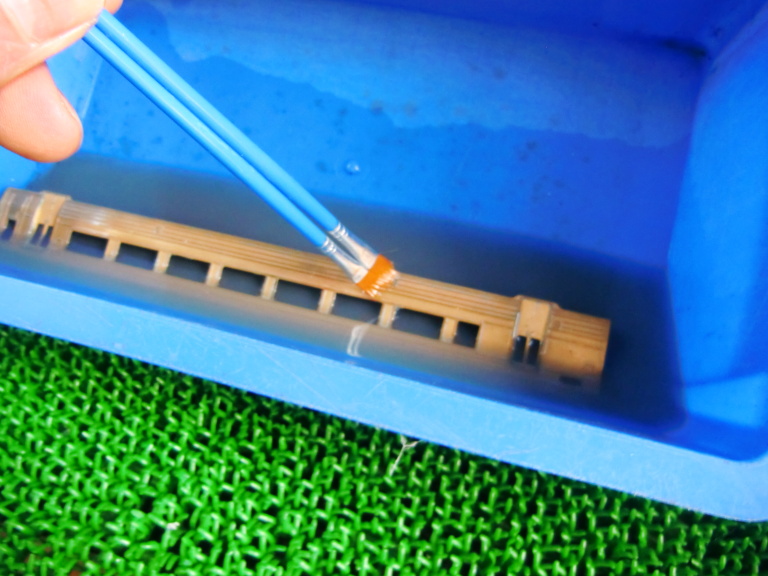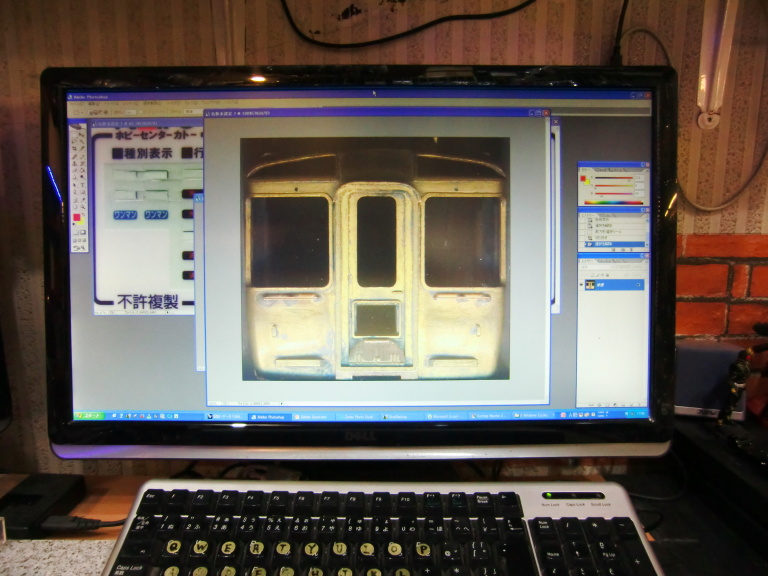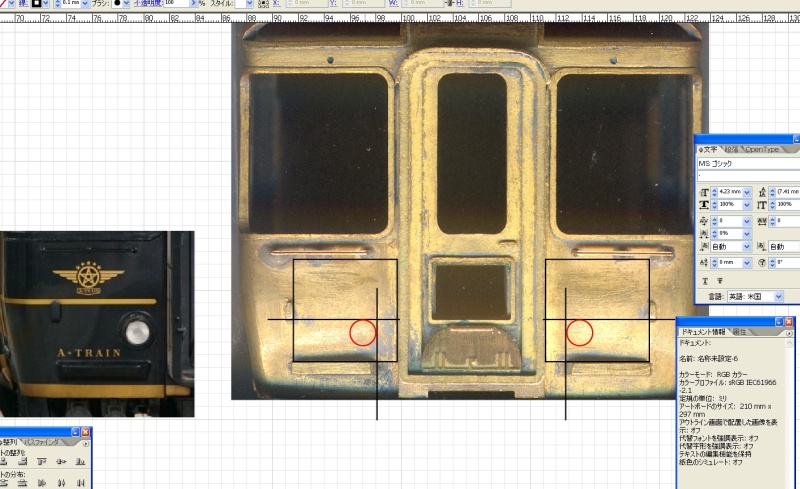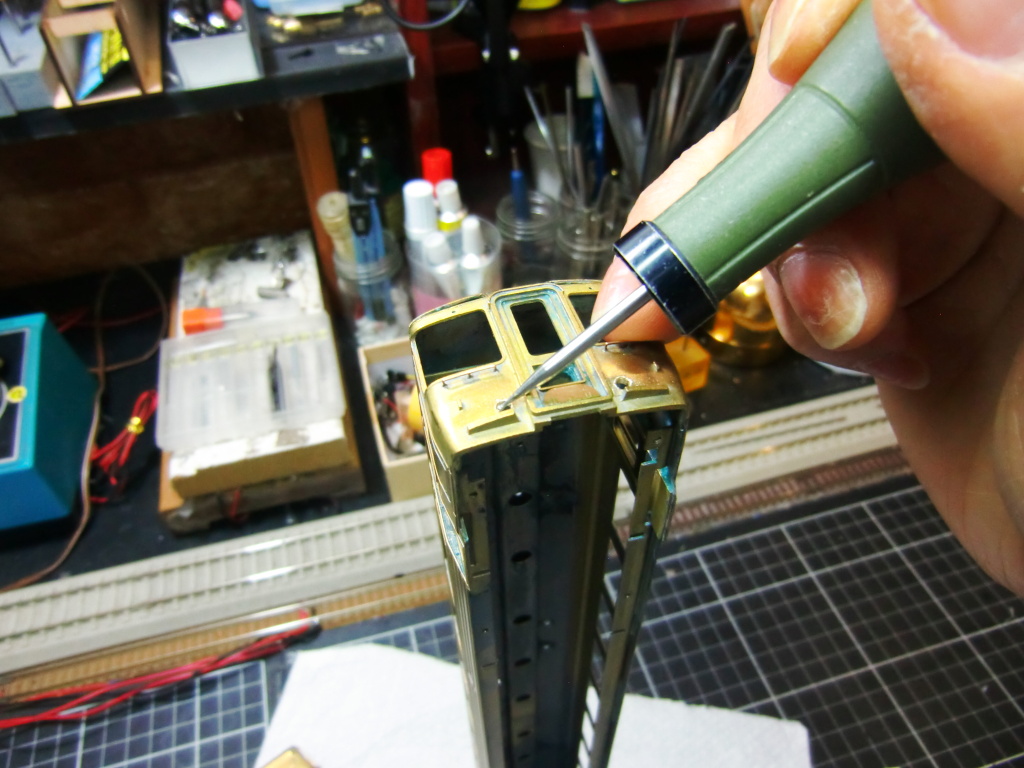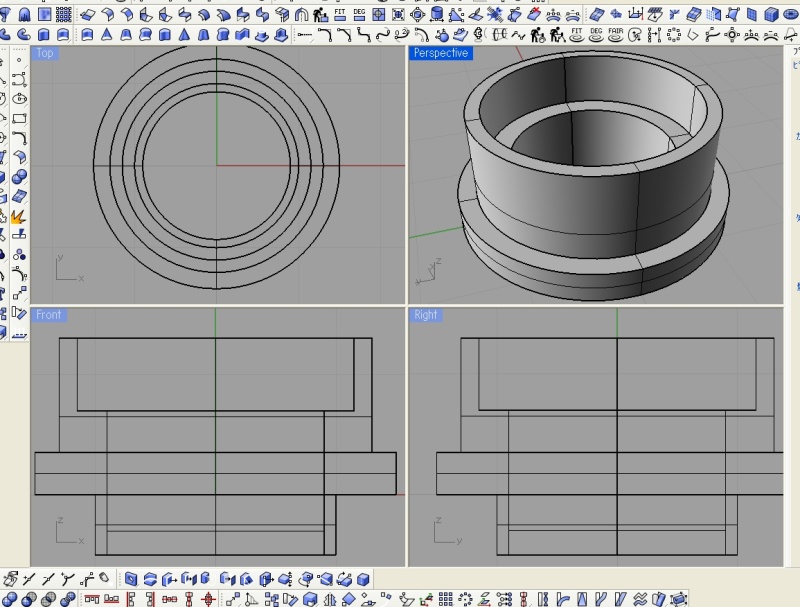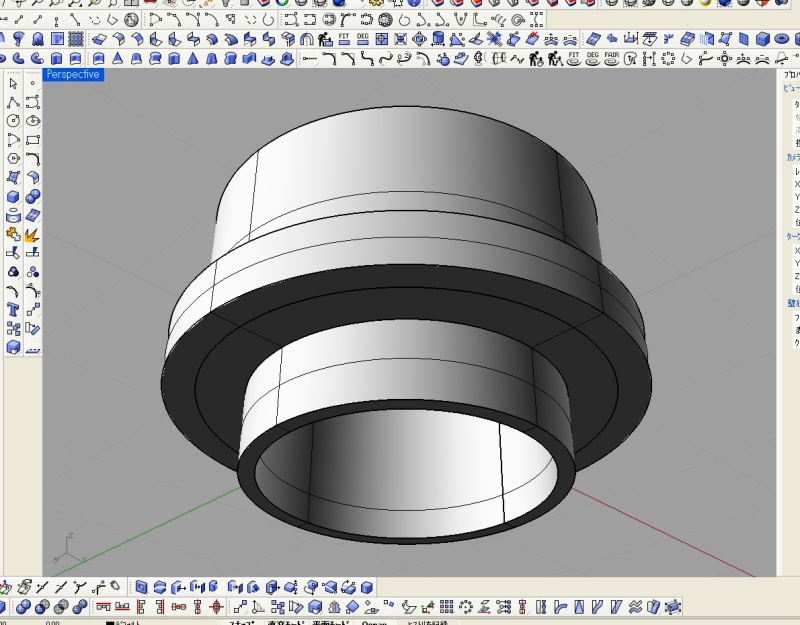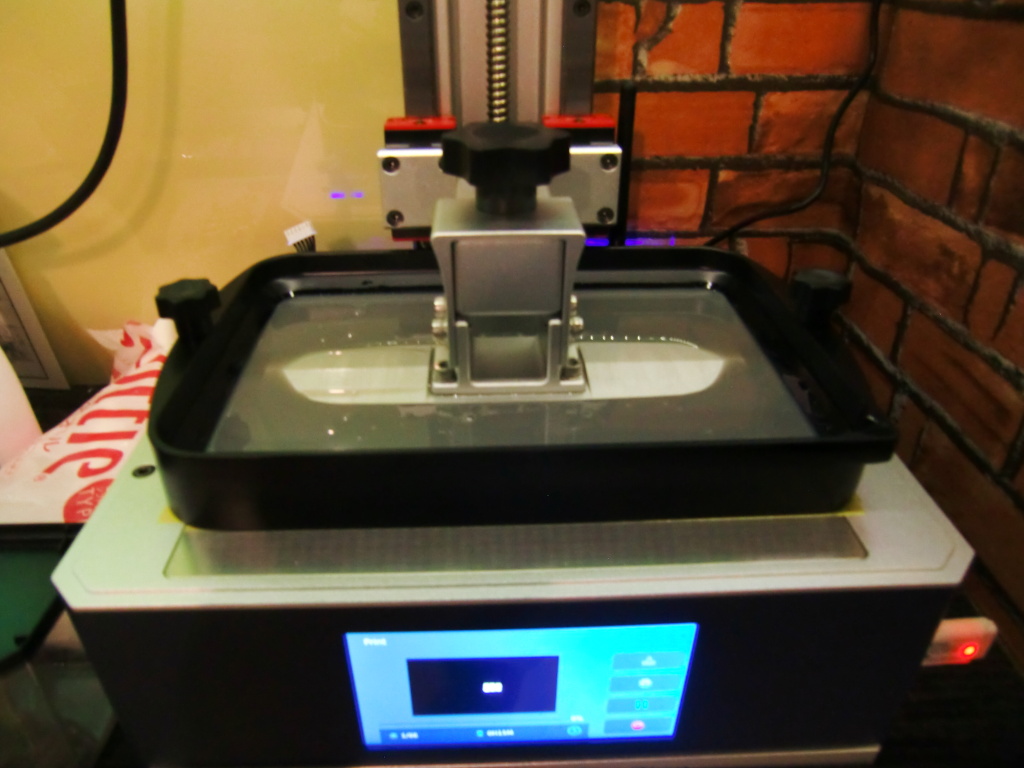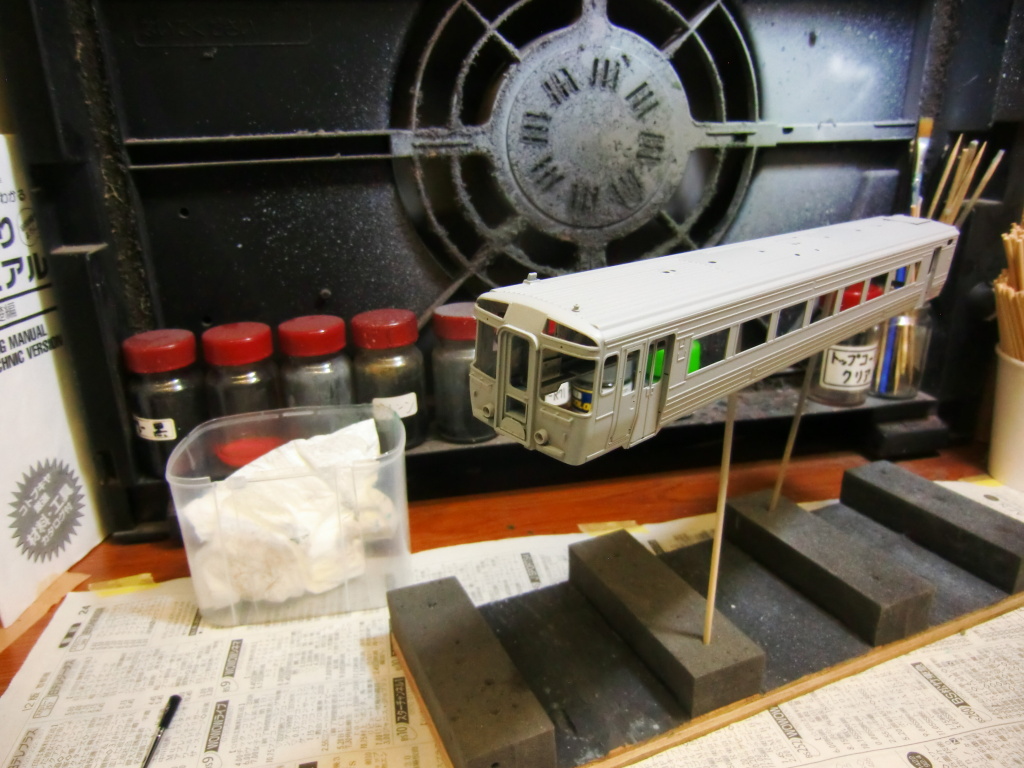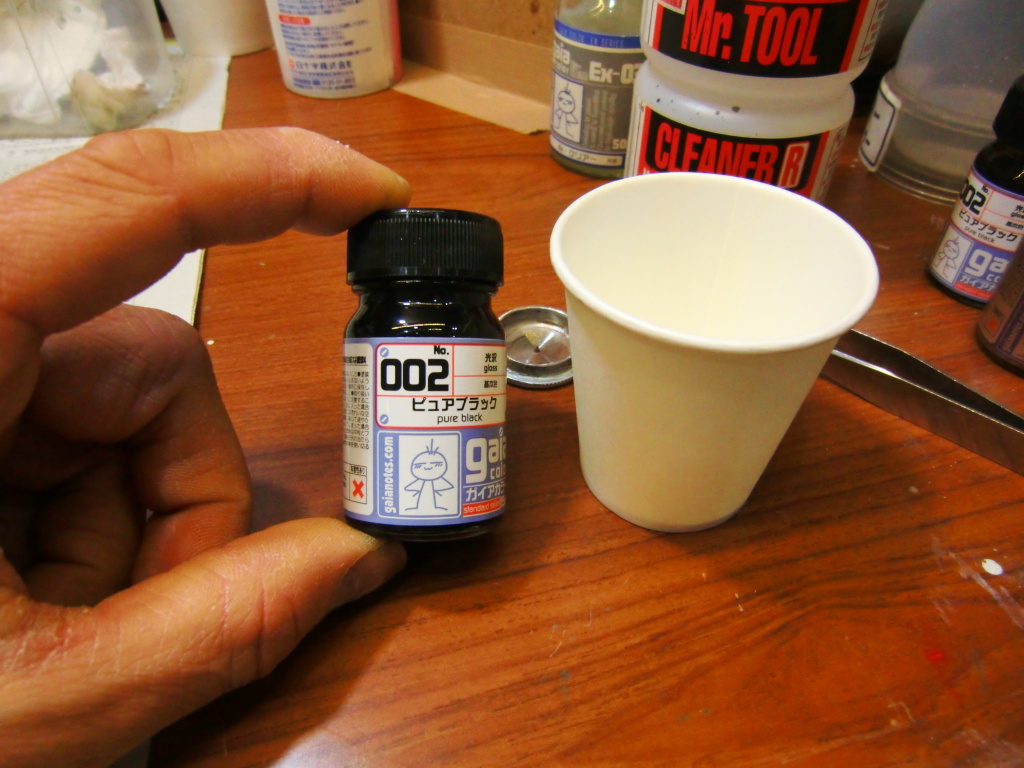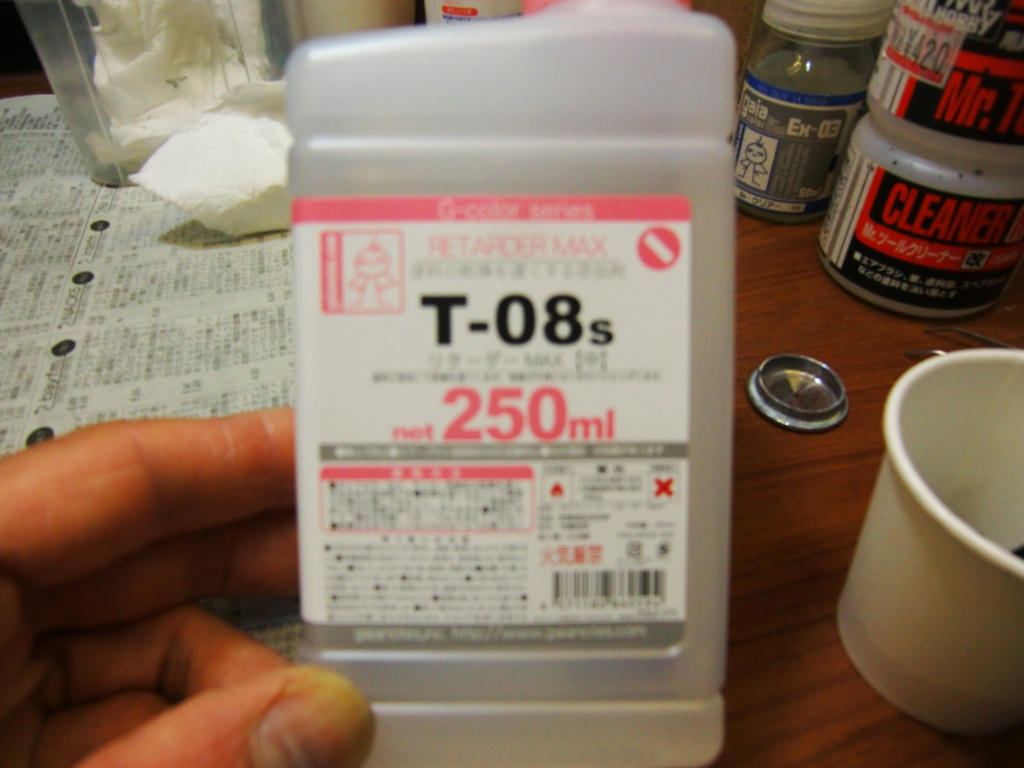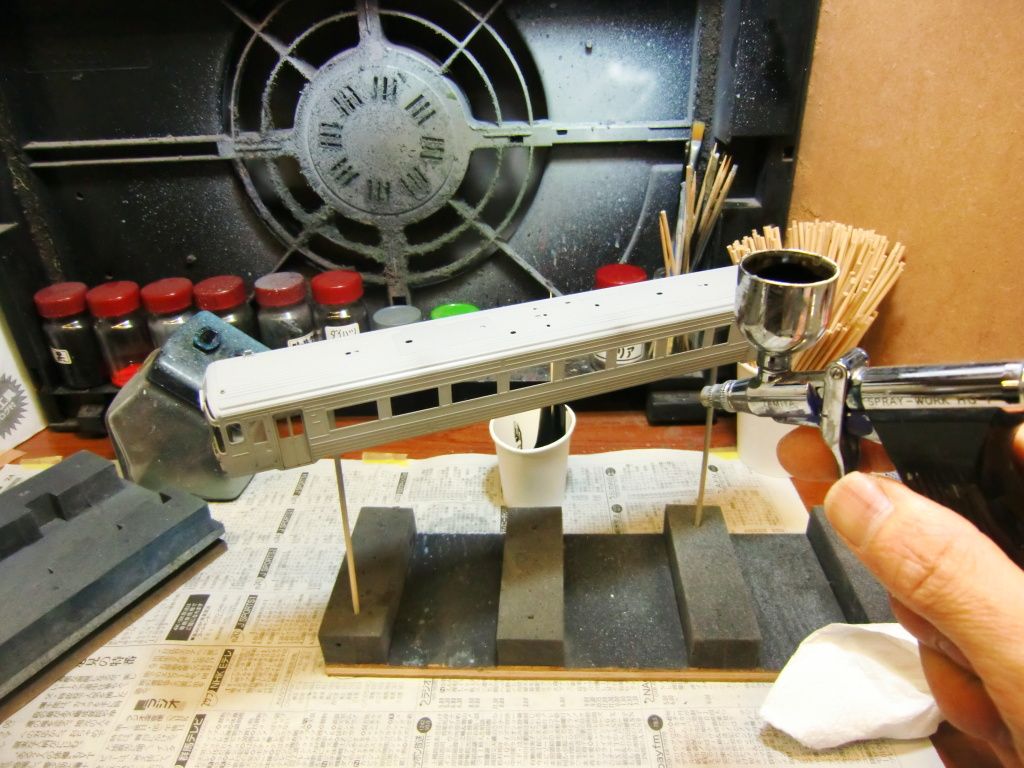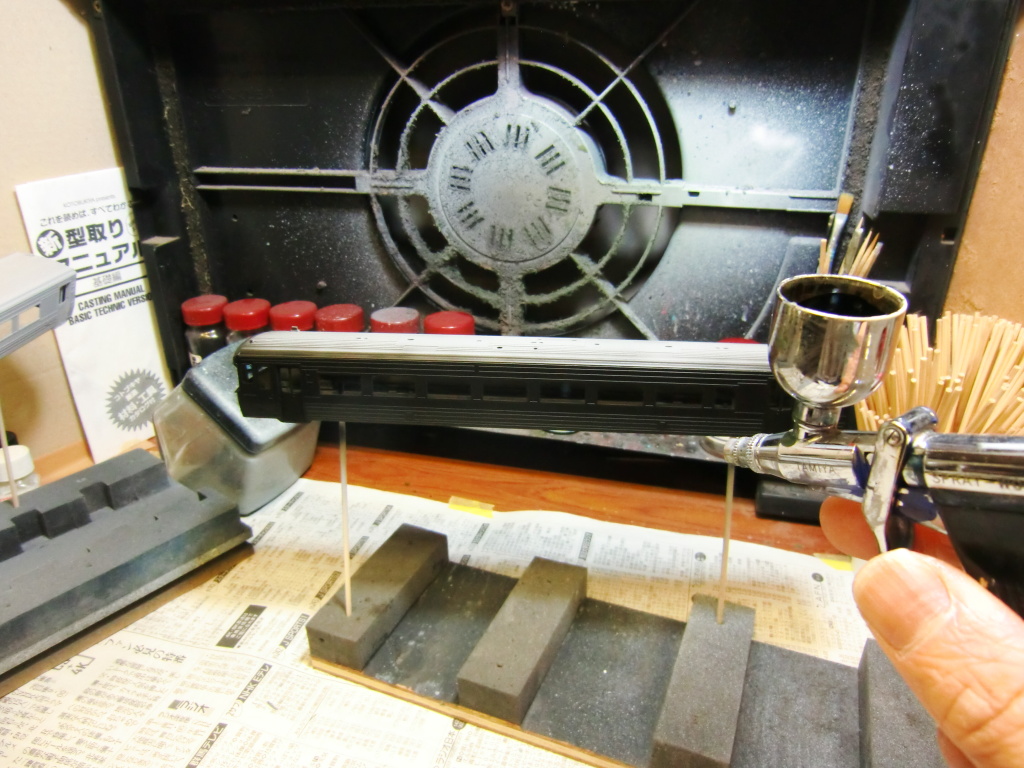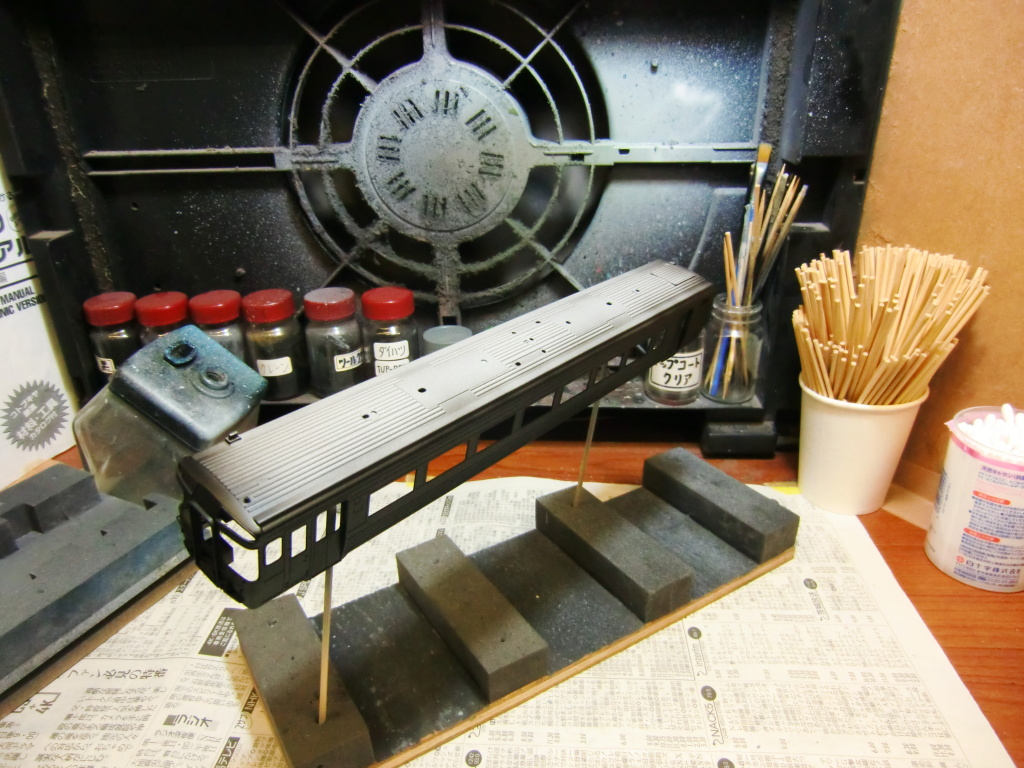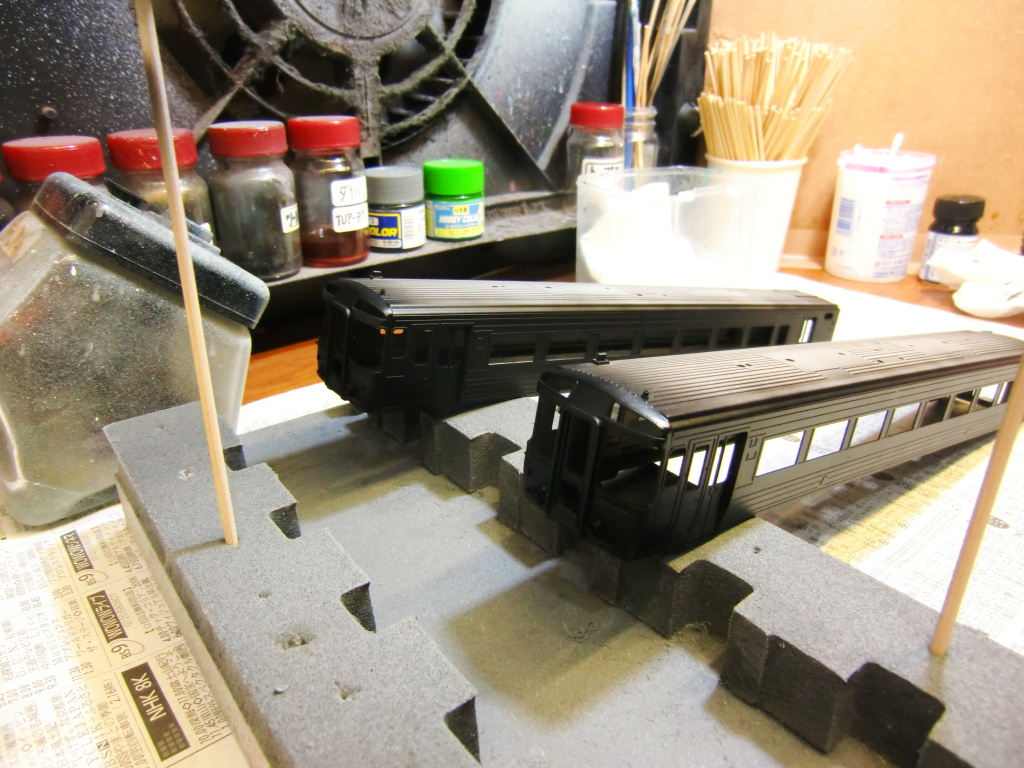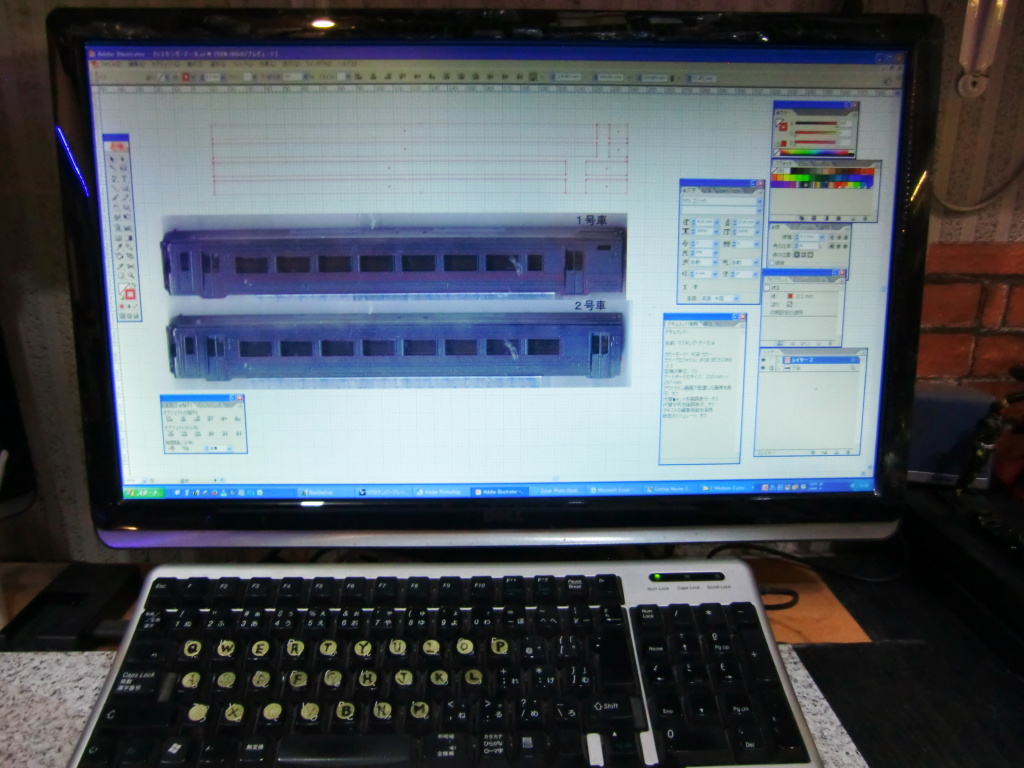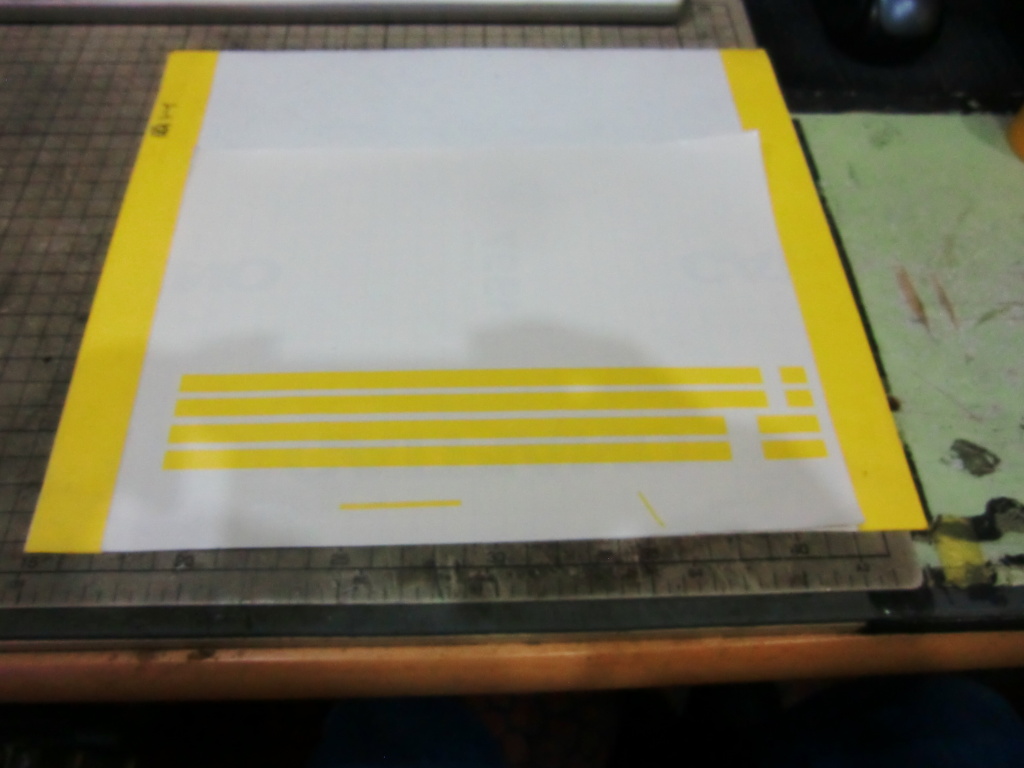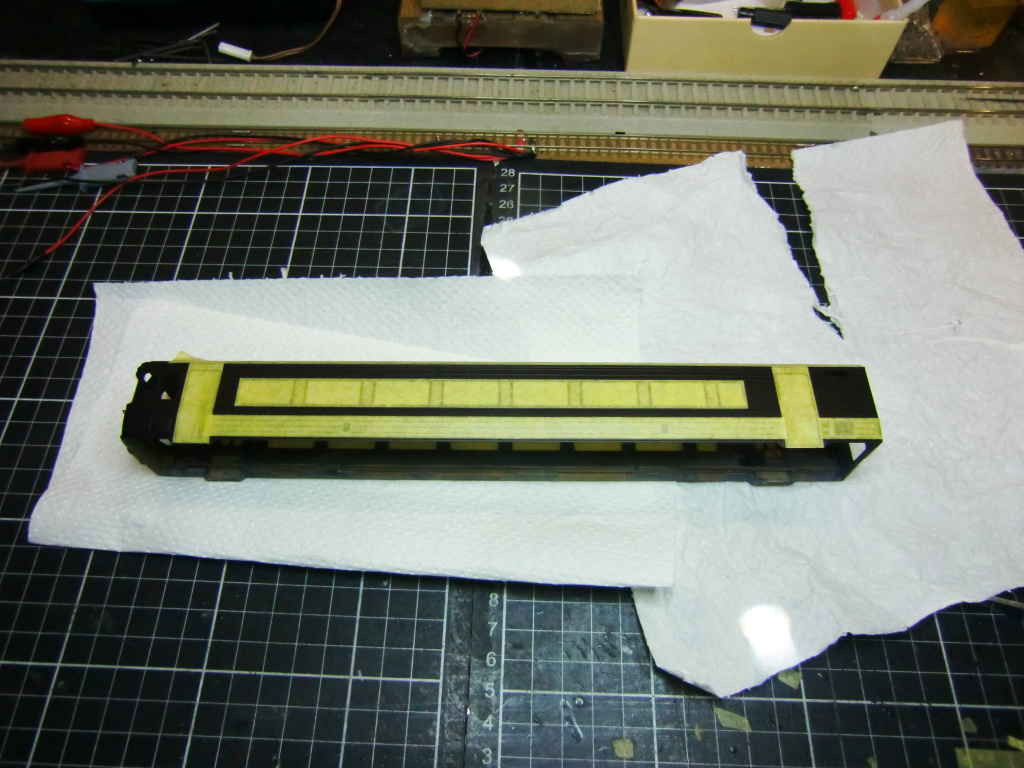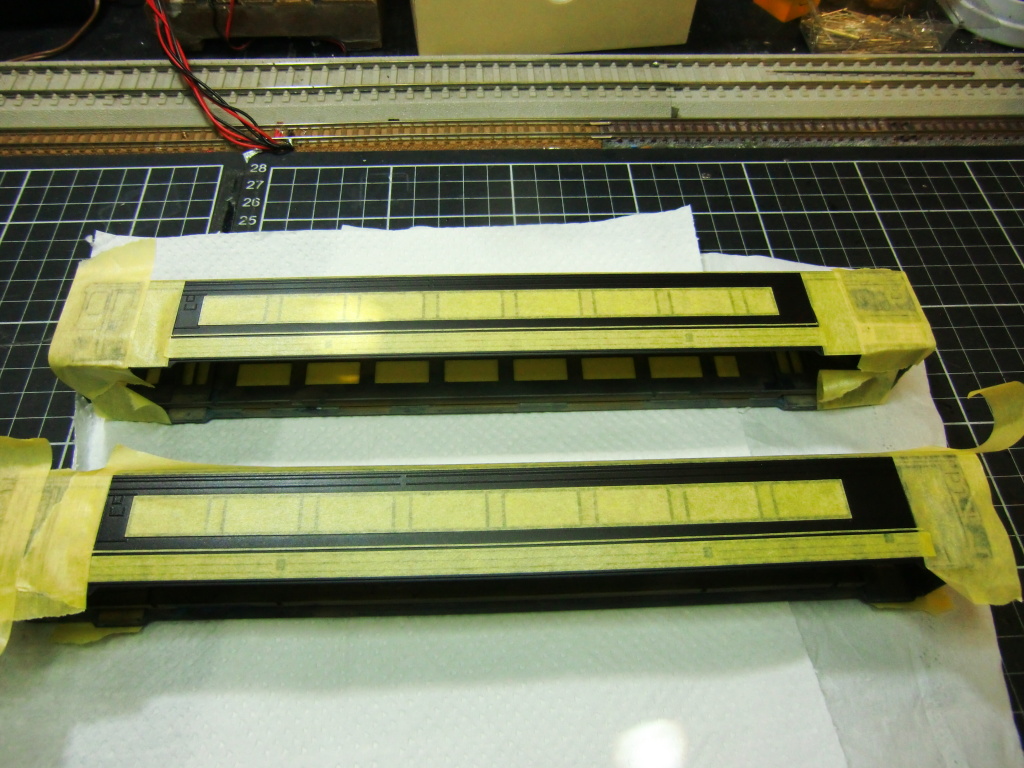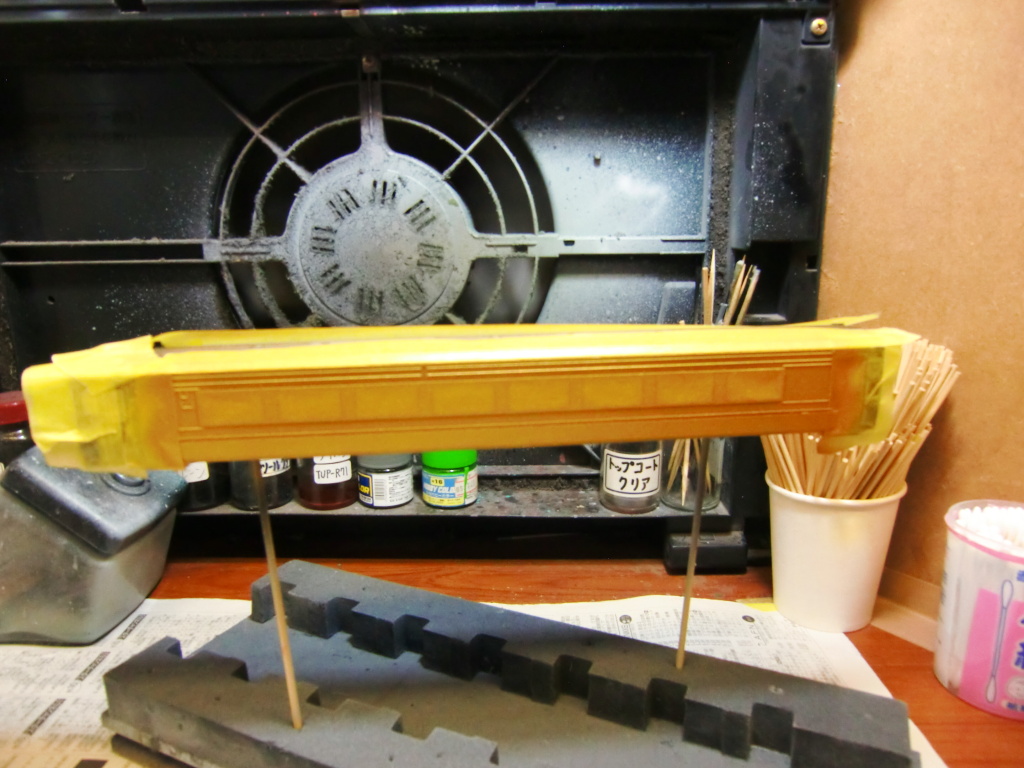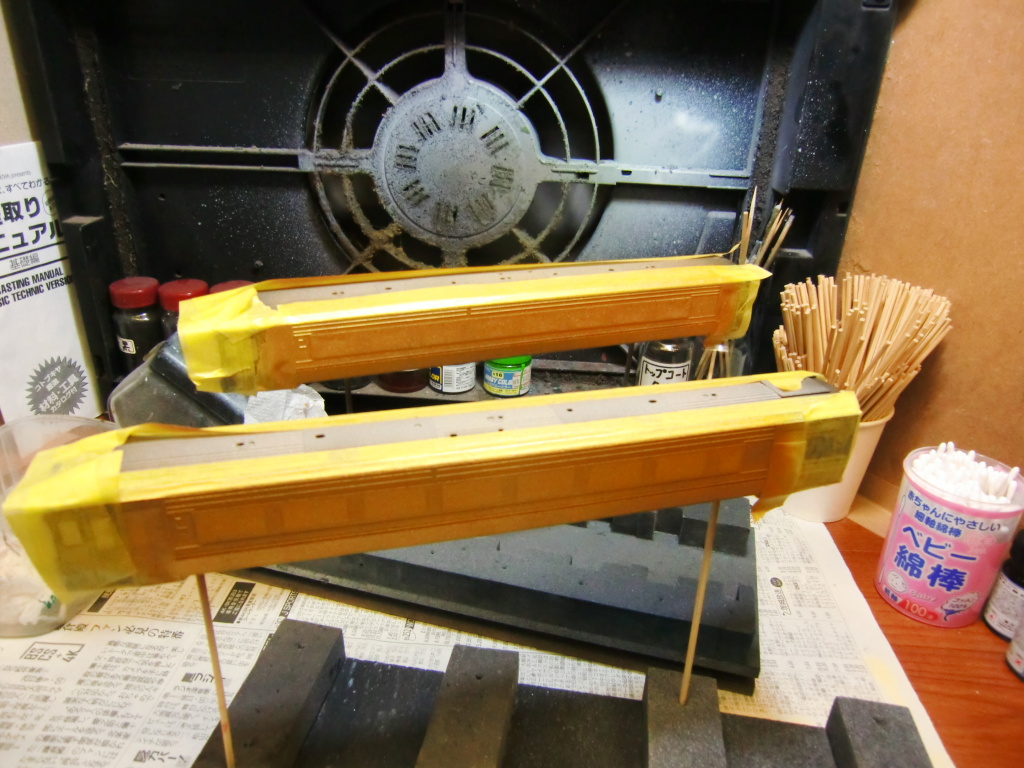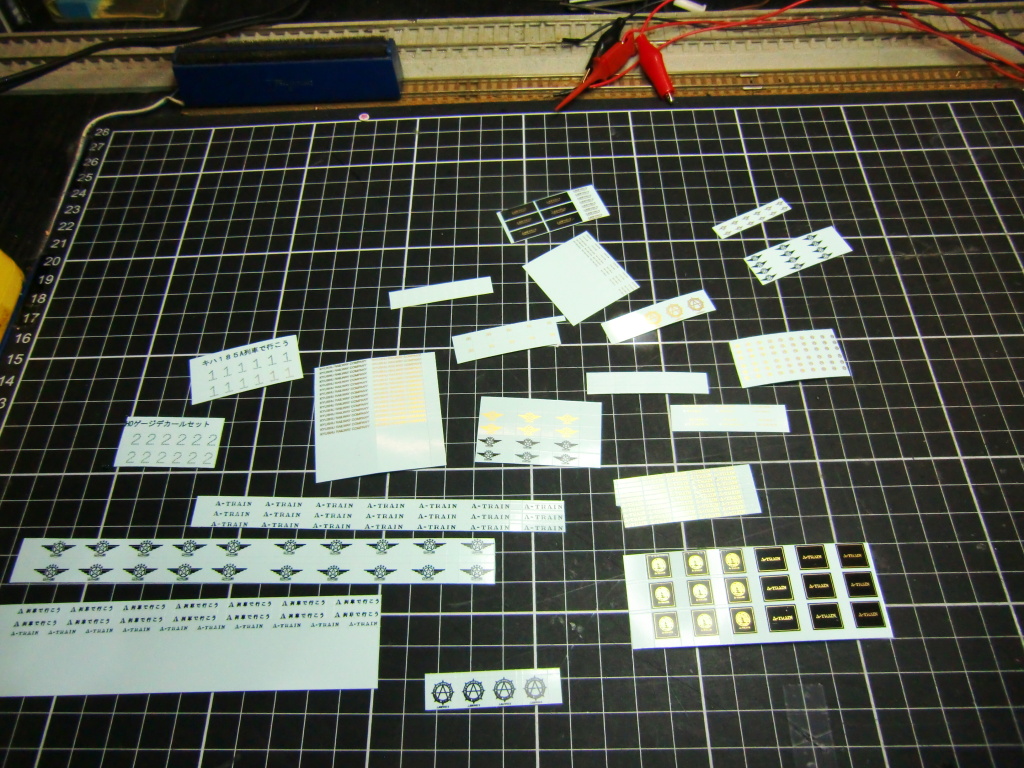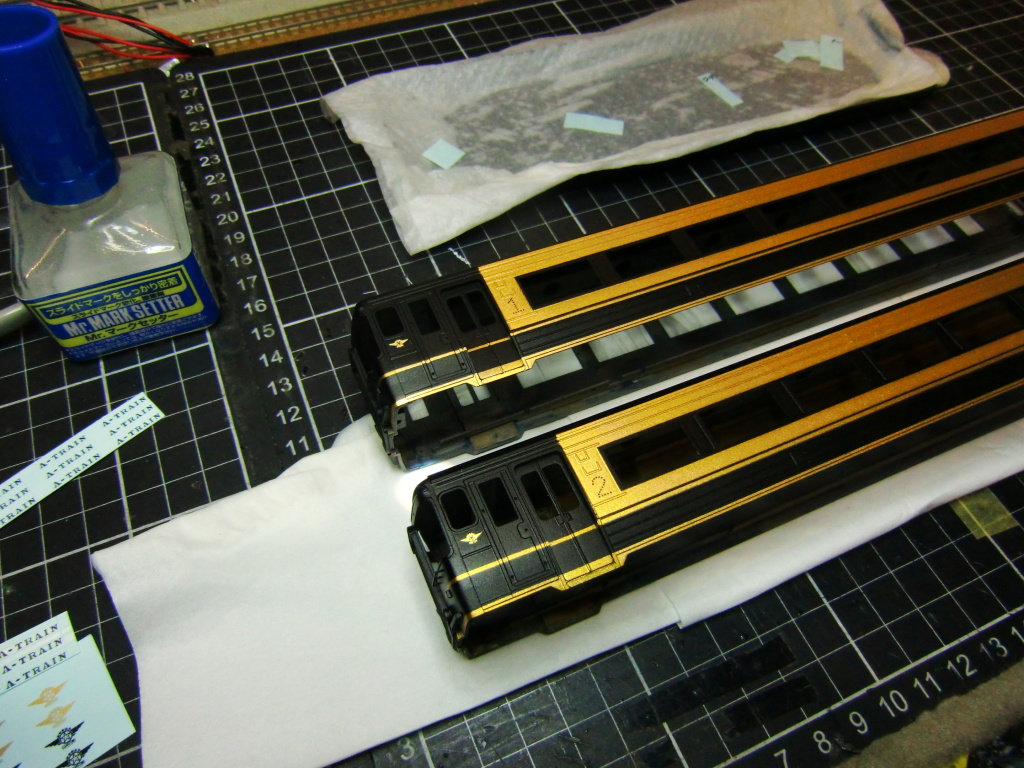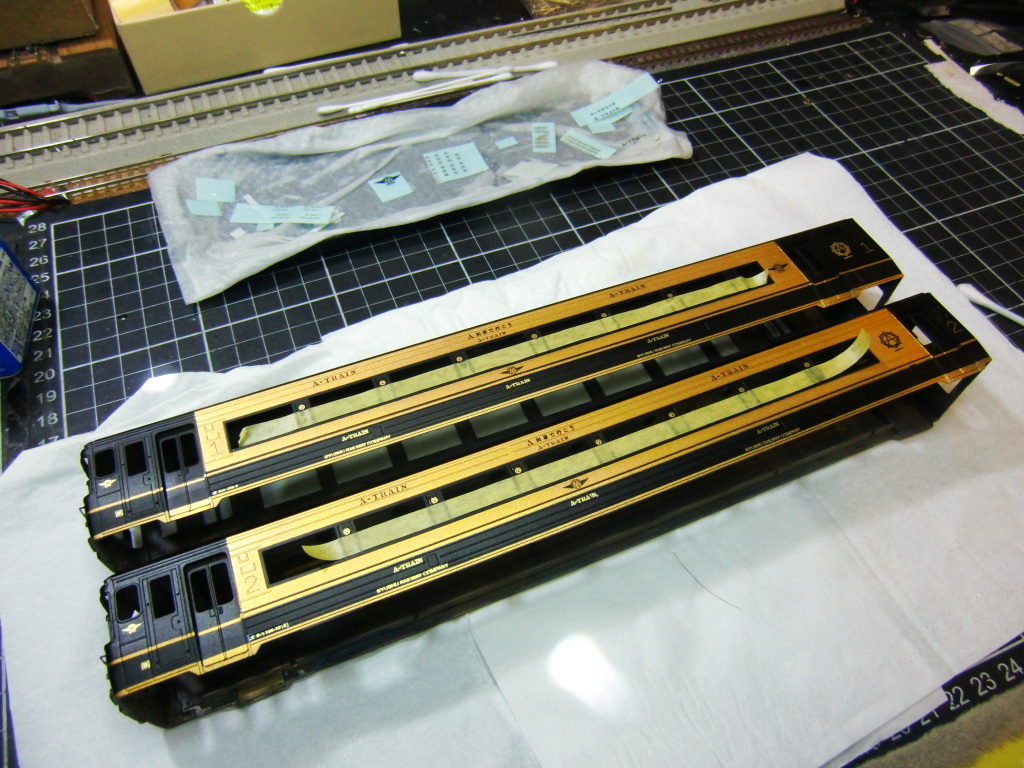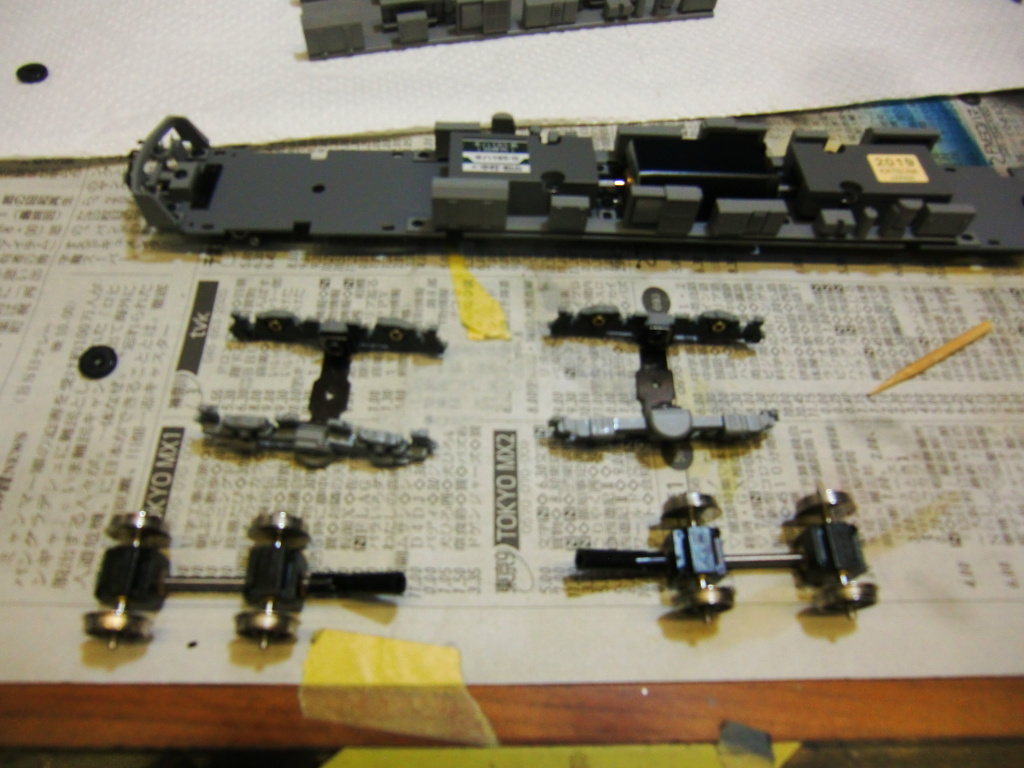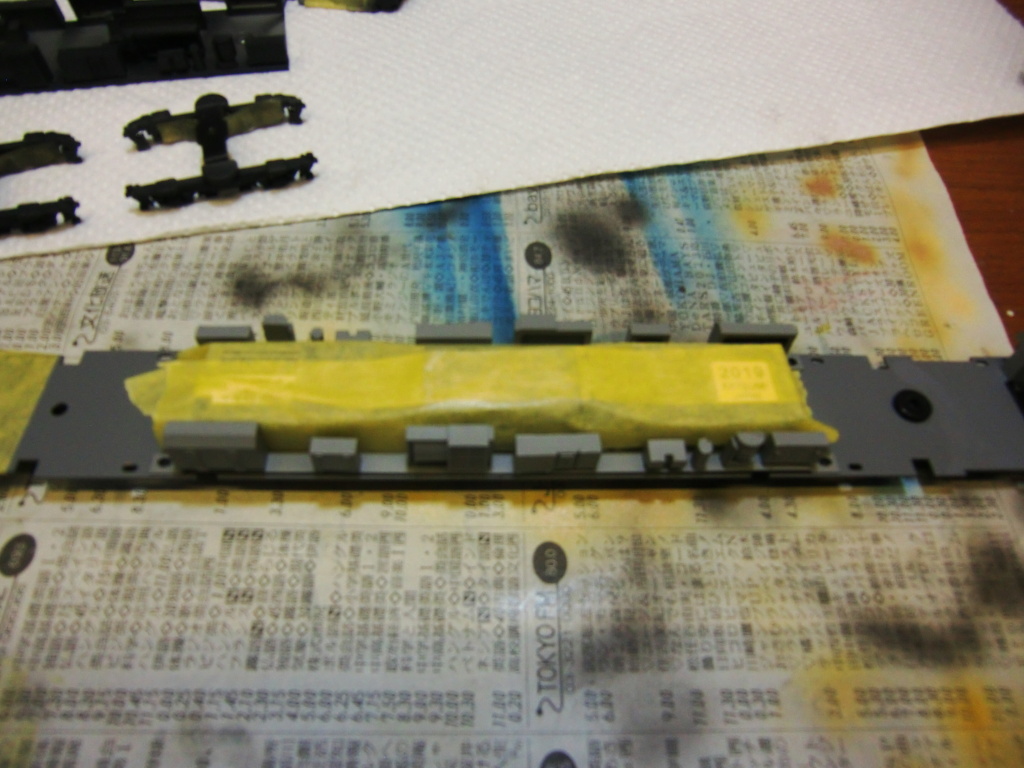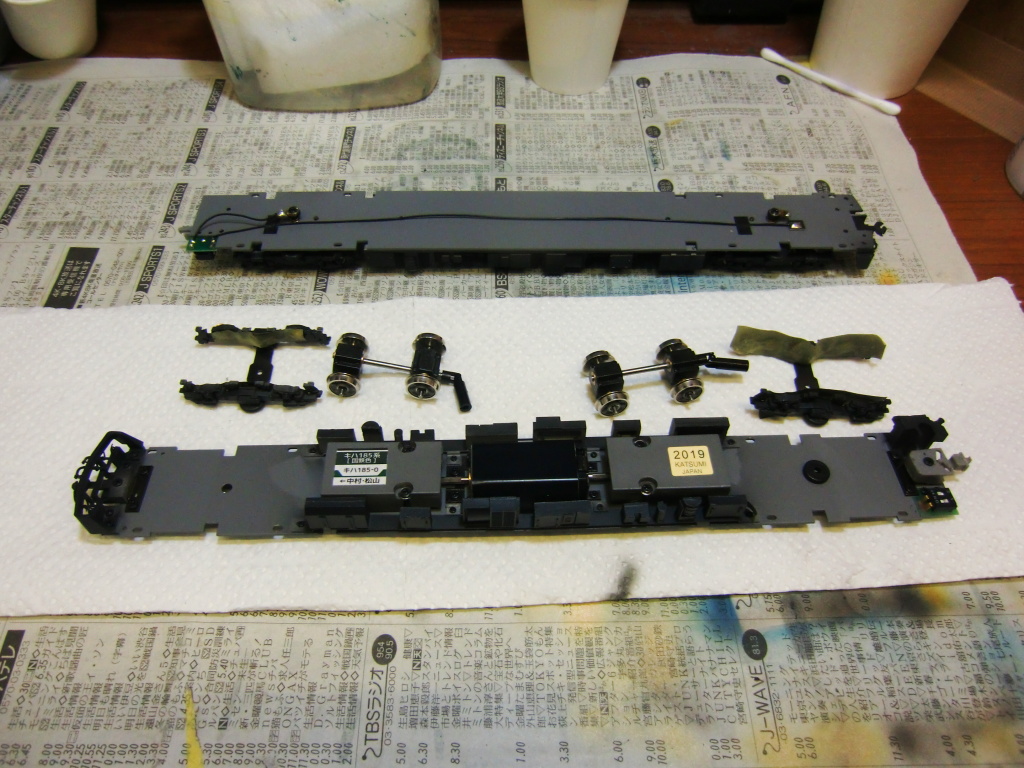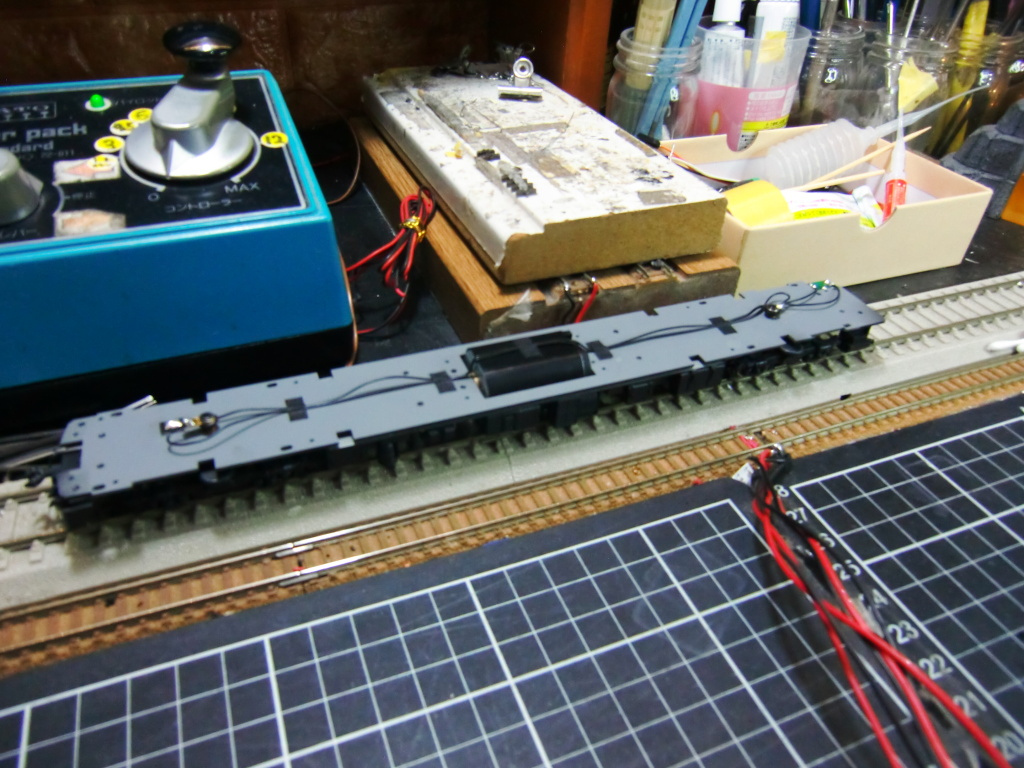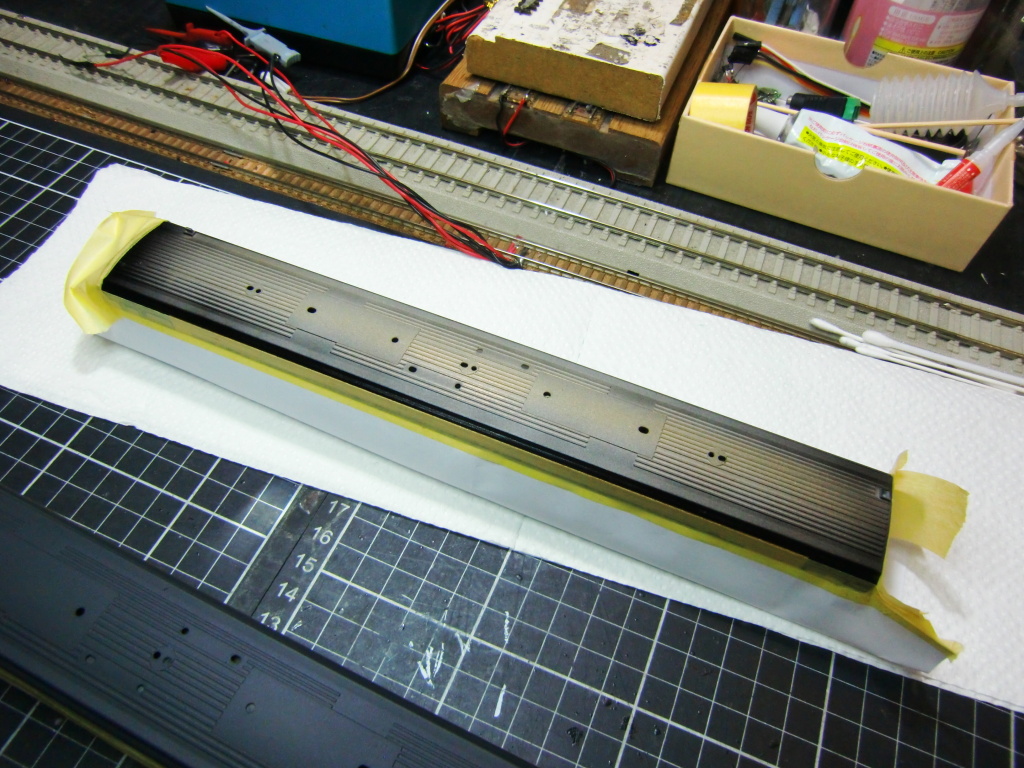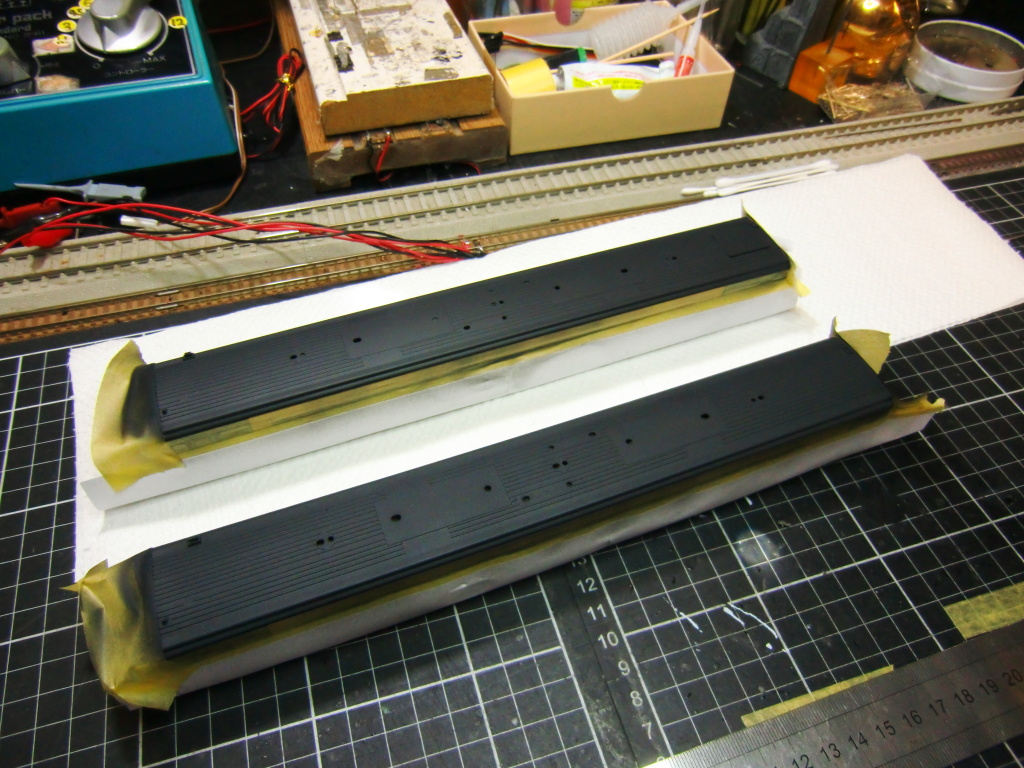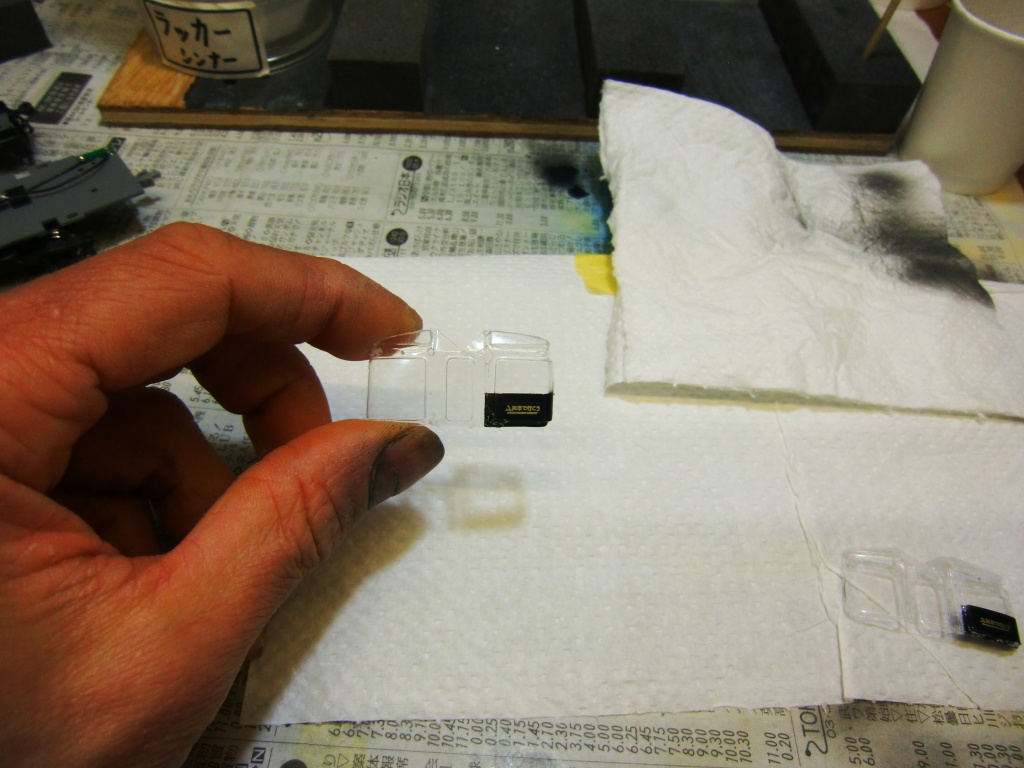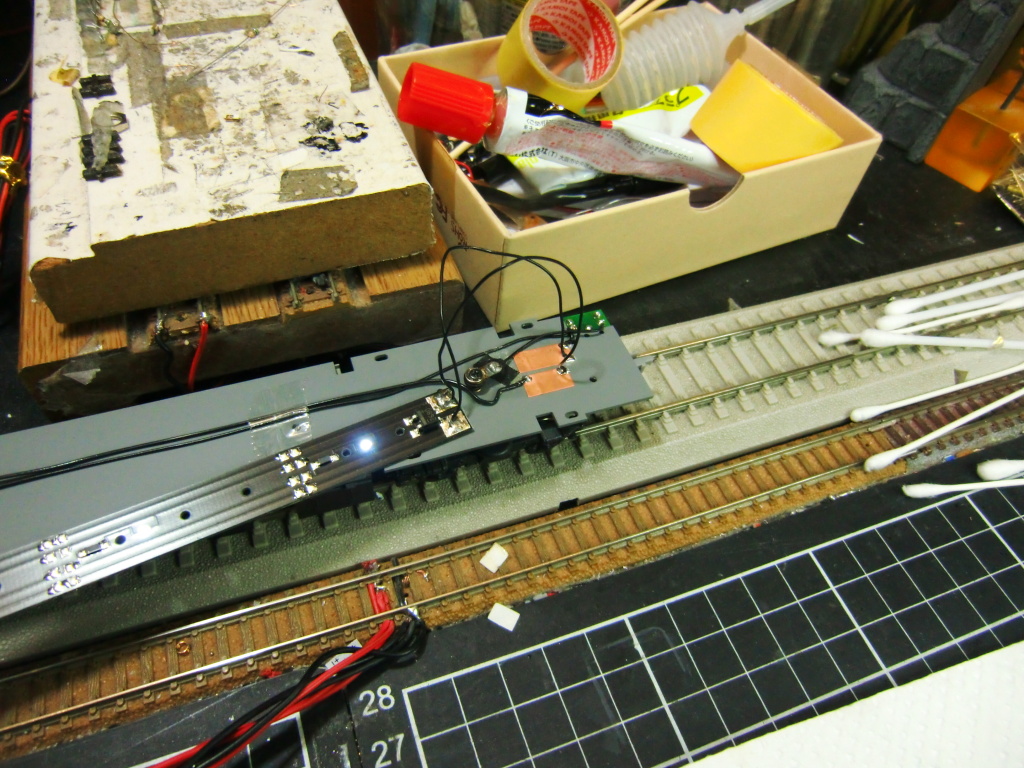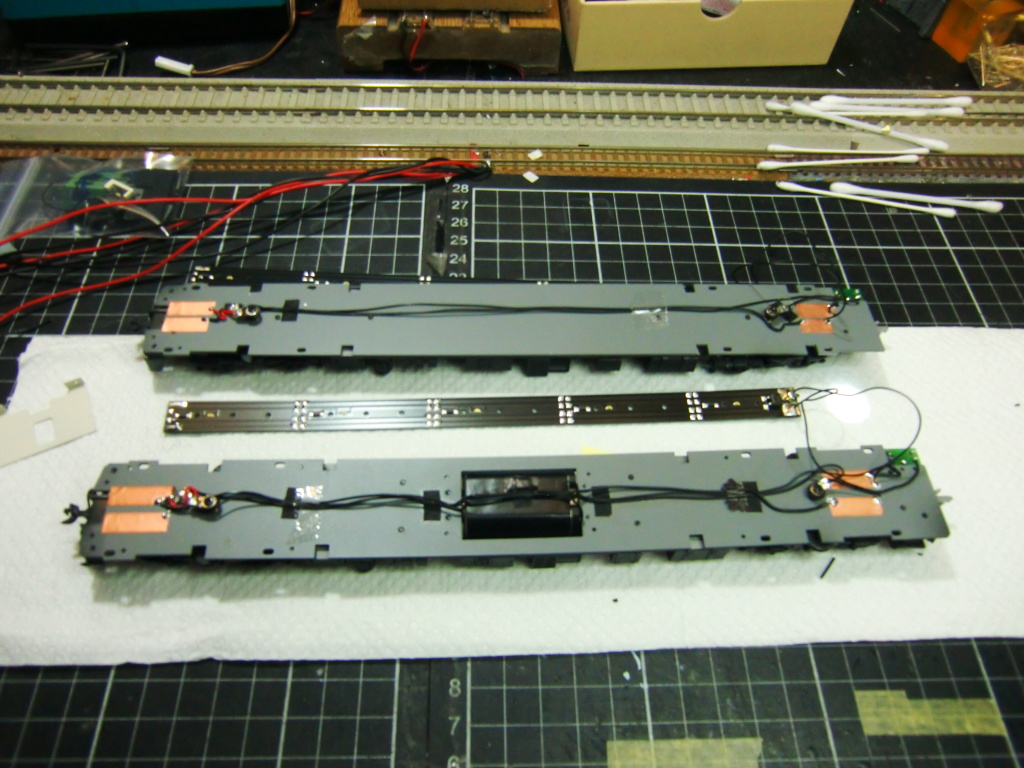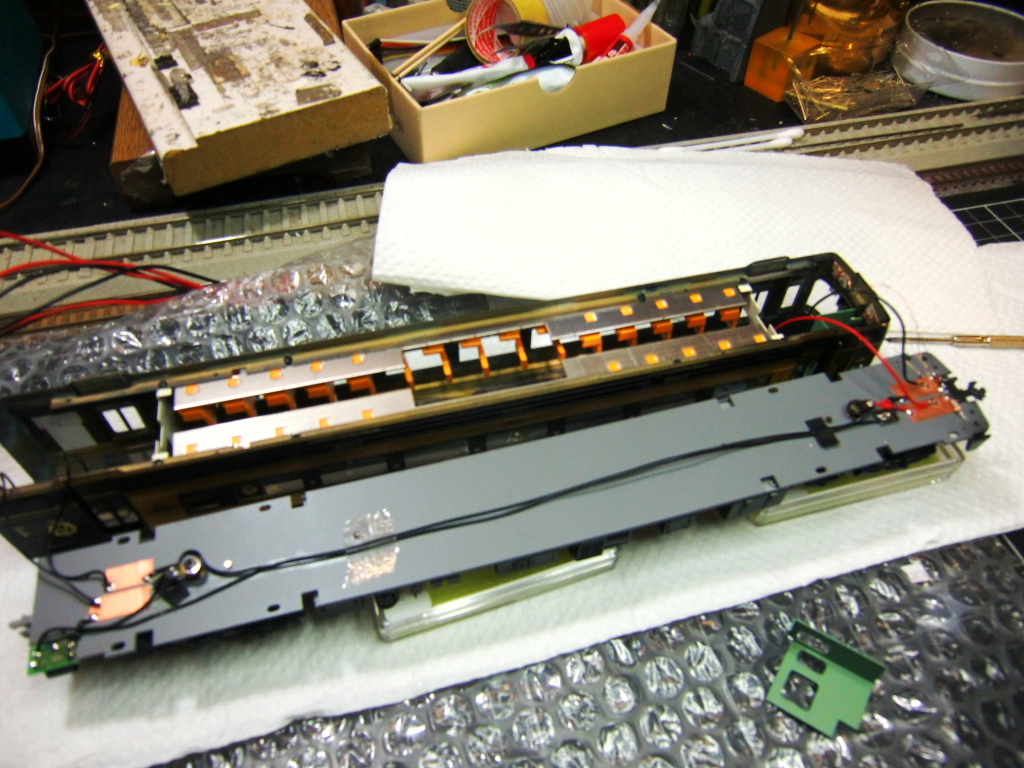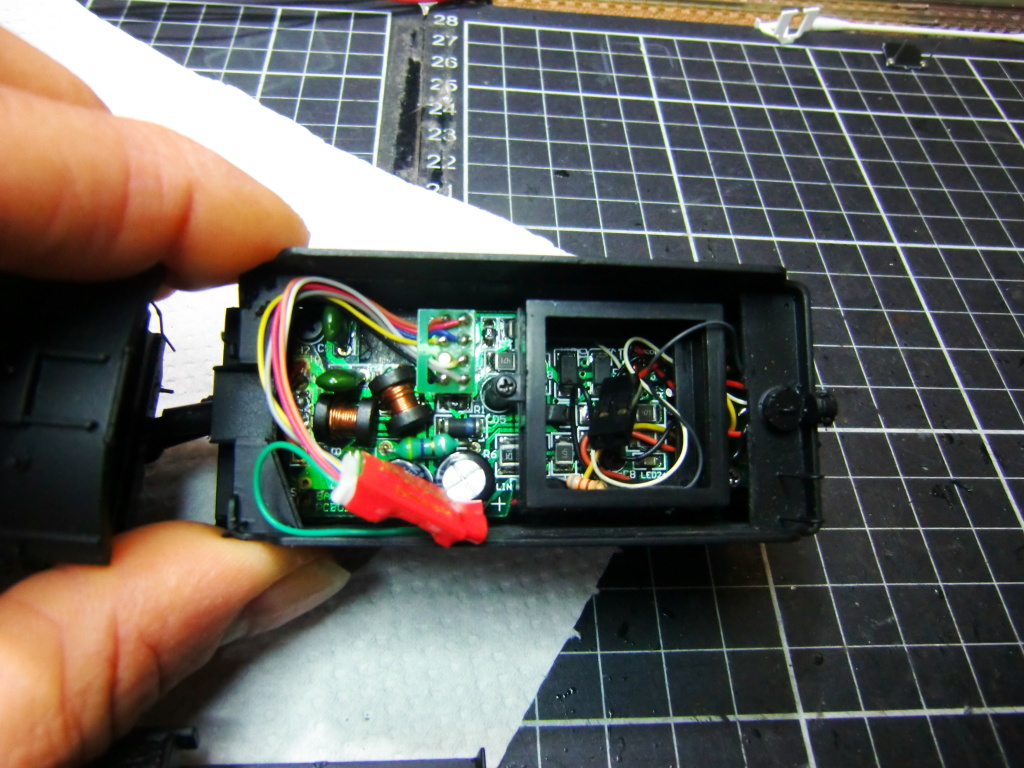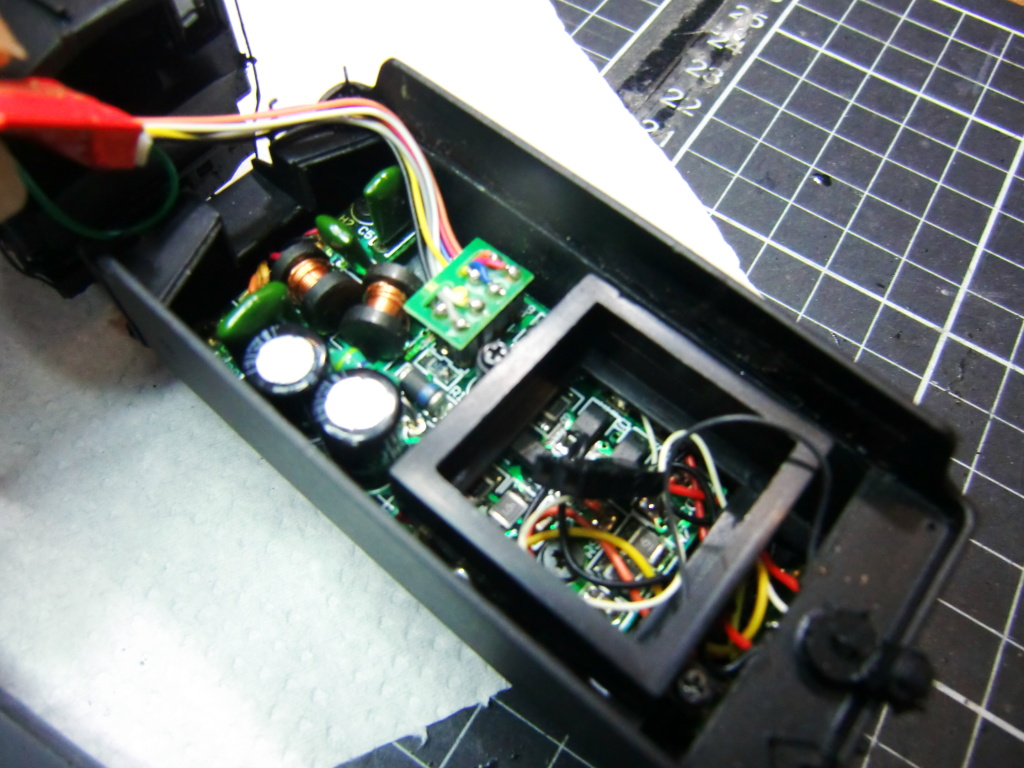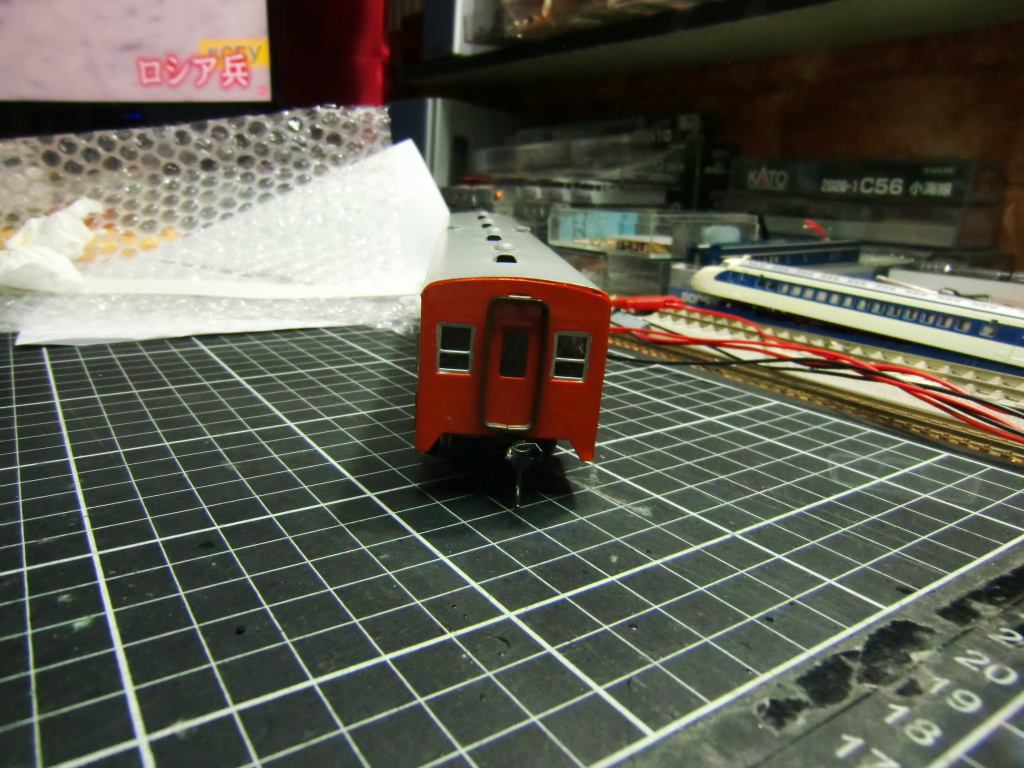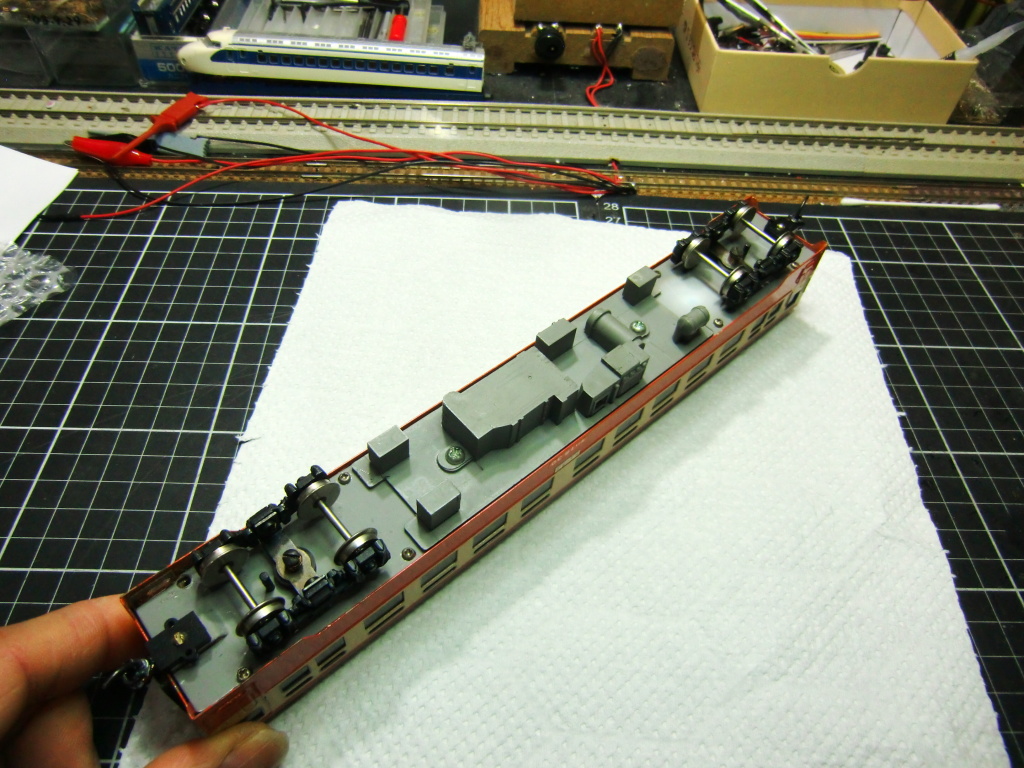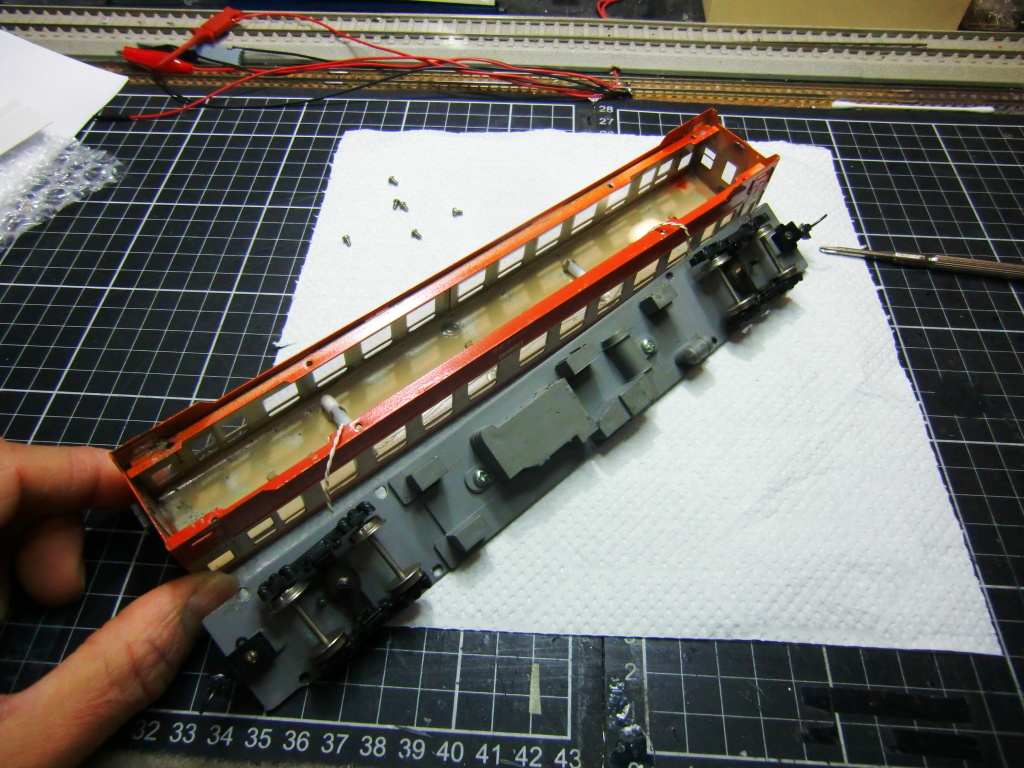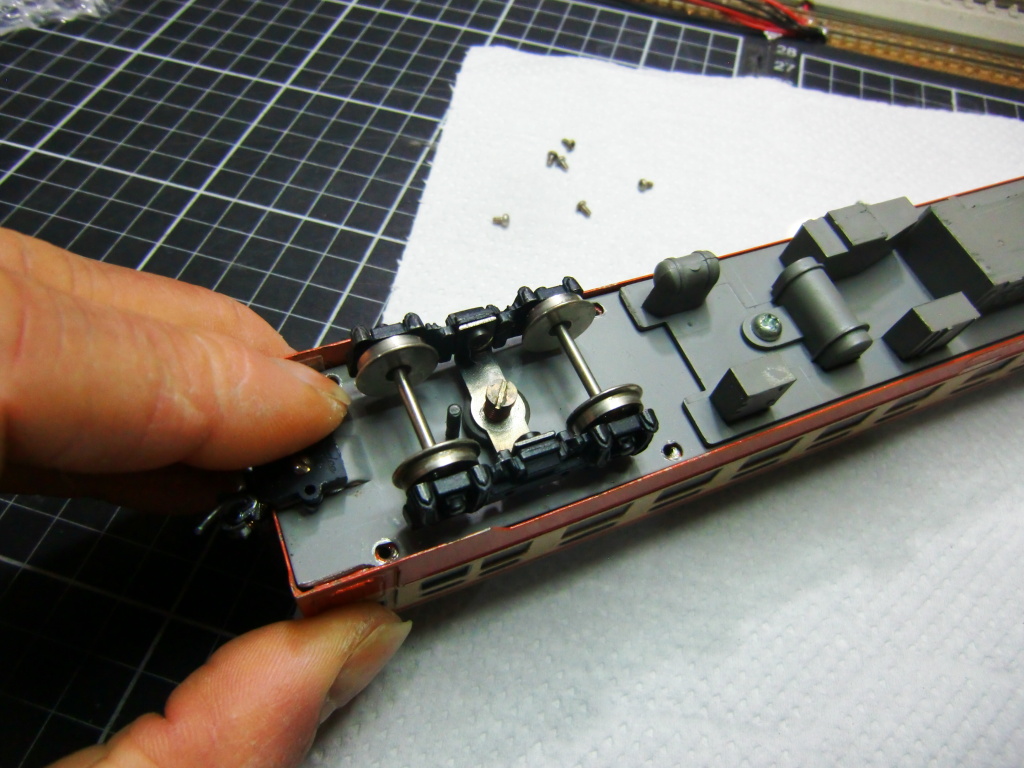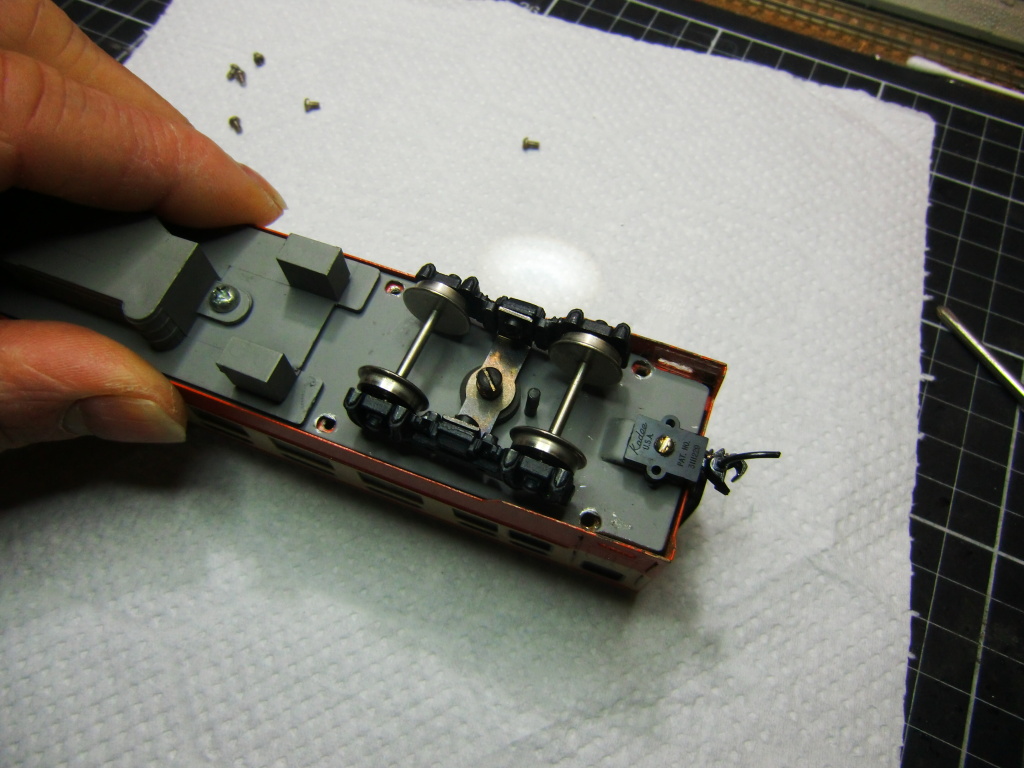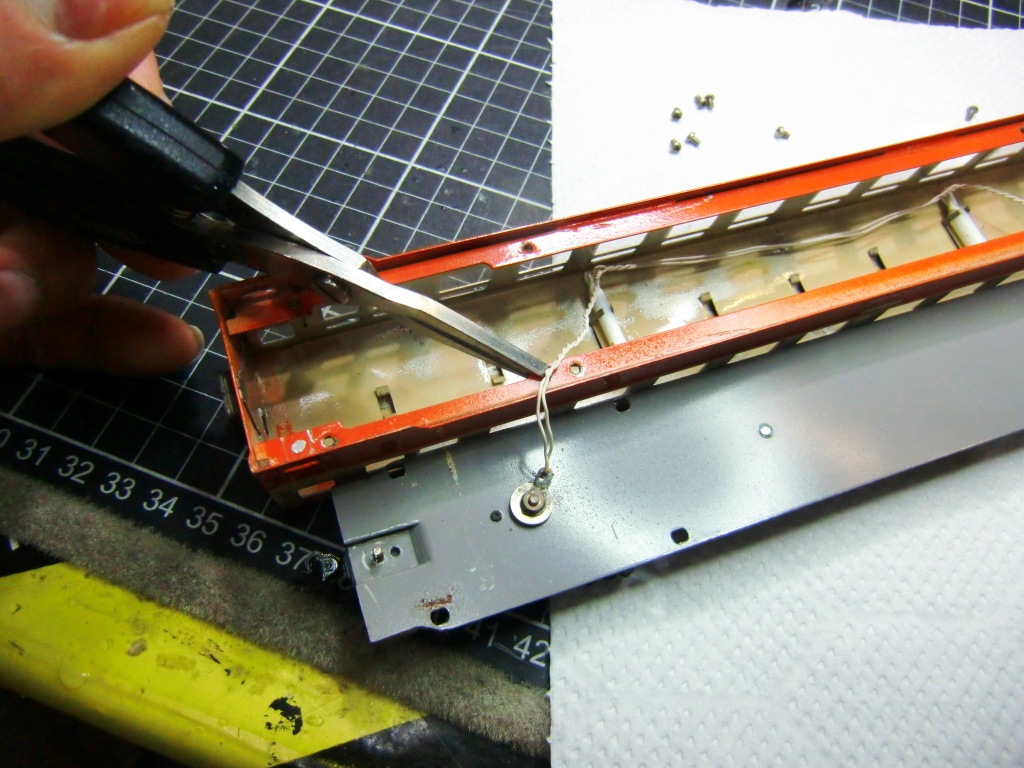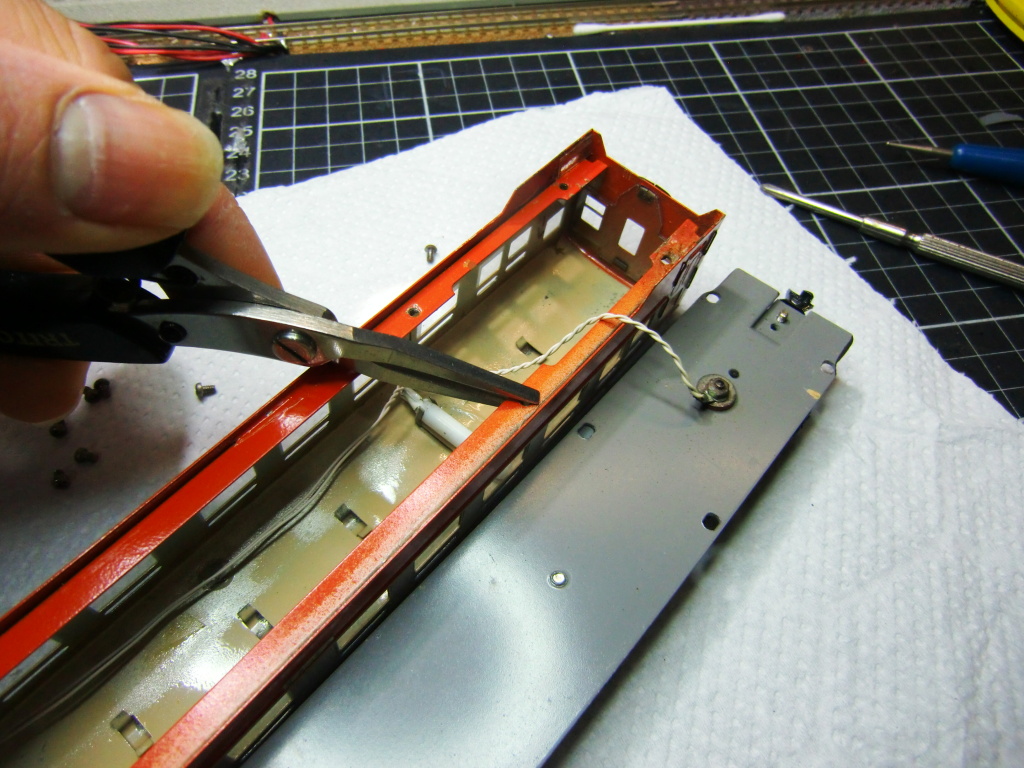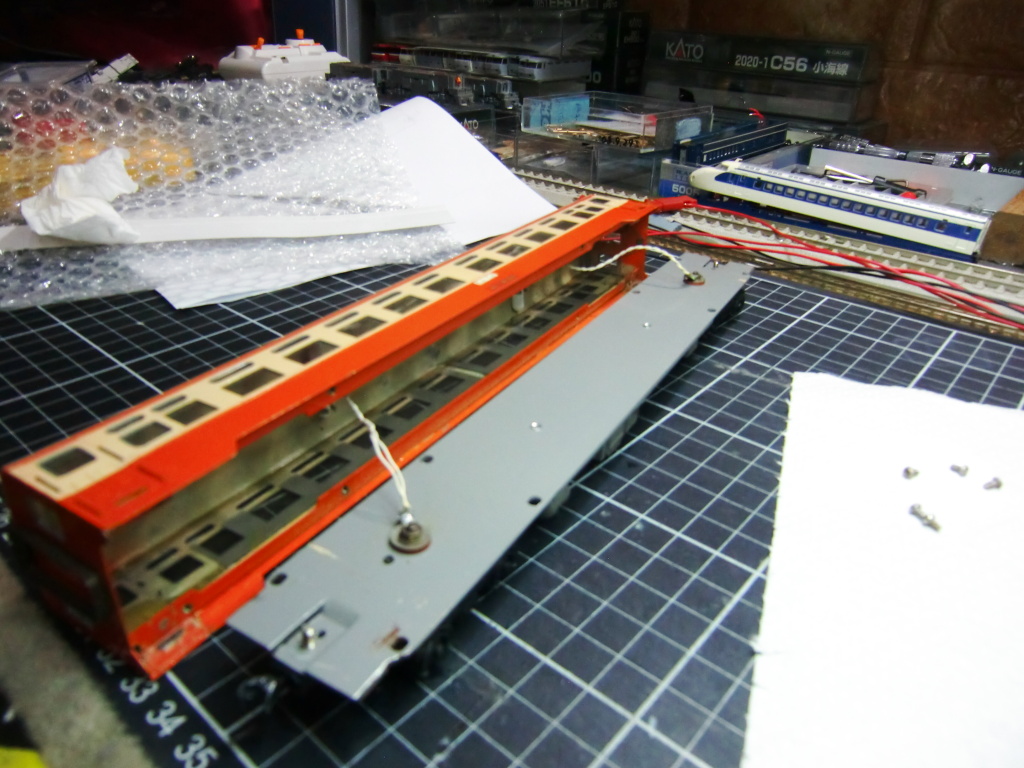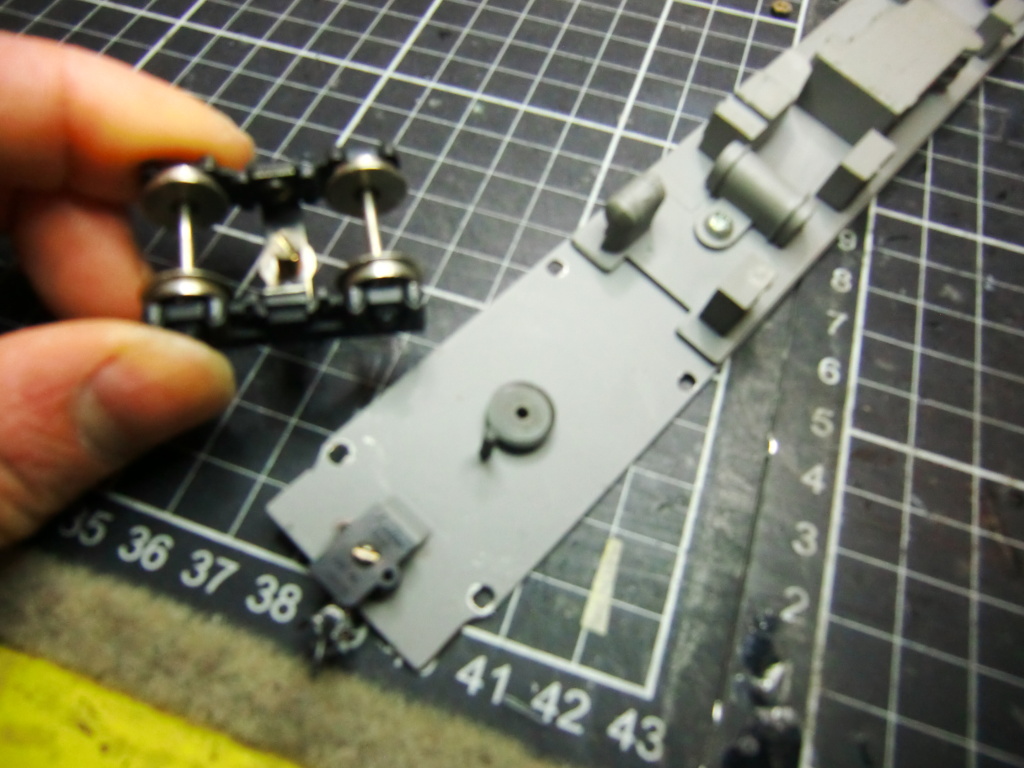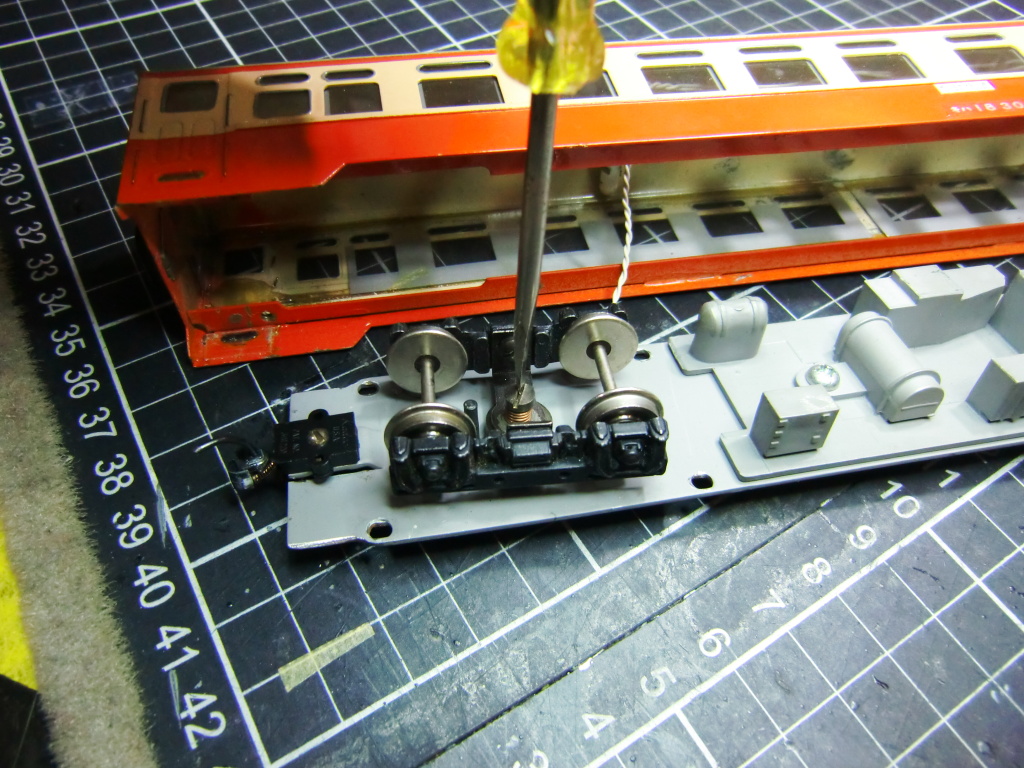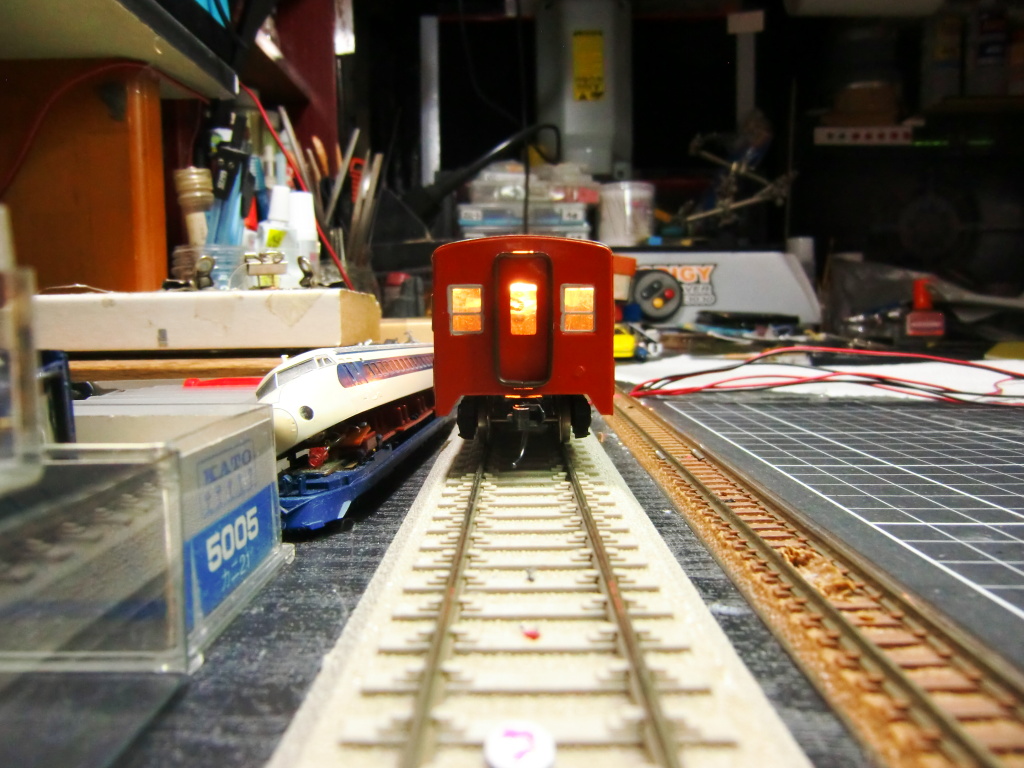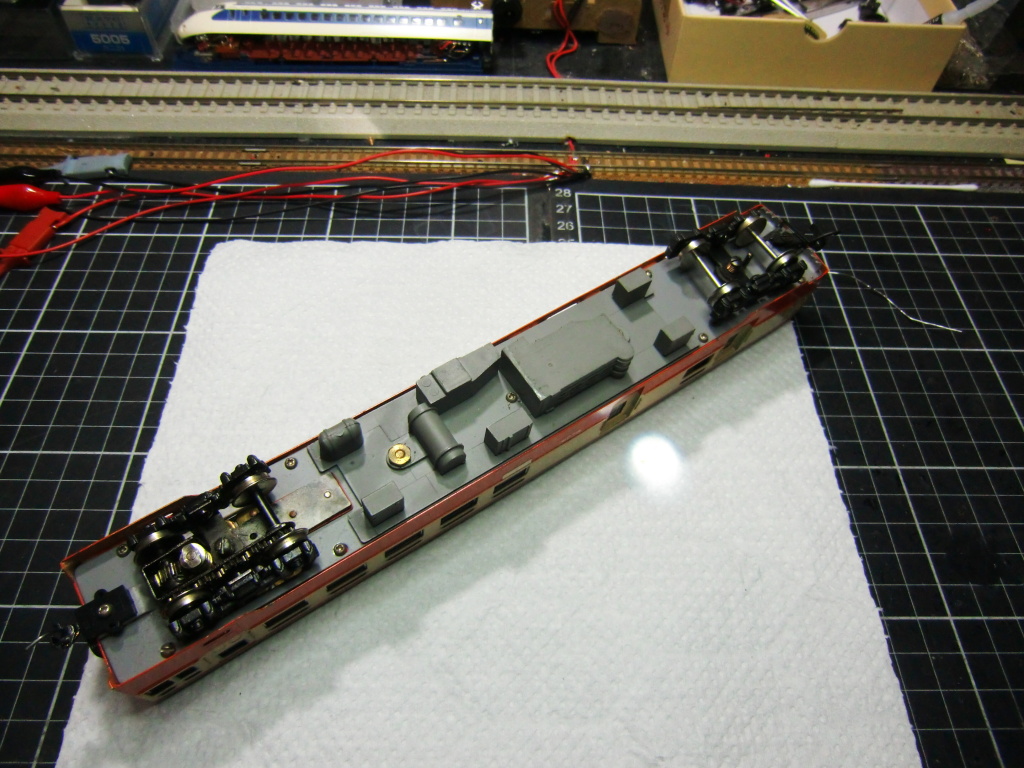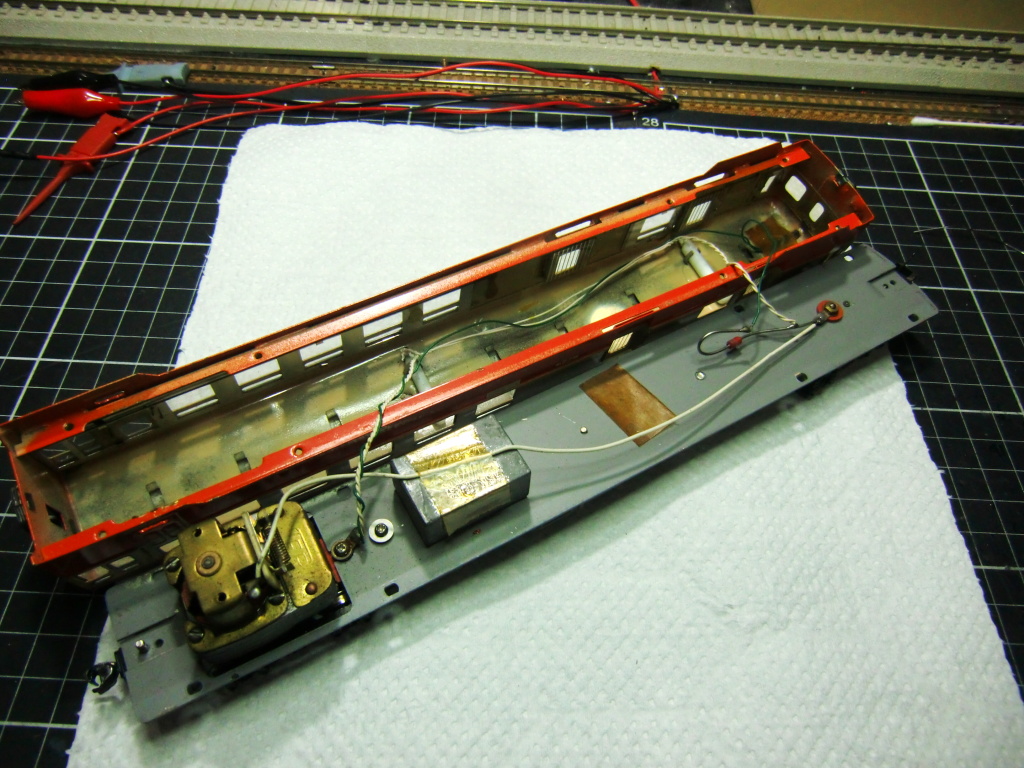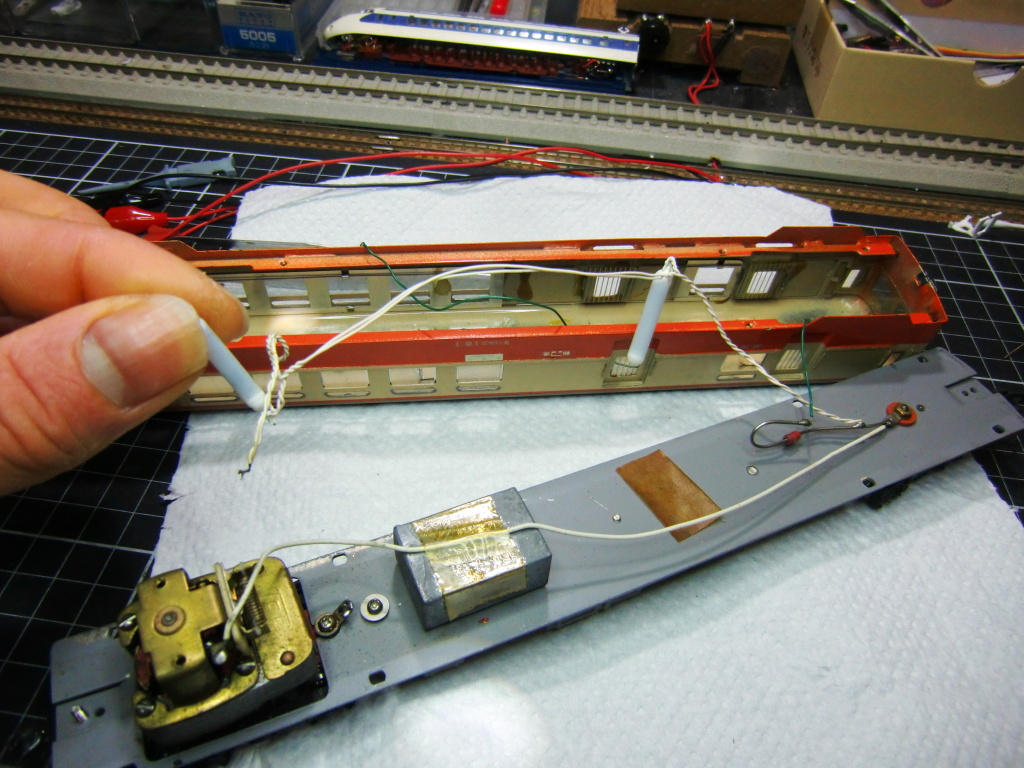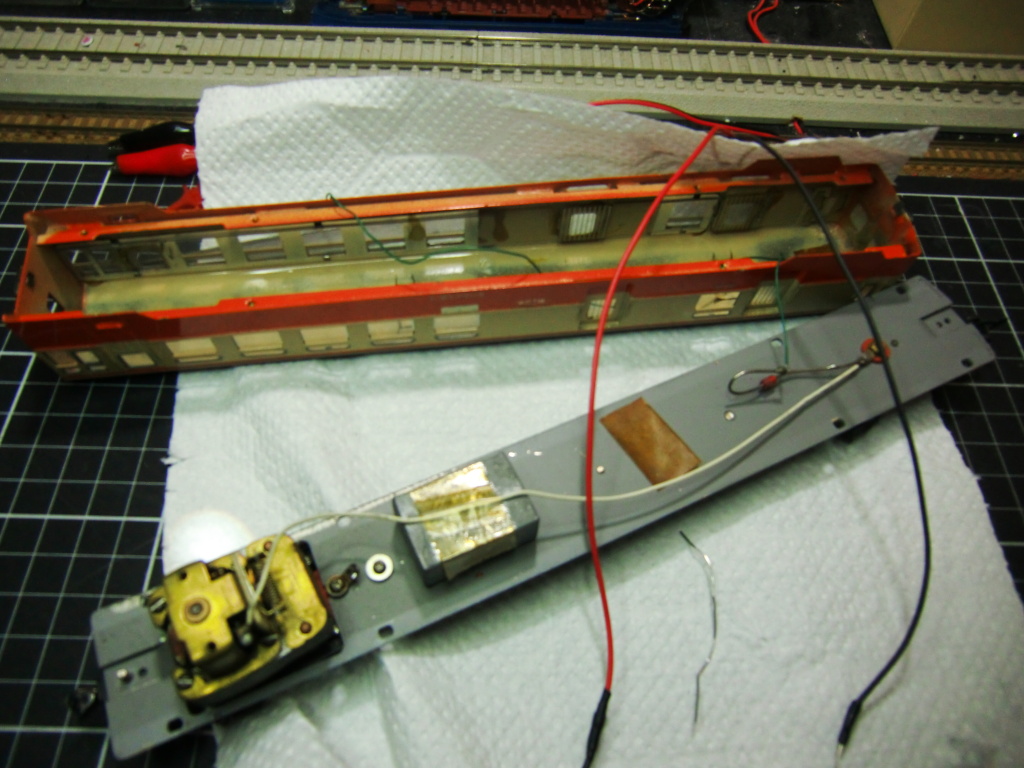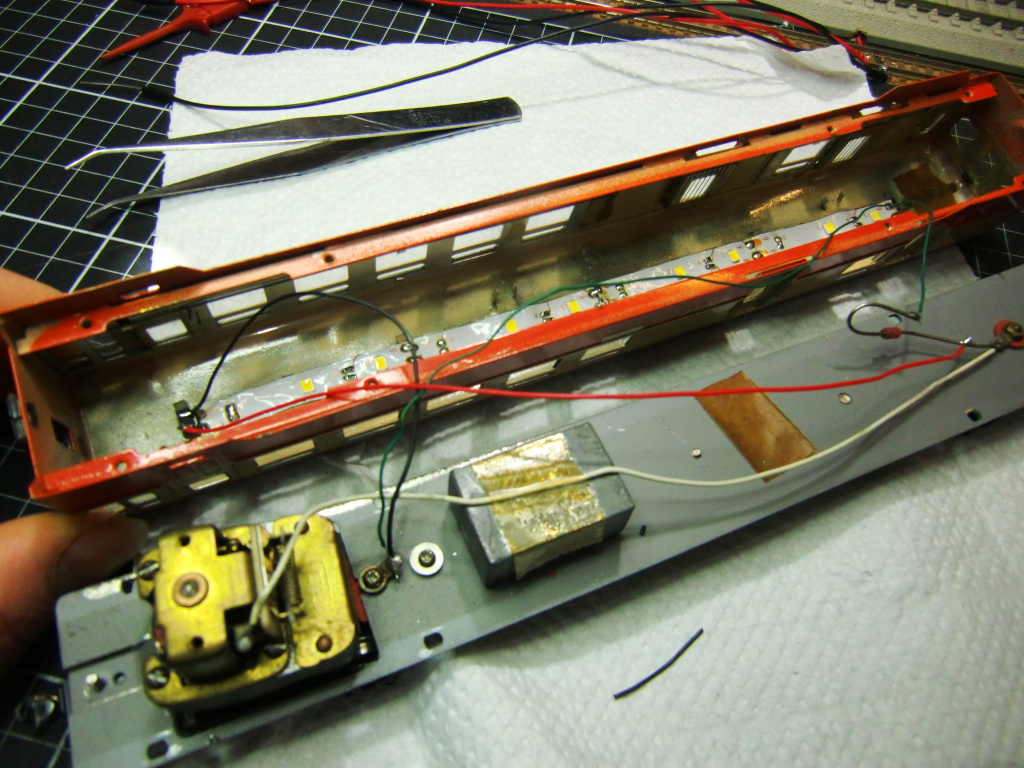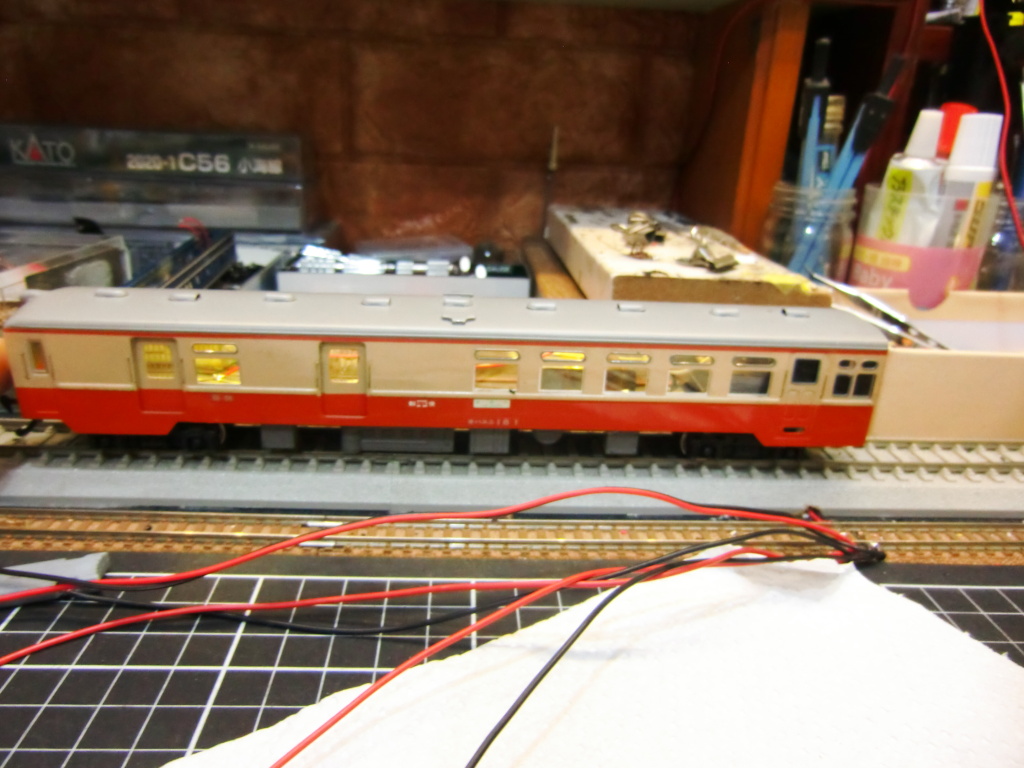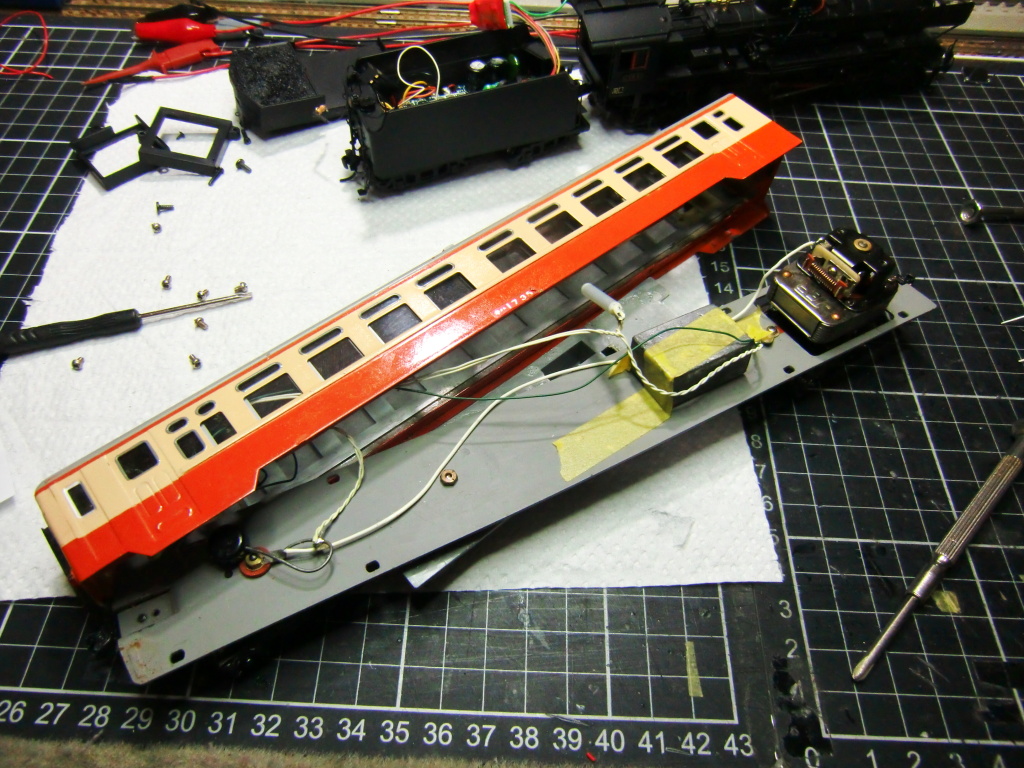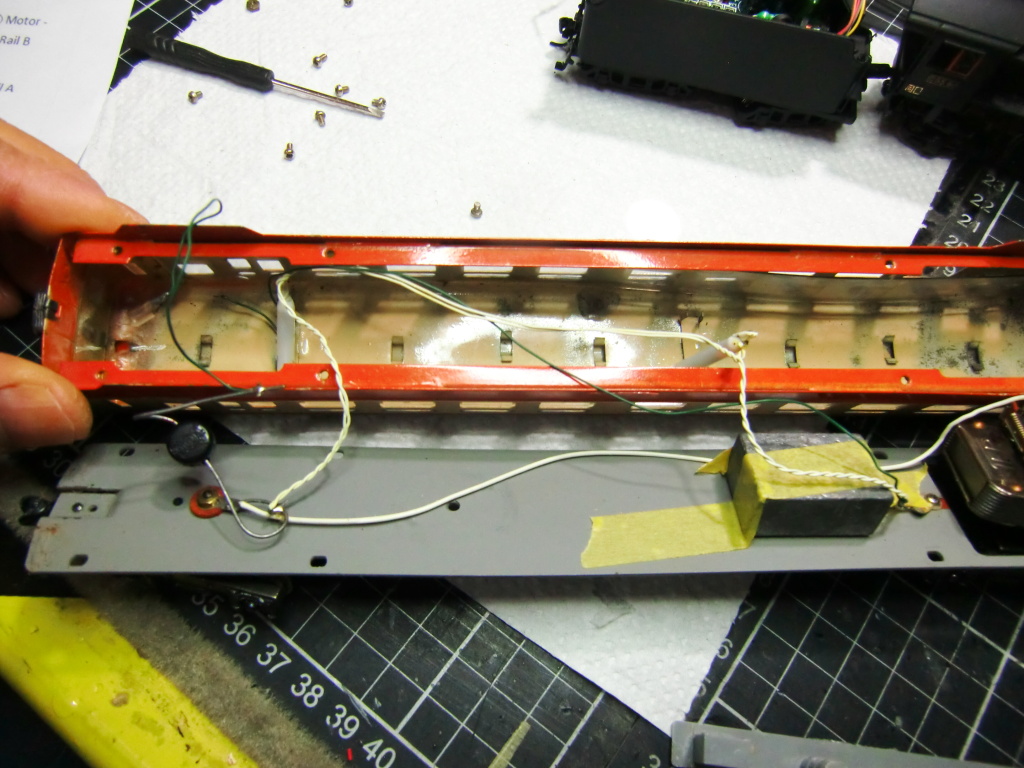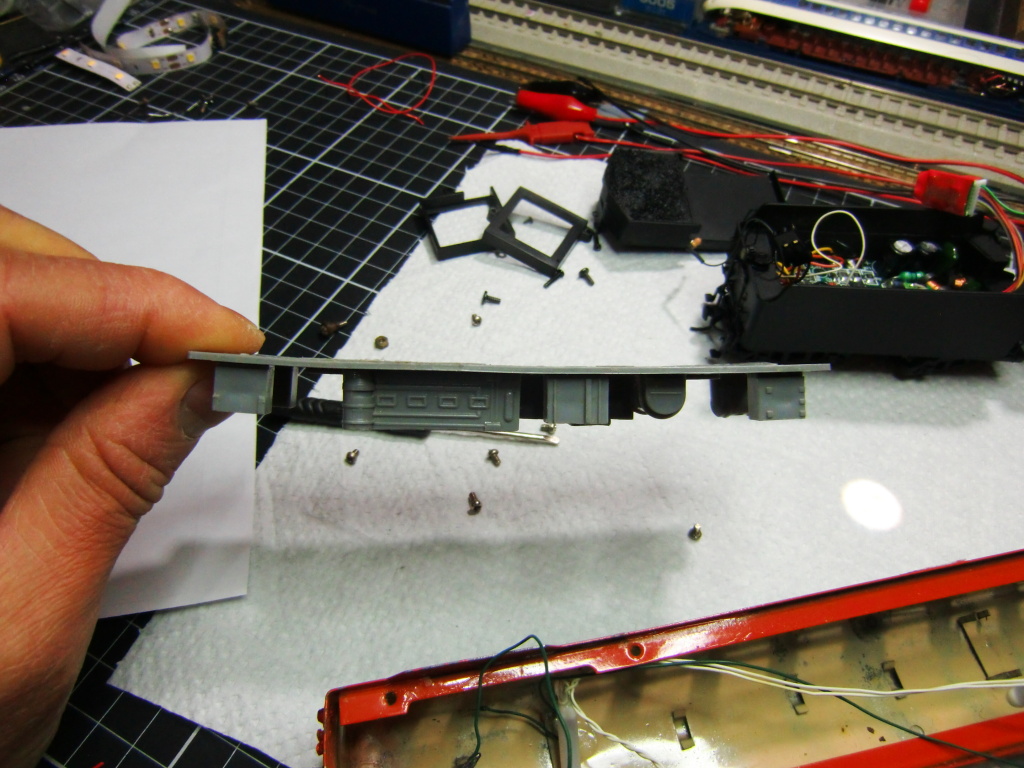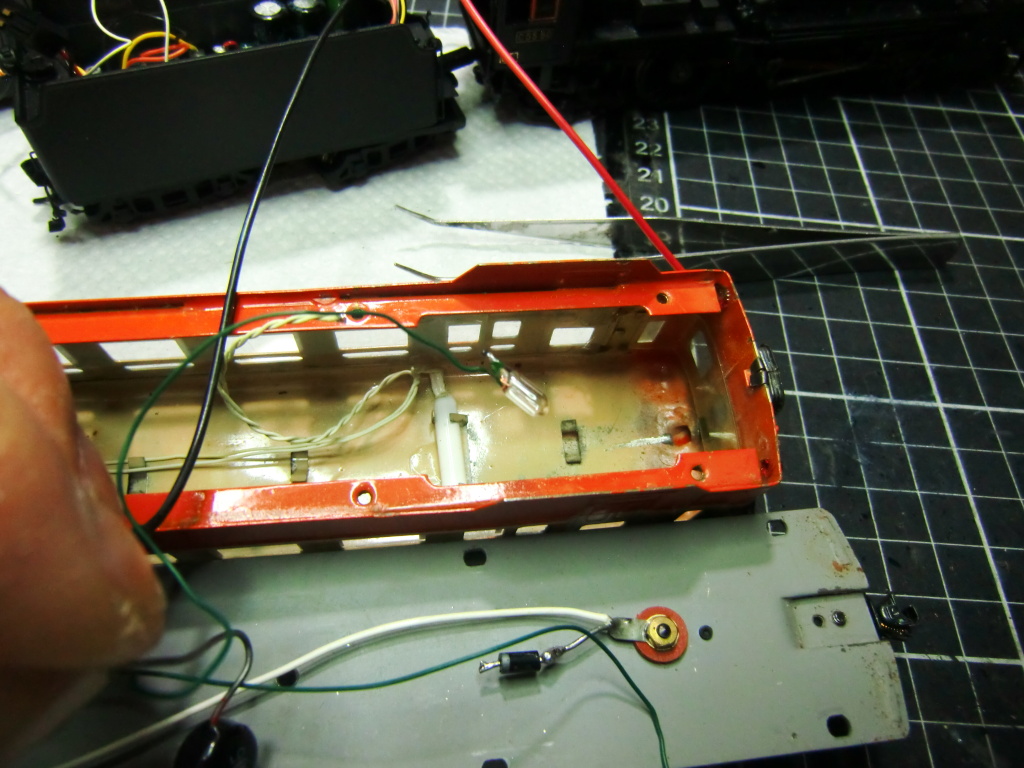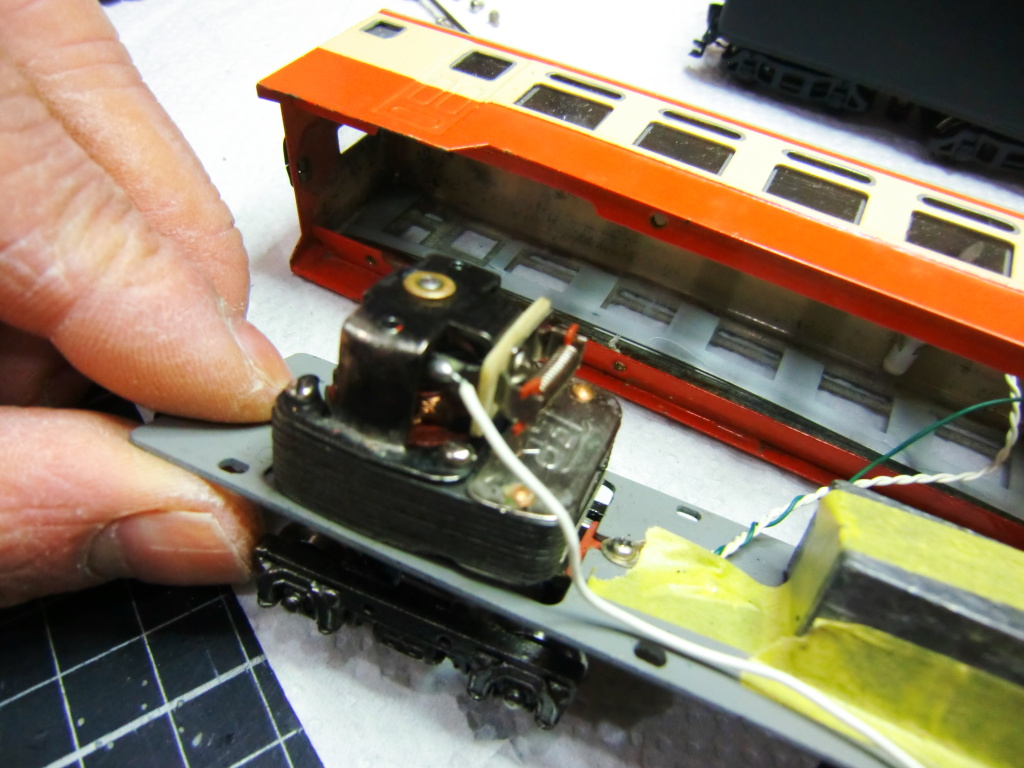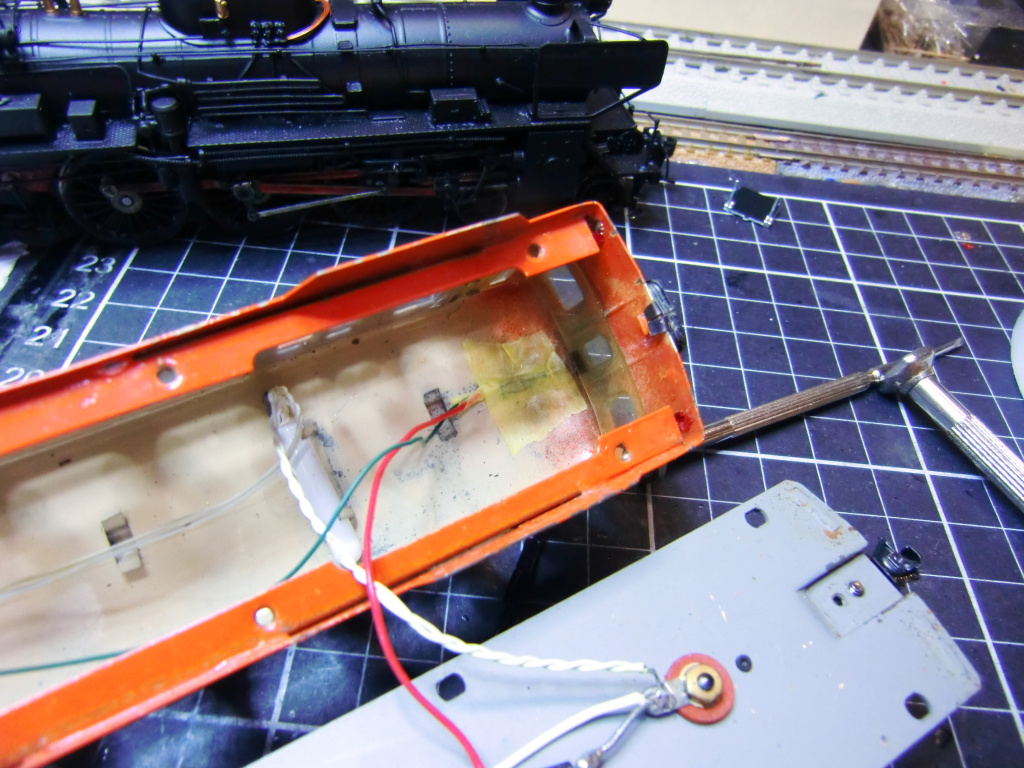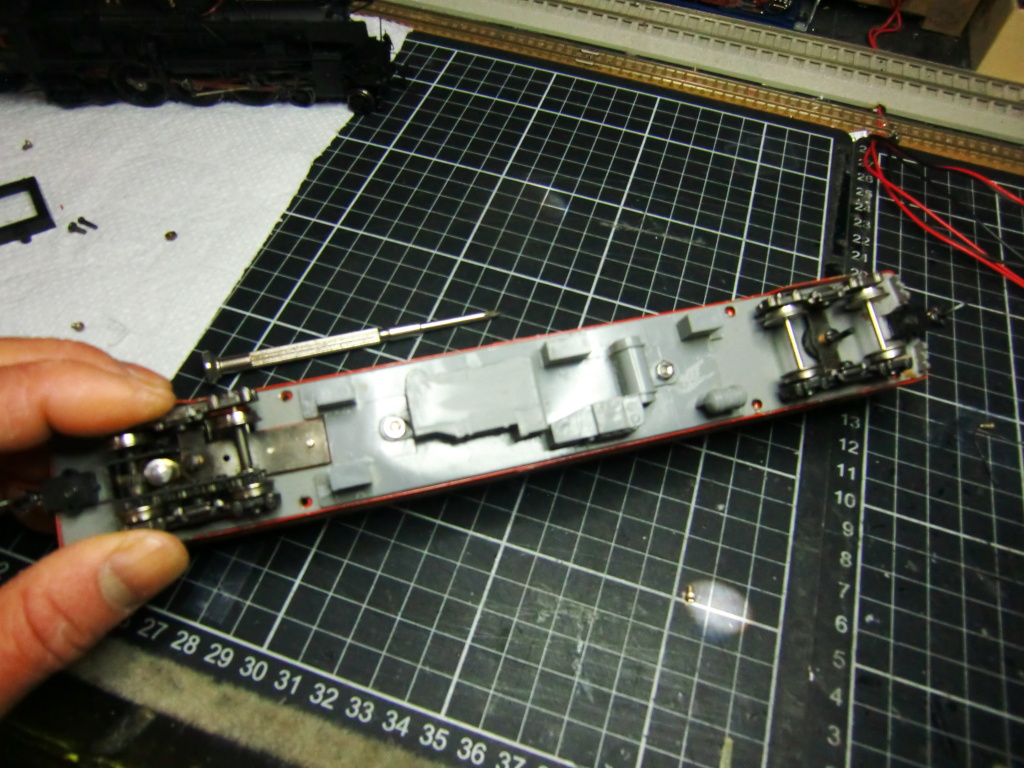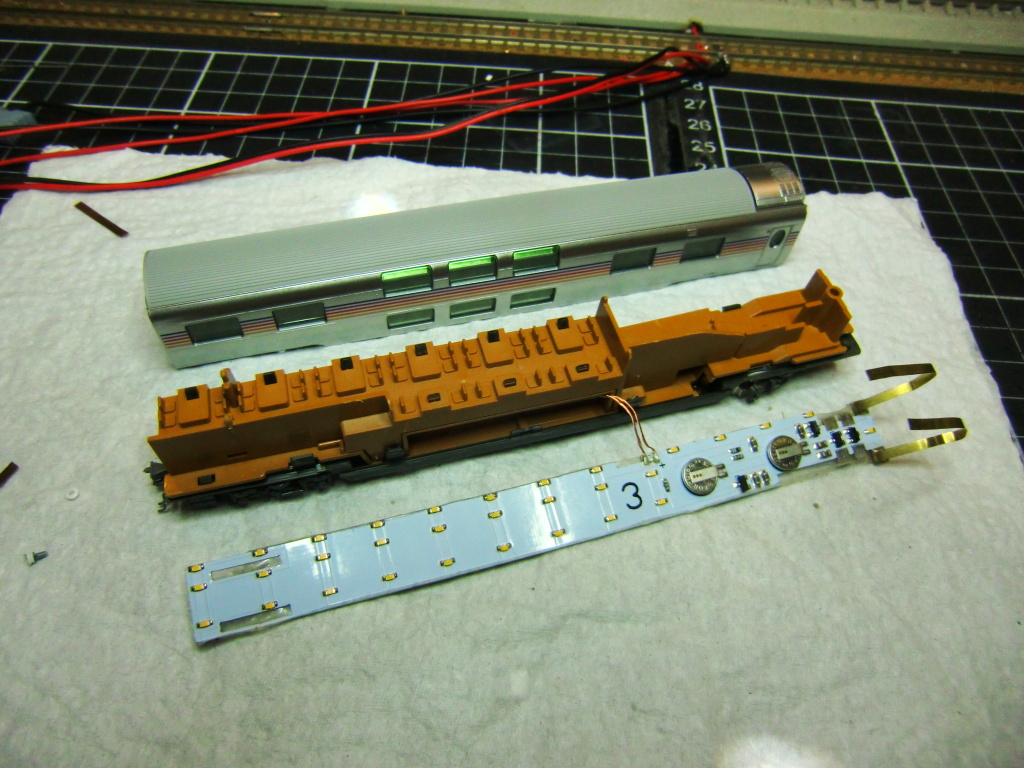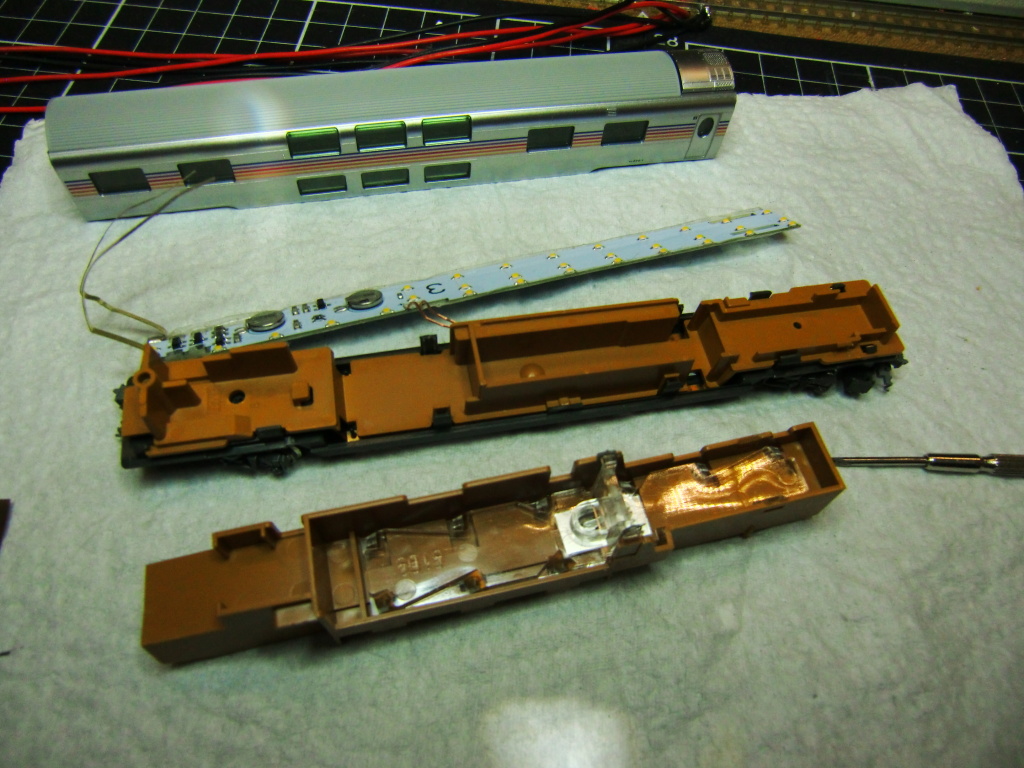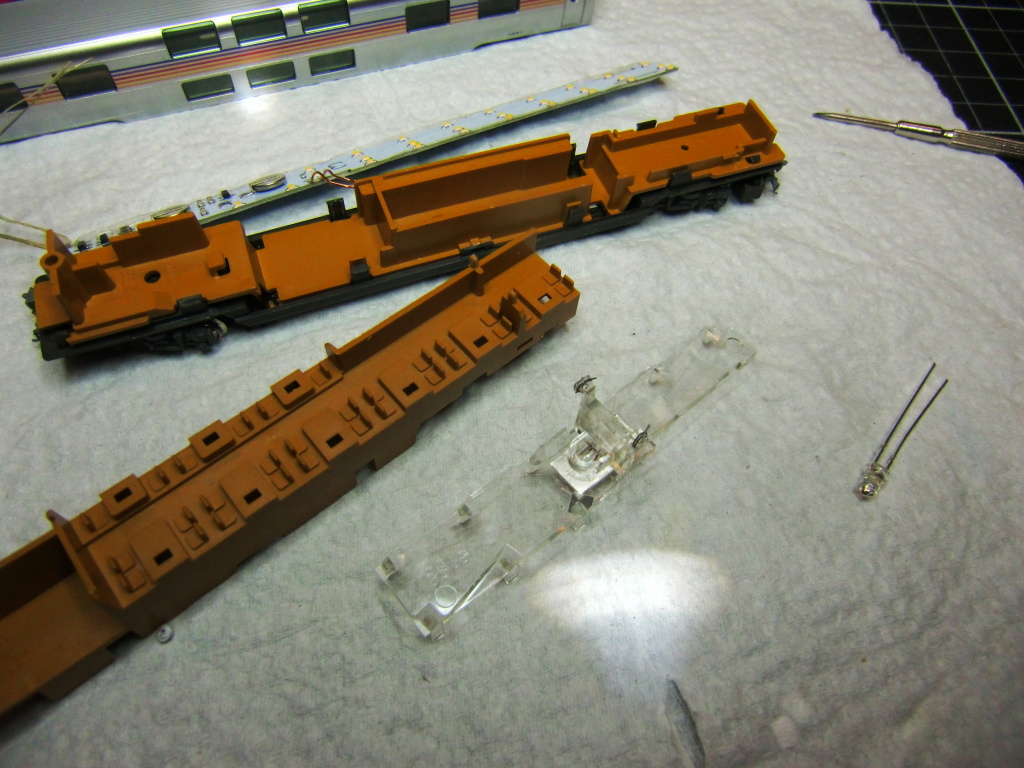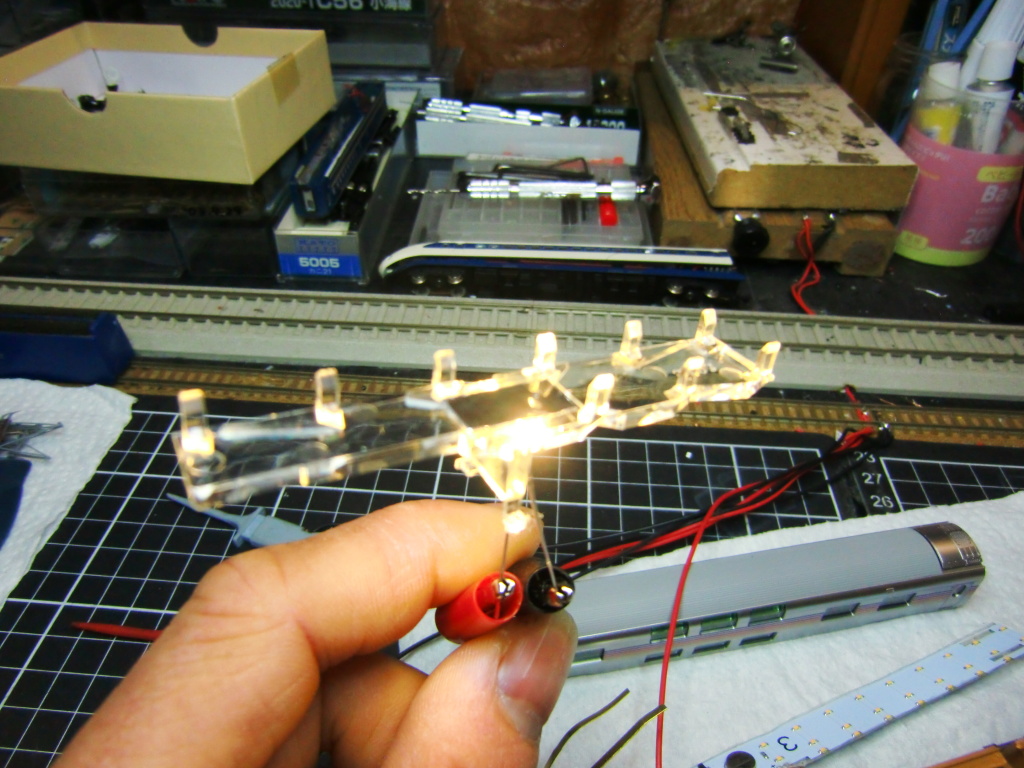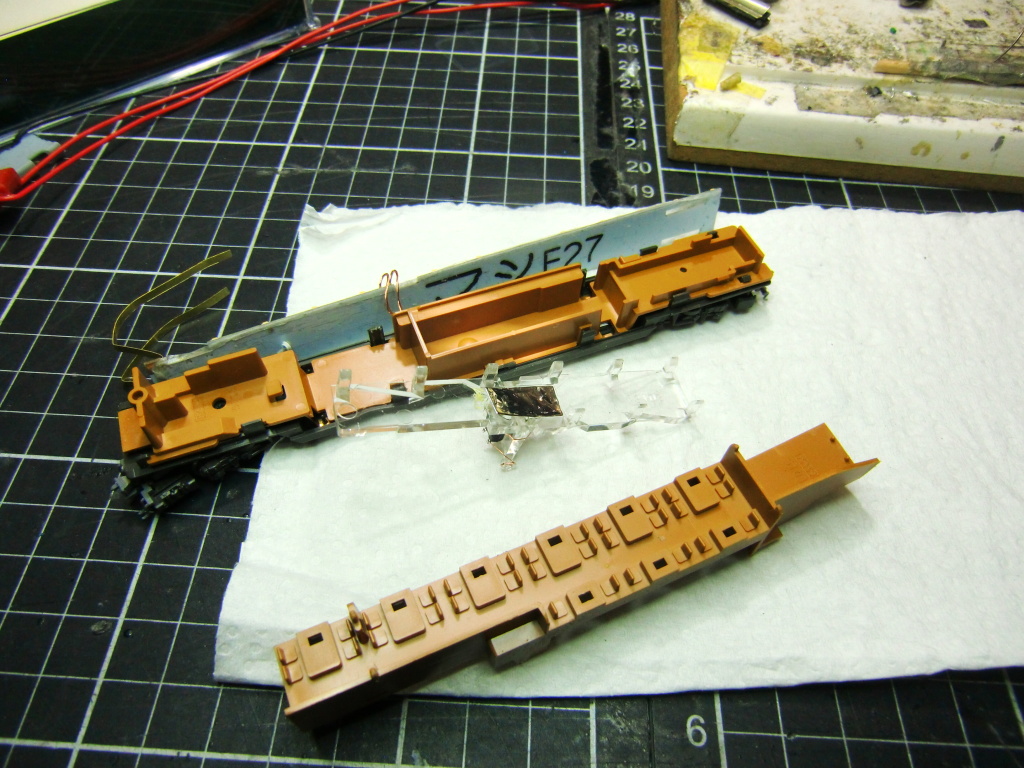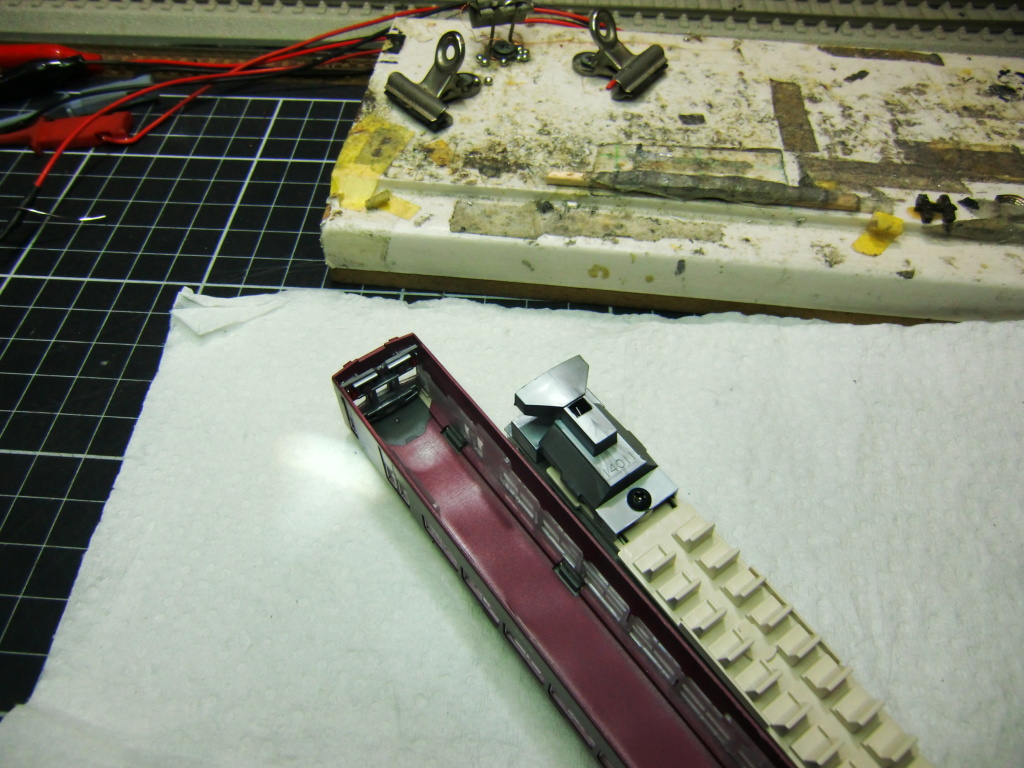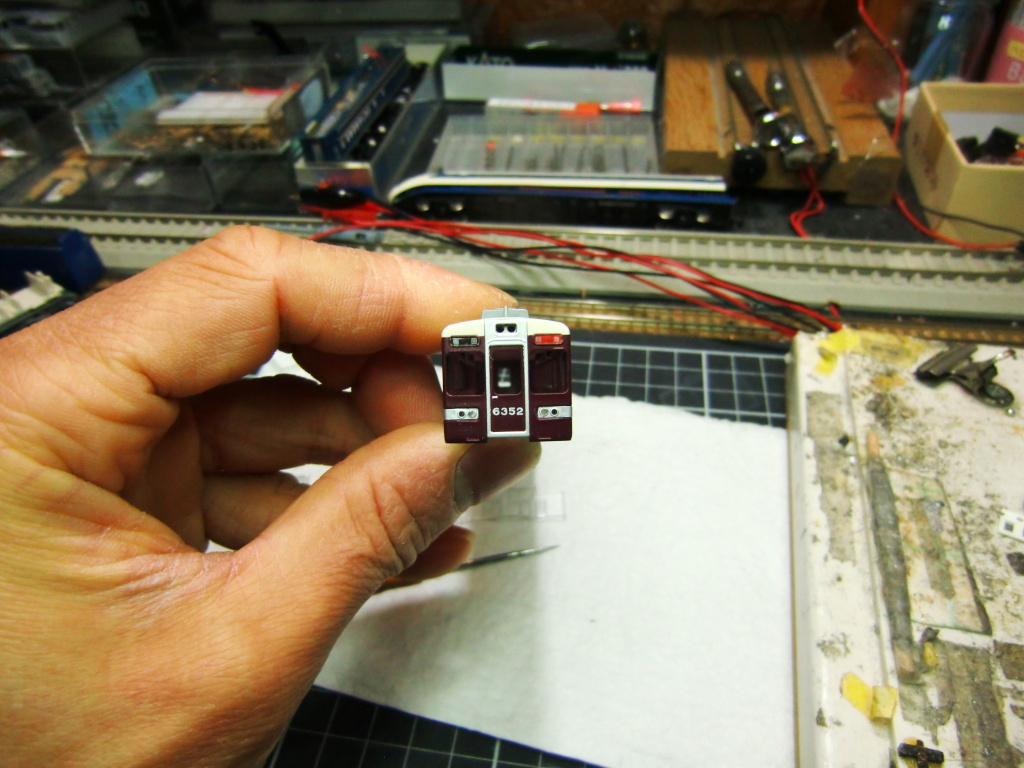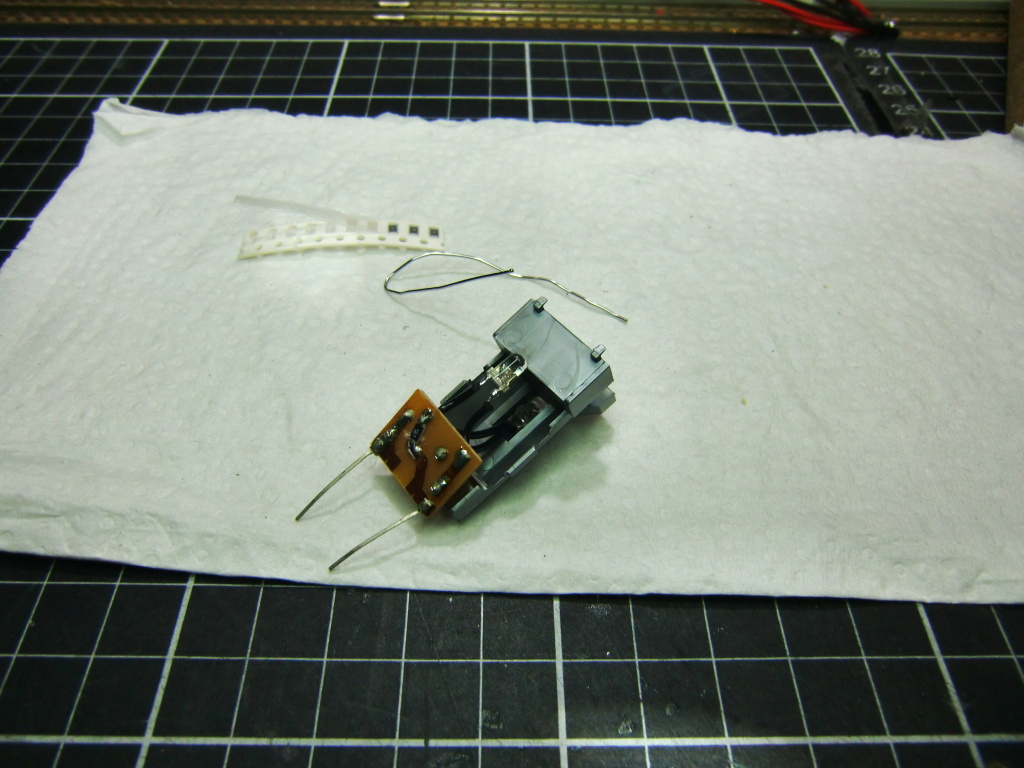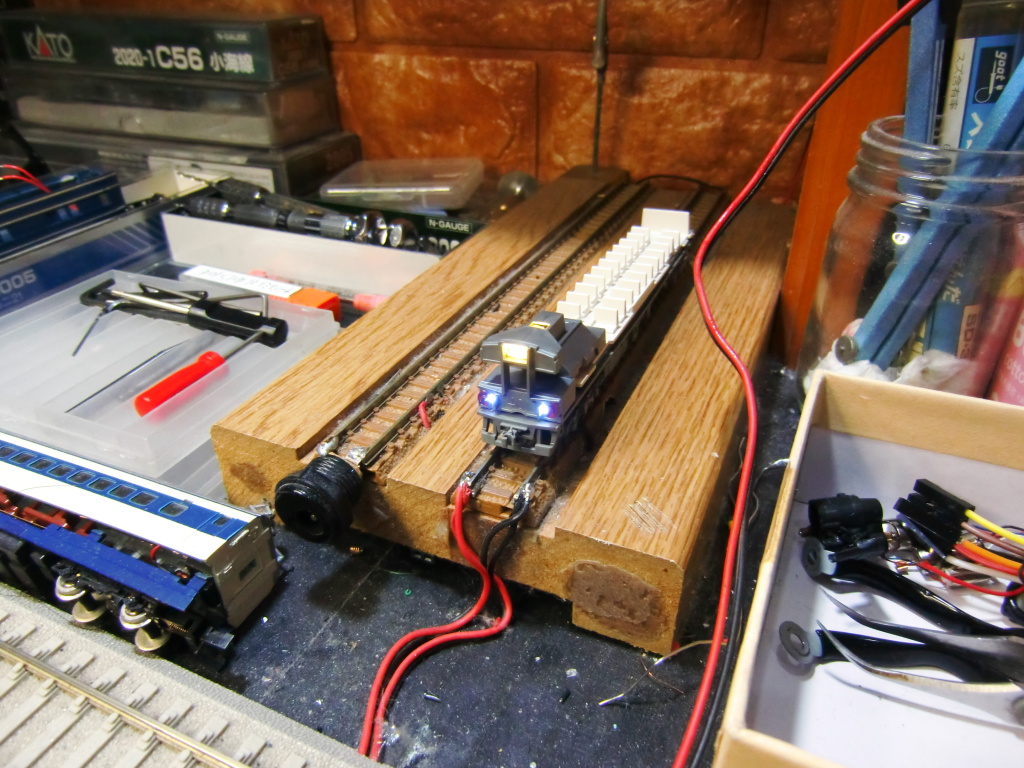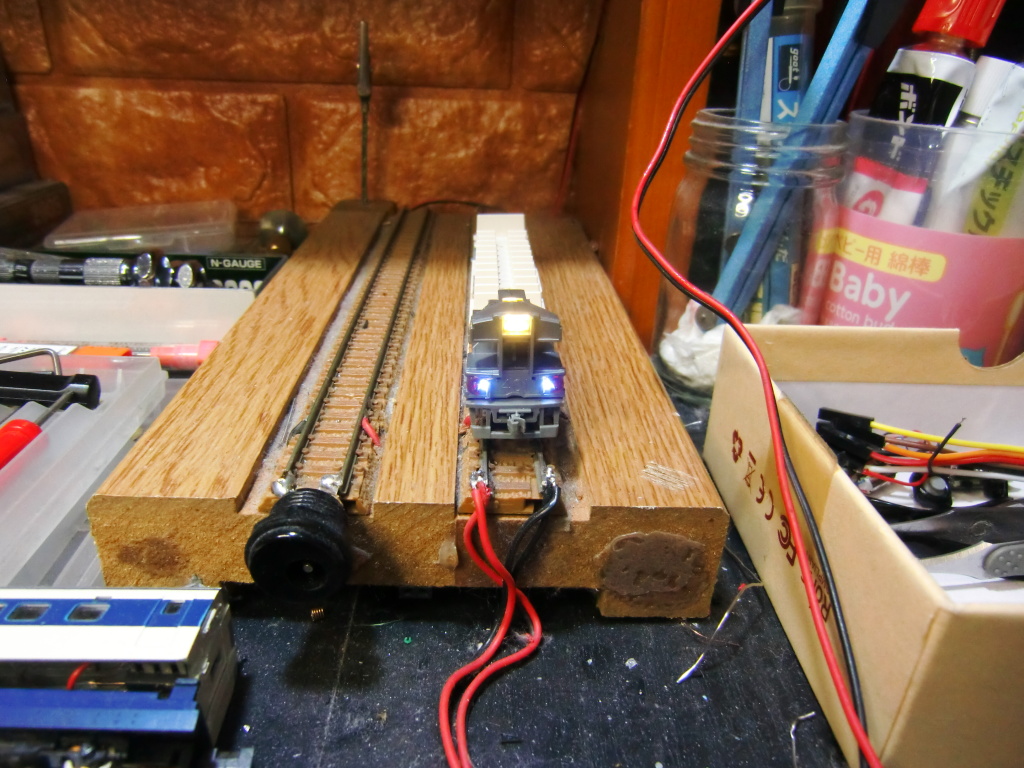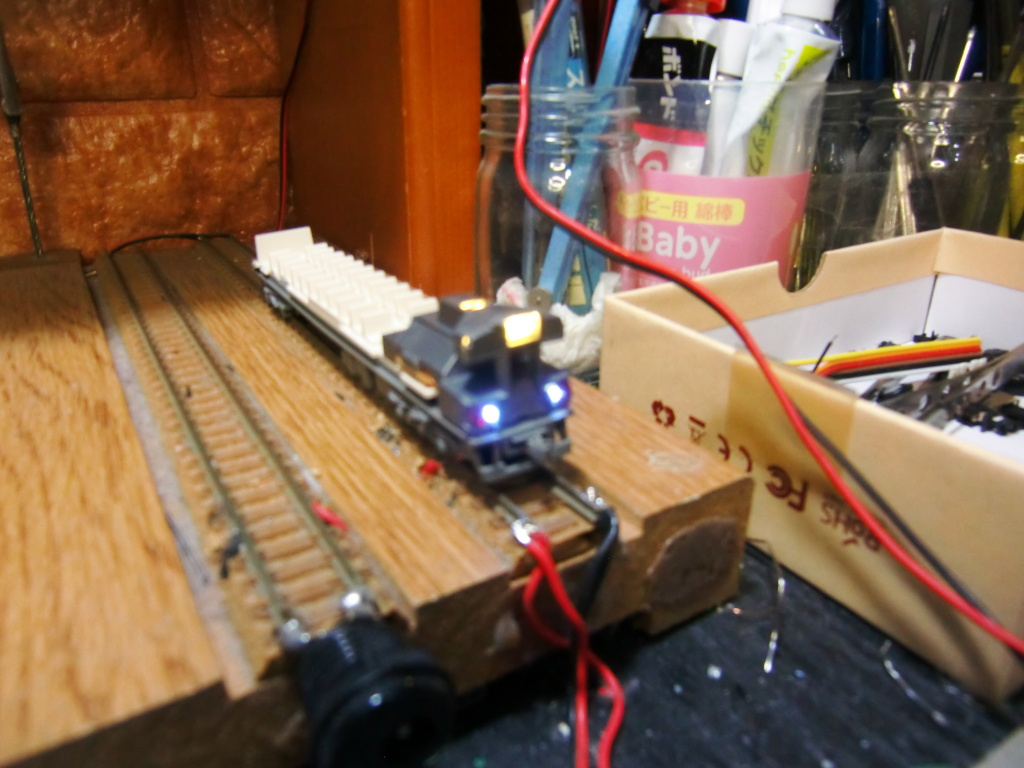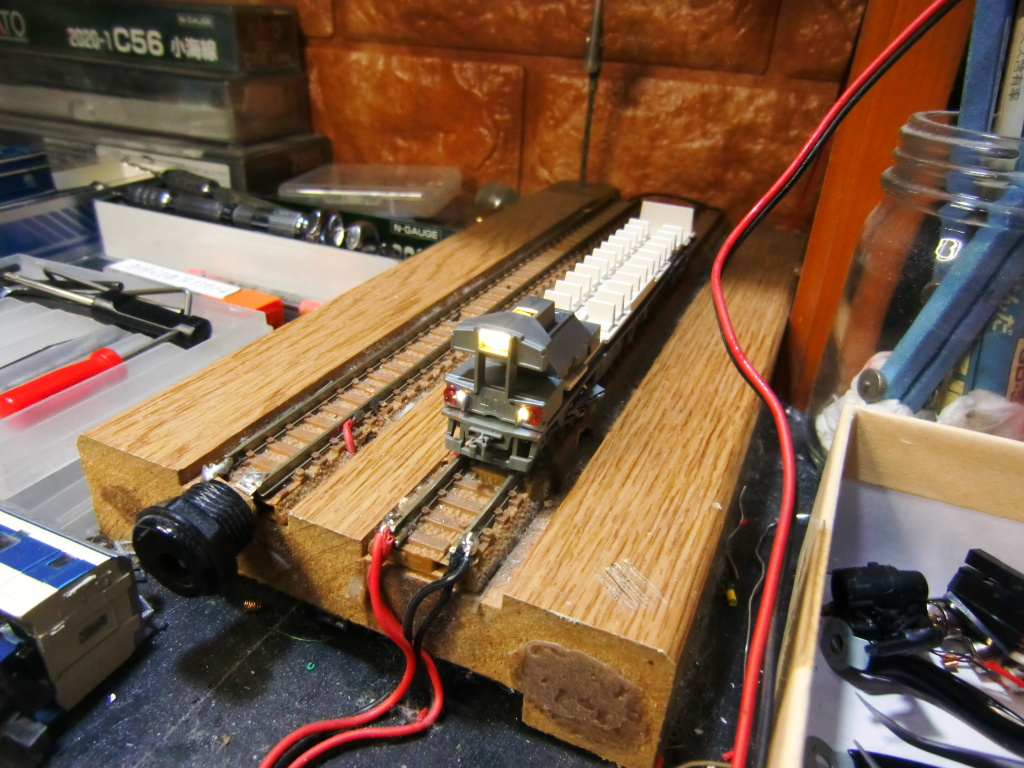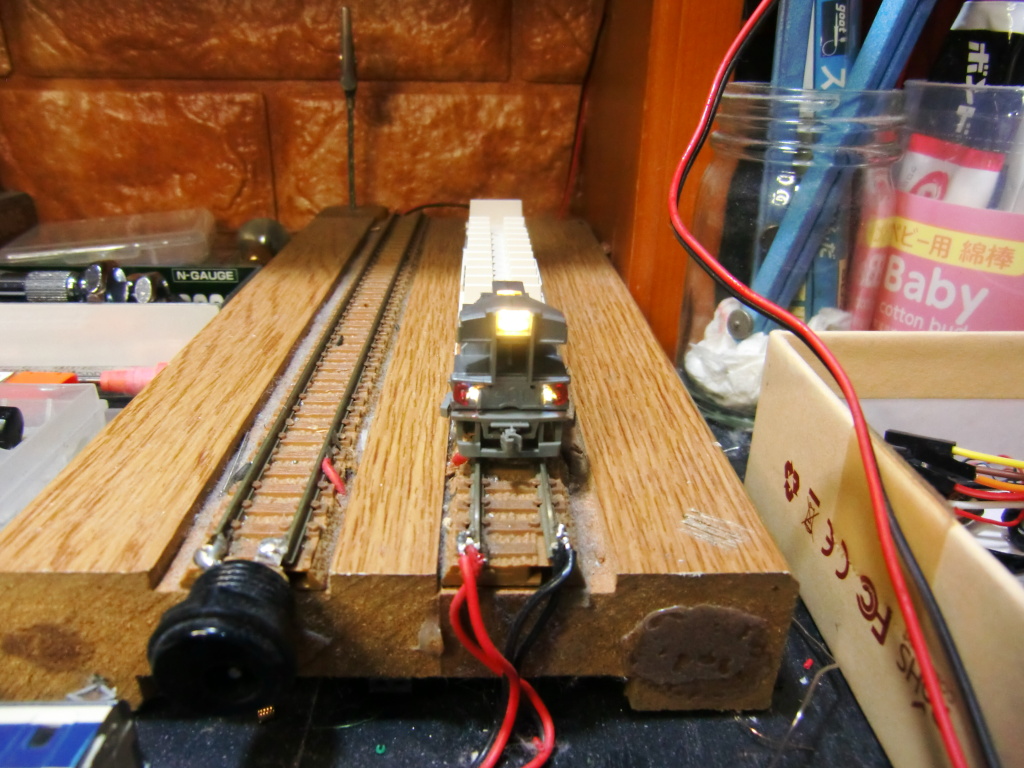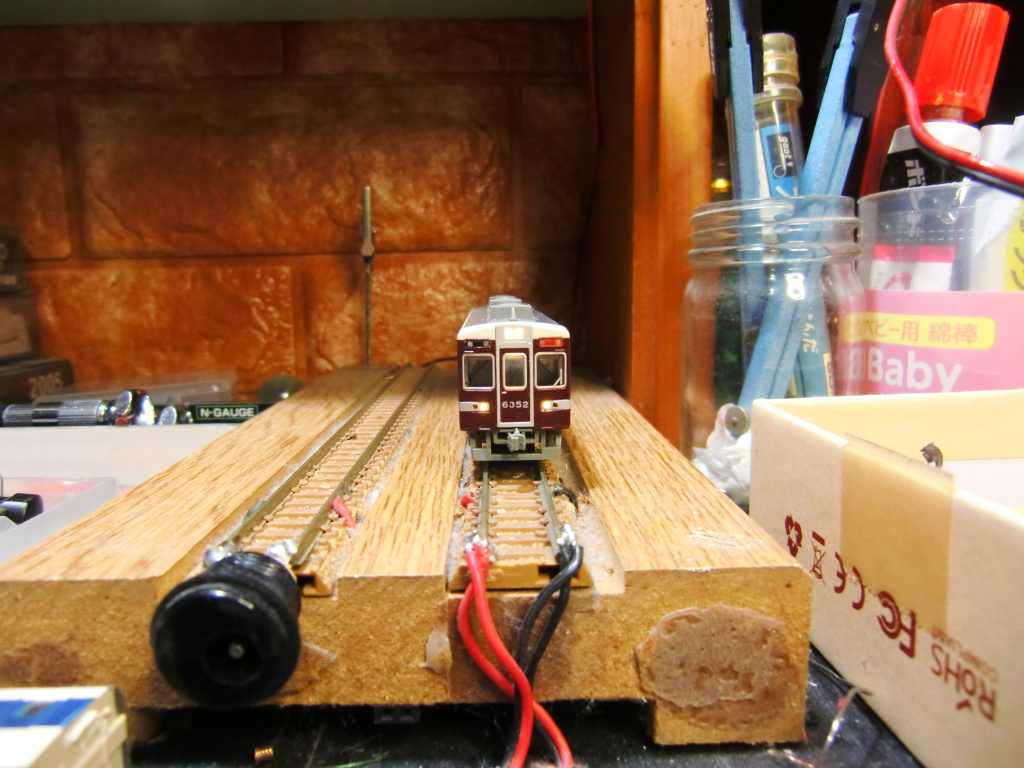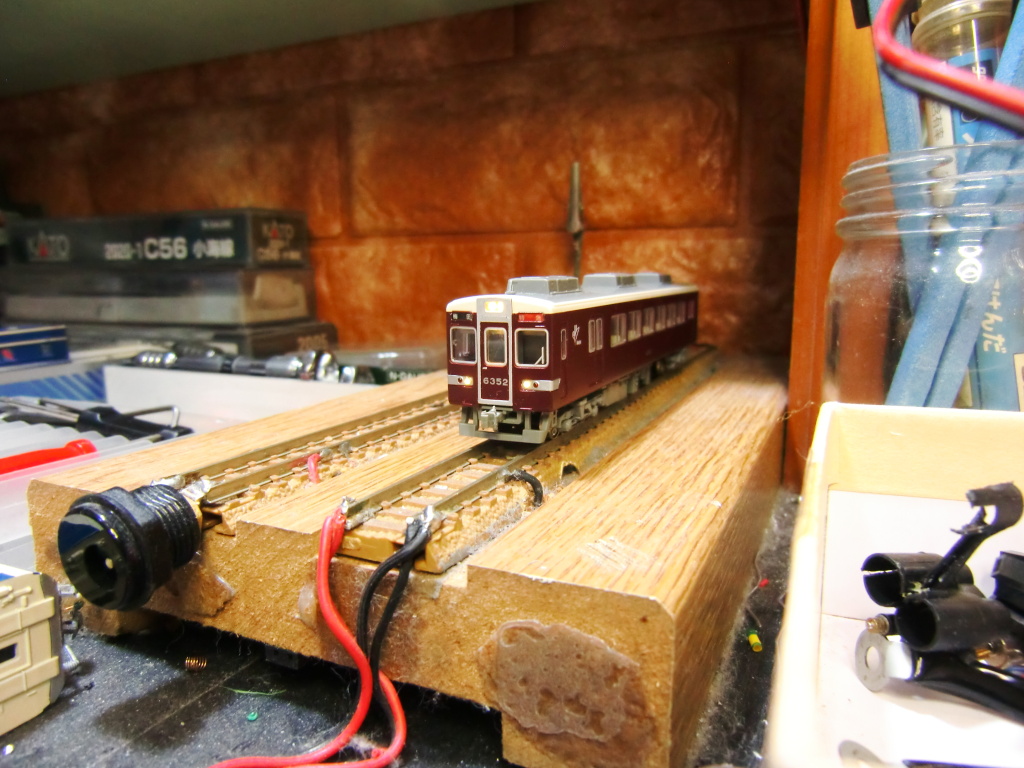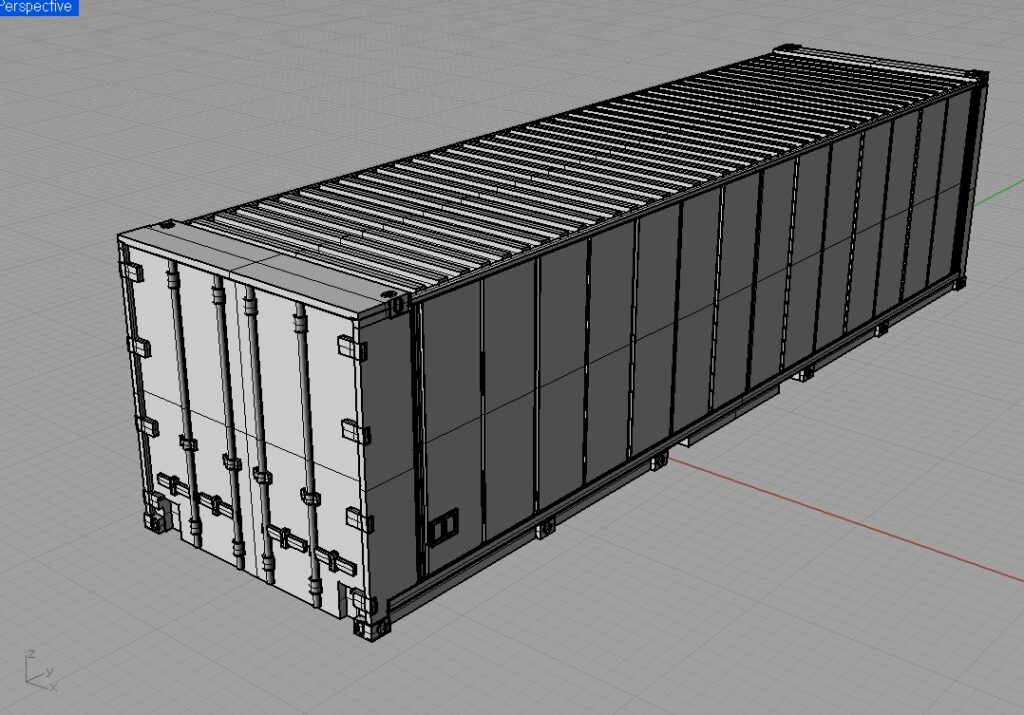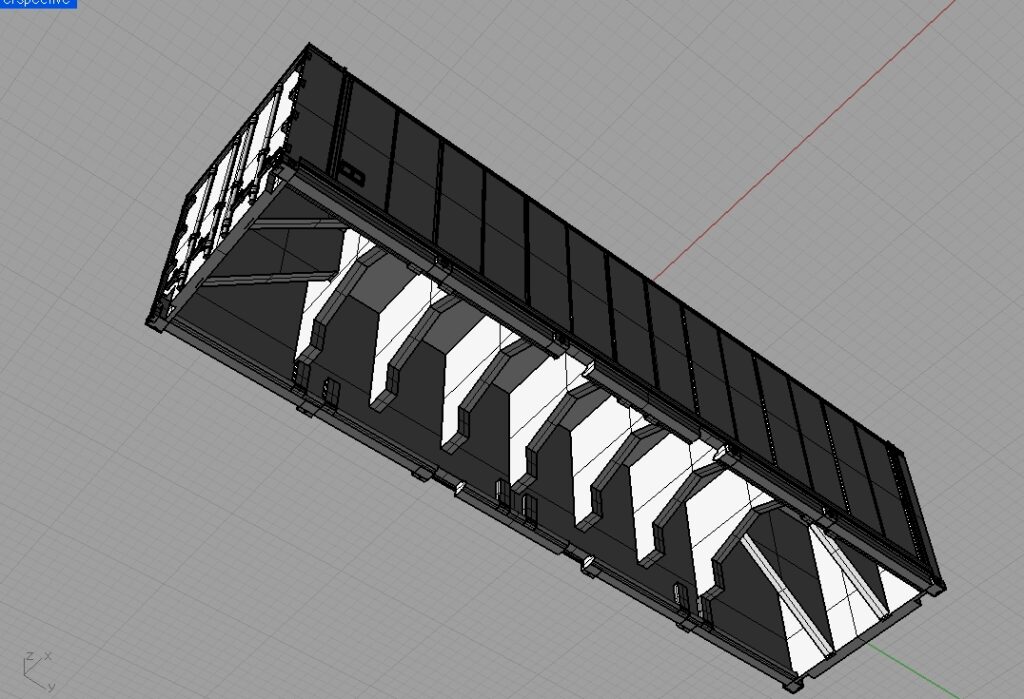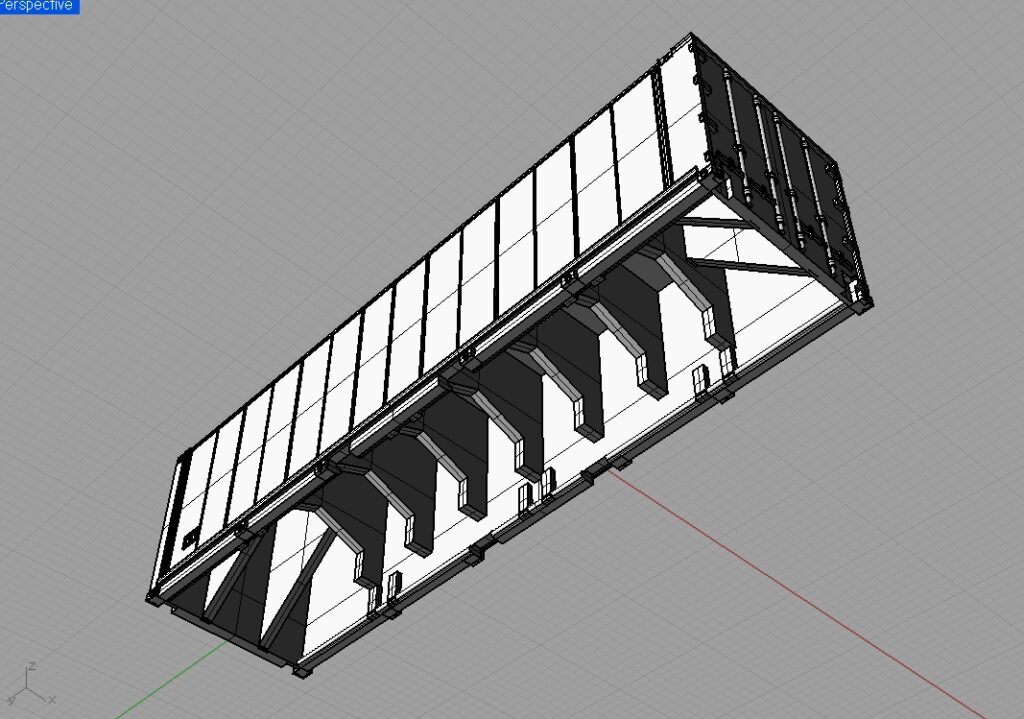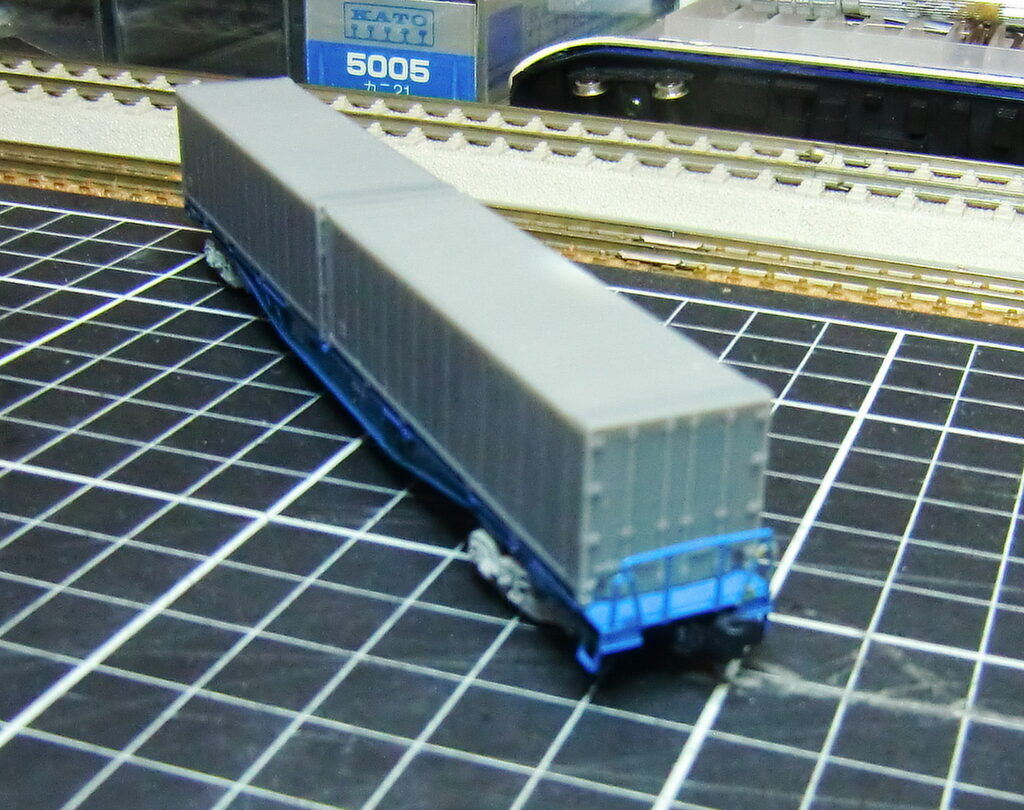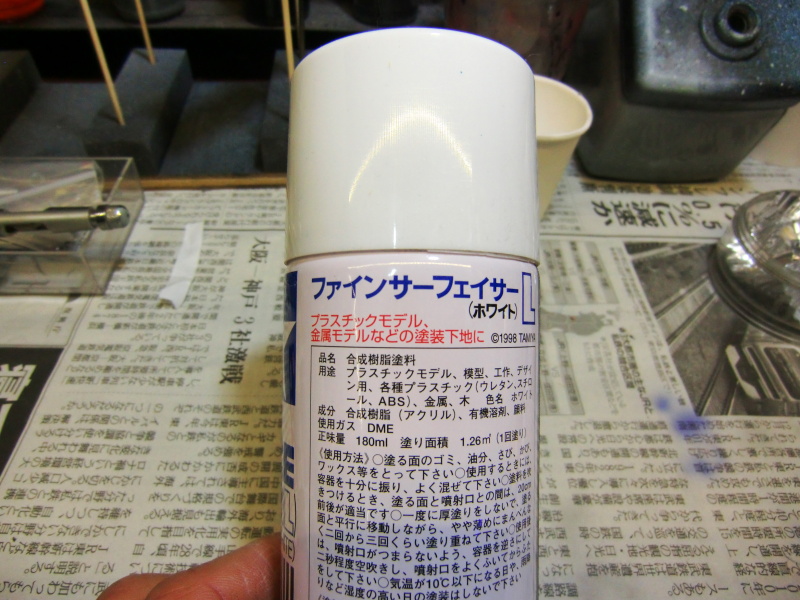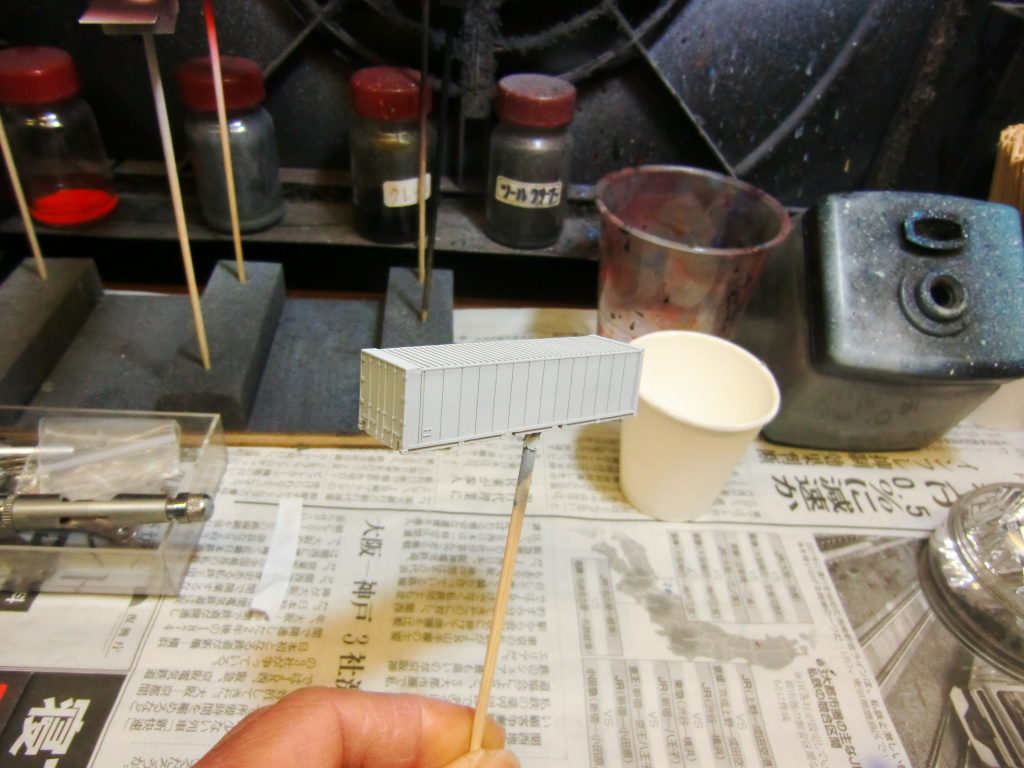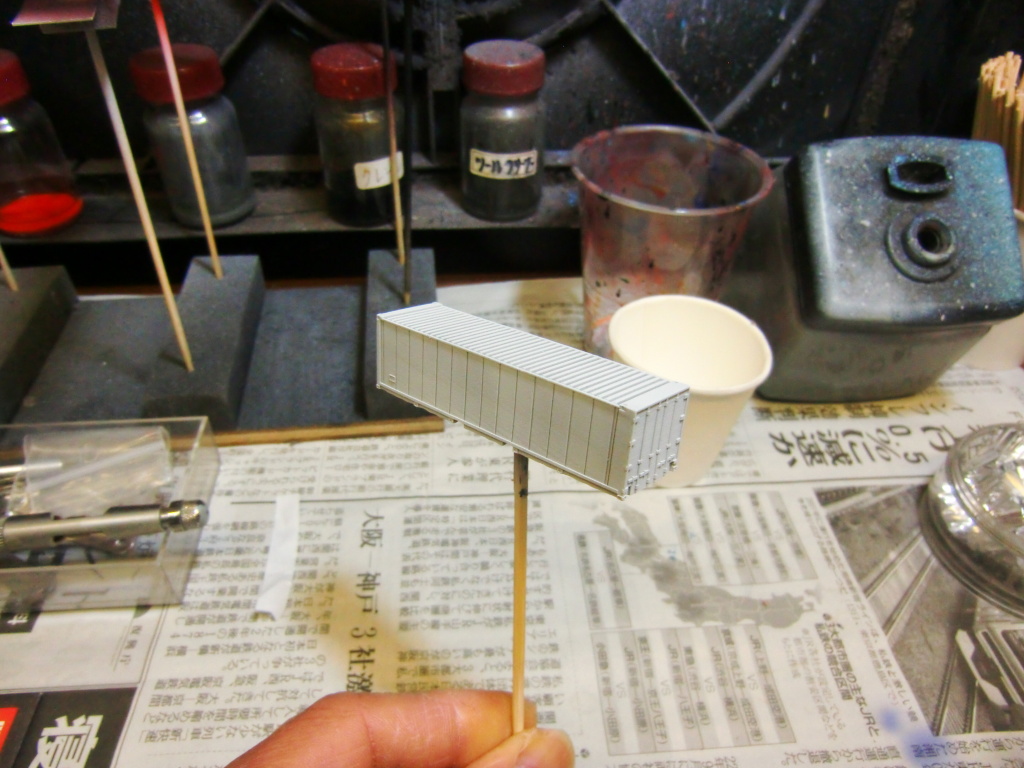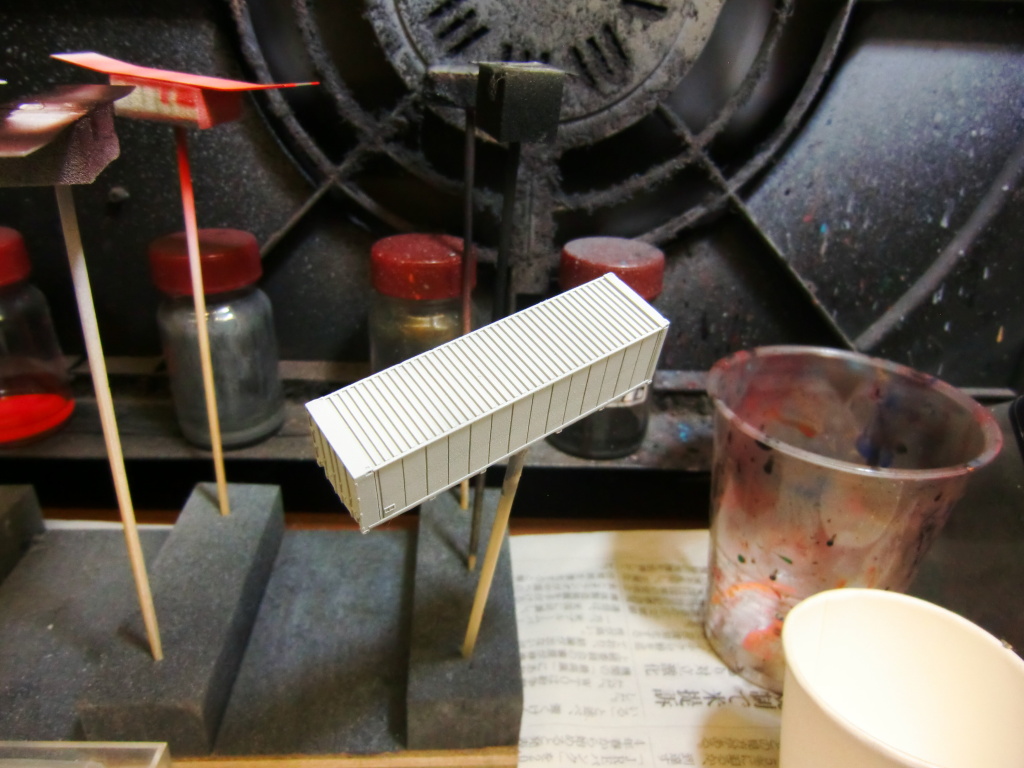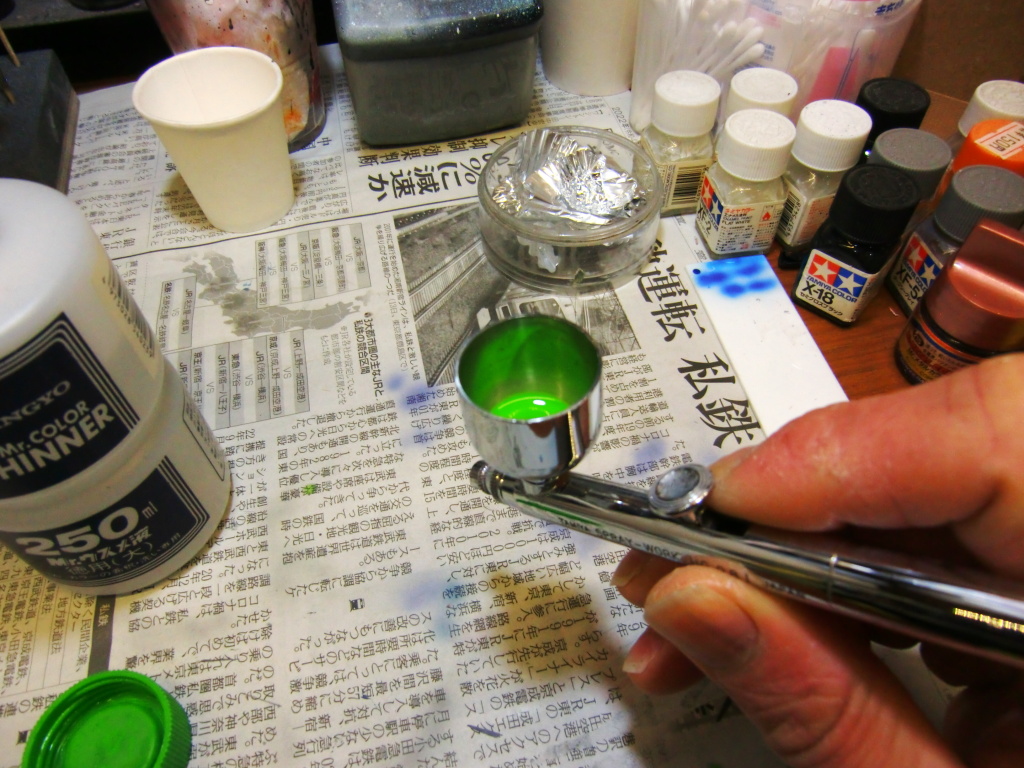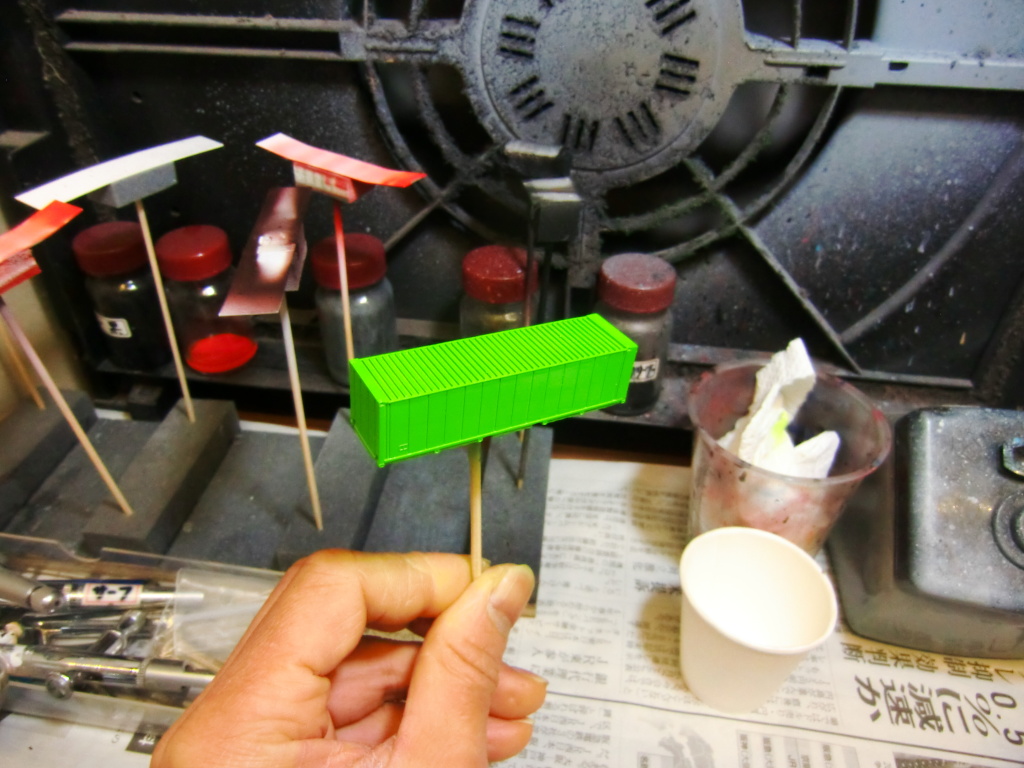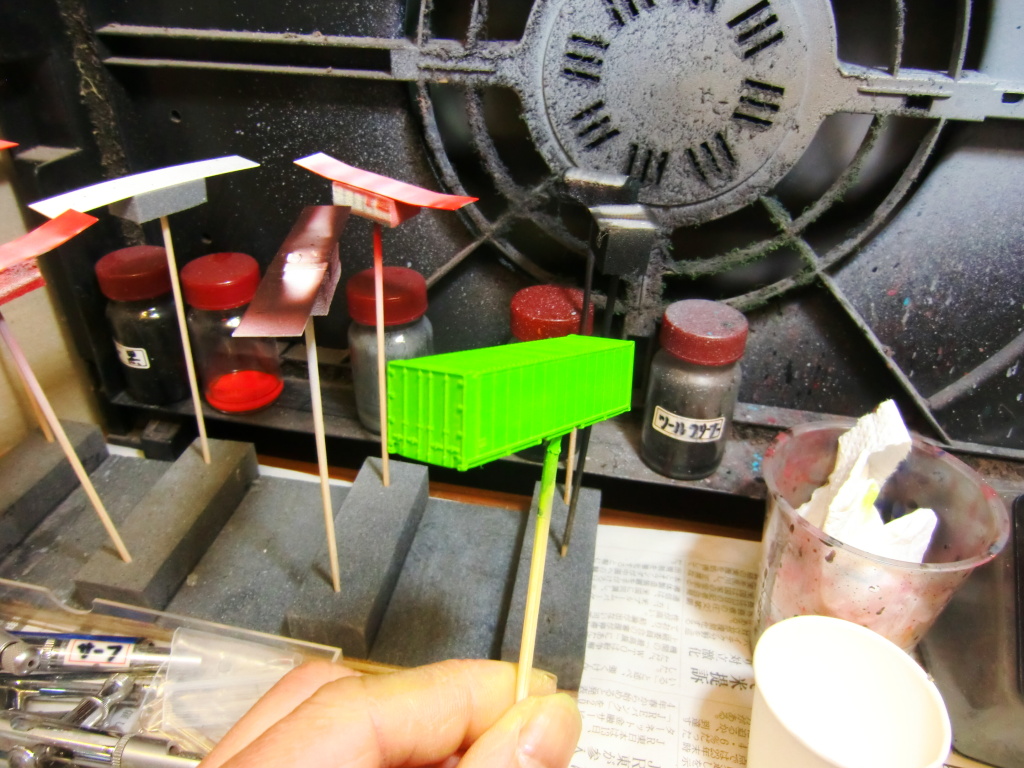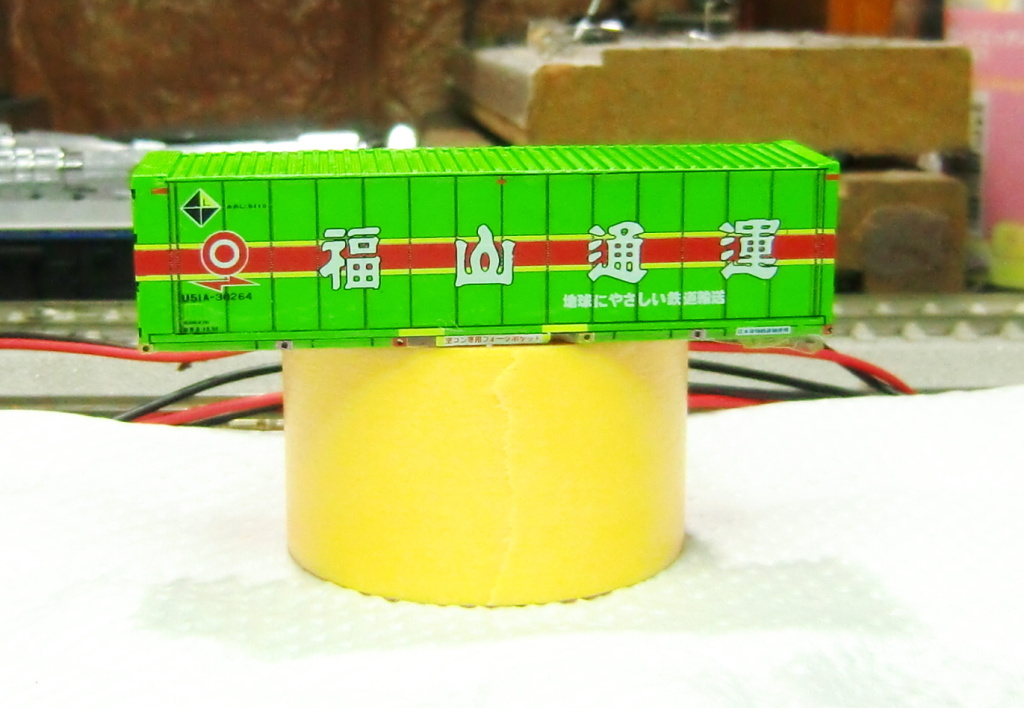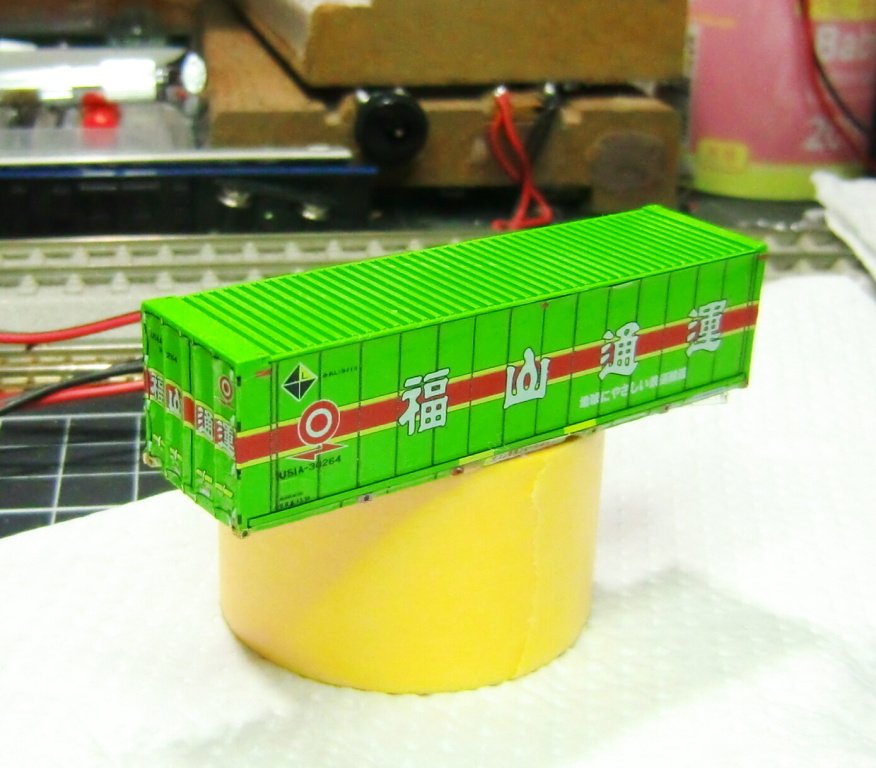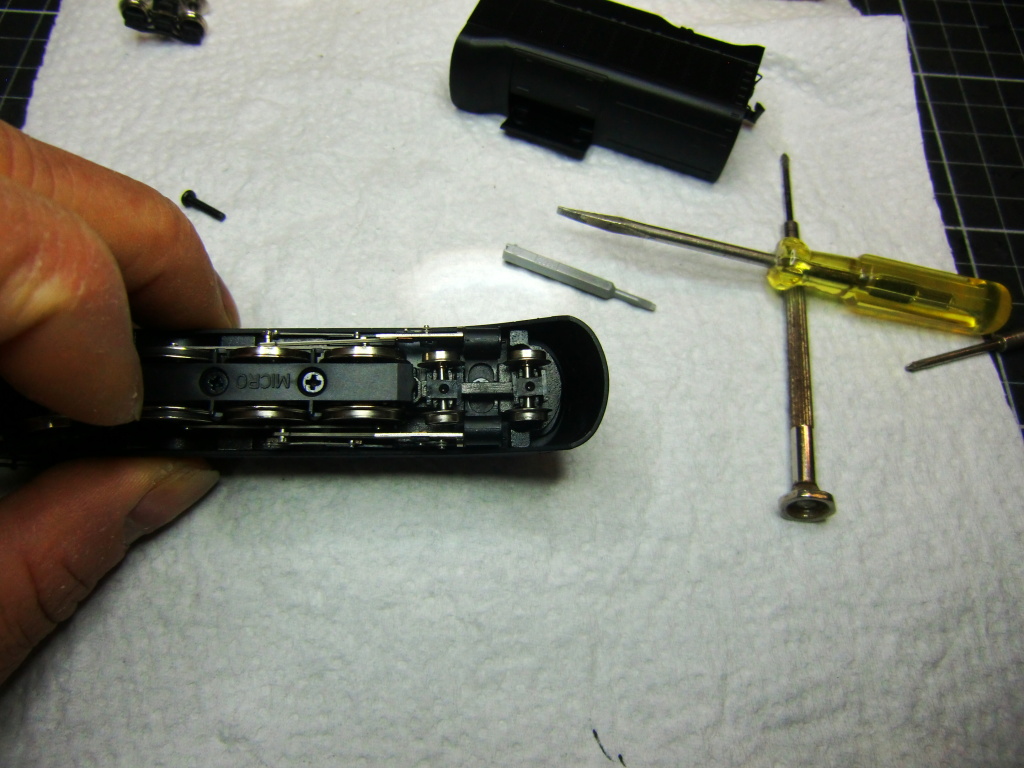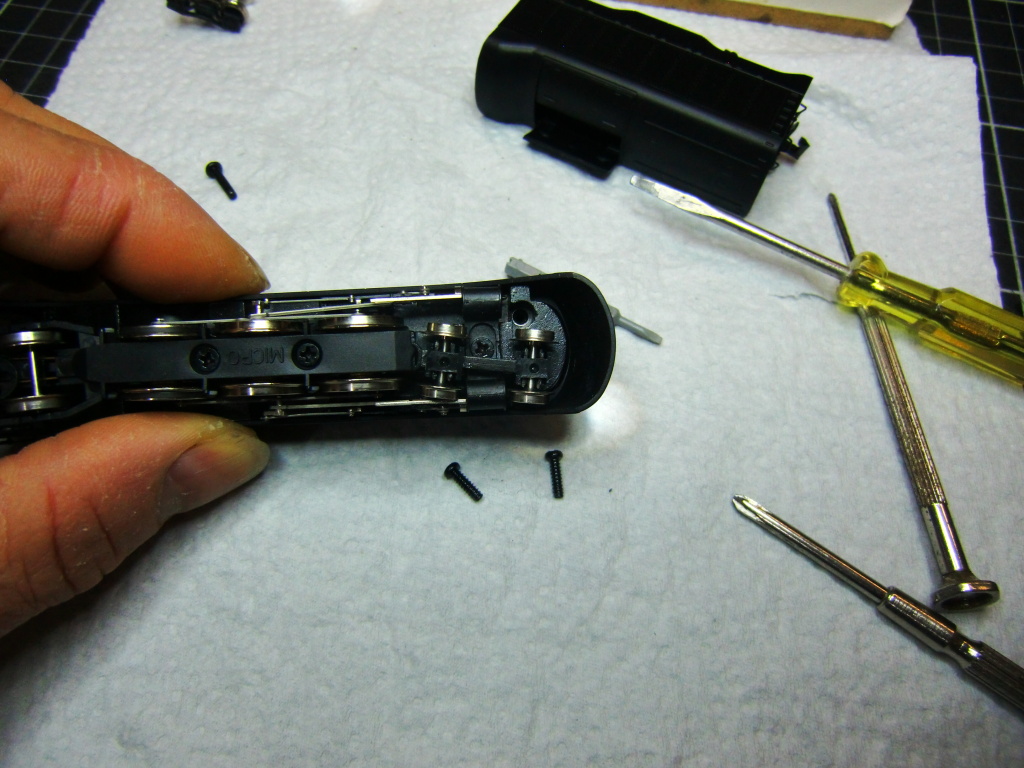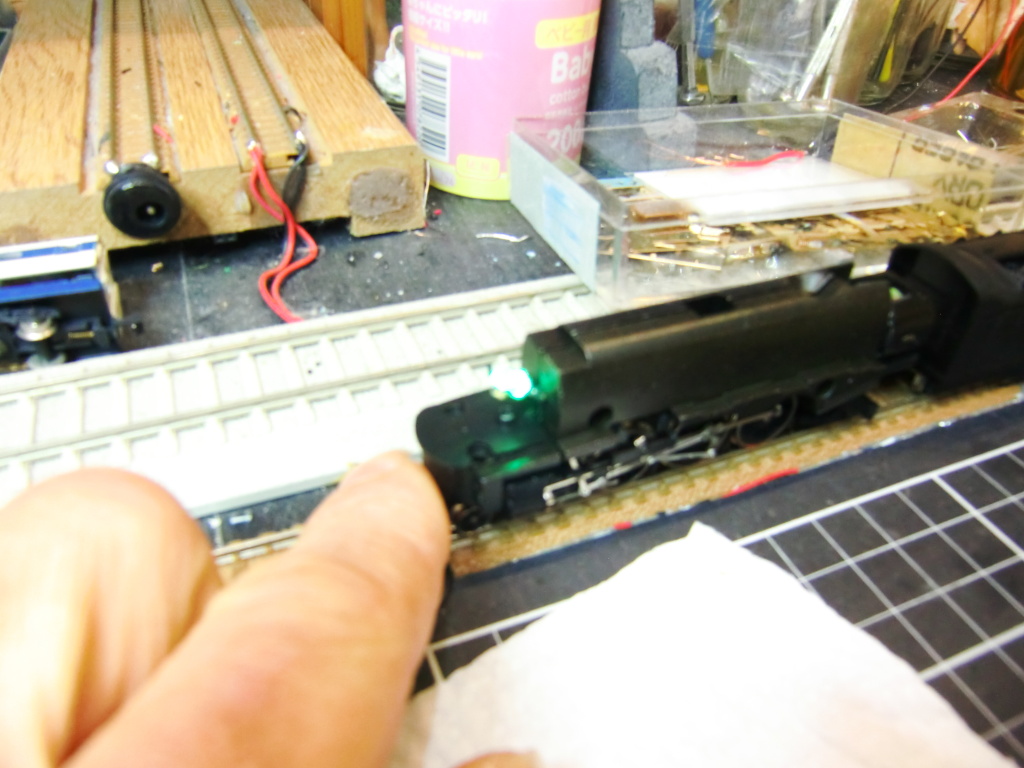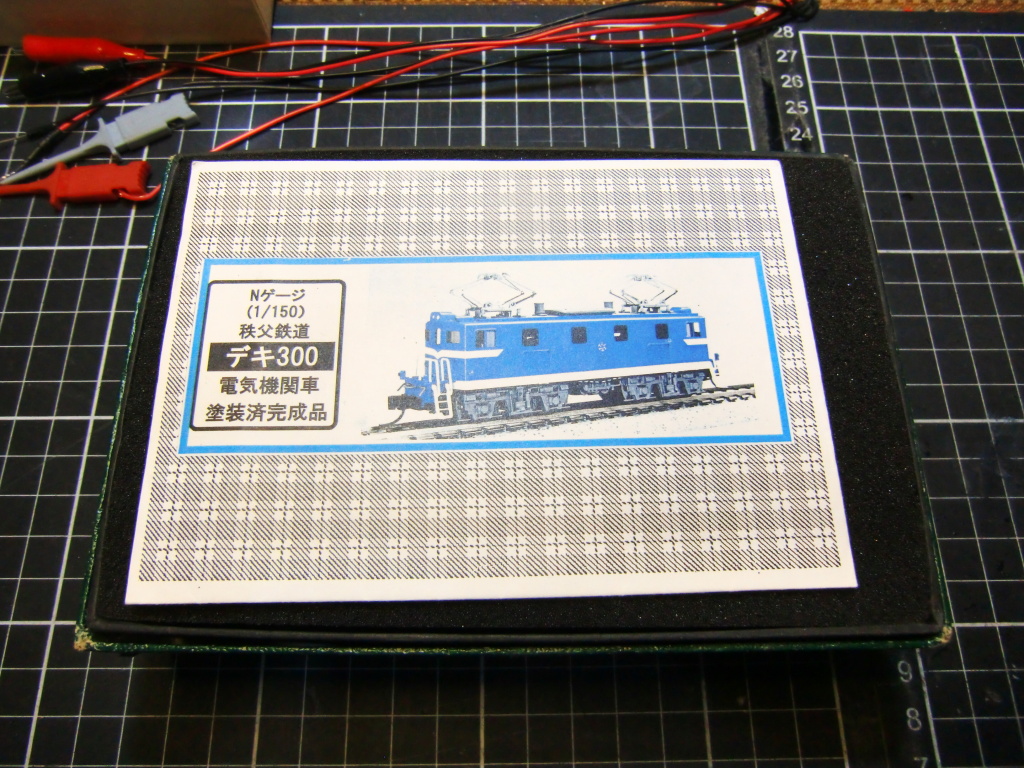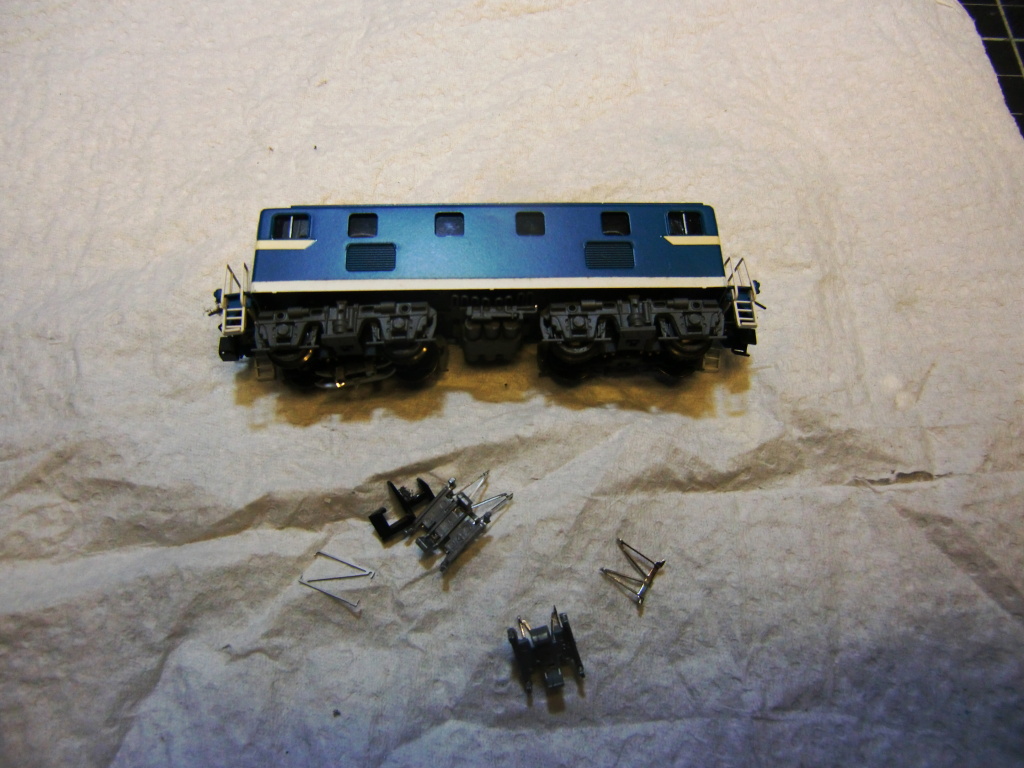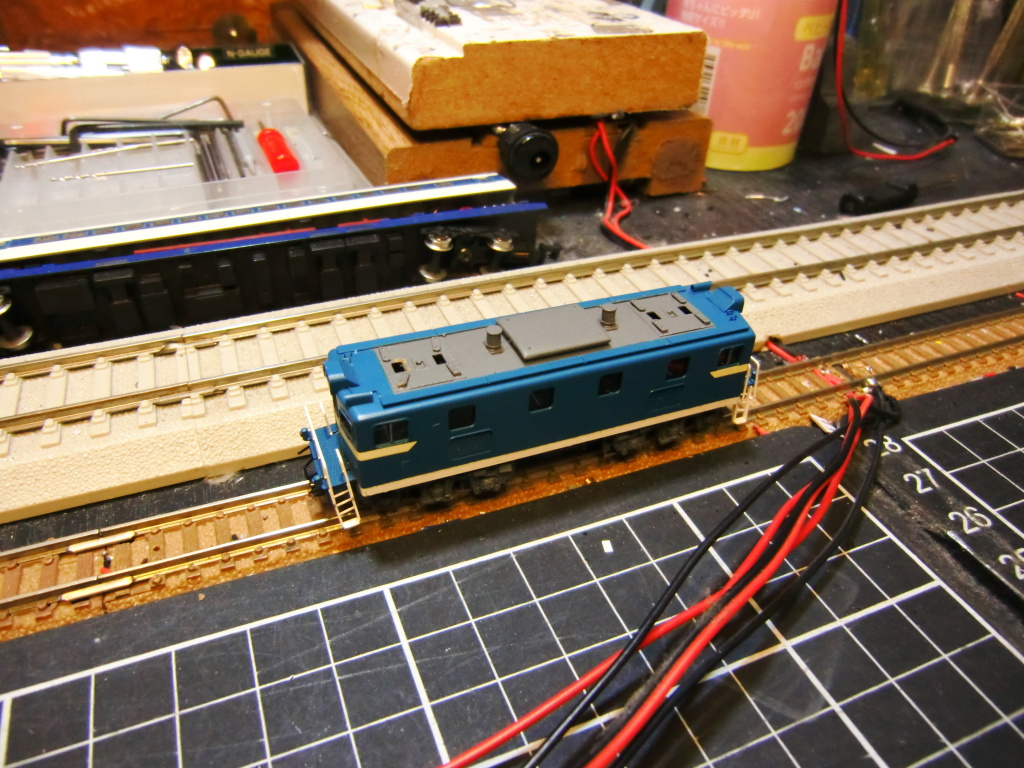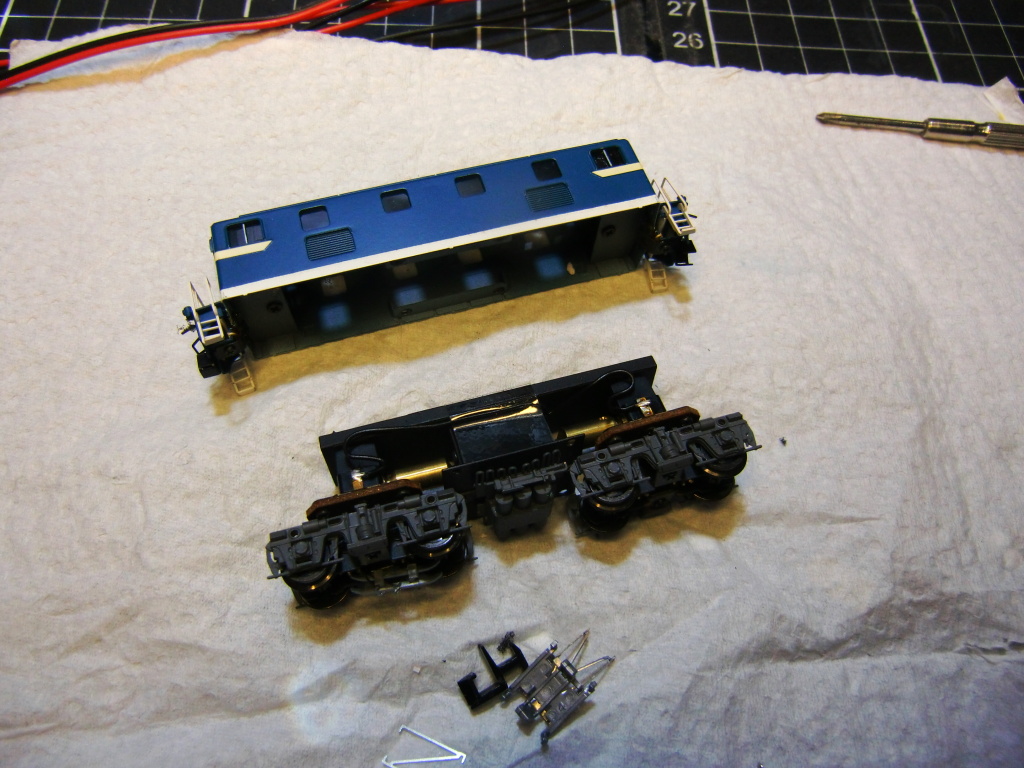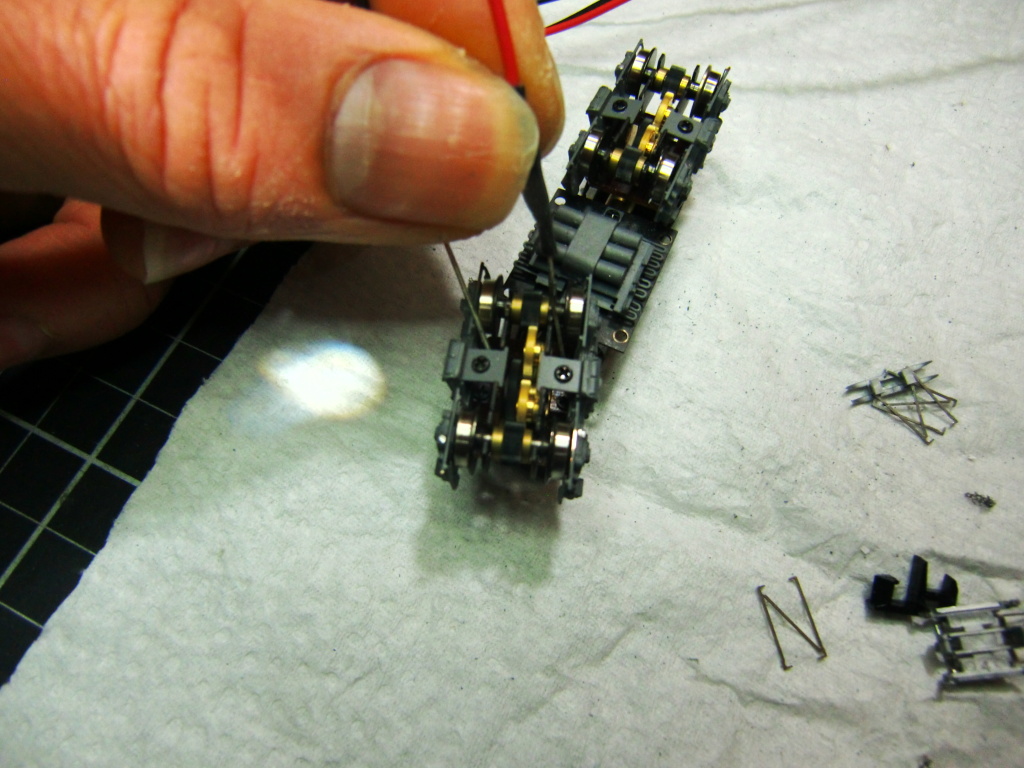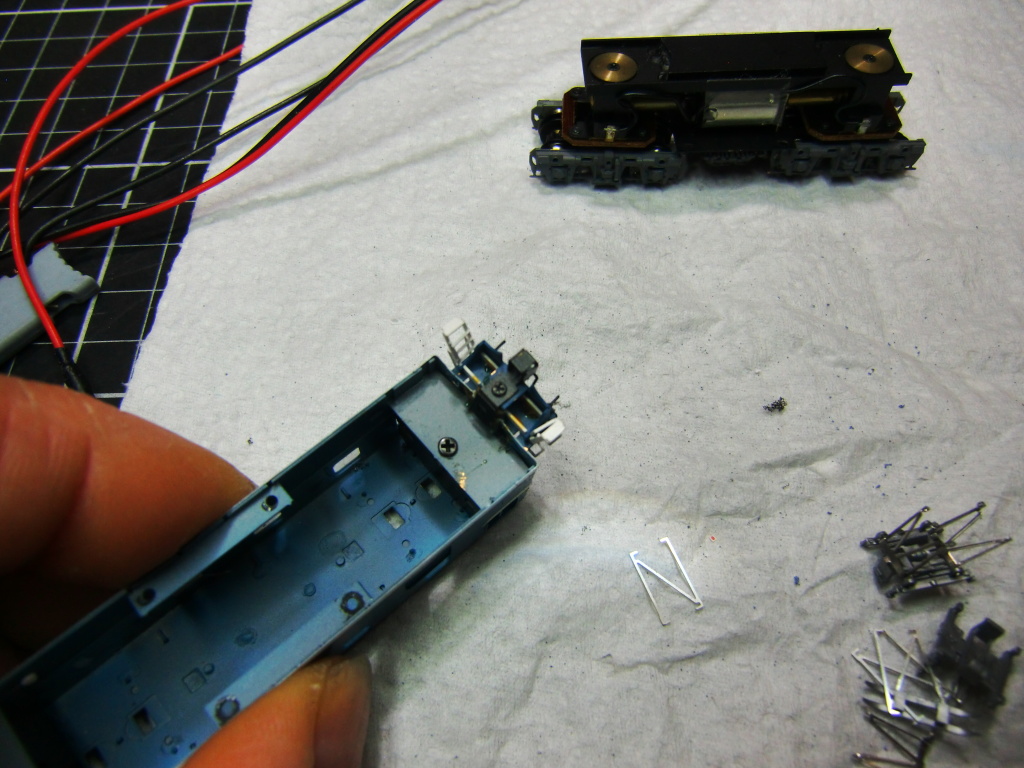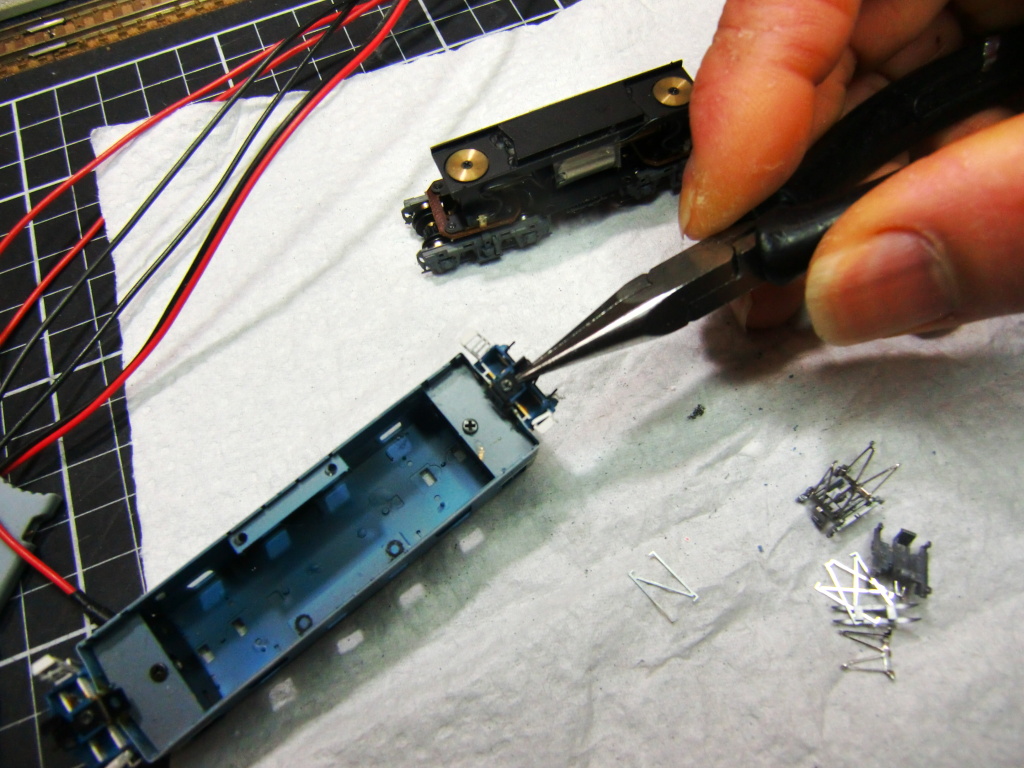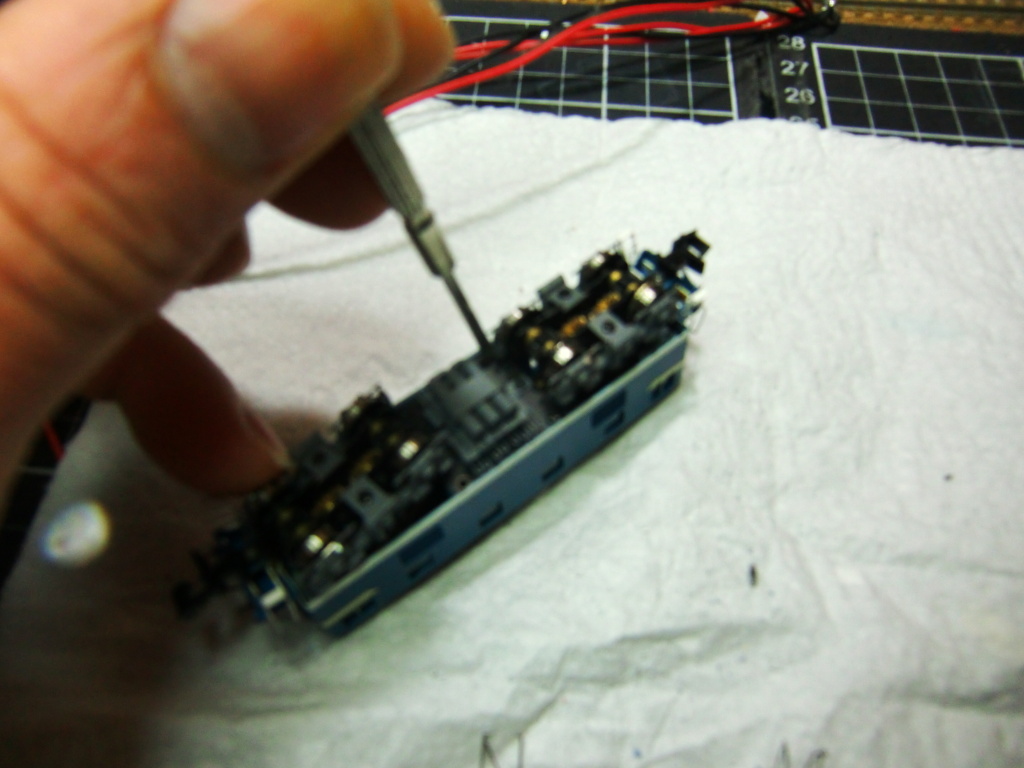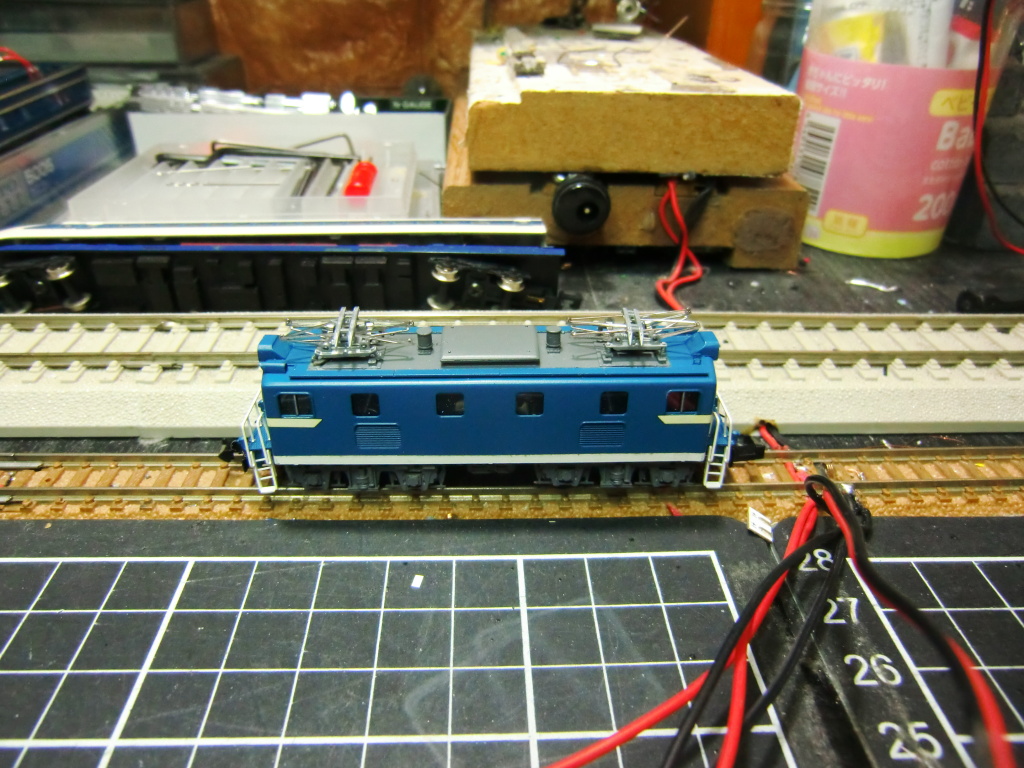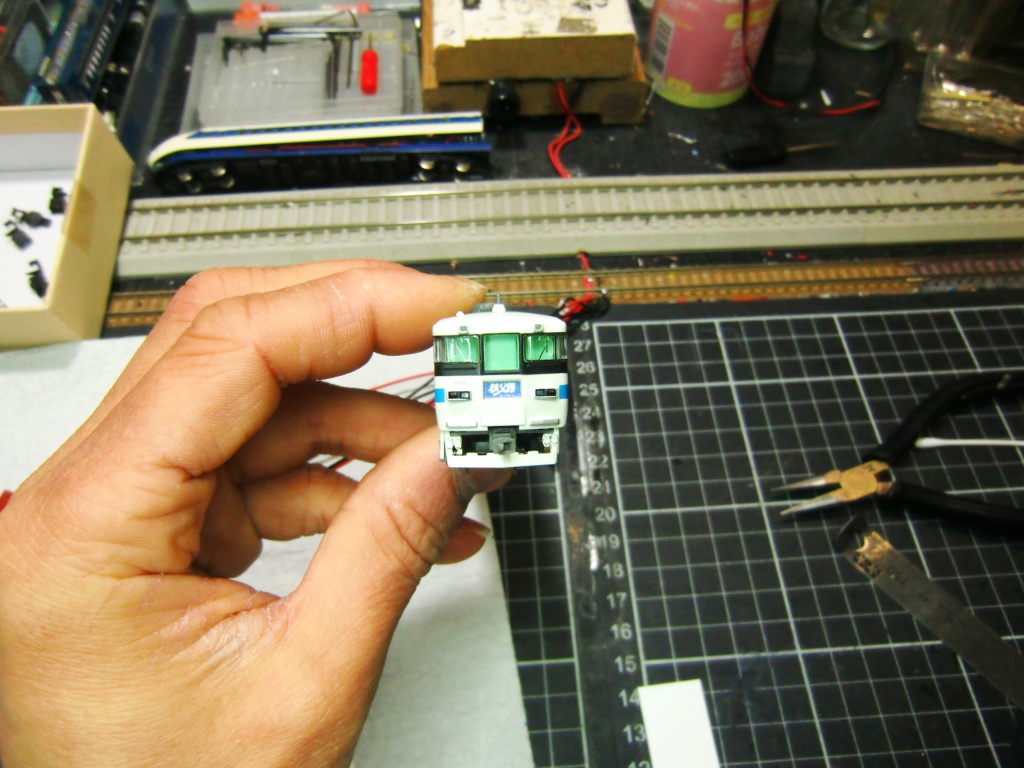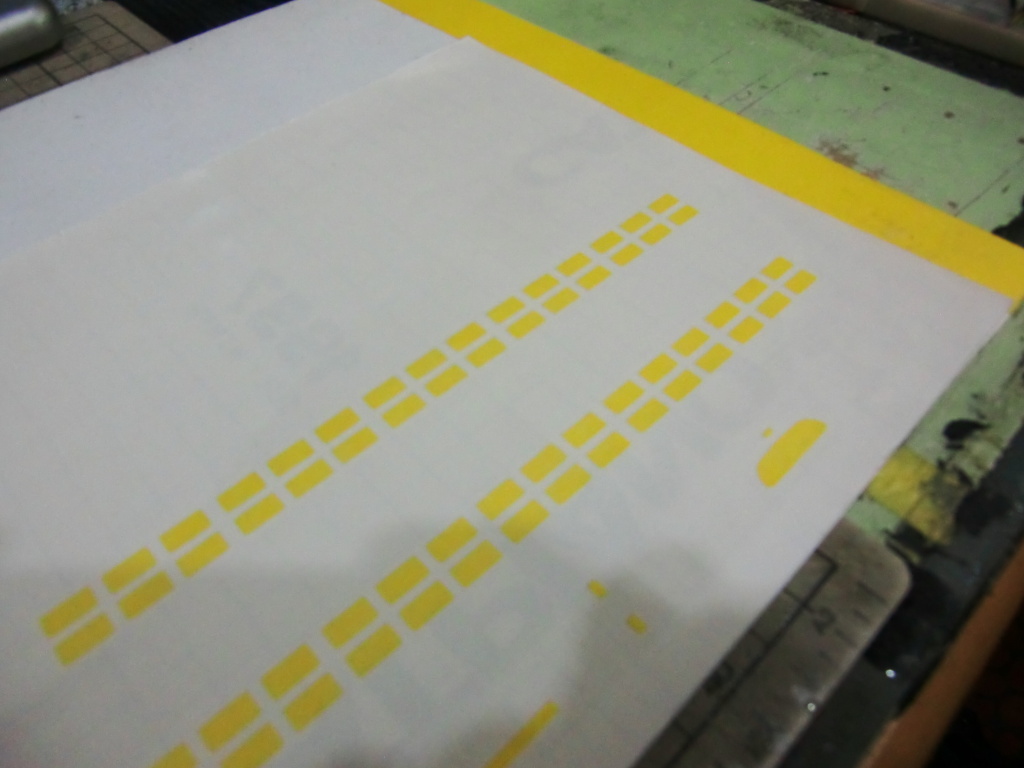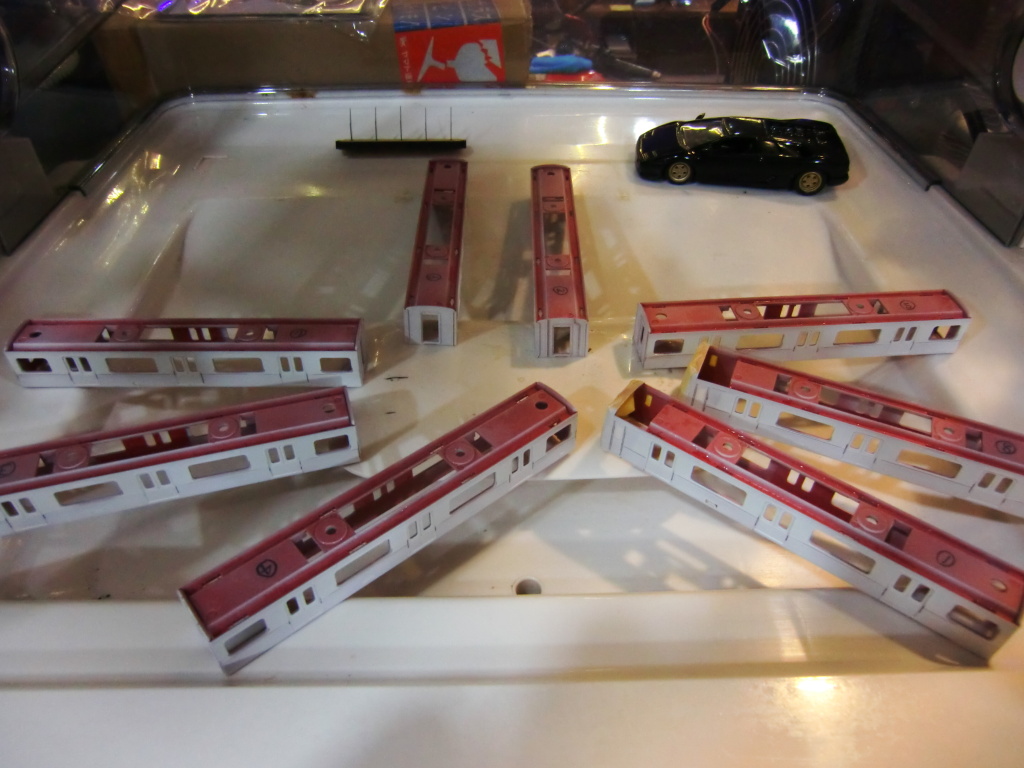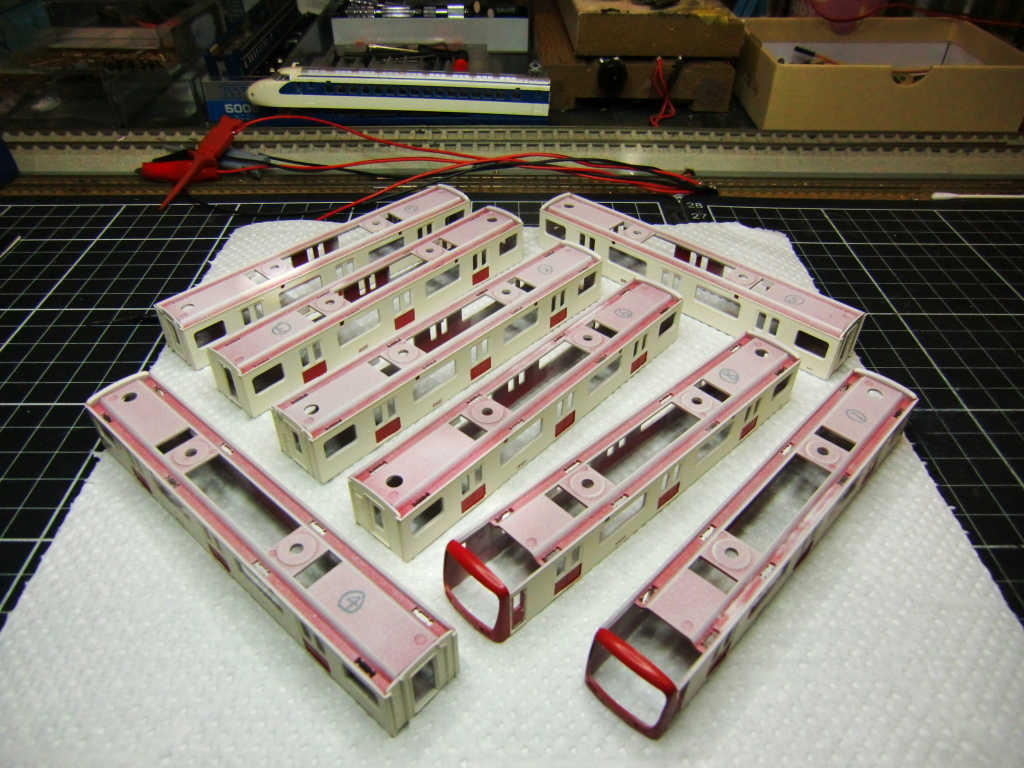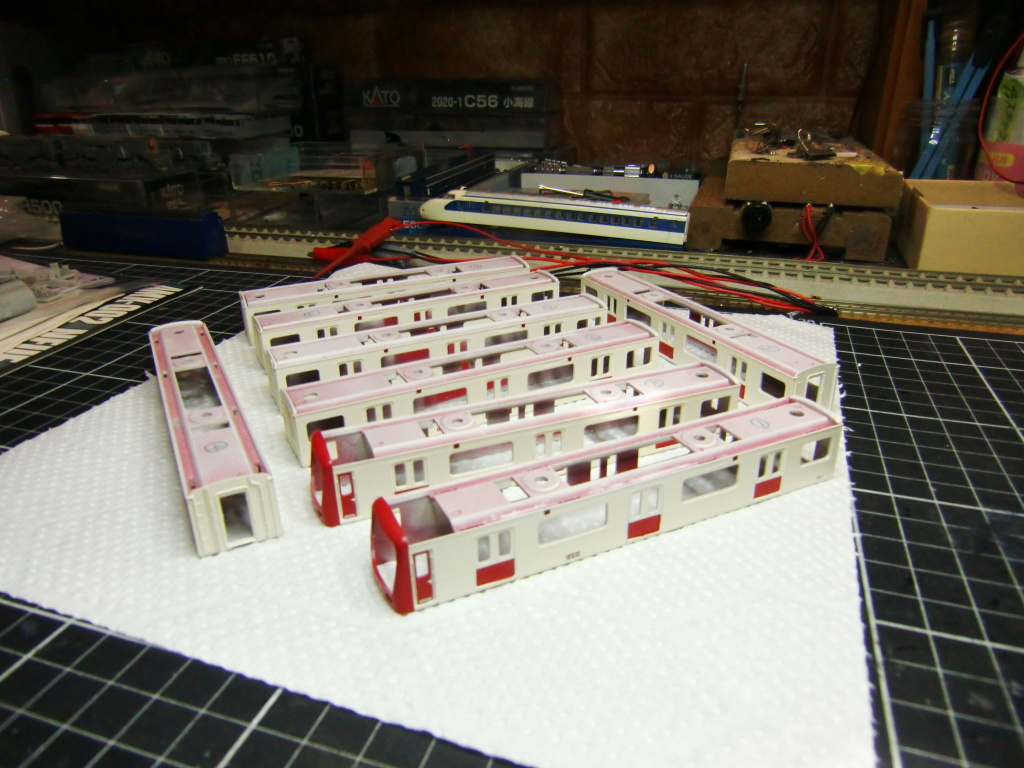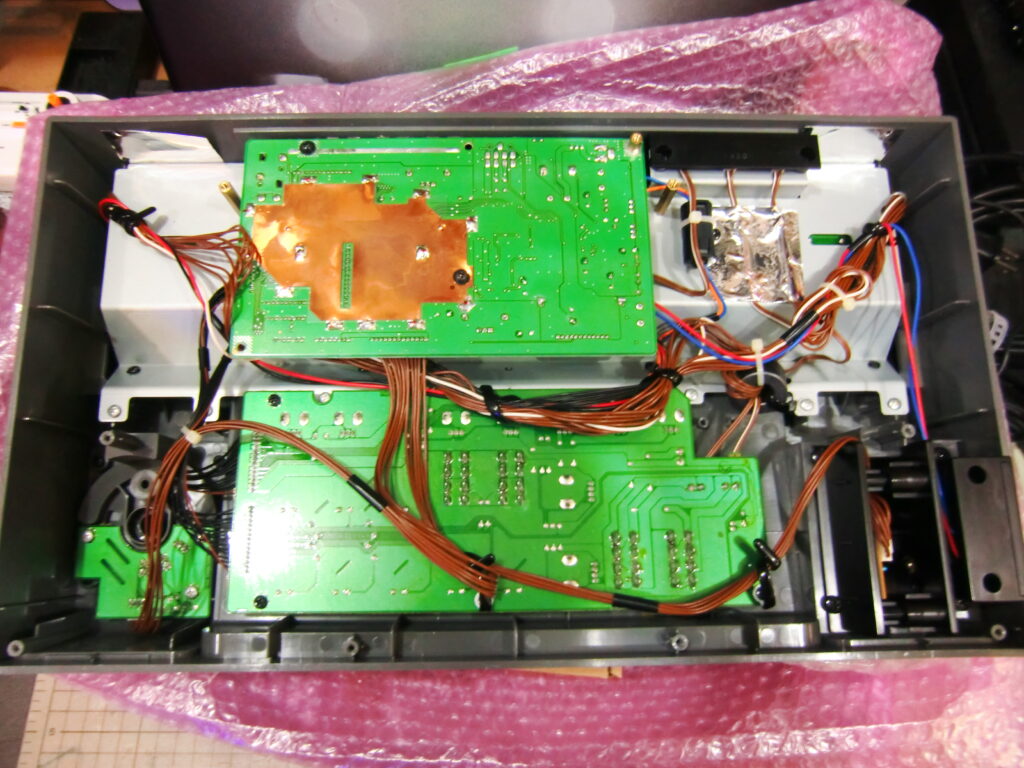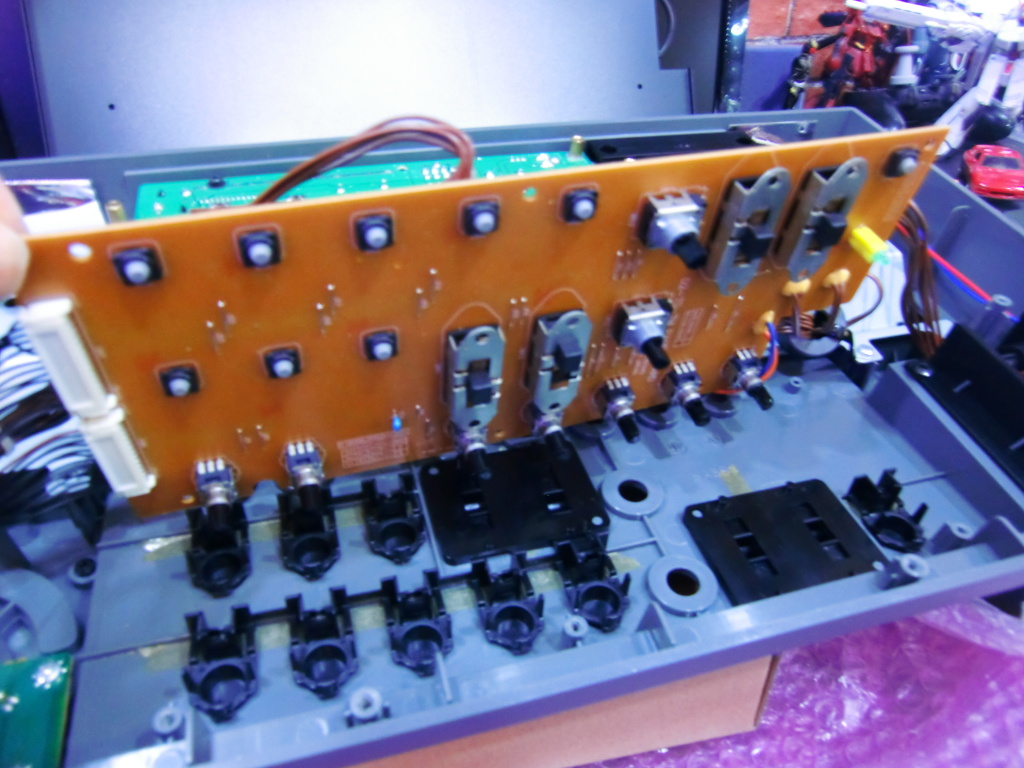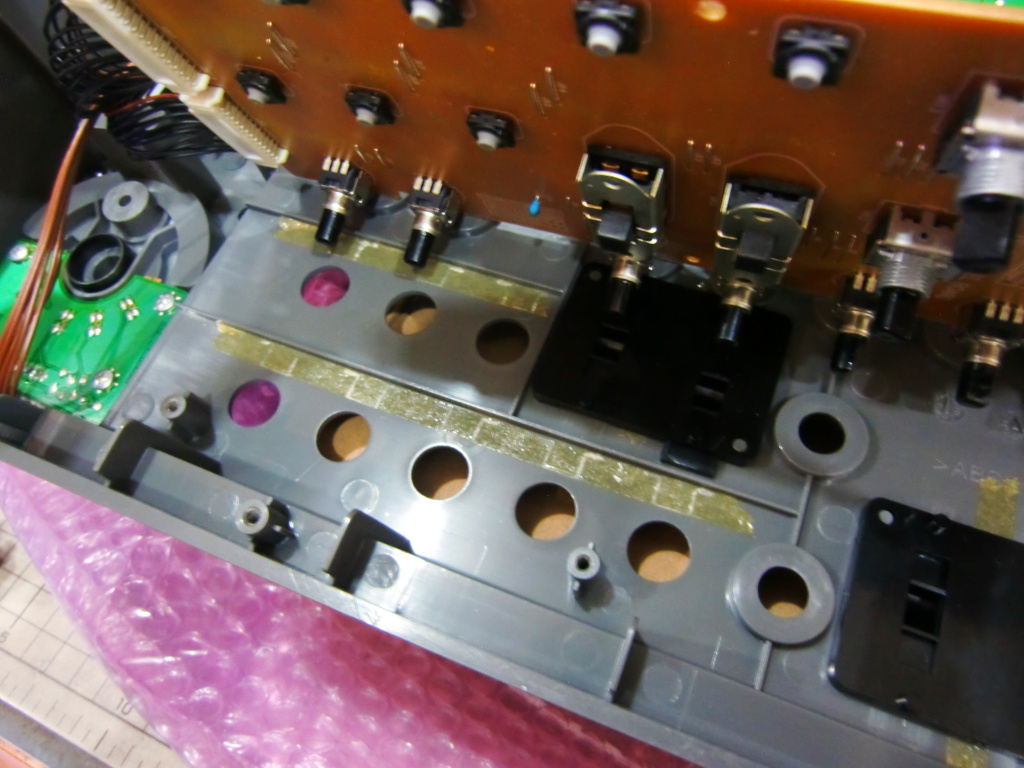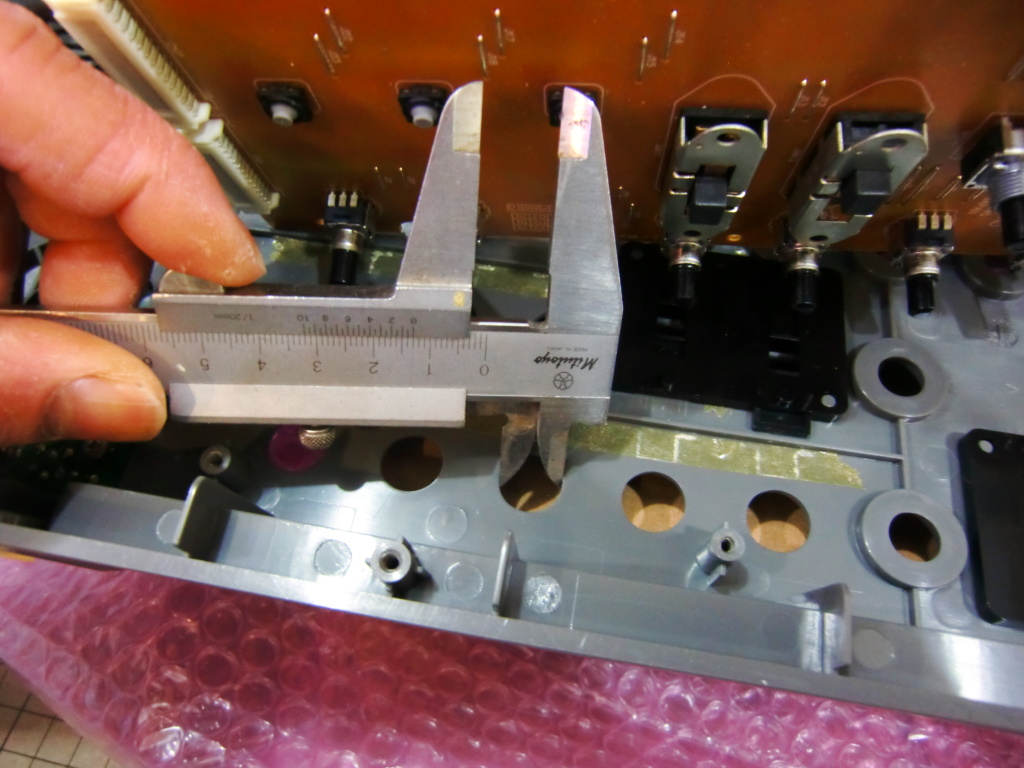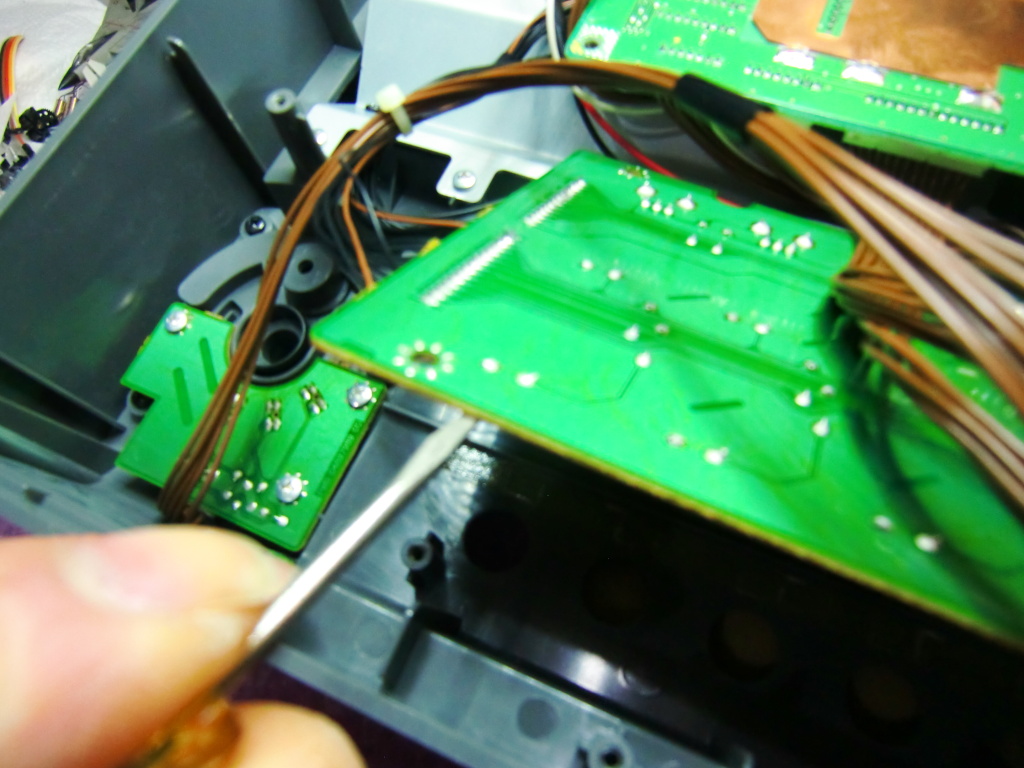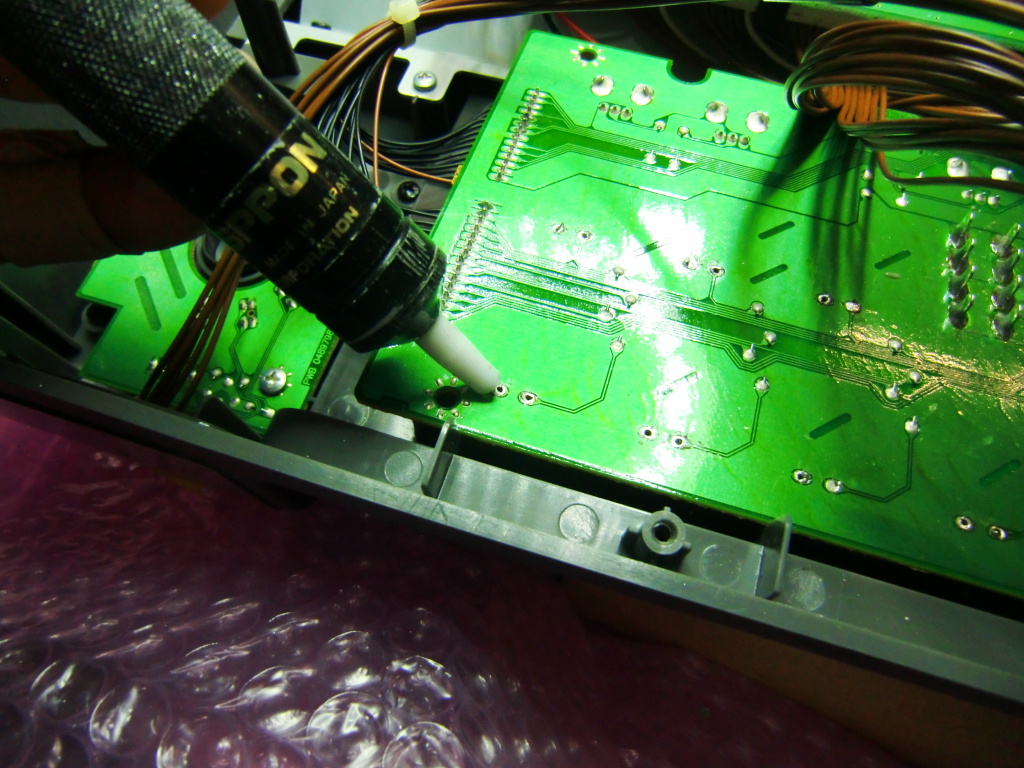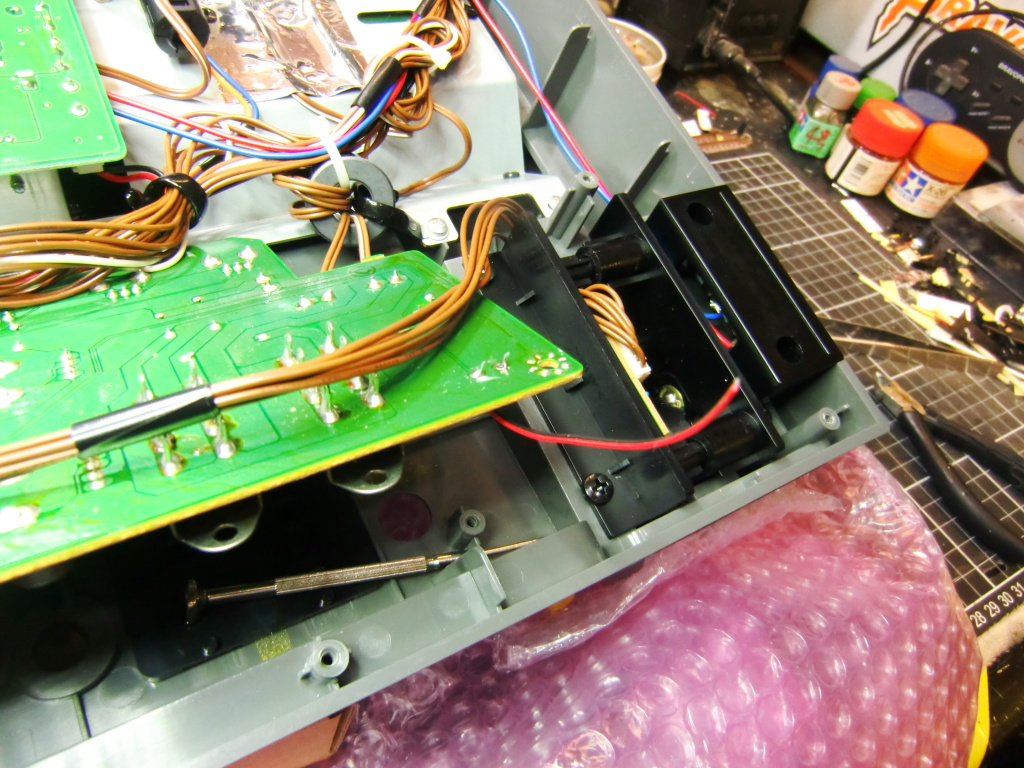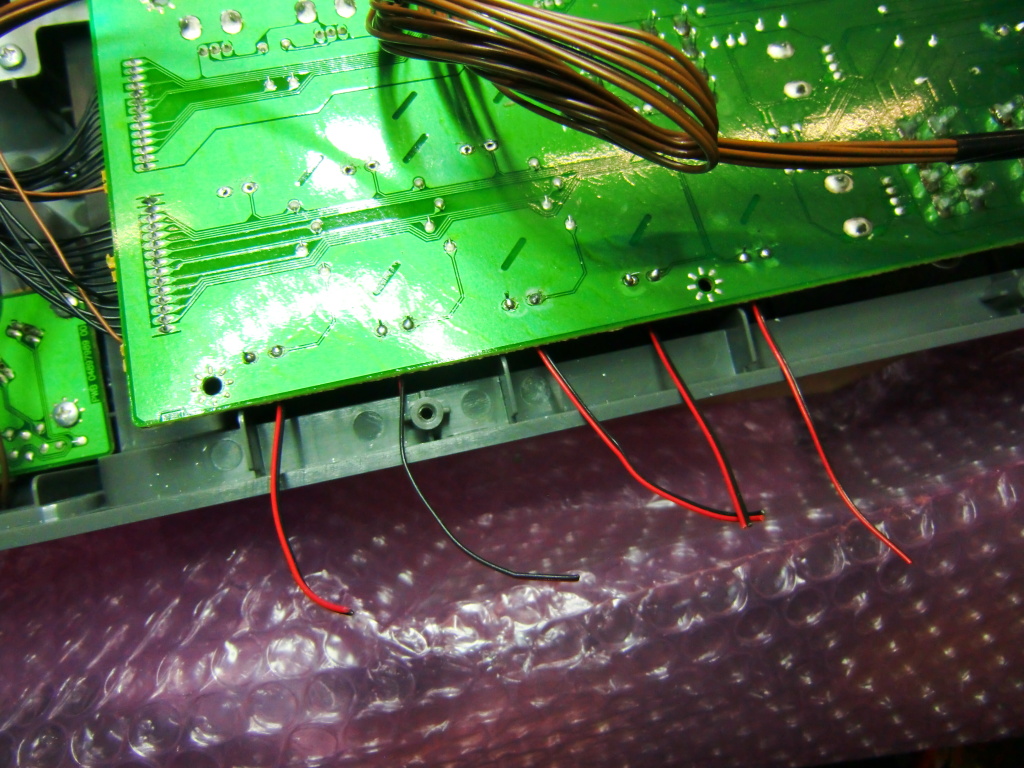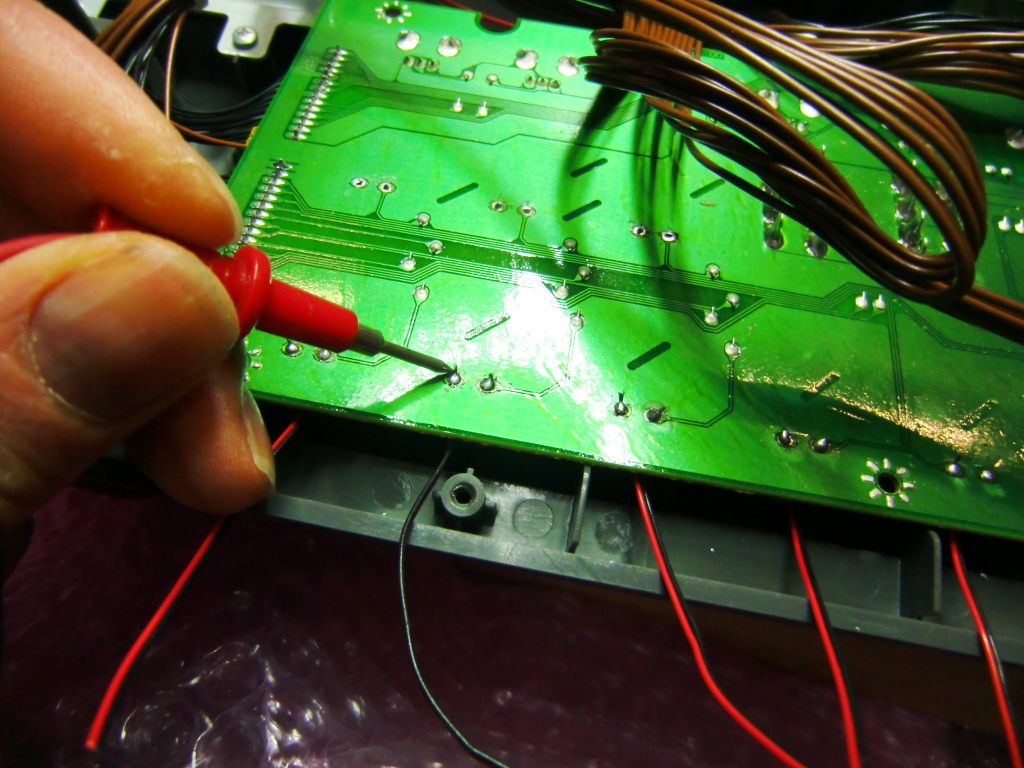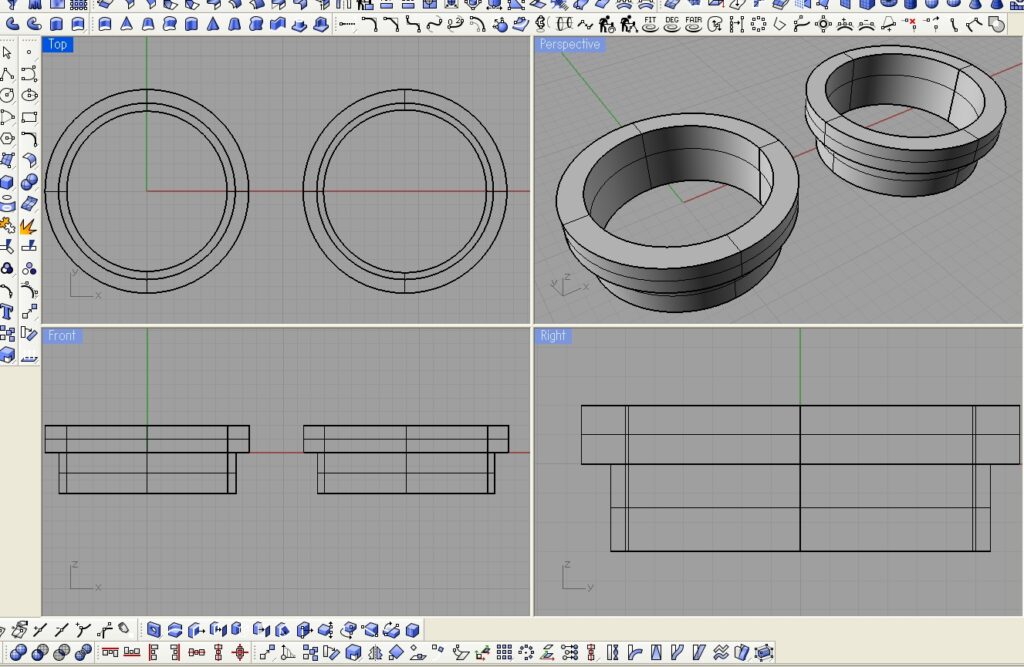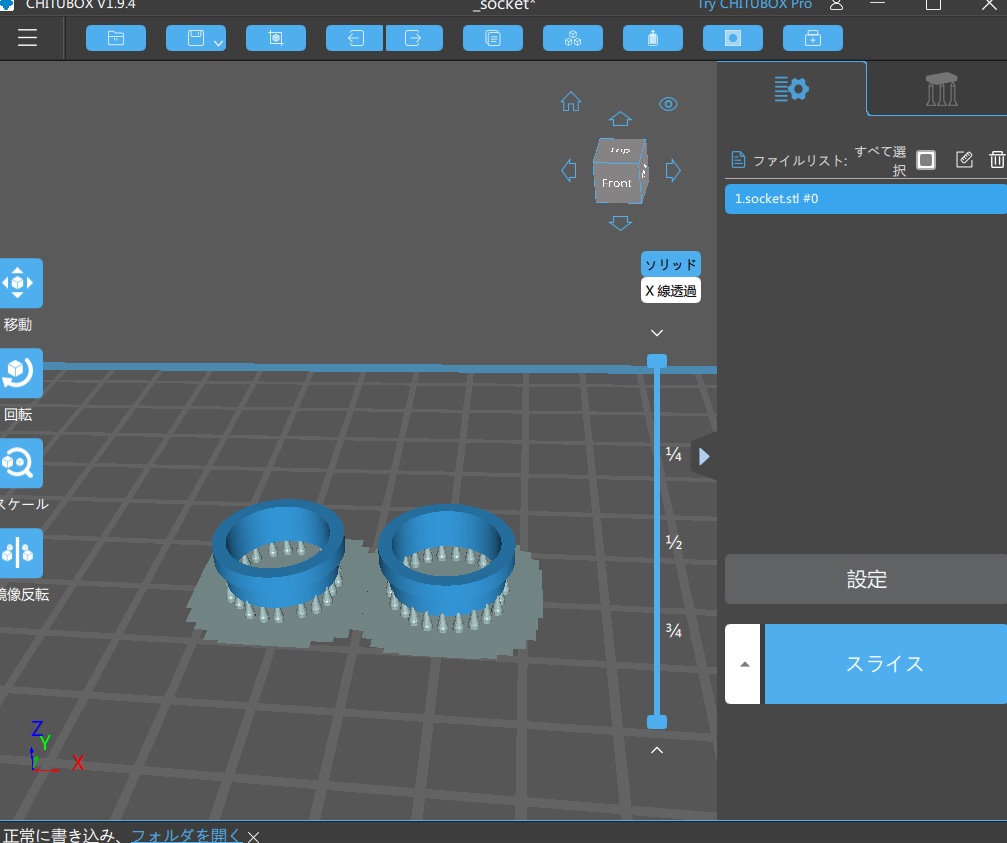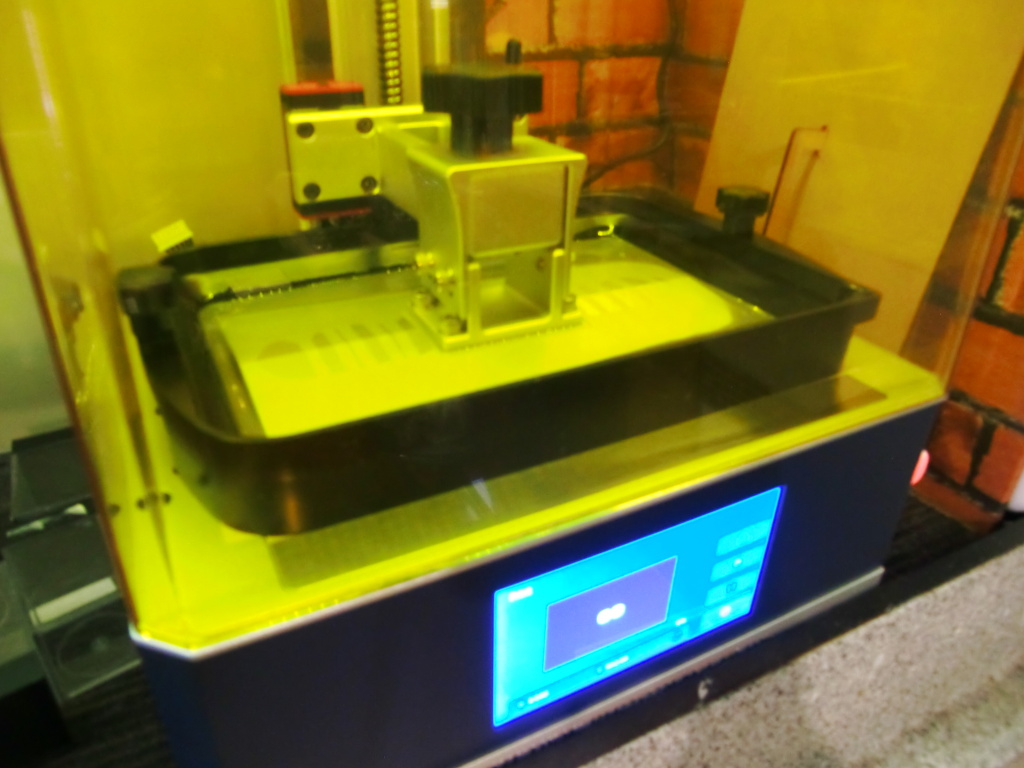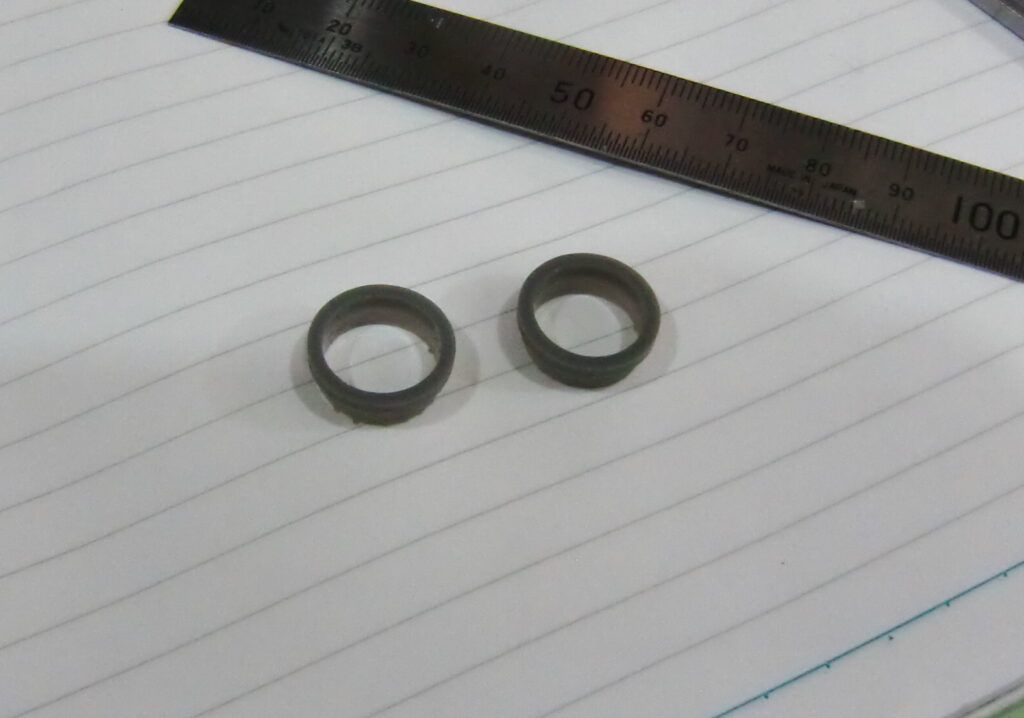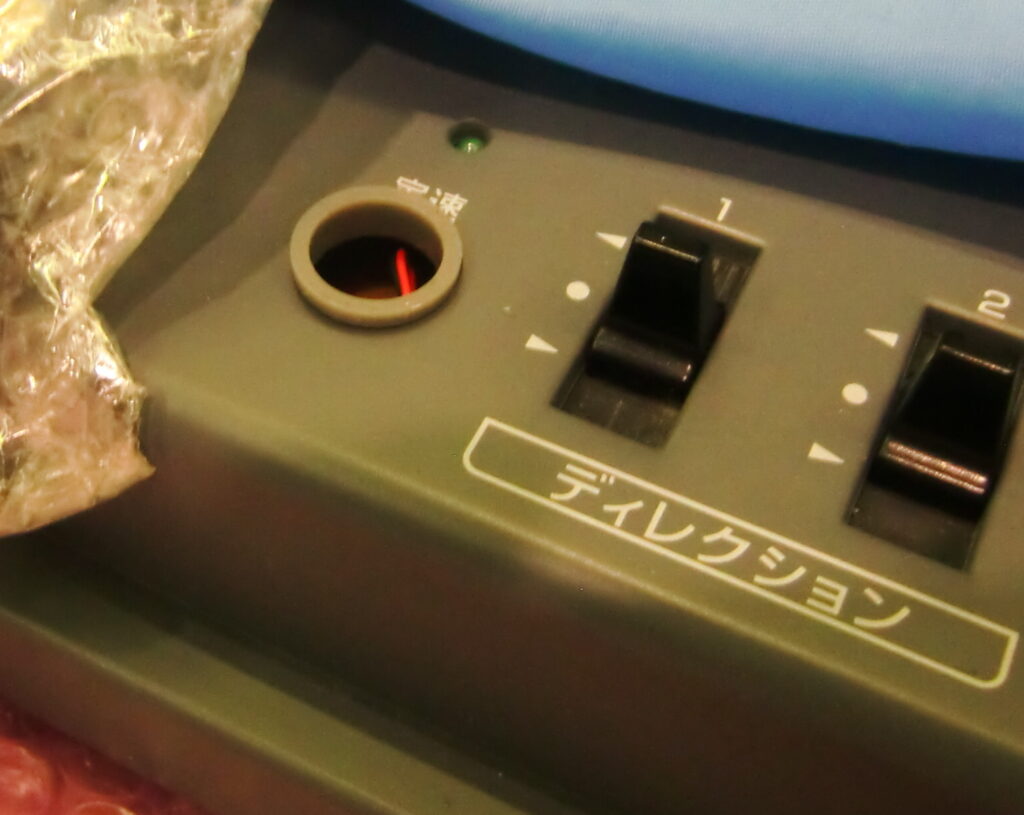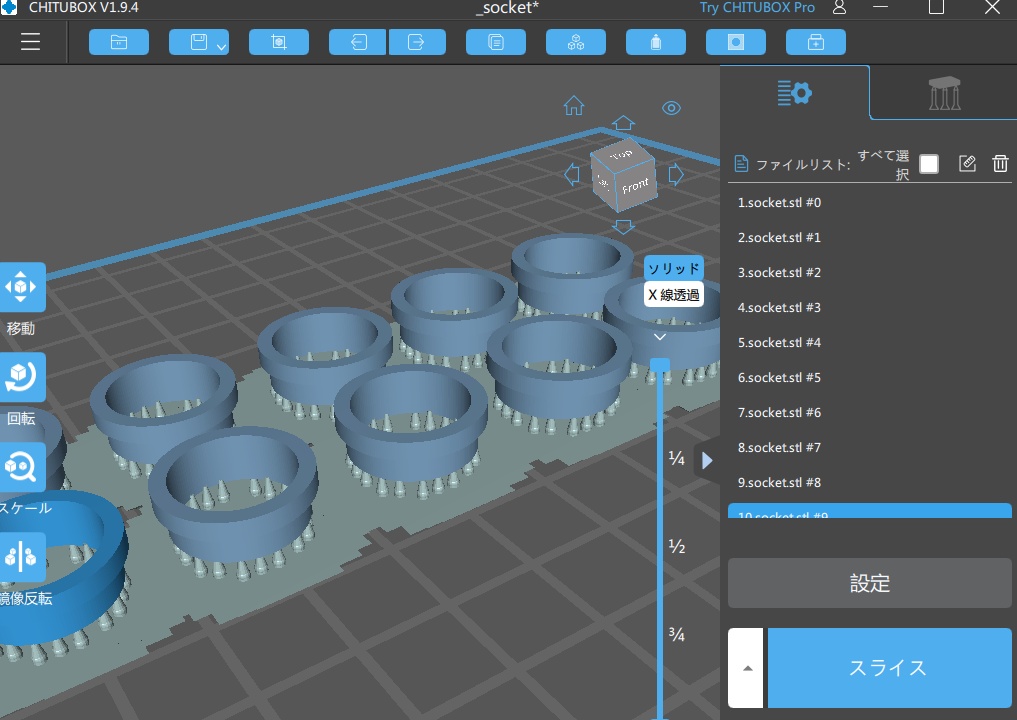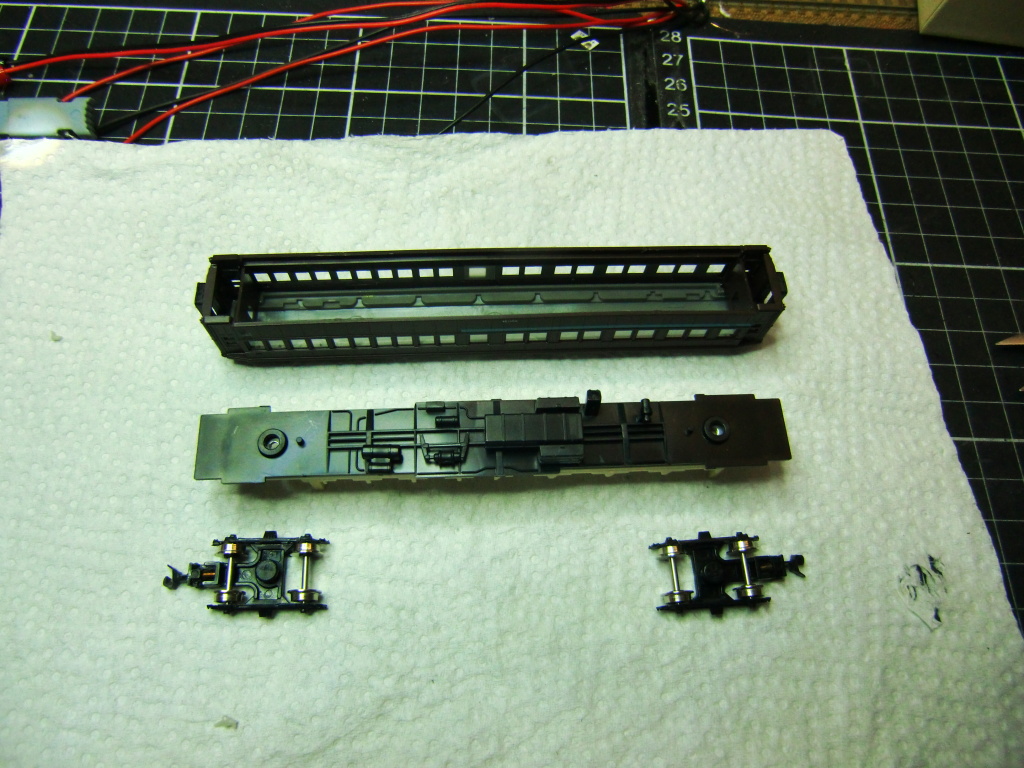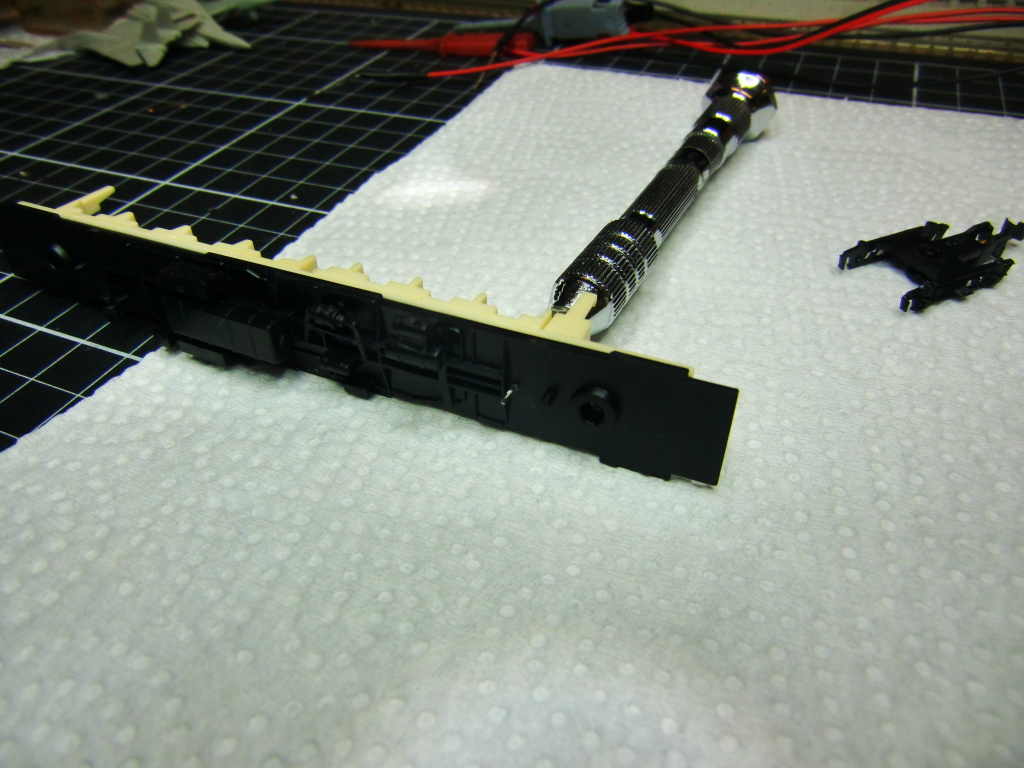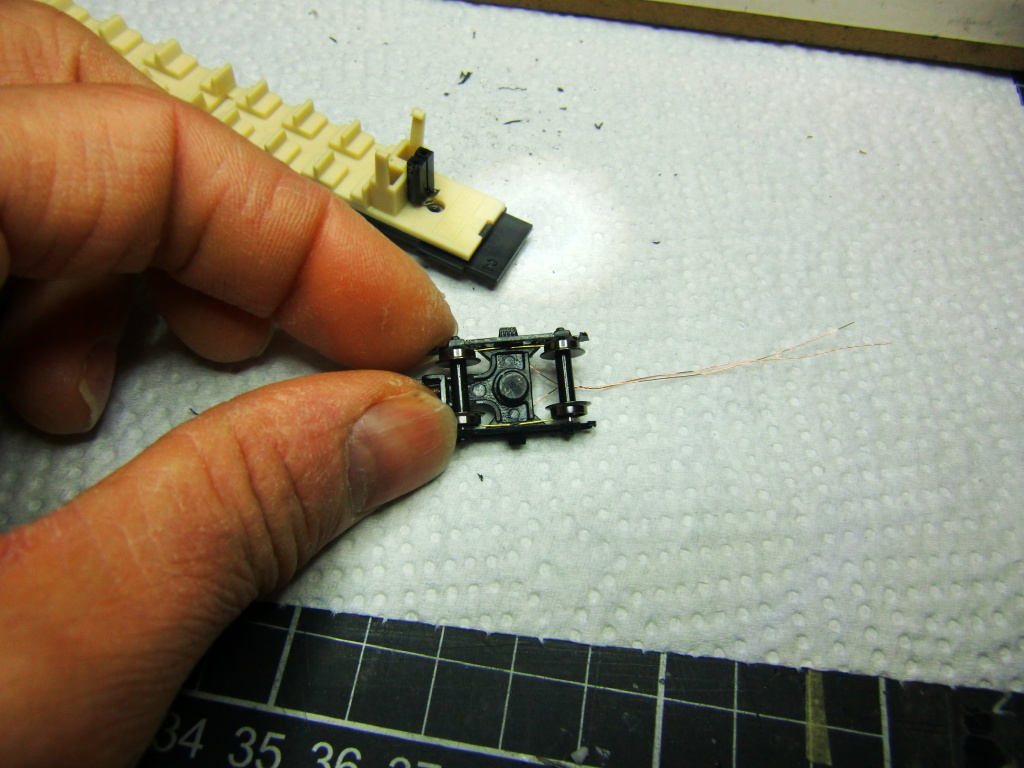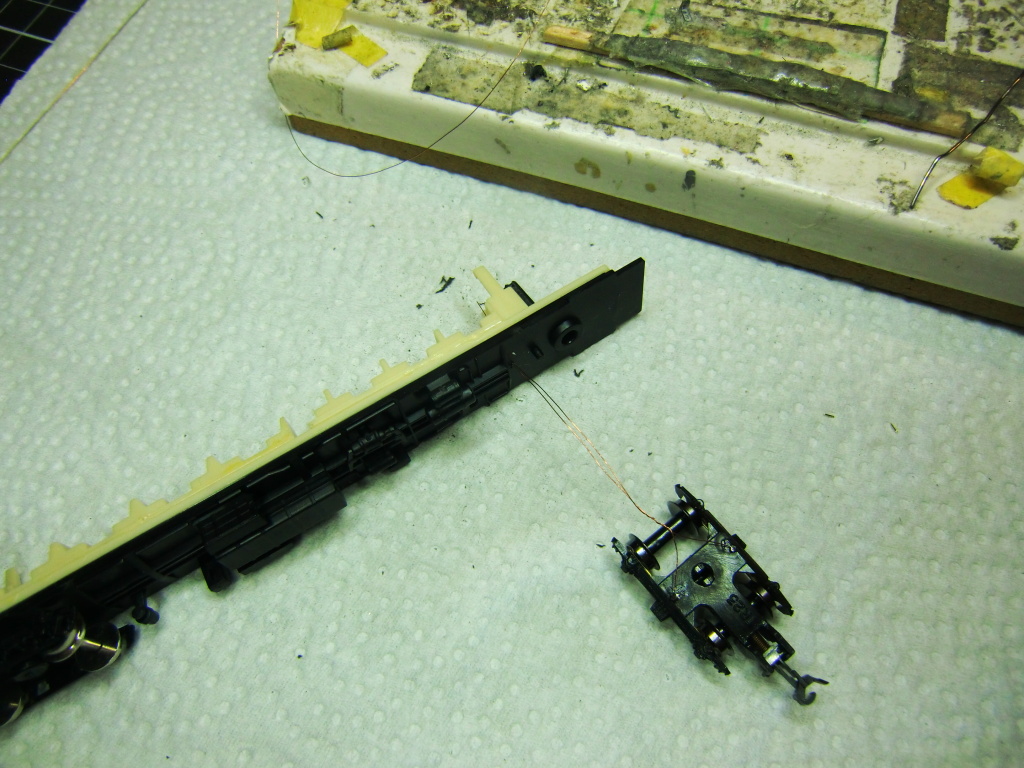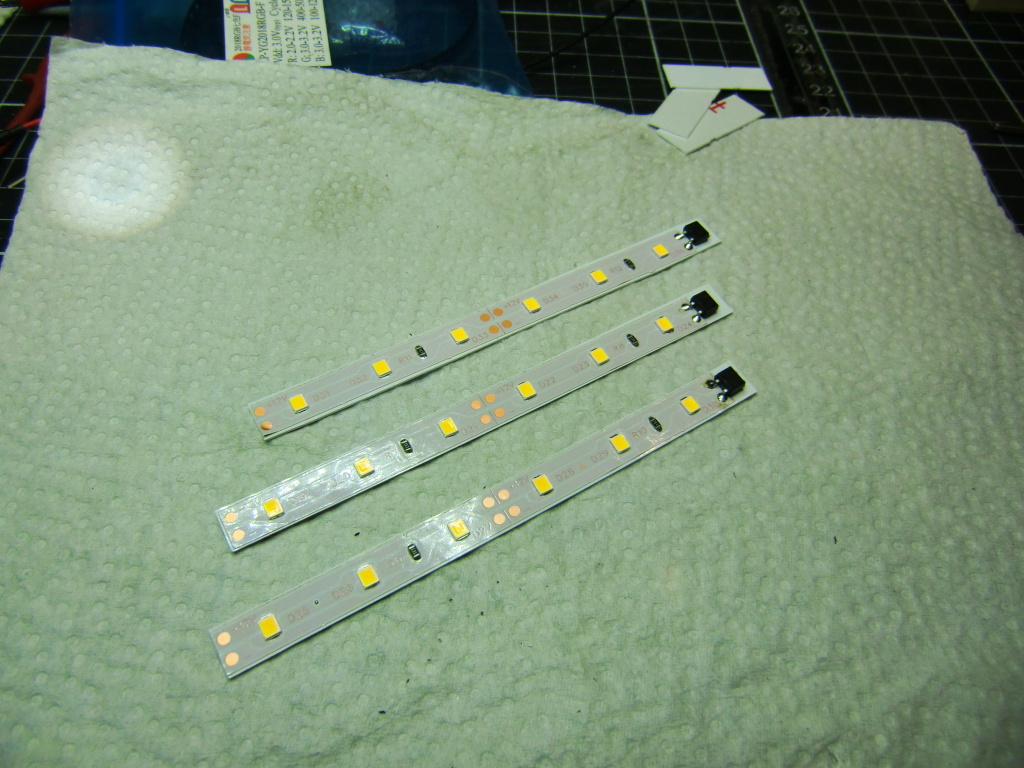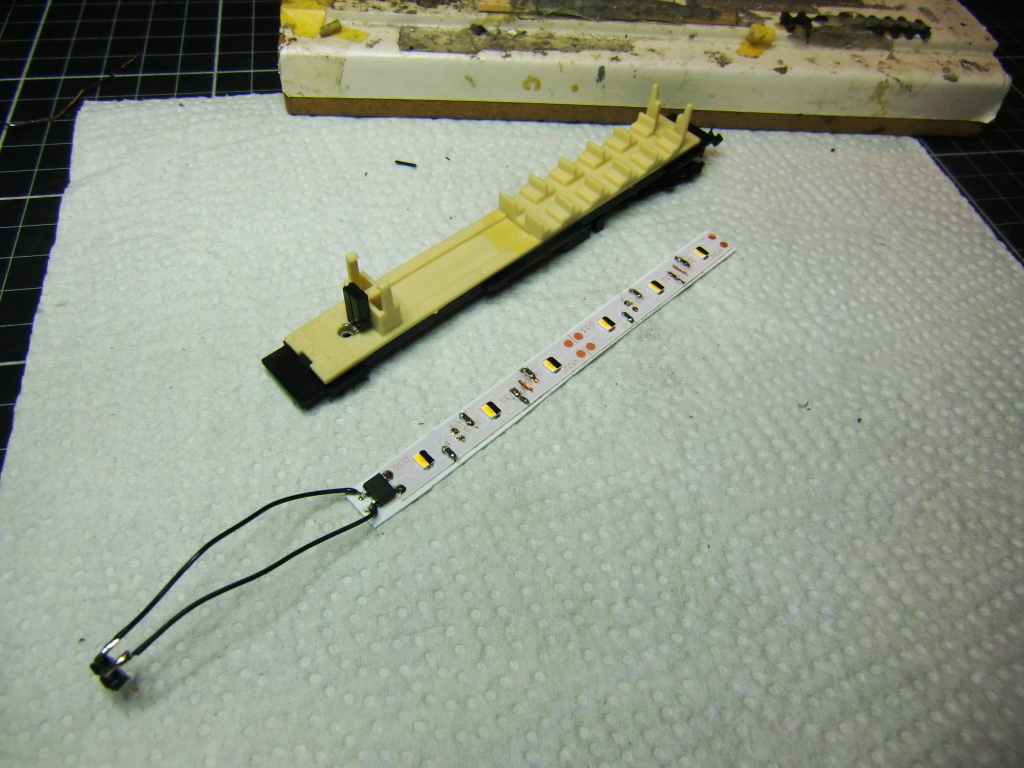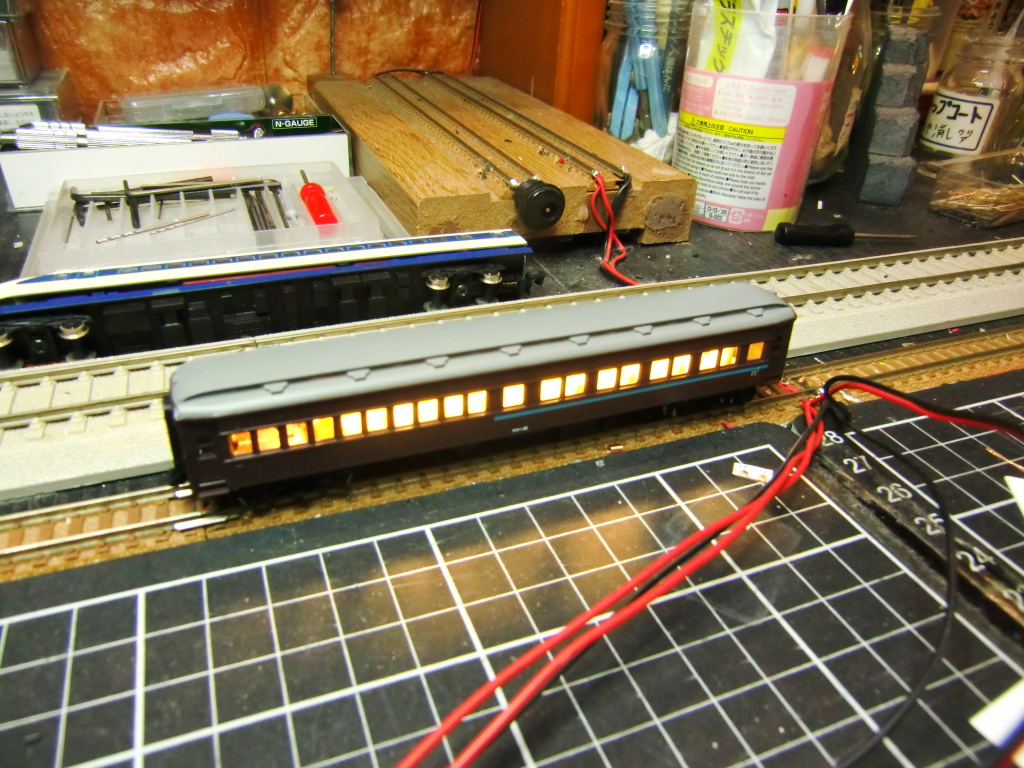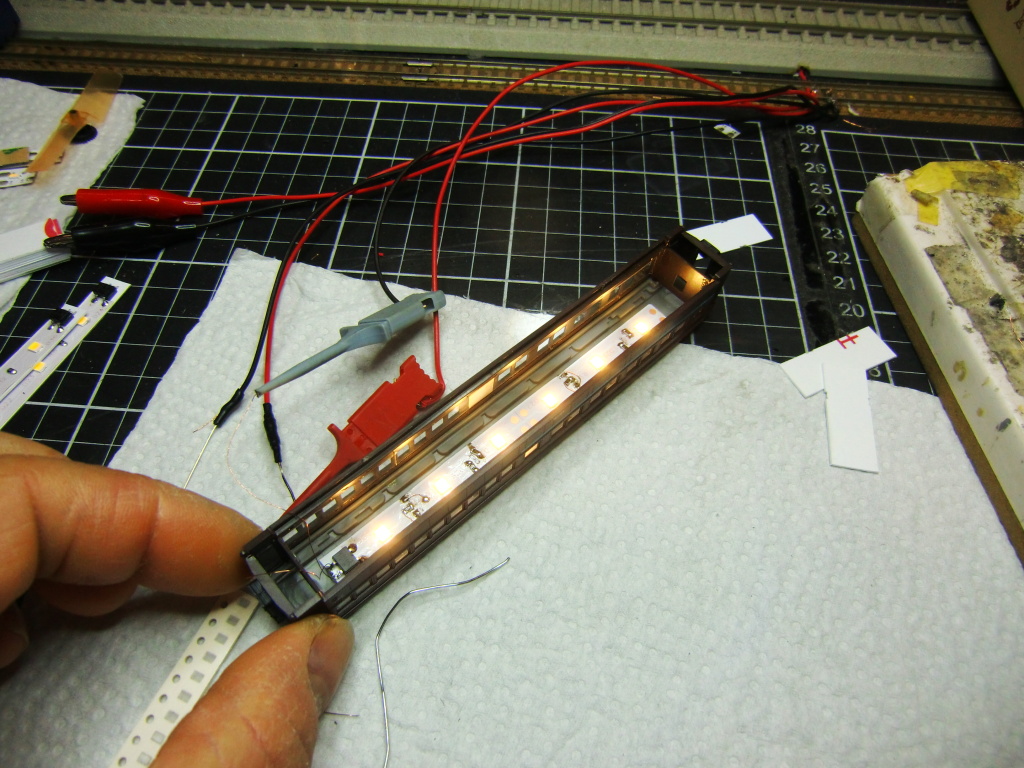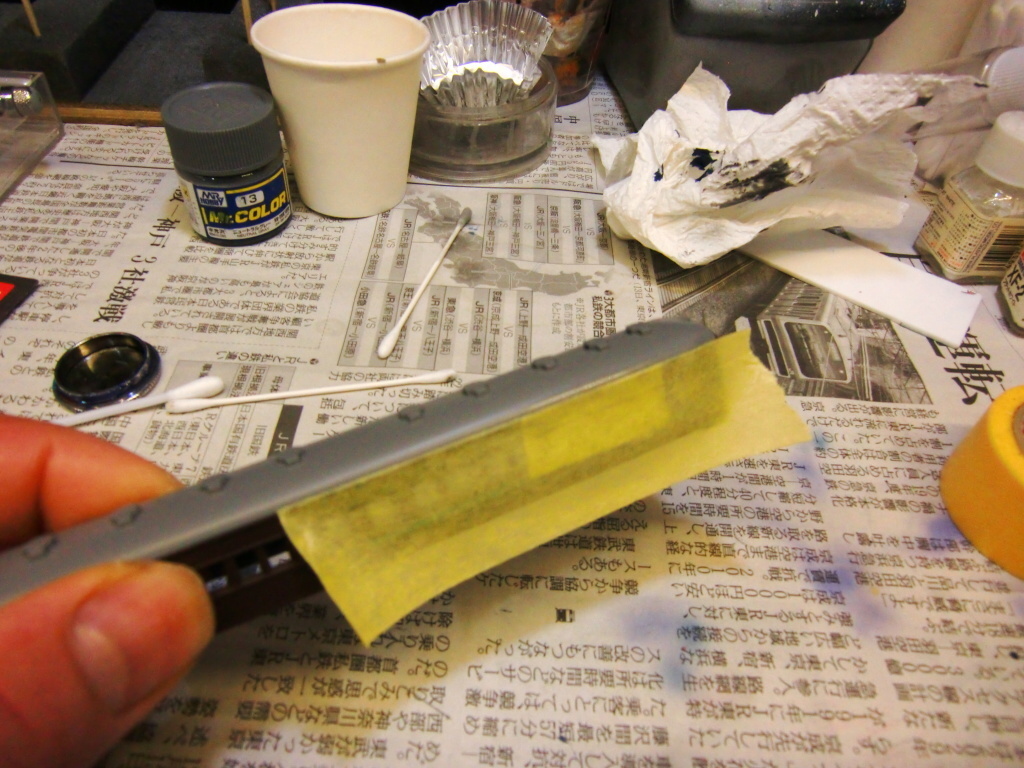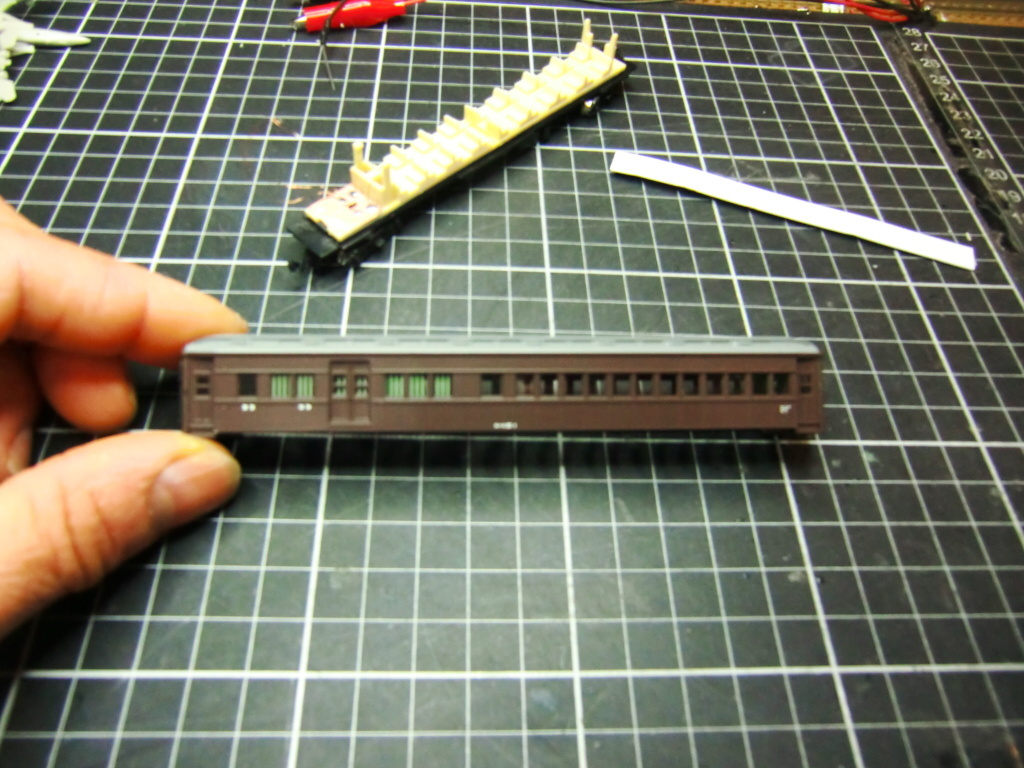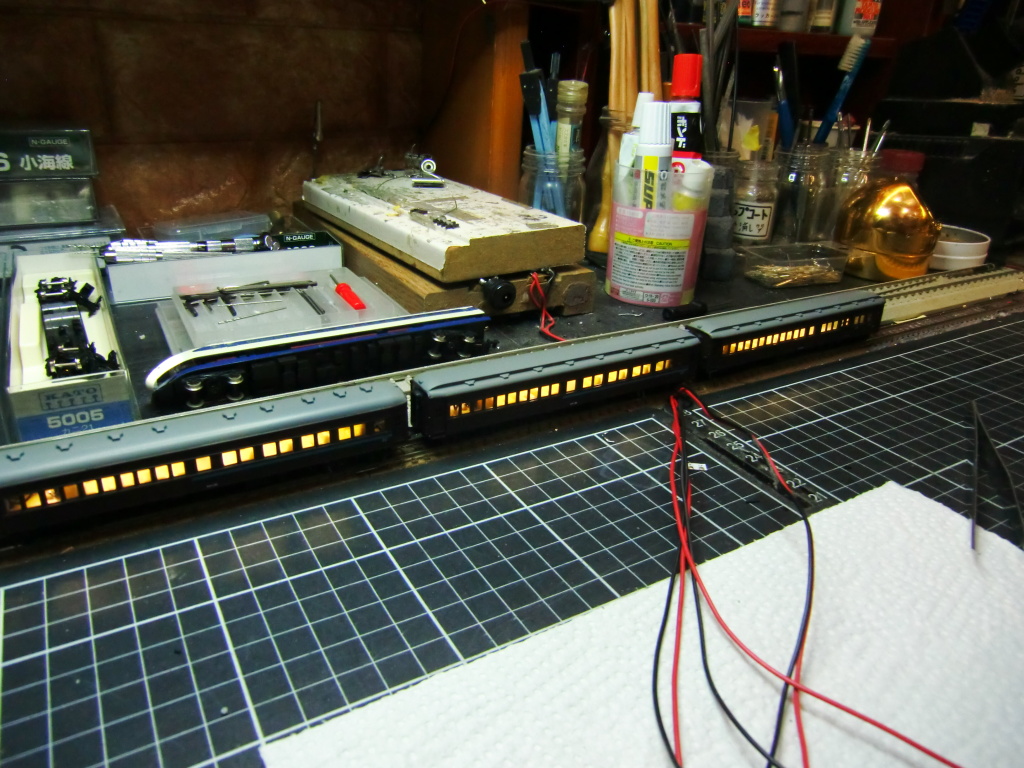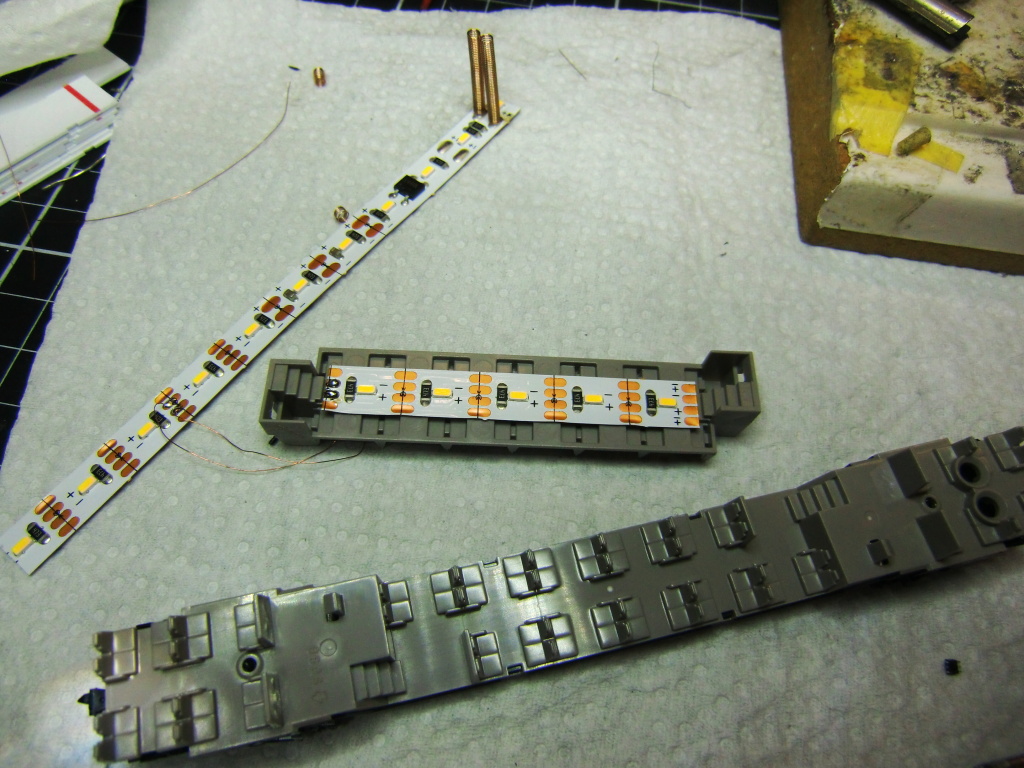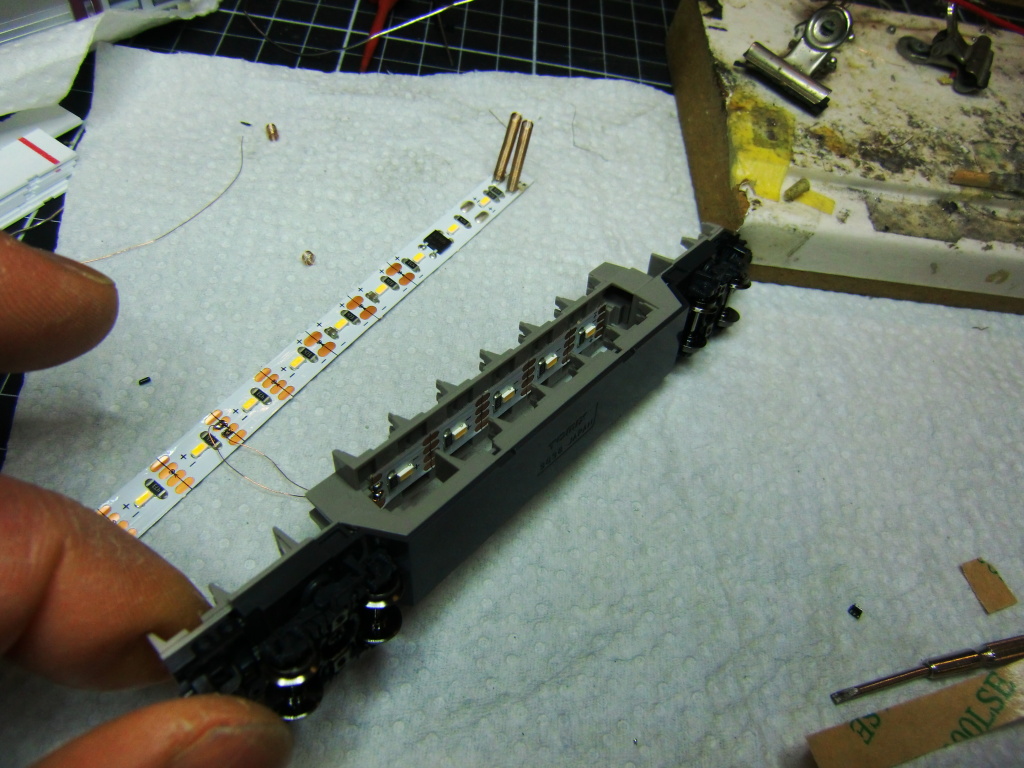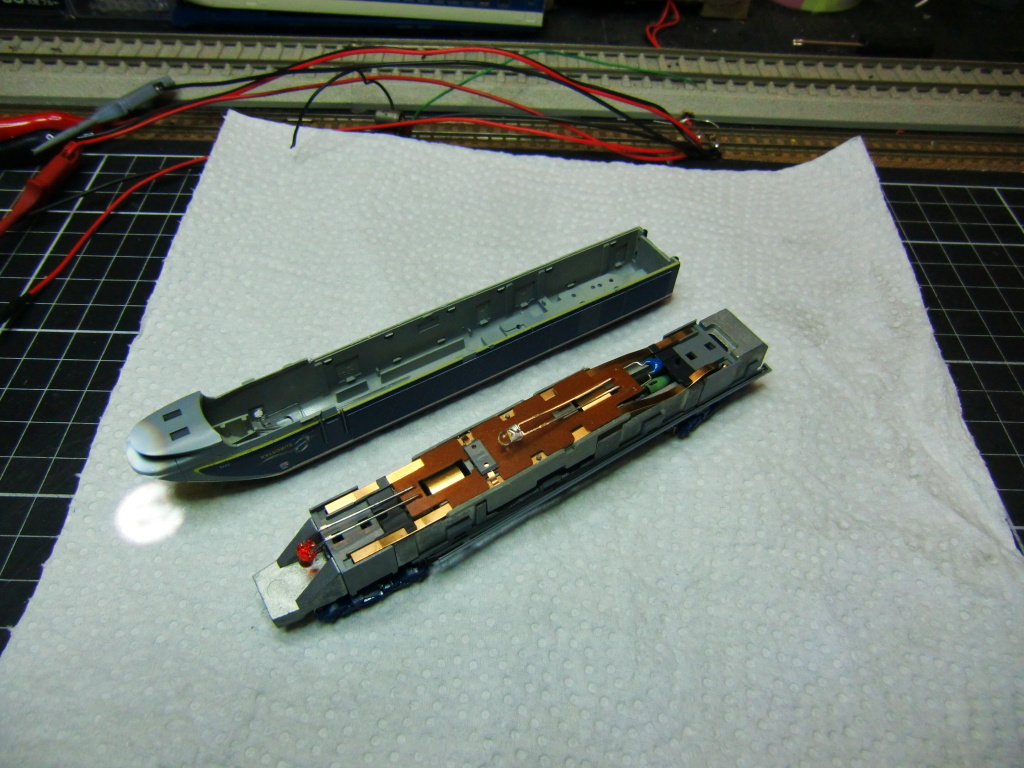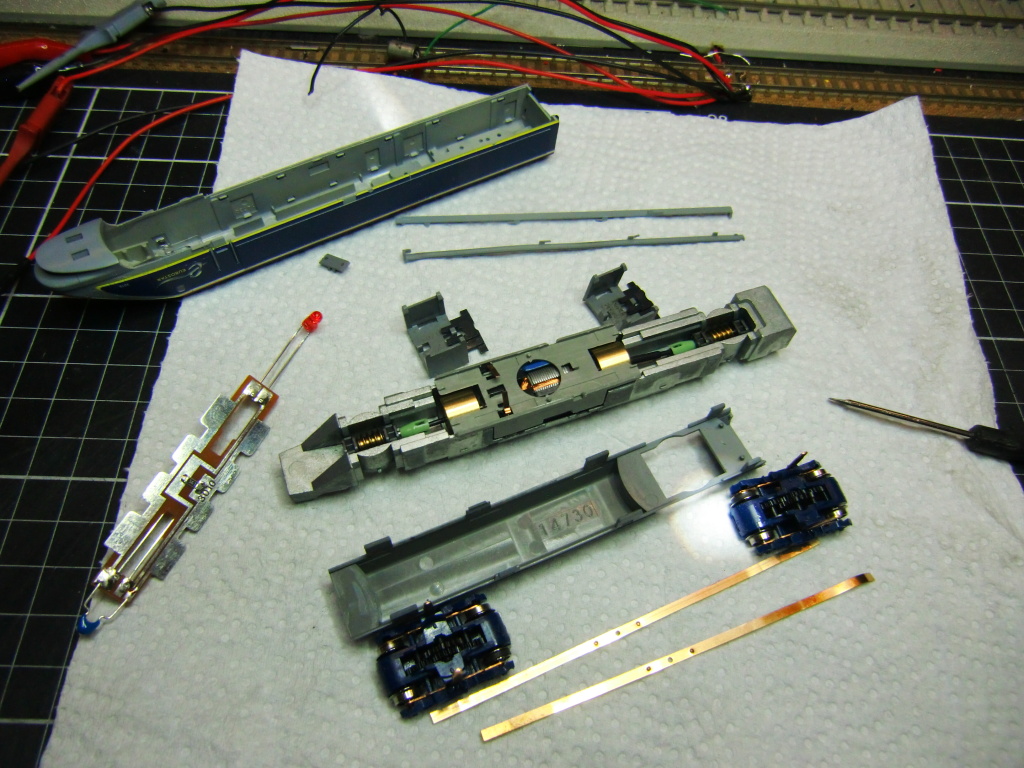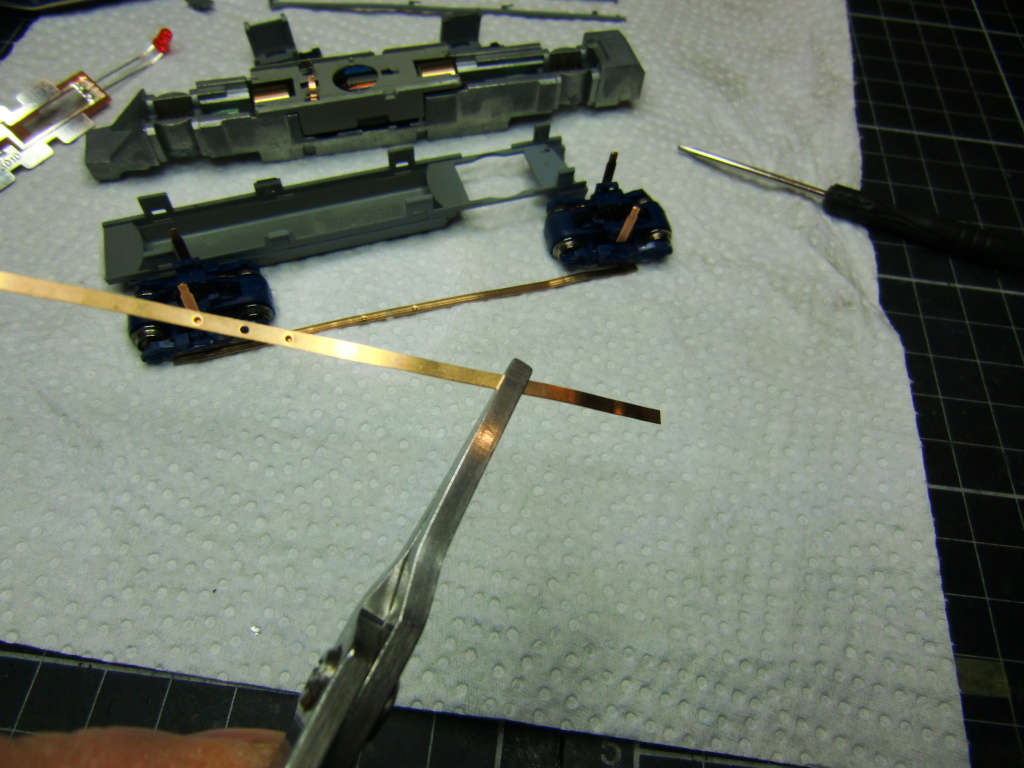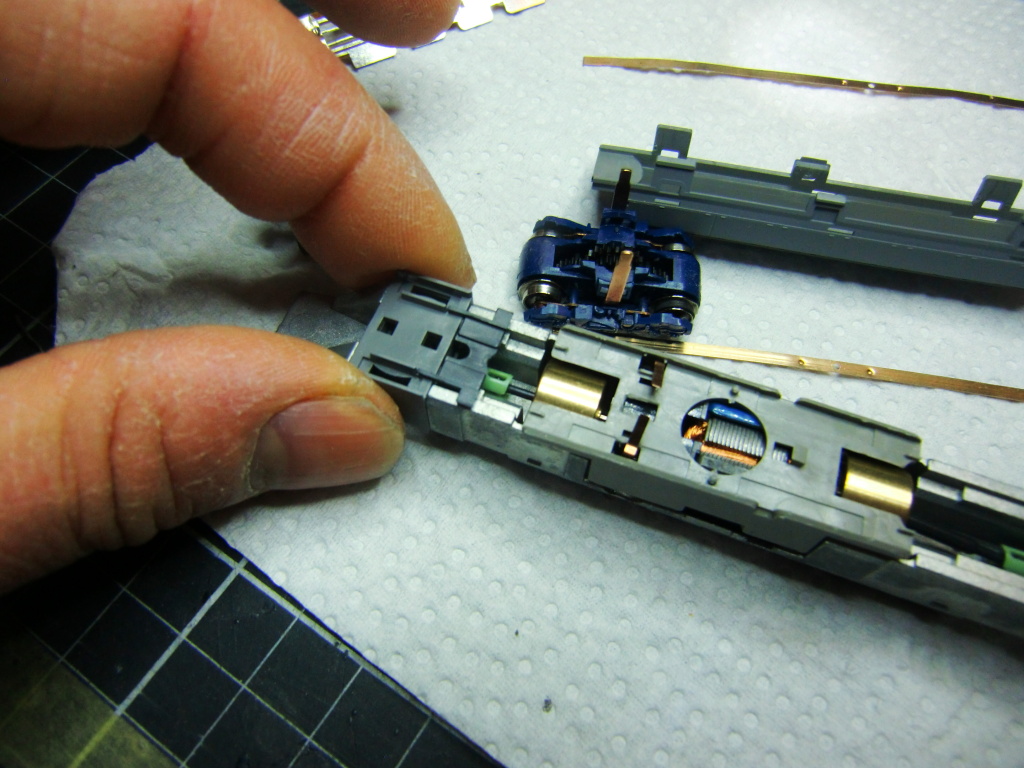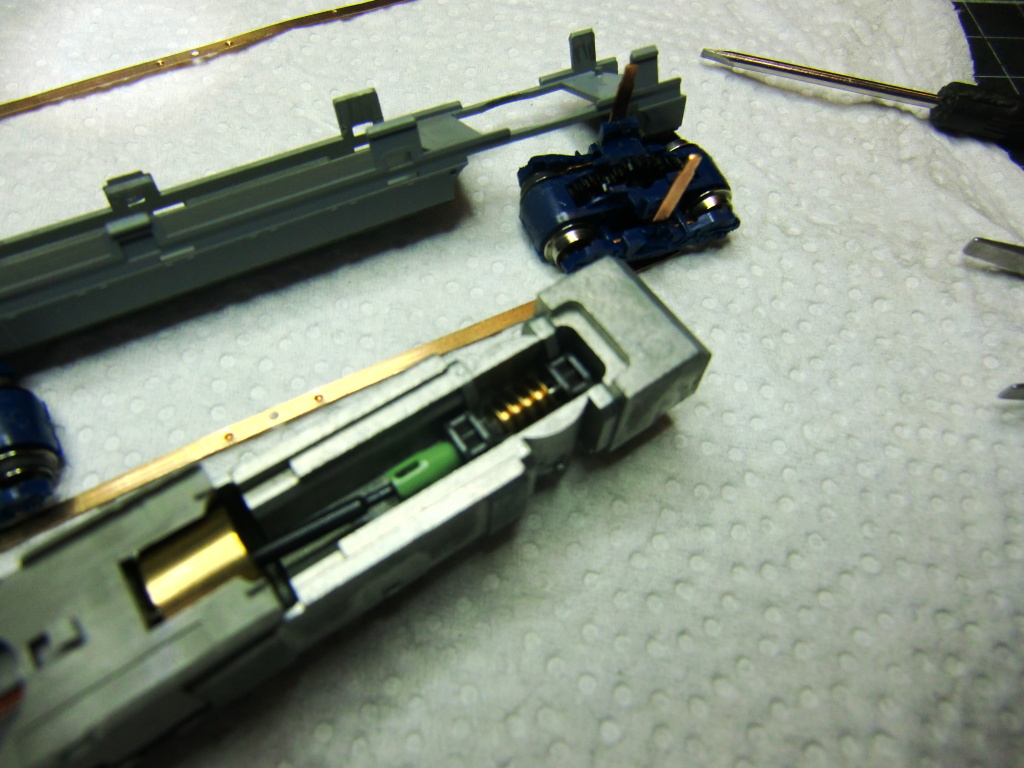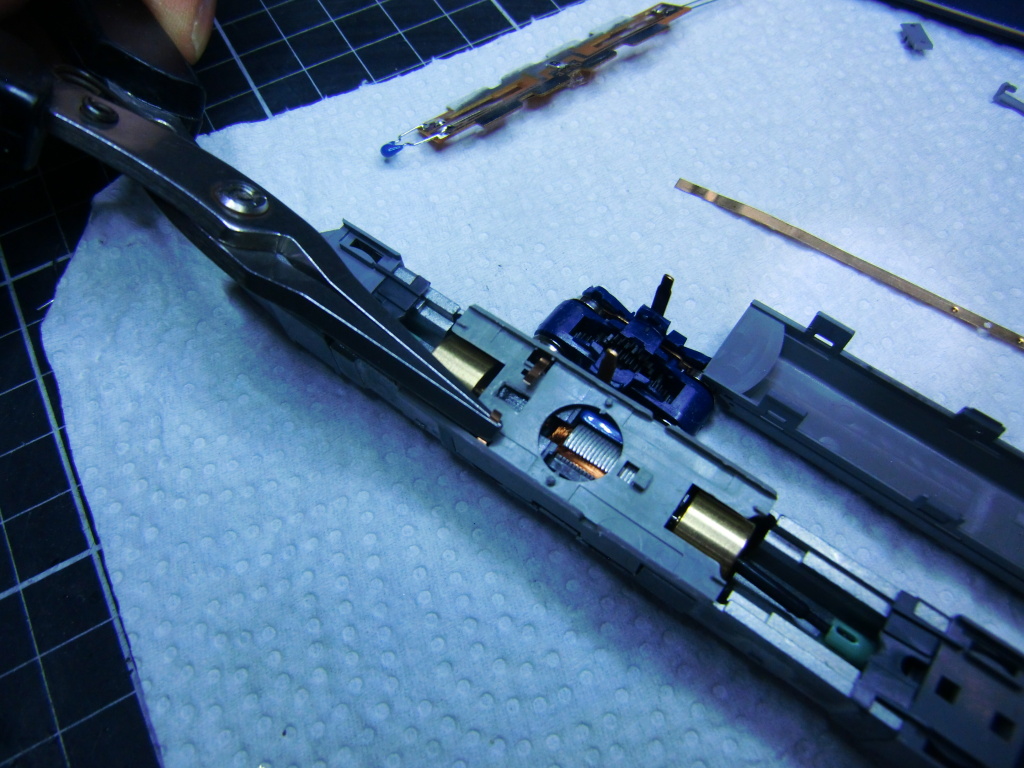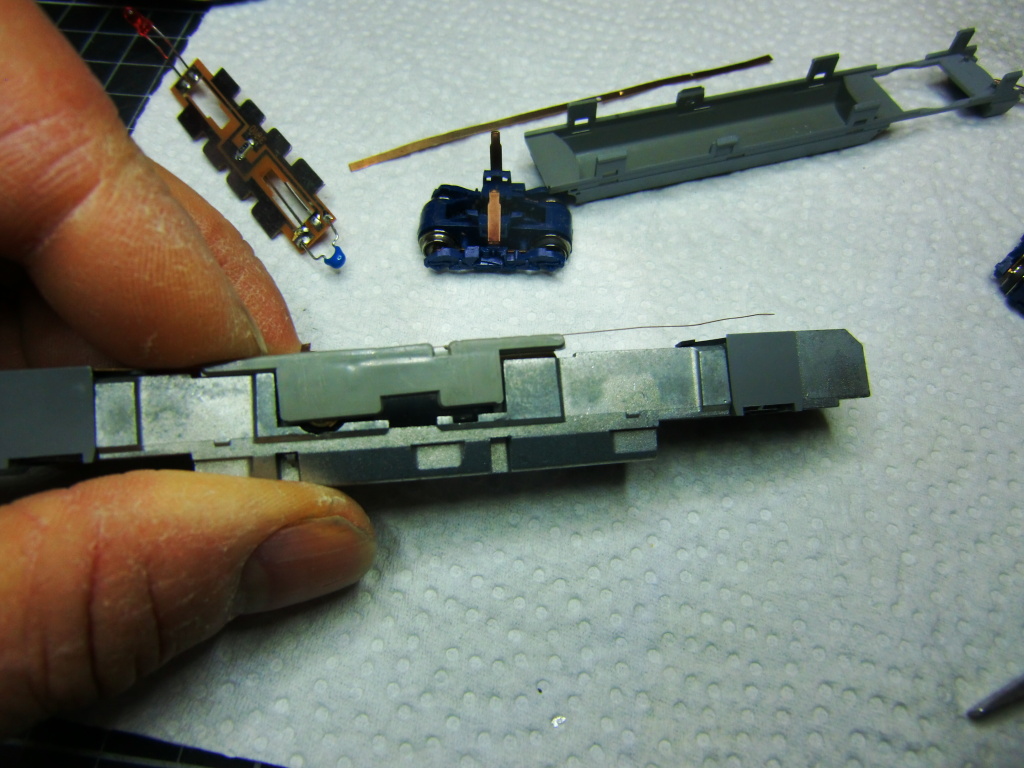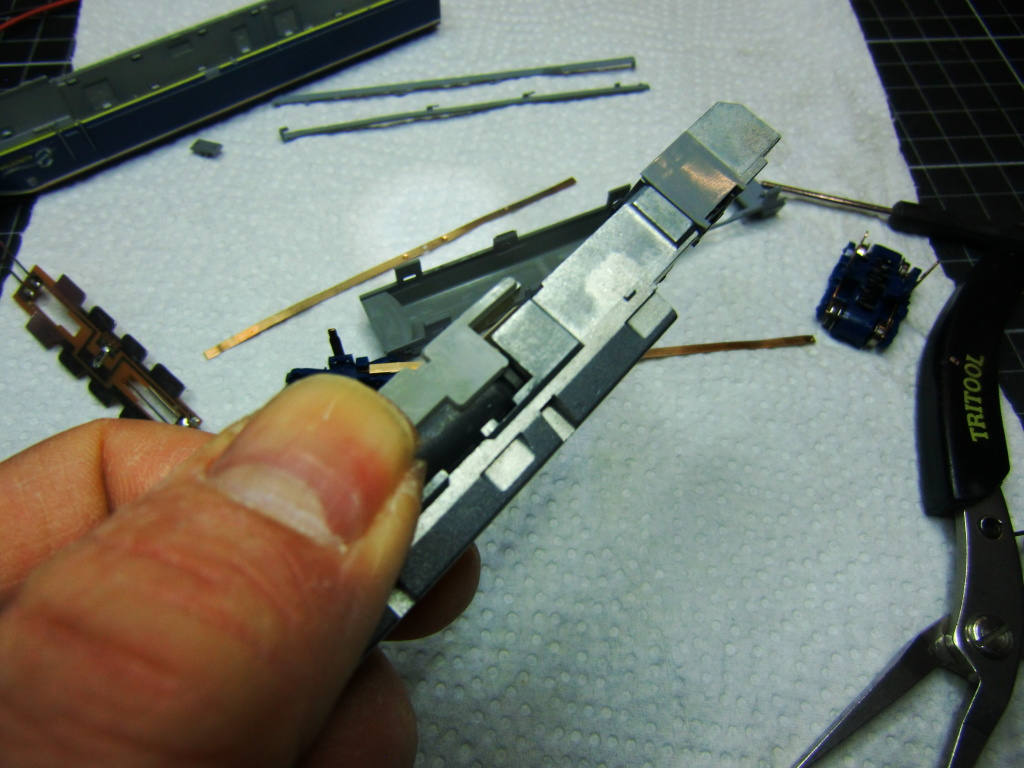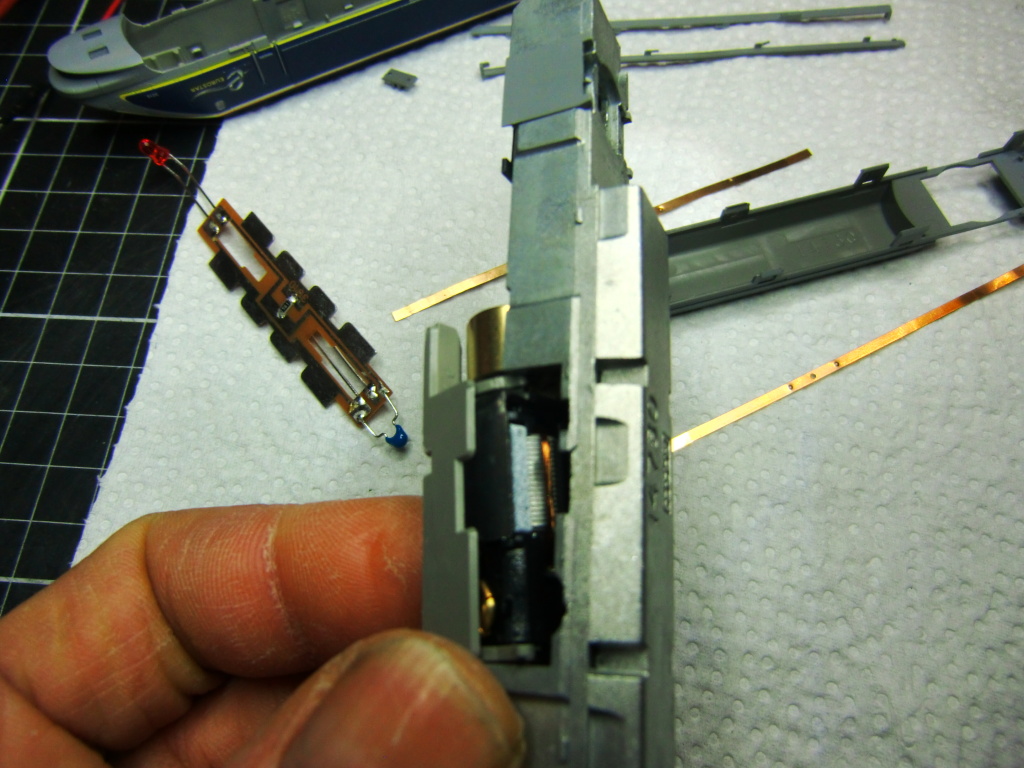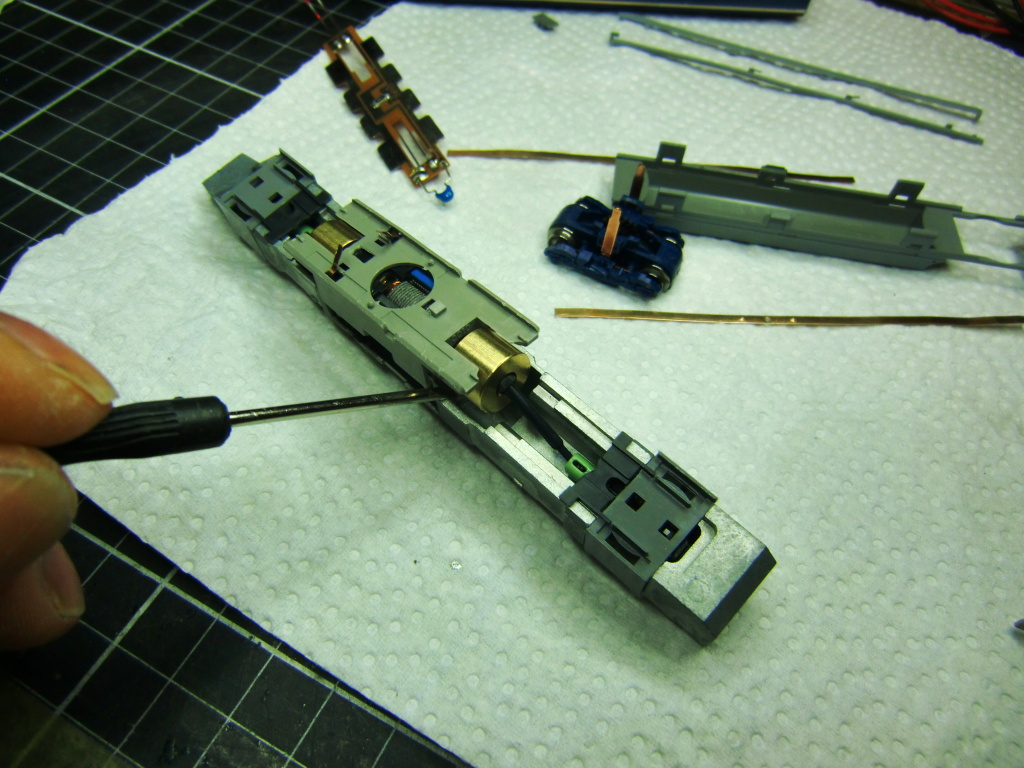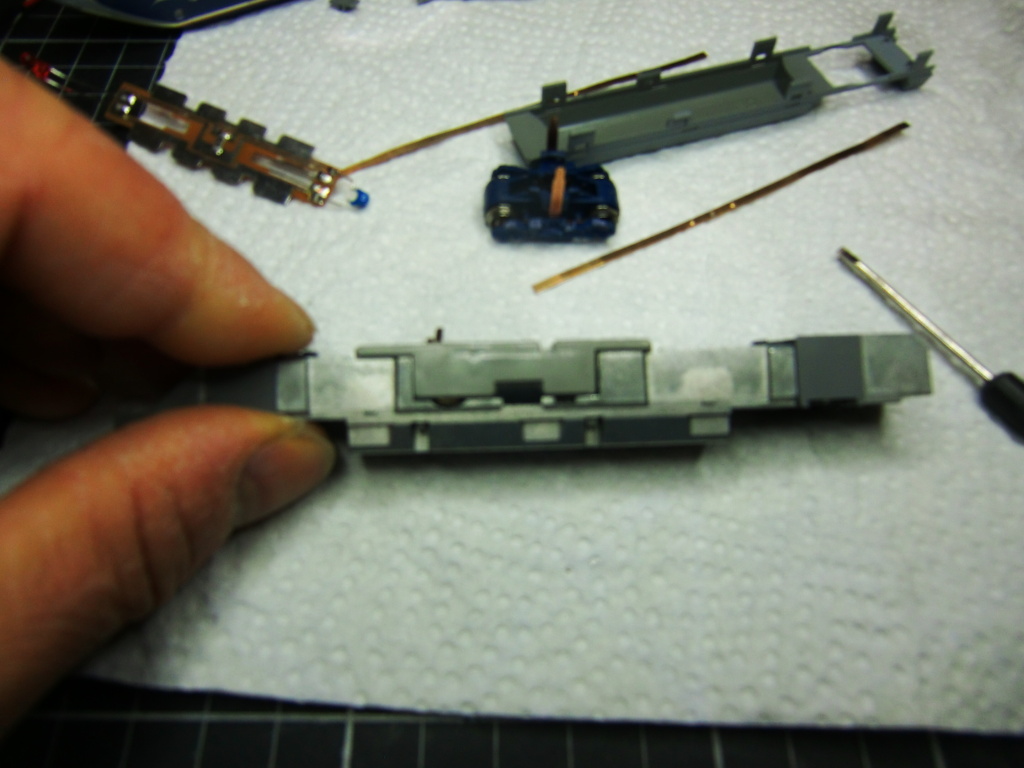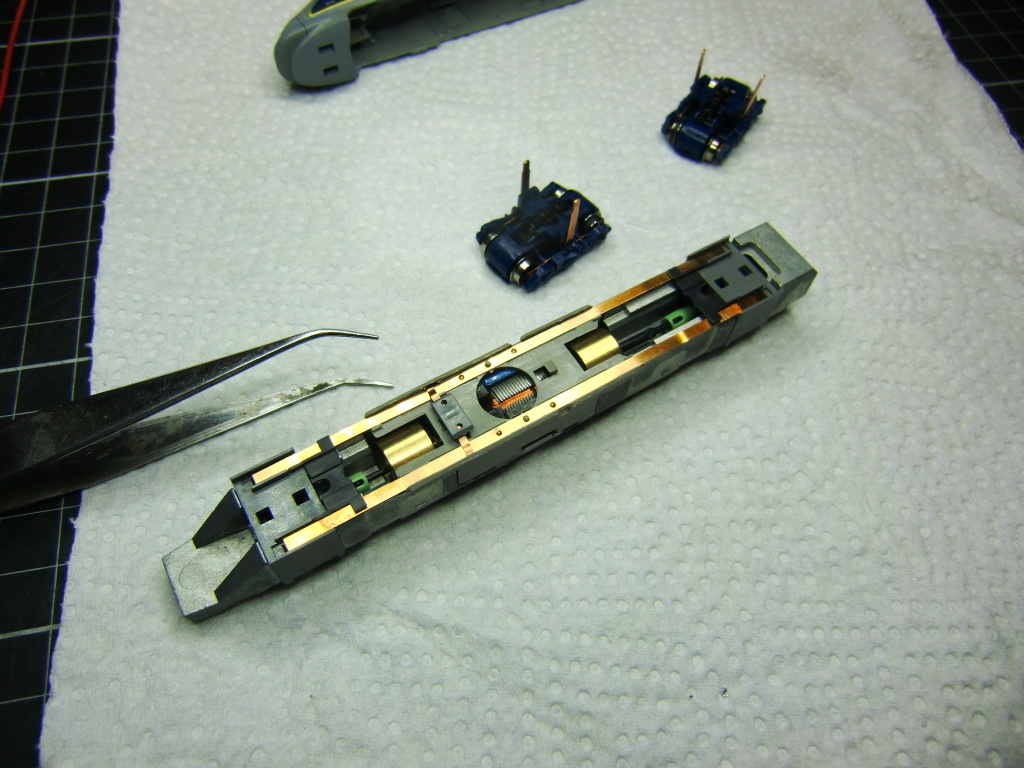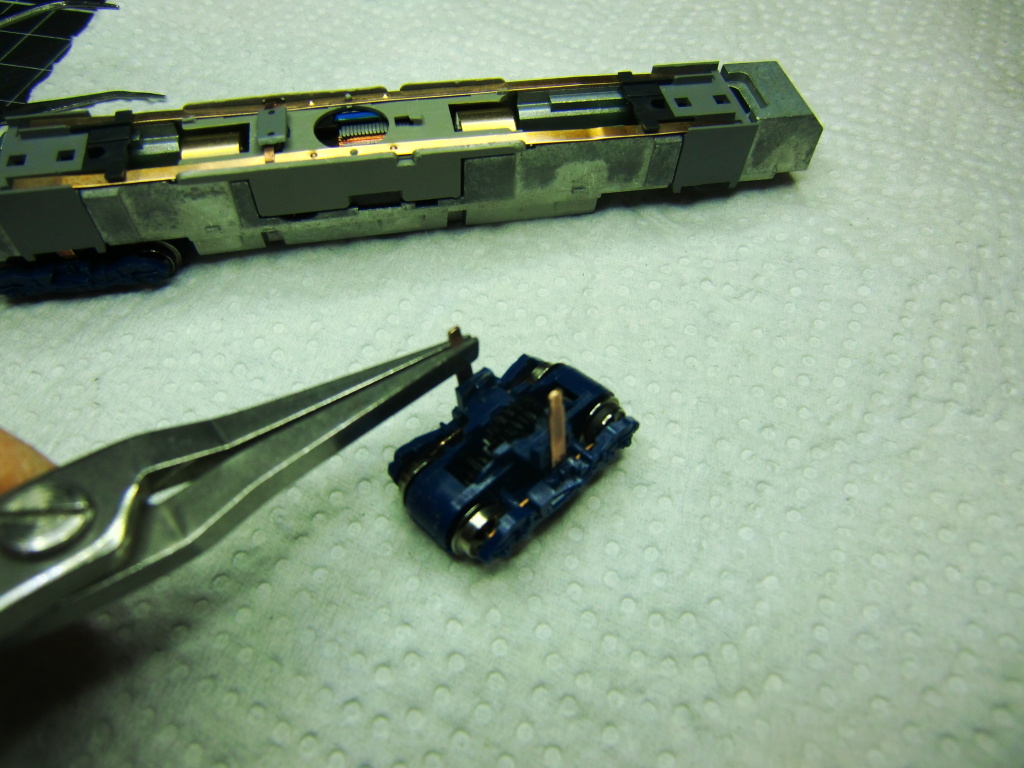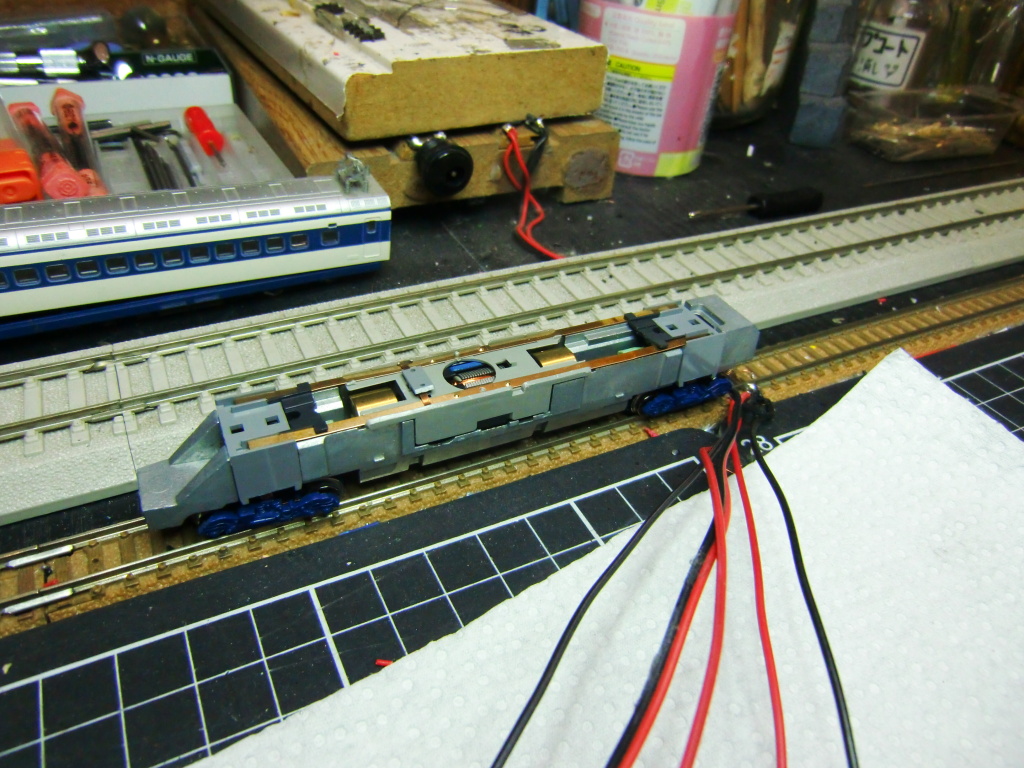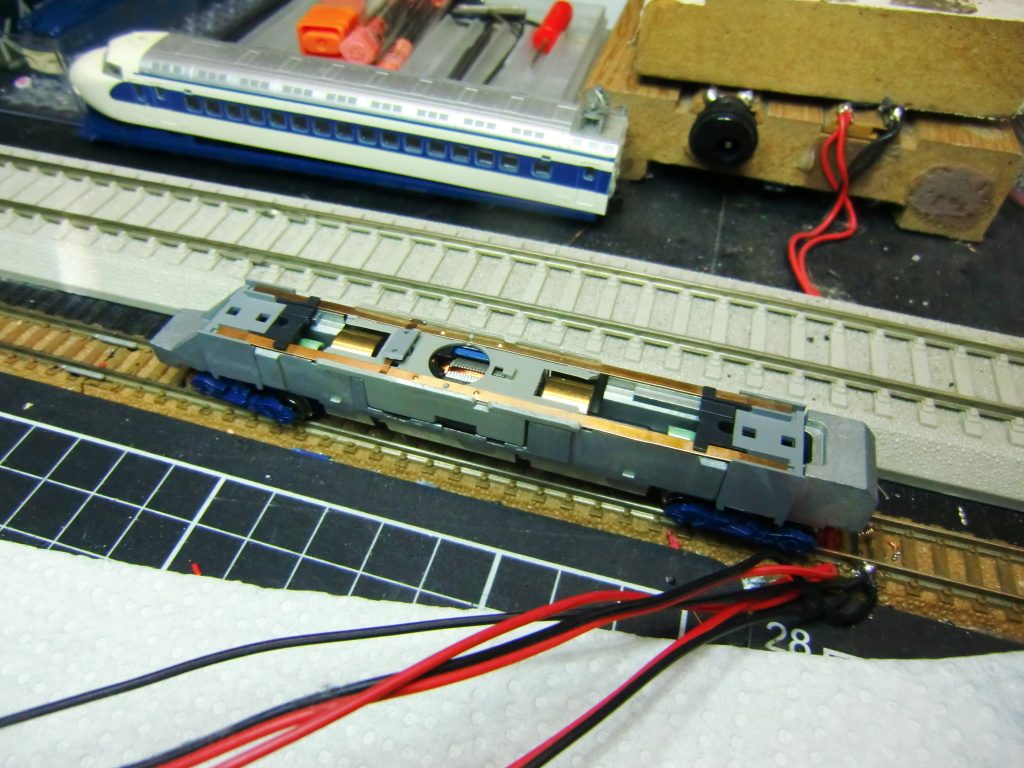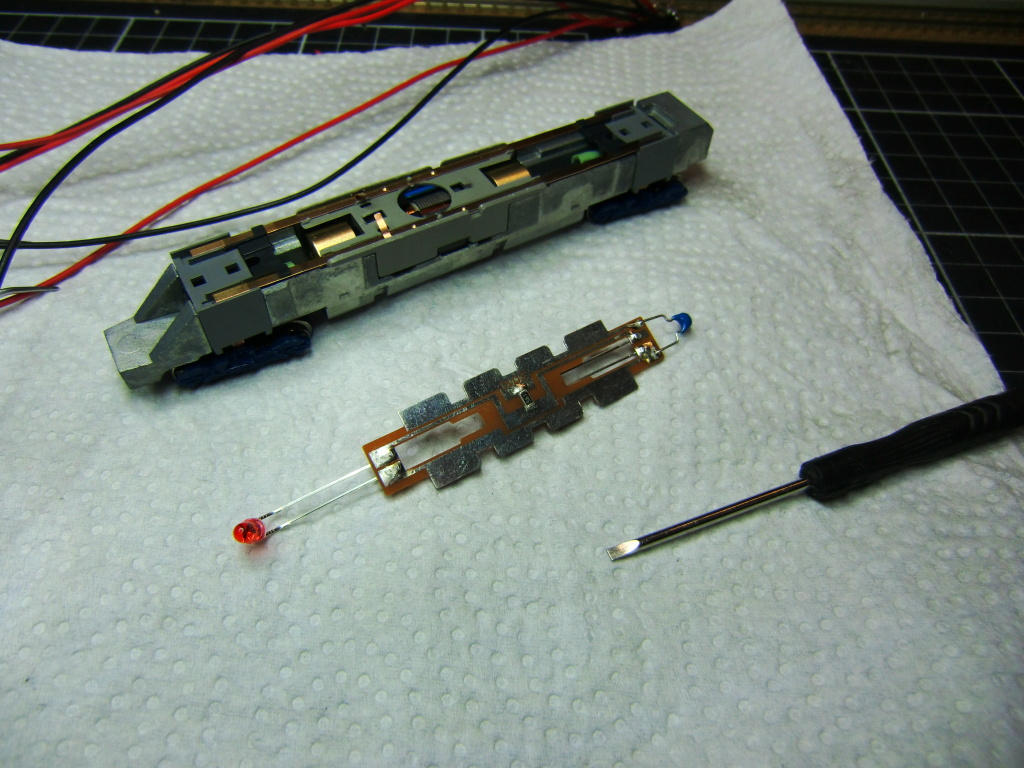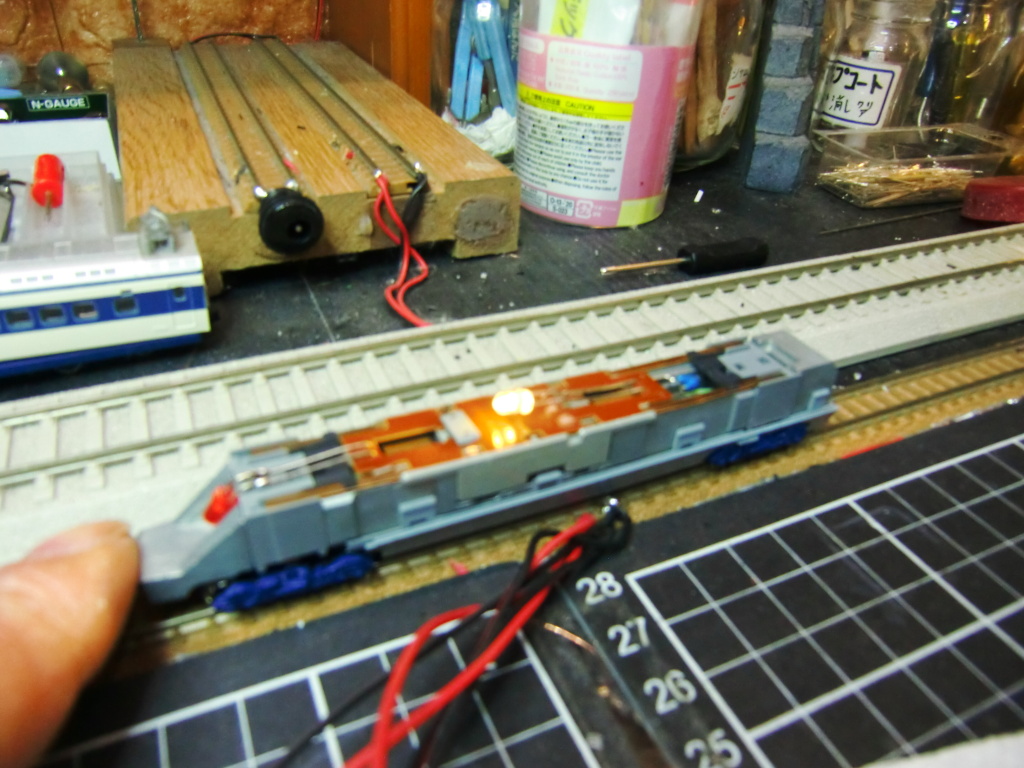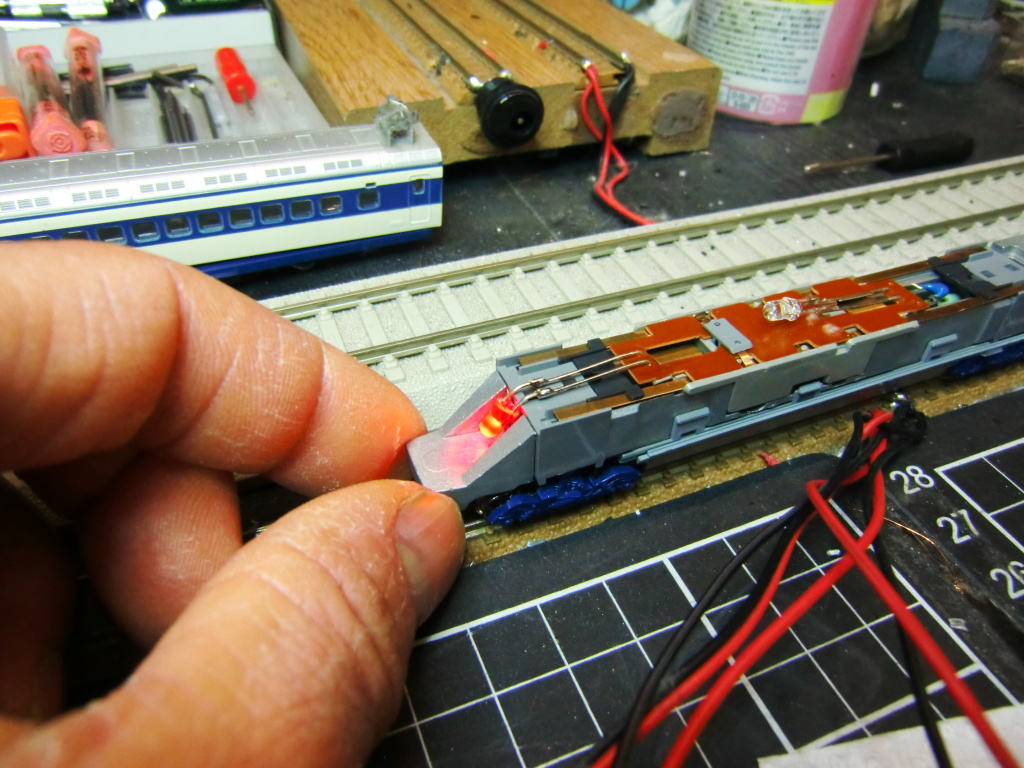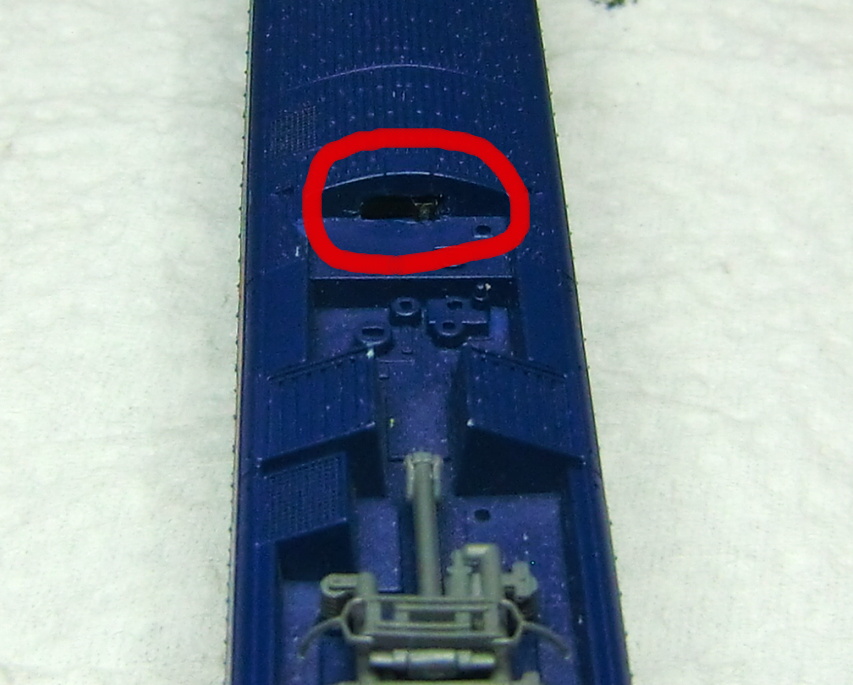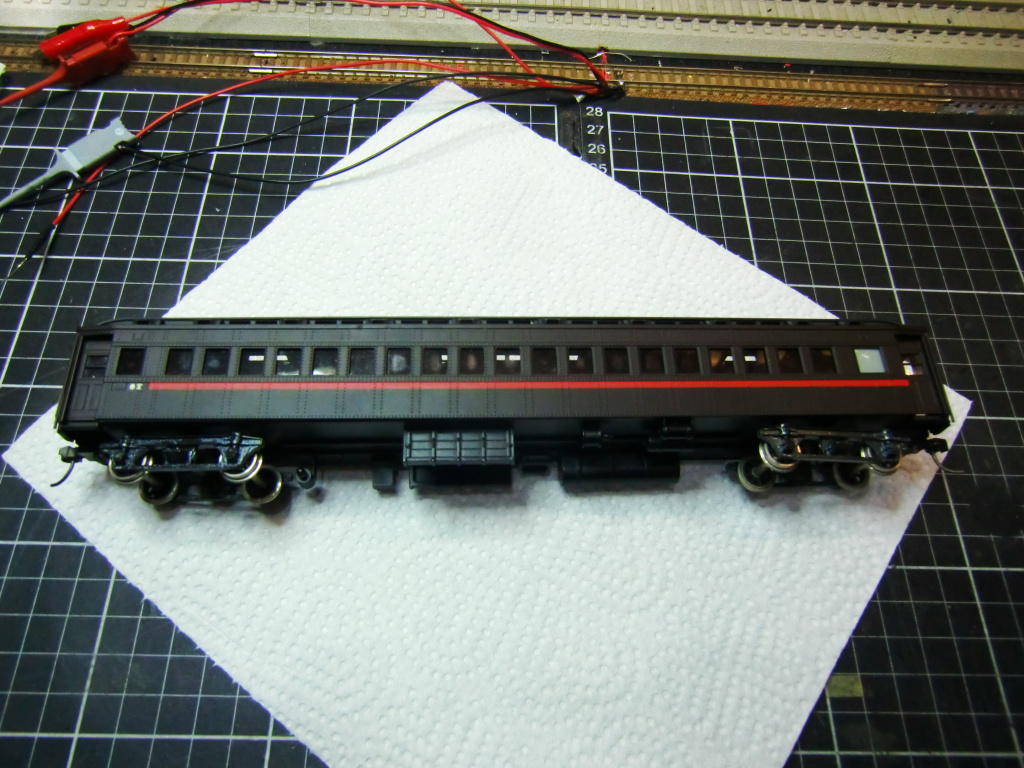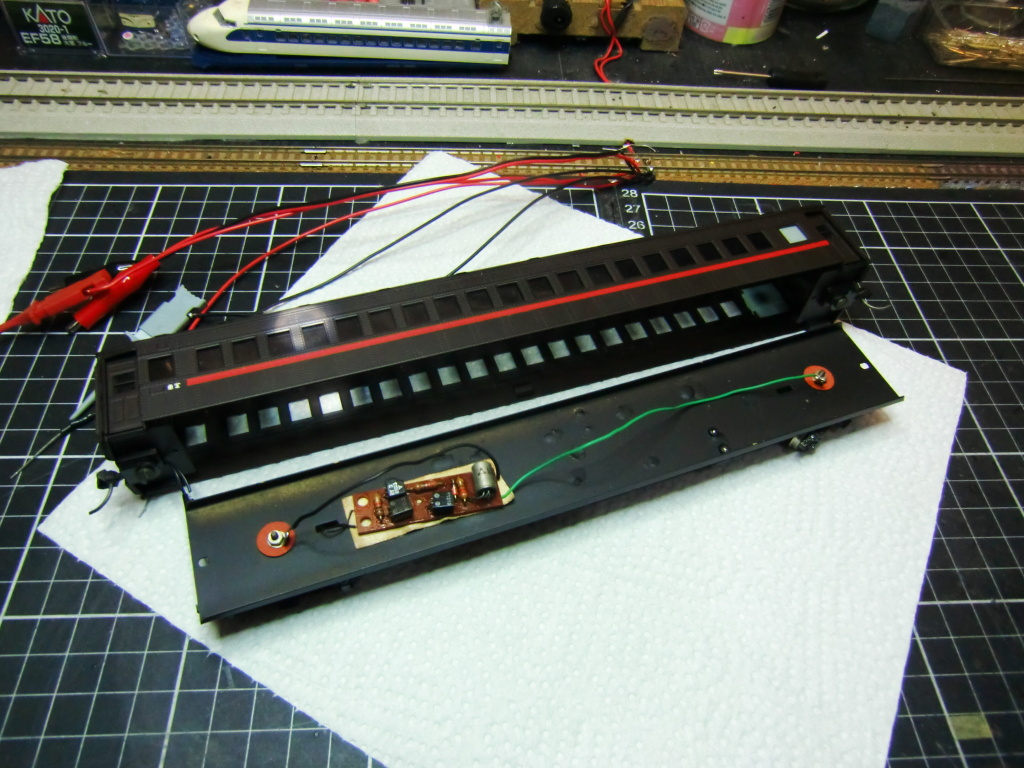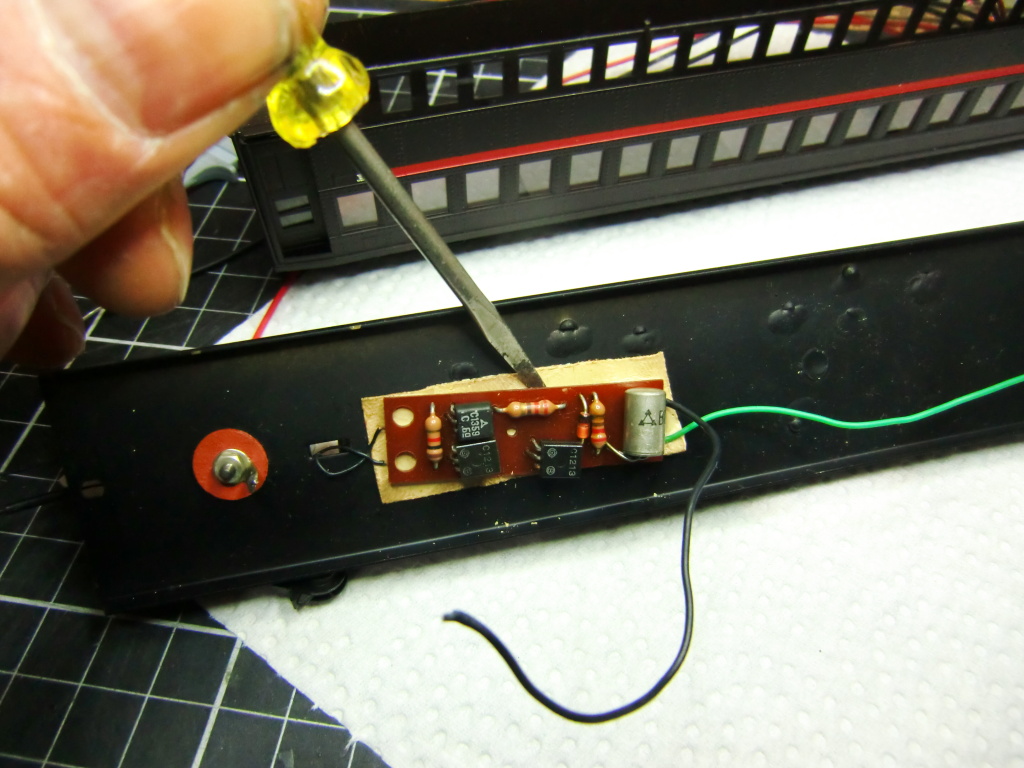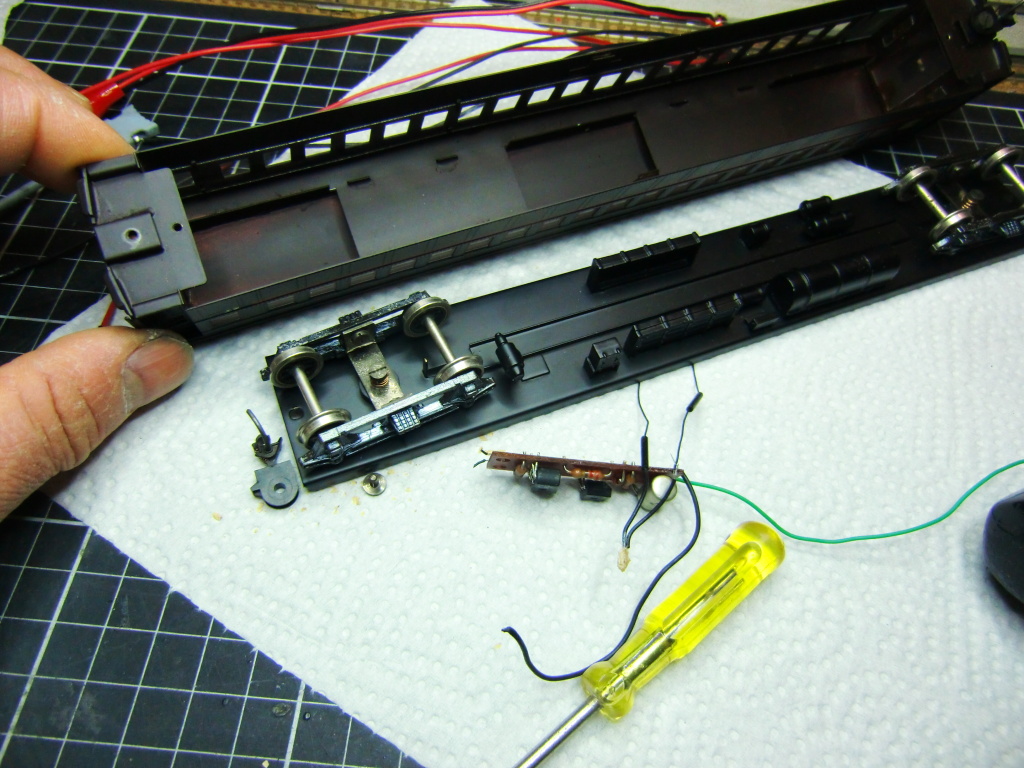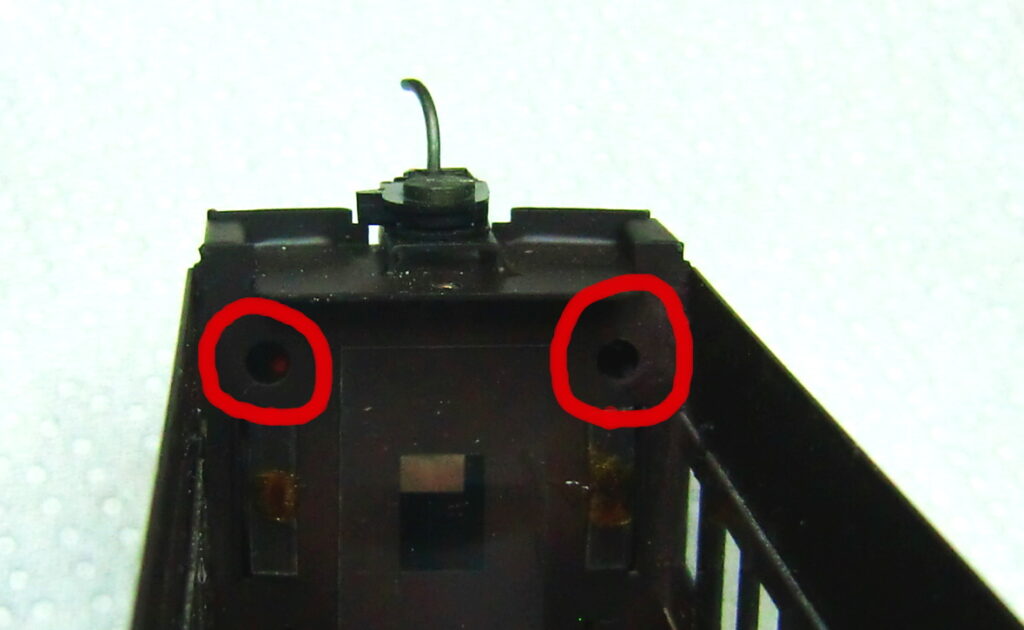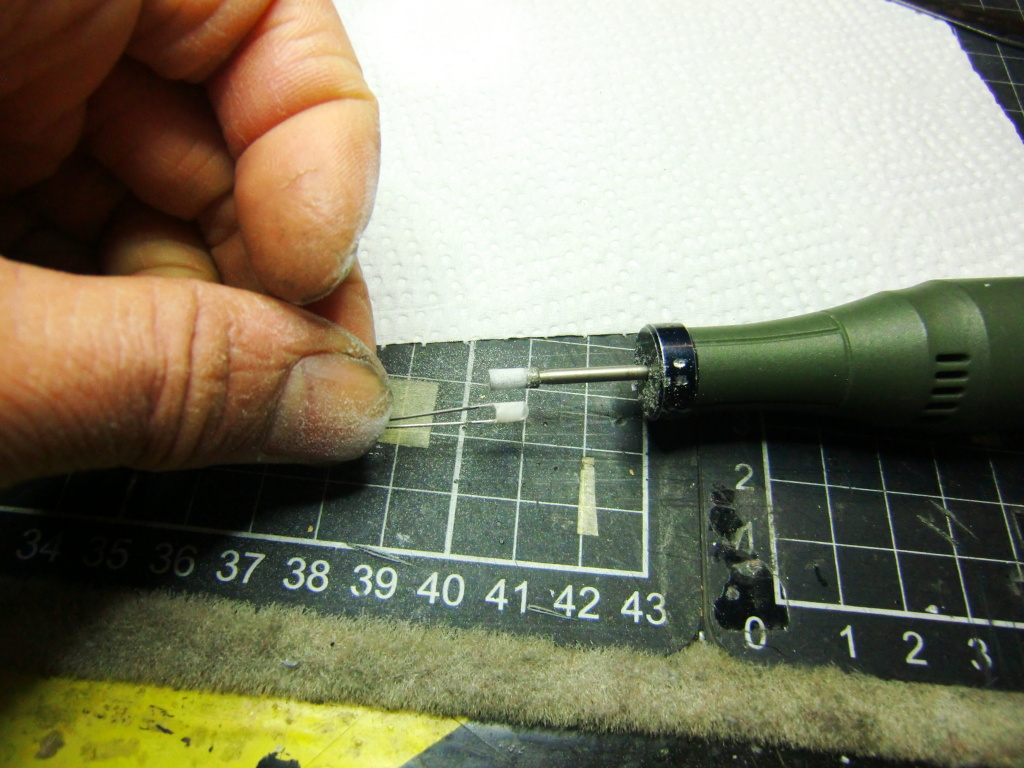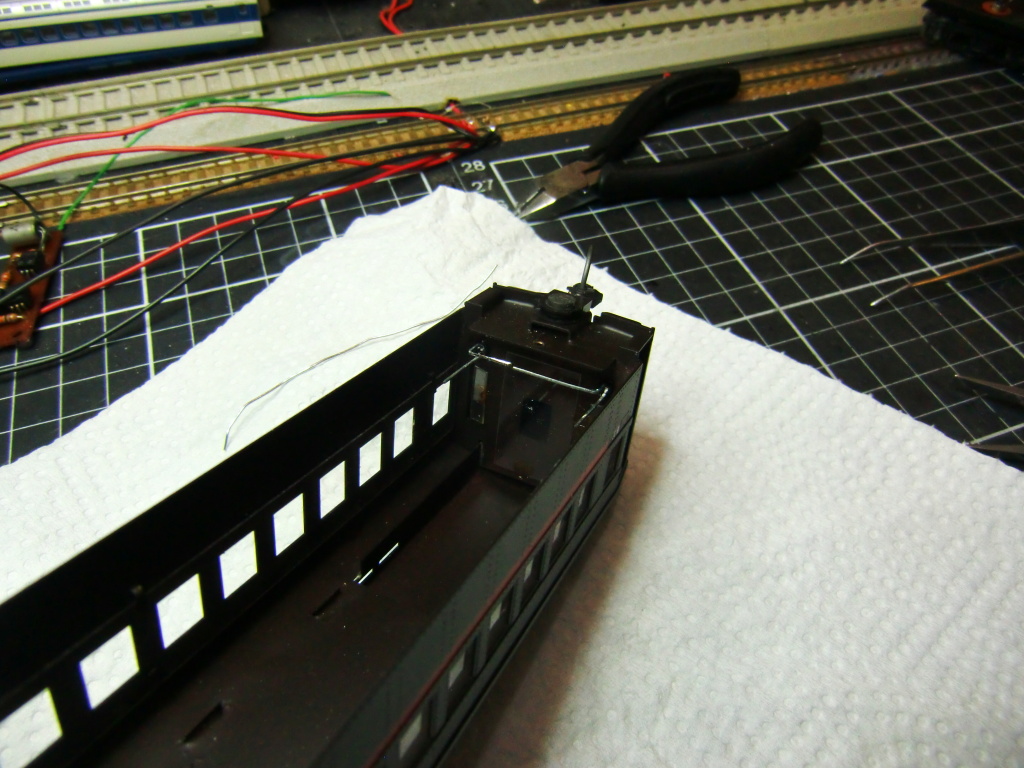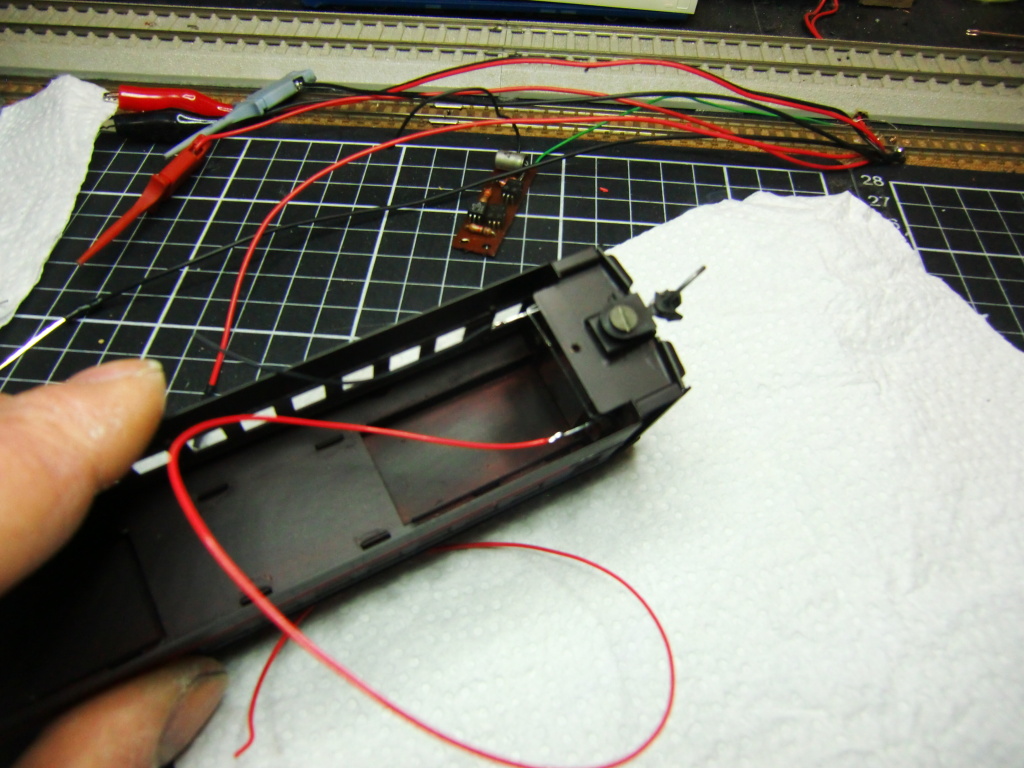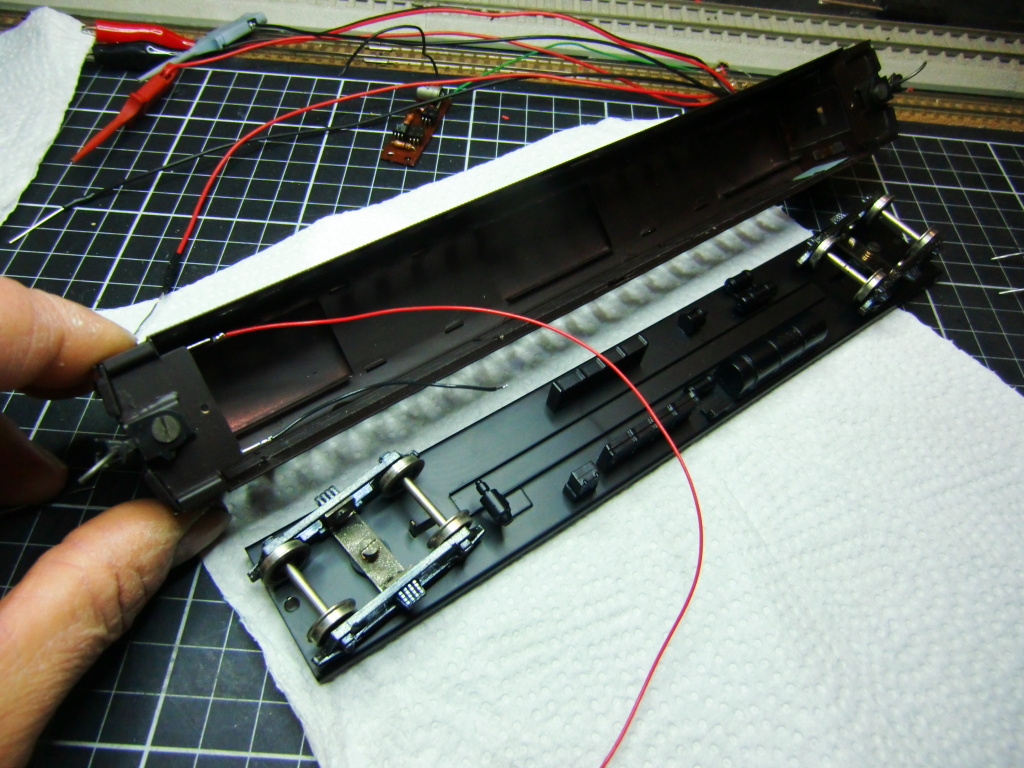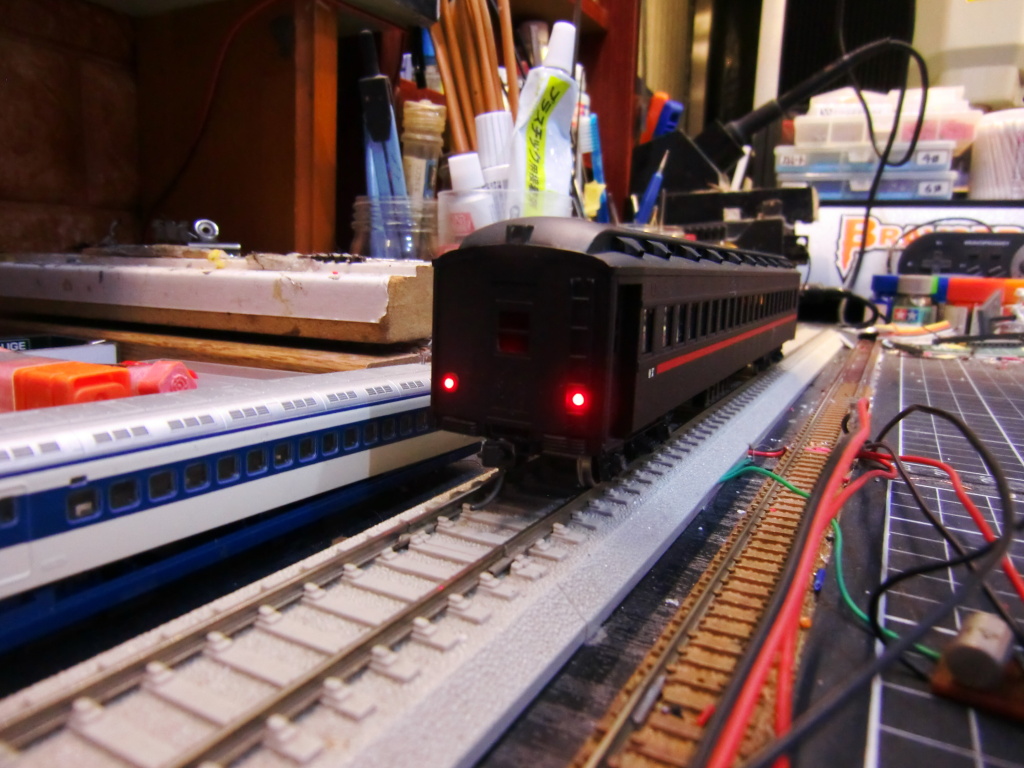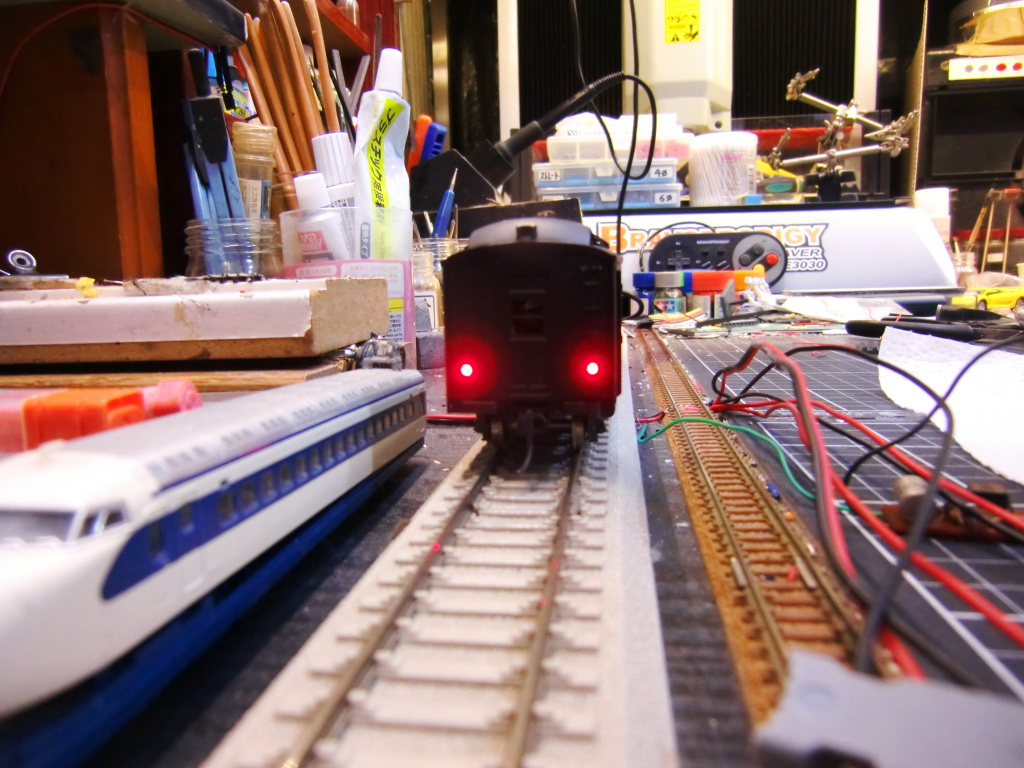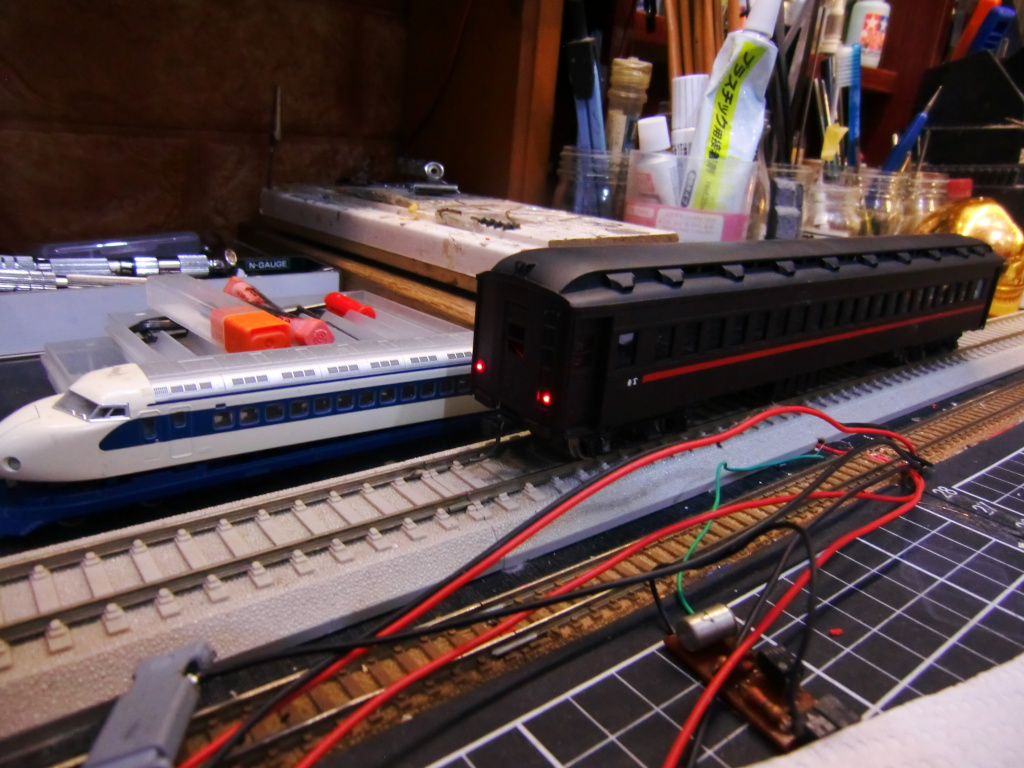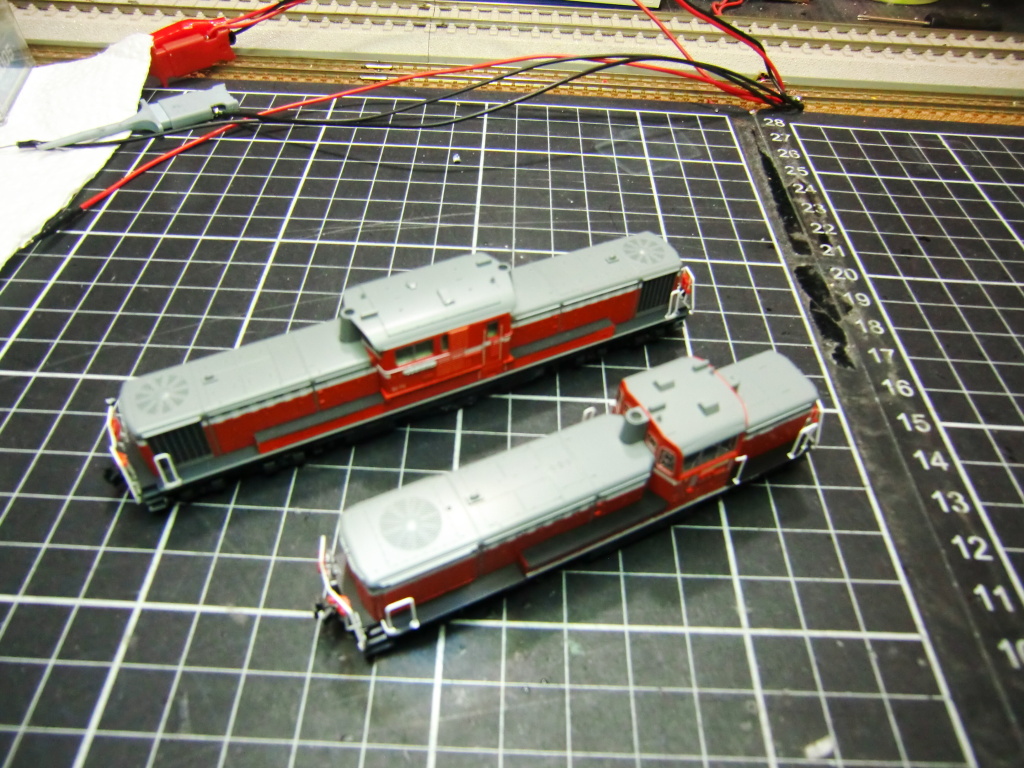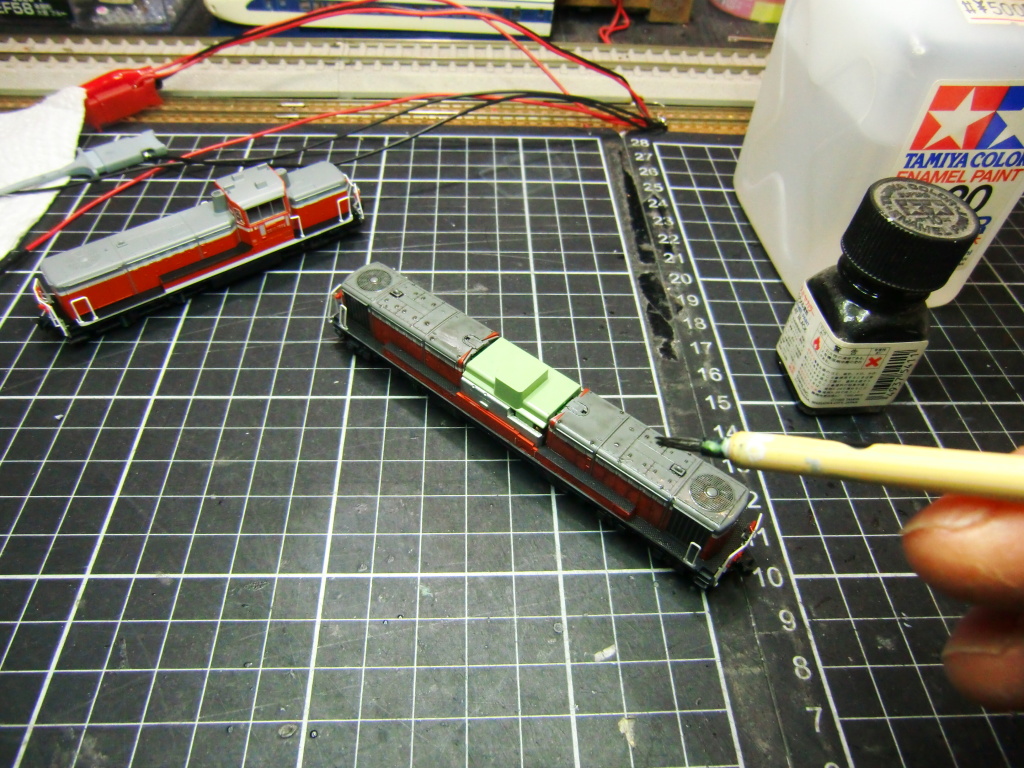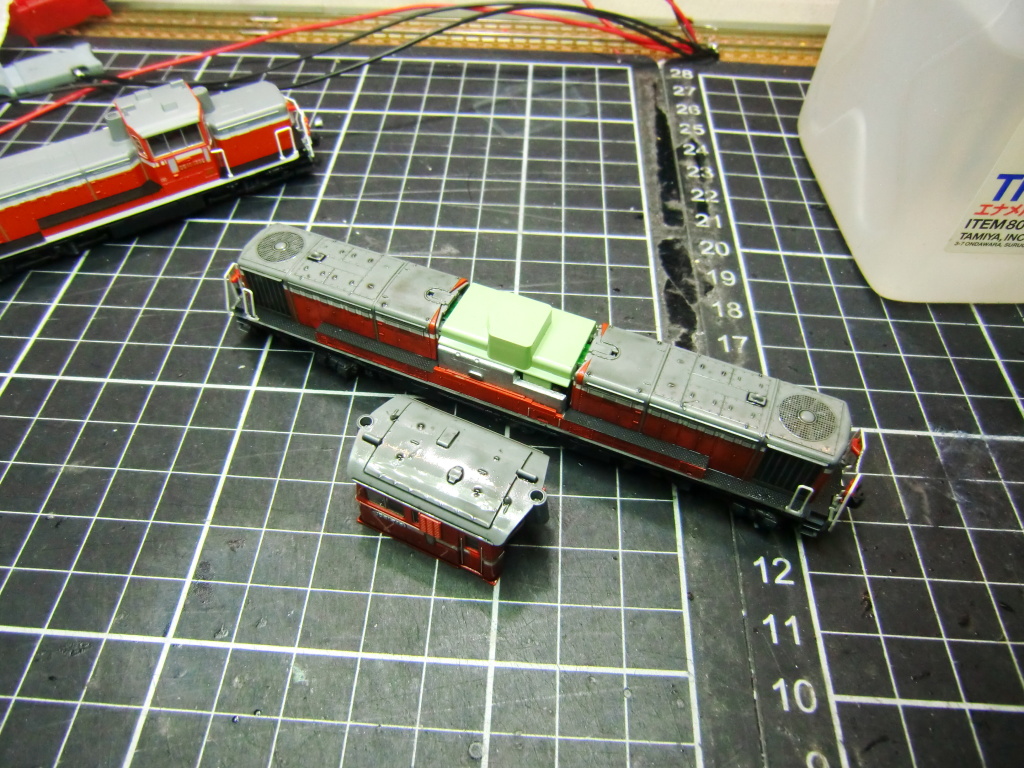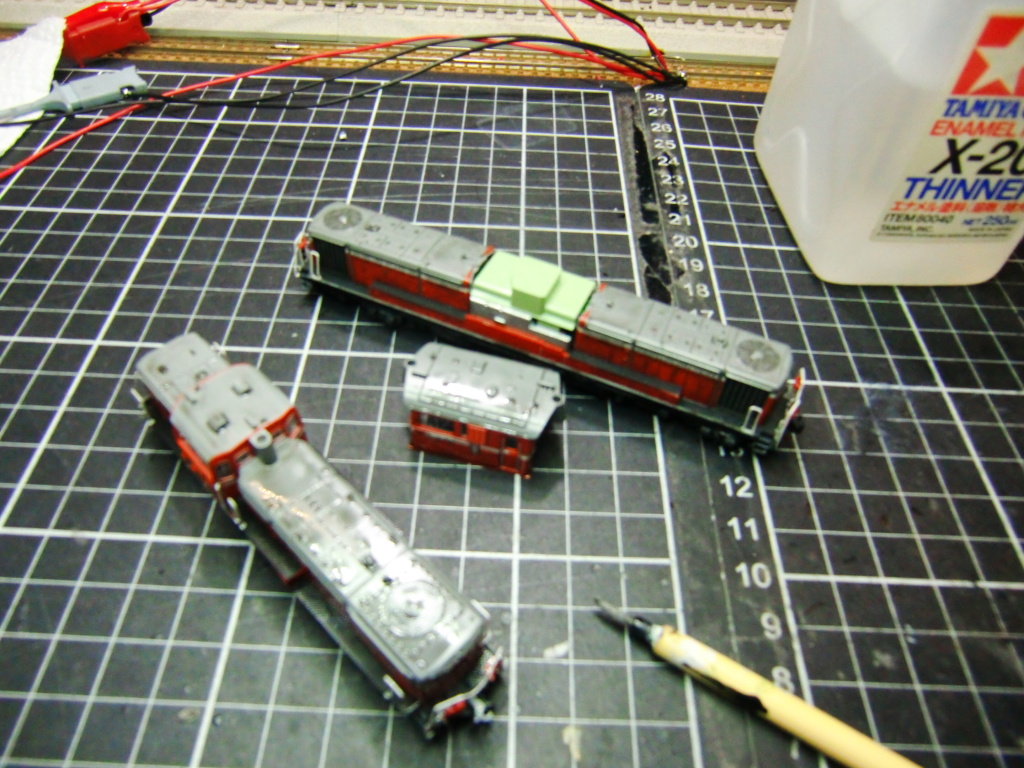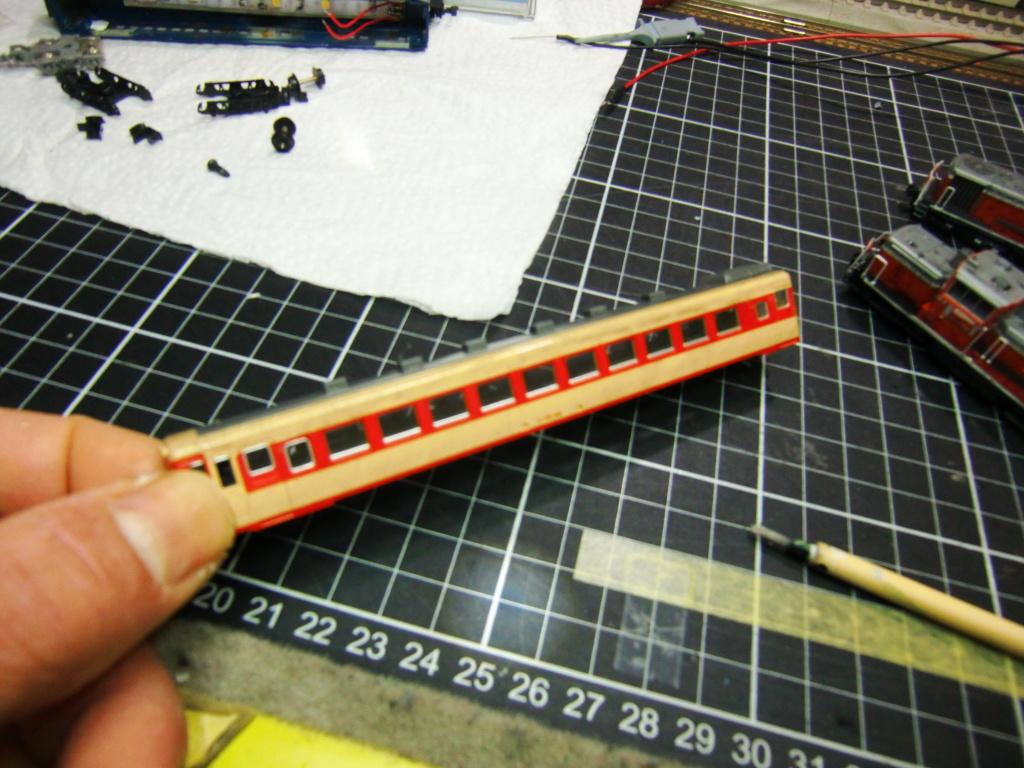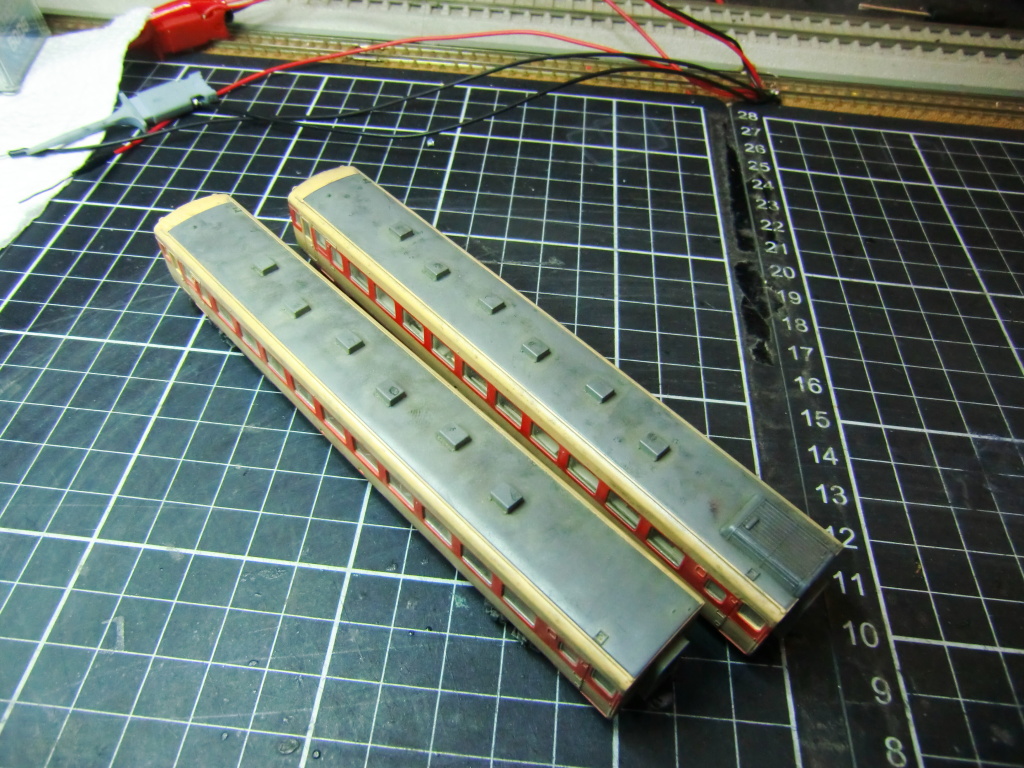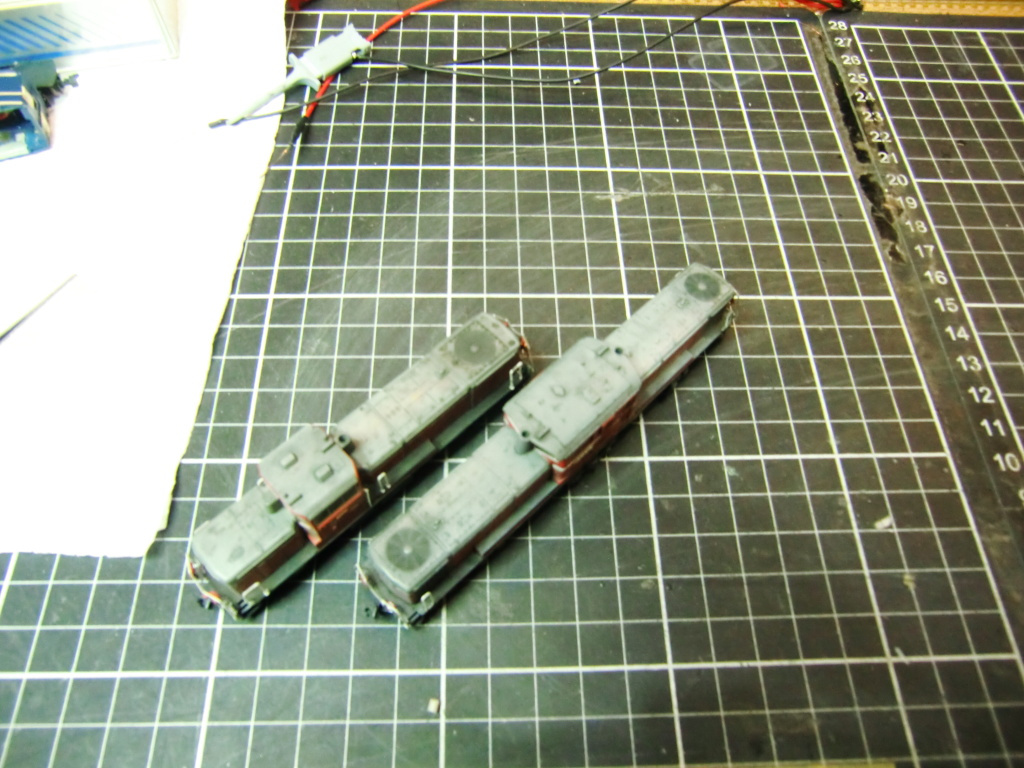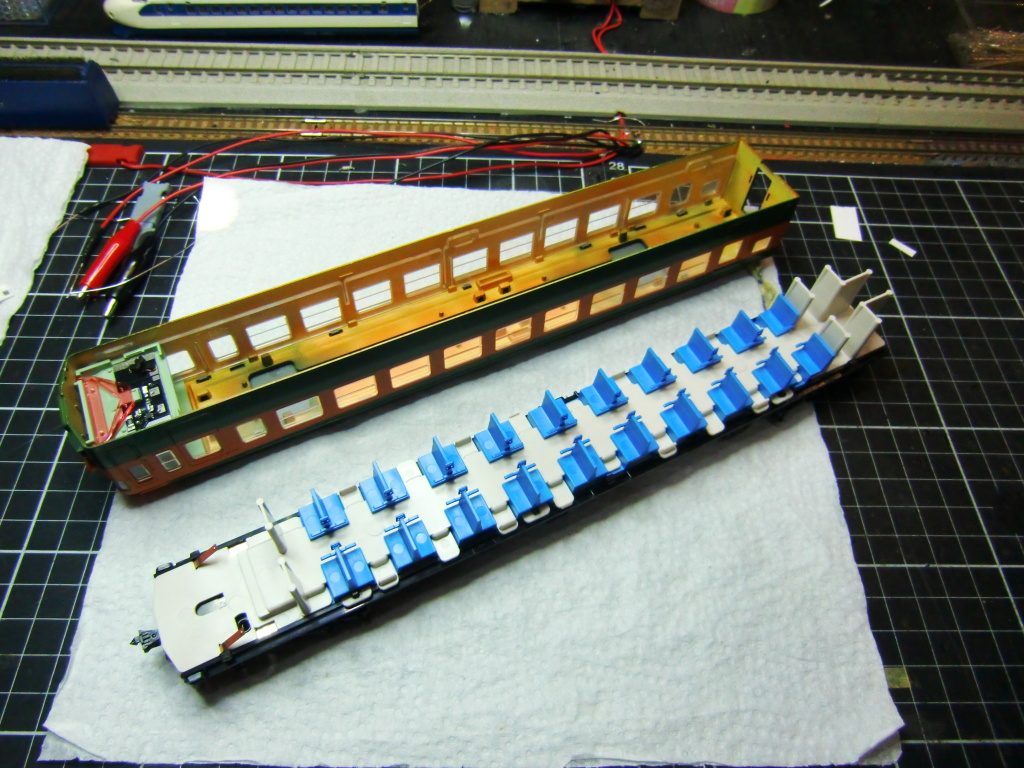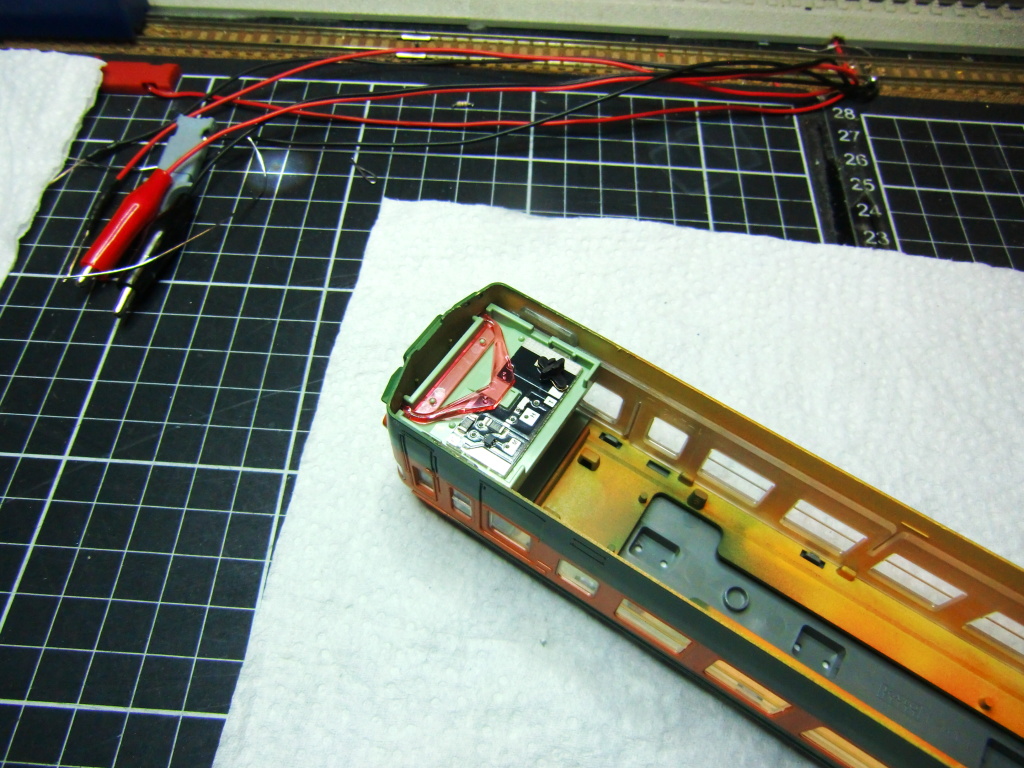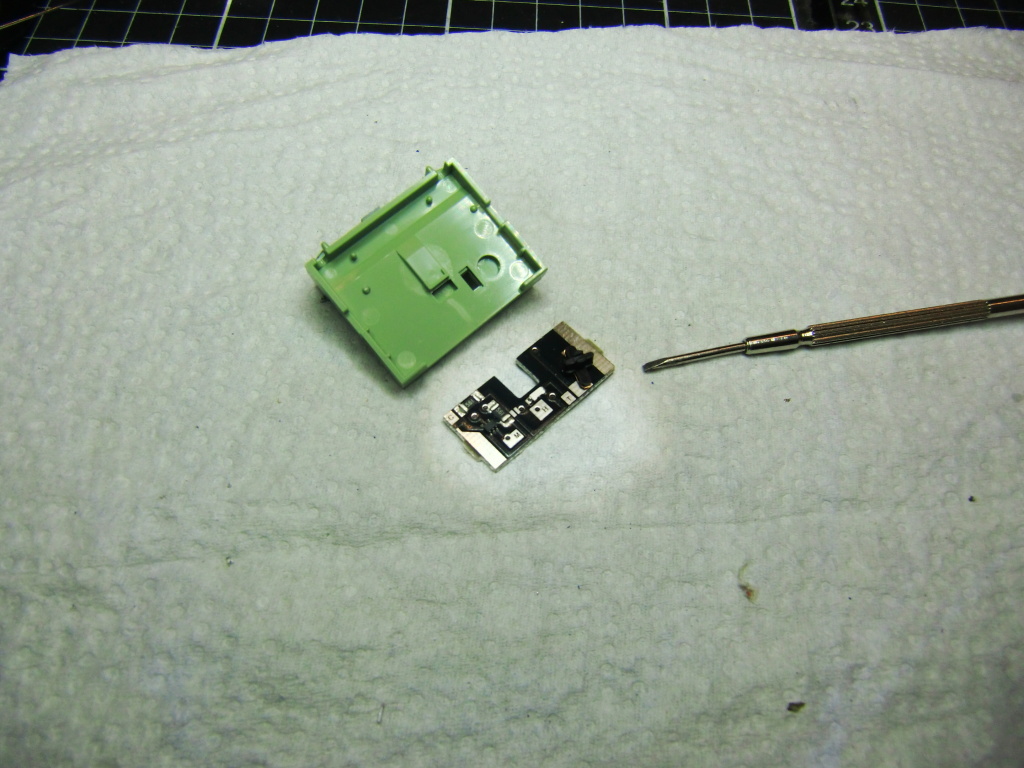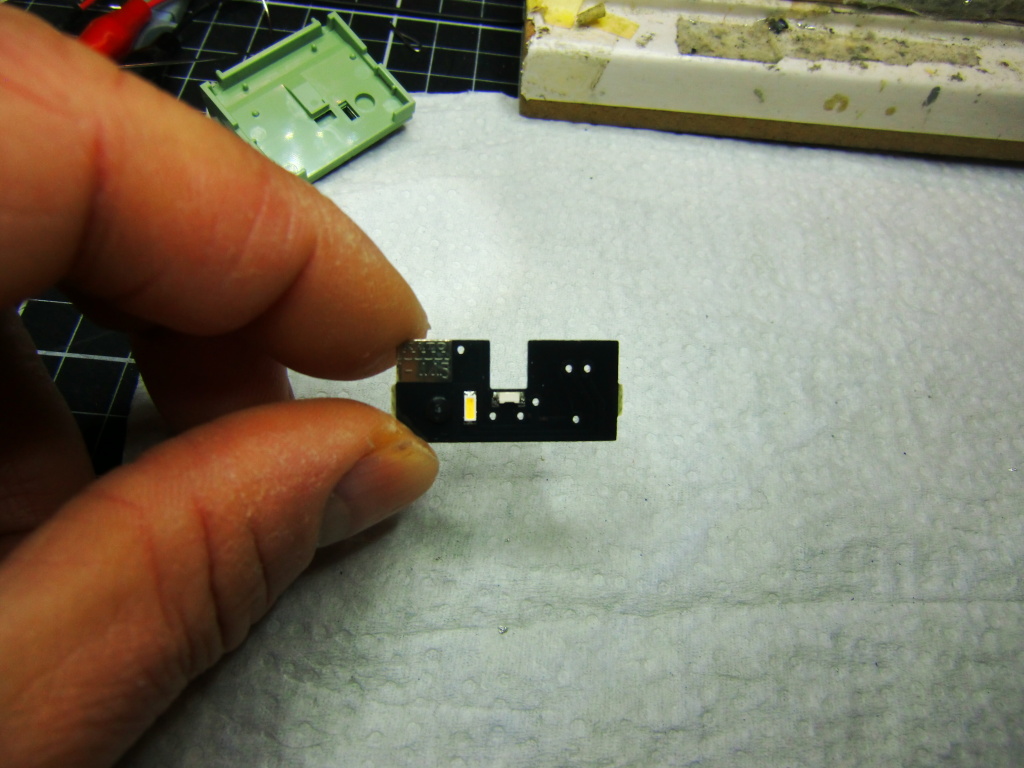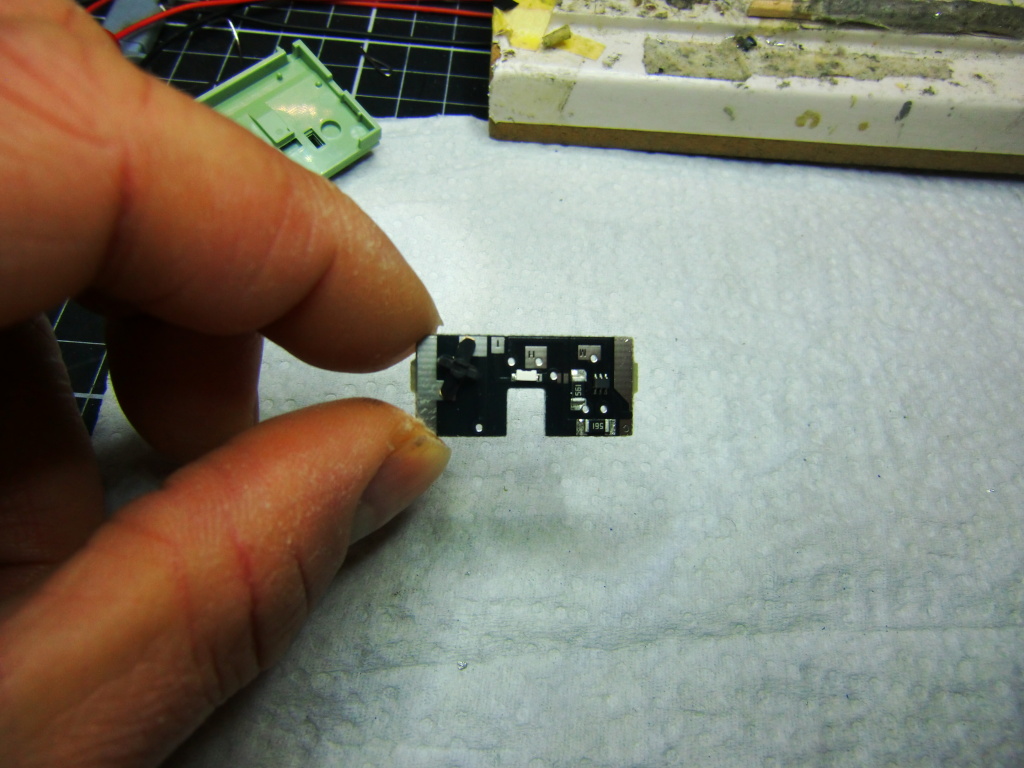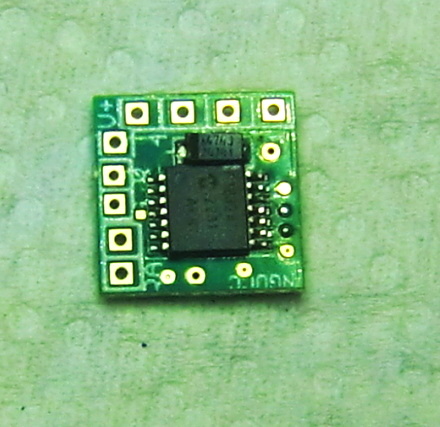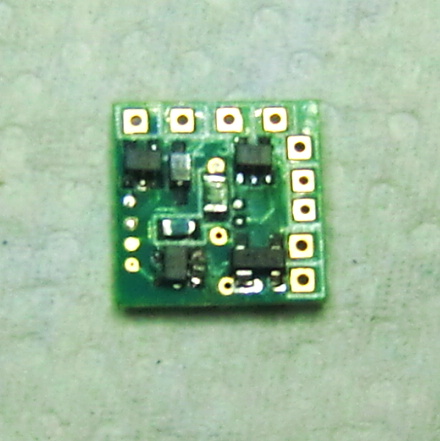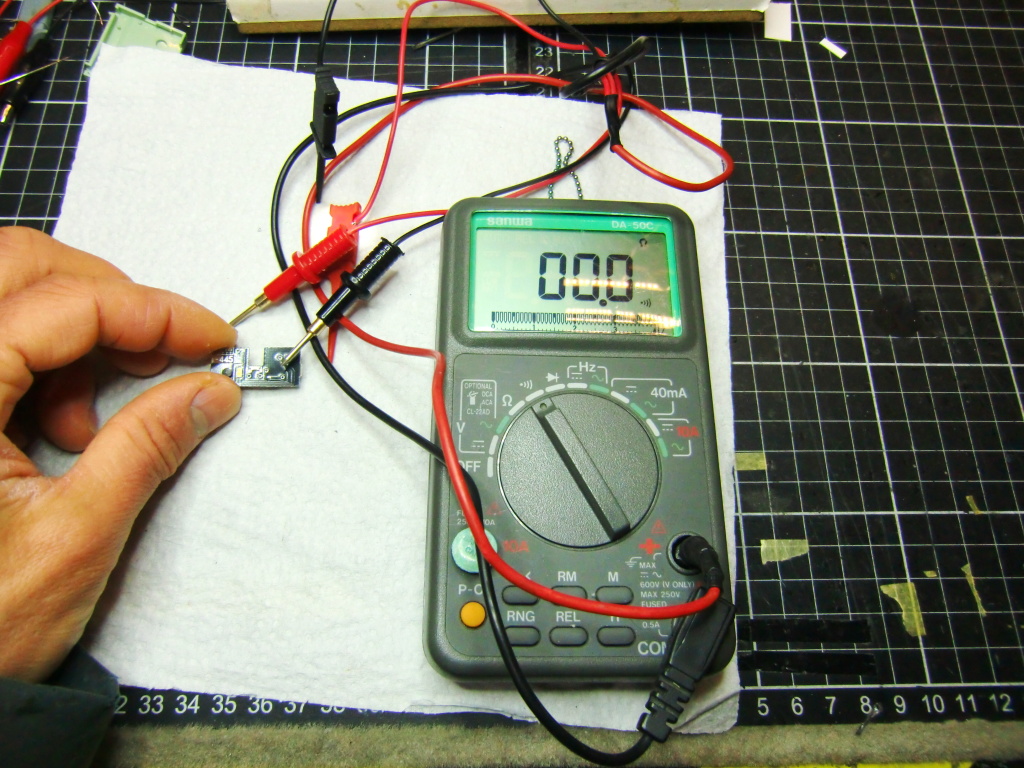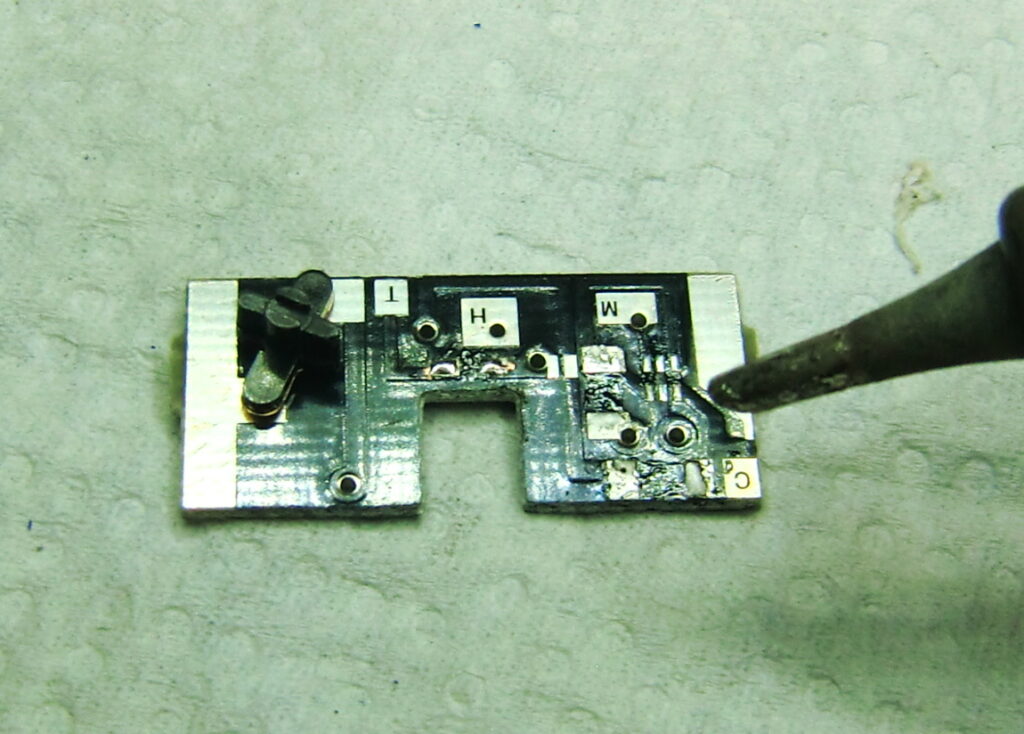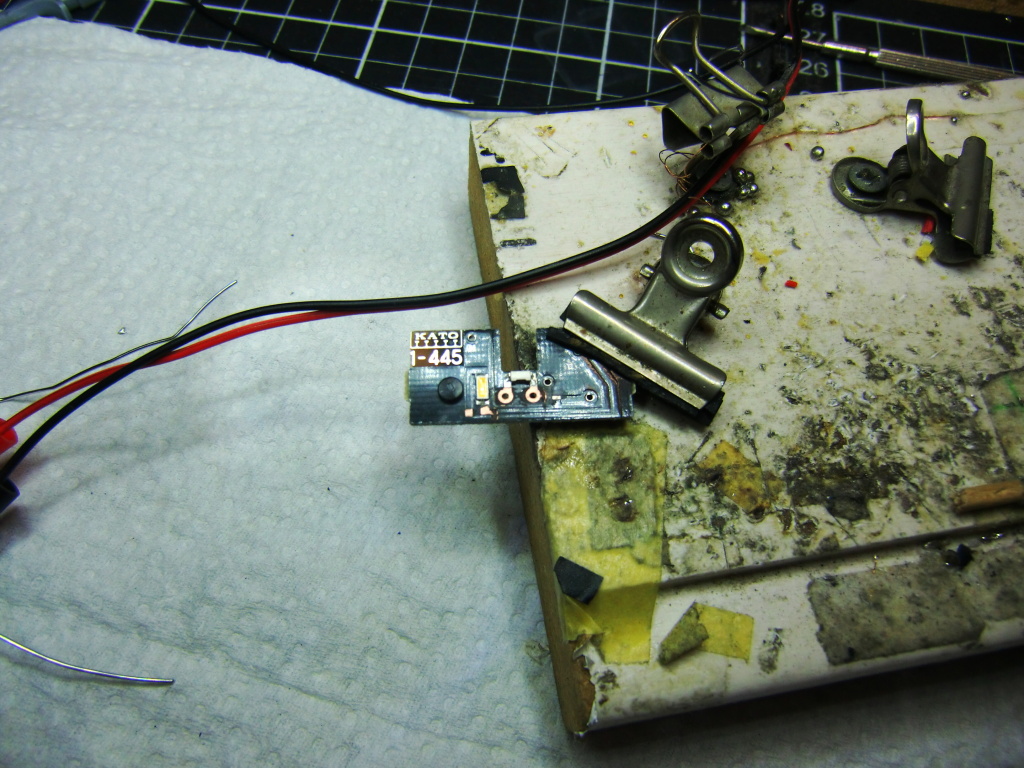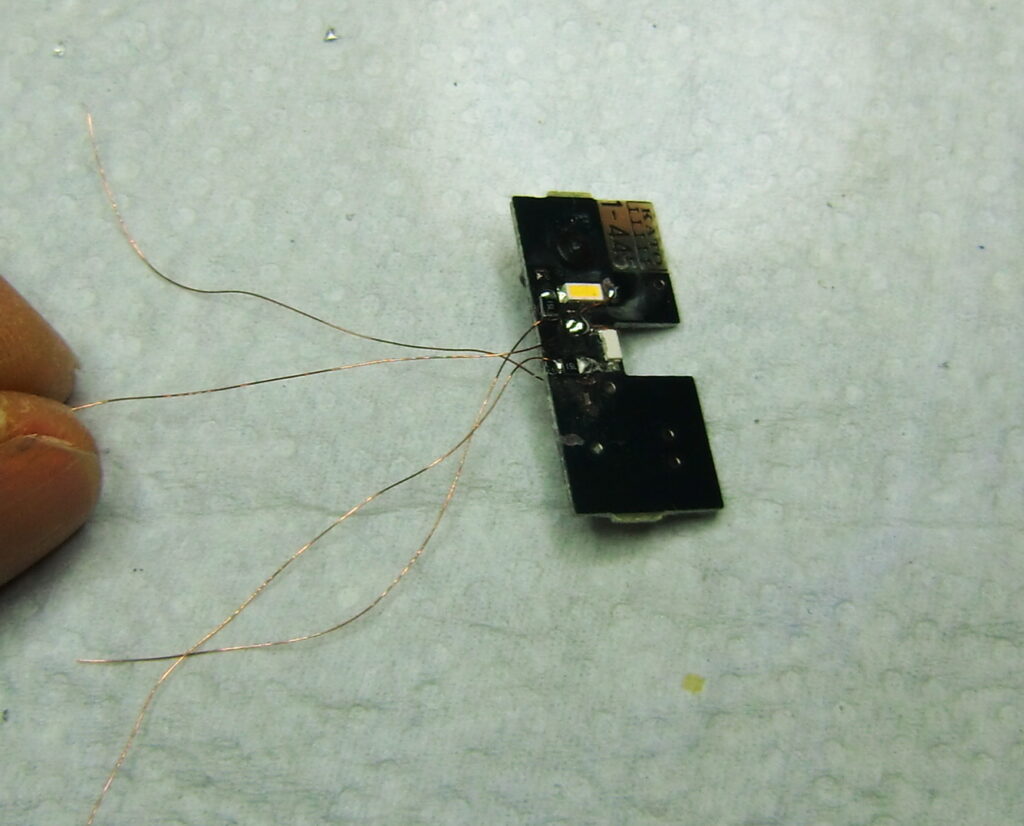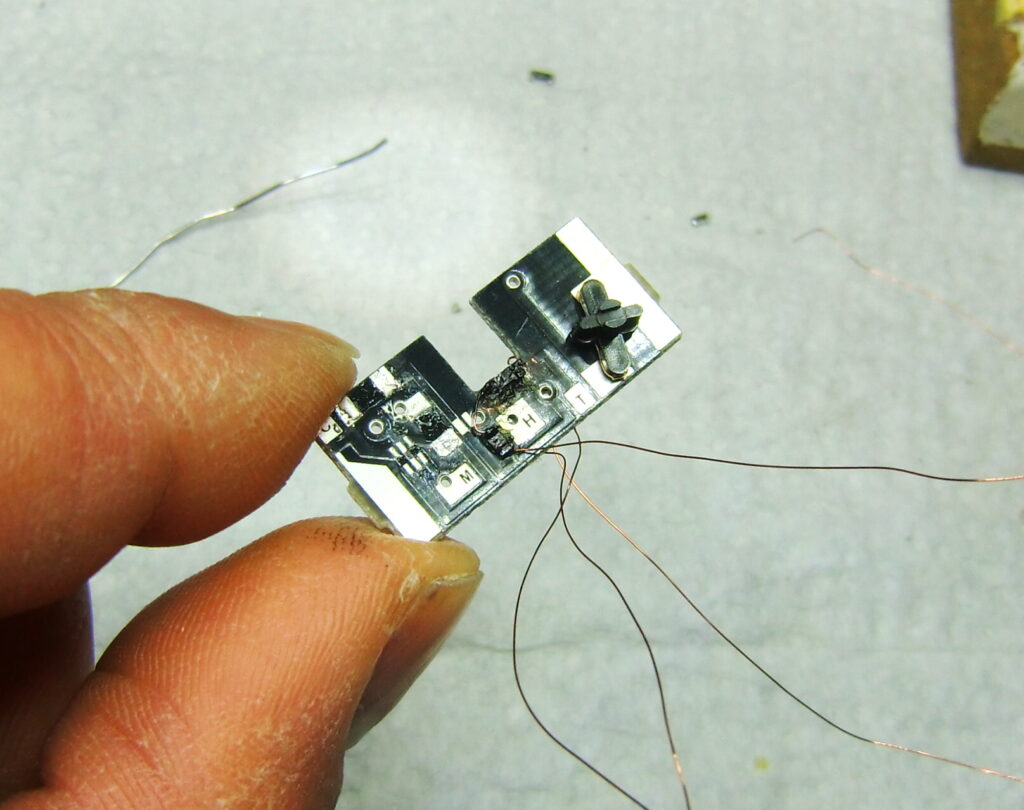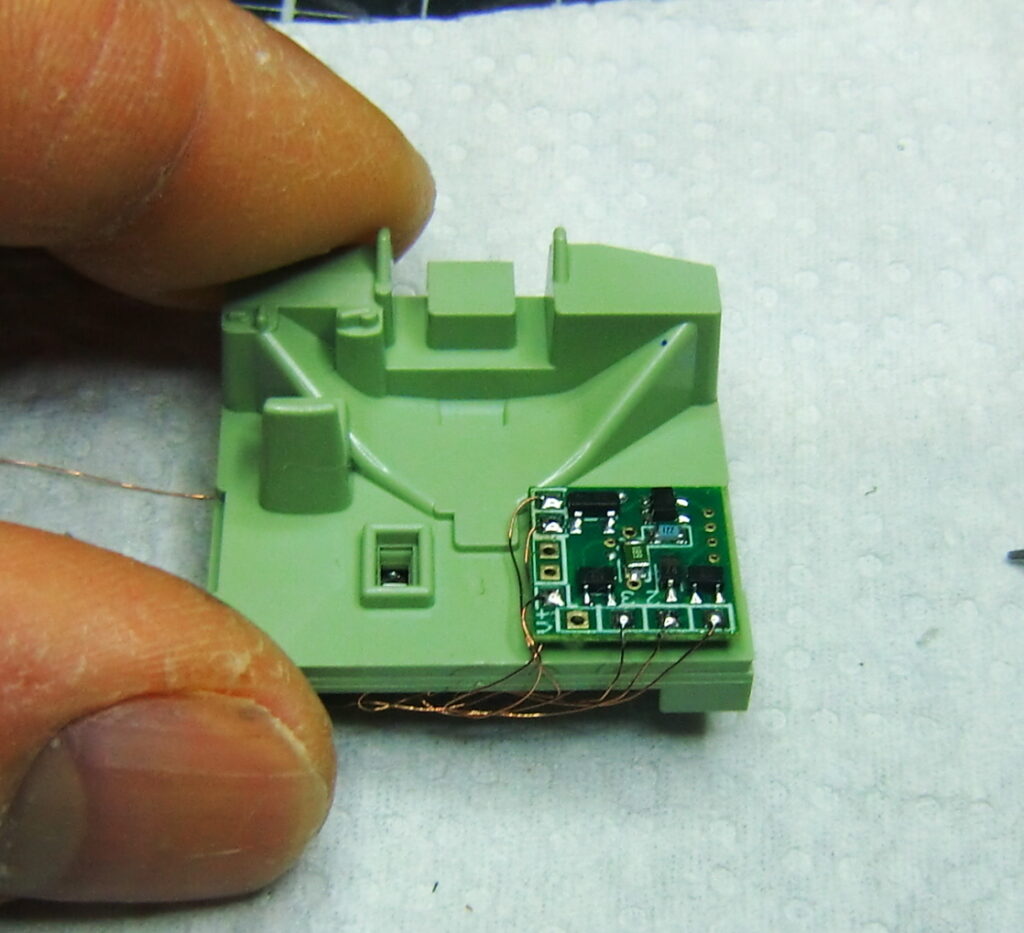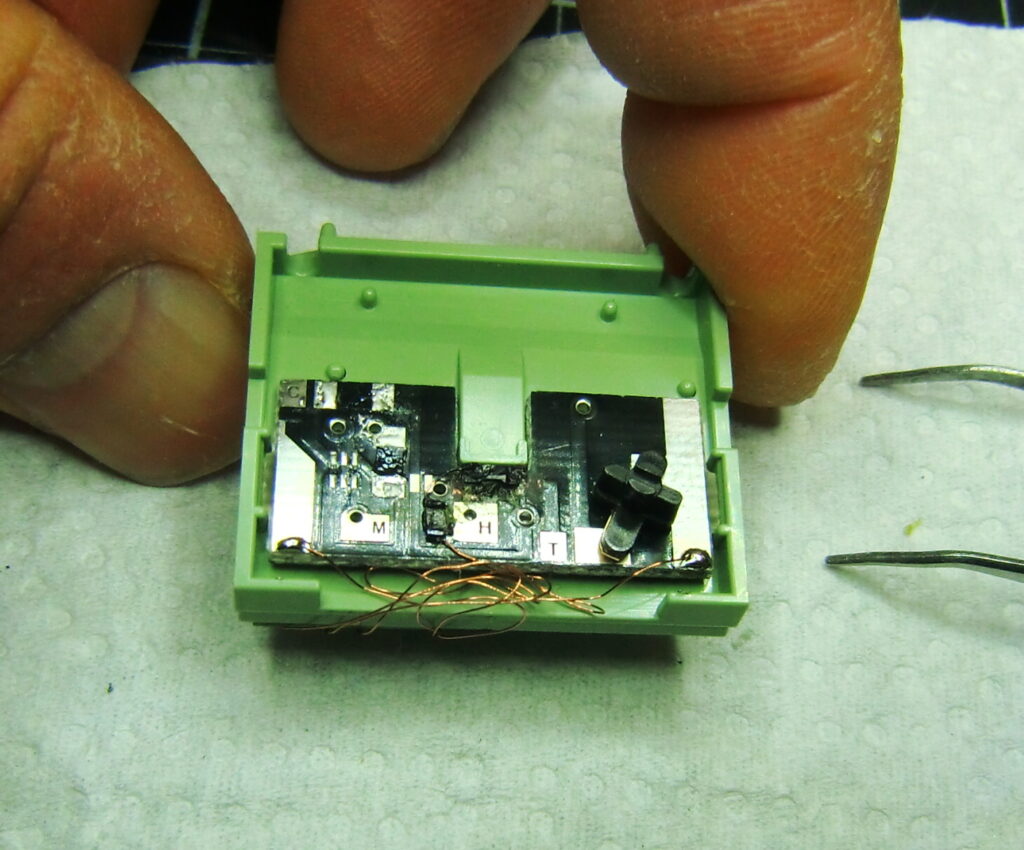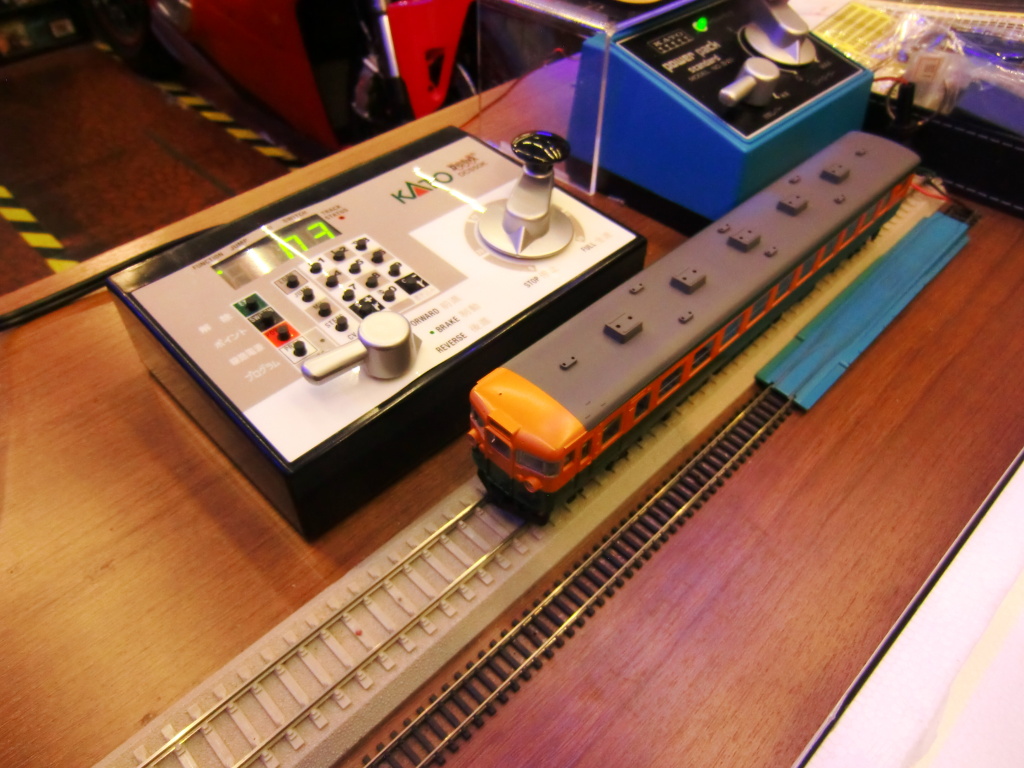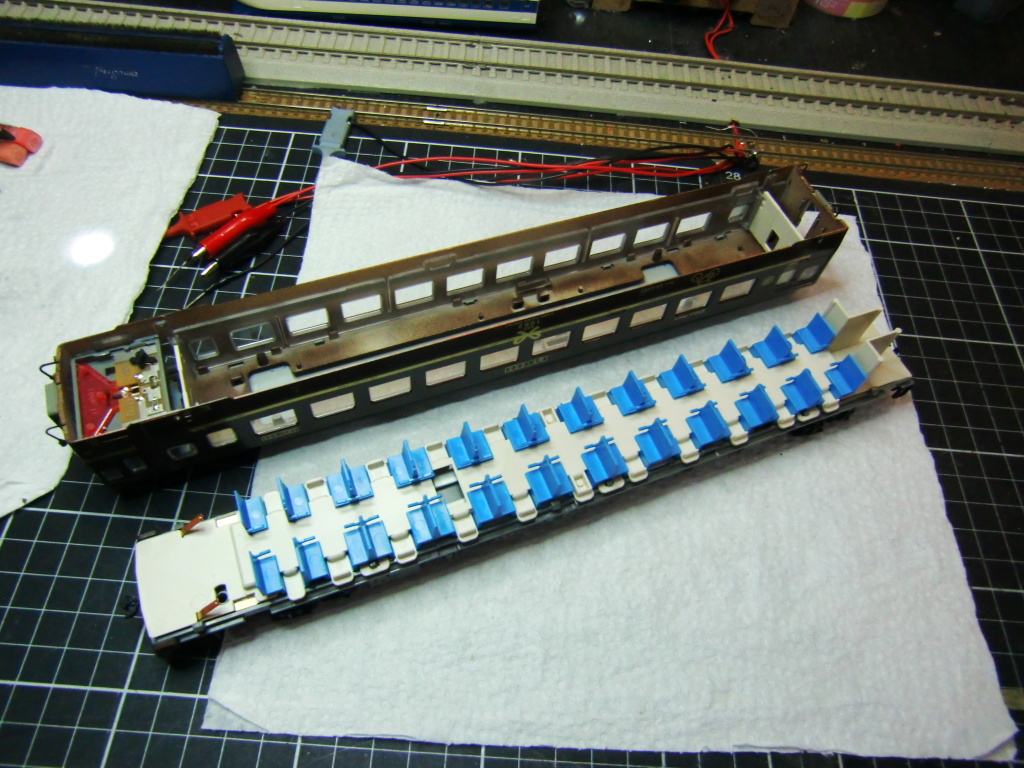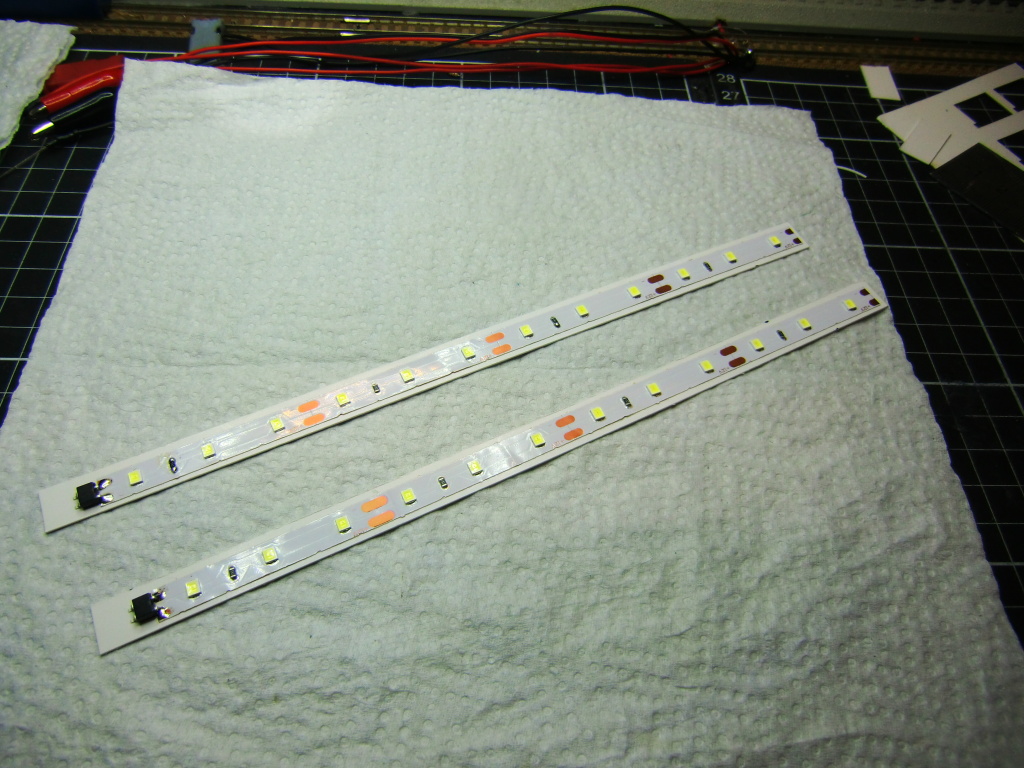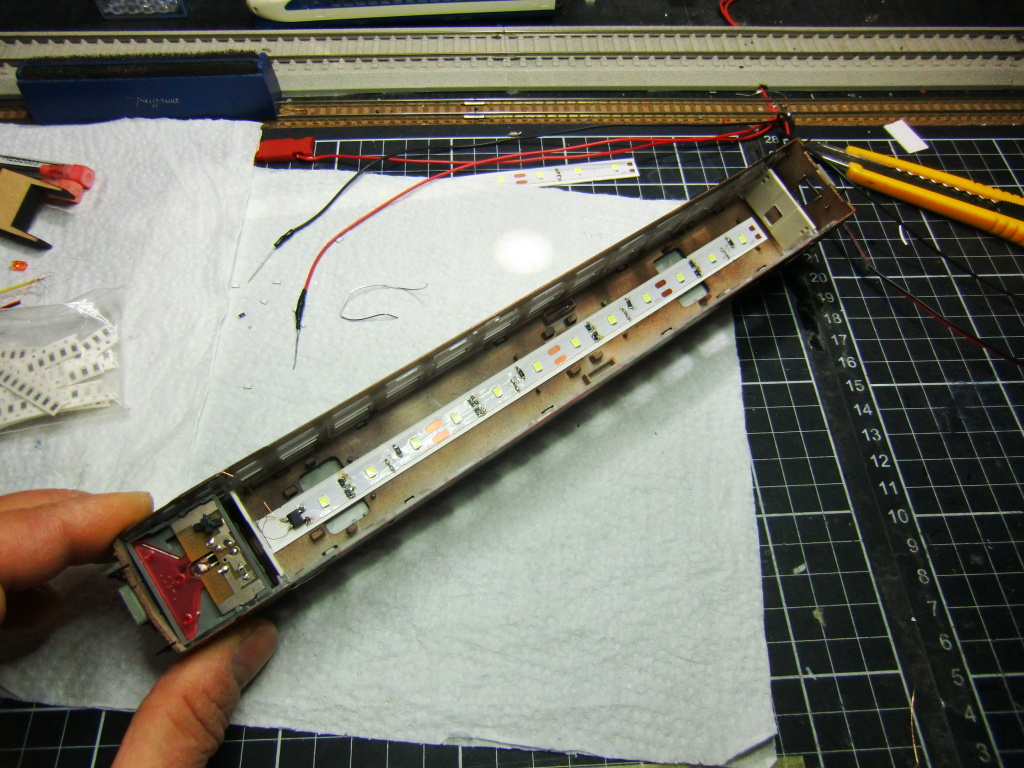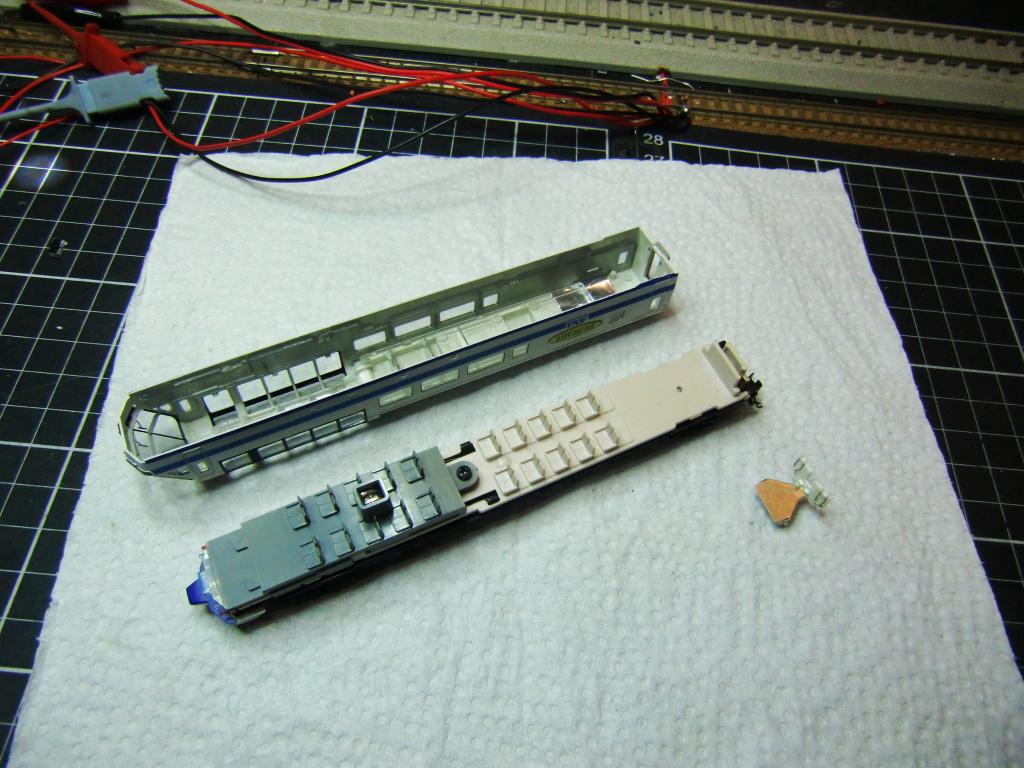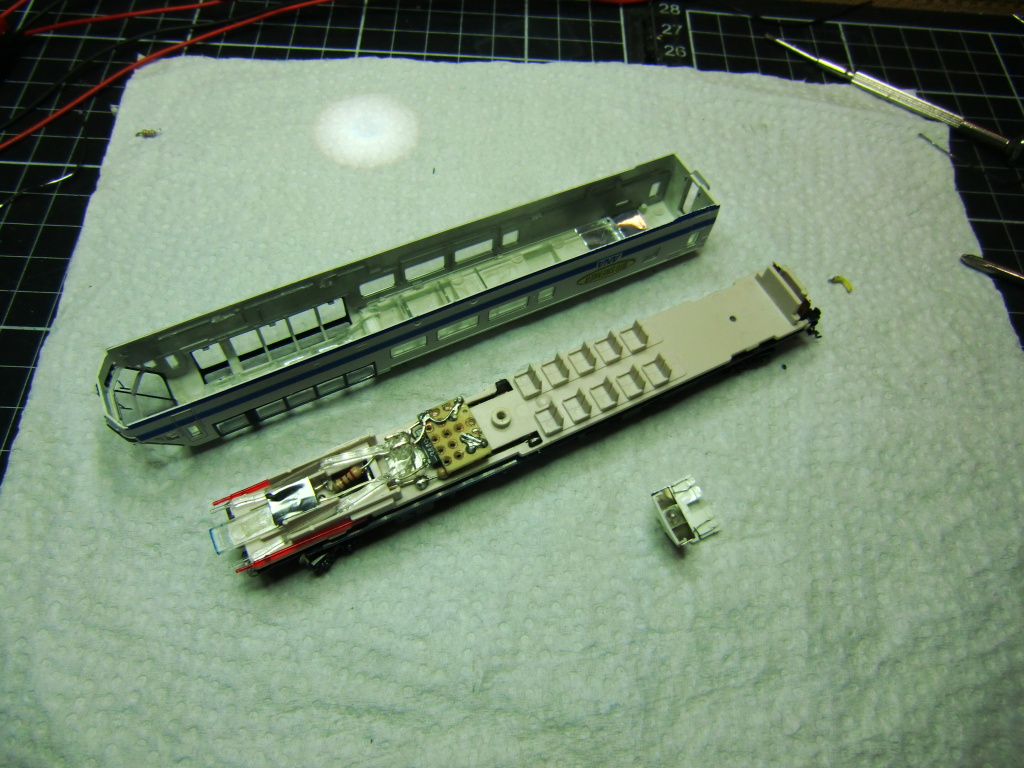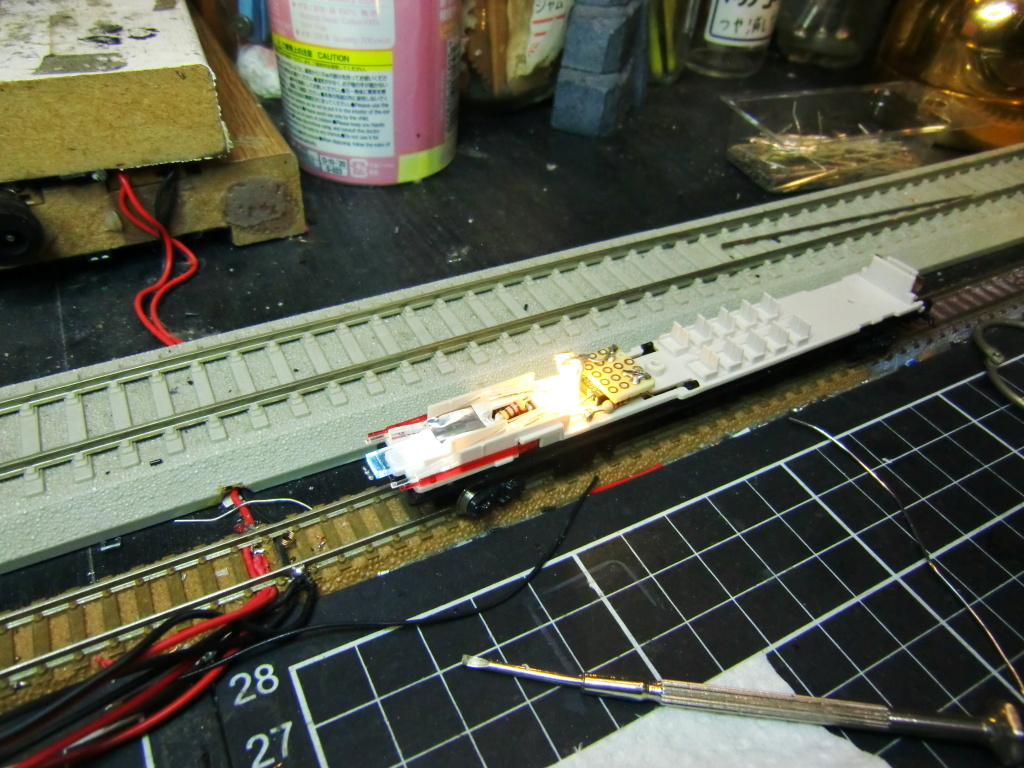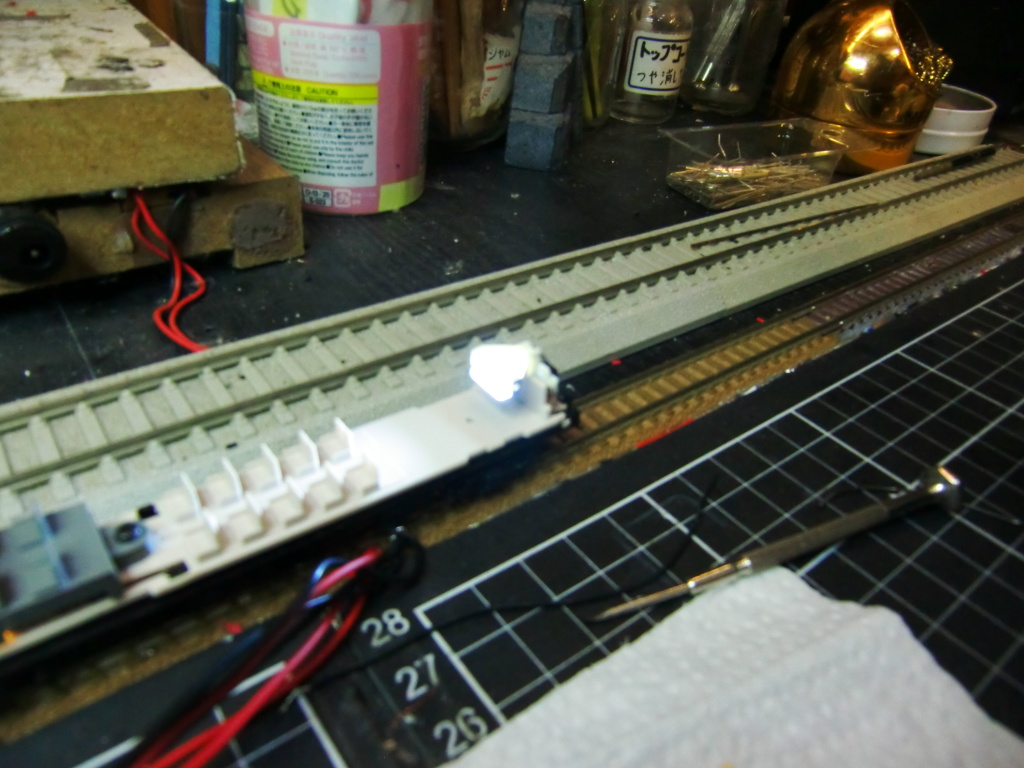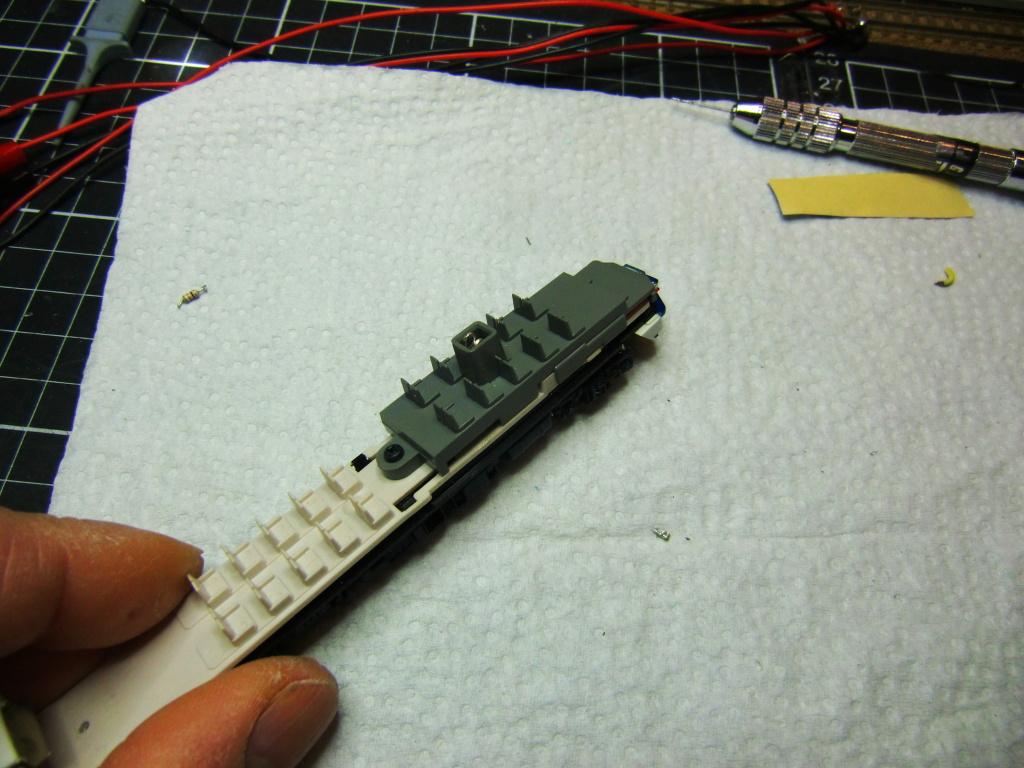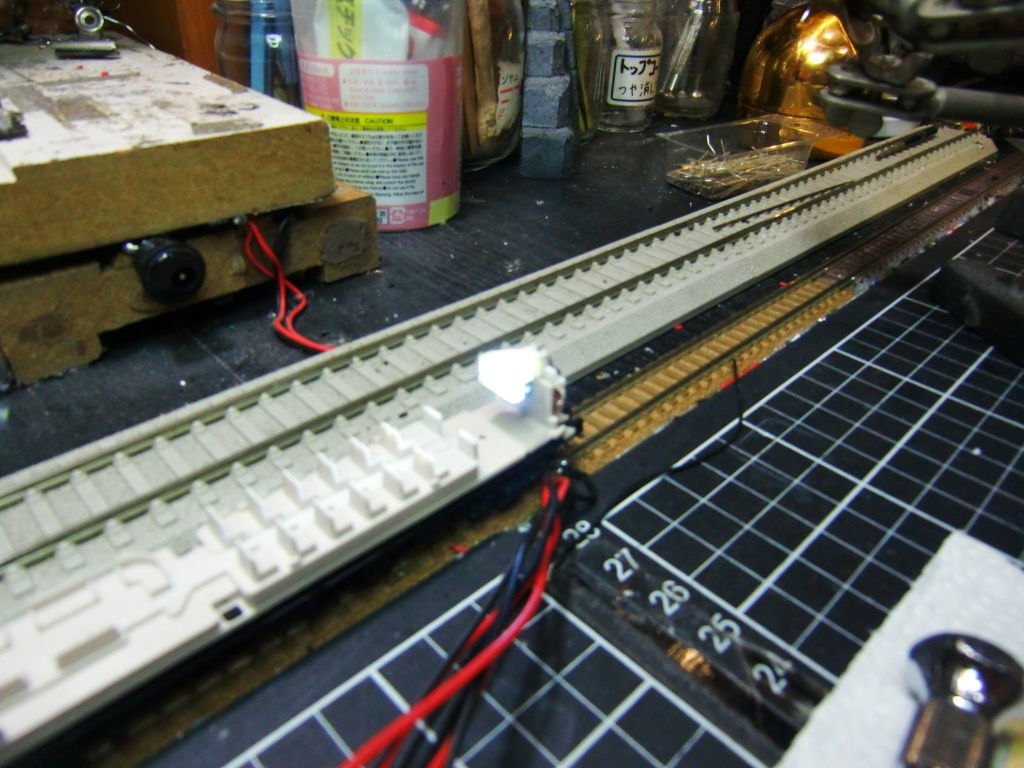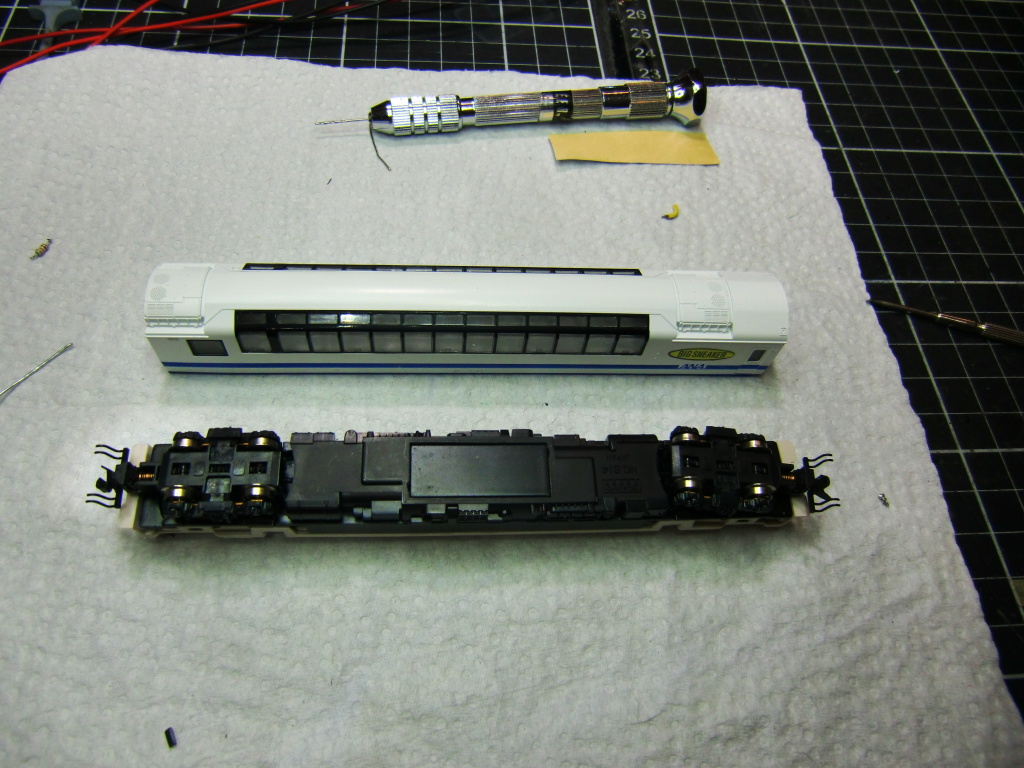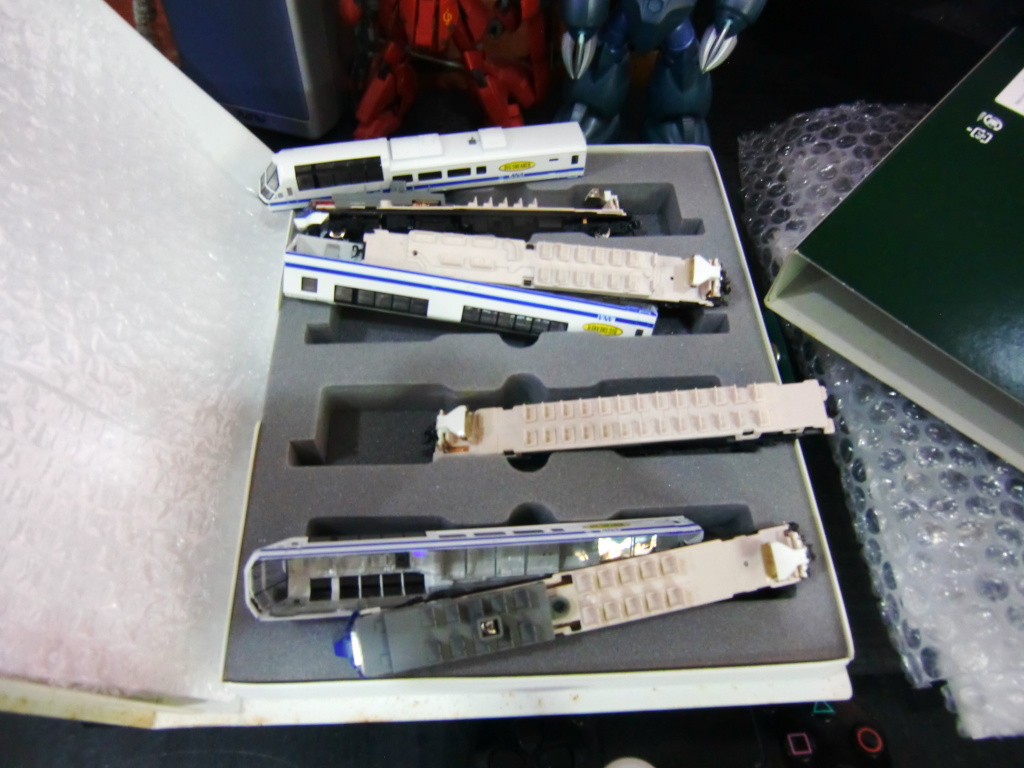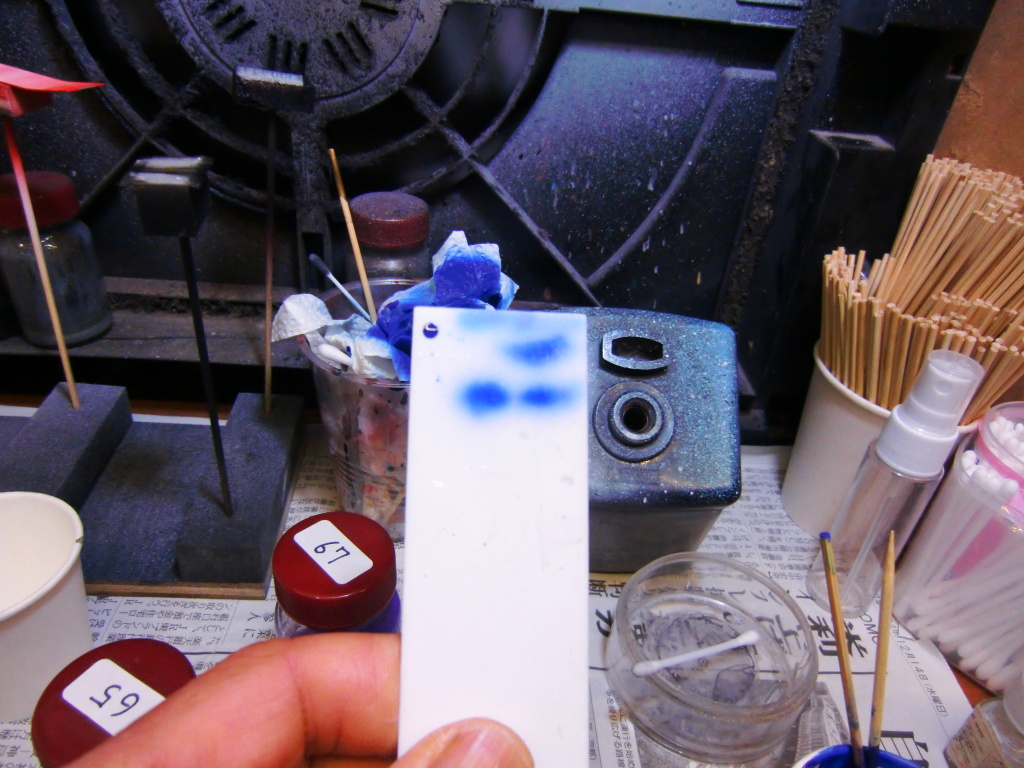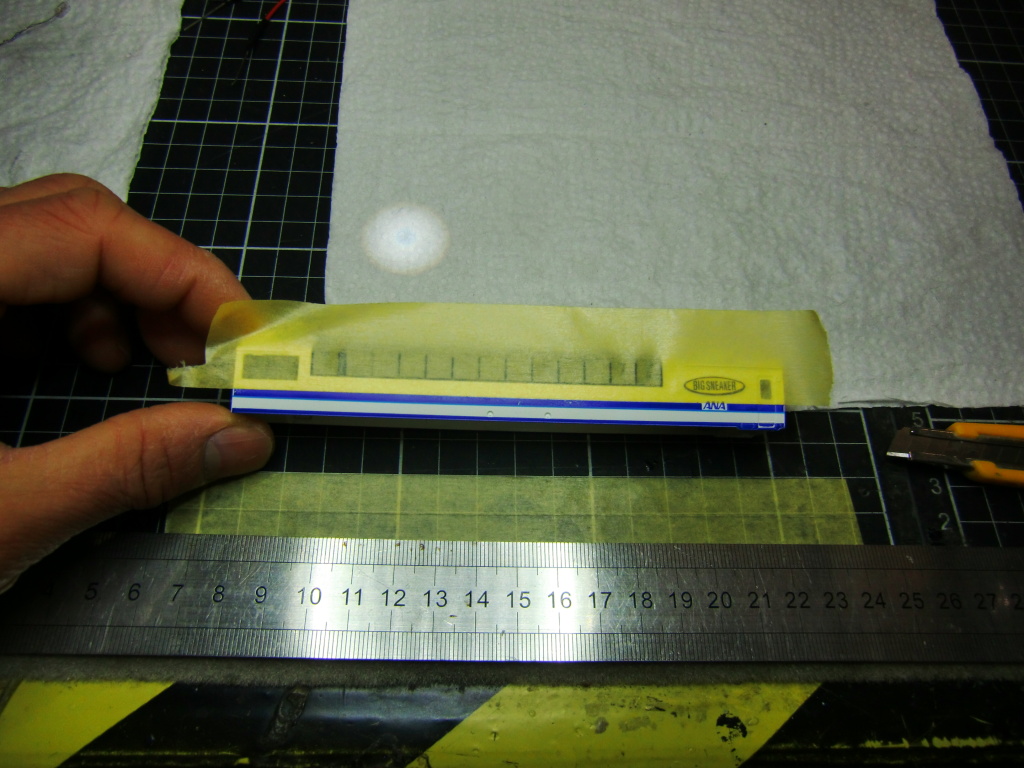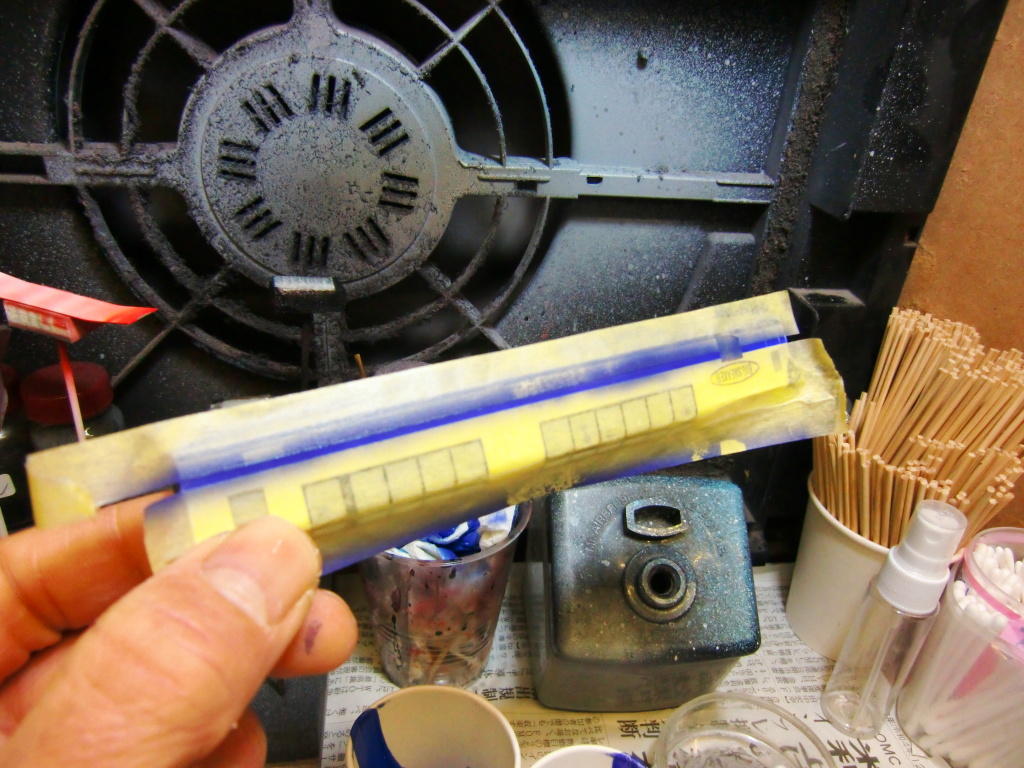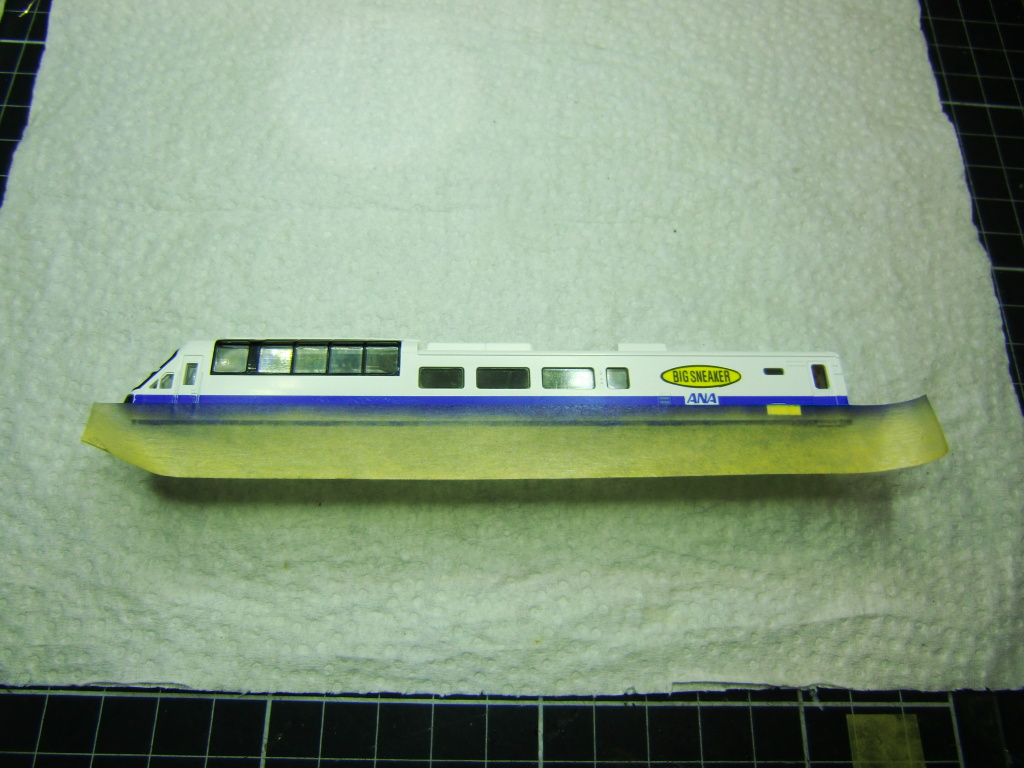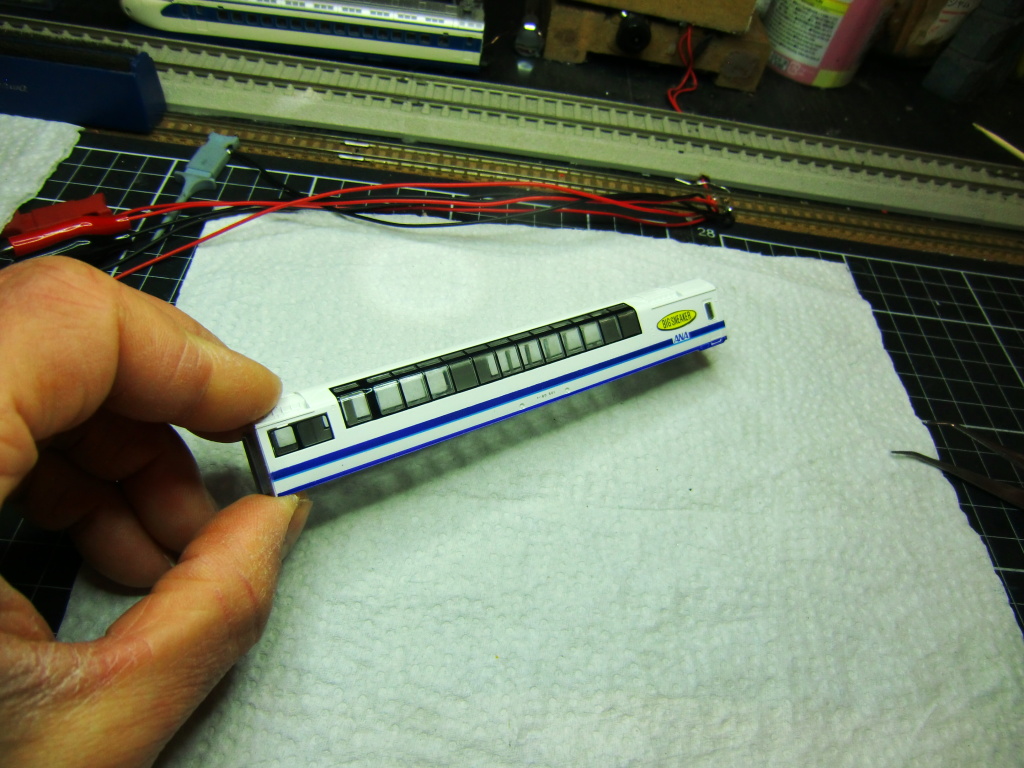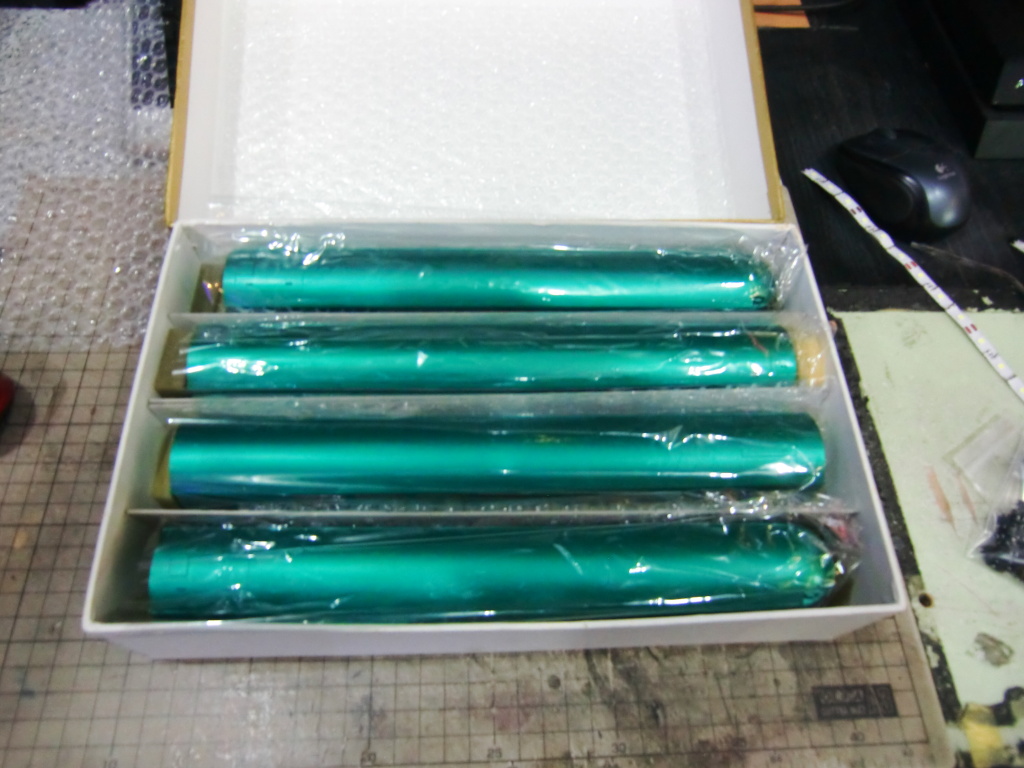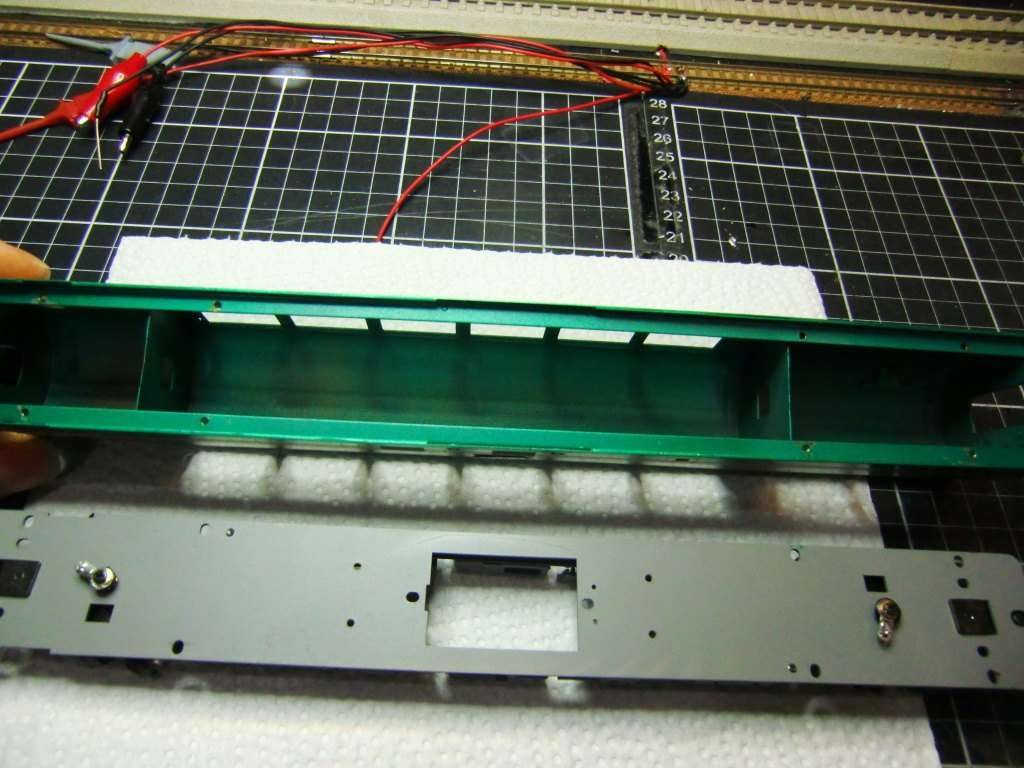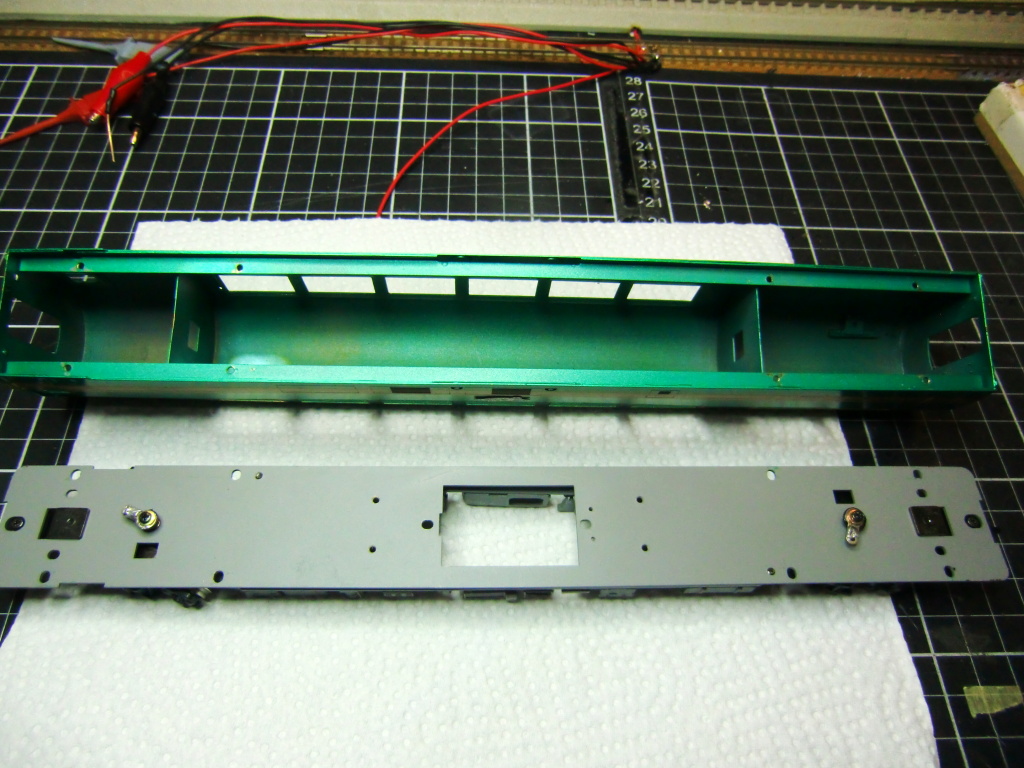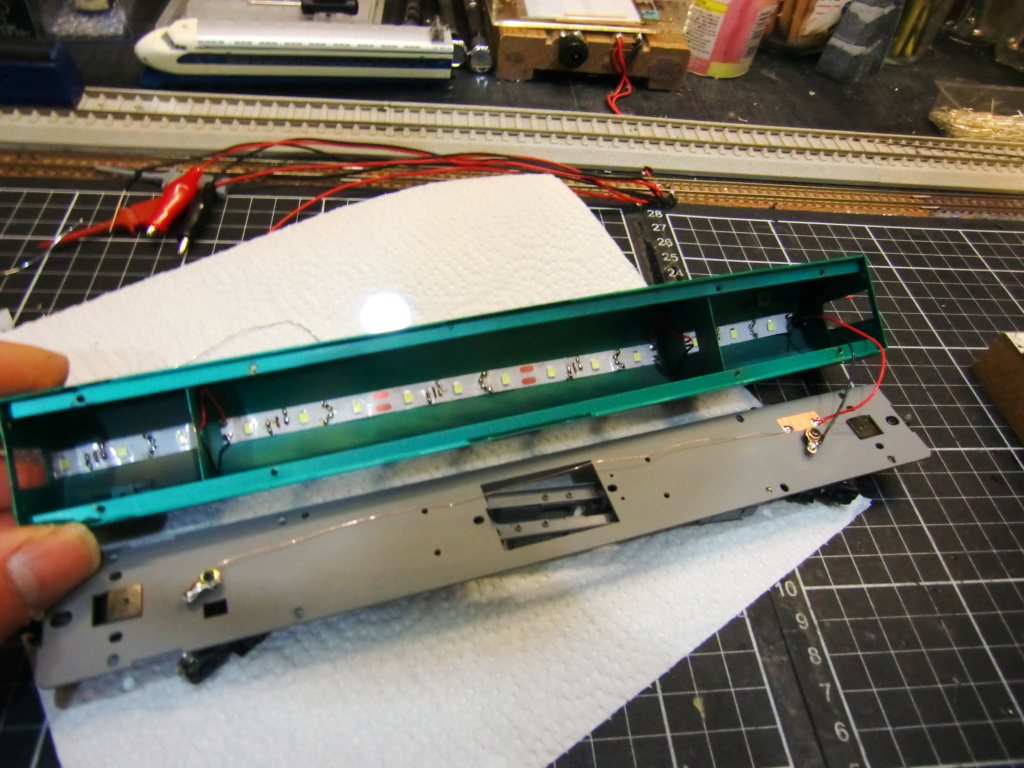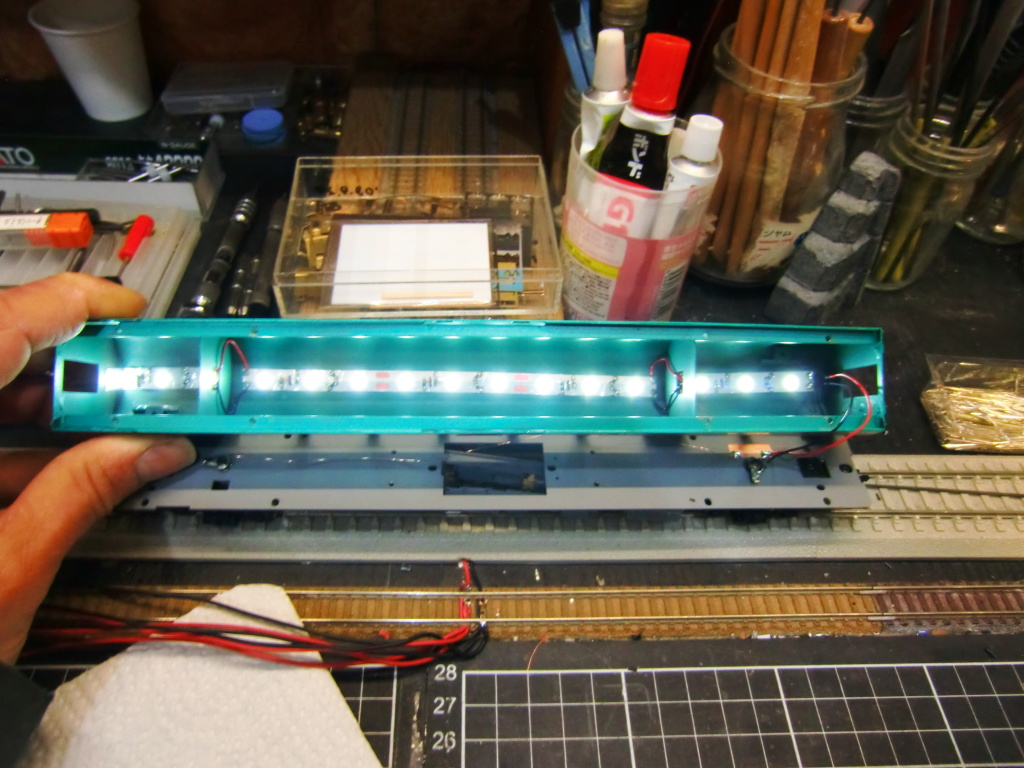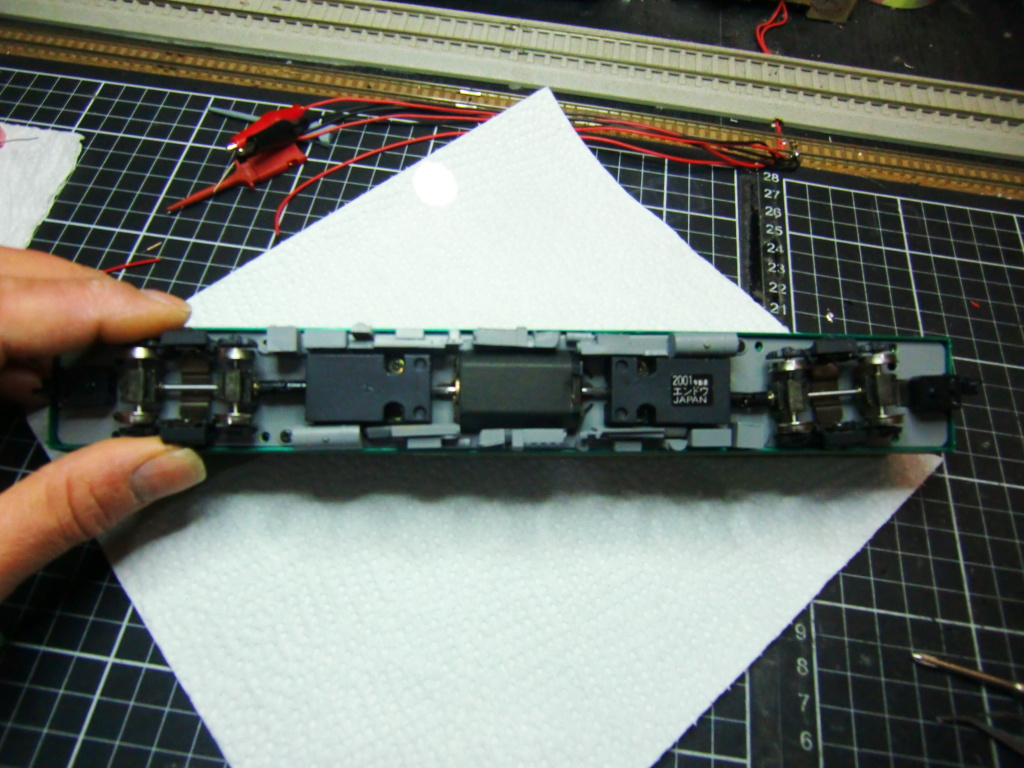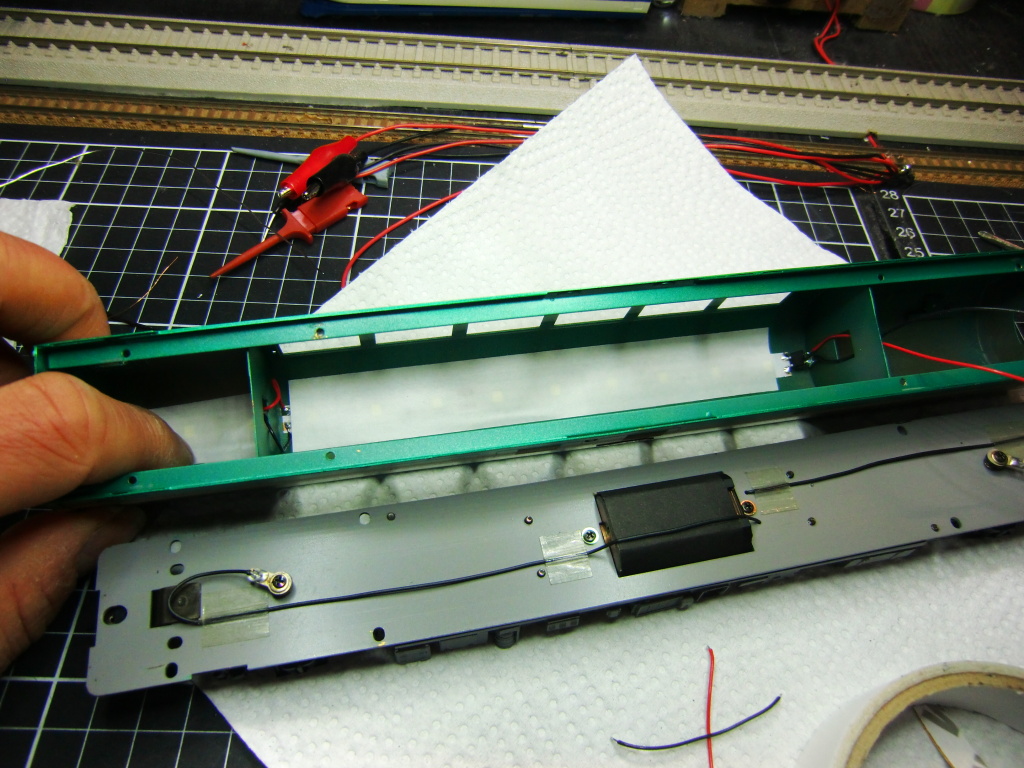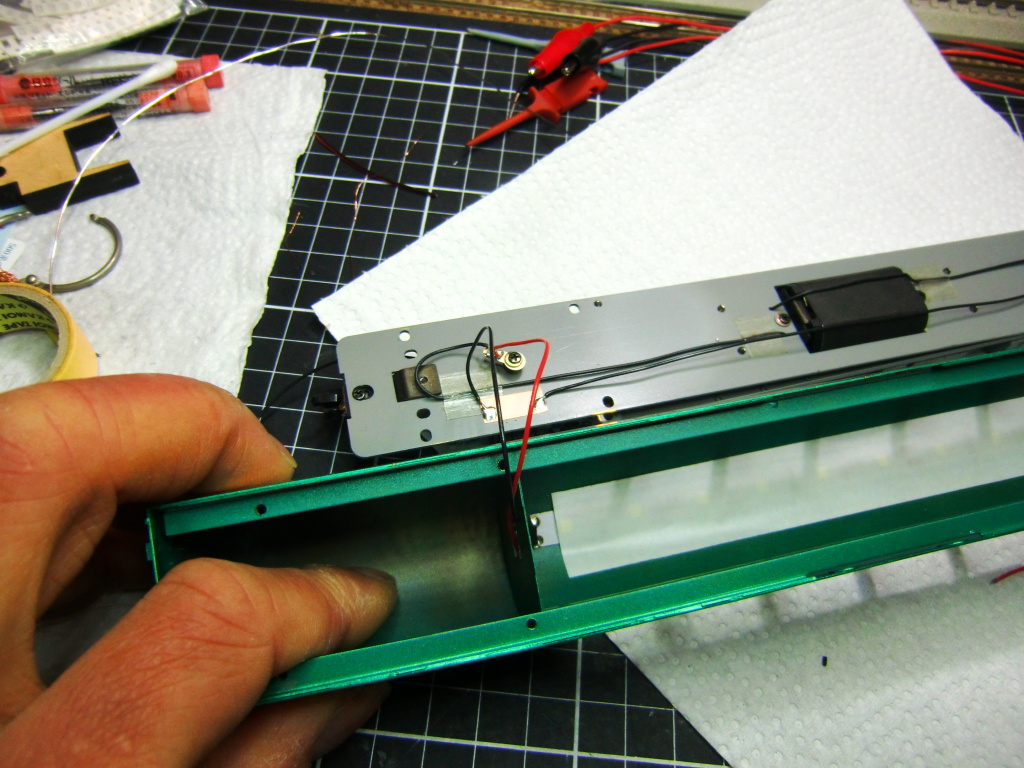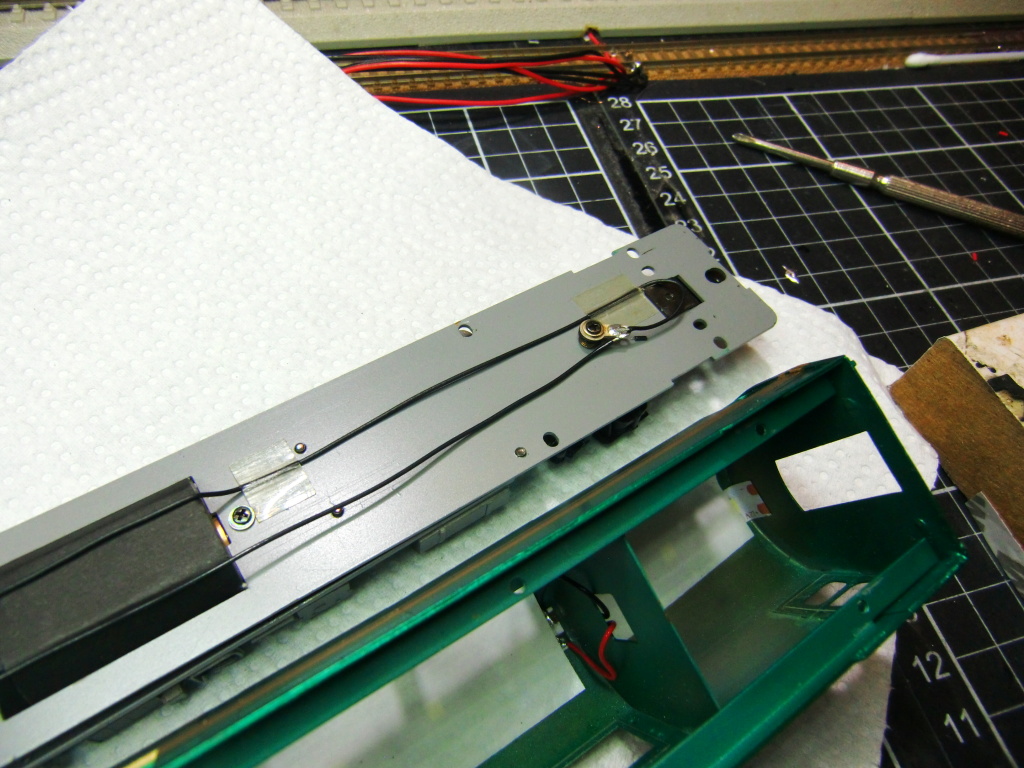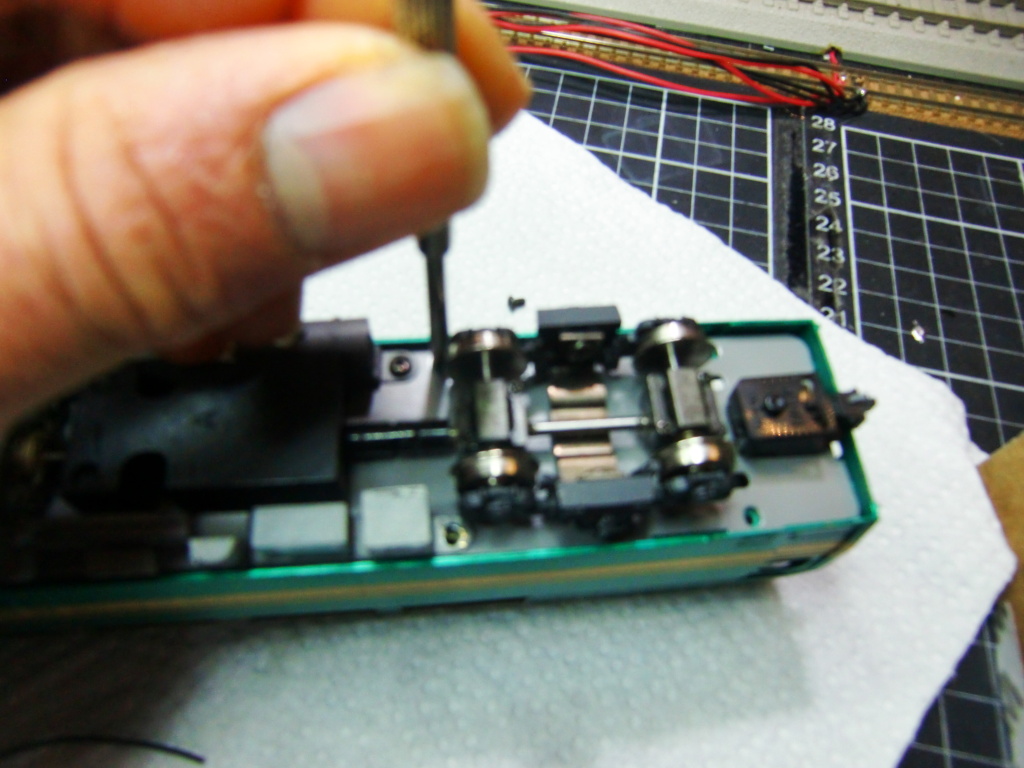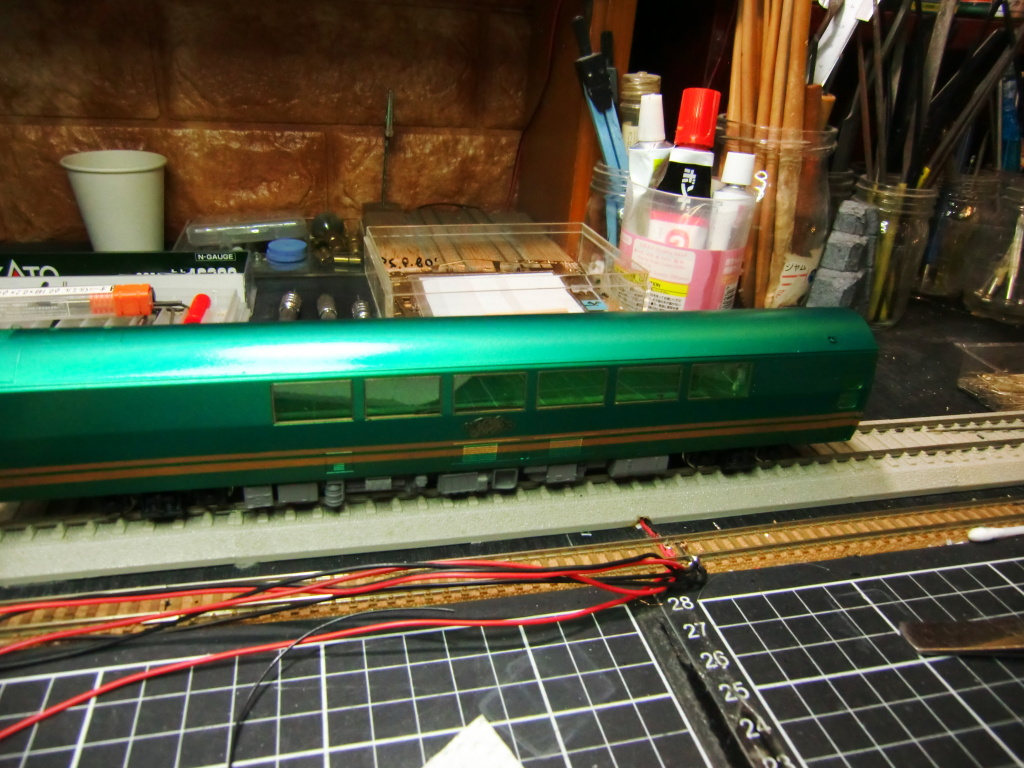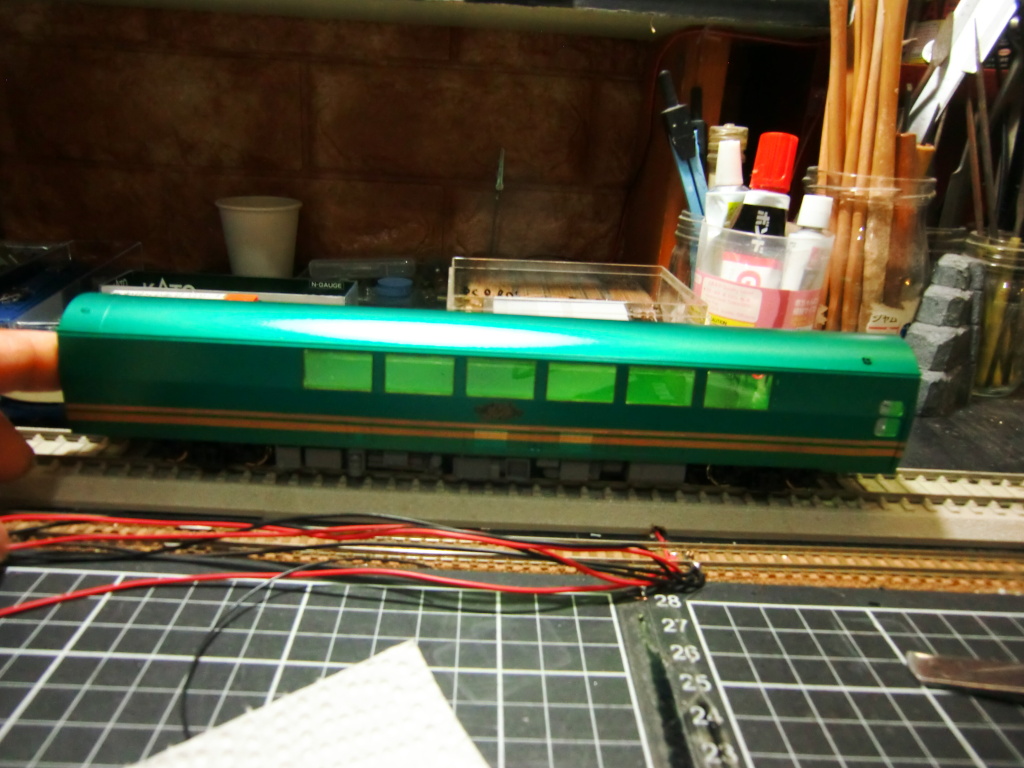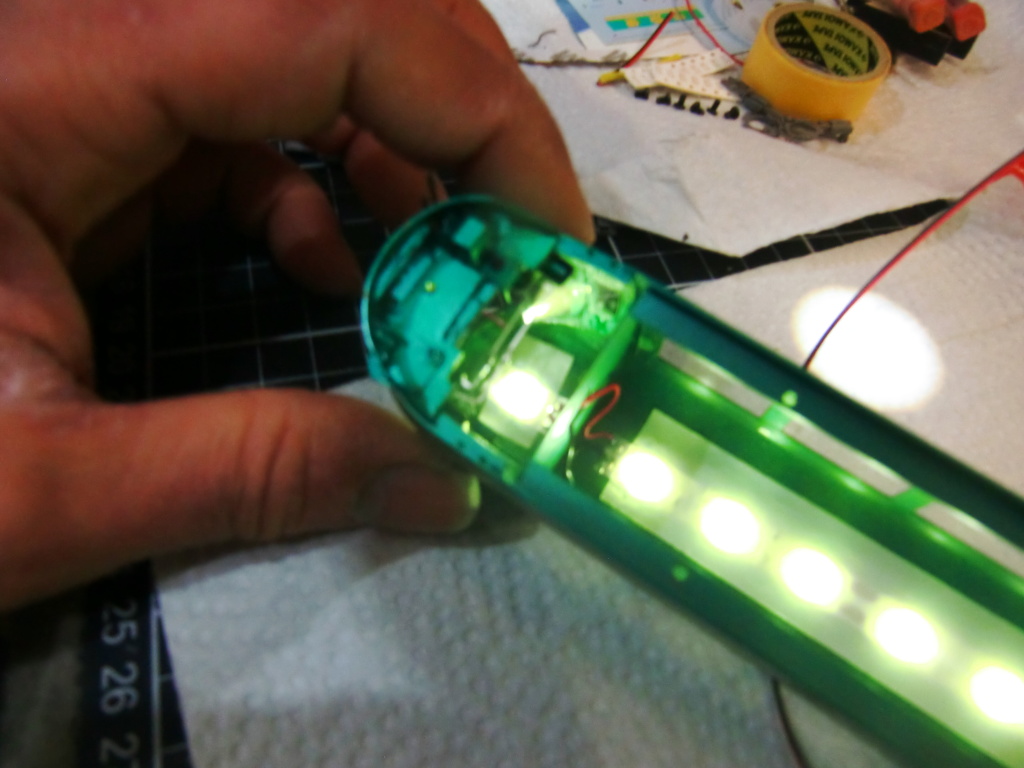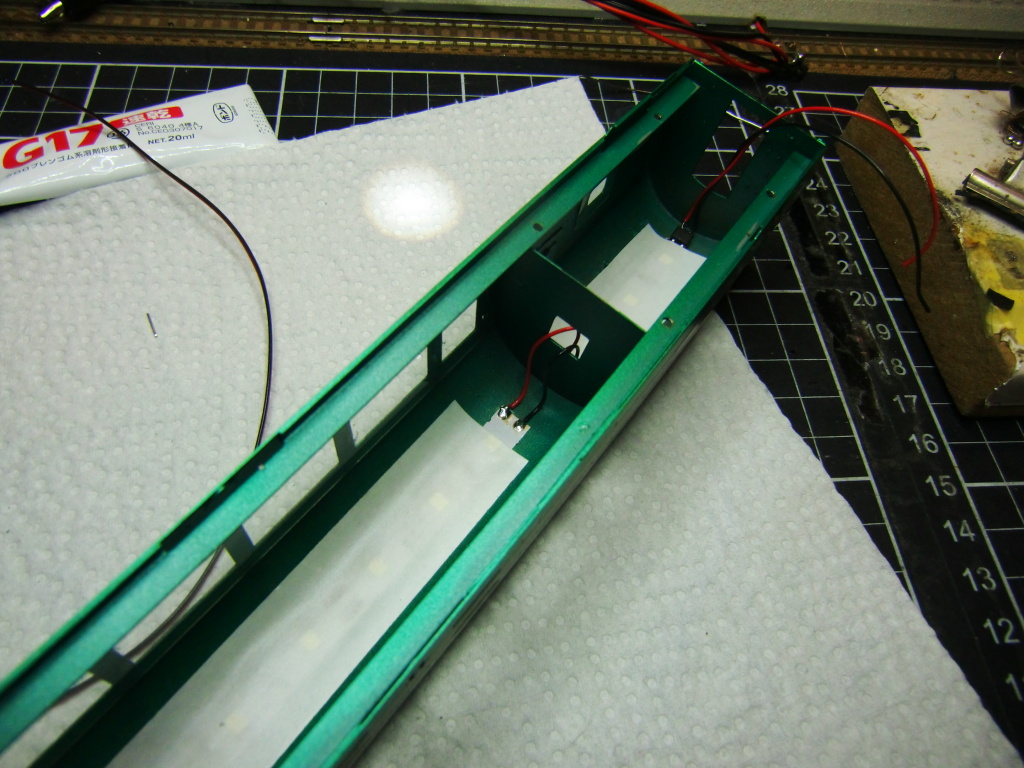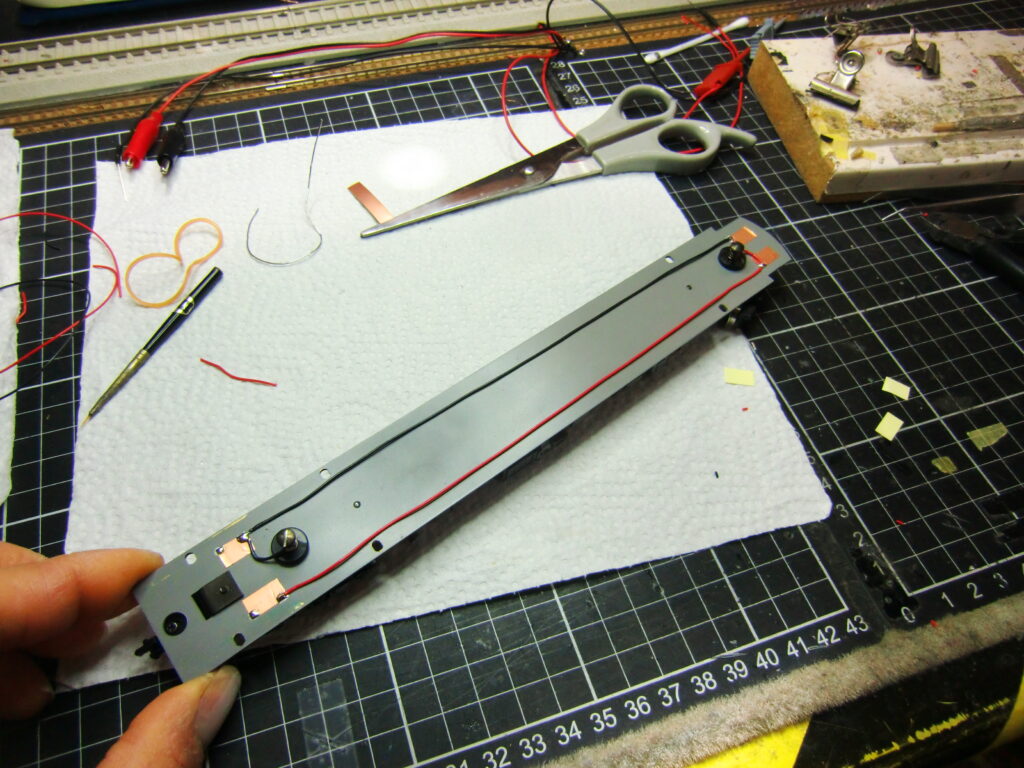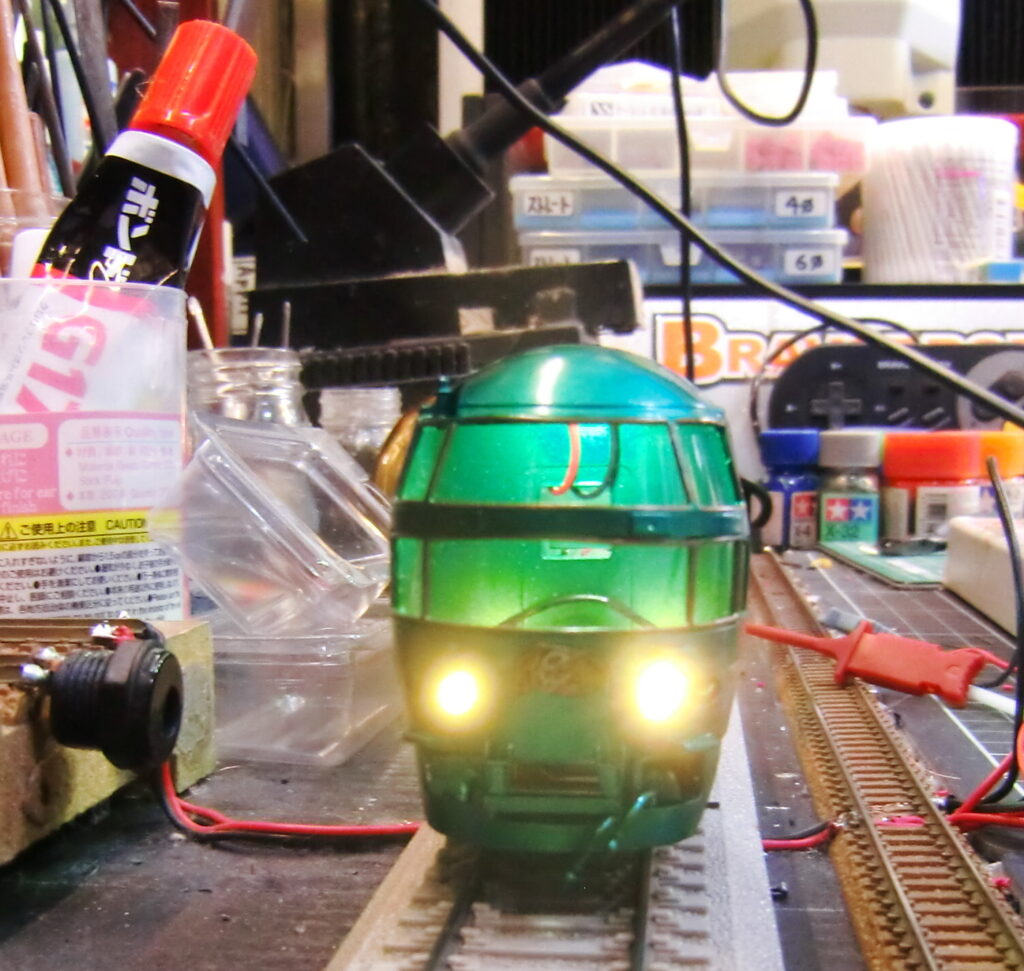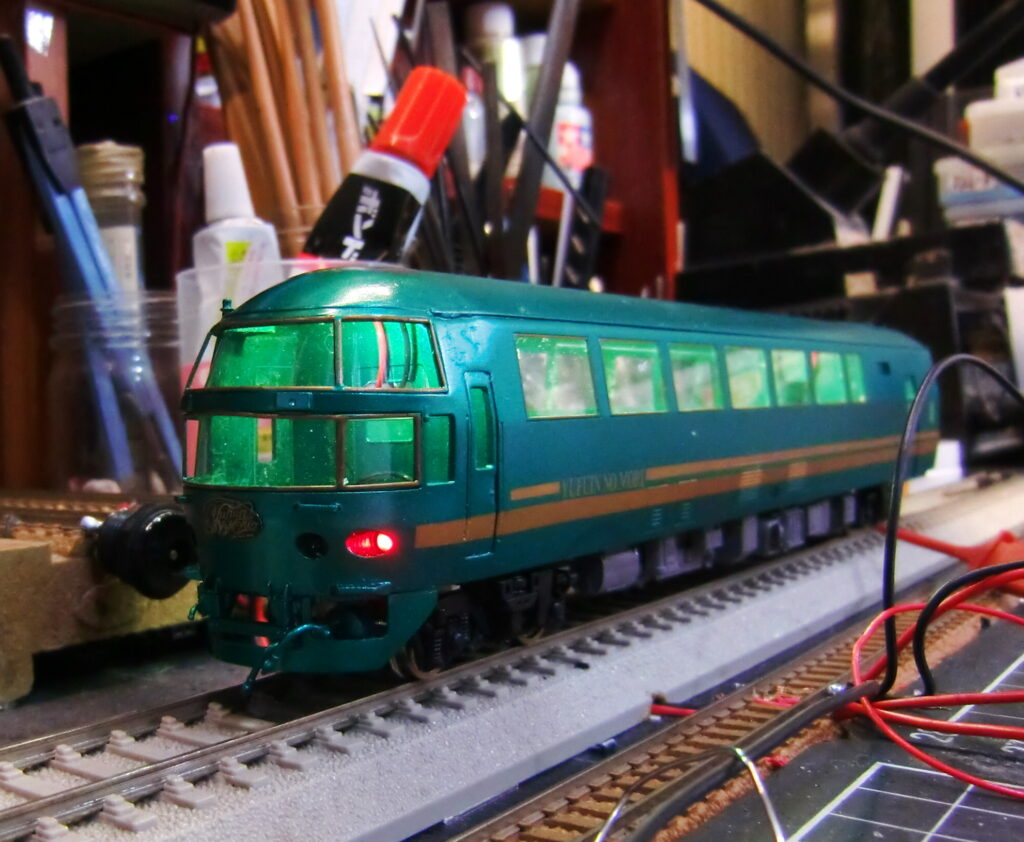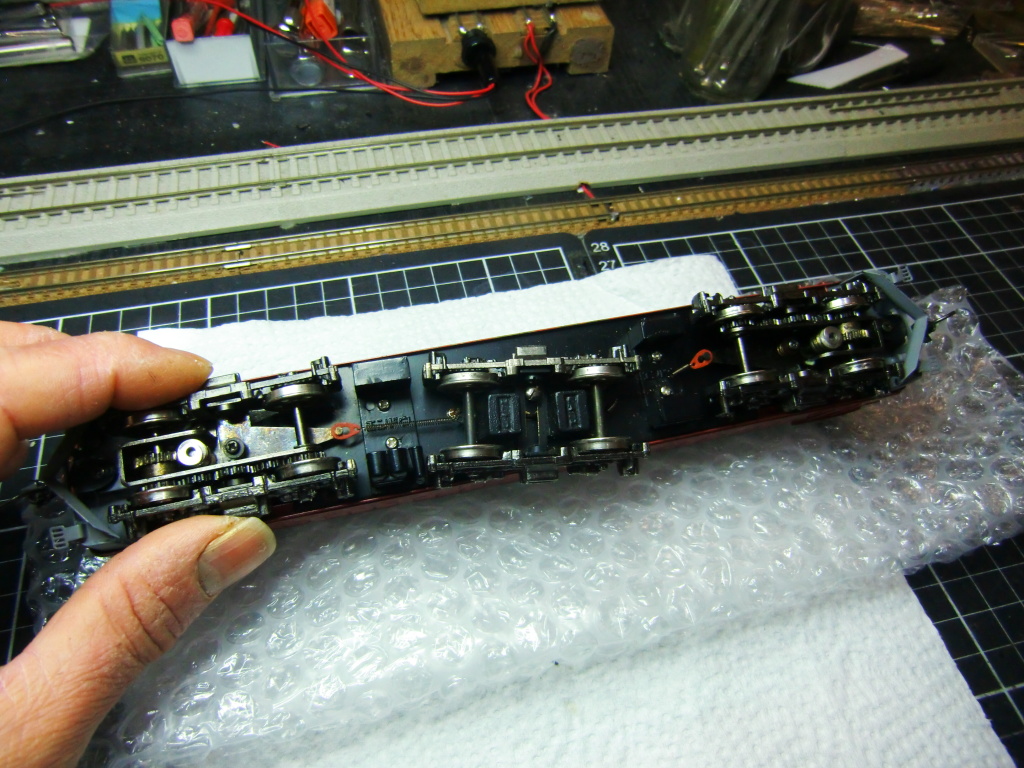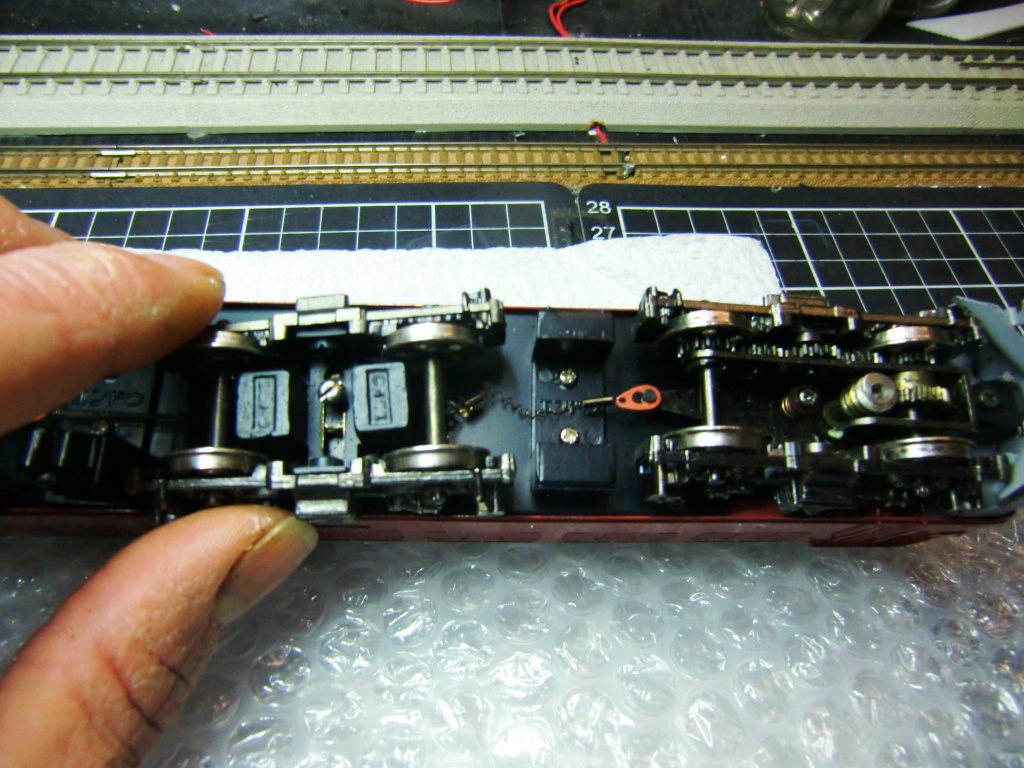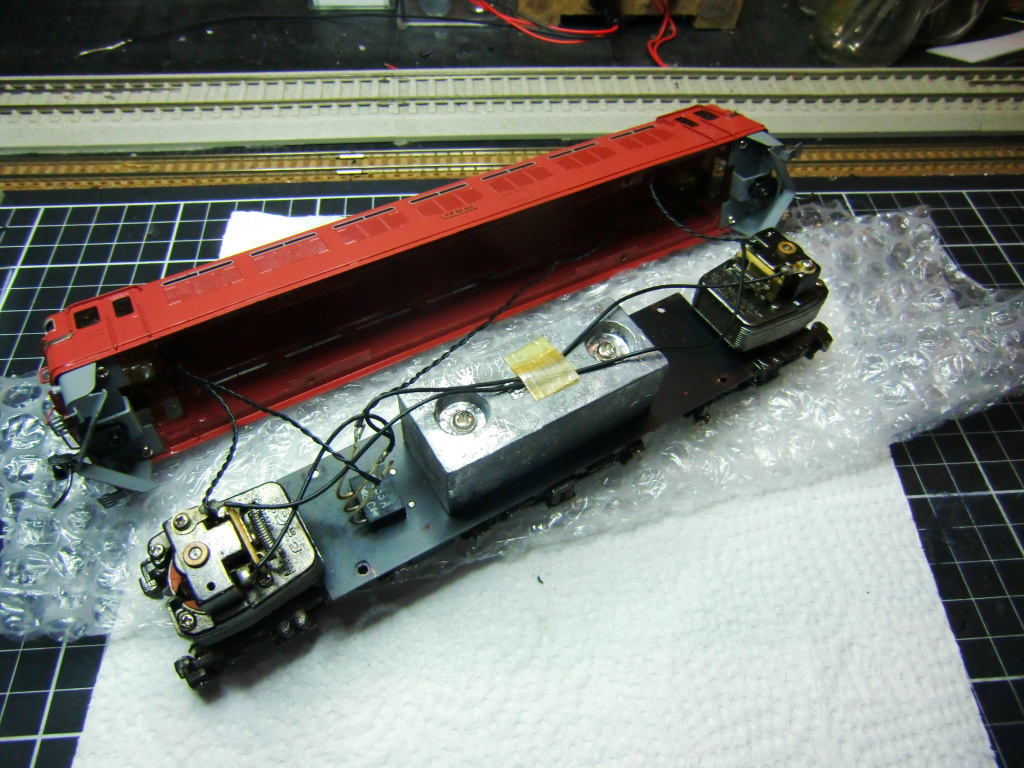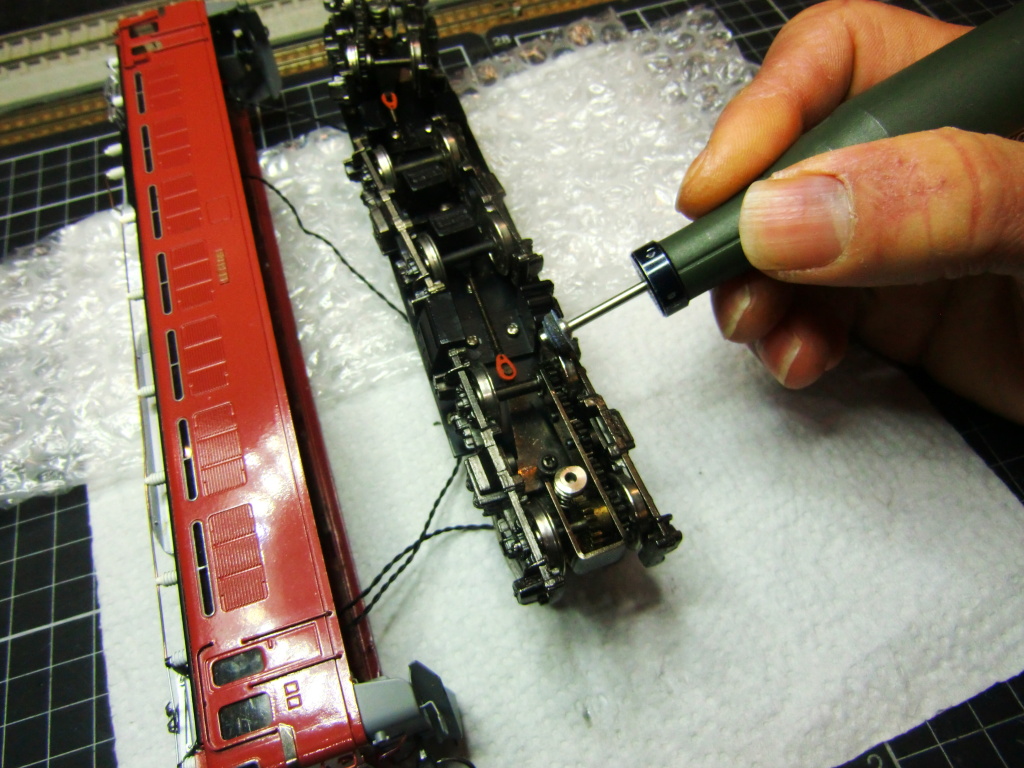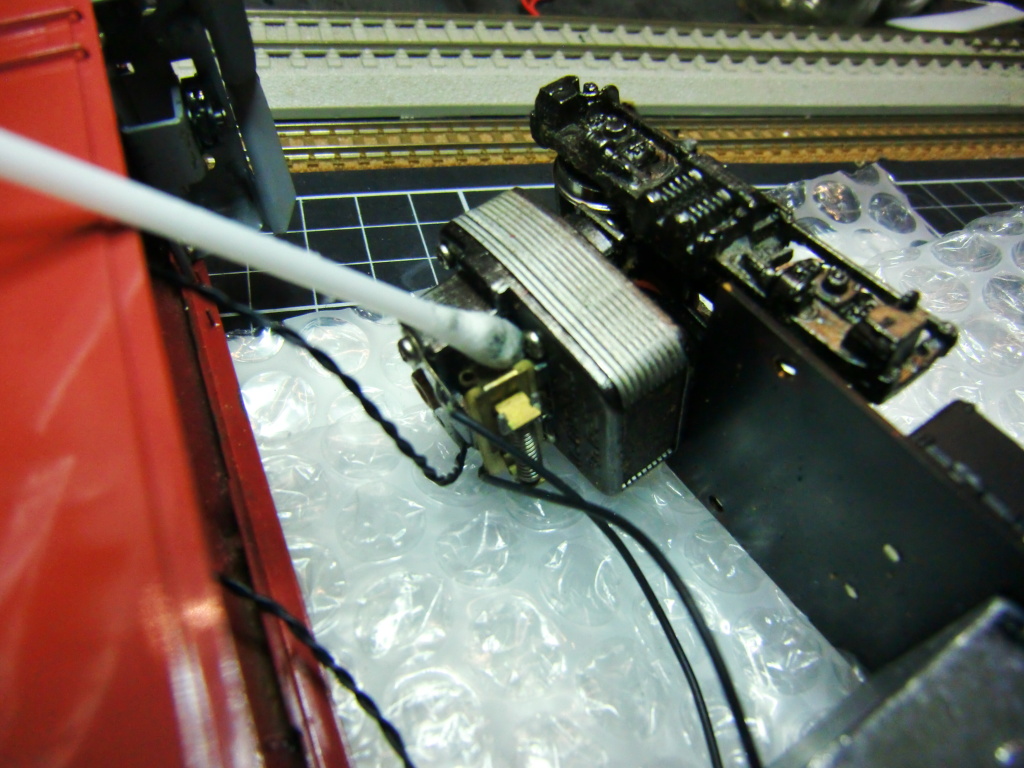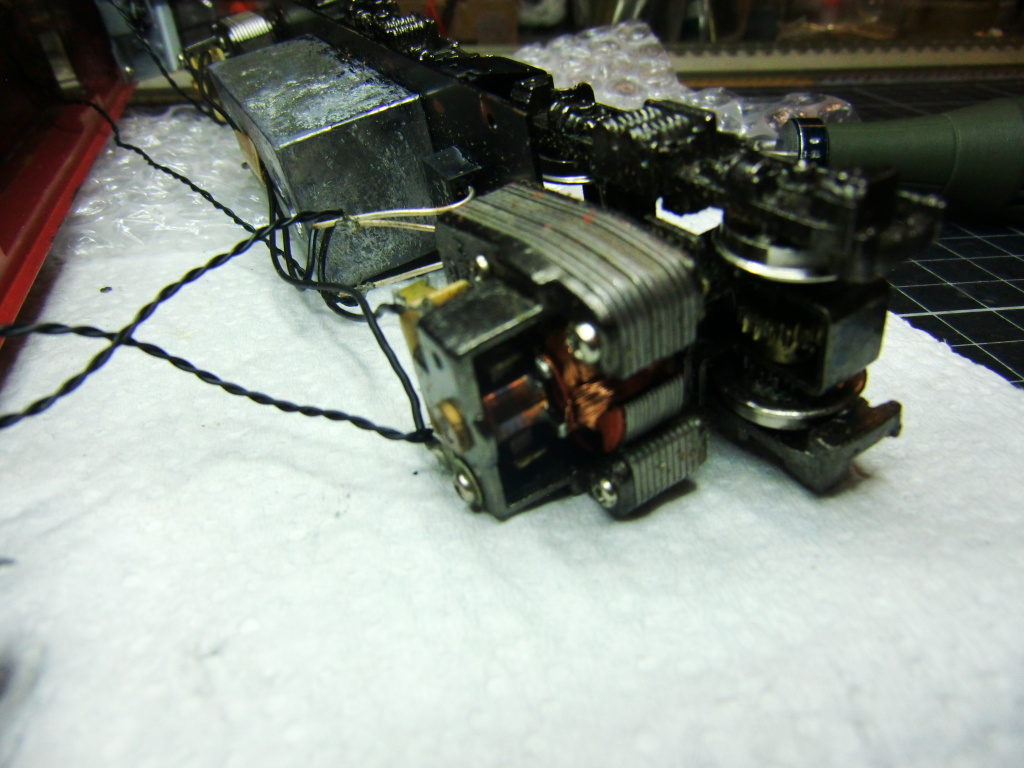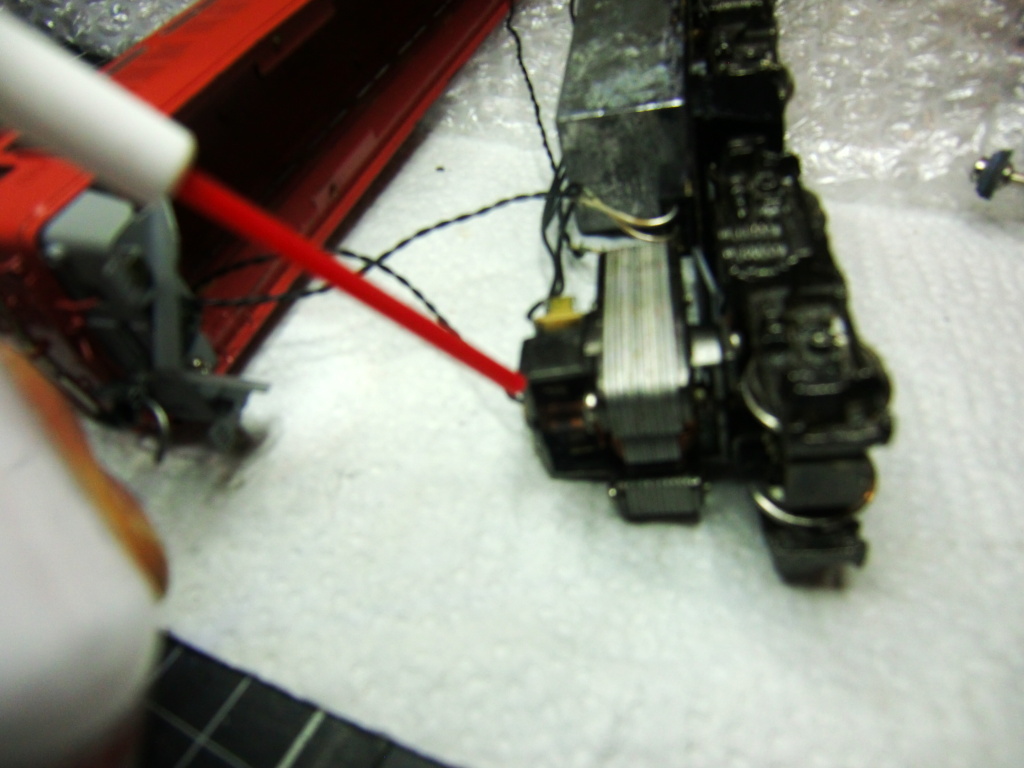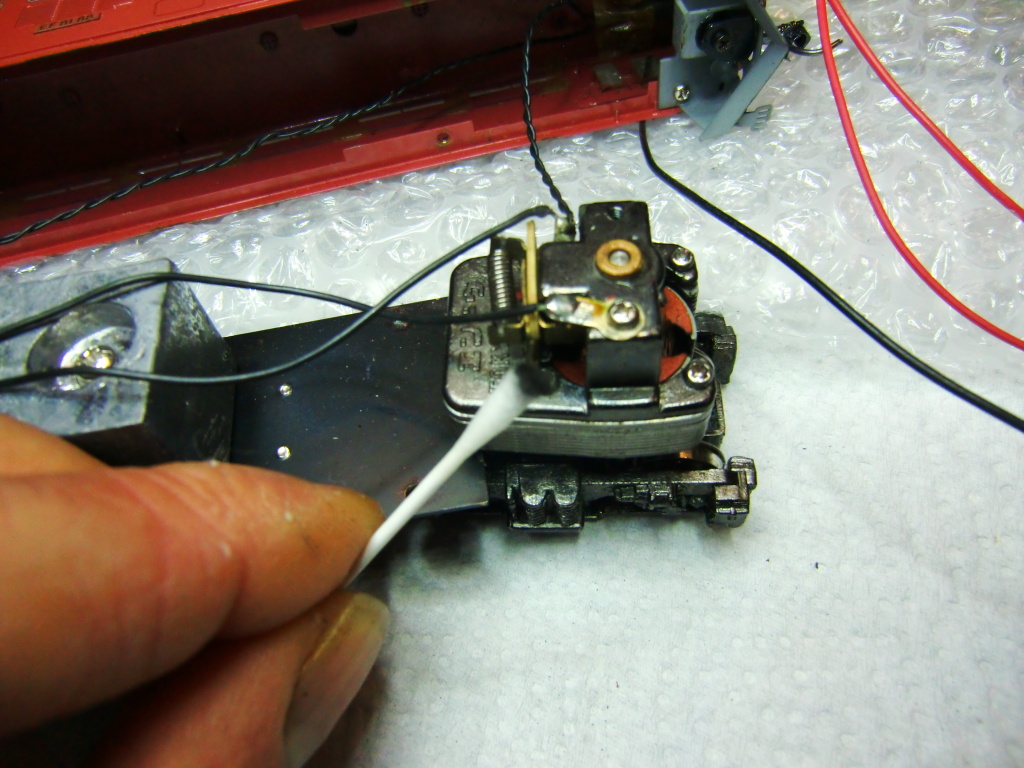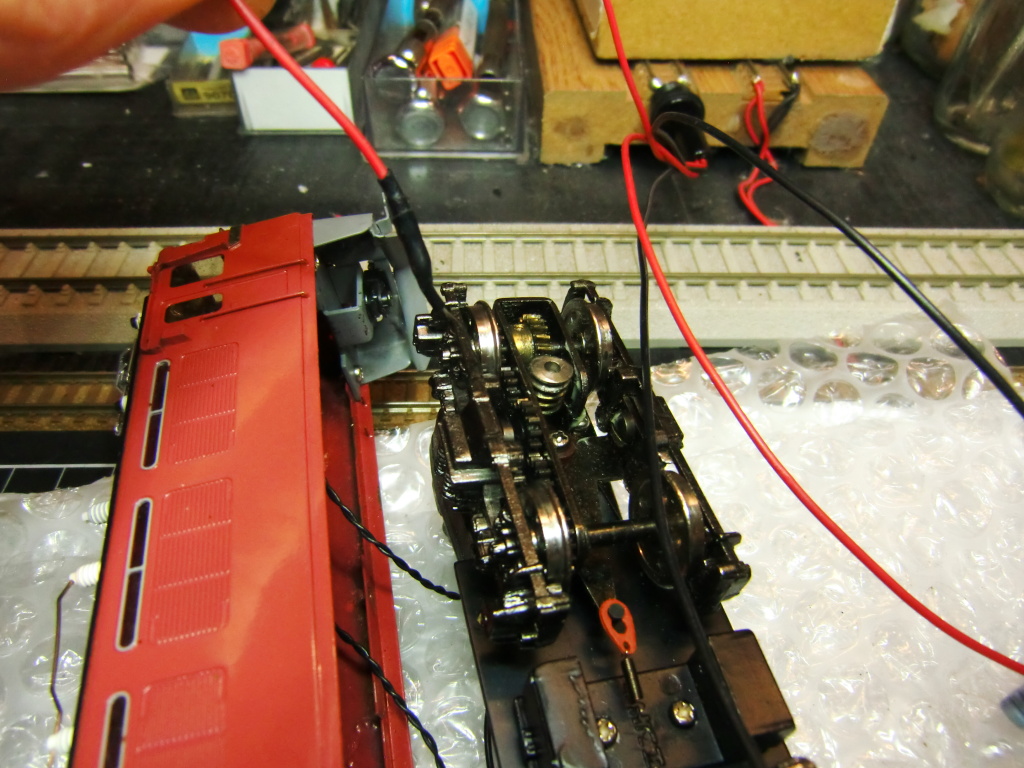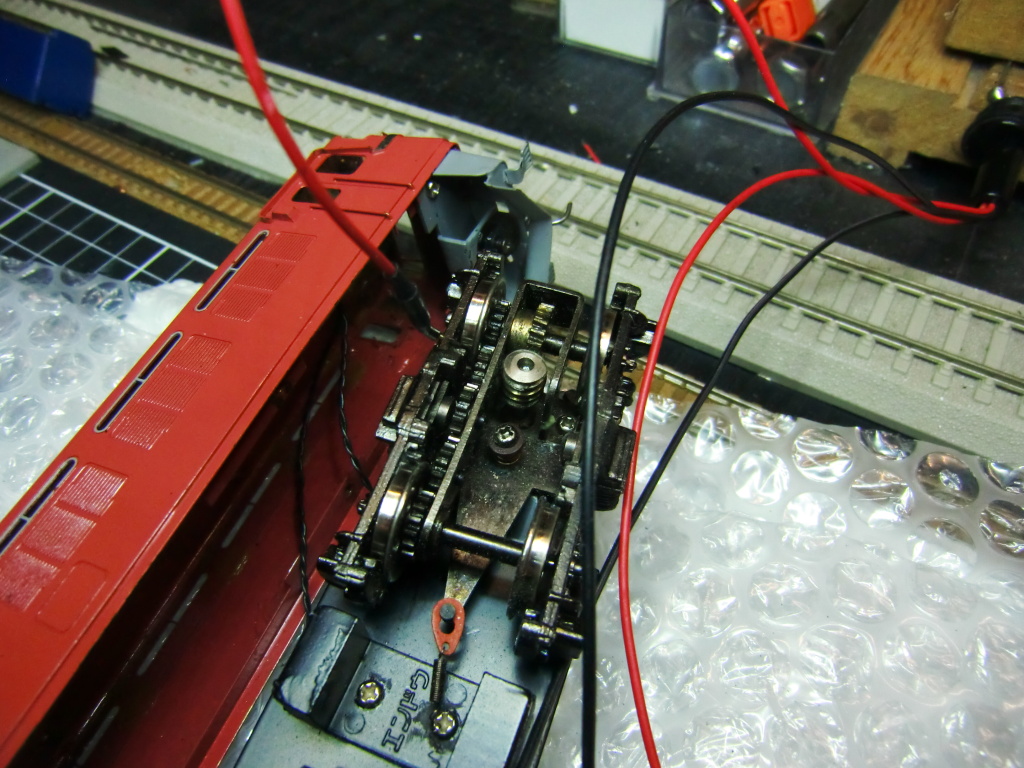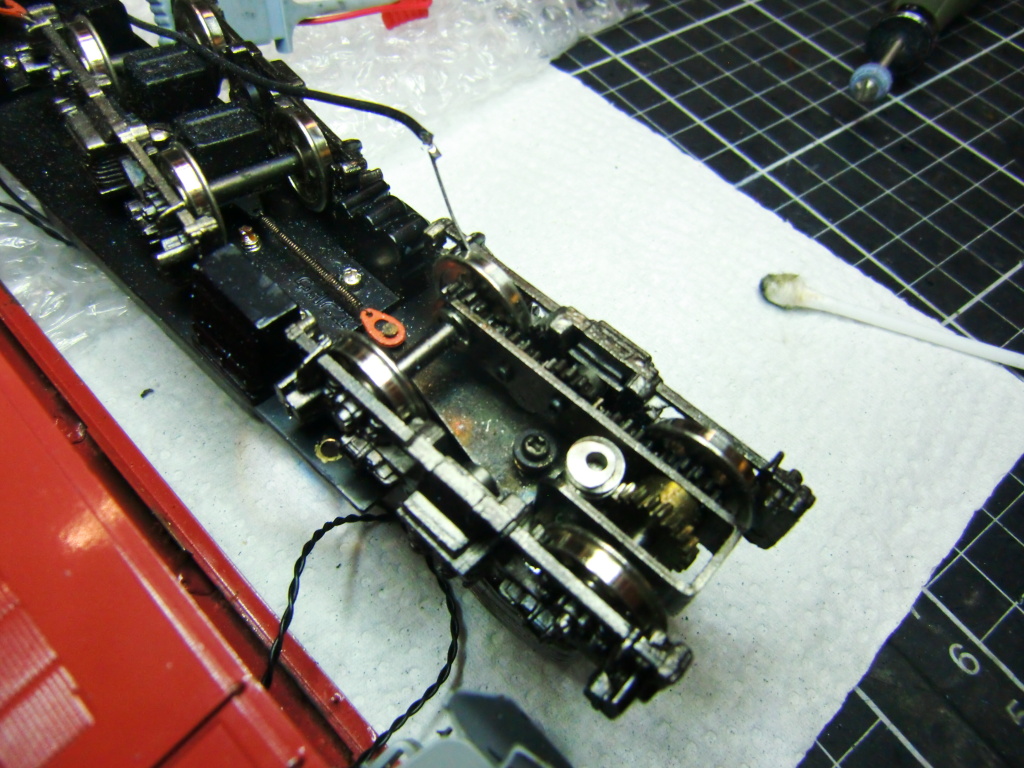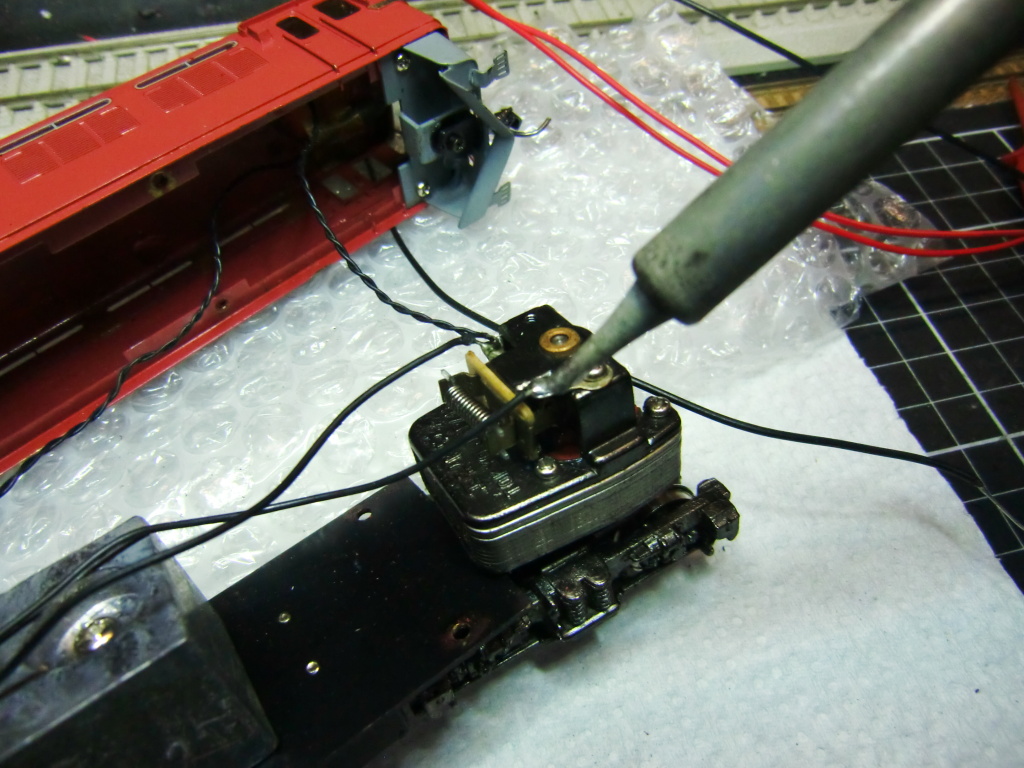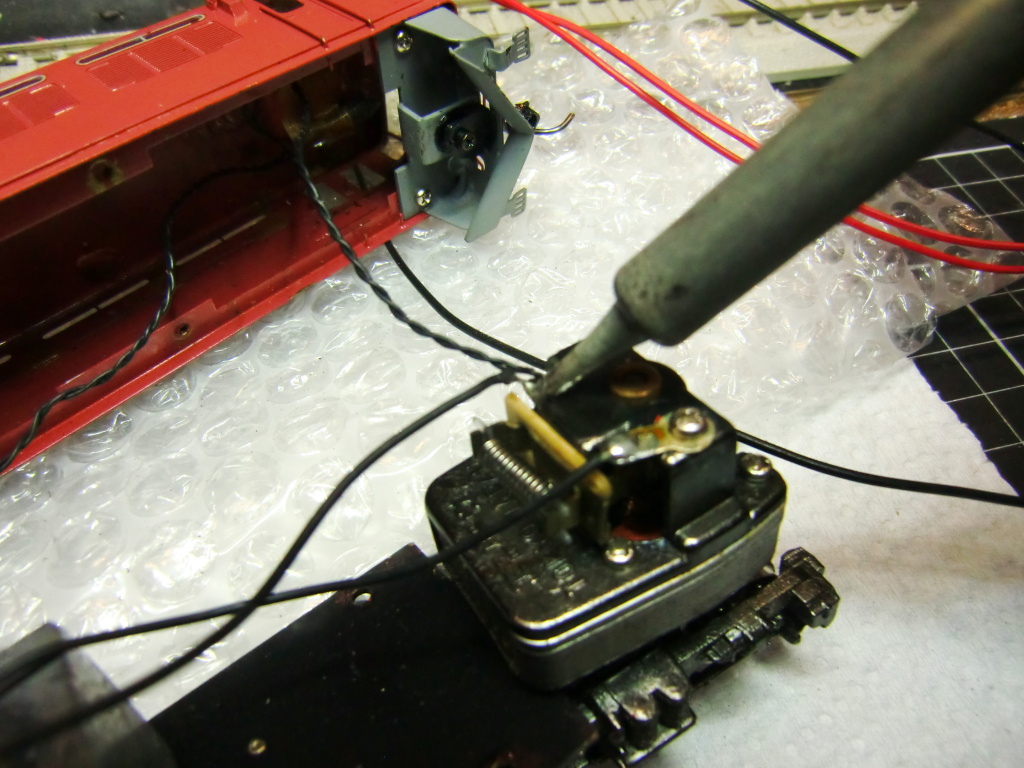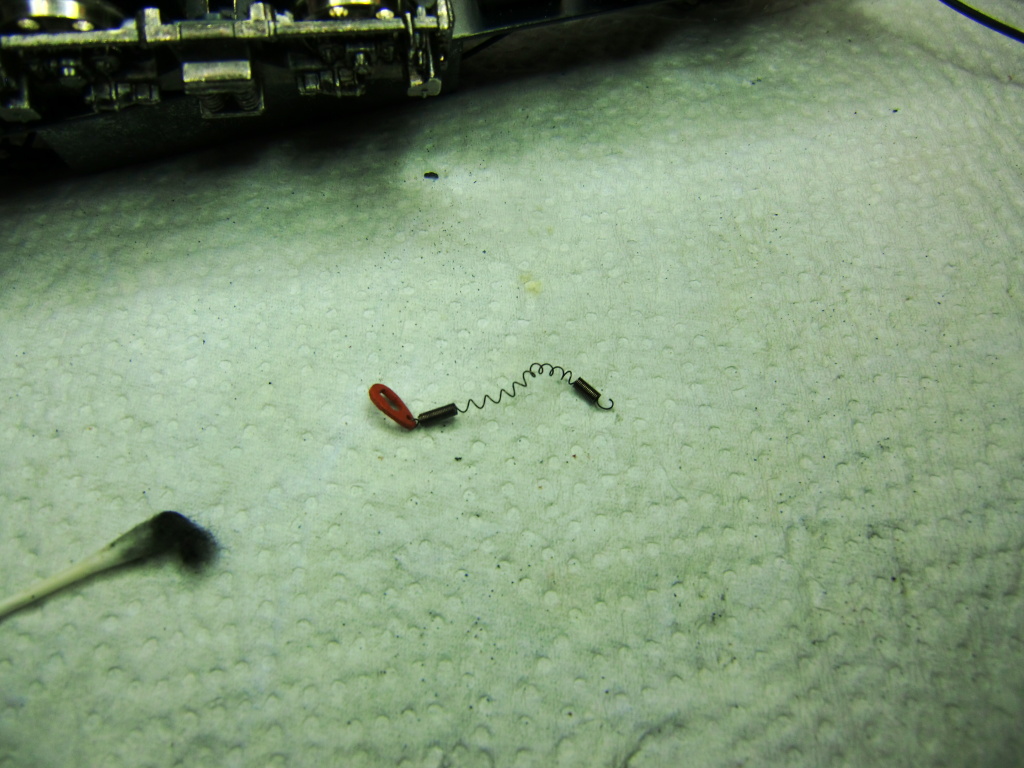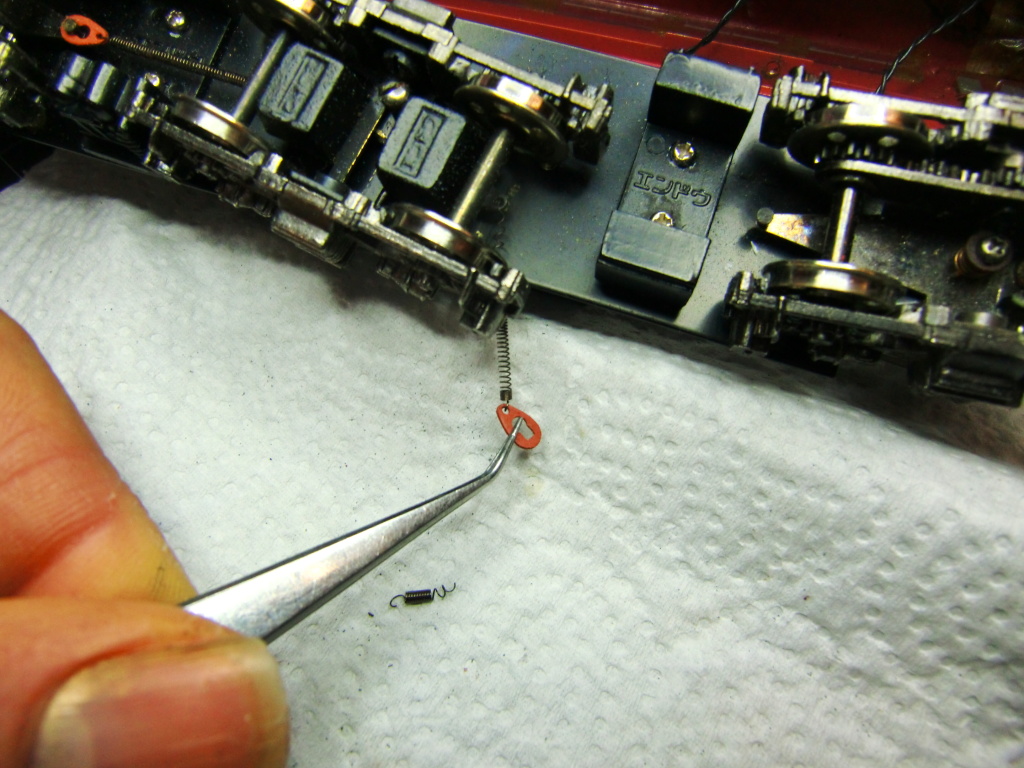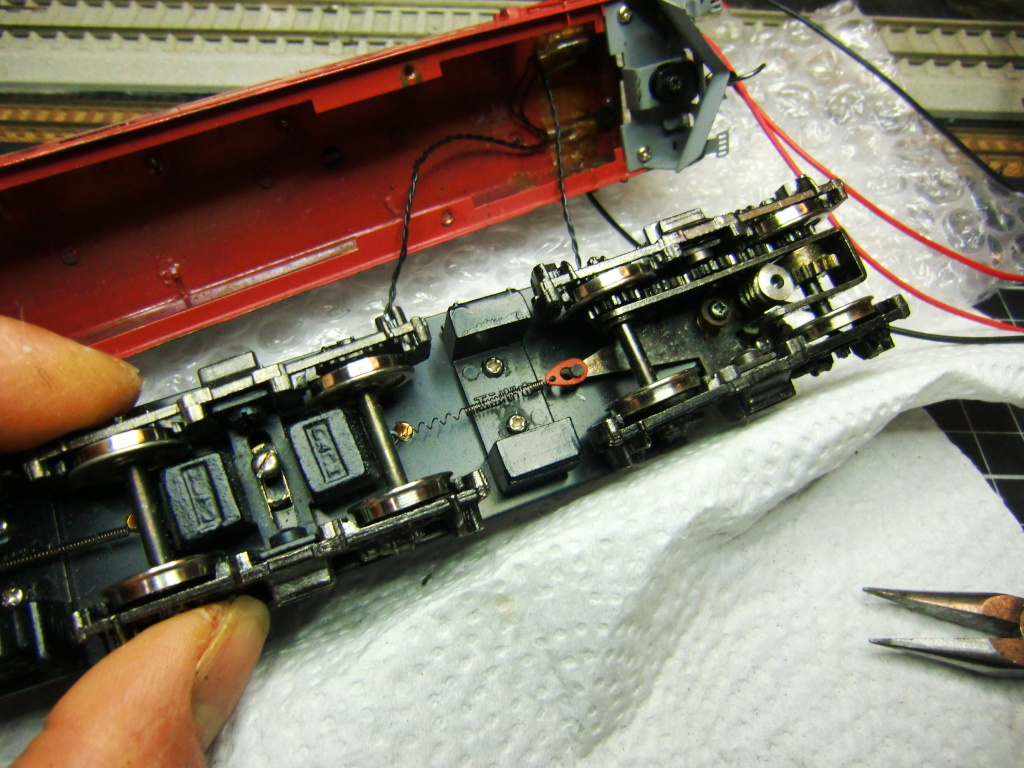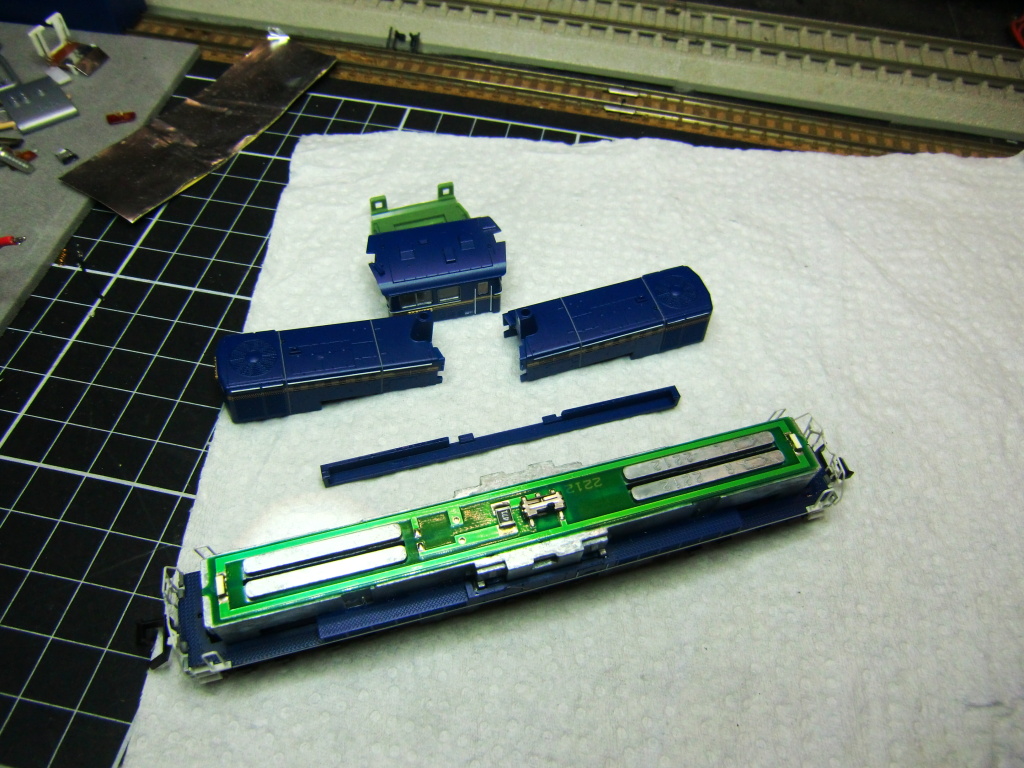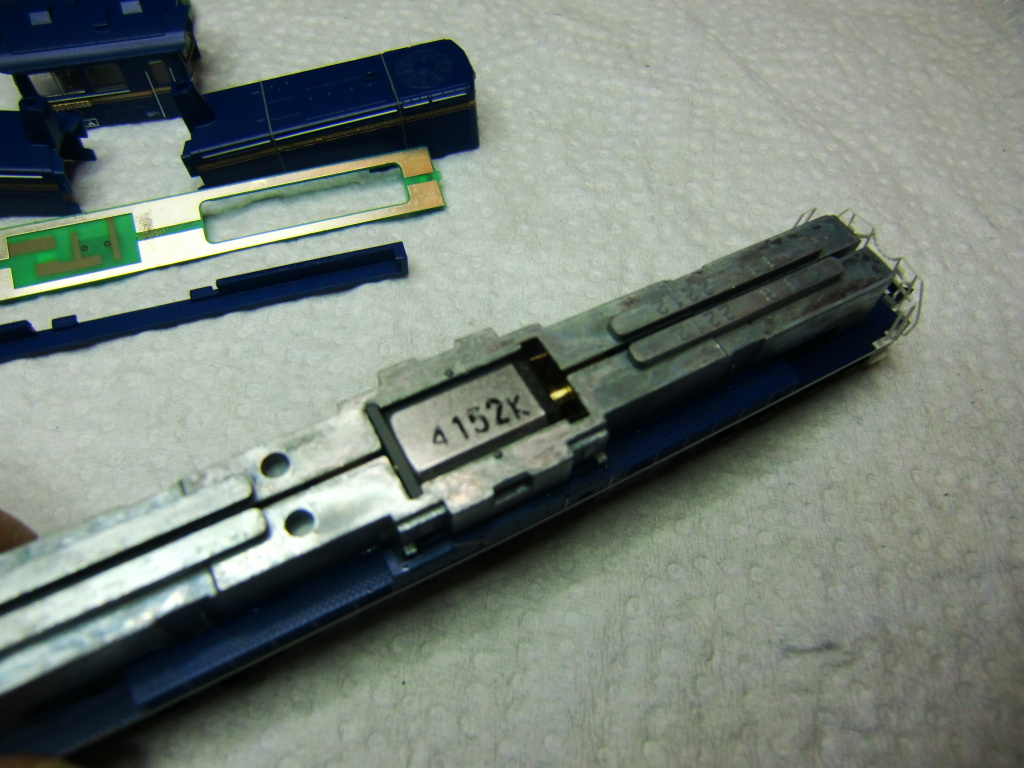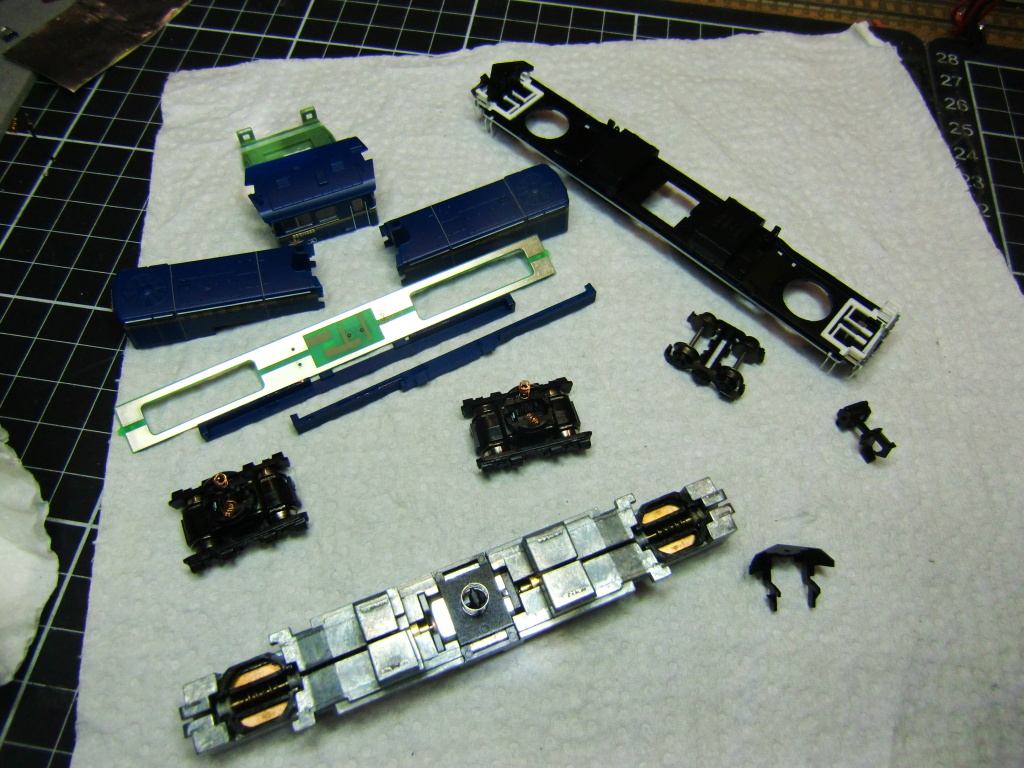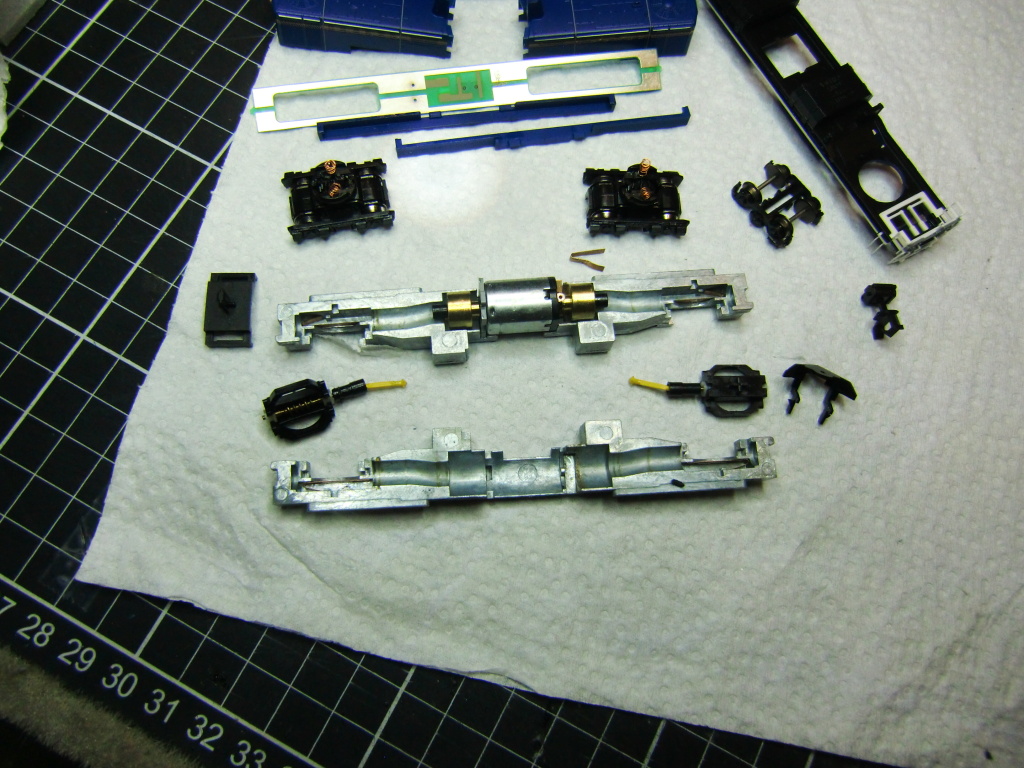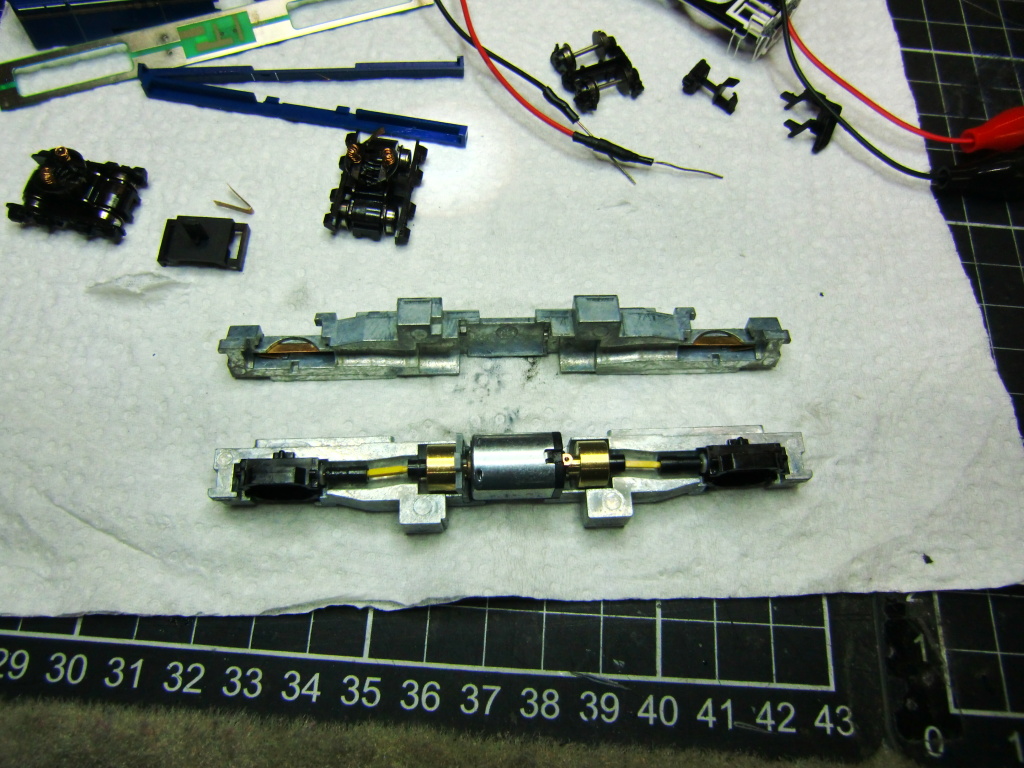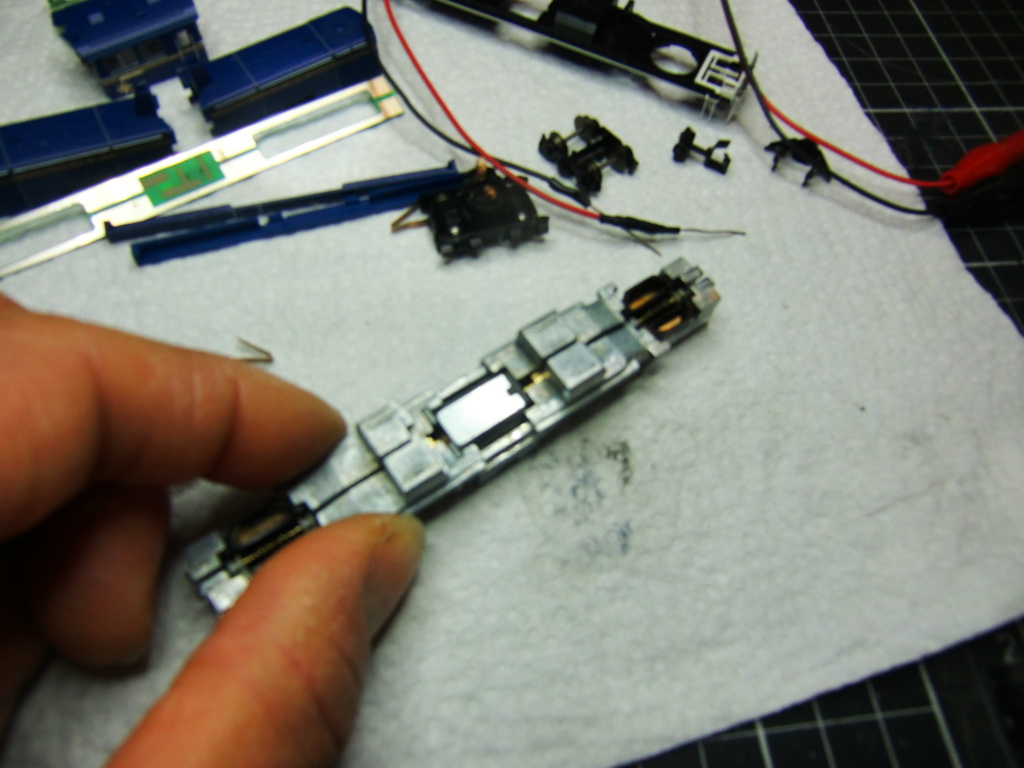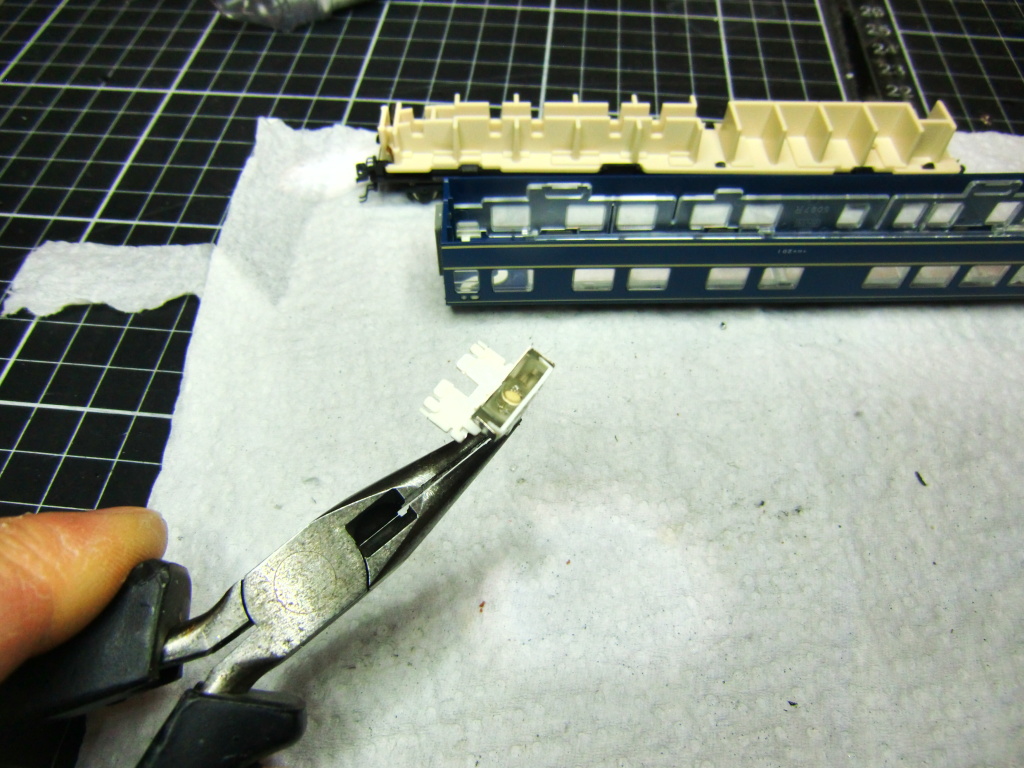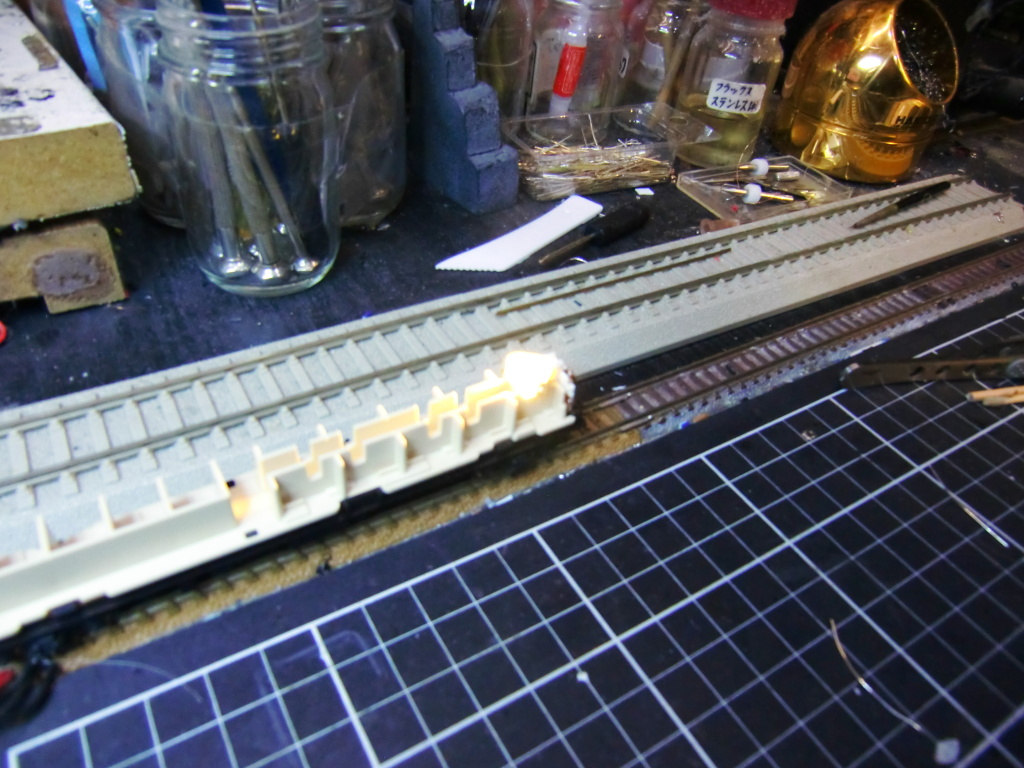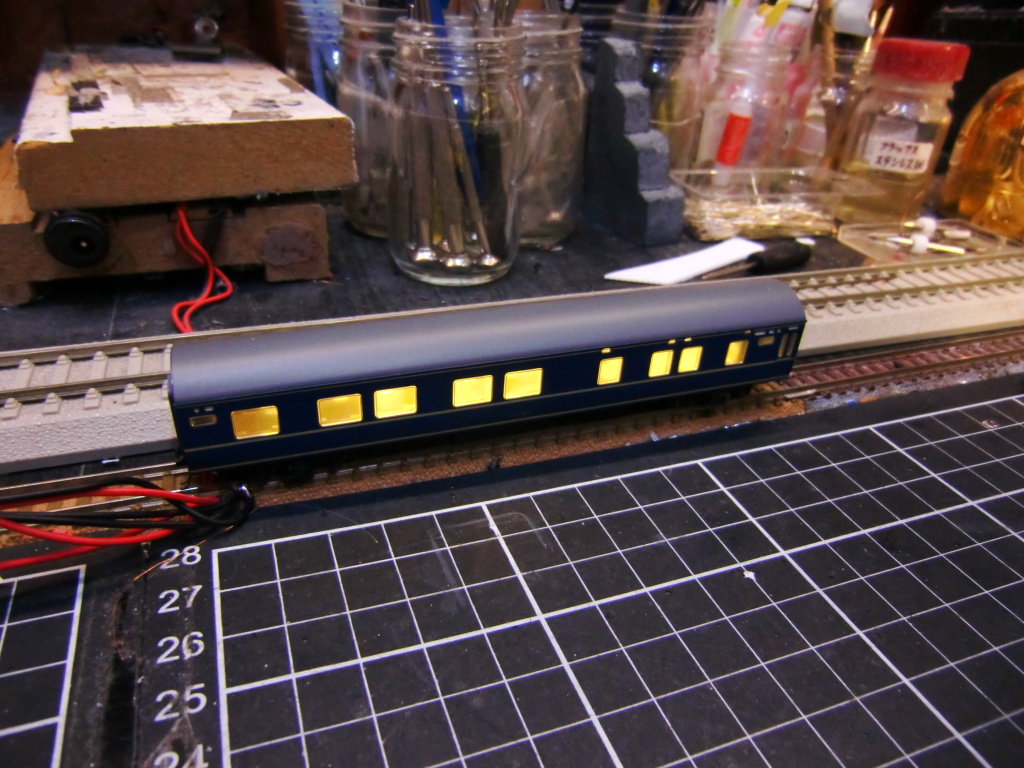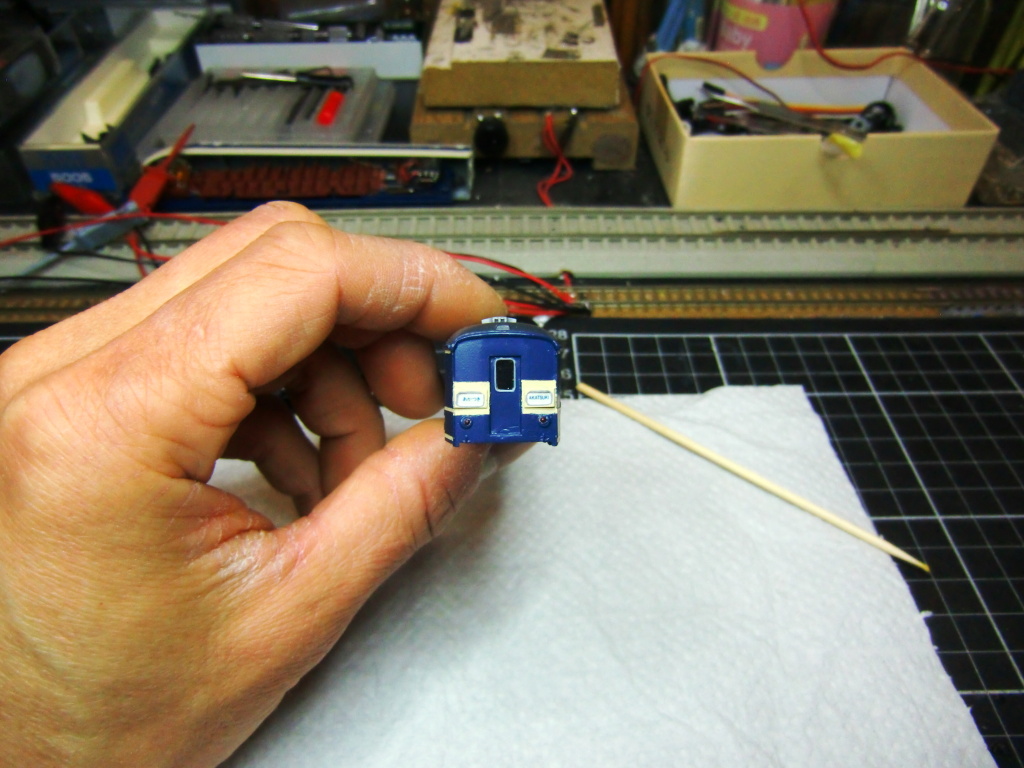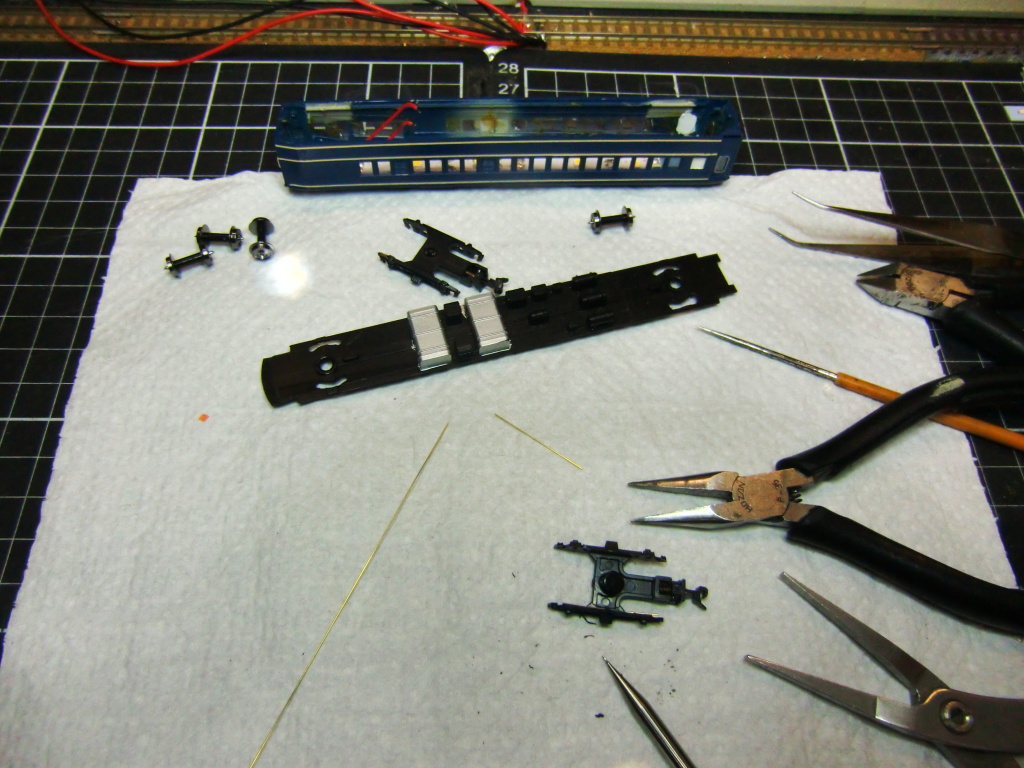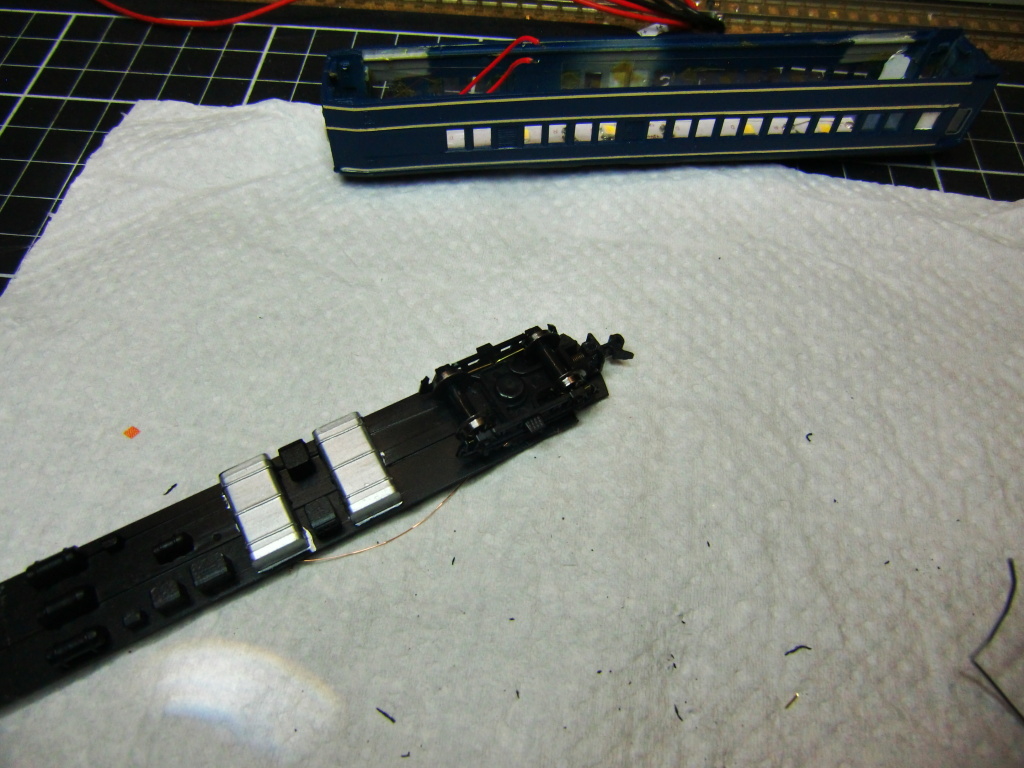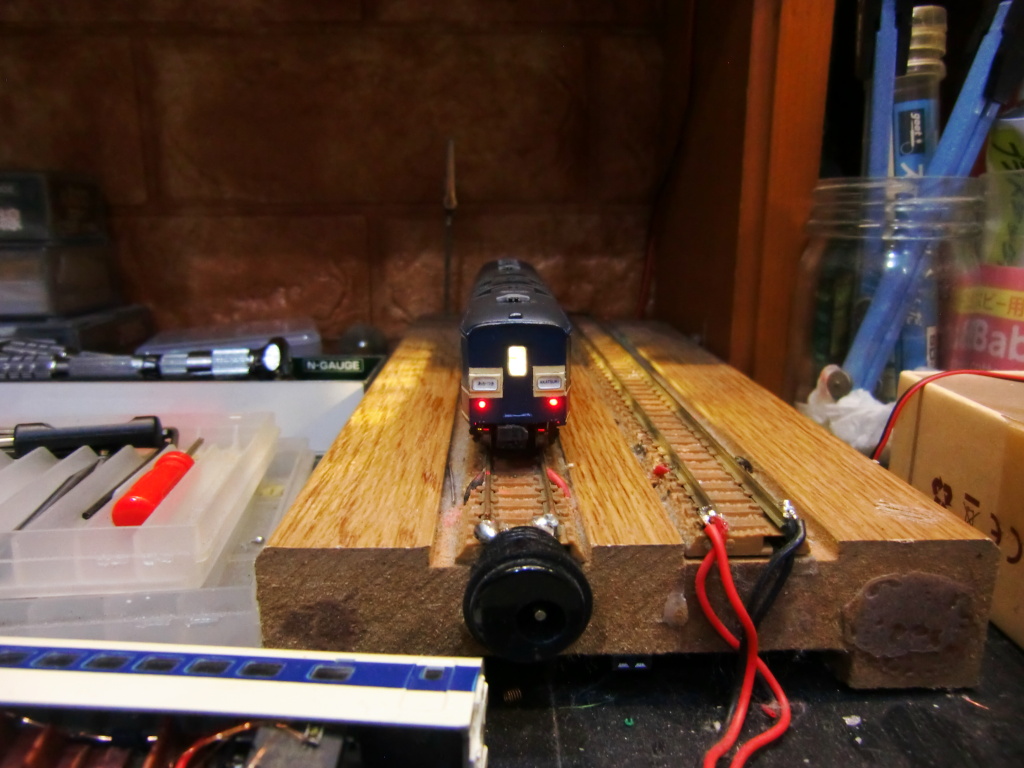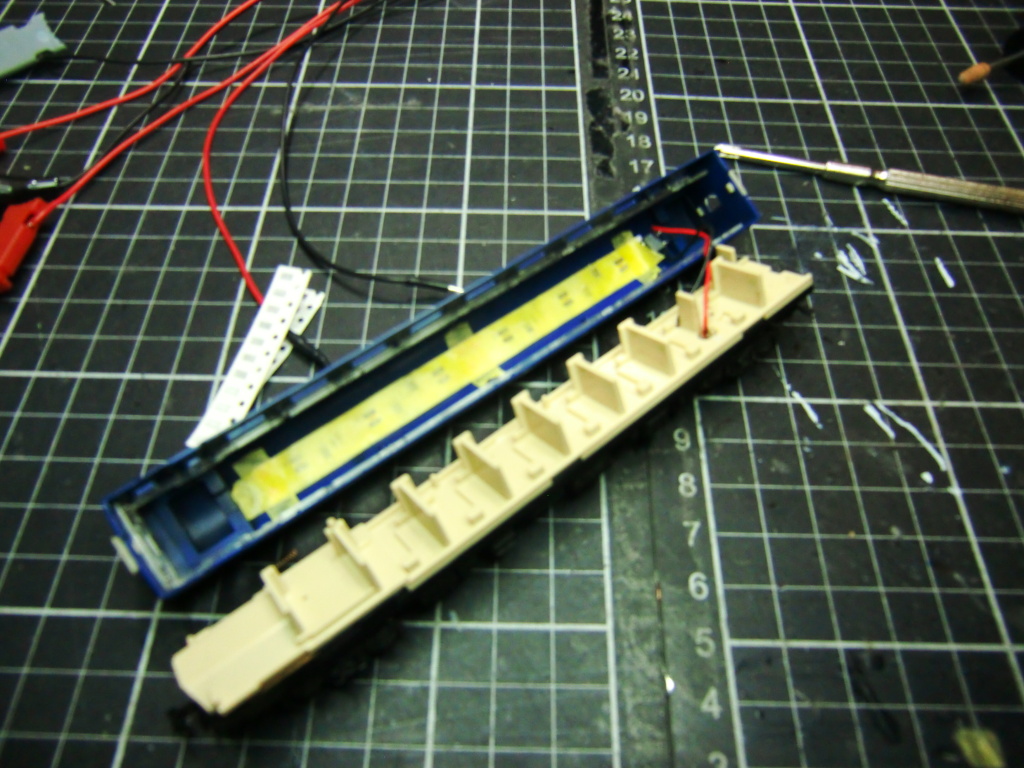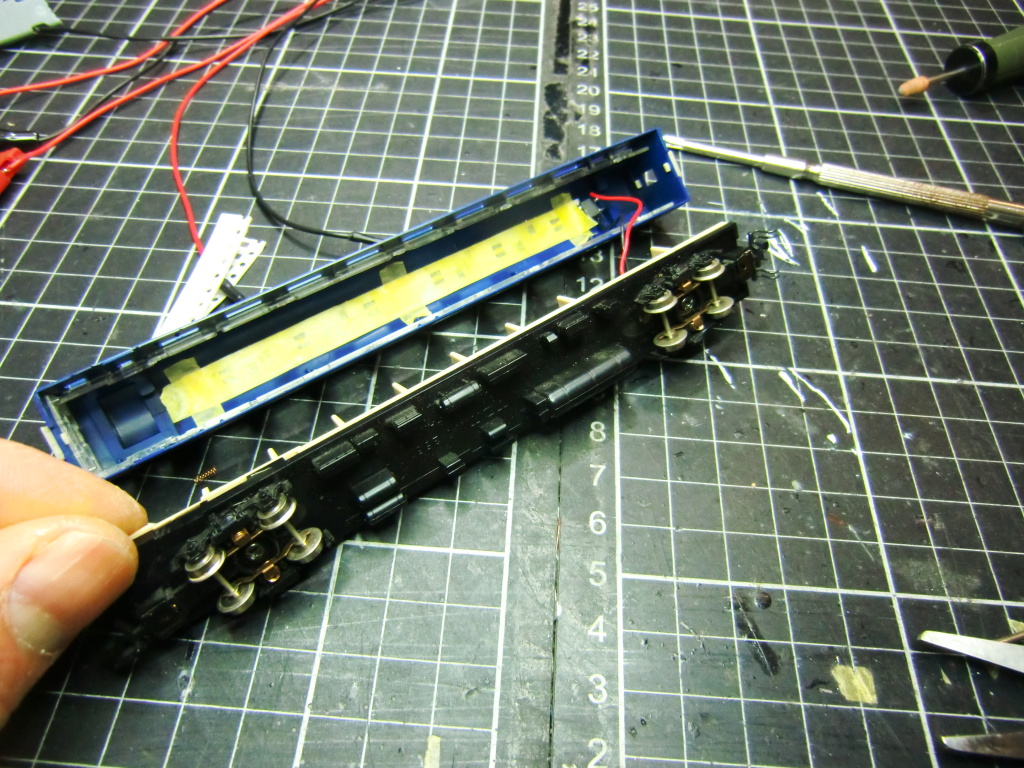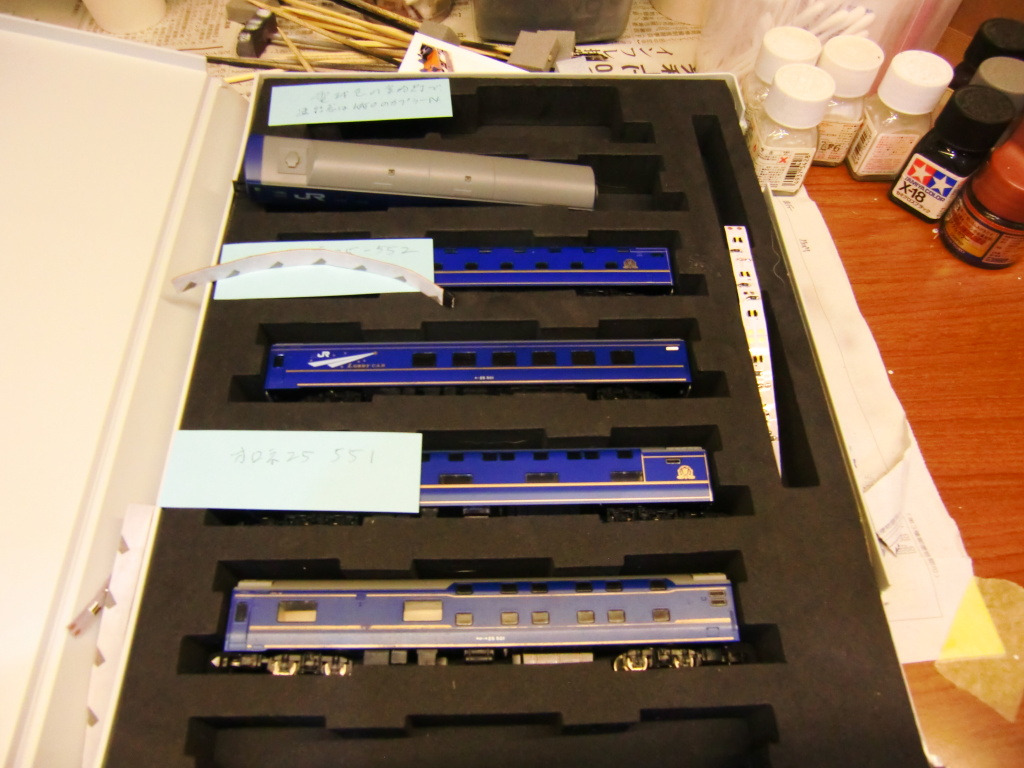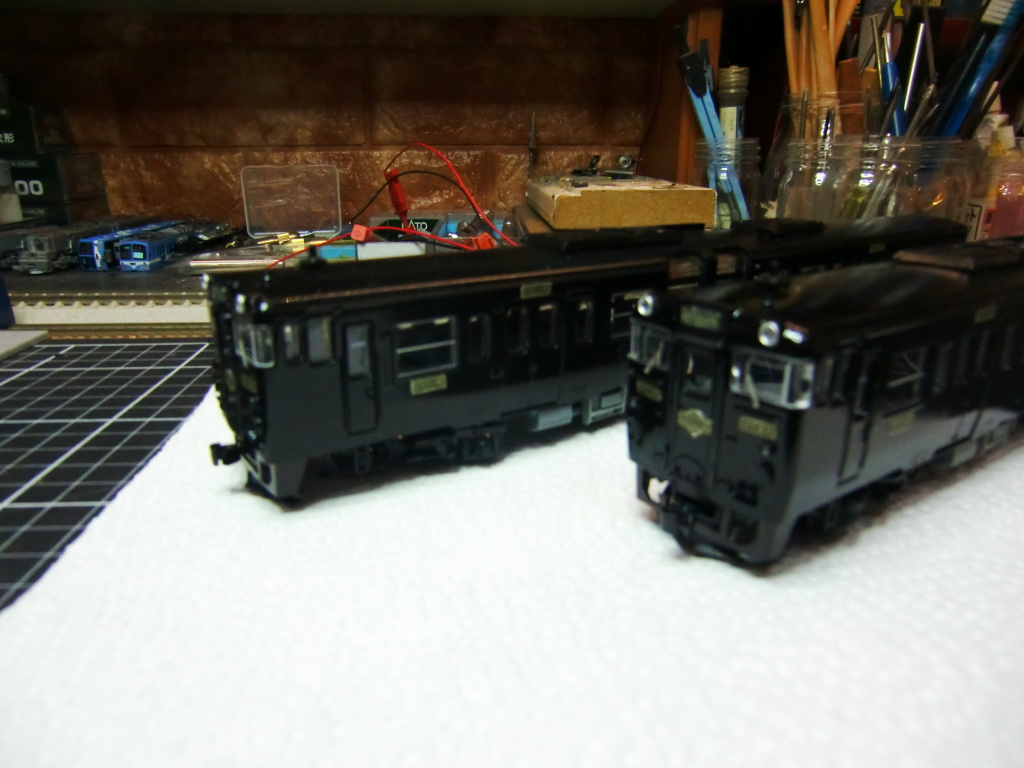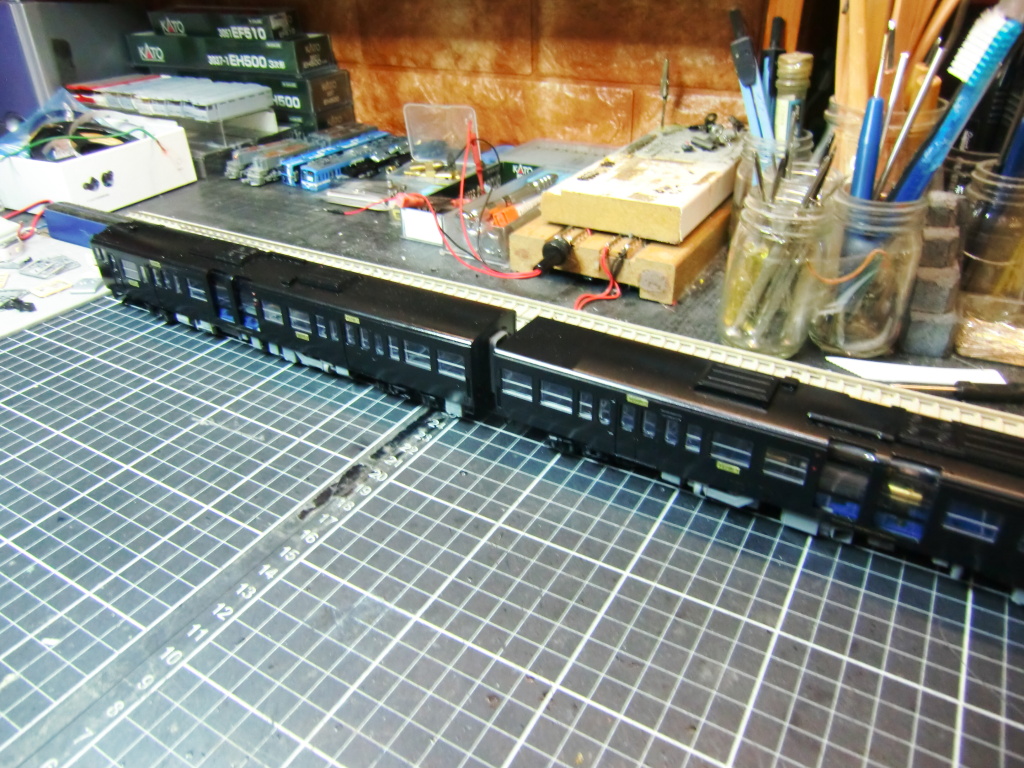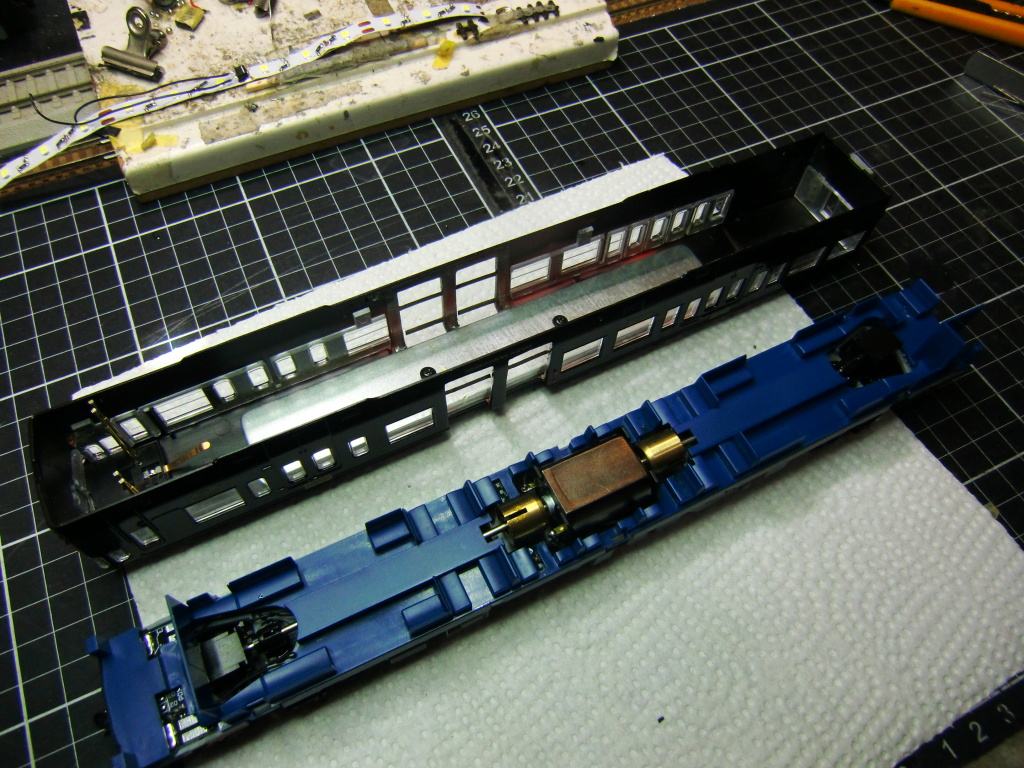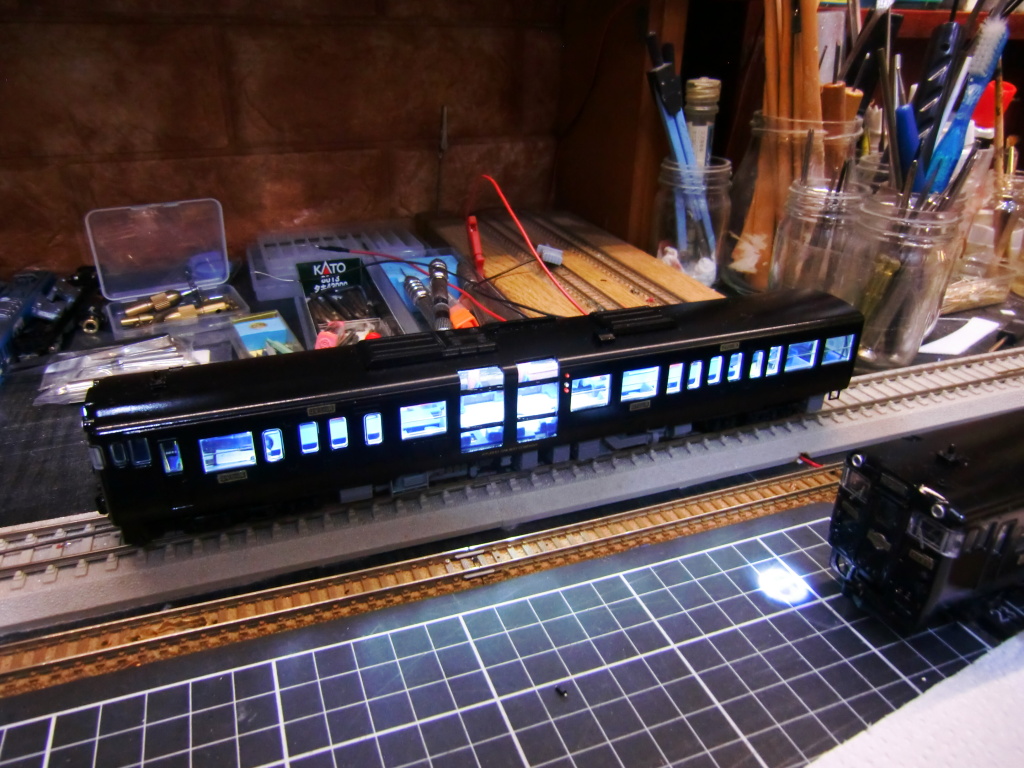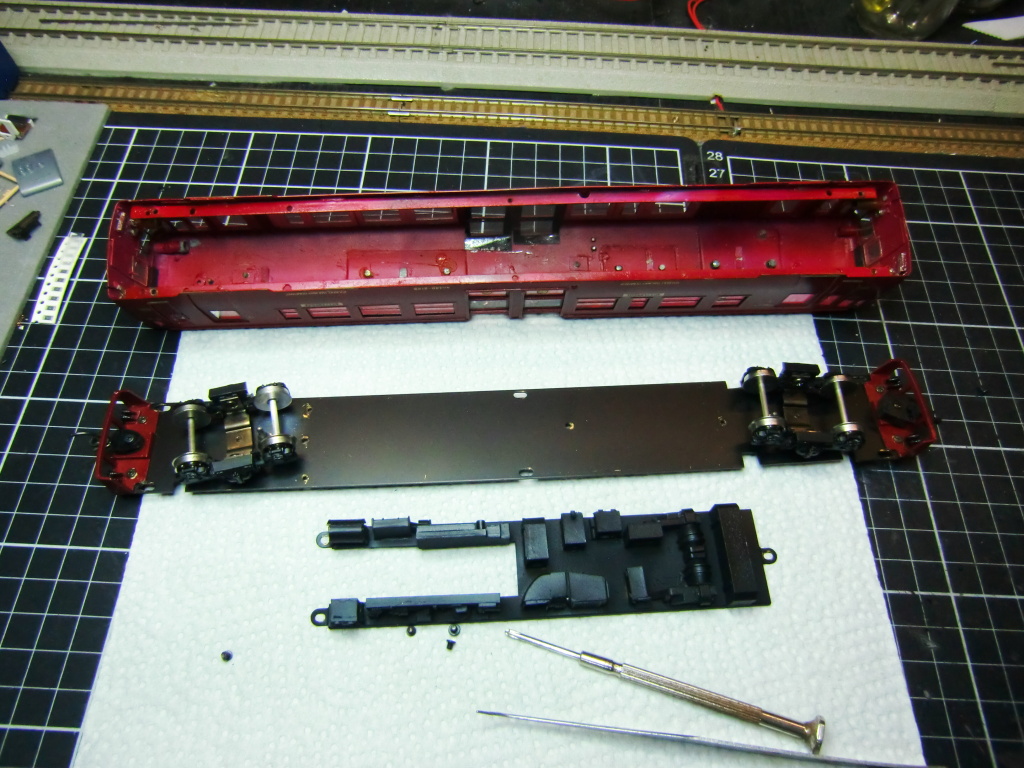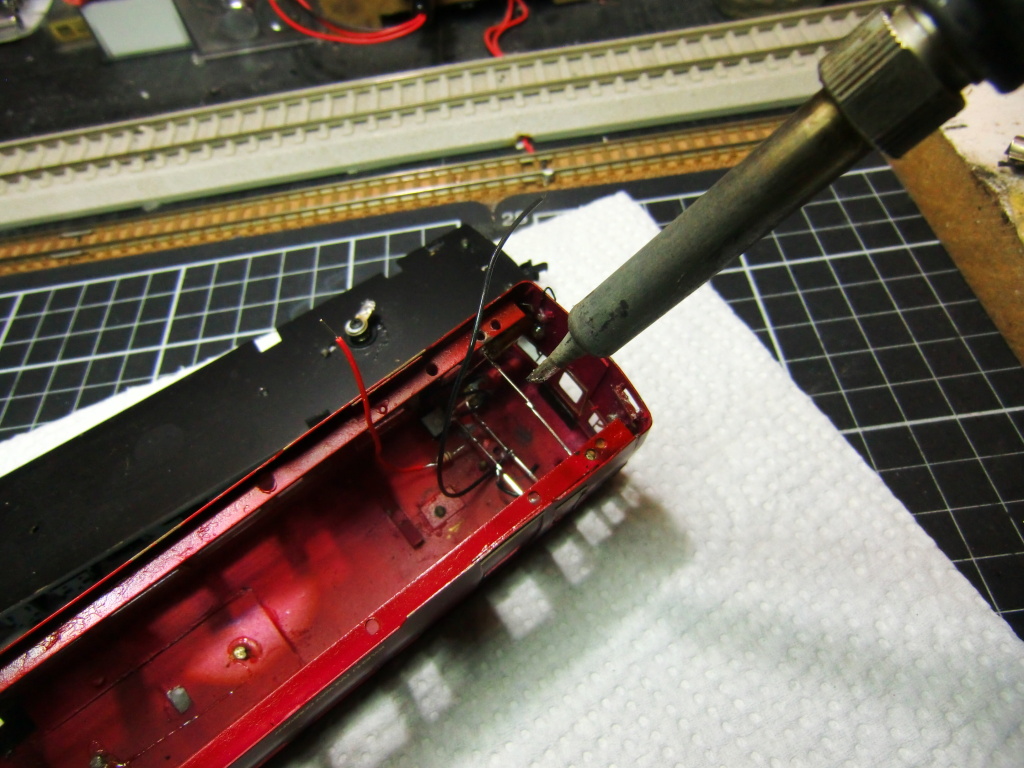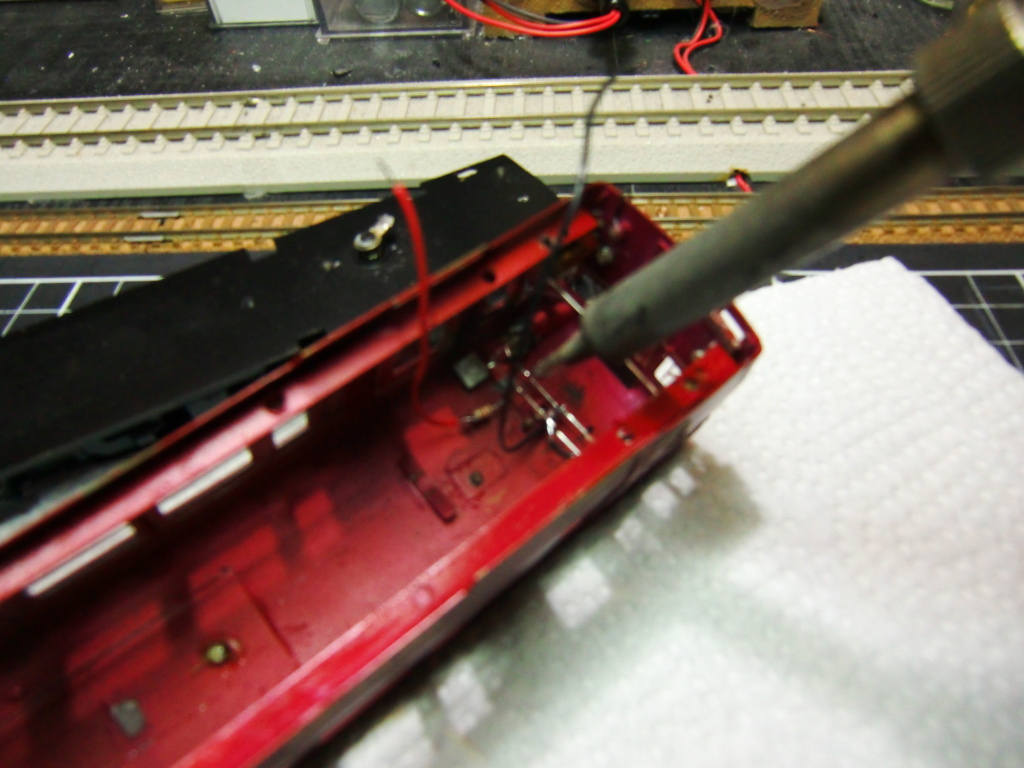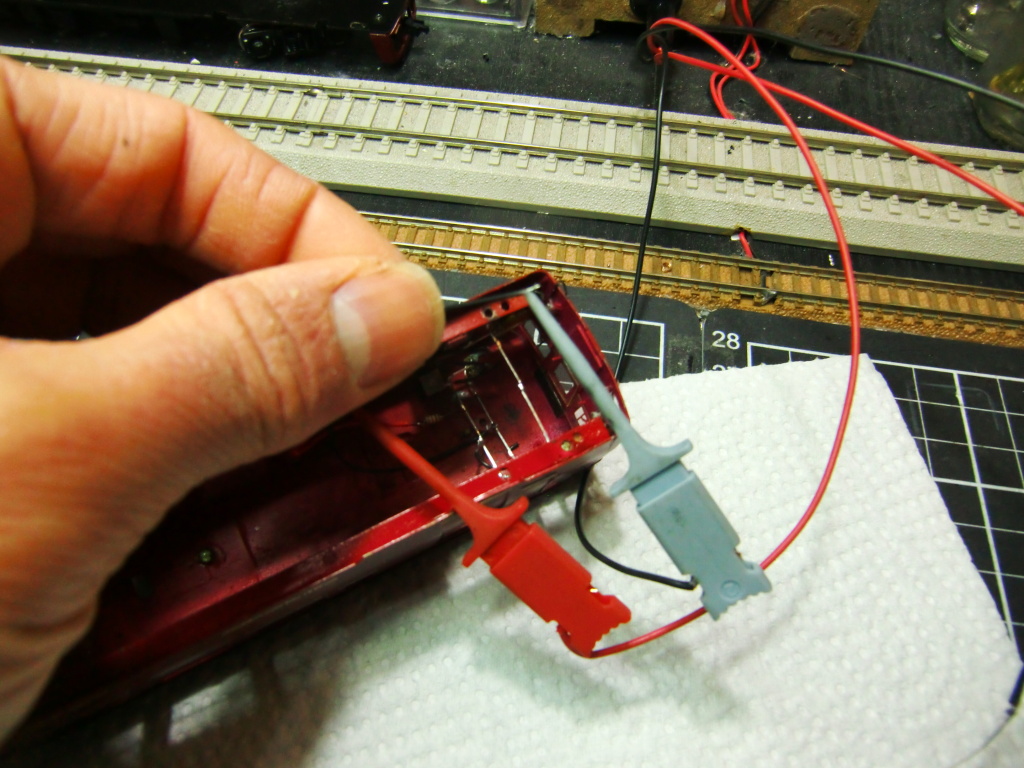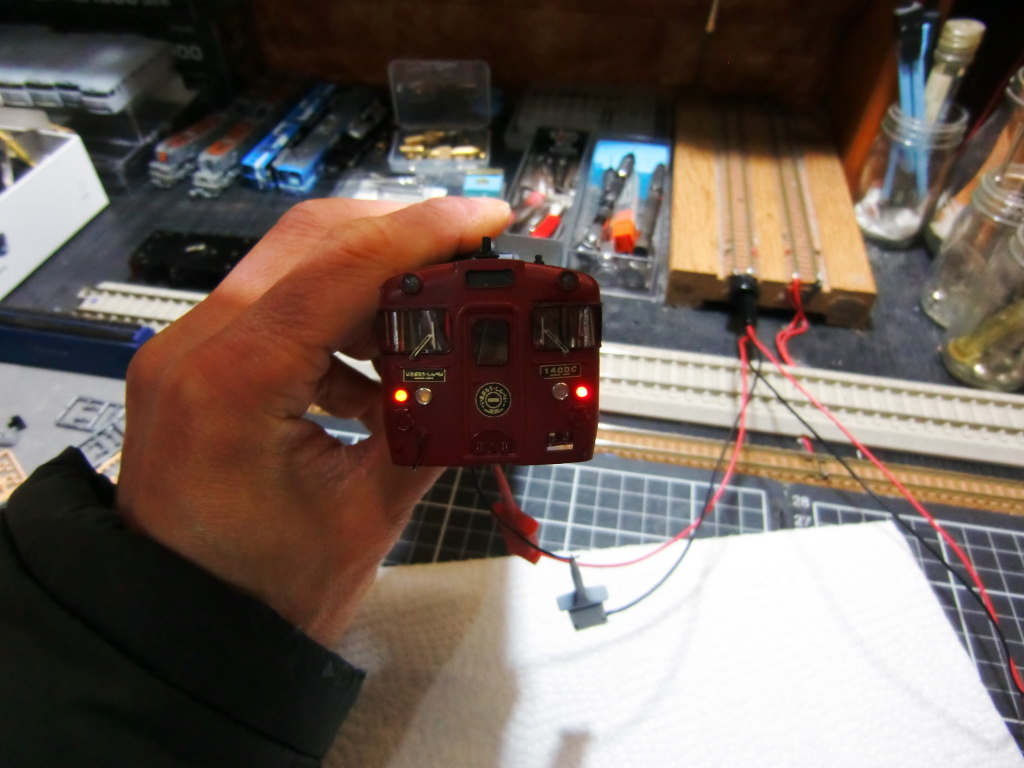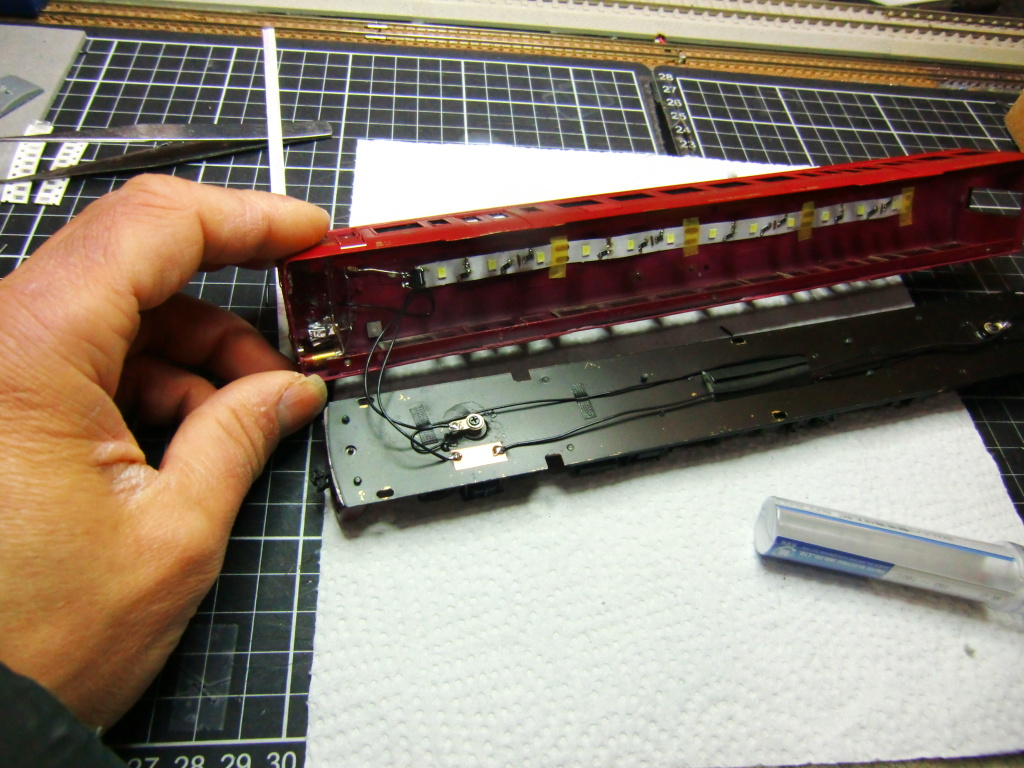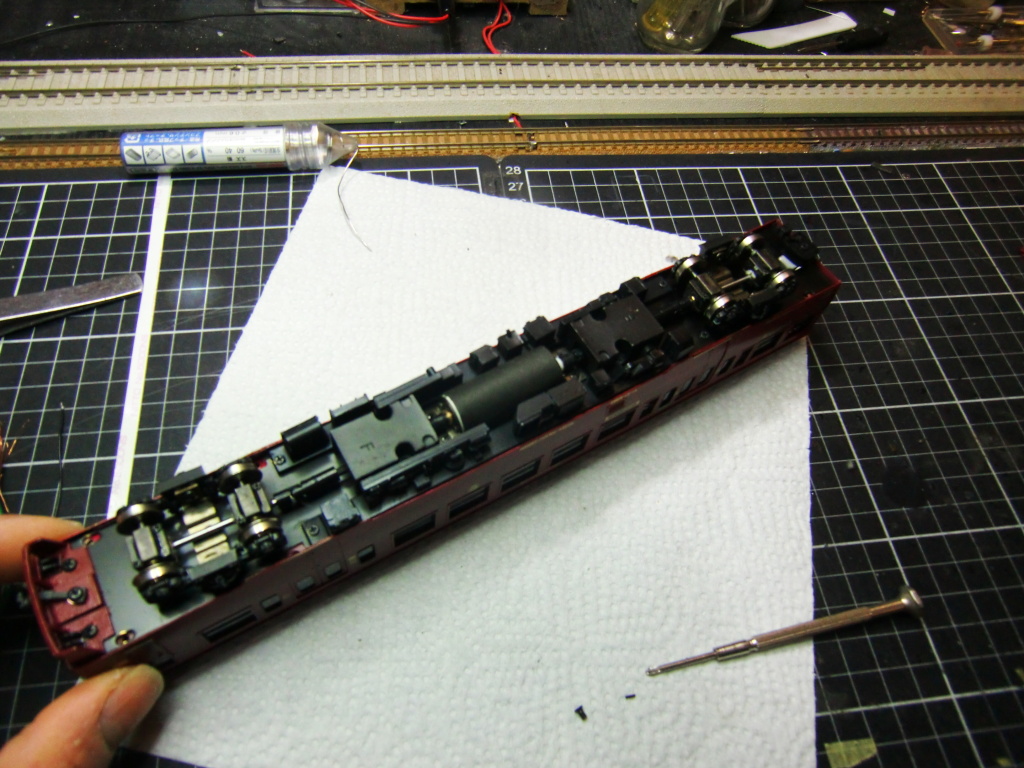今回の作業のご依頼は、まず「パシナ」を現状の白から青にリペイントされたいとのご要望です。次にHOゲージ「天賞堂C62 3」につきましては、破損部「凹みと欠損」の修復と車体のO/Hになります。


▼HO/16番ゲージ「天賞堂 C62 3」修理
まずは、こちらから取り掛かります。


こちらの写真では、凹んでしまっているのがわかると思います
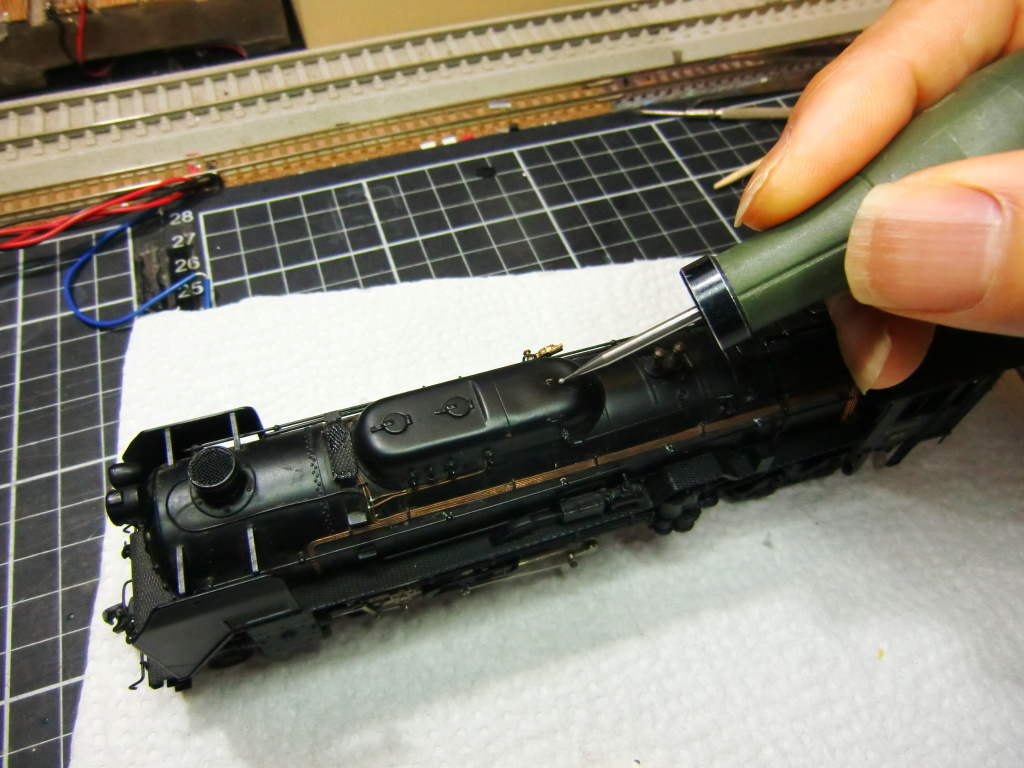
パテの食いつきを良くするためルーターで凹み部分を削ります。

続いて主剤と硬化剤を練り合わせてパテを作ります。

パテが完全硬化するまで時間がかかりますので、その間に車体を分解してオーバーホールを行います。
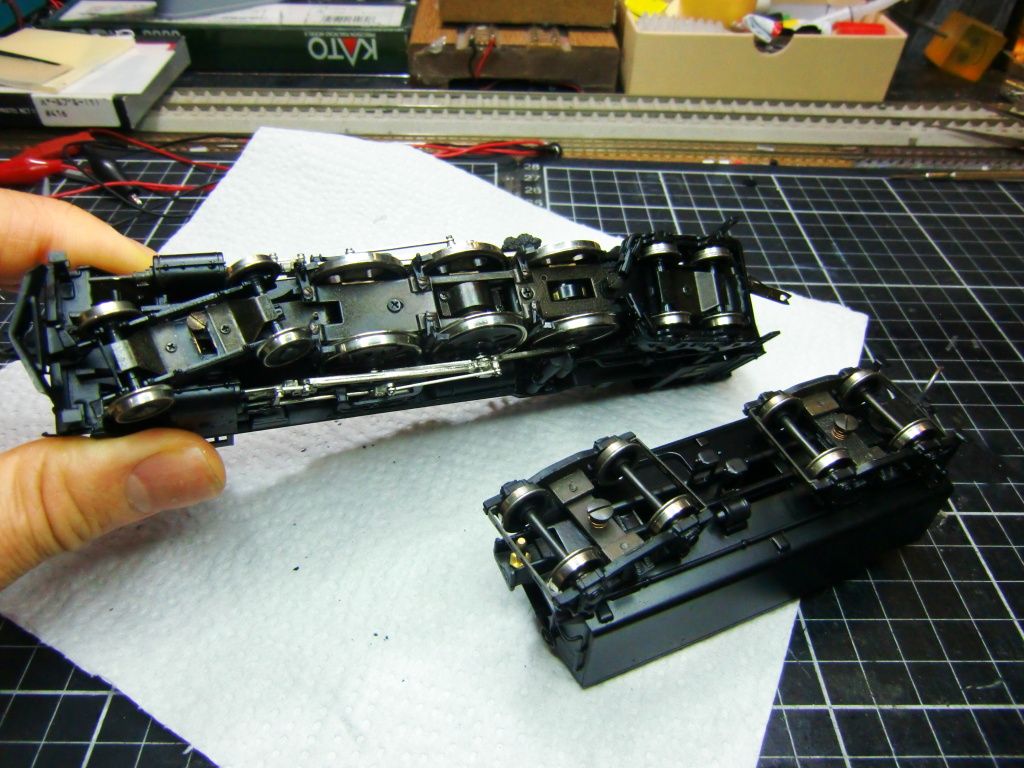

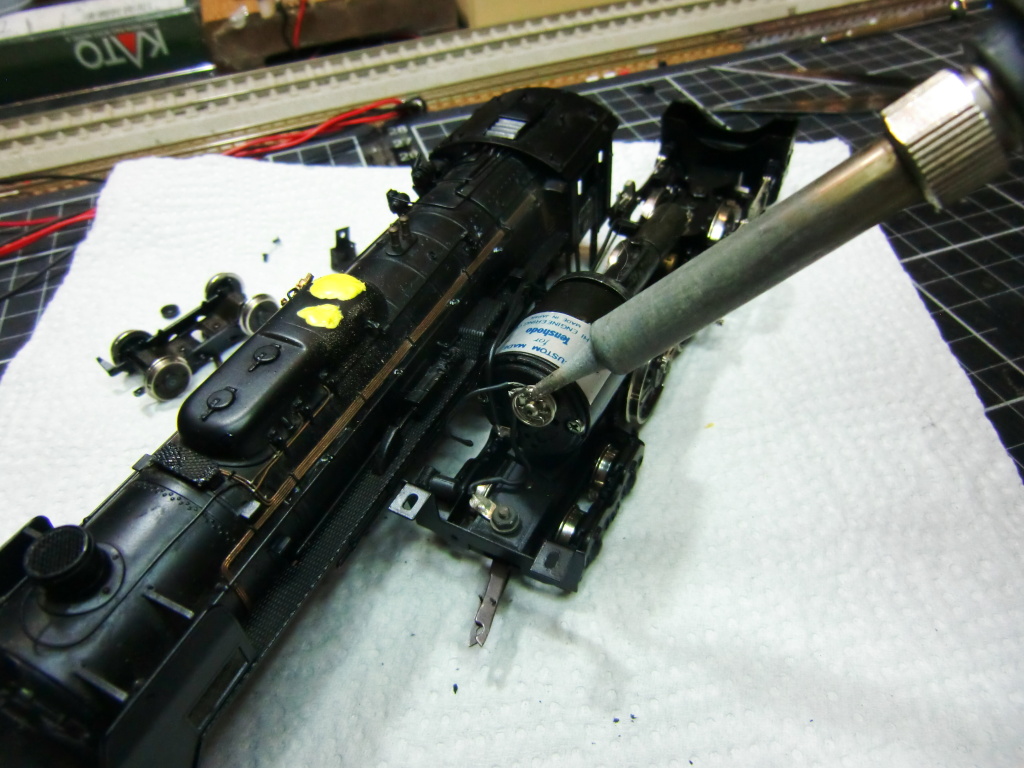
ライト用の配線はいったん外し駆動部と分離させます。
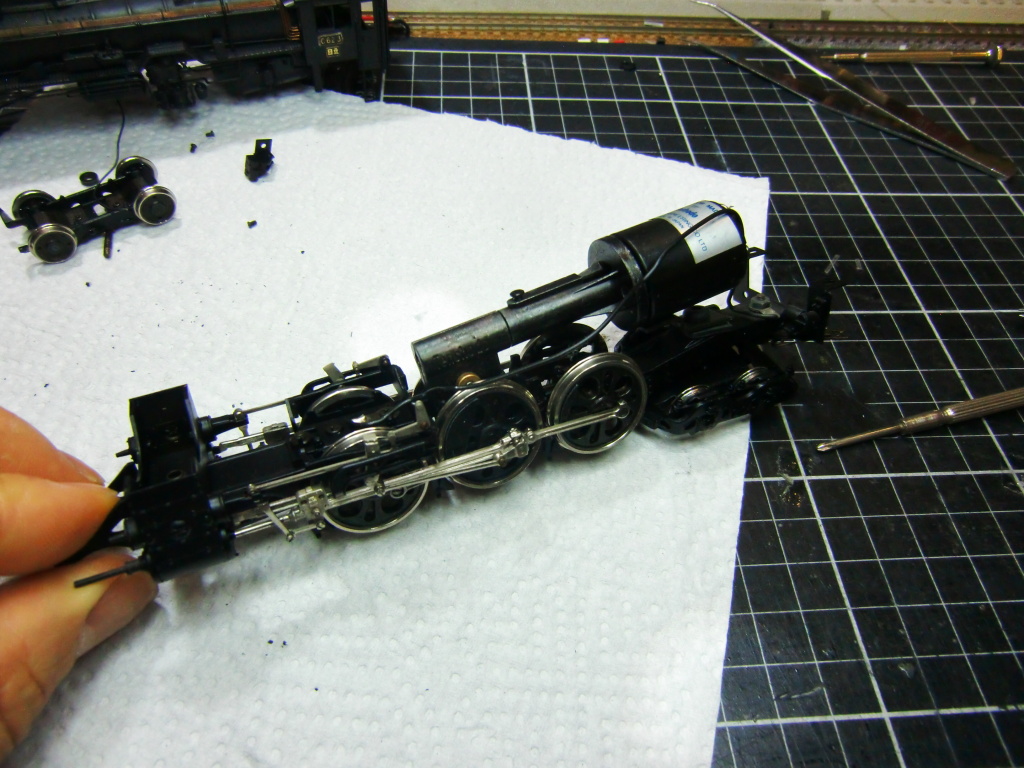
ここから各部の調整を1つ1つ行っていきます。
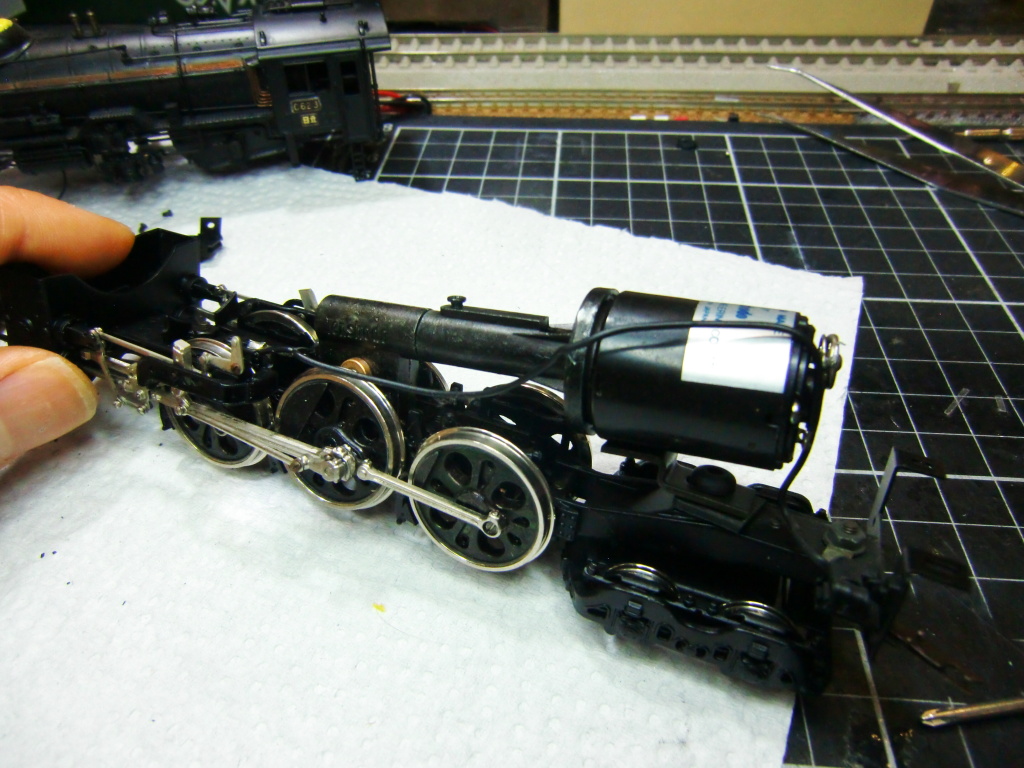
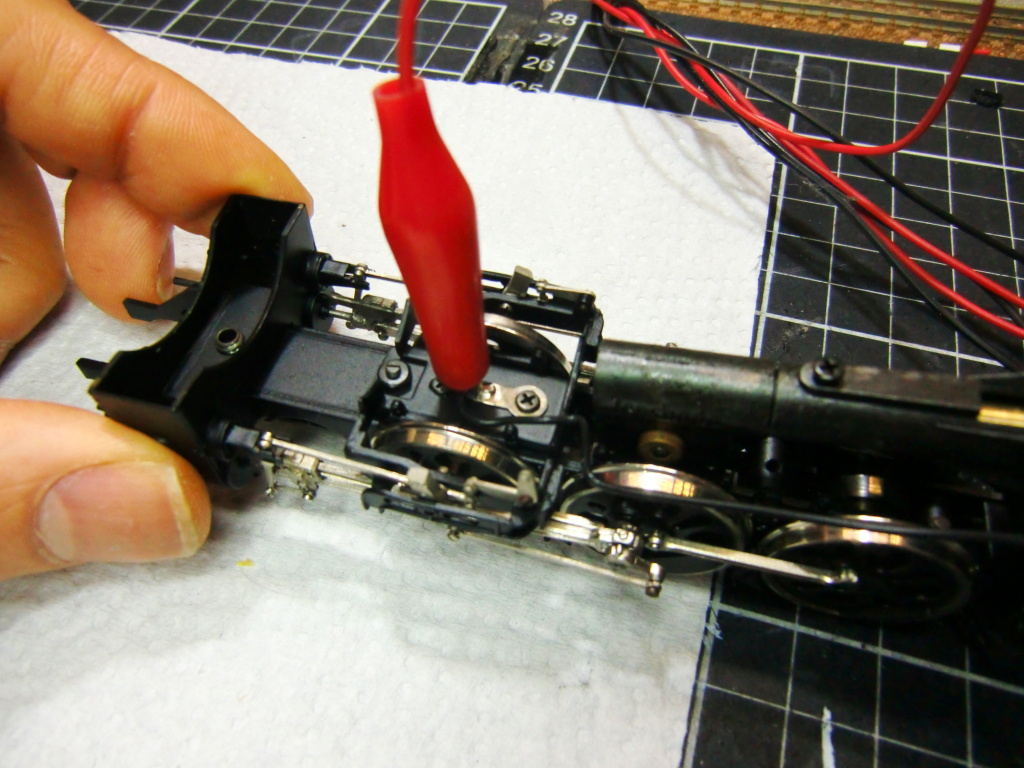
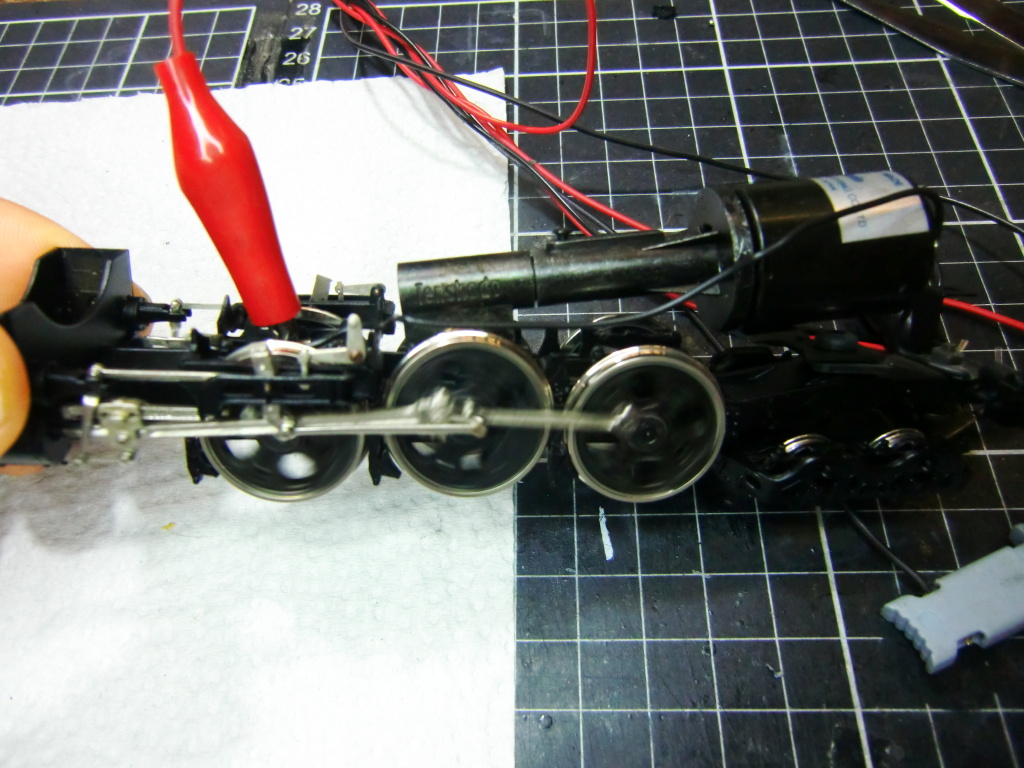
低速で回転させ確認していきます。
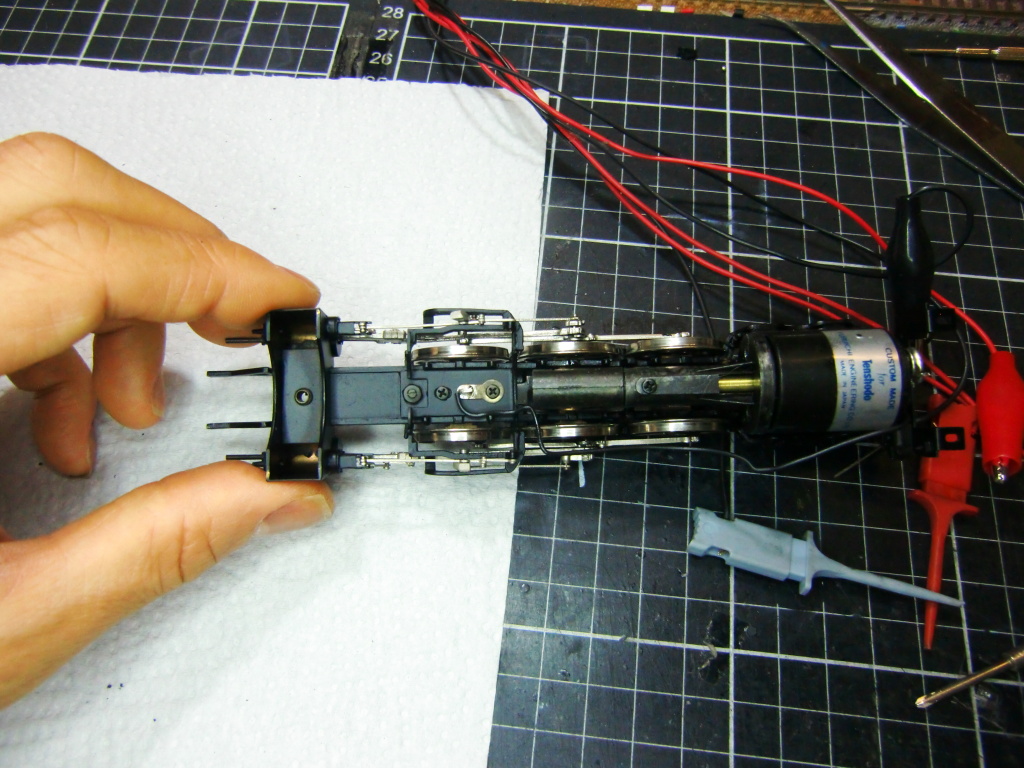
車輪の回転が不安定で波打ってます。
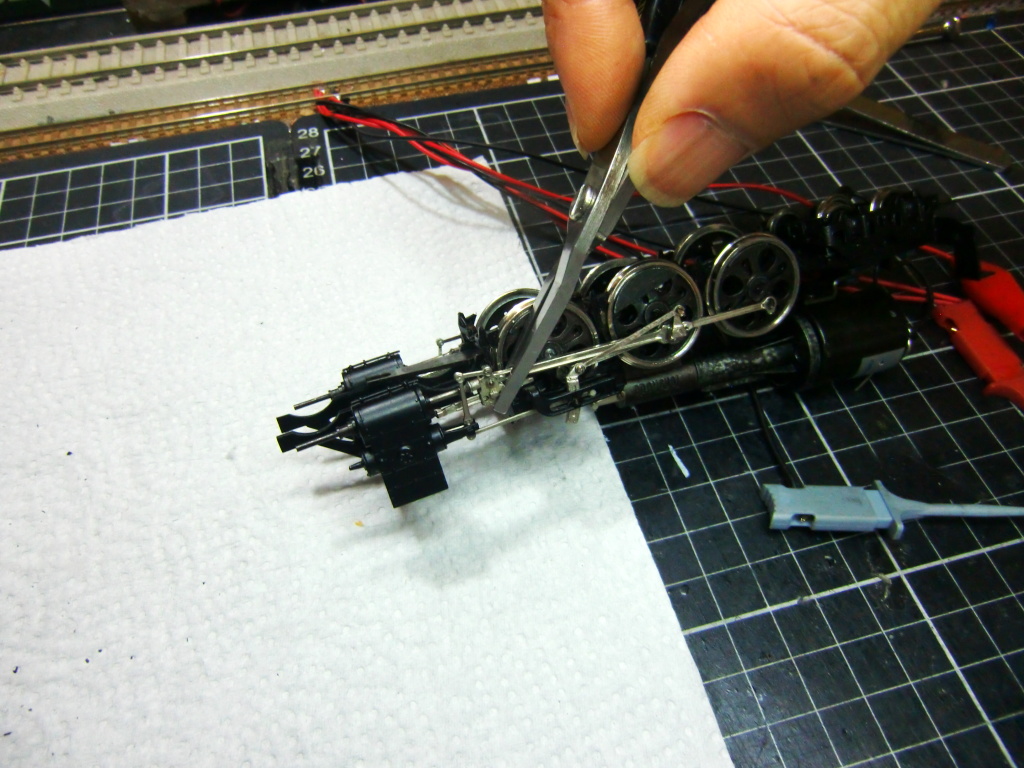
各部パーツの歪みを調整して正常位置に戻します。
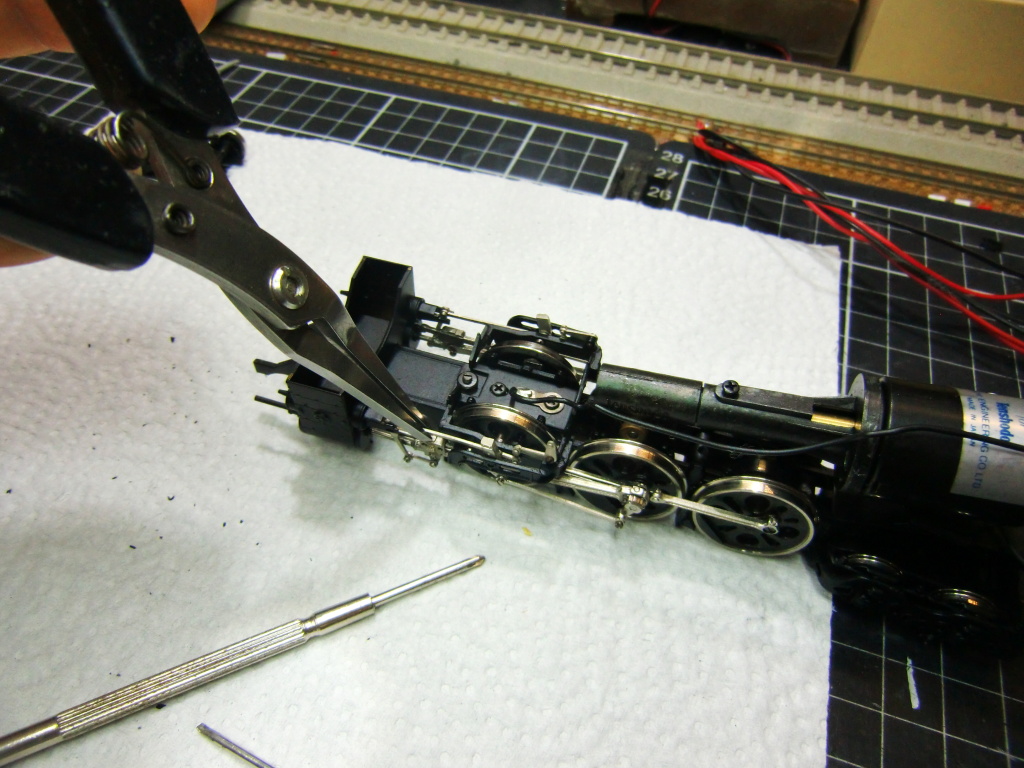
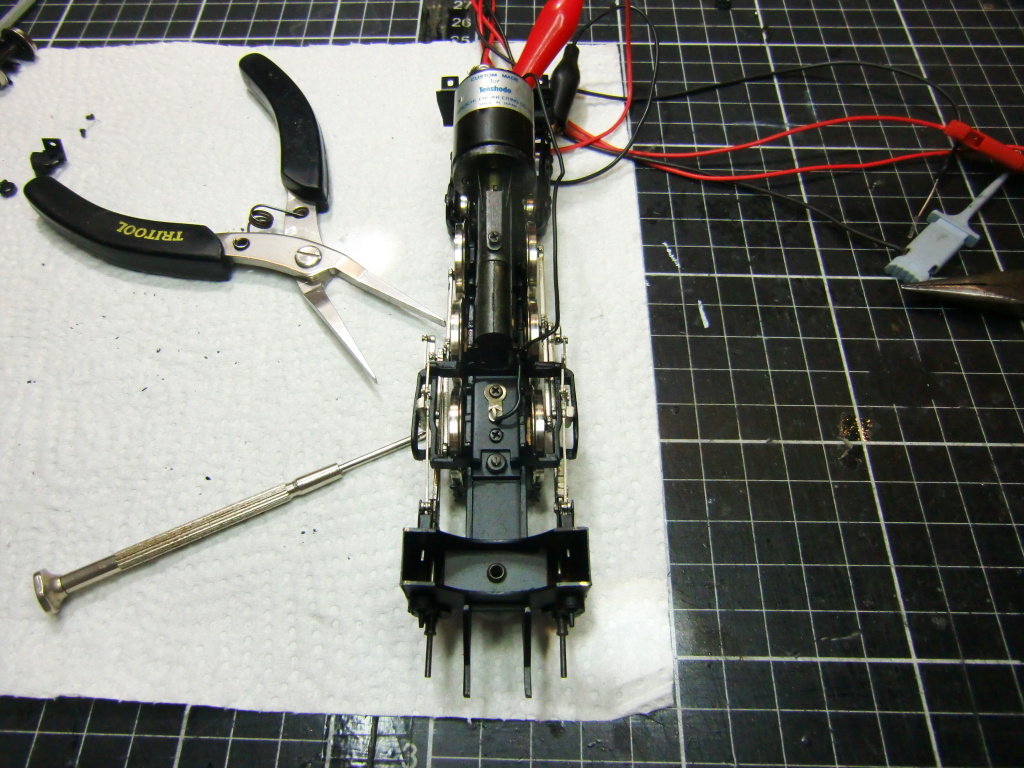

テンダーと連結固定するドローバー固定ピンがありません。開いたままの状態です。こちらも制作して組み込むことにします。
テンダー側も進めていきます。
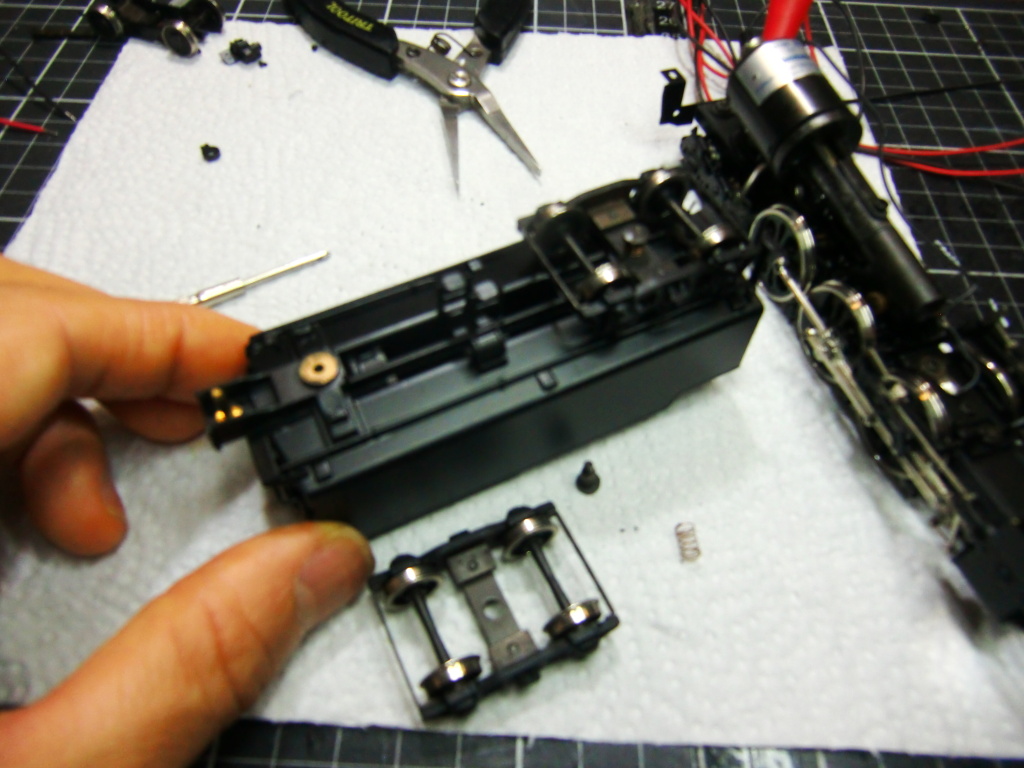
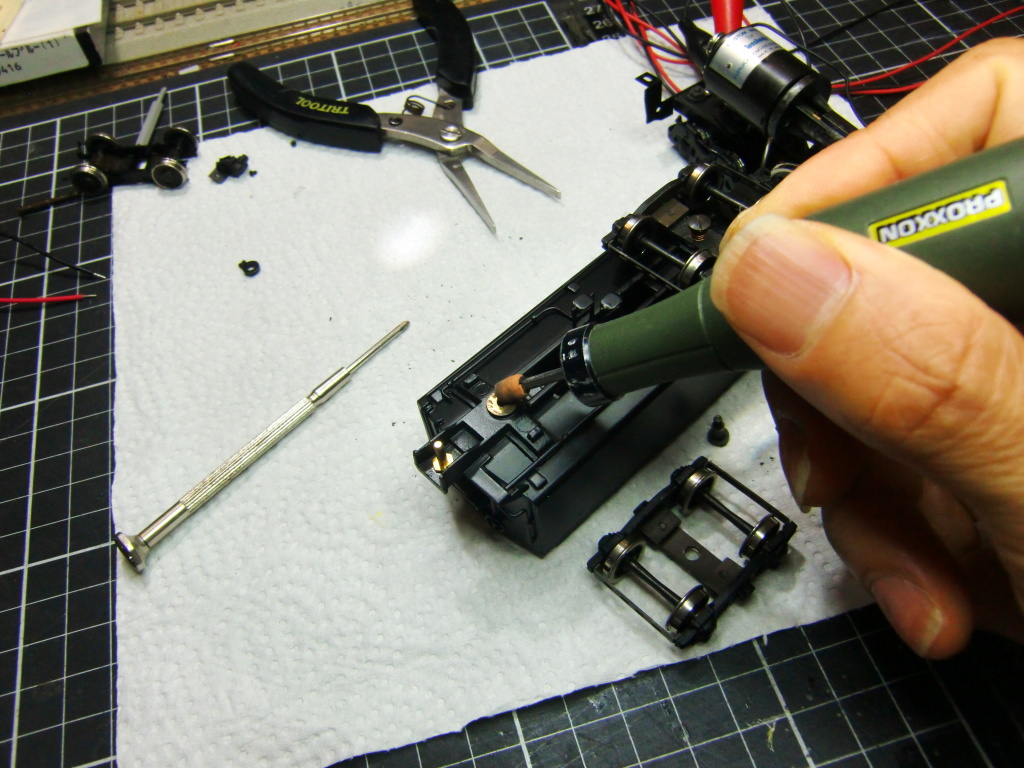
接点部分は所々さびが出てますので、光沢が出るまで磨き出します。
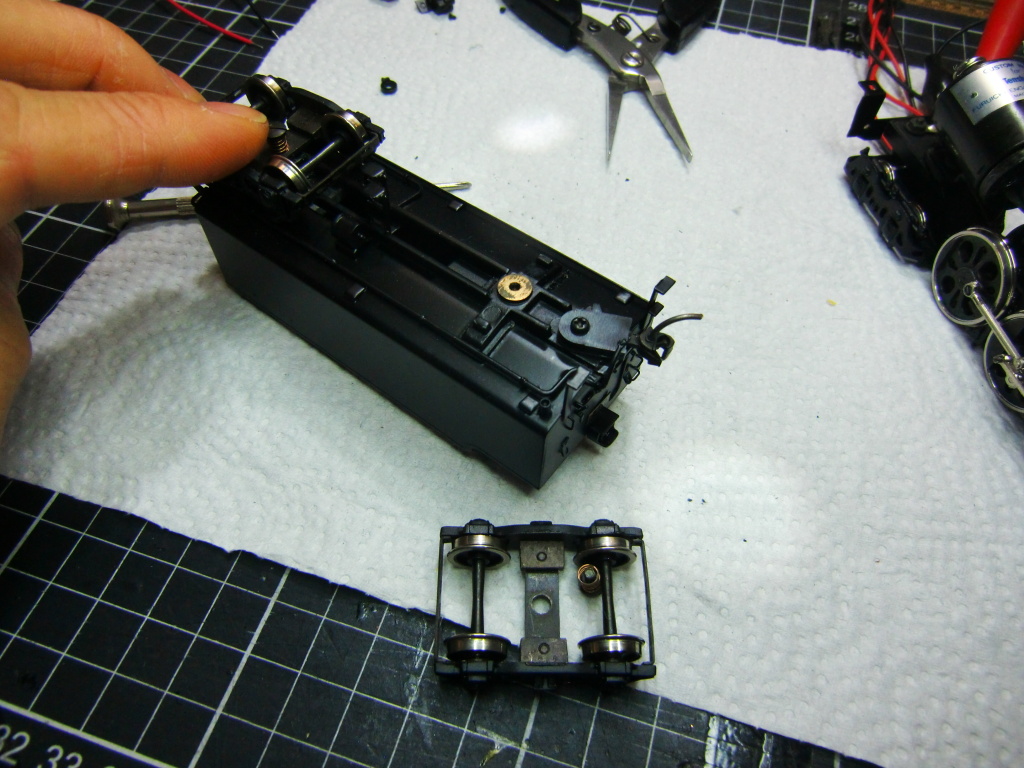
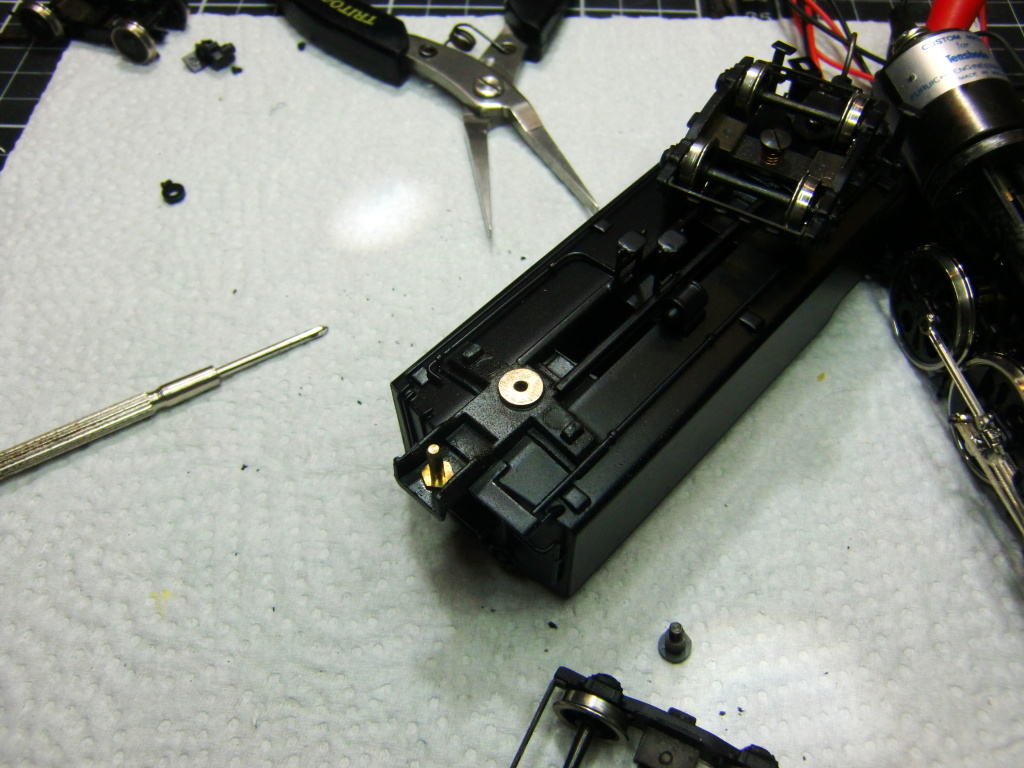
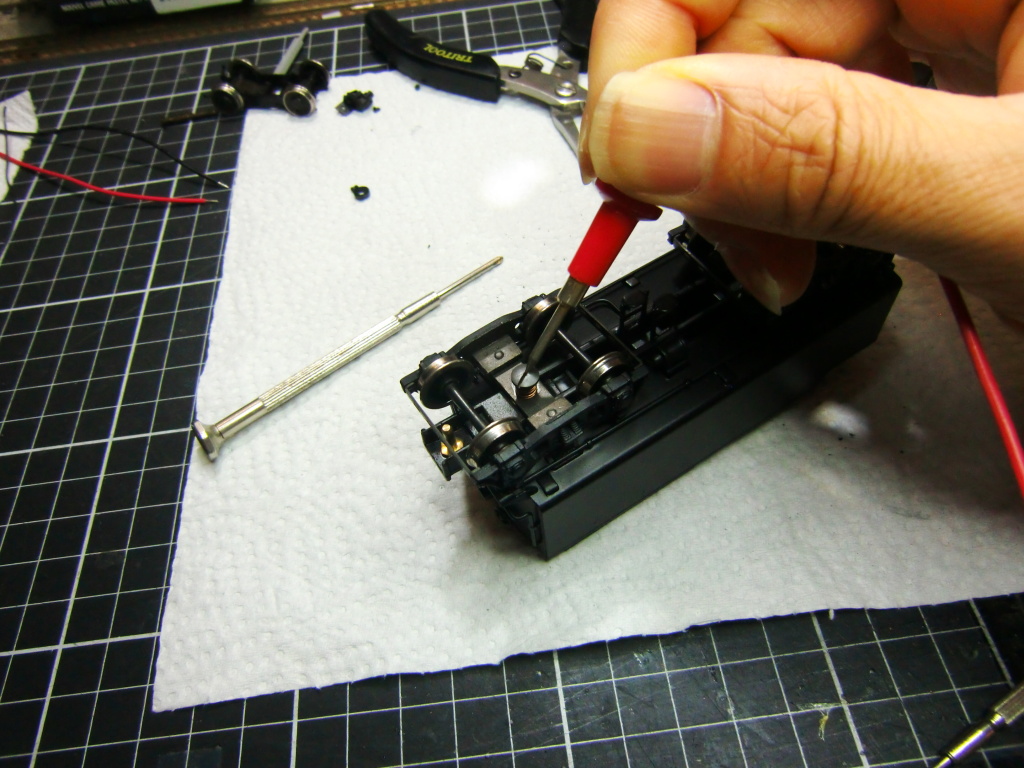
接点の通電状態をテスターで確認していきます。
パテが完全に硬化したので、再び機関車の作業へ

パテ自体が固いので、まずはルーターでギリギリまで削ります。
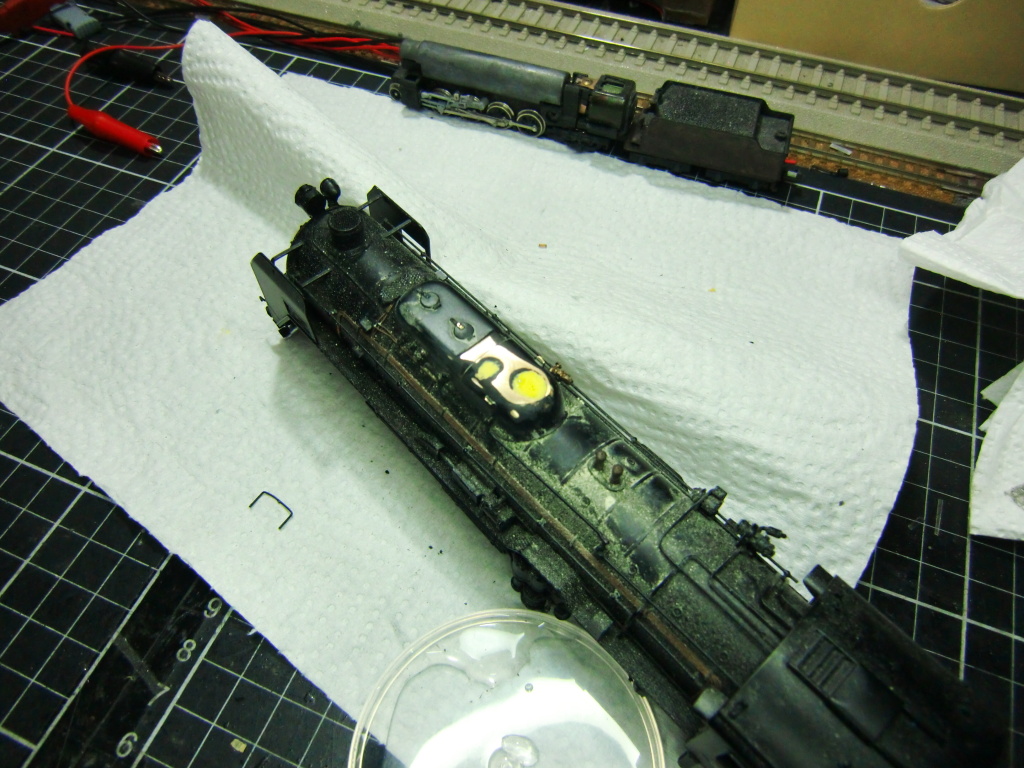
続いてペーパーで「#600 -> #800 -> #1000」と仕上げていきます。

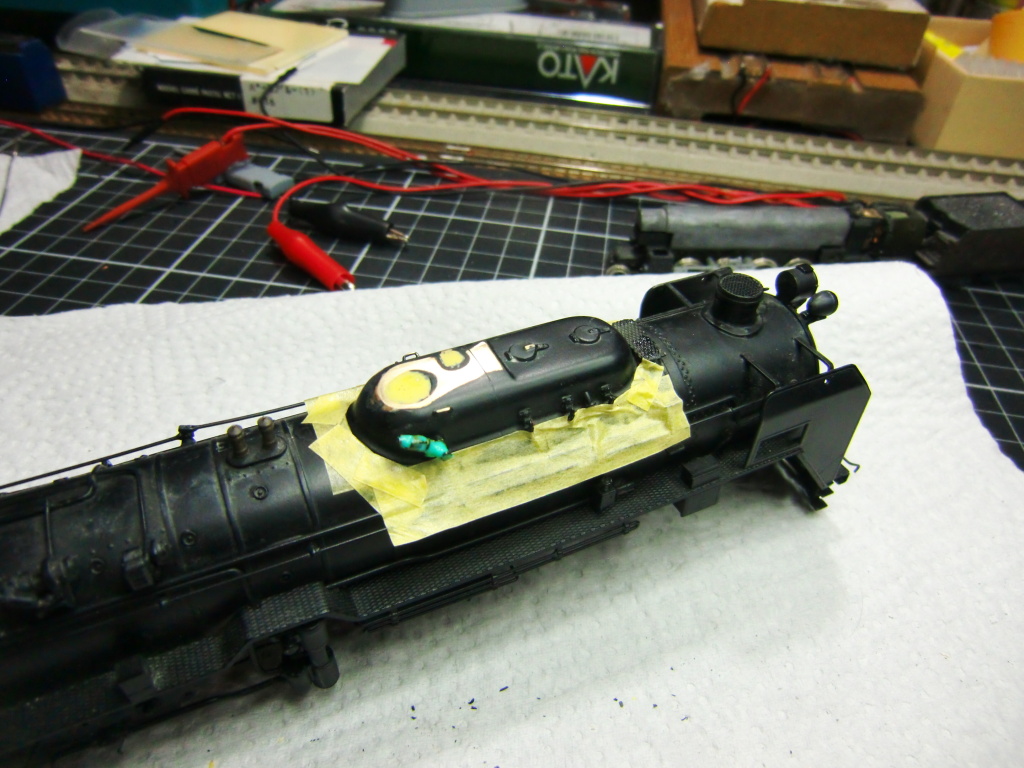
周りをマスキングテープで覆います。

折れた手すりは修復して機関車本体にハンダ固定します。




3~5回に分けて、塗膜を作ります。

一通り修理とメンテが終ったので、最後に組み戻して走行テストです。




前進・後進とも大変なめらかな走行が確認できました。まずは、C62完了です。さて、お次はパシナです。
▼Nゲージ「パシナ」オールリペイント
まずは、青に塗り替えるための準備として、資料を集めていきます。



部品はすべて外しておきます。全体的に錆びてしまっているようです。手すり類は表面がザラザラした感じですべて錆びてました。このあたりも処理していく必要がありそうです。
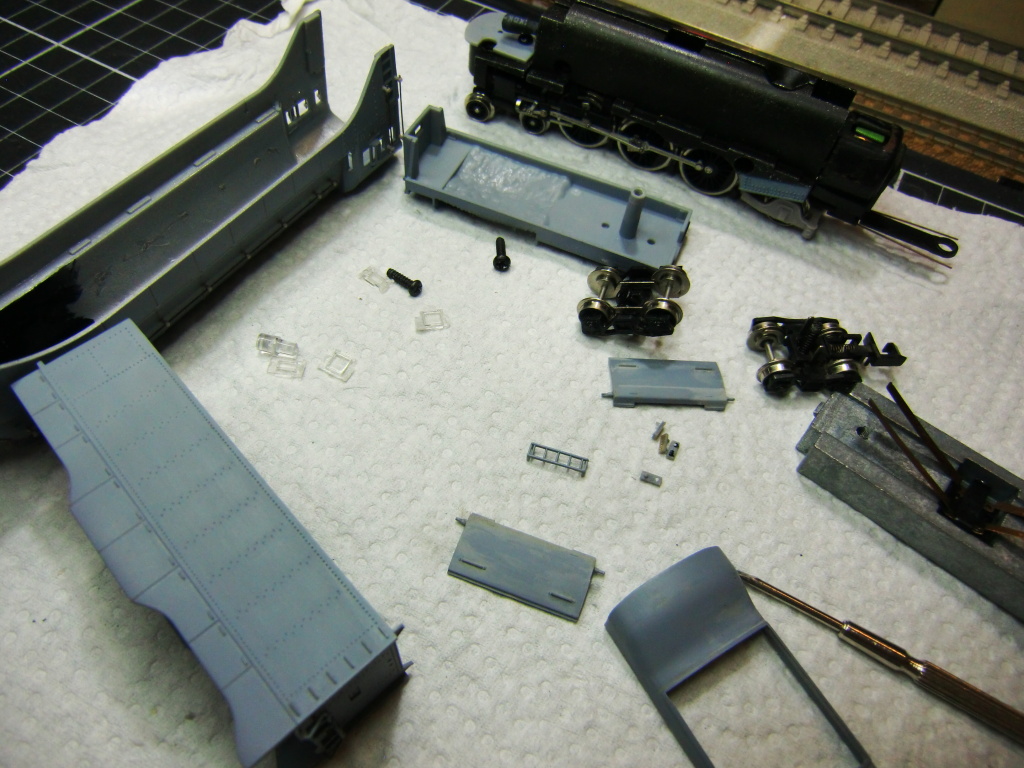
窓ガラス、手すり、ナンバーなどもすべて内側から押し出して外します。
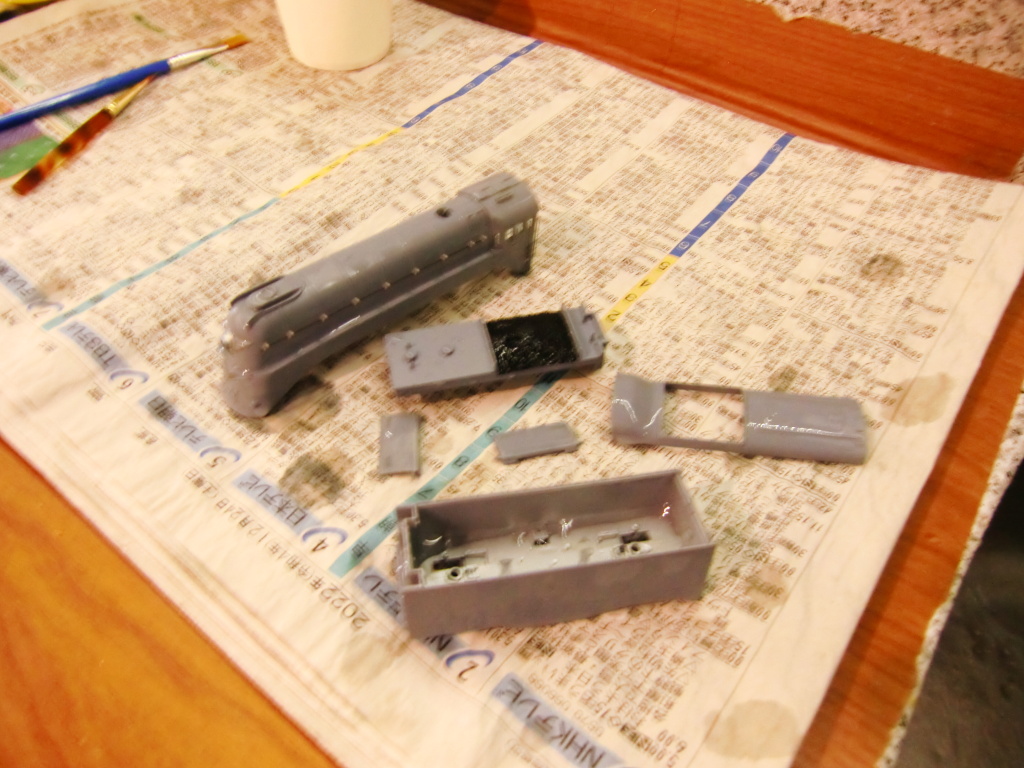
中性洗剤で念入りに汚れを落としたあと、しっかりと水洗いして乾燥させます。

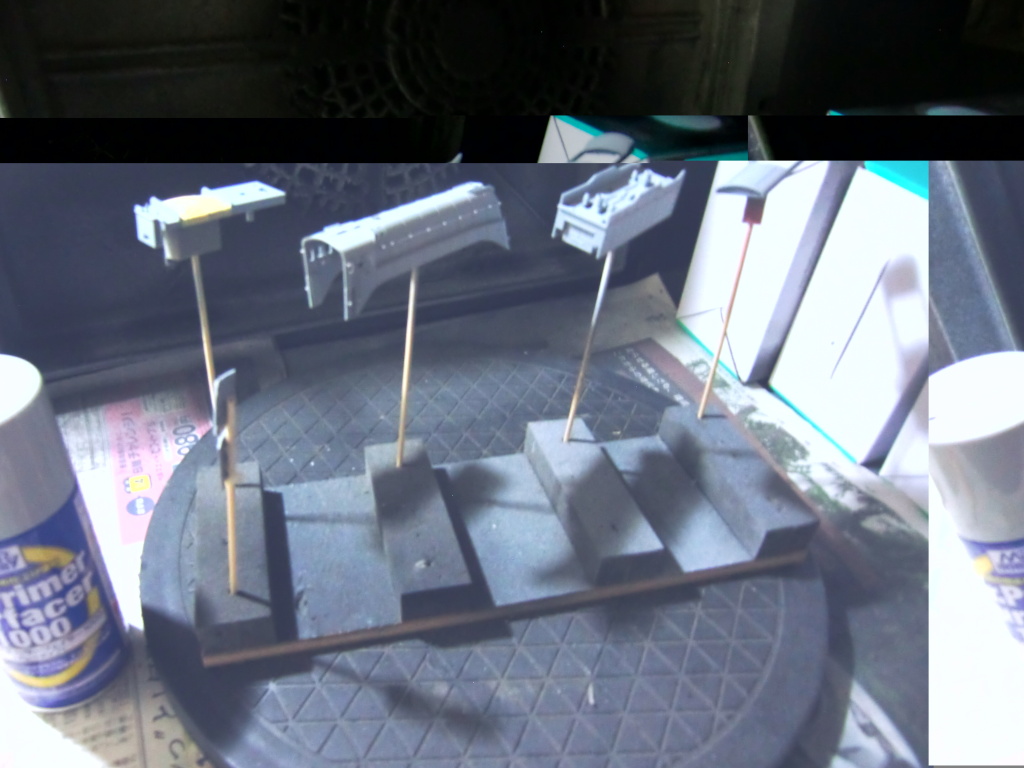
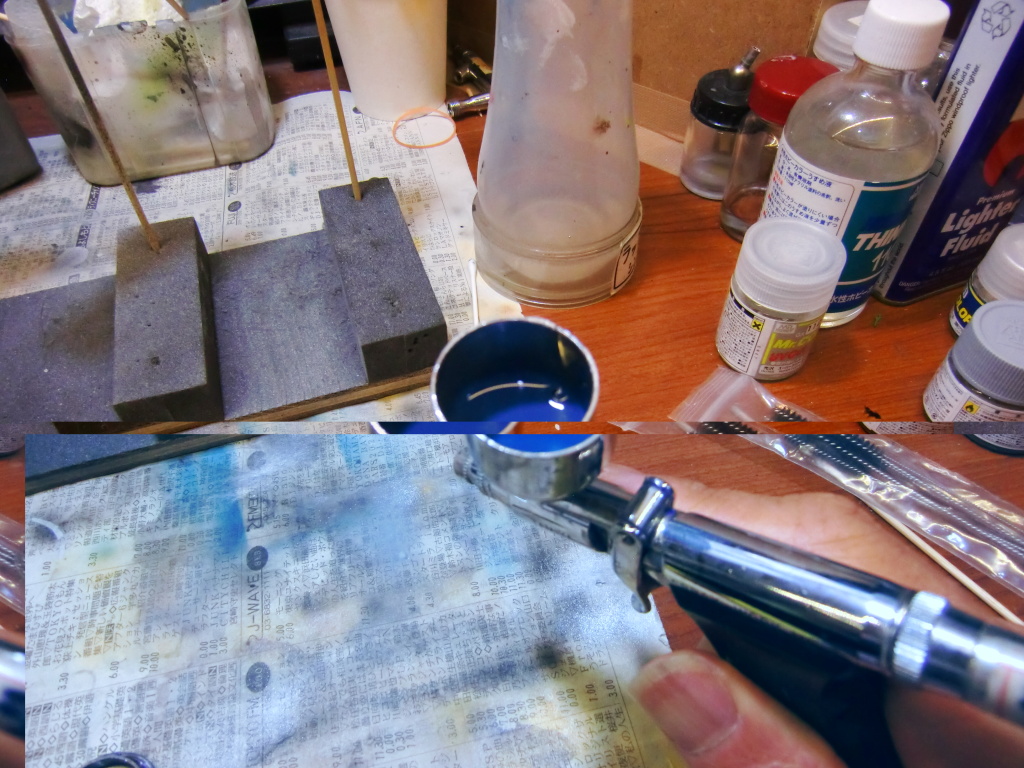



どうしても所有のデジカメでは、色が明るめにとれてしまいます。実際に塗装している色は、かなり深い感じの青です。

塗装と並行して各部のオーバーホールも進めていきます。
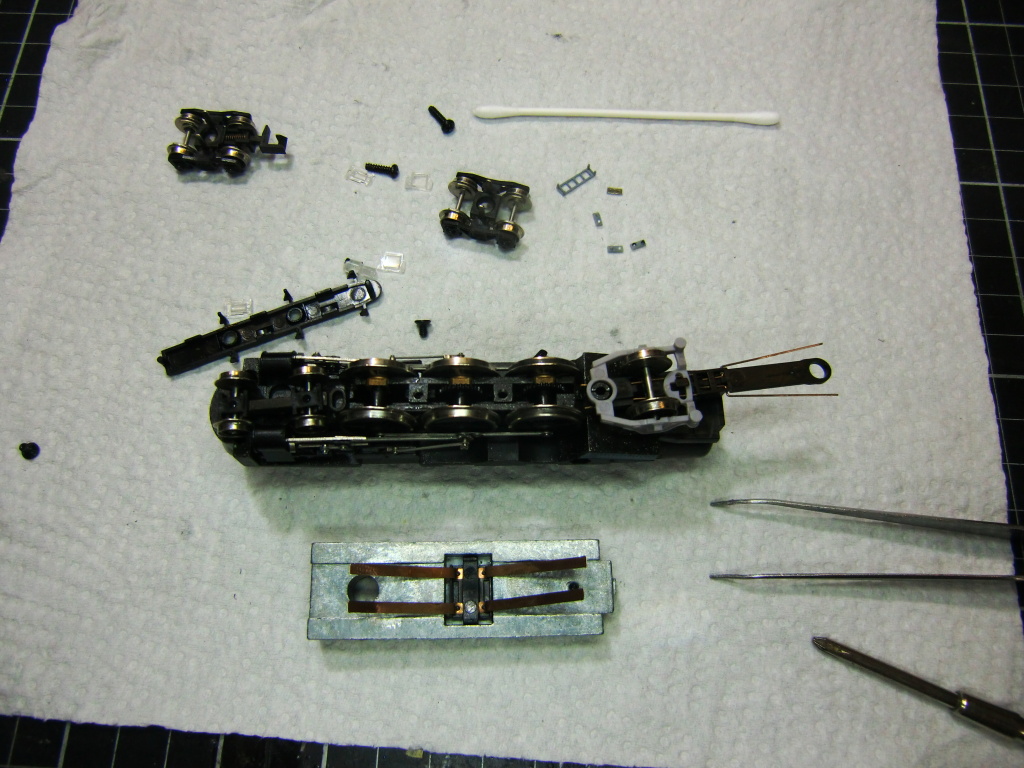


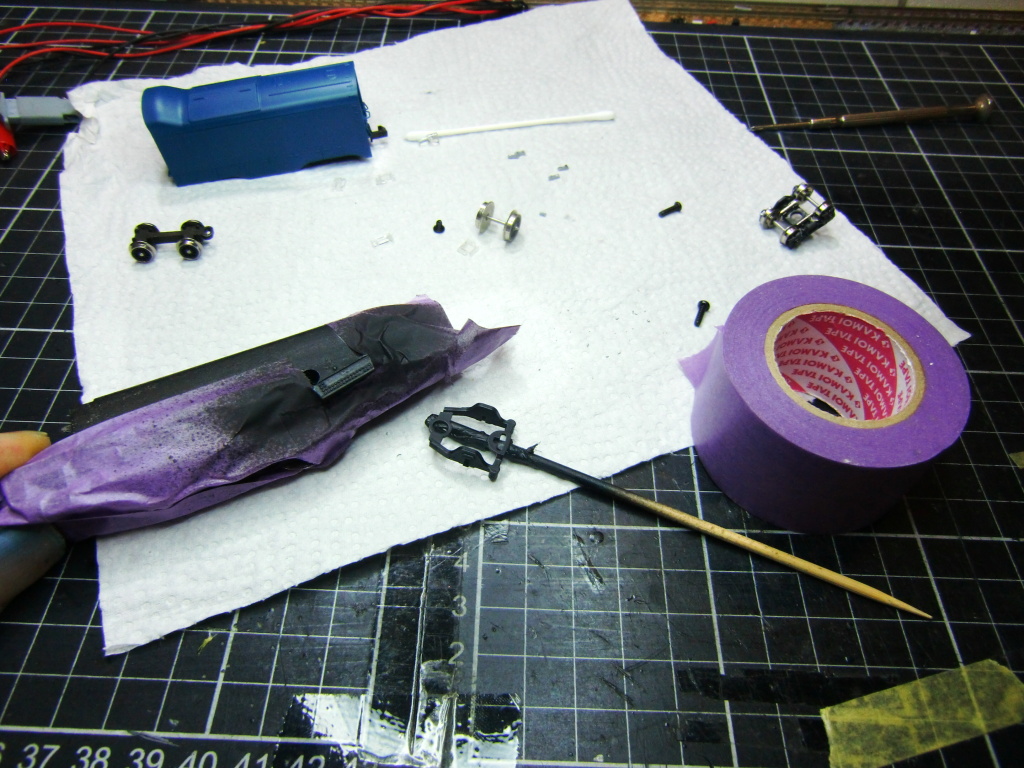
床下は黒で塗装します。

走行テストと調整を繰り返します。良さそうです。

本体の塗装も終わり、仕上げとして手すりをシルバーで筆塗りしてあります。


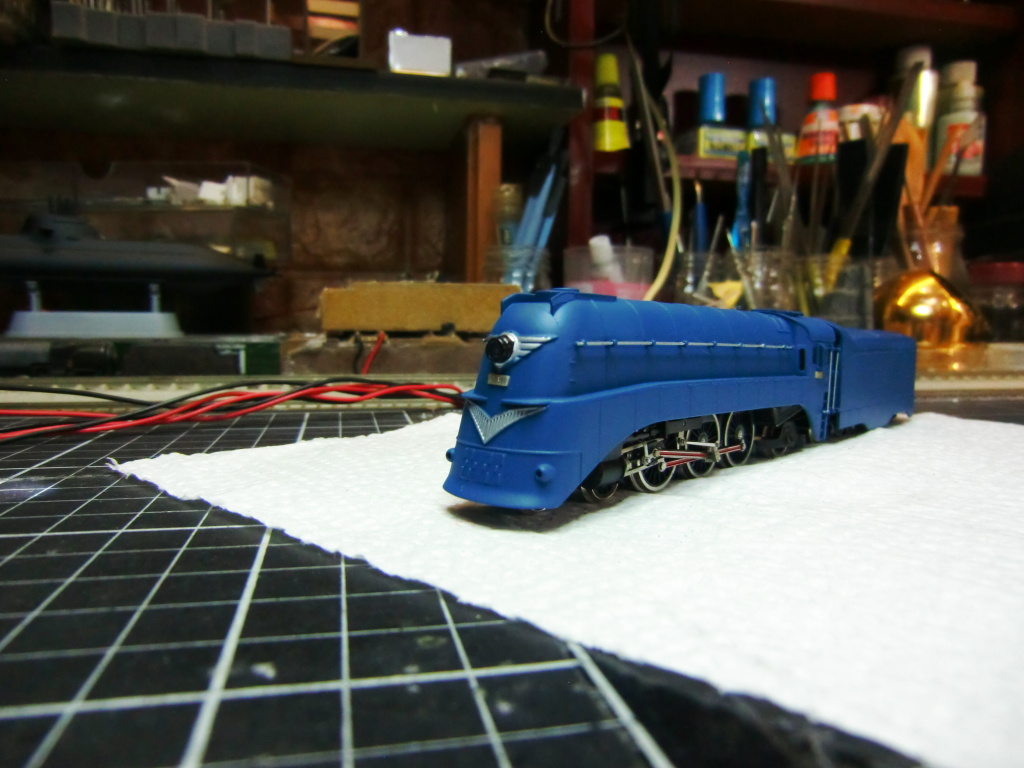
古いデジカメで撮影している関係で、色が明るくなりすぎてしまいます。実際には、かなり深みのあるダークブルーに仕上がっております。作業完了でございます。
まずは、機関車から作業にとりかかります。ご依頼者様のご要望として室内灯を入れたいとのことです。


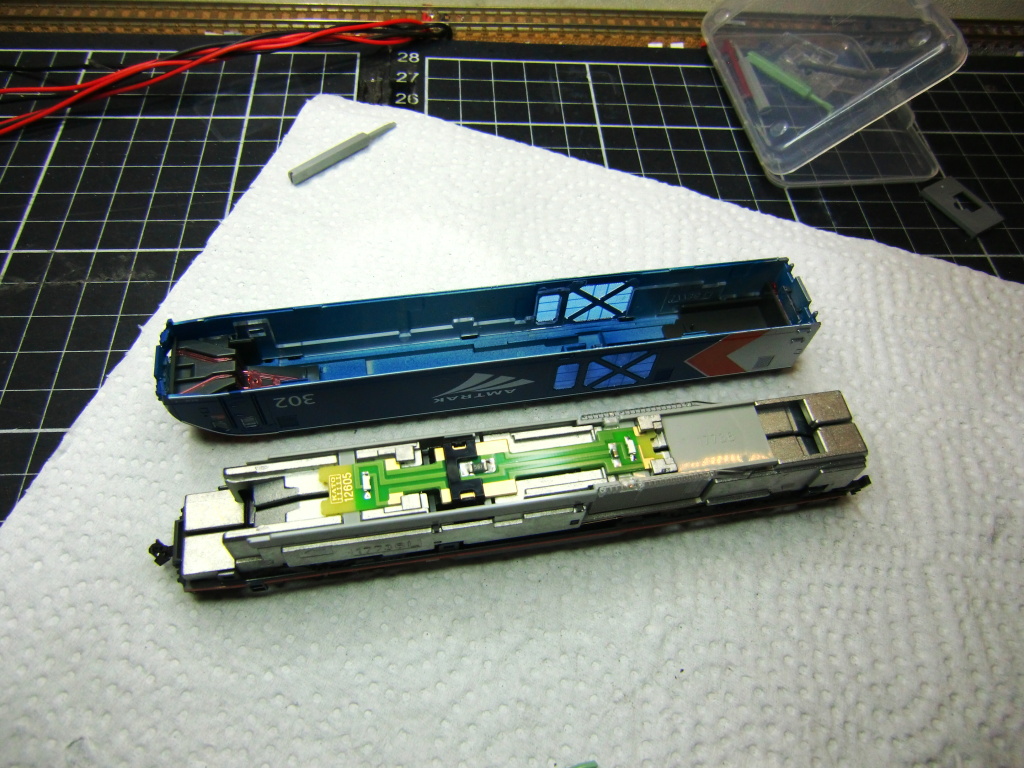
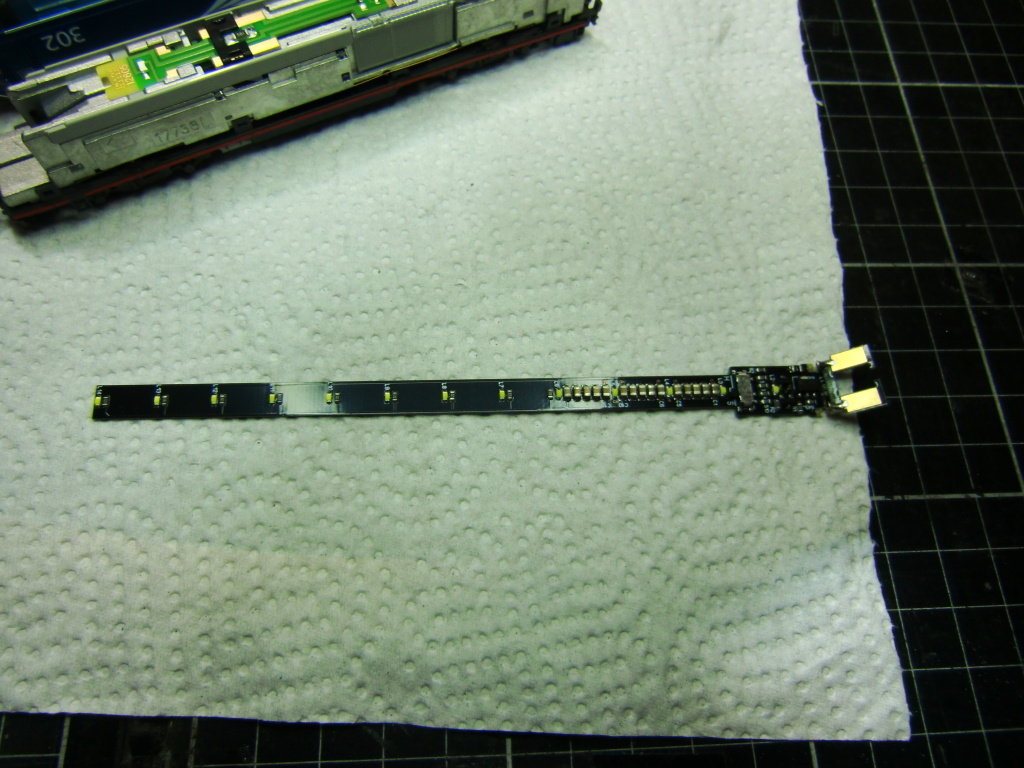
お持ちいただいた室内灯は基本的にどの機関車にもまず入りません。機関車の内部は通常スペースはないだけでなく、もともと室内灯をつけるようにできていませんので、なんらかの加工が必要になってきます。
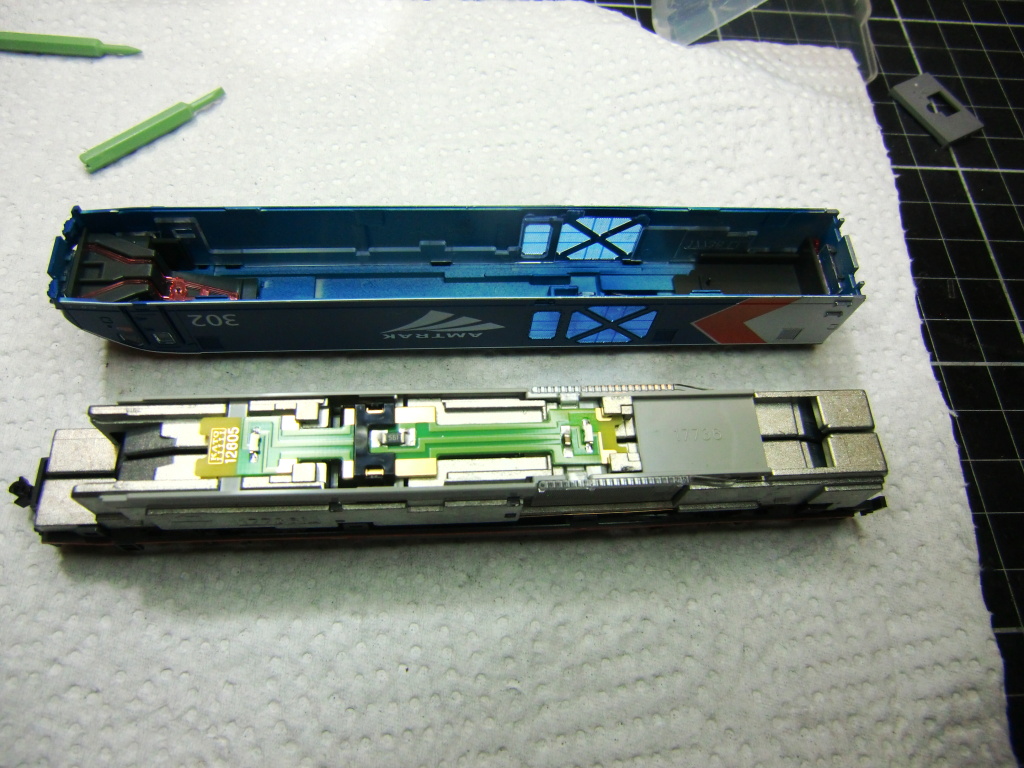
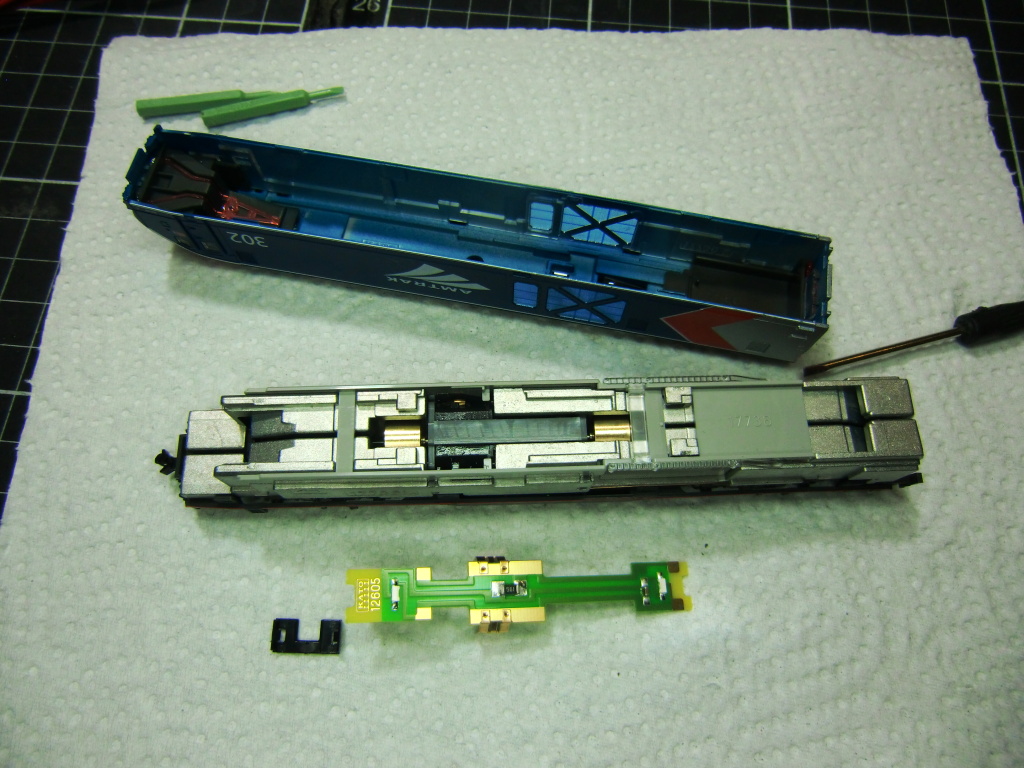
内部のパーツ構成と構造を確認して、どのような手順で行うかを決めていきます。

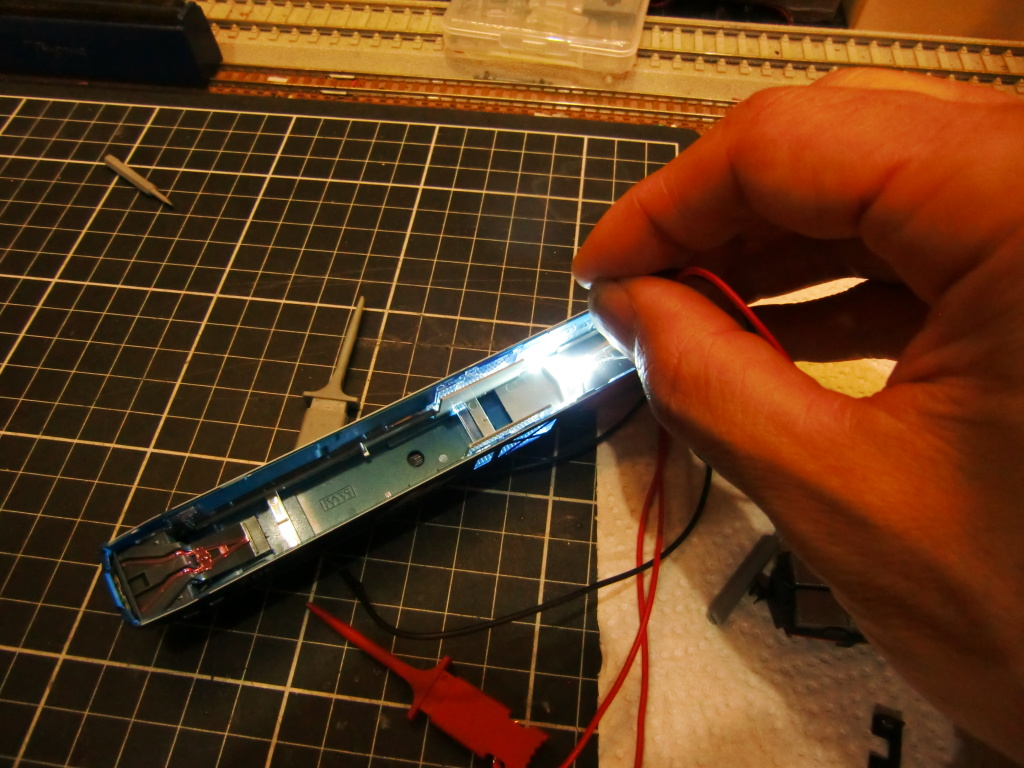
3mmの砲弾型LEDを後方の導光材に配置して、光具合を確認してみます。
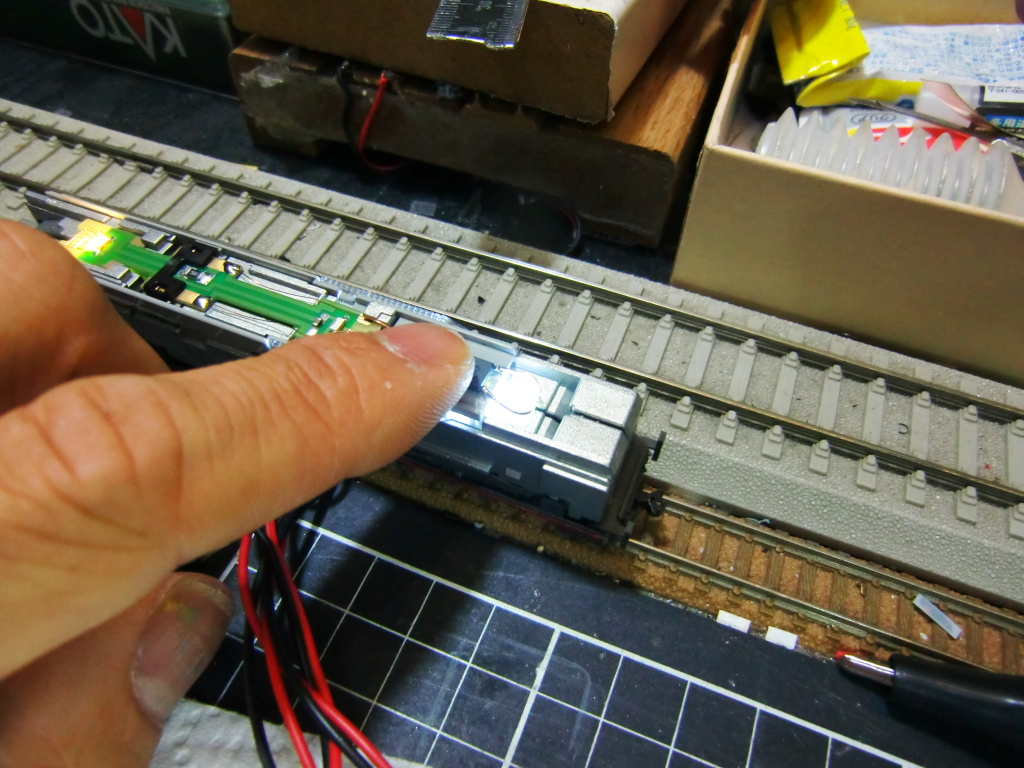
方法はいくつかありますが、ここでは大幅な加工なしにできる方法で作業を進めていきます。

両サイドの側面が発光しているのがわかると思います。

ボディーを被せて光り具合を確認して問題なければ完全に閉じます。

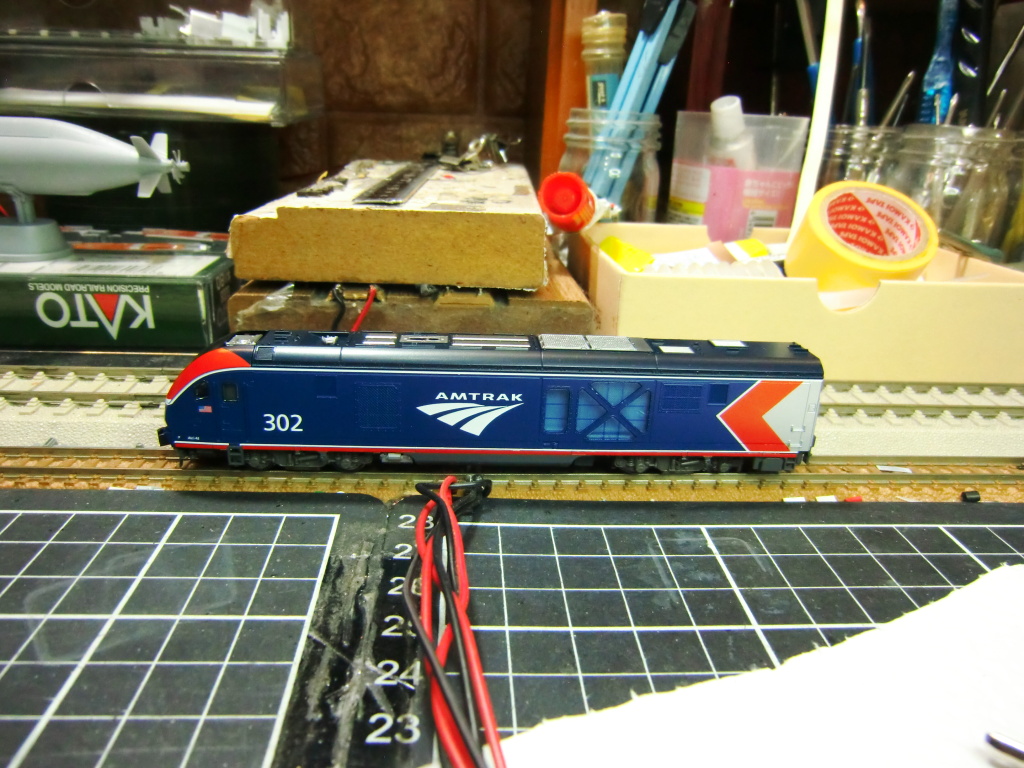
機関車は作業完了です。次は客車です。
片側のテール点灯改造です。

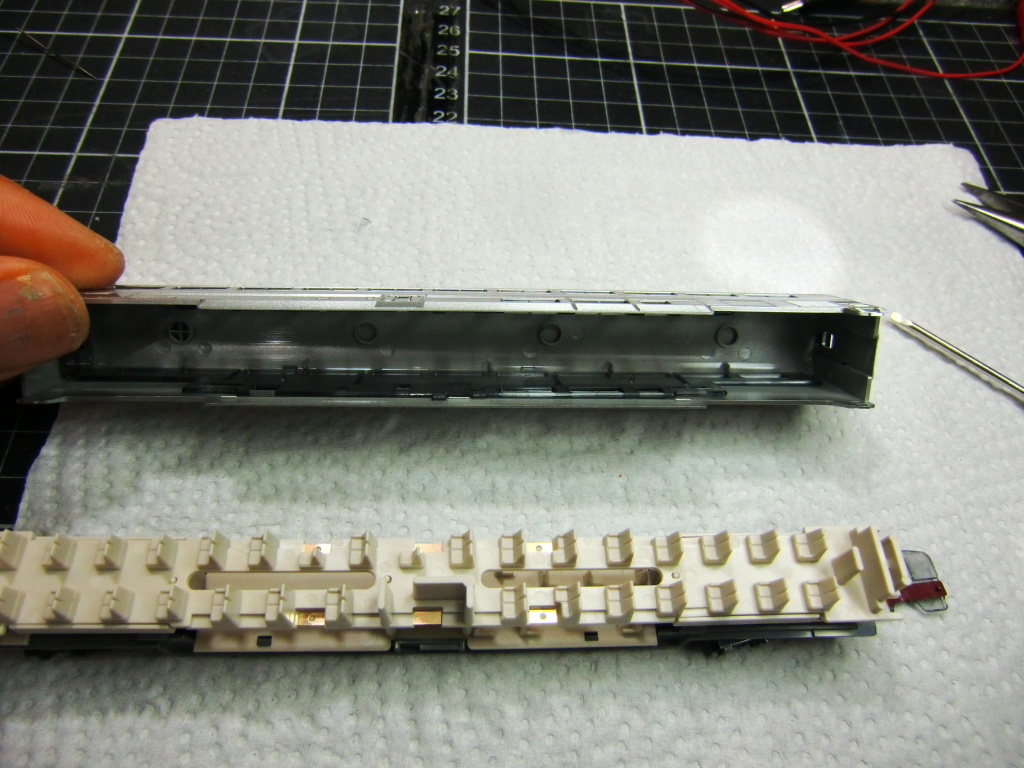
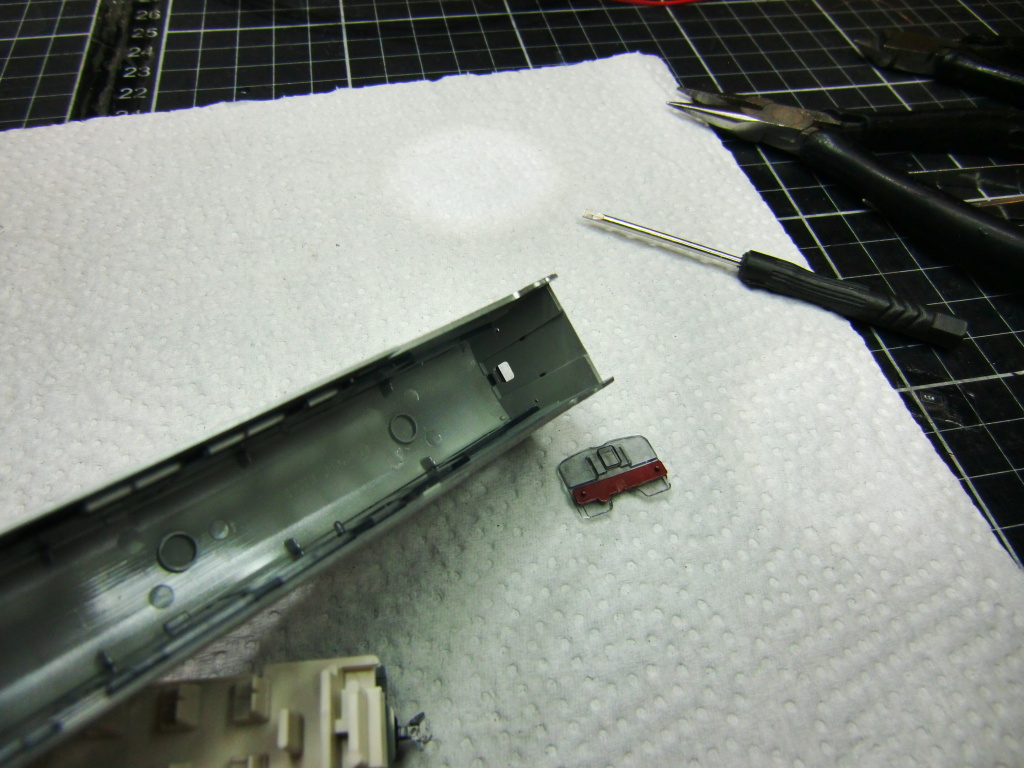
部品を抜き取ります。
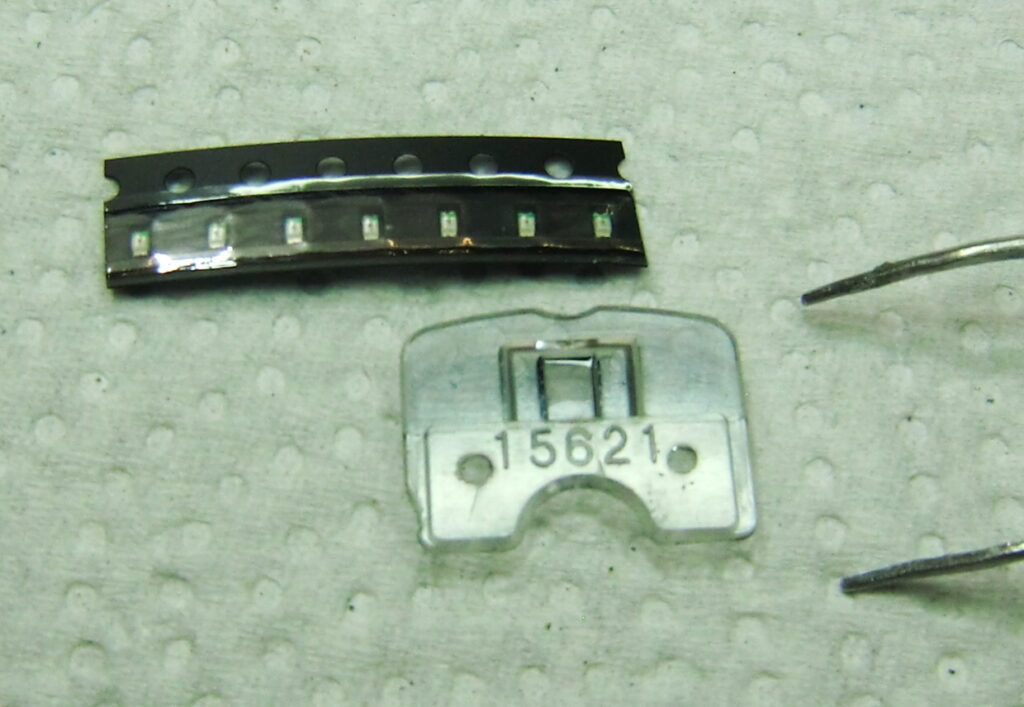
少し穴を広げておきます。以下、作業工程の写真は省力します。
1608赤チップLEDを左右直列に接続してあります。

何度か分解と調整を繰り返して、このようになりました。

作業完了でございます。
続いてこちらの機関車の修理のご依頼です。

こうして並べてみると、いかにパシナが大きいのかがわかりますね。


まずは現状を把握するため一通り動作確認を行っていきます。
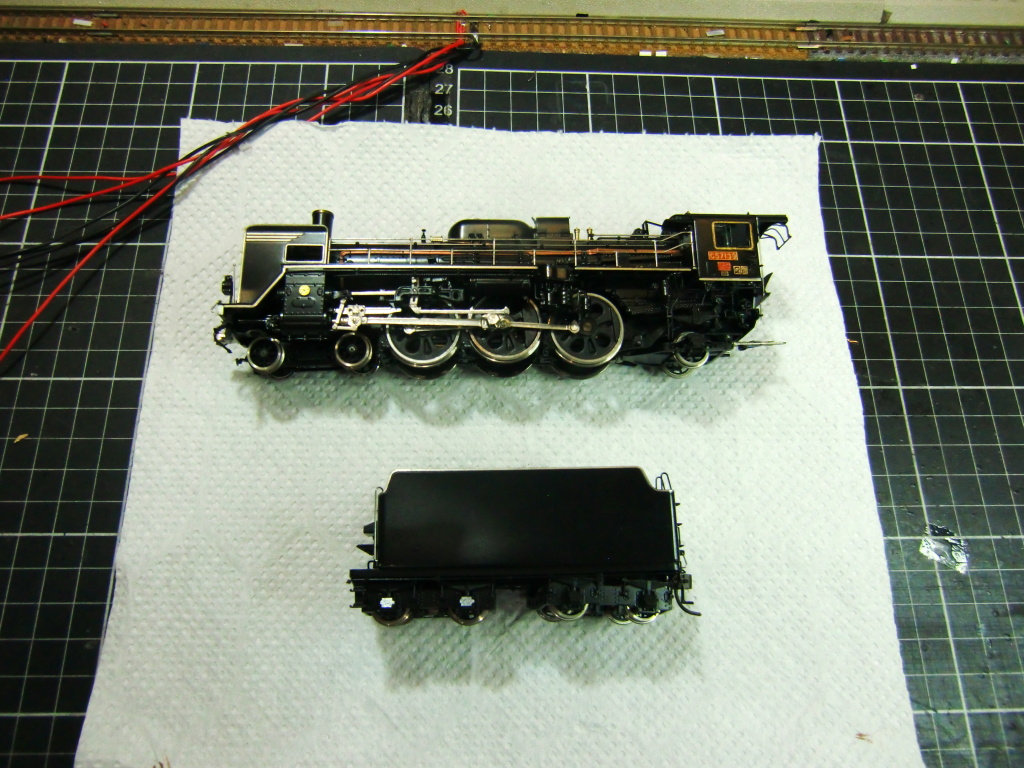
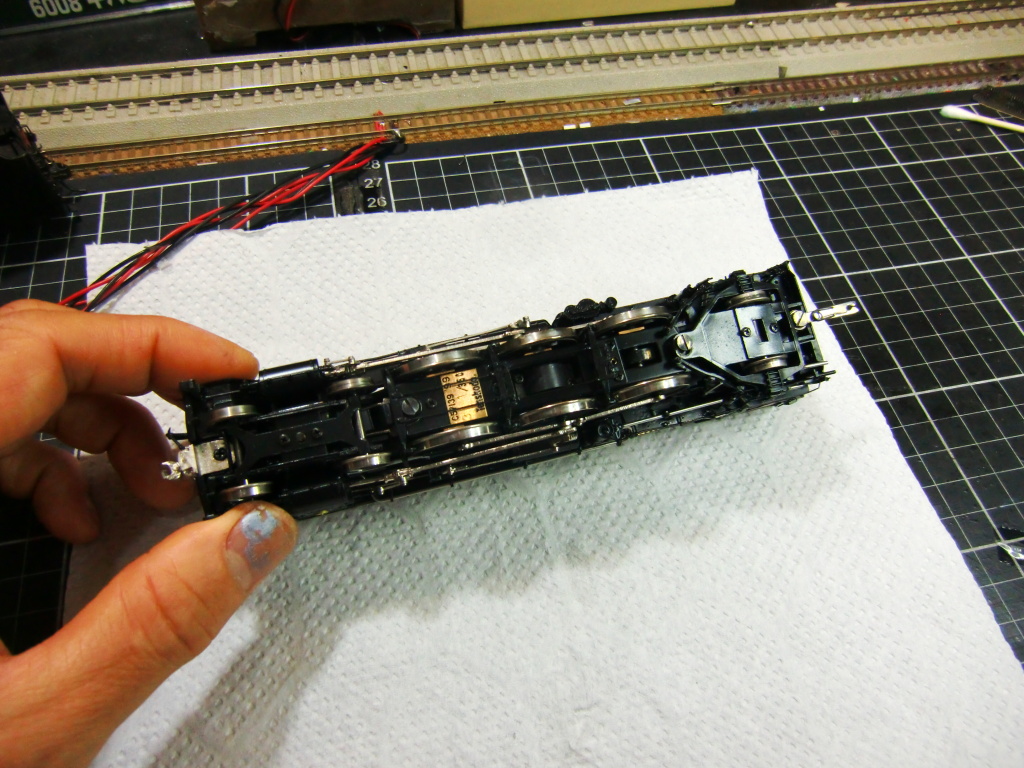
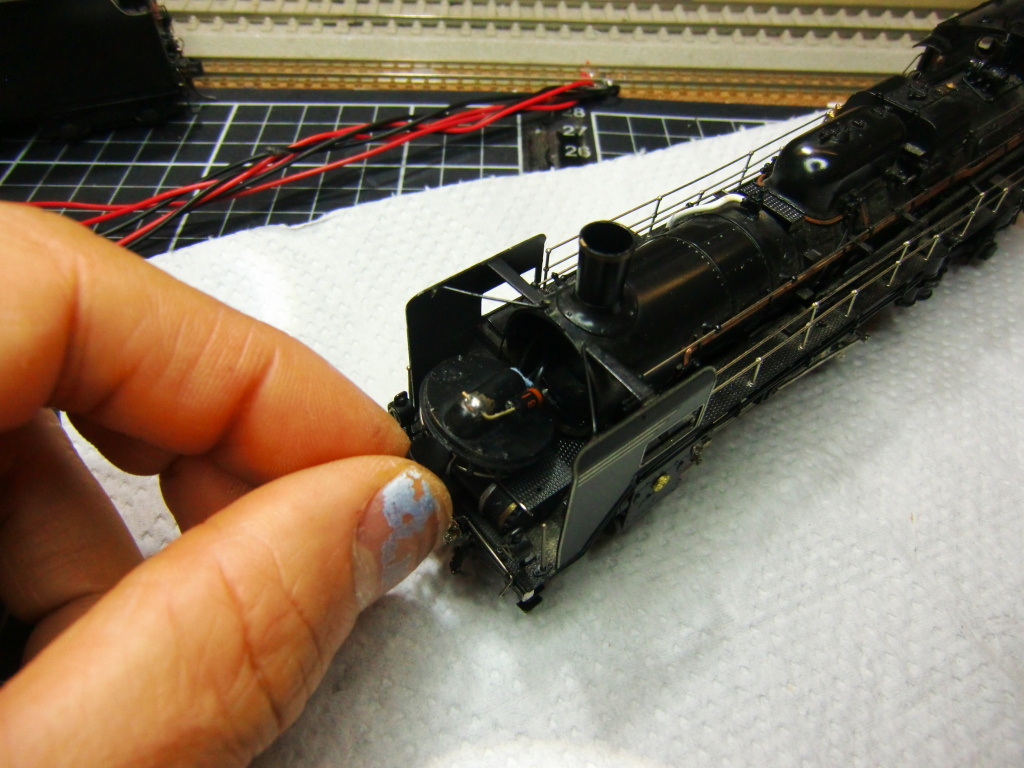
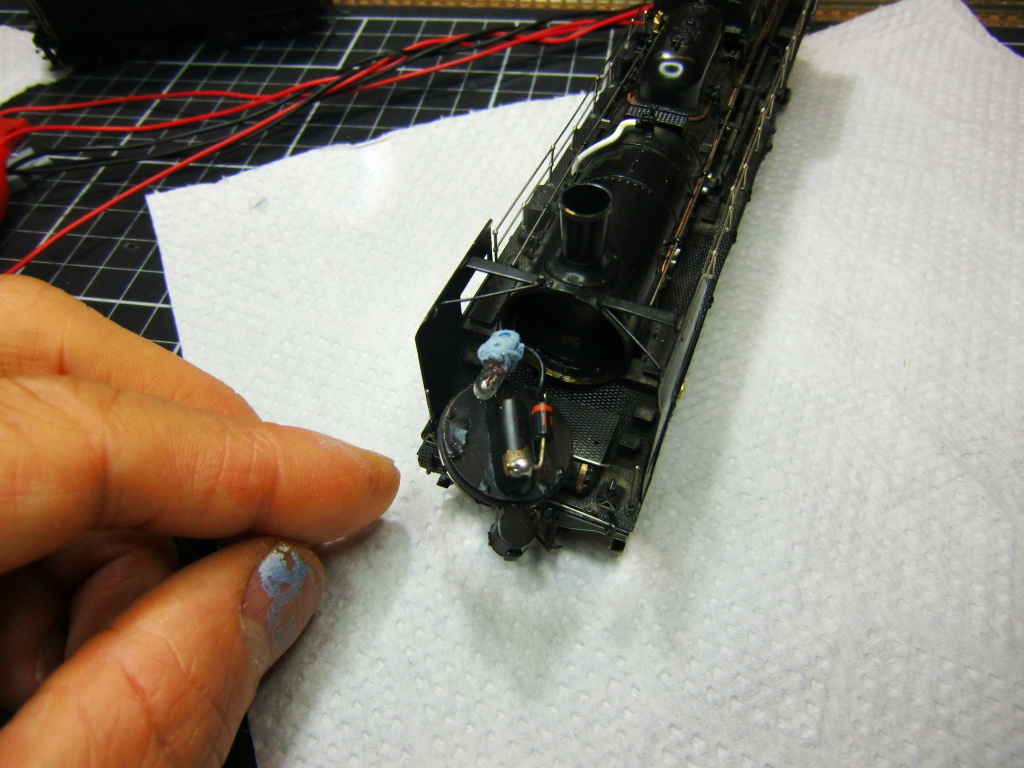
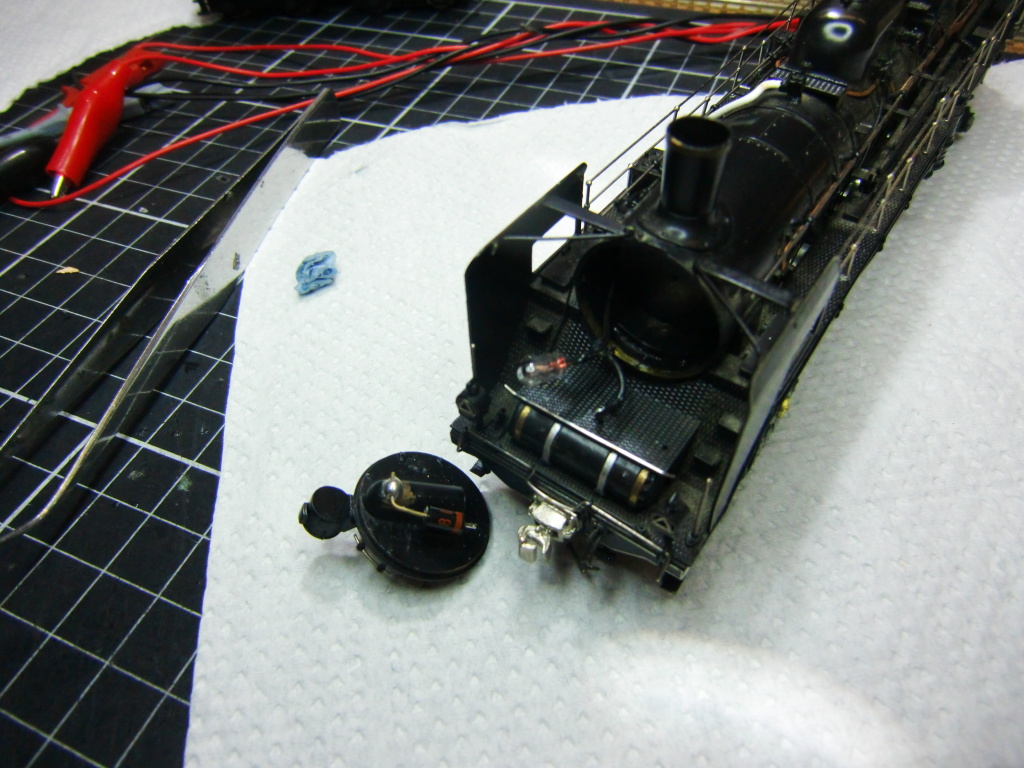
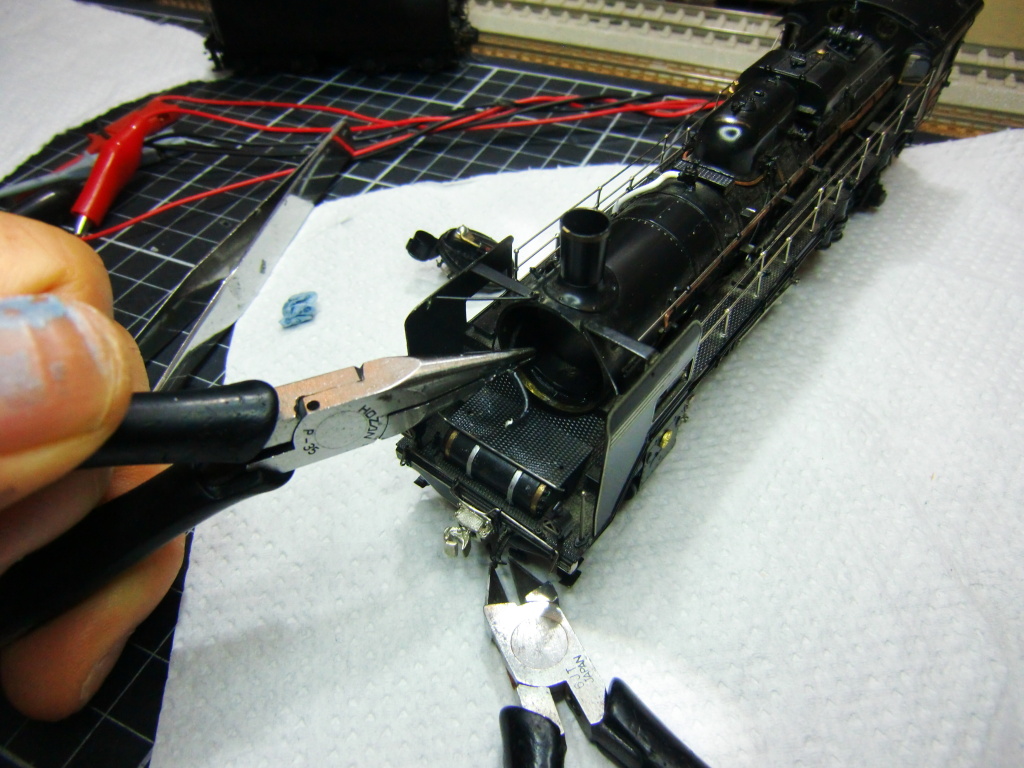
ヘッドライトは電球からLEDへ置き換えます。3mm砲弾型をギリギリまで削ってから内部に埋め込みます。
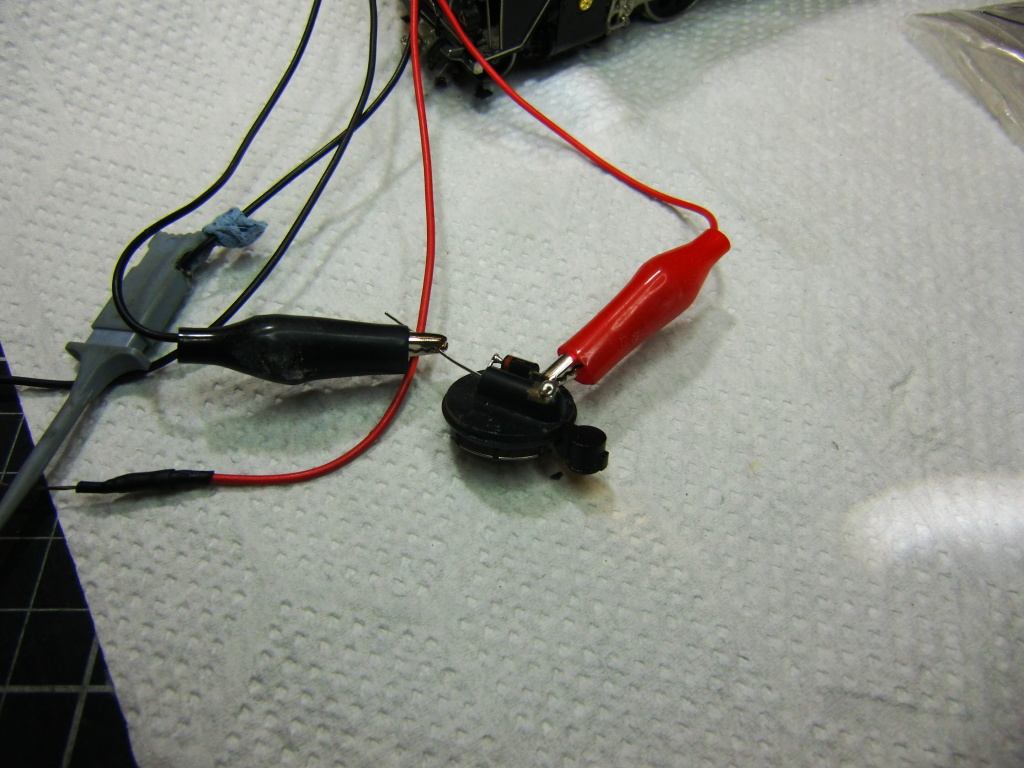
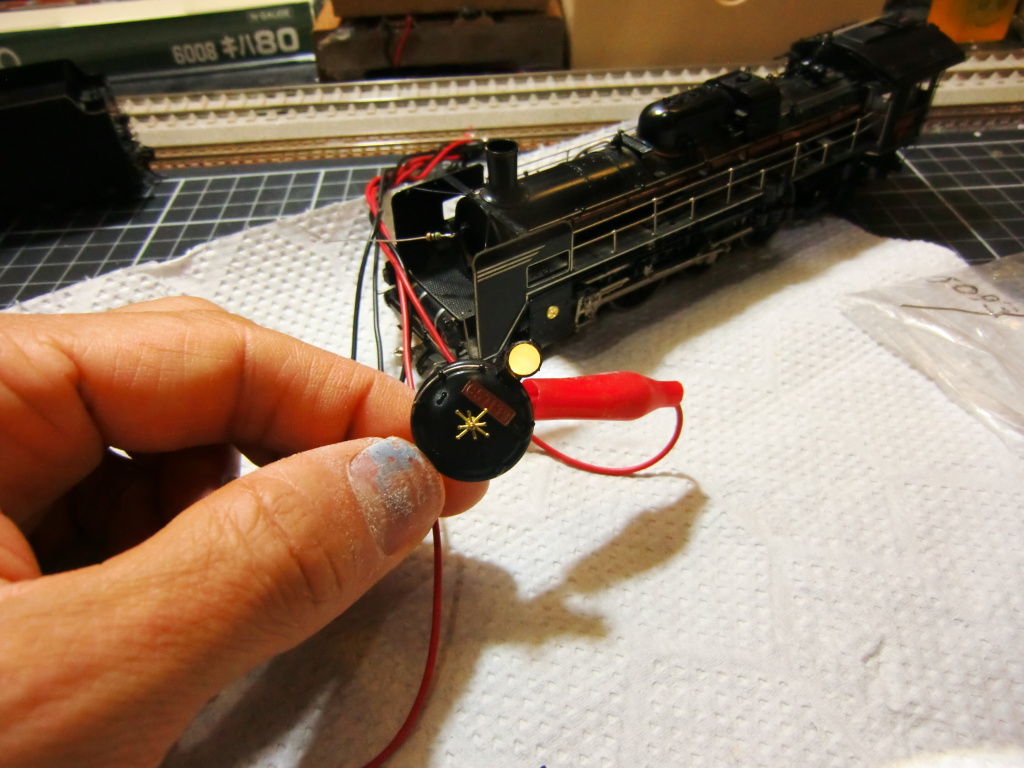
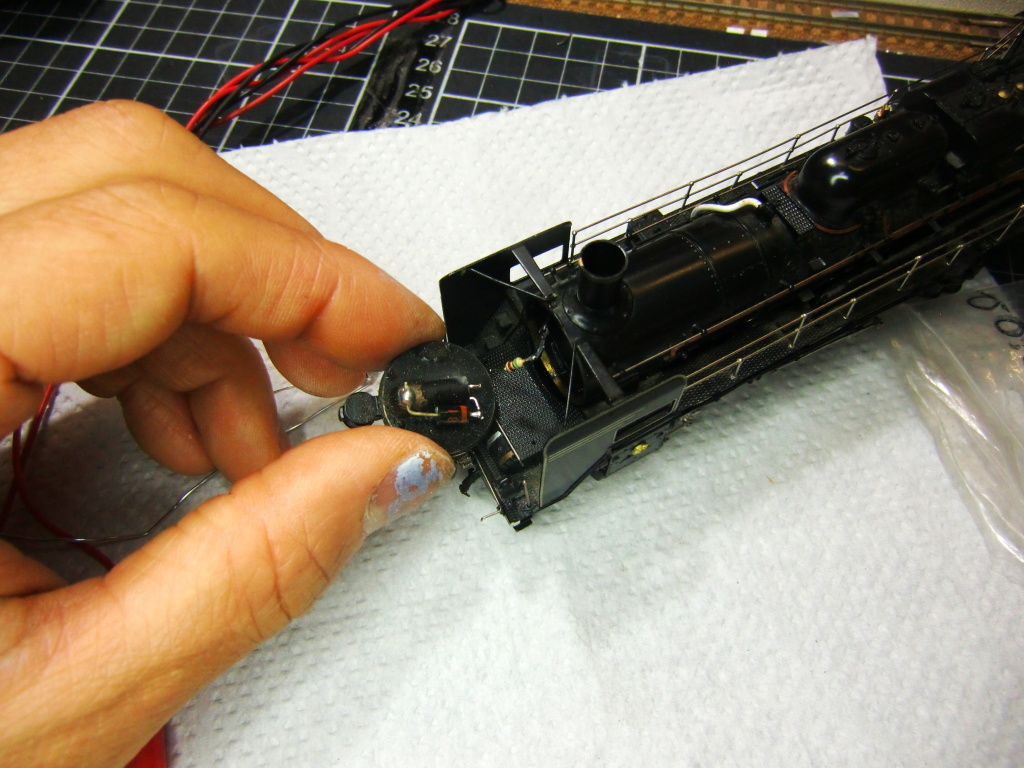
通電のための輪郭部を研ぎ出してはめ込みます。

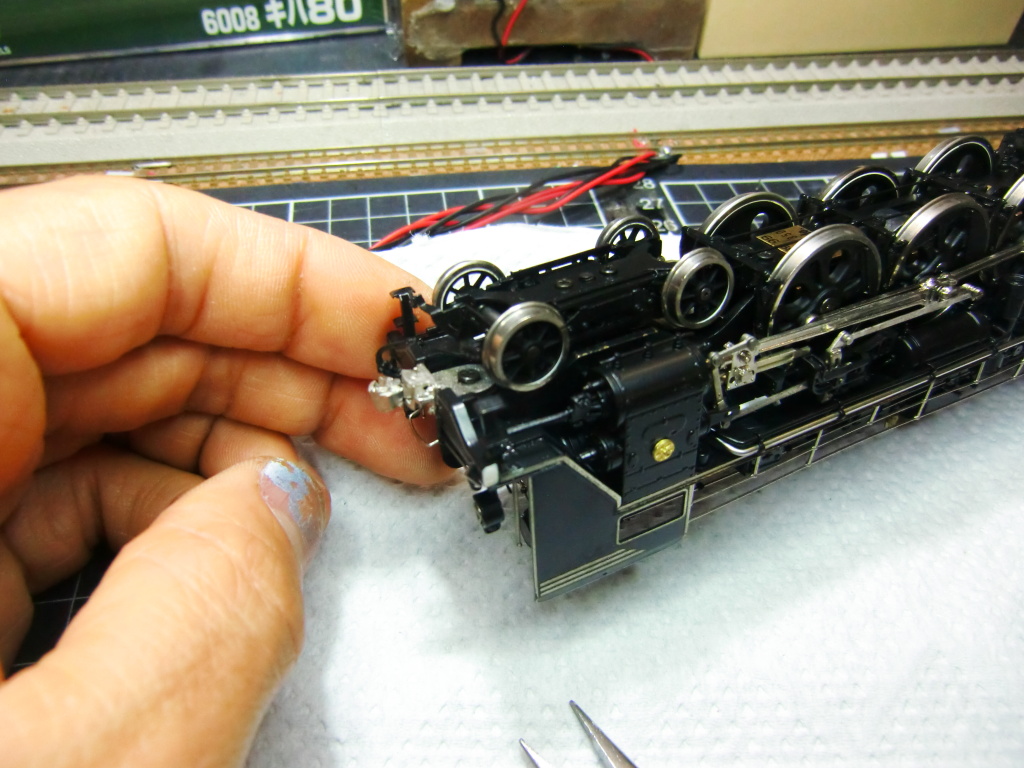
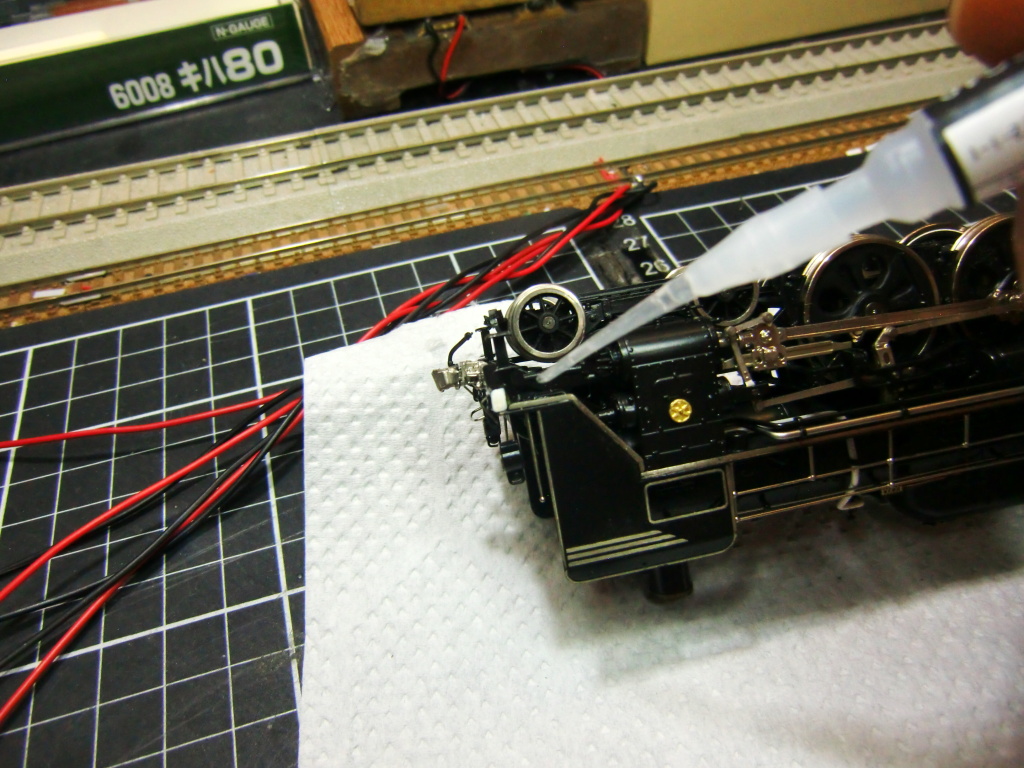
ステップがゴム系ボンドでグラグラしていたので、しっかりと固定しなおしました。


LED化したことで、低速時でもしっかり点灯を確認できるようになりました。
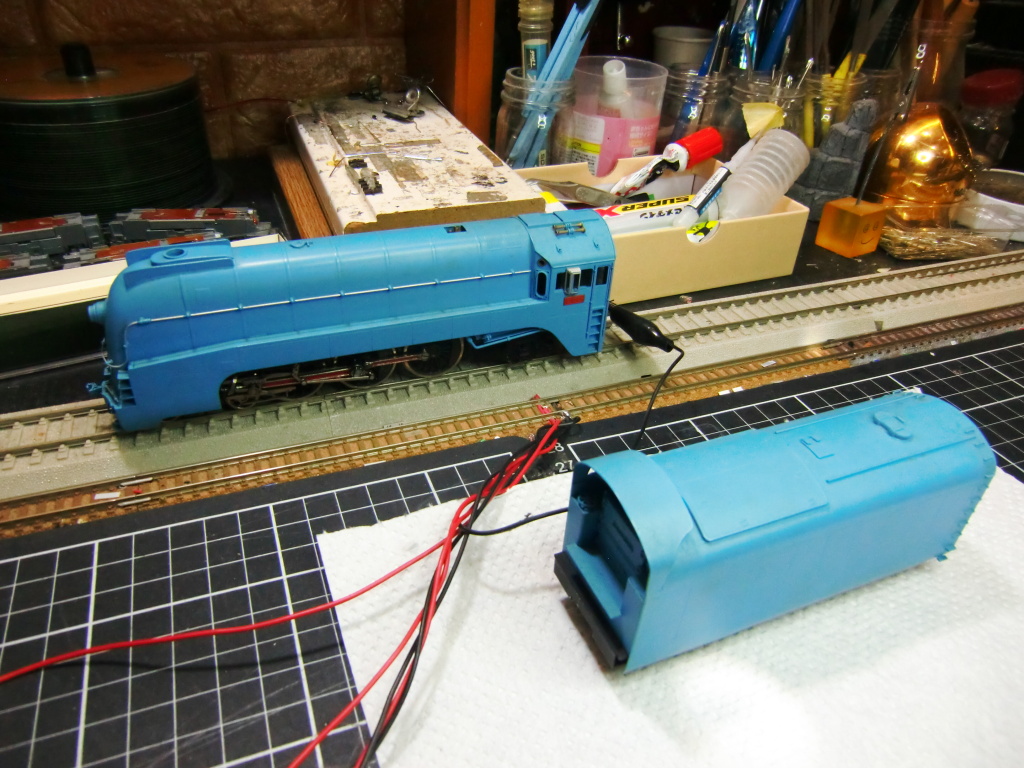
こちらはピクリとも動きませんので、分解していきます。
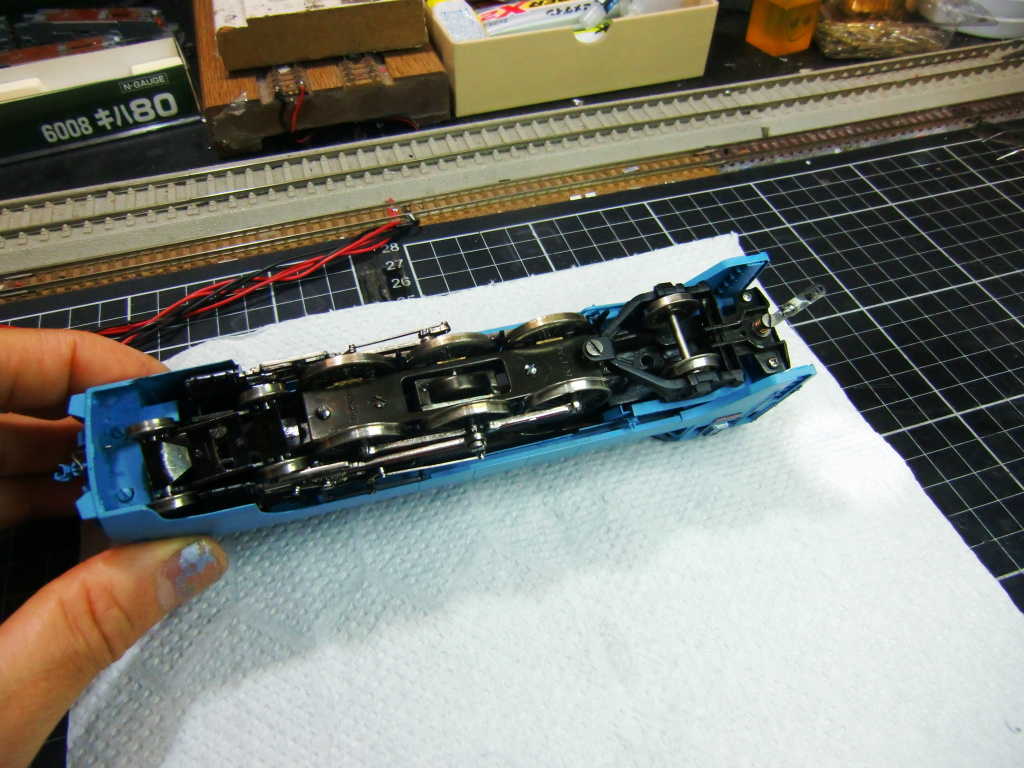
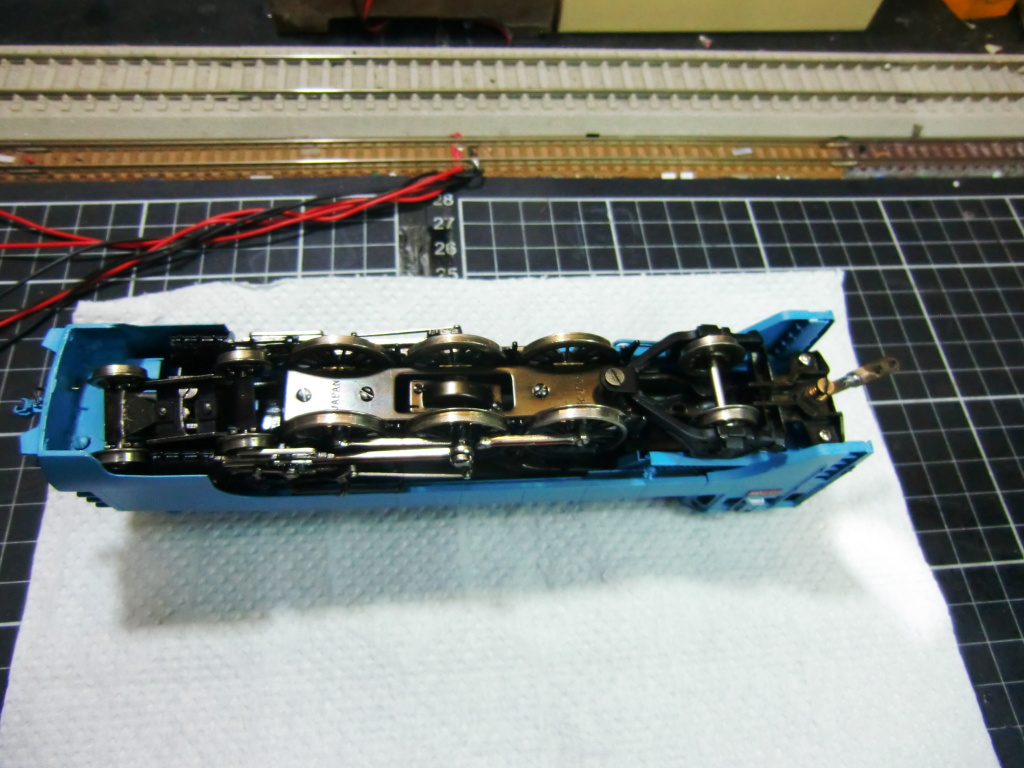
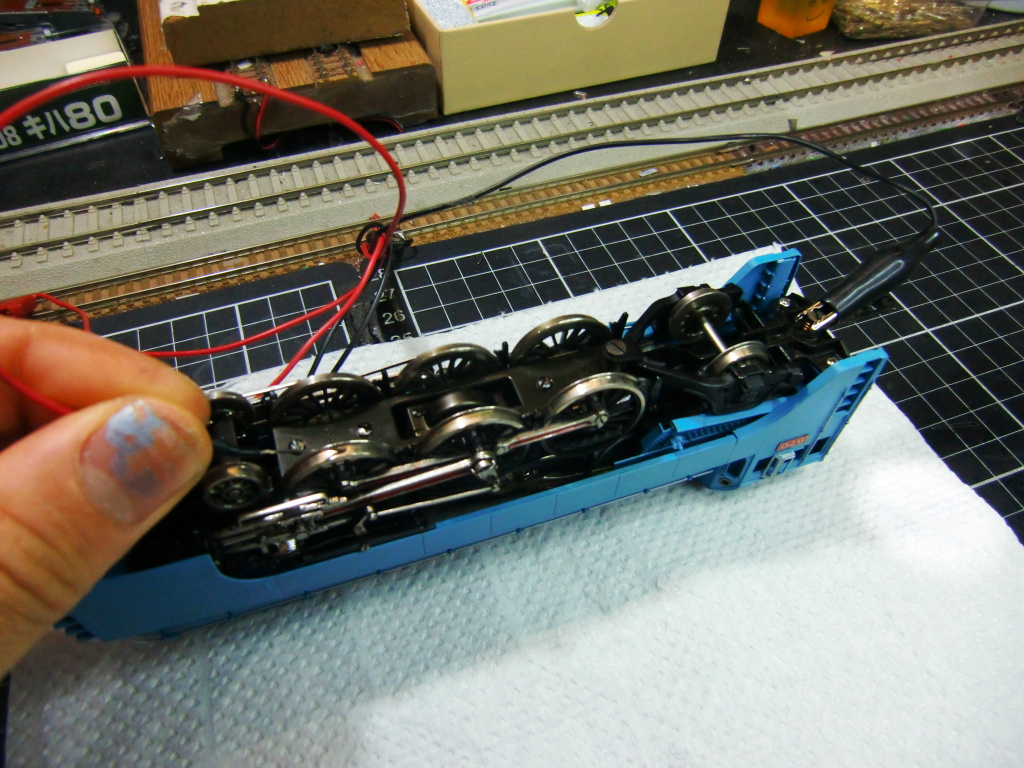
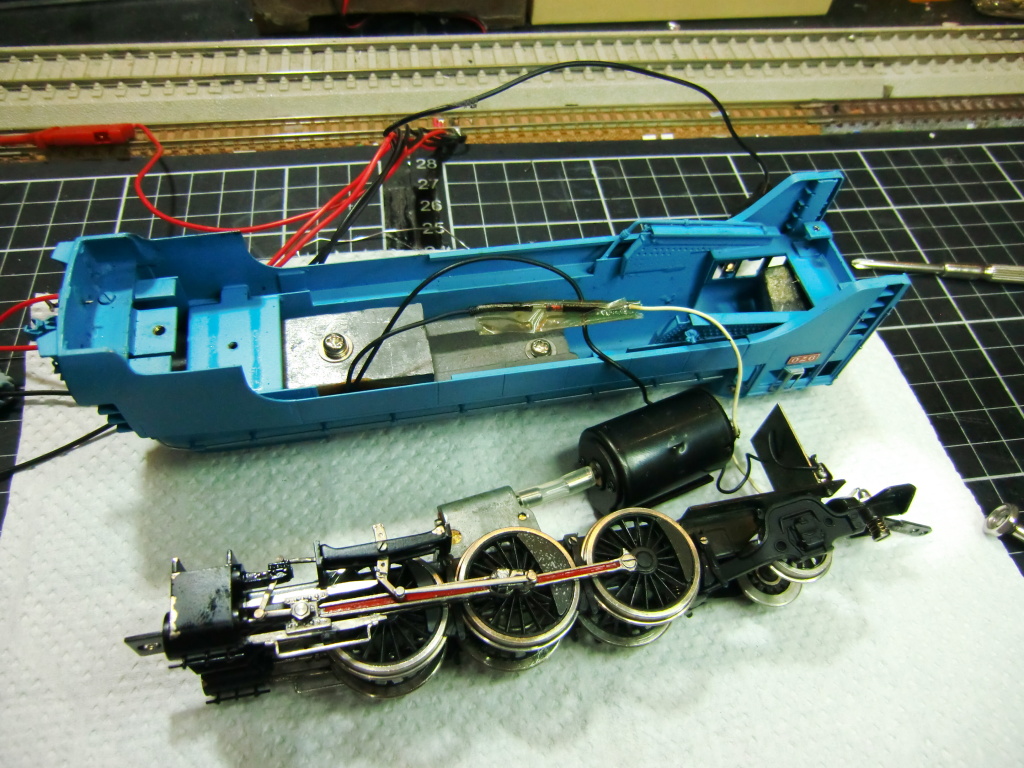
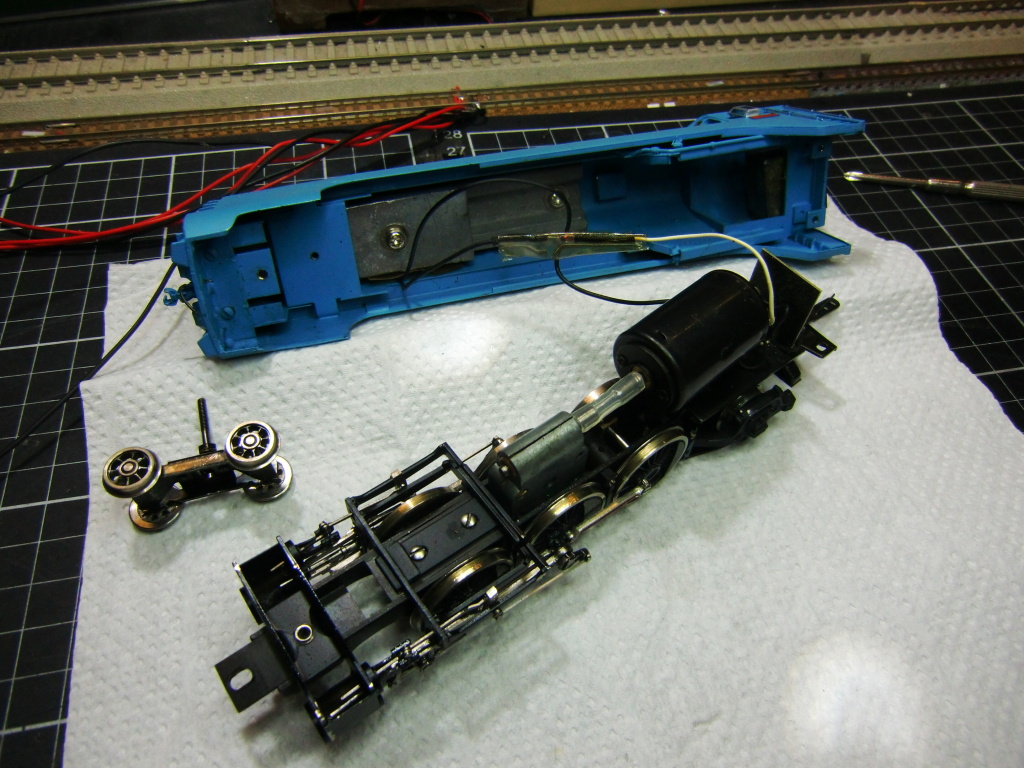
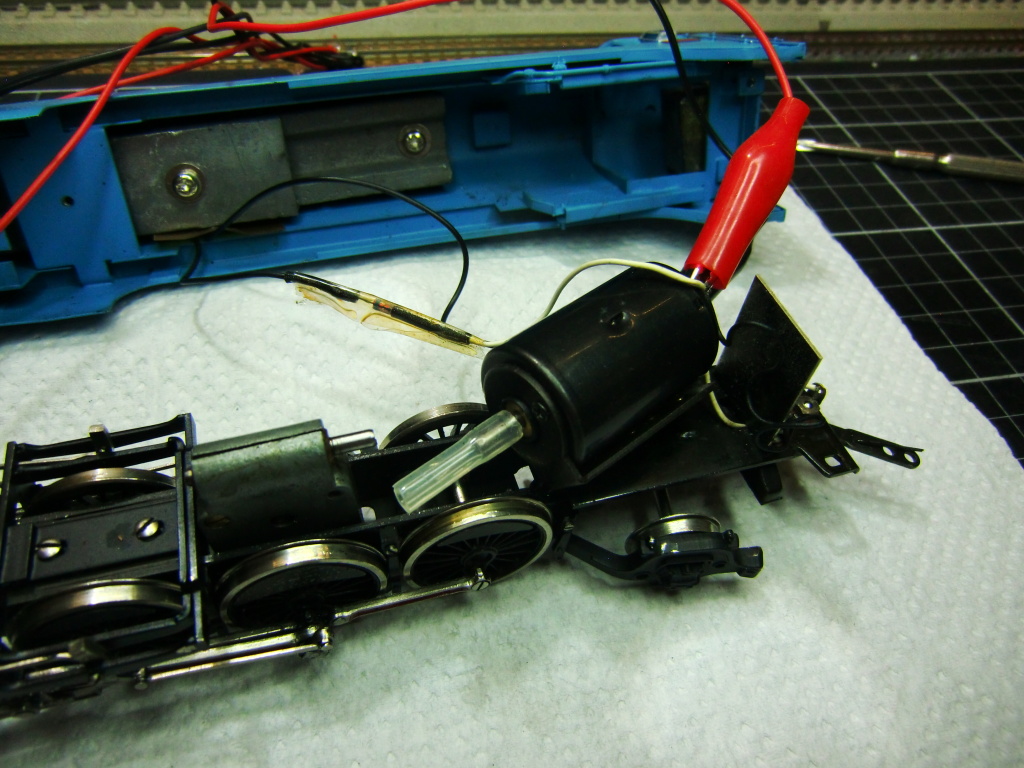
モーター単体でも動きません。さらに調べていくと、機関車のどこかでショートしているようです。この場所を見つけるのは意外と大変です。車輪から各部パーツを1つ1つチェックしていく必要があります。
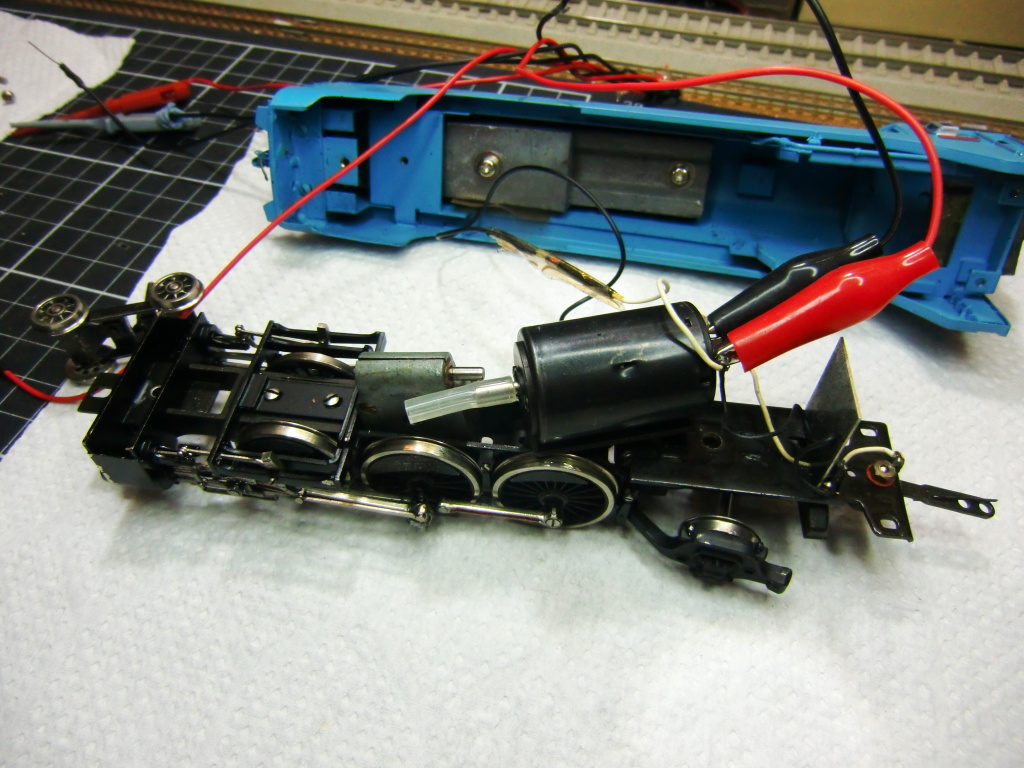
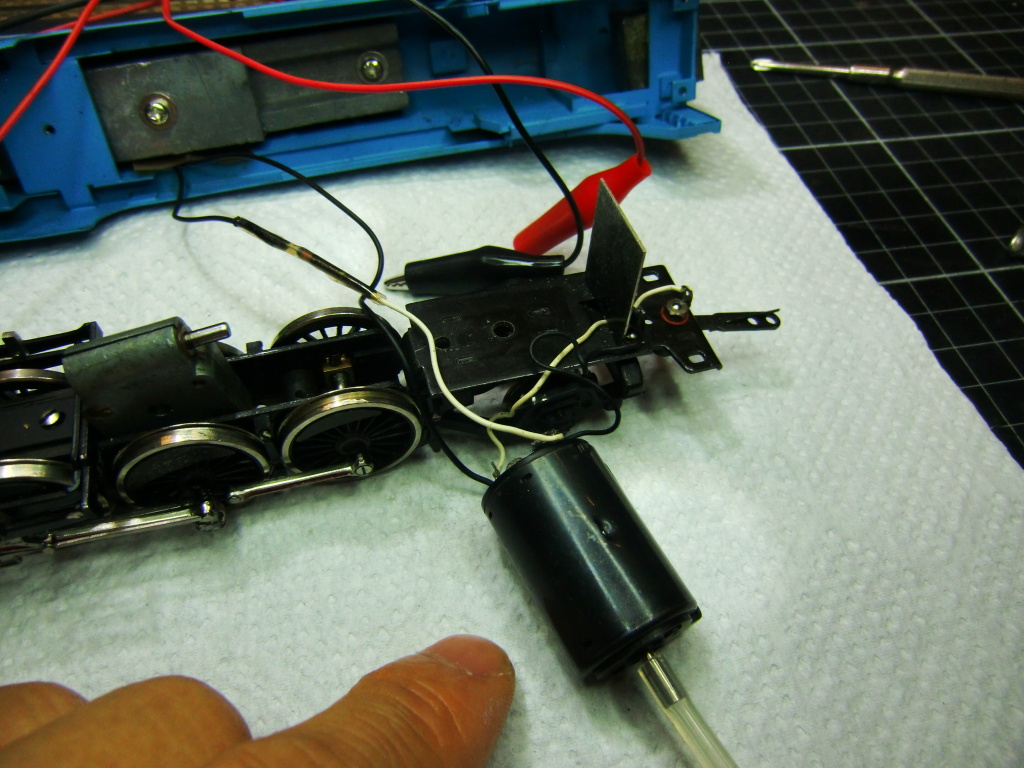

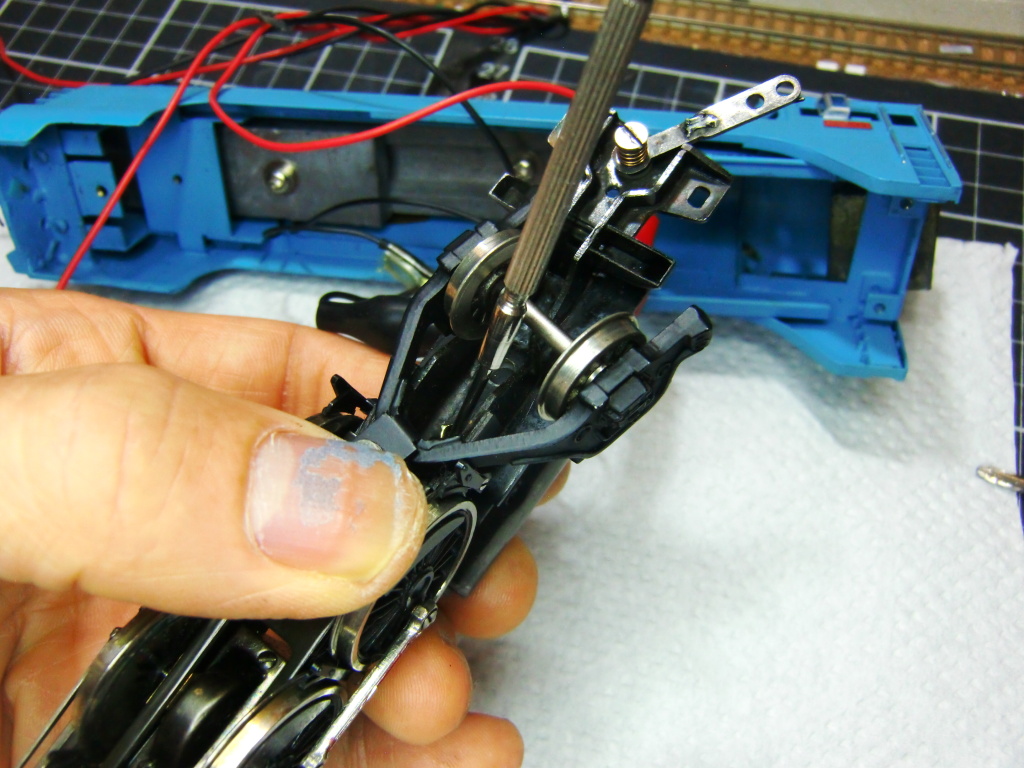


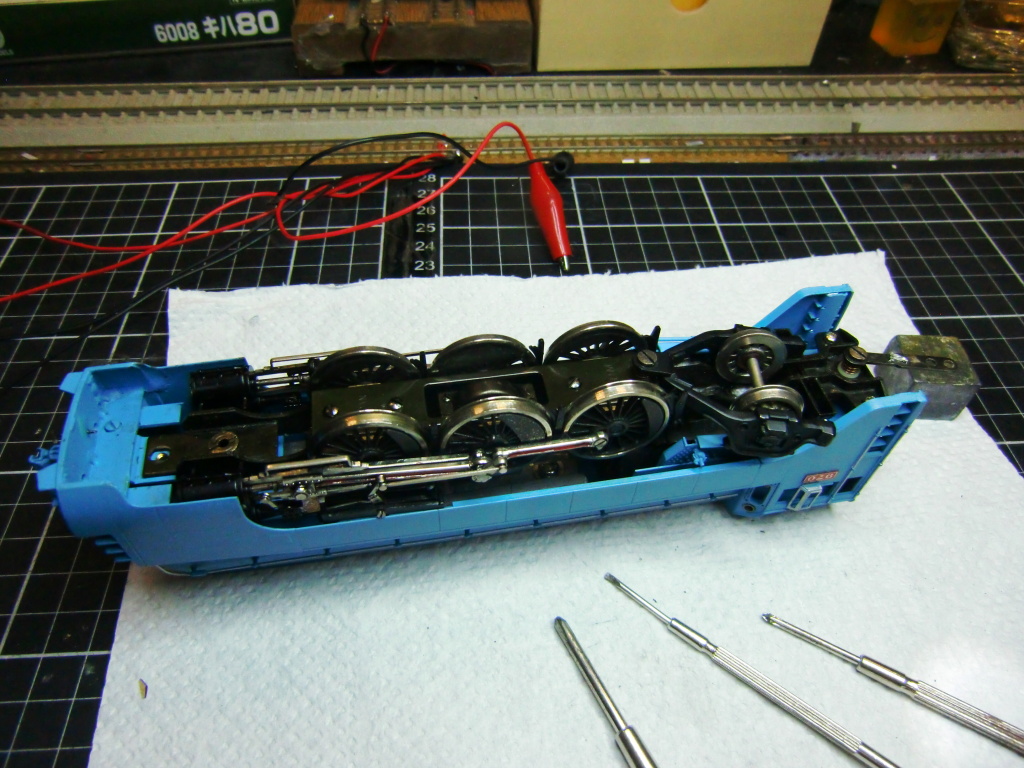
各部の調整を一通り行いました。

走行テストです。

後進の走行にやや違和感があります。もう一度分解します。
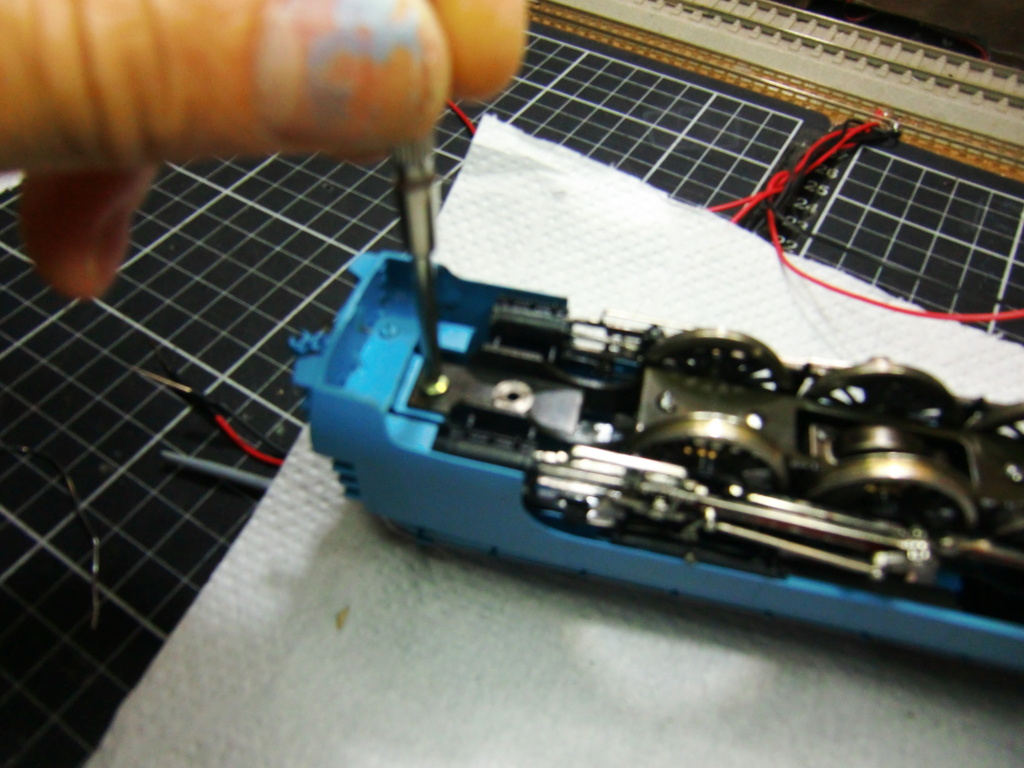
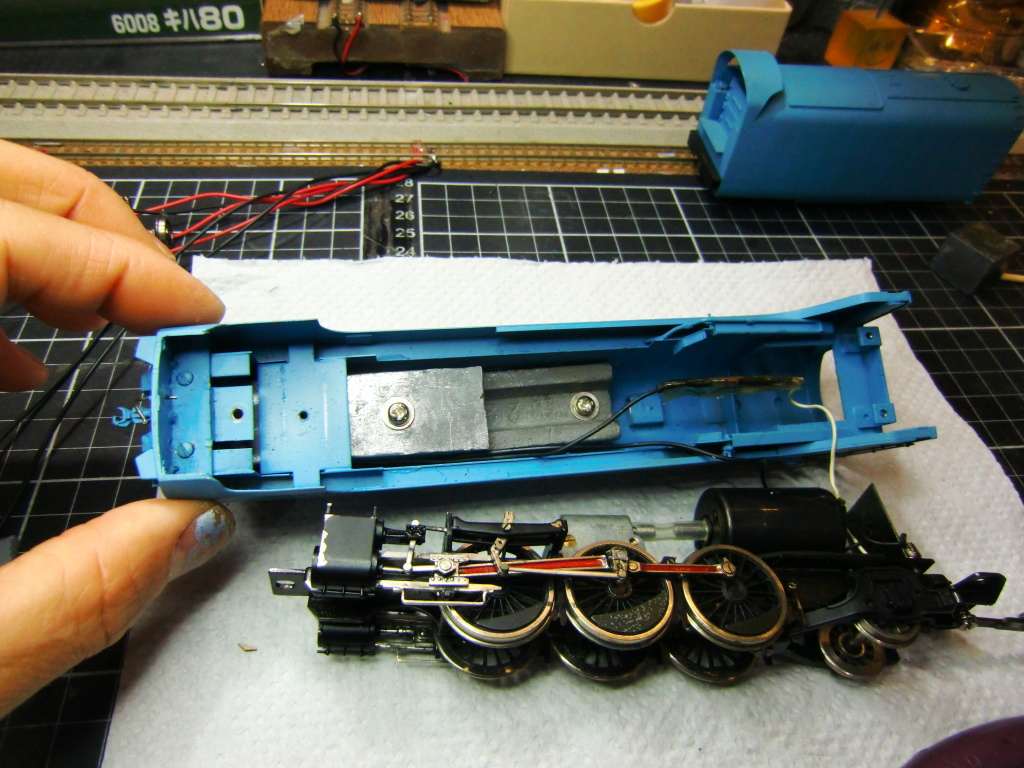
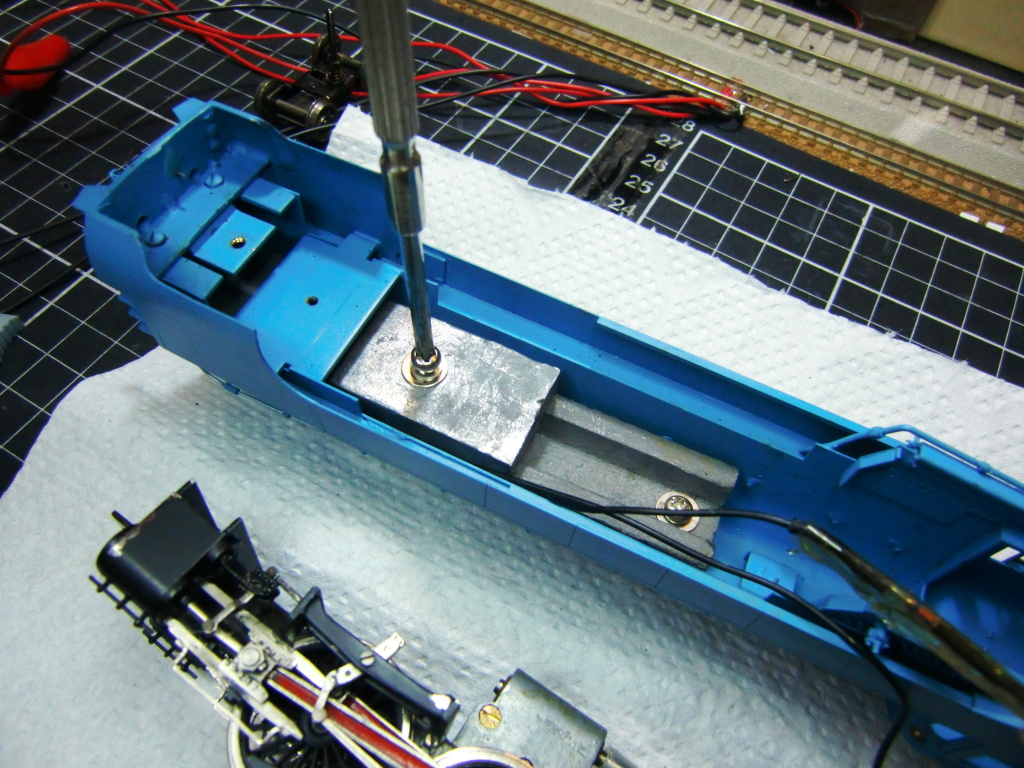
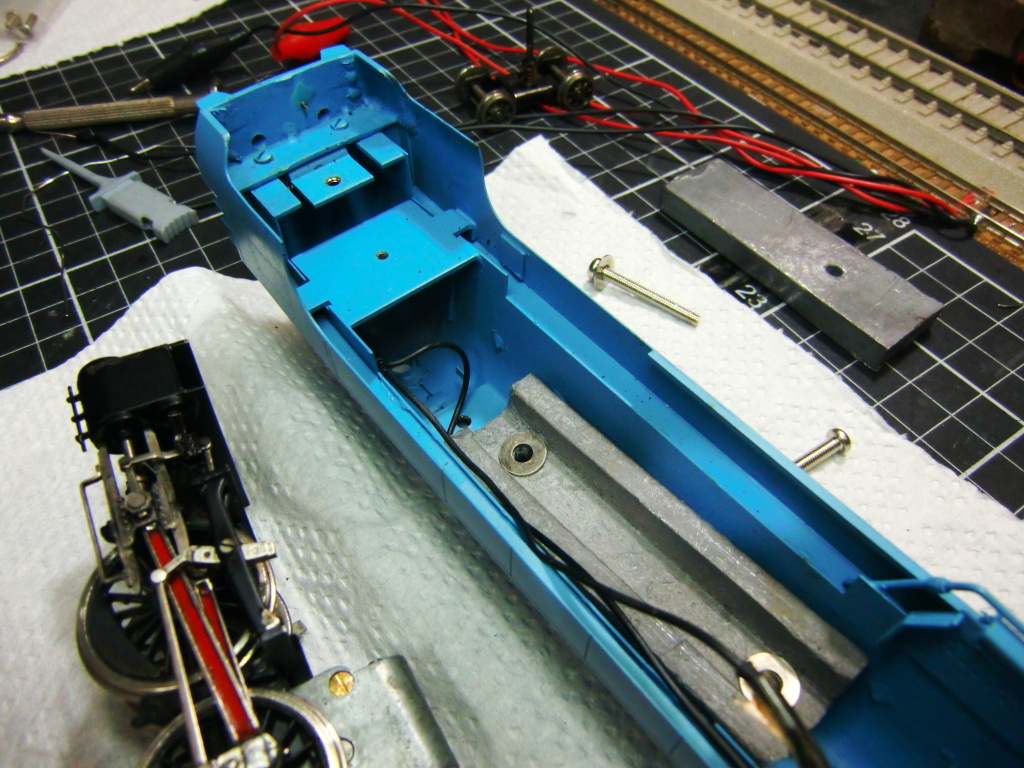
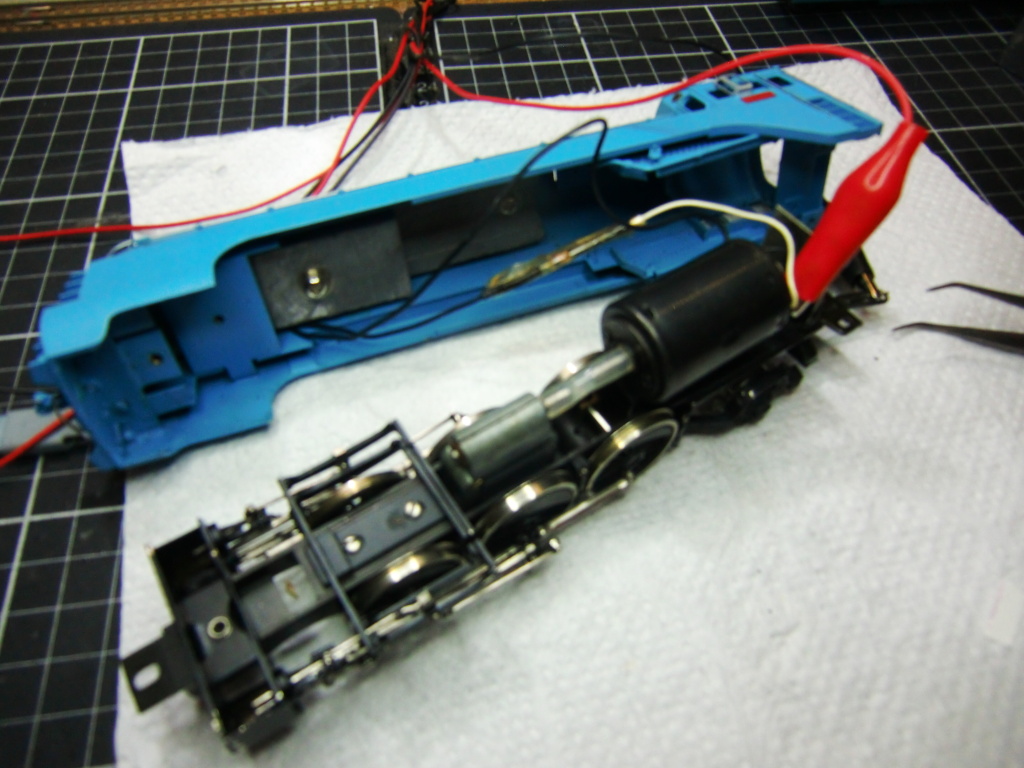
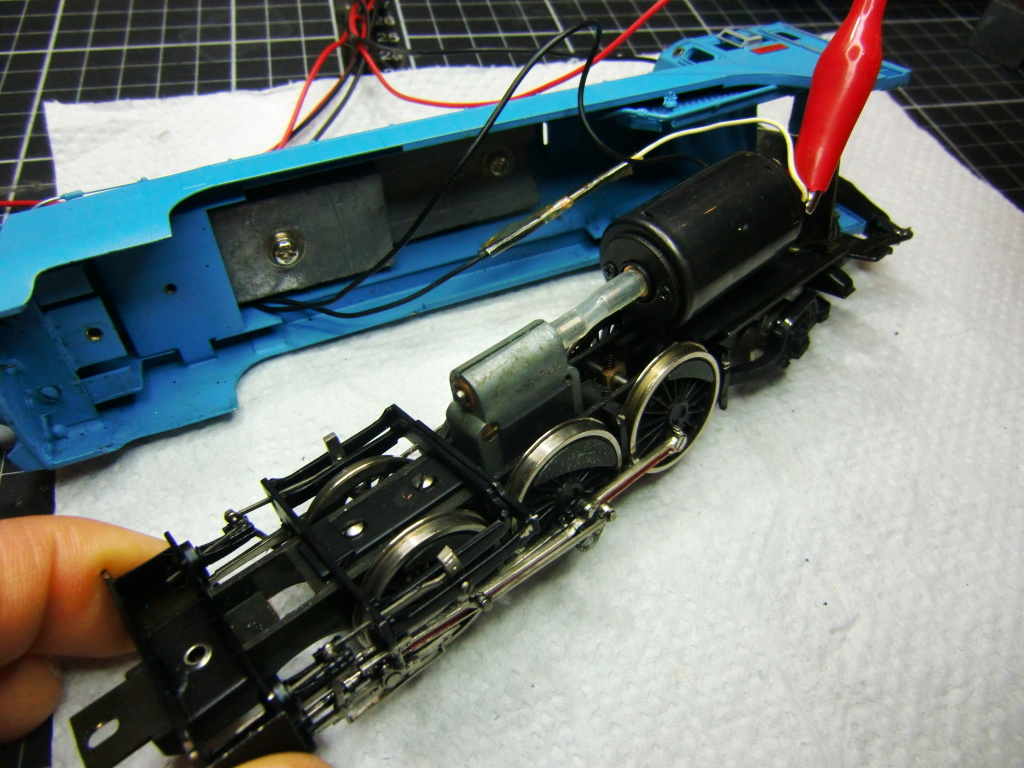
ギアボックスのバタつきを抑えるため、左右にゴムパッドを配置して振動を押さえました。
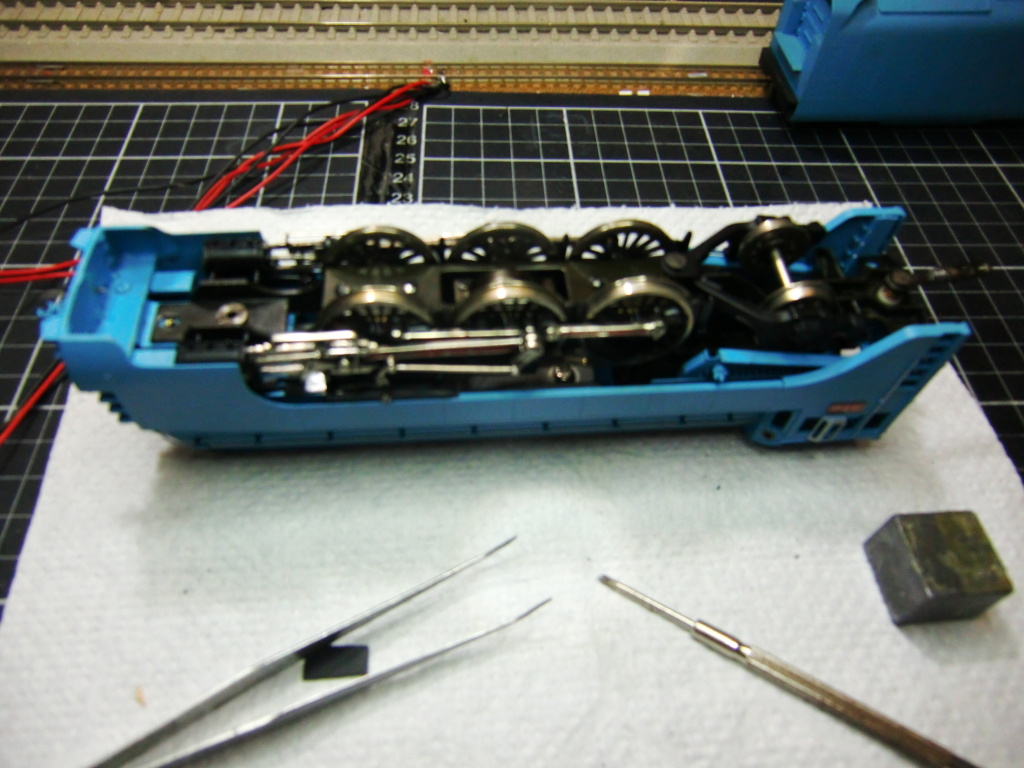

今度はいいようです。前進・後進ともに回転が非常にスムーズでかつ音も静かです。作業完了でございます。
昨年は、「都電6000形」を制作して約1カ月ほど展示走行いたしました。
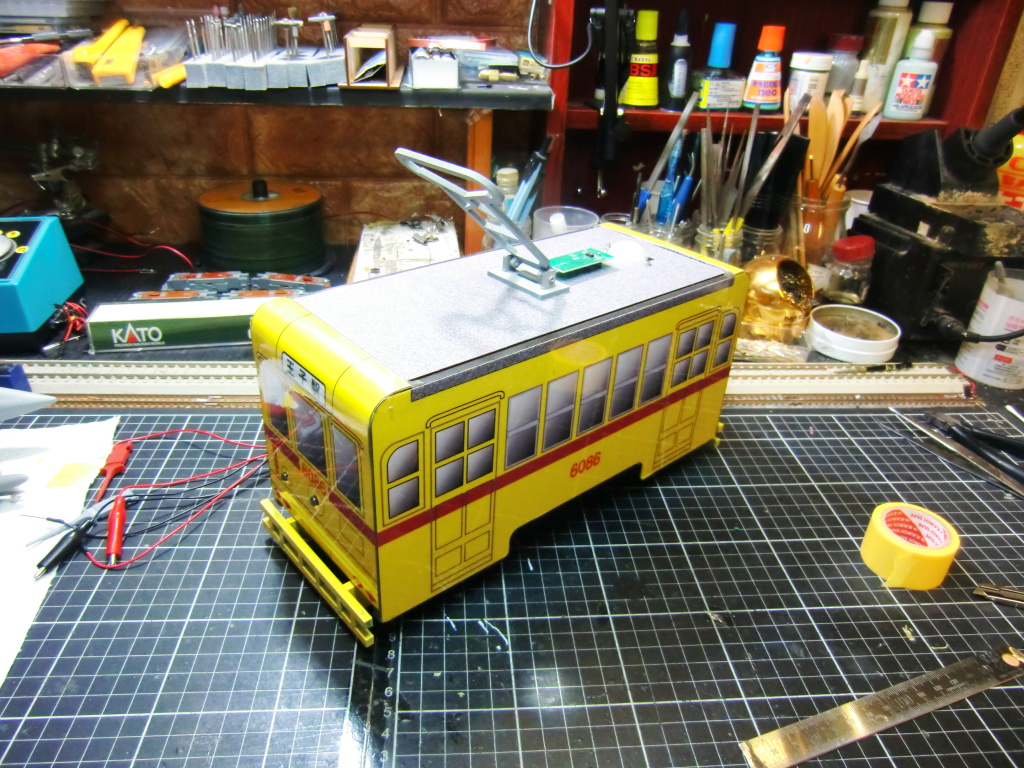

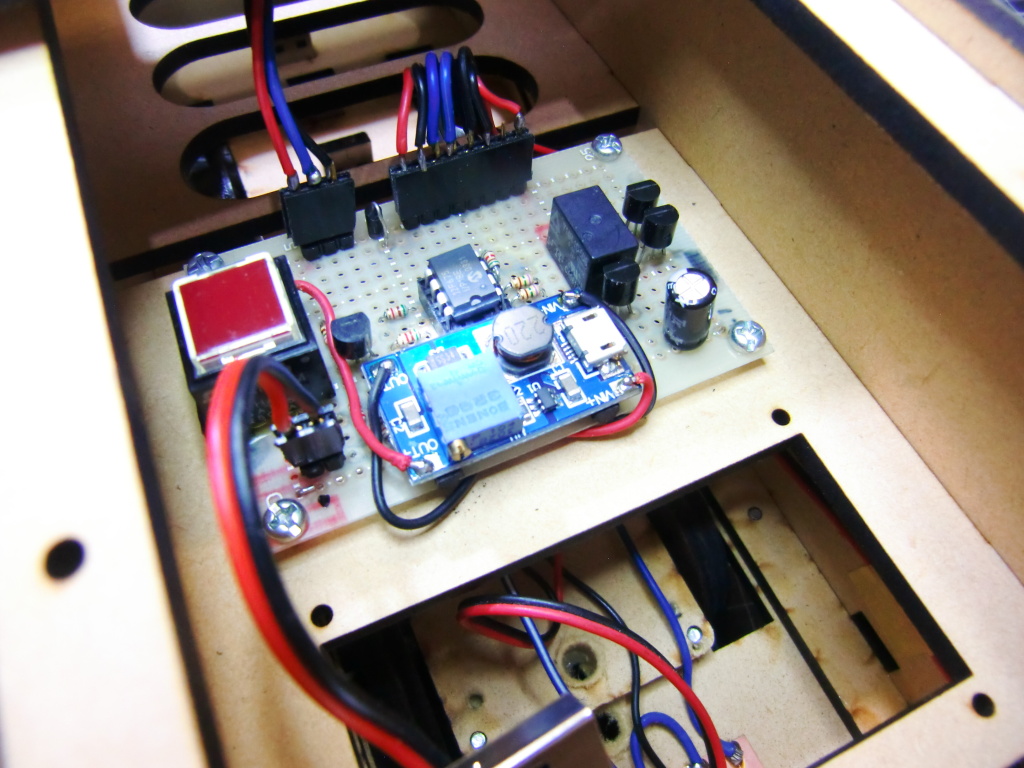
今年は「京成200形」ということで、以前に制作した「流鉄5000形」のデータを大幅に変更しての制作となります。
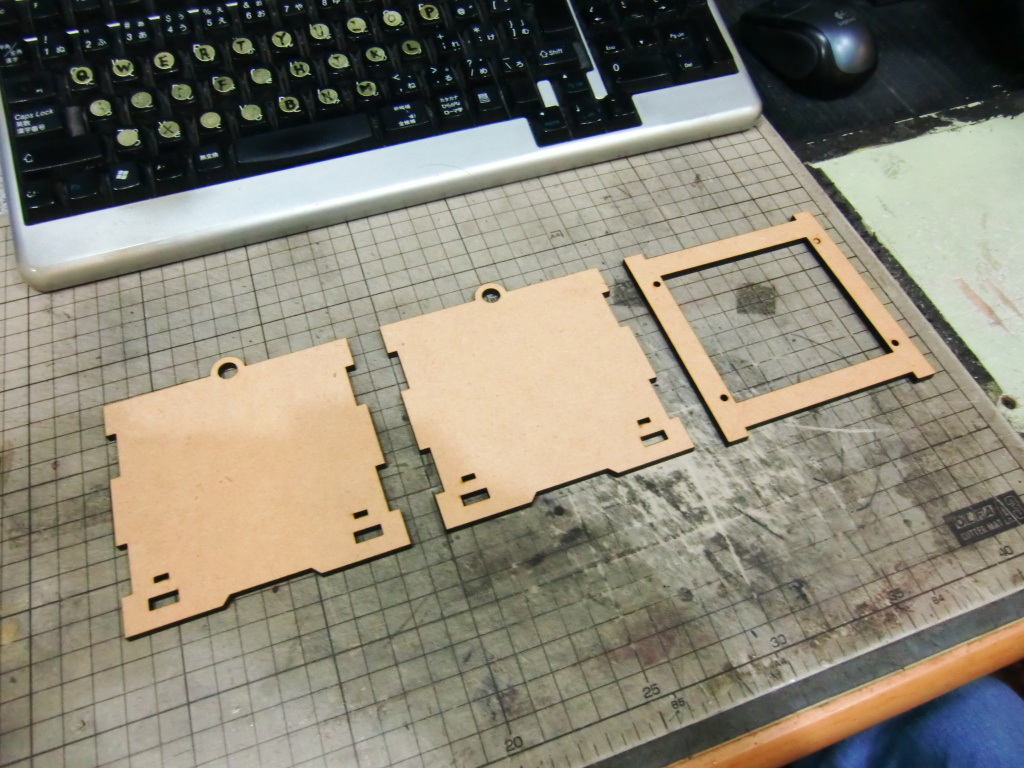
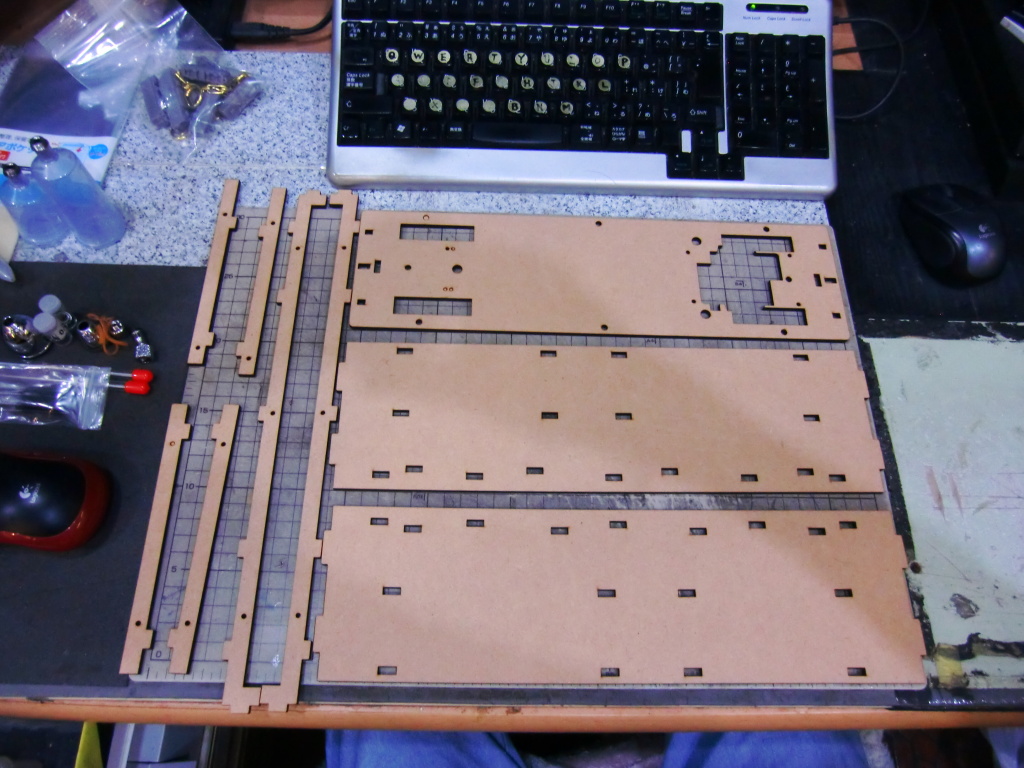

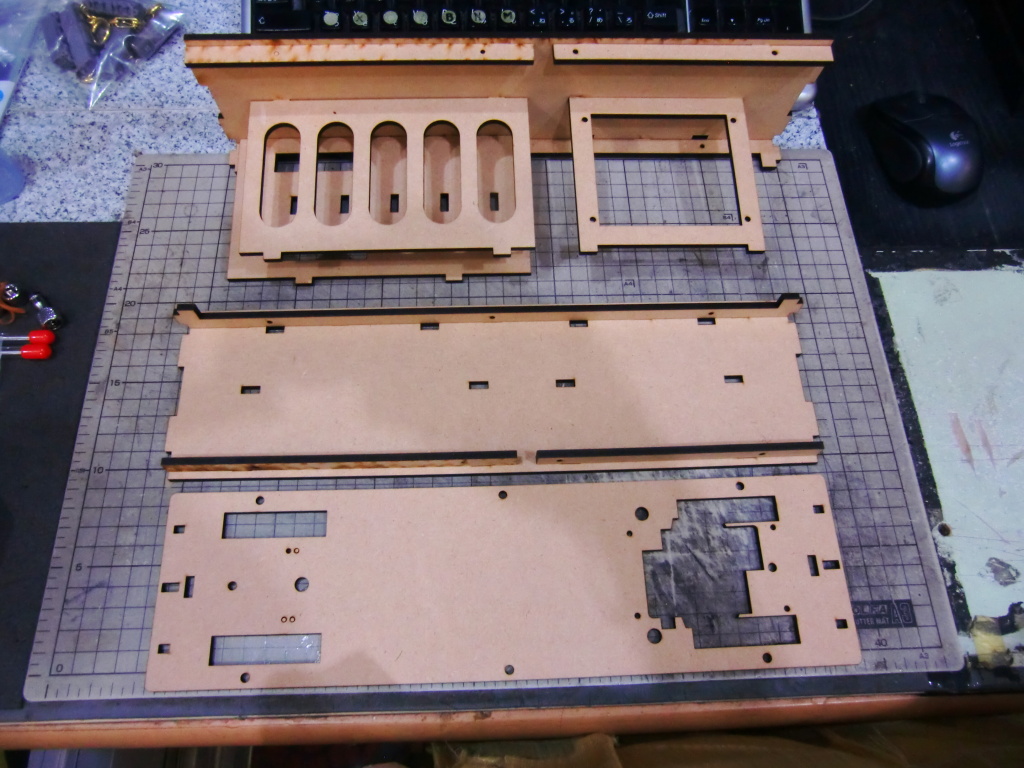
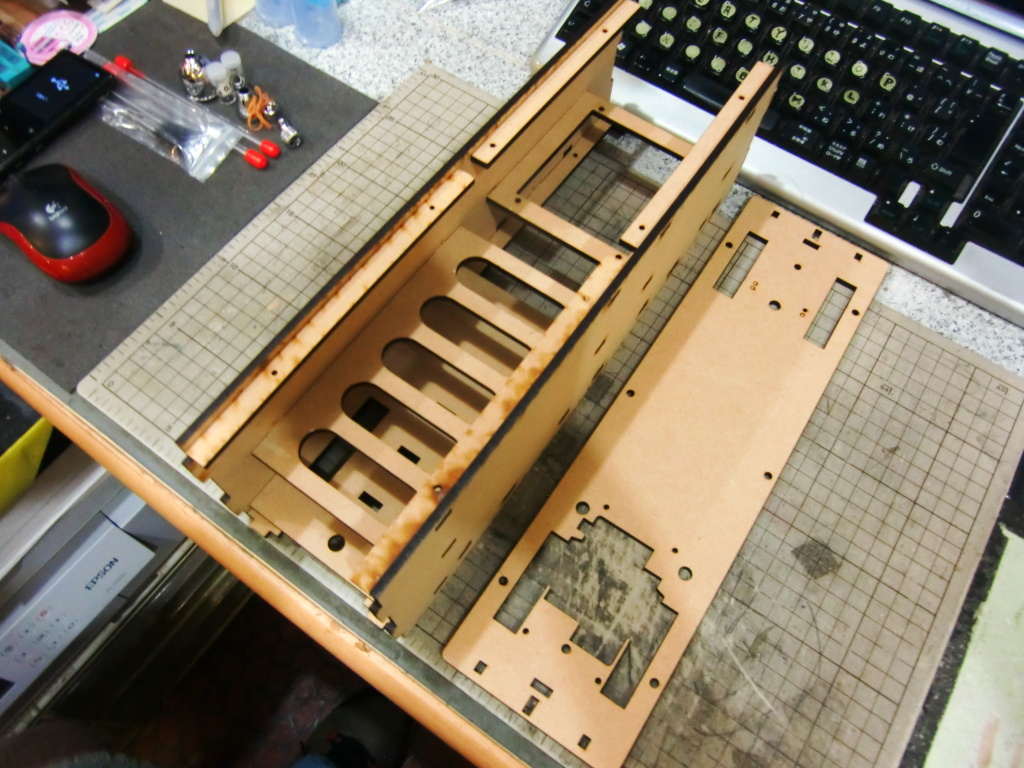
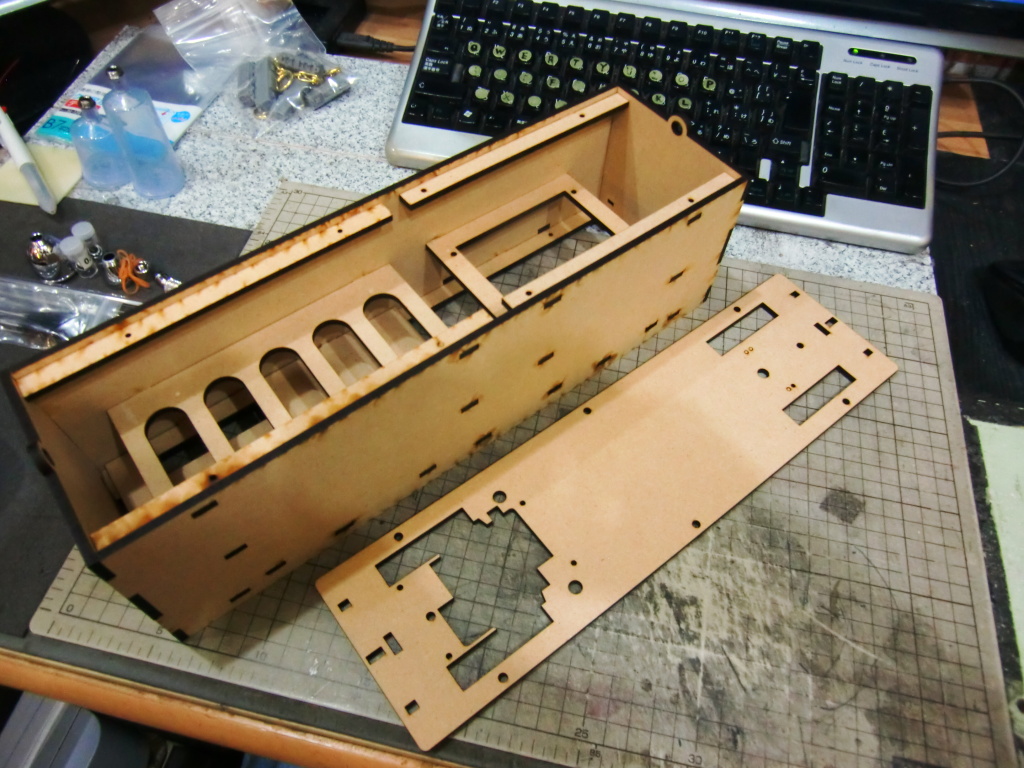
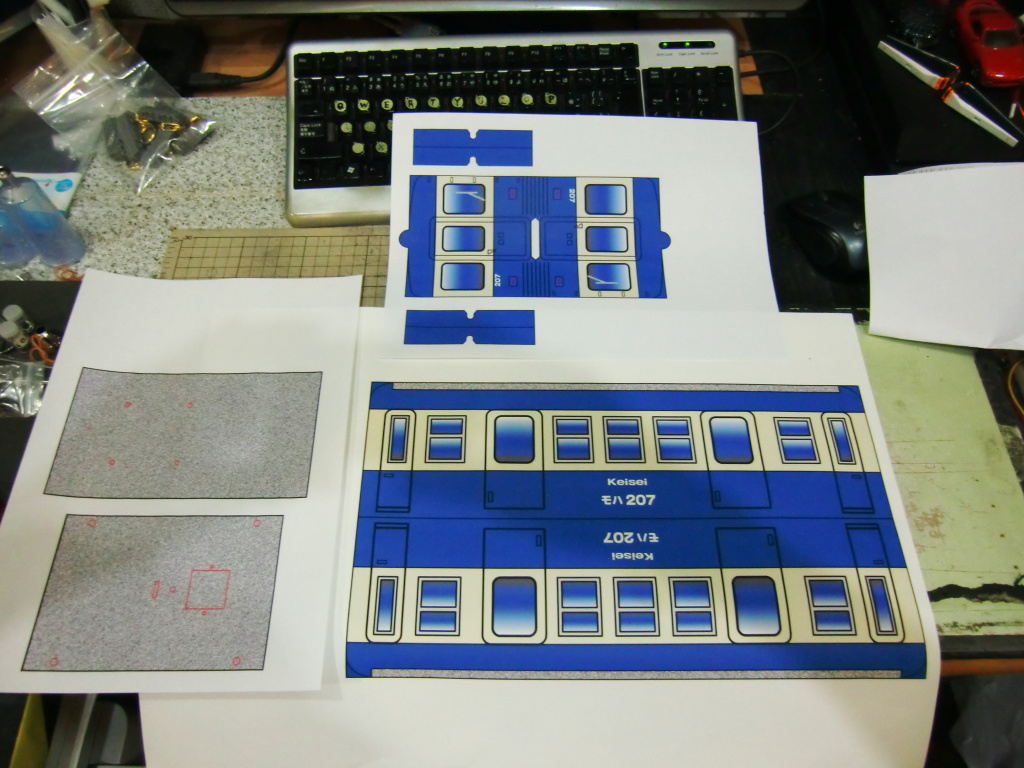
2両制作が間に合いそうもあいませんので、両運転台にしてアレンジしてあります。本来であれば、「クモハ」とするとこですが、あえて「モハ」にしてあります。

A3用紙に印刷を行いラミネートして切り抜きます。
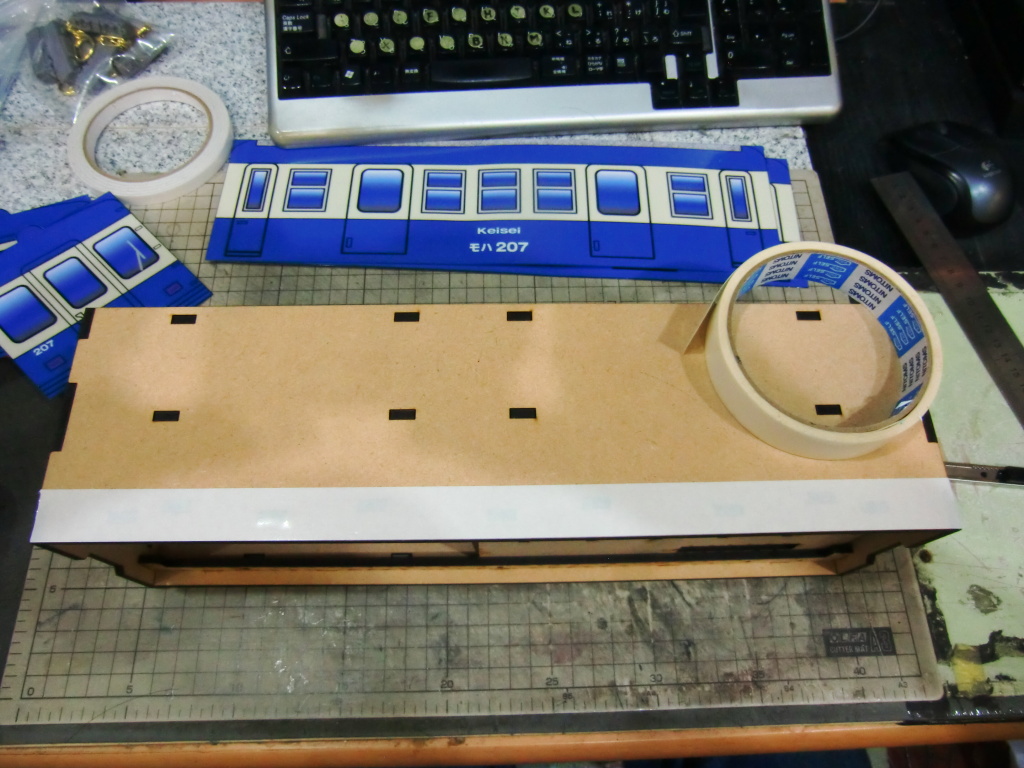
両面テープで貼っていきます。
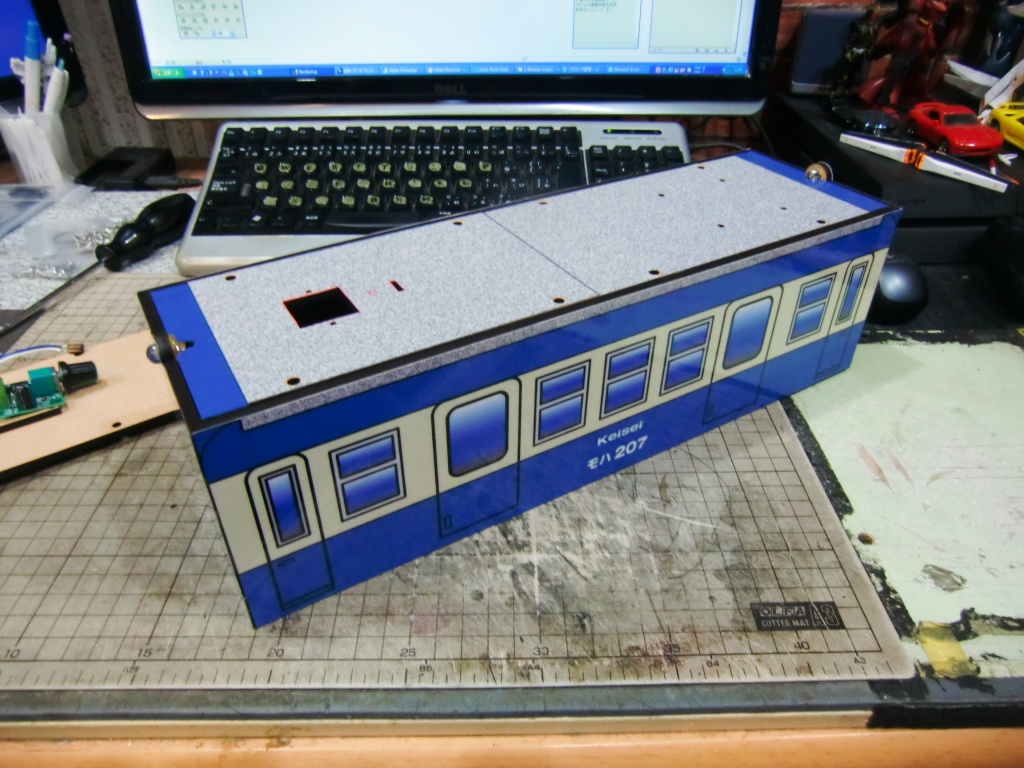
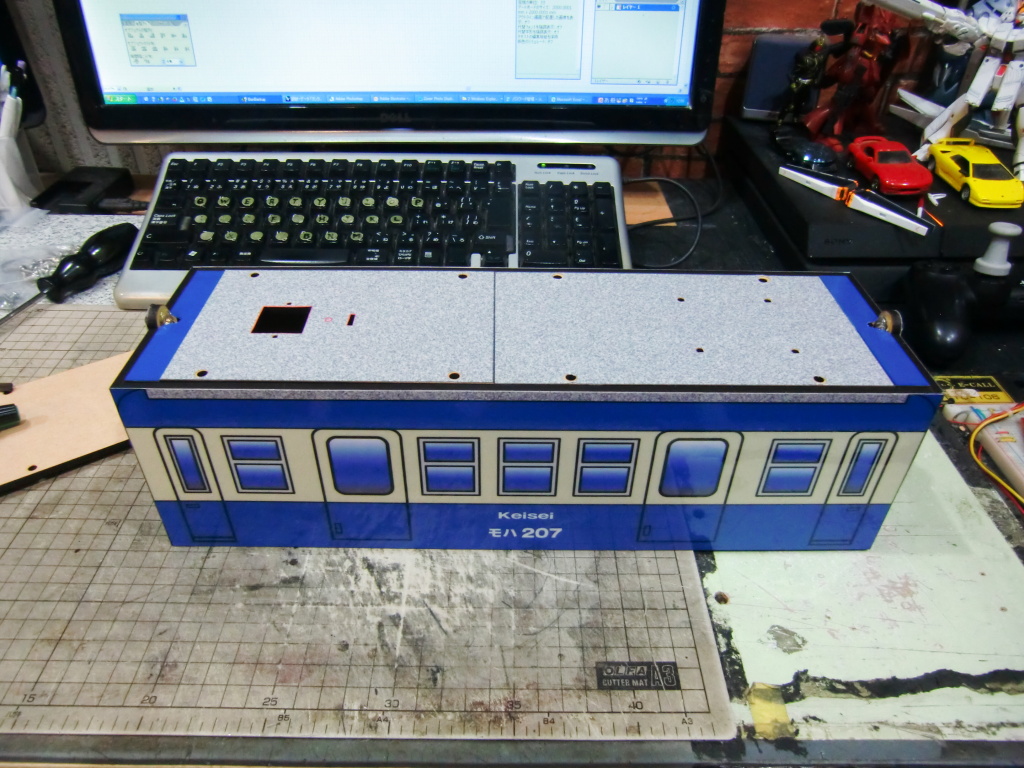
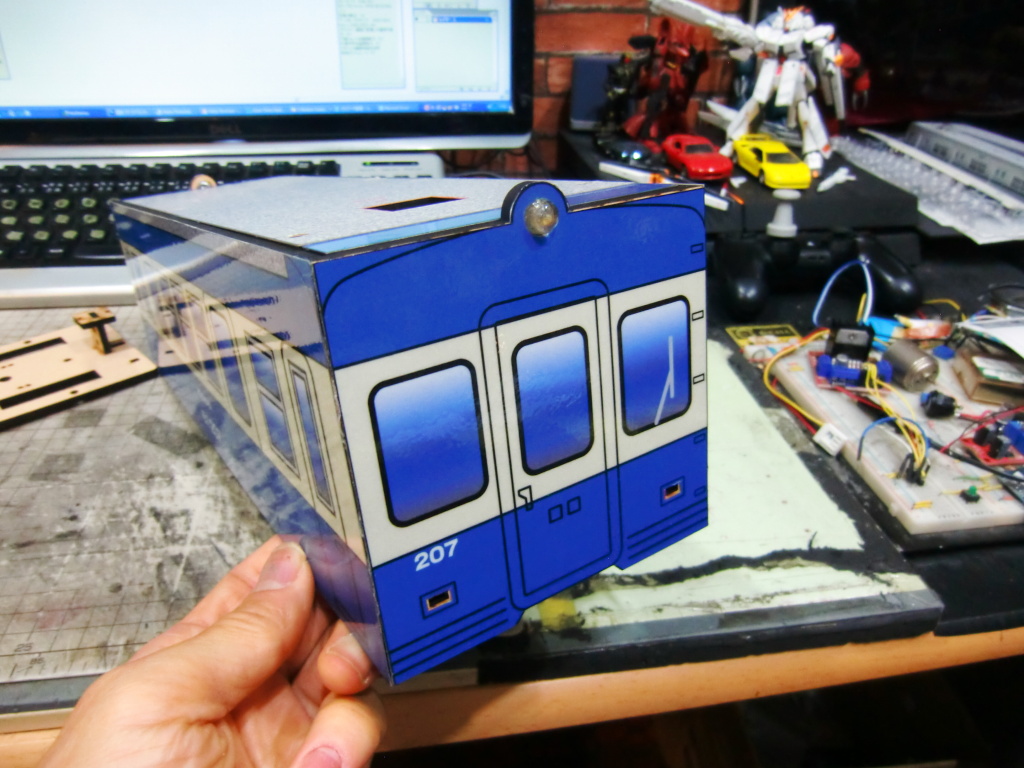
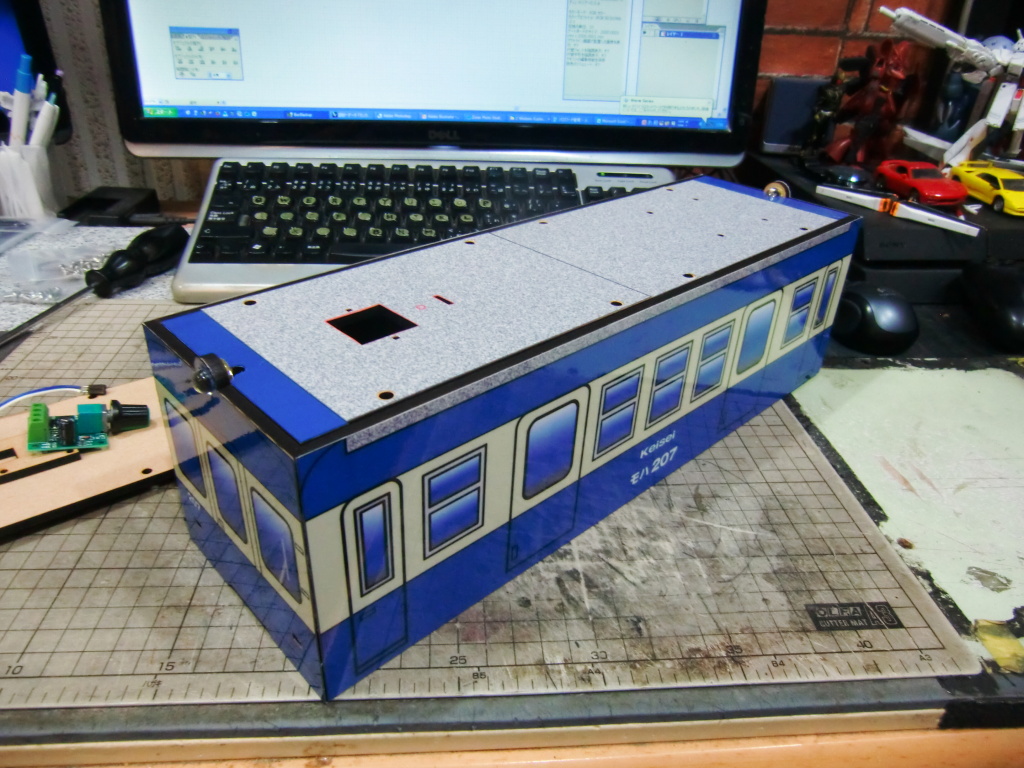

左が制御、右がバッテリー区画です。制御部は、基盤故障による修理の時以外は基本的に開けることはありませんので、屋根はネジ止めで固定します。
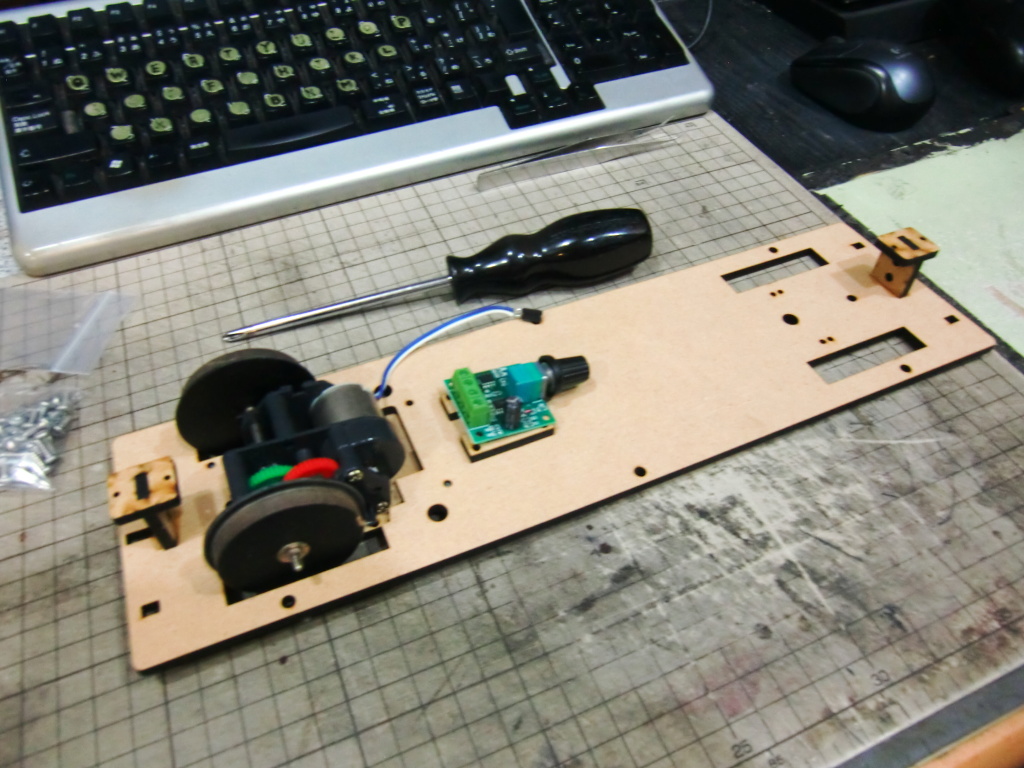
ボディーが出来上がったので、おつぎは床下です。
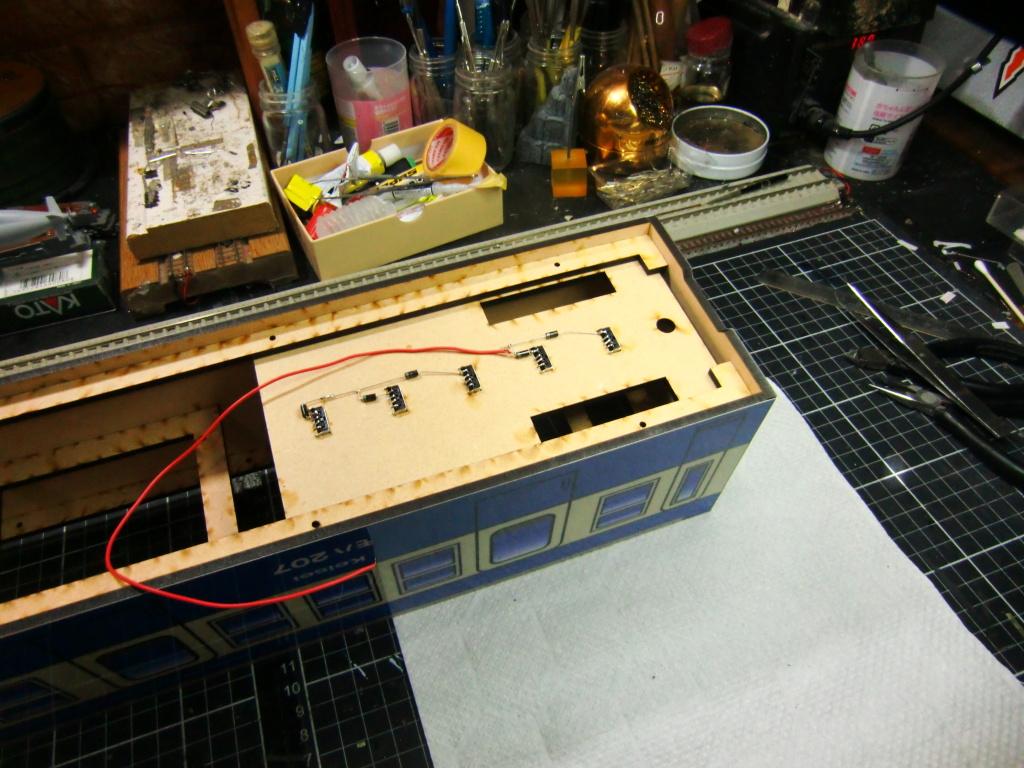
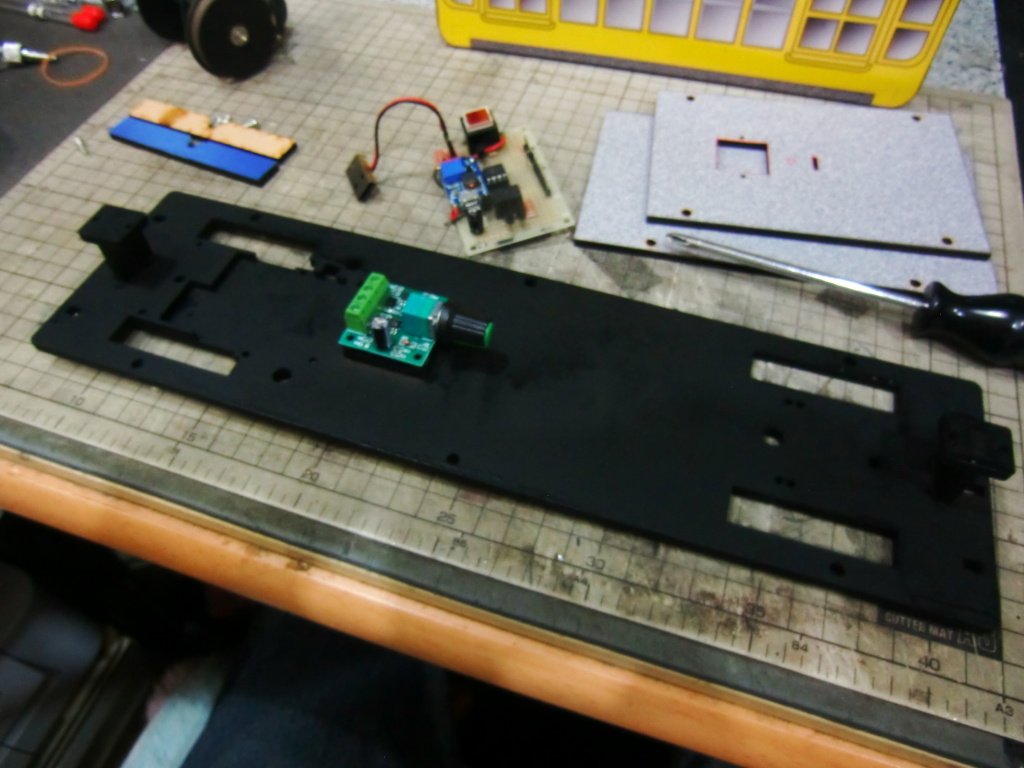
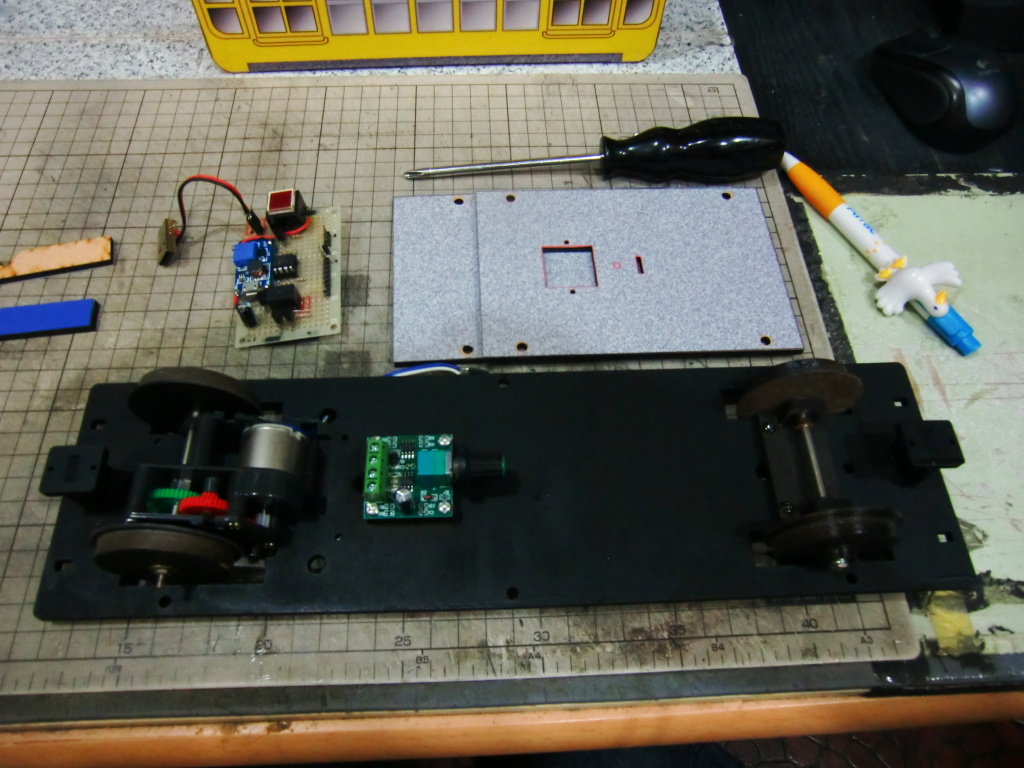
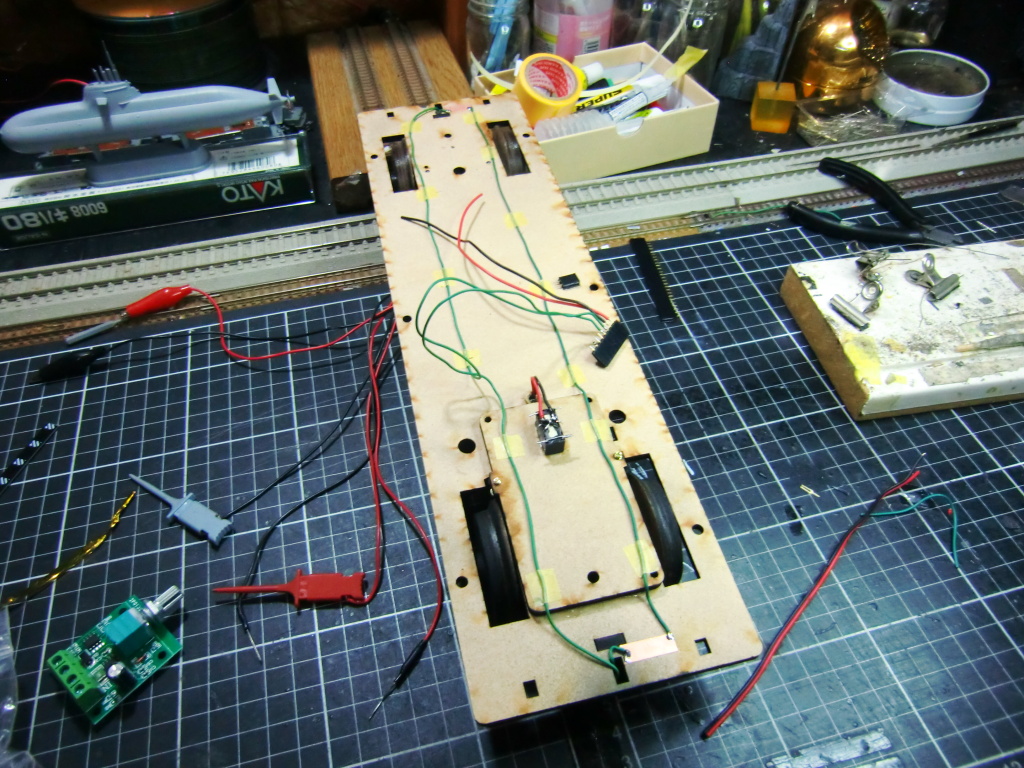
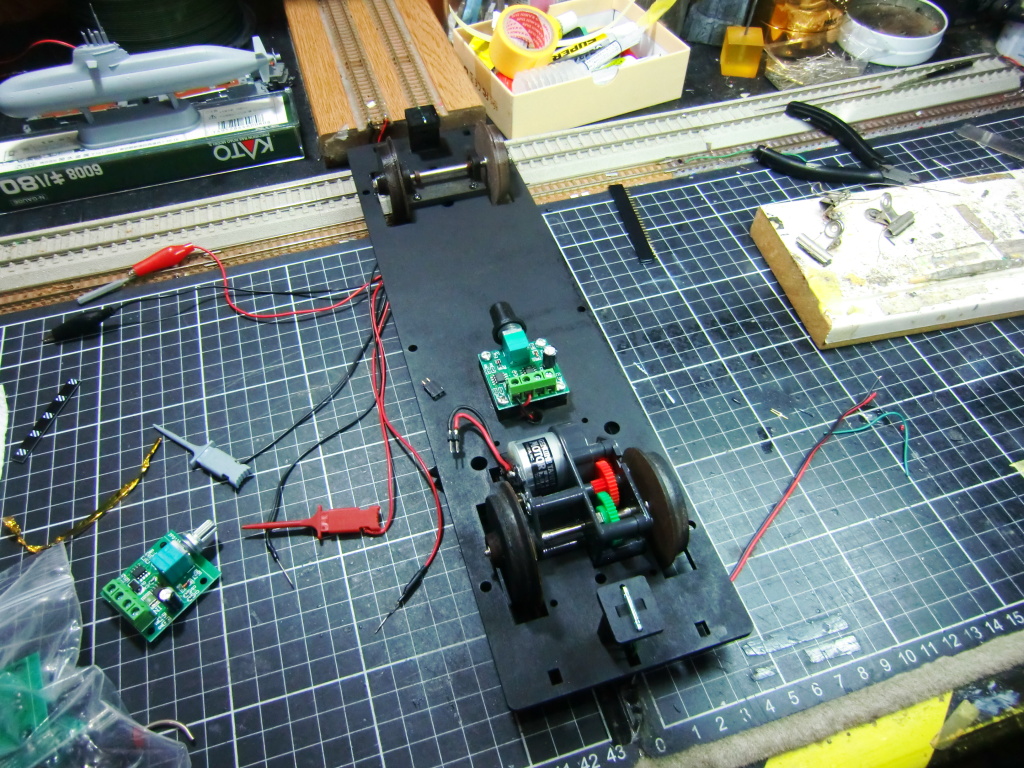
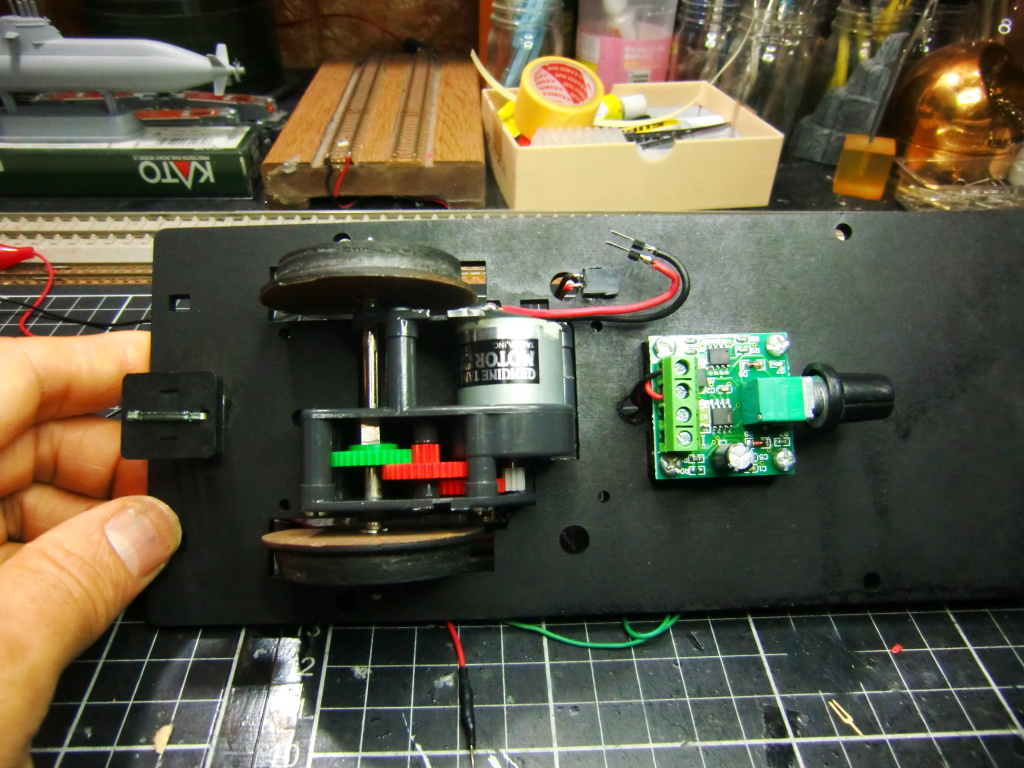
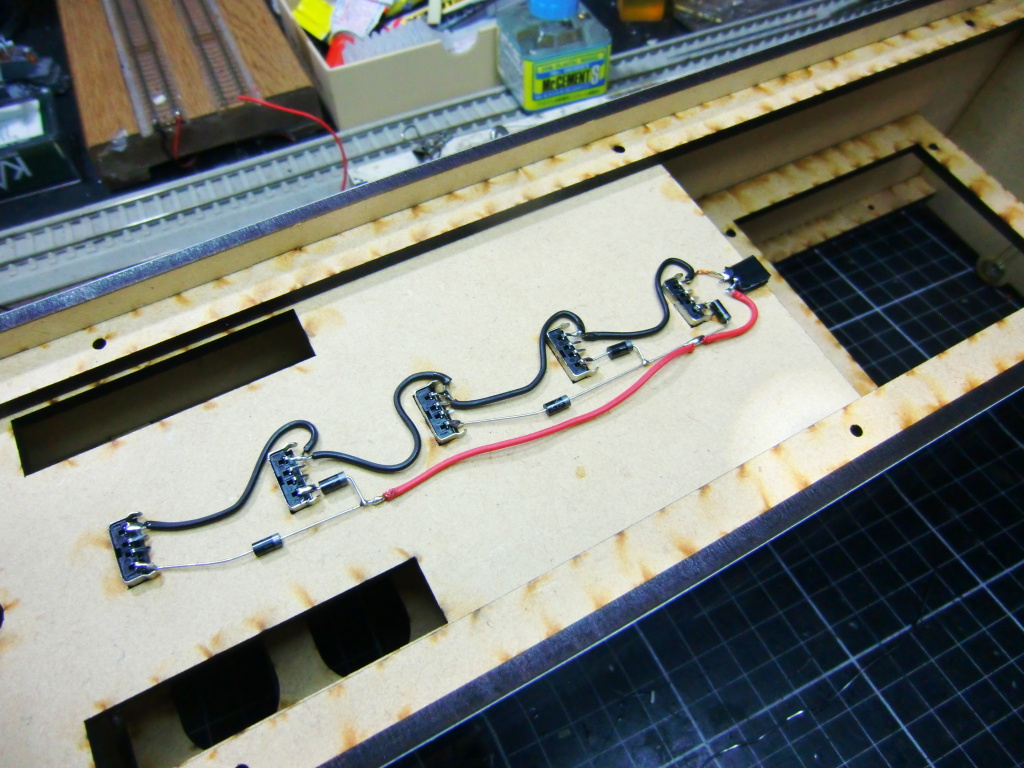
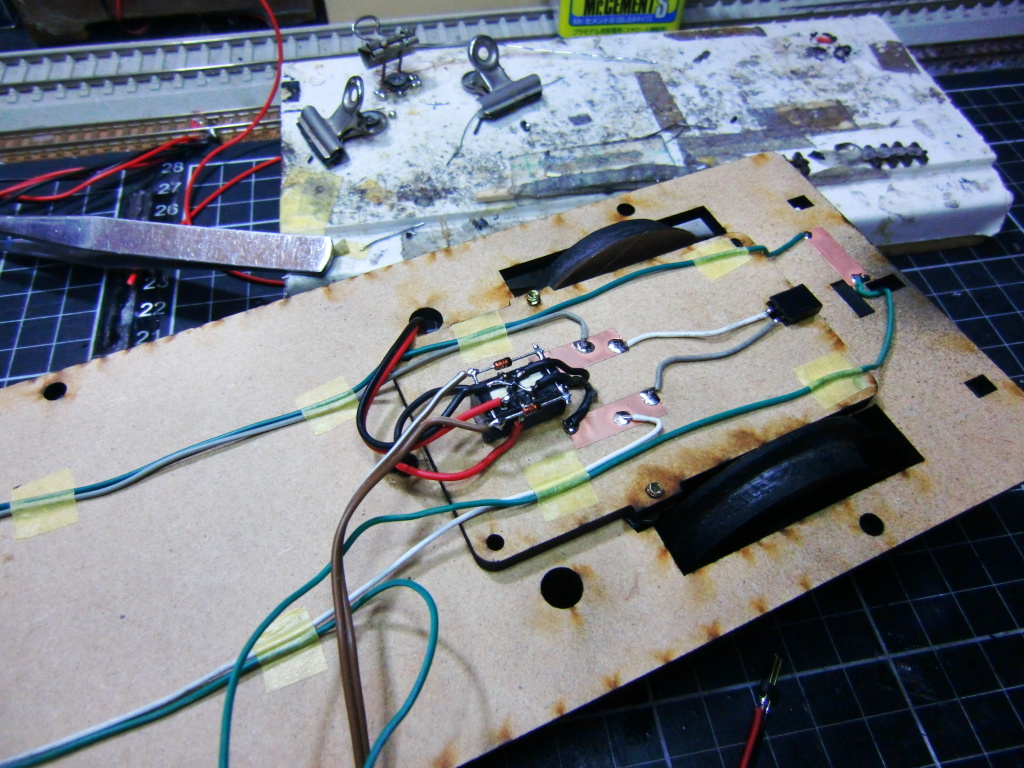
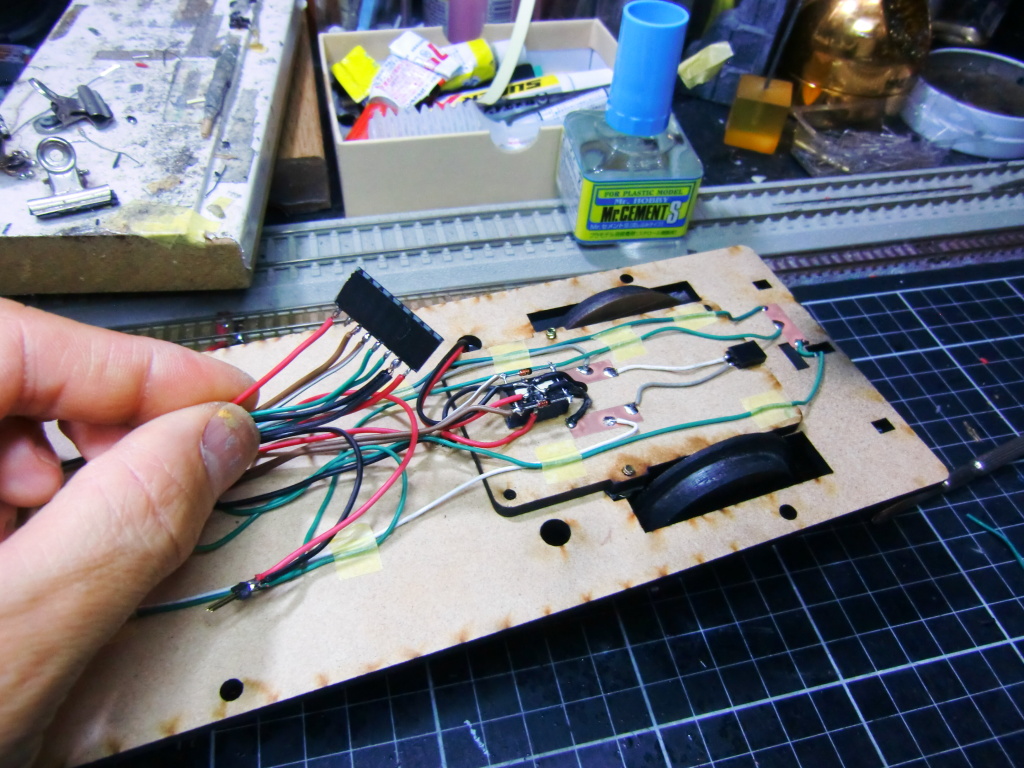
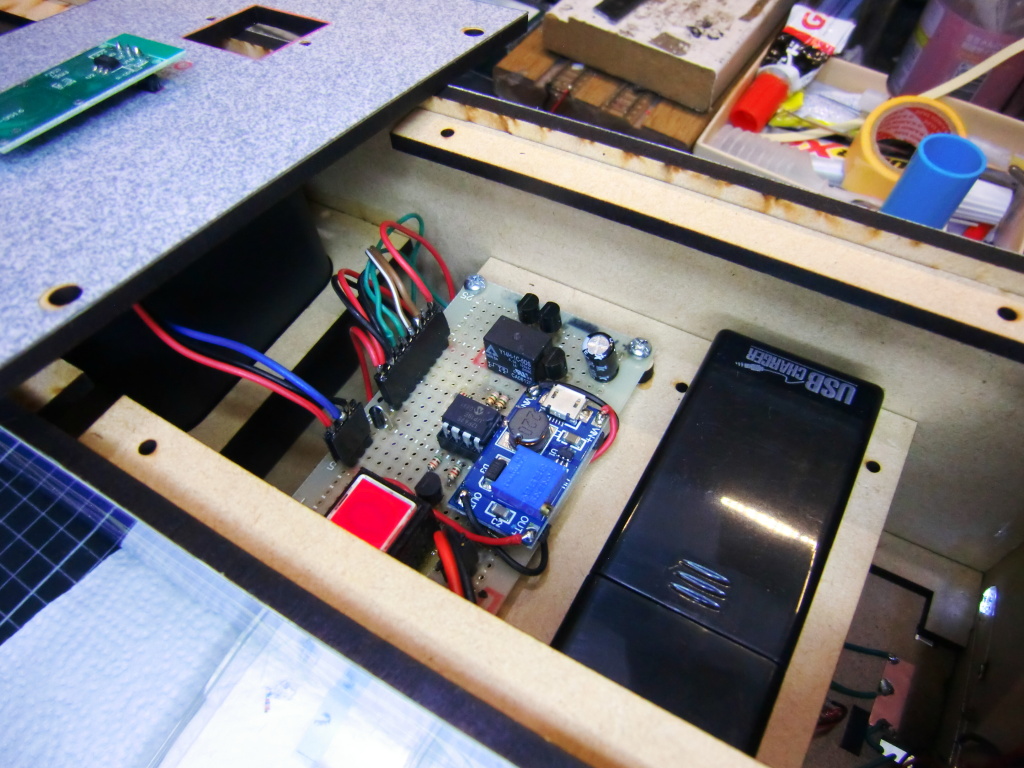
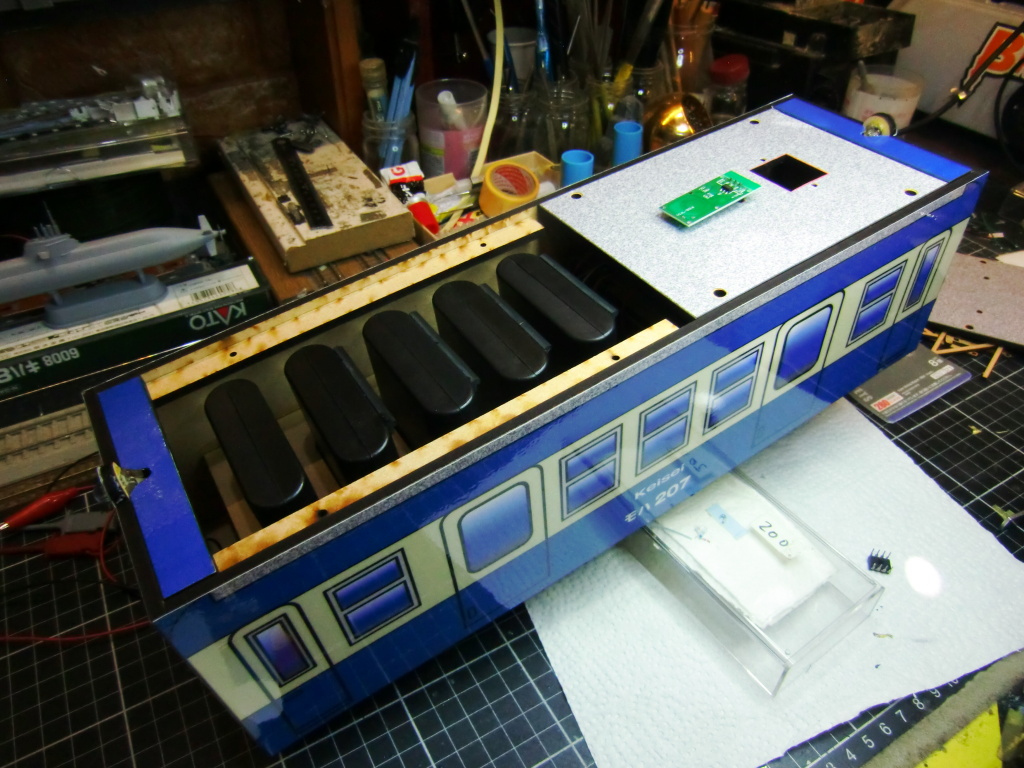
▼架線柱の制作
車両が出来上がったところで、架線柱の制作です。時間も差し迫っているのであまり凝った作りとはしません。

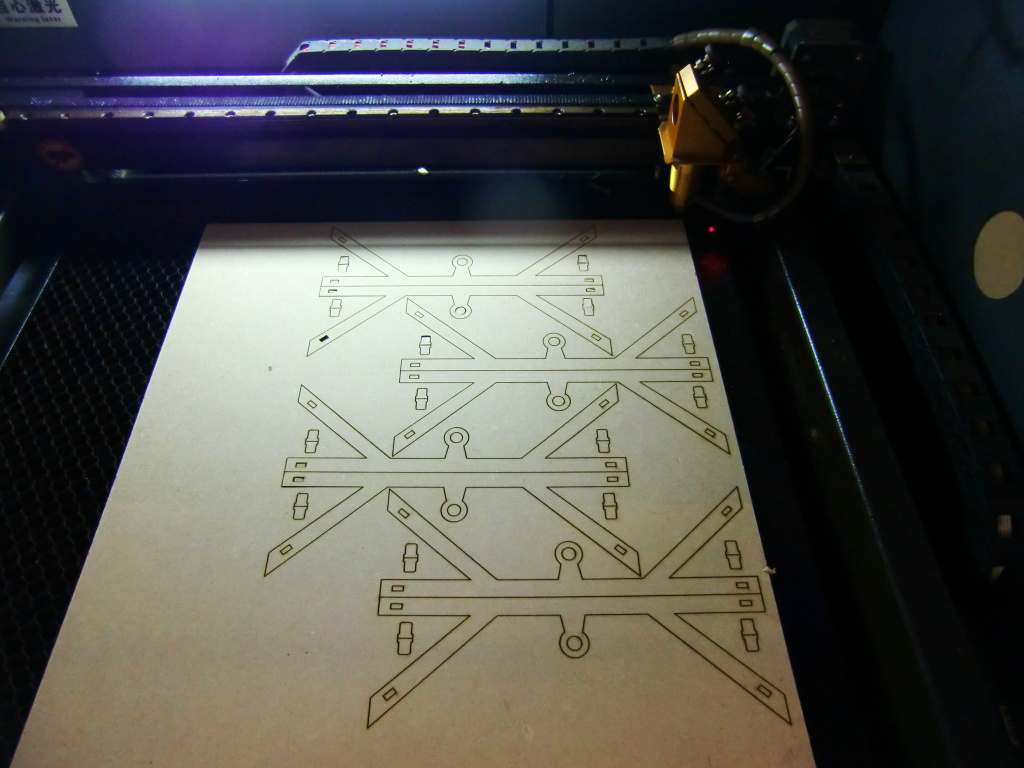
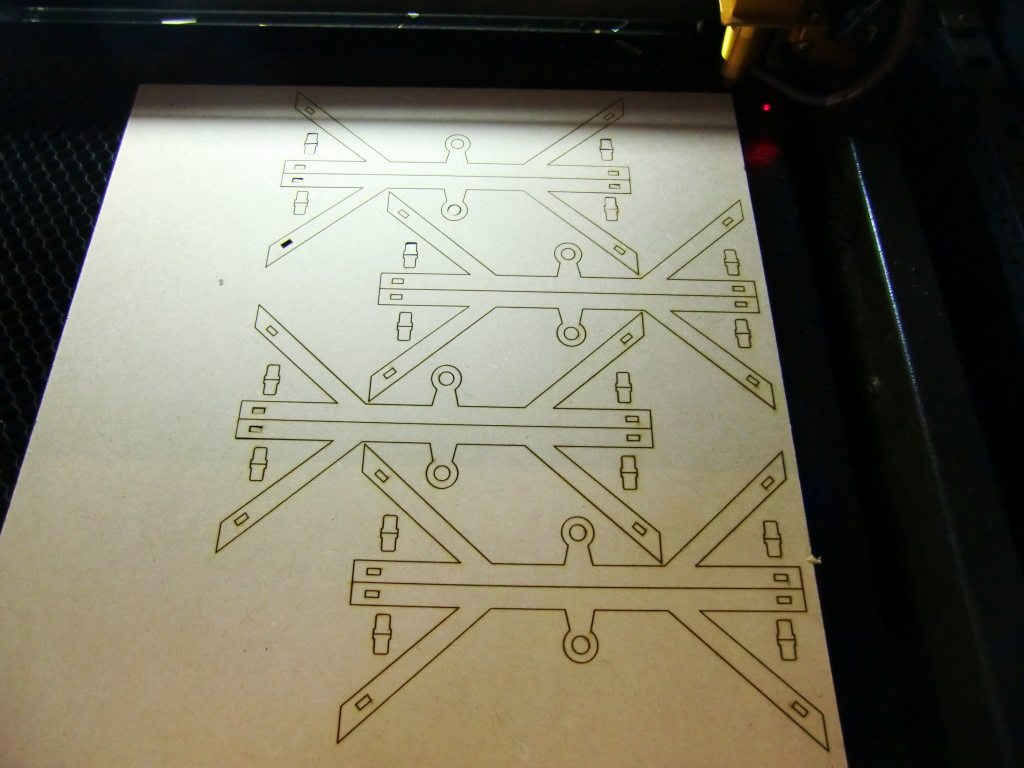
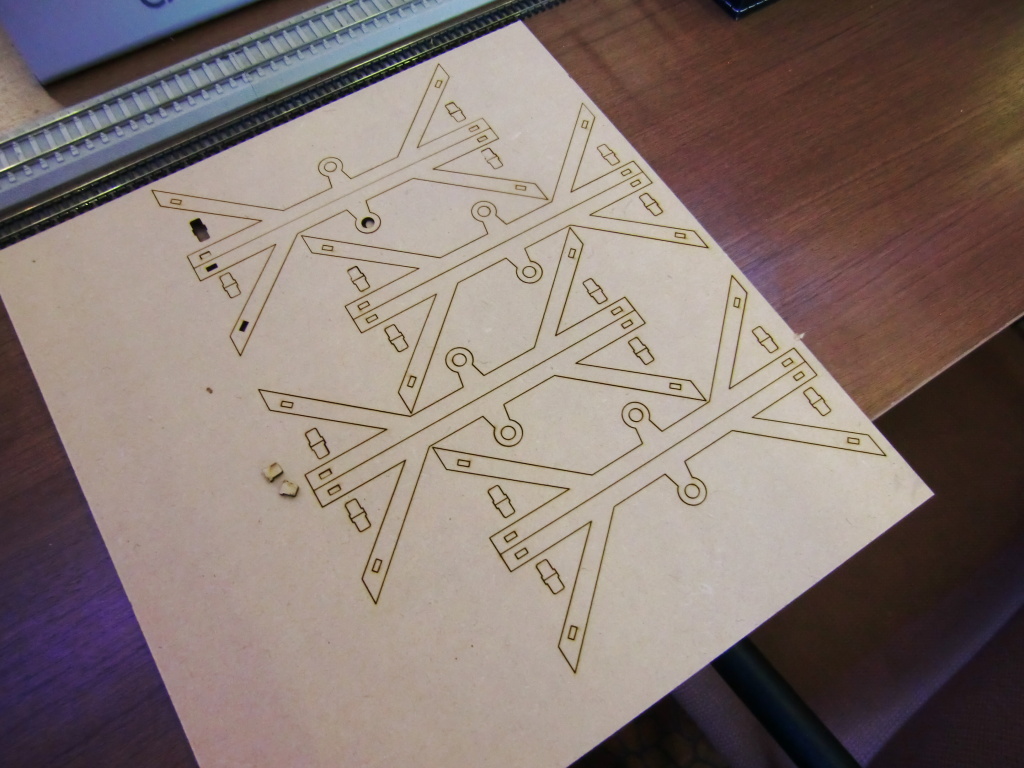



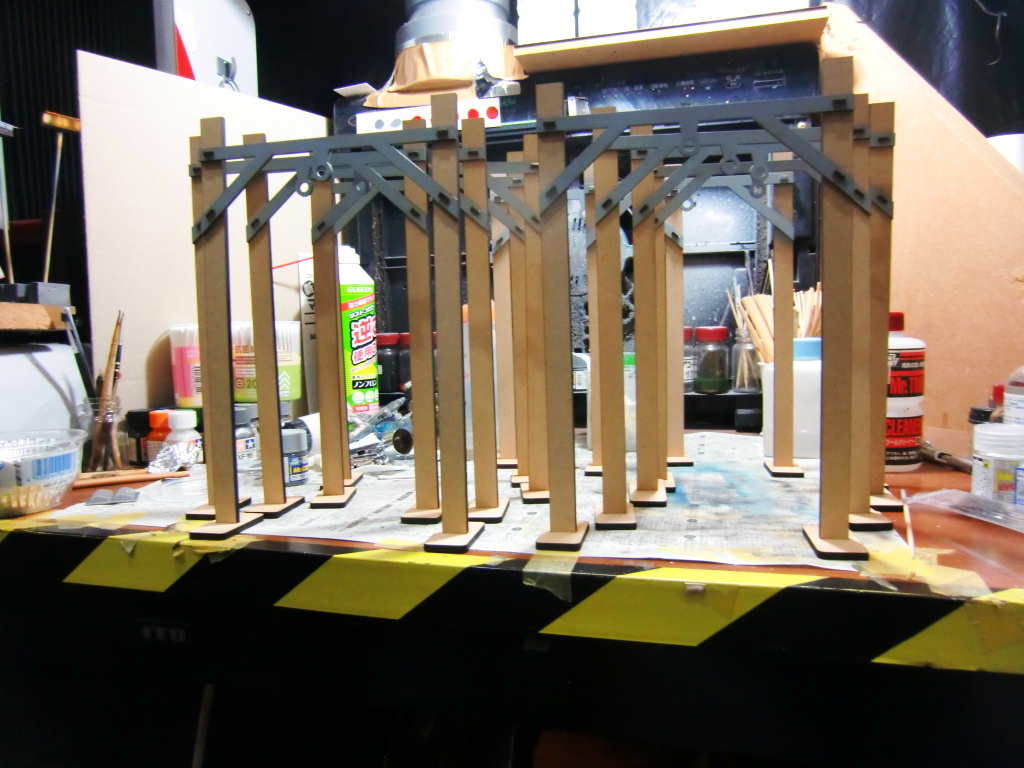
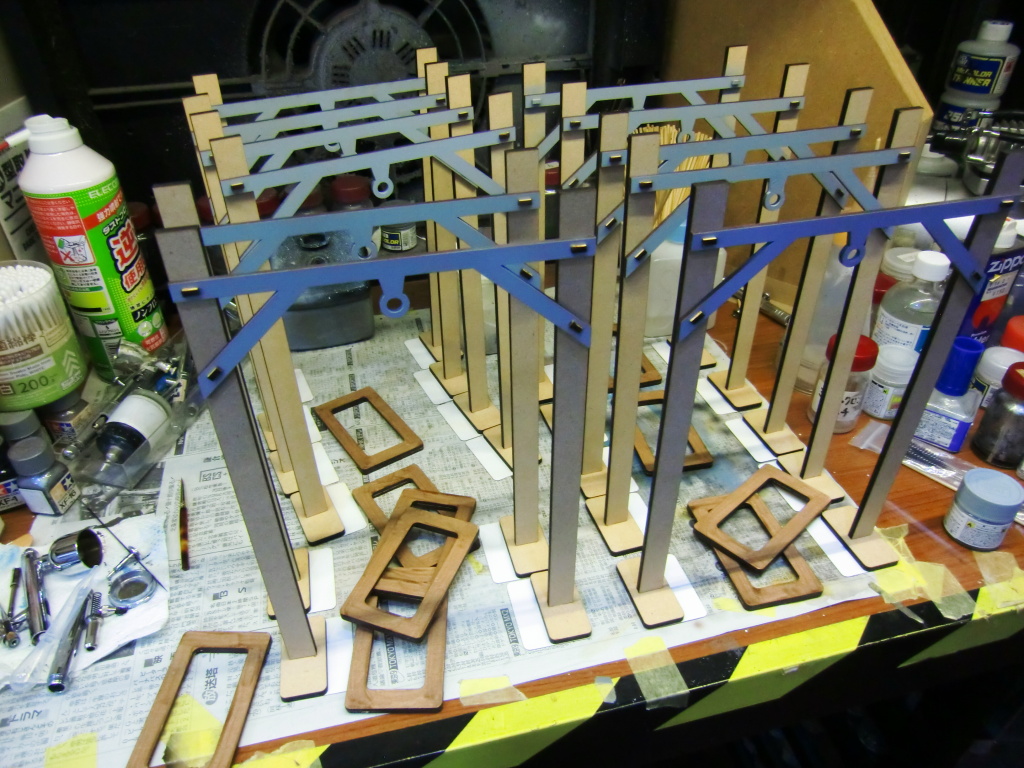
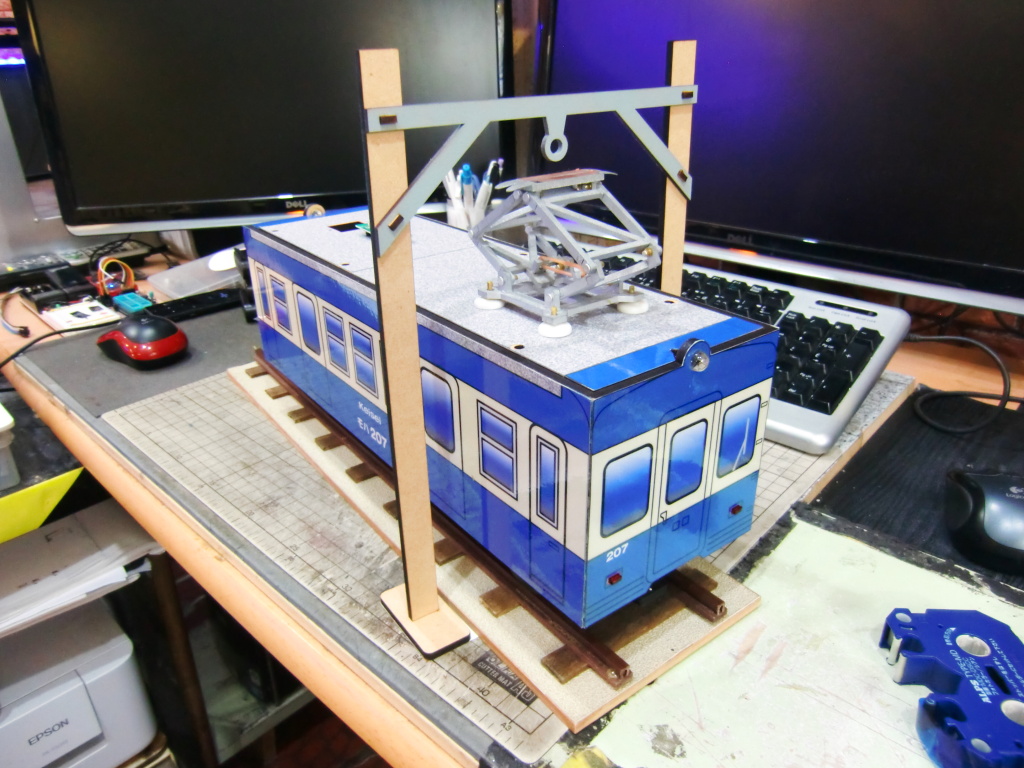
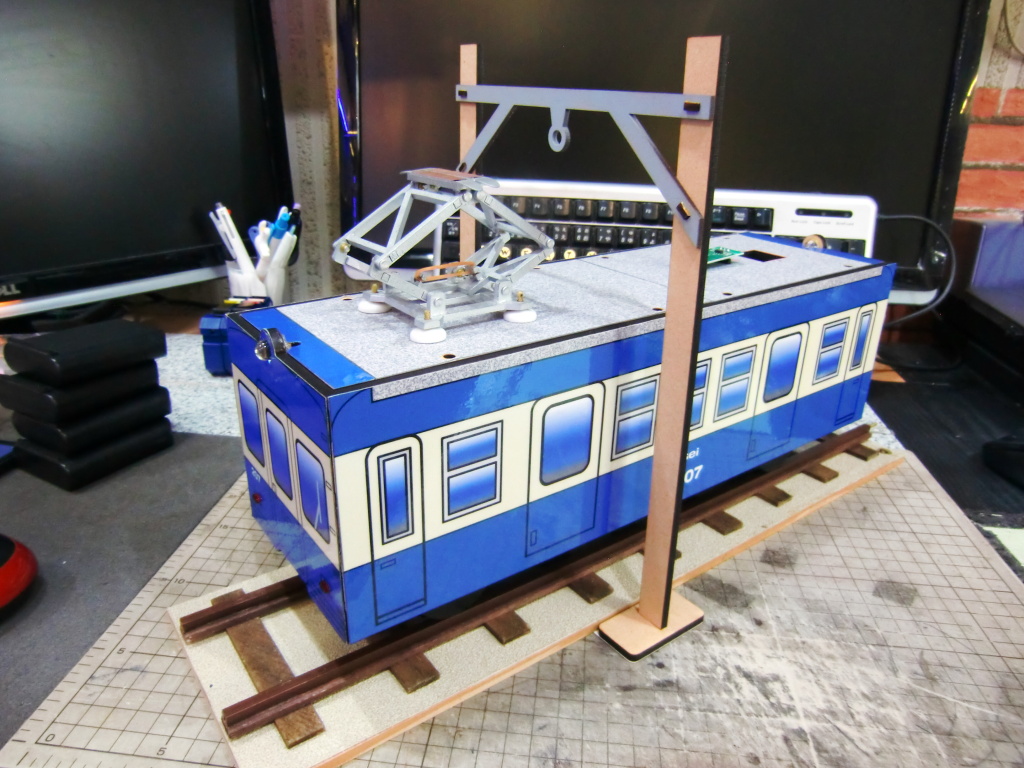








モーションセンサー搭載により、近くに人の動きが検知されない場合は、自動的に「スリープモード」に入ります。
現状の水色の帯を赤色(こうのとり色)へと変更します。

まずは、帯色変更を行う前に一旦車体を分解して洗浄する作業からです。

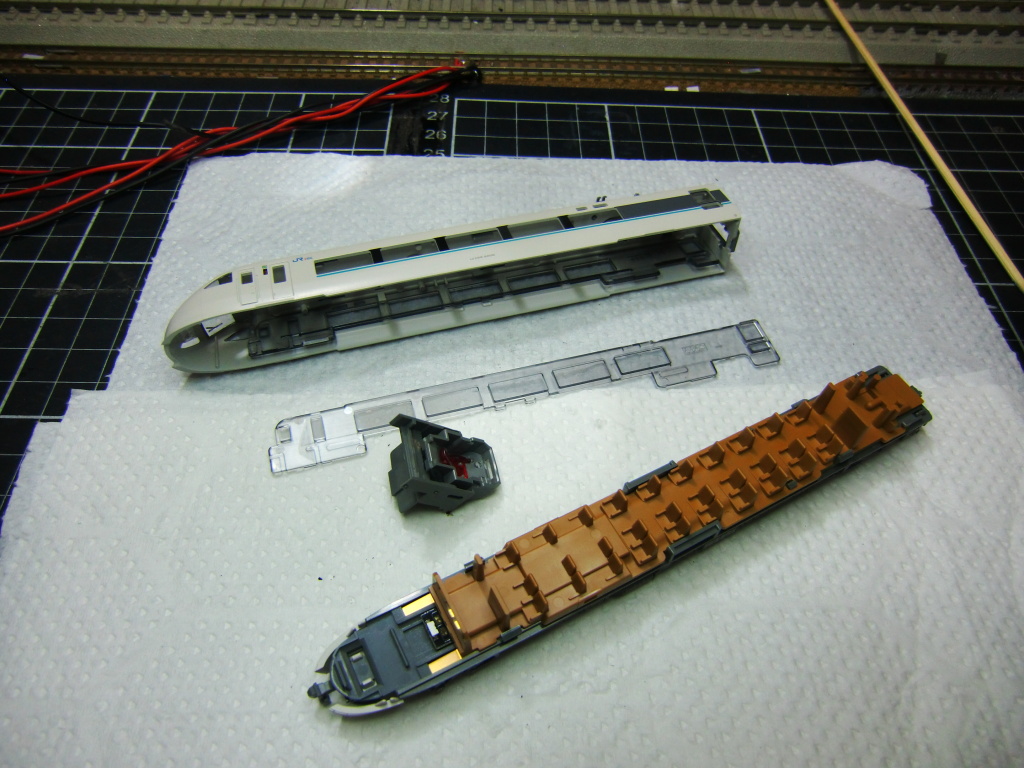
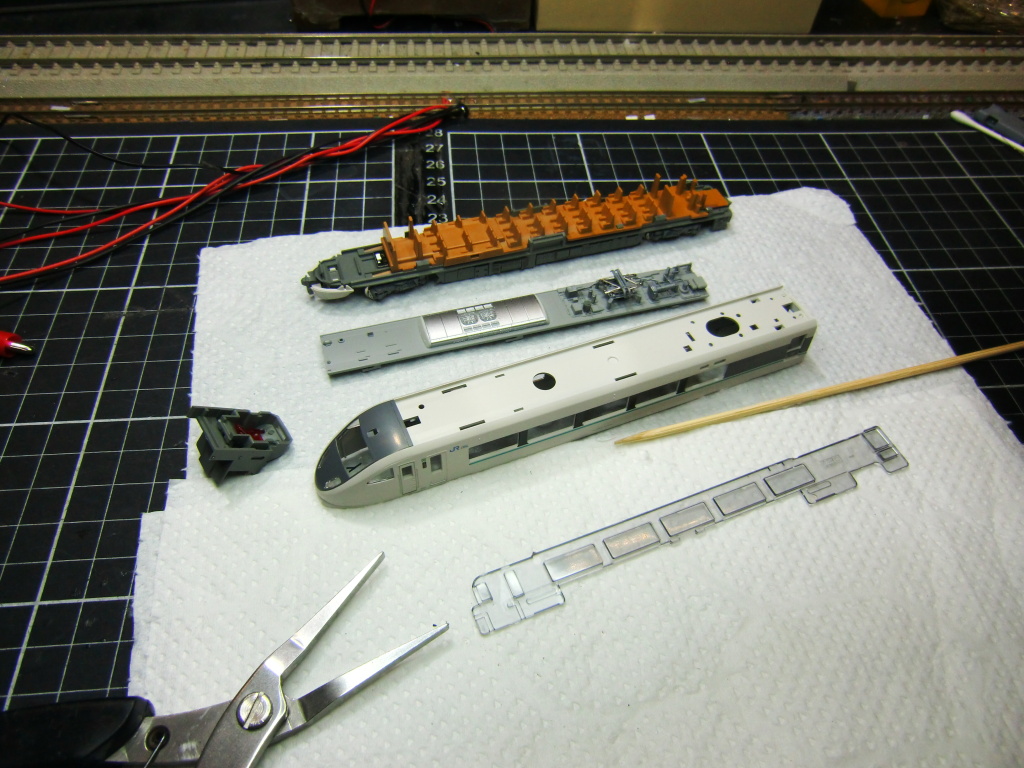
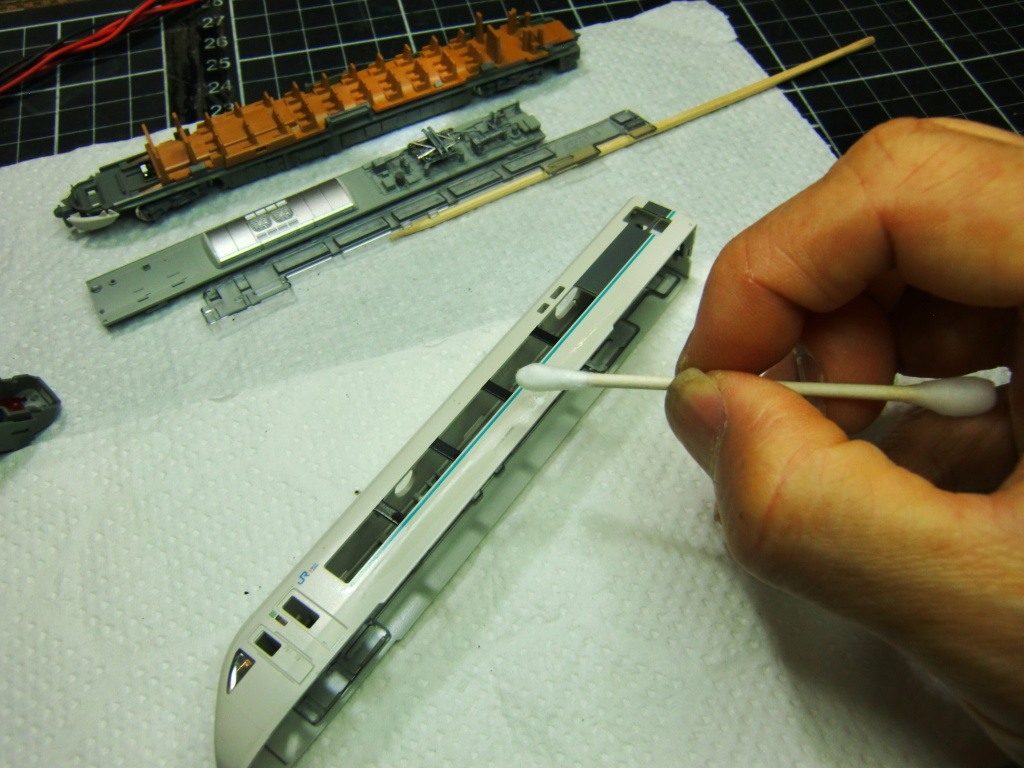
車体に残っている油分と汚れを中性洗剤で落としてから水で流し綿棒で水分を拭き取っていきます。
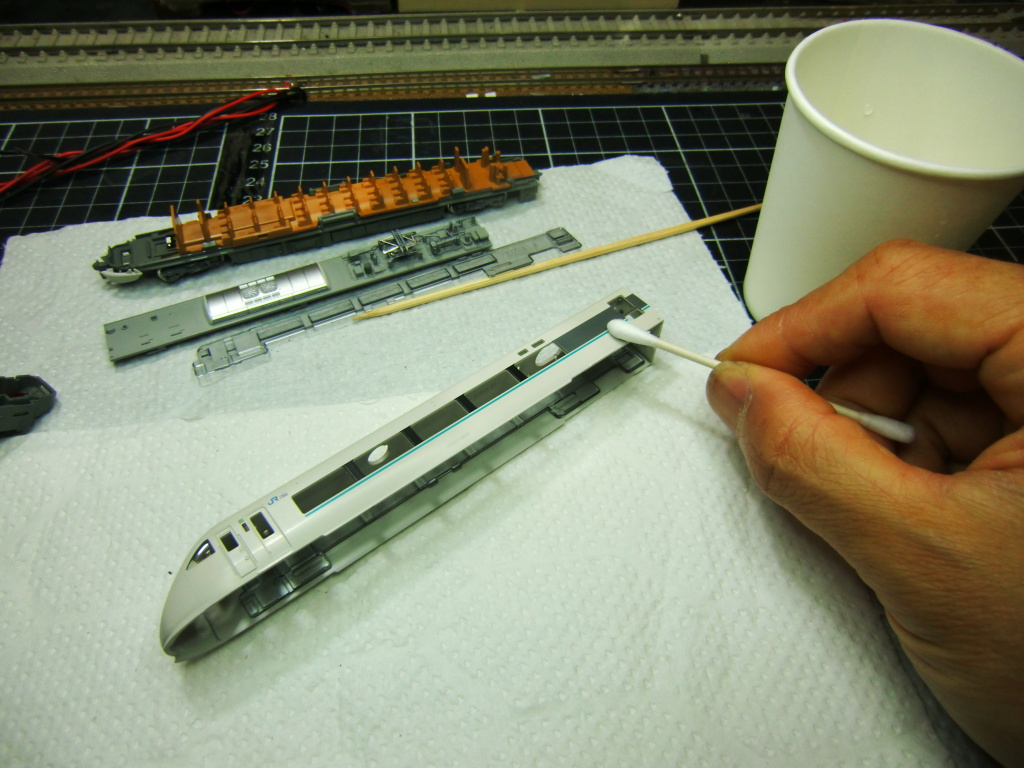
他の車両も同様に作業します。
ボディー洗浄が終ったところで、一旦組み戻します。その方が作業しやすためです。
貼り付け面を直接手で触れることのないように注意します。
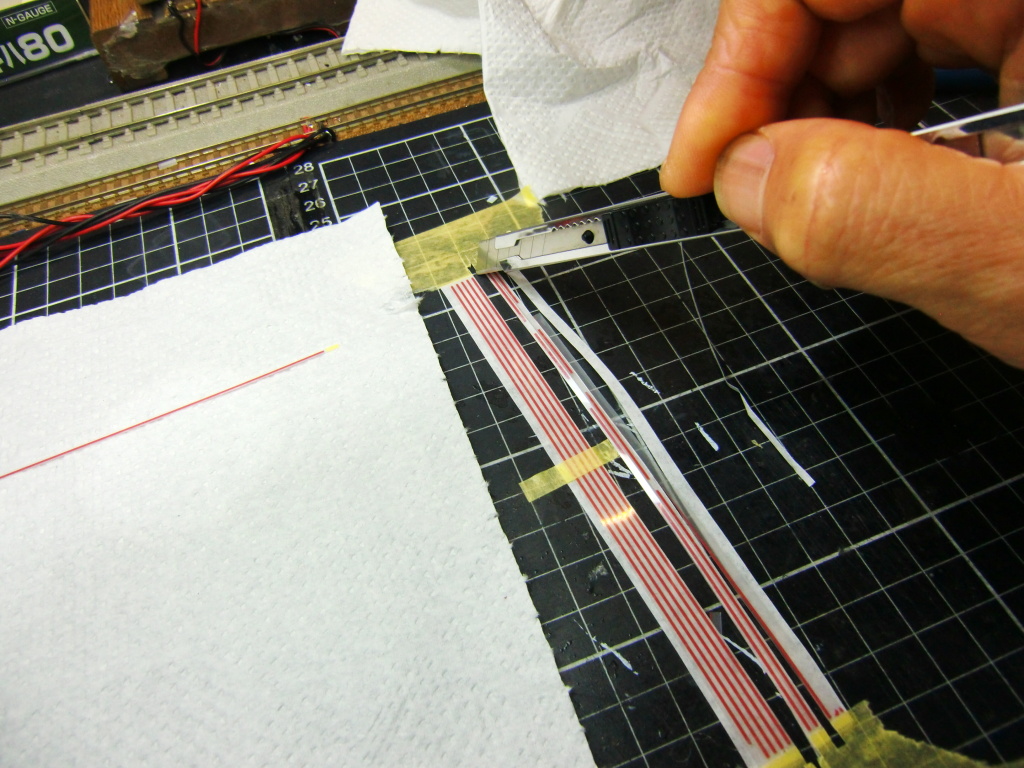
帯インレタの切り抜きです。
そのまま切ると、インレタシートが滑ってしまいますので、マスキングテープで固定します。
次に車体に転写するわけですが、ここでも注意があります。今回のように細いものを転写する場合は、動かないようにマスキングシートを細く切って位置を固定してから転写します。面倒だからと言ってそのまま転写すると曲がってしまう可能性が高くなります。
帯インレタは、簡単に帯色を変更できると思われがちですが、貼り付けにはそれなりのスキルと集中力が必要です。初めて作業される方にはちょっと難しいかもしれませんね。
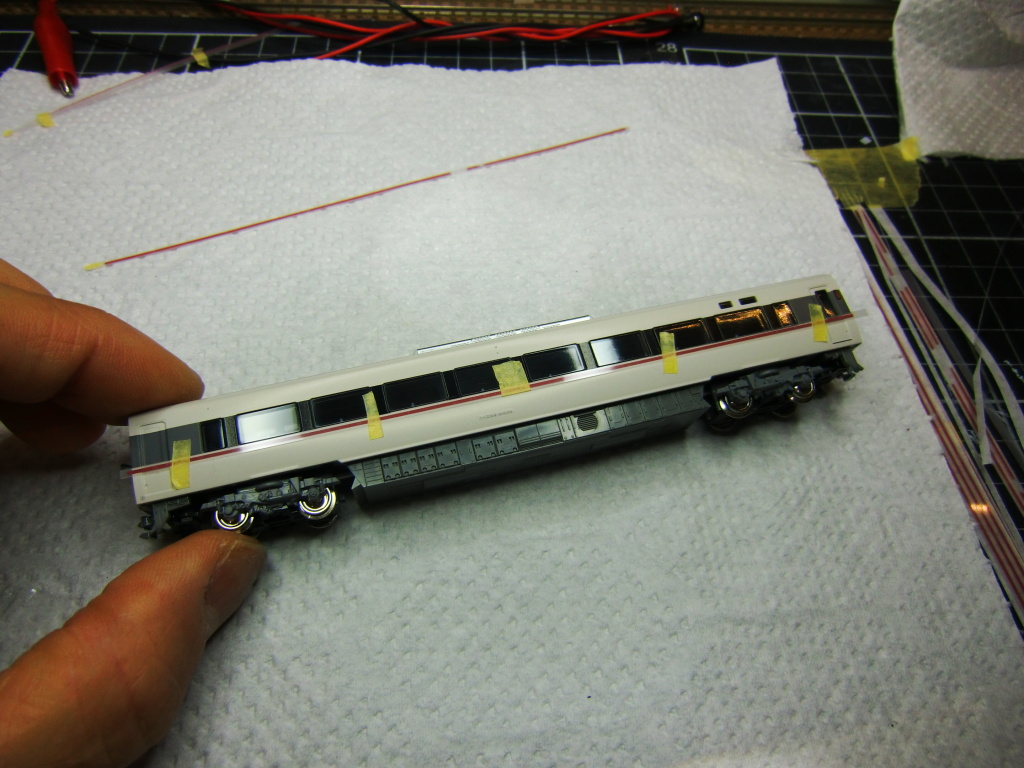
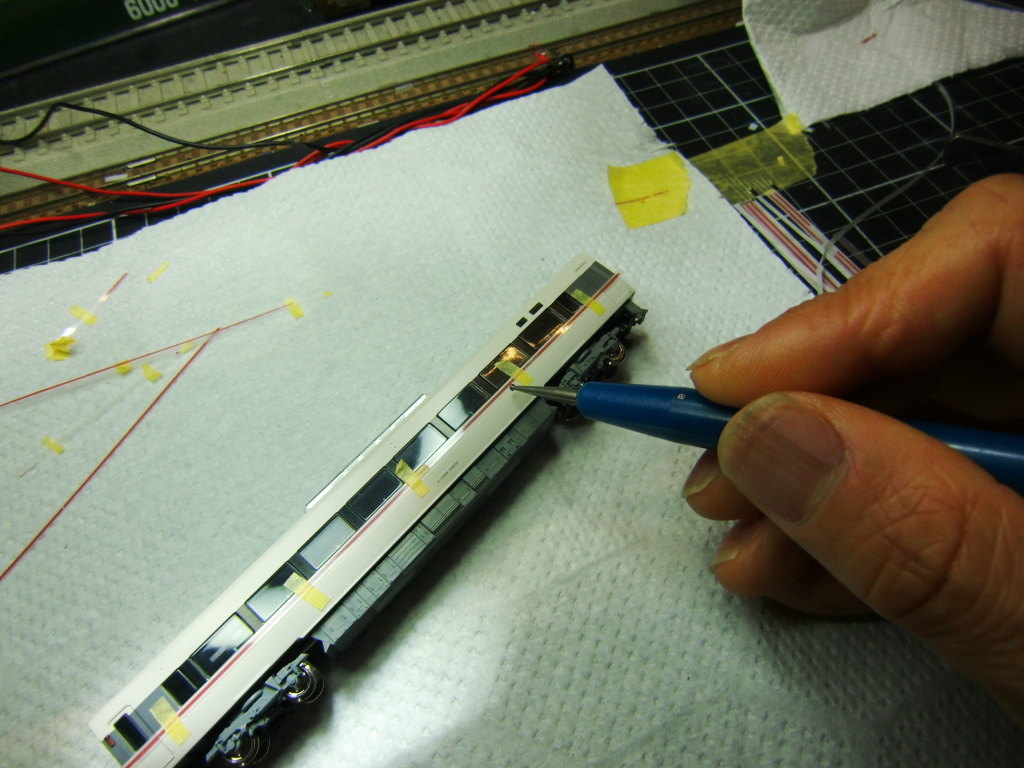
転写作業は慌てずゆっくり進めるのがコツです。
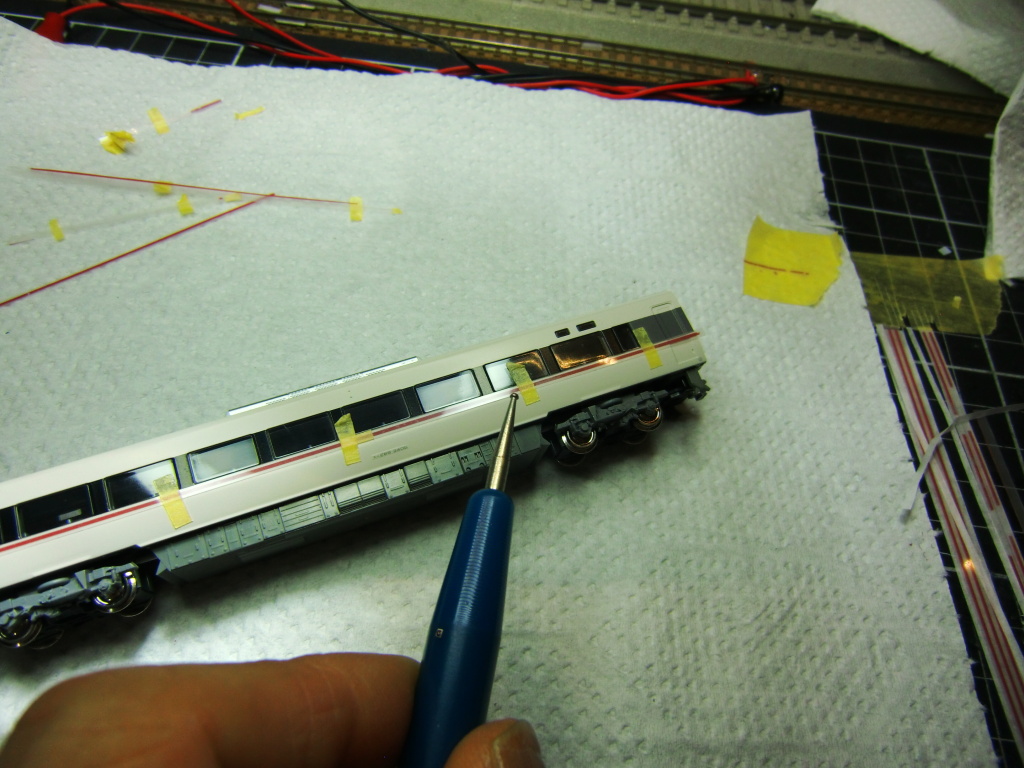
1回目はかるくなぞるかたちで軽く定着させます。これは、力を入れてこするとシートがずれてしまう可能性があるためです。2回目で少し力を入れてしっかりと定着させます。
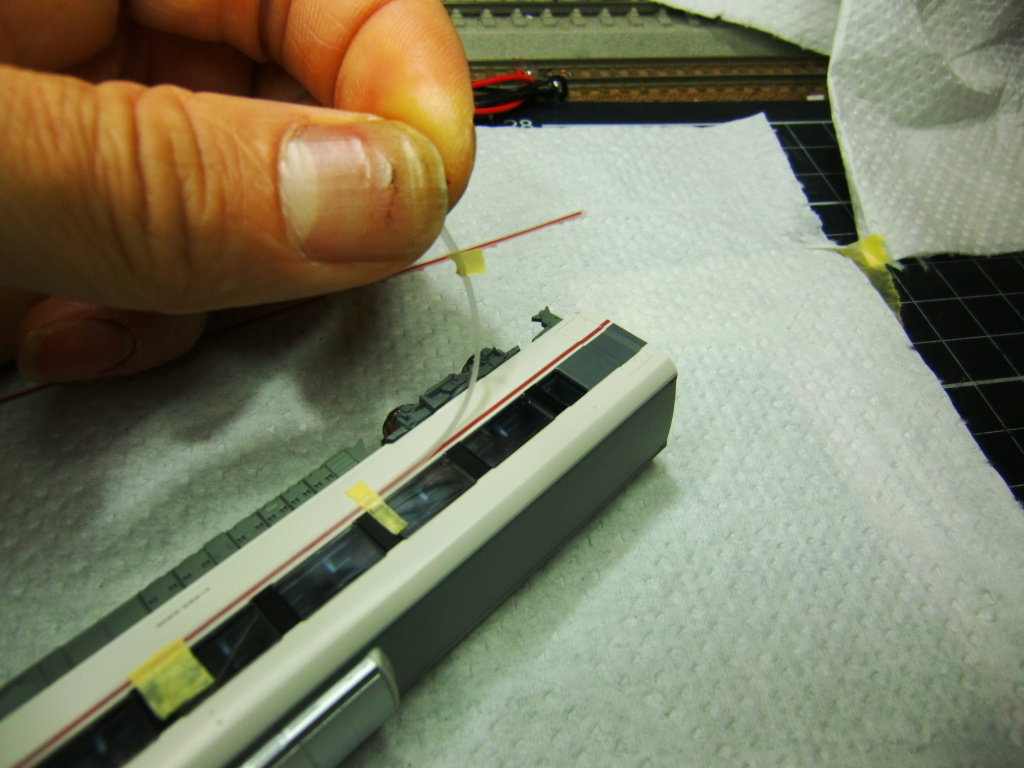
転写状態を確認しながらゆっくり剥がします。


一通り貼り終えたら、今度は表面保護のため「UVクリアーコート」を行います。

ちなみに、今回使用したインレタはコート処理必修です。そのまま何もしないと、短期間で帯が傷だらけになってしまうほど表面は薄く弱いです。中にはコートしなくても良いかな?と思えるくらい丈夫なインレタも存在しますが、今回のインレタはコート処理は必修です。


今回は、こちらの小さいエアーブラシ(ノズル径:0.2mm)を使います。

クリアーの濃度を調整していきます。エアー圧を調整して吹き付けていきます。
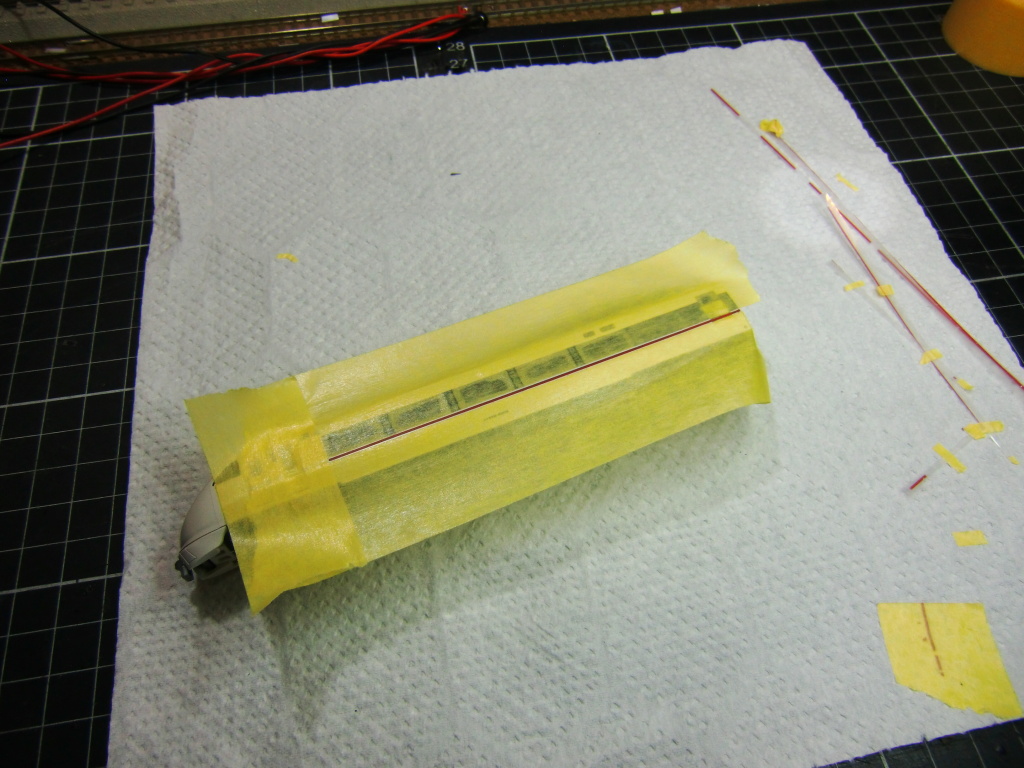
帯から約0.2mm程度あけてマスキングしていきます。
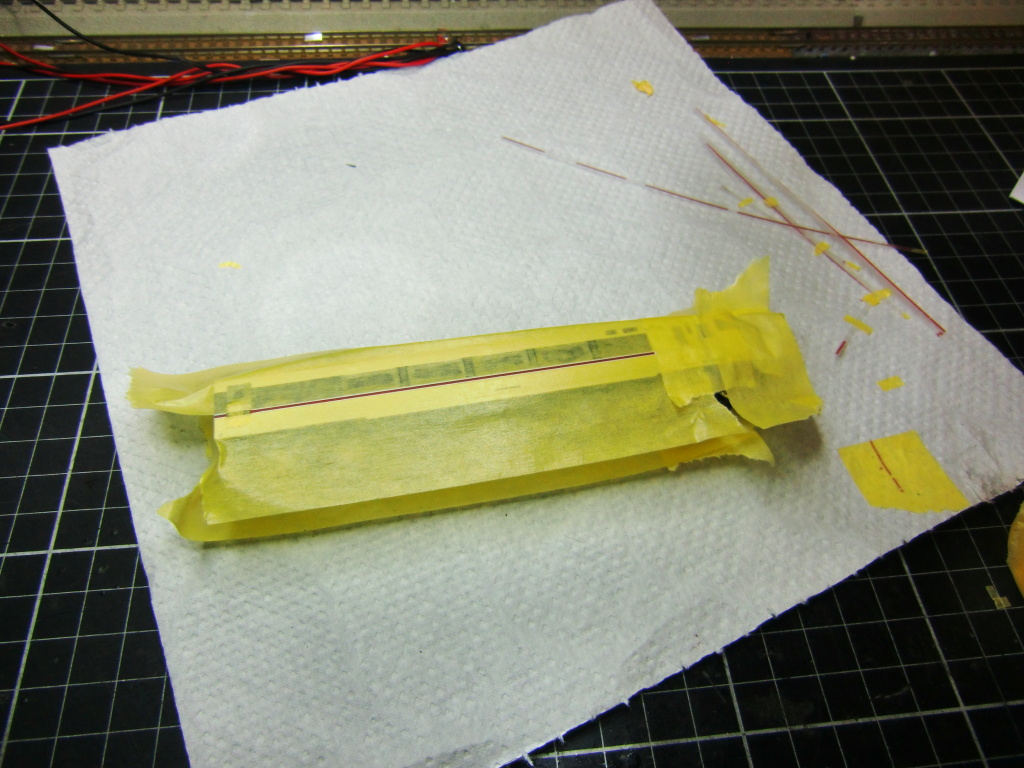


コート層の具合を見ながら、3~5回ほど薄く吹き重ねて層の厚みを付けていきます。
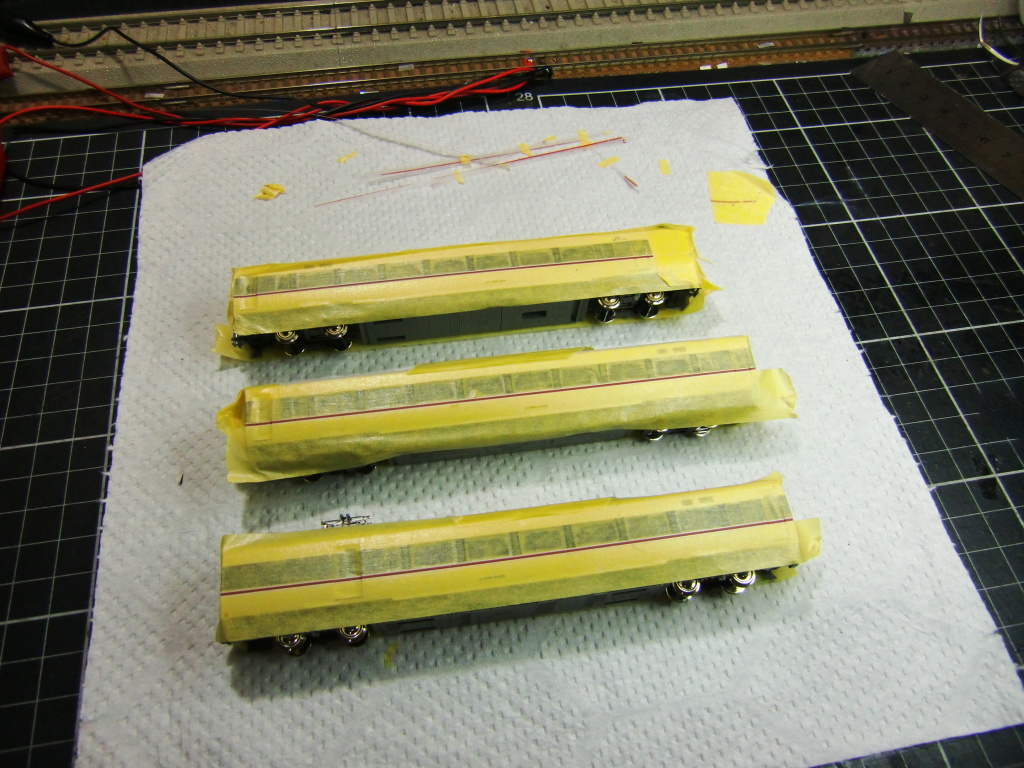




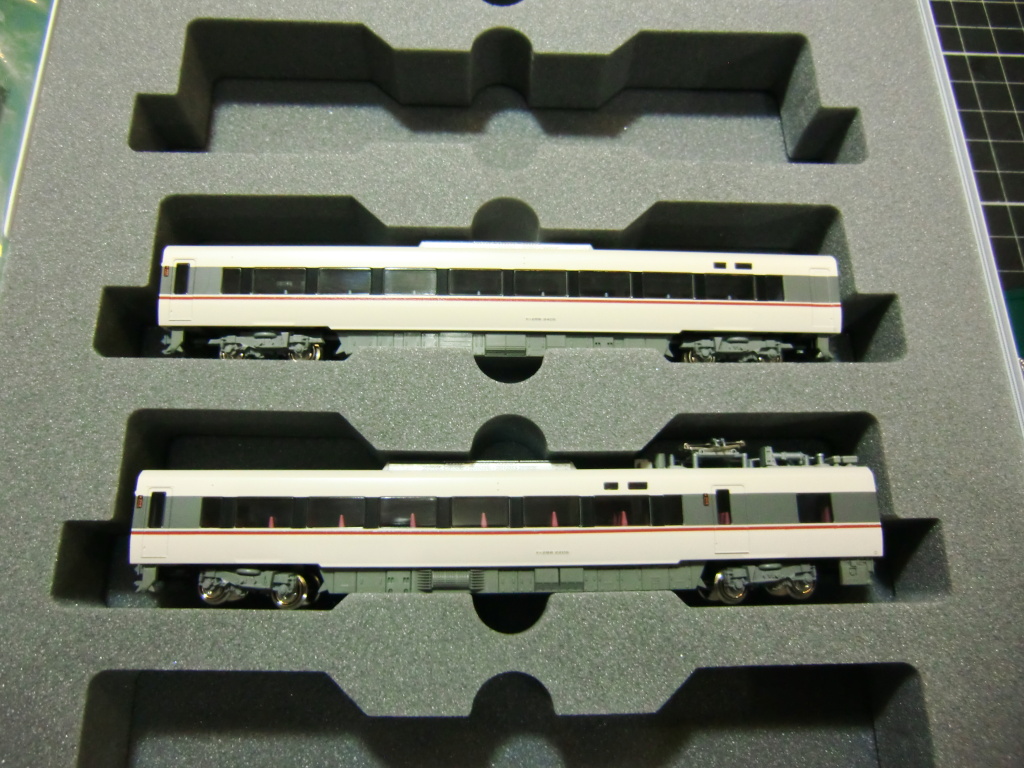

作業完了でございます。
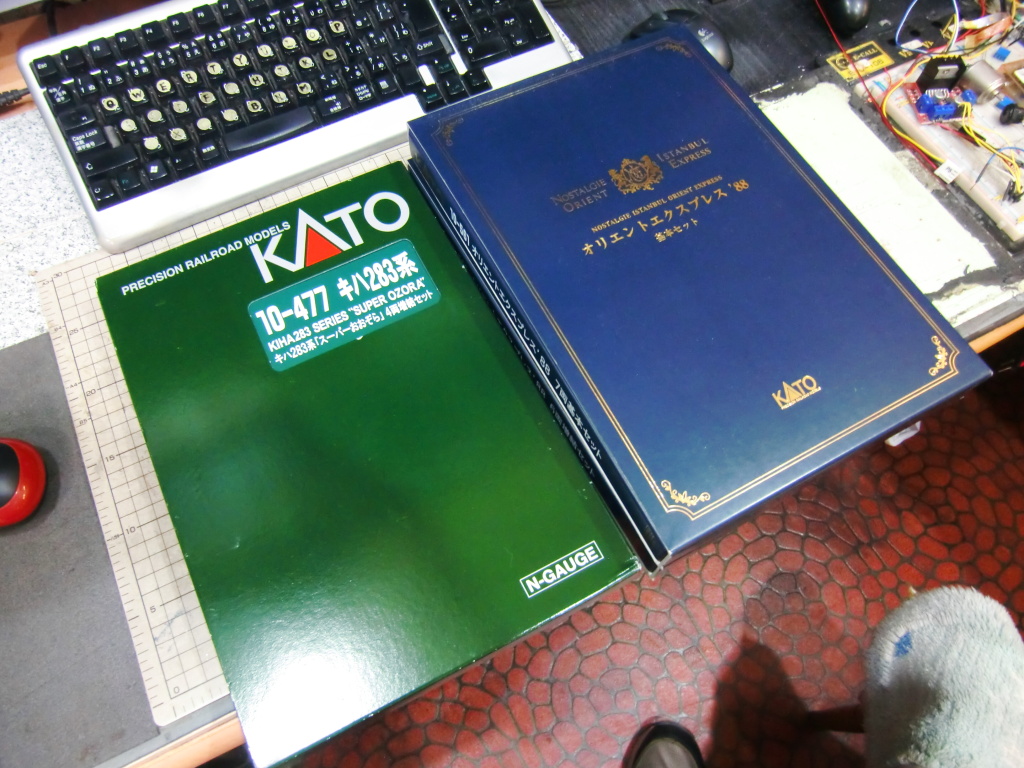

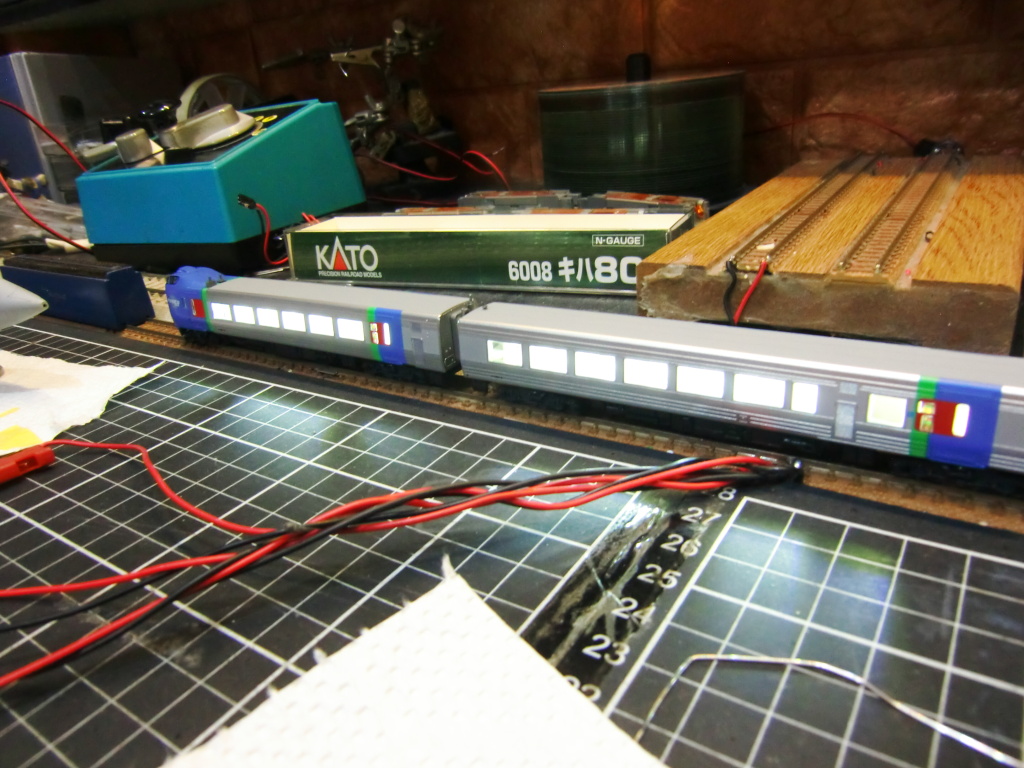
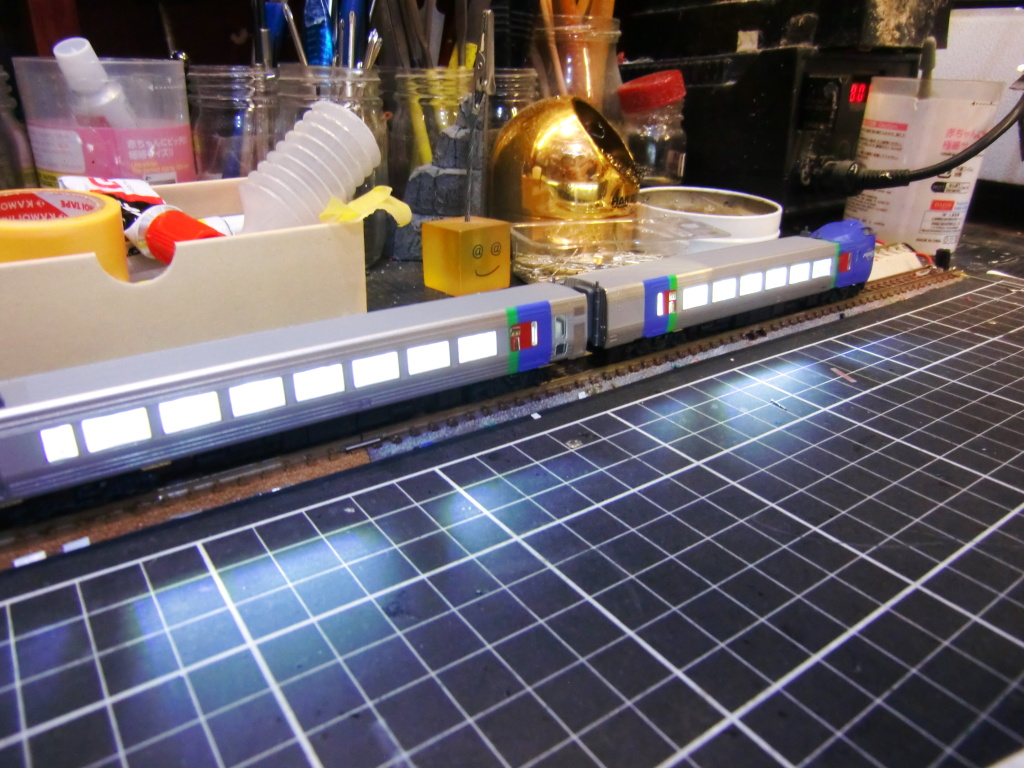

まずは、こちらの編成に対しての室内灯組込み完了です。


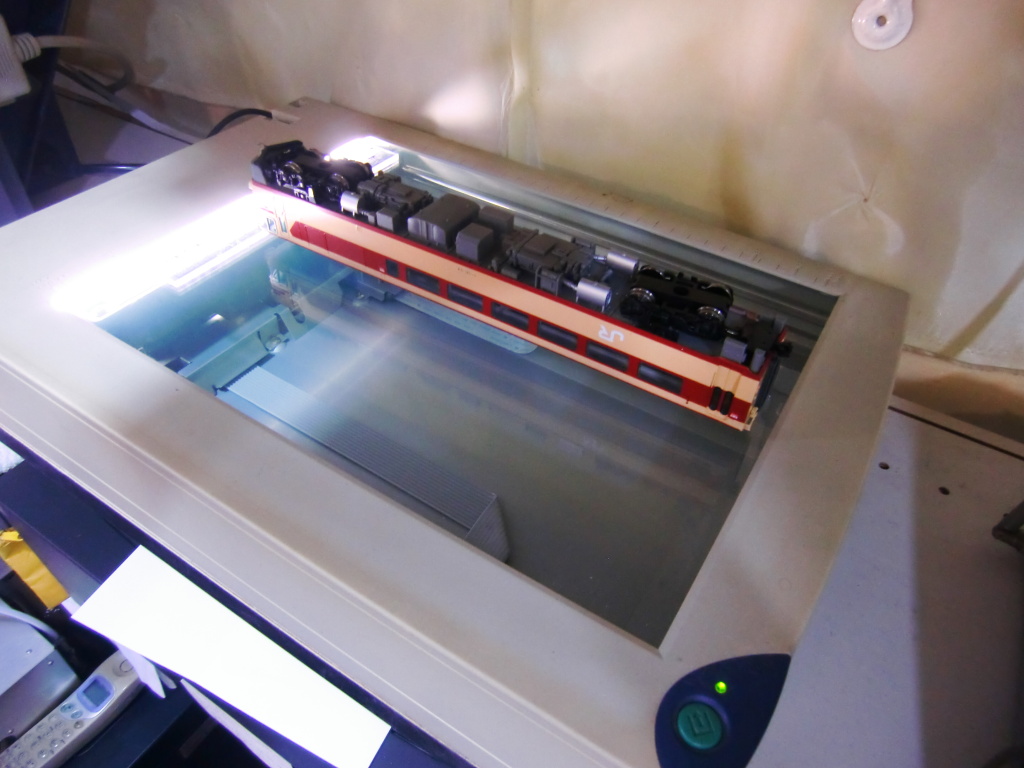
屋根上をPCに取り込みます。

パーツデータを作ります。
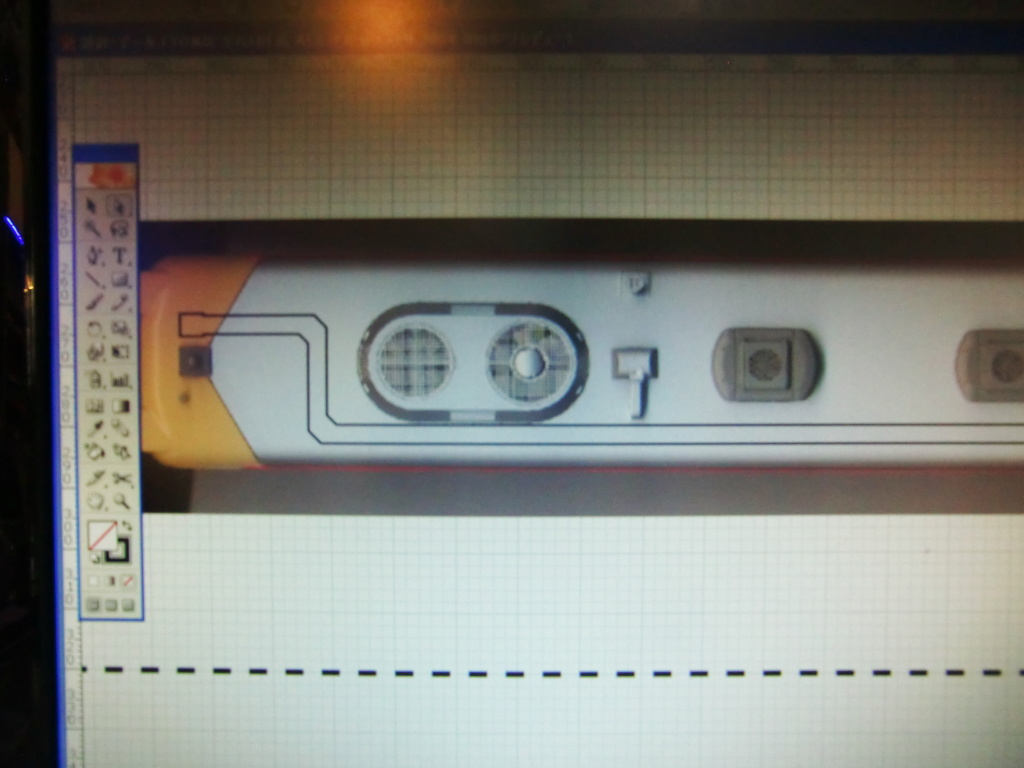

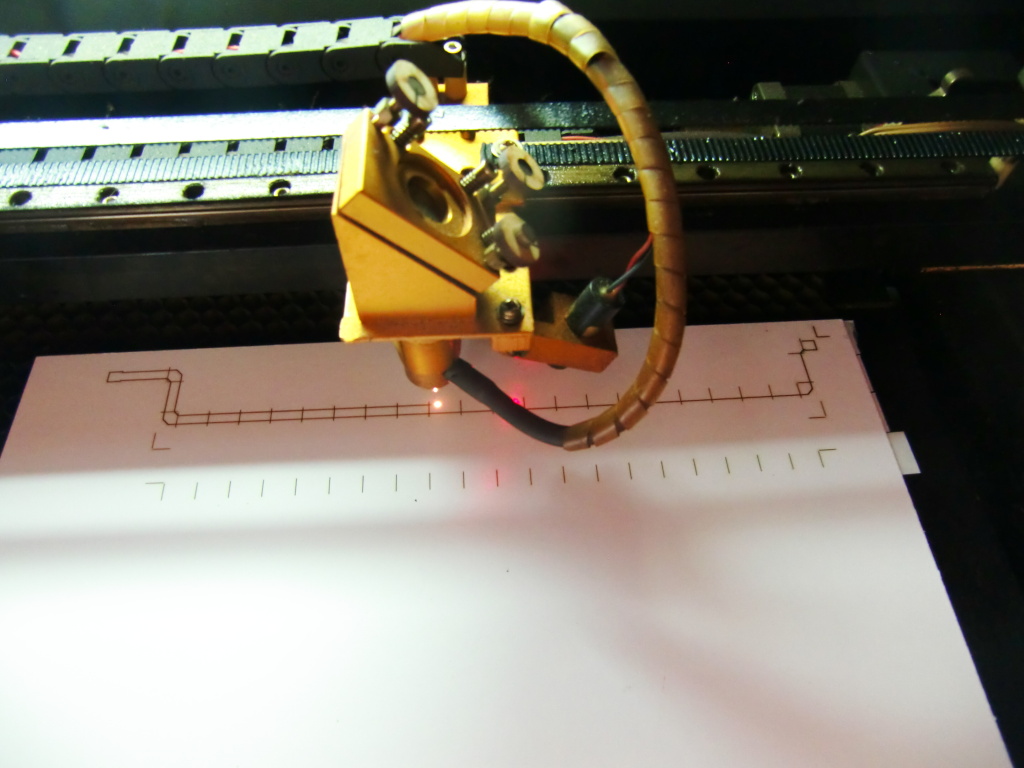
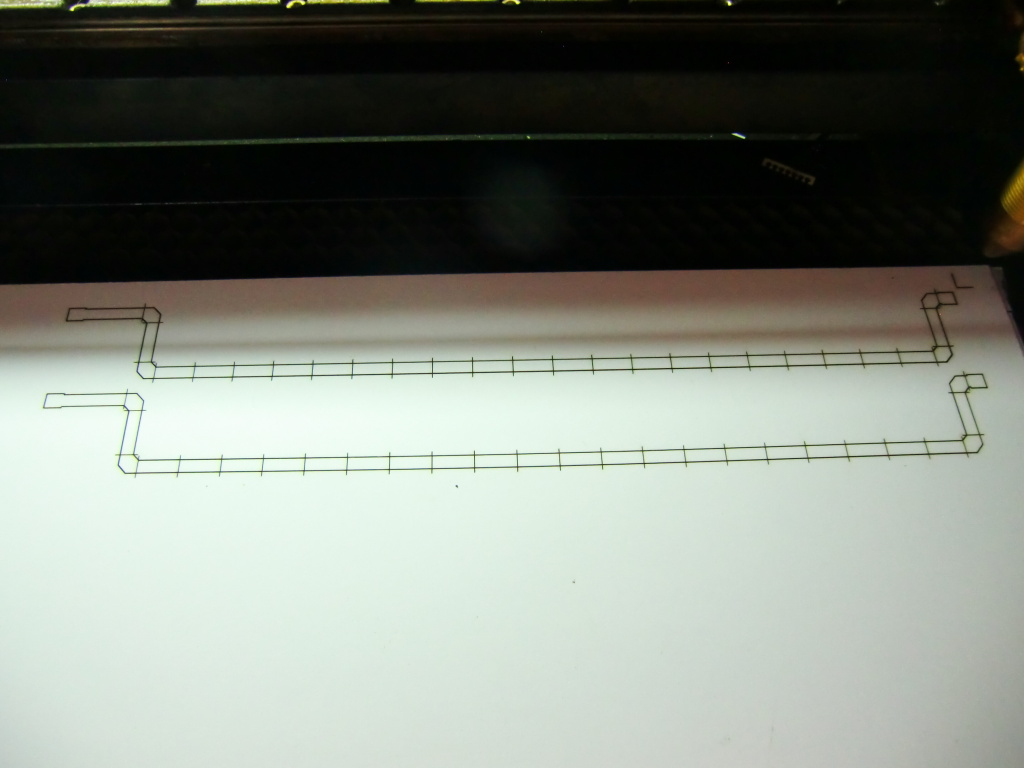
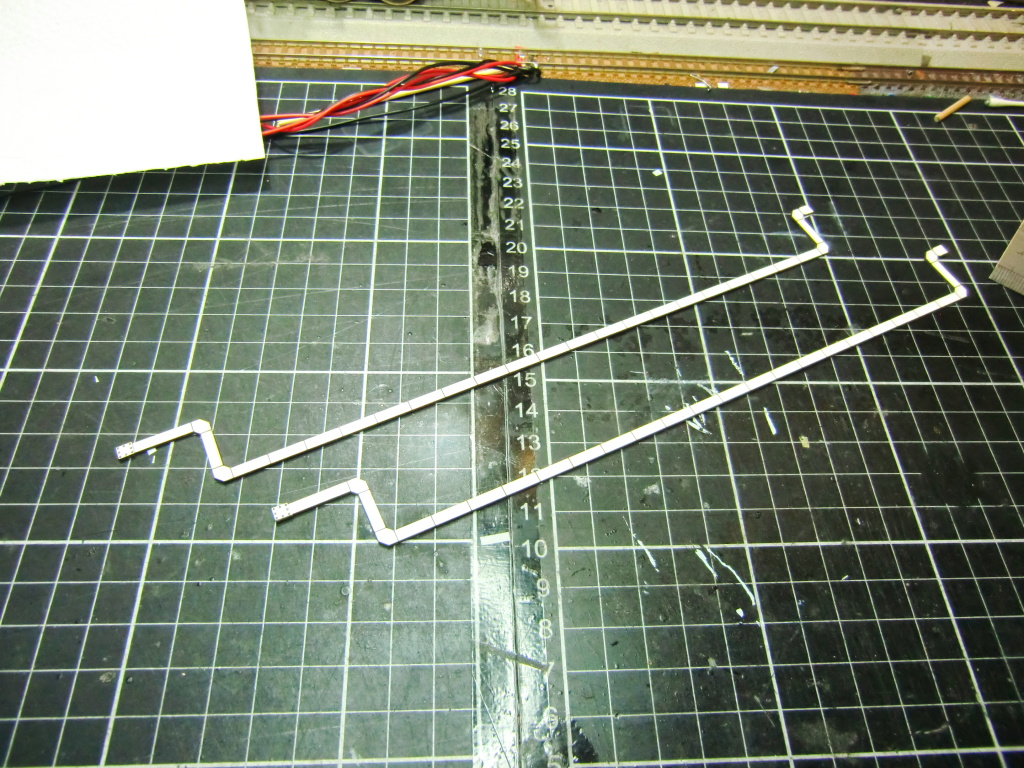
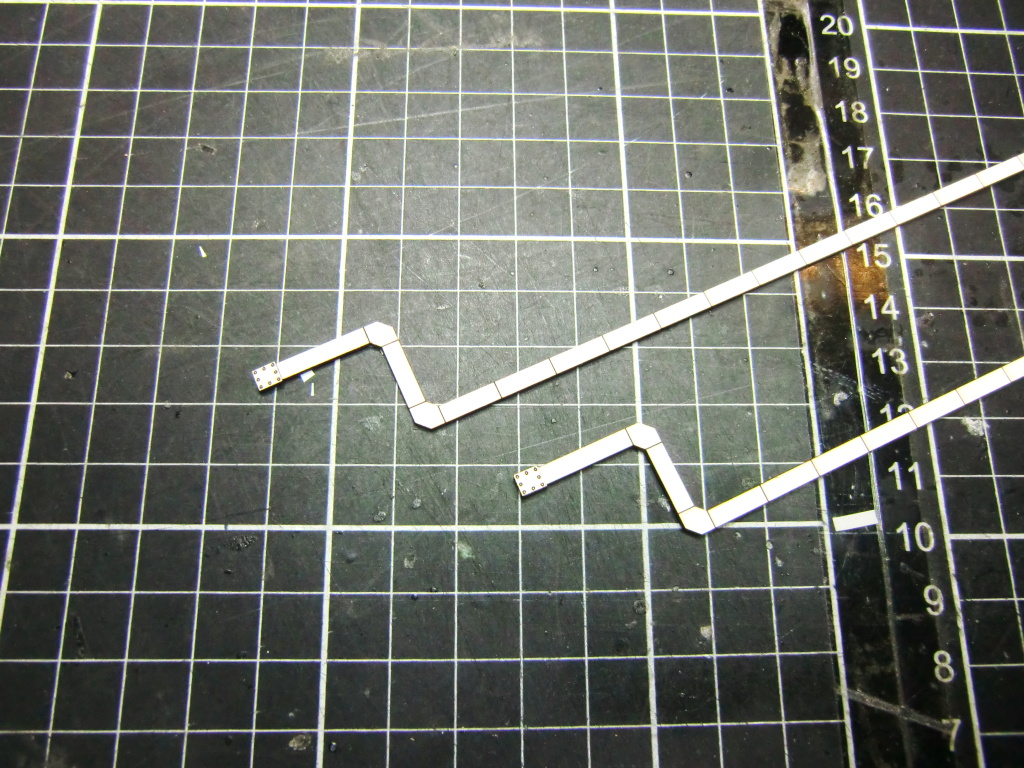
サーフェイサーを吹きます。
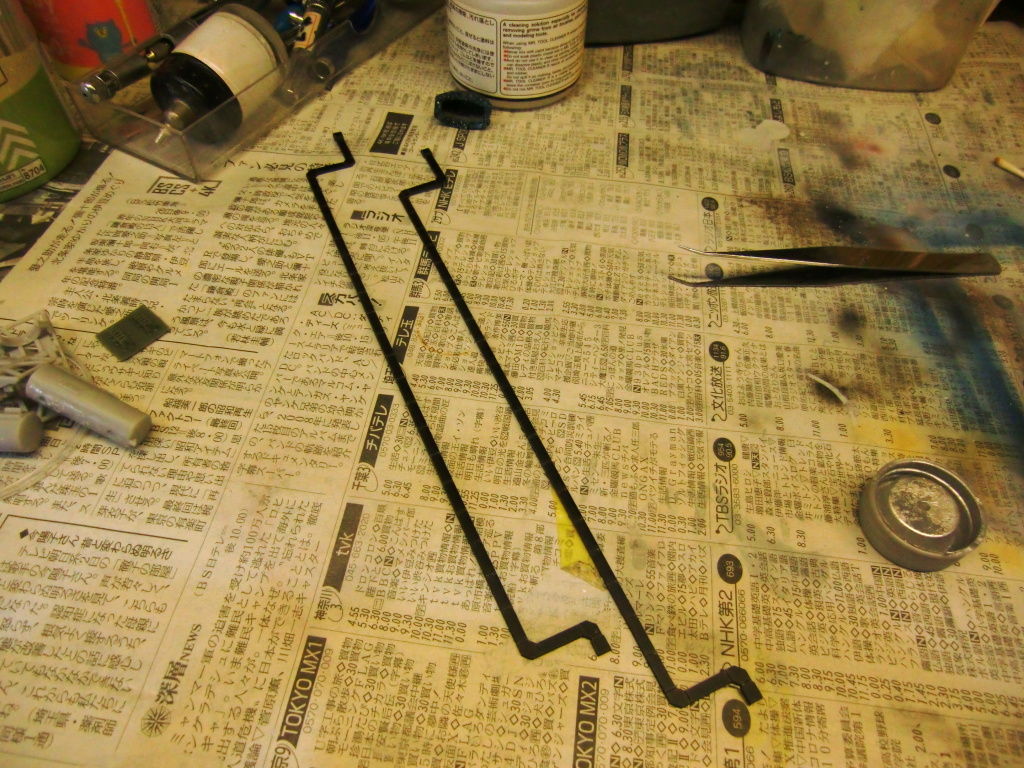
次に光沢ブラックを吹きます。

「ステンシルバー」を数回に分けて塗り重ねていきます。通常のシルバーでも良いのですが、今回はステンシルバーを使います。
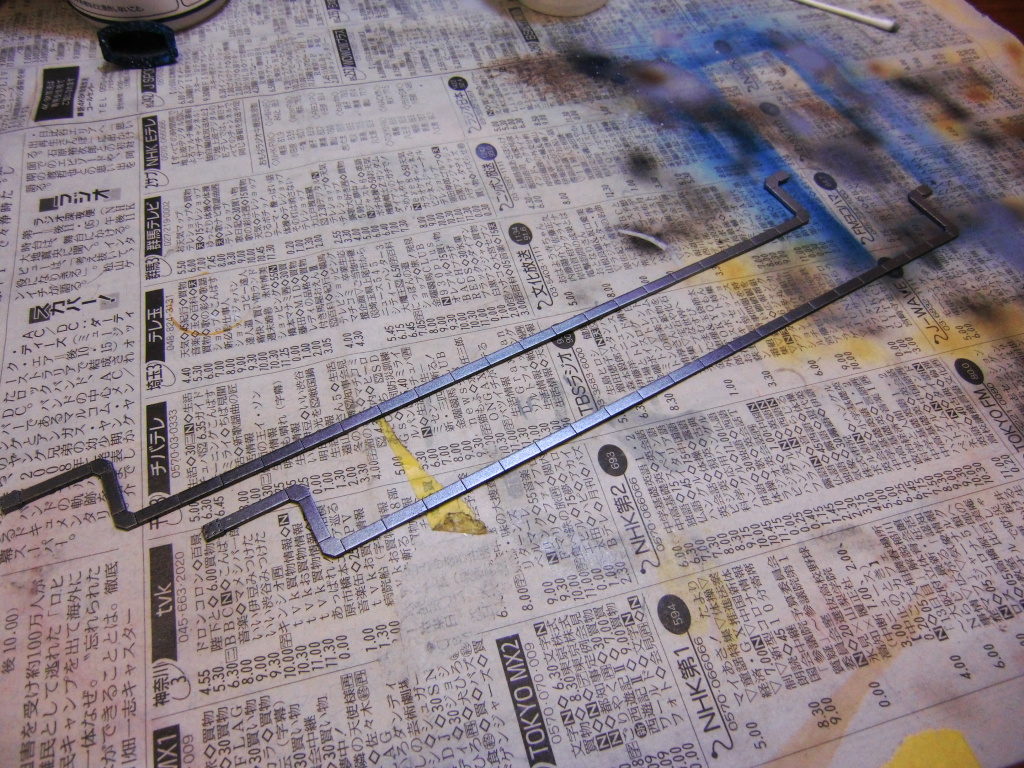

パーツ固定用のガイドを屋根に貼ります。
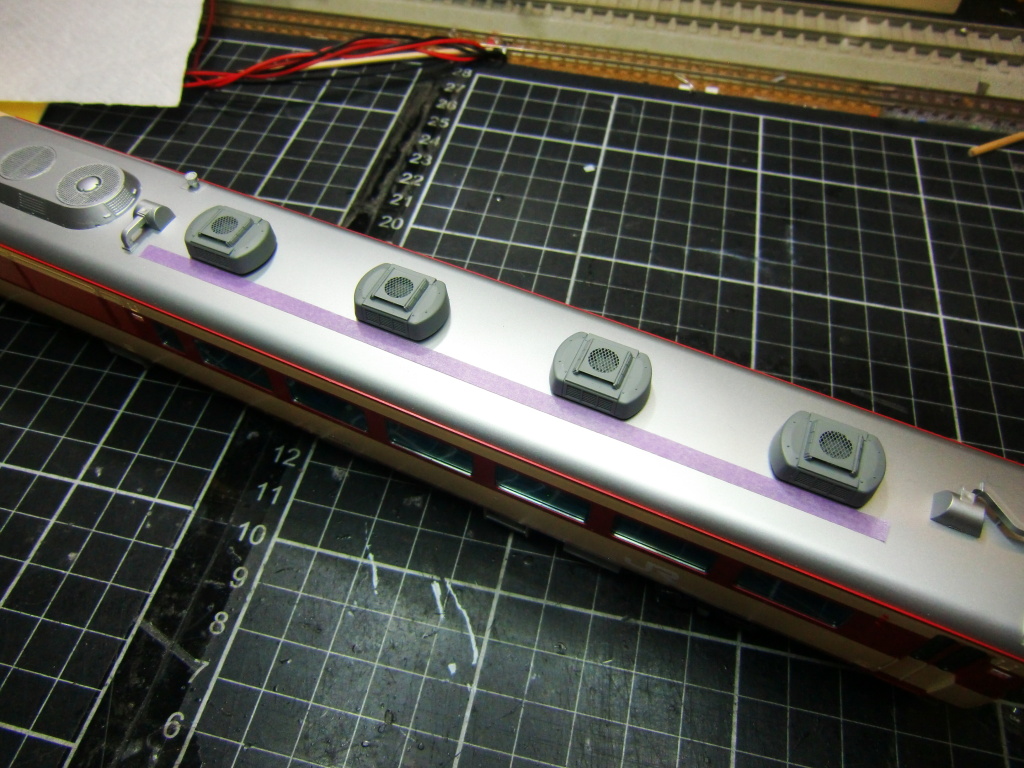
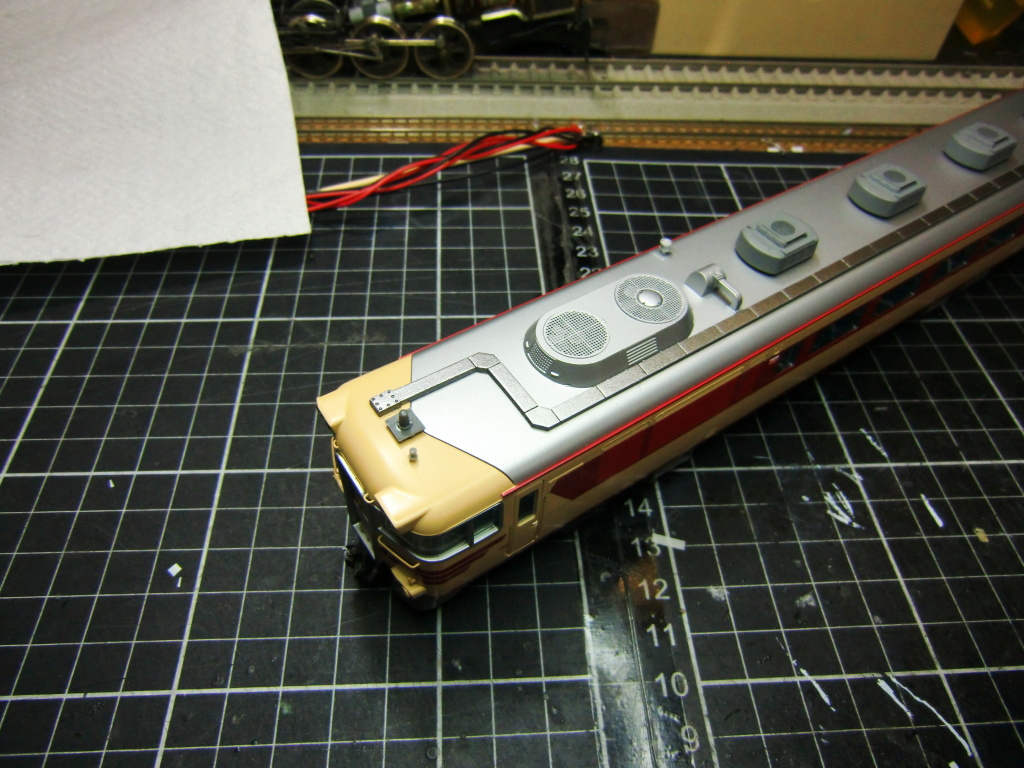
ガイドに合あせてパーツをしっかり固定します。
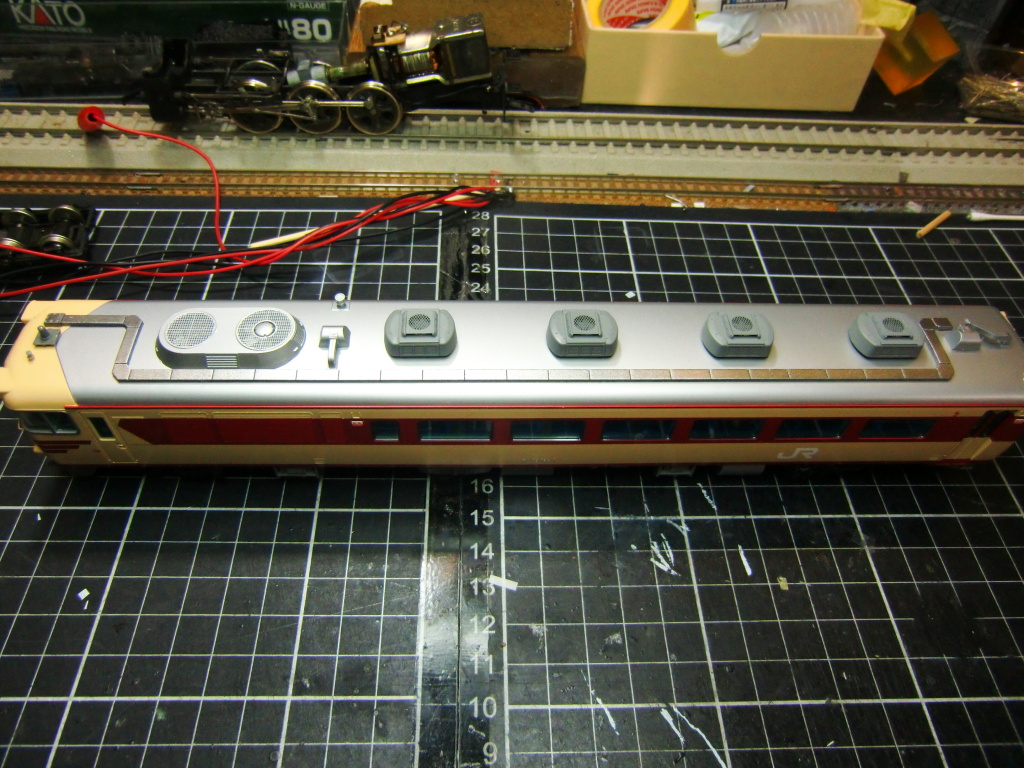
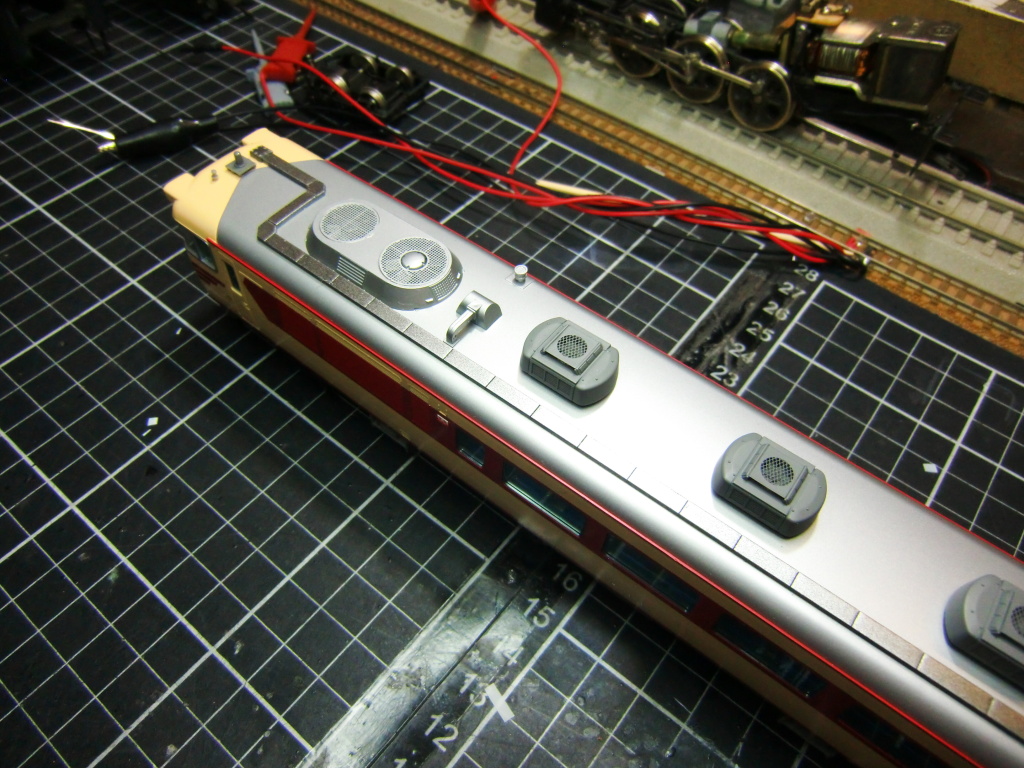

作業完了でございます。


この時代の製品は基本的には同じような配置の基盤が採用されているため、光の偏り(左右のライトの明るさが極端に違う)や明るさが暗くなってしいます。


まずは、現状ですがMAXでこのくらいです。真正面からよく確認しないと、ライトが点いているのがわからないくらい暗いです。
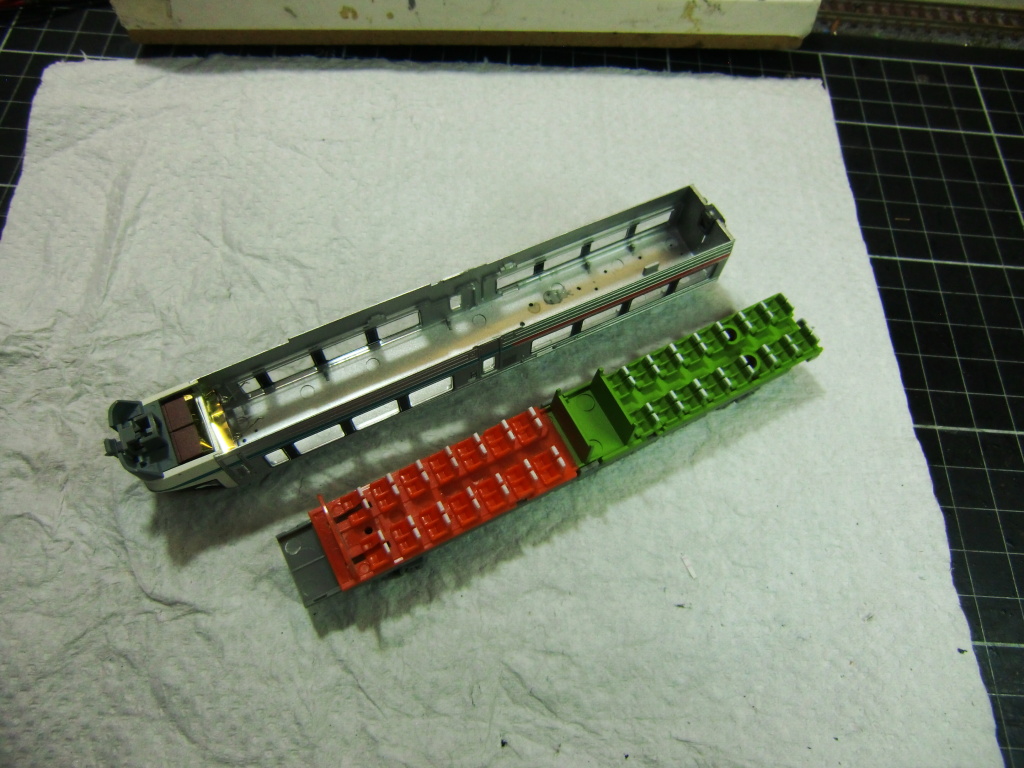
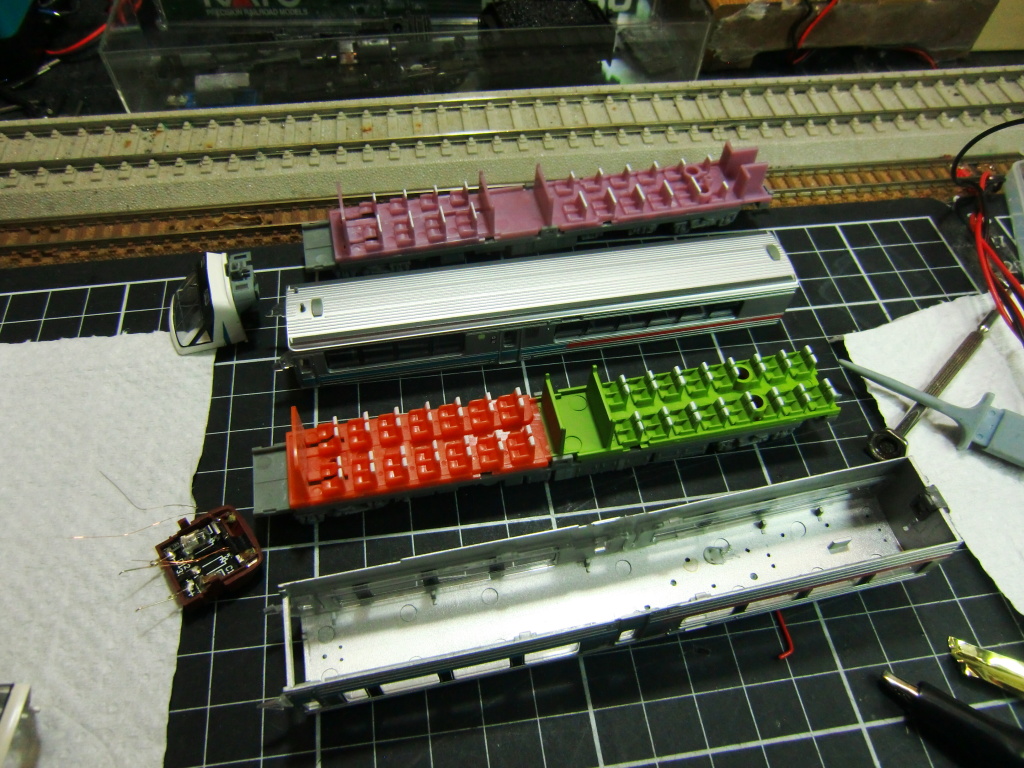
ライトユニットの取り出しですが、ちょっとしたコツが必要です。引っ張っても抜けませんのでご注意ください。外すには、前方部の三角窓を外側から内側に押し込んでから爪を外して引き抜きます。
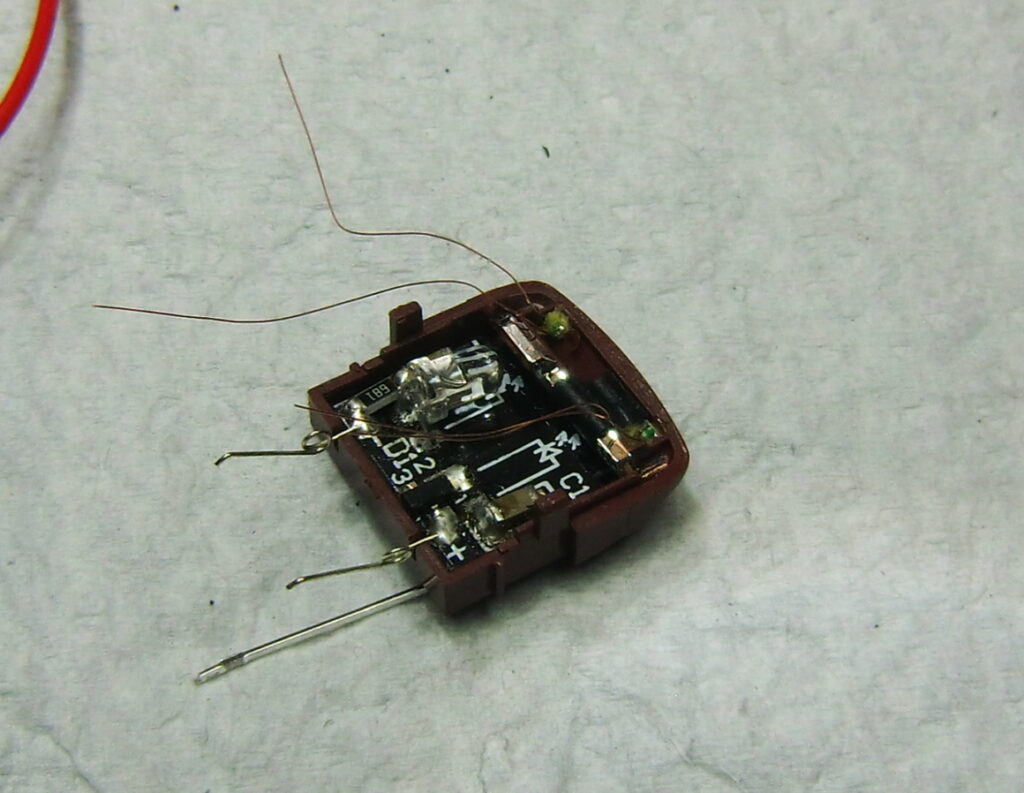
今回、テールはライトの構造はそのままに輝度をアップした白色LEDを使い、ヘッドライトは導光材を介さず直接にチップLEDをヘッドライトの左右に配置しました。このタイプの基盤は、単にLEDを明るいものに置き換えただけでは、ヘッドライトの明るさの変化は望めません。

正面はもちろん、横から見てもヘッドライト明るさを実感できるくらいまでになりました。


テールも加工前に比べてだいぶ明るくなっています。作業は無事に完了です。今回は、通常の加工では対処できないため特殊加工として作業いたしました。
今回は、ギア破損ということでご依頼いただきました。修理の中でギア破損は大変難しい部類に入る作業でございます。ギアは大変精度が求められるパーツだけに難しいのであります。
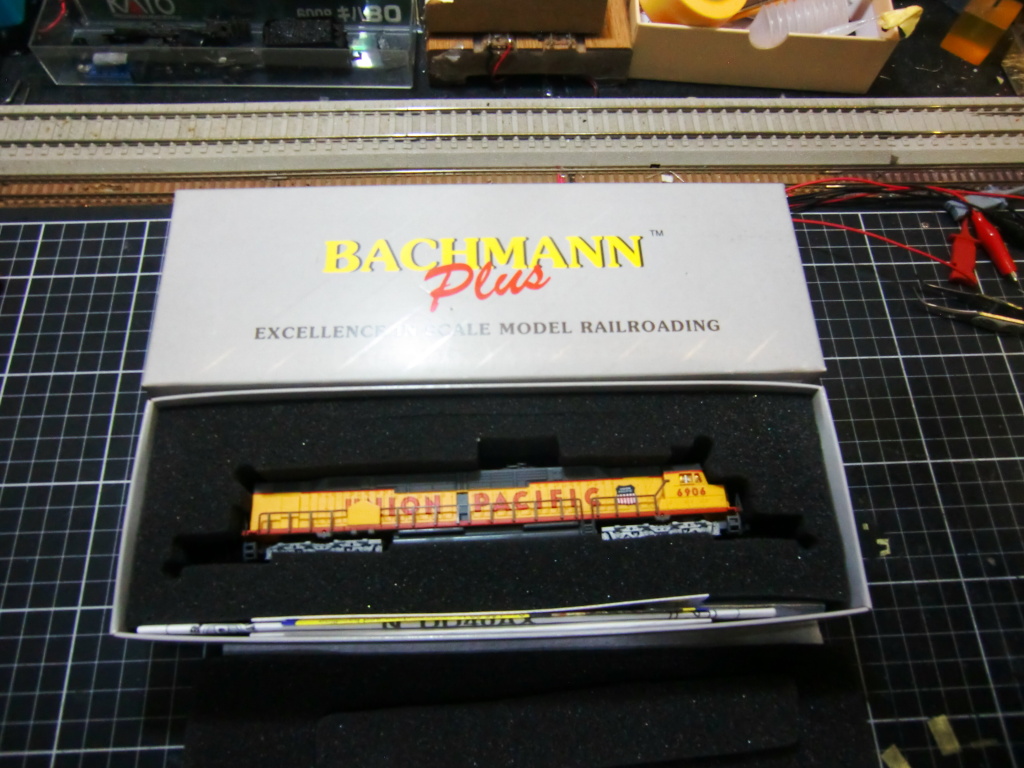

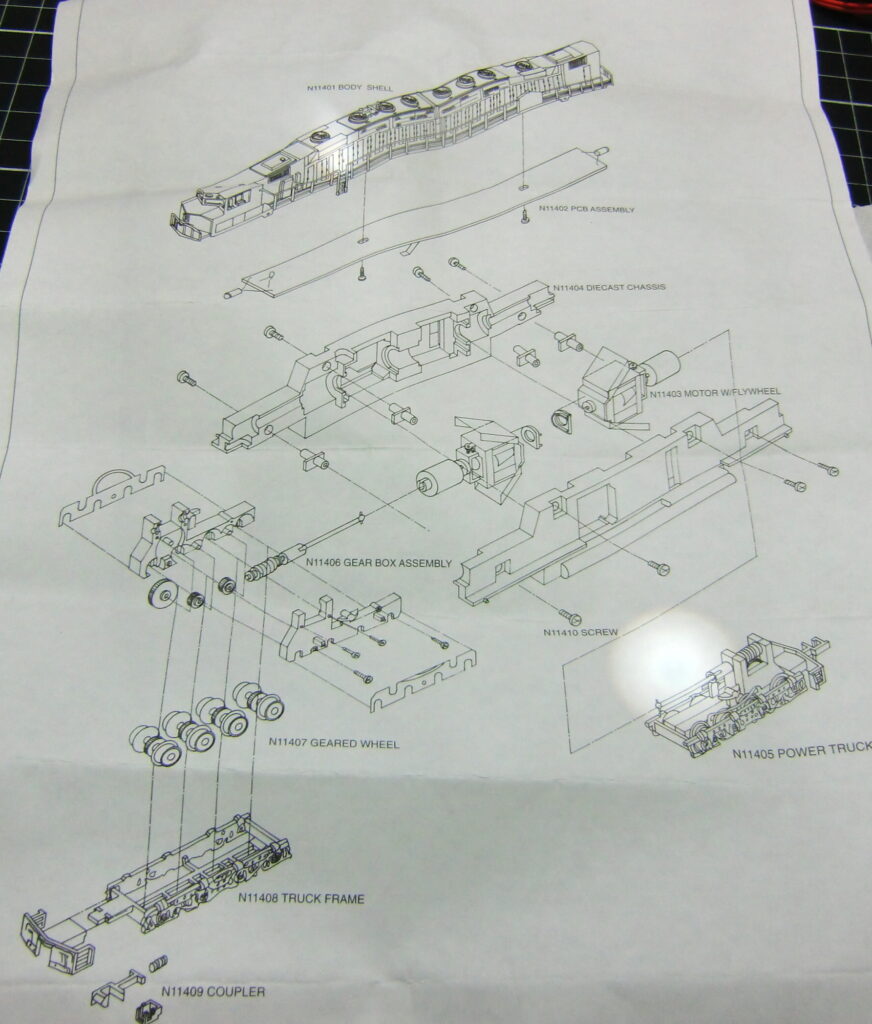
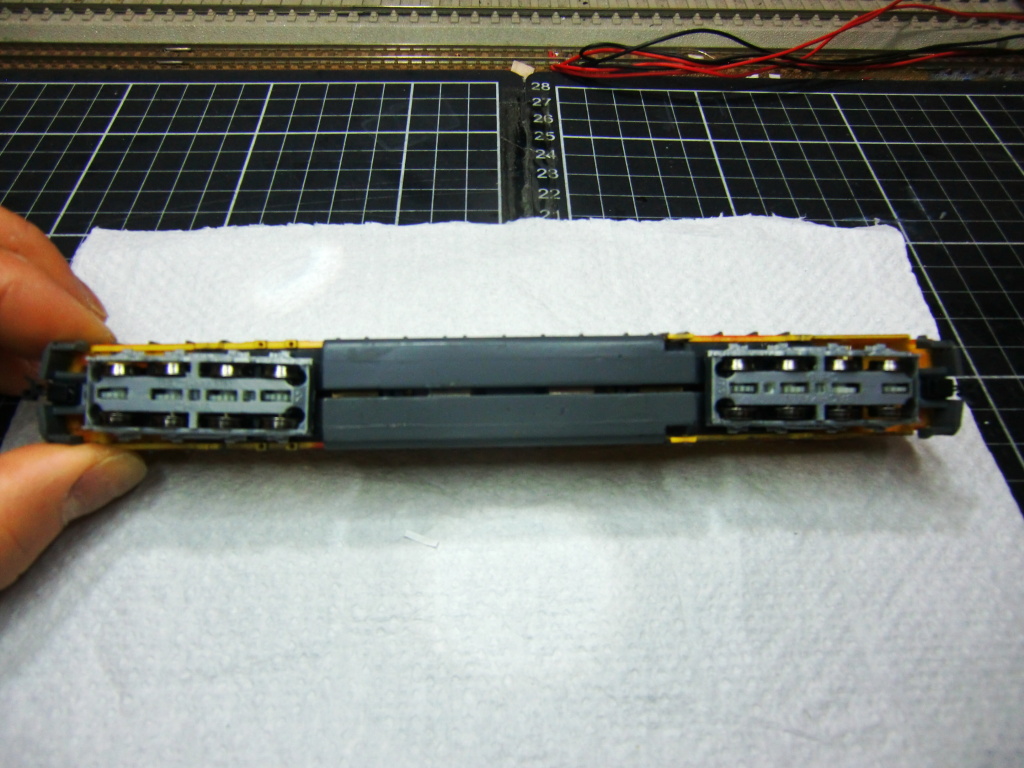
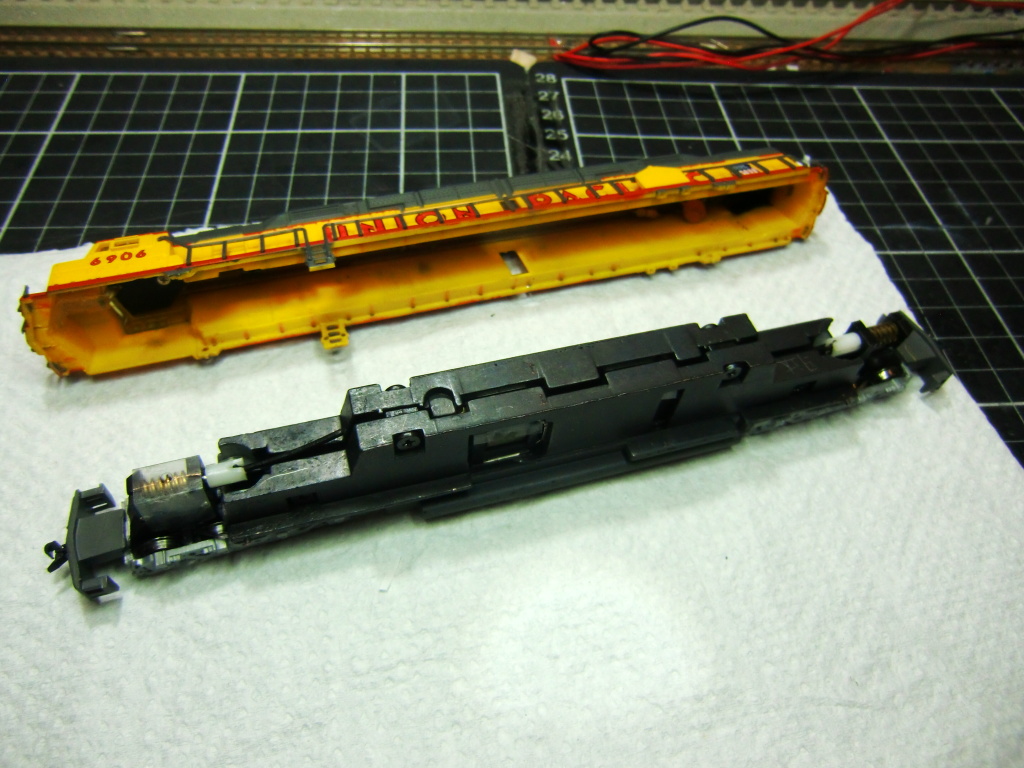
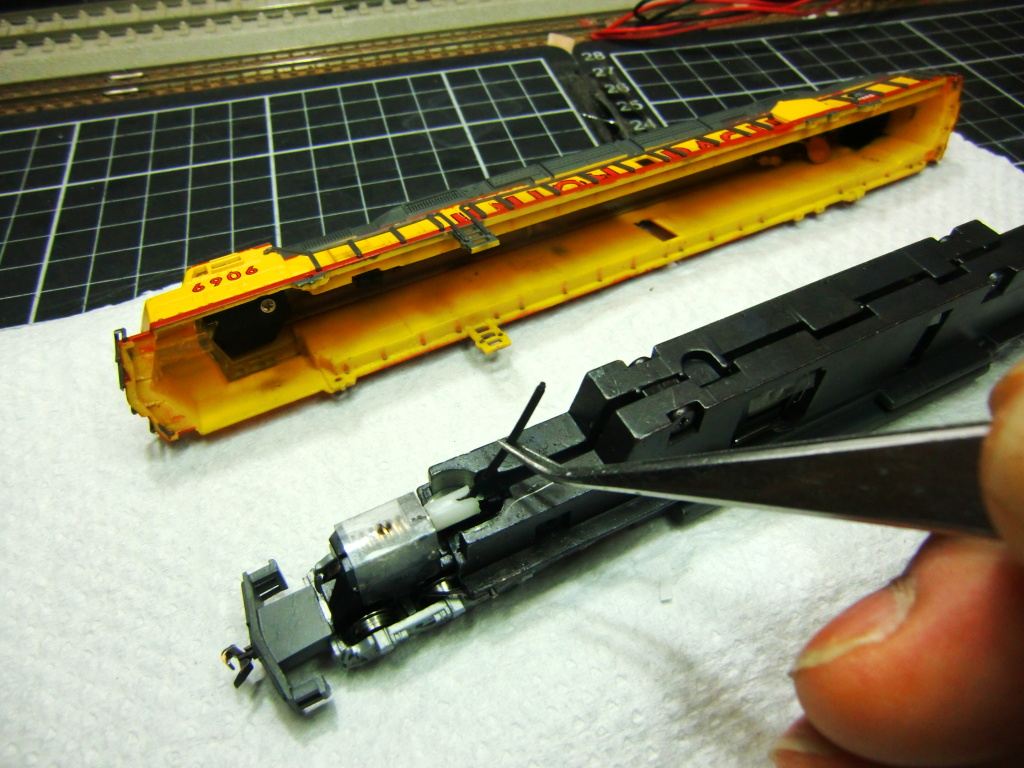
ドライブシャフトも途中からもげてなくなっています。これは、ギアが破損しているため、回転がロックされたことでモーターの回転を止める大きな力がシャフトに加わったことでネジ切れてしまったものと考えられます。
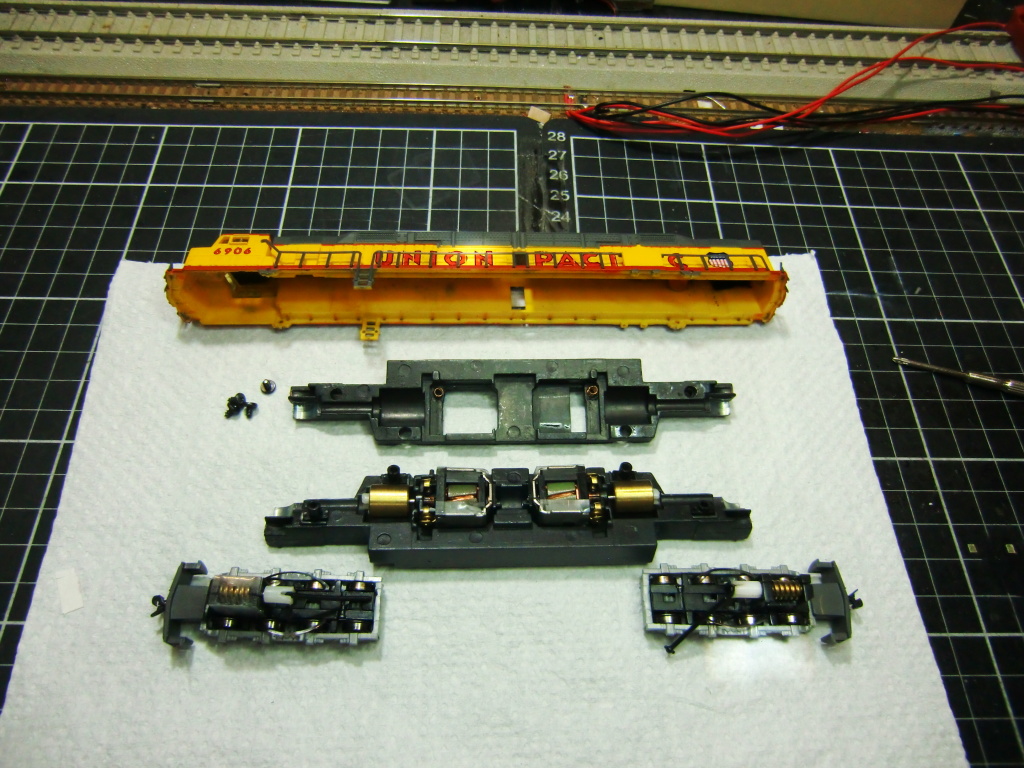
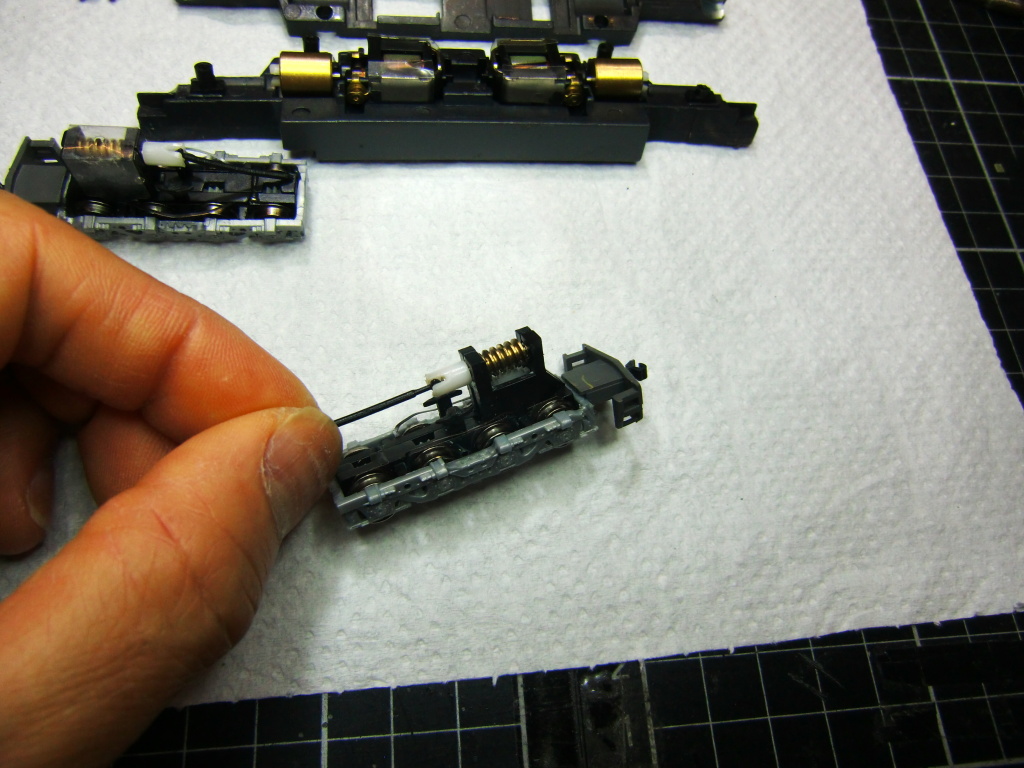
手で少しずつ回して問題となるポイントを探ります。両台車とも特定の位置でロックされます。これはギア割れによりピッチ幅が変わったことにより起こる症状ですね。
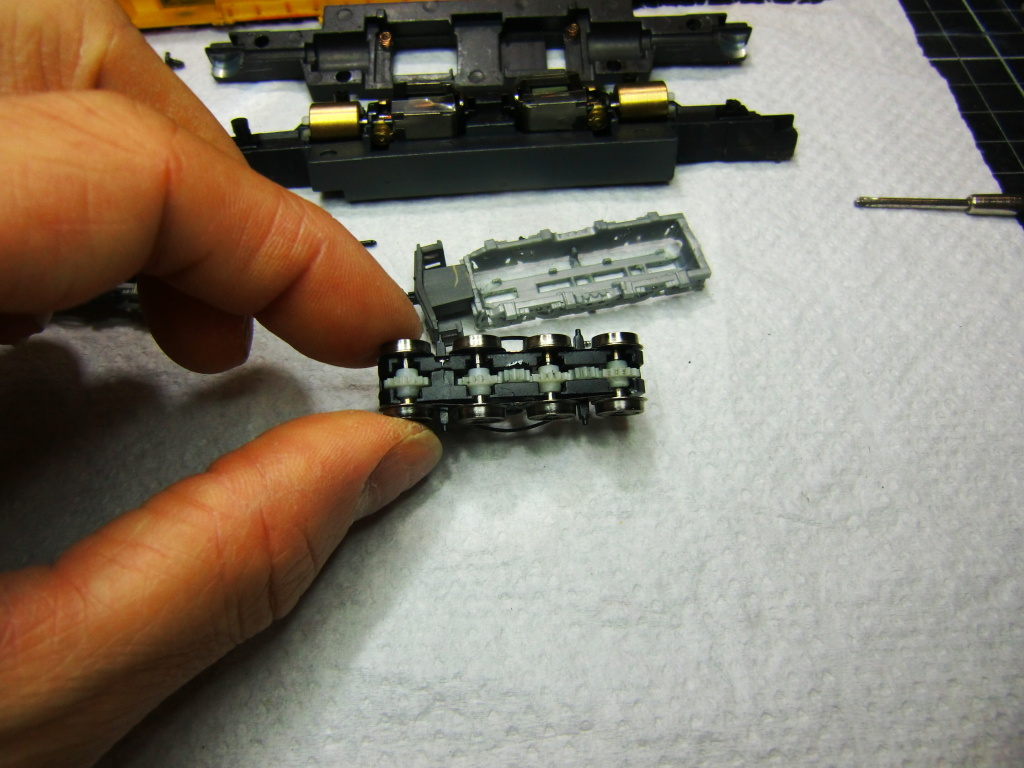
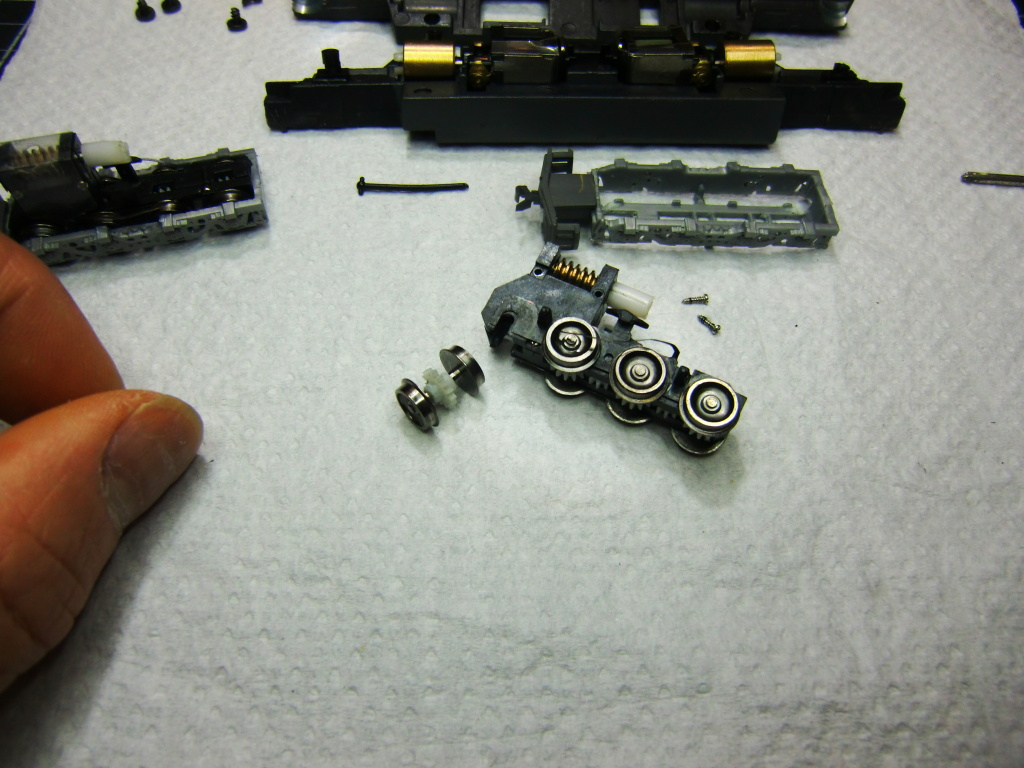
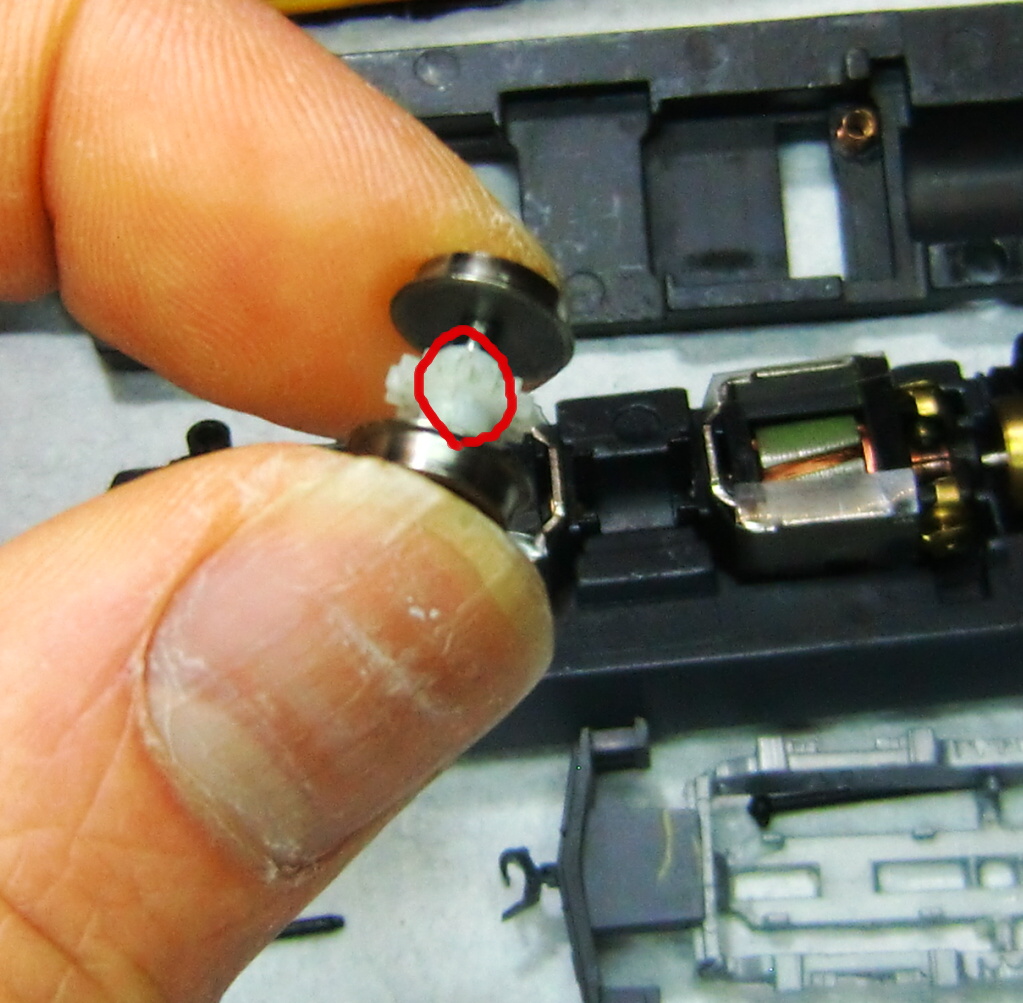
これですね。他にないか確認していきます。

台車のギアは、かろうじて無事な2個だけでした。
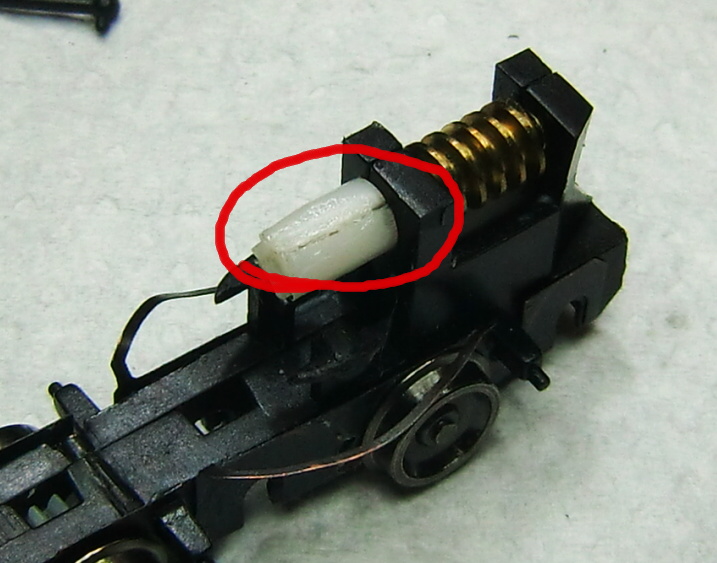
ギアだけでなく、集電板も片側が折れています。また、こちらのパーツも開いて割れています。当初考えていたよりも問題個所が広範囲に及んでいるようです。上記のパーツはロックタイトを亀裂に流して進行を止めました。

すべての車輪を外してルーペでよくよく確認してみたところ、結局すべて割れてました。過去の修理の中で、2個のギア割れを修復したことはありましたが、今回は全ギア8個と多いことから難航しそうです。
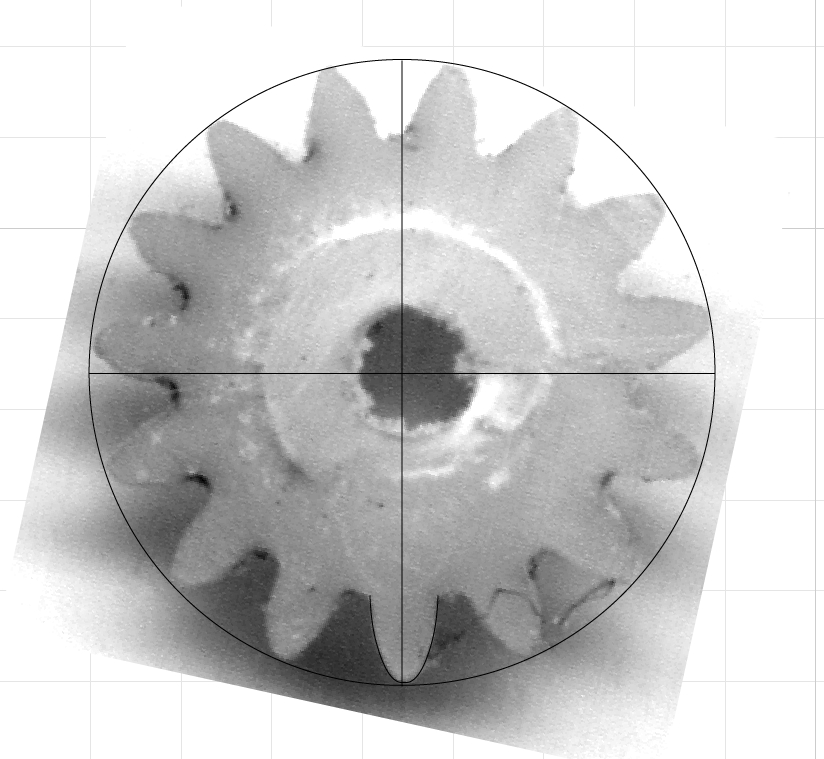
まずは、ギアの出っ張りをニッパーで切ってからヤスリで平らにならしてから、スキャナーでパソコンに取り込みます。直径と中心点を調べるため、外円と線を描きます。そこからギア形状のピッチを割り出します。
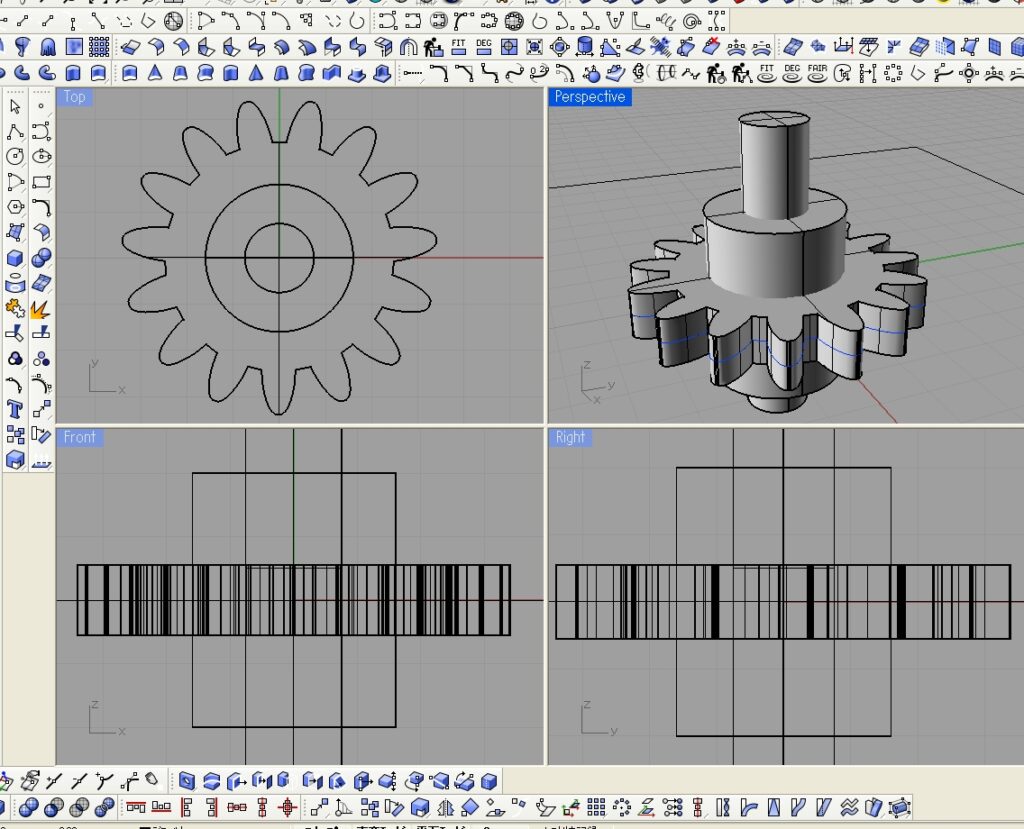
続いて、ギアとドライブシャフトの3D設計を行います。
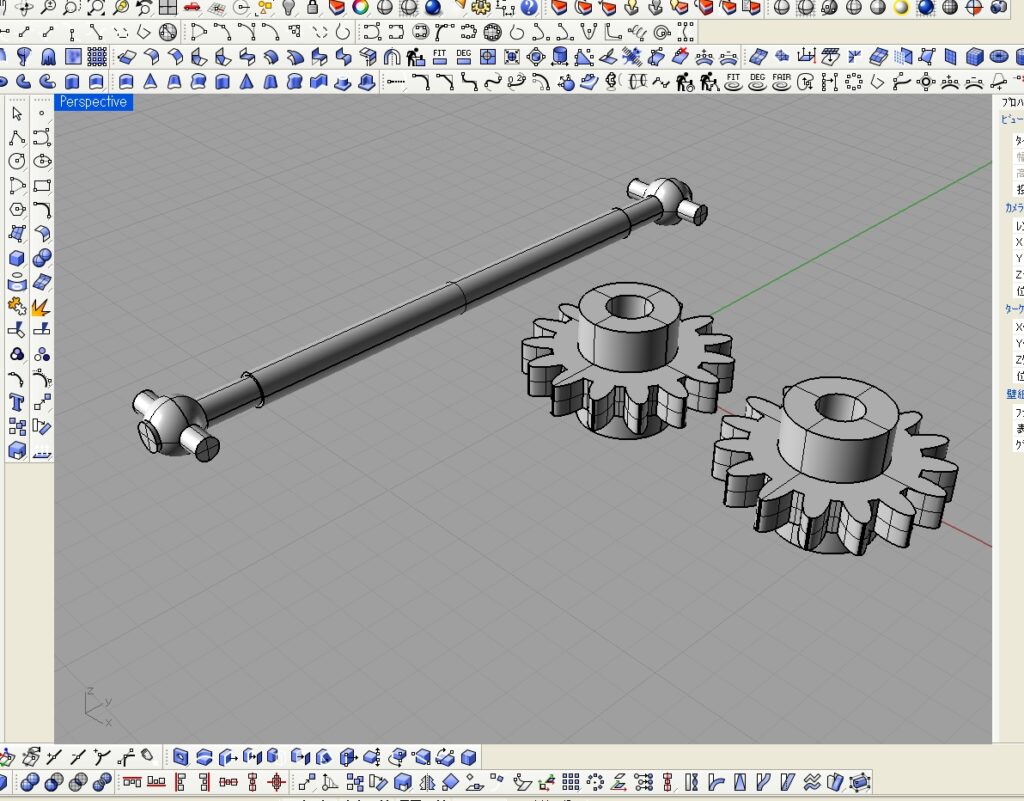
破損しているドライブシャフトについても復元します。問題はギアで、現物合わせを繰り返しながら、微調整していくことになります。

ギアとドライブシャフトが出来上がりました。ギアについては内径を0.1mm違いの2種類を制作してみました。


実際に台車に組み込んで、スムーズに回転するか手の間隔で1つ1つ確認していきます。今回から、新たに導入した高精細3Dプリンターで出力を行いましたので、従来よりも出力後の誤差はかなり少ないと思います。

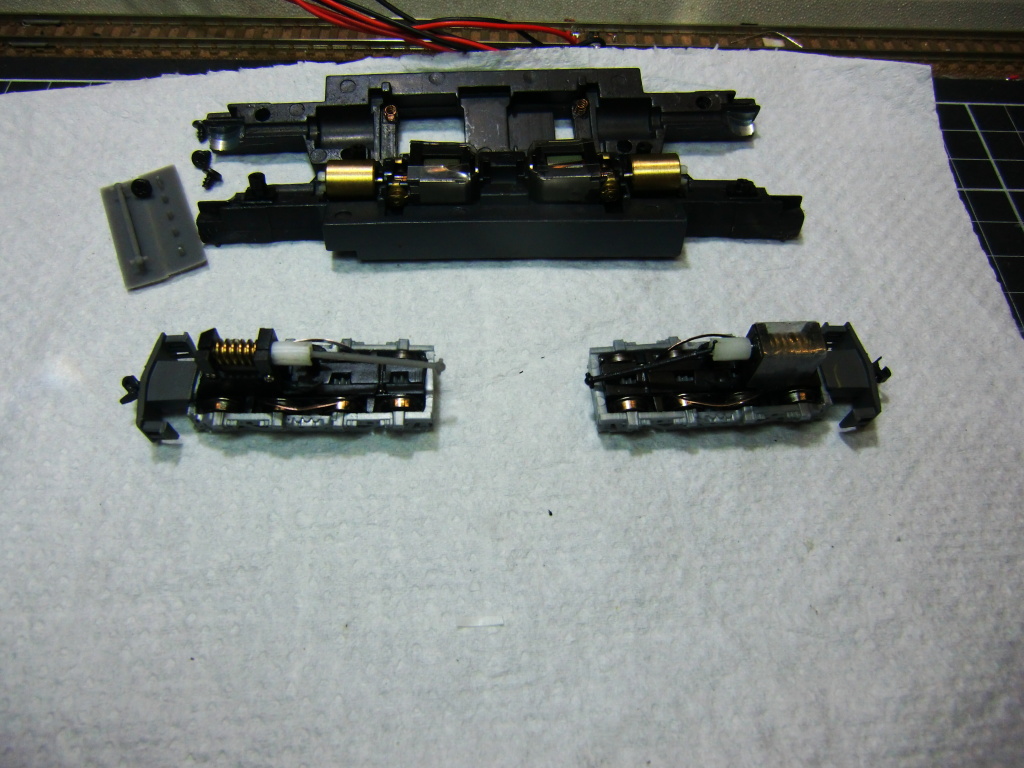
変色した集電板をポイント磨きを行って通電を良くします。また、折れた個所はハンダで繋ぎ直しました。
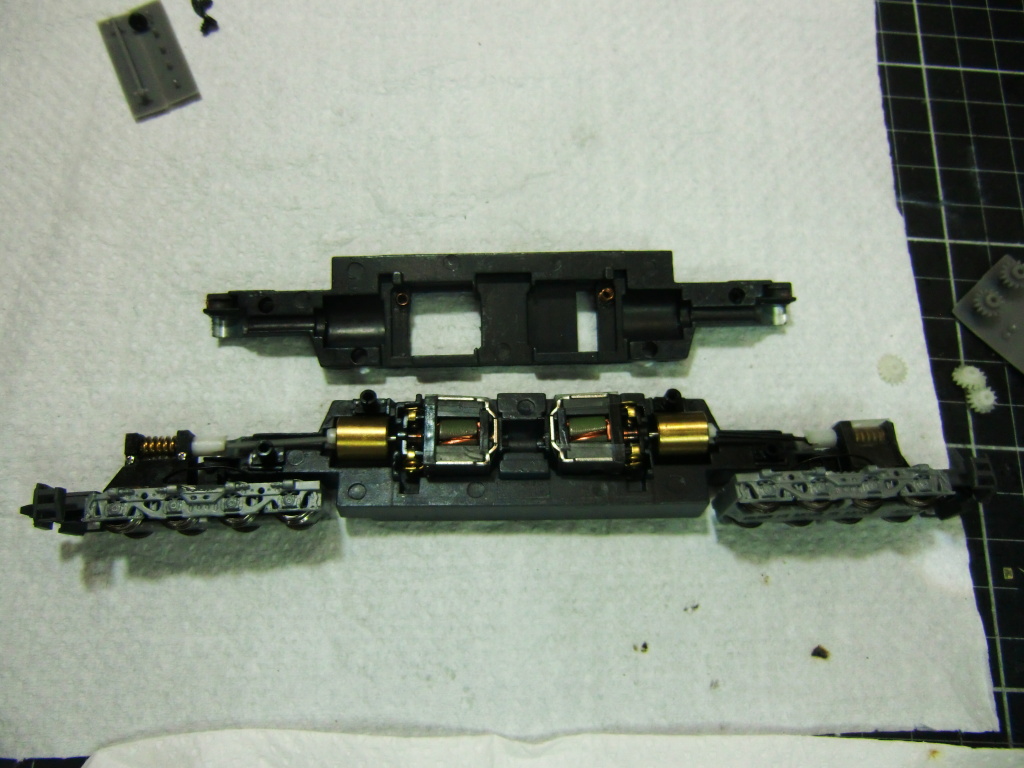

走行が安定するまでギアの微調整を繰り返します。

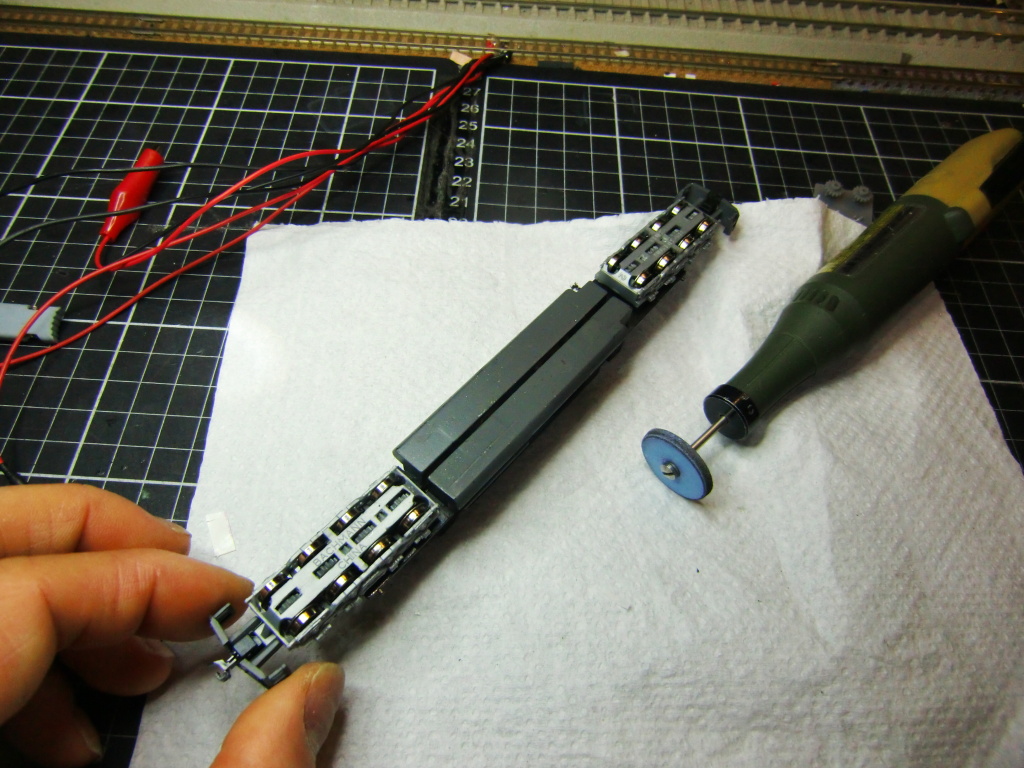
最後に車輪の磨き出しとギアに少量の注油を行い作業は完了となります。


無事にお直しできました。作業完了でございます。
まずは、Nゲージから修理に取り掛かかることにいたします。

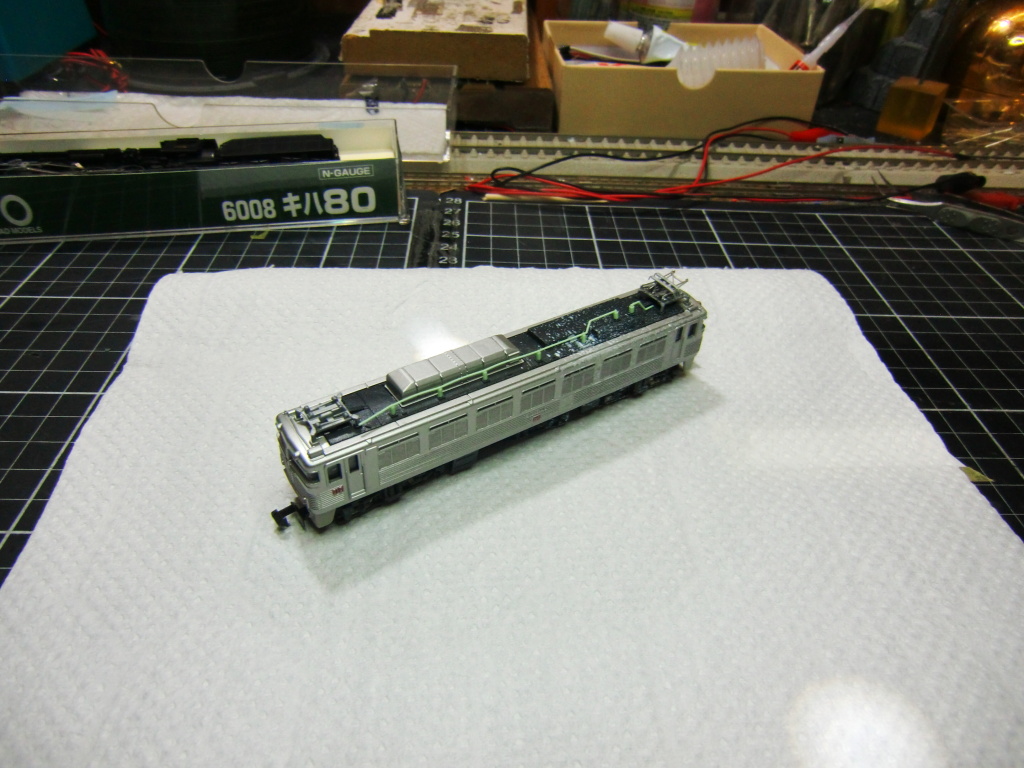
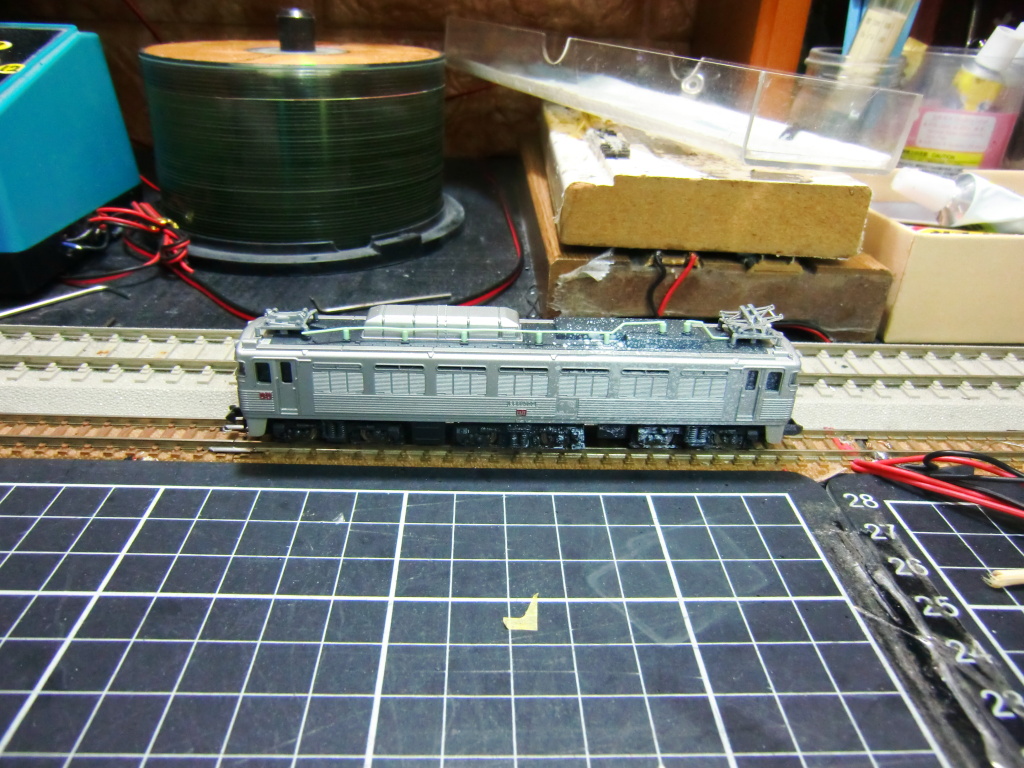
かなり電圧をかけないと動きません。また回転が不規則です。

一旦分解してモーターのブラシを慣らしていきます。
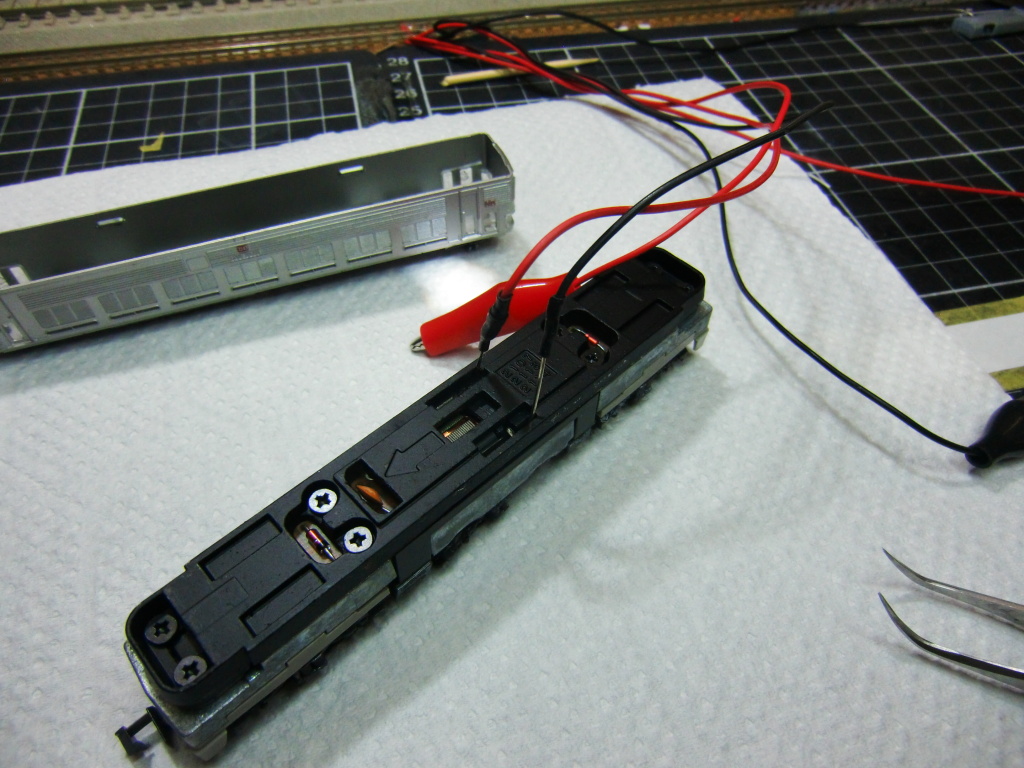
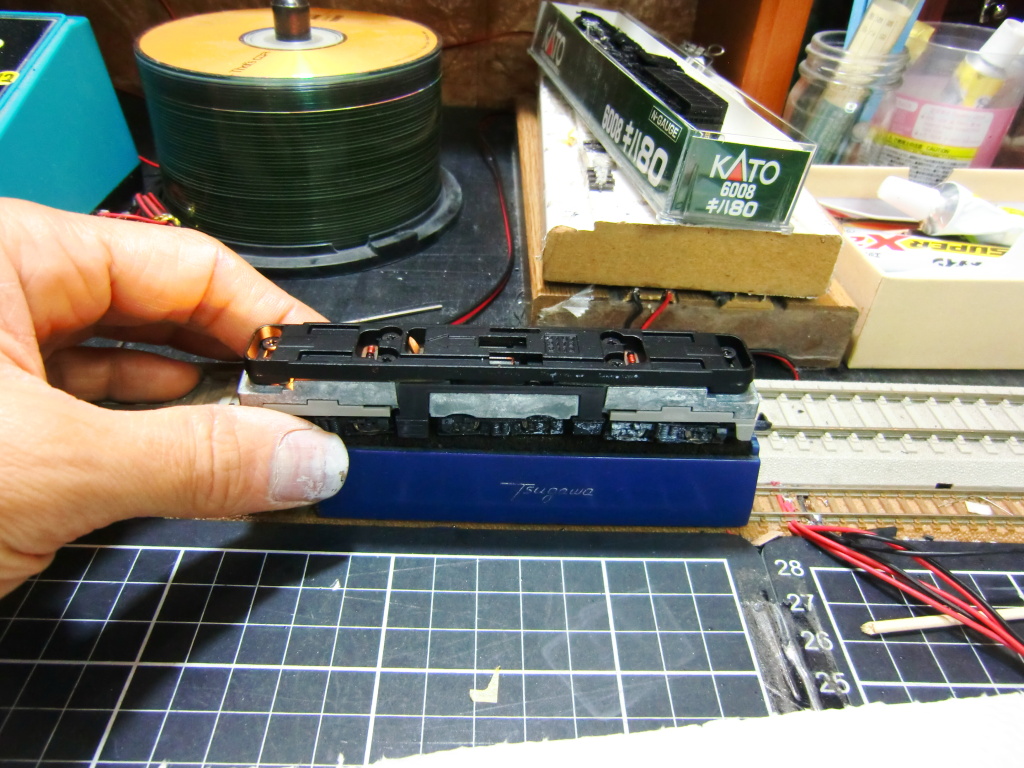

走りがだいぶ安定しました。
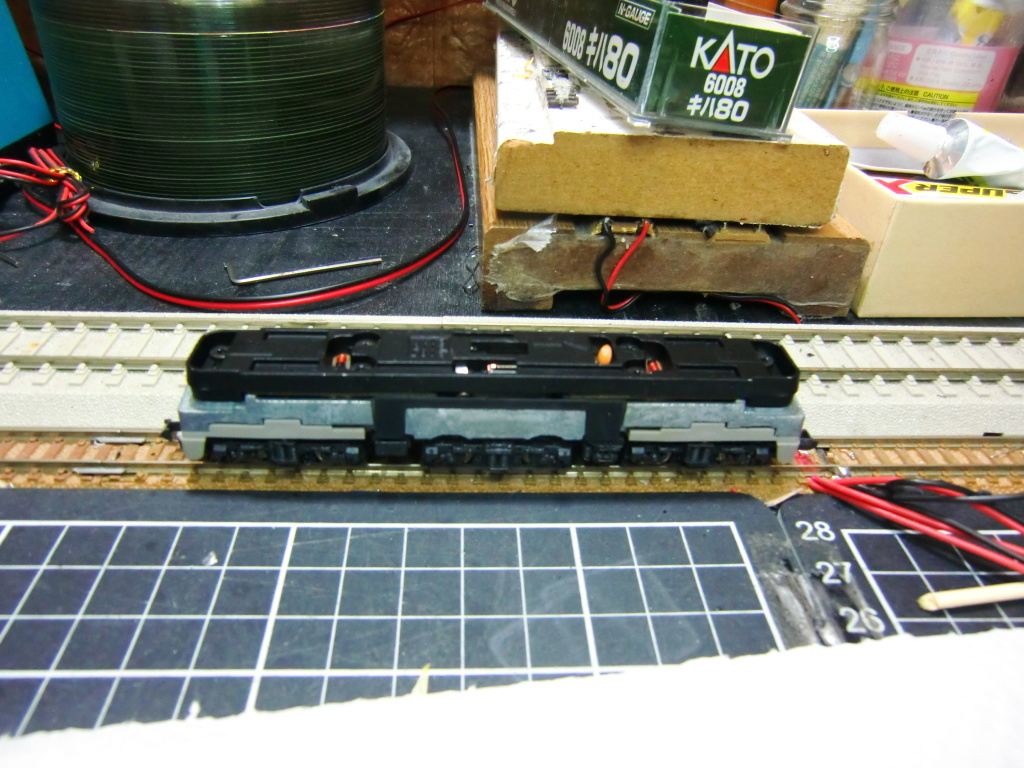

次にパンタの破損を直していきます。


まずは、EF81ステンレス修理完了です。

お次は蒸気機関車ですが、これはちょっと手こずりそうです。


こ、これは!!ダイカスト崩壊しております。
車体底面の刻印(メーカー)を確認して、納得しました。
この時代の某メーカーの製品は、保管状態に関係なくダイカスト崩壊の報告は多々ございました。
Nゲージの修理としては、かなり大変な作業となりそうです。


中はこんな具合です。軽く触れただけも簡単に砕けていきます。現状からの修復はちょっと無理そうですね。また、反り返る形で変形もしています。ここは走行は考えずディスプレイ用として修復する方が現実的かもしれません。走行可能まで修復するとなると、内部パーツを1から作り直す必要がございますので、費用面でもあまり現実的ではありません。とりあえず、どこまでできるか考えてみることにいたします。

まずは、瞬着を多数ある亀裂に流してこれ以上崩壊が進まないようにします。この車体の修復には相当な時間を要するため、ここで一旦作業を停止して、HOの修復作業へ移行します。
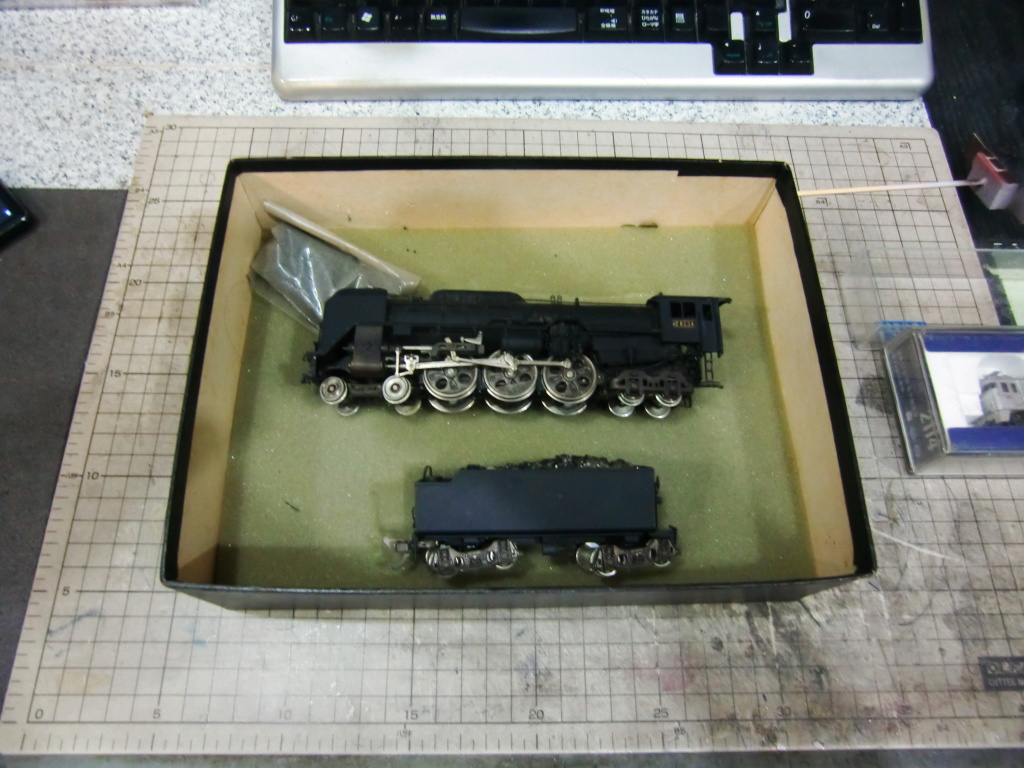
HO カツミ製 C62修理作業です。

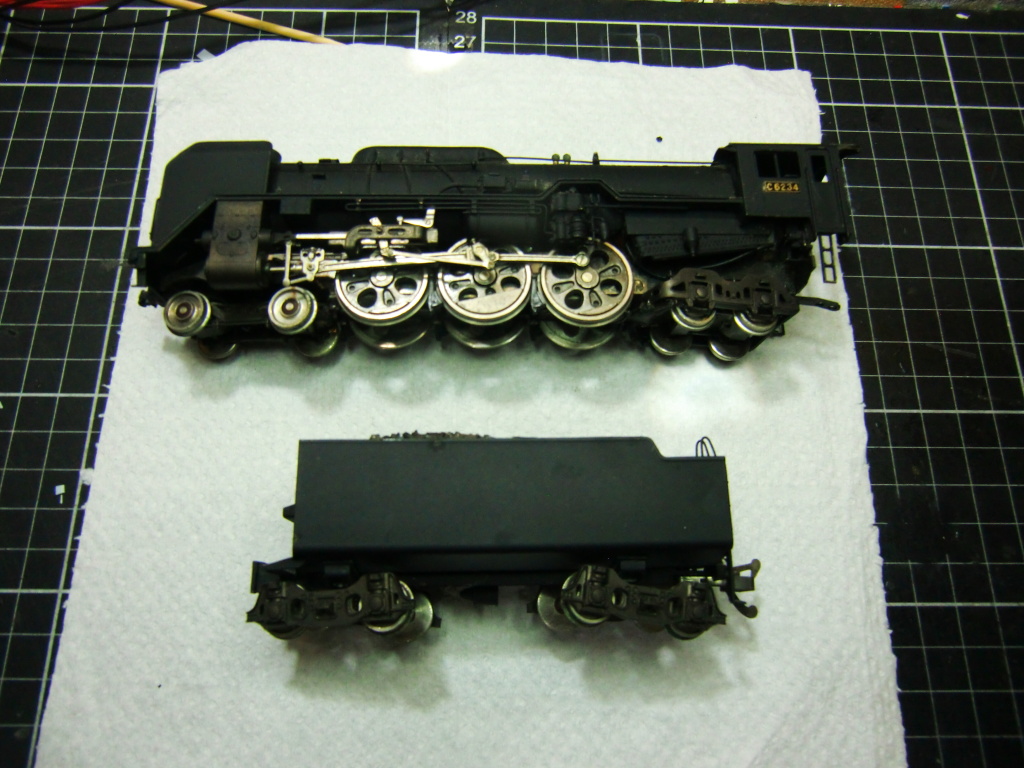
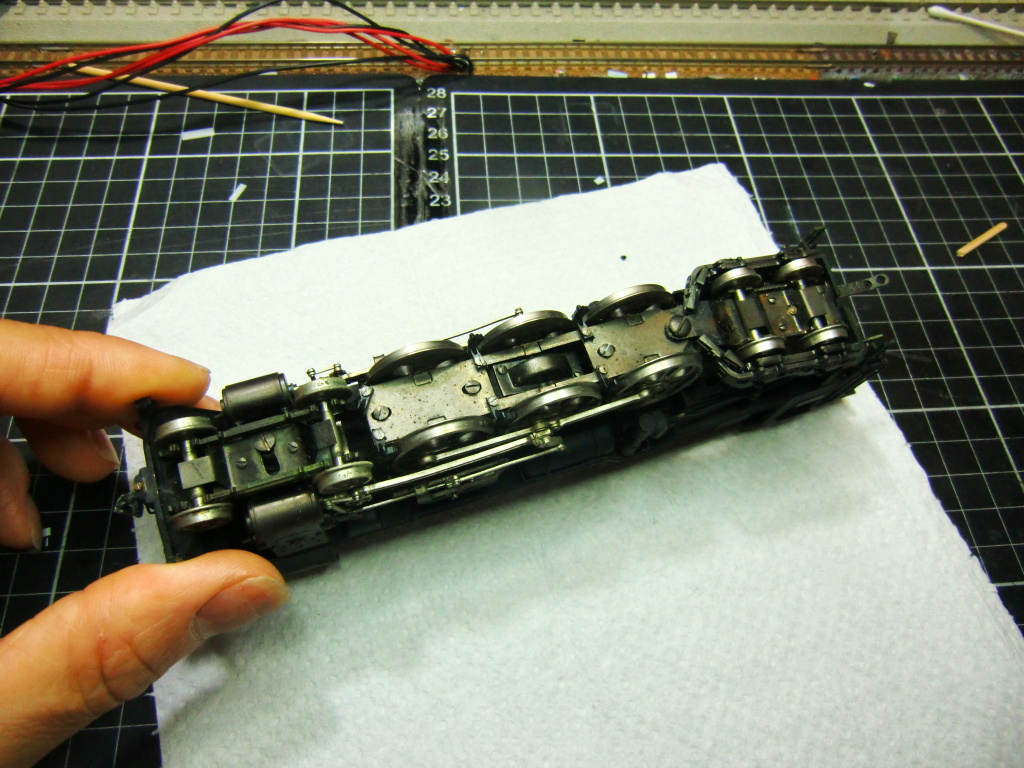
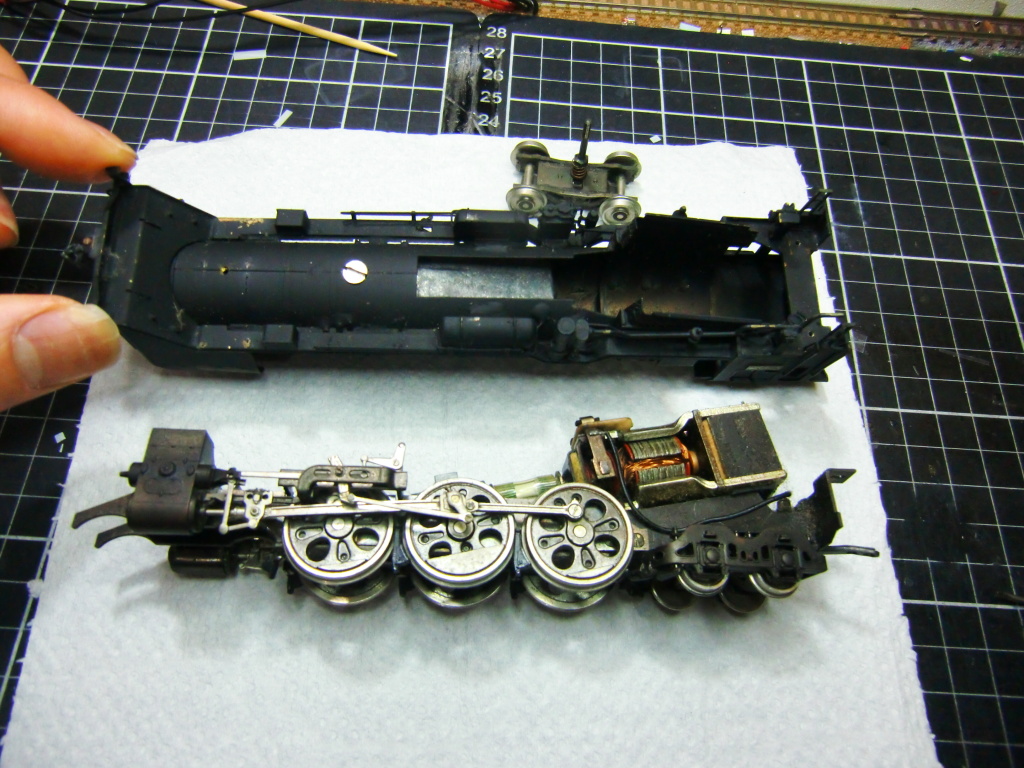
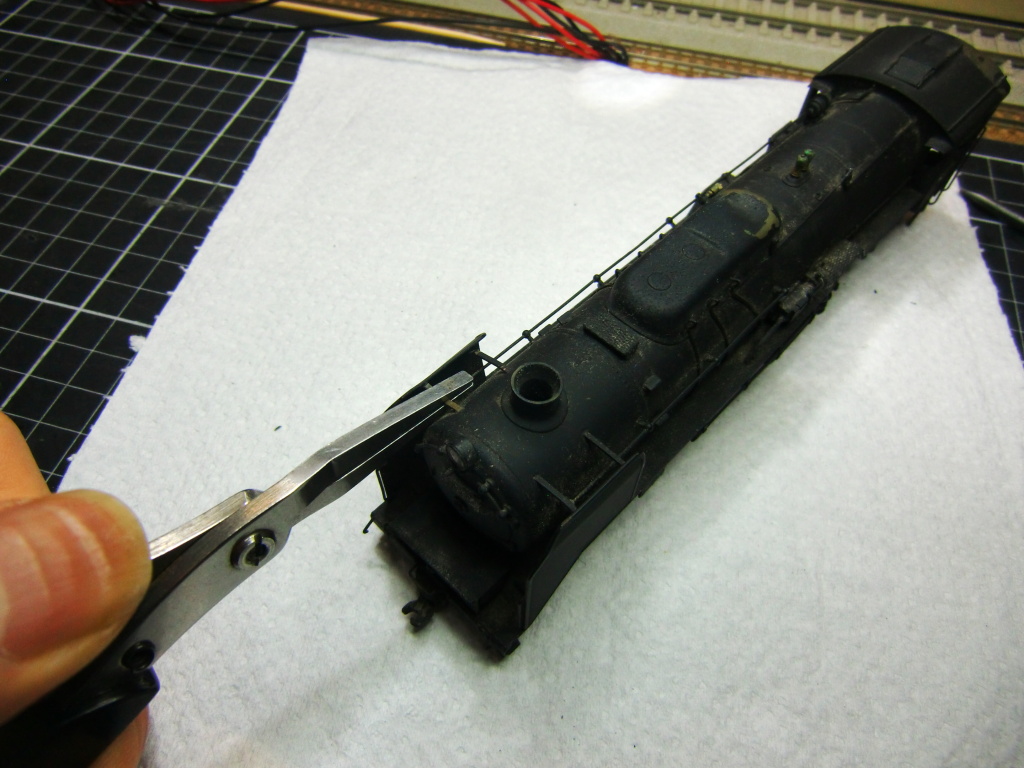
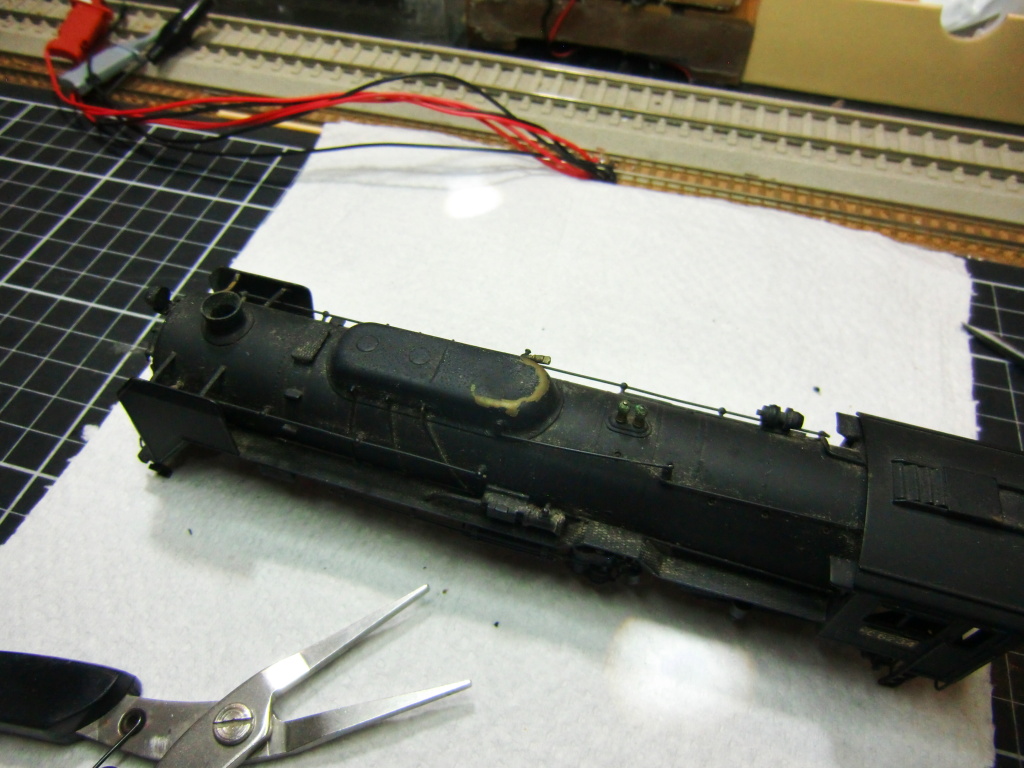
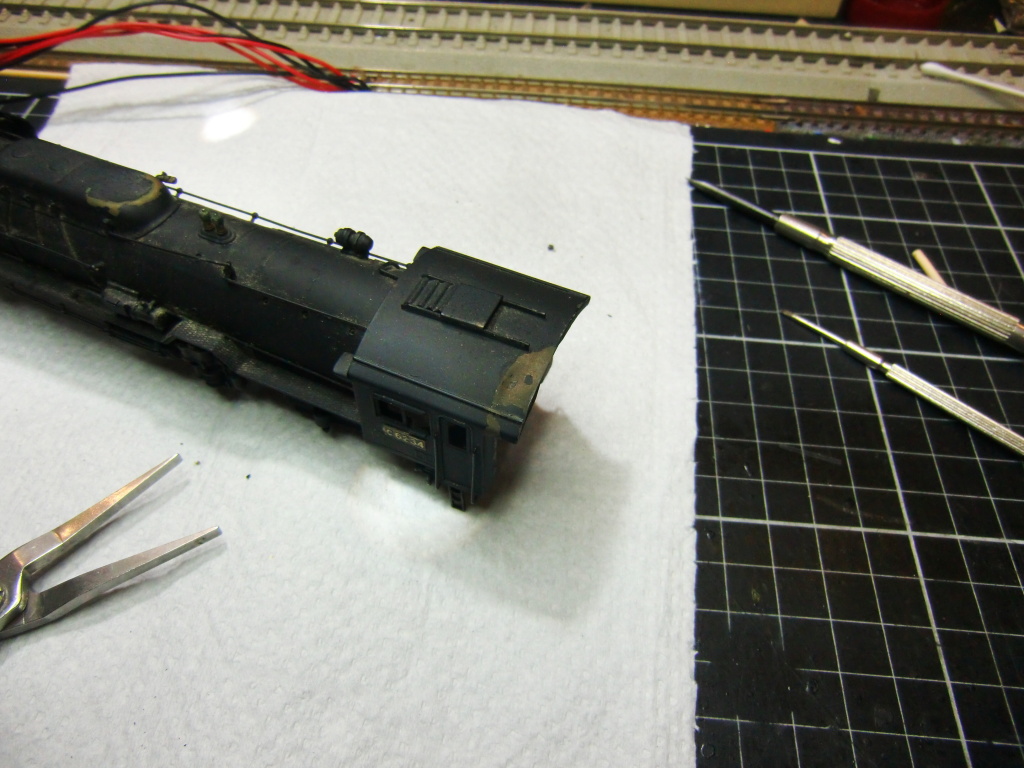

デフの片側が完全に変形しおり、上部の補強もねじれています。
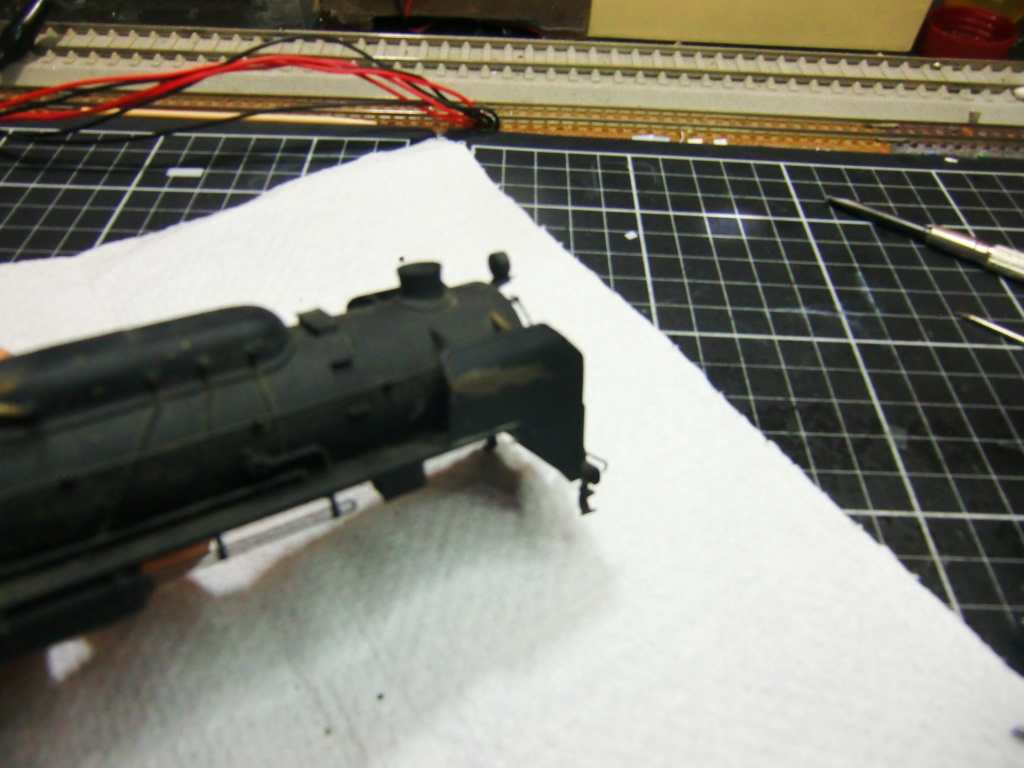

大小プライヤーを駆使して、できるだけ元の状態に戻していきます。金属ですので、力加減が大変難しいです。
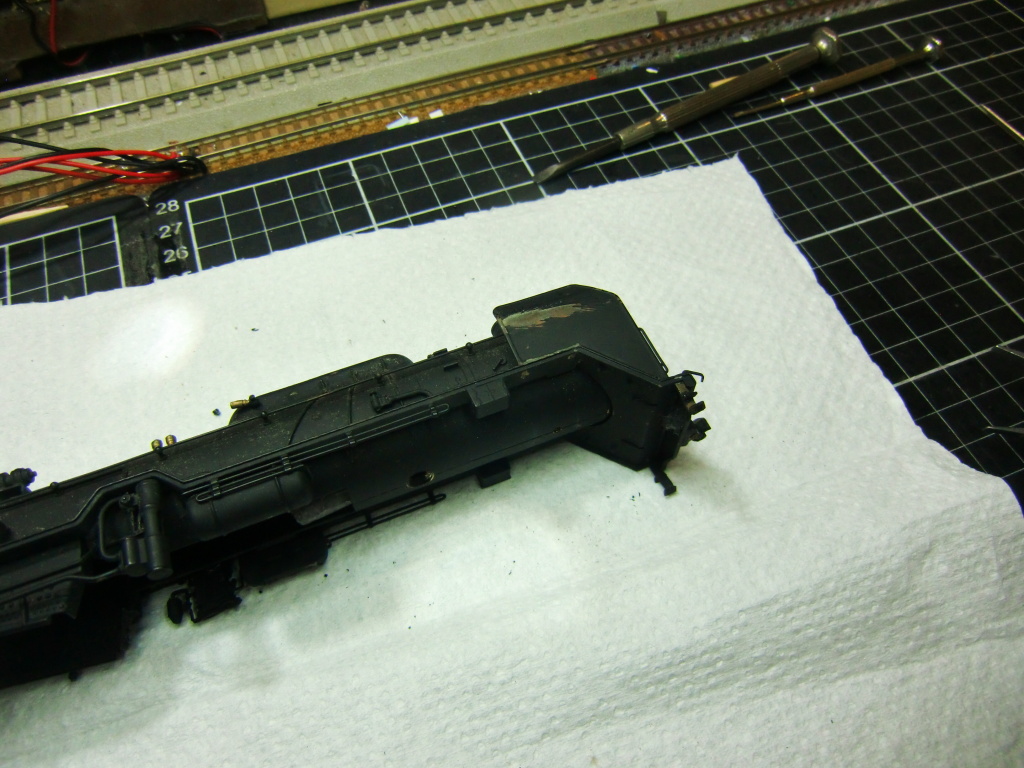
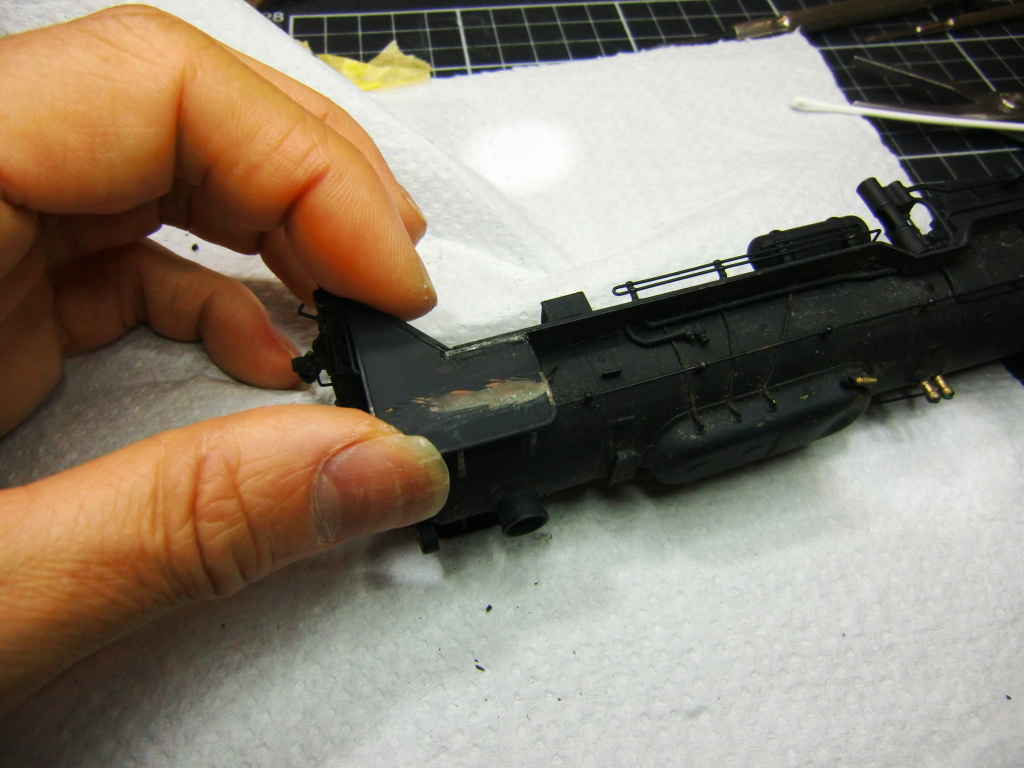
デフ表面も塗装が削れていますが、最後に全体を研ぎ出してから再塗装を行います。
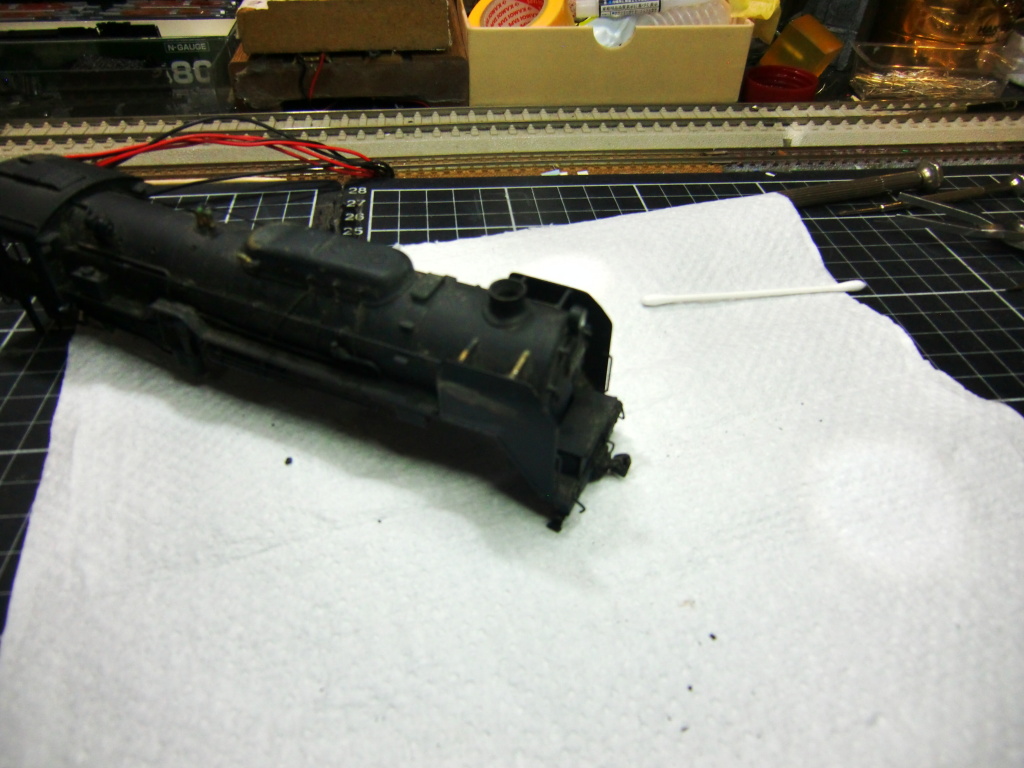
だいぶ元の状態に戻ったのではないかと思います。
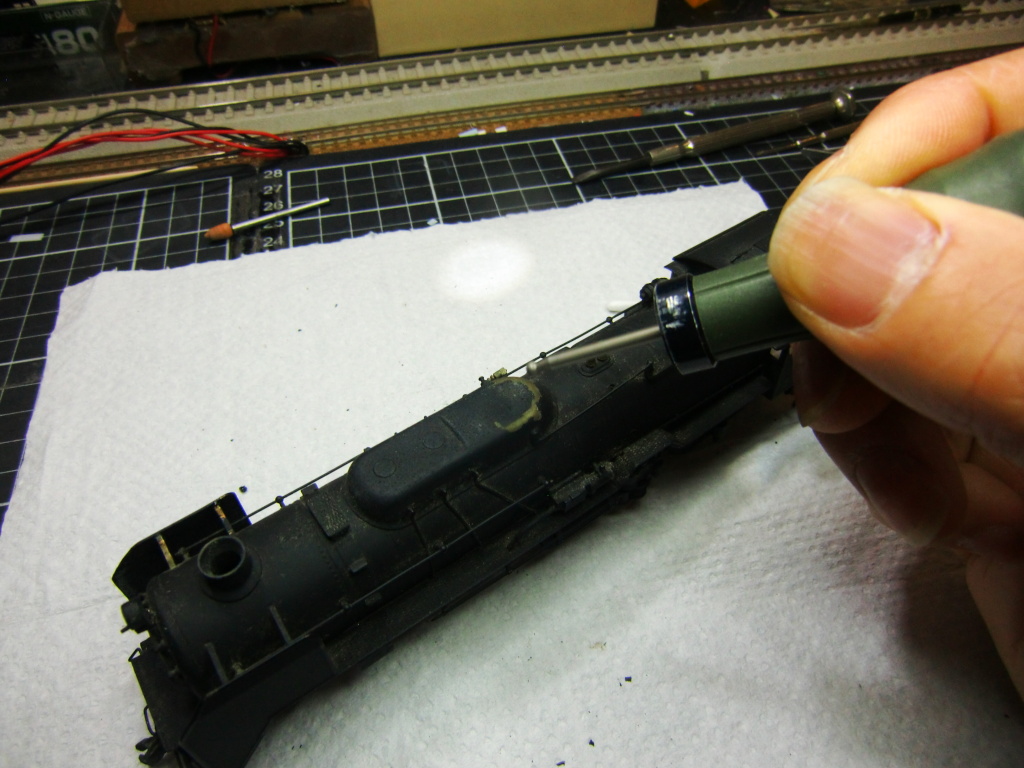
次に各部の凹みを直していきます。こちらの凹みは大変深いため、パテを使って補修することにします。まずは、凹み部分をルーターで削ってザラザラにして下地を作ります。

キャブの屋根も凹んでいます。

このように完全に下地を出します。
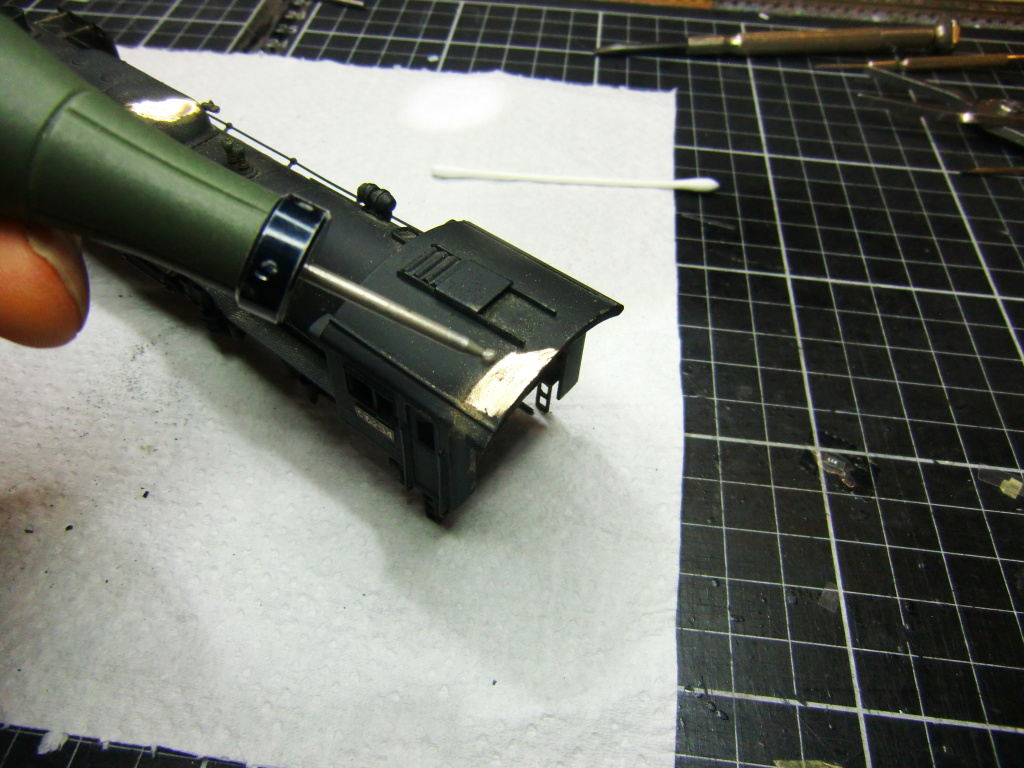
こちらも同様です。パテが届くまで先に駆動系の修理と各部O/ Hを行います。↓
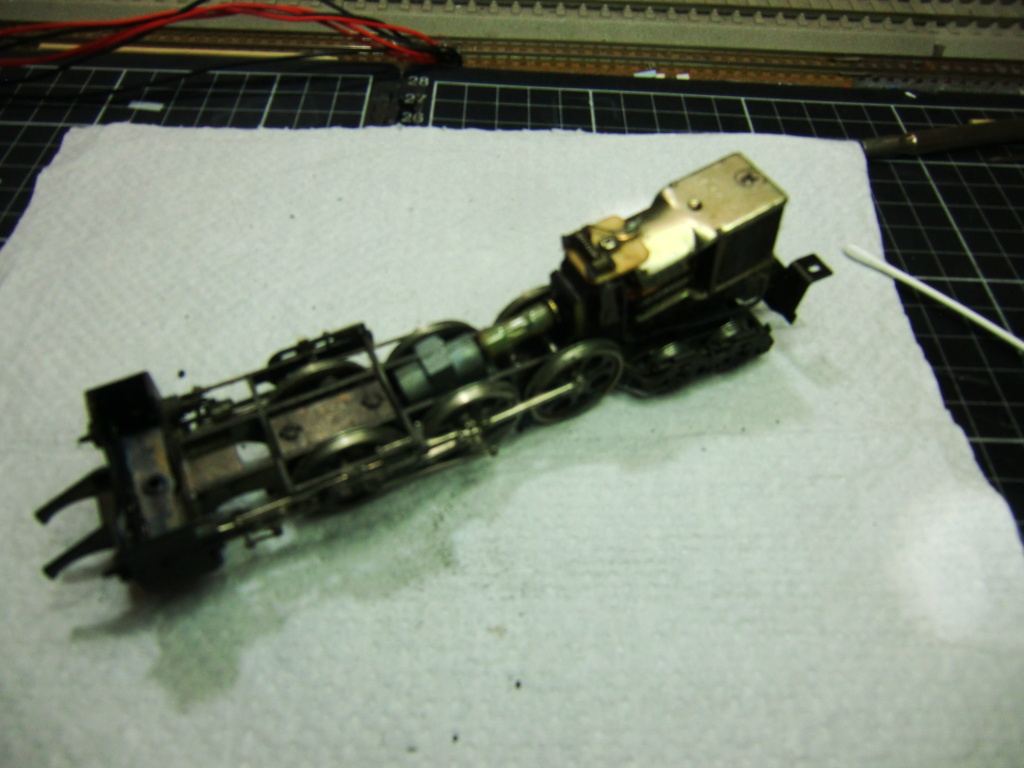
とりあえず、現状確認のため通電させてみましたが、まったく動く気配がしませんでした。
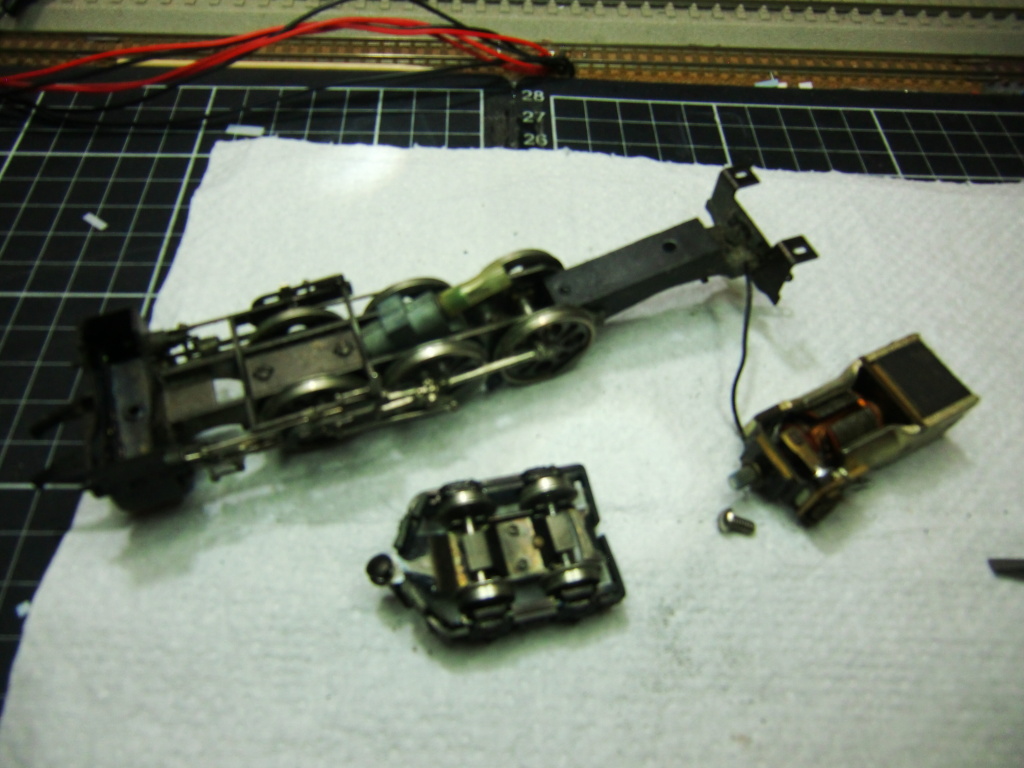
分解して1つ1つメンテナンスを行っていきます。

まずは、内部に詰まったホコリや表面の汚れをクリーナーで除去します。
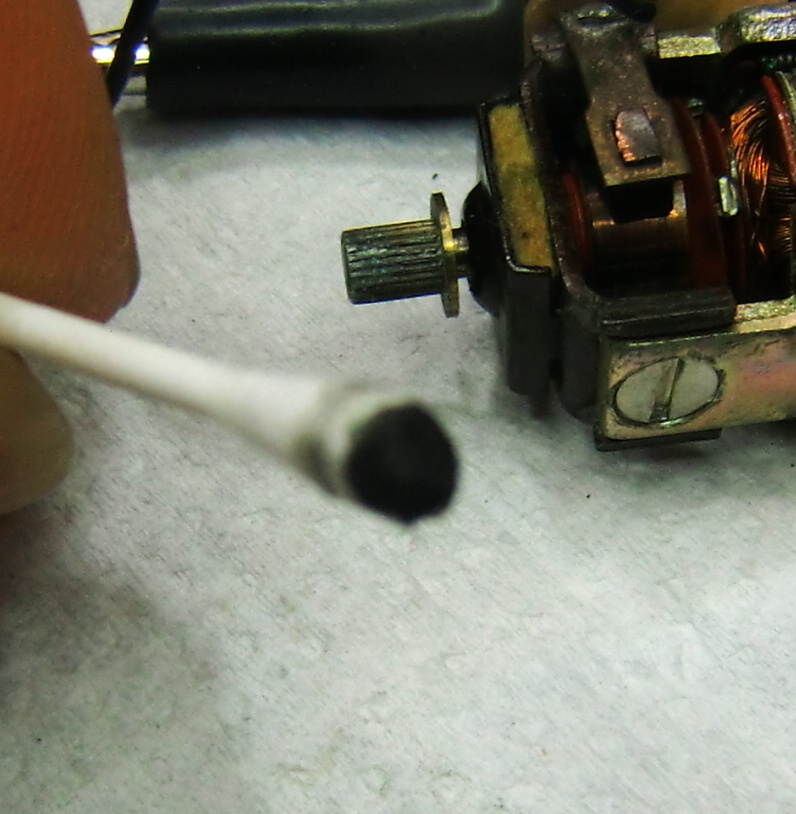
モーター単体のメンテに入ります。モータ内部も真っ黒です。
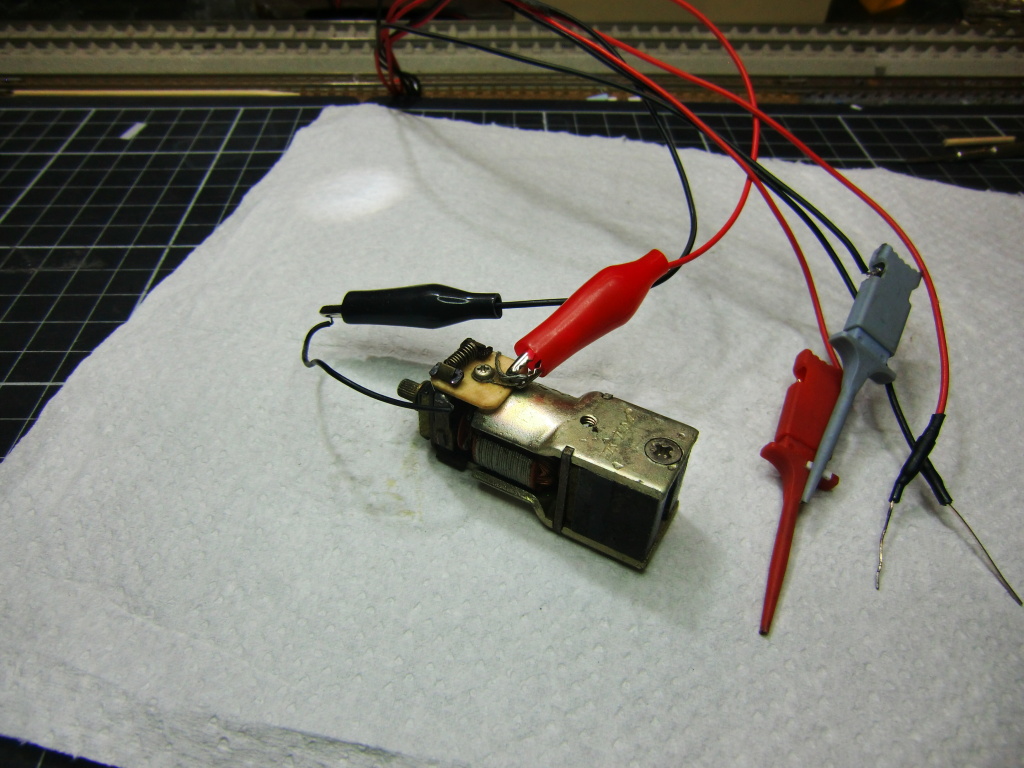
汚れを一通り除去できたところでブラシを慣らします。正転・逆転をそれぞれ中速で30分ずつ行います。10分おきにコミュの汚れを拭き取っていきます。
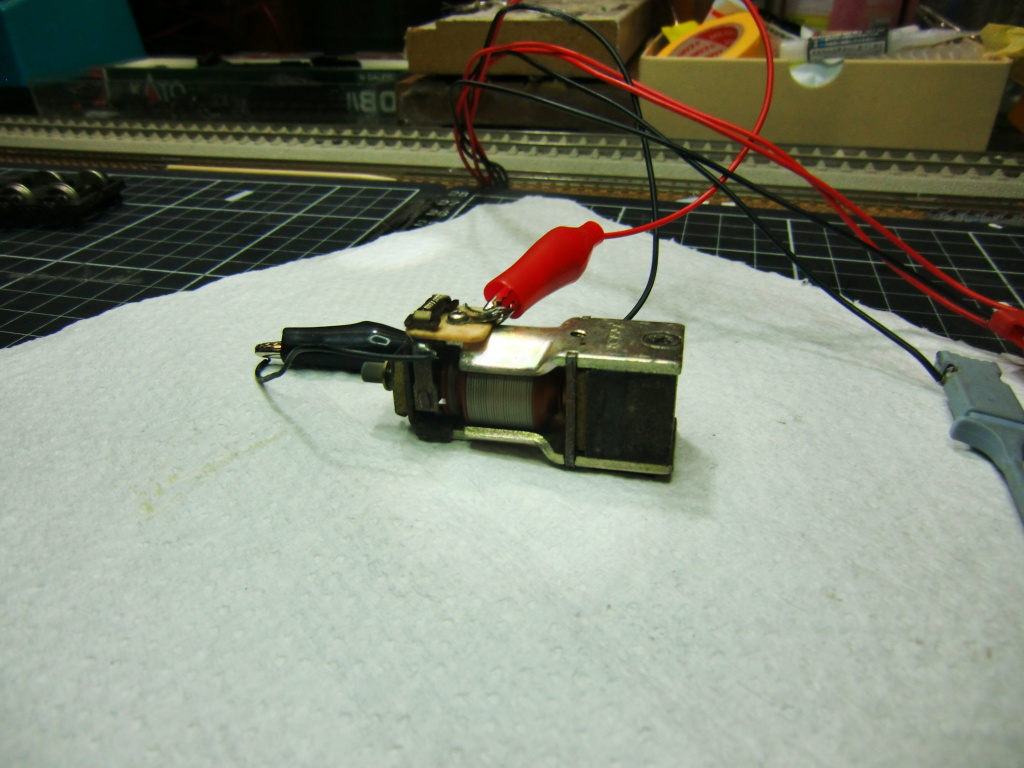
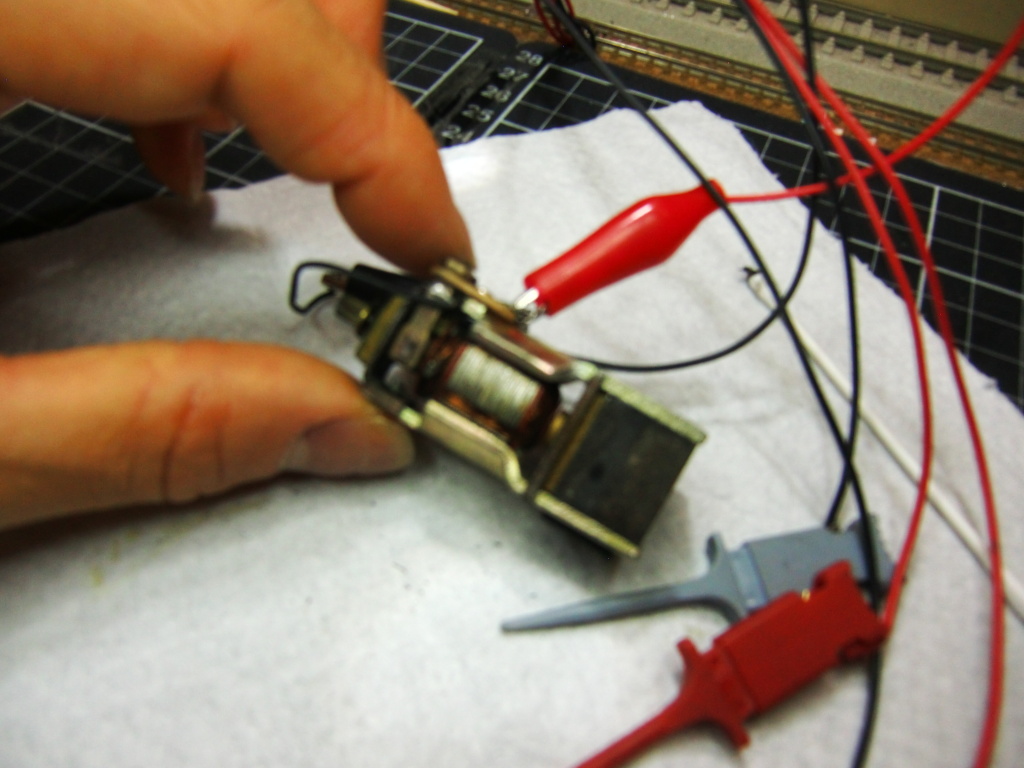
一通りモーターのメンテが終ったところで、軸受けに少量の注油を行っておきます。
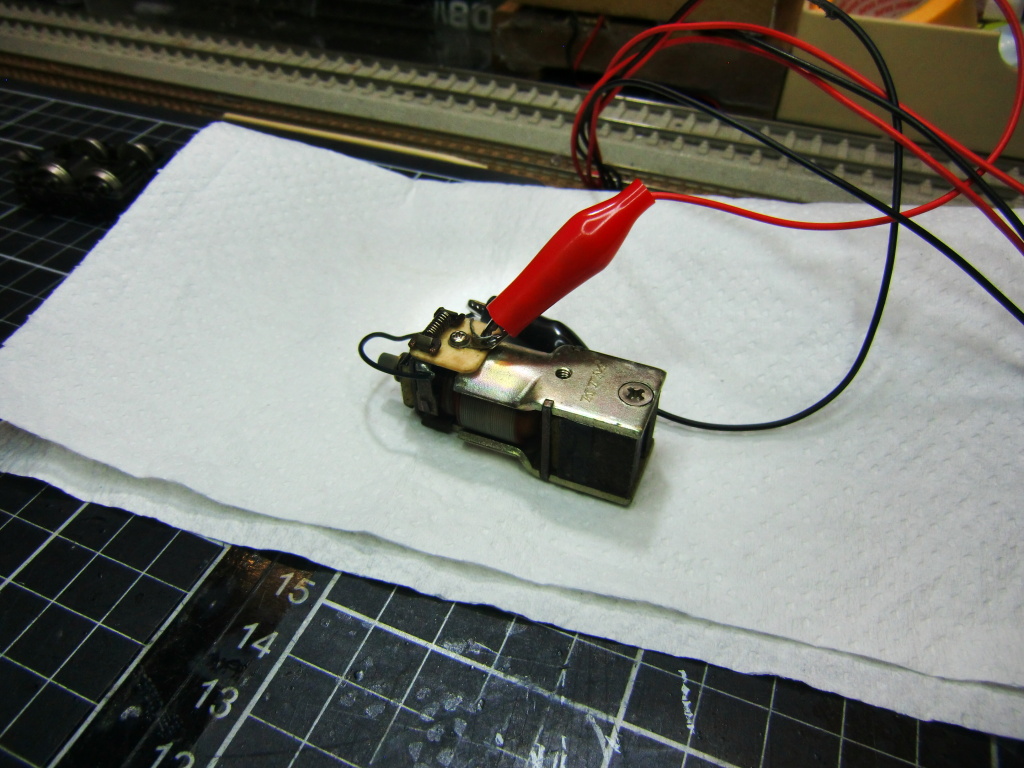
モーター復活です。回転が安定しました。

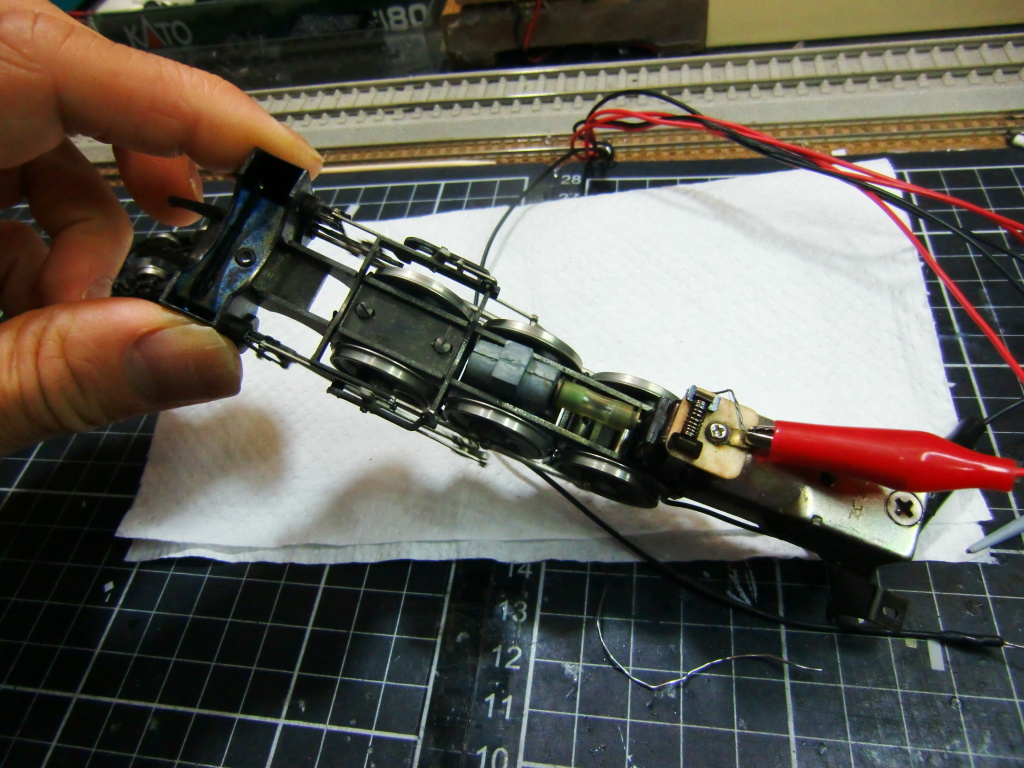
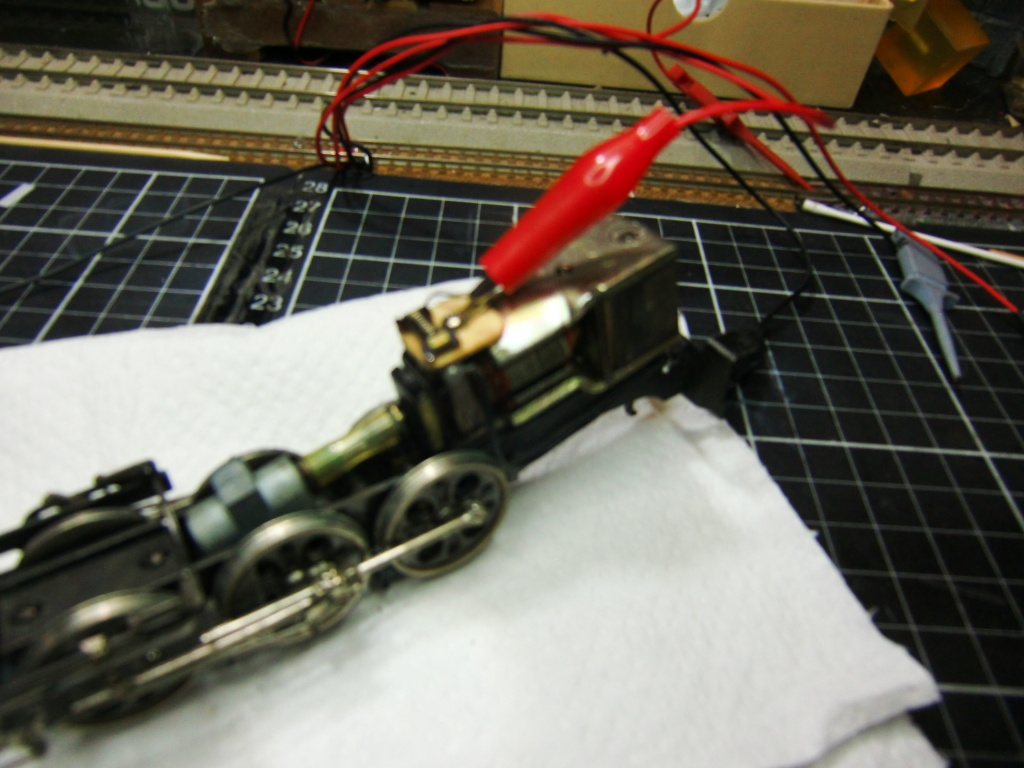
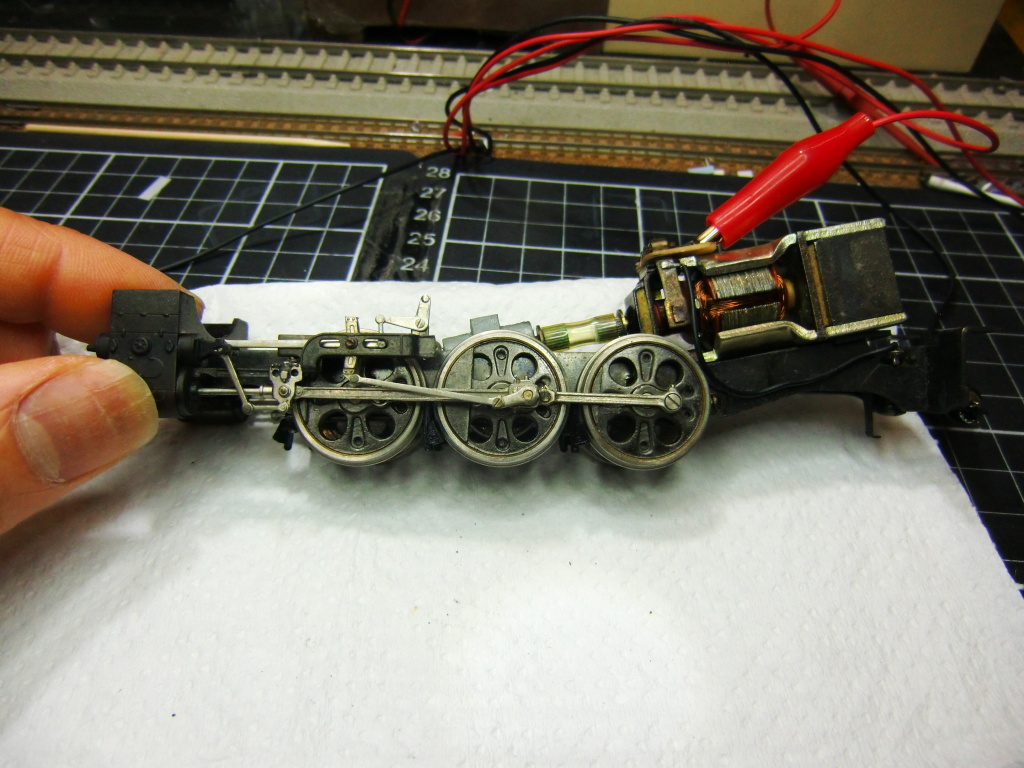
モーターを戻し、各種動輪のバランス調整を行い回転が安定する位置調整を繰り返し行います。ようやくスムーズに動輪が回転を始めました。駆動系の復活です。
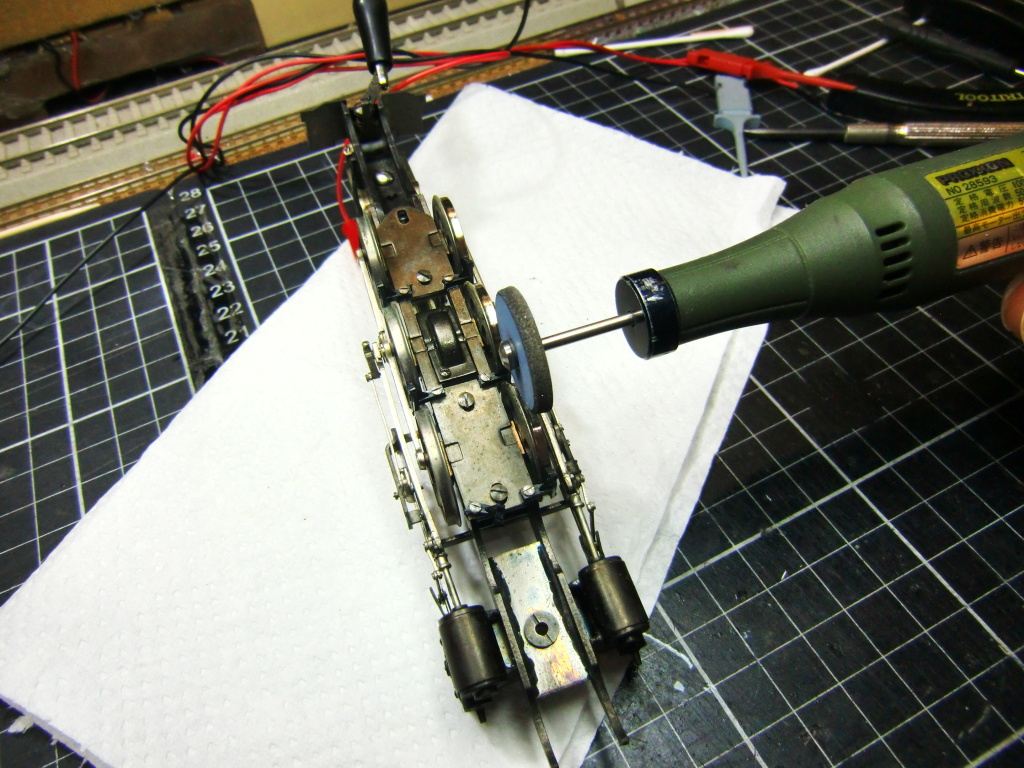
つづいて、長年の車輪への汚れの焼き付きをコンパウンドで丁寧に削り落としていきます。
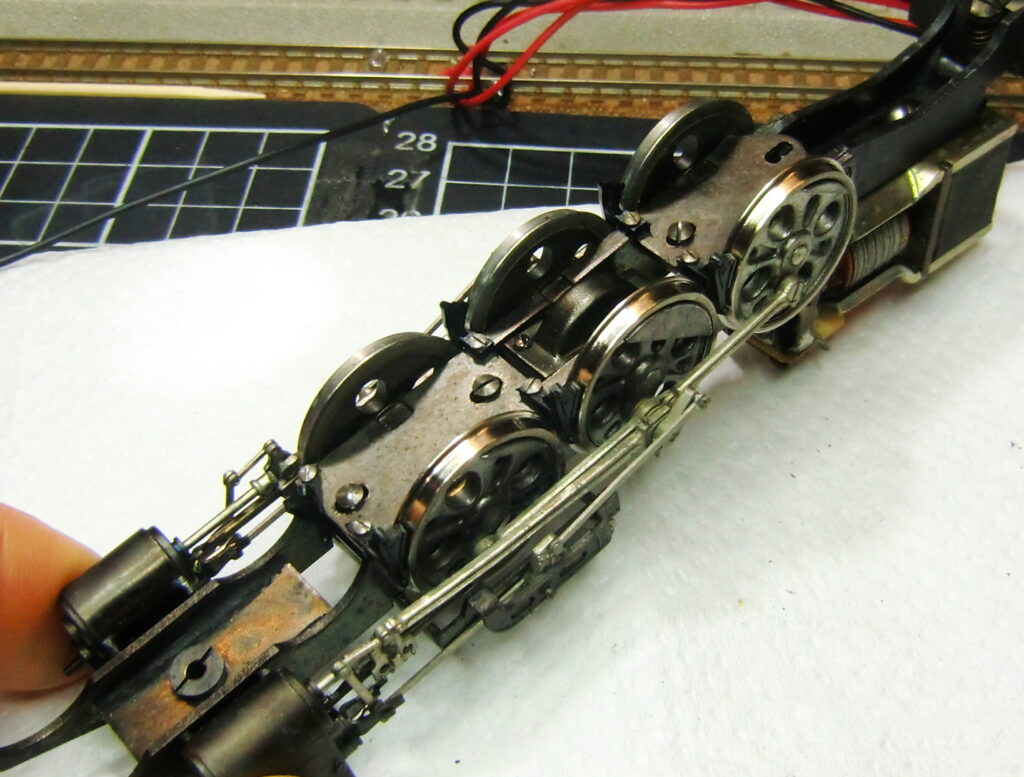
車輪が本来の輝きを取り戻しました。このあとロッドなど各種金属パーツを金属クリーナーで丁寧に磨き上げていきます。
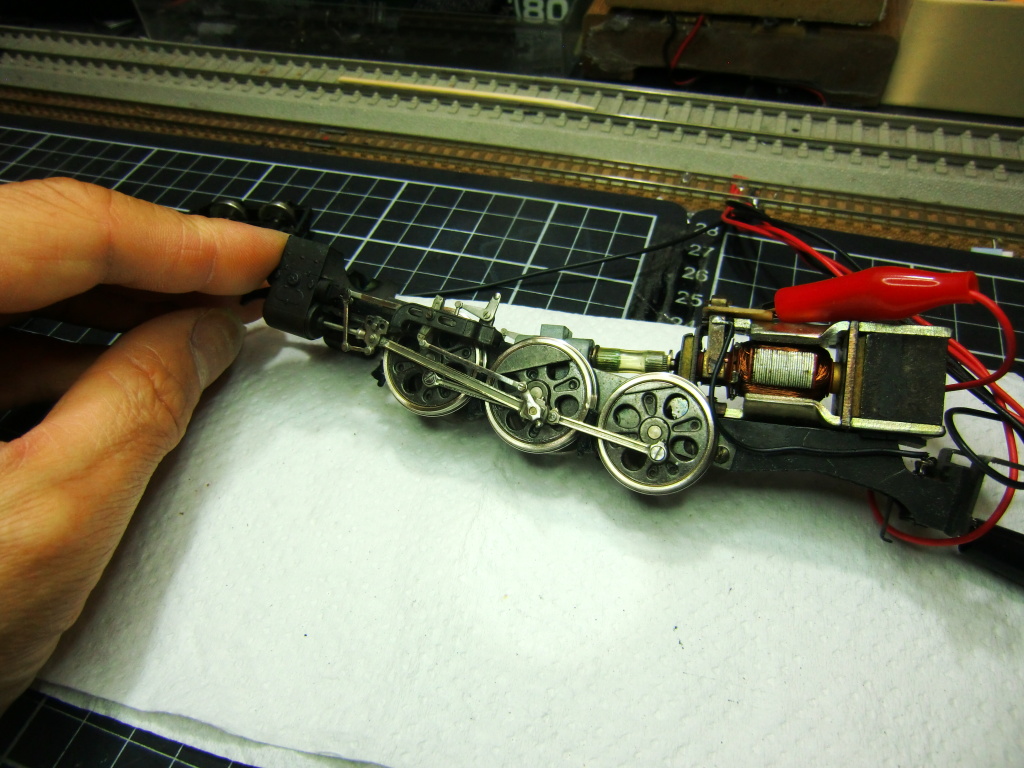
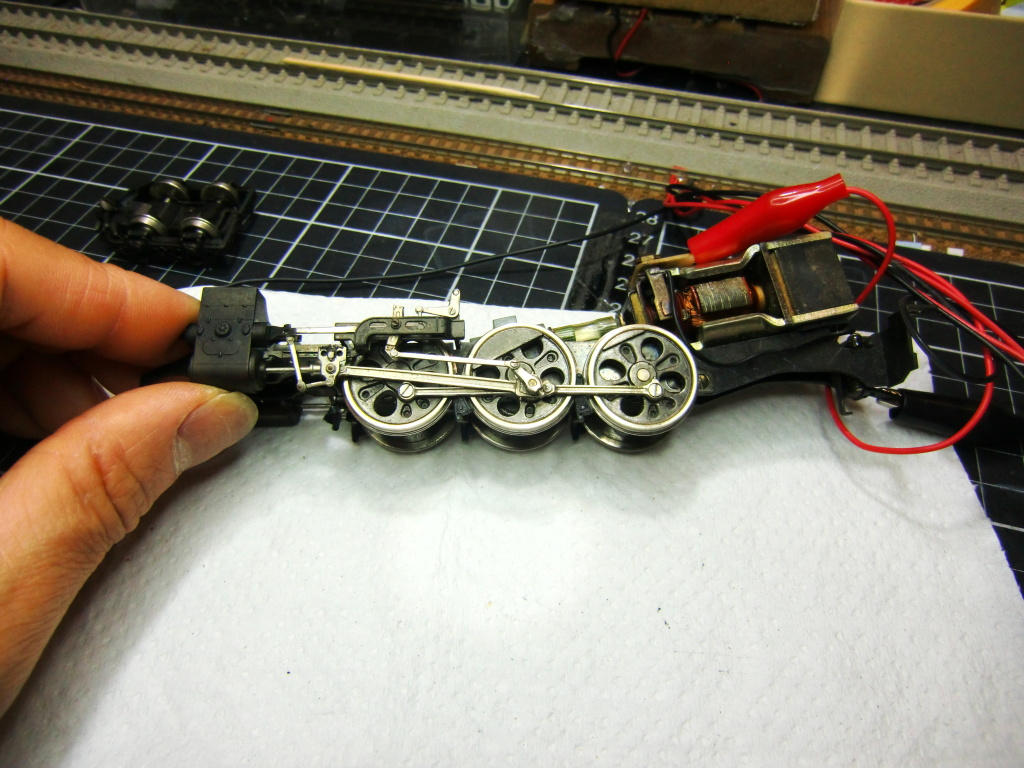
白く変色していた、ロッドや車輪の淵もすべて磨き上げました。

この状態でテスト走行してみます。

前進・後進ともに大変安定しています。

主剤と硬化剤を混ぜて補修用パテを作ります。




やや盛り上がるように盛りつけます。このまま12時間おきます。
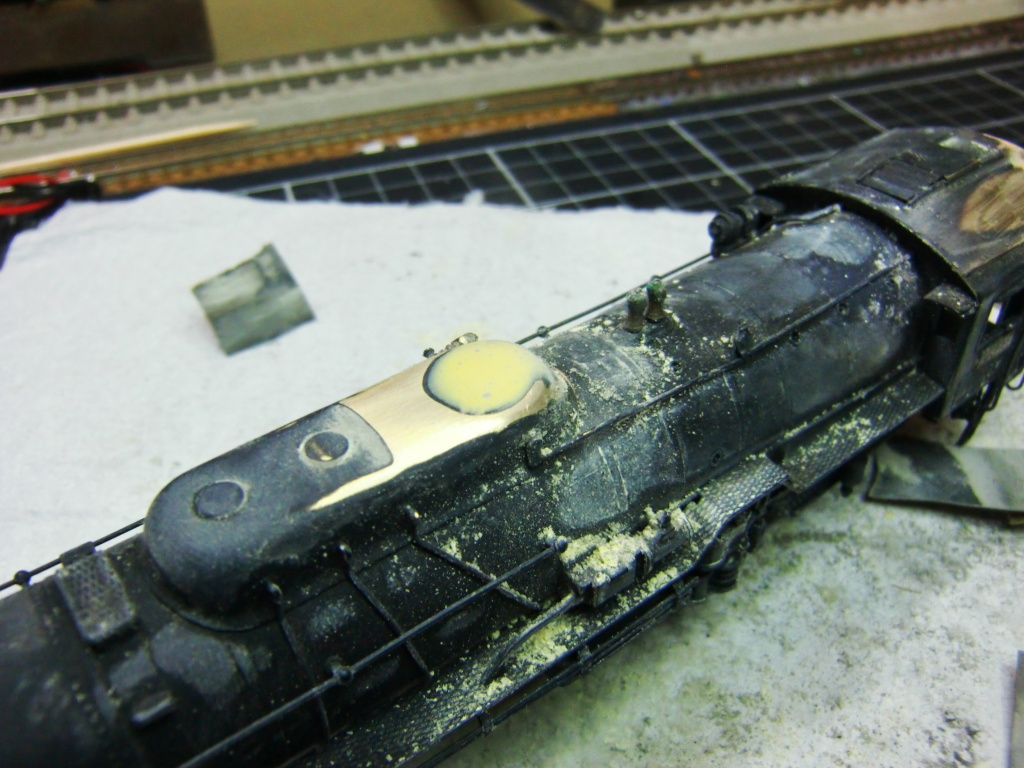
パテは自体は、大変固く強度があります。まずは、ルーターでおおまかに削り出してから、ペーパーで番数を変えながら成形していきます。
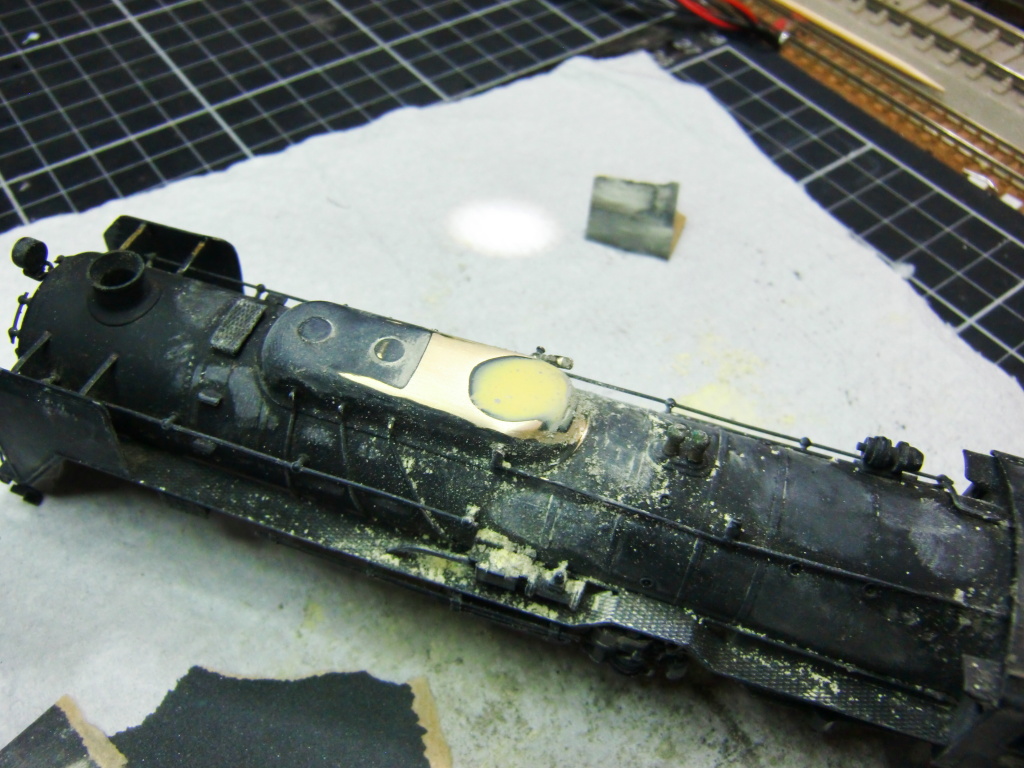

穴埋めが終ったところで、ボディー洗浄を行い全塗装へと移行します。
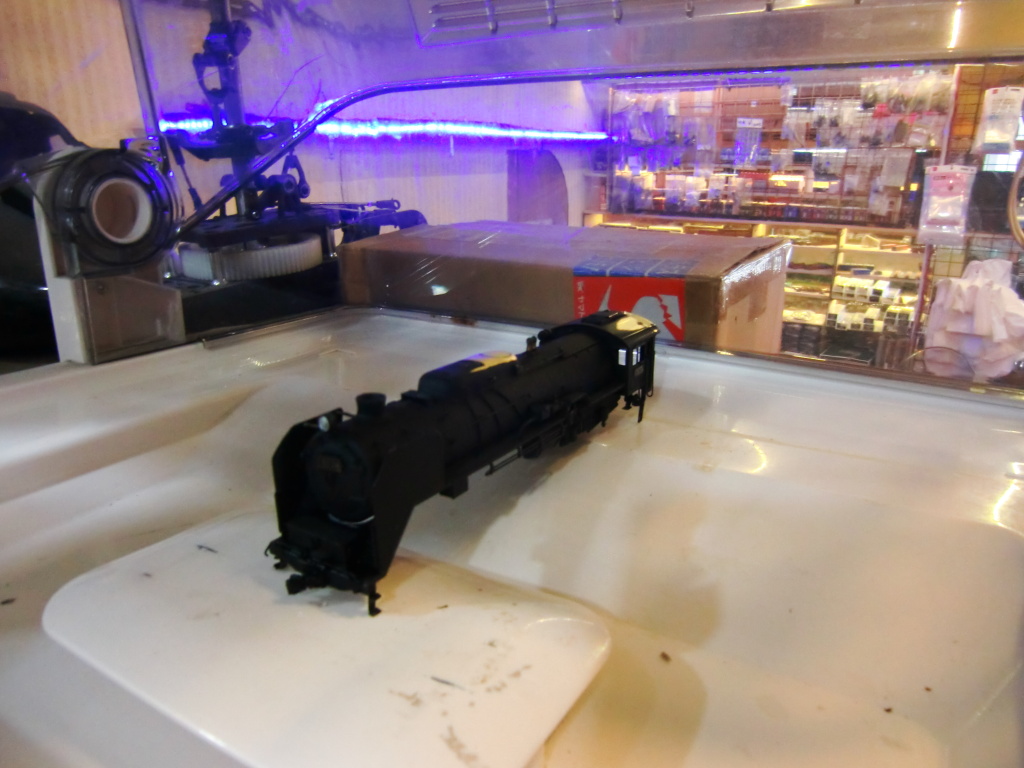
洗浄後に乾燥室に入ります。
その間にテンダーの準備を進めます。

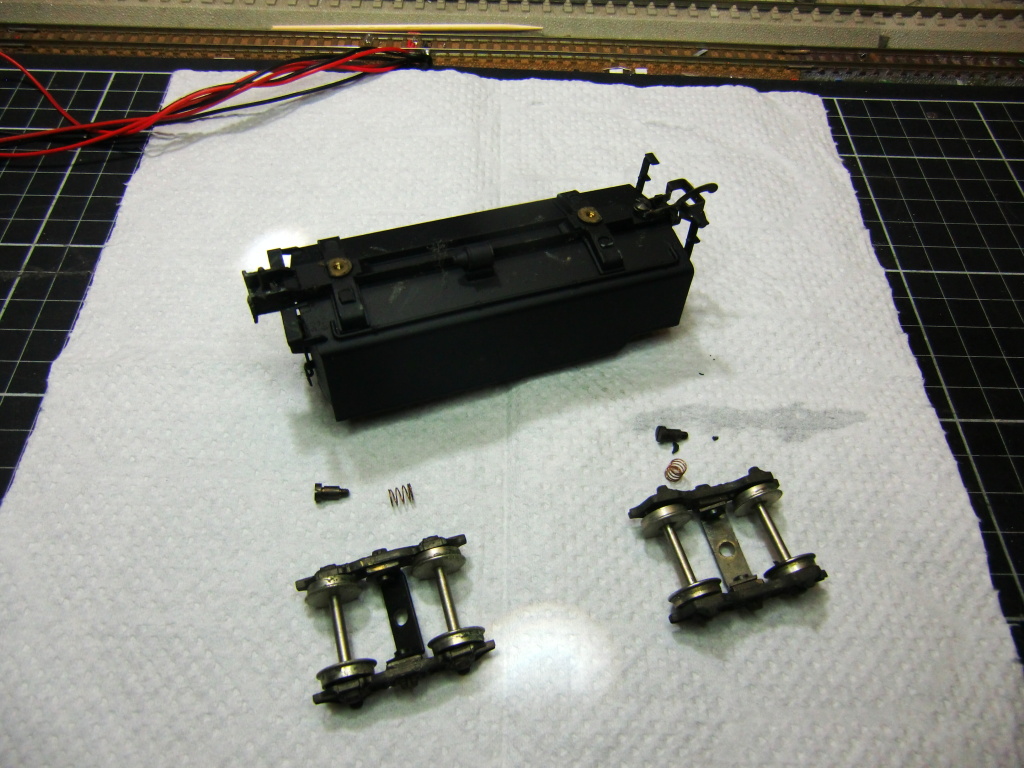

長年の車輪の汚れと焼き付きなど落としていきます。
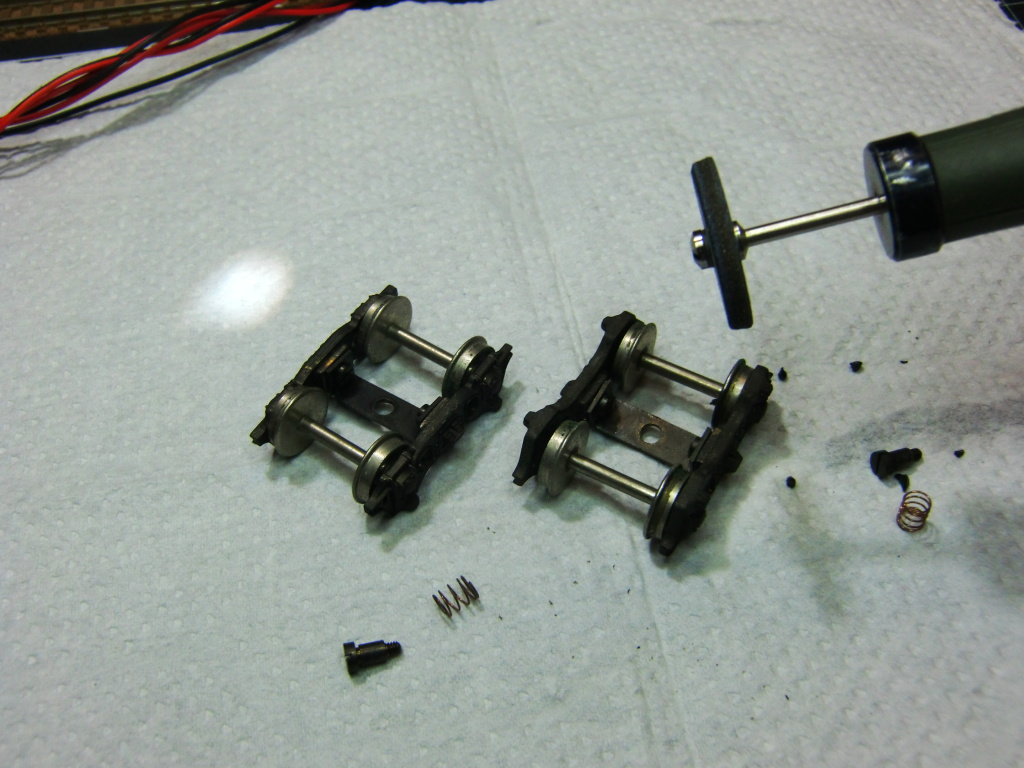

右下がメンテを終えた車輪です。
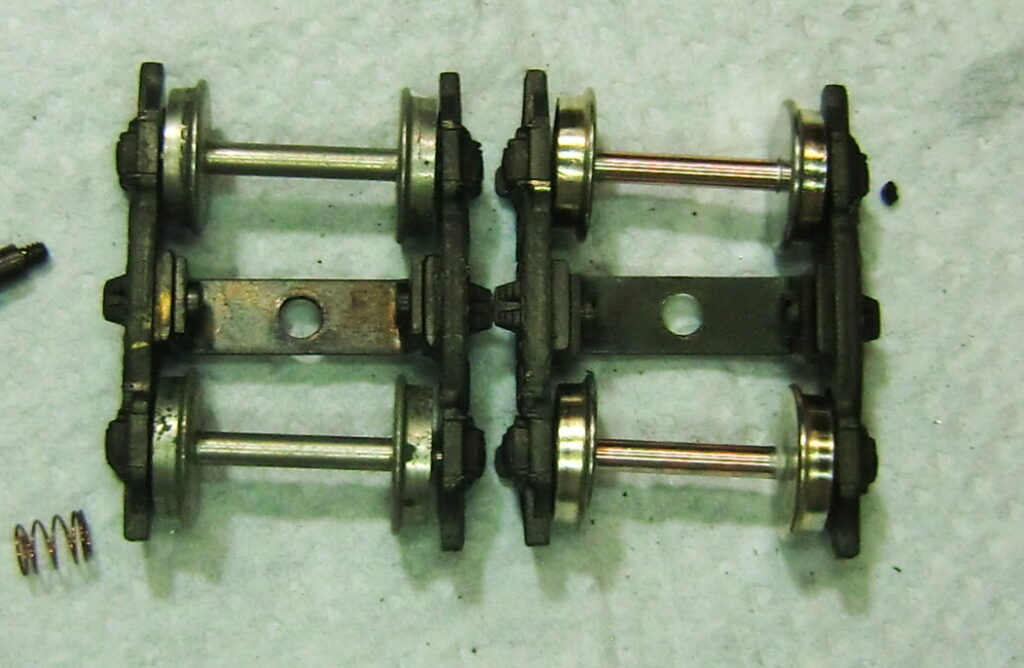
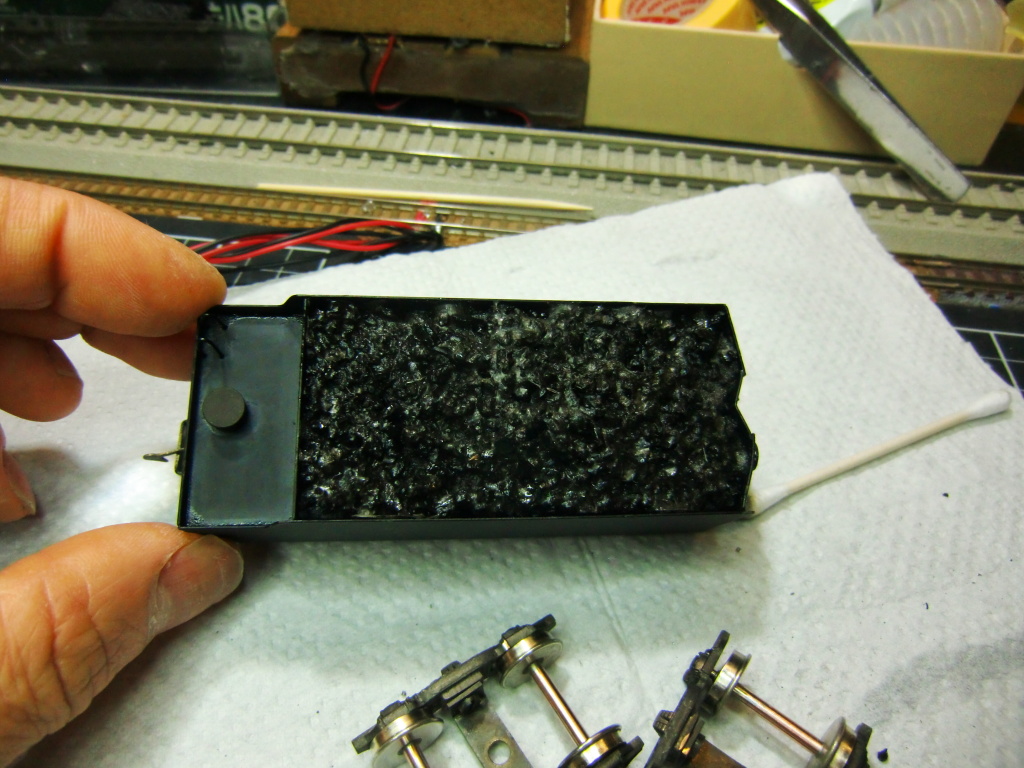
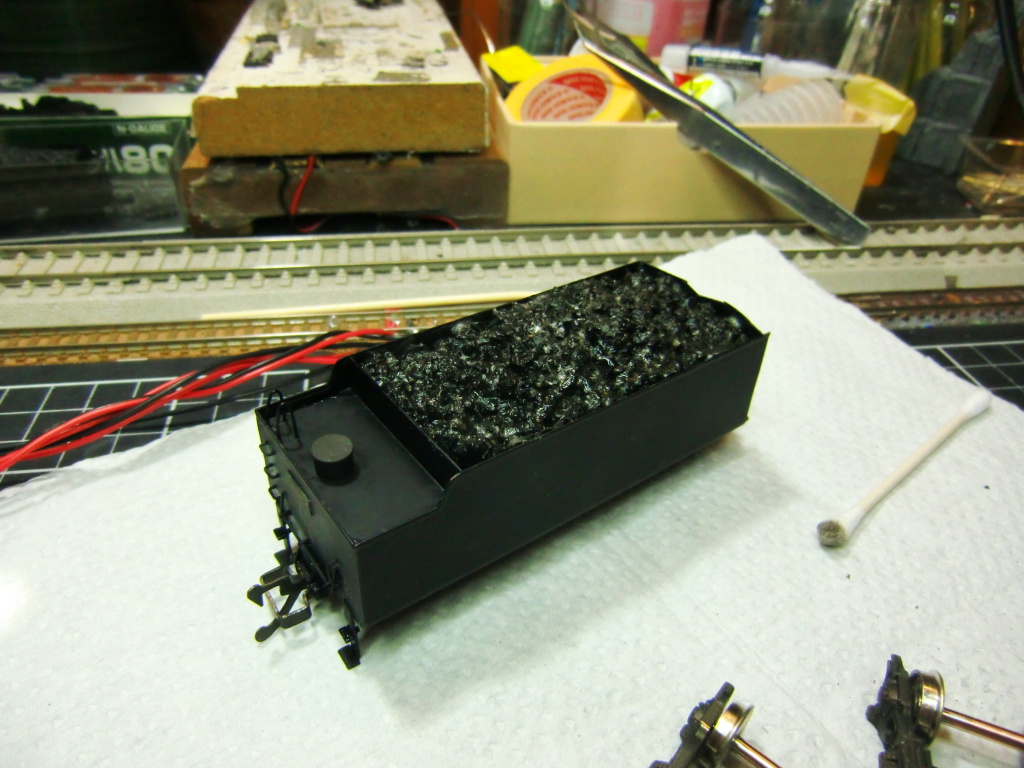
洗浄を終えて戻ってきたテンダーです。長年の湿気やホコリなどがこびり付いて白く変色していましたが、だいぶきれいになりました。こちらも全塗装しますので、塗装前にさらに念入りに洗浄します。
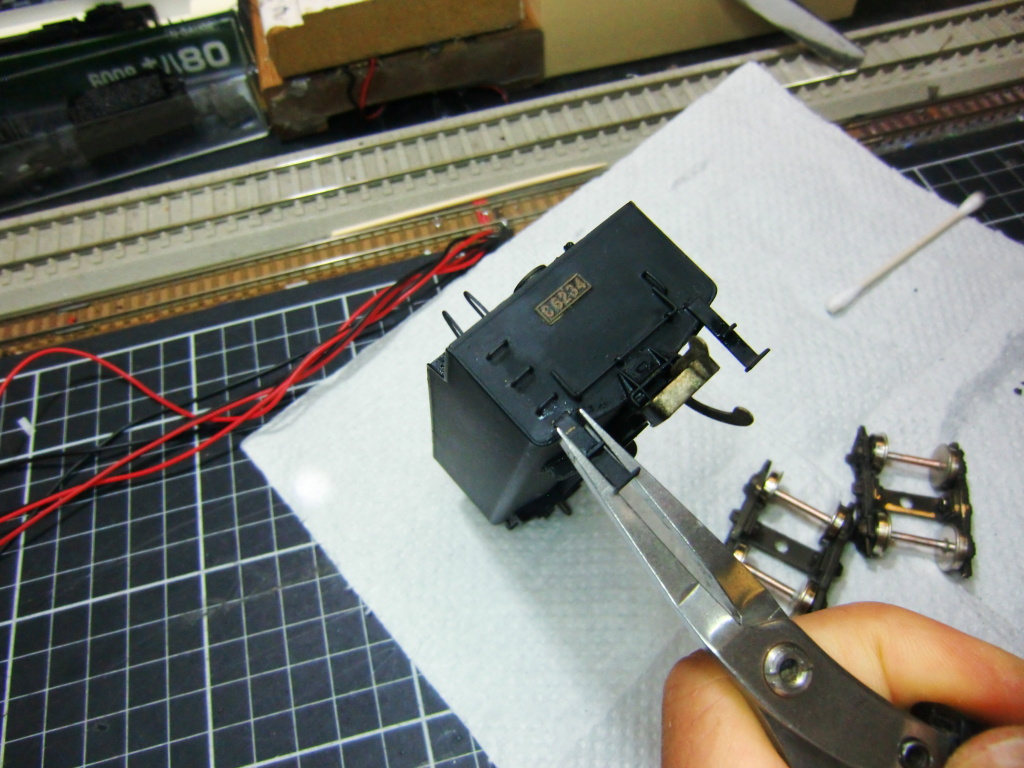
機関車同様、こちらも変形してしまっている箇所を修理ます。
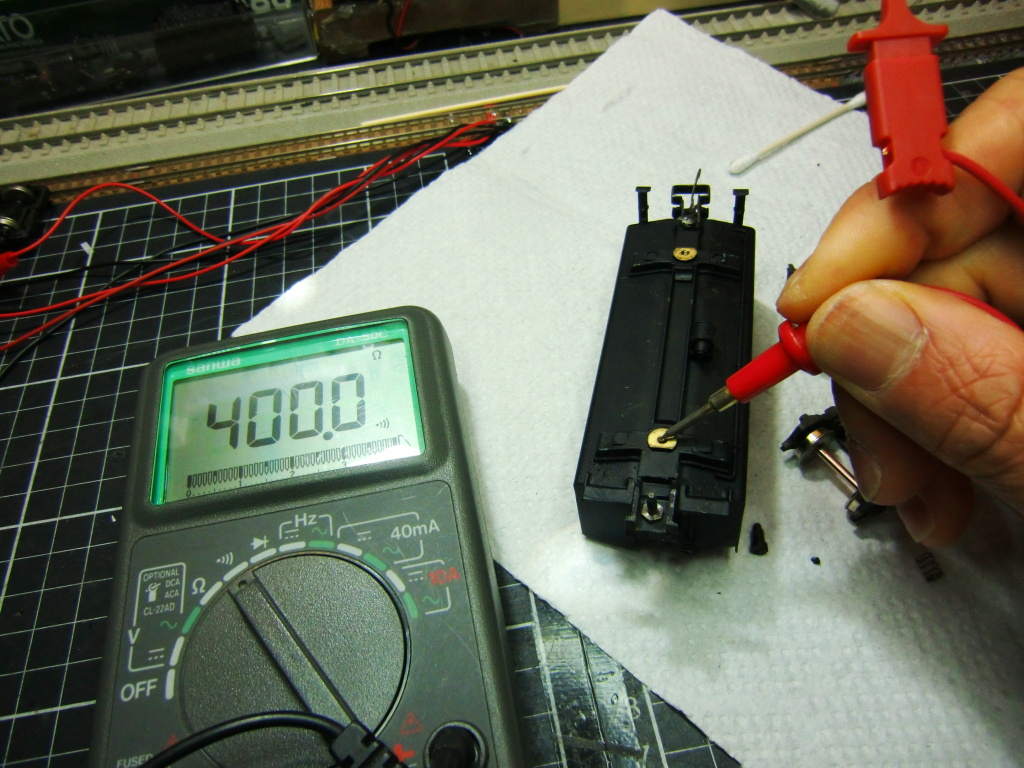
機関車が乾燥機から出てきましたので、塗装へ移行します。

まず、プレートは白く変色してましたので、上記のように磨き出しを行って表示がはっきり読み取れるように処理ました。


ライトはマスキングゾルでマスクします。

続いて下地塗装を全体に施します。

テンダーも同様に処理していきます。

下地ができたところで、「つや消し黒」を吹き付けていきます。

大変深みのある黒が蘇りました。数回に分けて色を吹き付けて、丈夫な塗膜を形成します。
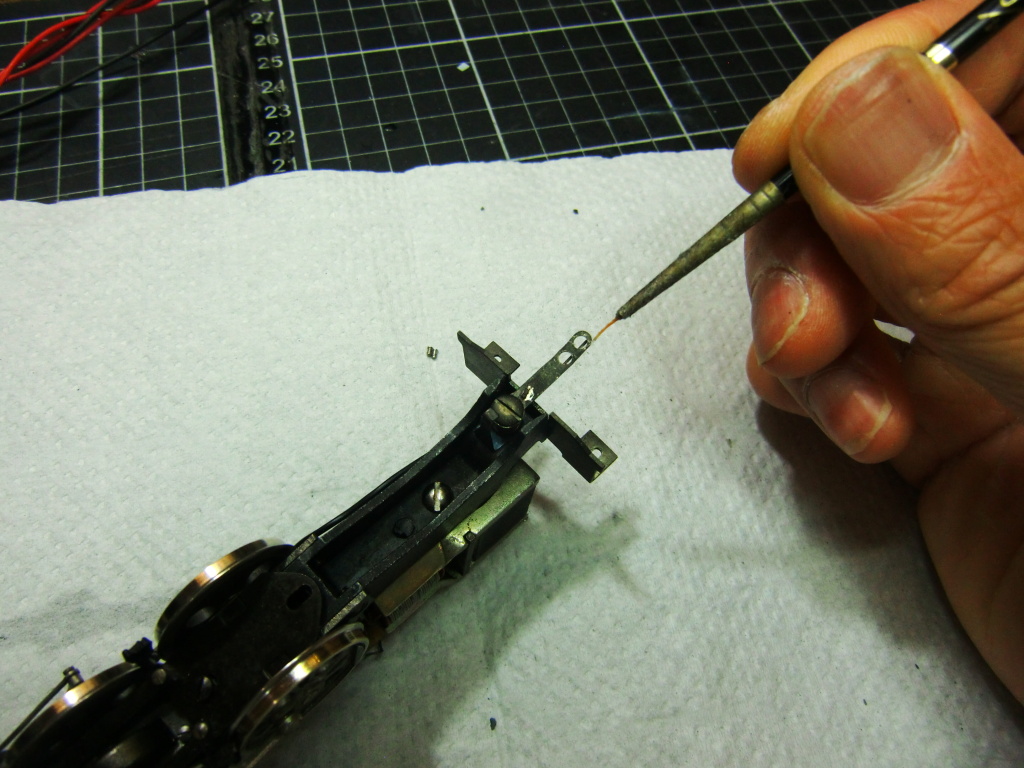

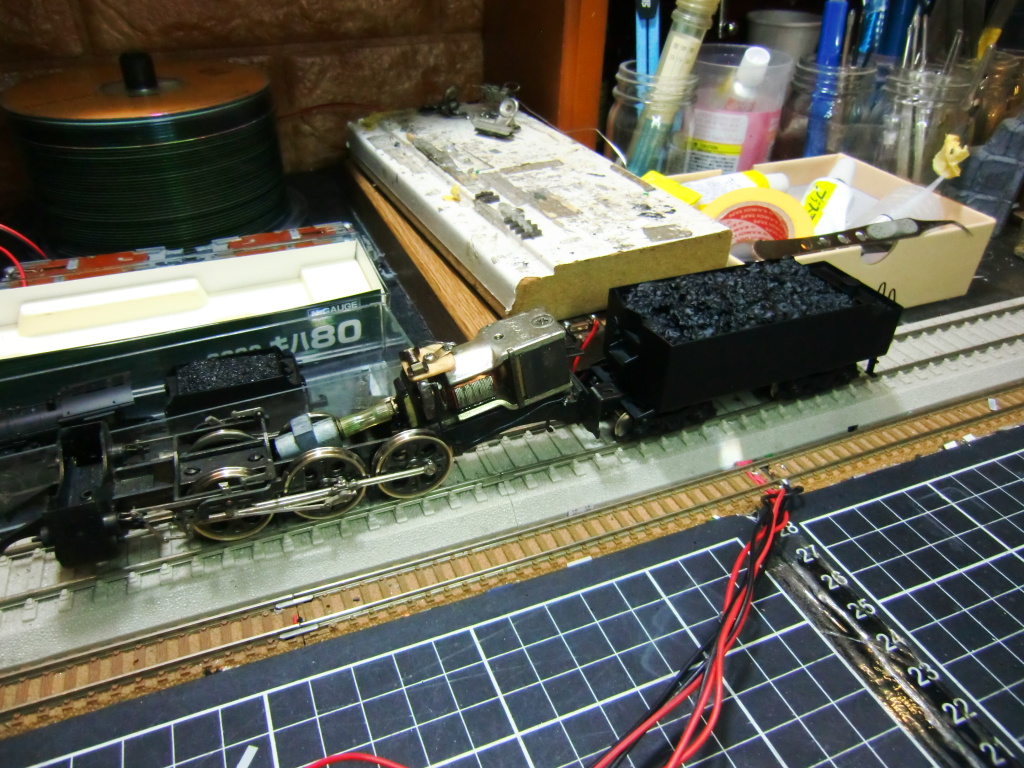
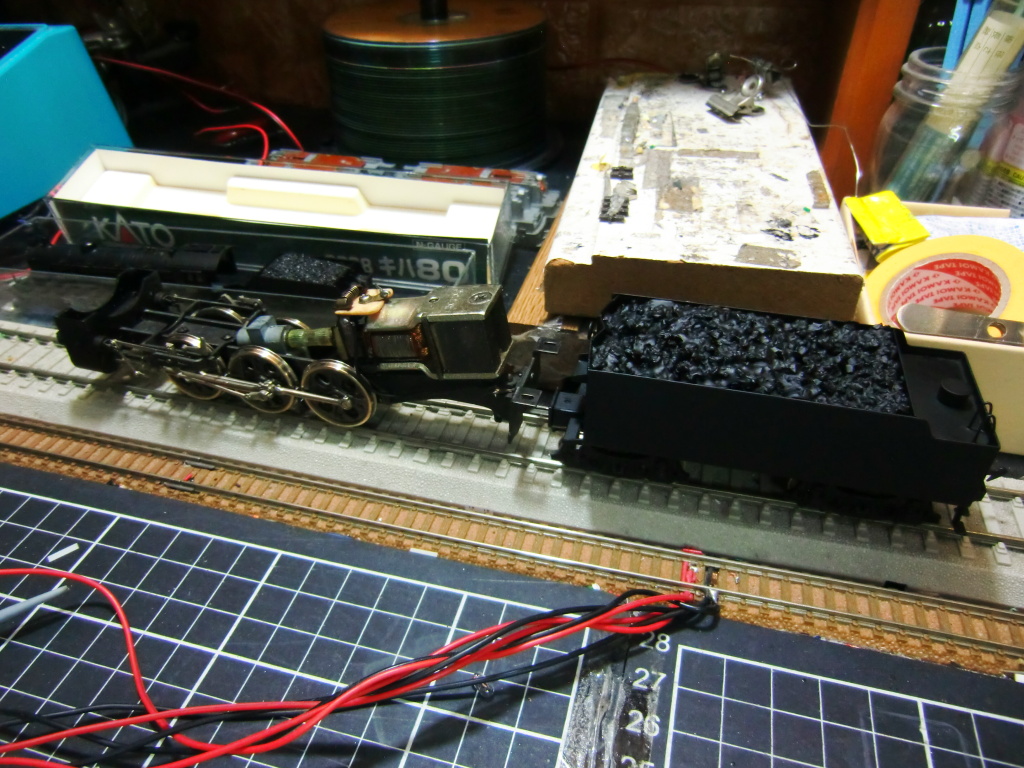

テンダーもだいぶ色あせておりましたが、この通り復活です。
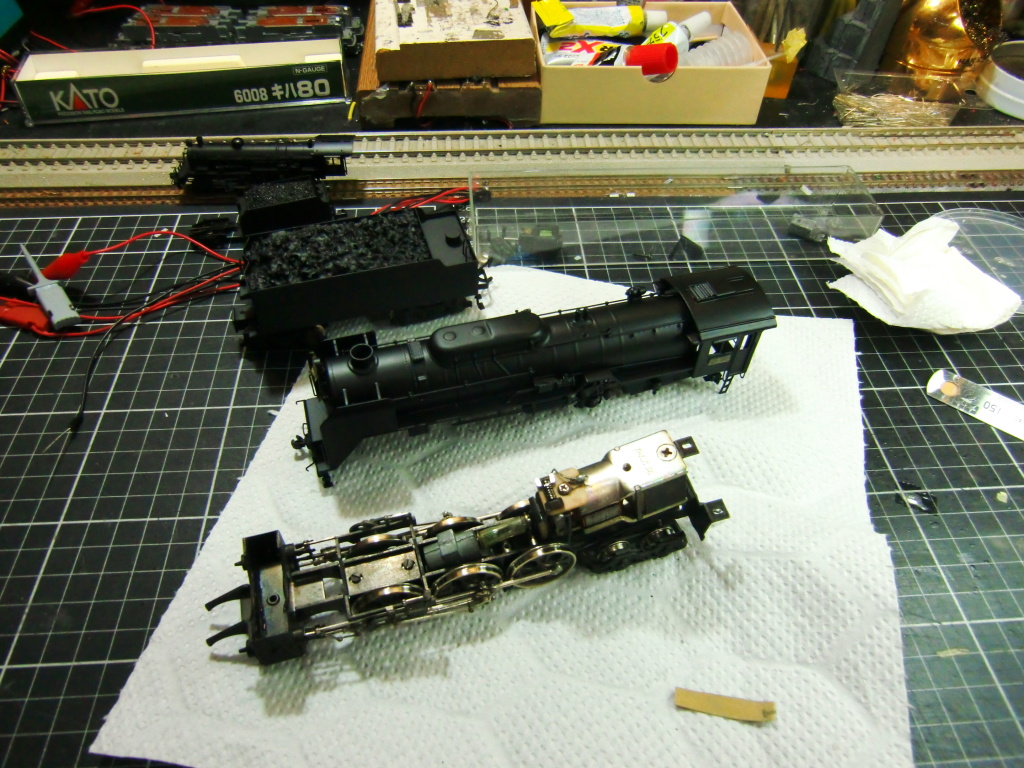
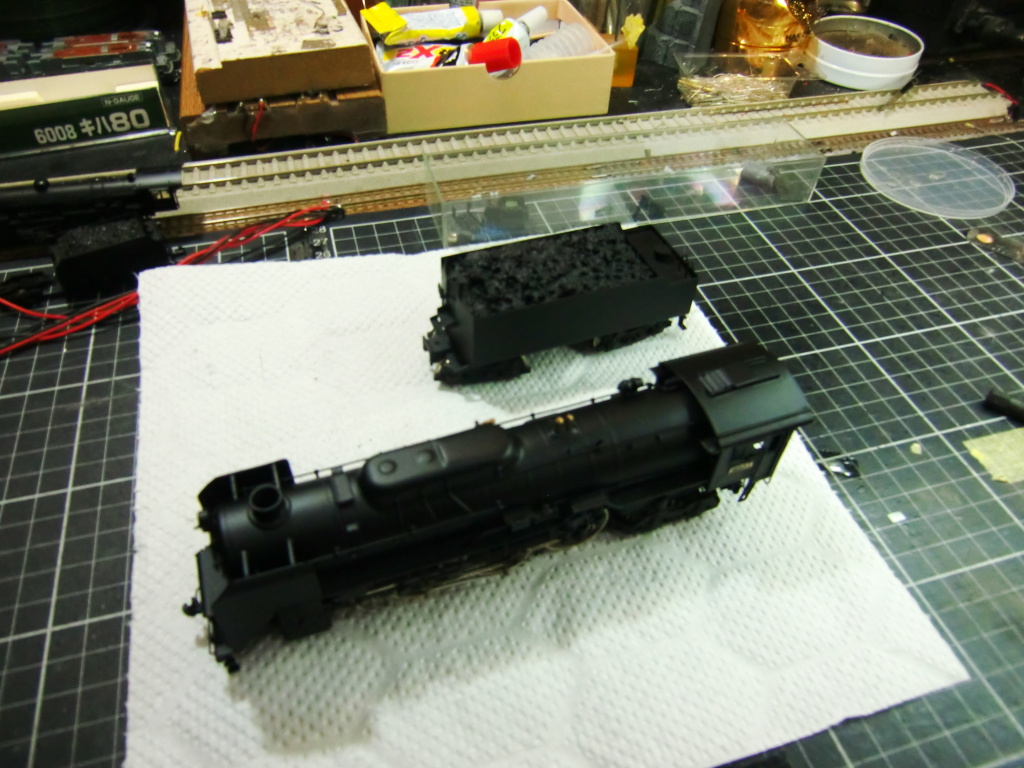
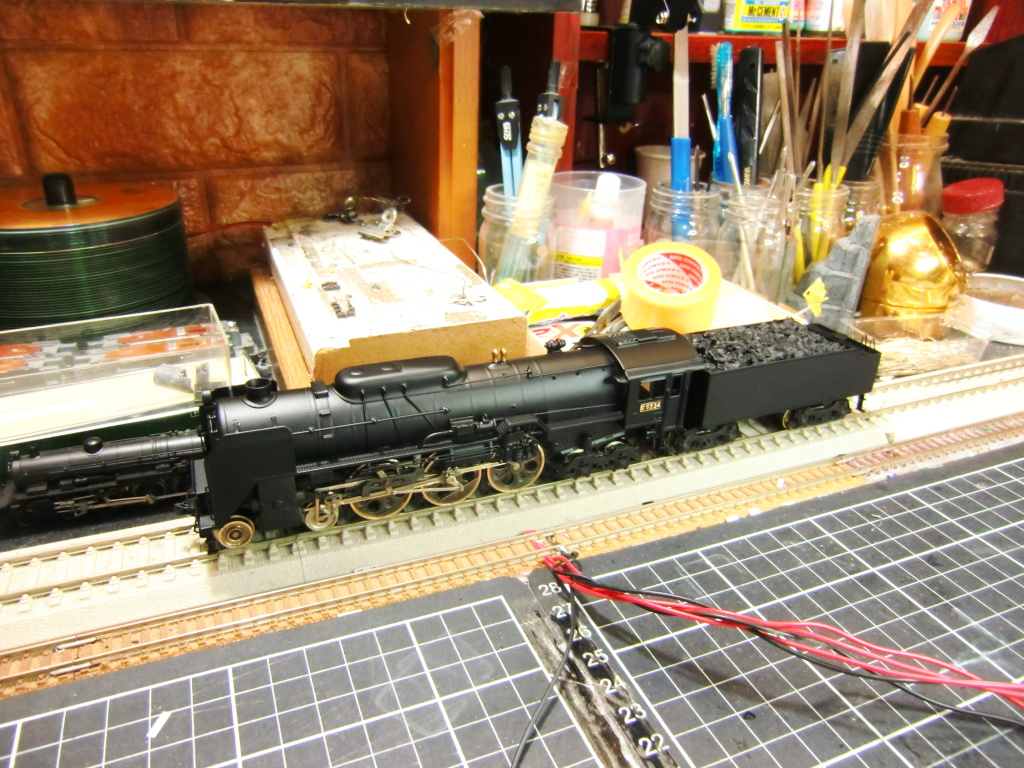

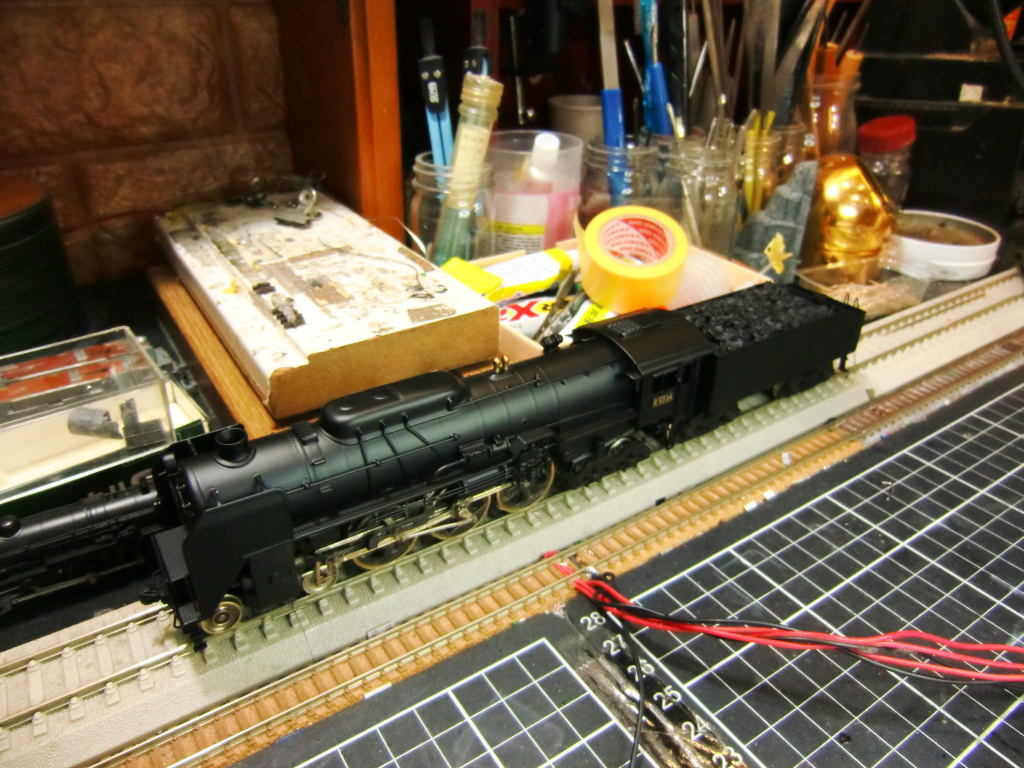


作業完了でございます。



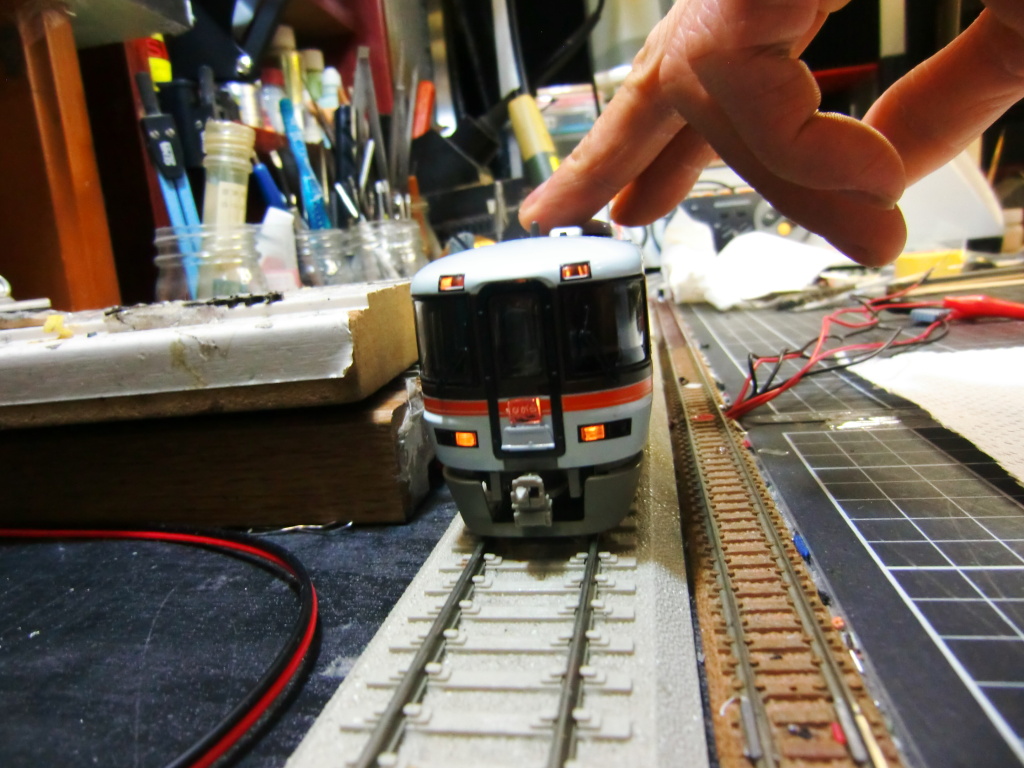
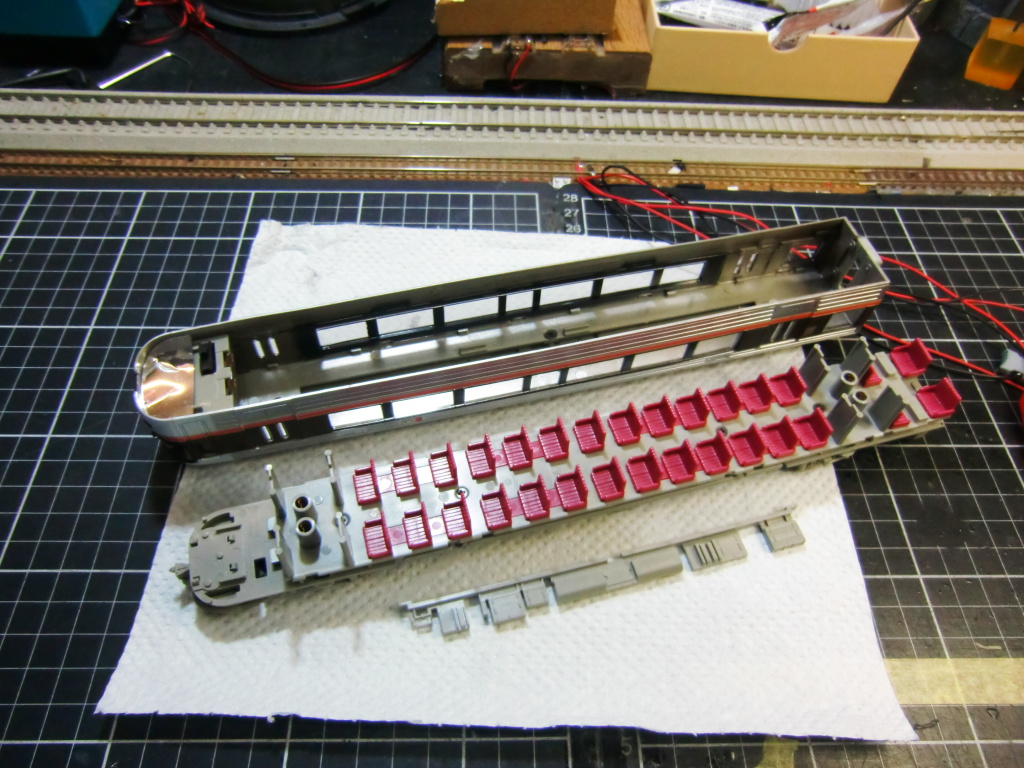
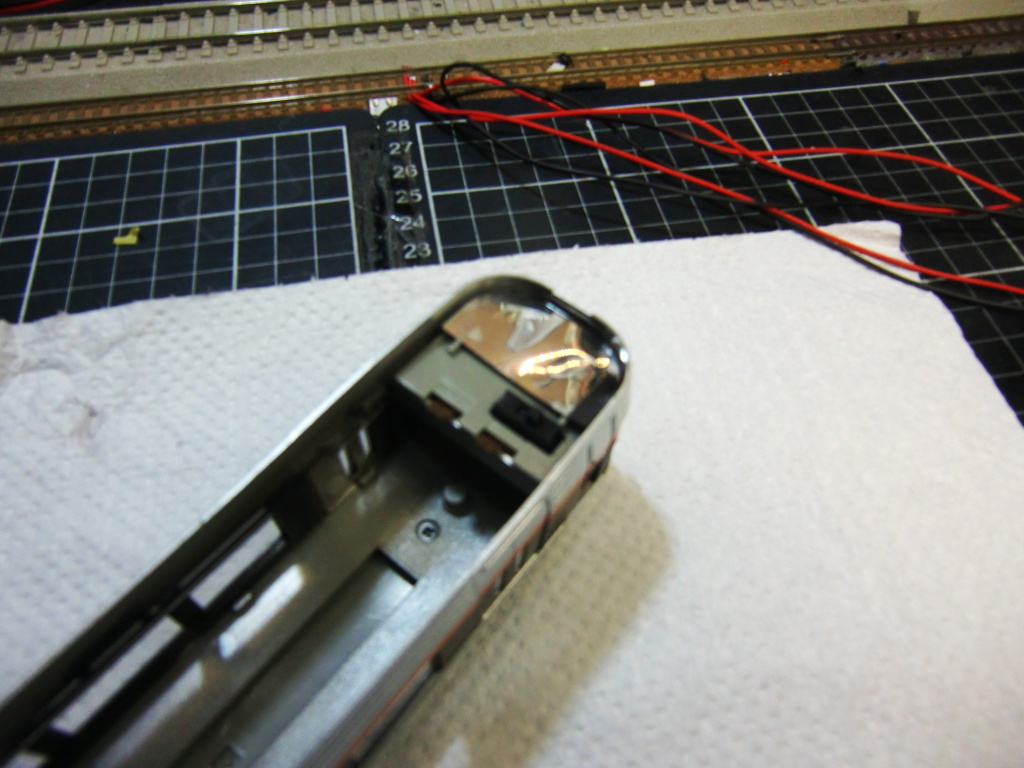
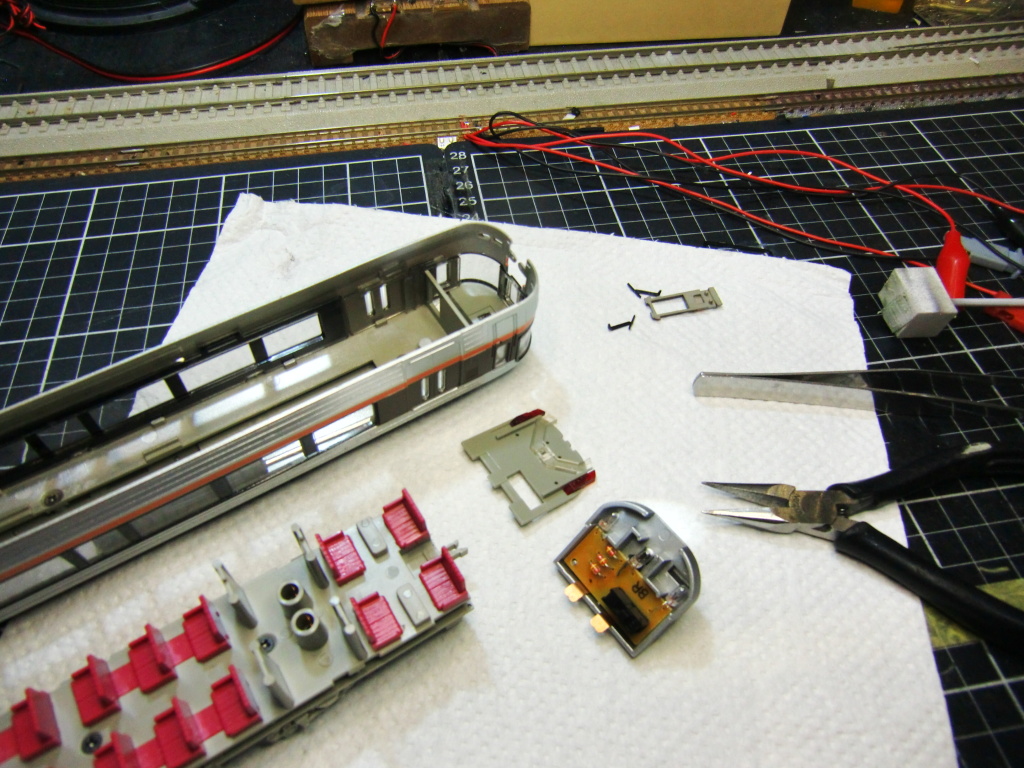
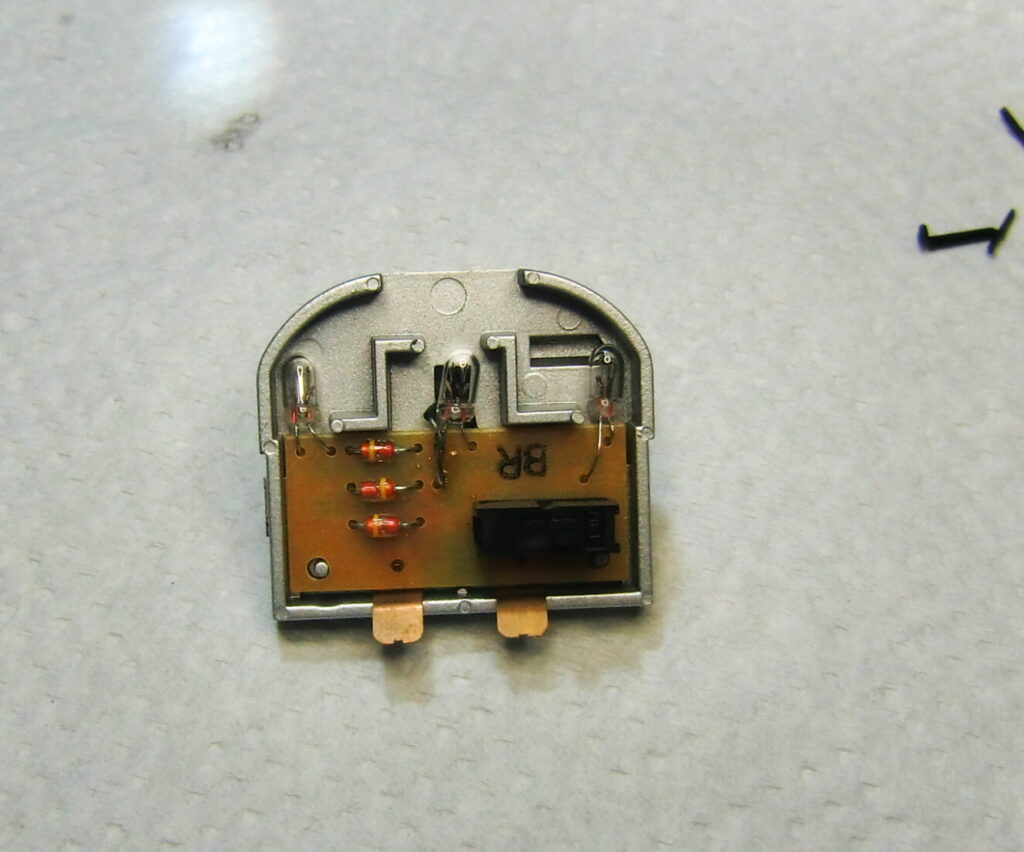
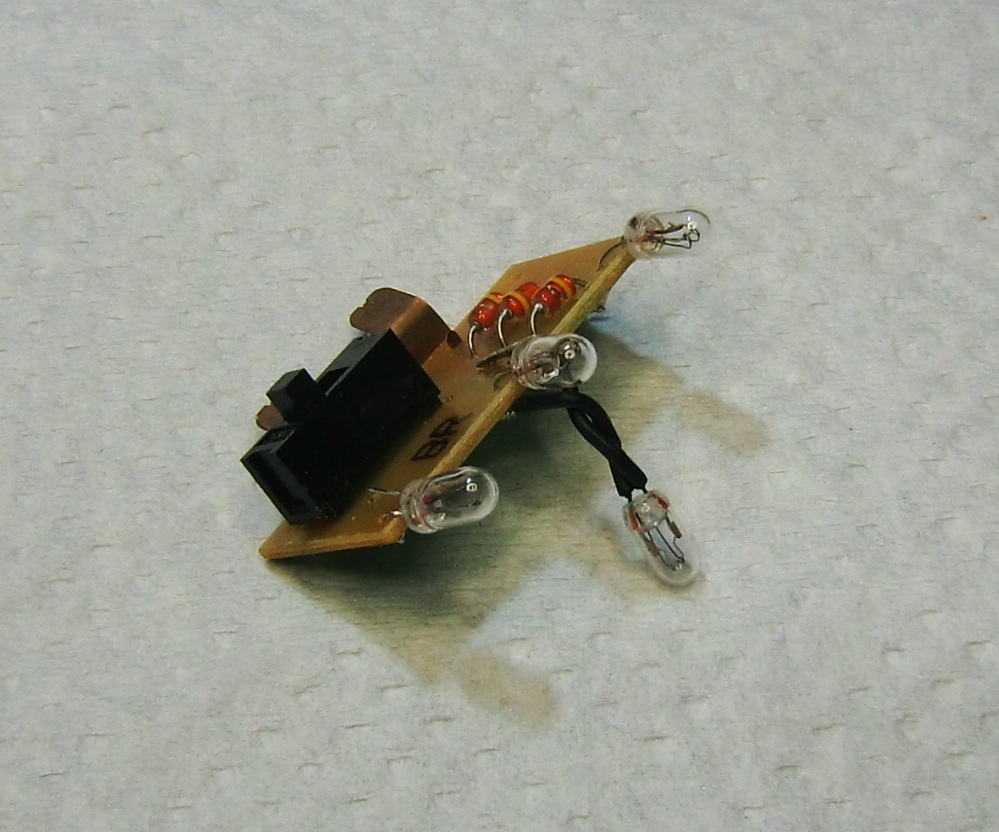
全部で4つの電球が使われています。
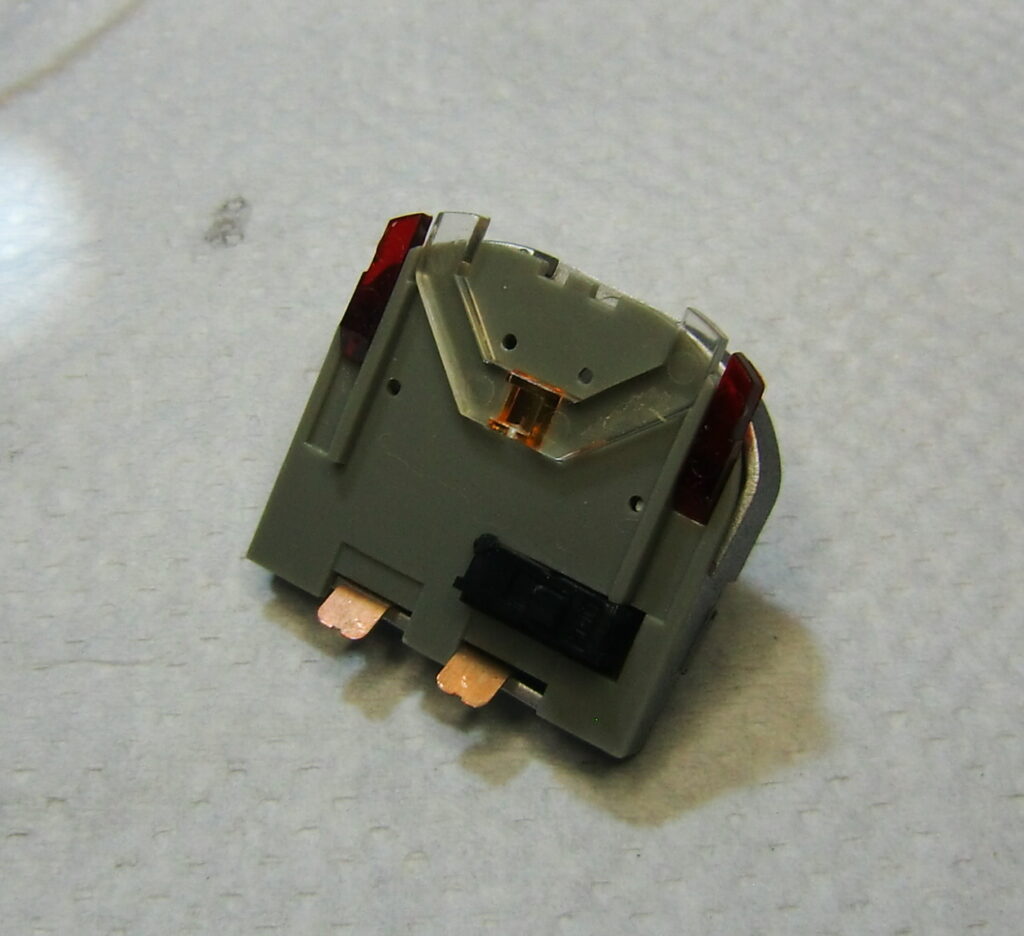
これをヘッド上側1つ(電球色LED)を除いて、すべて白色LEDにします。

ヘッドライト用の導光材の底面を着色して電球色発光にします。
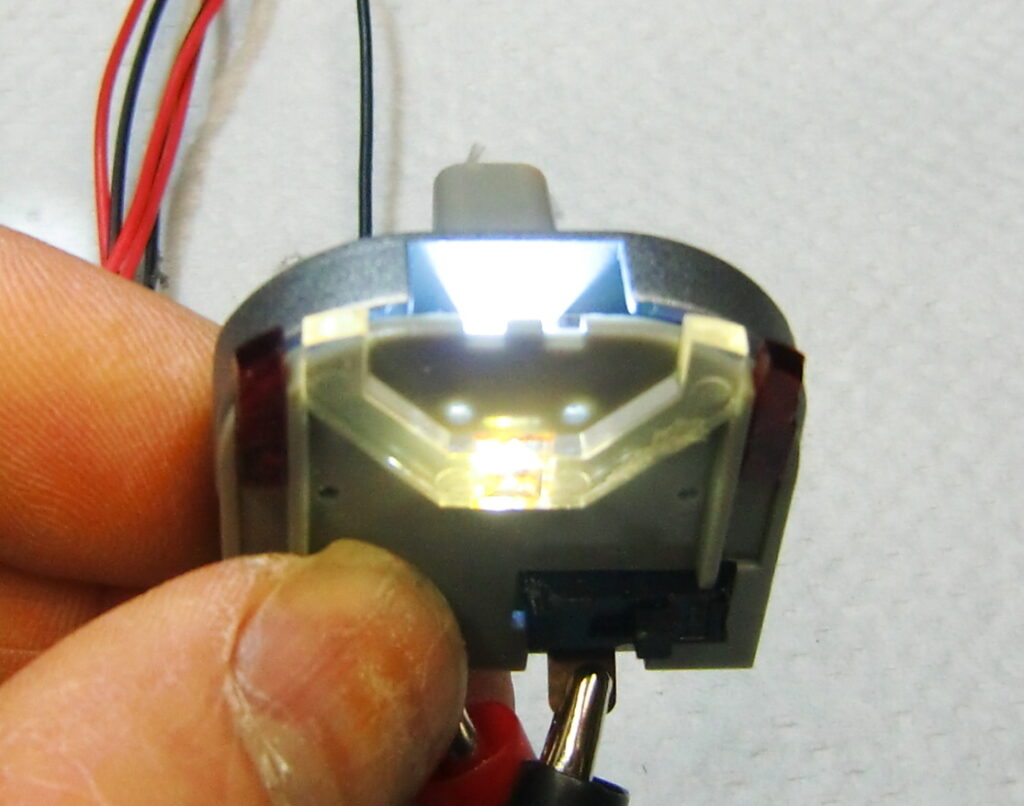
このような色いあとなります。




作業完了でございます。
ナメさんの空気溜めタンクの脱落修理対応でございます。
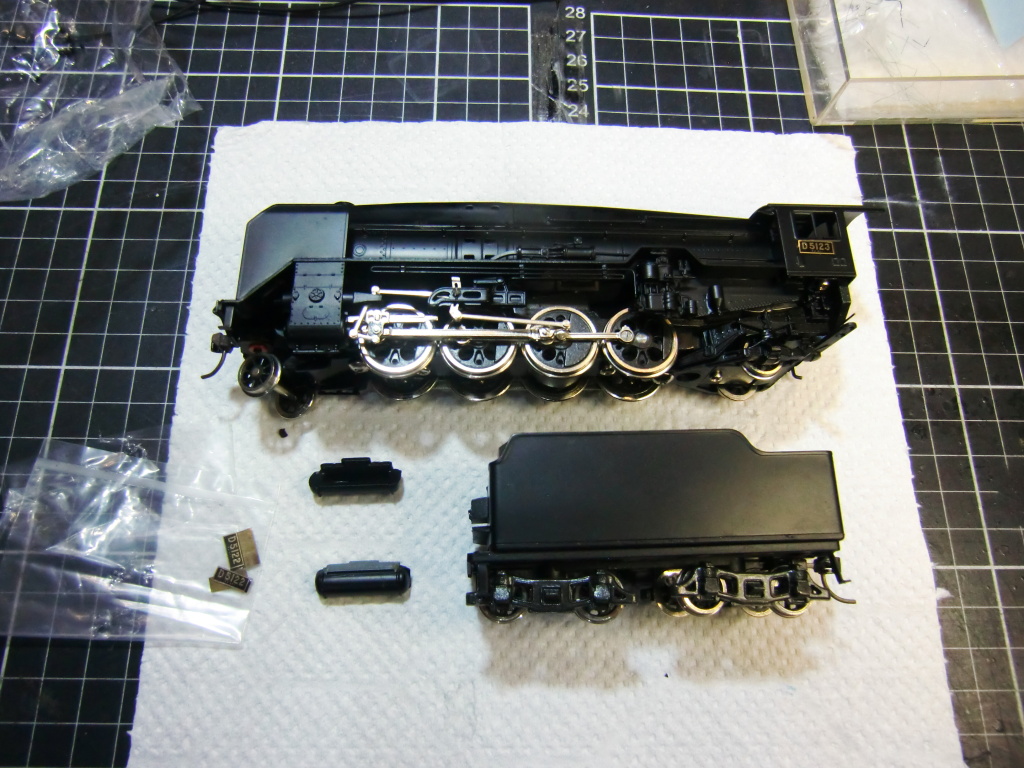
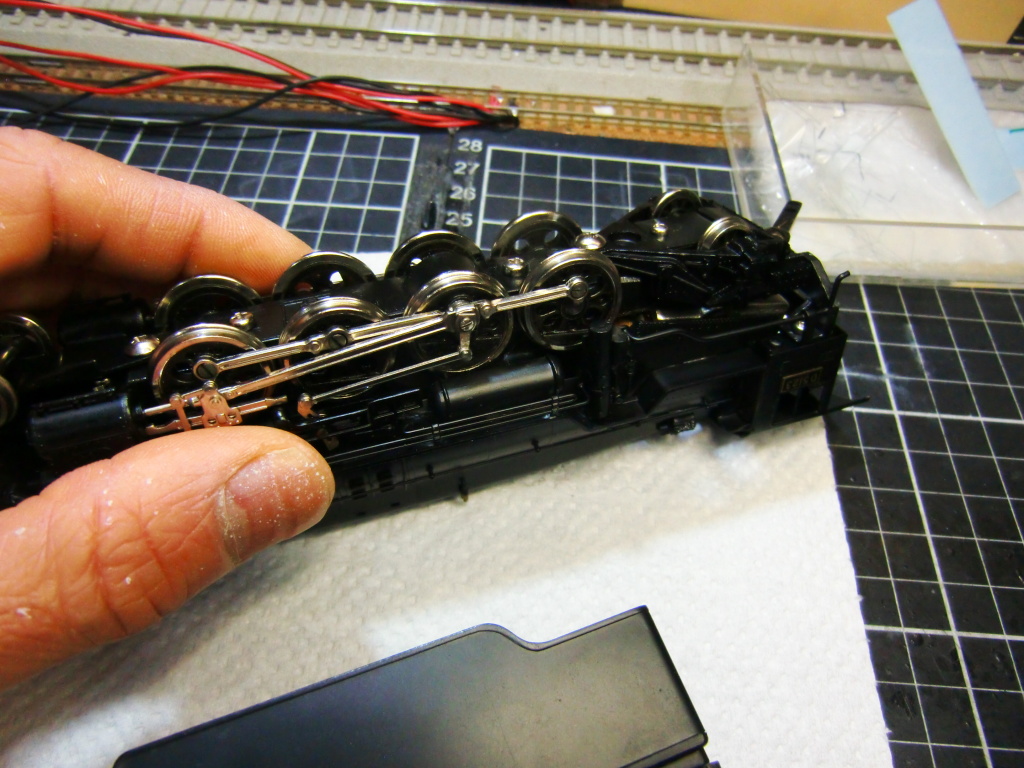
まずは本固定する前に位置関係とを確認していきます。固定面を慣らしたのち固定します。
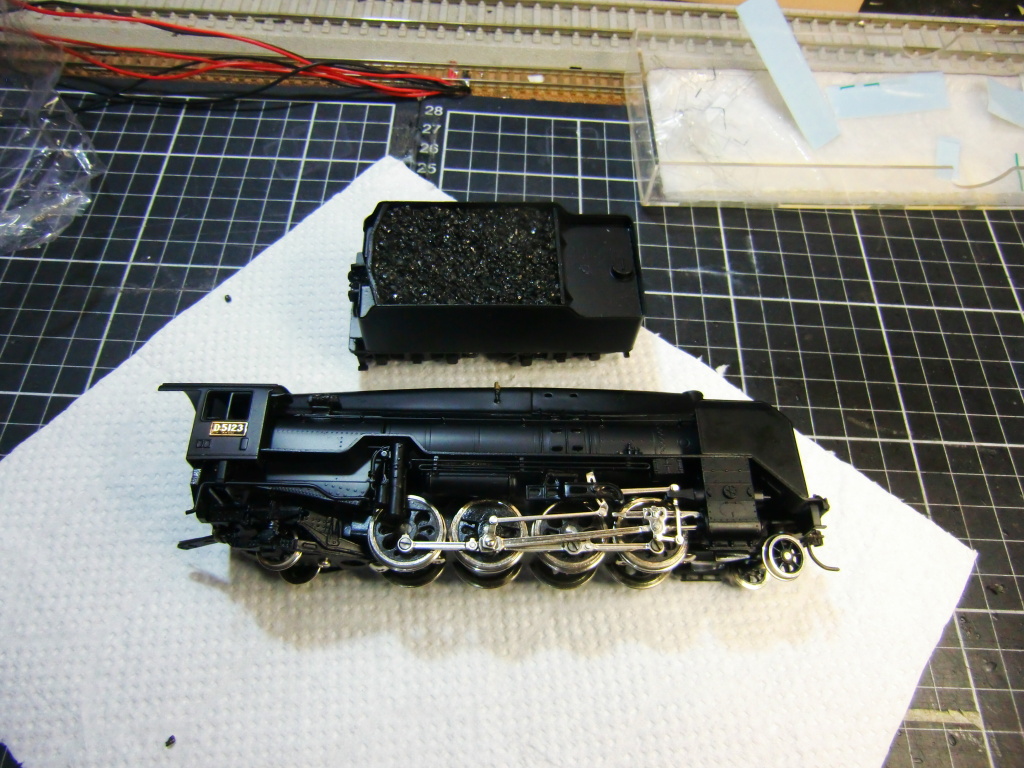
反対側も同様に作業を行います。

固定が終ったところで、継ぎ目にフラットブラックを塗ります。

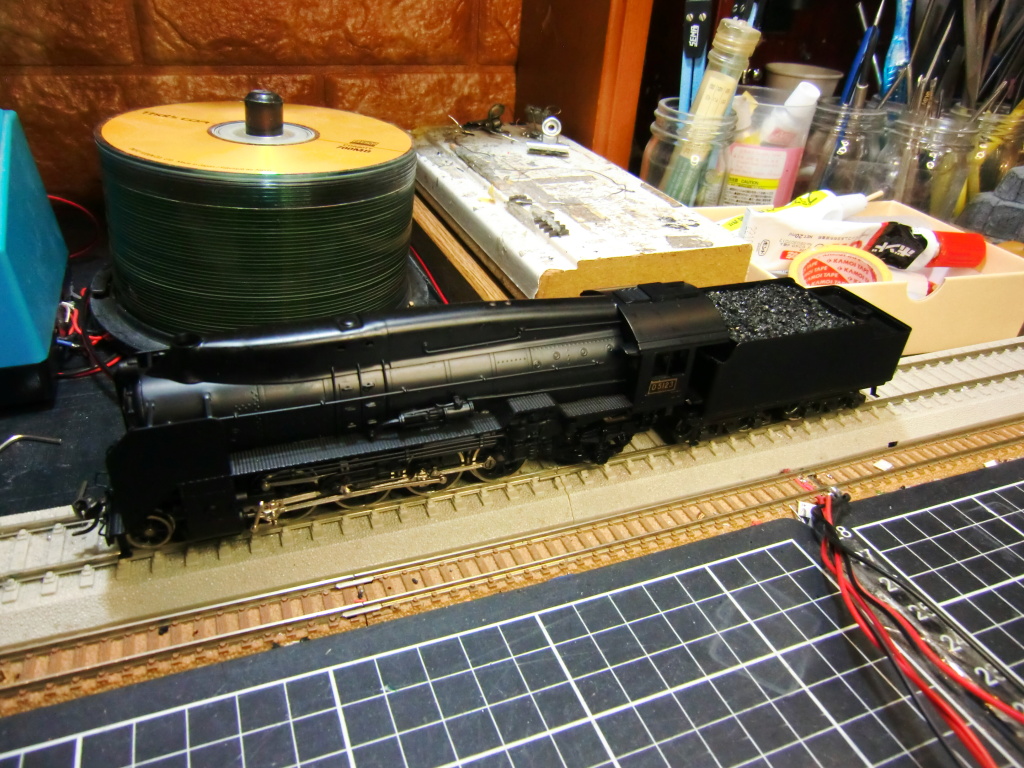
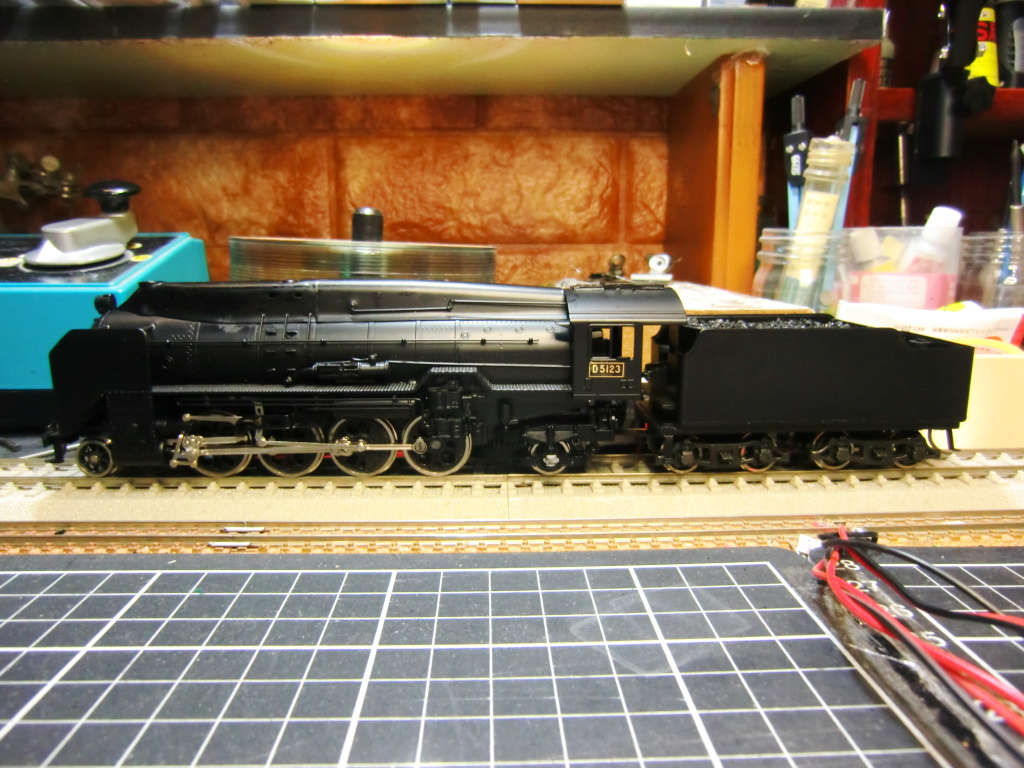


作業完了でございます。
ご要望のございました、「EF210用床下機器パーツ・ATS車上子パーツ」ただいま製作中でございます。
2023/05より、完全自動運転型レイアウトの制作を開始しました。※レンタルレイアウトではございませんので、ご了承ください。
今回の制作にあたり、自動運転におけるシステムの構築から実際に列車を運用させるまでの一連の流れを学んでいきます。そのための、試験的レイアウトでございます。
制作を進める過程で、さまざまなストラクチャー素材を制作してまいります。それに伴いまして順次、ぴょん鉄商品リストに追加してまいります。
▼2023/05/22 レイアウト設計を開始
まずは、路線設計からです。
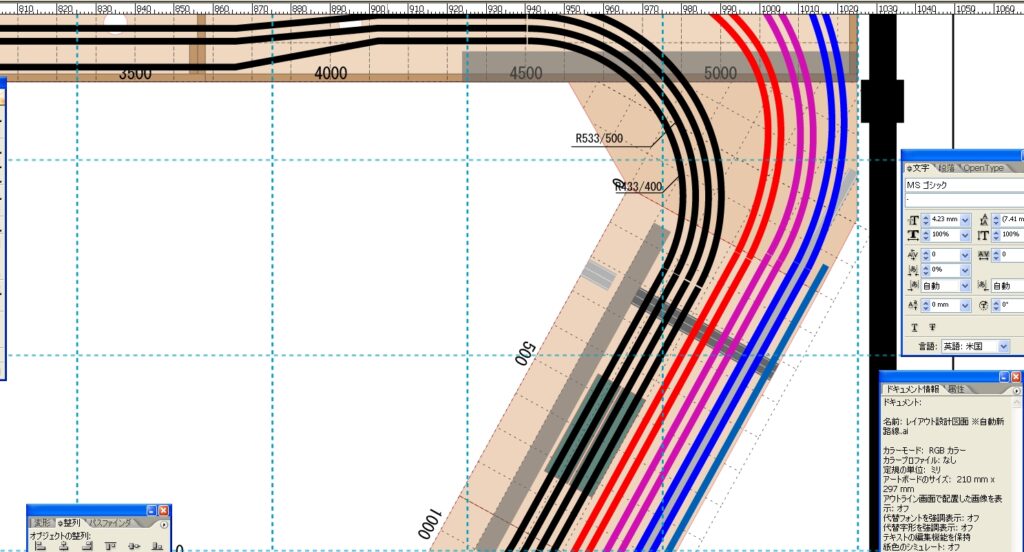
全11線がすれ違うポイントです。まだ、設計段階ですので修正が入ってくると思います。
今回のご依頼は、進行方向と逆に走ってしまうというものです。恐らく、モーターが逆に取り付けられていると思われます。

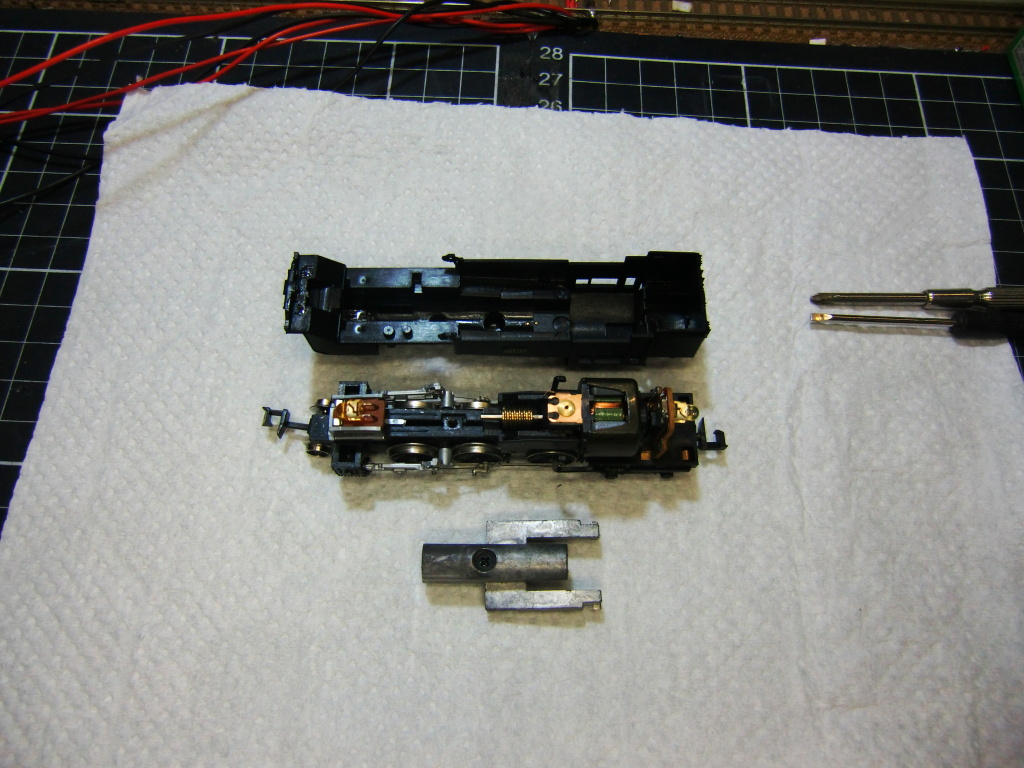
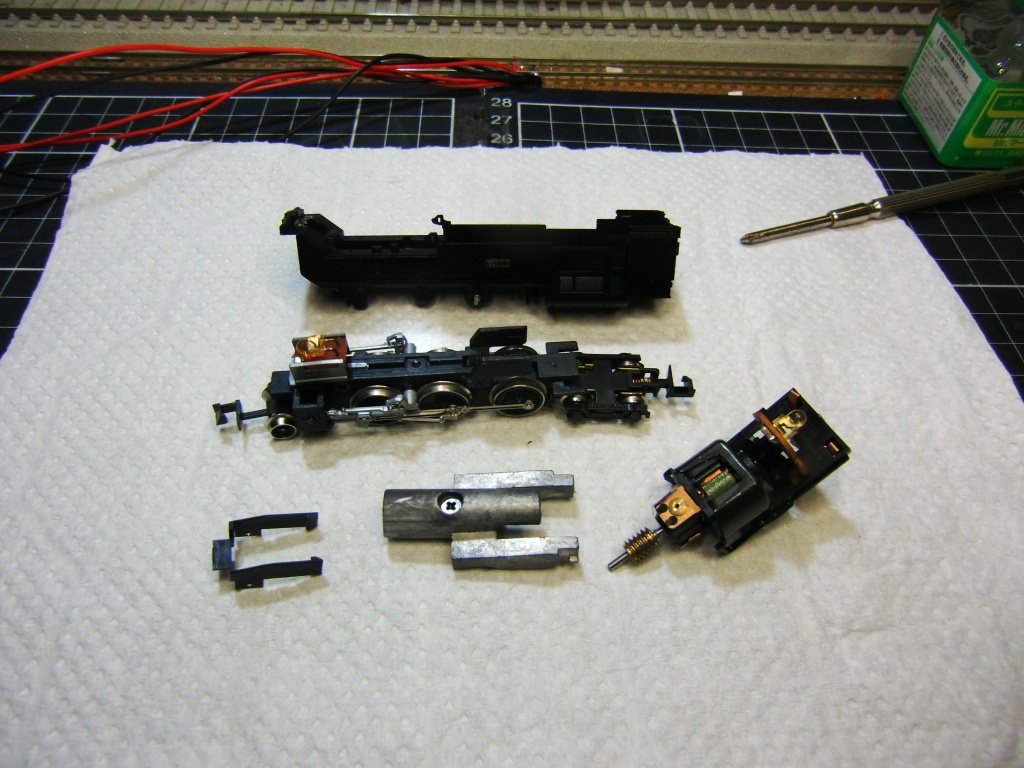
モーターを取り外すには、周りのパーツを先に外してから後方にスライドさせます。

組み戻す方が少々難しく、台車をいったん外してからの方が作業はしやすくなります。

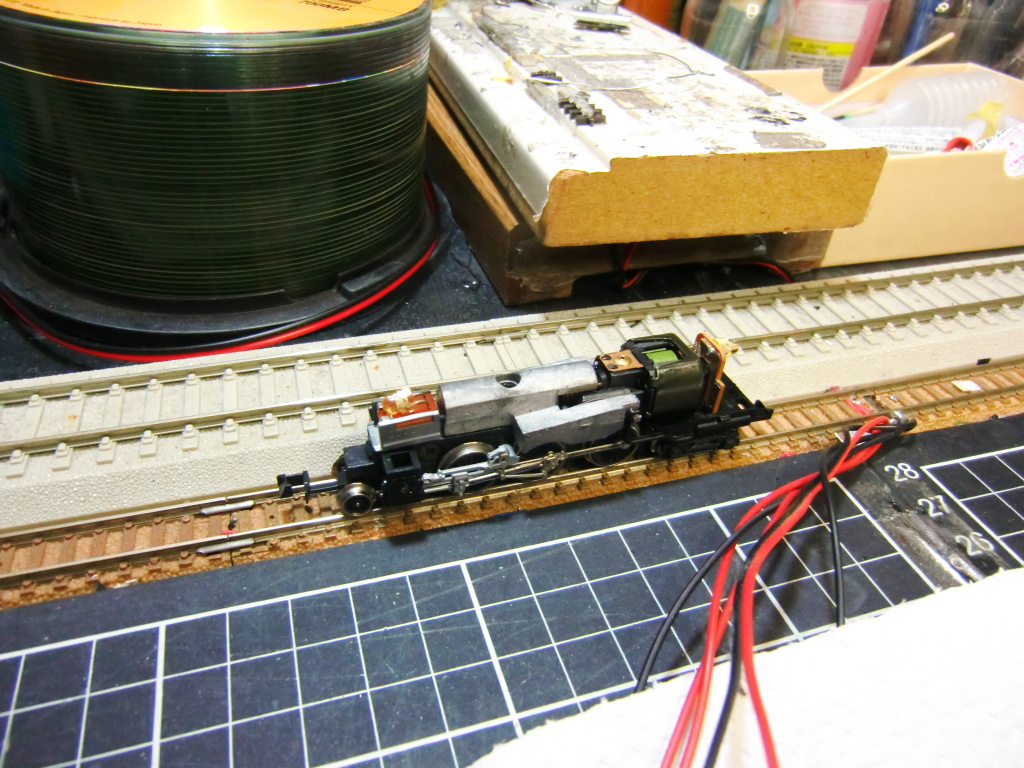
走行がややぎこちないの感じです。よく見ると、ギアの隙間に何か挟まっているようです。一旦分解して取り除き、車輪の回転が安定しました。
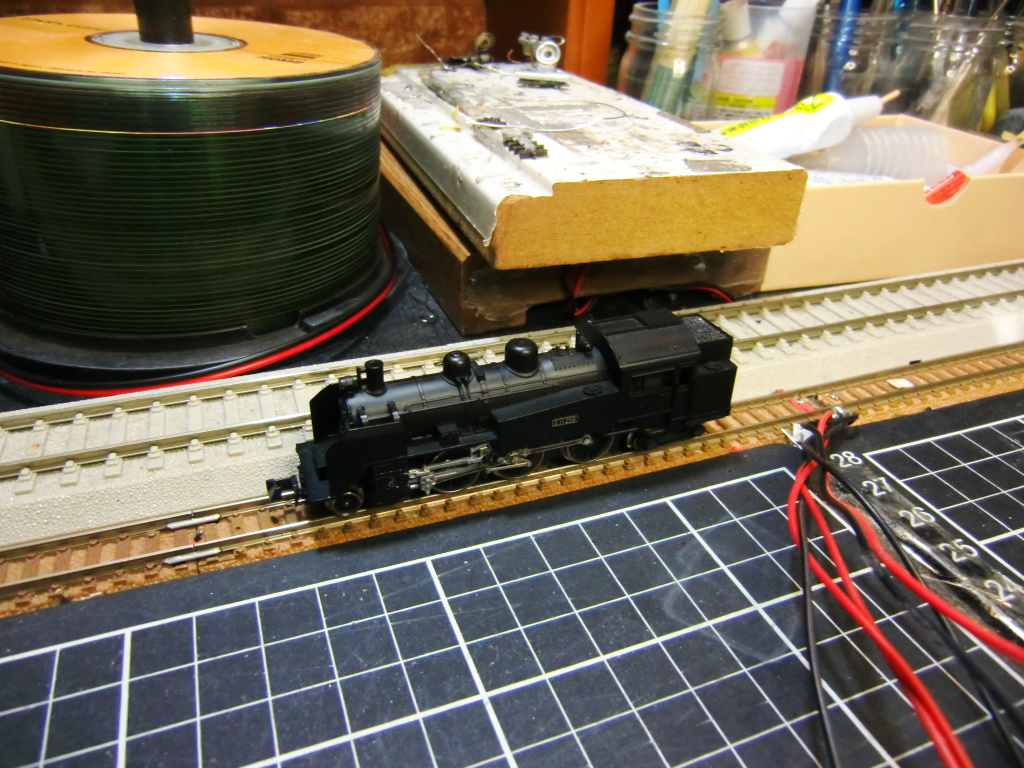
作業完了でございます。


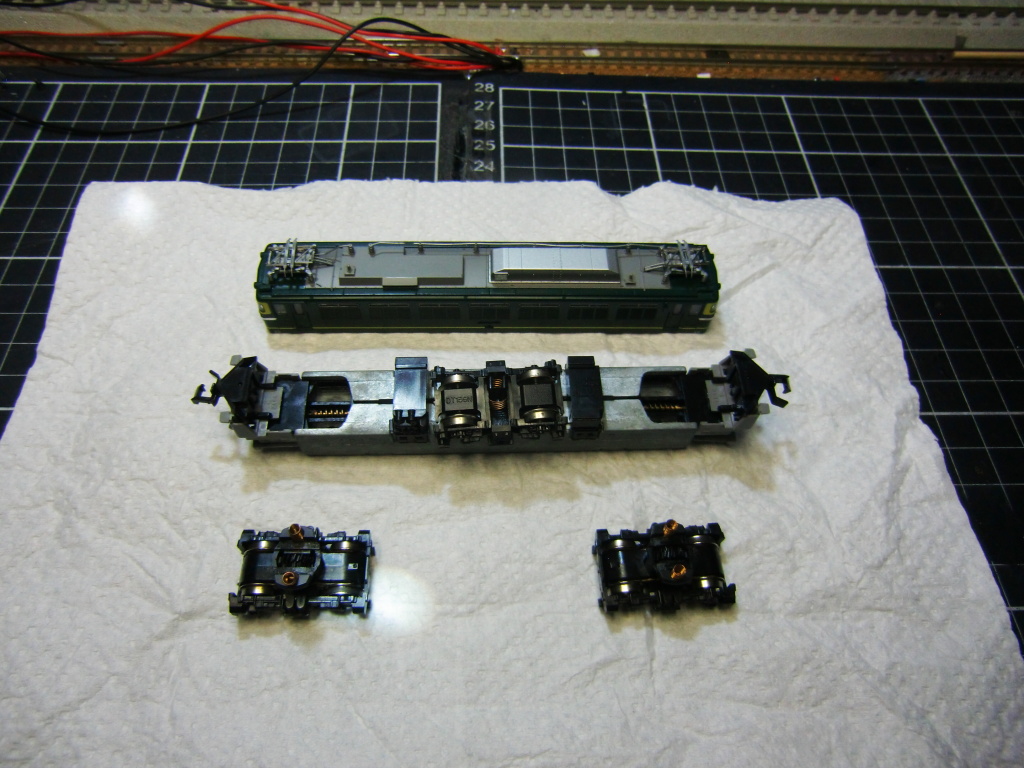

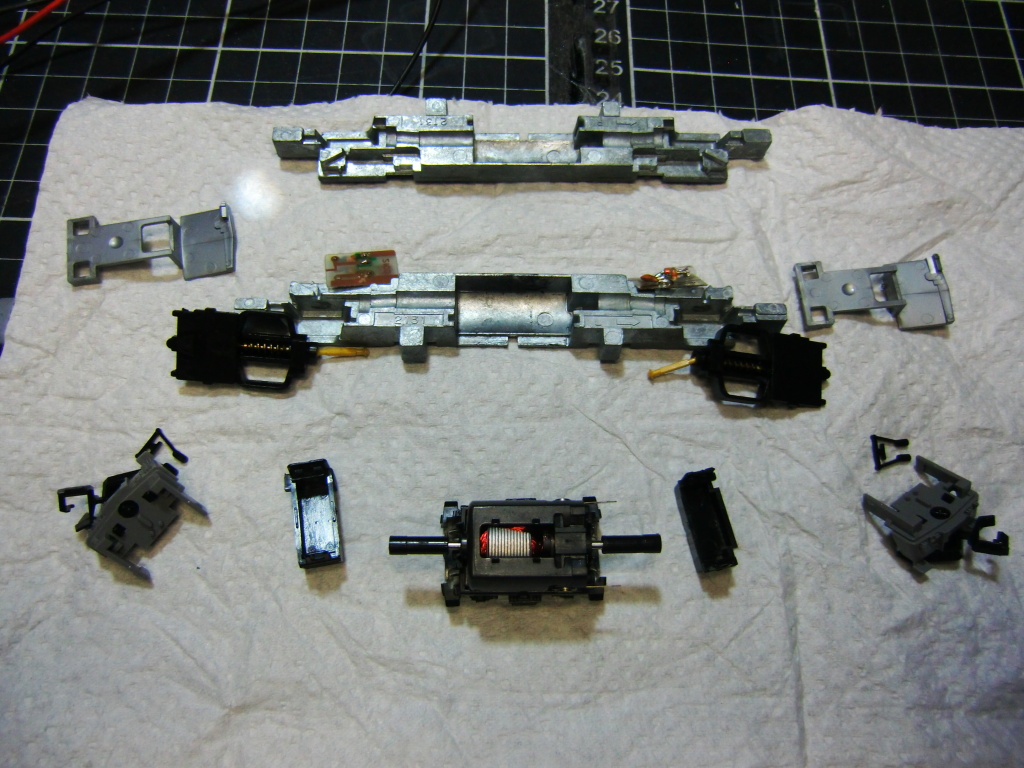
M車は基本的に全分解して、問題個所の特定と対策およびO/Hを行います。

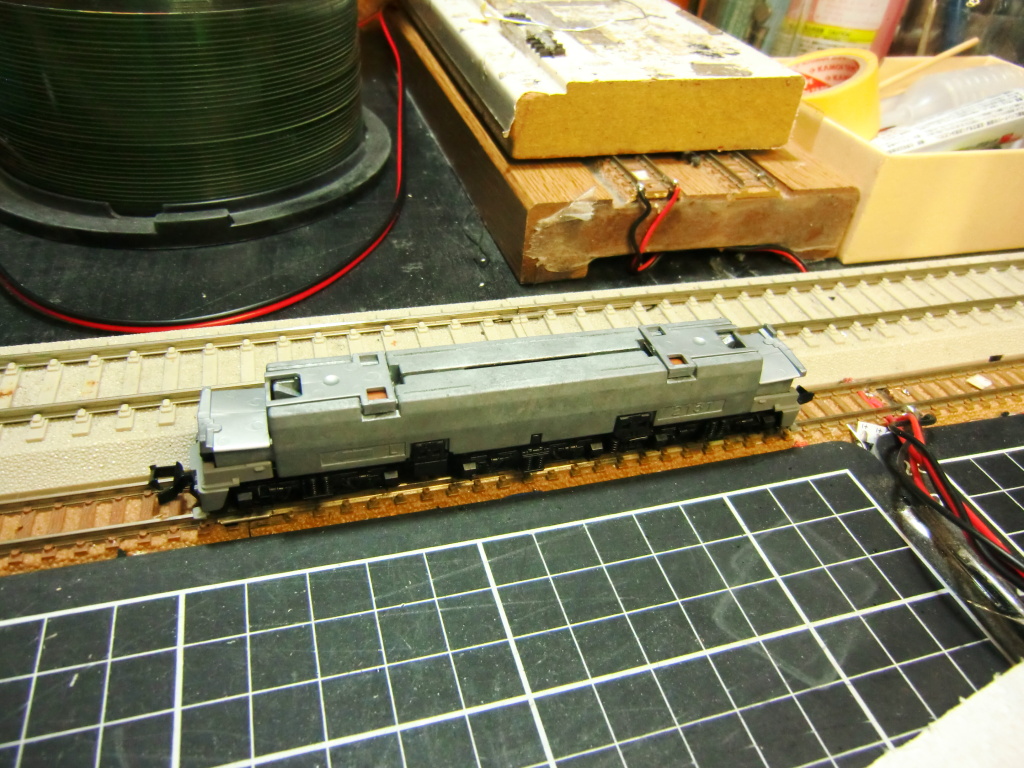
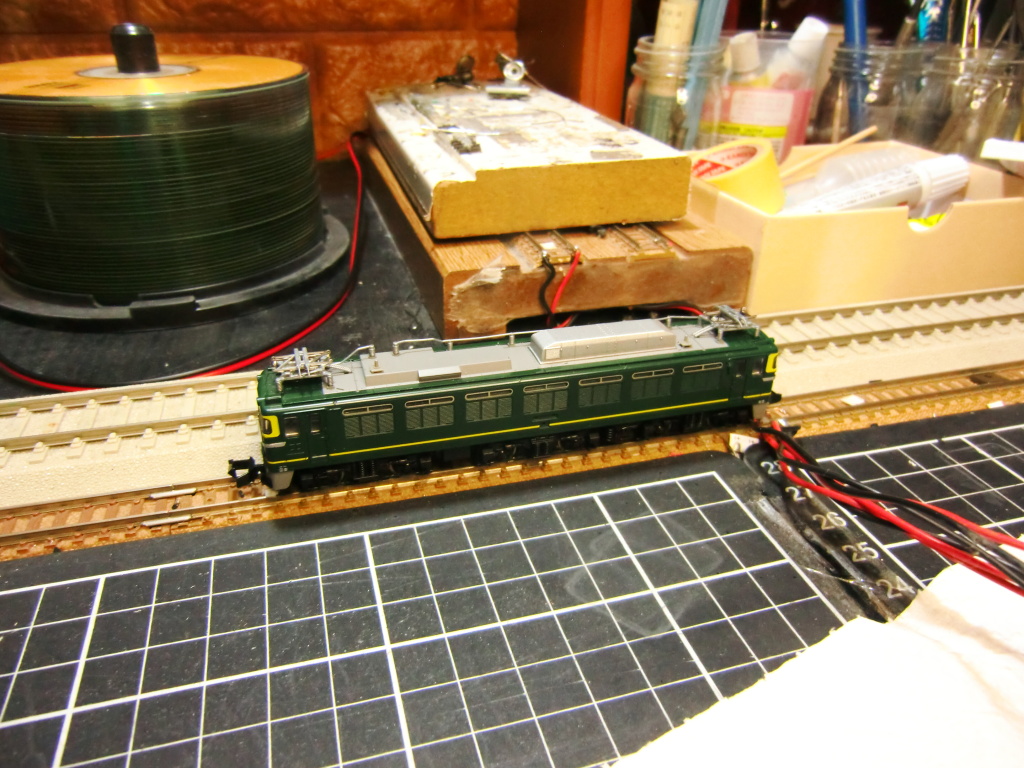


各部の集電が著しく悪くなっていますので、1つ1つ手を入れていきます。

こちらの車体も同様です。
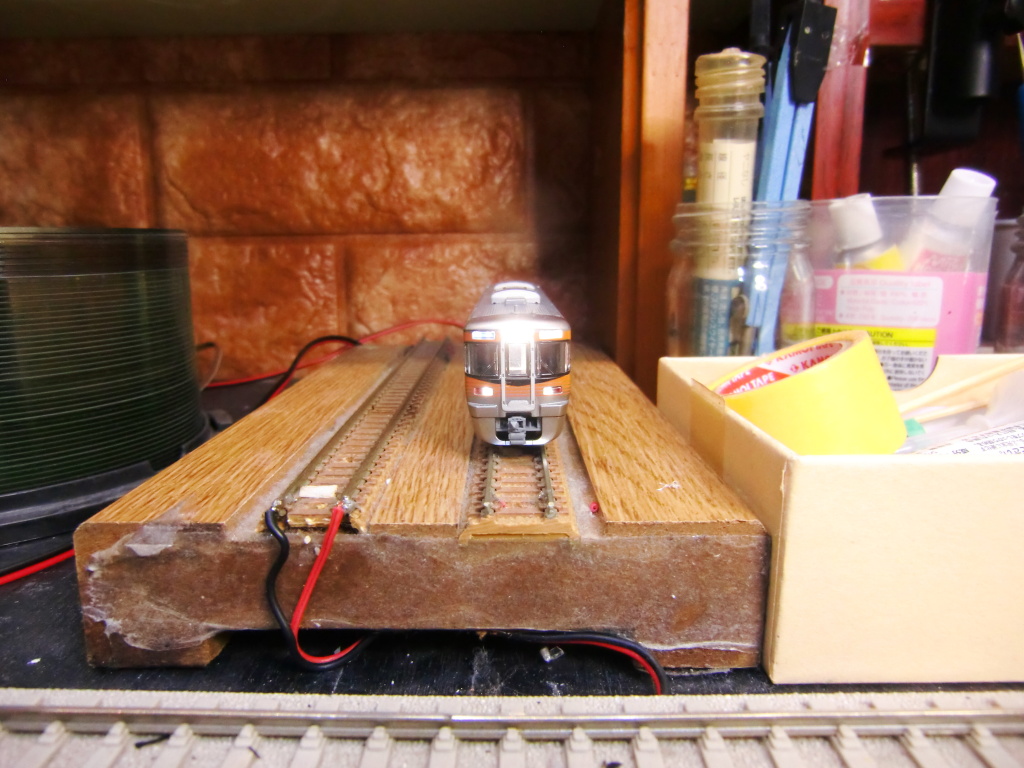
O/Hを終えてこの通り、ライトもしっかり点灯。


続いて、こちらのM車です。まったく反応しません。
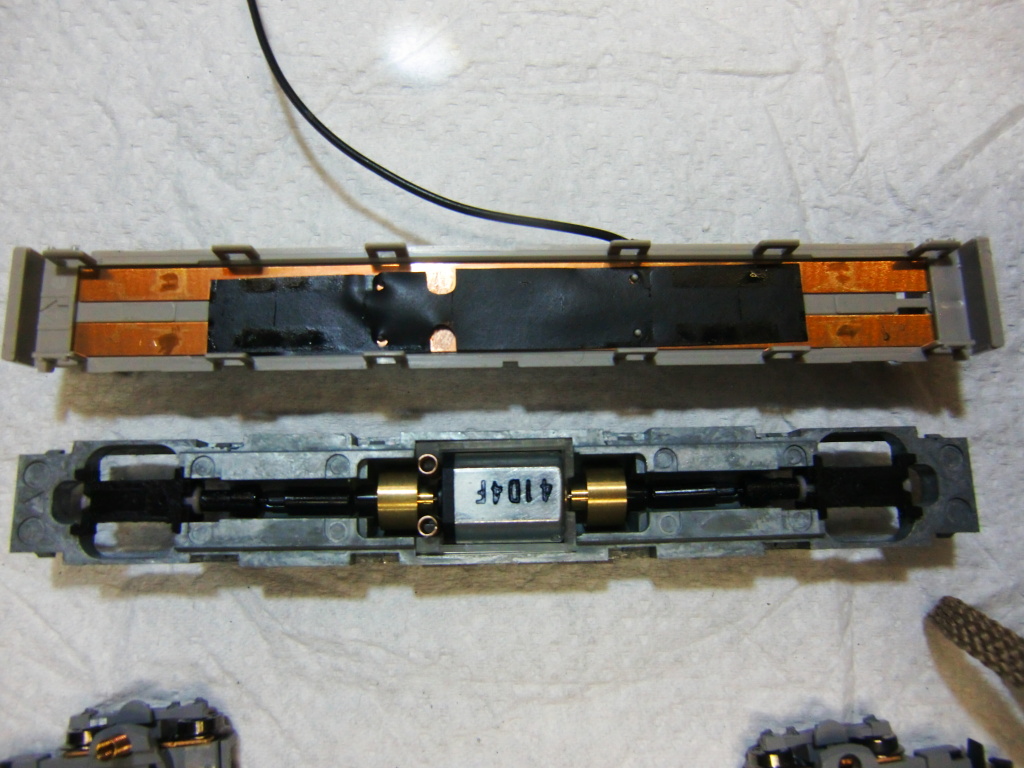
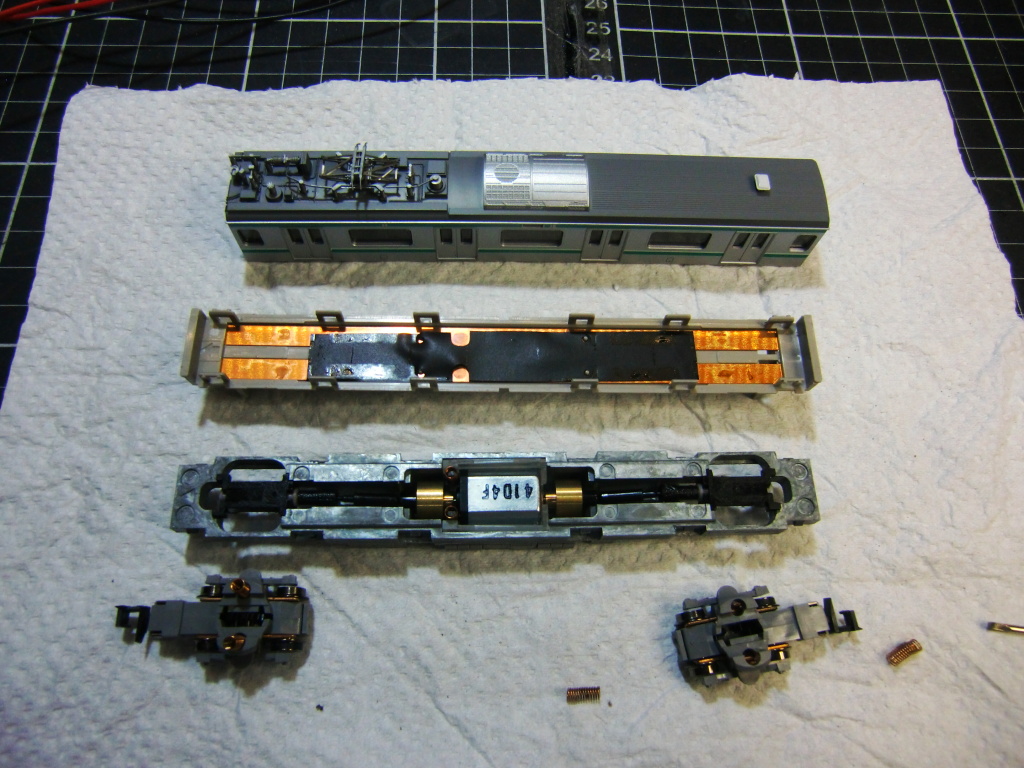
モーターの端子はもちろん、金属表面の酸化被膜により通電不良がございましたので、対処いたしました。
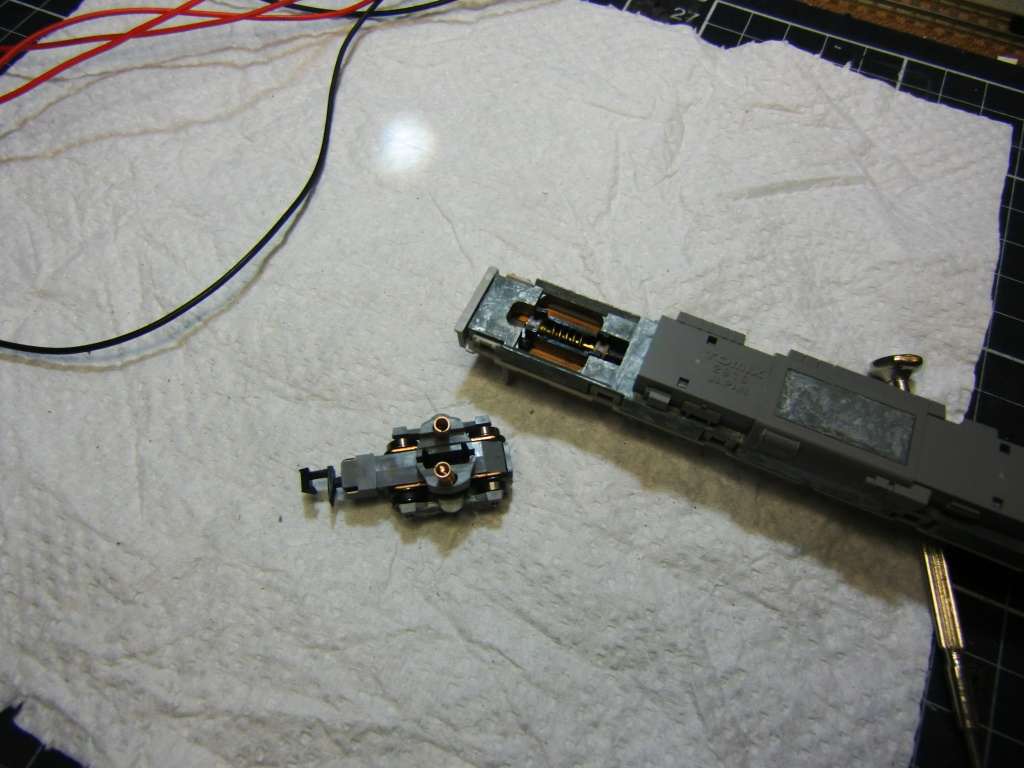
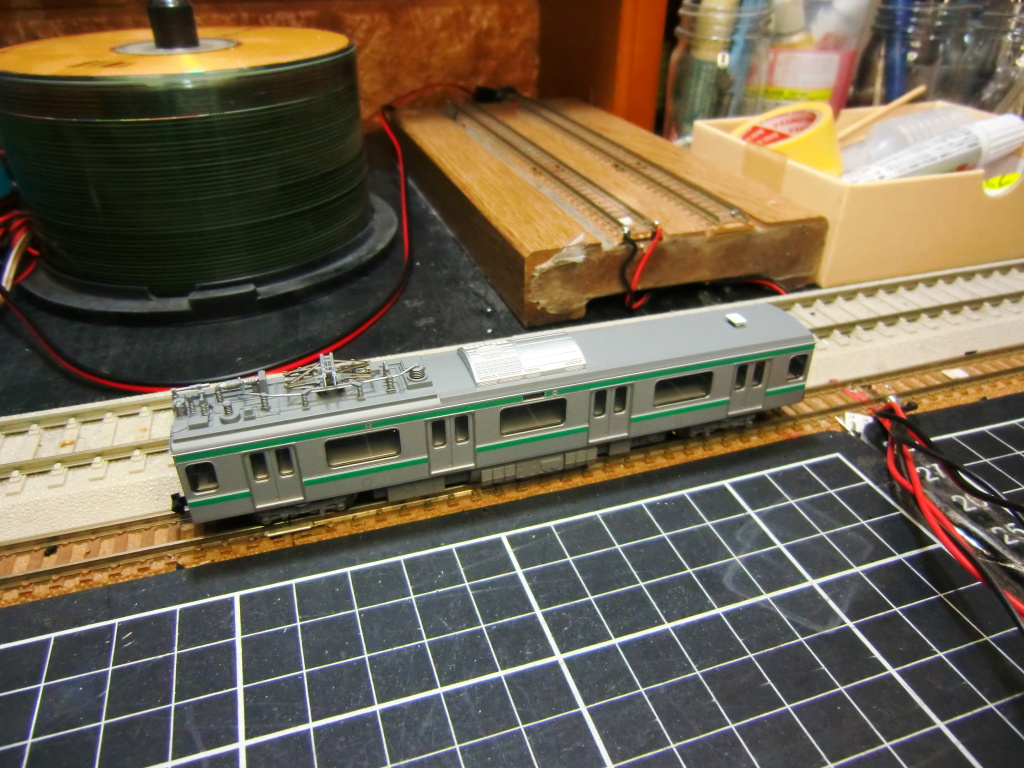

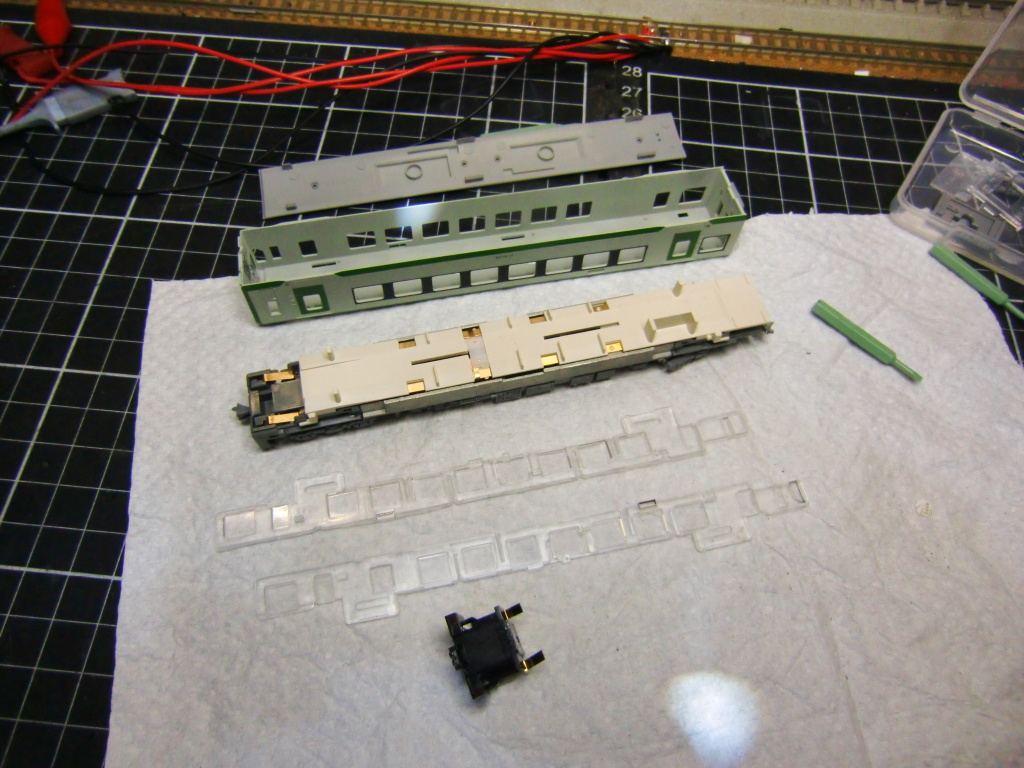
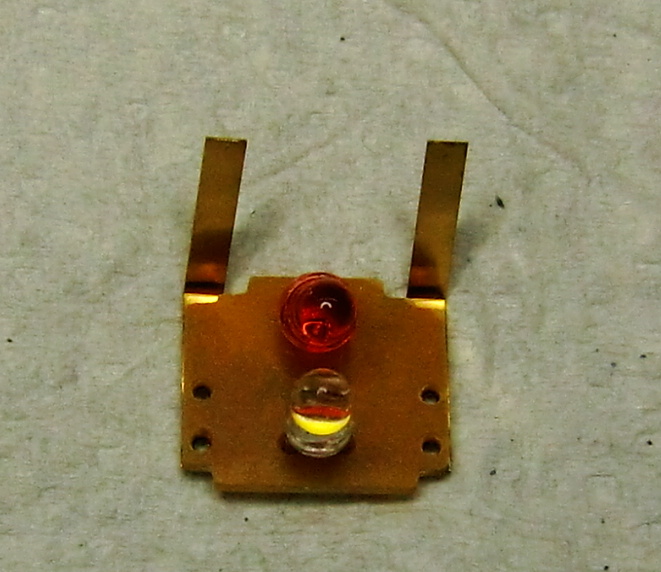
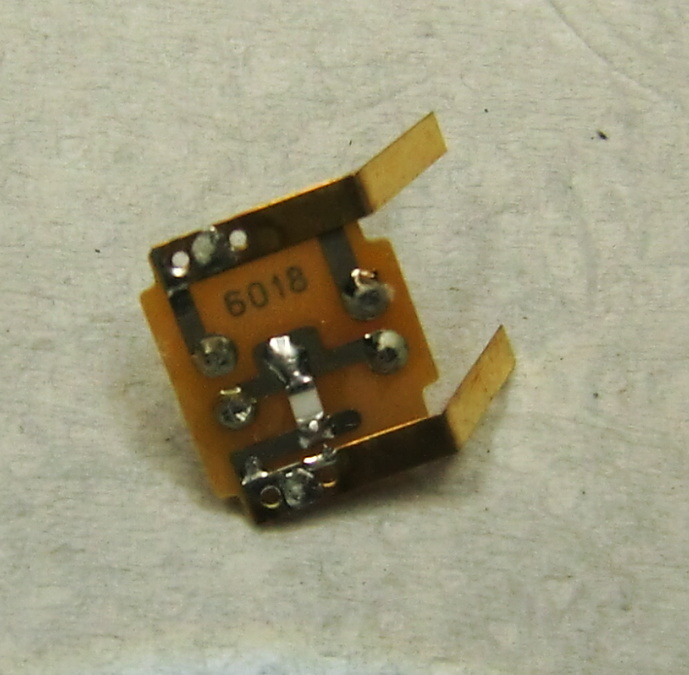

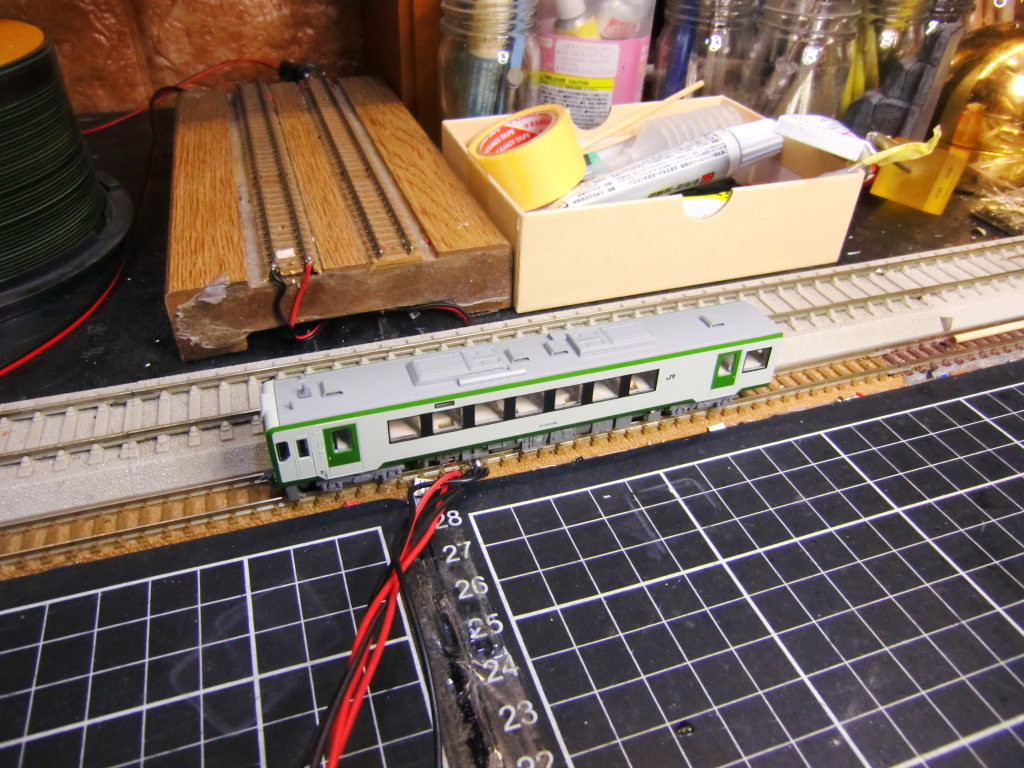


作業完了でございます。
今回の修理のご依頼はこちらのコントローラーです。以前にも同一のコントローラーを修理したことがございました。


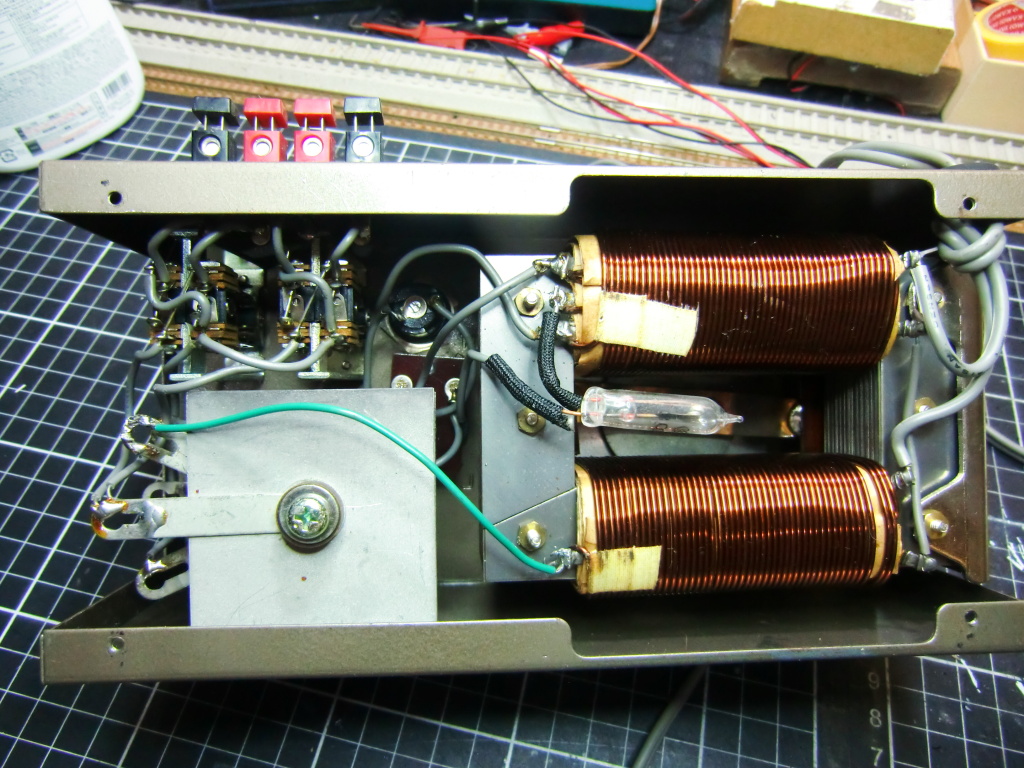
分解します。
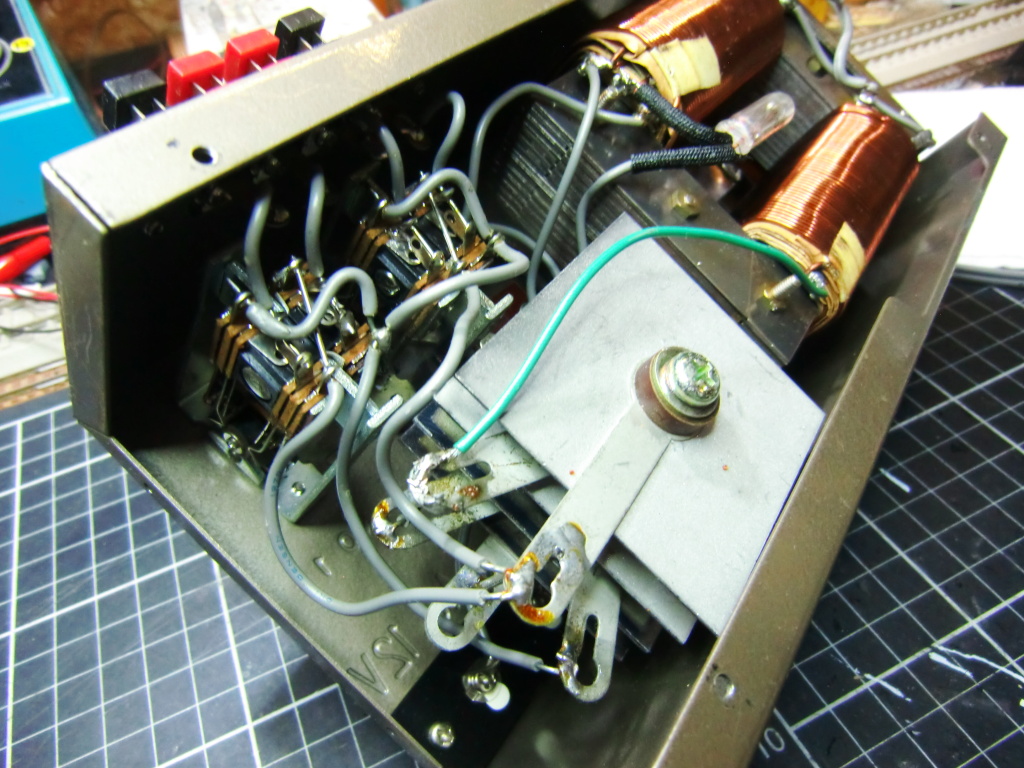
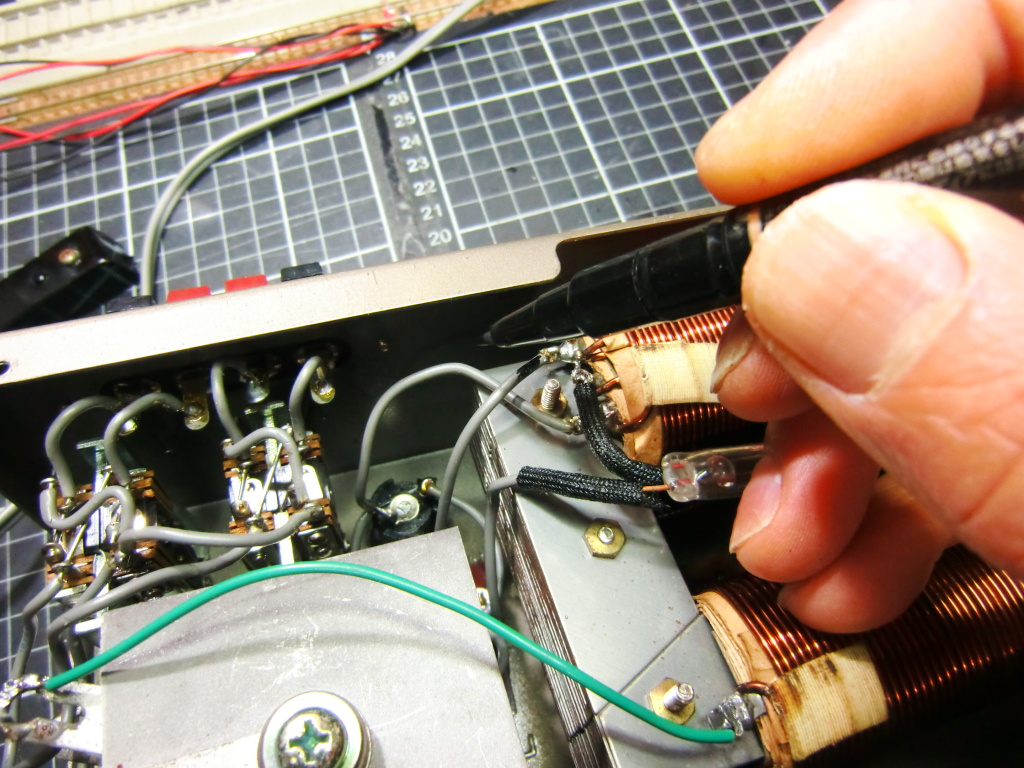
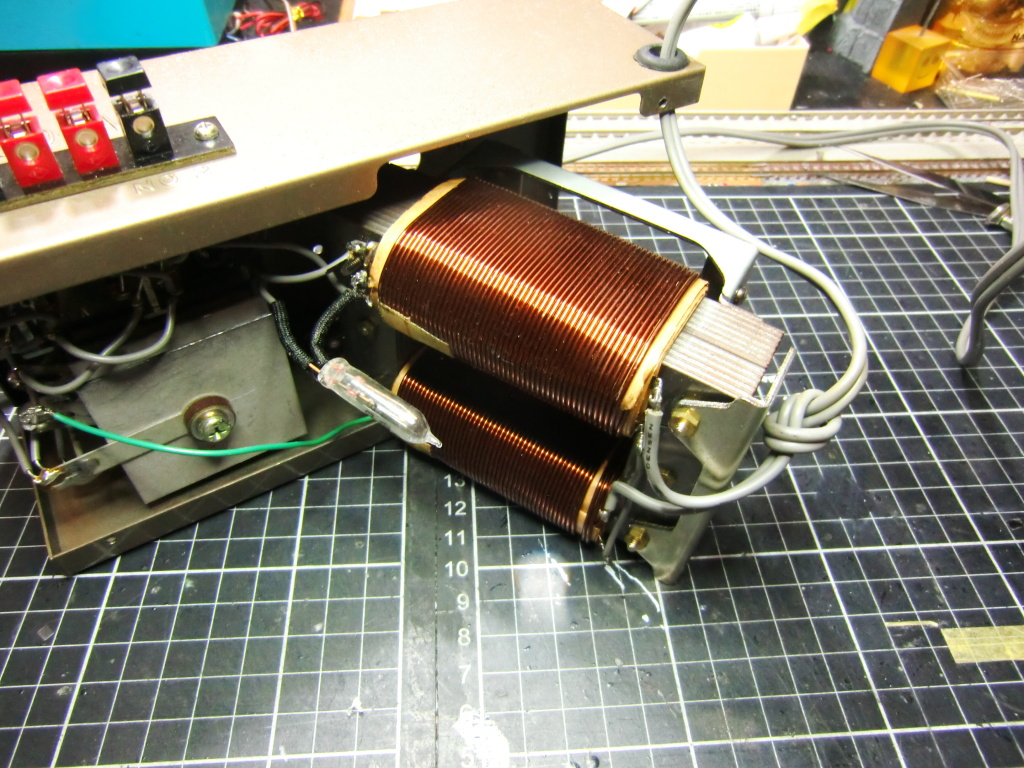

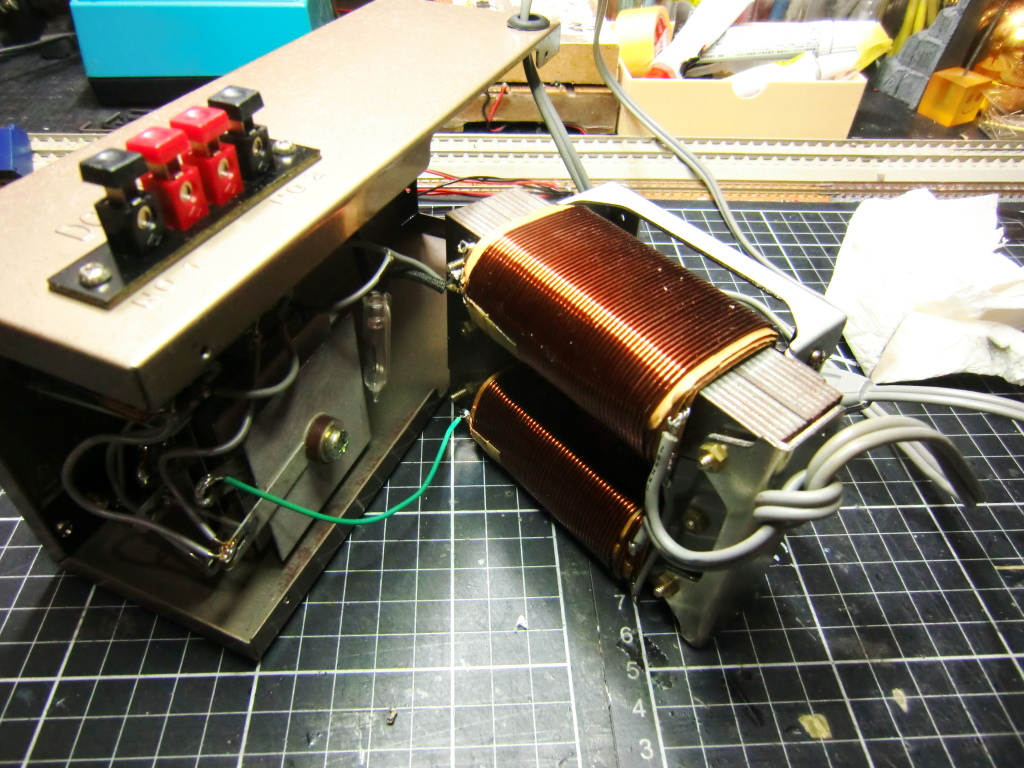
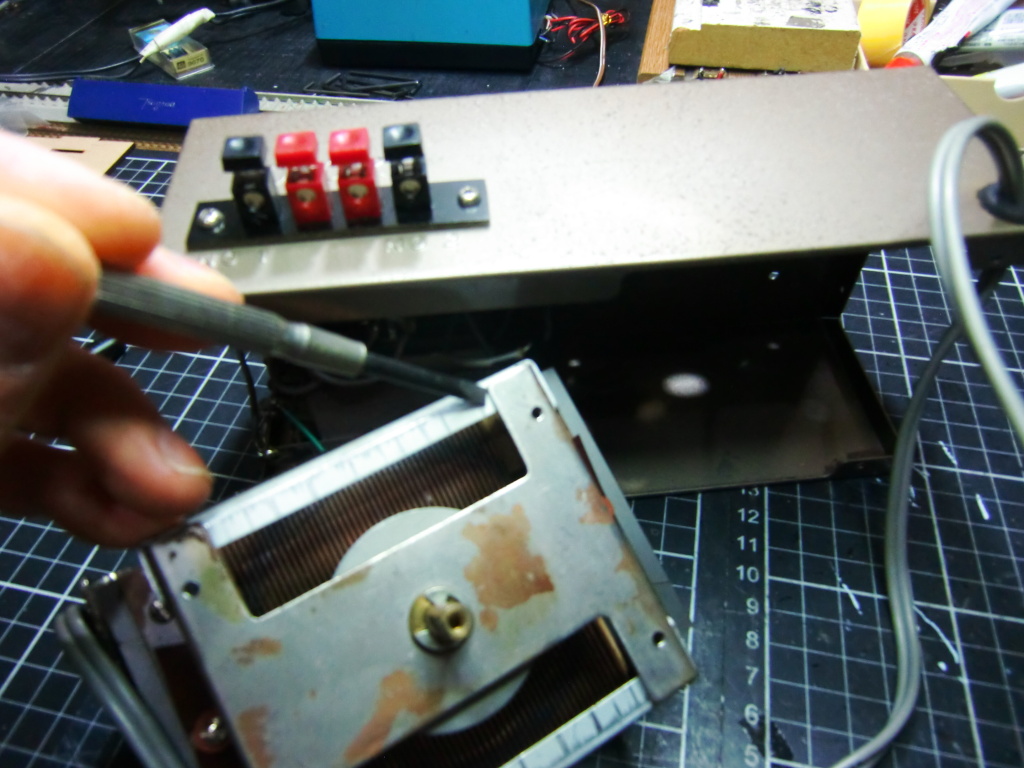
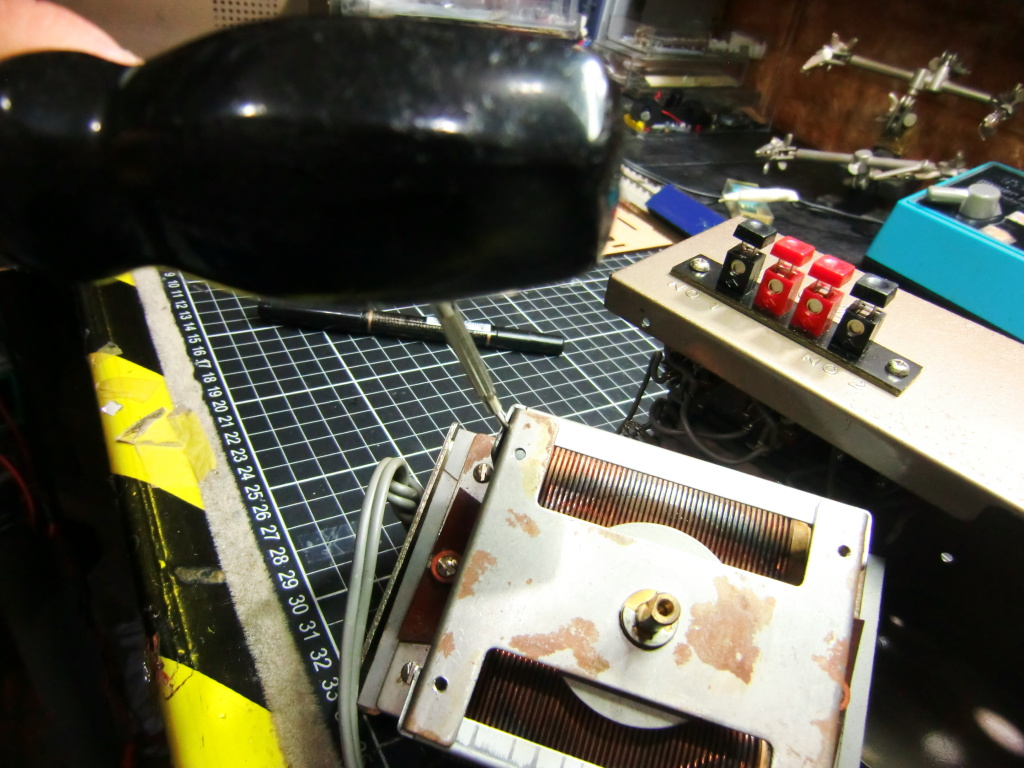

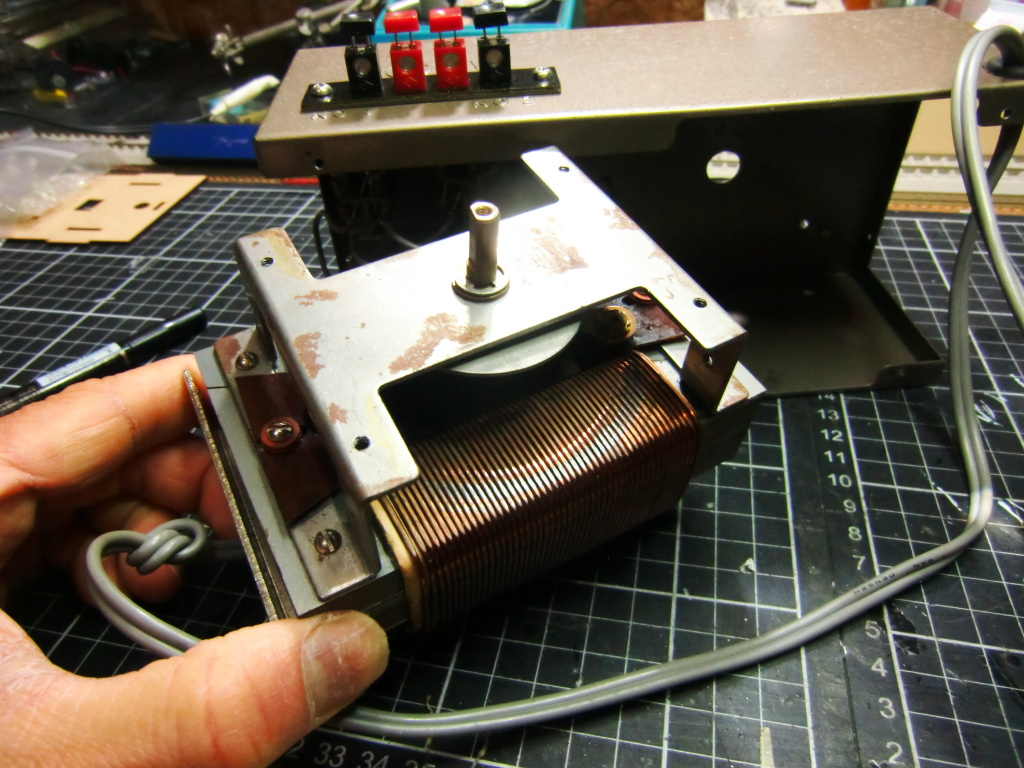
問題があると思われる箇所を見えるところまで分解しました。大変古いものですから、各部が錆びついています。
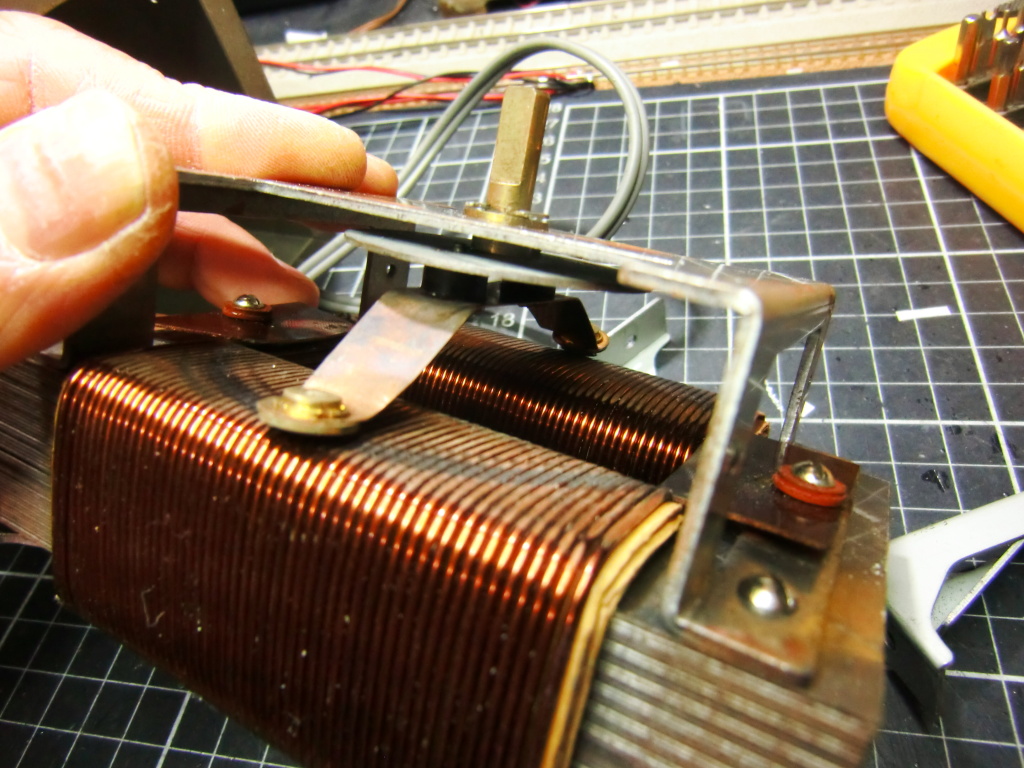
内部を一旦洗浄と研ぎ出しによるさび落とし、各部のパーツの調整と修復作業を行います。
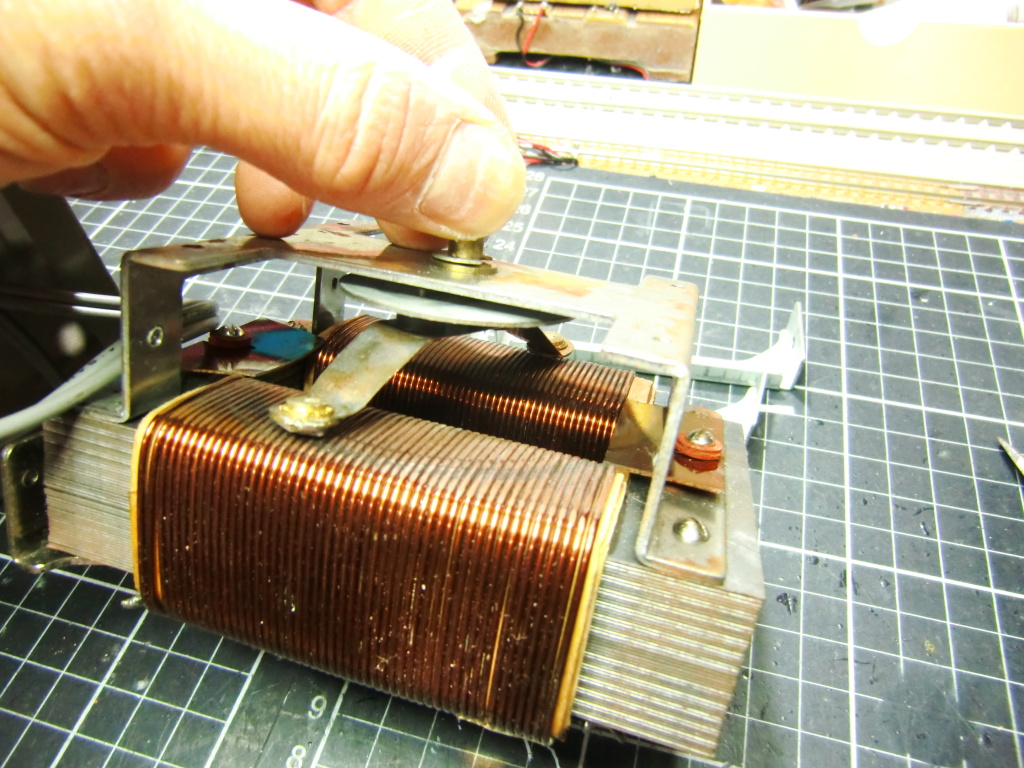
テスターで抵抗値を見ていきます。接点の安定化を施し確認と調整を繰り返して数値が正常になるまで作業します。
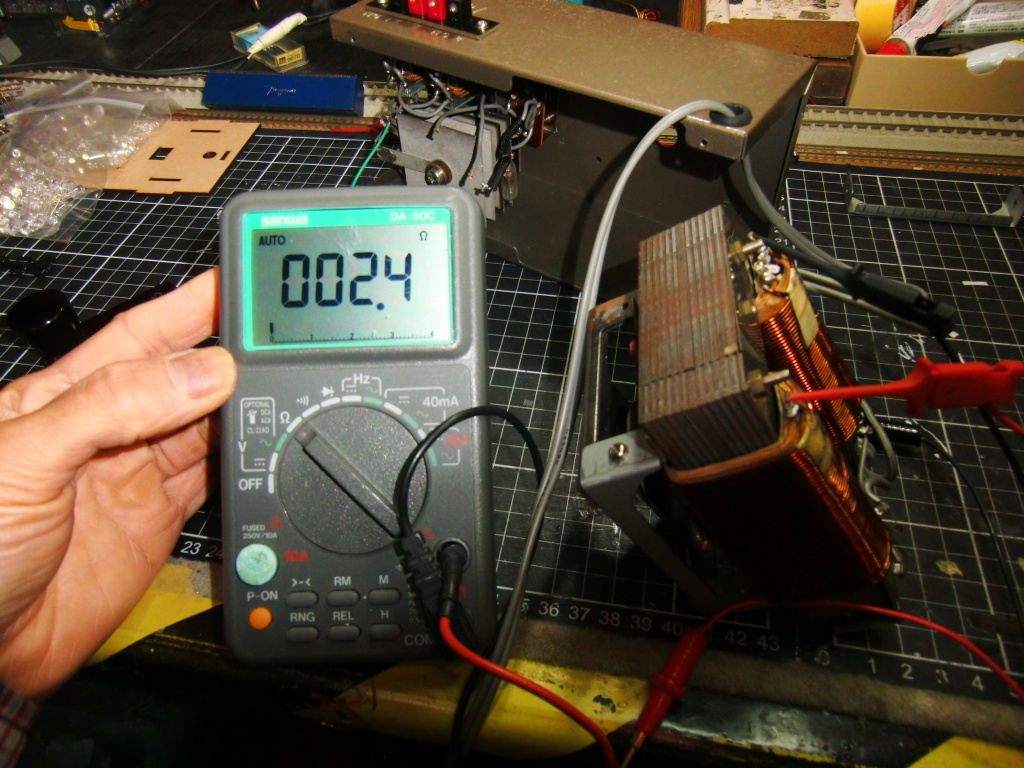

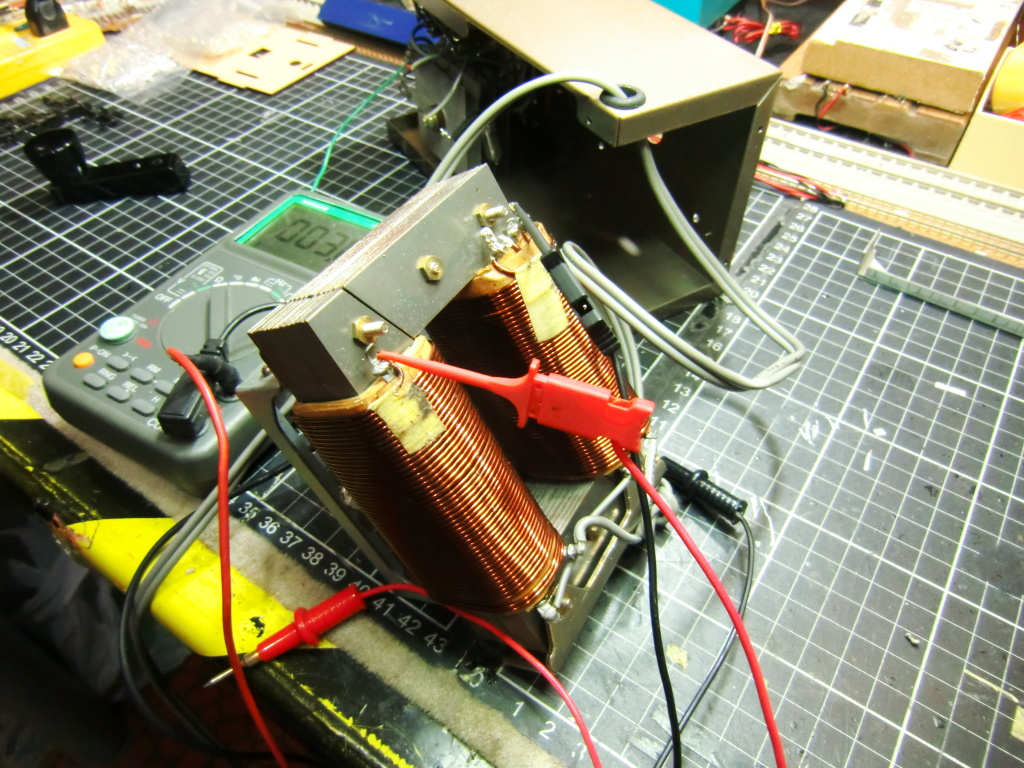

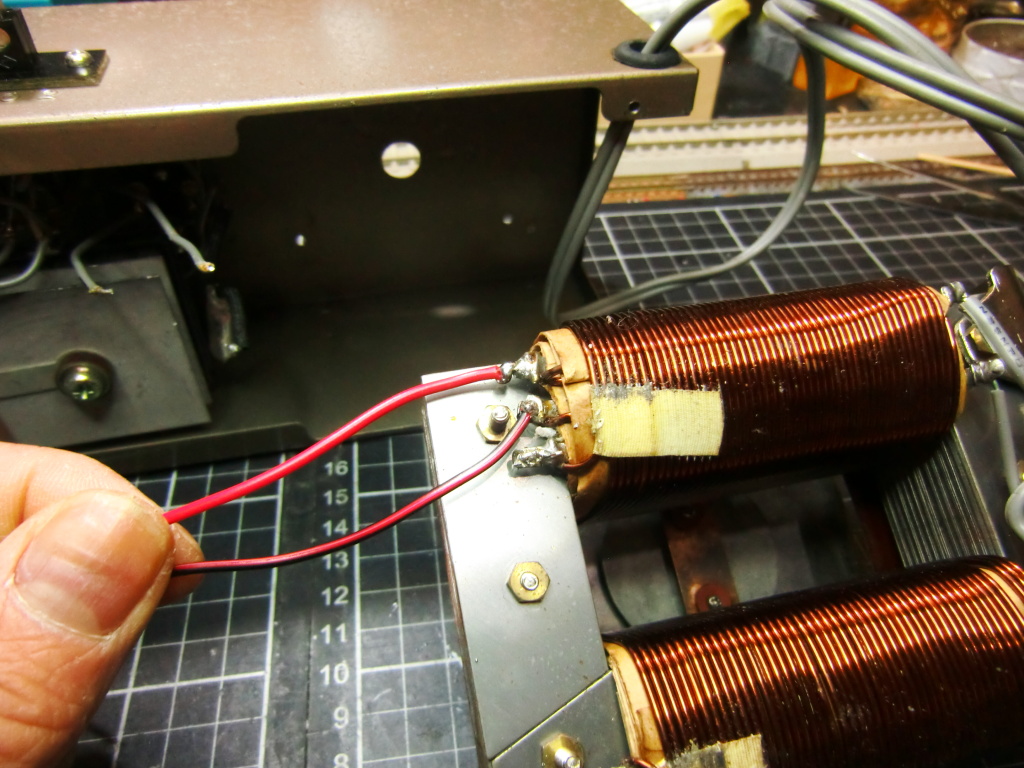
個々の配線を延長して、カバーが開いた状態で各種テストできるようにします。
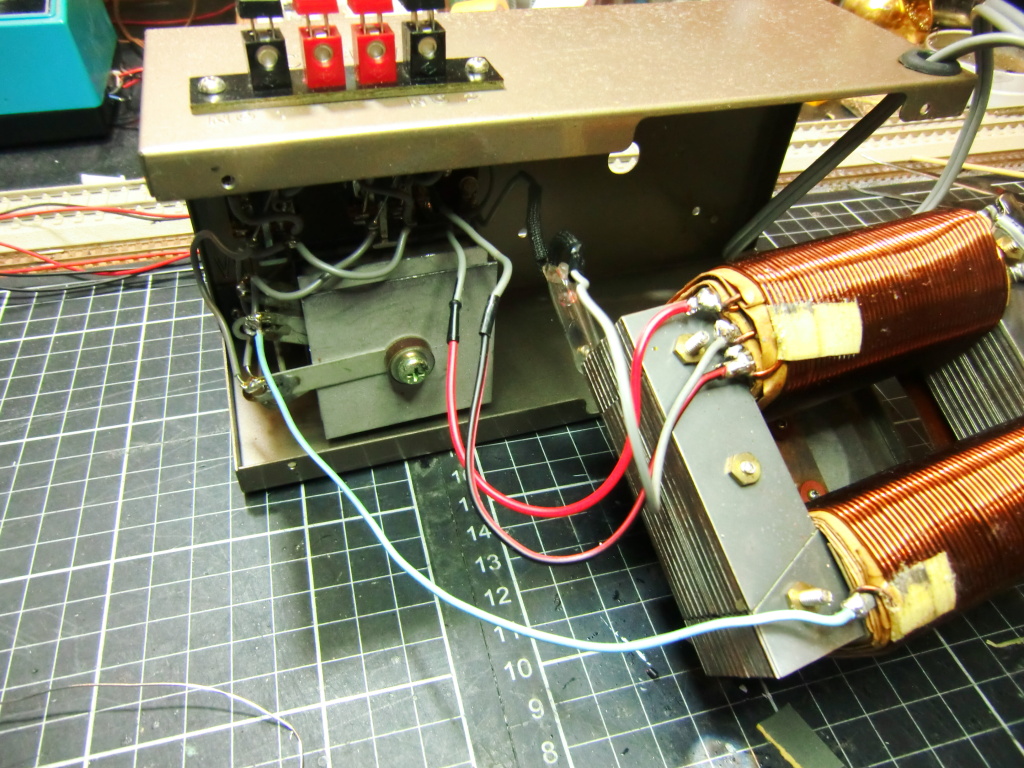
このように配線を延長して各種端子に接続しました。
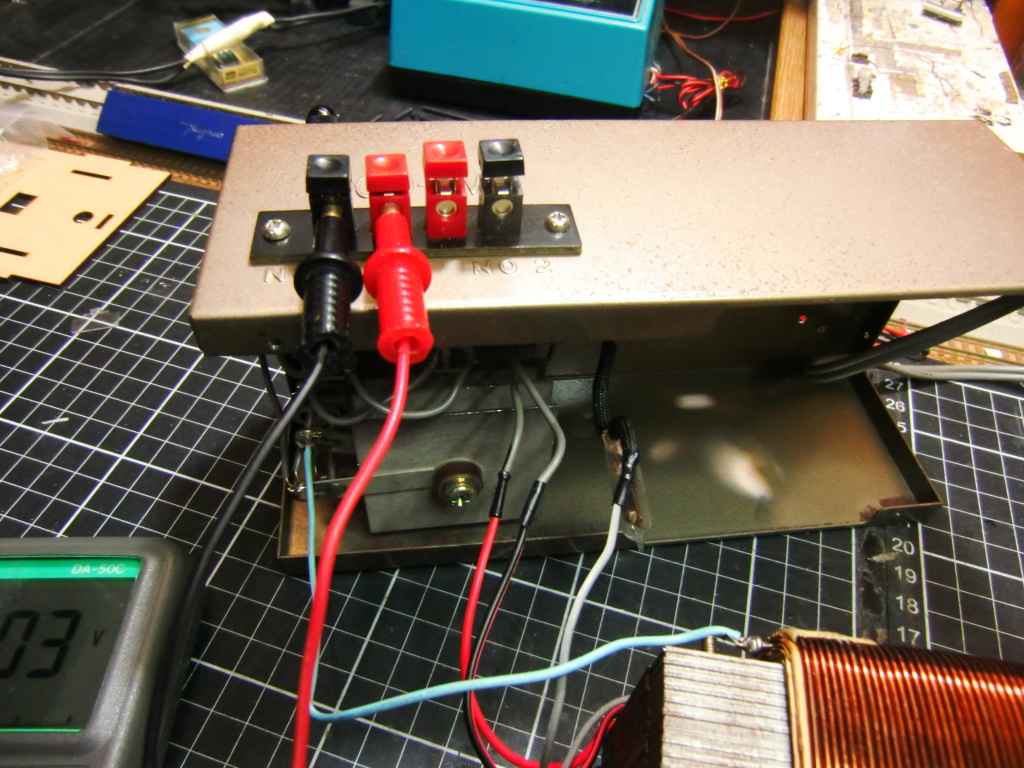
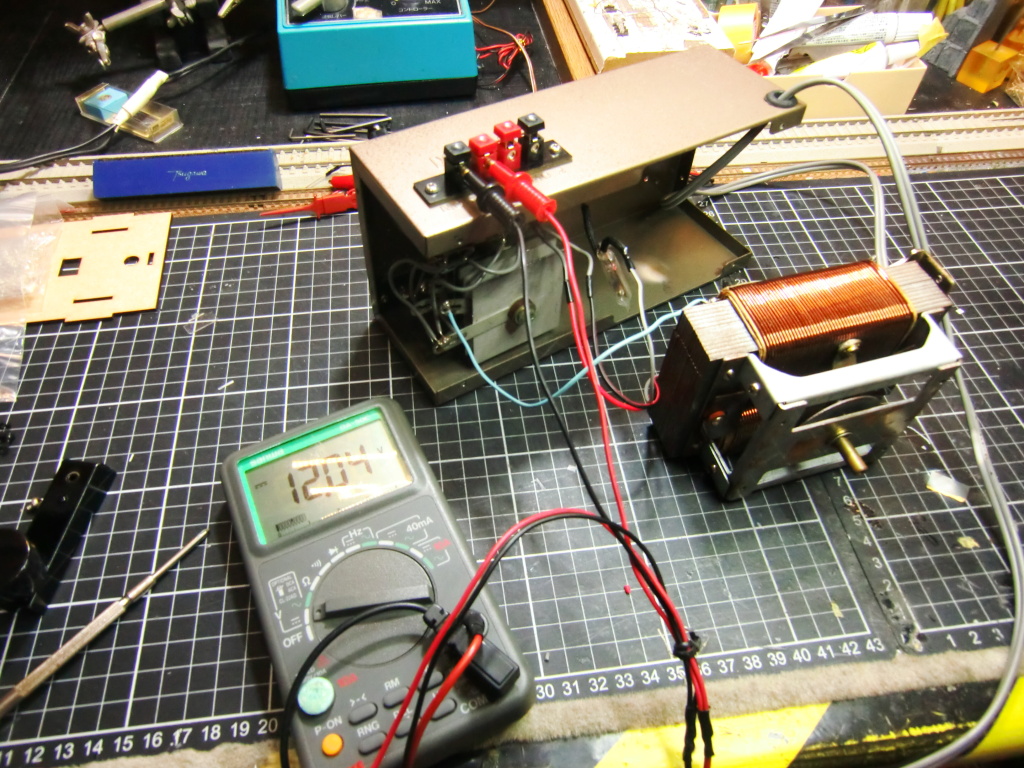
電圧テストを行います。



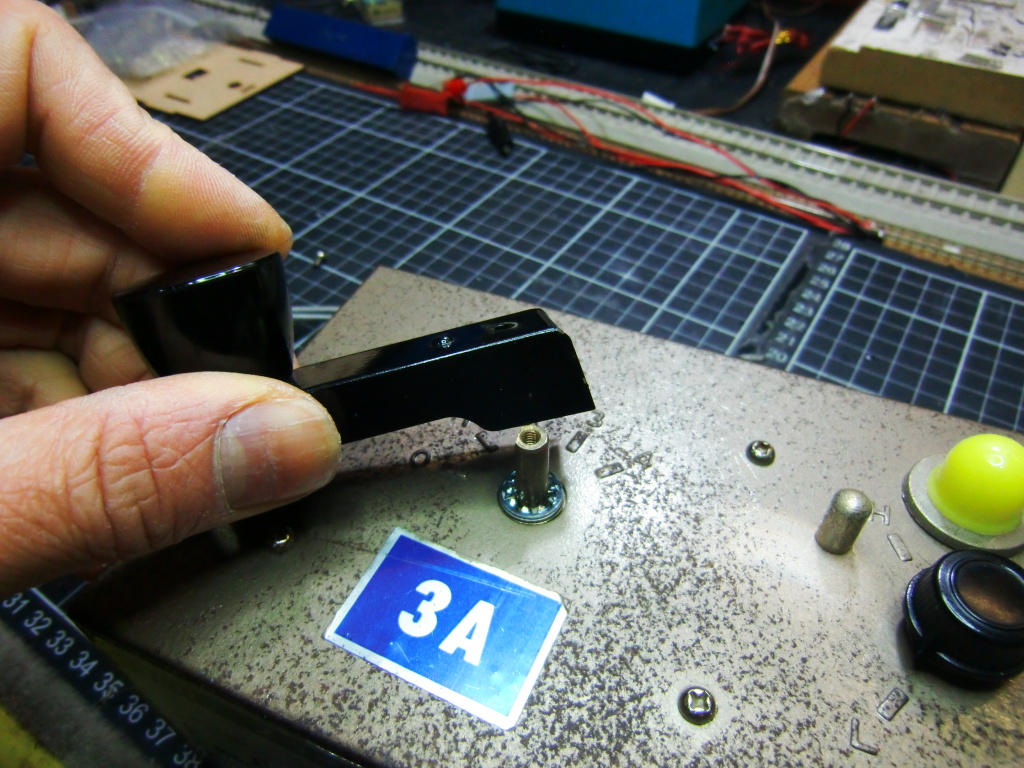

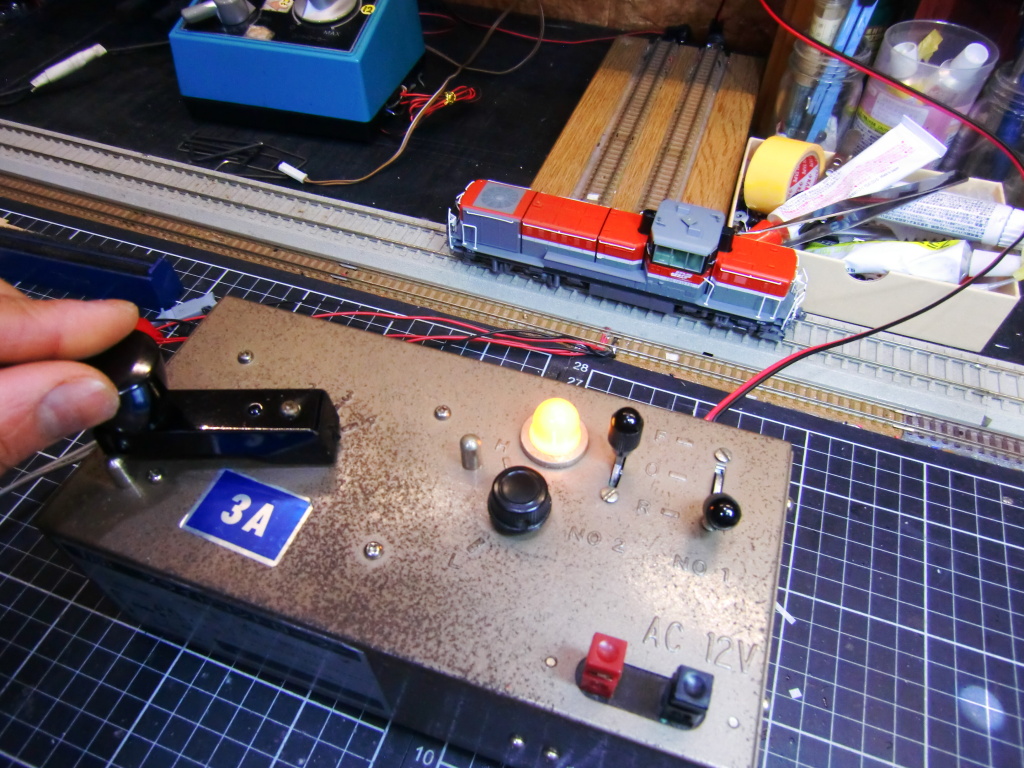

▼動作確認
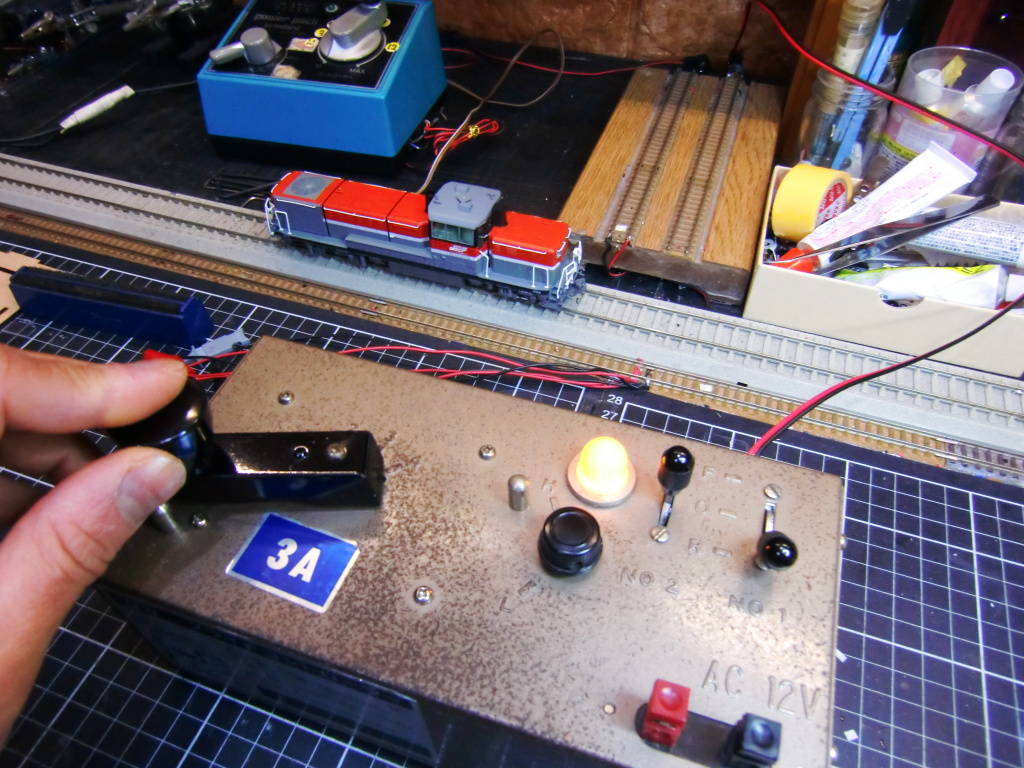
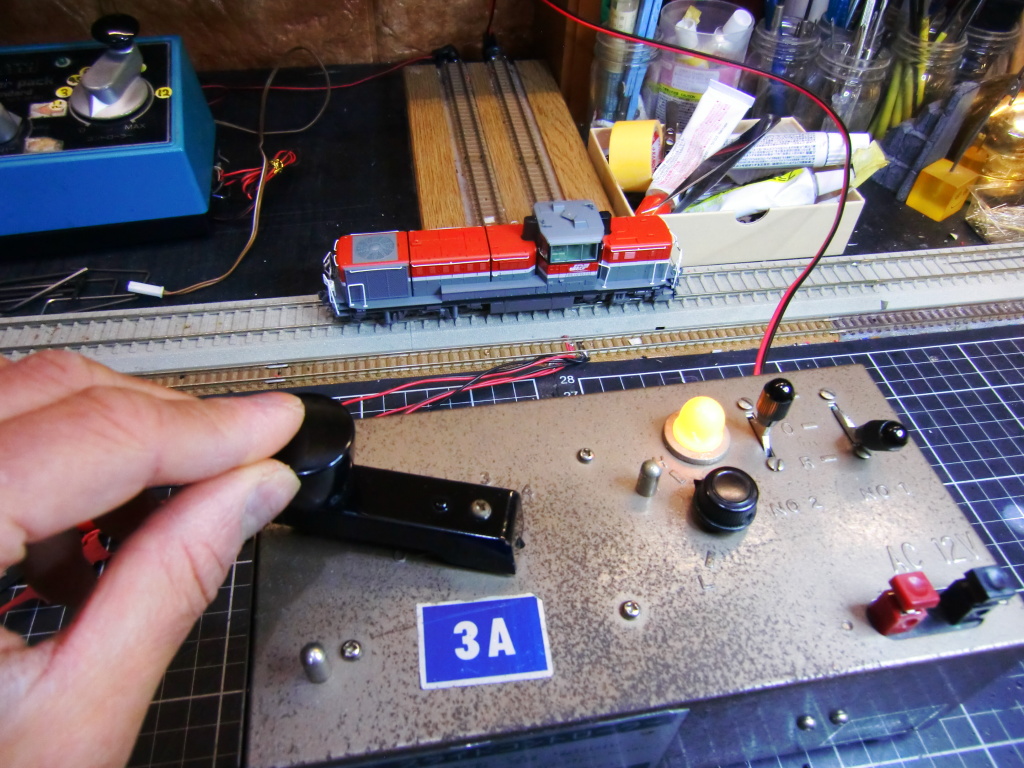
スムーズな電圧変化による安定した走行が可能となりました。
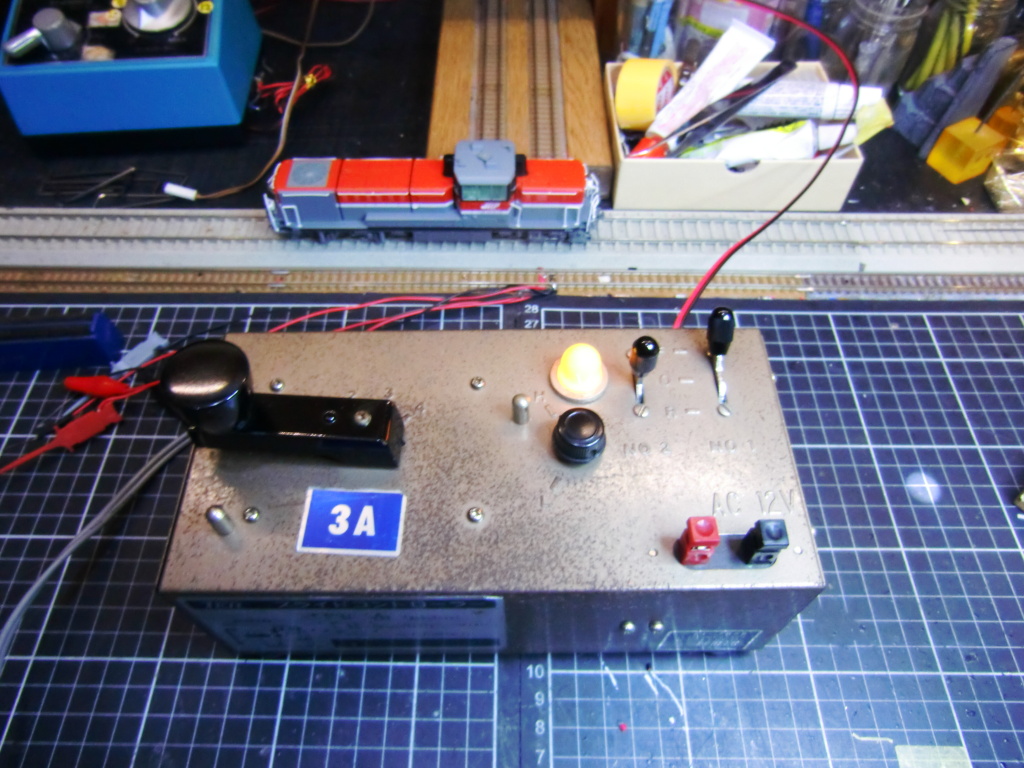
複数回におよぶ動作確認を終えて、作業は無事完了いたしました。最後に本体外装のクリーニングを一通り行いました。
少し数がありますので、コツコツ作業していきます。作業が完了した順に掲載してまいります。
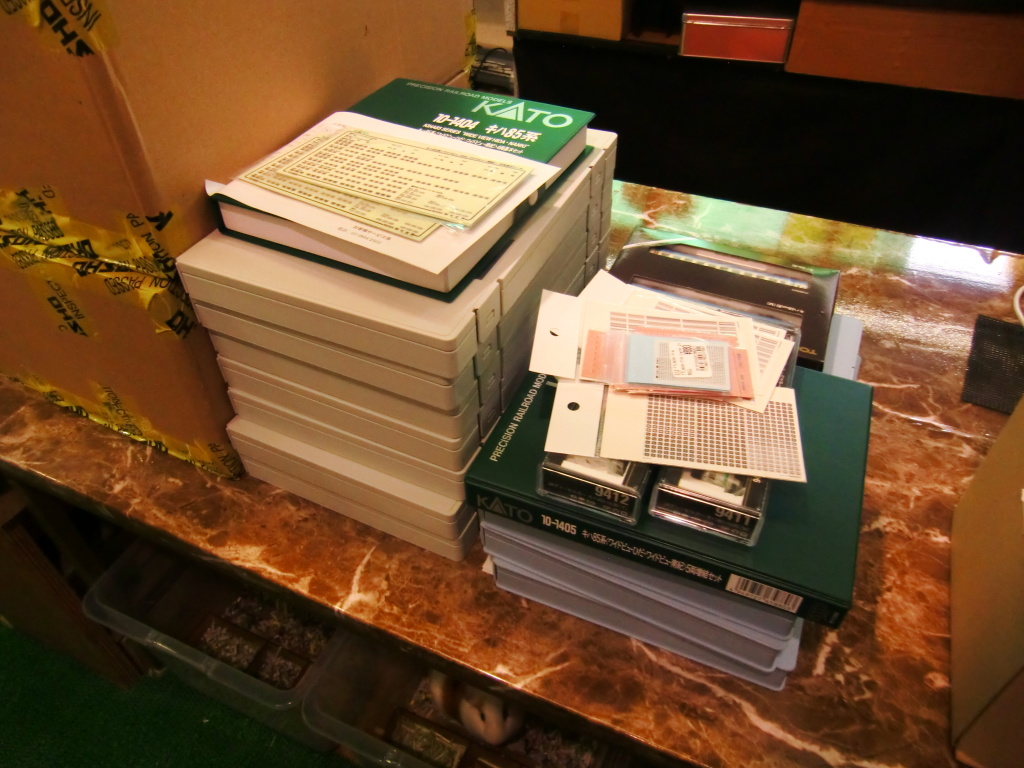
▼マイクロ「西部10000系」TNカプラー+シール貼り
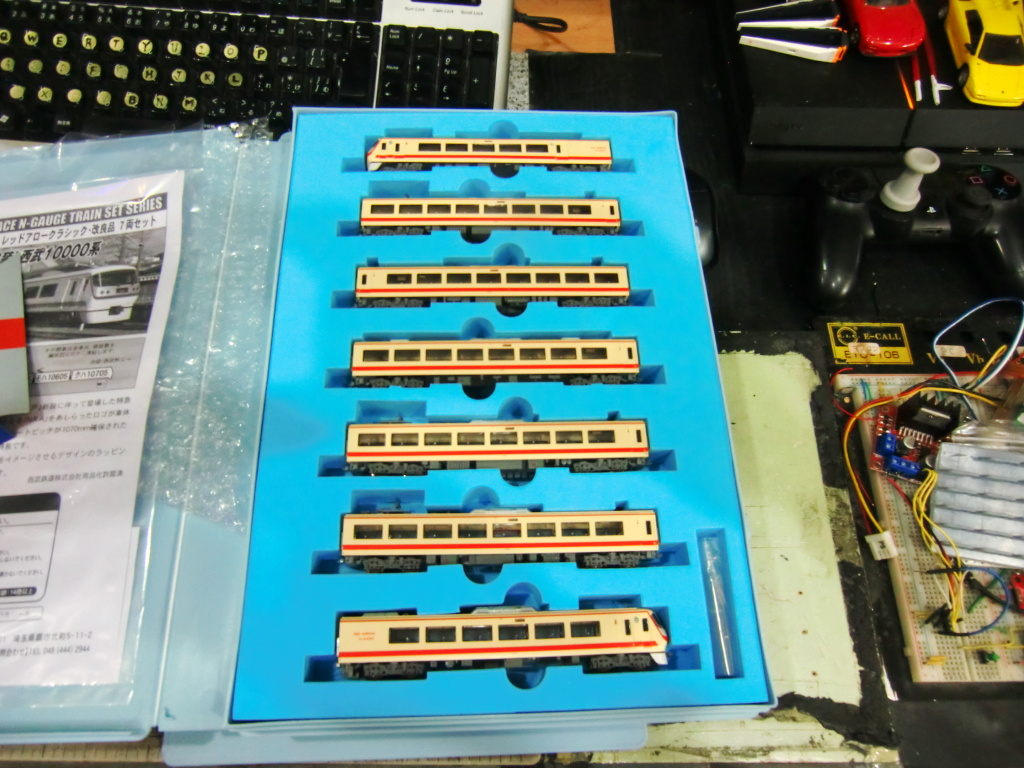
TNカプラー取付け:x12/シール貼り:x16
作業完了
▼マイクロ「キハ140+47 いさぶろう」TNカプラー+シール貼り
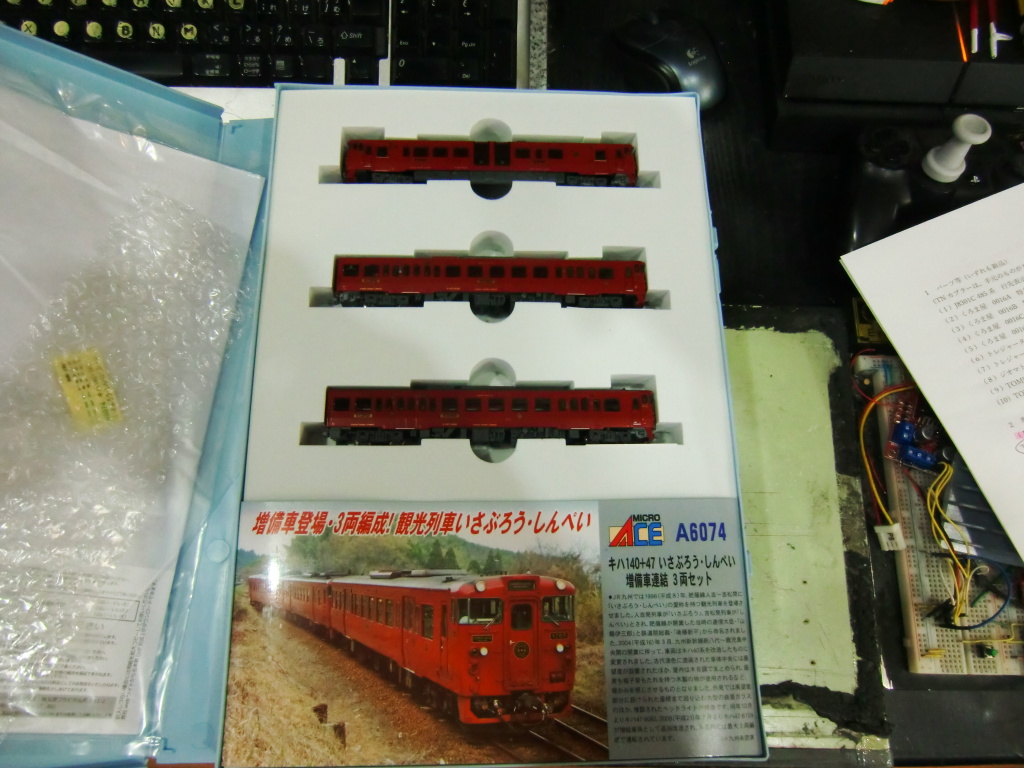
TNカプラー取付け x 4/付属シール貼り x 7
作業完了
▼マイクロ「371系特急あさぎり」TNカプラー+シール貼り

TNカプラー取付け x 12/付属シール貼り x 28
作業完了
▼KATO「キハ85系ワイドビューひだ」シール貼り

シール貼り x 25
作業完了
▼TOMIX「キハ58系急行ディーゼルカー(よしの川)」

パーツ取付け x 4/上級パーツ x 2/台パーツ x 1/インレタ貼り x 4
作業完了
▼TOMIX「キハ40 1700型 M+T」

パーツ取付け x 12/上級パーツ x 8/台パーツ x 4/インレタ貼り x 4/インレタ貼り前面 x 6
作業完了
▼TOMIX「485系しらさぎ新塗装 A+B+C」

パーツ取付け x 27/パーツ取付けB x 17/上級パーツ x 7/台パーツ x 6/インレタ x 34/他シール x 30/他インレタ x 136
作業完了
▼TOMIX「485系しらさぎ A+B」

パーツ取付け x 14/パーツ取付けB x 10/上級パーツ x 4/台パーツ x 4/インレタ x 20/他シール x 20/他インレタ x 80
作業完了
▼TOMIX「583系N1・N2編成」

パーツ取付け x 8/パーツ取付けB x 12/上級パーツ x 4/台パーツ x 4/他シール x 28/他インレタ x 96
作業完了
これですべての作業が完了いたしました。
過去にも何度か修理のご依頼のございました「KATO旧製品ロマンスカー(ドローバー)」の折れによる修理でございます。
既に発売から20年を超えている製品ということもありまして、経年により折れやすくなっています。

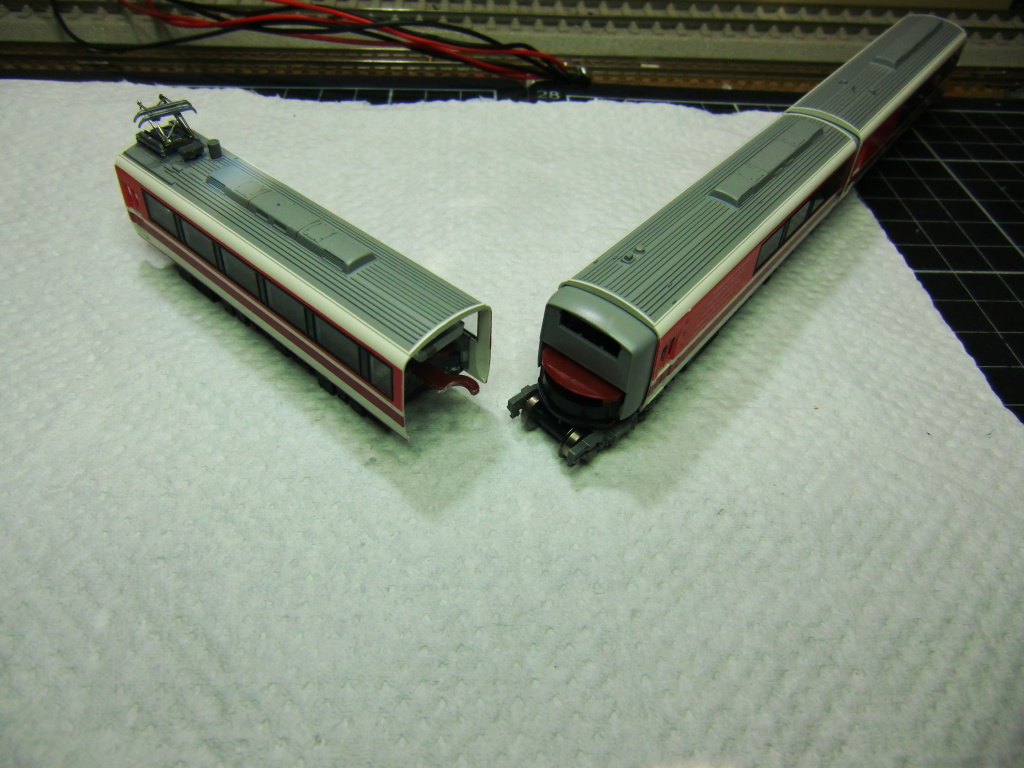
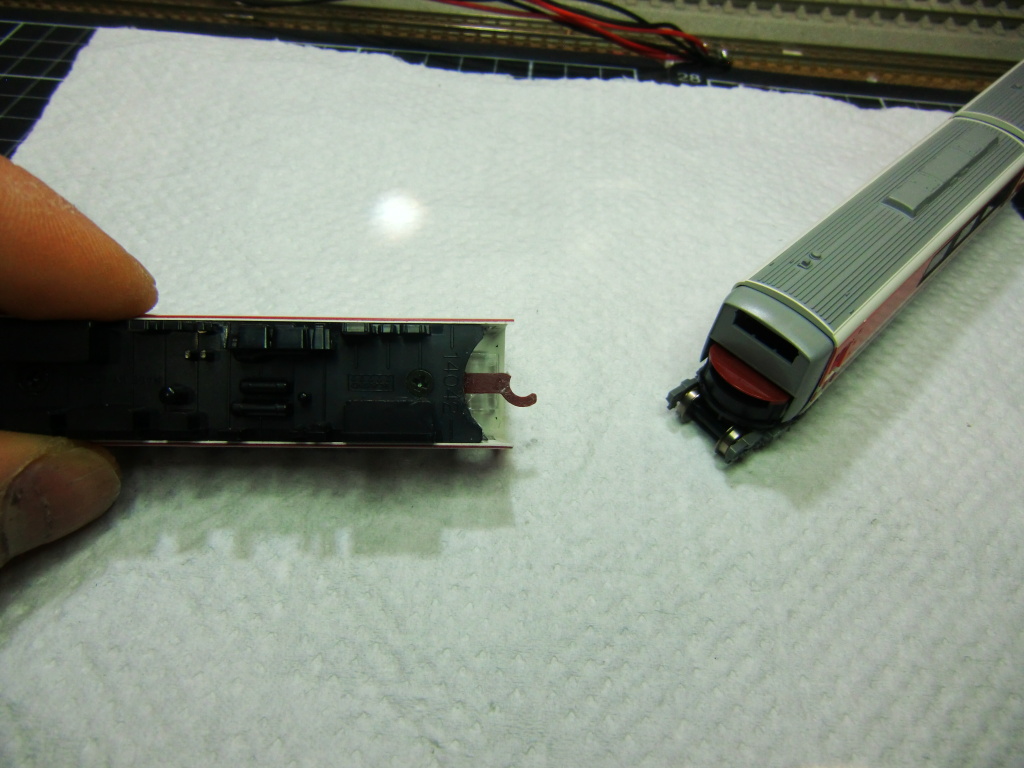
このように折れてしまっています。折れたパーツが残っていれば接着剤でくっつければ良いのでは?と思われるかもしれませんが、場所によります。また、接着面がある程度確保できないと接着自体難しく、毎回負荷のかかる箇所ではまた折れます。

他の箇所も問題なく見えても既にプラがもろく折れやすい状態となっていると思われます。
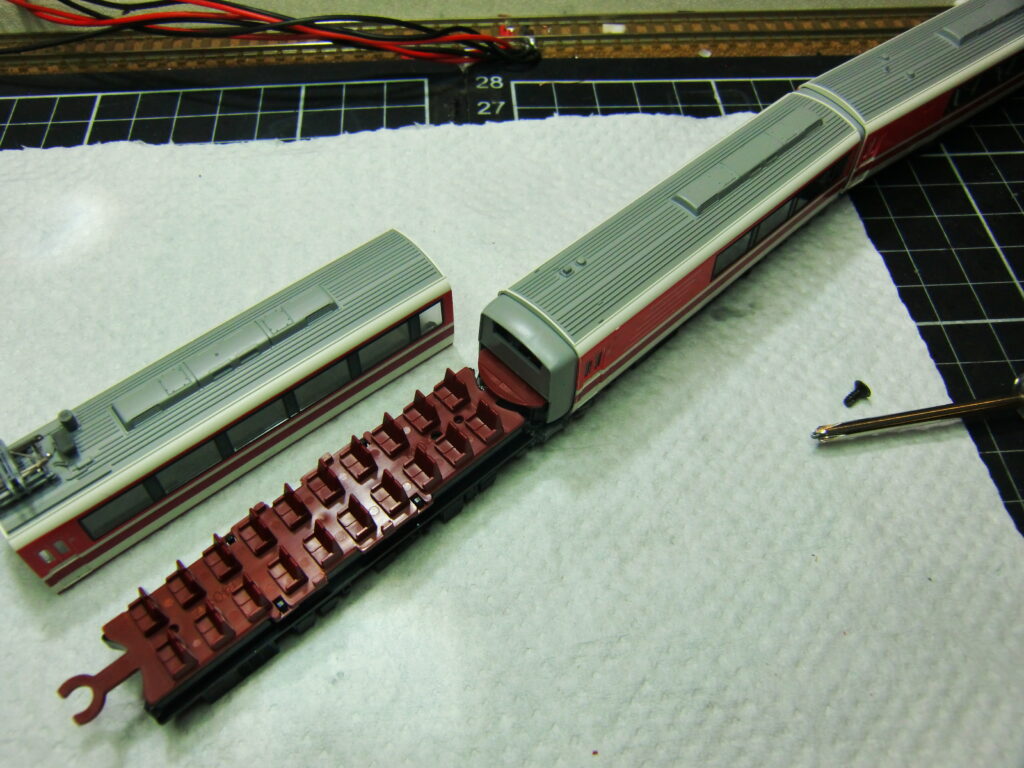
この車体の修復の難しいところは、上記のように車体同士が密着している点です。多少スペースに余裕があれば差込パーツなどを制作してはめ込むこともできますが、そのようなスペースはありません。また、上下の隙間もほとんどありませんので、板状の補強材を入れることもできません。
そこで、今回の修理ではドローバーを根元からカットしてドローバー自体を新規に制作します。
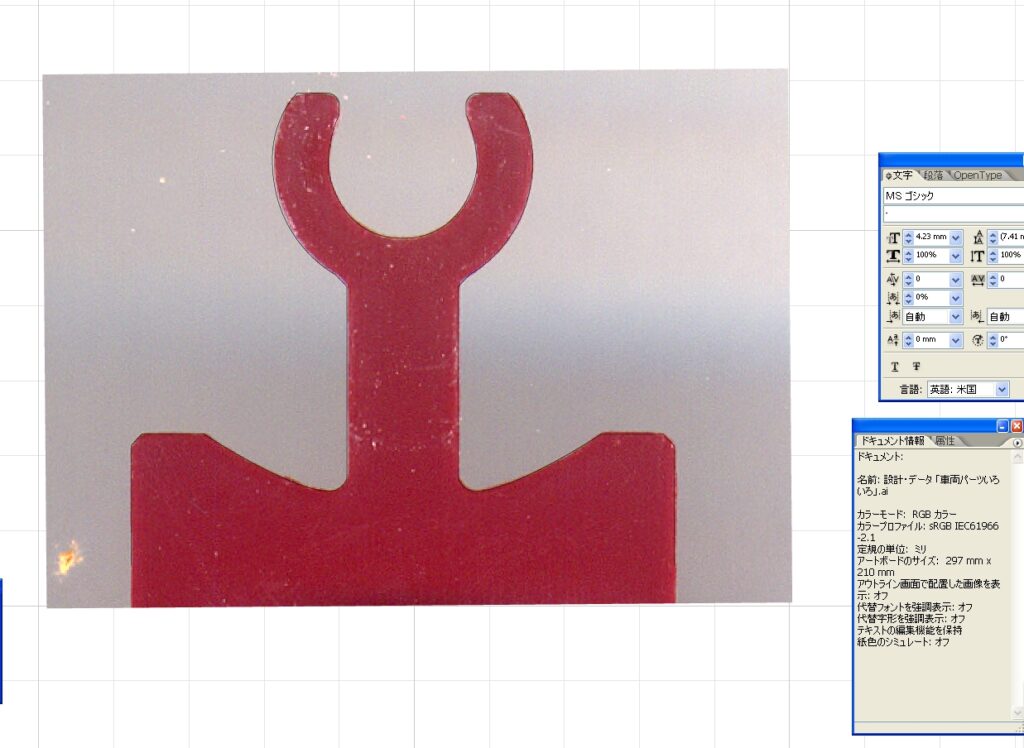
まずは、ドローバーをスキャンしてPCに取り込みます。ここから寸法を出していきます。
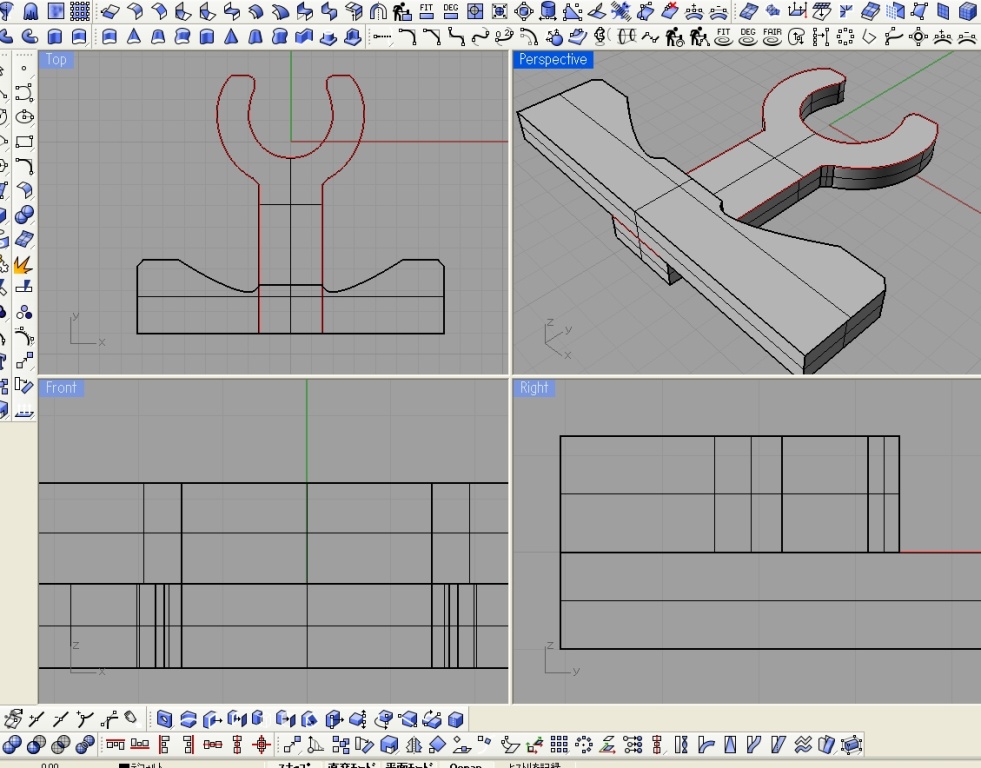
車体に合うようにデータを制作して3Dプリンターで出力します。
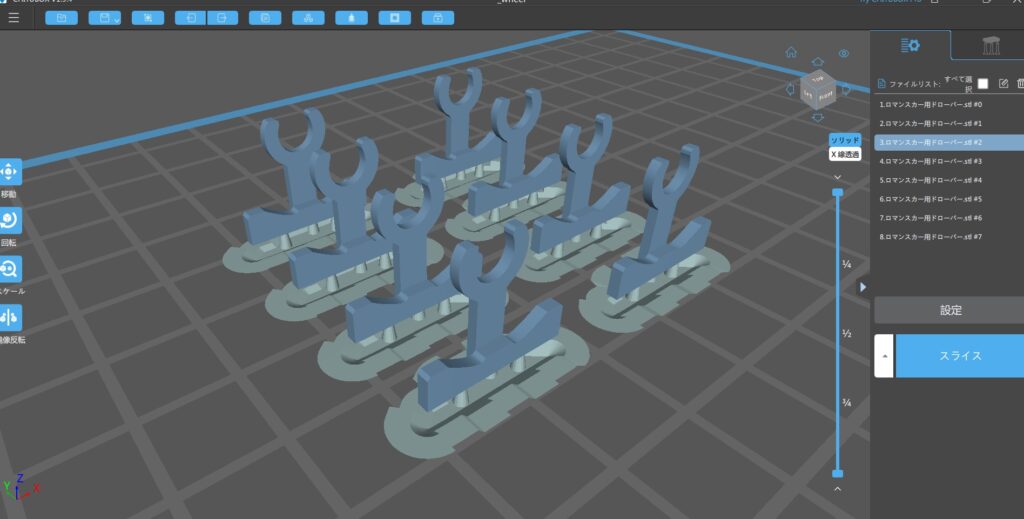
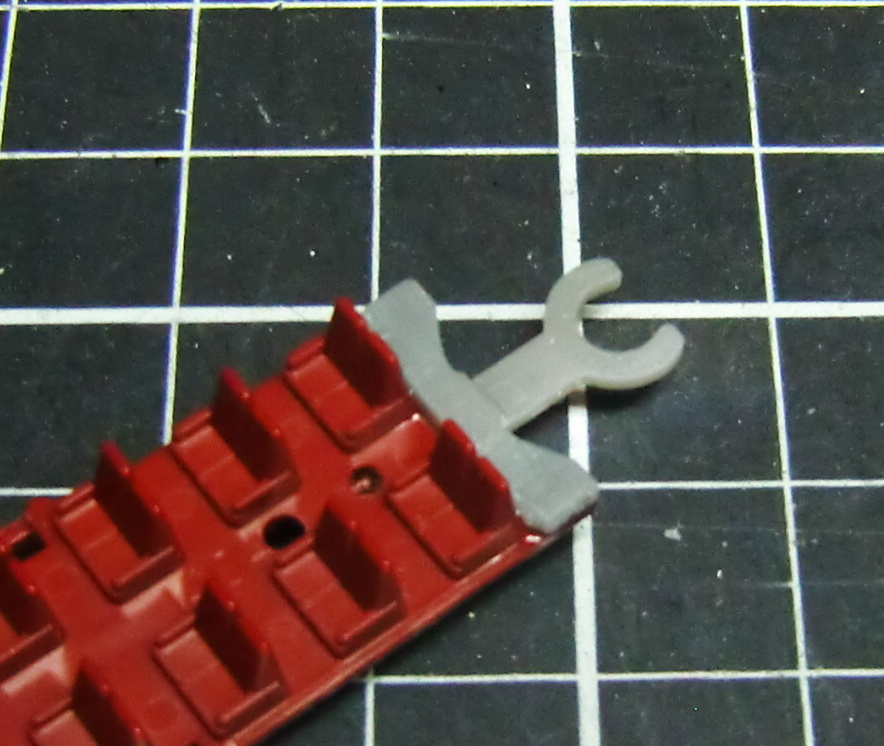
イスとの間に1.5mm程度の隙間をあける必要があります。

床板を上記のように若干カットしてドローバーが入るようにします。
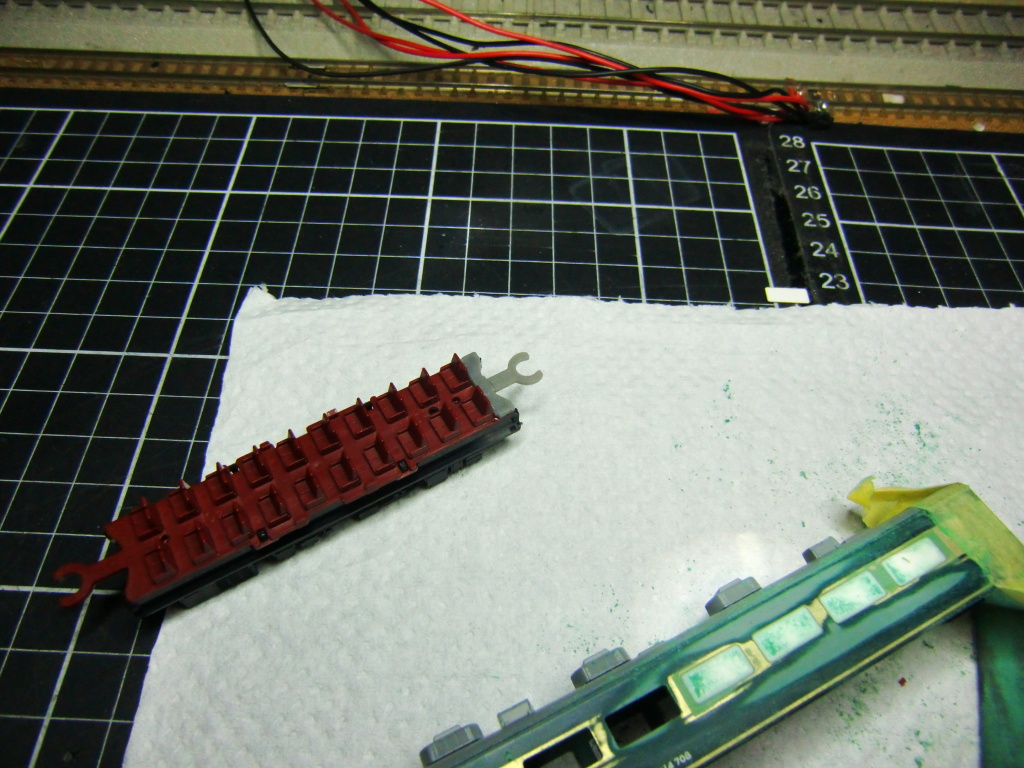

「ABS LIKEレジン」を使用しておりますので、連結部などのパーツ制作には適した素材と言えます。

無事に作業完了でございます。


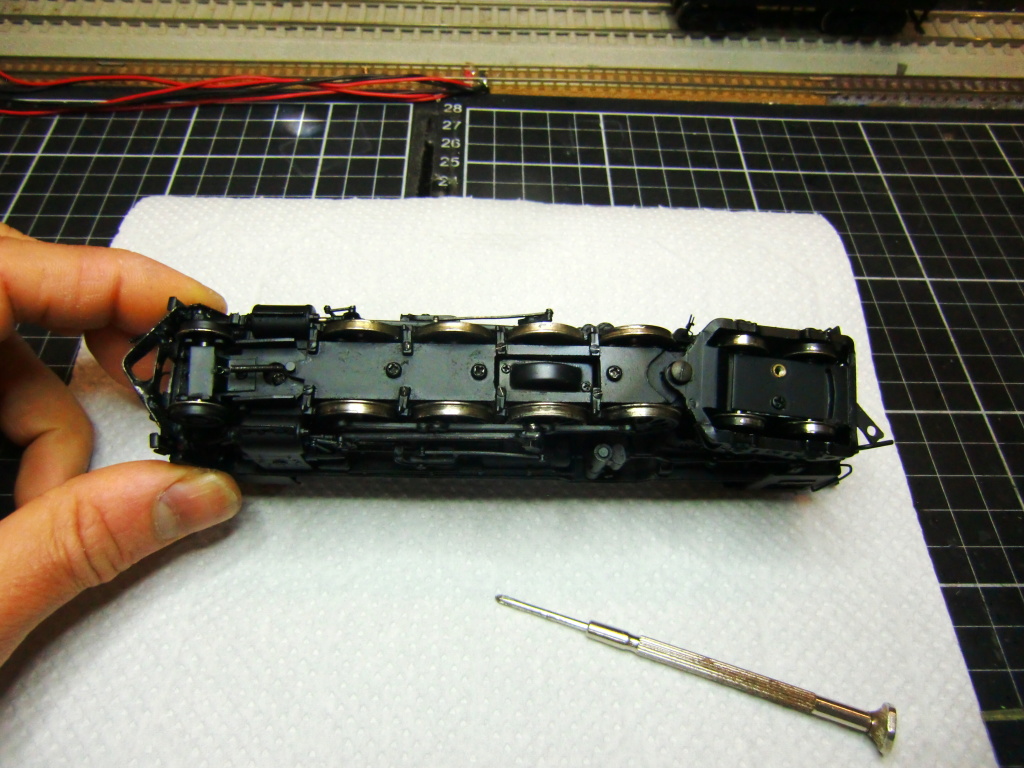

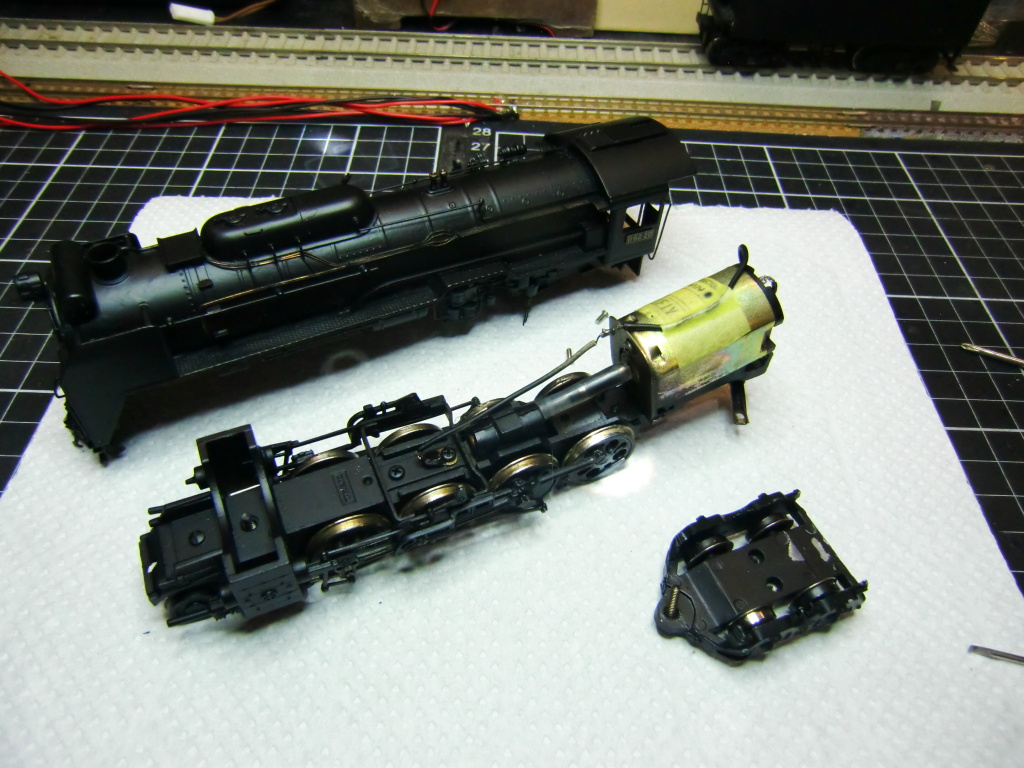
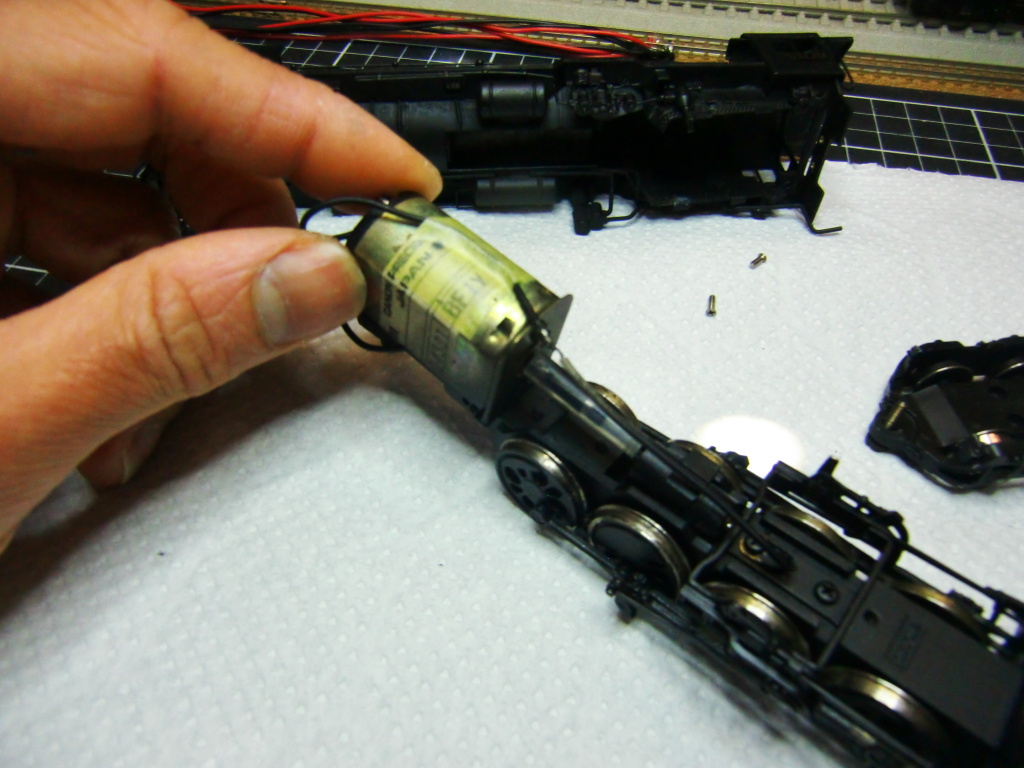



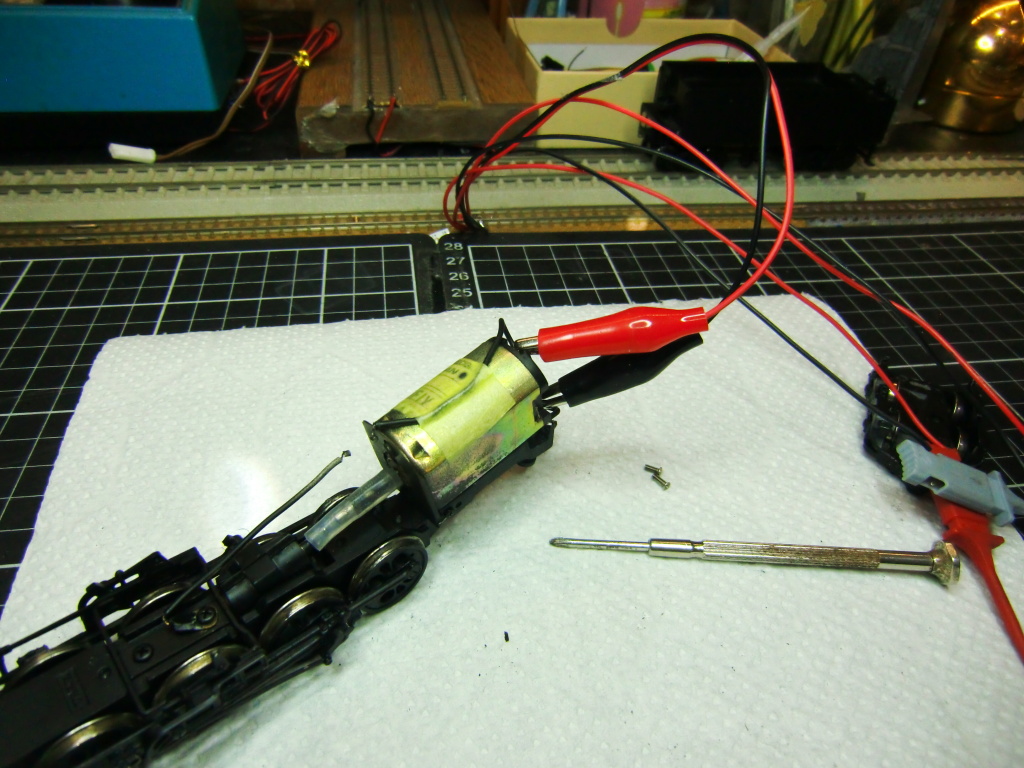
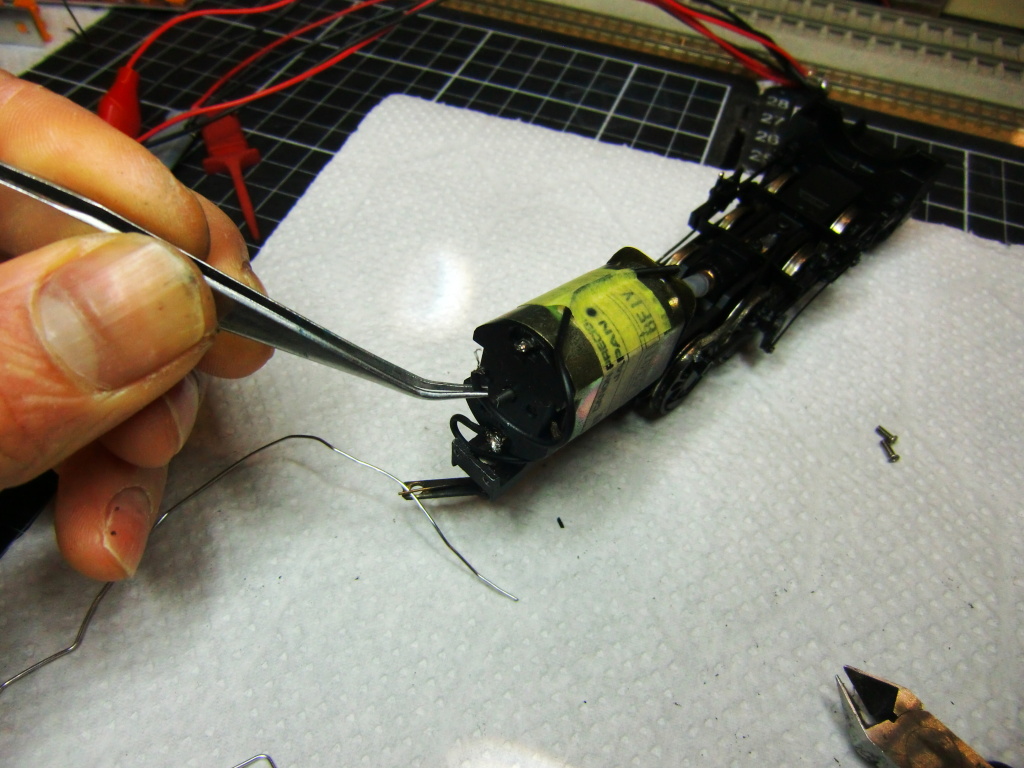



ヘッドライトにドリルで穴をあけ、チップLEDを埋め込み配線を内部に通しておきます。

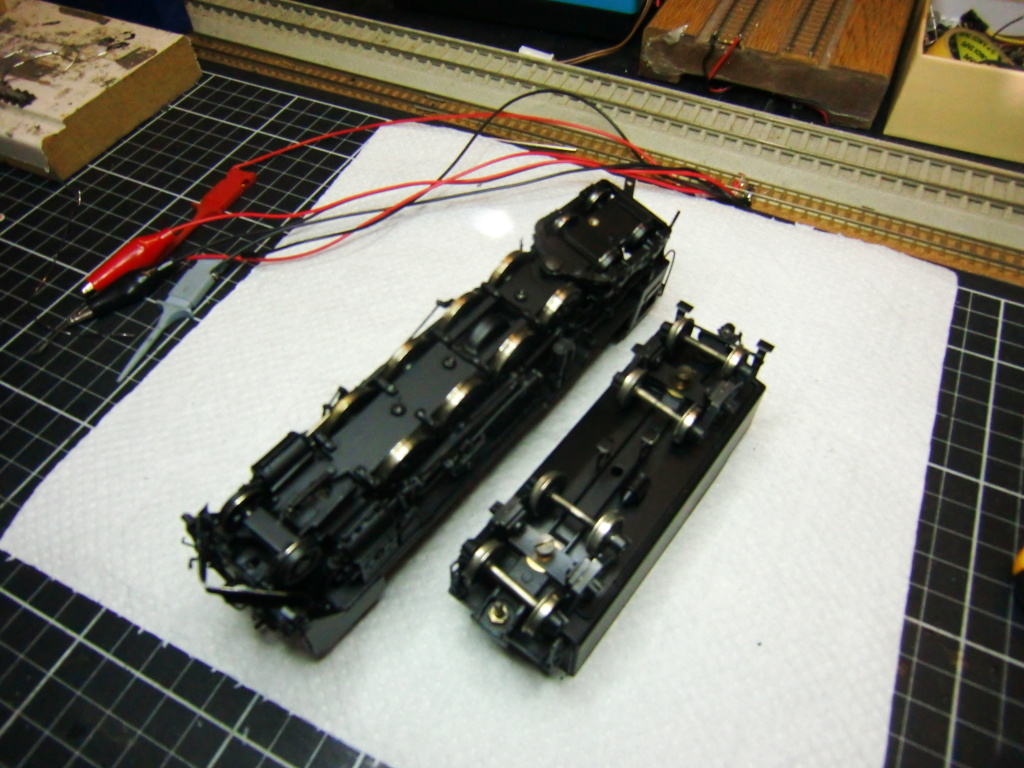
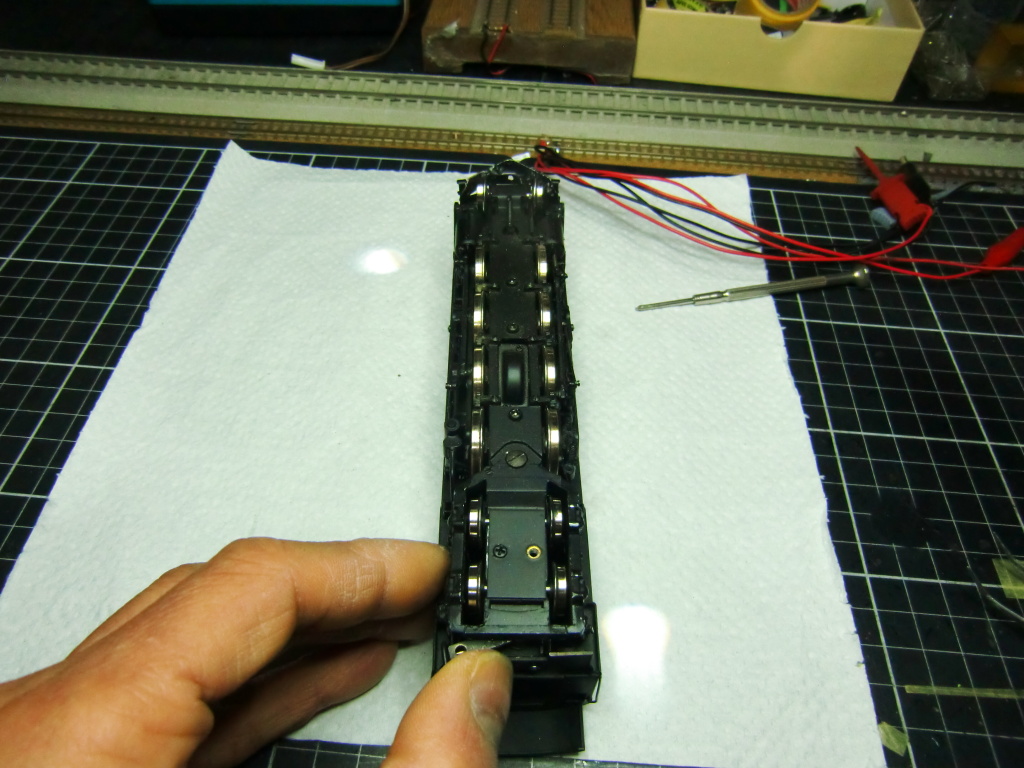
テンダーはもちろん、機関車の車輪もピカピカに磨きだします。



調整と確認を返しながら、スムーズな走行が確認できるまで各部の調整を繰り返します。



ヘッドライトの点灯化改造も終わり、一通り動作に問題ないことを確認しました。作業完了でございます。


まずは車体の分解作業からです。塗装に際して外せるものはすべて外します。


ナンバープレート、窓ガラス、ヘッドライト、手すり、その他、細かな部品を内側から慎重に1つ1つ押し出して外していきます。
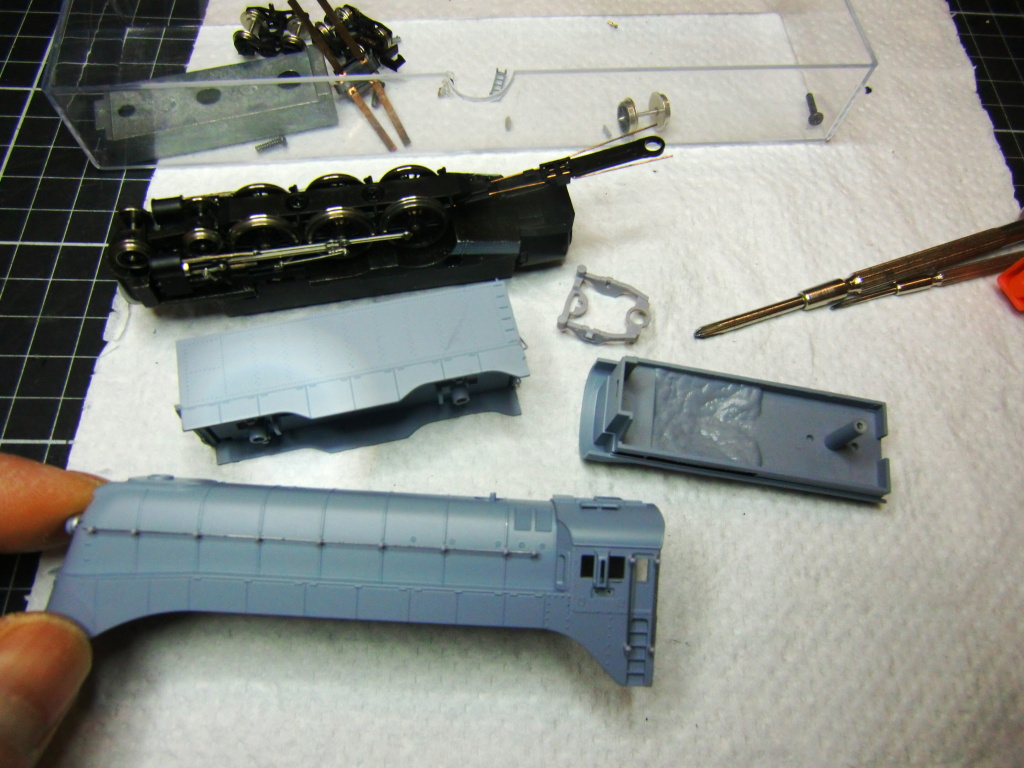
ようやくここまで外せました。側面の棒状のパーツは内面から溶かしして部品が固定されているため、少々塗装はしにくいのですがこのまま作業することにします。
集めた数少ない資料写真を頭にいれながら作業手順を考えていきます。

車体の洗浄をしっかりと行って乾燥後にプライマーを吹き付けます。

今回の塗装にあたっては、この2色を基本色として塗装を行っていきます。
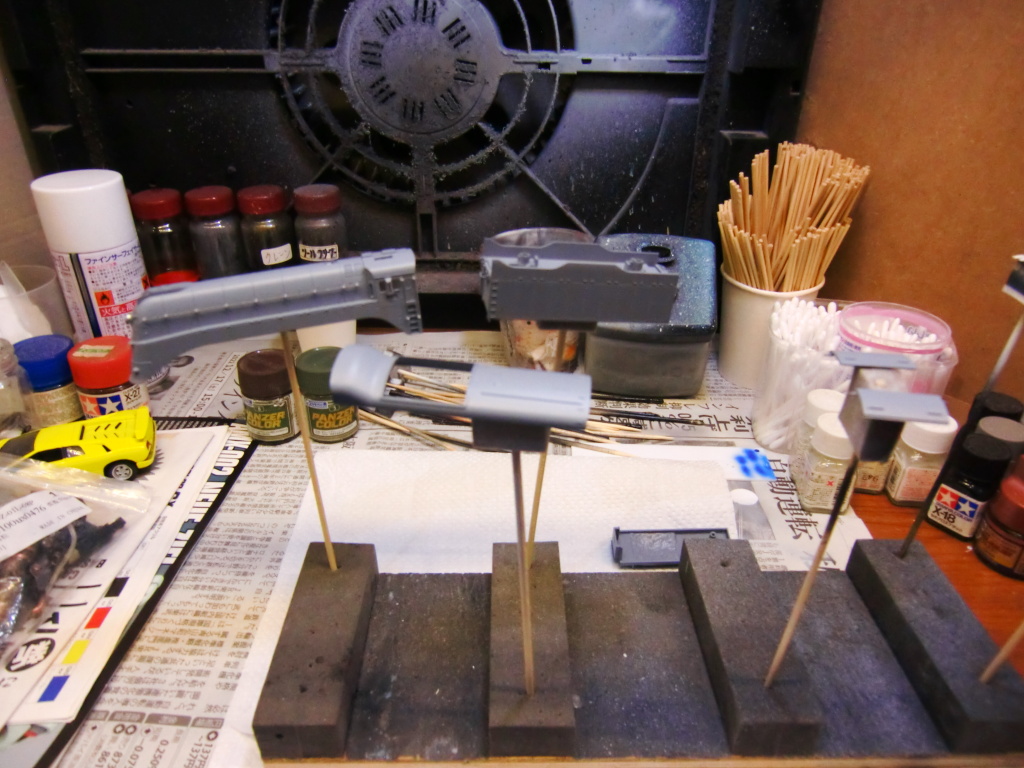
テンダー石炭開閉部の表裏も塗装するので、下塗りをしっかり行っておきます。

下塗りのプライマーサーフェイサーを吹き終わりました。



写真では光の関係で緑が濃く見えますが、実際にはもう少し薄い感じで落ち着いた感じの緑です。
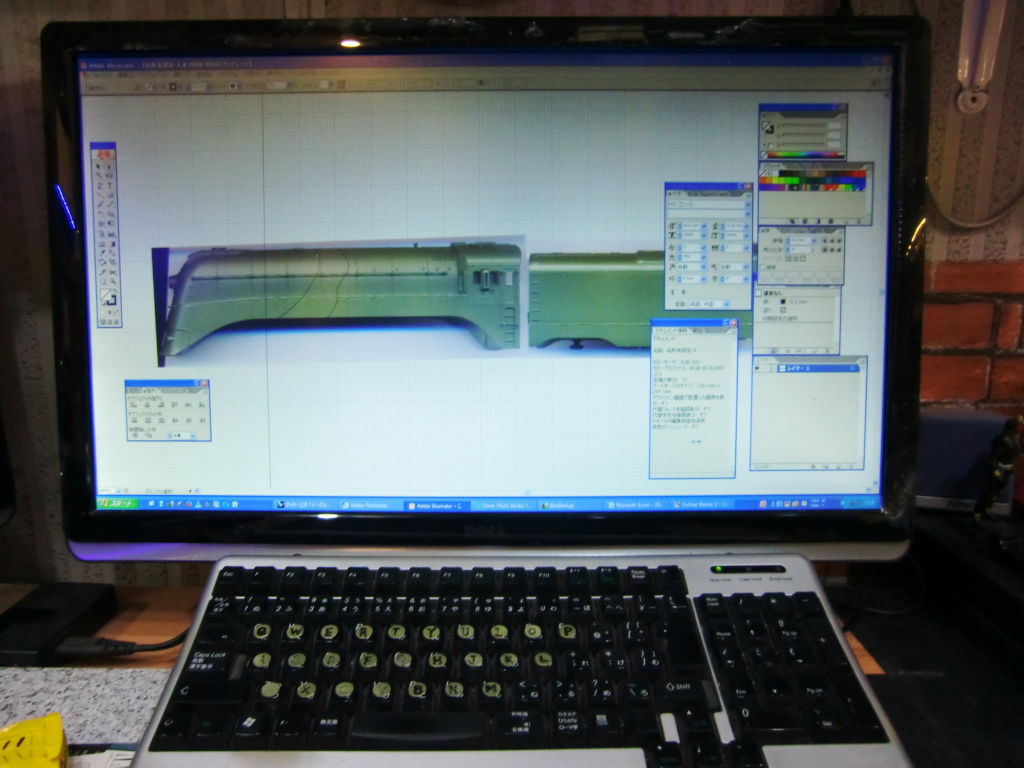
車体をスキャンしてPCに取り込み模様のマスクデータを作ります。
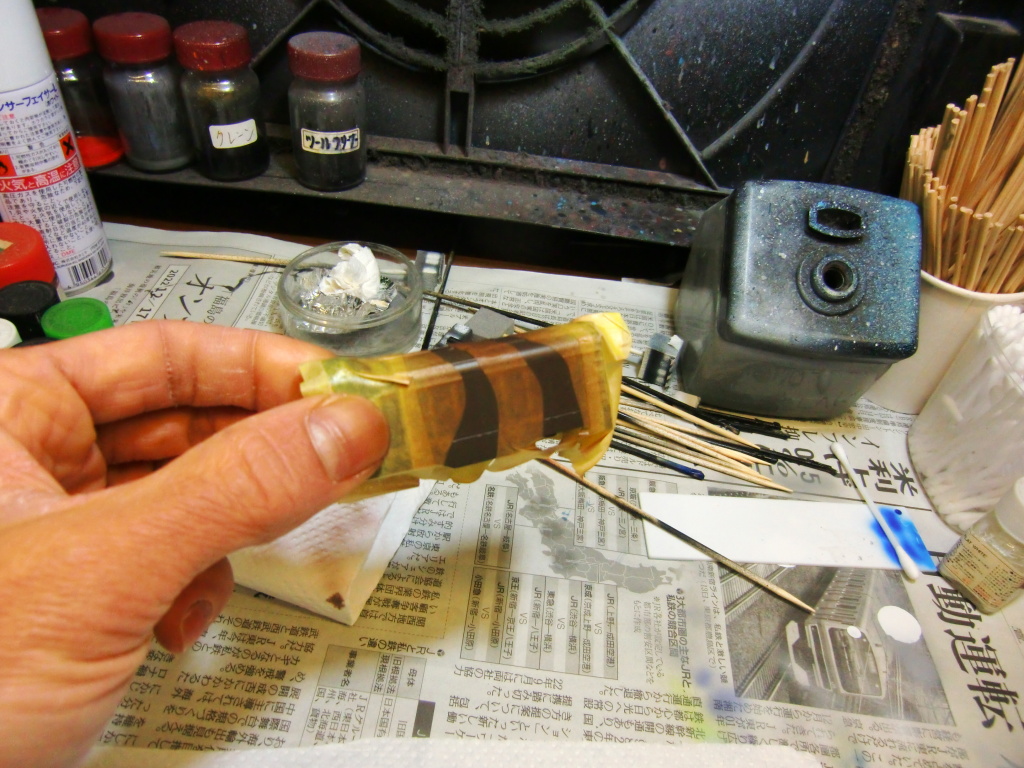


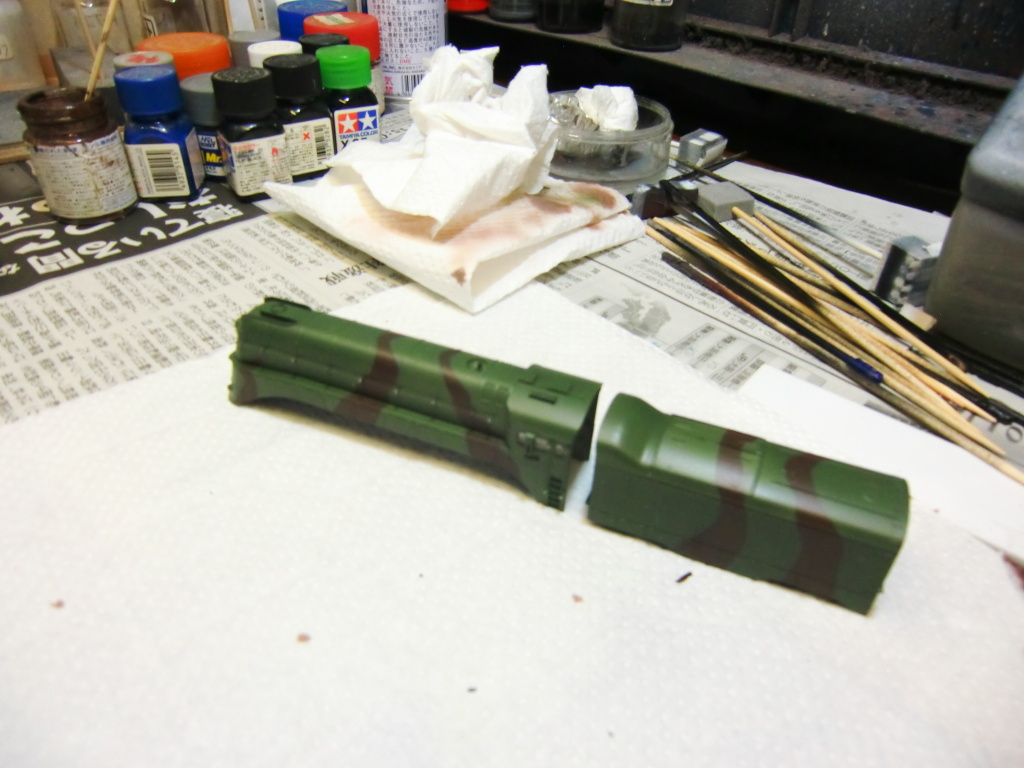



筆で正面を黒で塗分けます。





下回りも黒に塗装します。
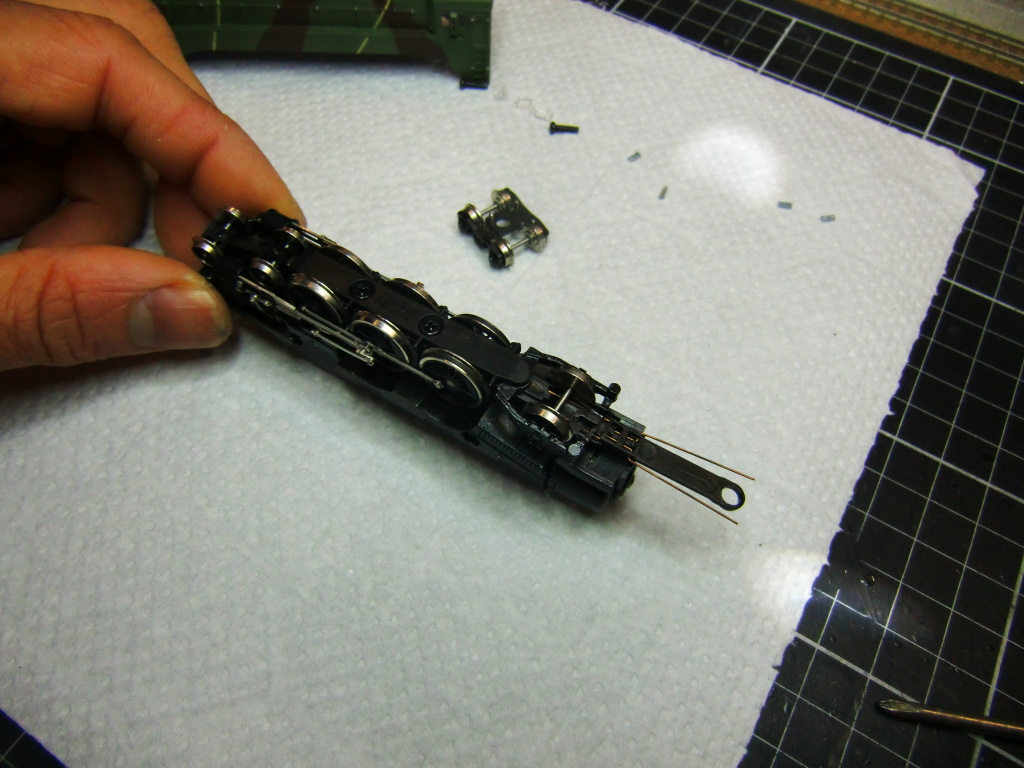
取り付けます。

ヘッドライトも既存の電球からLEDへ交換しました。




作業完了でございます。

まずは車体の全分解作業からです。

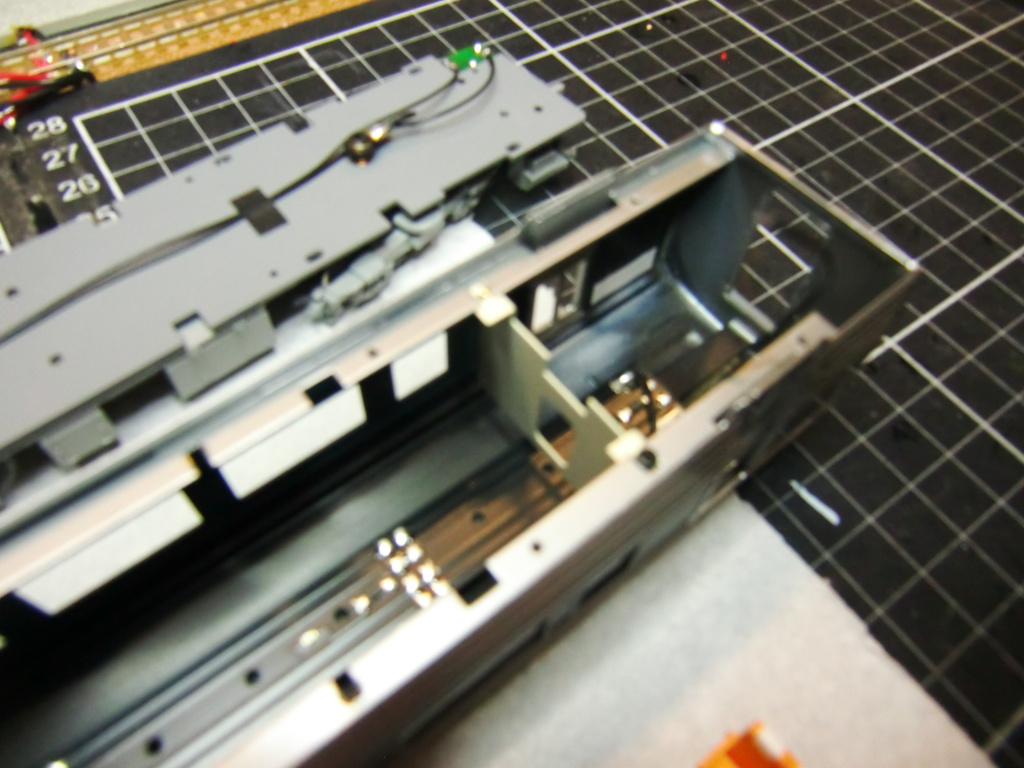
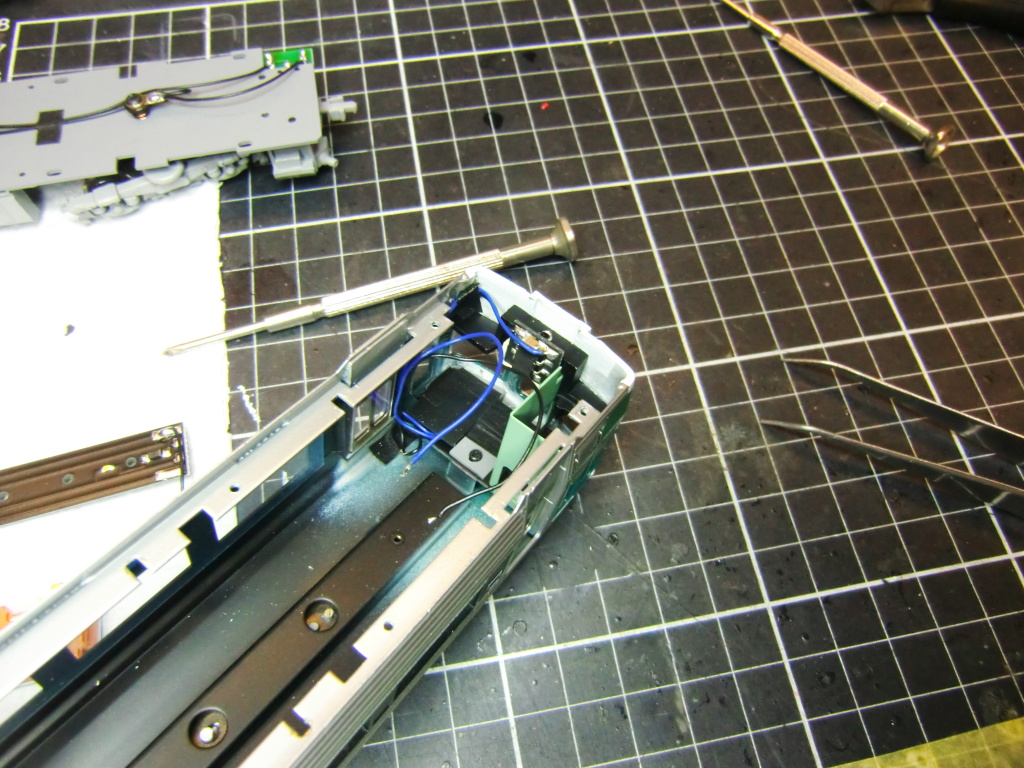
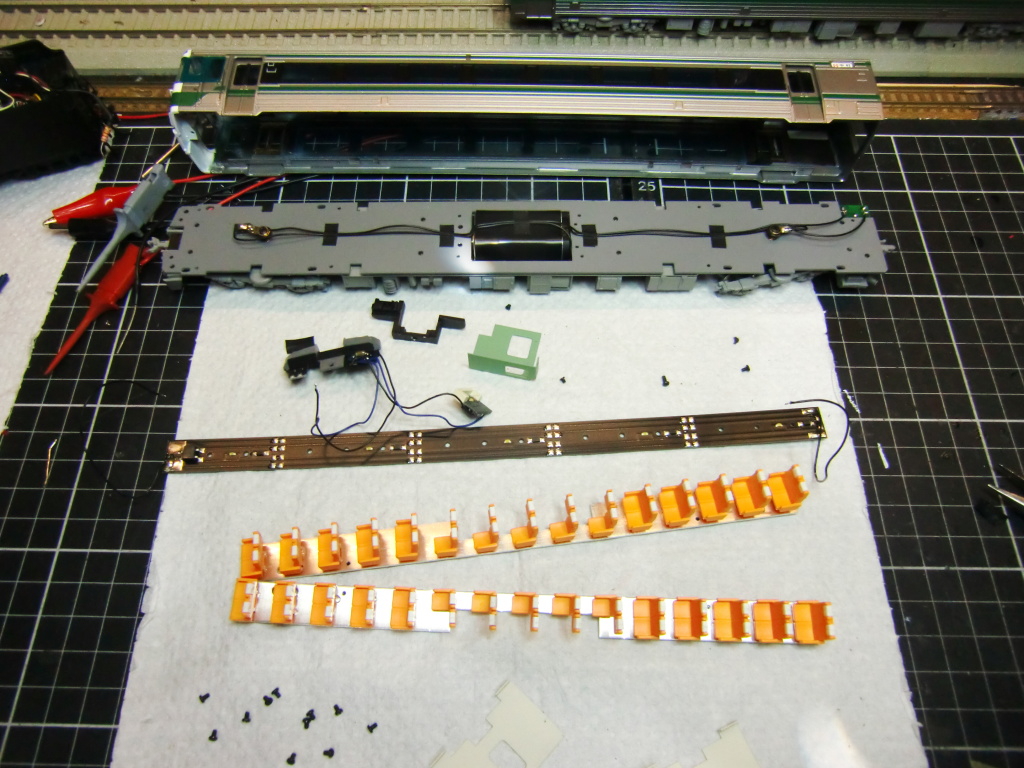
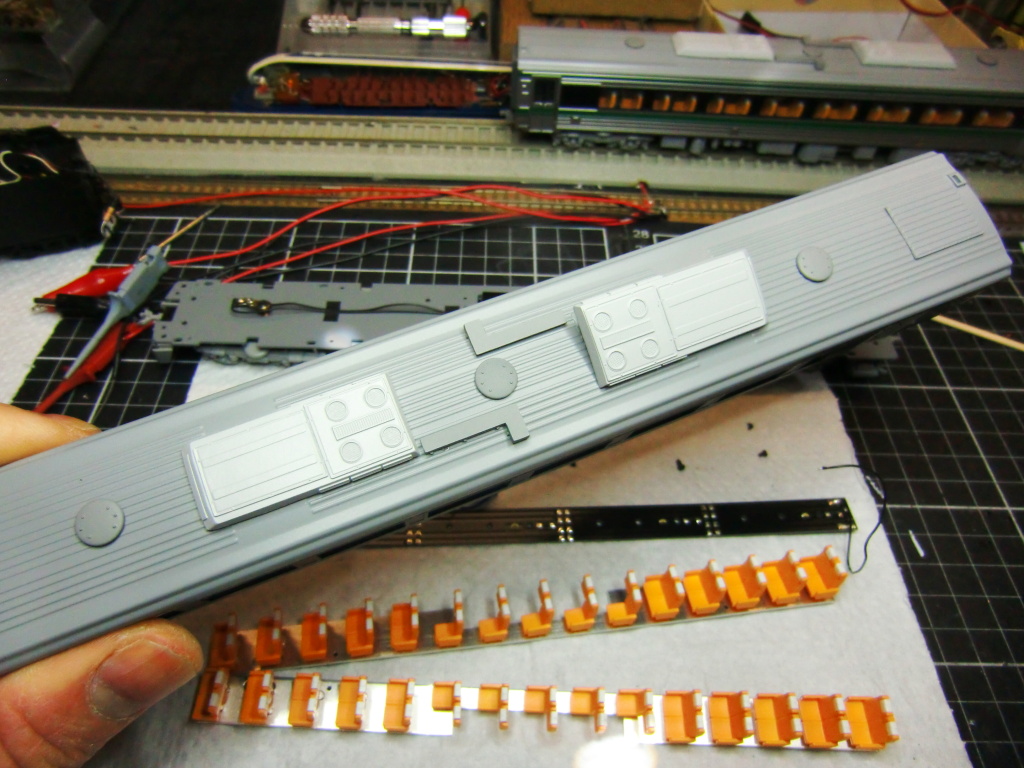
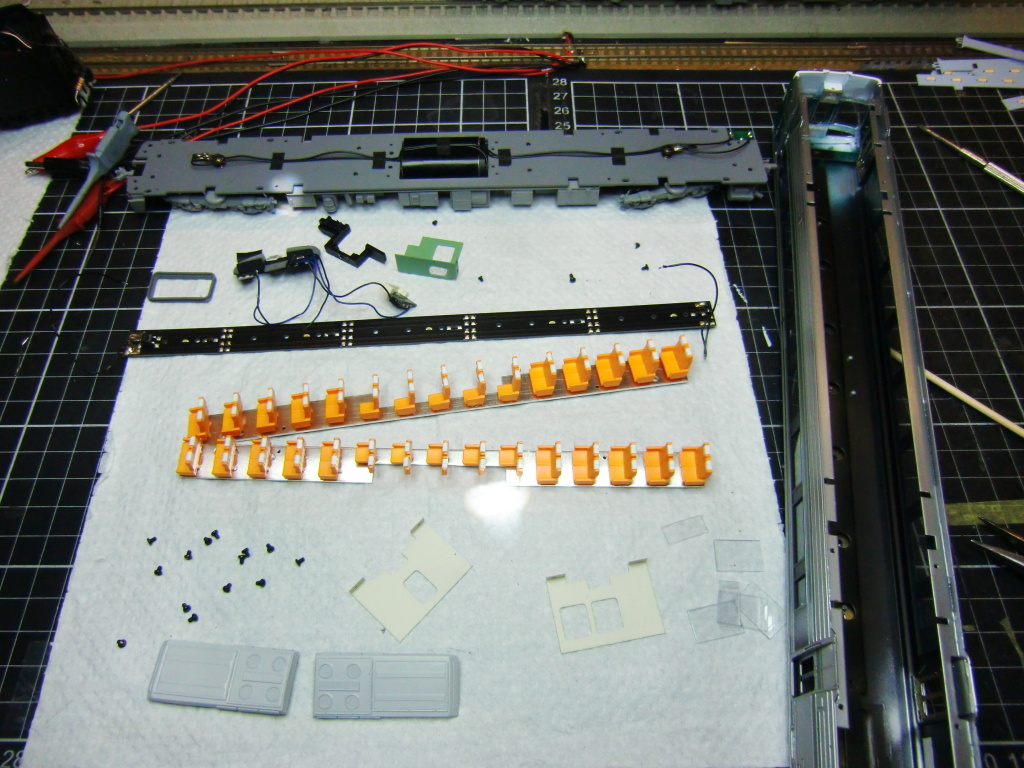
分解だけでも一仕事です。また、ガラスパーツはすべて接着固定されており、塗装前の準備だけでもかなり時間がかかりそうです。上記は1両分です。

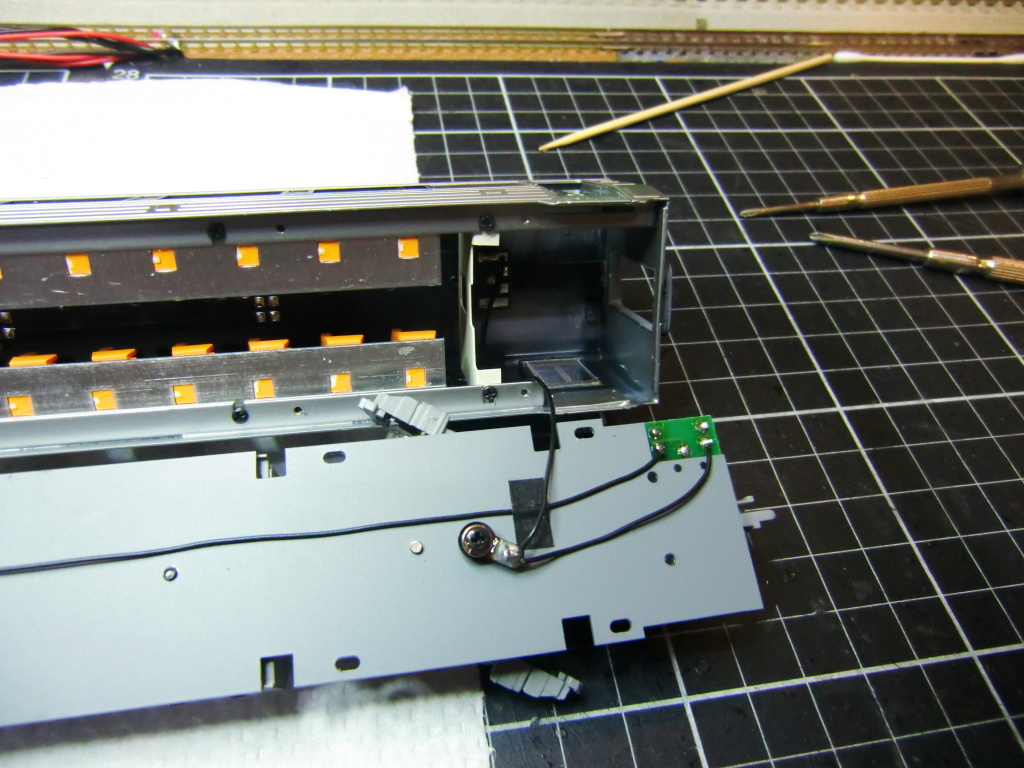
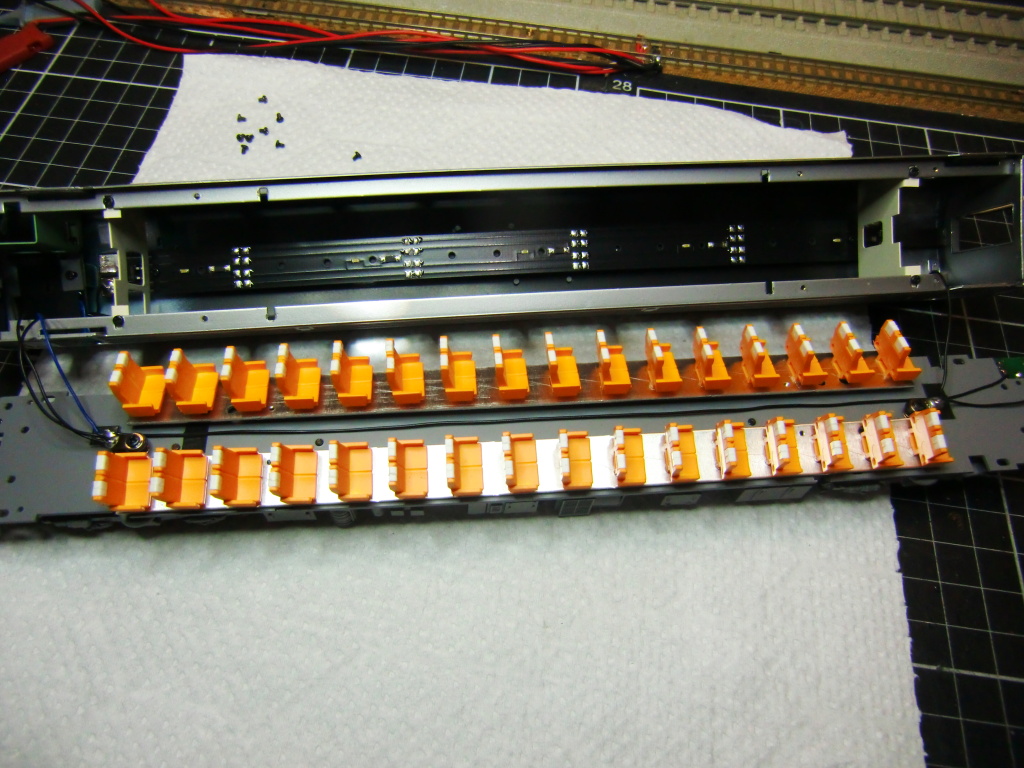

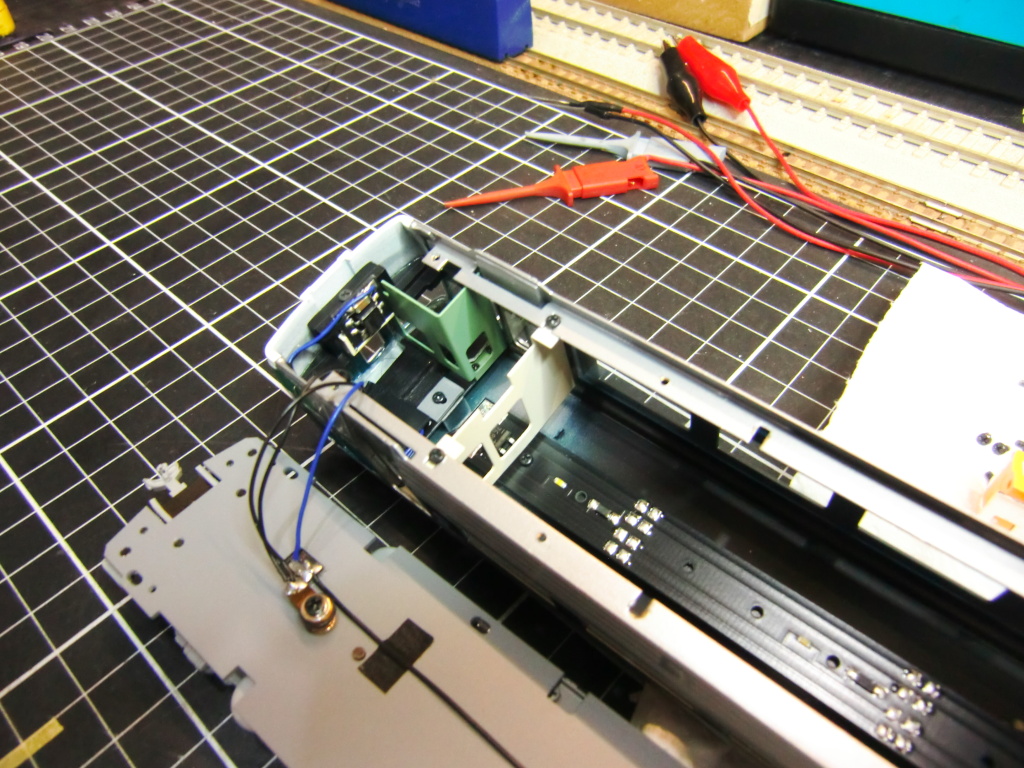
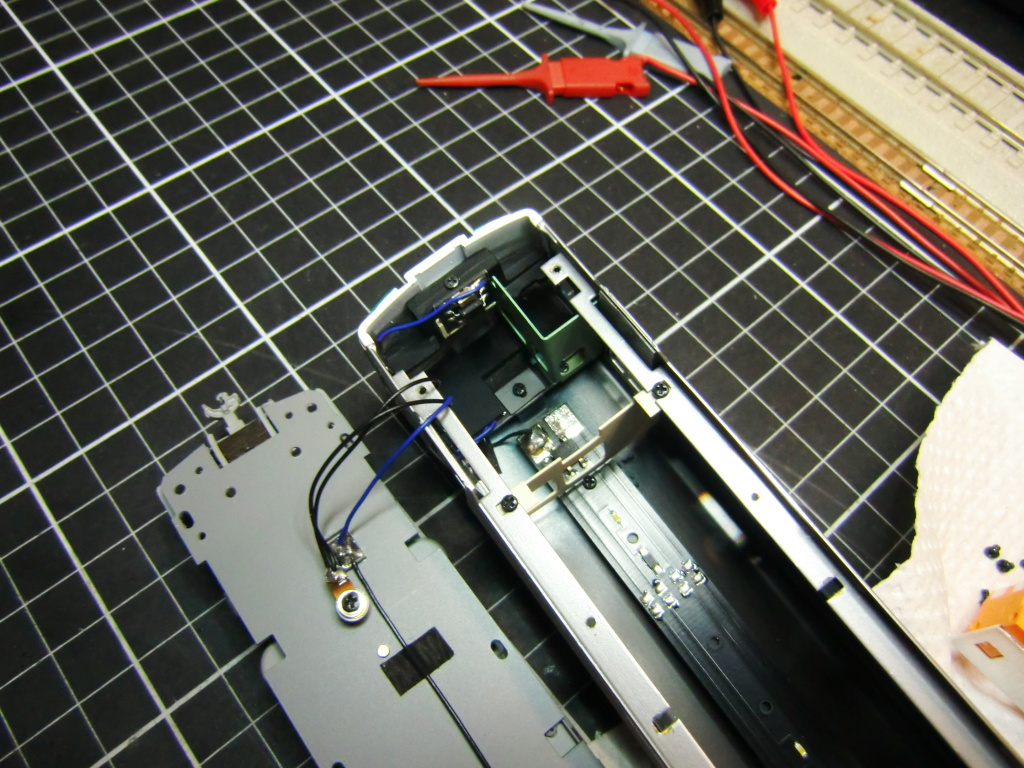
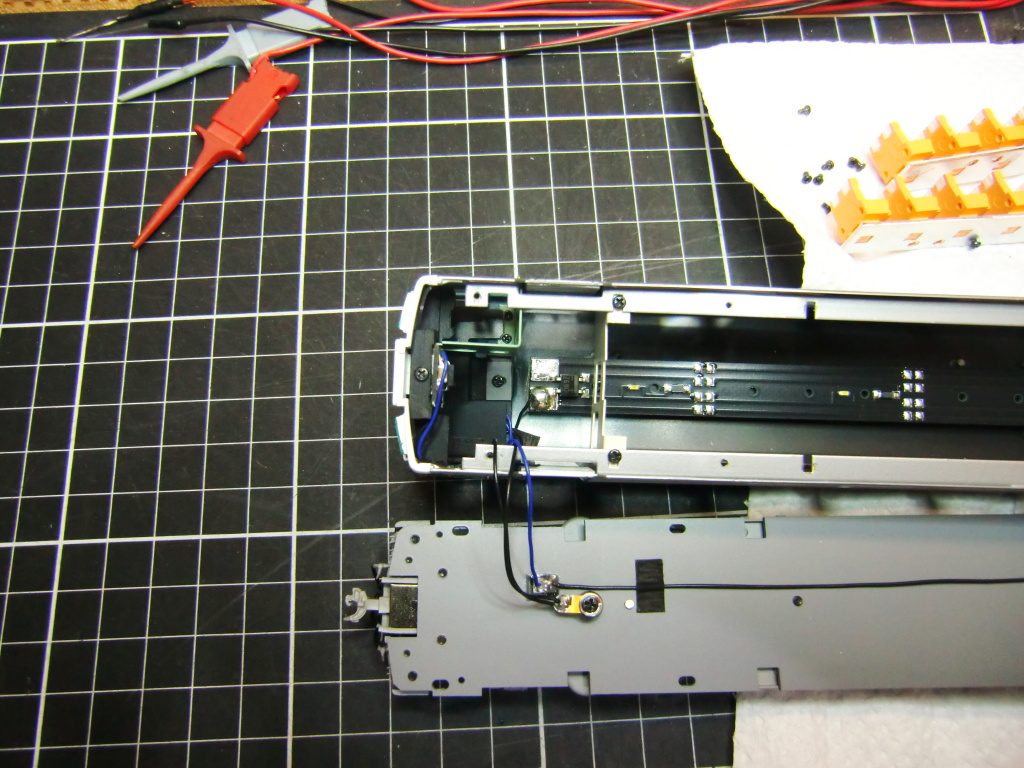

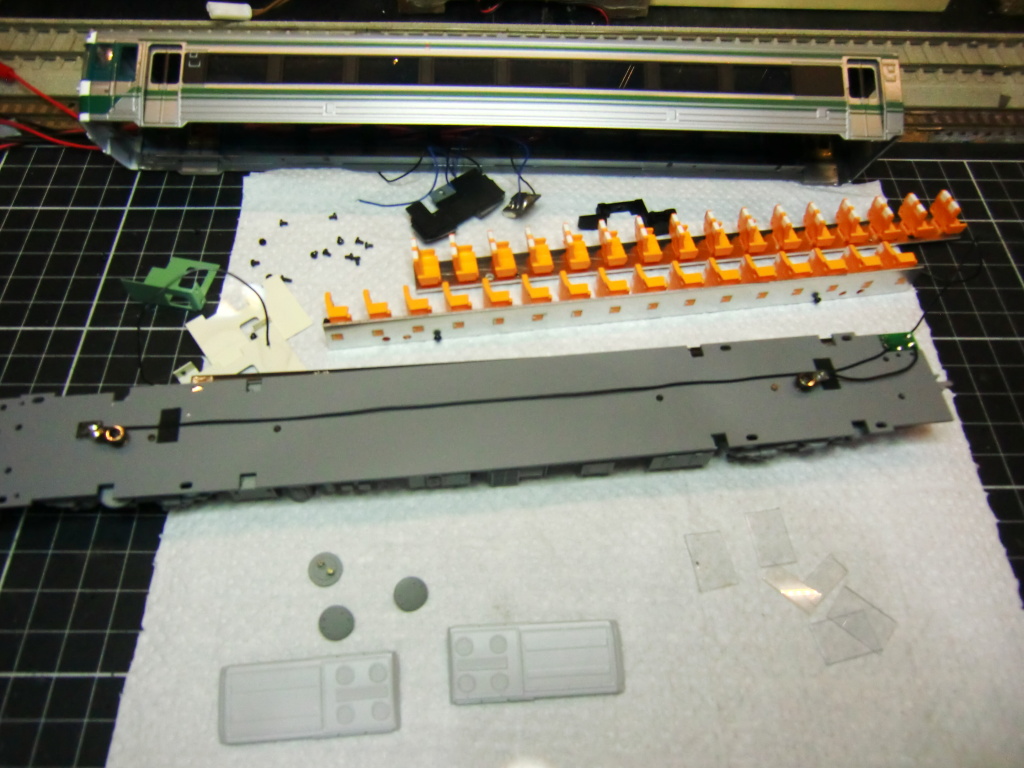


前面の窓ガラスは特に注意して外さなくてはなりません。無理に外そうとすると凹みでパーツが変色してしまい、再利用できなくなります。
ちなみにこのパーツ「バキュームフォーム」により制作されていますので、破損させてしまうと原型から作り直さなくてはなりませんので、取り外しは特に慎重に行いました。
▼塗装落とし
ようやく分解が終ったところで、今度は塗装落としです。

リムーバーを使うことで、元の塗装がドロドロに溶けます。




ある程度拭き取ってからシンナープールにドボンします。
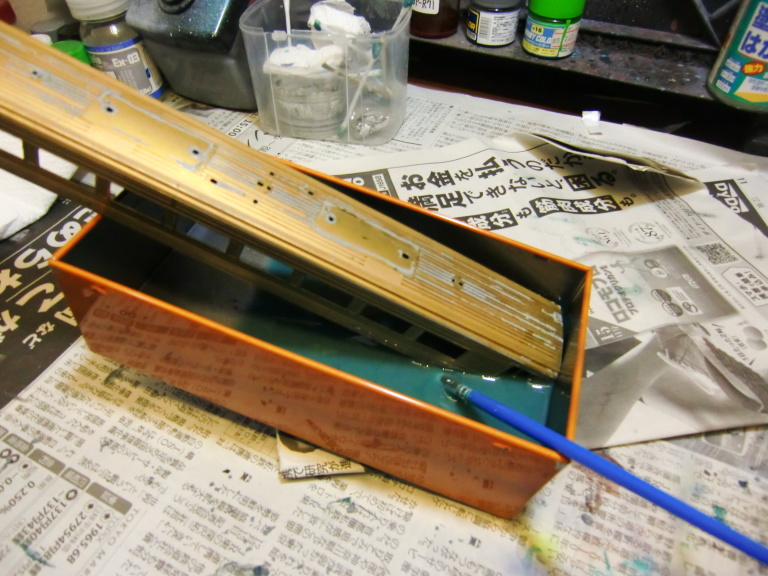

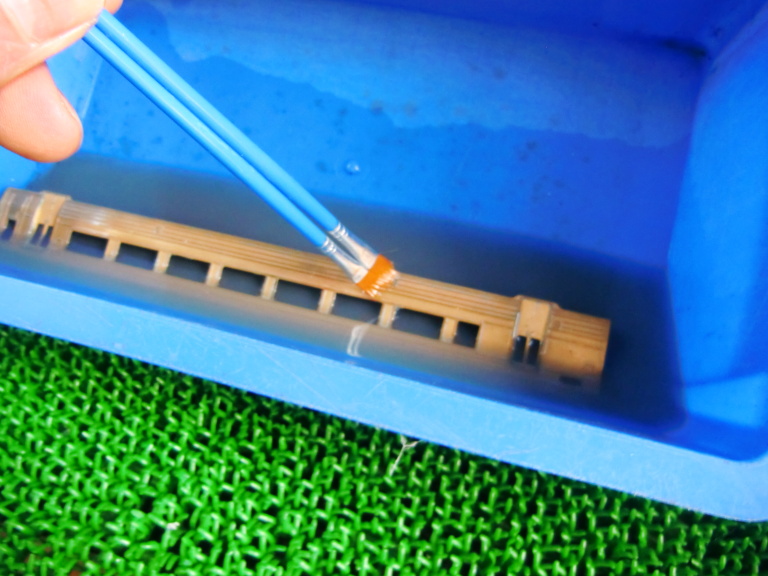



シンナープールからきれいになって出てきました。

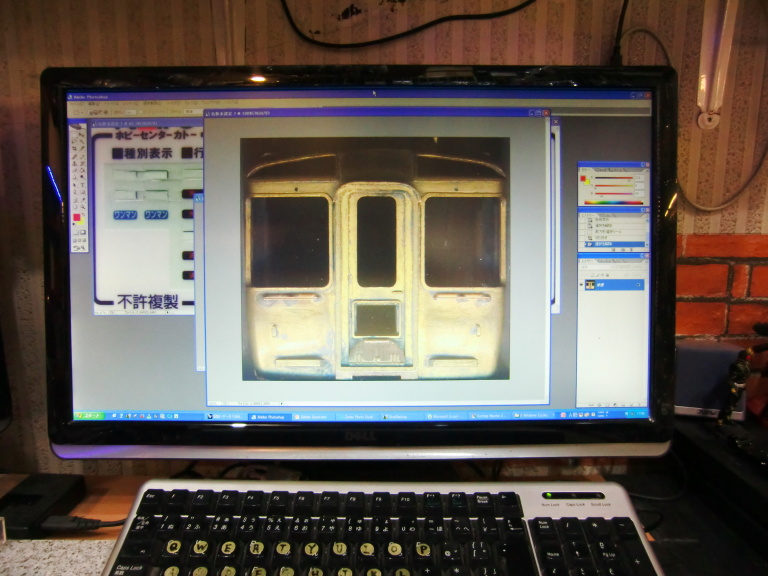
続いてヘッドライトの穴あけ位置を決めるため、正面をスキャンしてPCに取り込みます。
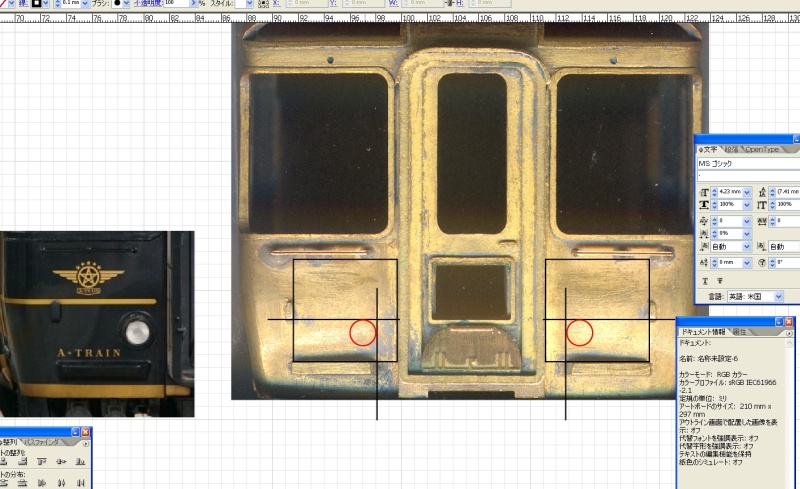
実車の写真とよく比較しながら穴あけする正確な位置を割り出します。1つ1つの工程を時間をかけて丁寧に進めていきます。
次に、レーザーでテンプレートを作り車体に印を打っていきます。

センターポンチを打ち、ドリルで穴をあけます。1.0mm->1.5mm->2.0mmの順で行います。


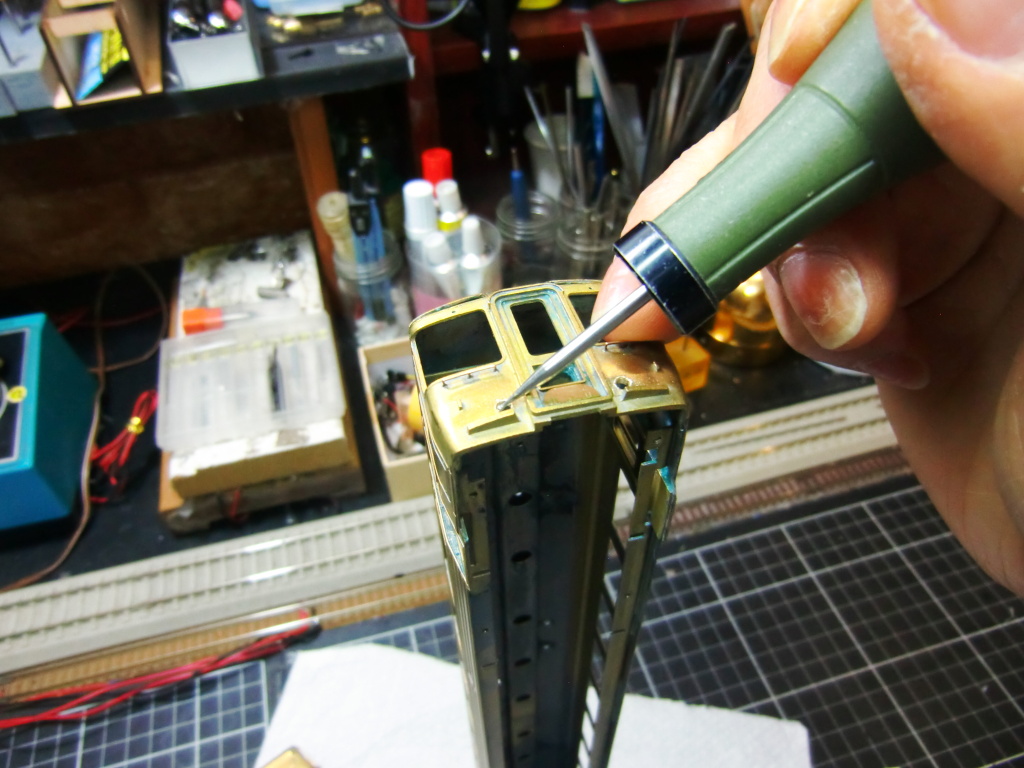
穴あけした周りのバリをルーターで丁寧に処理します。
▼ライトパーツ制作
穴あけが終ったところで、そこにはめ込むライトを作ります。ライトレンズの受けも内側につけておきます。
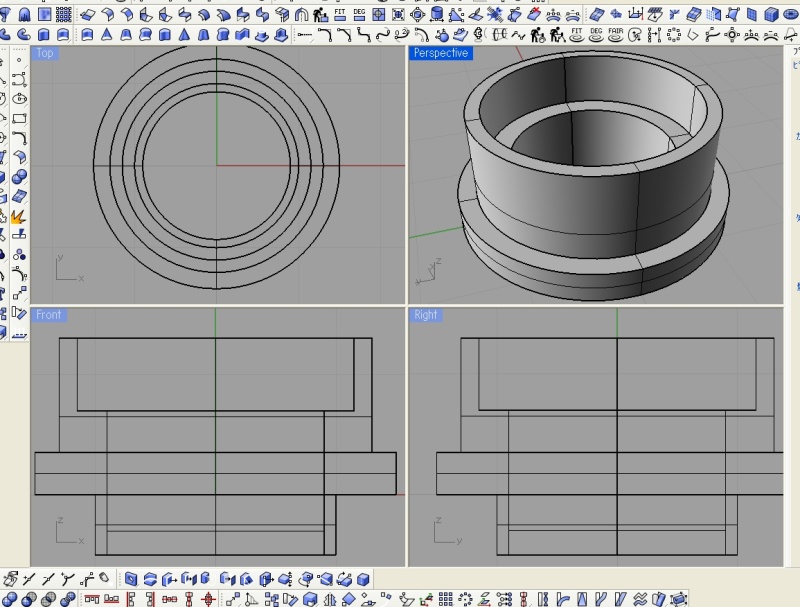
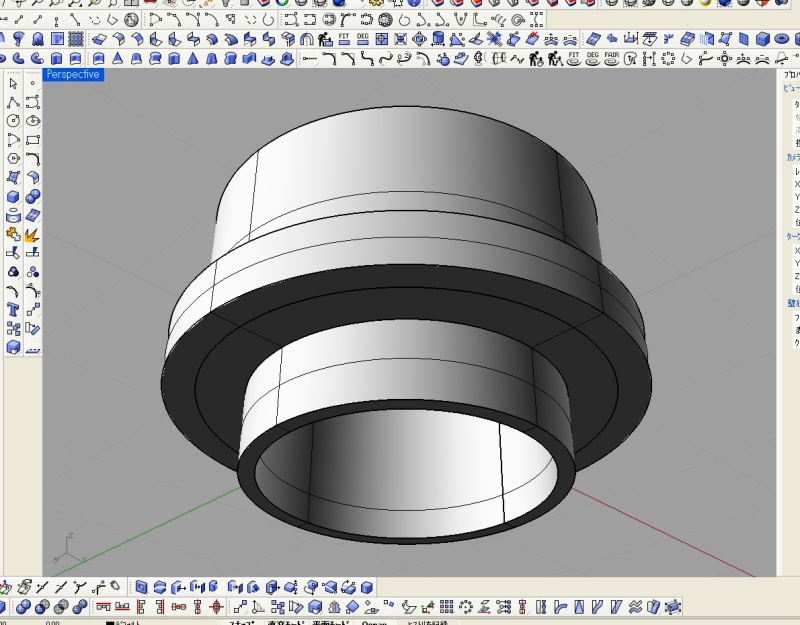
設計が終り3Dプリンターで出力します。
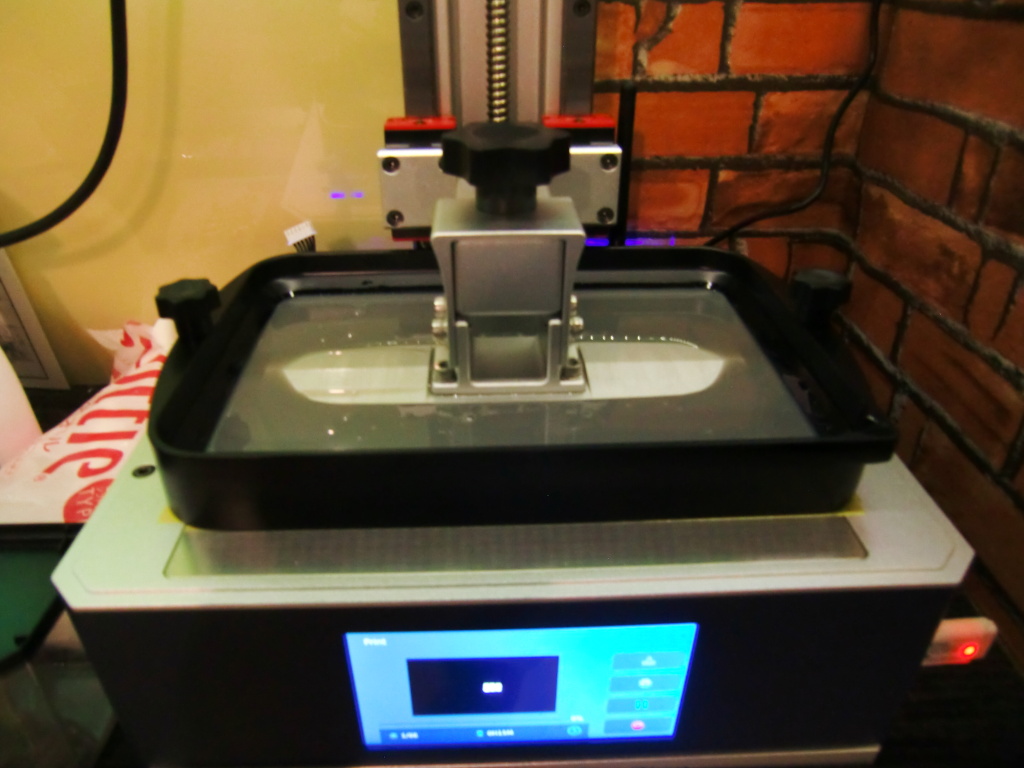
3Dプリンターでライトパーツの出力を行ってから2次処理を施してから車体に組み込みます。実際に組み込む際にも注意が必要で、車体の傾斜に合わせて角度を調整して固定しなくてはなりません。そのまま取り付けると、下に向いた状態でライトが固定されてしまいます。
▼塗装作業開始

下地処理です。数回に分けてまんべんなく下地を吹き付けます。


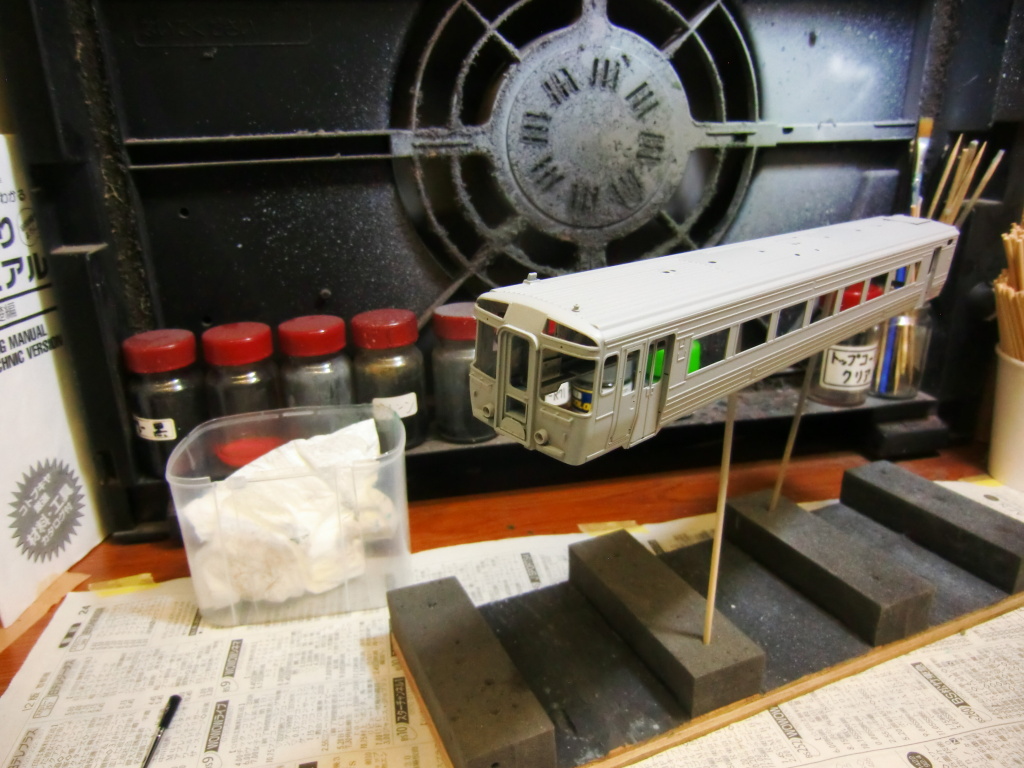
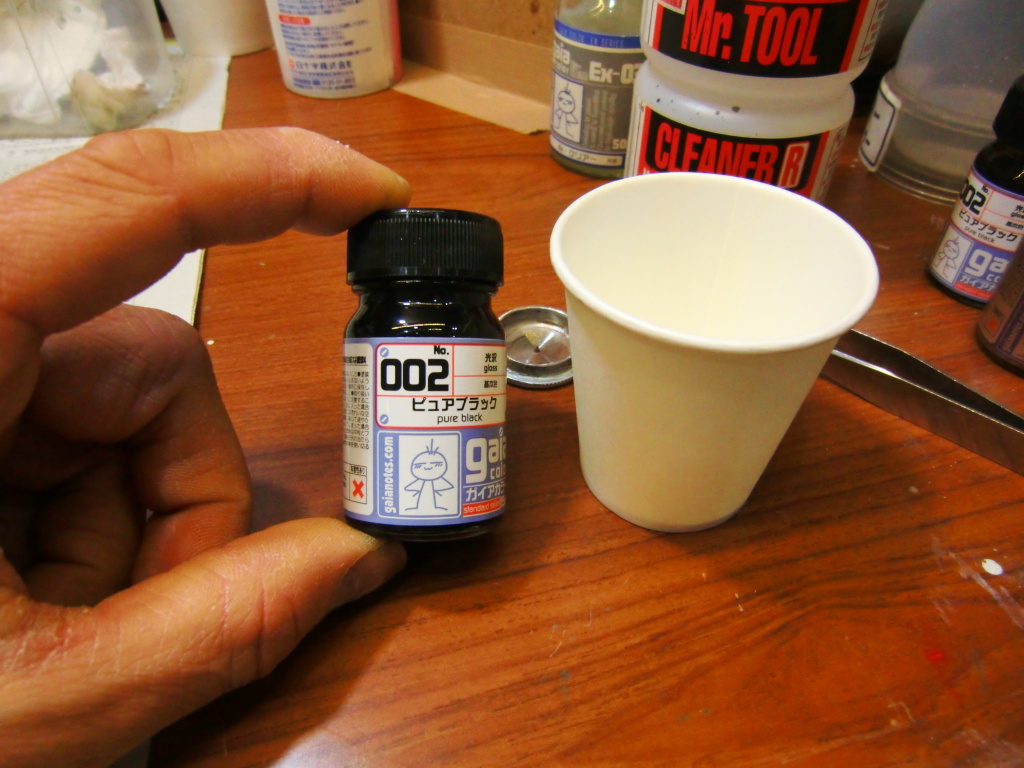
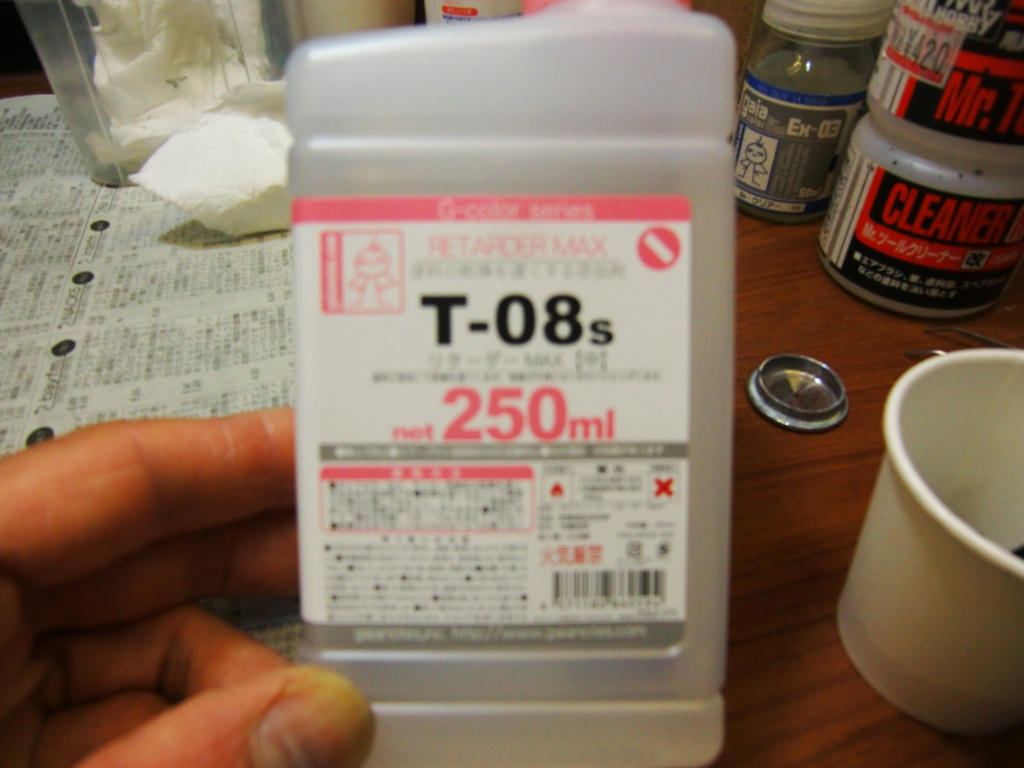
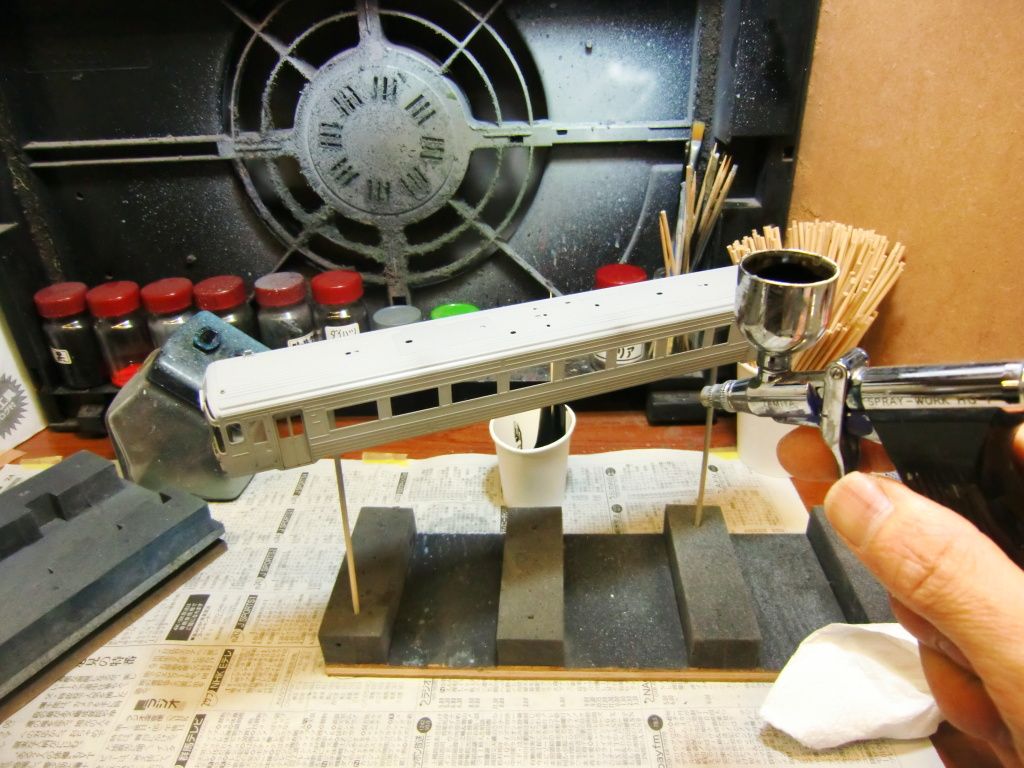
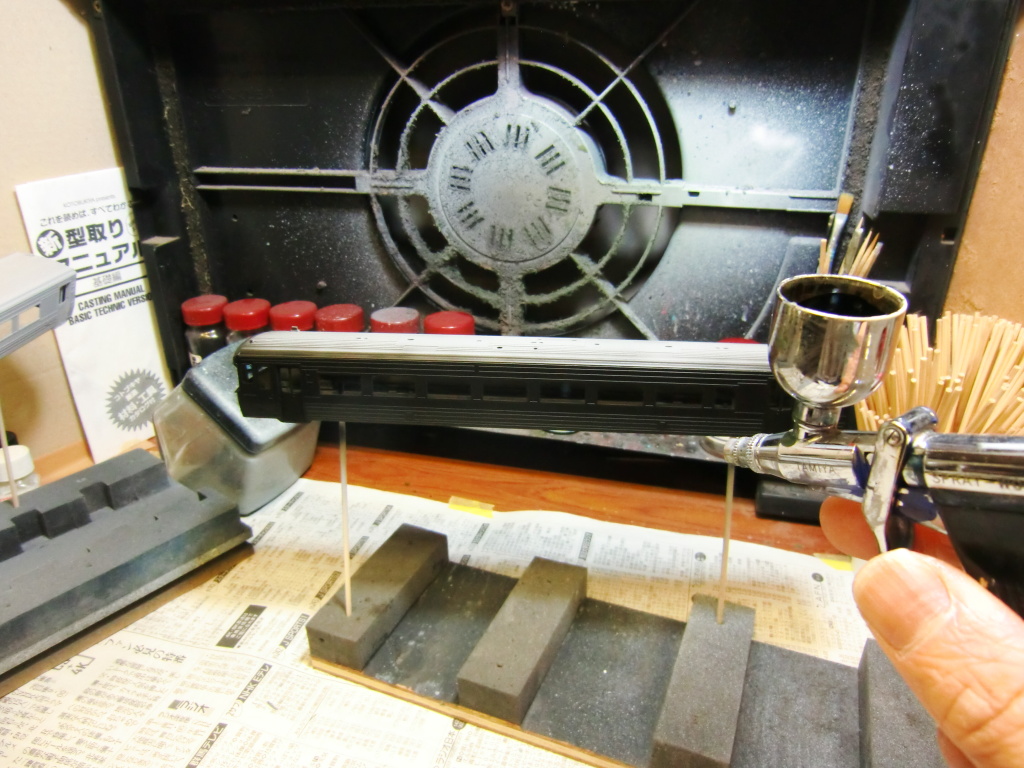
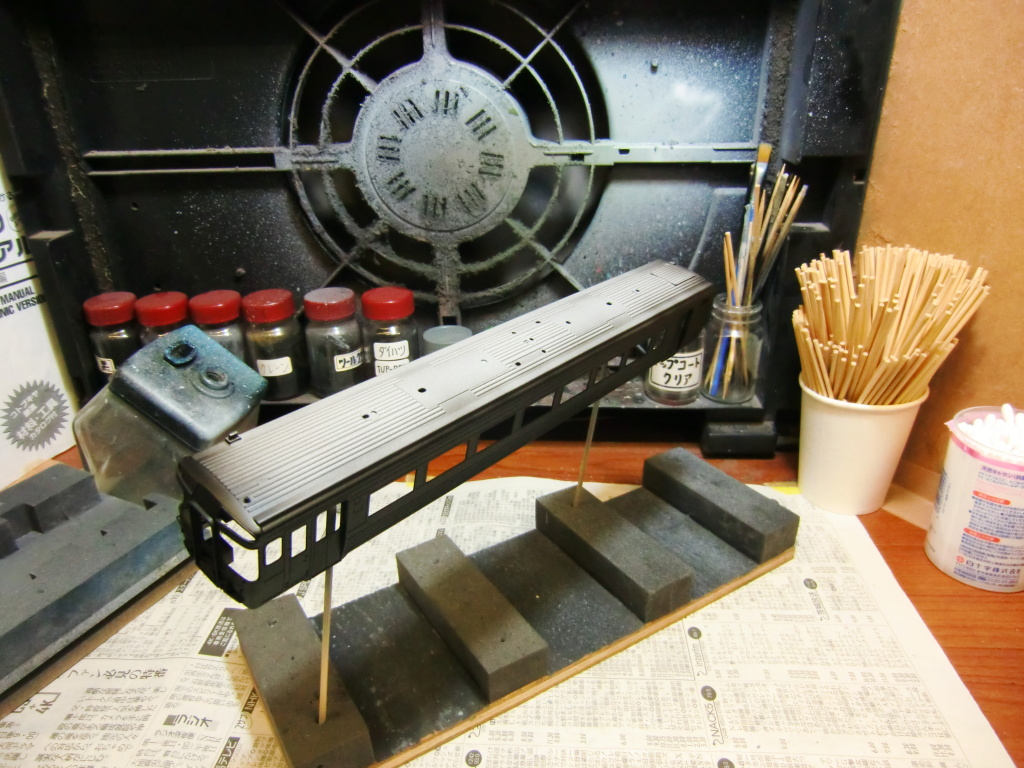
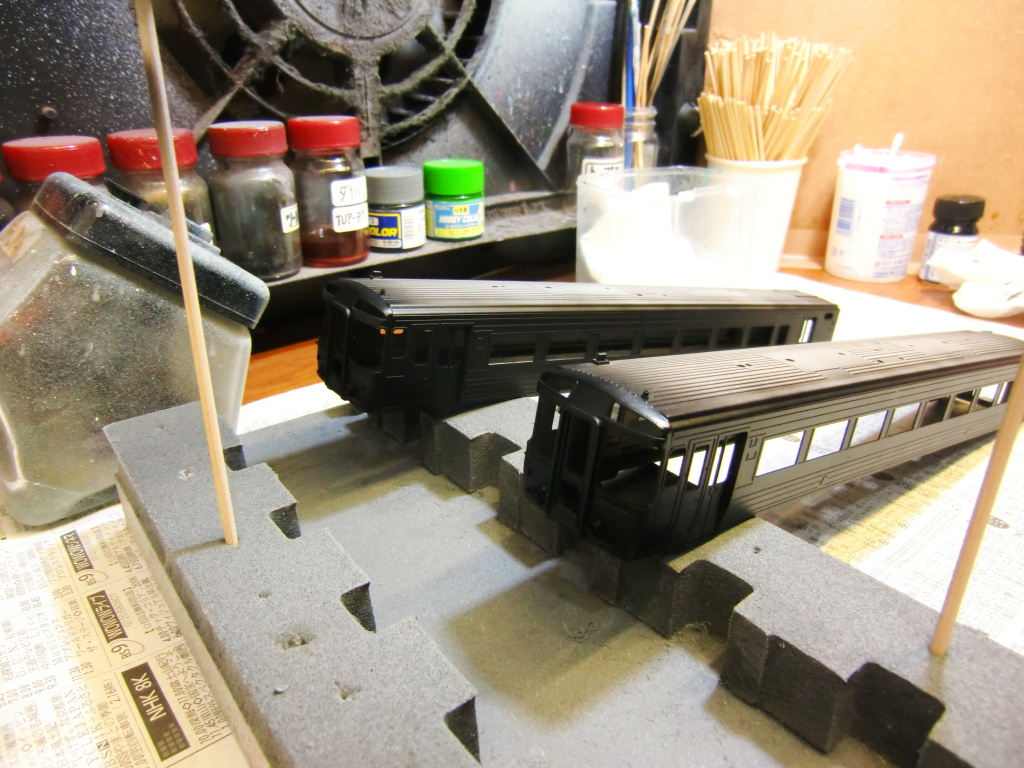
▼マスキングデータの制作

数回に分けて色を重ねていきます。
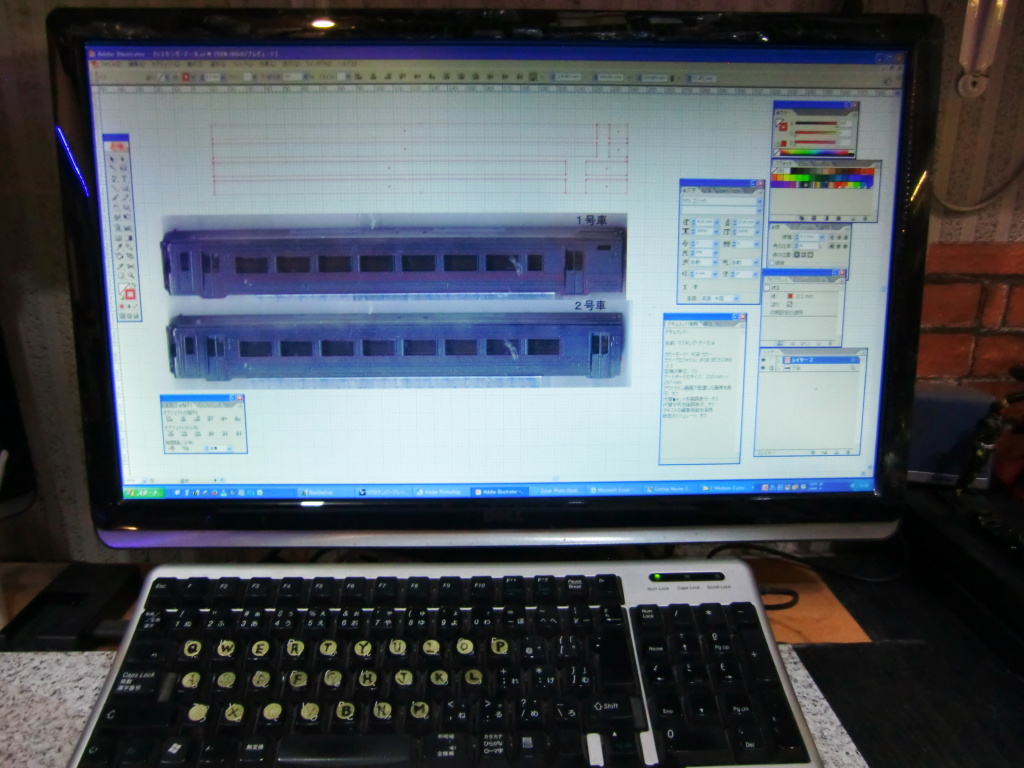
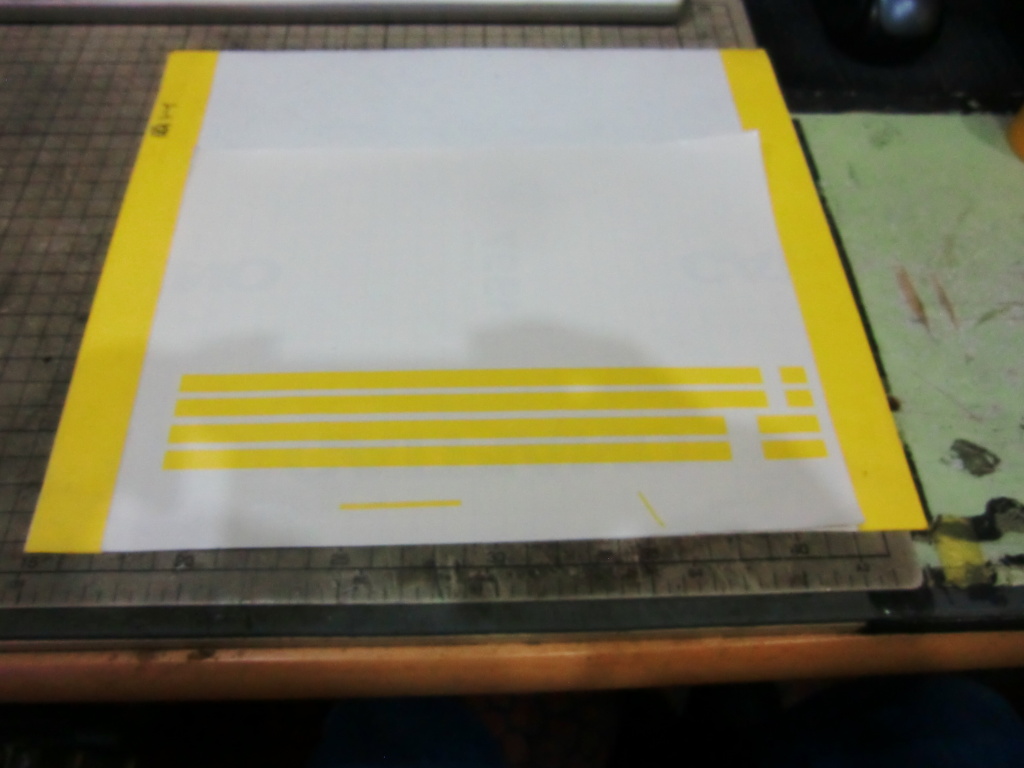
車体側面をスキャンしてマスクデータを作ります。
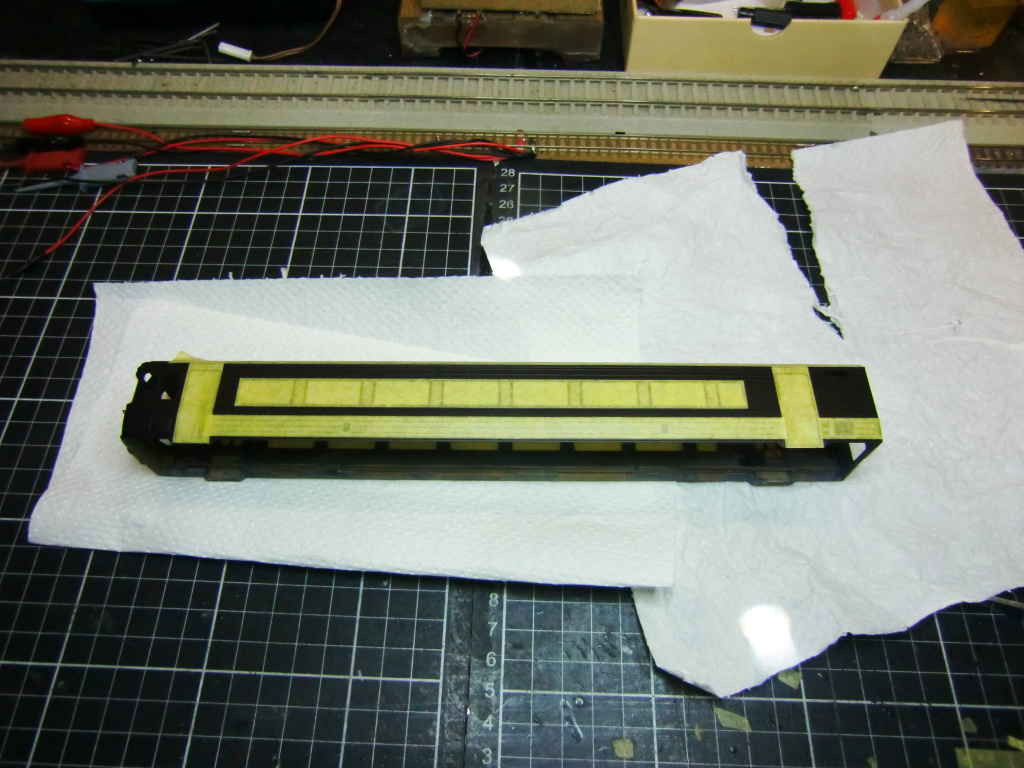
写真を何度も確認しながら、金帯の位置と幅の修正作業が続きます。貼っては直しの繰り返しです。詳細な説明書があるわけではないので、こうした作業には本当に大変な時間がかかるんですよね。ここはもう仕事抜きにして趣味の範囲で納得がいくまで時間をかけている感じです。
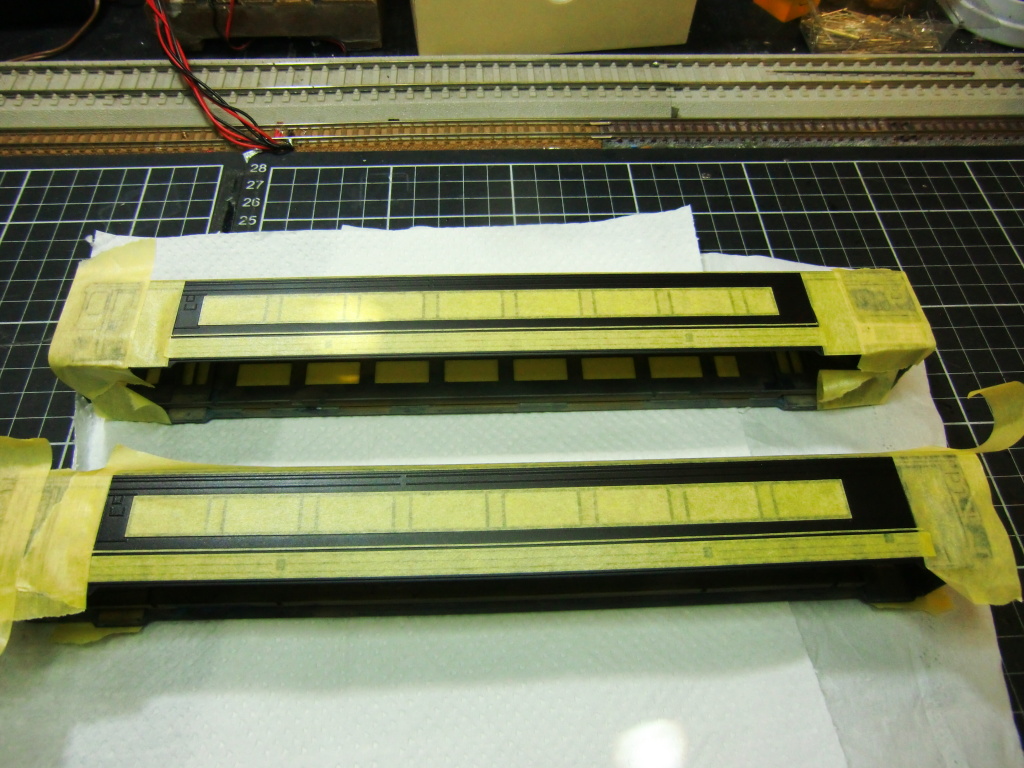
いよいよ「スターブライトゴールド」の塗装です。3つのブロックに分けて塗装していきます。


今回は、希釈にメタリックマスターを使います。

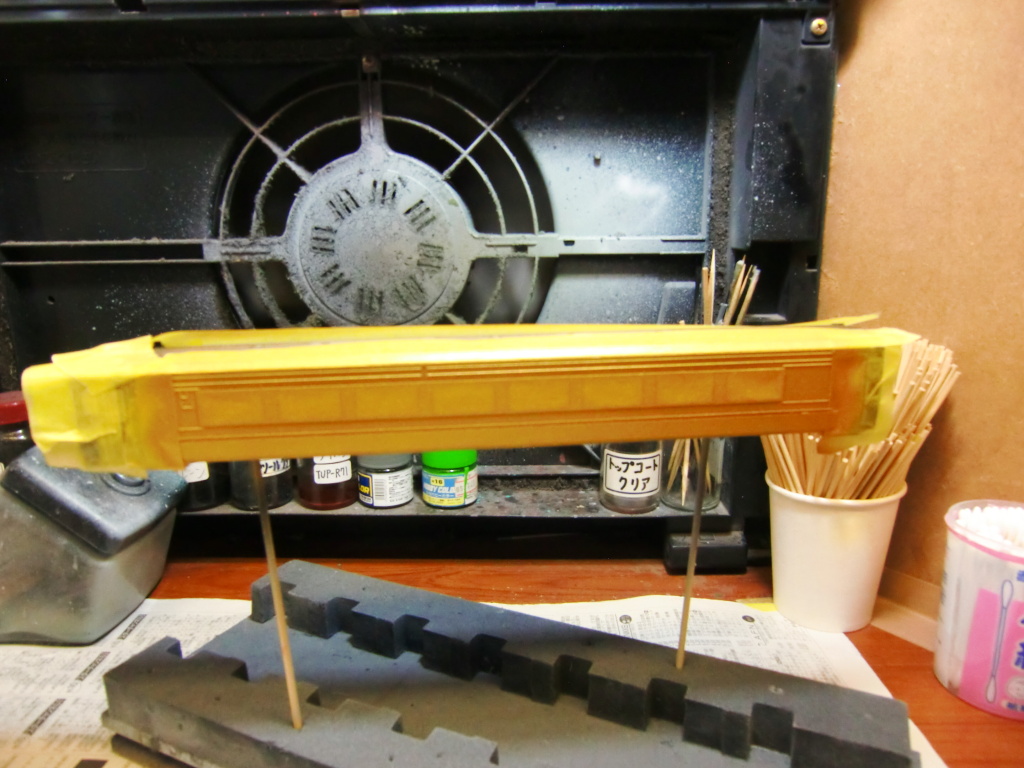
複数回に分けて色を載せていきます。
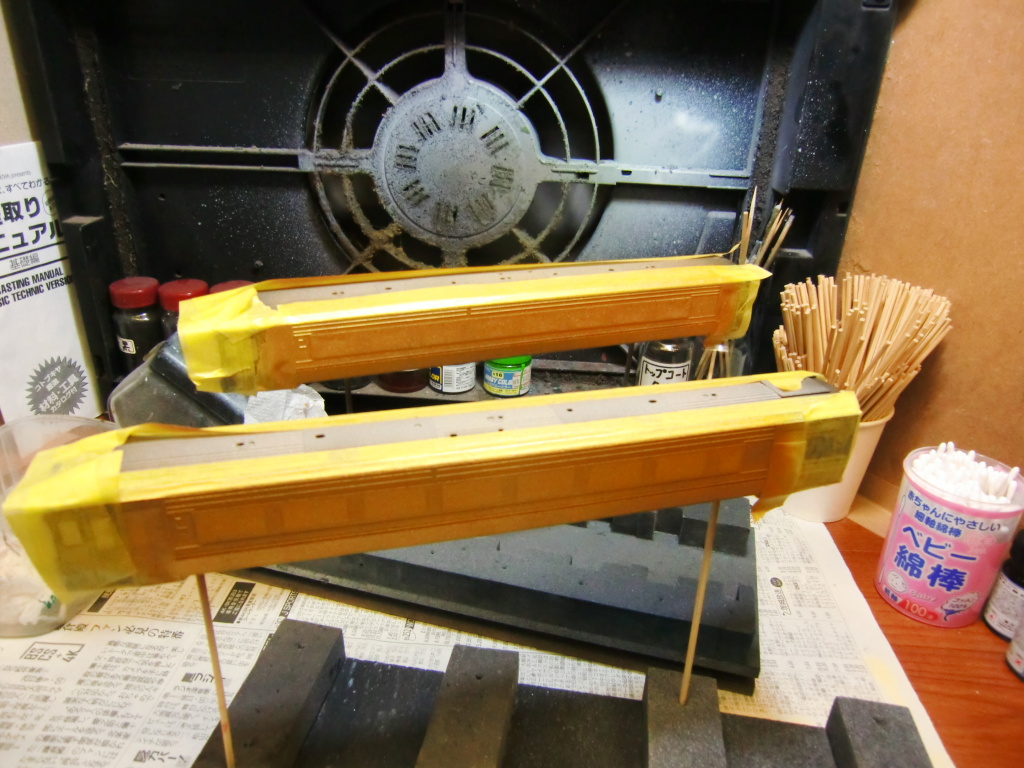


中央の金塗装が終ったところで、今度は前後の金帯を塗装します。屋根につきましては、デカールをすべて貼り終えたのち光沢クリアーを吹き付けて最後に屋根塗装を行います。
▼デカール貼り作業
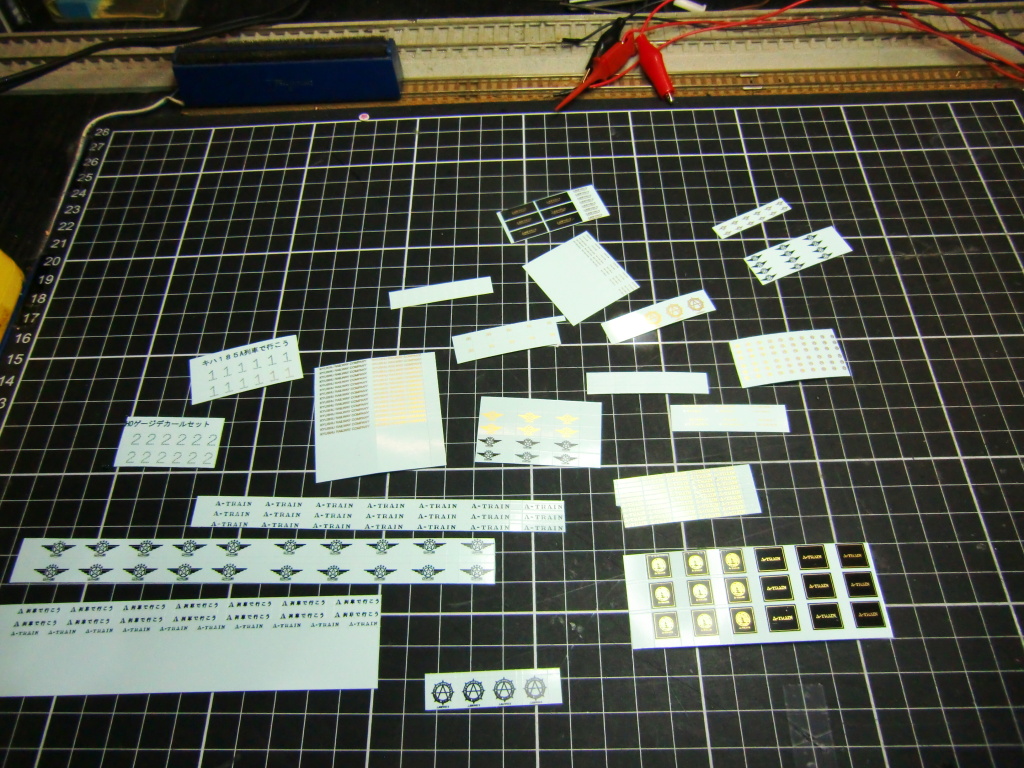



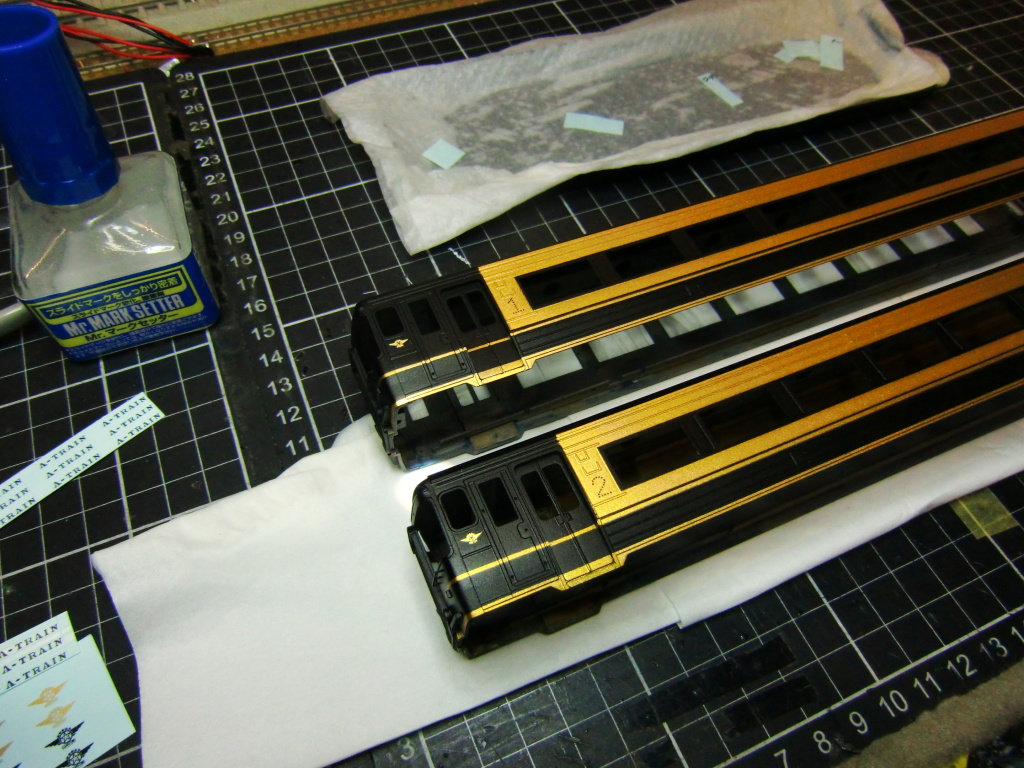
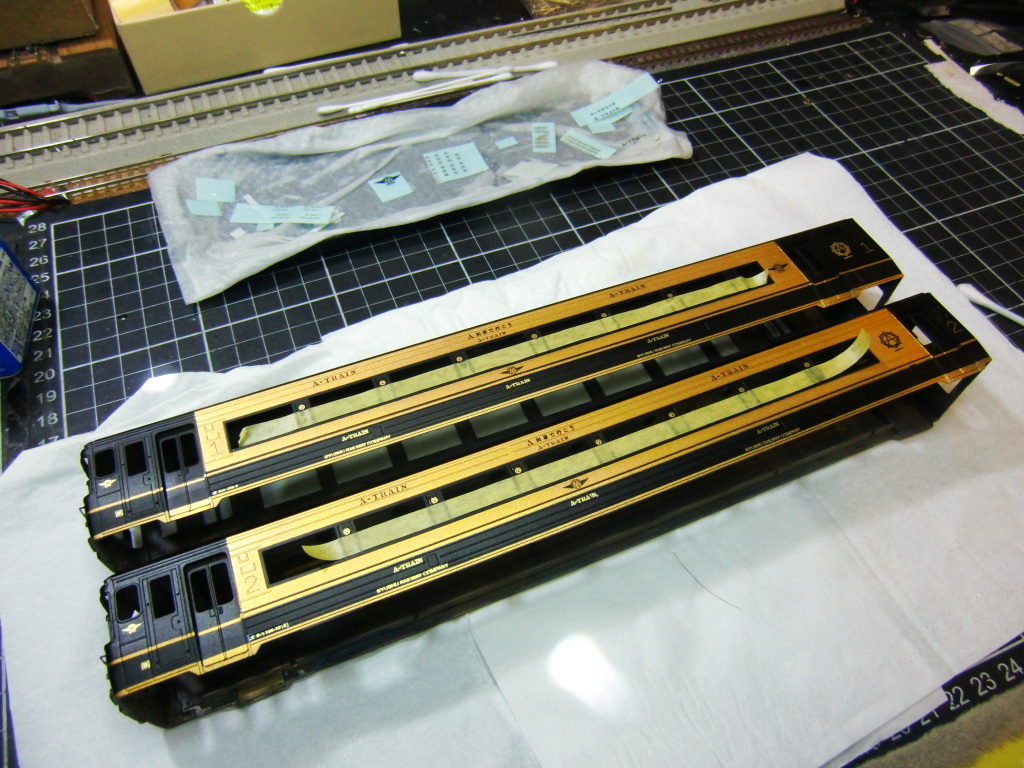



「UV Cutスーパークリアー」で車体全体をコート(保護)します。

1回目は全体に薄く吹き付けます。2回目以降は、濃度を調整しながら厚みを増していきます。5~6回ほど時間をかけて塗り重ねていきます。

ようやくクリアー塗装が終り光沢感のあるきれいな車体となりました。写真暗くてみずらいですけど・・・
この状態で24時間自然乾燥させます。その後、マスキングして屋根の塗装を行います。その間に床下と台車の塗装準備を行っていきます。




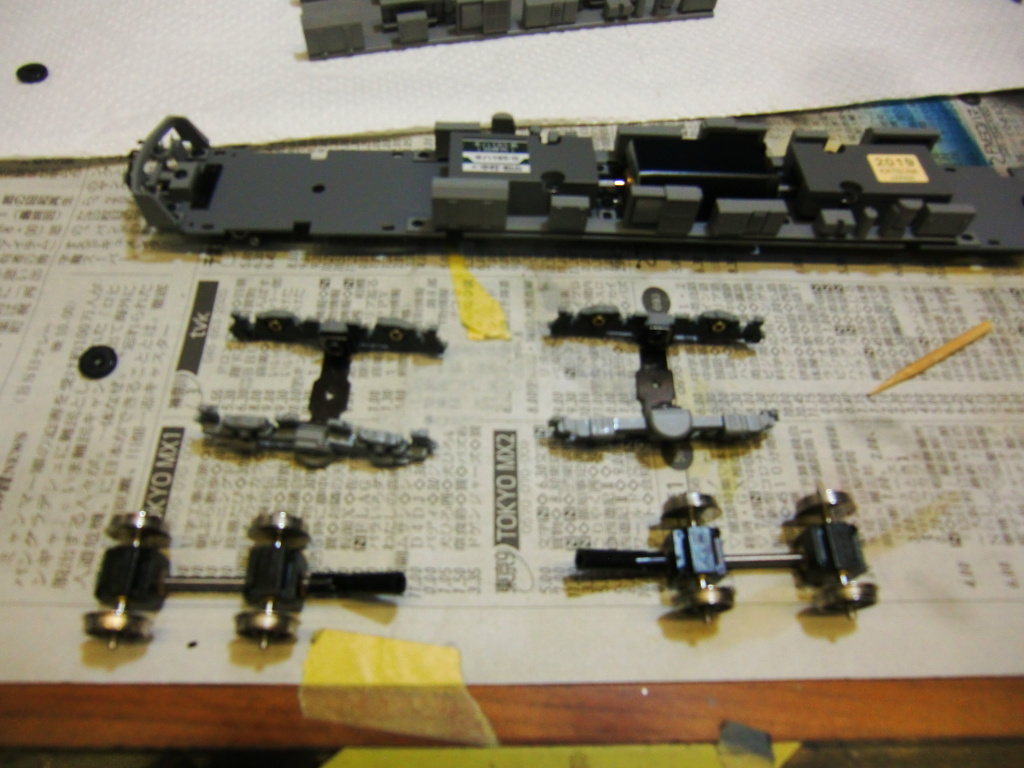


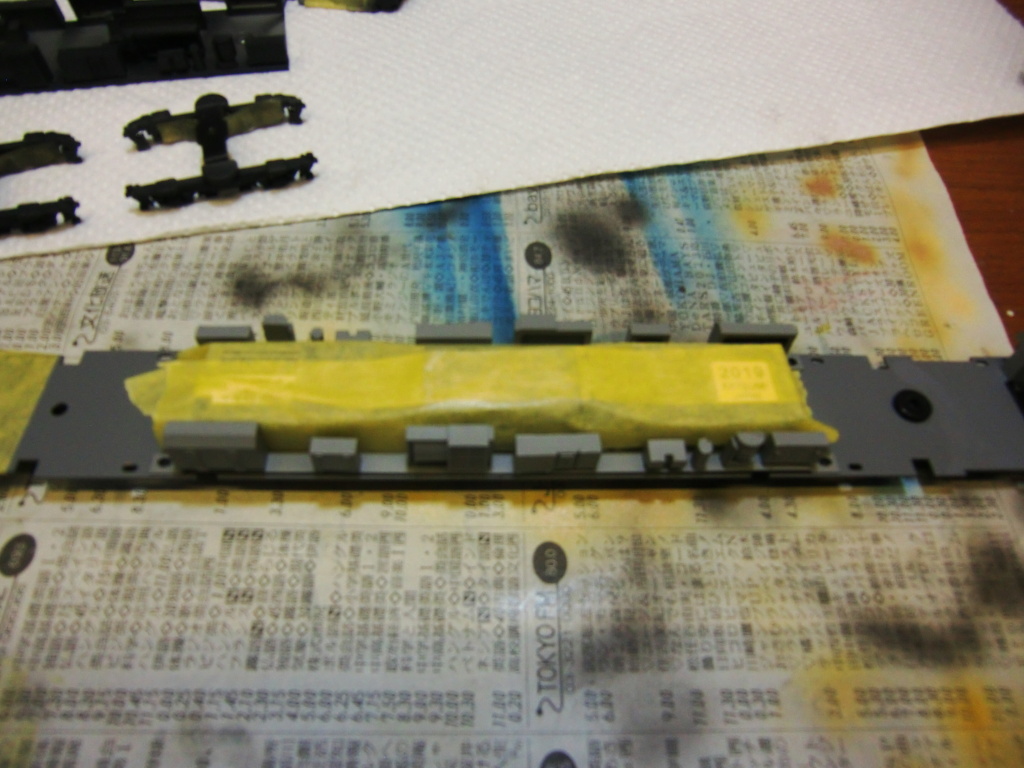




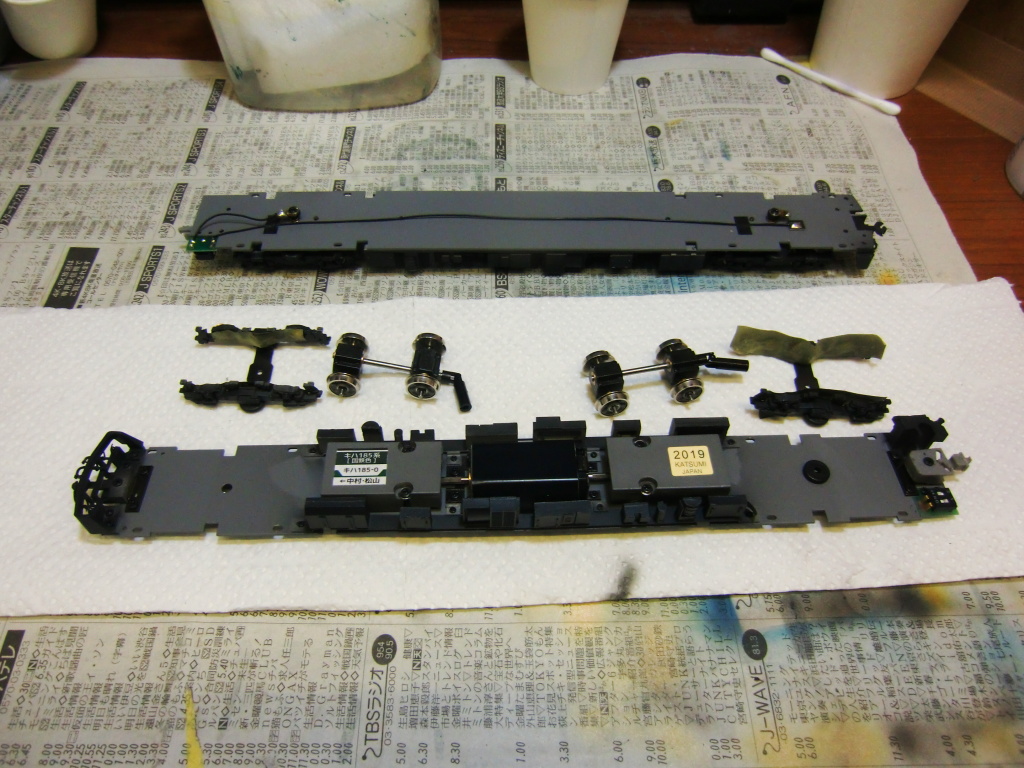
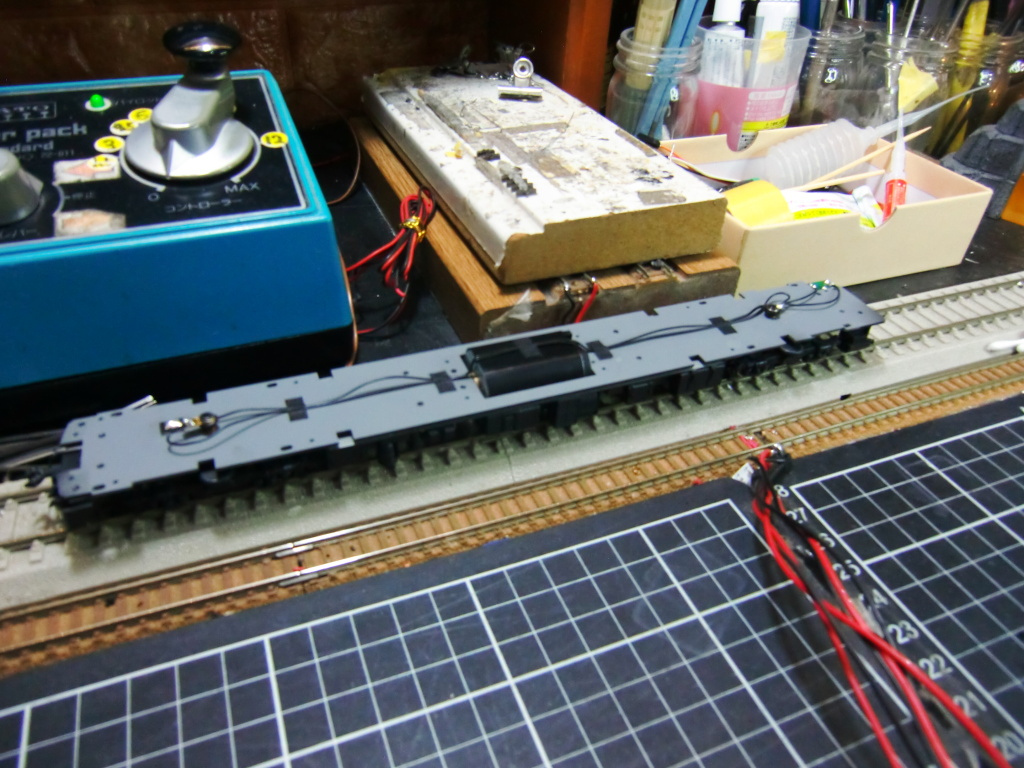



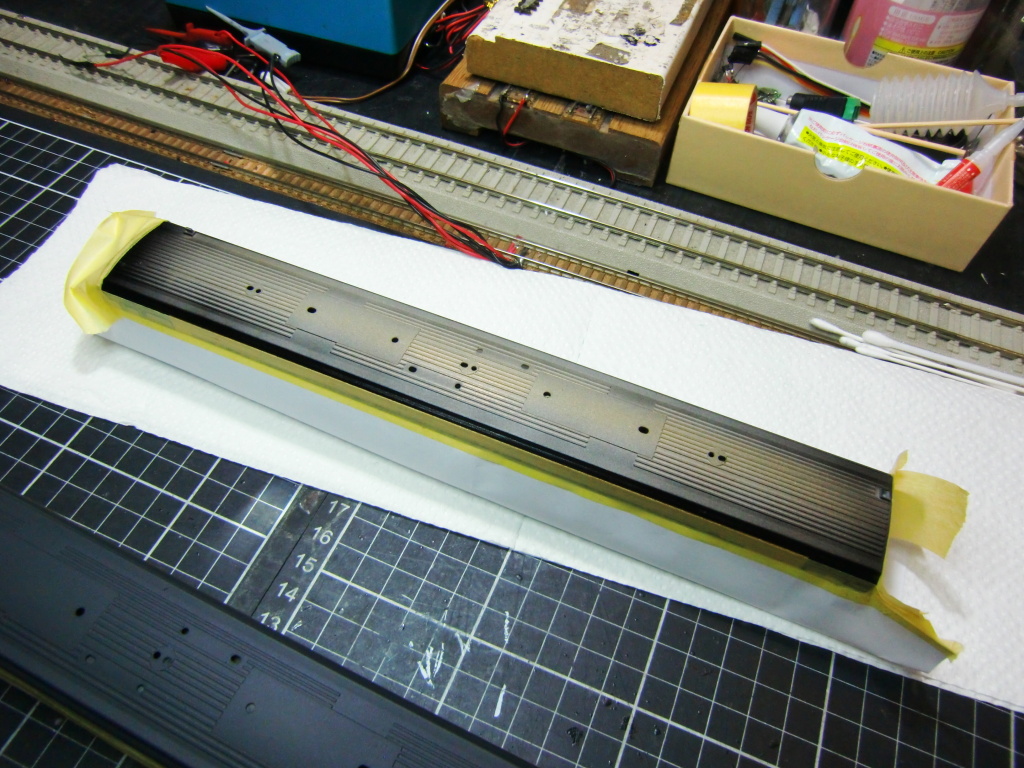
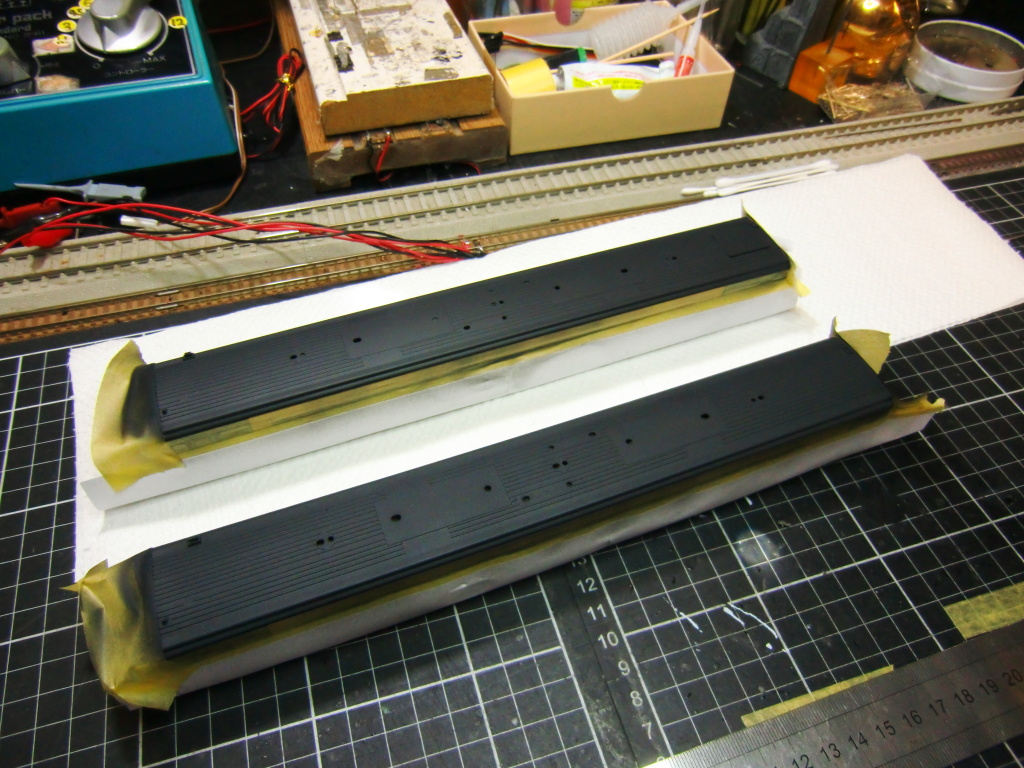

正面窓右は、裏面からマスキングを行ってから、ブラックで塗装します。
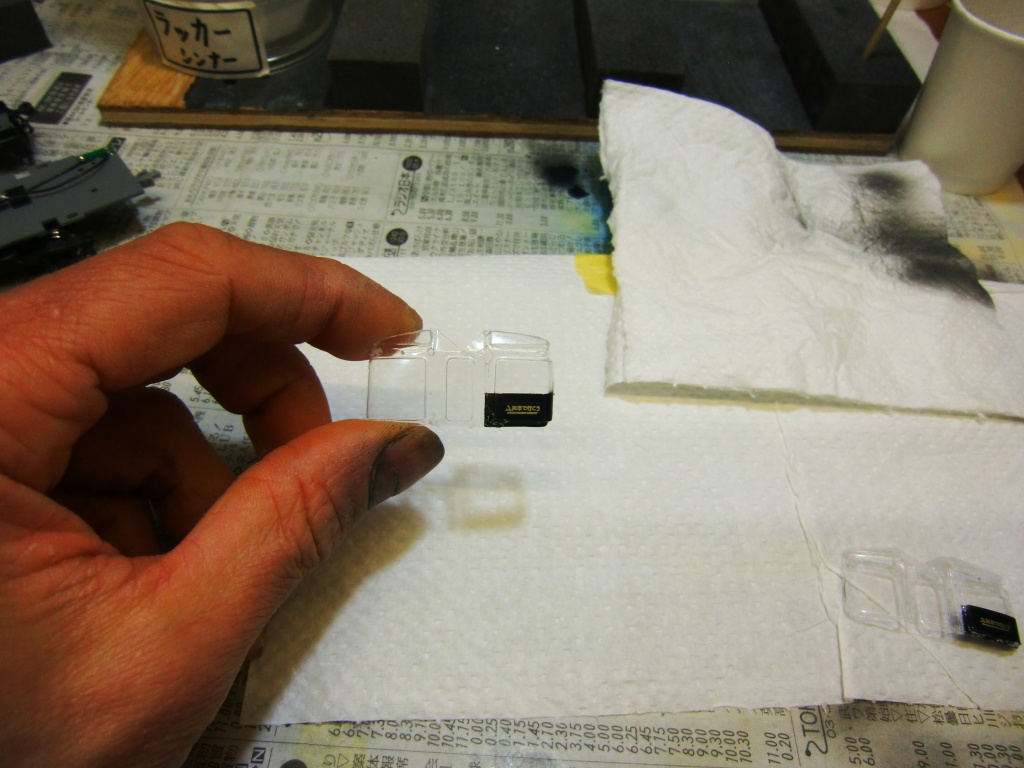

この時点で塗装におけるすべての工程が完了したことになります。あとは、新規に追加したヘッドライトのユニットを組み込めば完成となります。あと2~3時間といったところでしょうか。
まもなく完成・・・・・
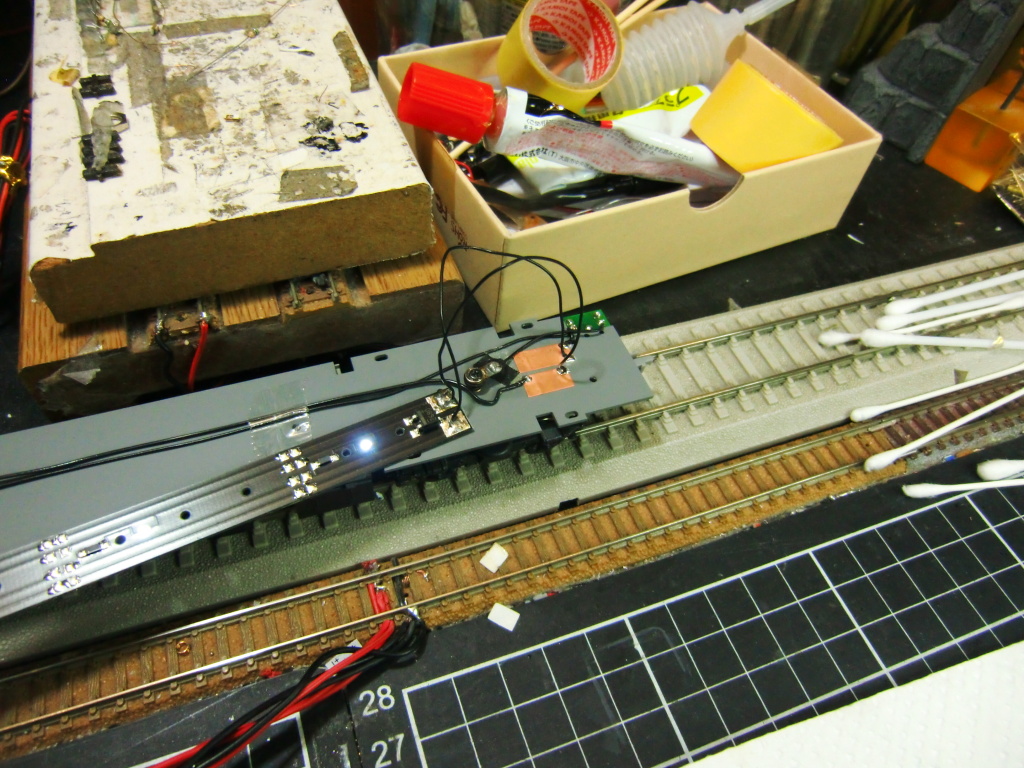
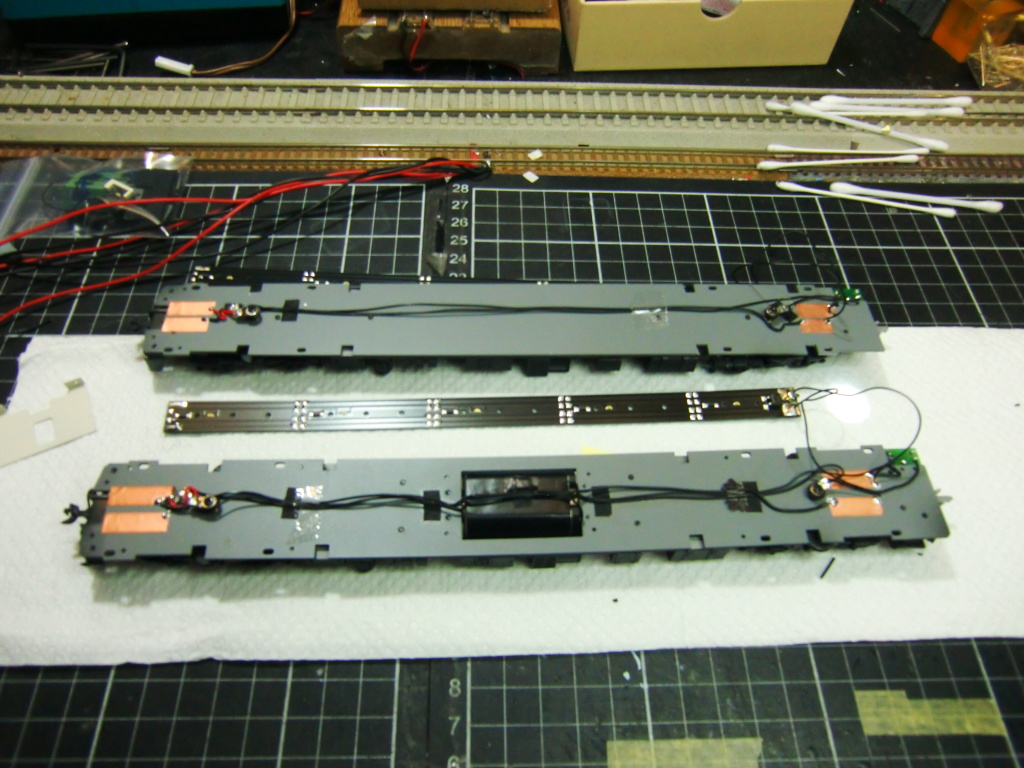
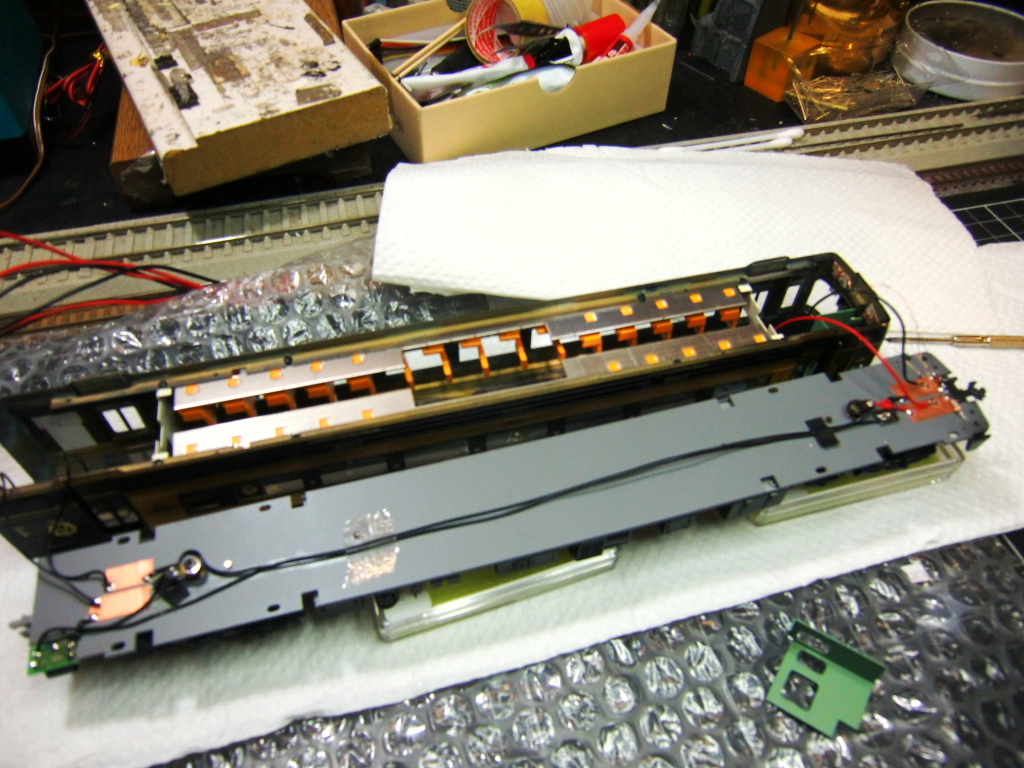









最後にライトレンズを入れて作業は完了となります。当然ながら追加したヘッドライトも点灯するように改造してあります。

ご依頼者様にお引き渡しが完了いたしました。
まずは車体の傾きのお直し作業です。

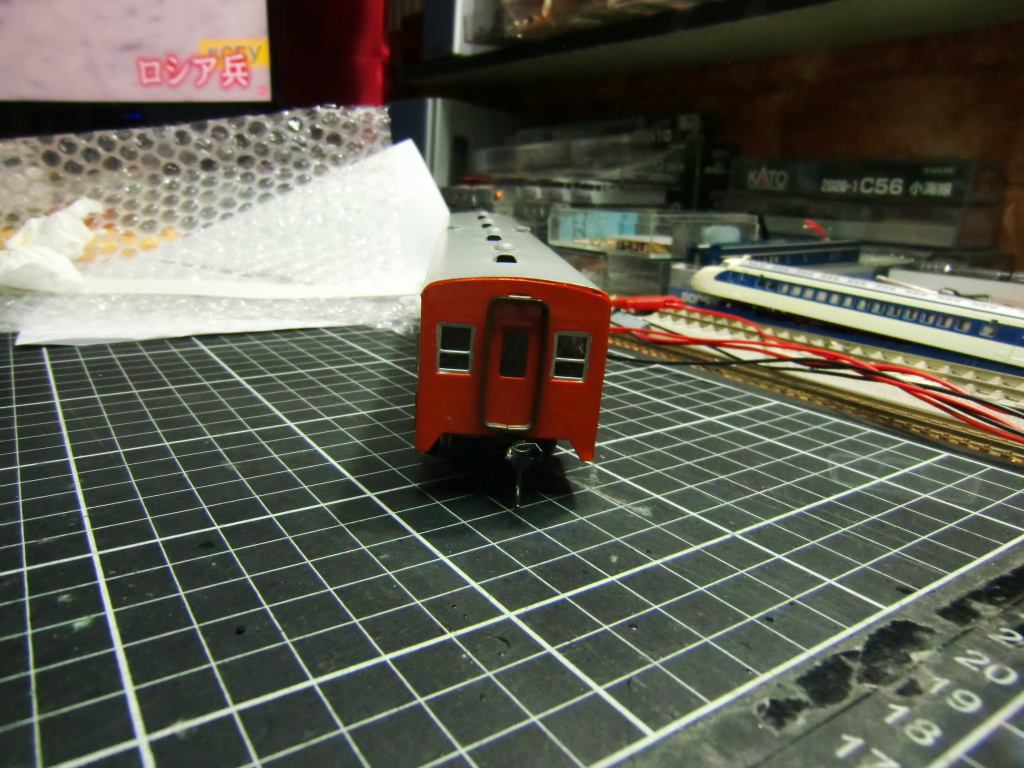
現状はこのような感じです。かなり傾いていますね。
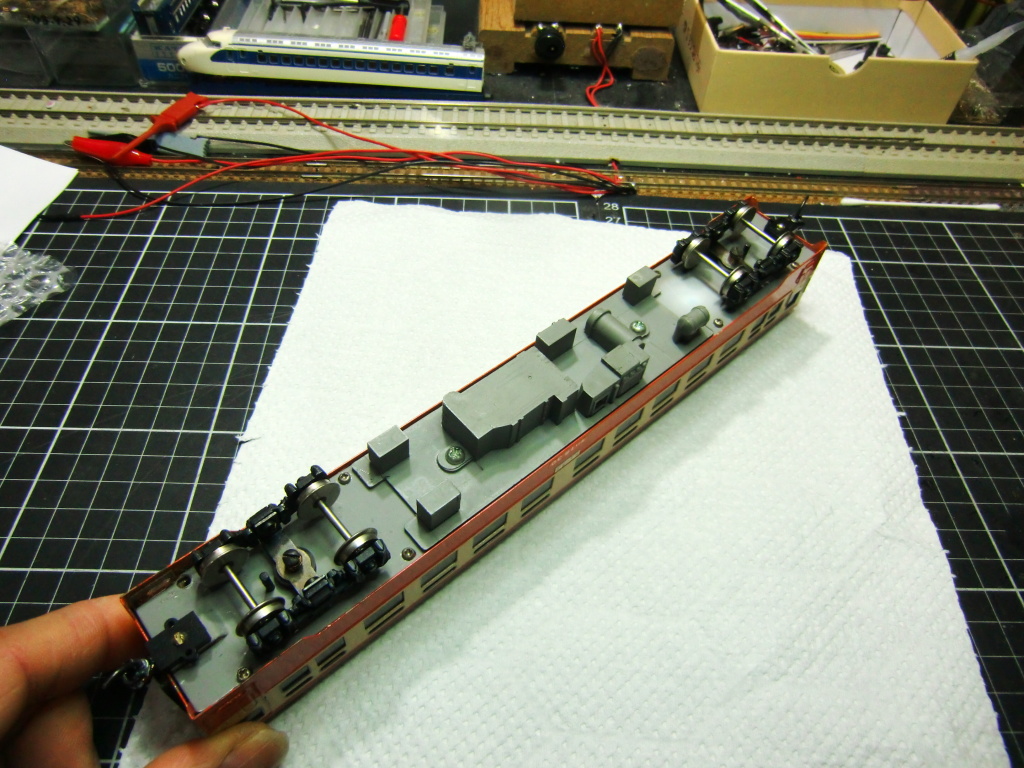
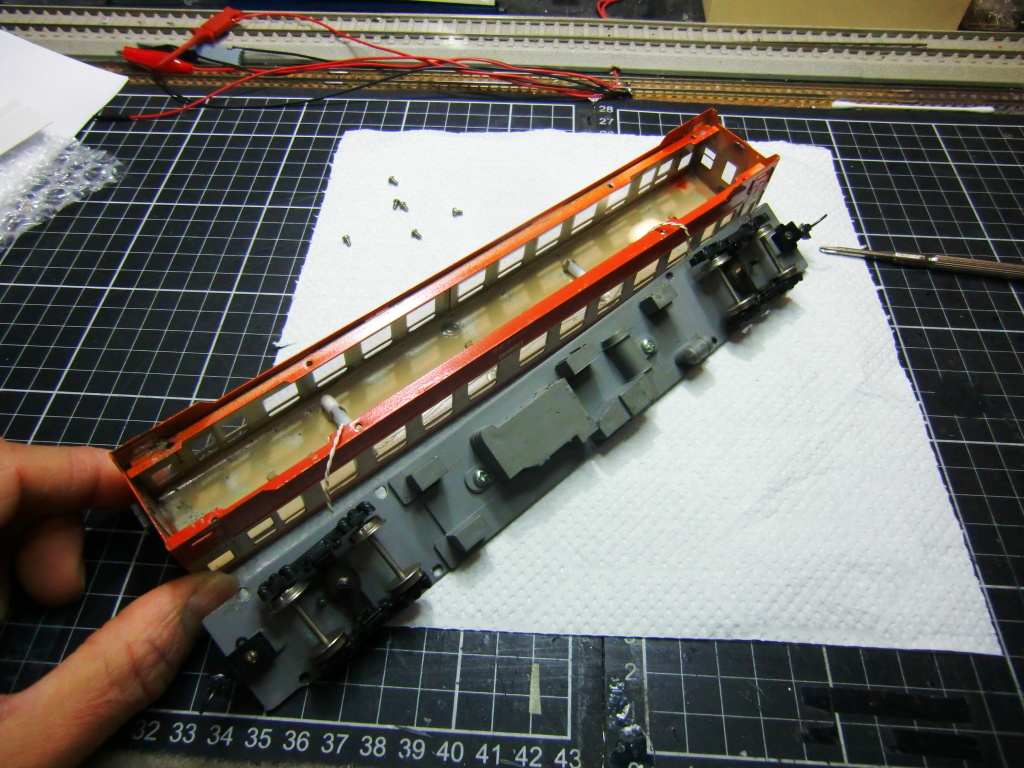
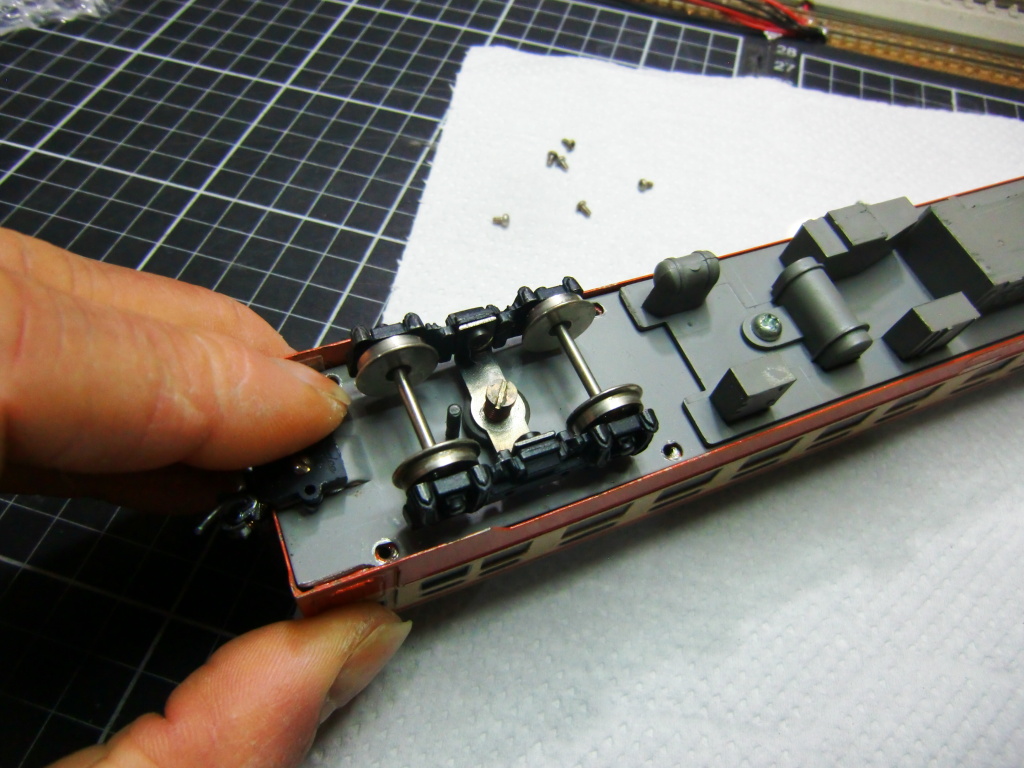
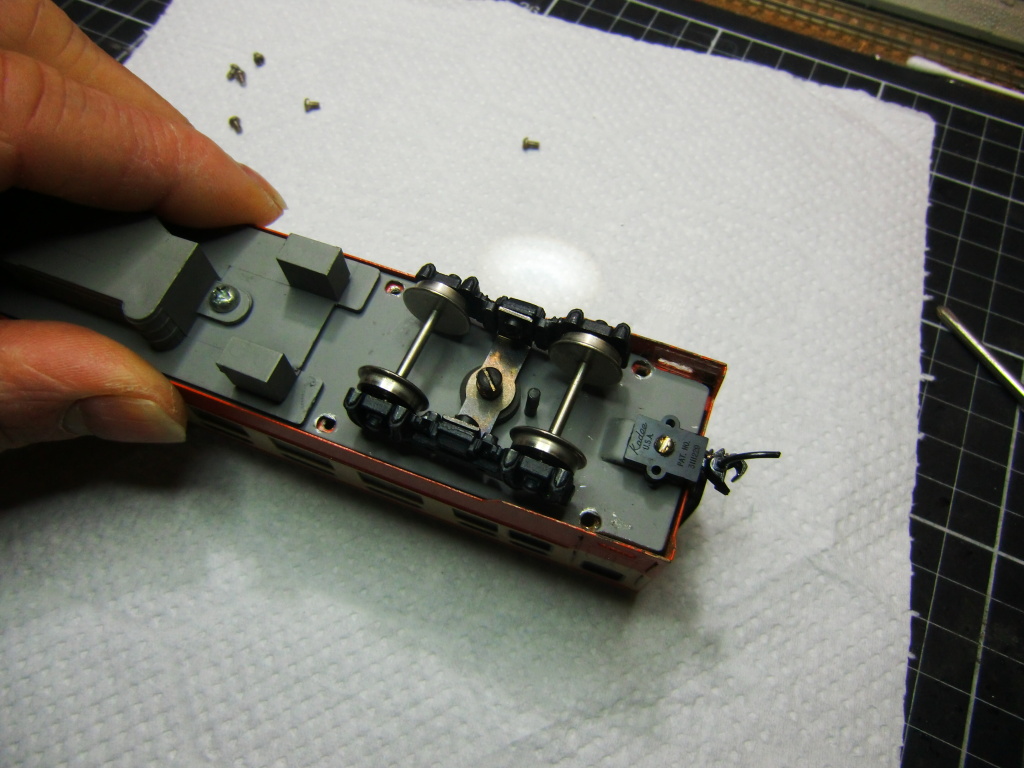
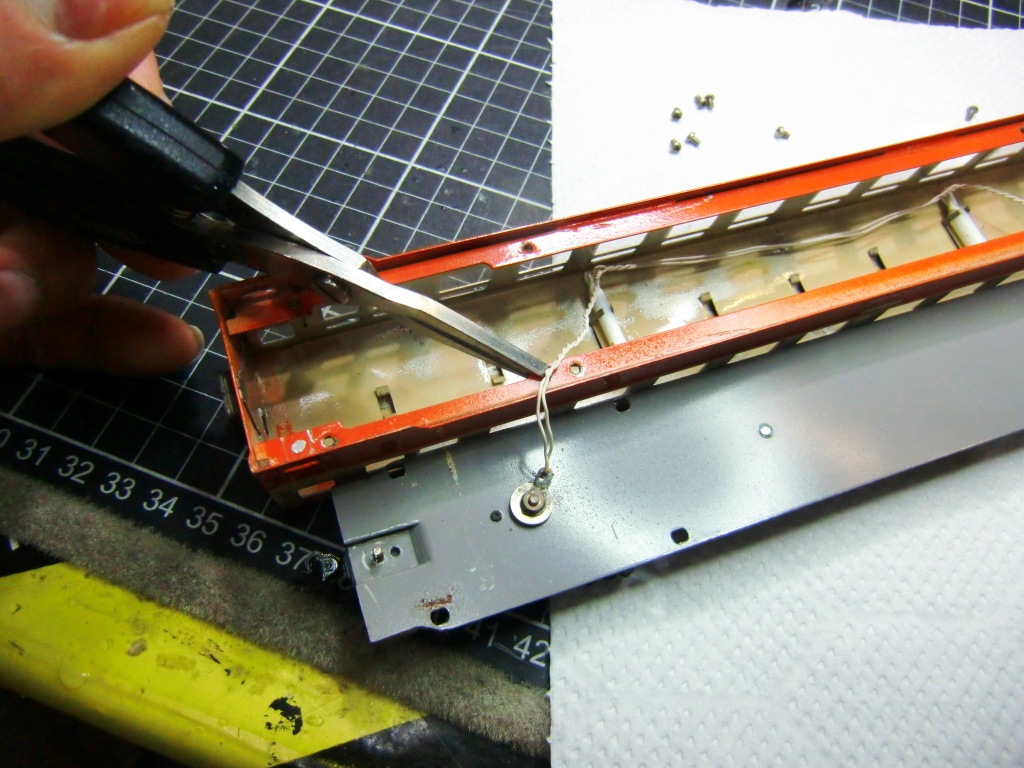
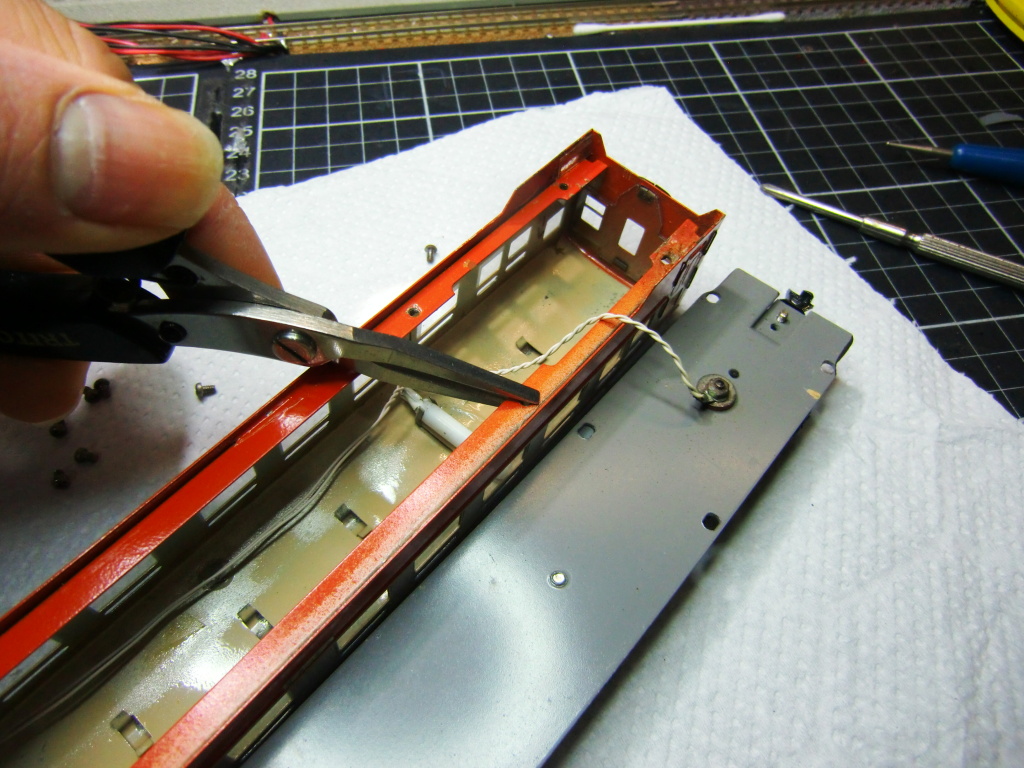
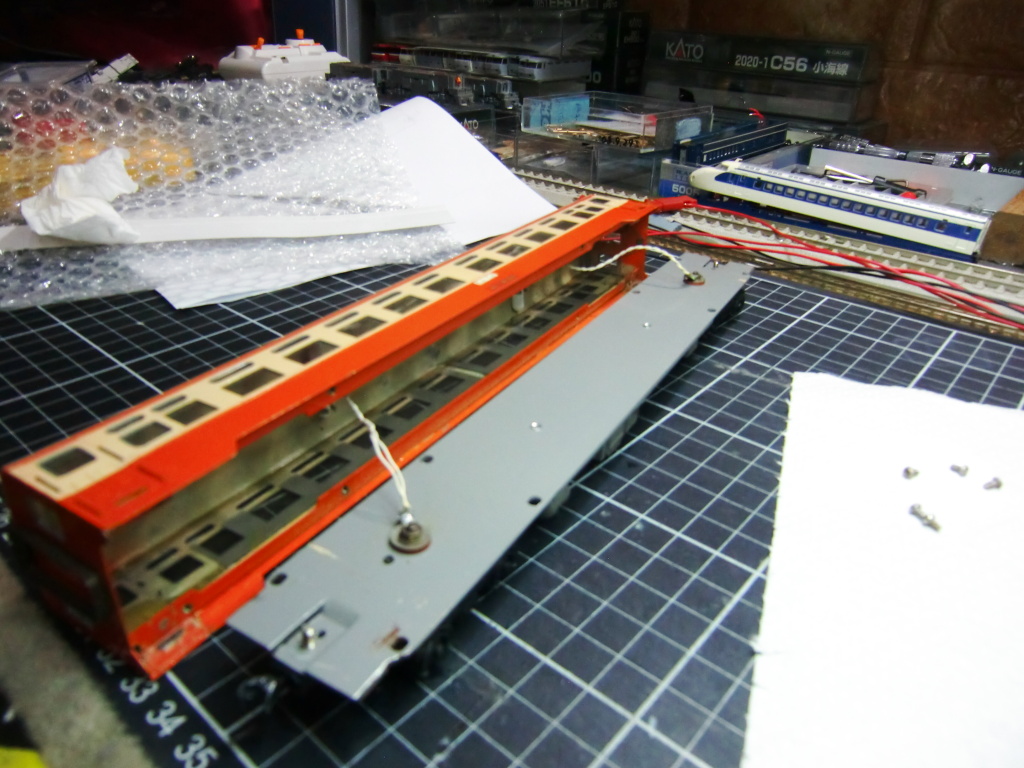

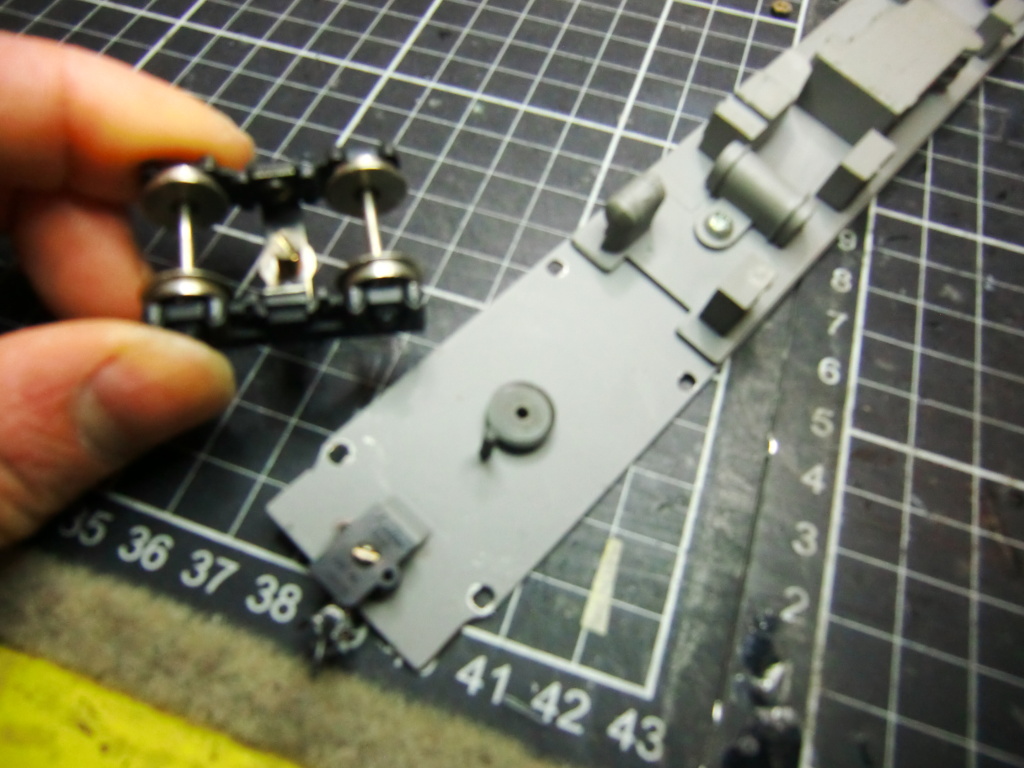
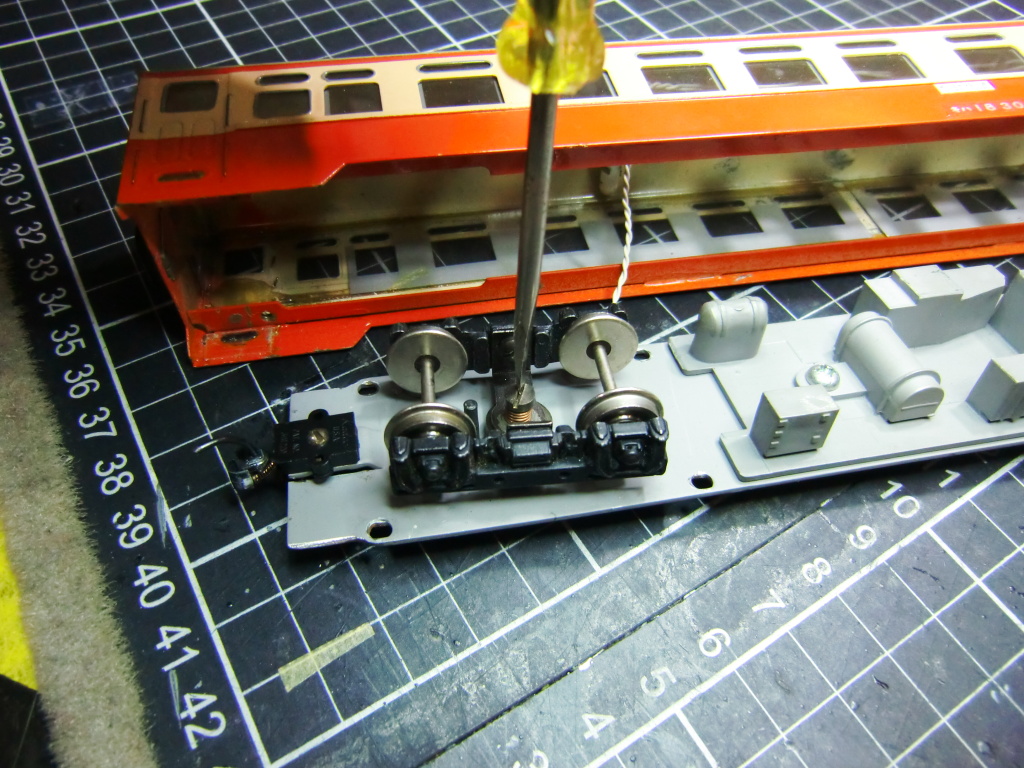


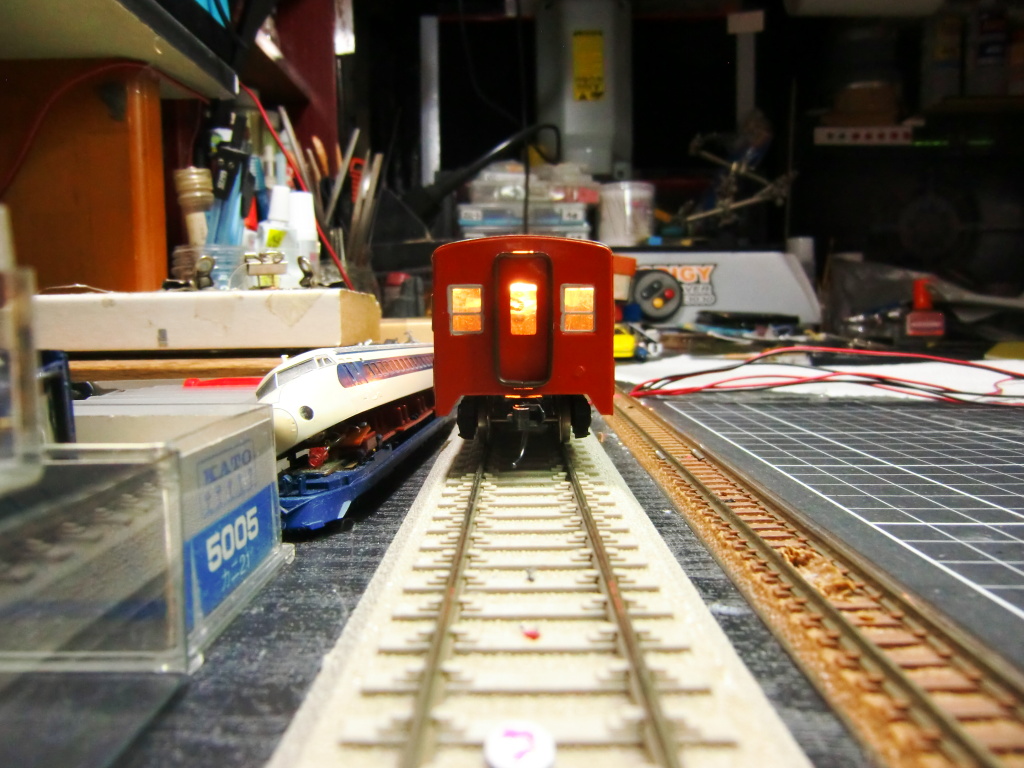
このようになりました。
続いての車体はこちらです。室内灯が片半分点灯しないとのことです。


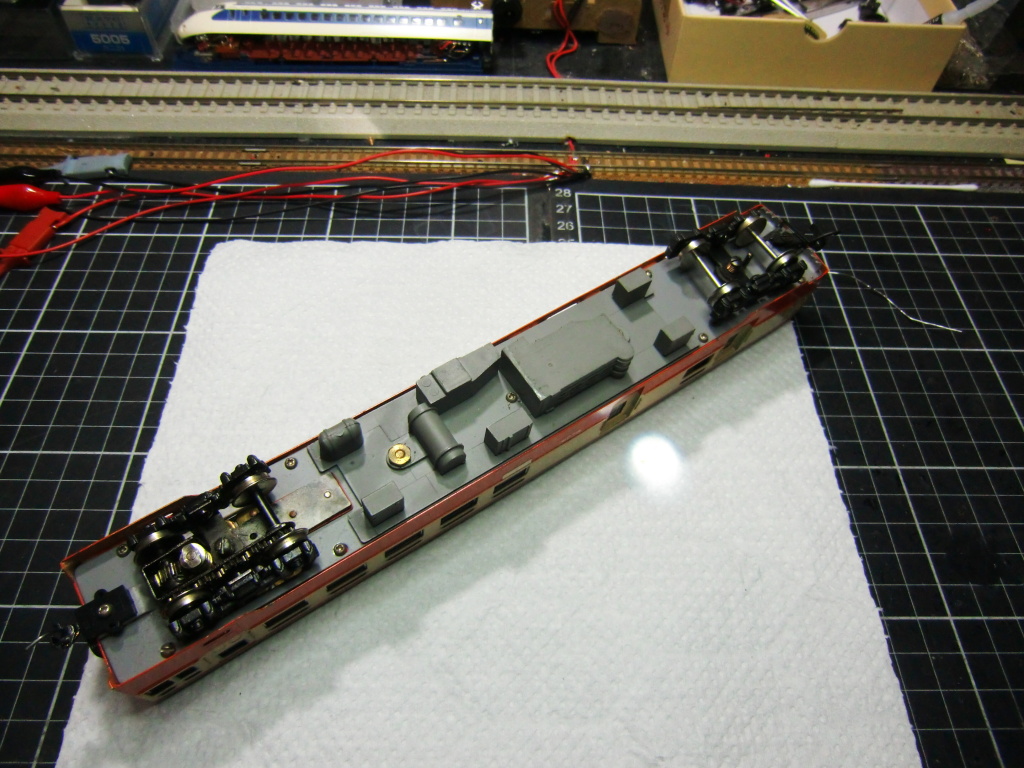
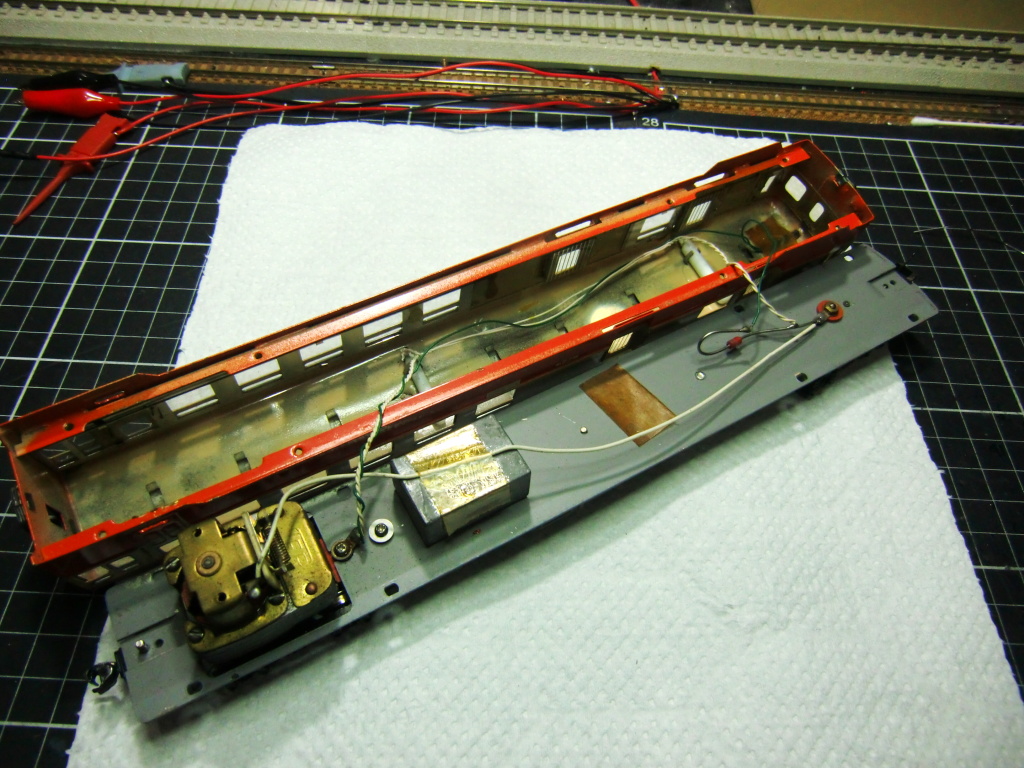
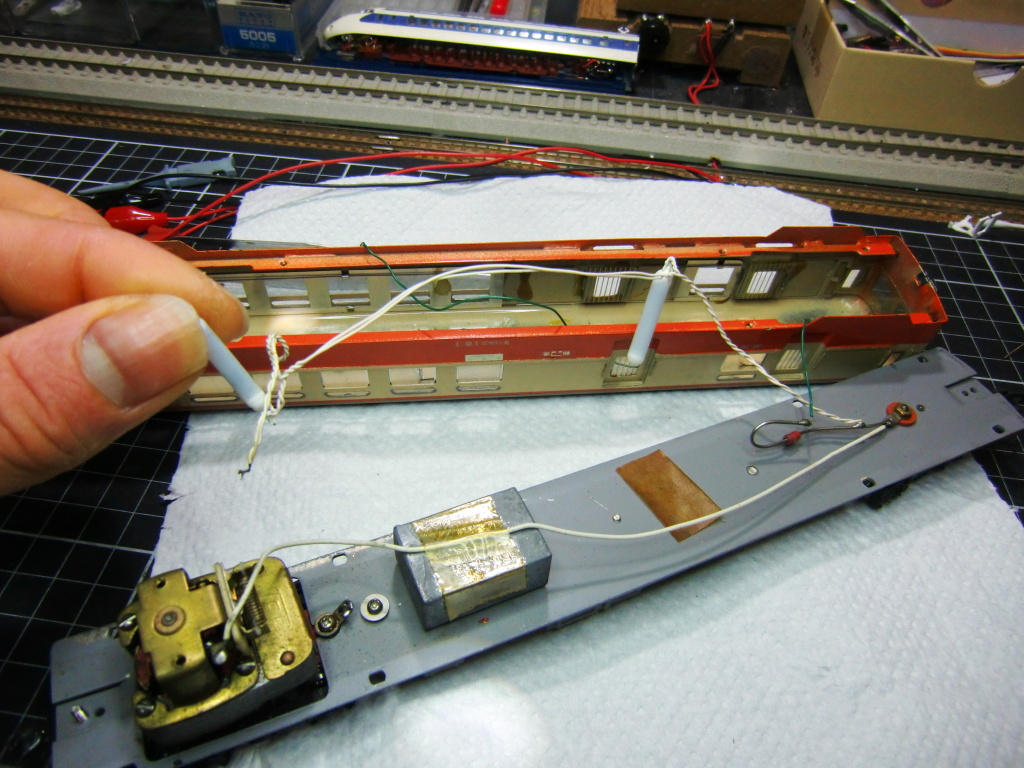
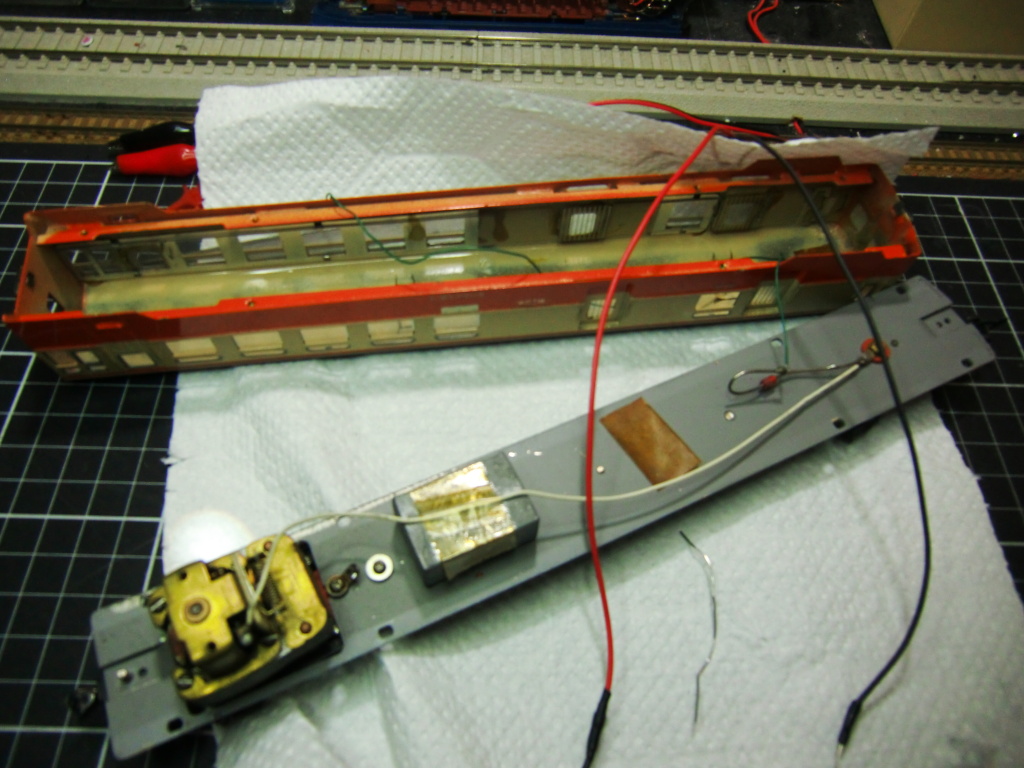
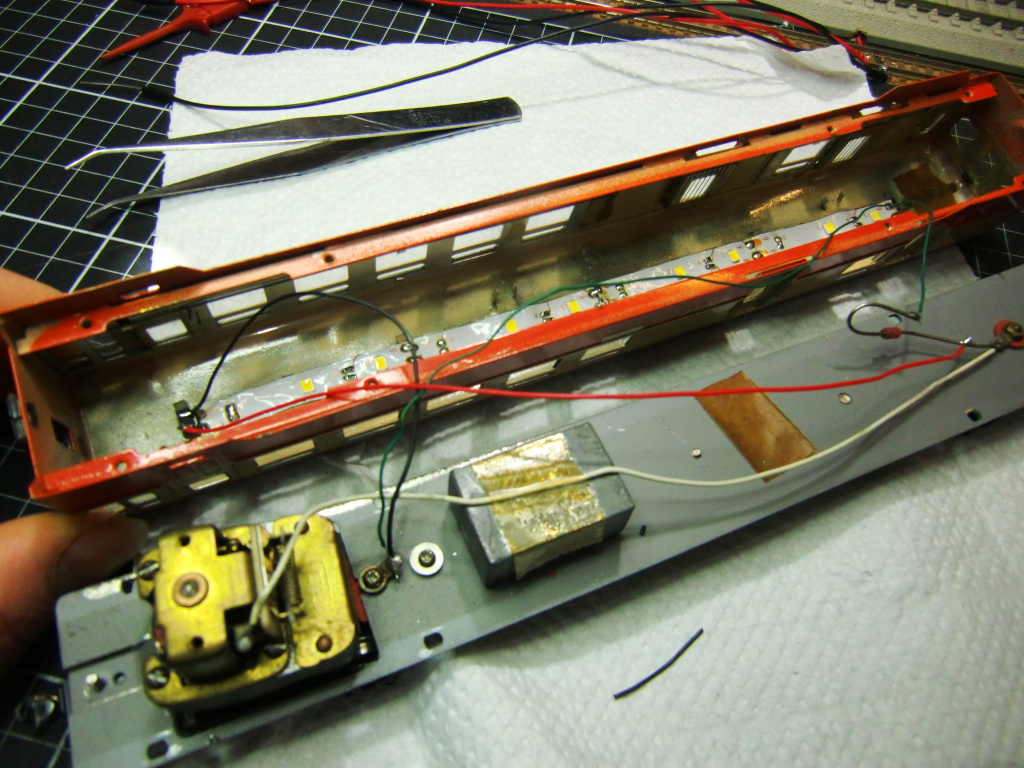
光源はLEDタイプに置き換えていきます。
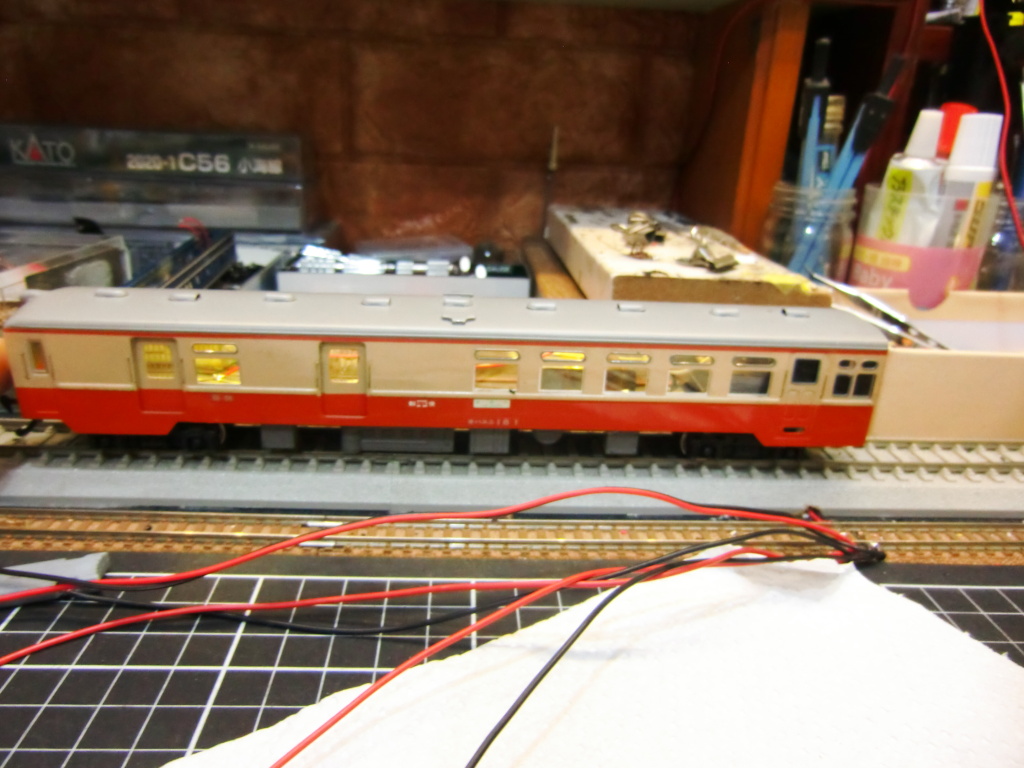

車内全体が均一に点灯するようになりました。

さて、今回お直しする車両の中で一番大変そうな車体です。

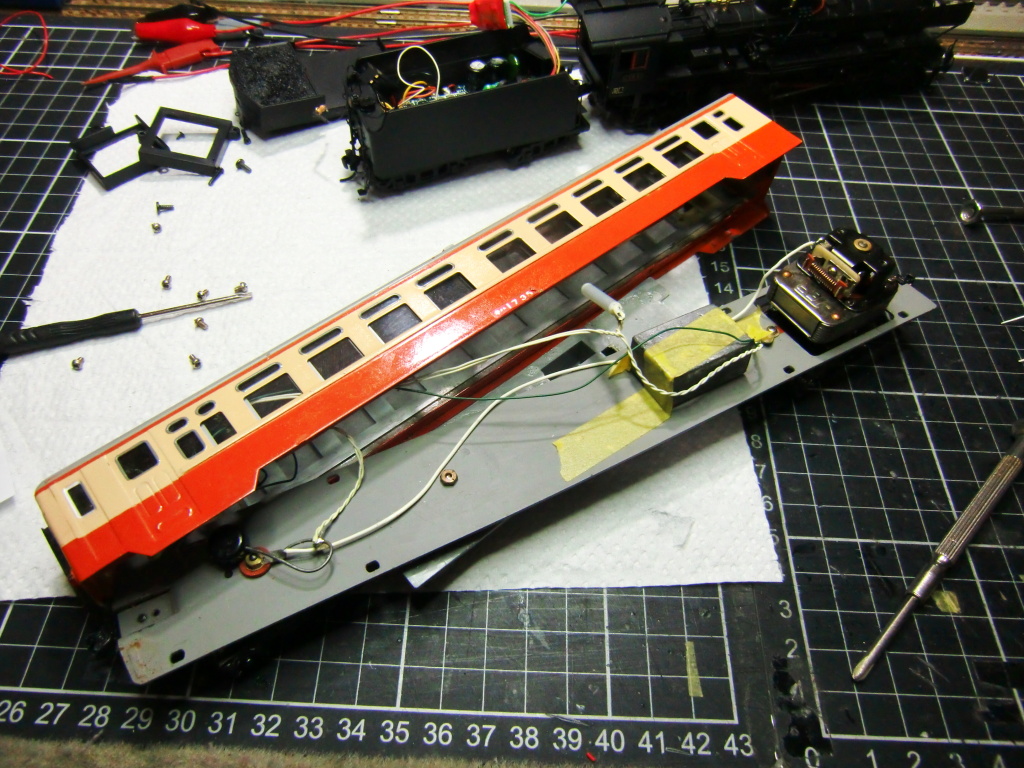
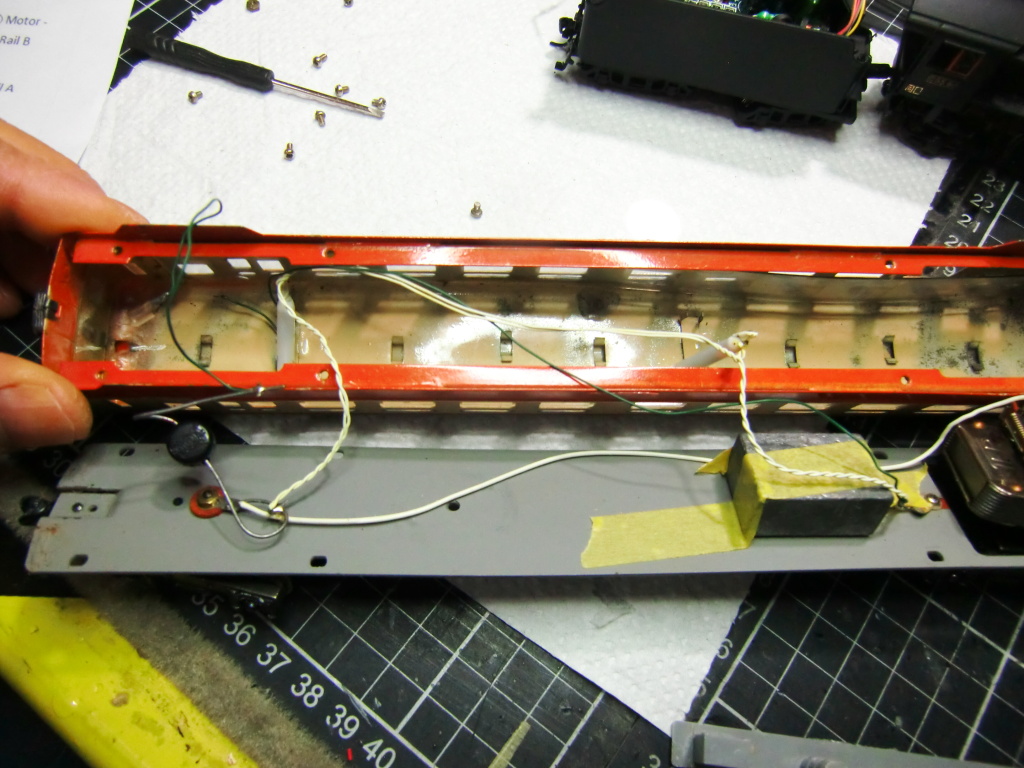
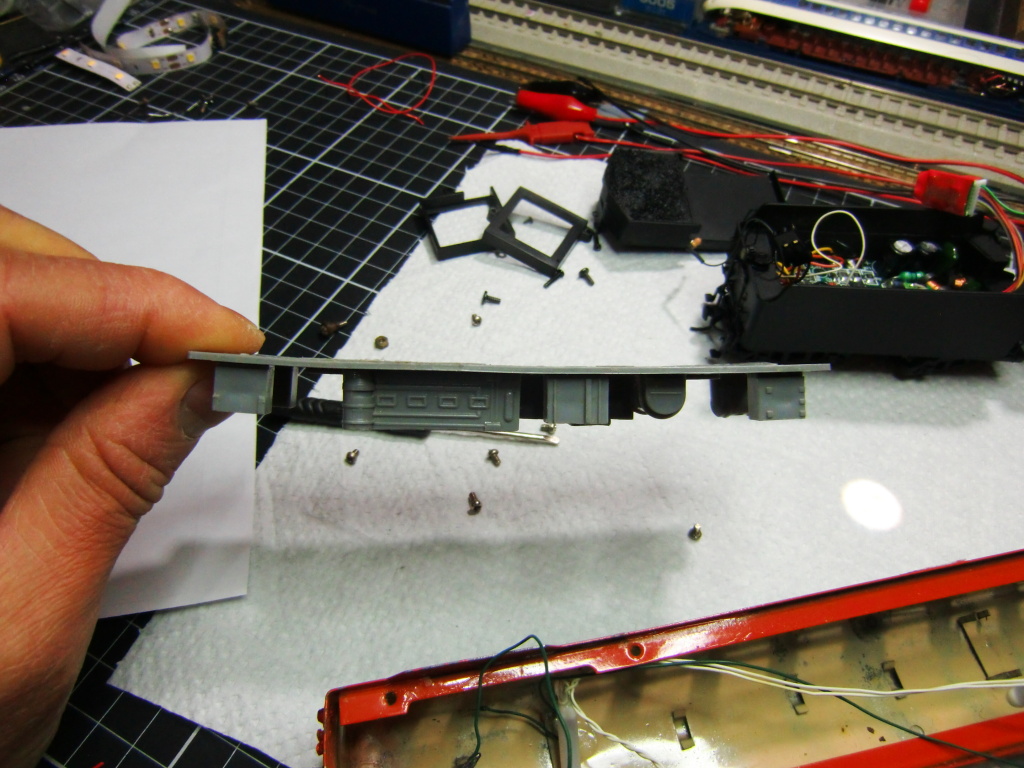

分解して歪みを補正していきます。
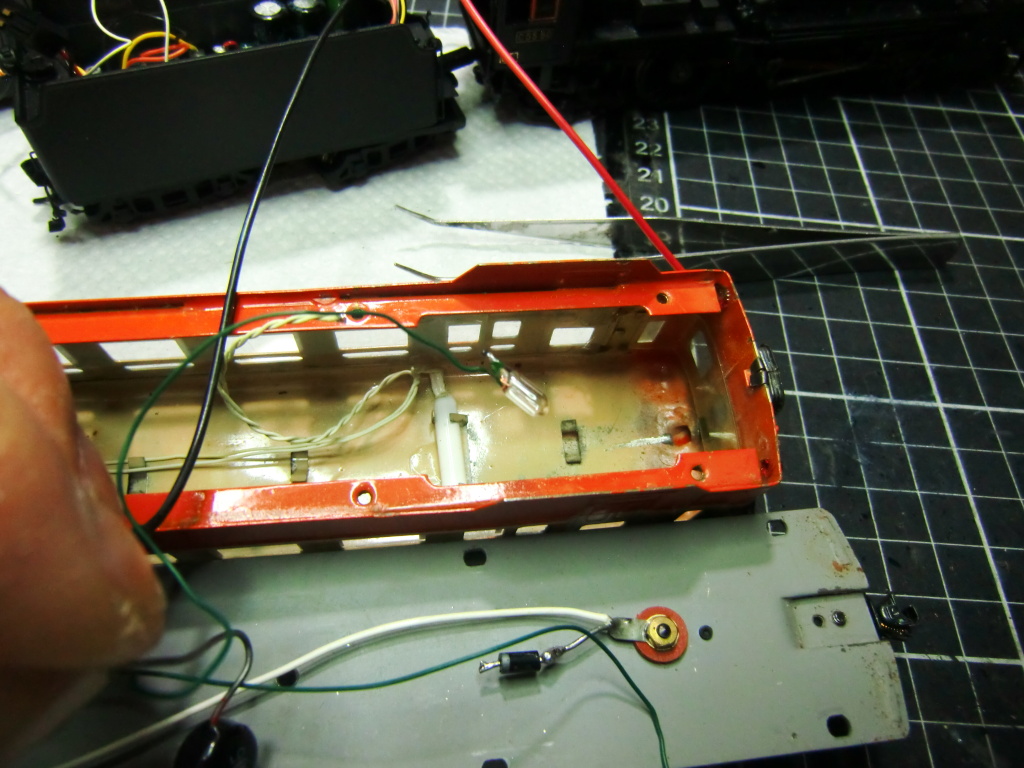

モーター内部も徹底したメンテを行います。このようにきれいになりました。
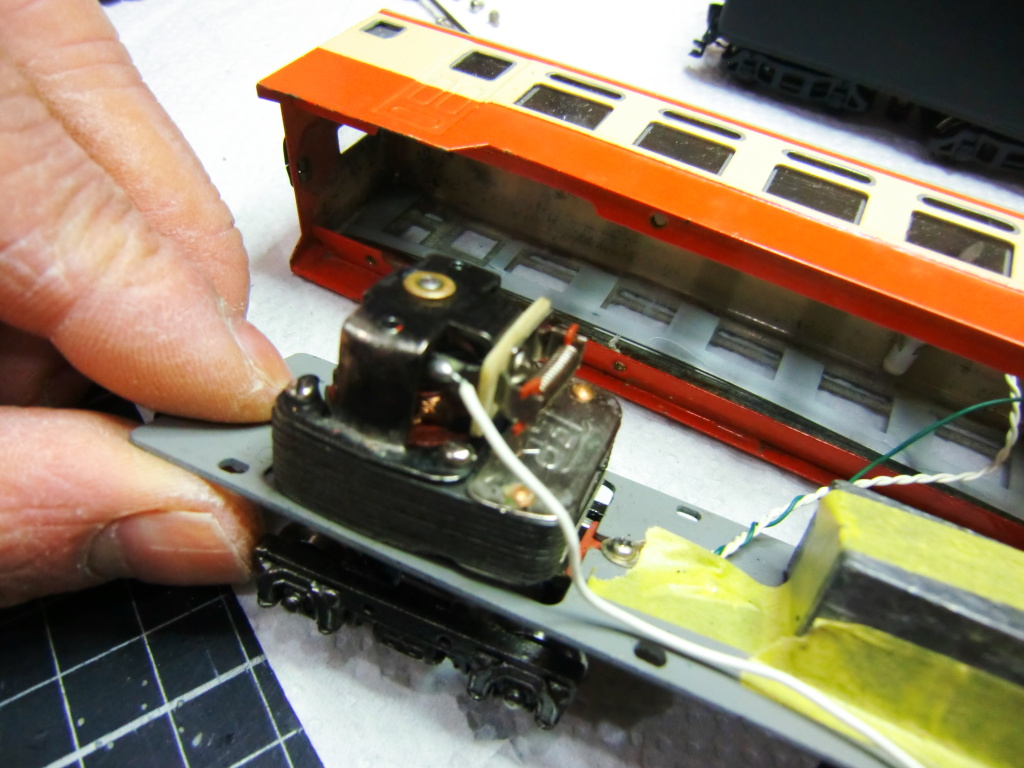
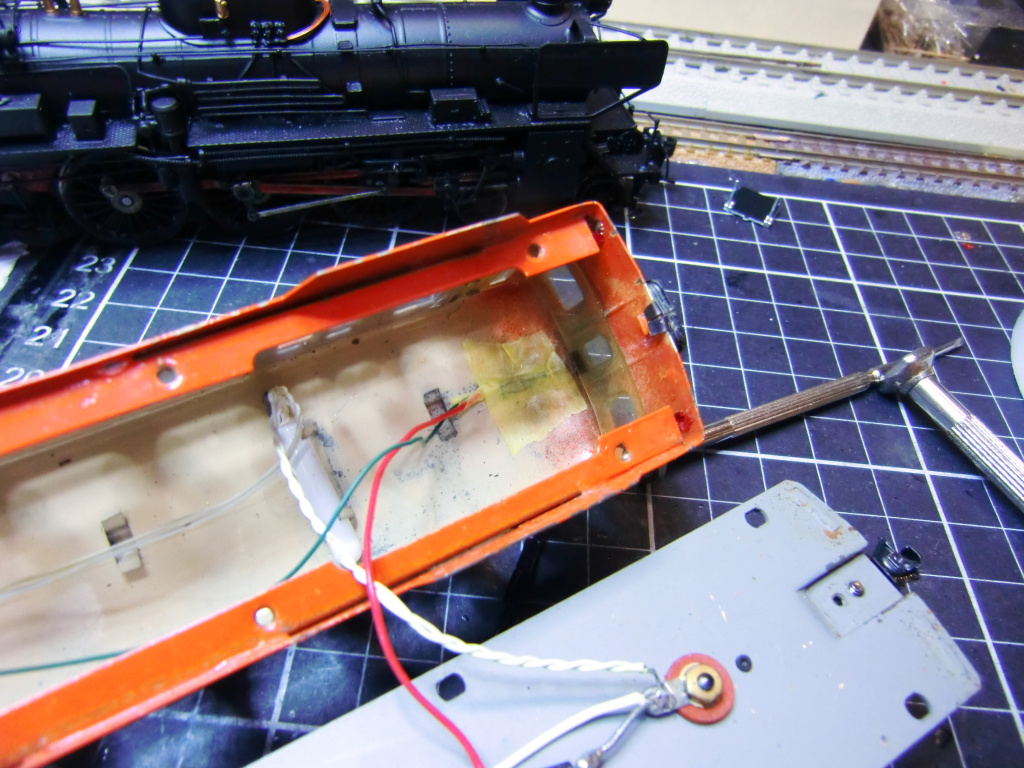
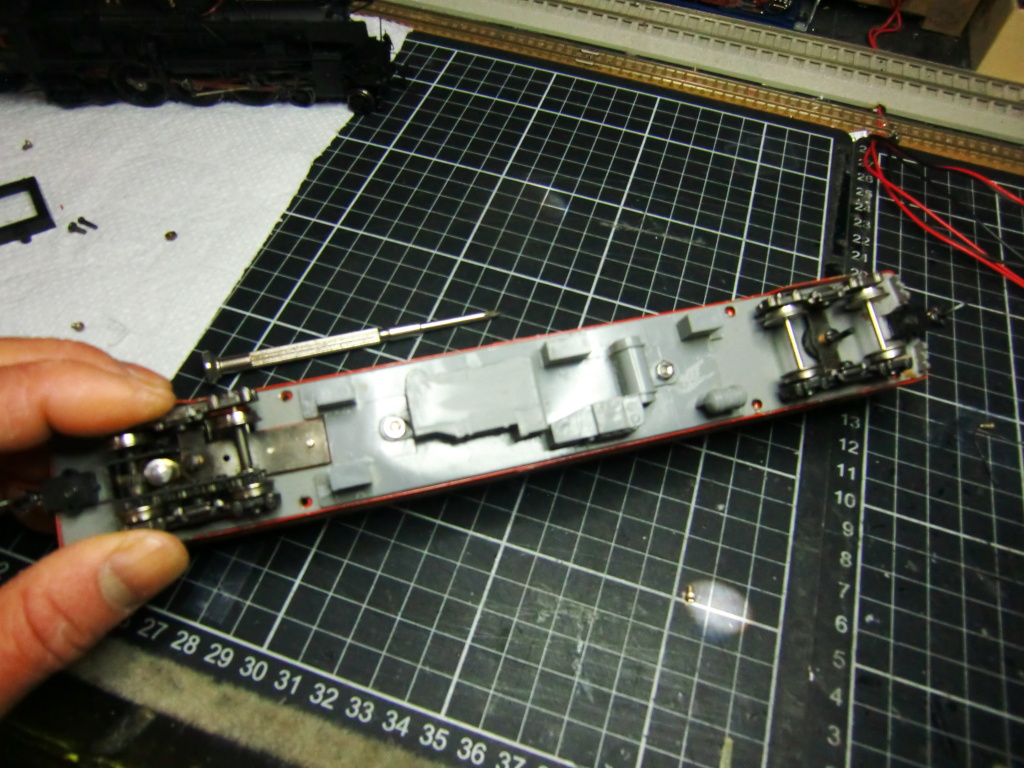

ヘッドライトも玉切れしてましたので、明るい電球色LEDに置き換えました。

すべての作業が完了しました。


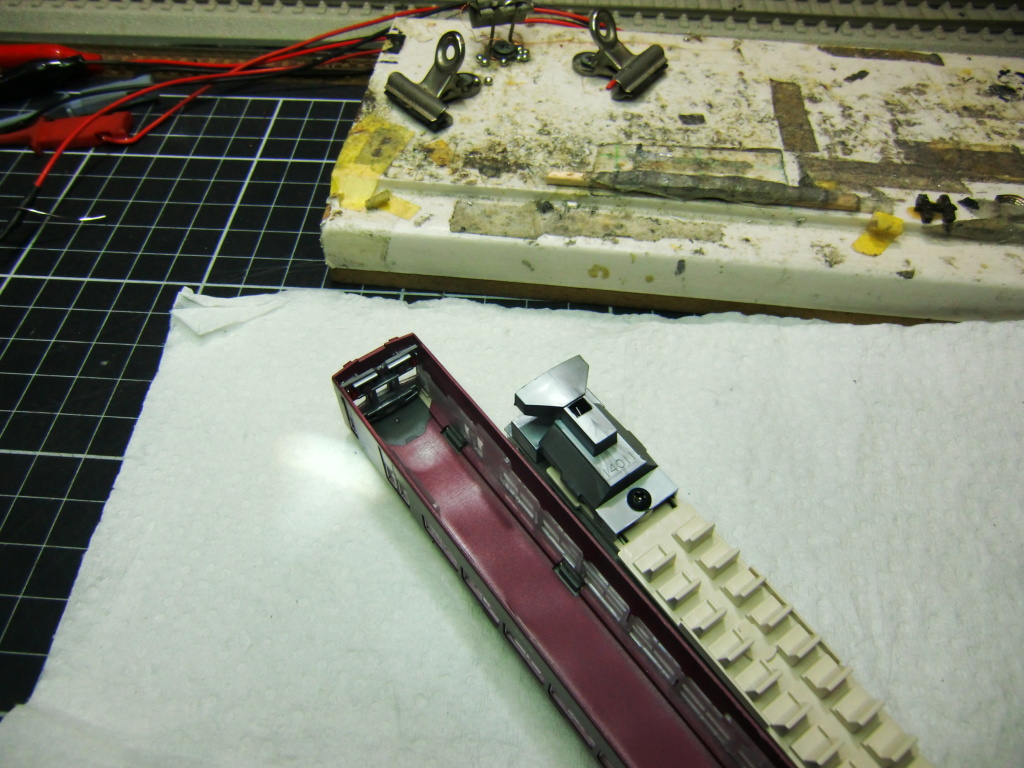
一通り分解してから作業手順を考えていきます。客車のテール点灯化改造よりもずっと難しい作業となります。


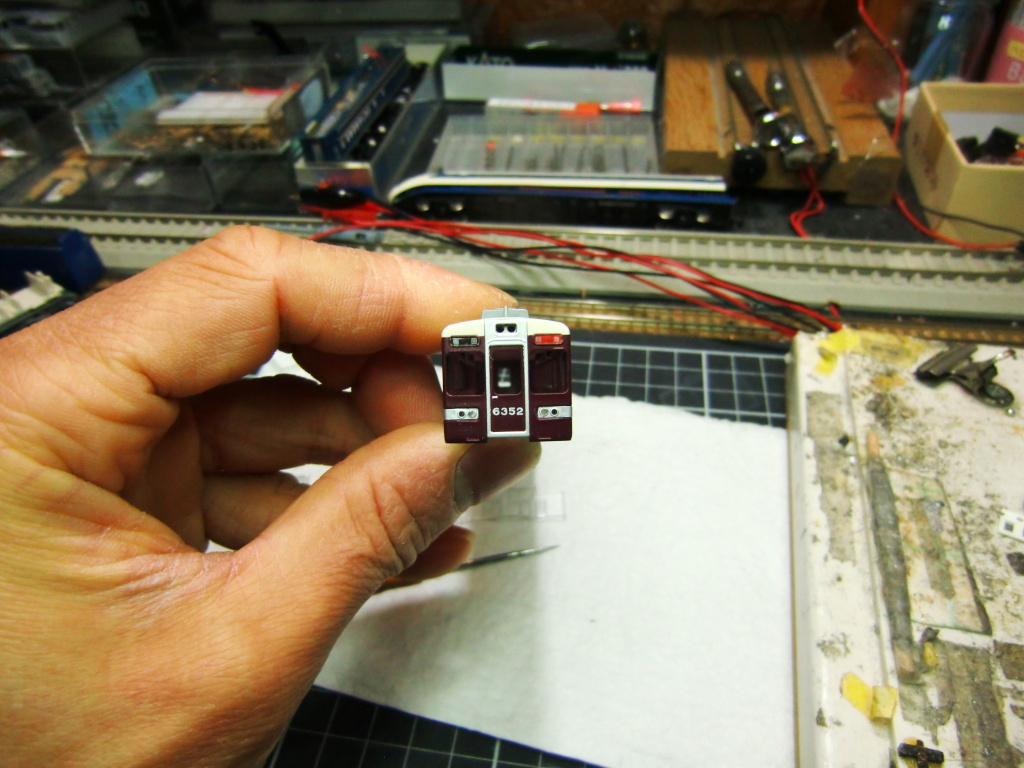
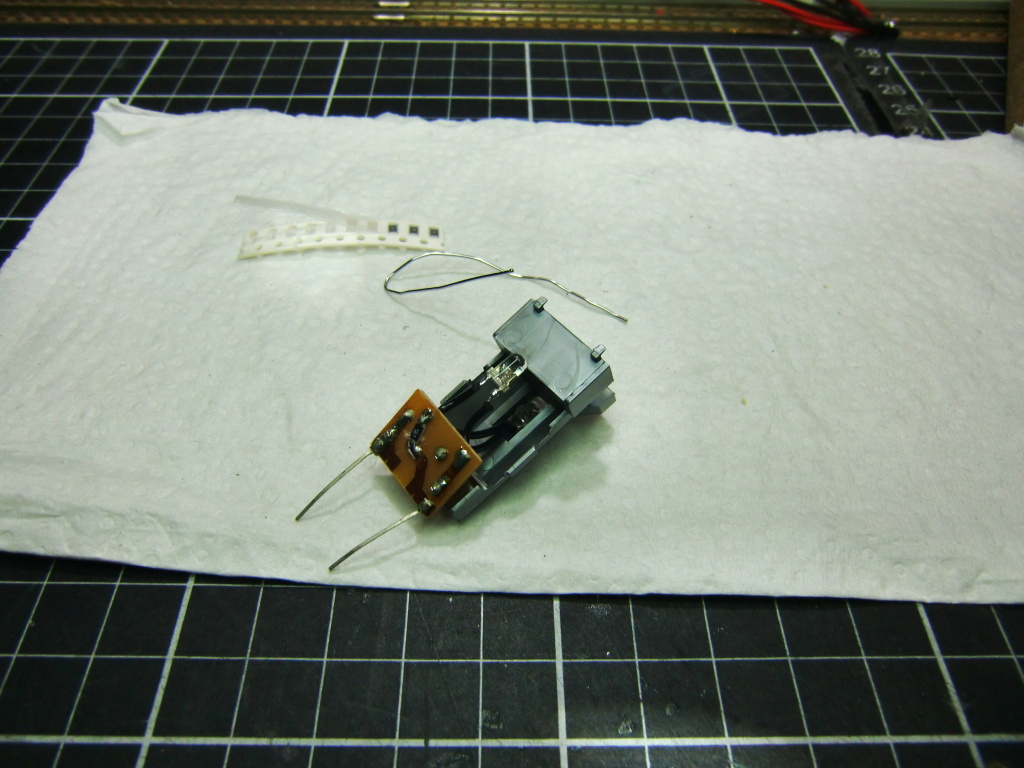
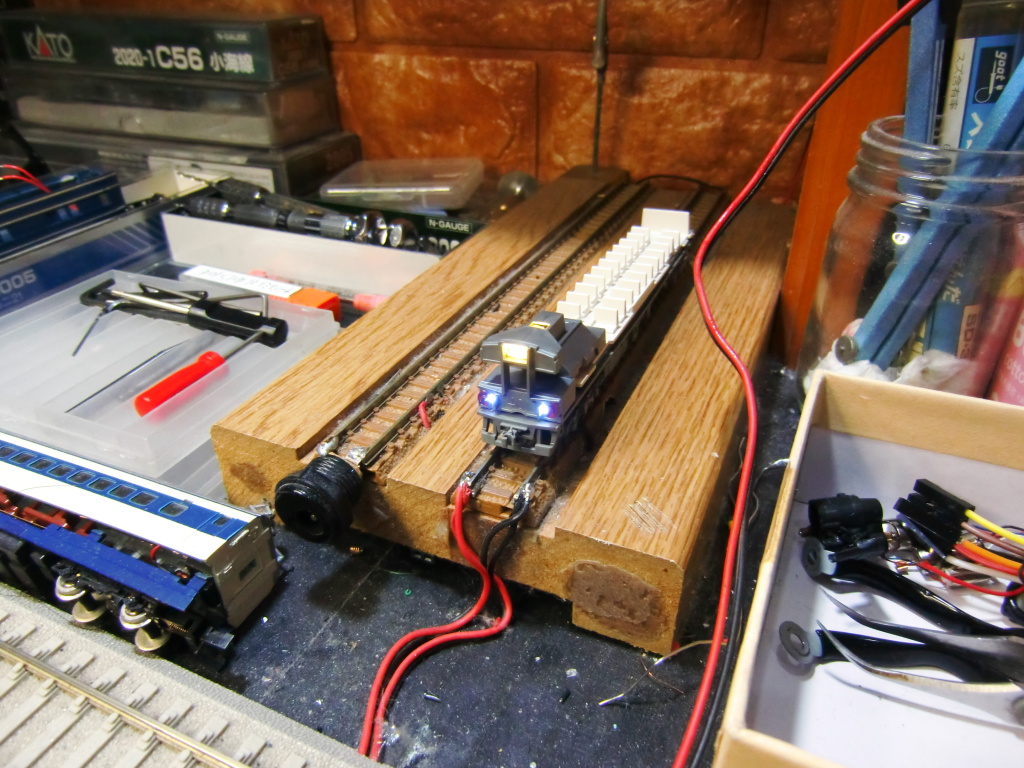
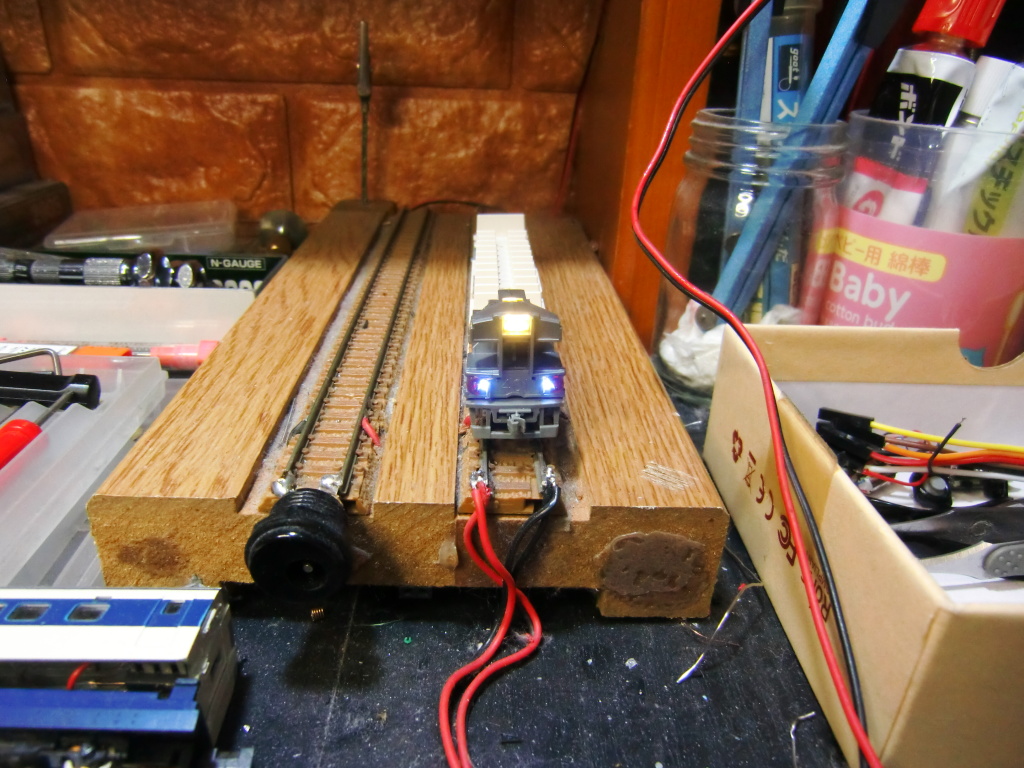
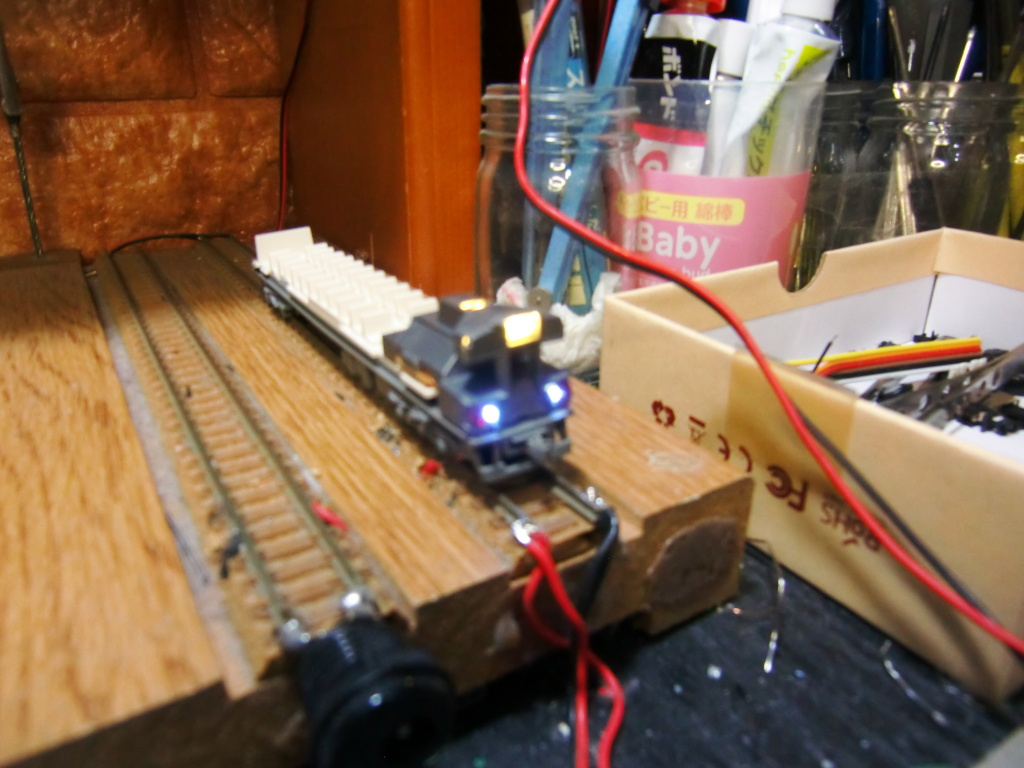
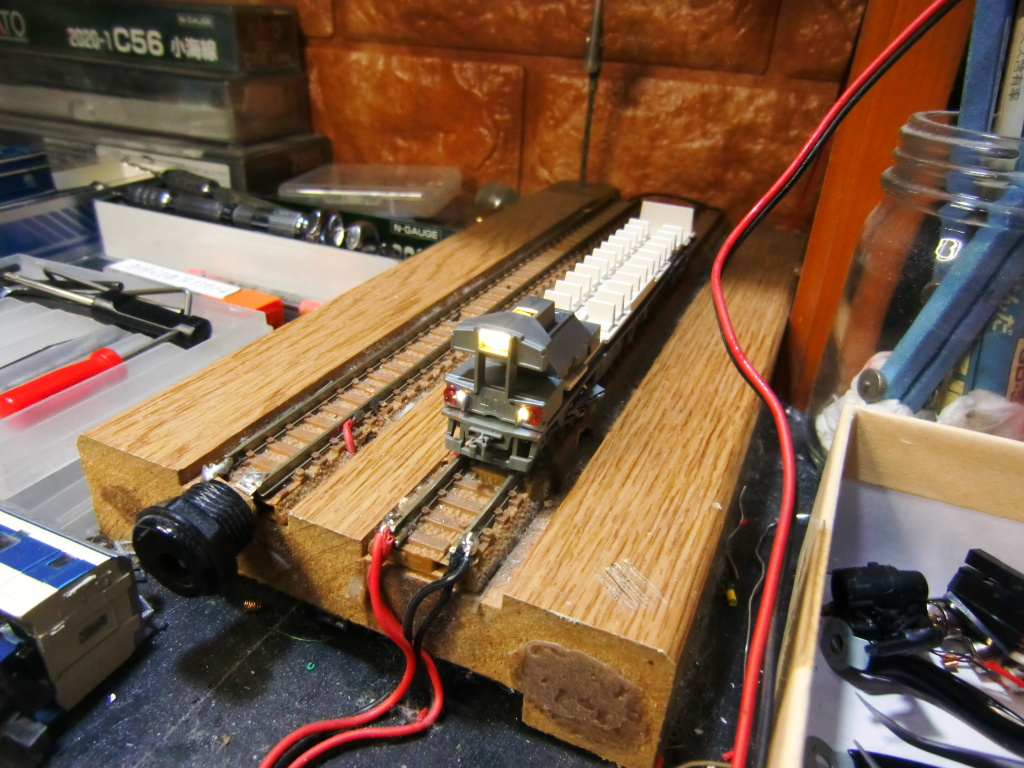
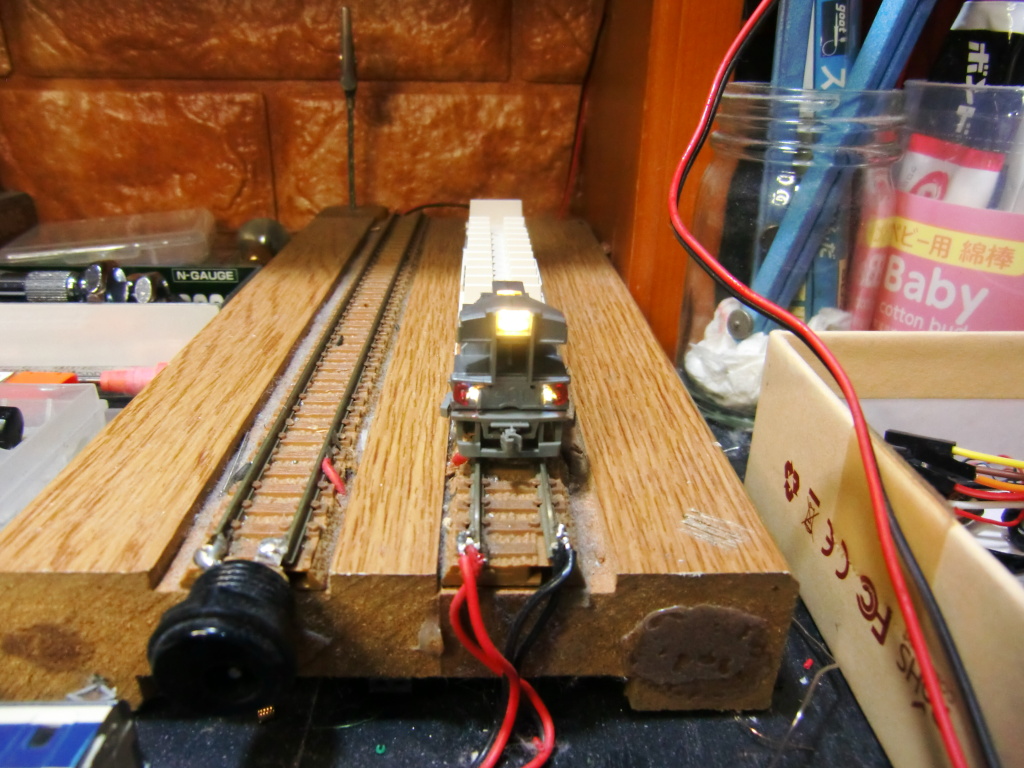
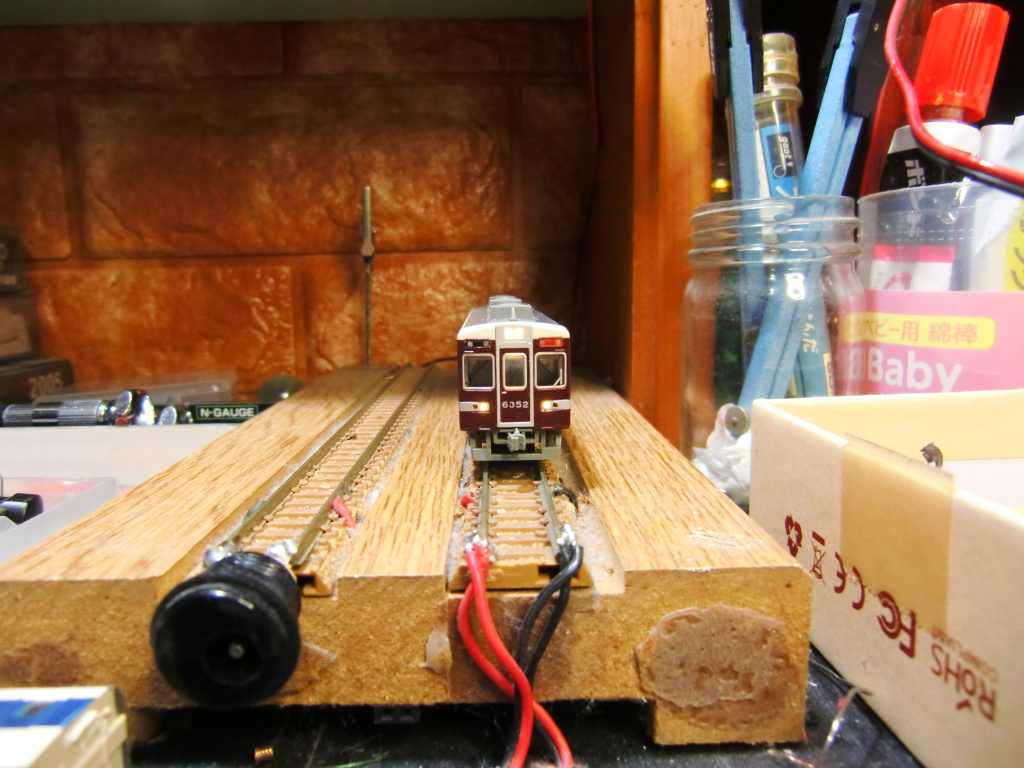
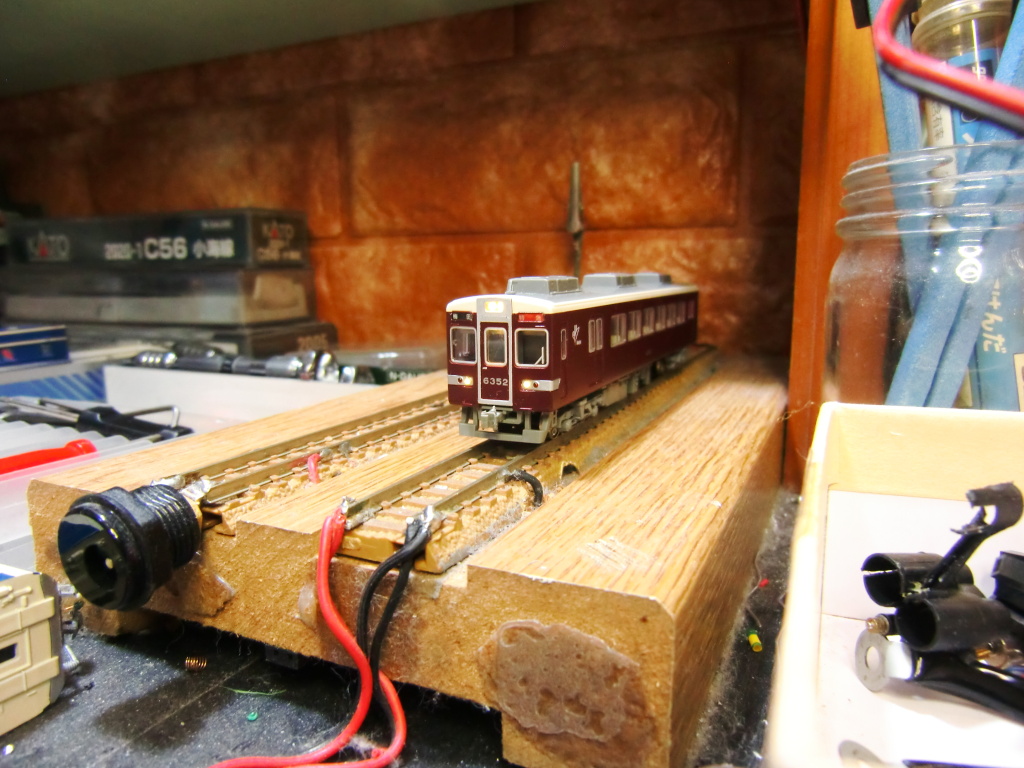


作業完了です。
今回は、ヘッドライトを「青緑 or 水色」による点灯色をご希望です。なお、現状は電球ですのでLEDタイプへと変わります。


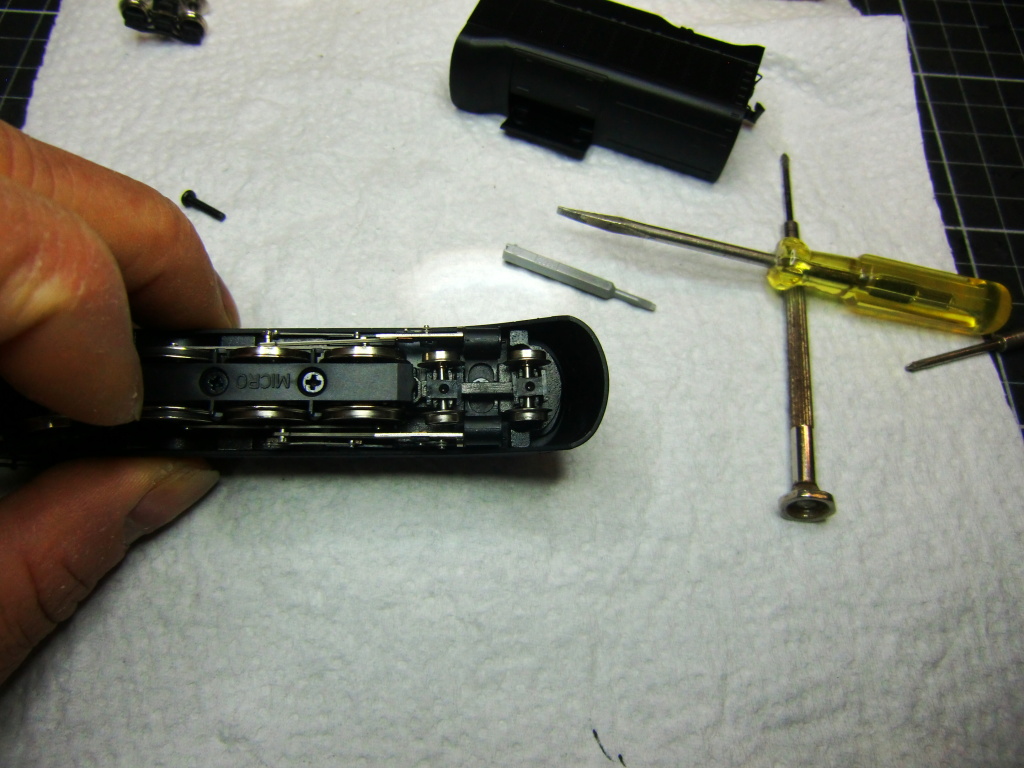
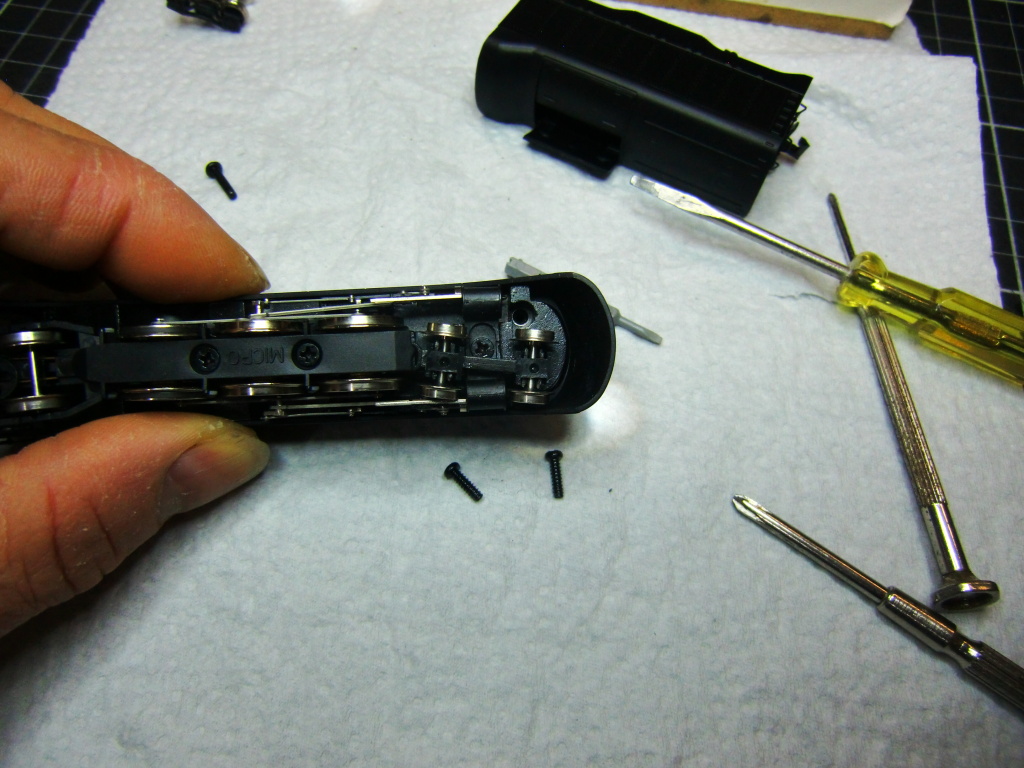


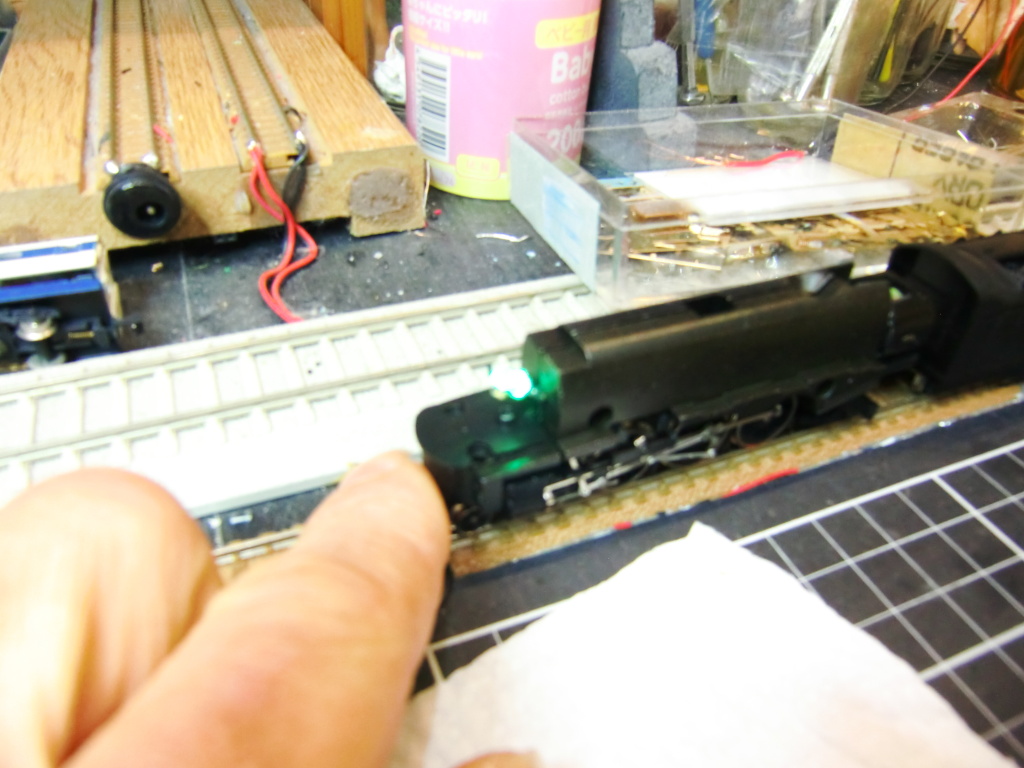
今回は、青緑仕様として組み込みました。

このような色合いとなりました。作業完了でございます。
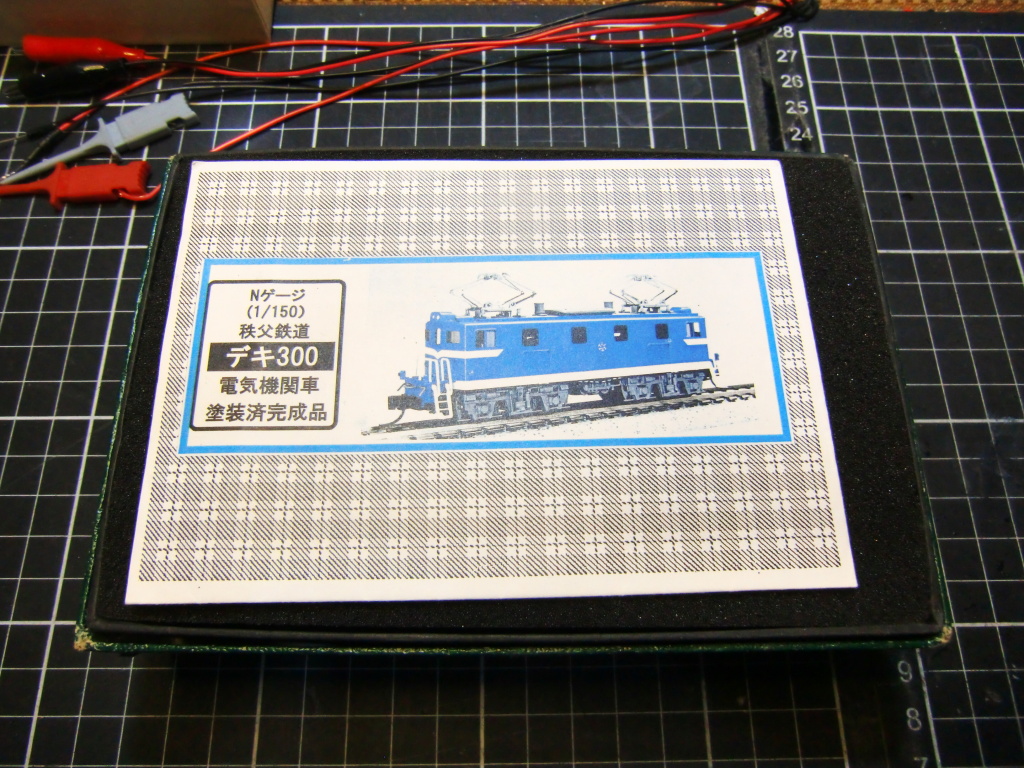
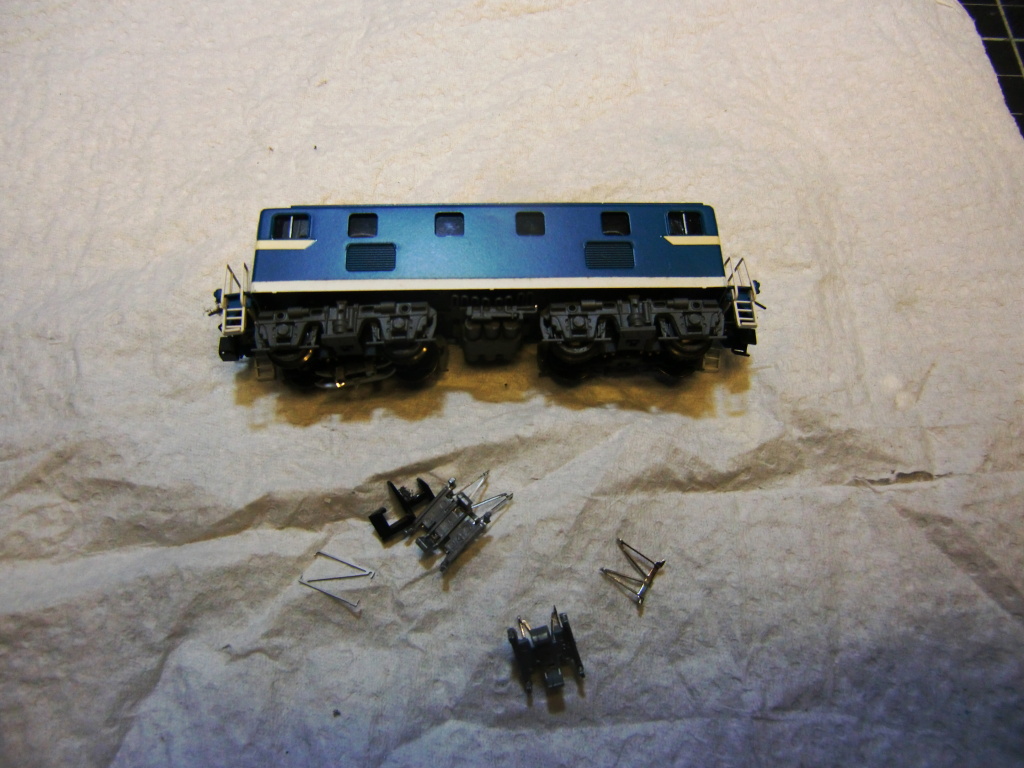
まずは確認ですが、パンタとカプラーが破損してついていません。
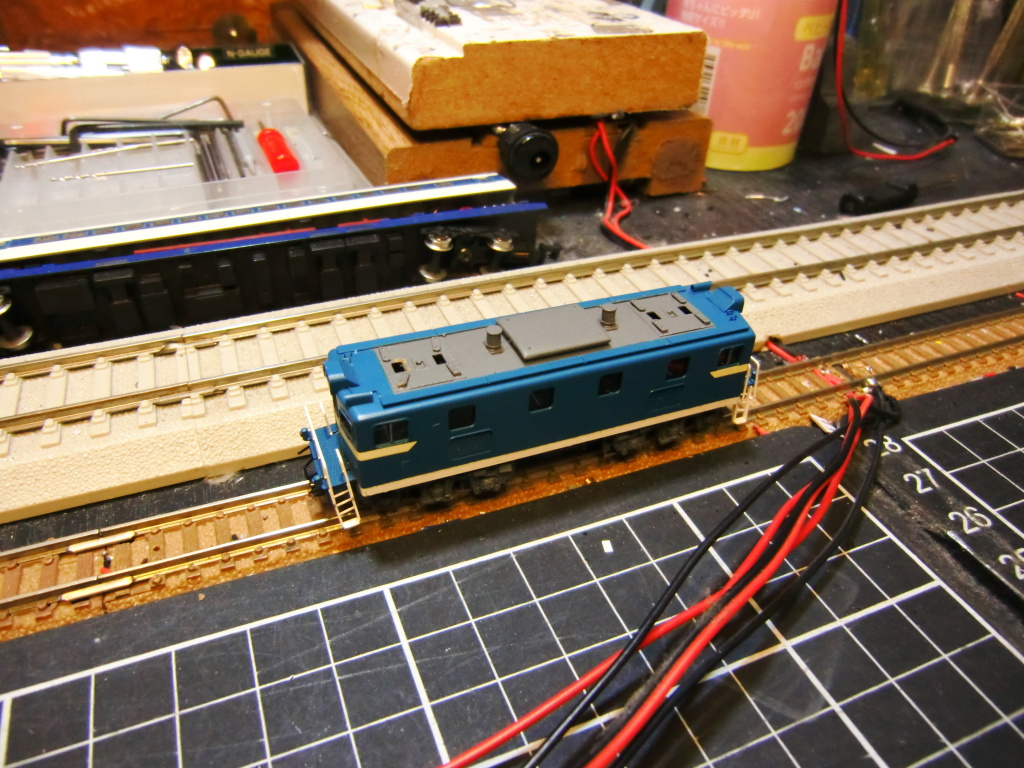
続いてモーターですが、こちらも動きません。
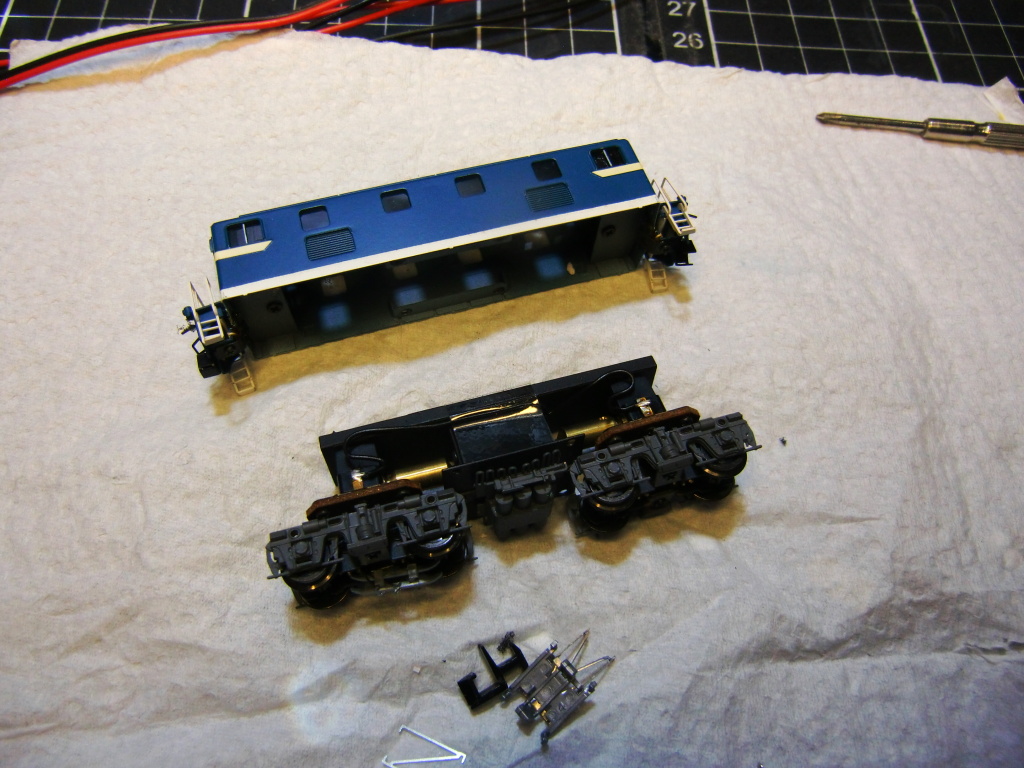

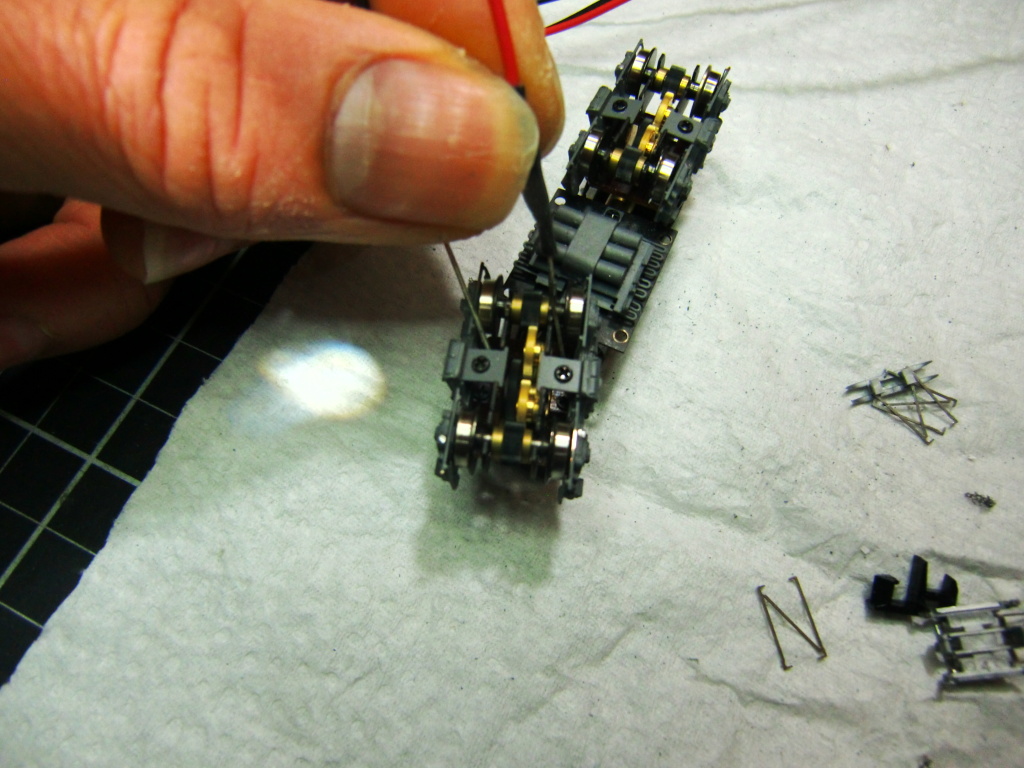
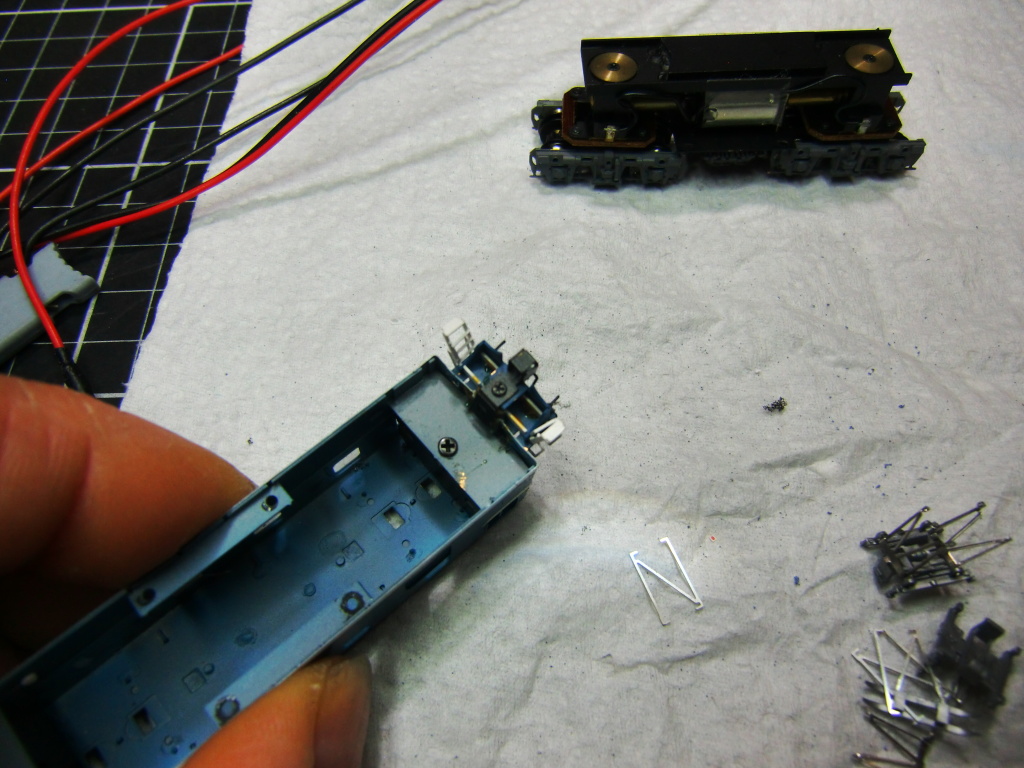
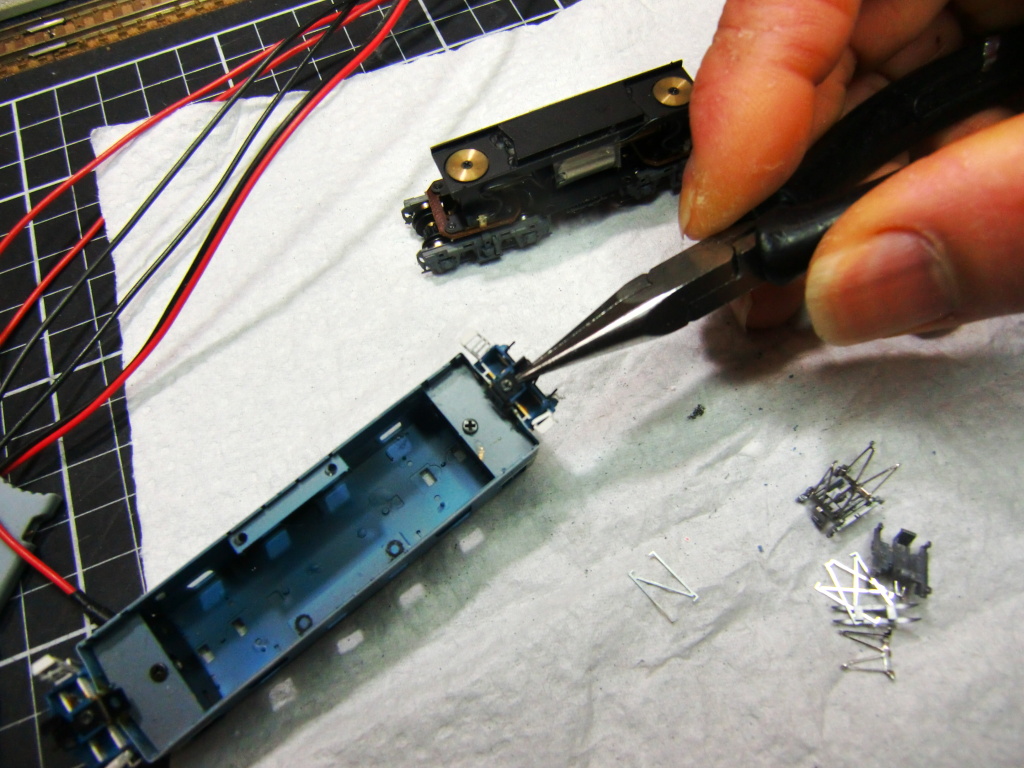
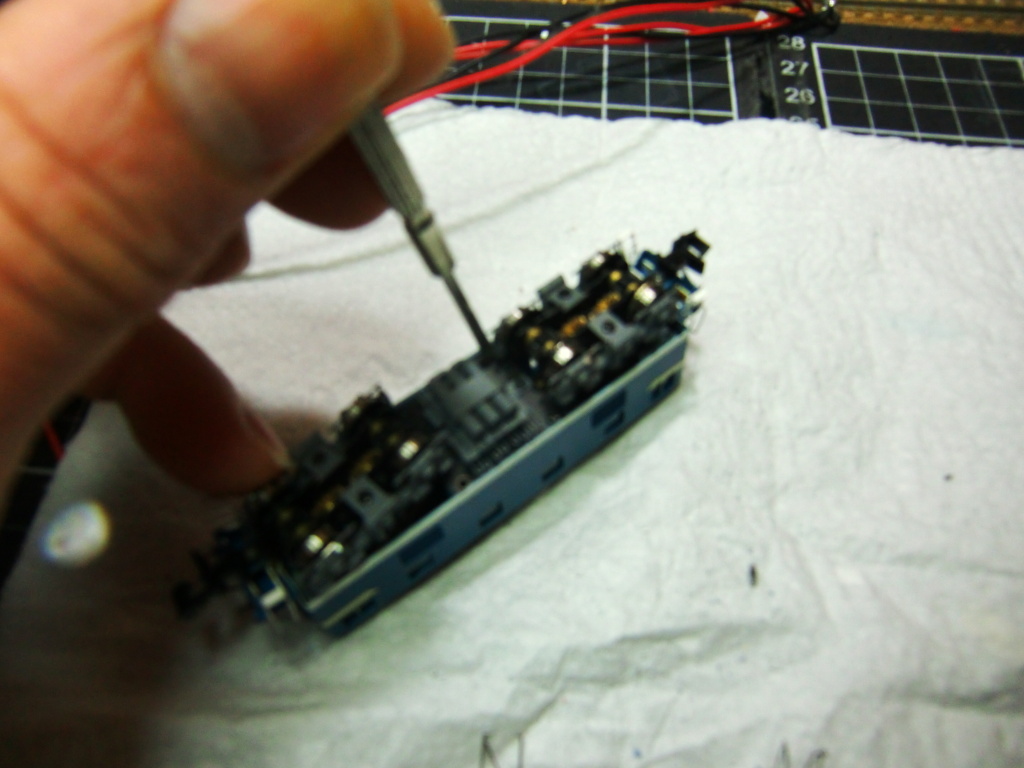

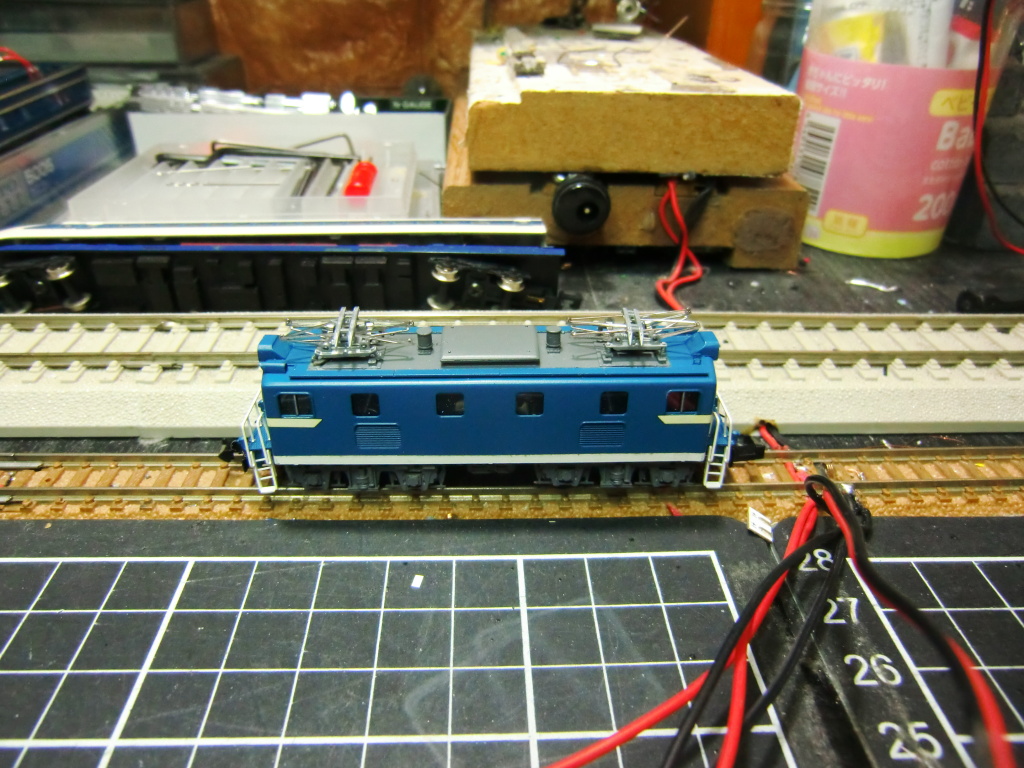
▼それ以外の作業

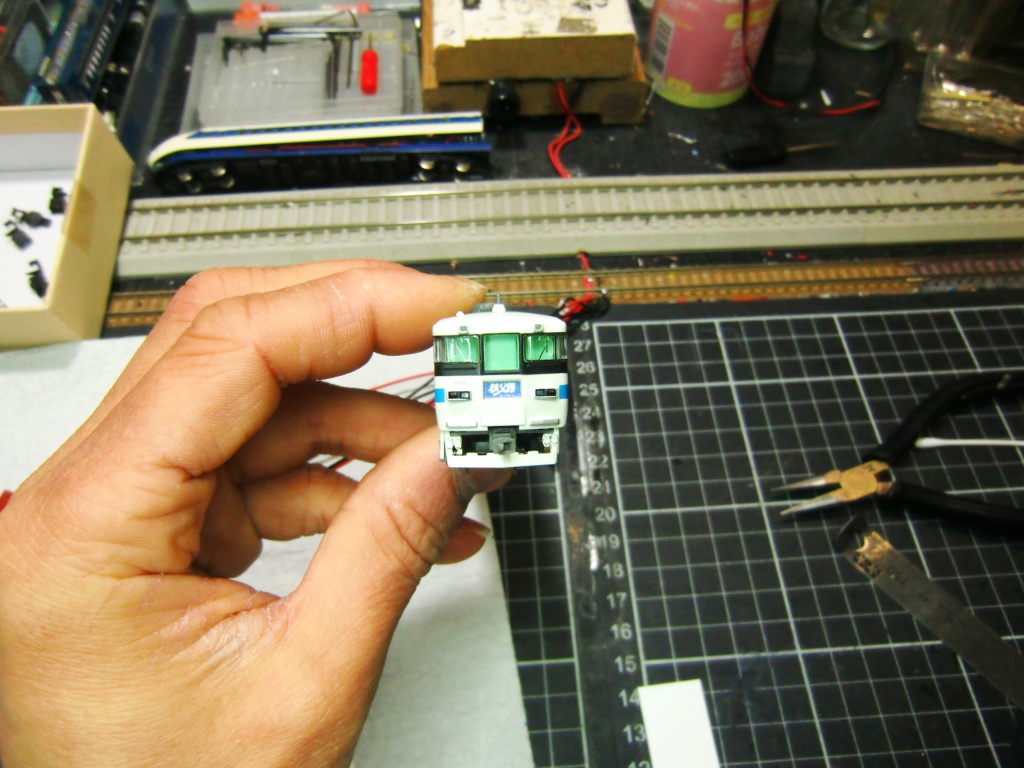


すべての作業が完了しました。

通常は2階通路中央に開いた隙間から1階を照らすようになっていますが、1階を独立点灯させる加工でございます。

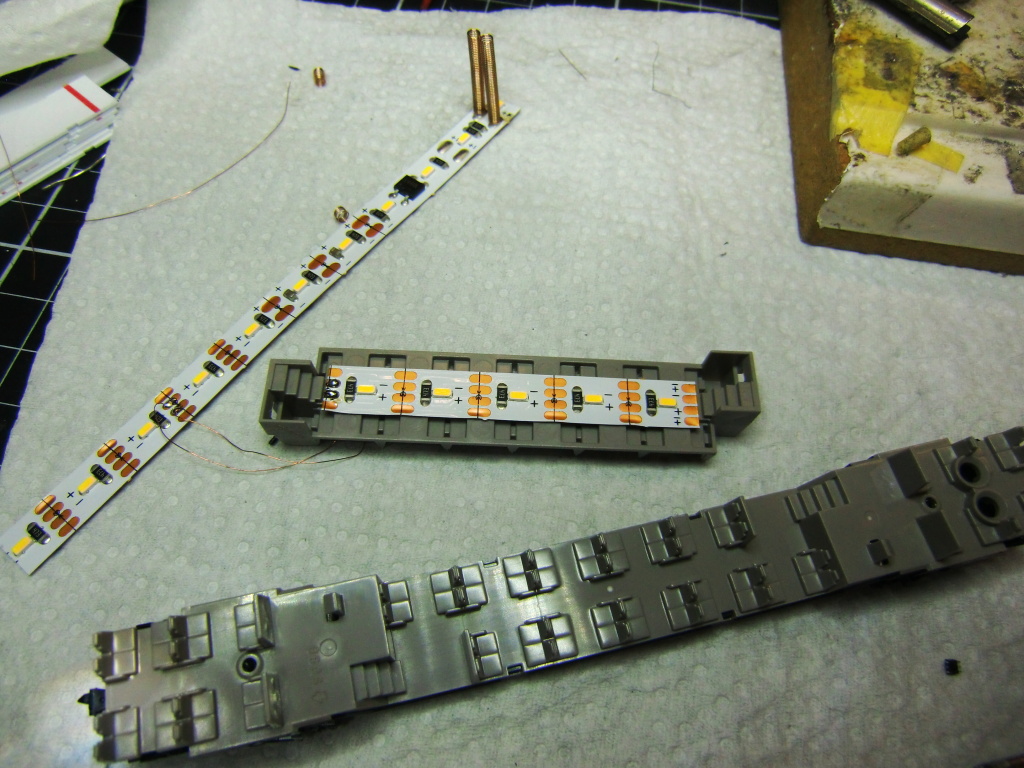
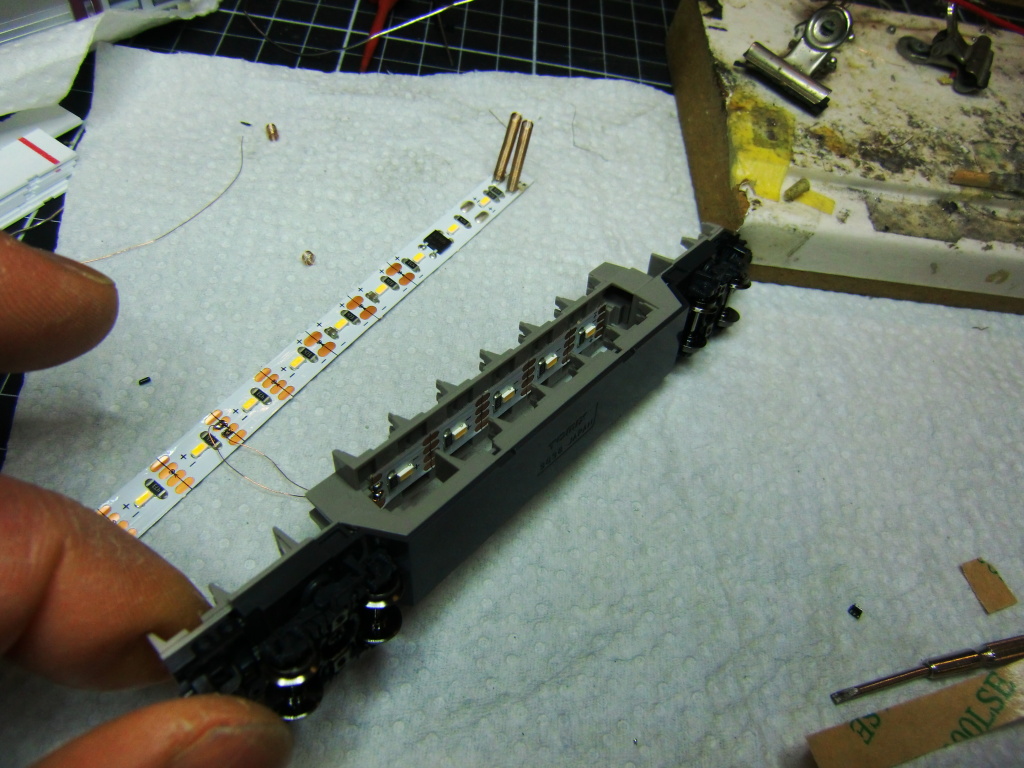

このようになります。

1、2階ともに車内全体にまんべんなく点灯するようになりました。作業完了でございます。

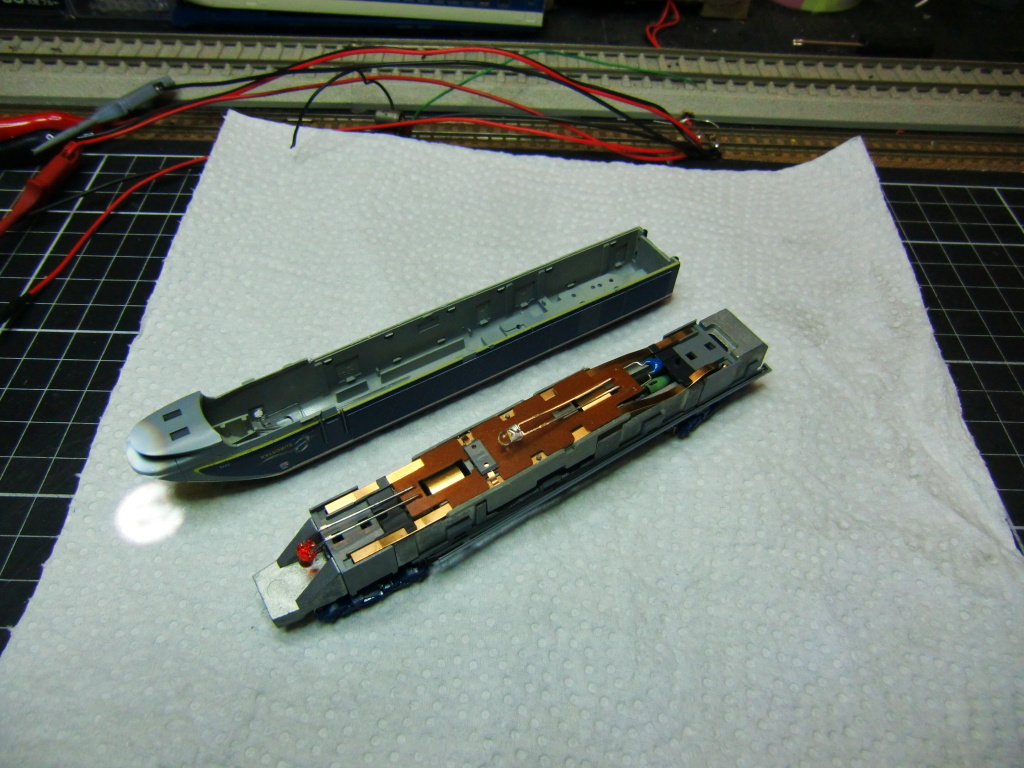
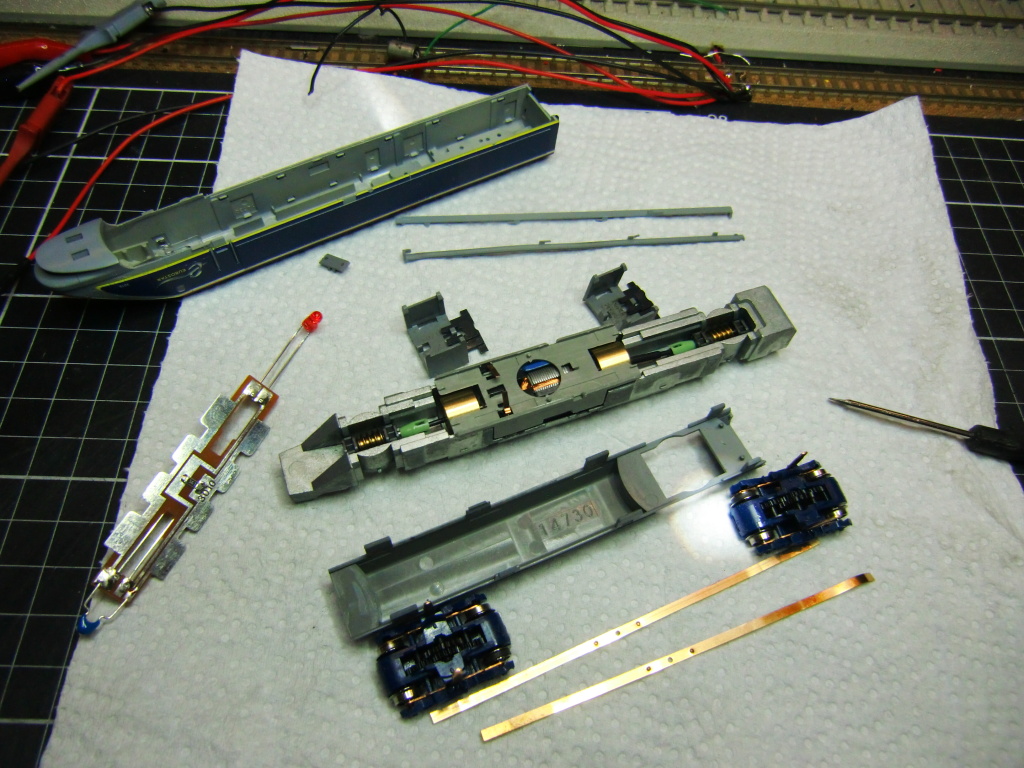
まずは全分解して問題となる箇所を特定して対処します。
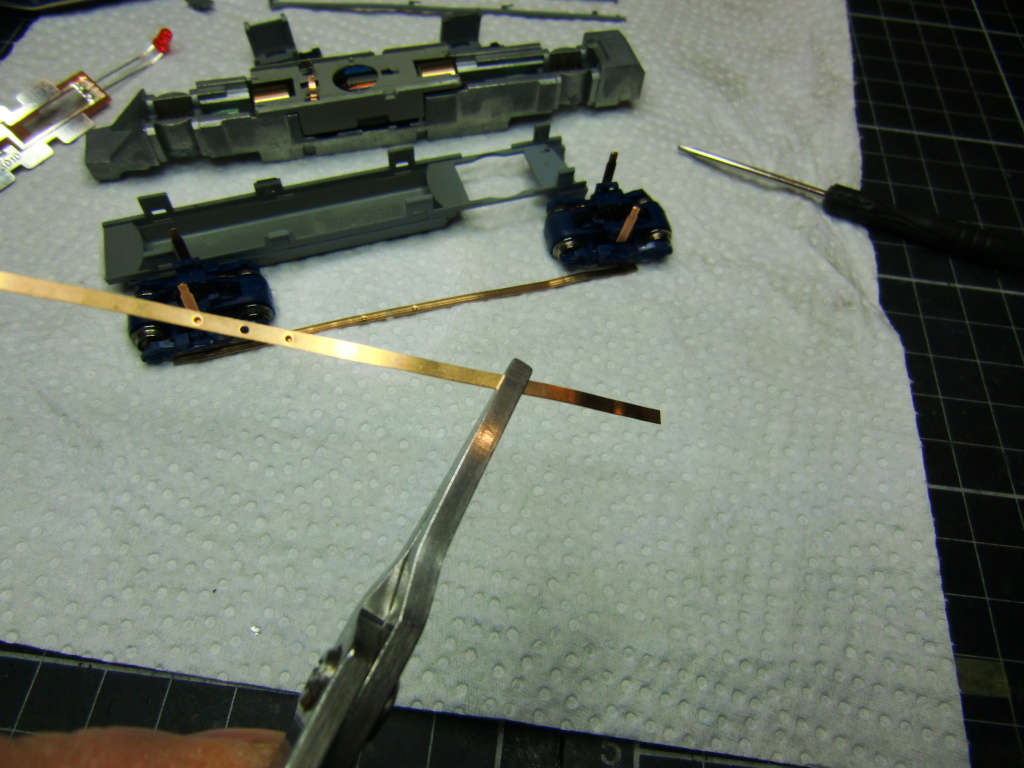
変形している集電シューをプライヤーで適正な位置に戻します。
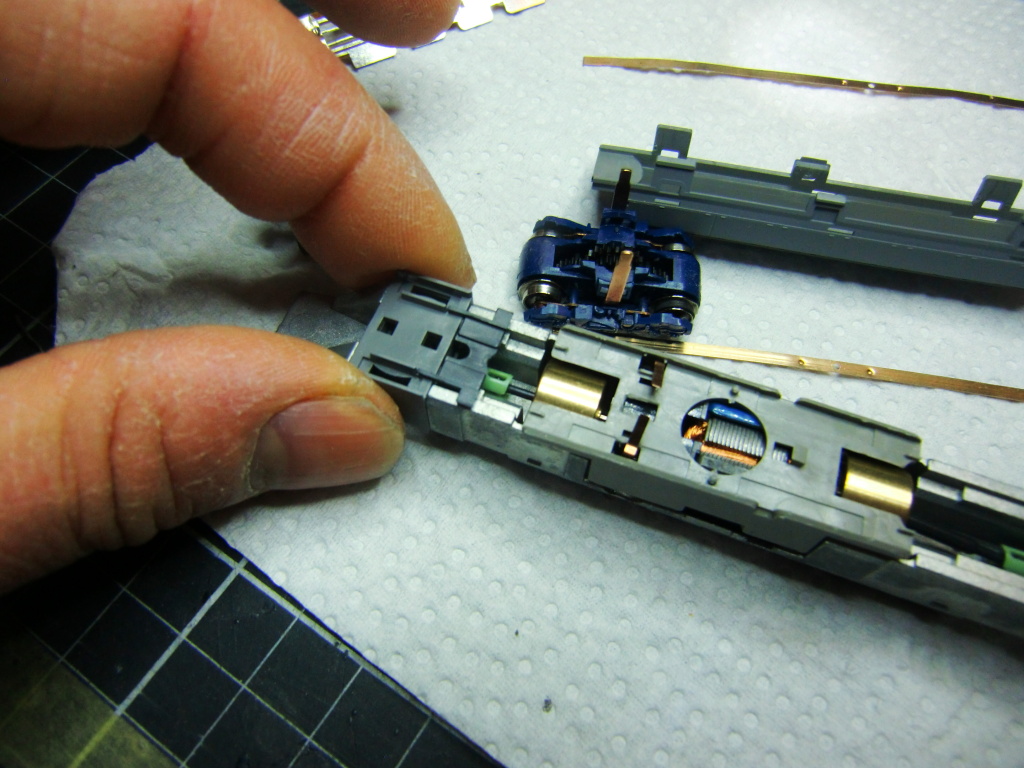
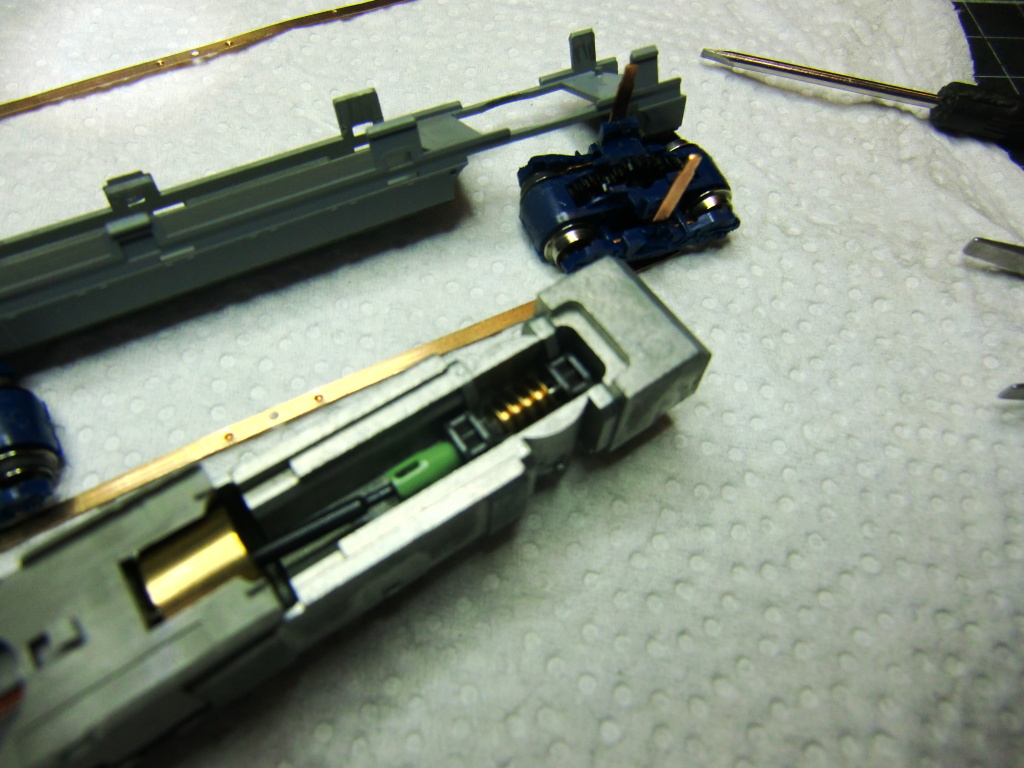

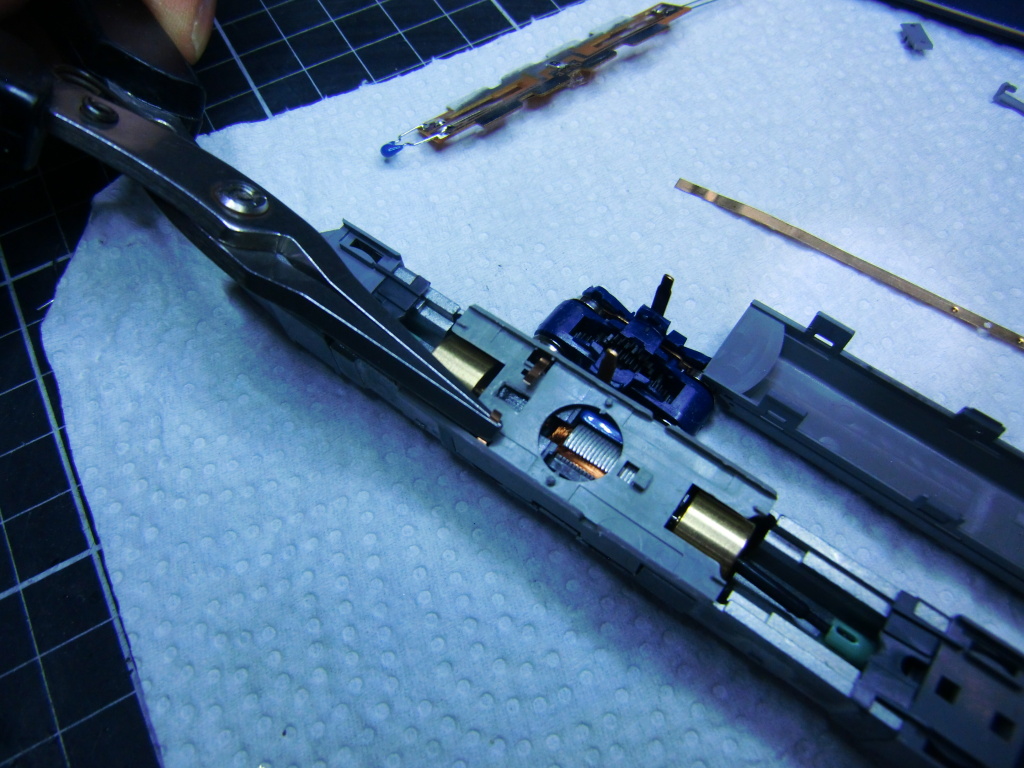
モーターの集電箇所も変形してます。
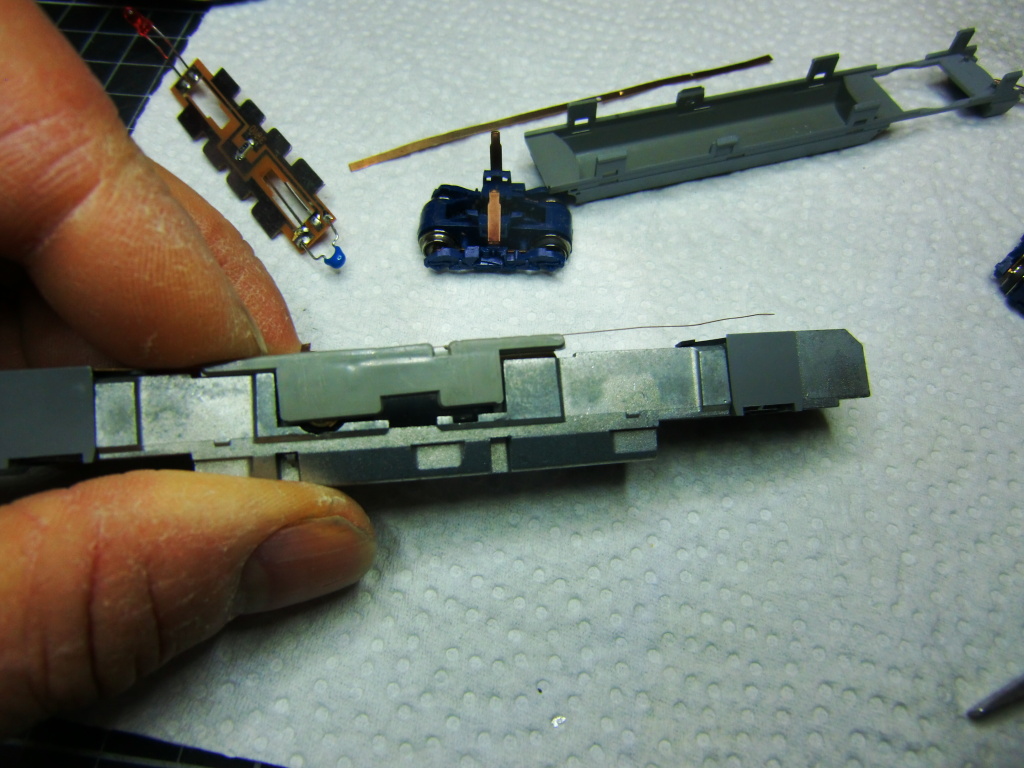
「う~ん」モーターがなぜか浮いてます。※上記写真を参照
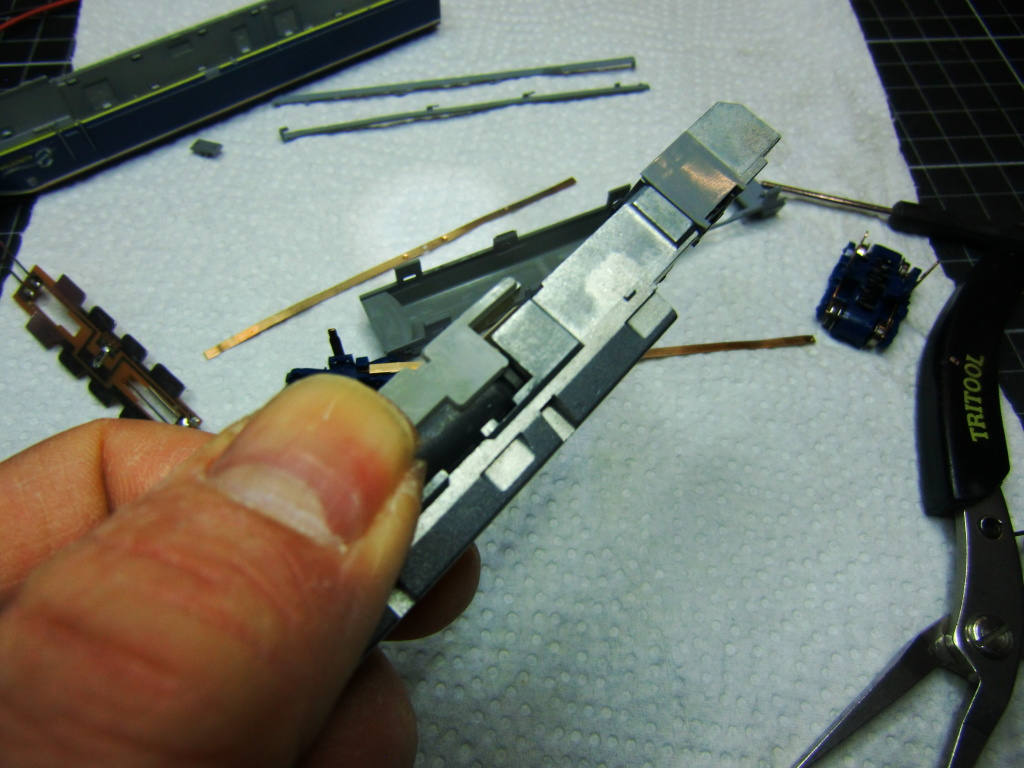
さらに分解してみると、固定カバーの爪が変形してしっかり固定できなくなっおります。
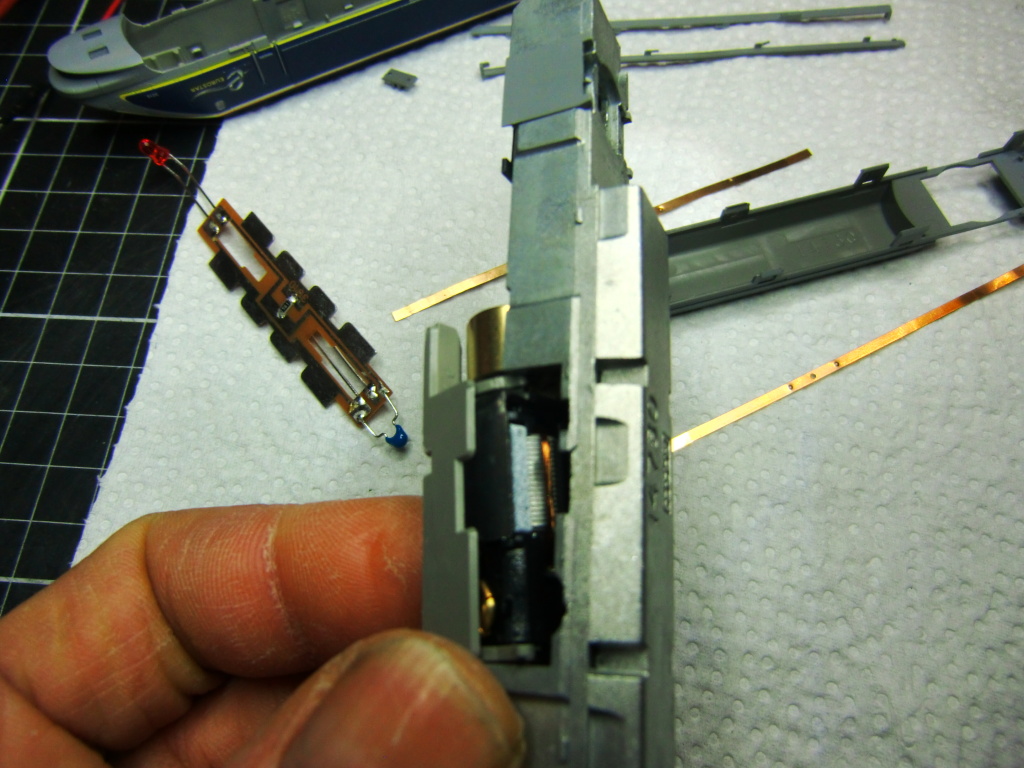
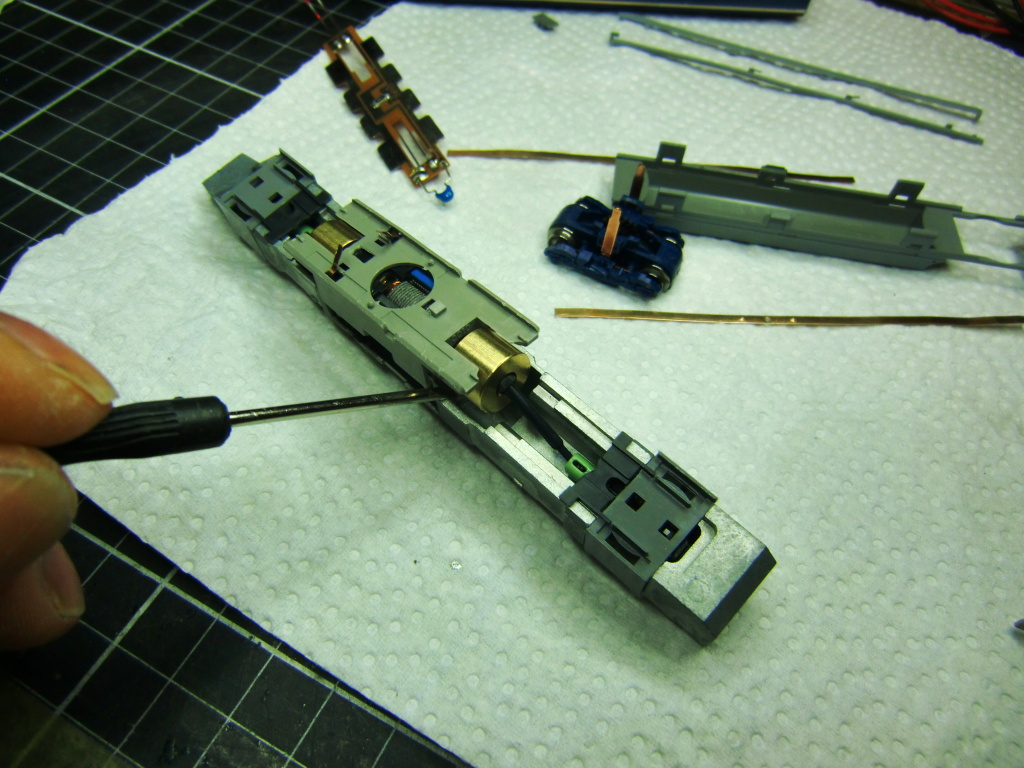
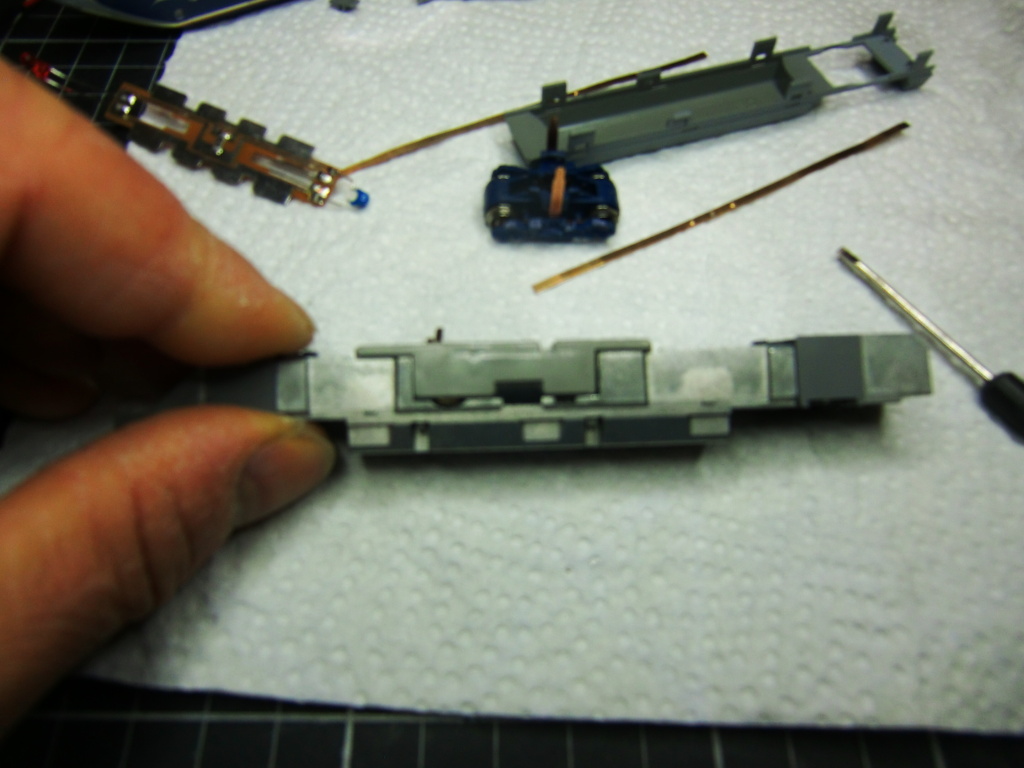
修復作業により、しっかりとモーターが固定されました。
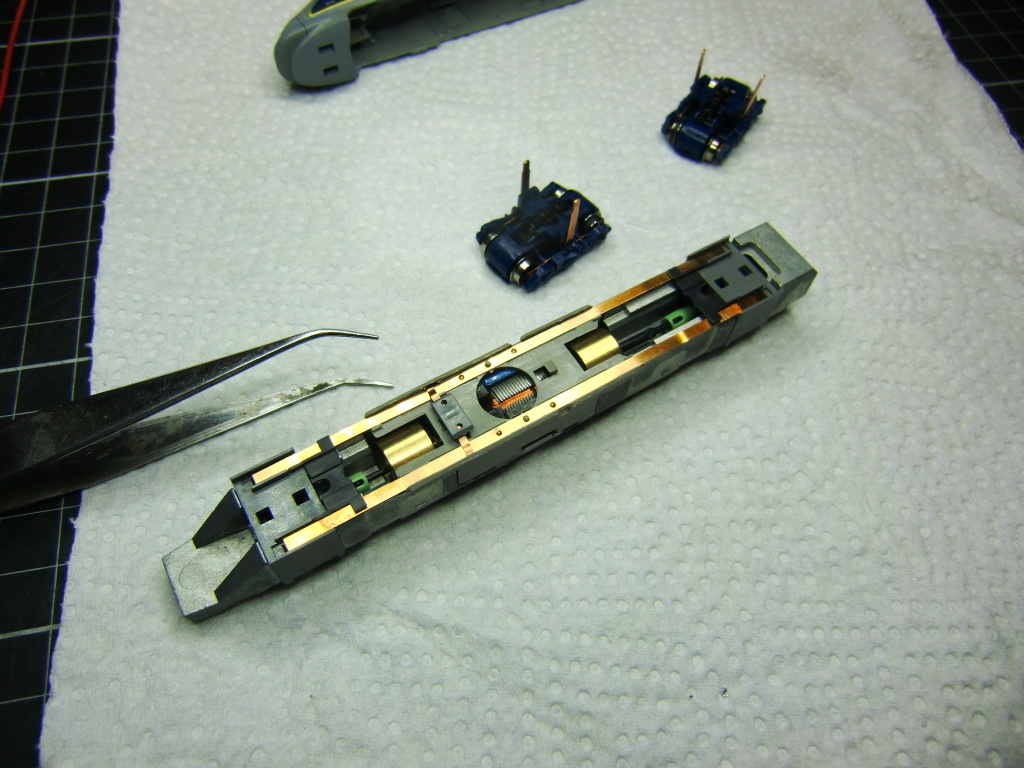
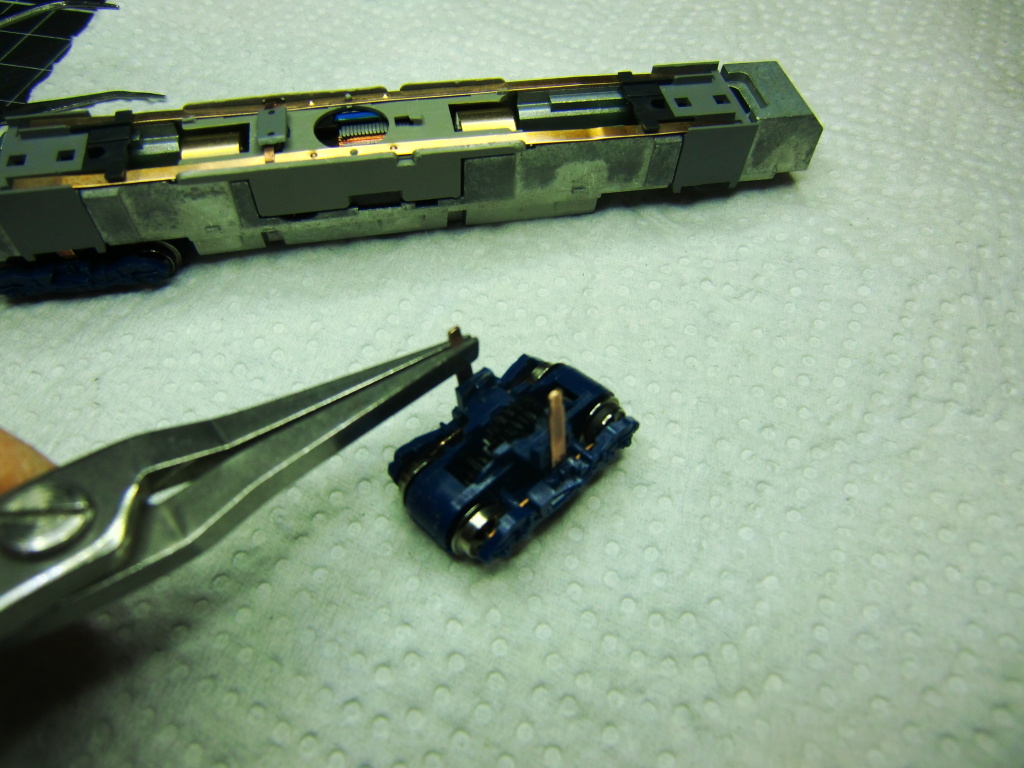
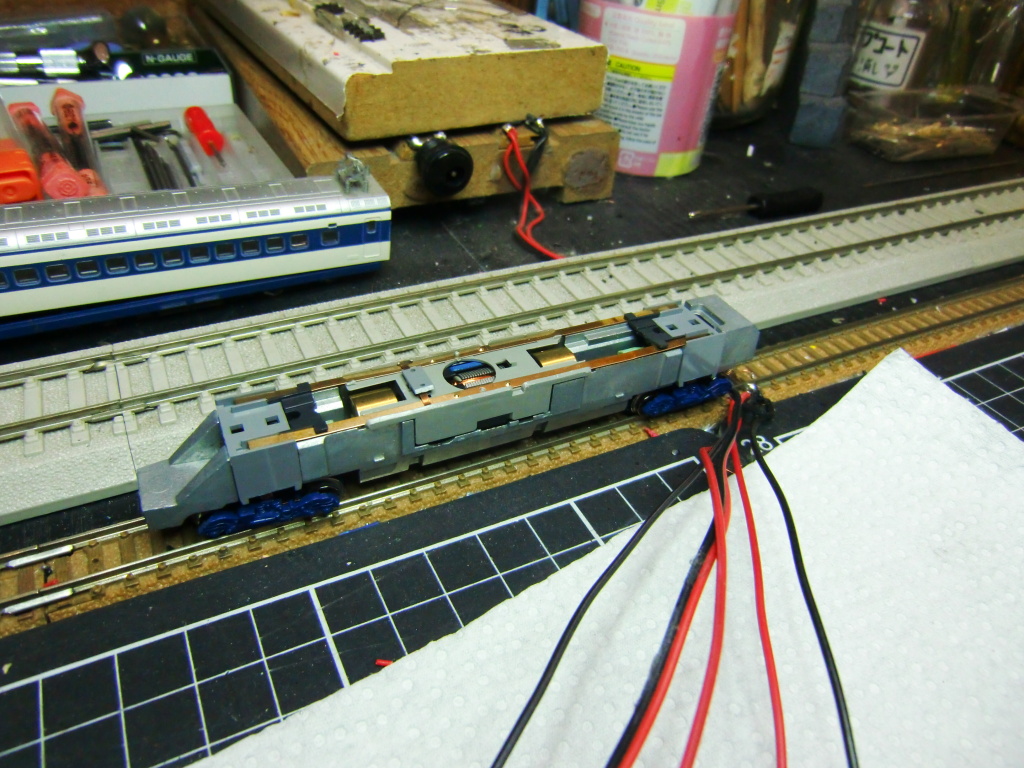
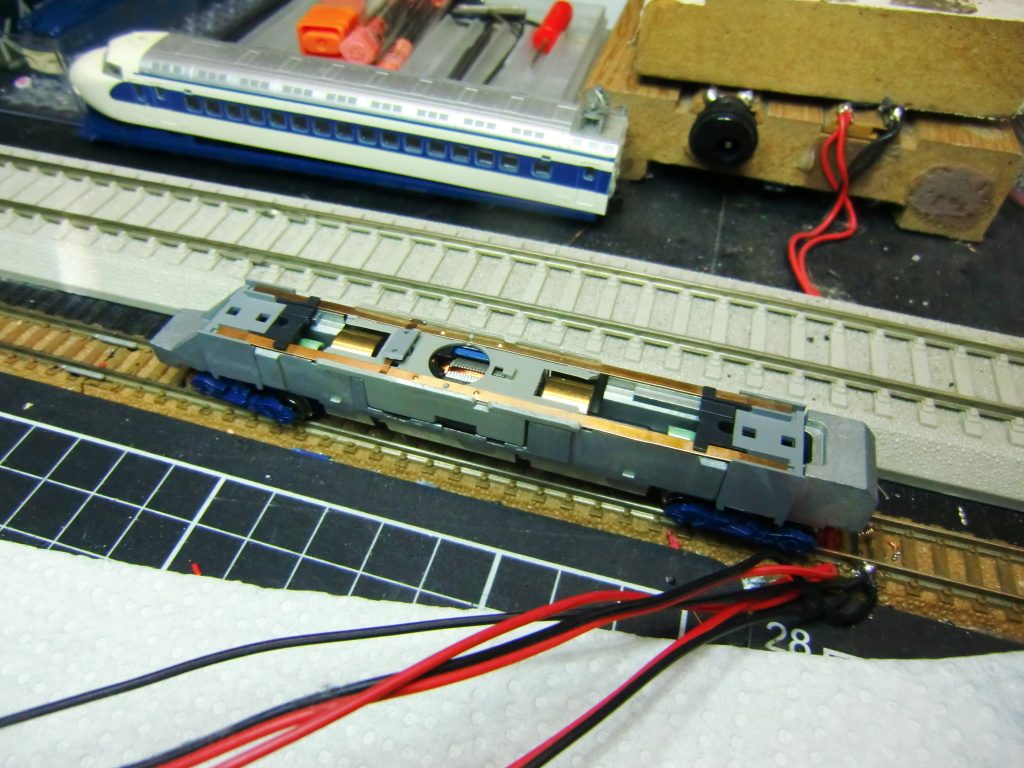
各部の調整も終わりテスト走行です。
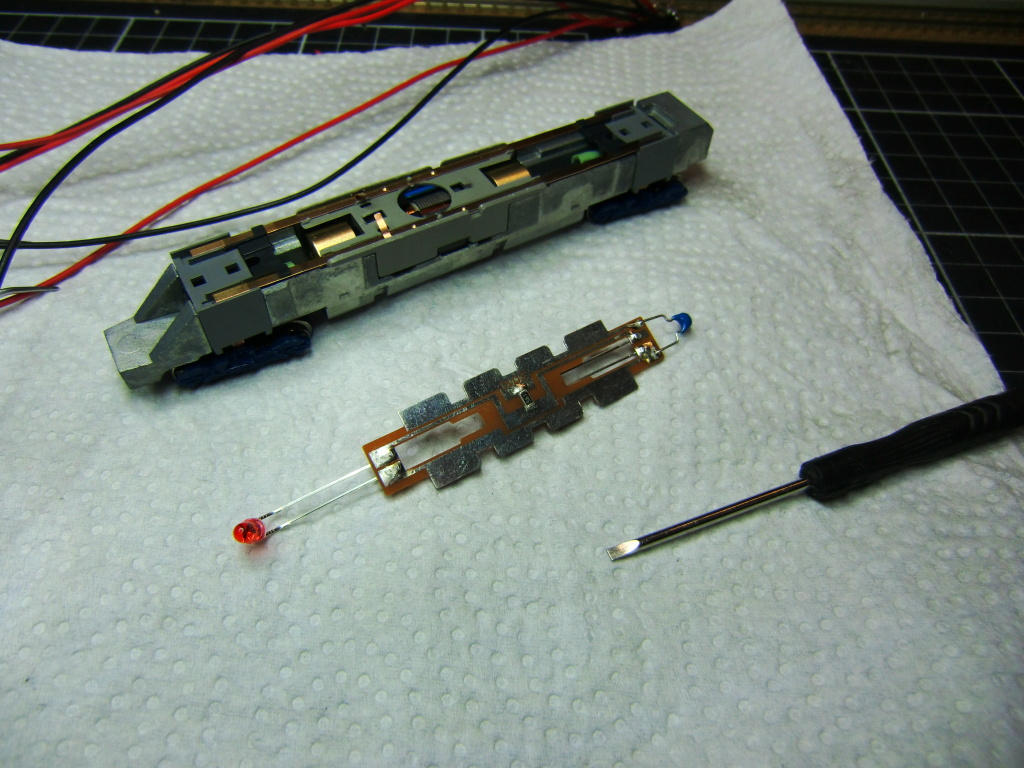

ライト不点灯の原因ですが、「ヘッド/テール」共にLEDが損傷しておりました。LEDは新しいものに交換します。
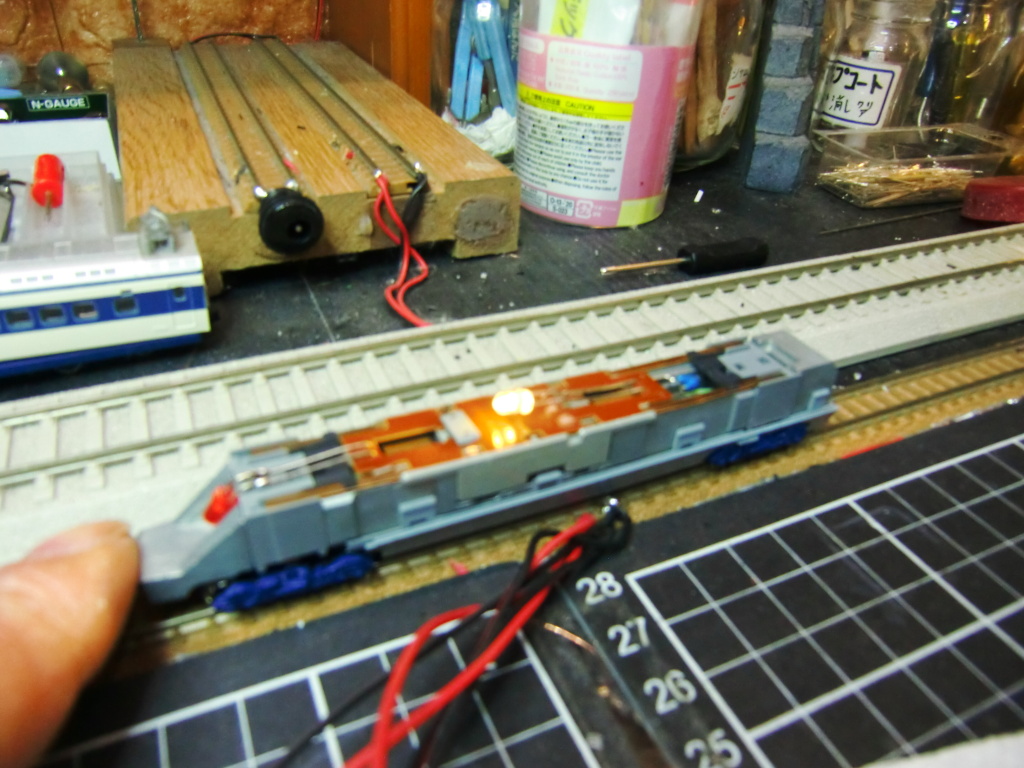
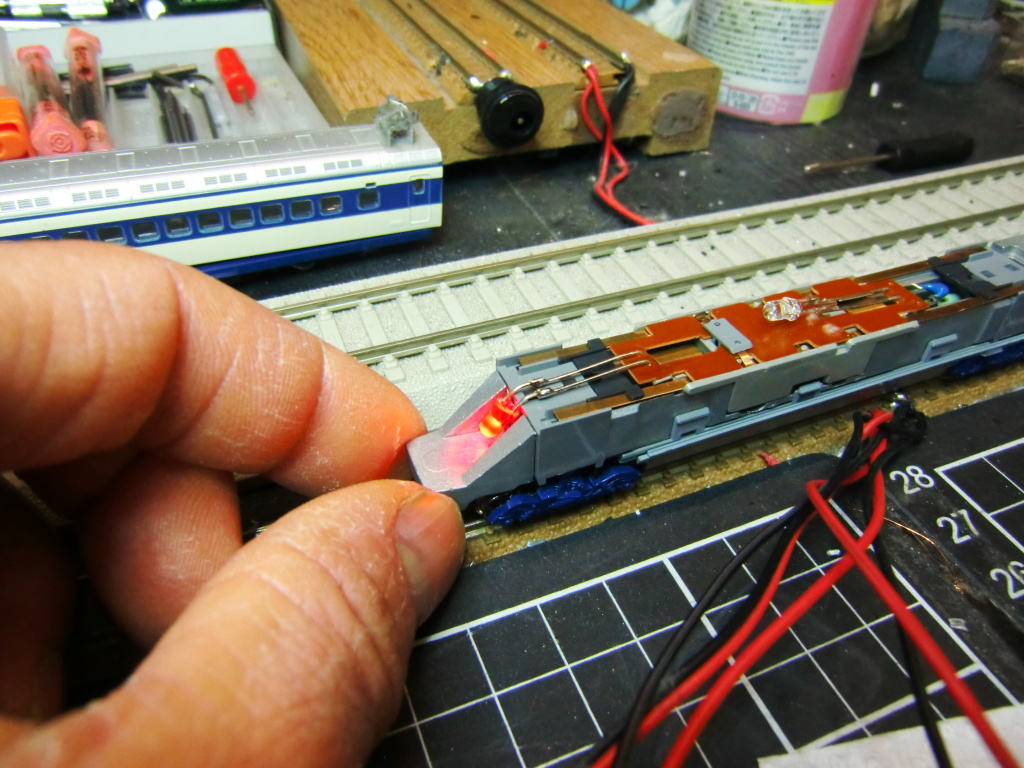

続いてパンタ加工に入ります。
途中過程の画像は省略します。今回の作業でもっとも難航したのがスイッチの取り付け位置です。通常は床下機器のスペースに配置しますが、この車両にはまったくスペースがありません。また連結面のわずかなスペースに入らないか試してみましたが、ボディーが閉まらなくなりダメでした。そこで屋根上の空間を利用して、初となる上部スイッチを組み込む形で対応しました。

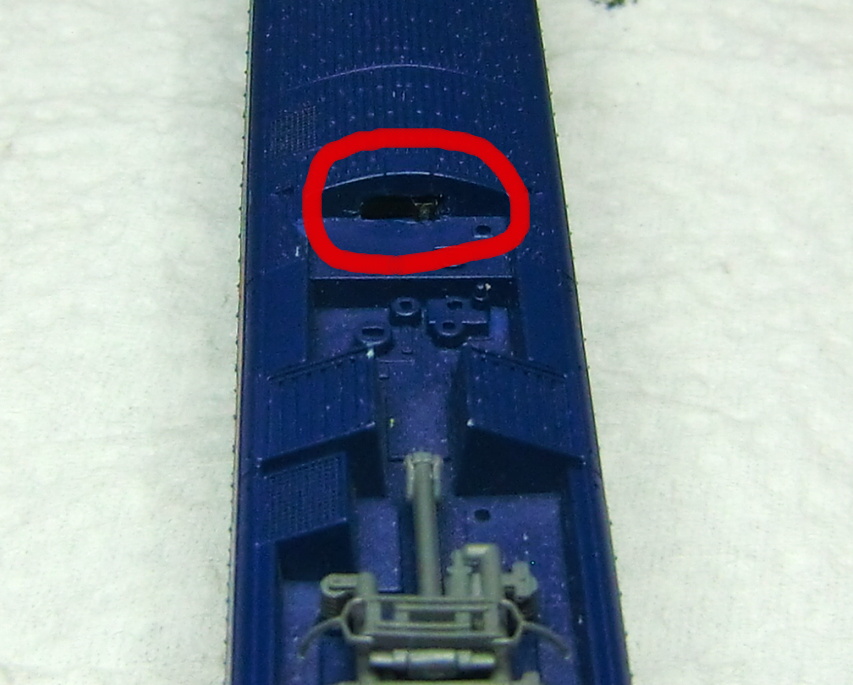

ようやく作業完了でございます。スイッチの組込みにここまで作業が難航したのは初めてです。

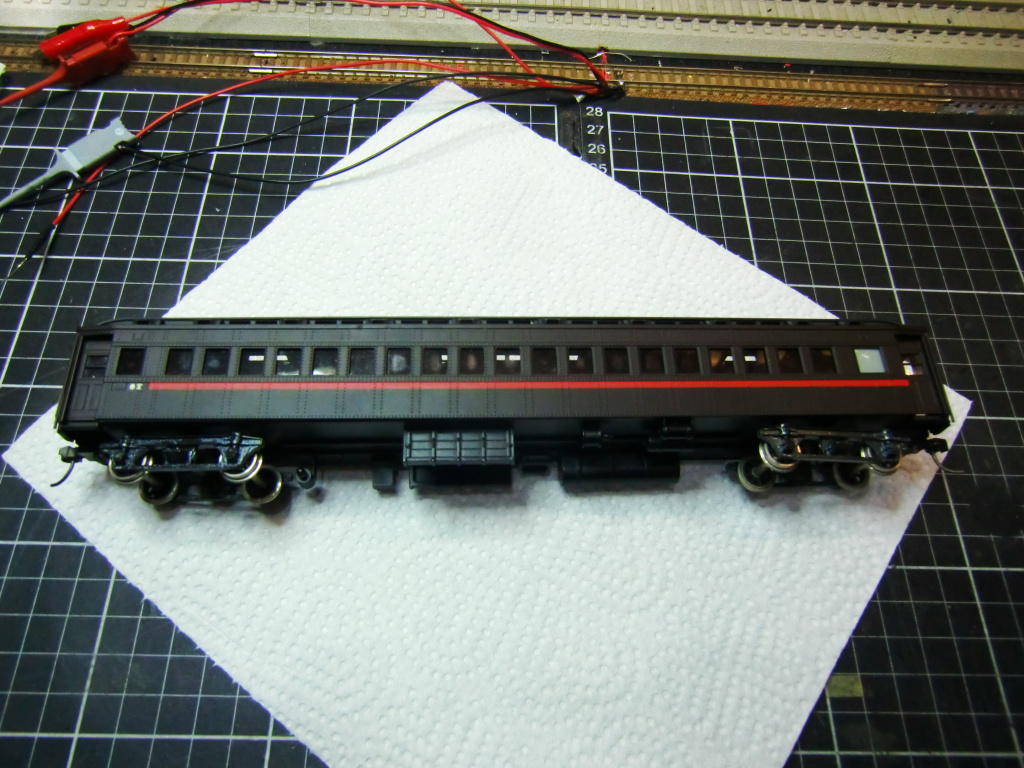
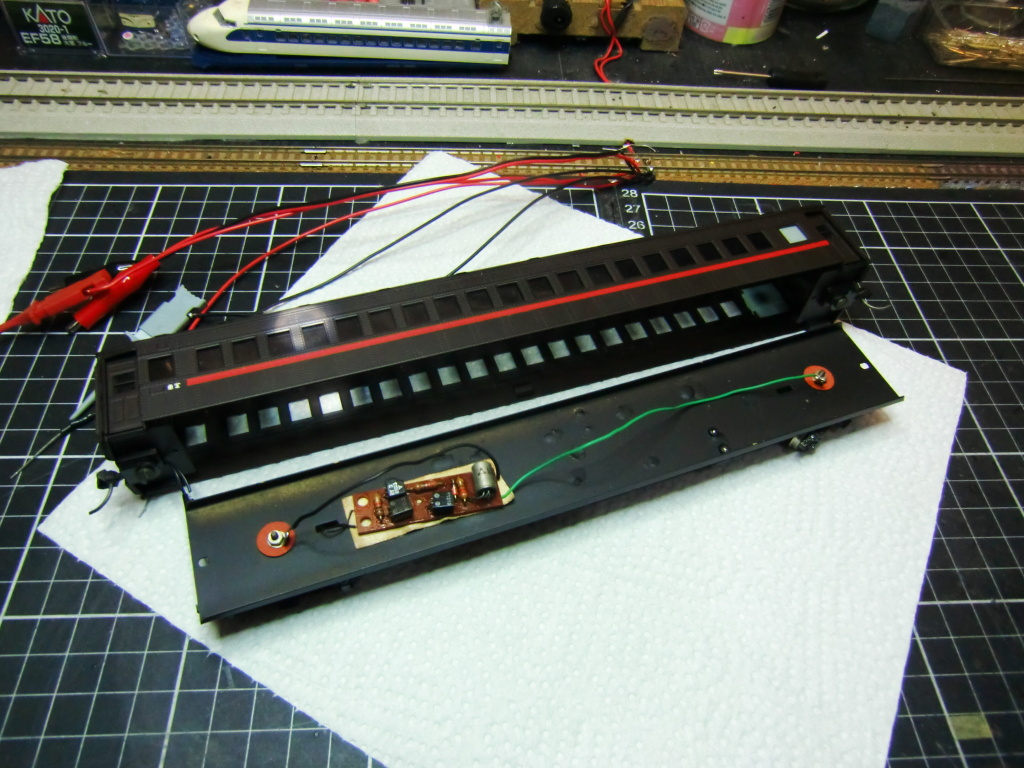


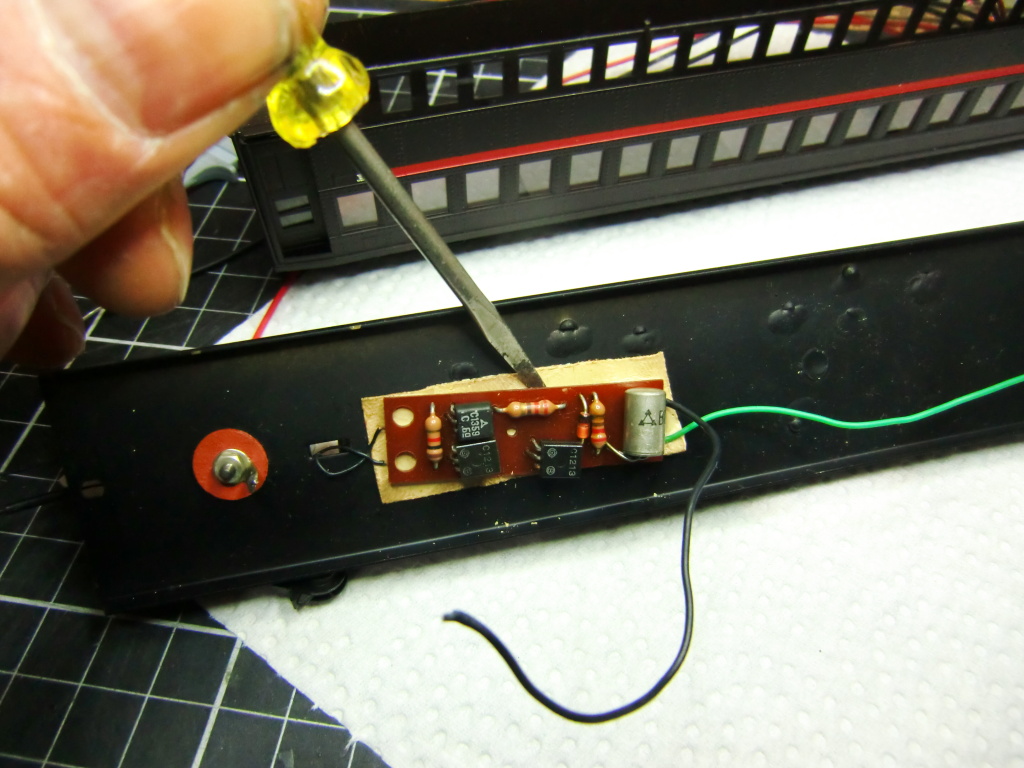
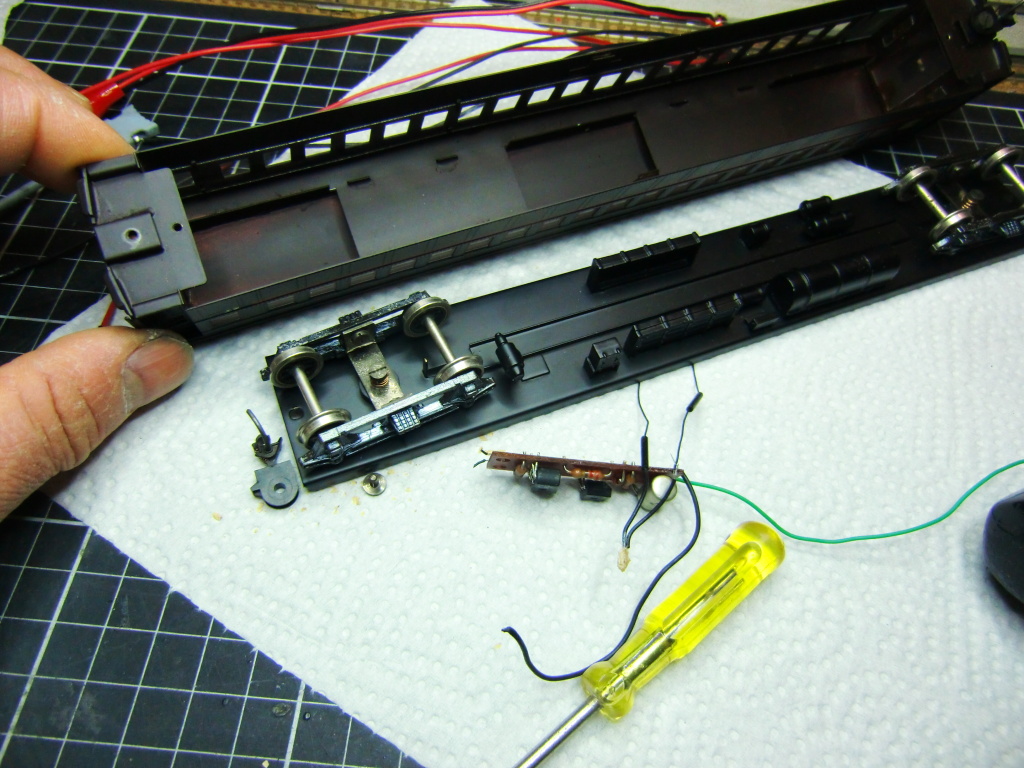
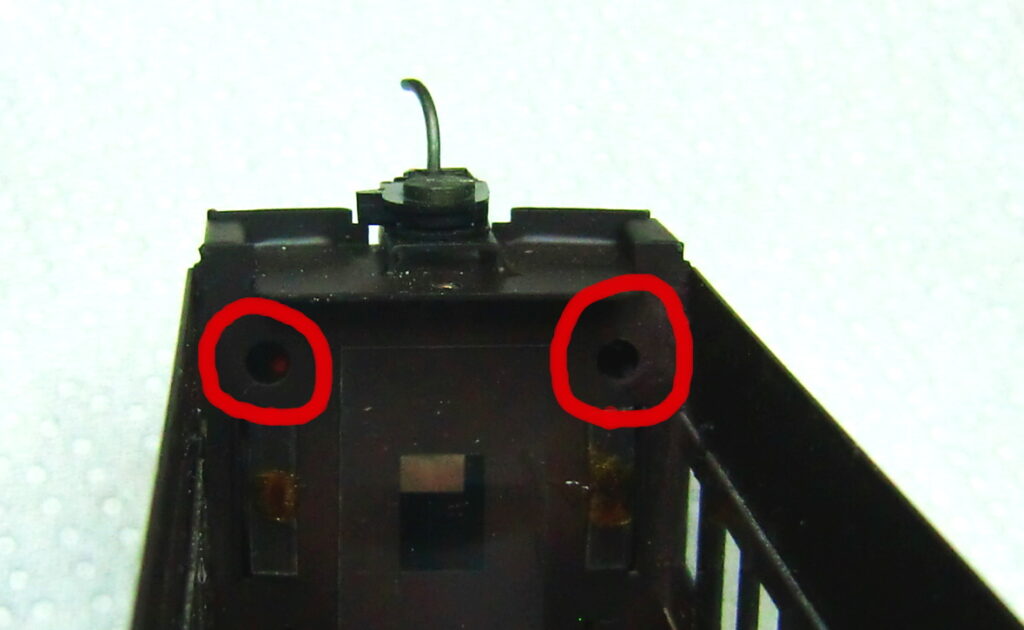
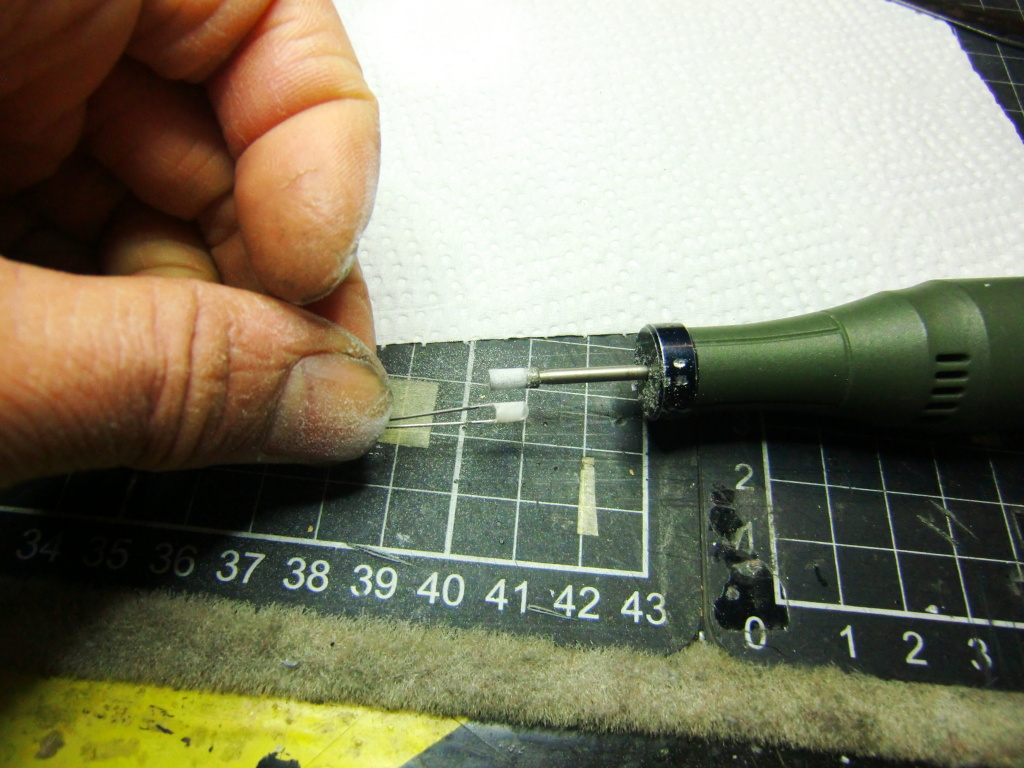
LEDを削ってテールライトの径に合わせます。

LEDを埋め込んで、まずは点灯テスト

良さそうです。
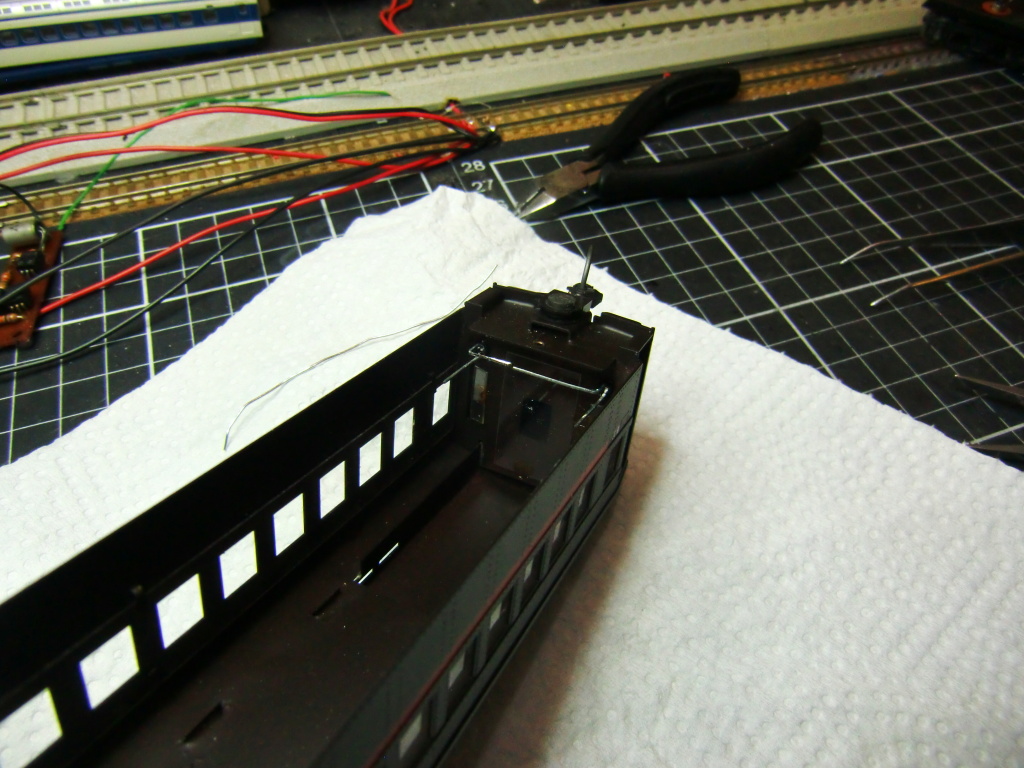
ライト周りを黒で遮光して固定します。続いてLED同士を直列でつなぎます。
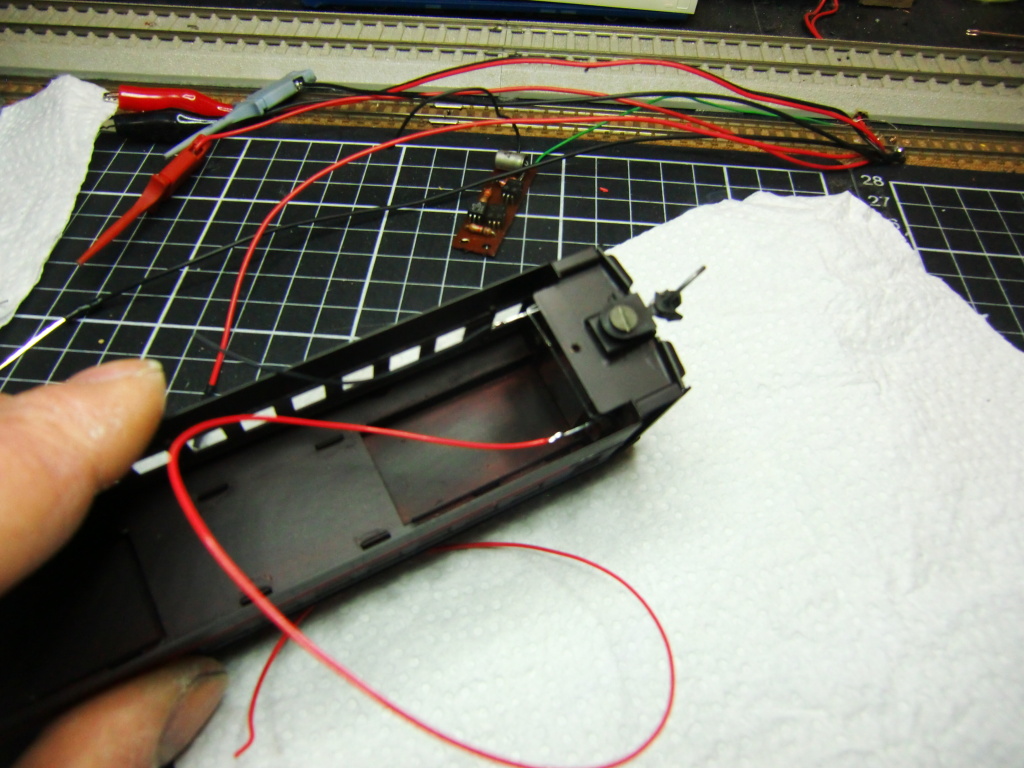
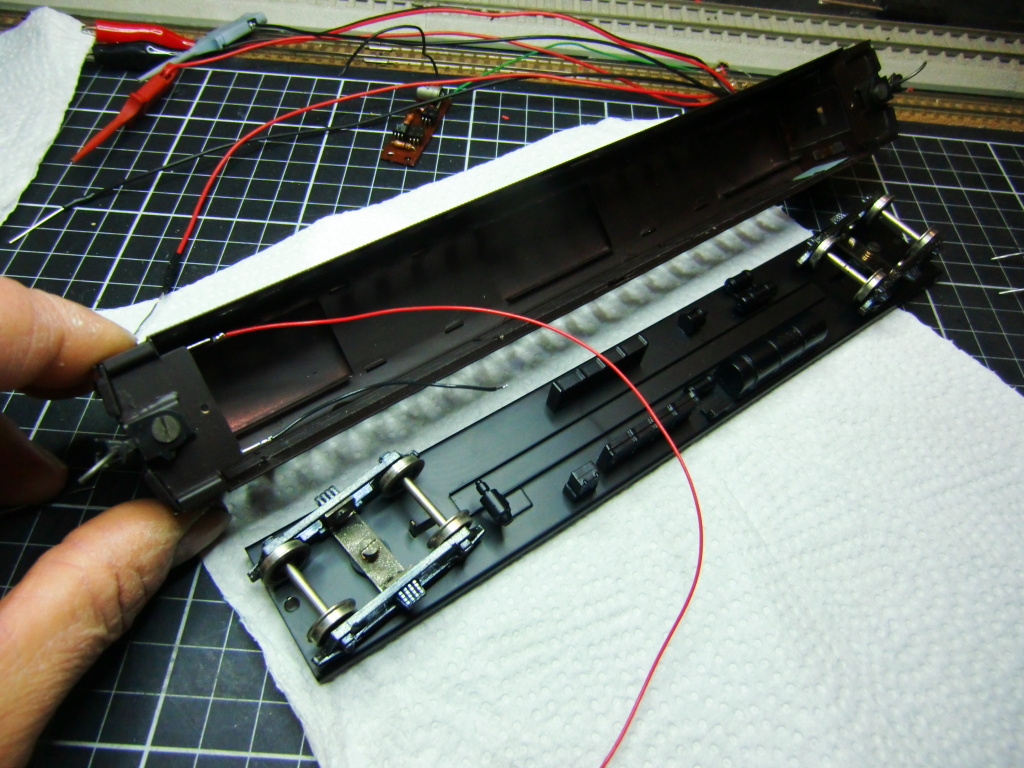

抵抗とダイオードを取付け台車の端子にそれぞれつなぎます。
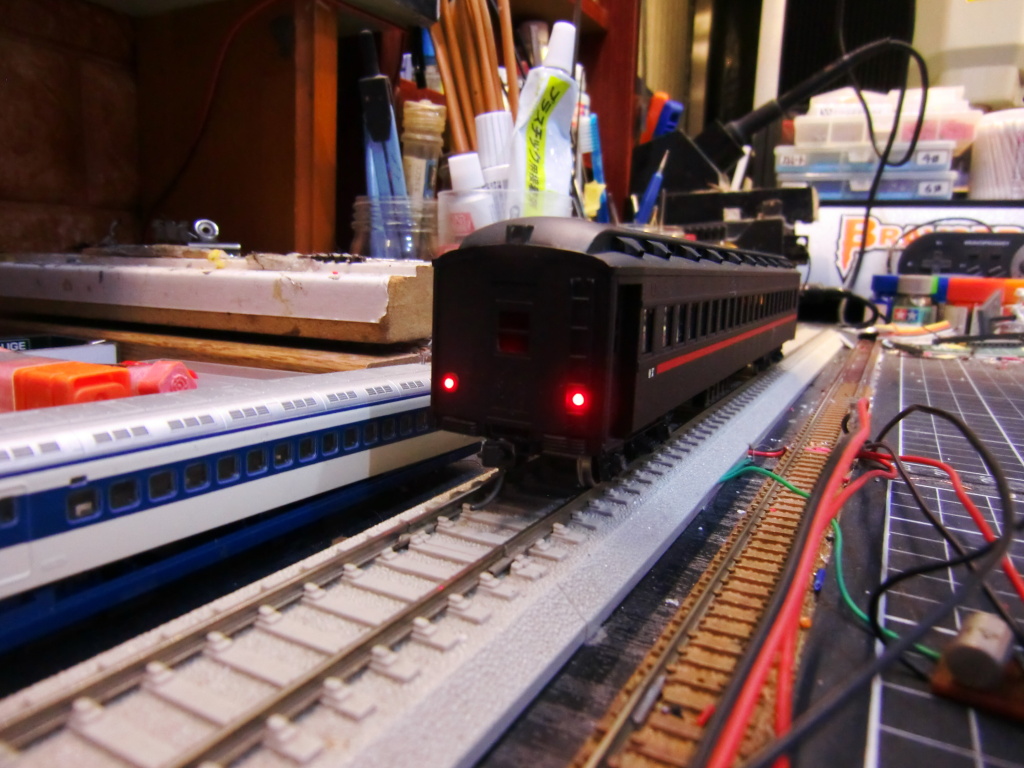
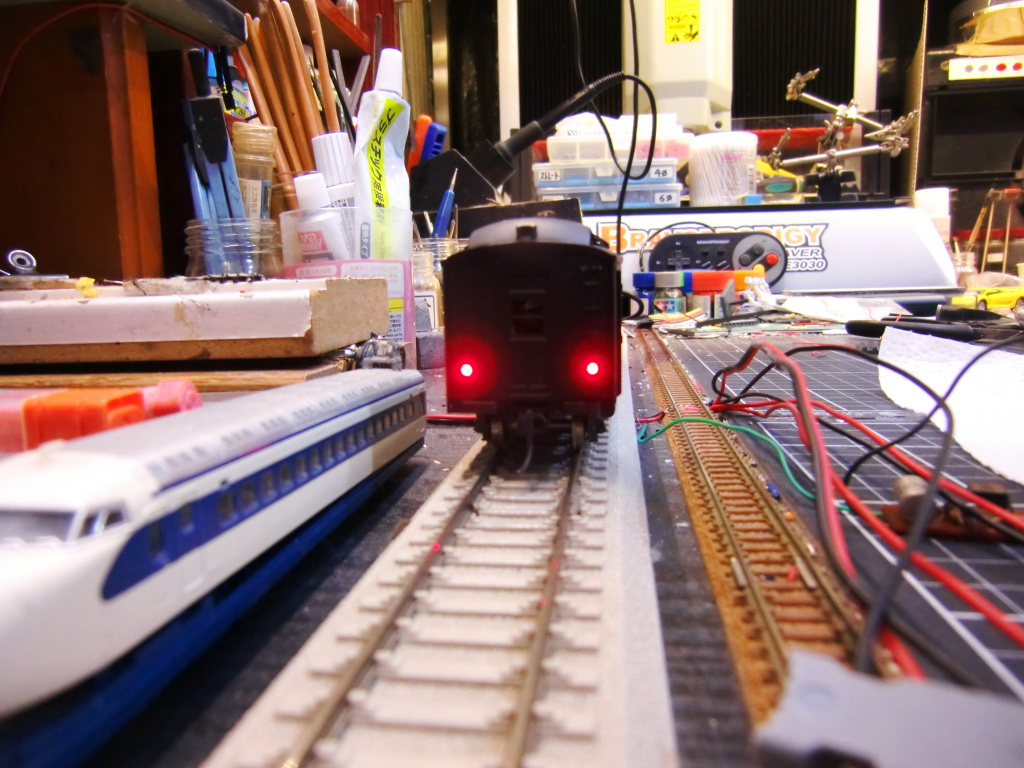
明るさも良い感じです。
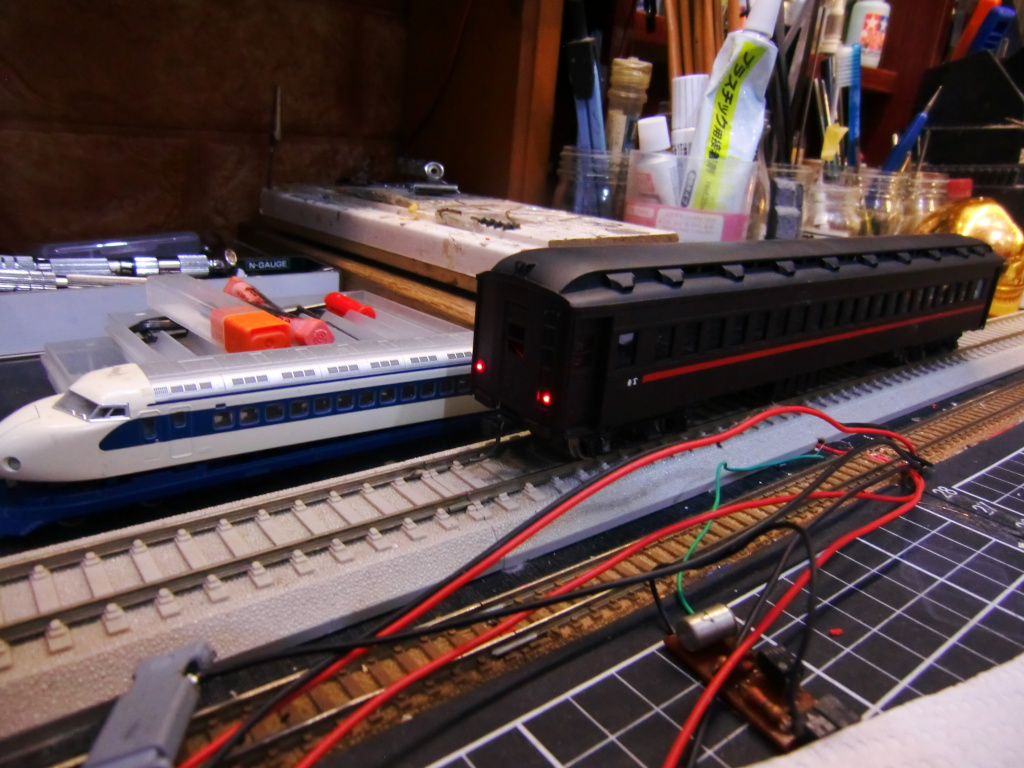
作業完了でございます。

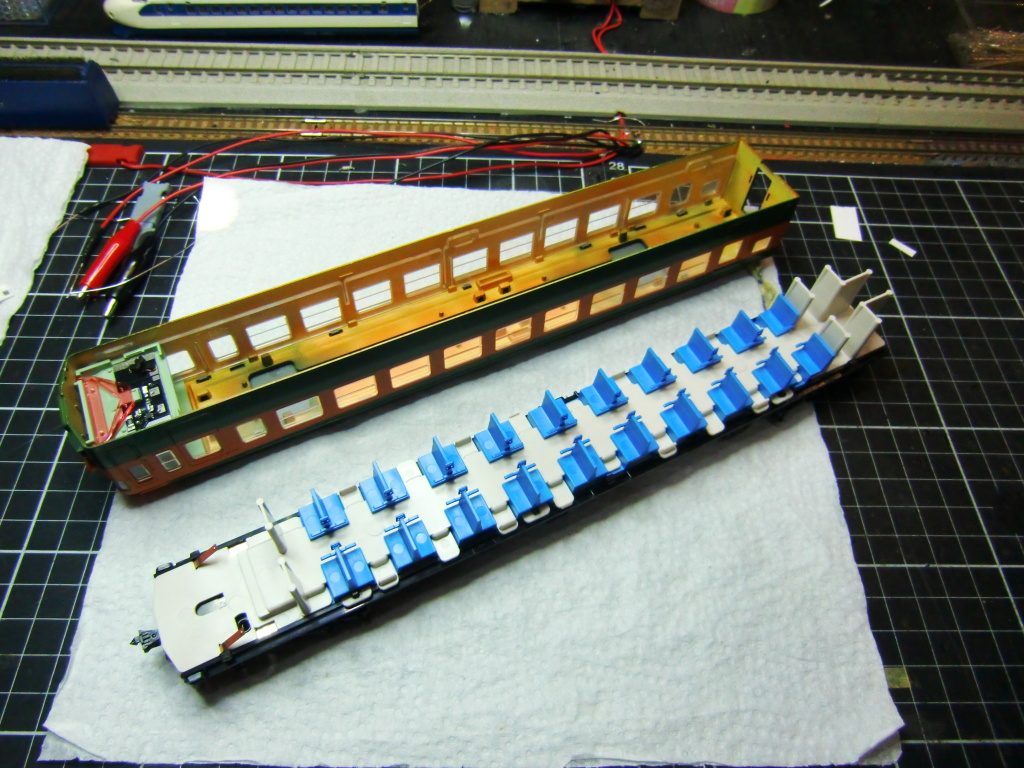
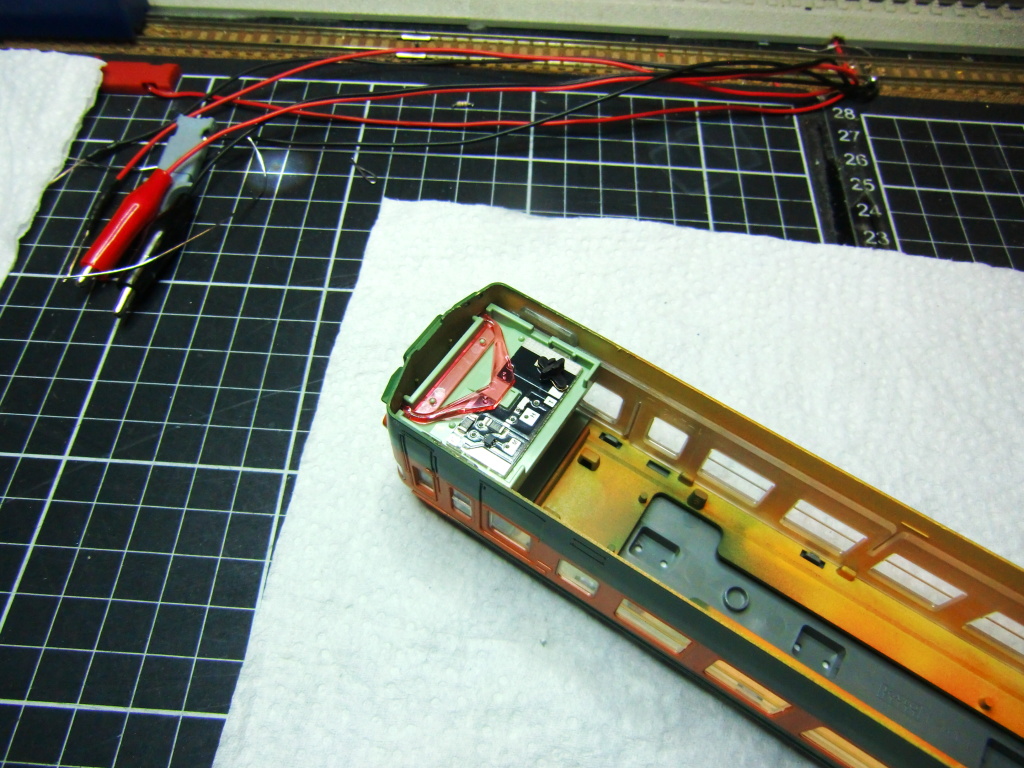

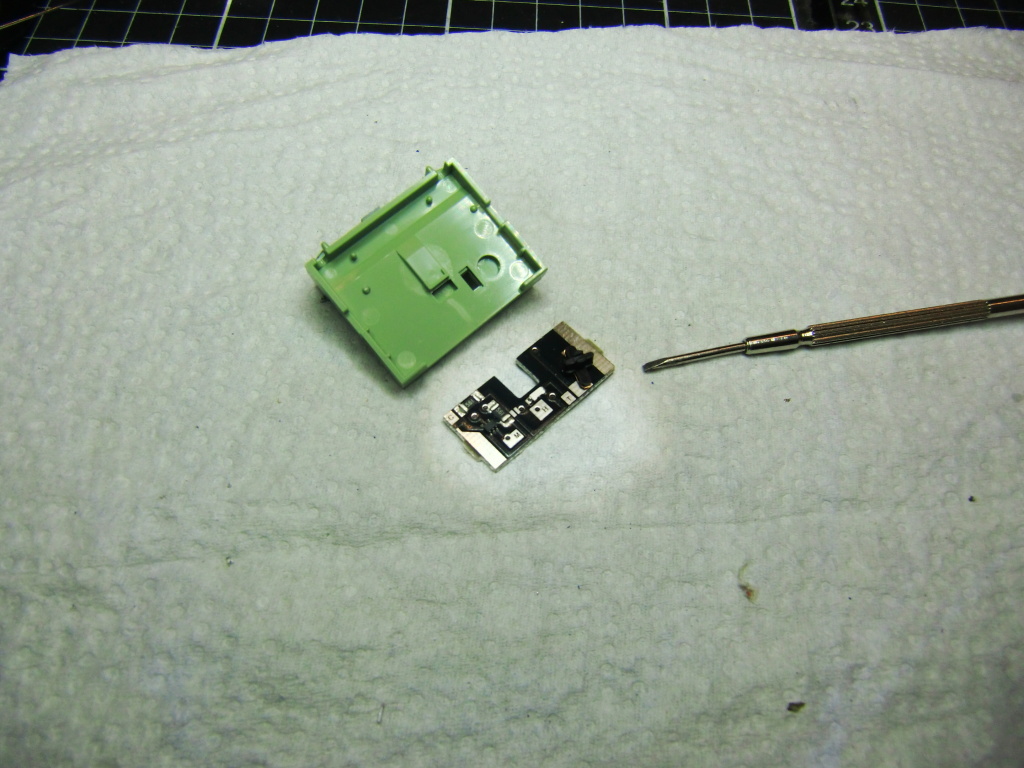
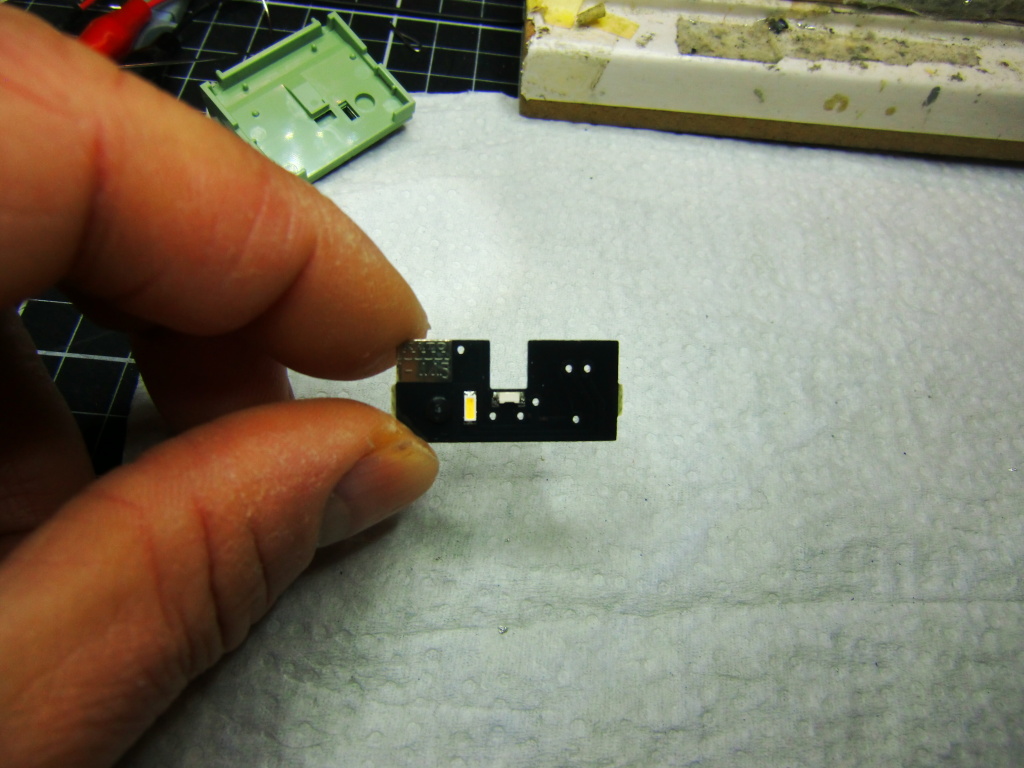
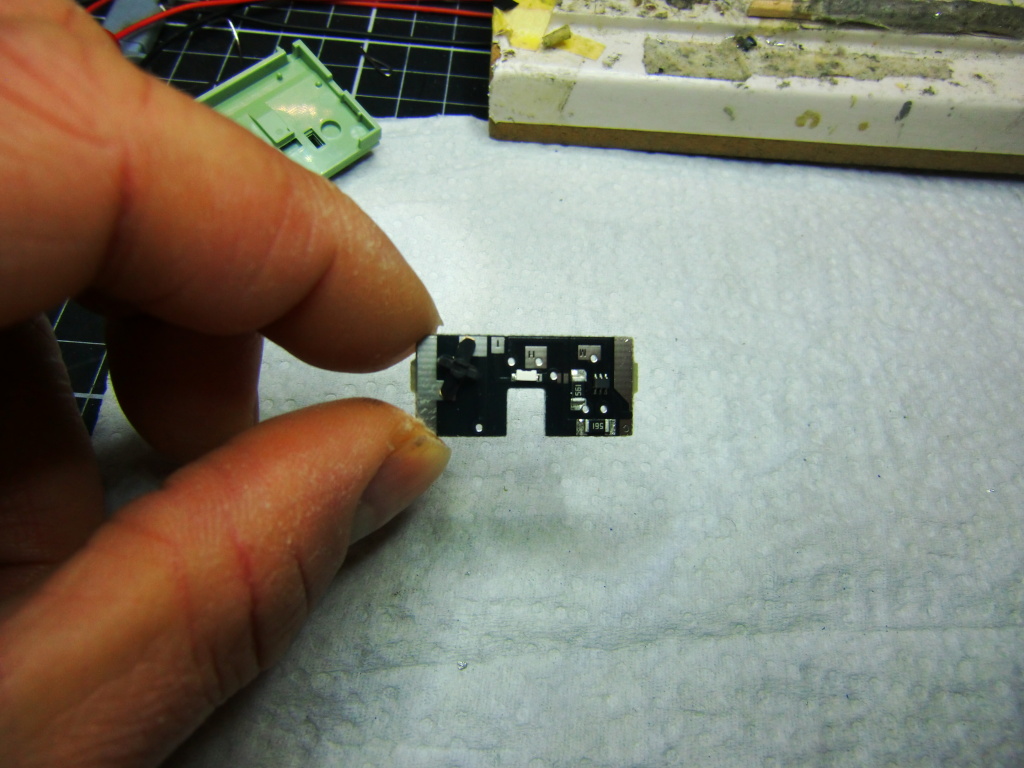

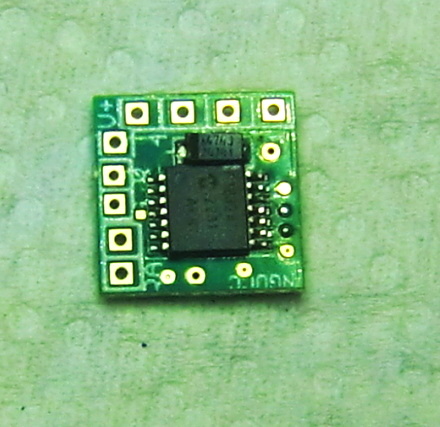
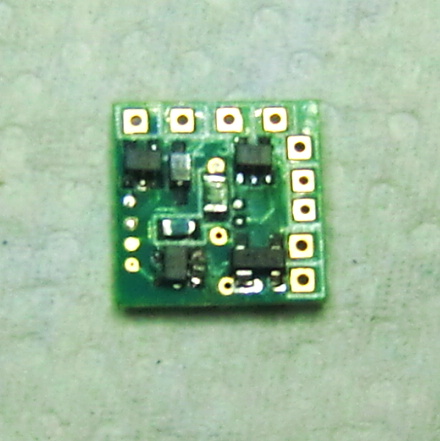
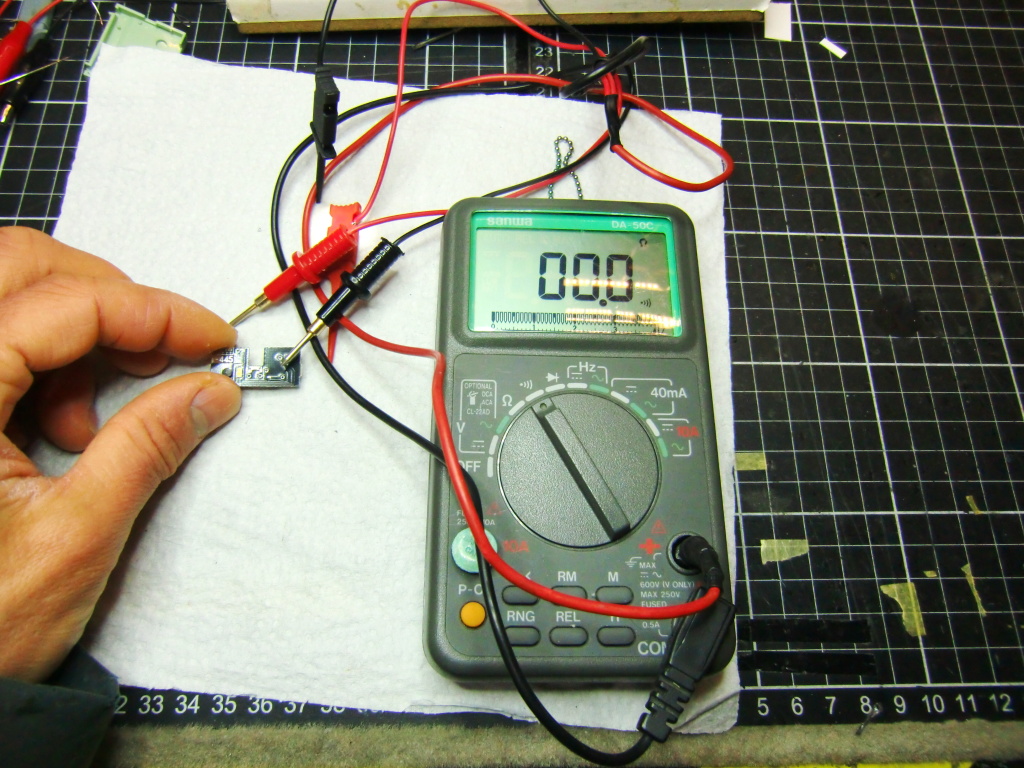
ライト基盤の電気の流れを1つ1つ確認していきます。
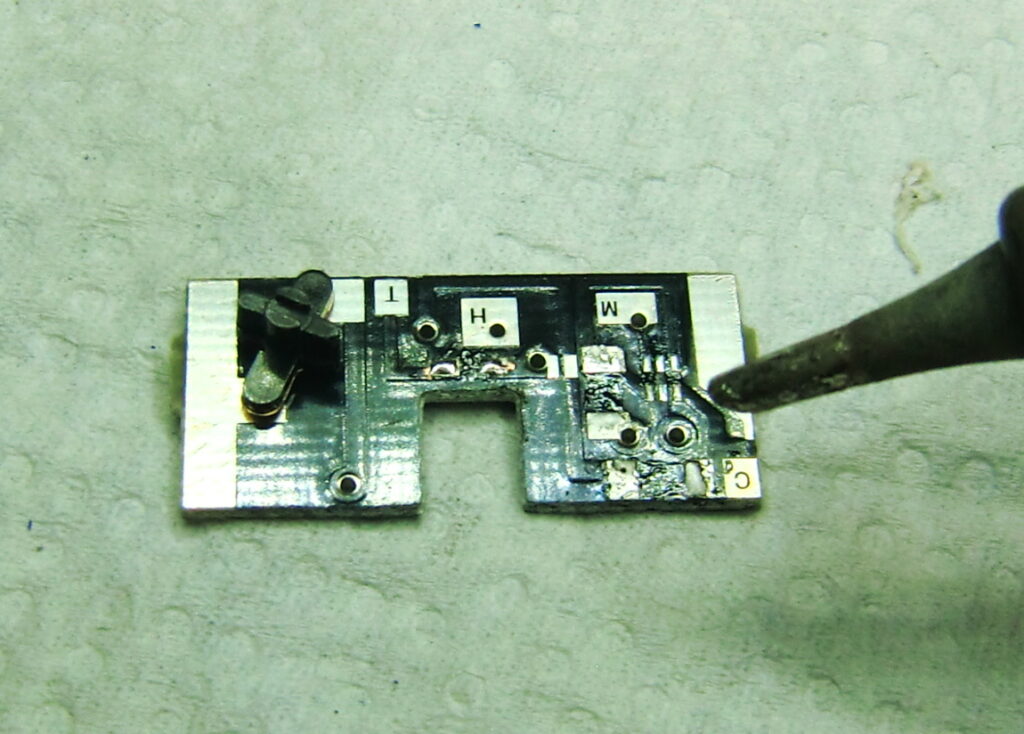
現状付いている裏面の部品をすべて外します。表面のヘッドおよび種別灯用の配線は、絶縁して独立させます。
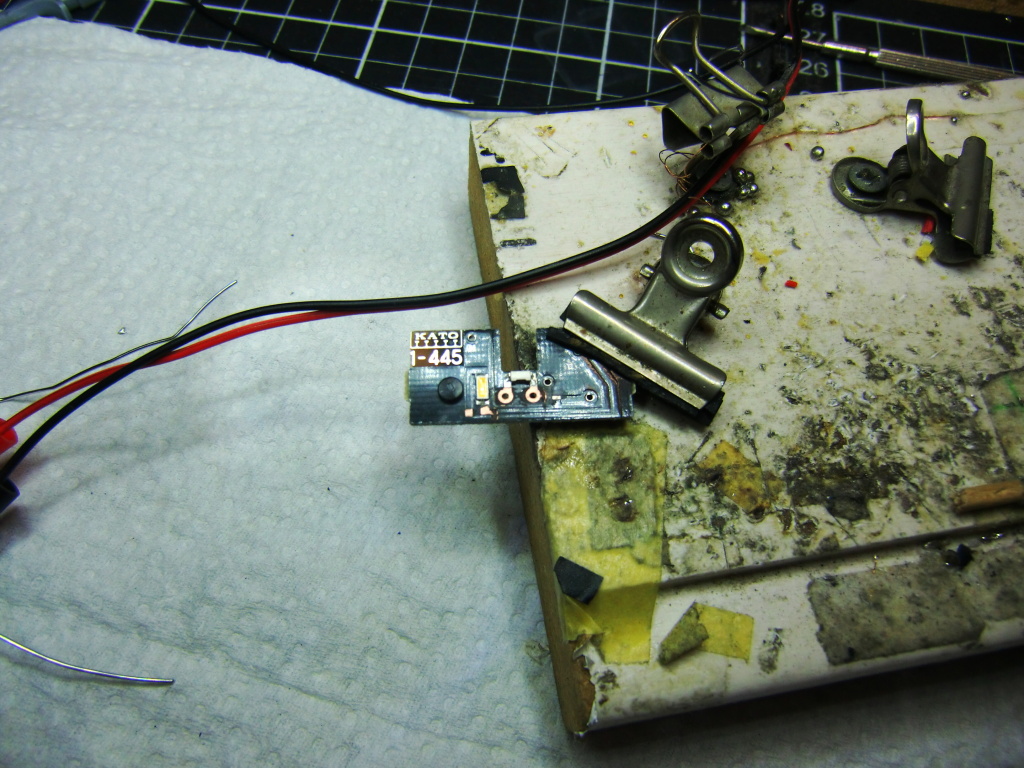
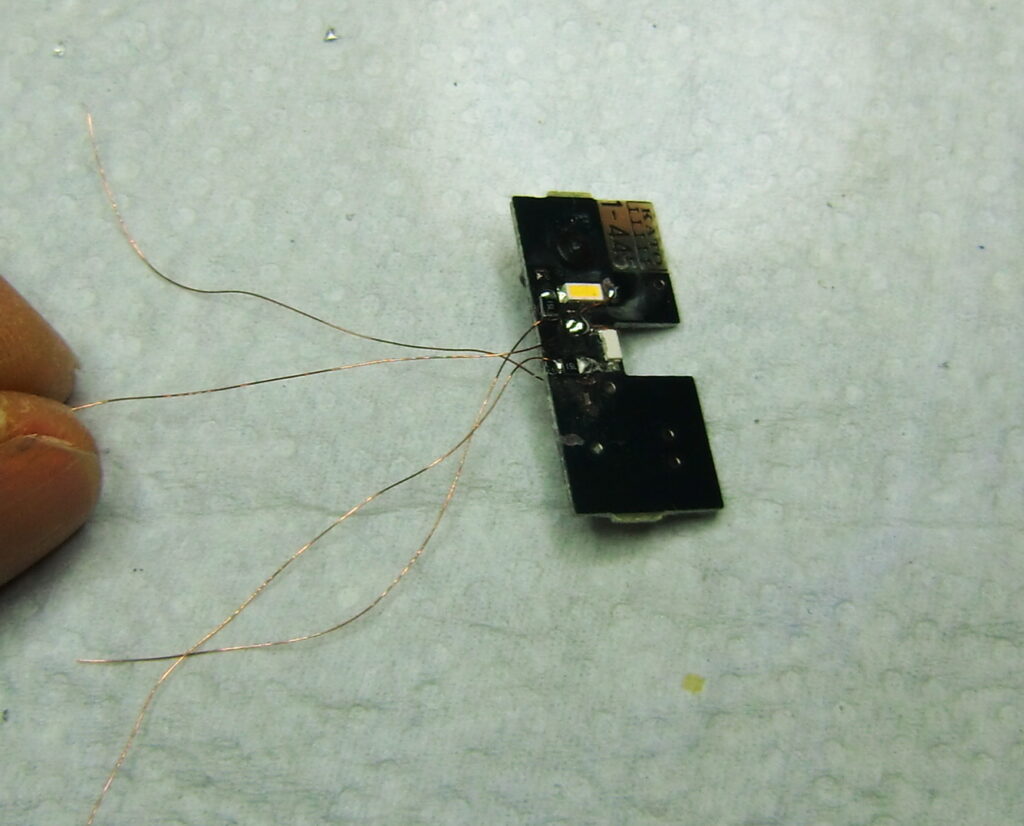
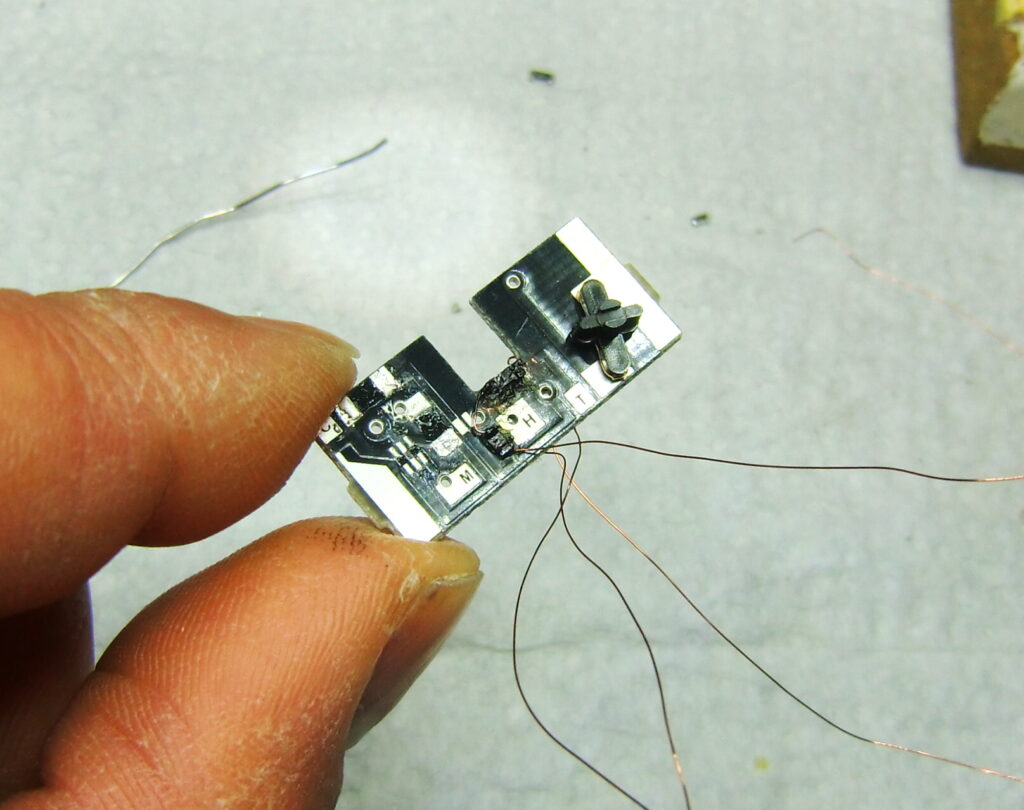
ようやく組み換え加工の終わったライト基盤です。普段からライト加工等を行っていない方にとっては、ちょっと難しいかもしれませんね。
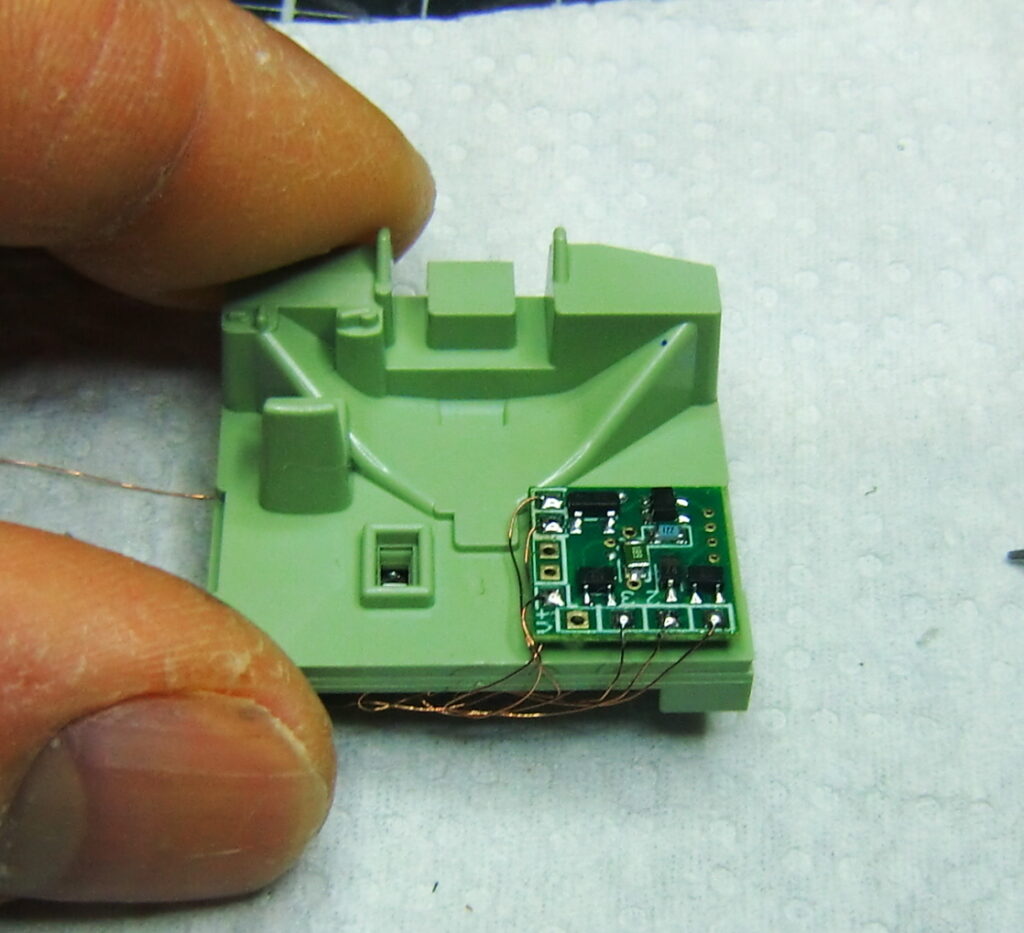
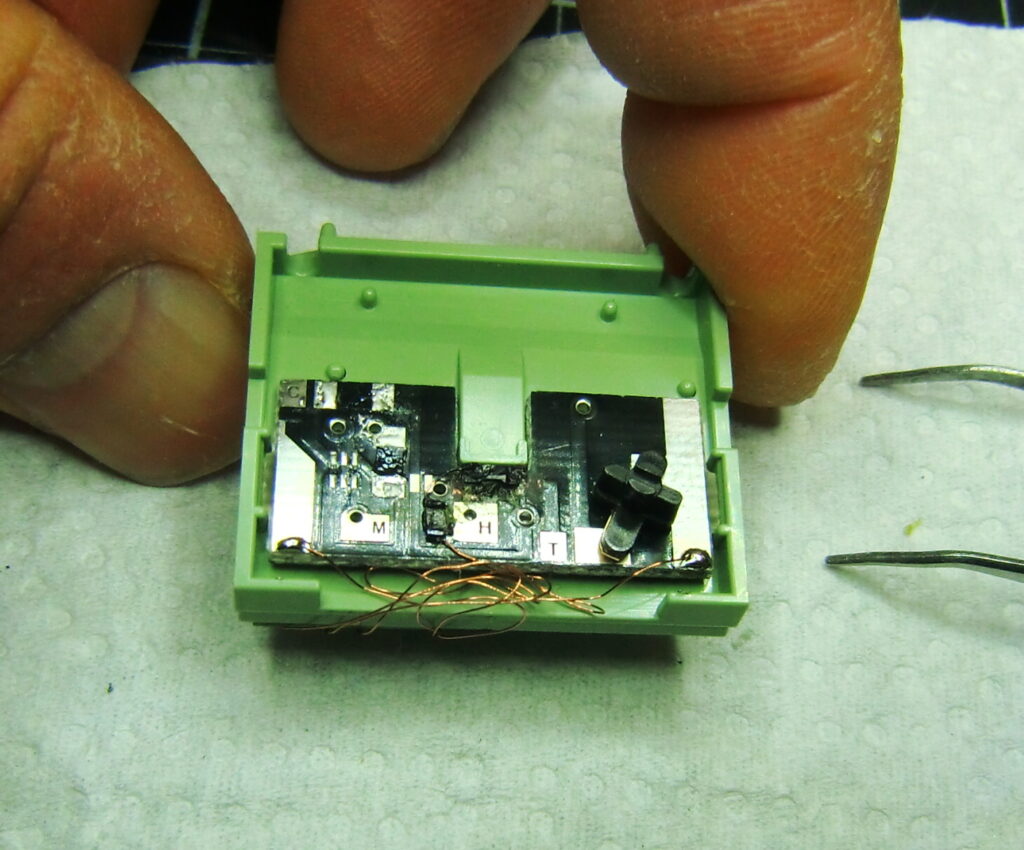
このように配置して結線してみました。

基盤の組込みが終ったところで、最後に動作確認をします。
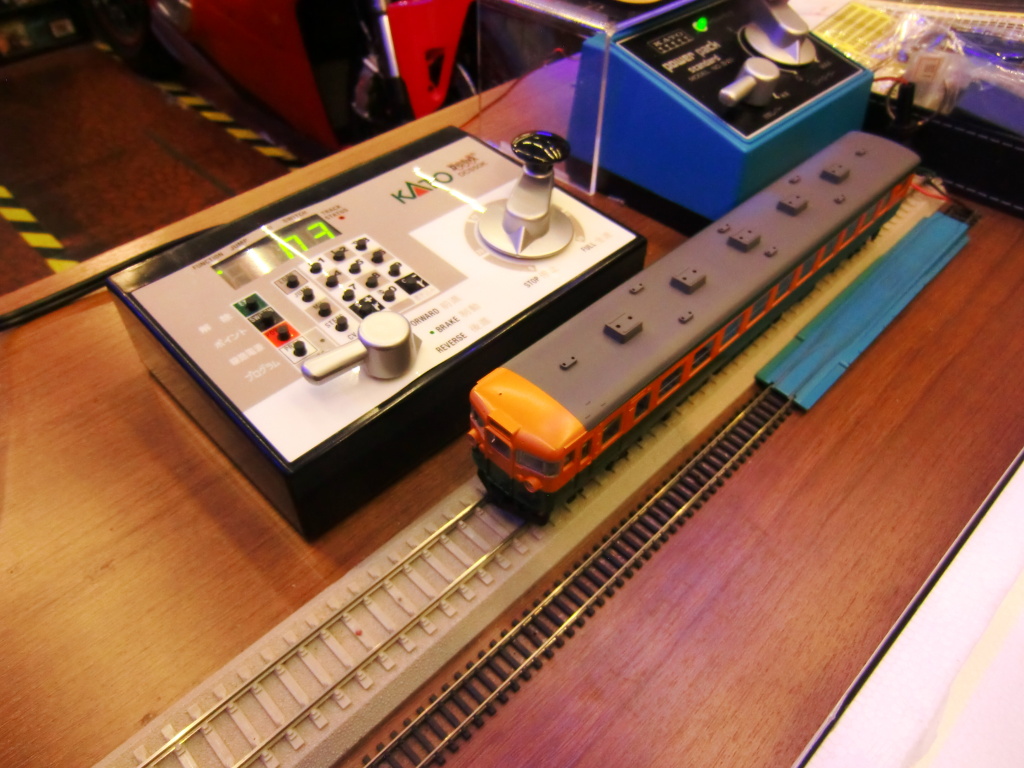

コントローからの信号も正常に受信され、各ライトの点灯を確認しました。作業完了でございます。


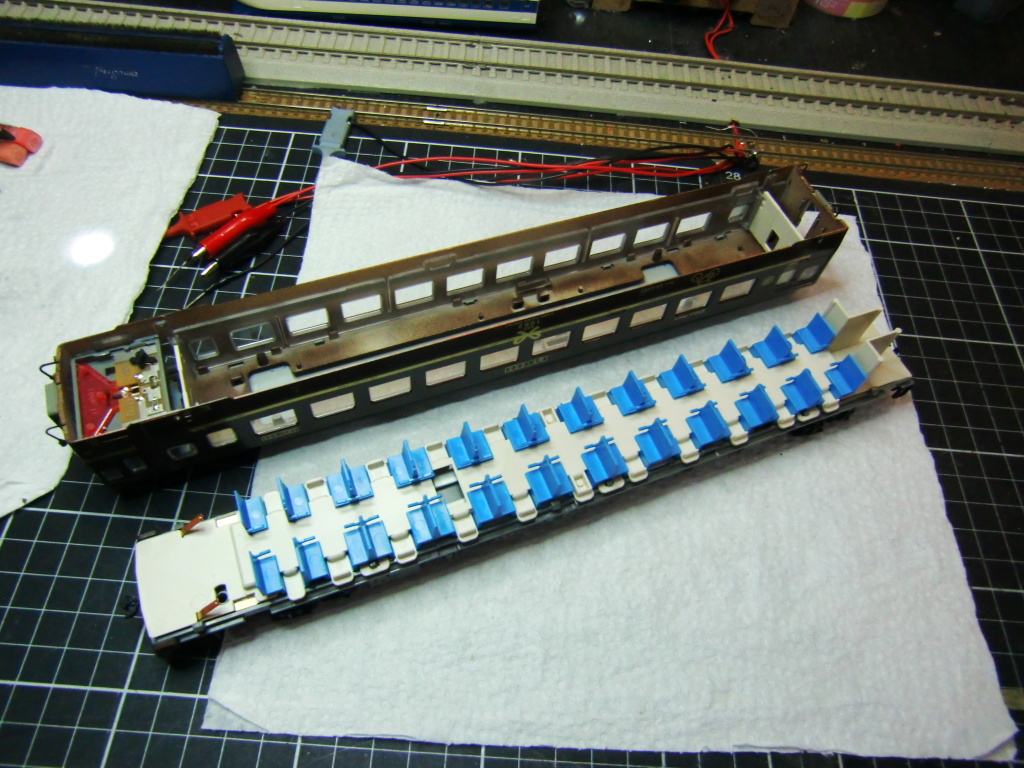
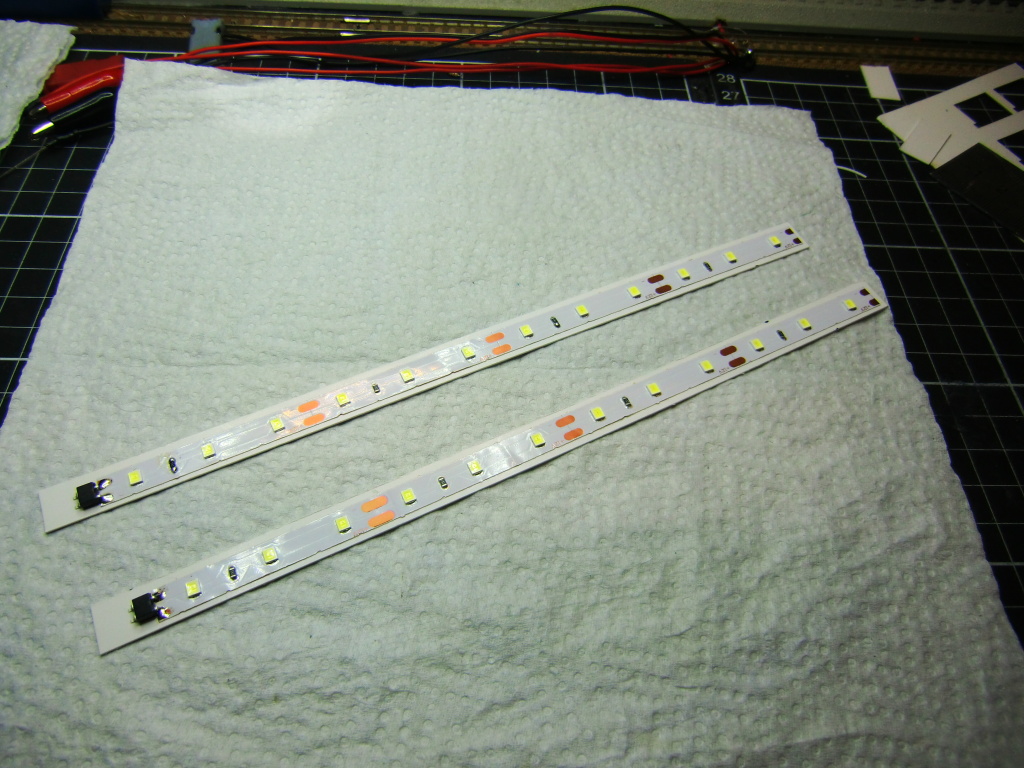
ユニットをベースに固定して、このあと並列に作り替えます。
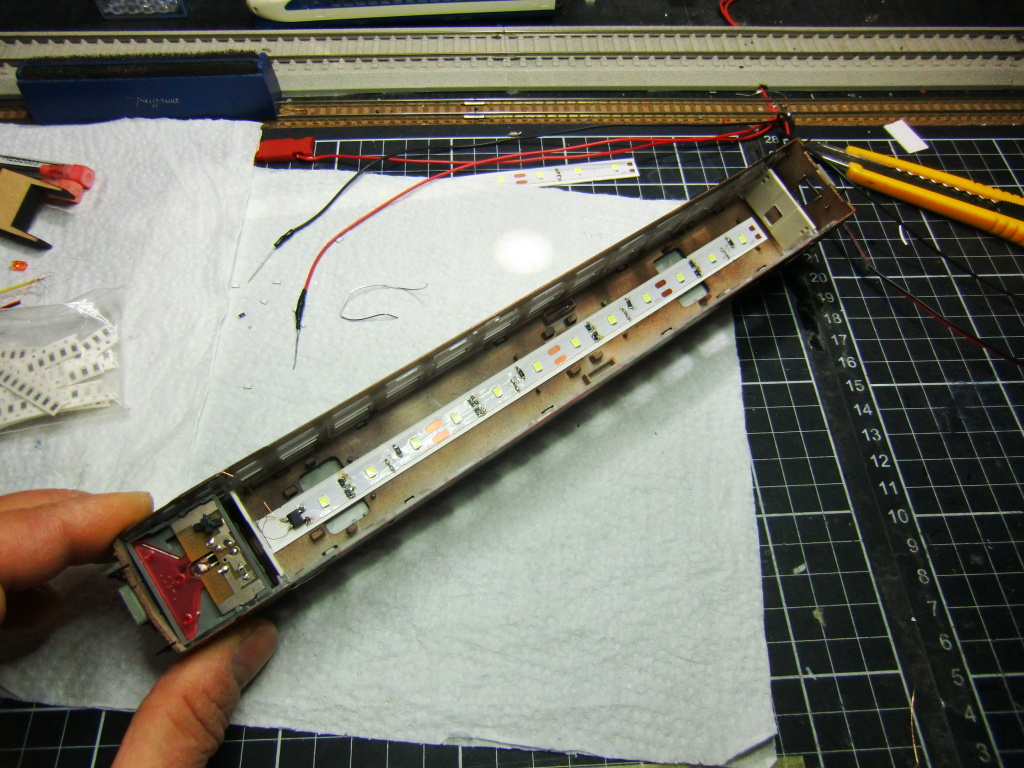
各LEDにそれぞれ抵抗を配置したものにすべて作り替えます。なお、ライトユニットの基盤から電気を供給するようにしました。



作業完了でございます。
今回の作業では、塗装の色落ちによる再塗装およびライト加工、集電O/Hです。

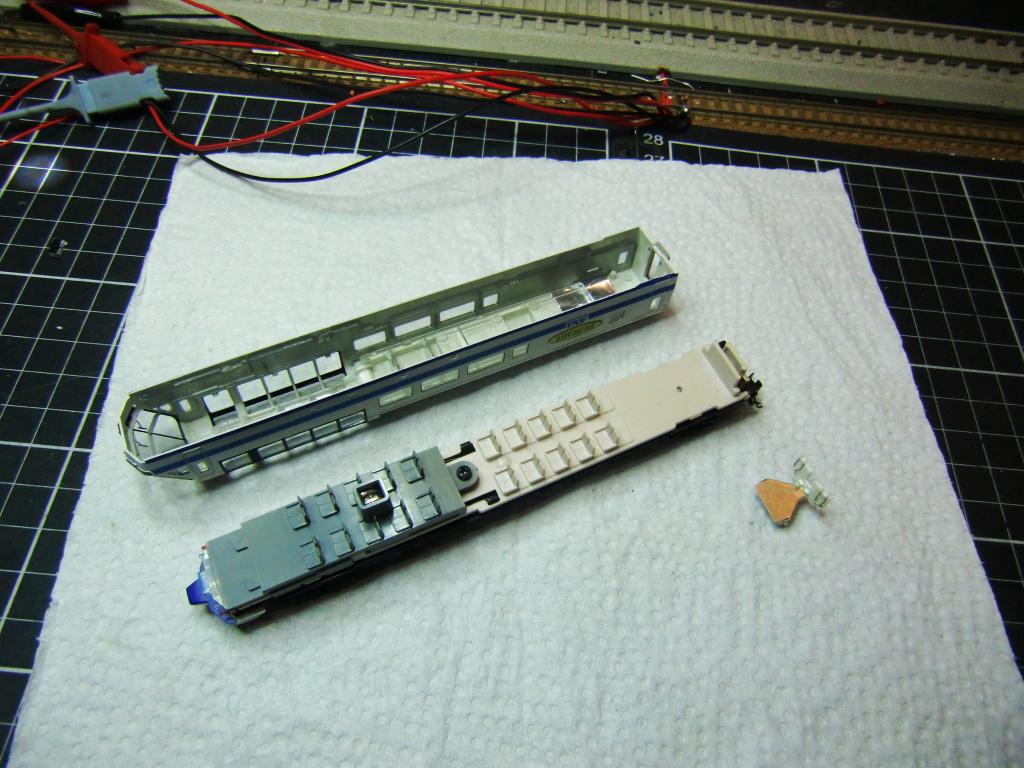
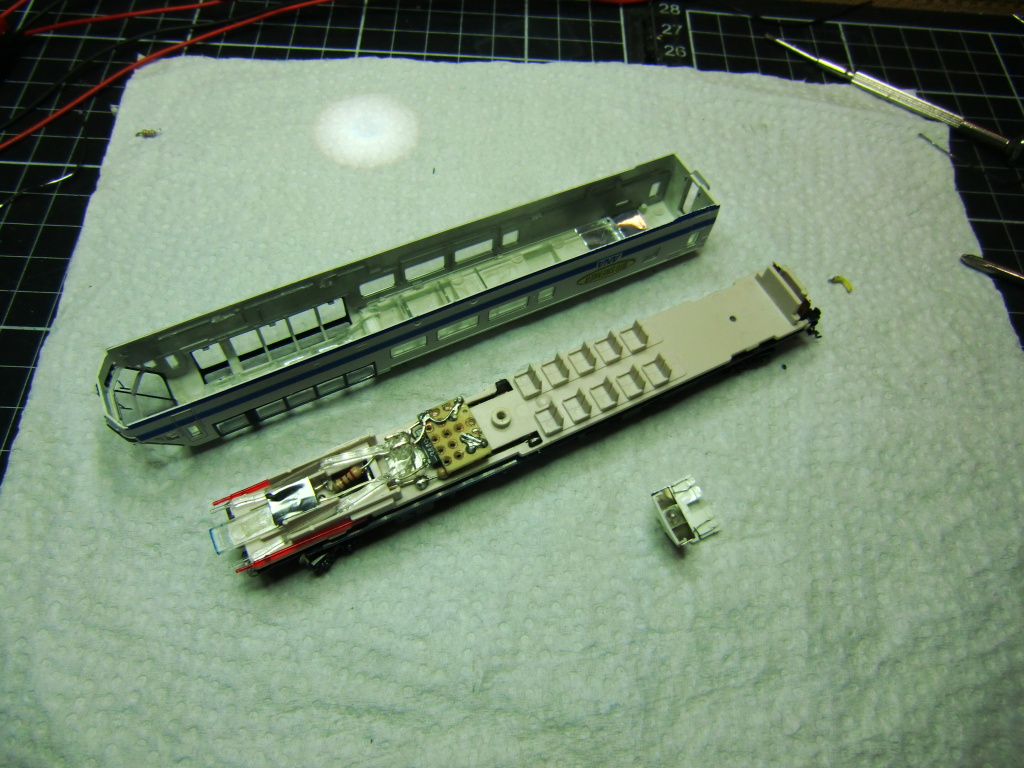
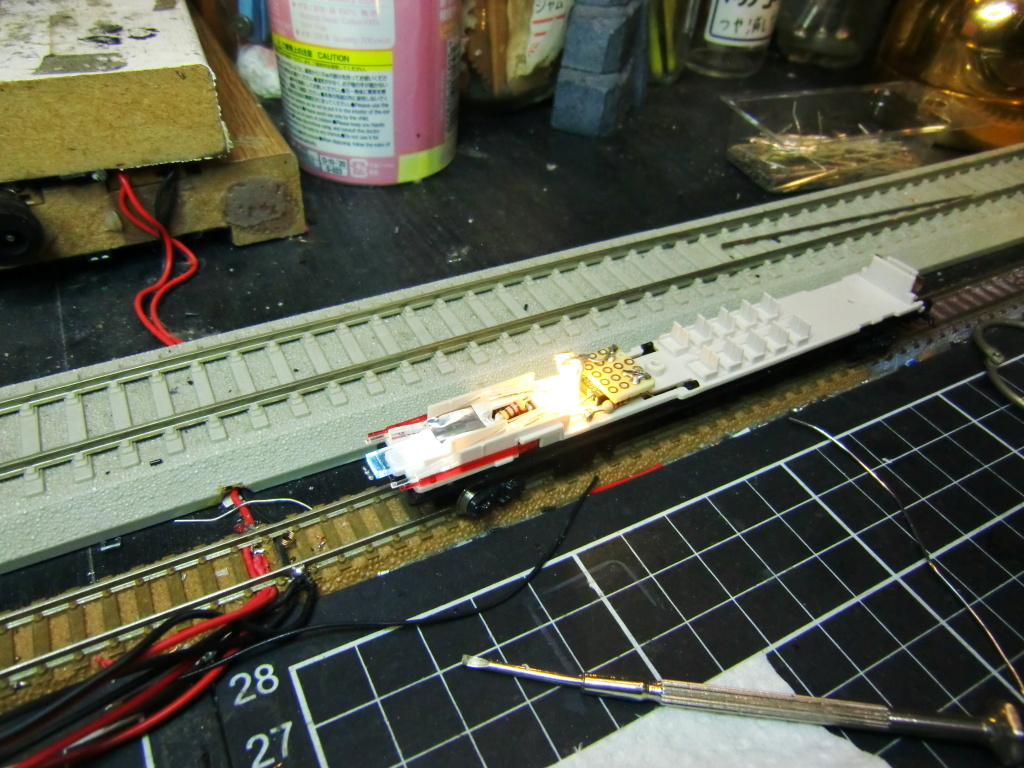
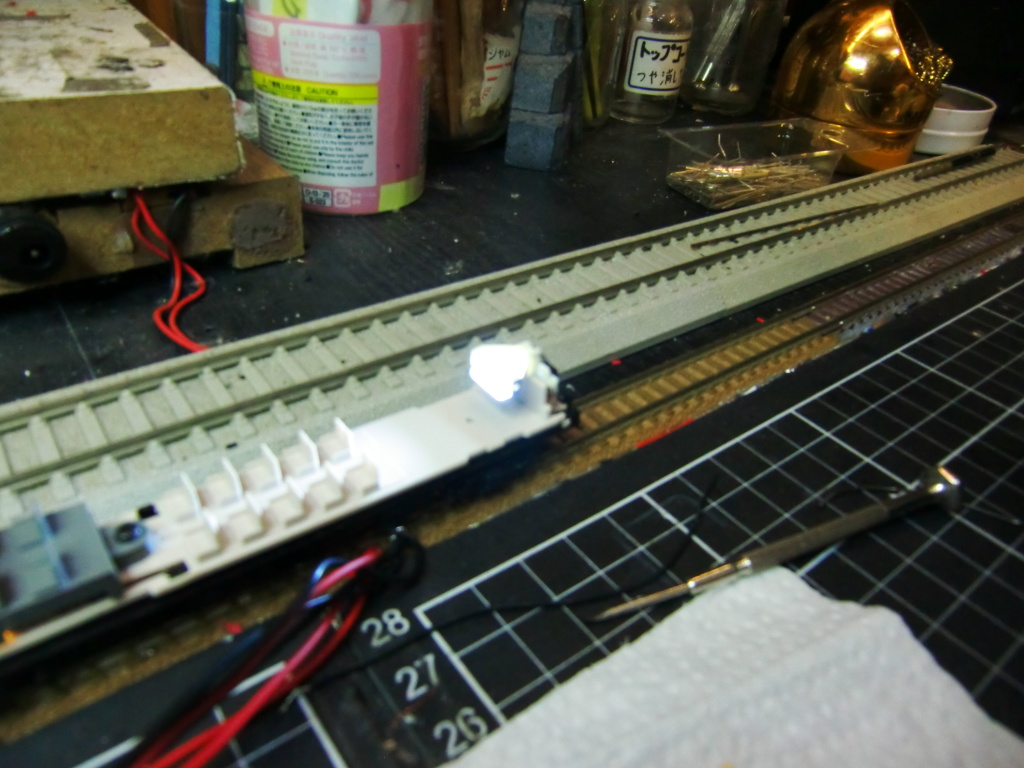


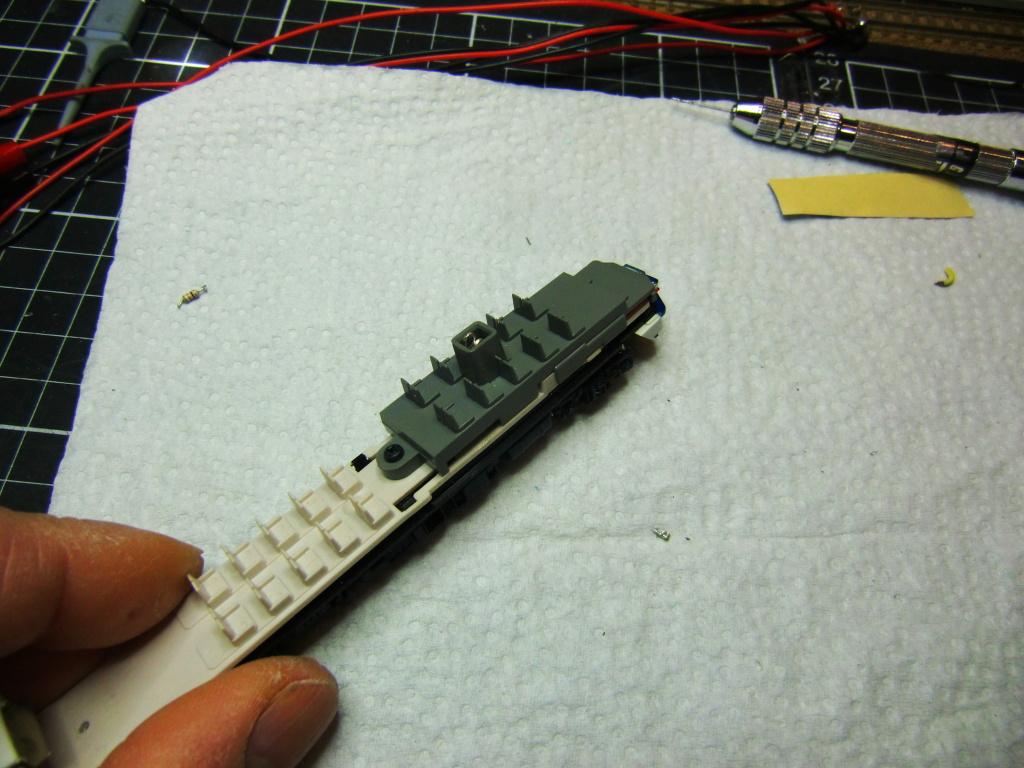
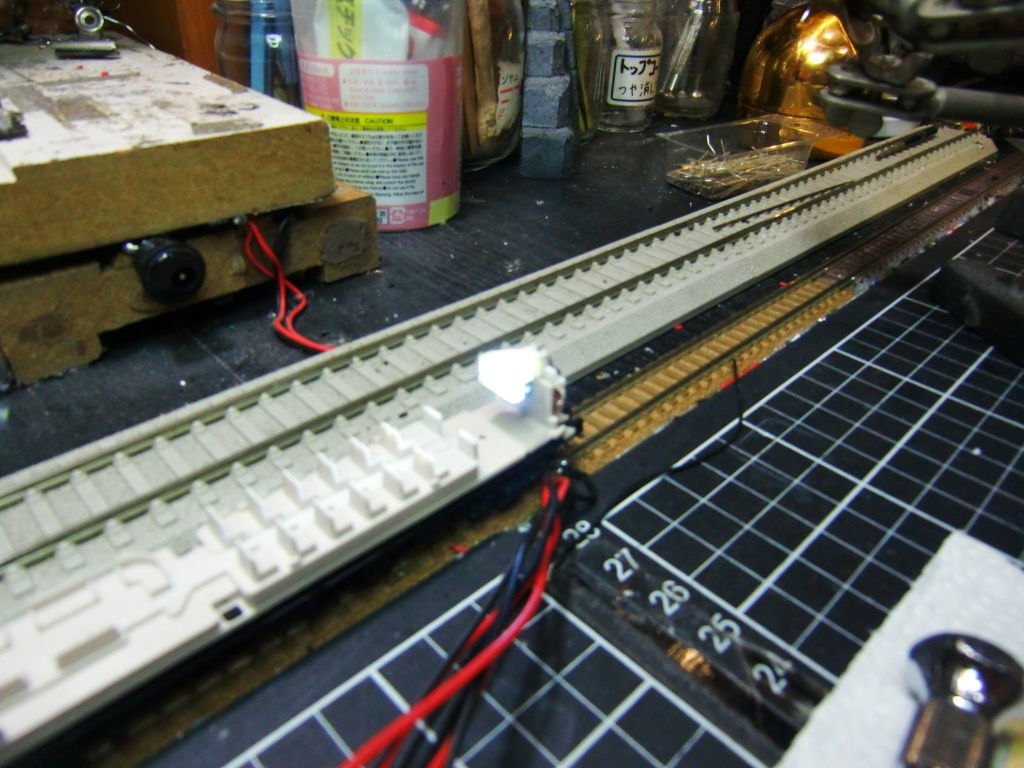

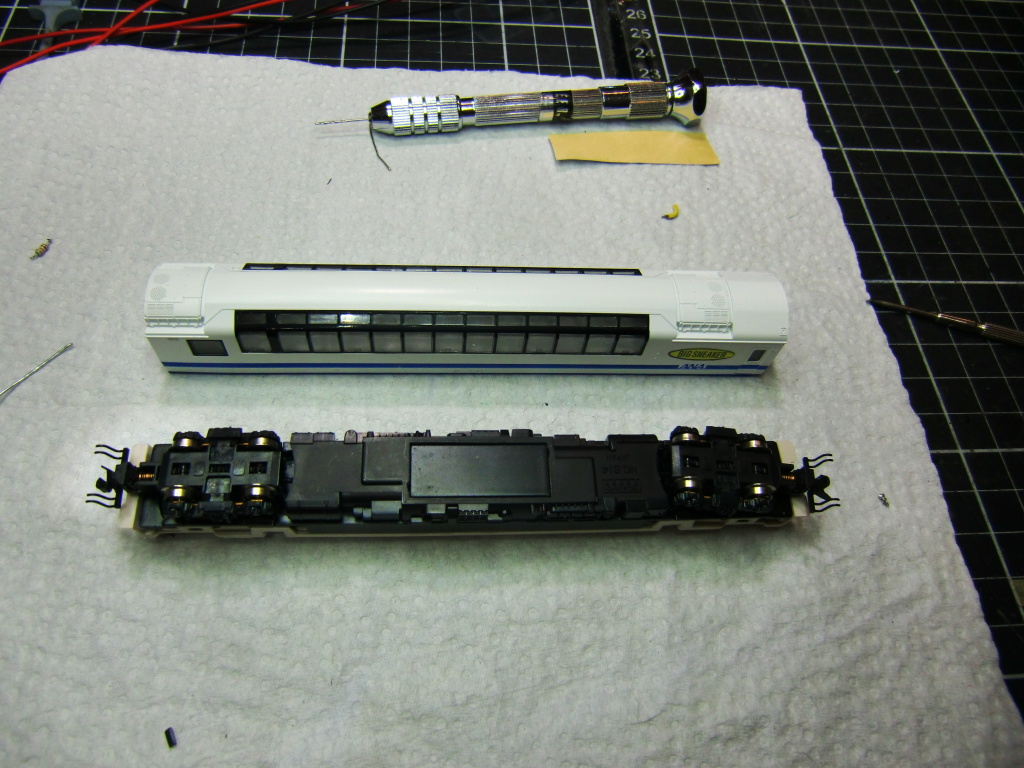

▼帯修復作業

所々、色あせや色が剥がれています。

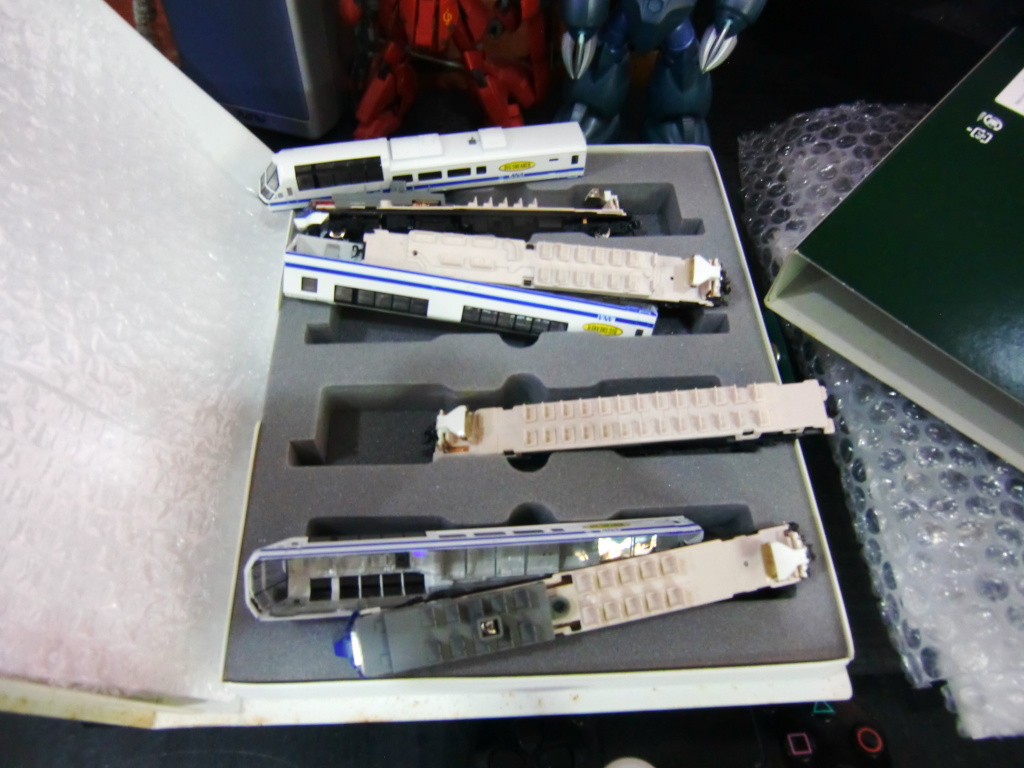

帯は、一見濃いブルーに見えますがよく見ると紫っぽい感じです。

調合作業は、大変時間のかかる作業です。
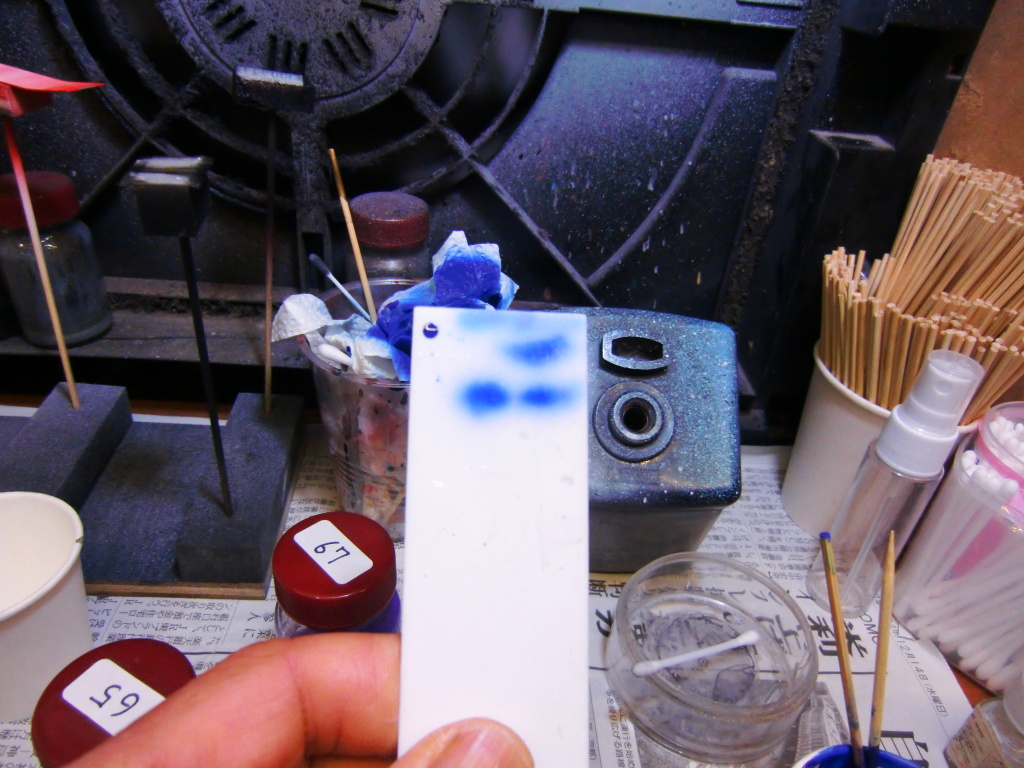

調合を繰り返してようやく目的の色が出来上がりました。今回の配合は、パープル+インディーブル=3:1くらいの割合でちょうどよくなりました。意外と紫成分が多くなりました。
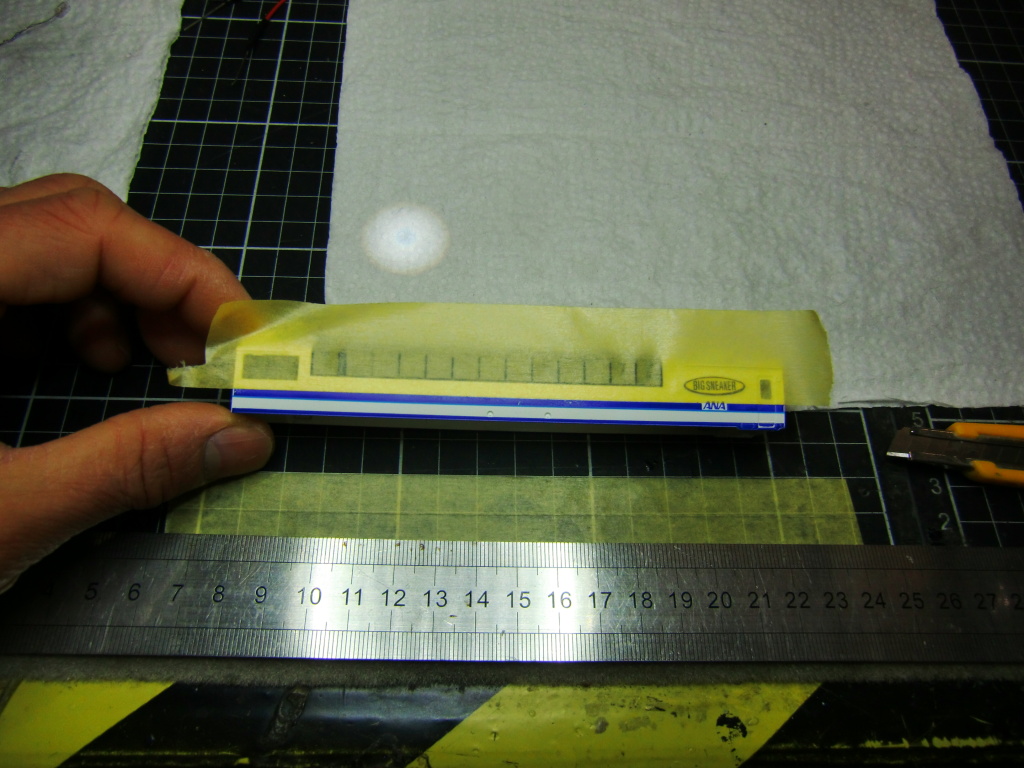
事前に塗装箇所を洗浄してから、マスキングで覆います。

帯全体を均等に塗装しなおします。

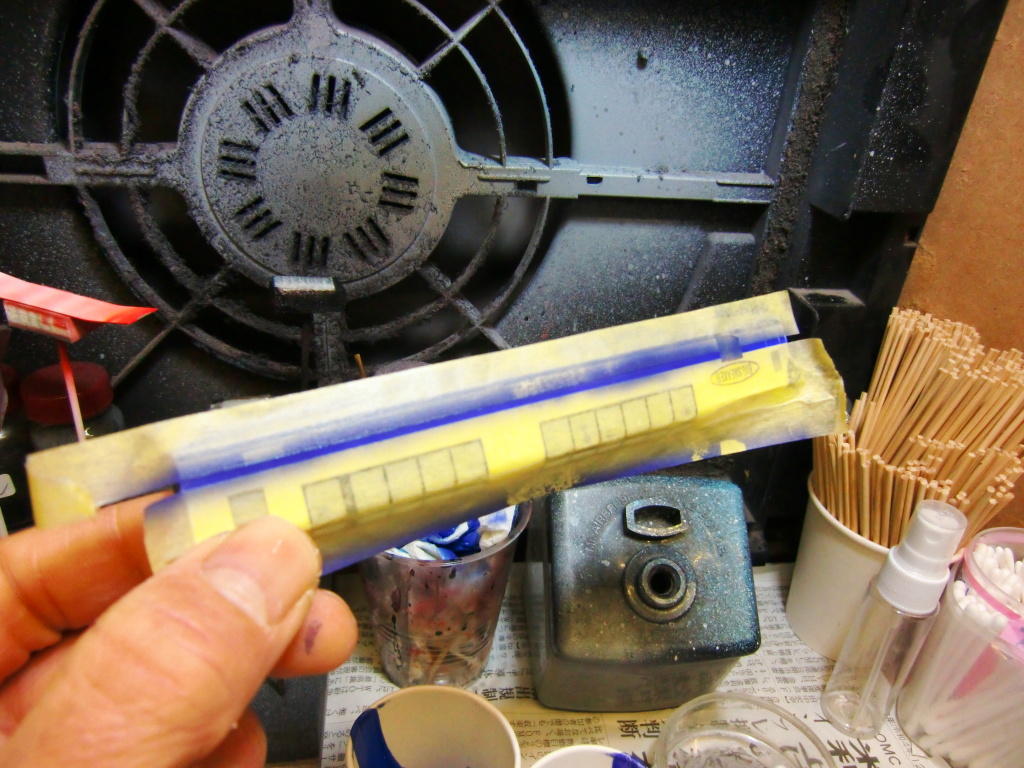
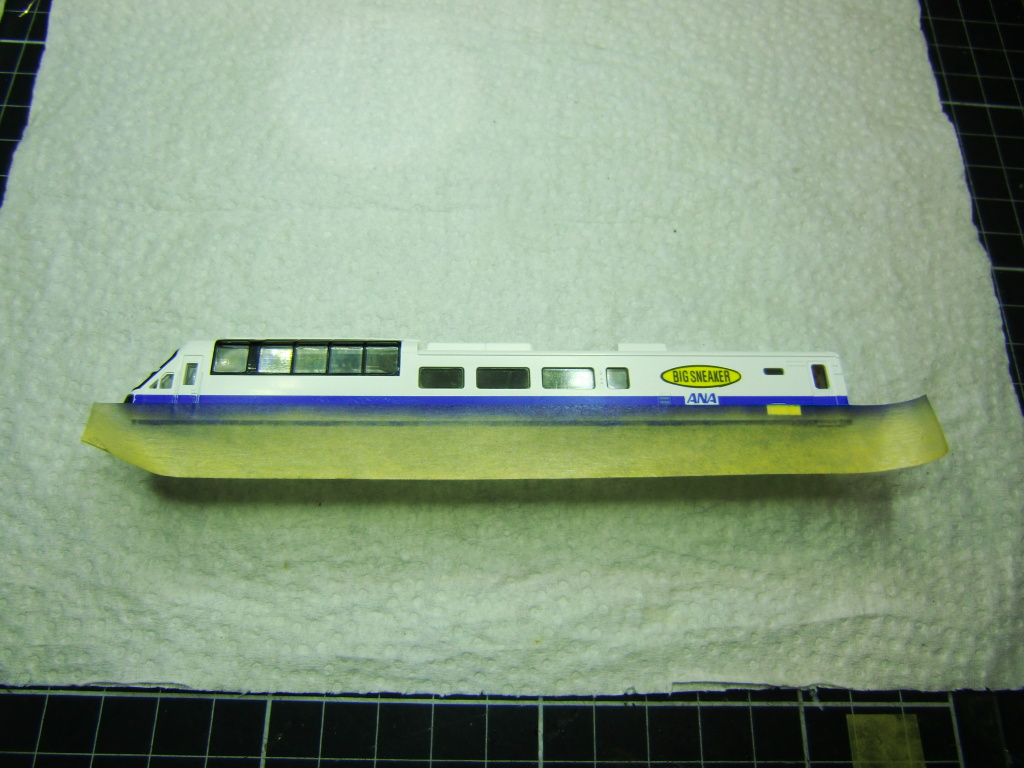
こちらは先頭車です。


マスキングを剥がす瞬間が楽しいです。

「お~」きれいな帯が復活しました。
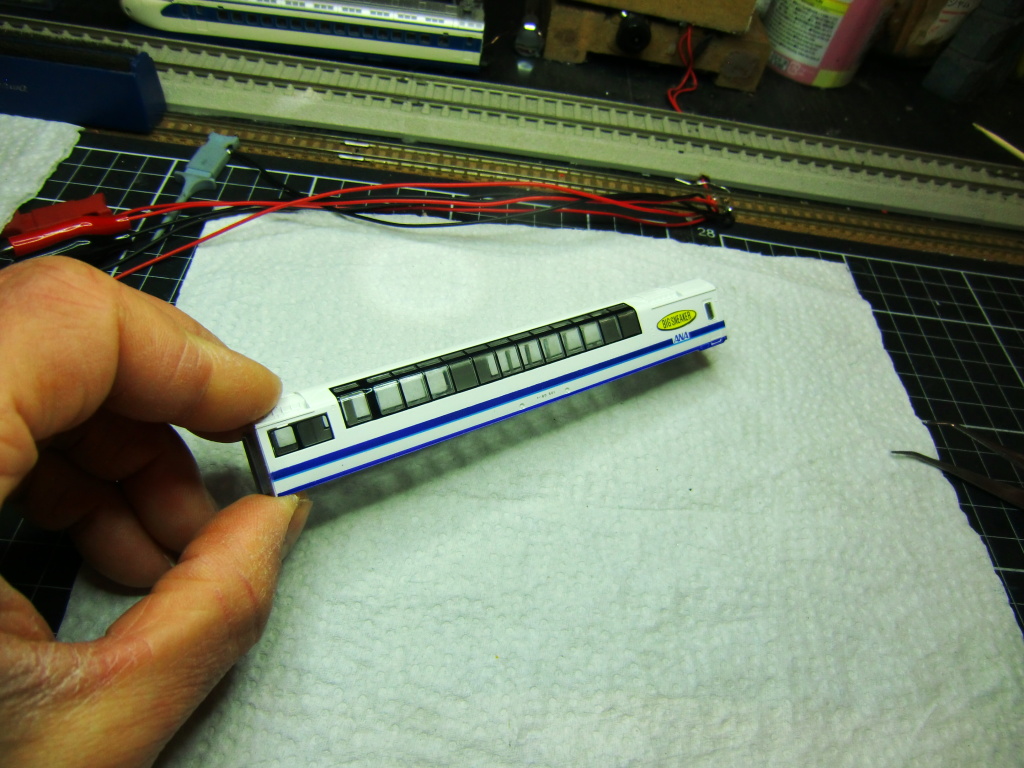

作業完了です。

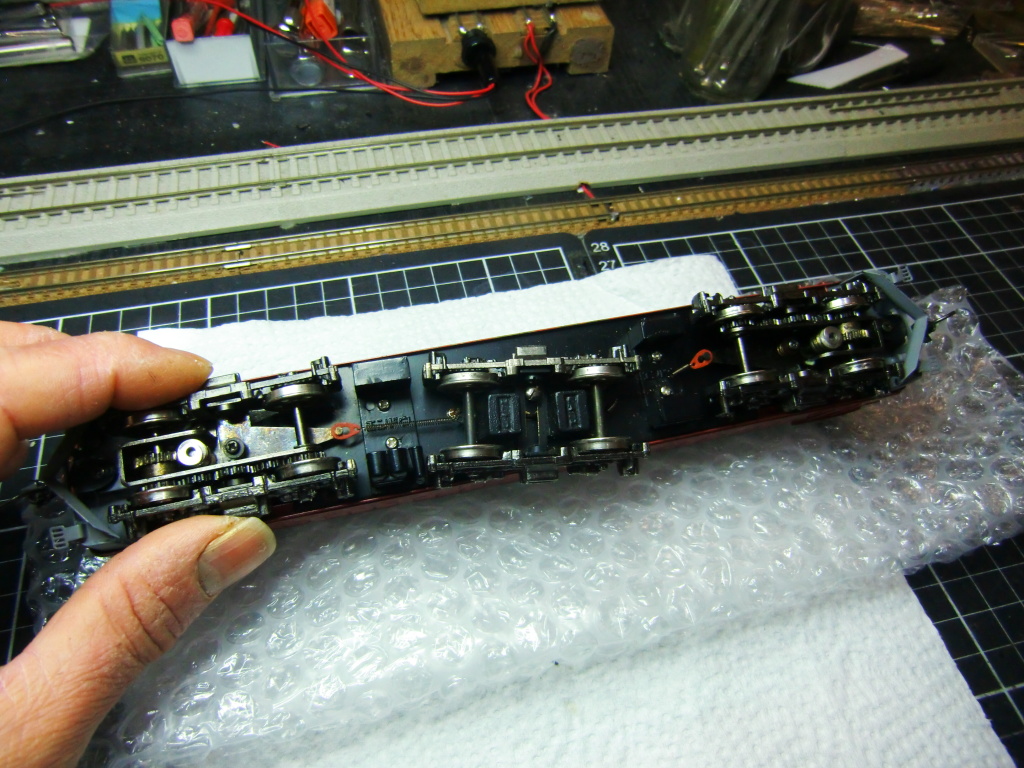
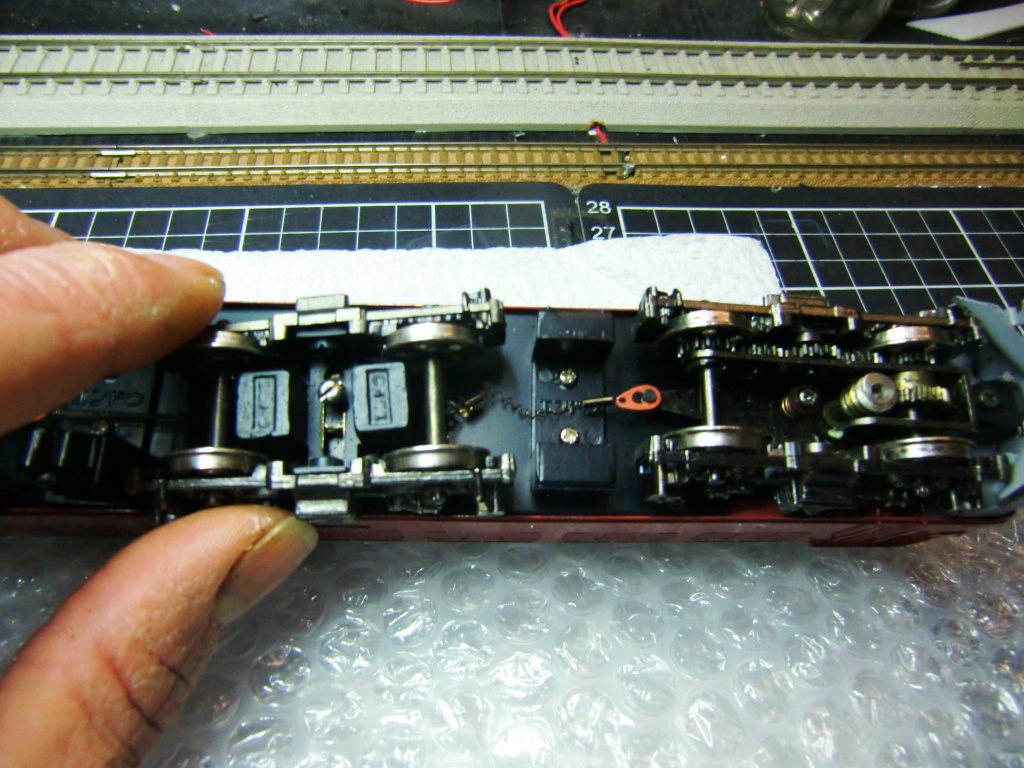 ¥
¥
中間台車を引っ張るバネが完全に伸びきって機能していません。これについては最後に直すことにします。

分解して各部のメンテと確認、調整を行っていきます。
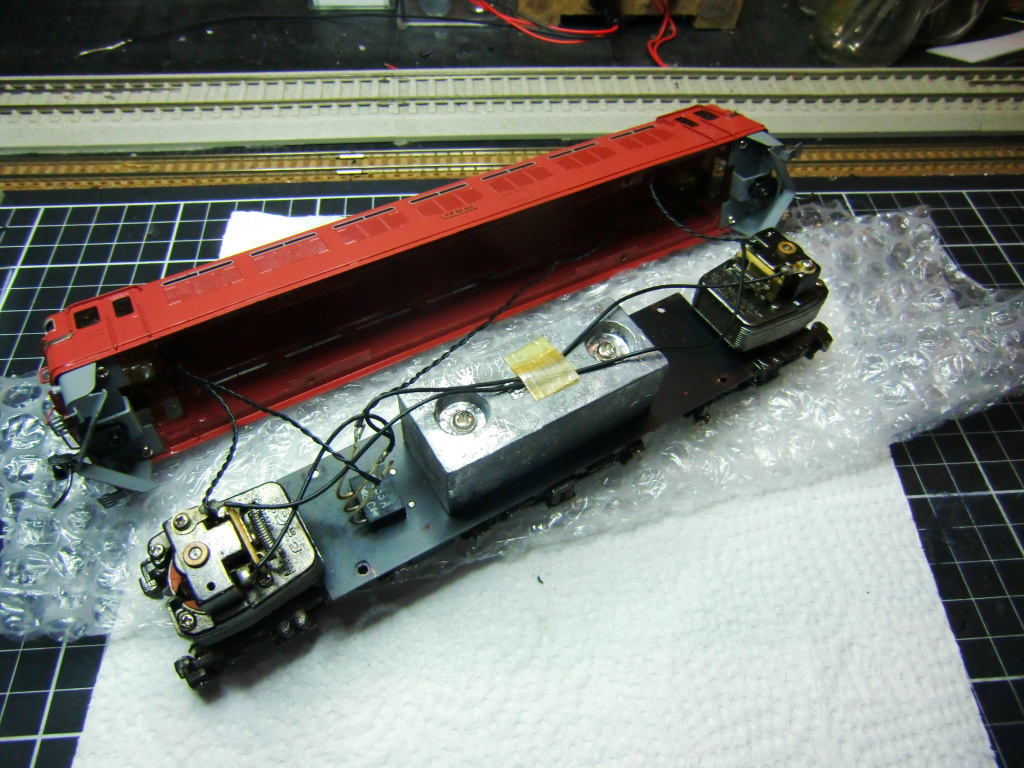

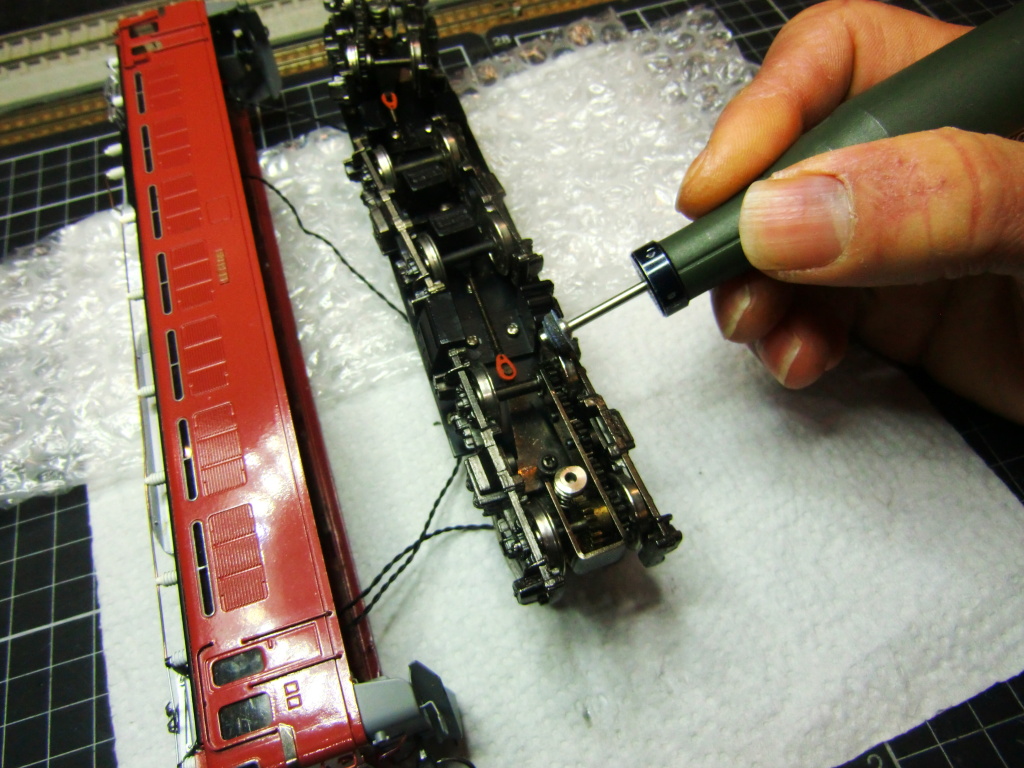
車輪の表面に焼き付いた汚れも磨き出して落としていきます。

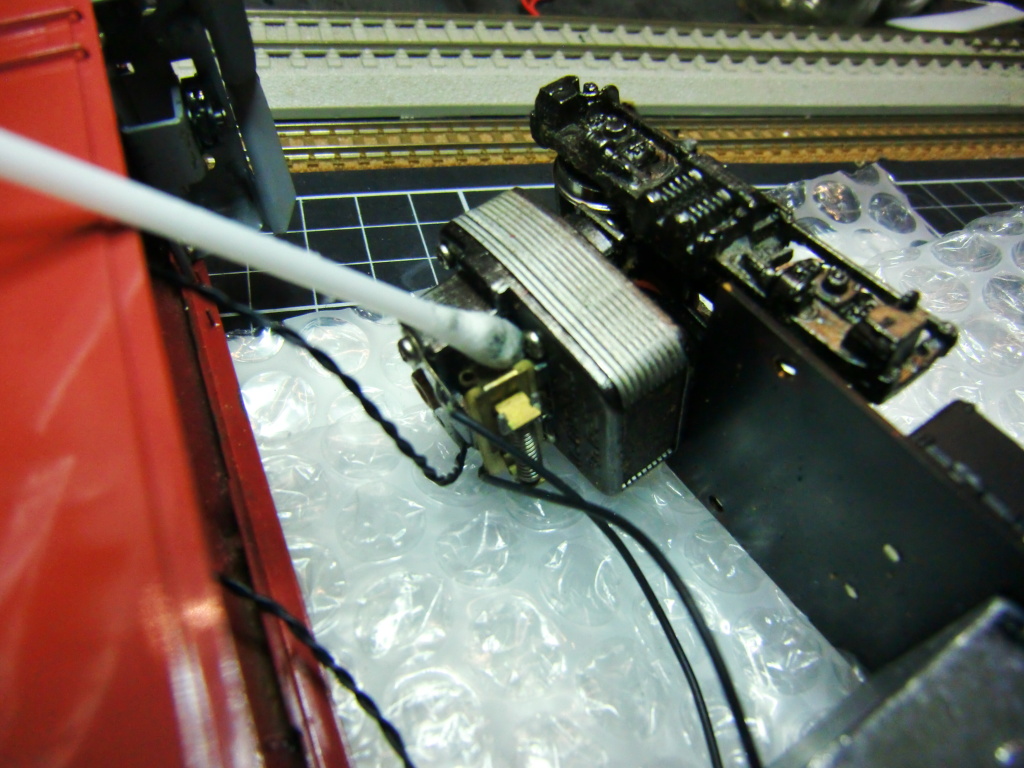

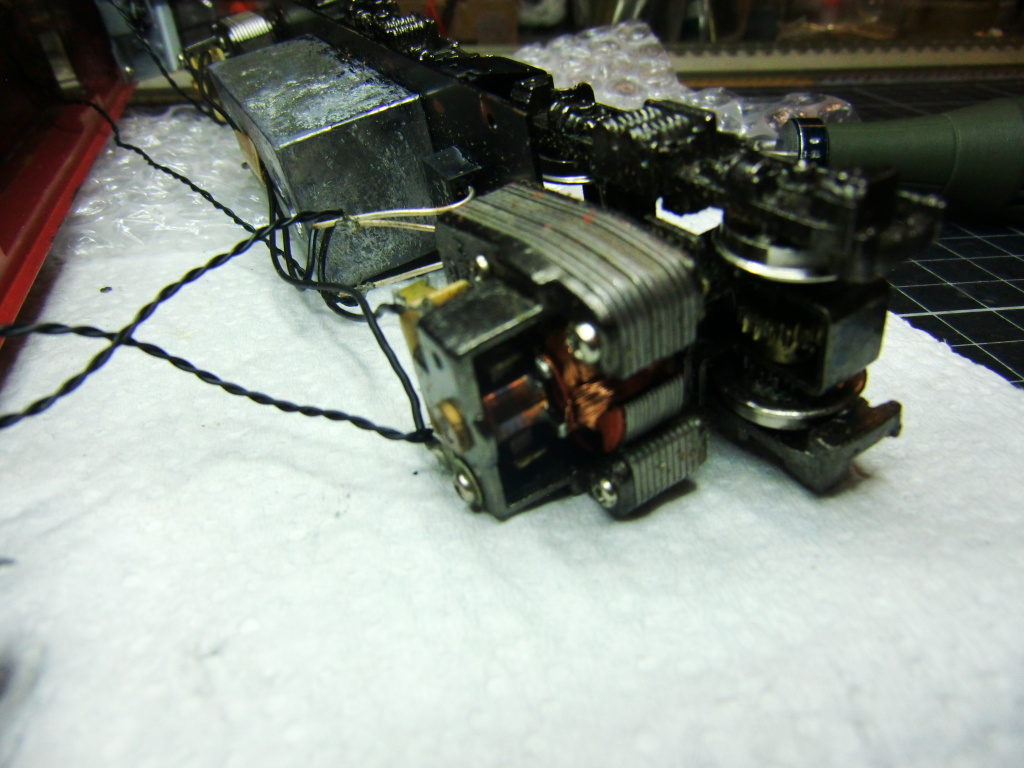

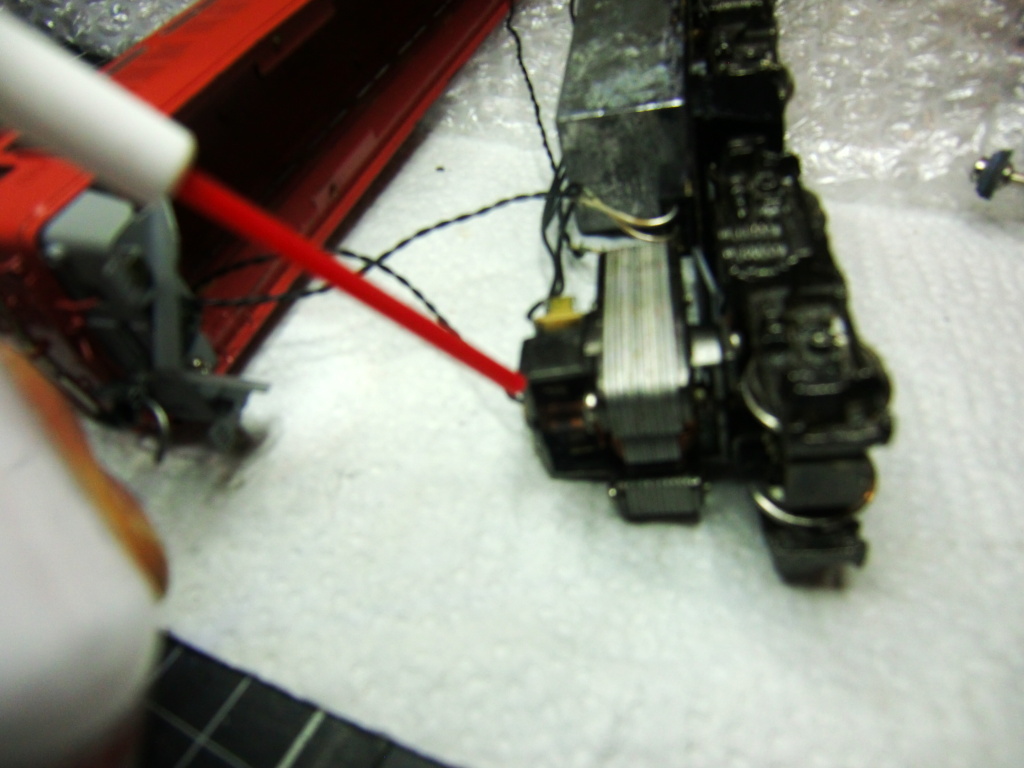
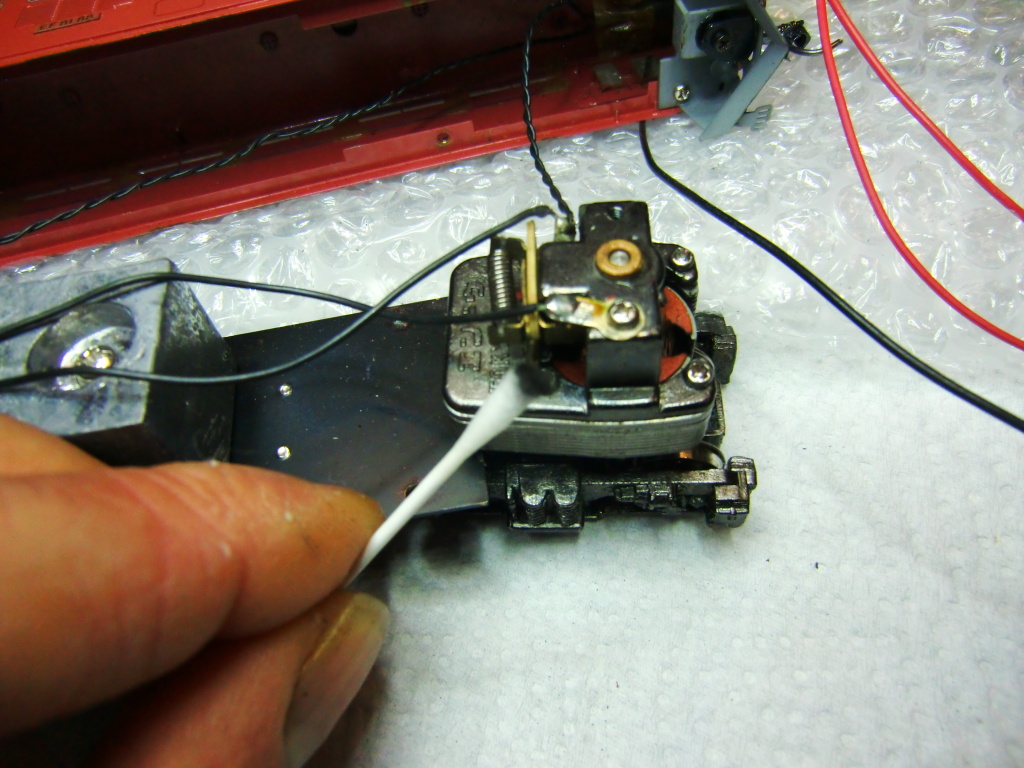
モーター内部も真っ黒です。各部のメンテを1つ1つ時間をかけて進めていきます。
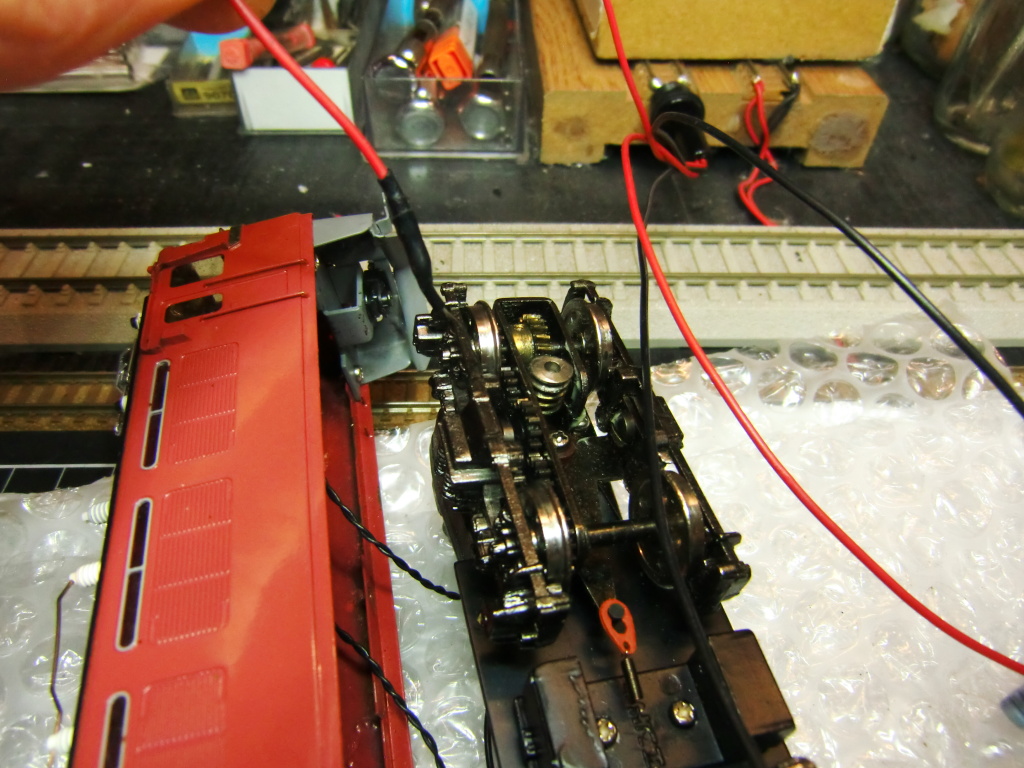
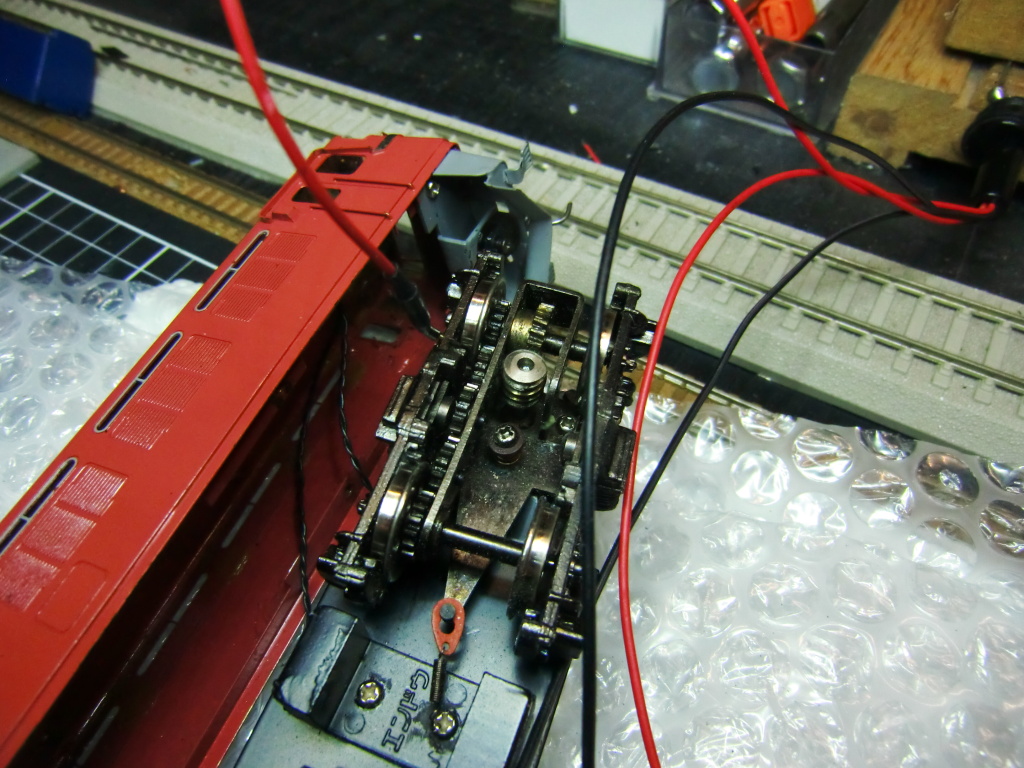
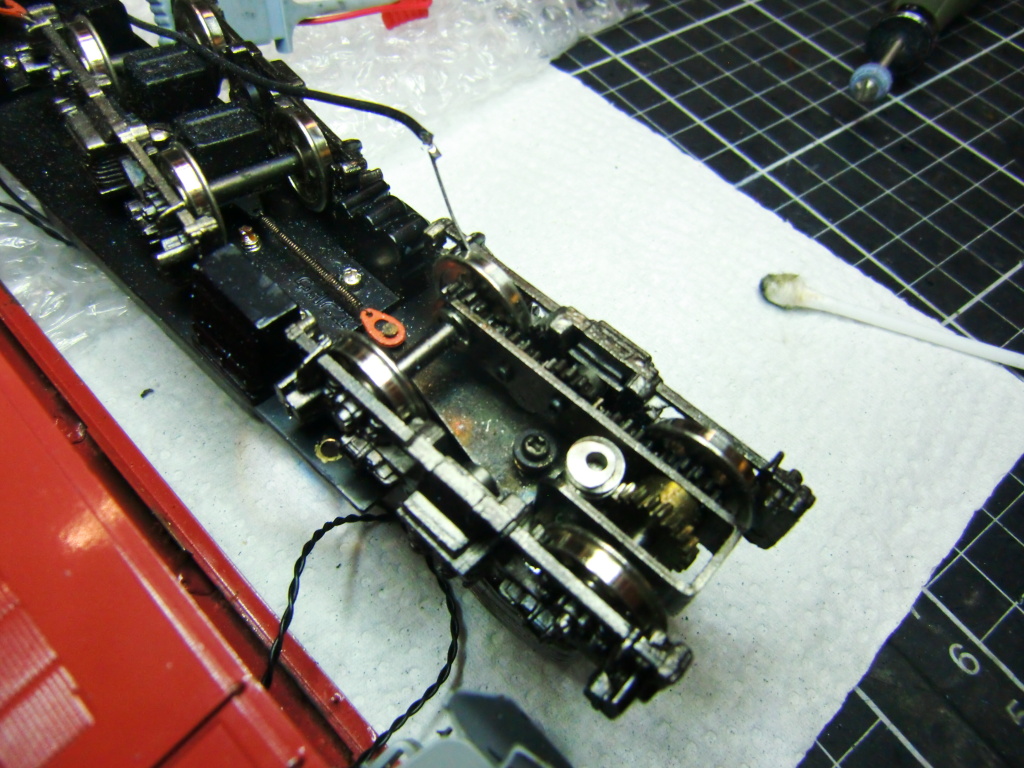
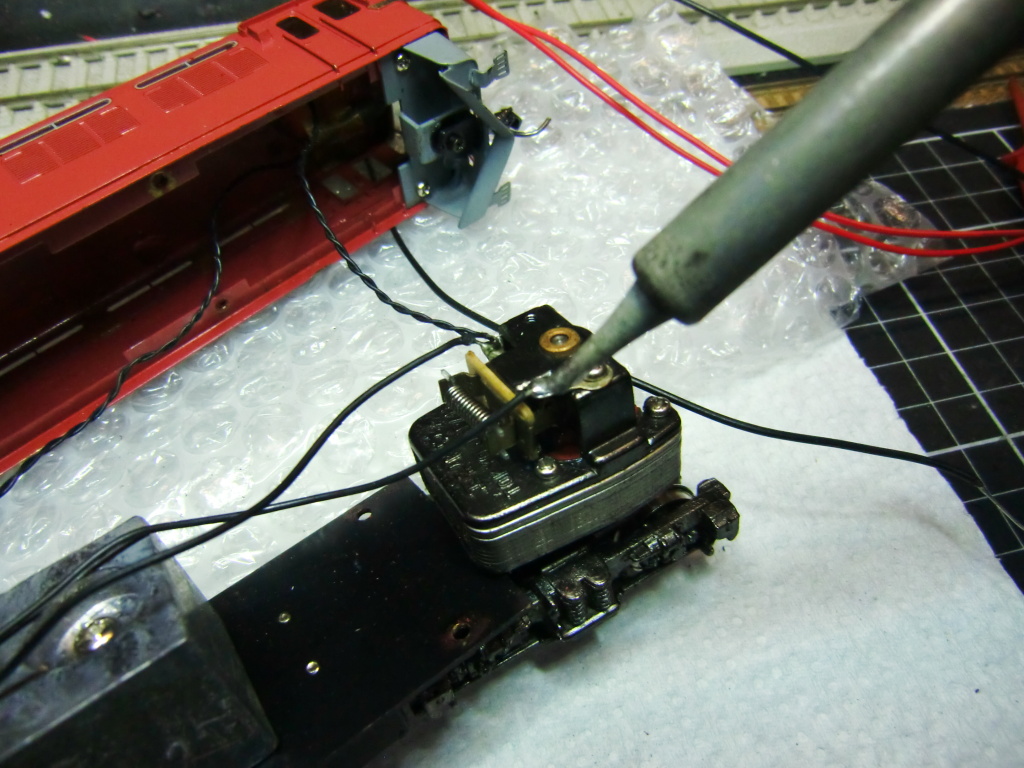
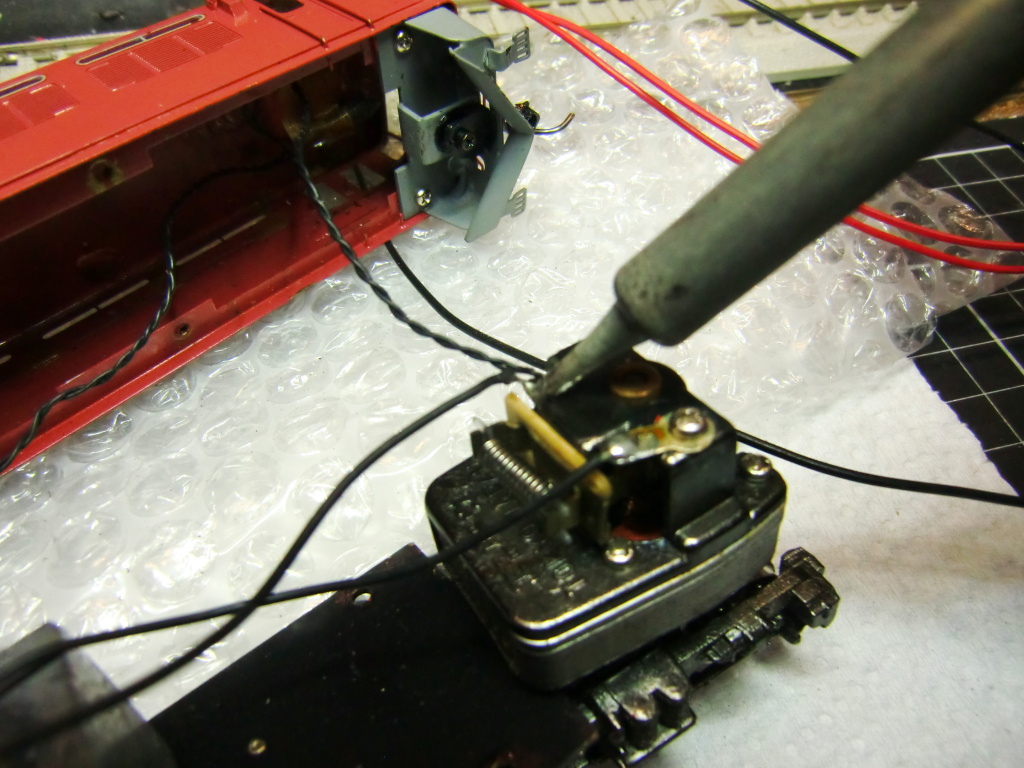
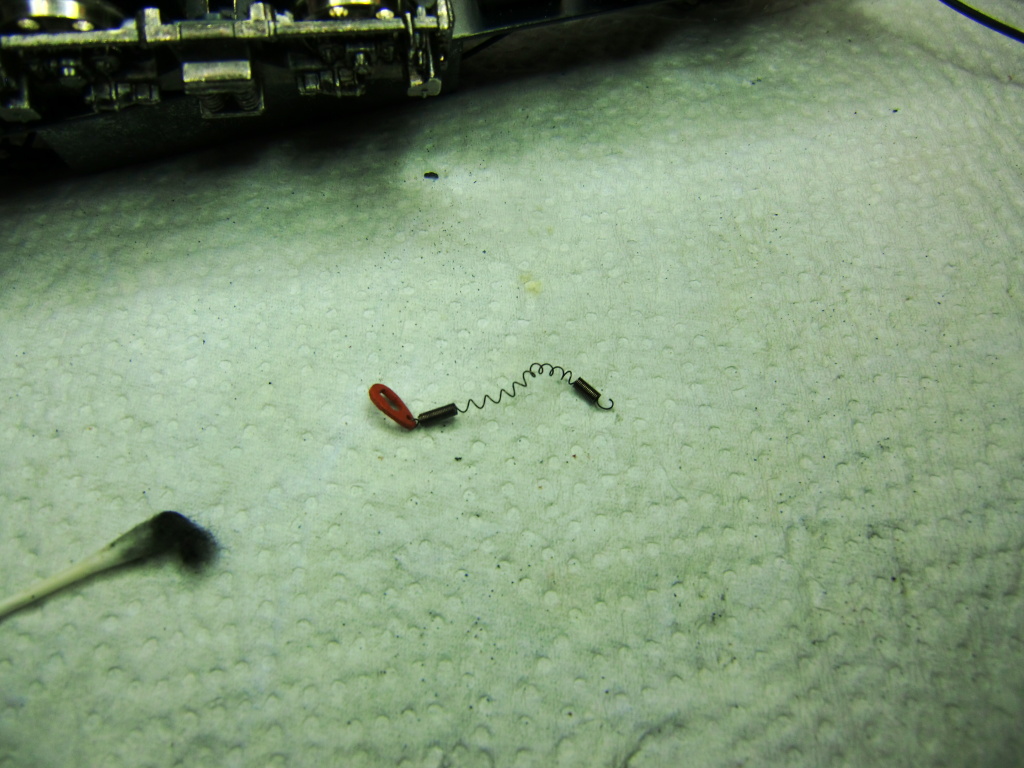
伸びきったバネを使用できる状態に加工します。
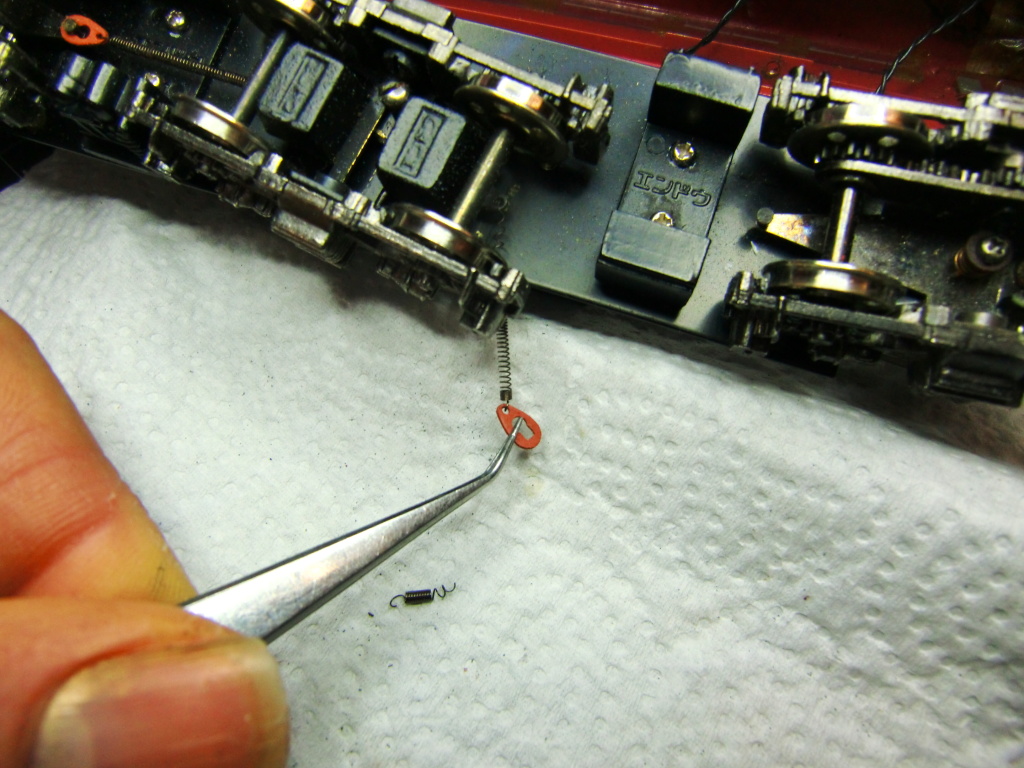
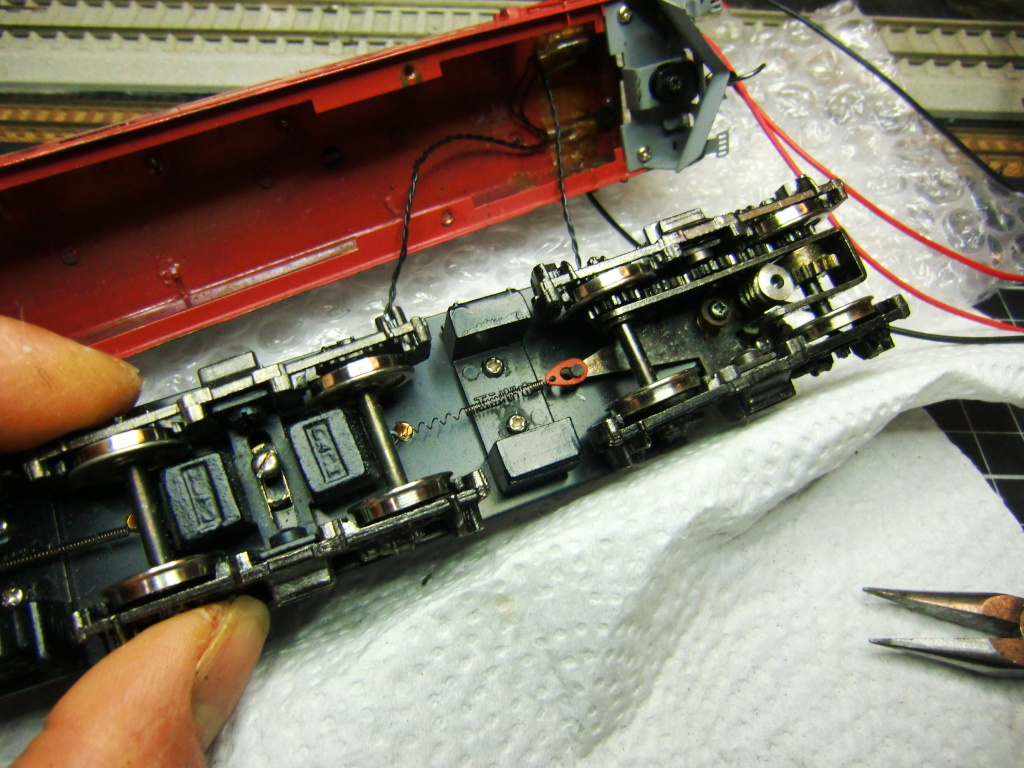
このようになりました。しっかりと中間台車をバネで引っ張手います。


スムーズに走行できるまで分解と調整を繰り返します。

問題なくスムーズに走行できるようになりました。作業は完了でございます。
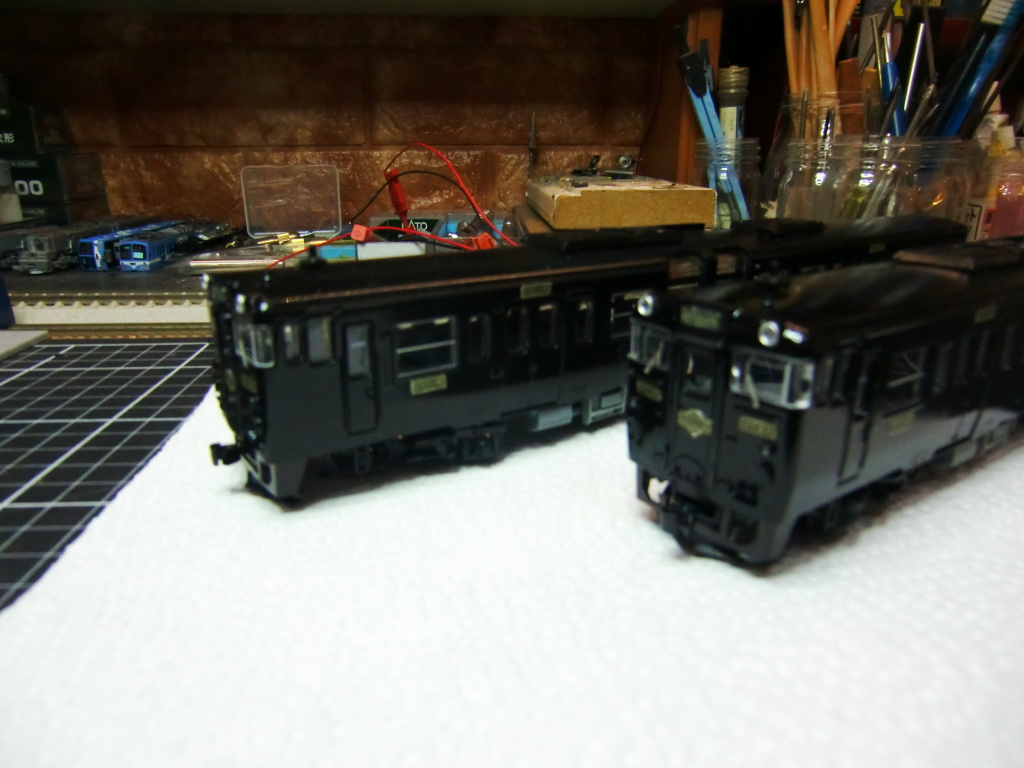
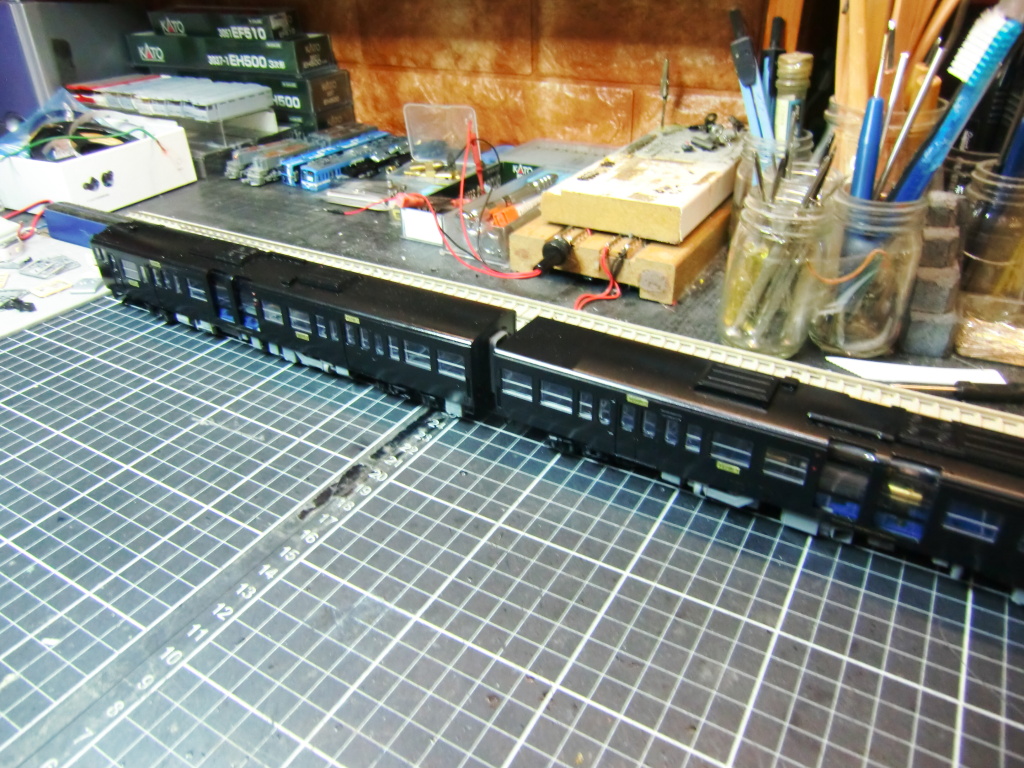

まずは、室内灯用を作ります。
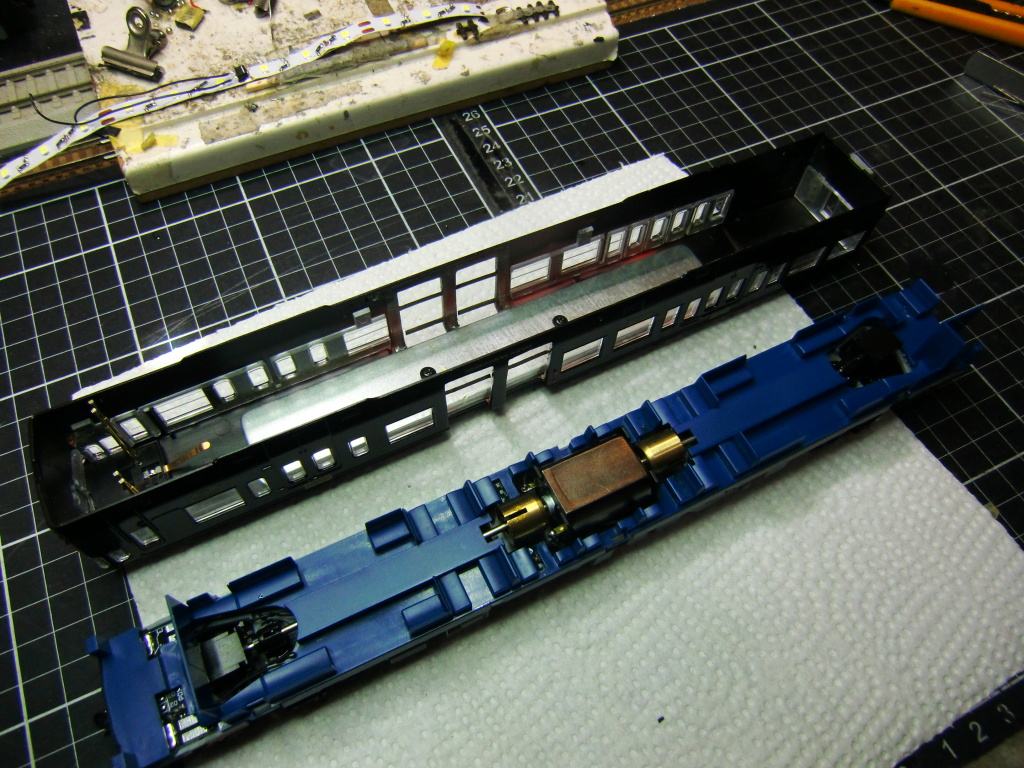
こちらはM車側です。モーター端子に1.0μF程度のセラコンを追加しておきます。
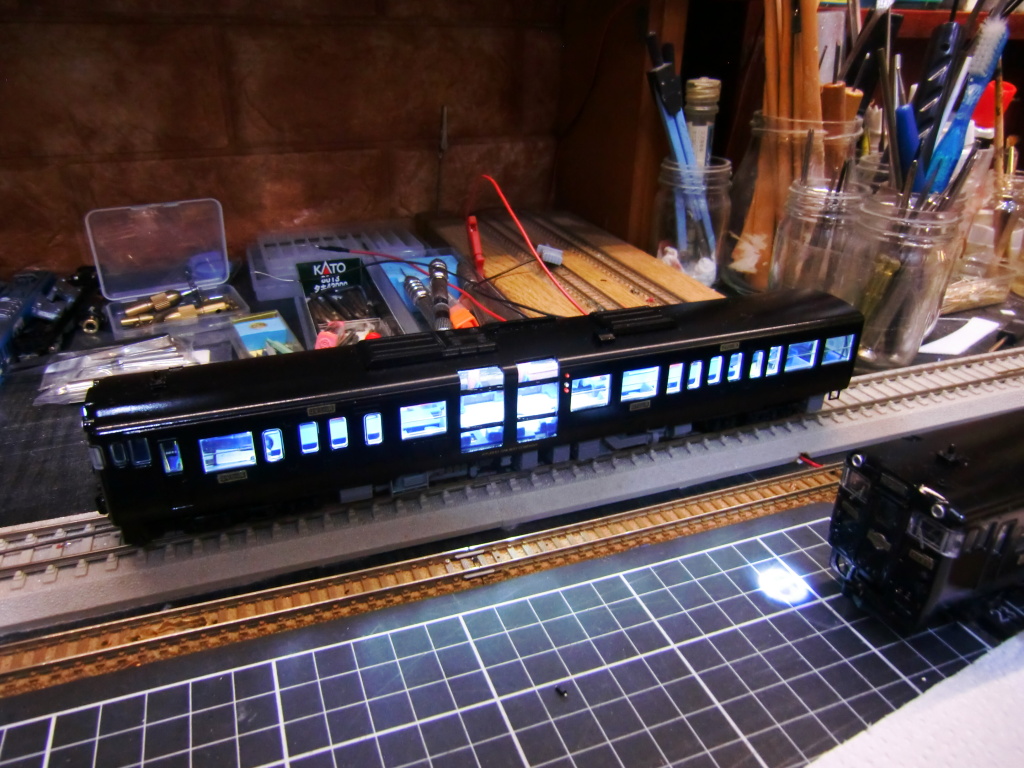
組込み途中の写真は、ここでは省略します。実際に組み込むとこのように点灯するようになりました。


続いてこちらの車体ですが、室内灯以外に、ご依頼者様のご希望で「ヘッド・テール」も点灯化させるので、作業は難しくなっていきます。


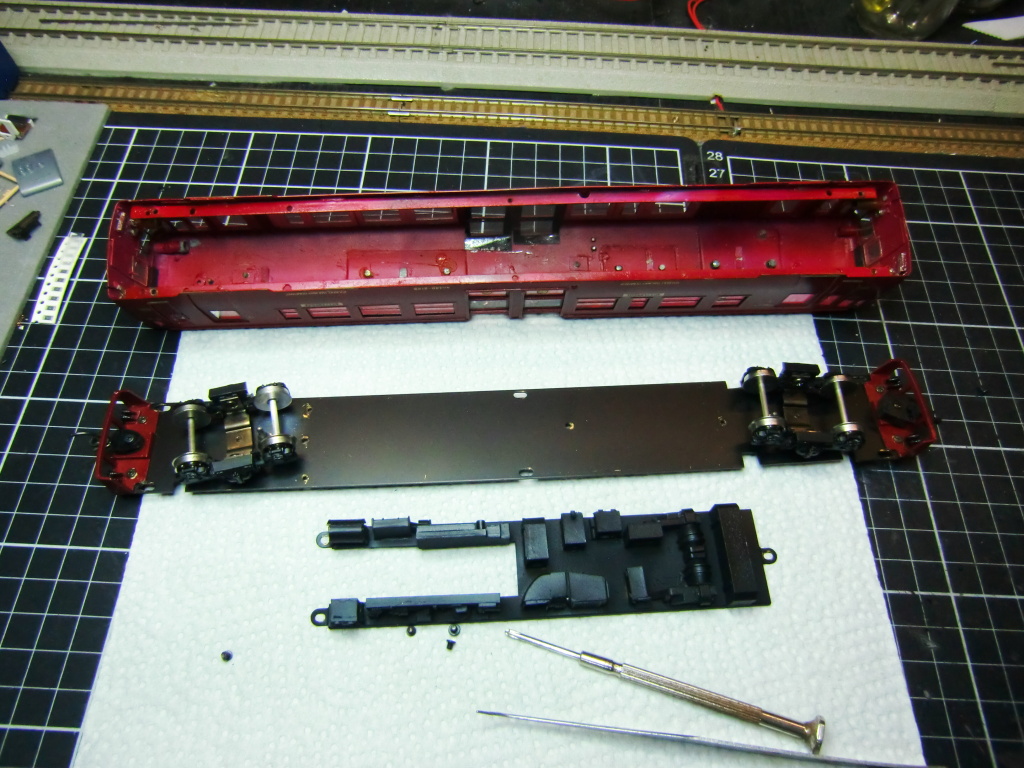
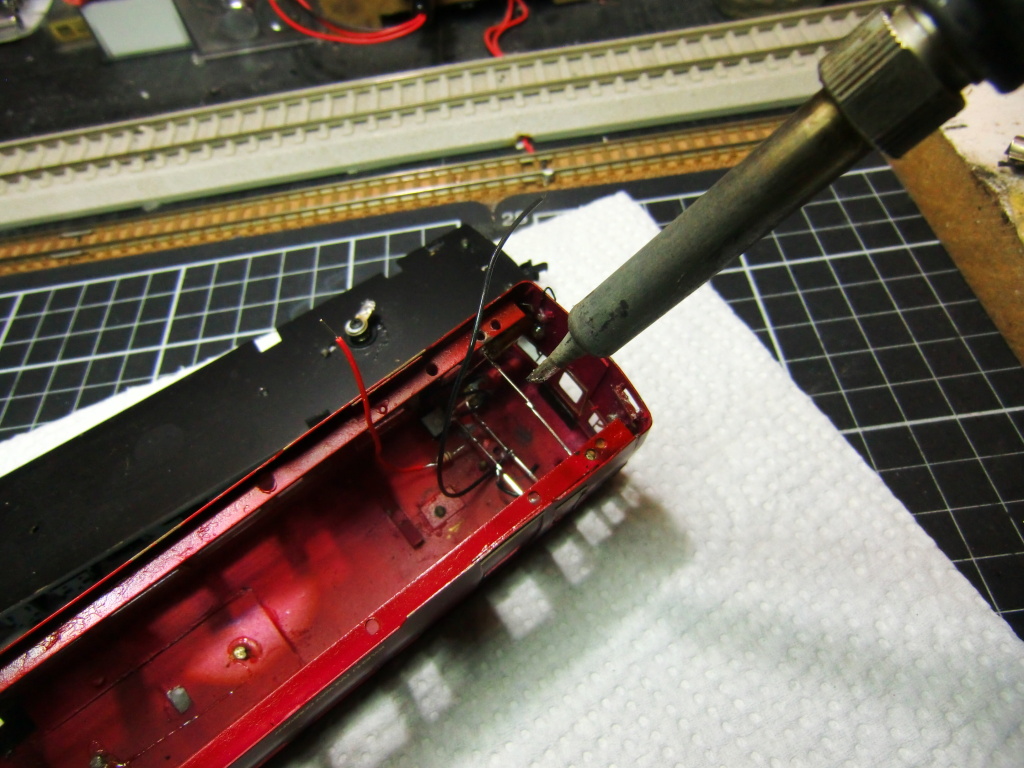
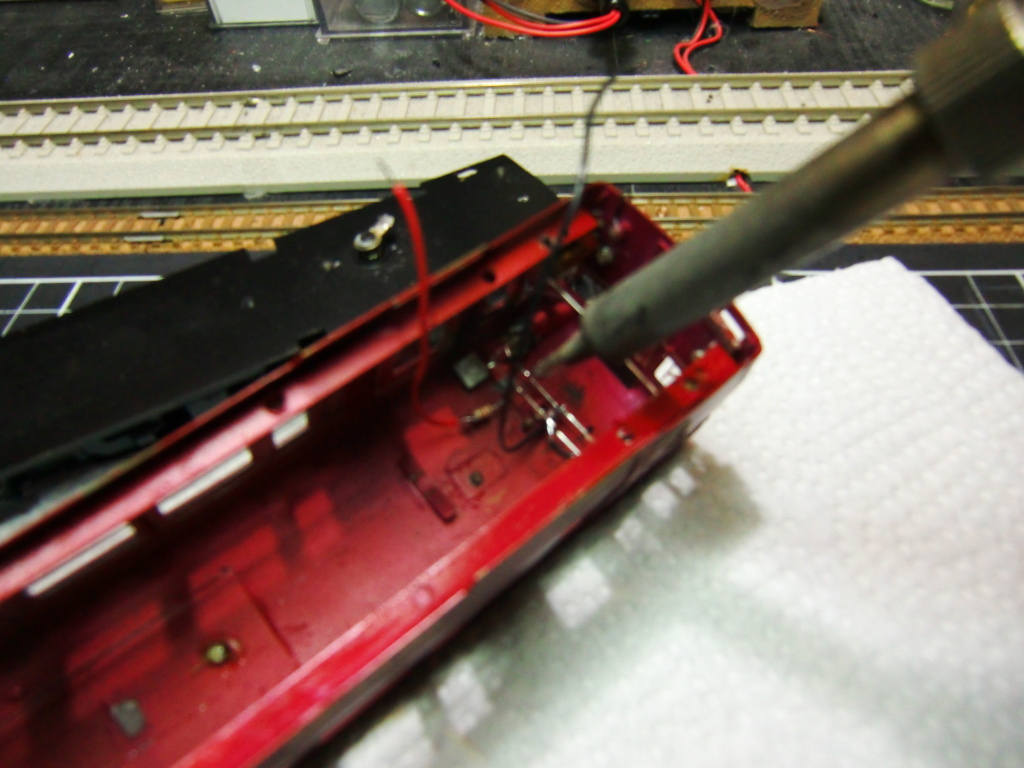
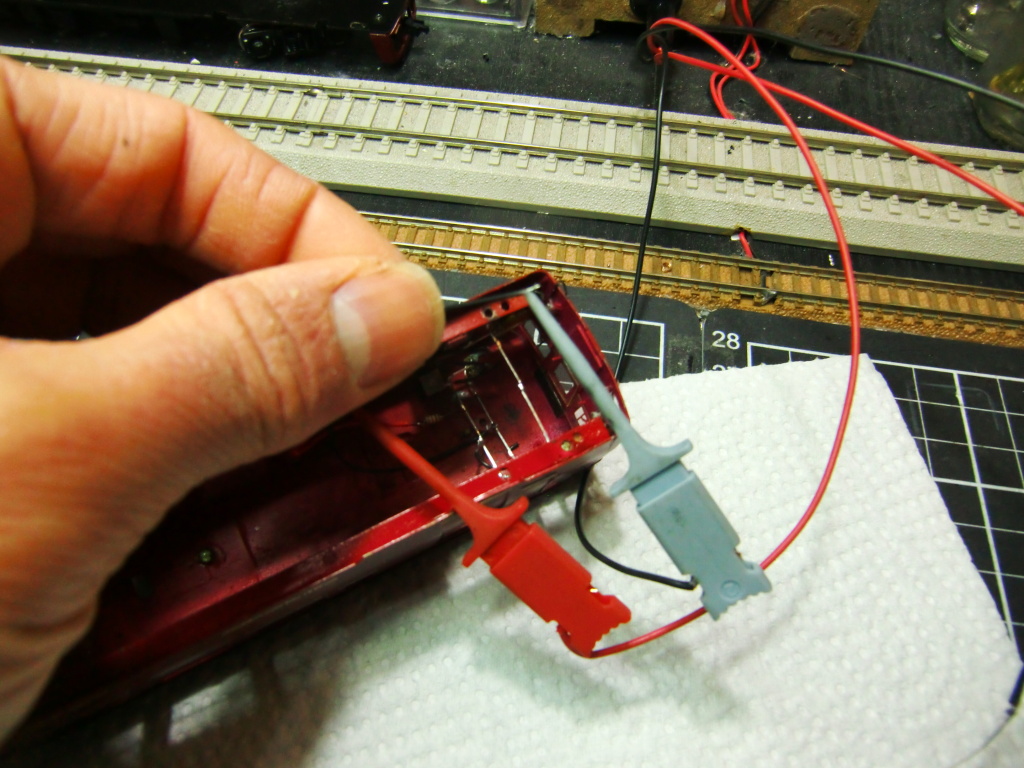

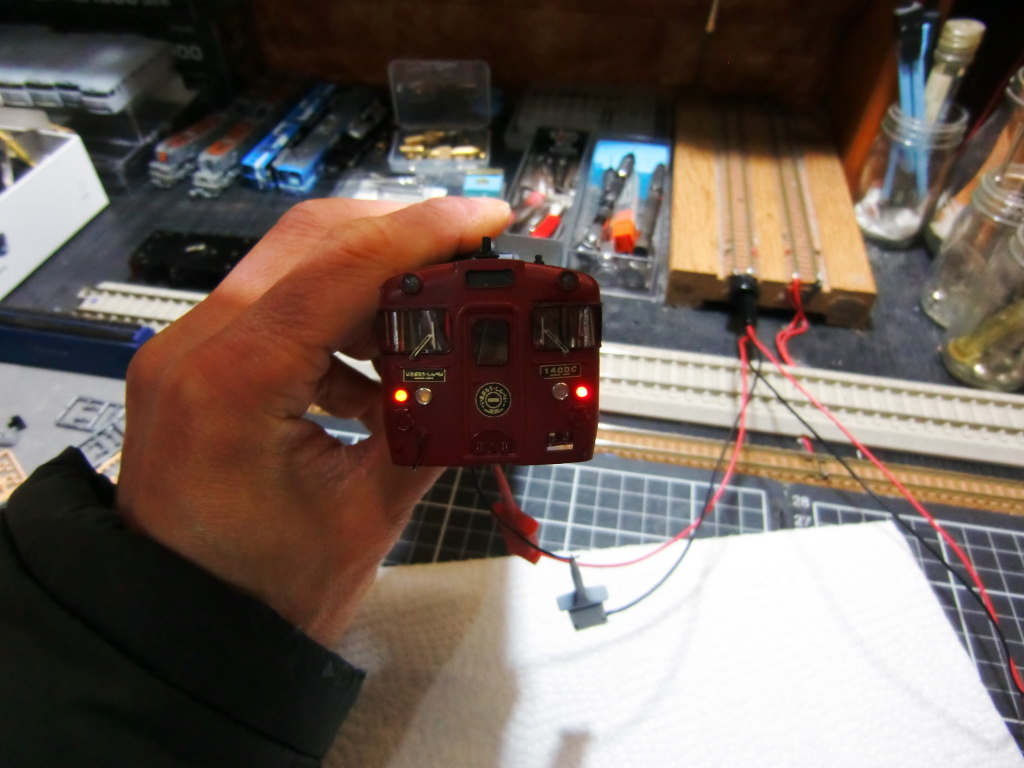



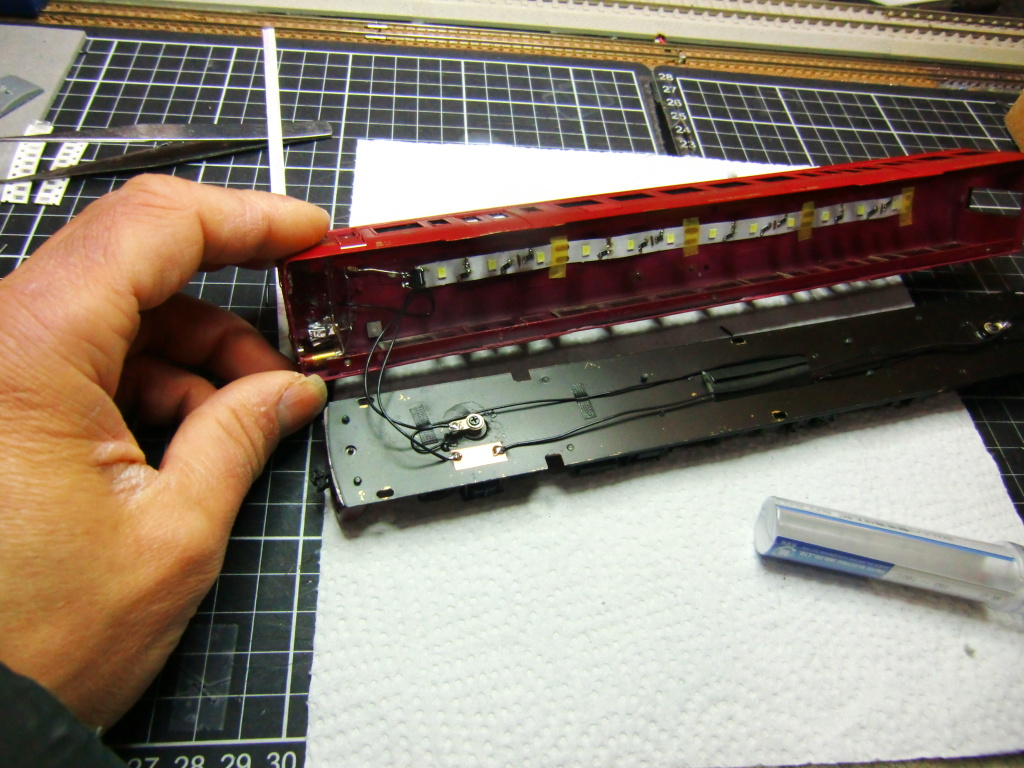
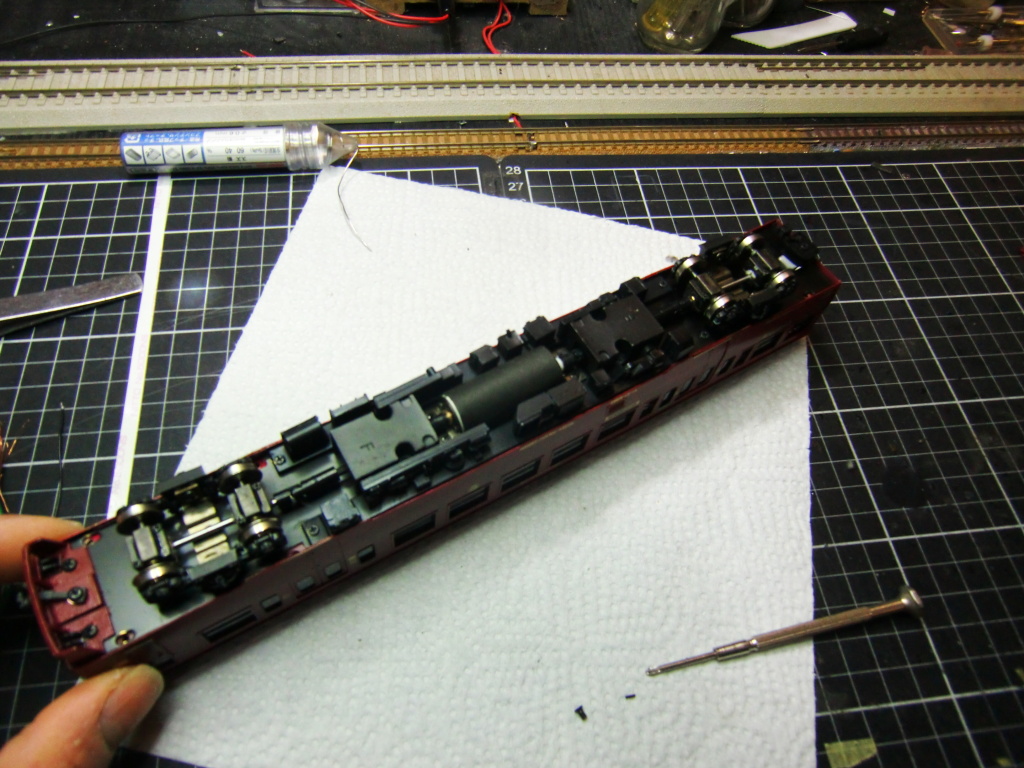



作業完了でございます。