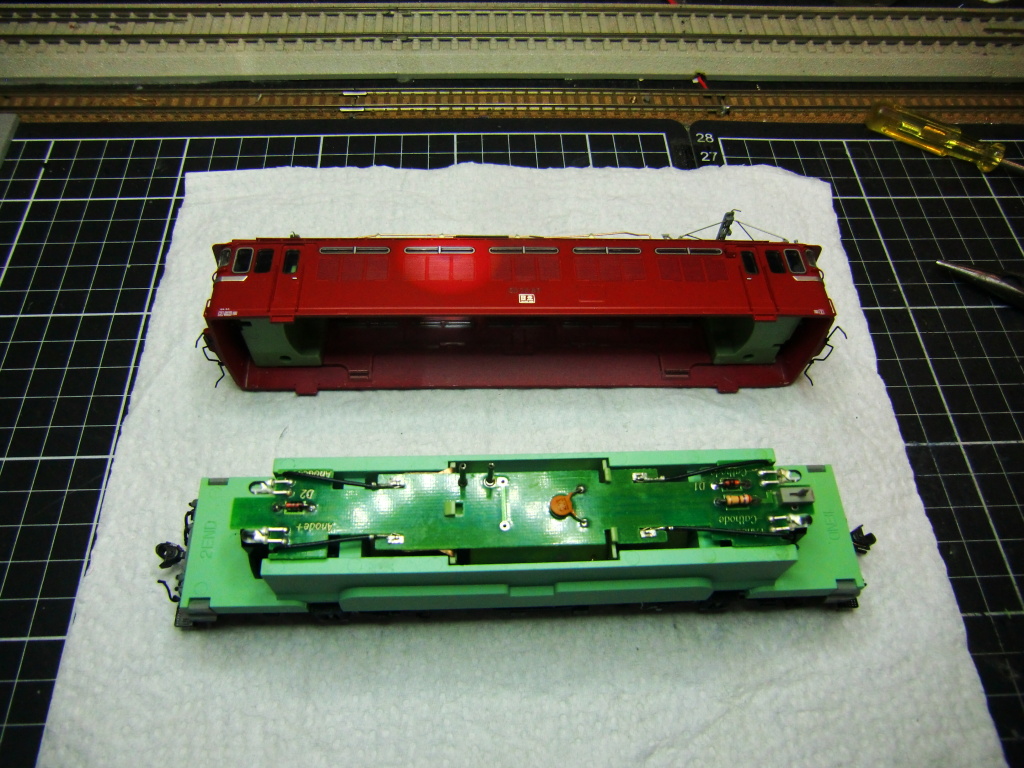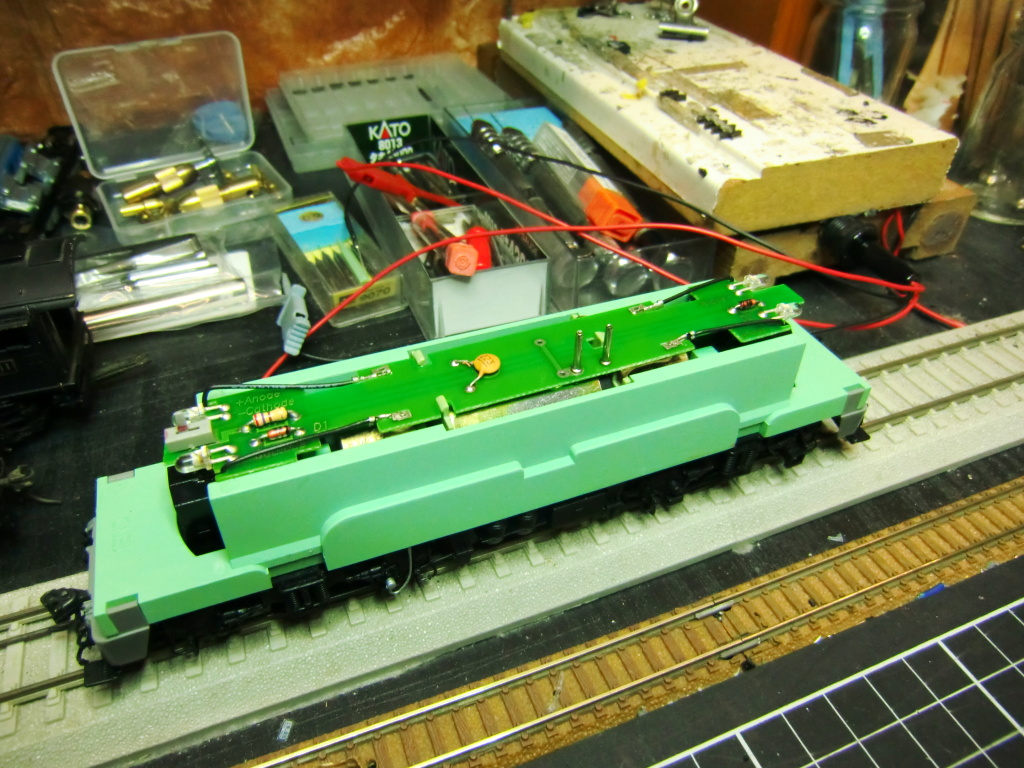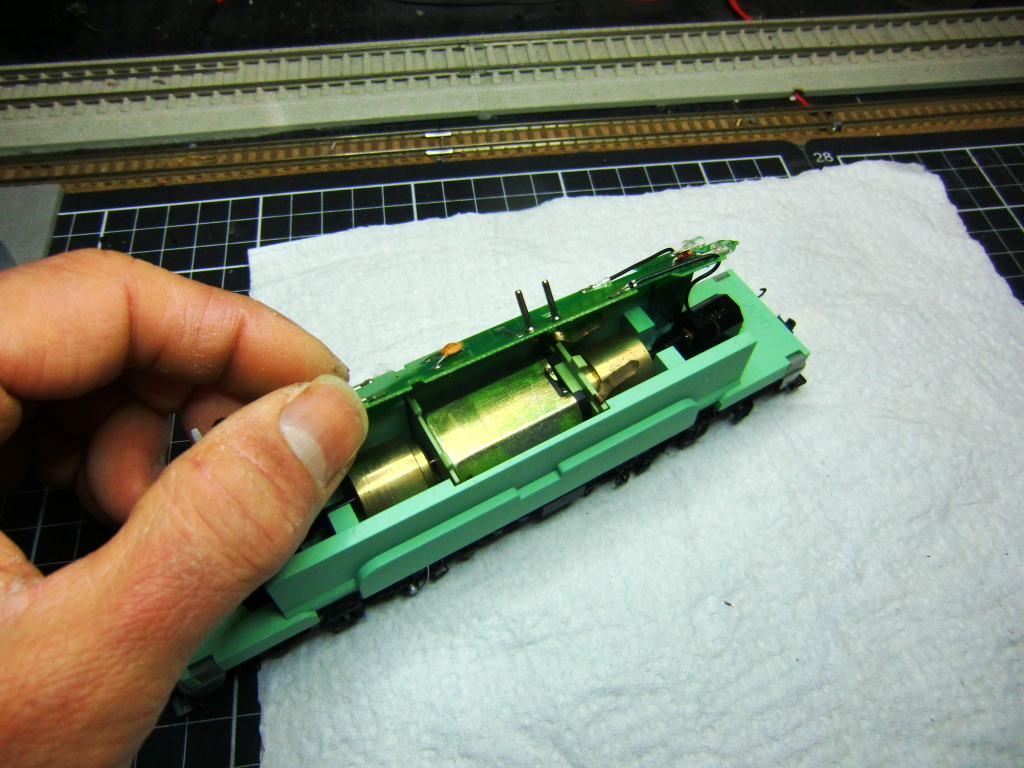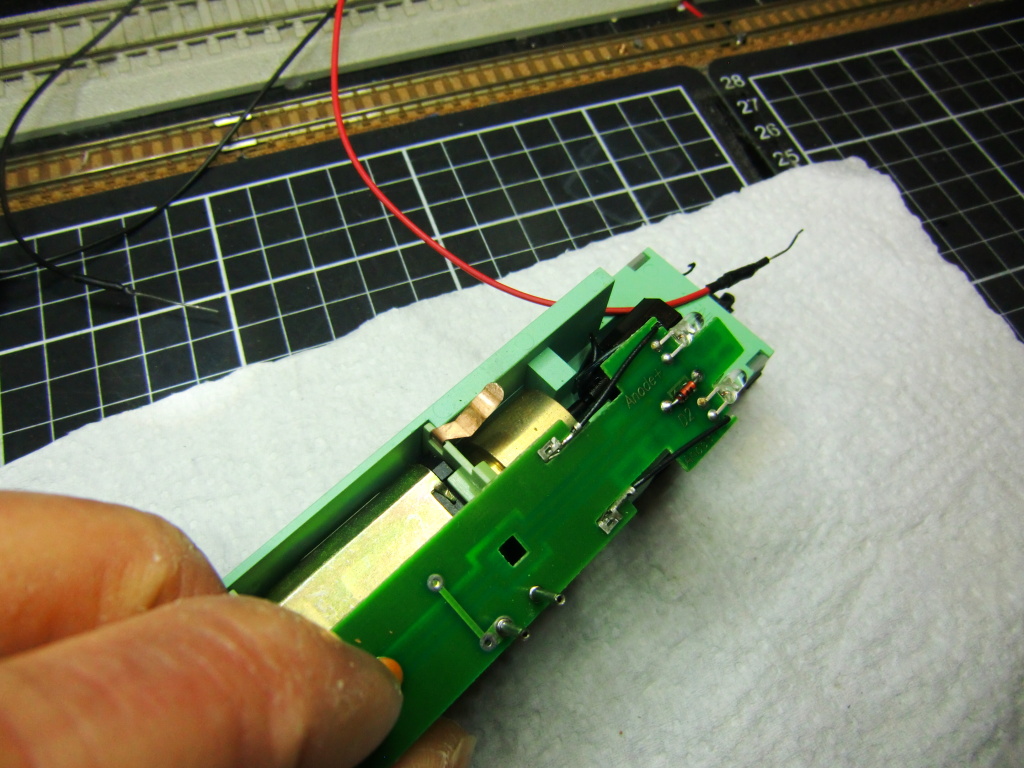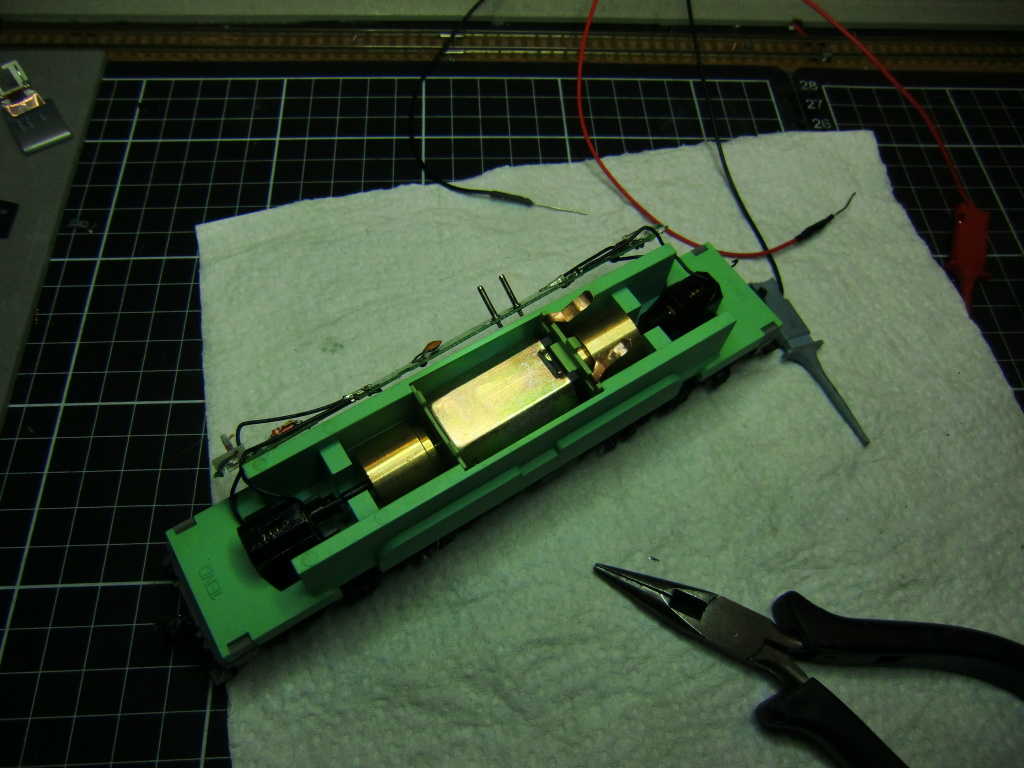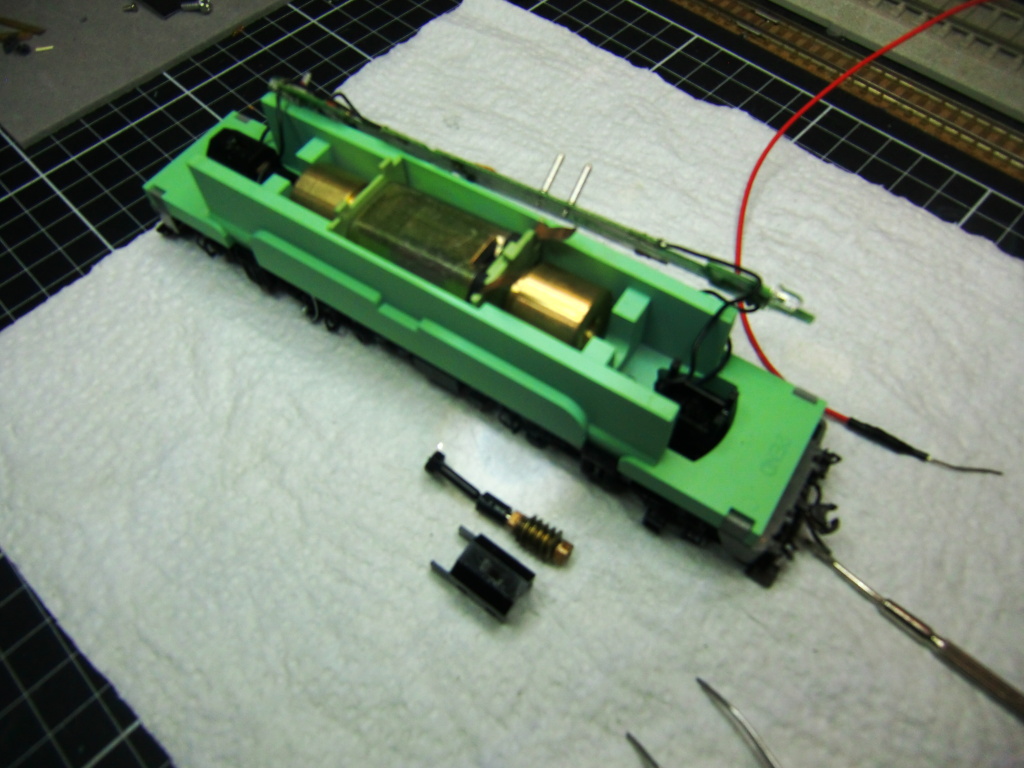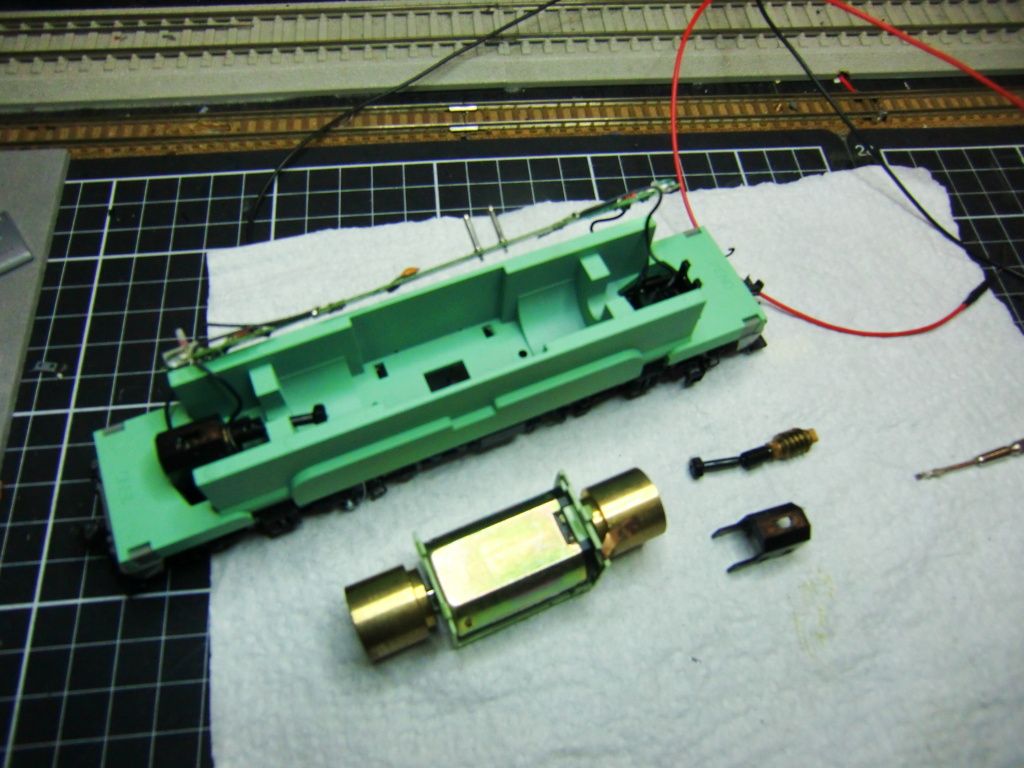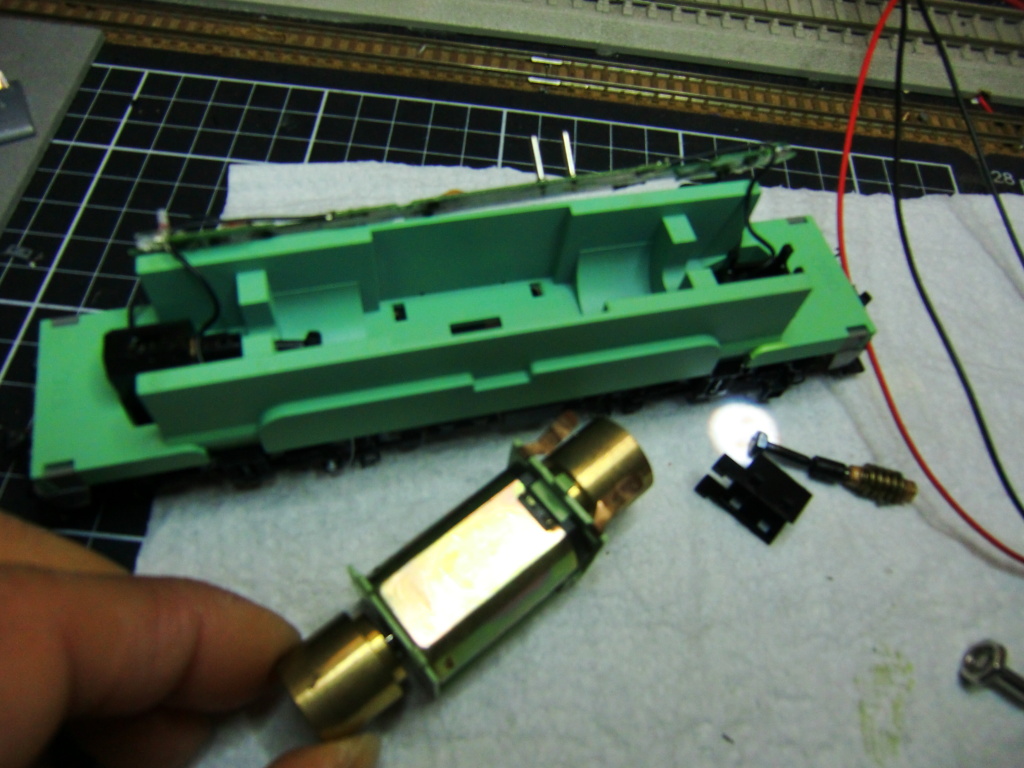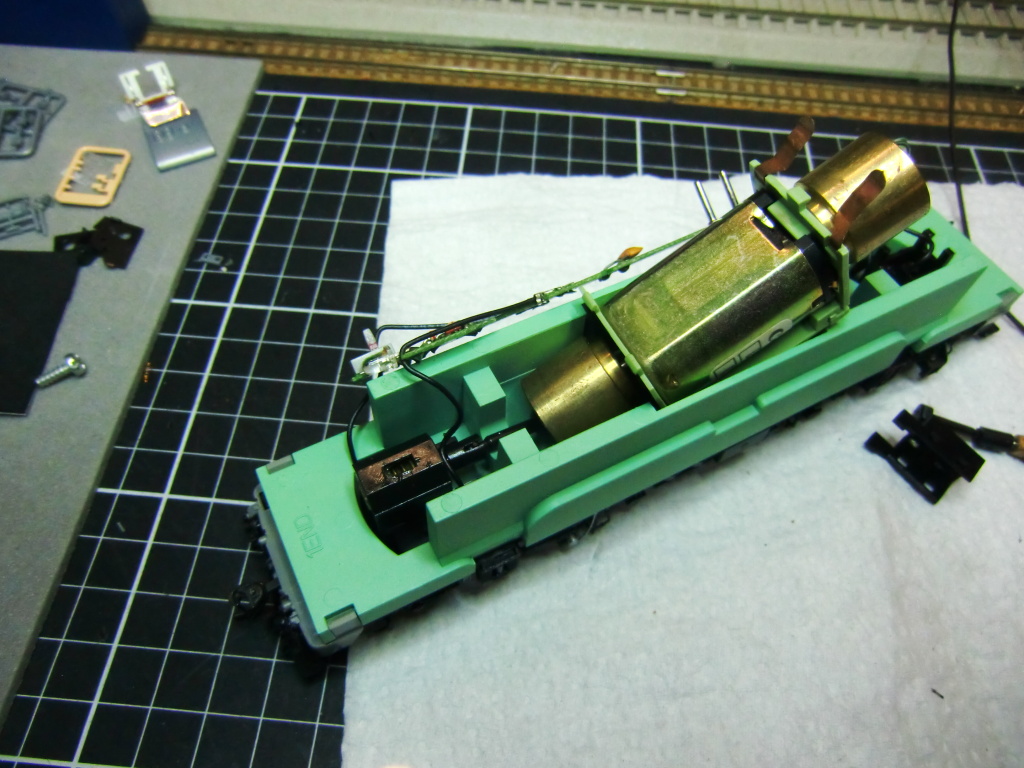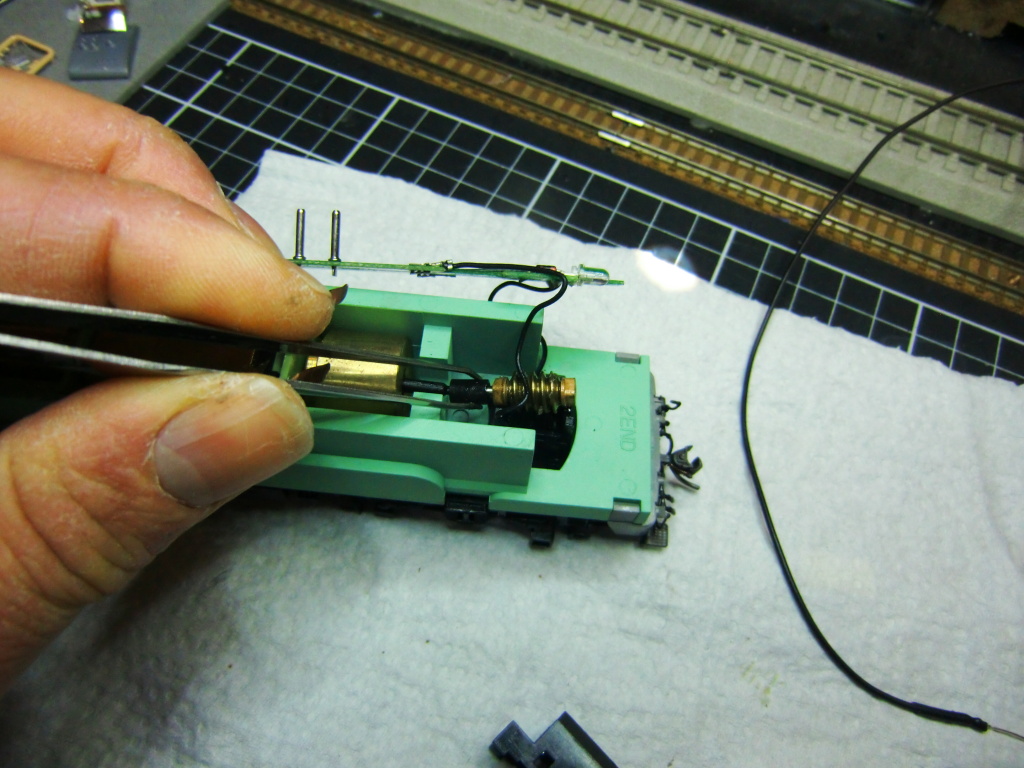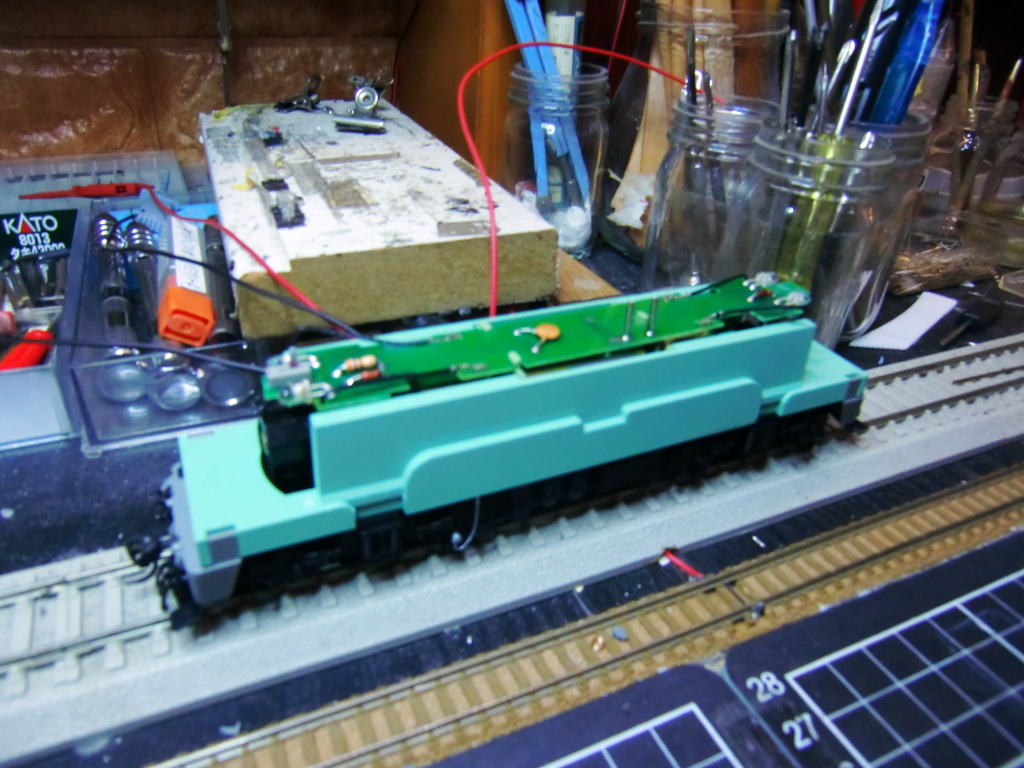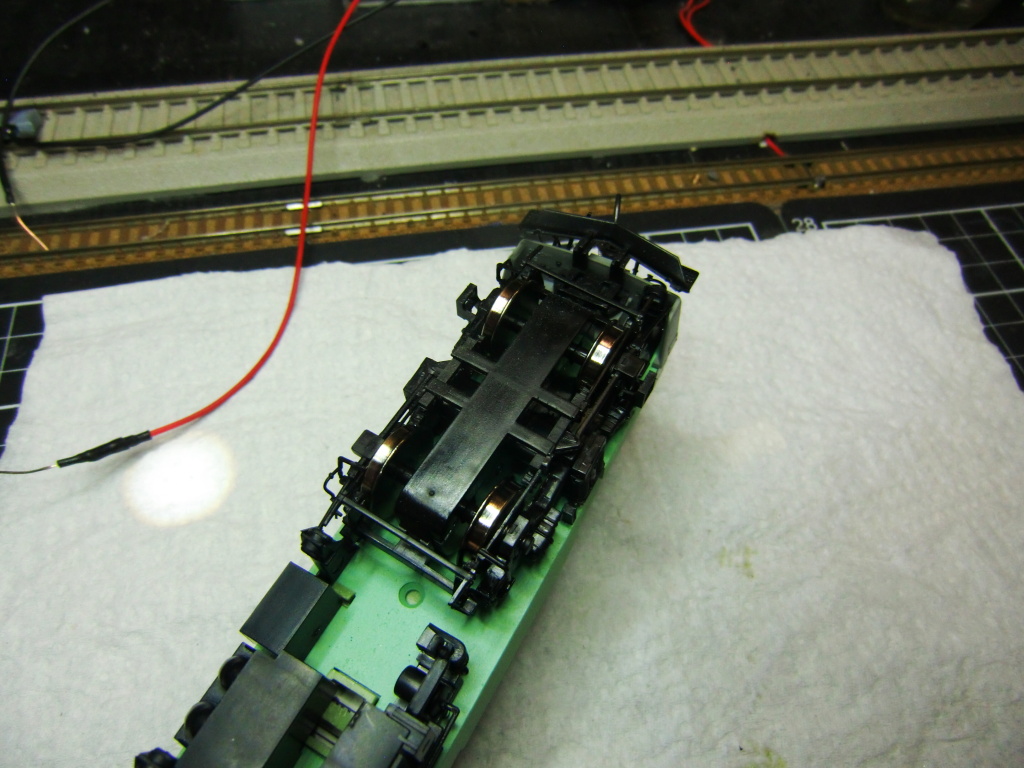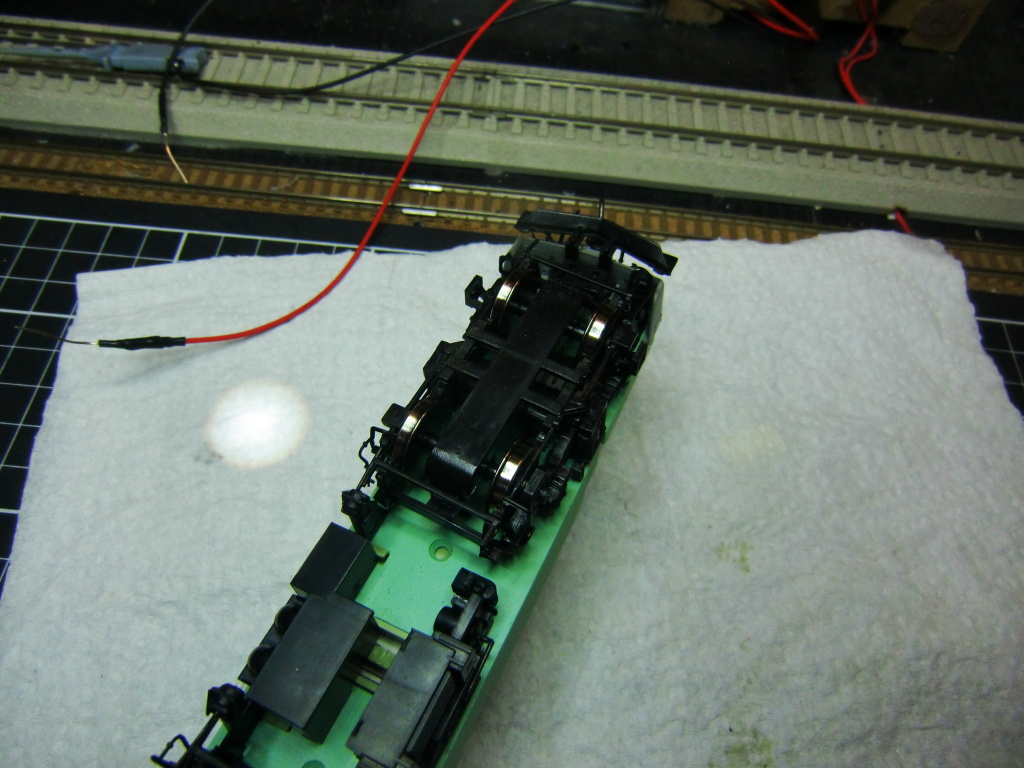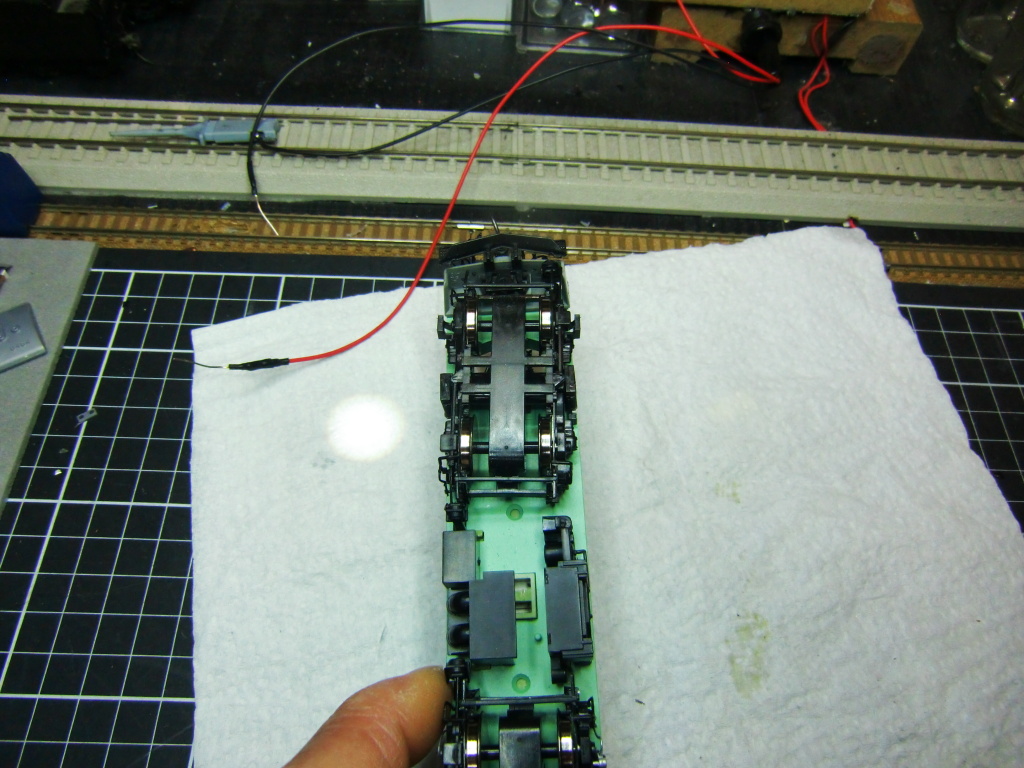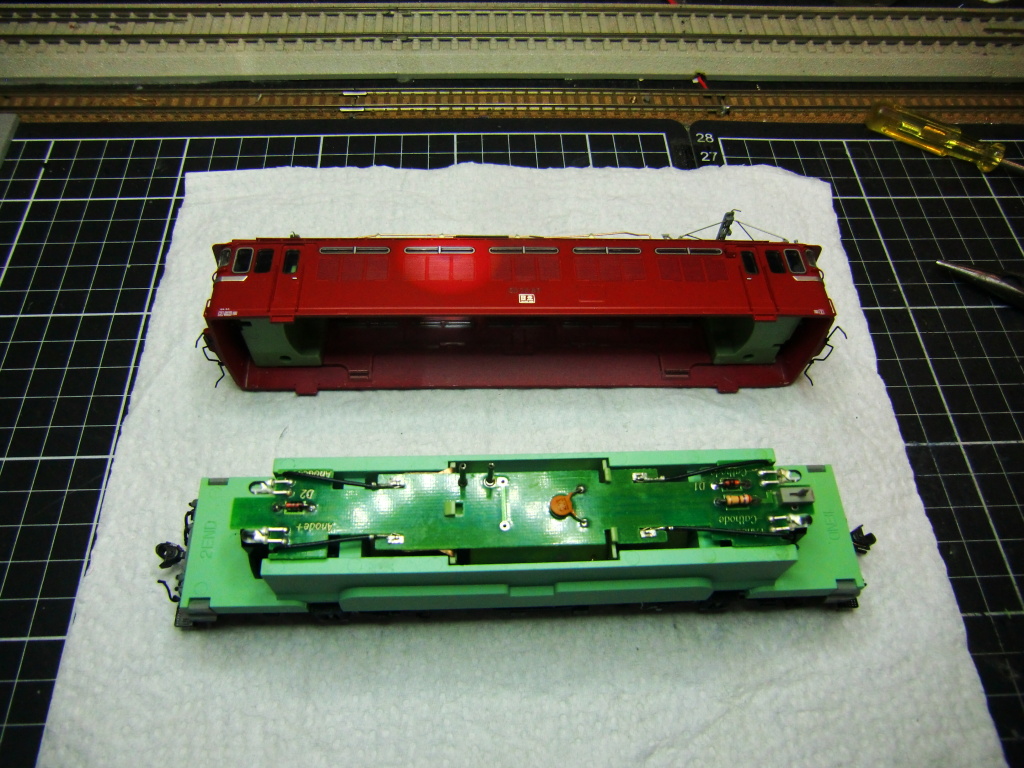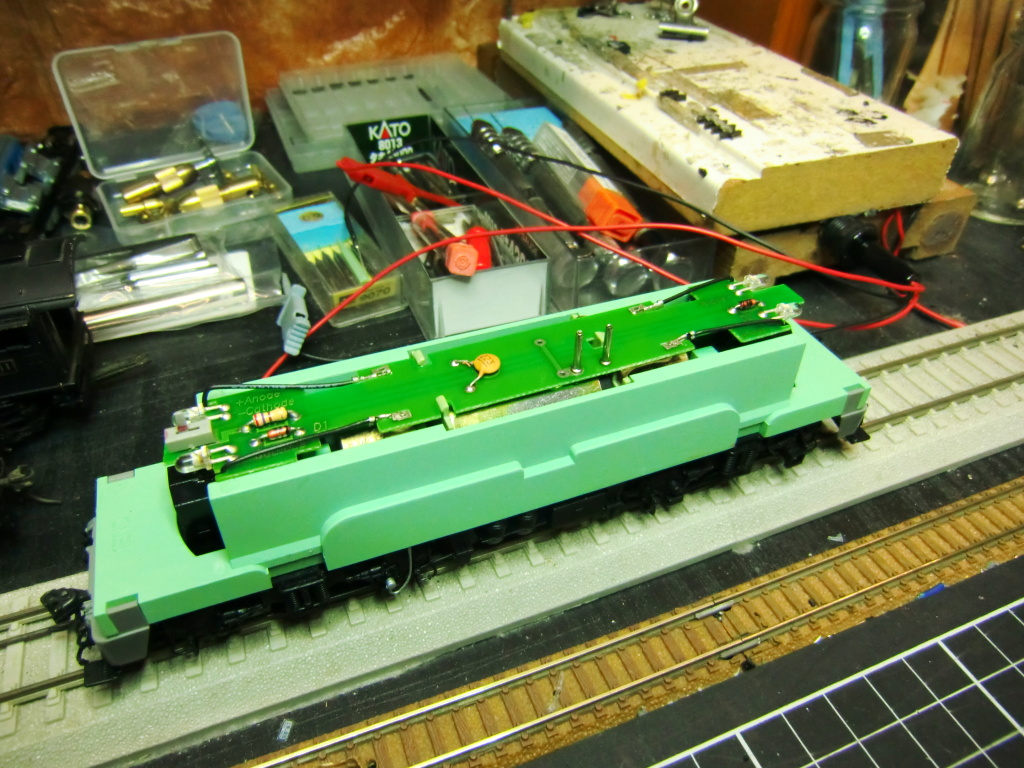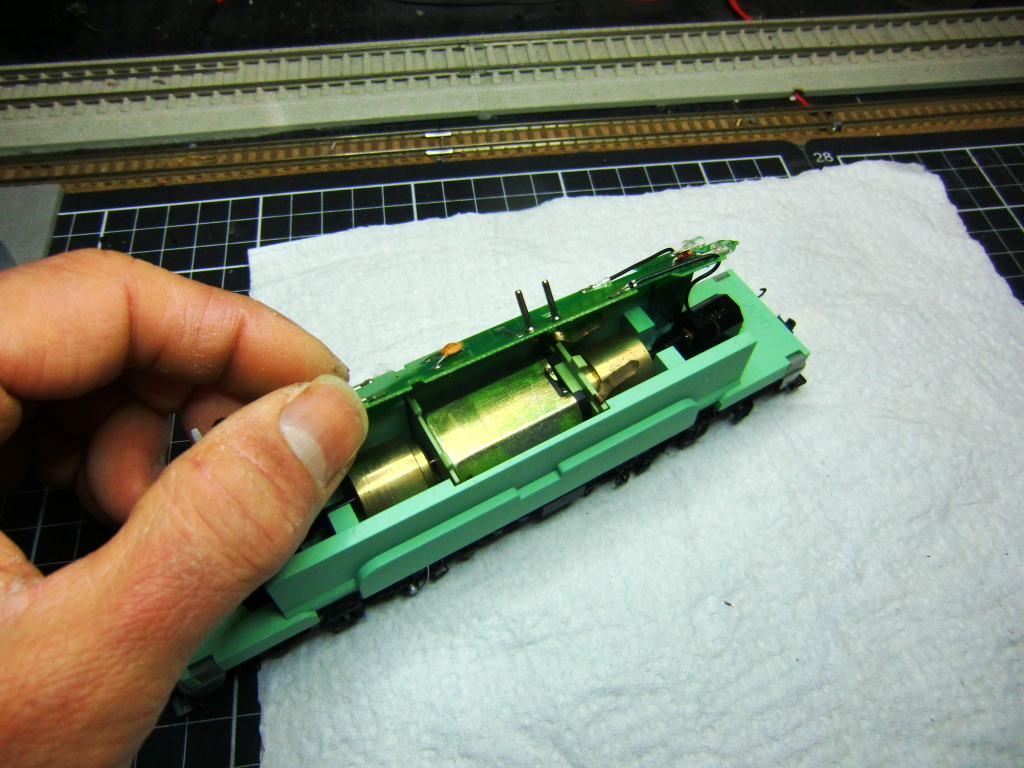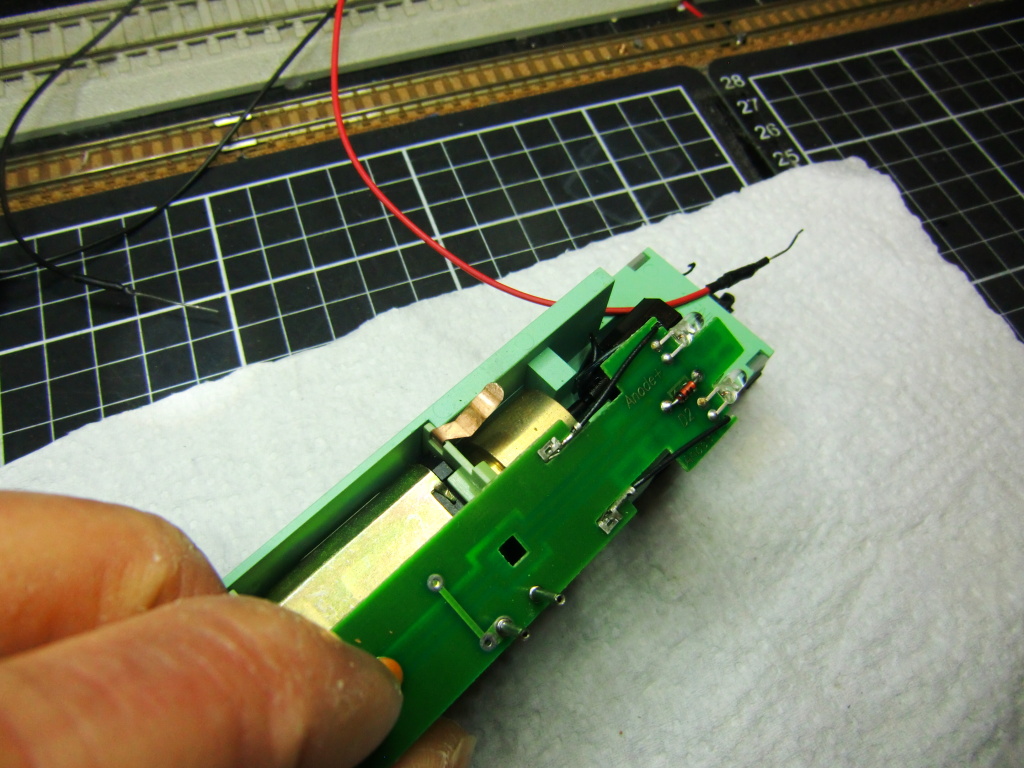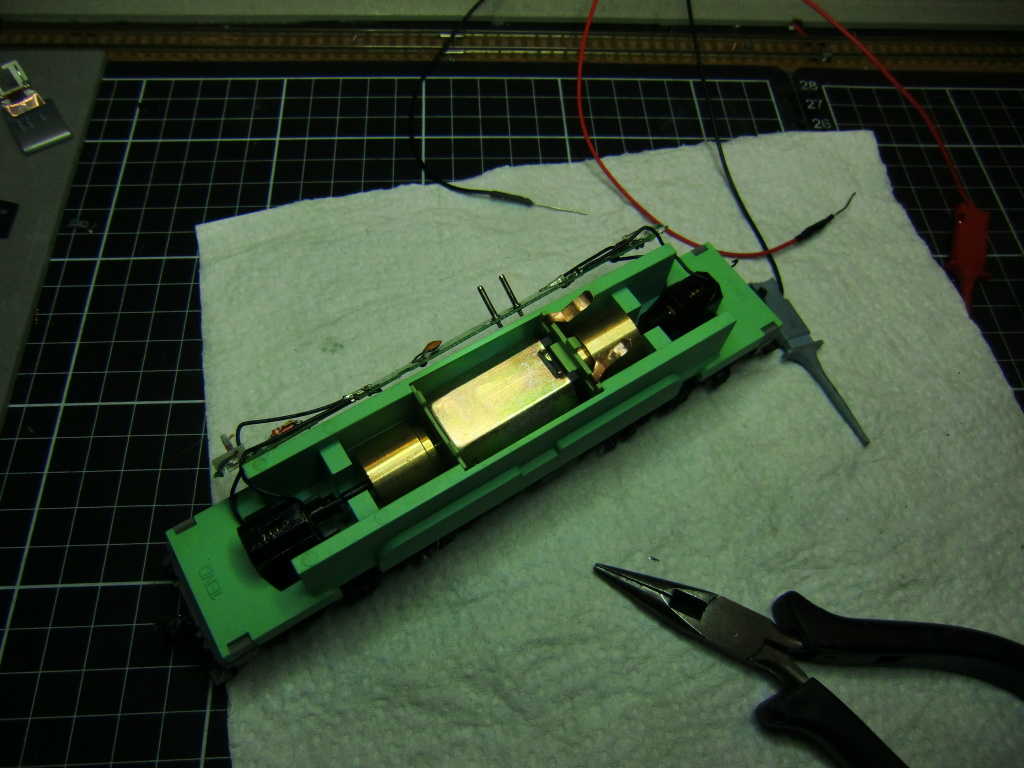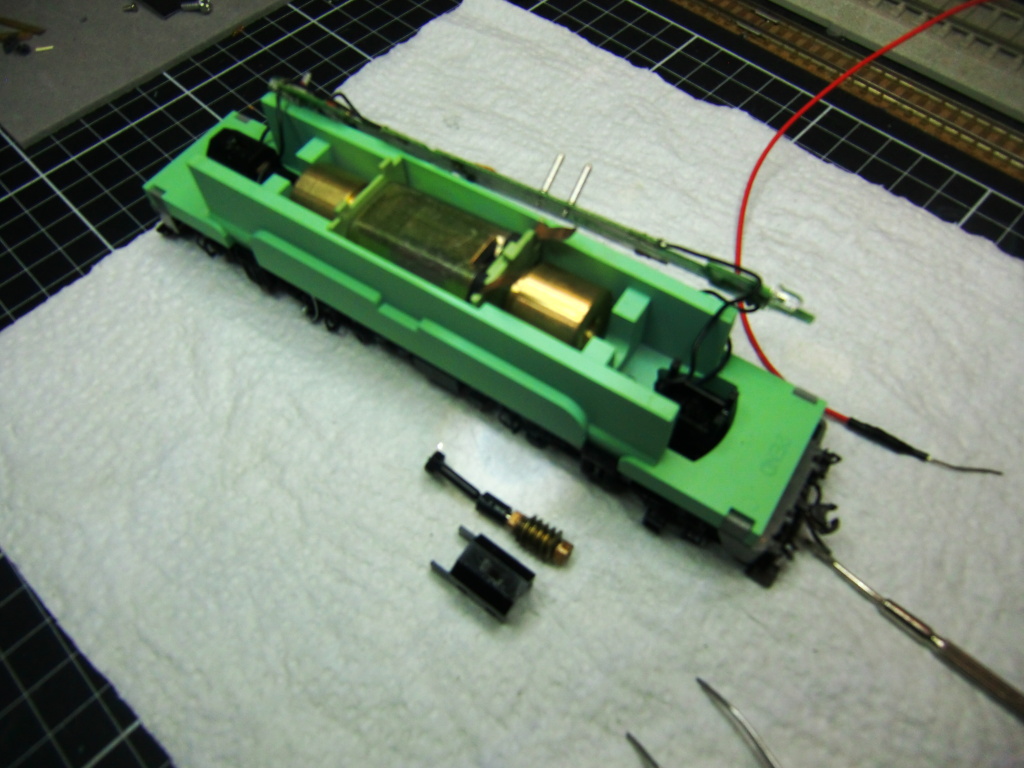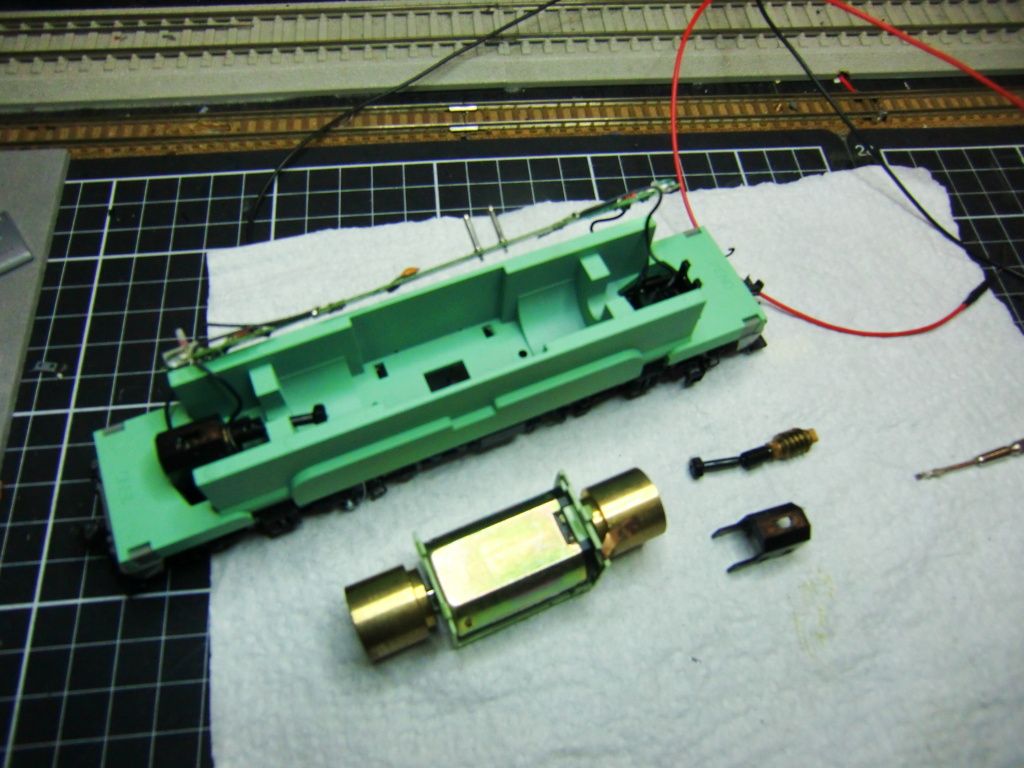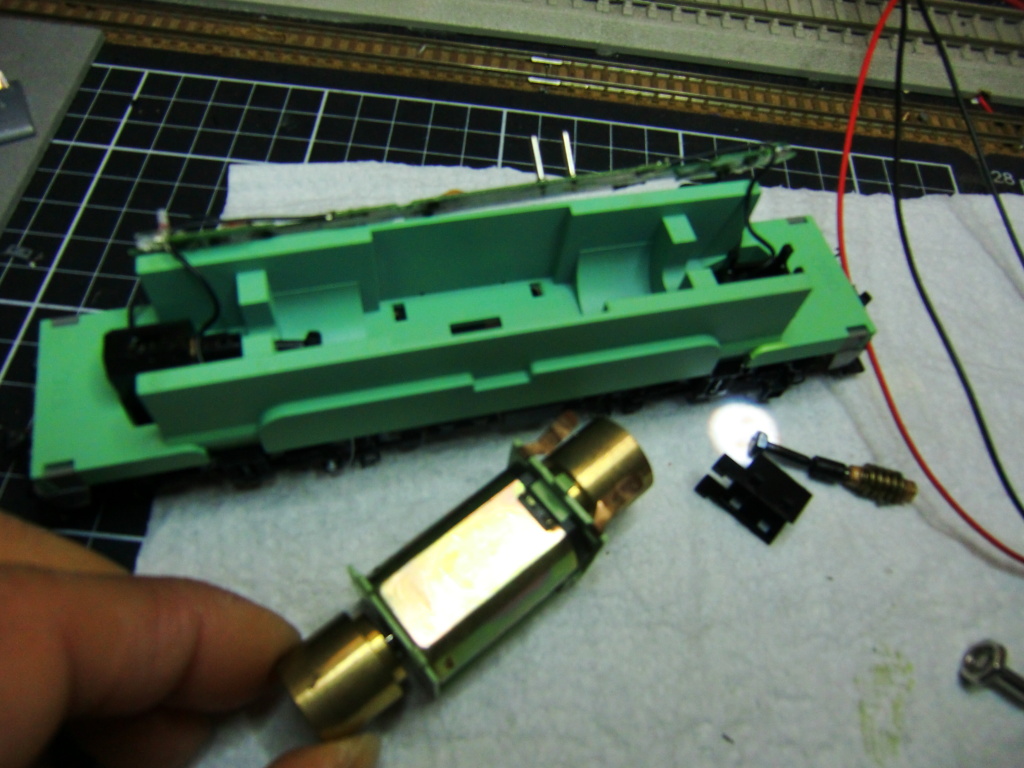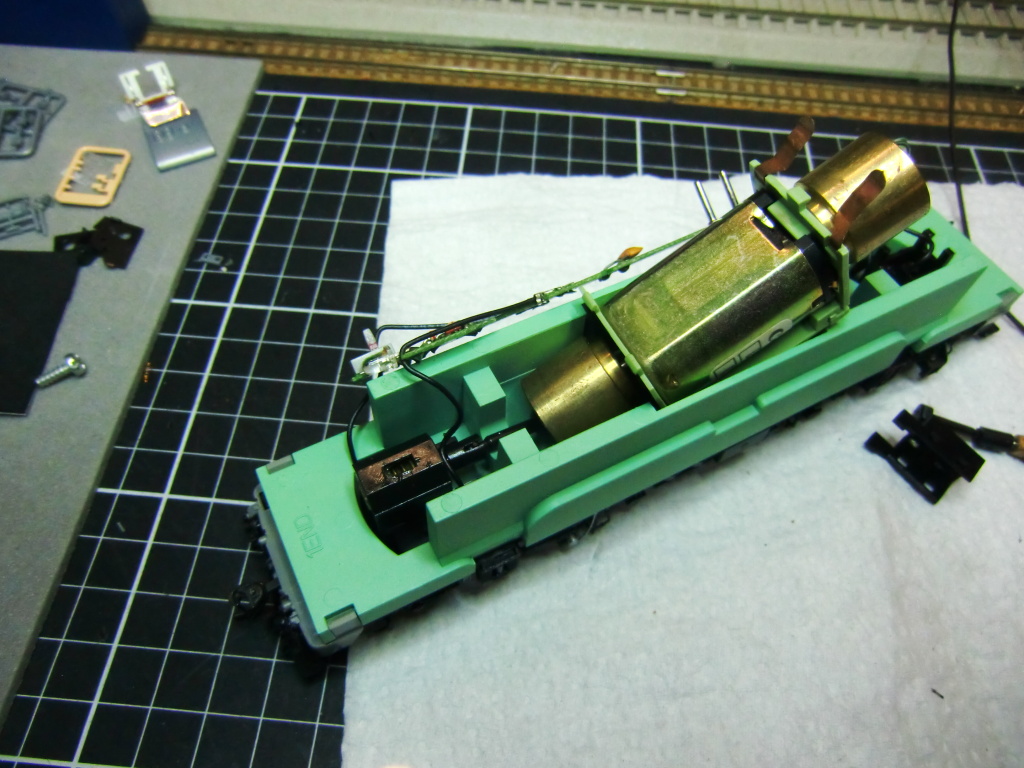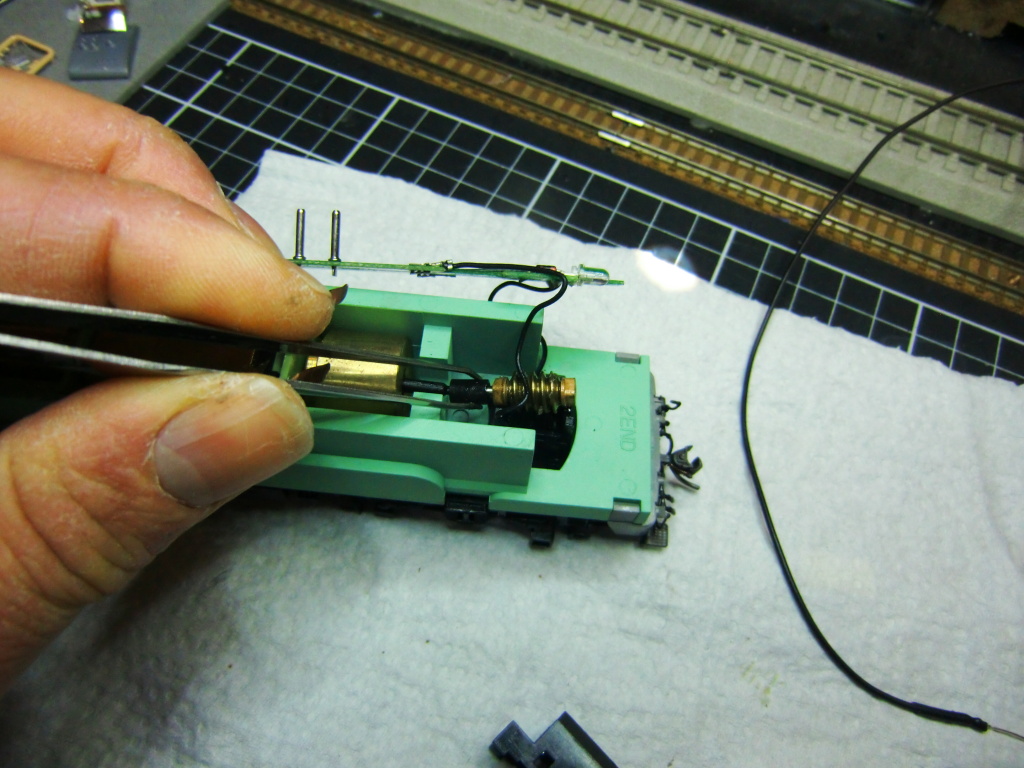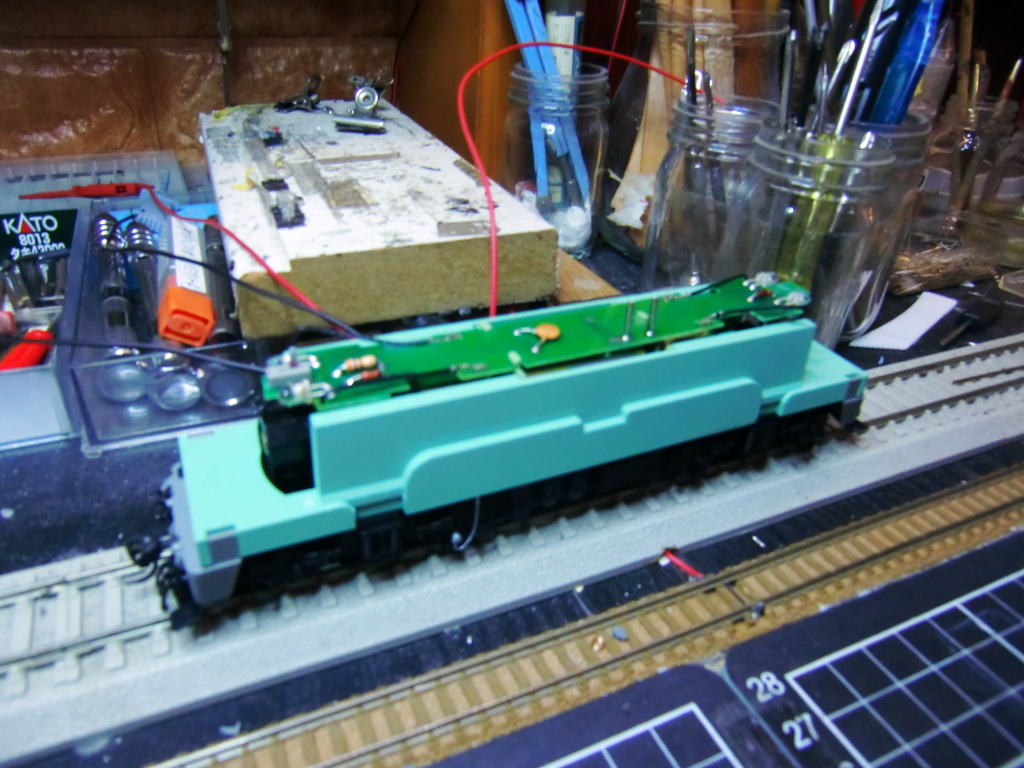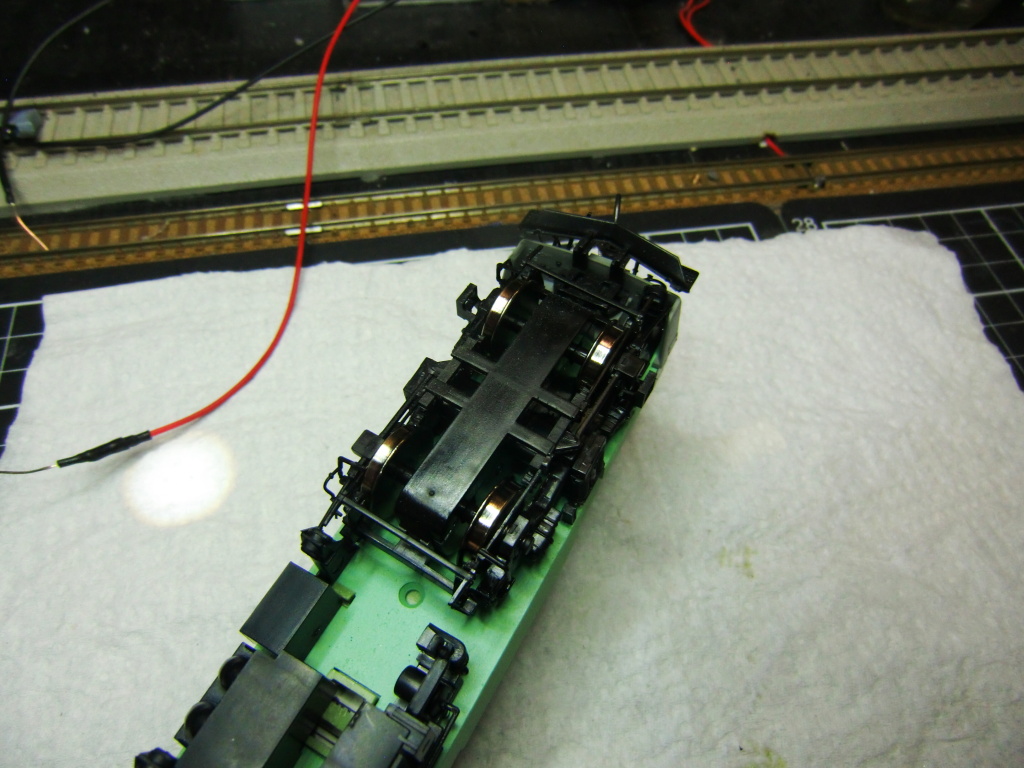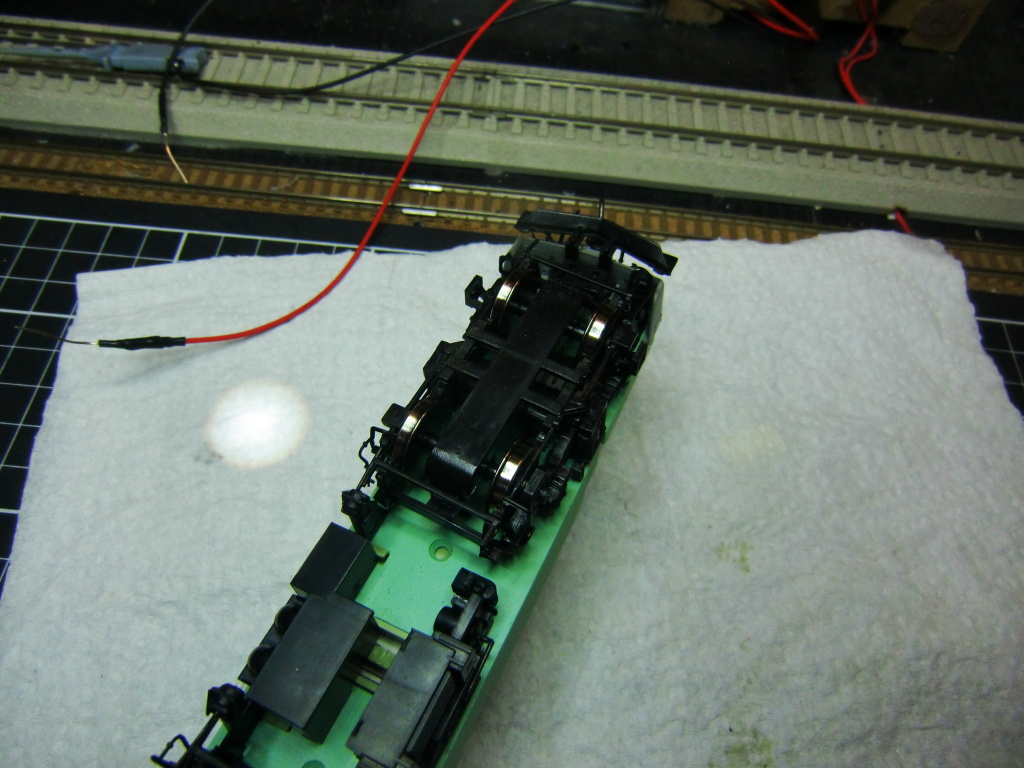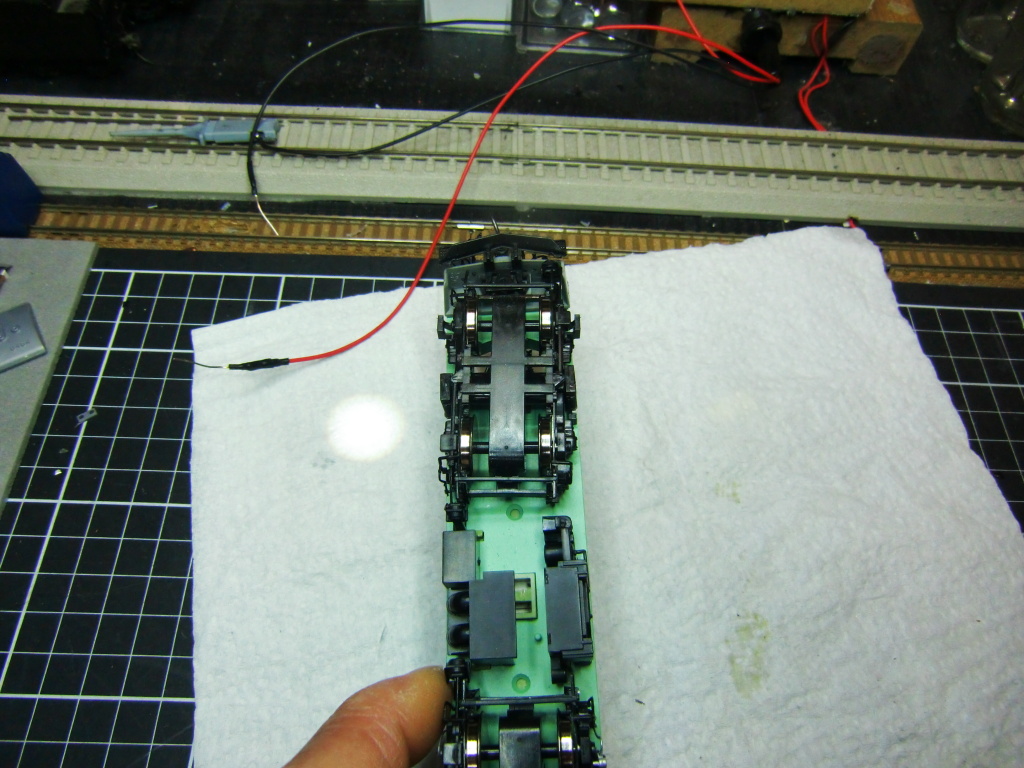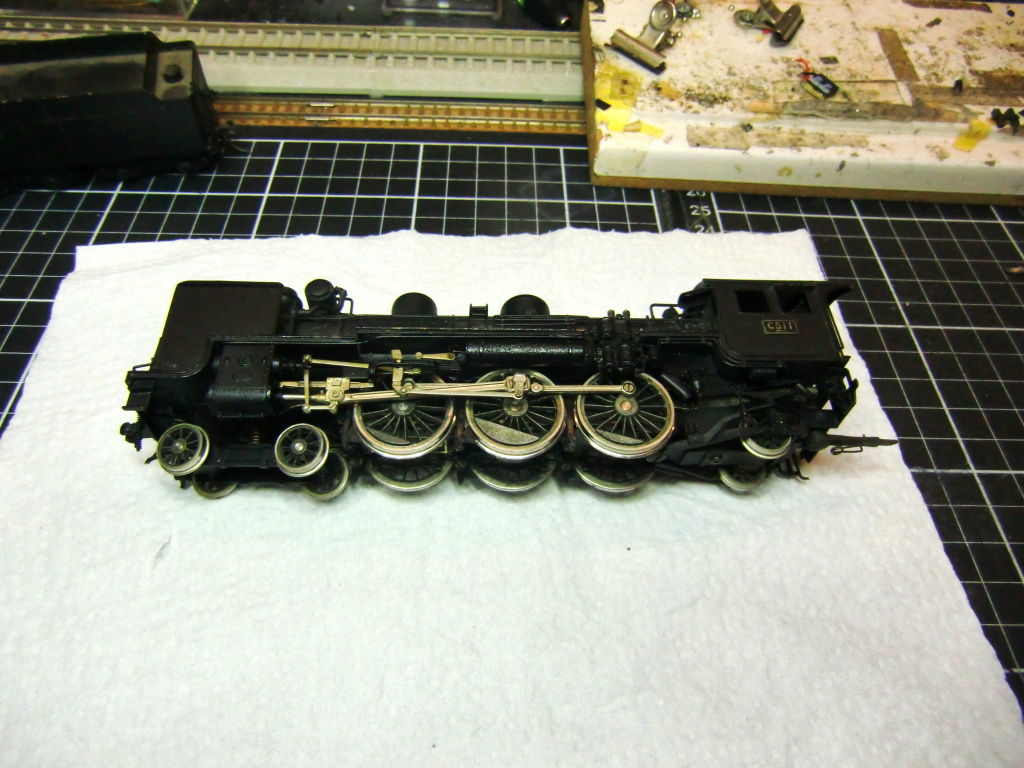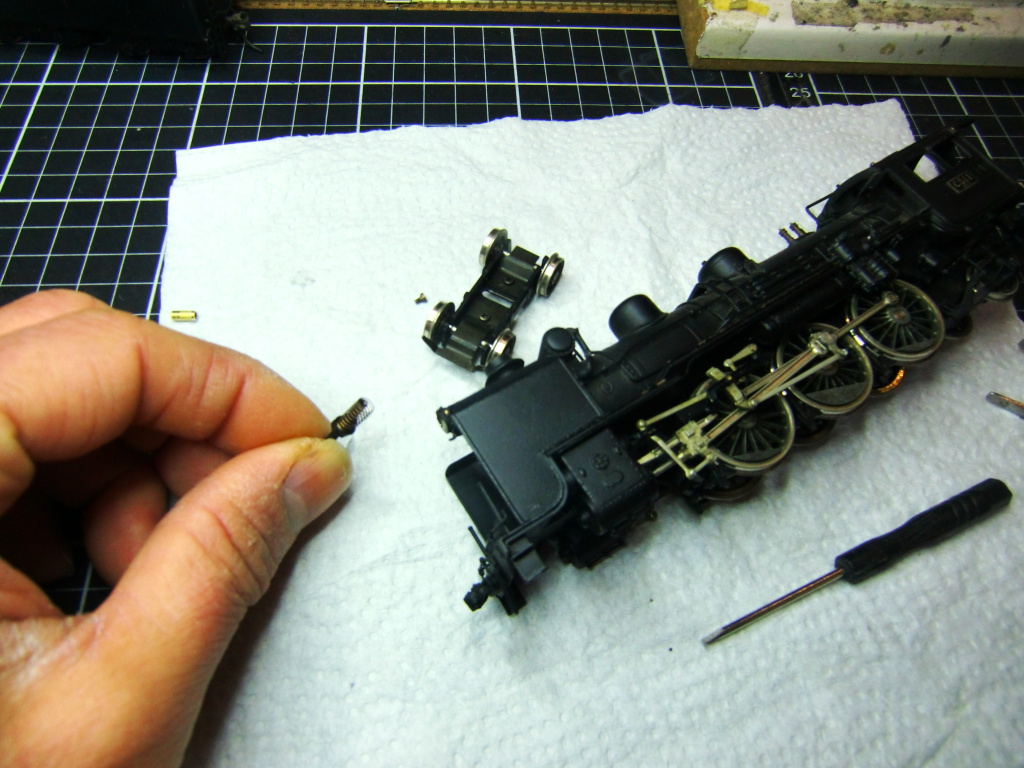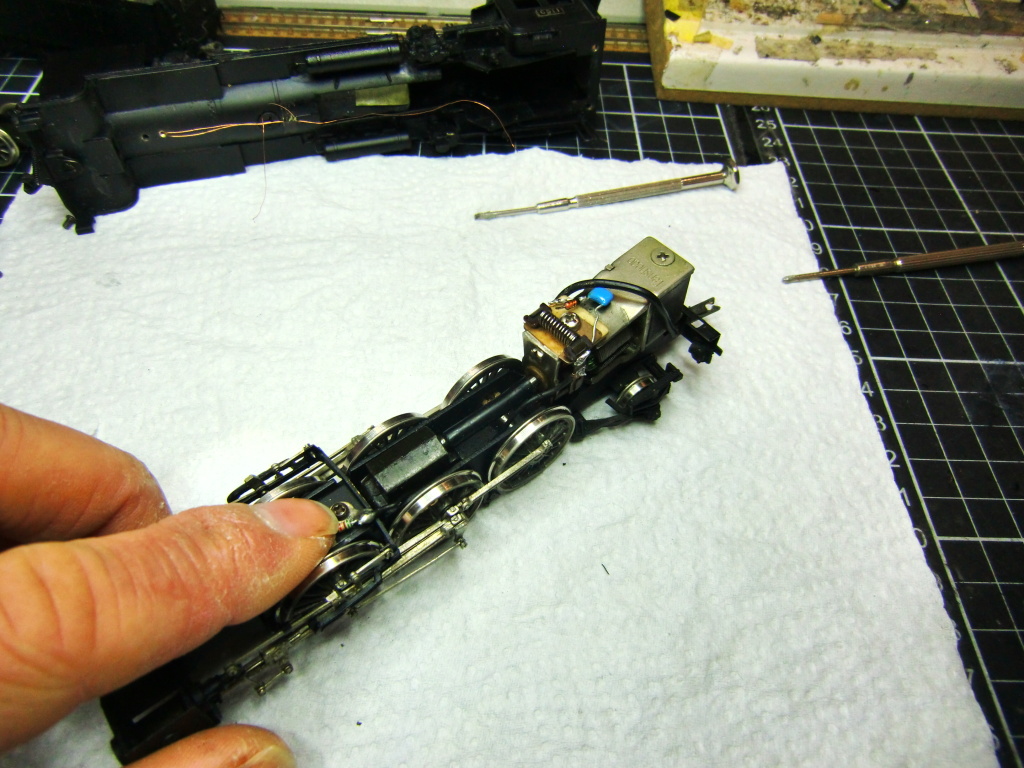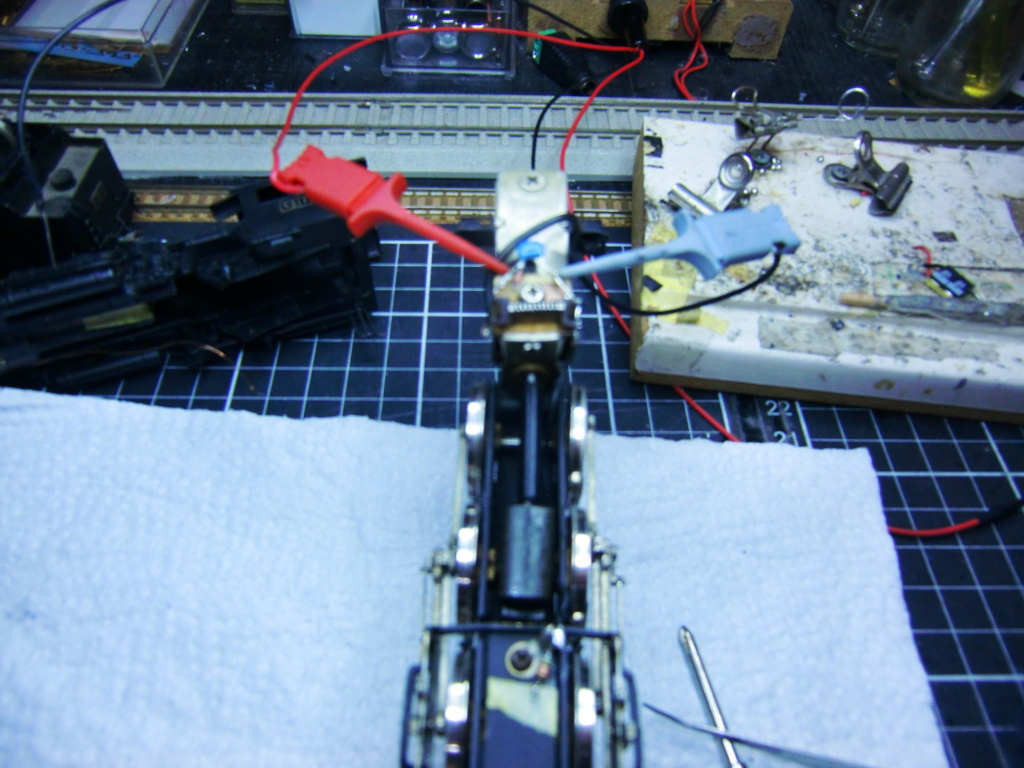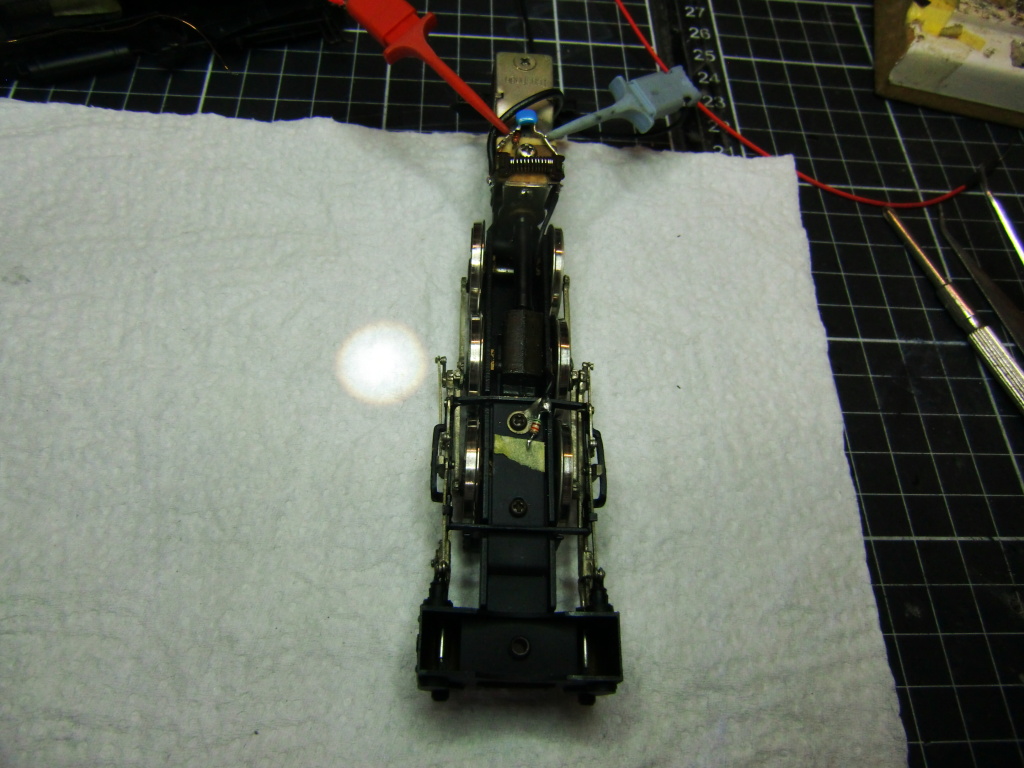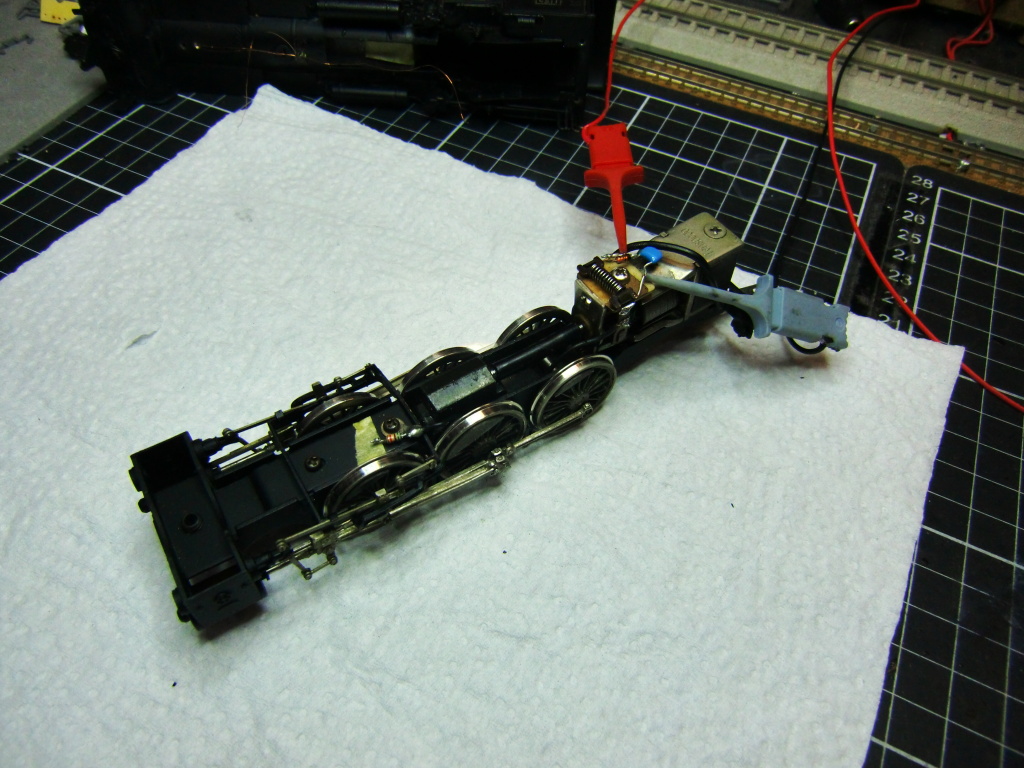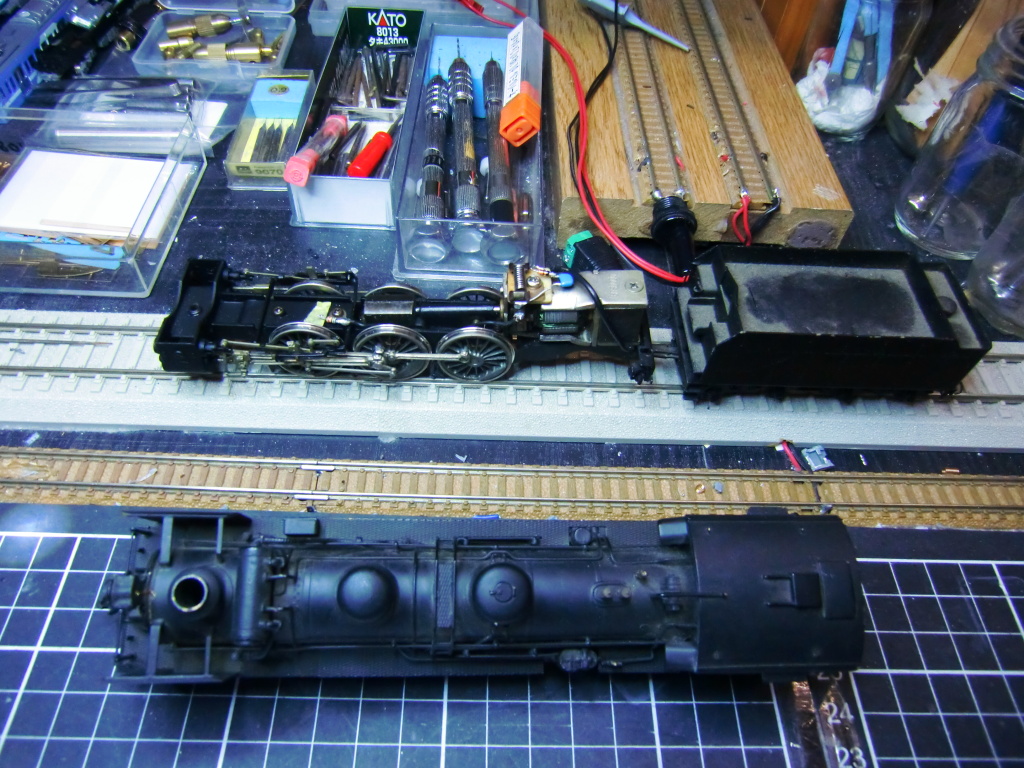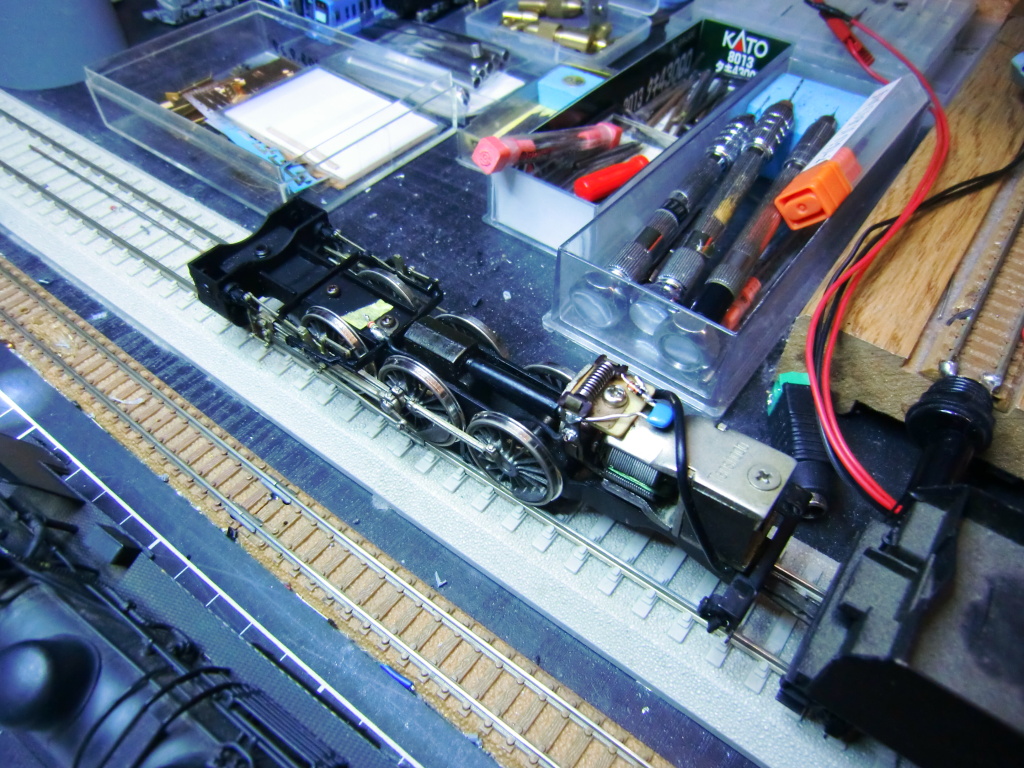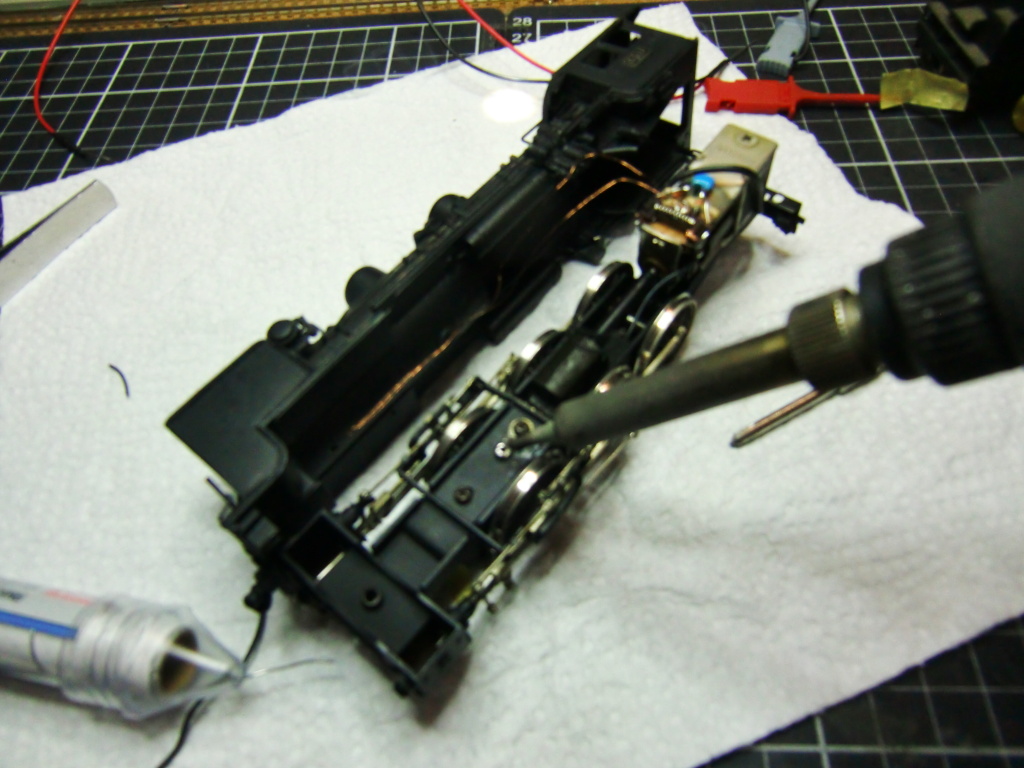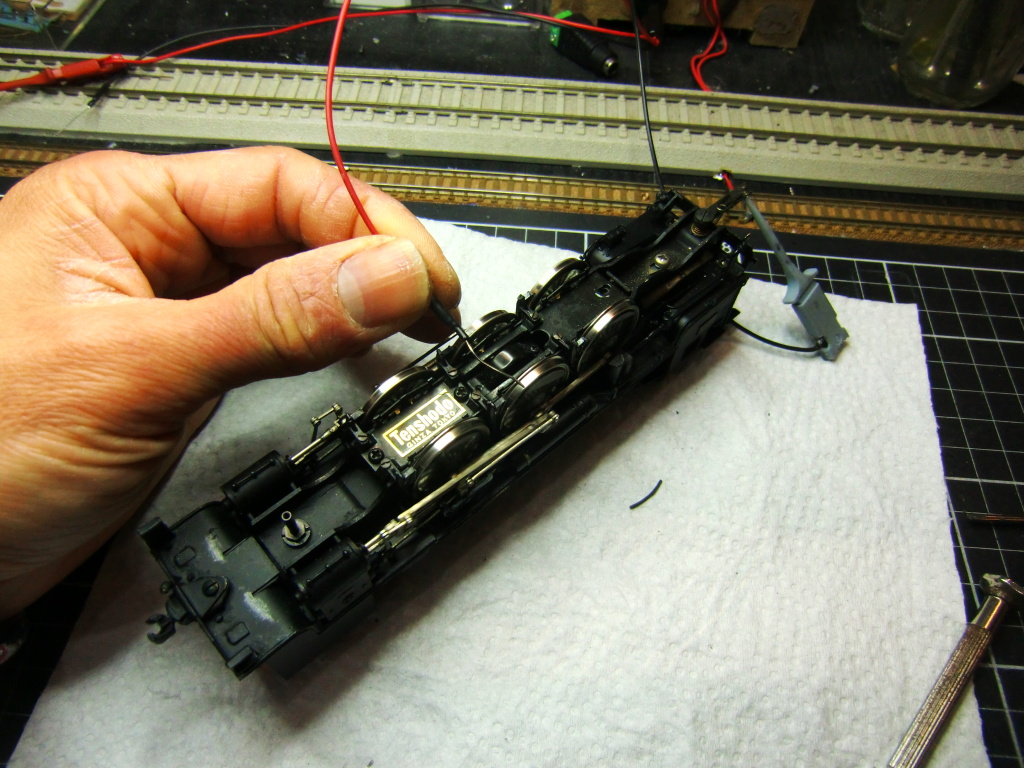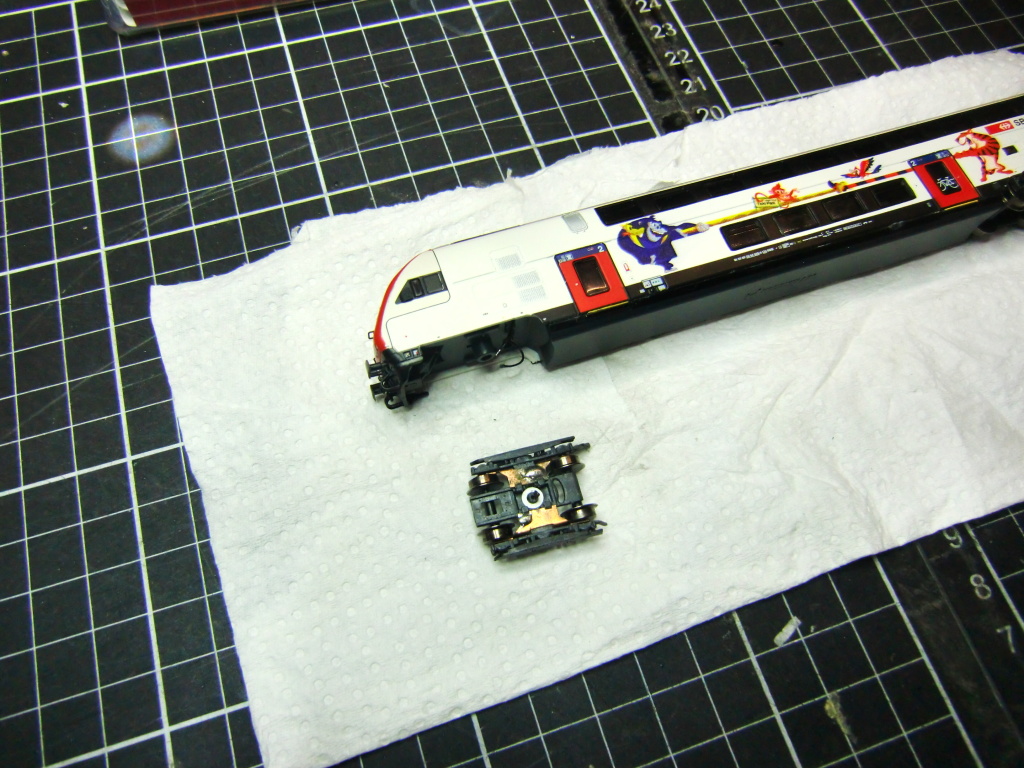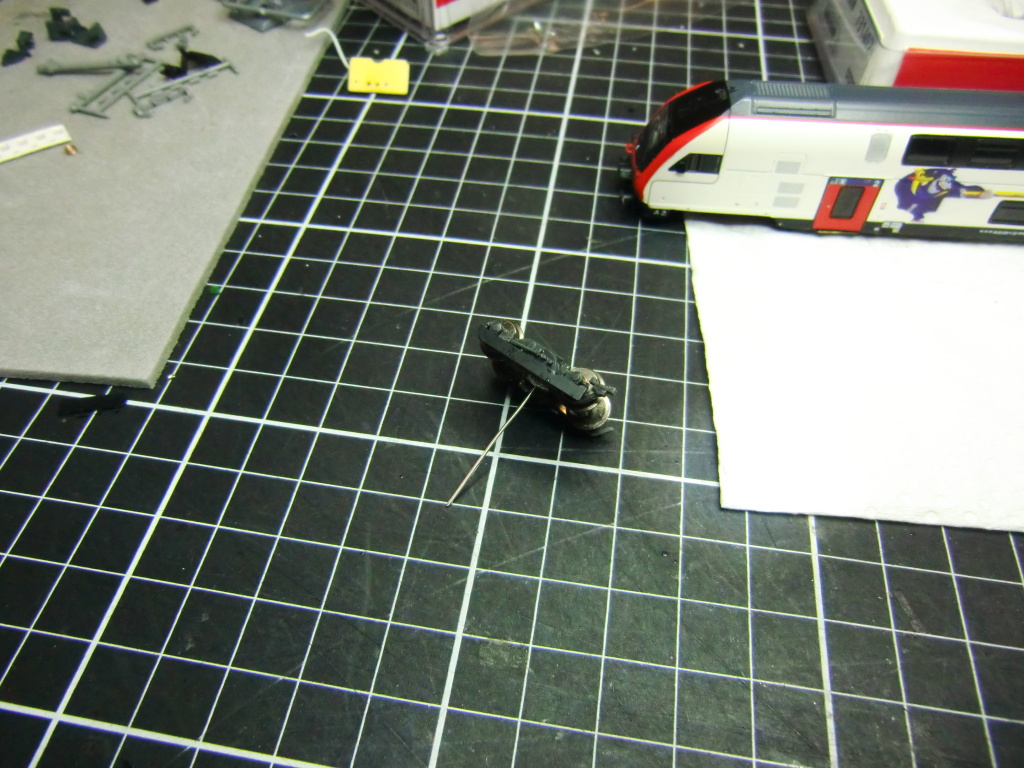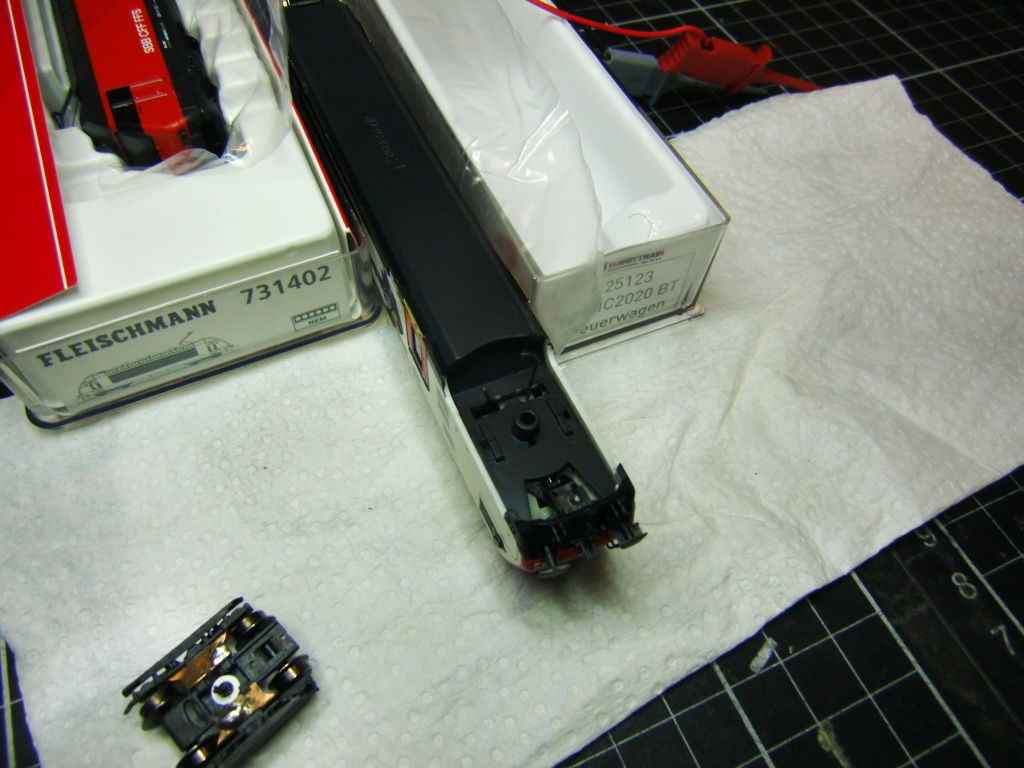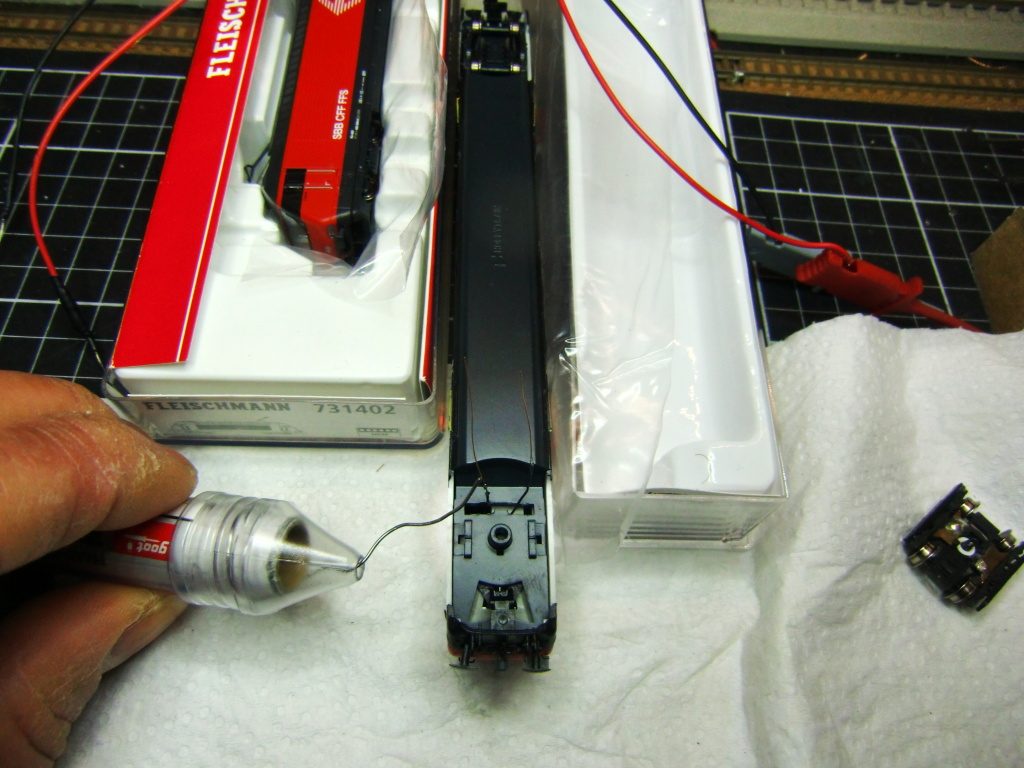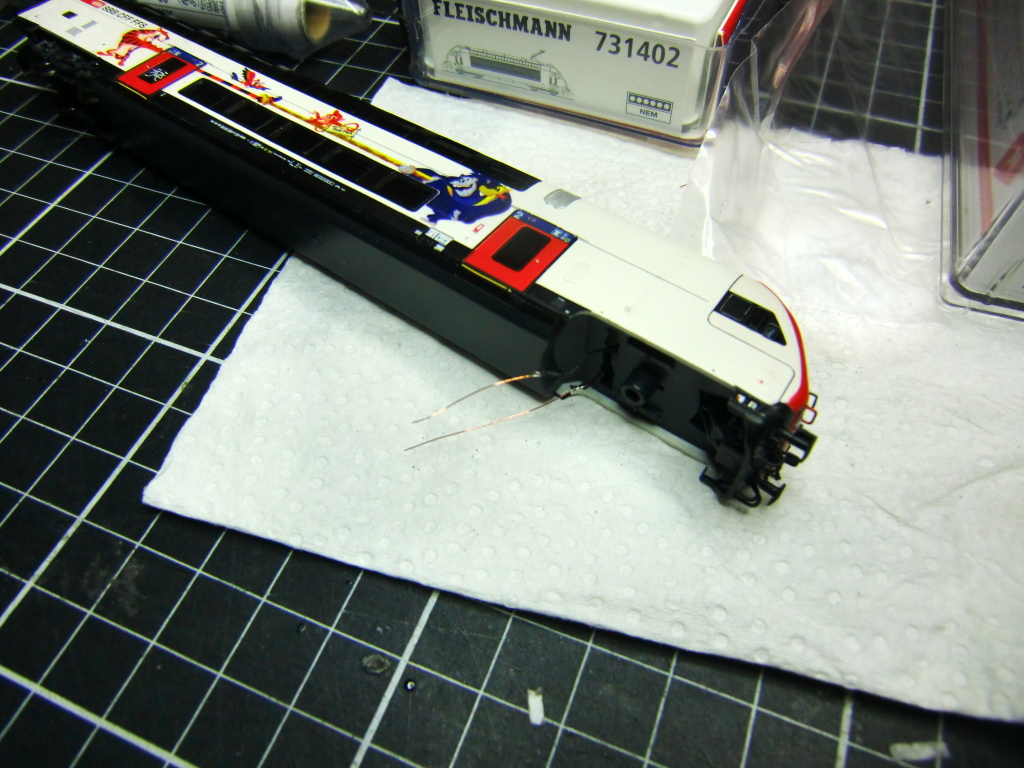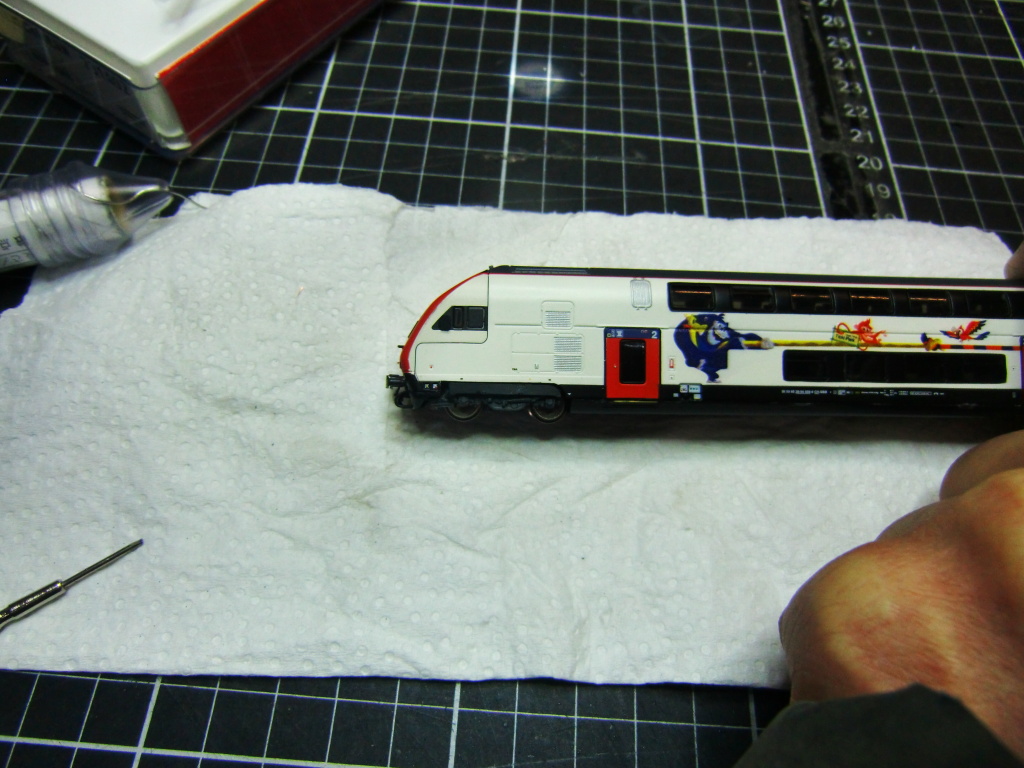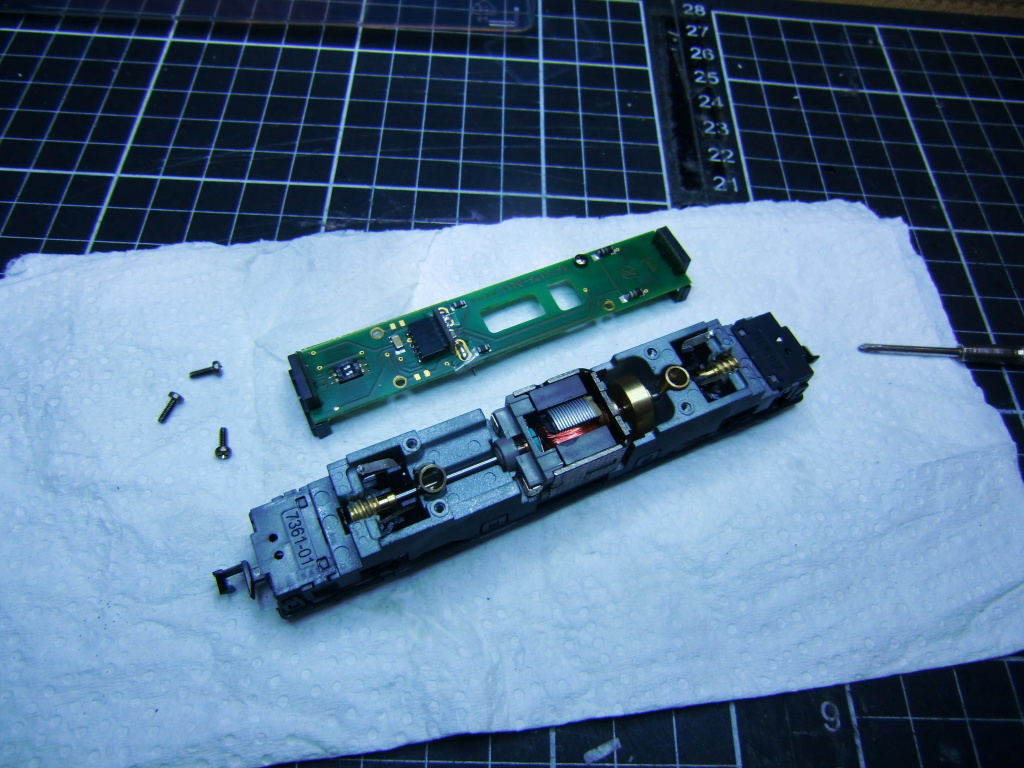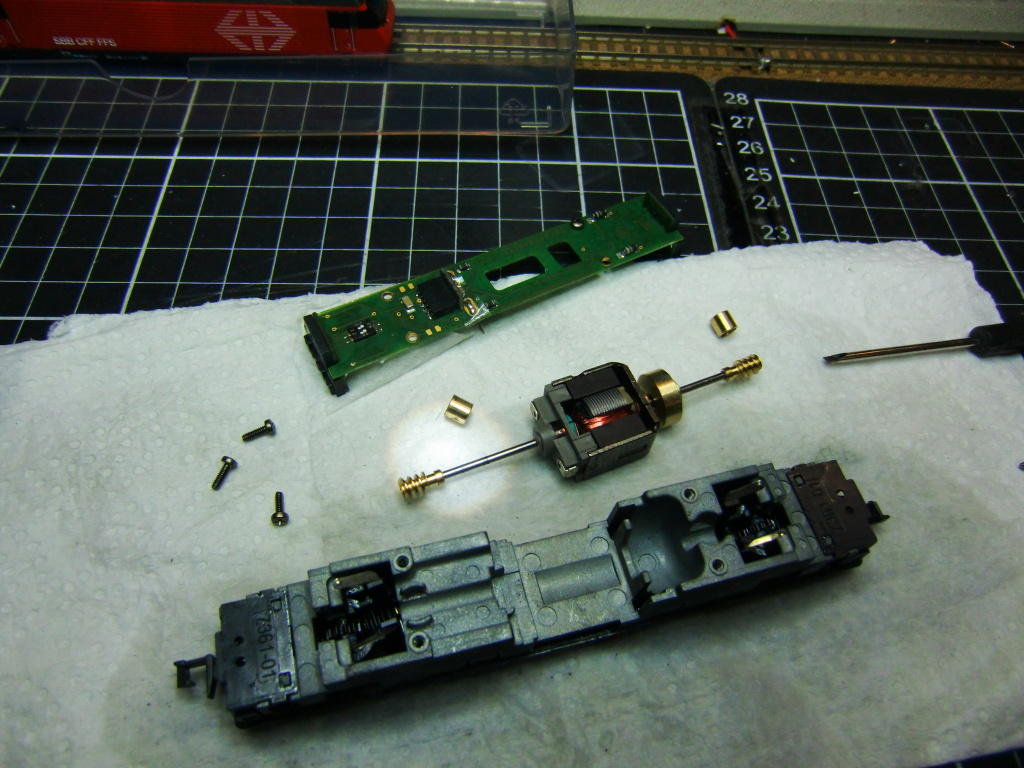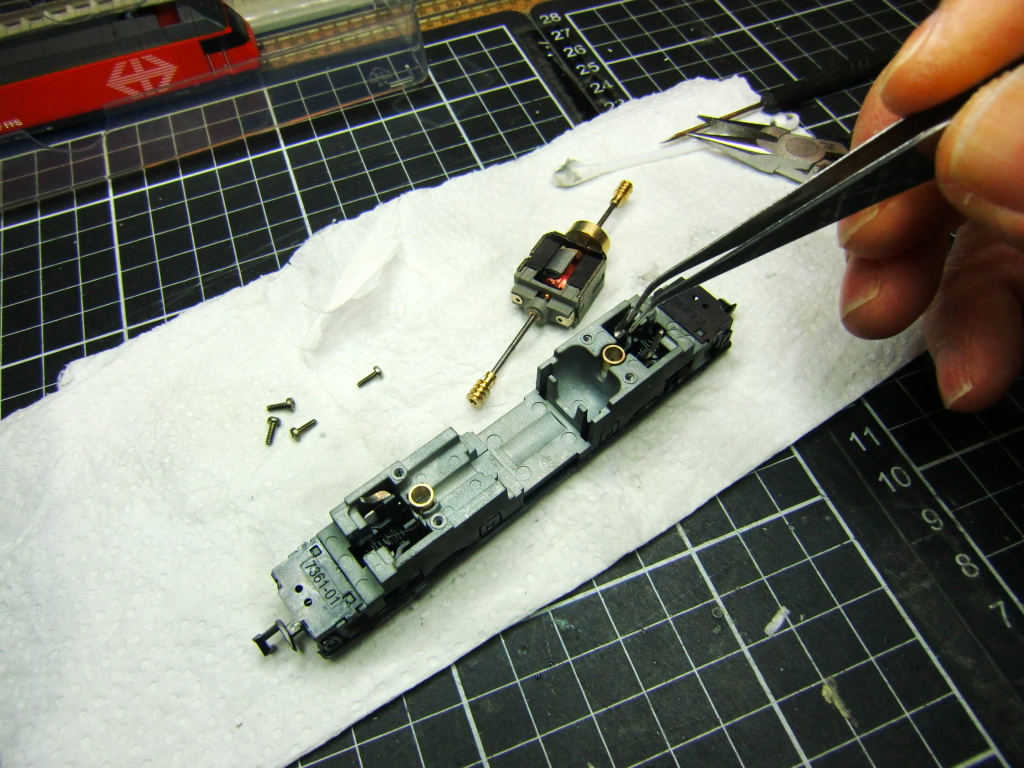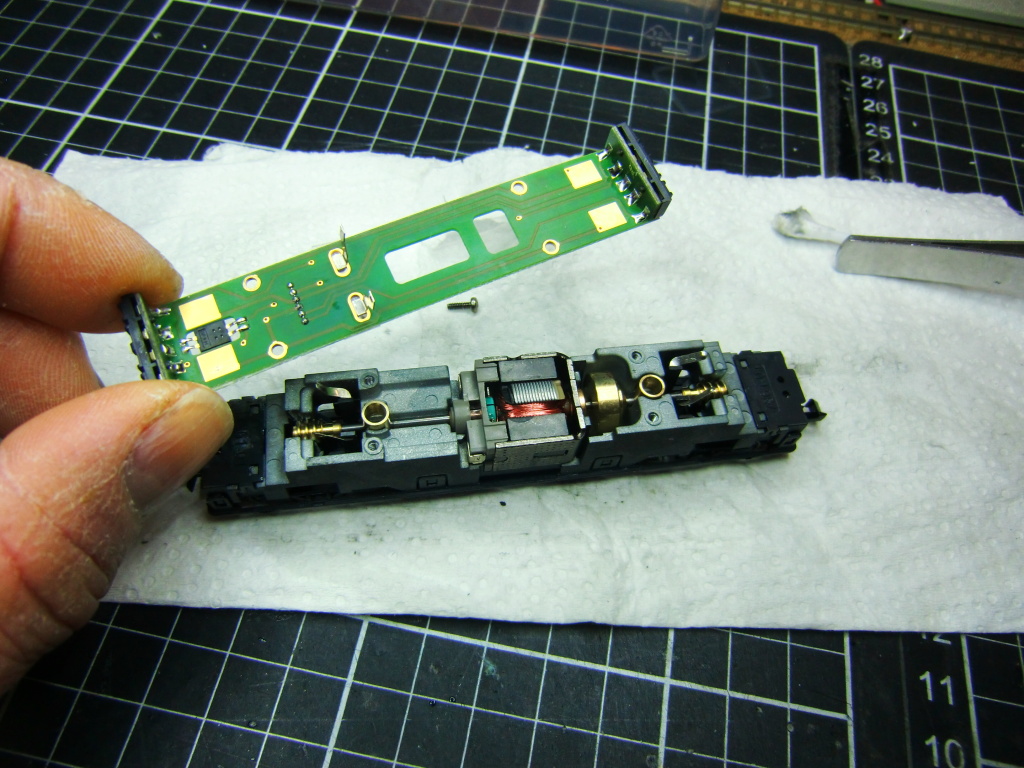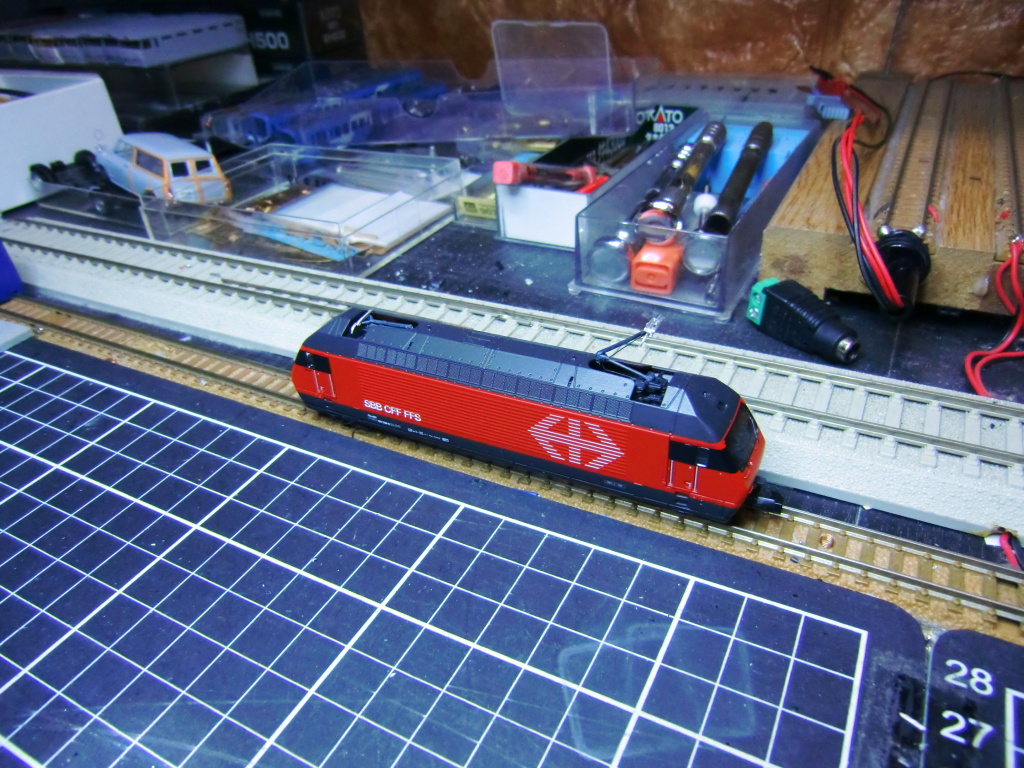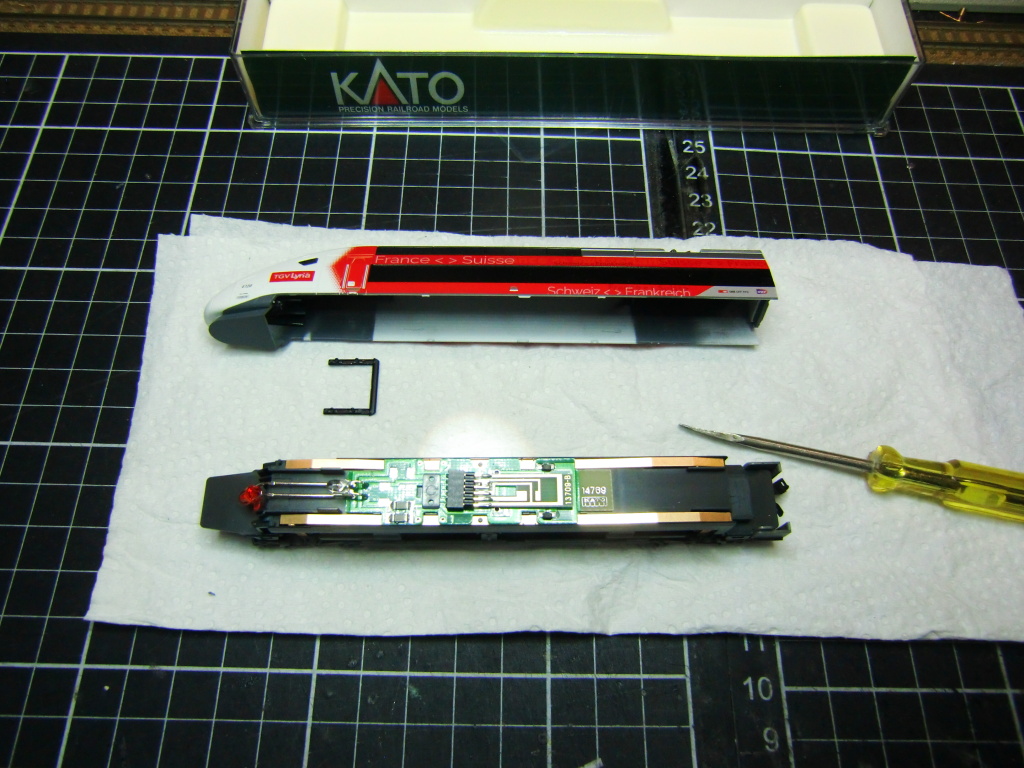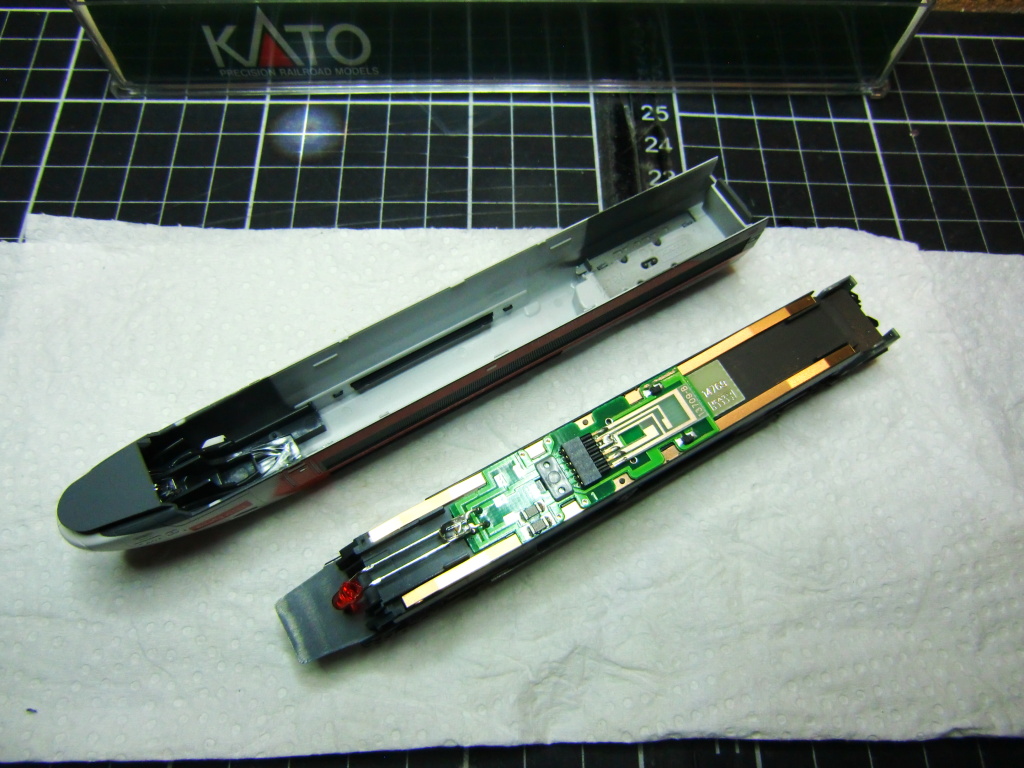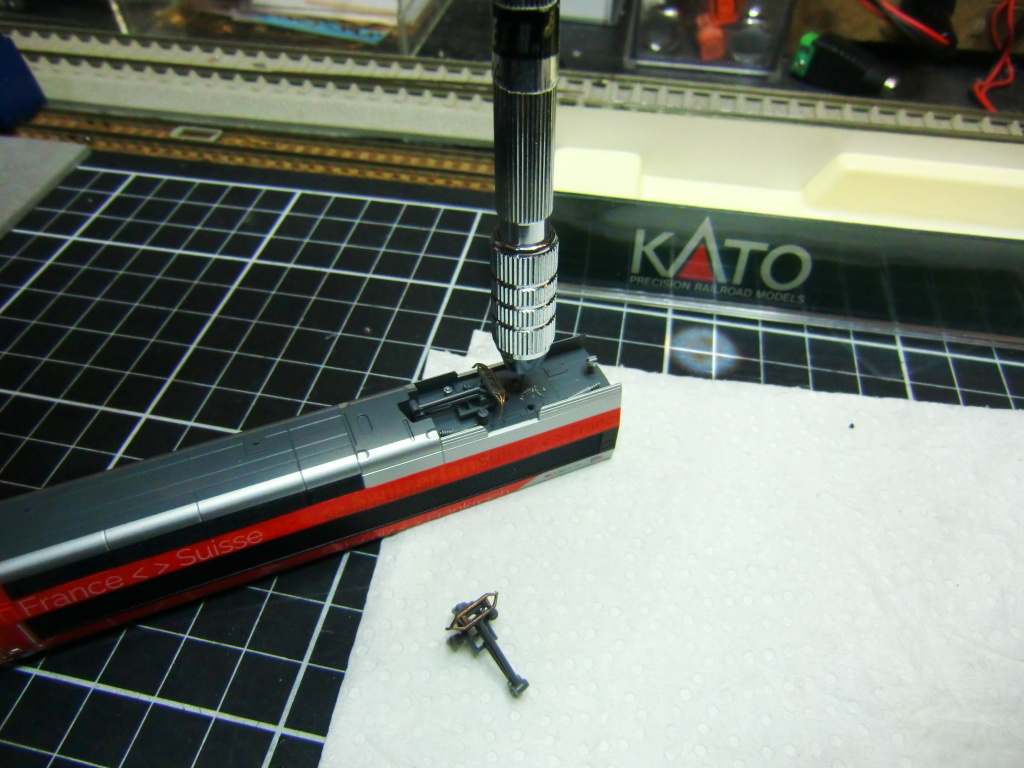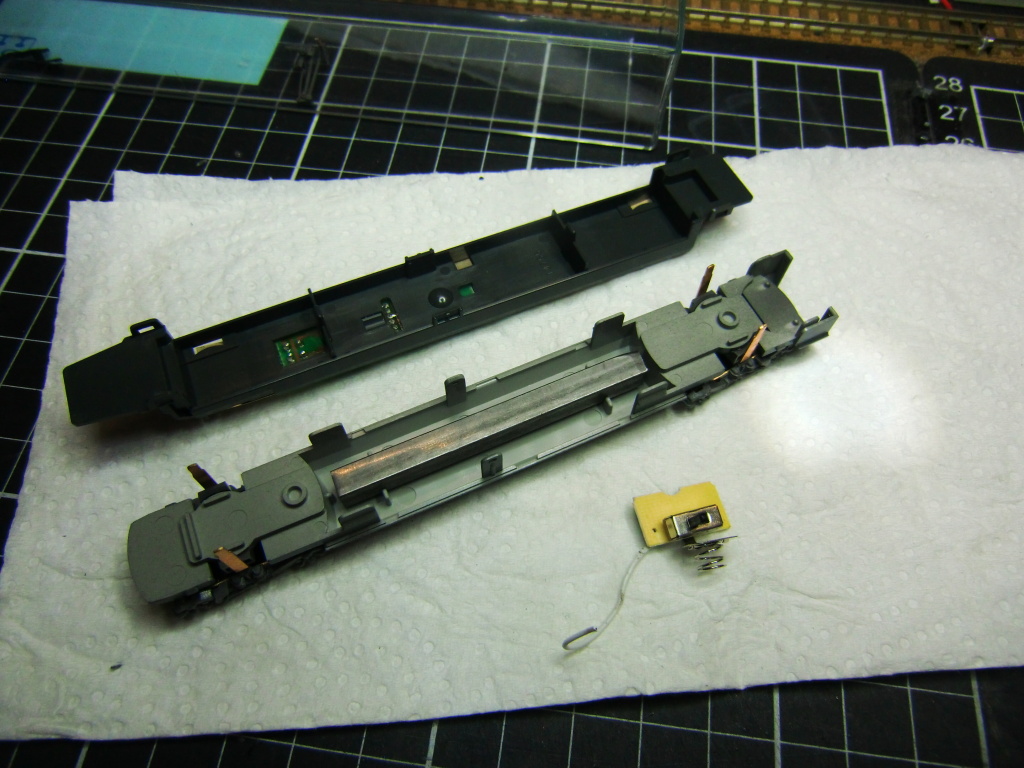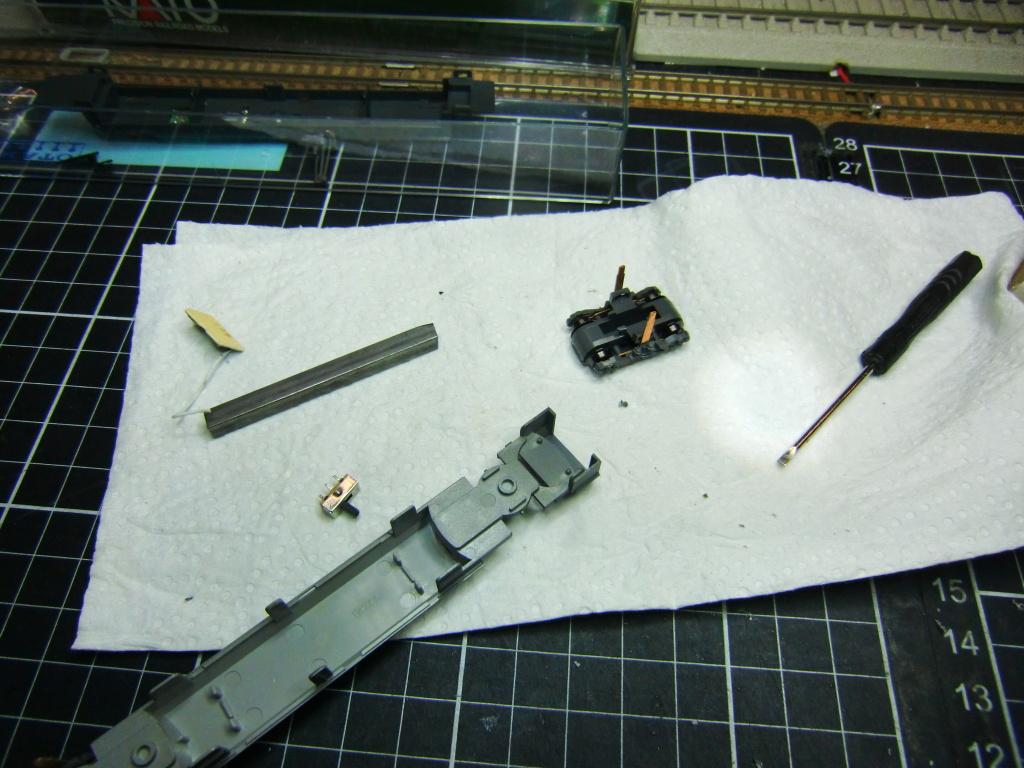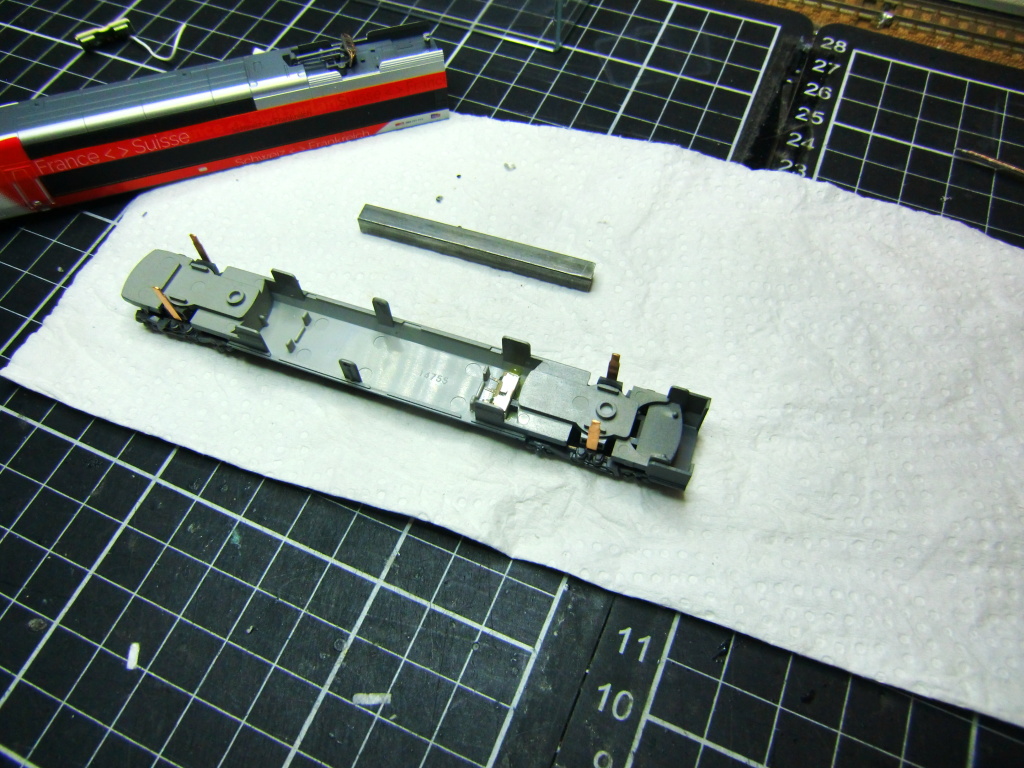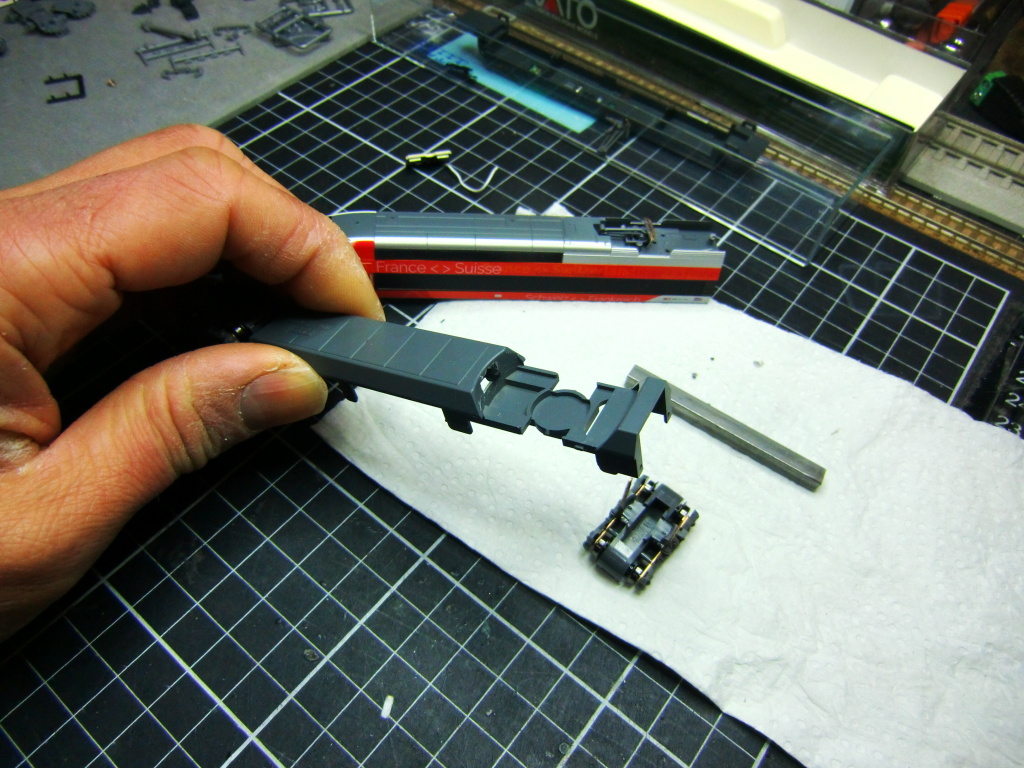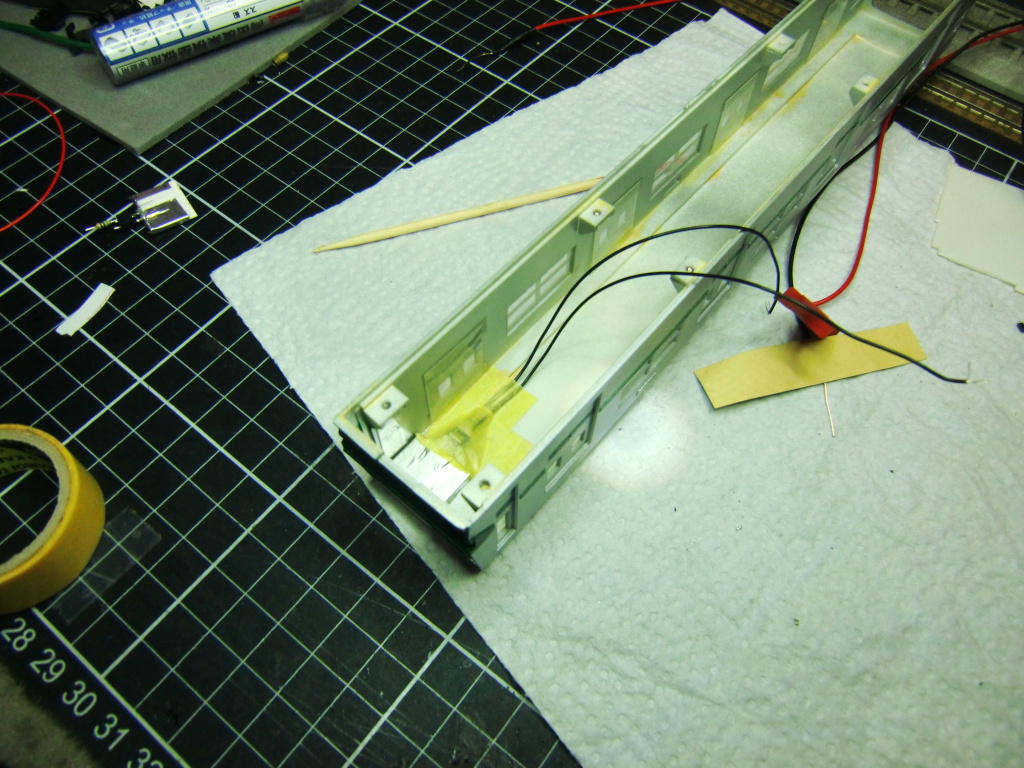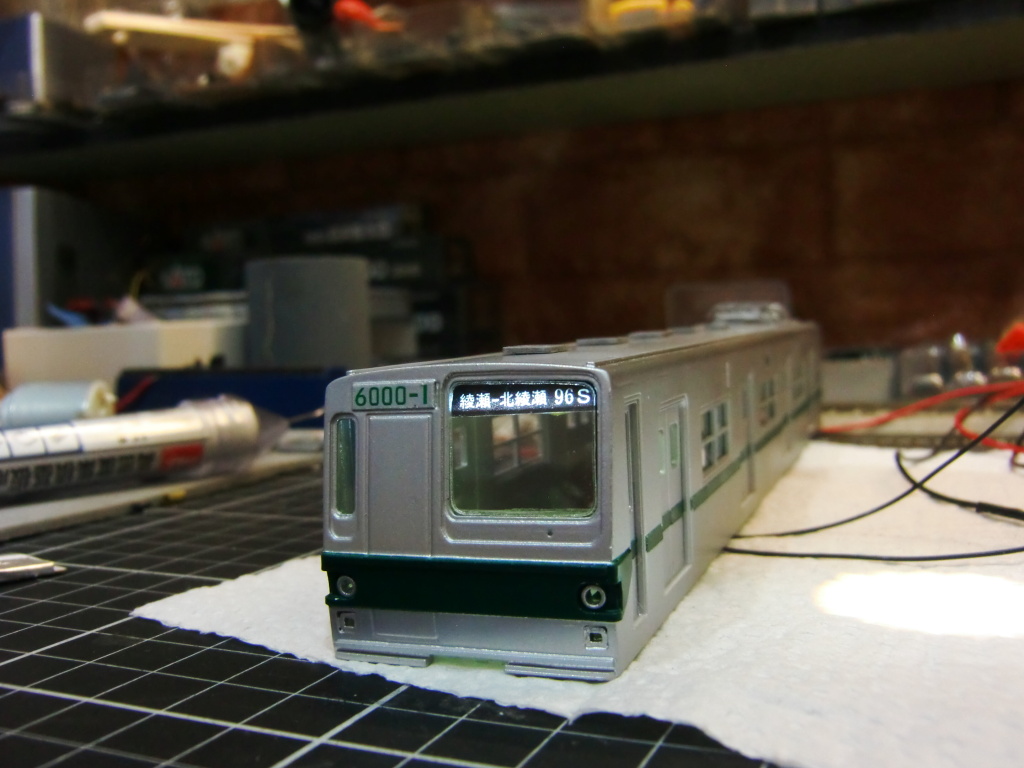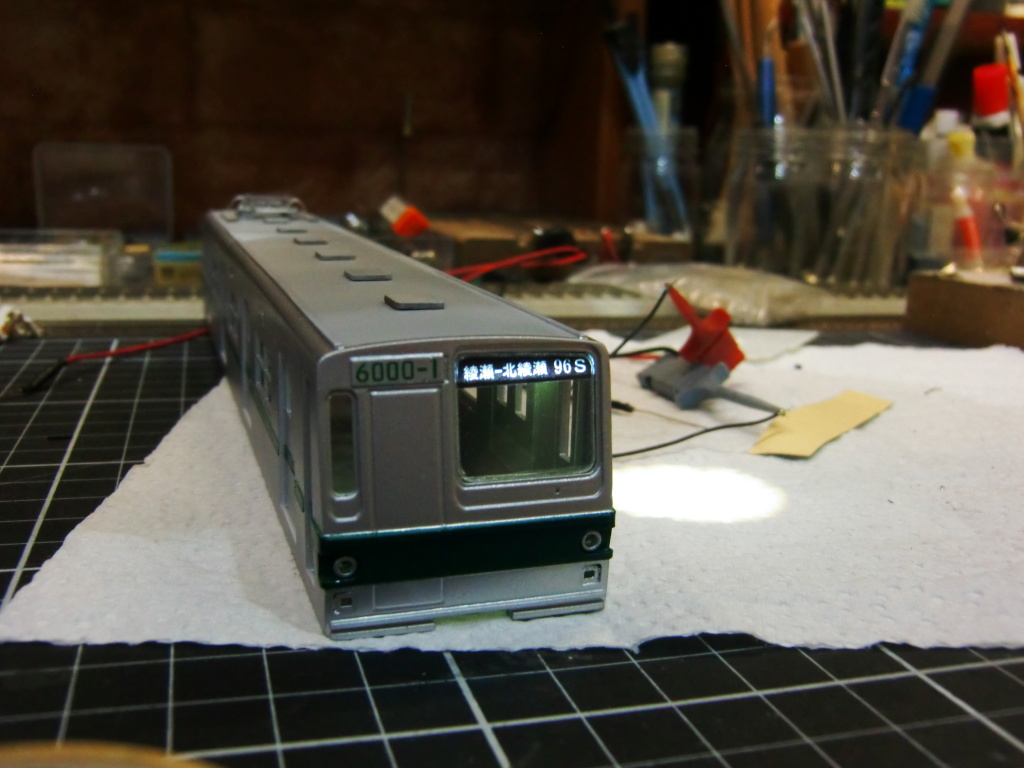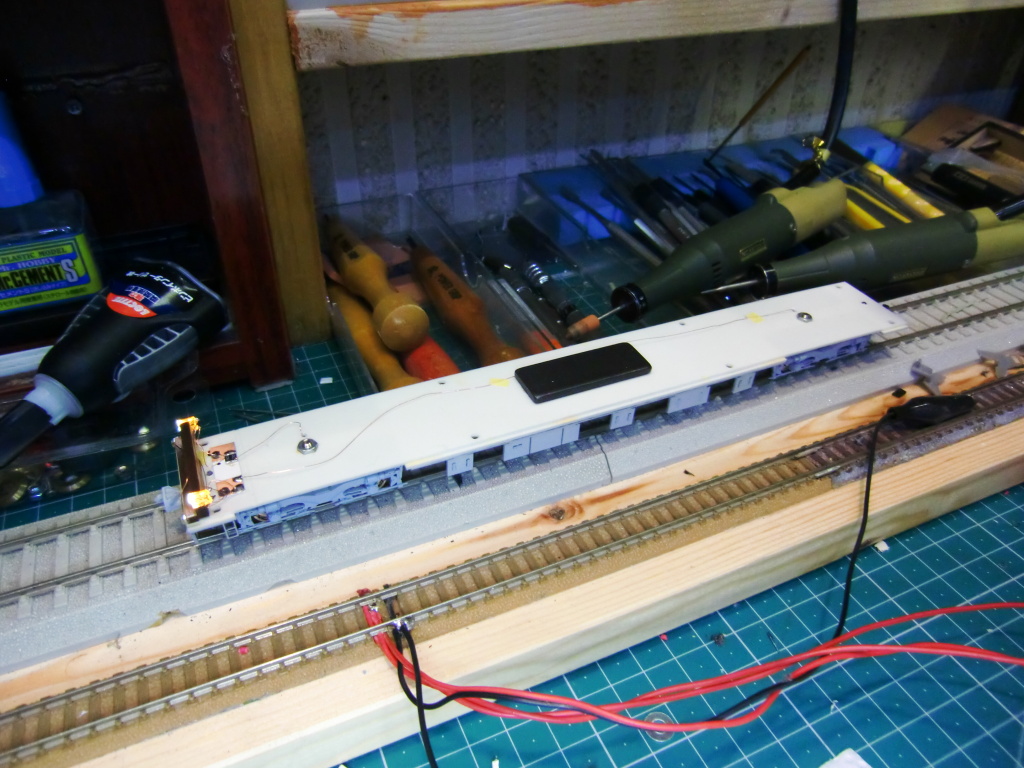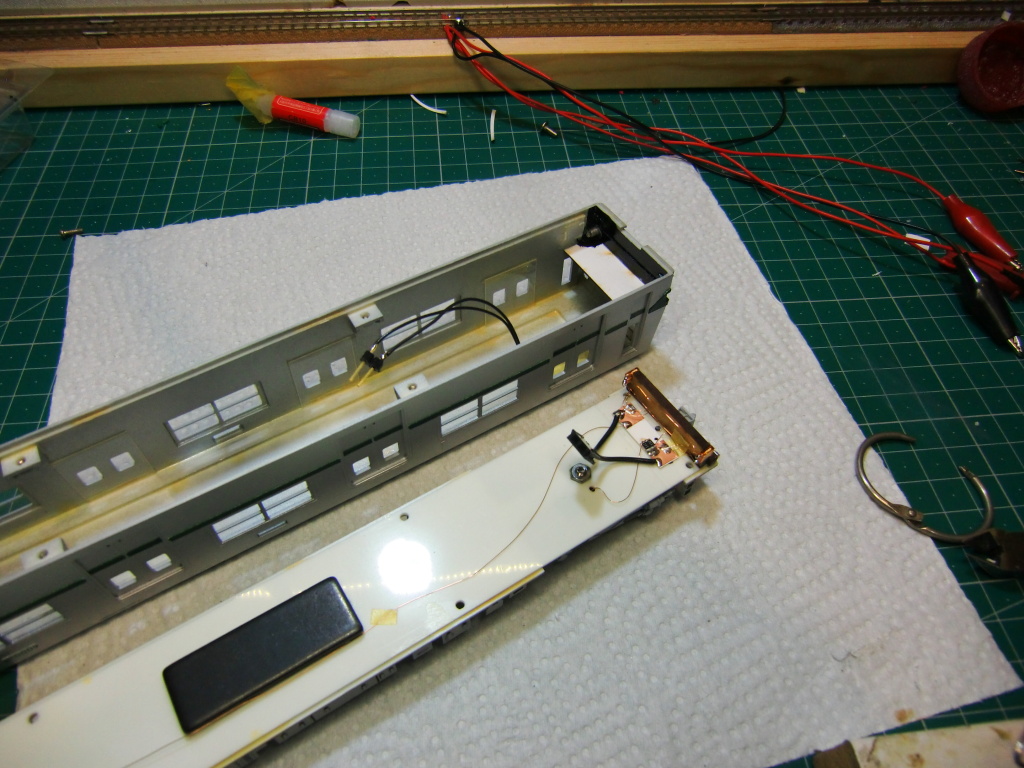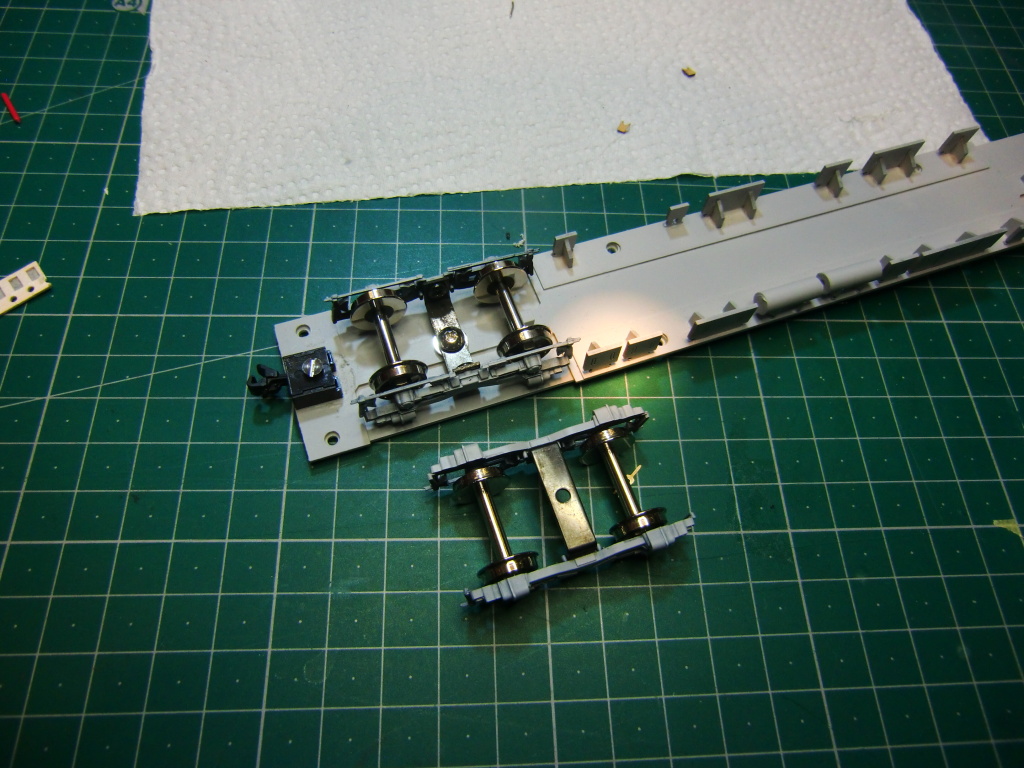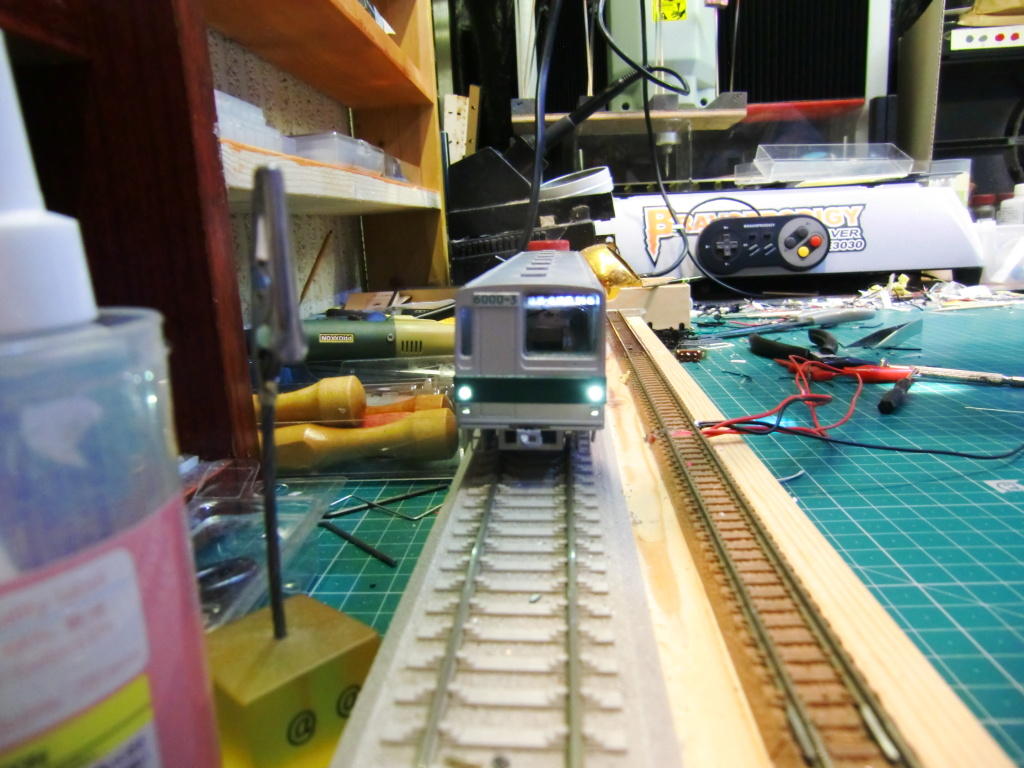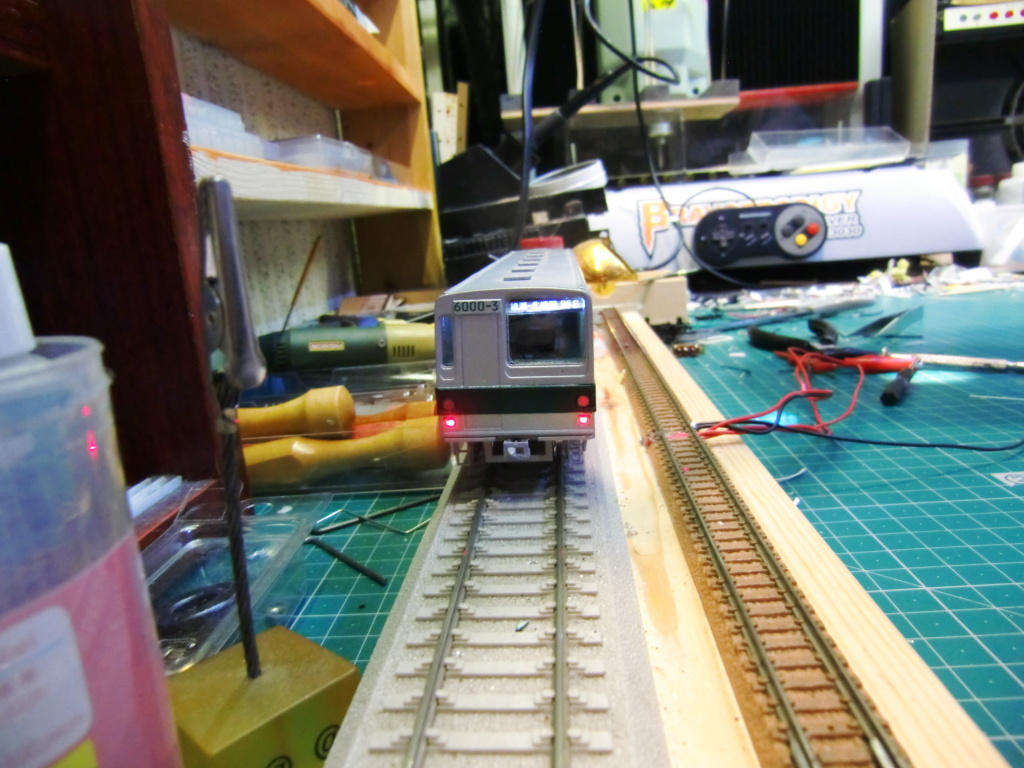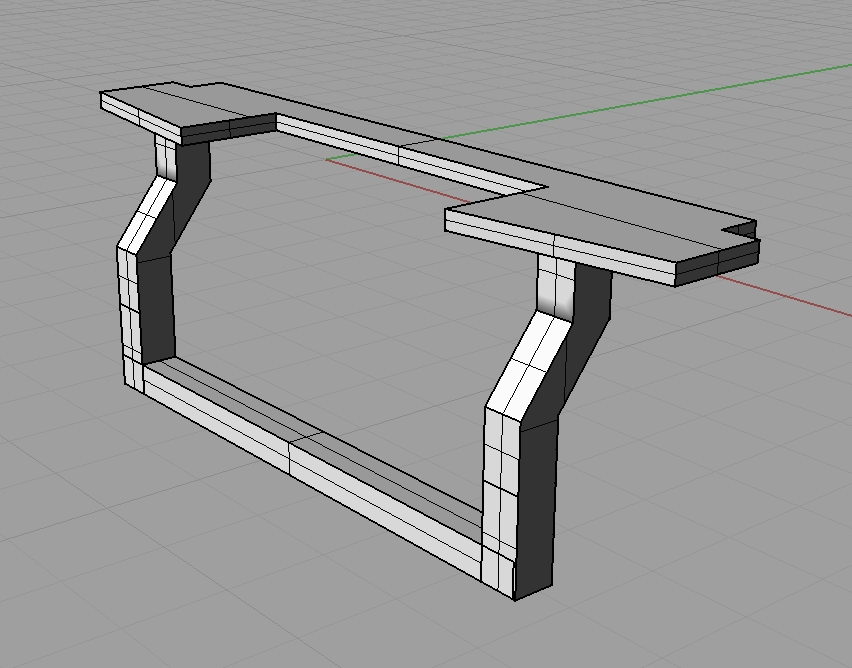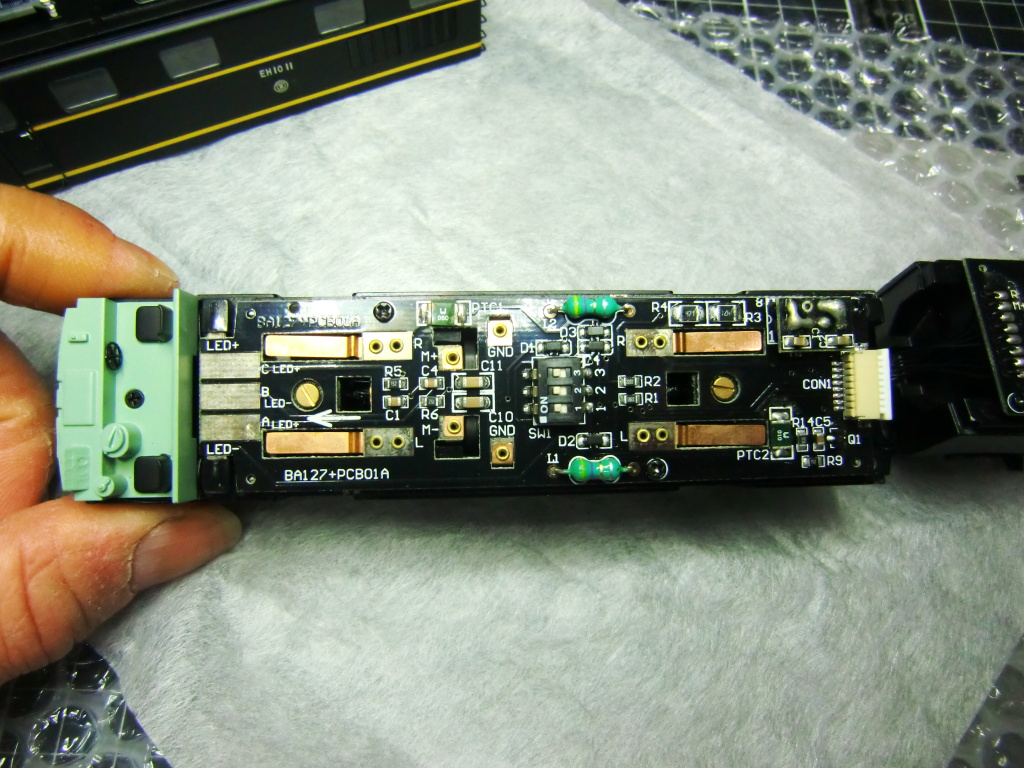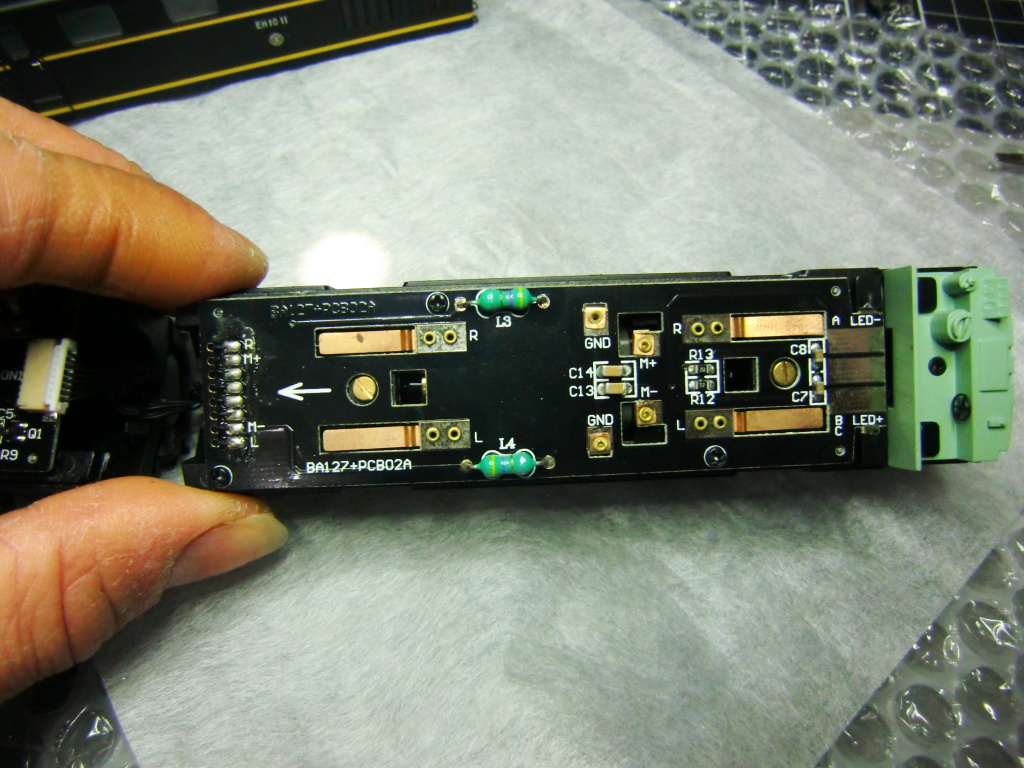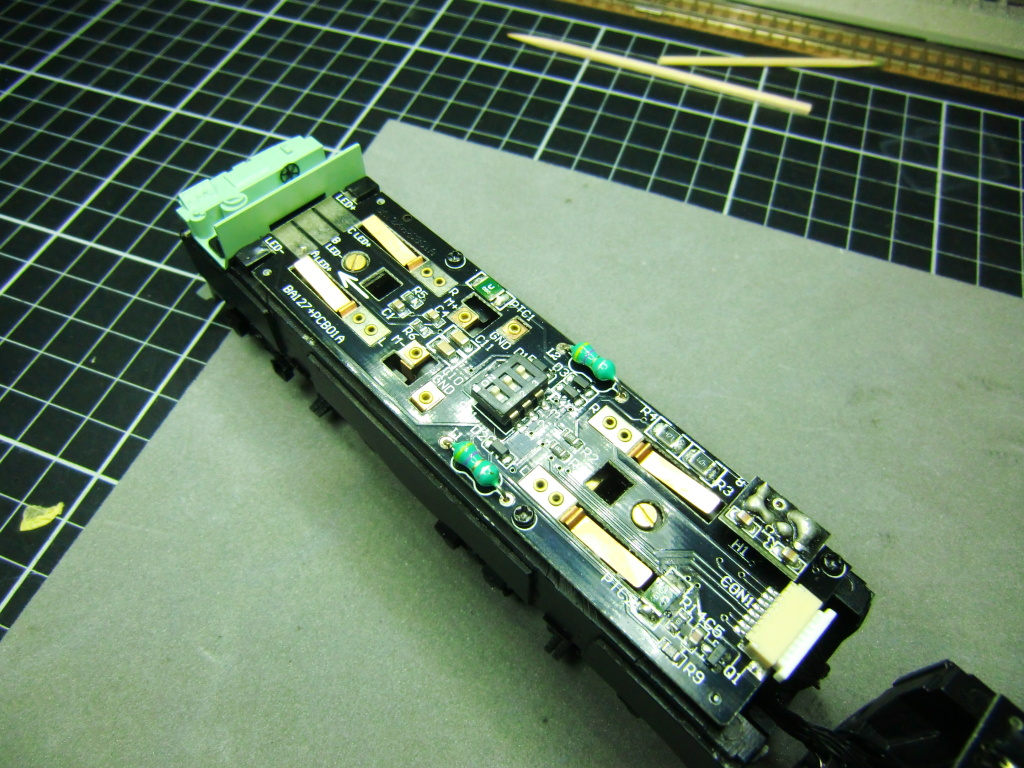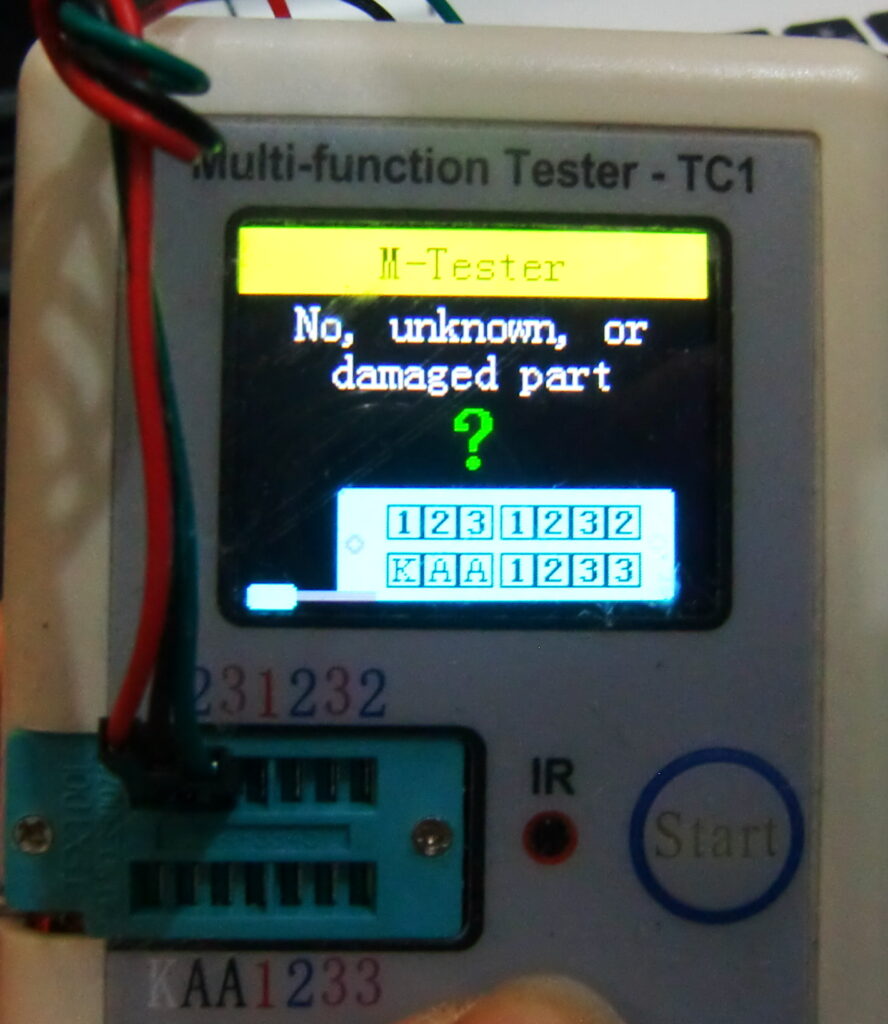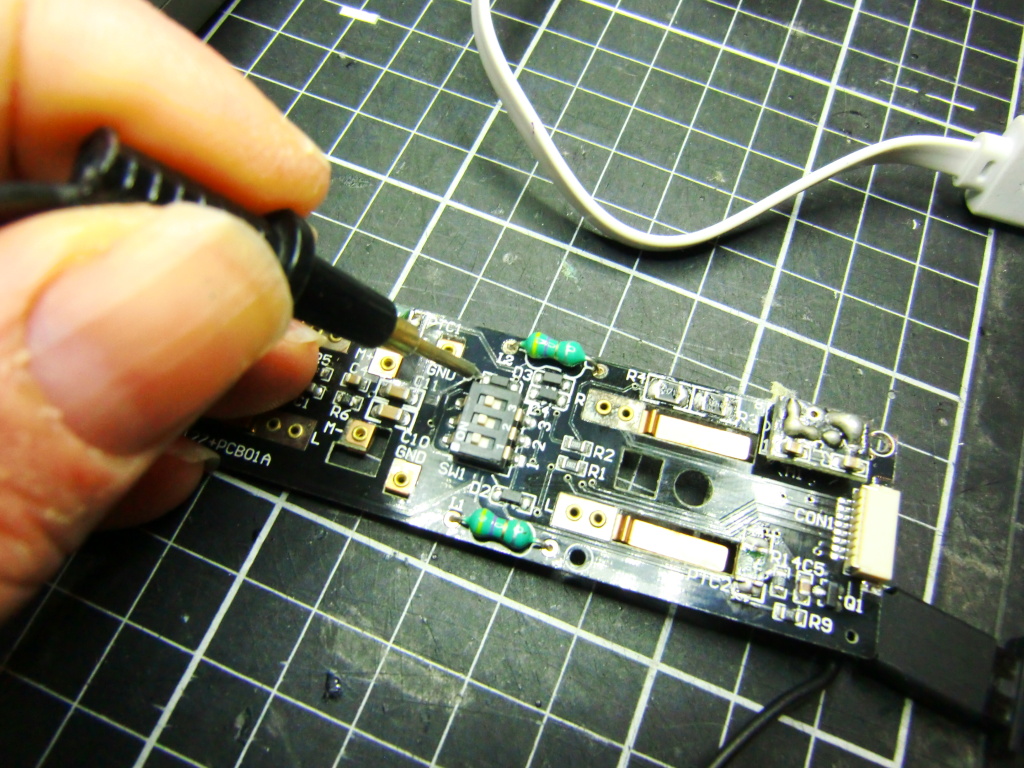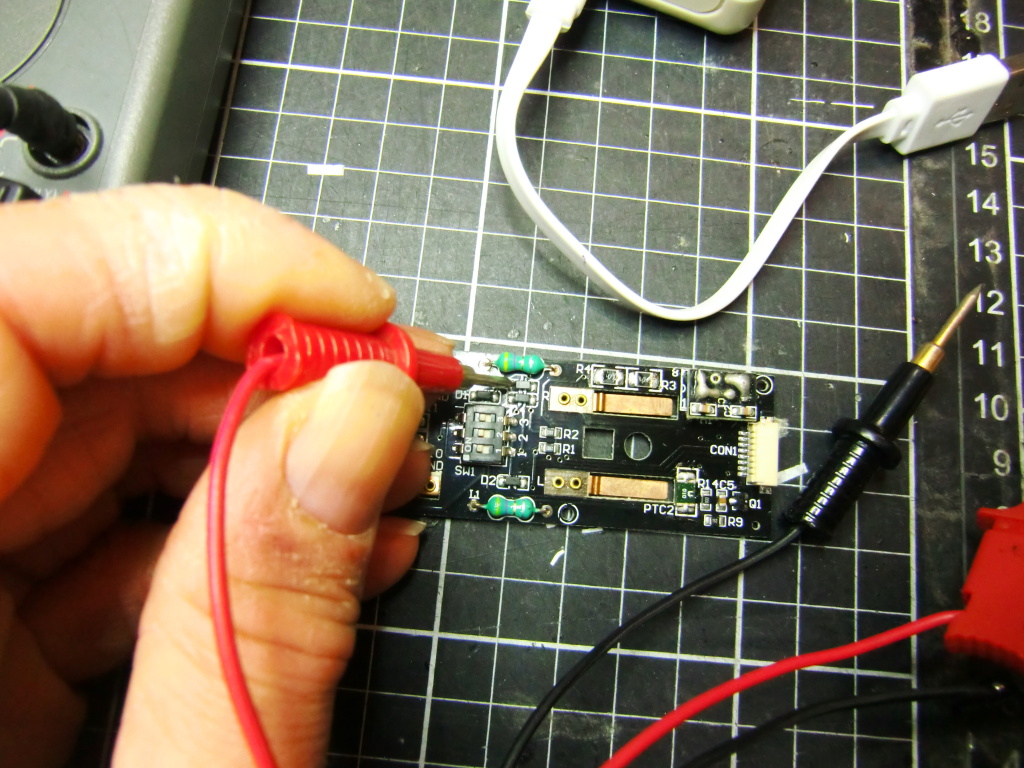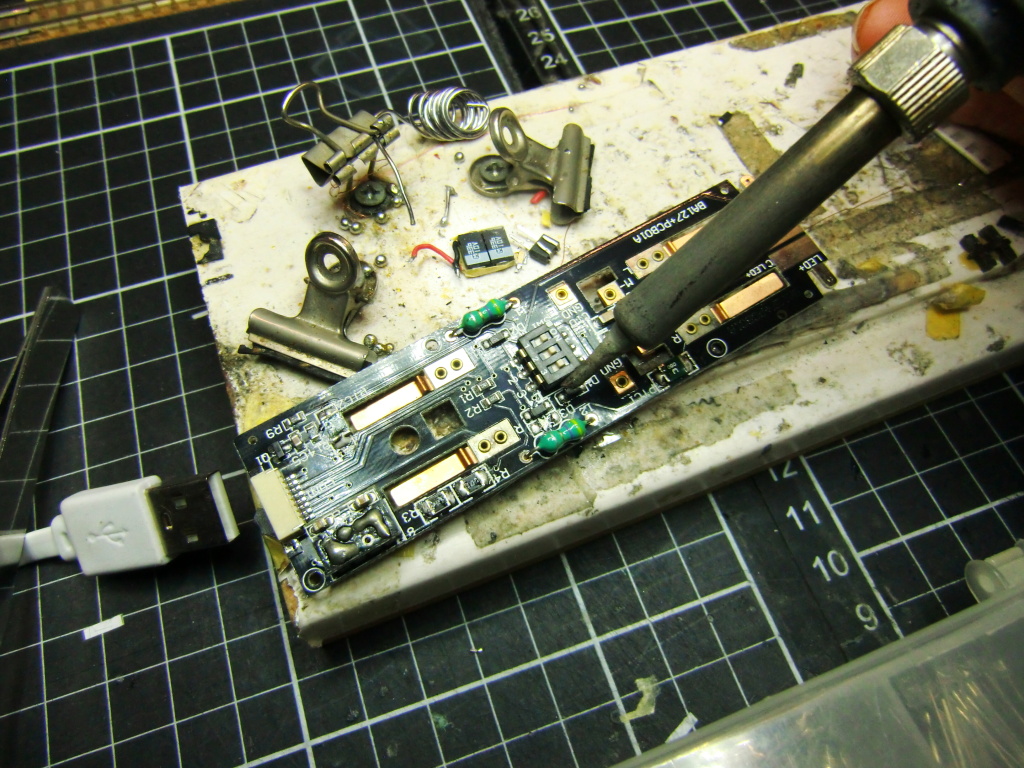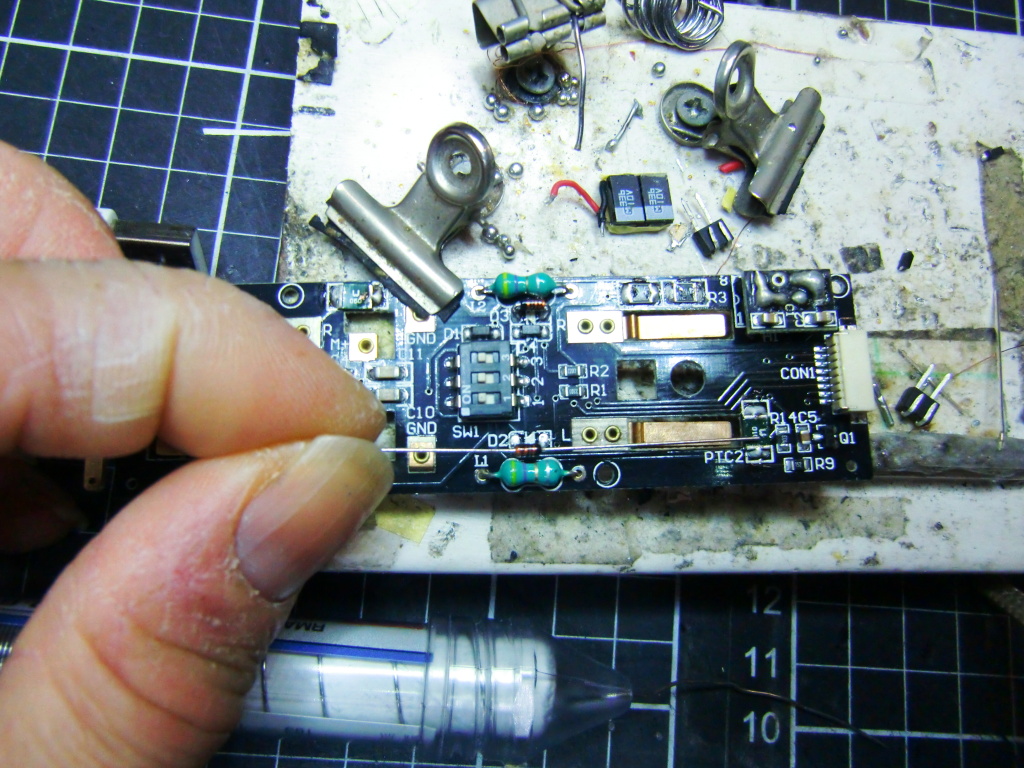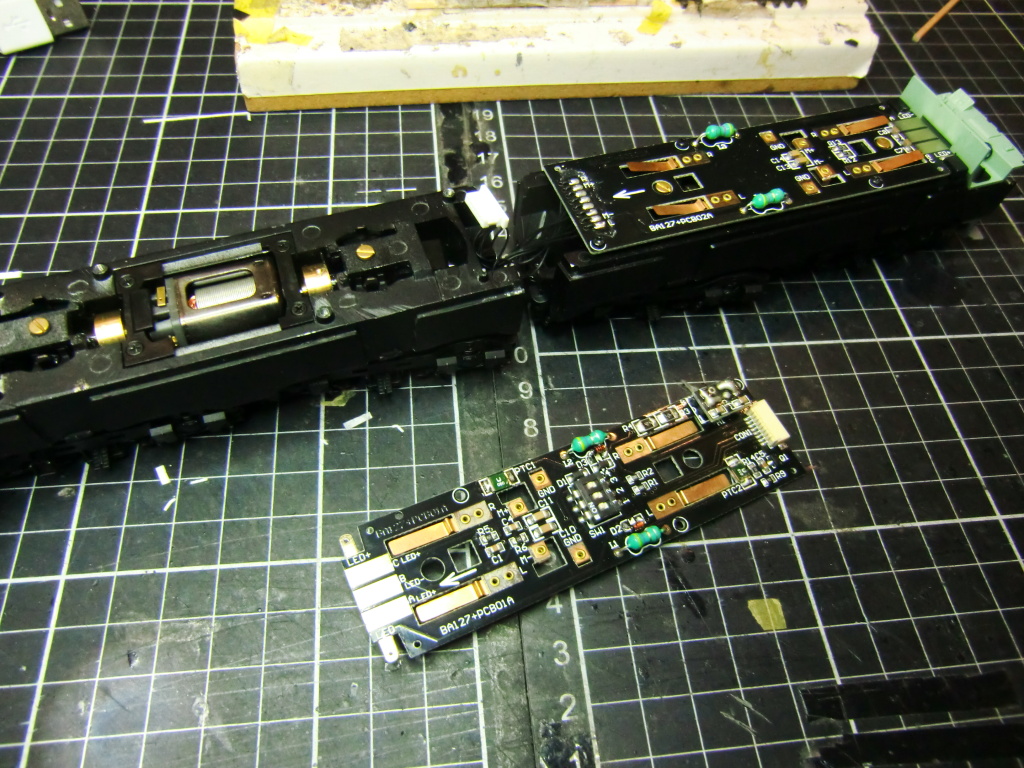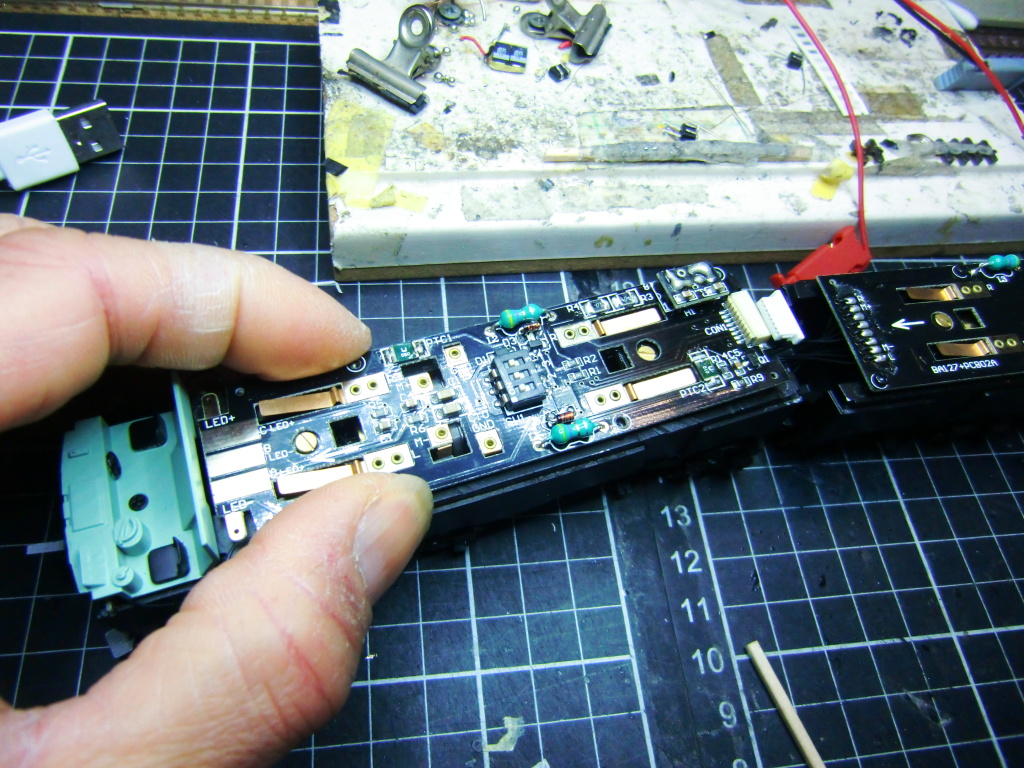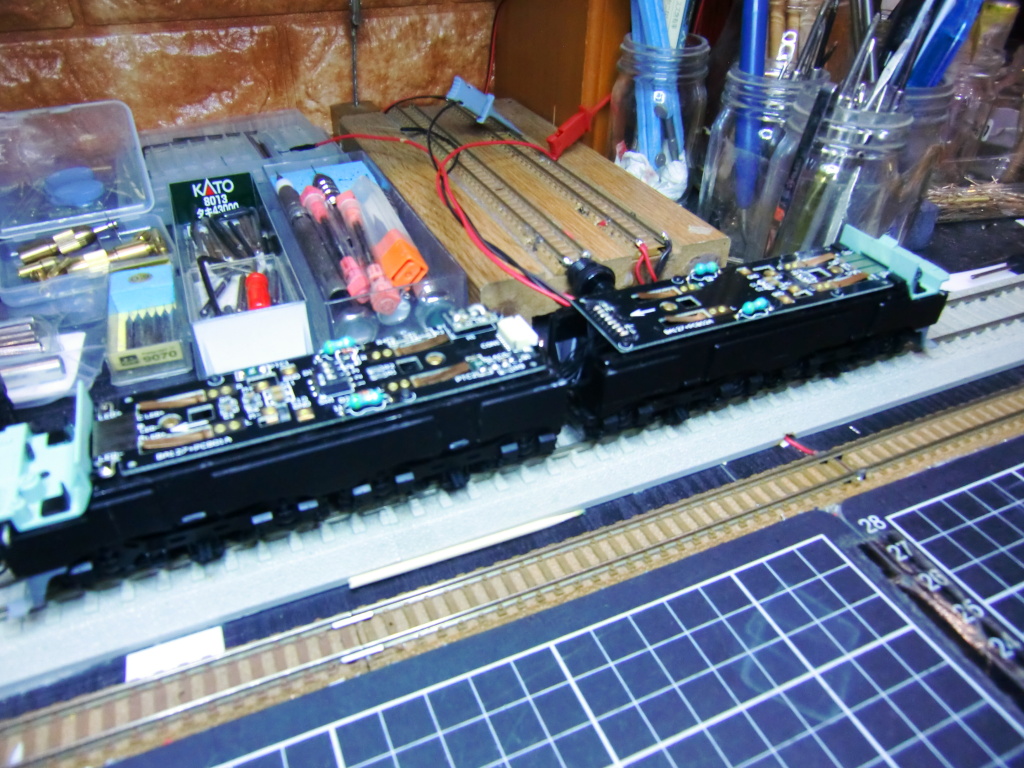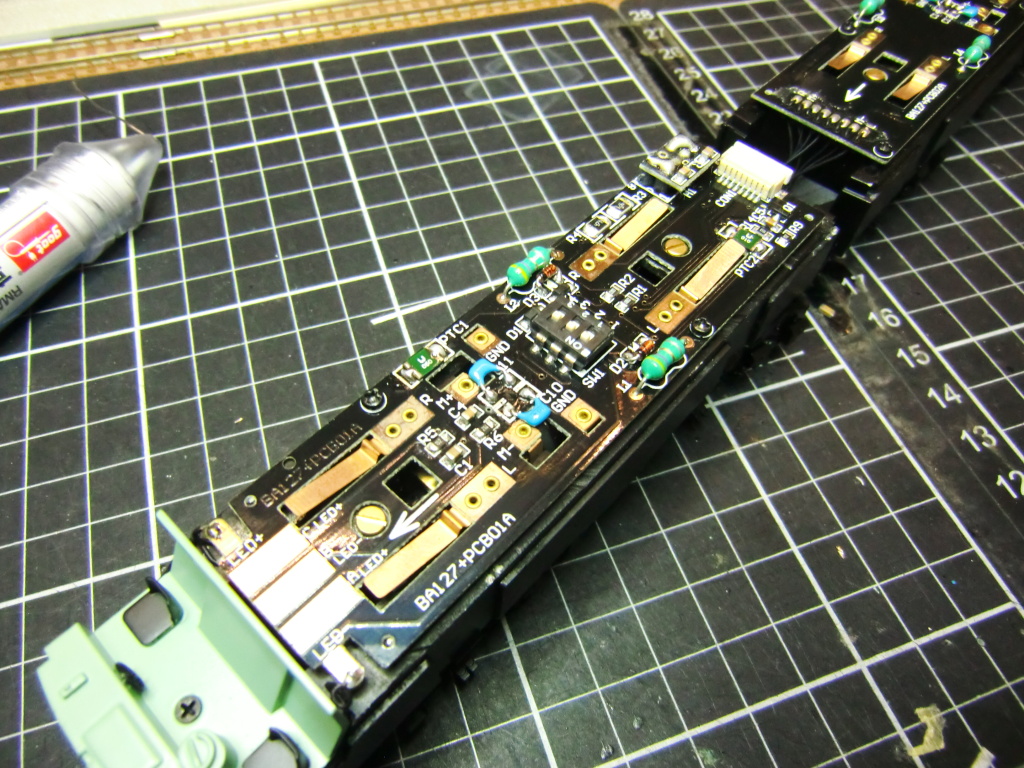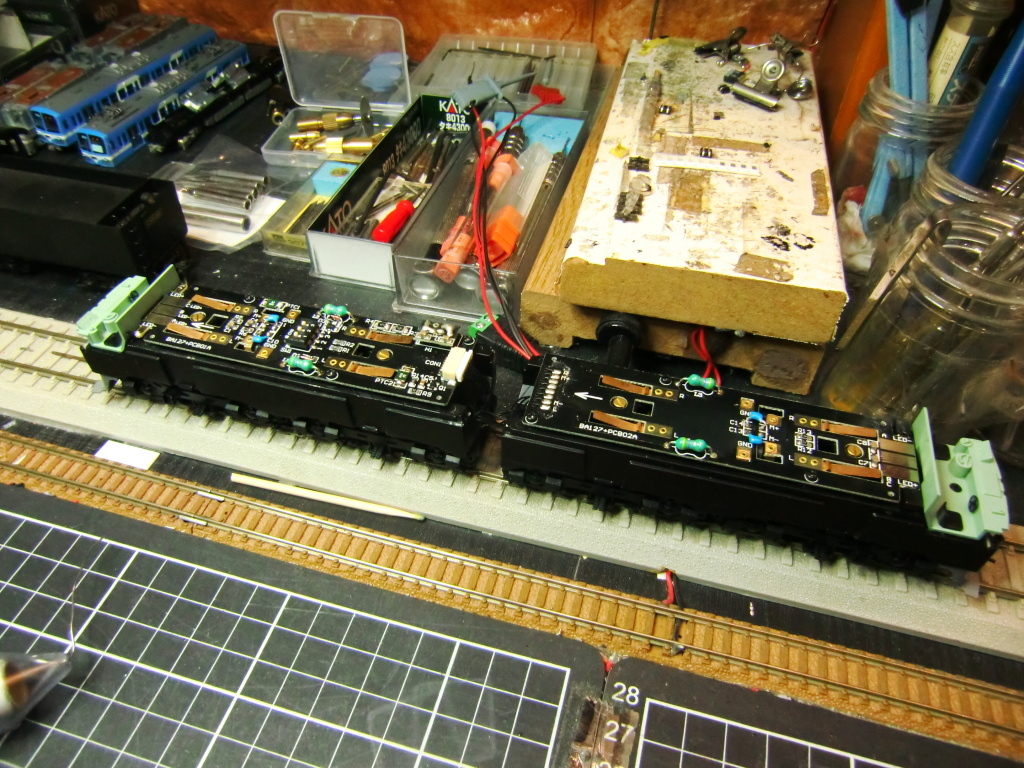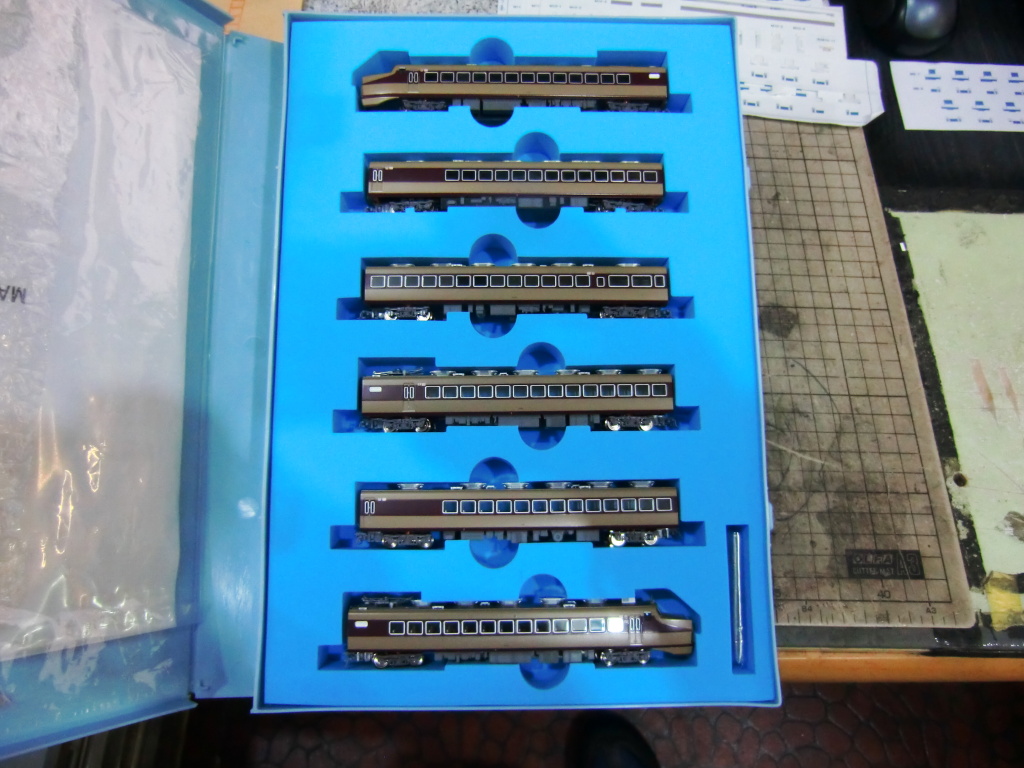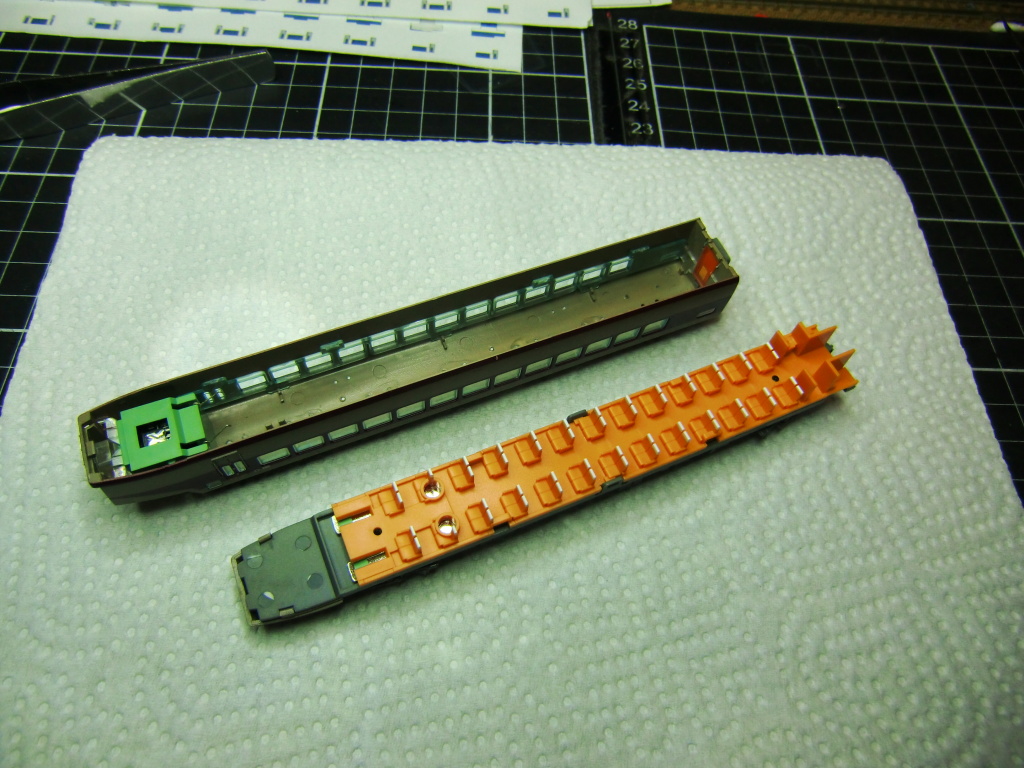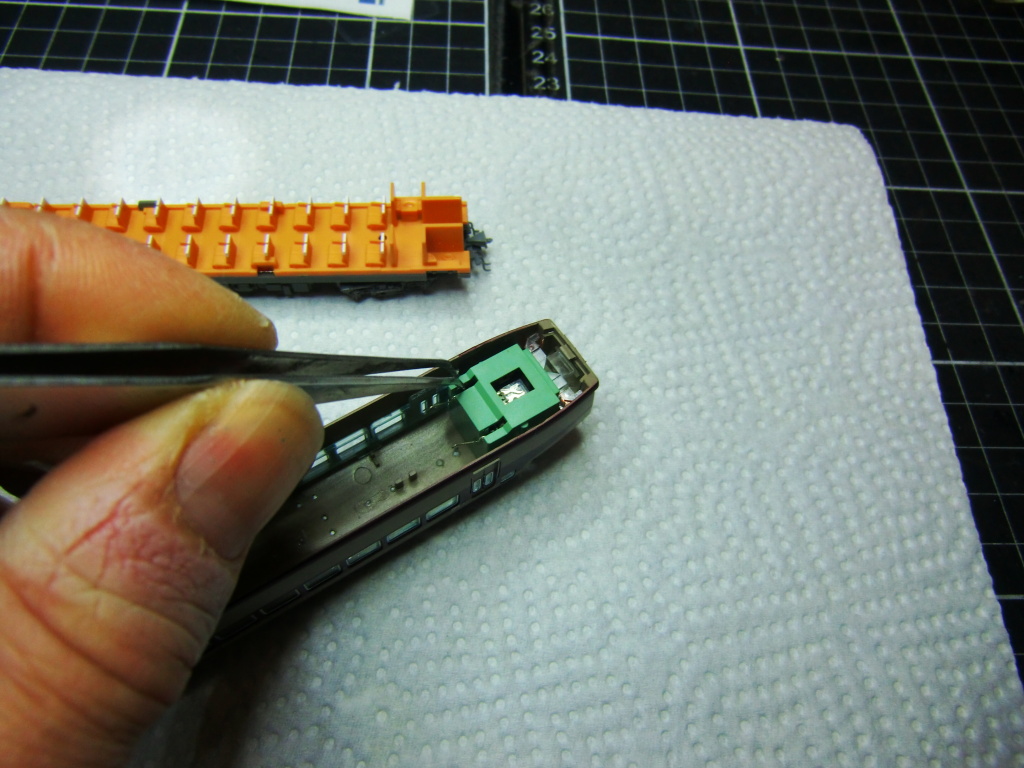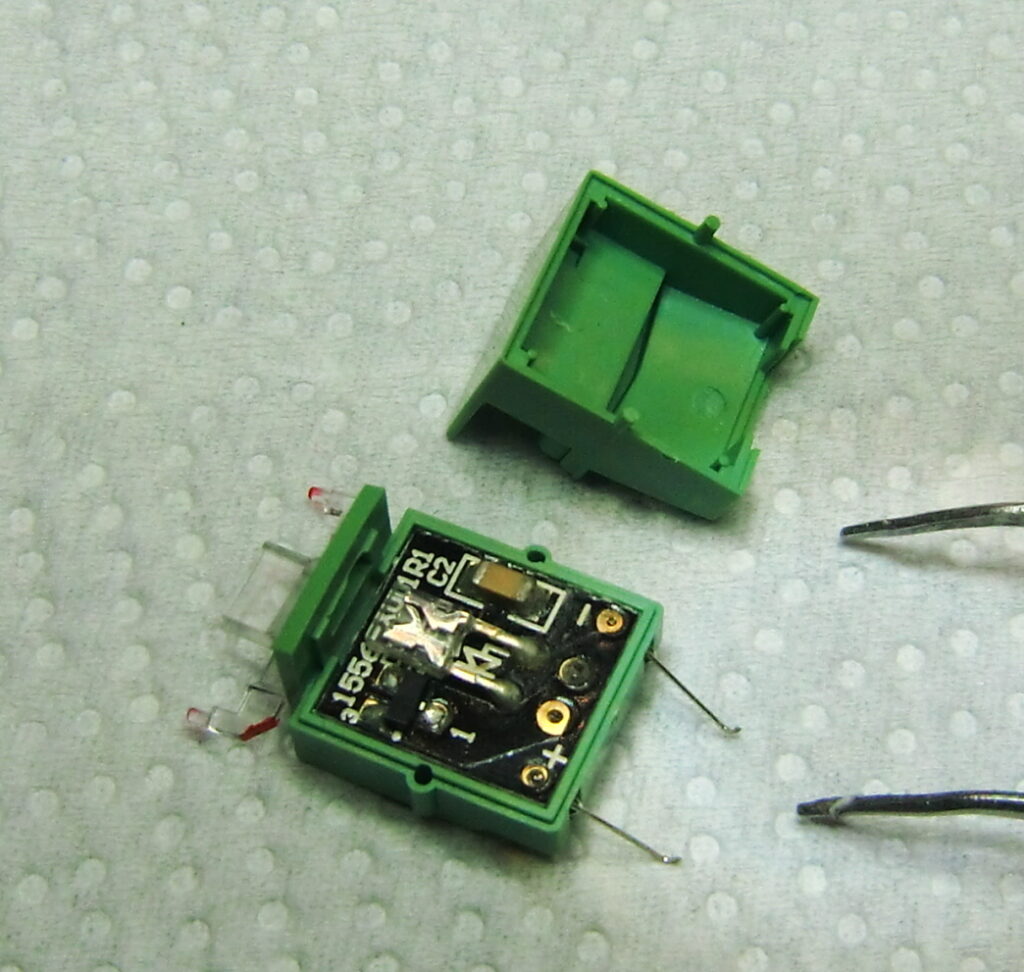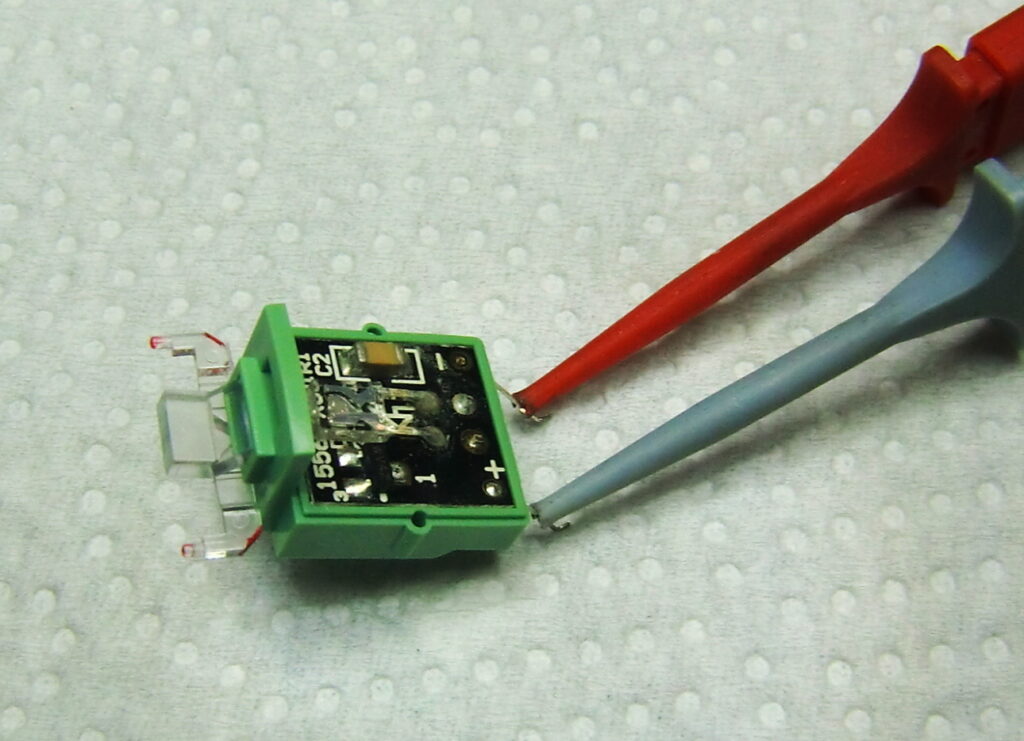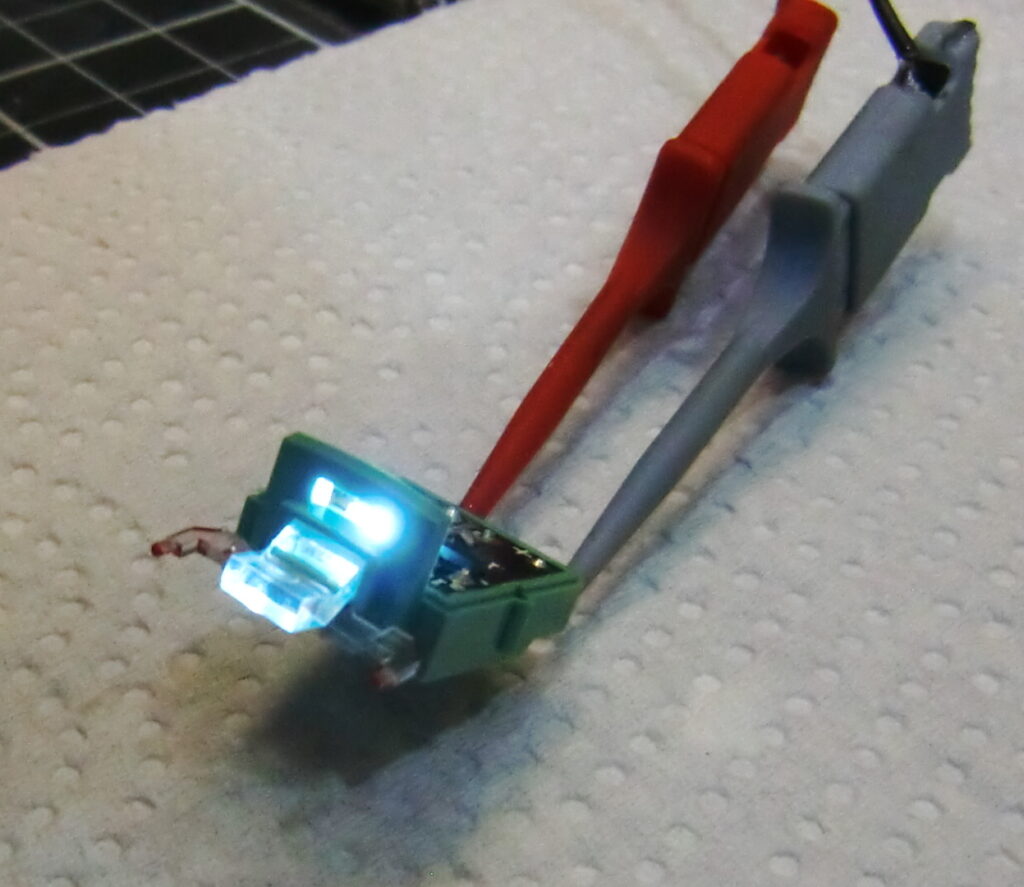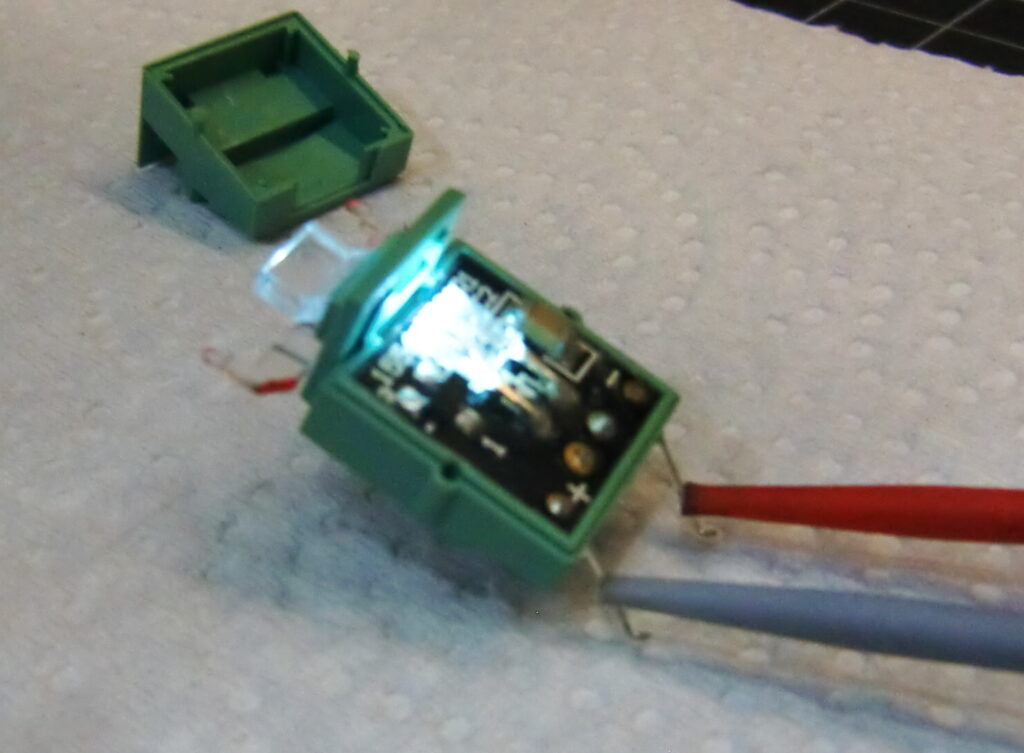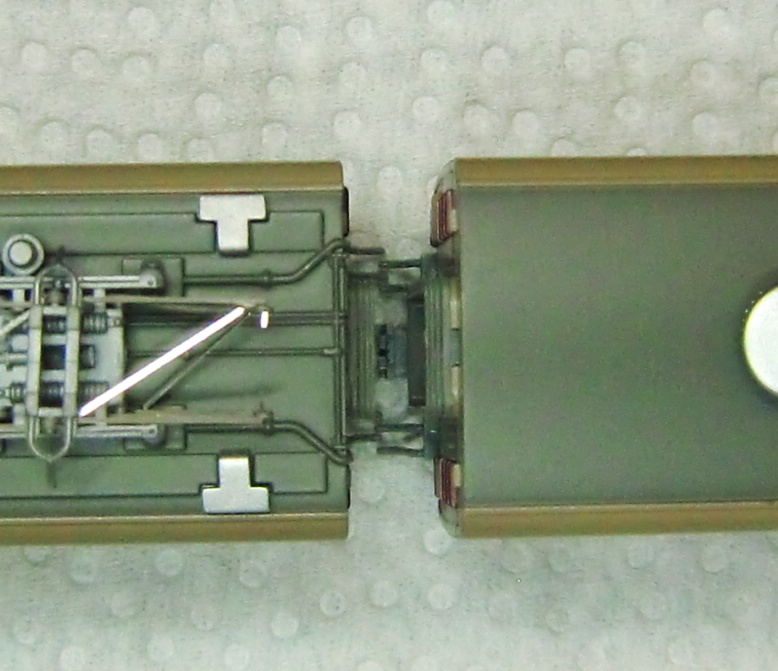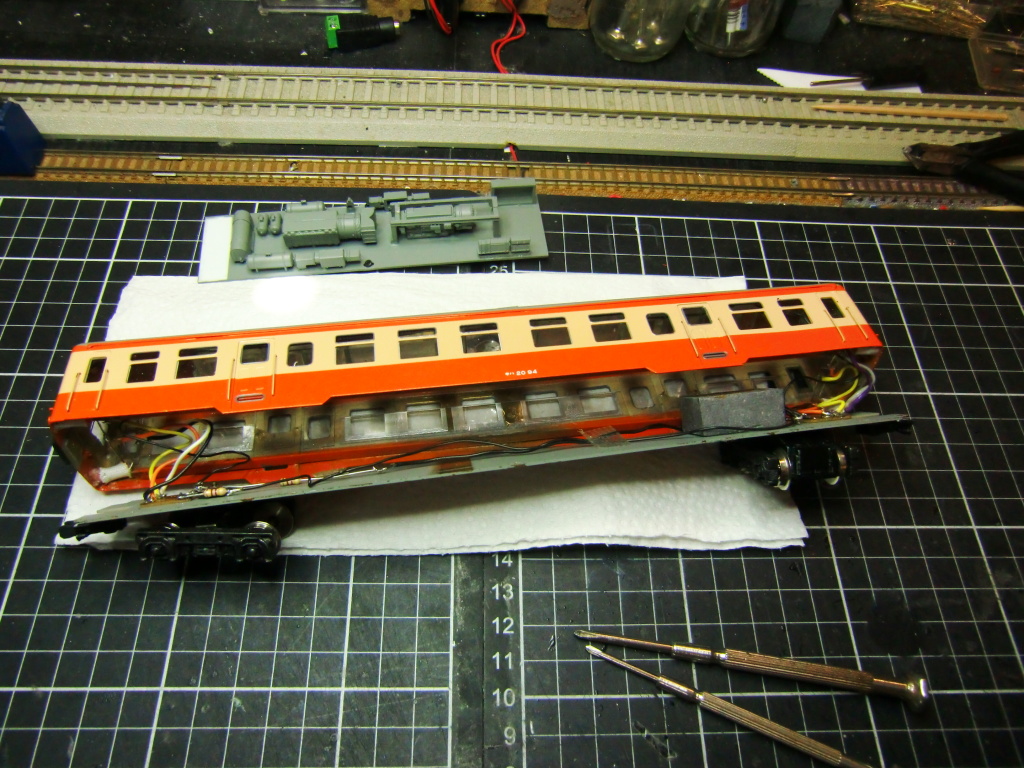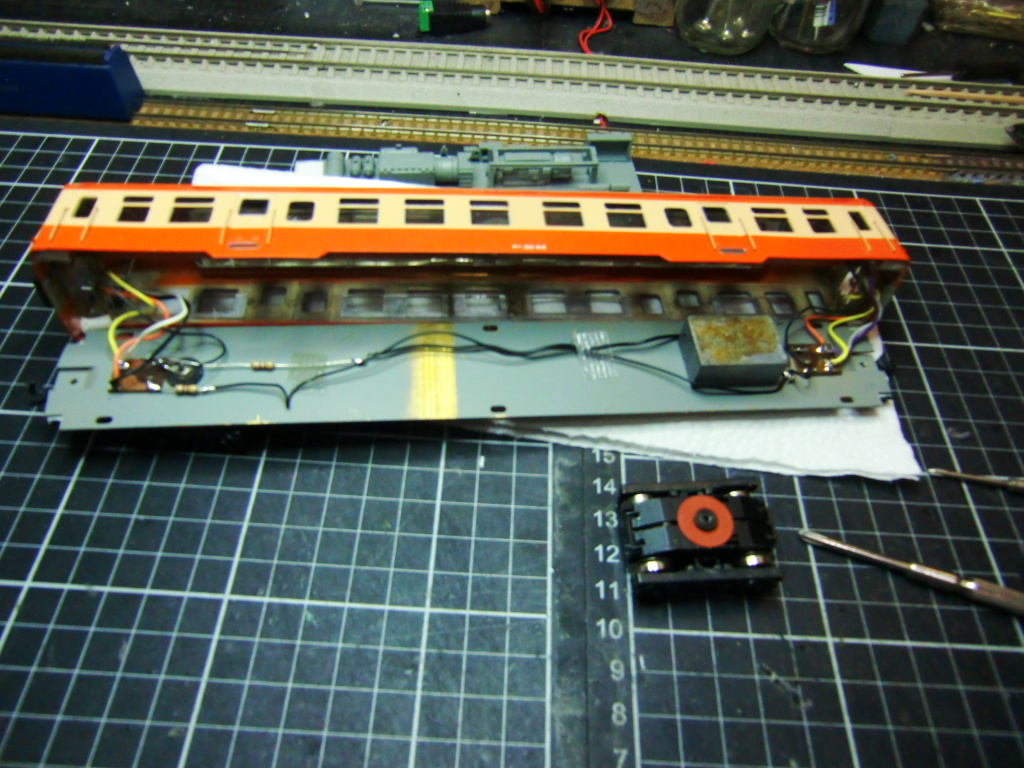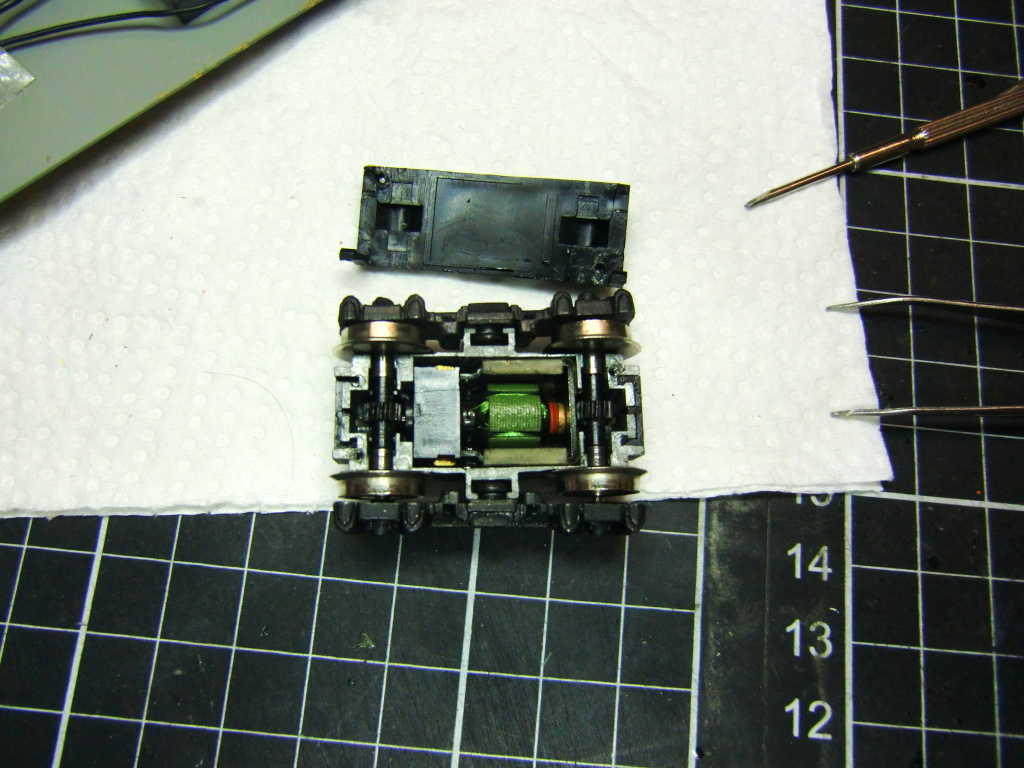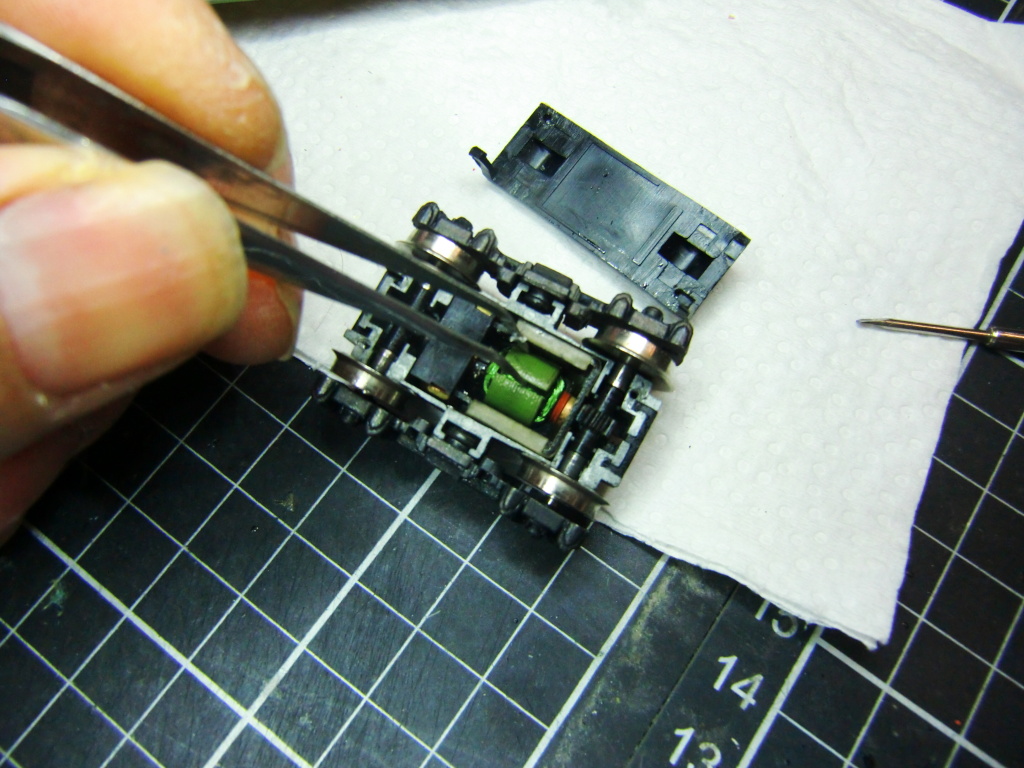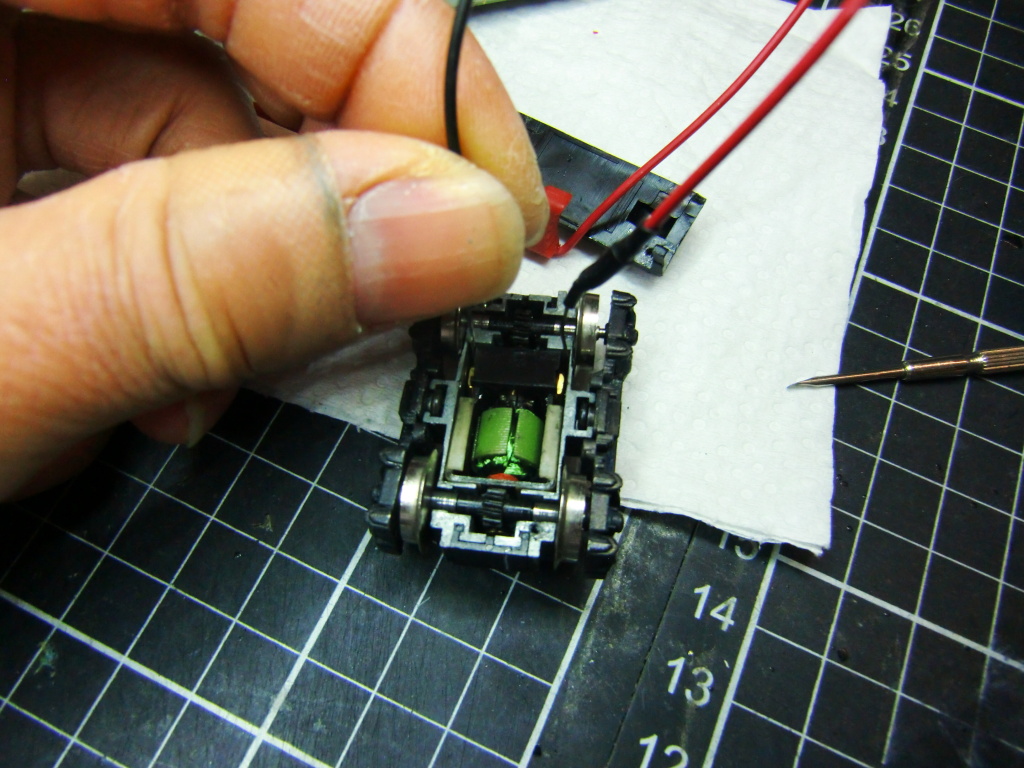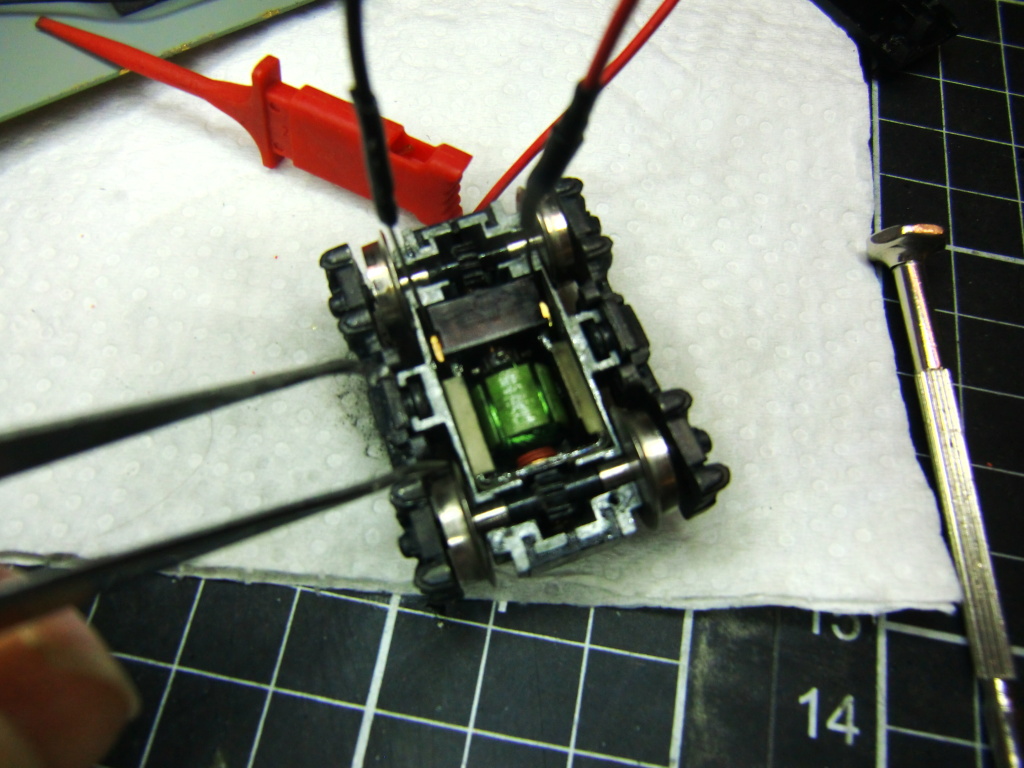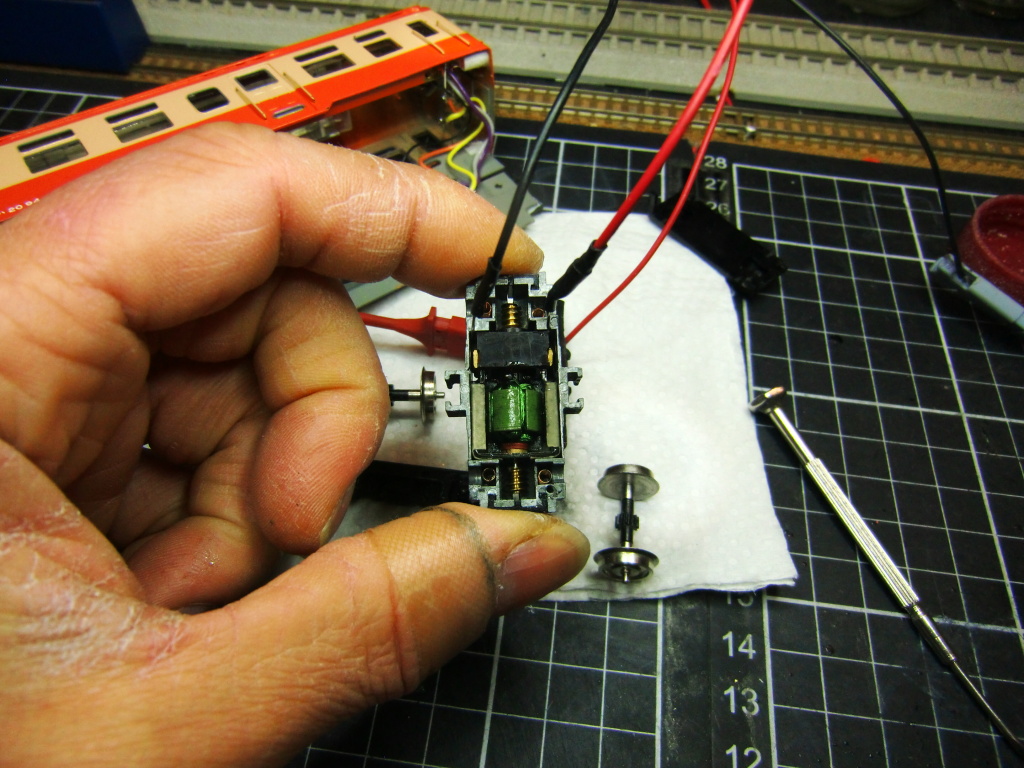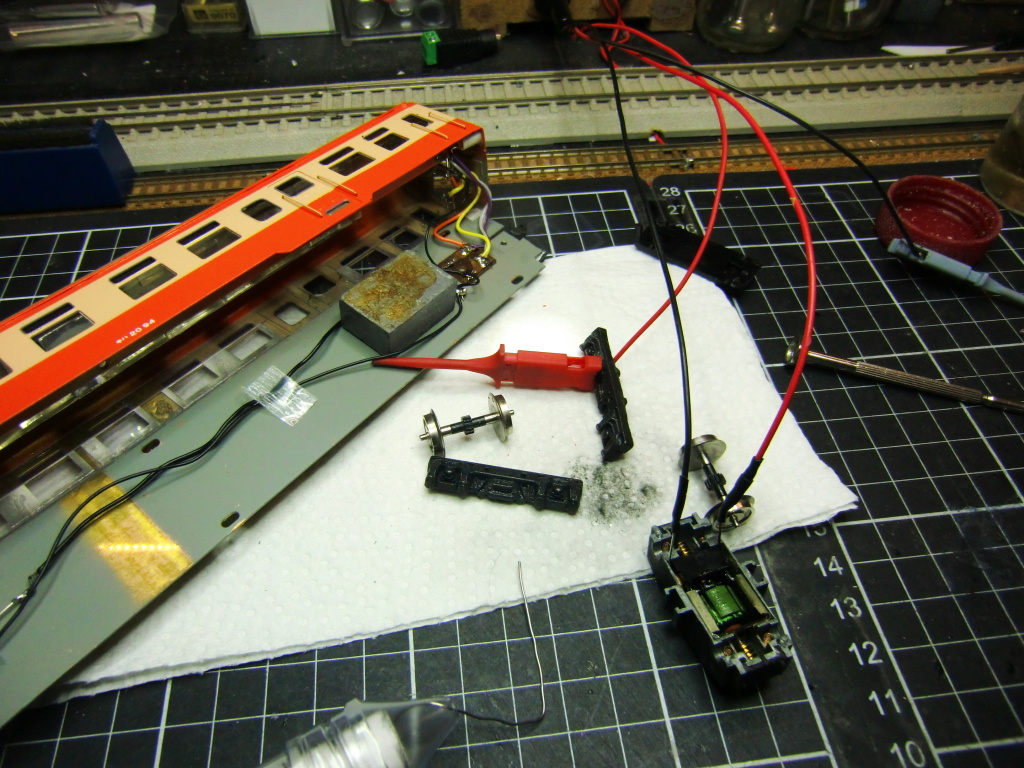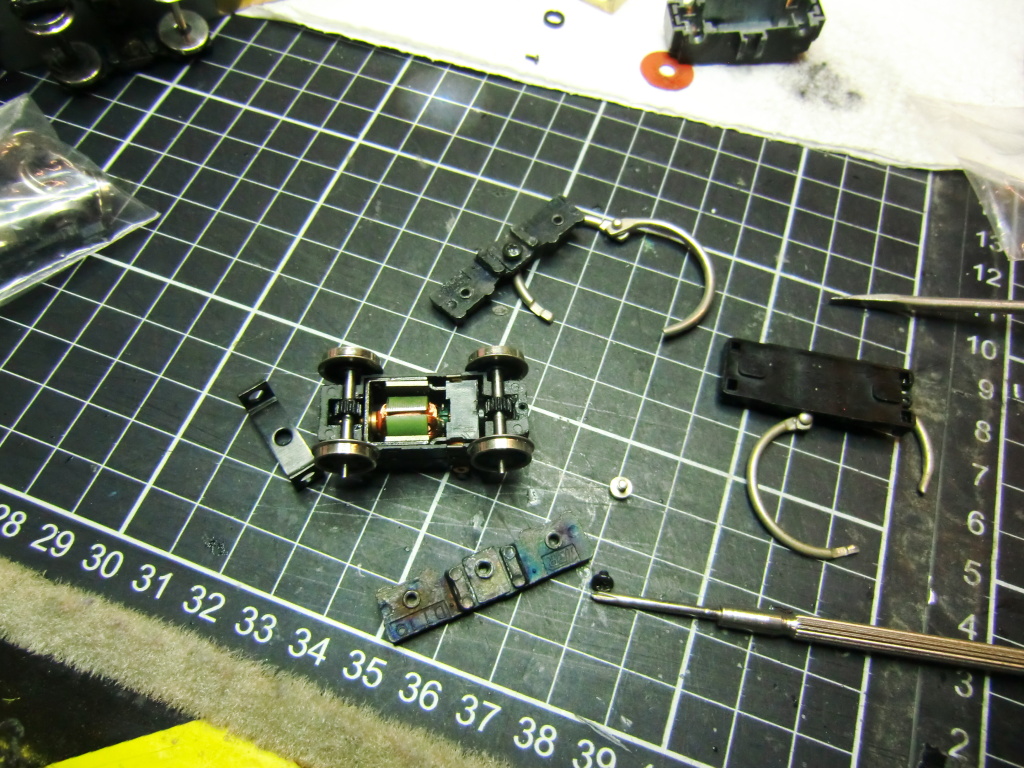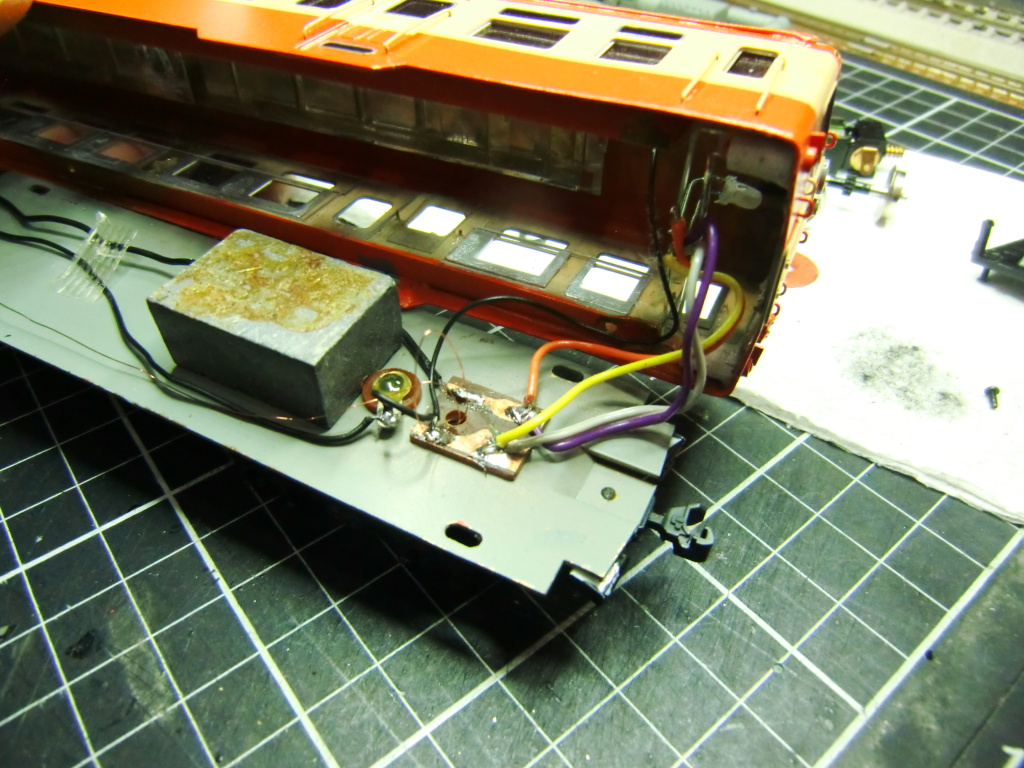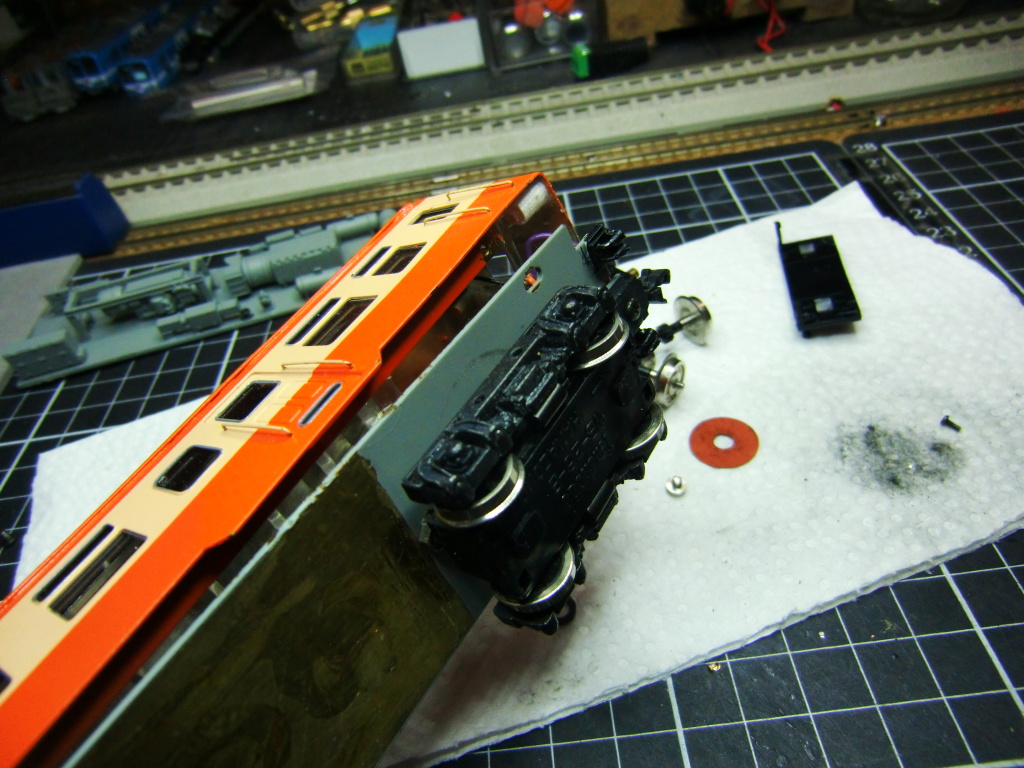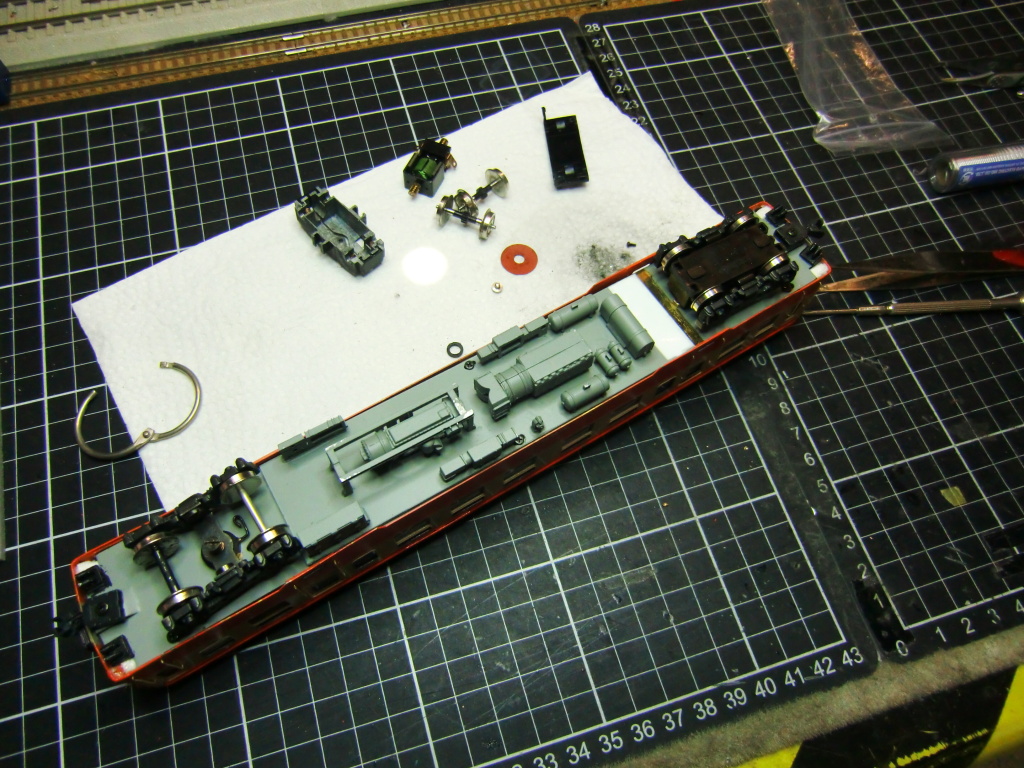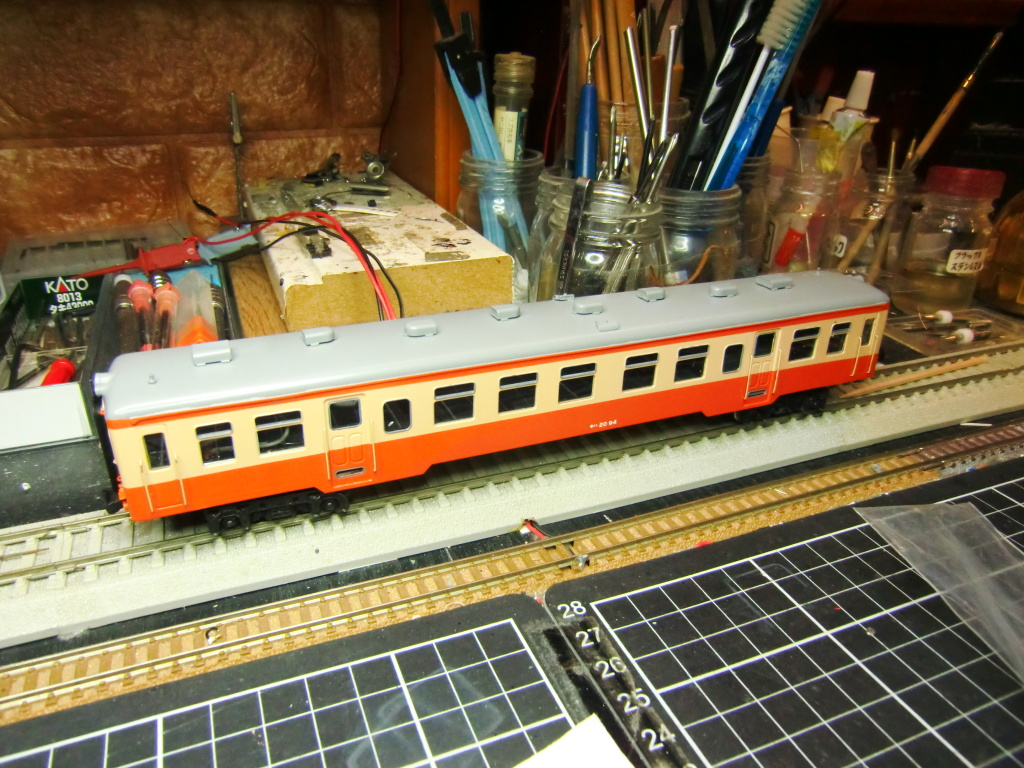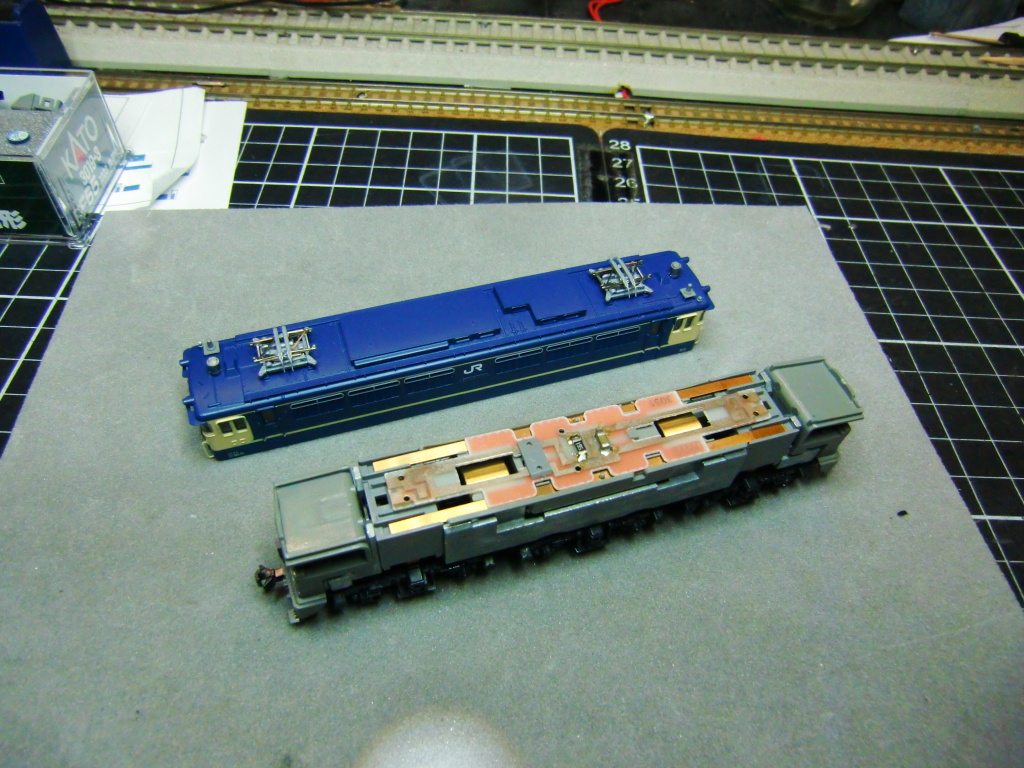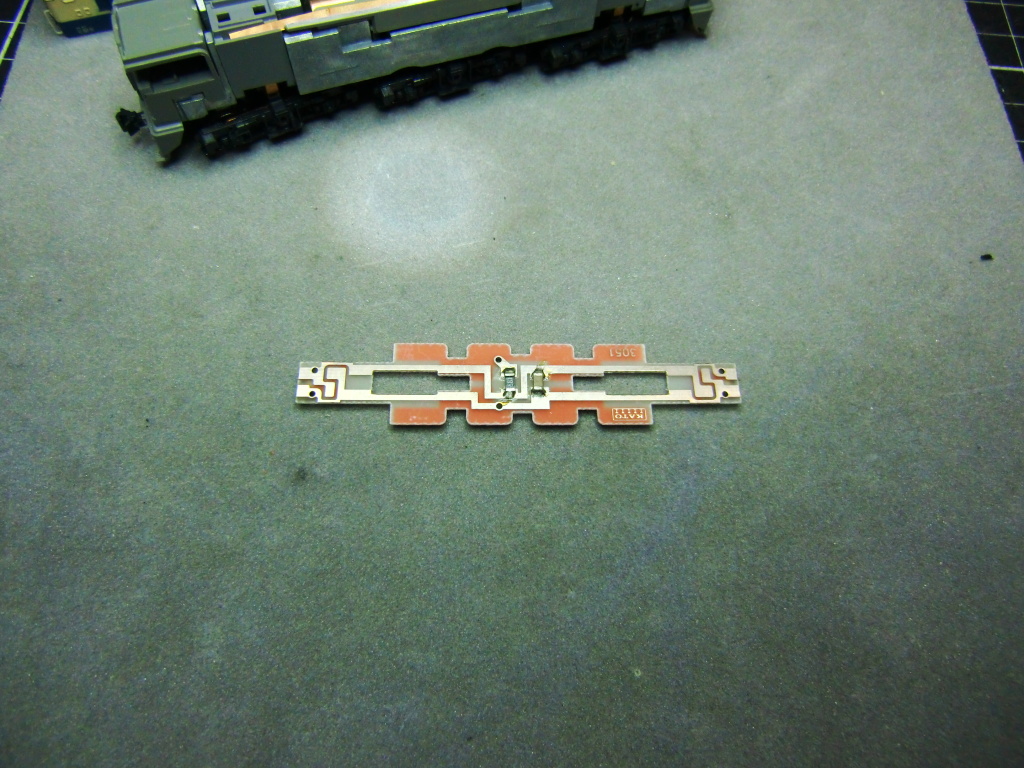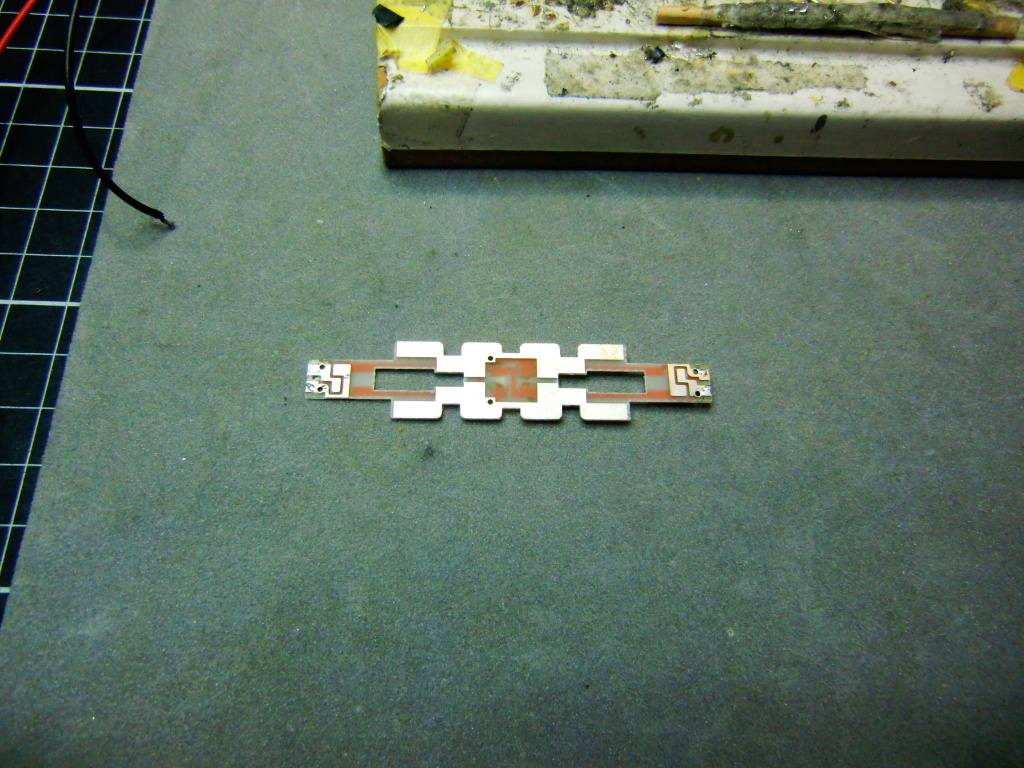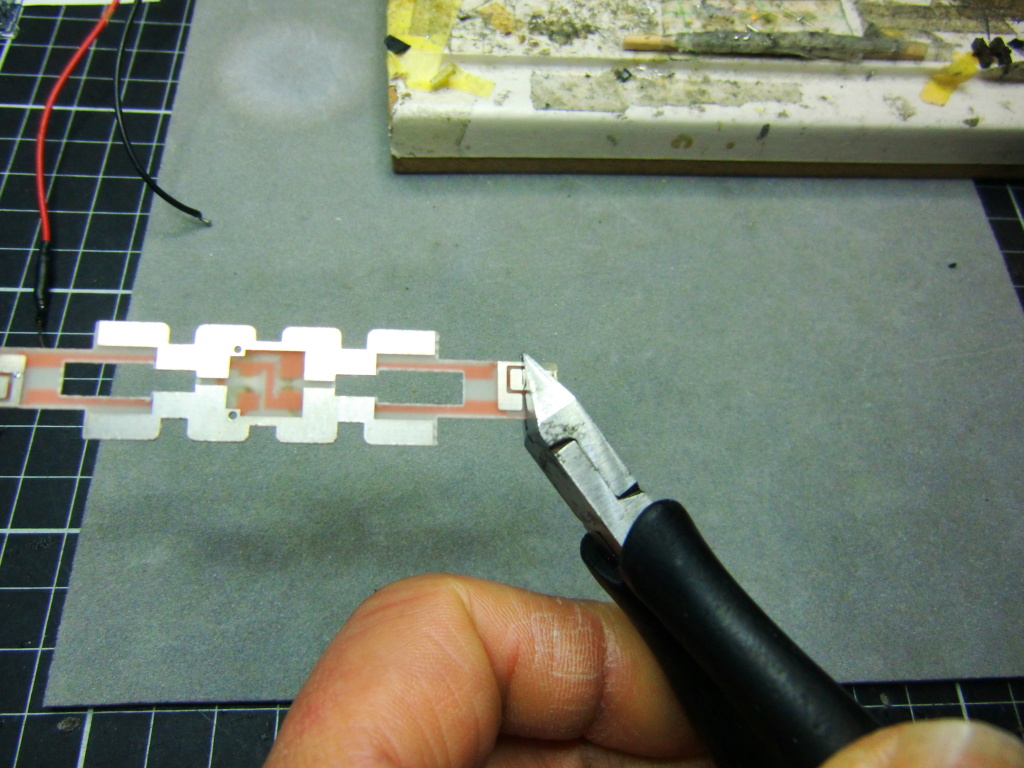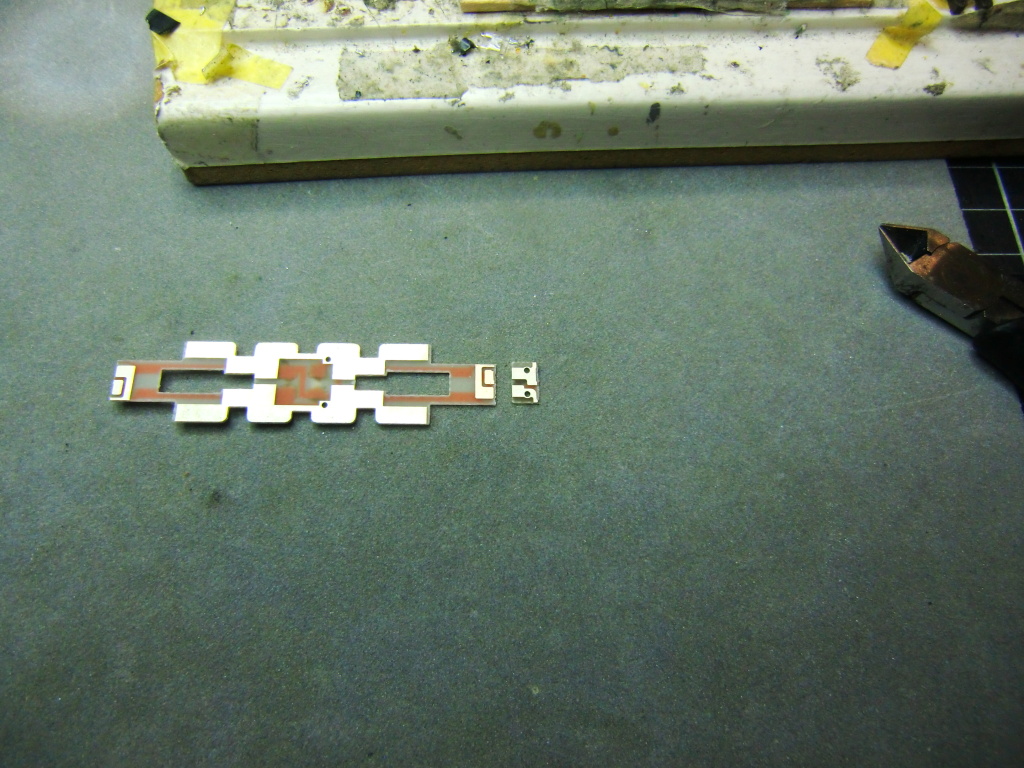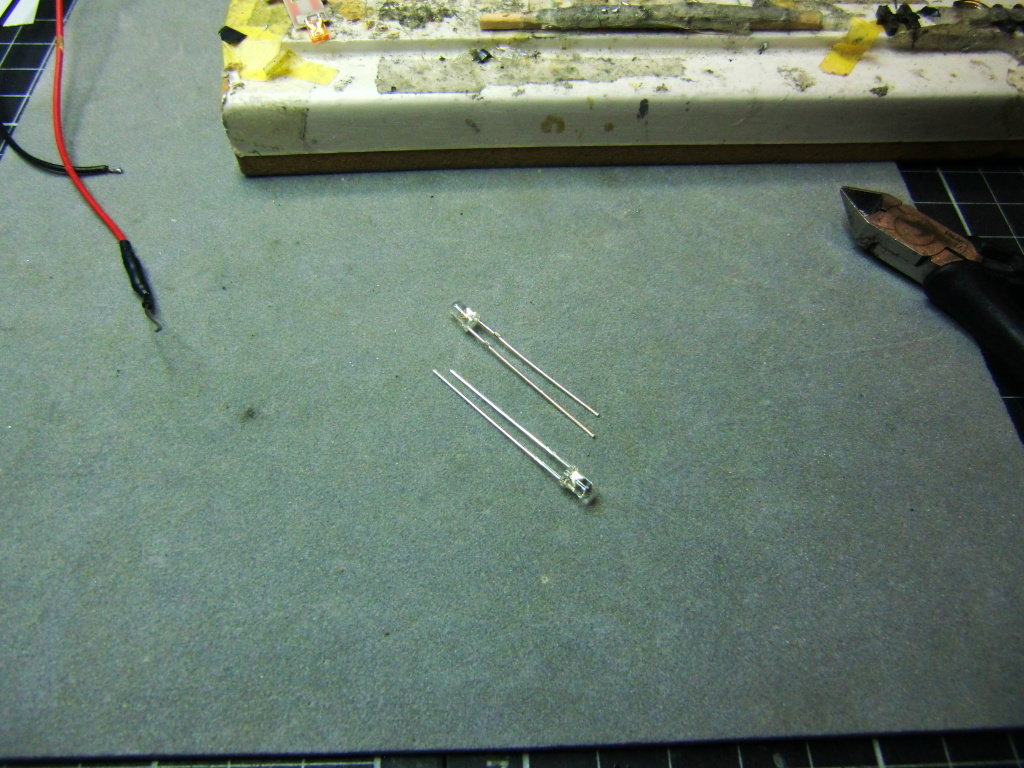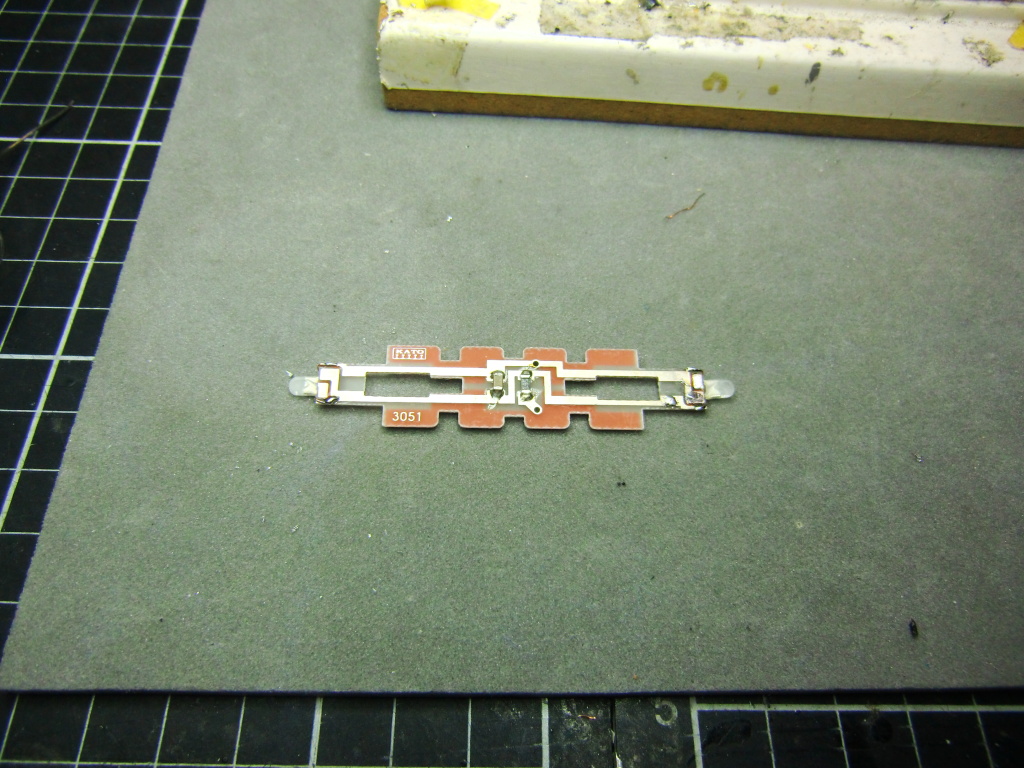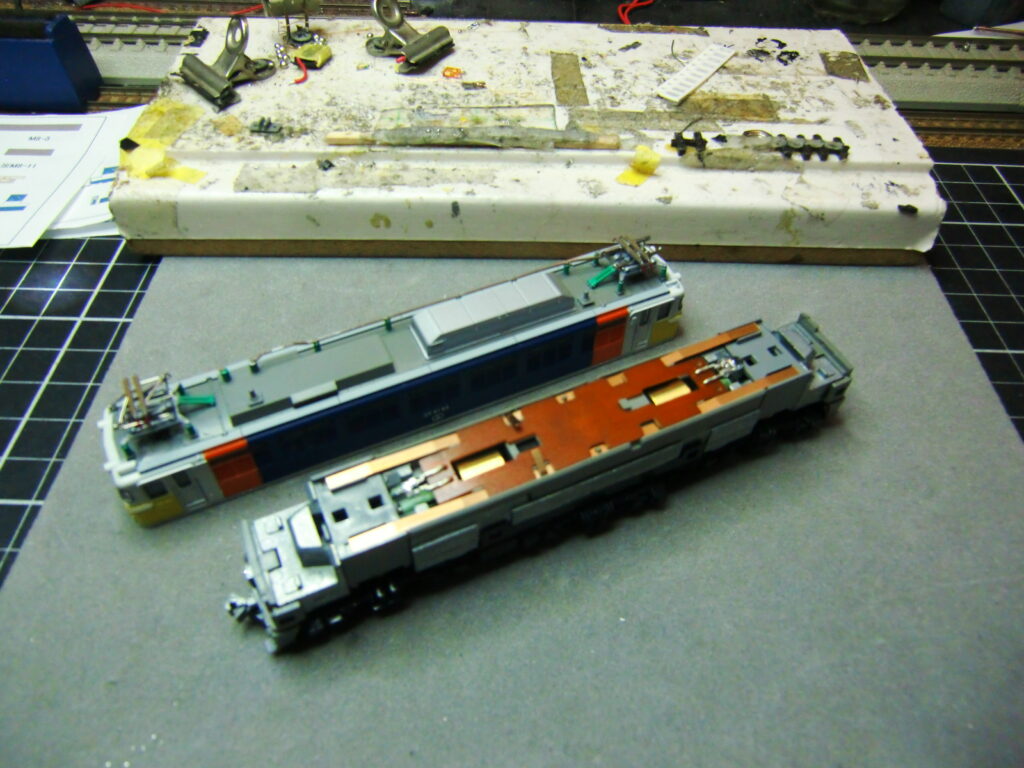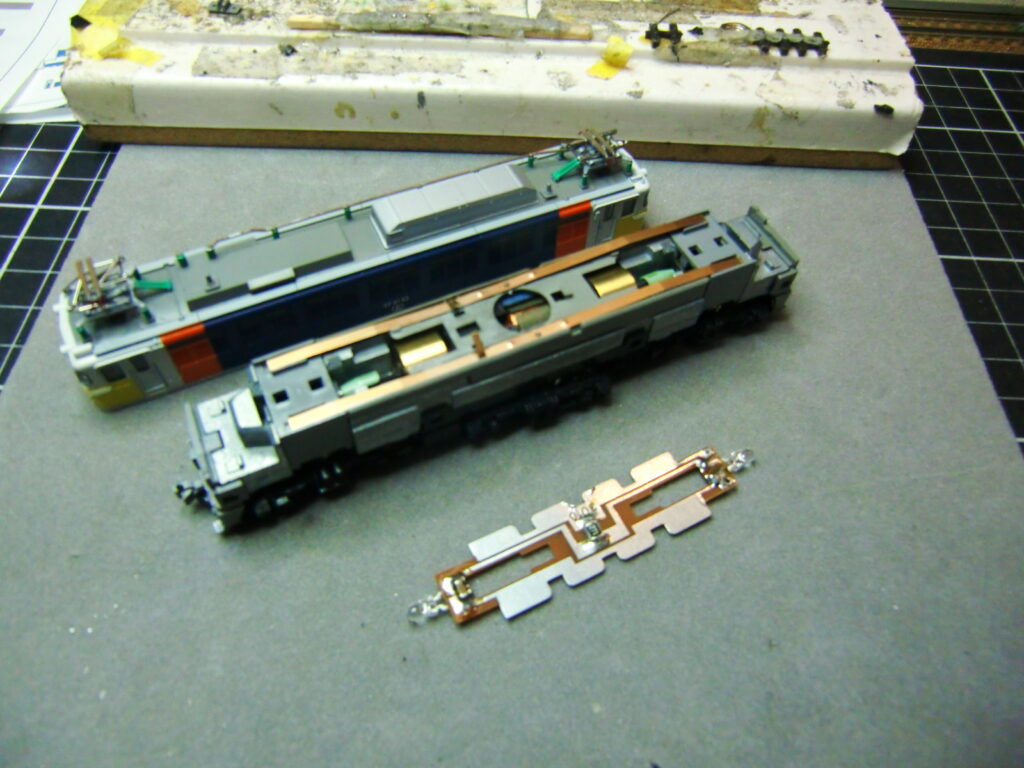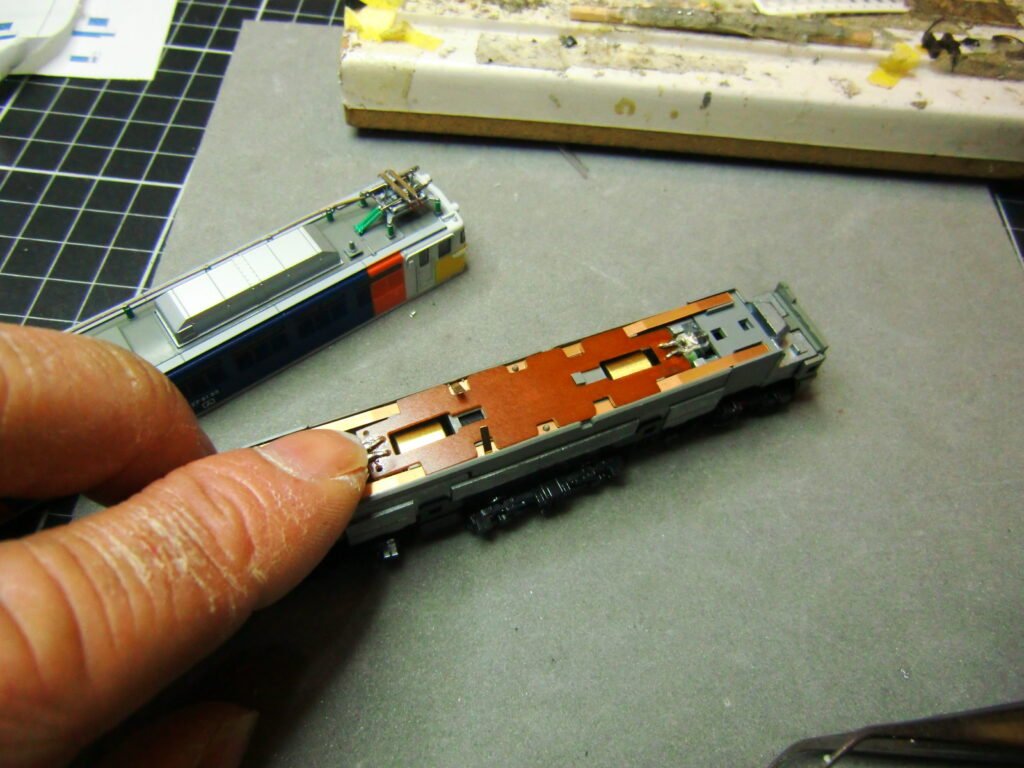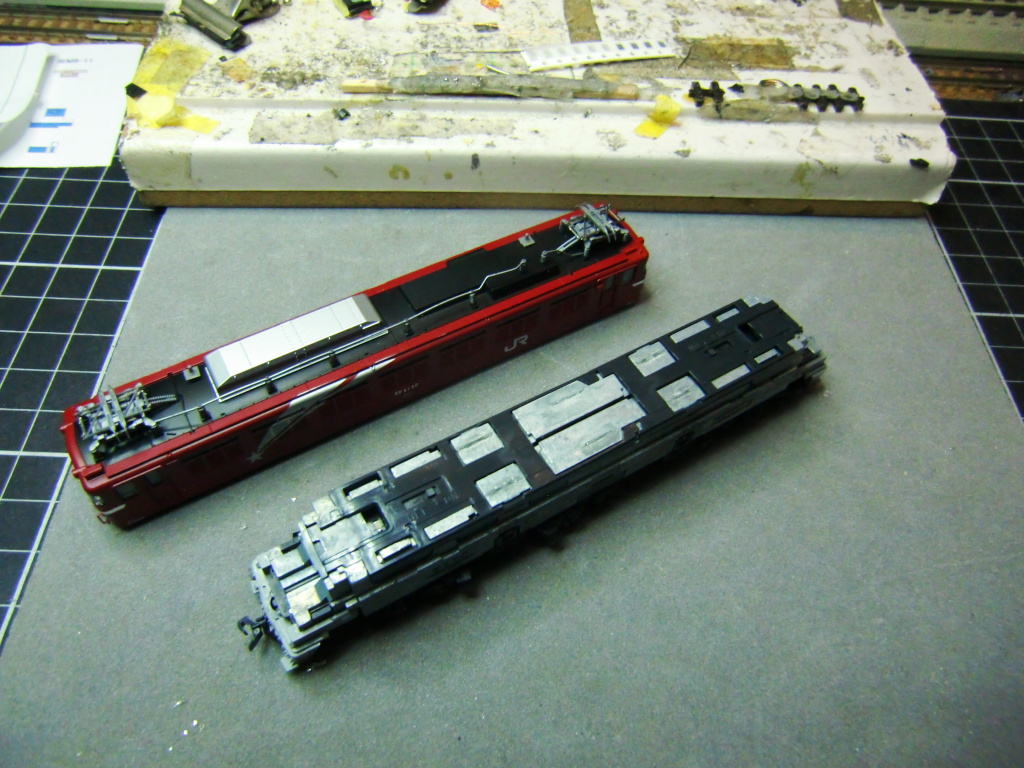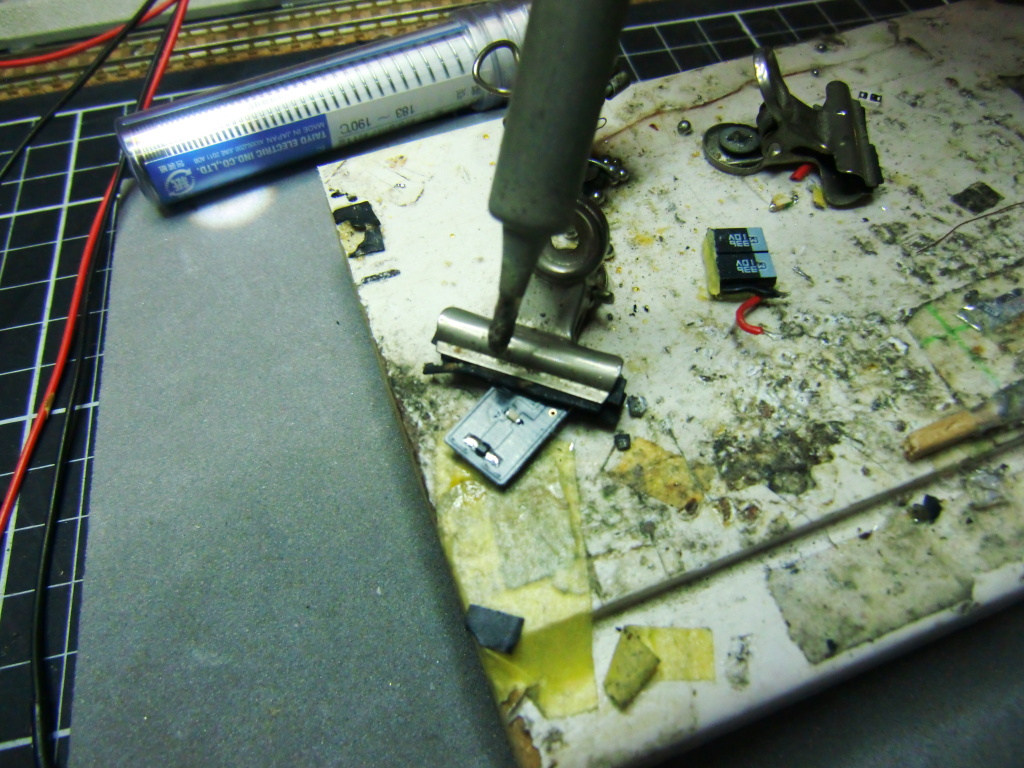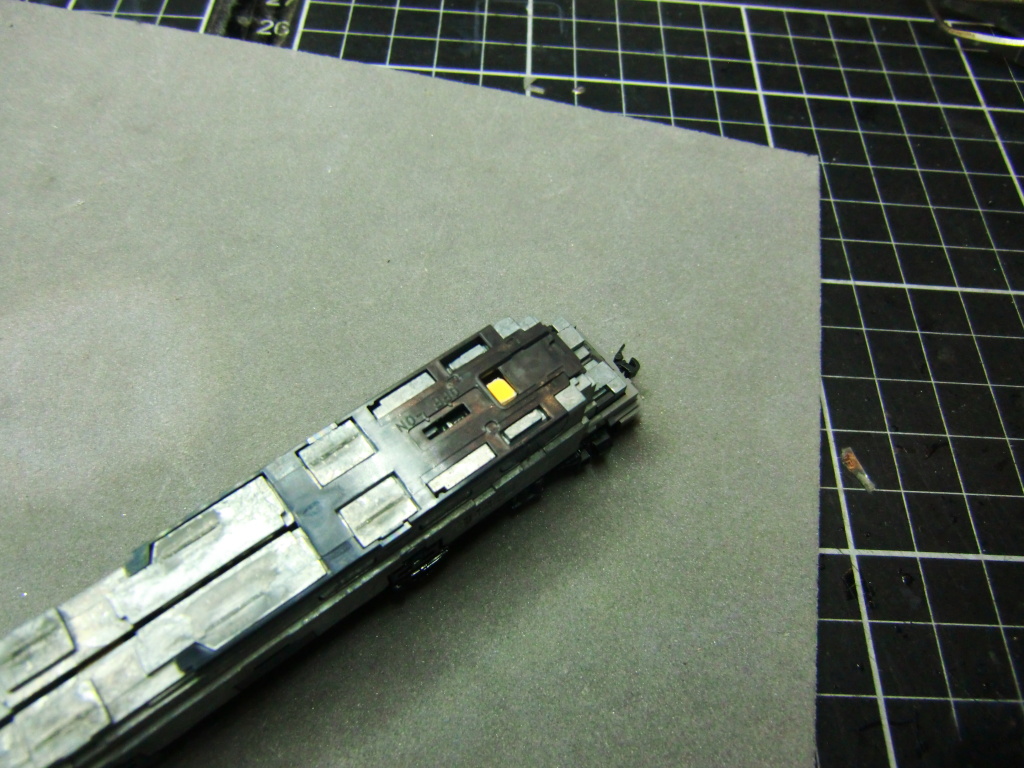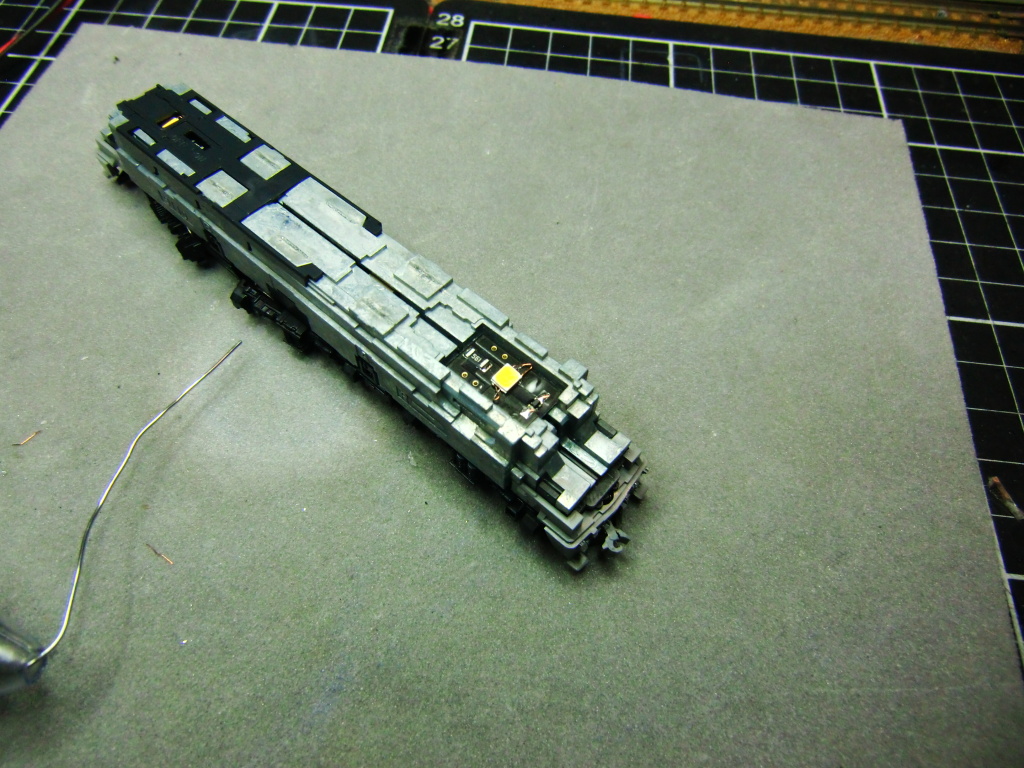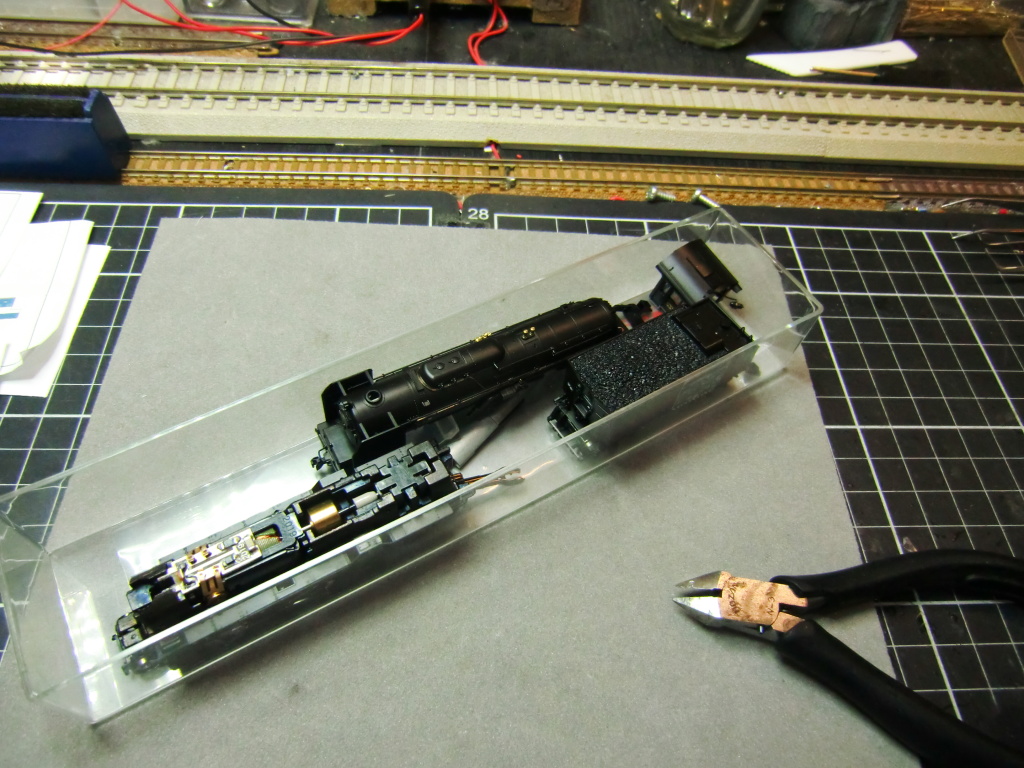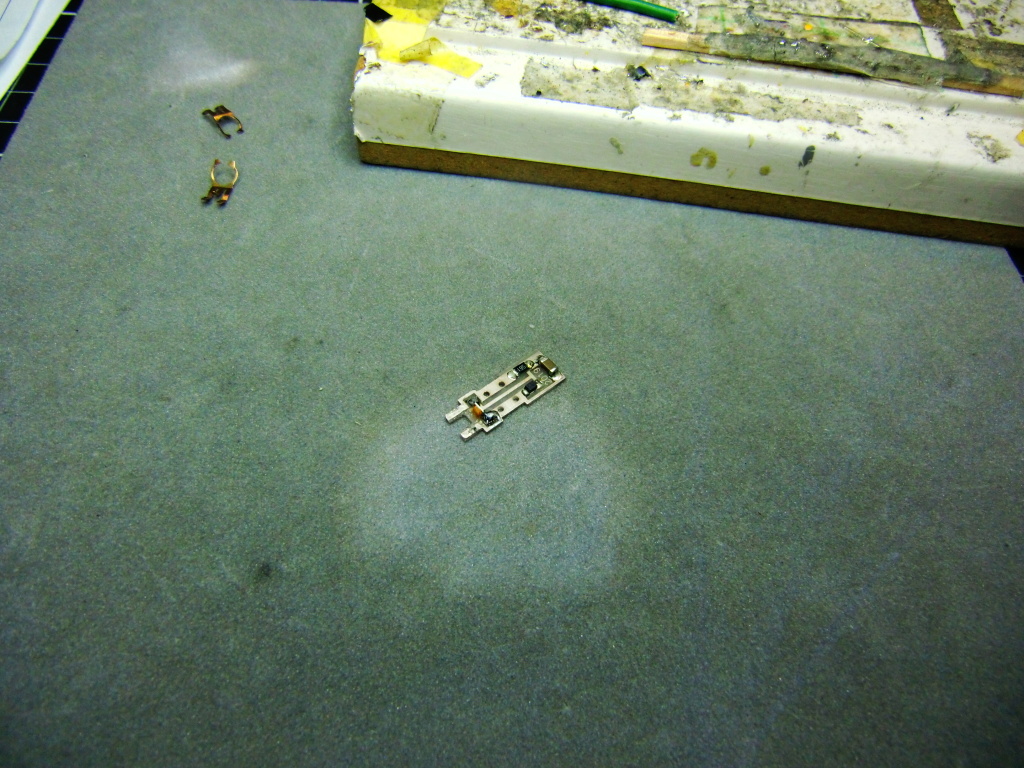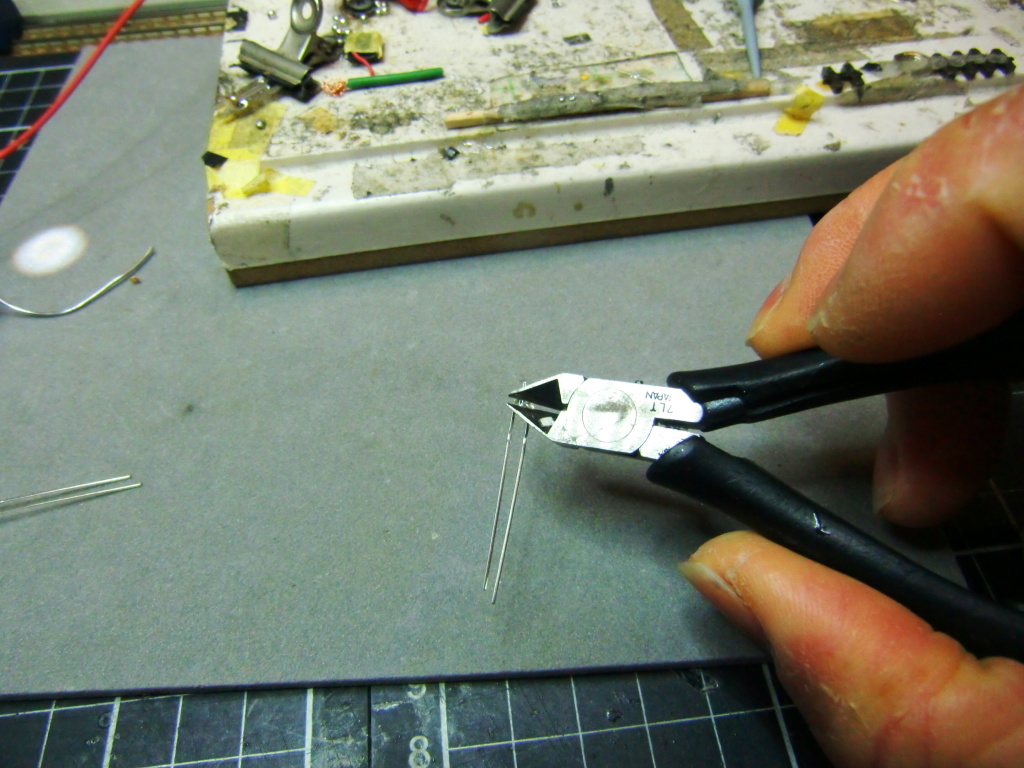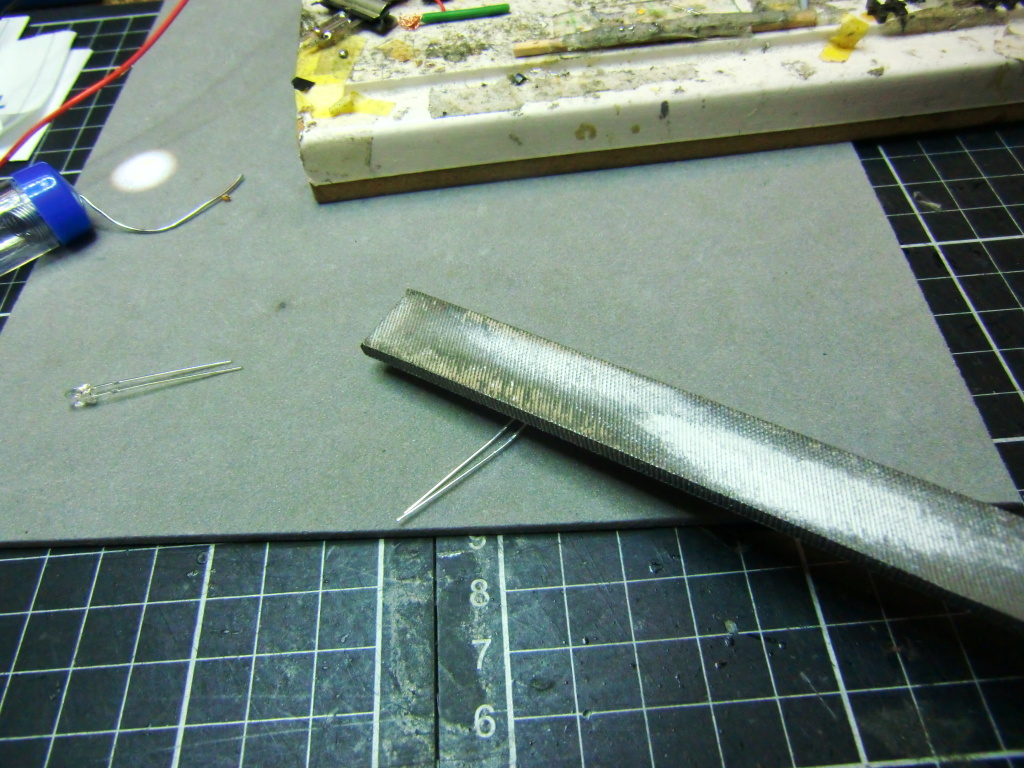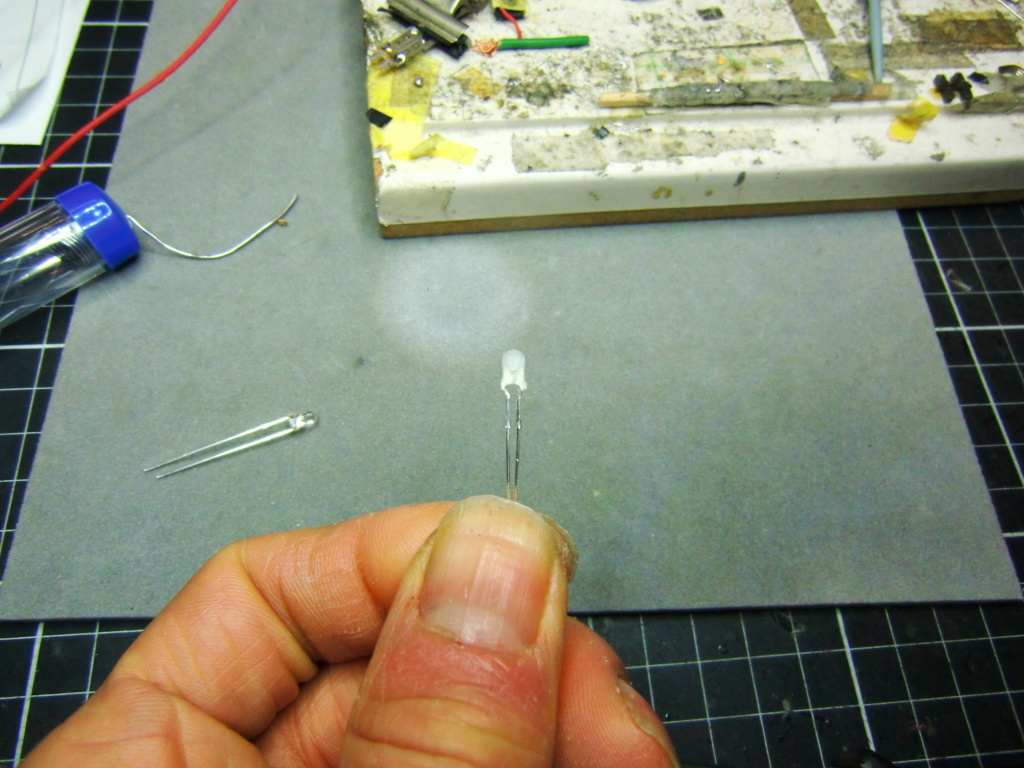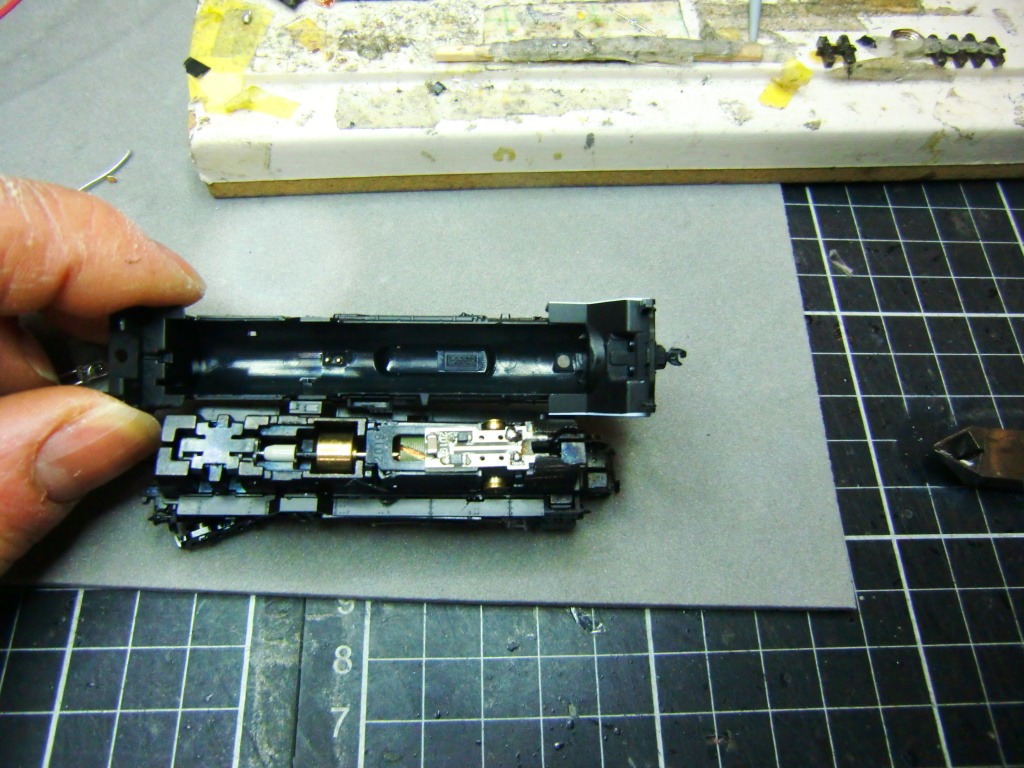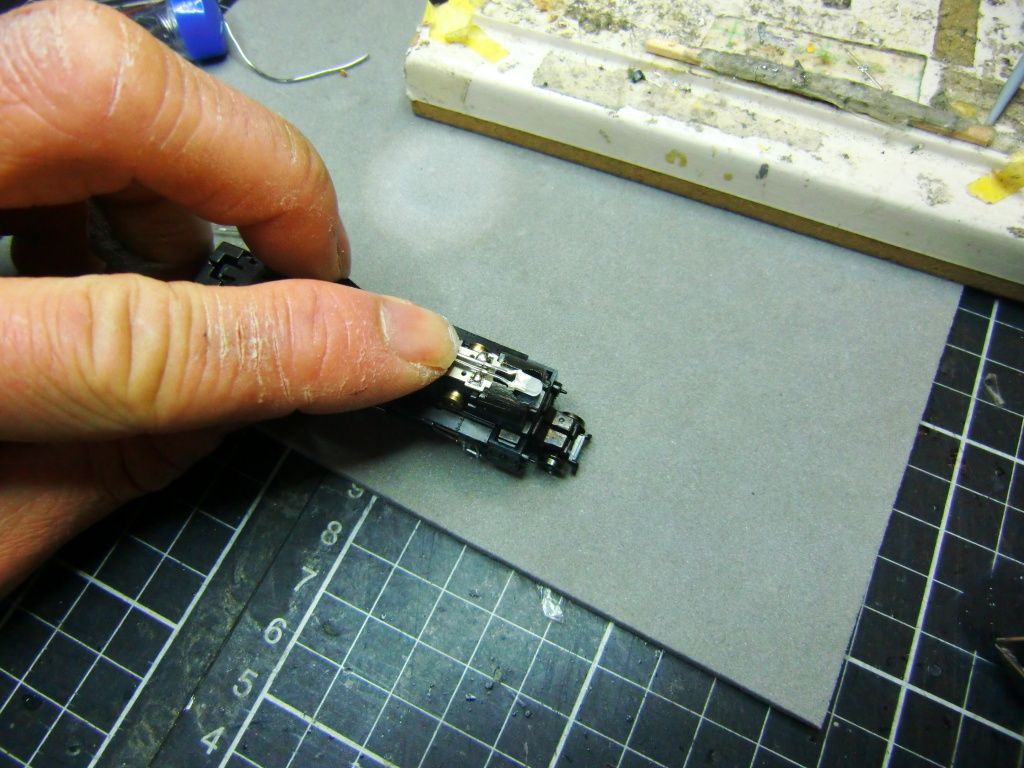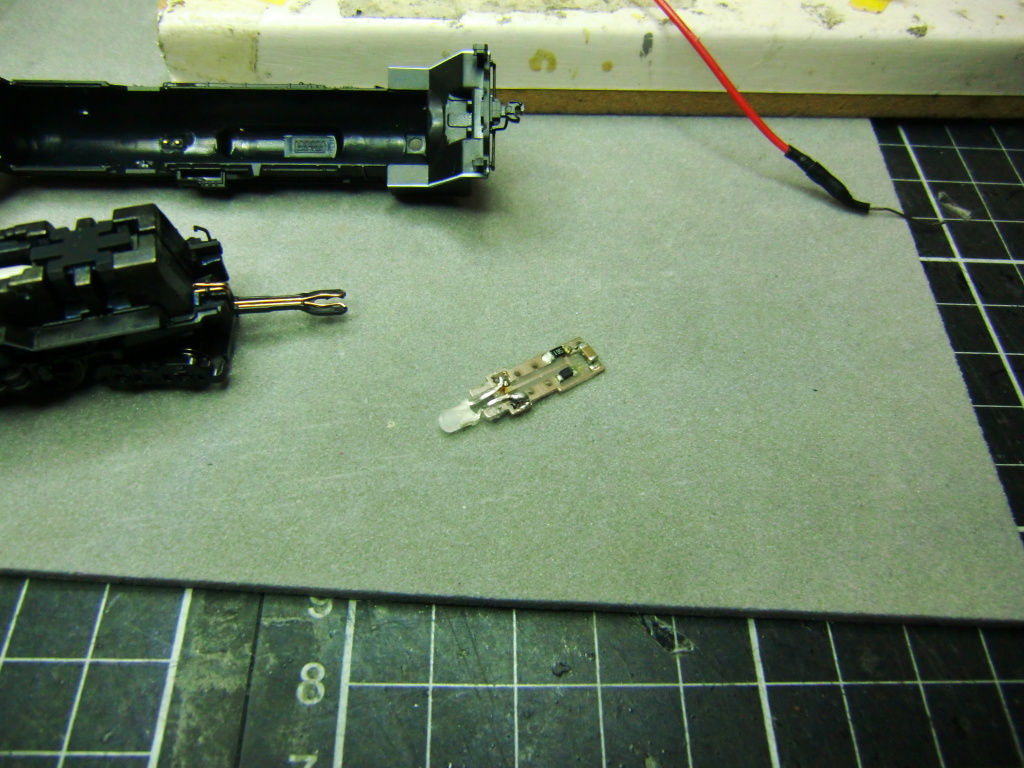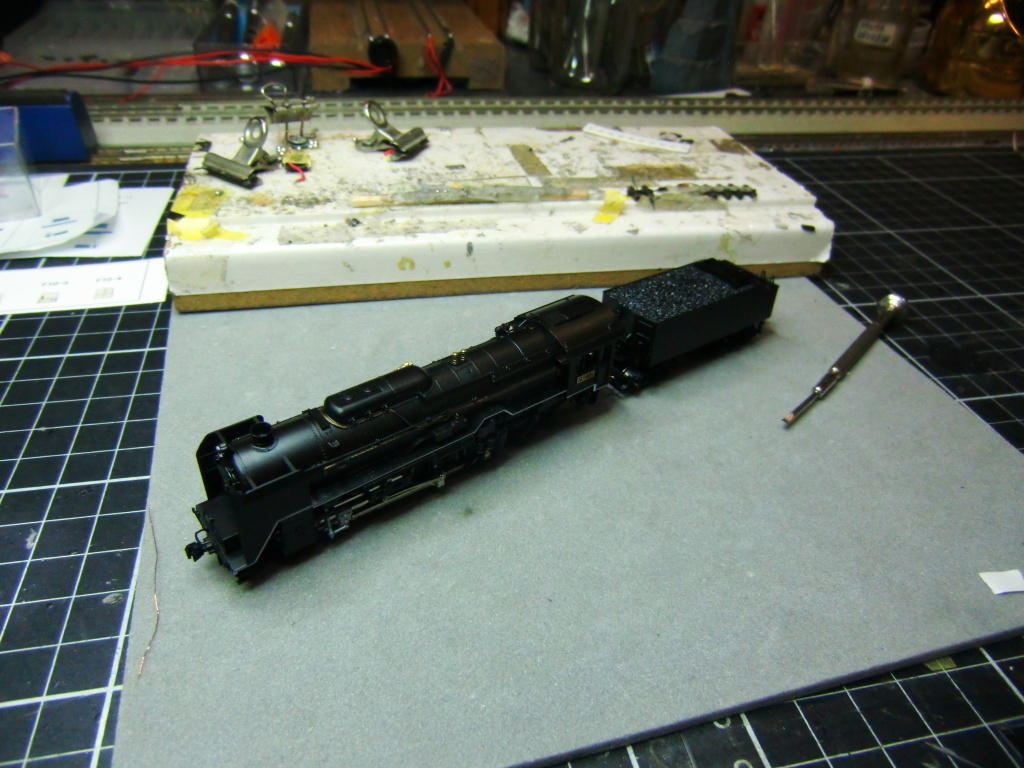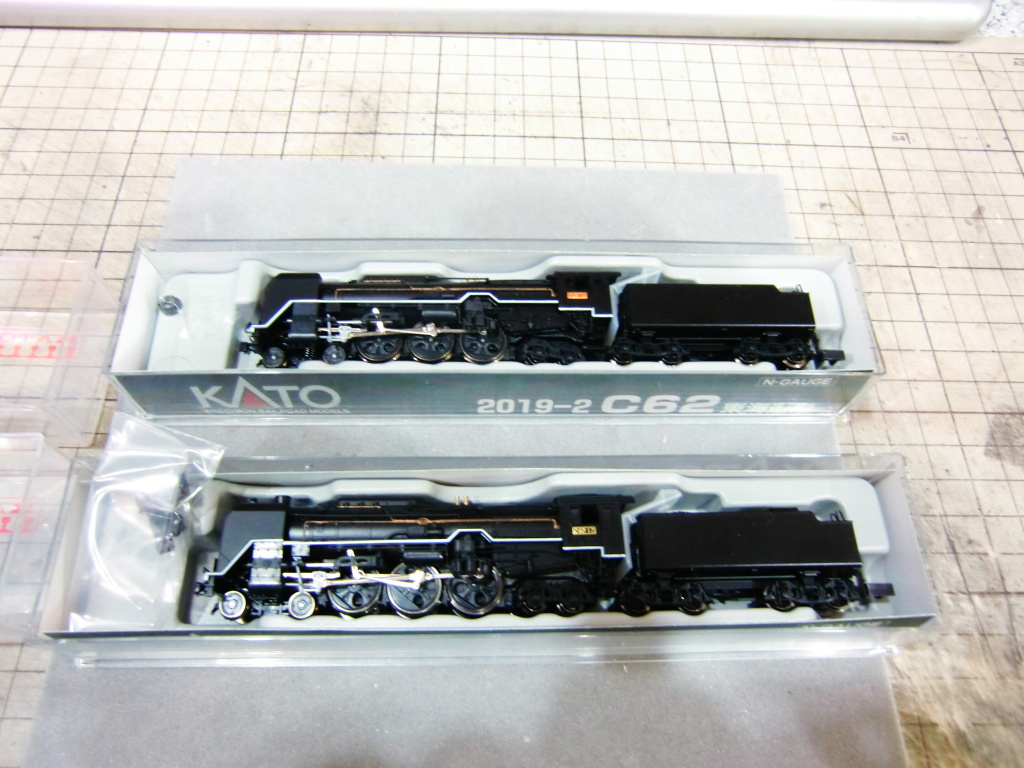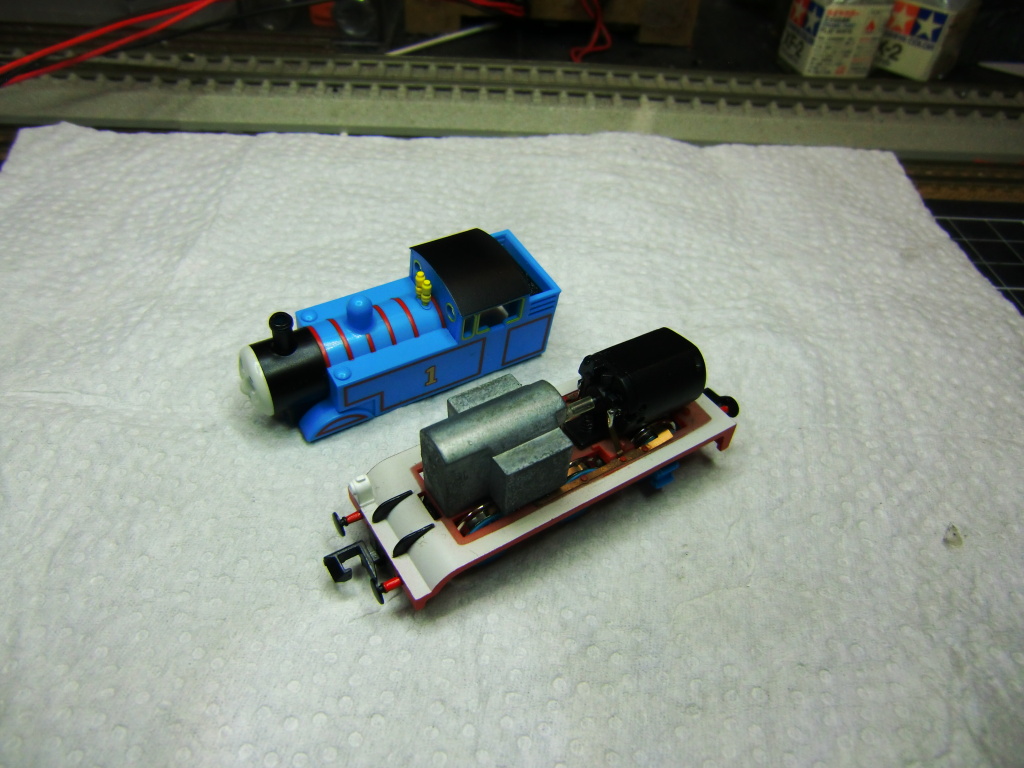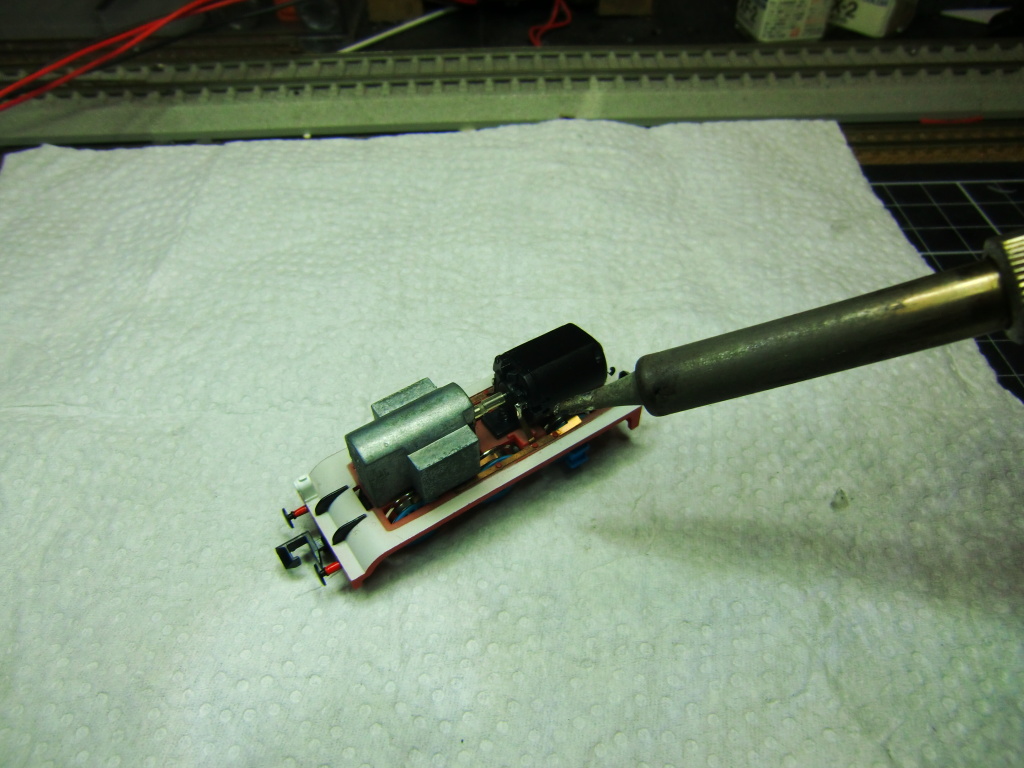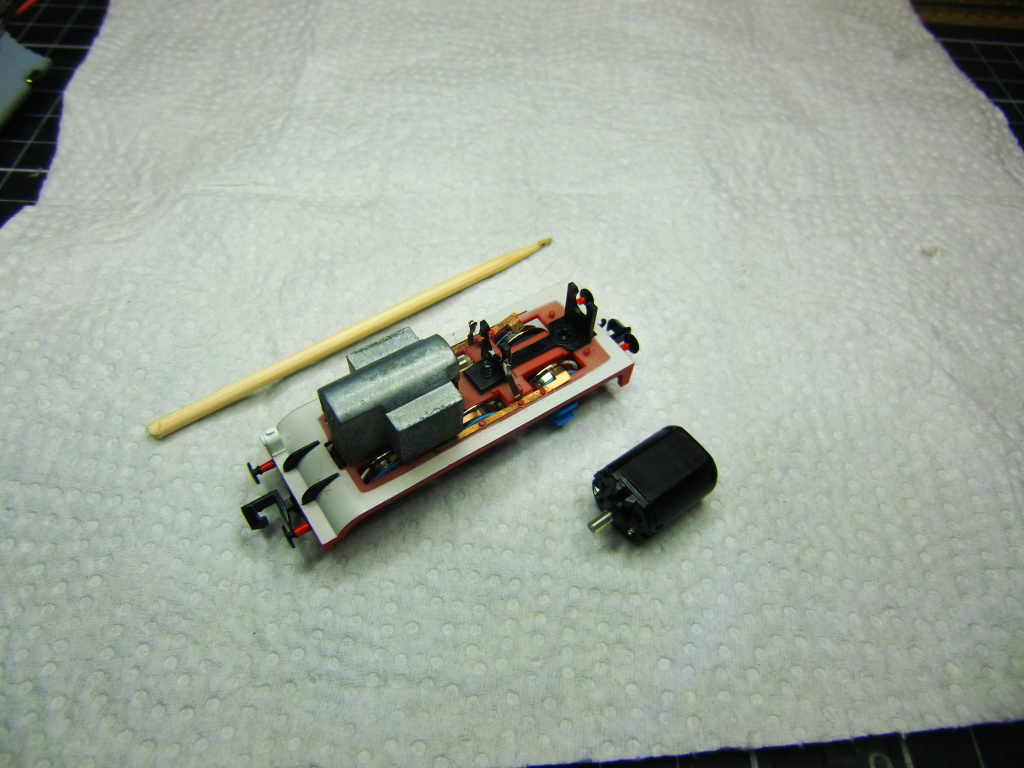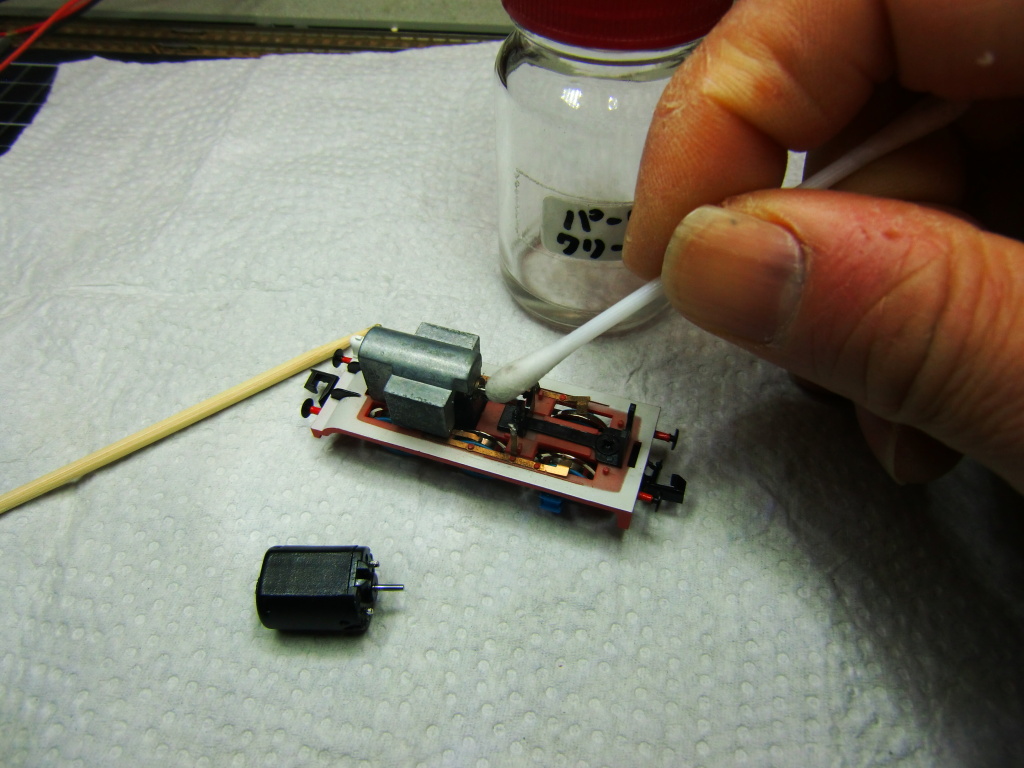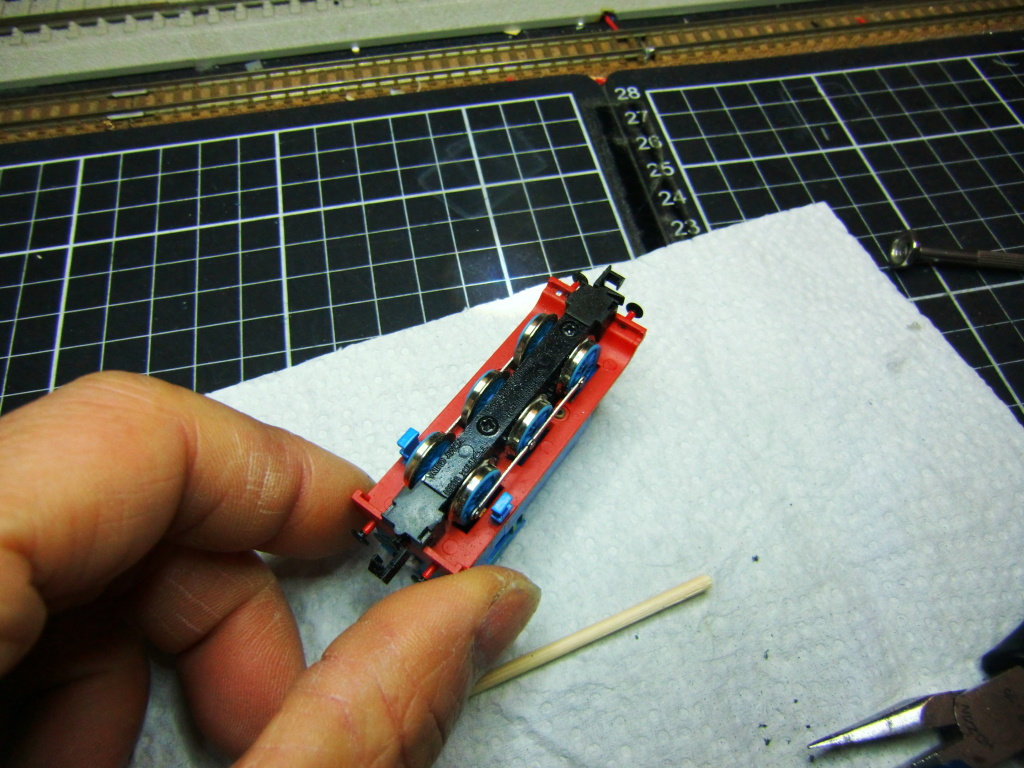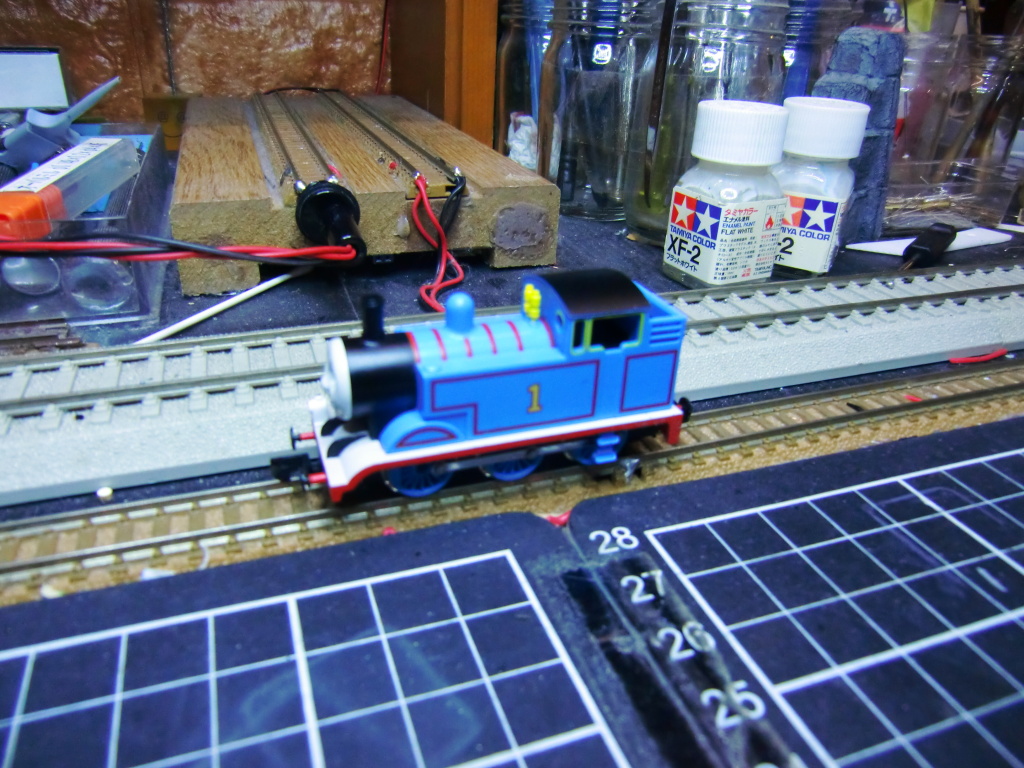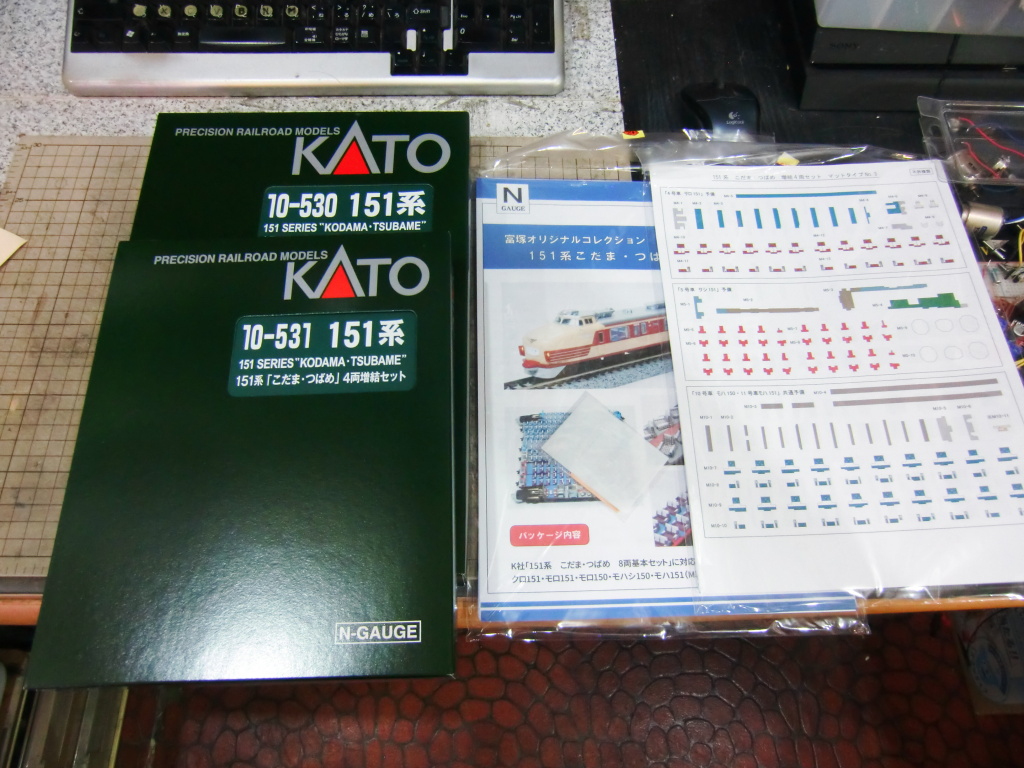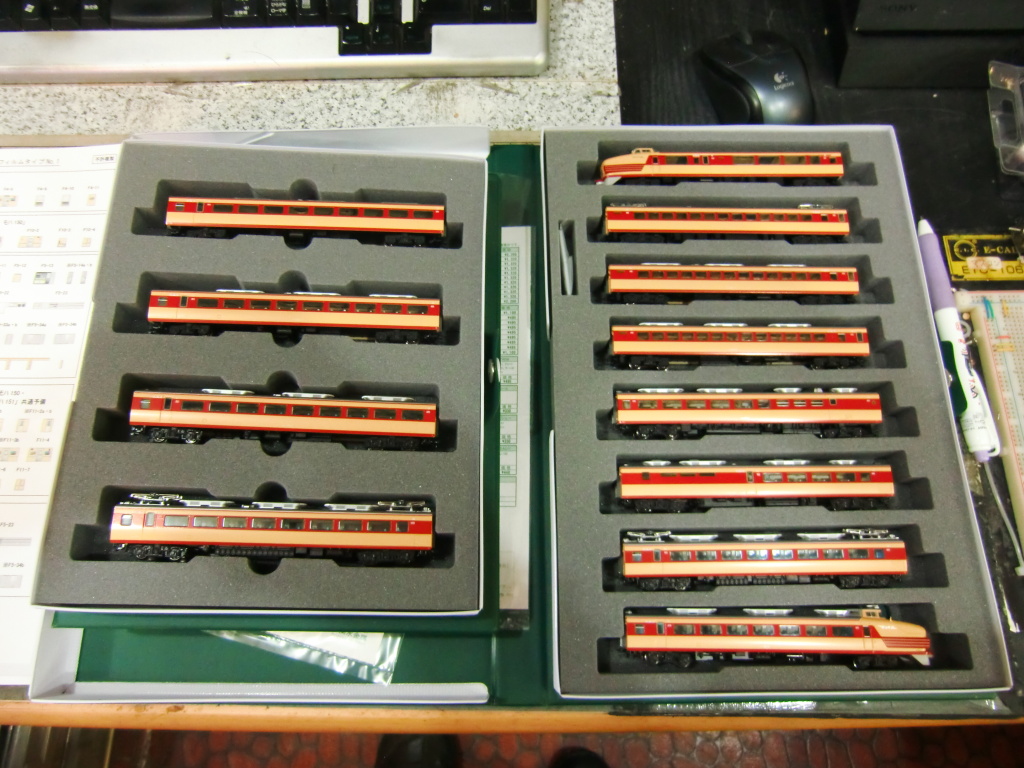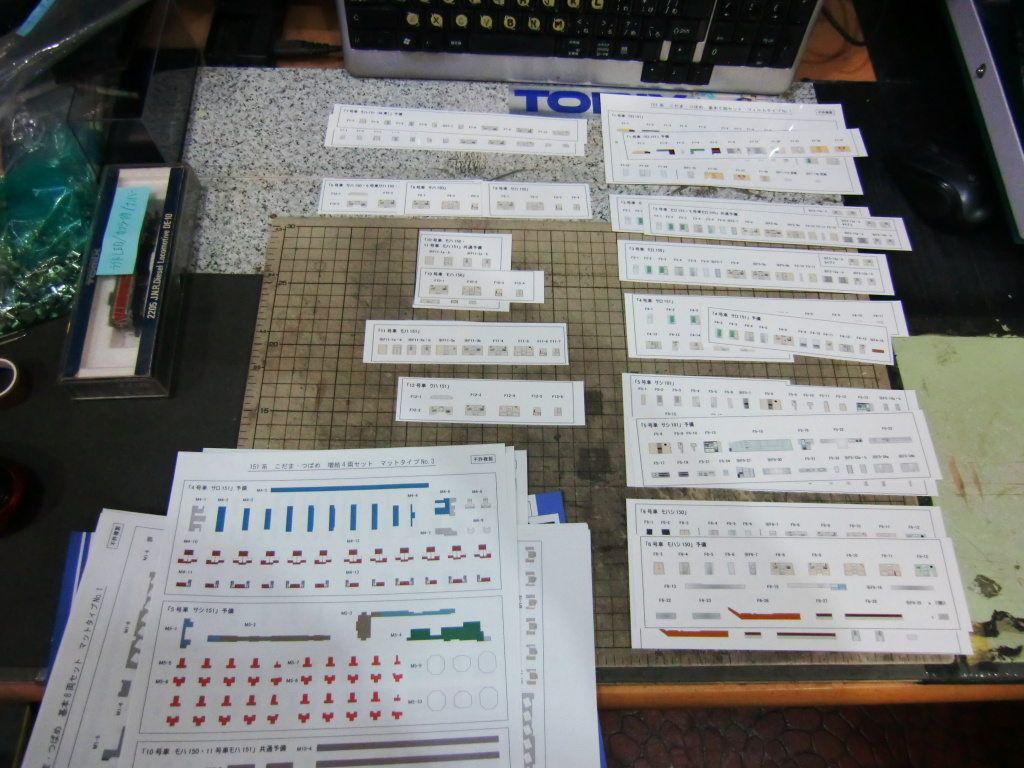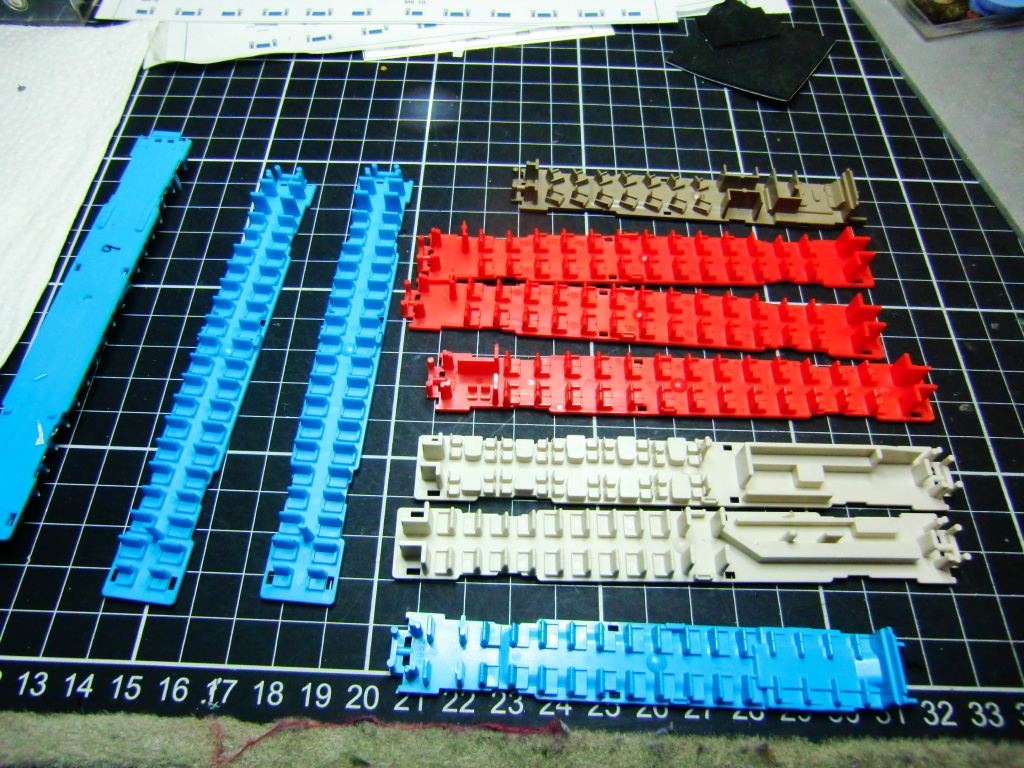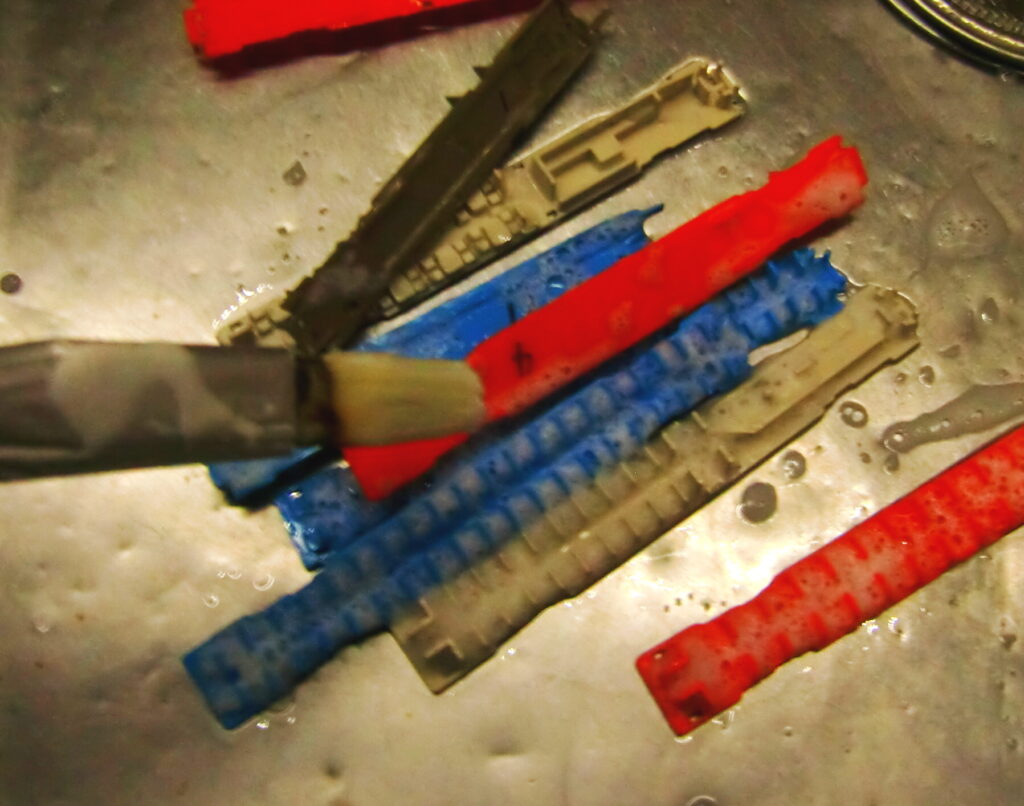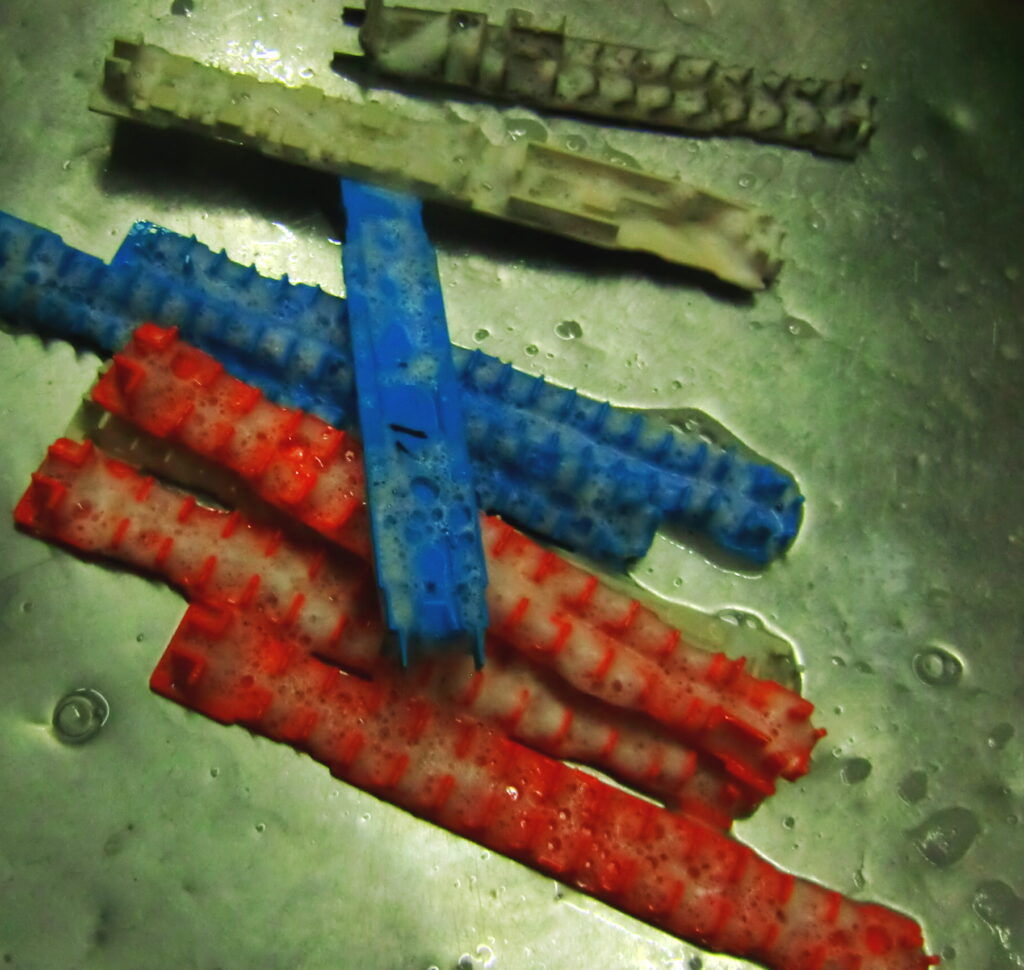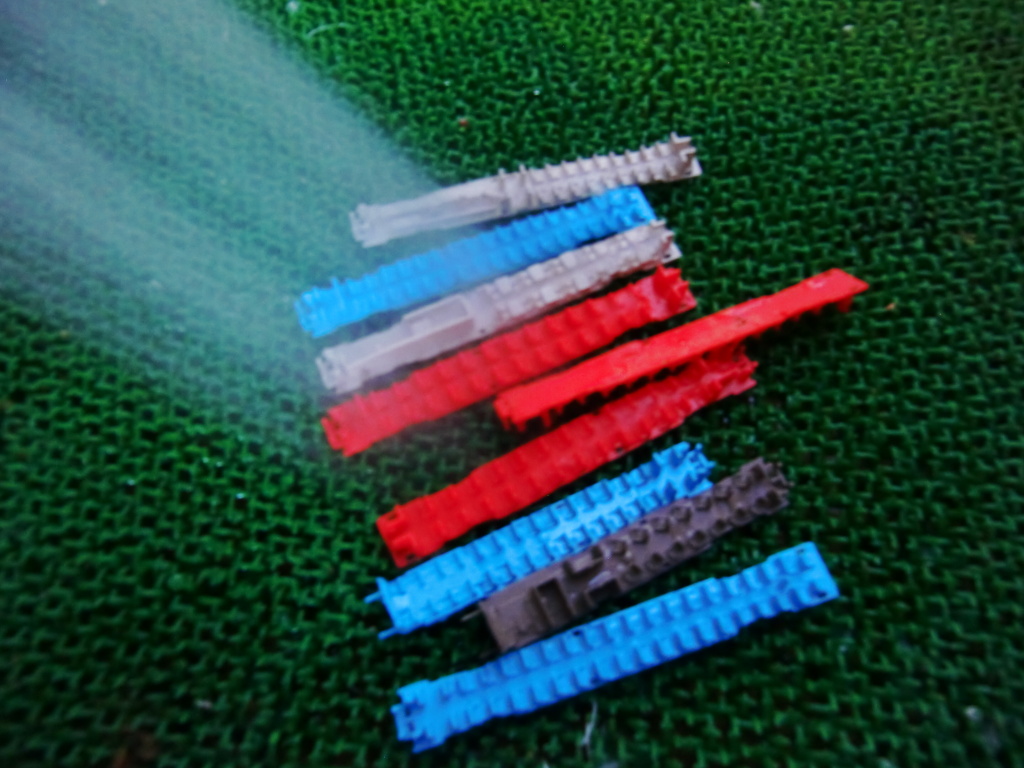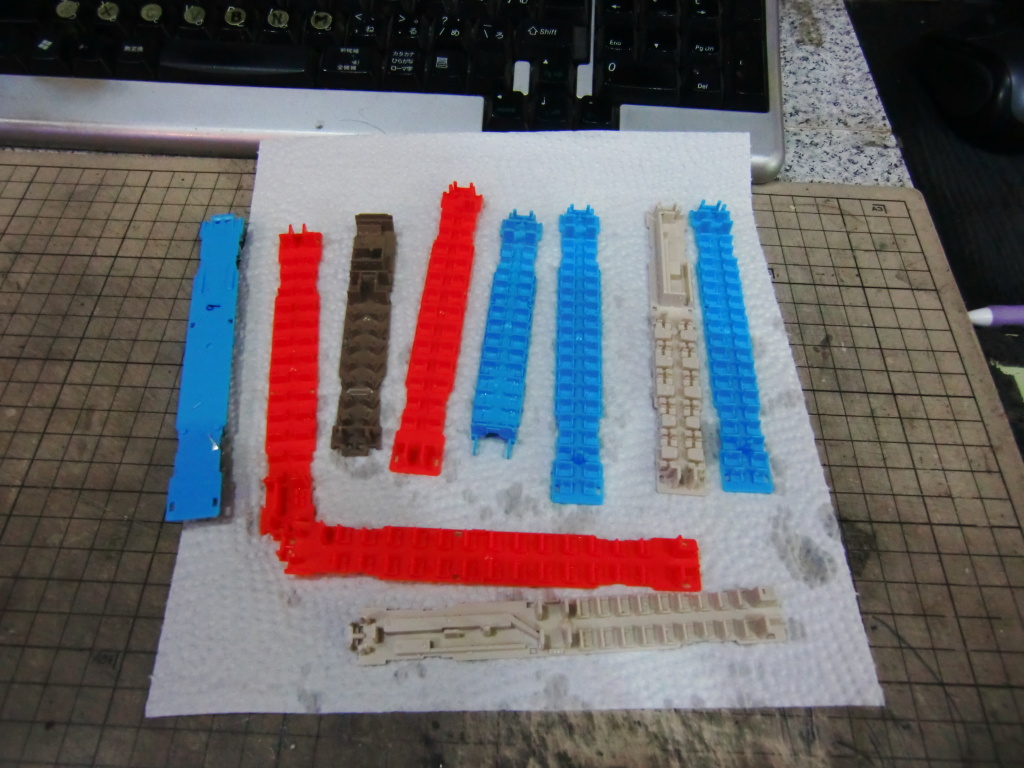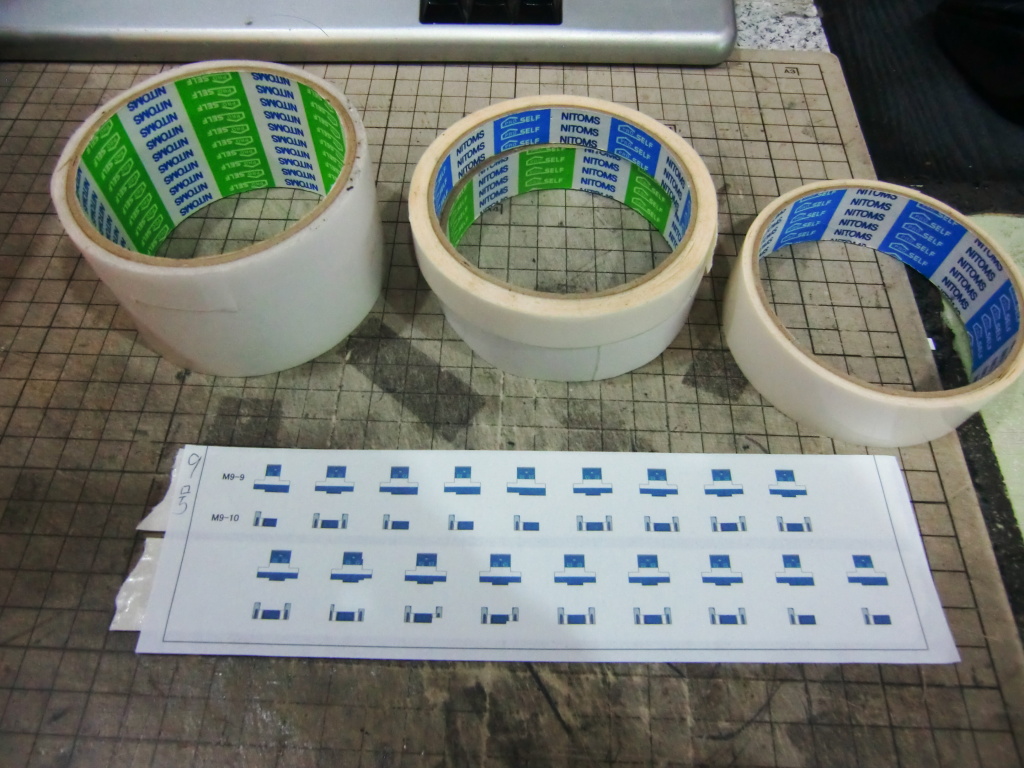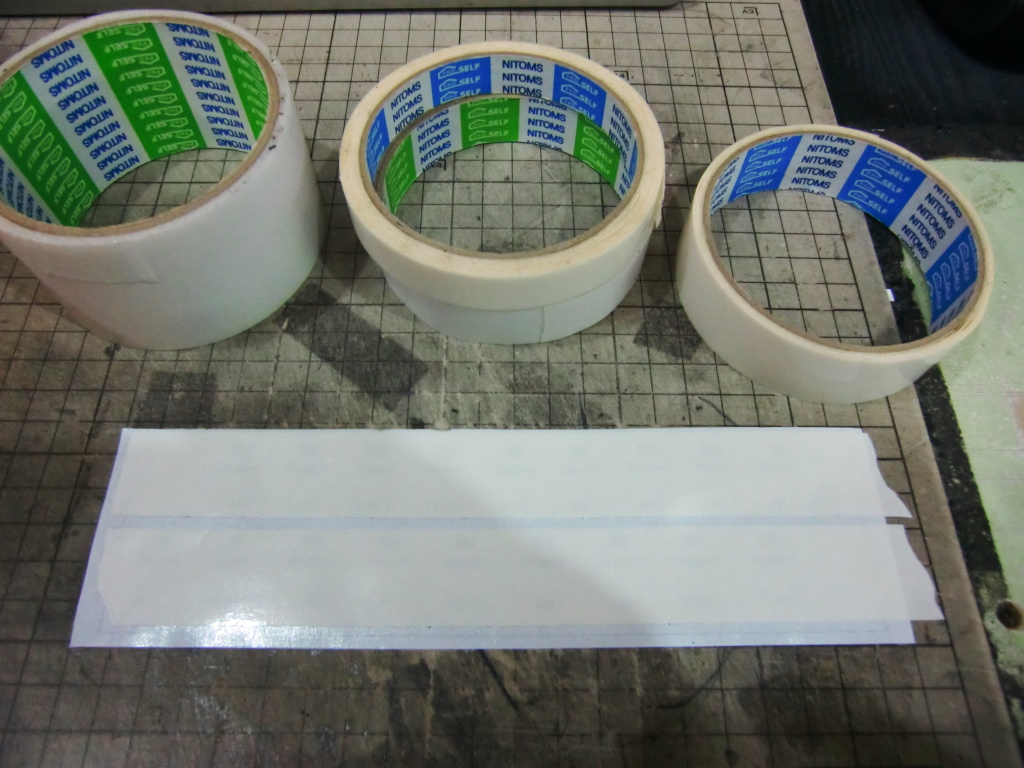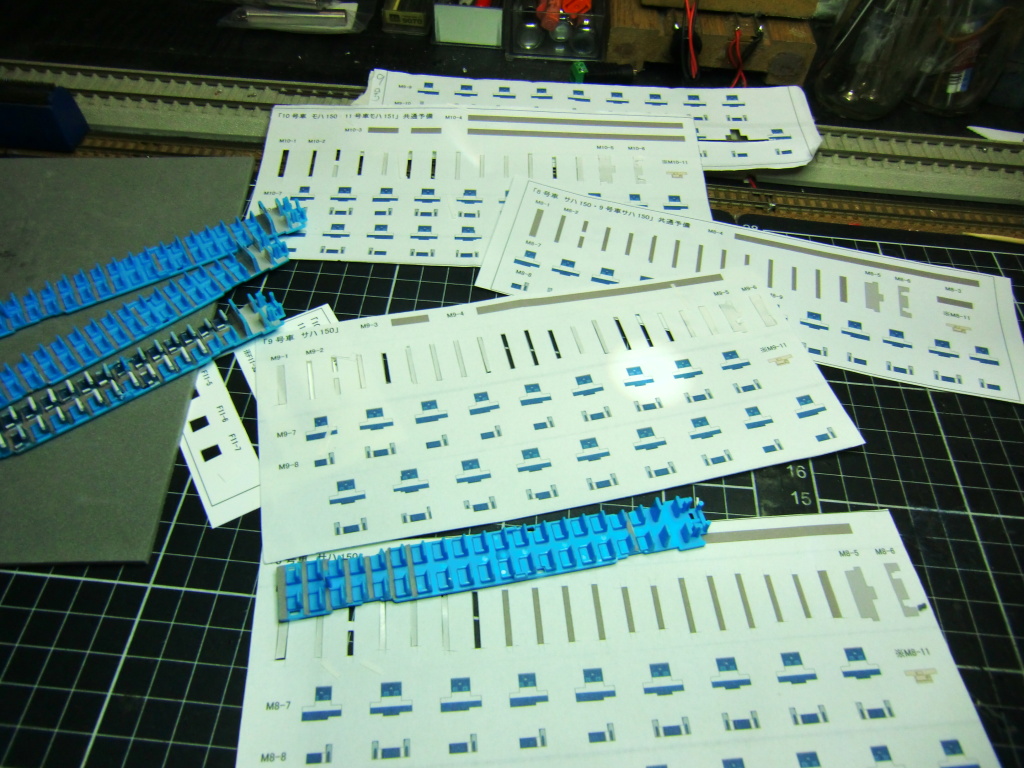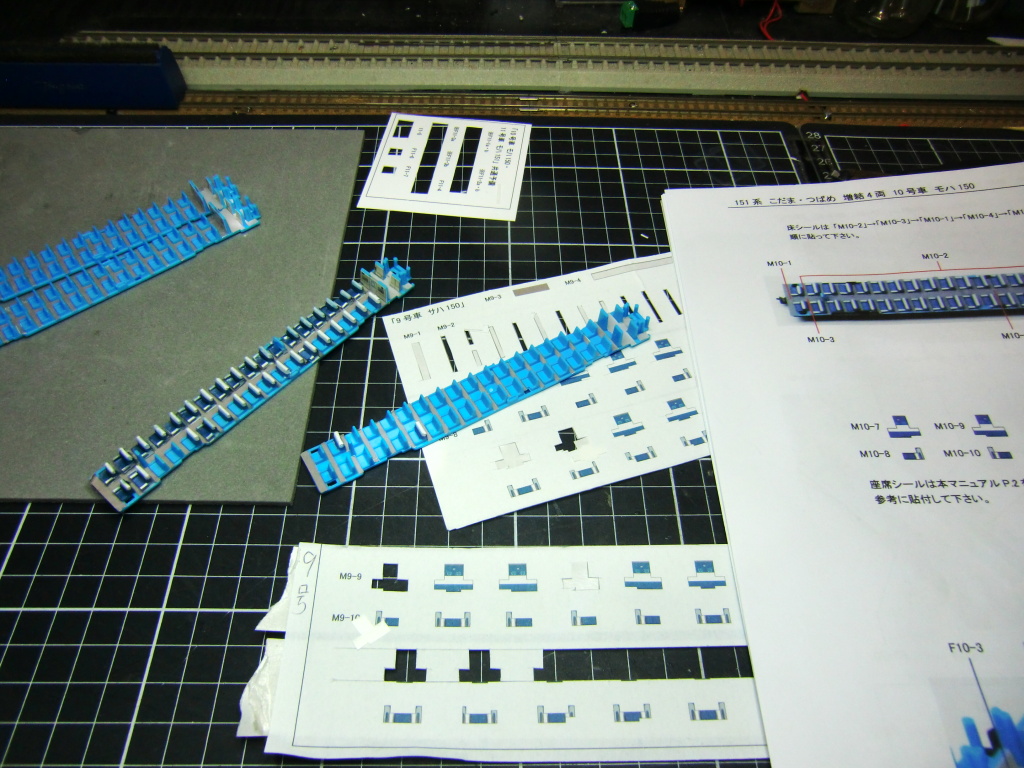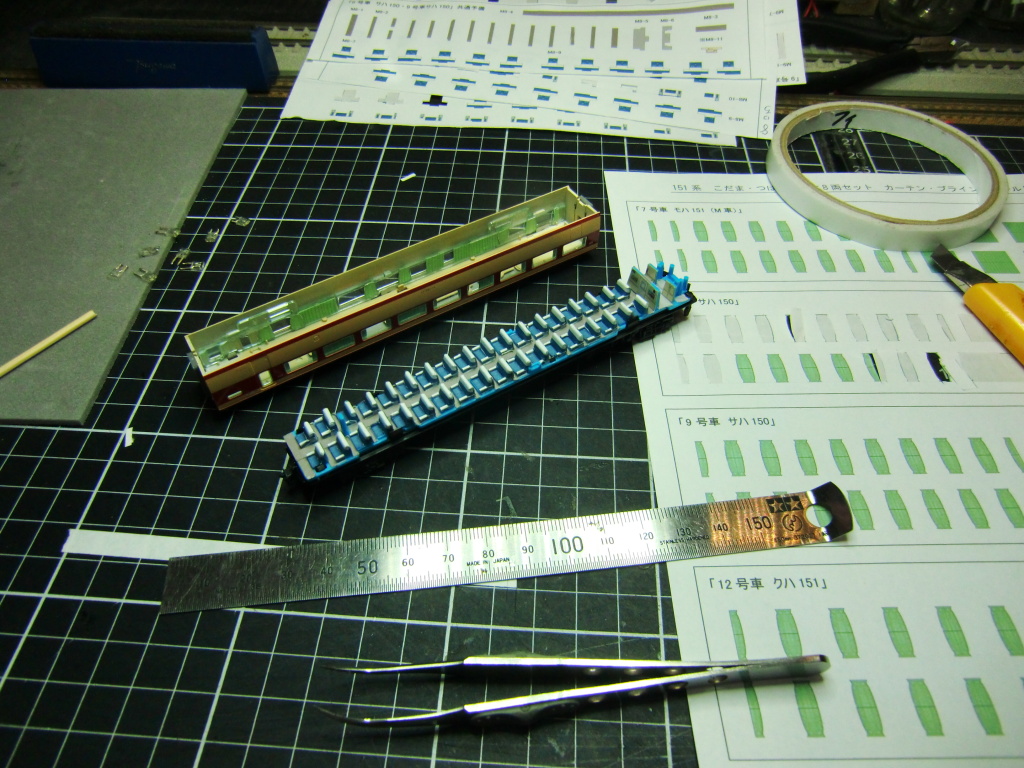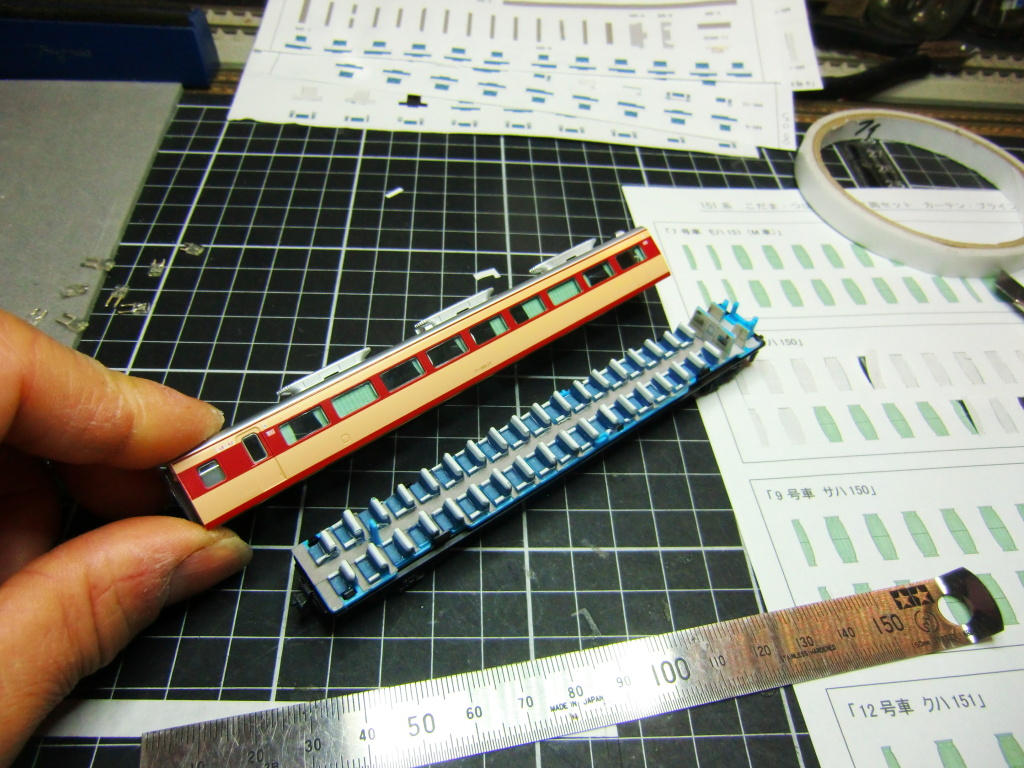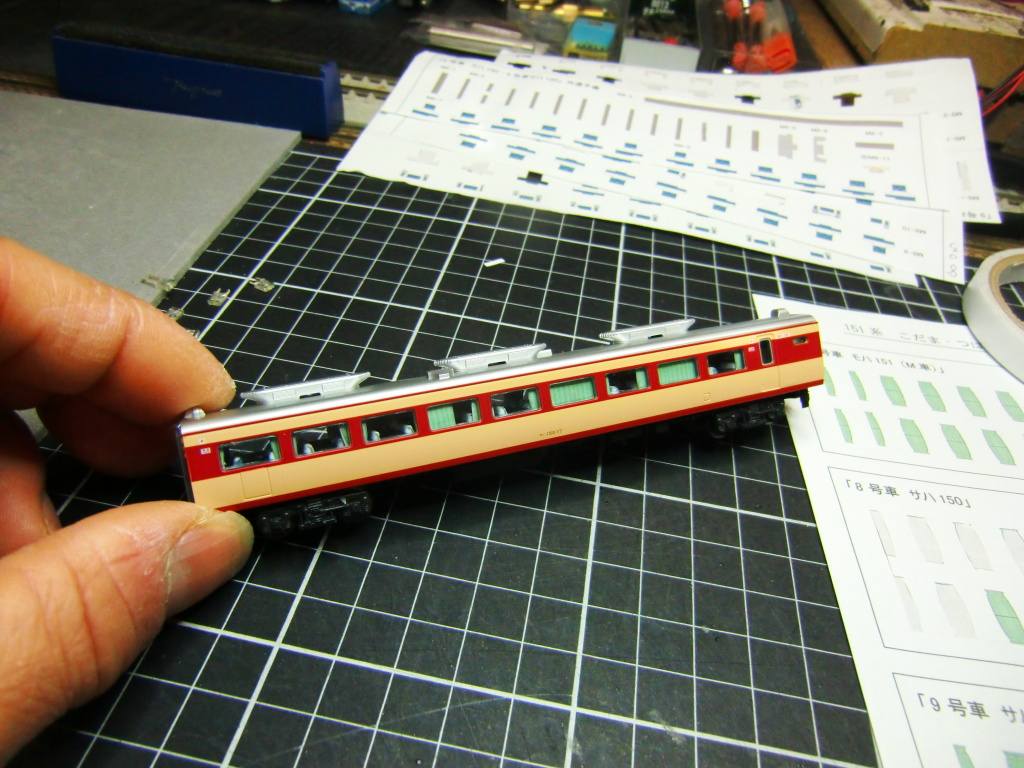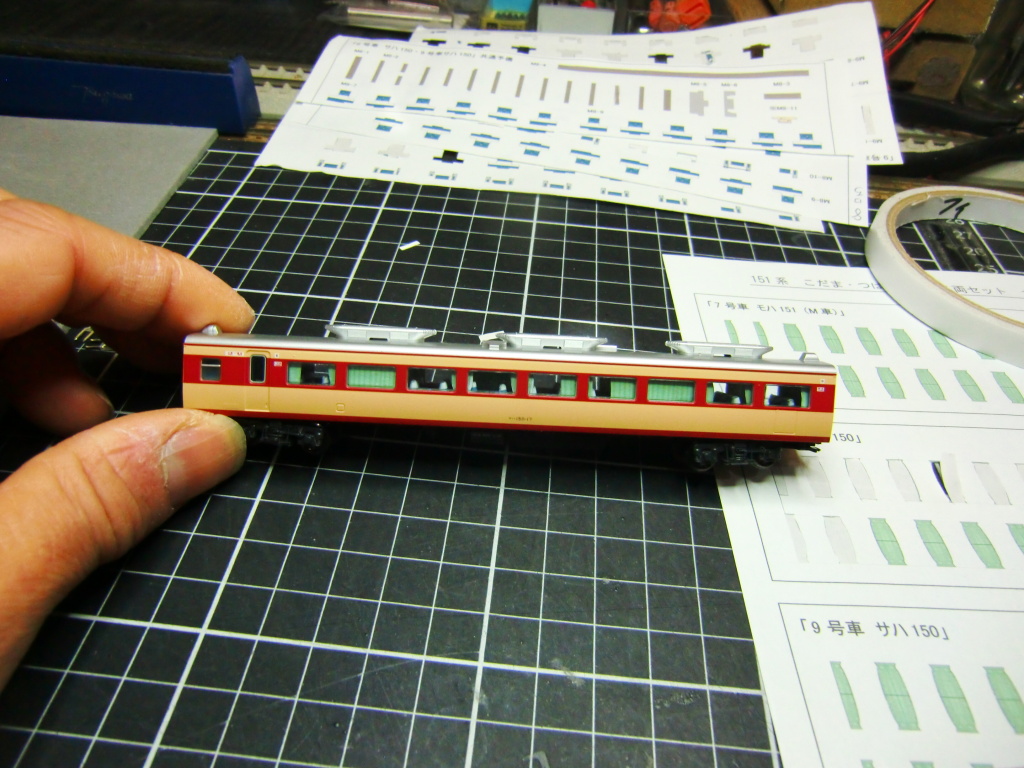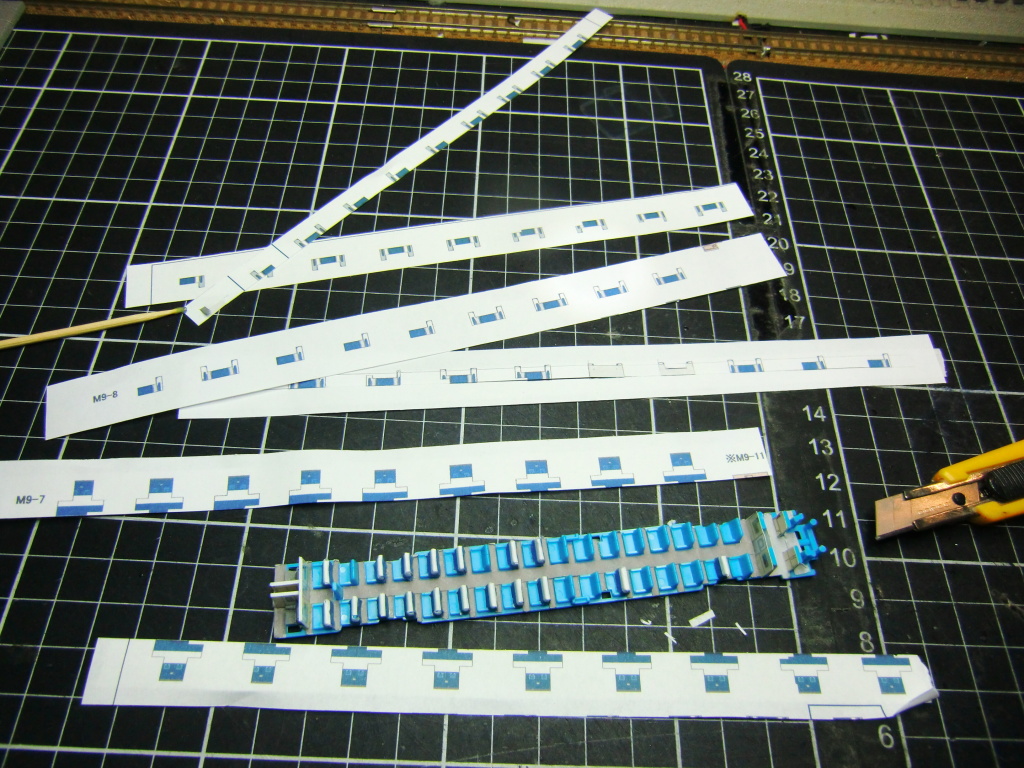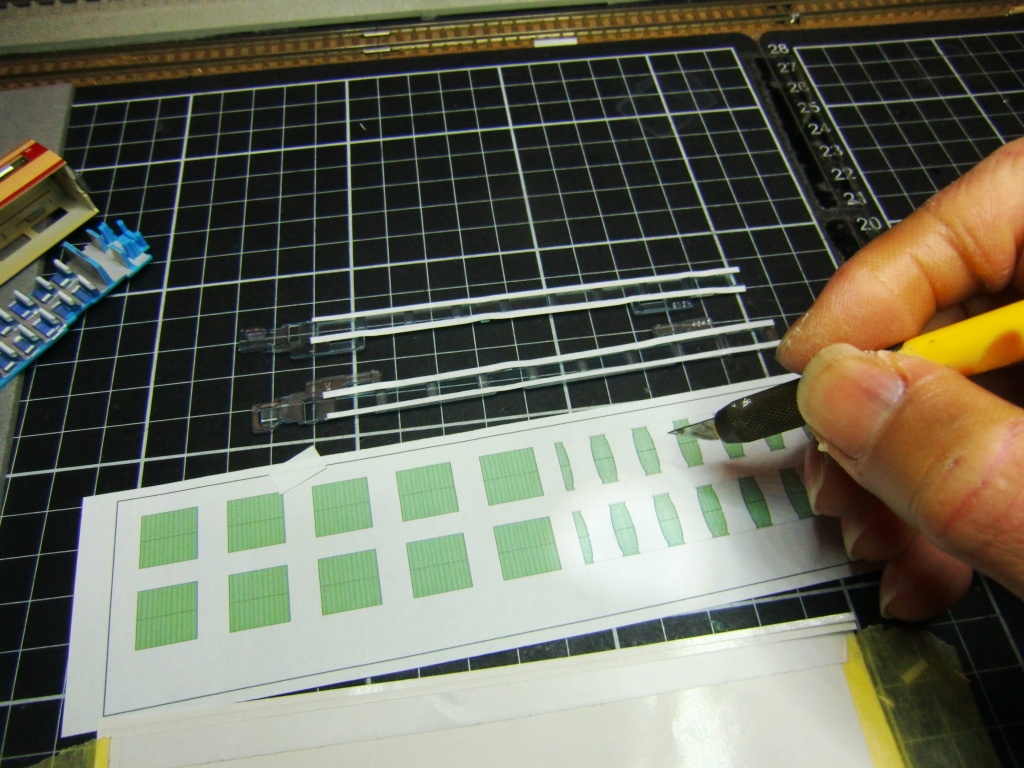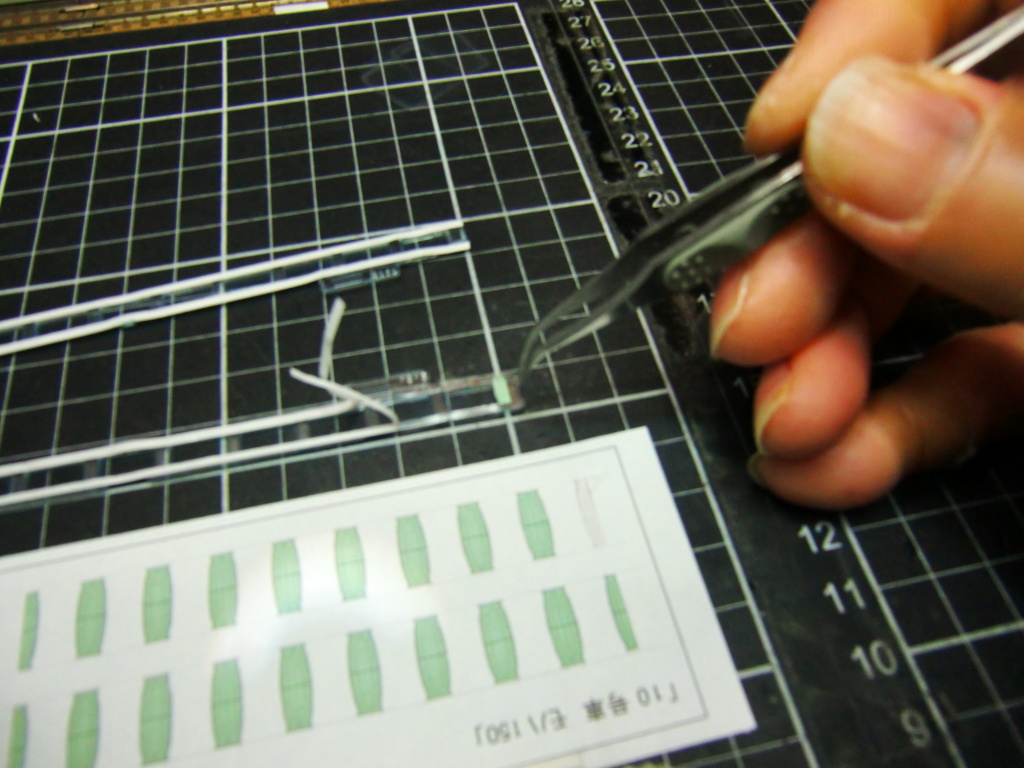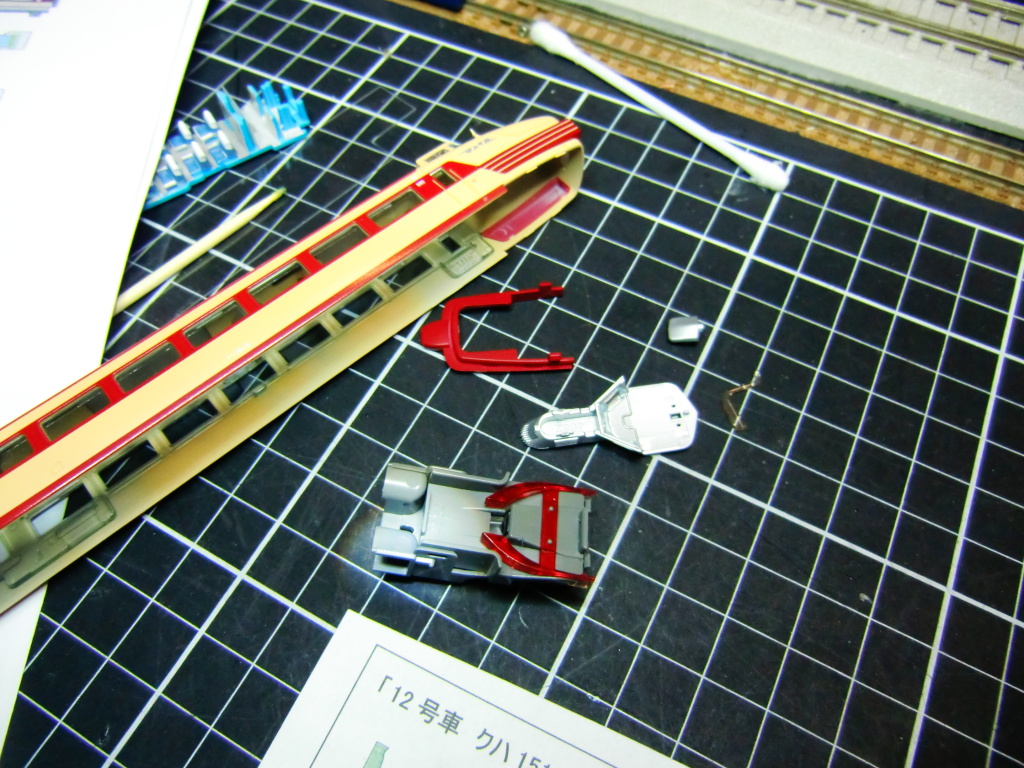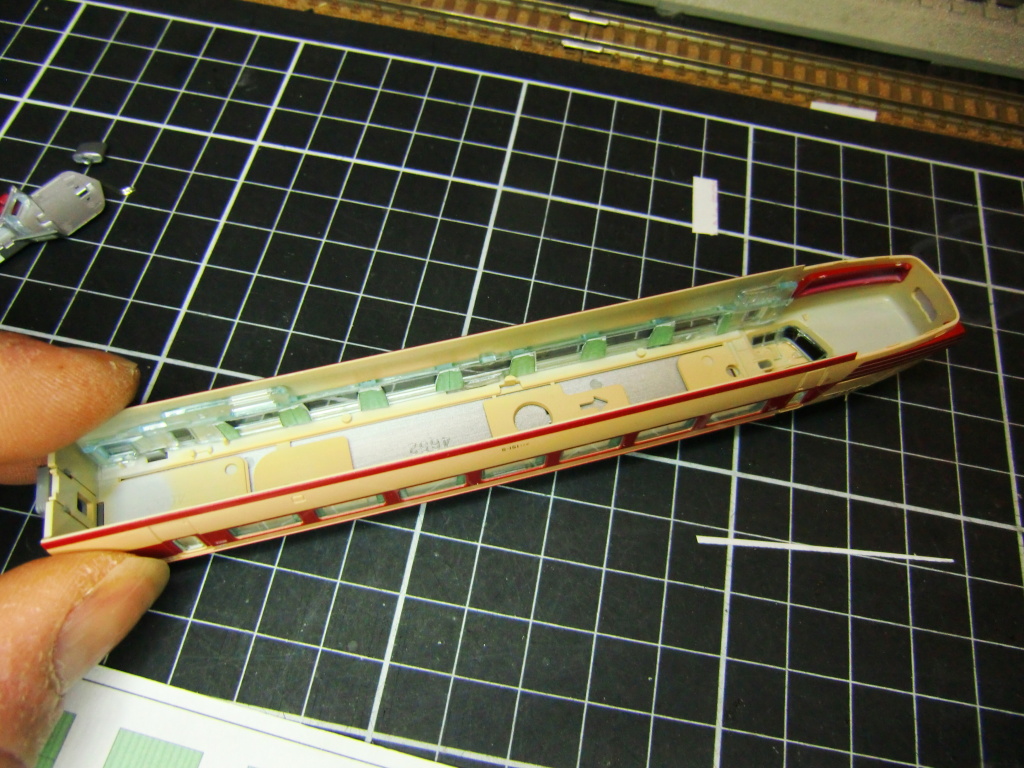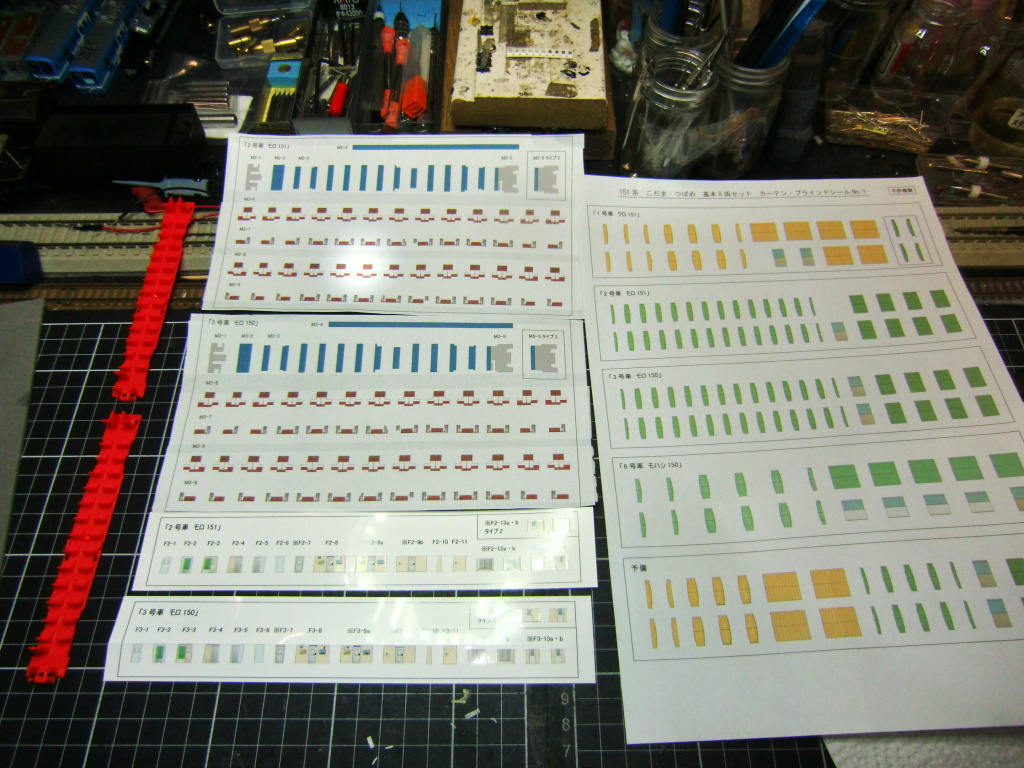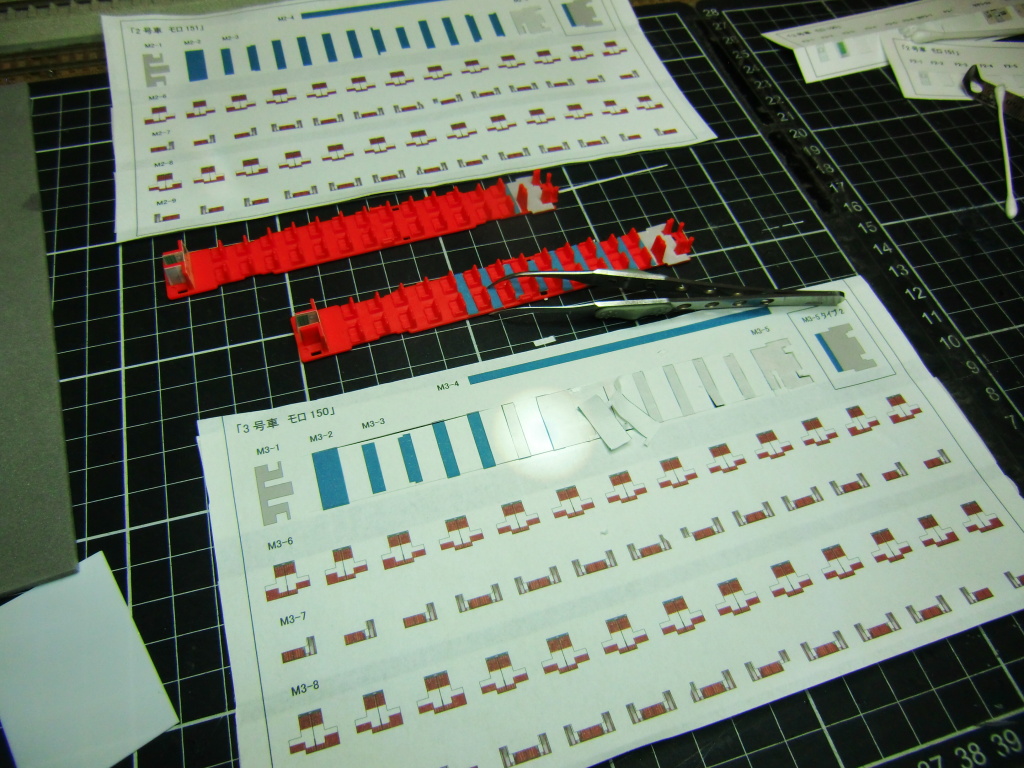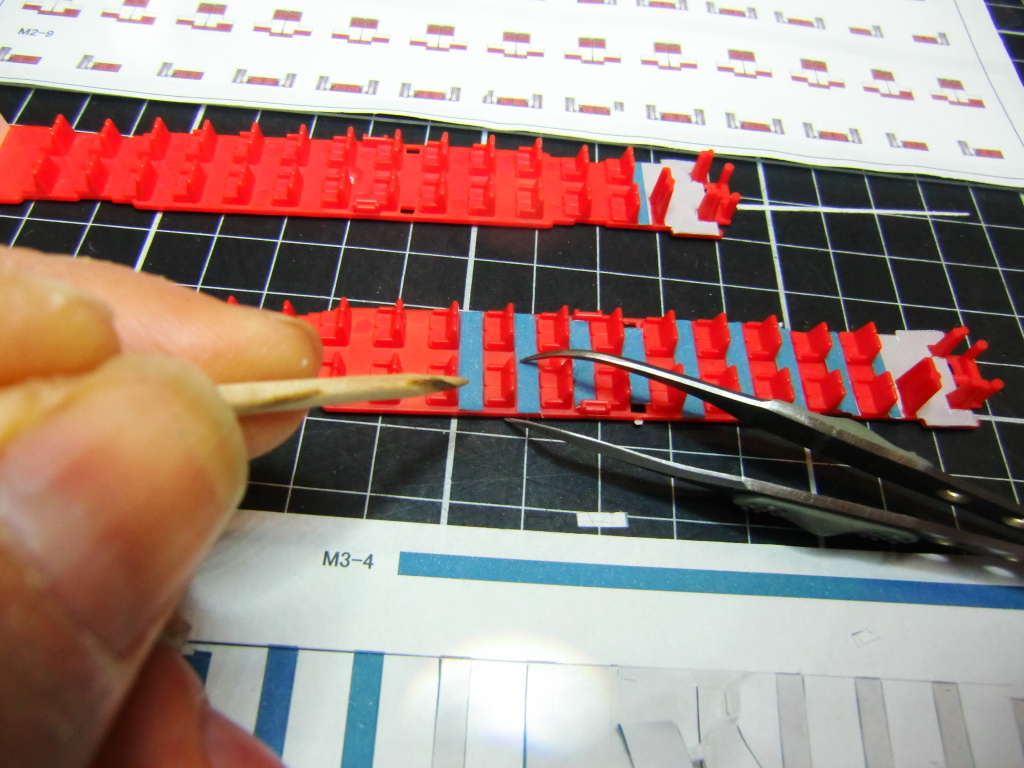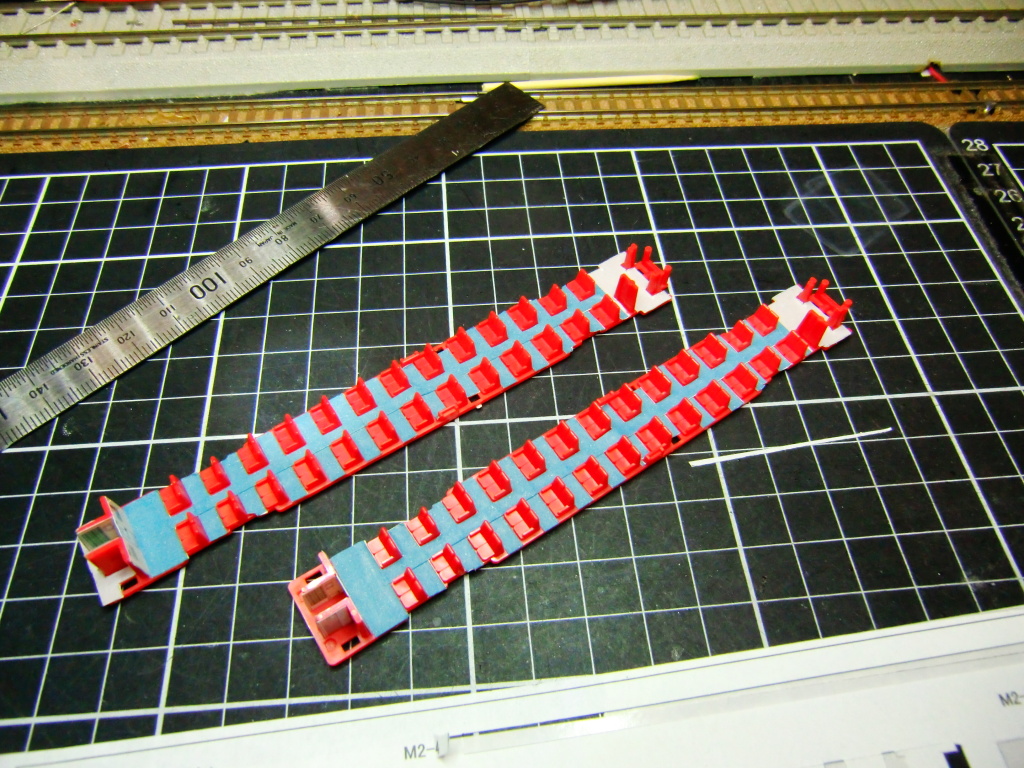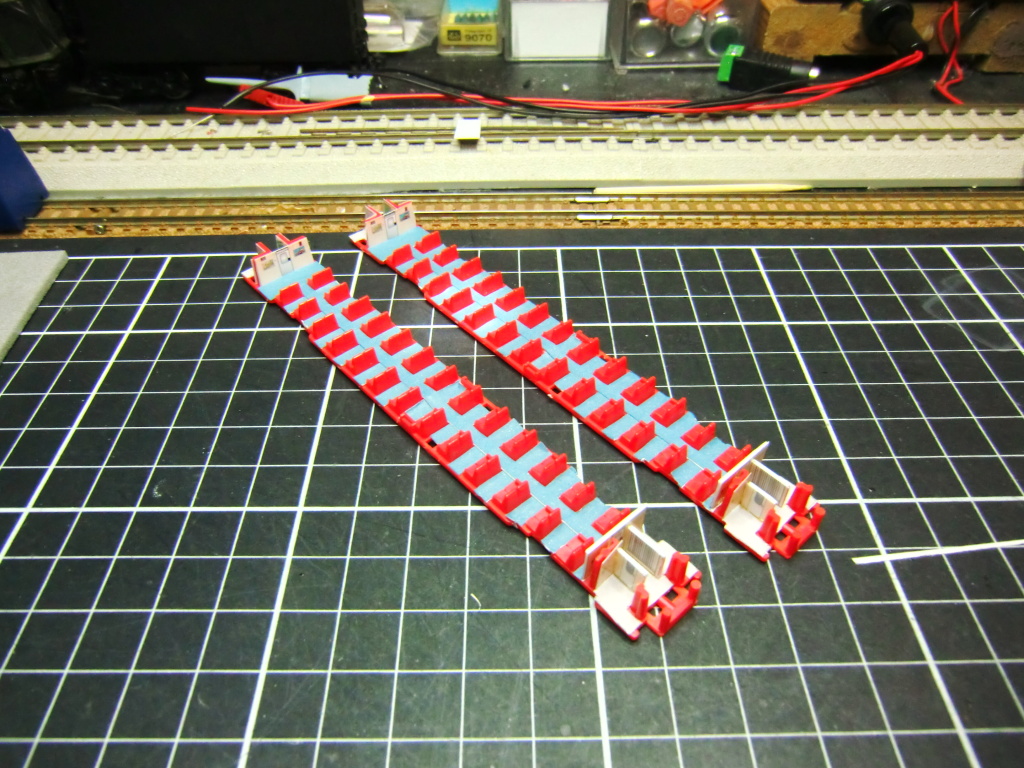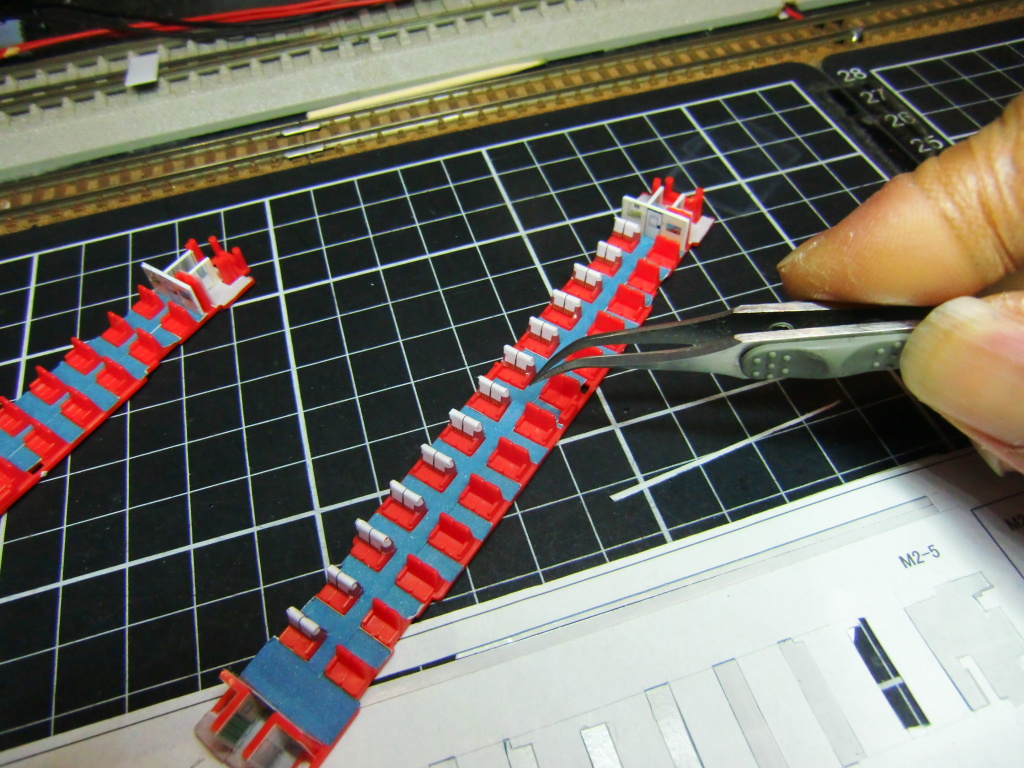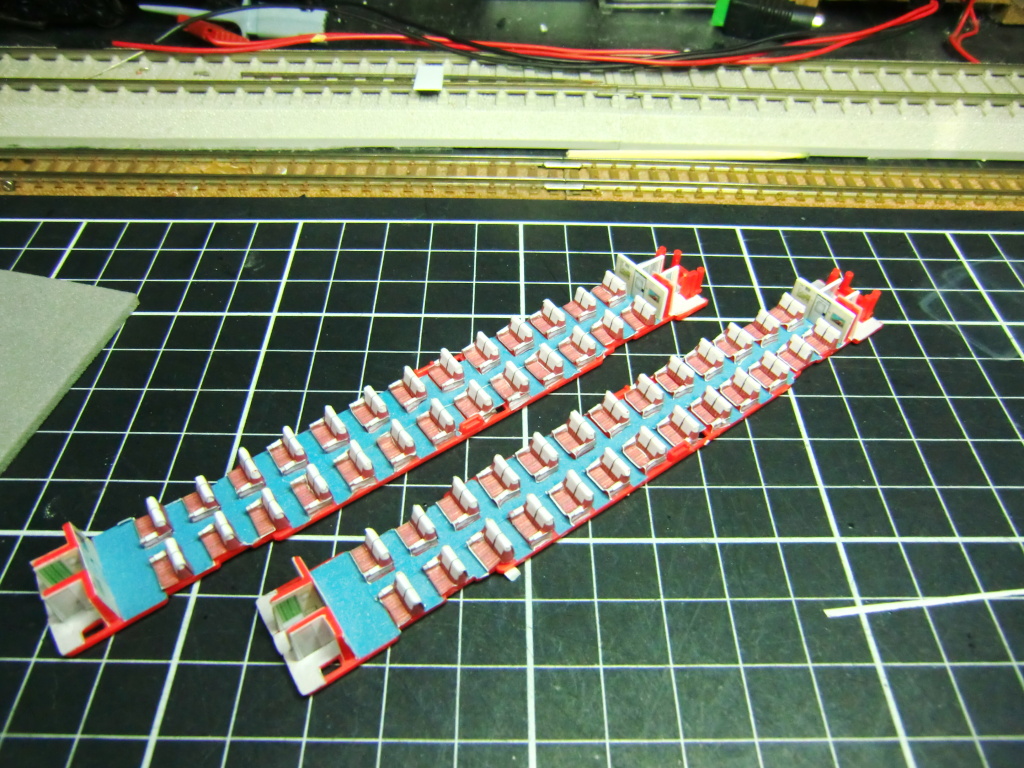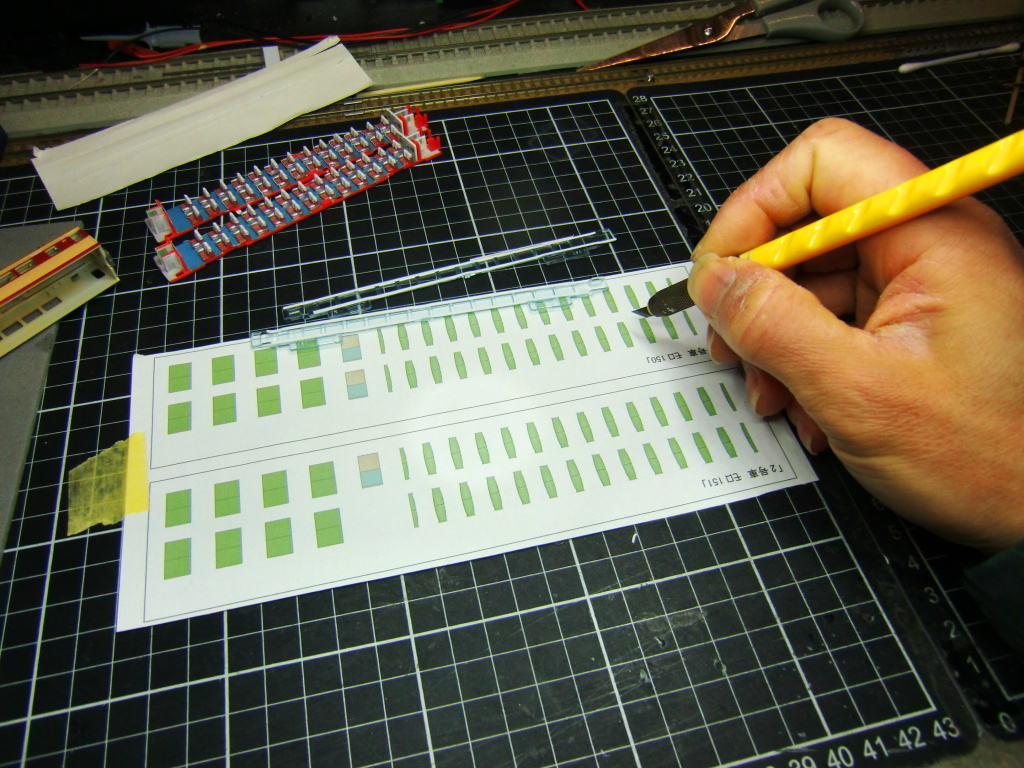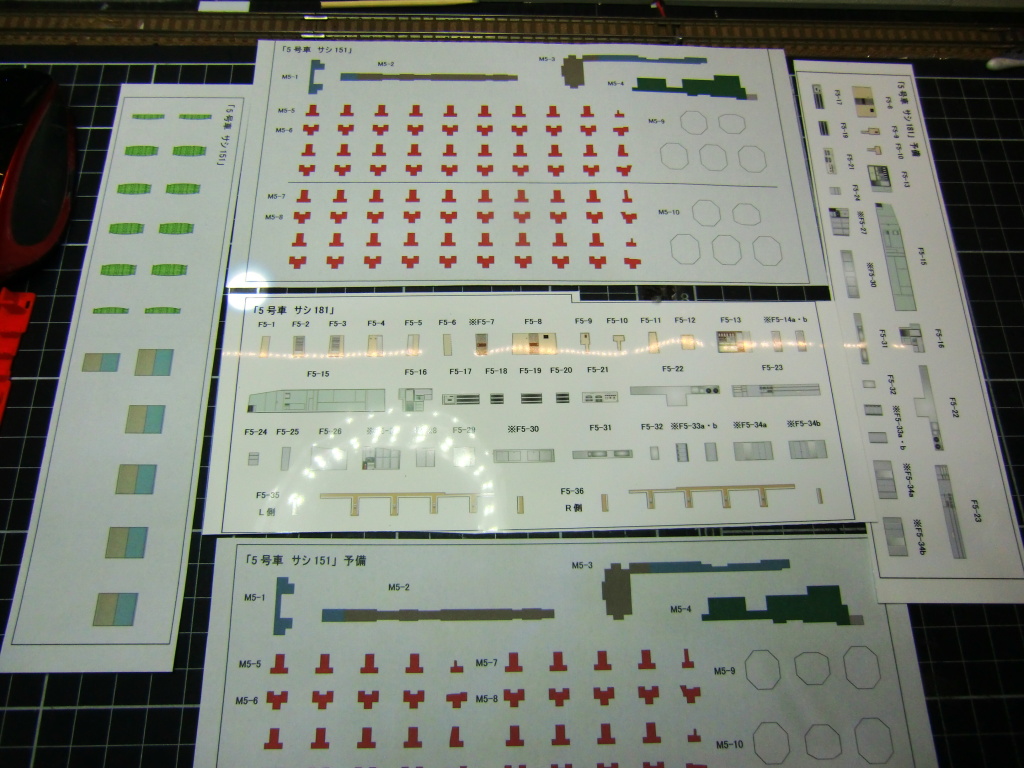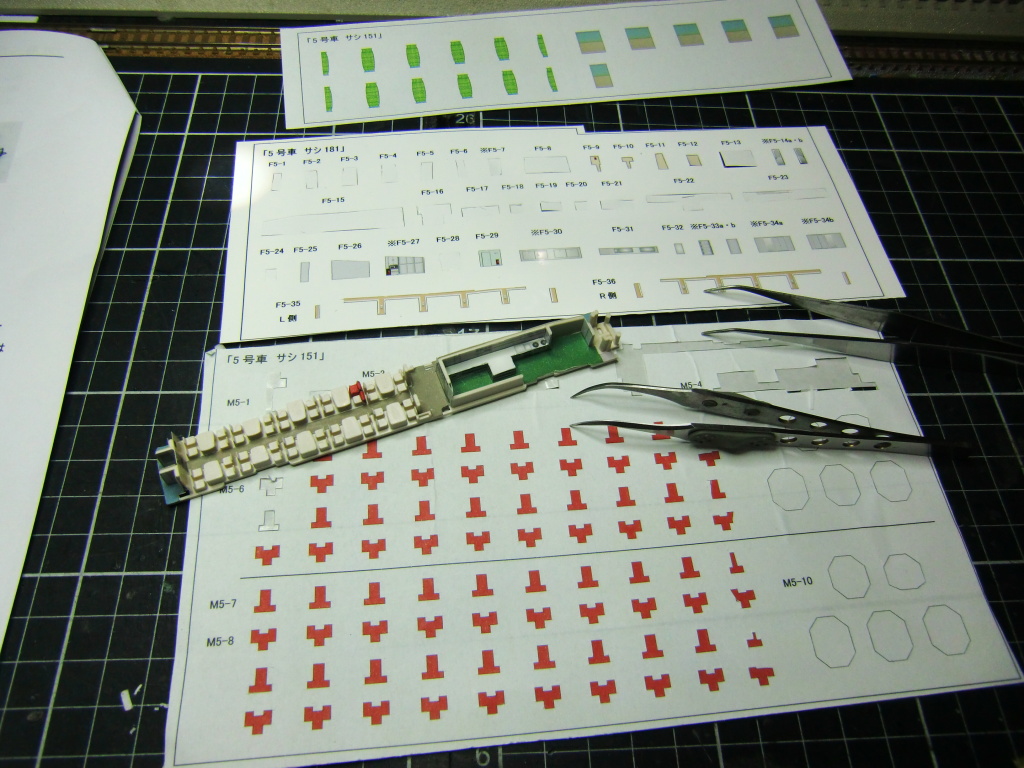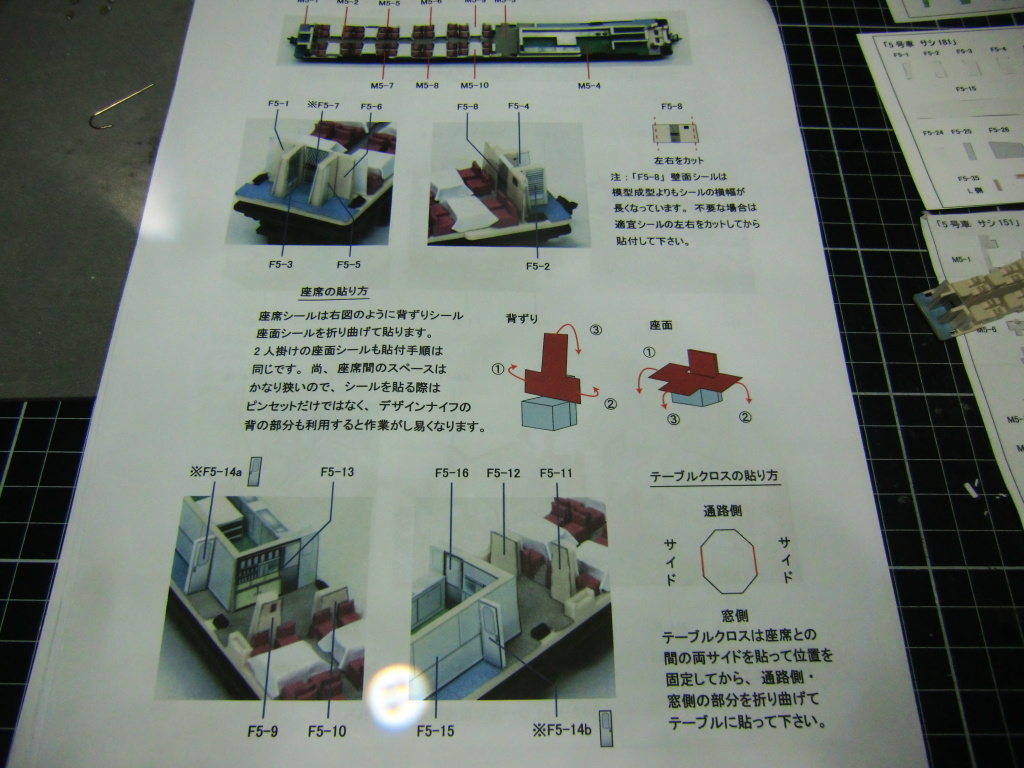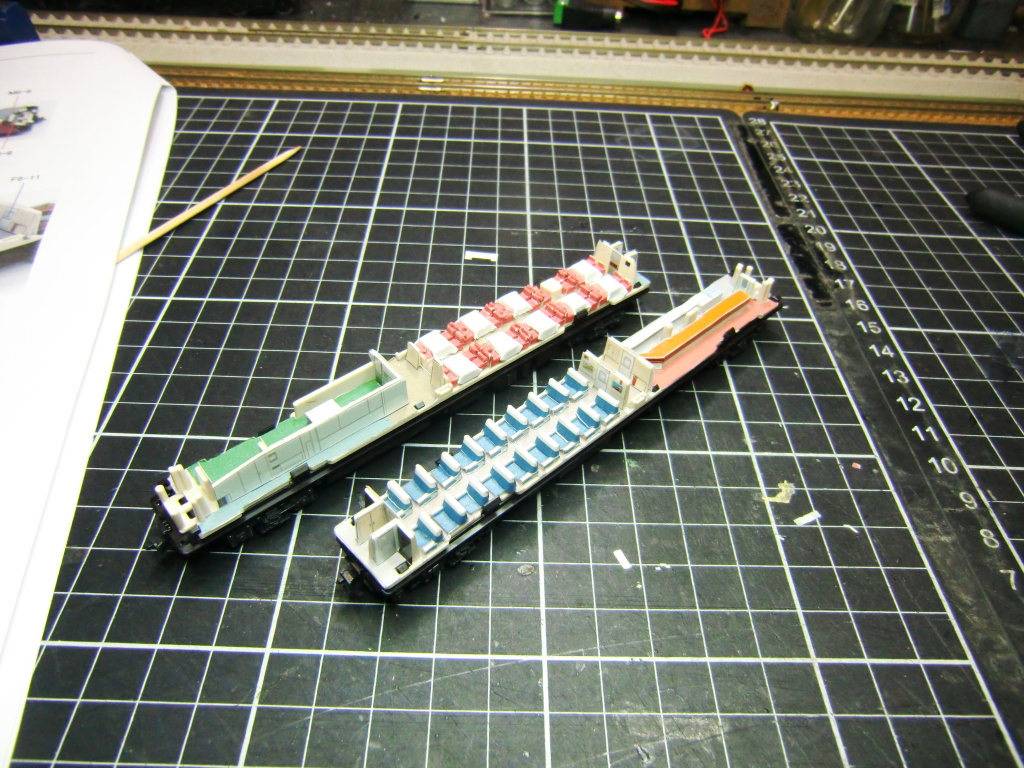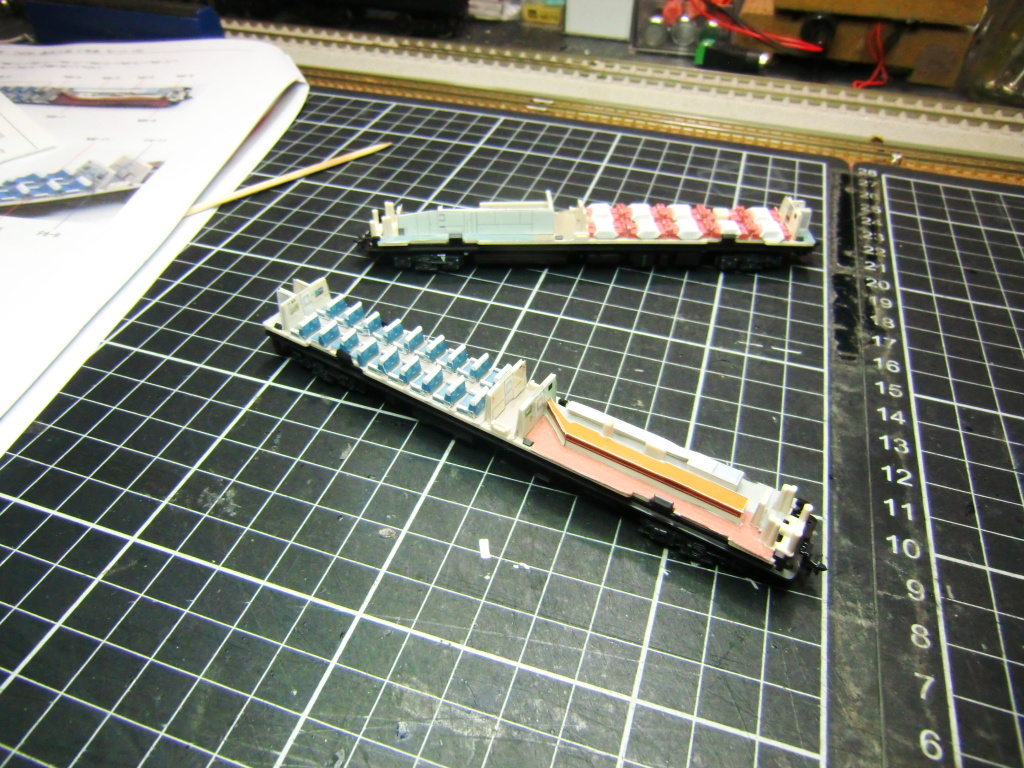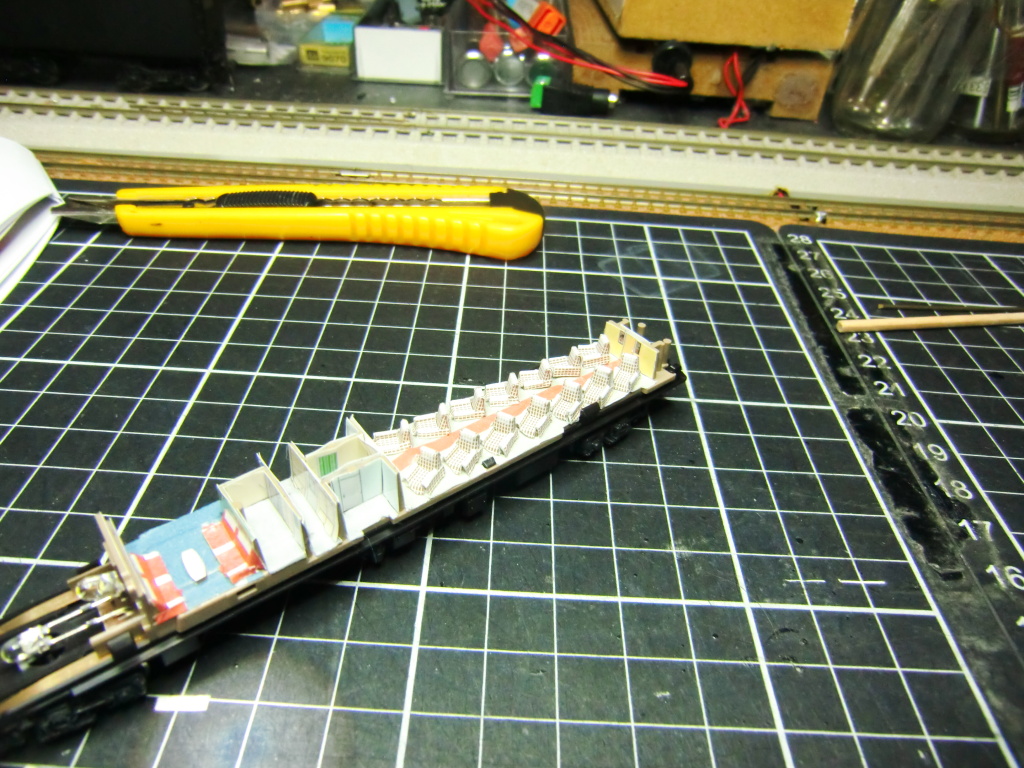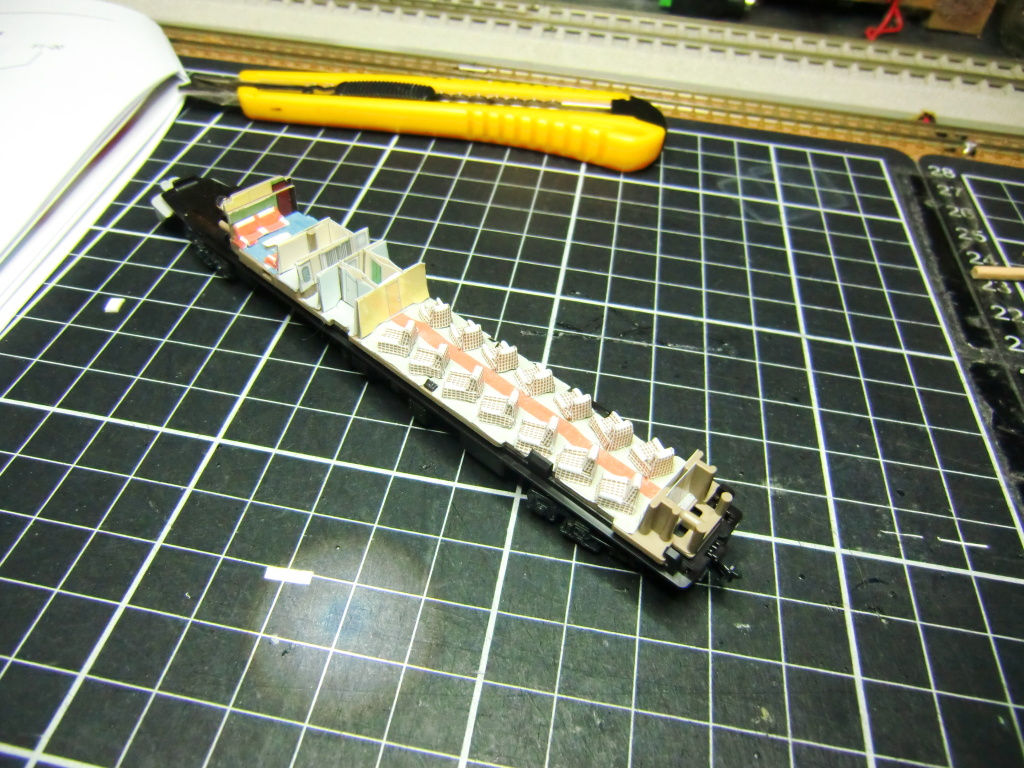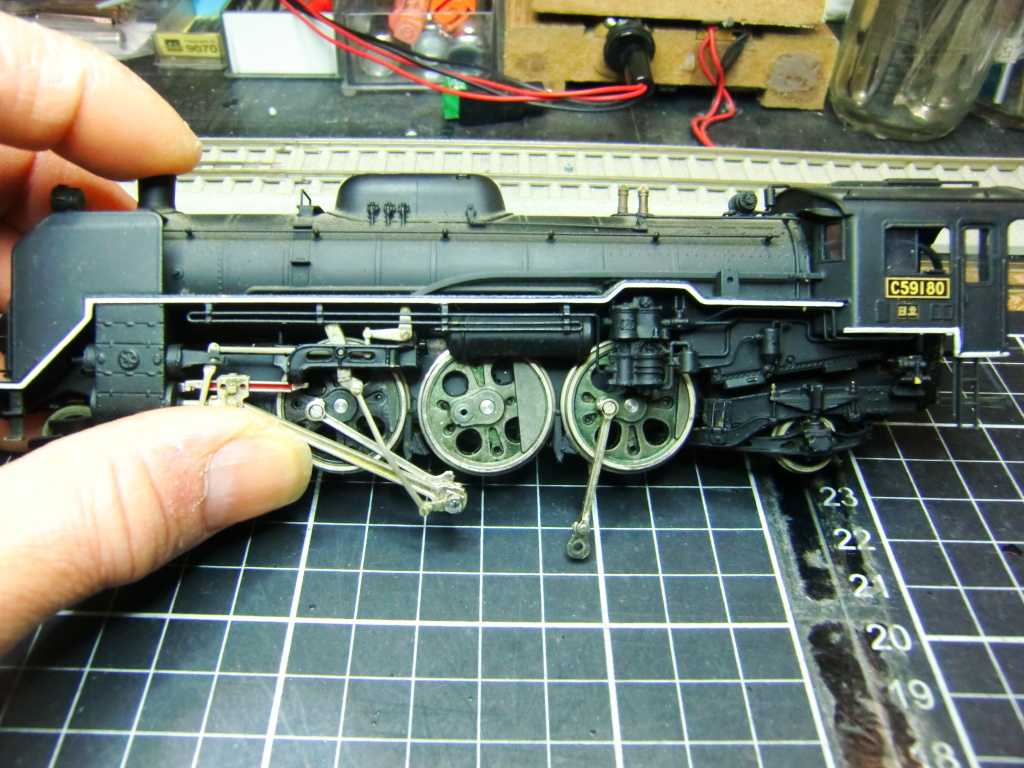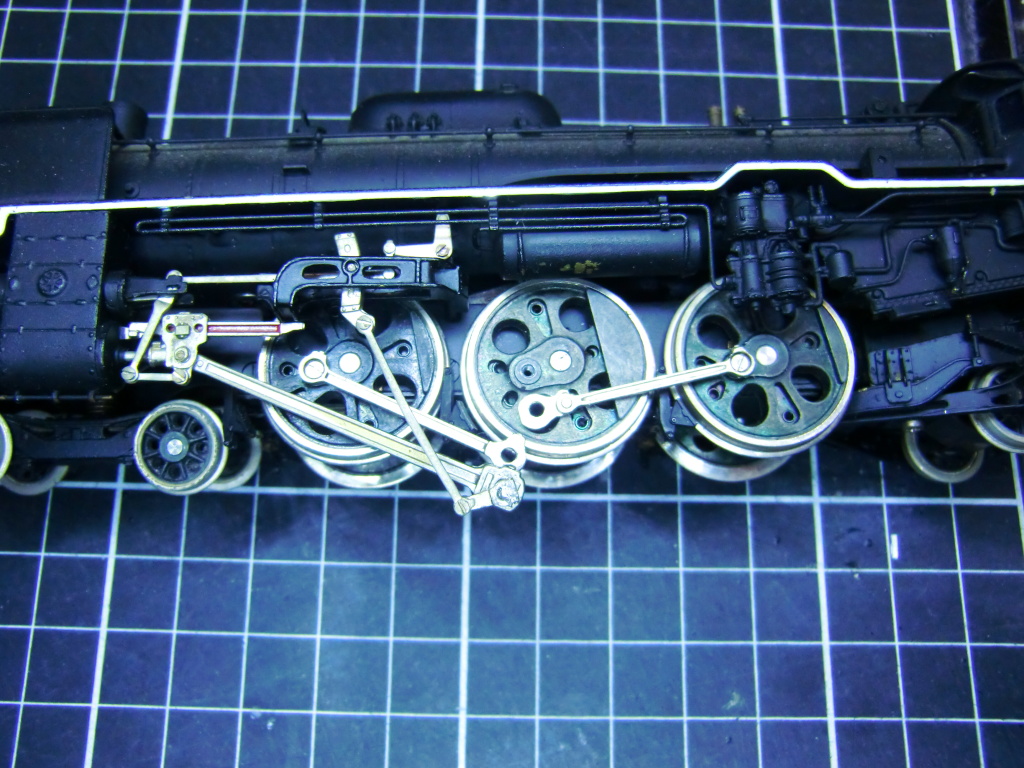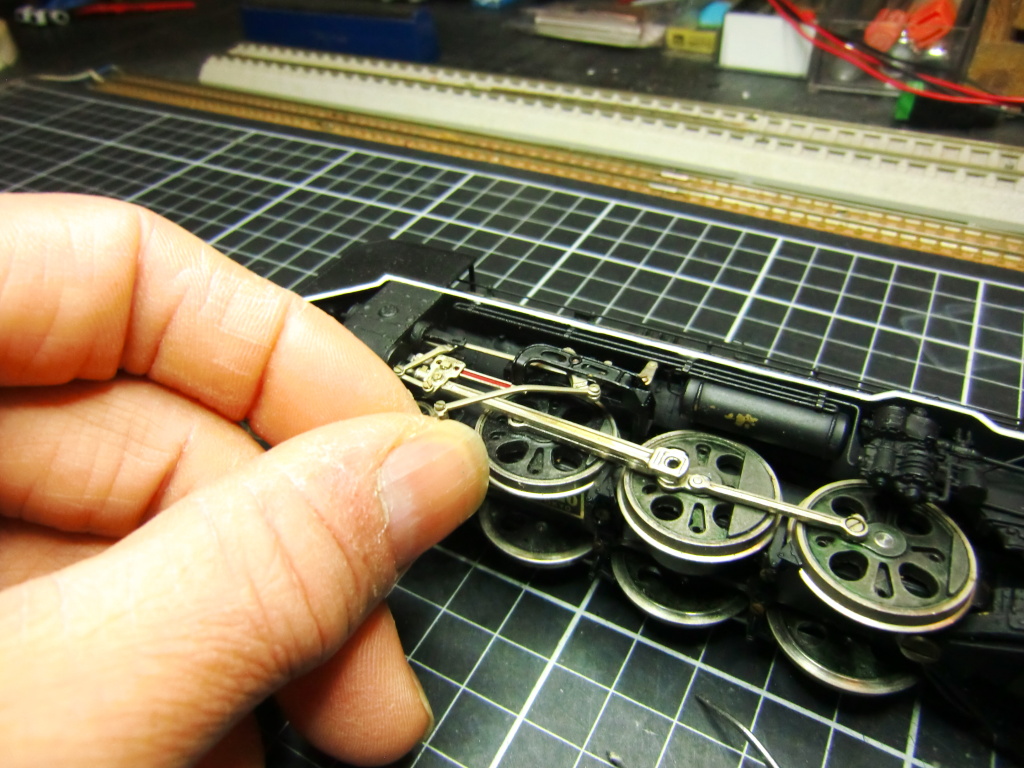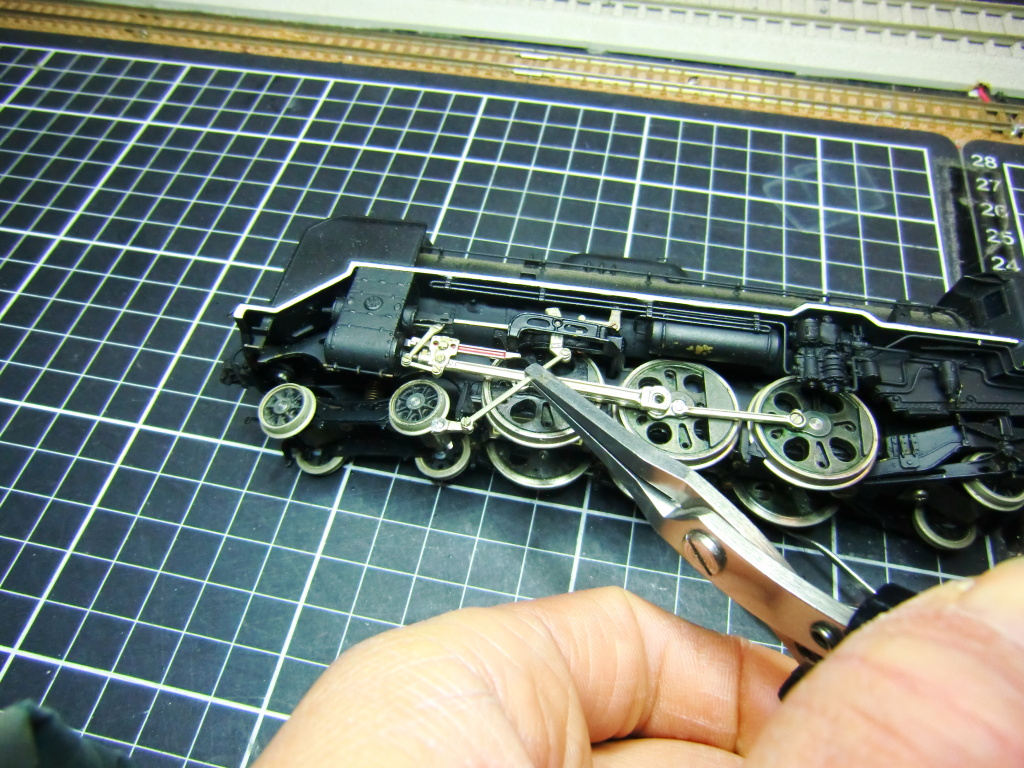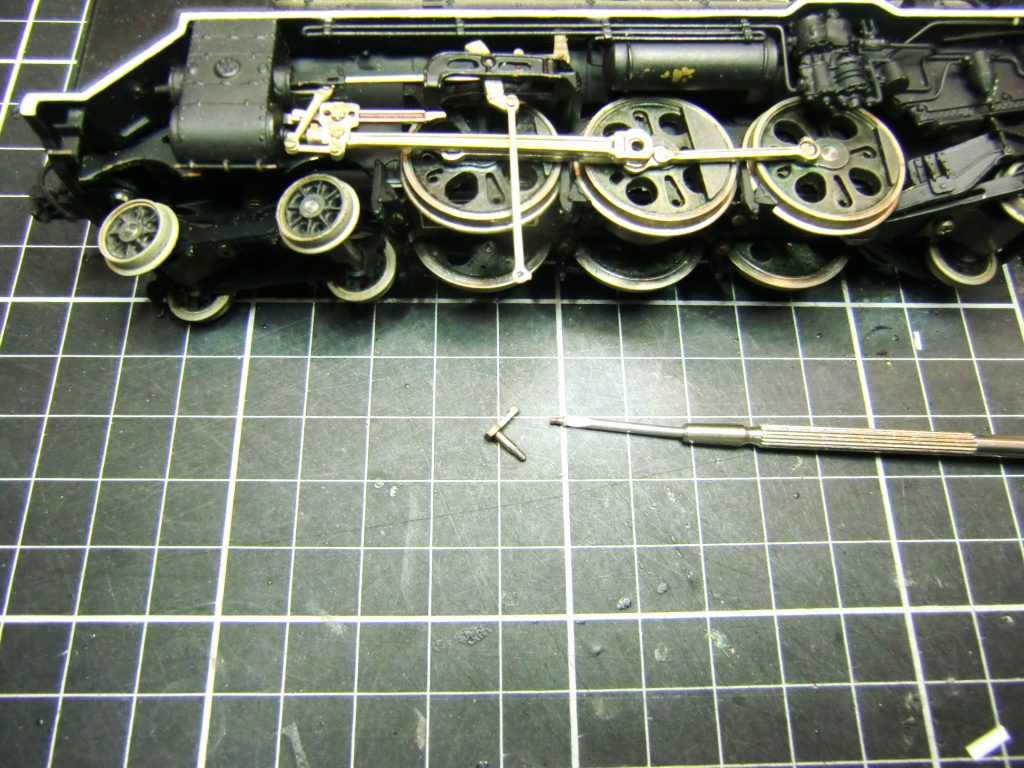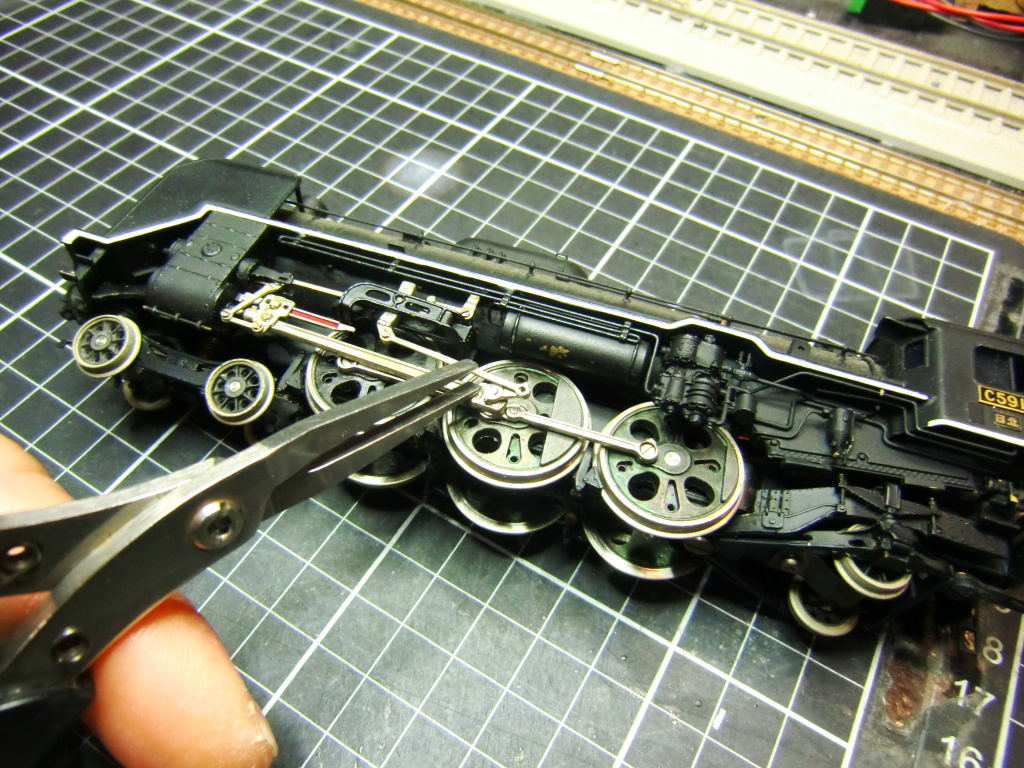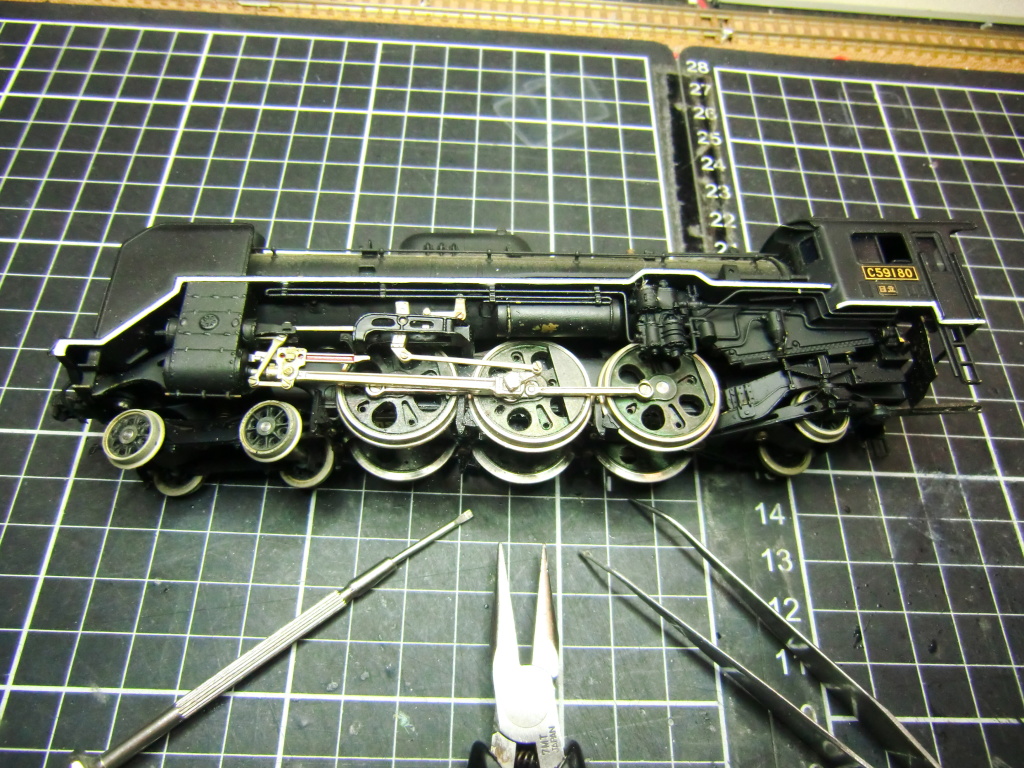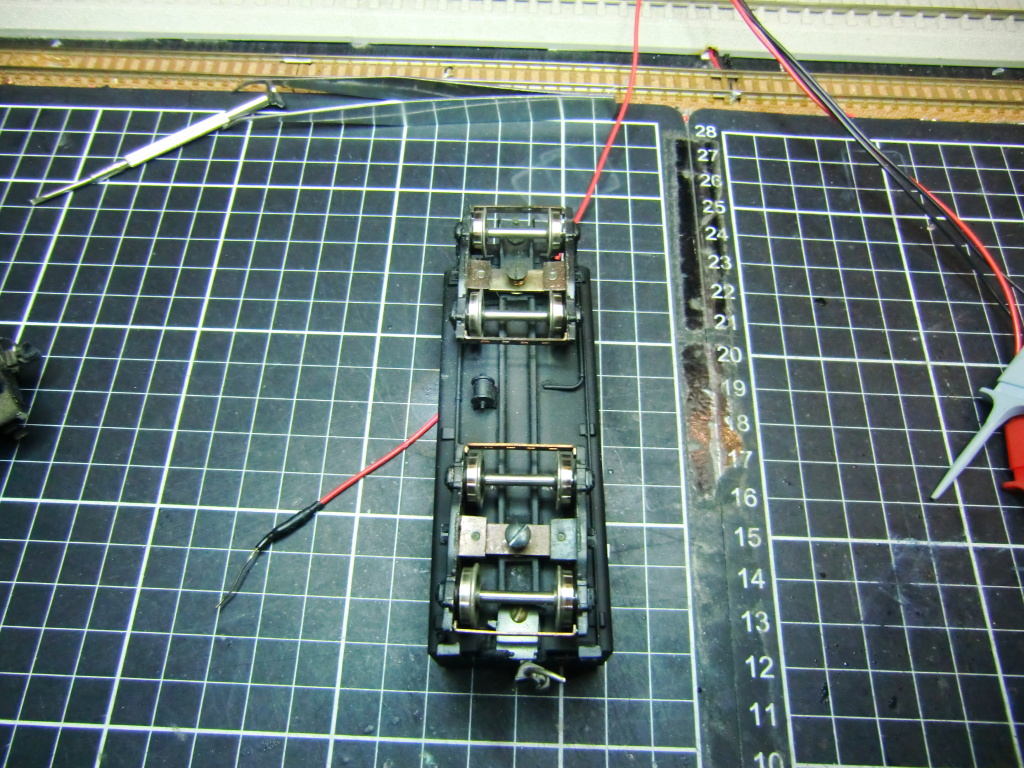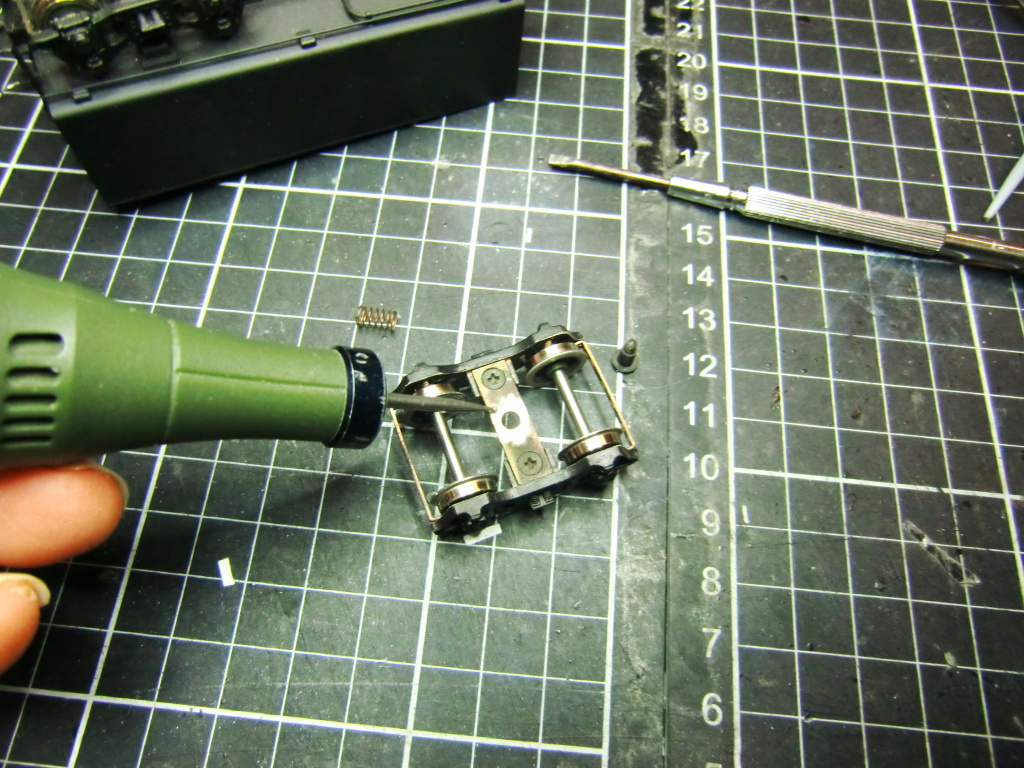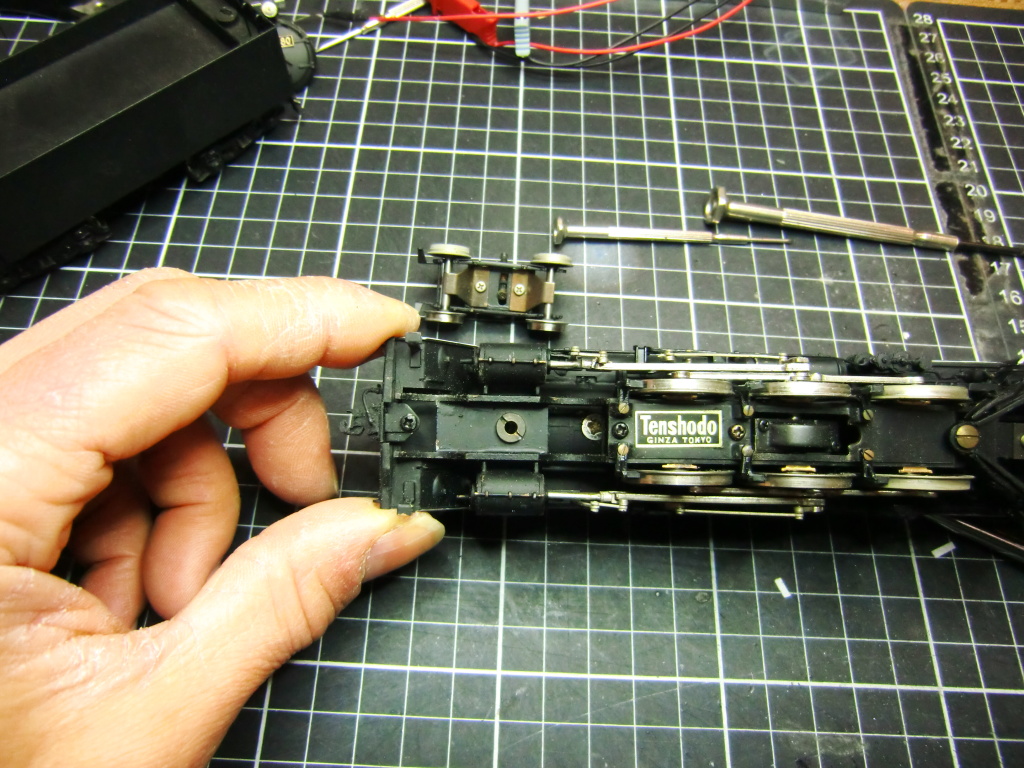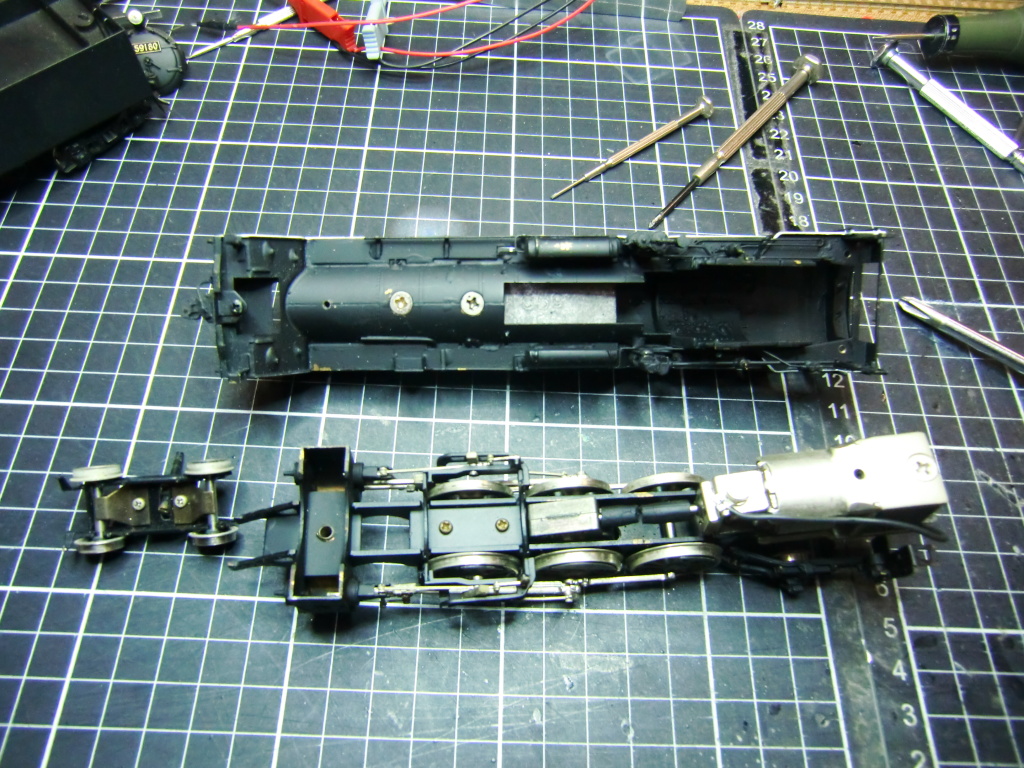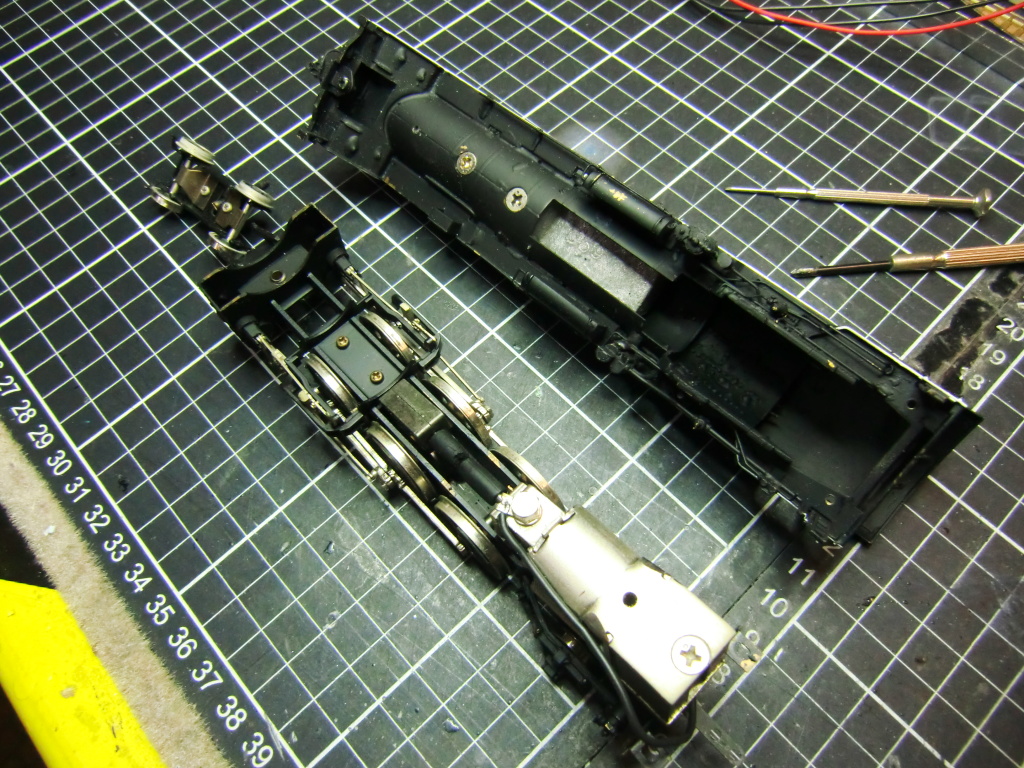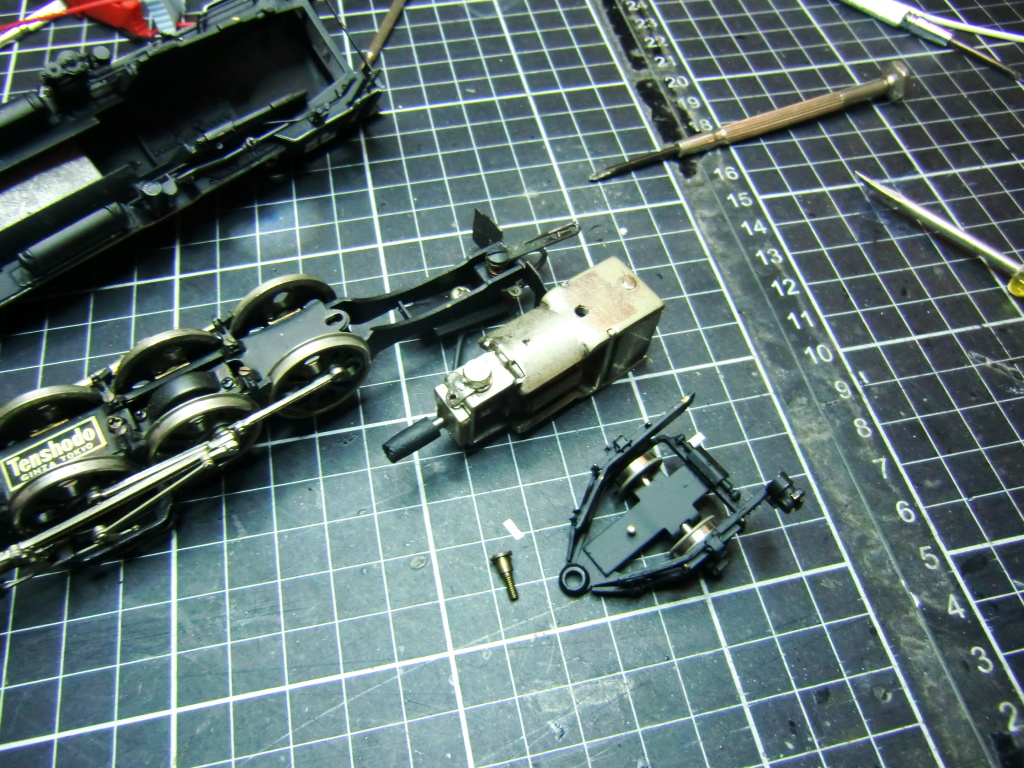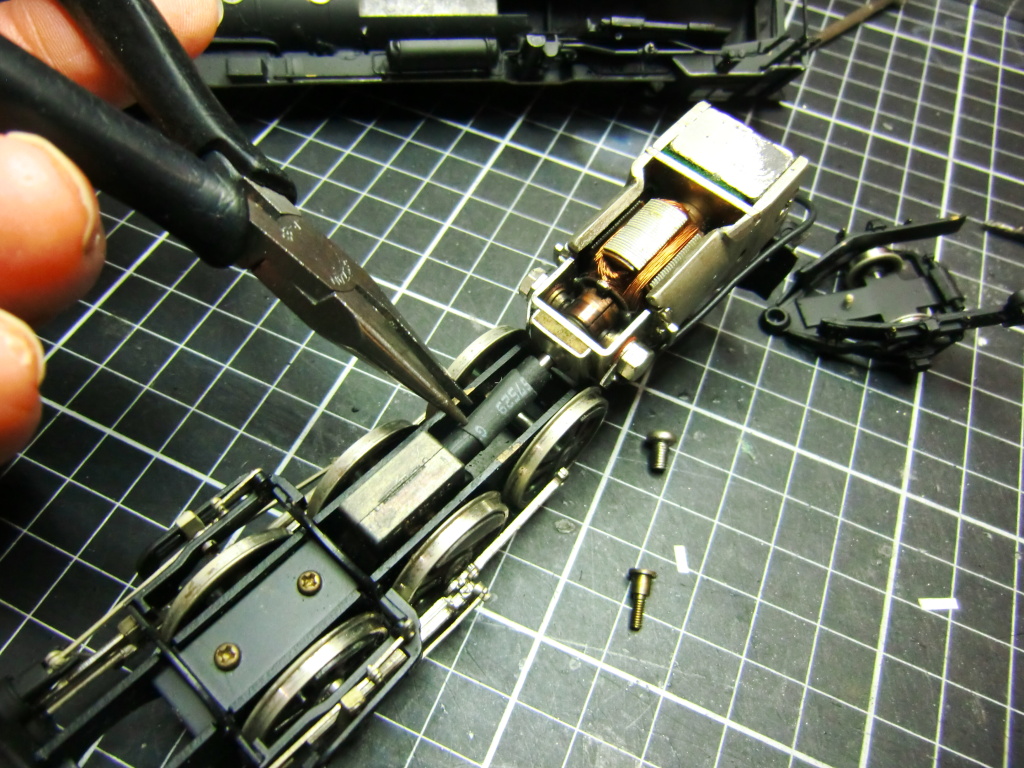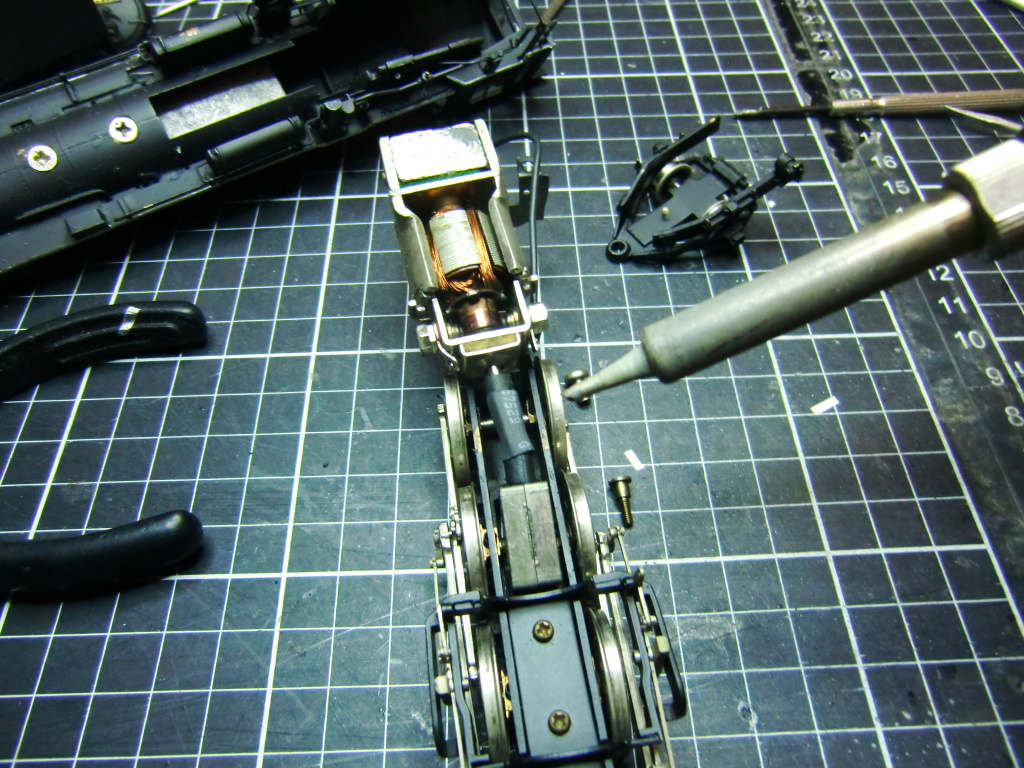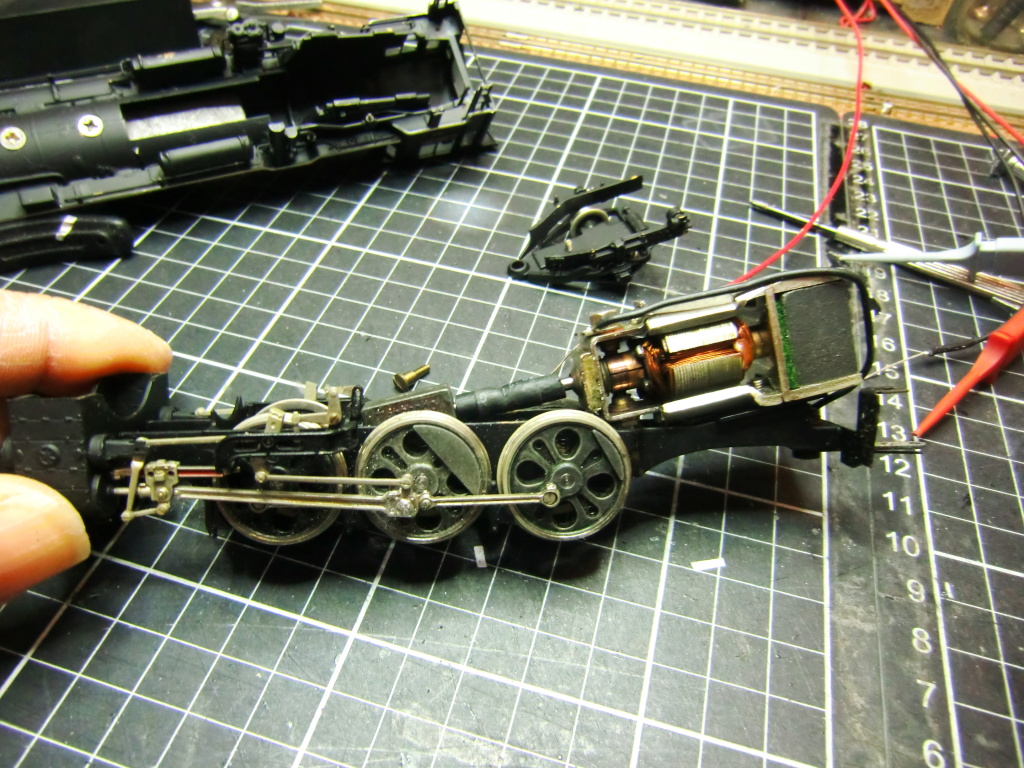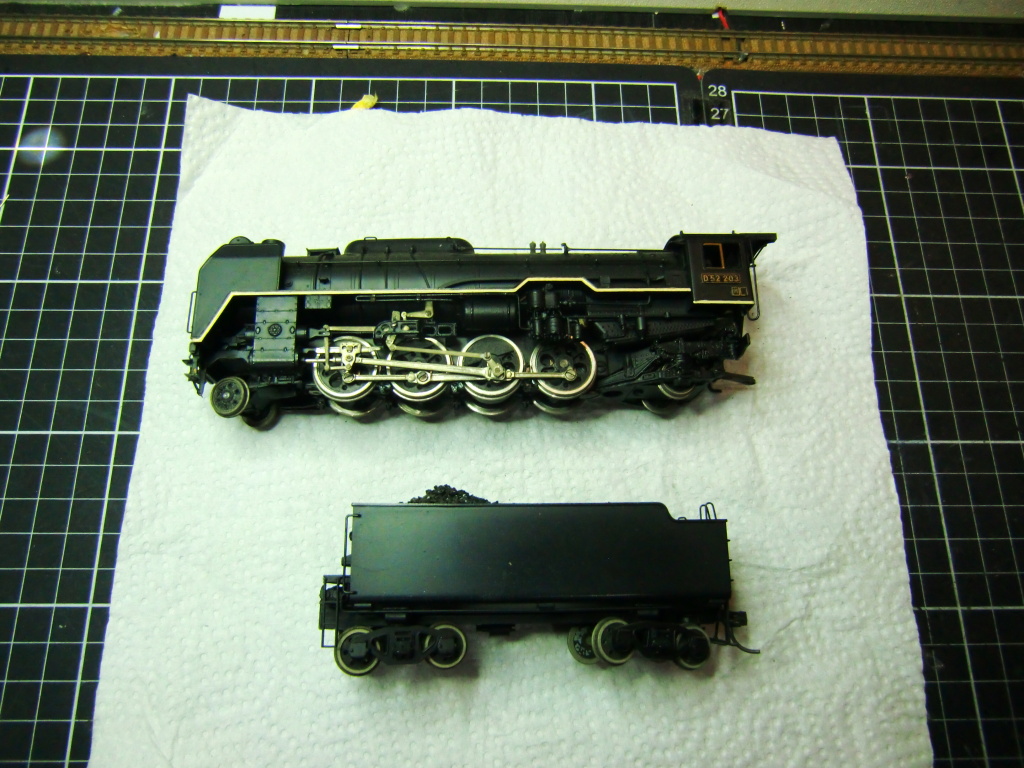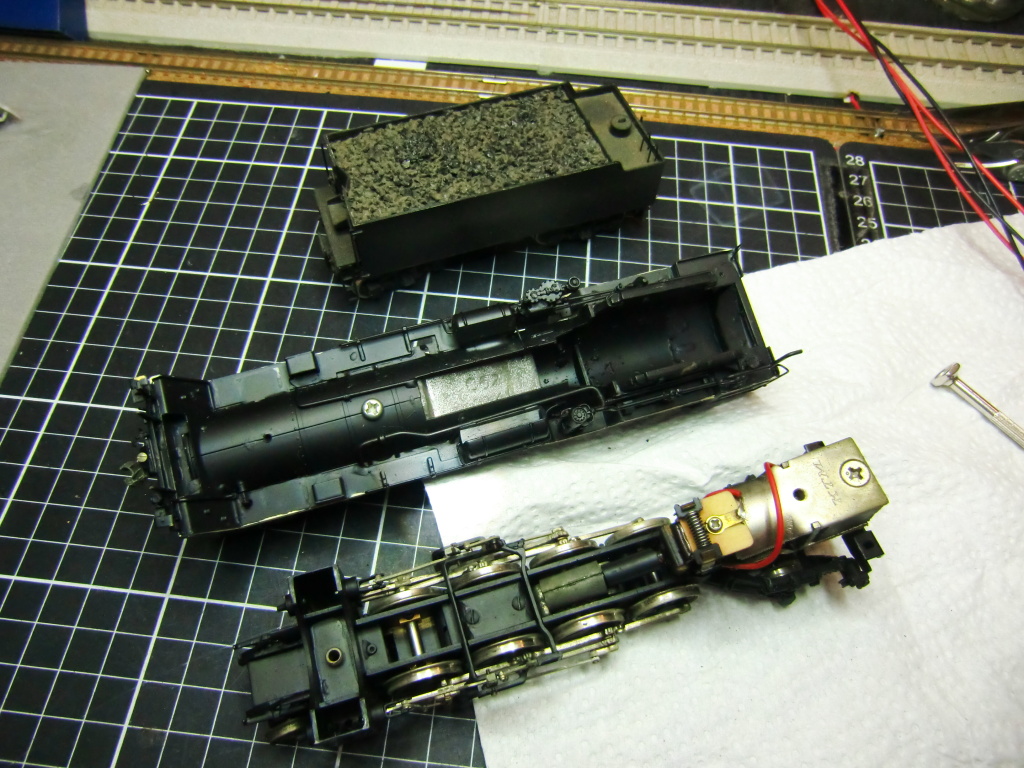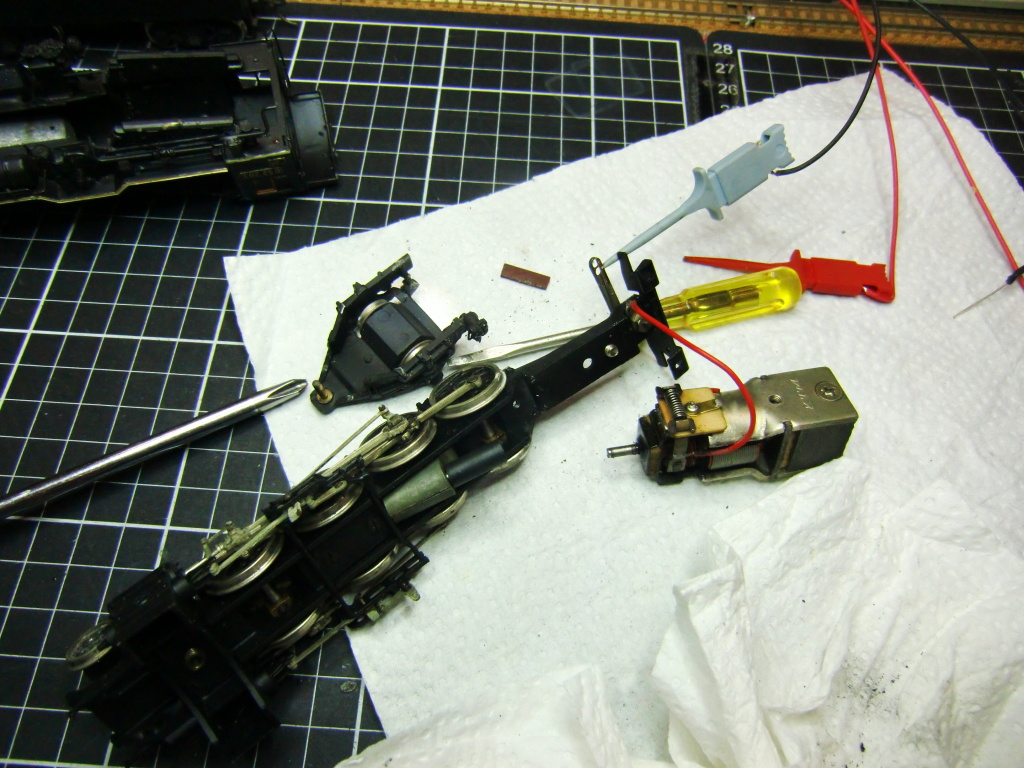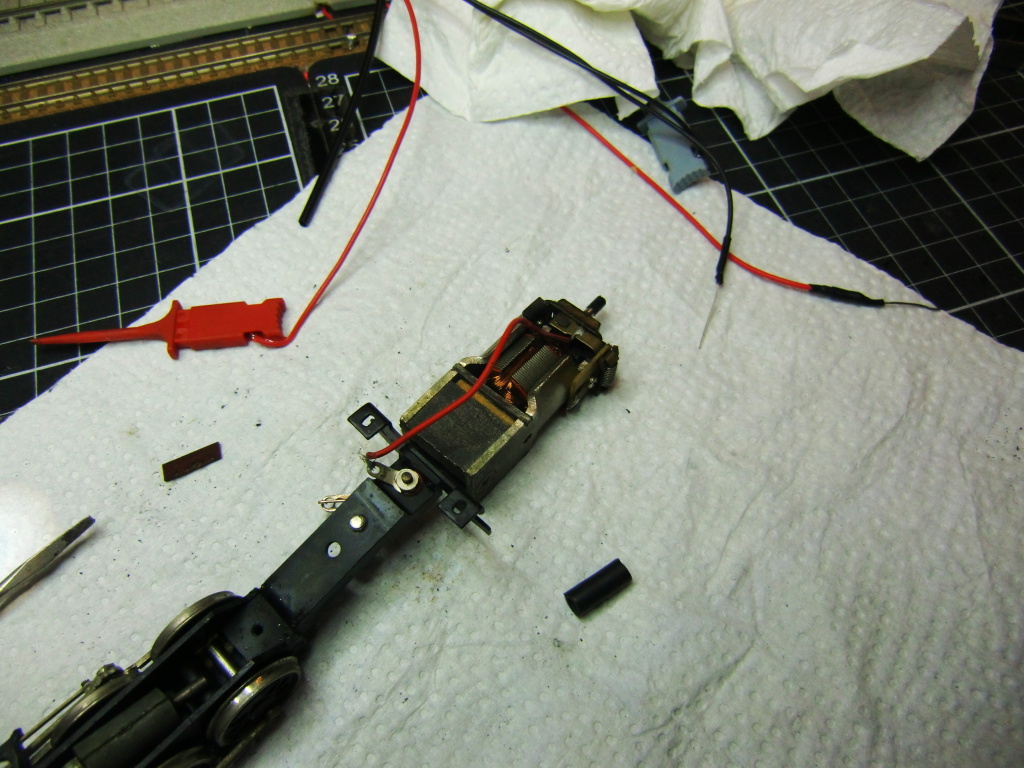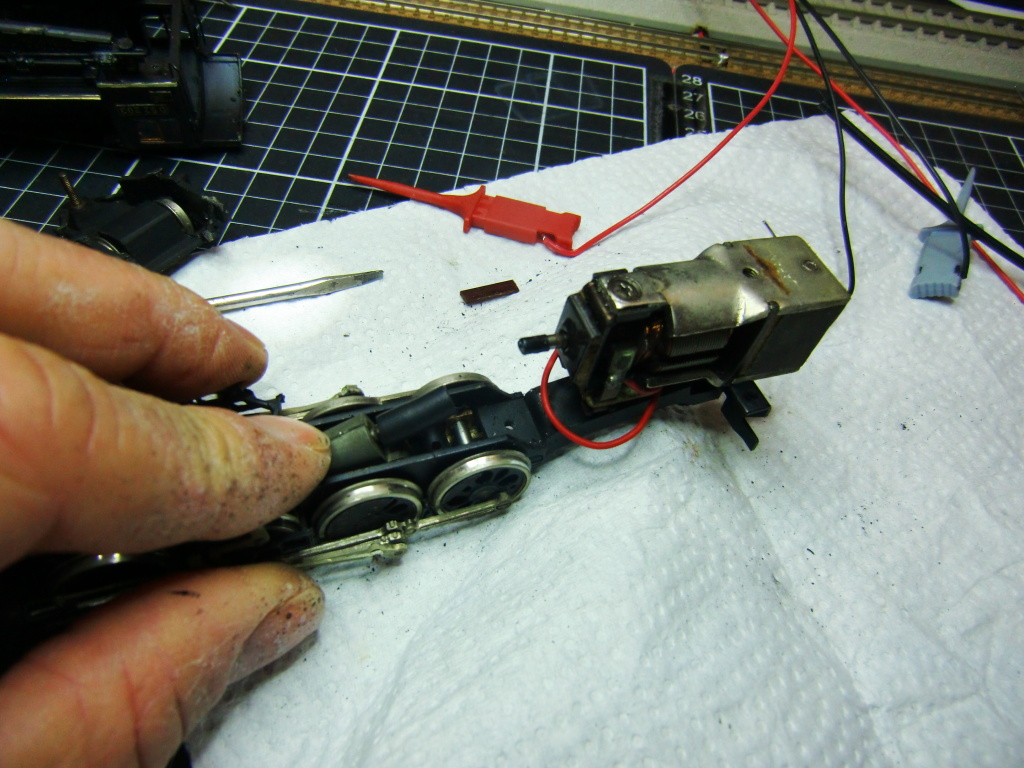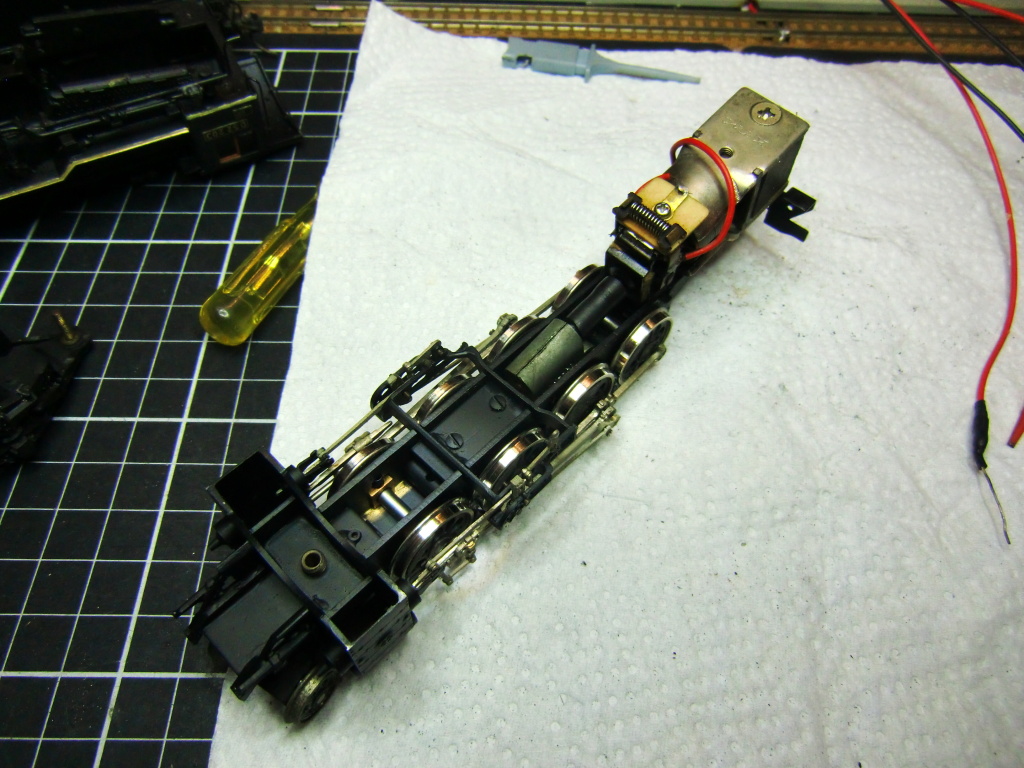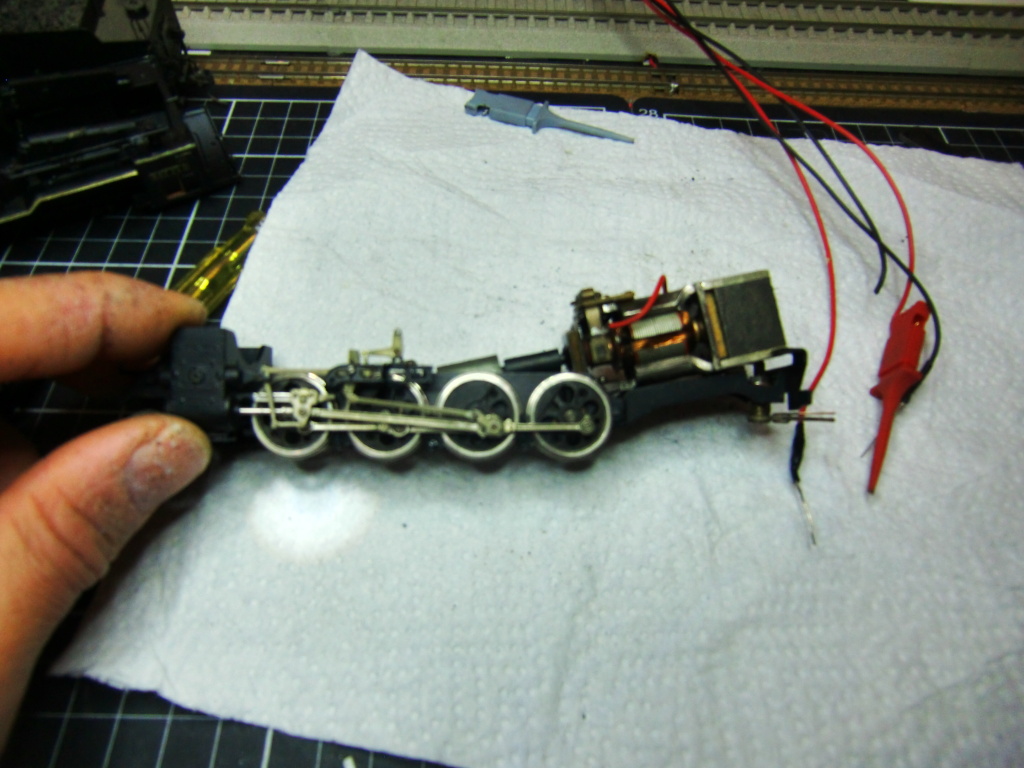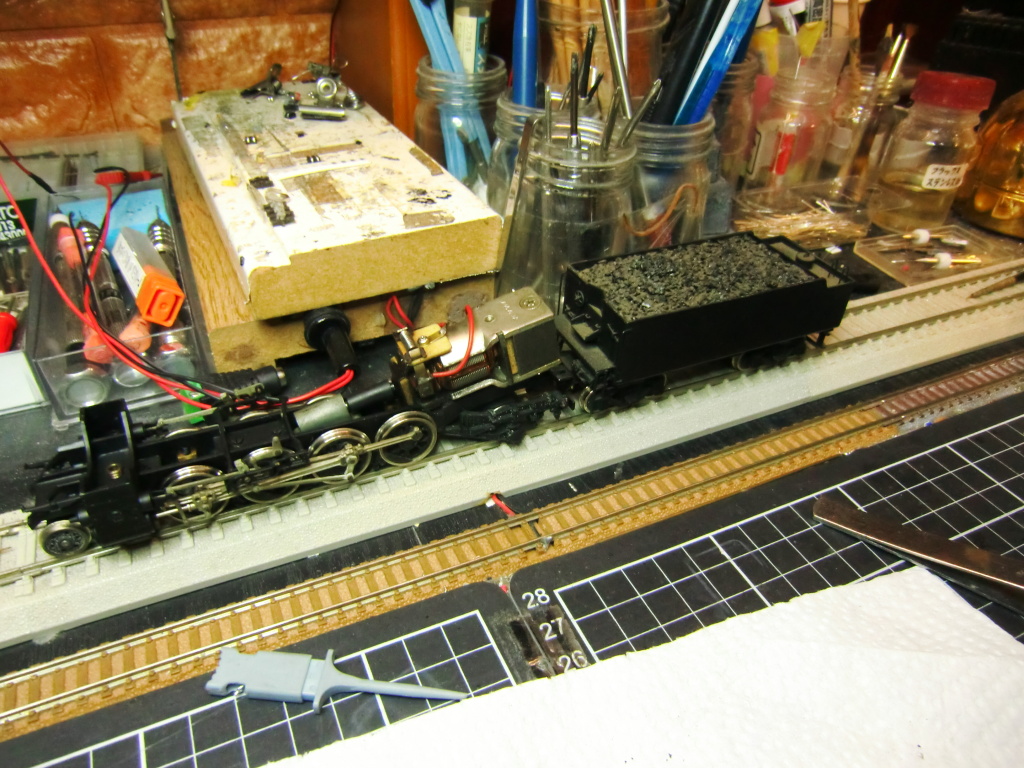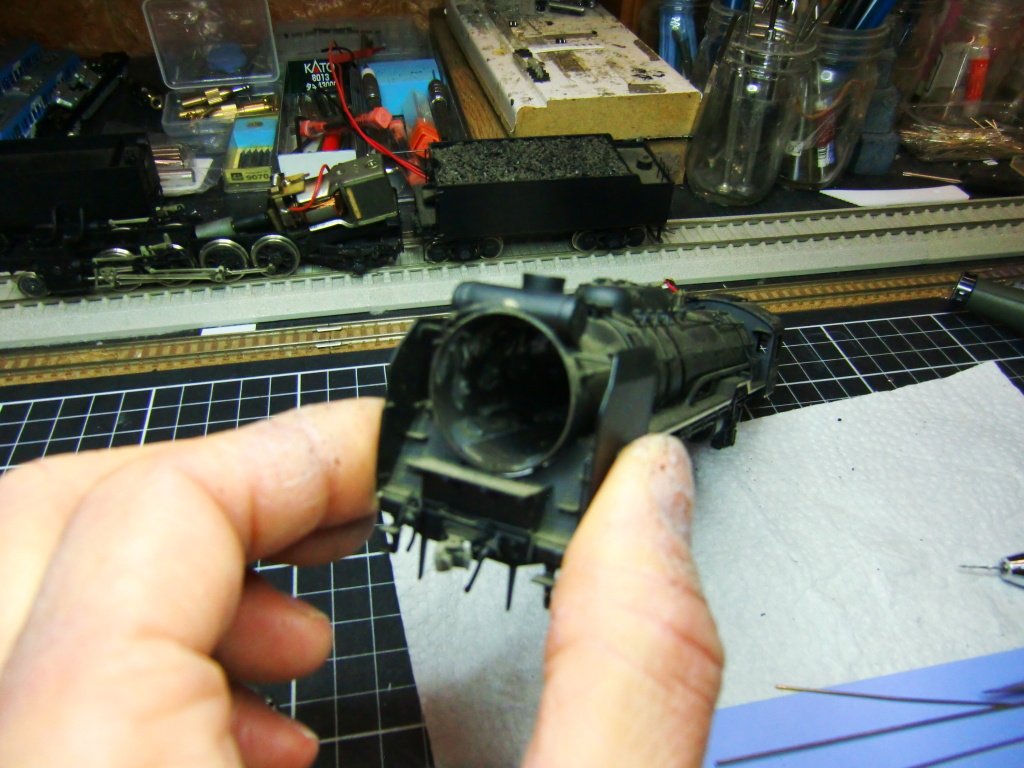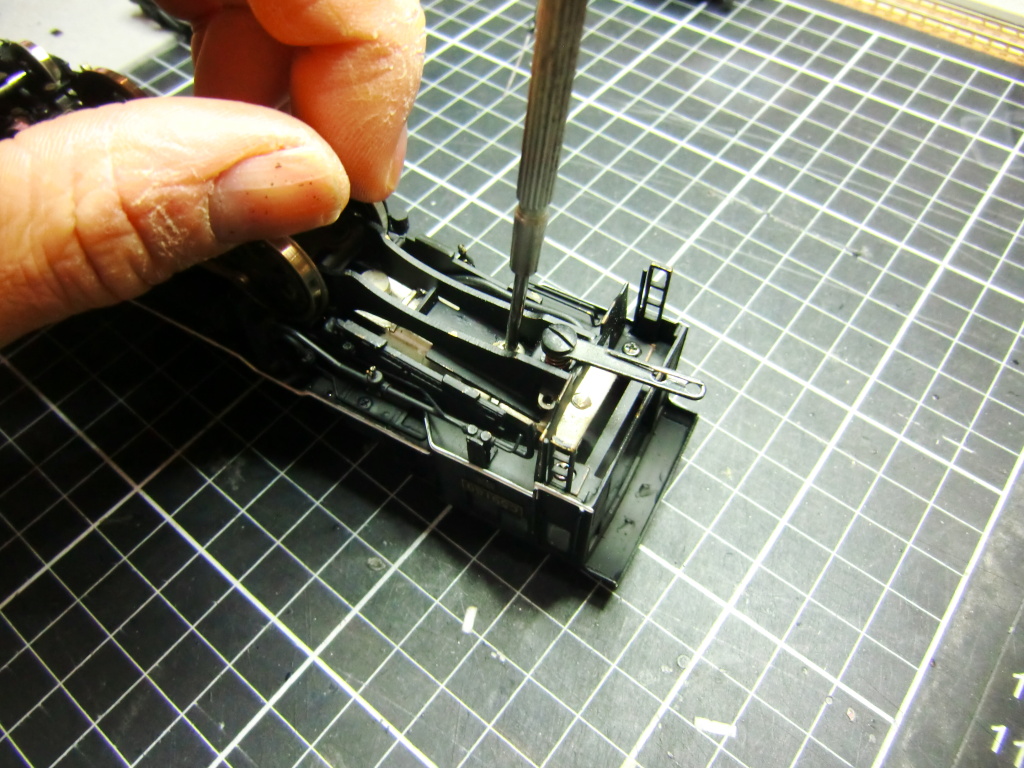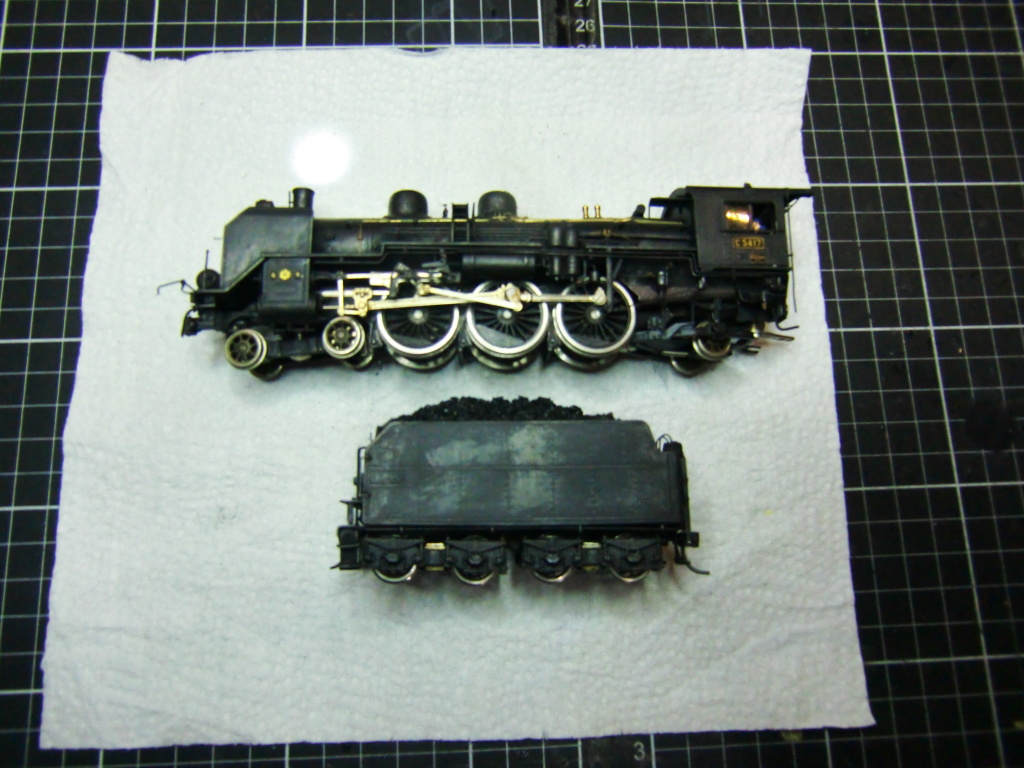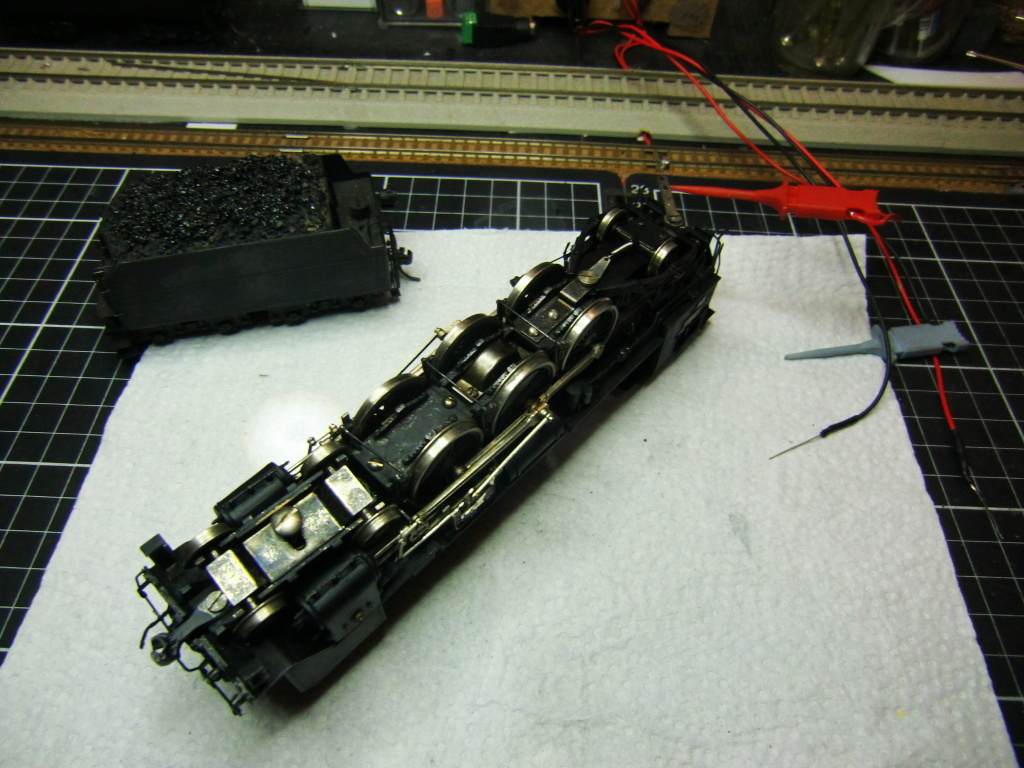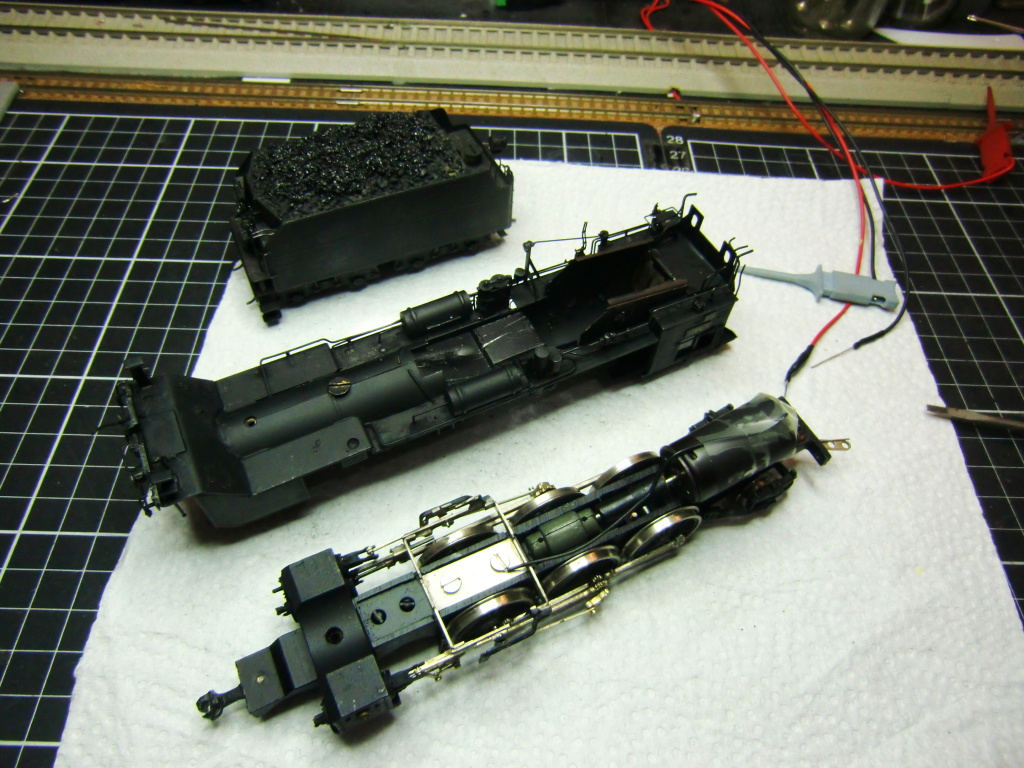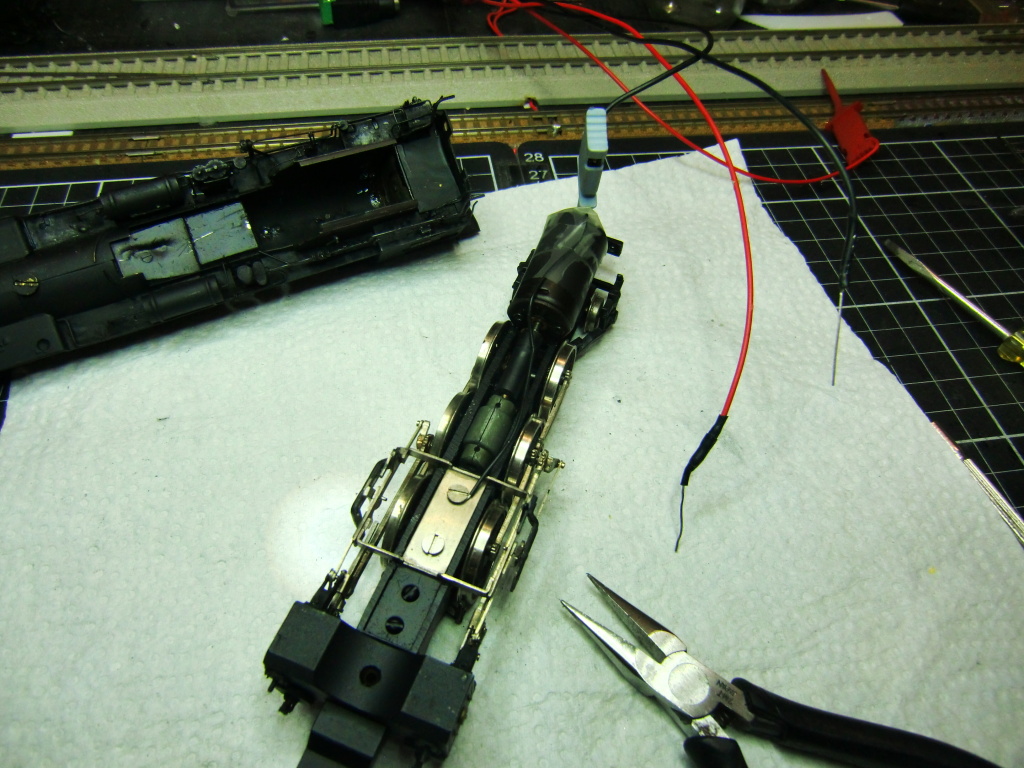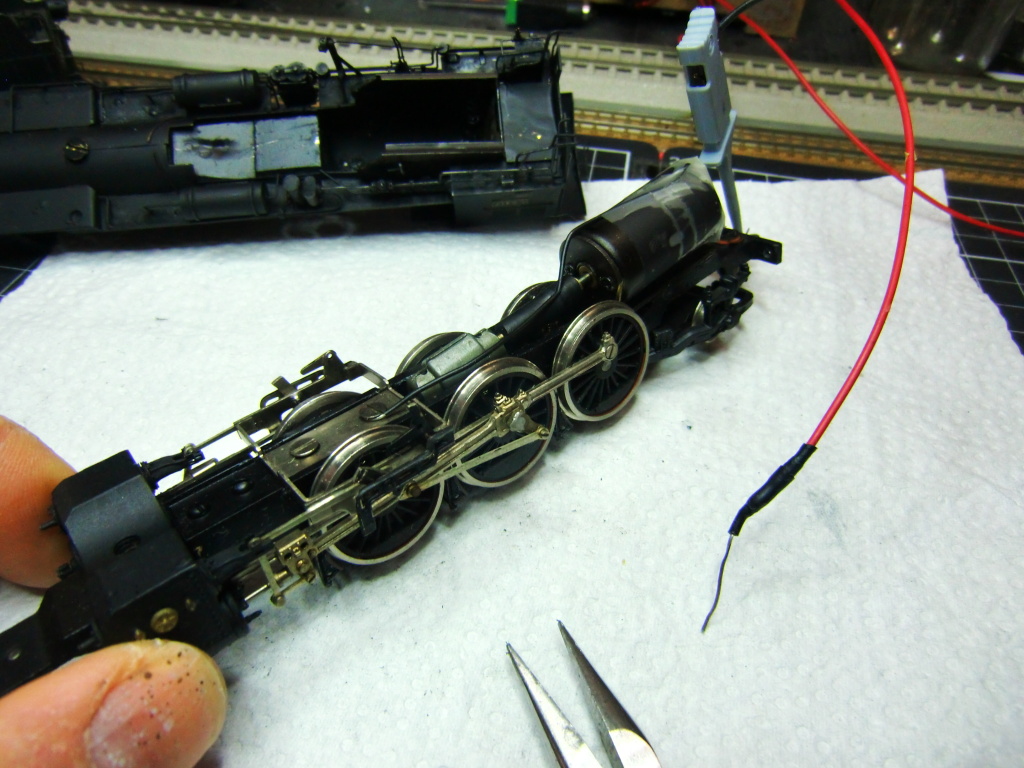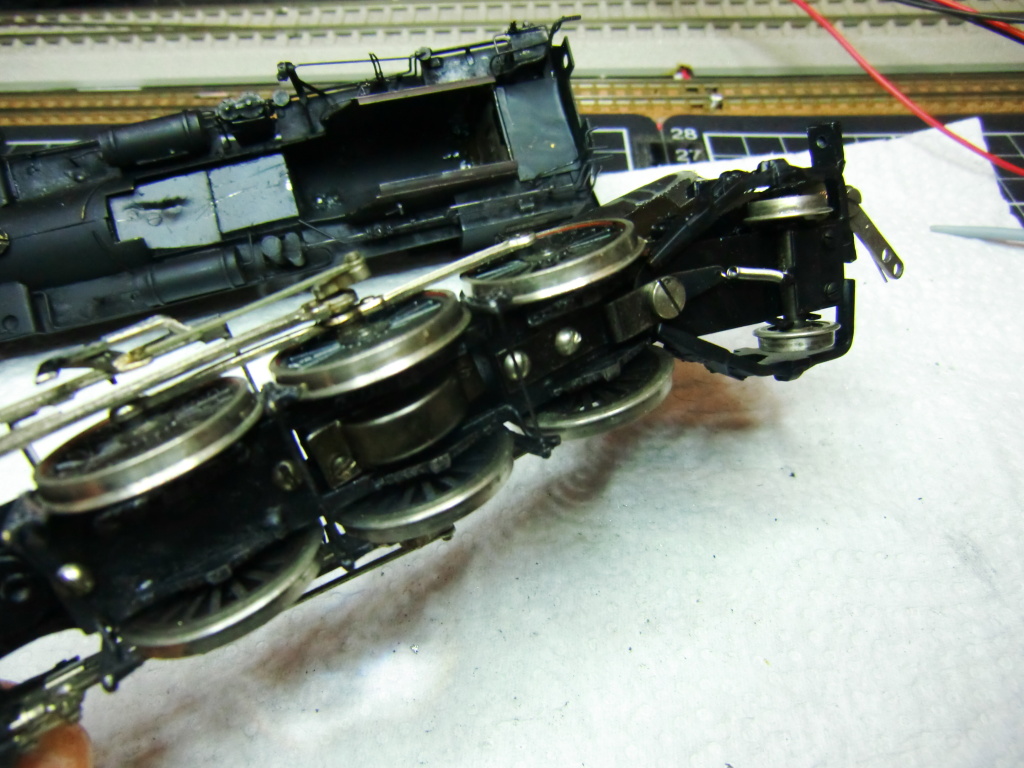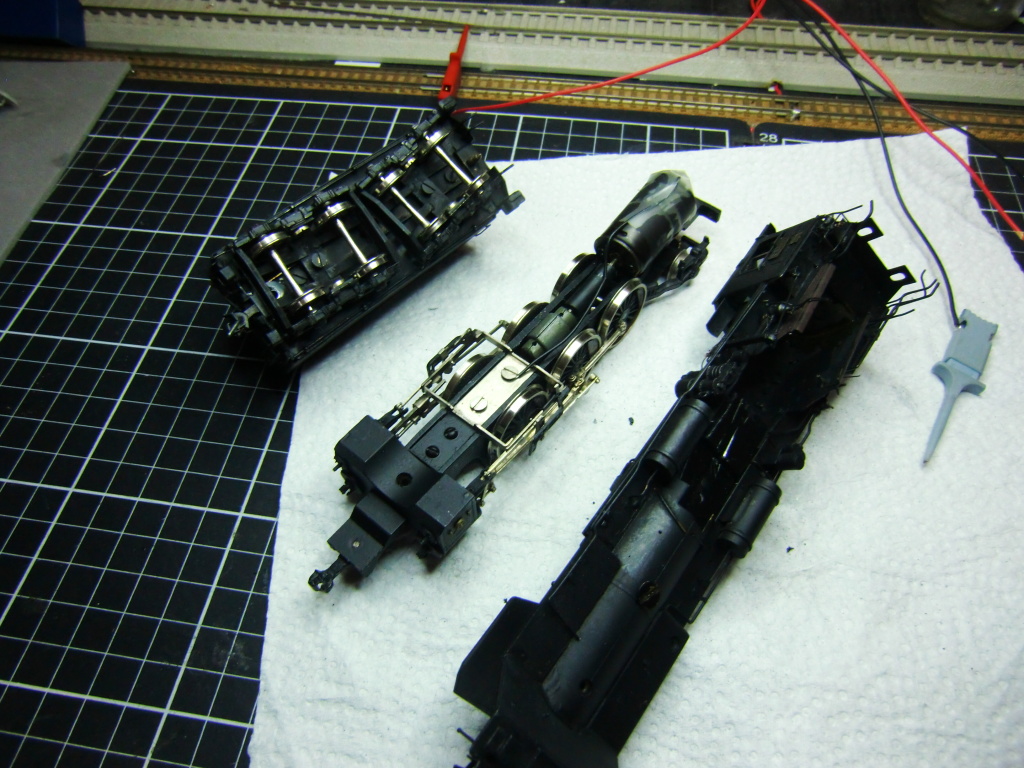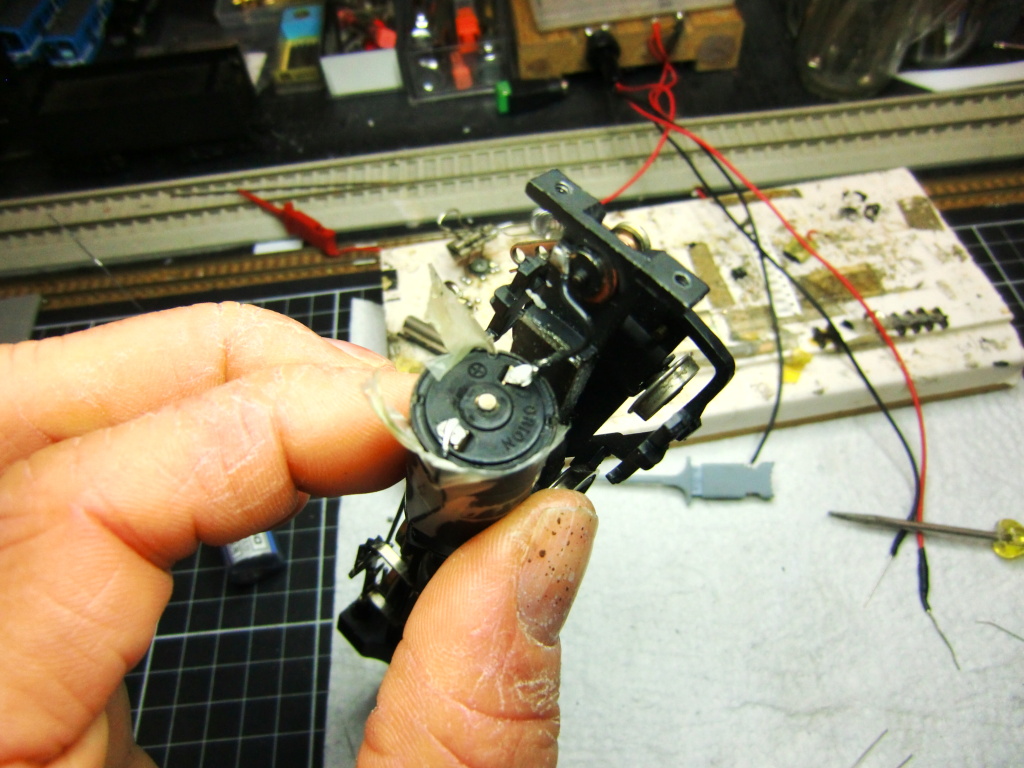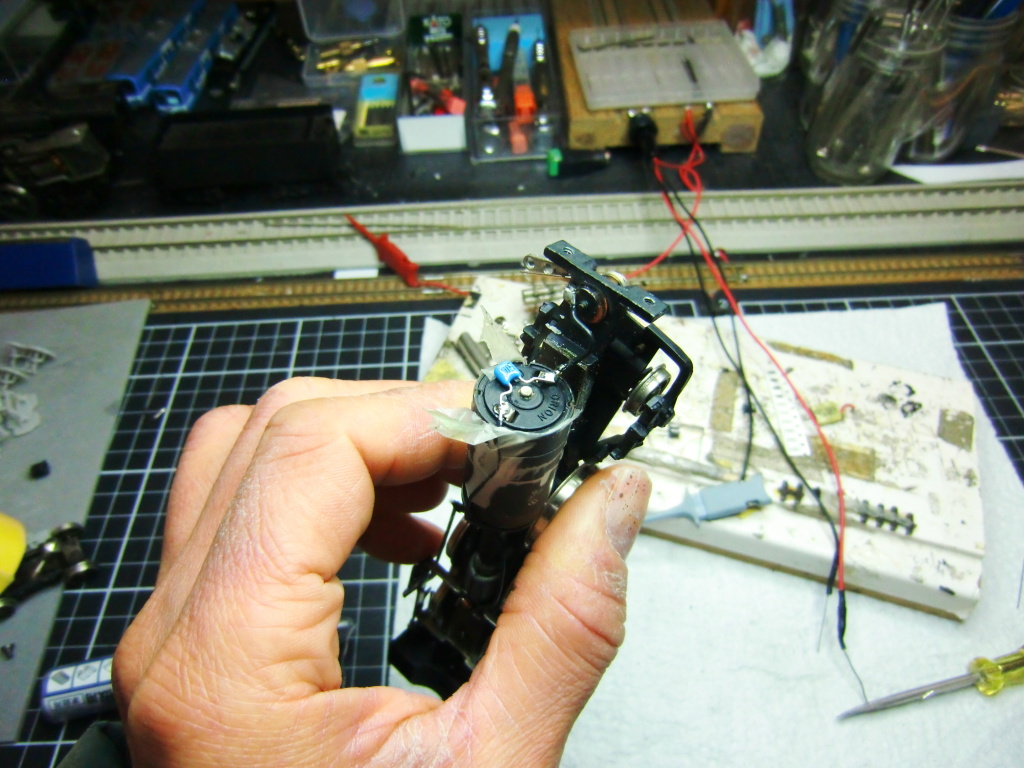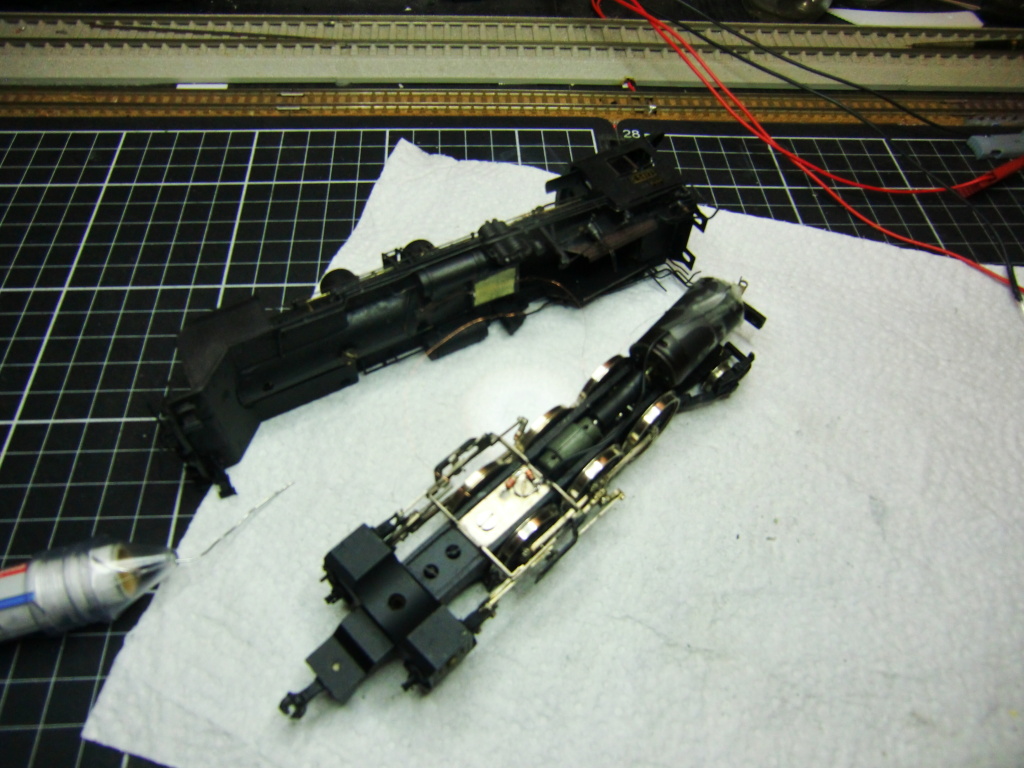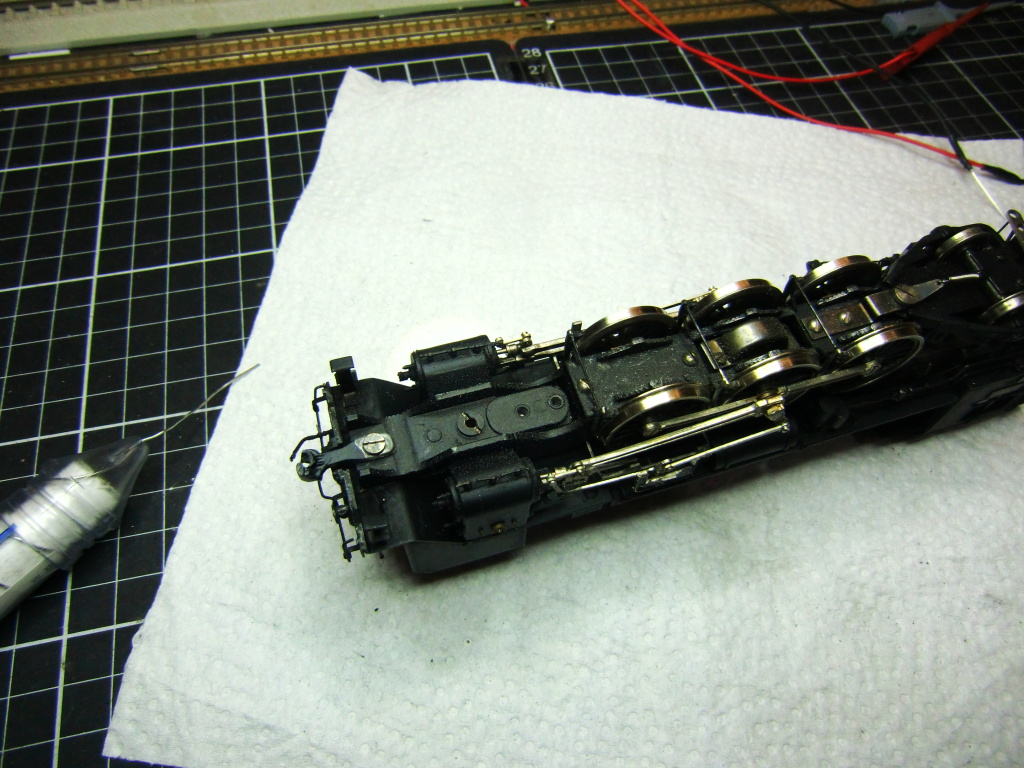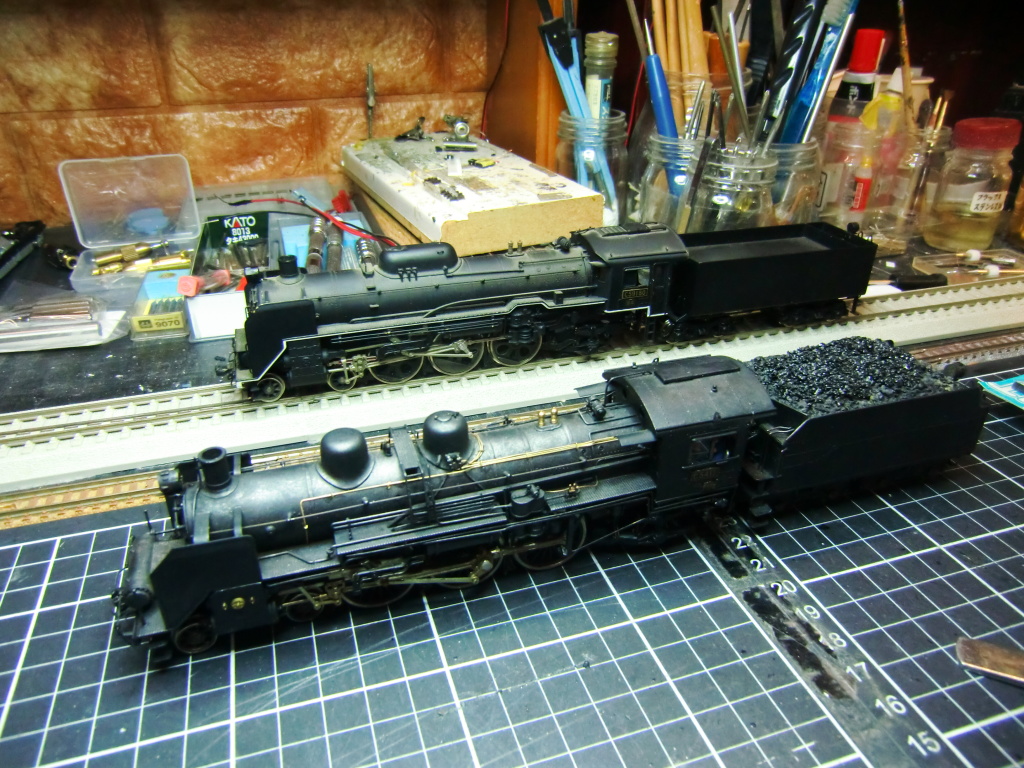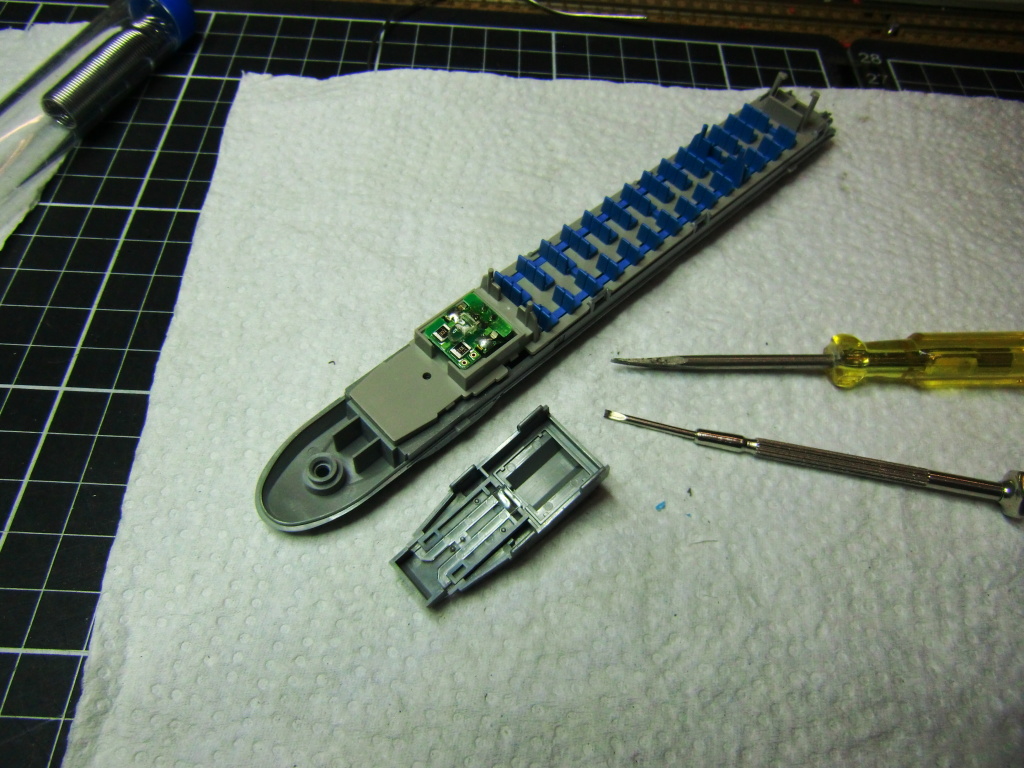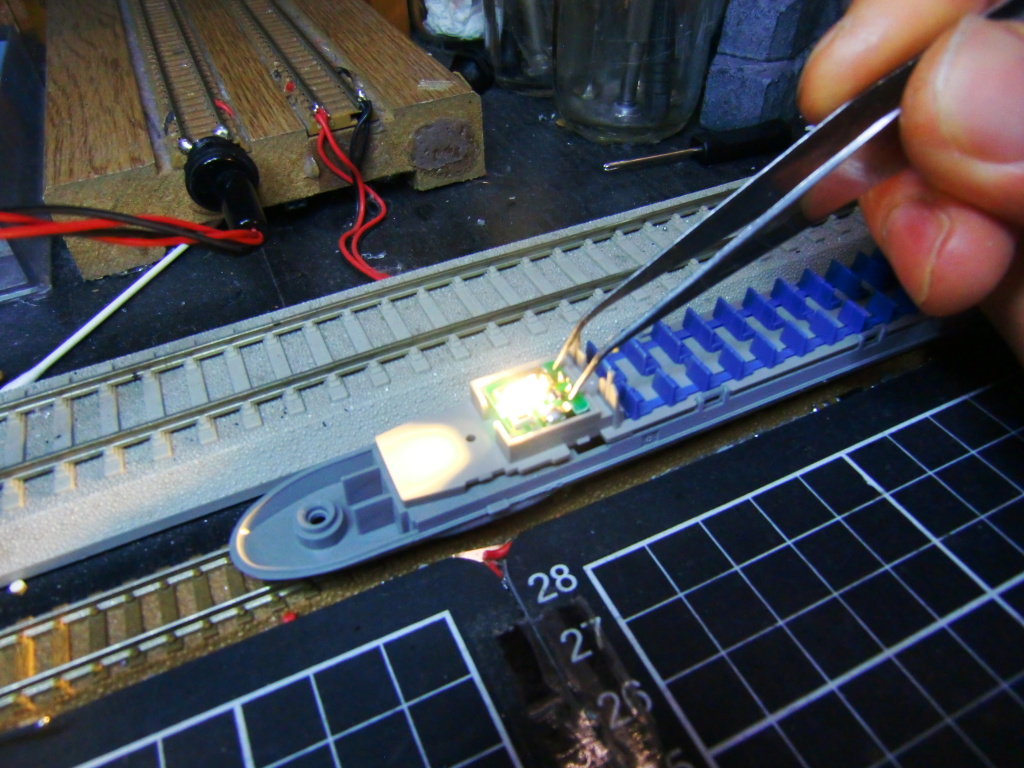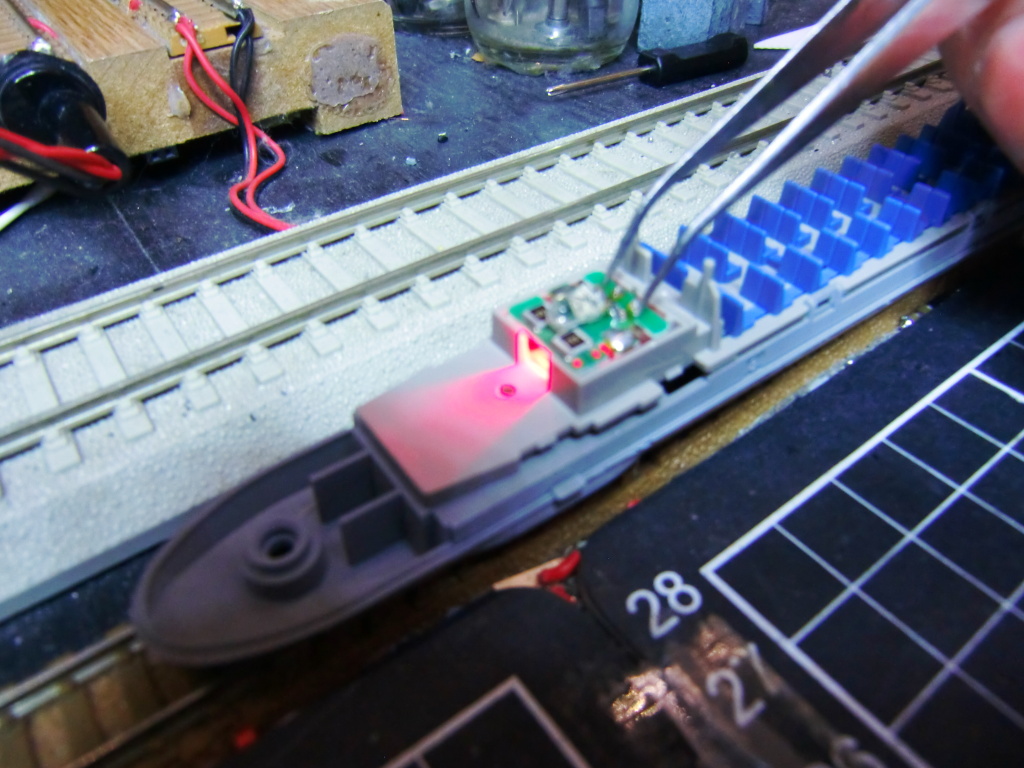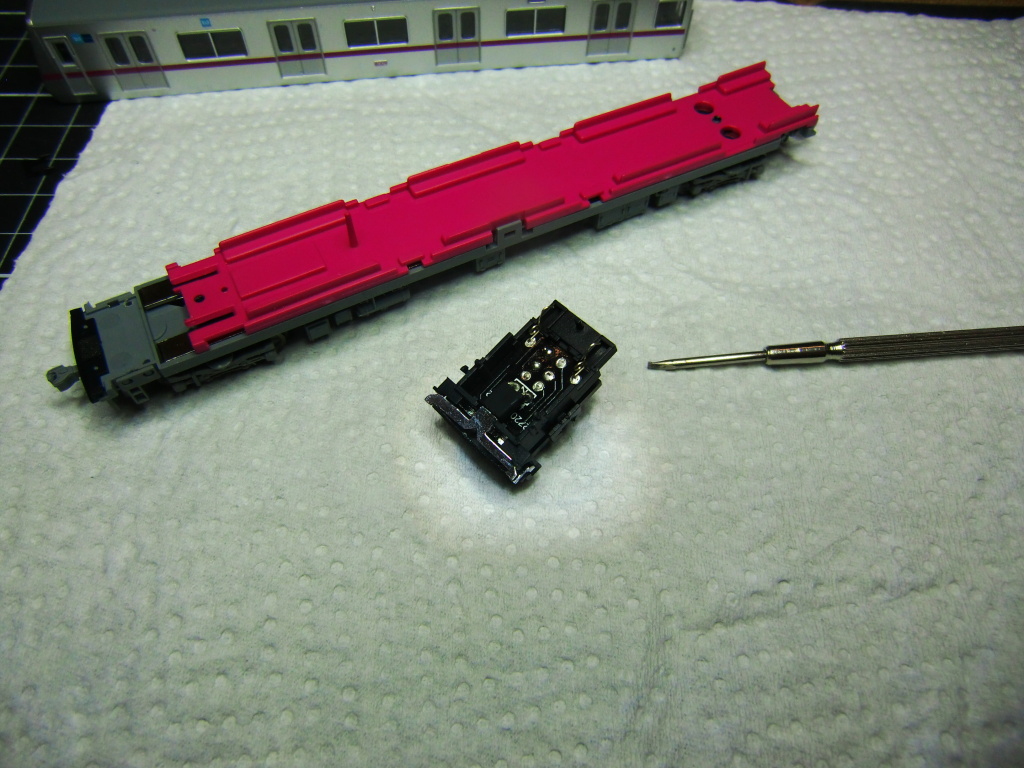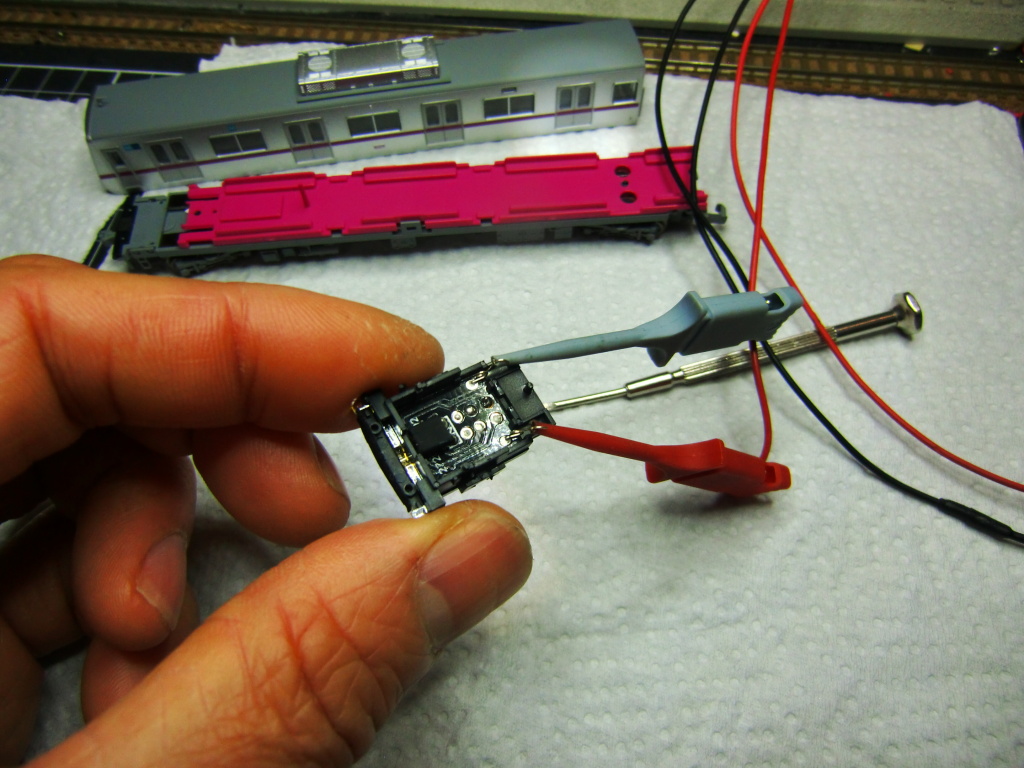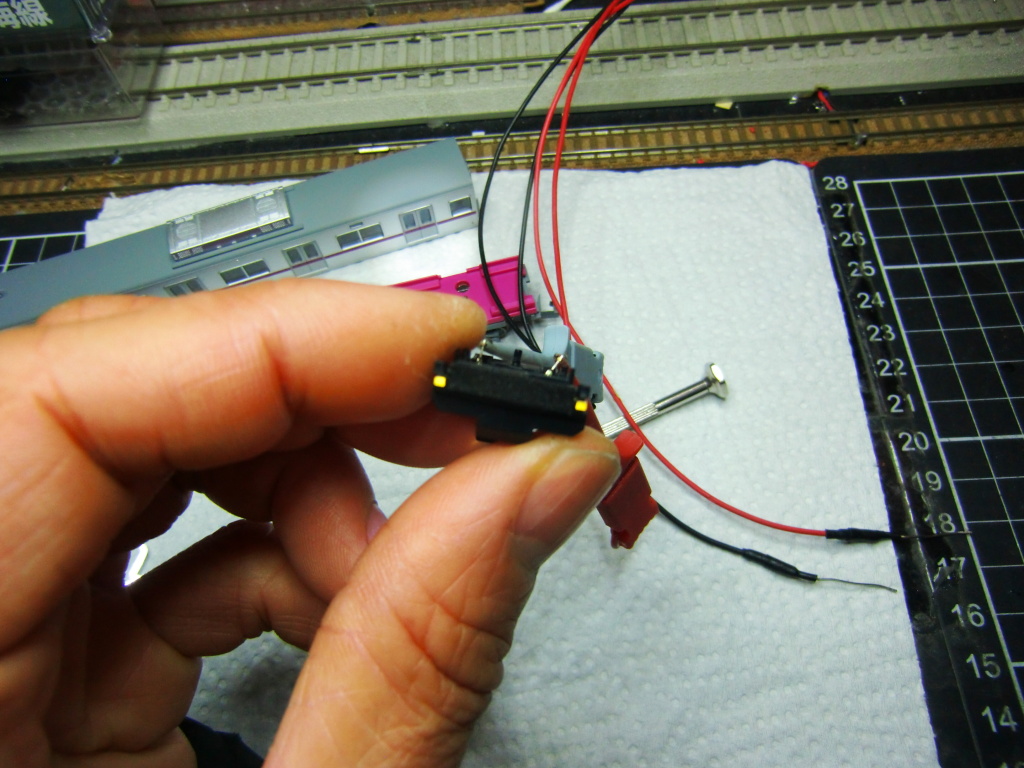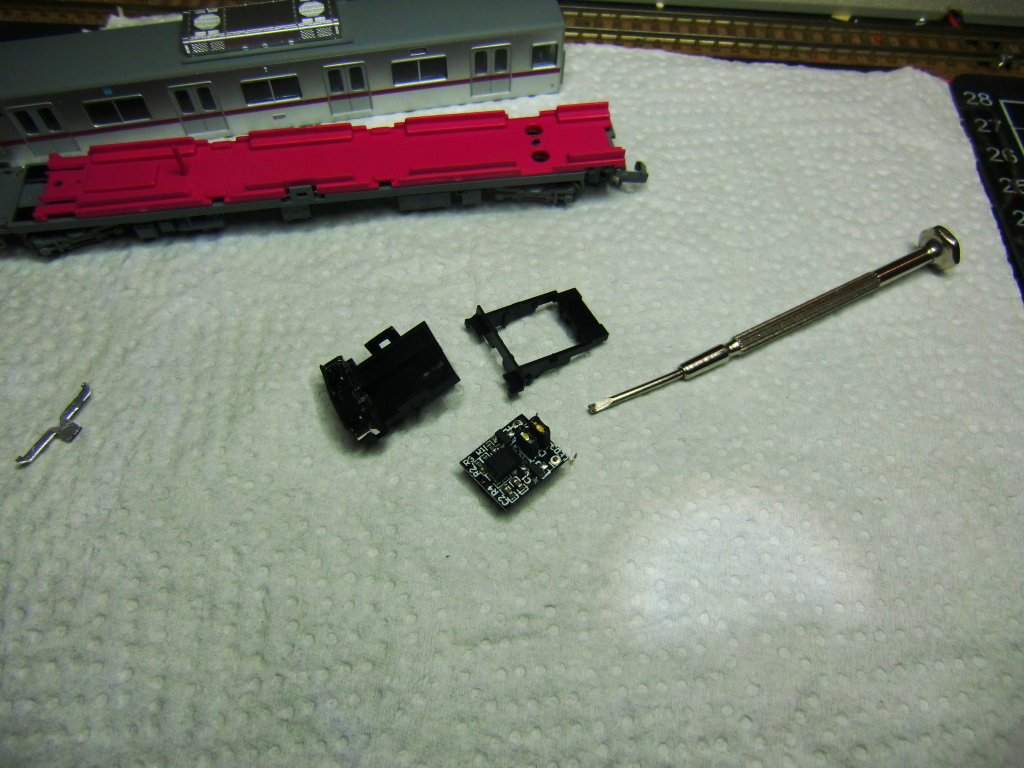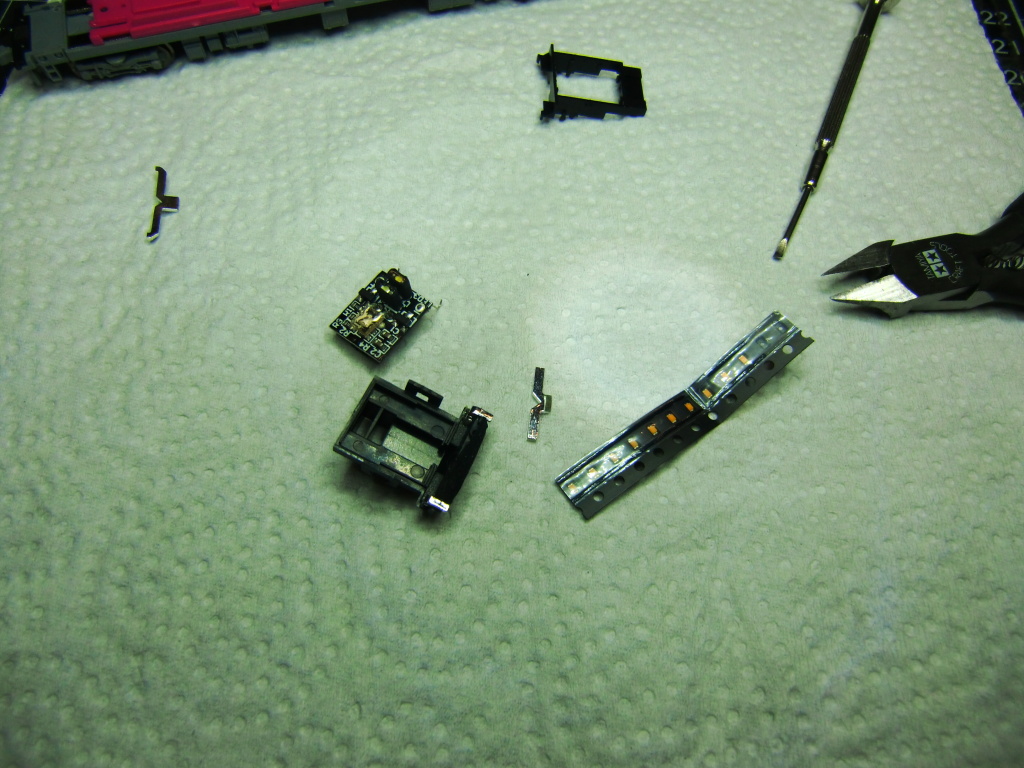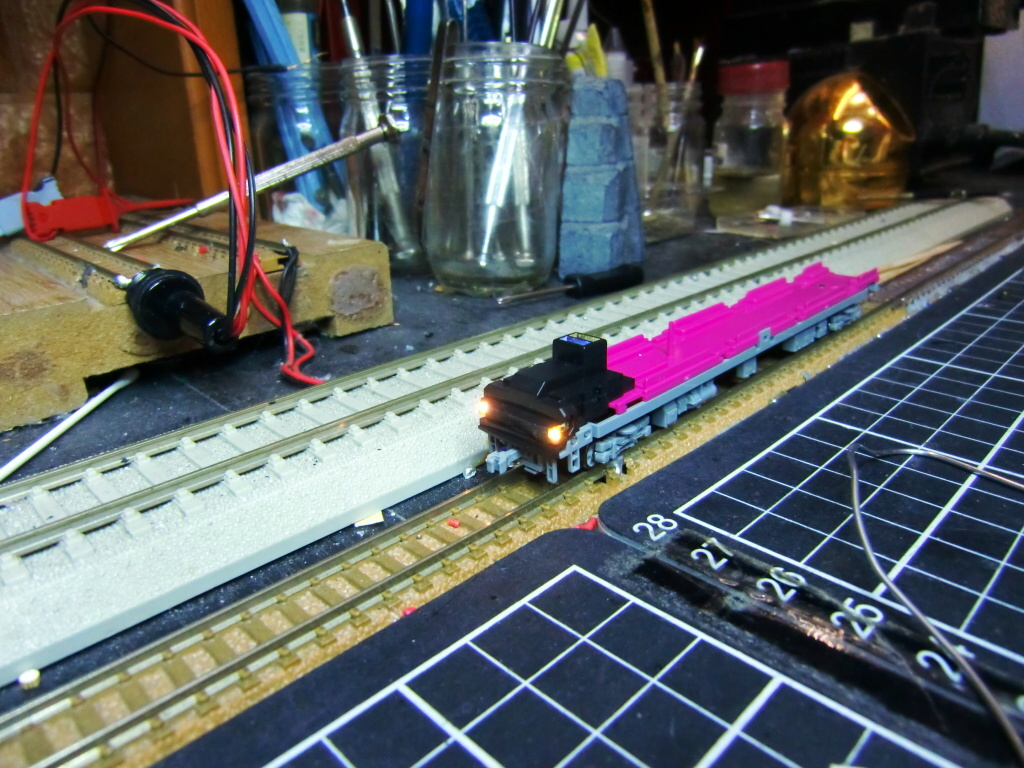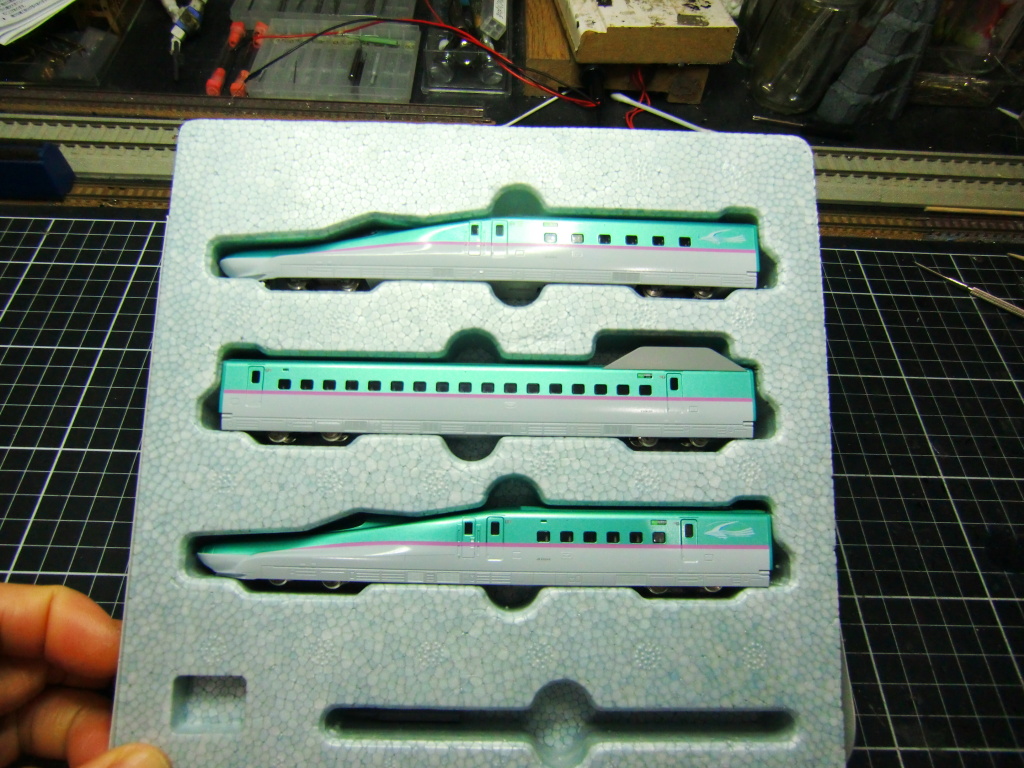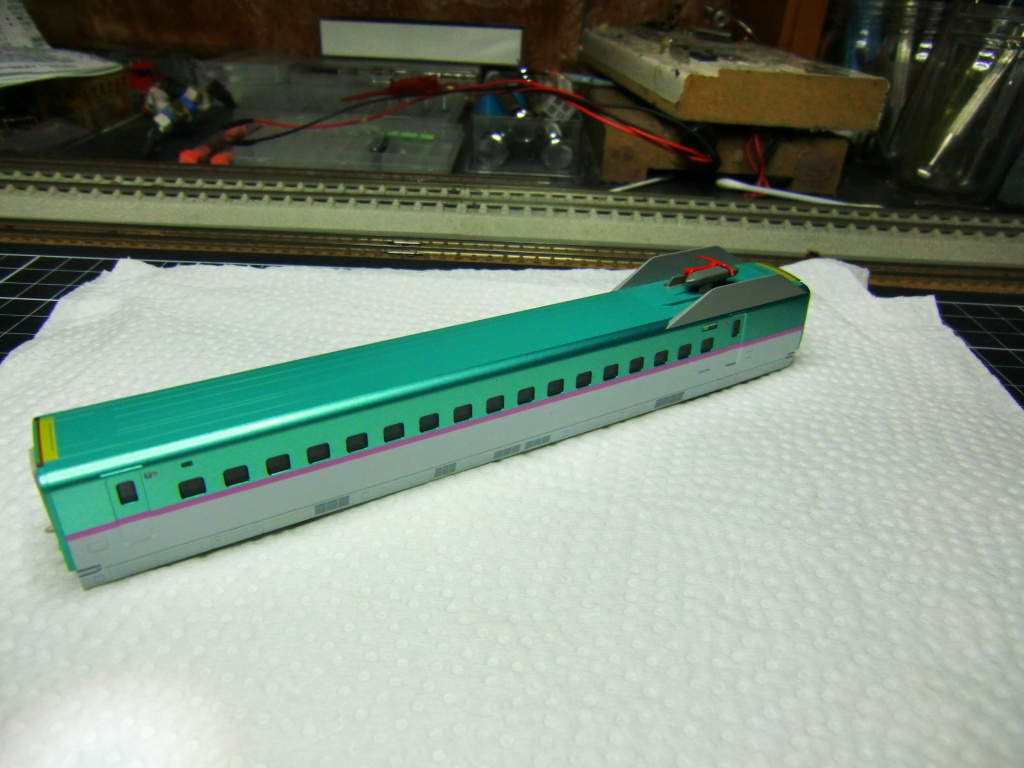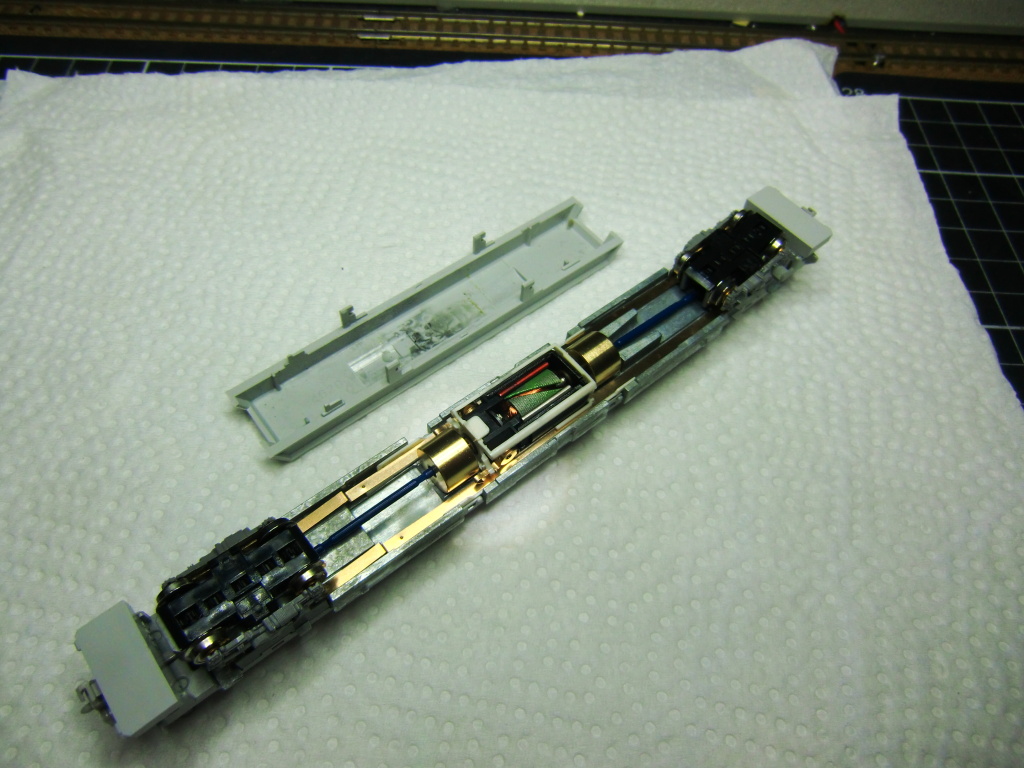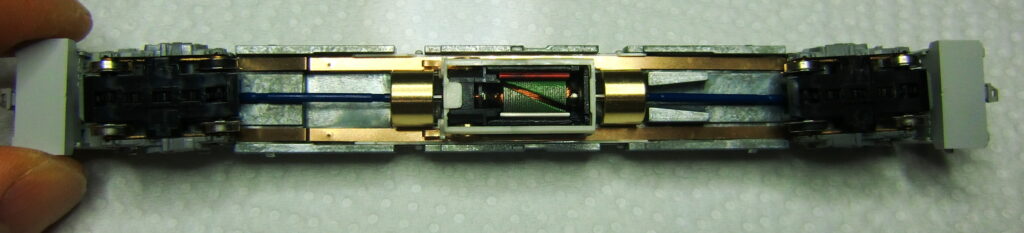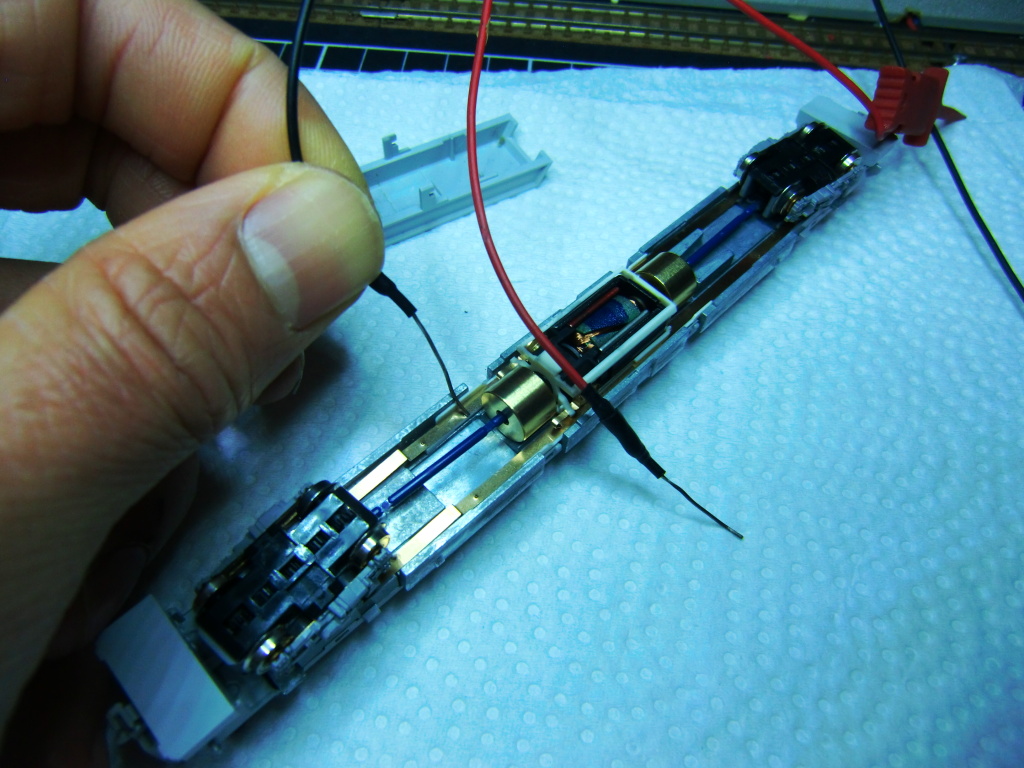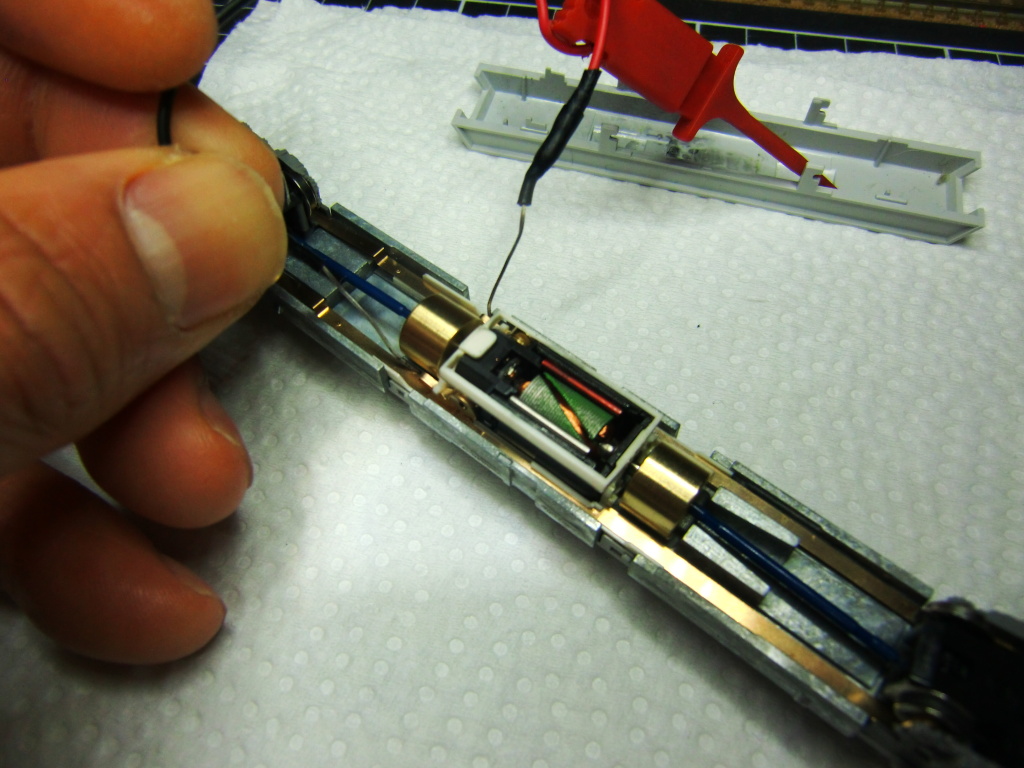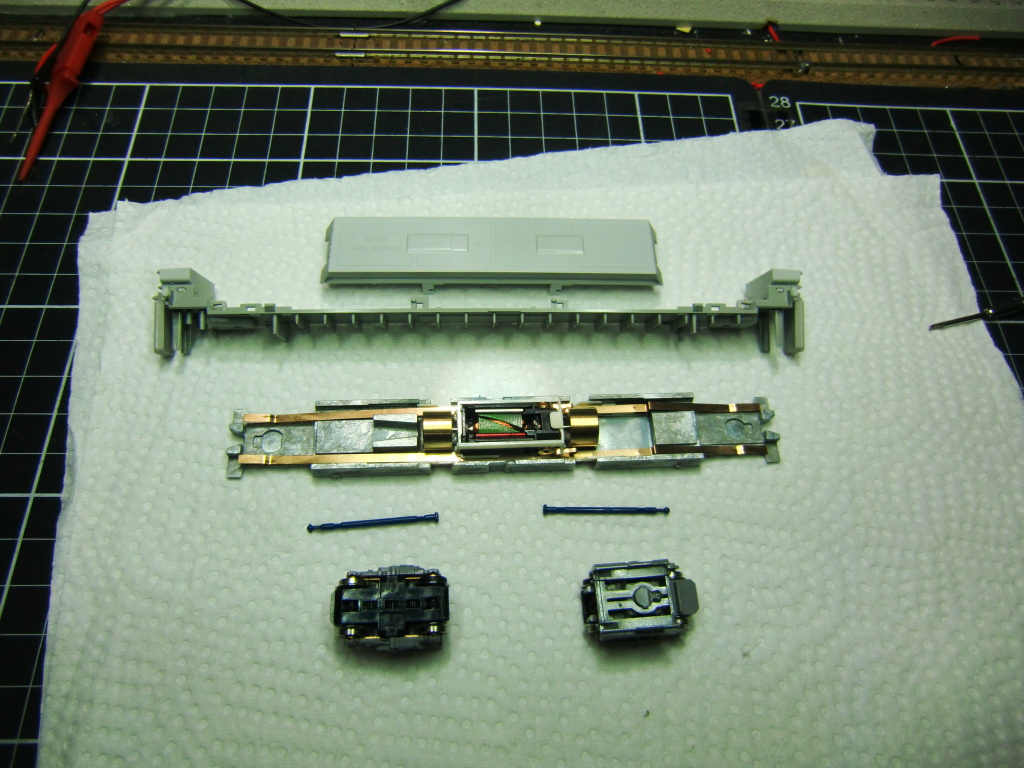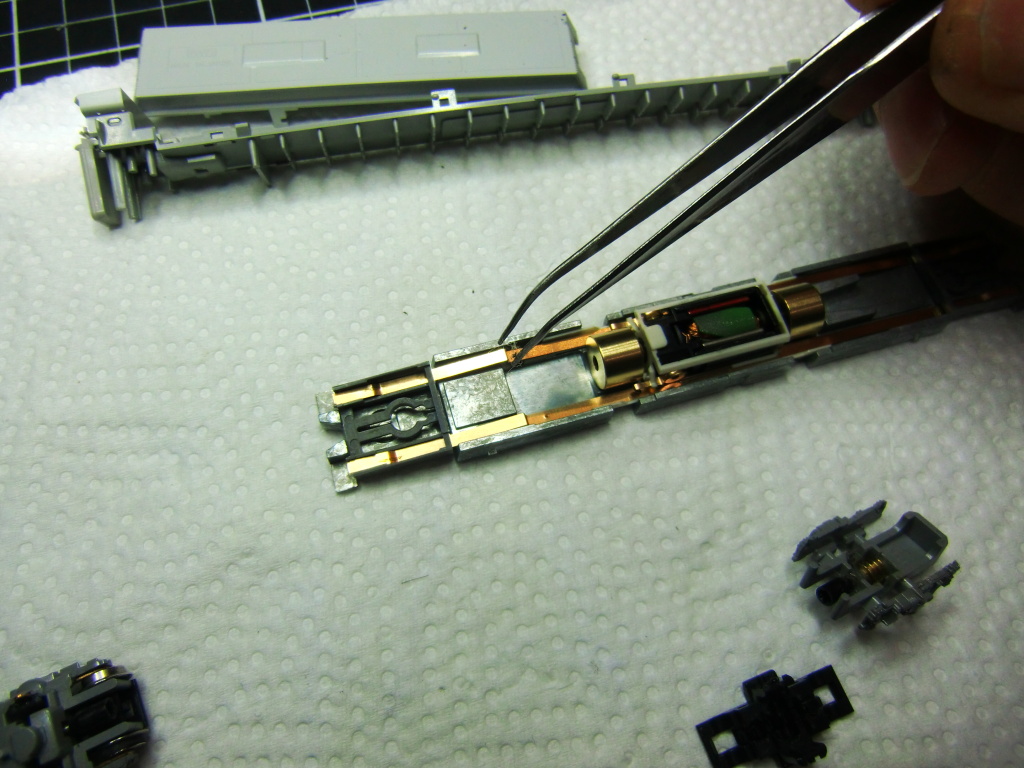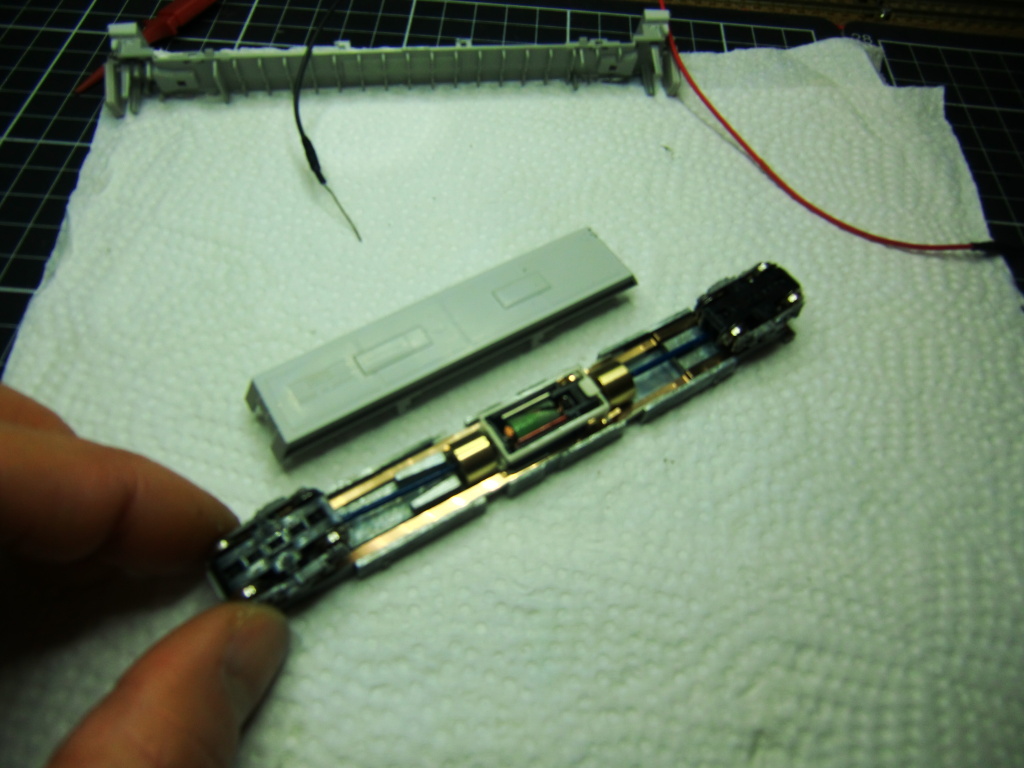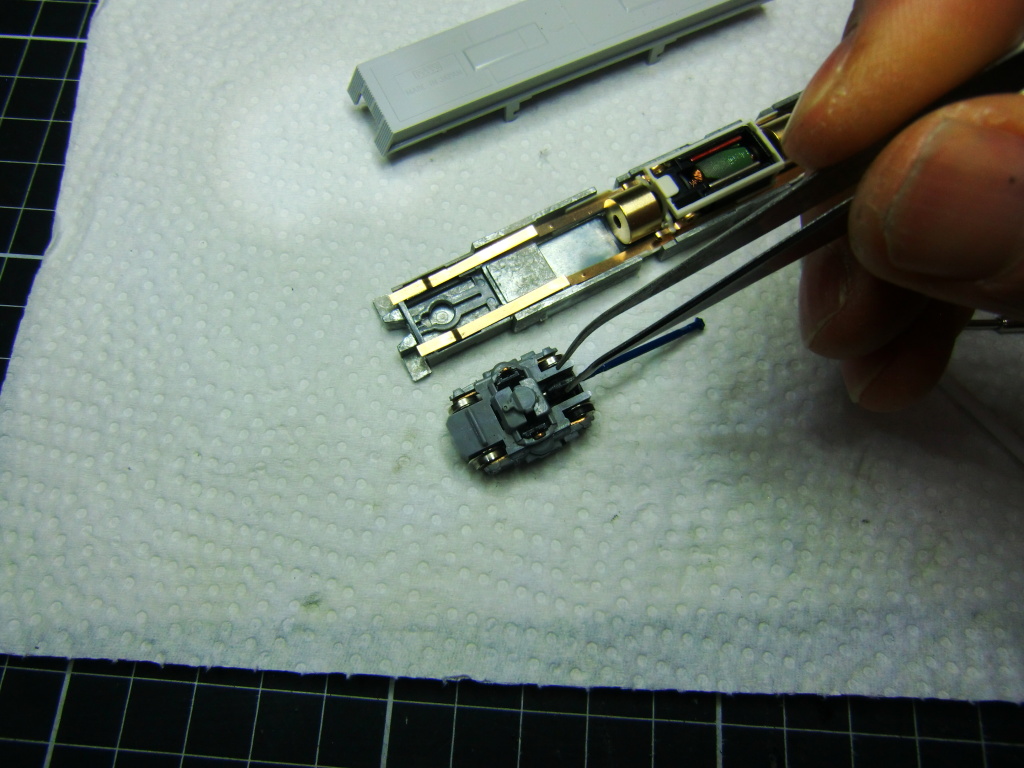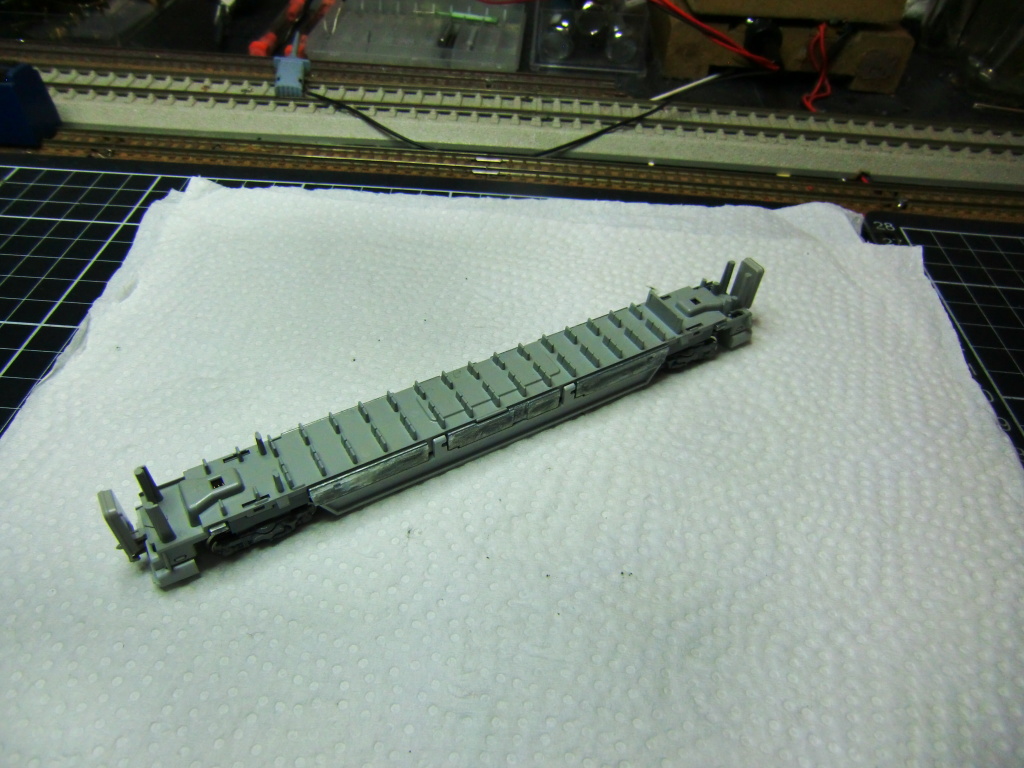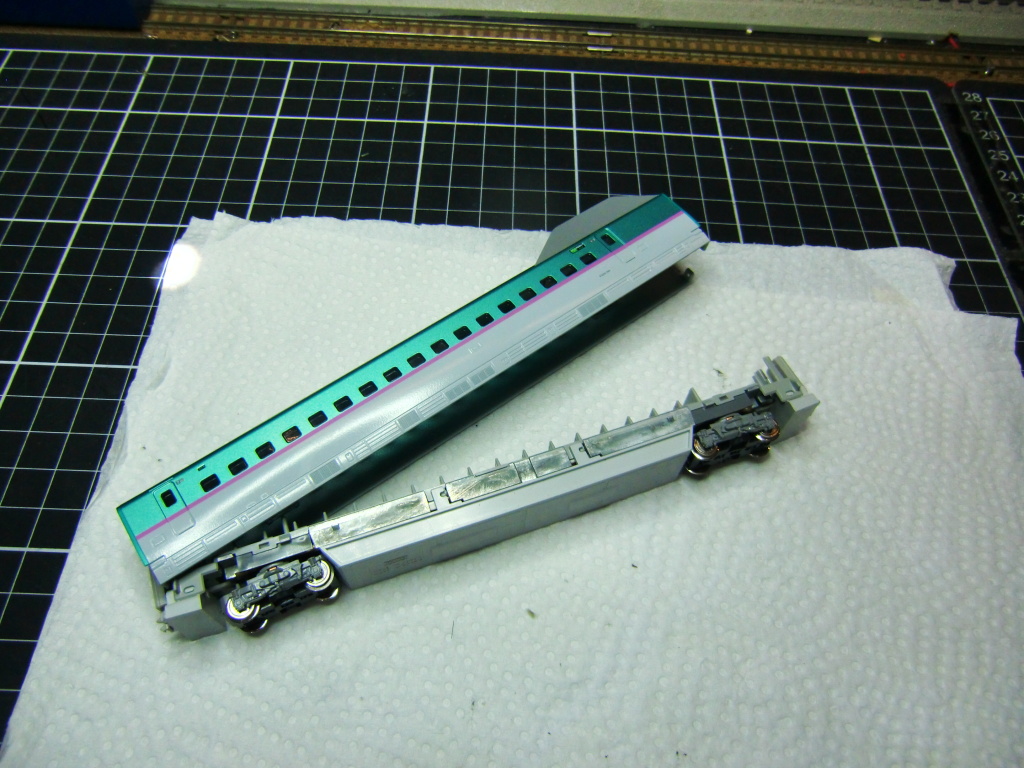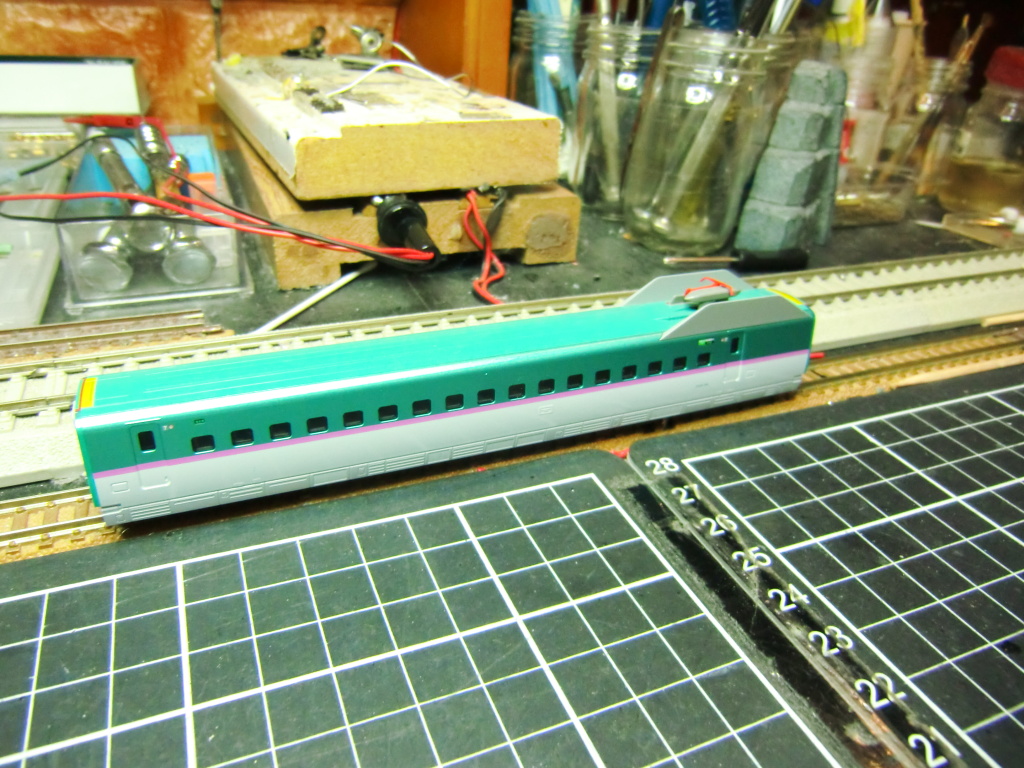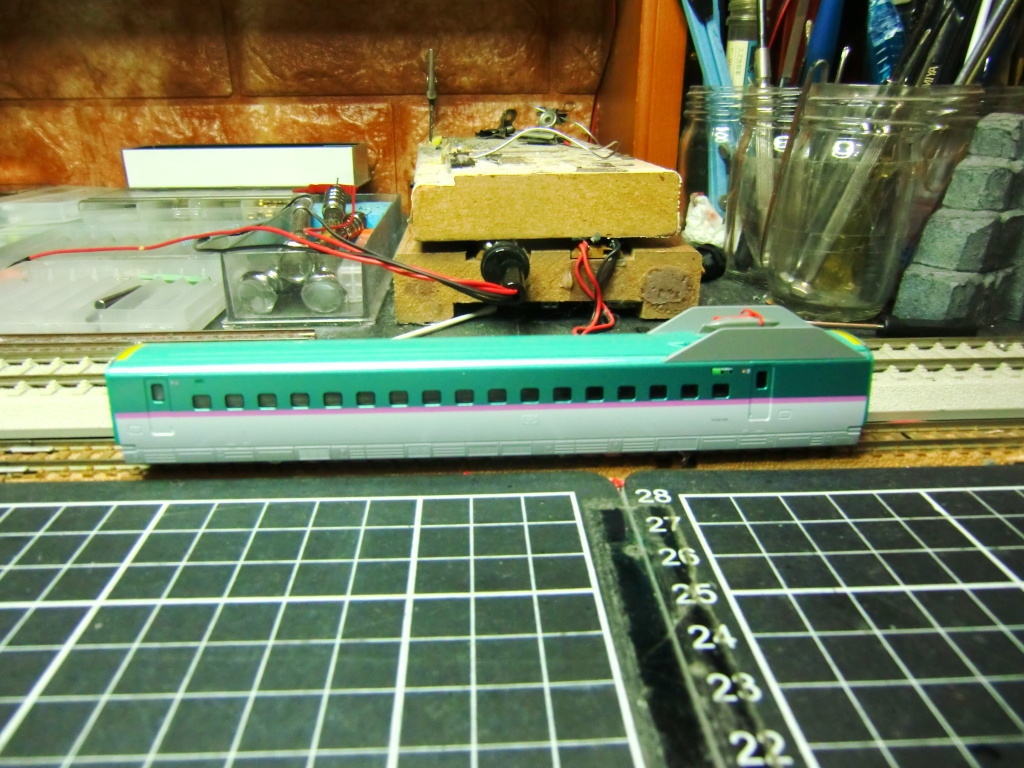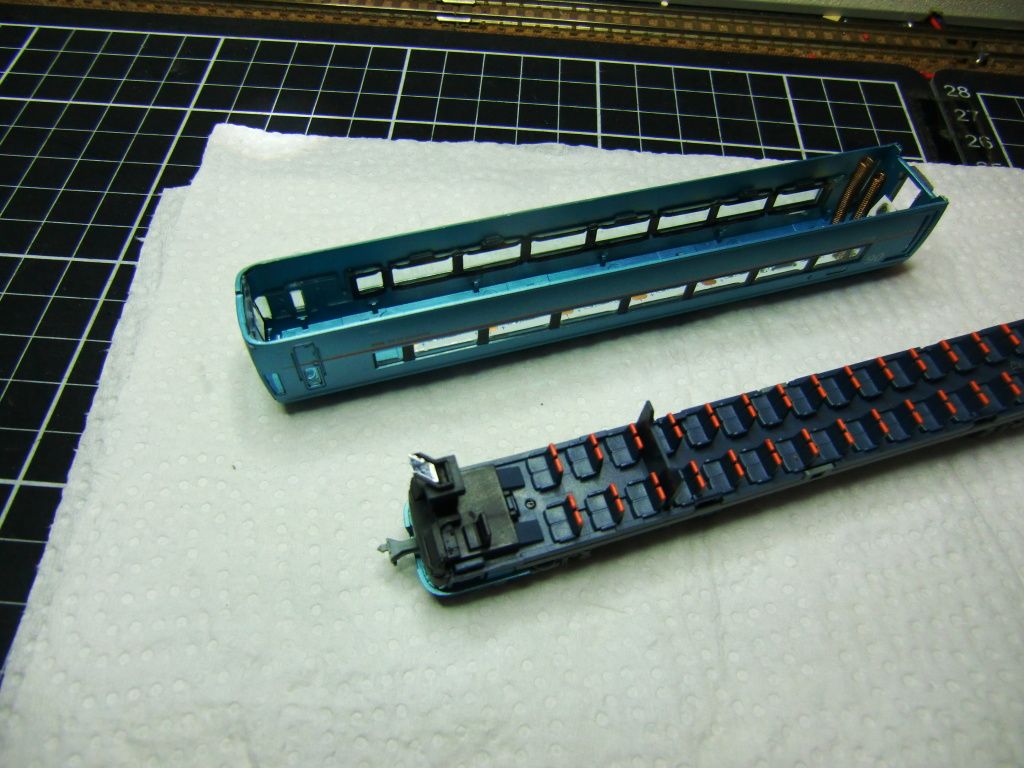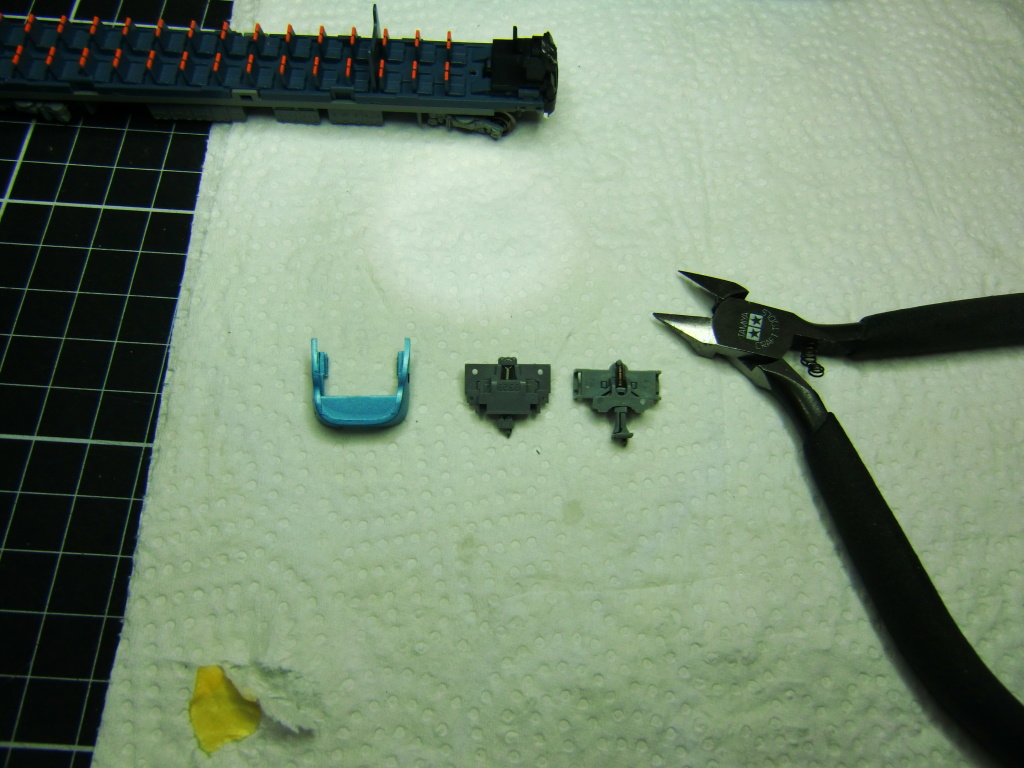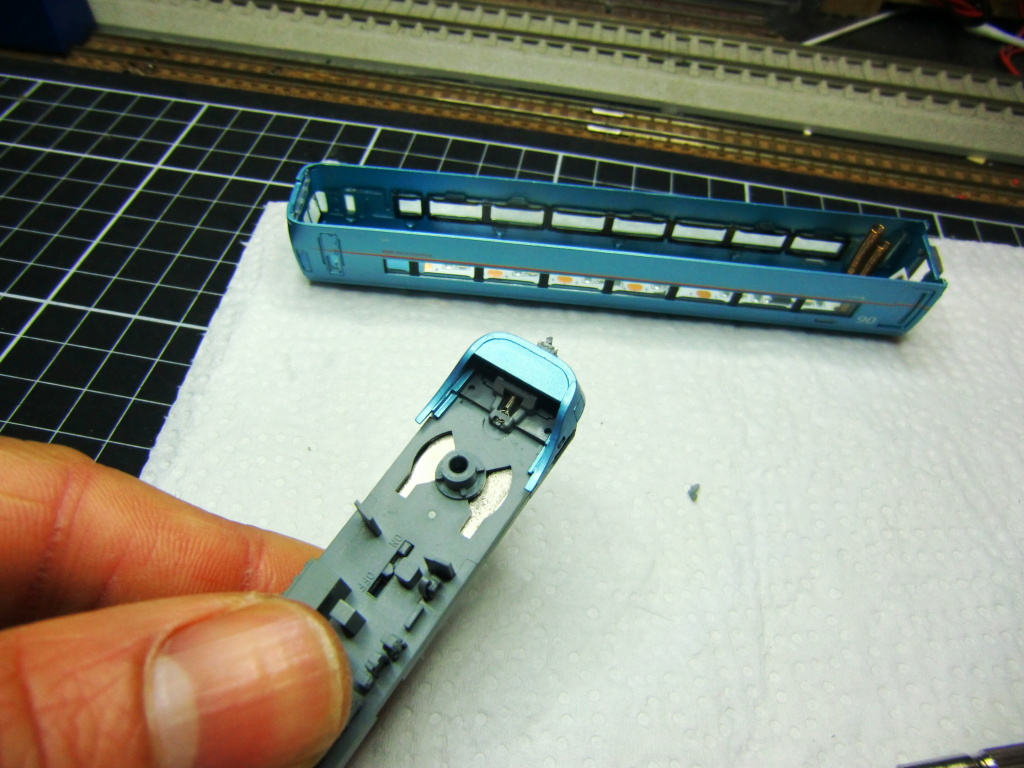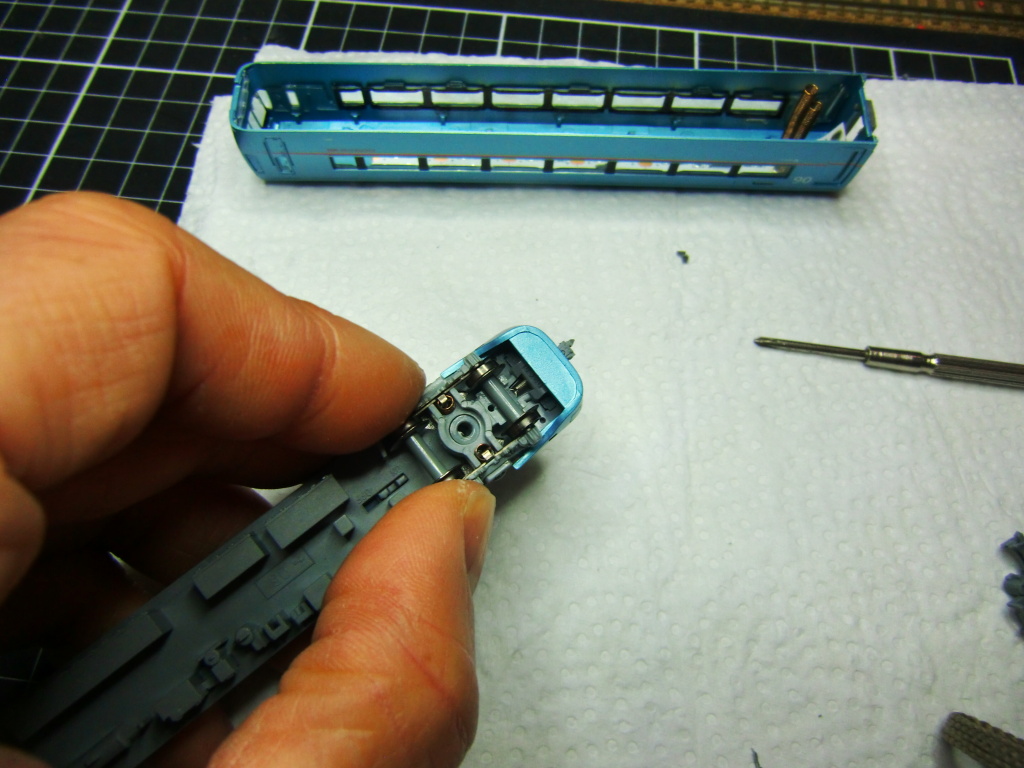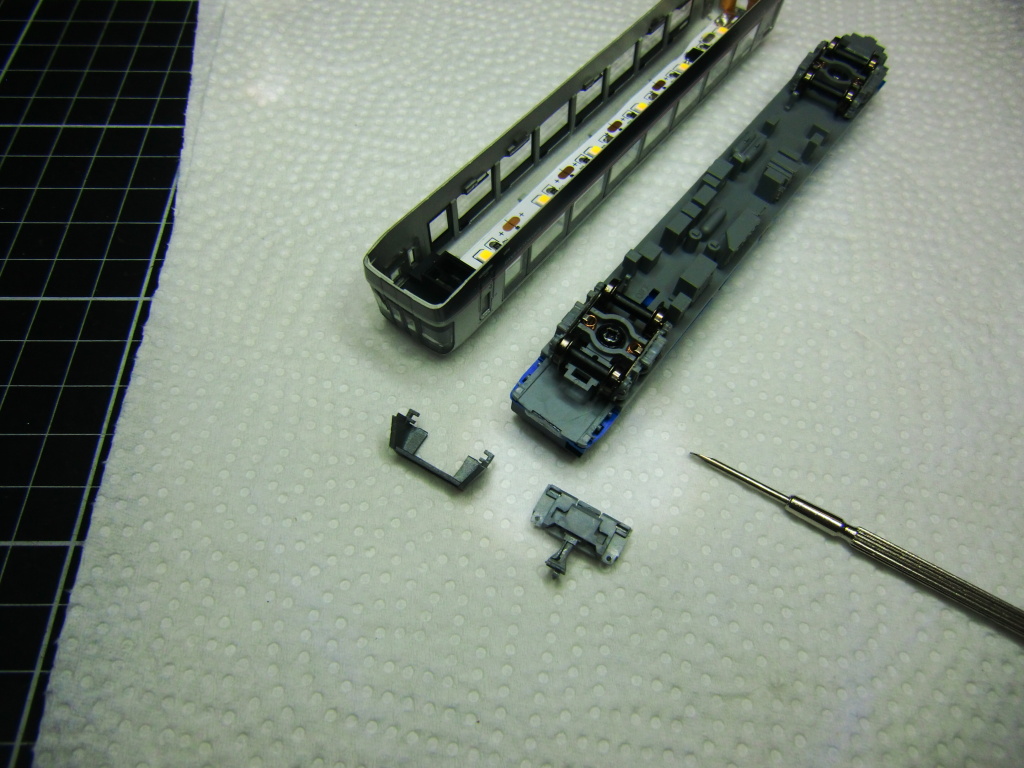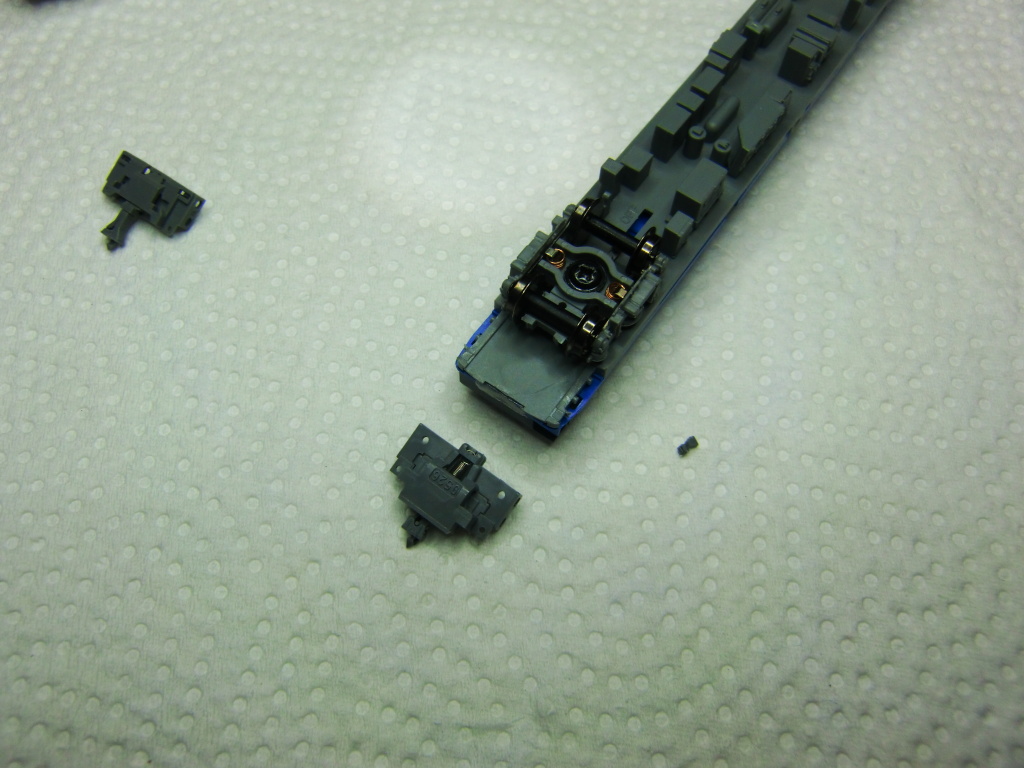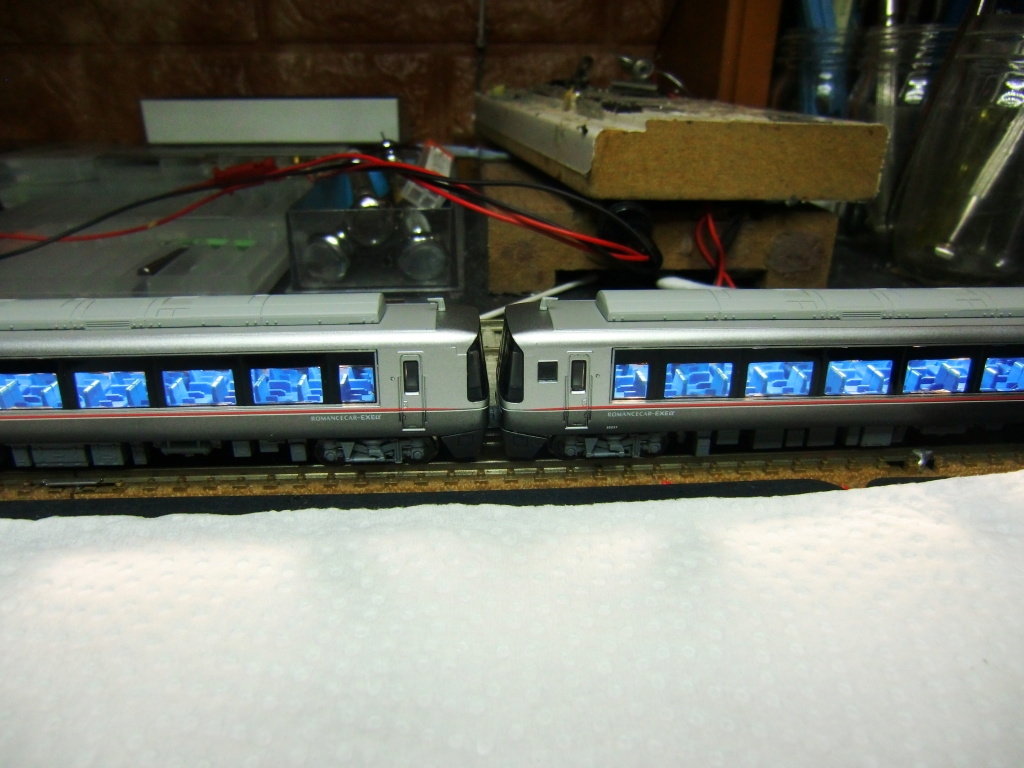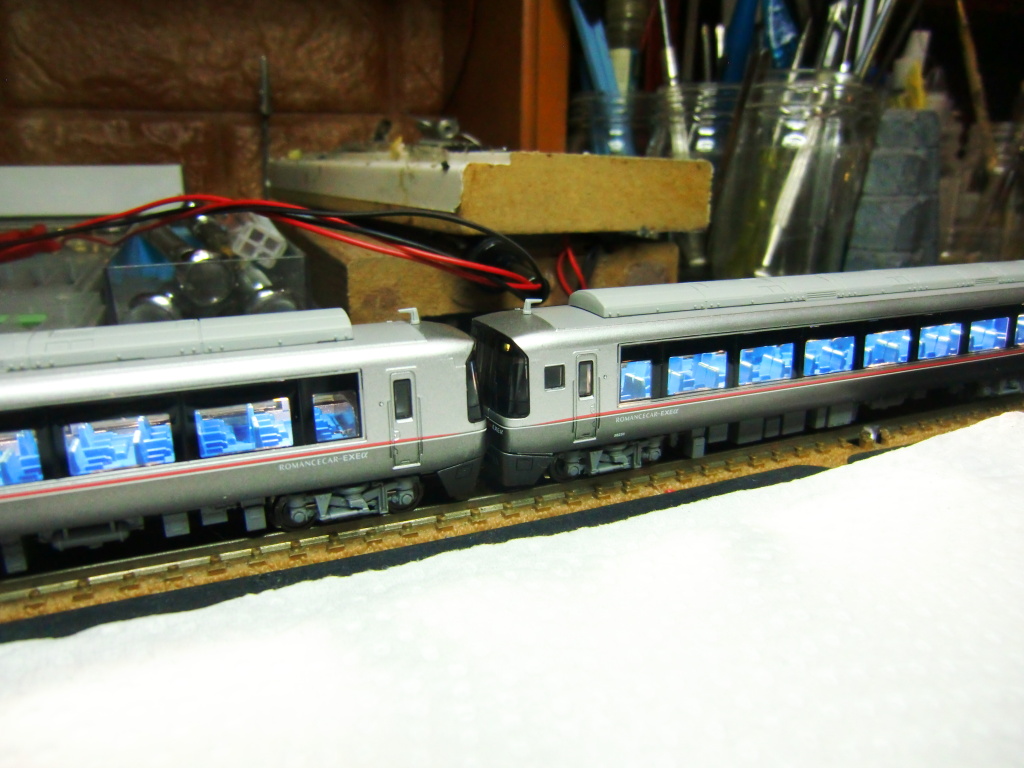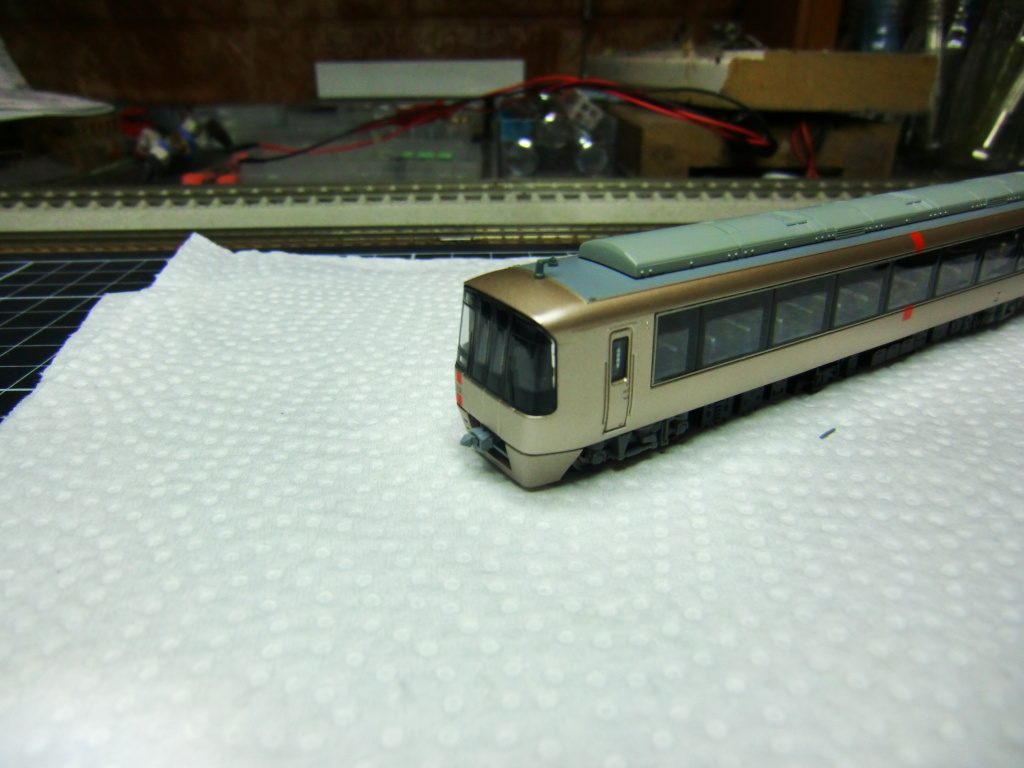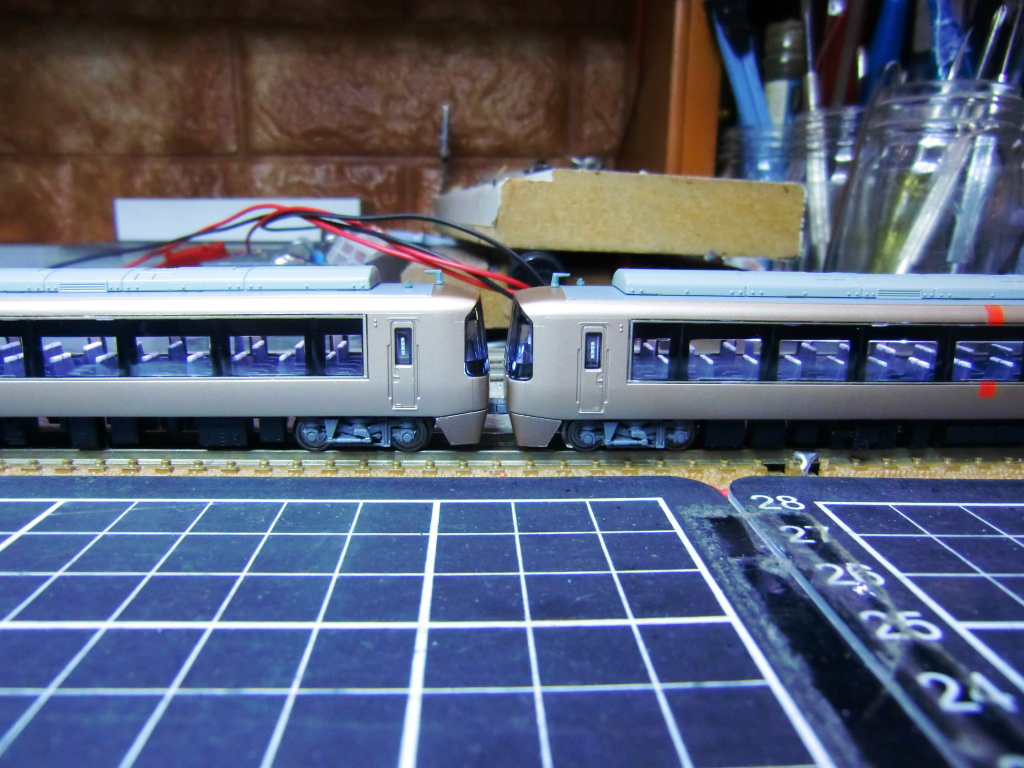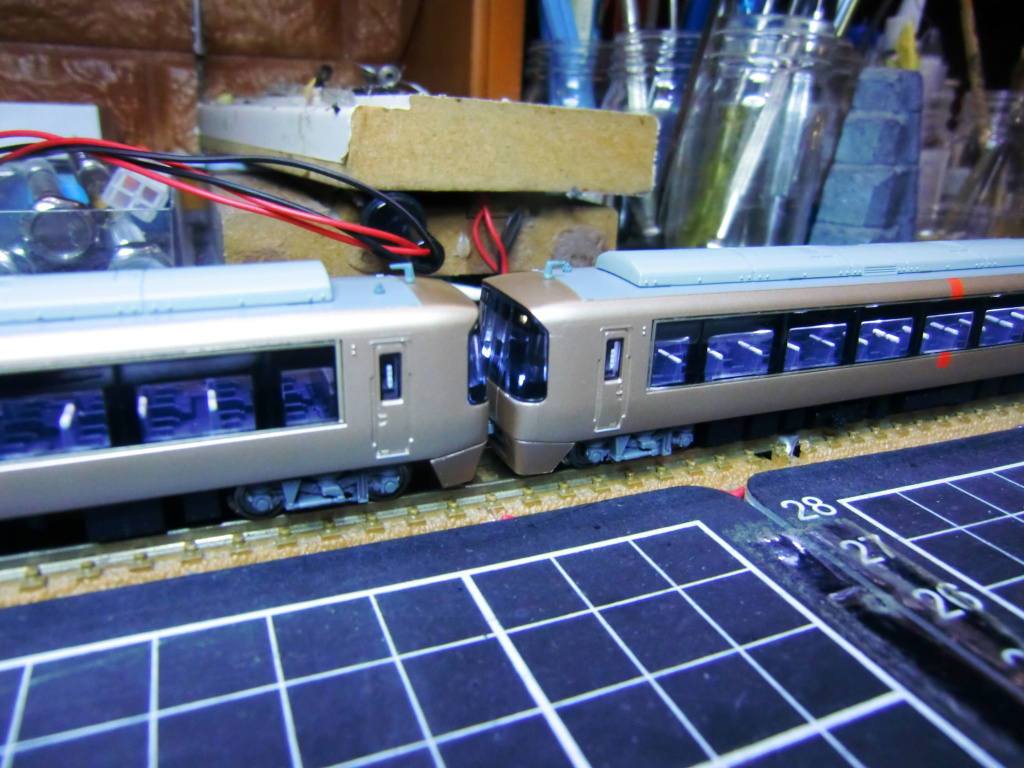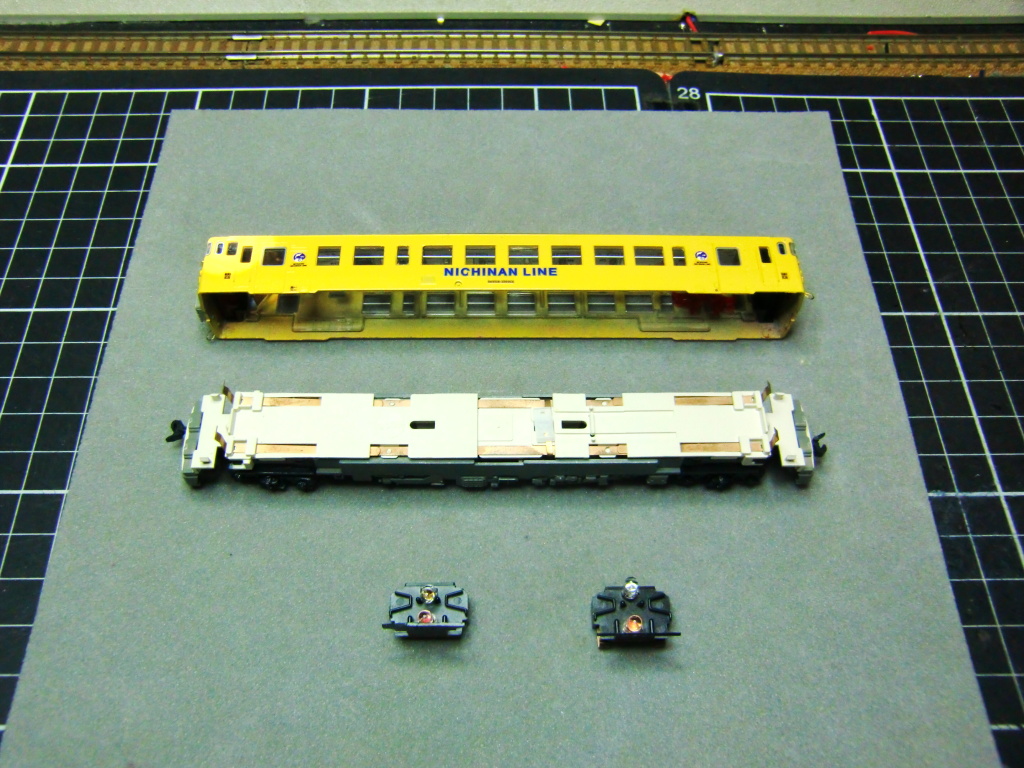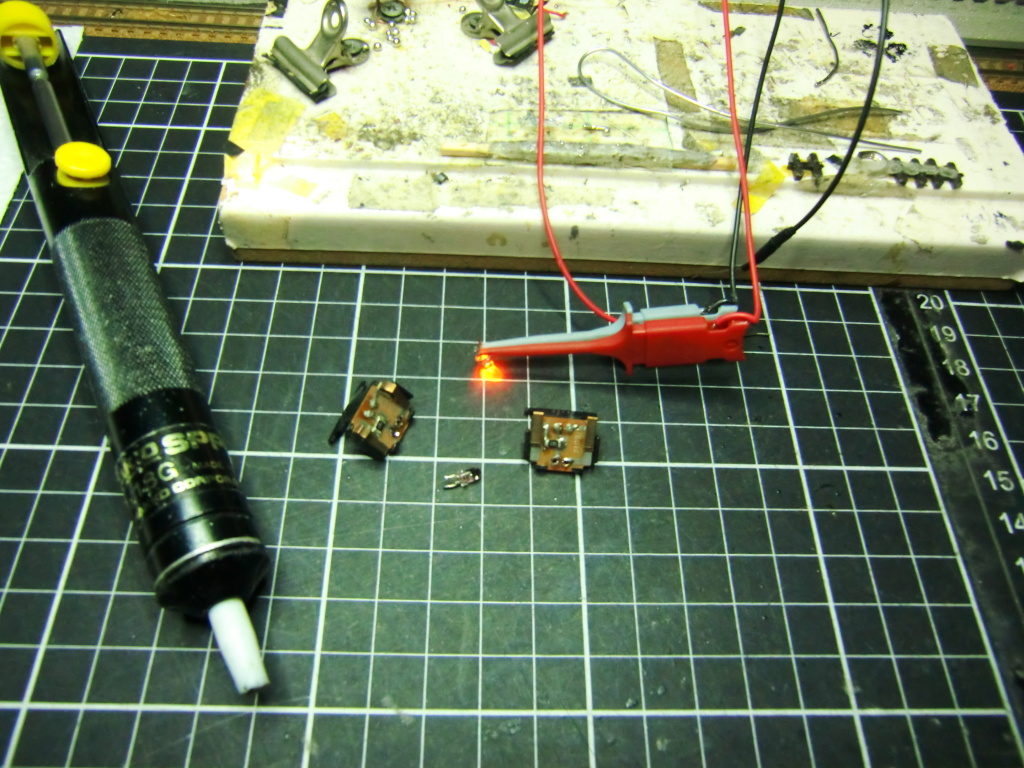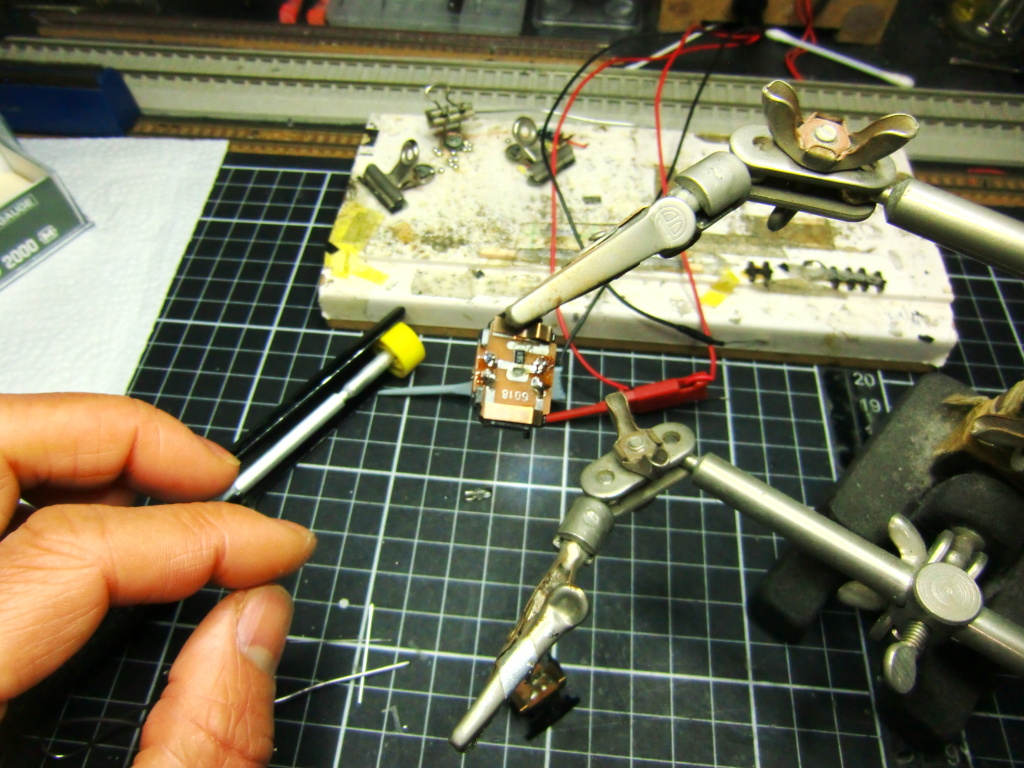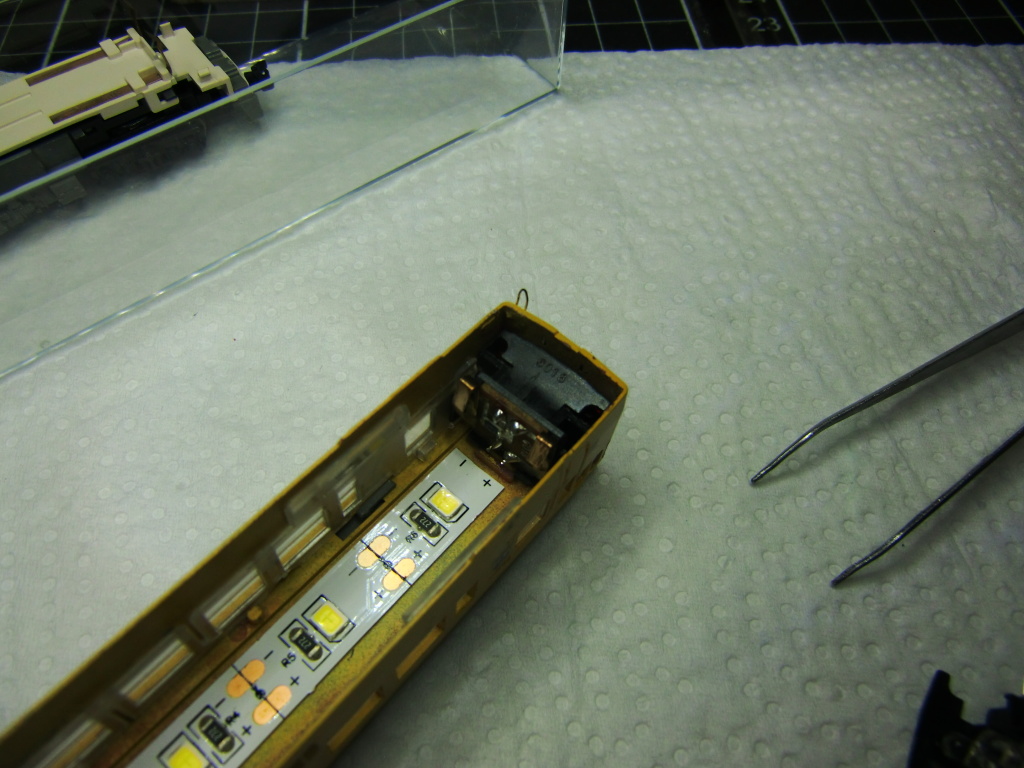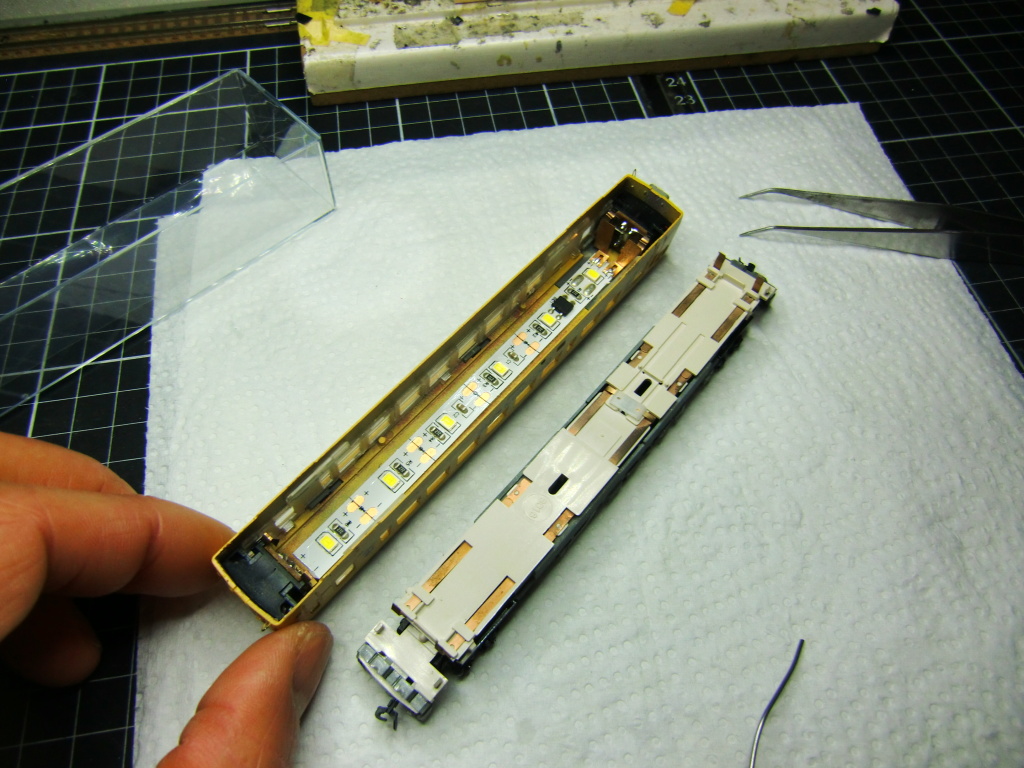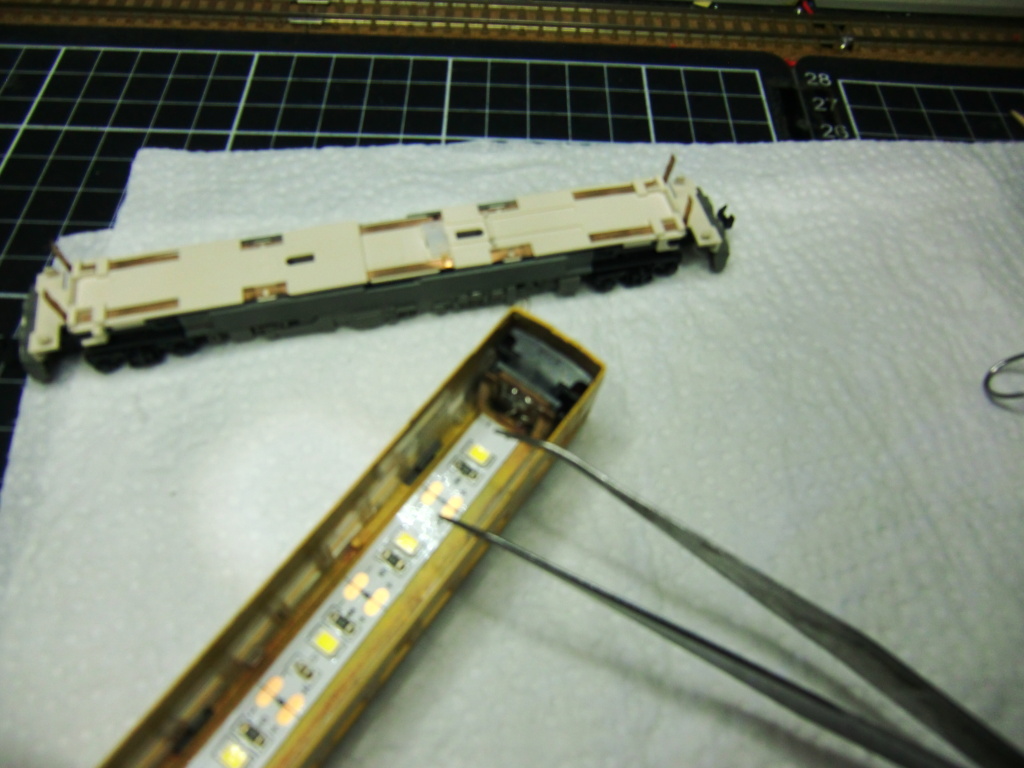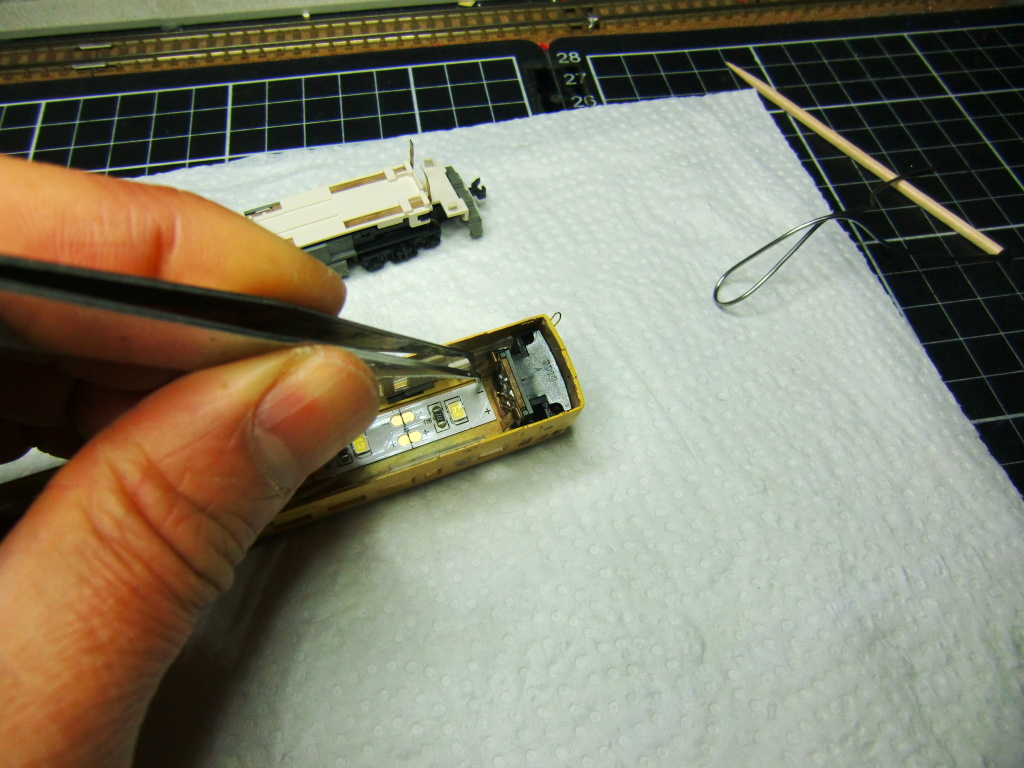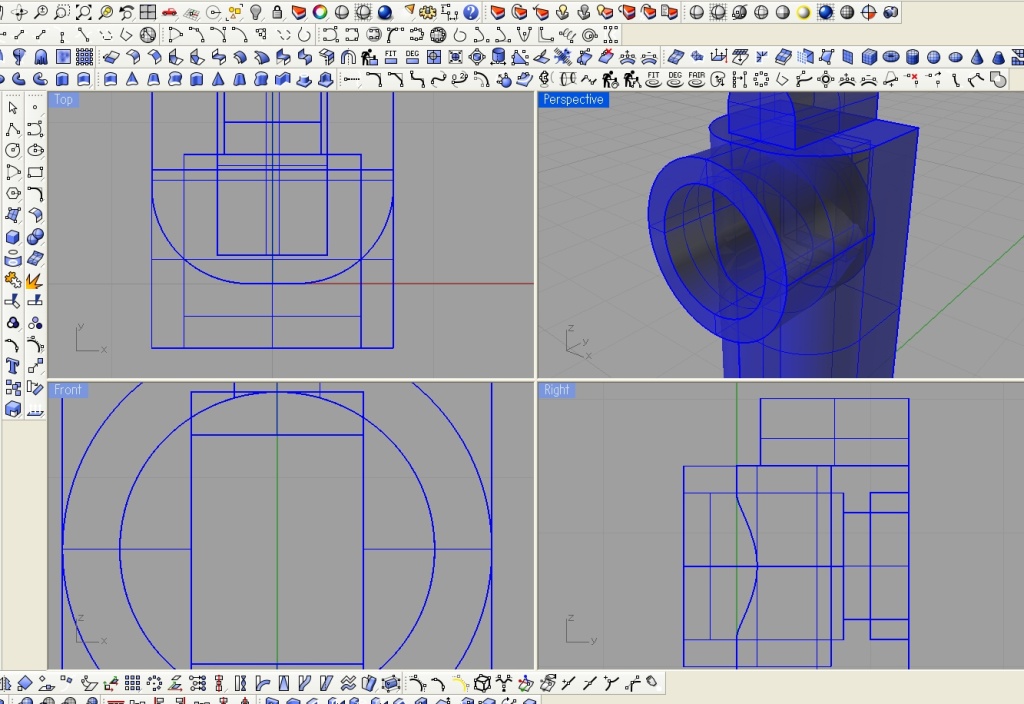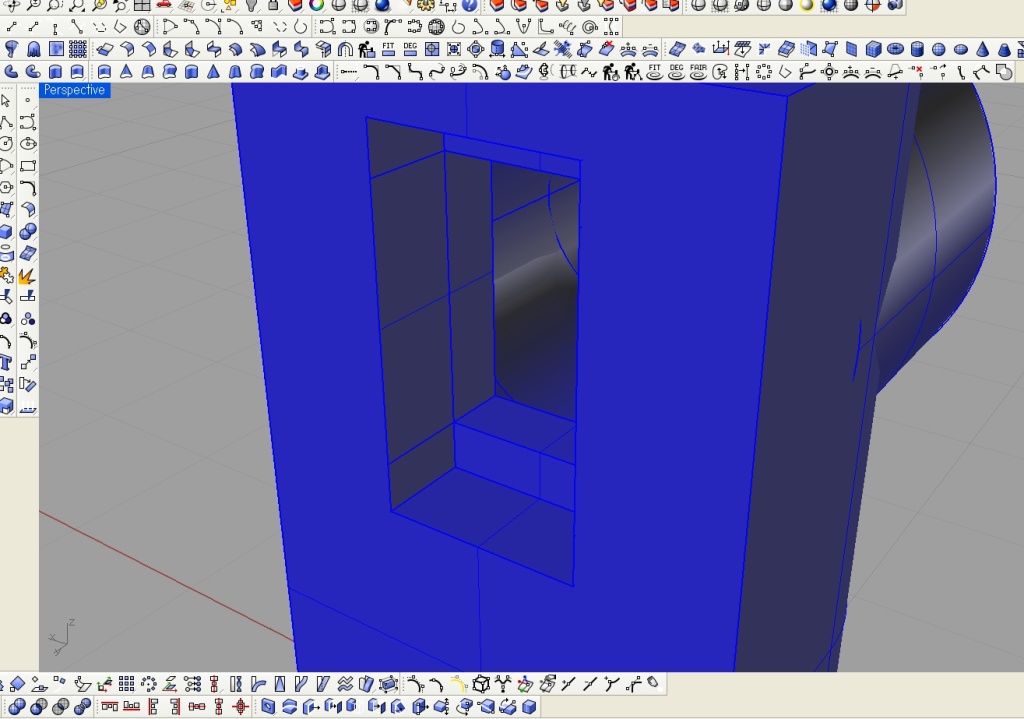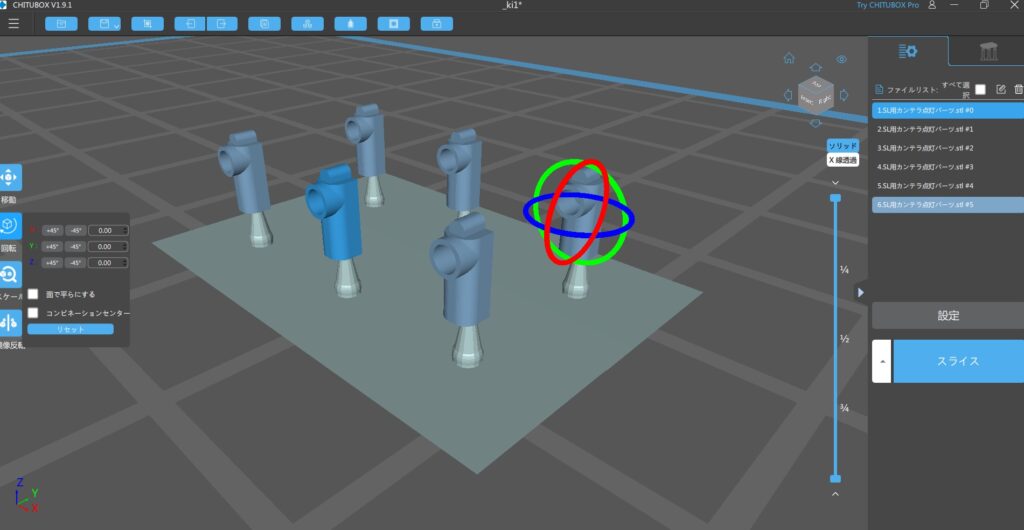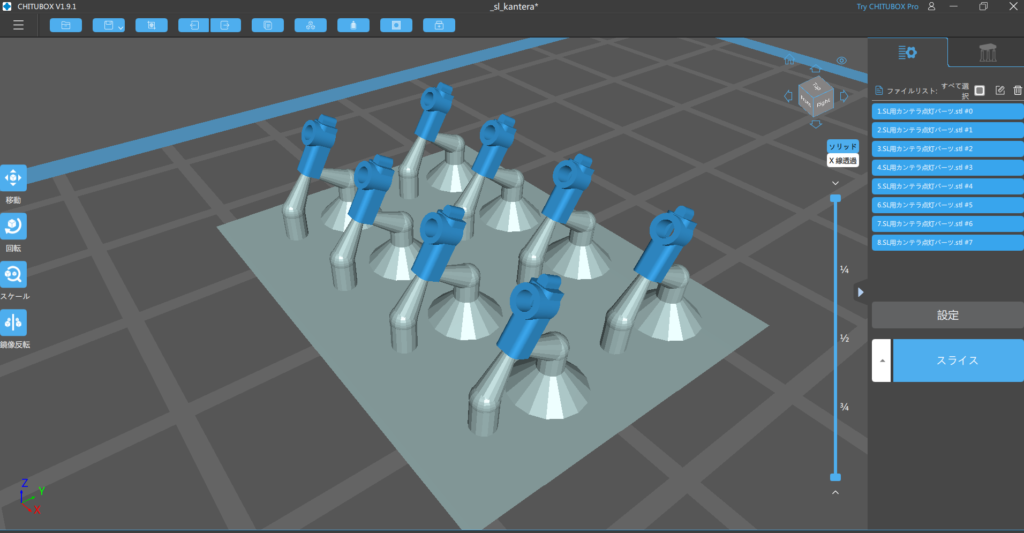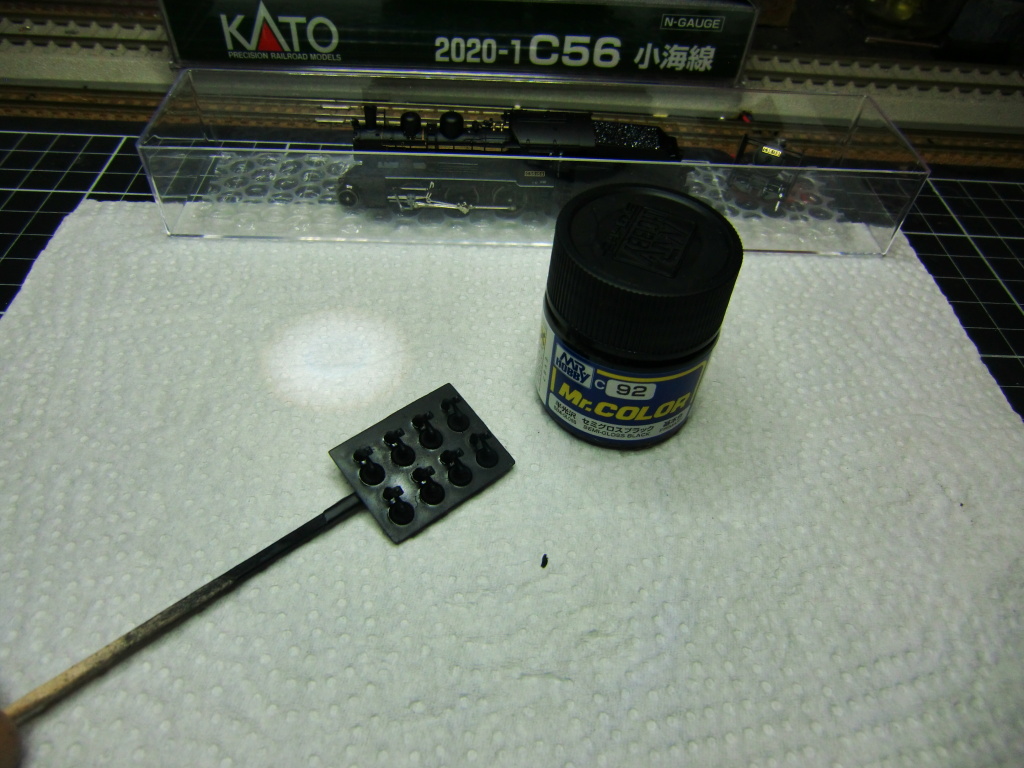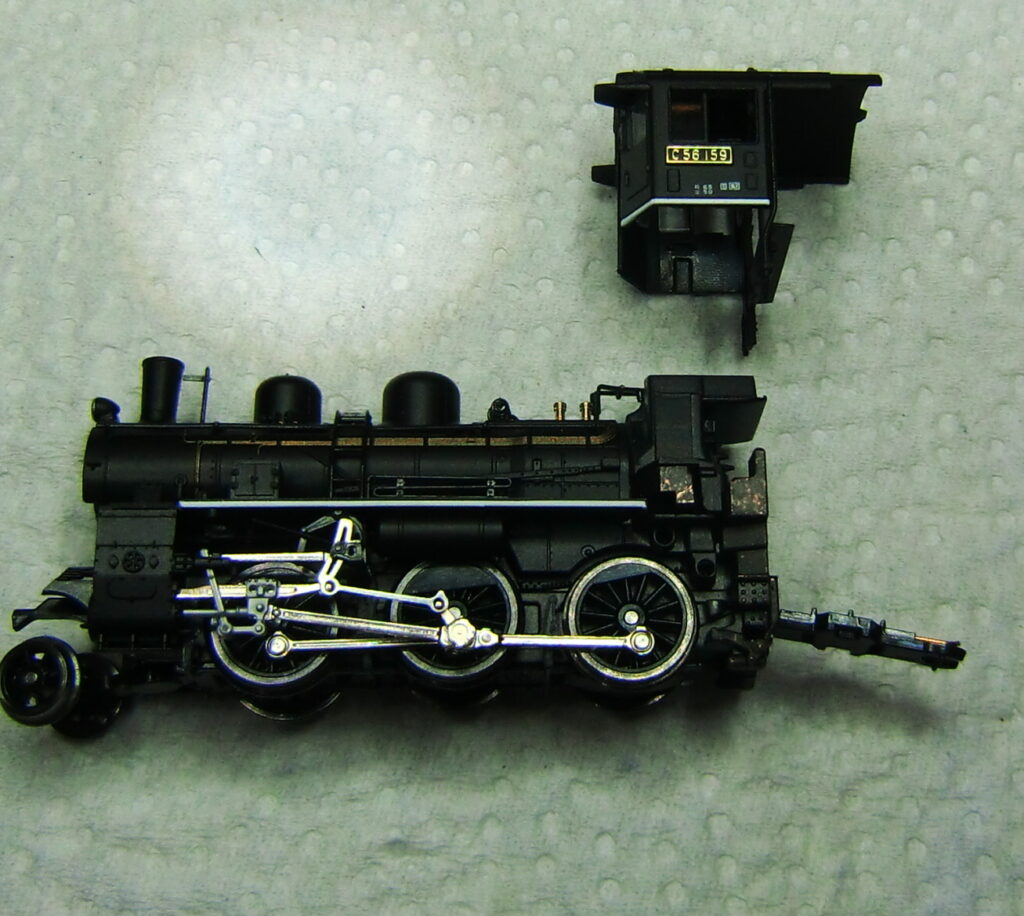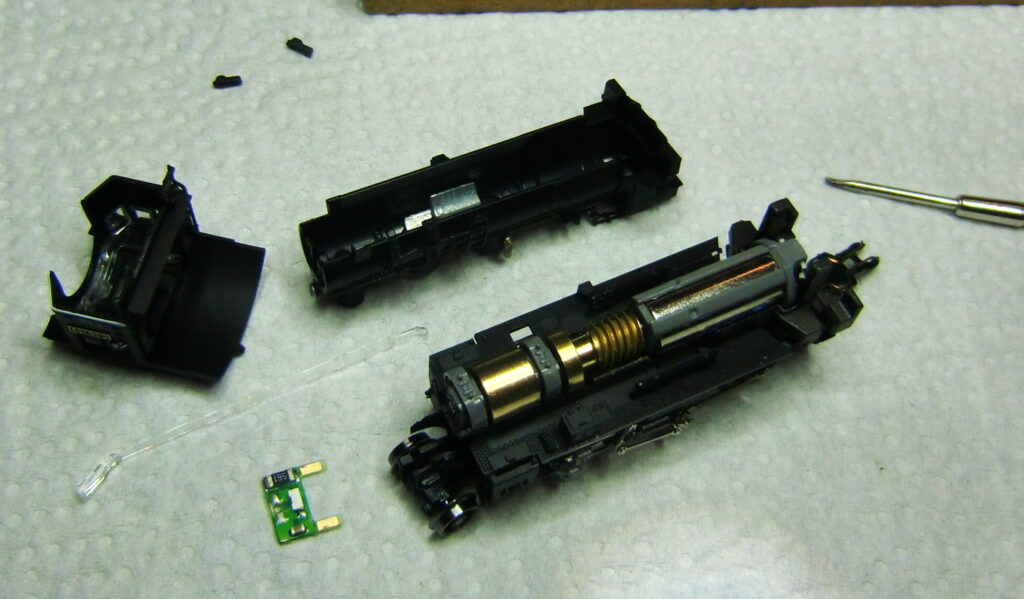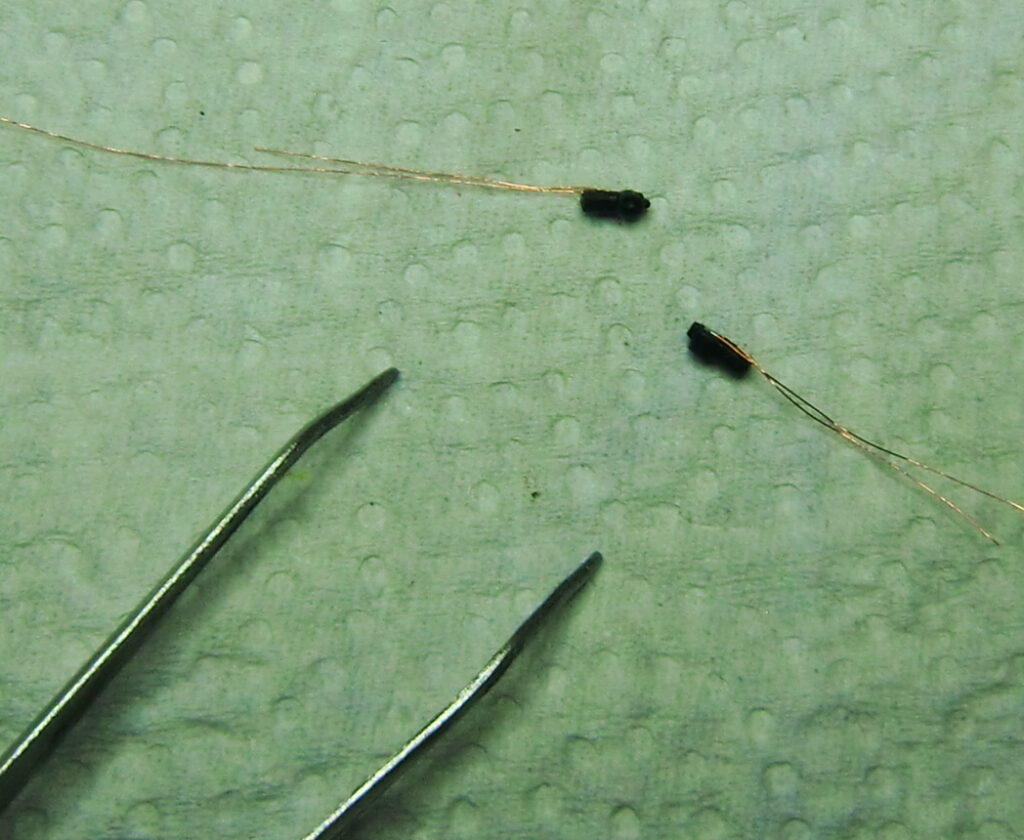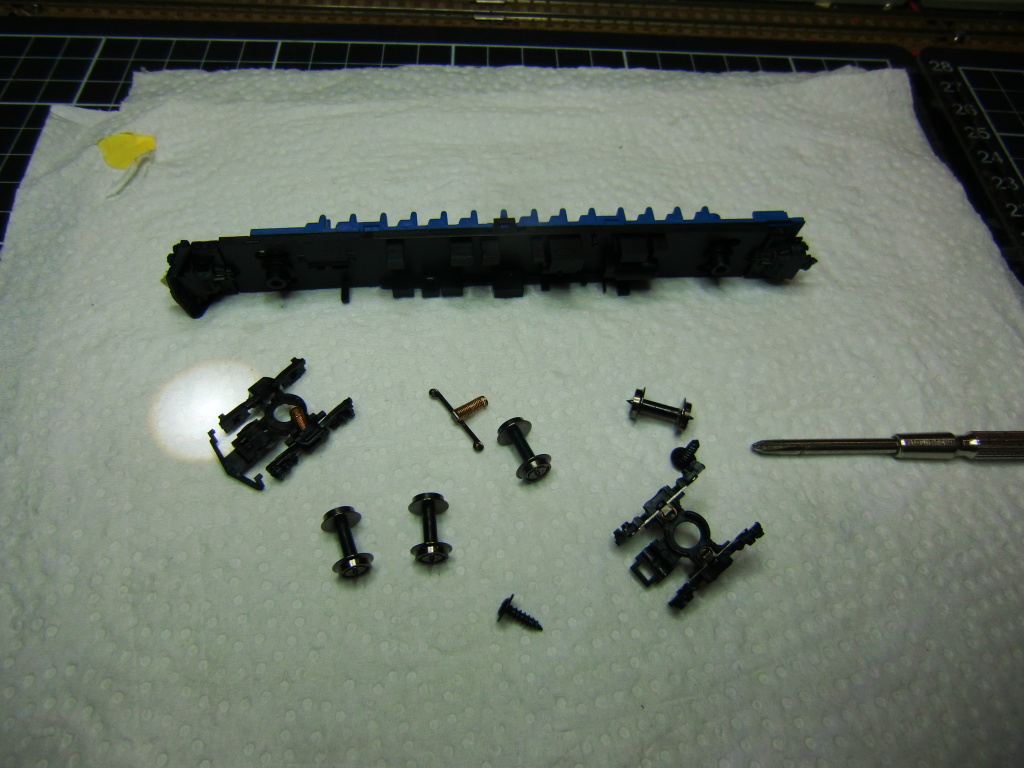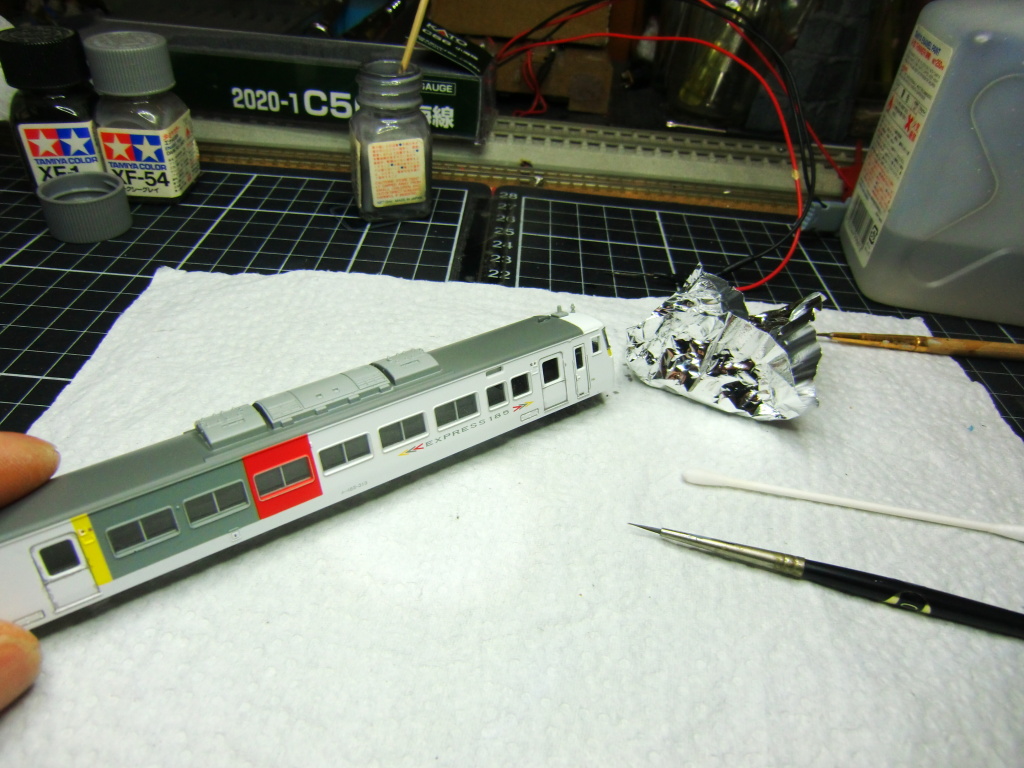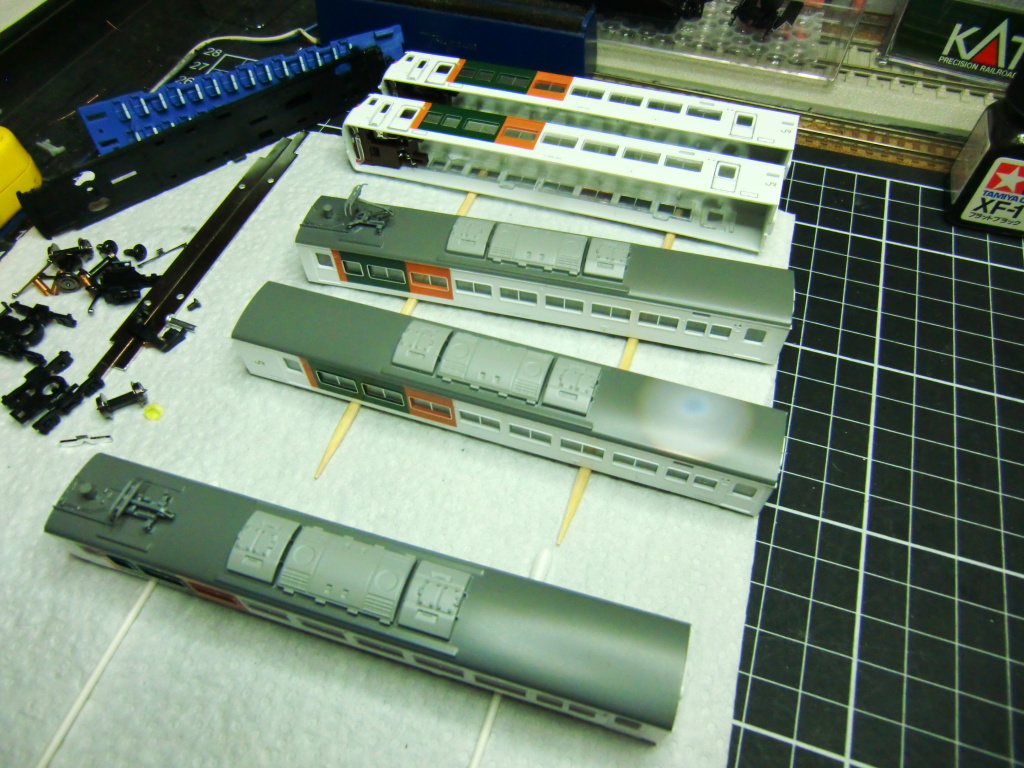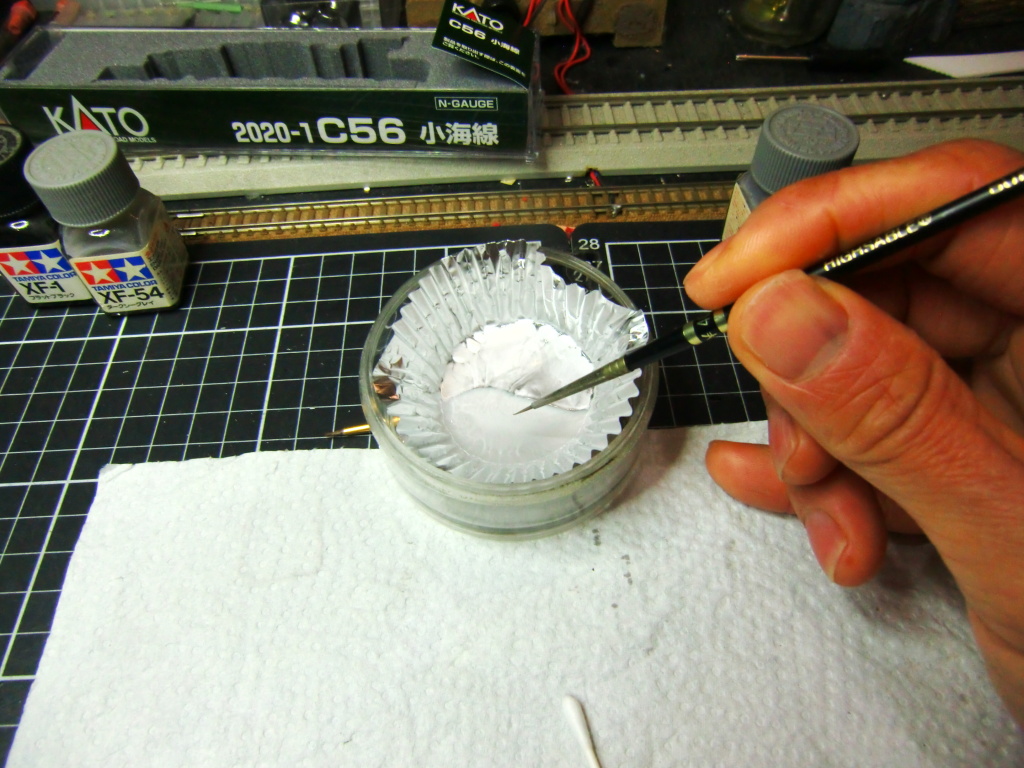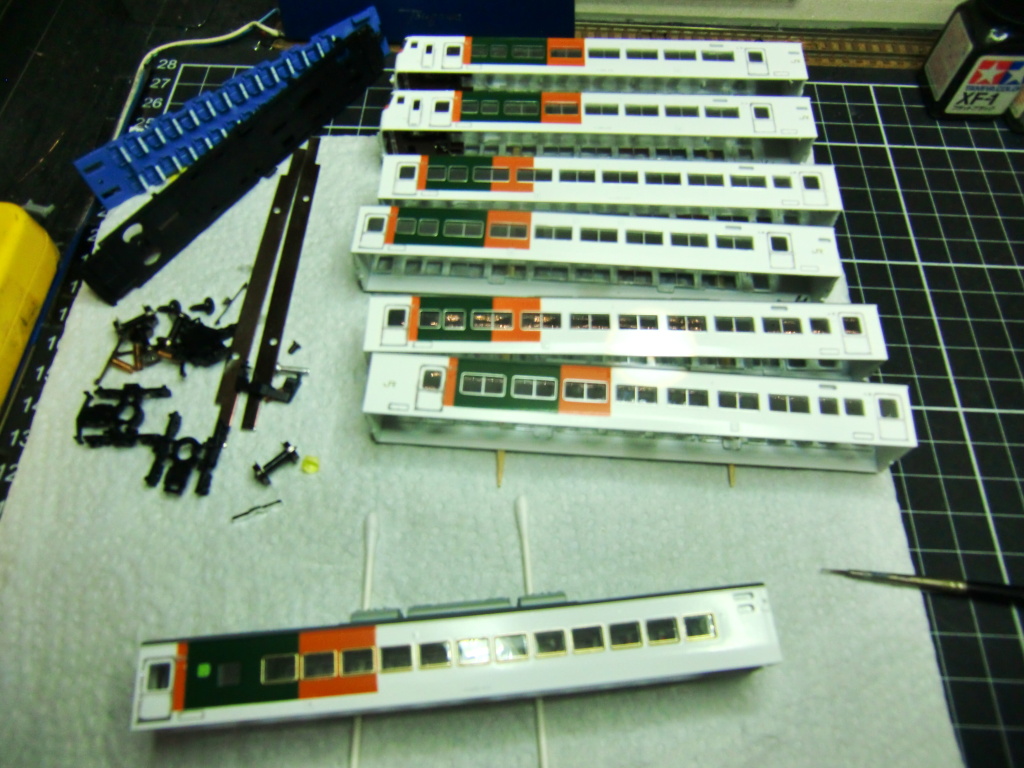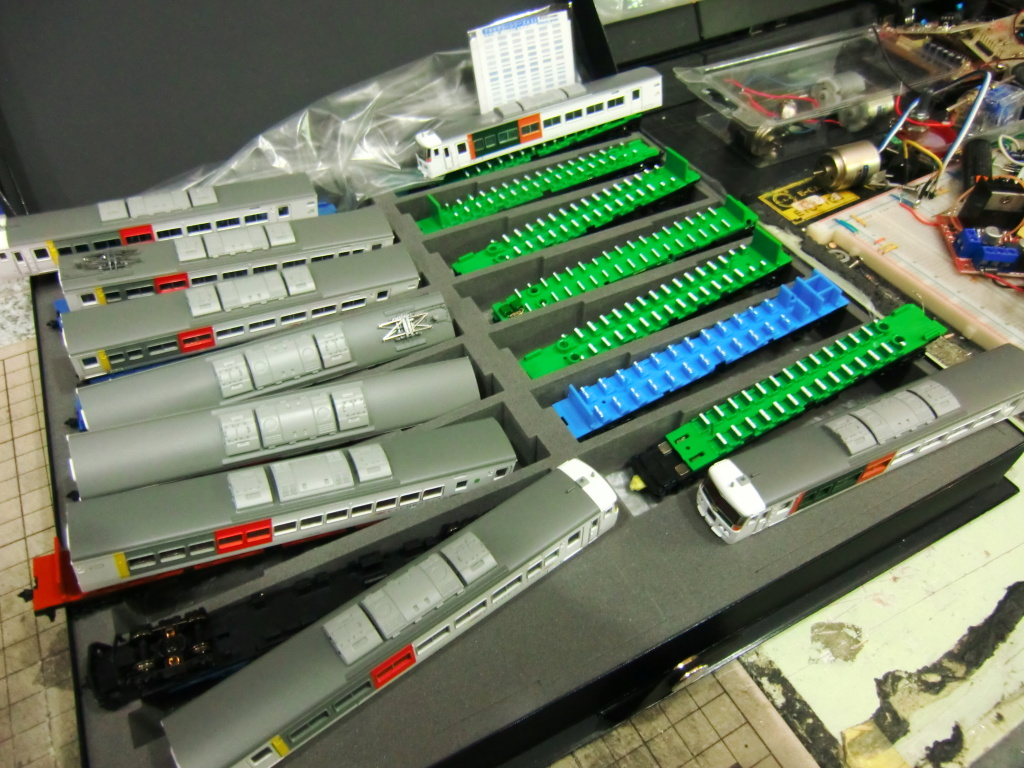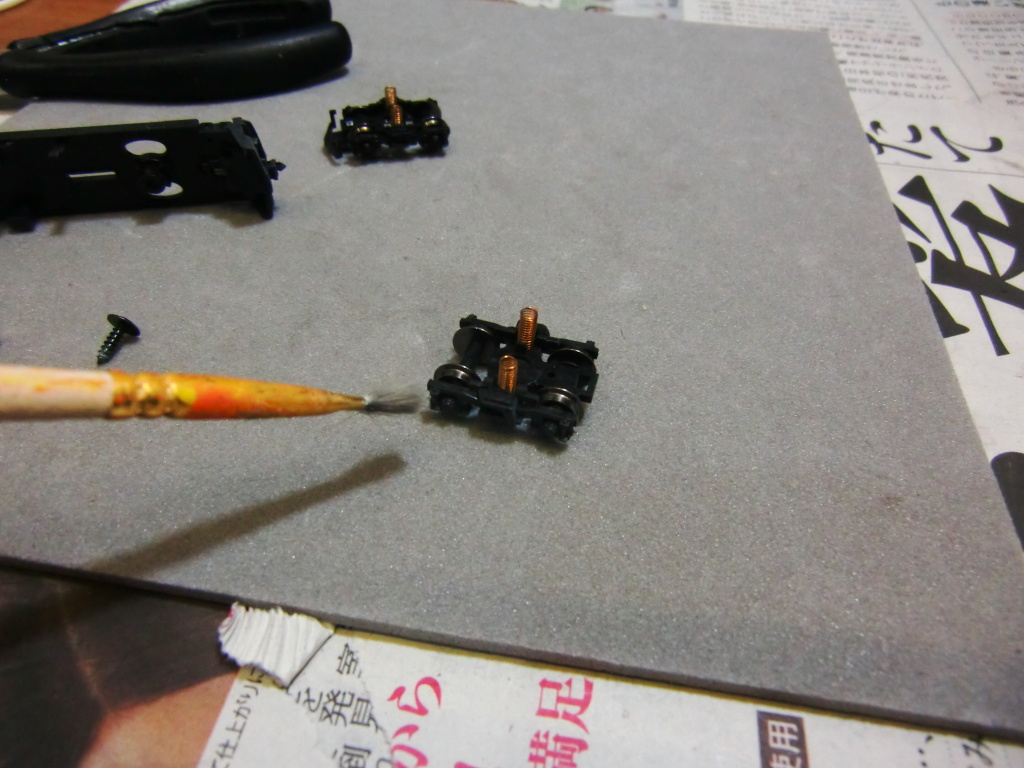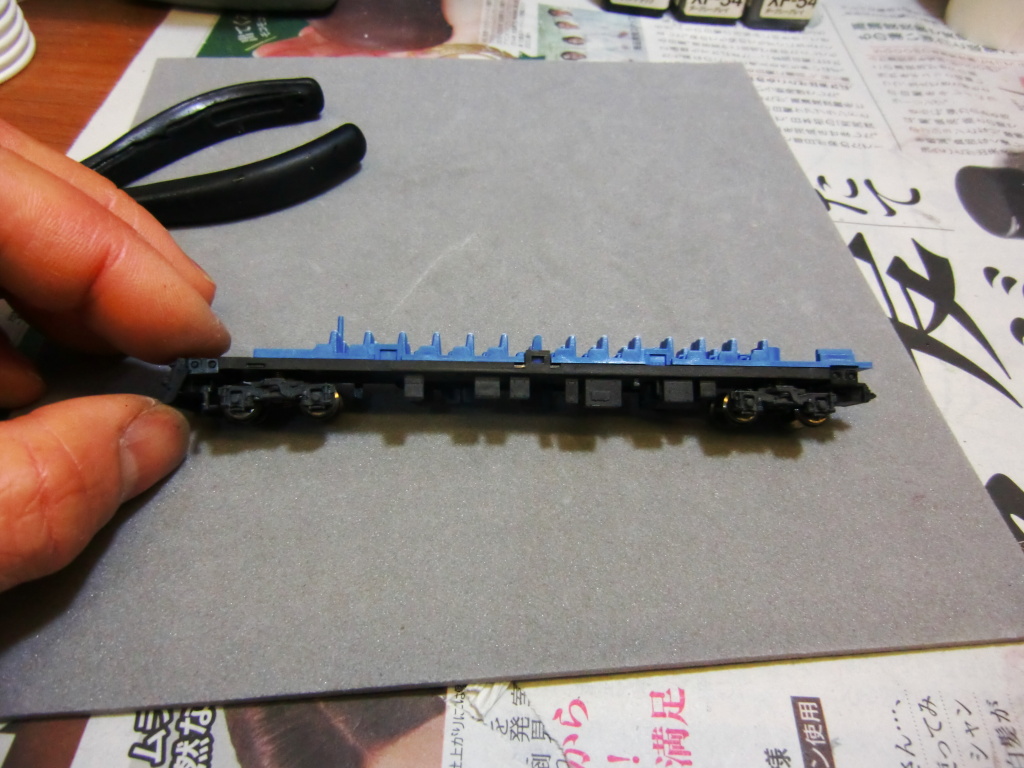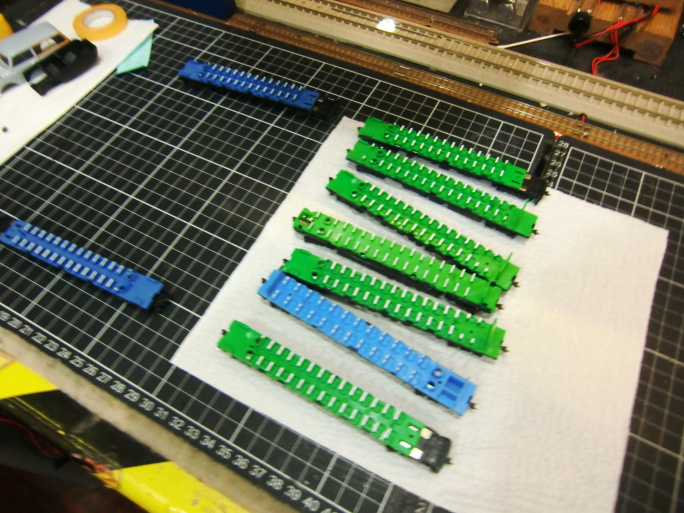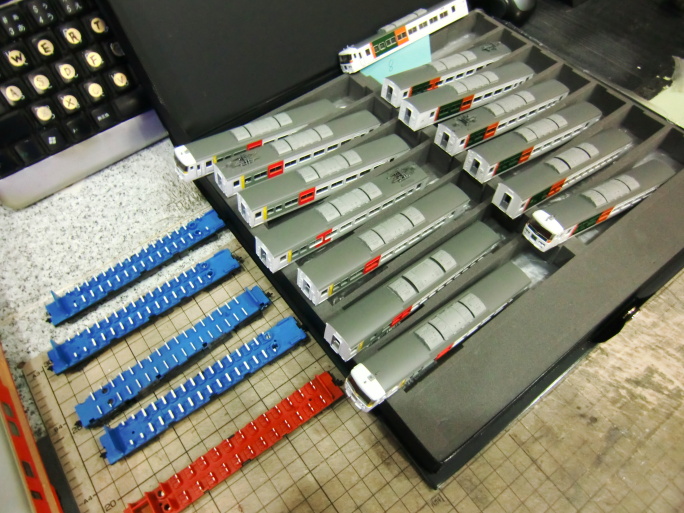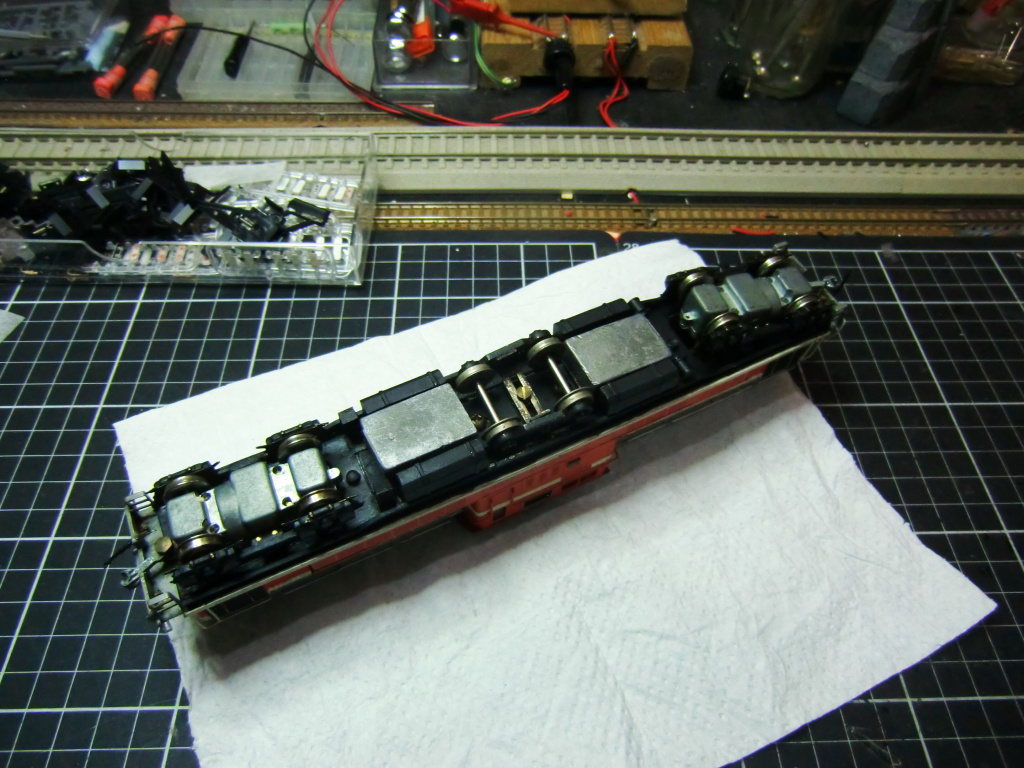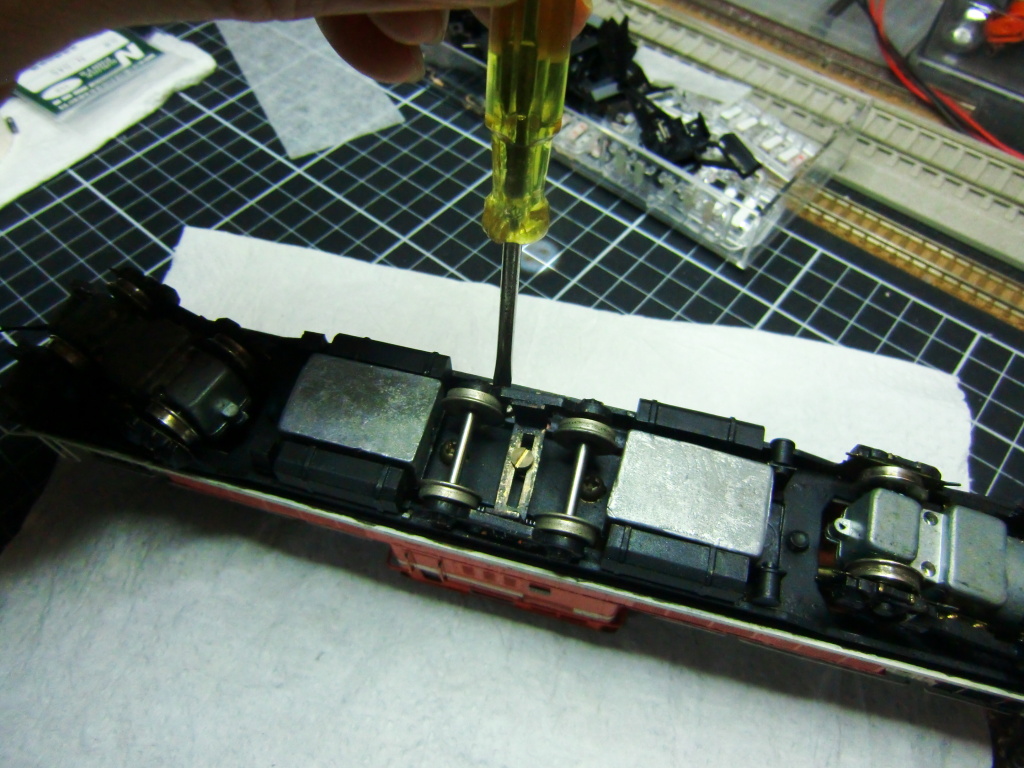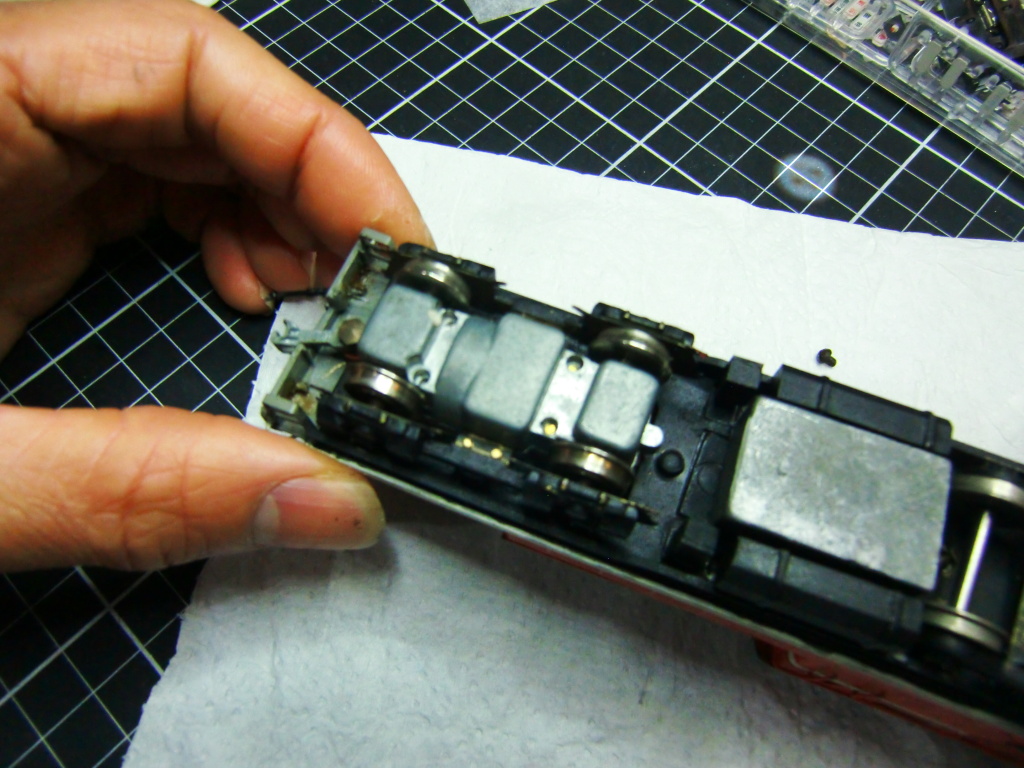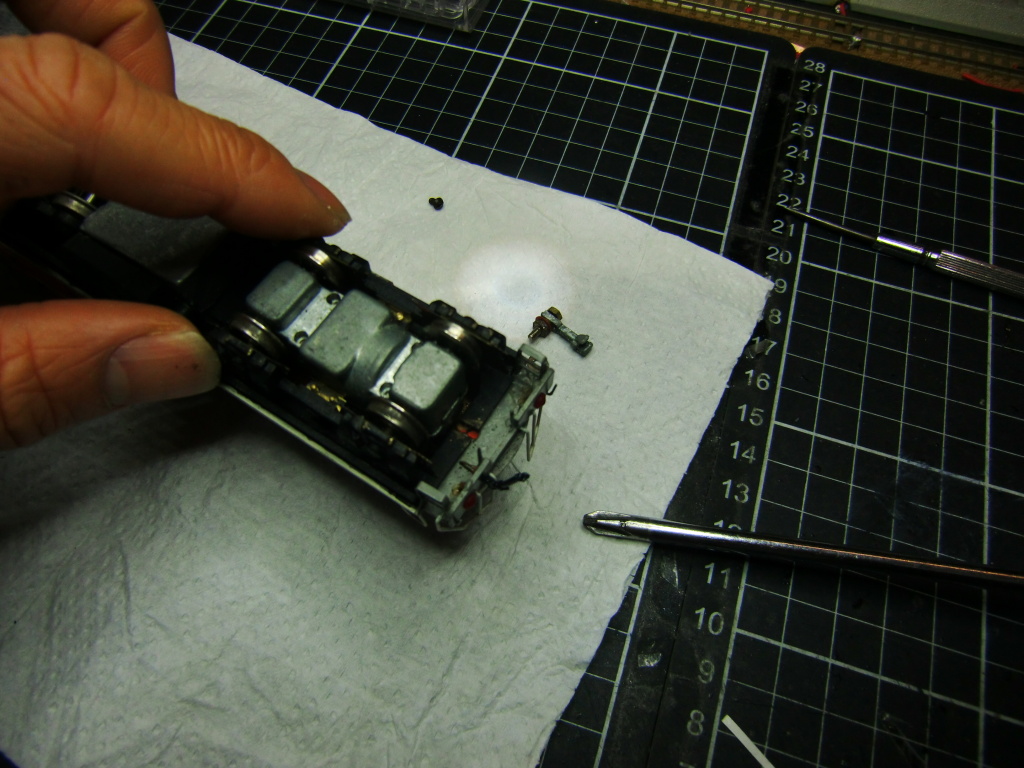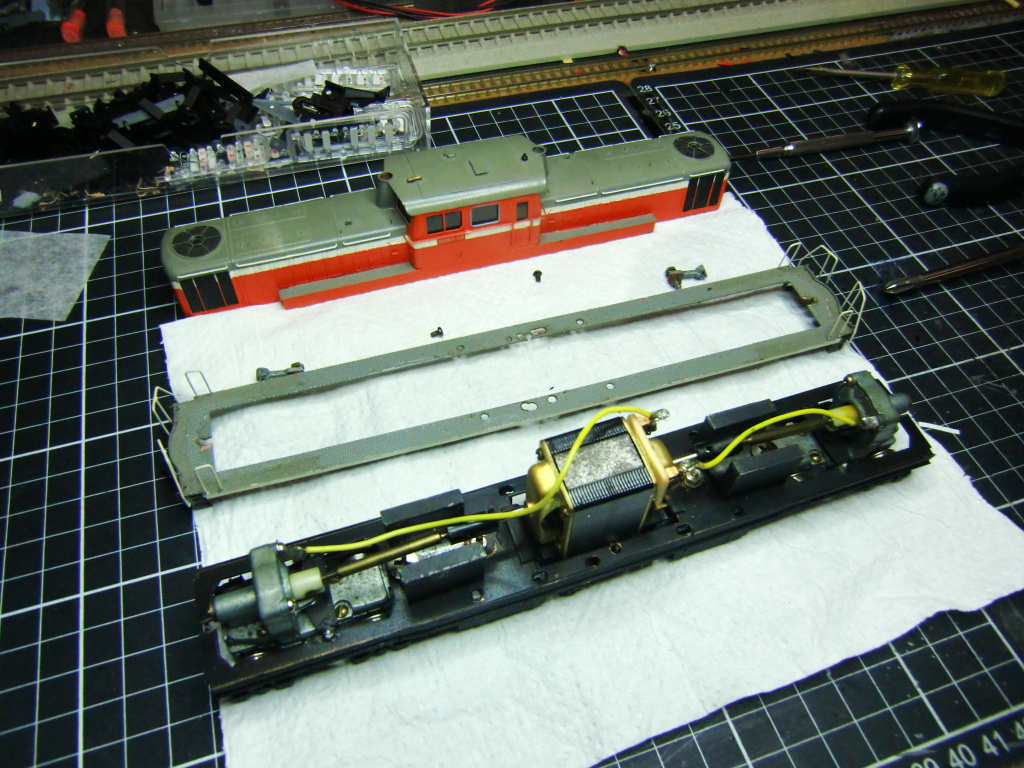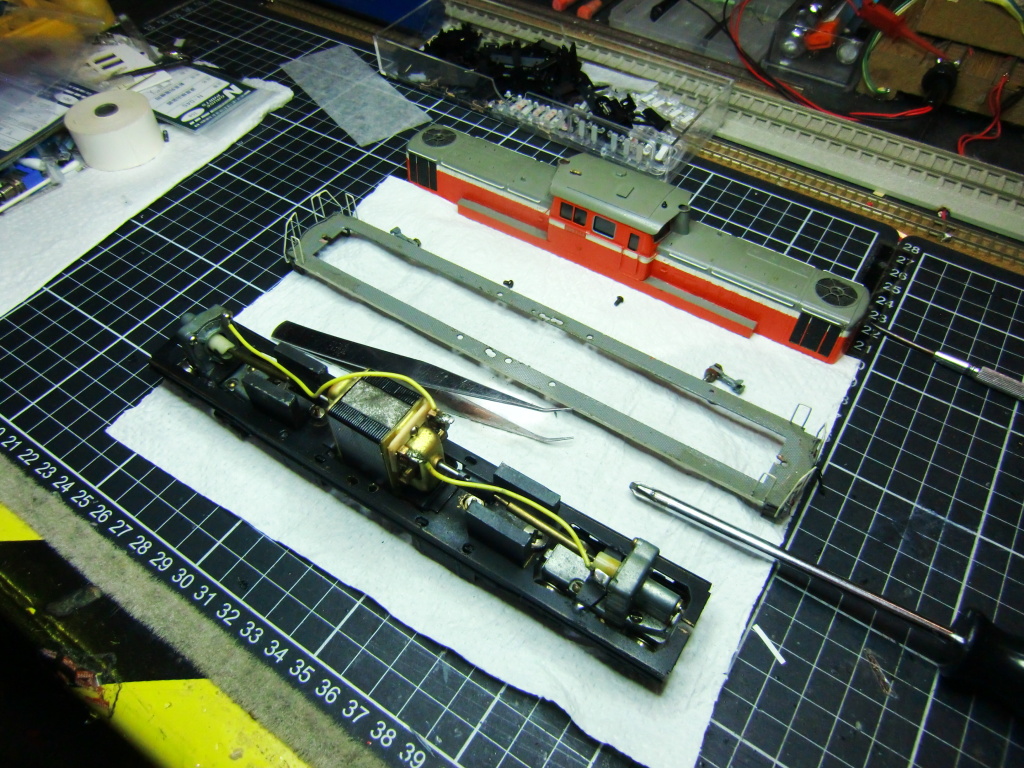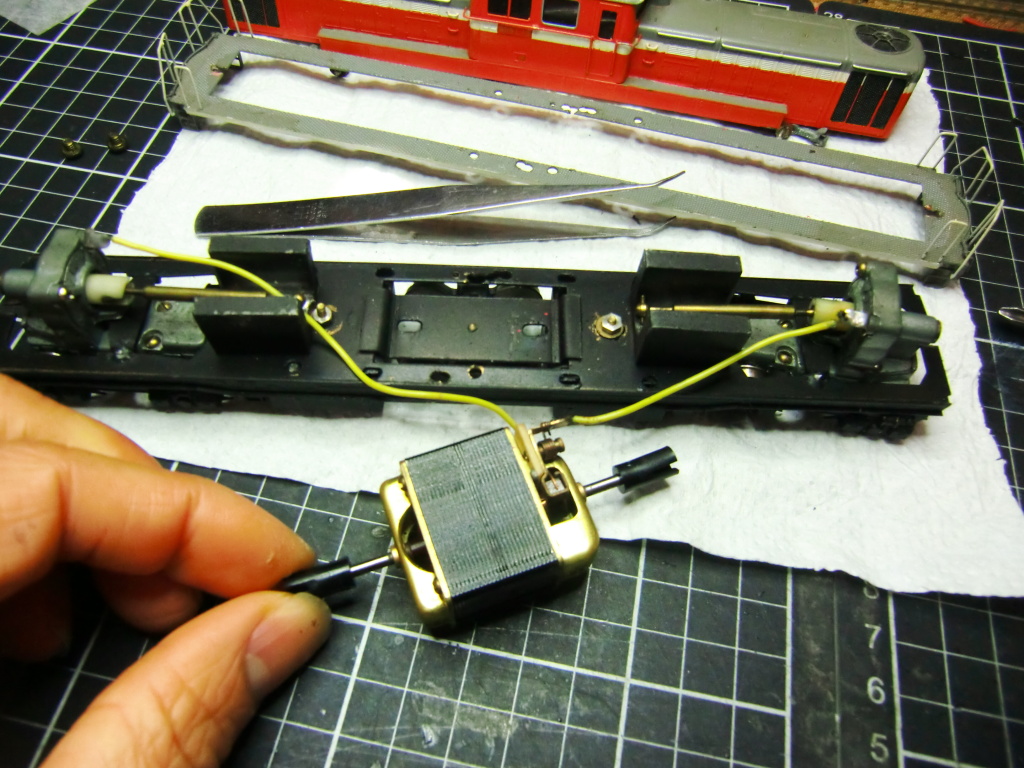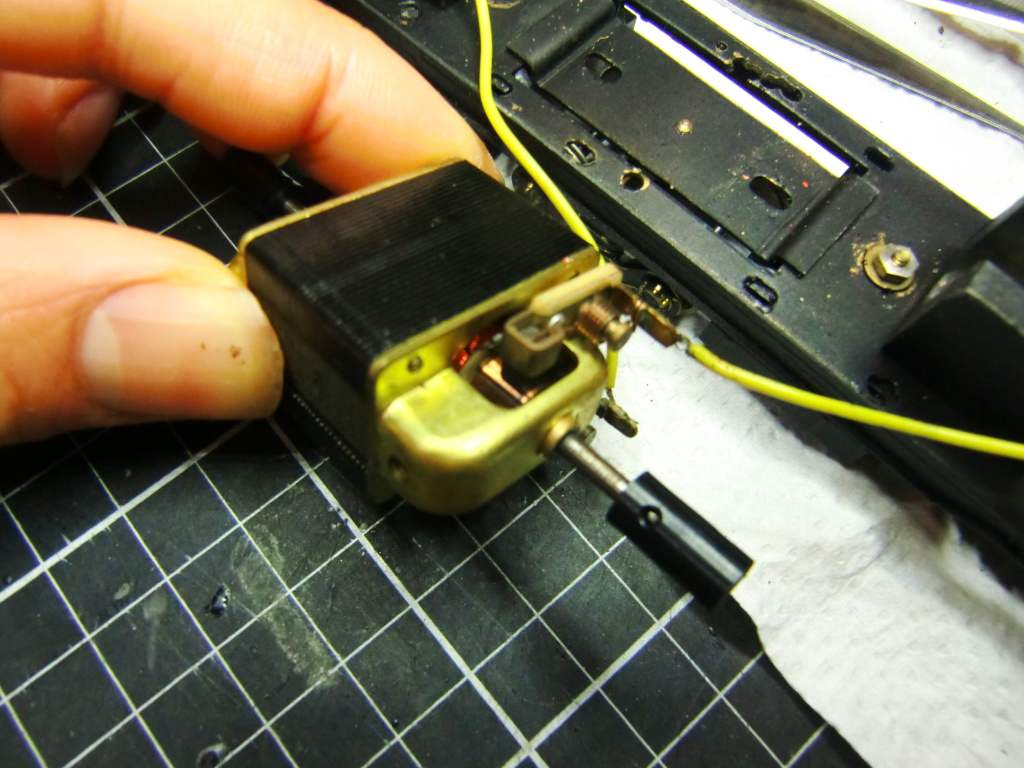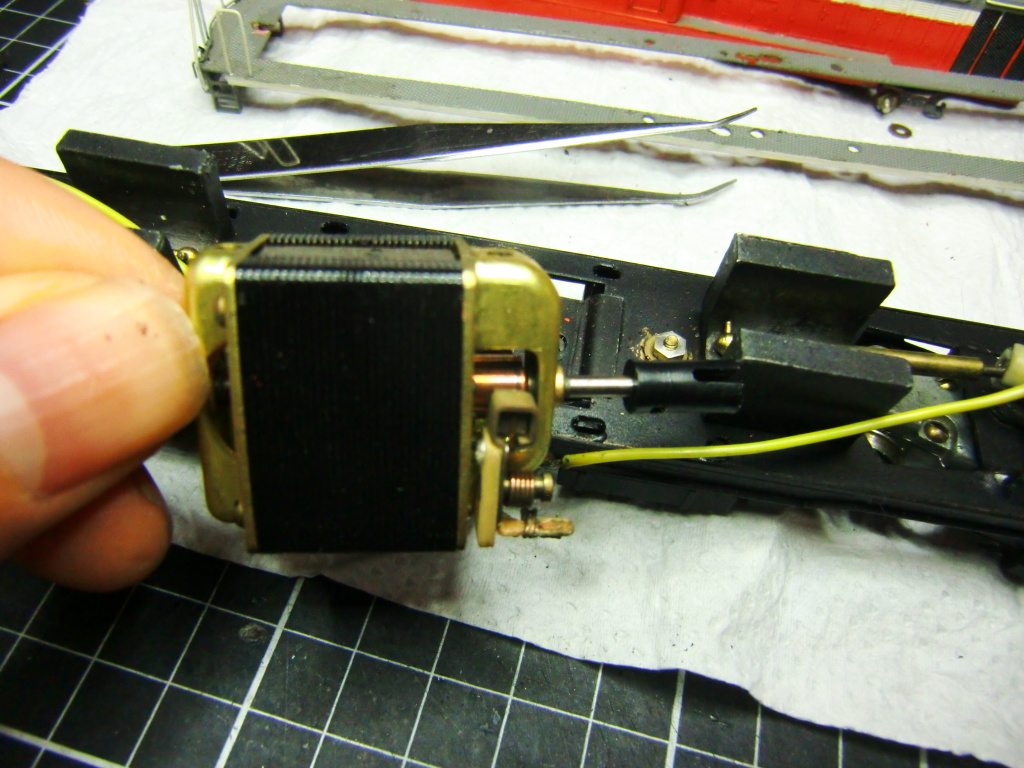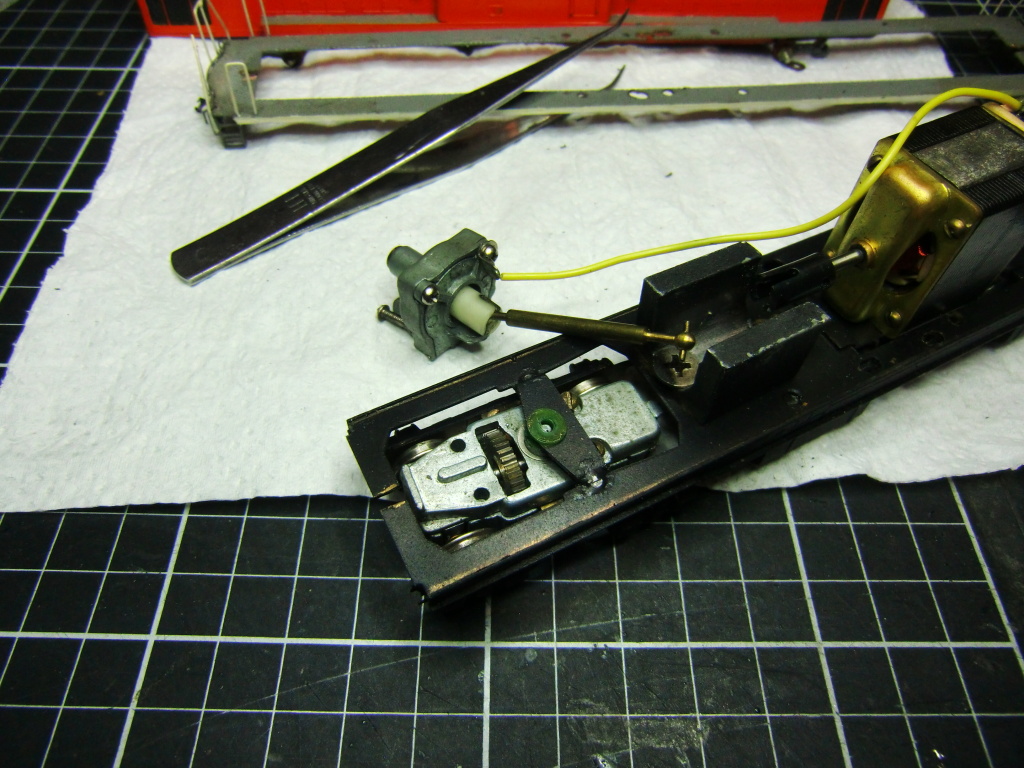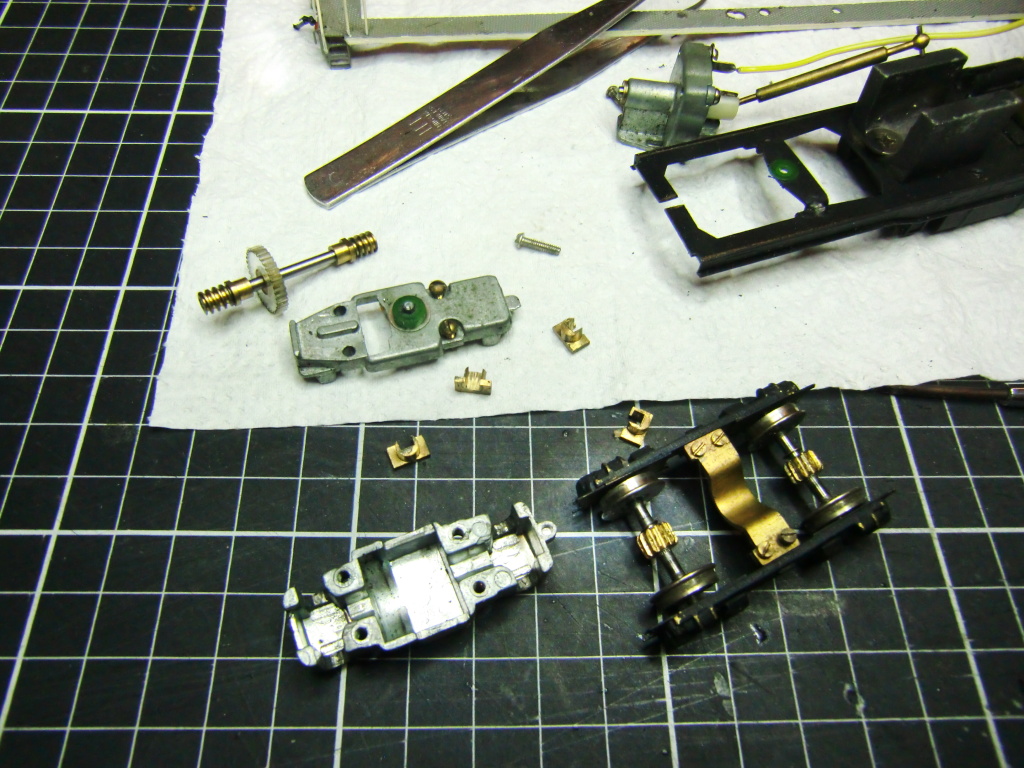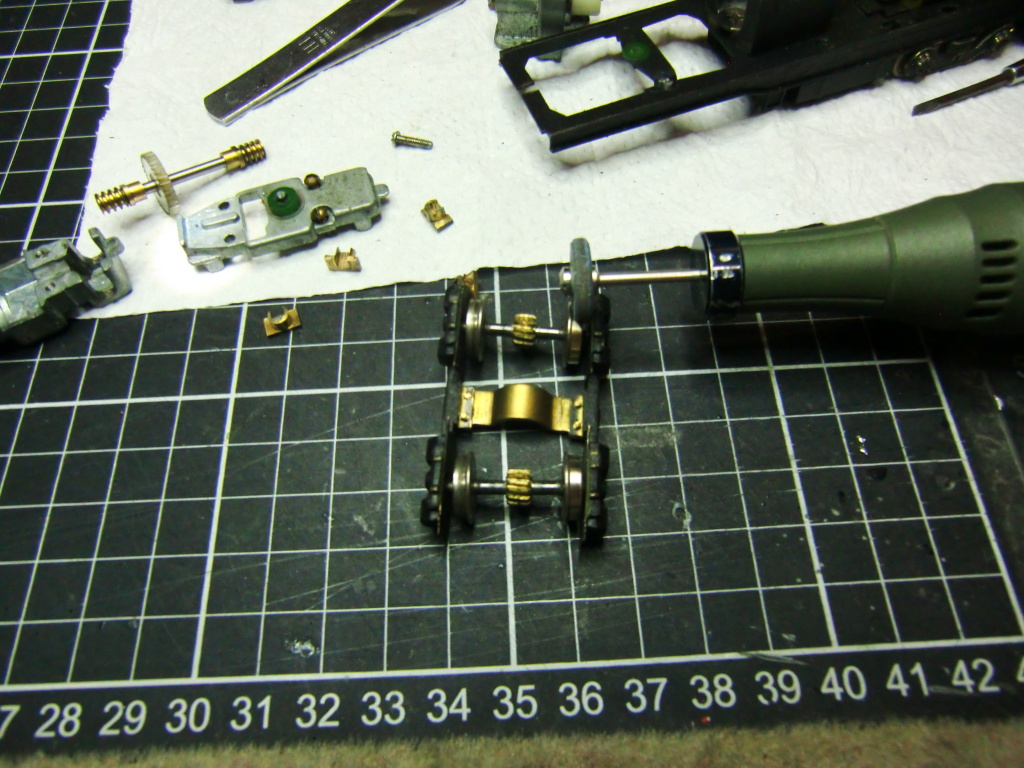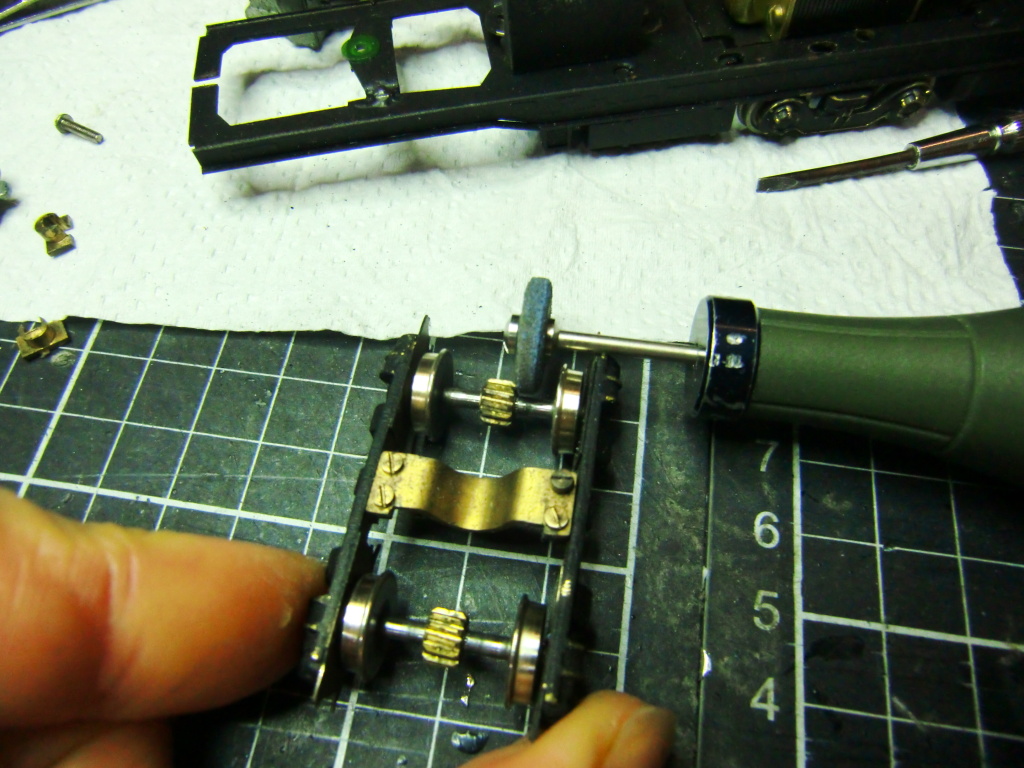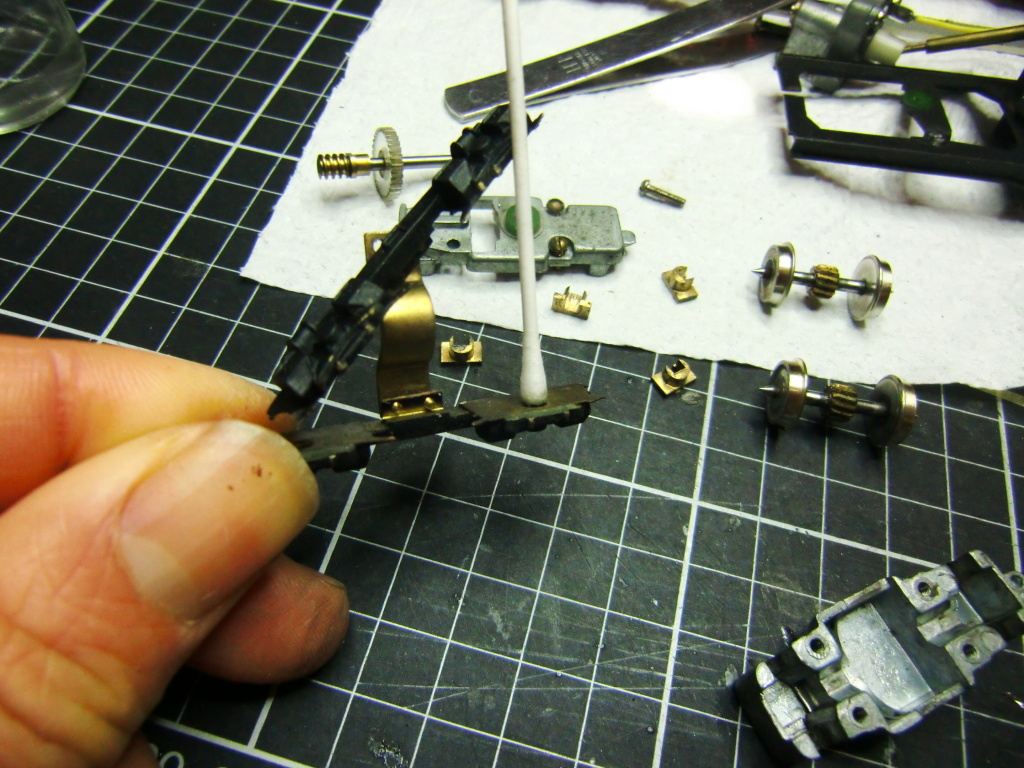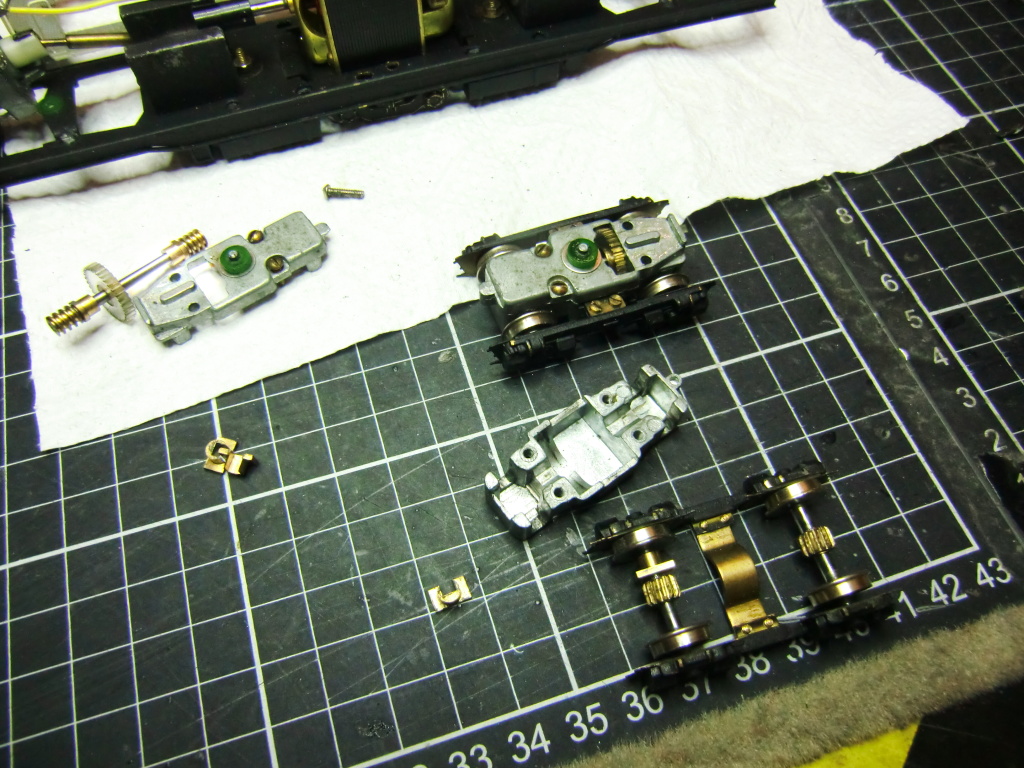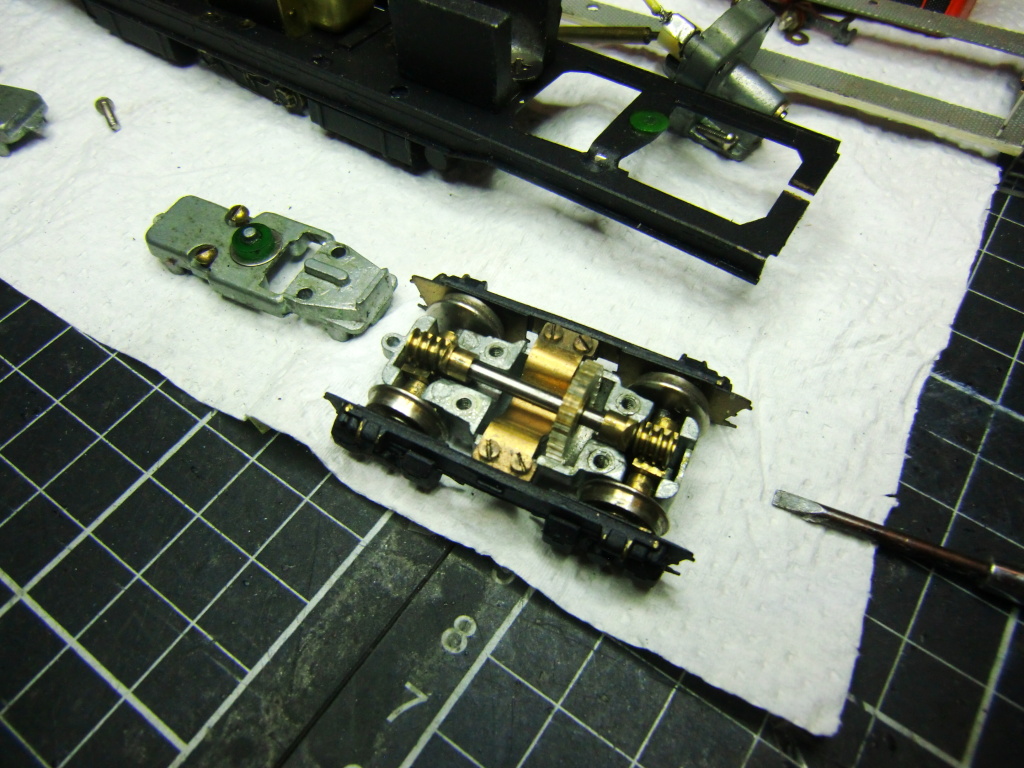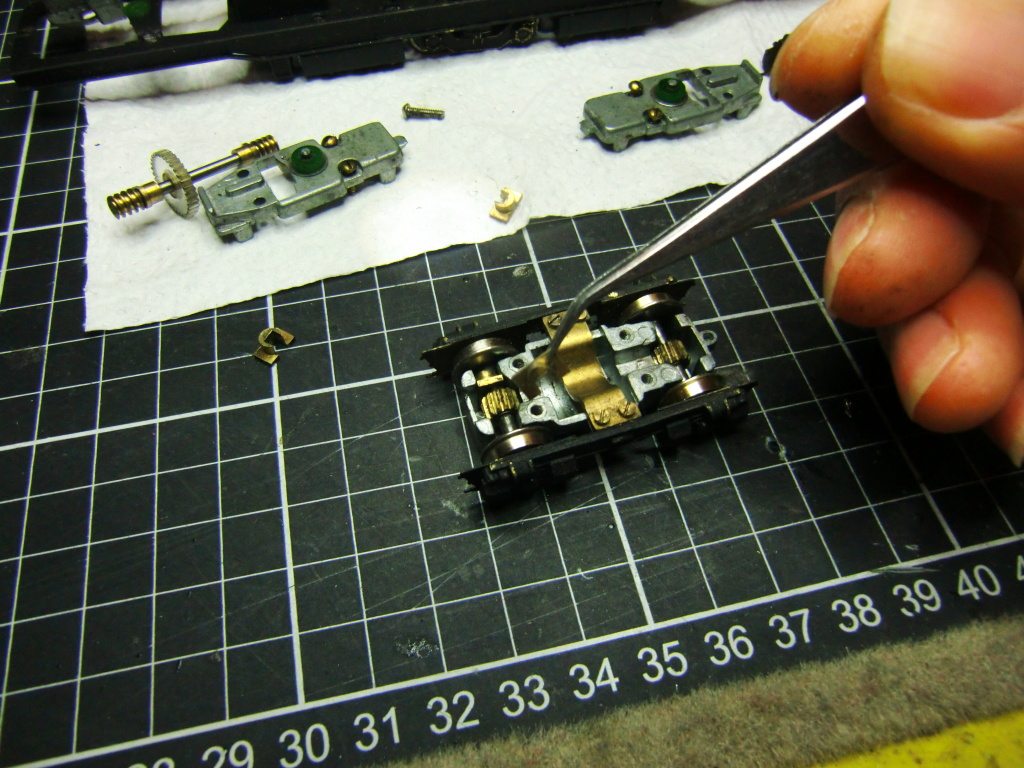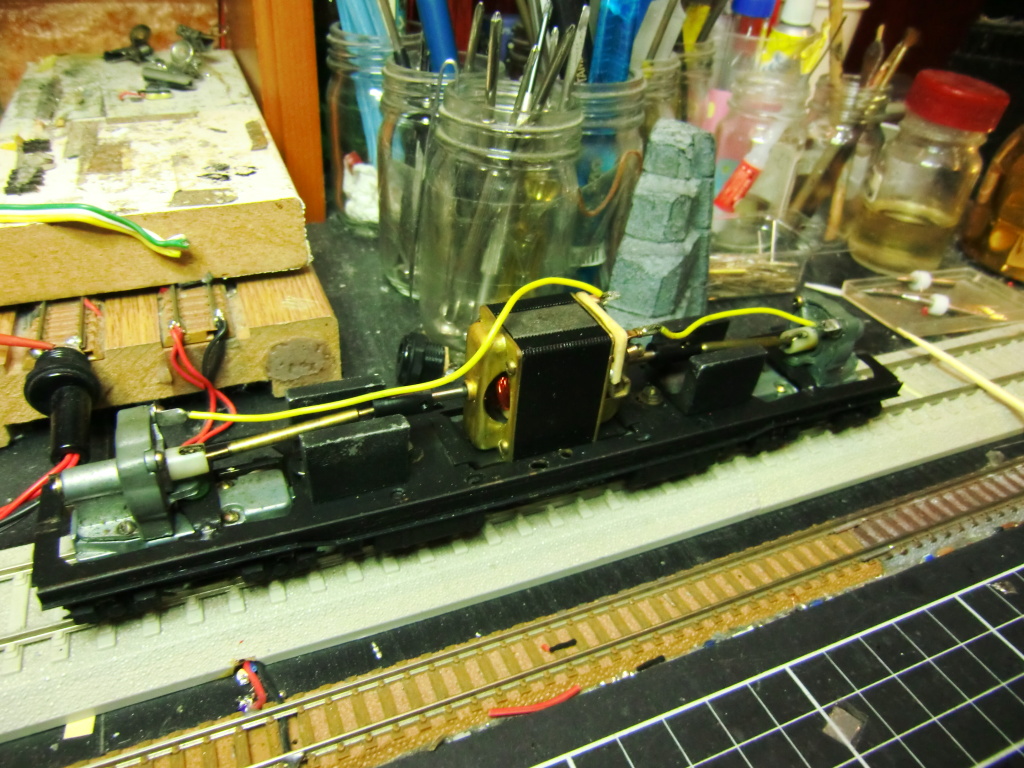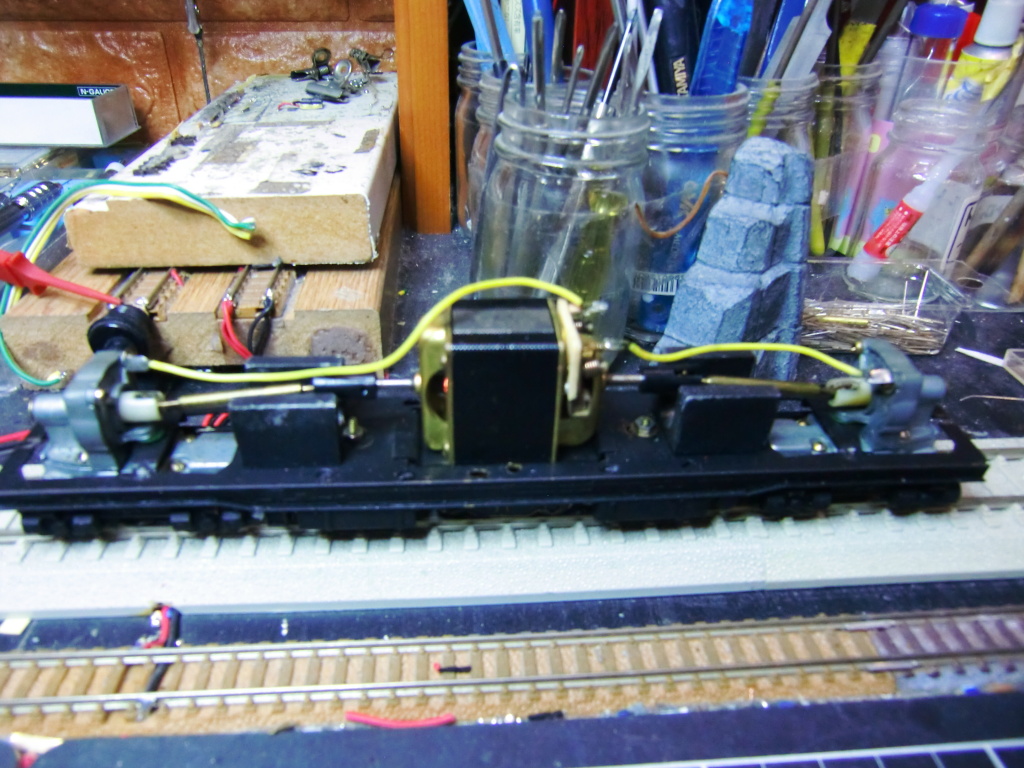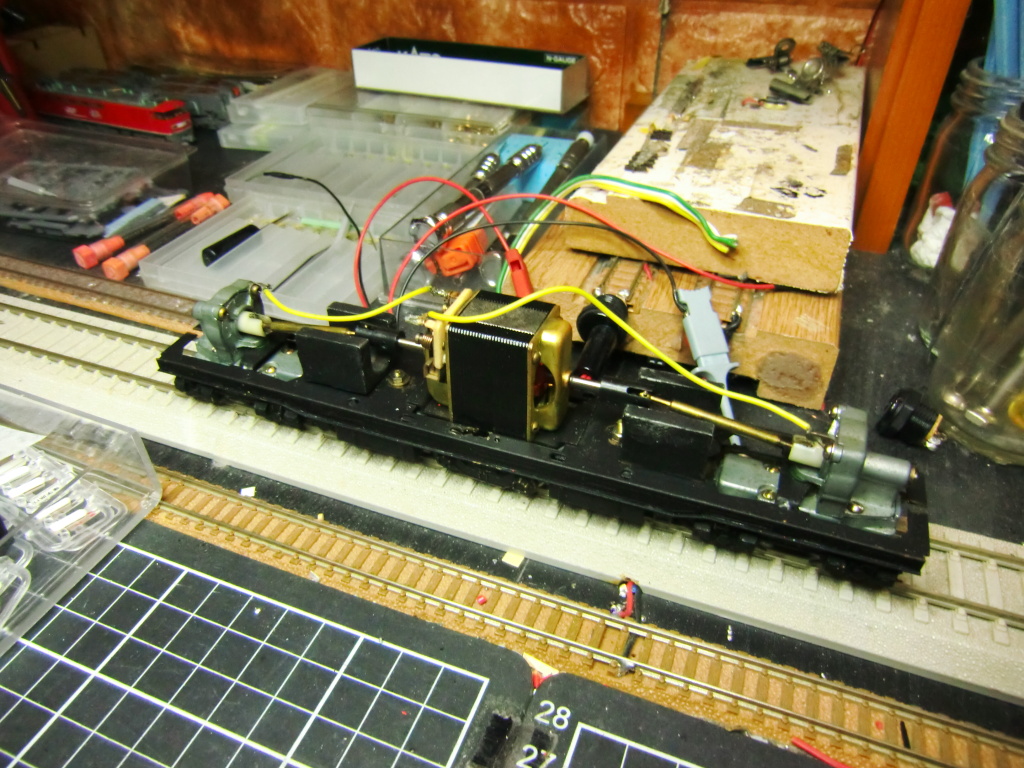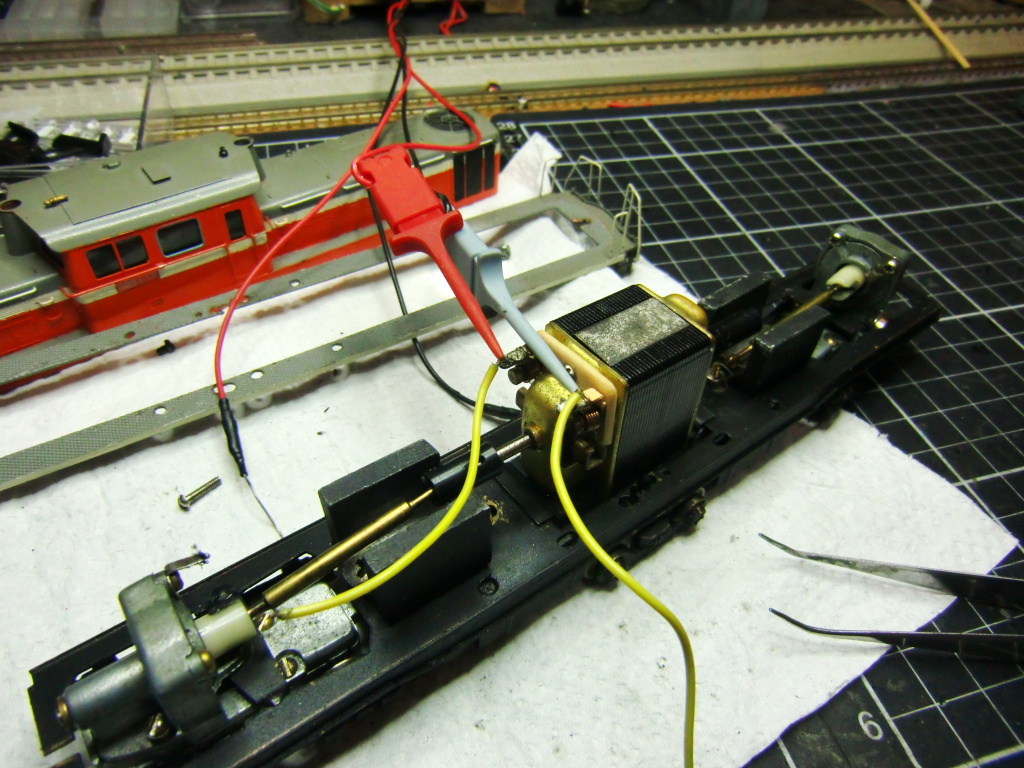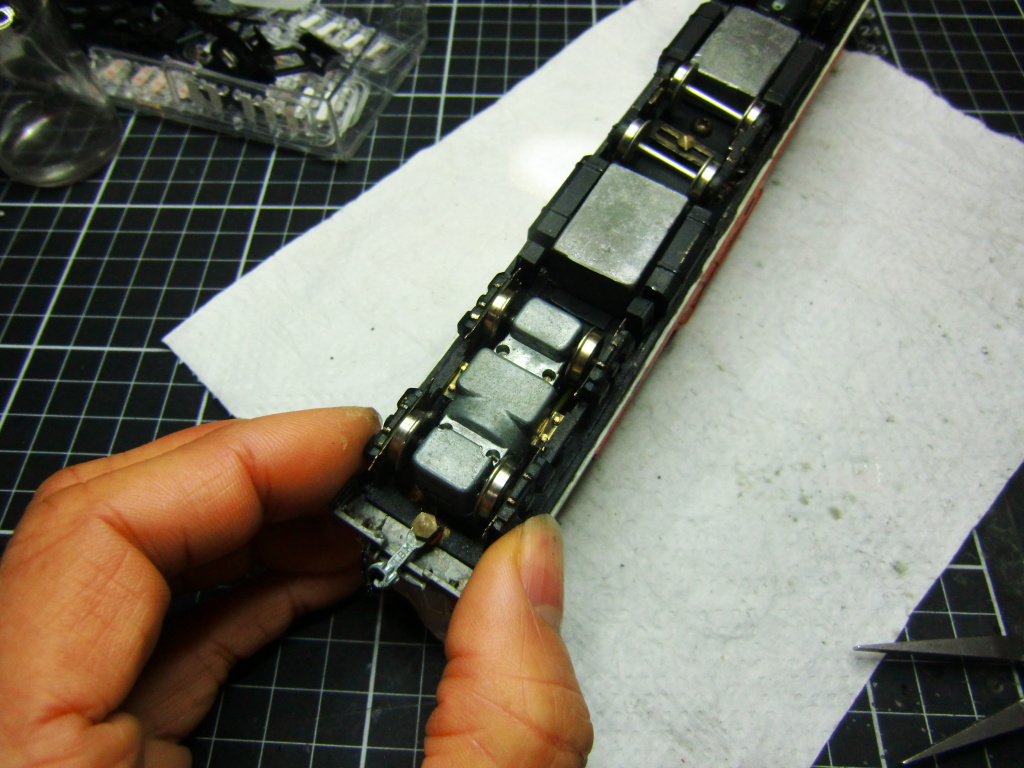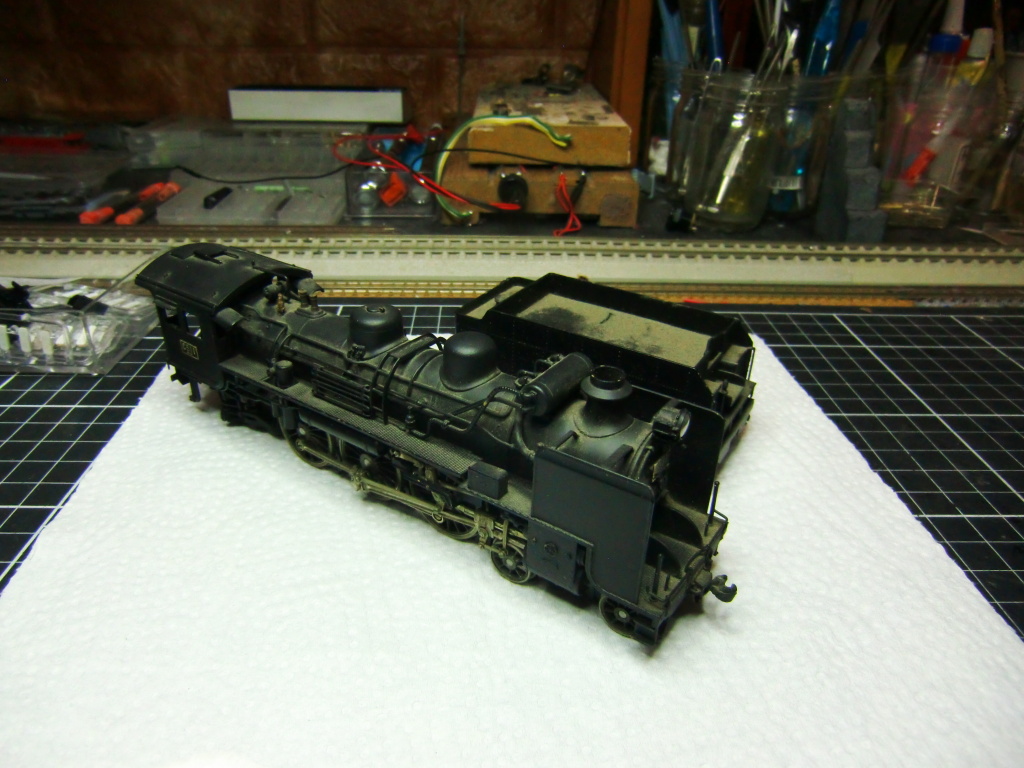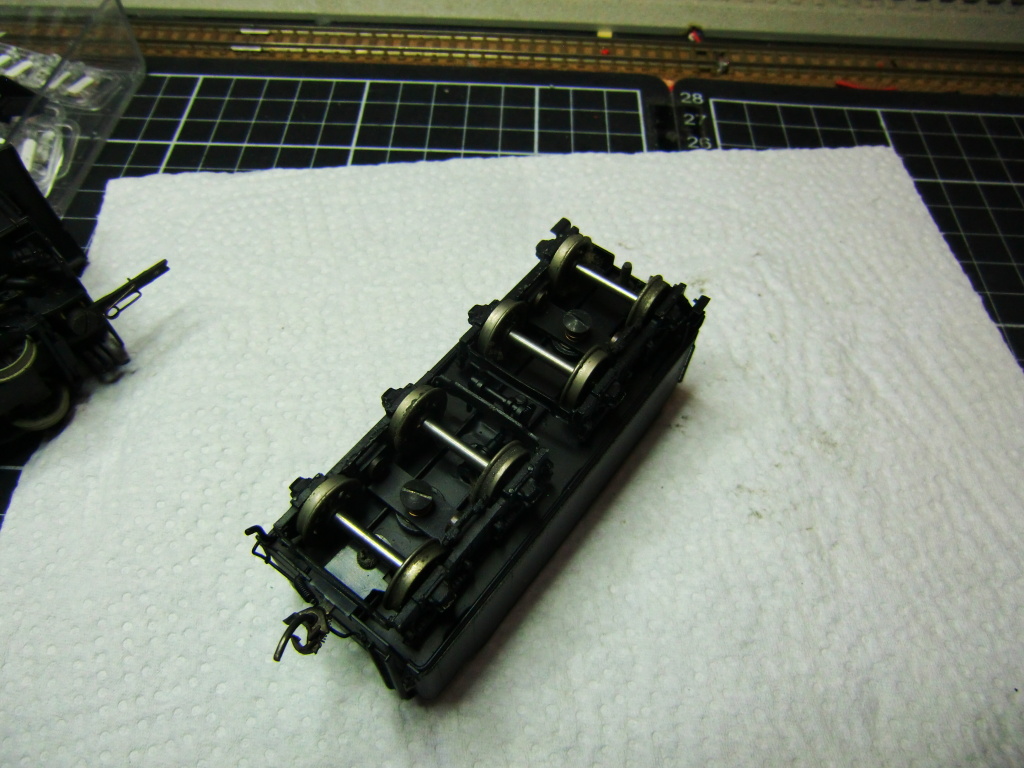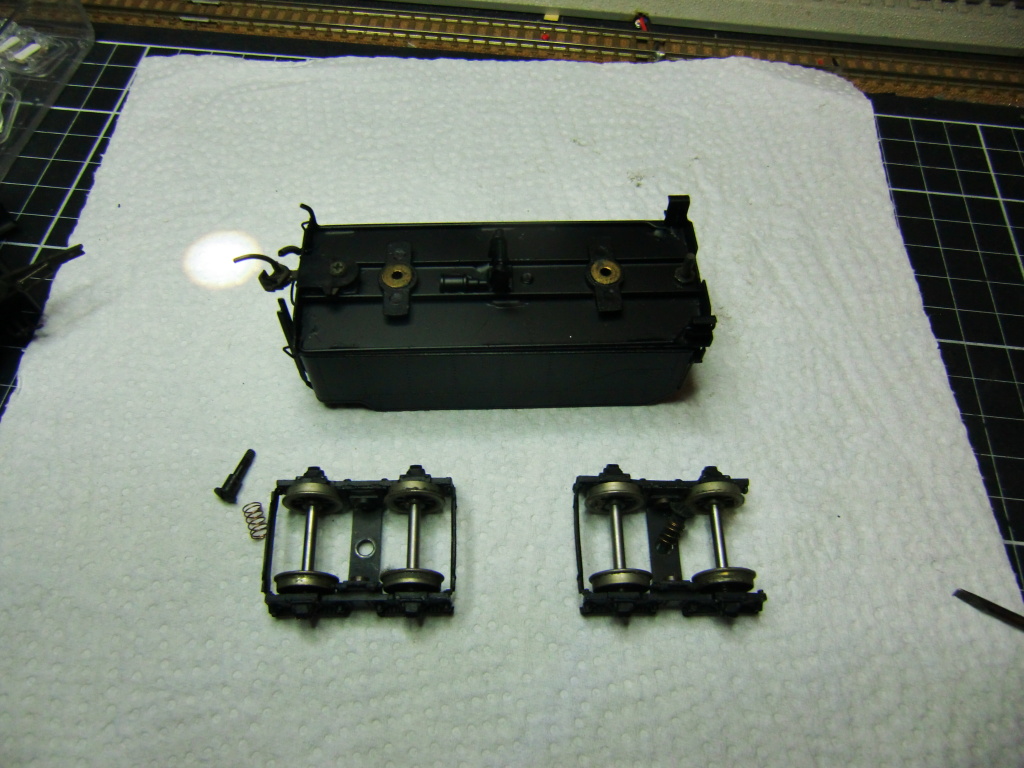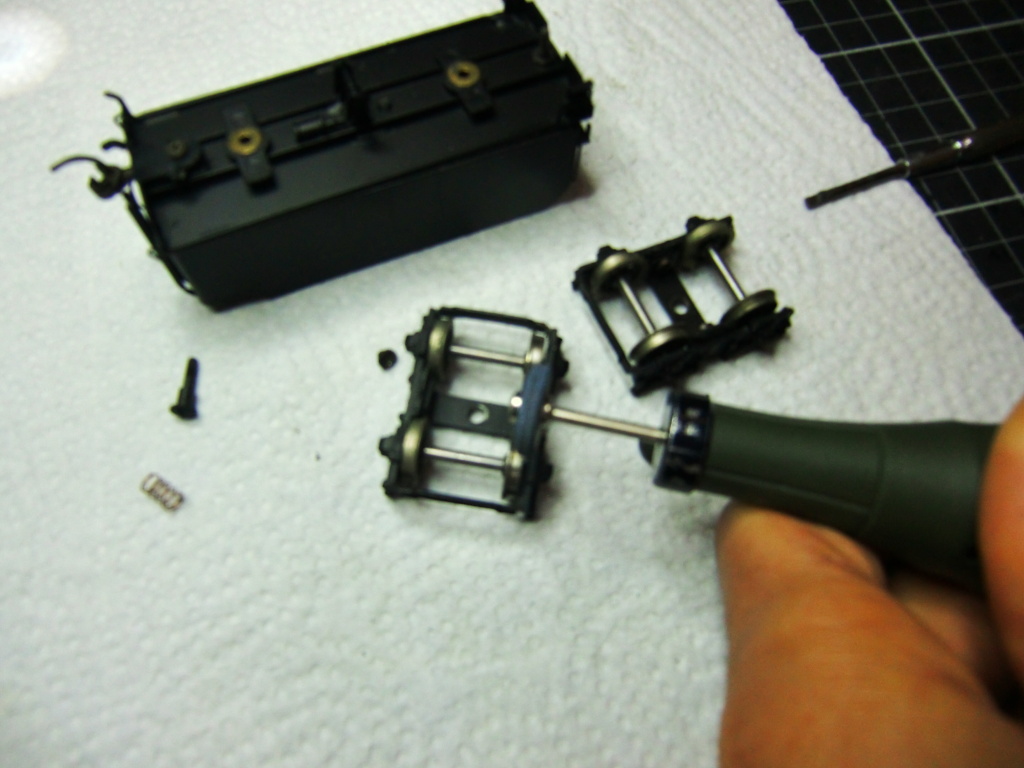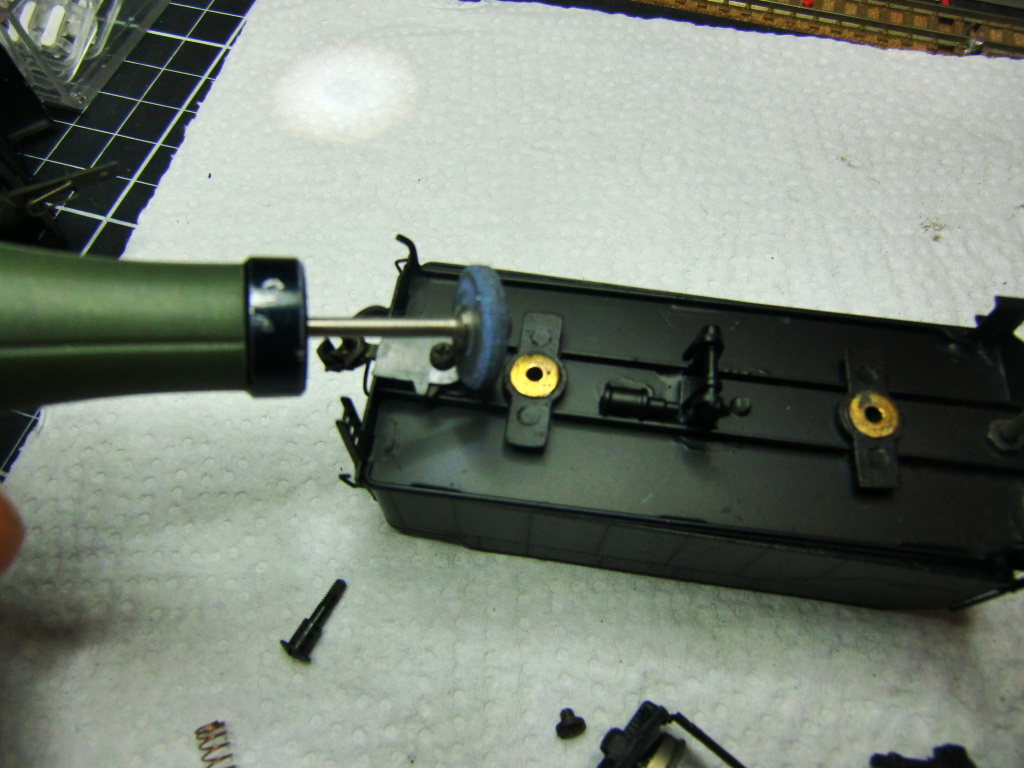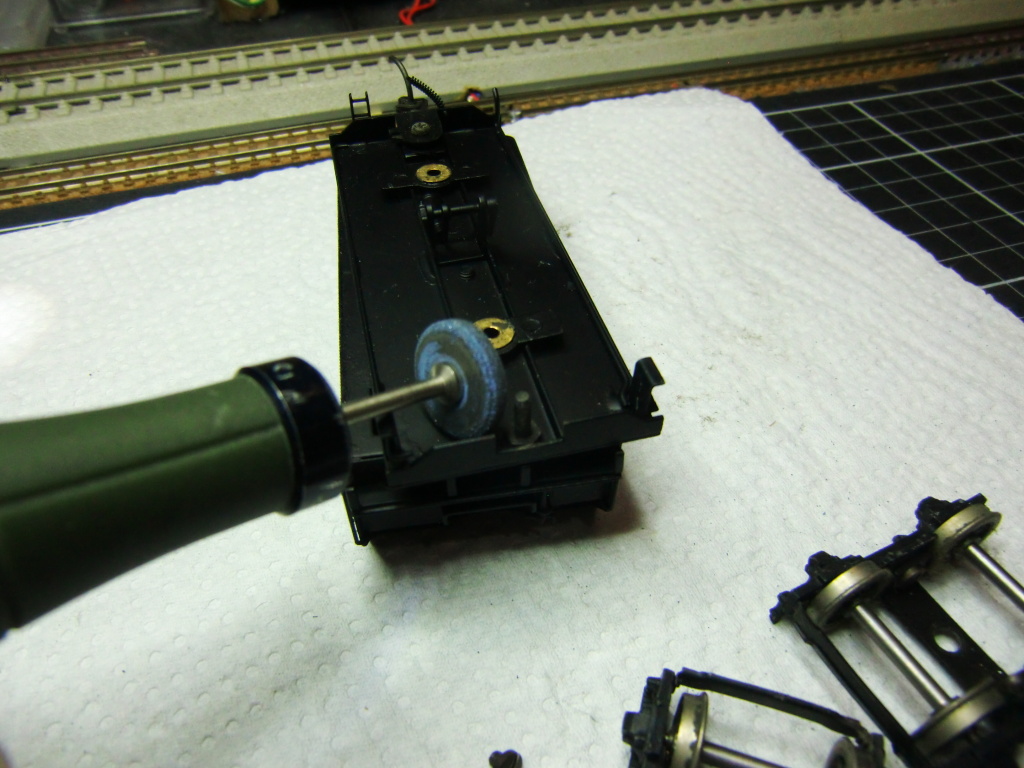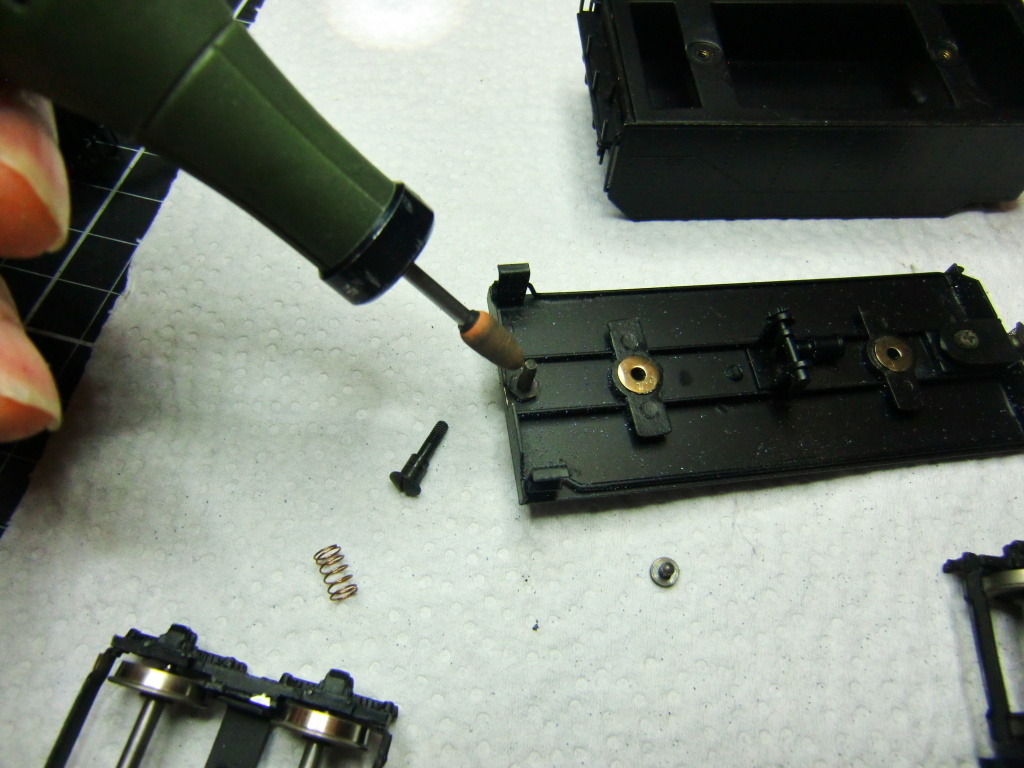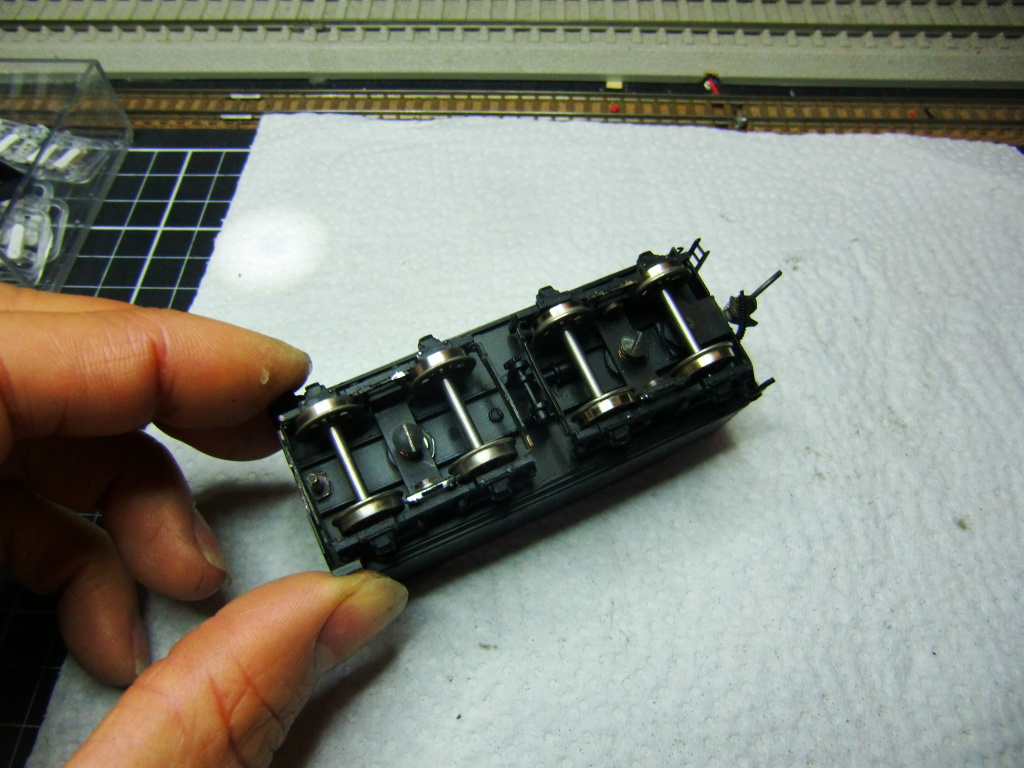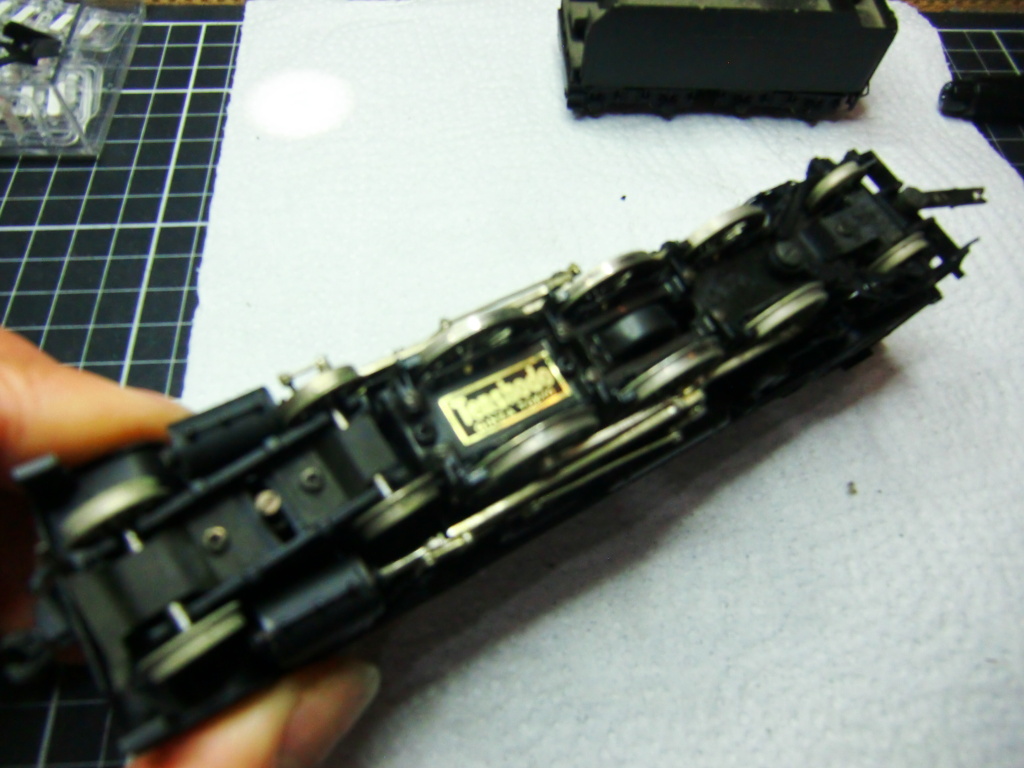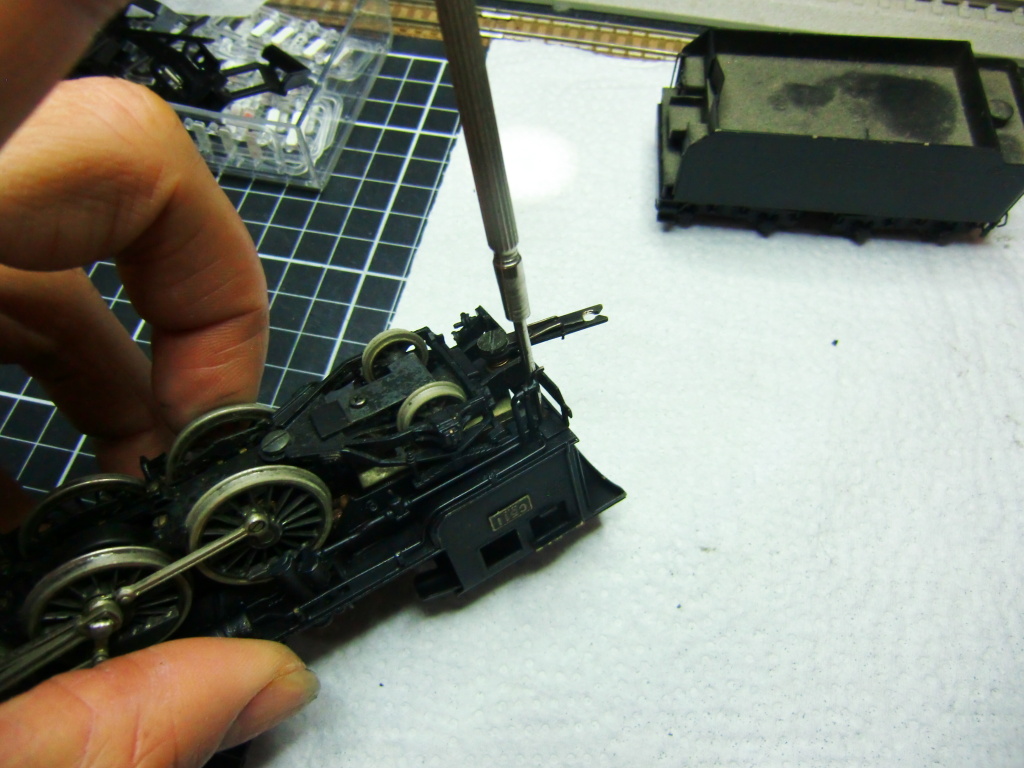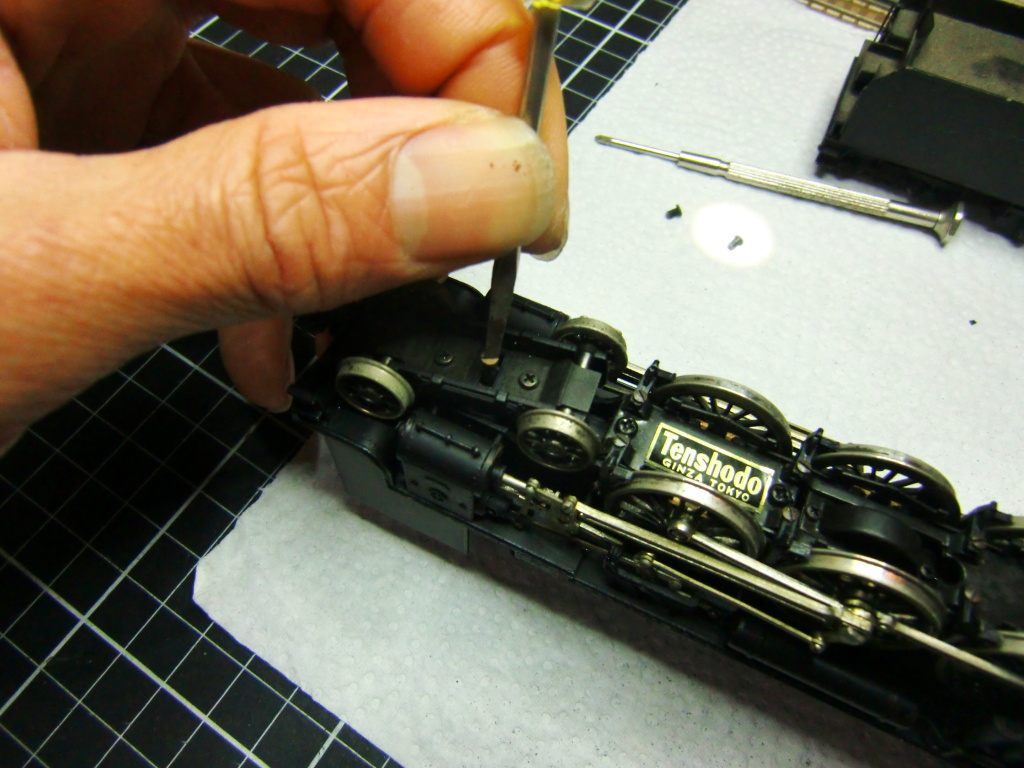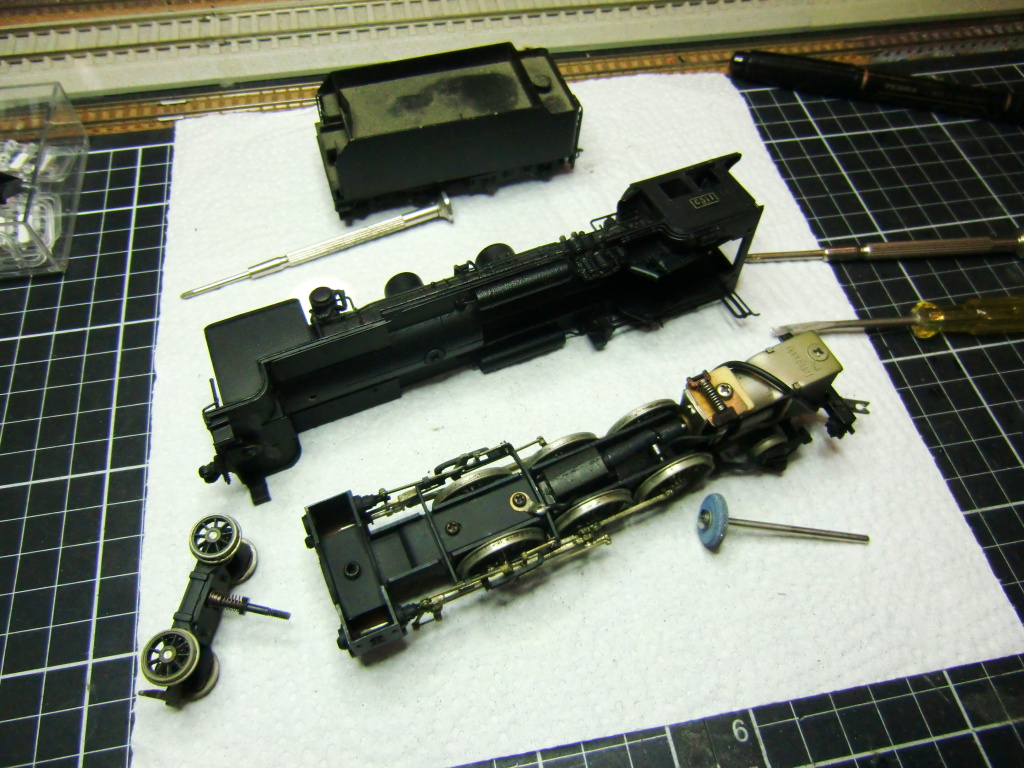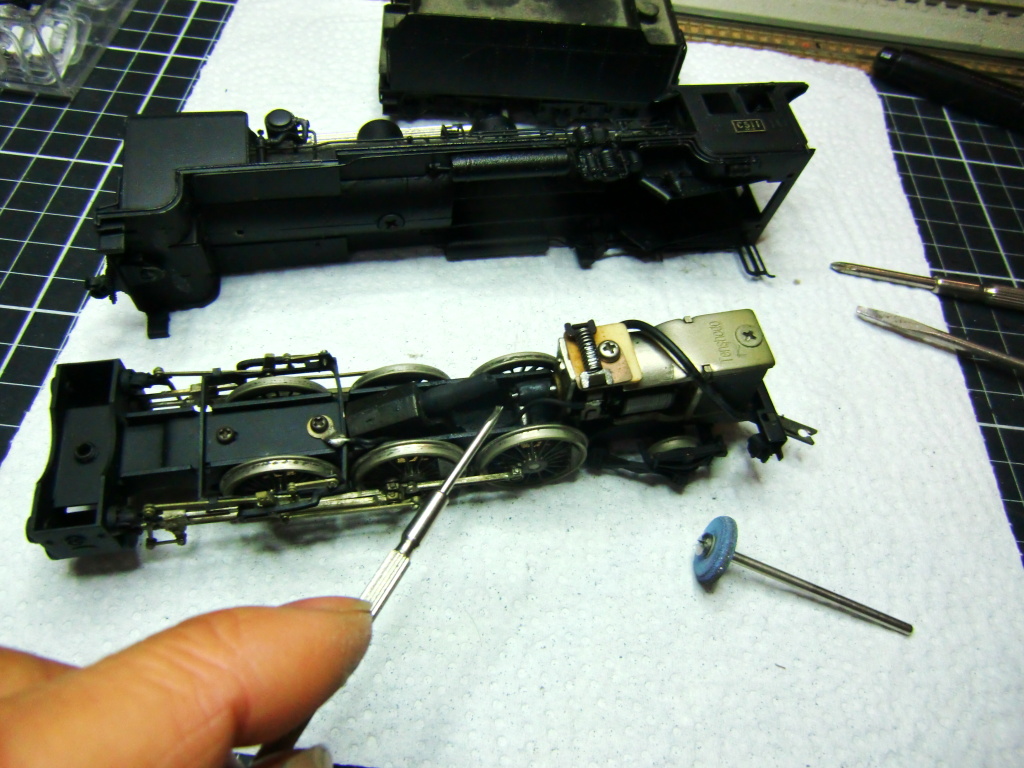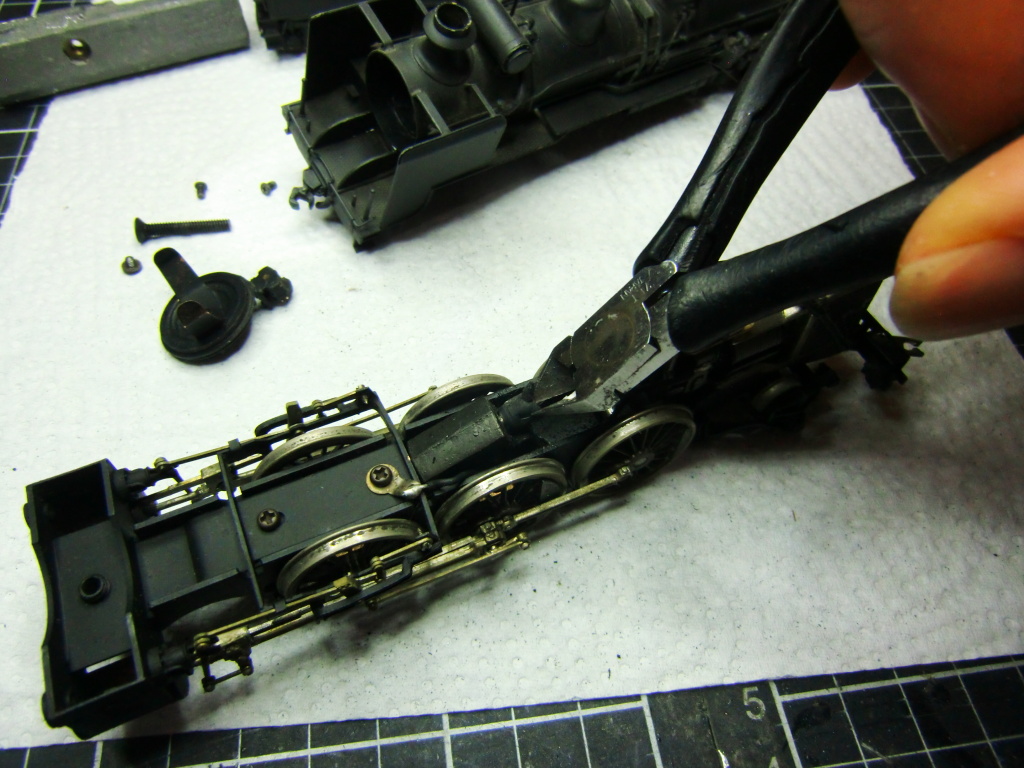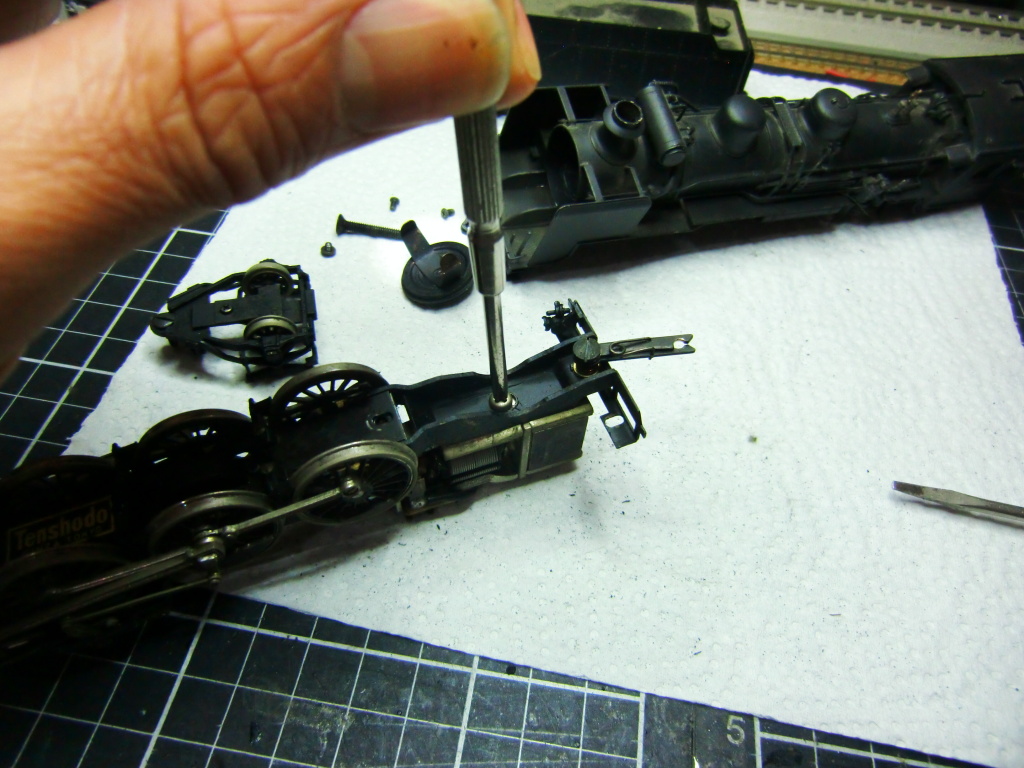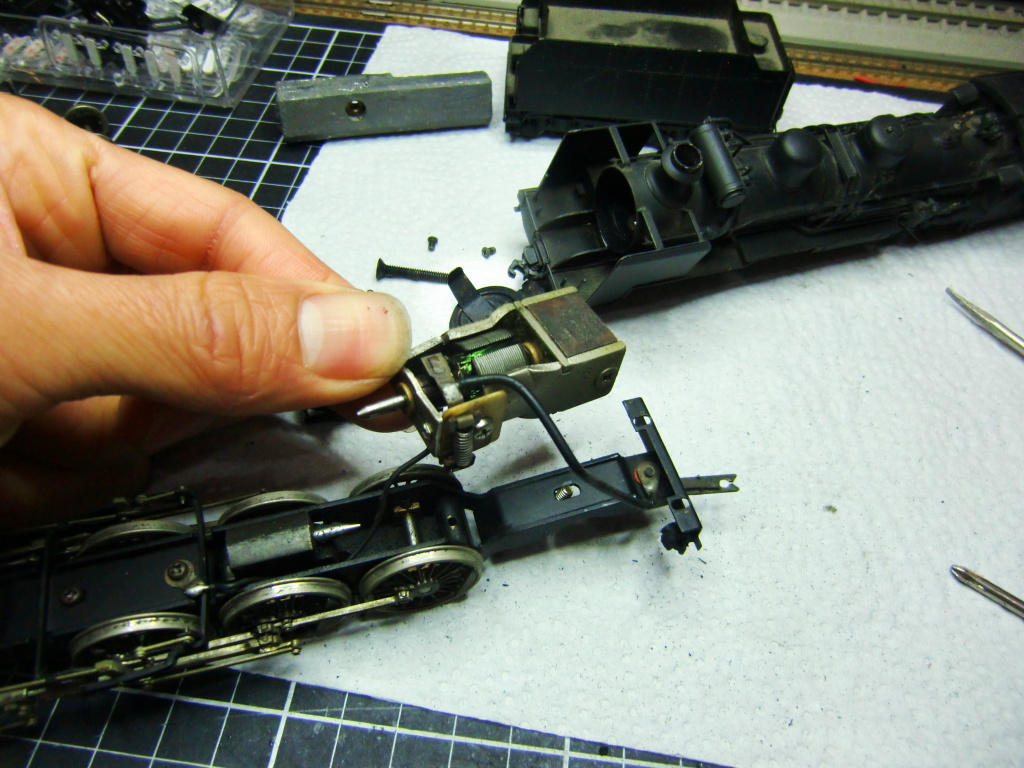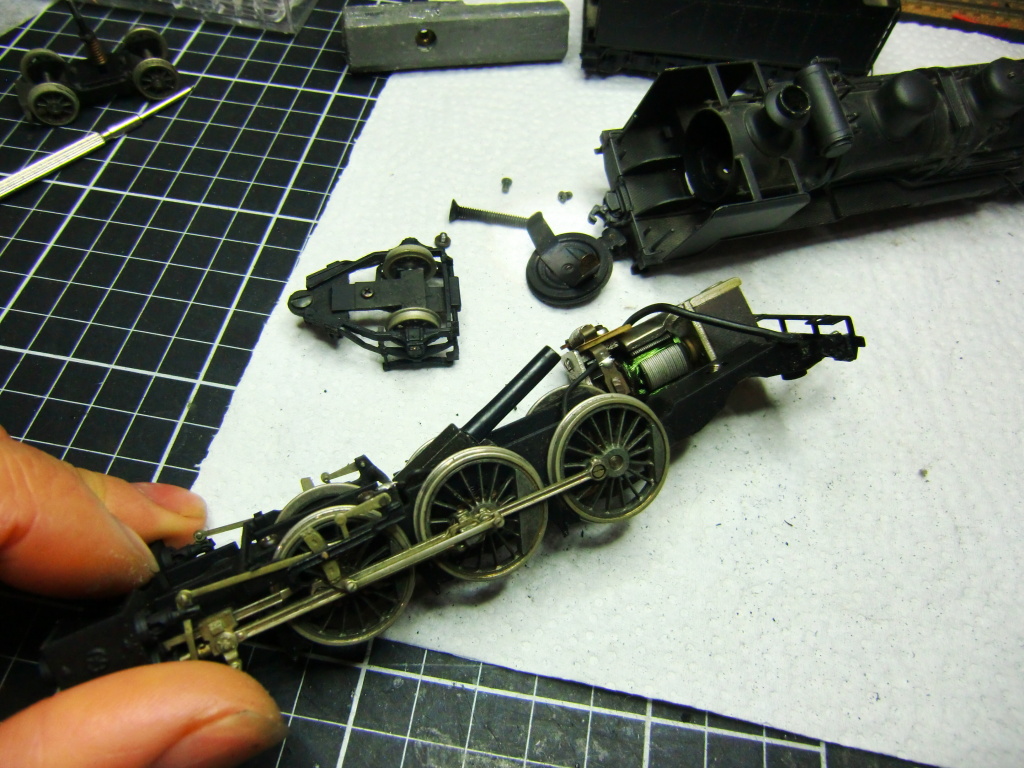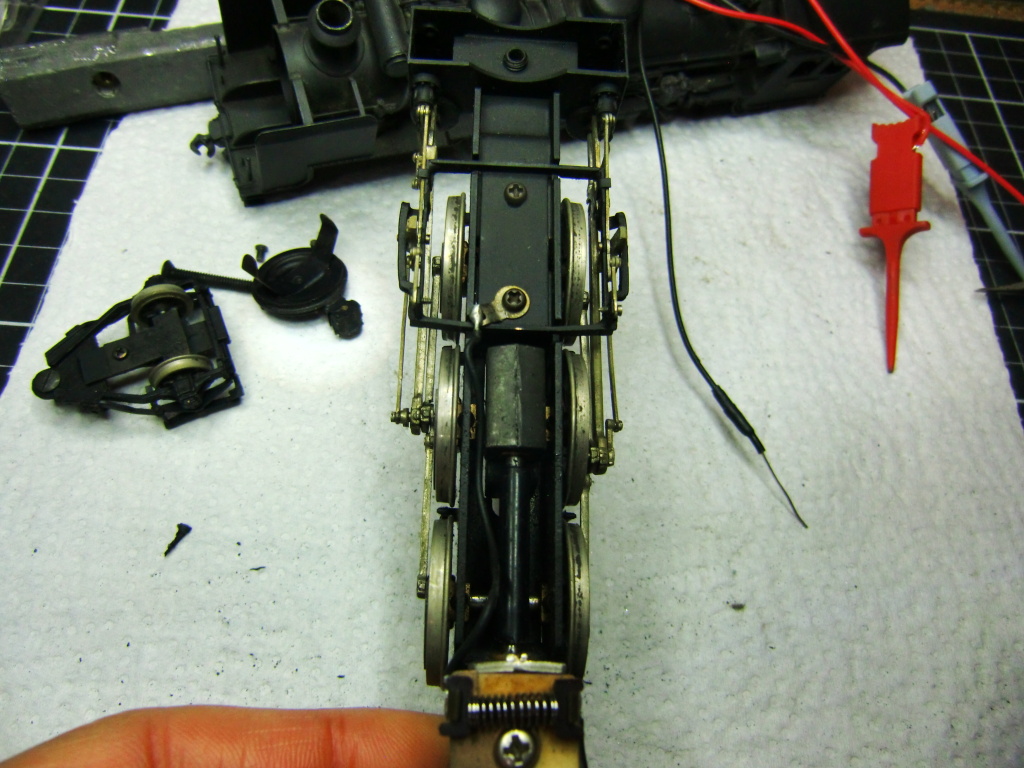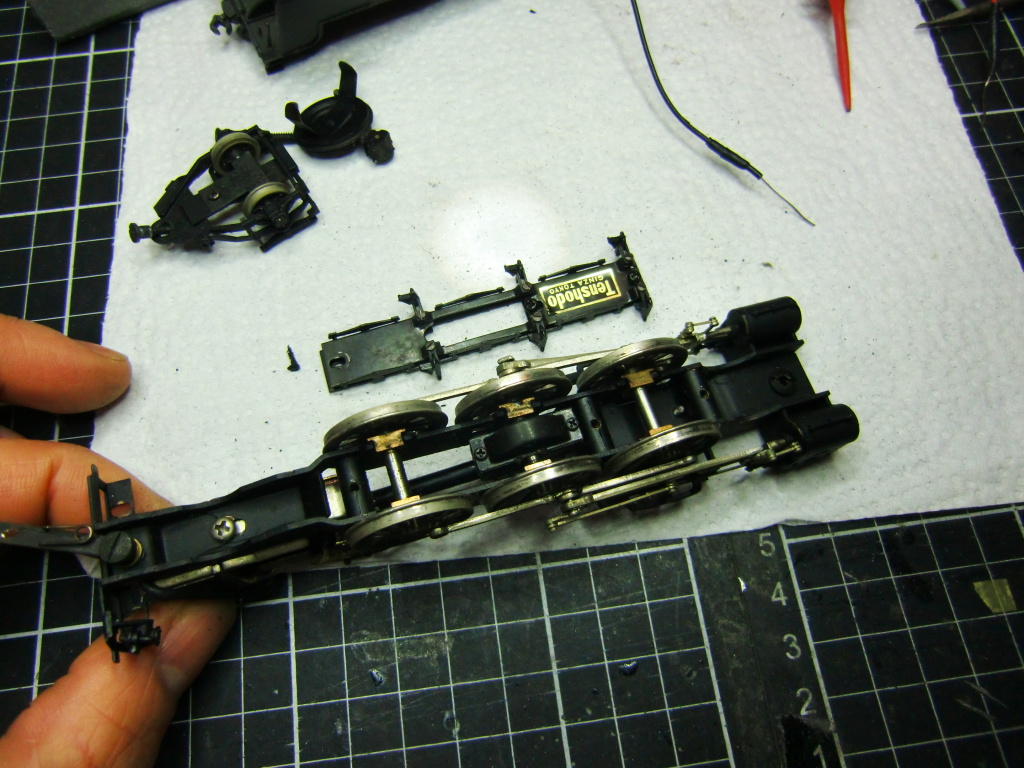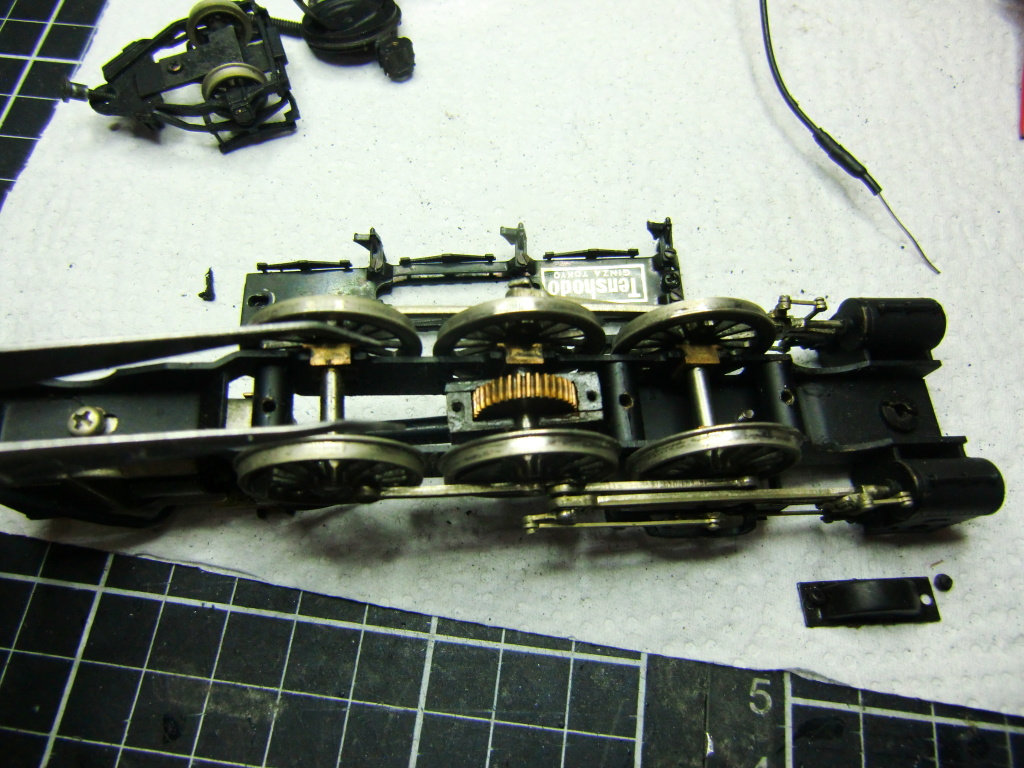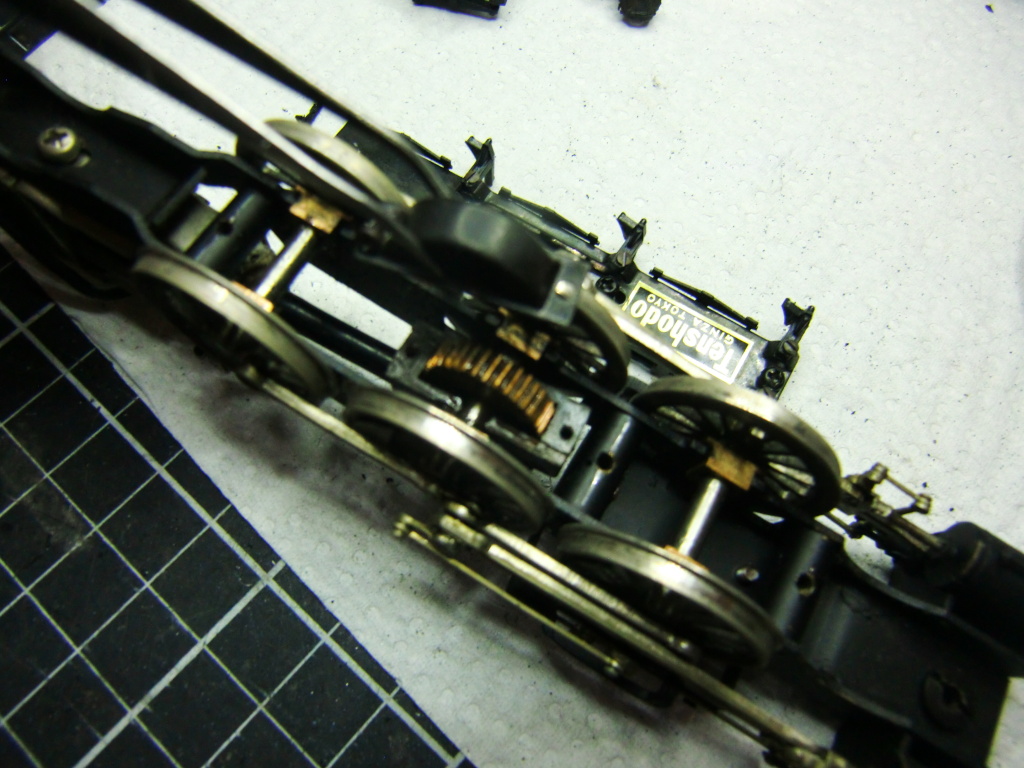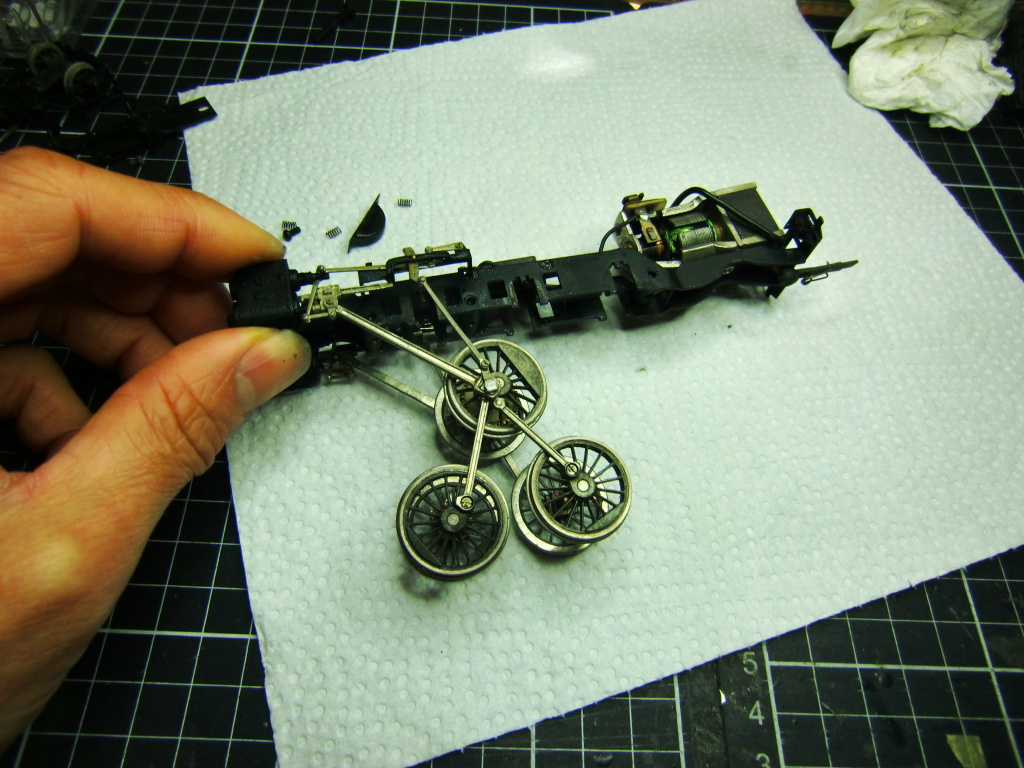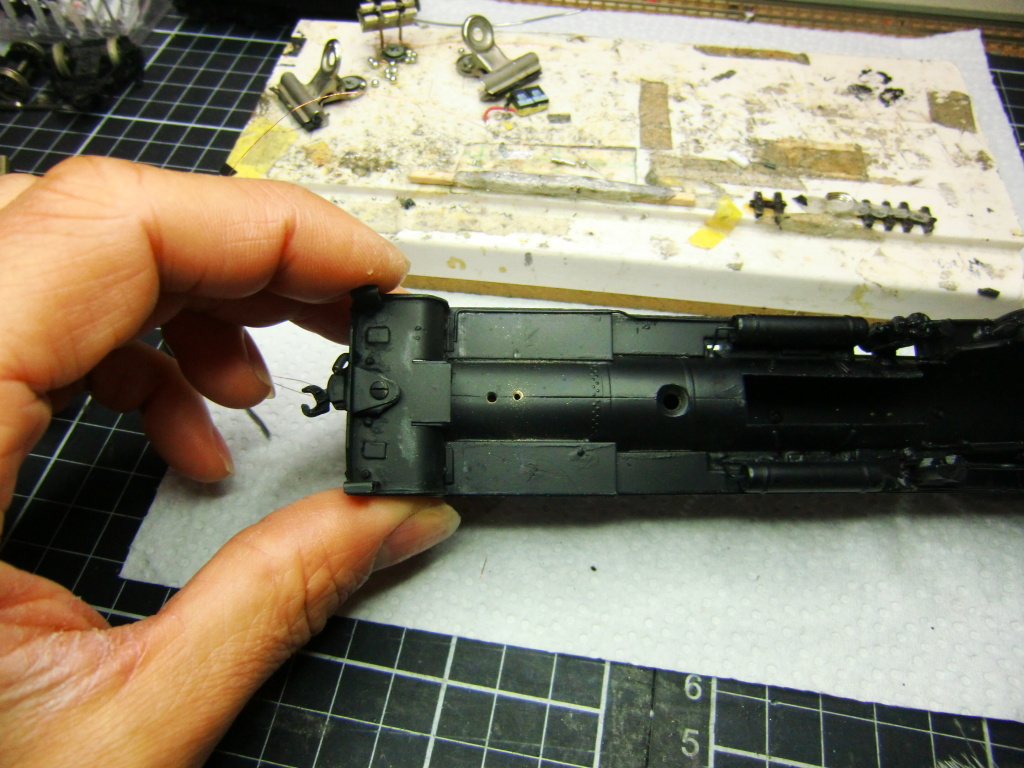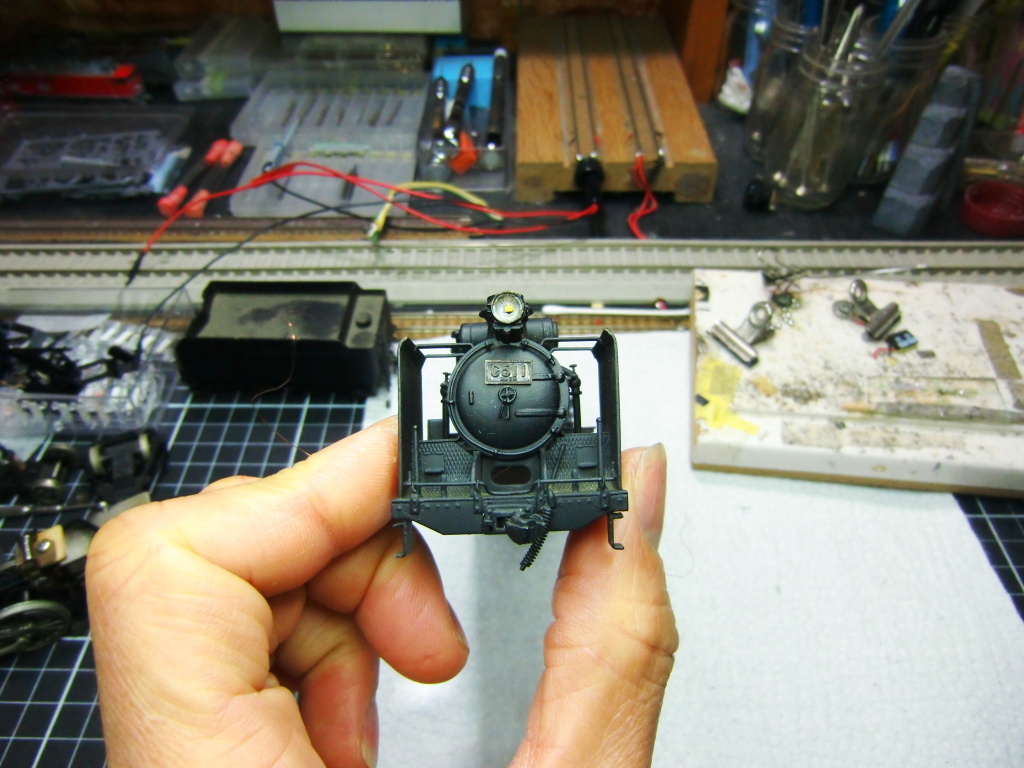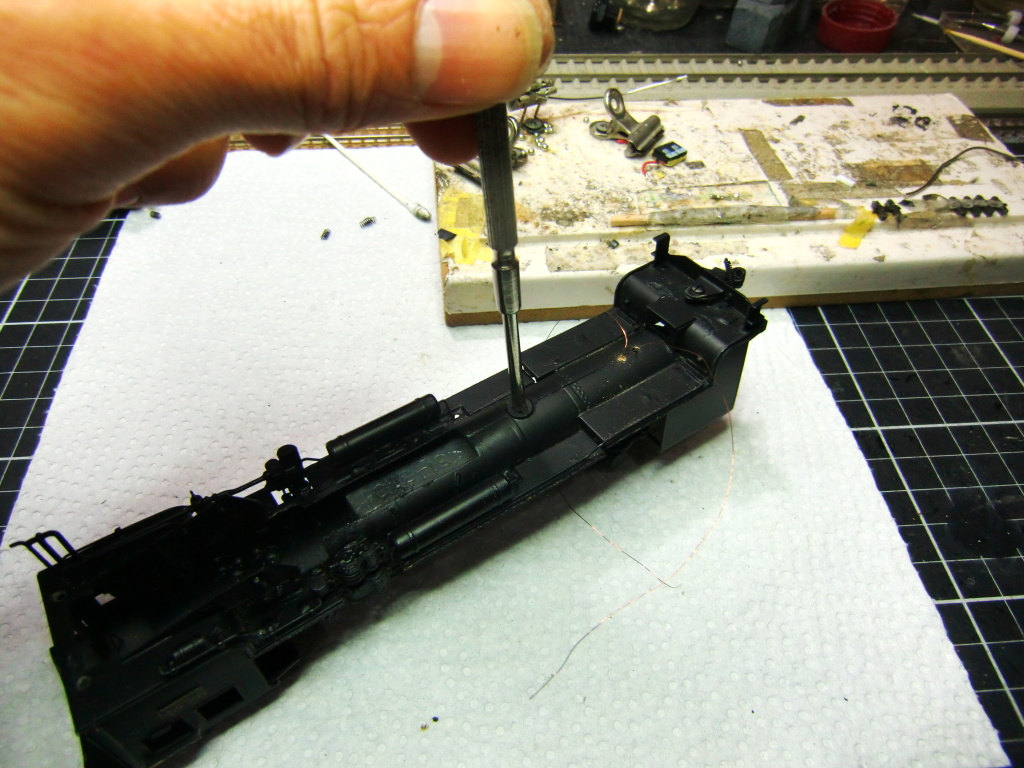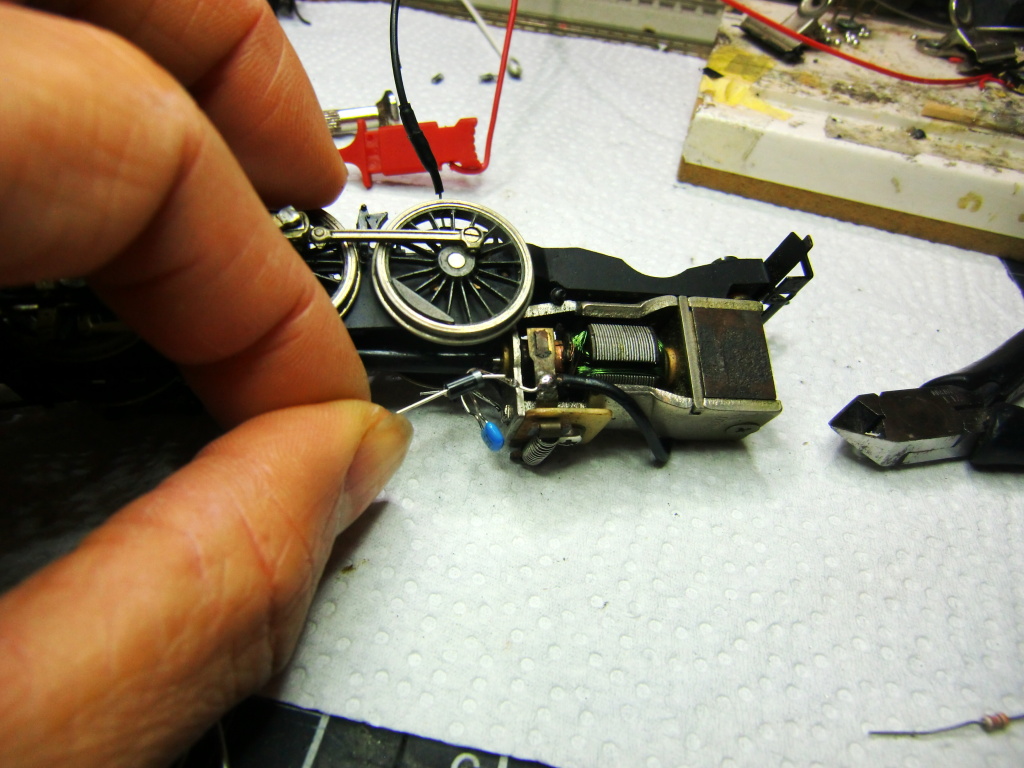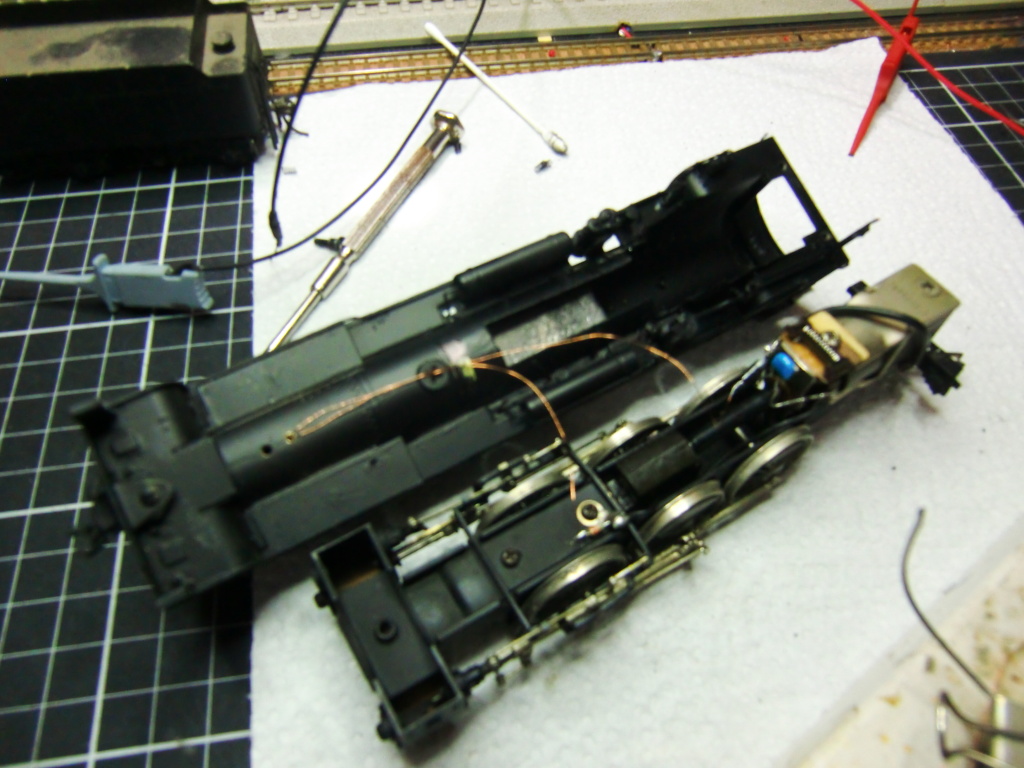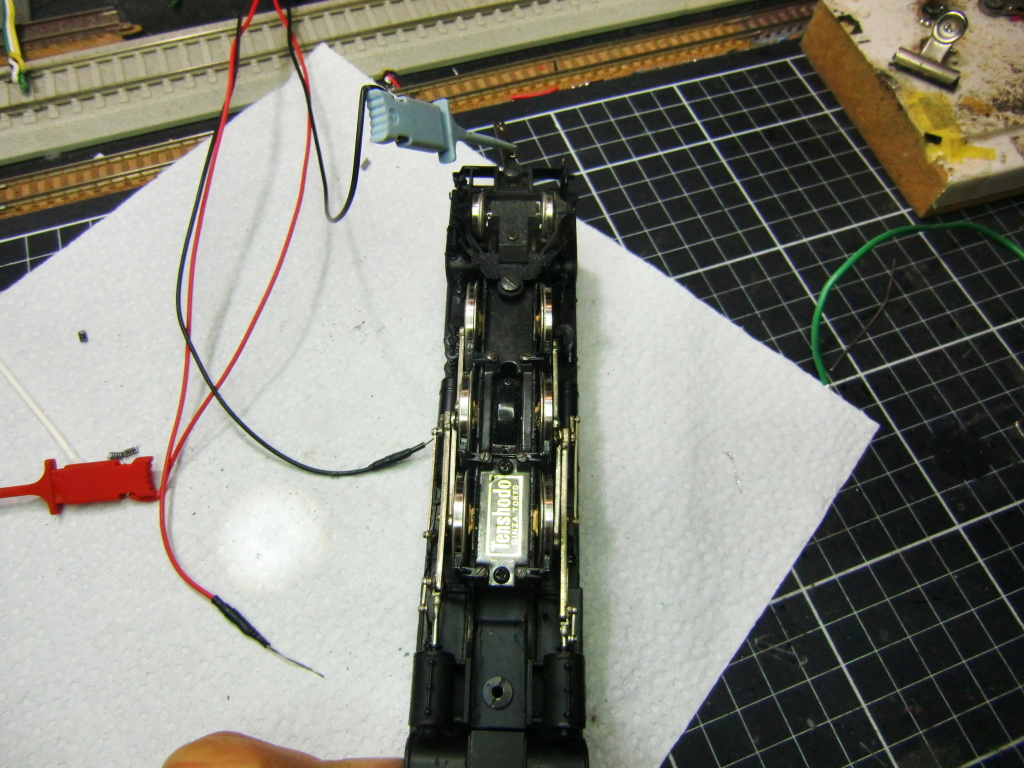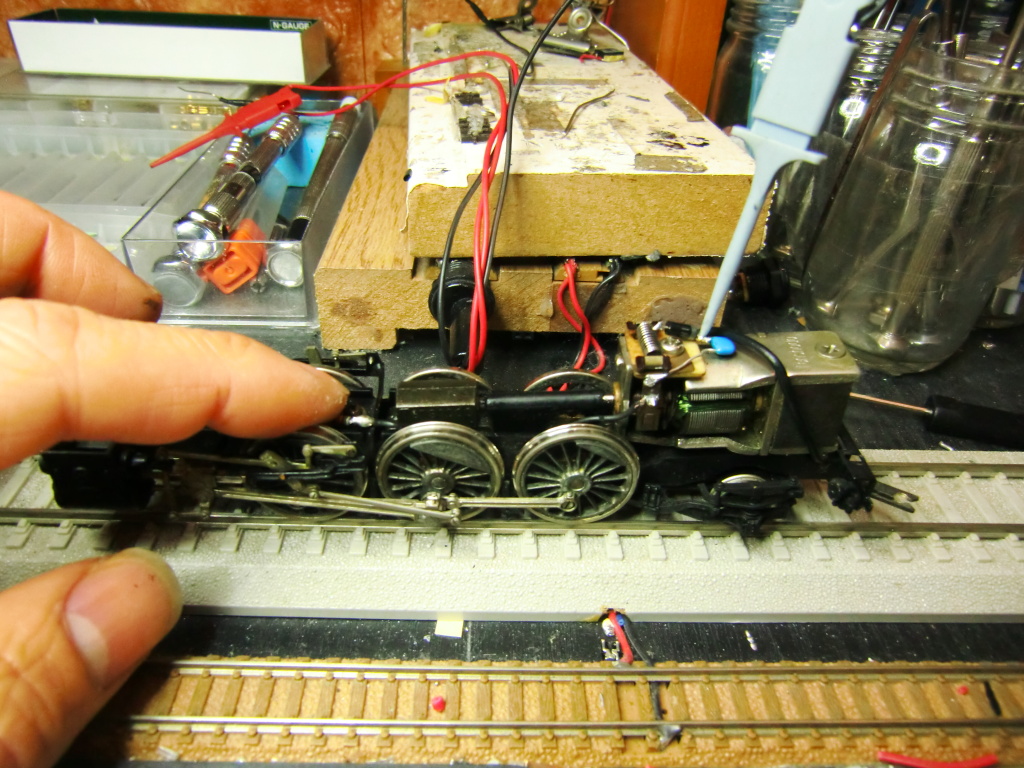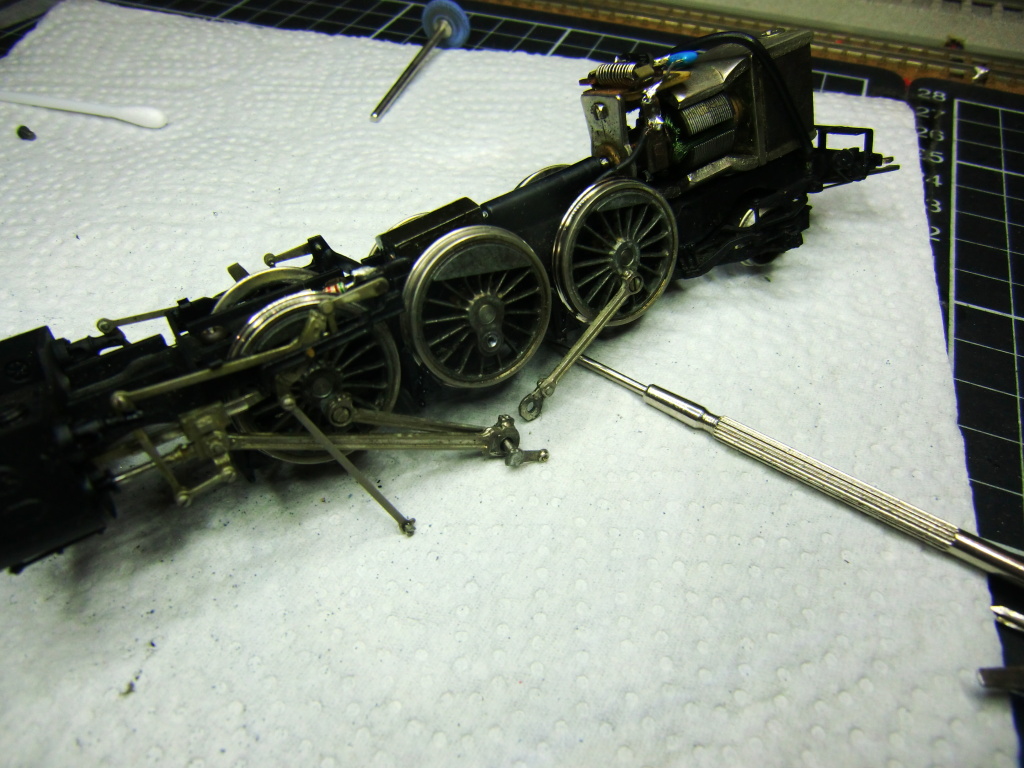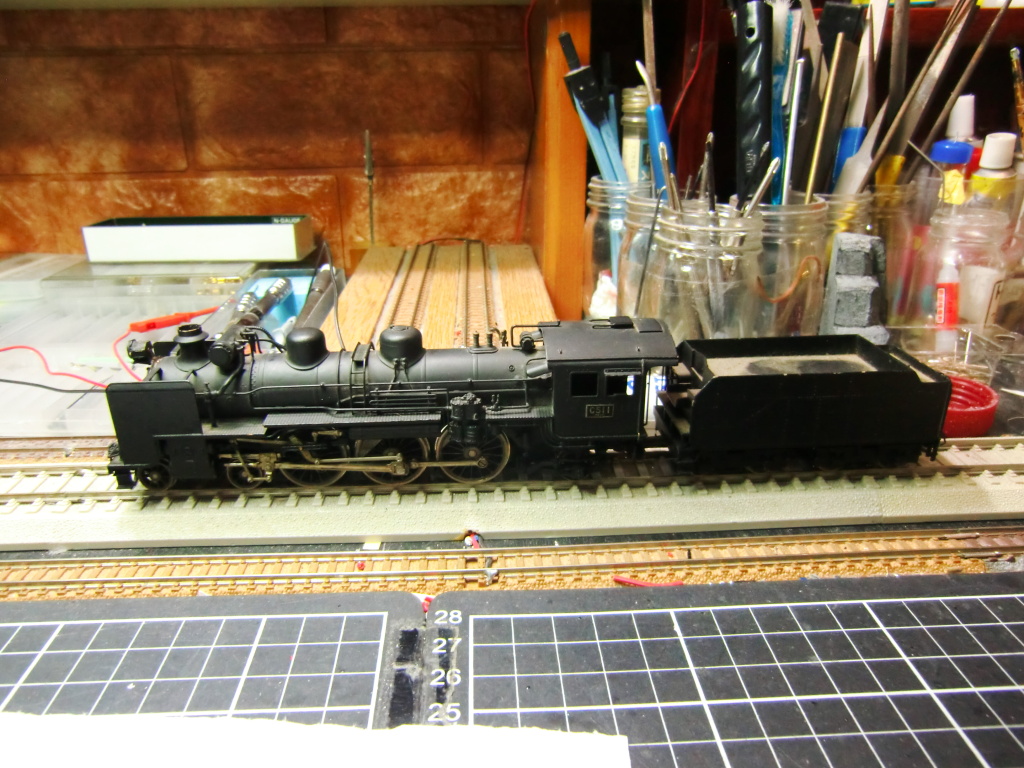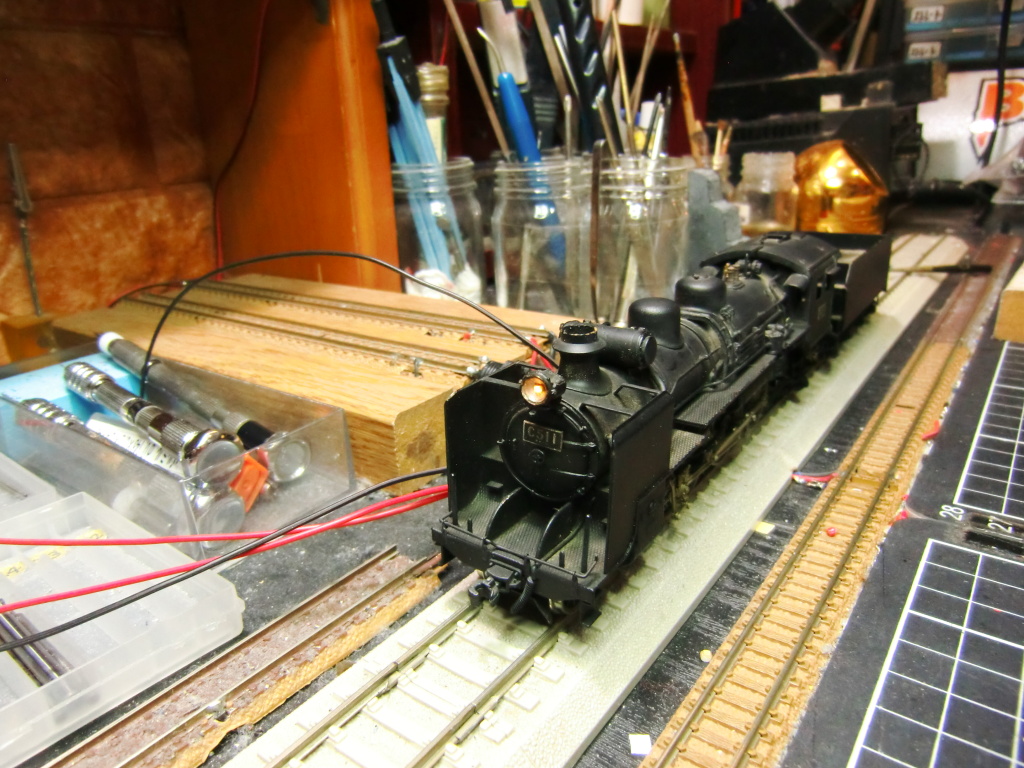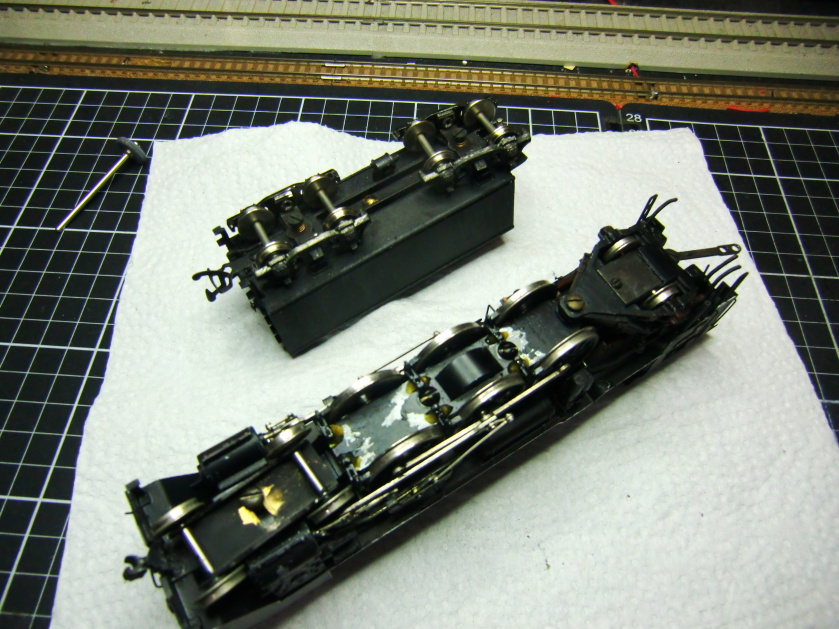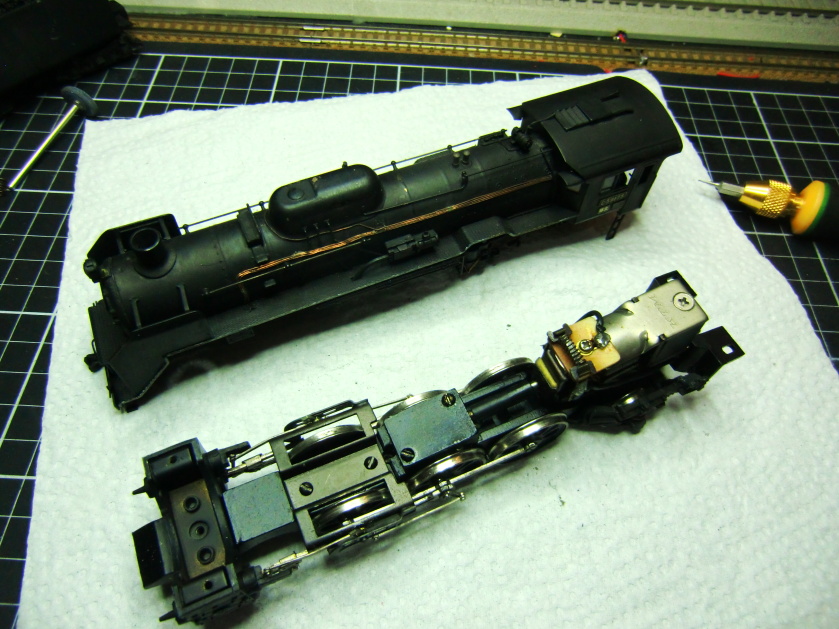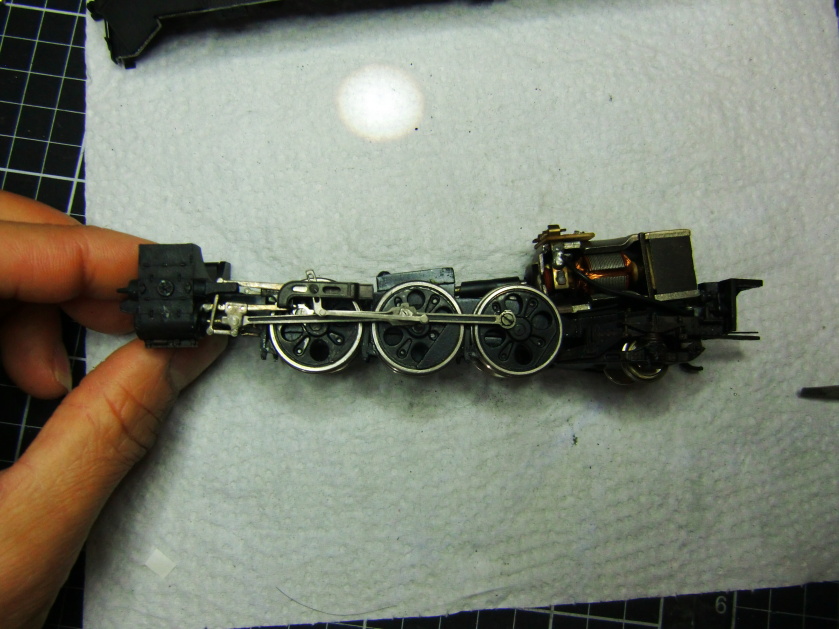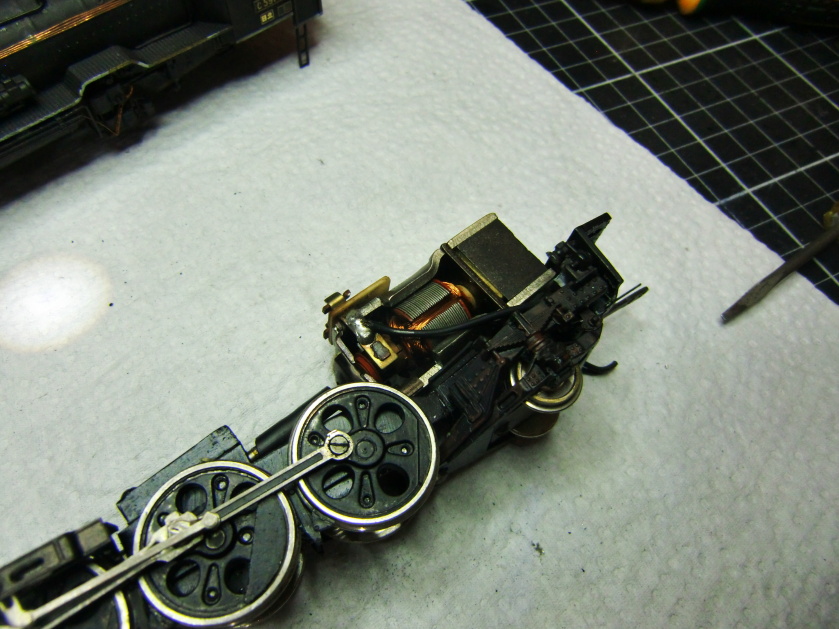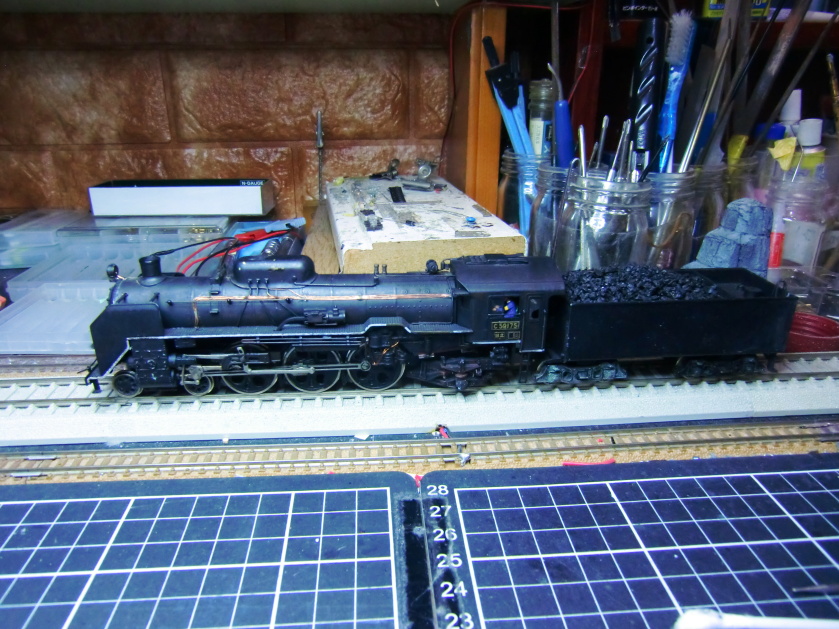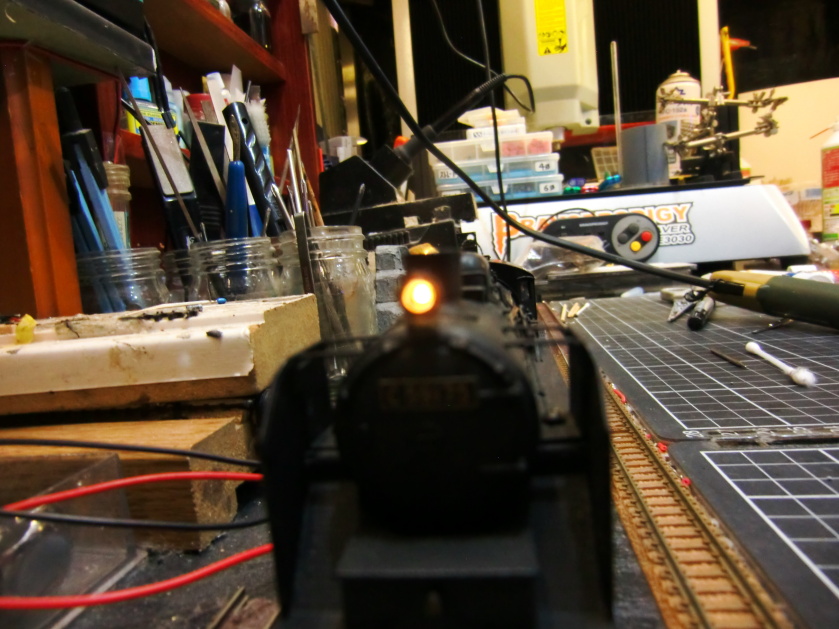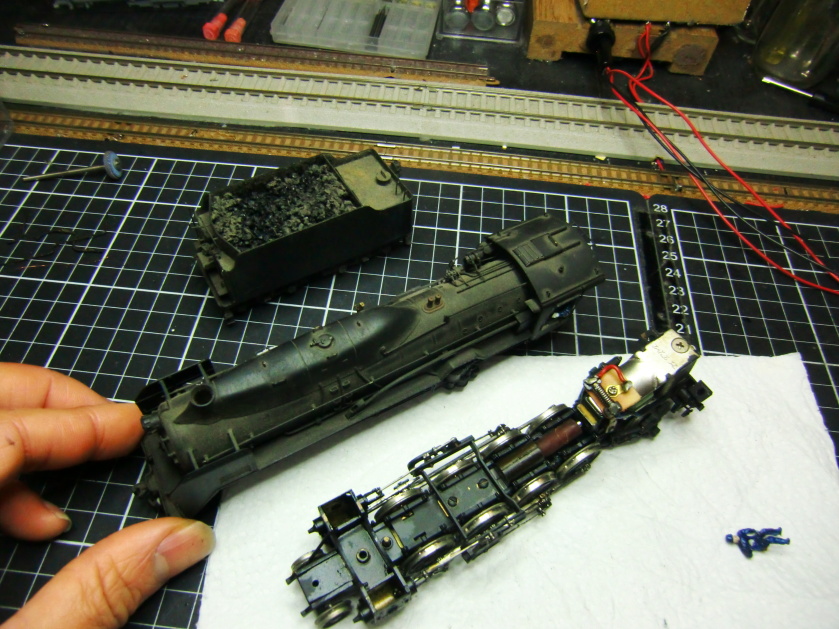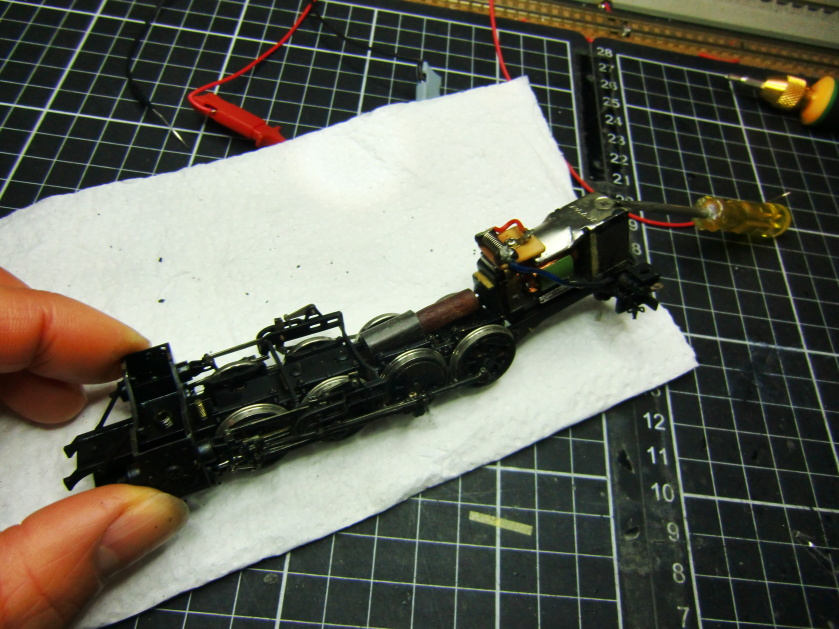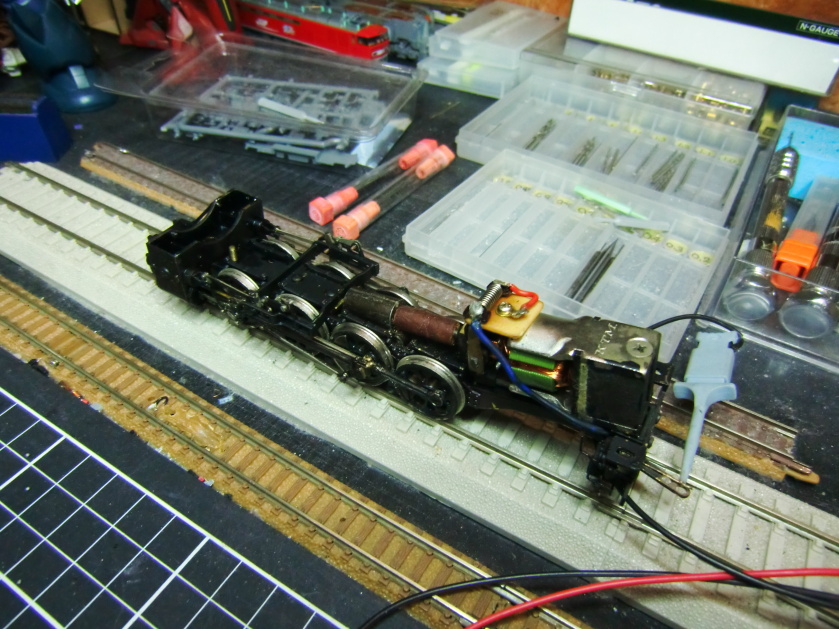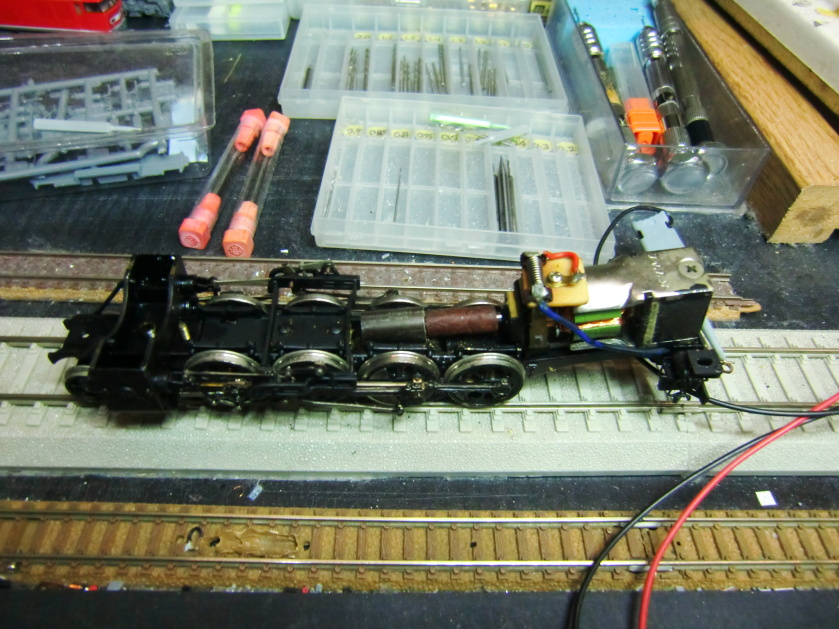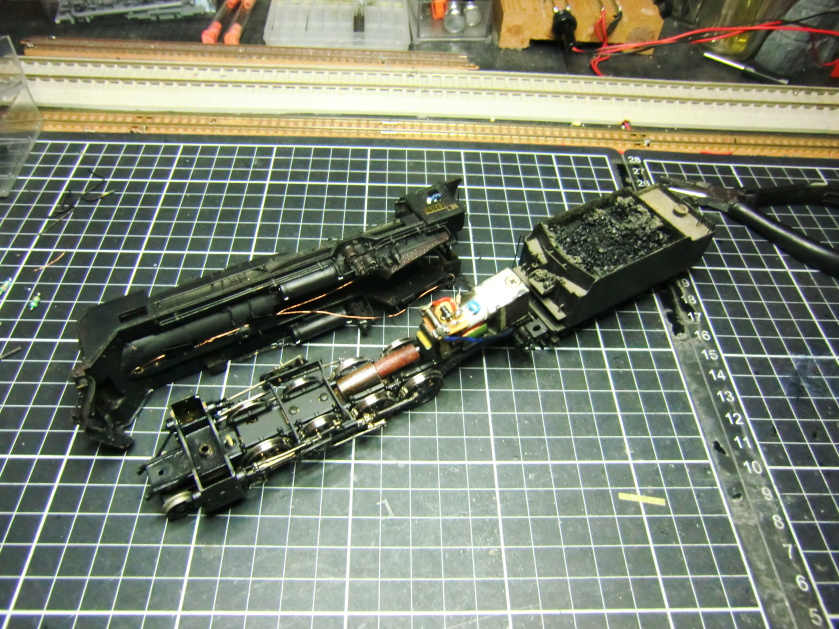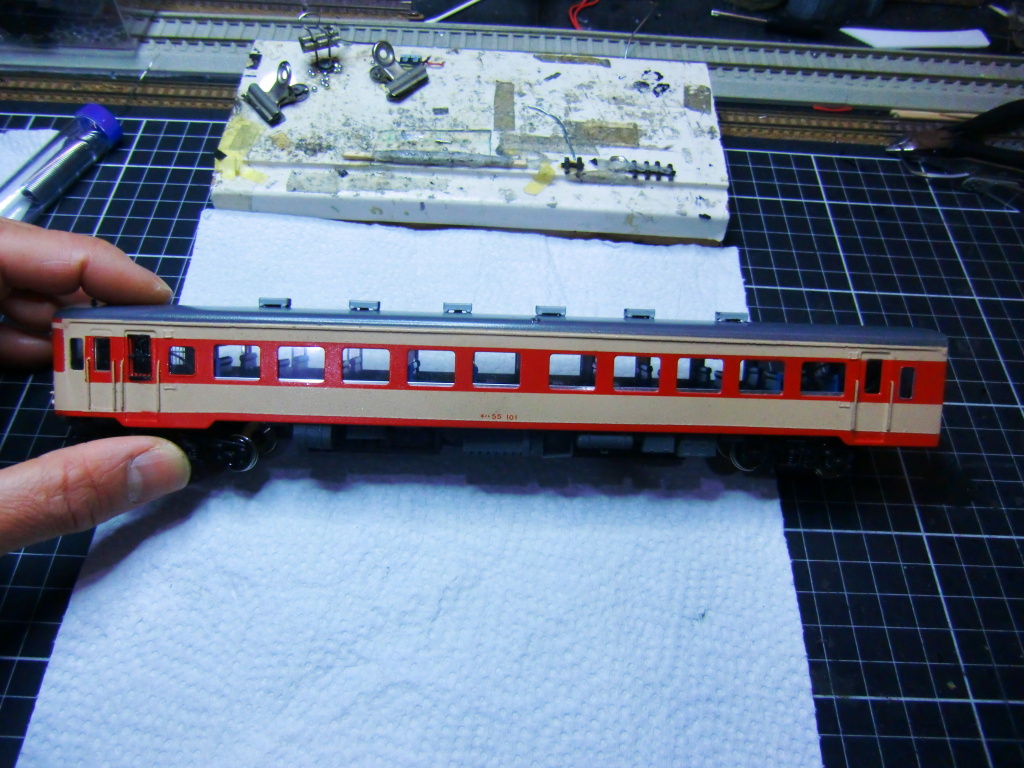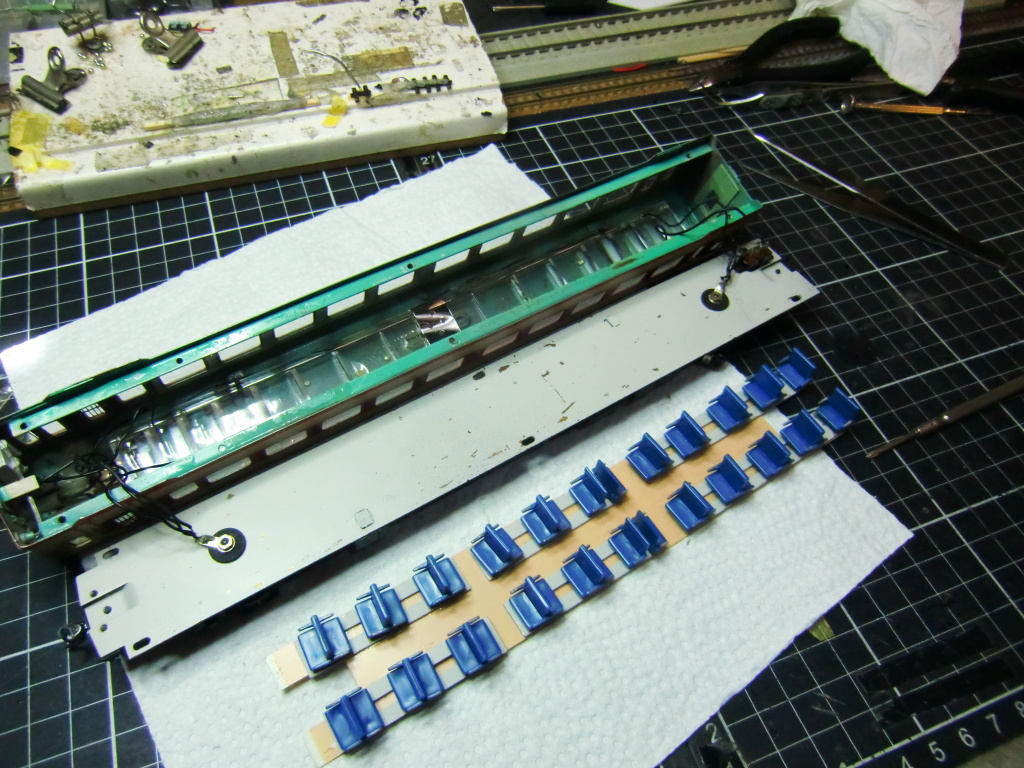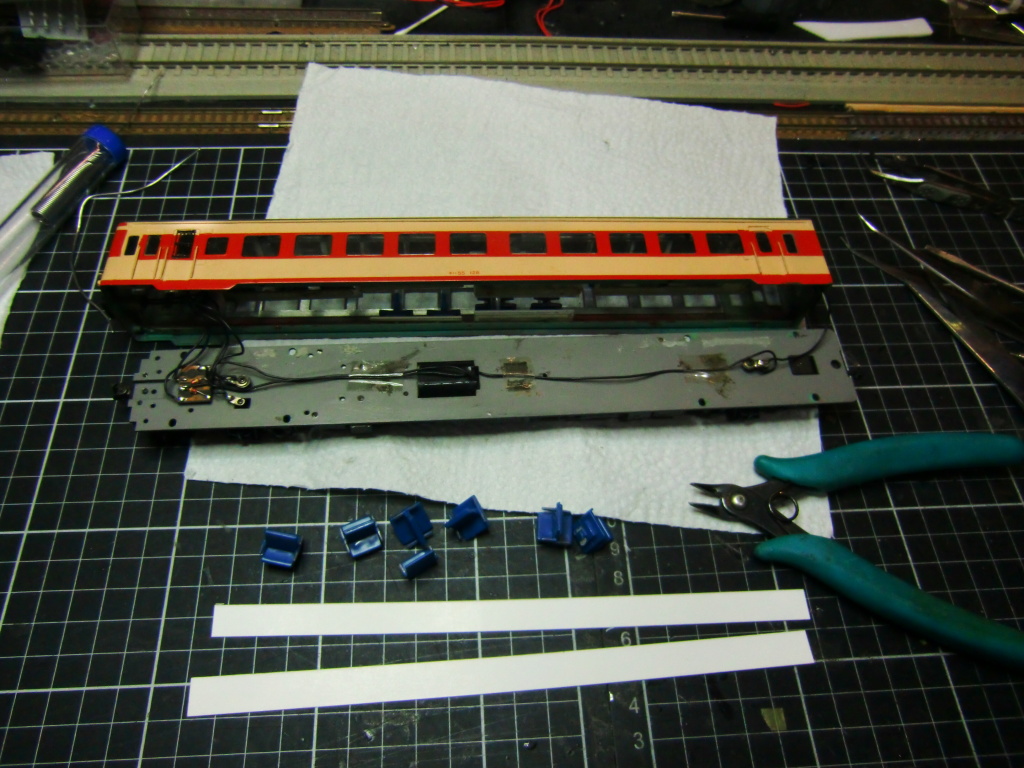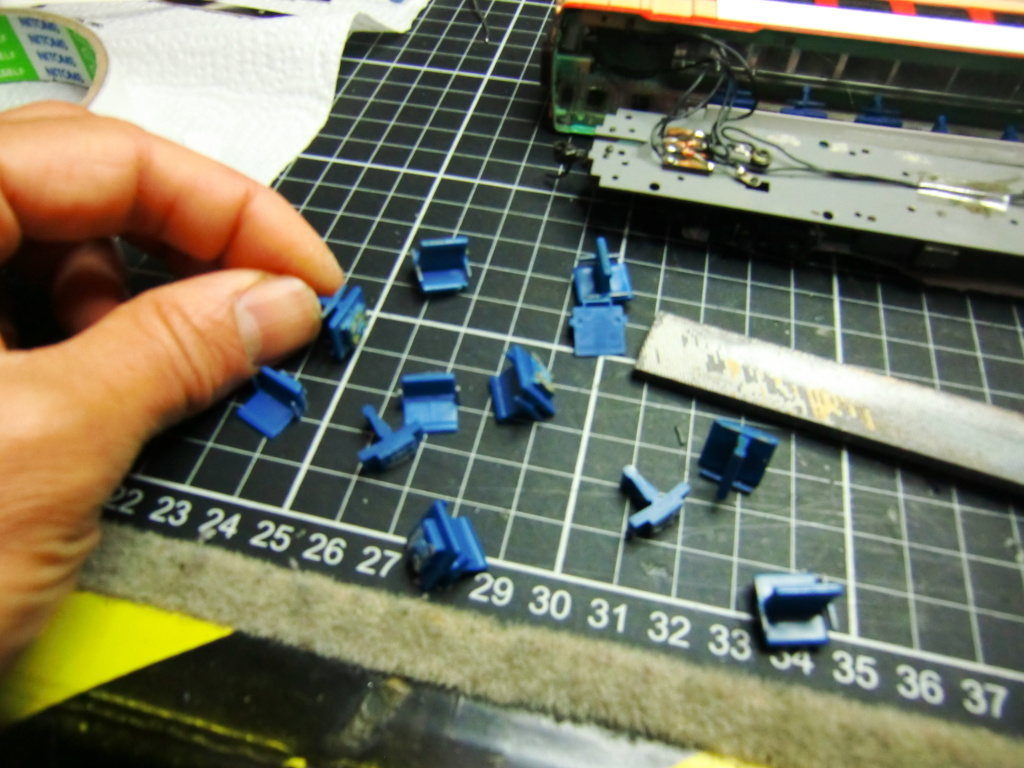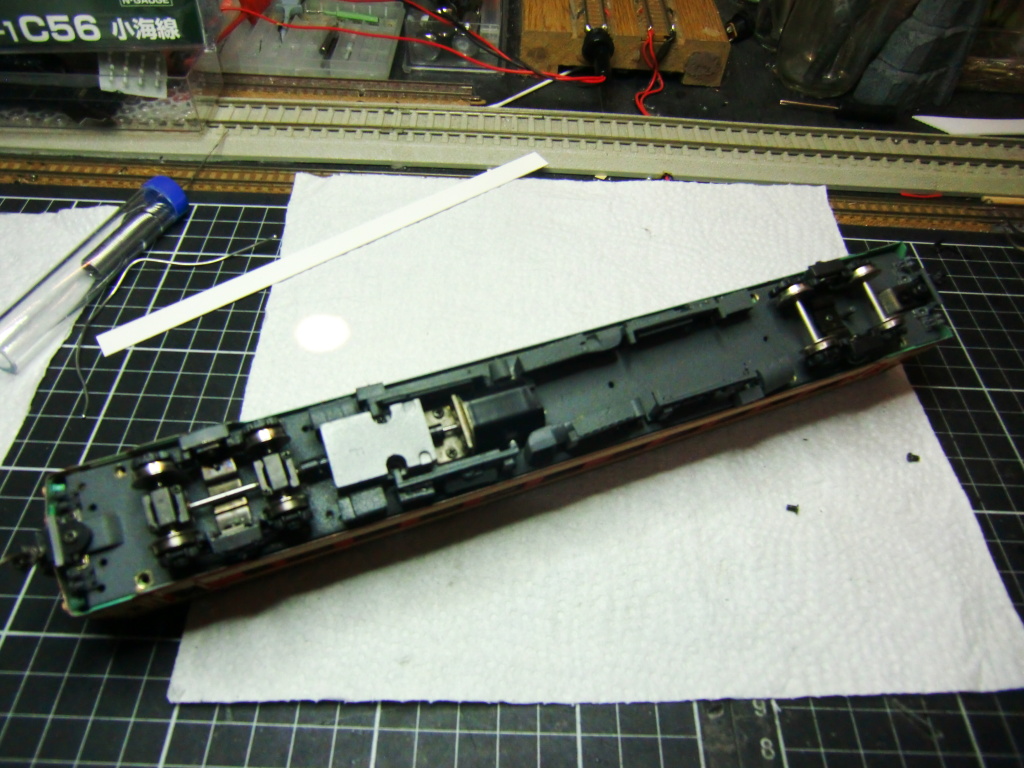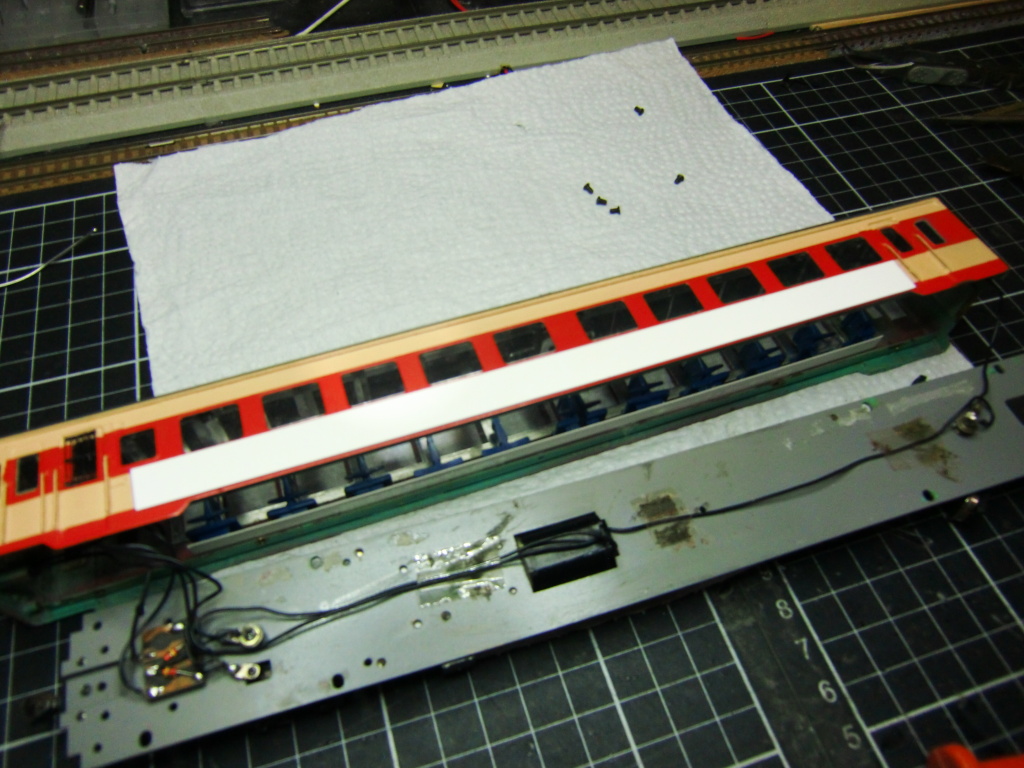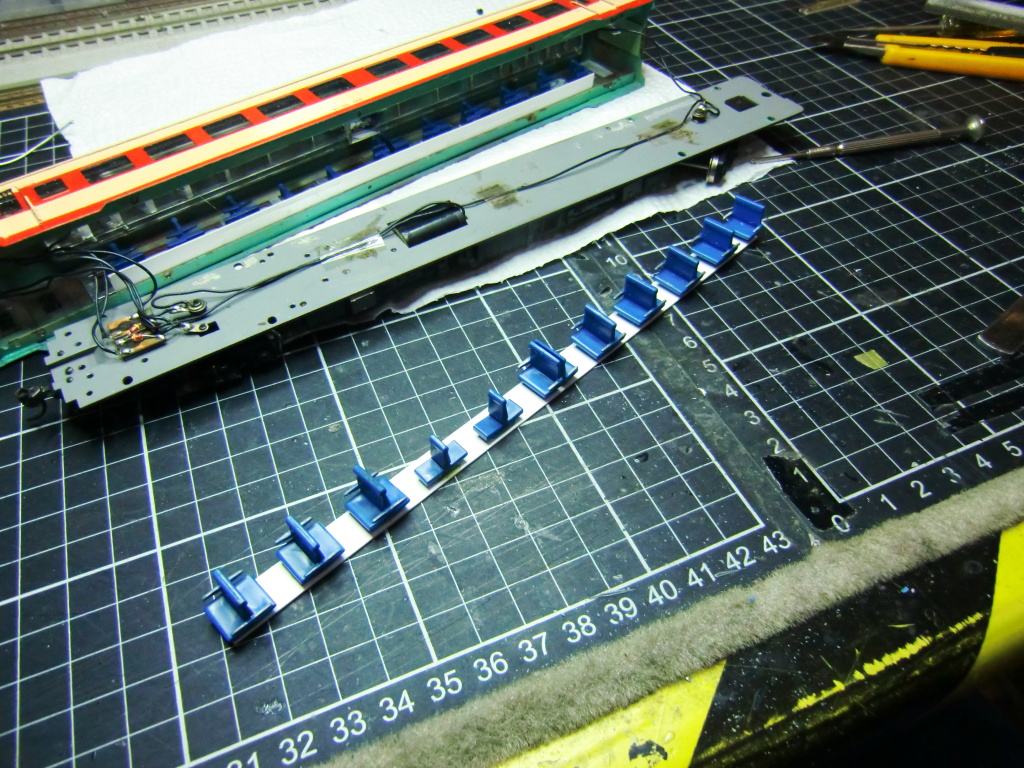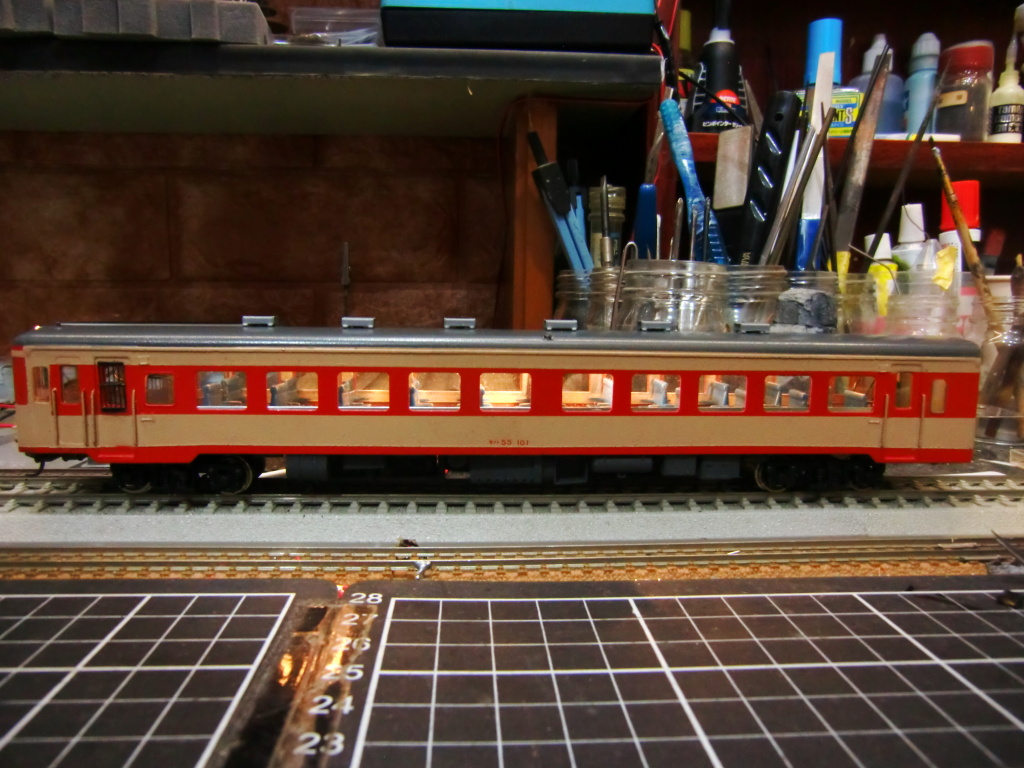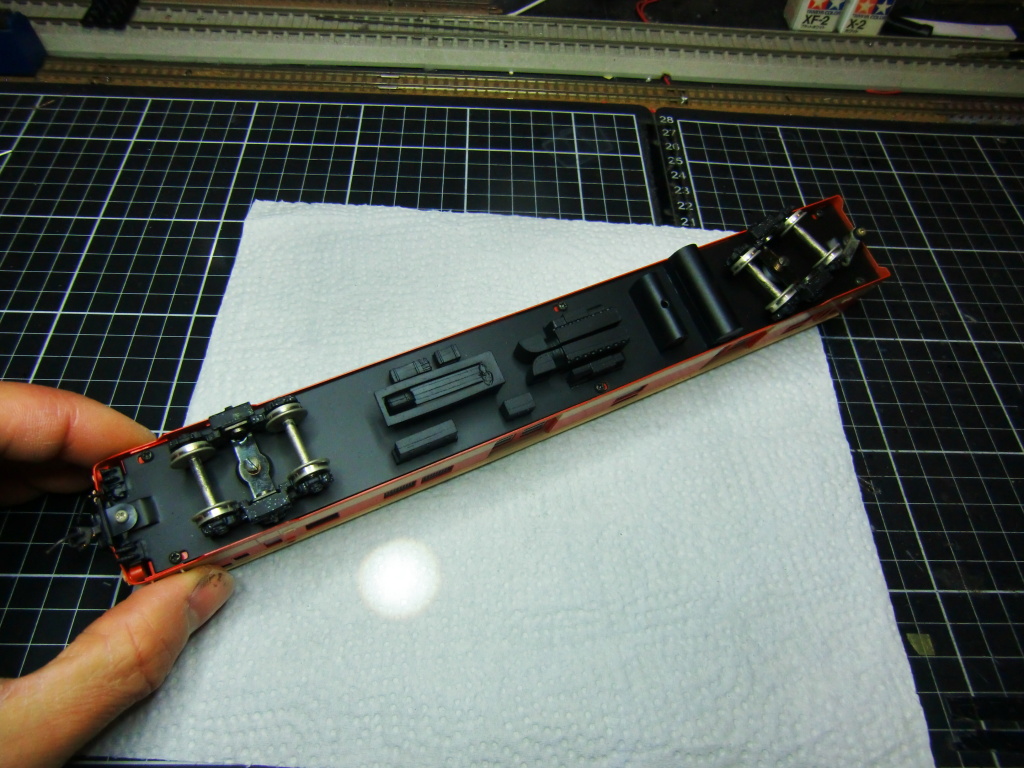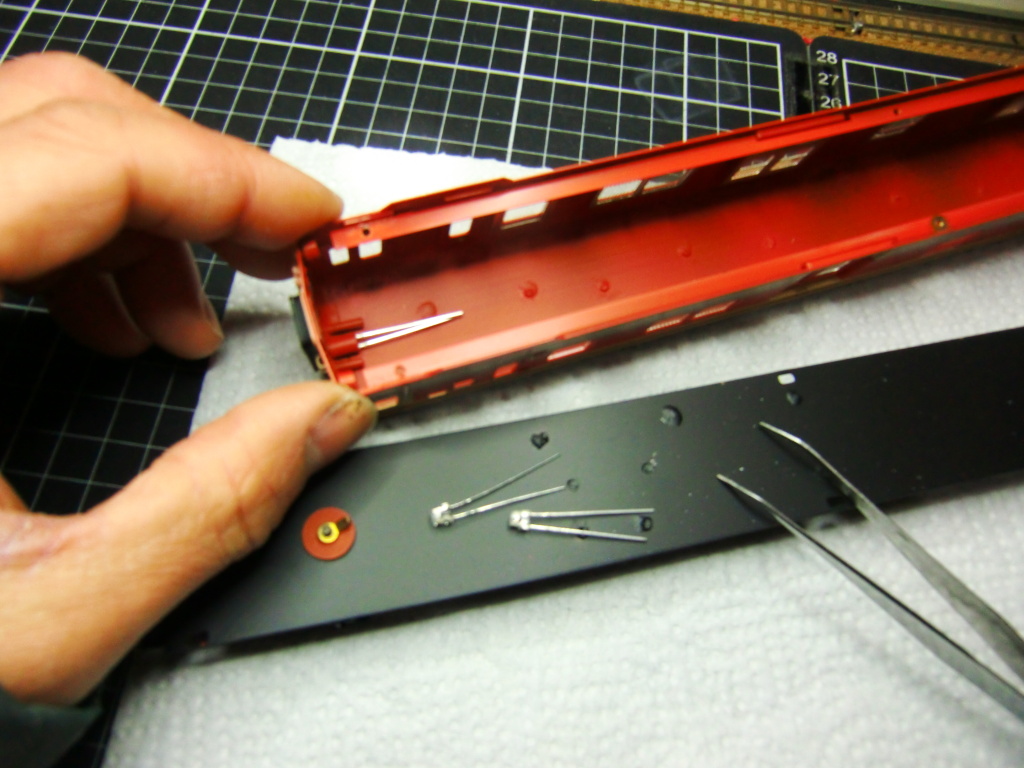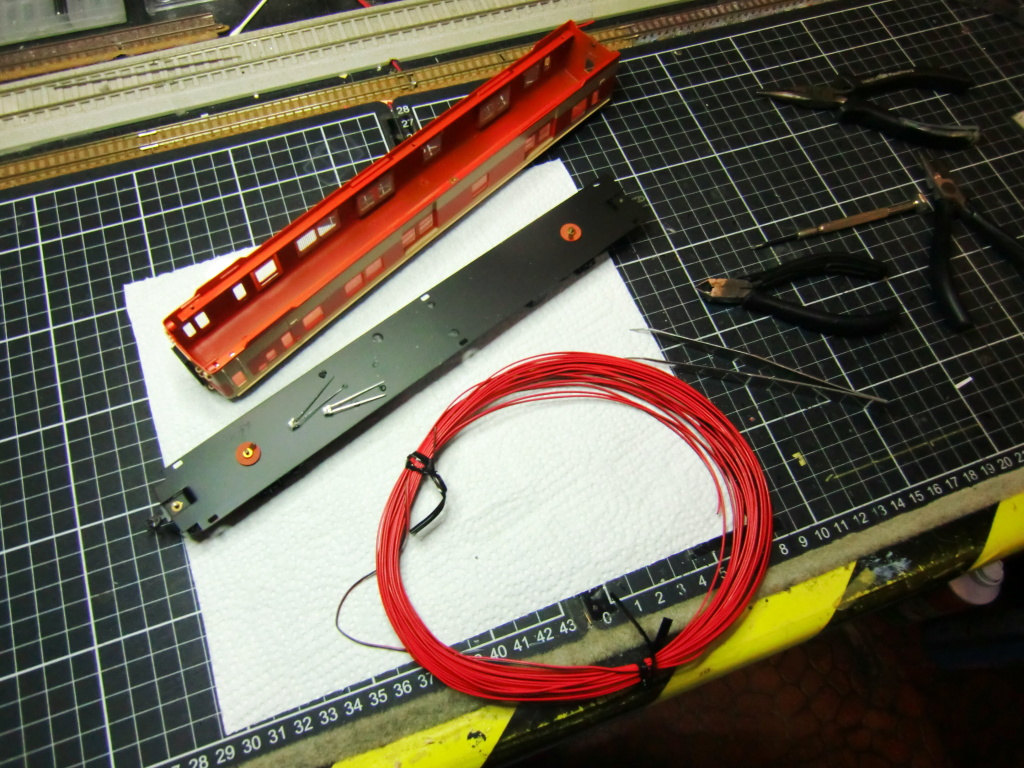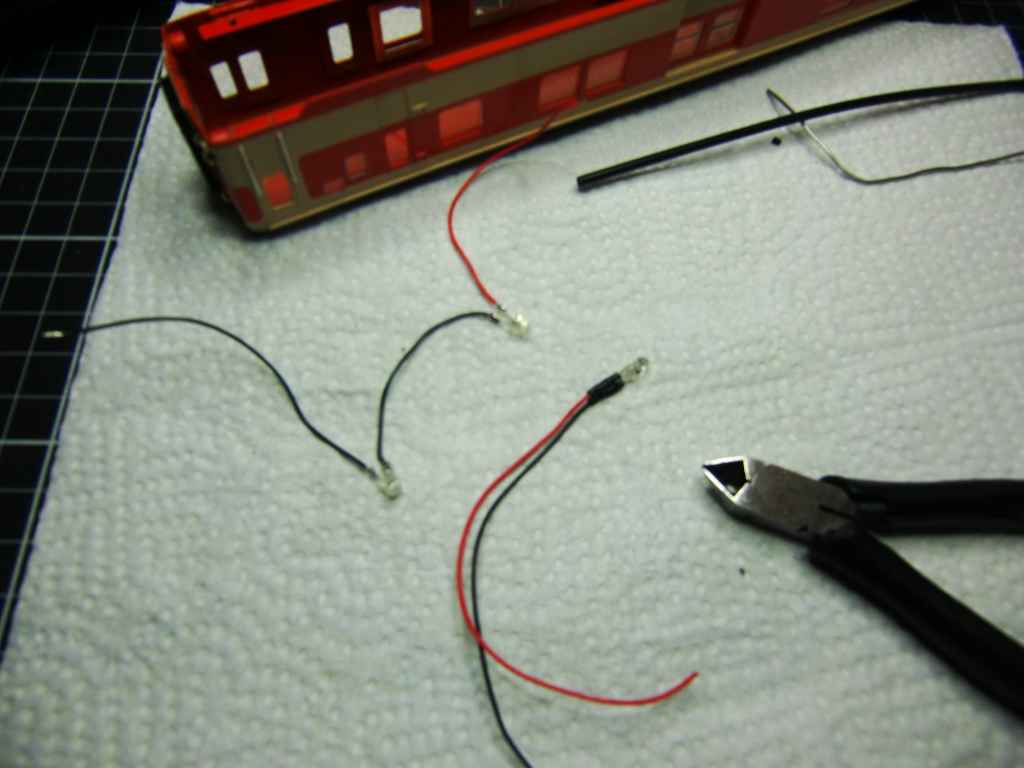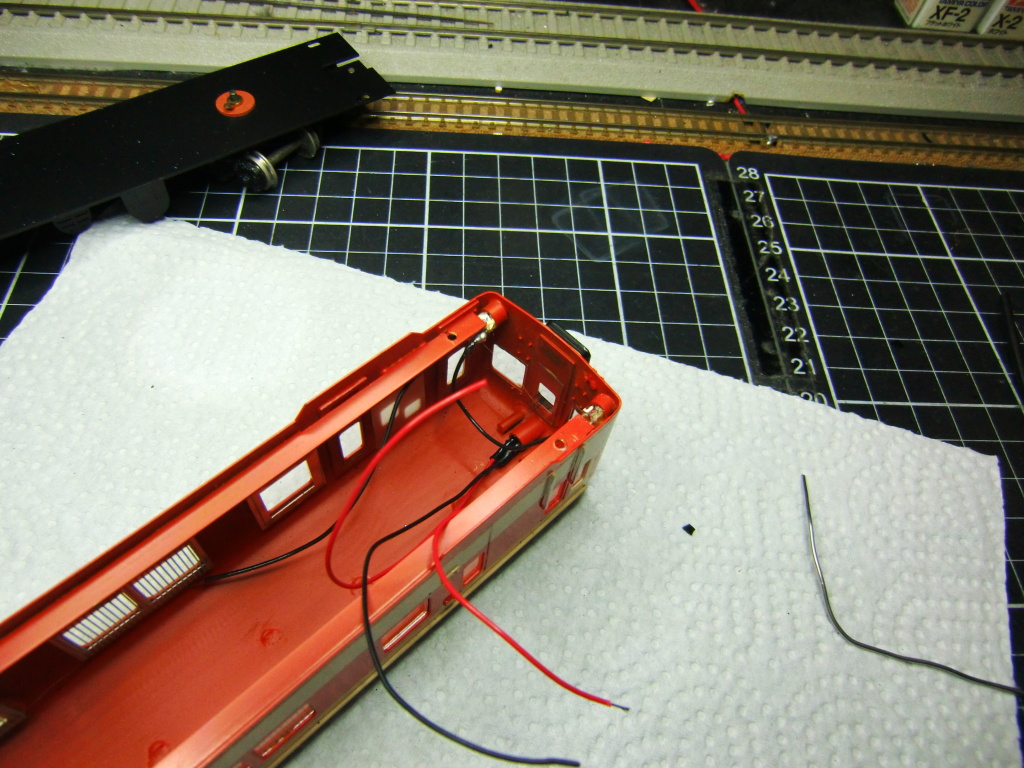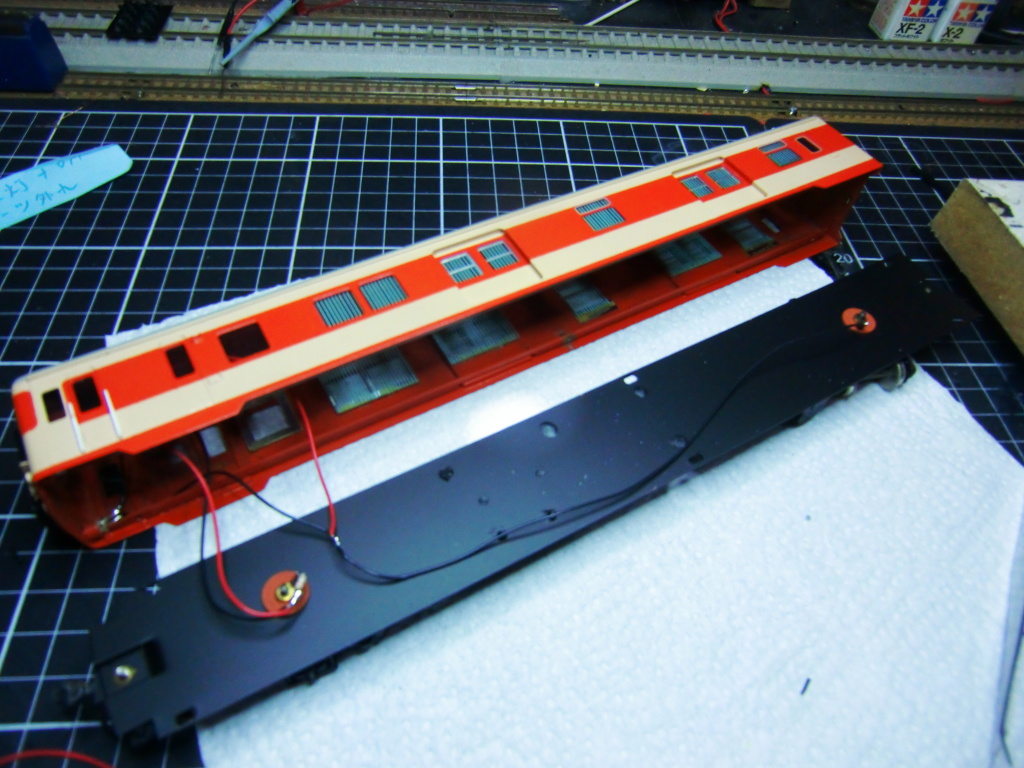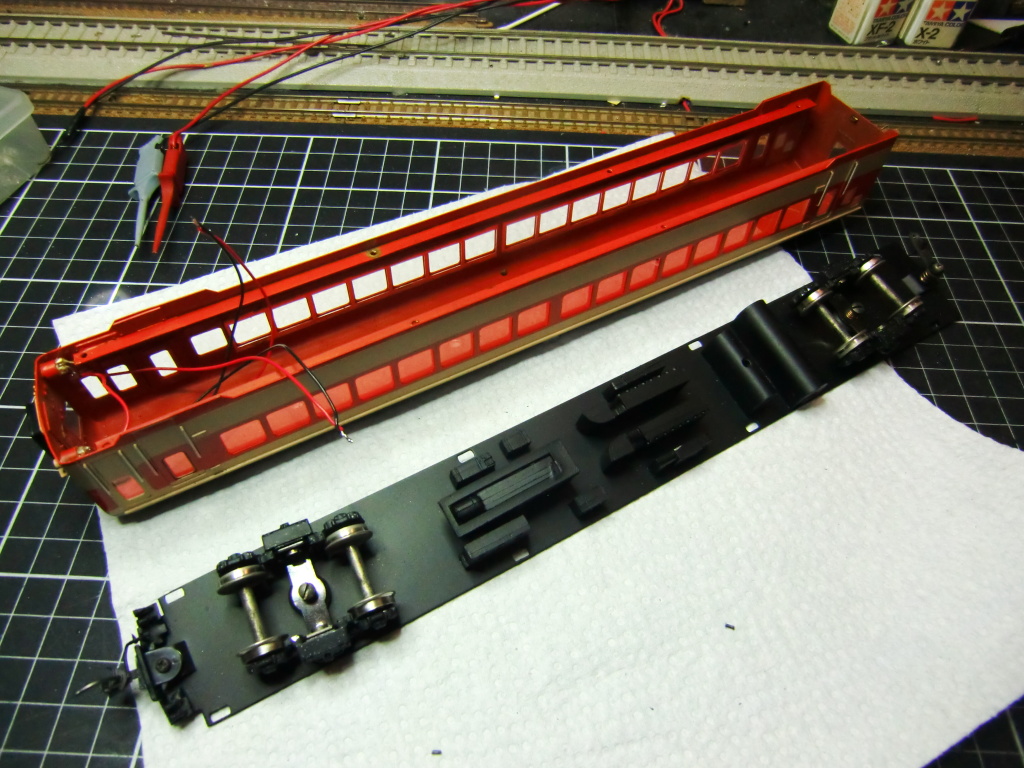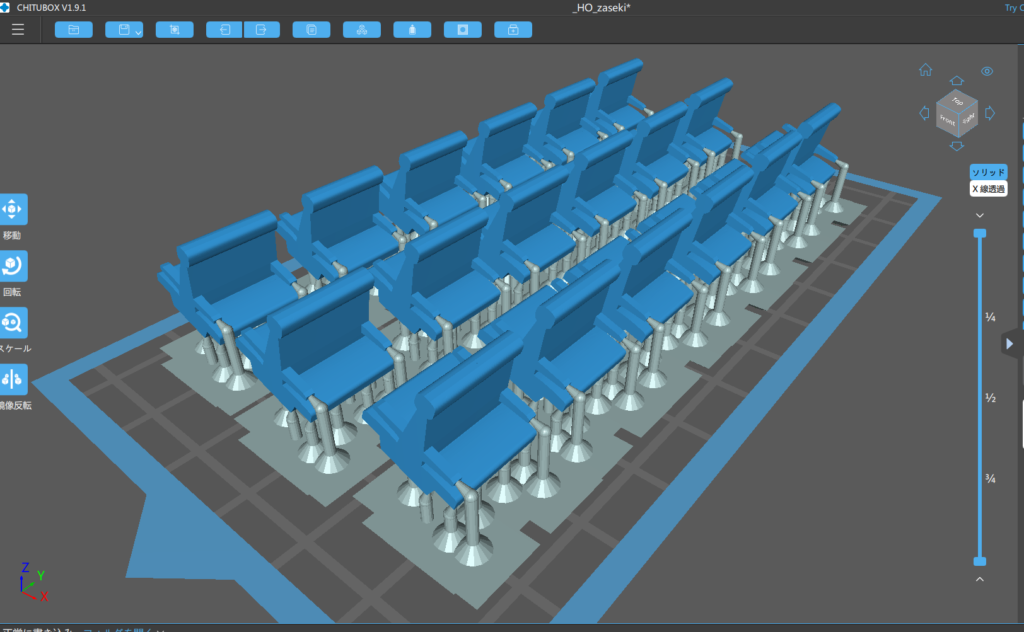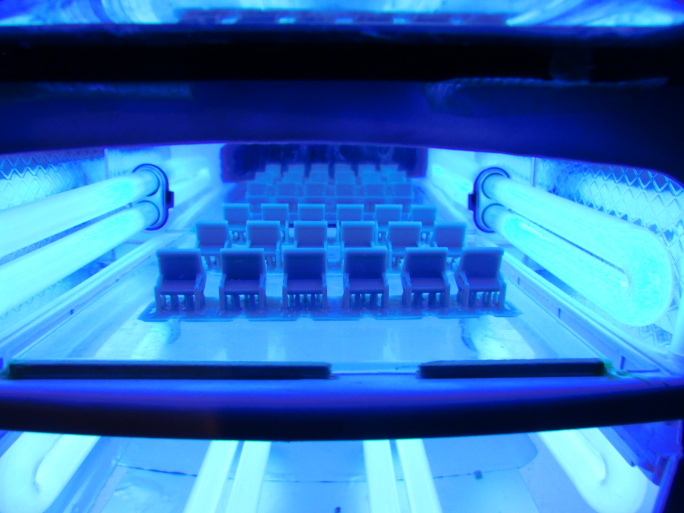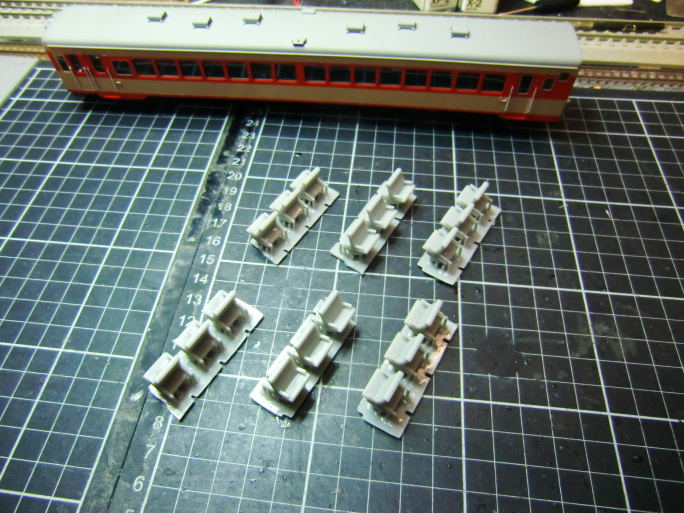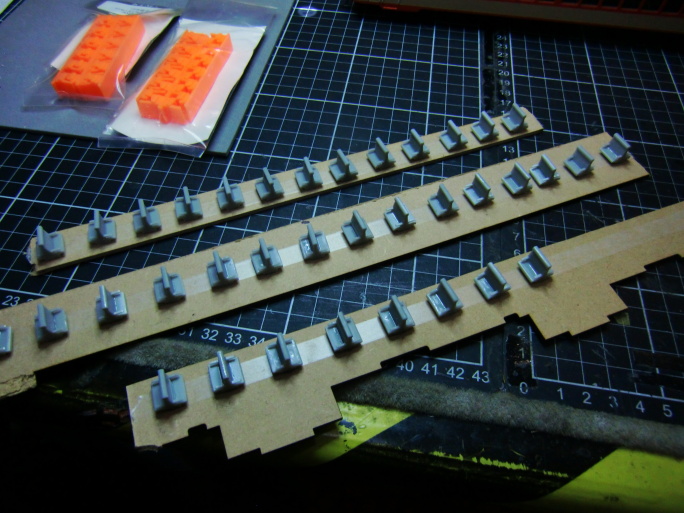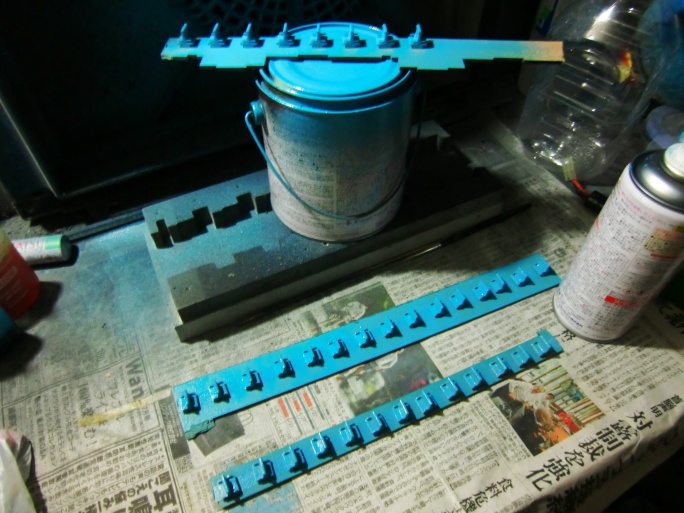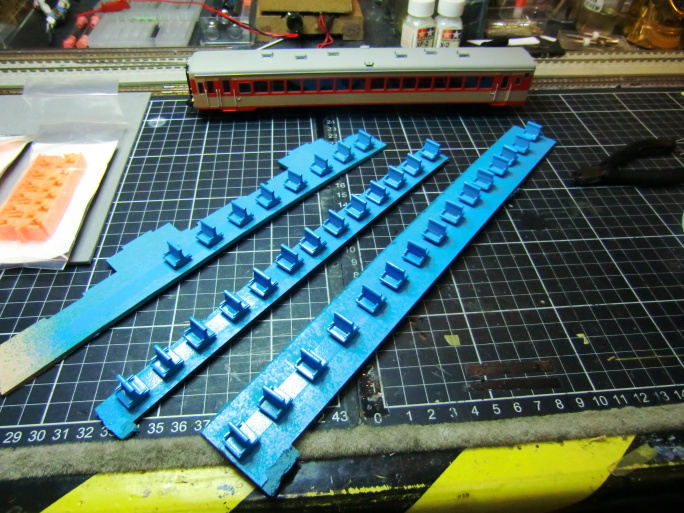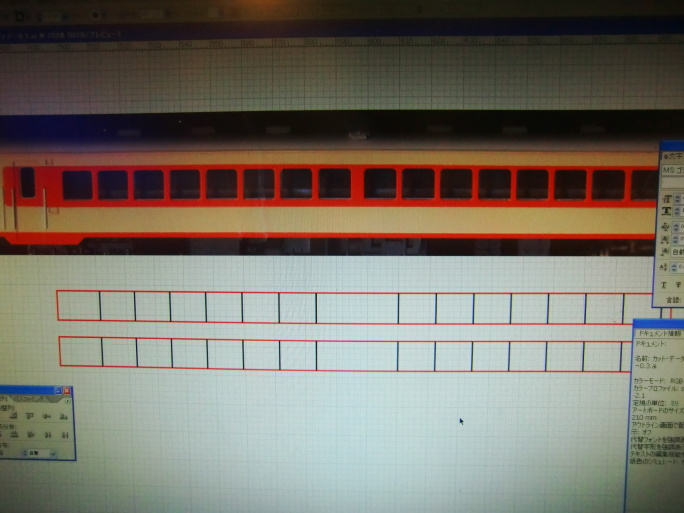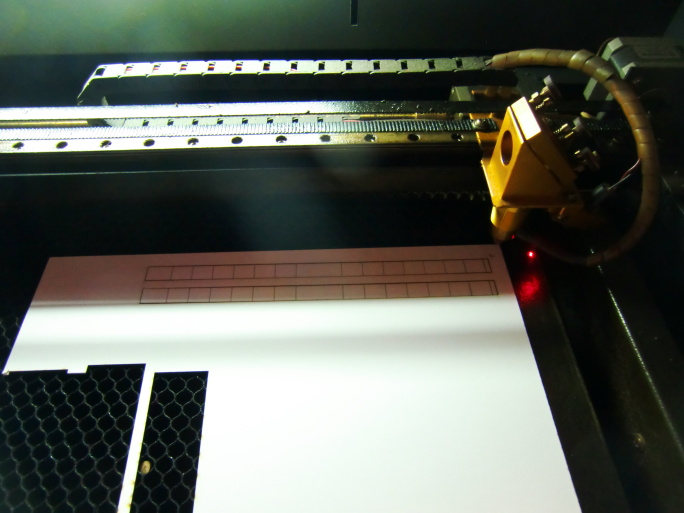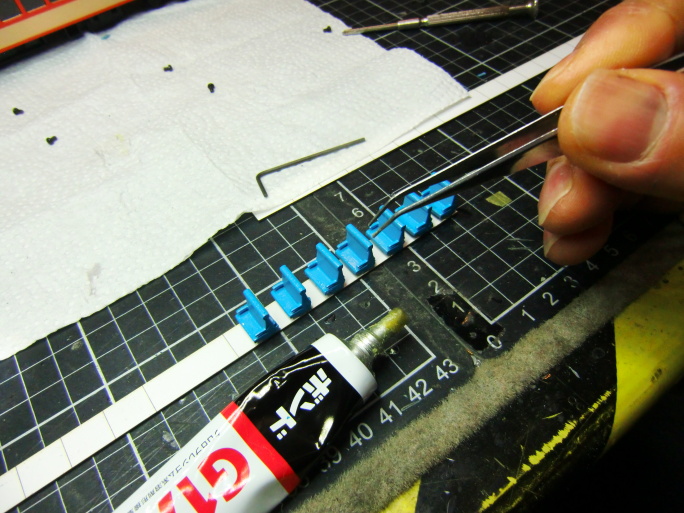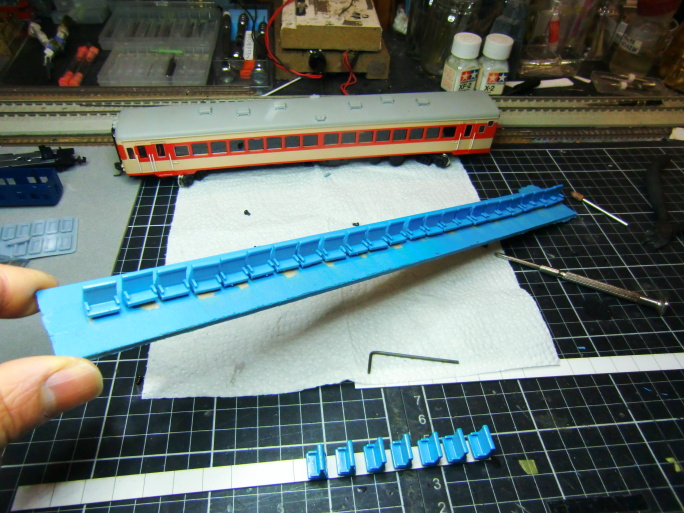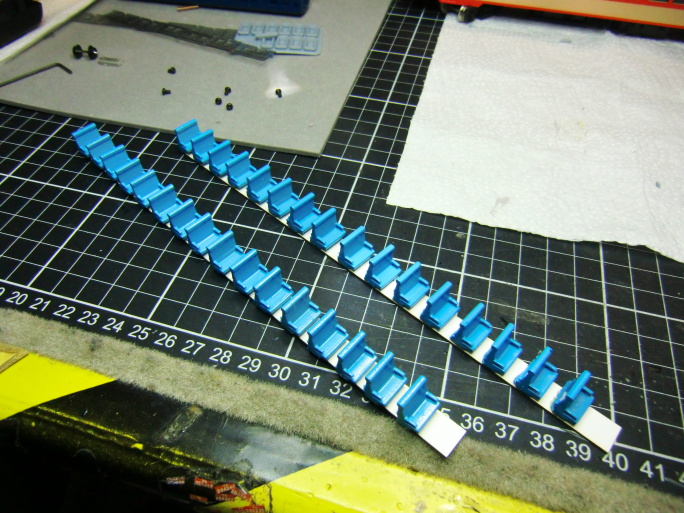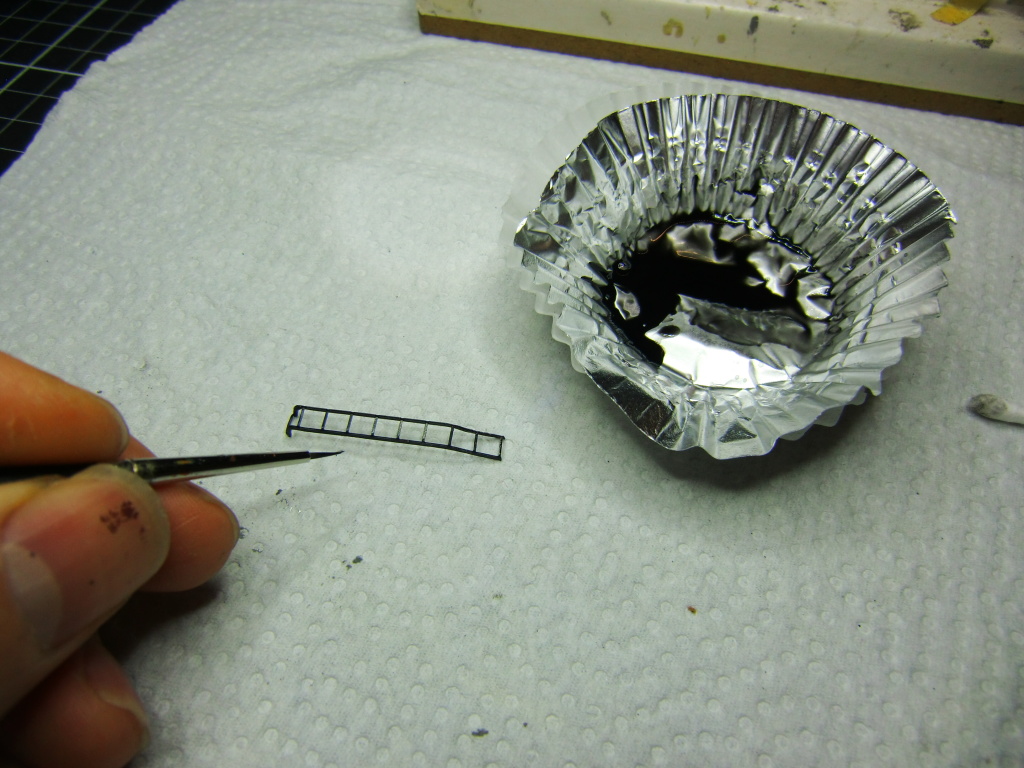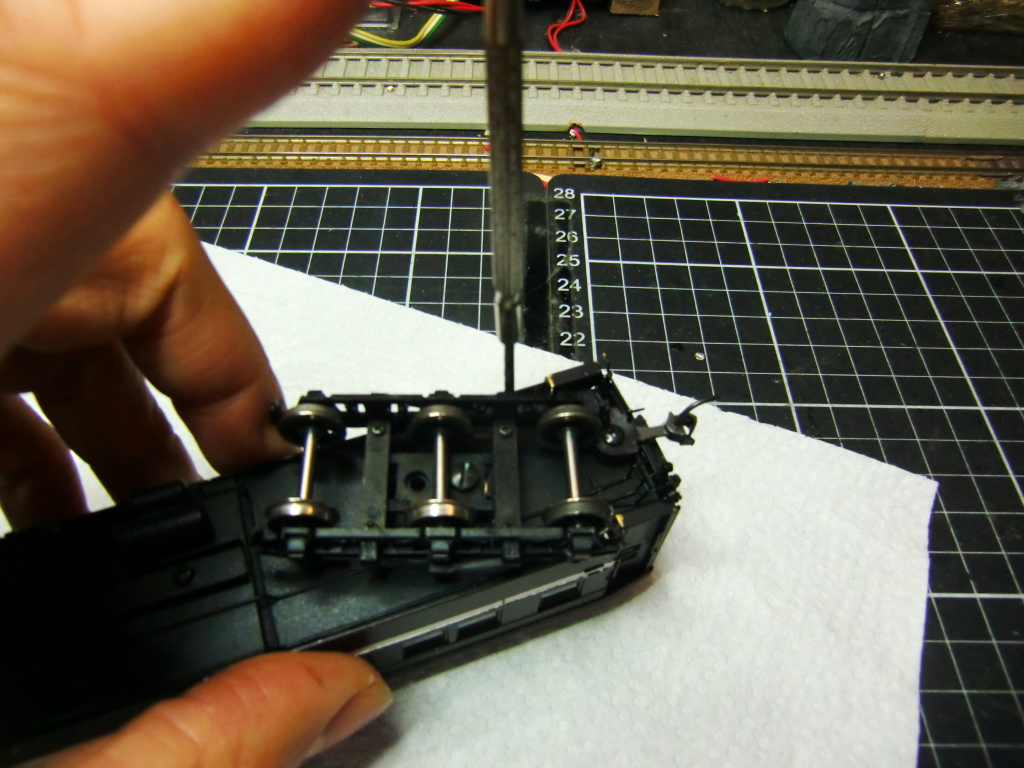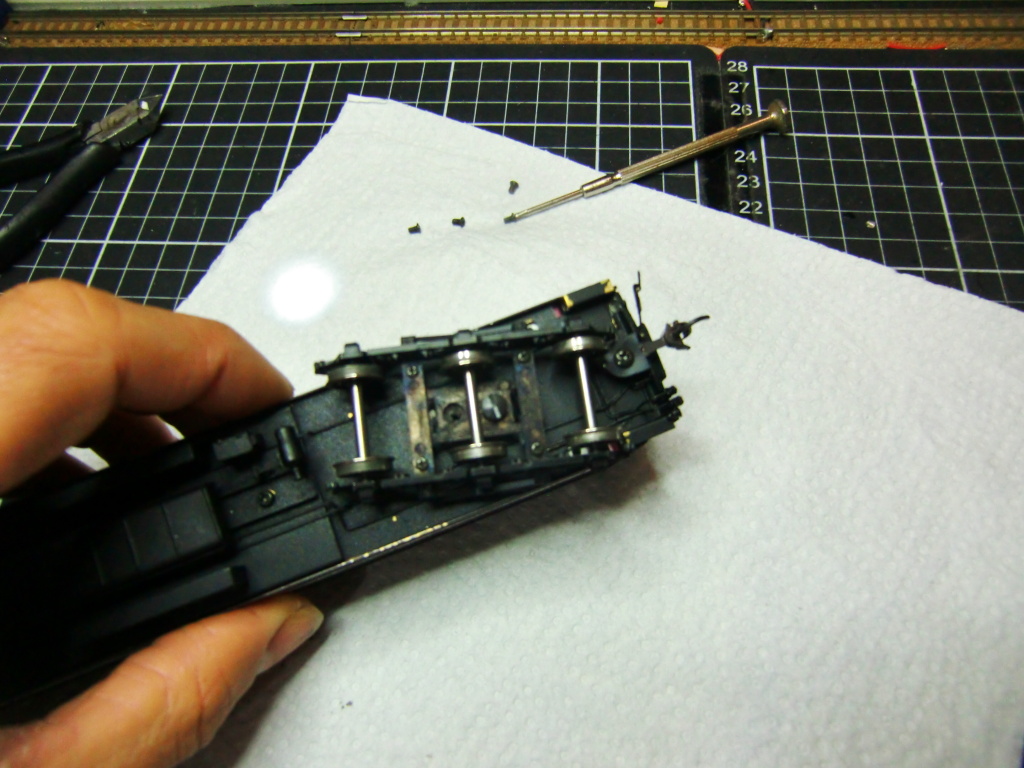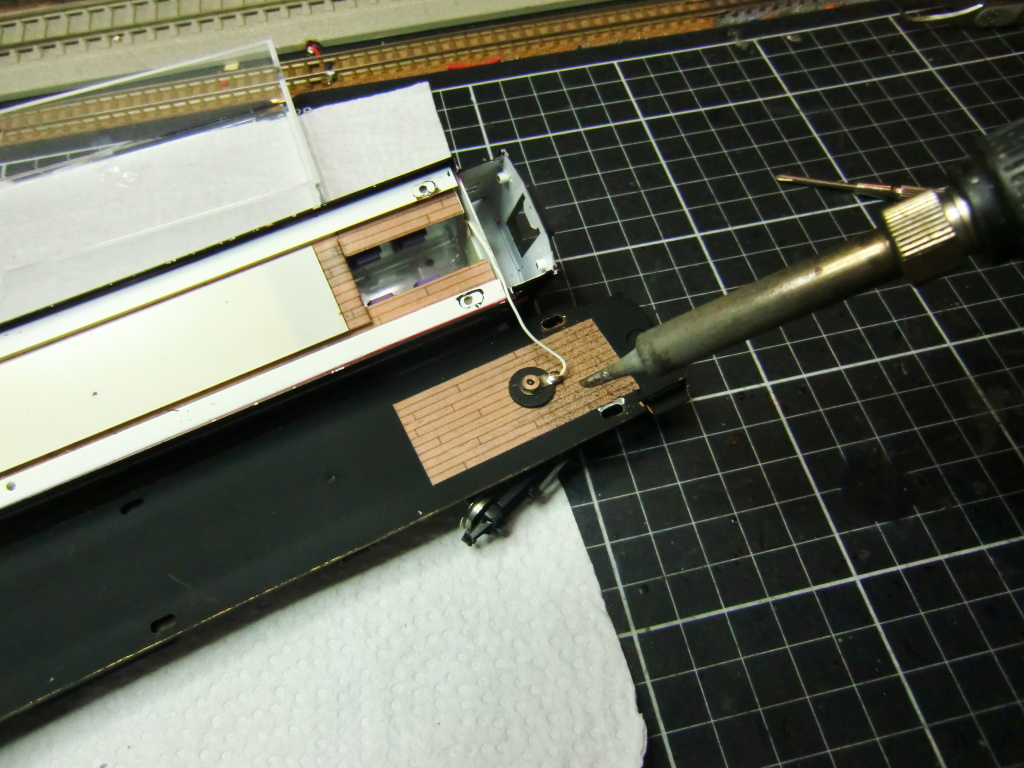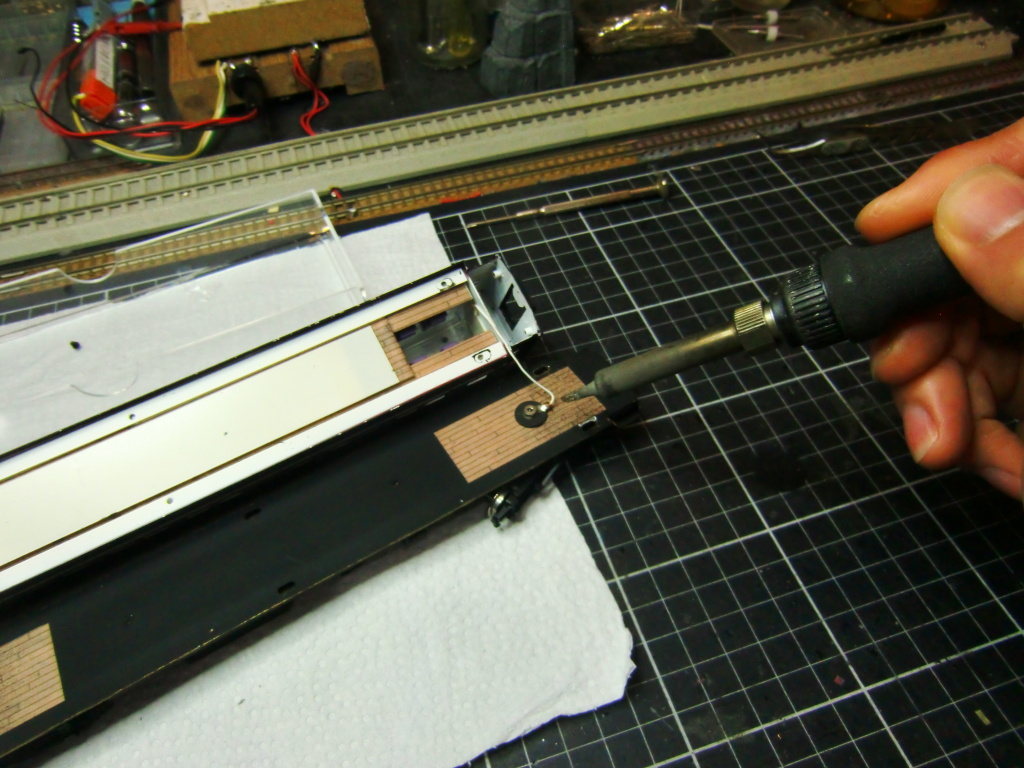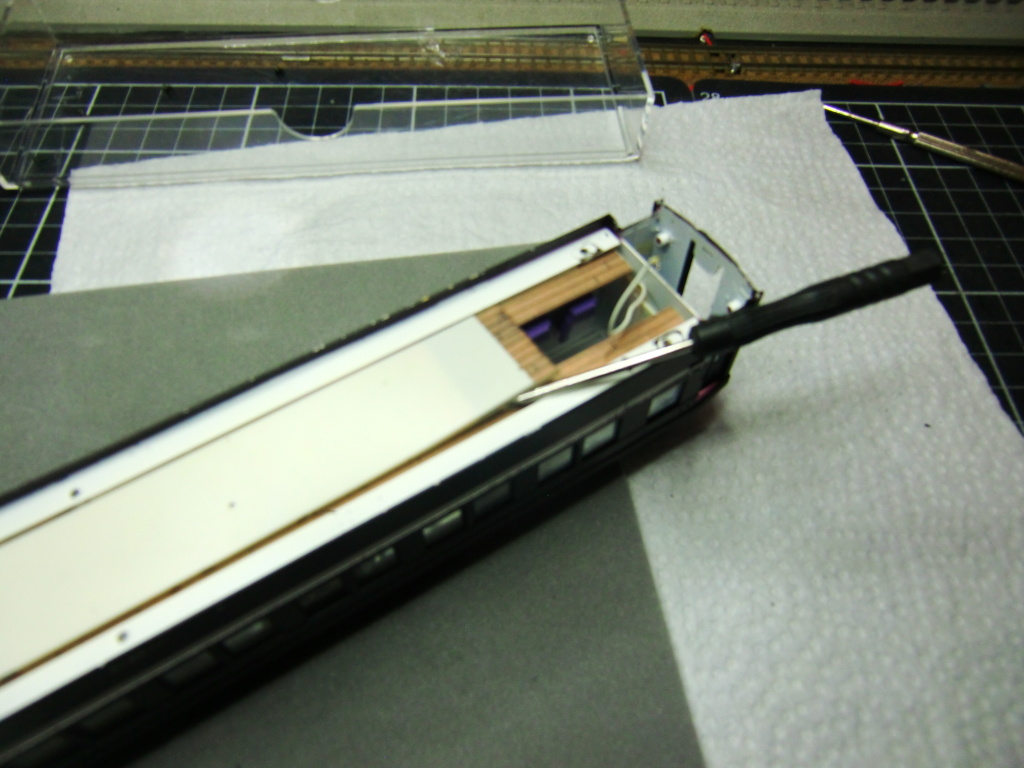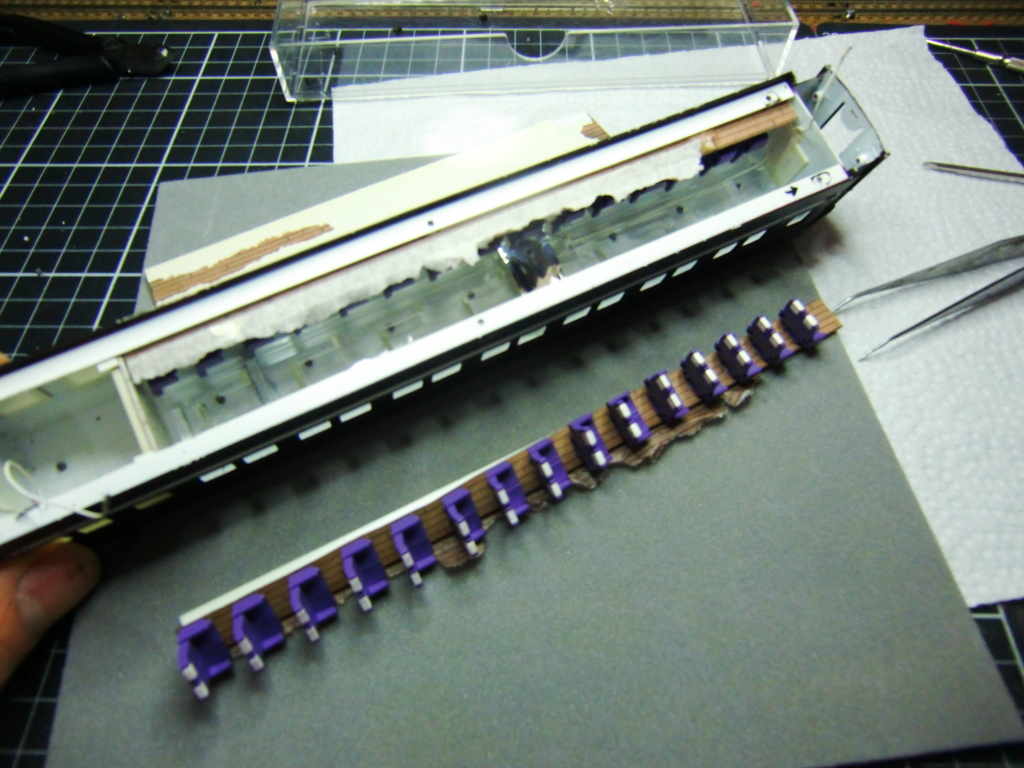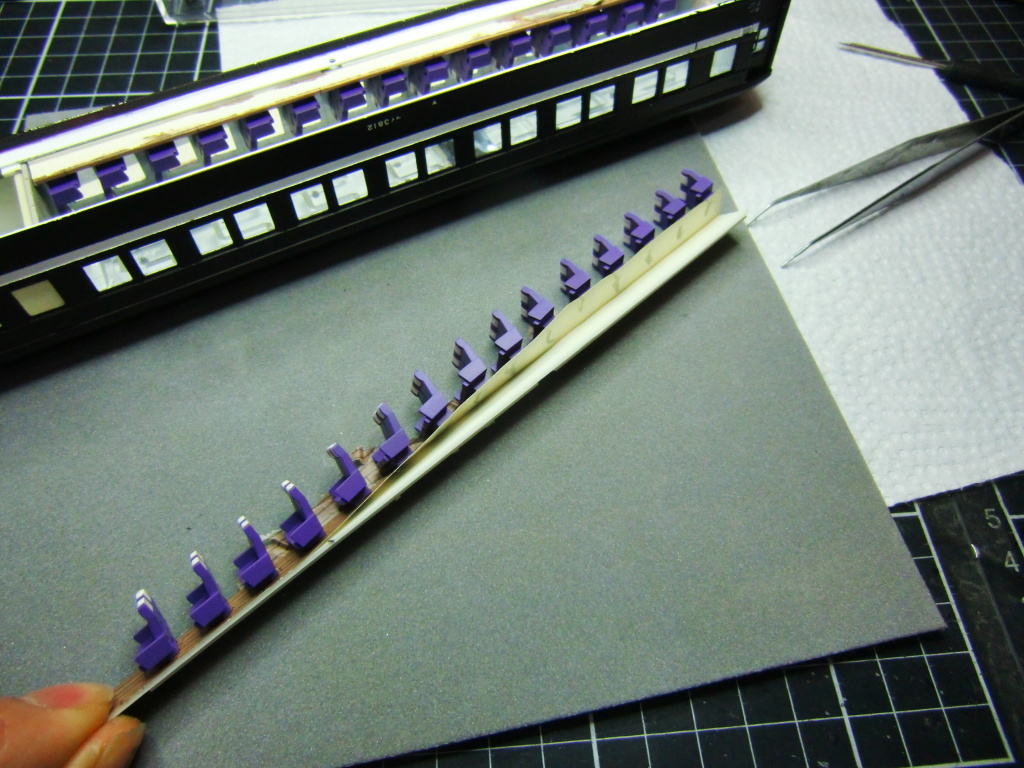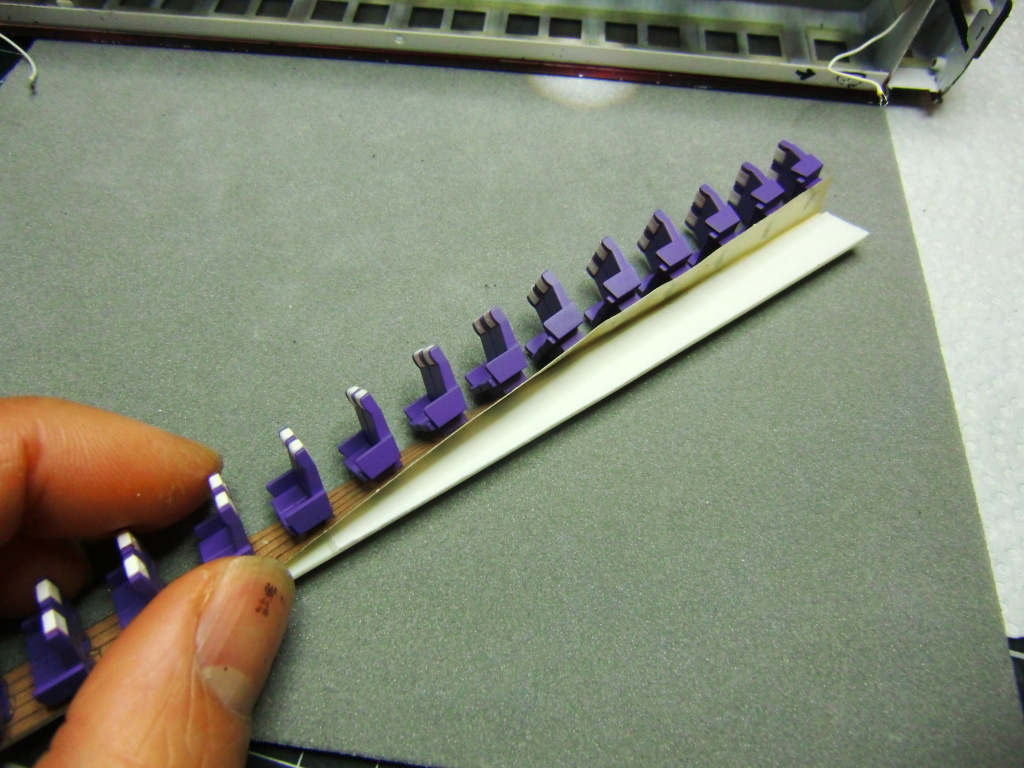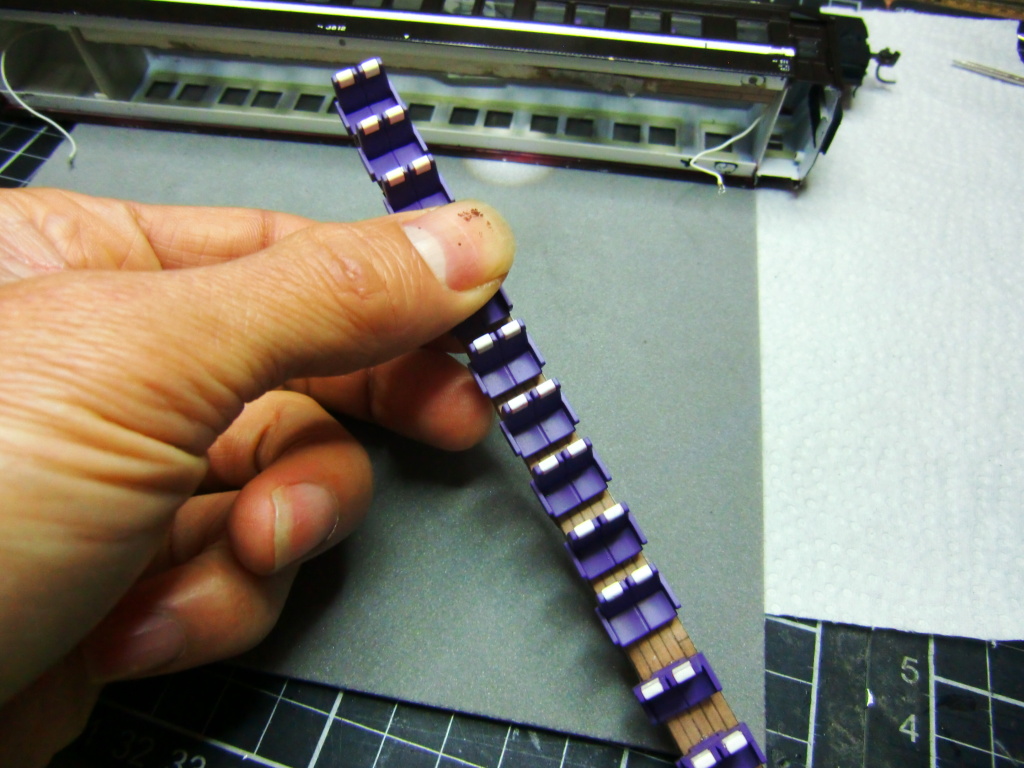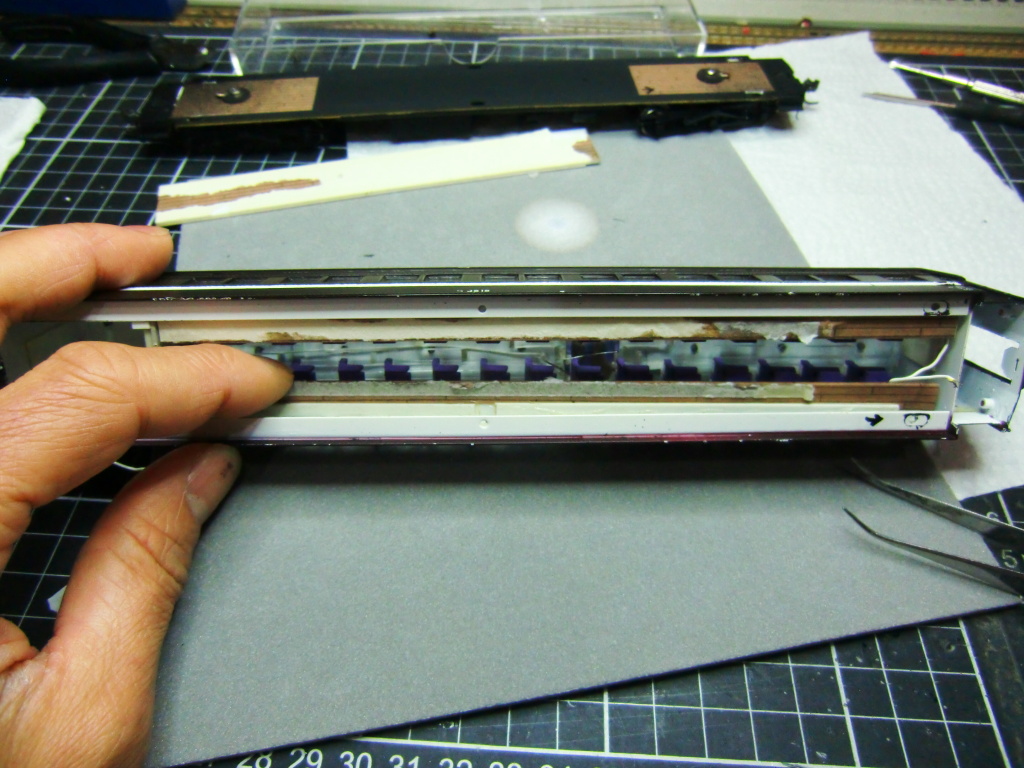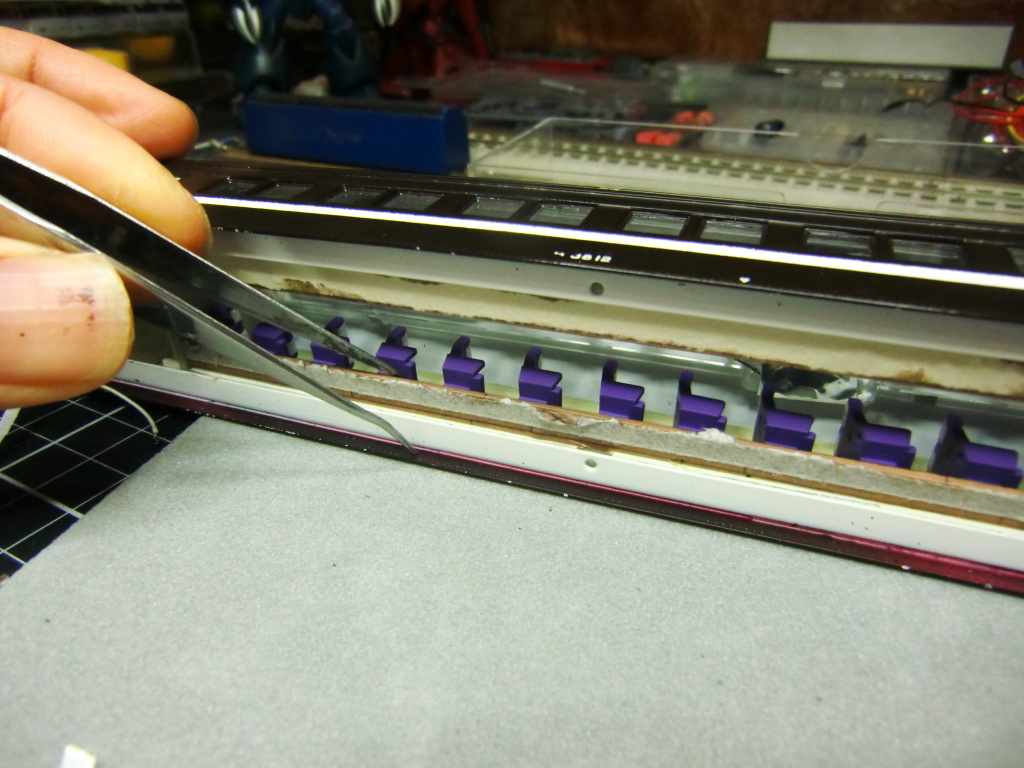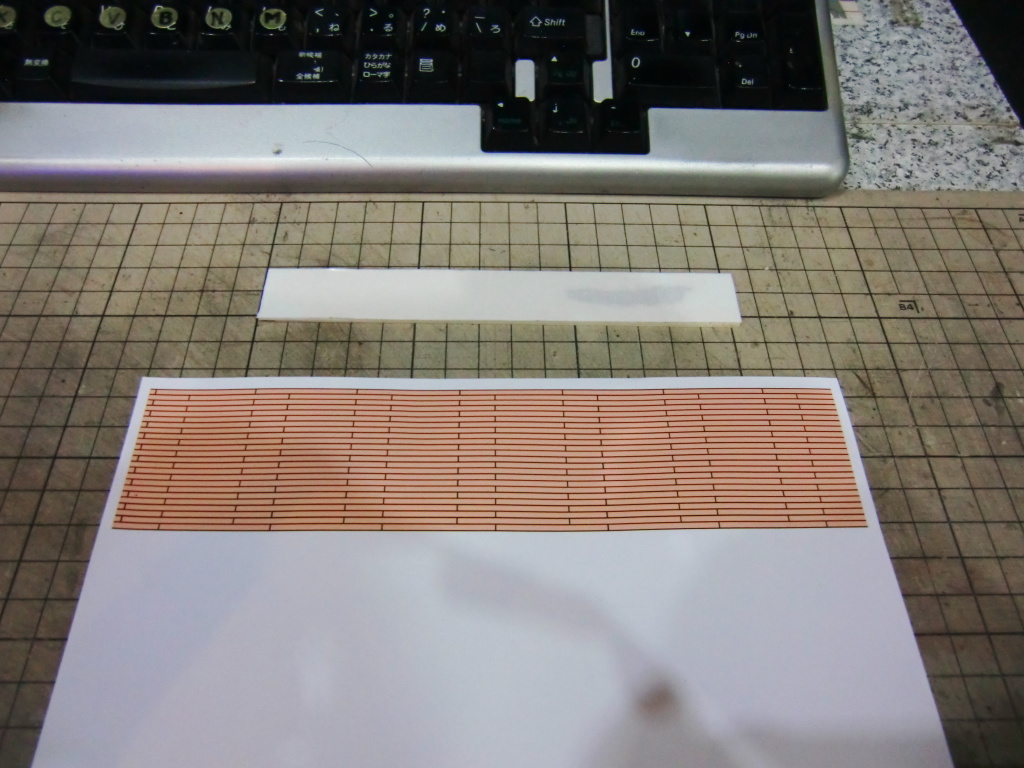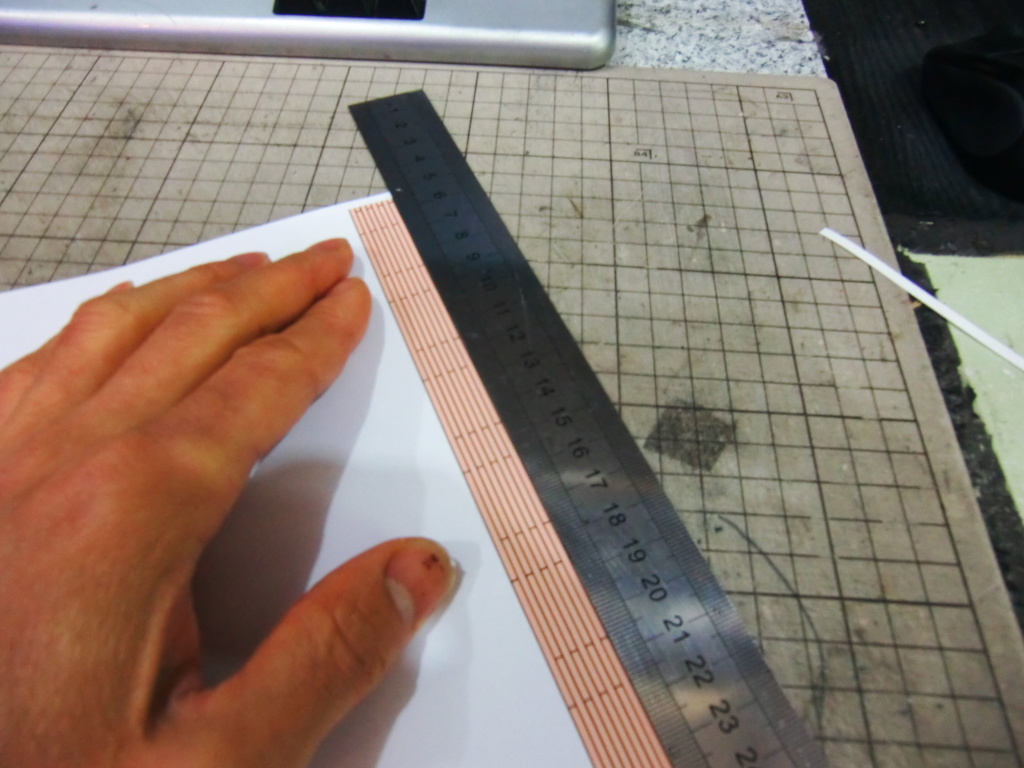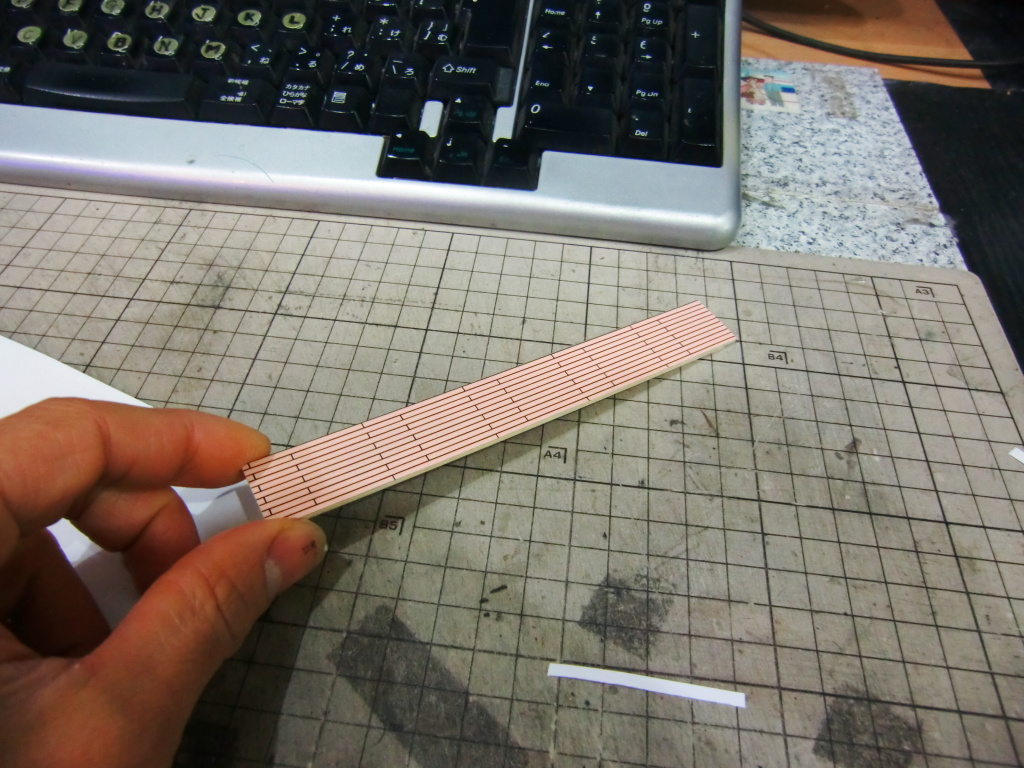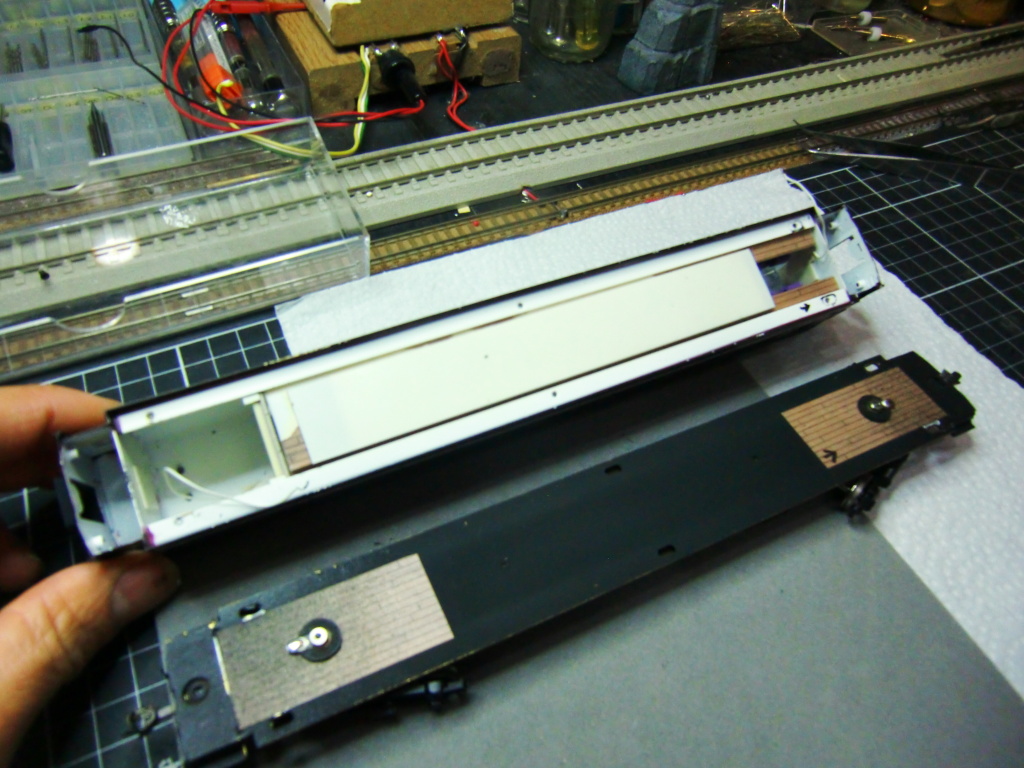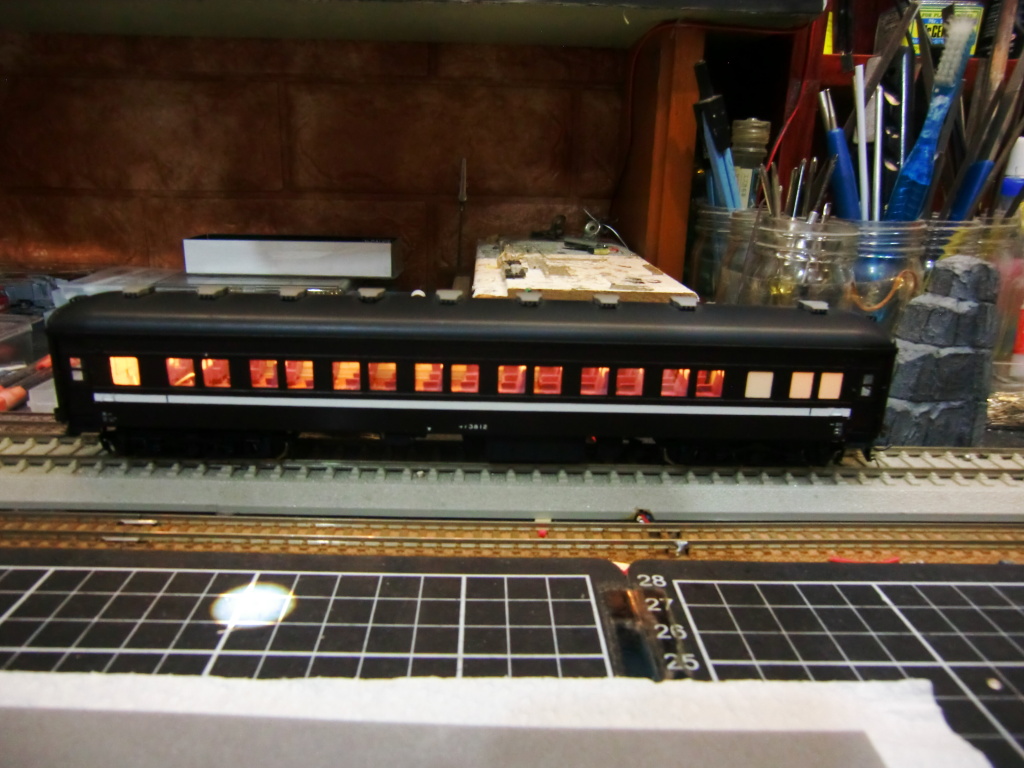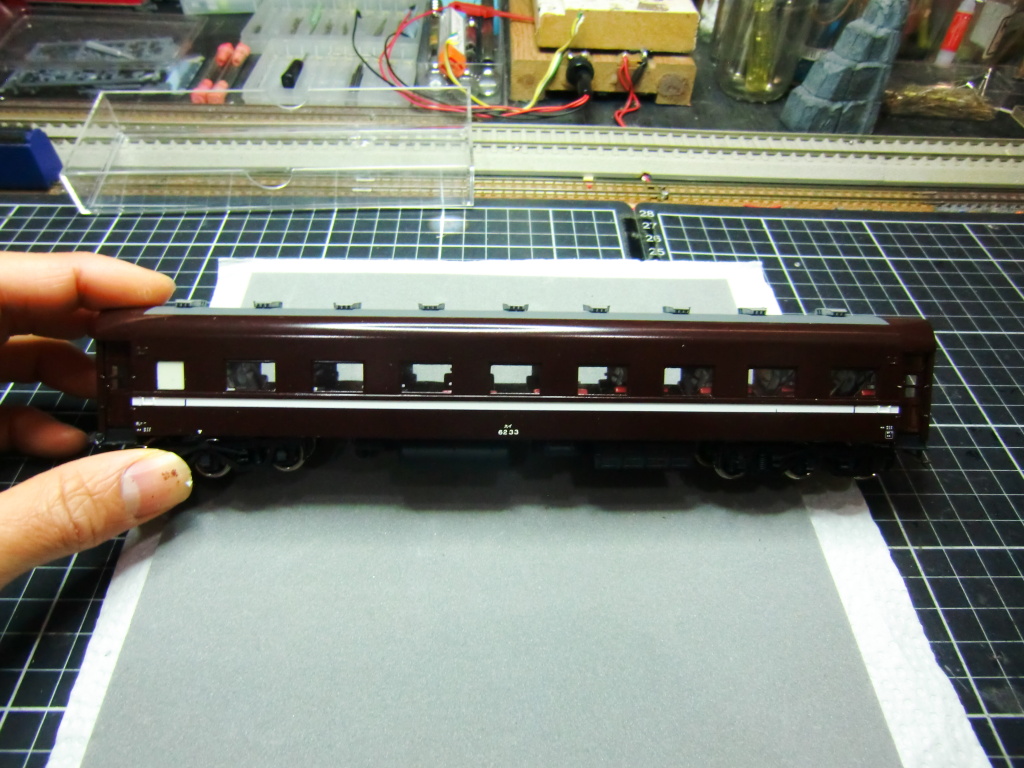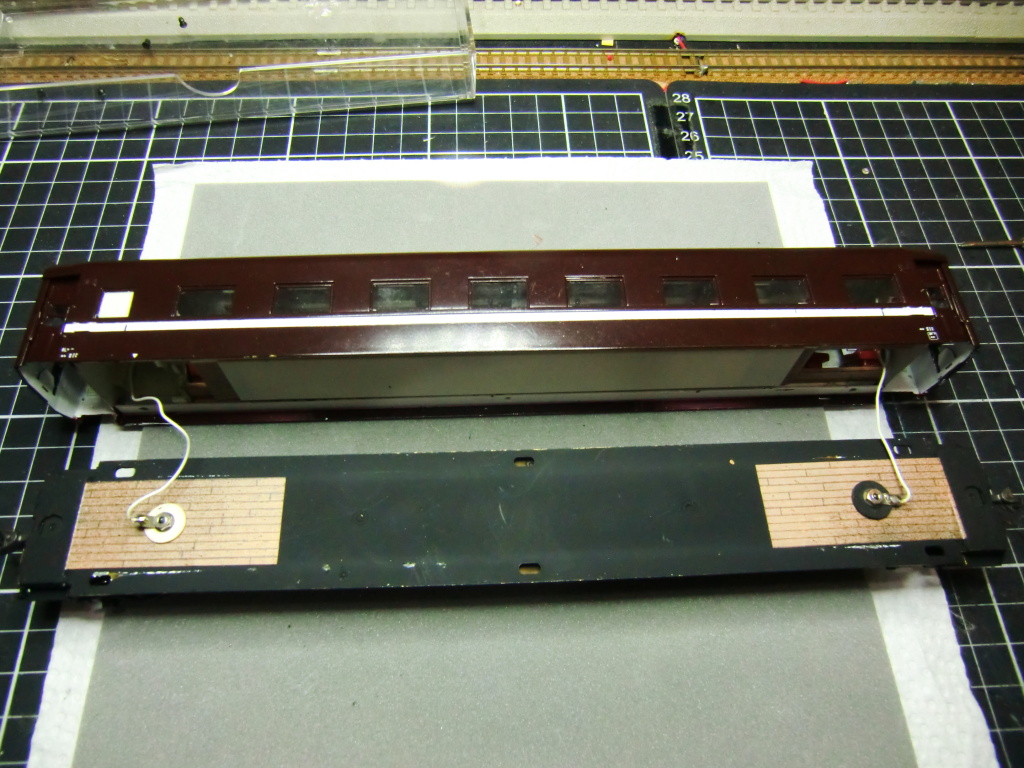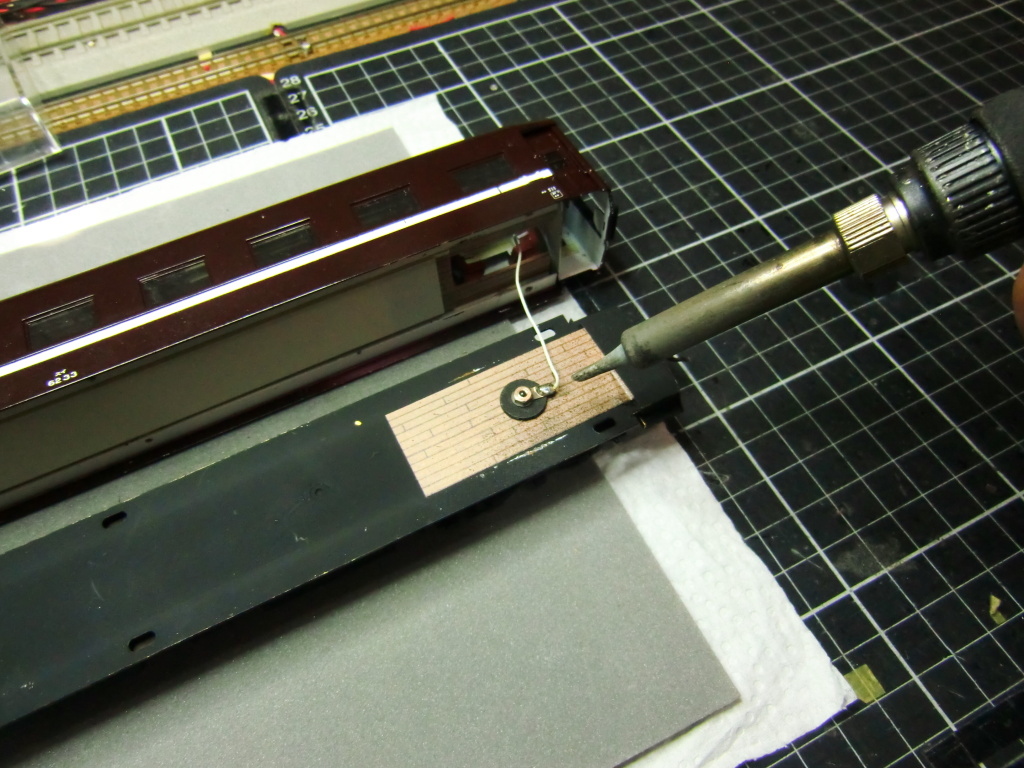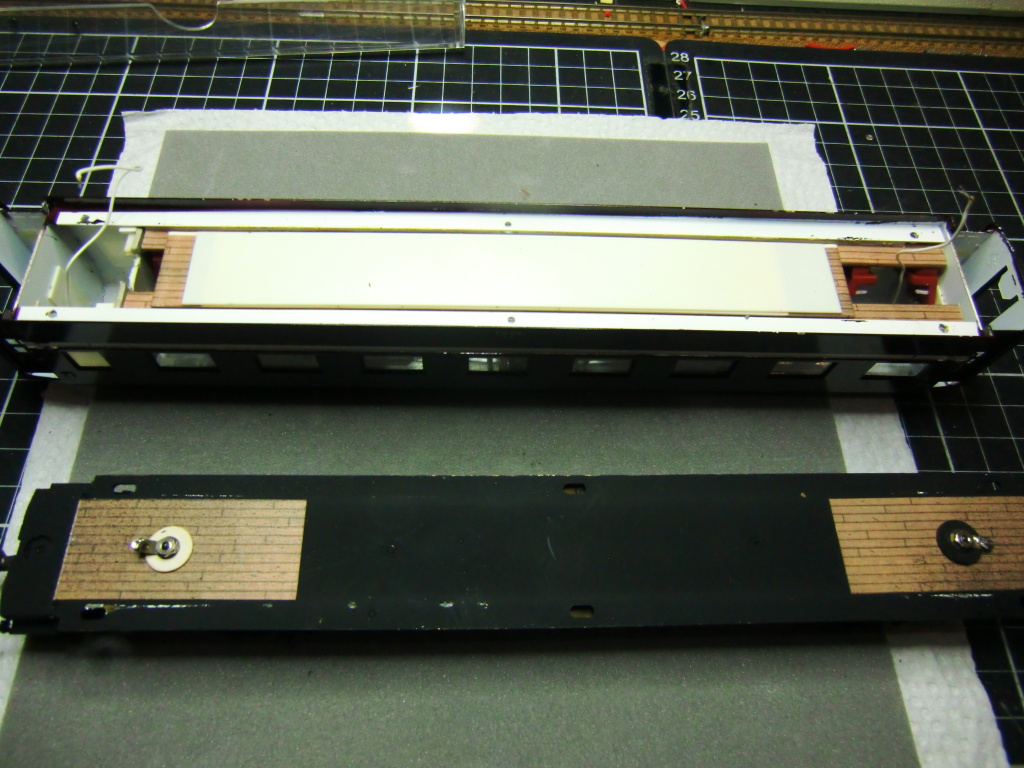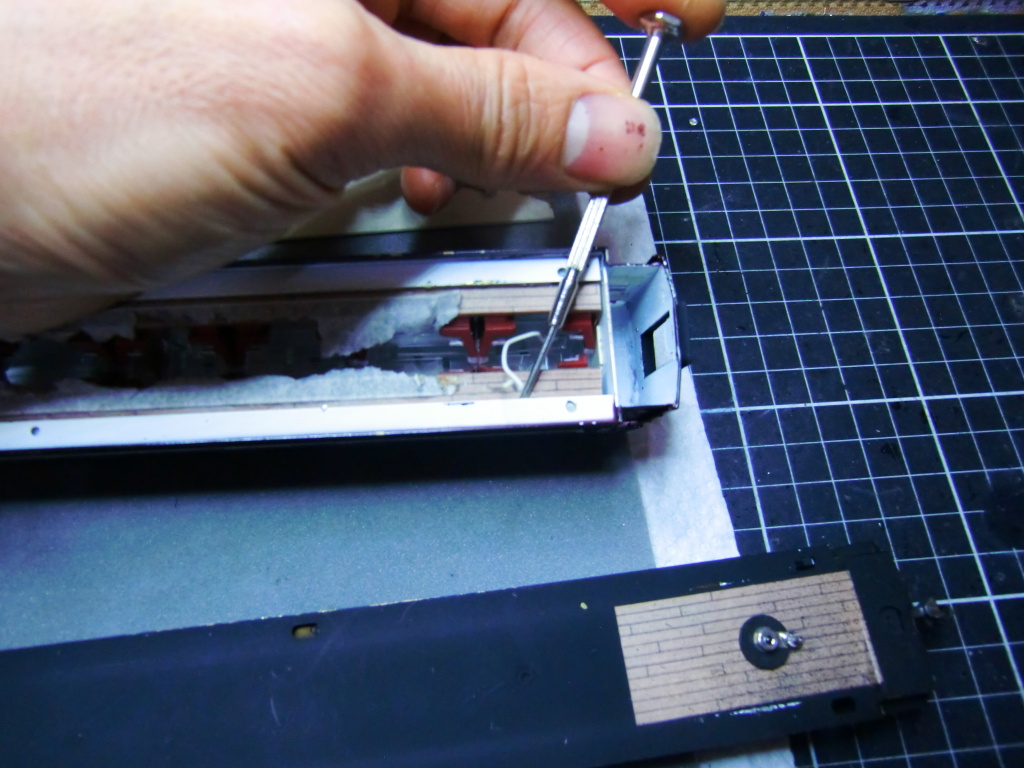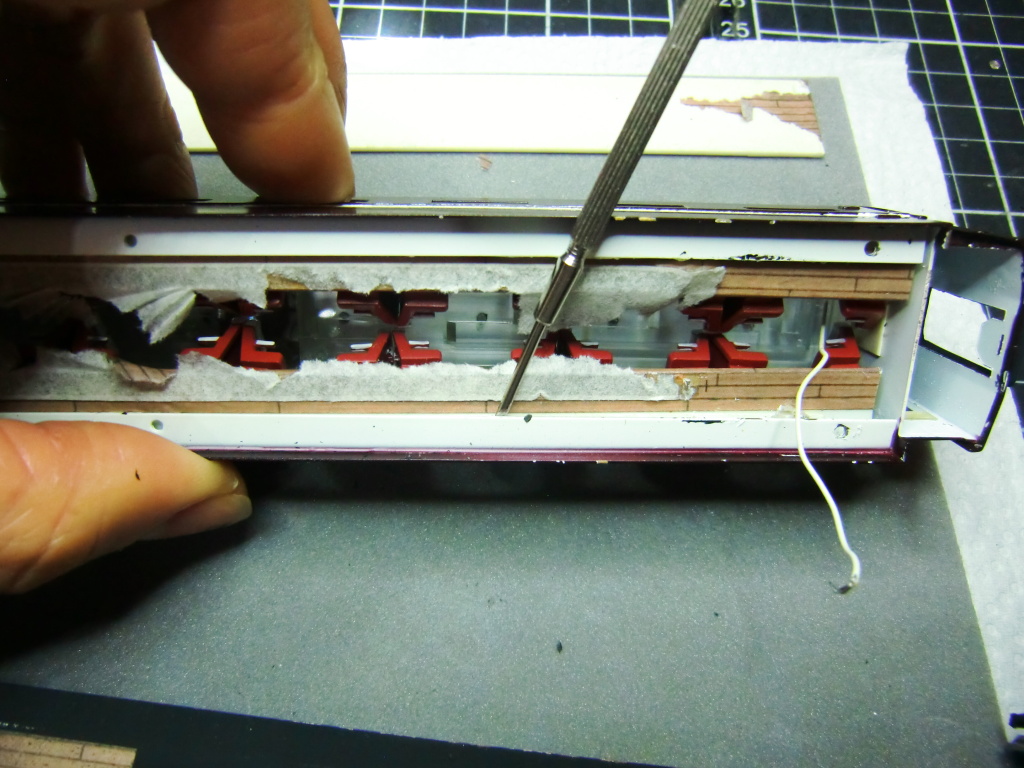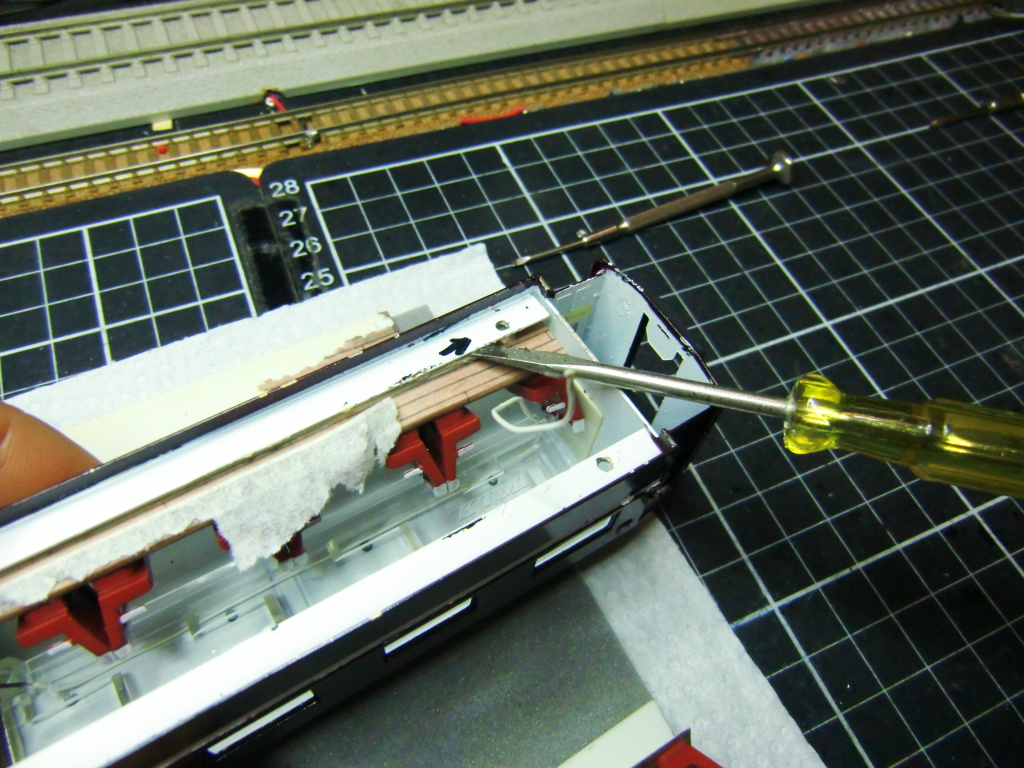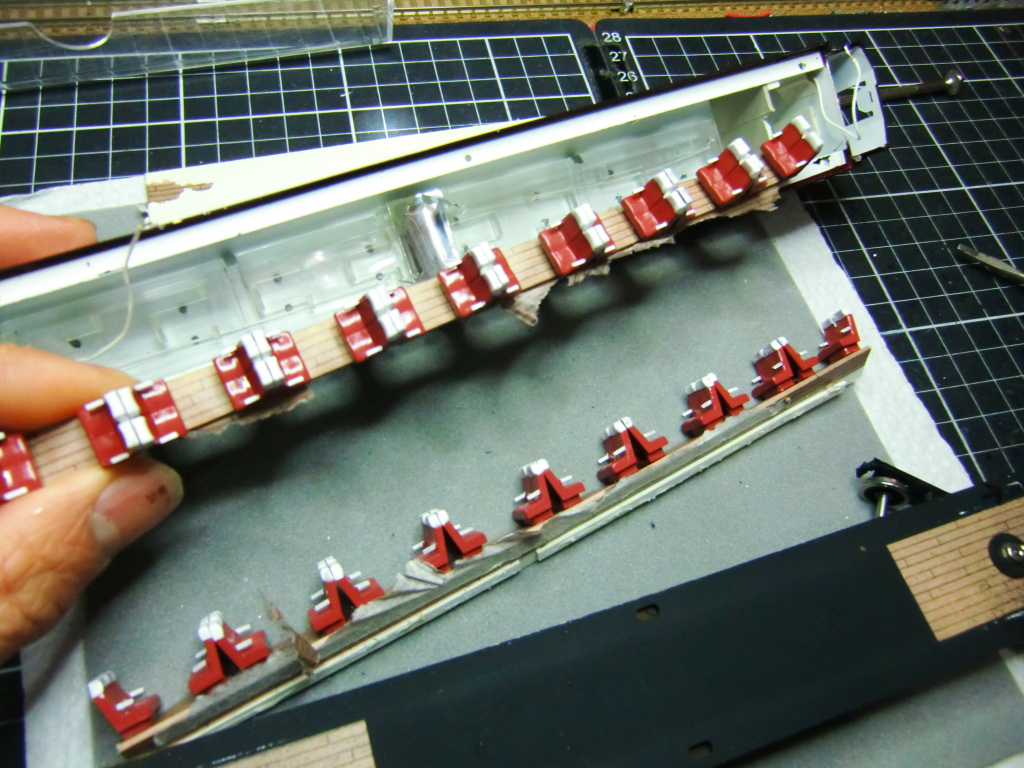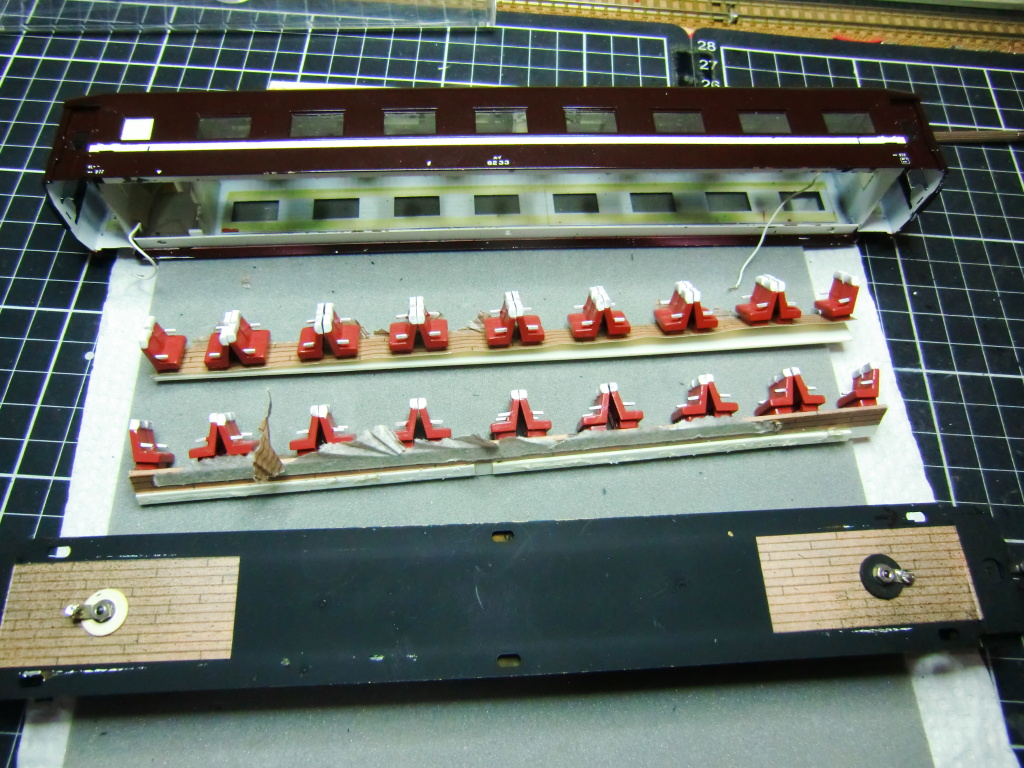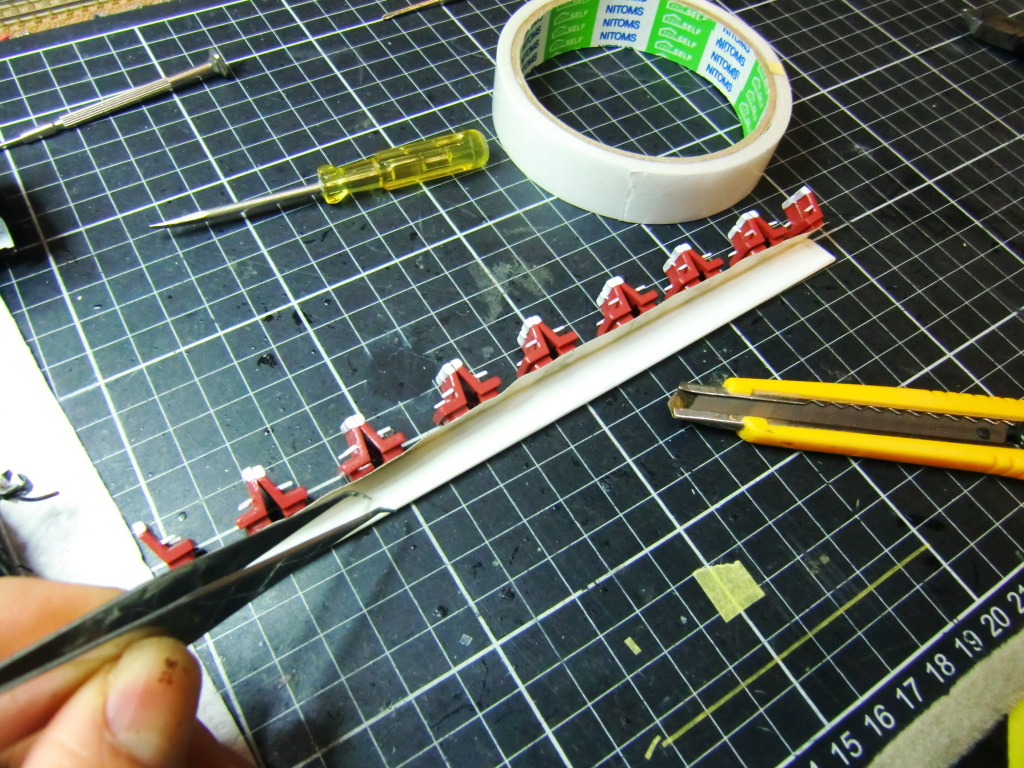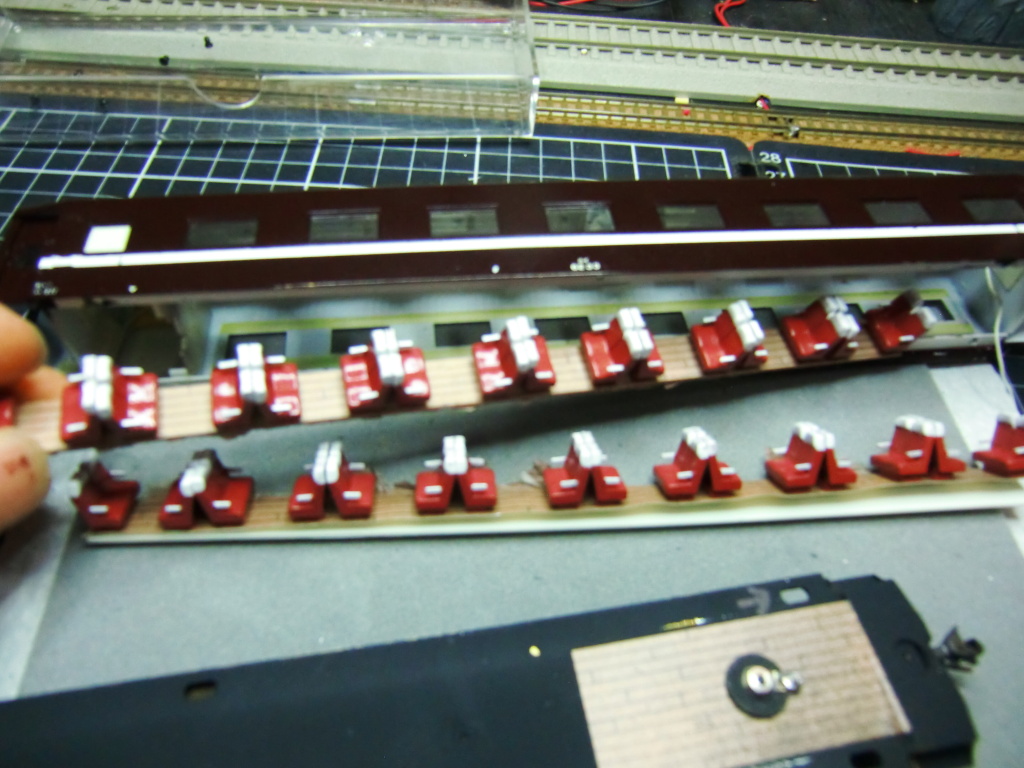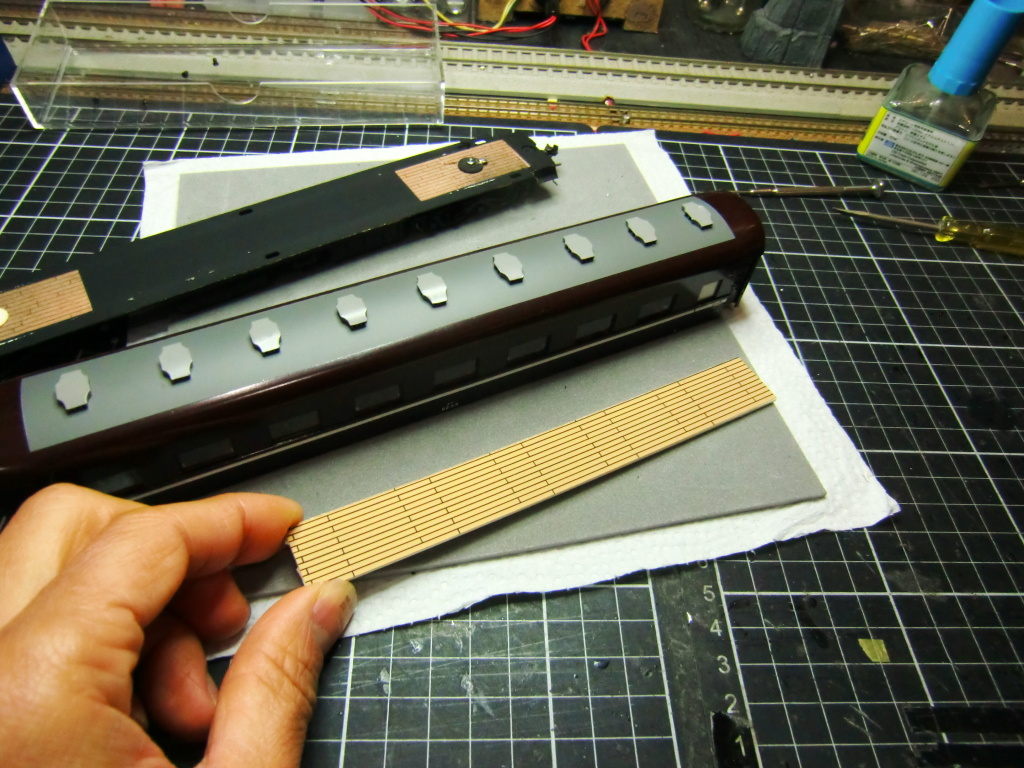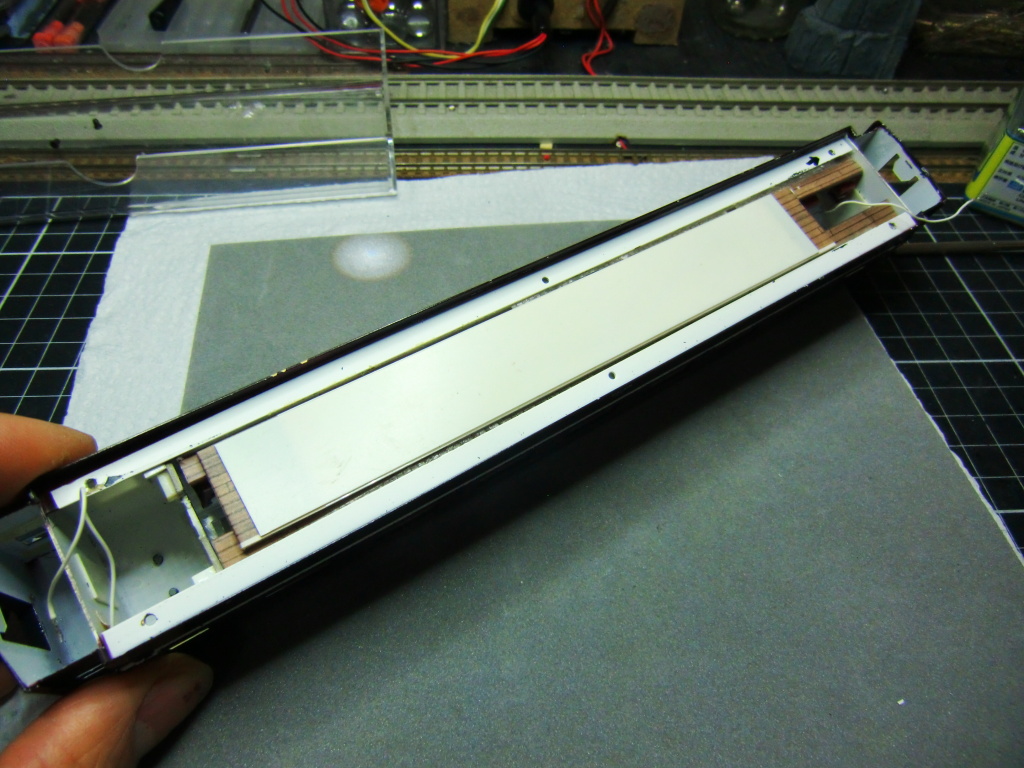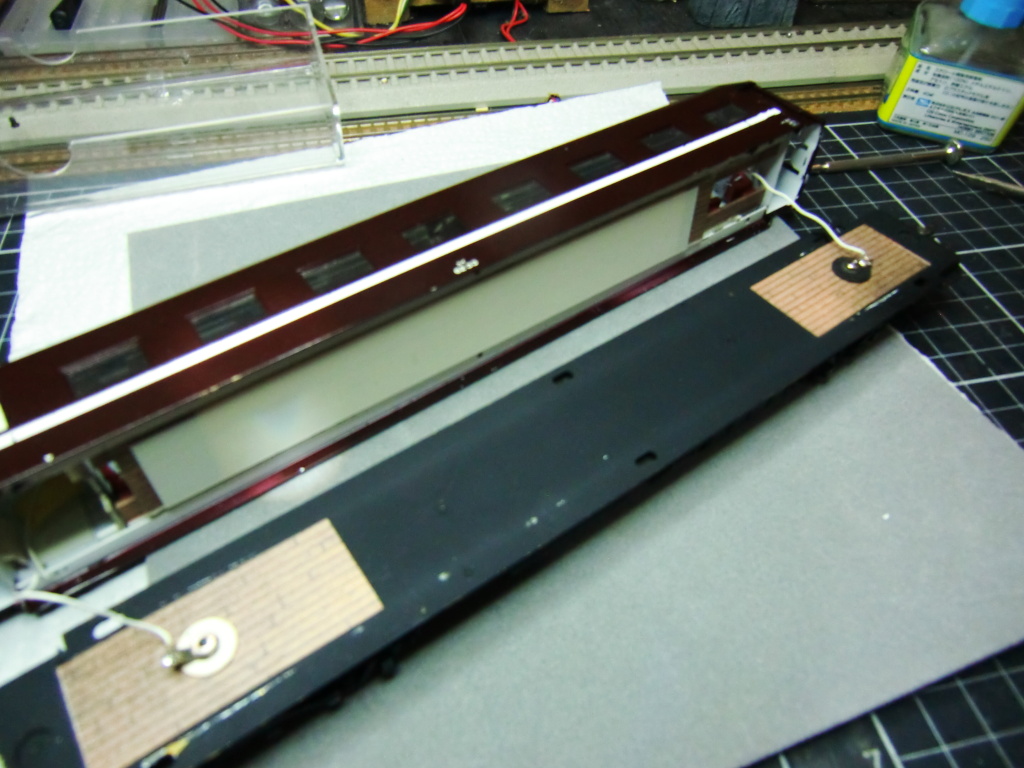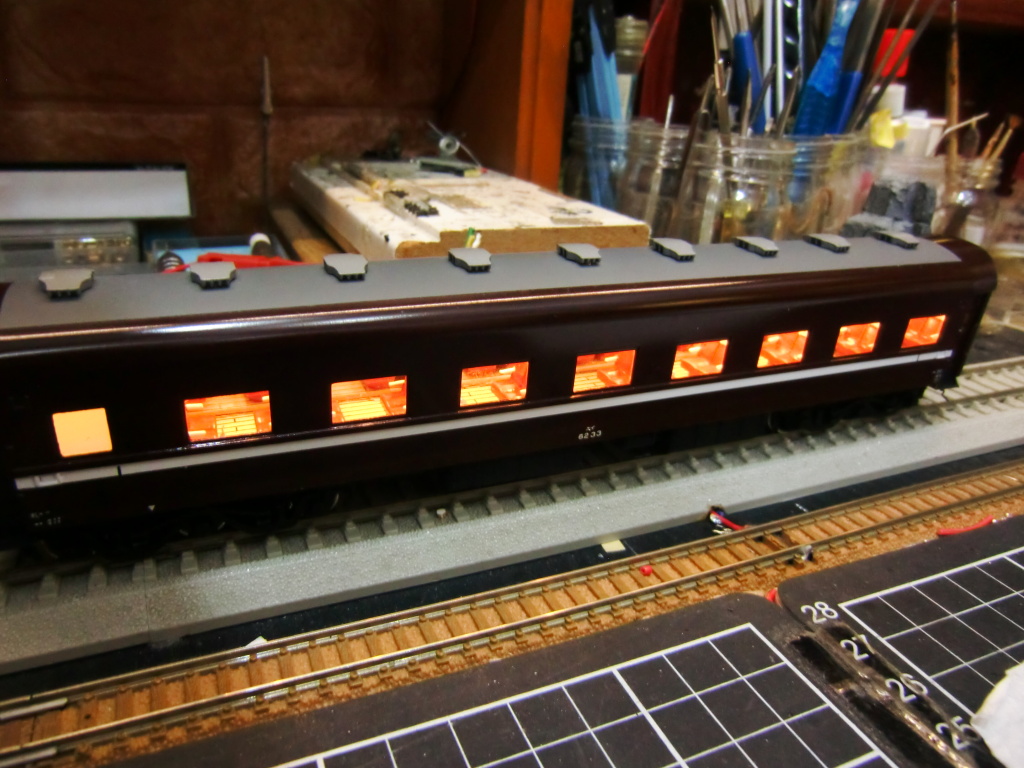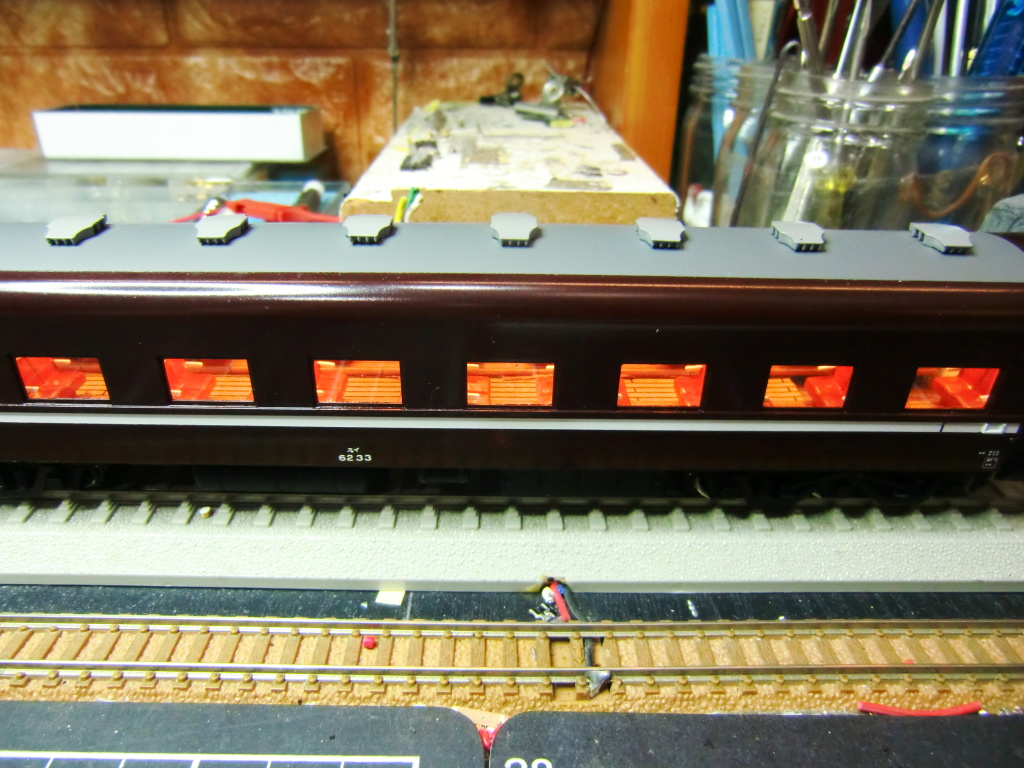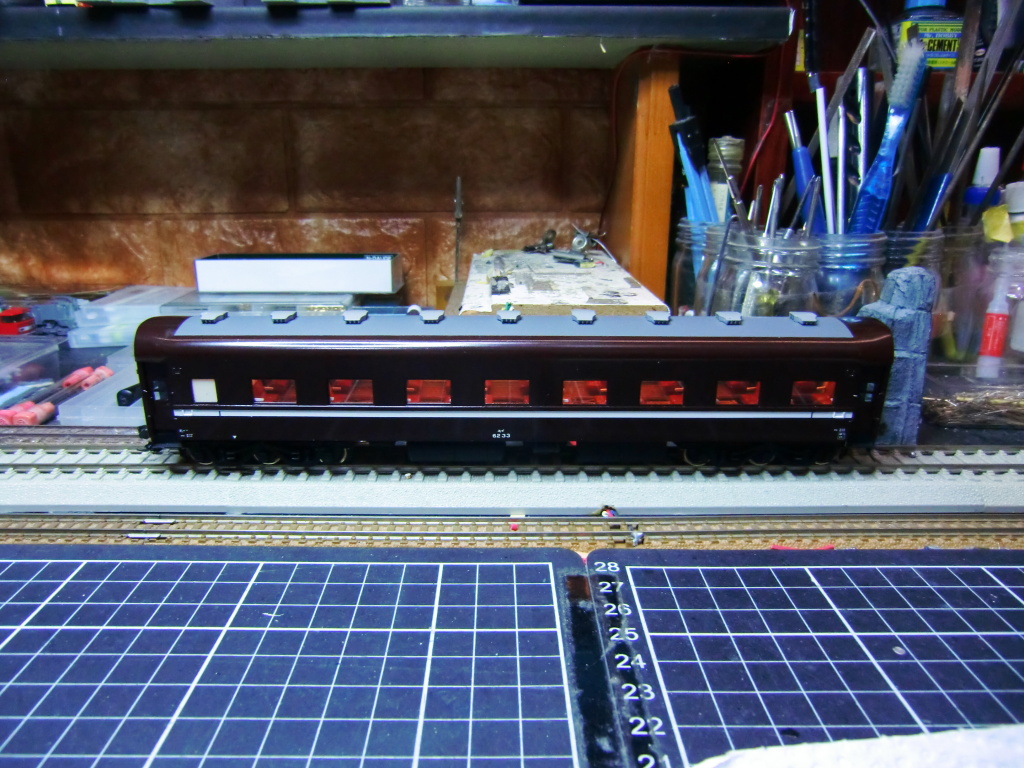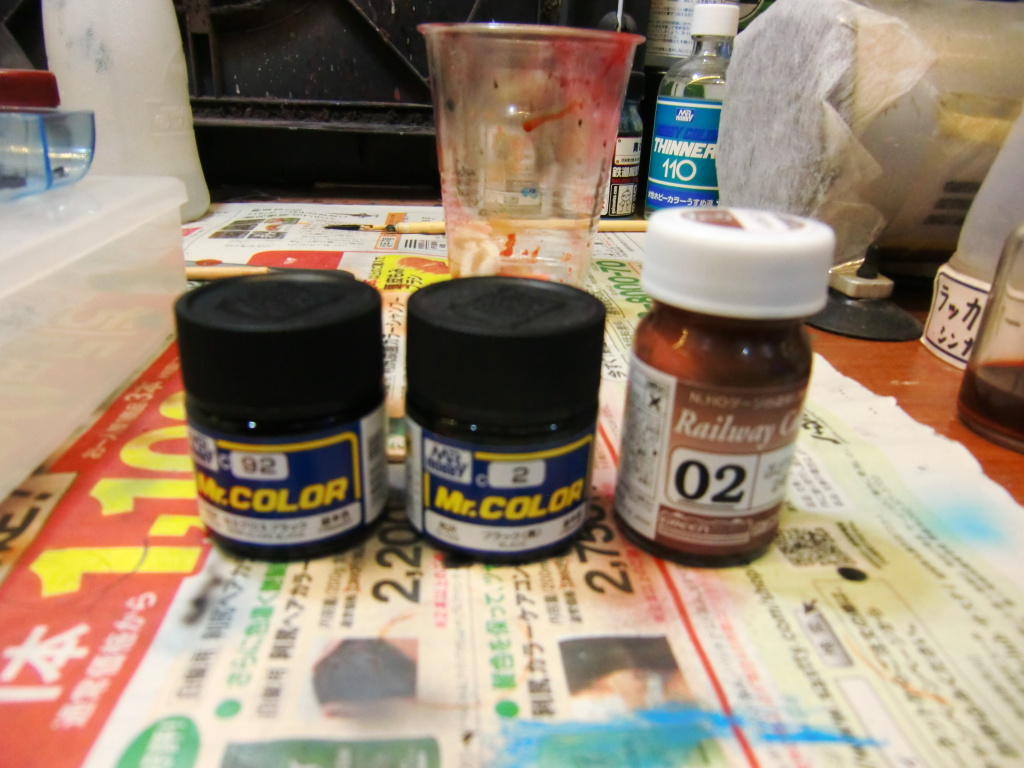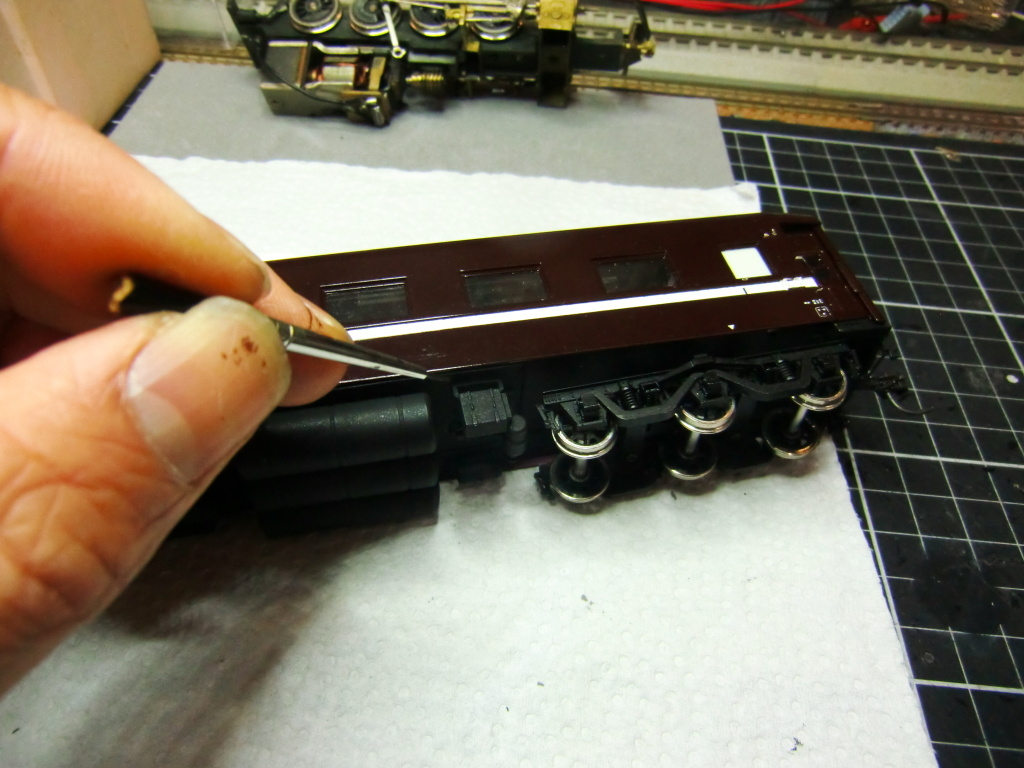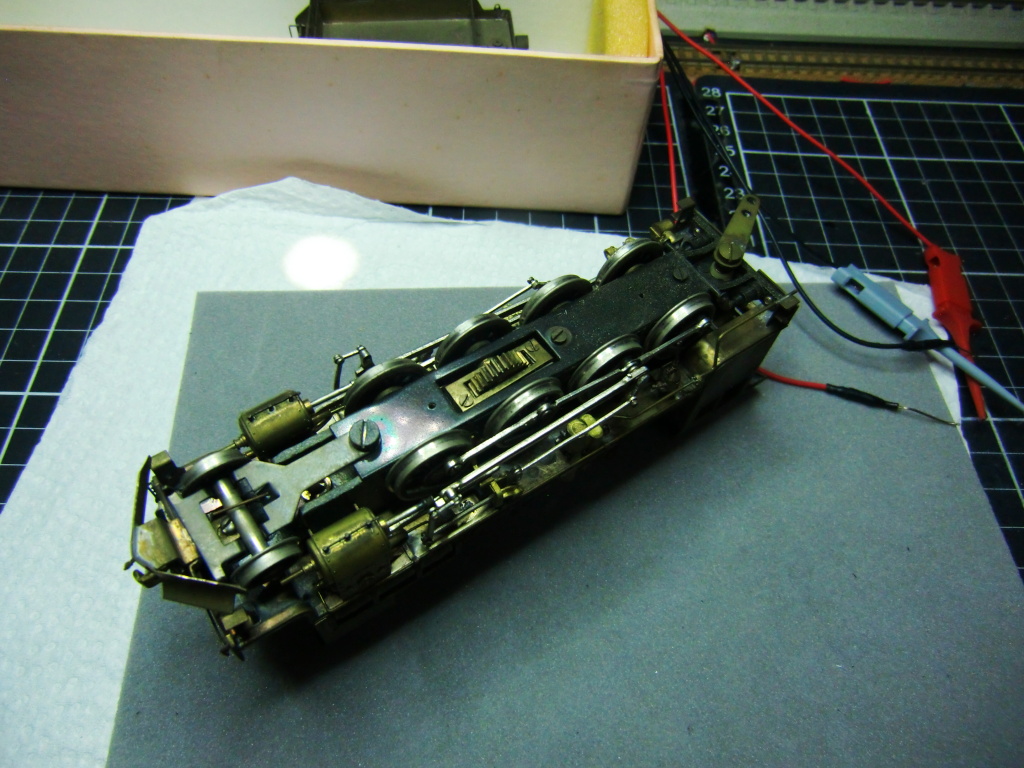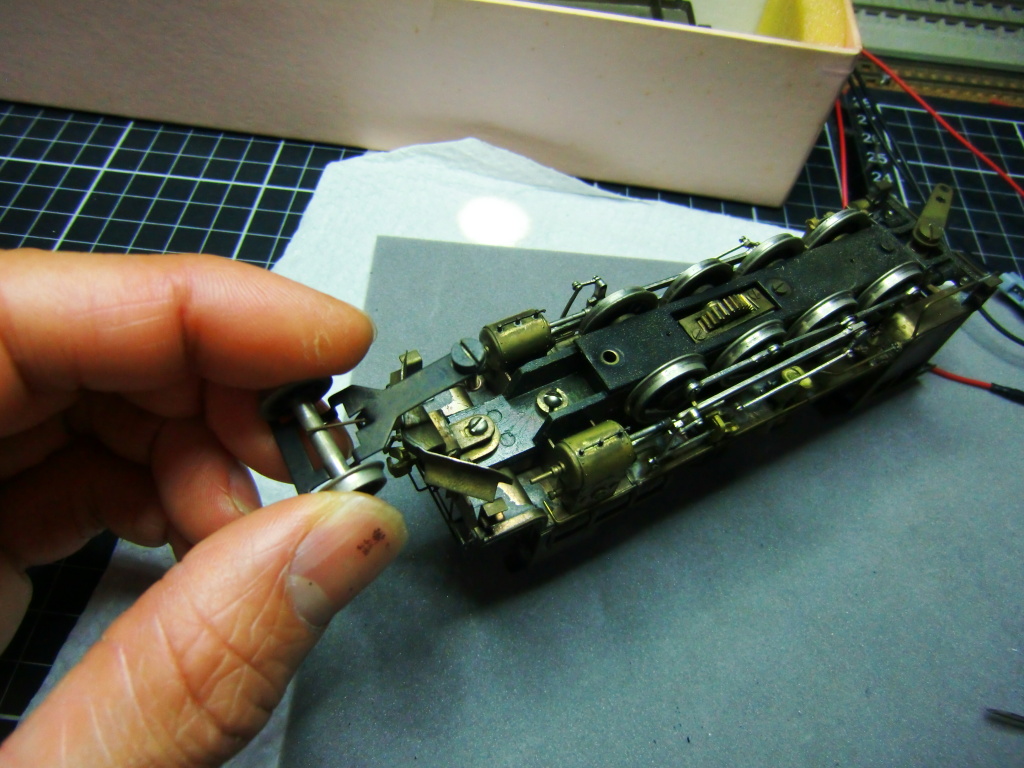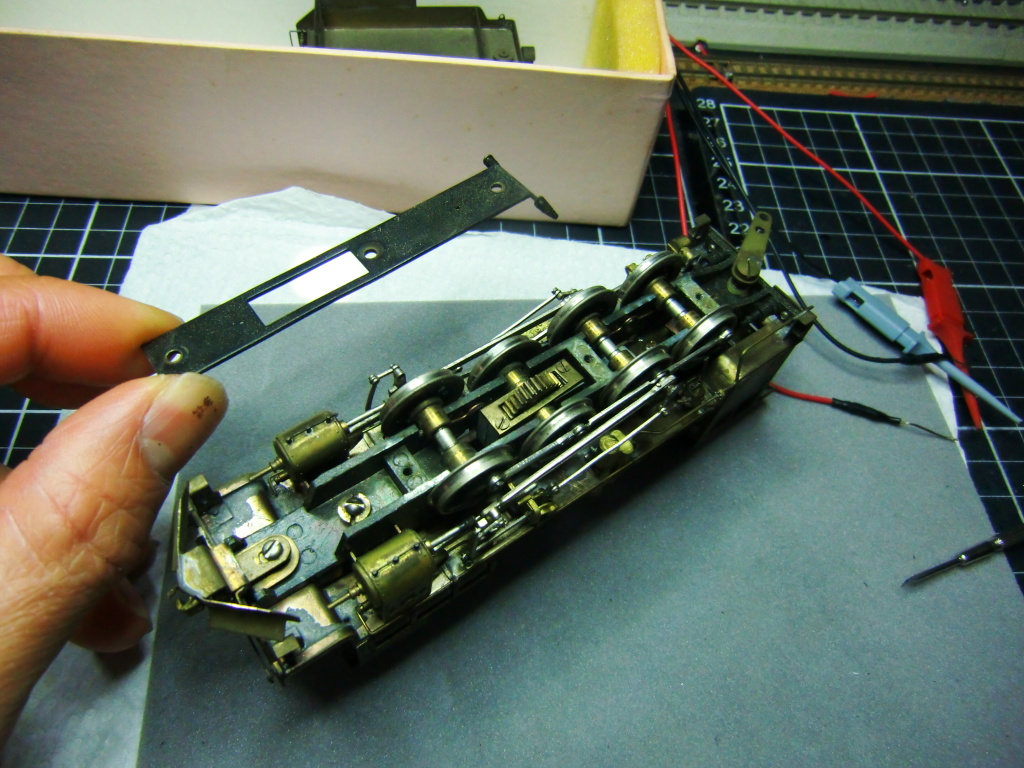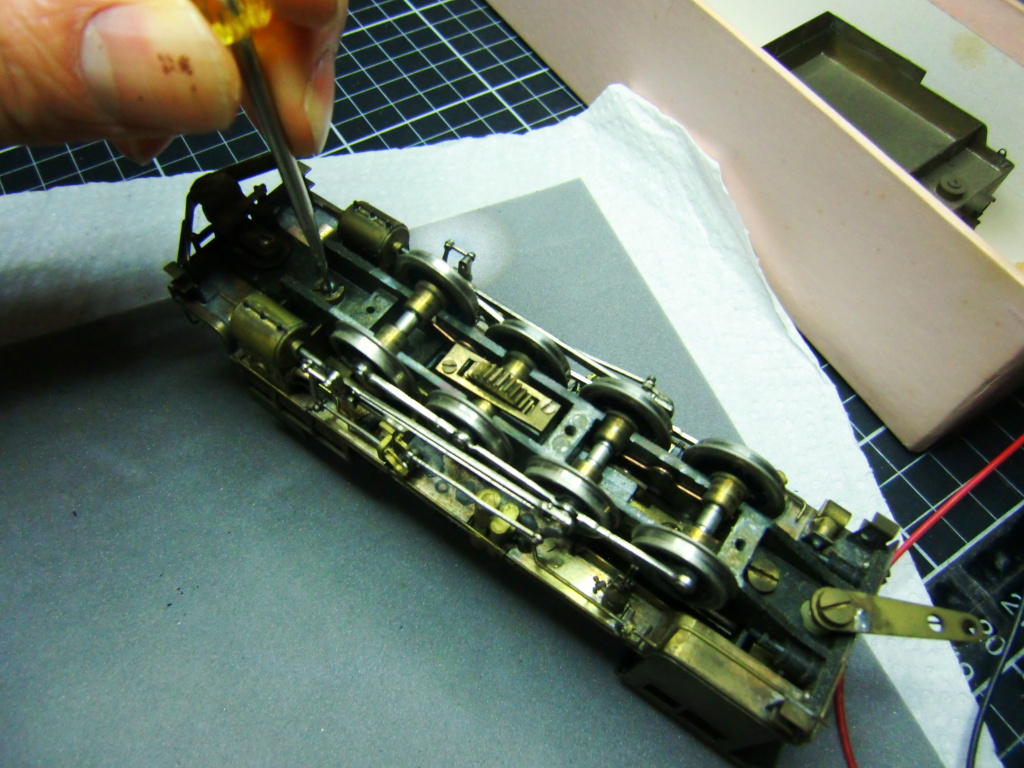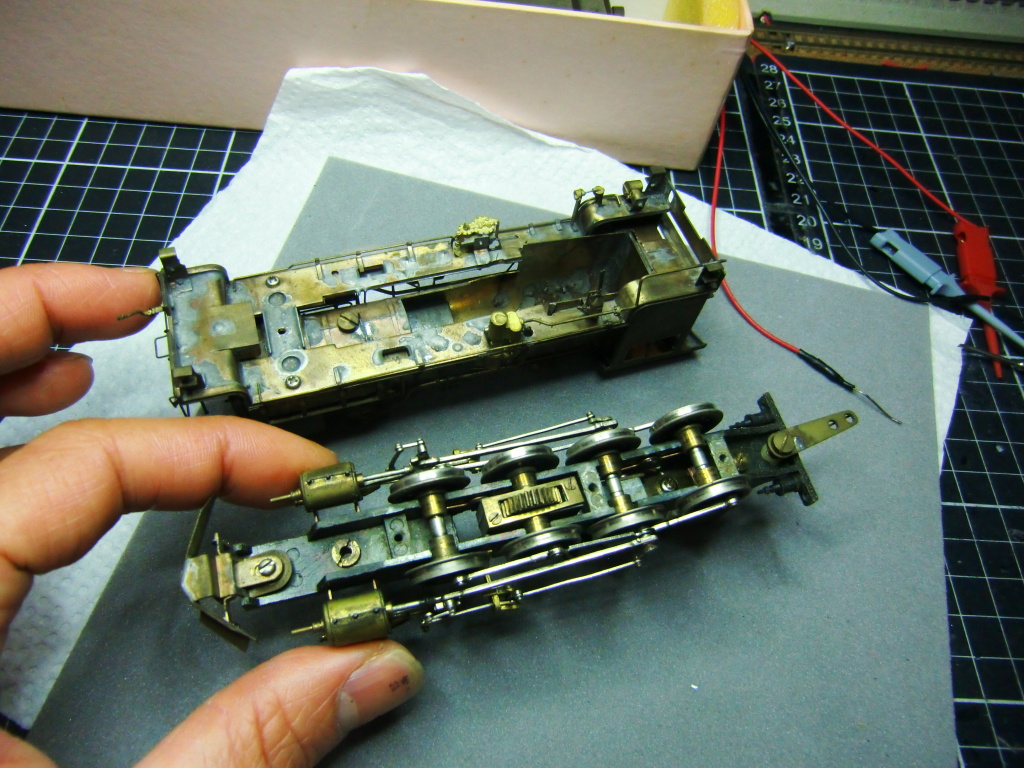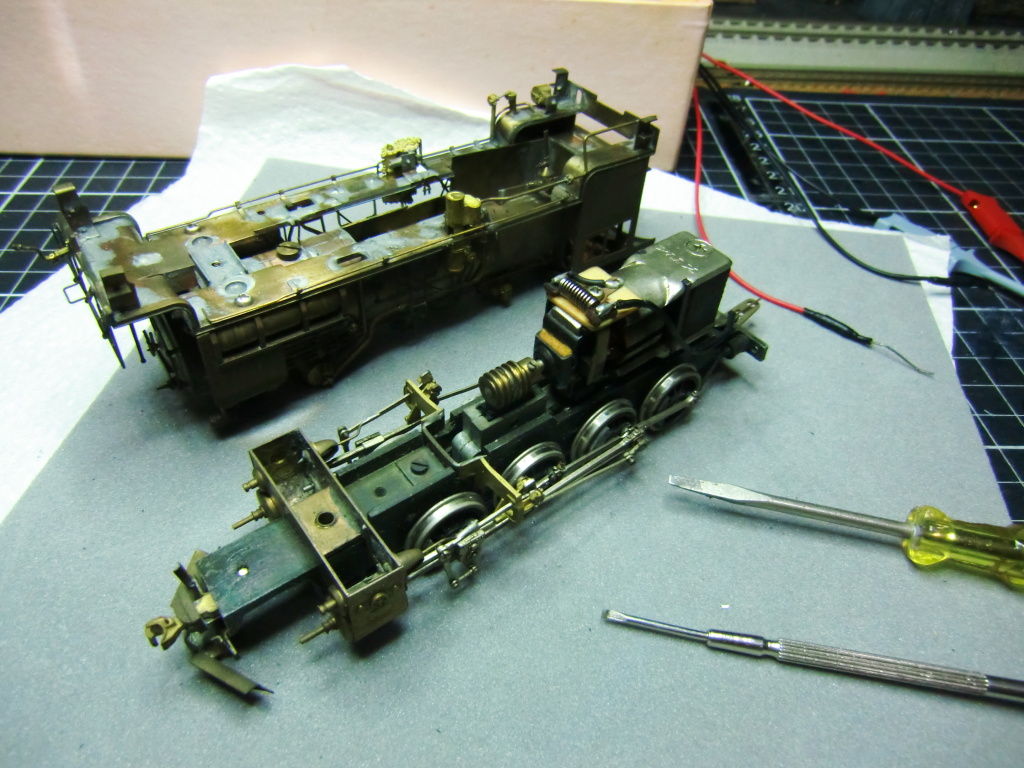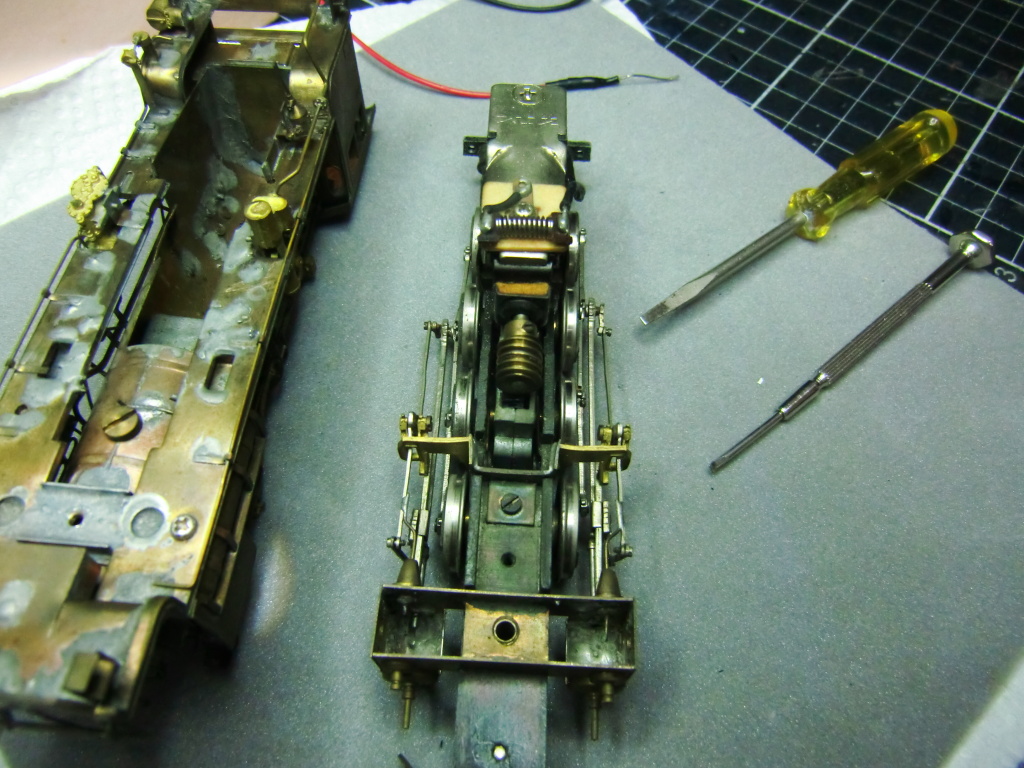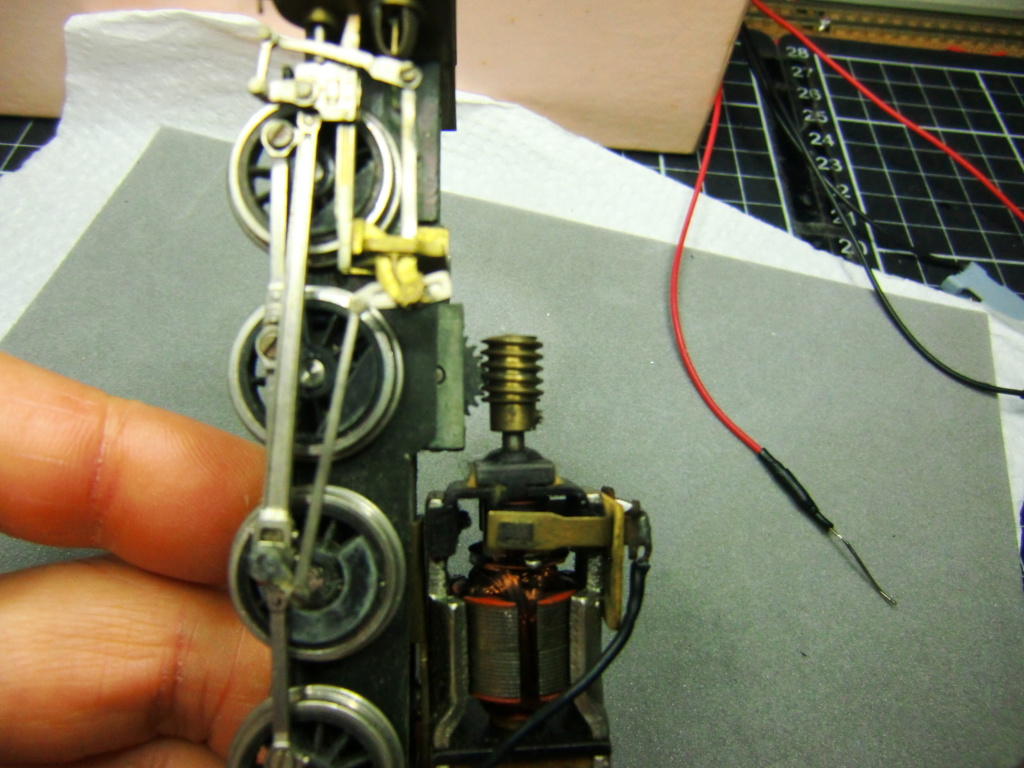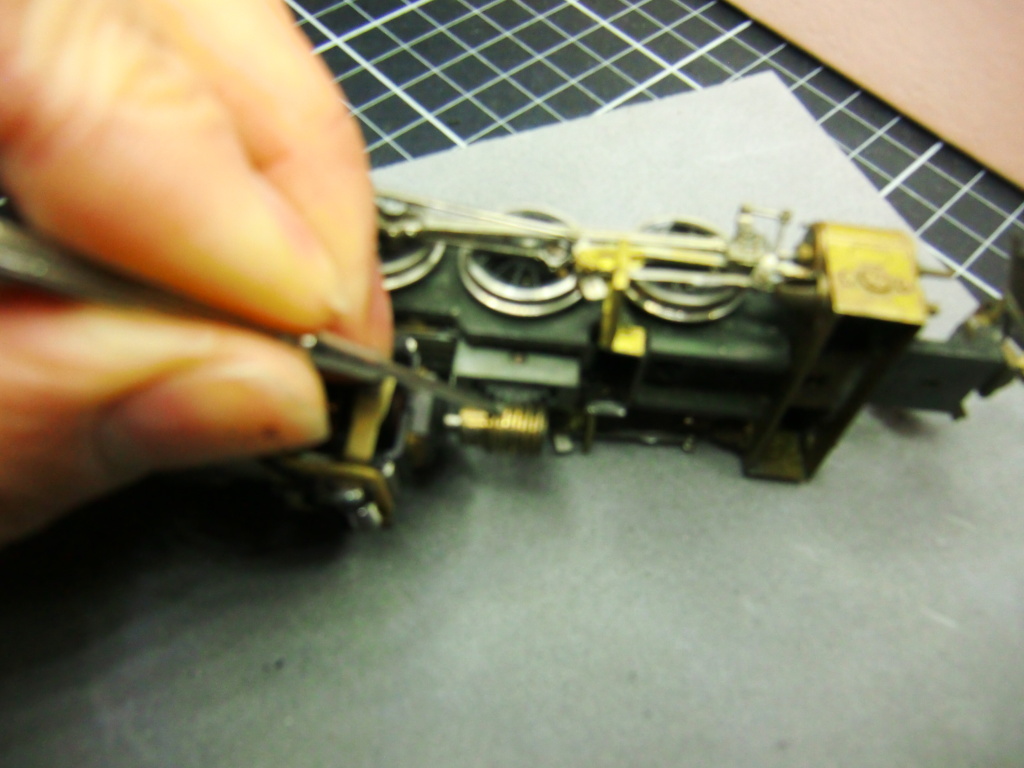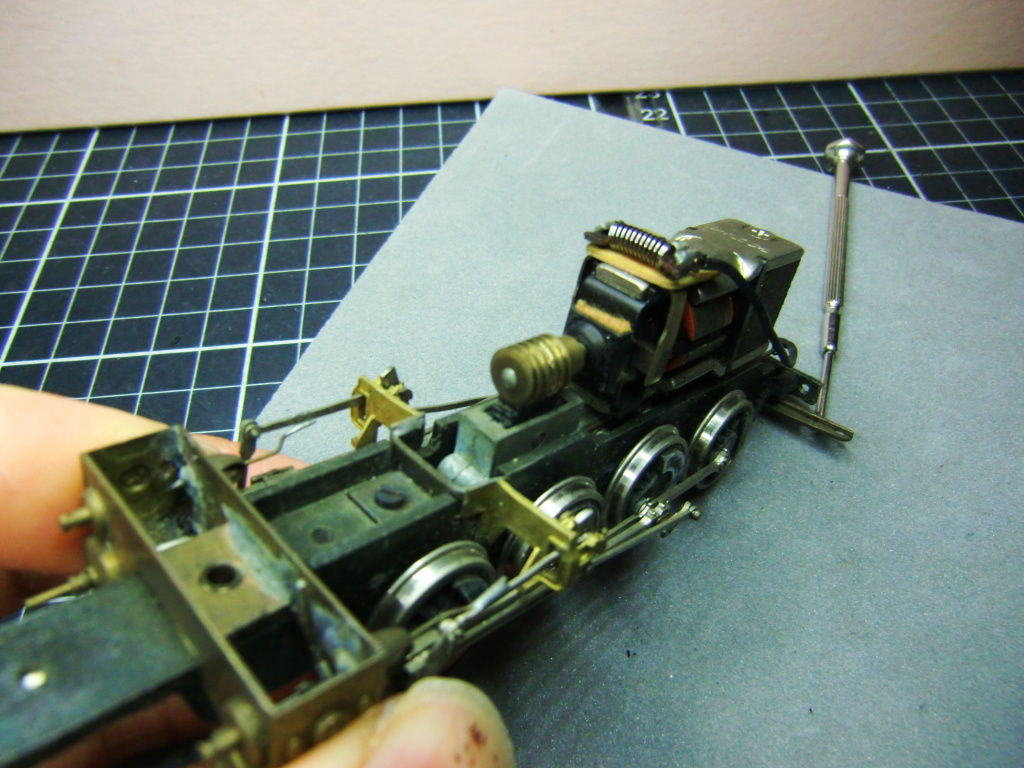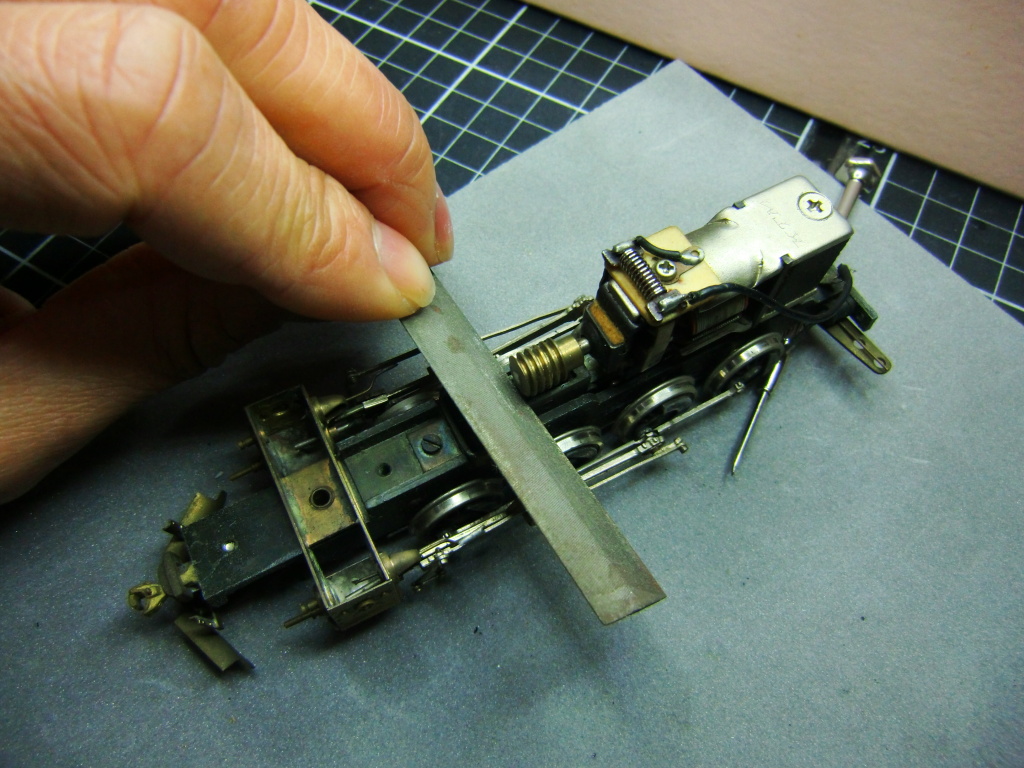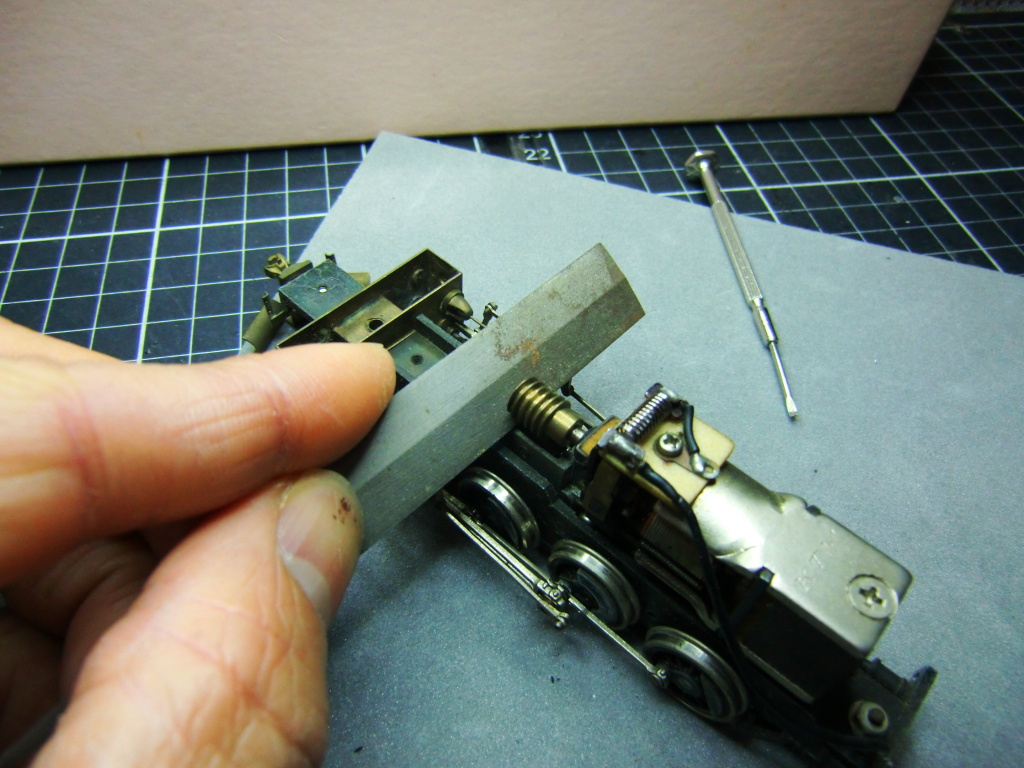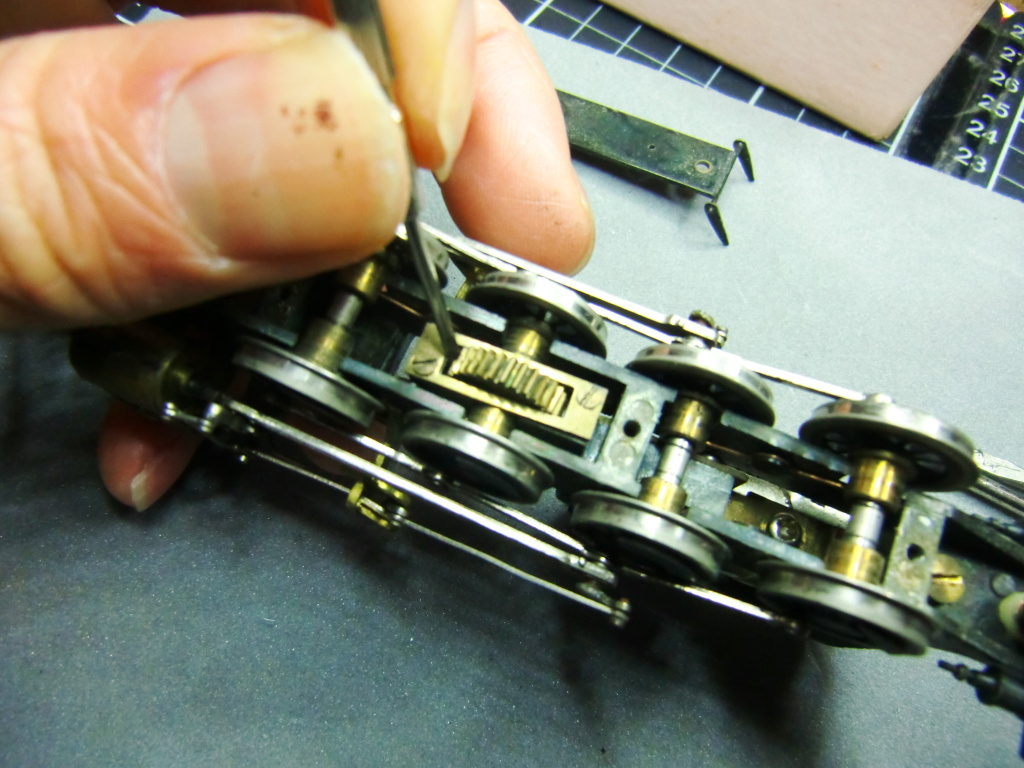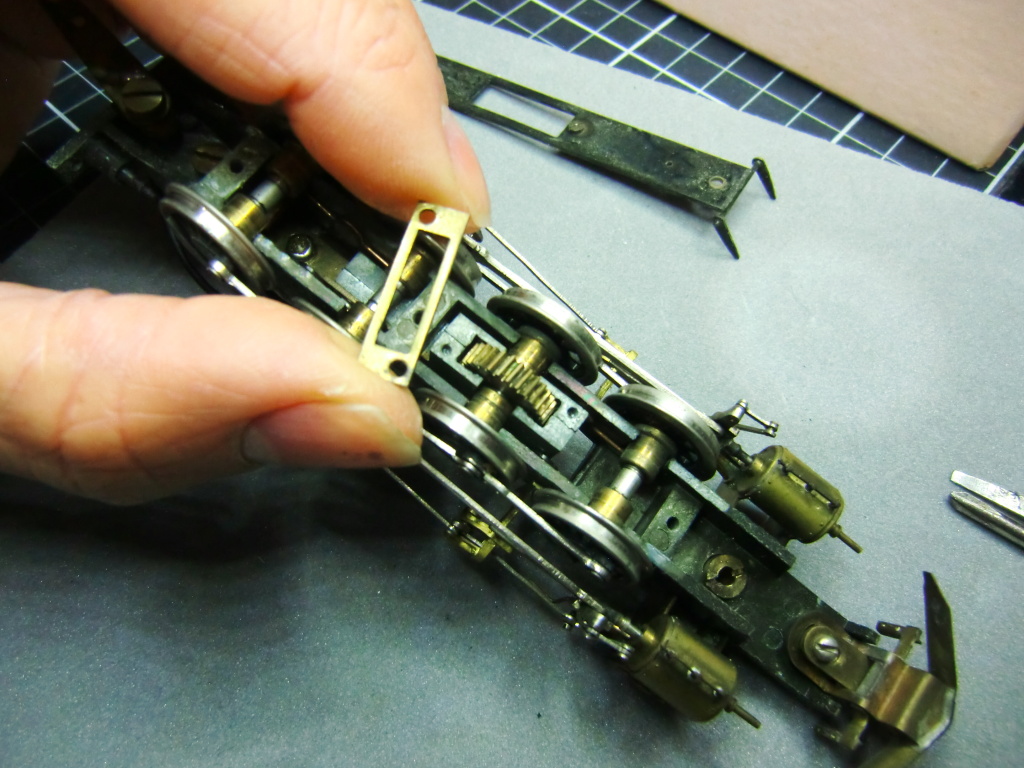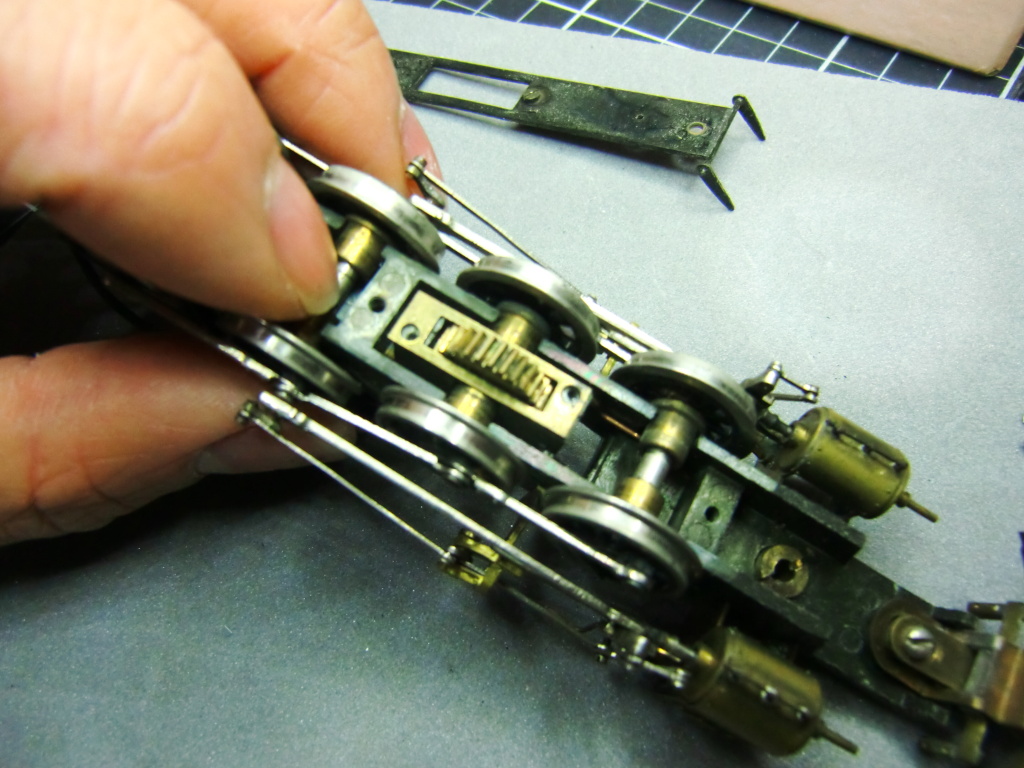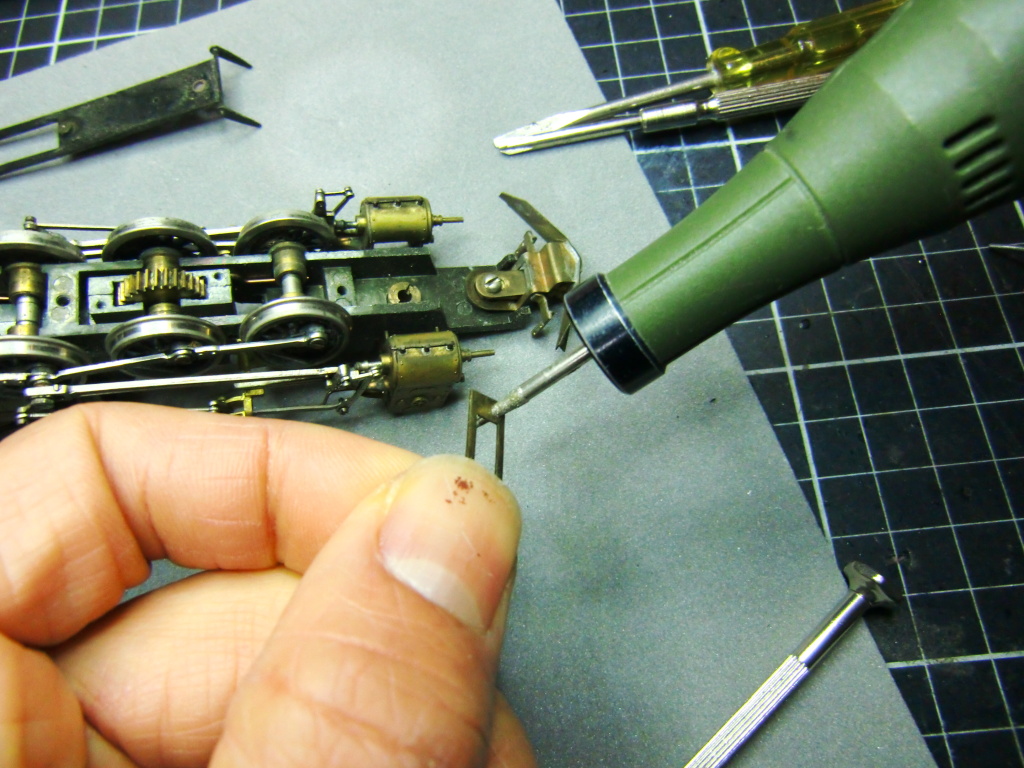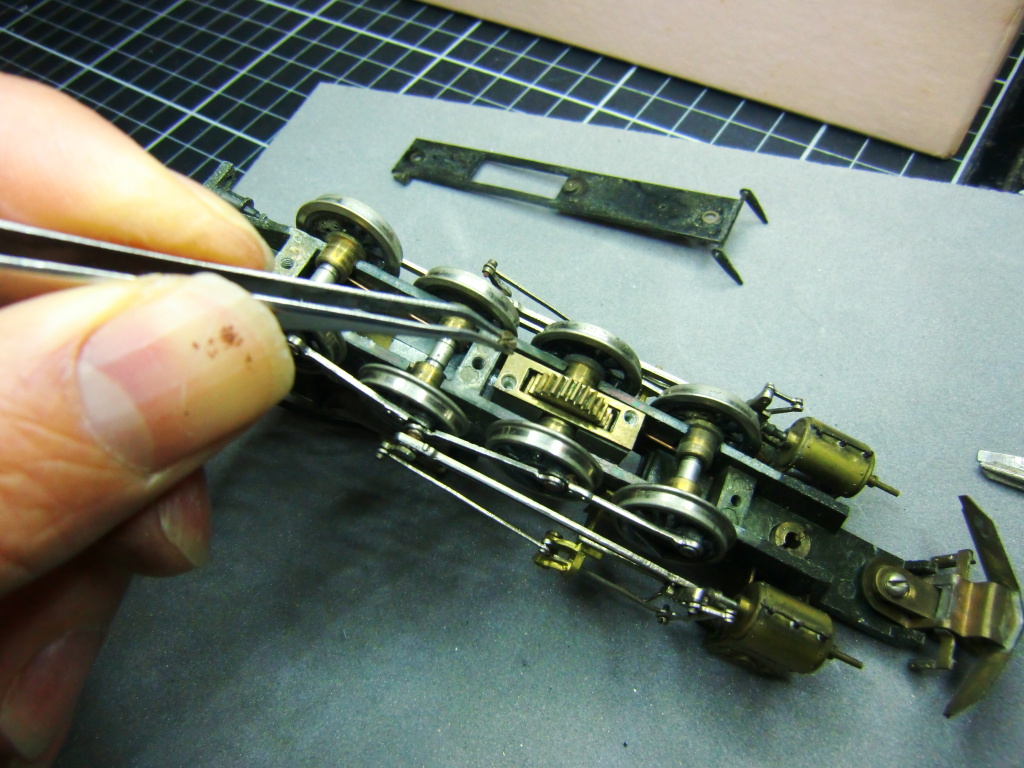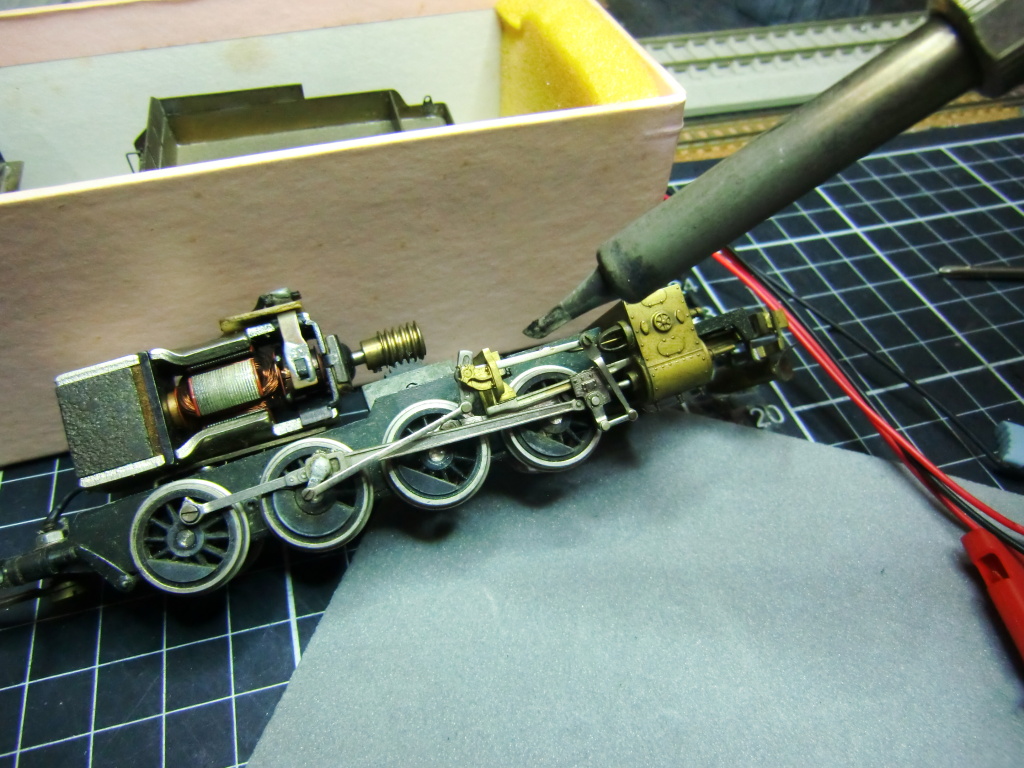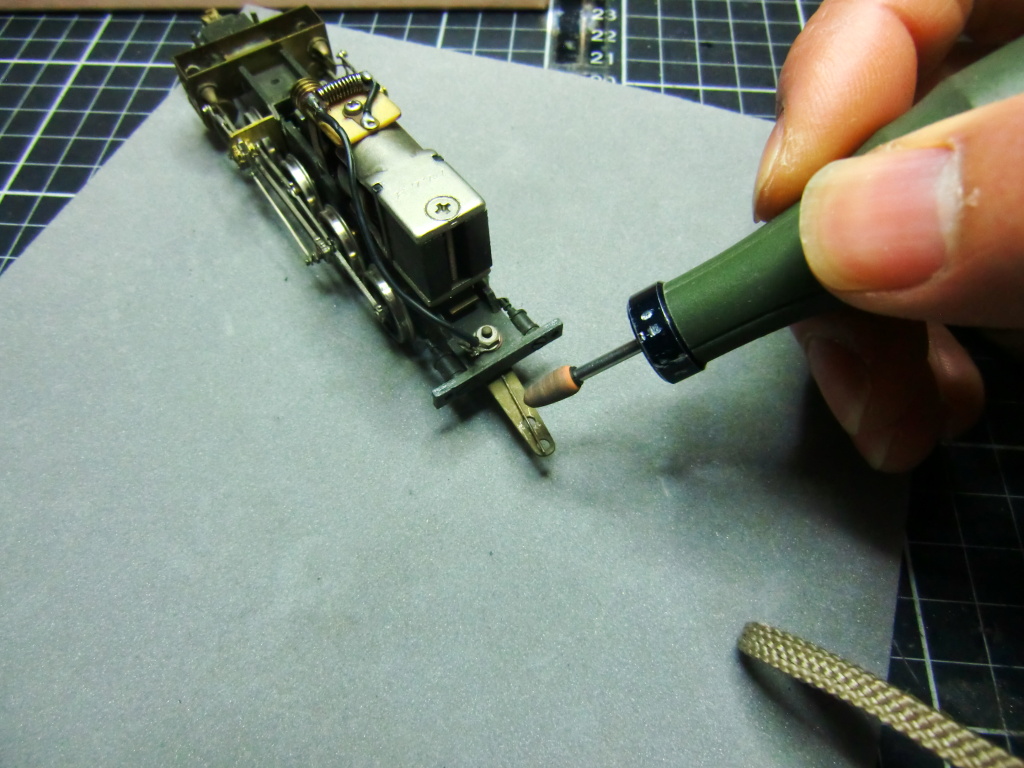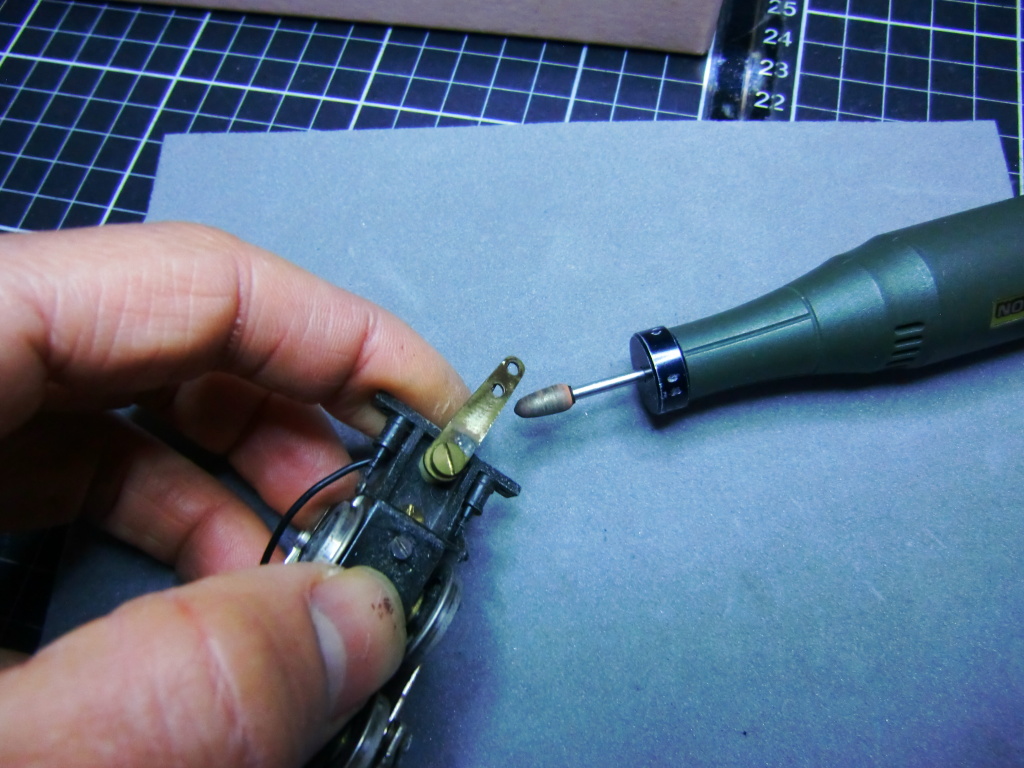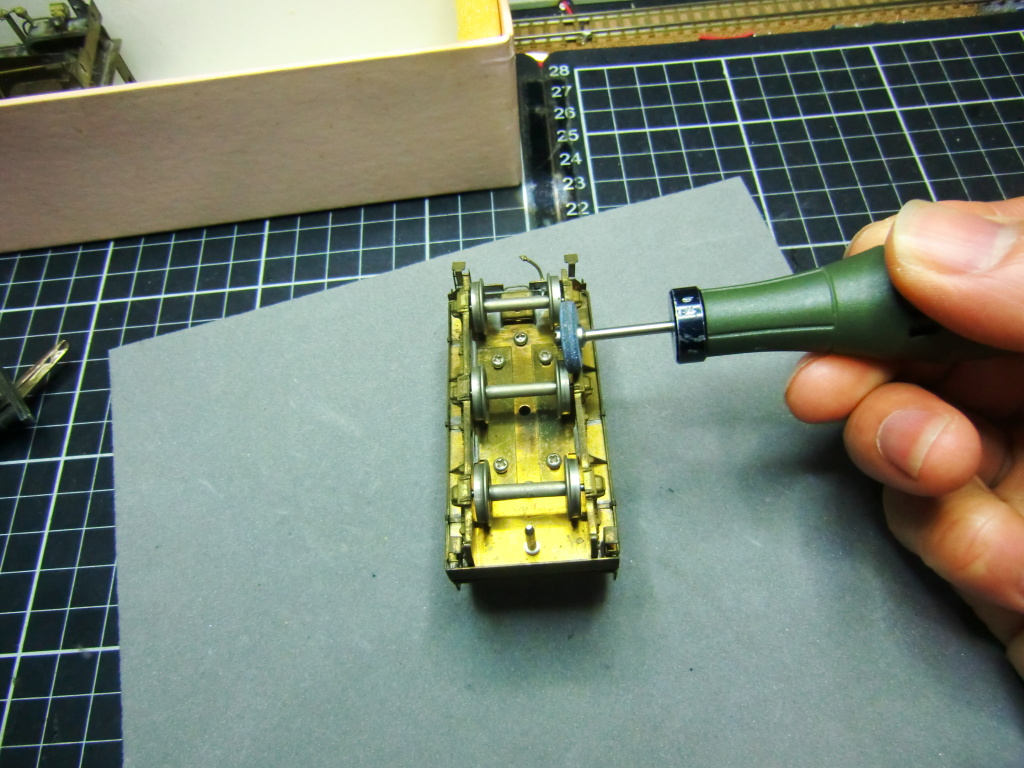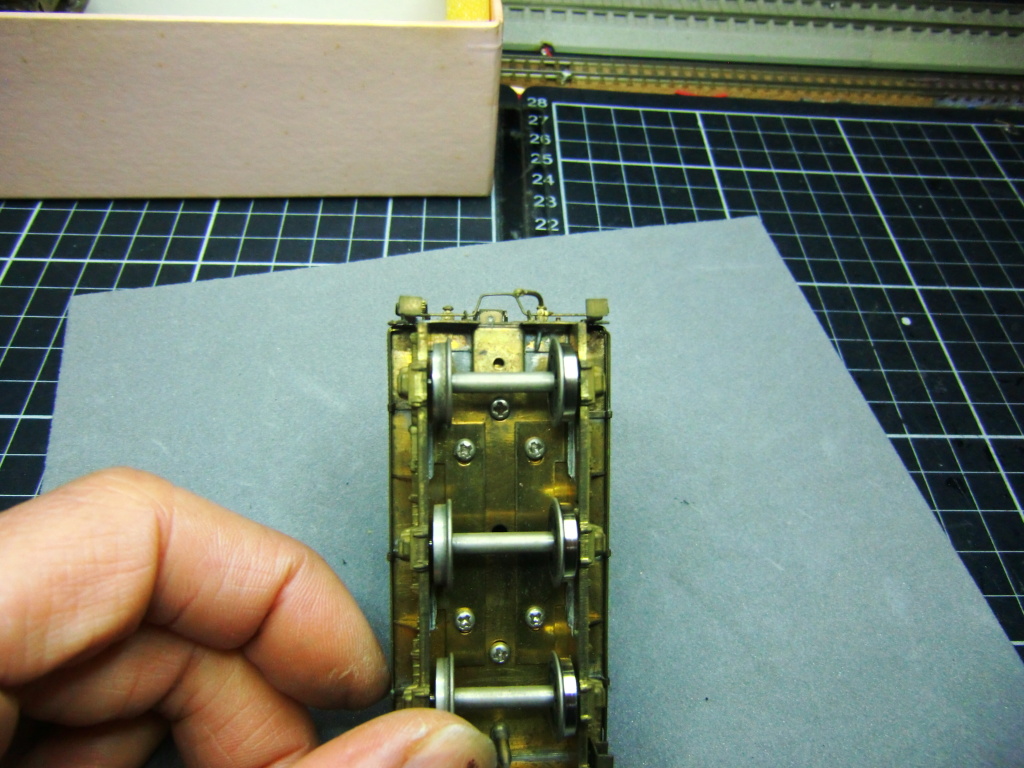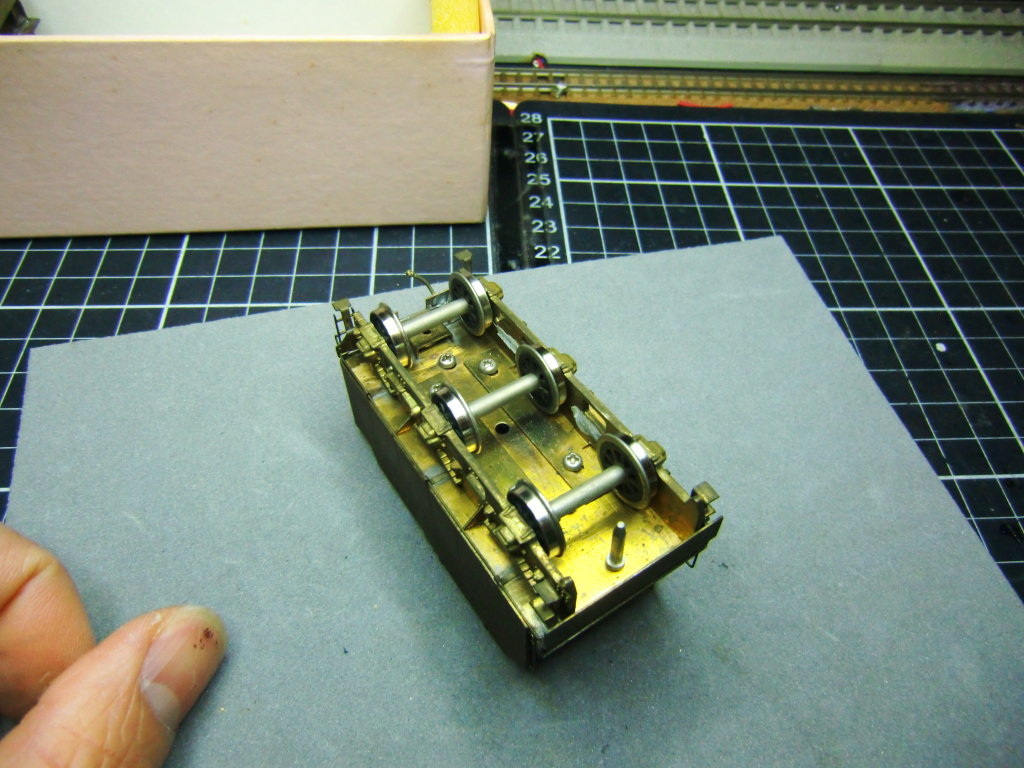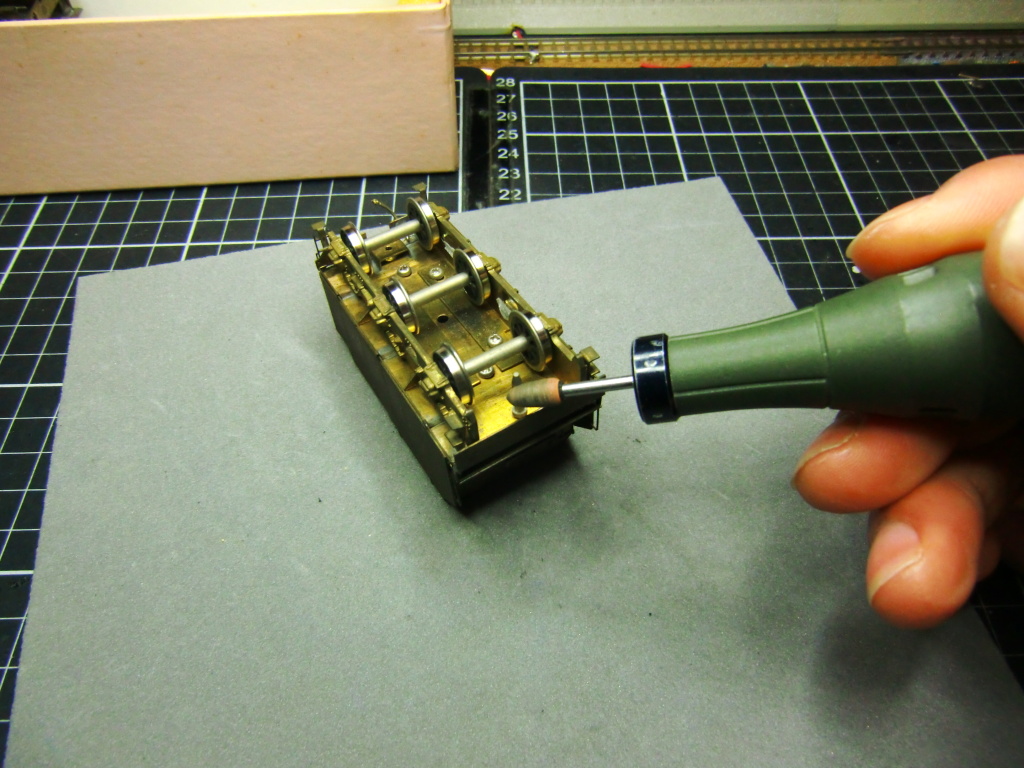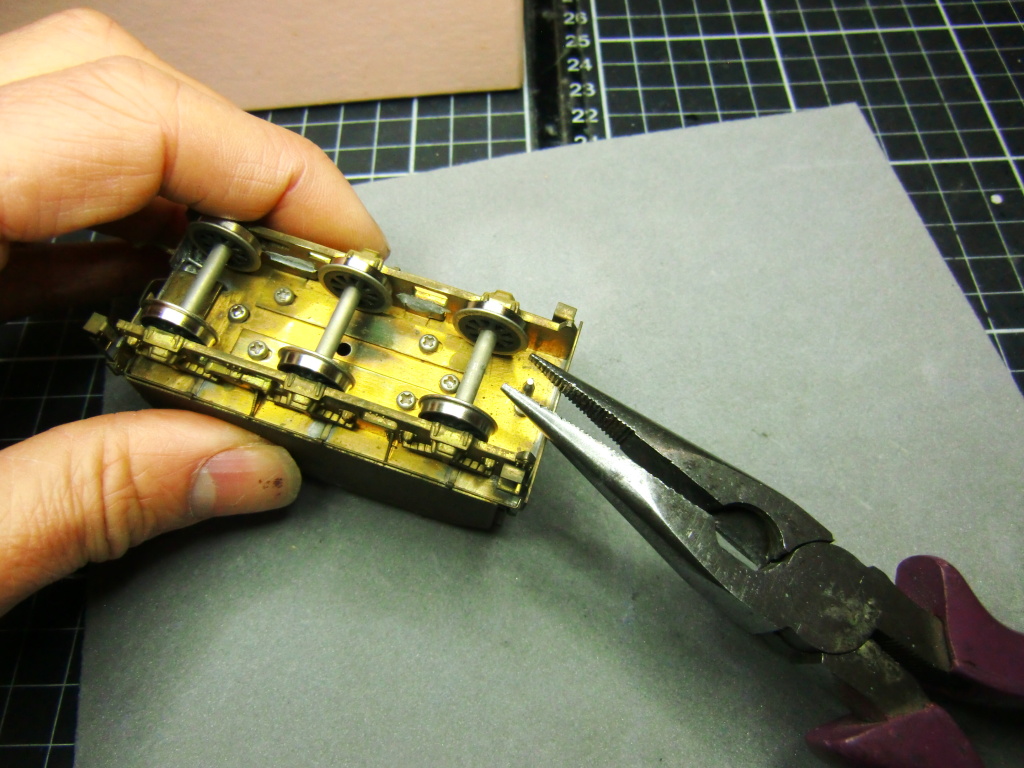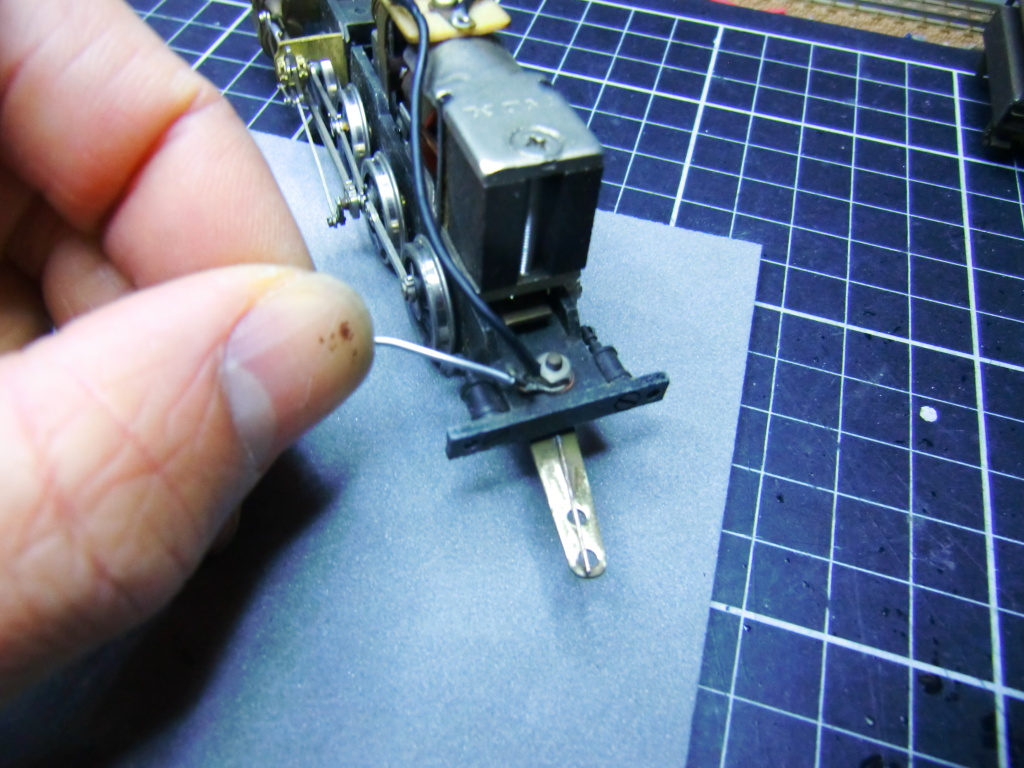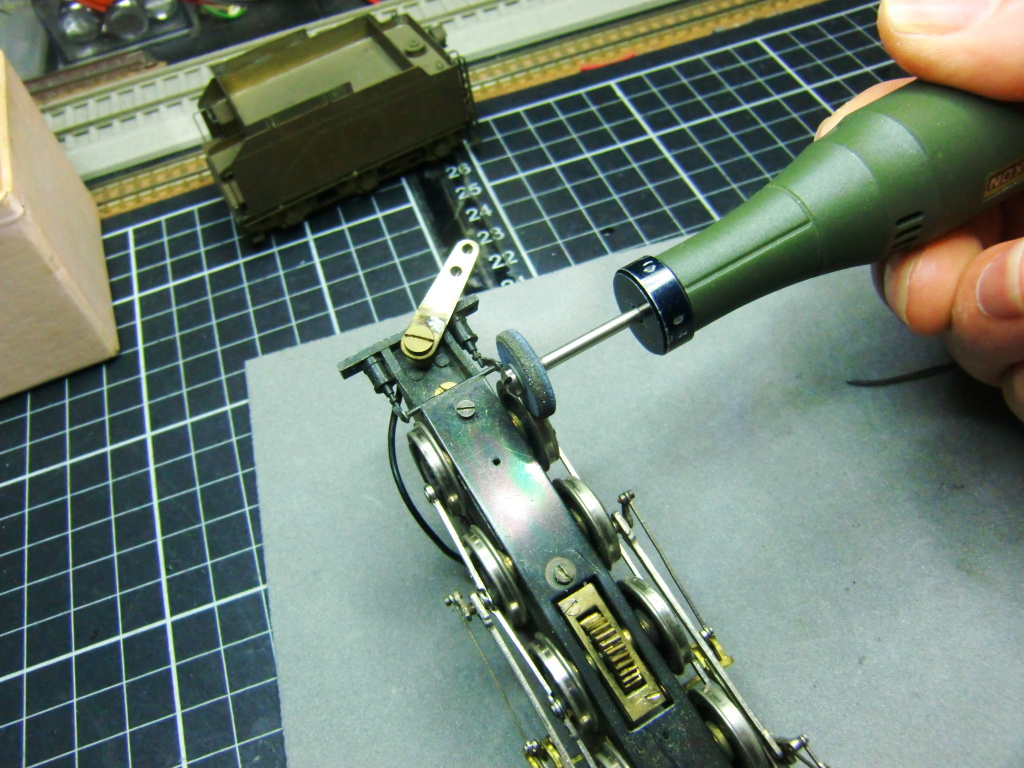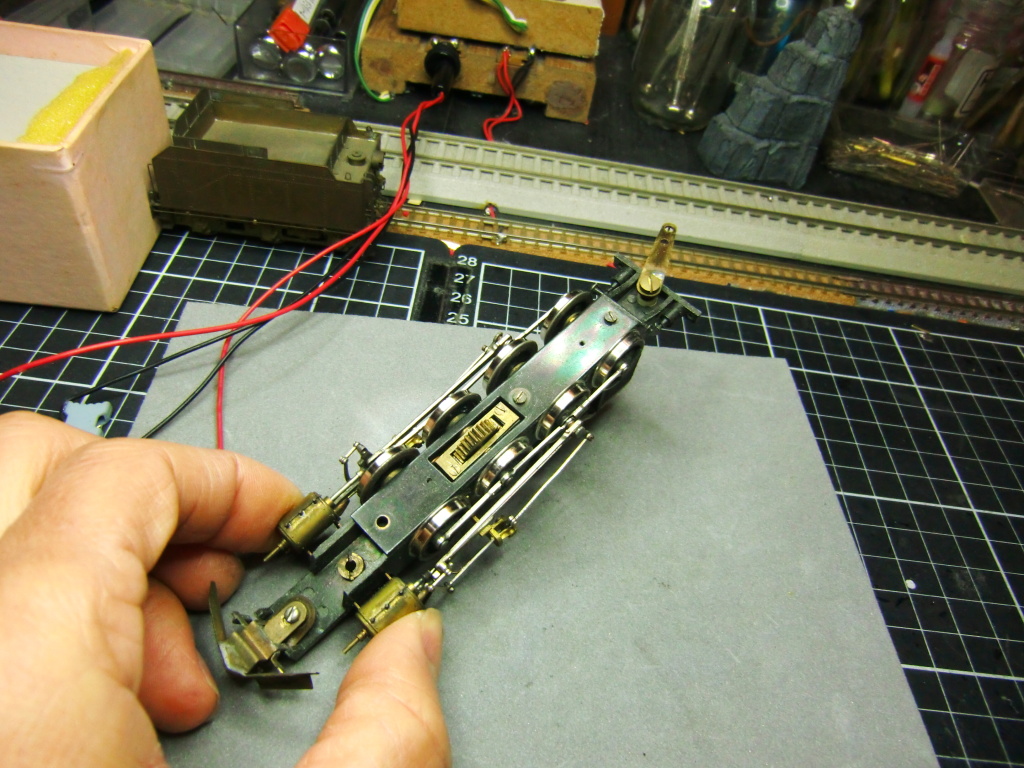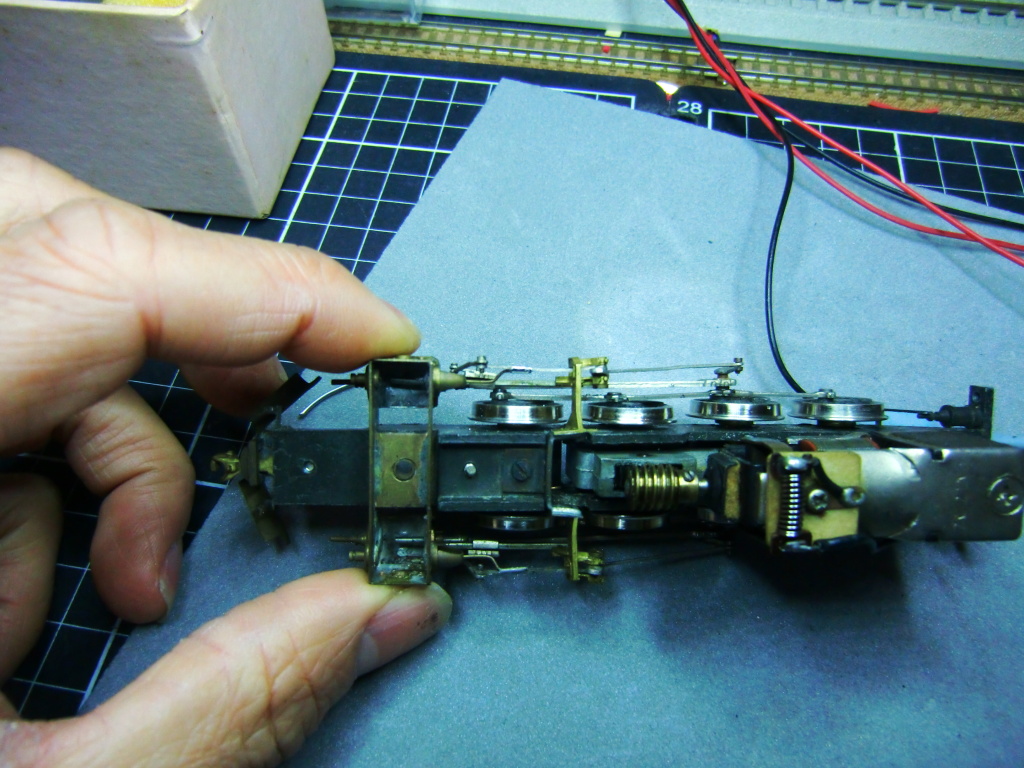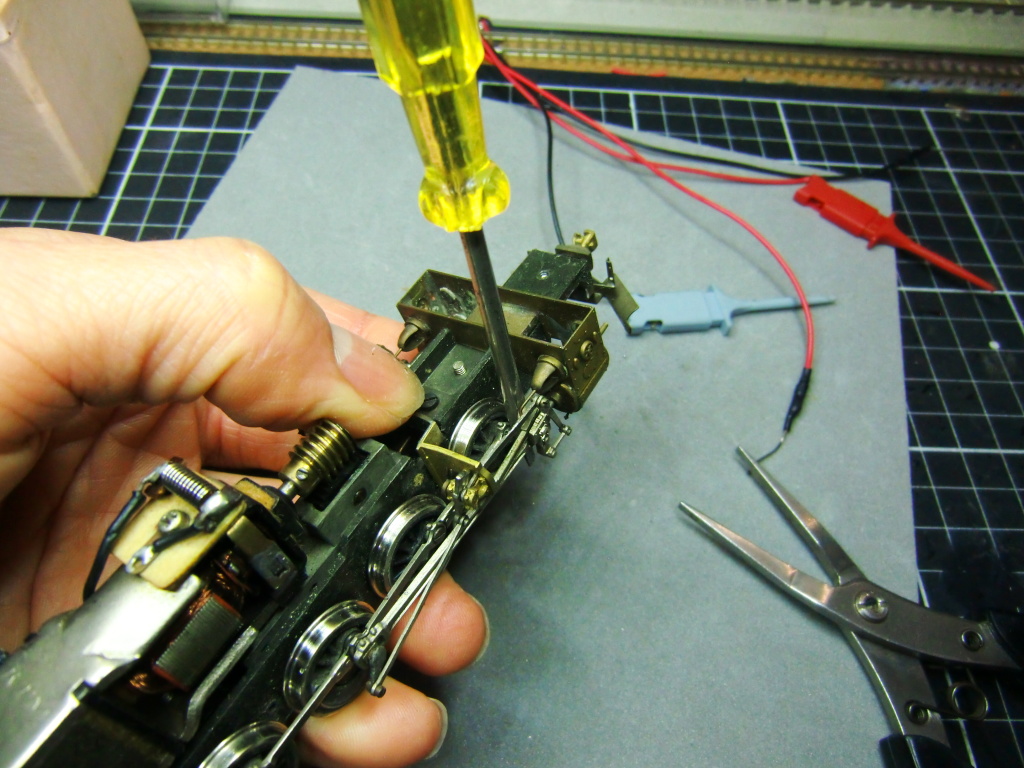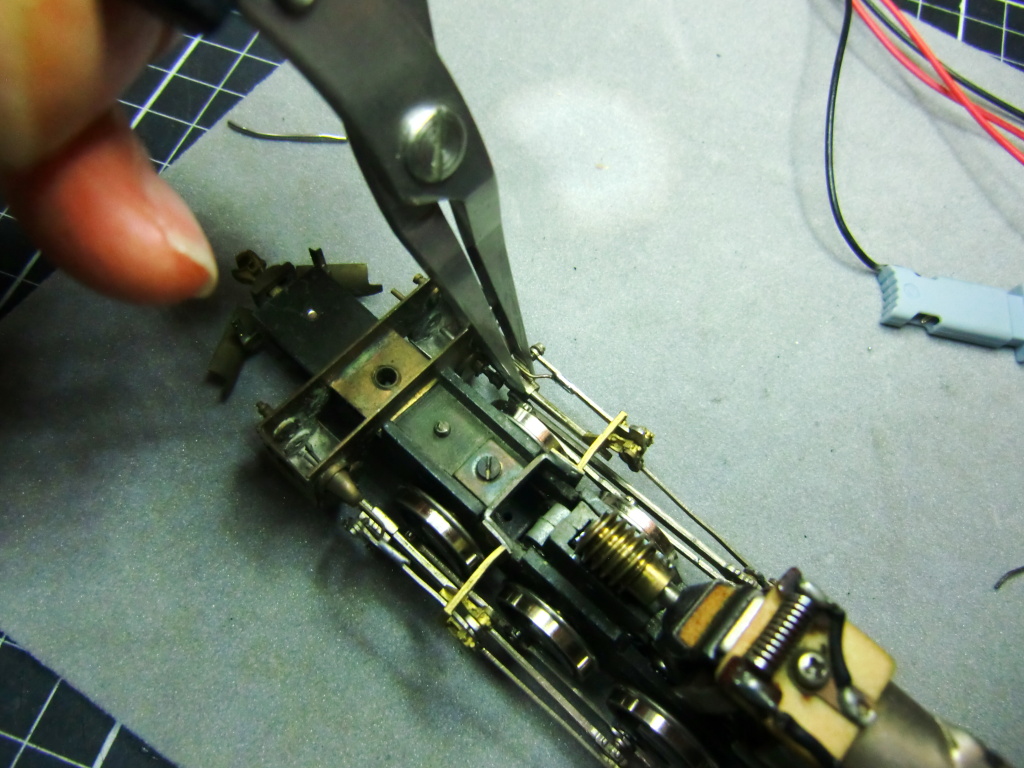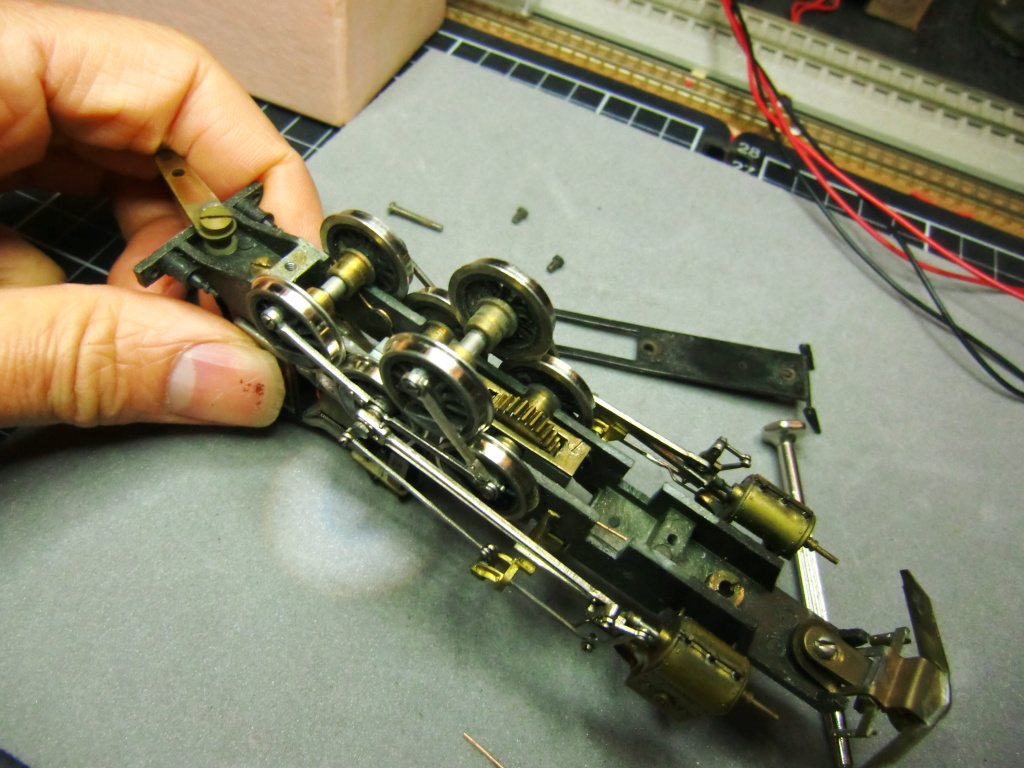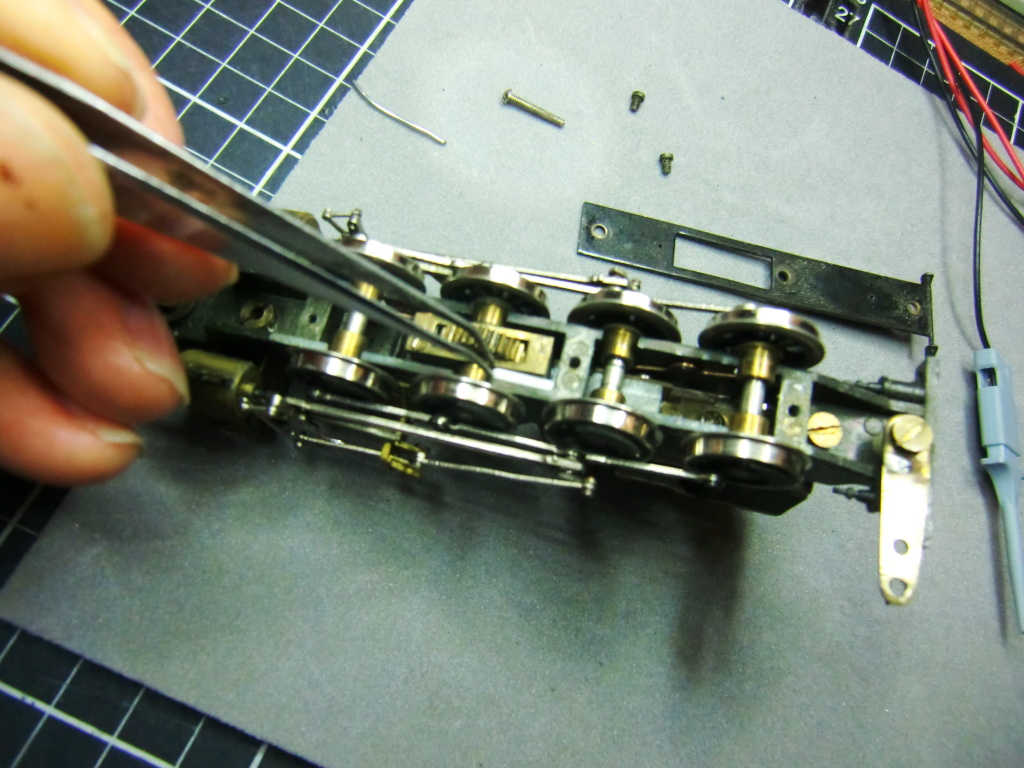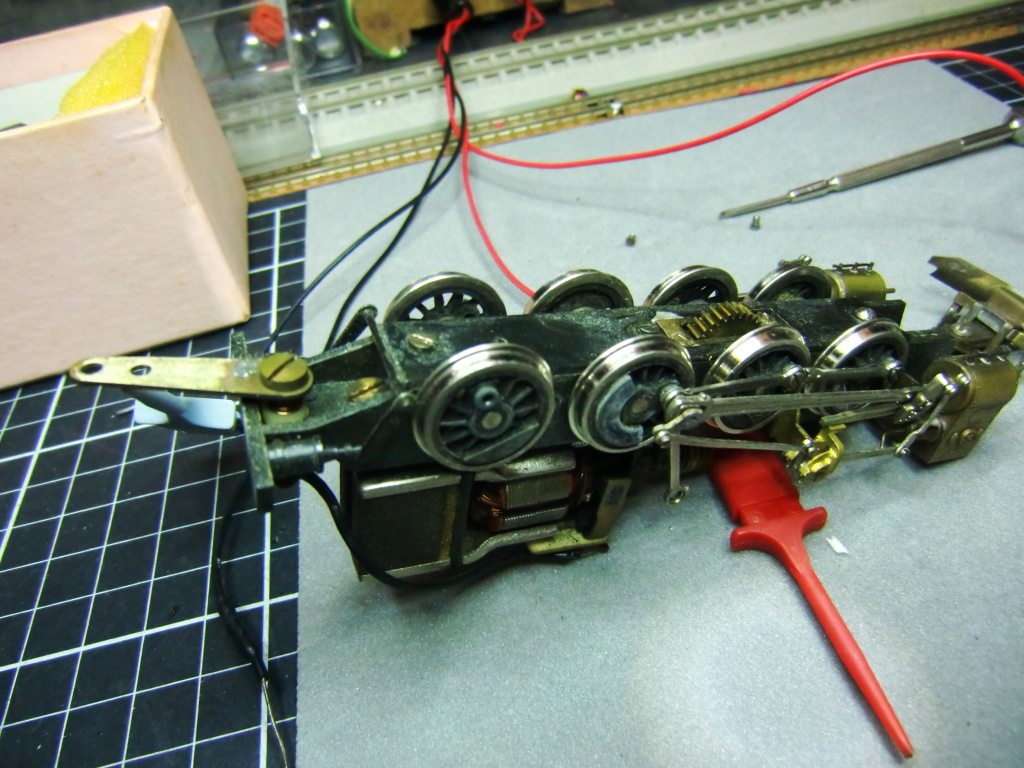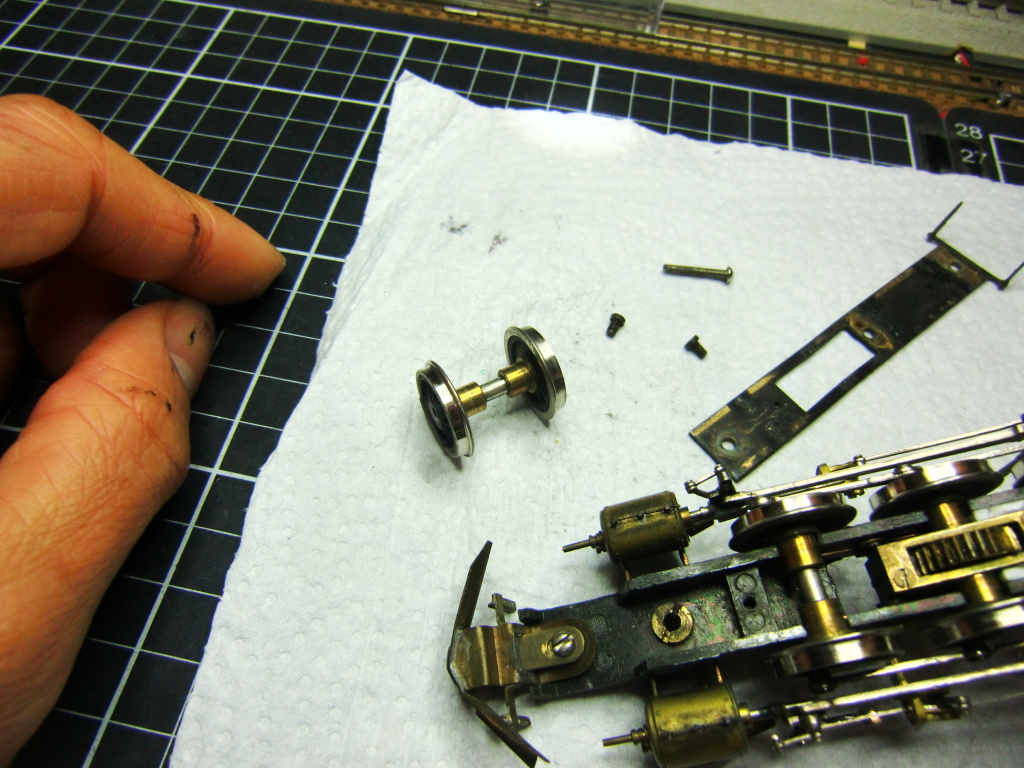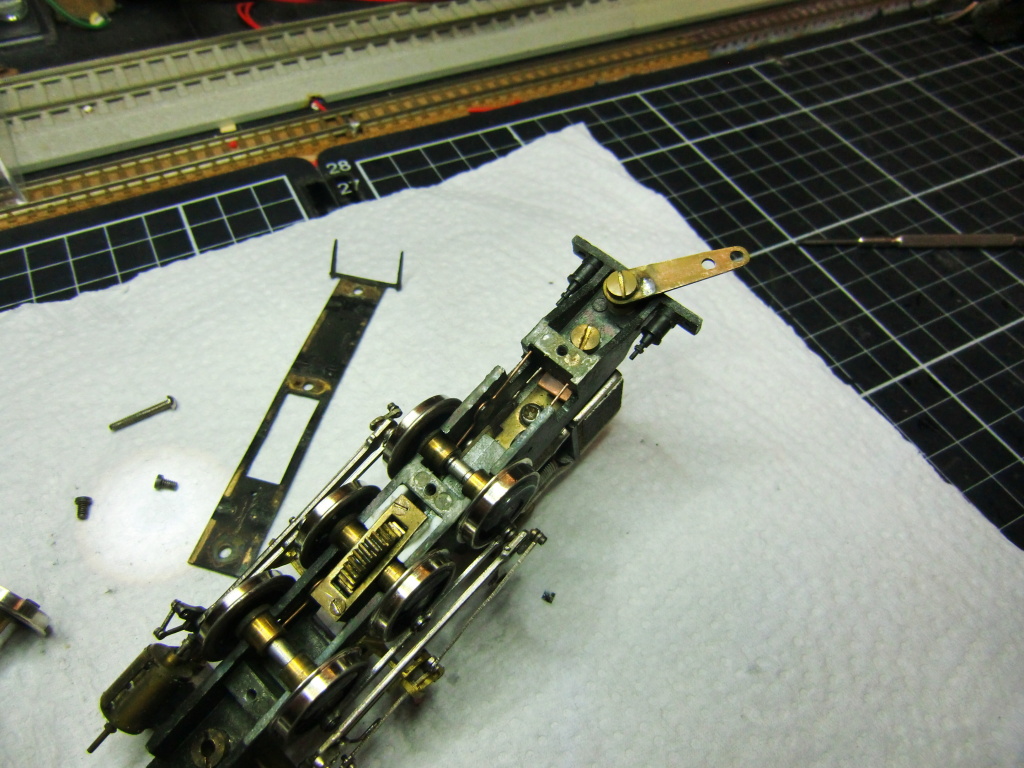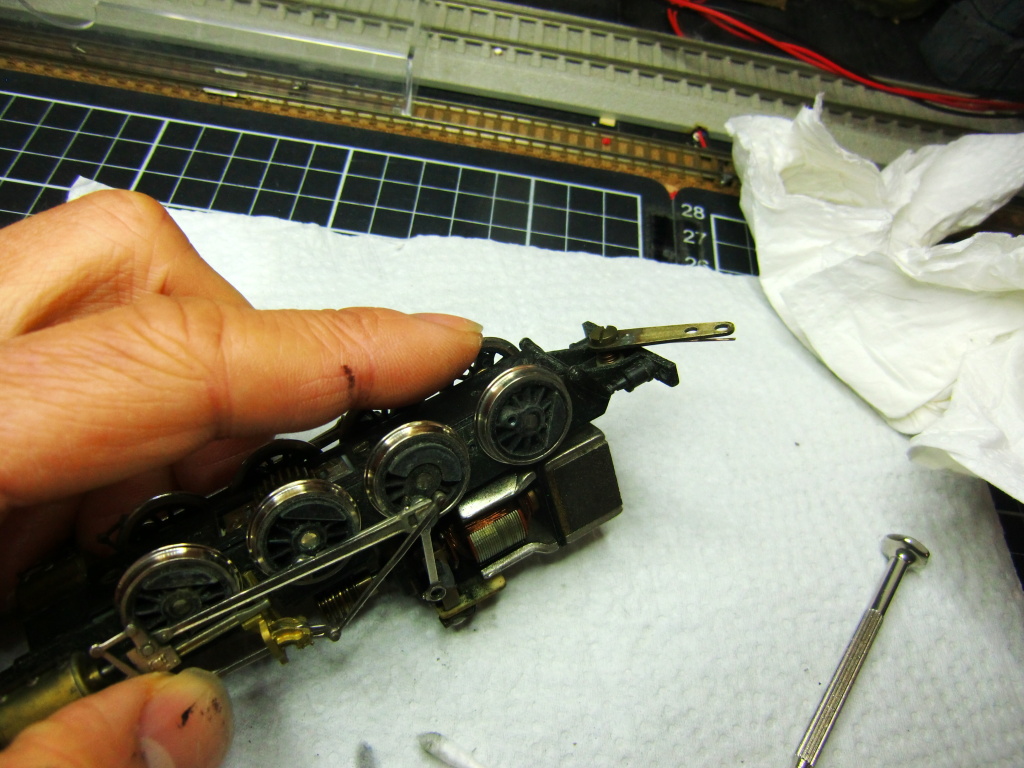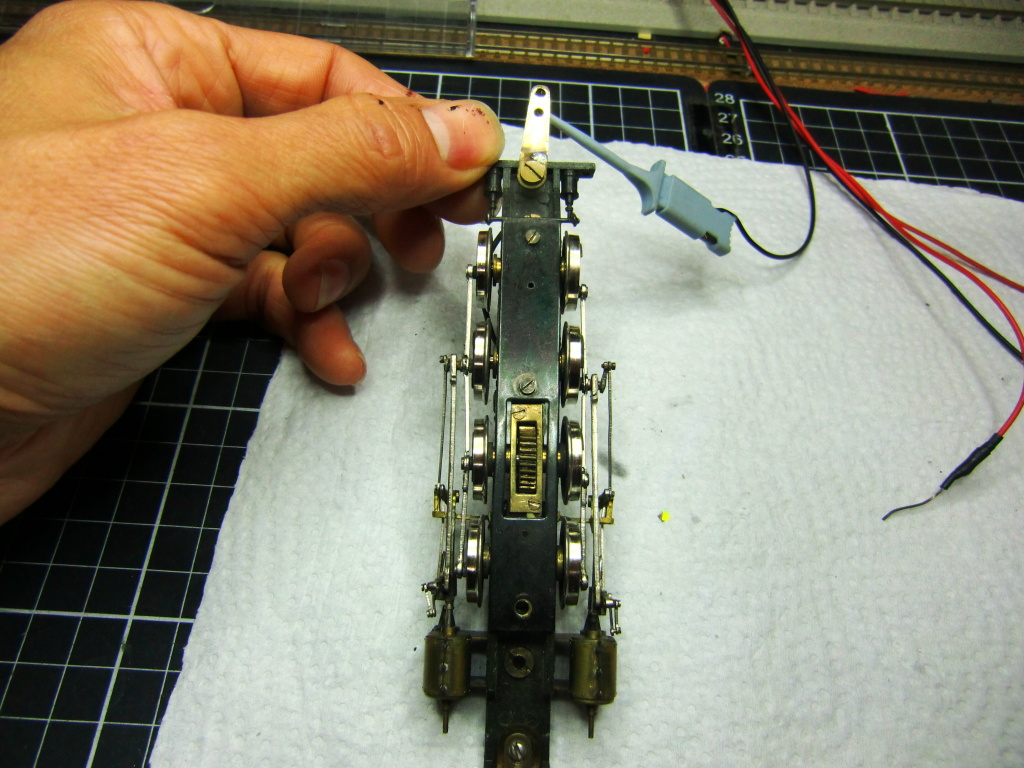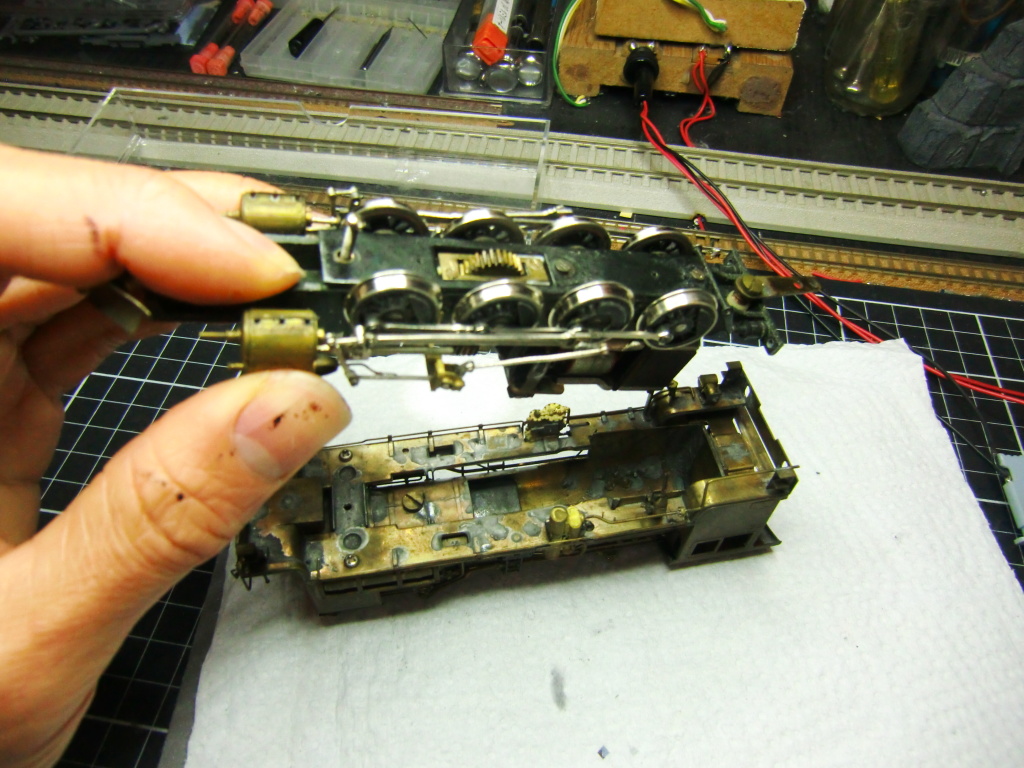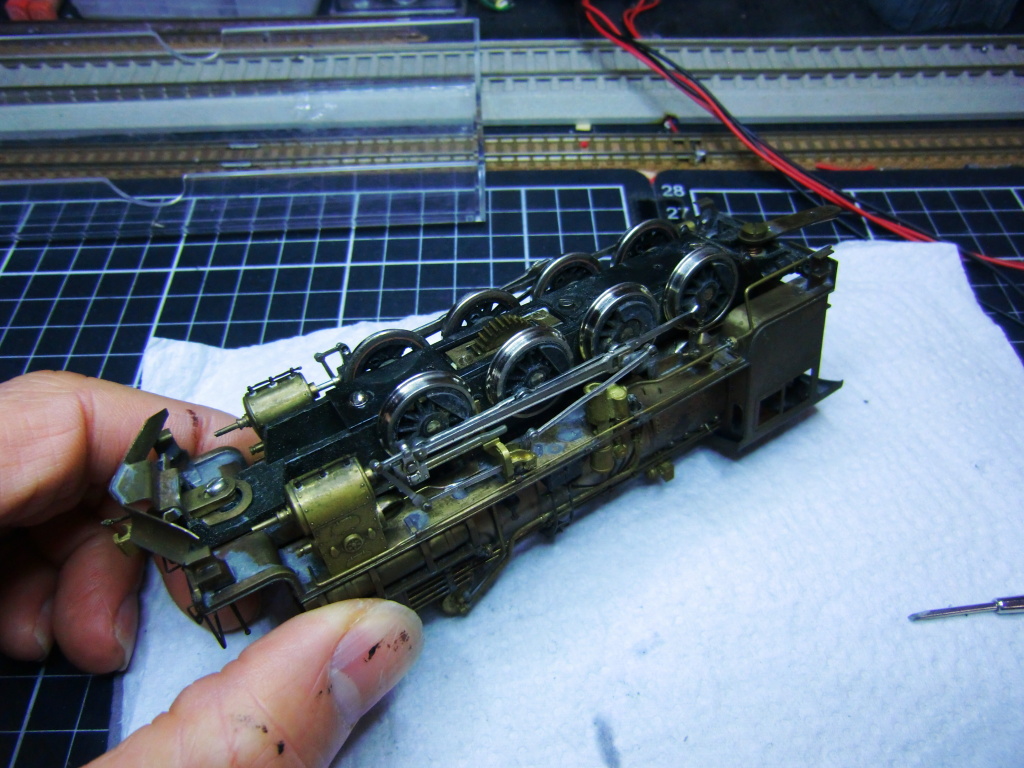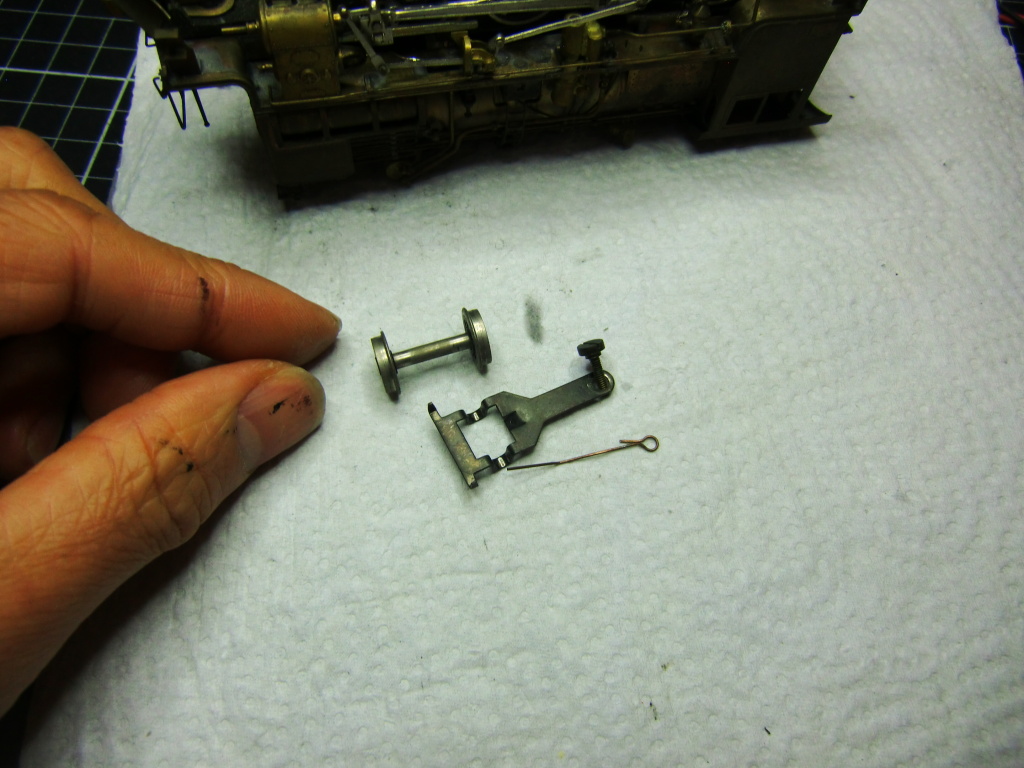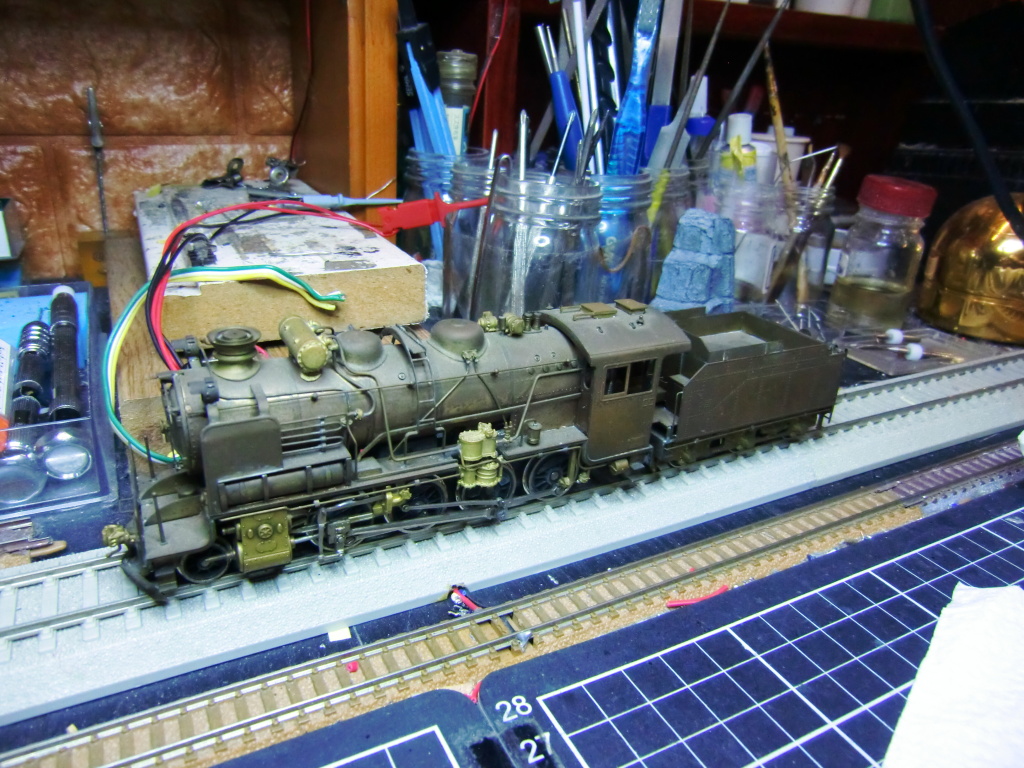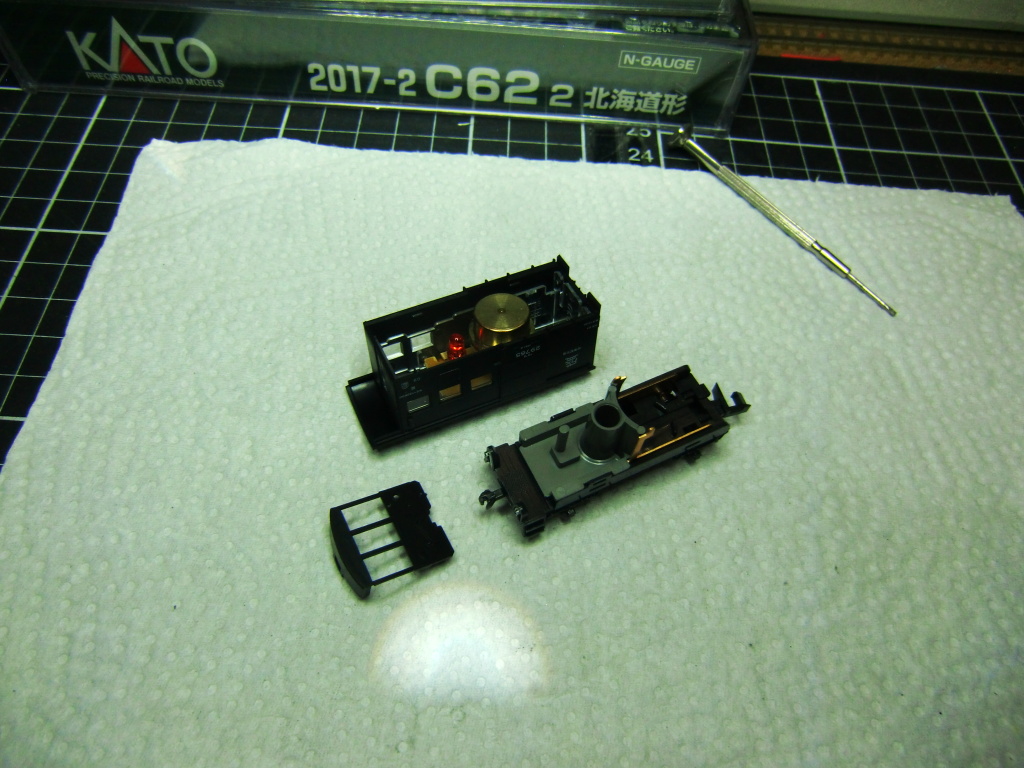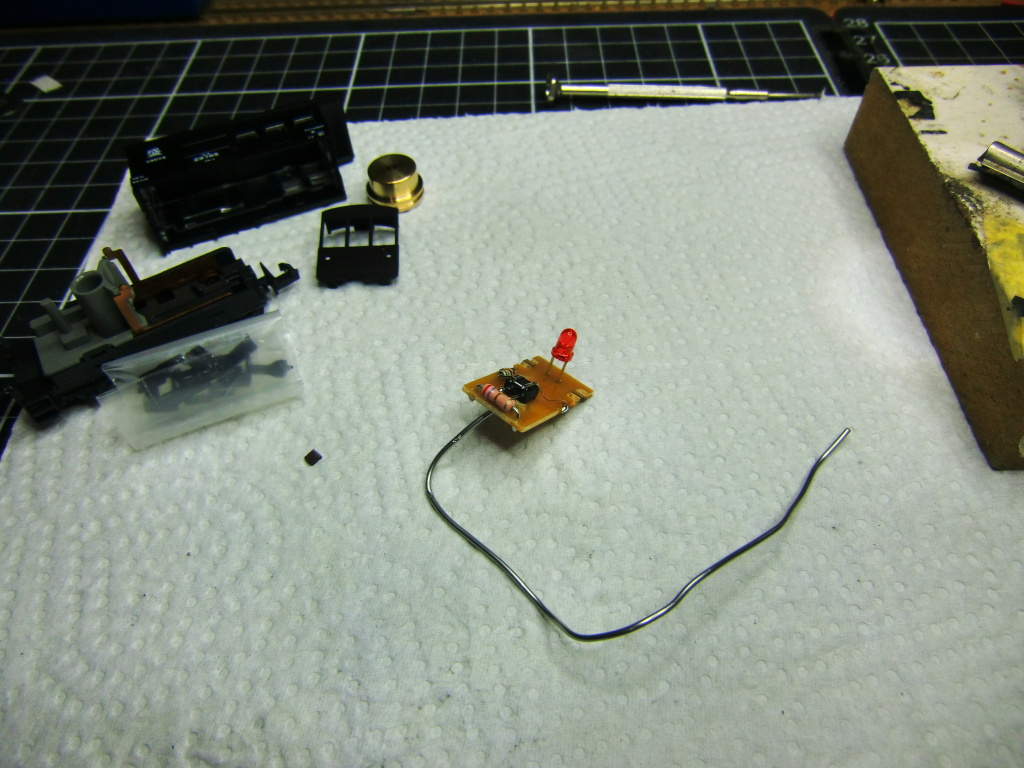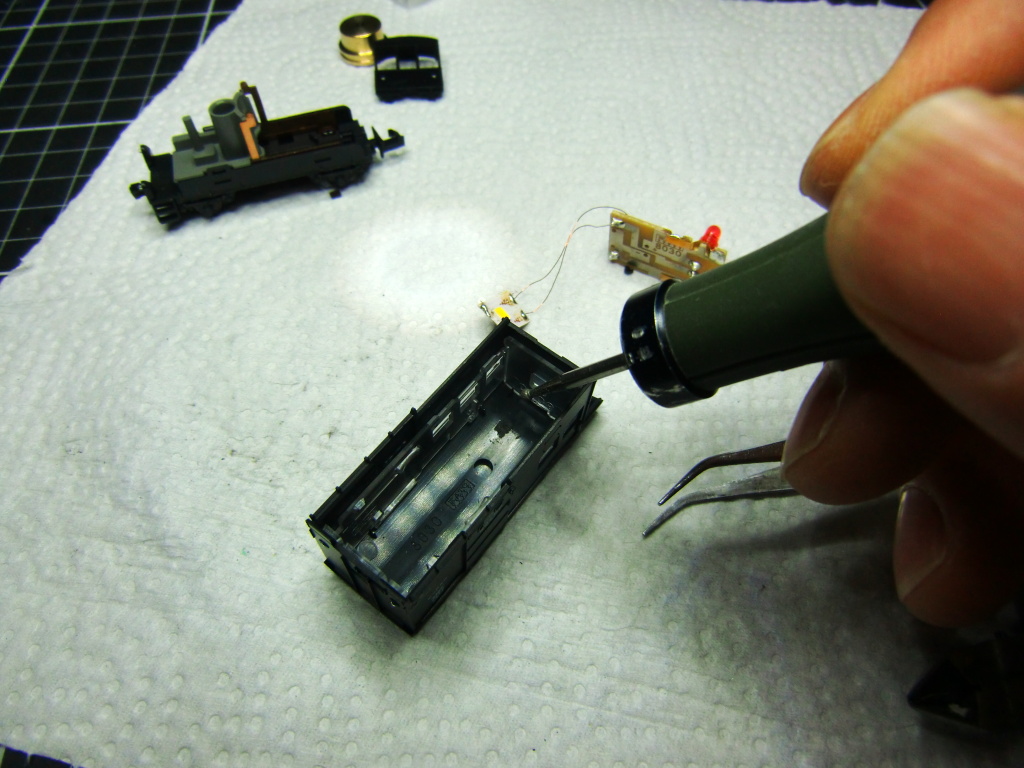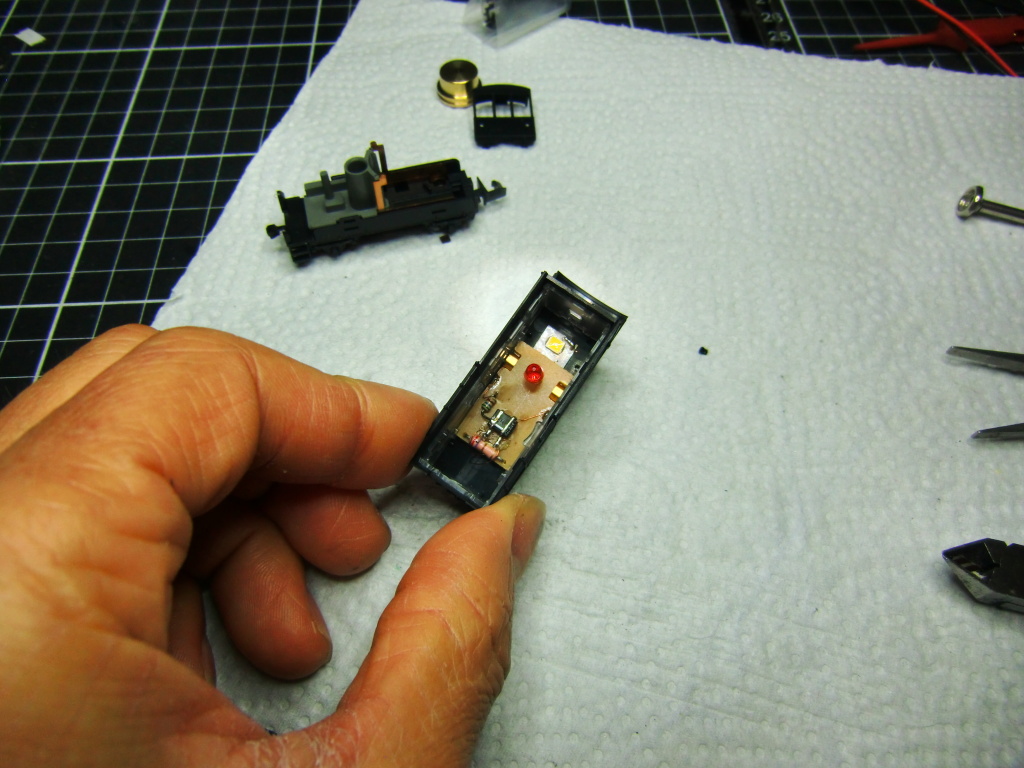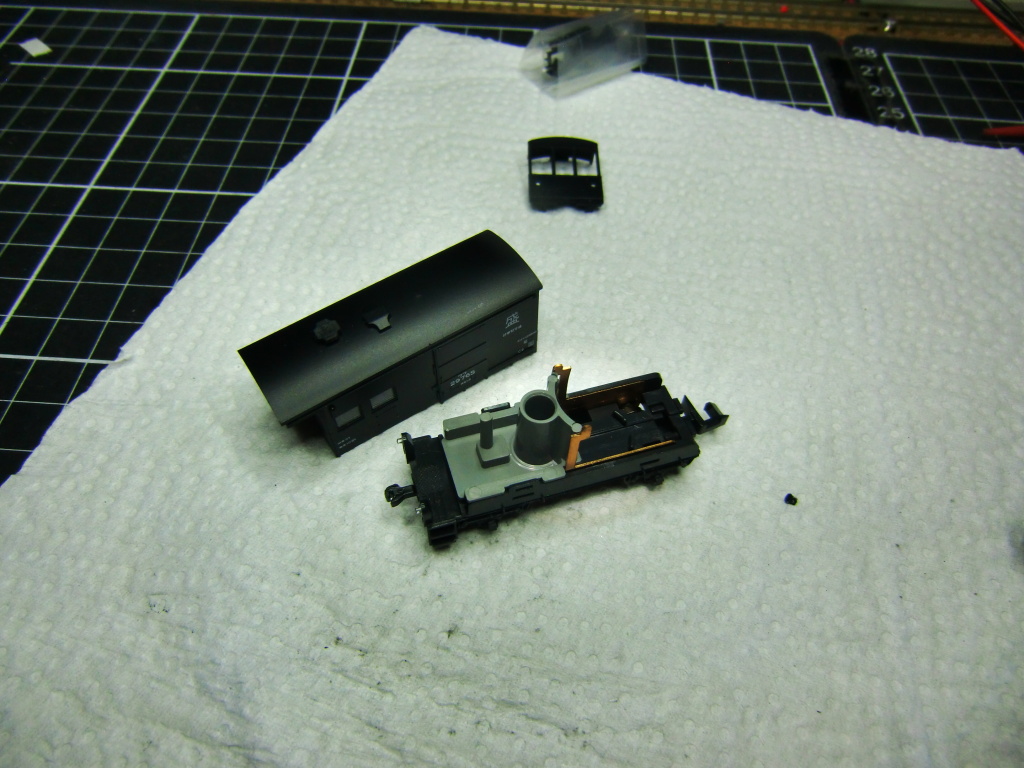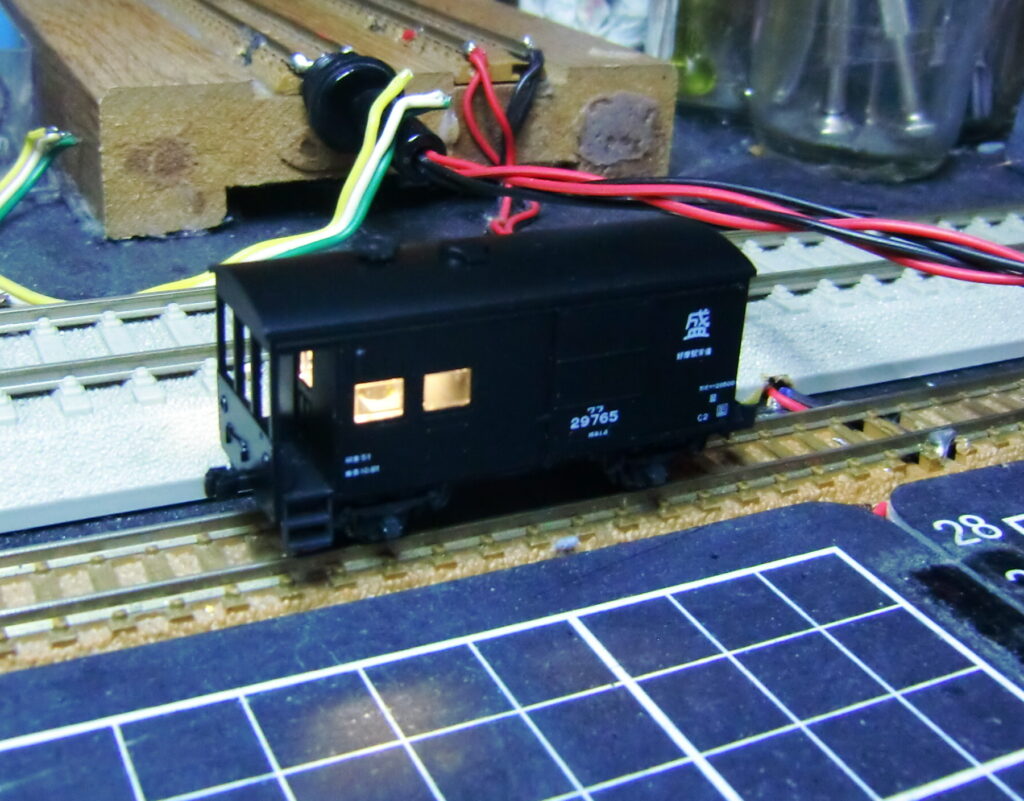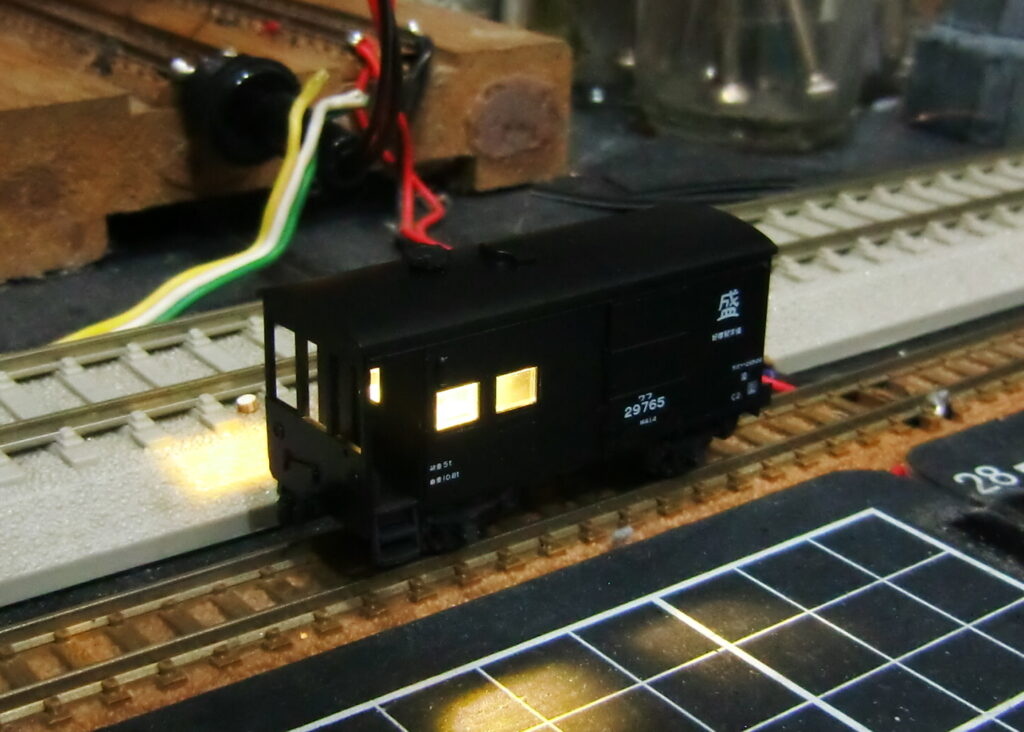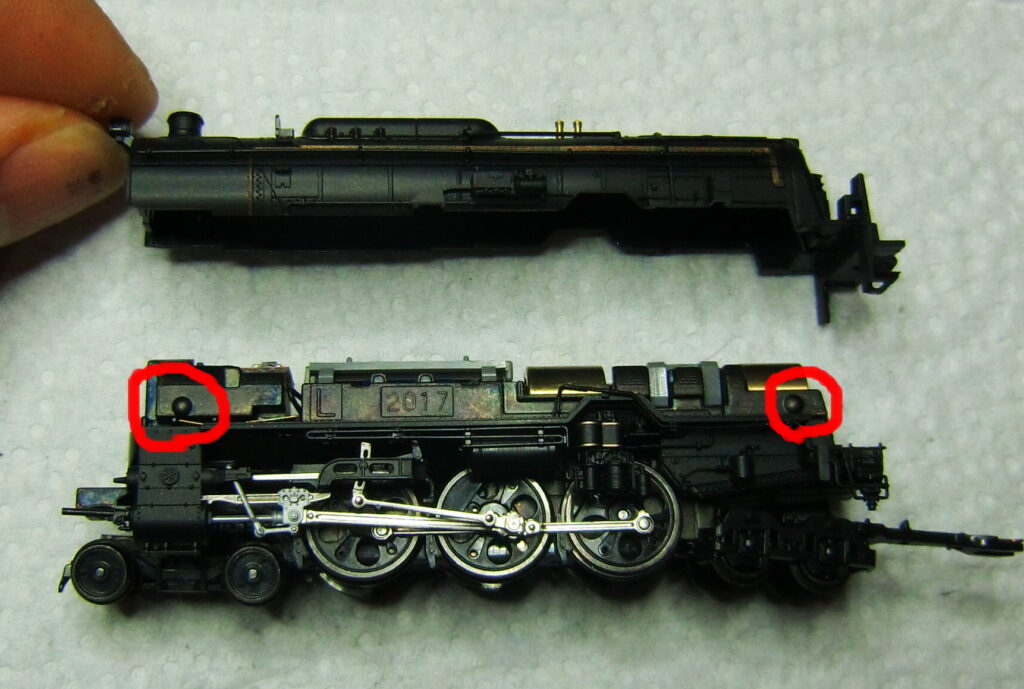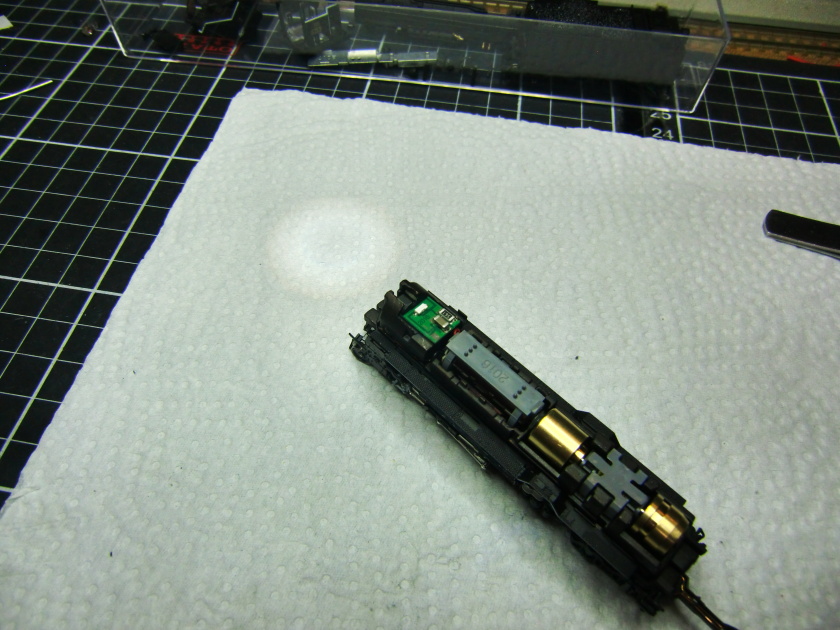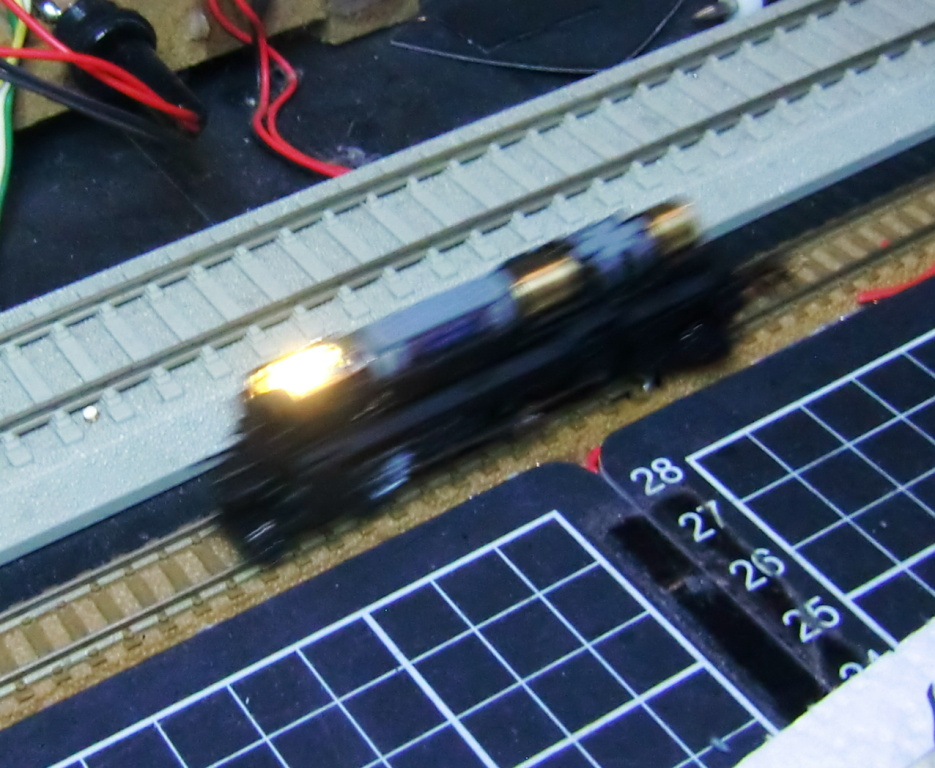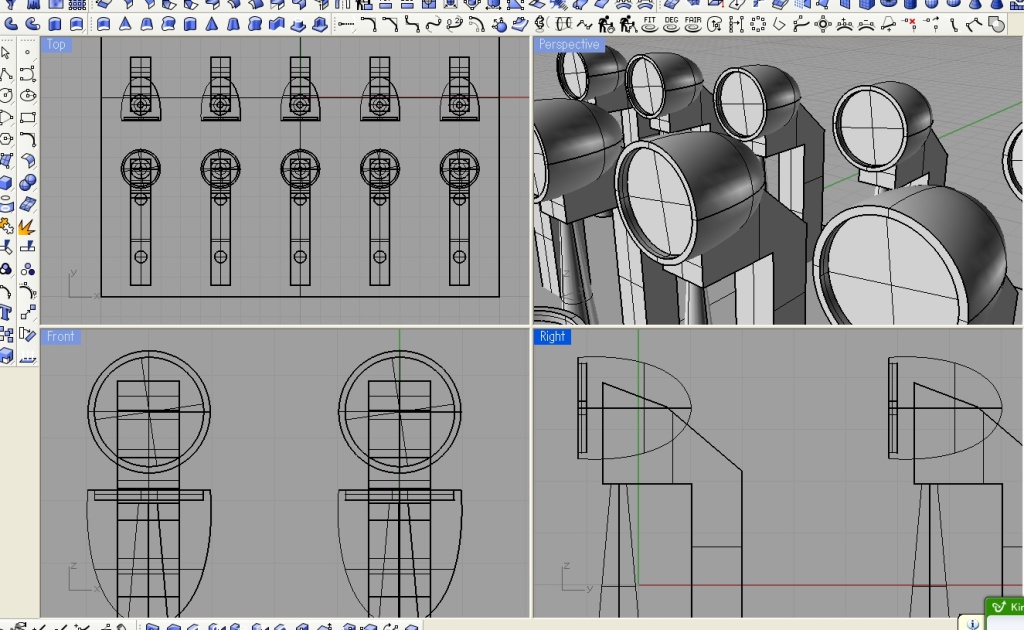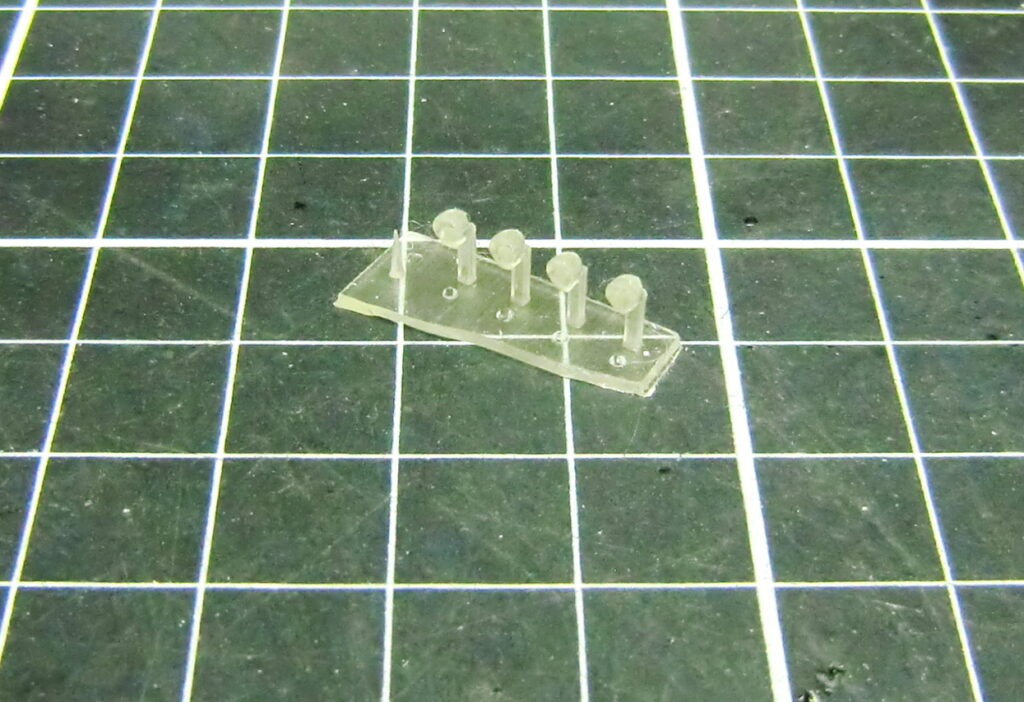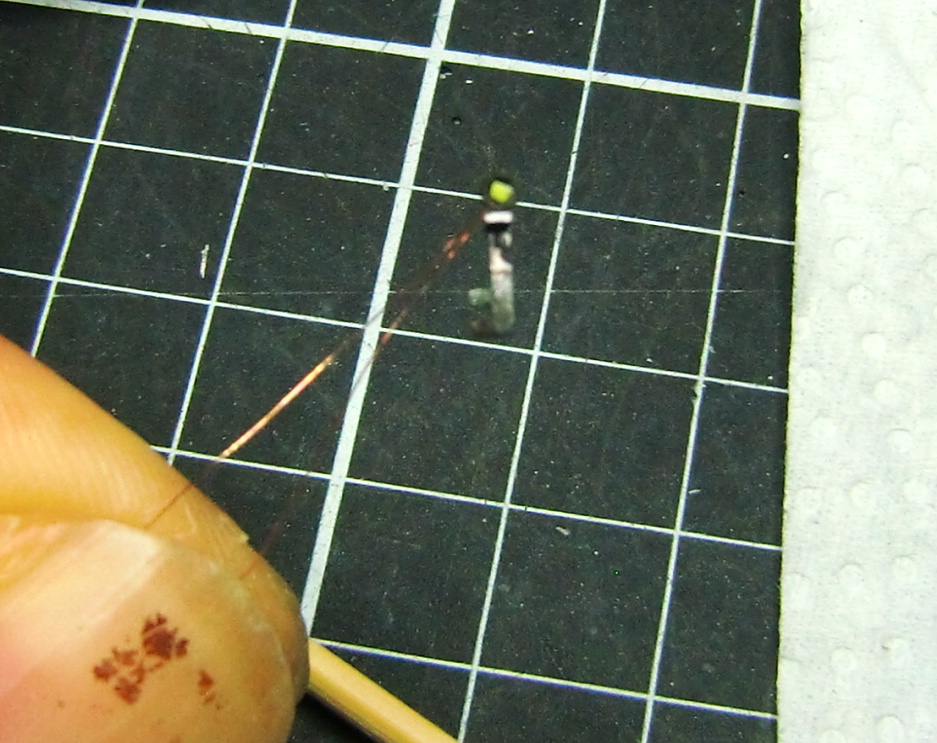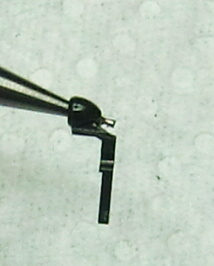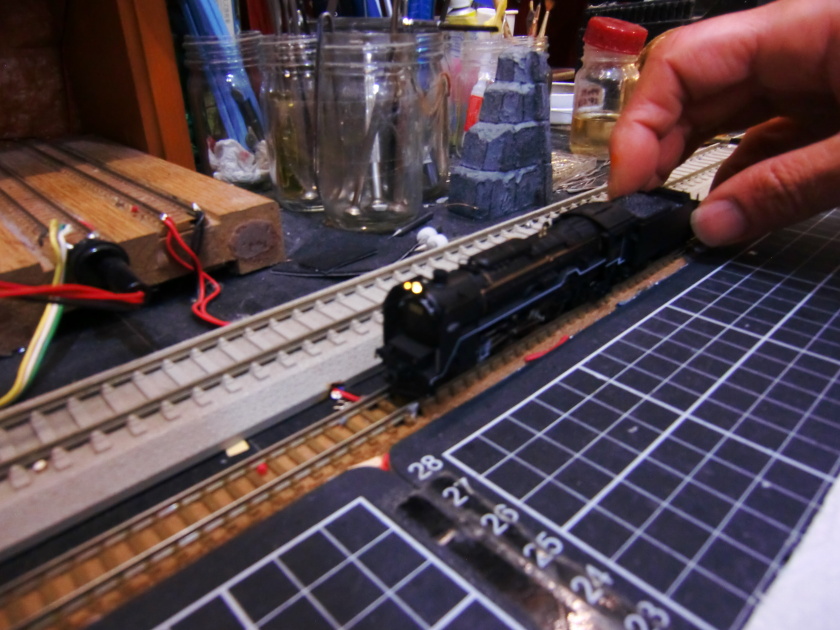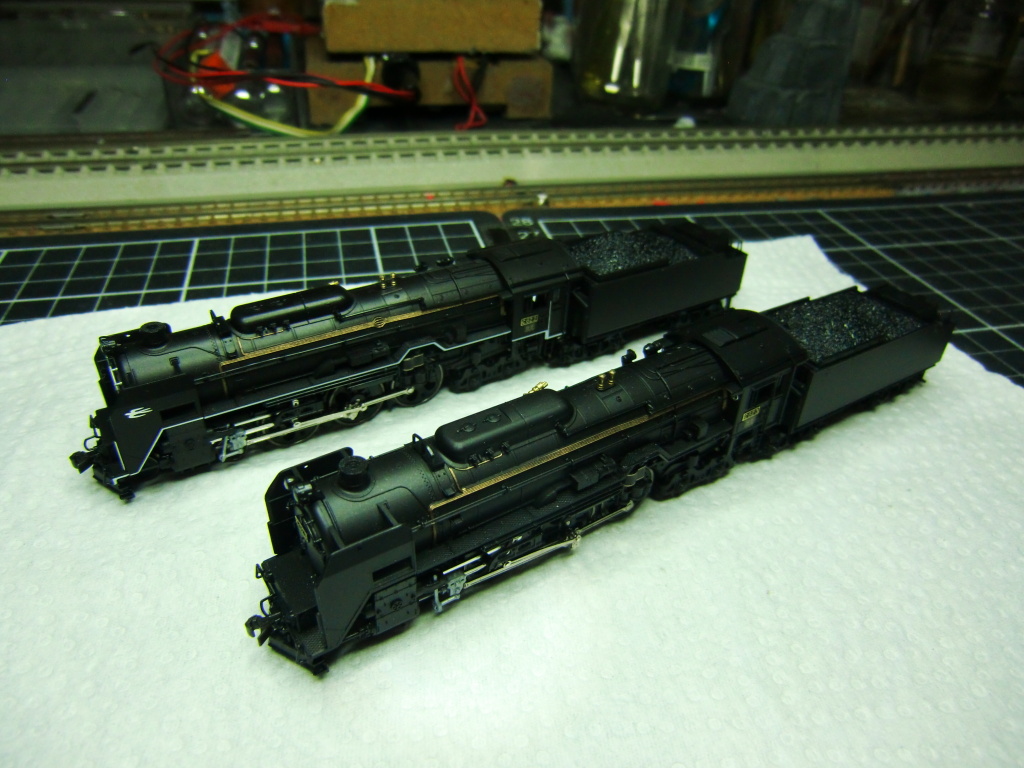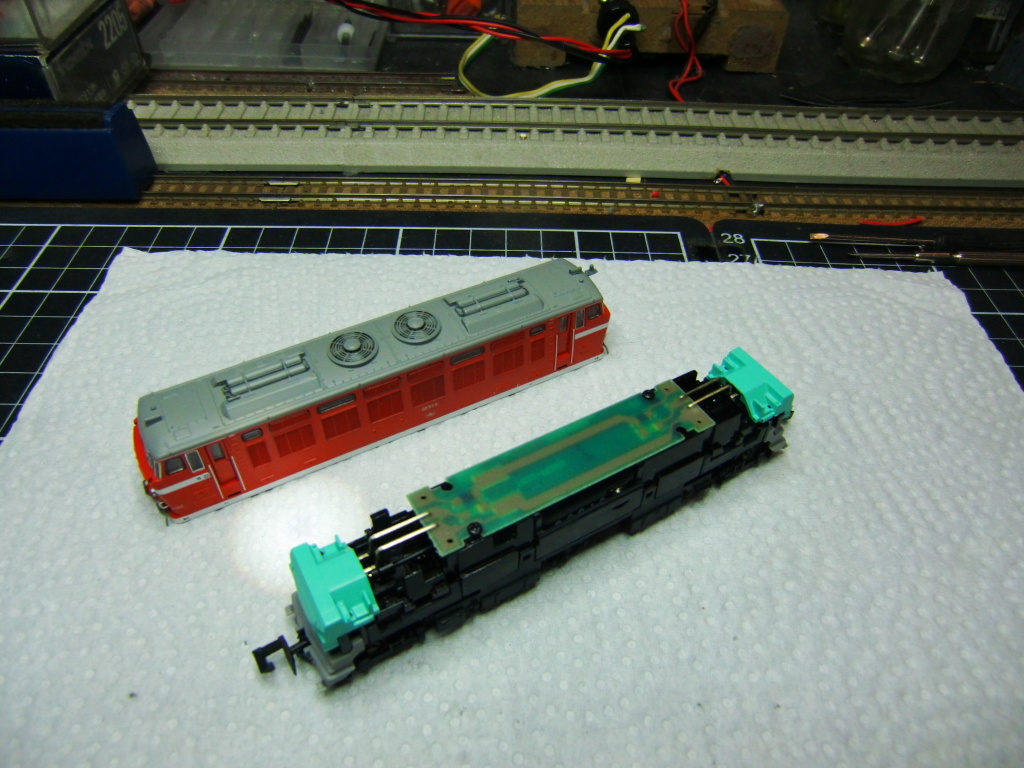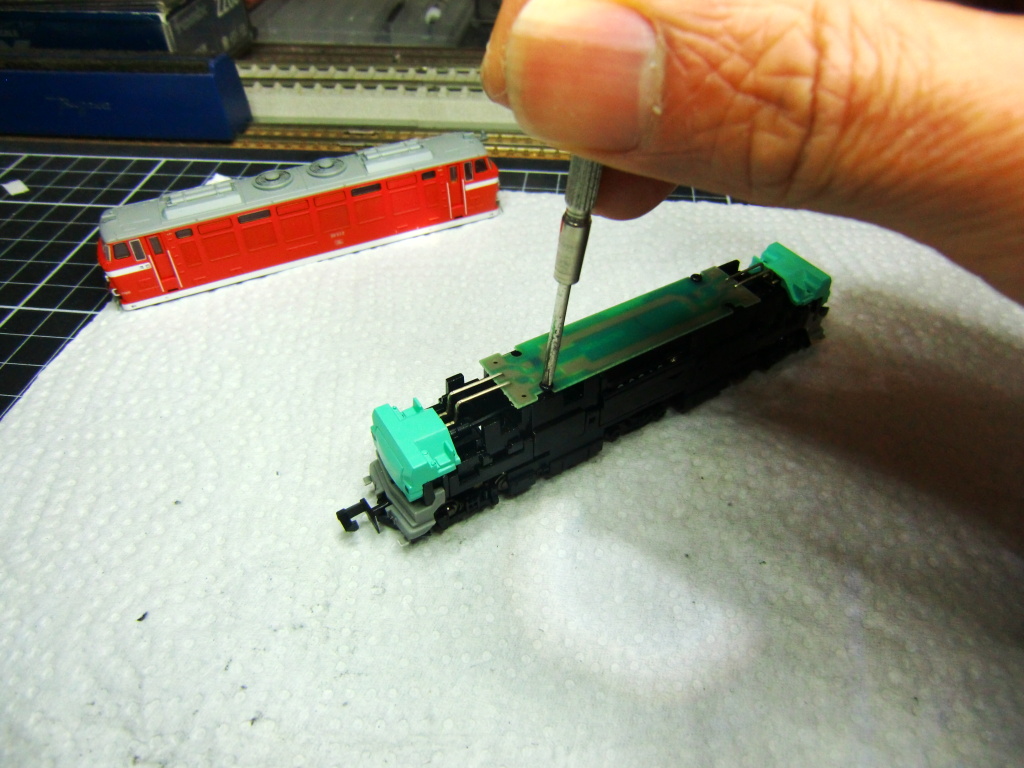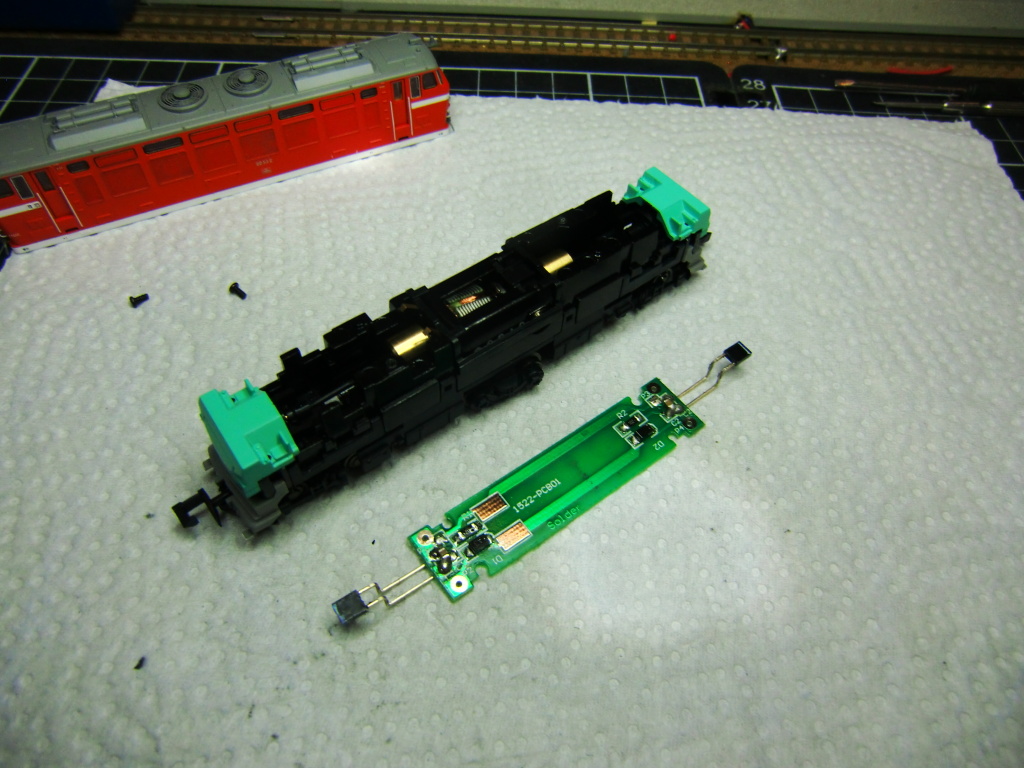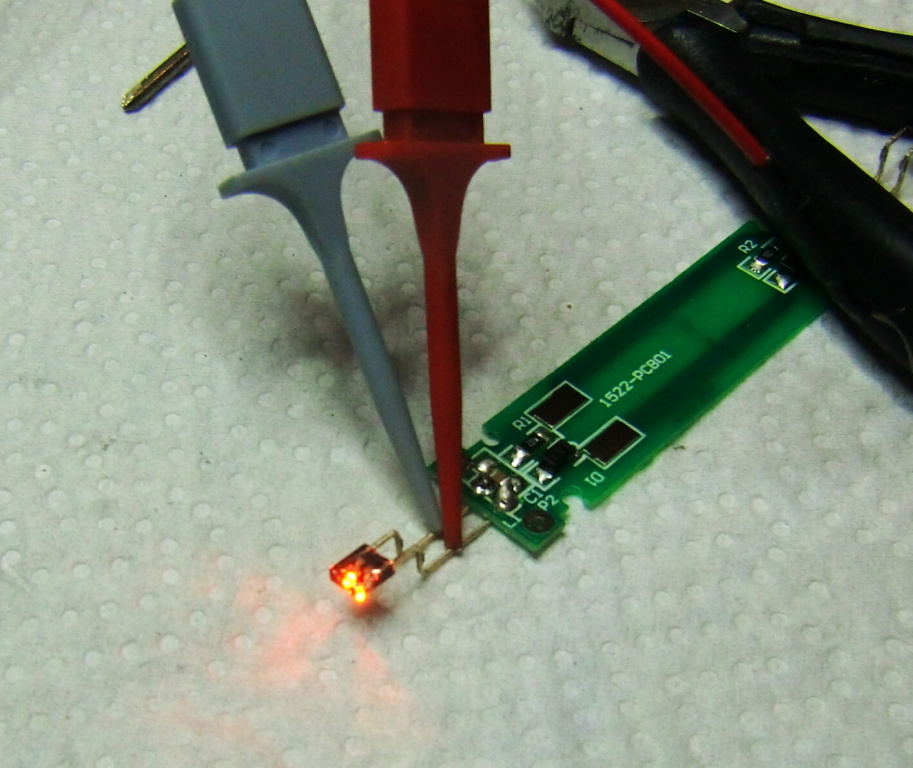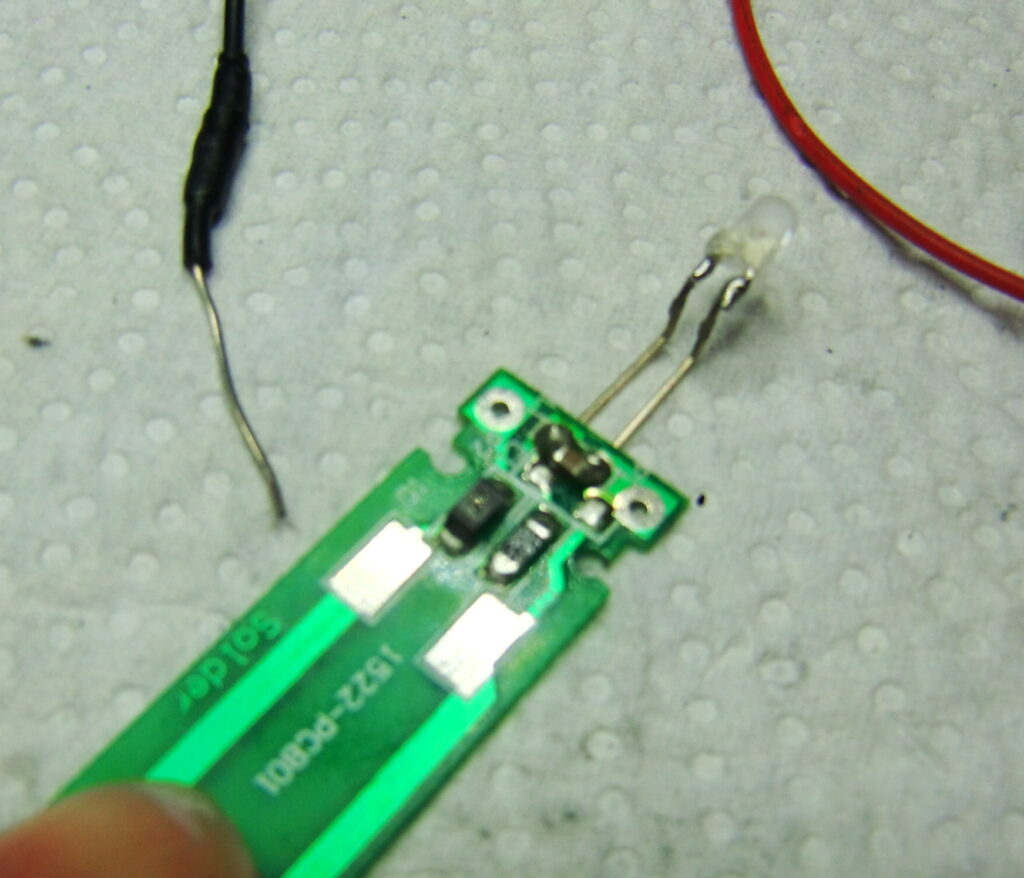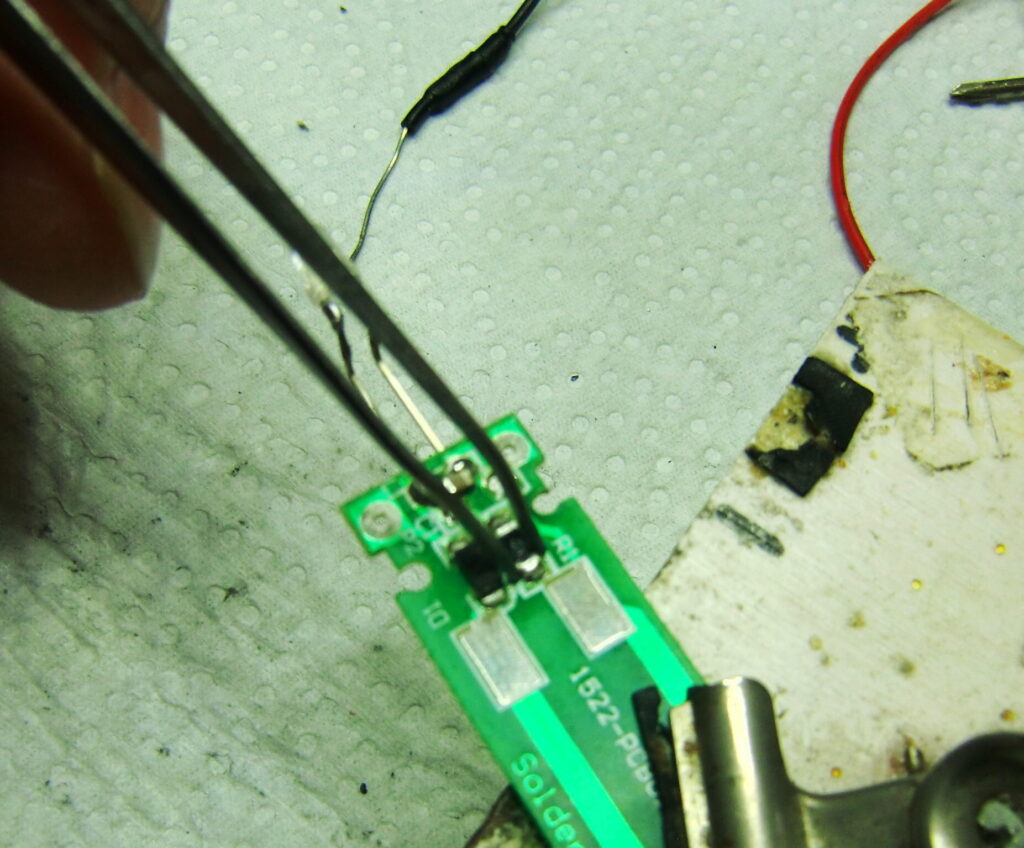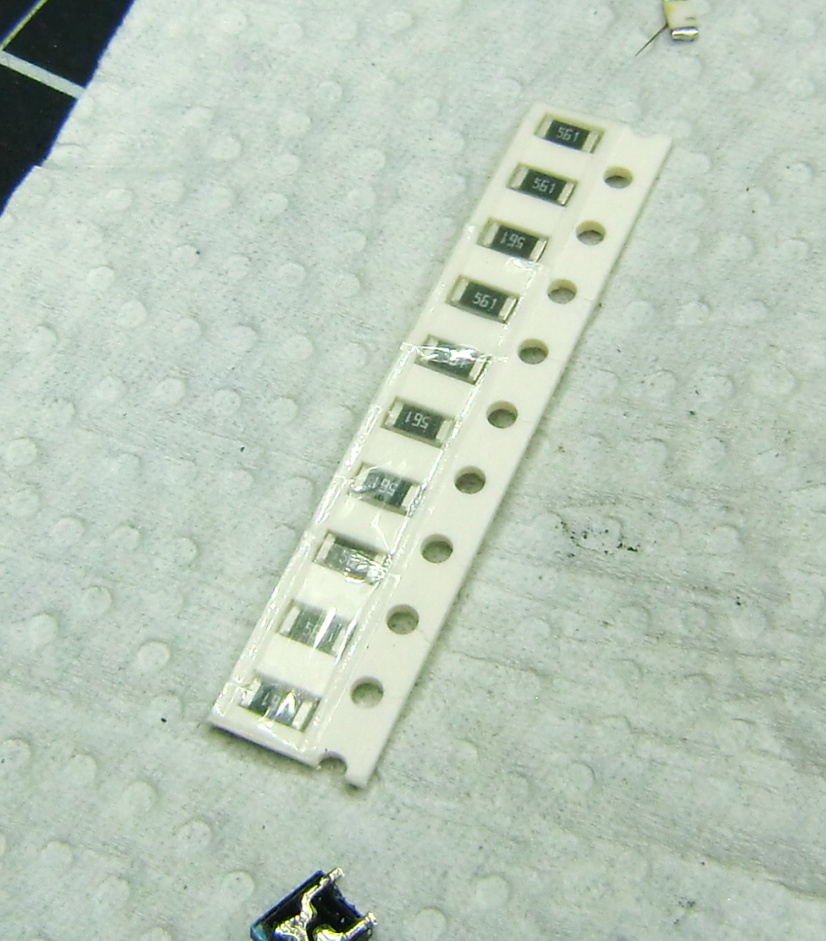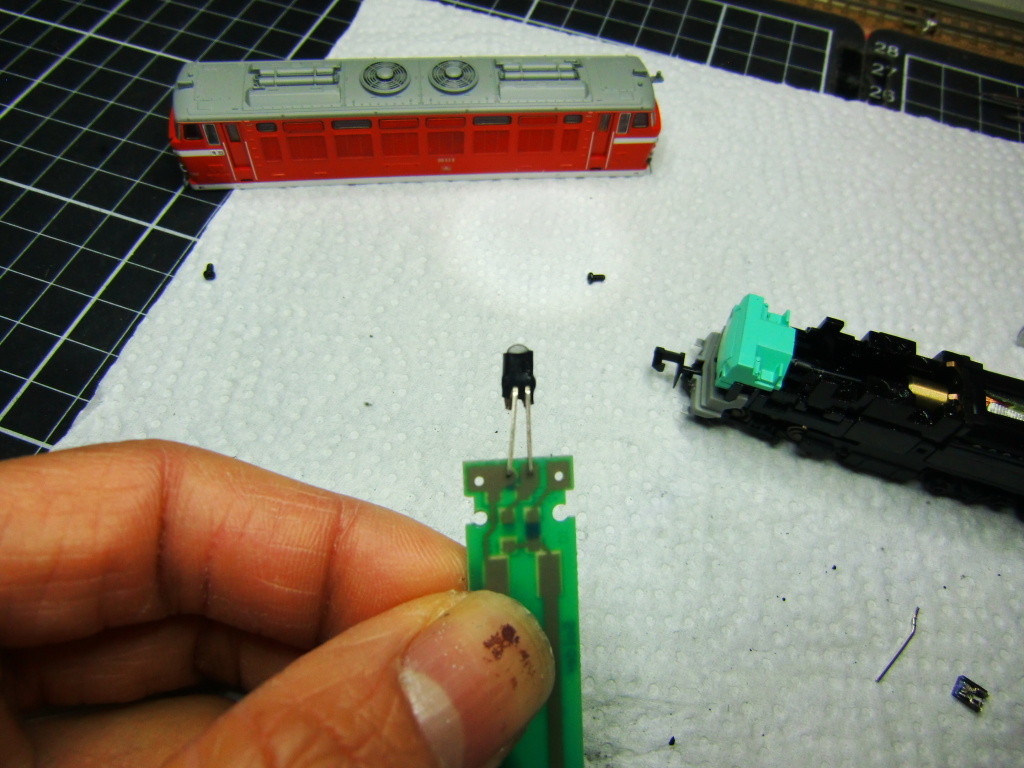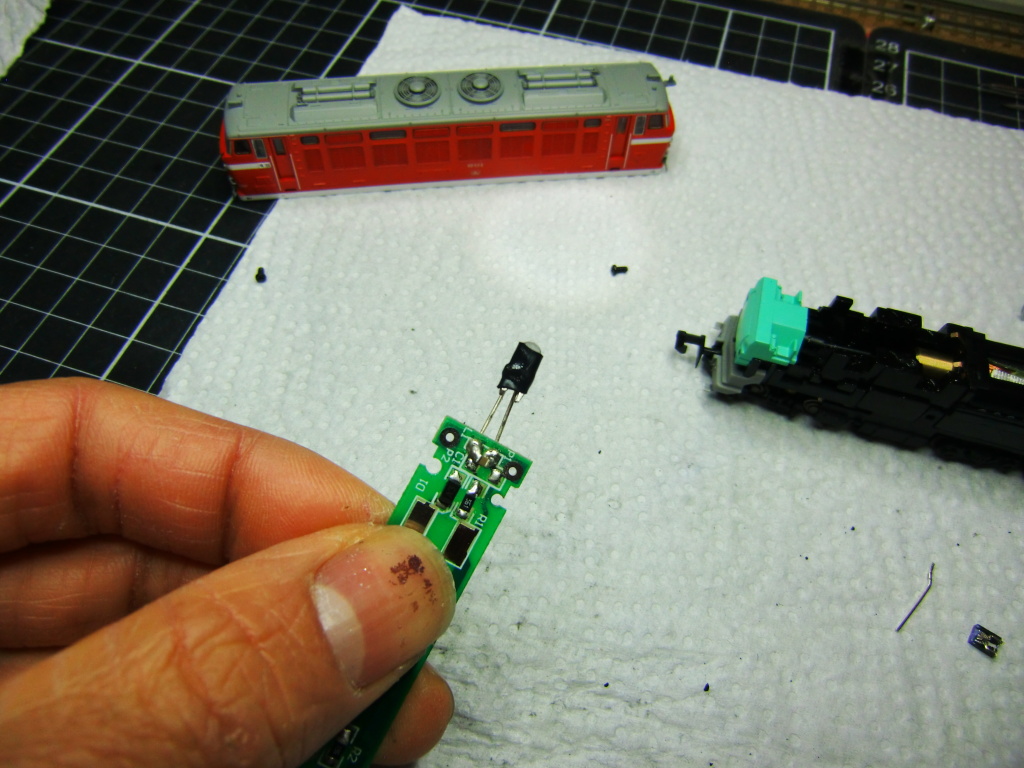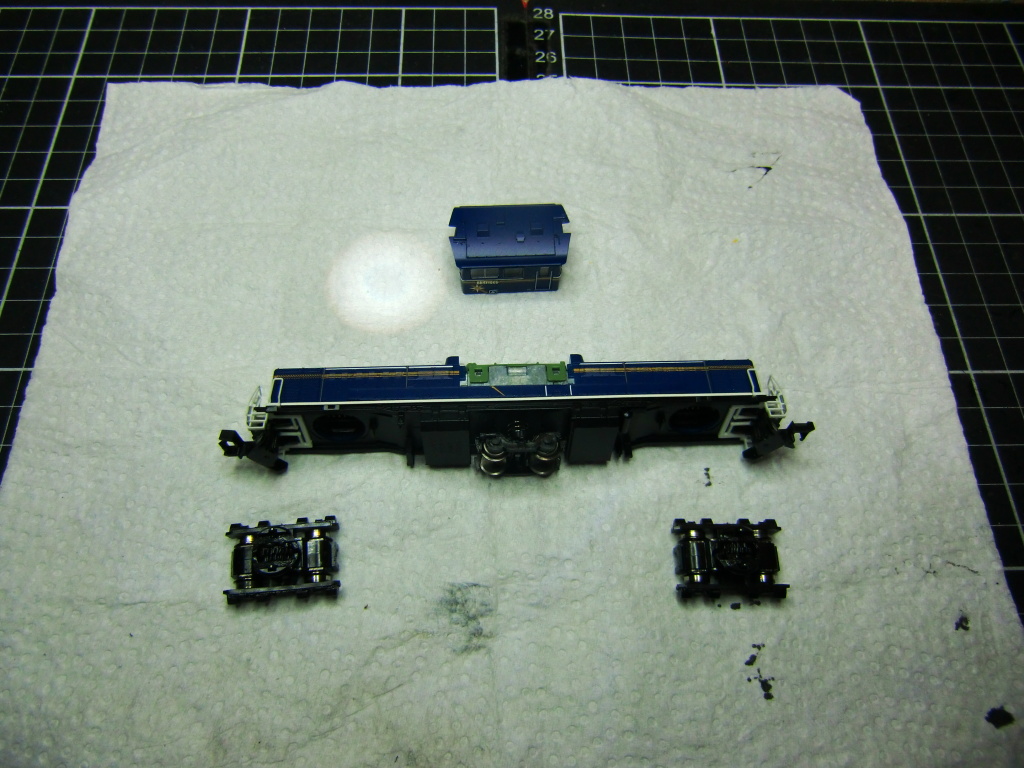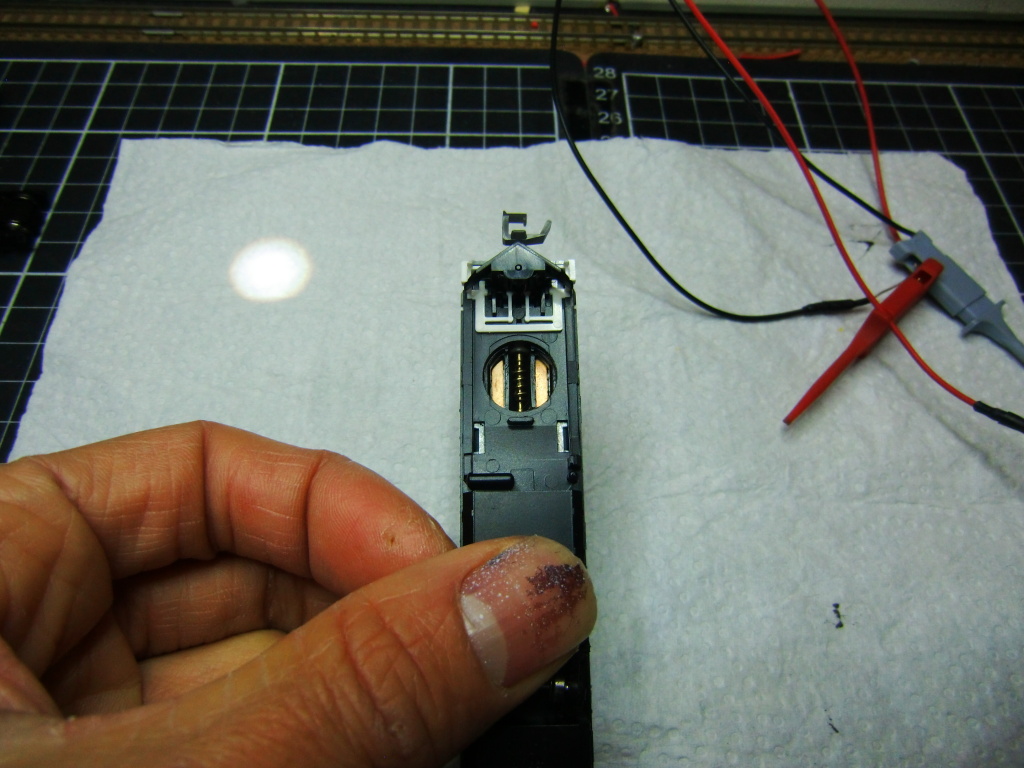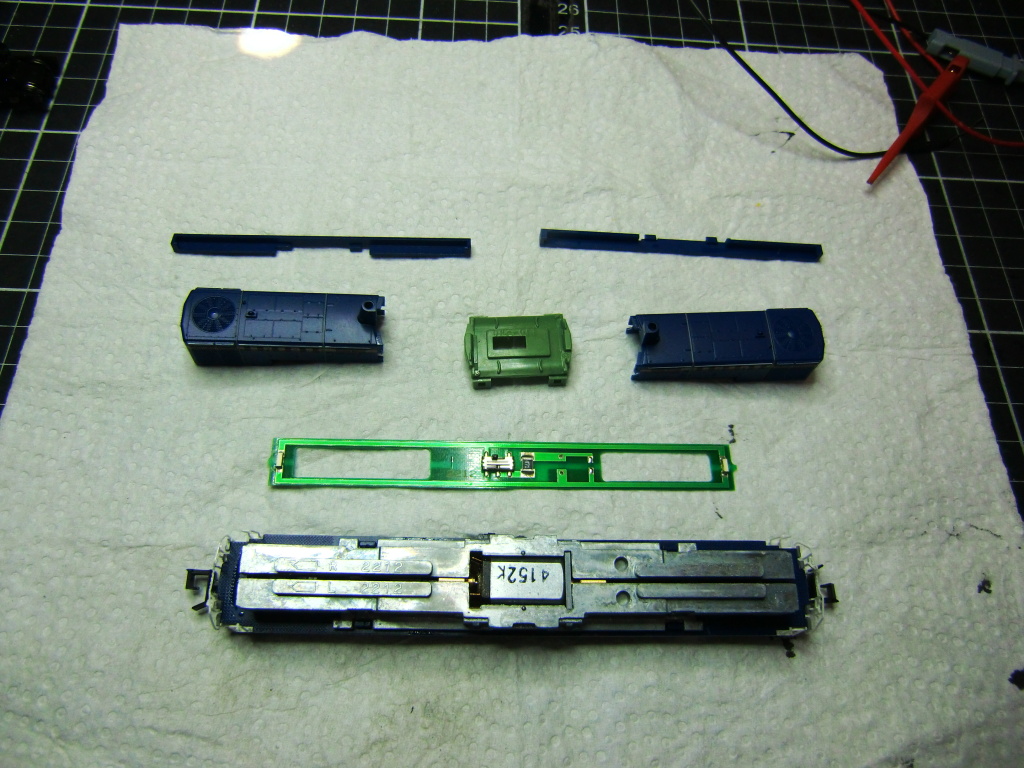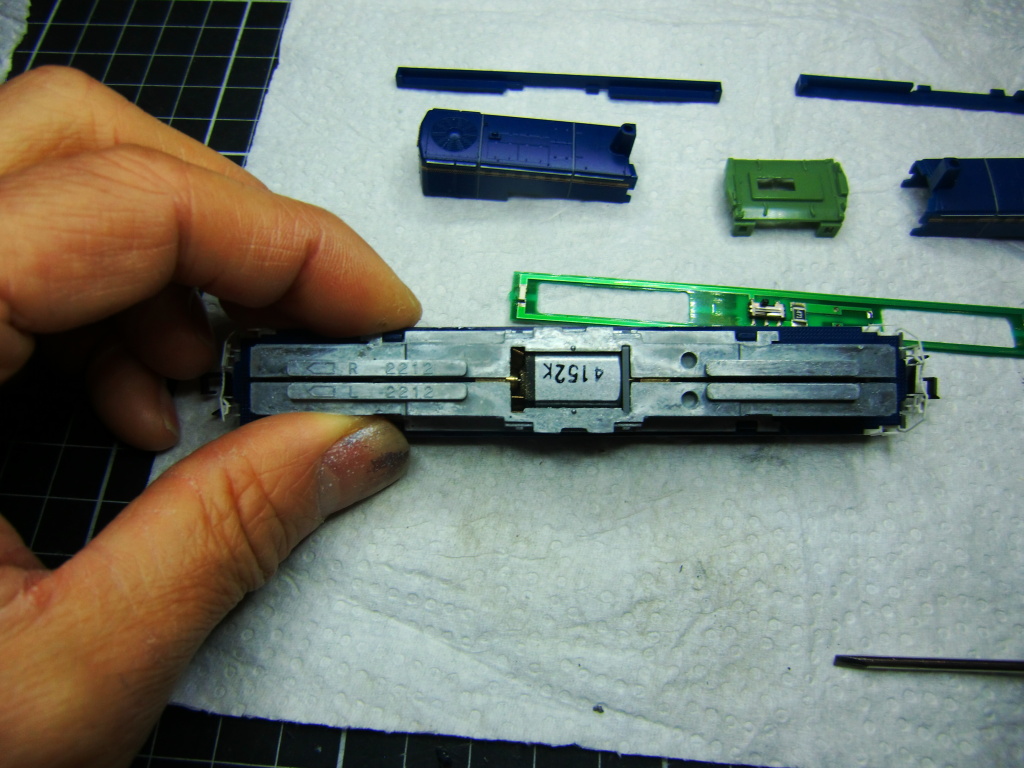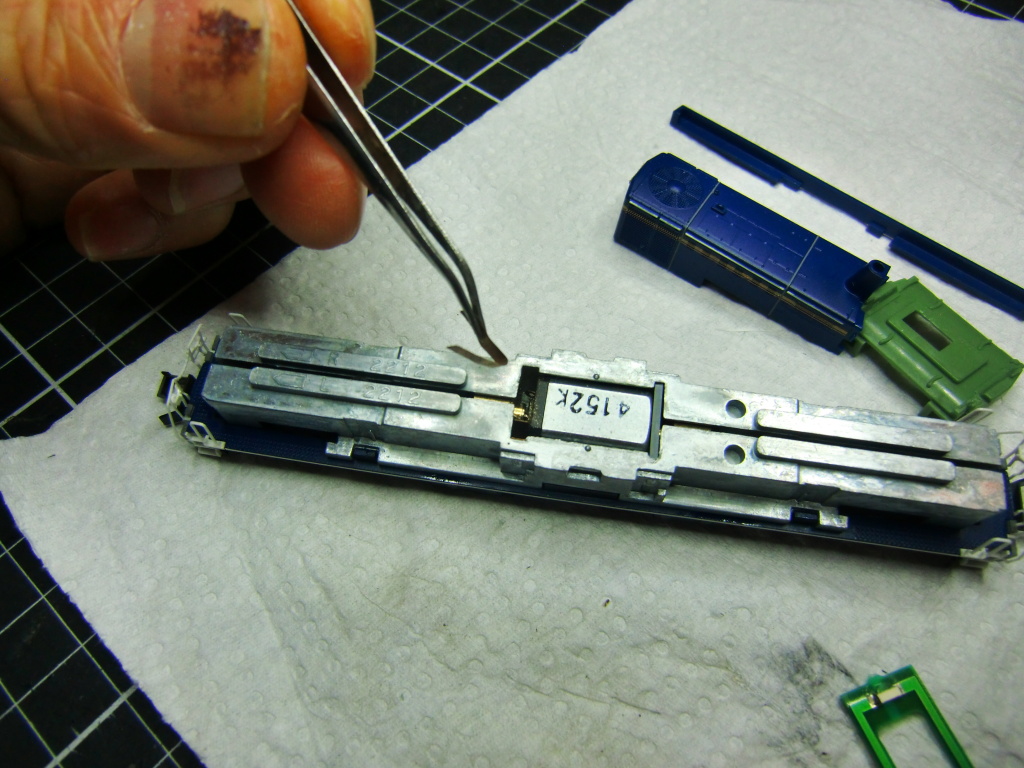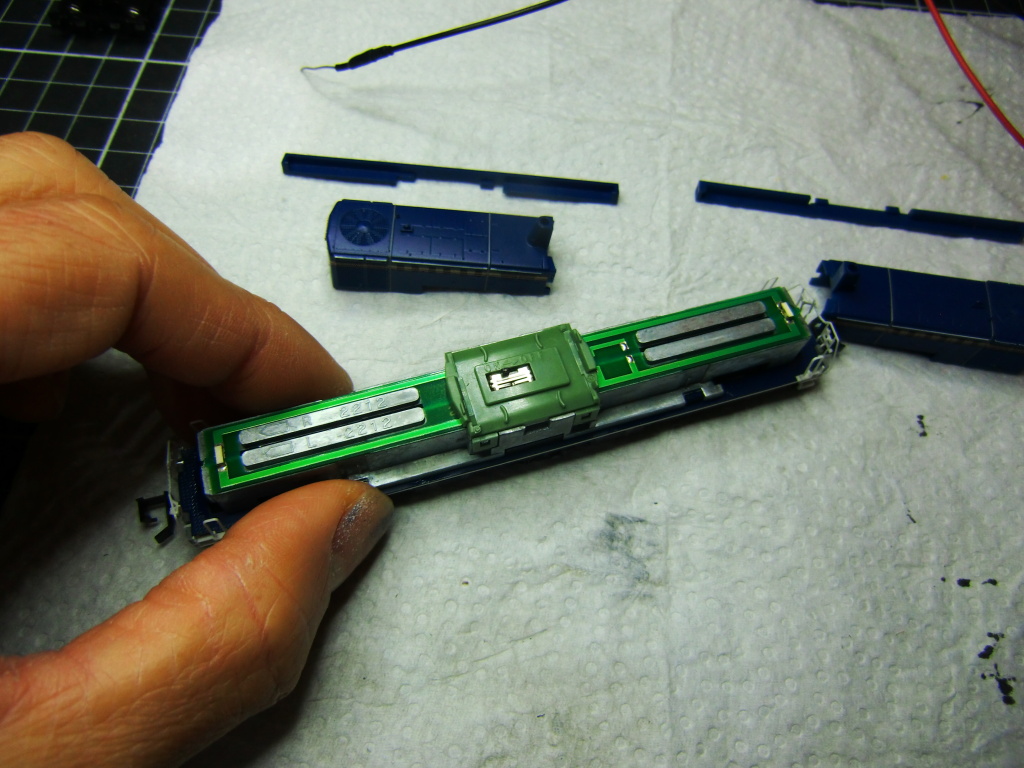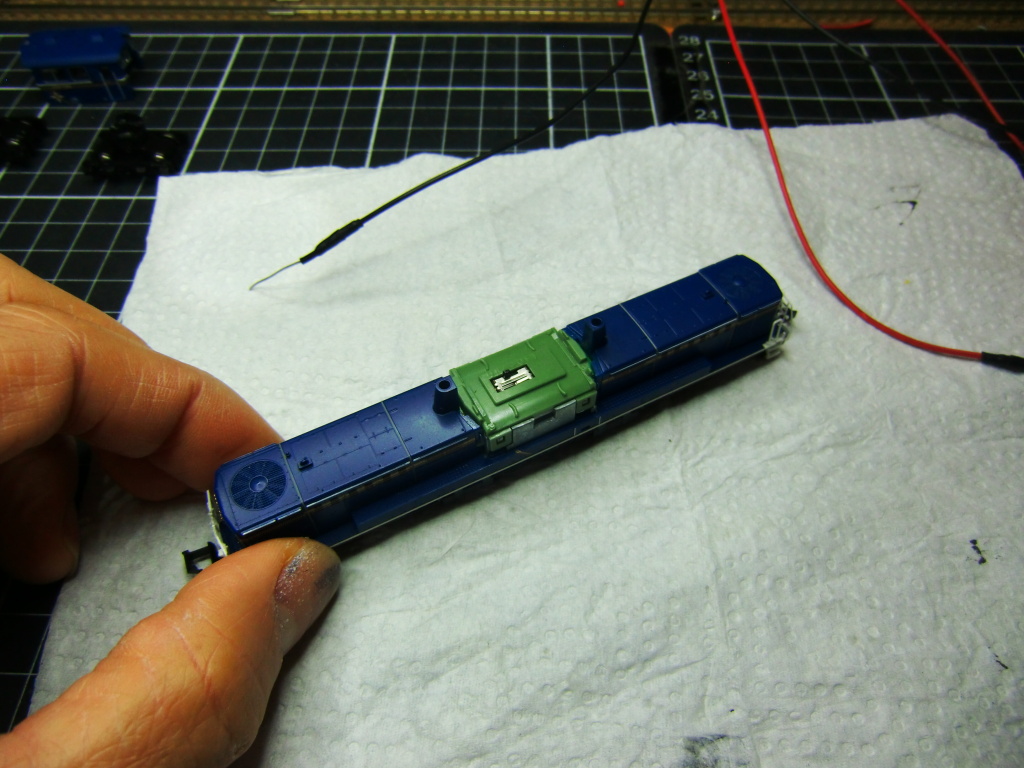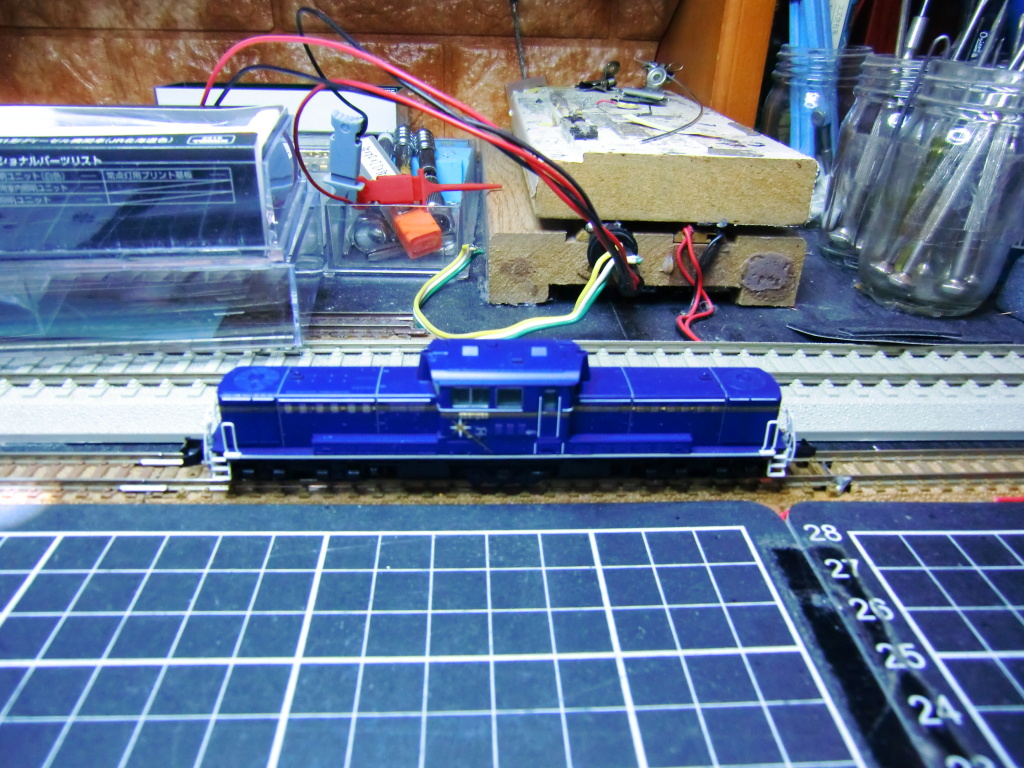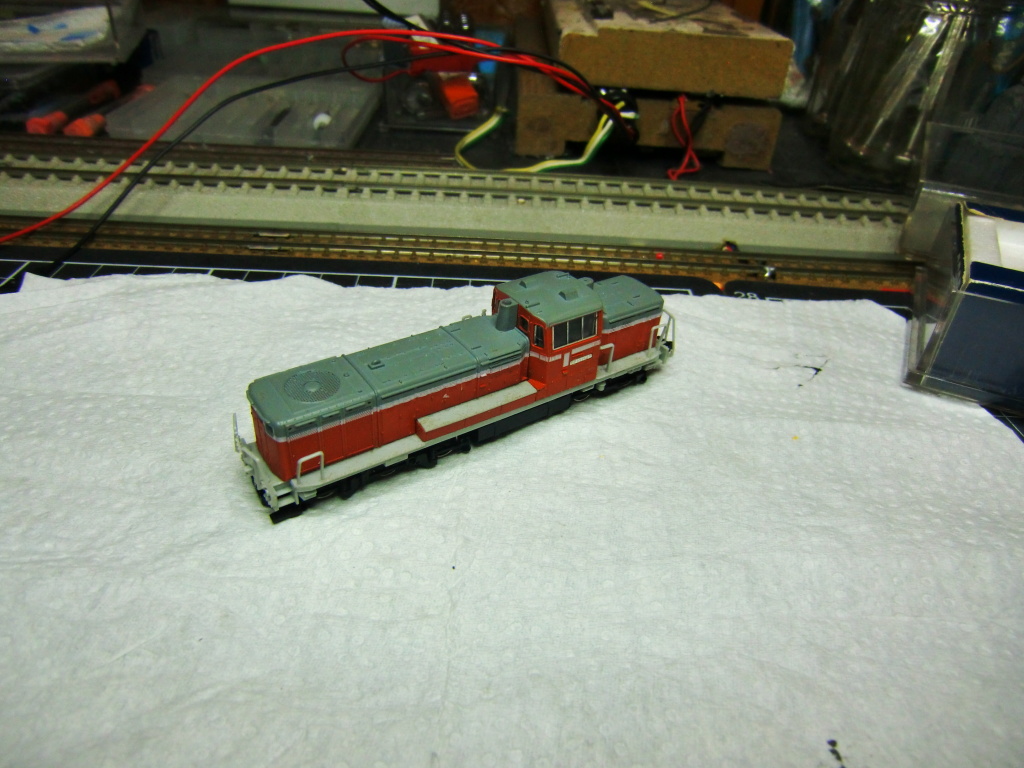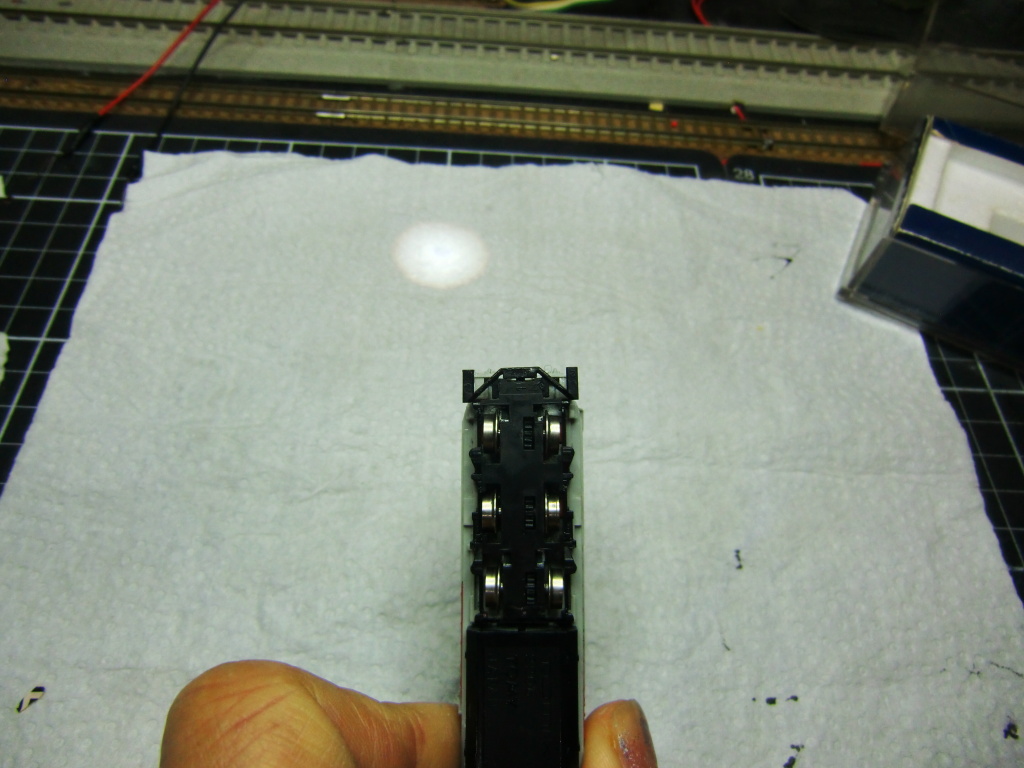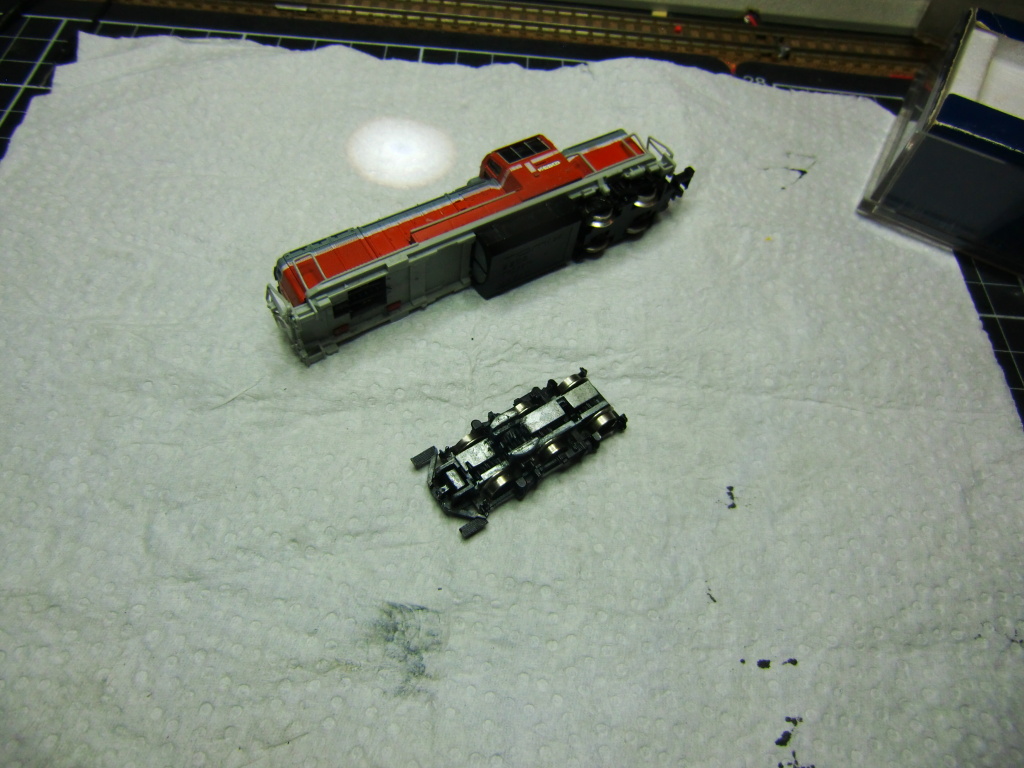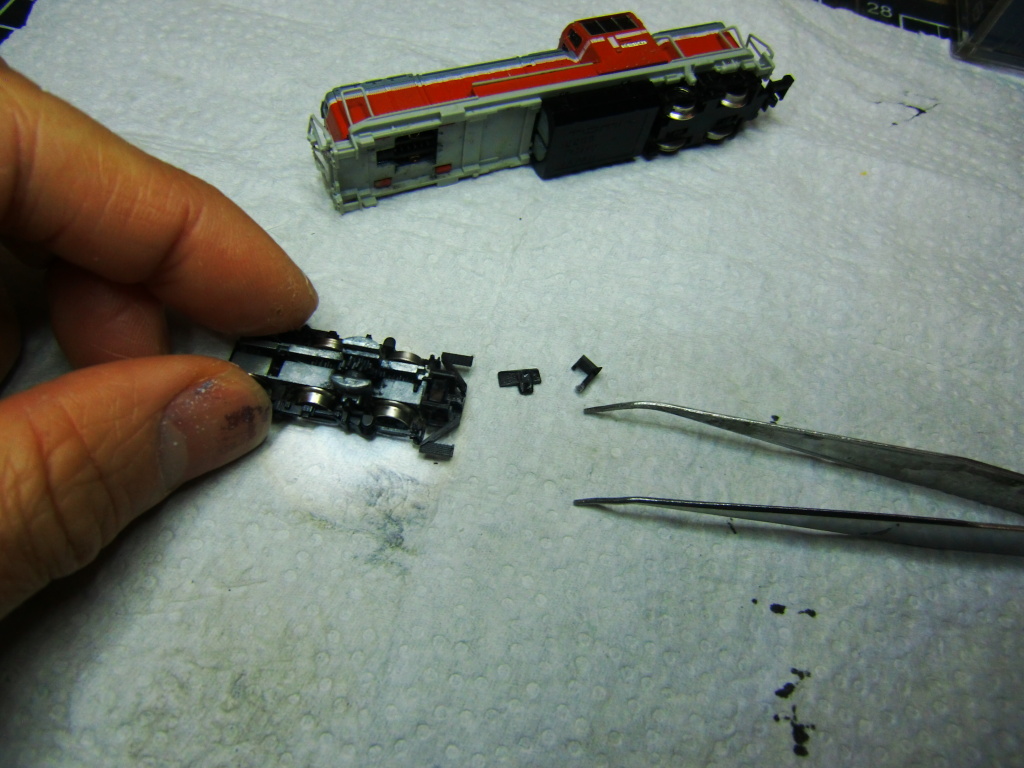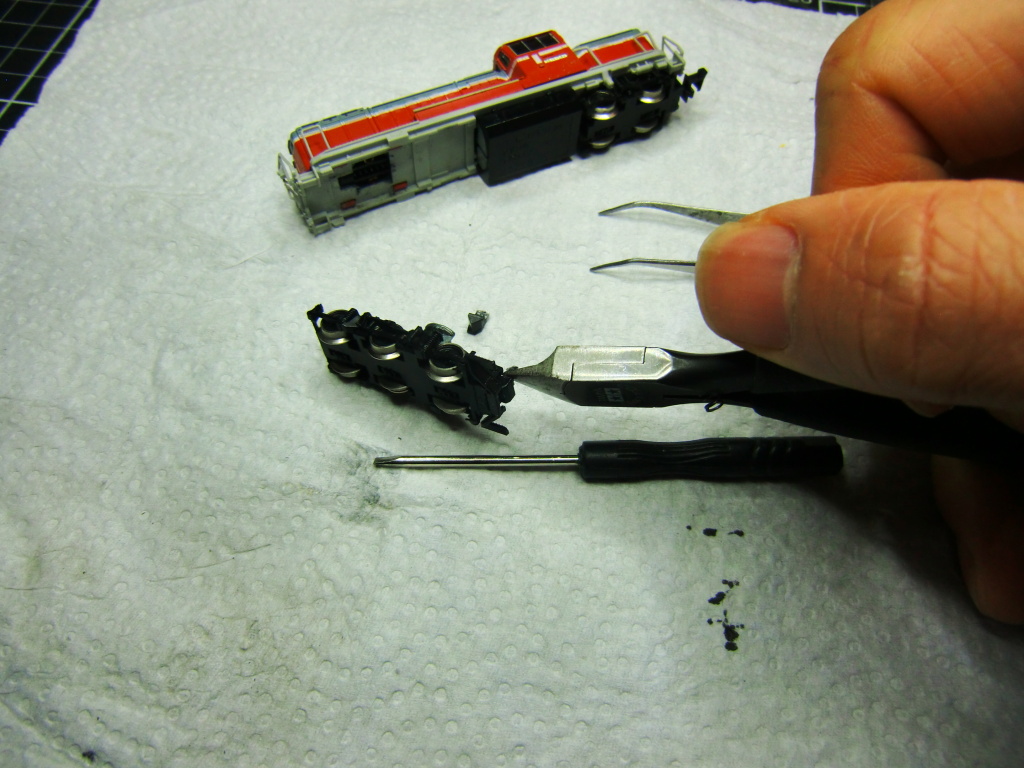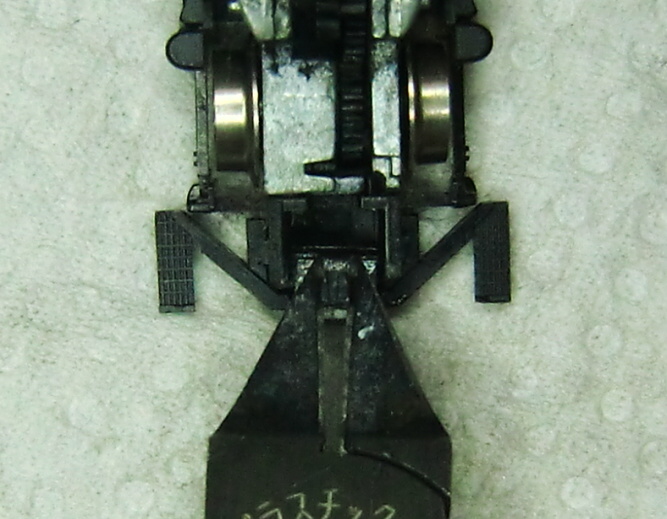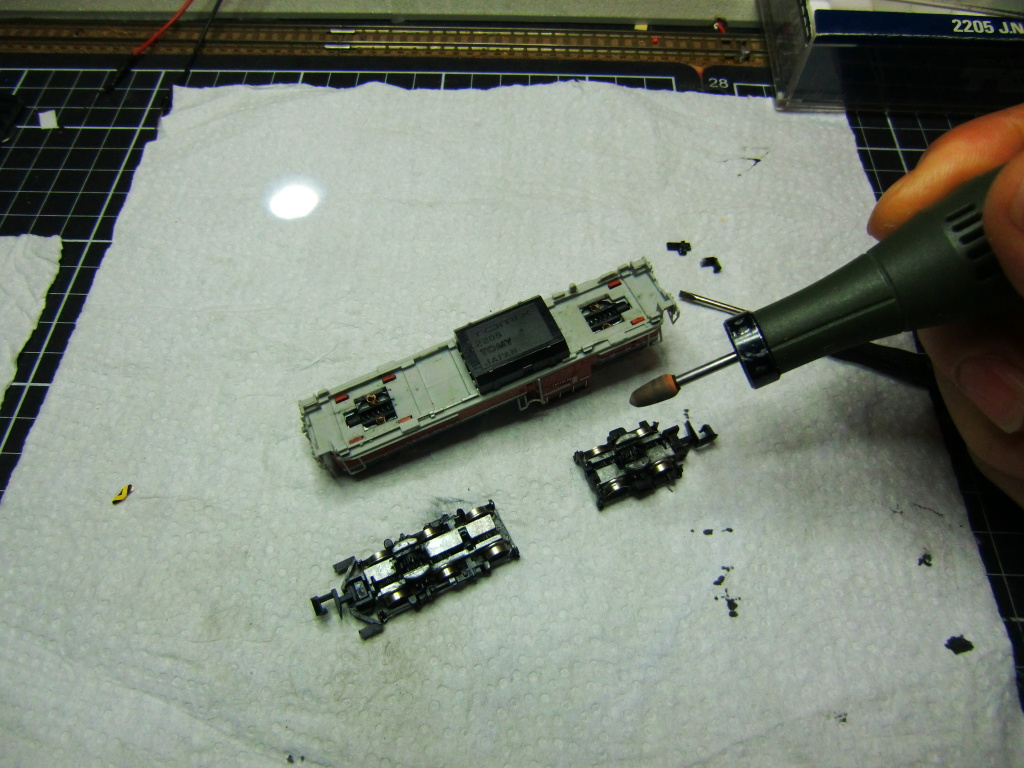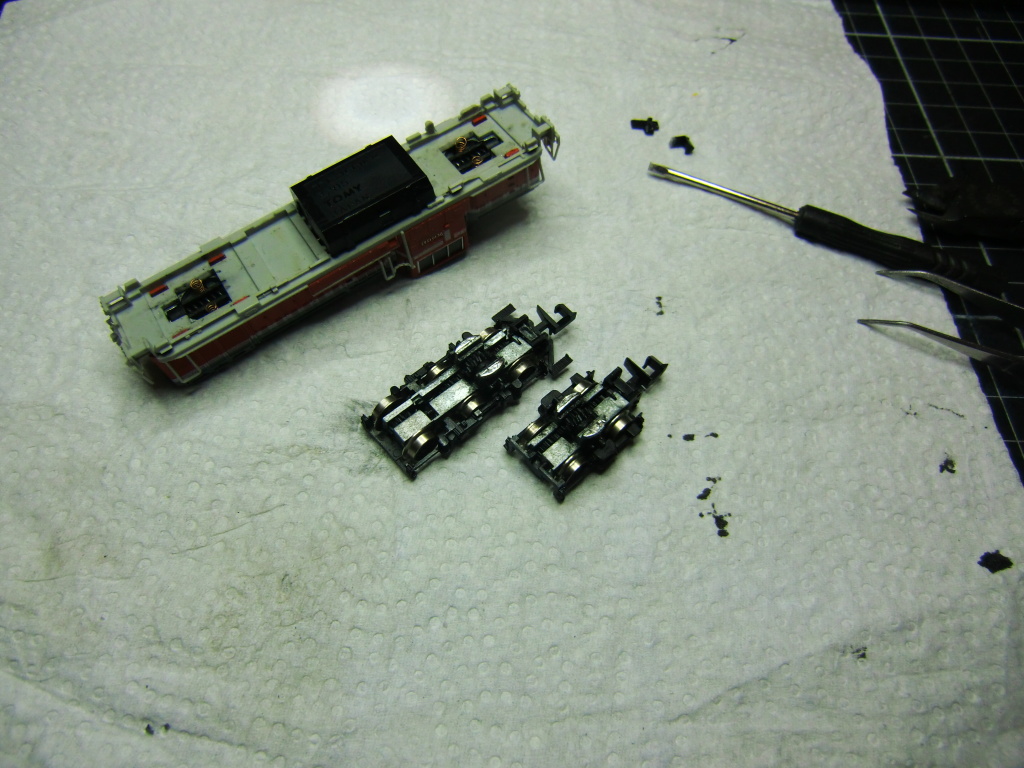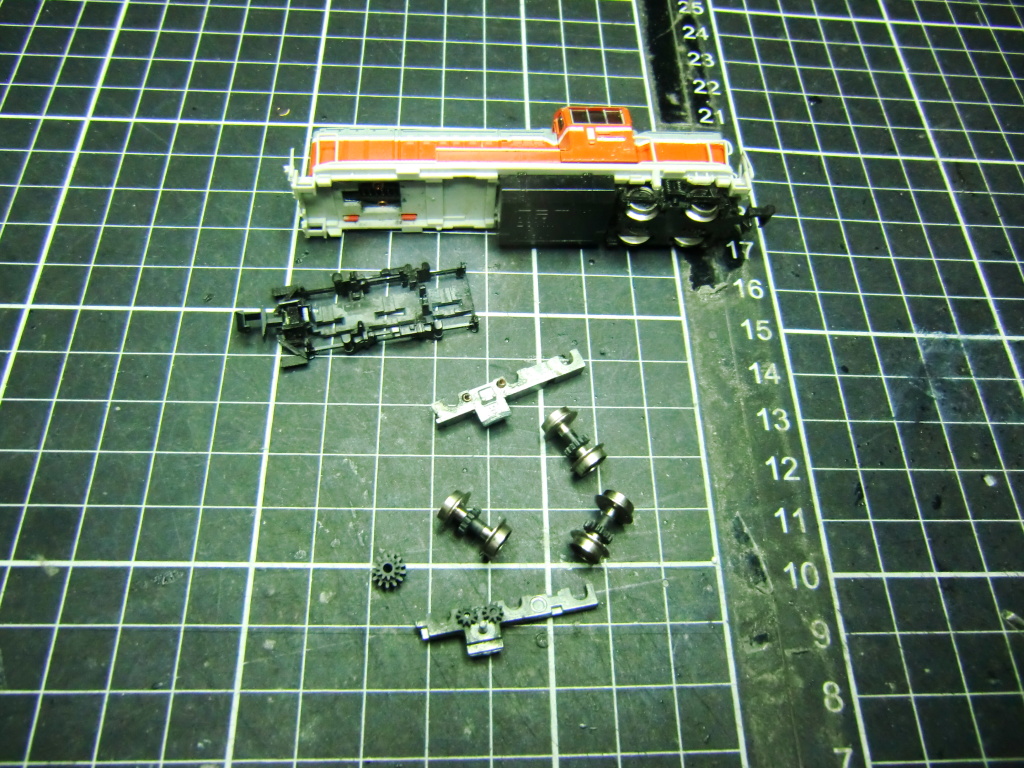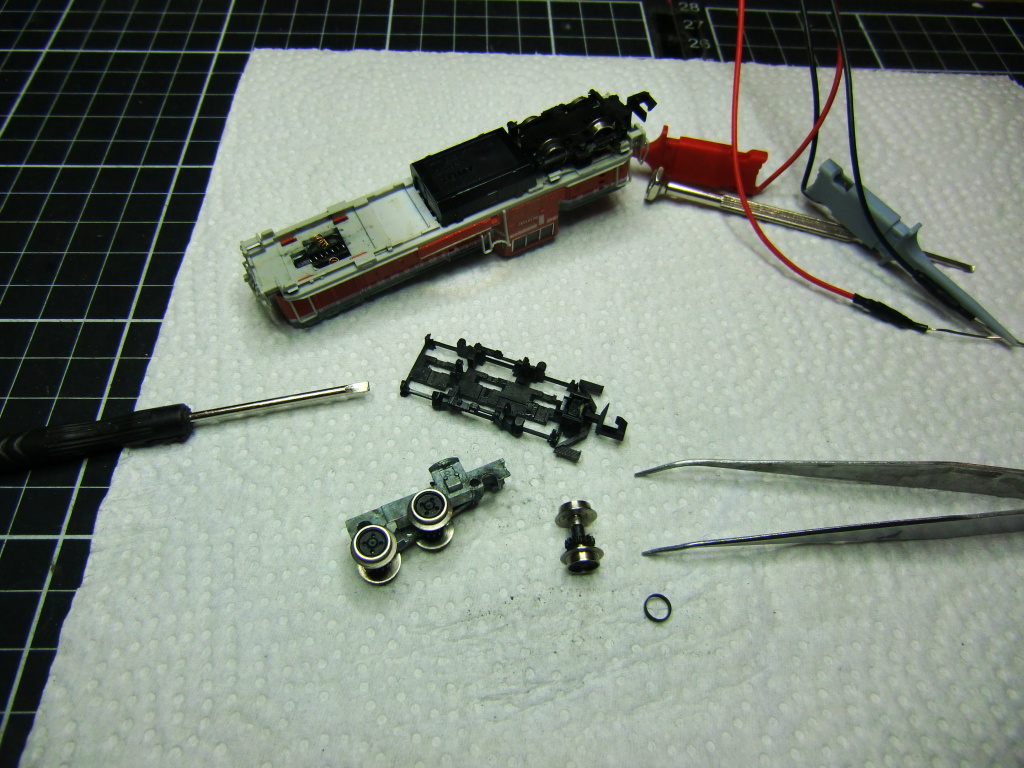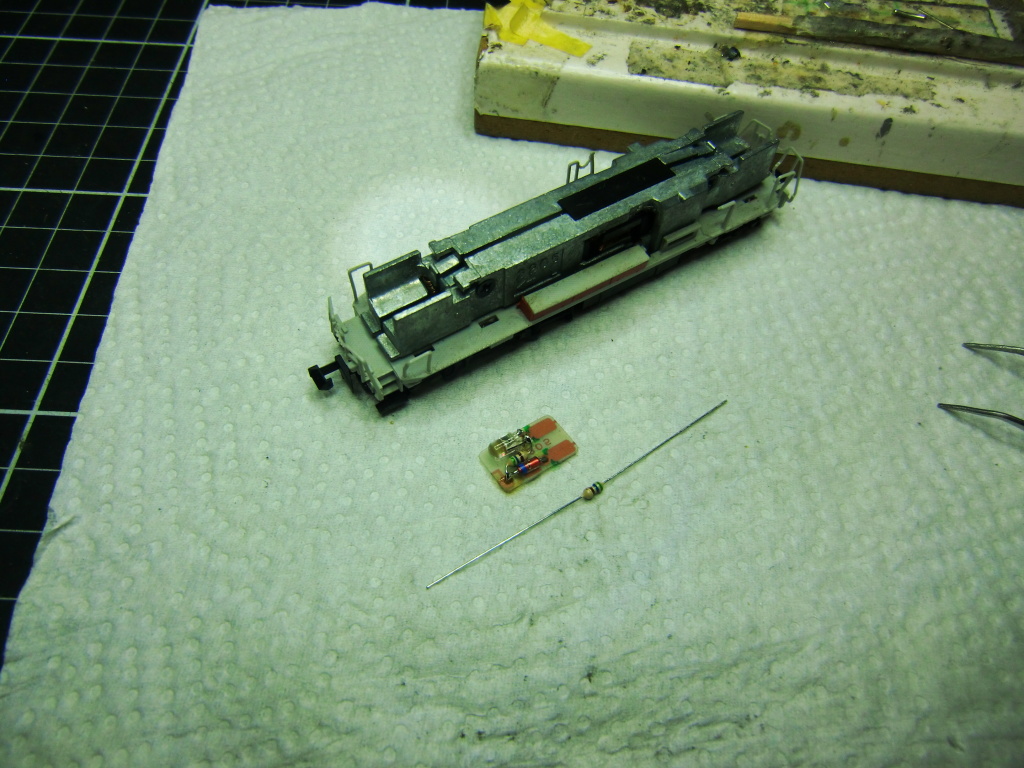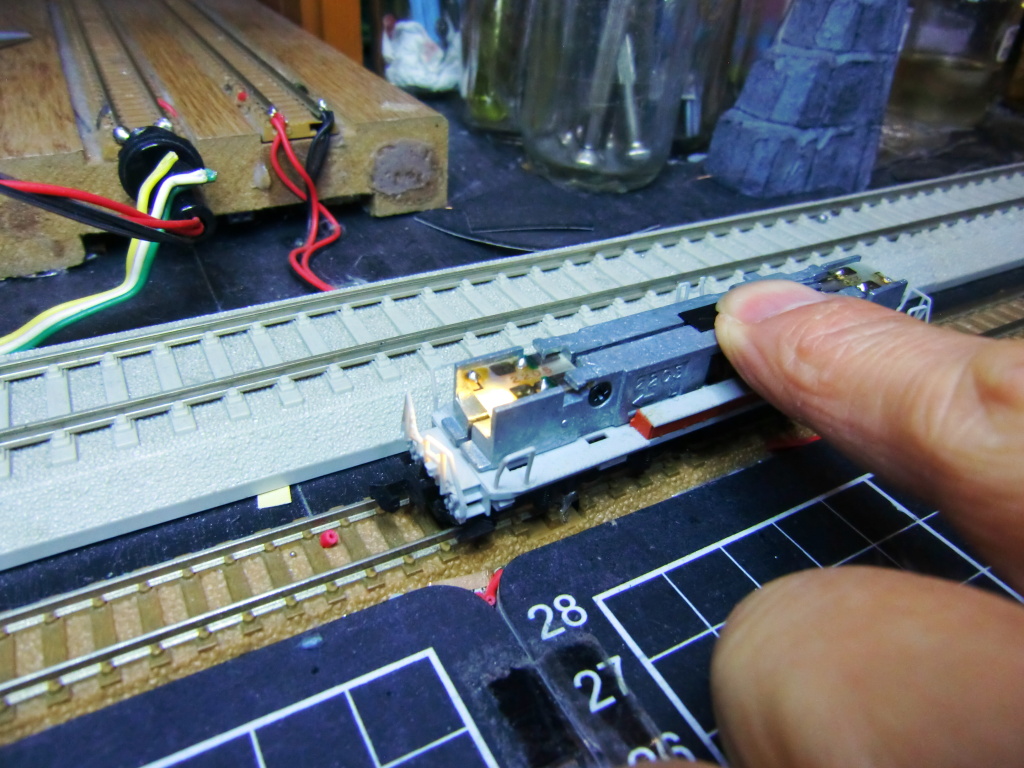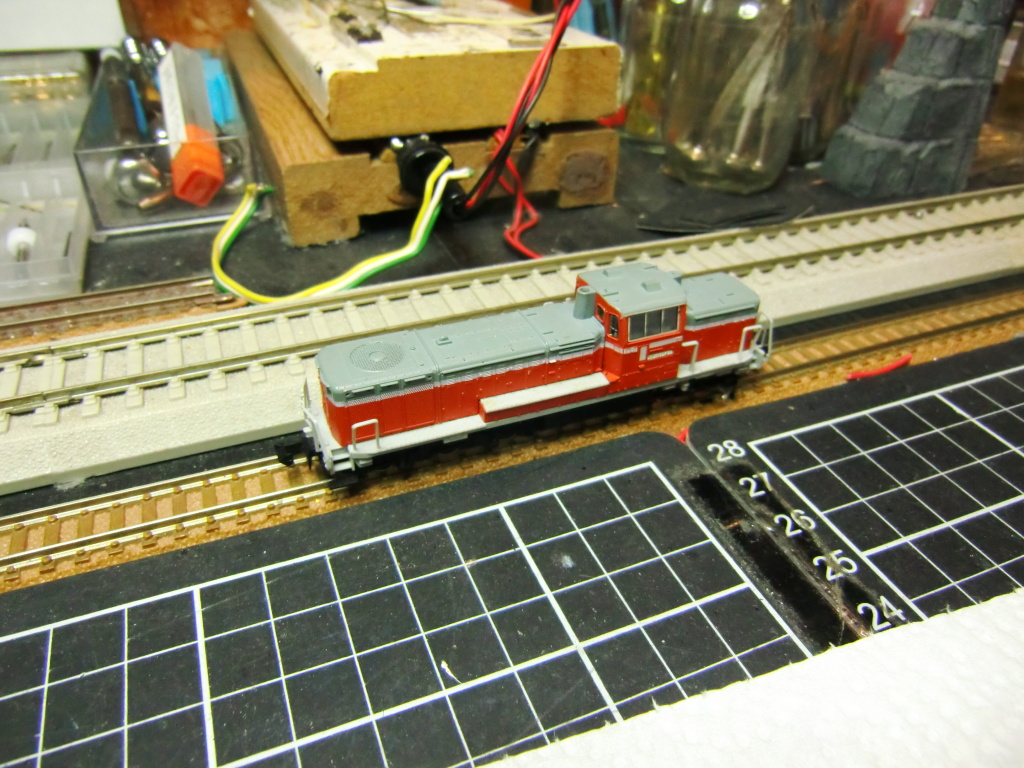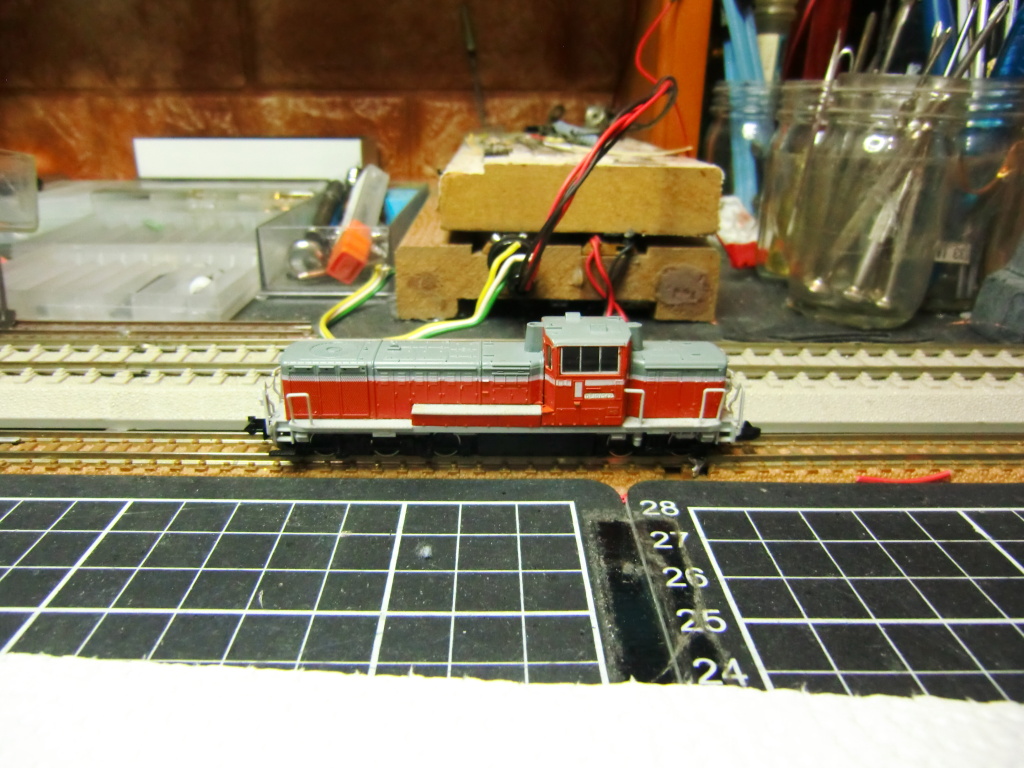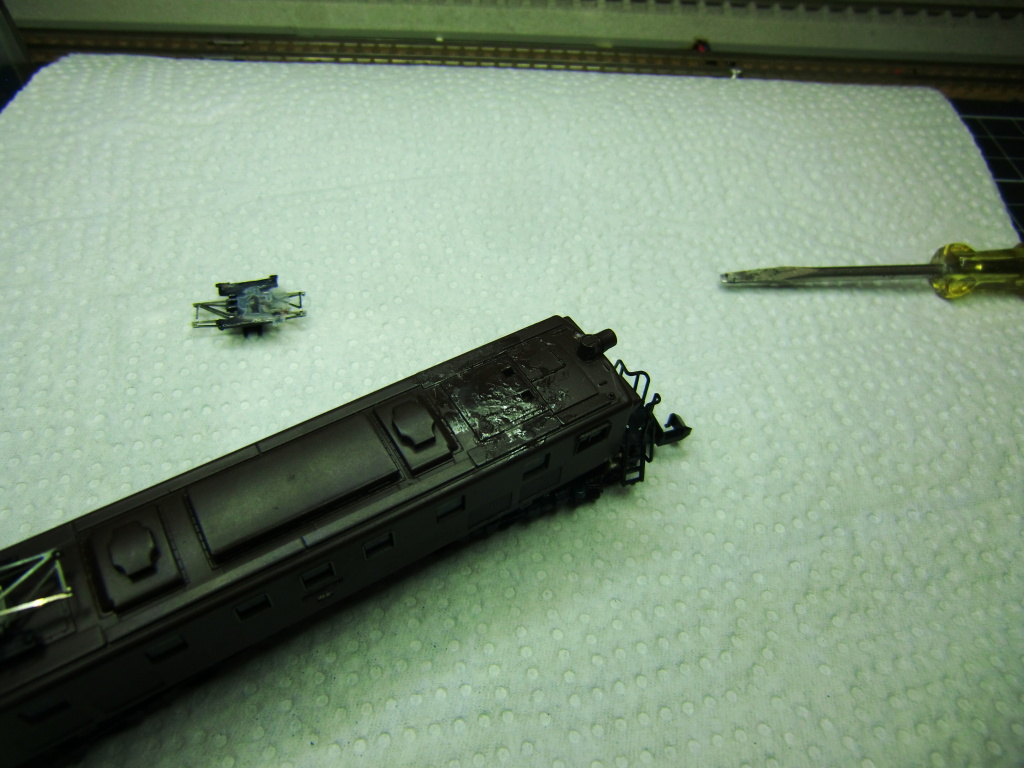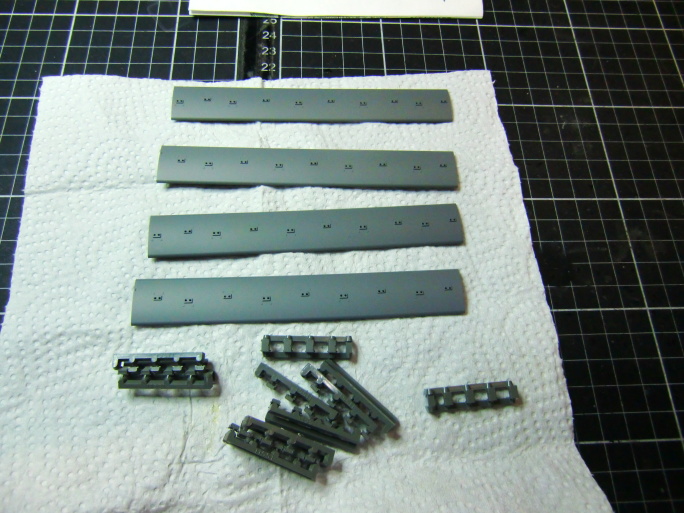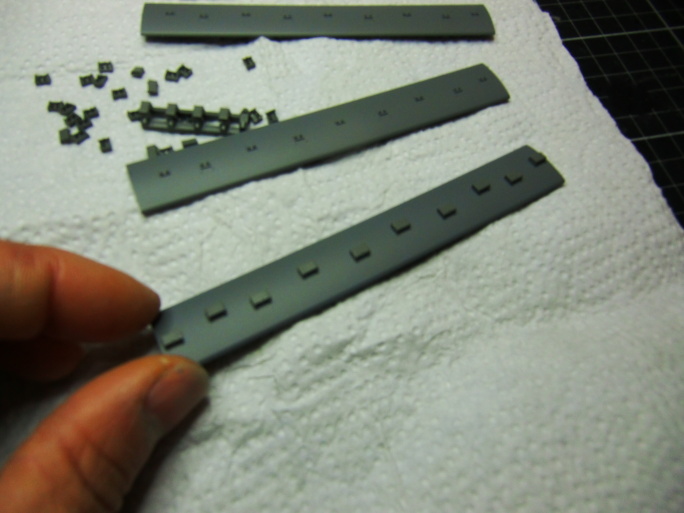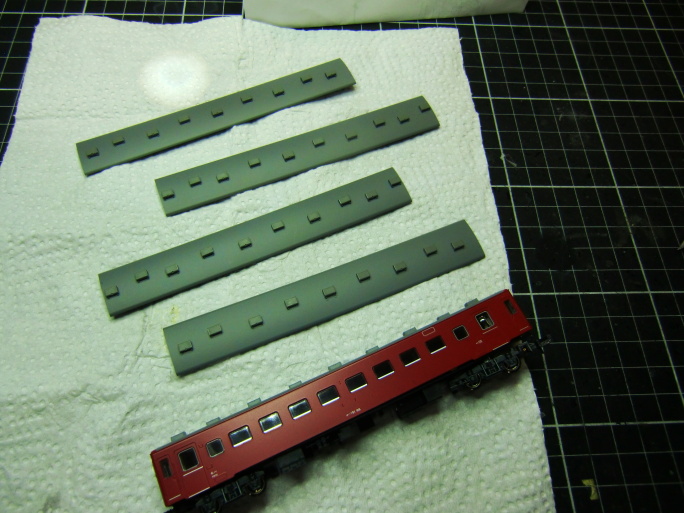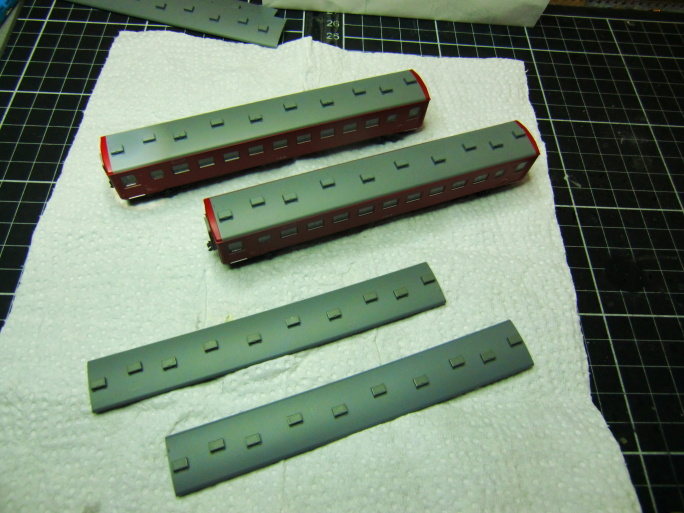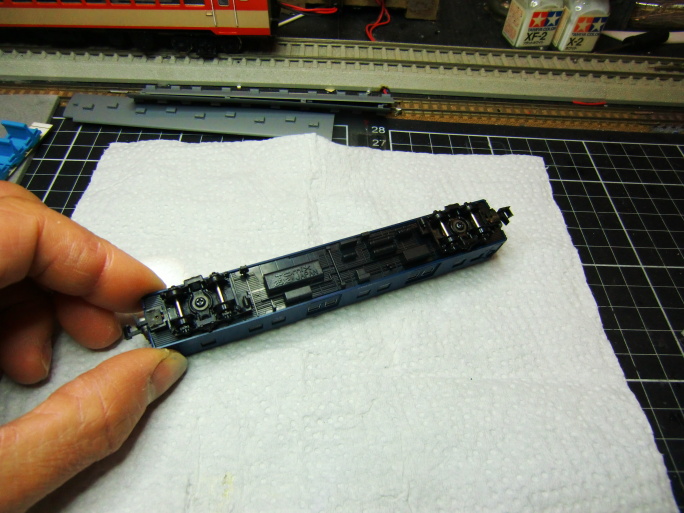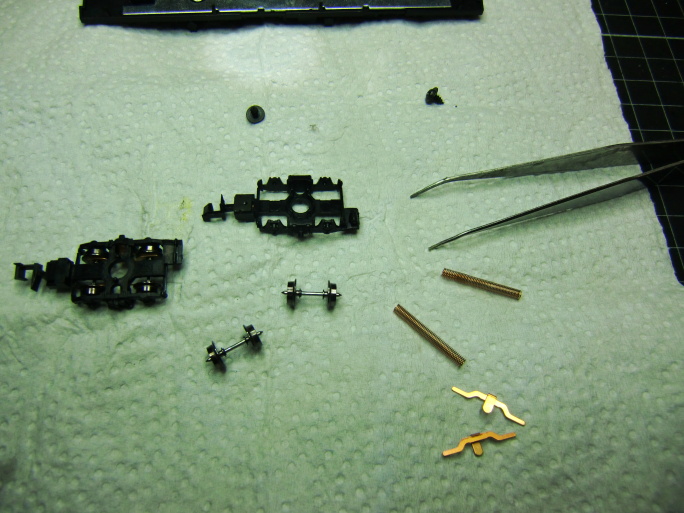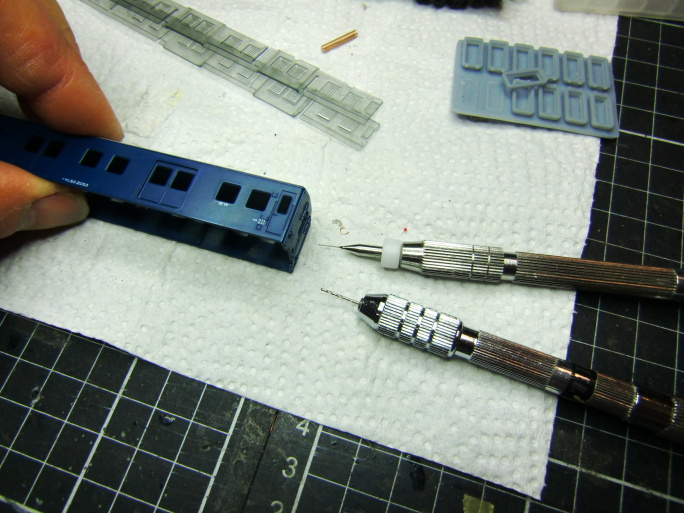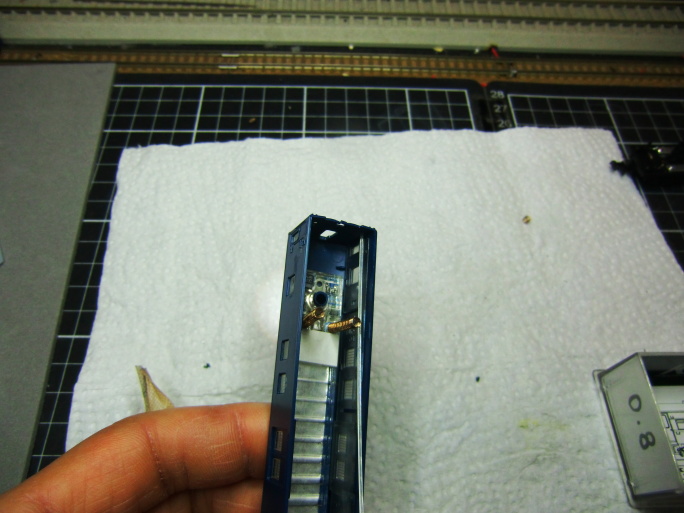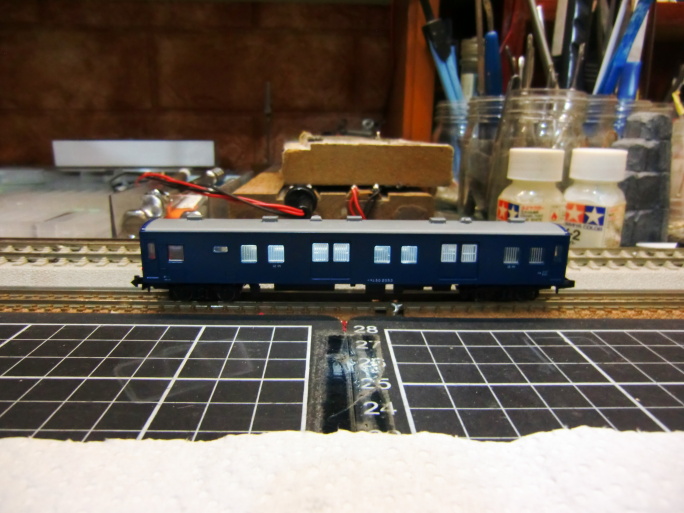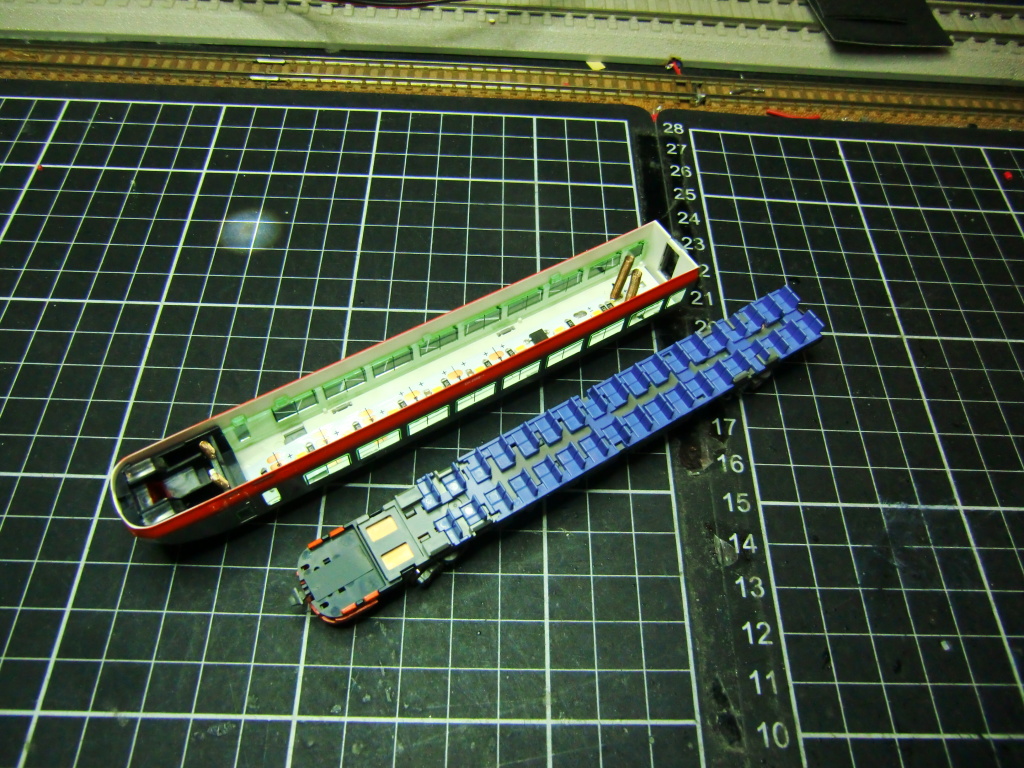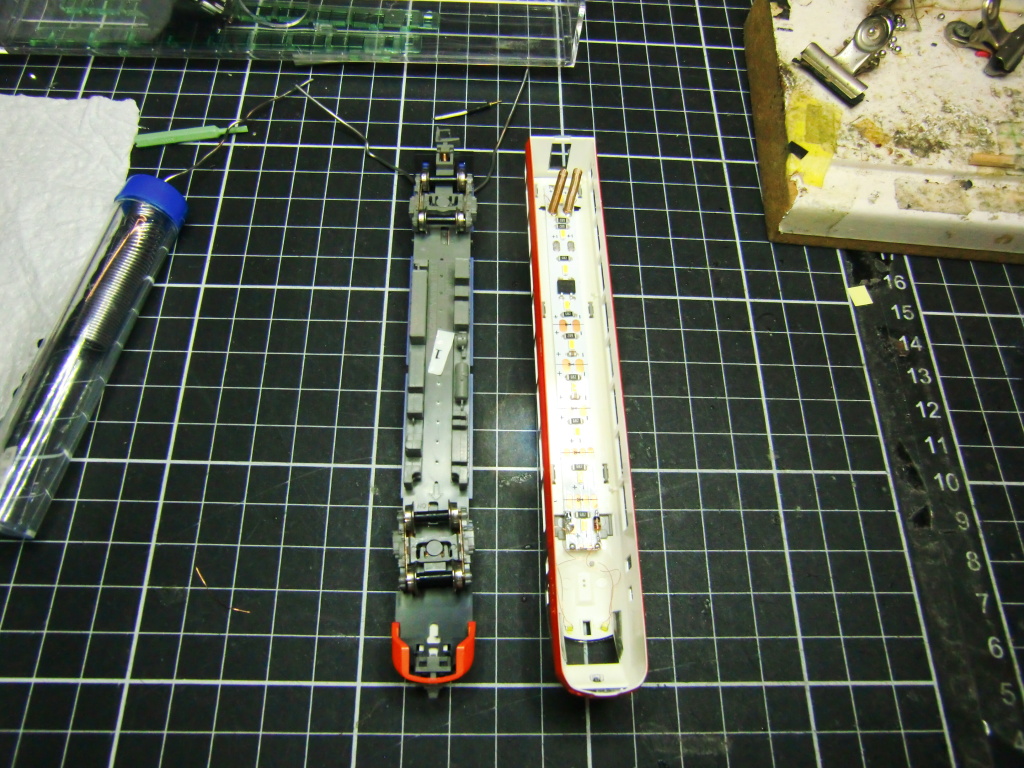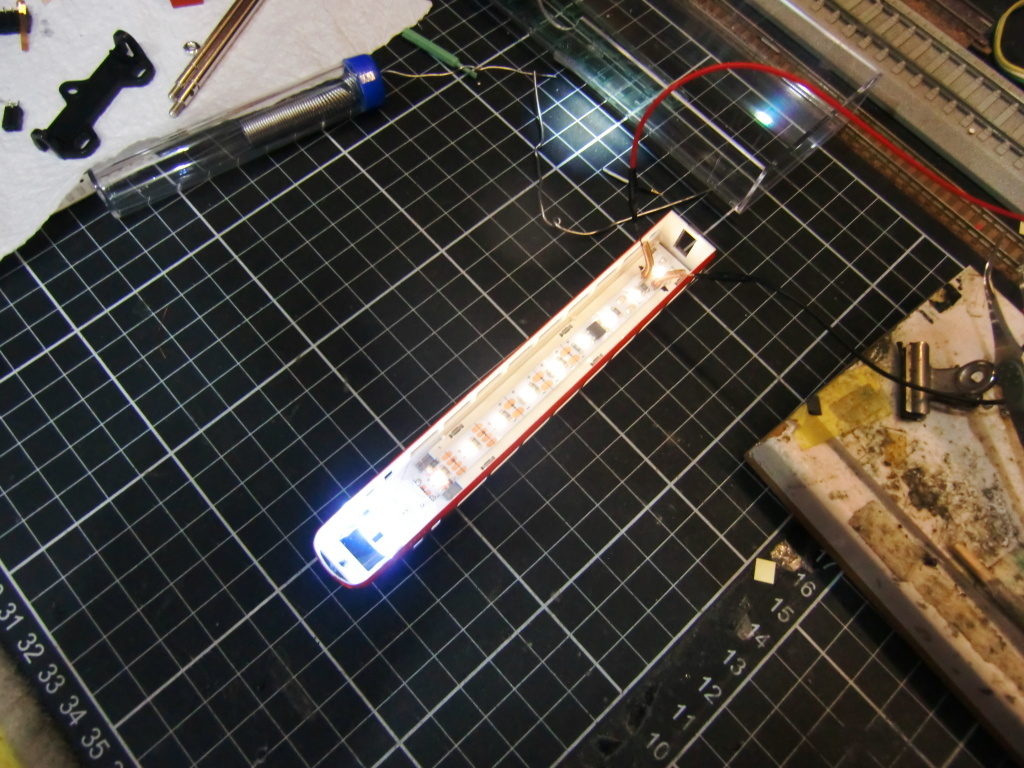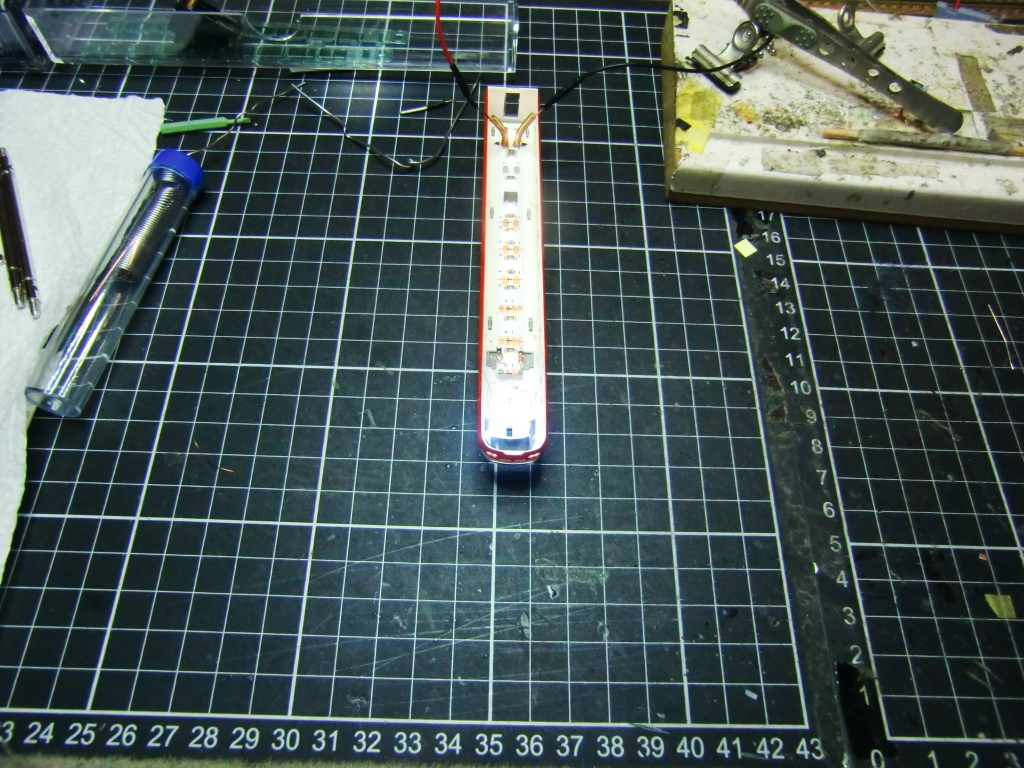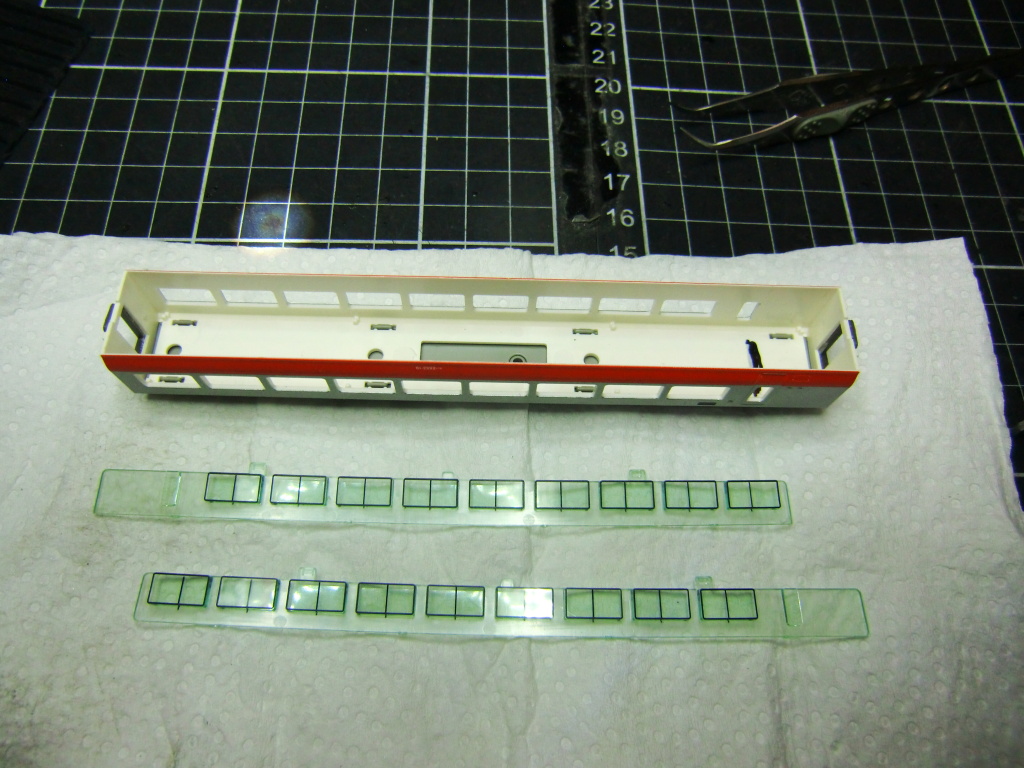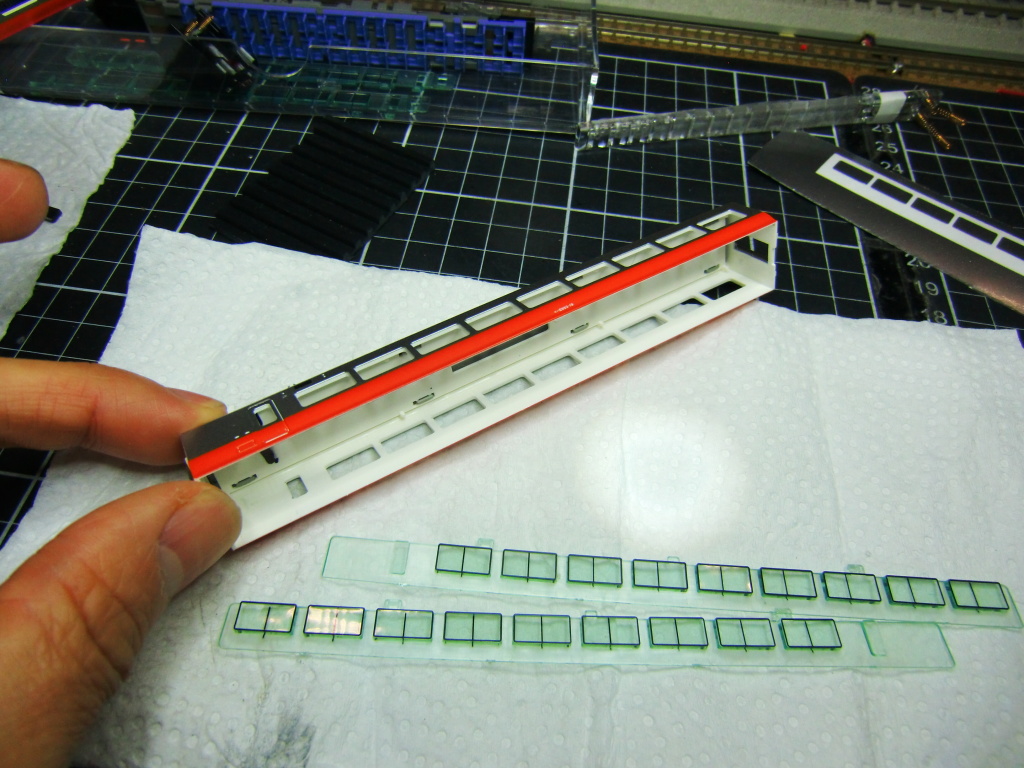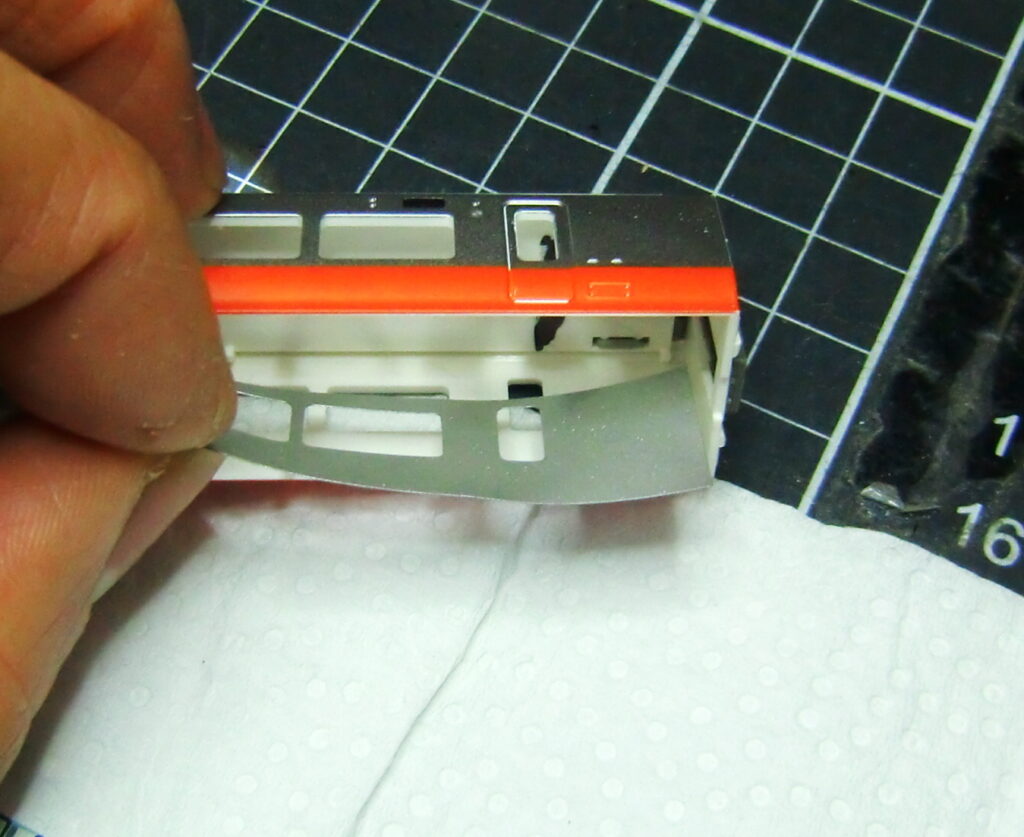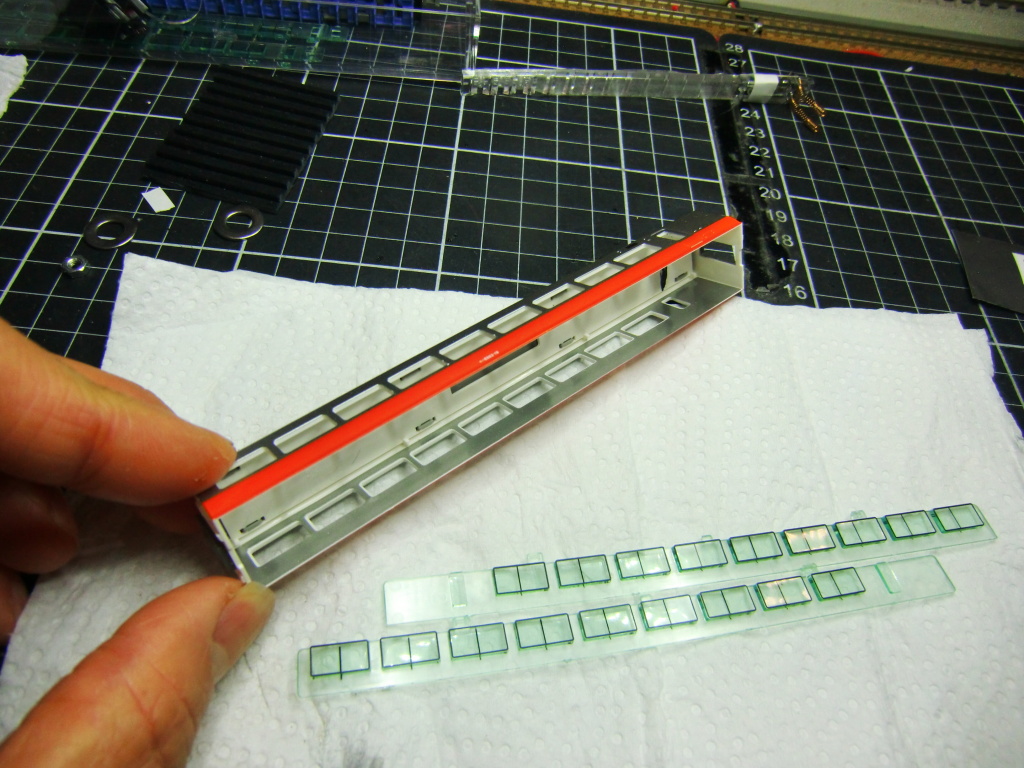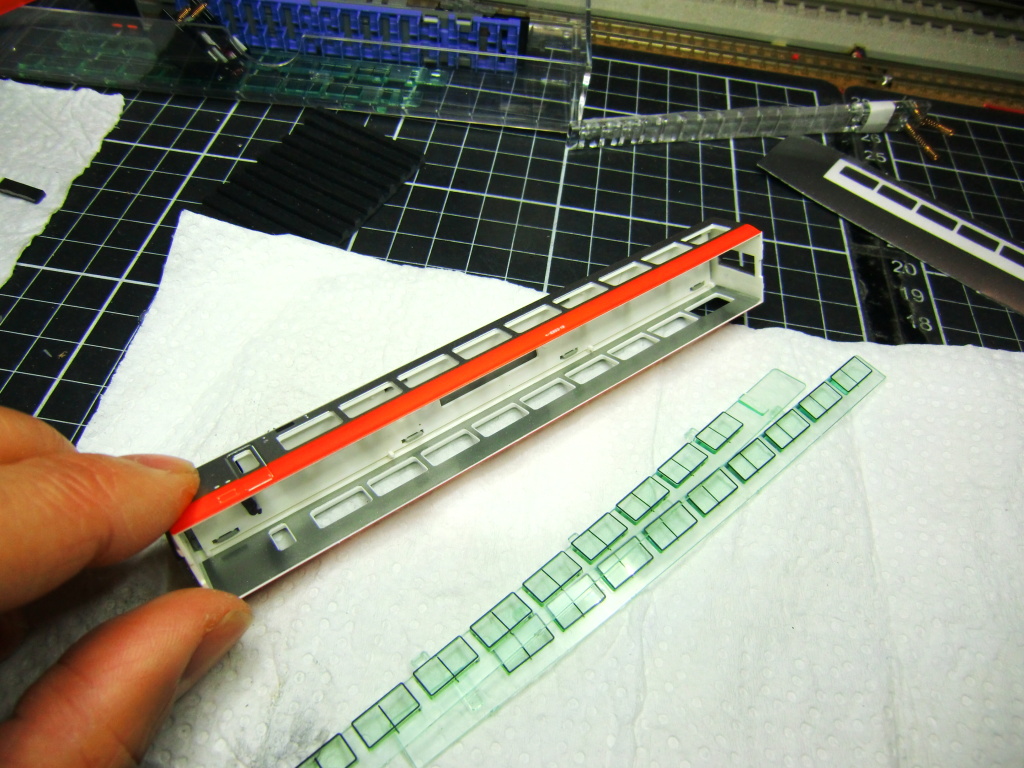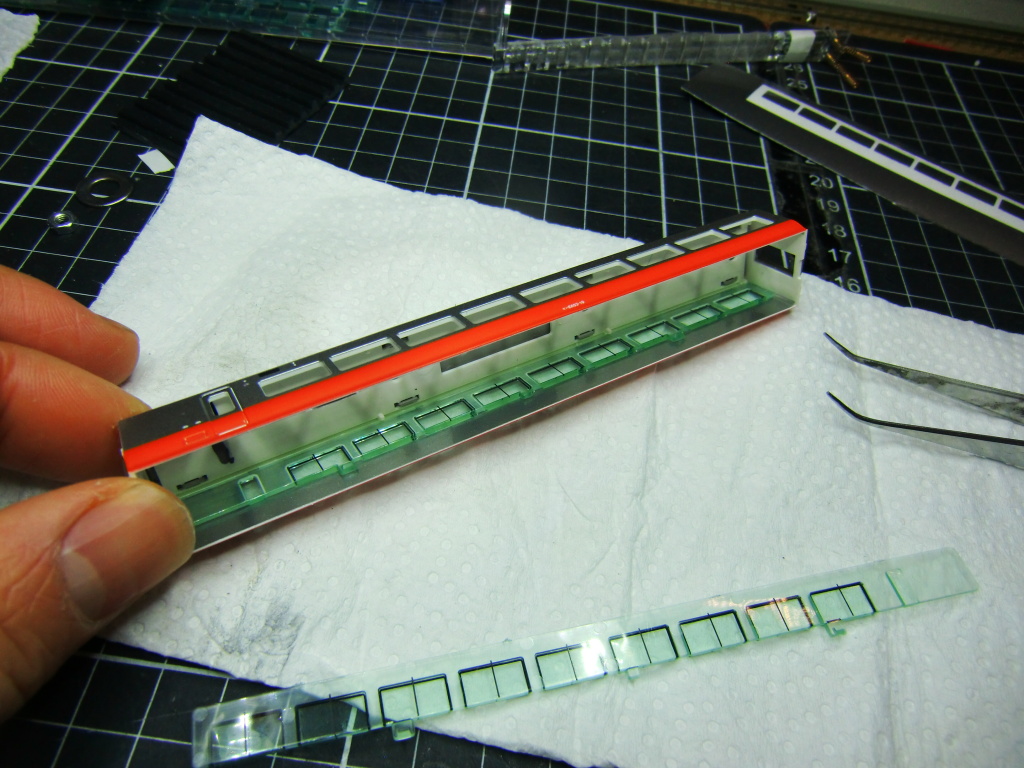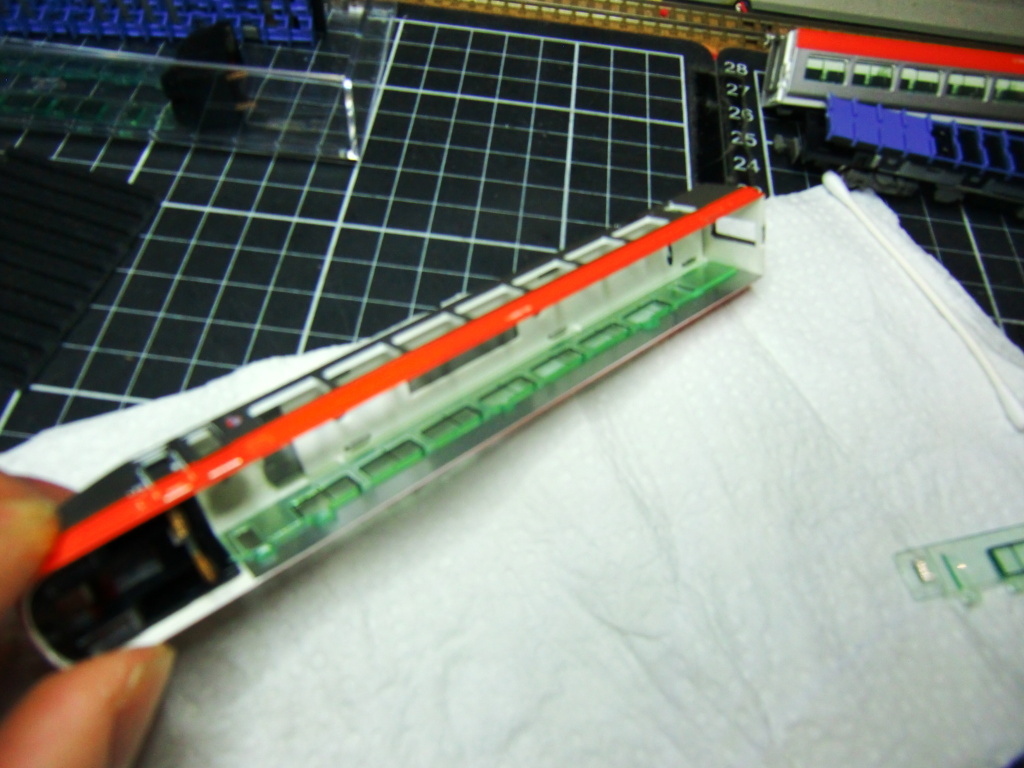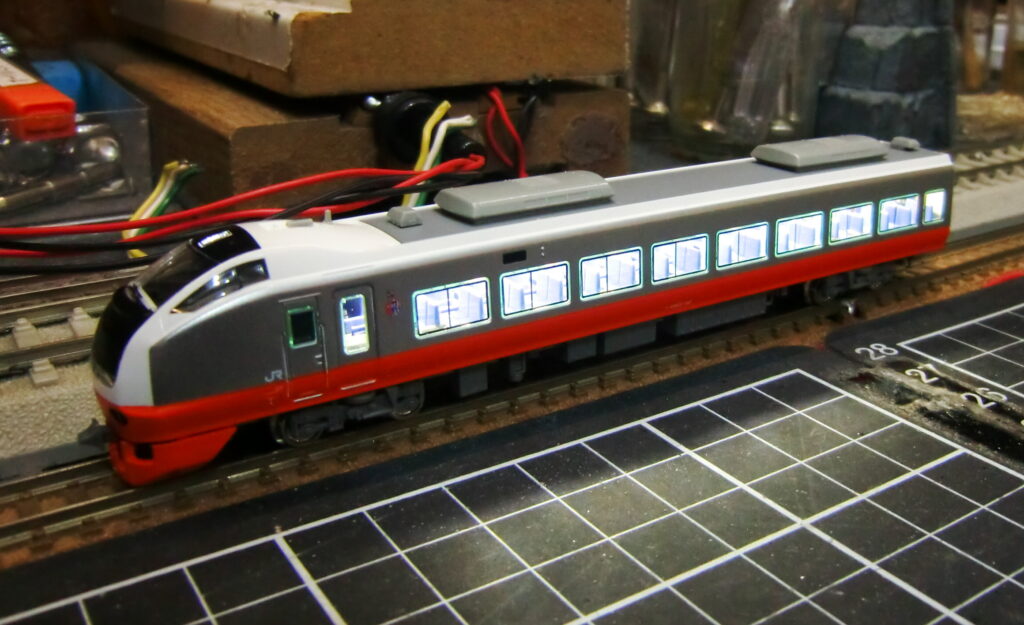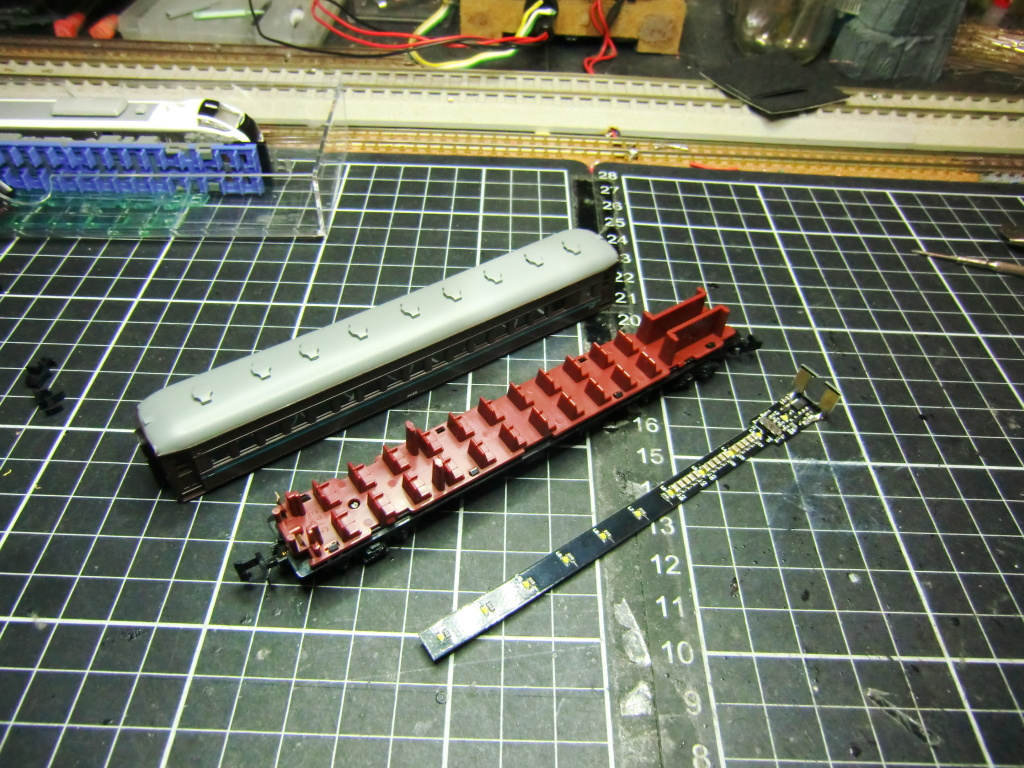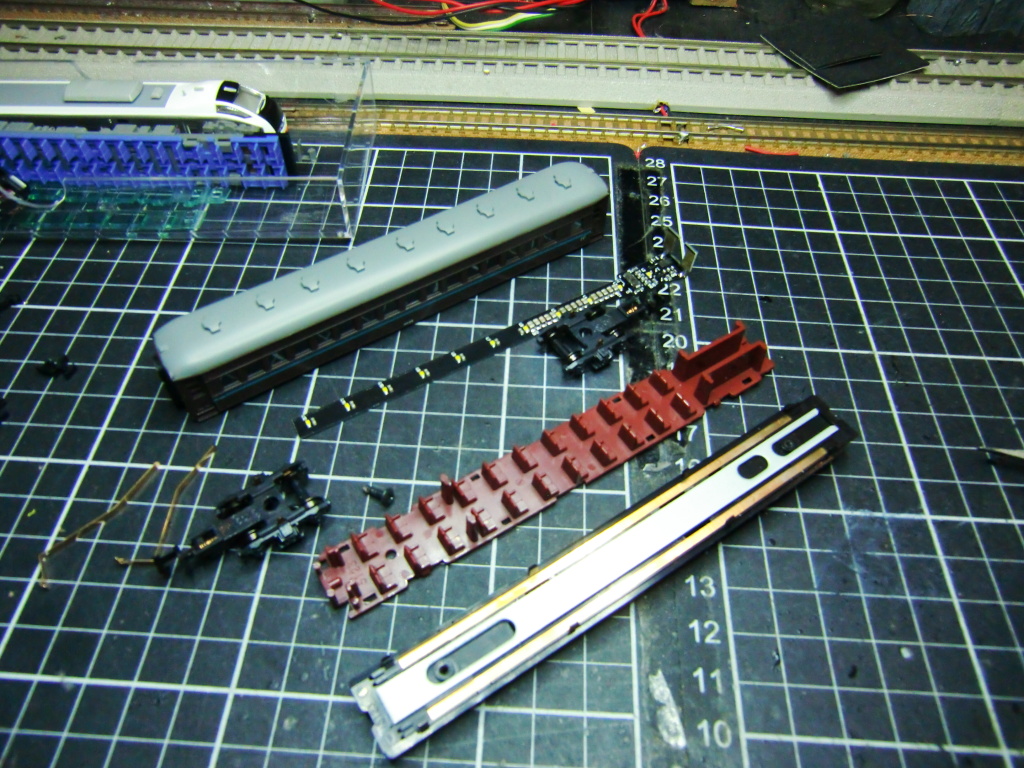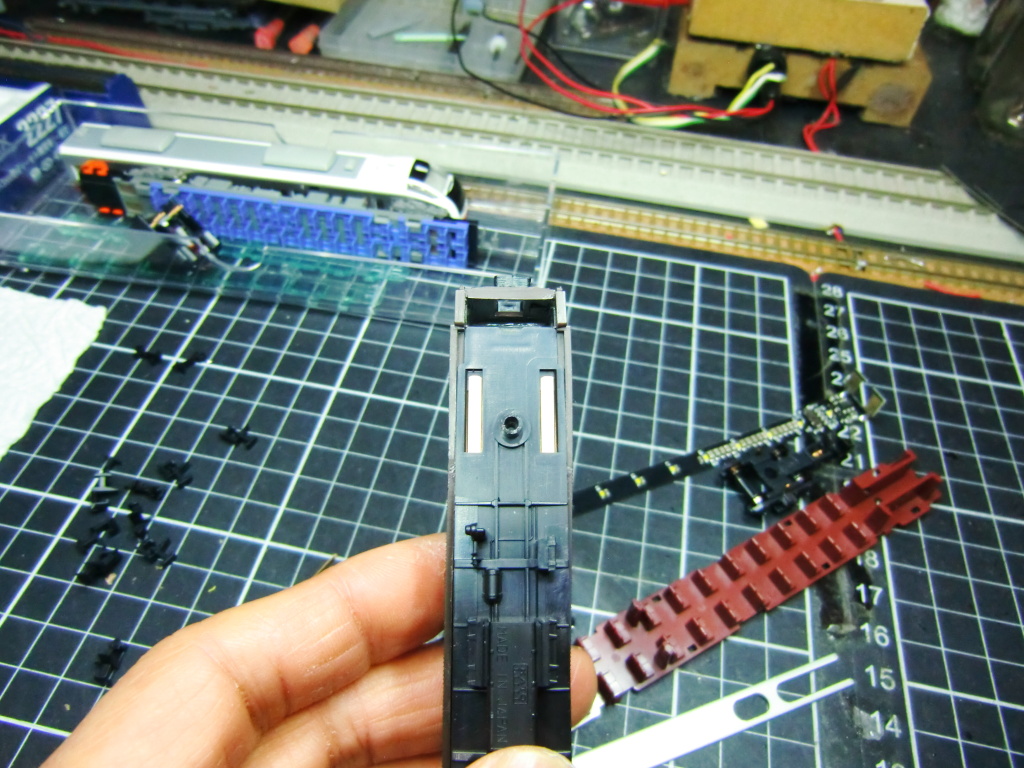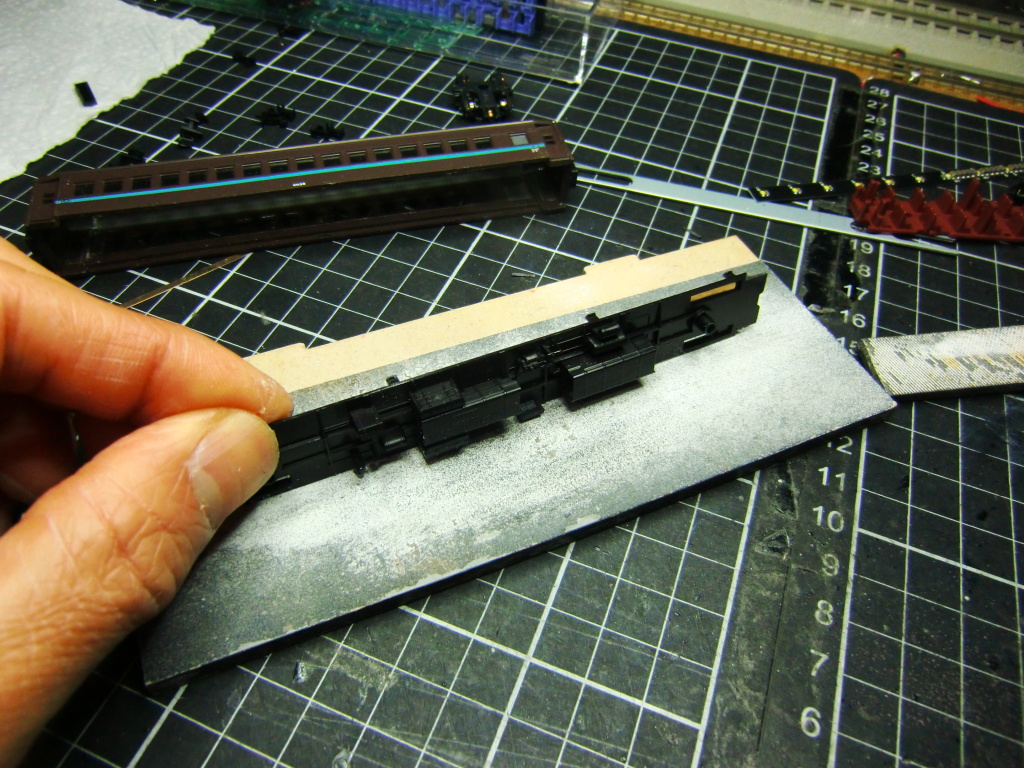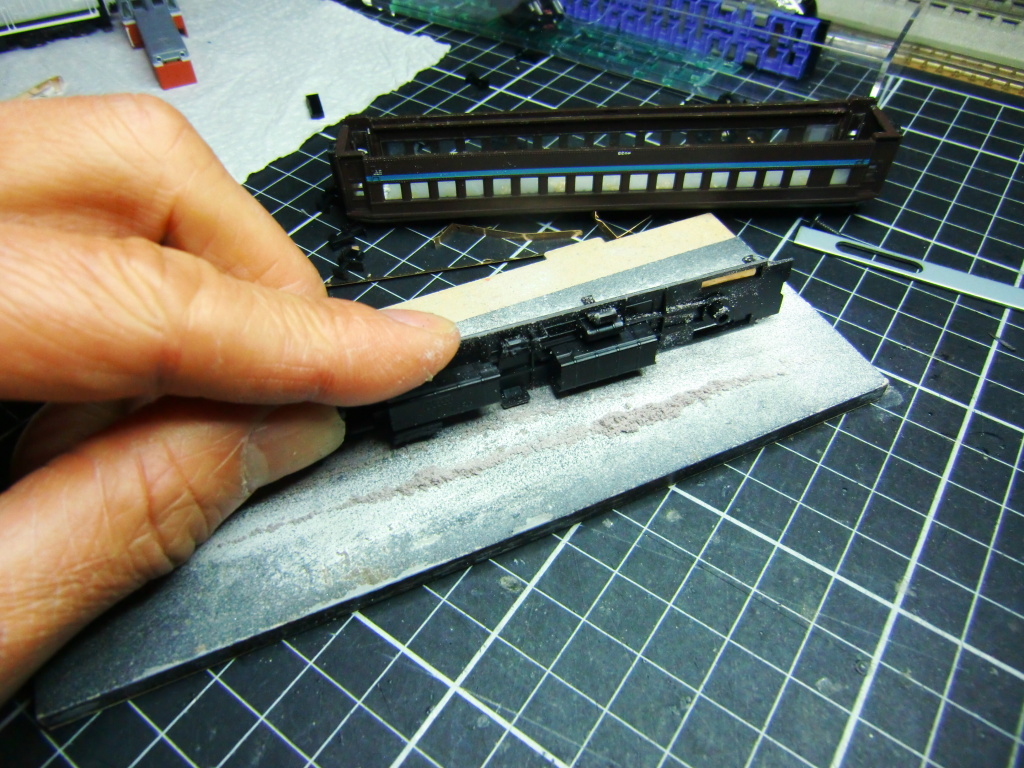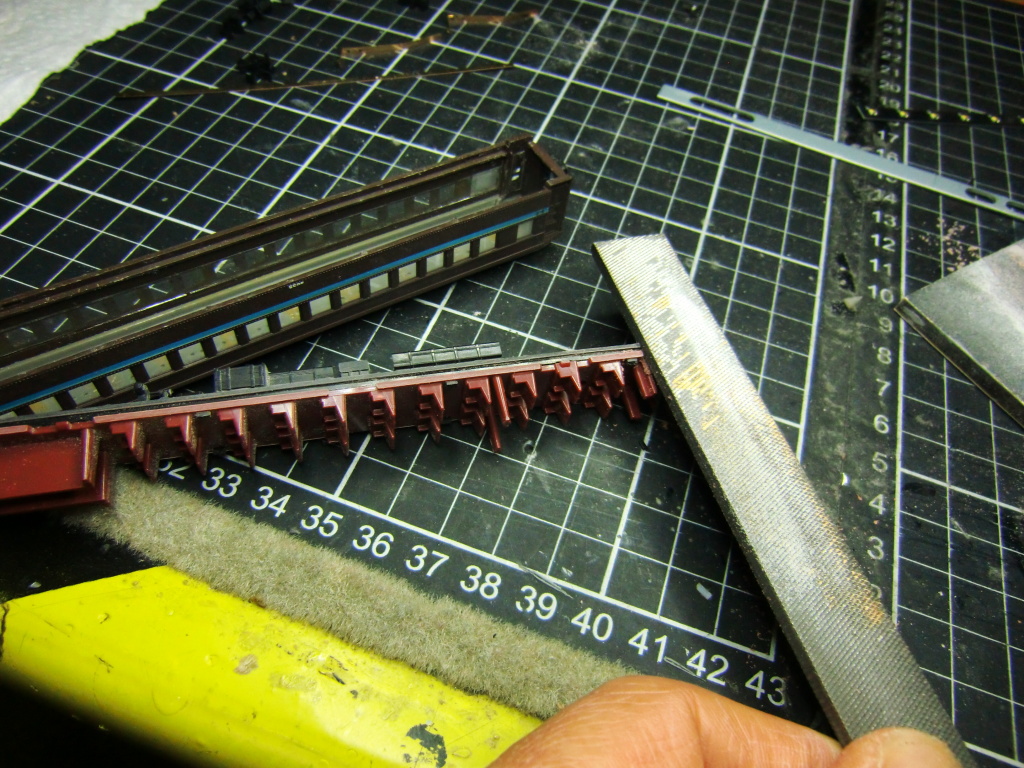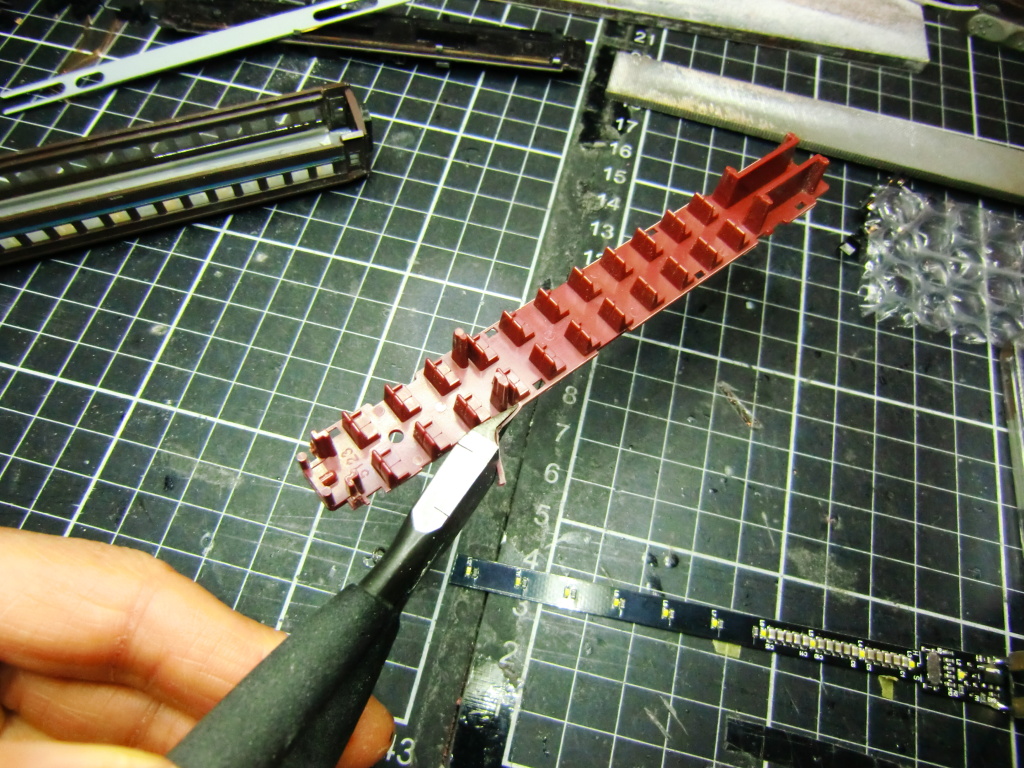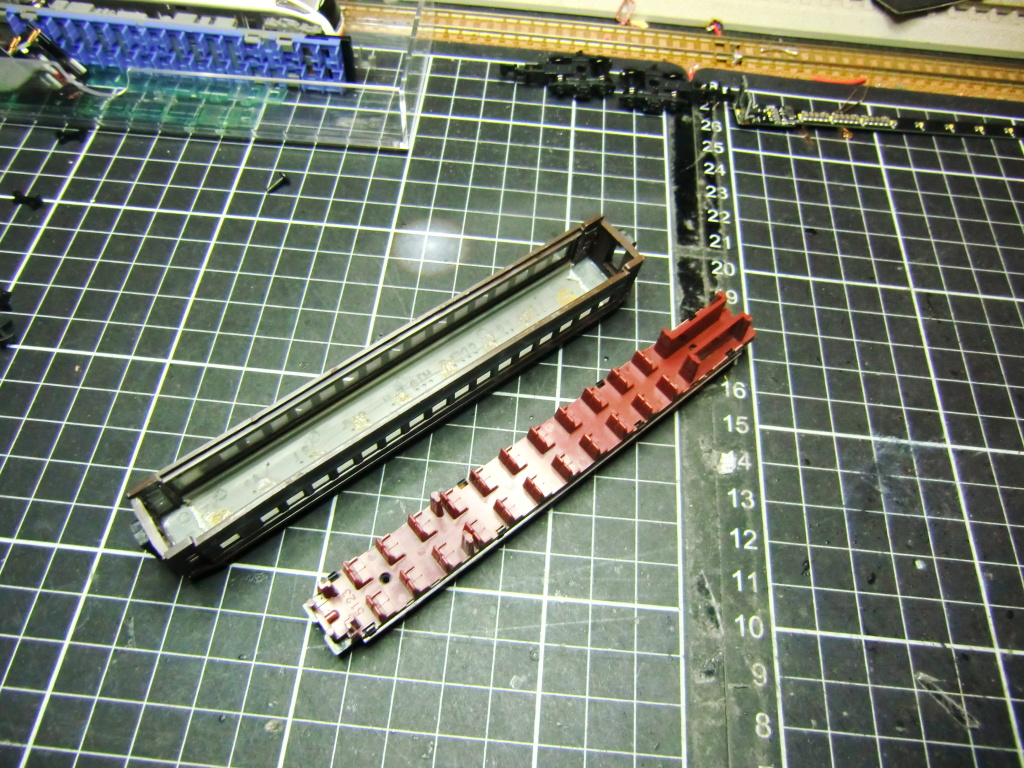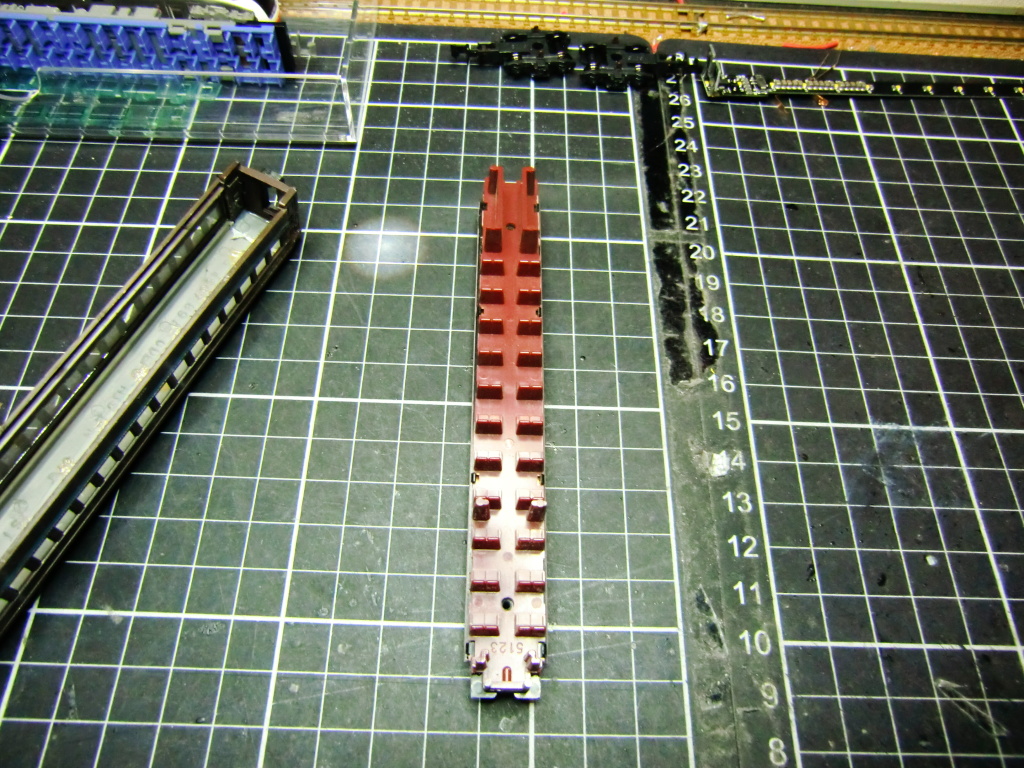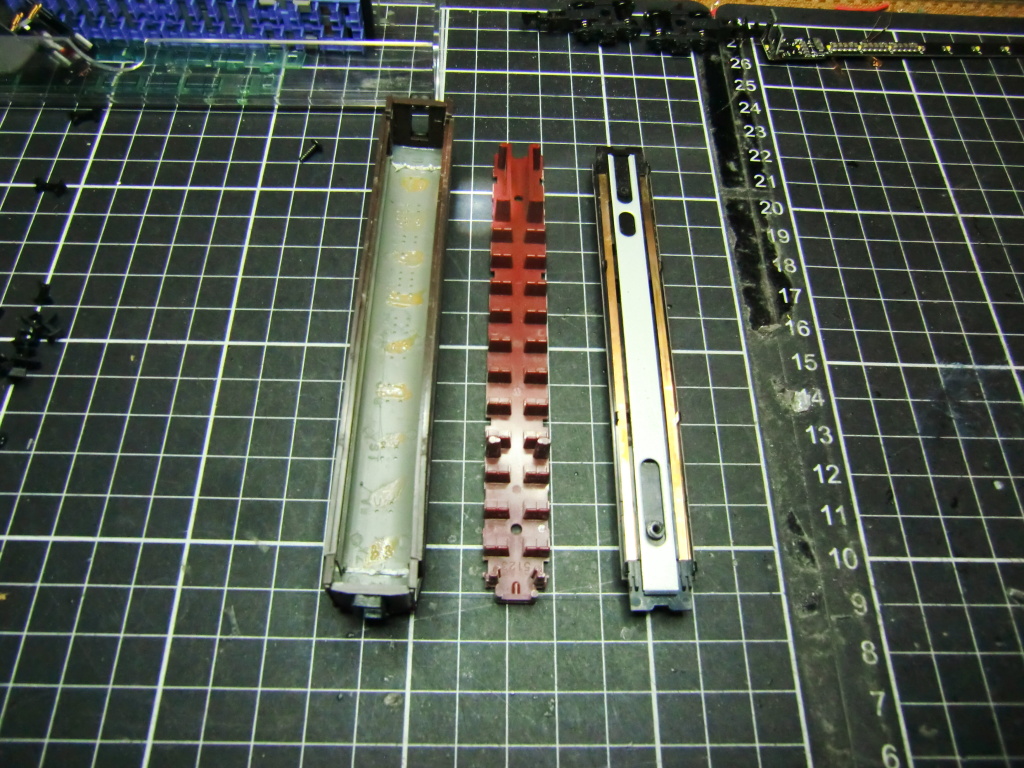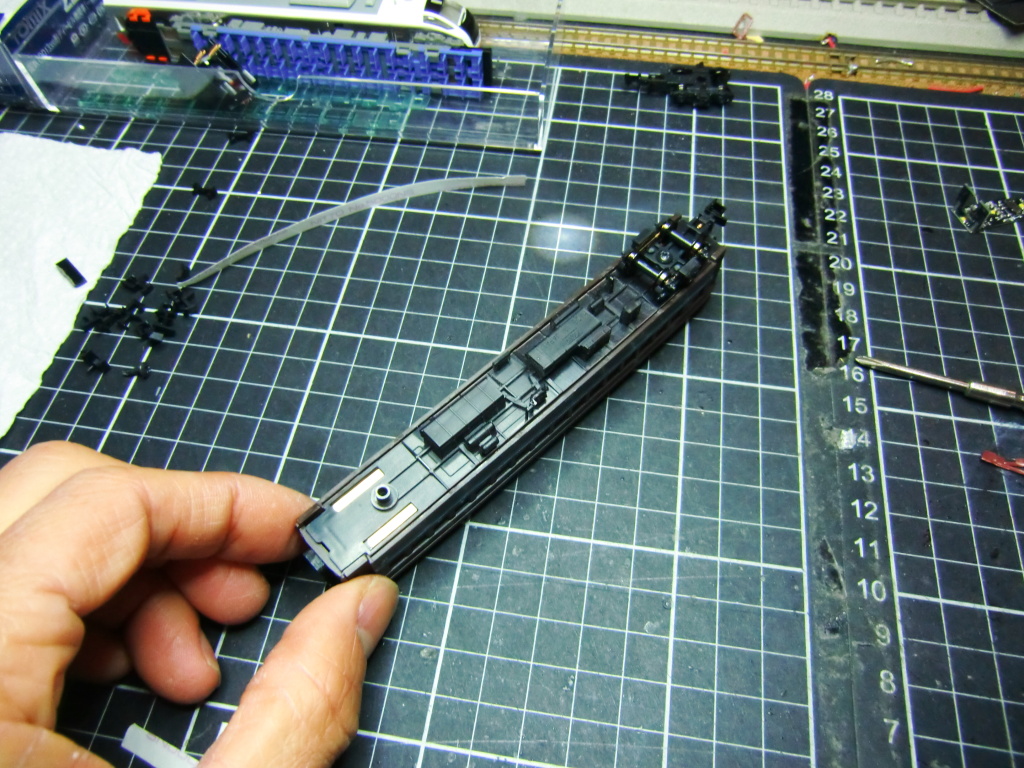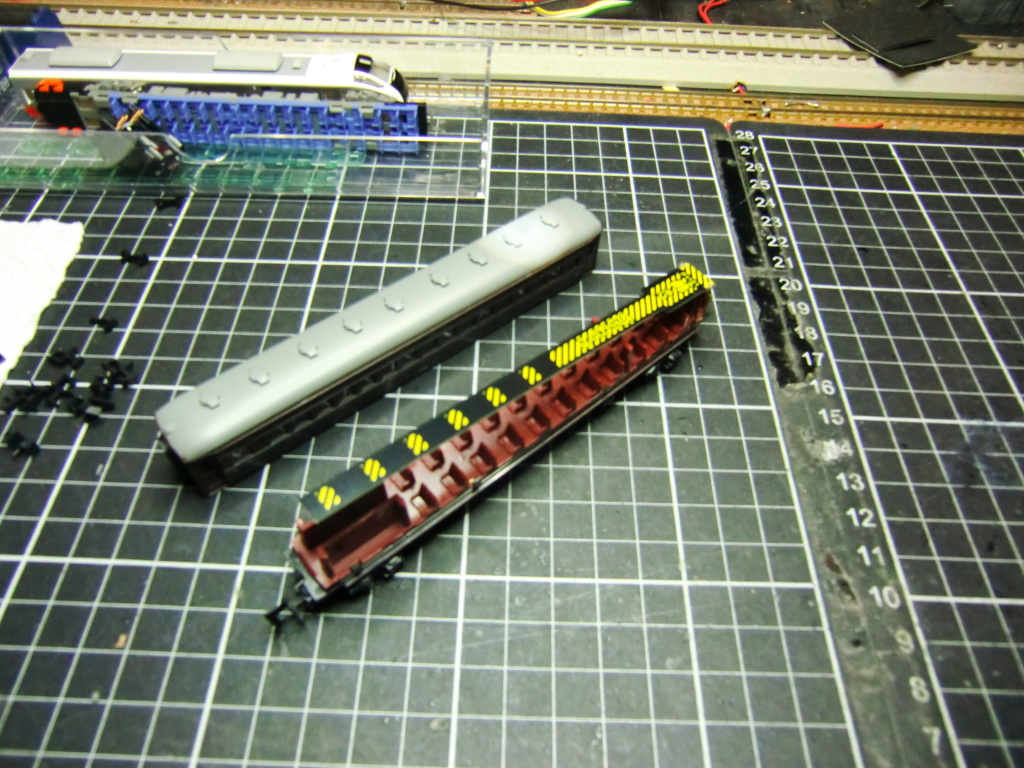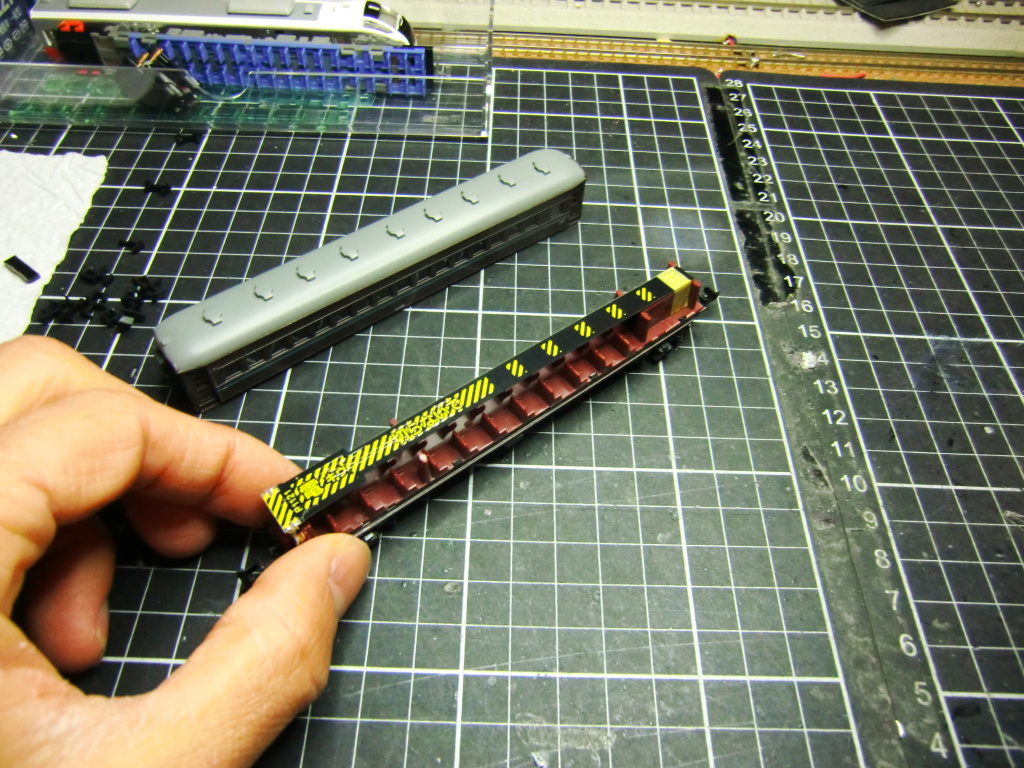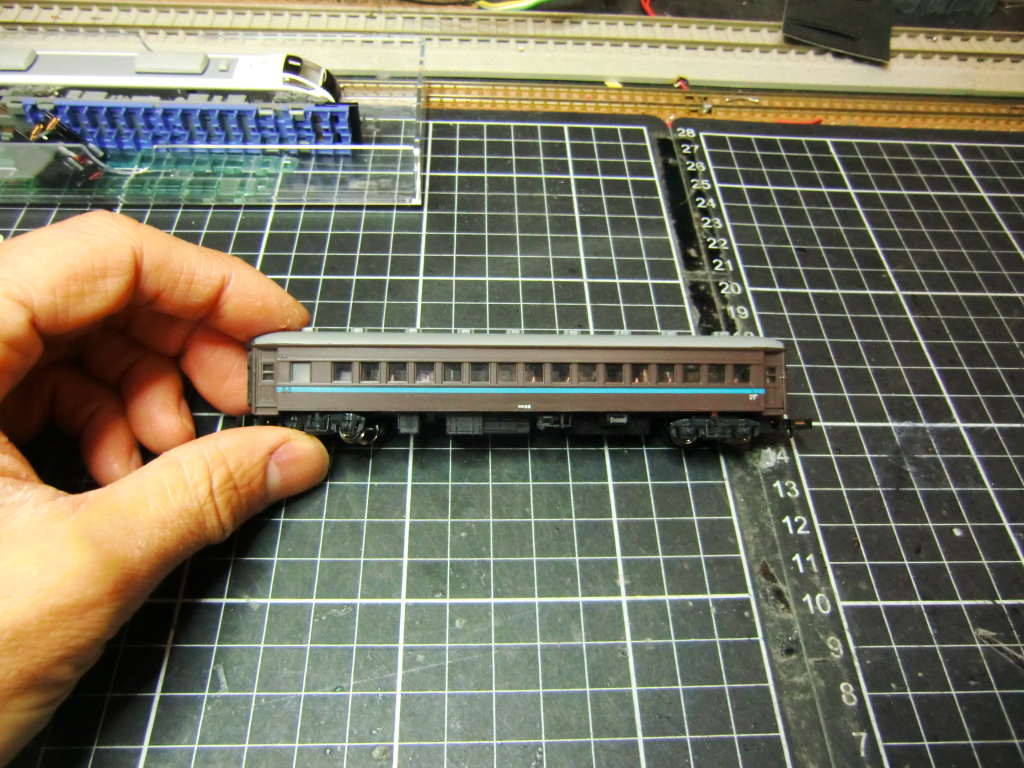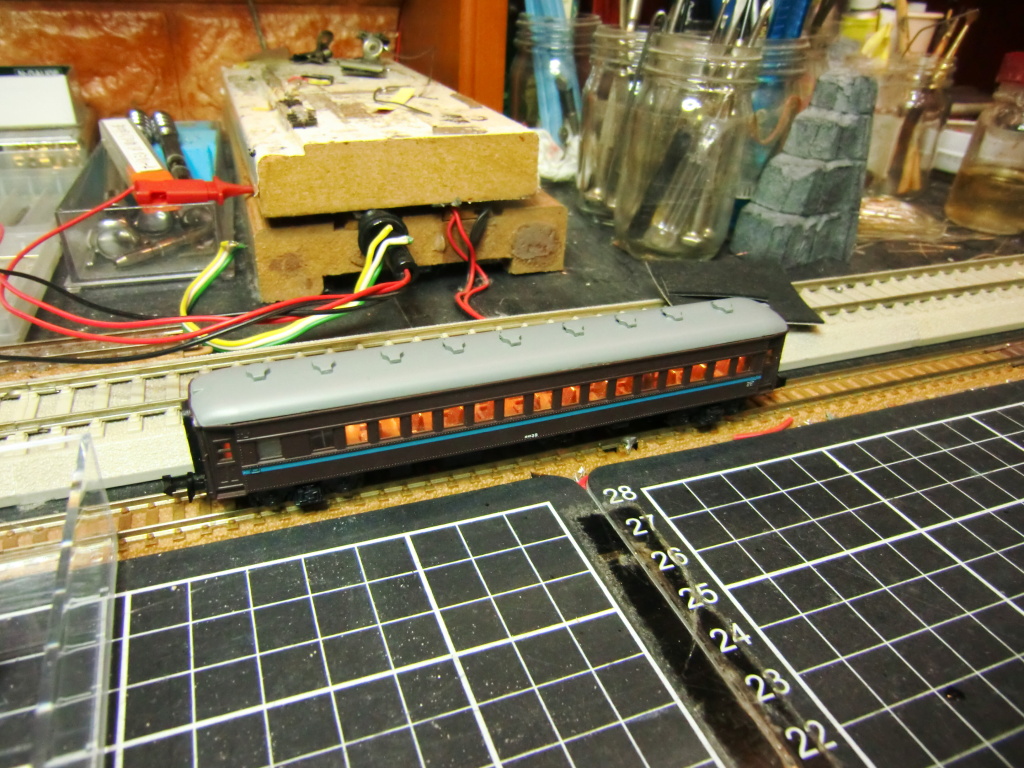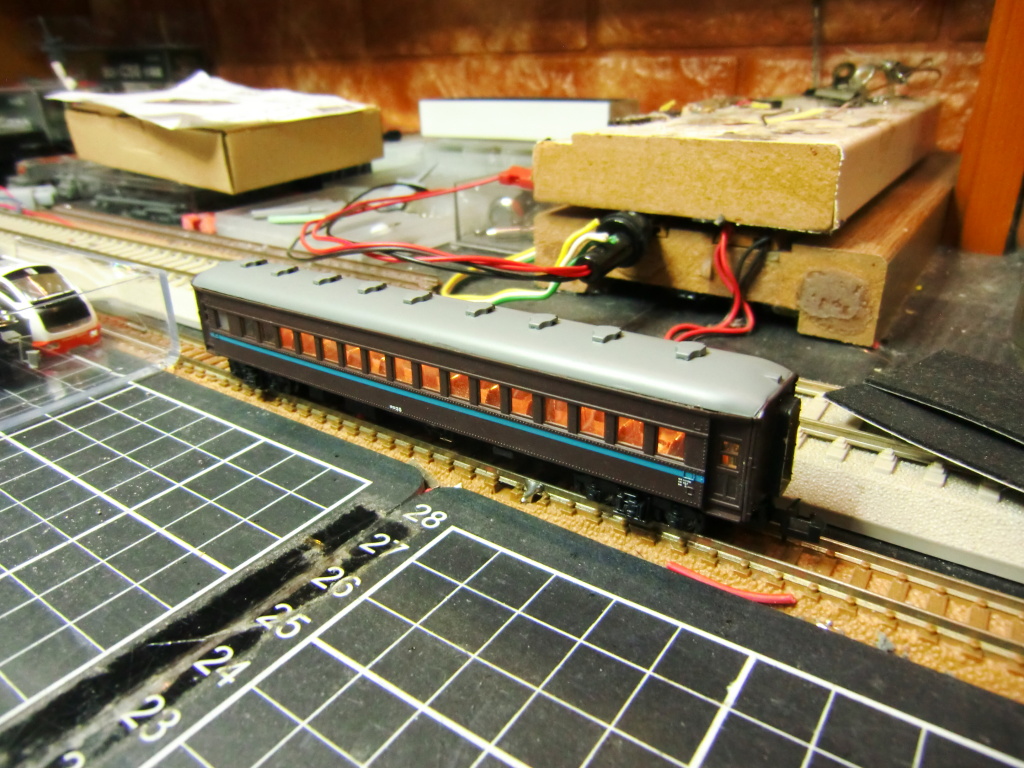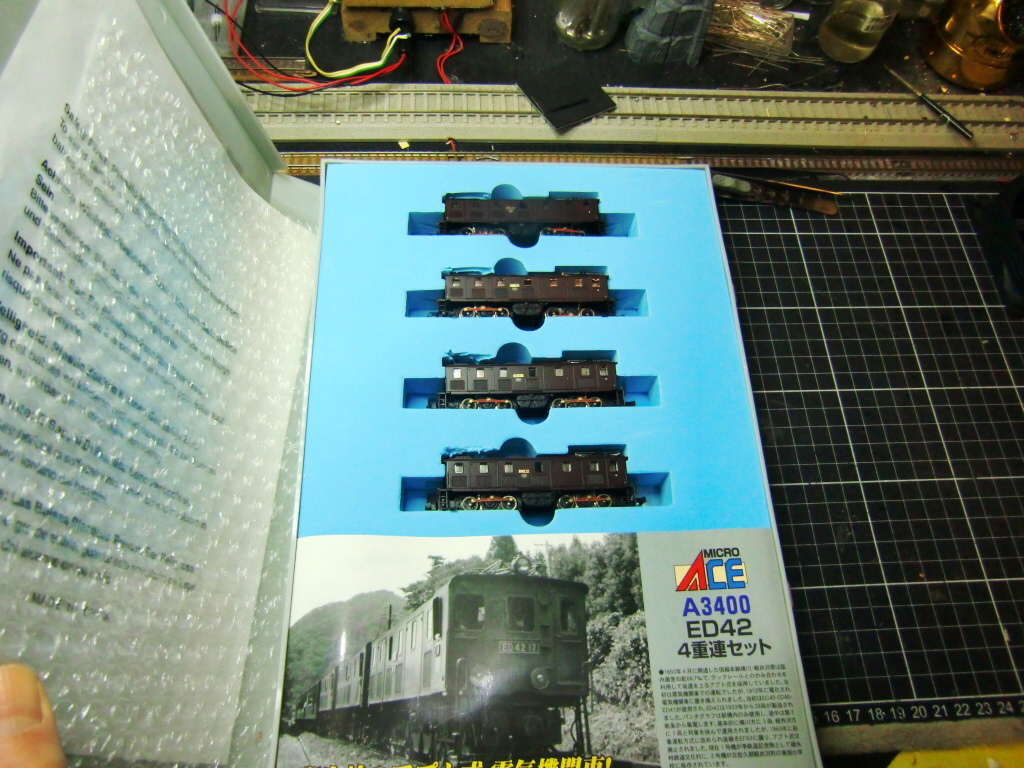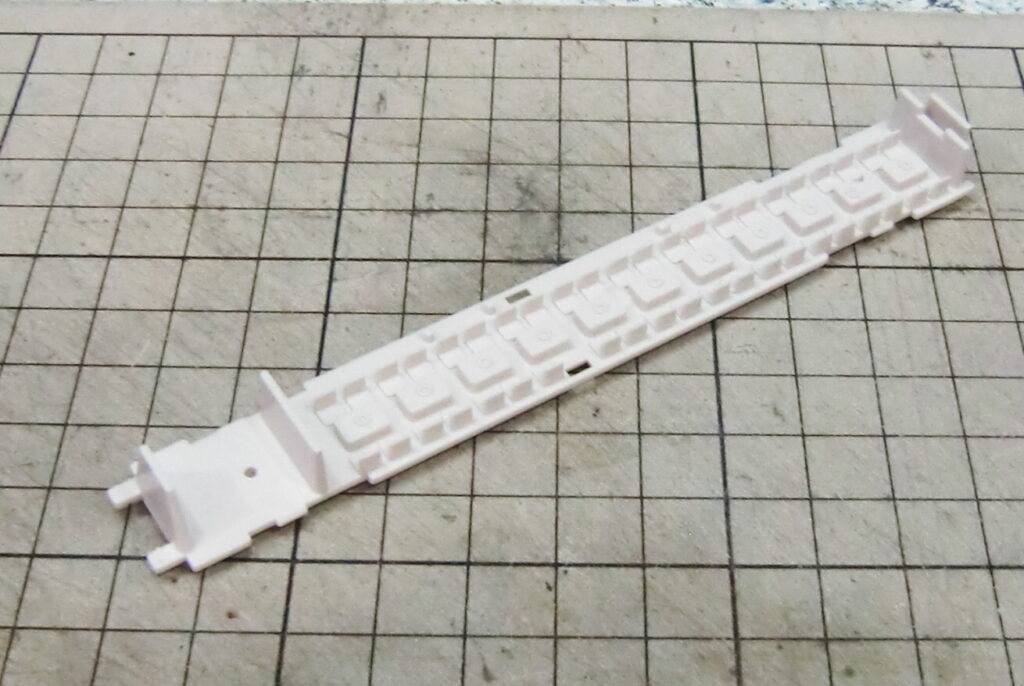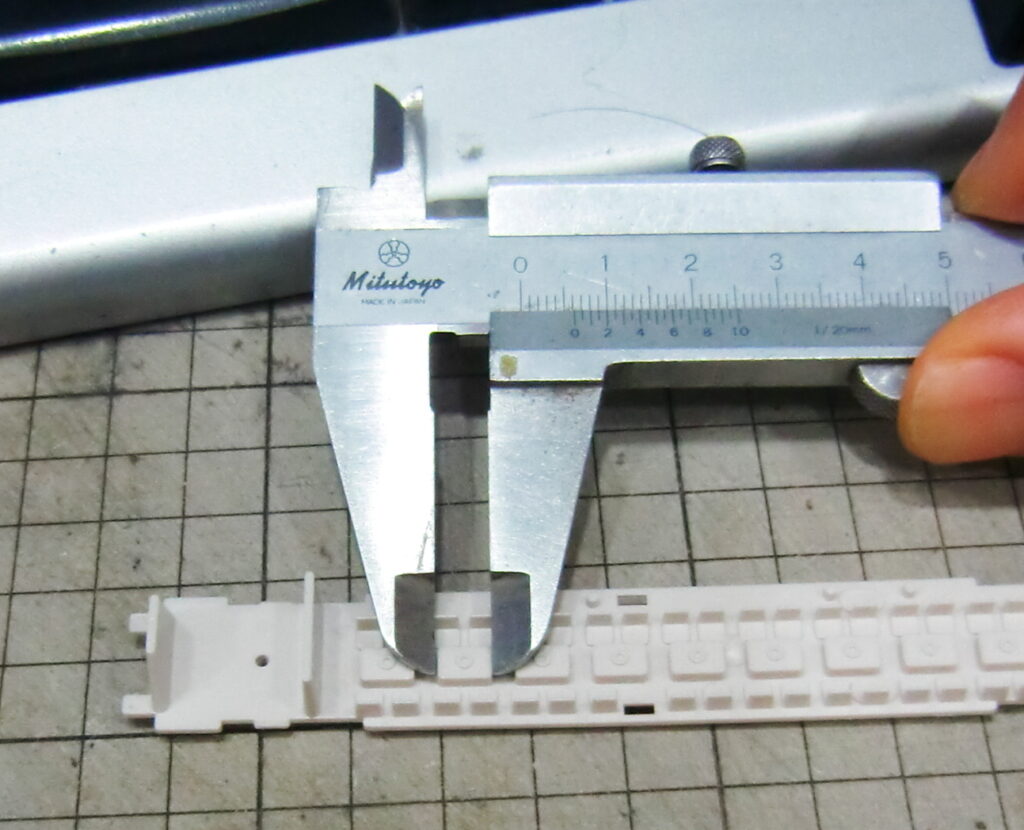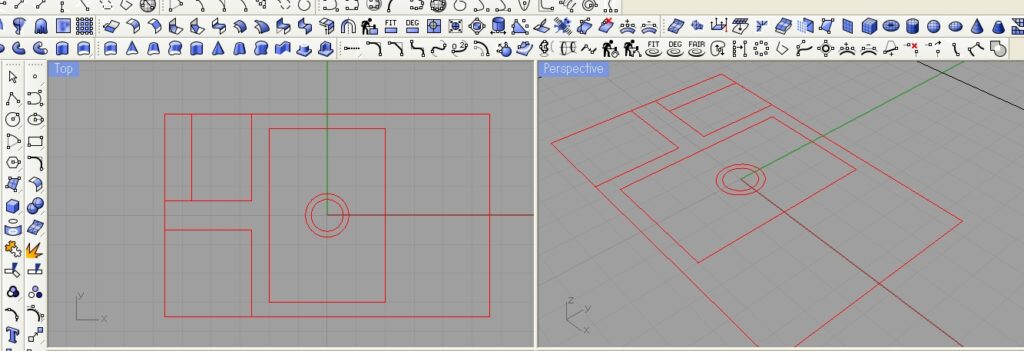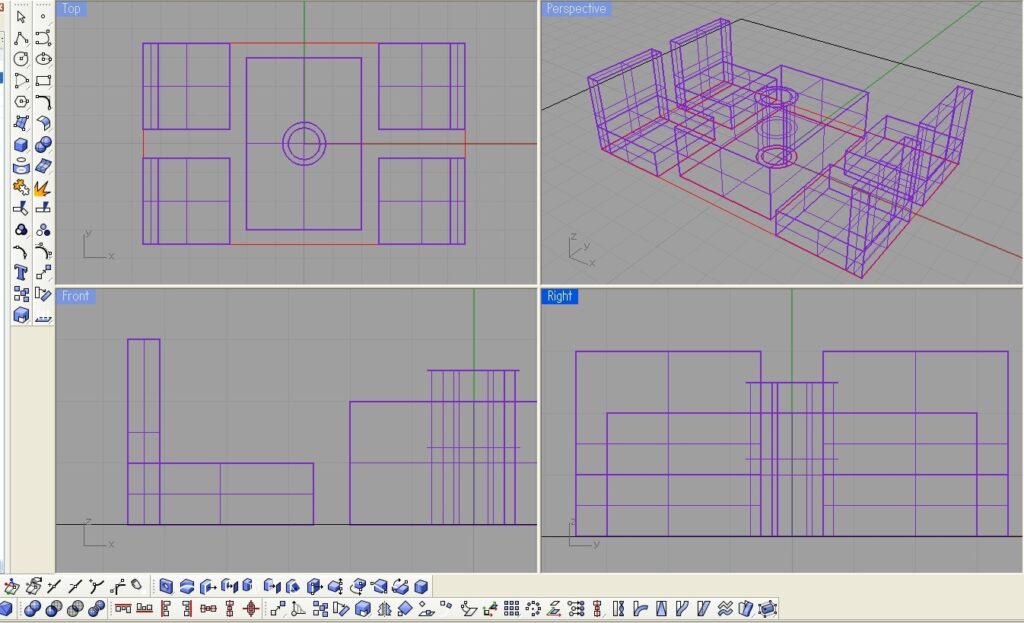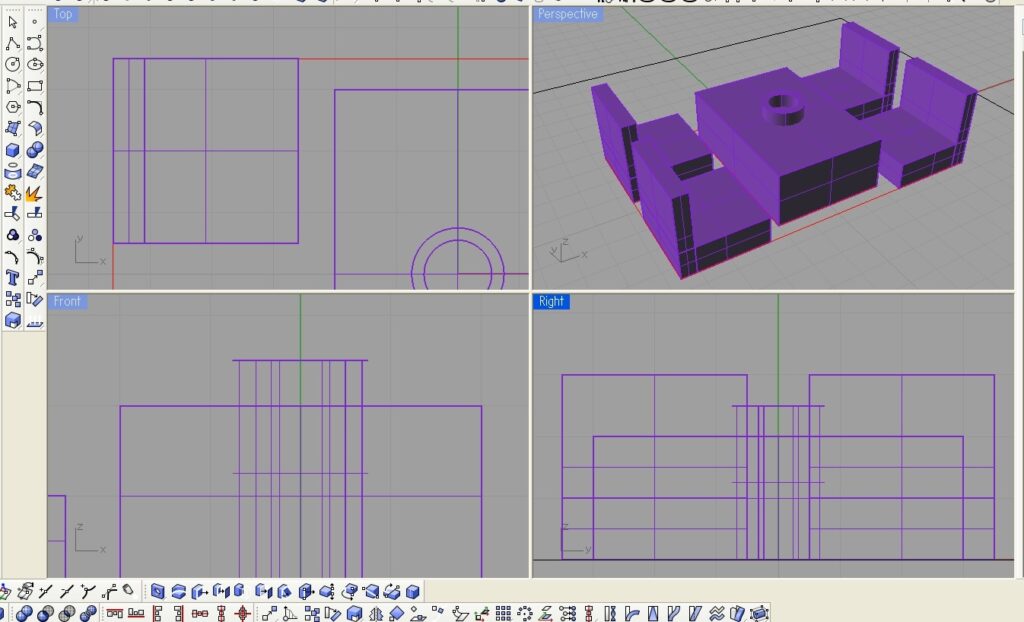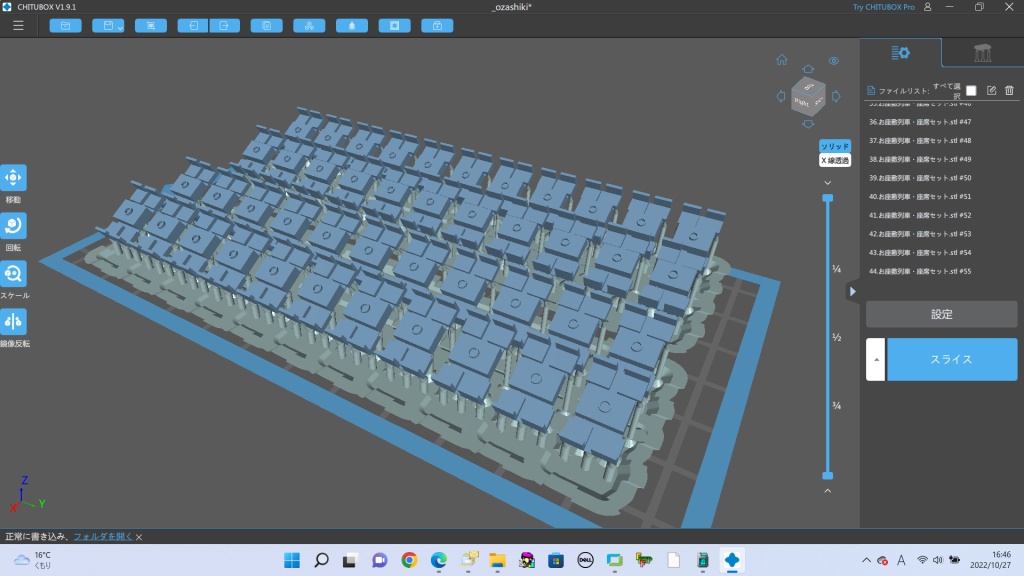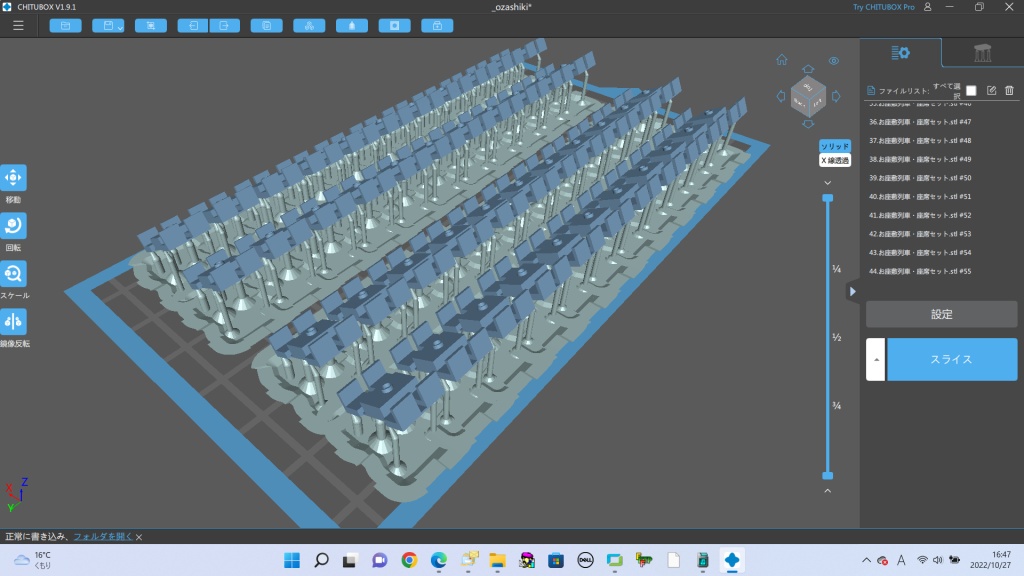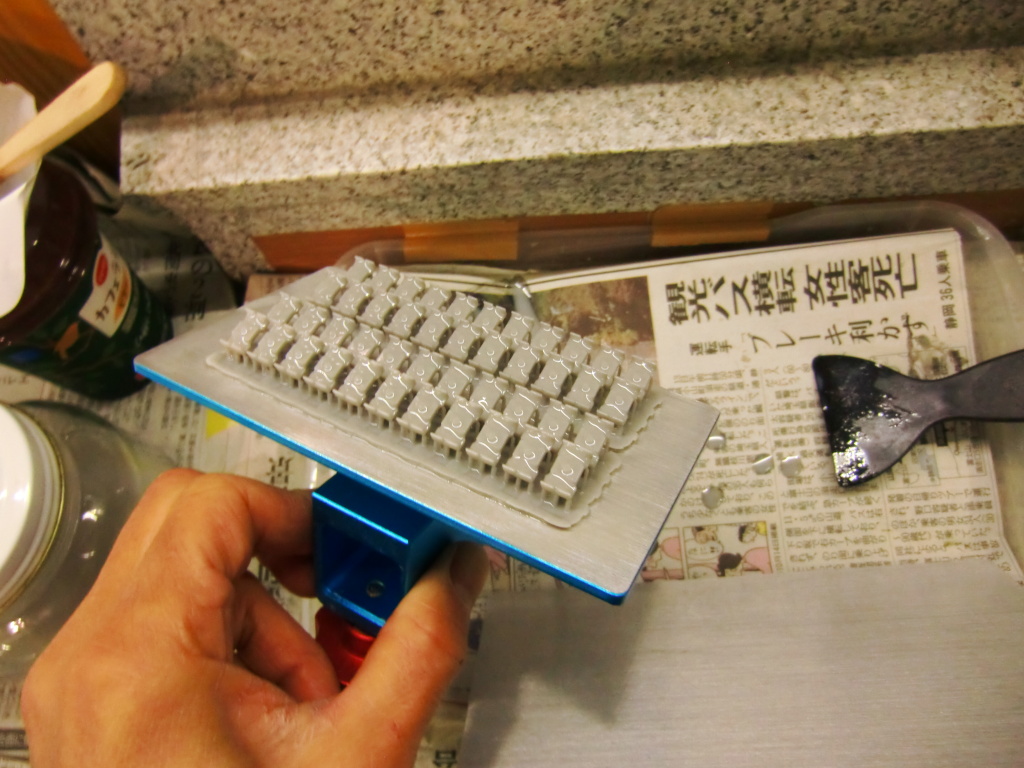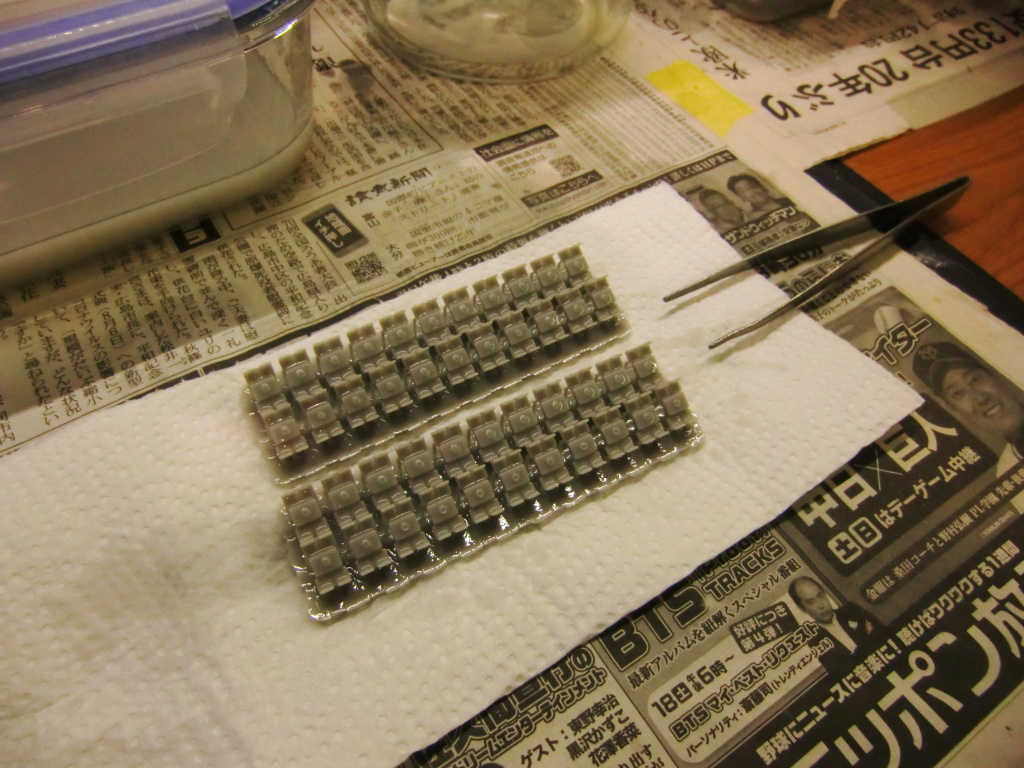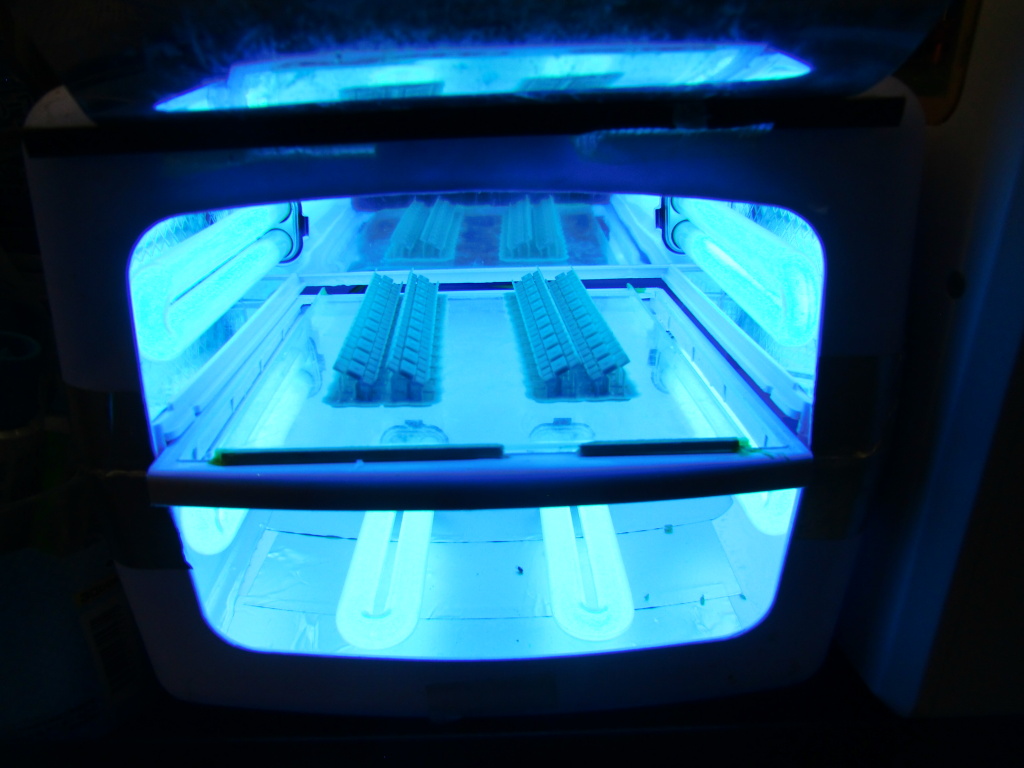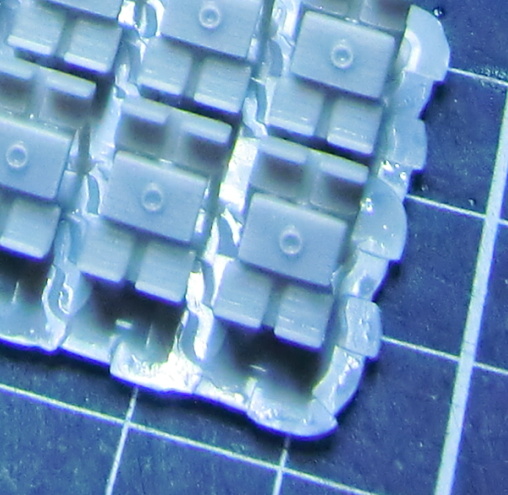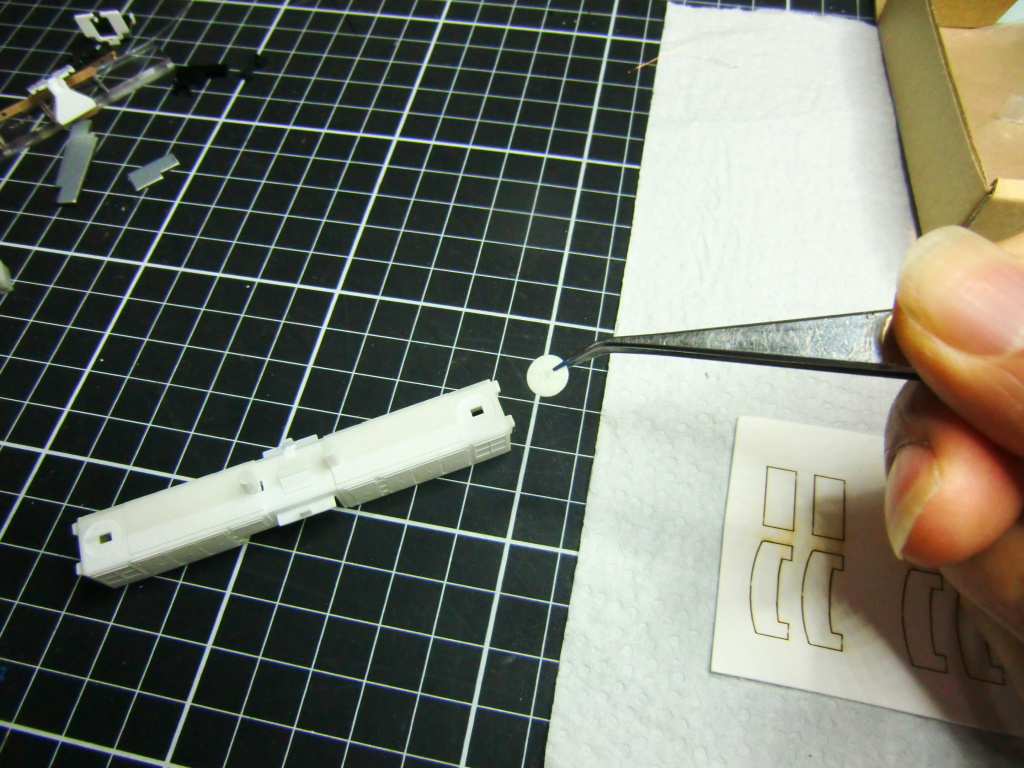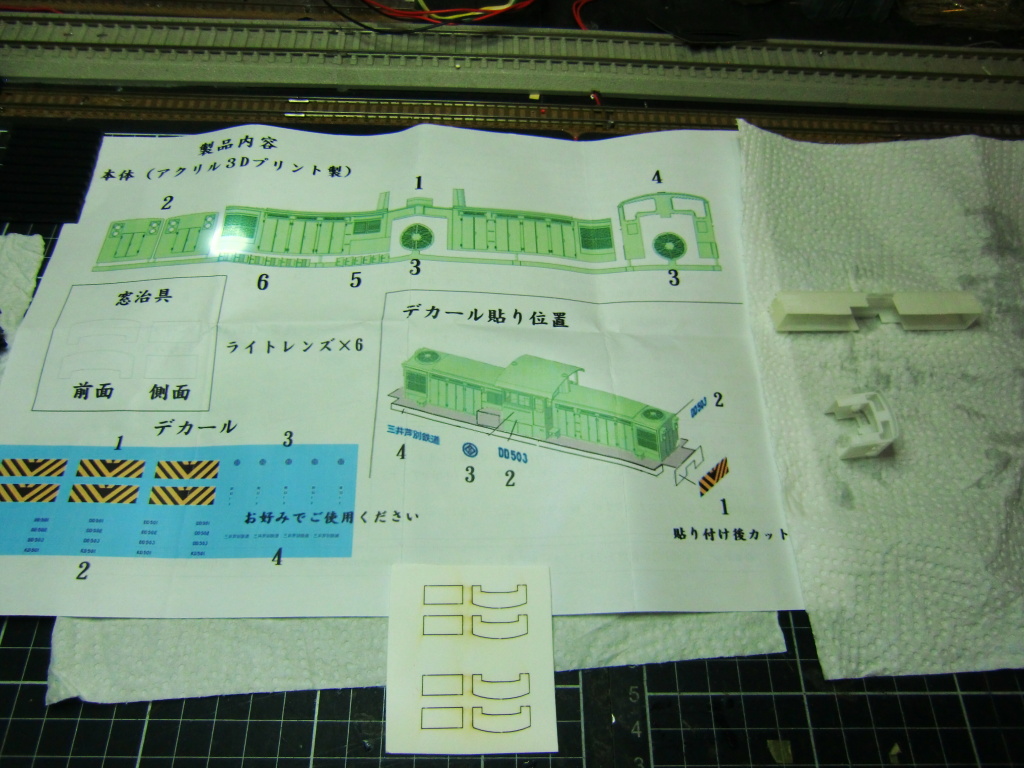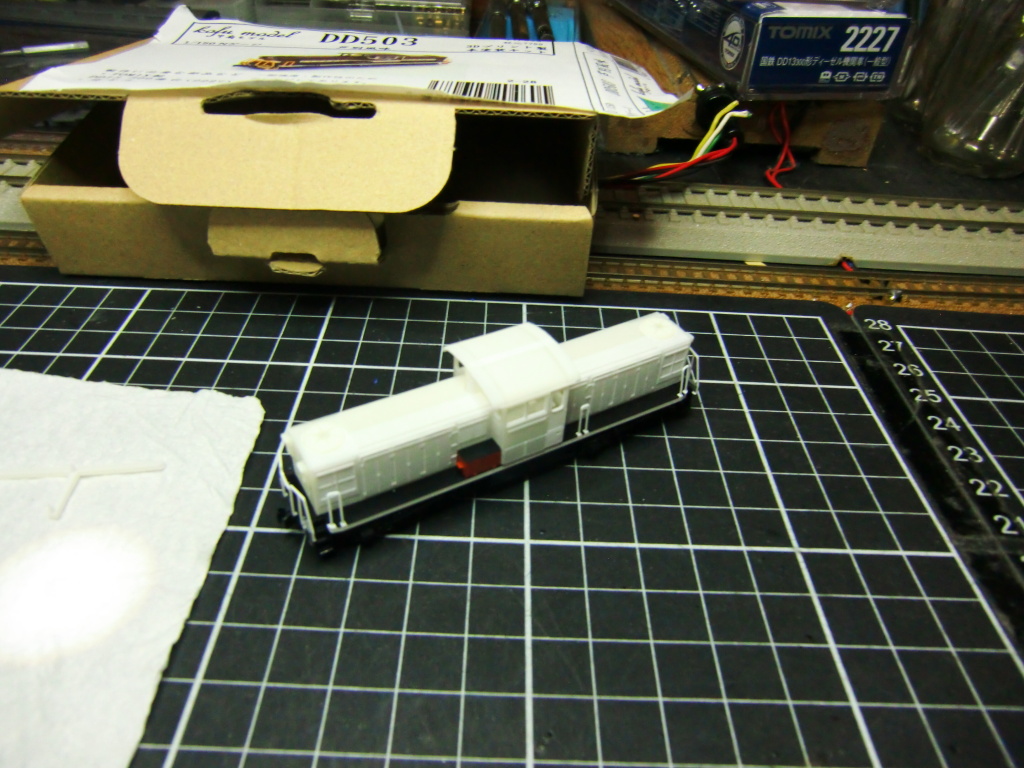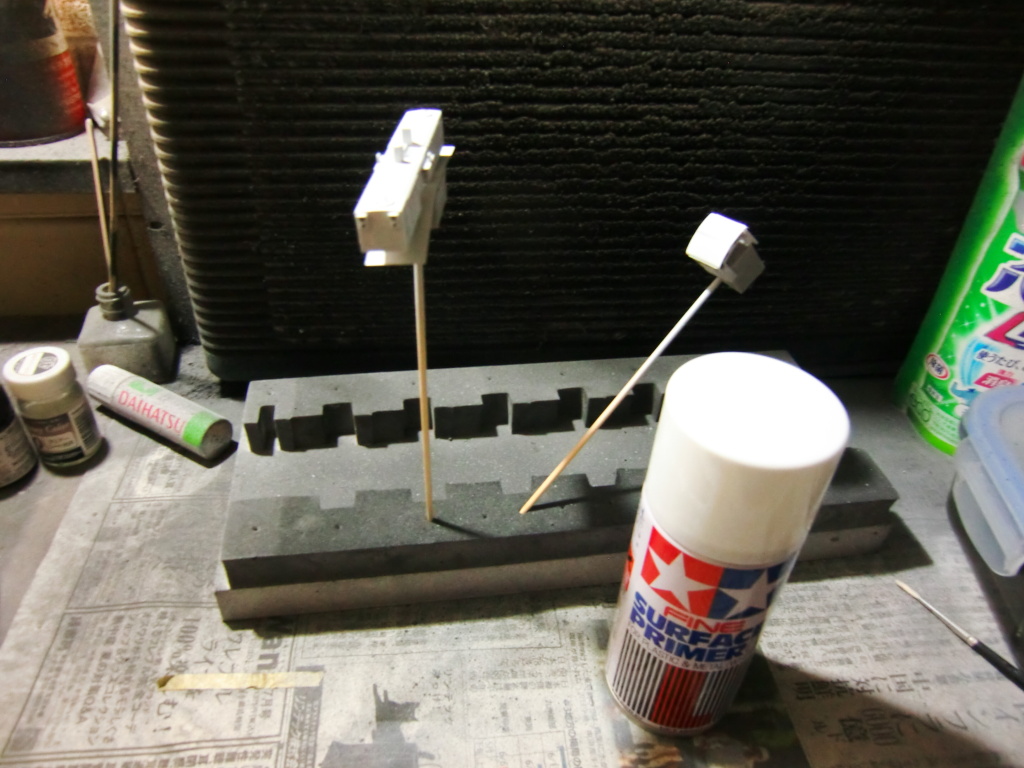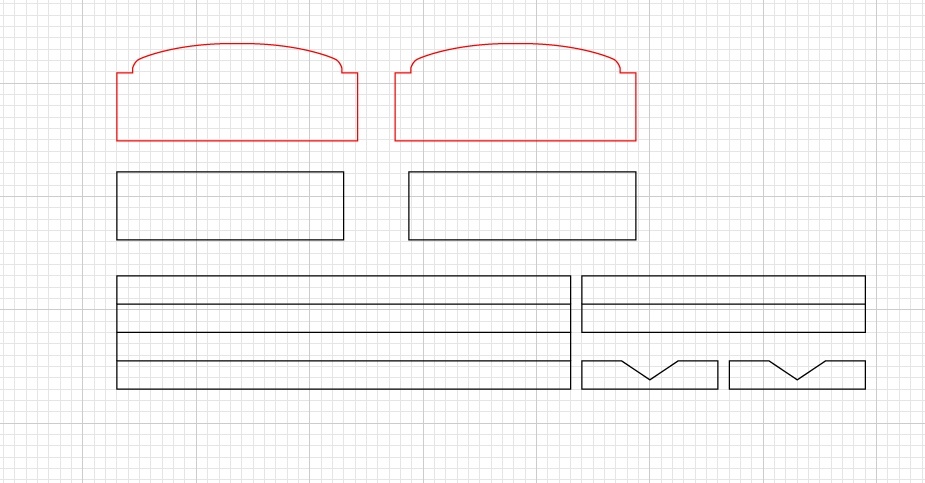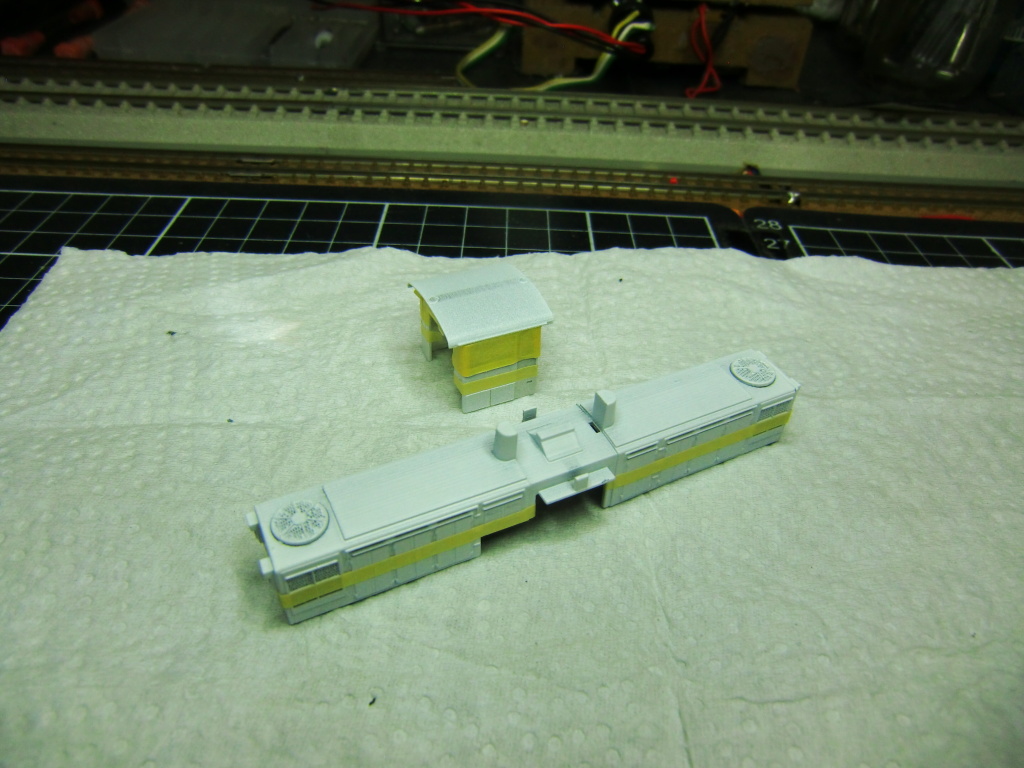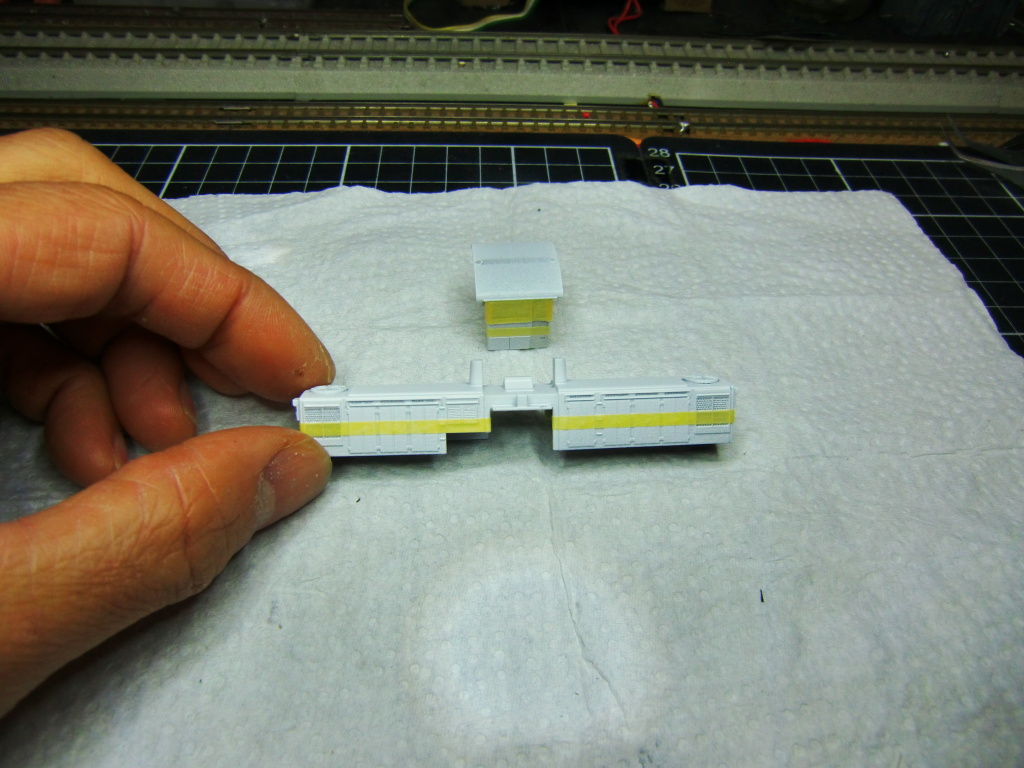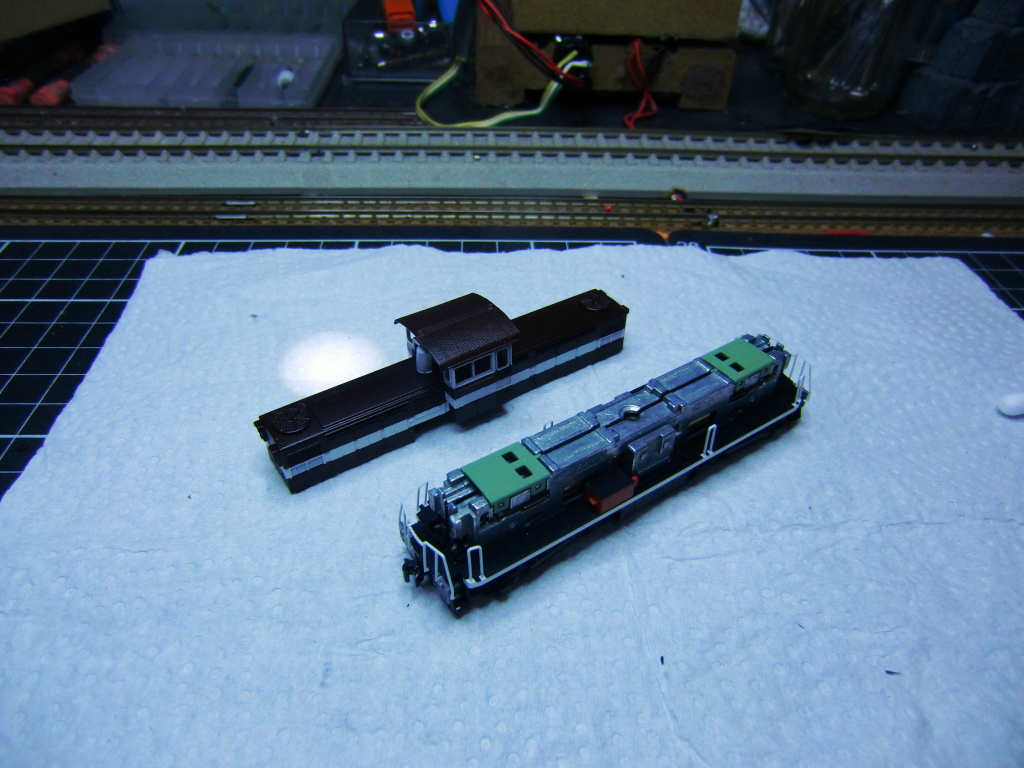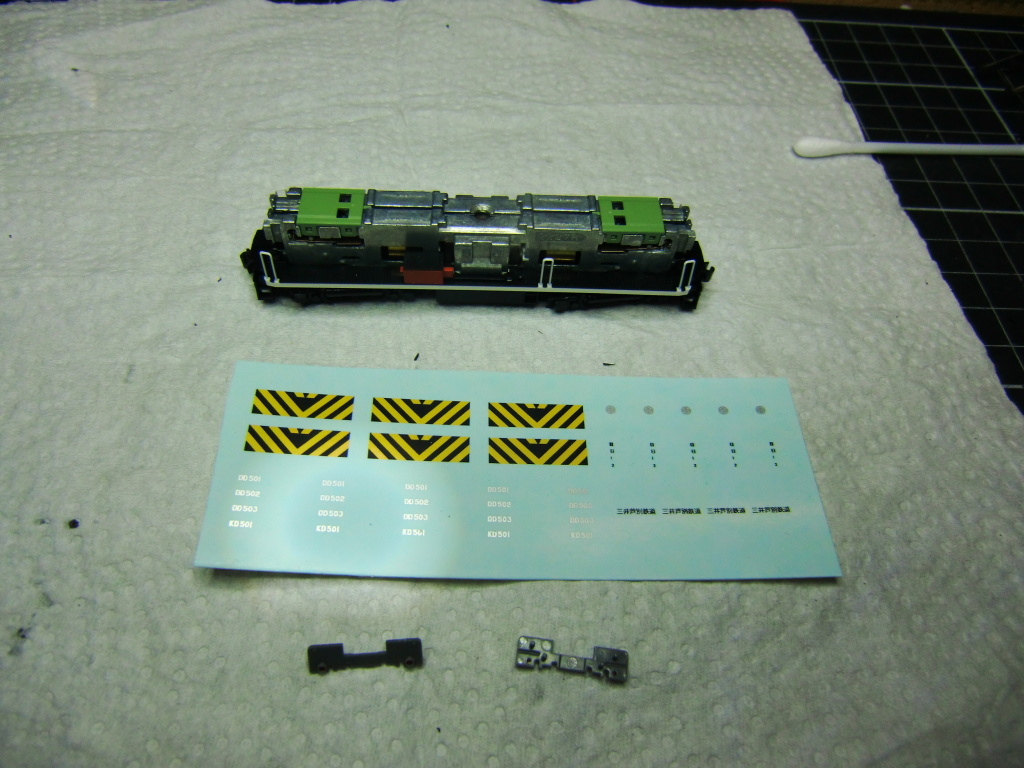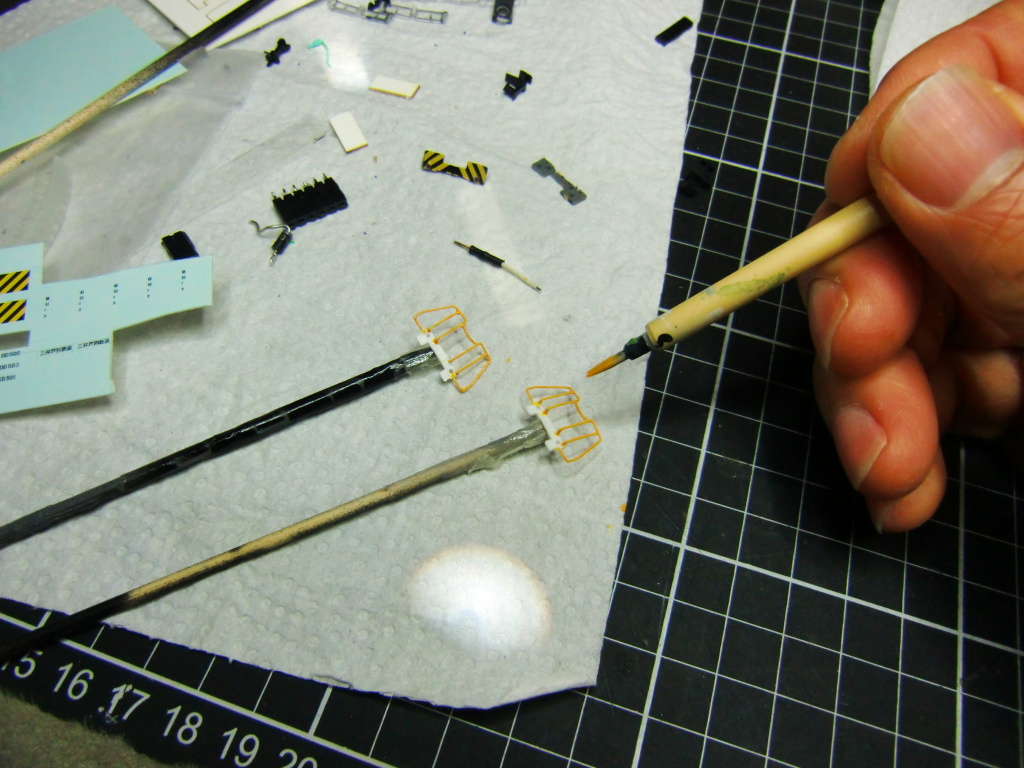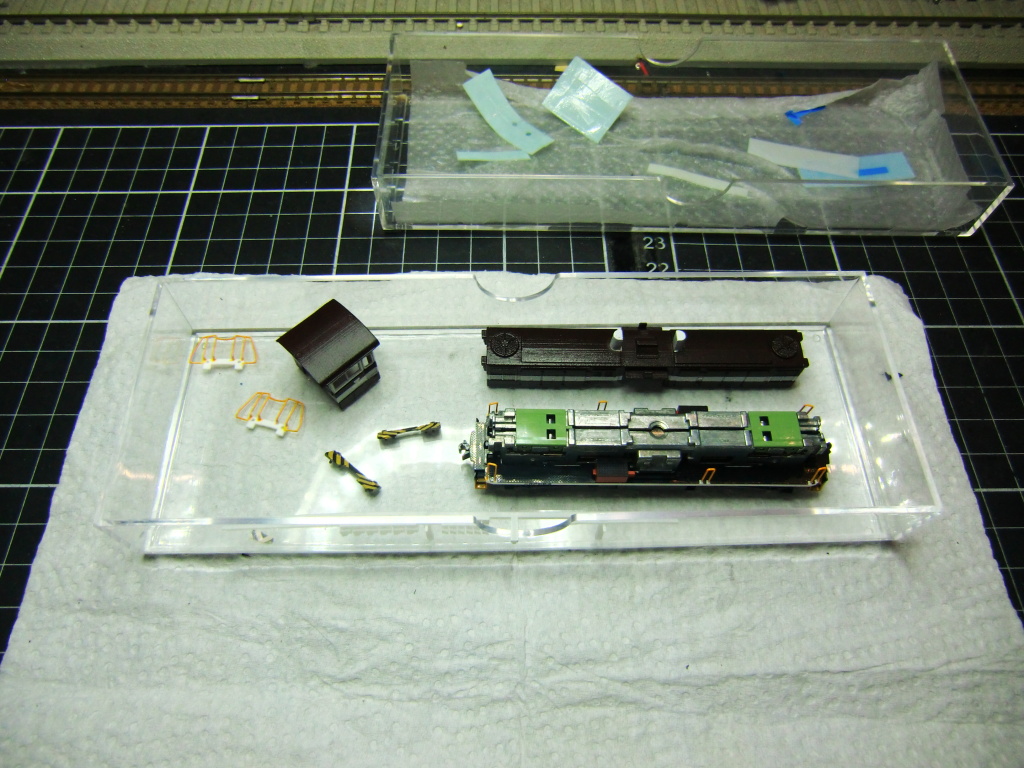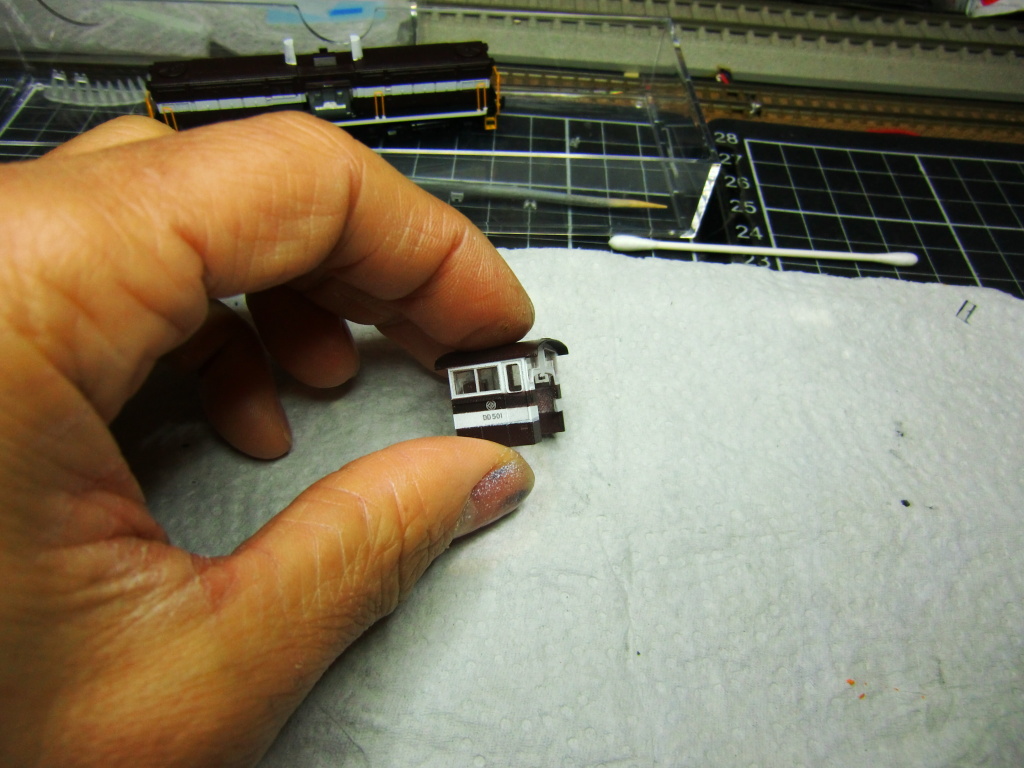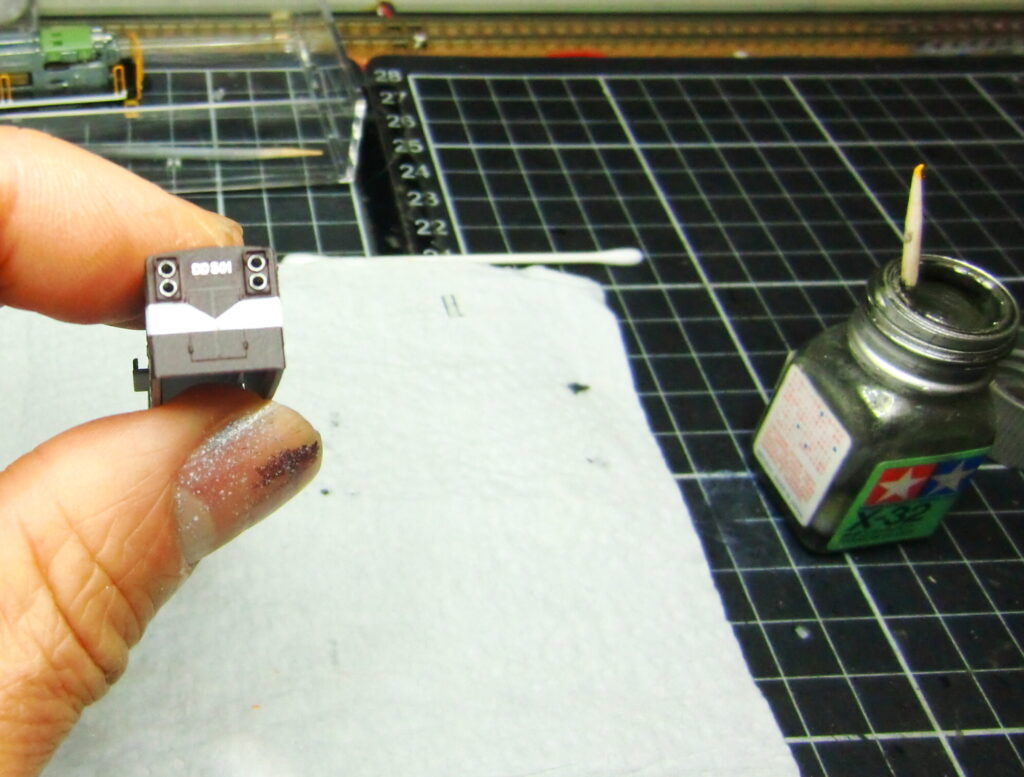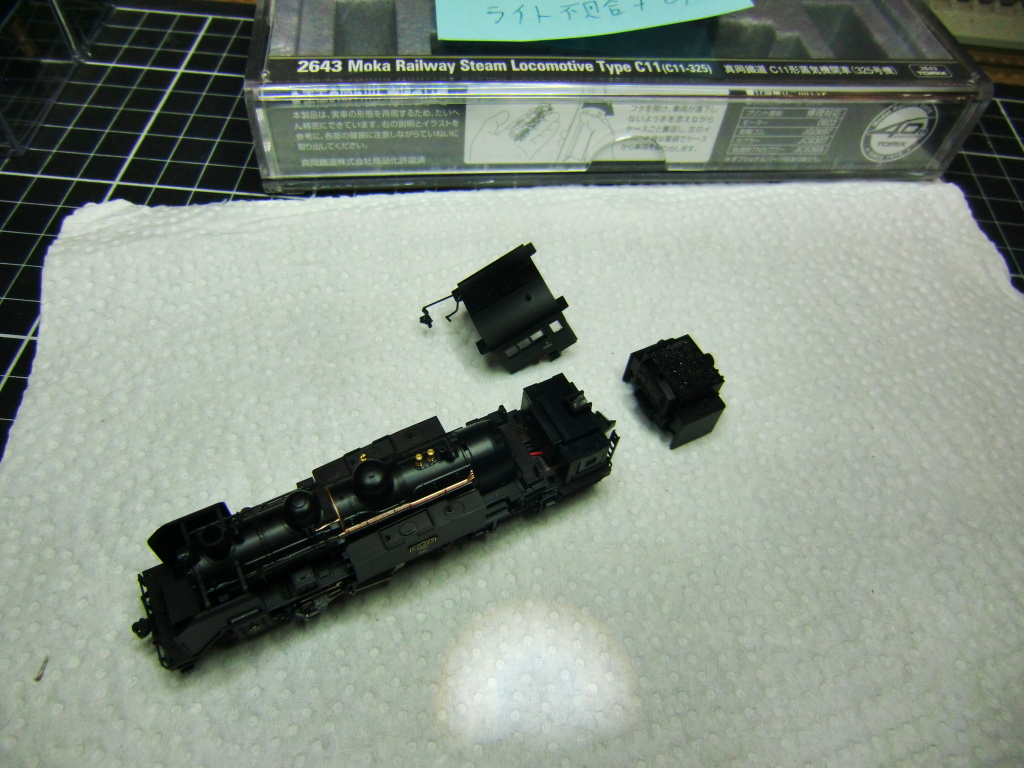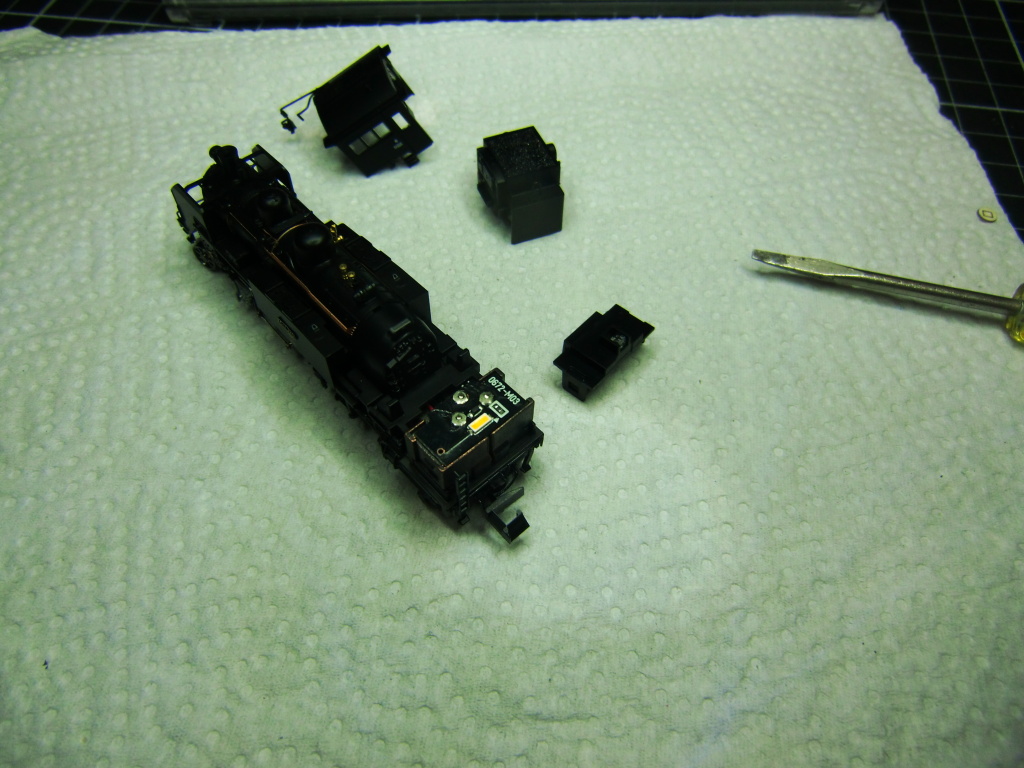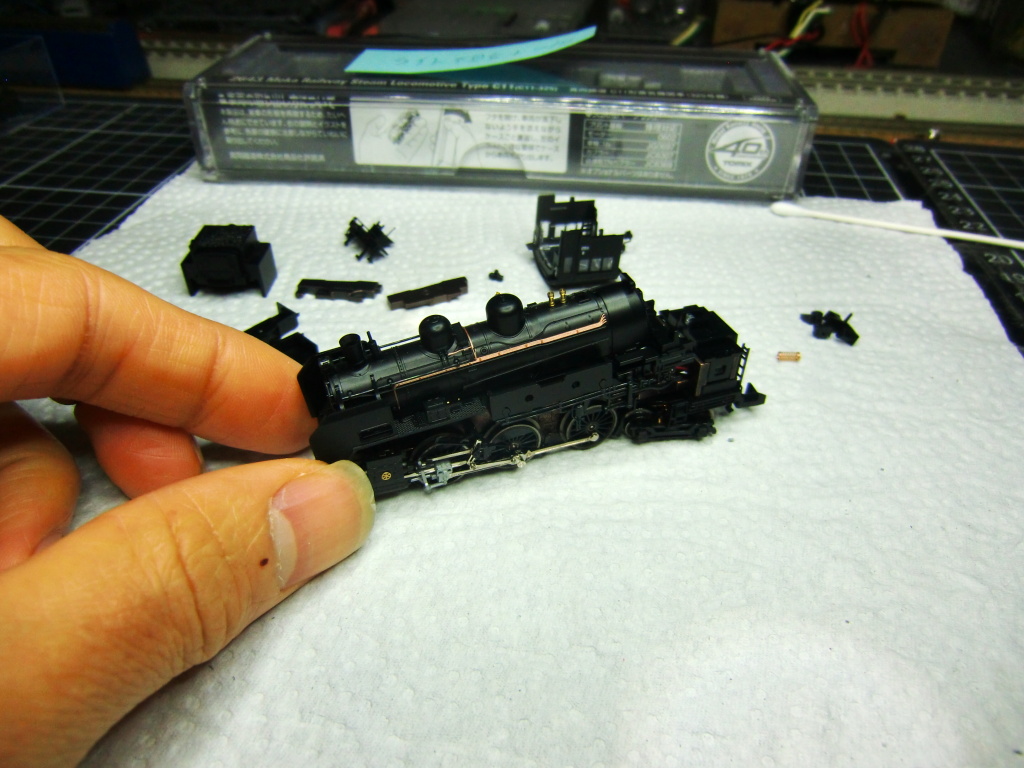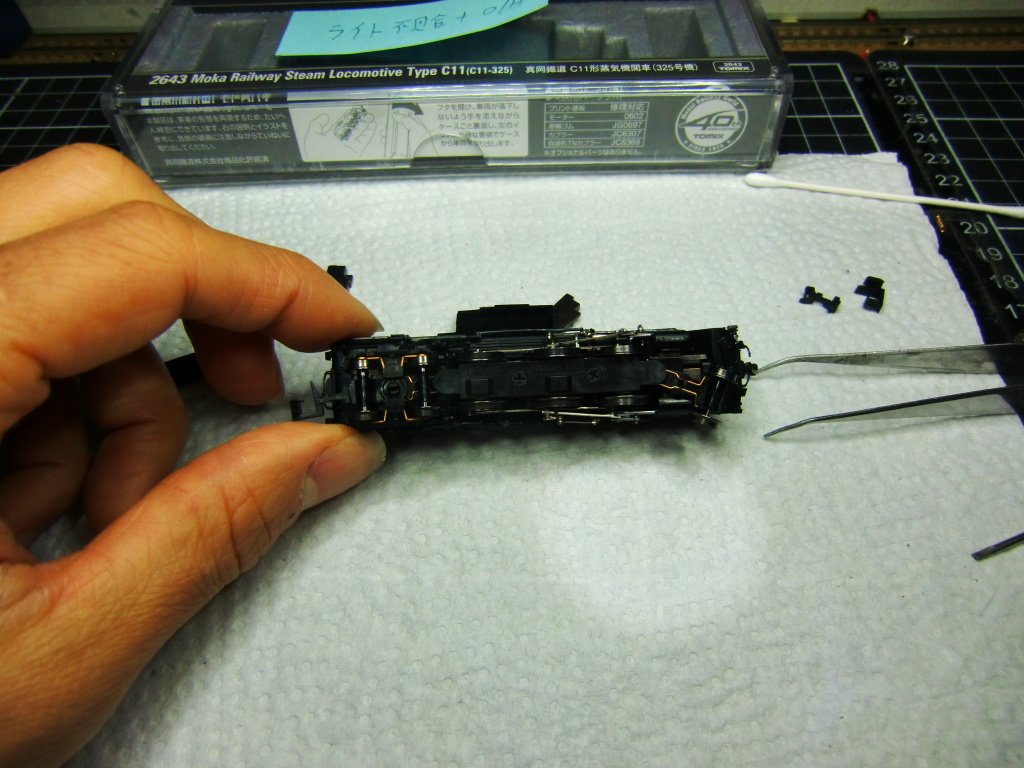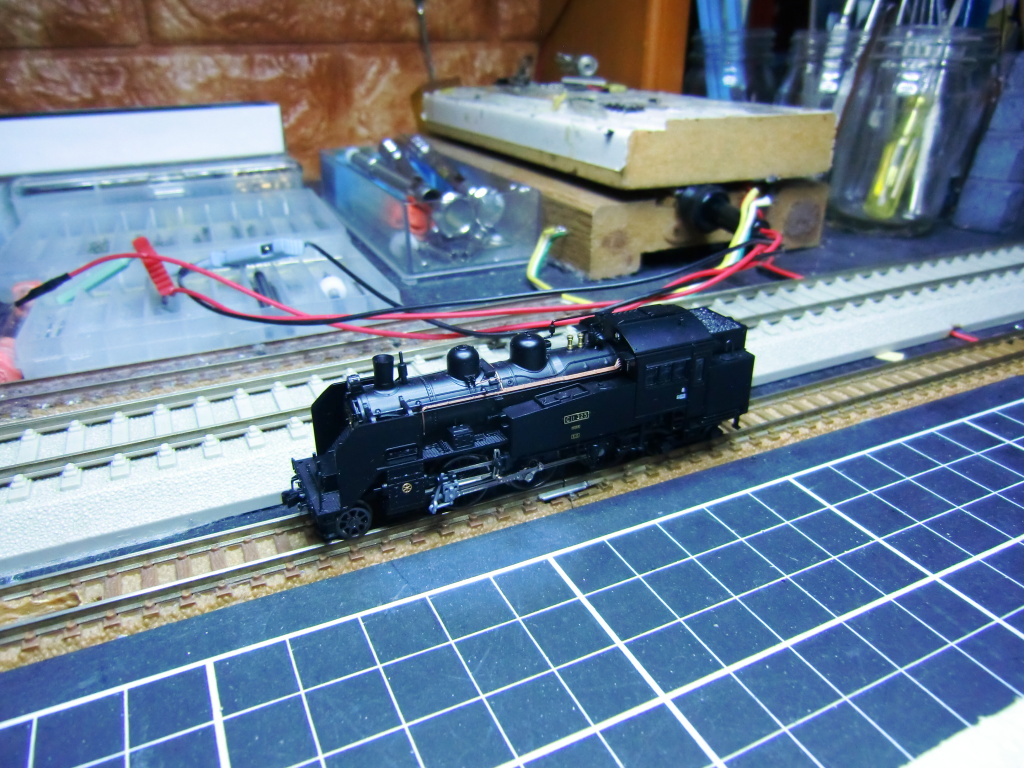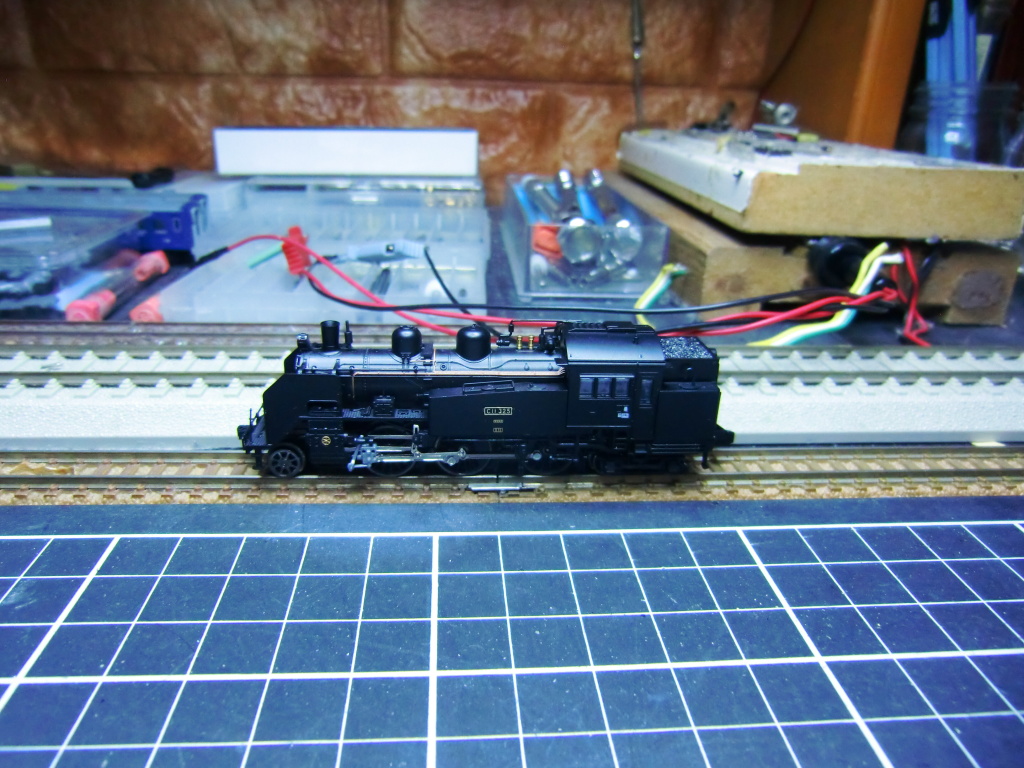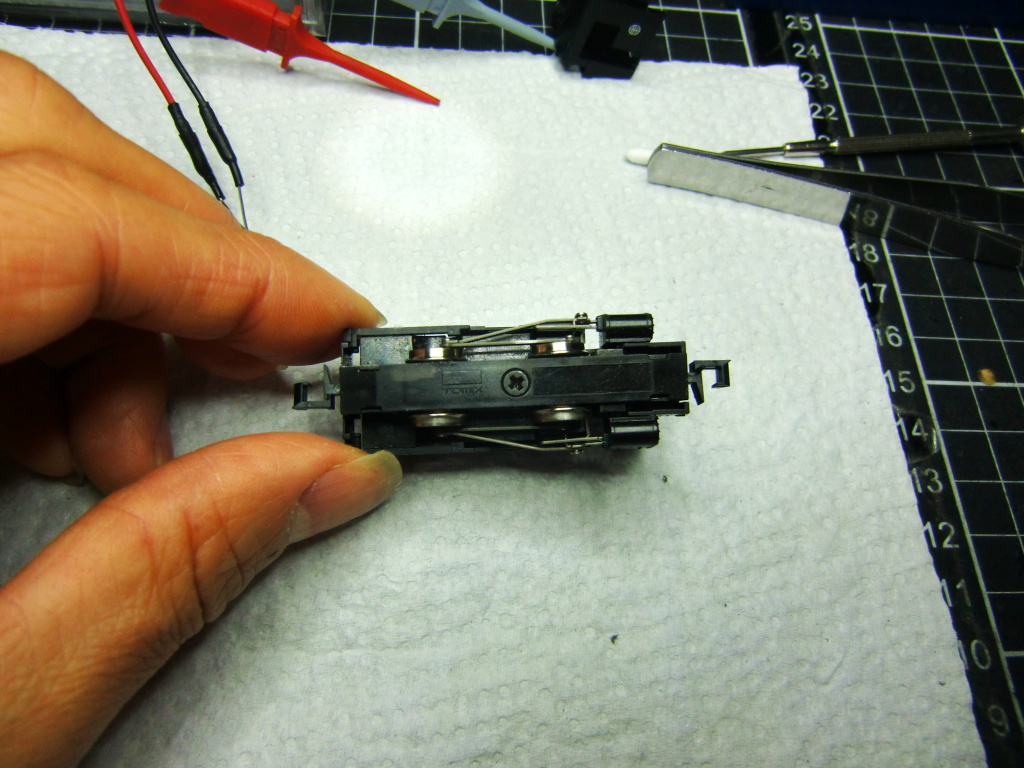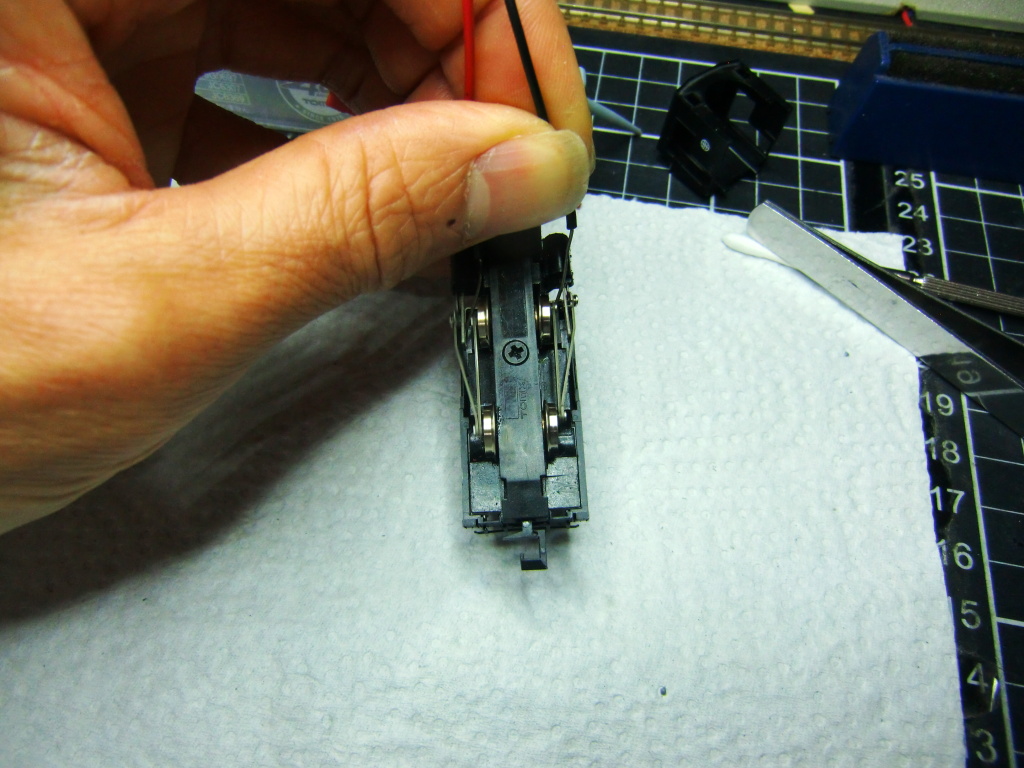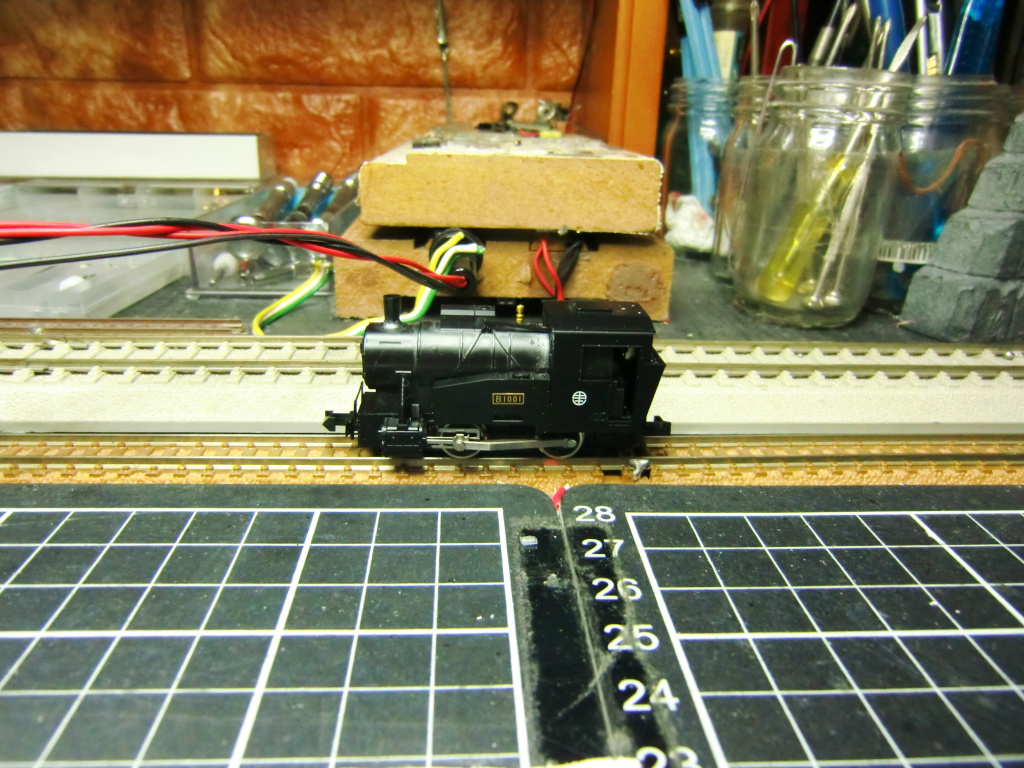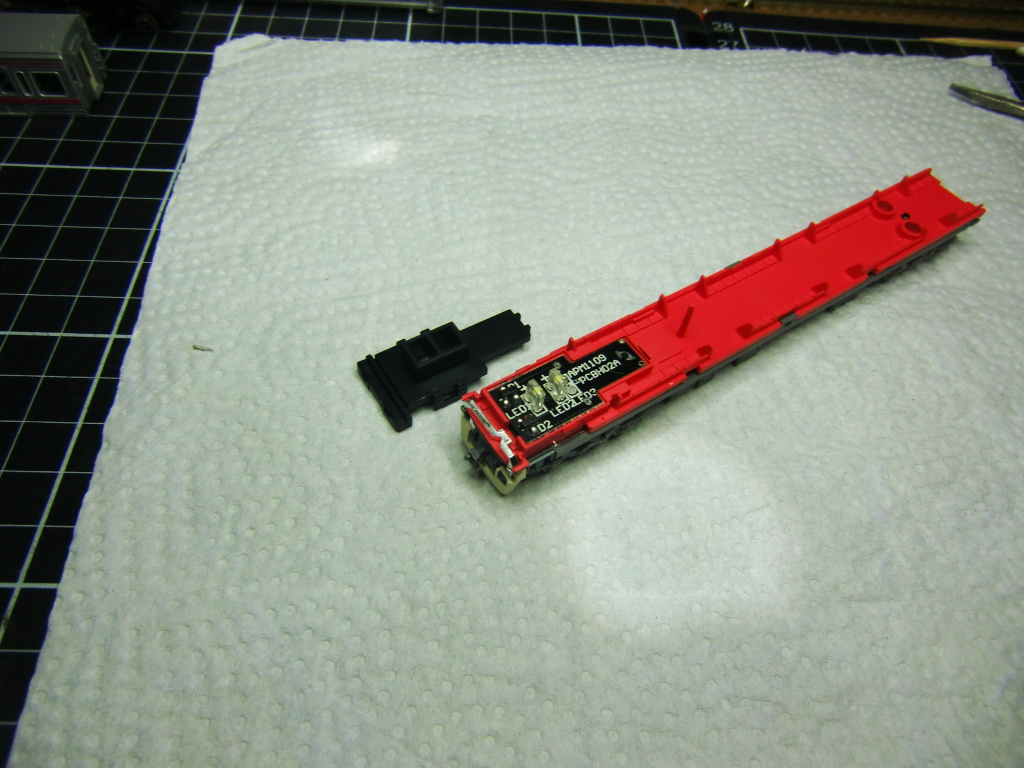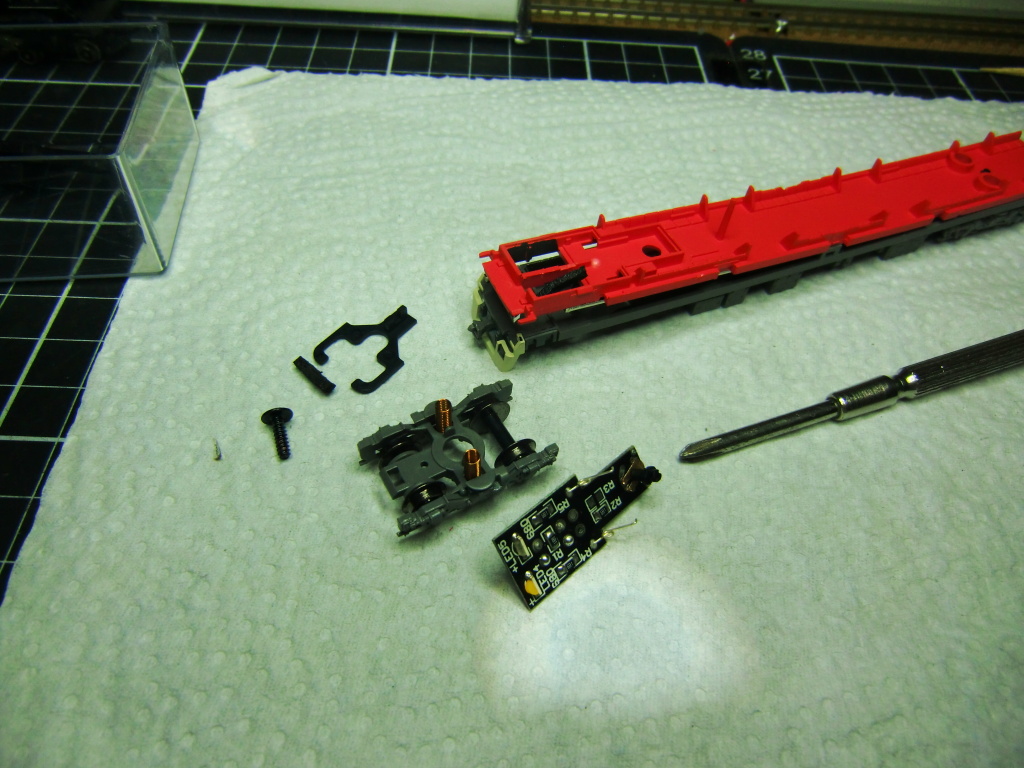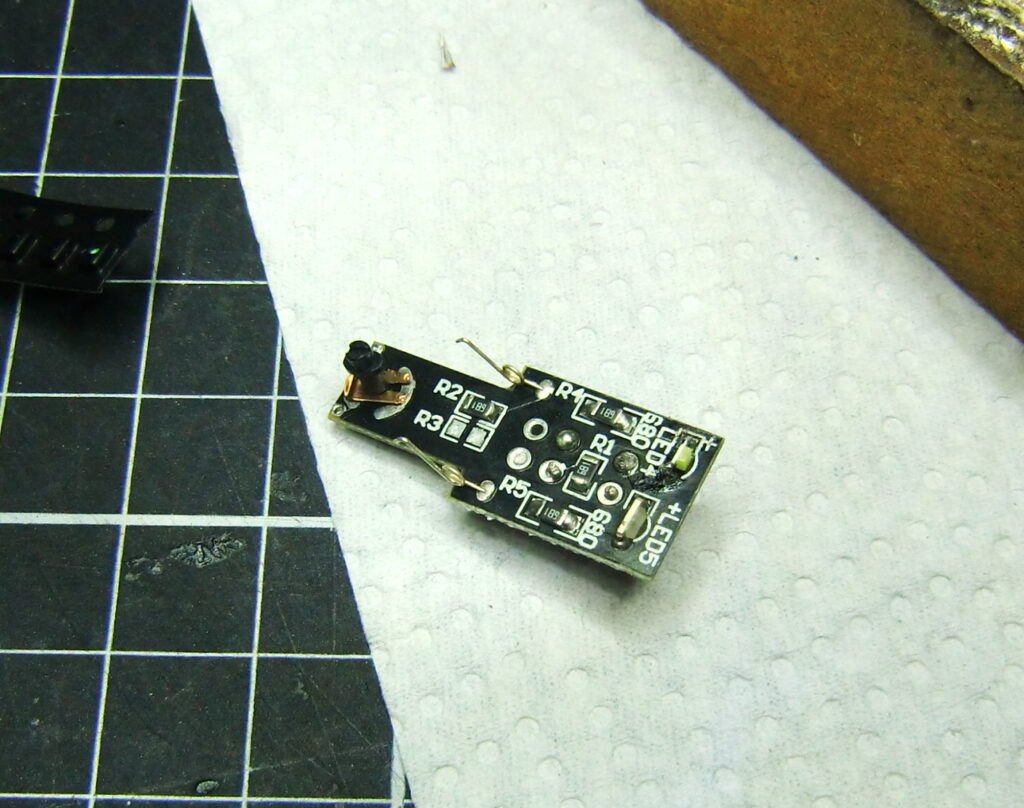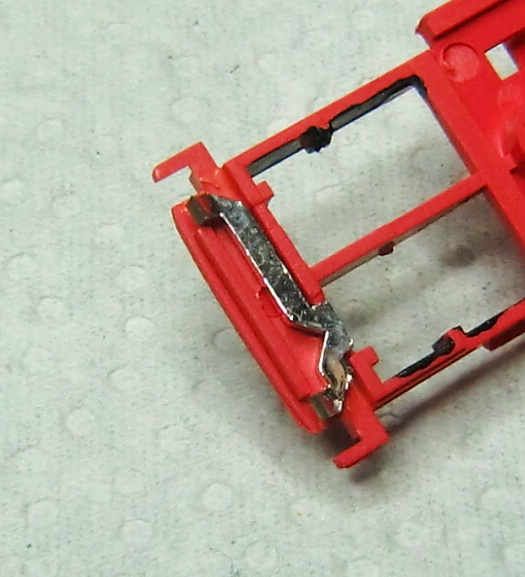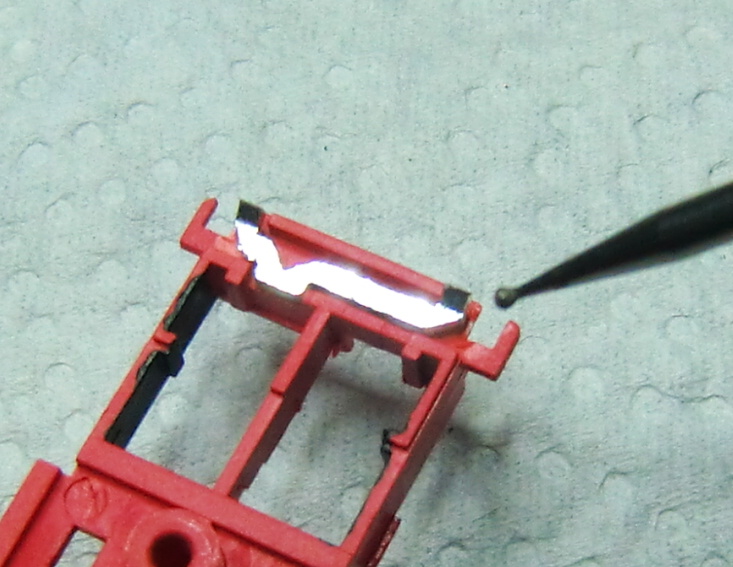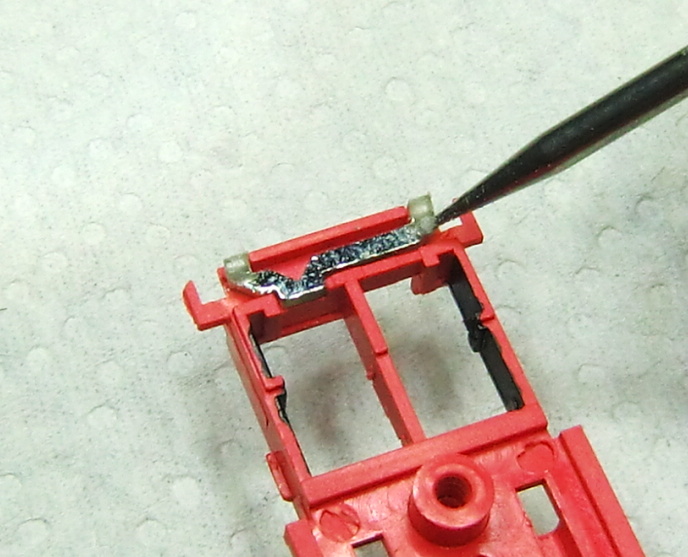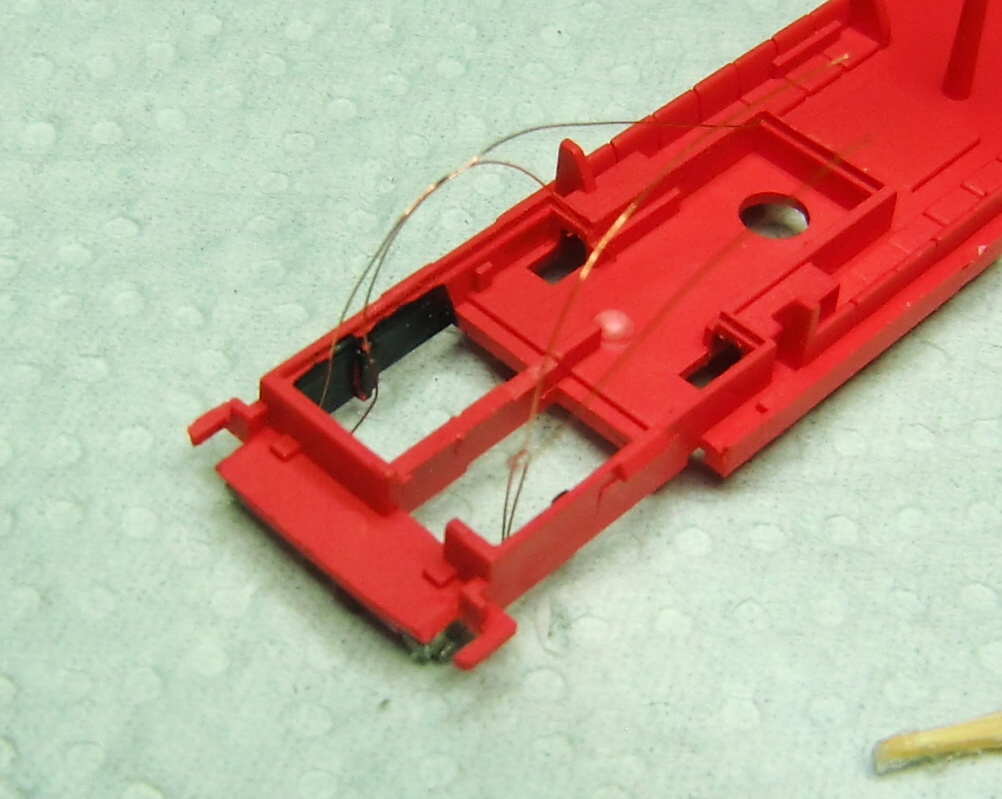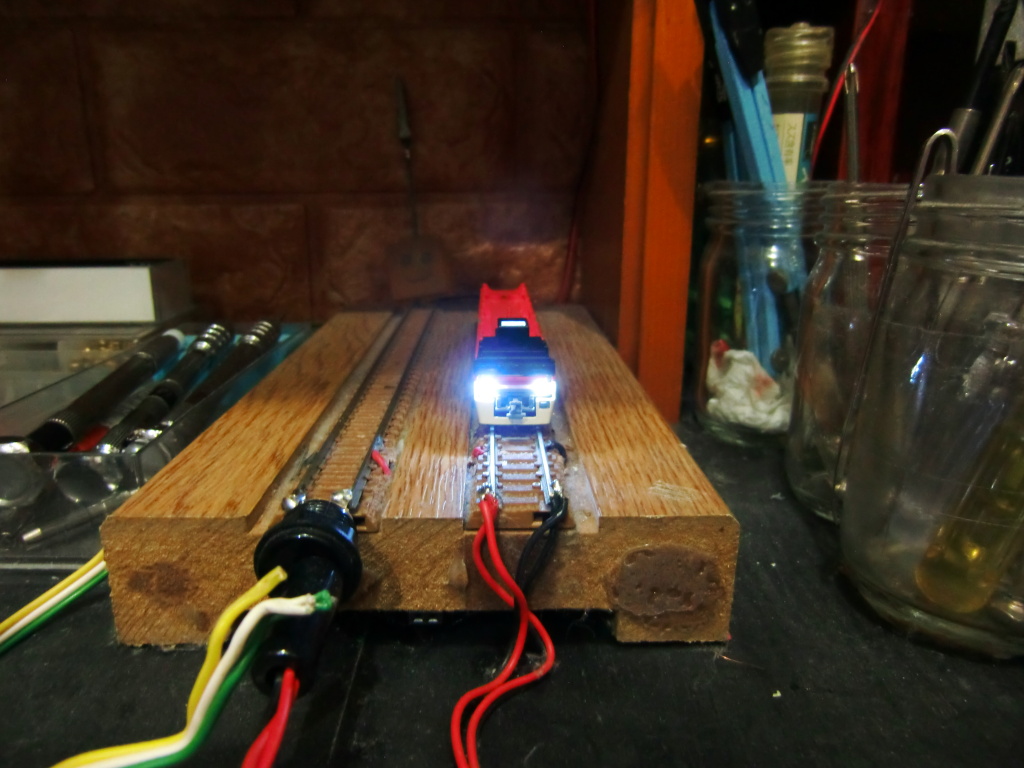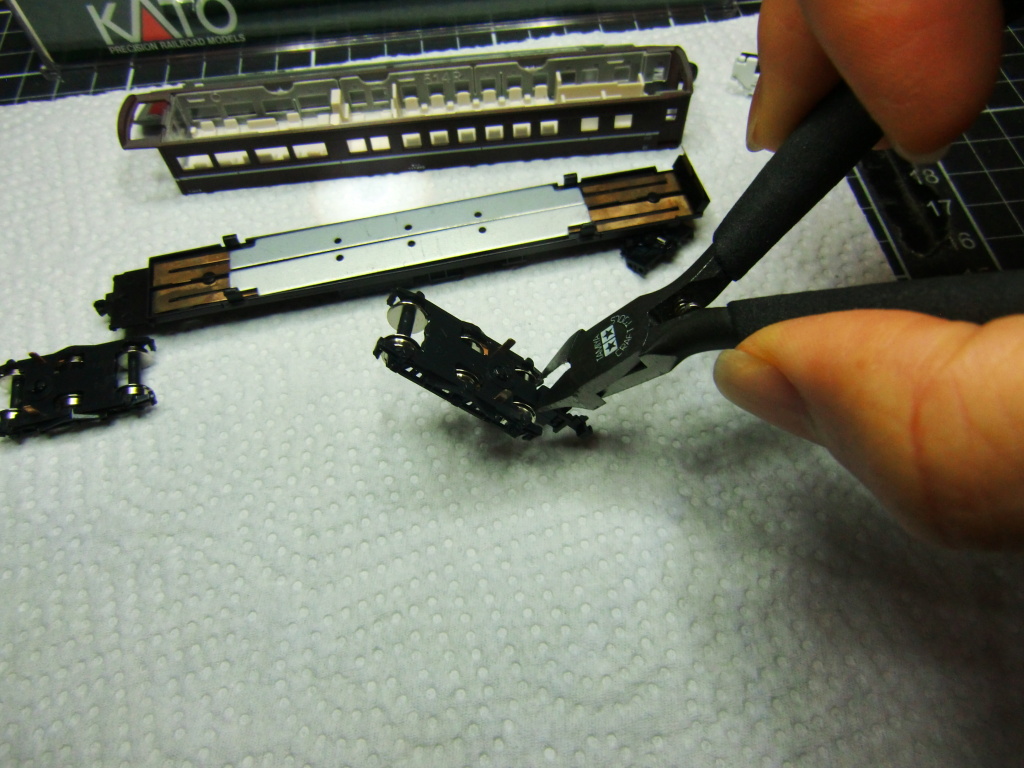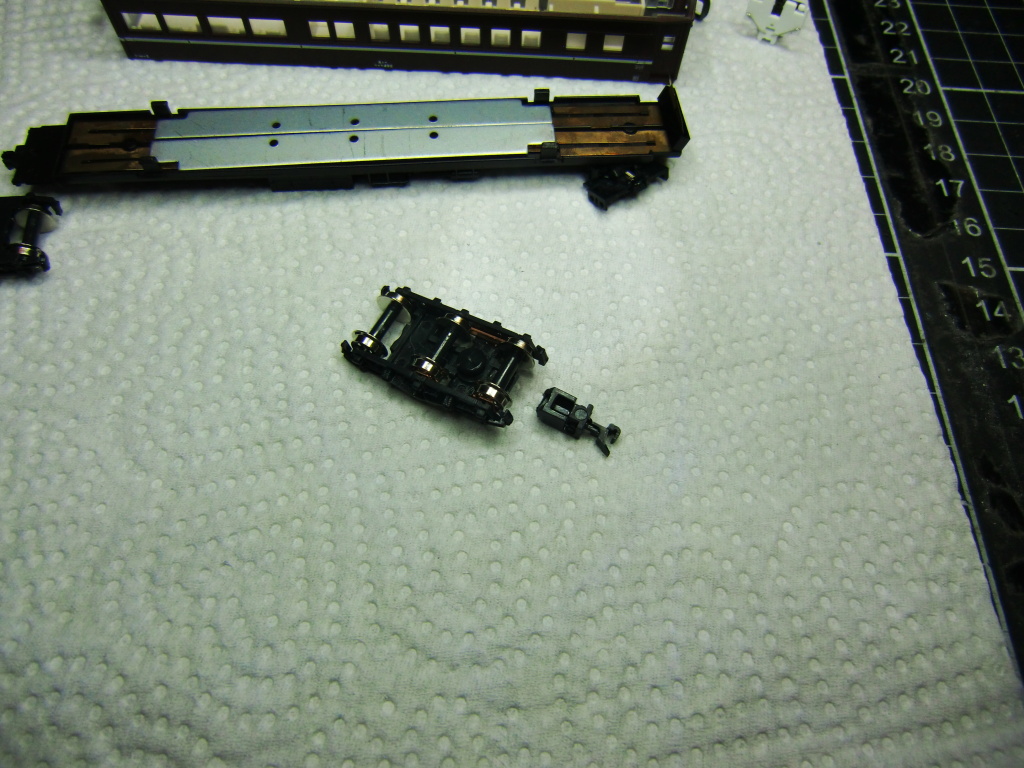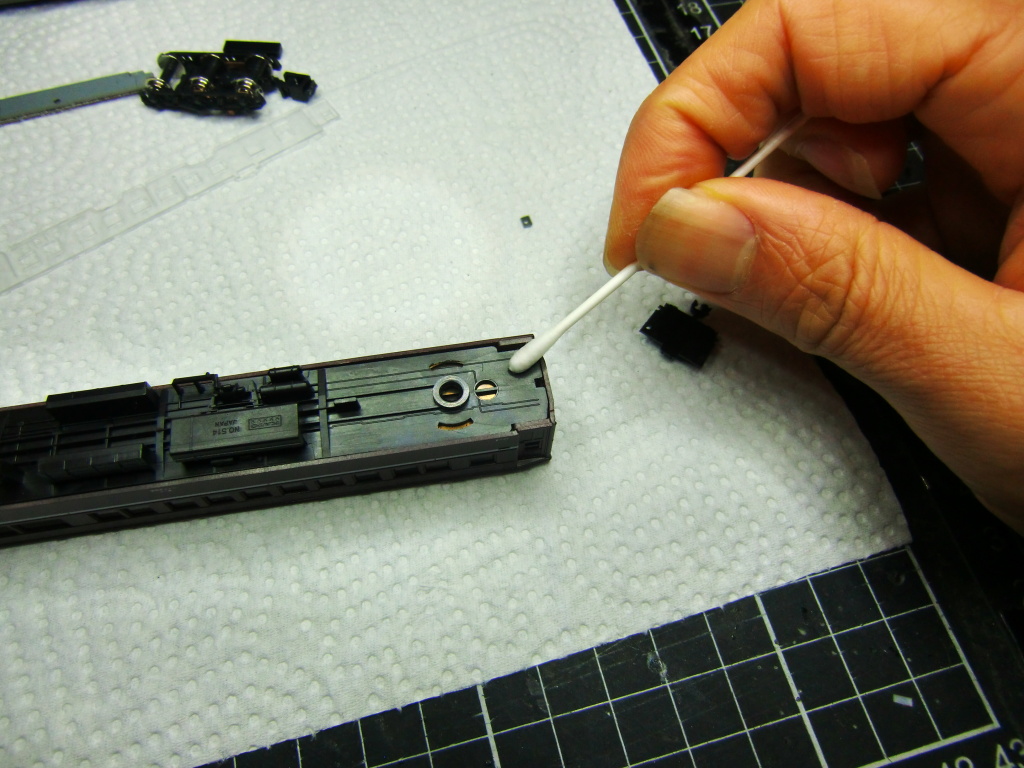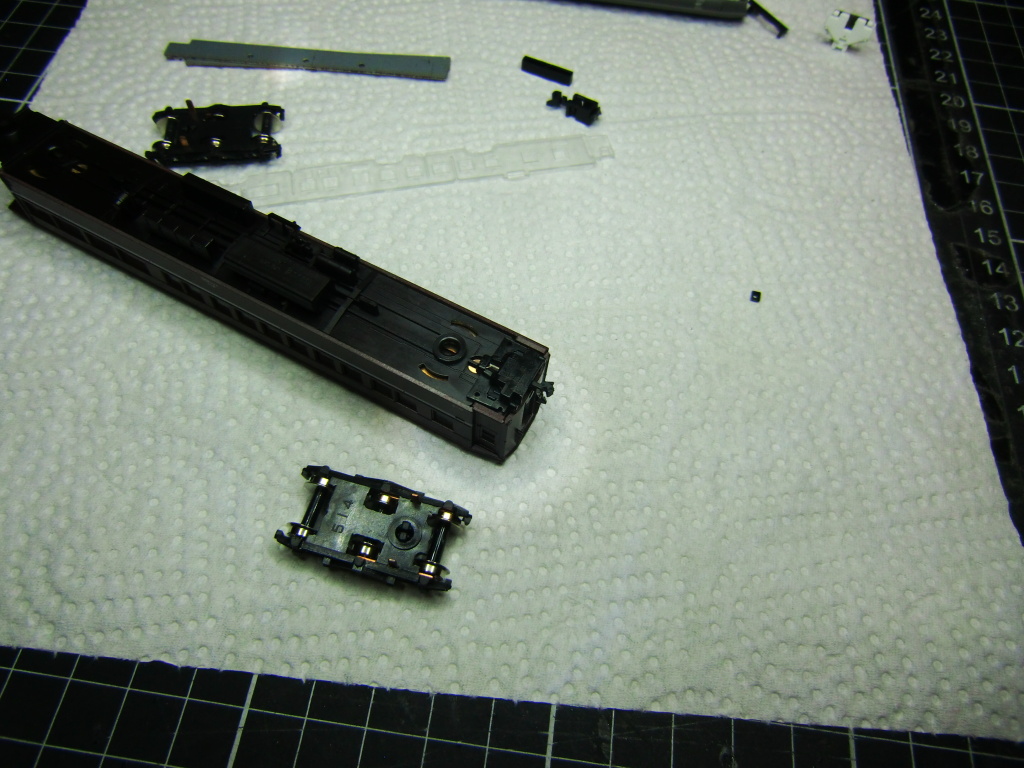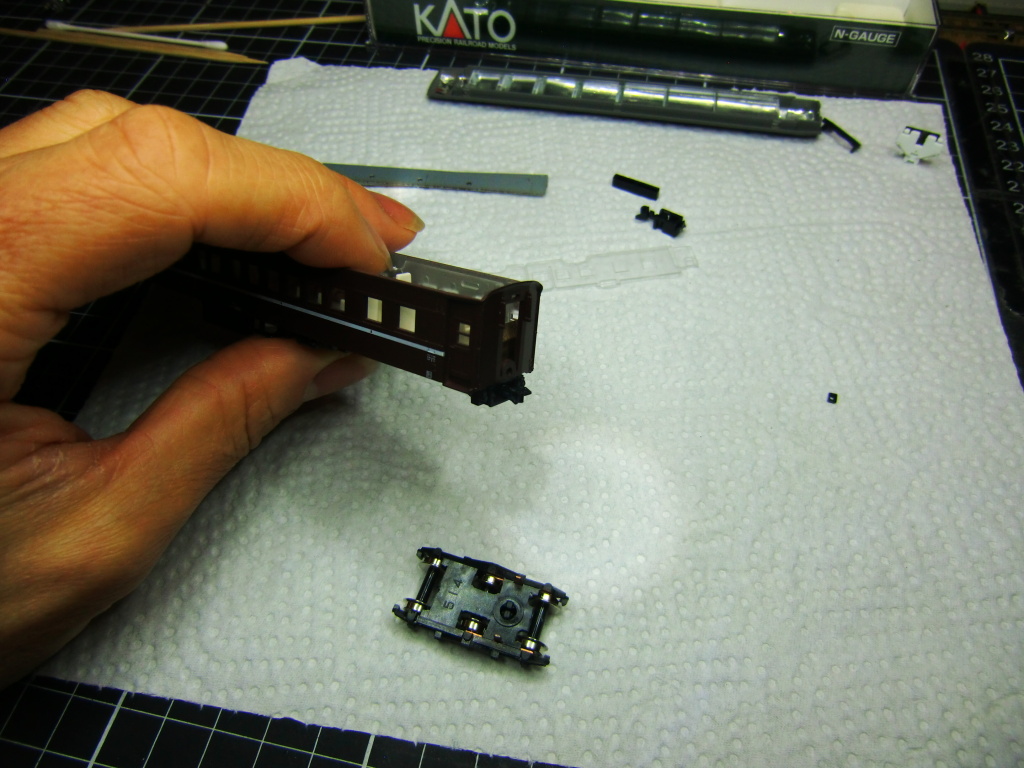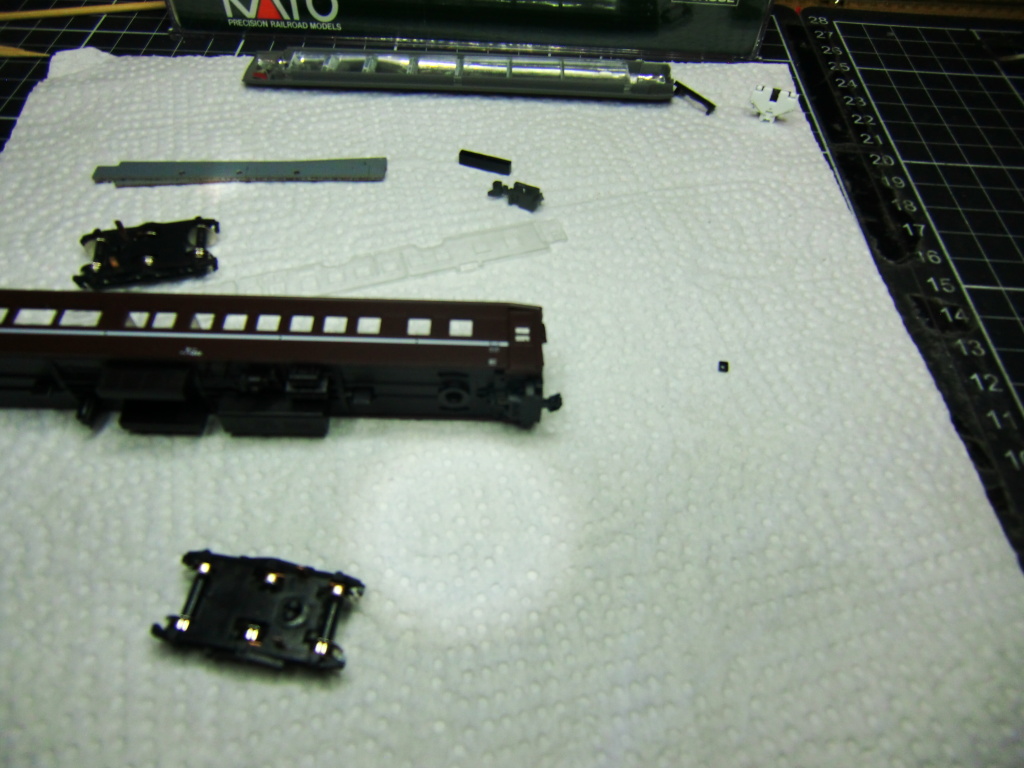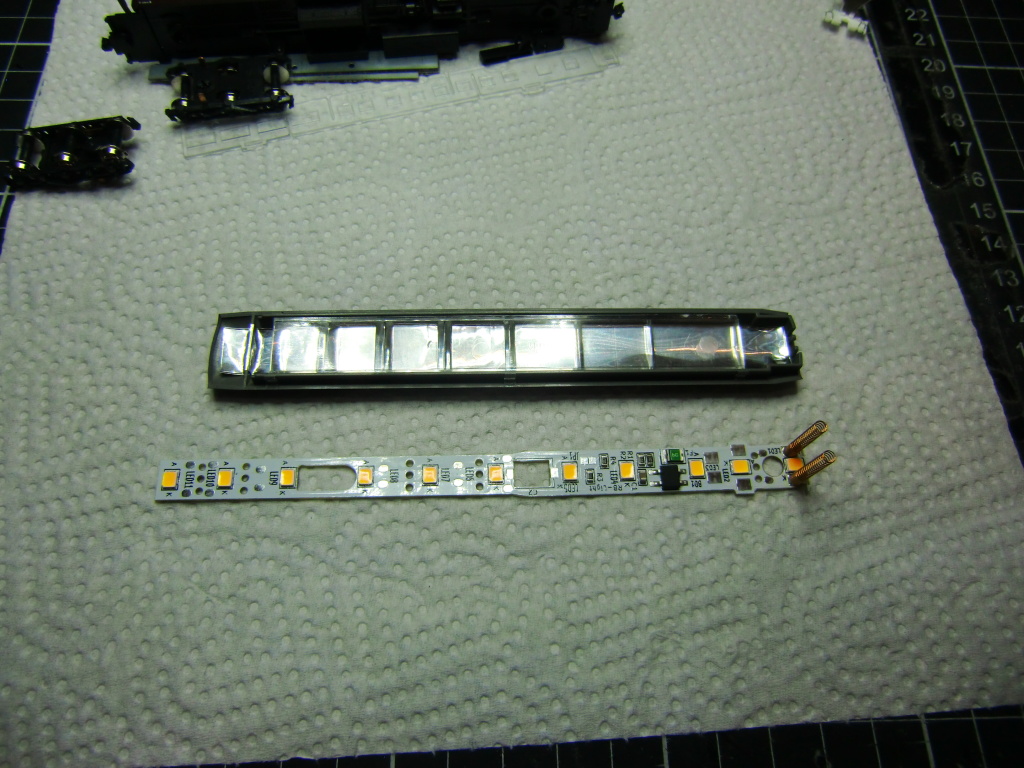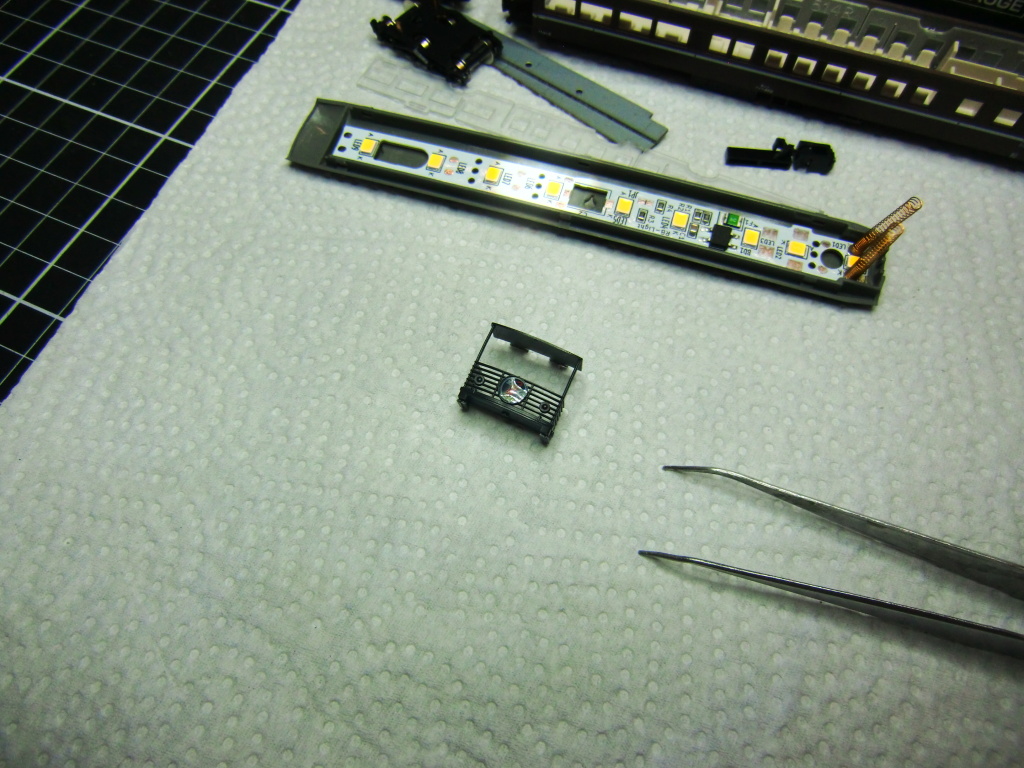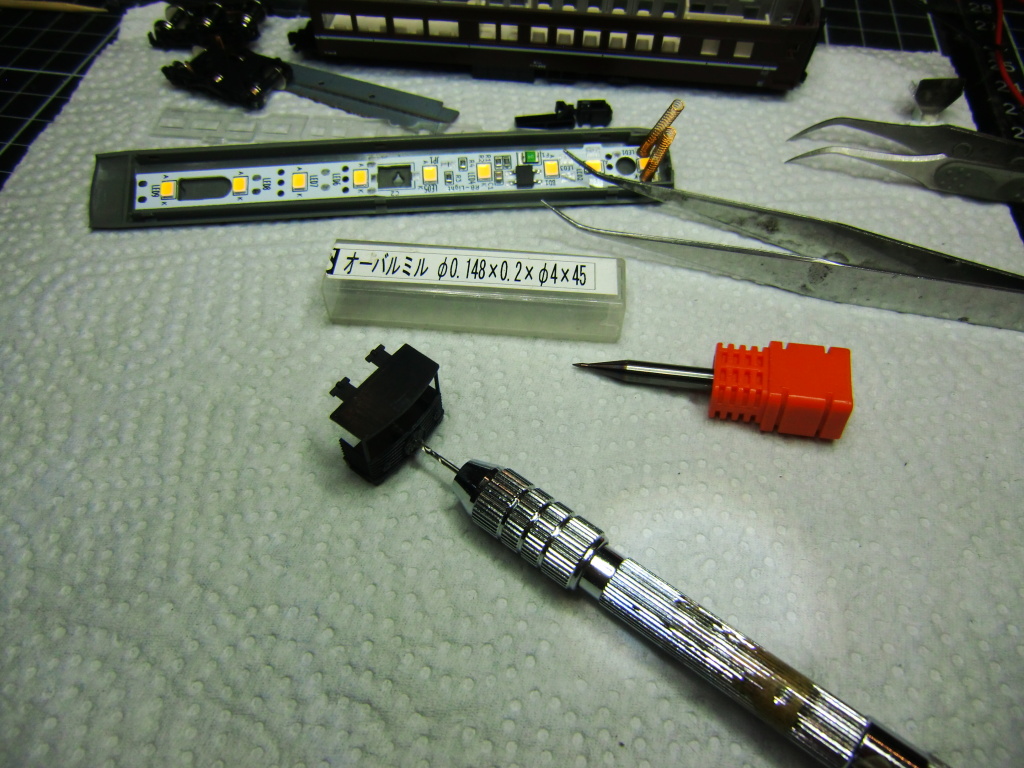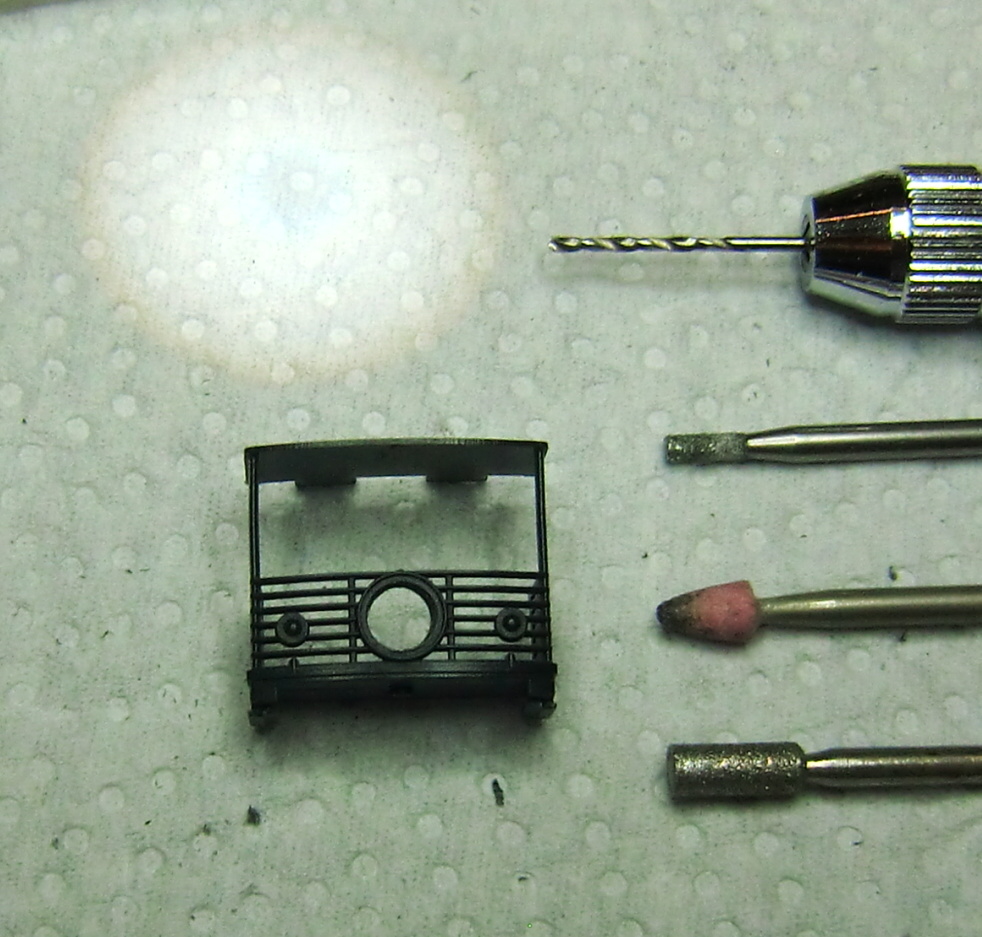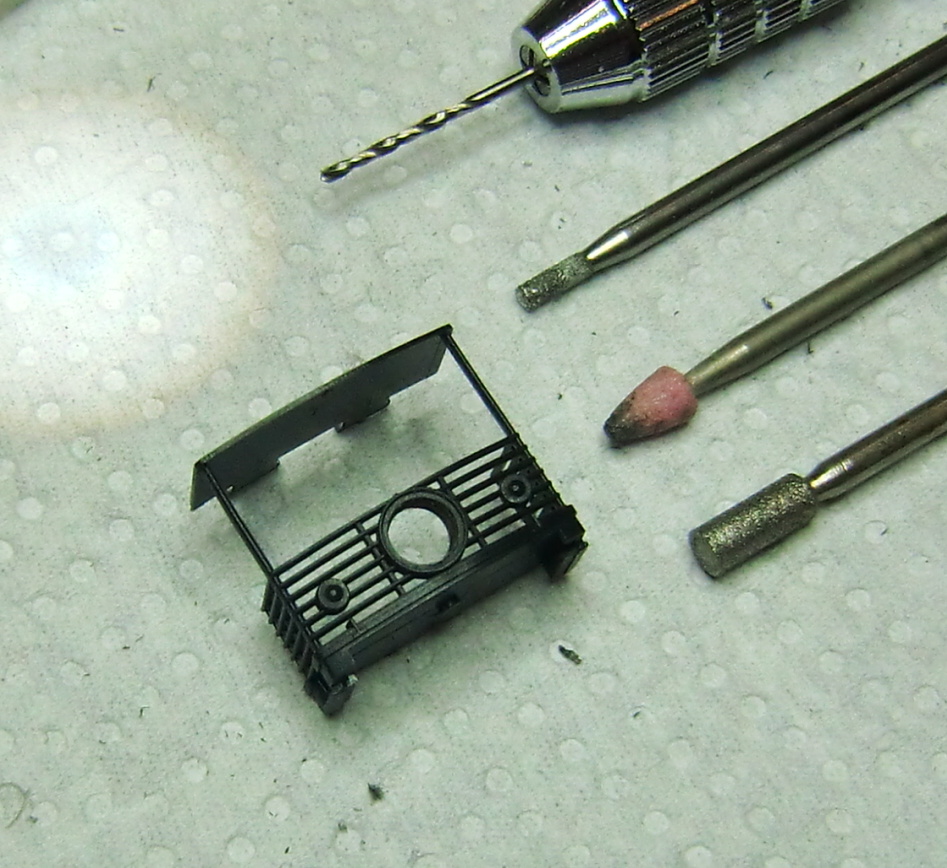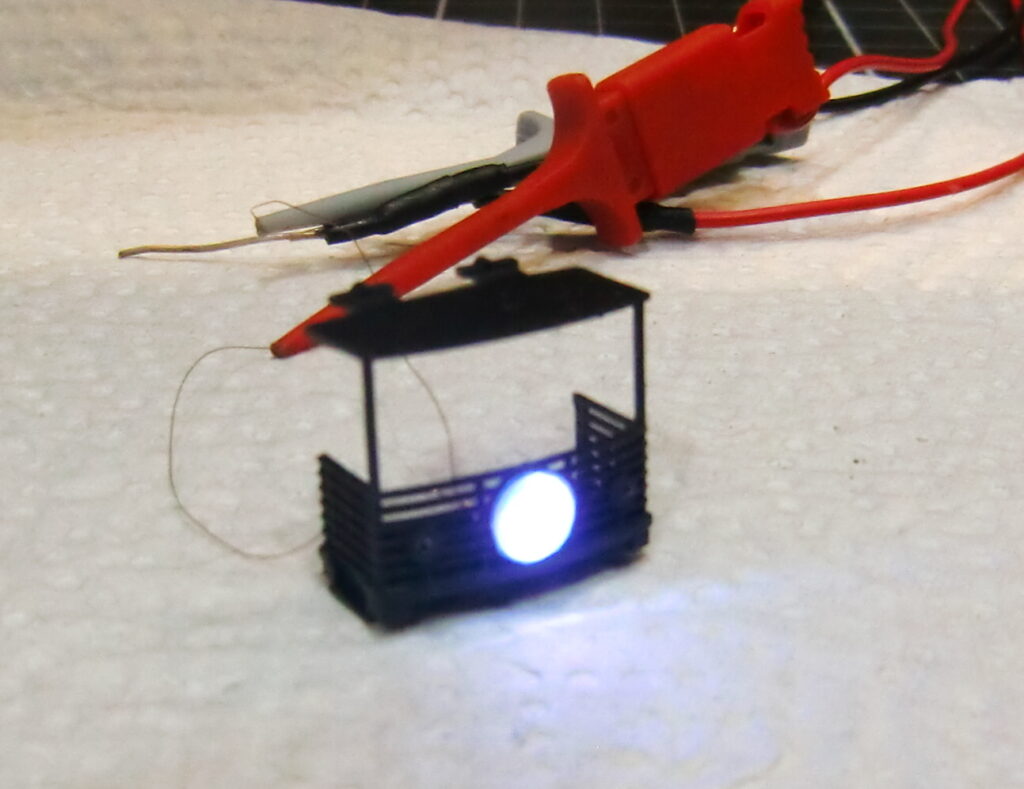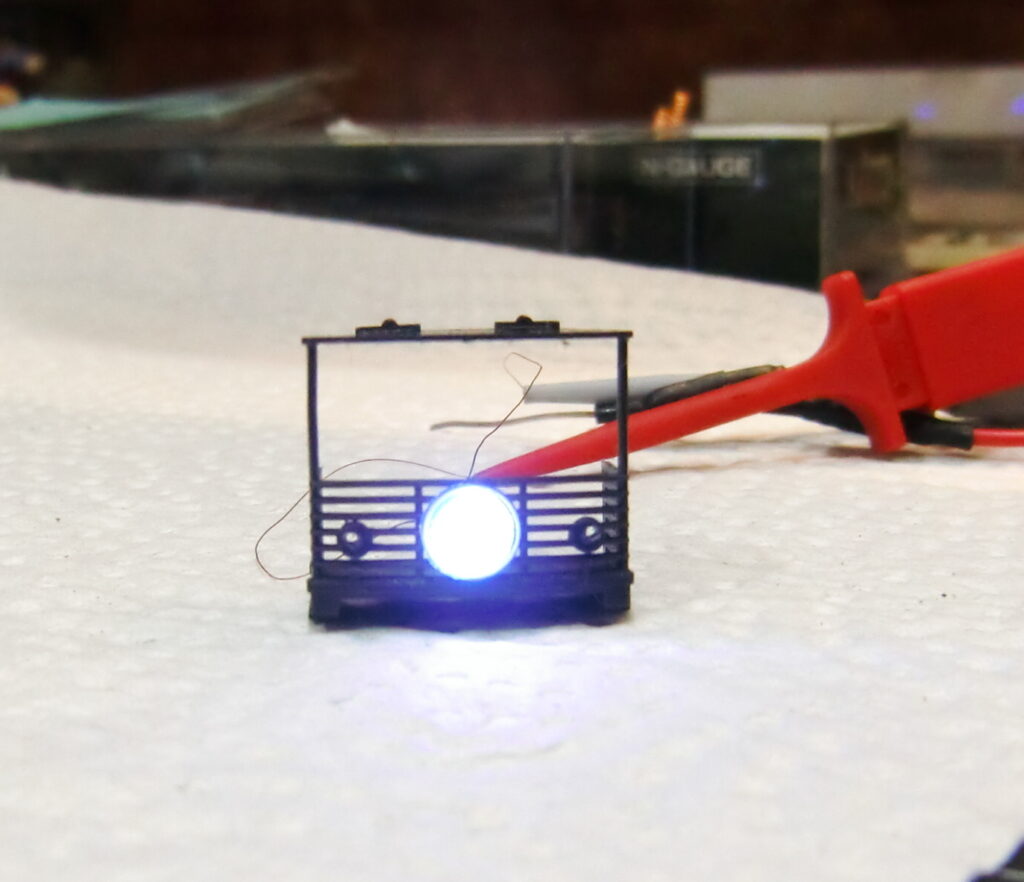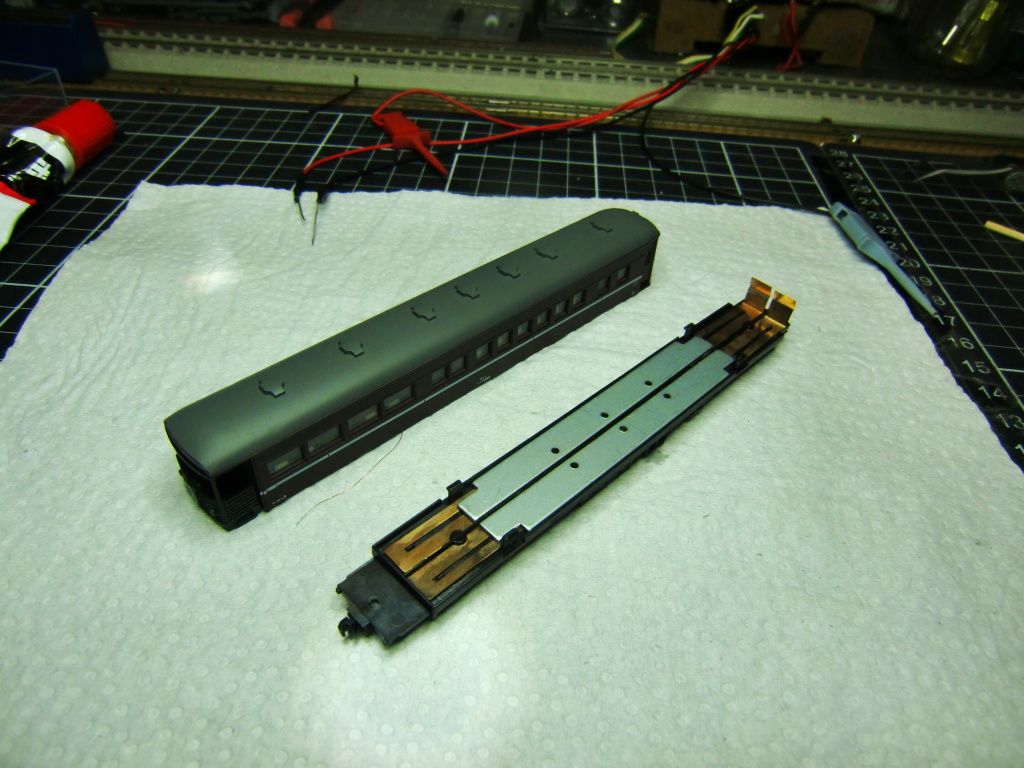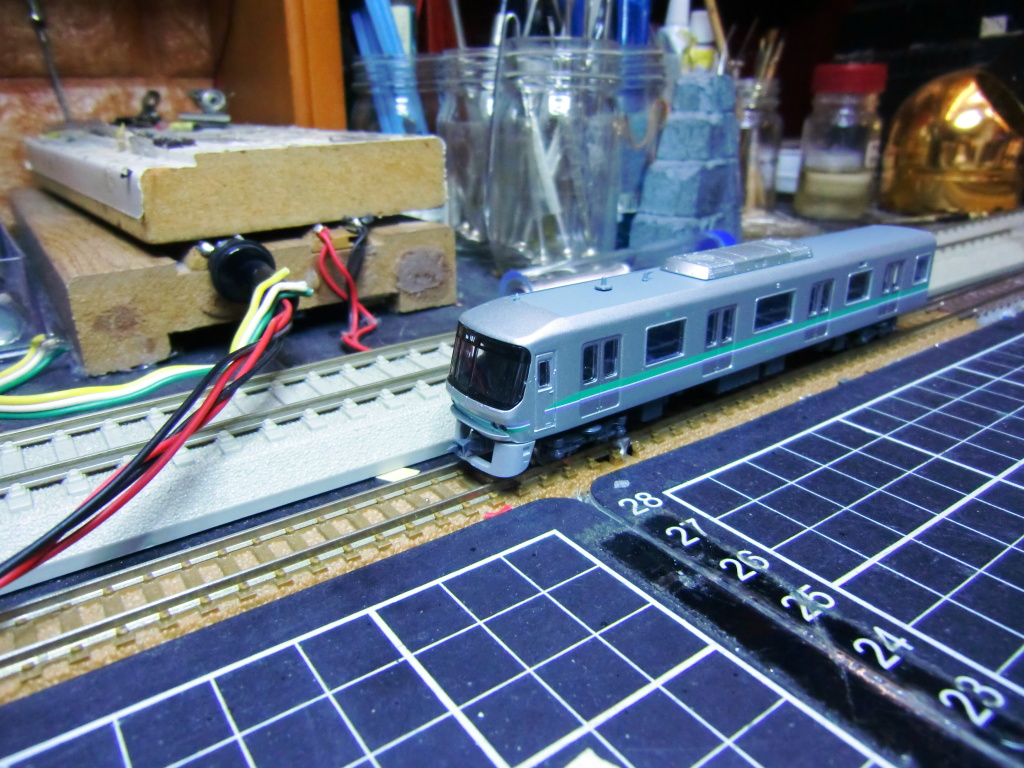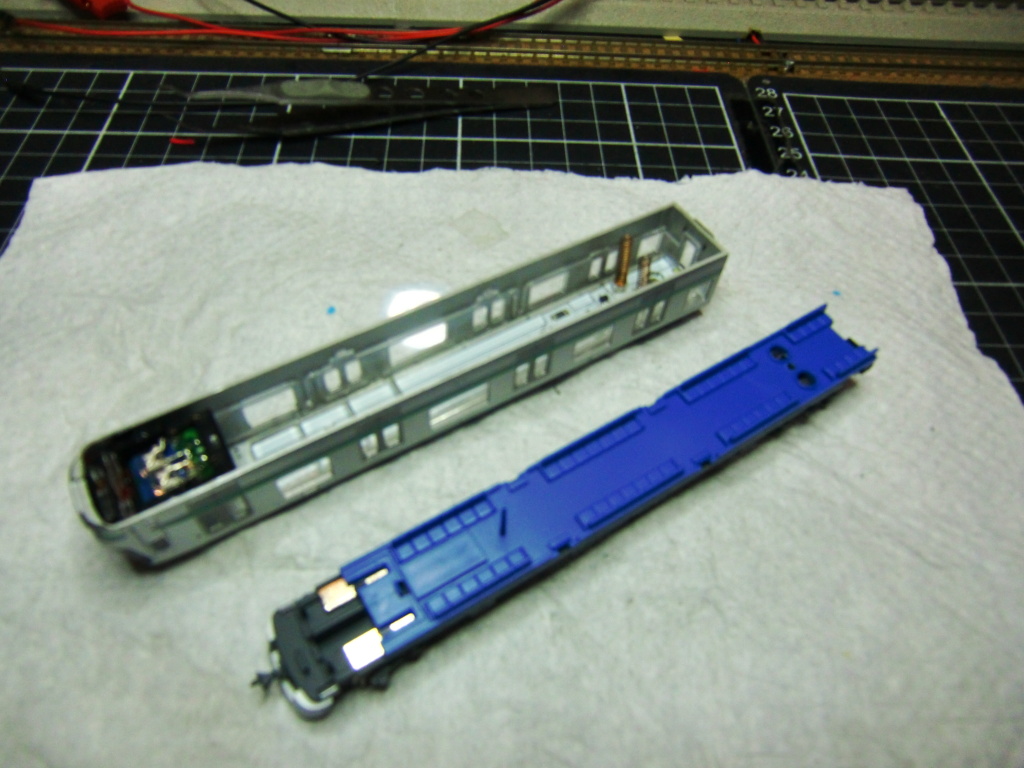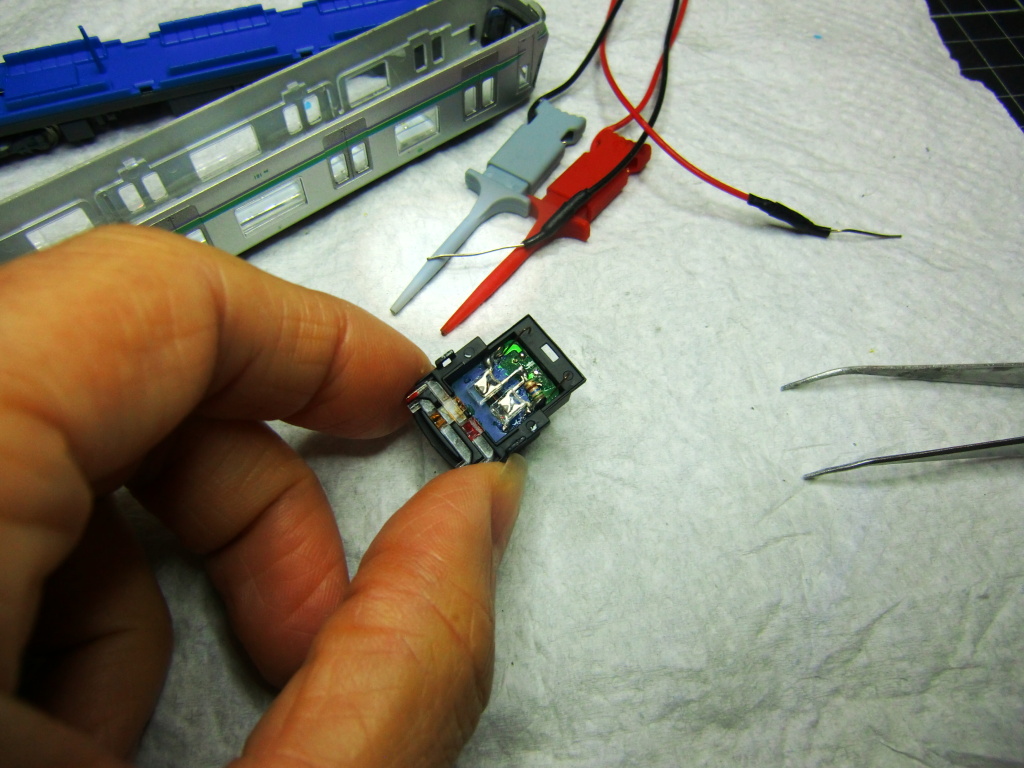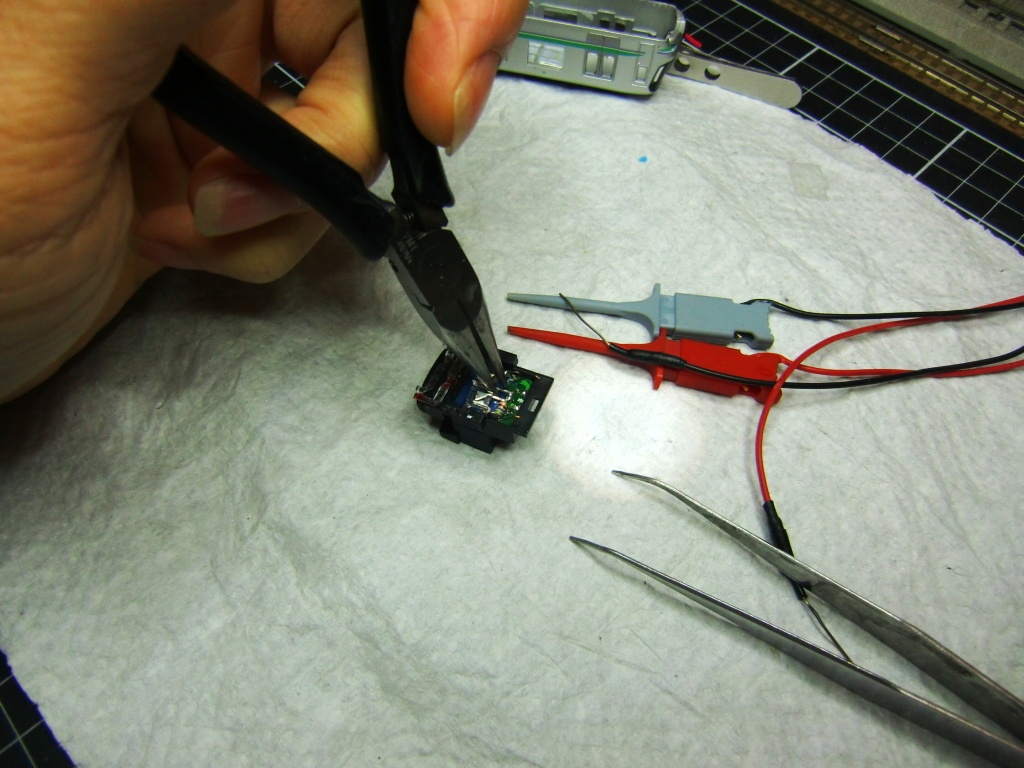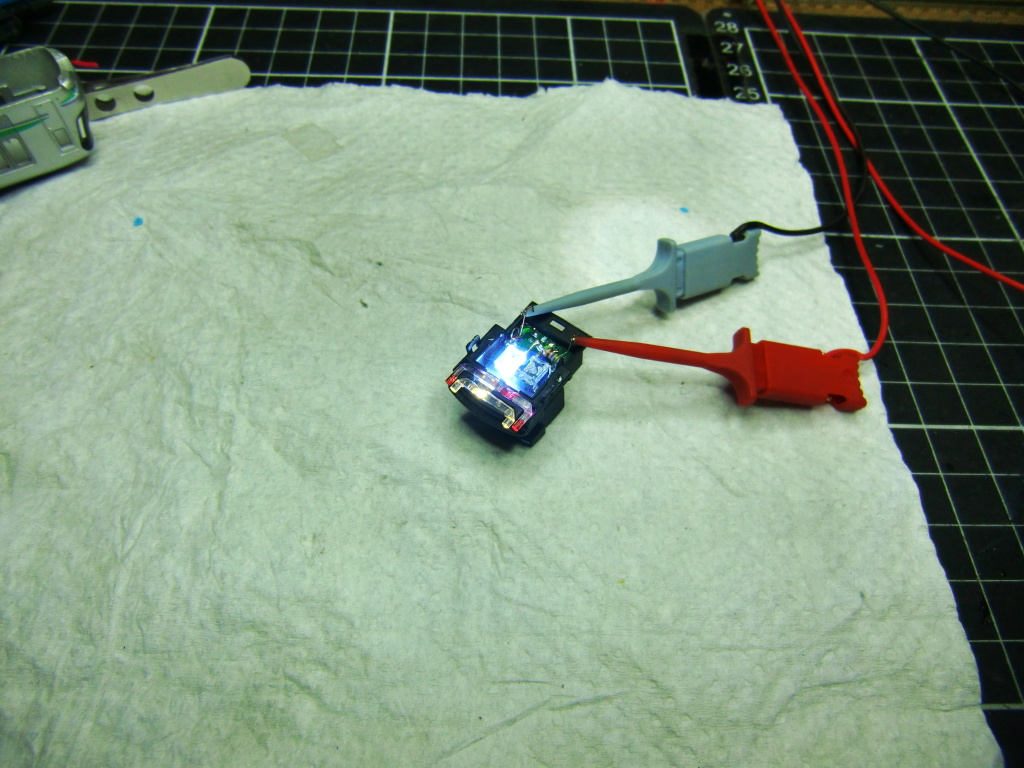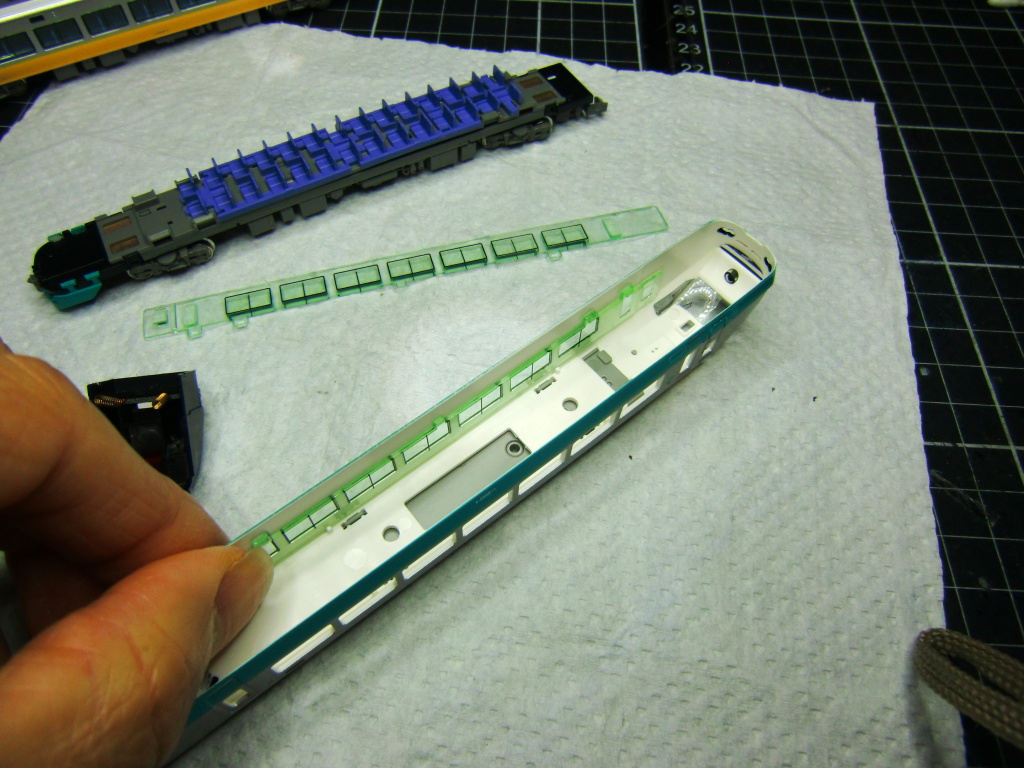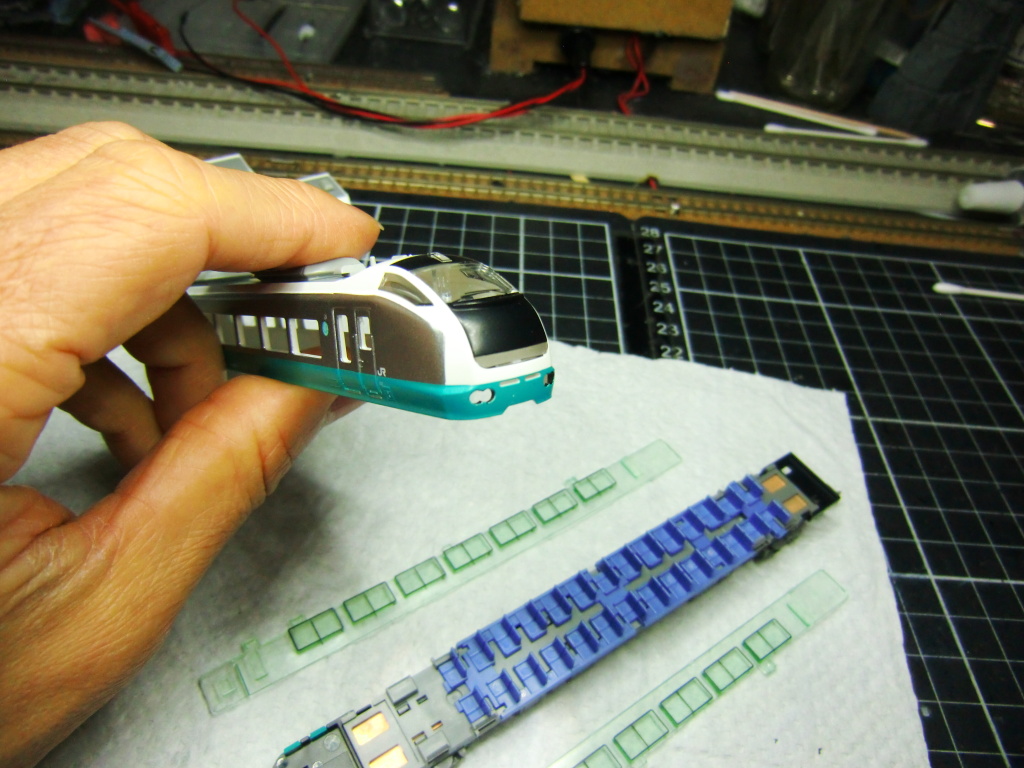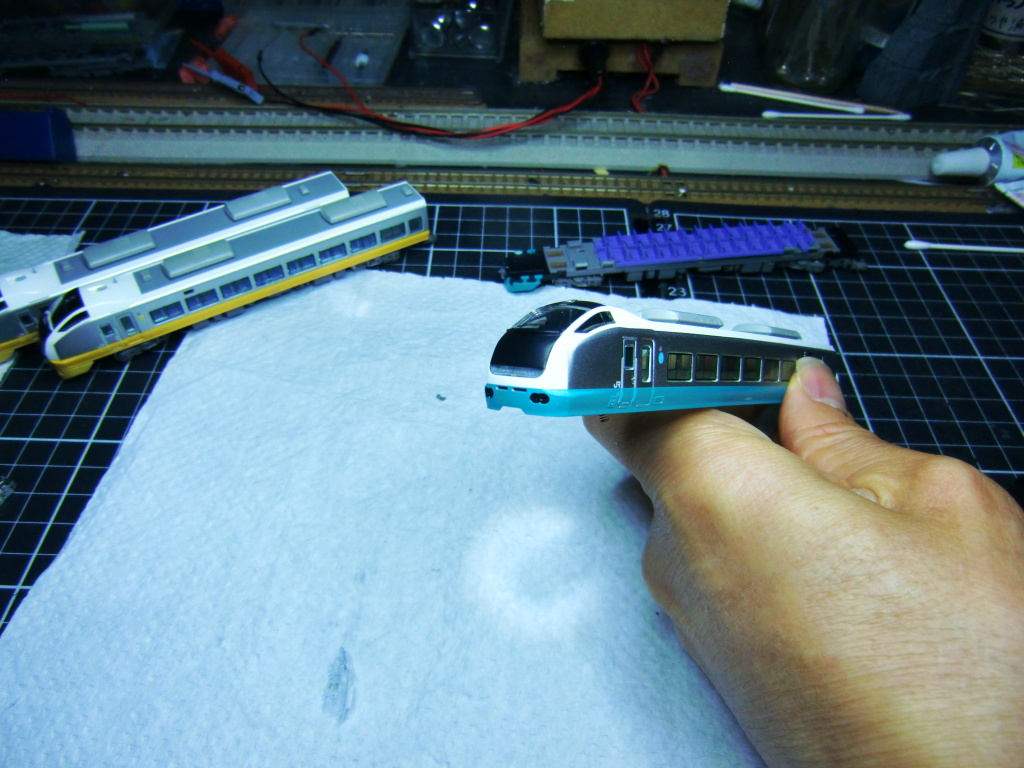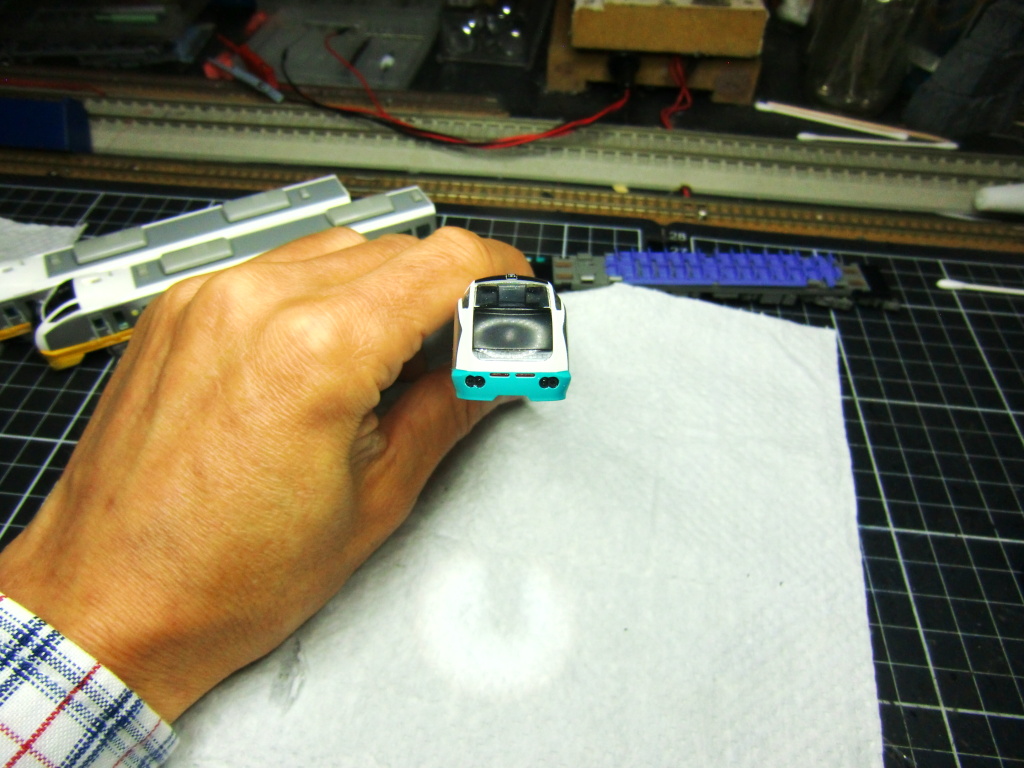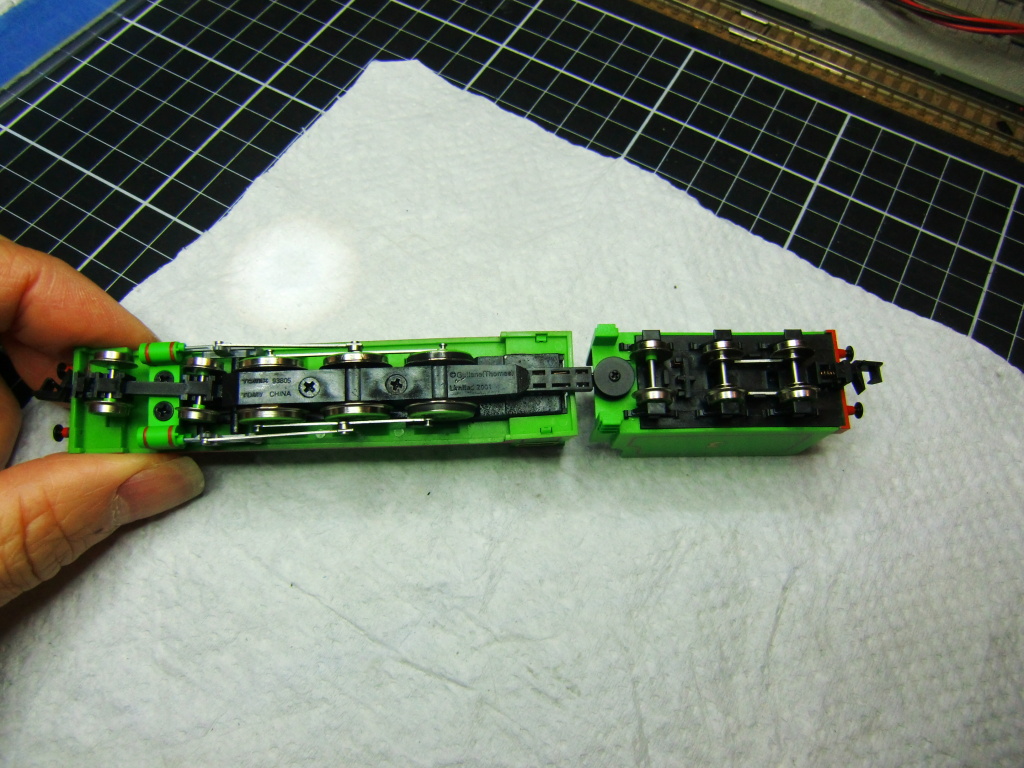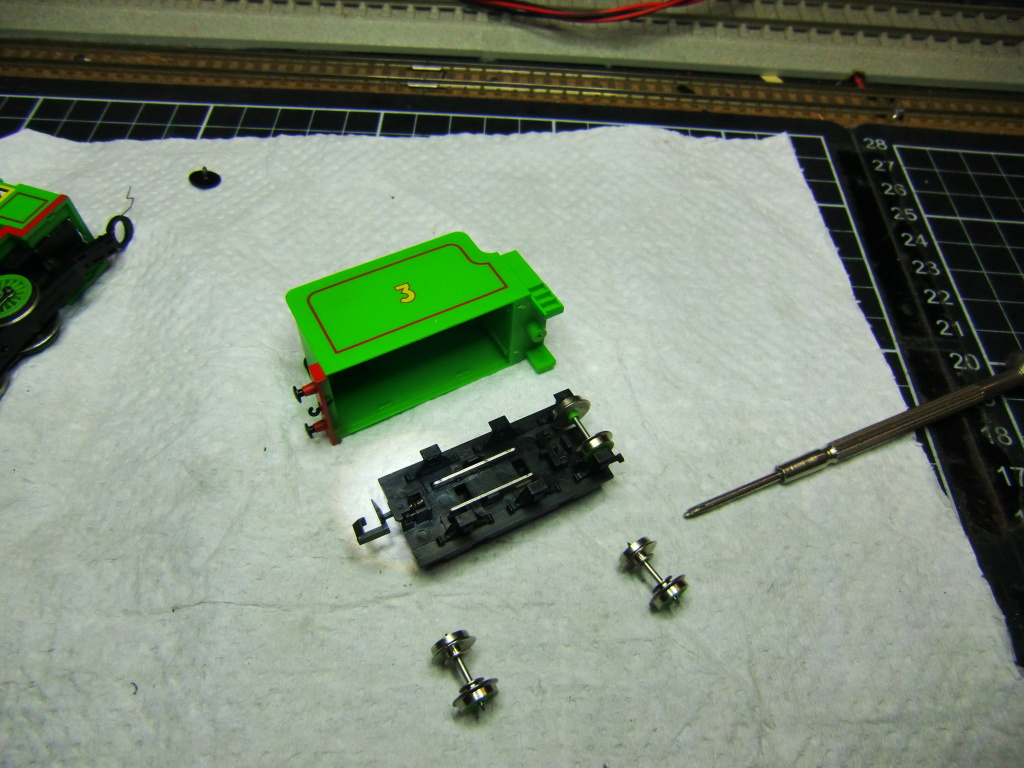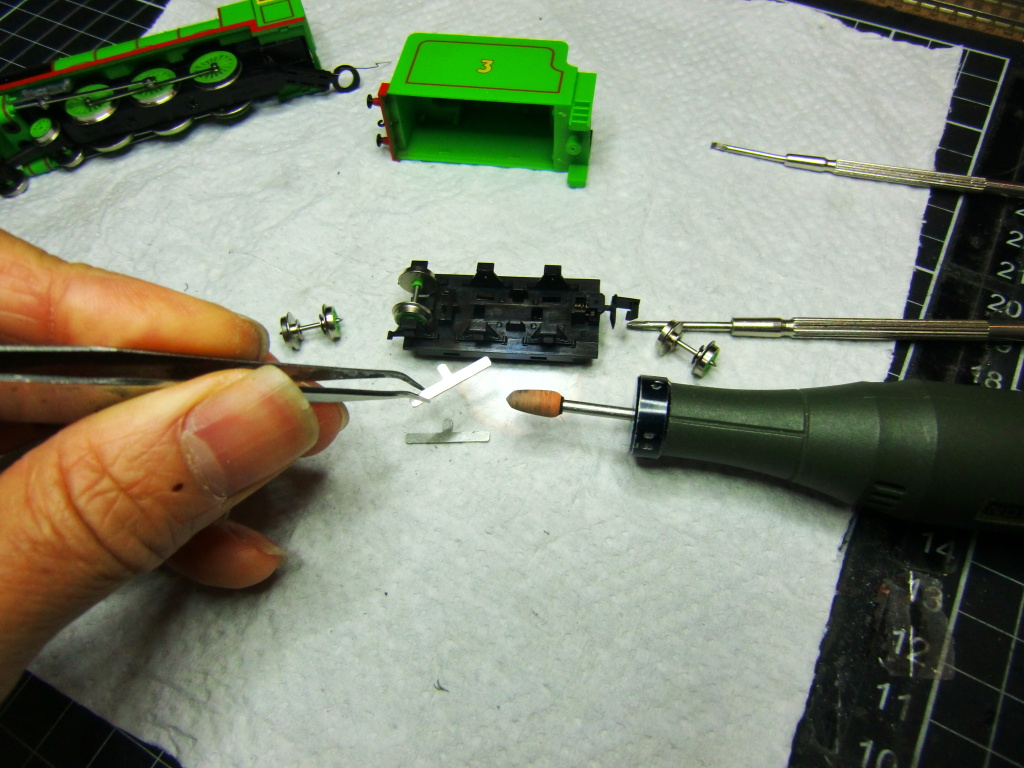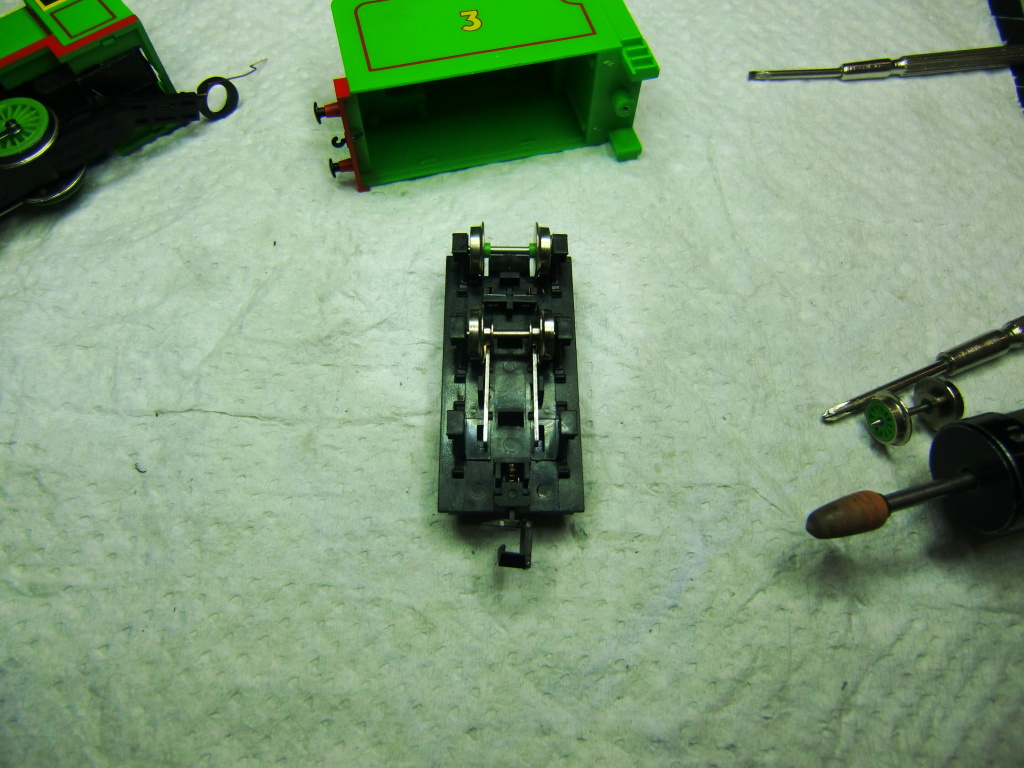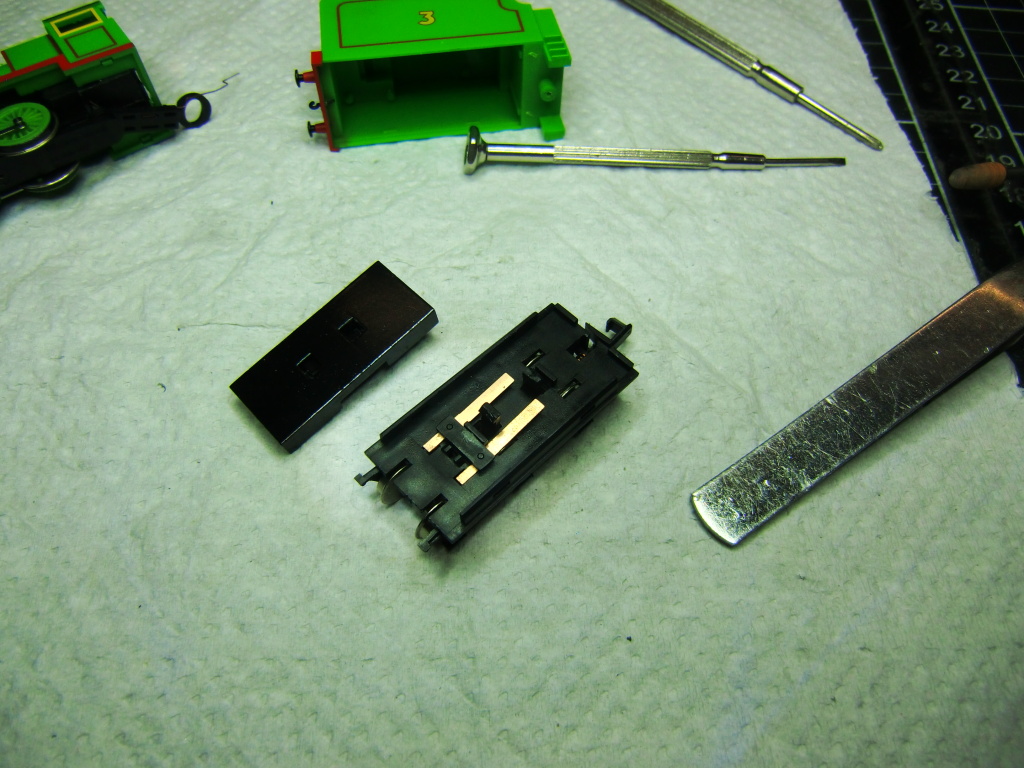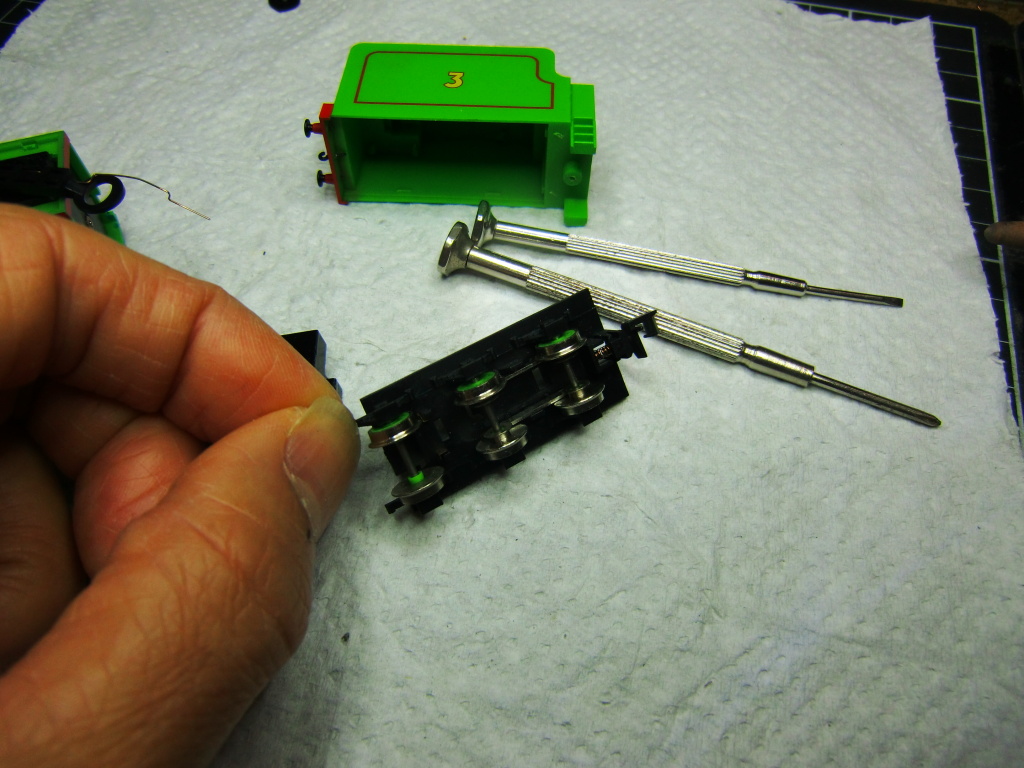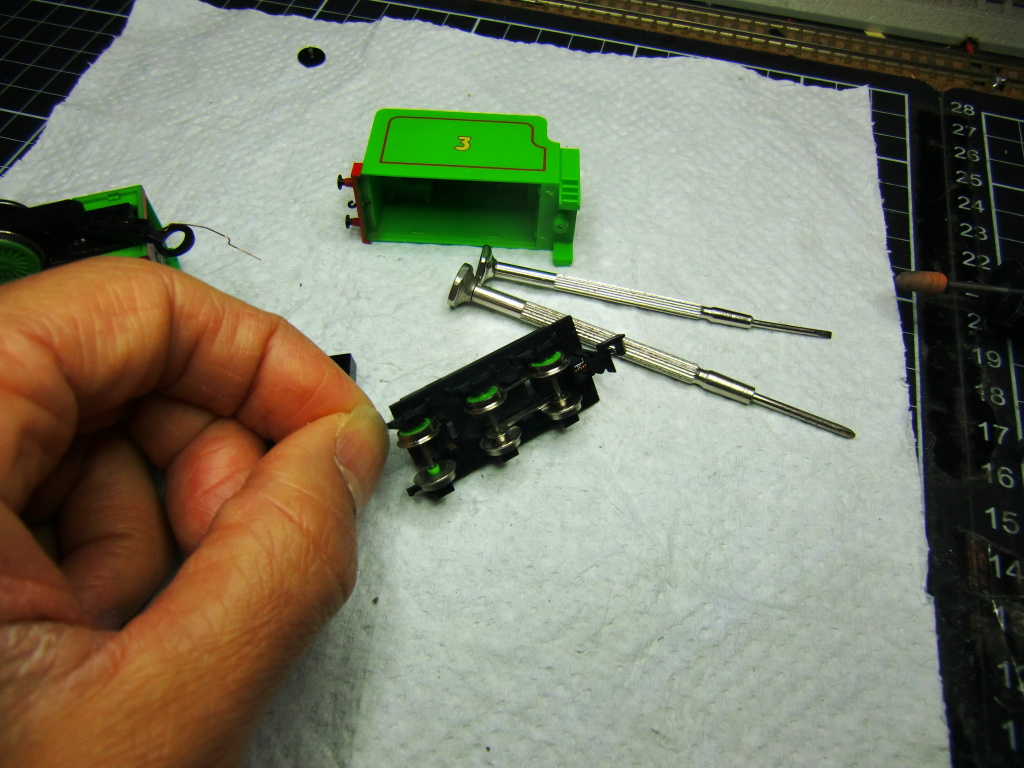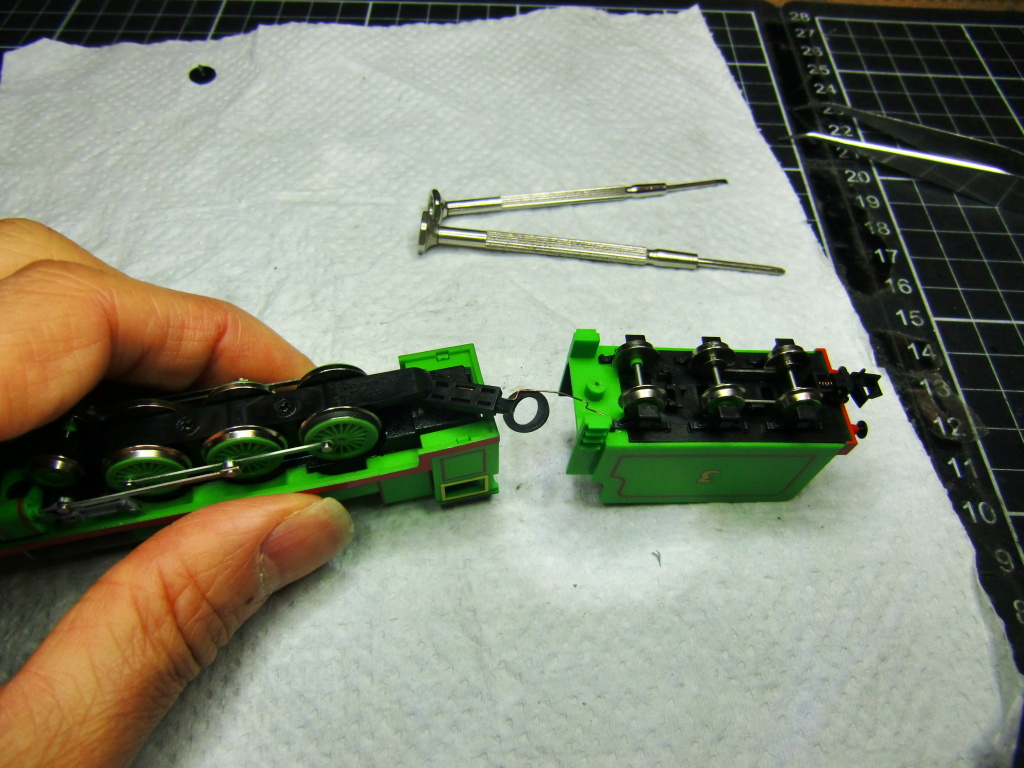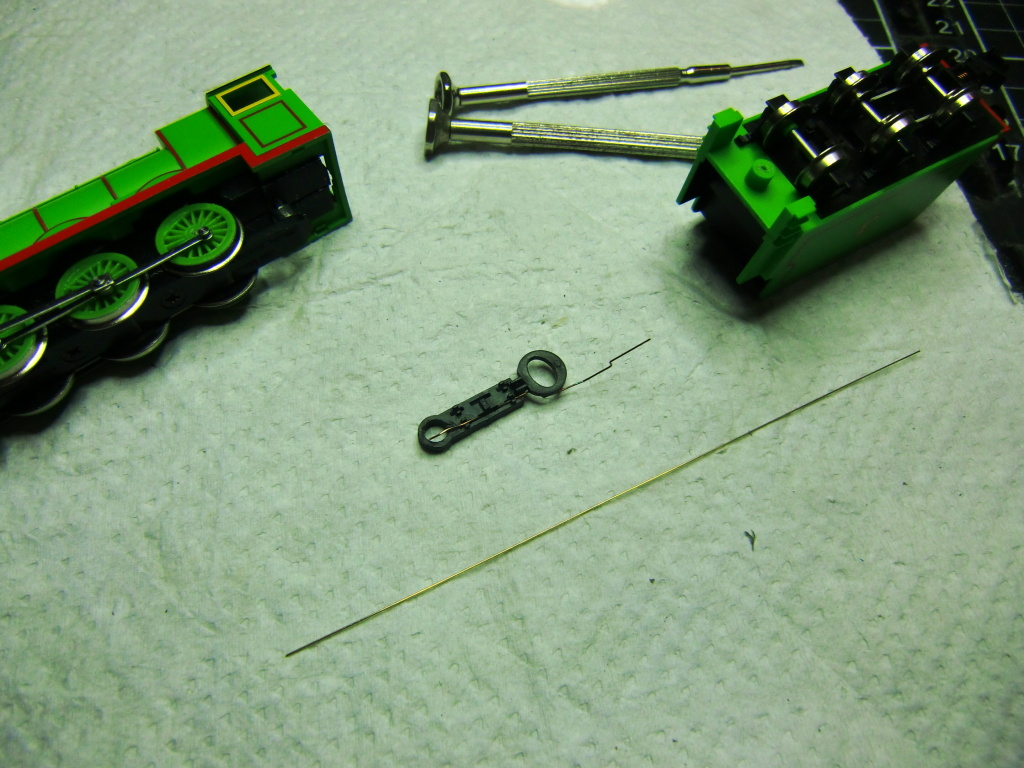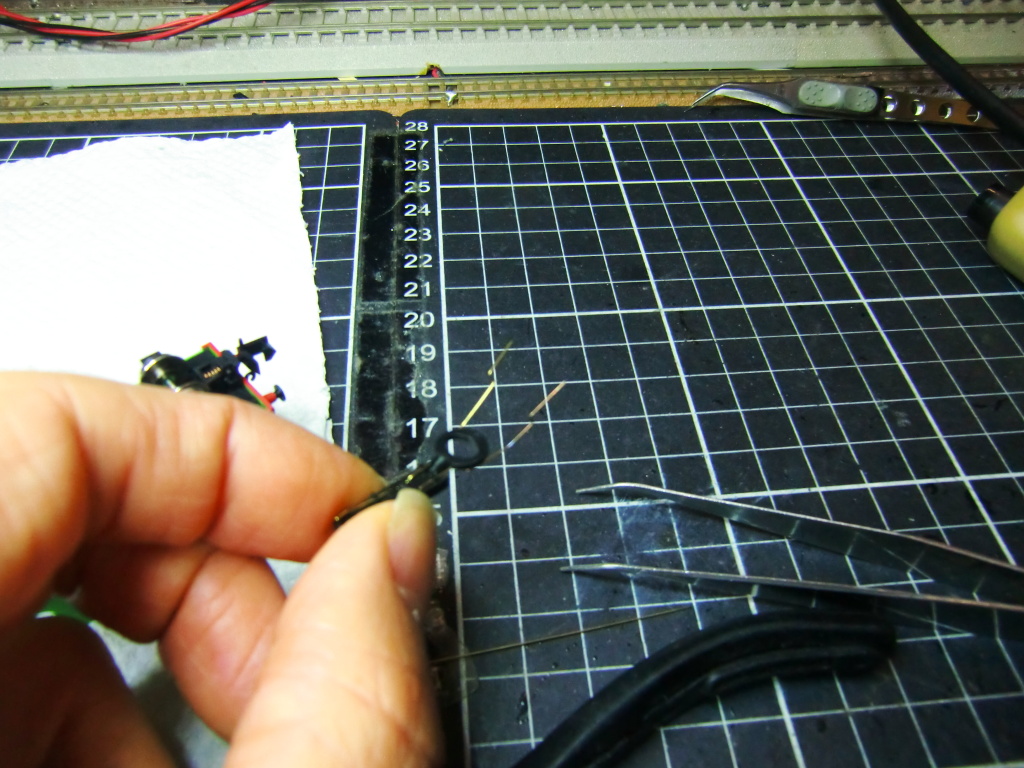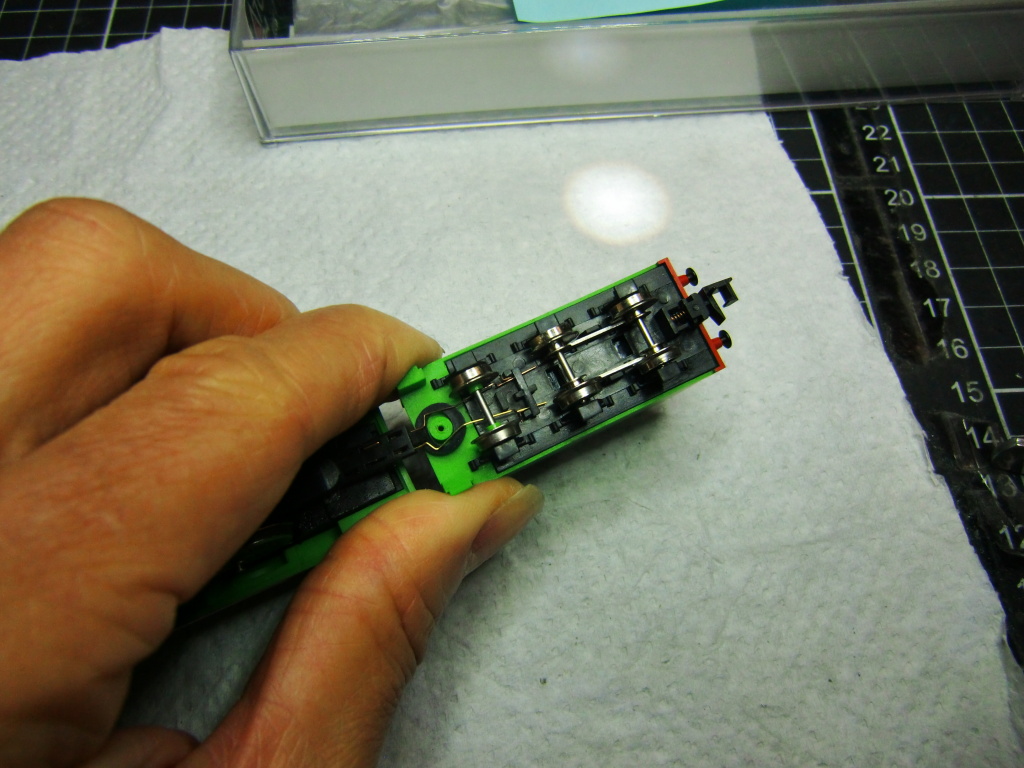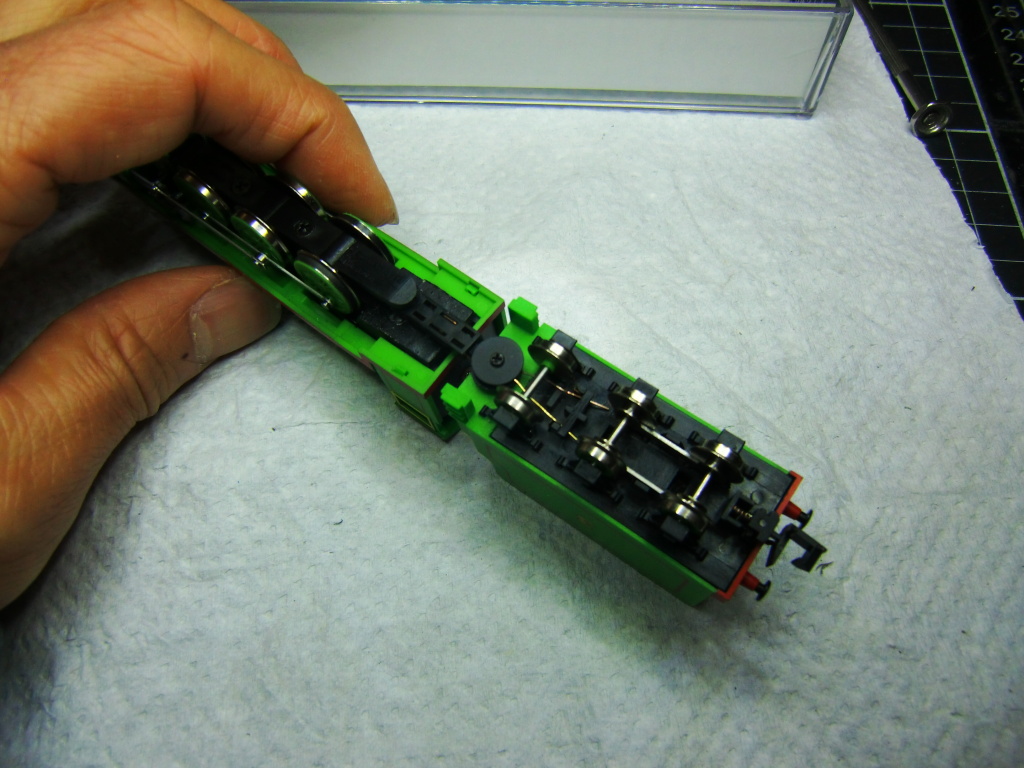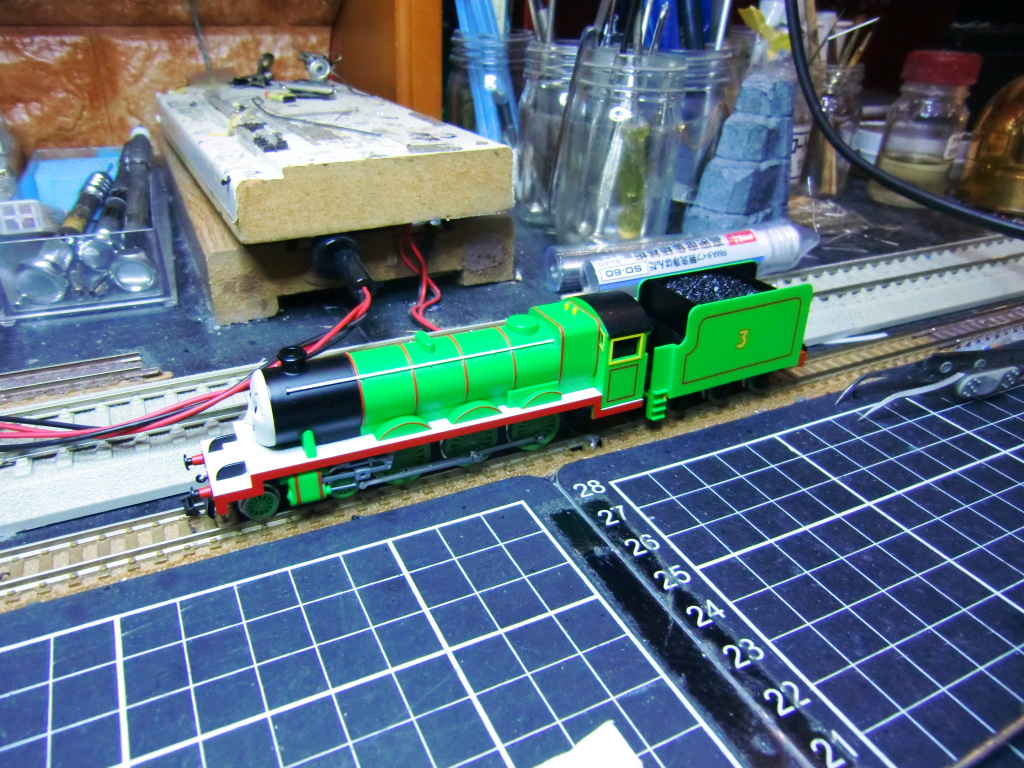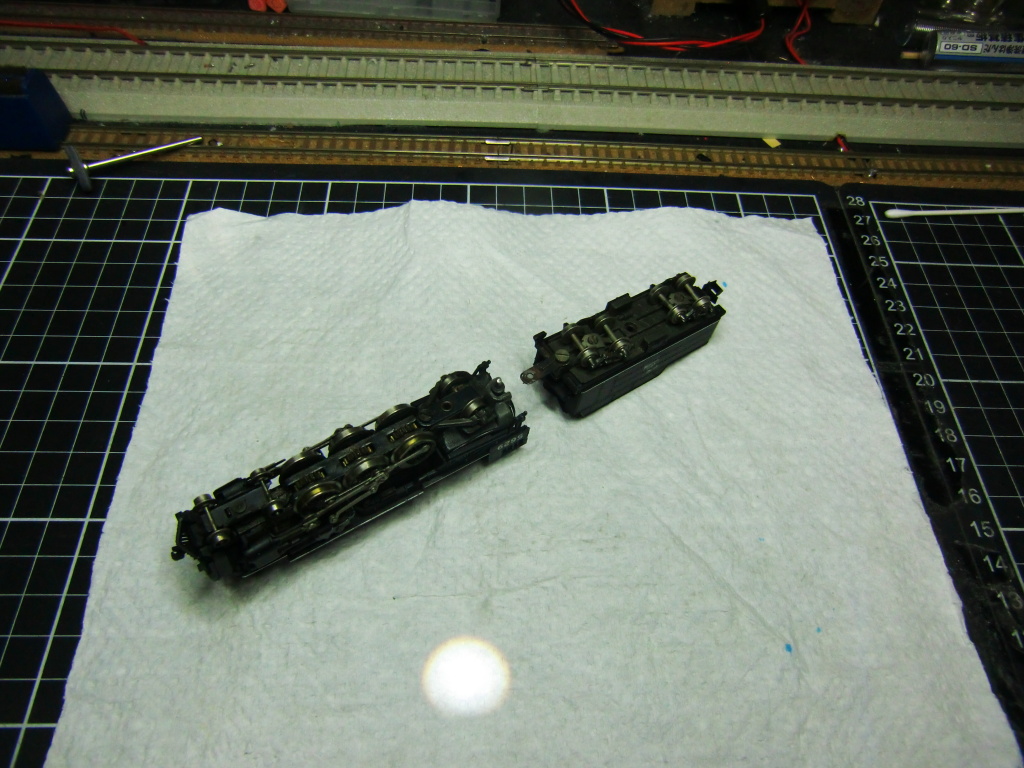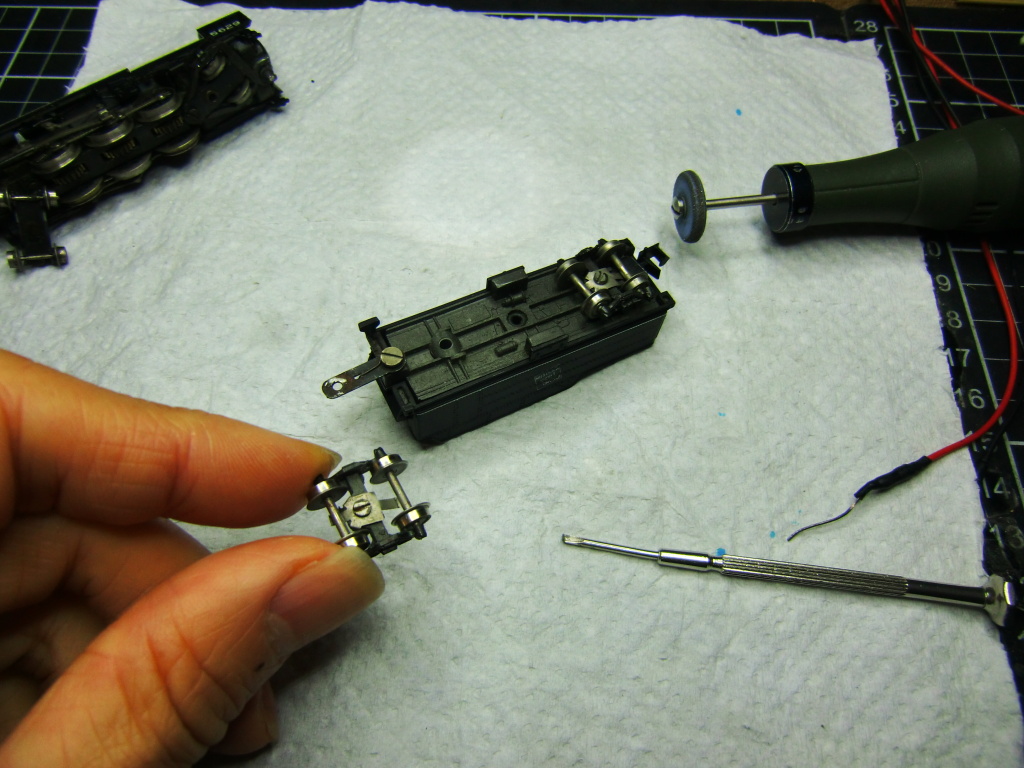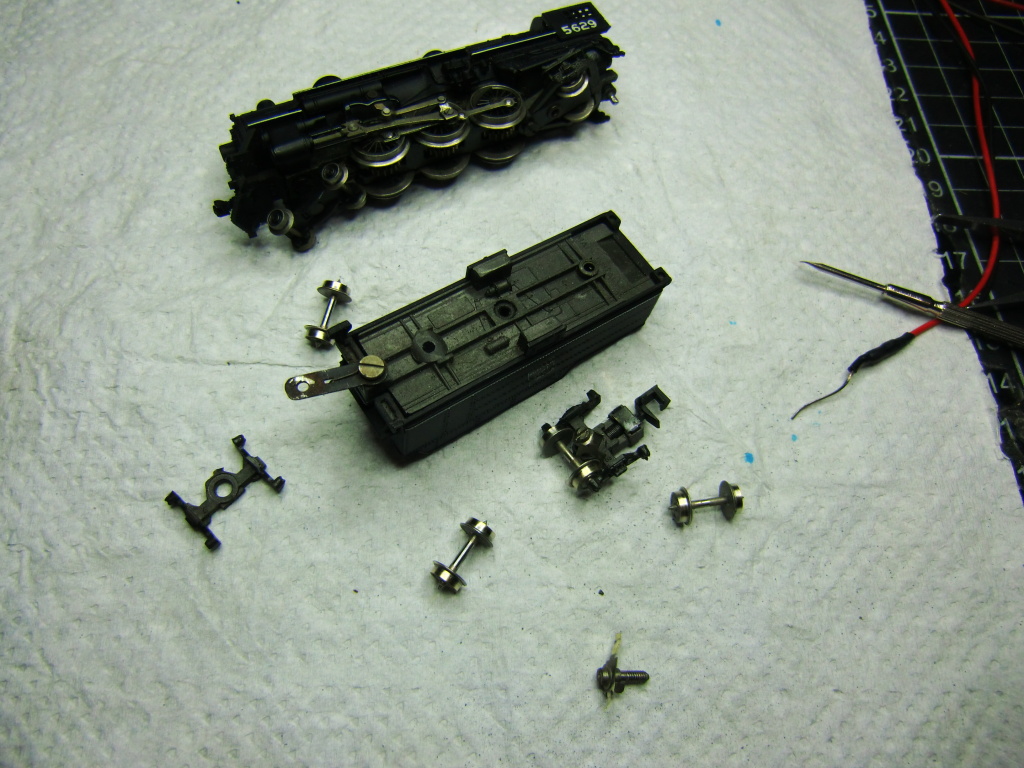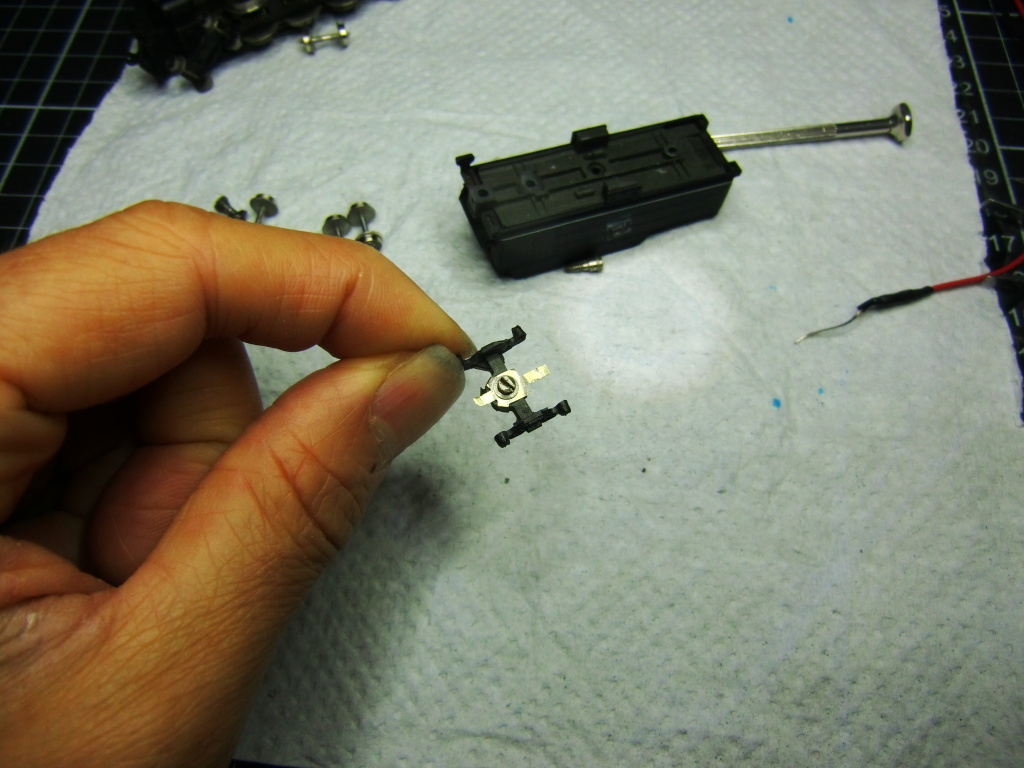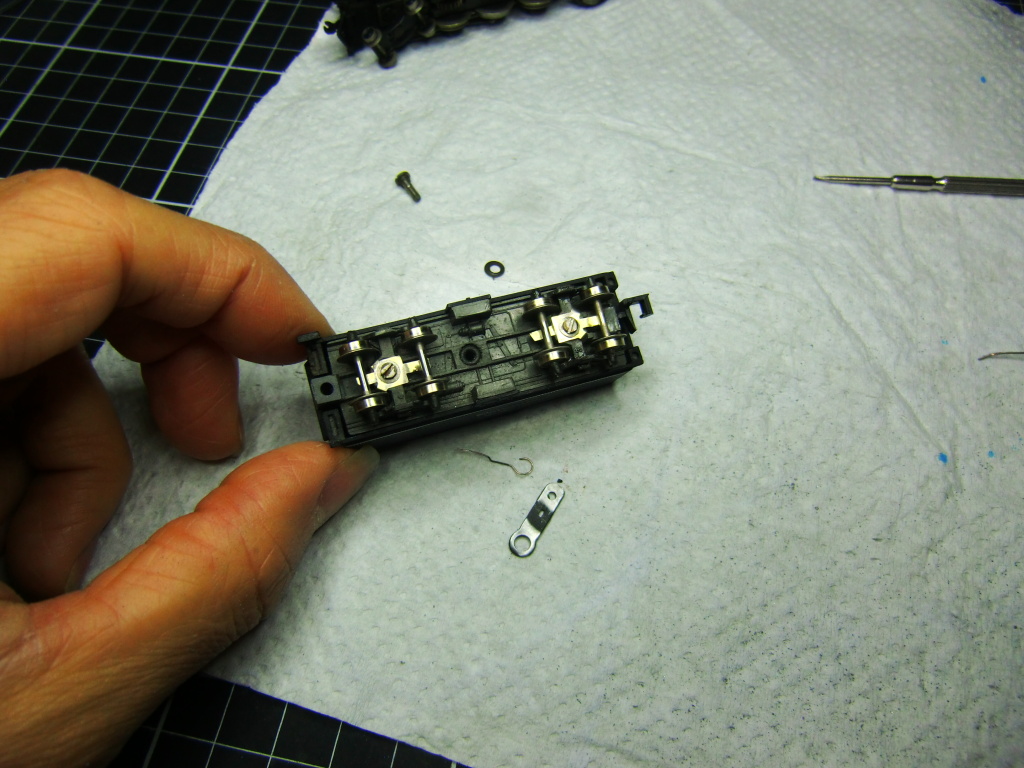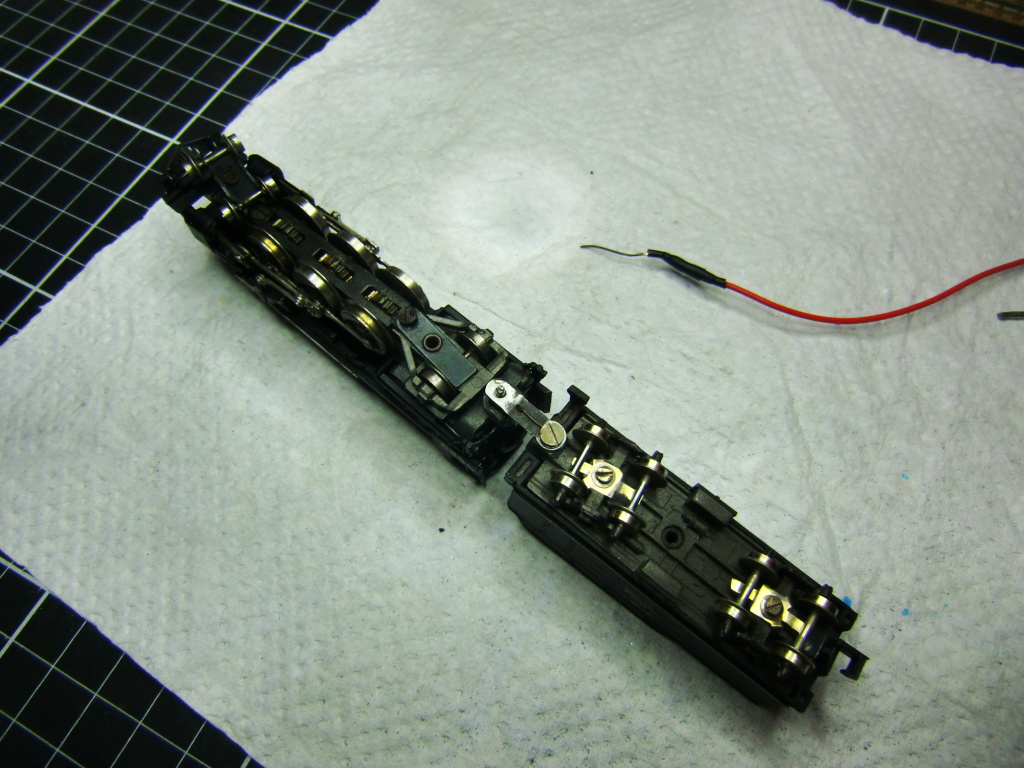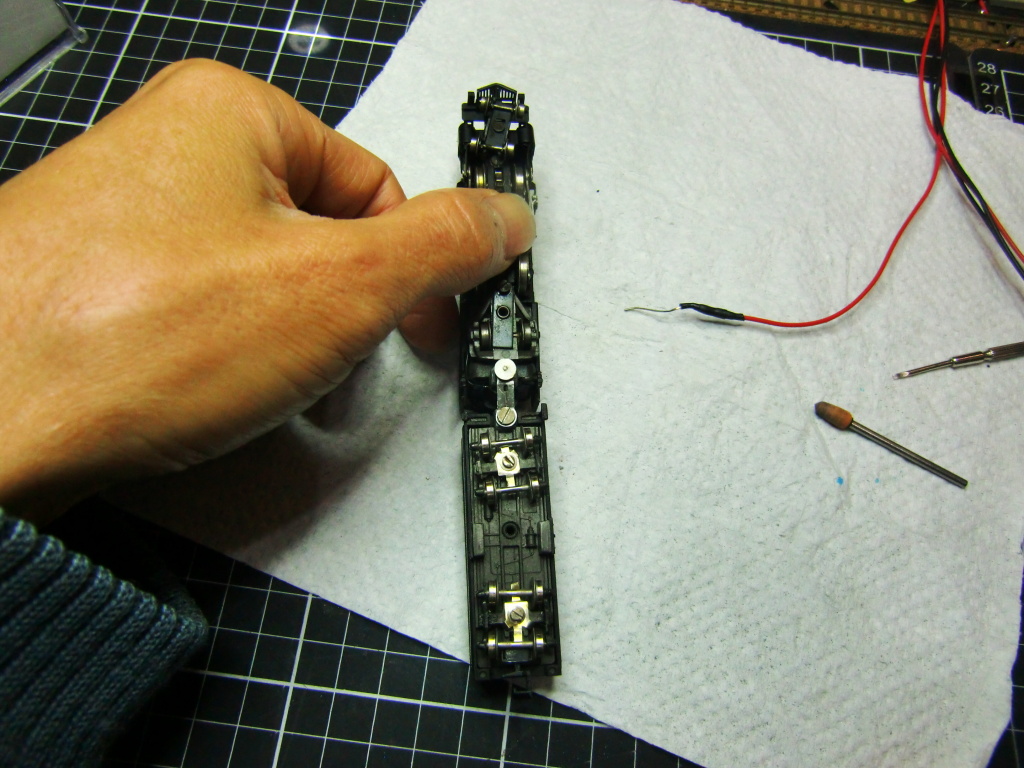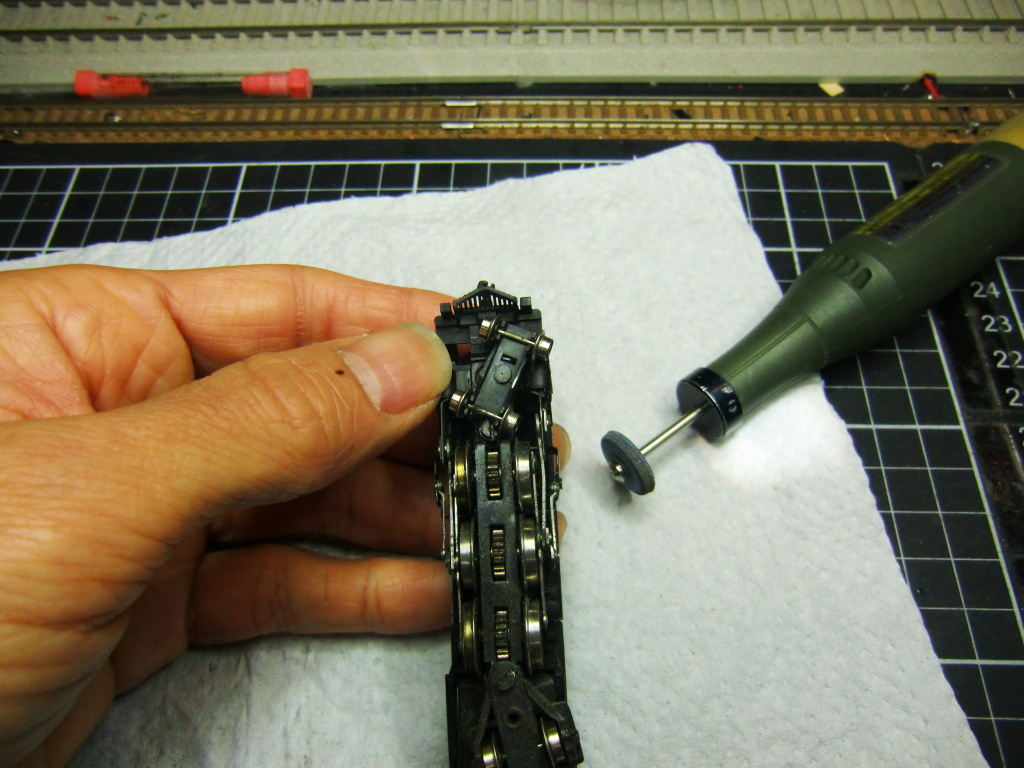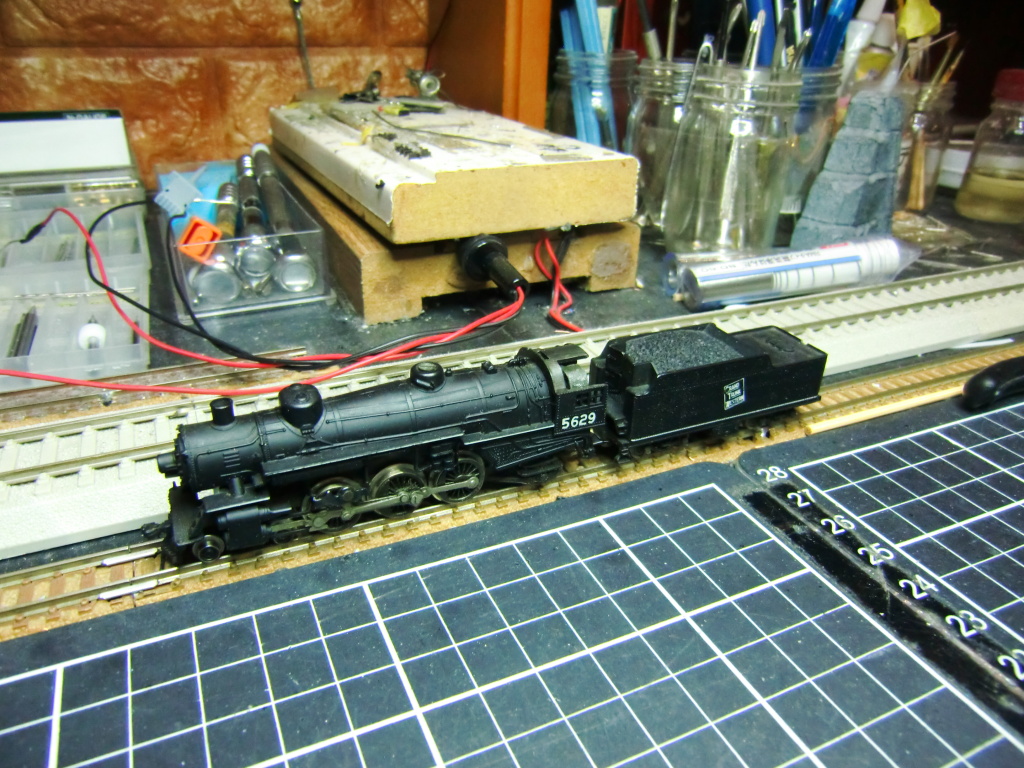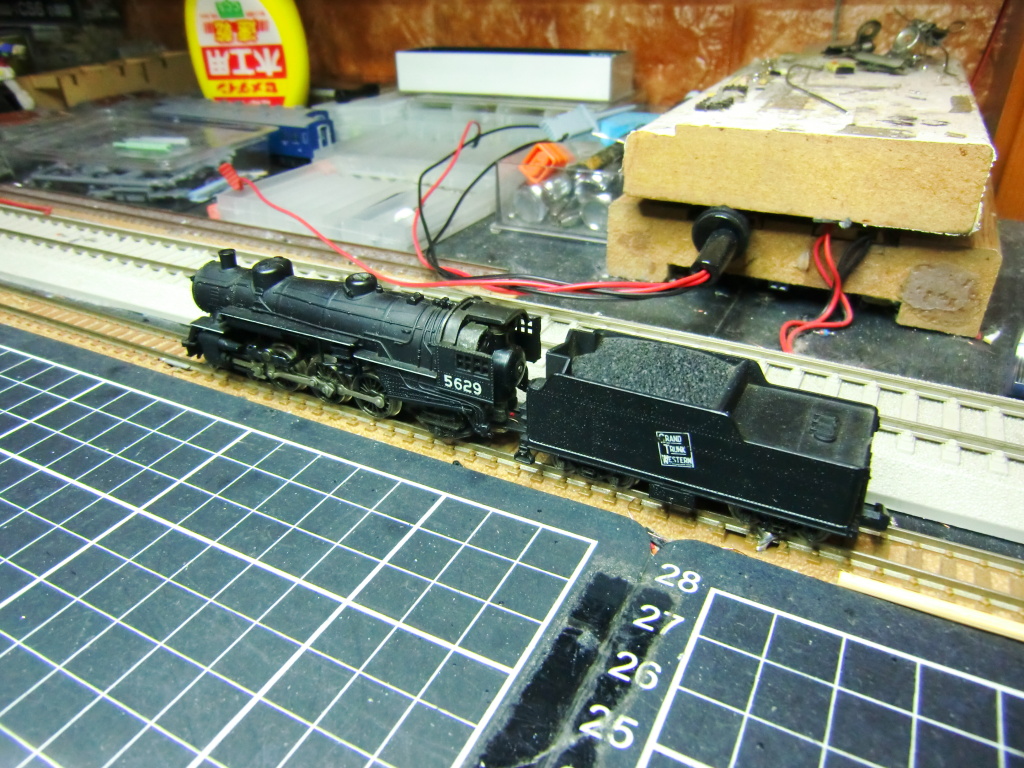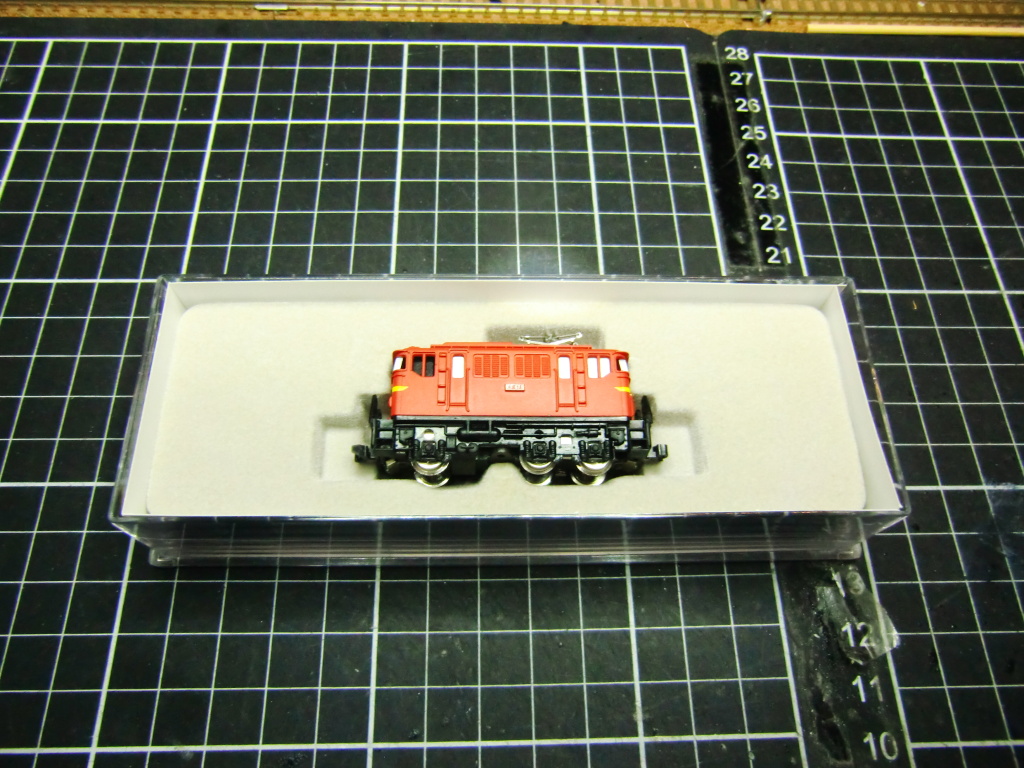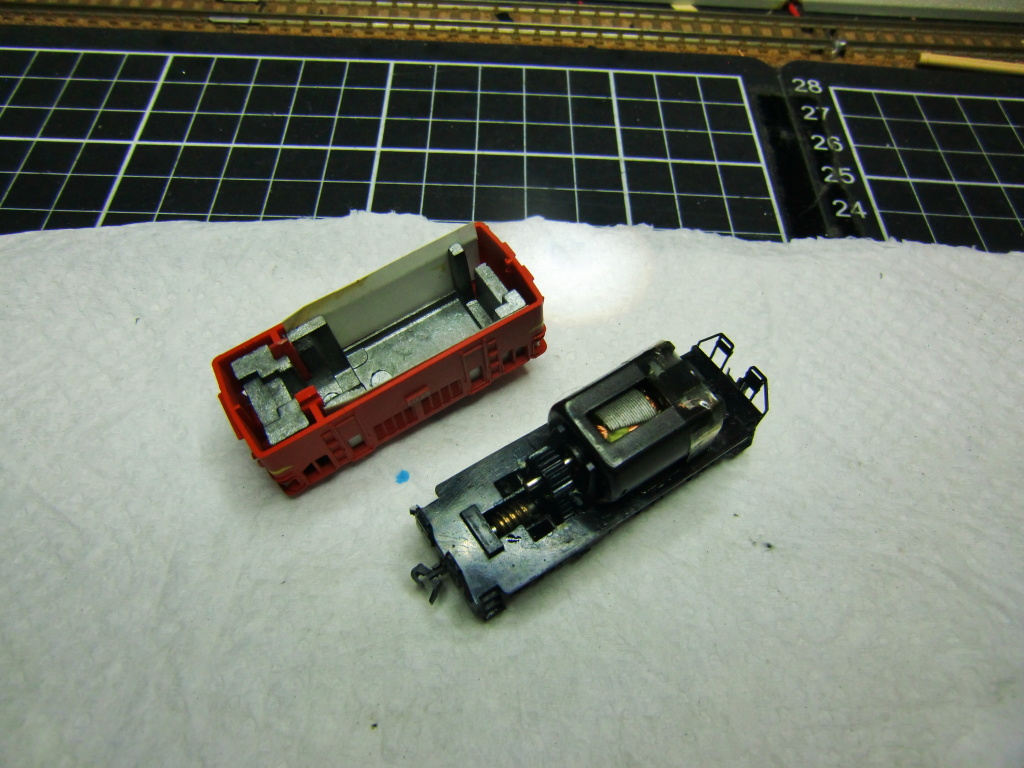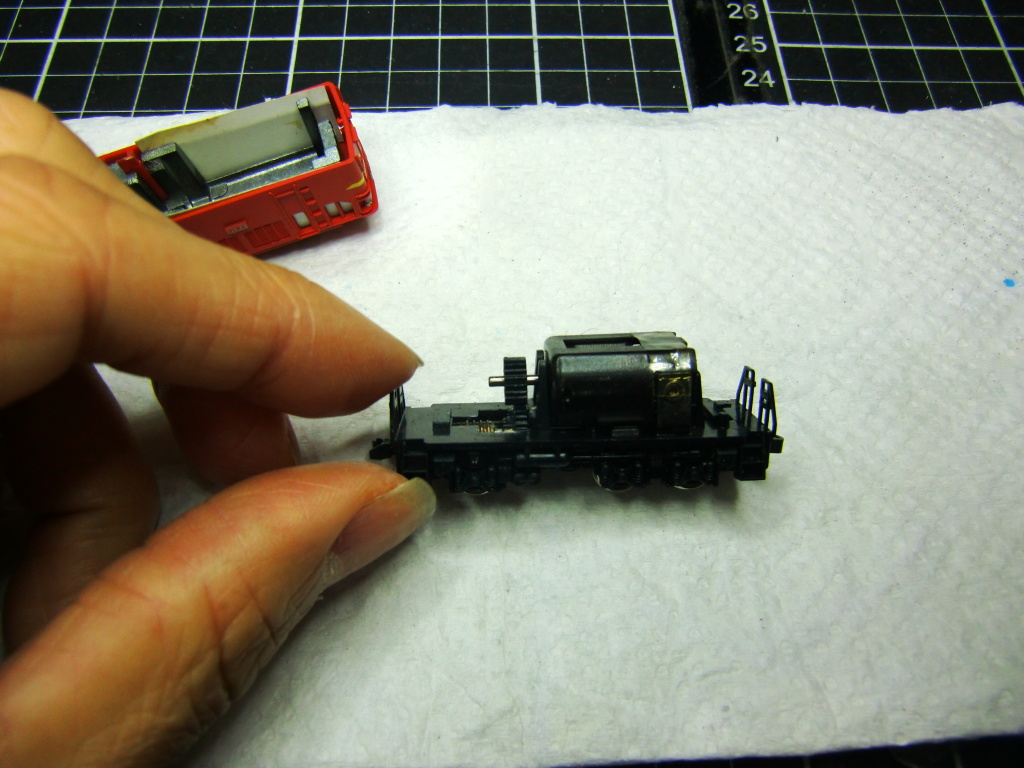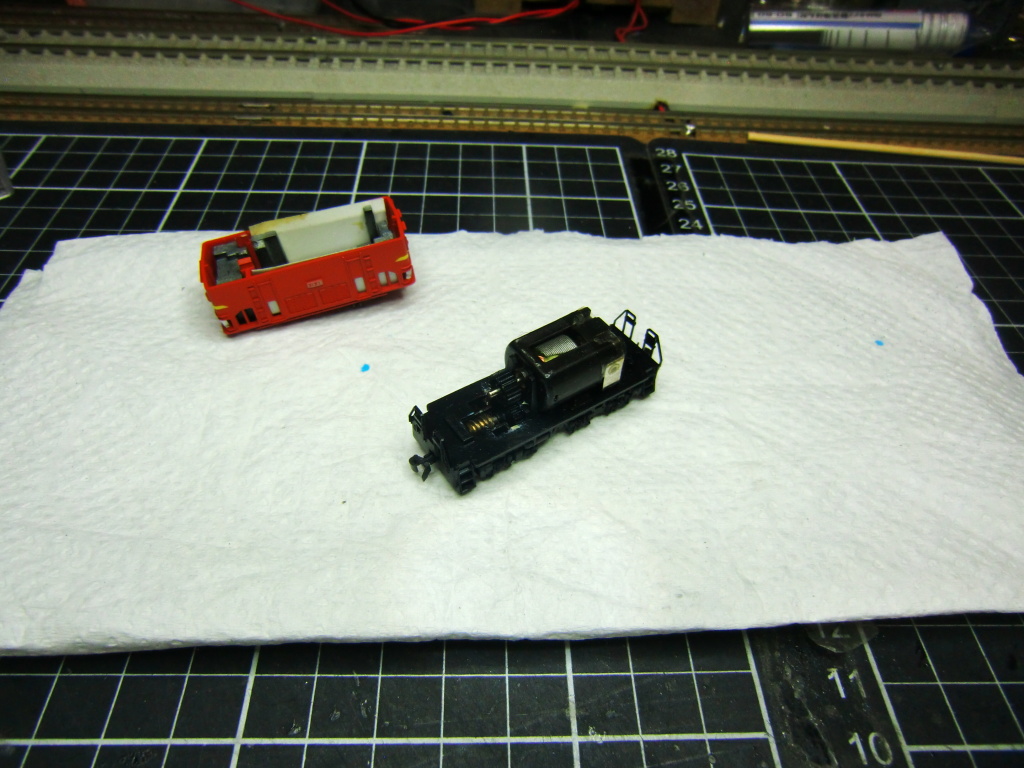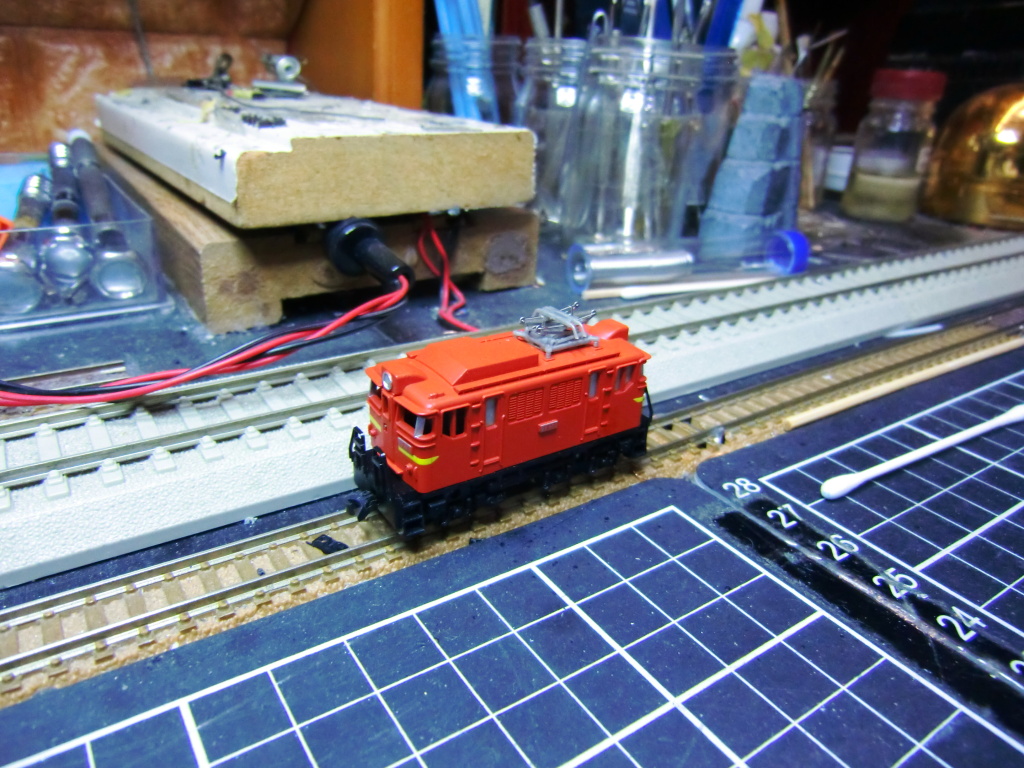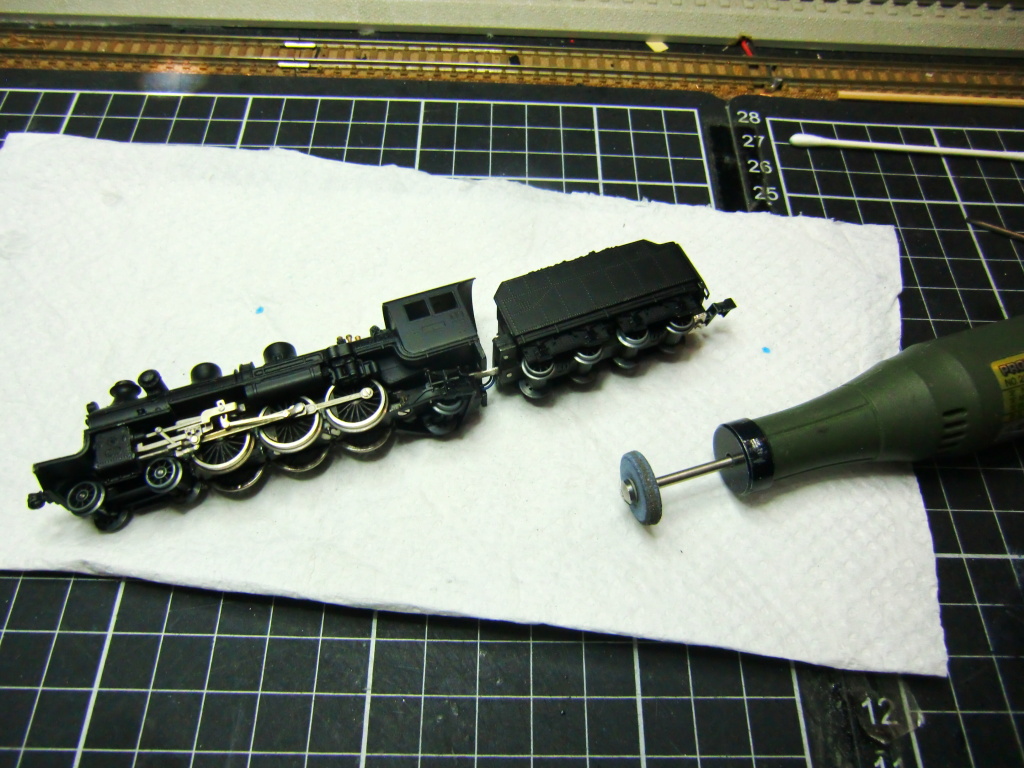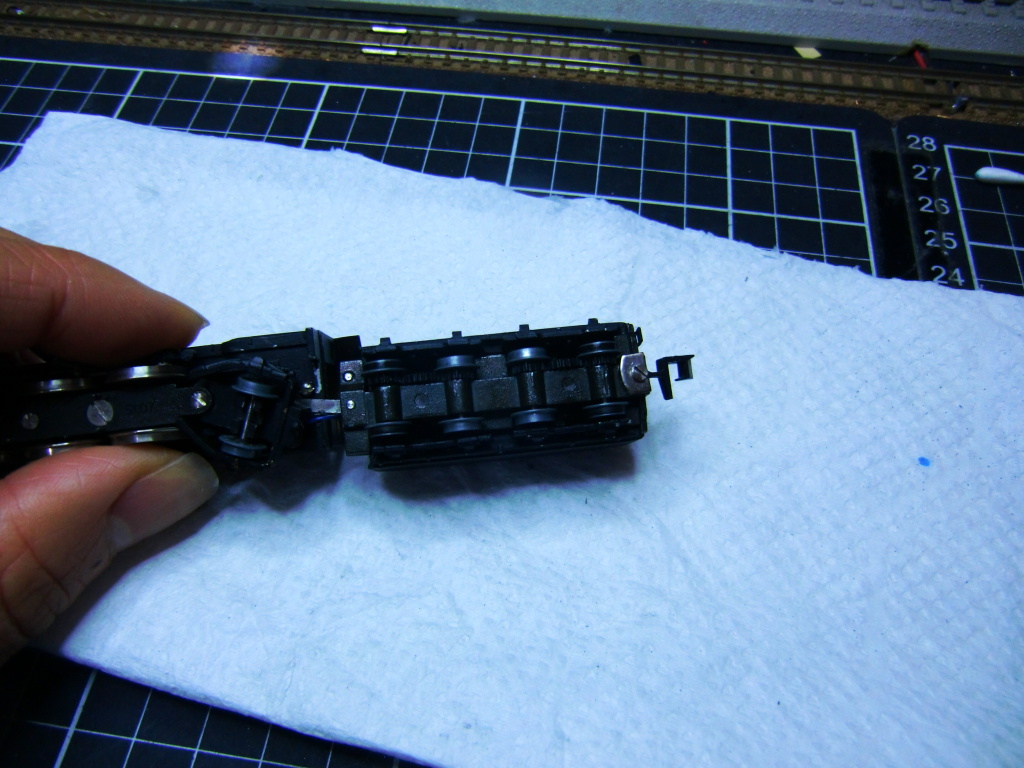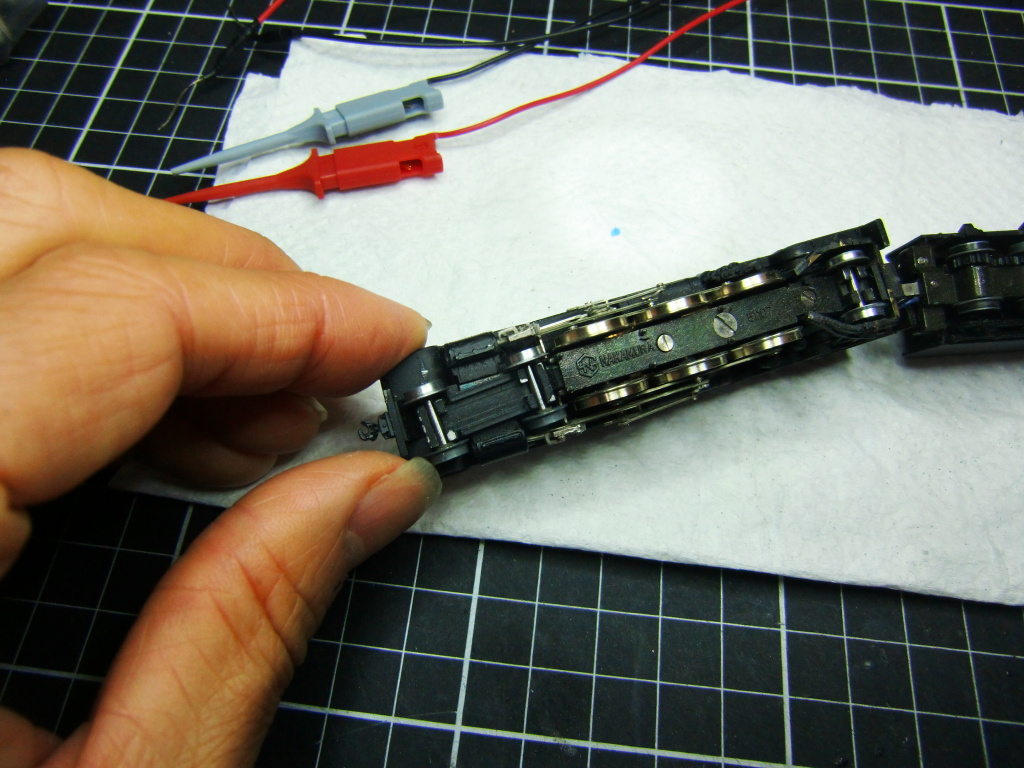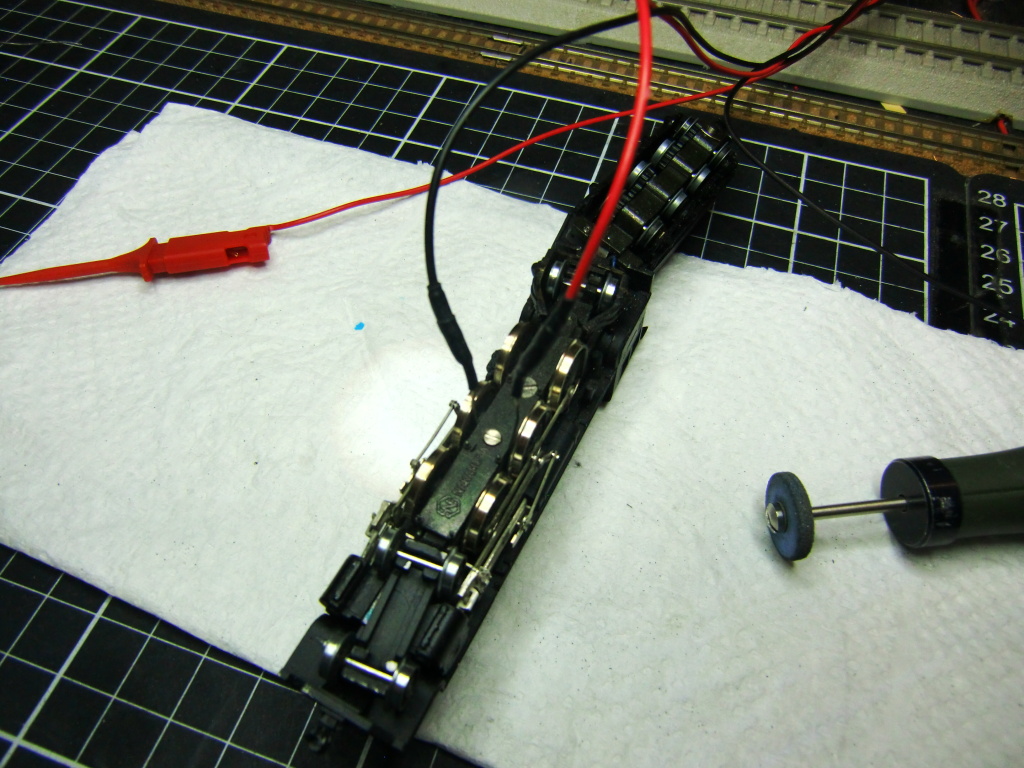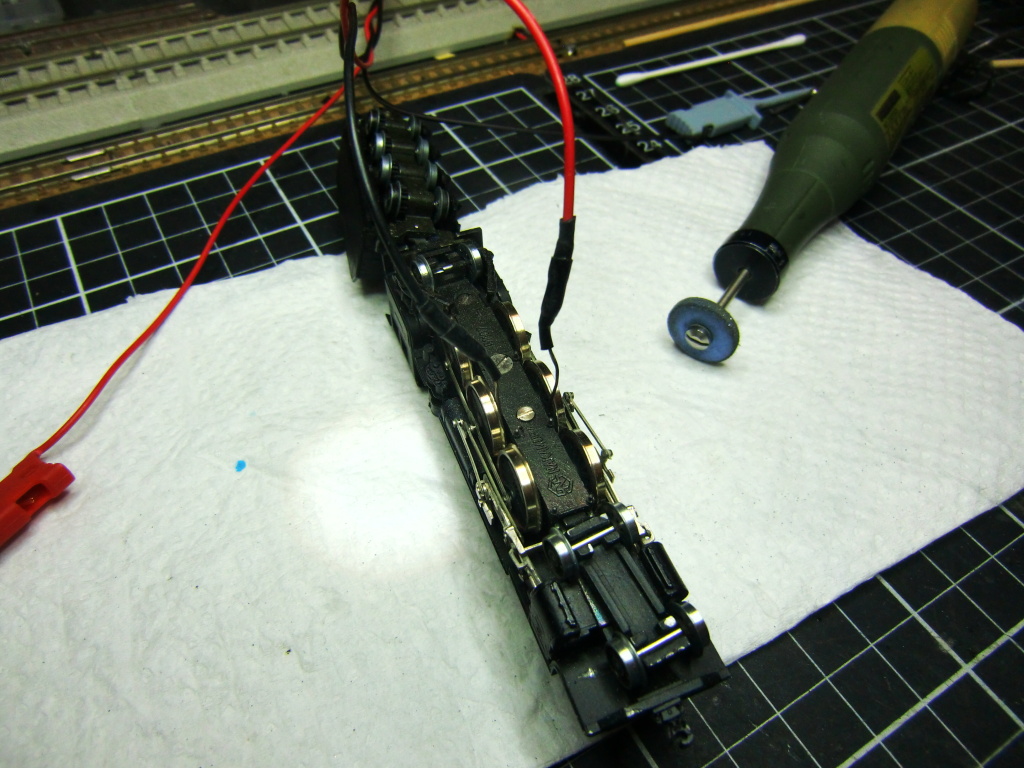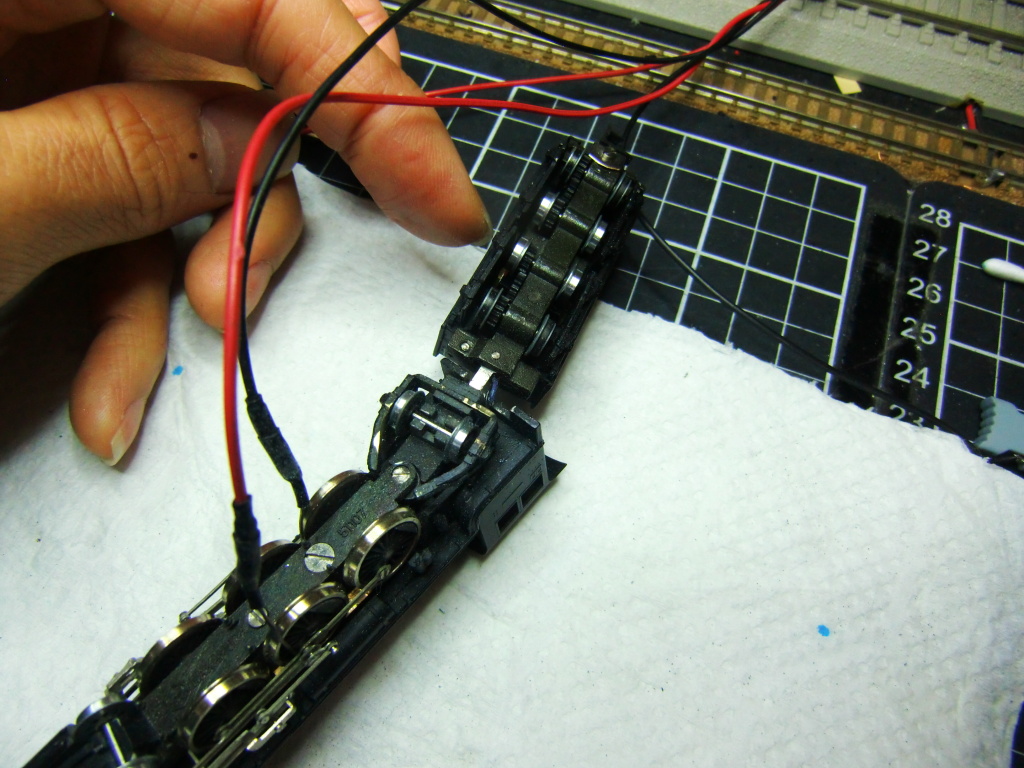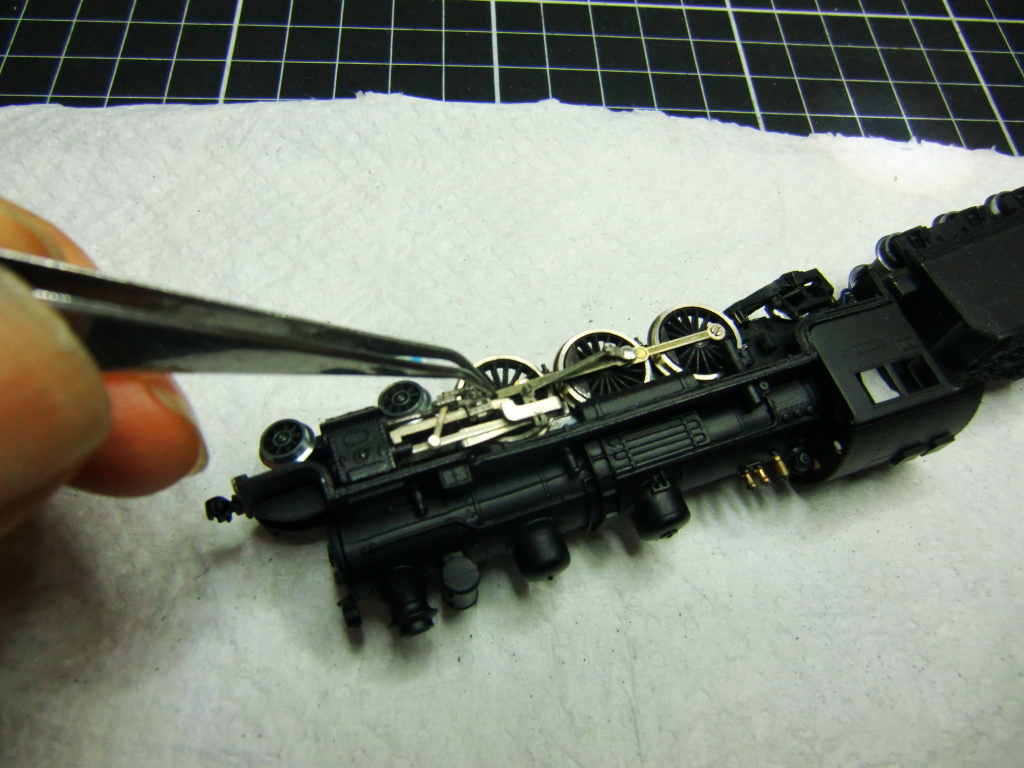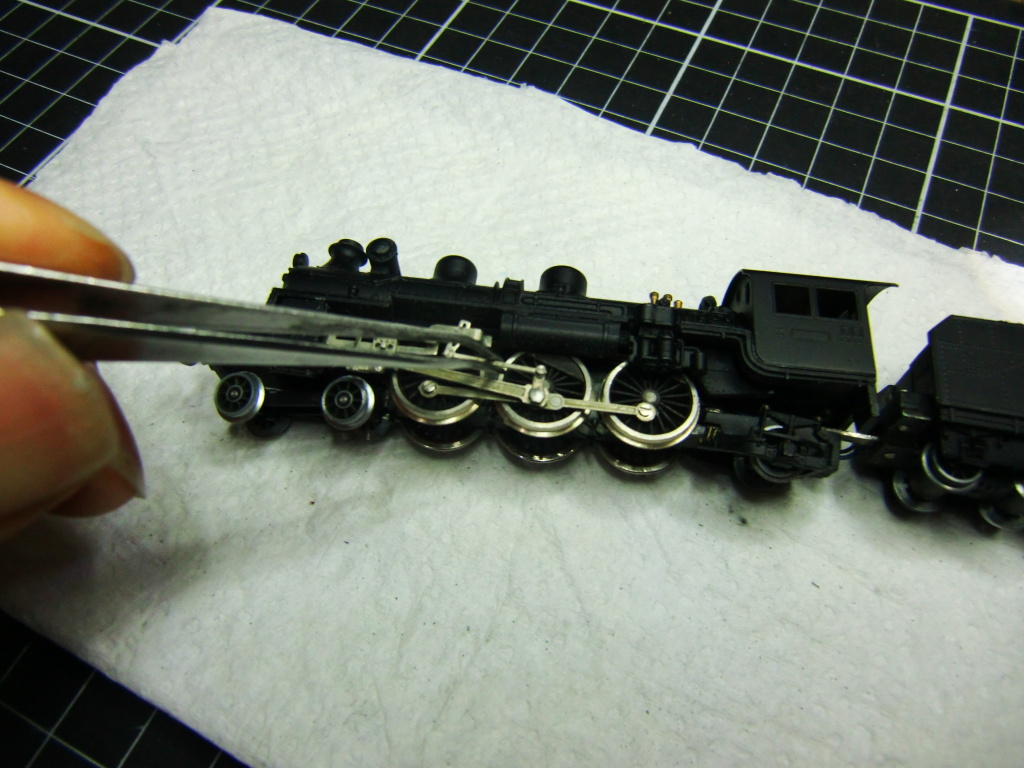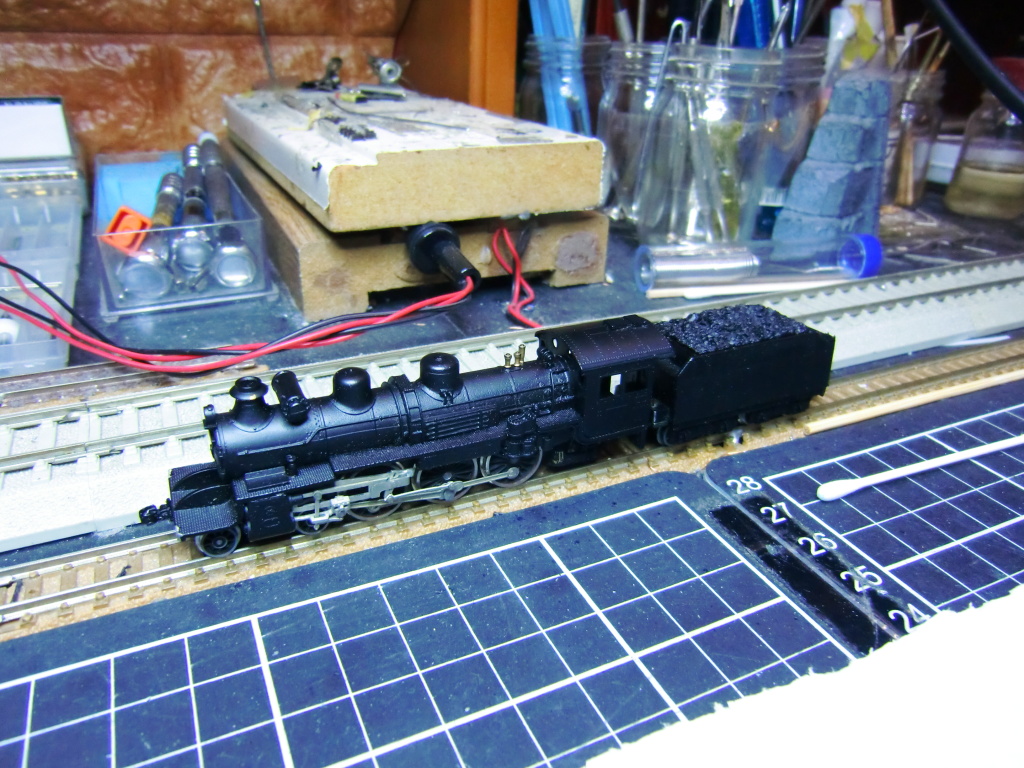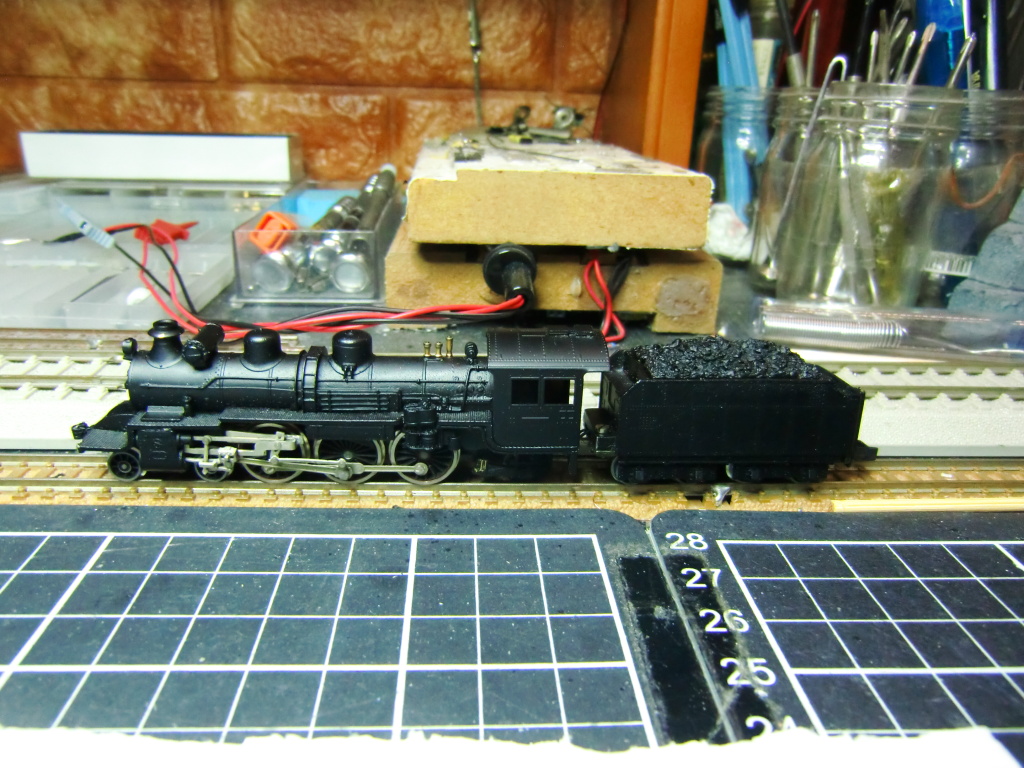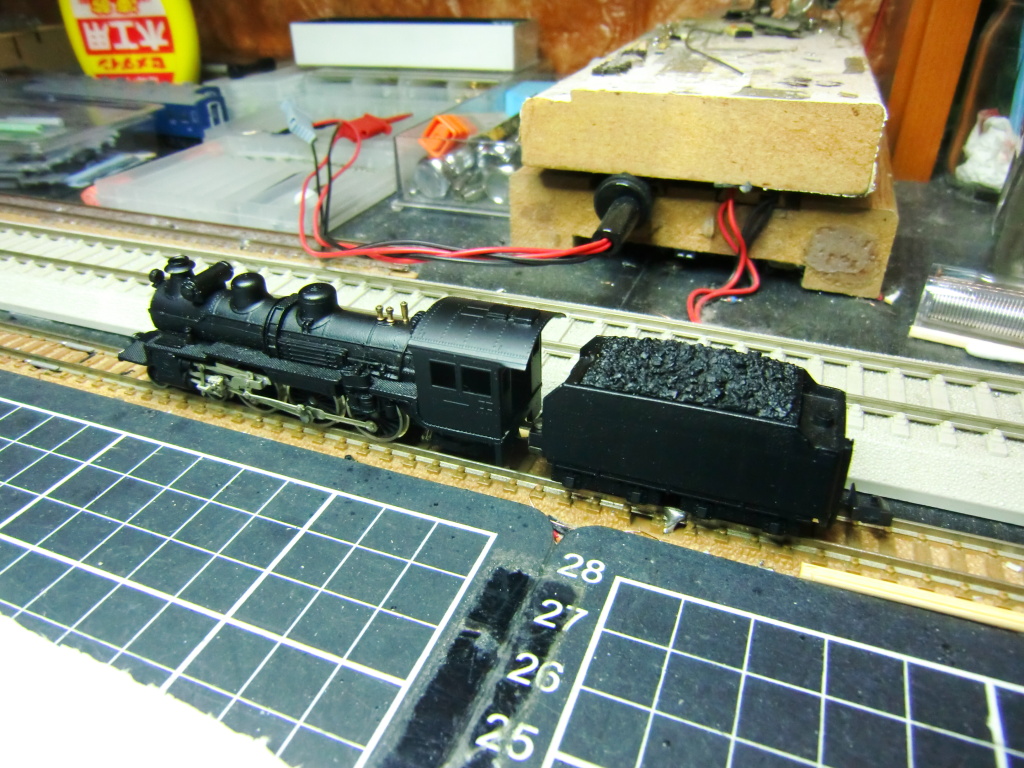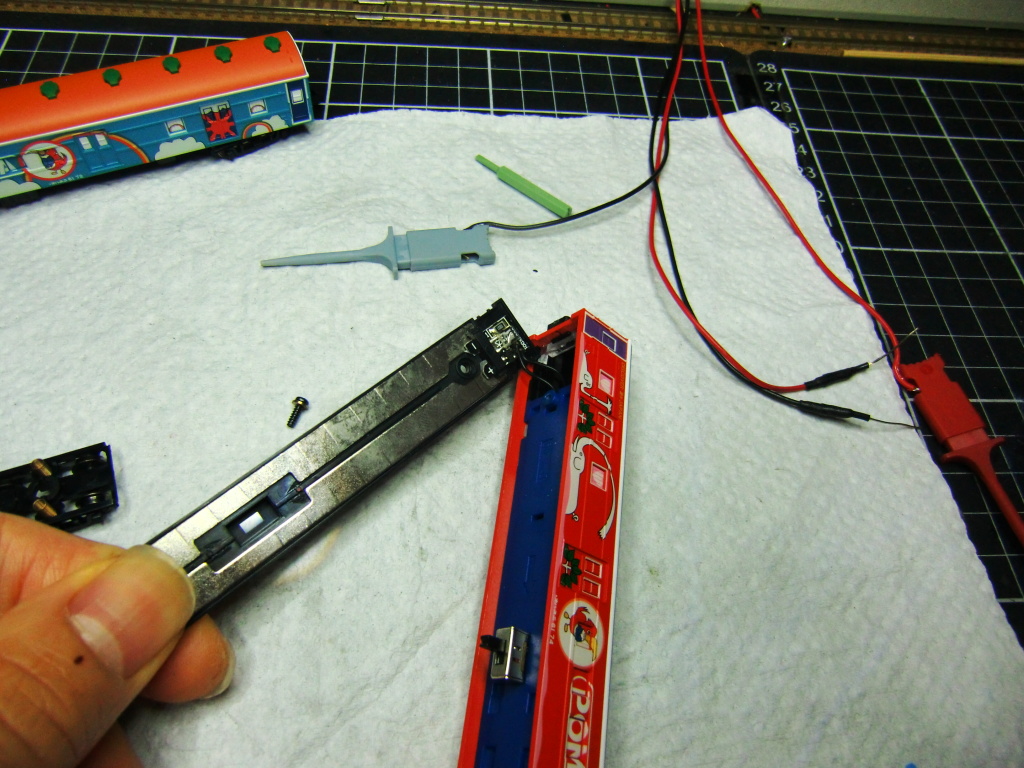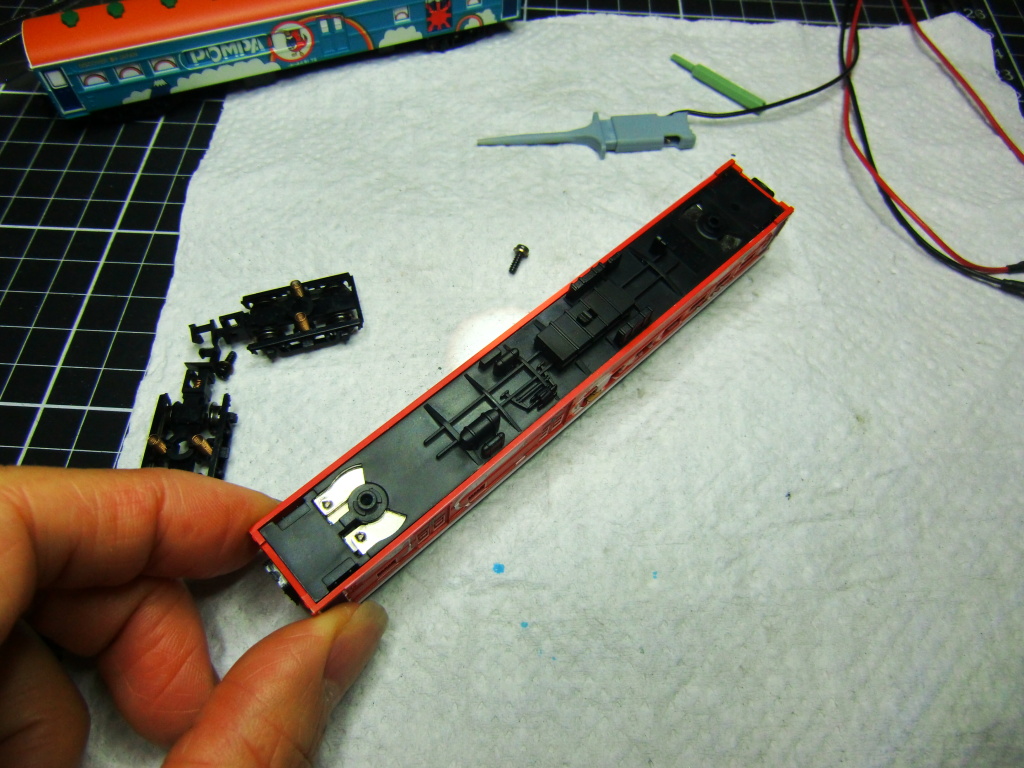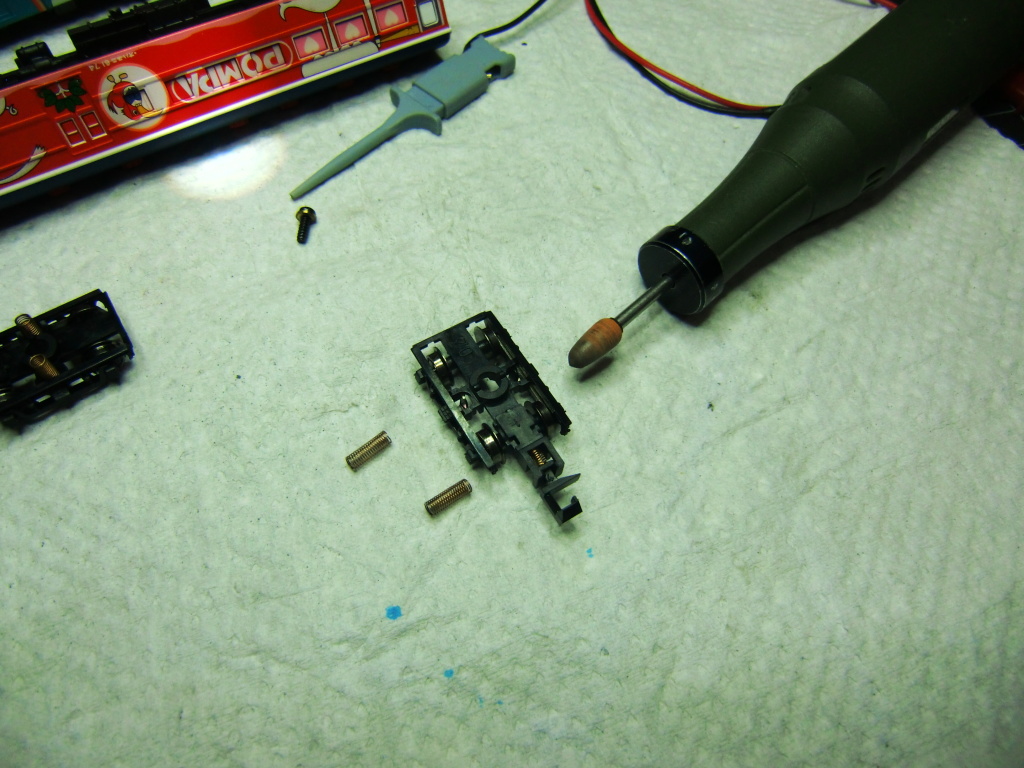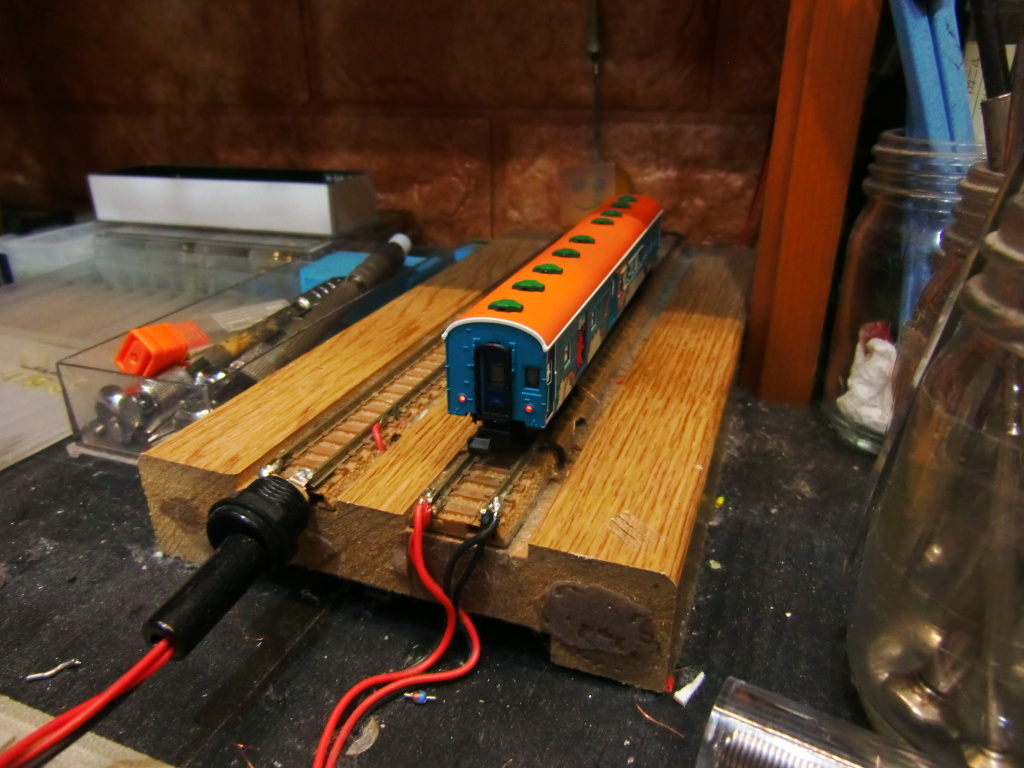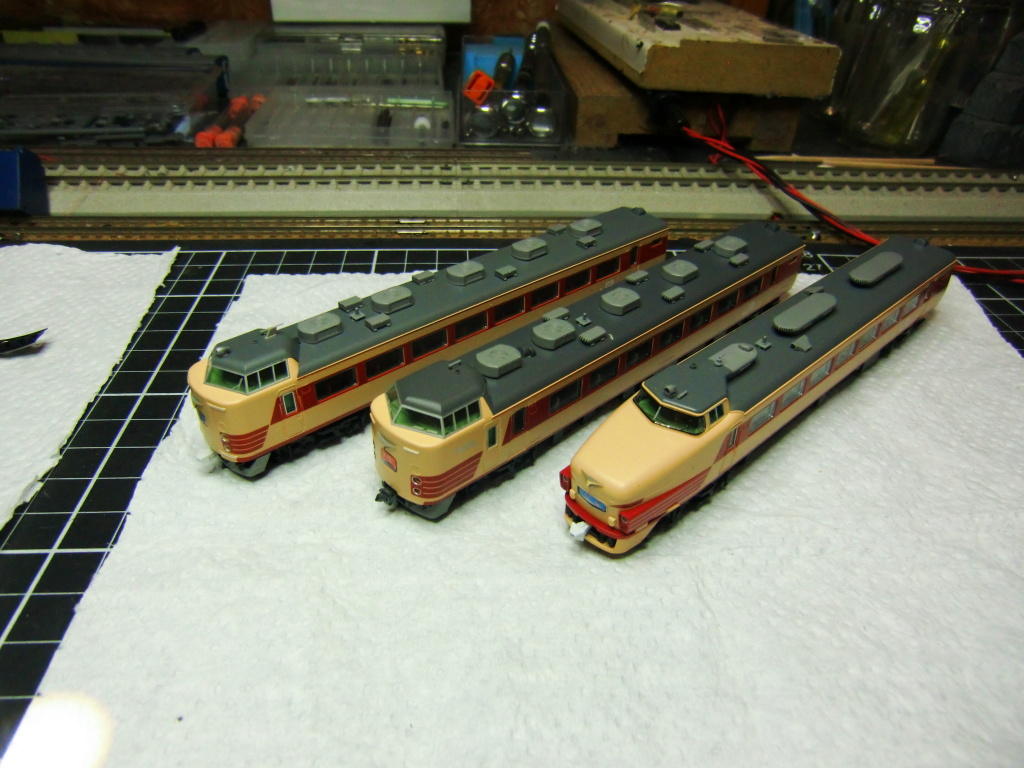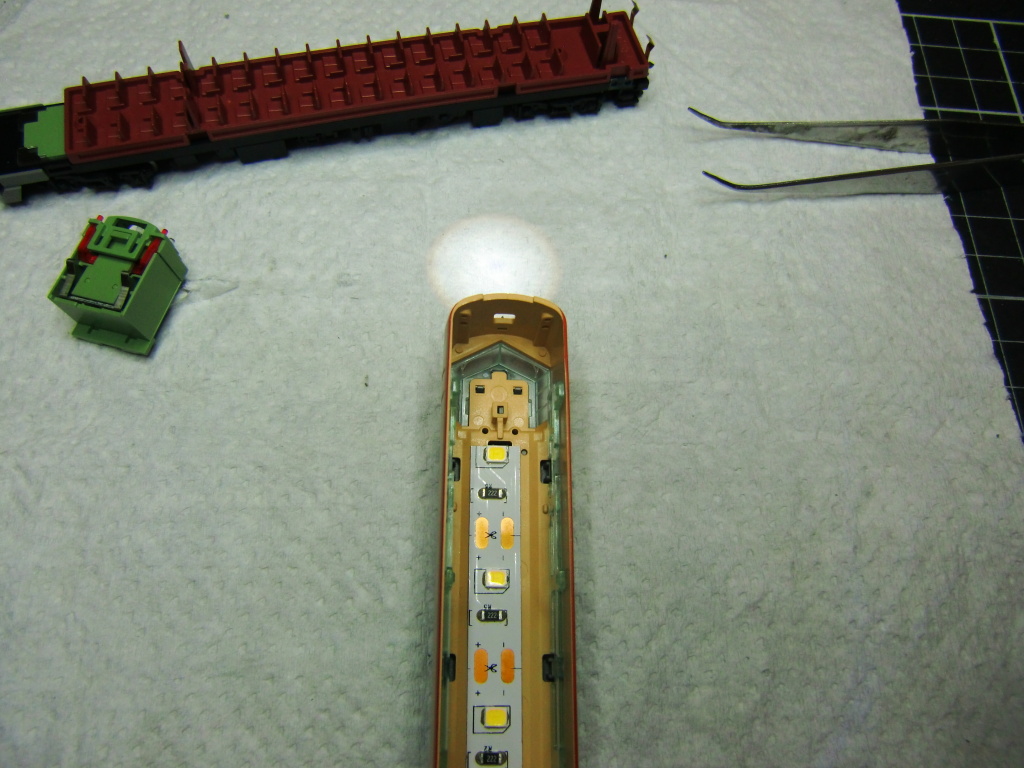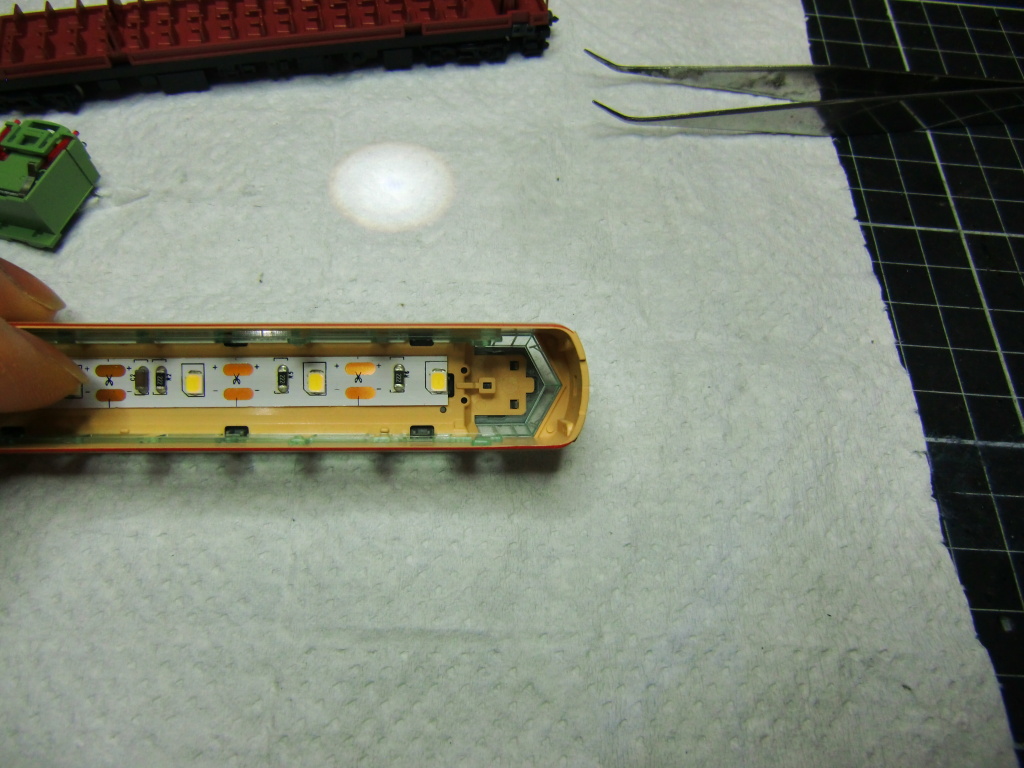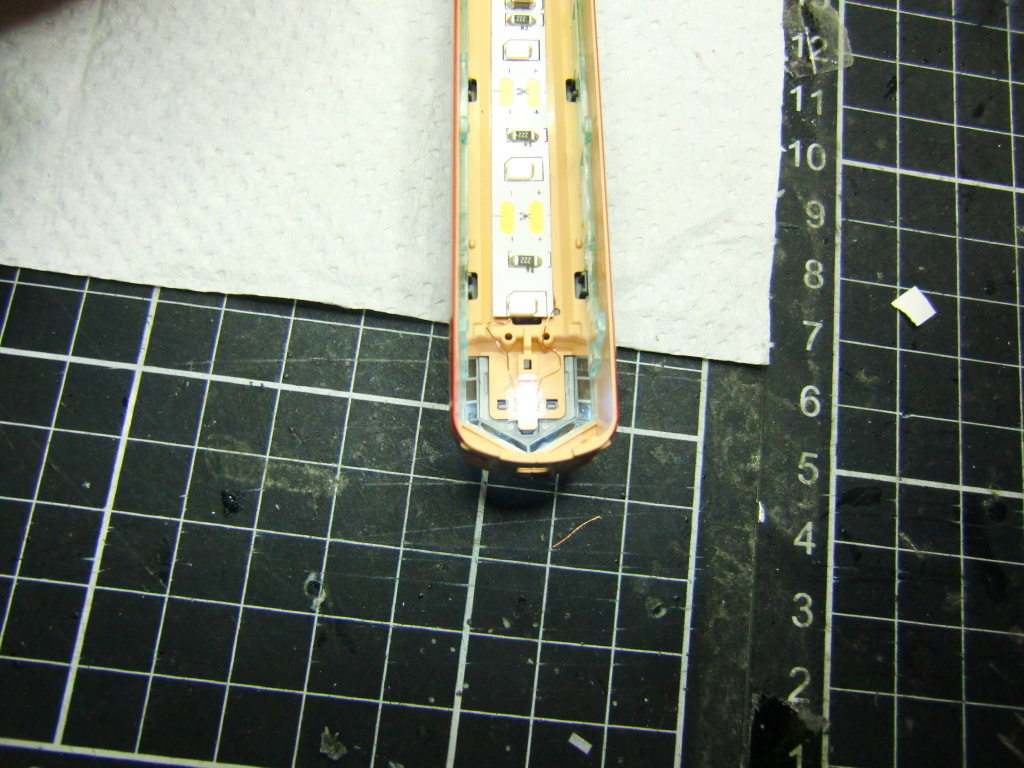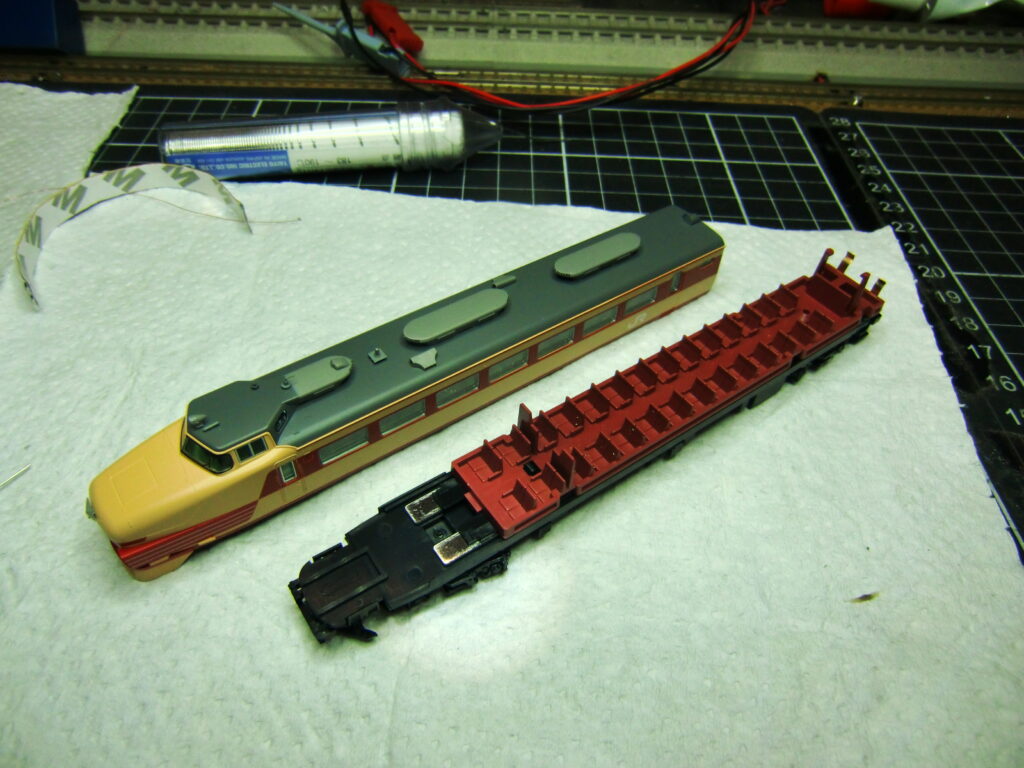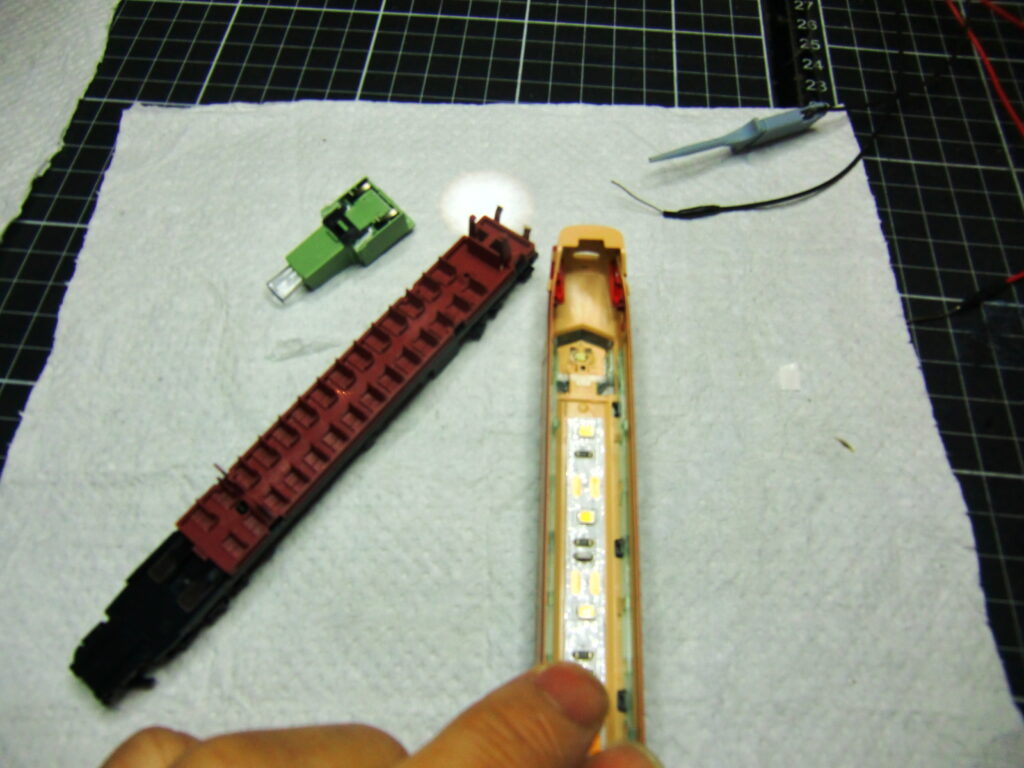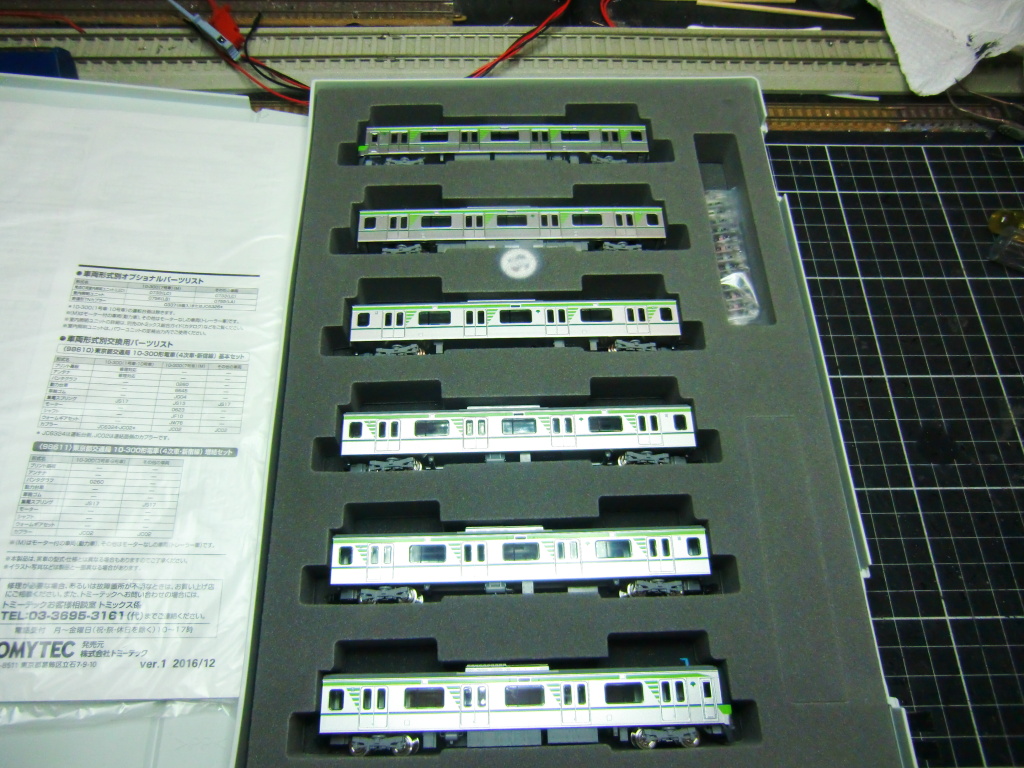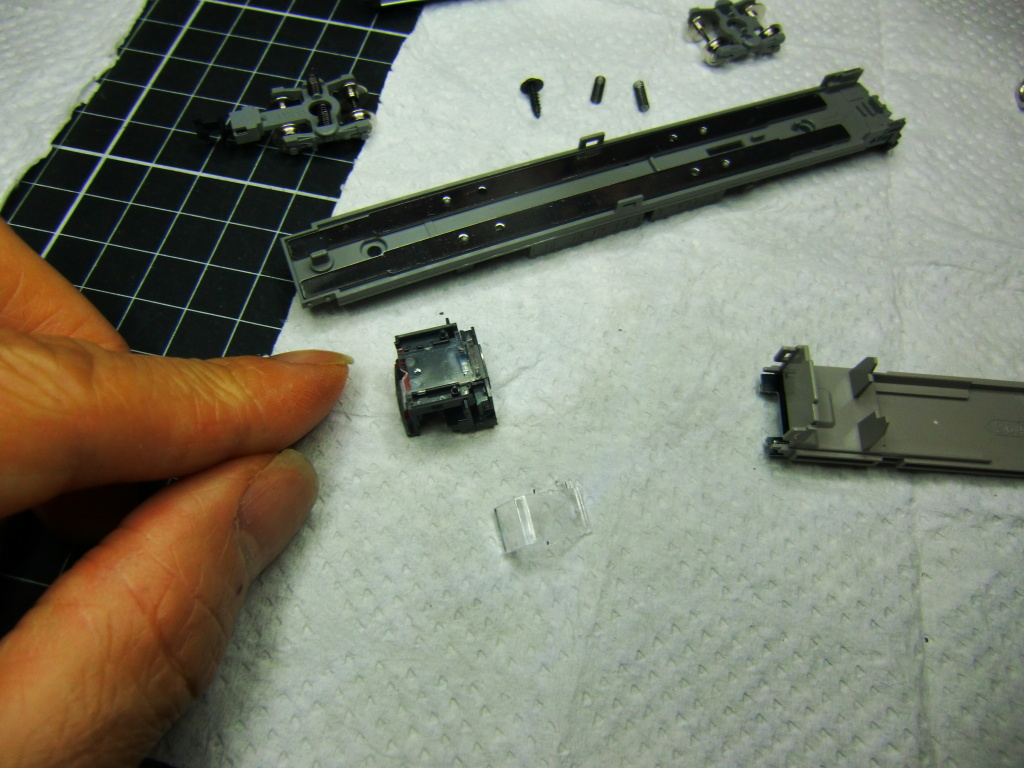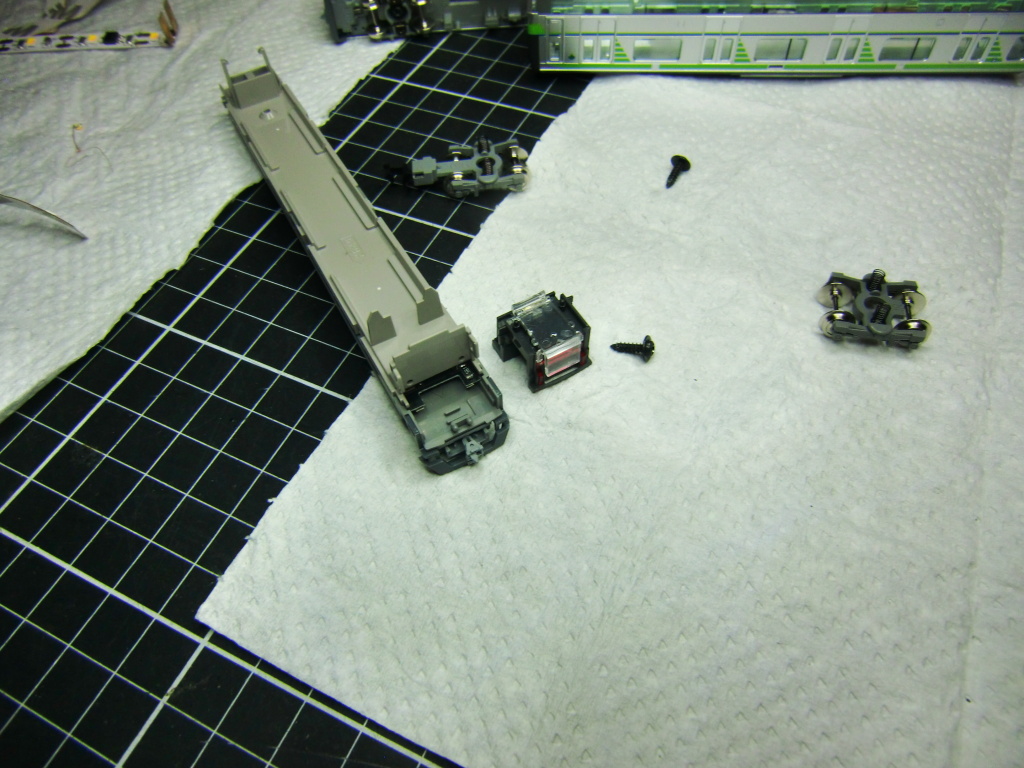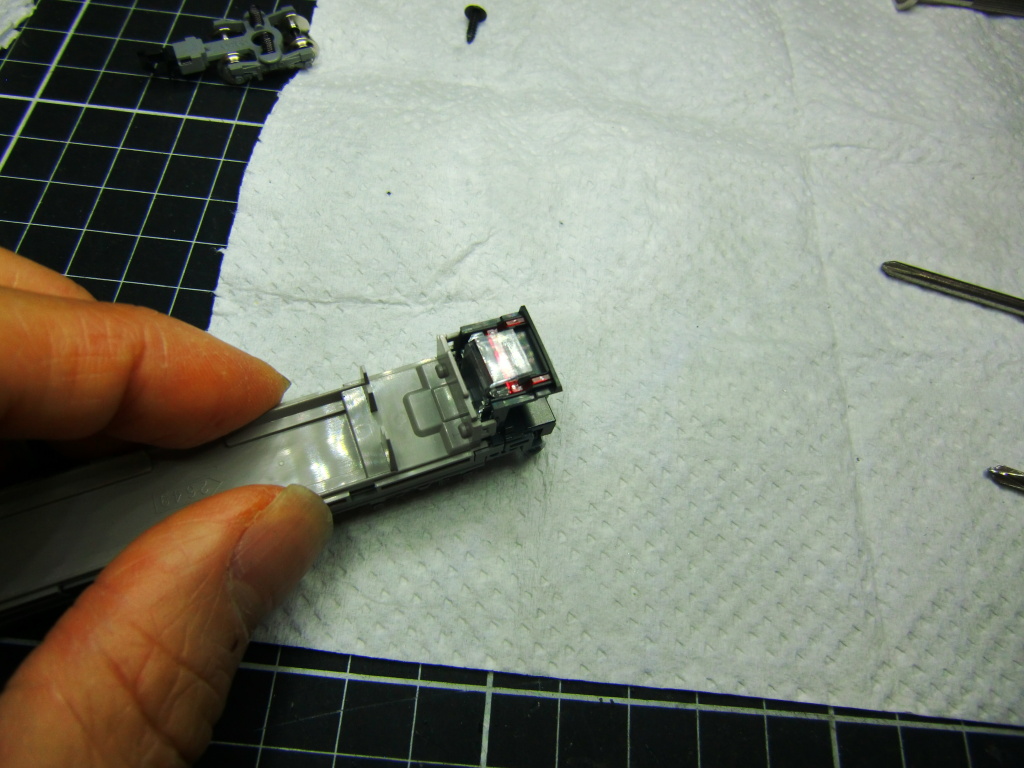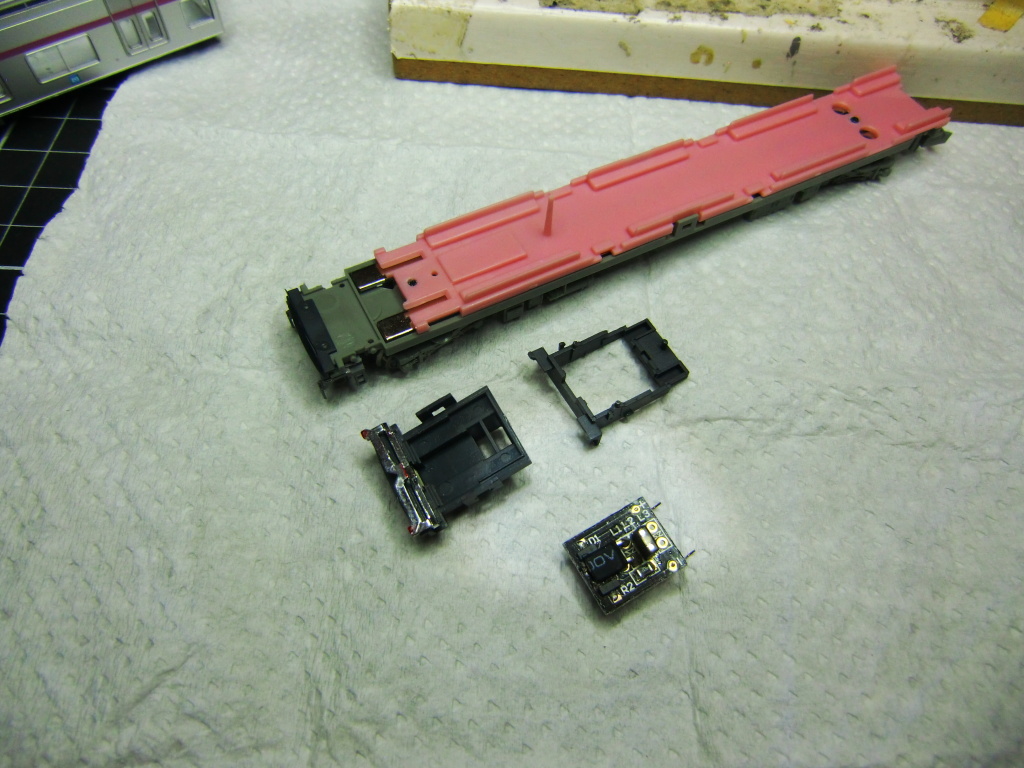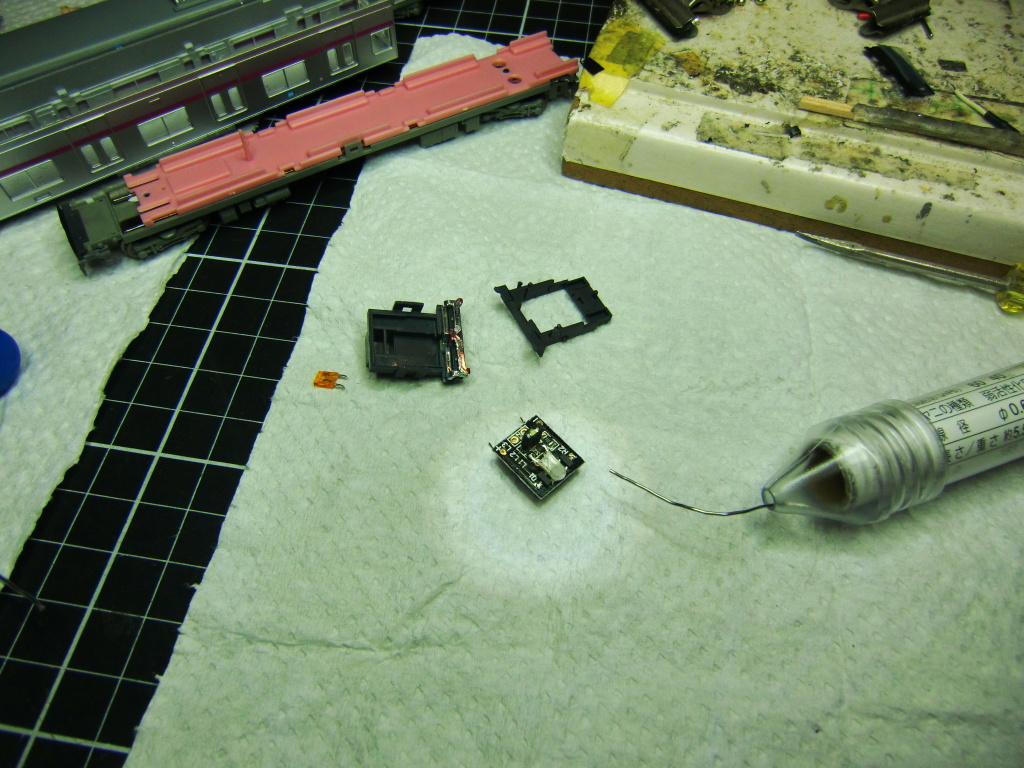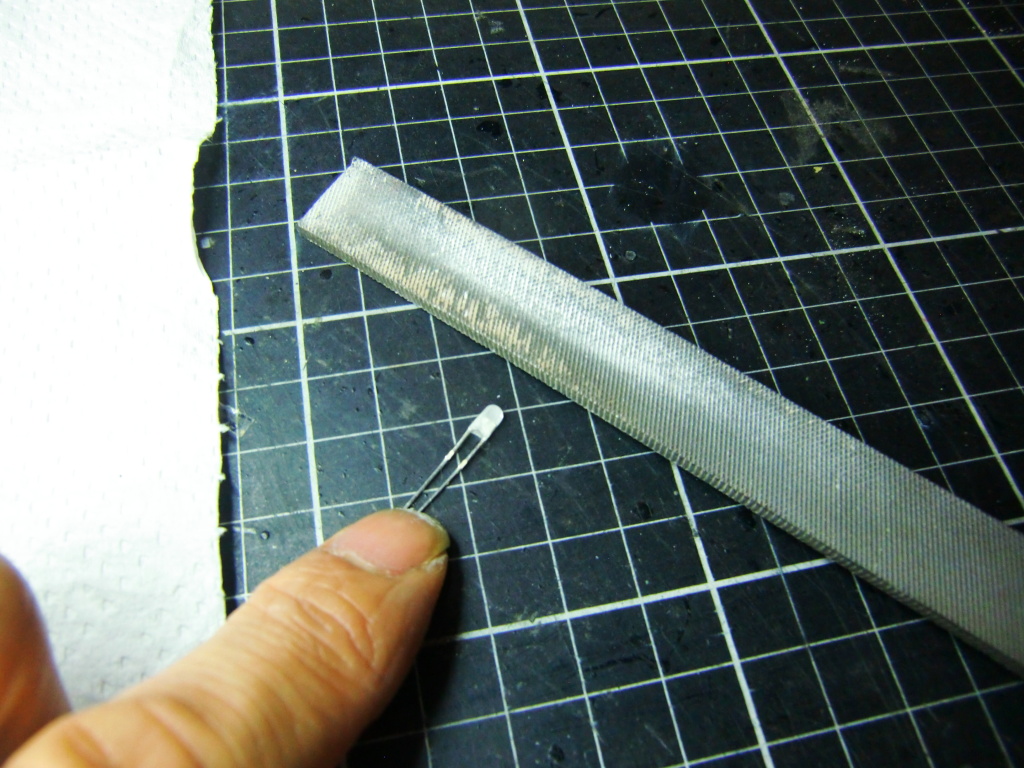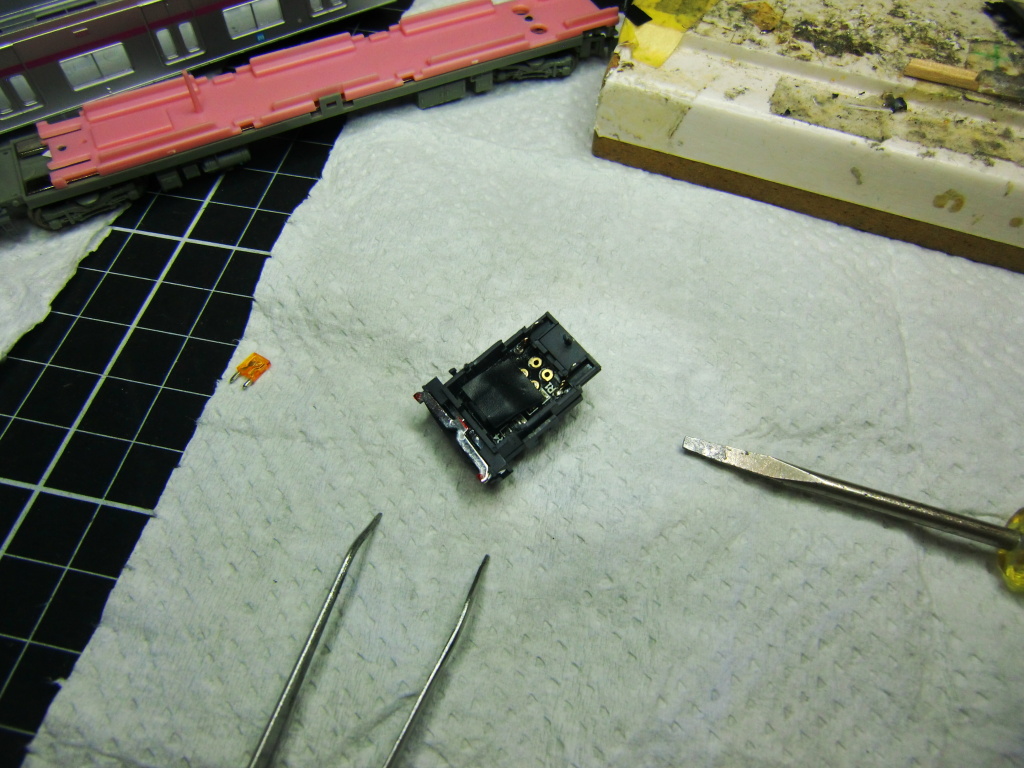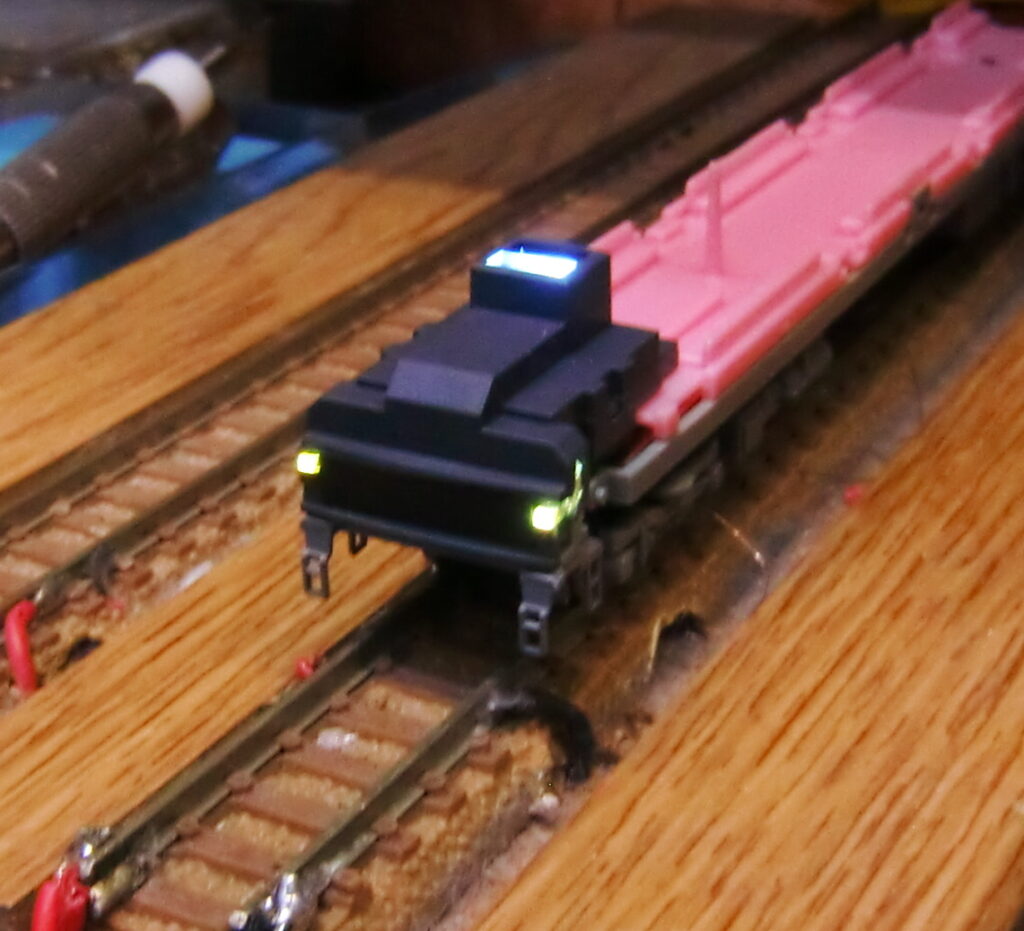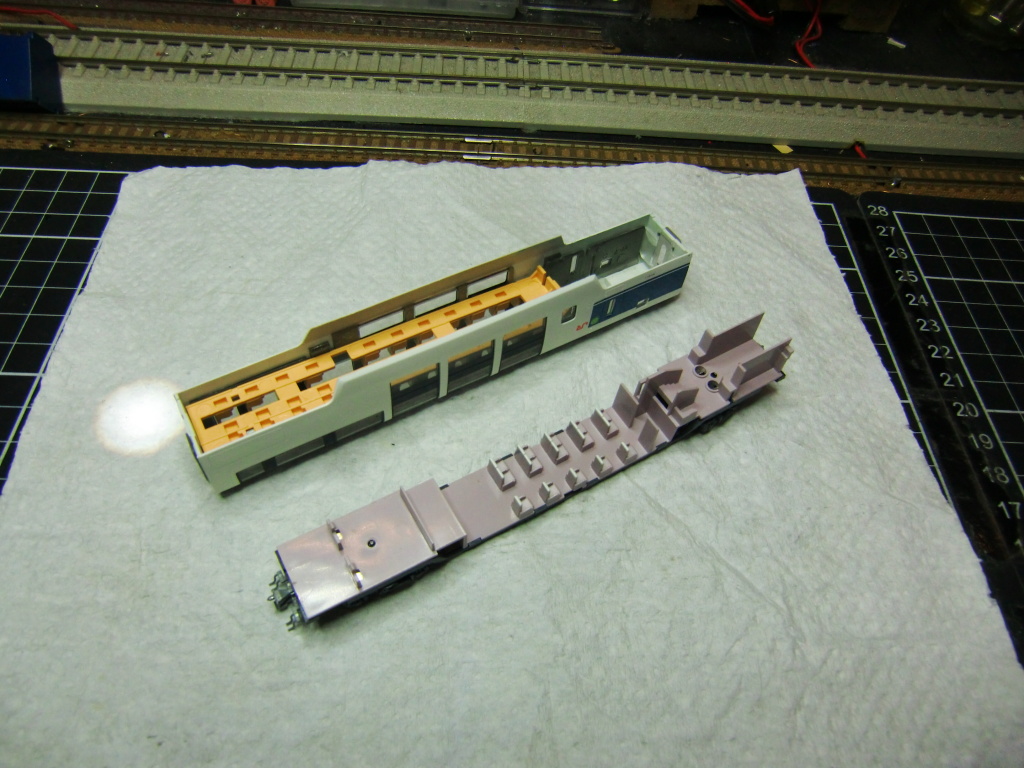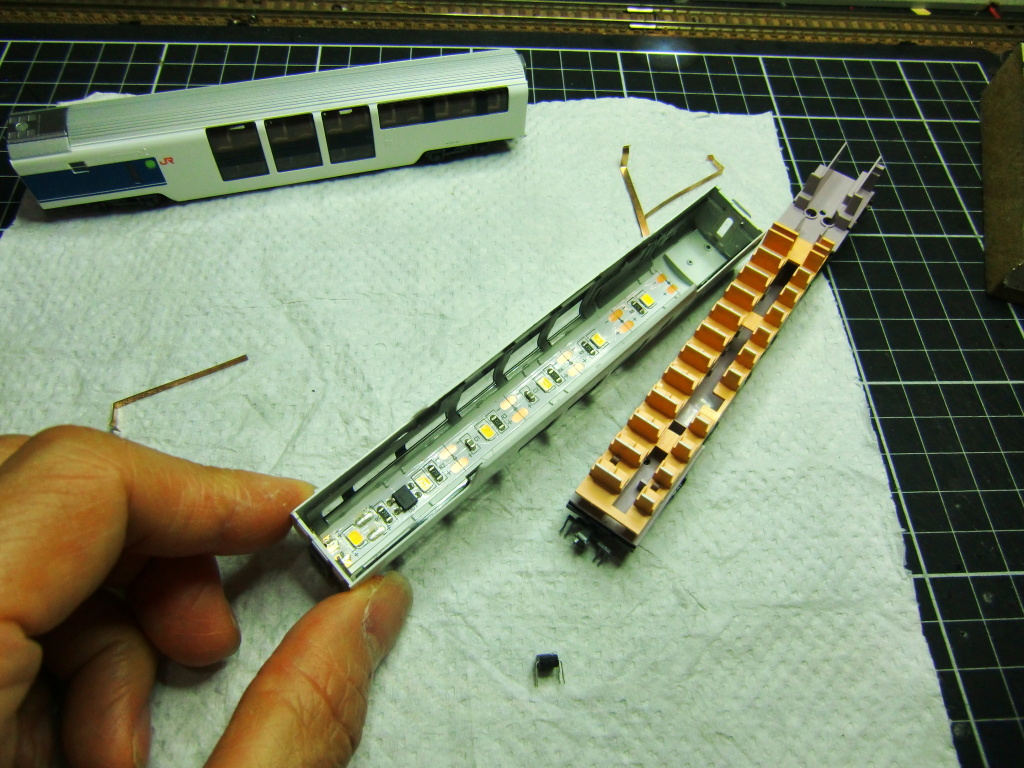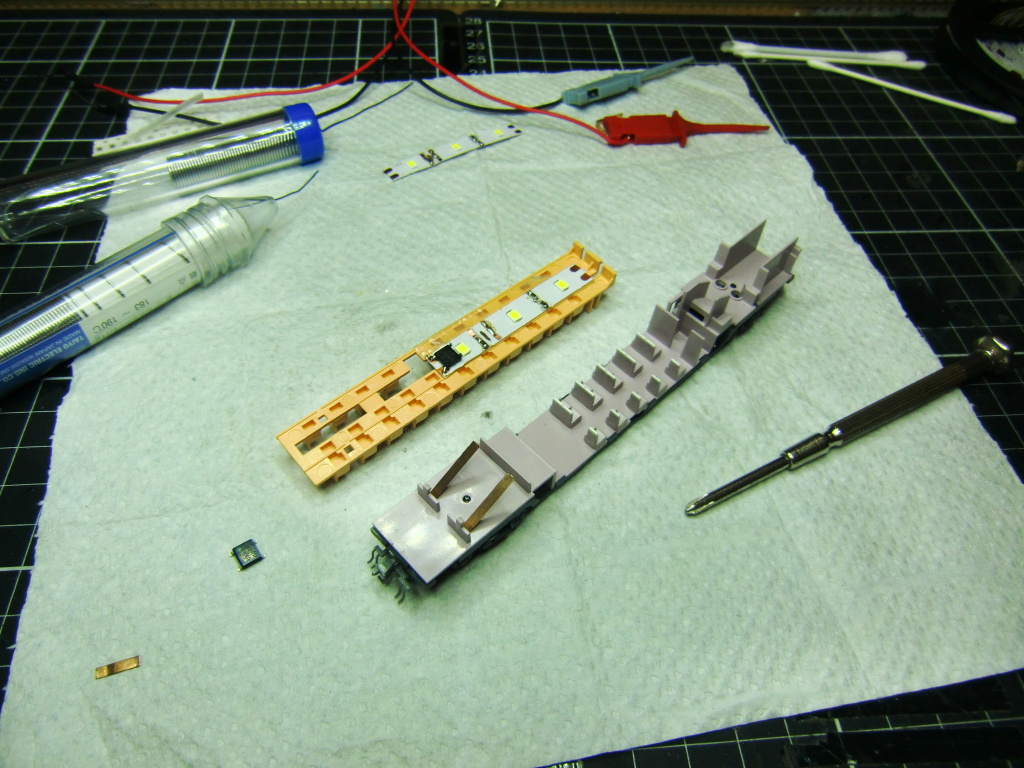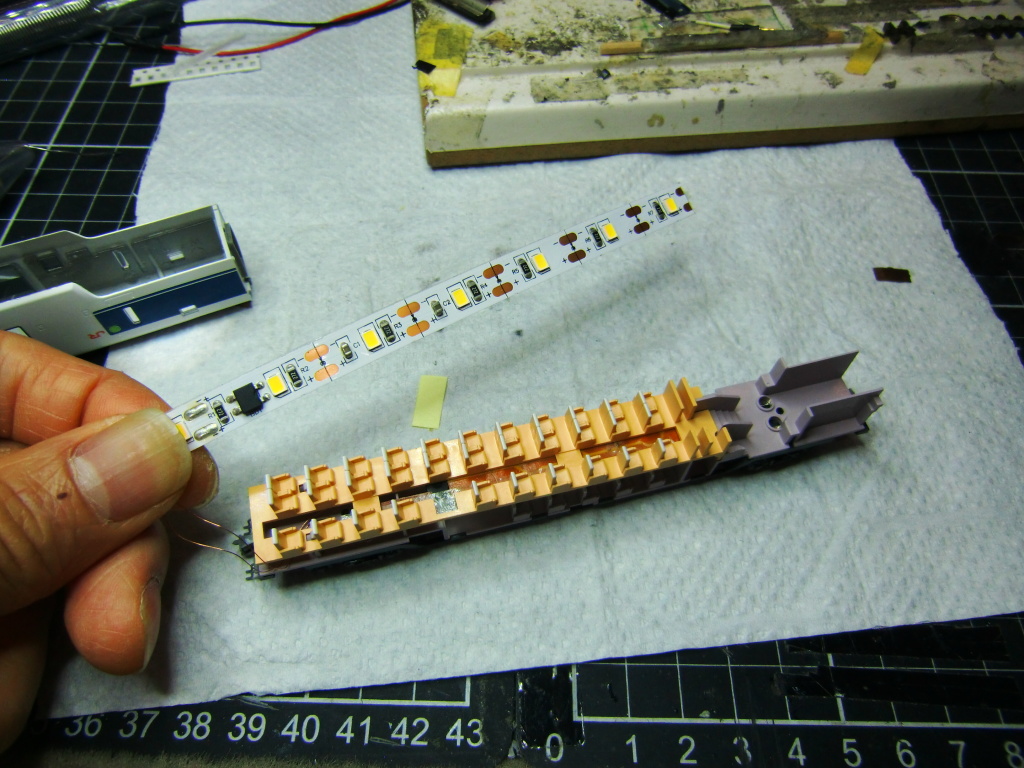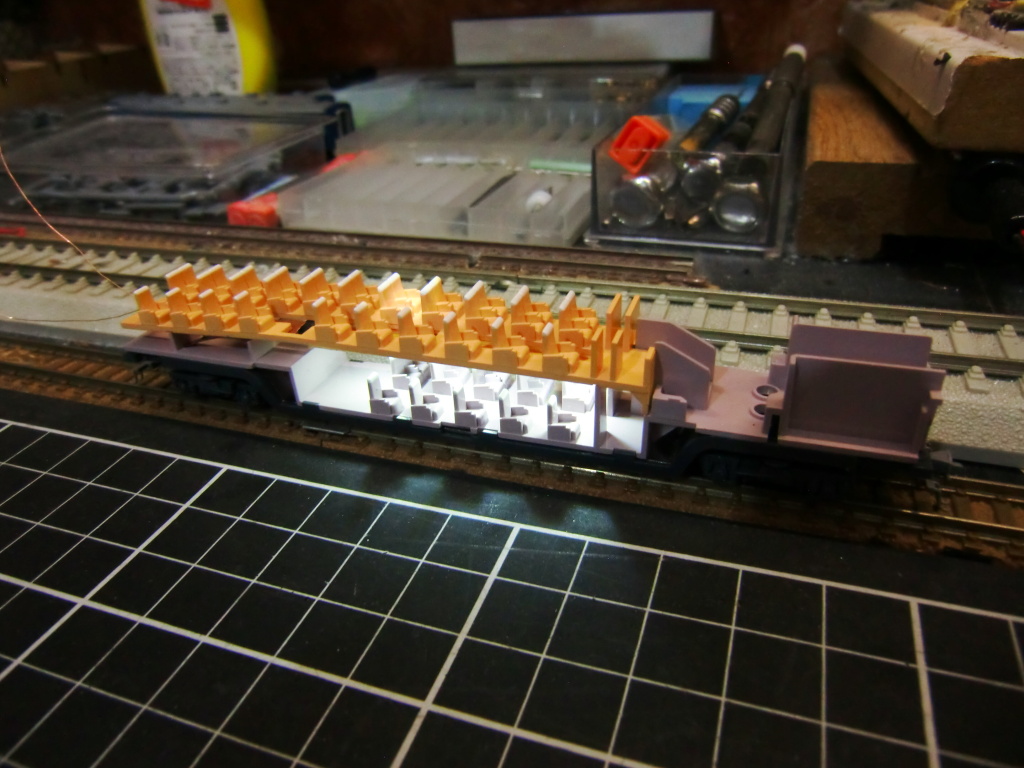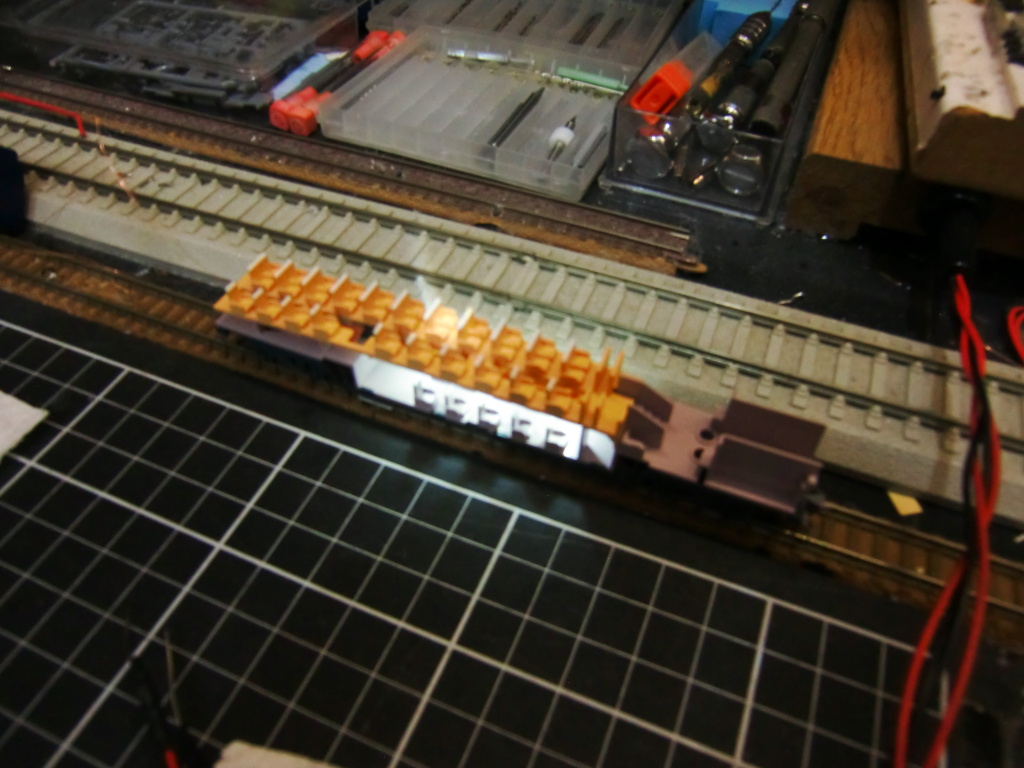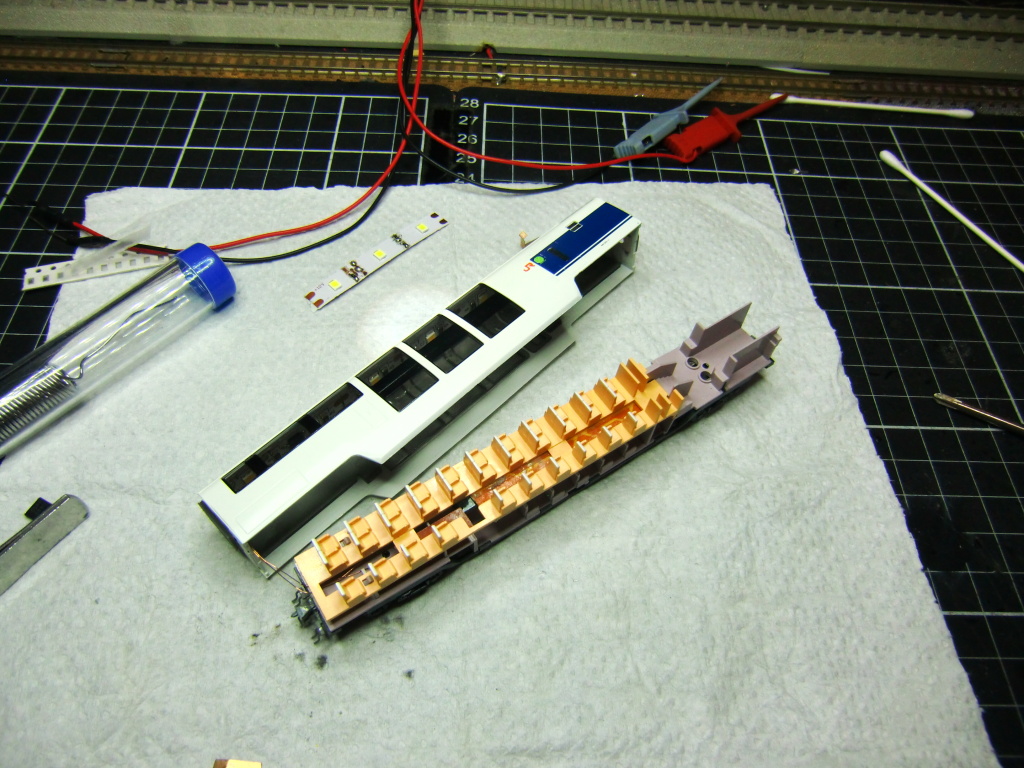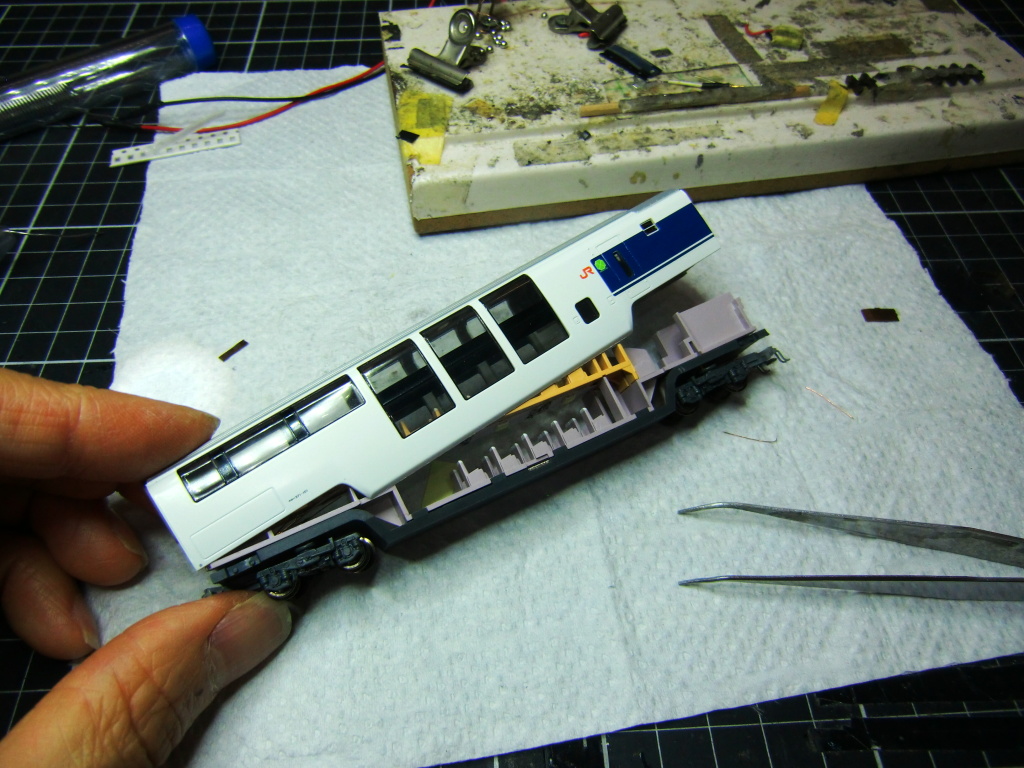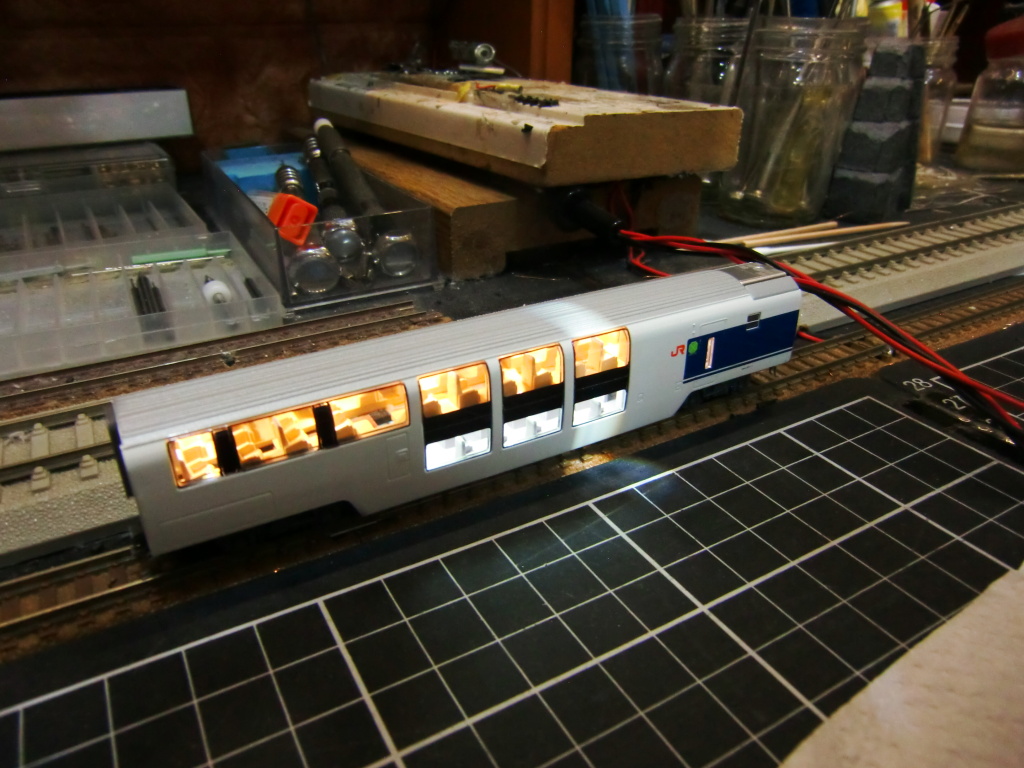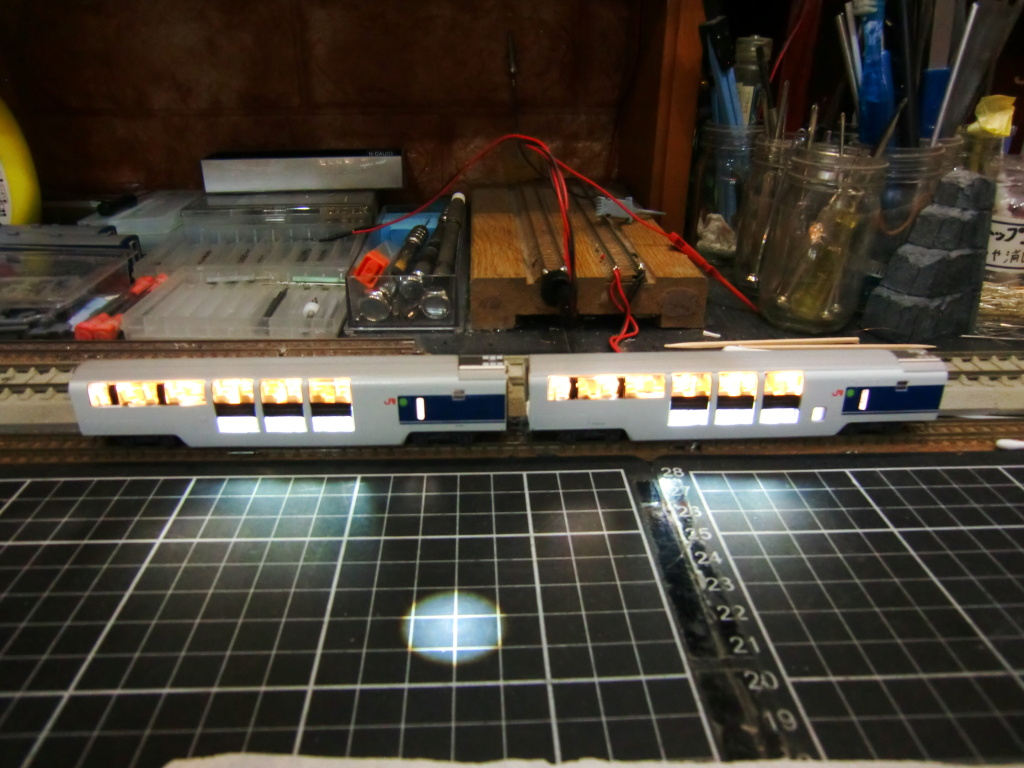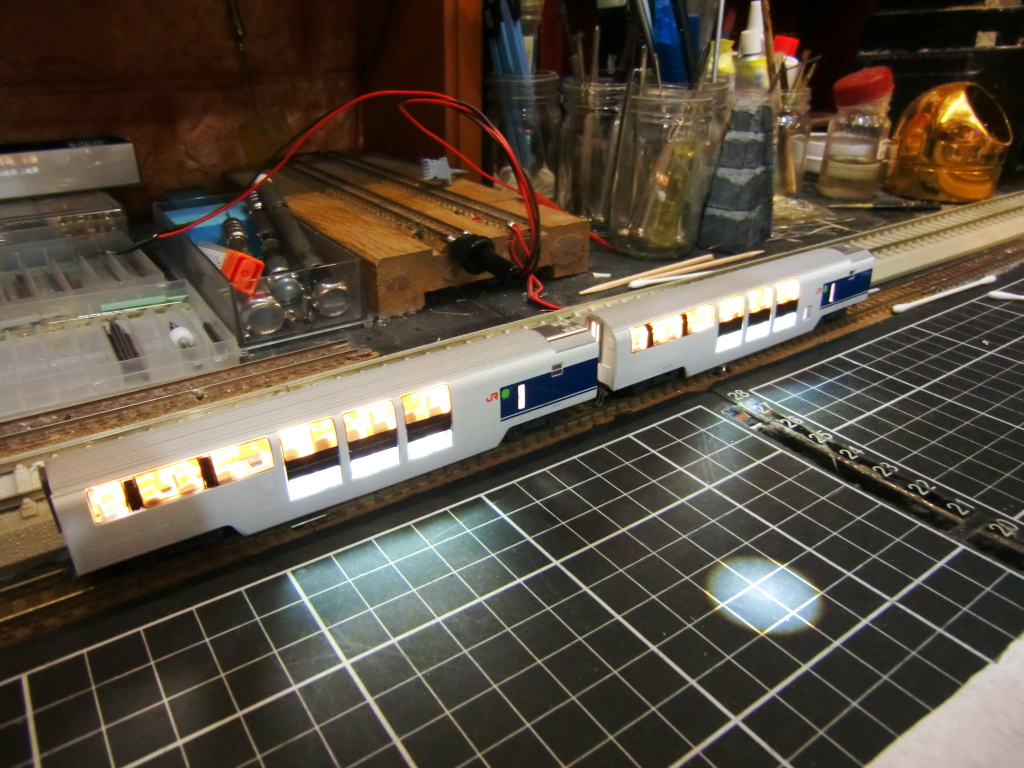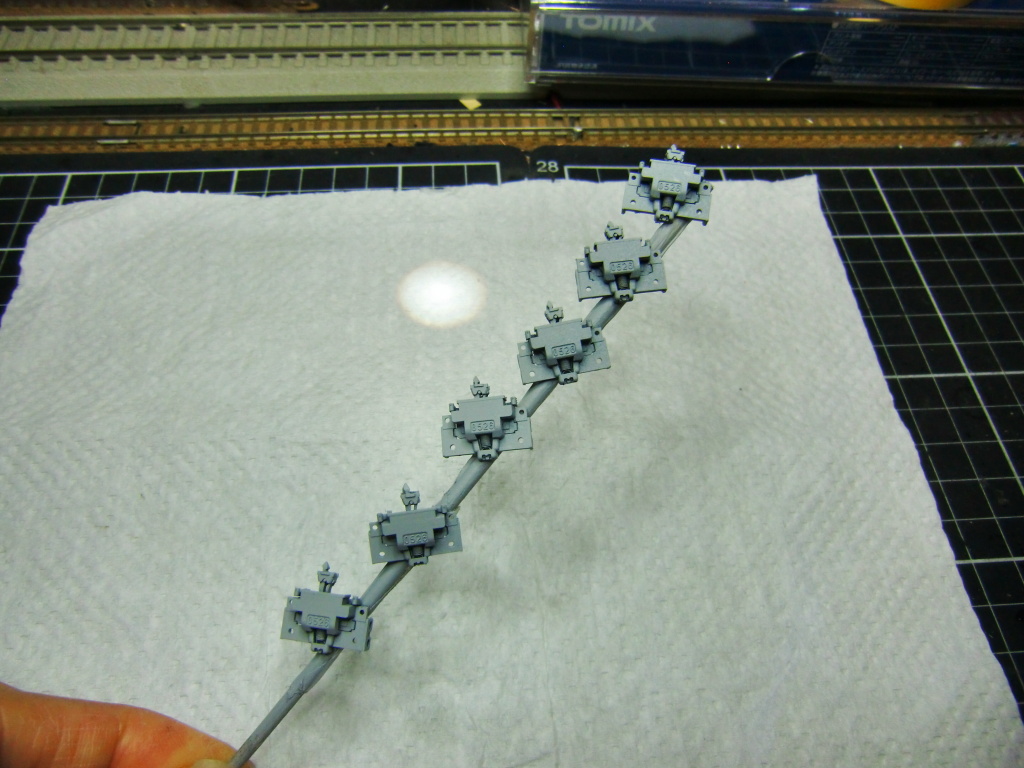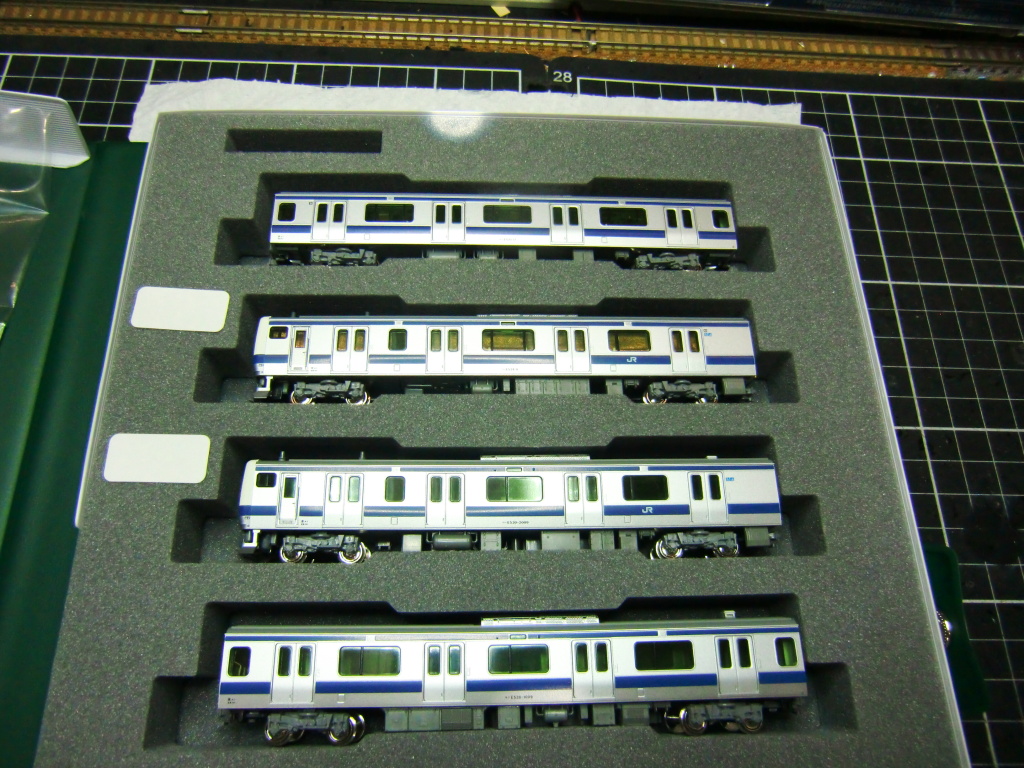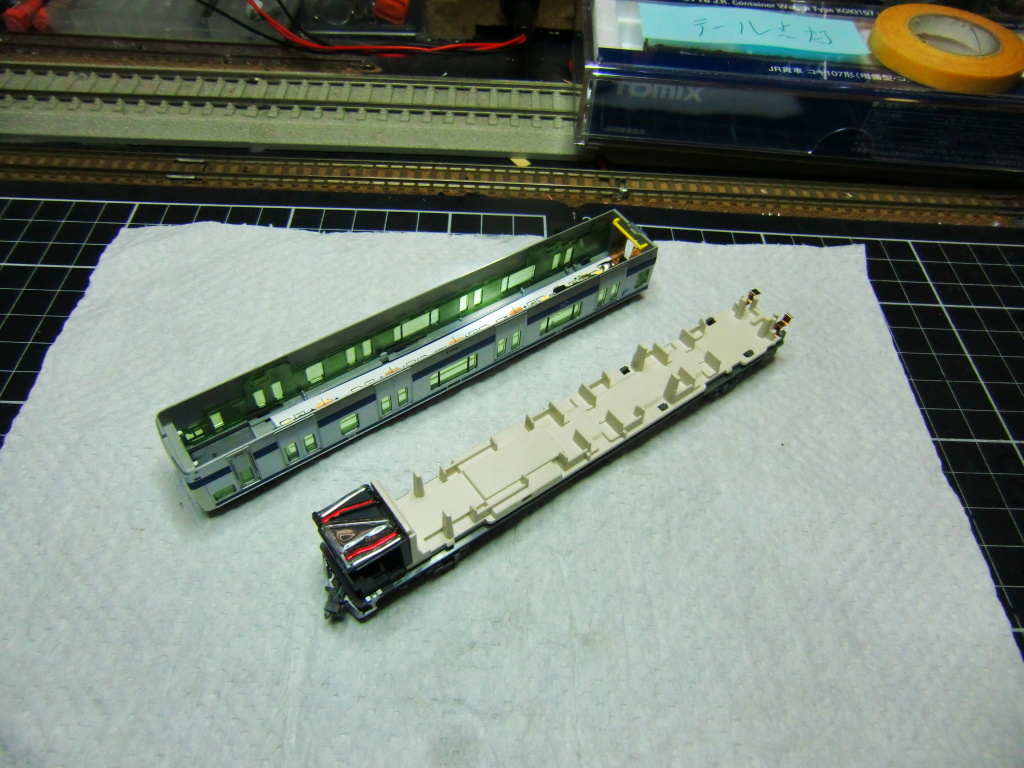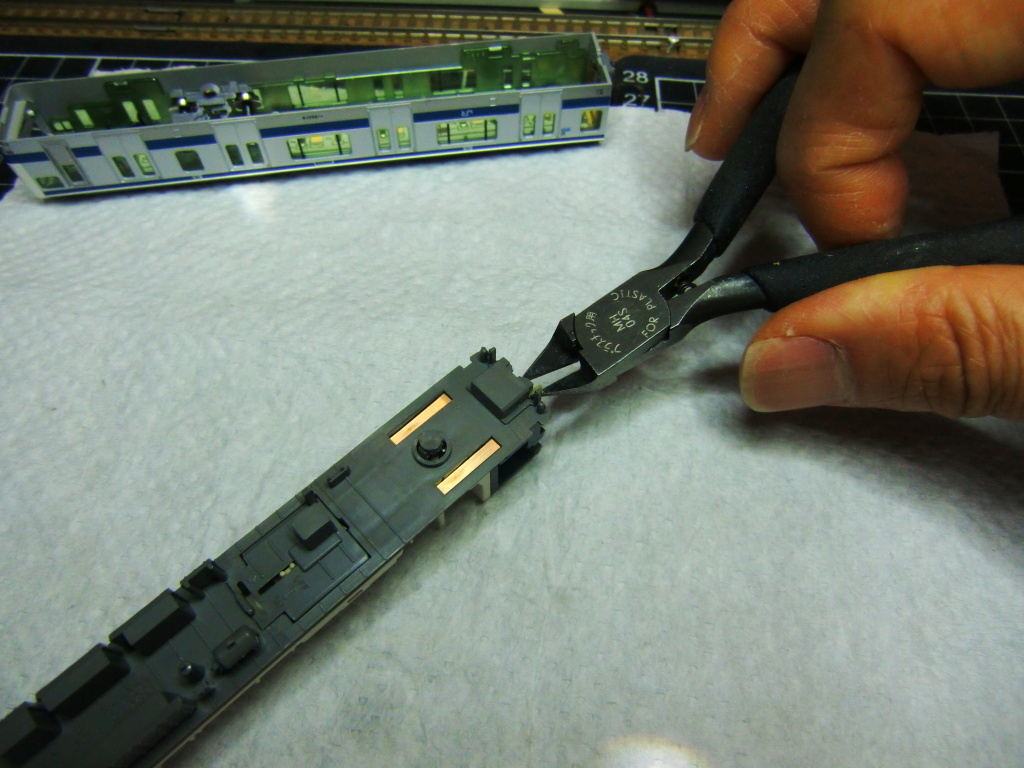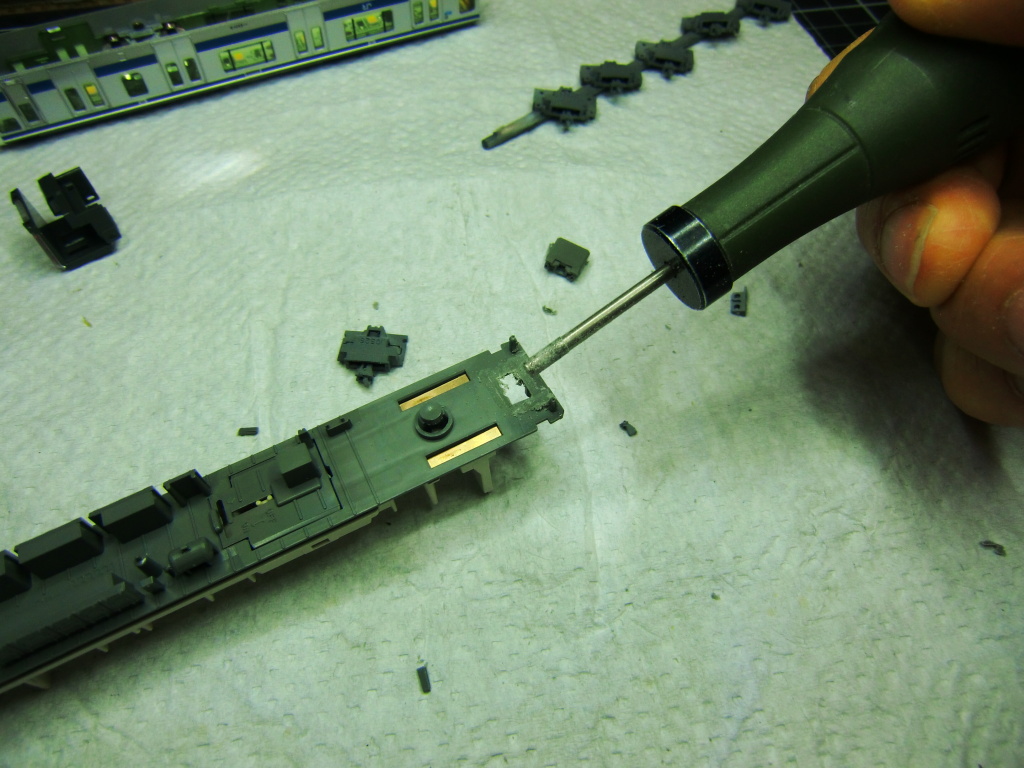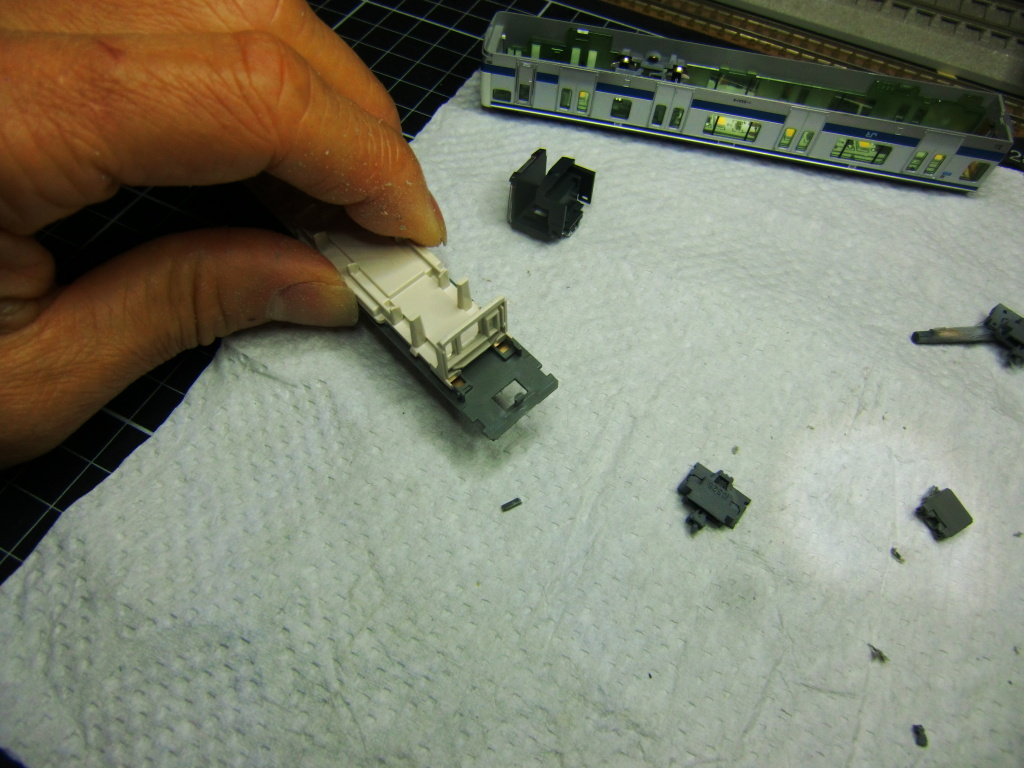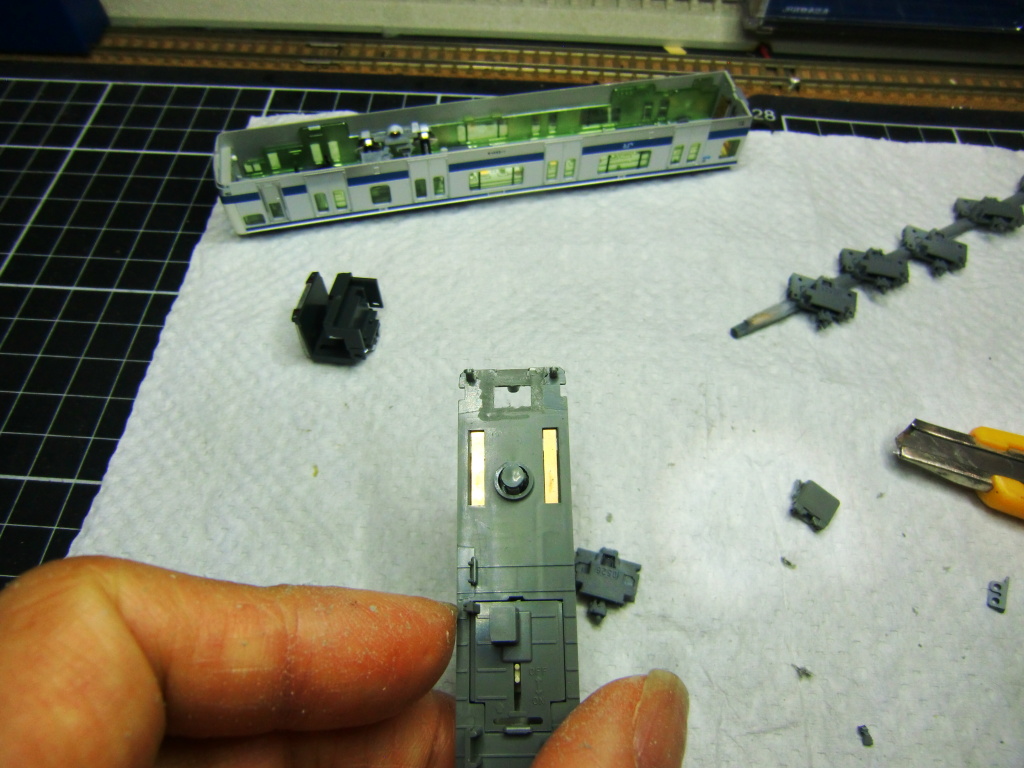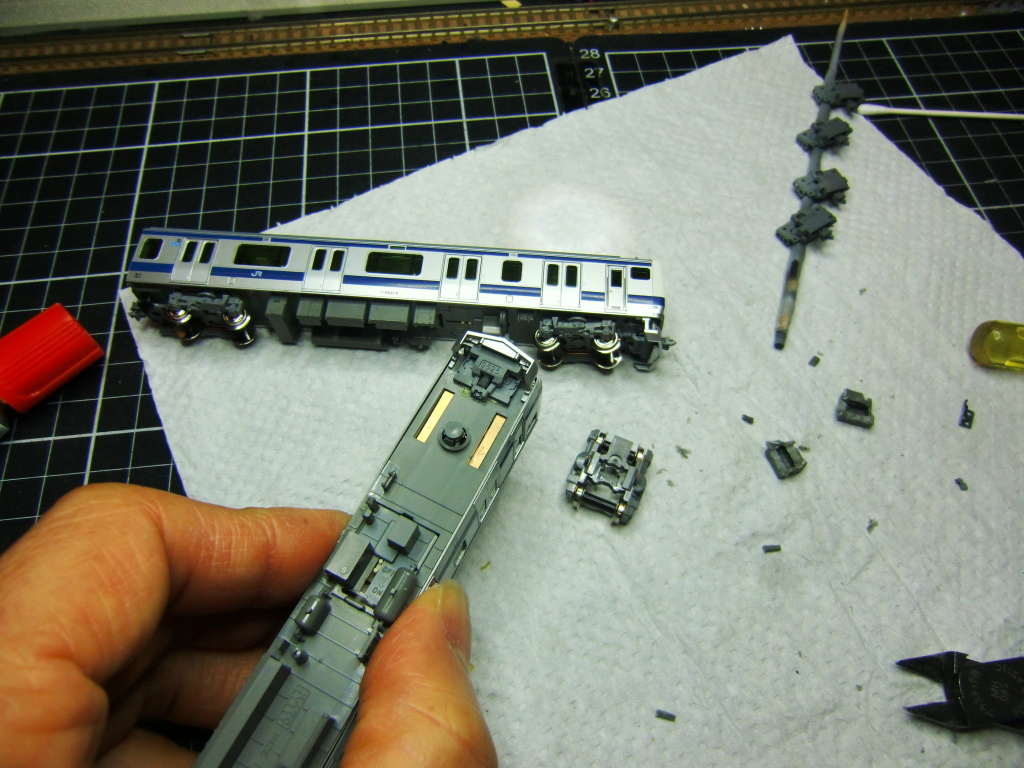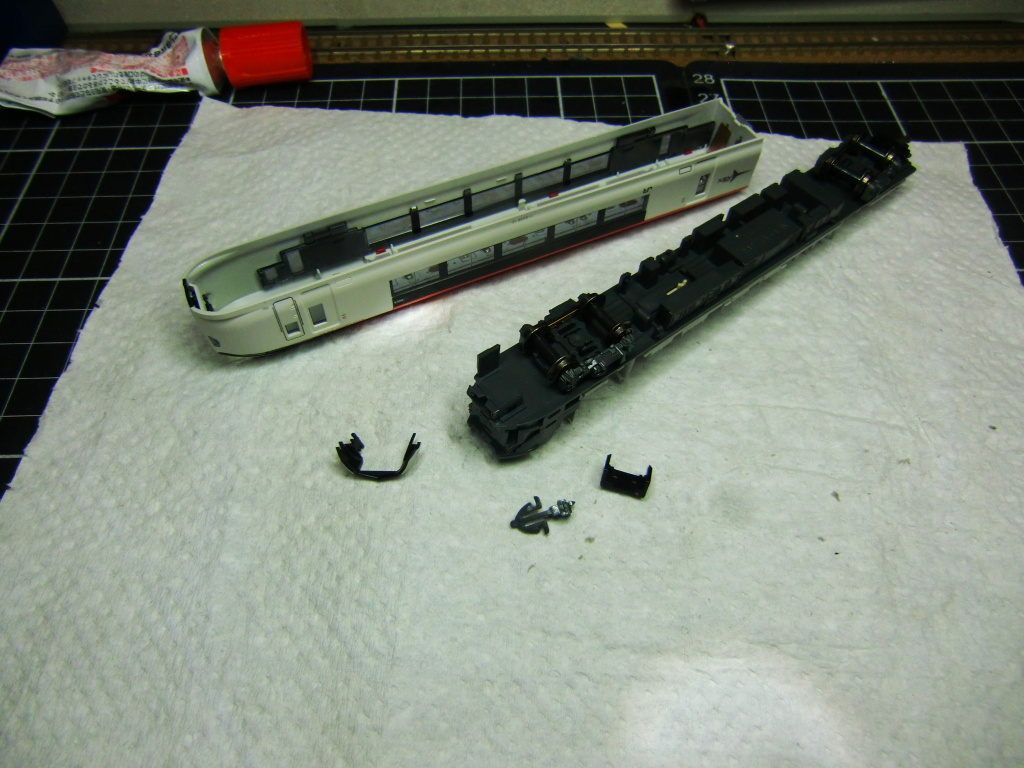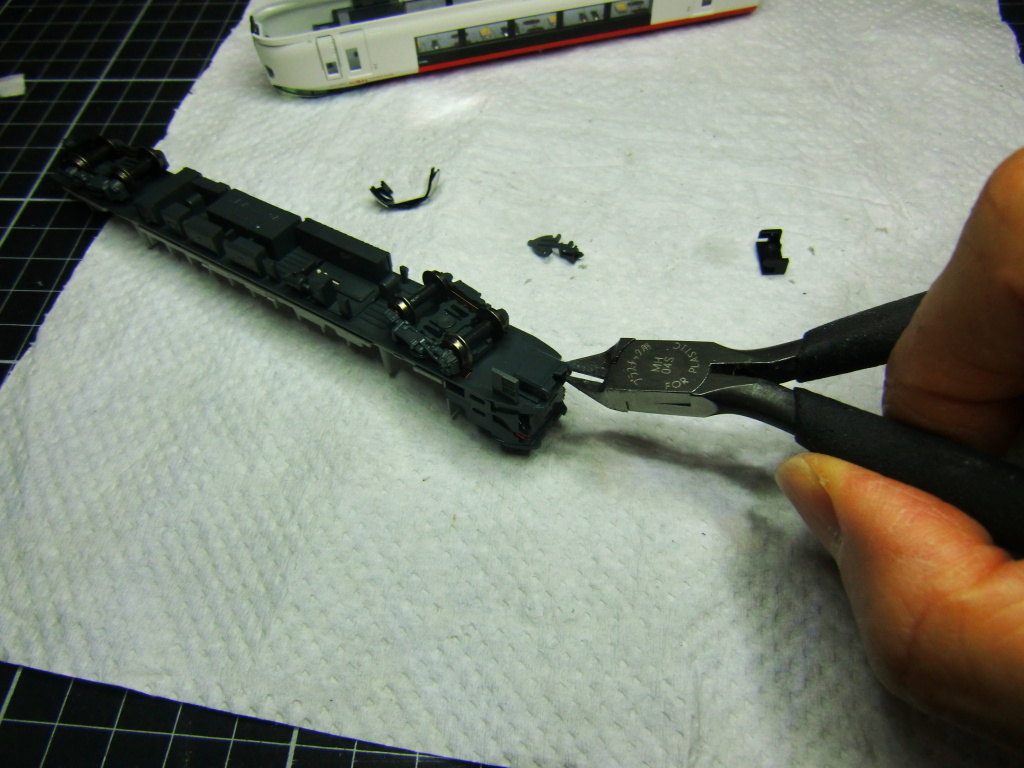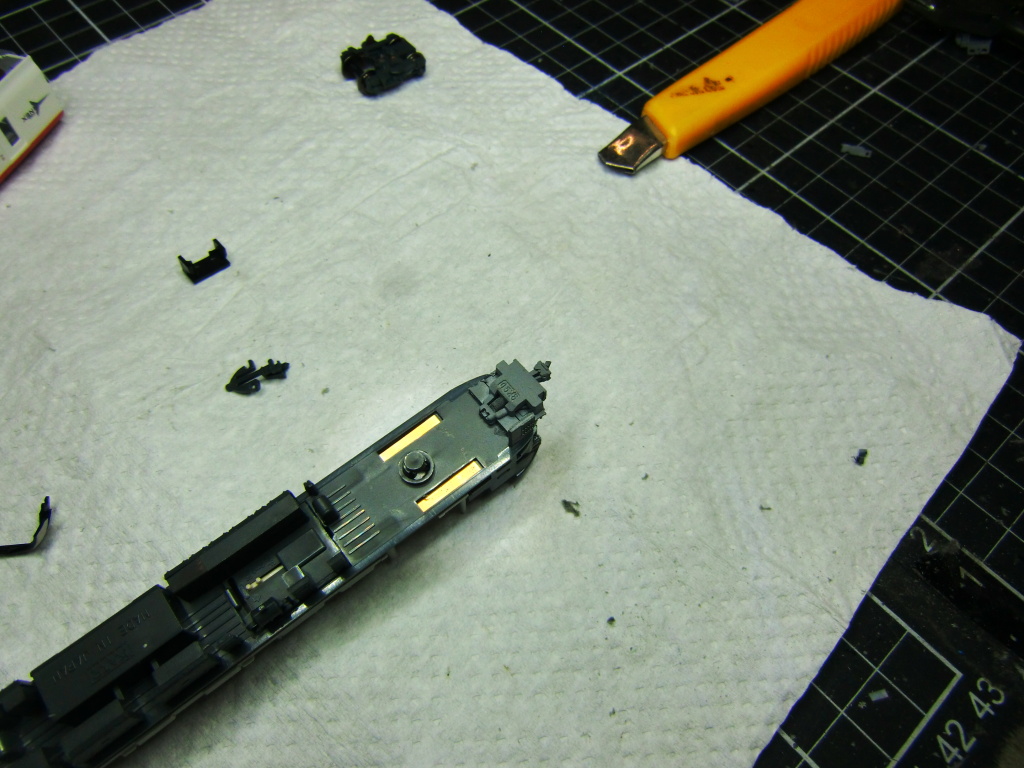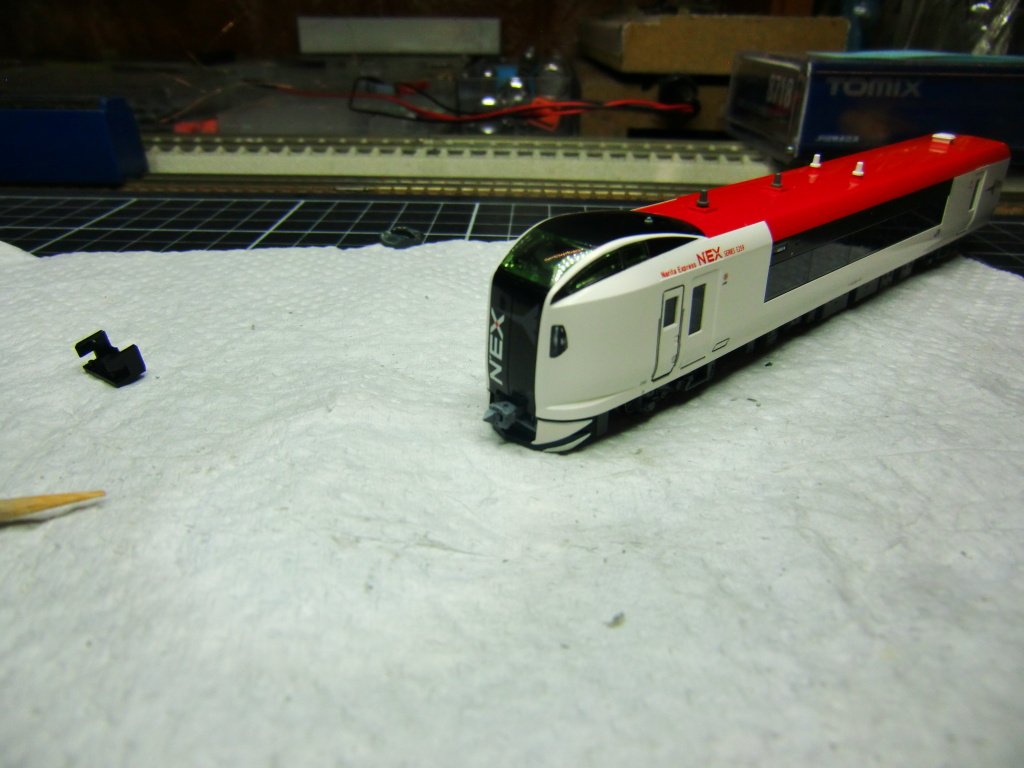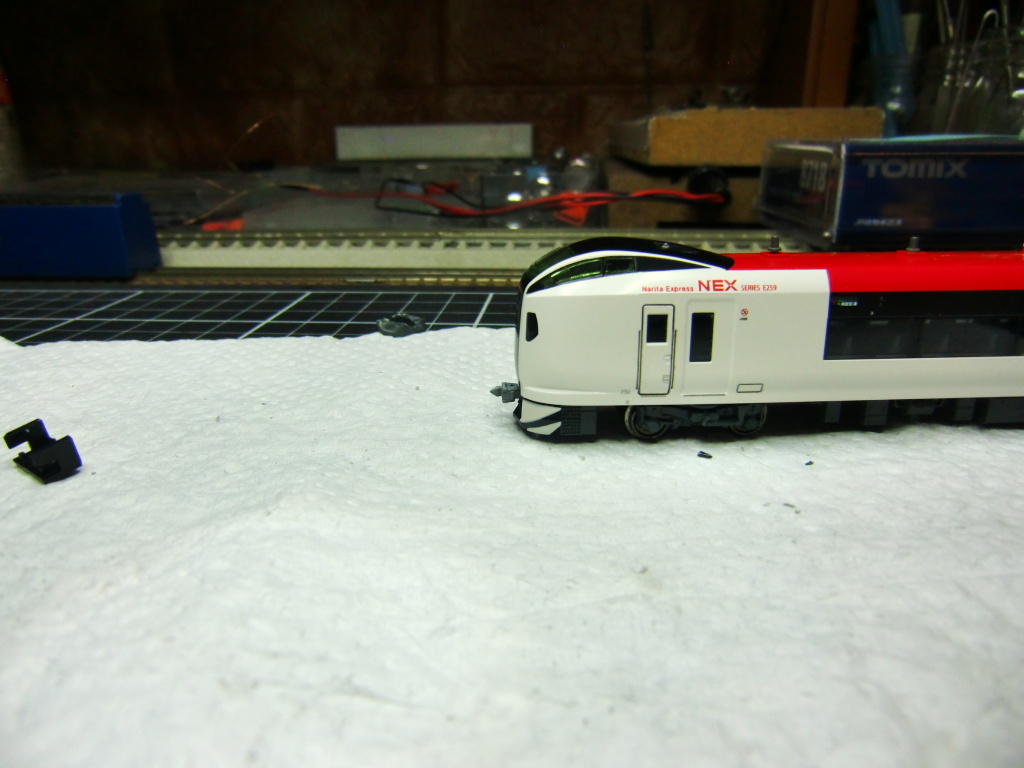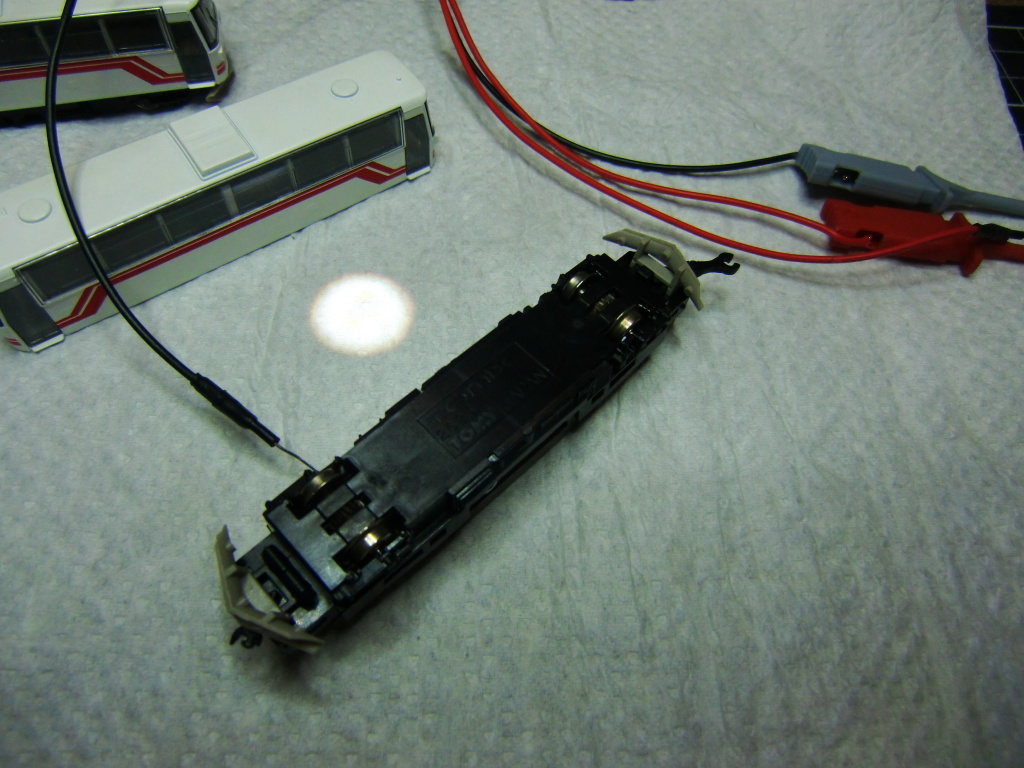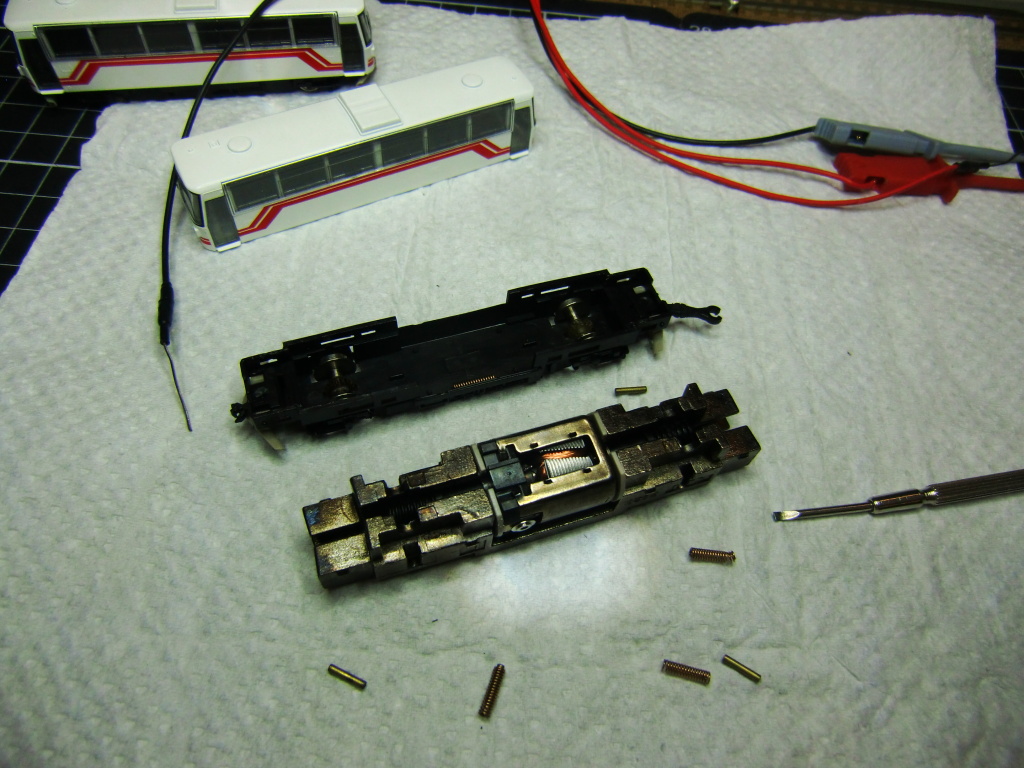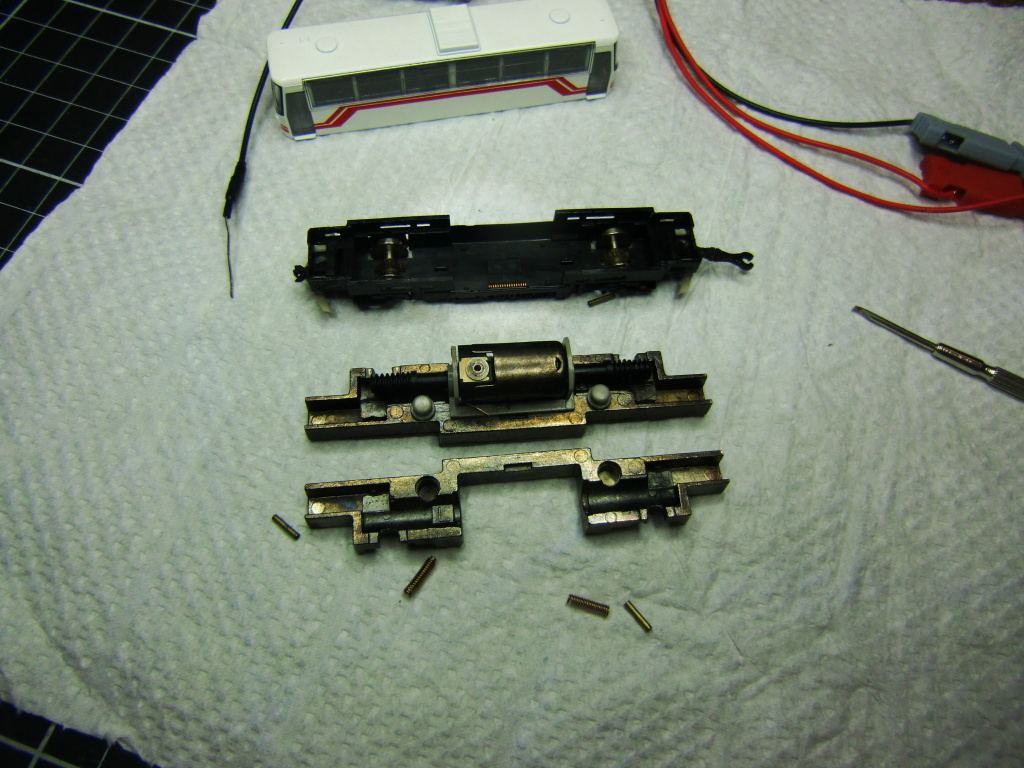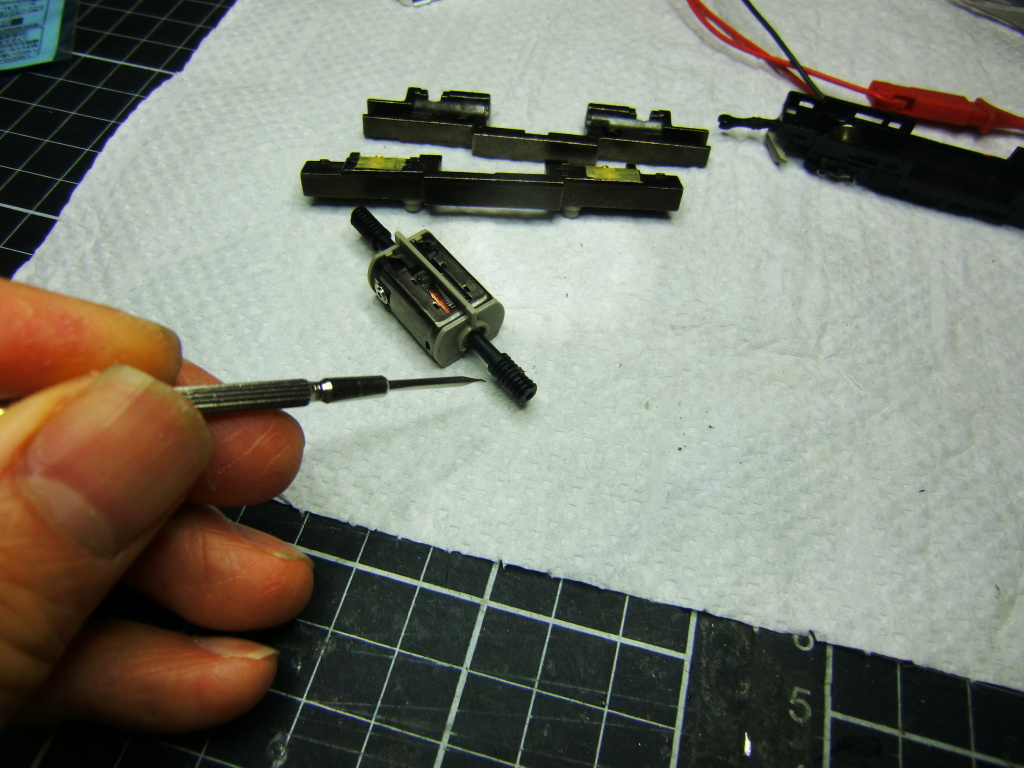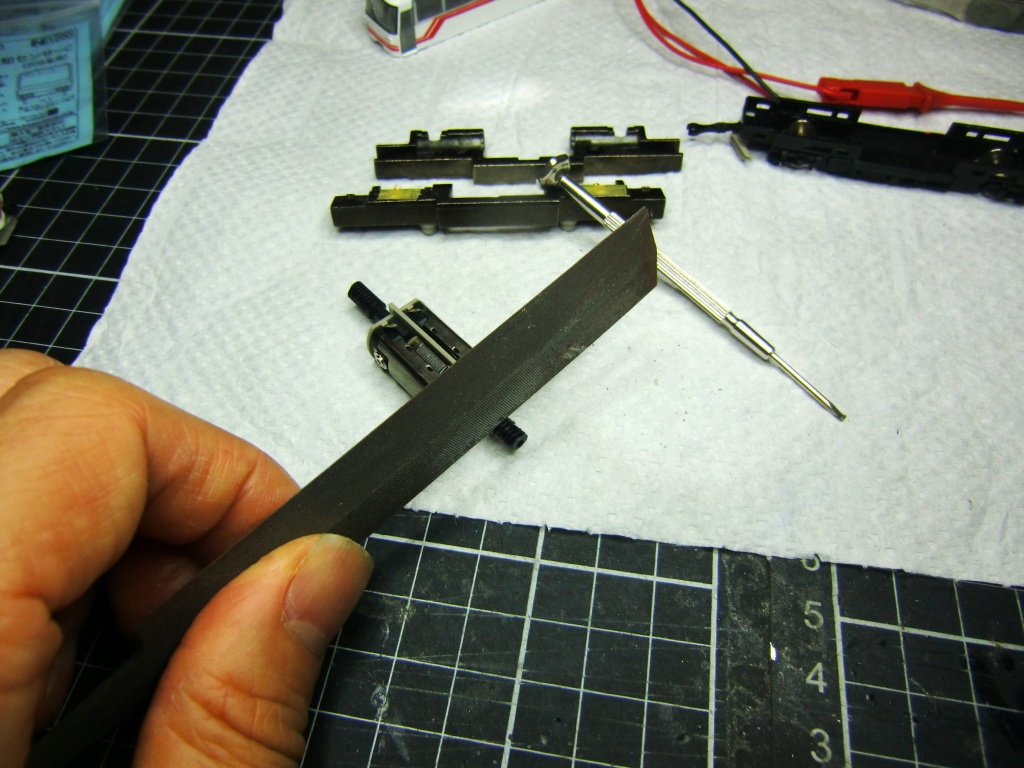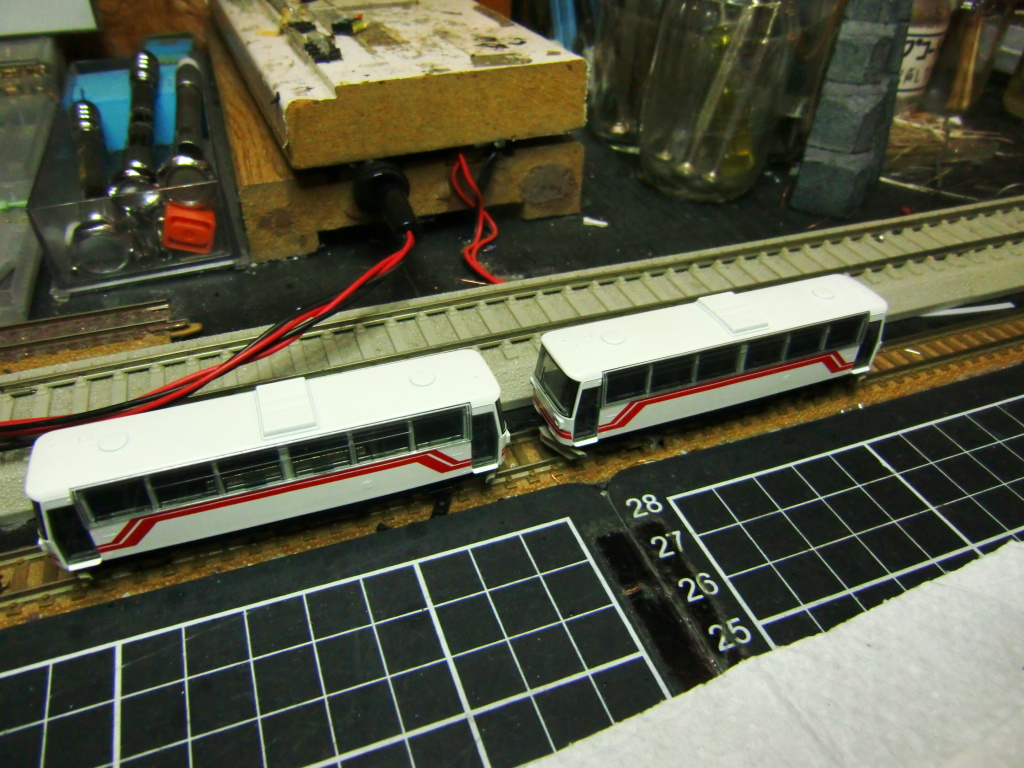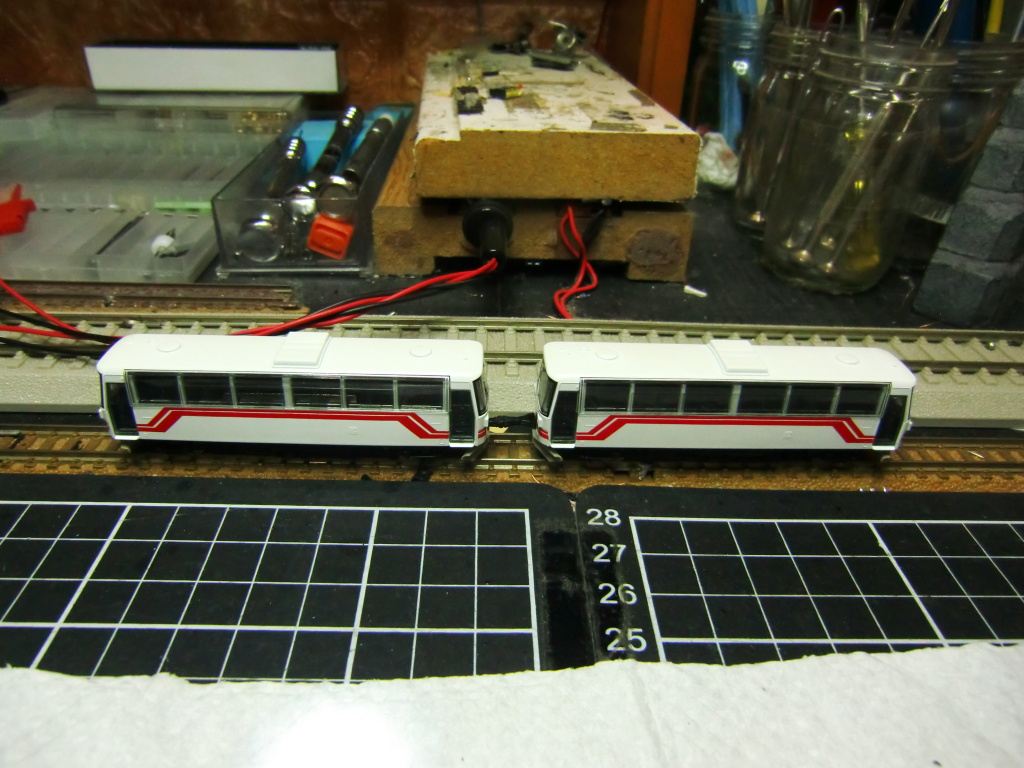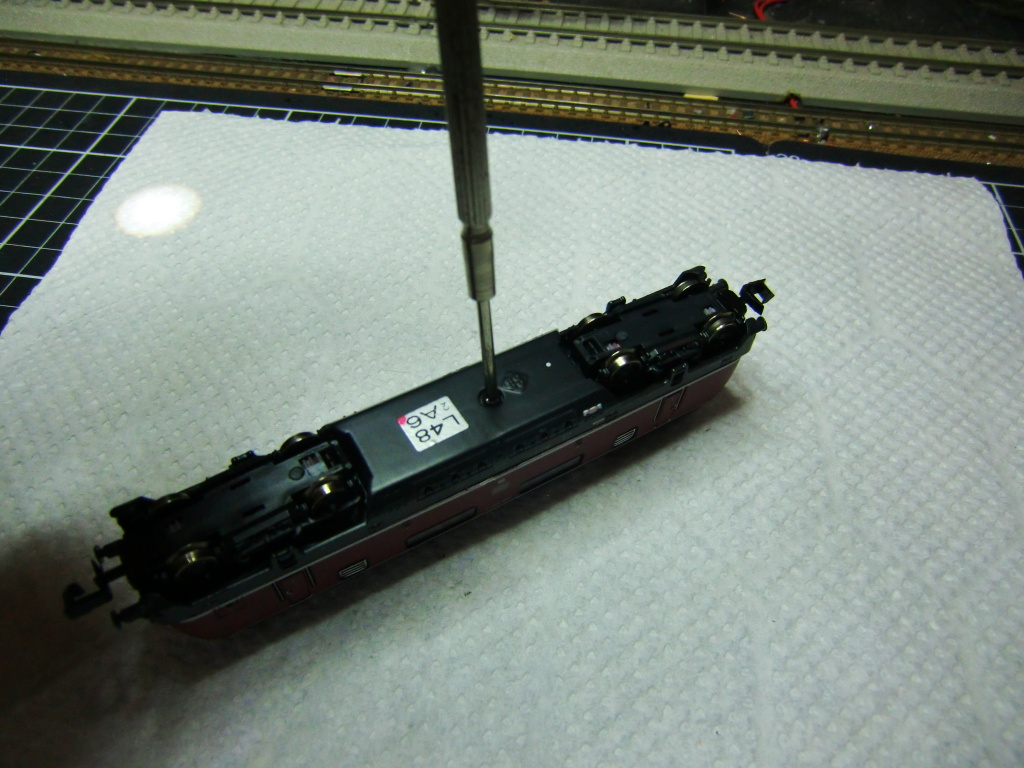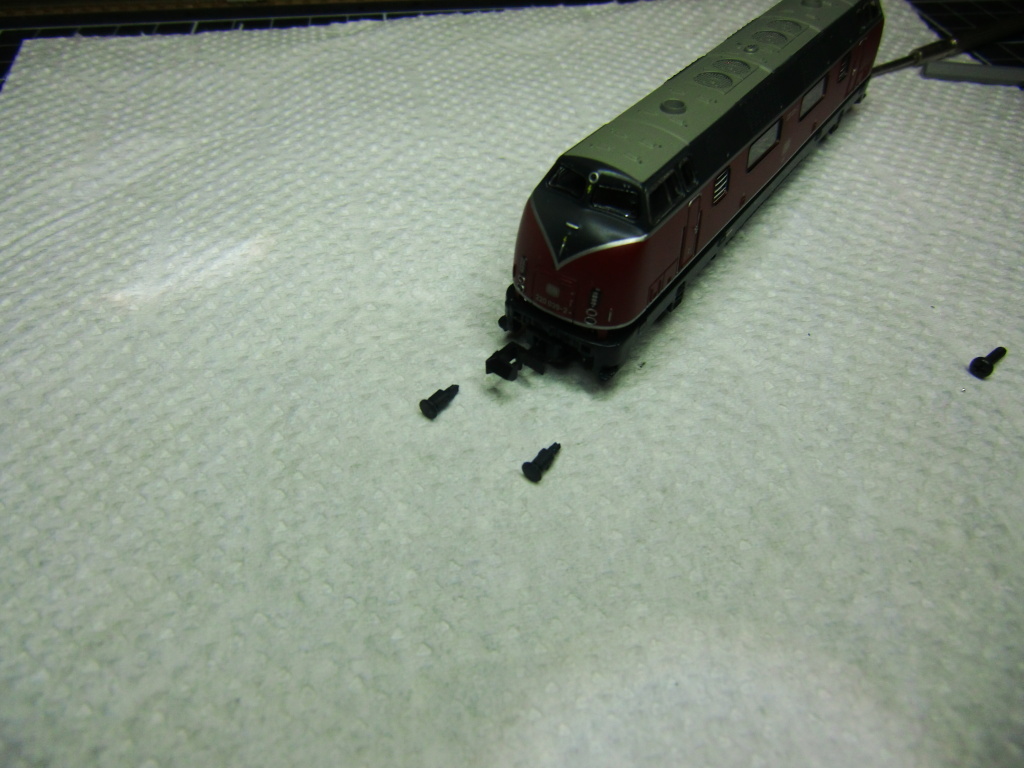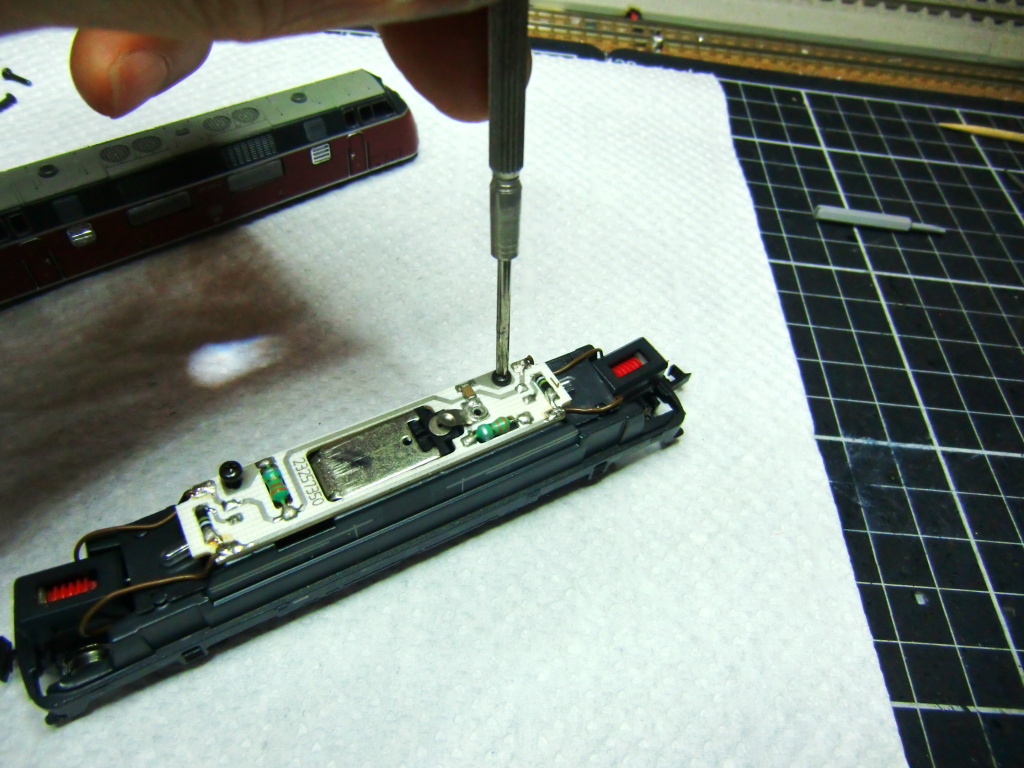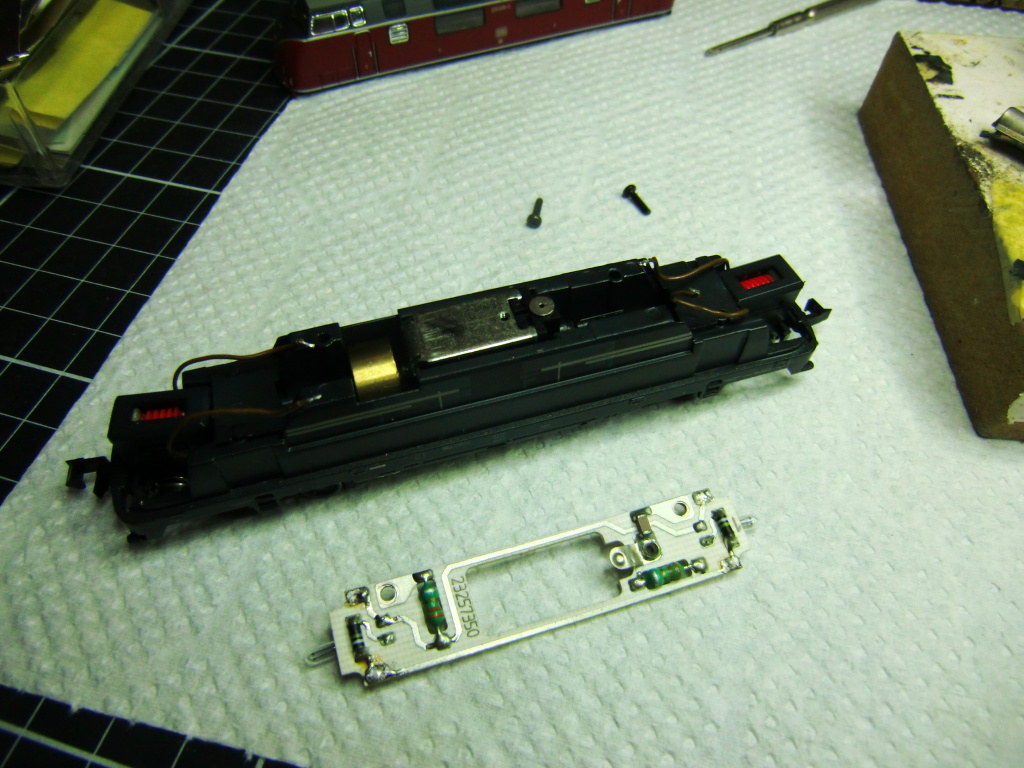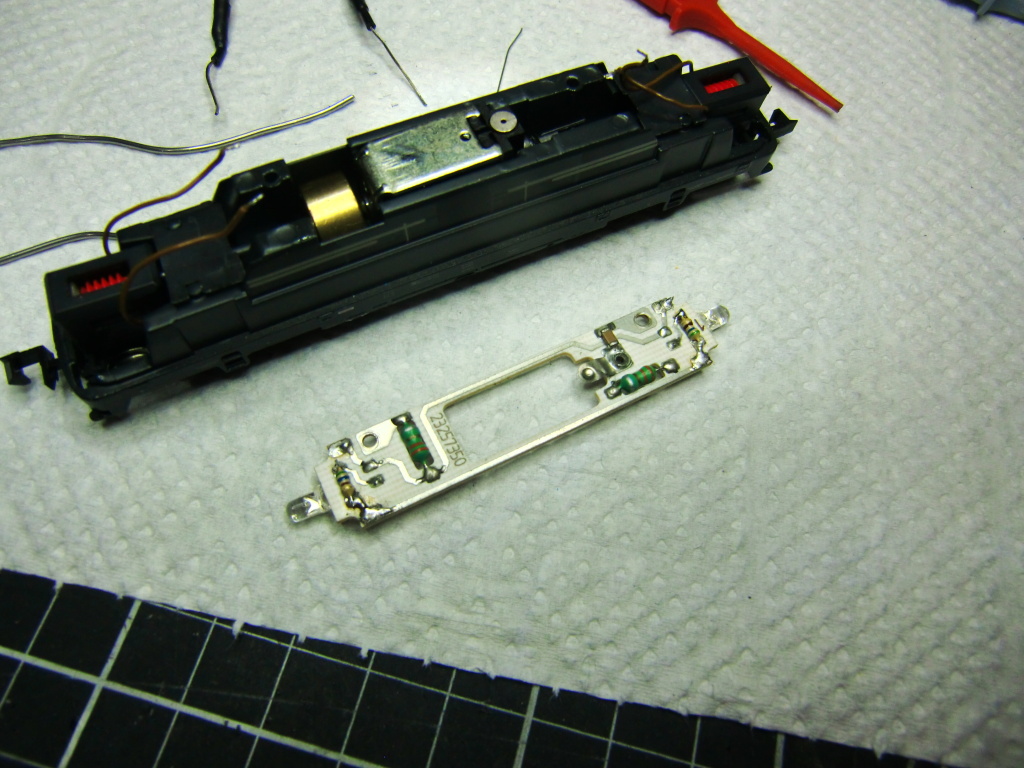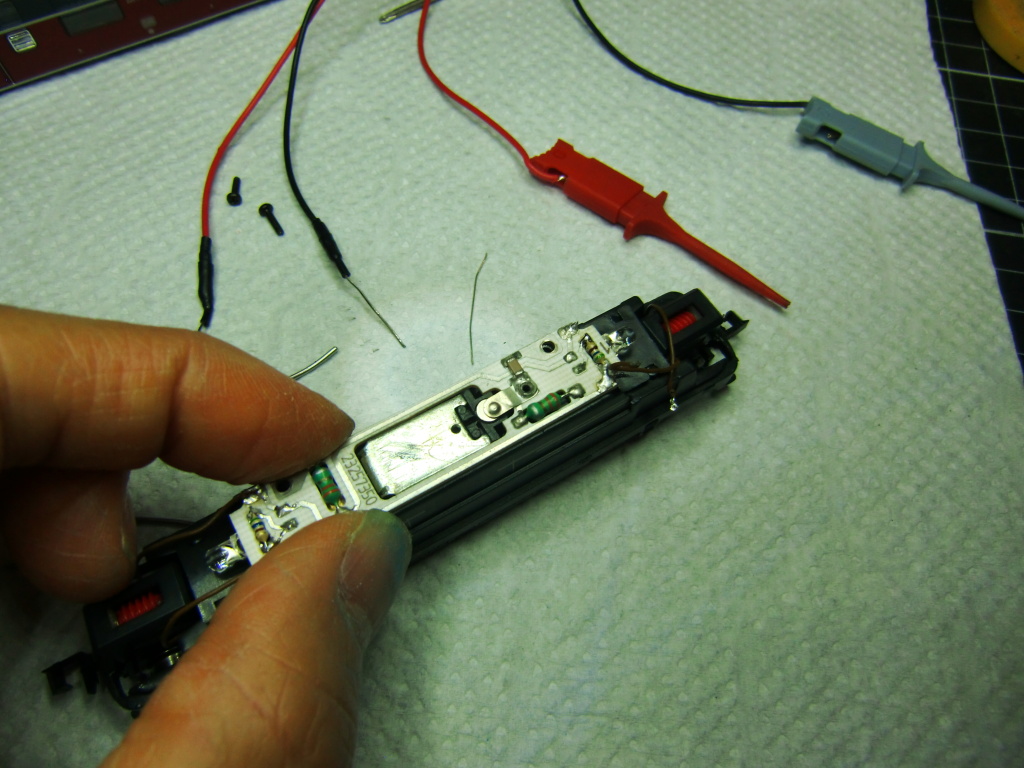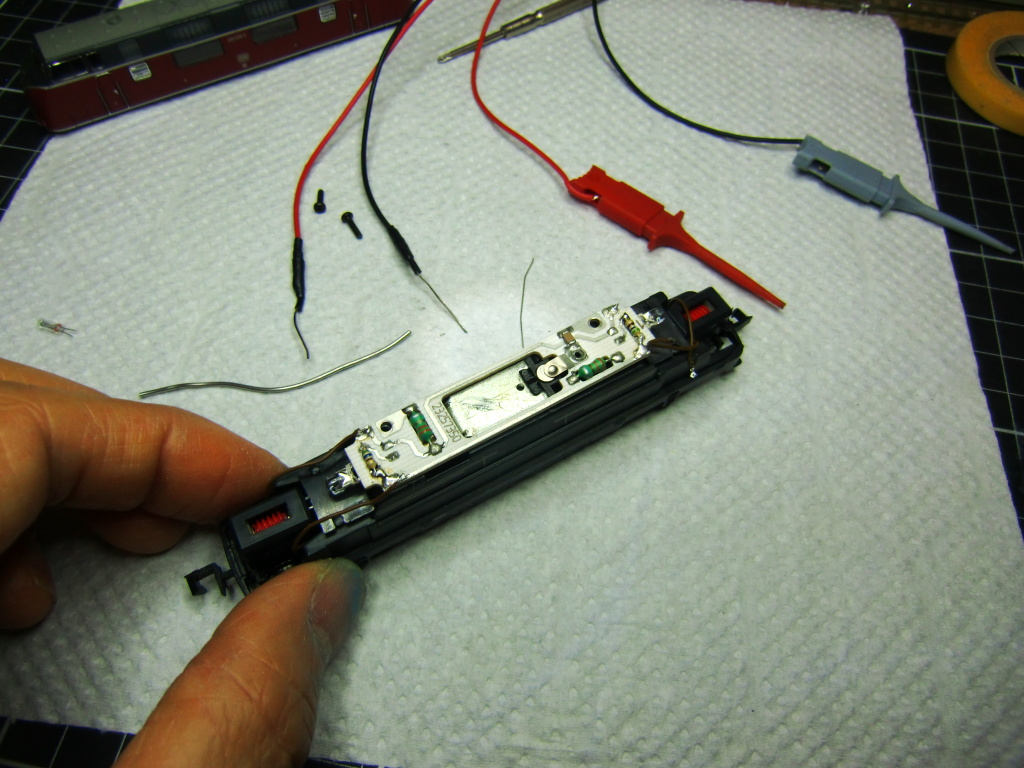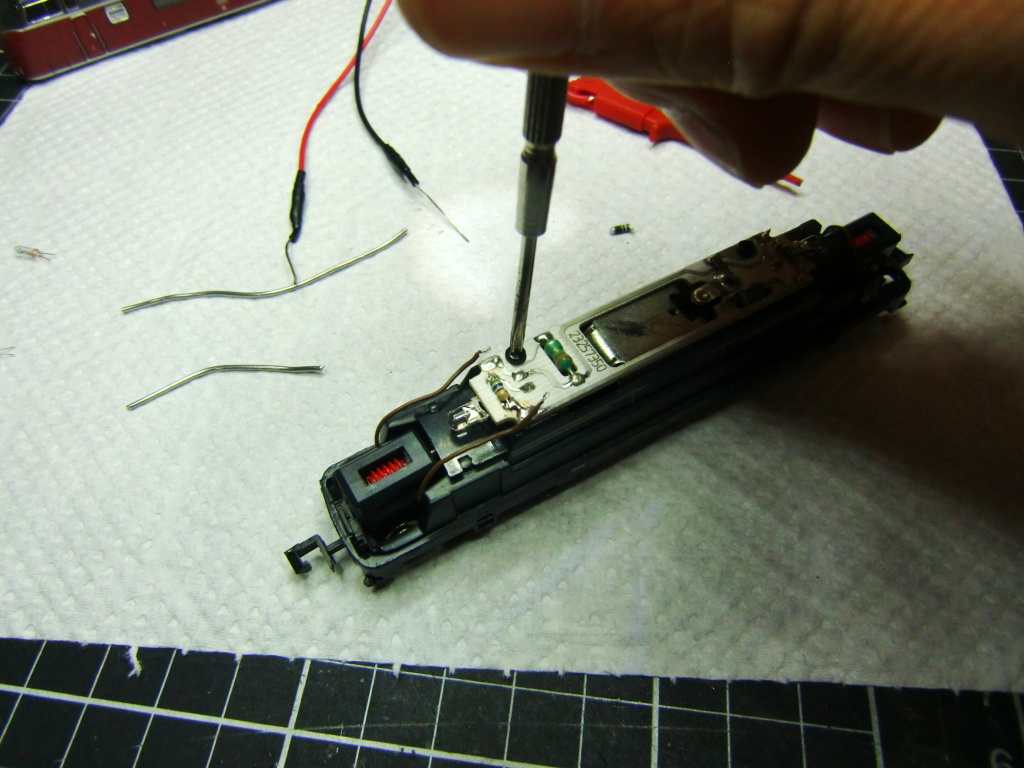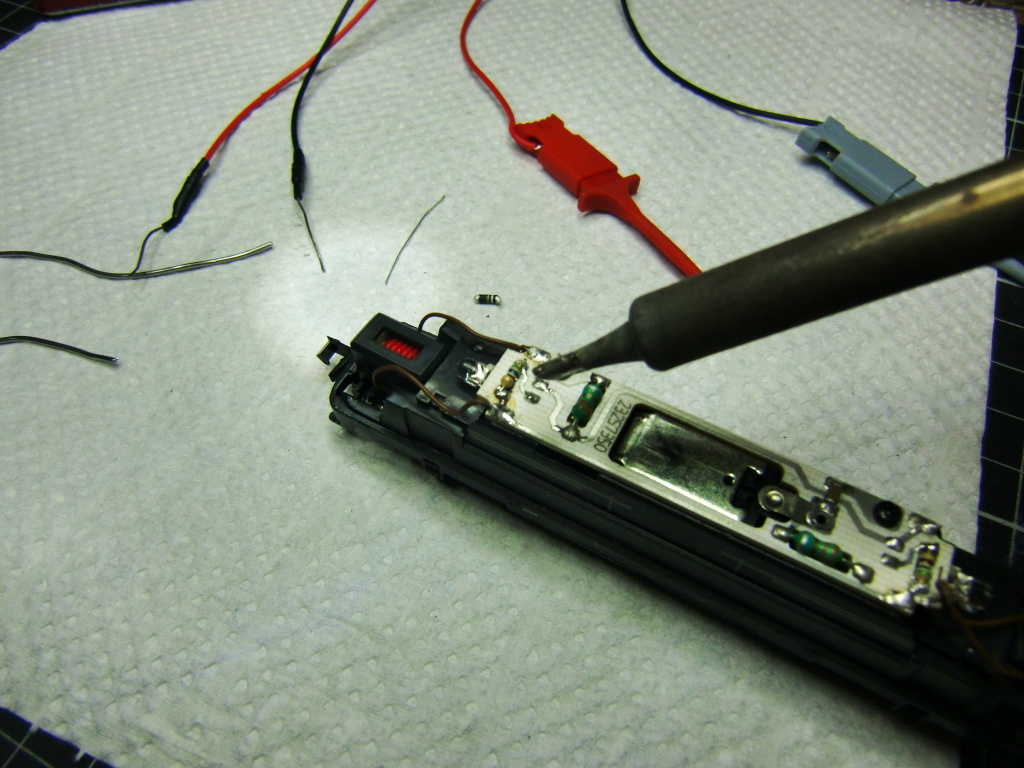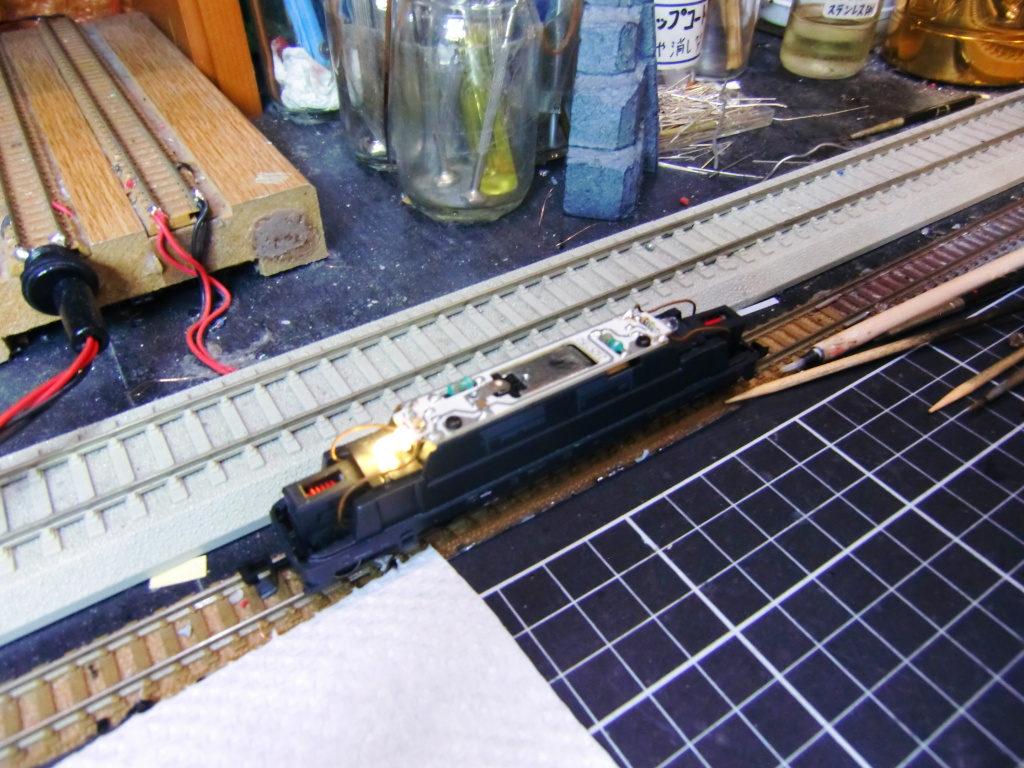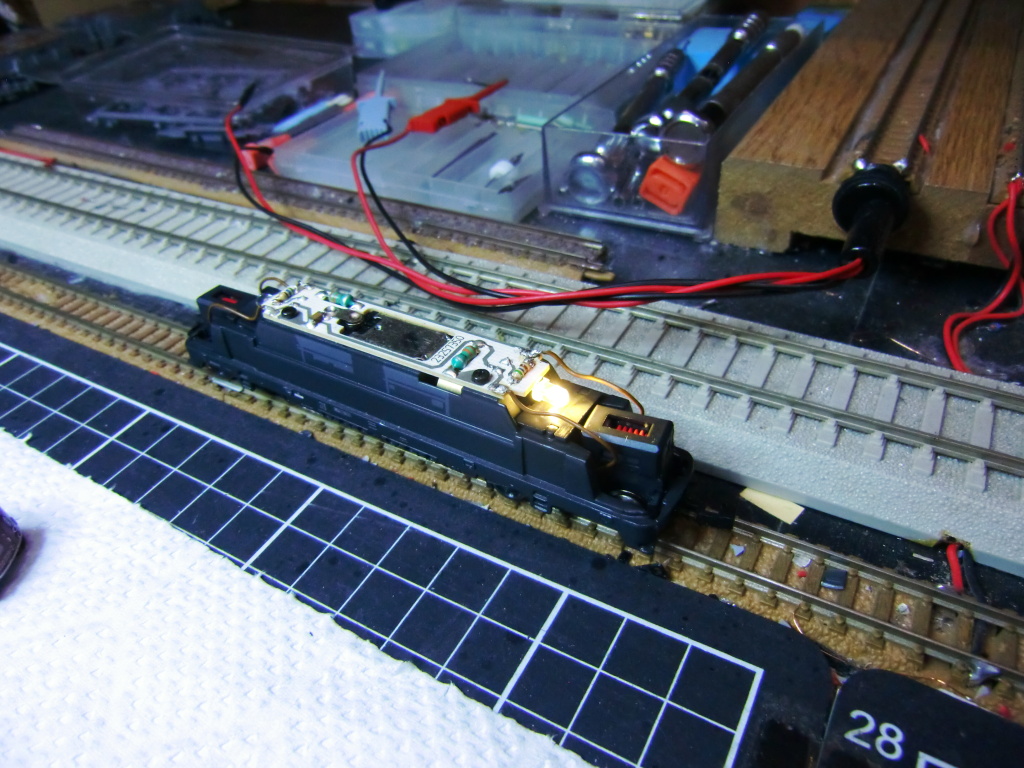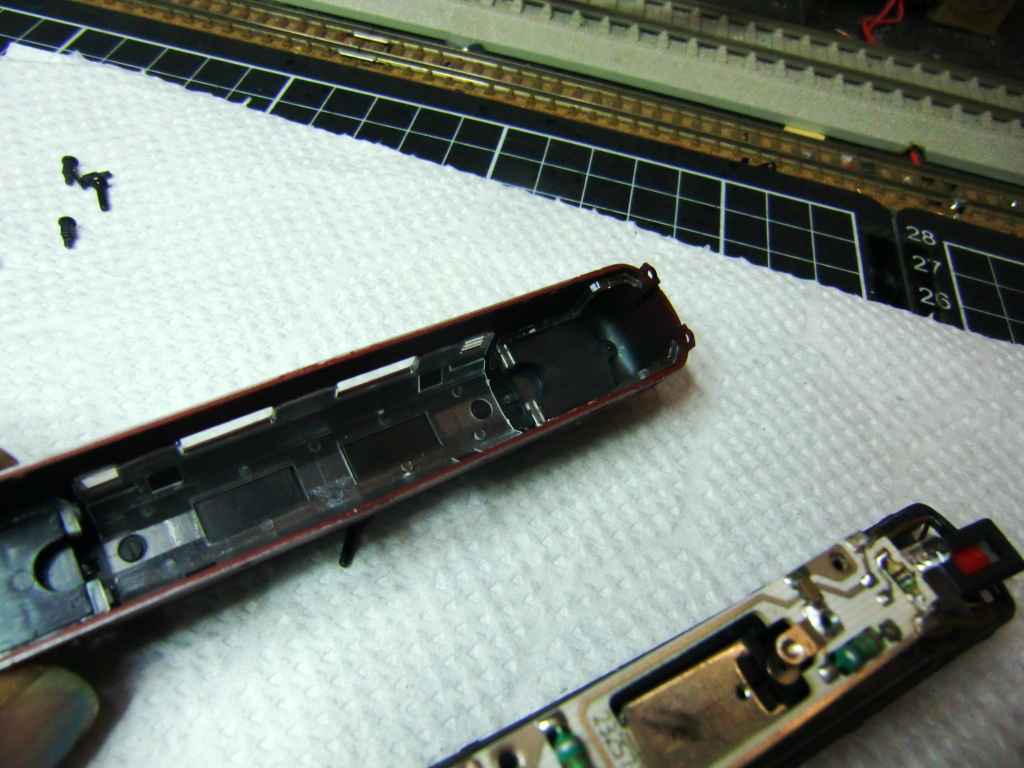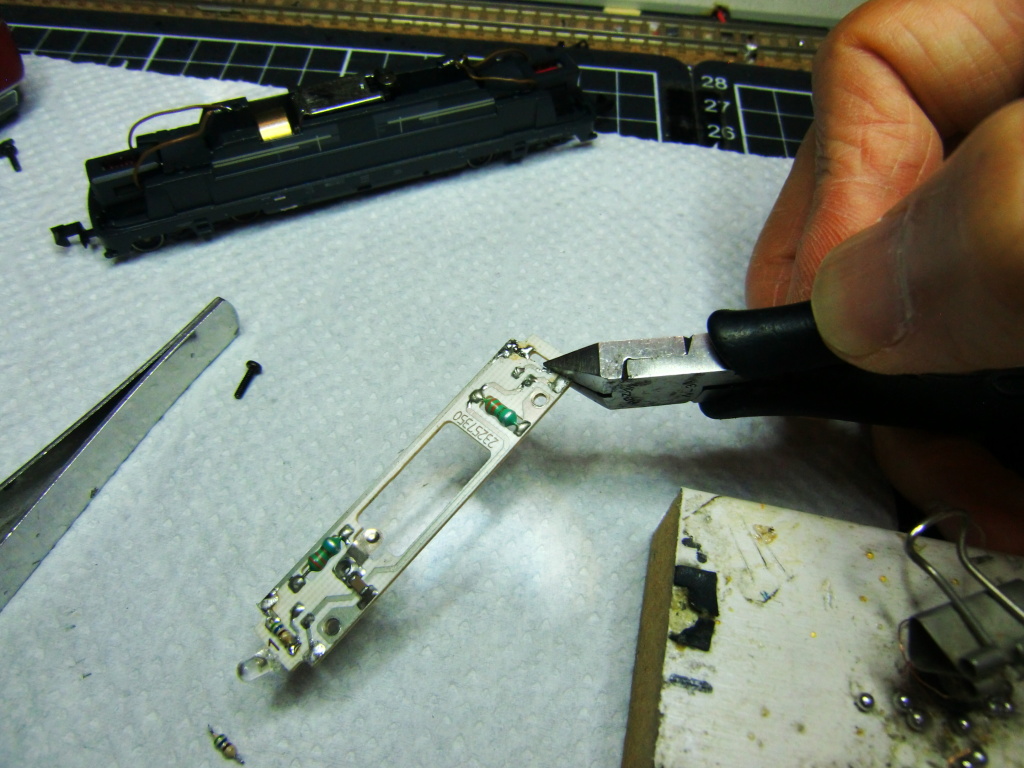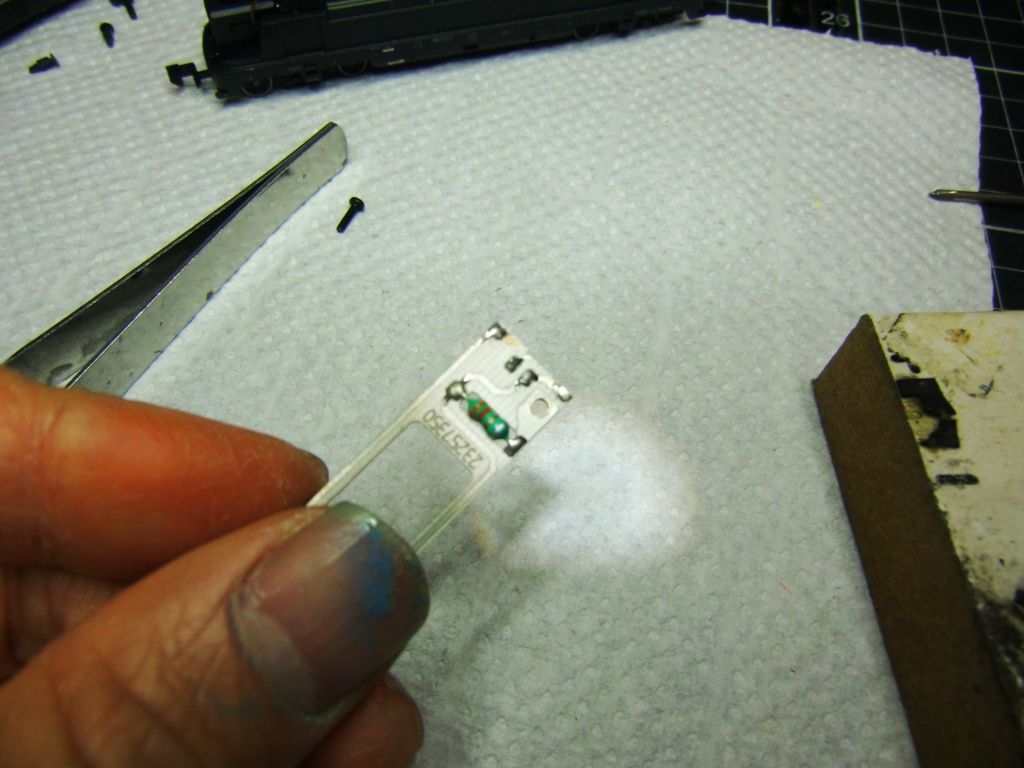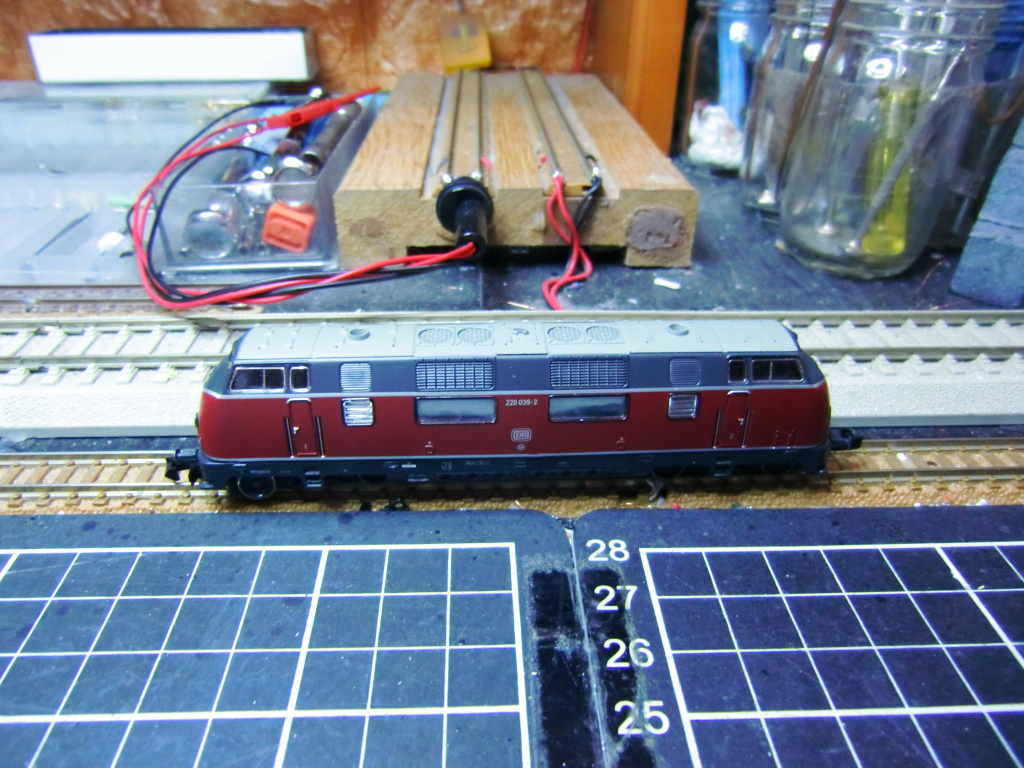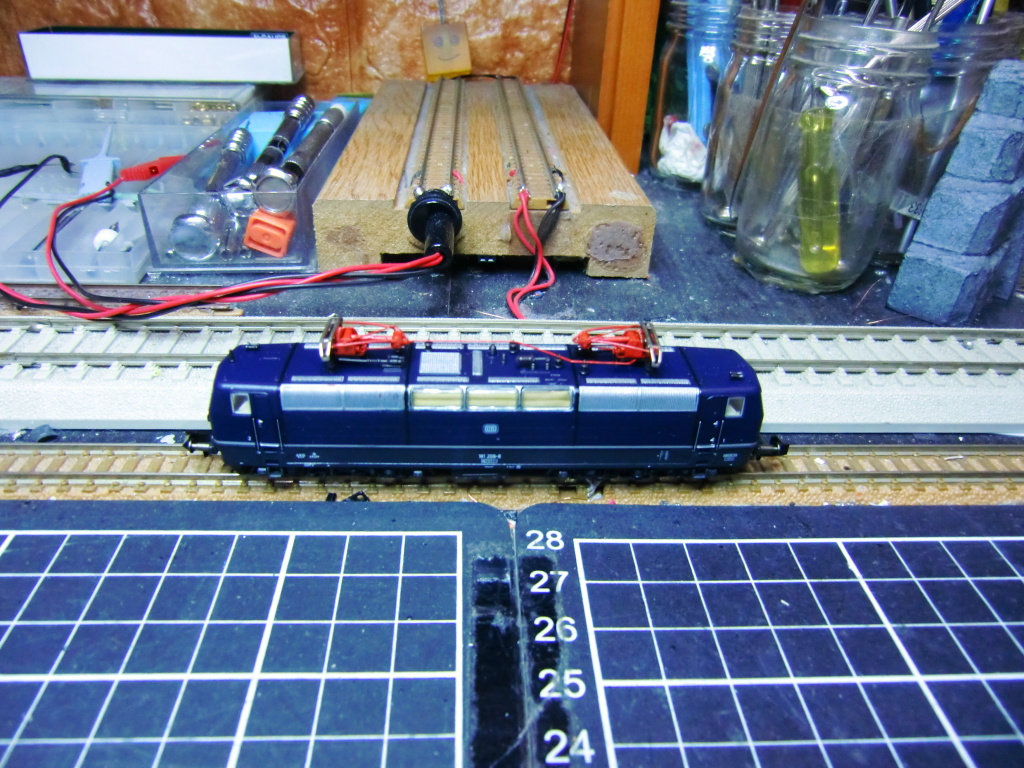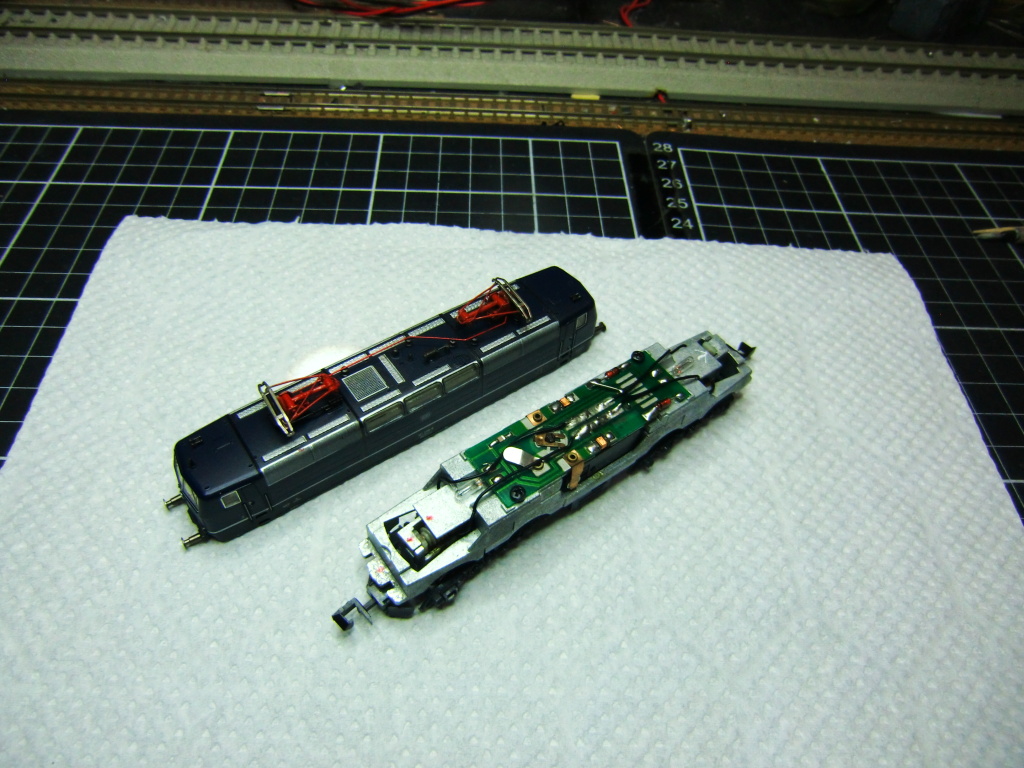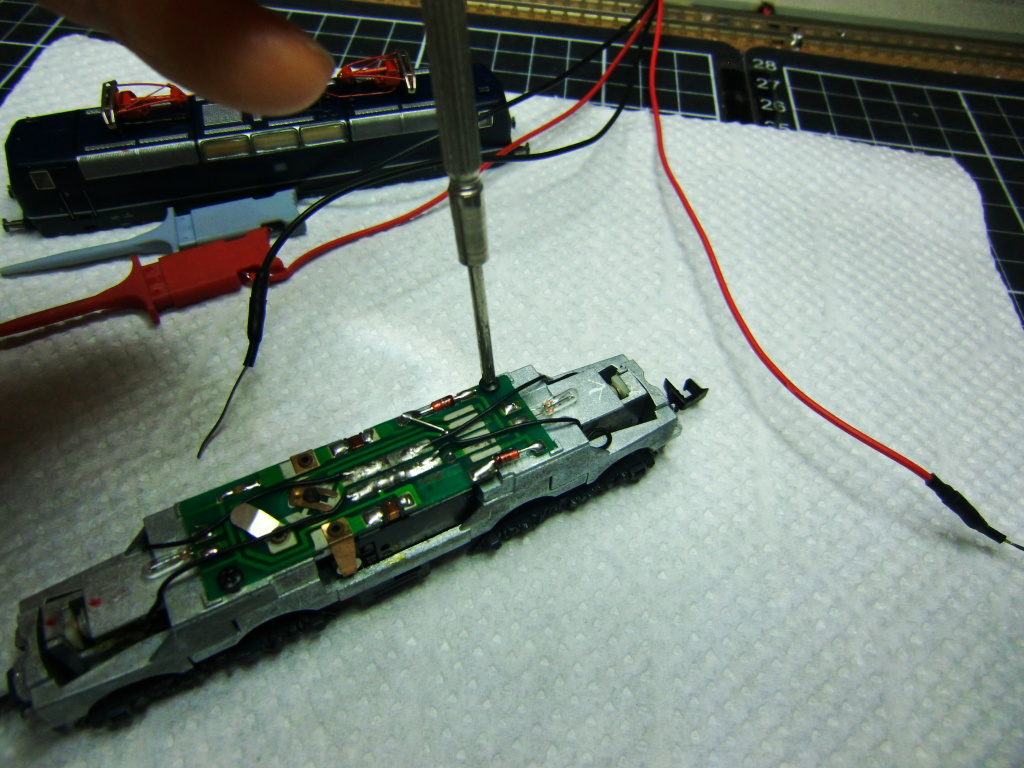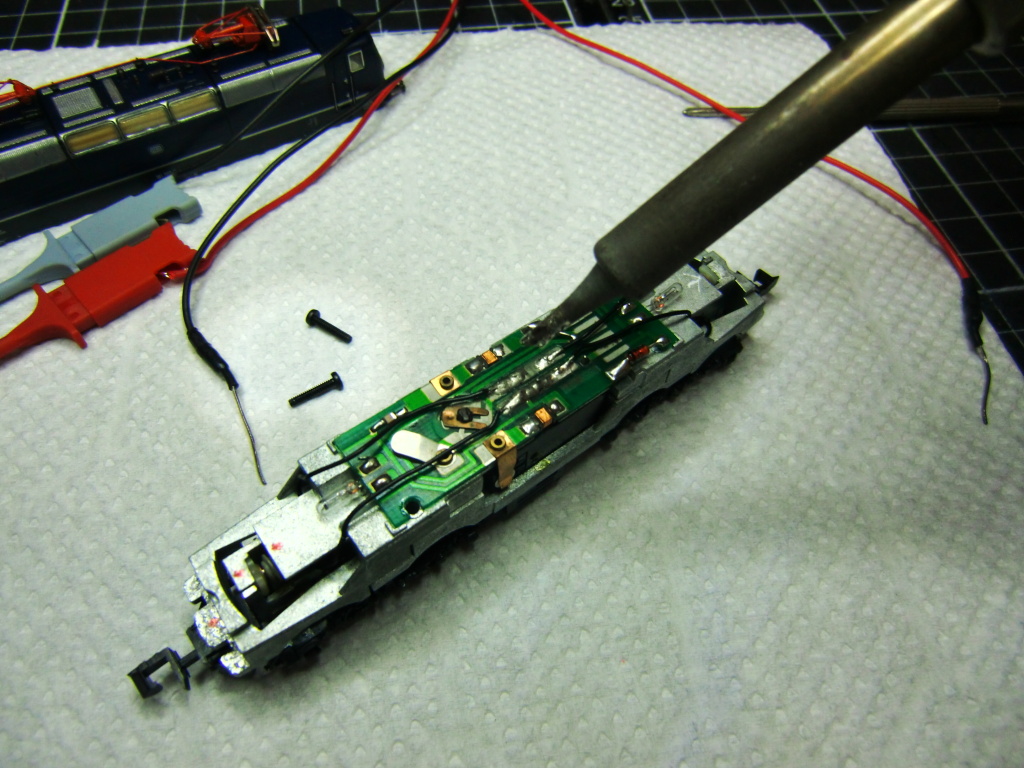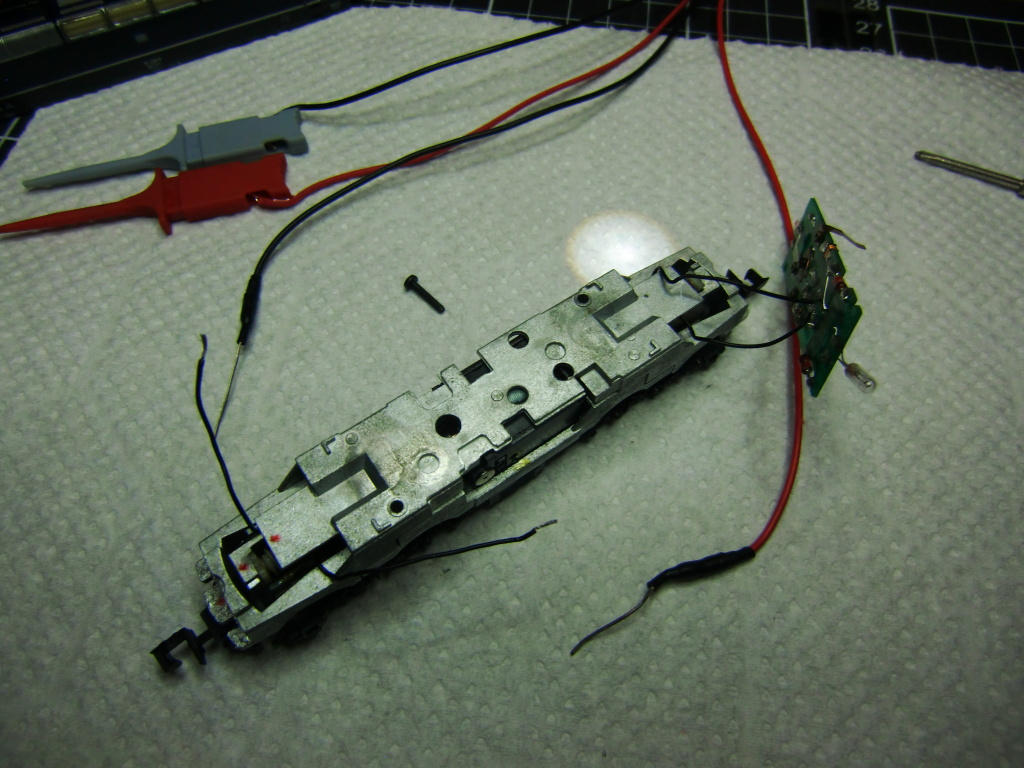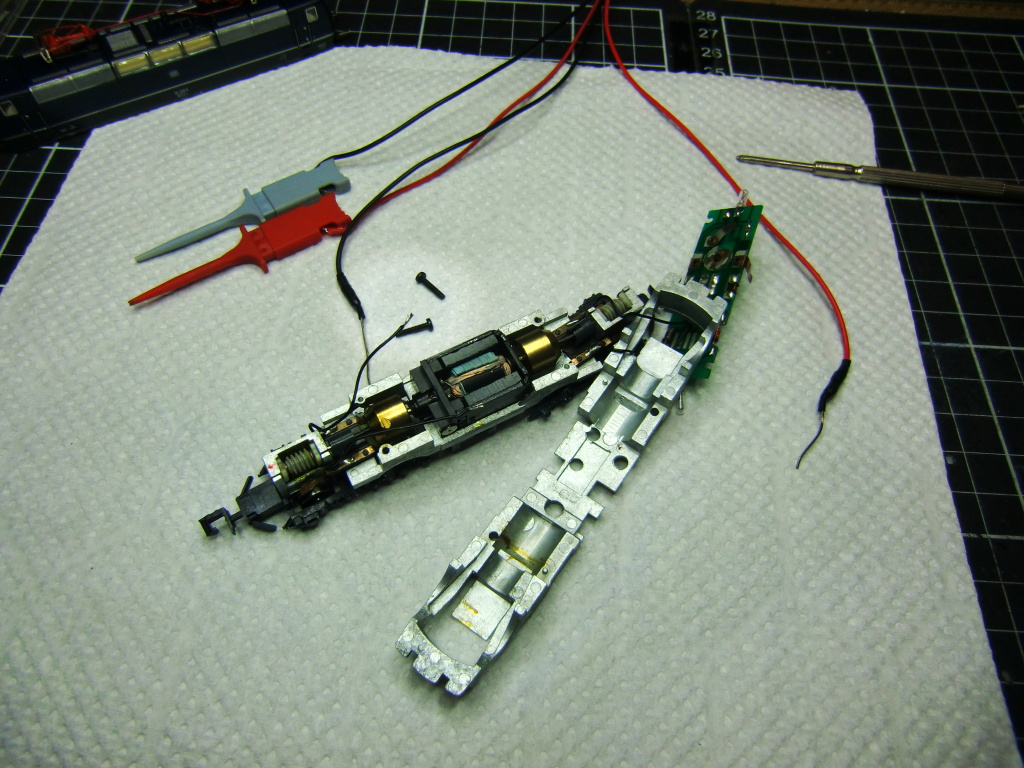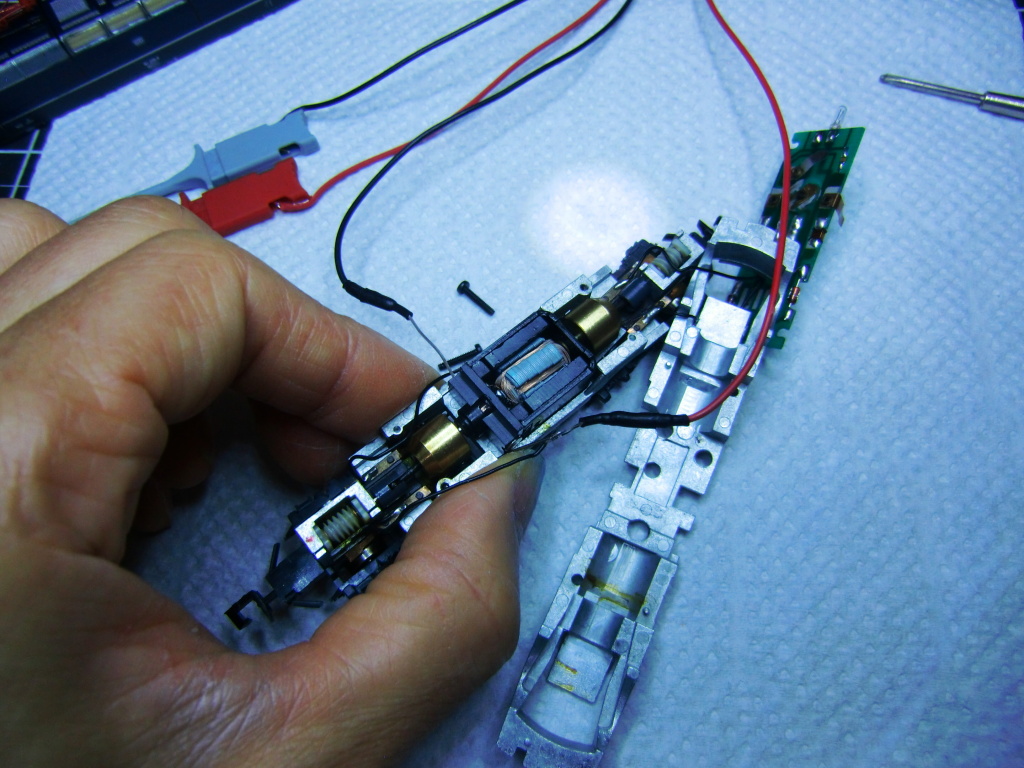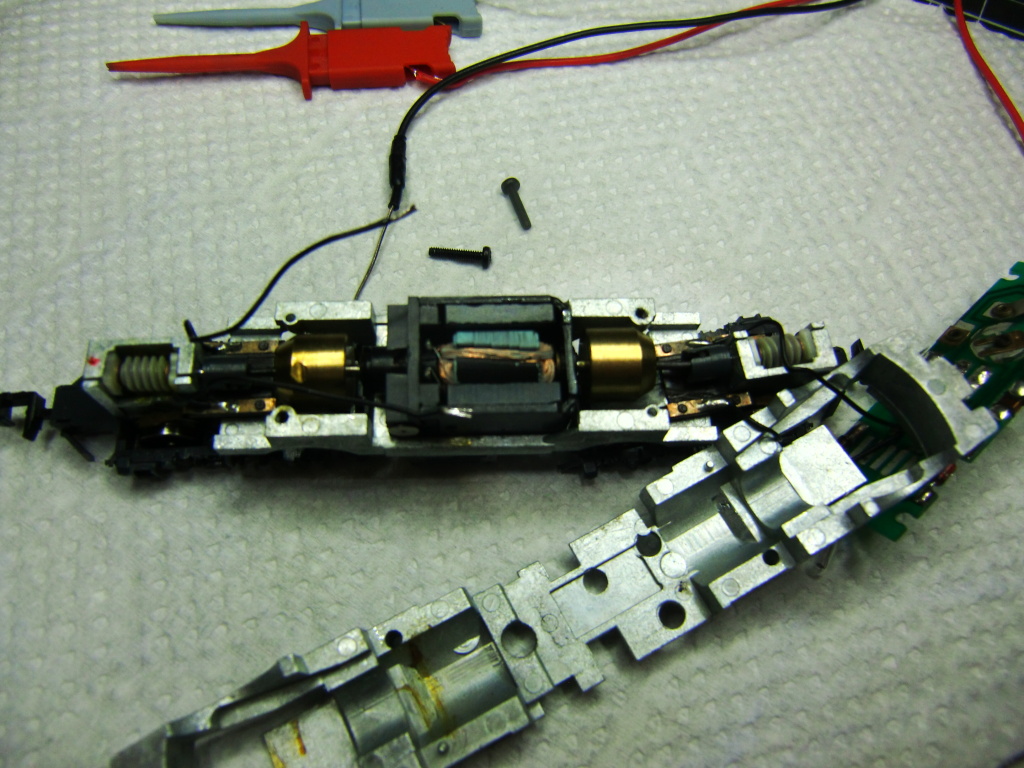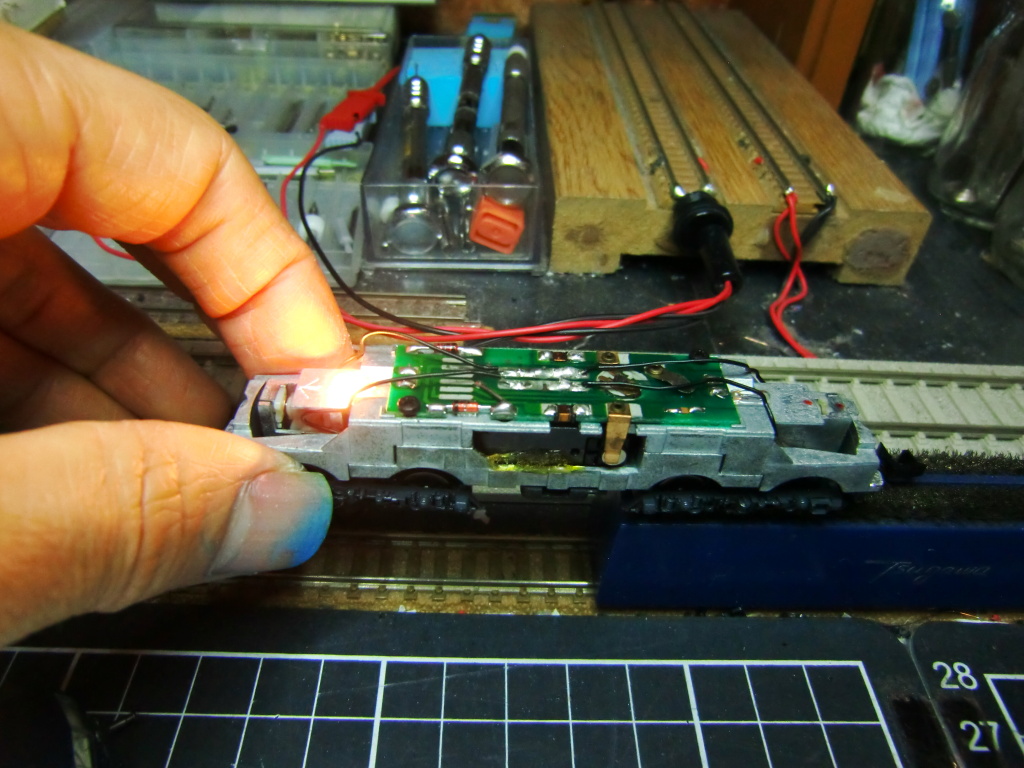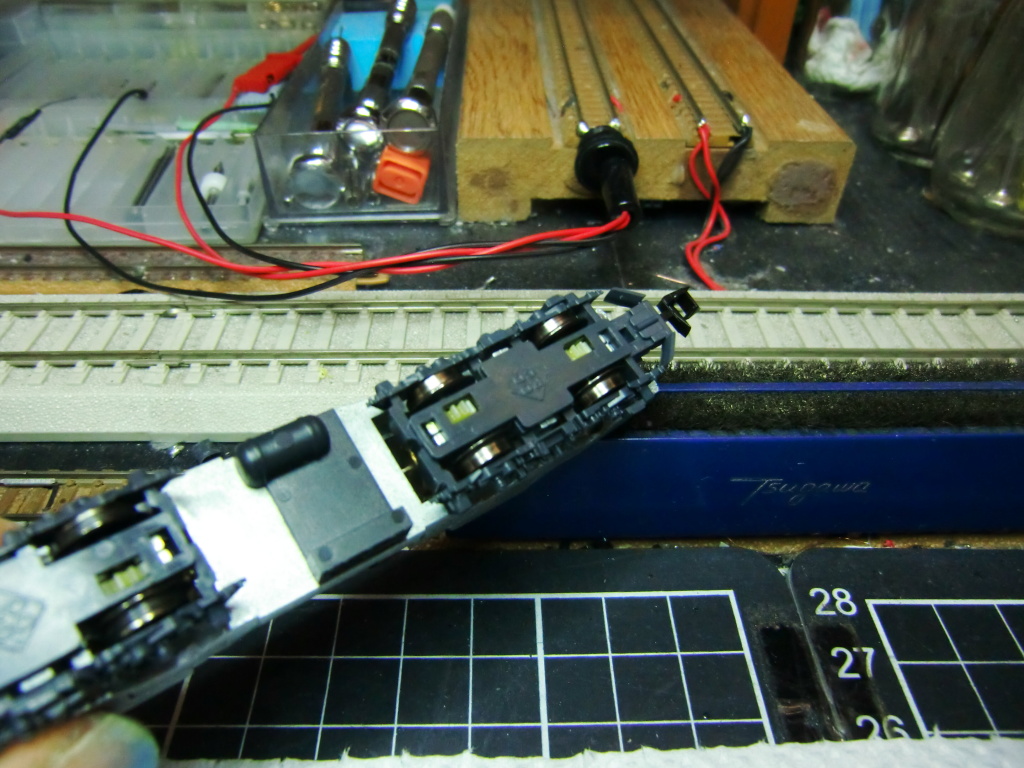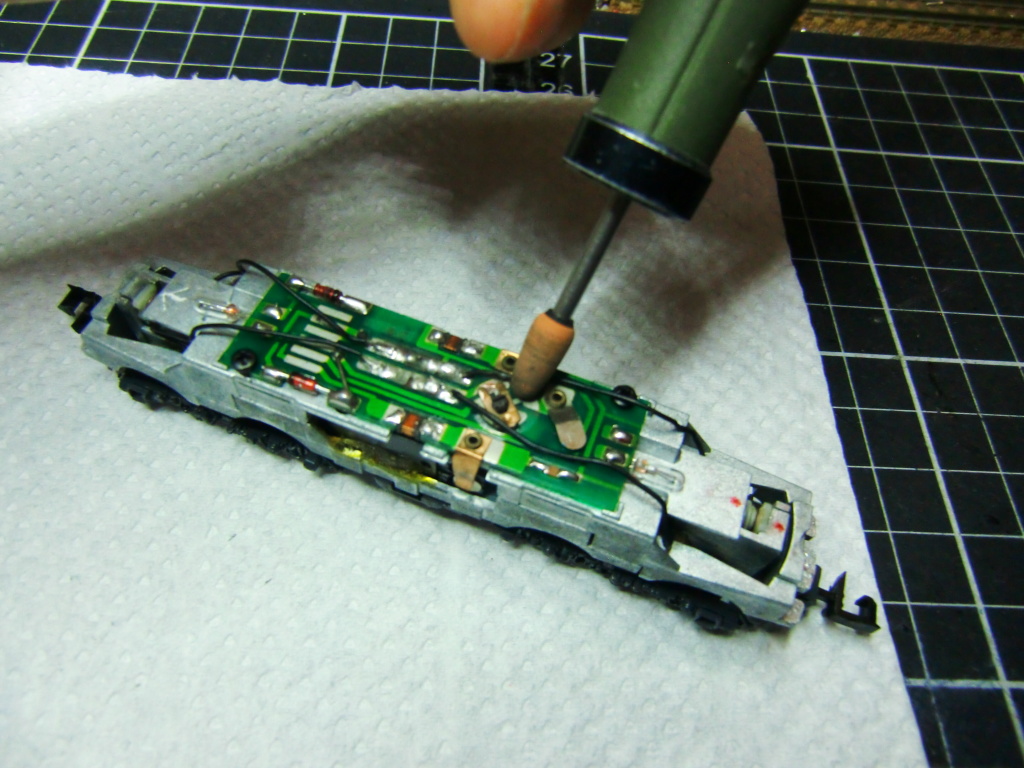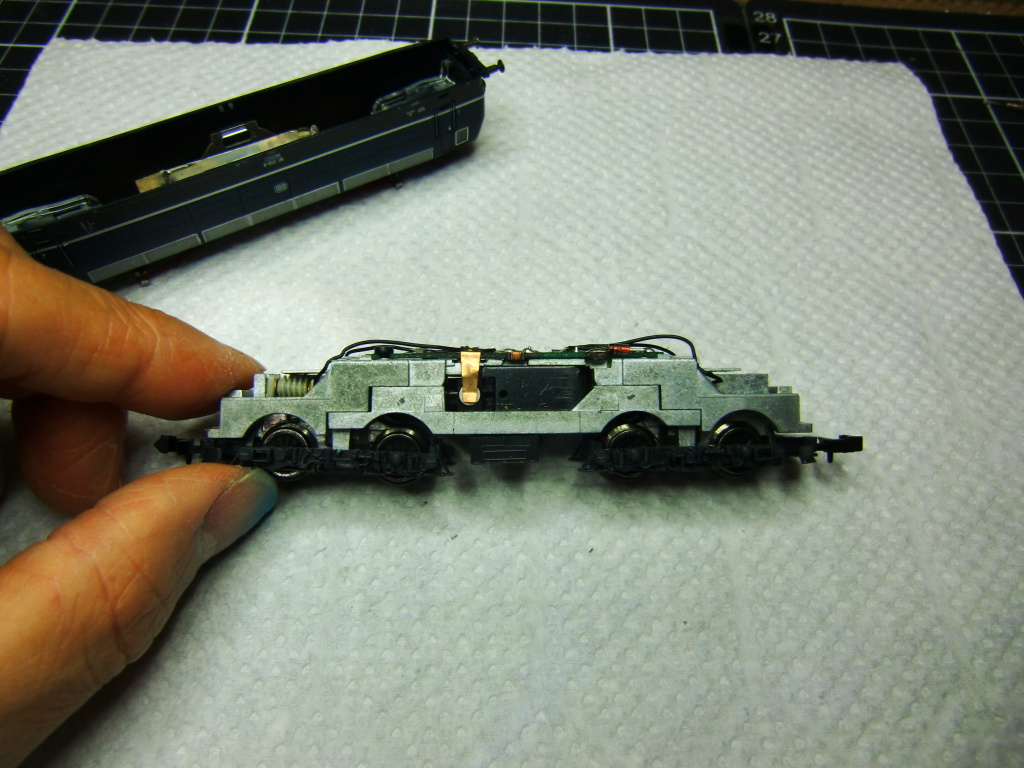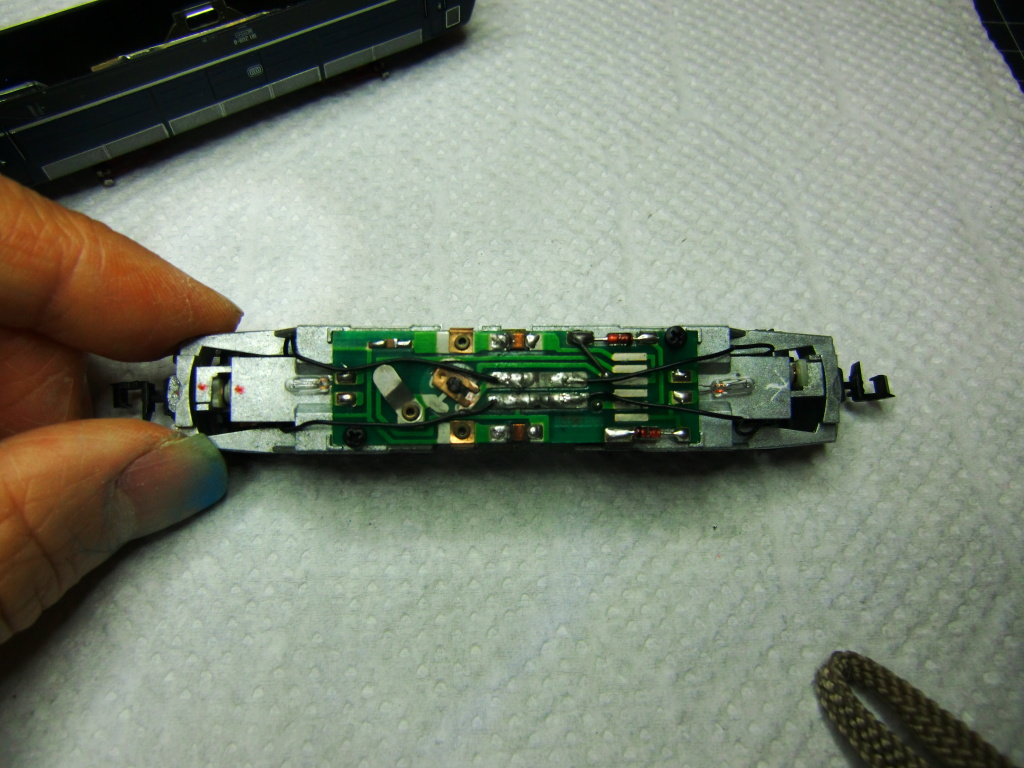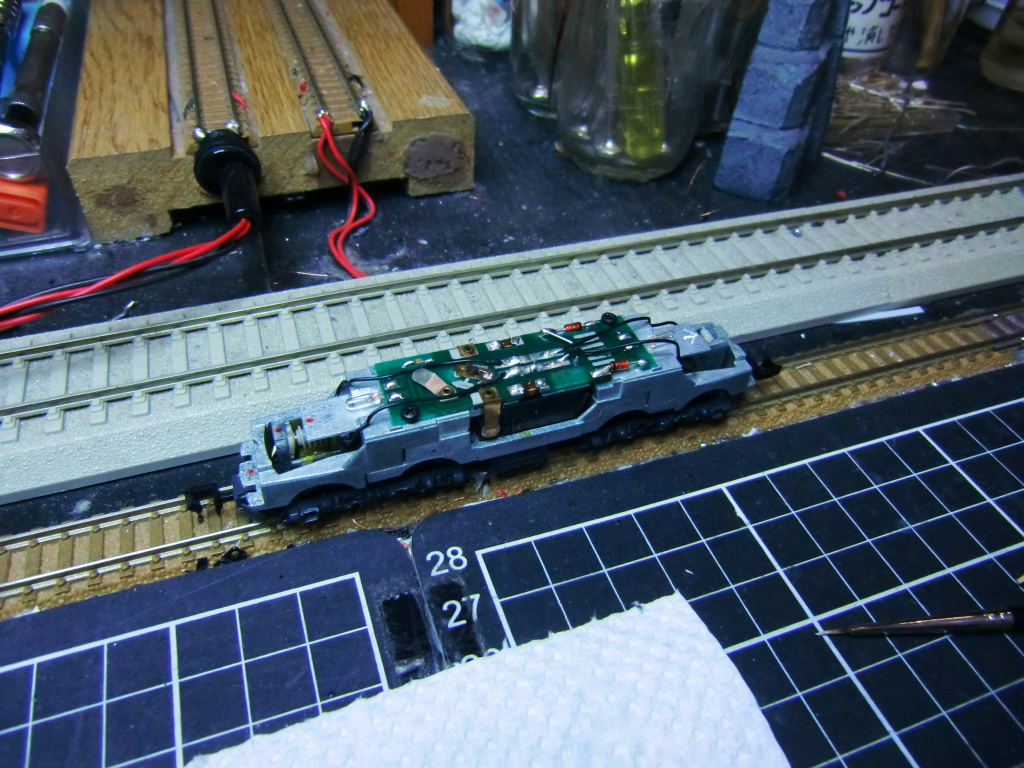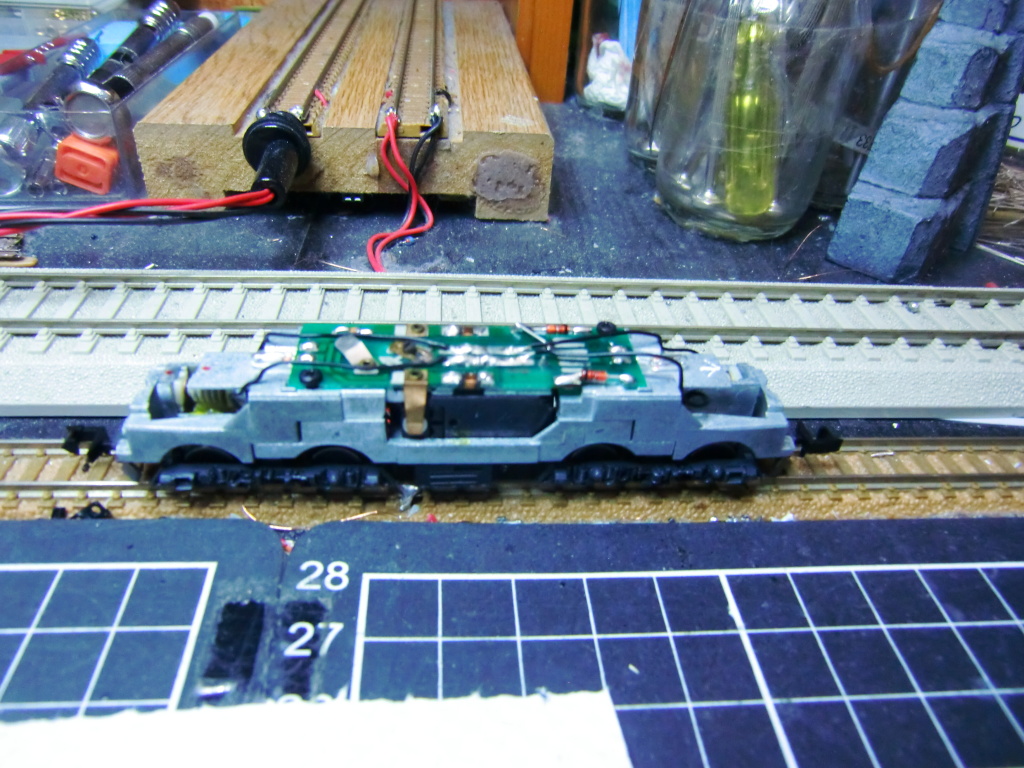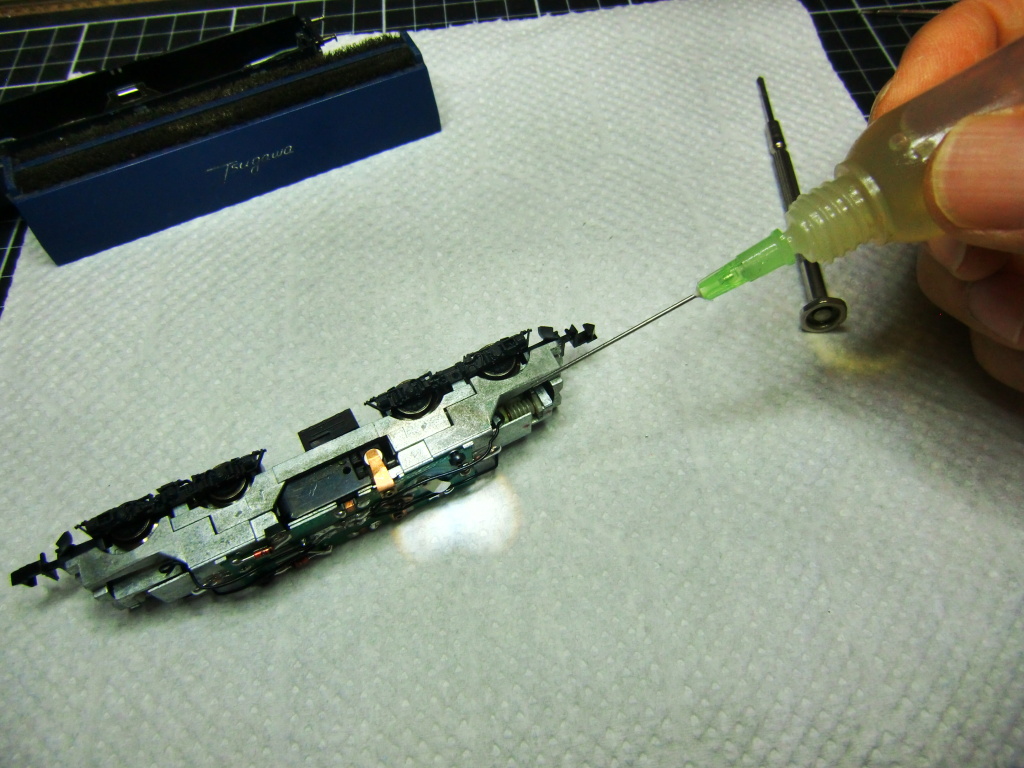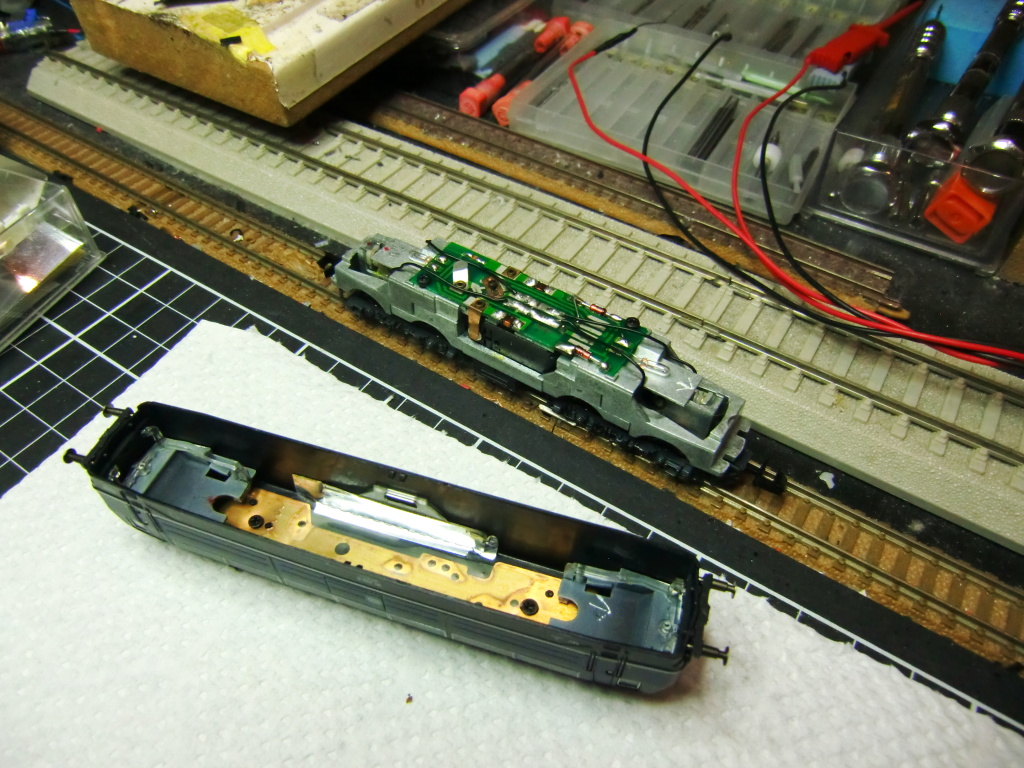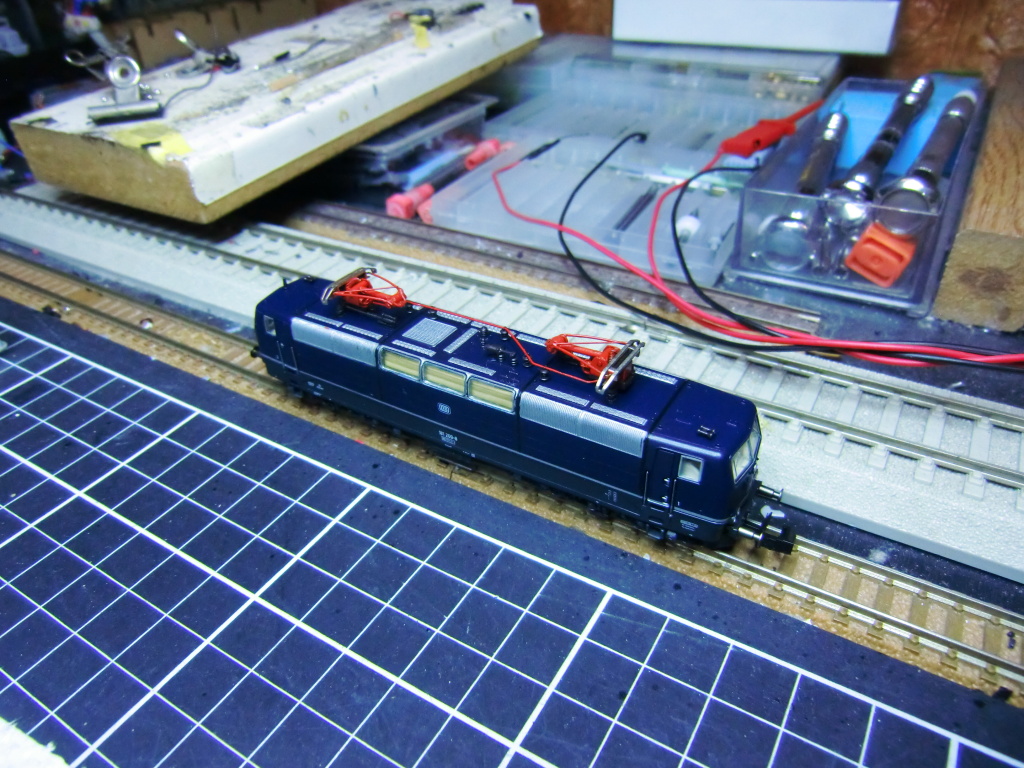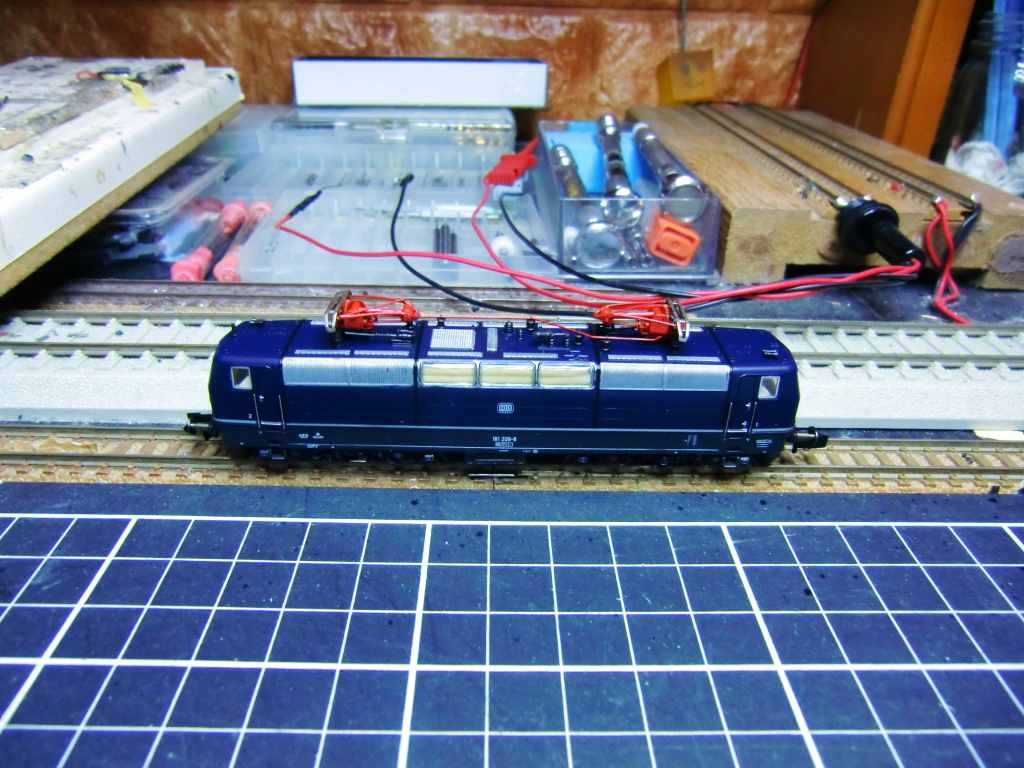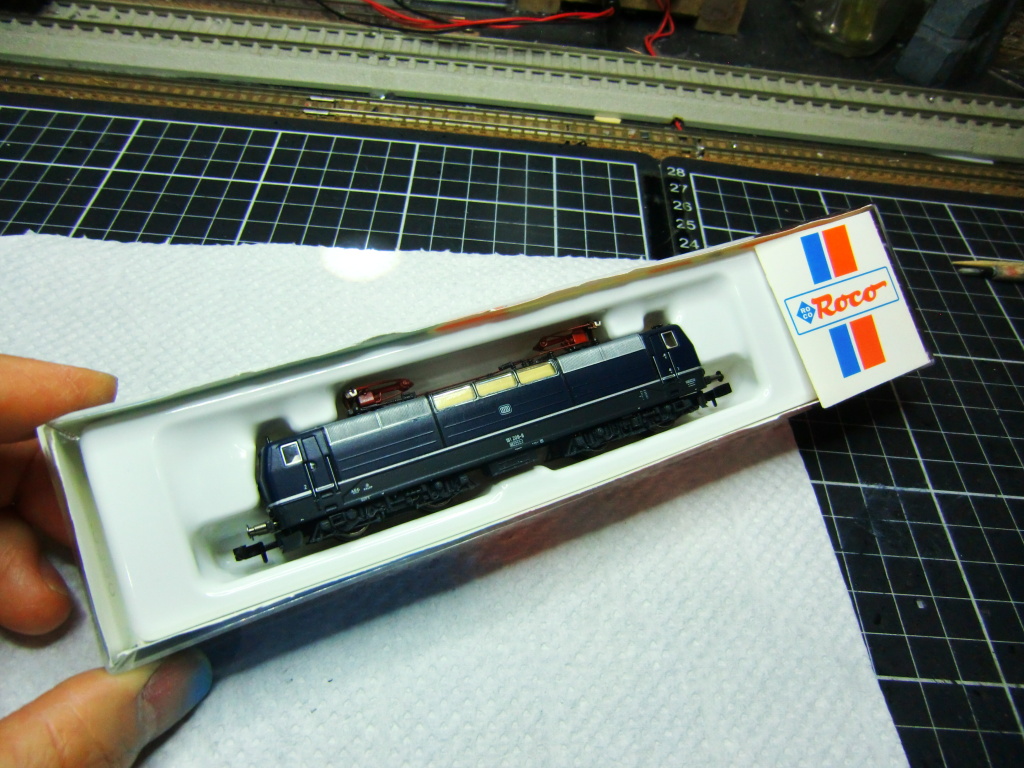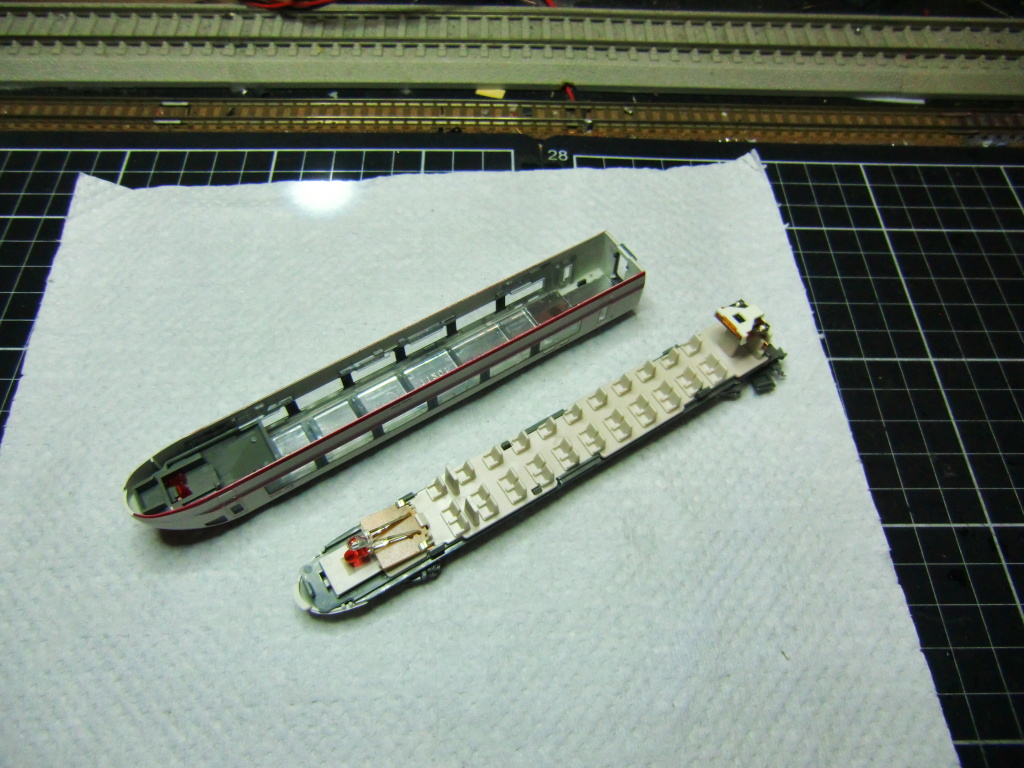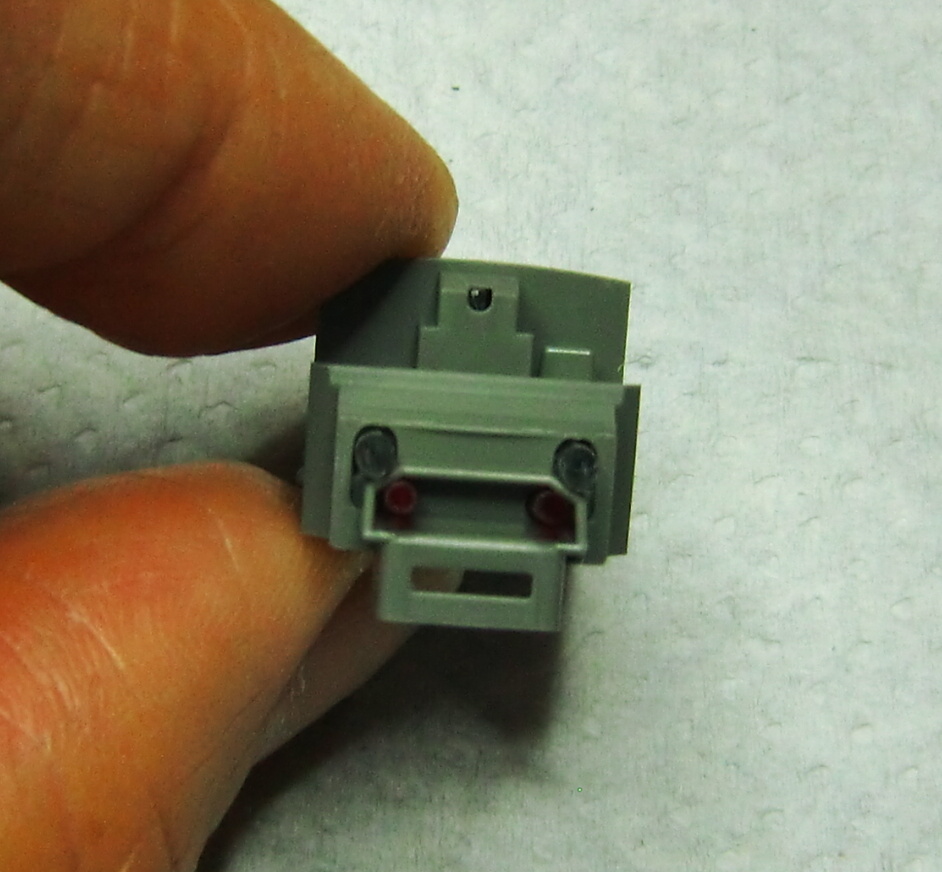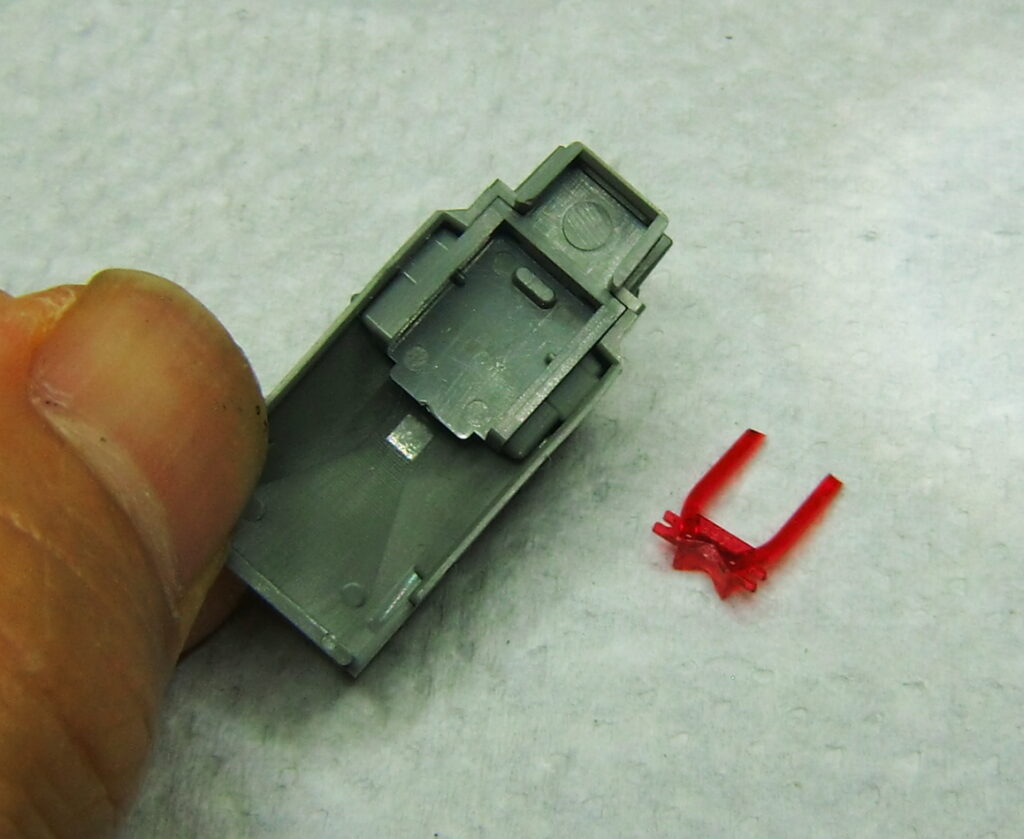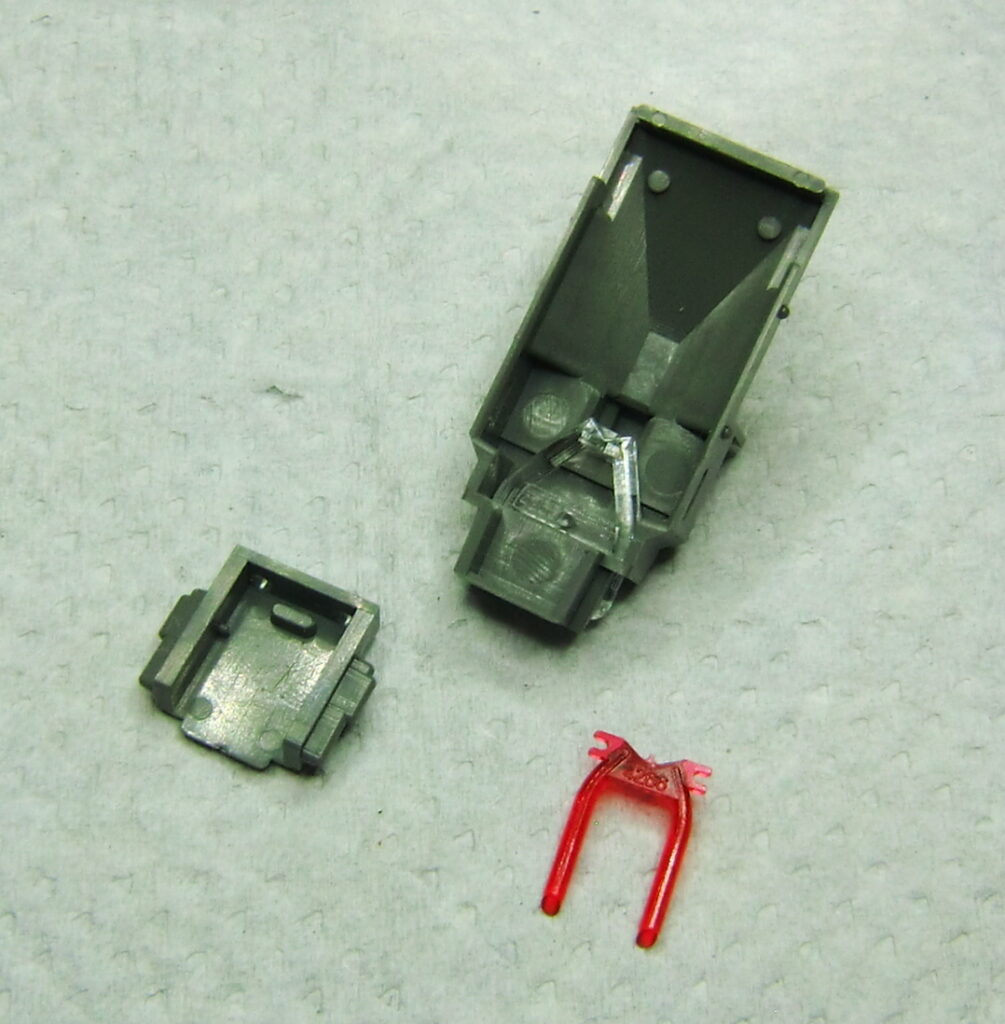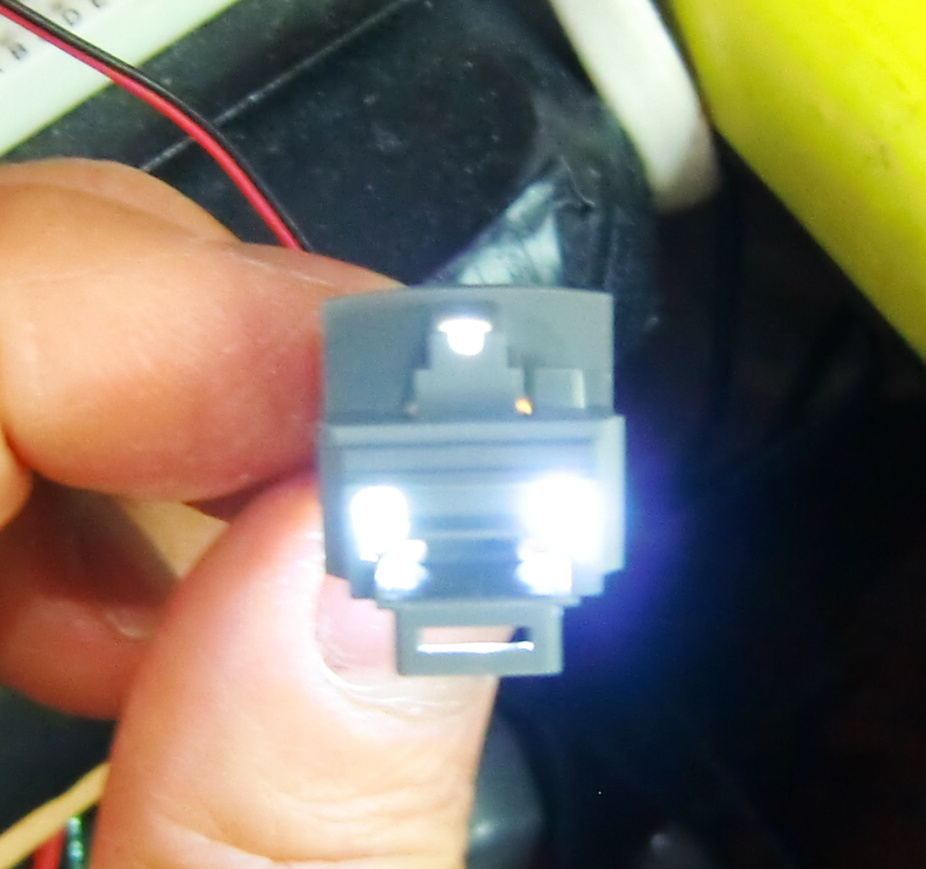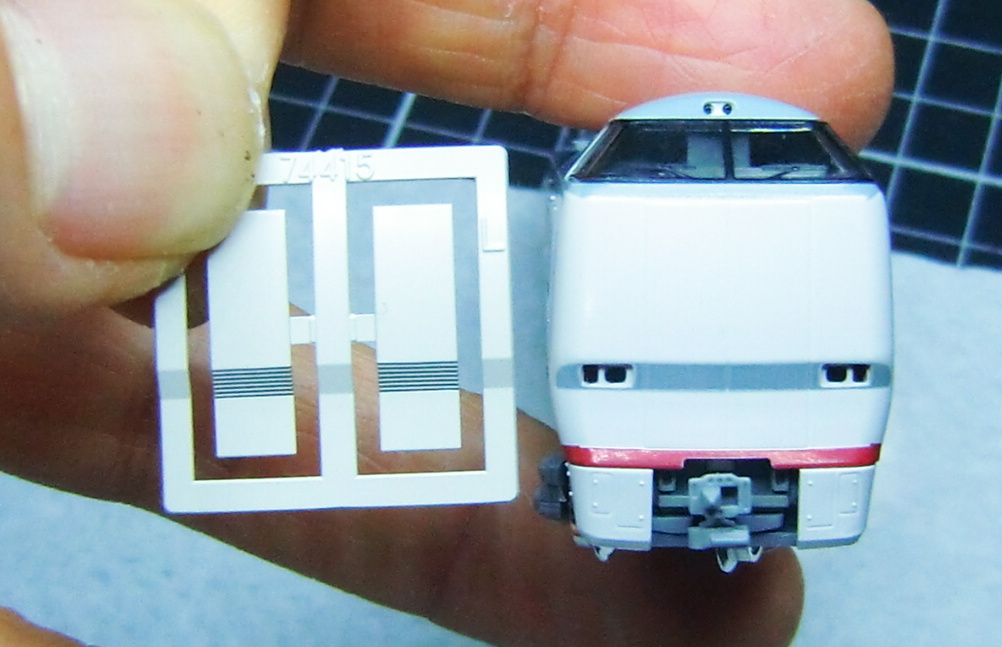現状ですが、まったく動きません。

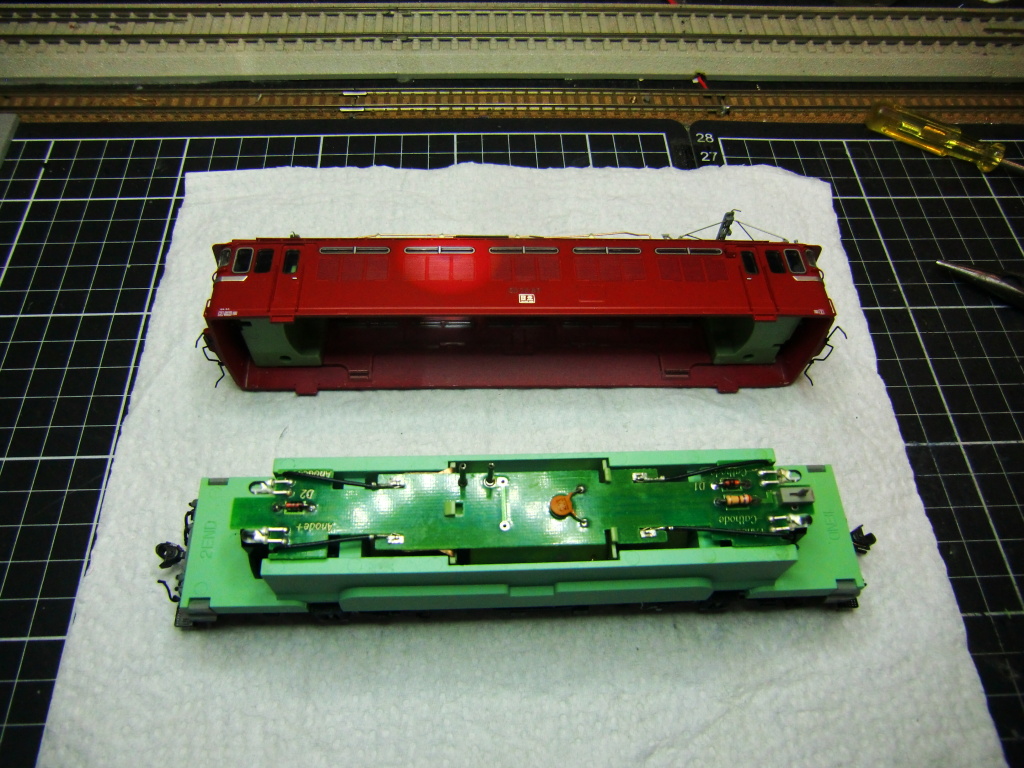
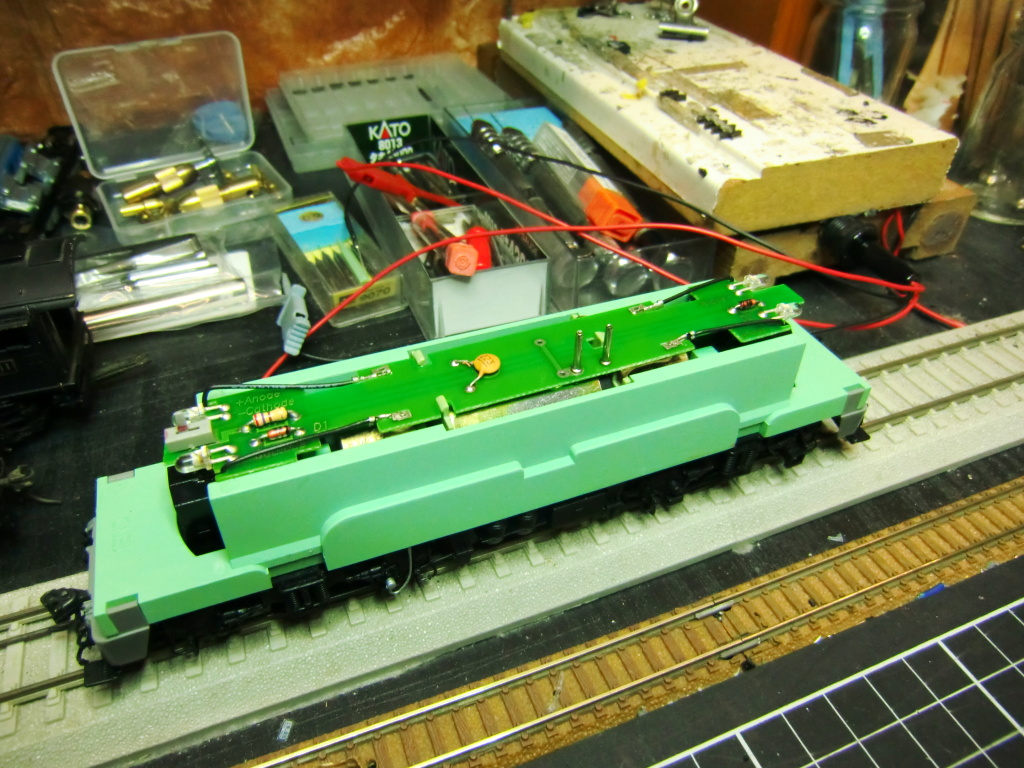
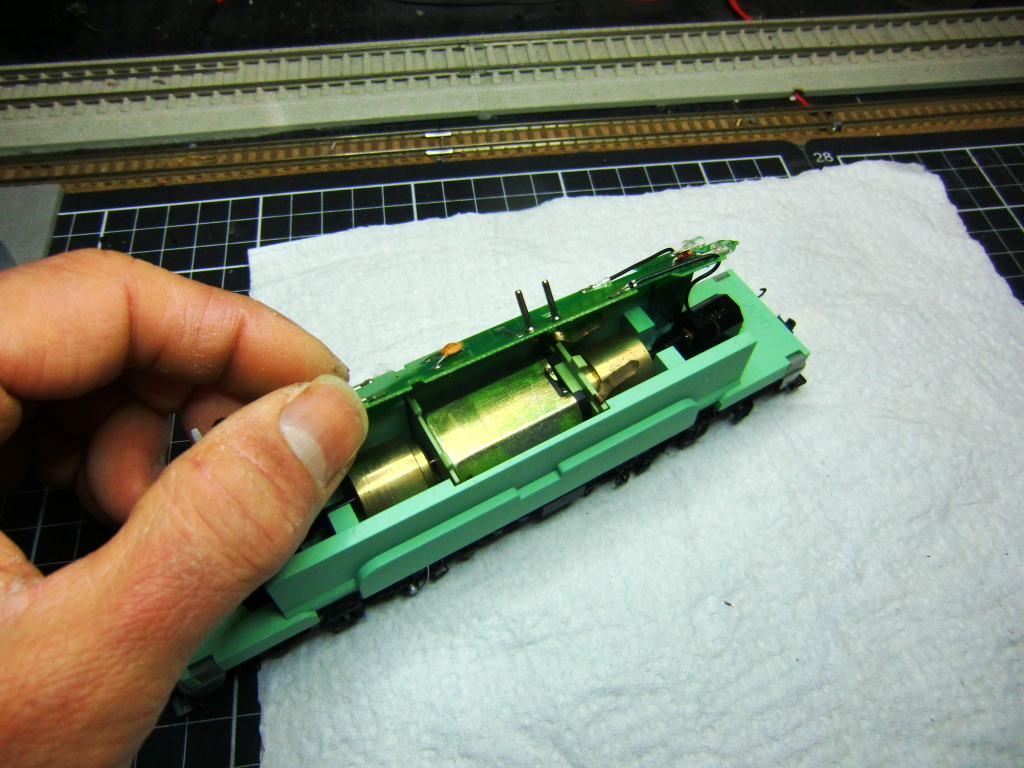
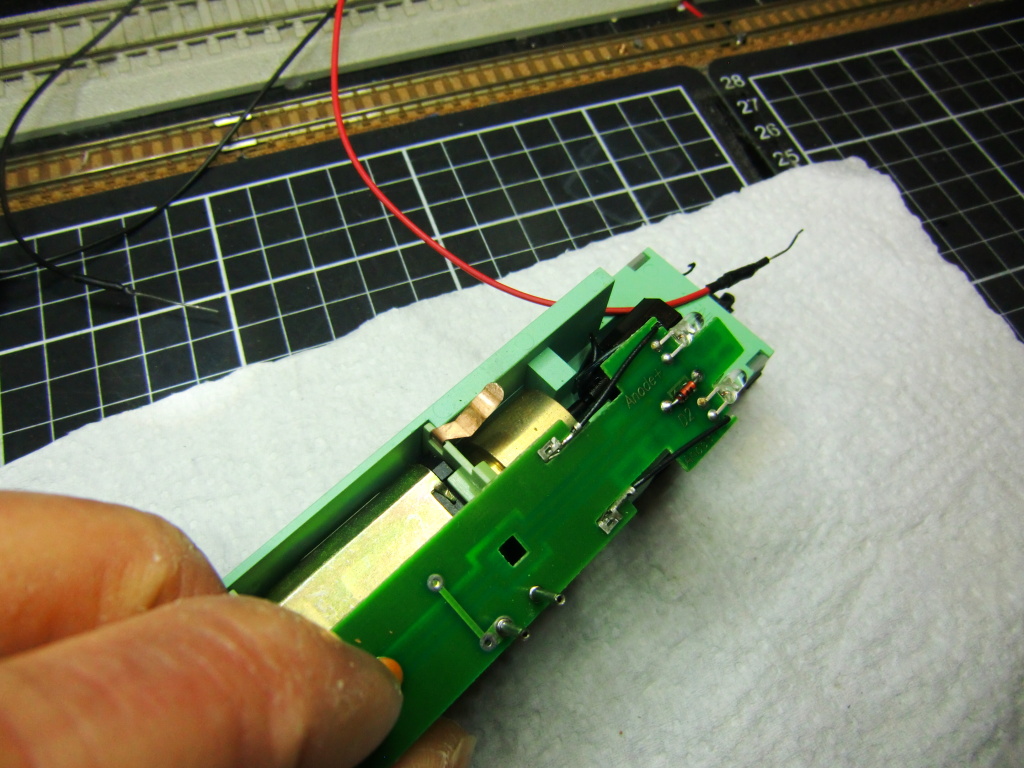

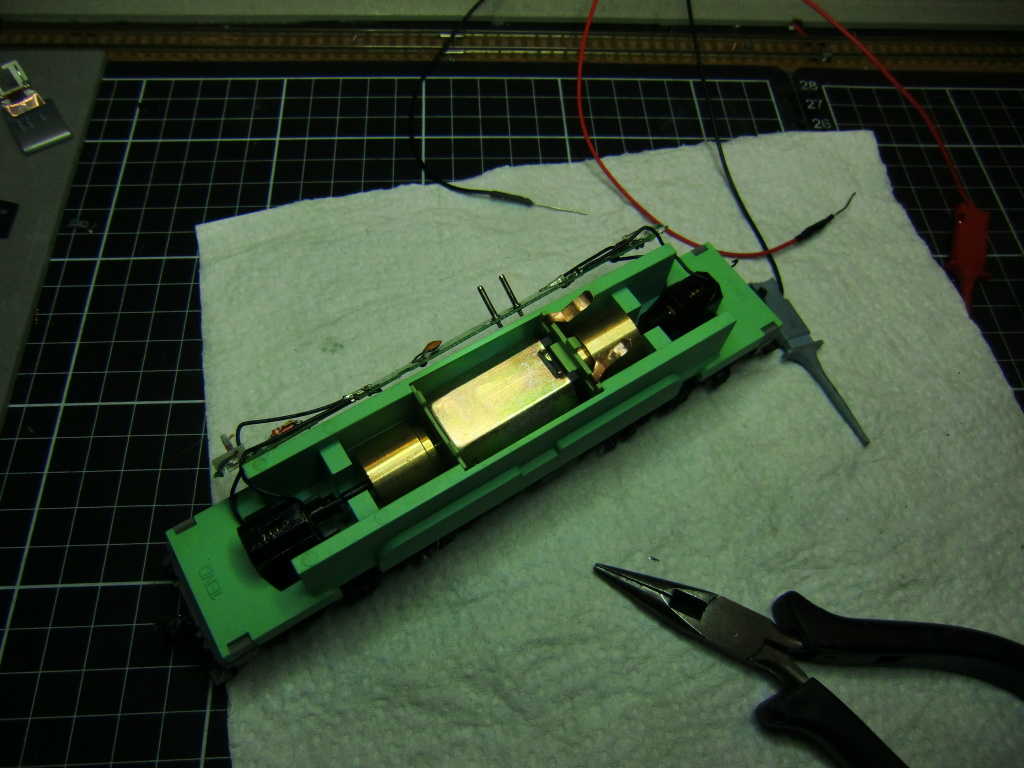
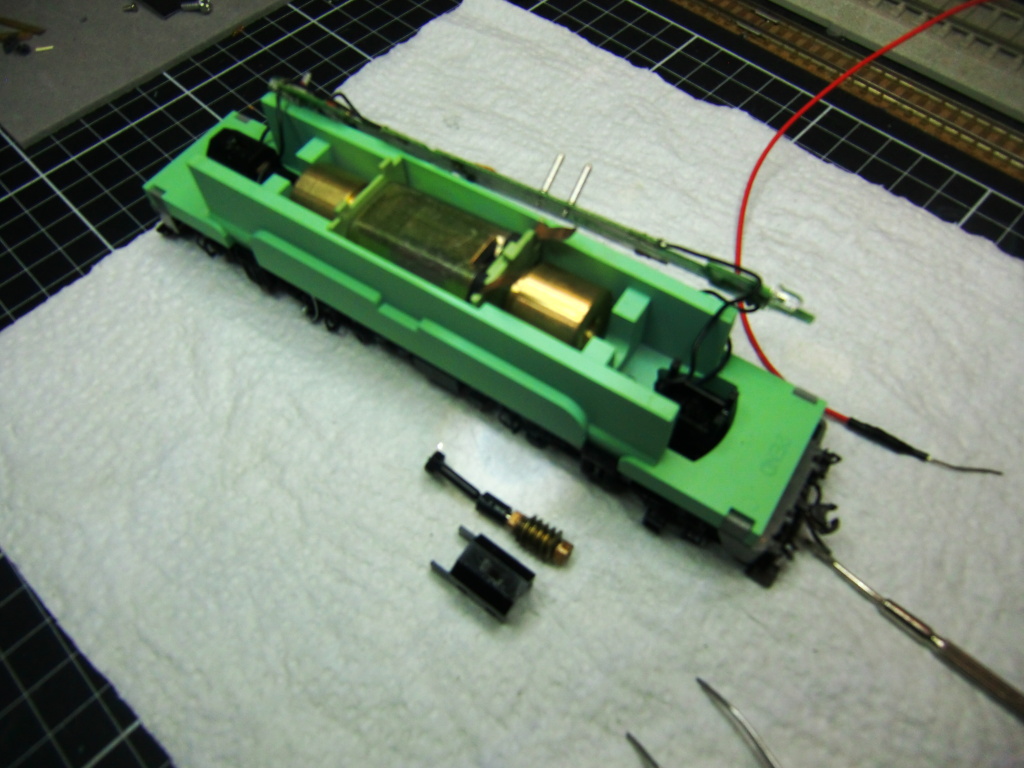
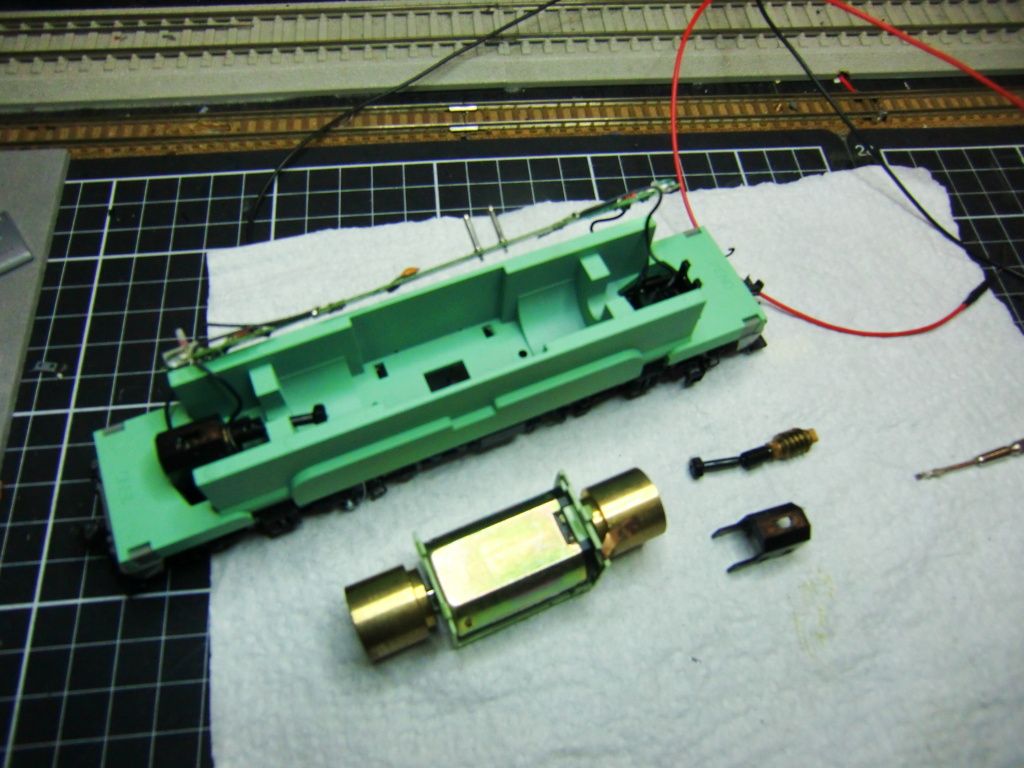
モーターを取り出して問題個所の特定と対処を行います。

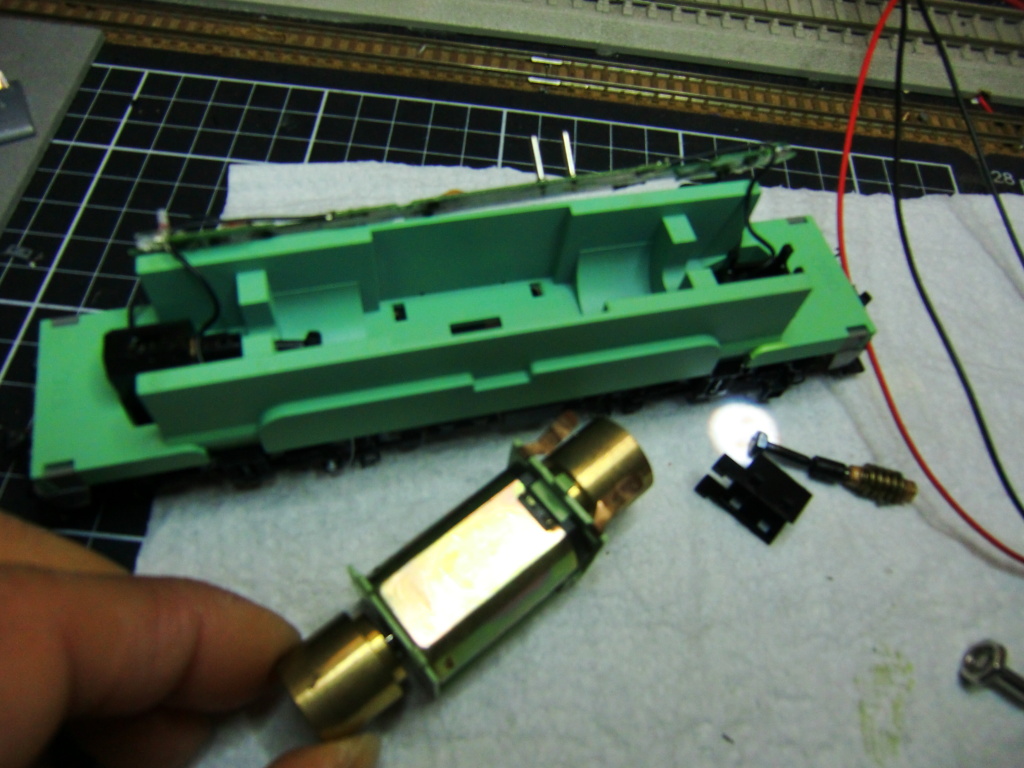
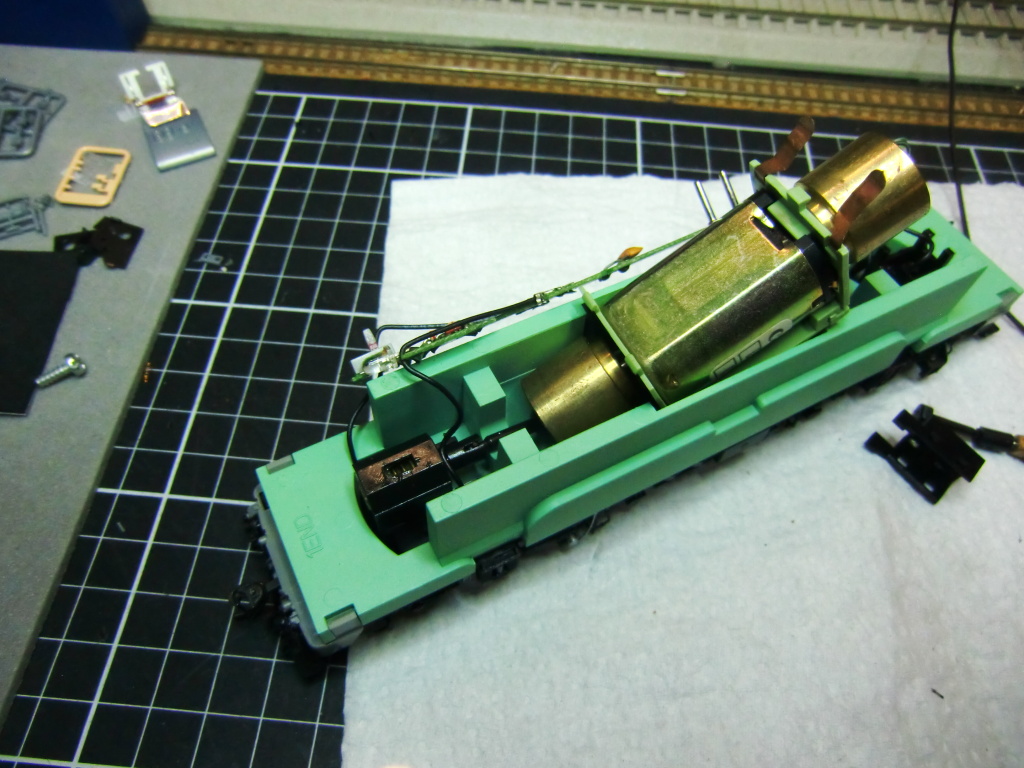
対策を行ったあと、元に戻して動作確認を行います。
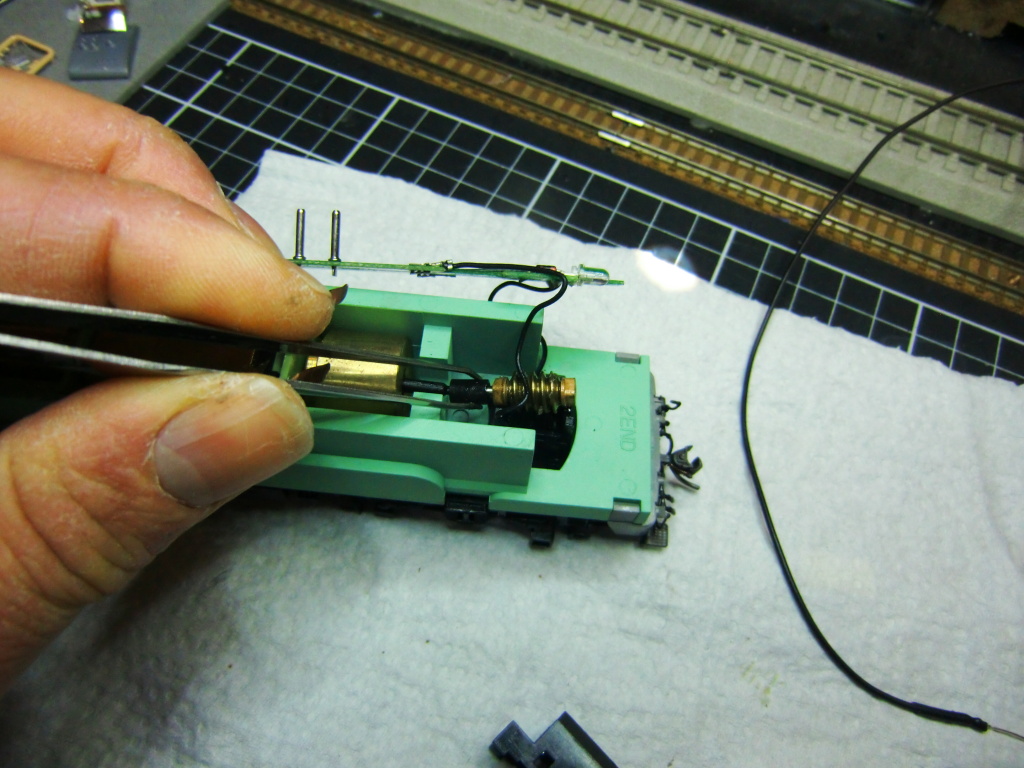

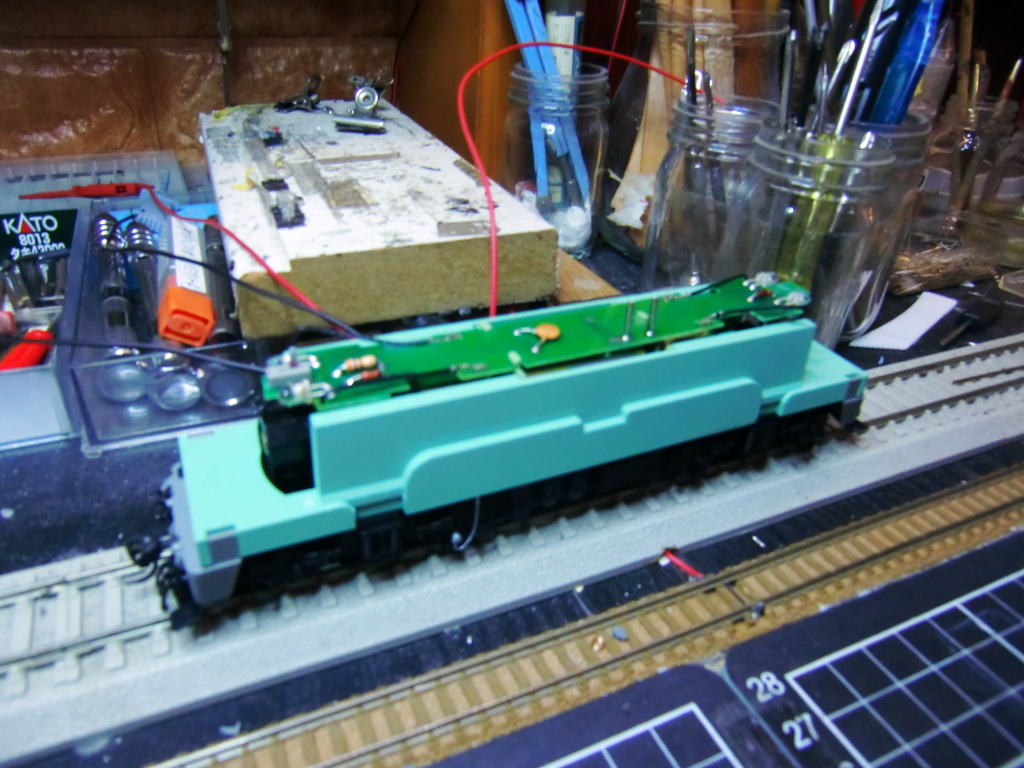
何度か分解と組立を行いスムーズに動くまで繰り返します。

最後に車輪をピカピカに磨きだして作業は完了となります。
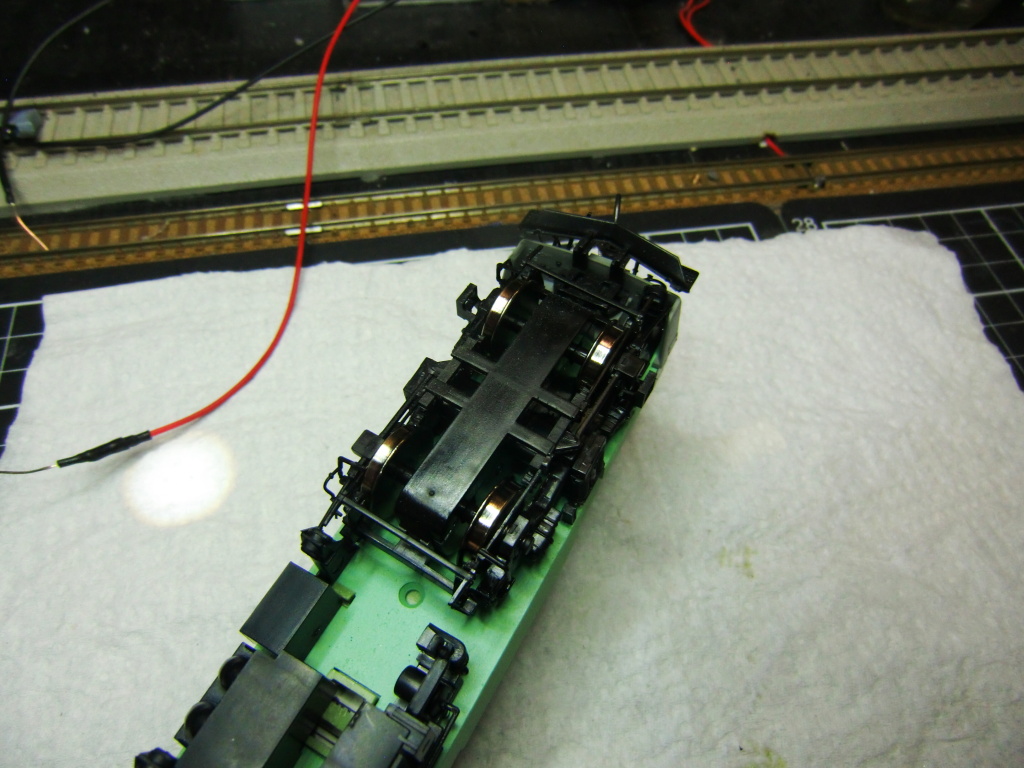
このように光沢も蘇りました。
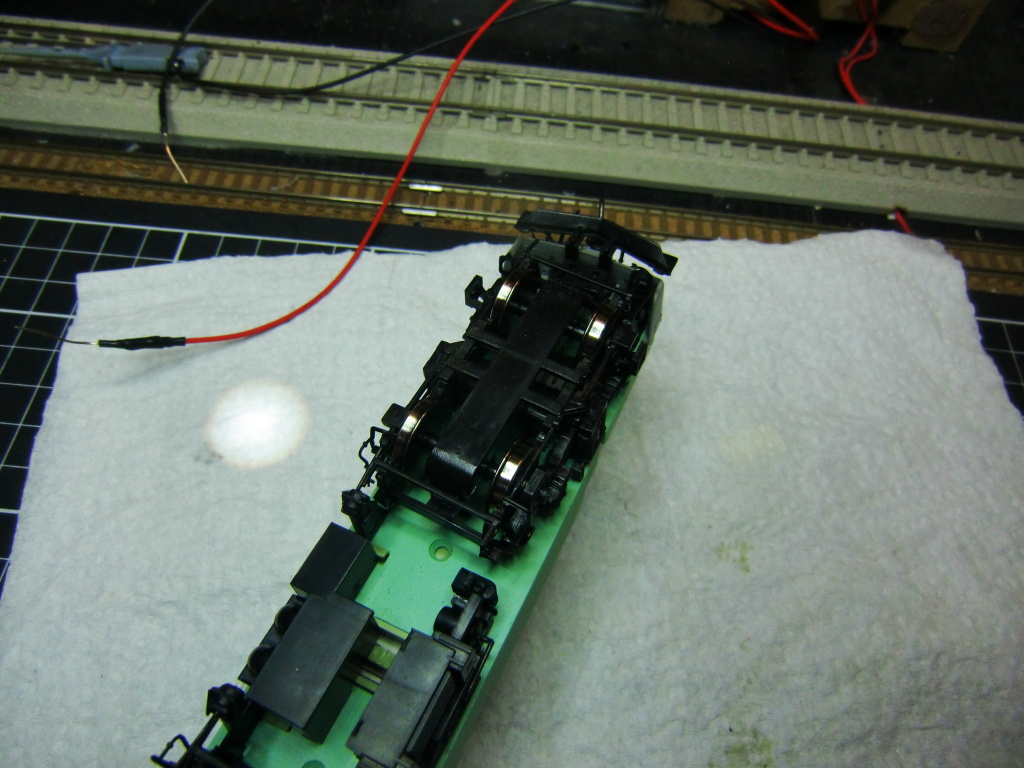
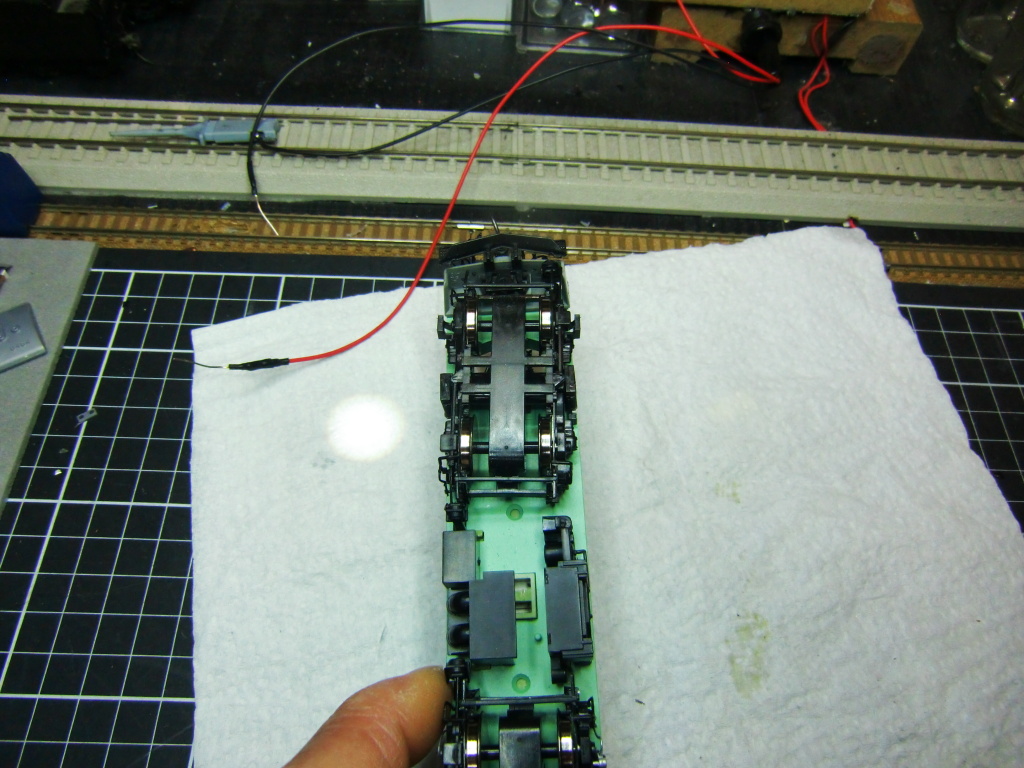


ボディーを被せた状態で最終動作確認です。スムーズに走るようになりました。

作業完了でございます。
前進走行時に速度が出ない問題と車体が上下に揺れる点の改善を行います。

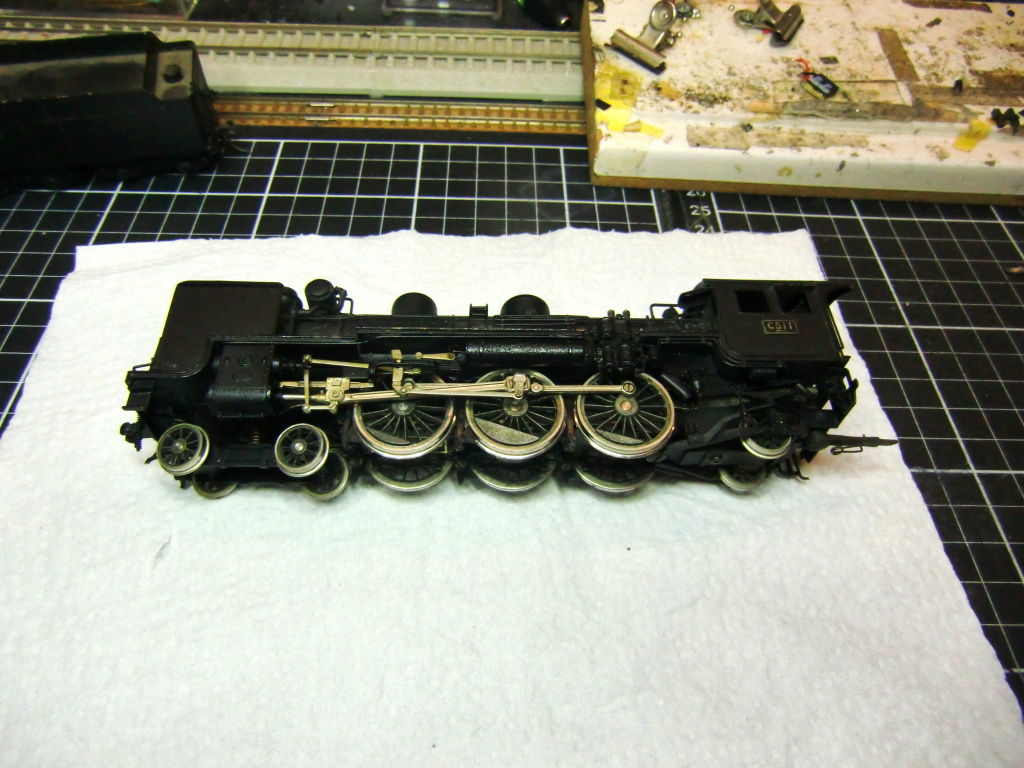
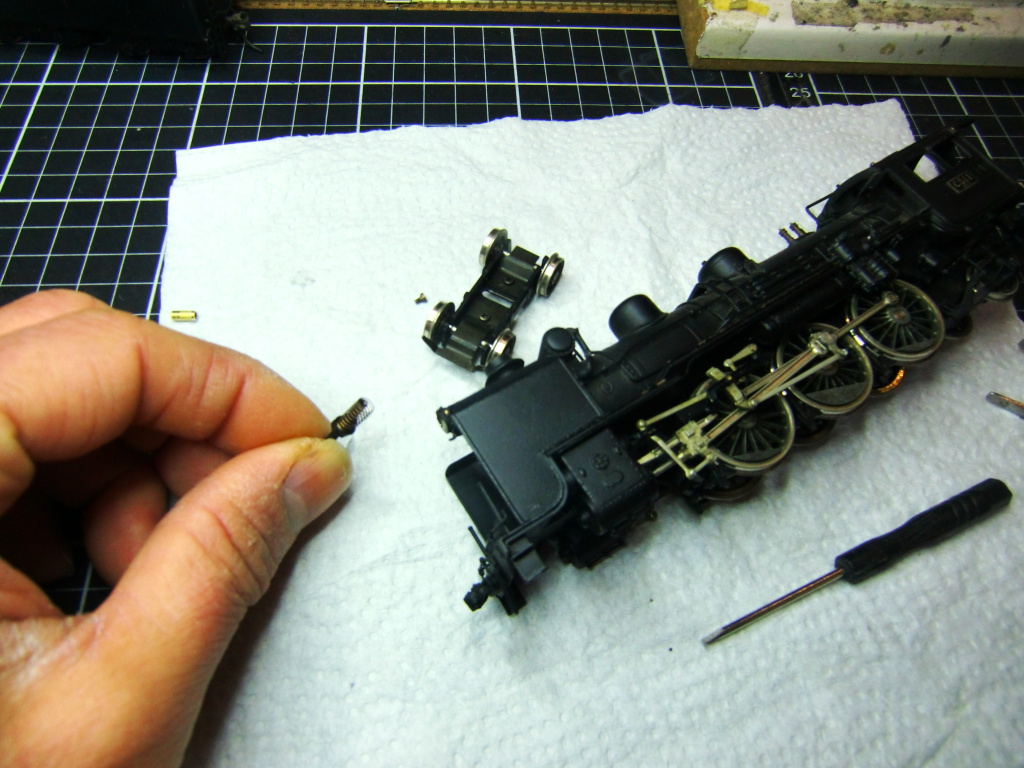

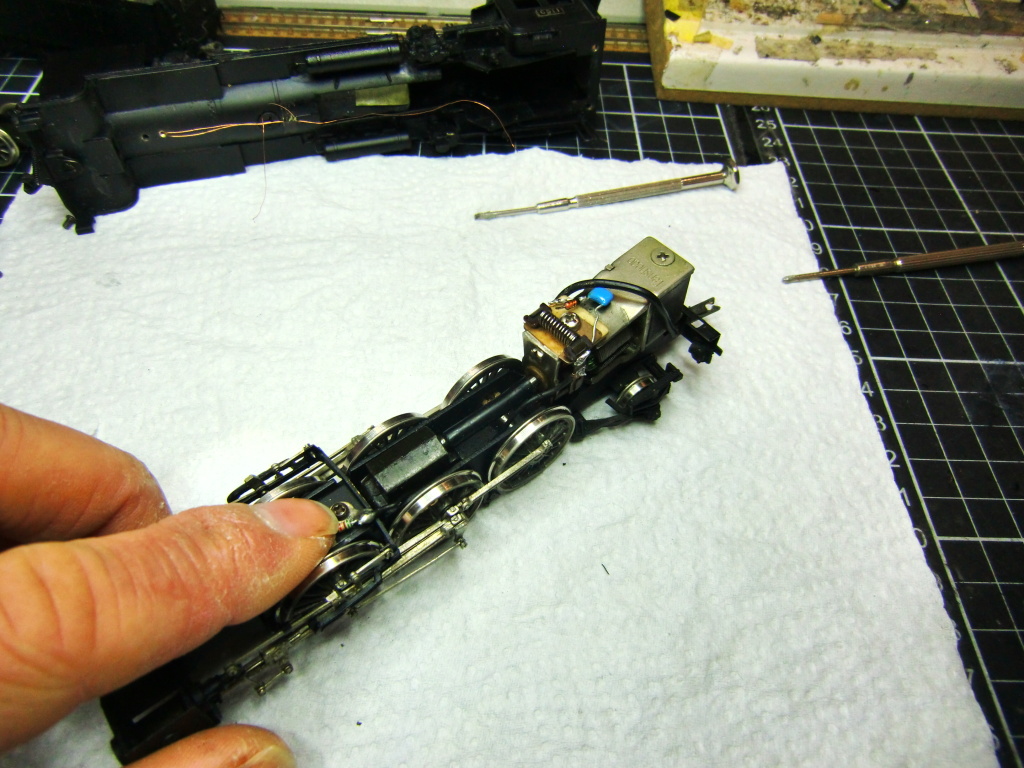

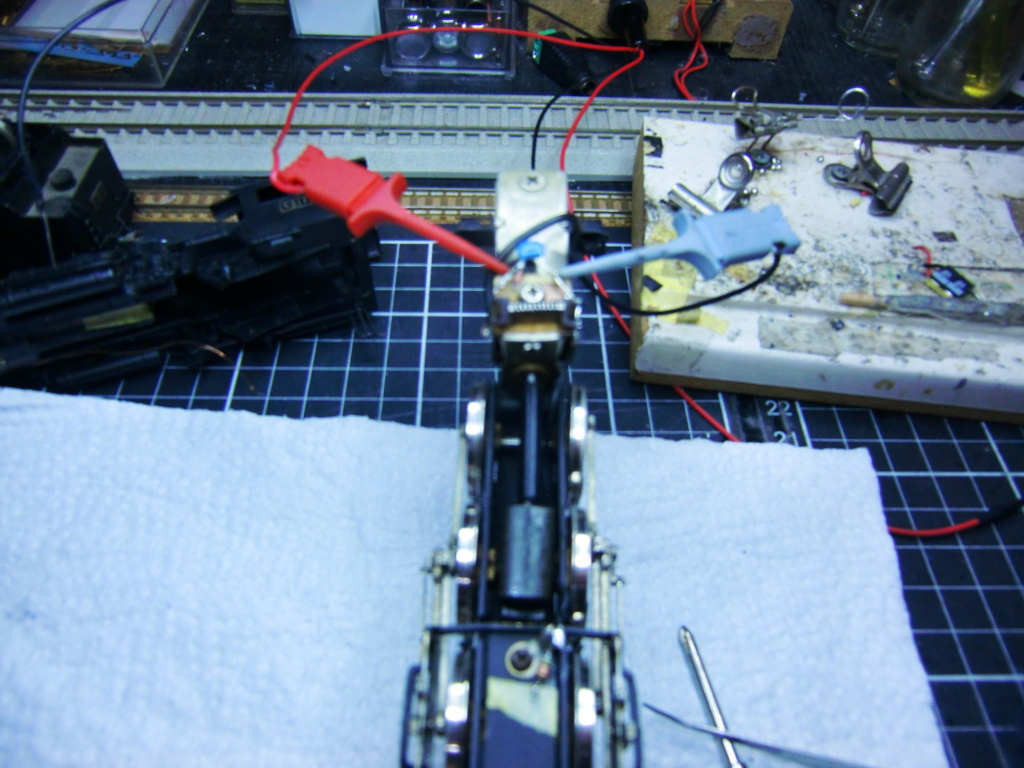
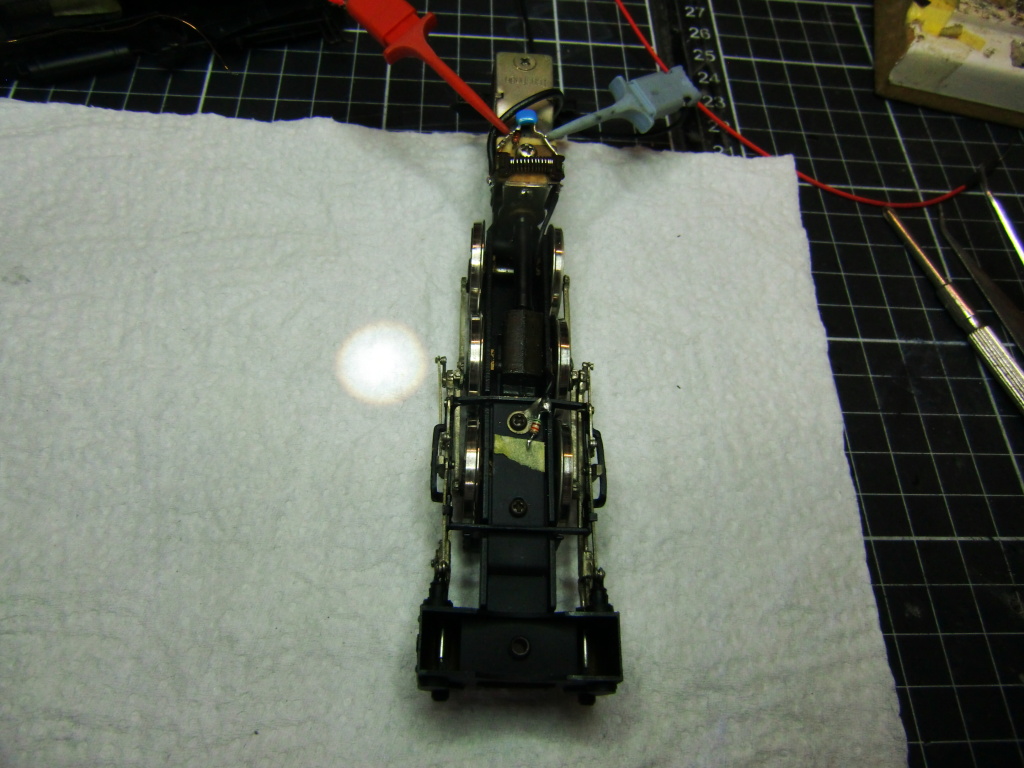
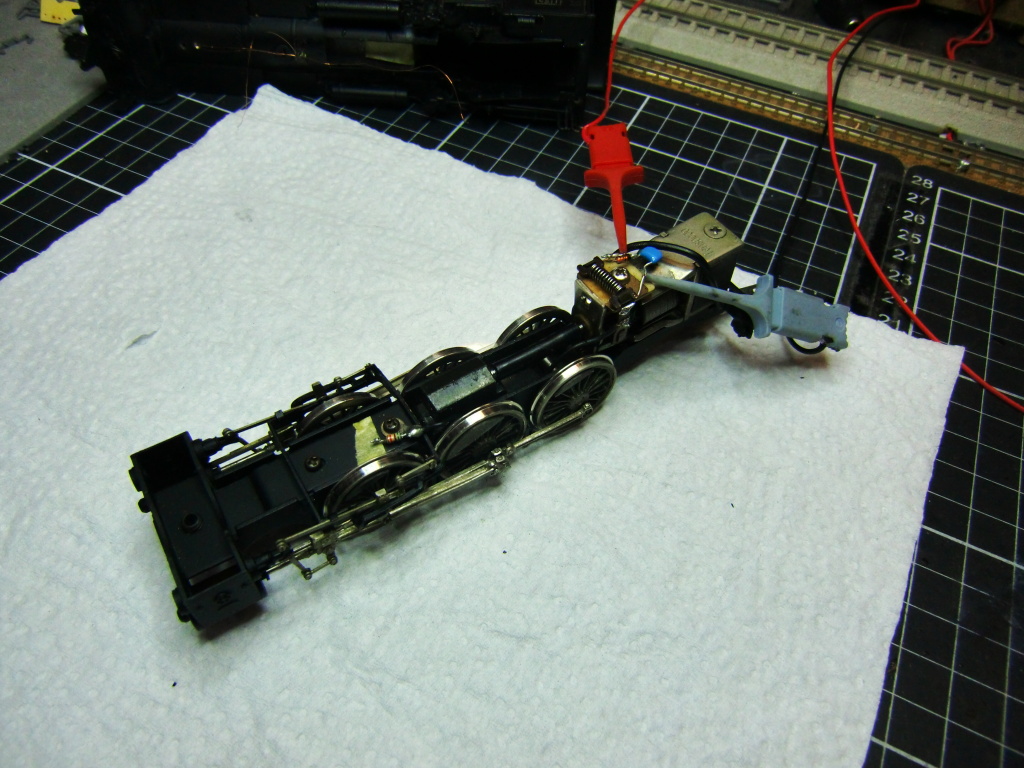
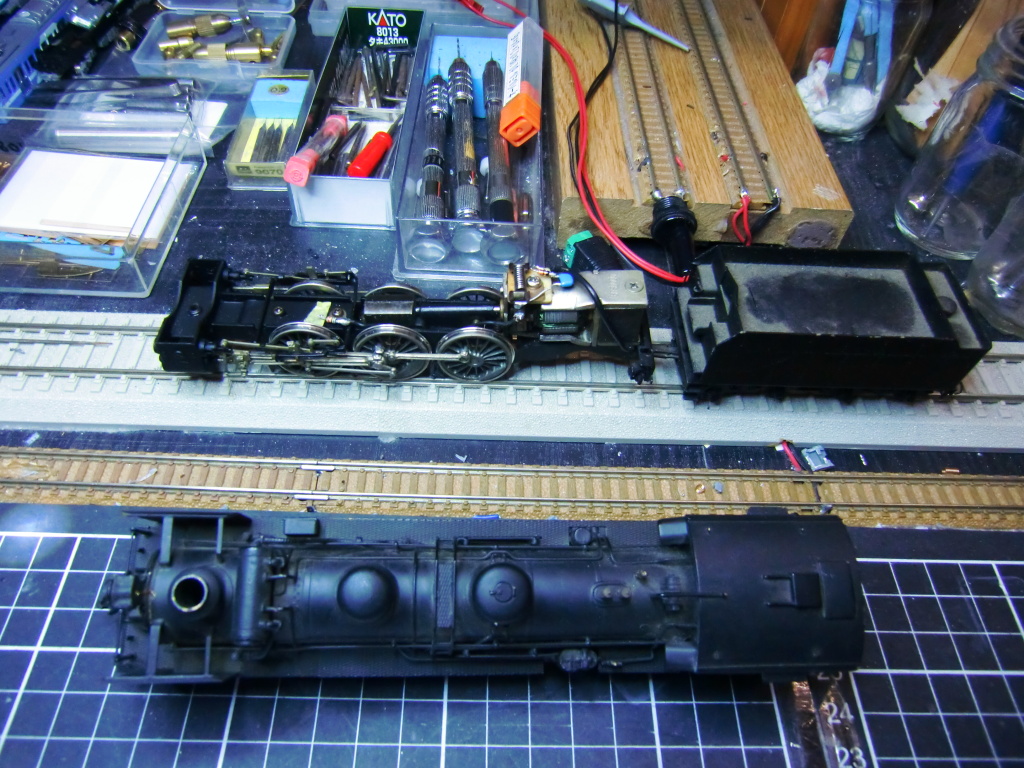
なかなかうまくいきません。問題個所の特定と対処方法で作業はかなり難航しています。
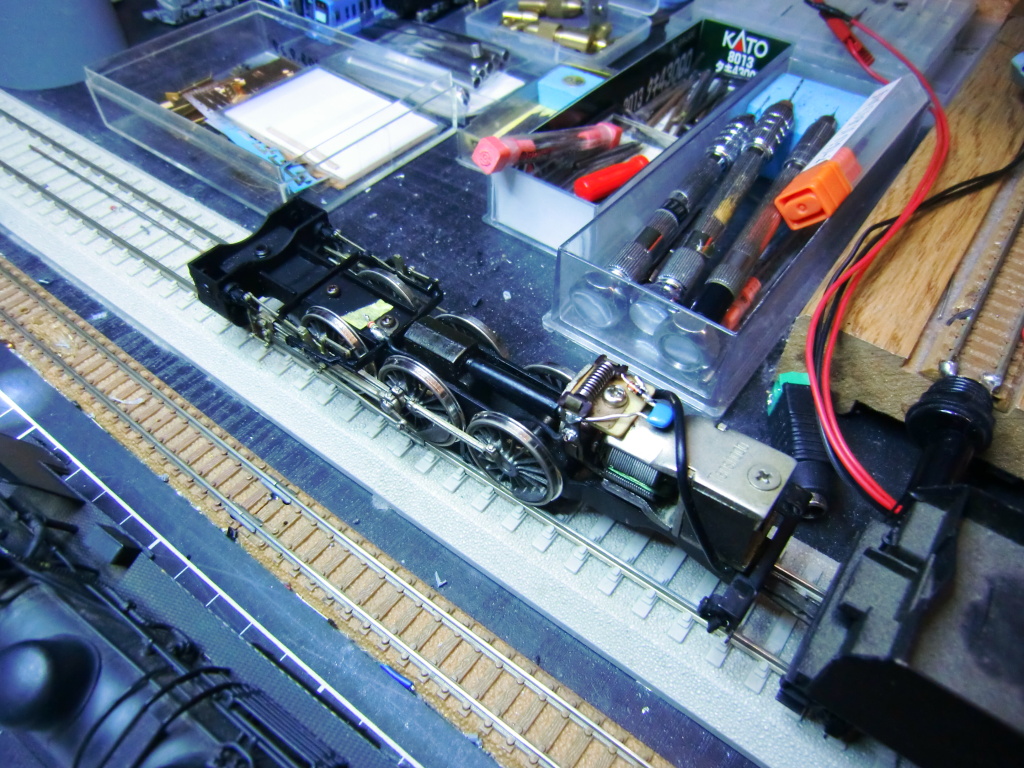
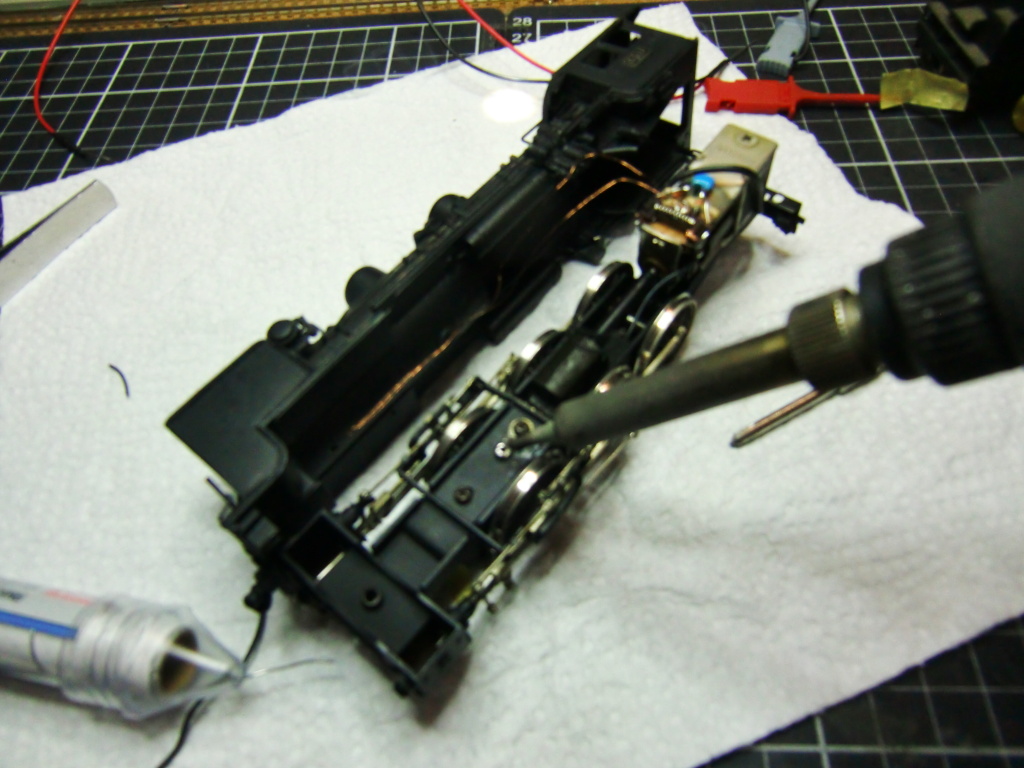
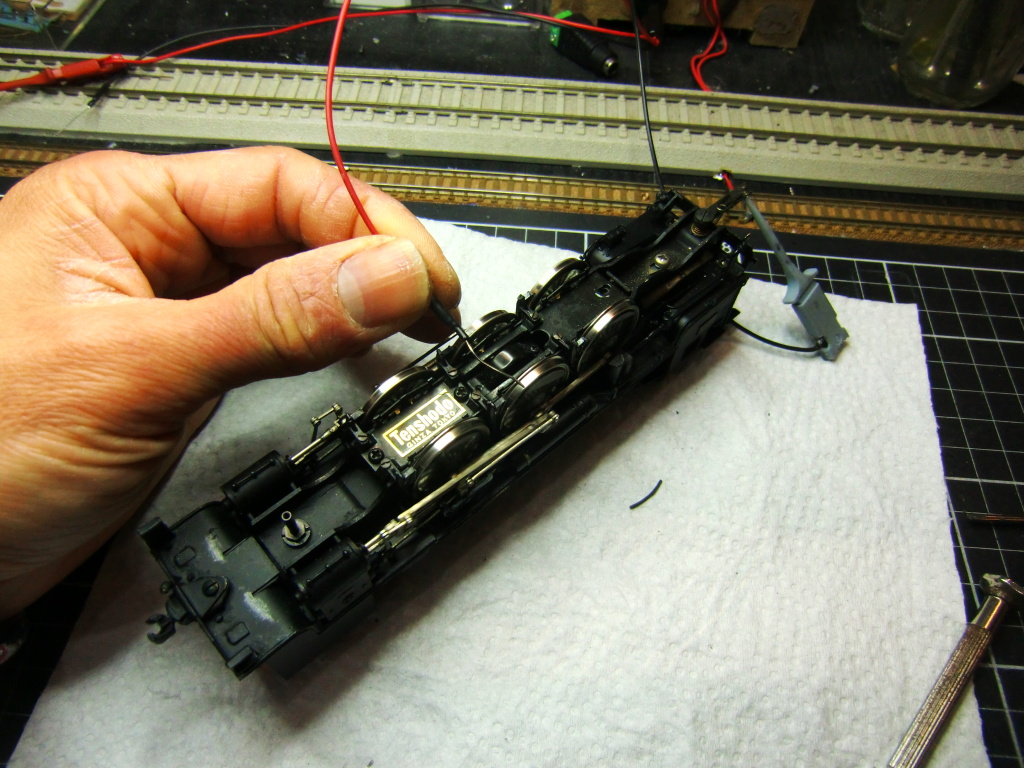




どうにか作業は完了いたしました。当初、半日程度で終わると思って作業にあたりましたが、分解と調整を繰り返すうちに数日程度の時間を要する形となりました。
かんたん貼り付け内装シールと吊皮他、只今制作中でございます。
2023年よりキットおよび車両パーツのラインナップを強化してまいります。順次、「ぴょん鉄ショップよりお知らせ」にてご案内させていただきます。
TOMIX 185系ヘッドマーク光沢化フィルムができました。フィルムは弱粘着で大変貼りやすくなっております。
また、貼る際に失敗しても剥がして簡単に貼り直しが出来ます。

写真ではお伝えするのが難しいお品ですが、ヘッドマーク正面に貼るだけで光沢感のあるヘッドマークとなる光沢フィルムです。厚さもそこそこありますので、大変貼りやすくなっております。
販売価格:2両分(2枚入り)・・330円(税込)
貼り付けのご依頼をご希望の場合は、「150円/両」でお受けしております。
▼お客様ご自身で貼る場合について
①貼り付け面の汚れを充分落とします。
②ピンセットでフィルムの隅を軽く持ち、ヘッドマークの上に載せます。この時、ピンセットで強く挟みすぎるとフィルムに傷がつきますので、軽く挟みましょう。
③位置に問題なければ、小さい綿棒などで軽く押して定着させます。あまり強い力でゴシゴシやらなくてもフィルムは付きますので大丈夫です。
今回のご相談は、こちらの機関車を走行させると頻繁にコントローラーのブレイカーが作動してしまうといったものです。





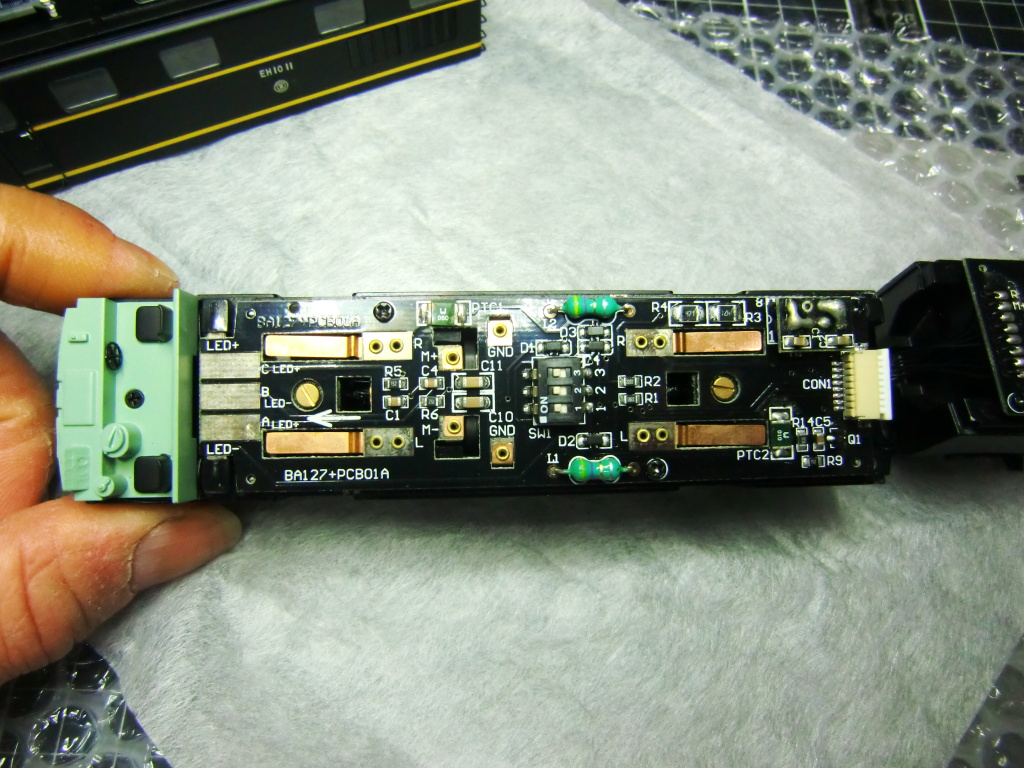
基盤には意外とたくさんの部品が付いています。※1側
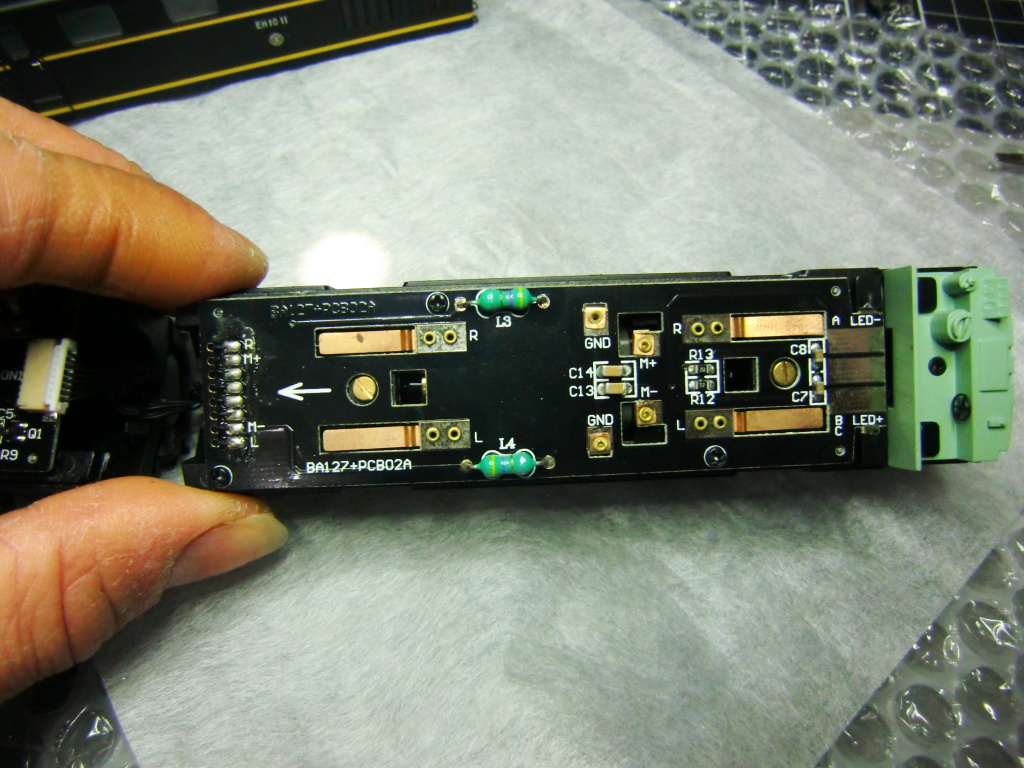
こちらは2側ですが、1側から8本のケーブルがつながれてきています。このあたりも1つ1つ追っていく必要がありそうです。
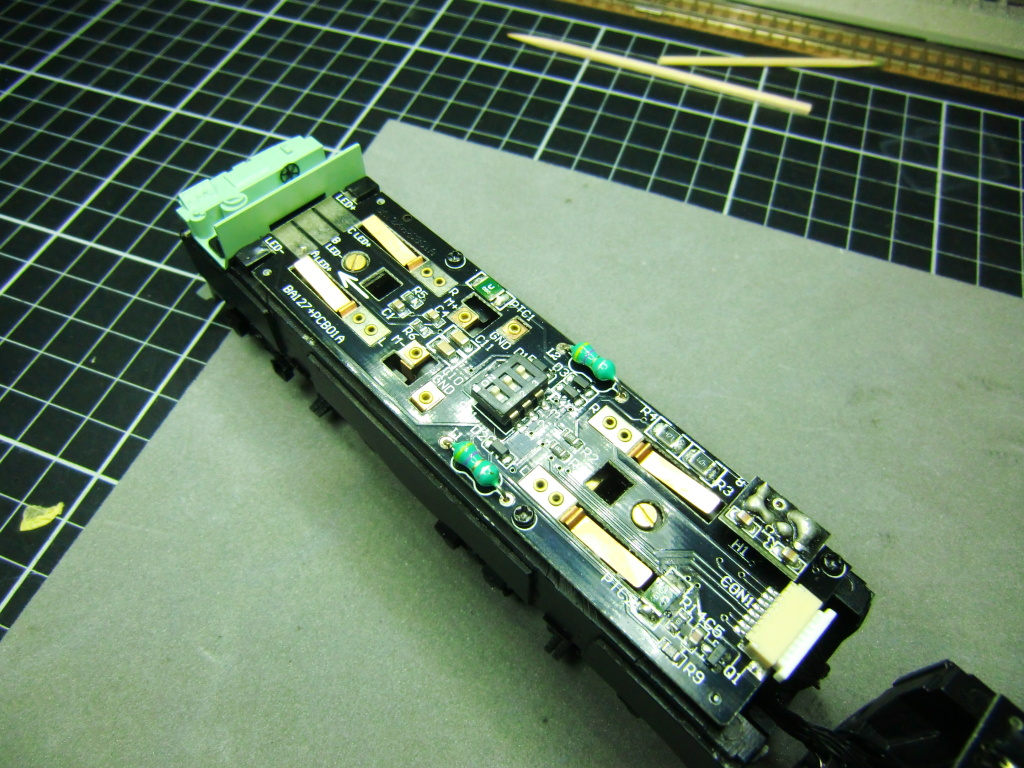
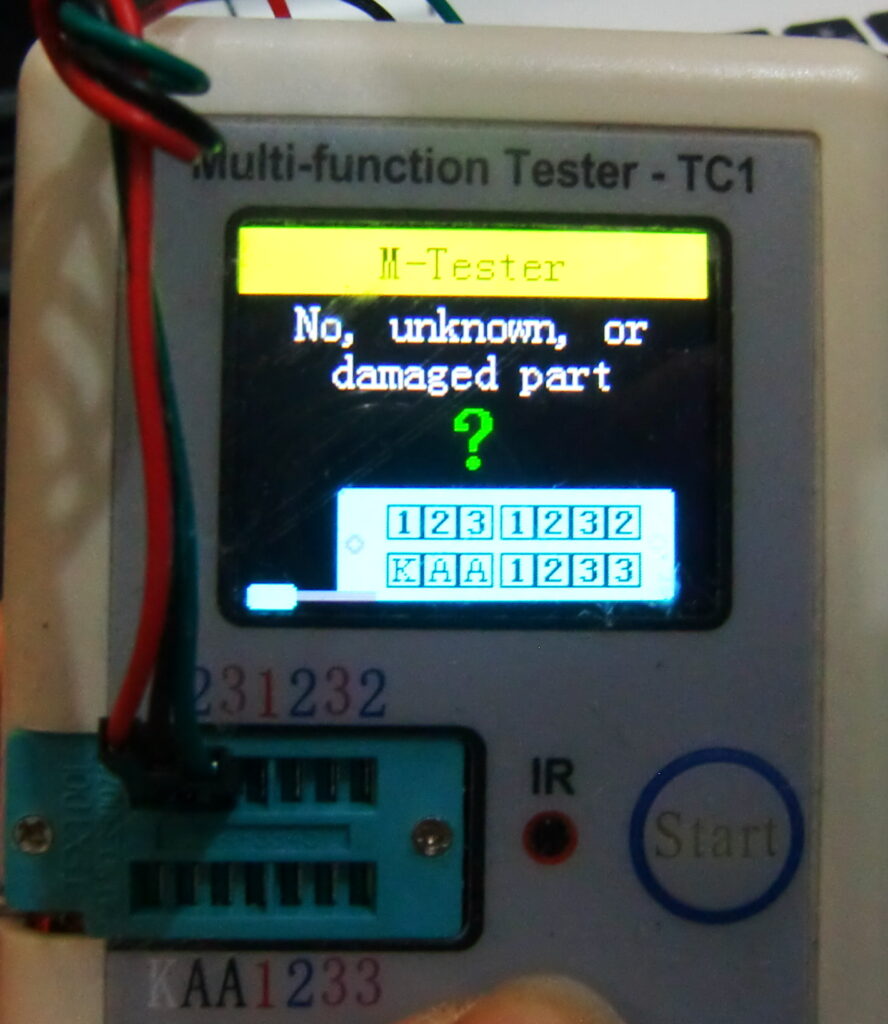
M-TESTERを使い、セラミックコンデンサー他、個々の部品に問題がないかを1つずつチェックしていきます。

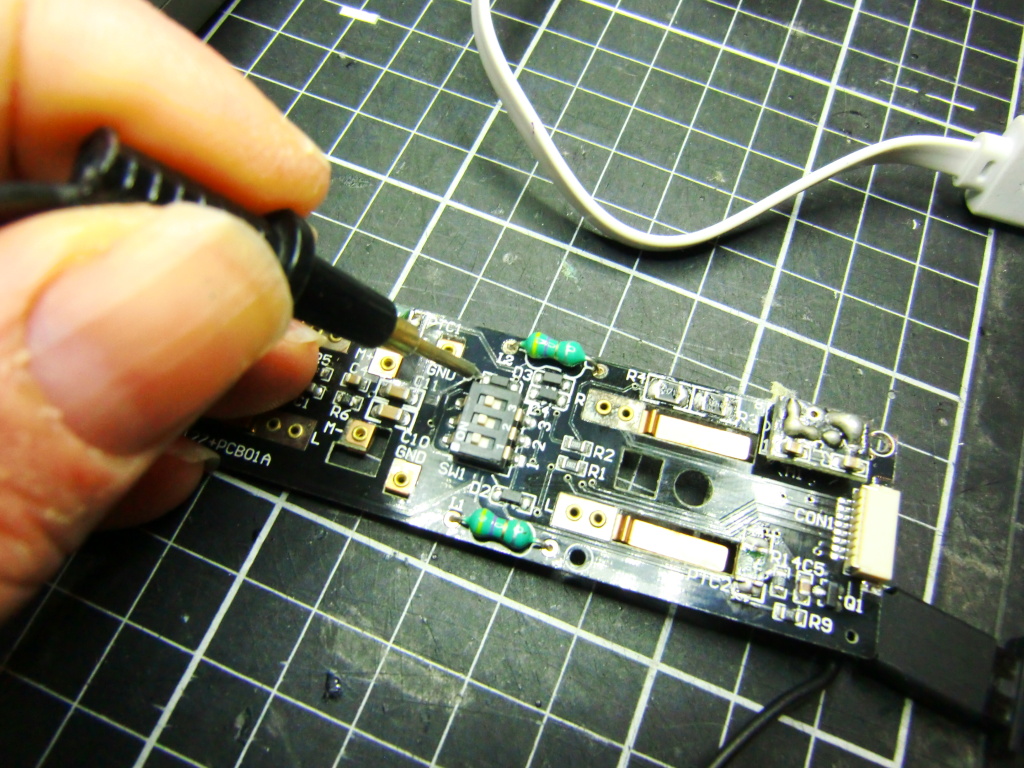

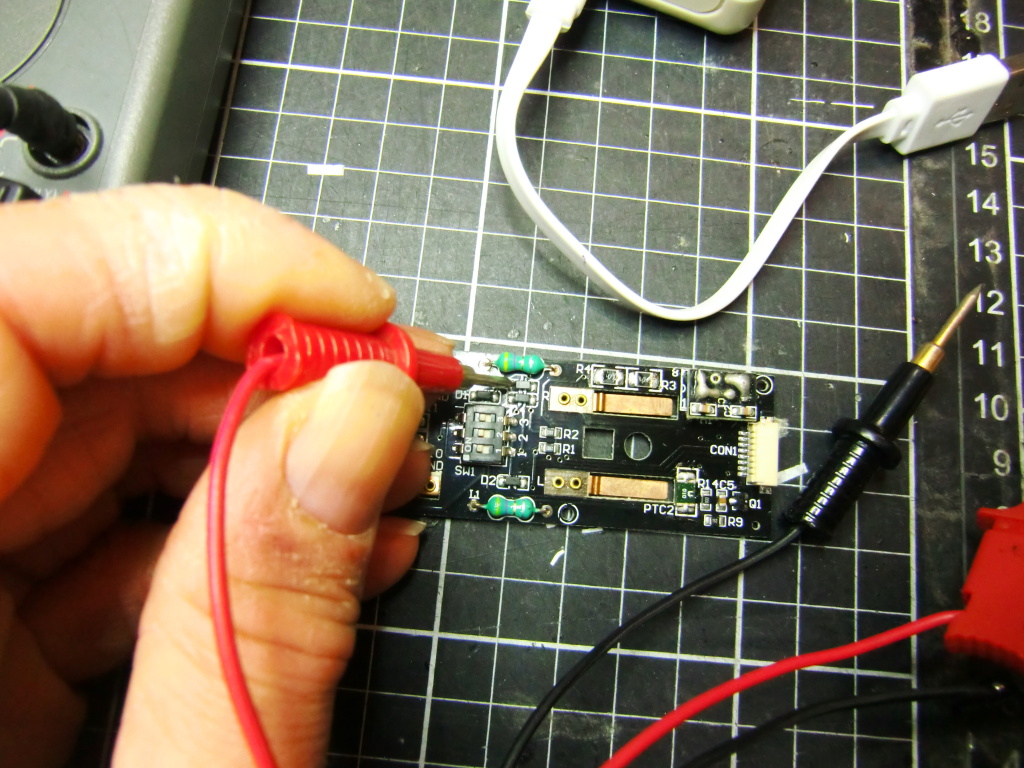
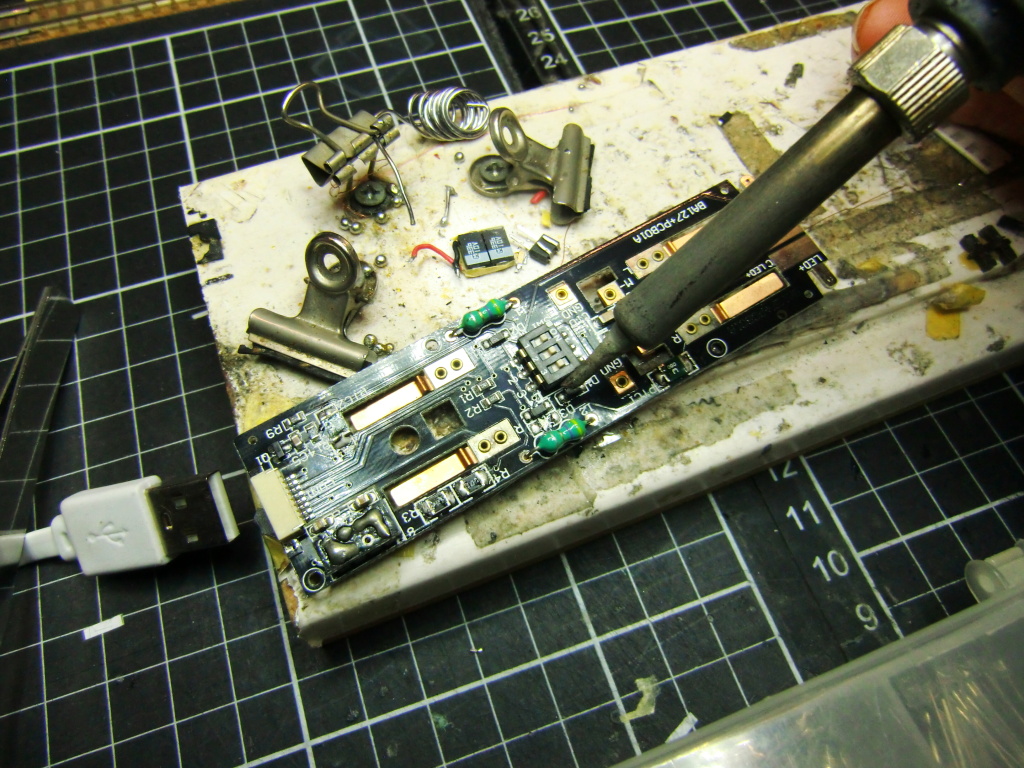
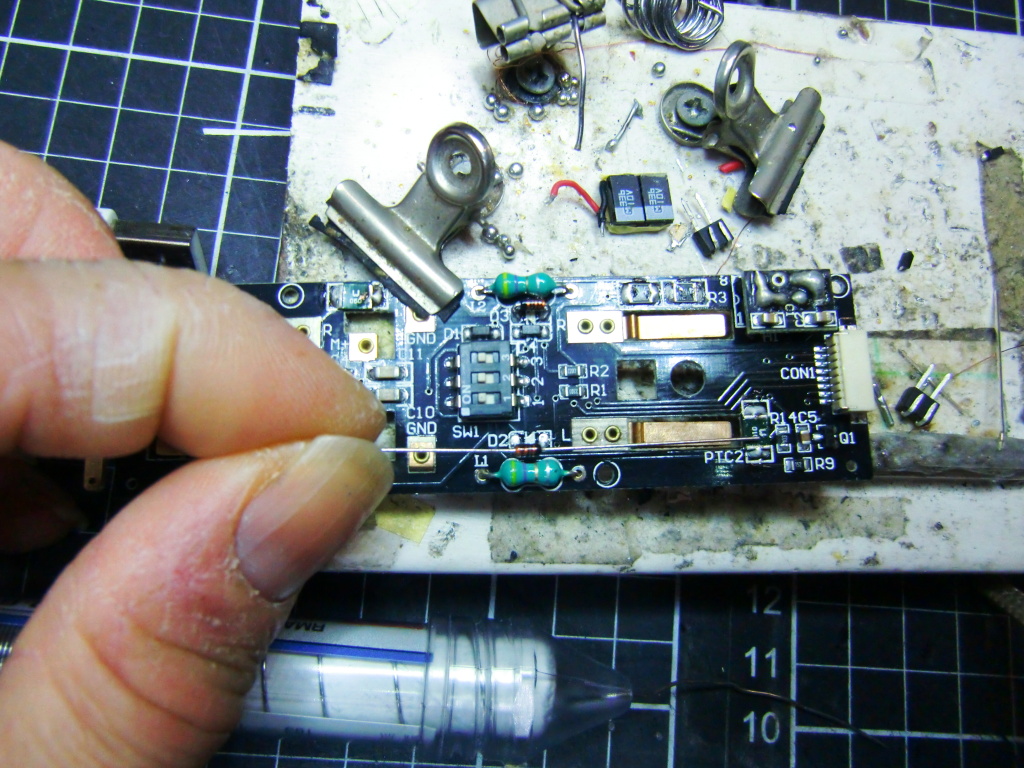
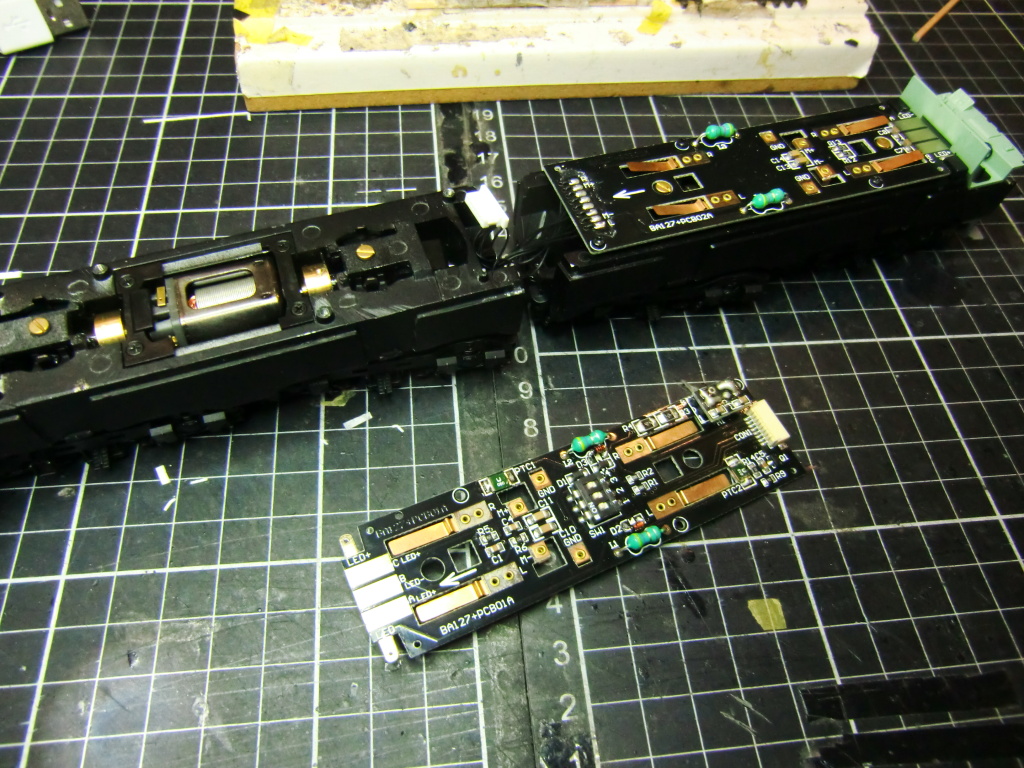
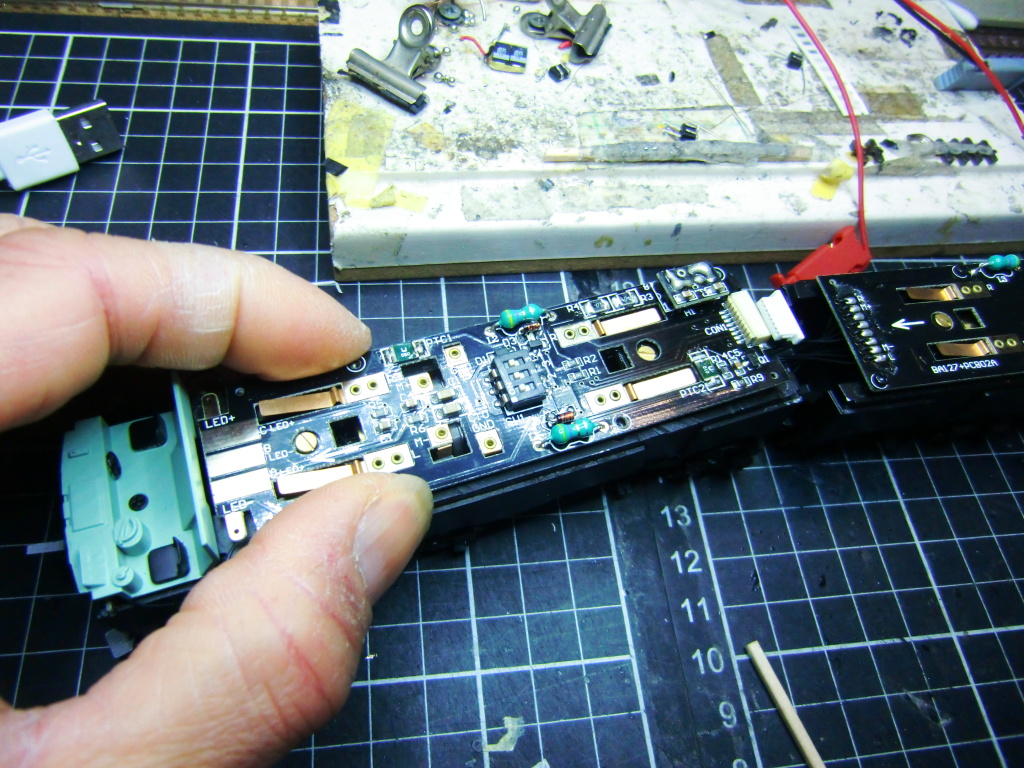
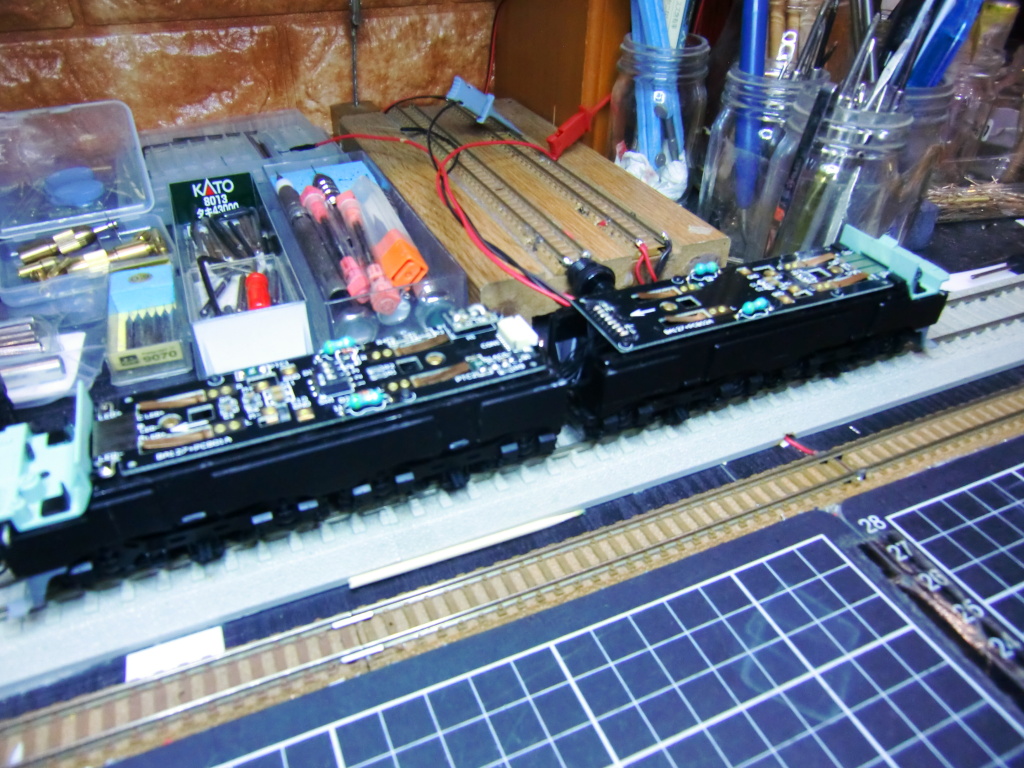
回路から不具合となりうる箇所にあたりをつけて、一通り部品のチェックと交換を行いました。
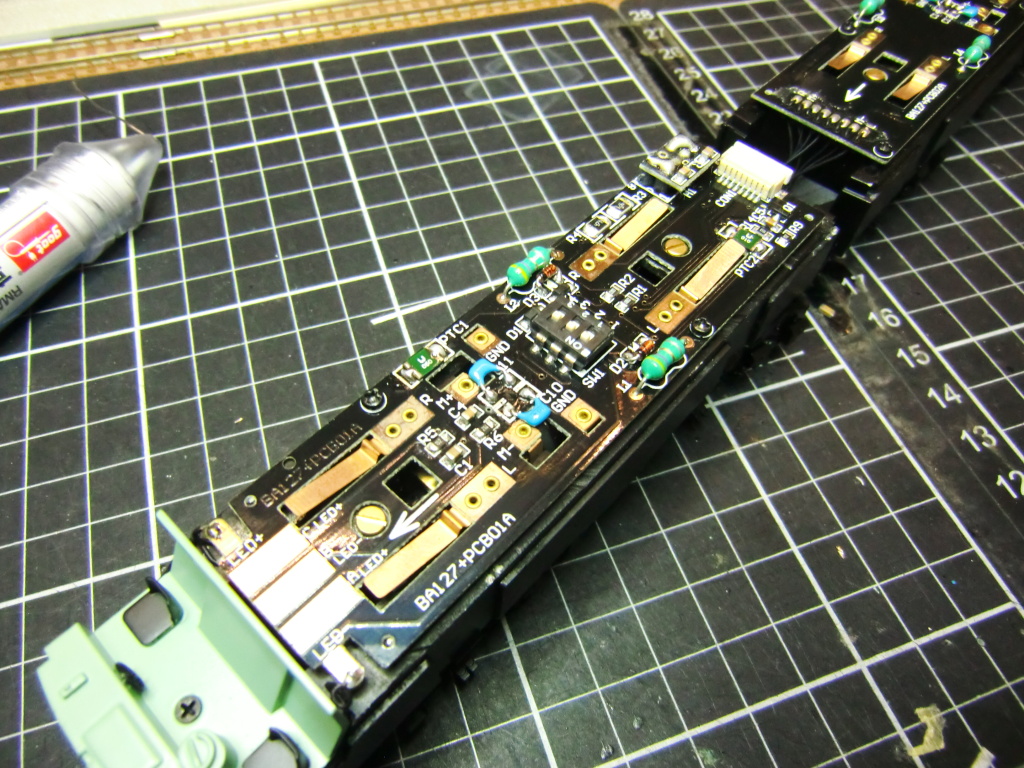
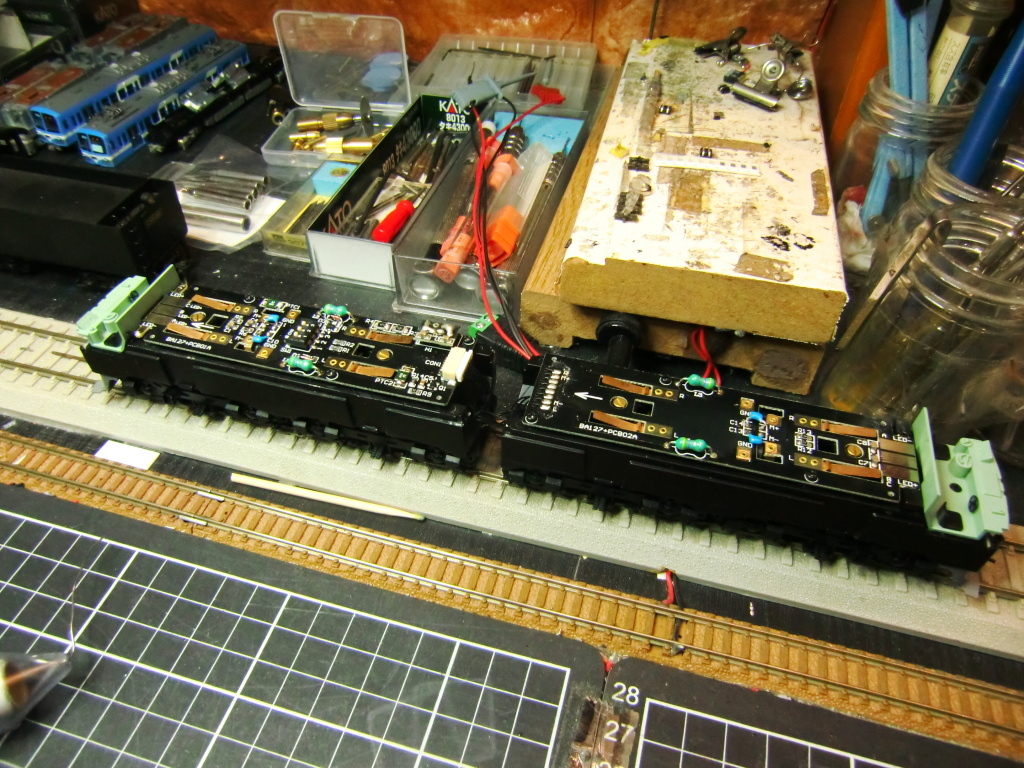
最後に動作に問題がないか時間をかけて確認していきます。


作業完了でございます。
さて、今回の作業では現状からのヘッドおよびテールの明るさアップ加工でございます。
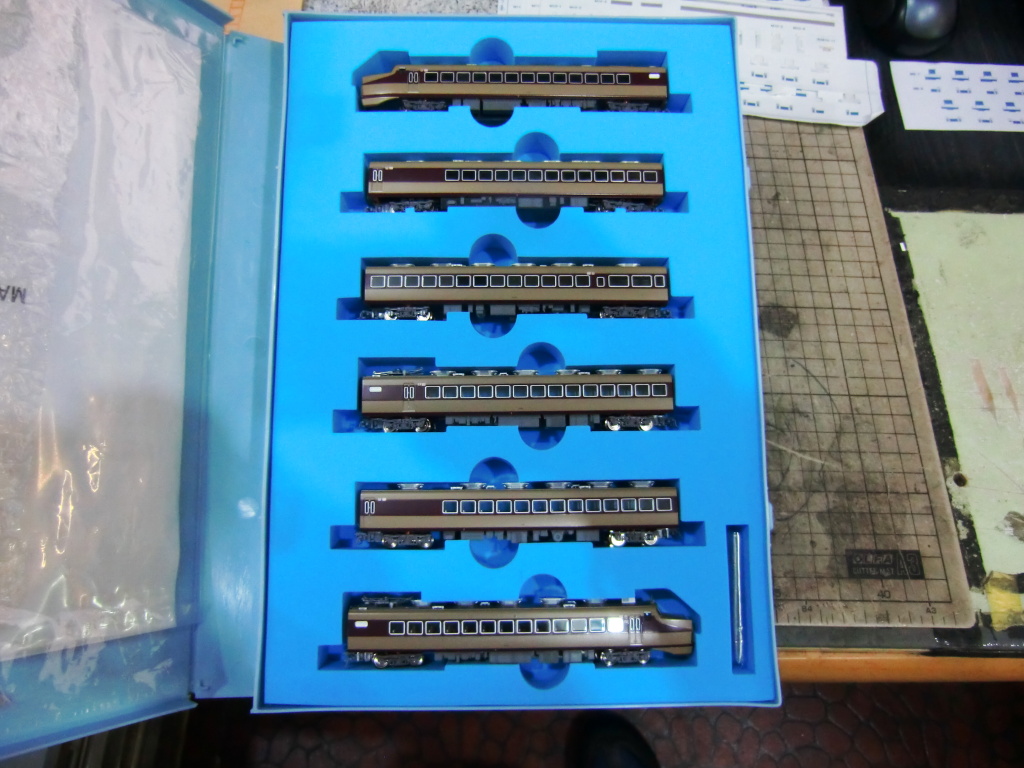

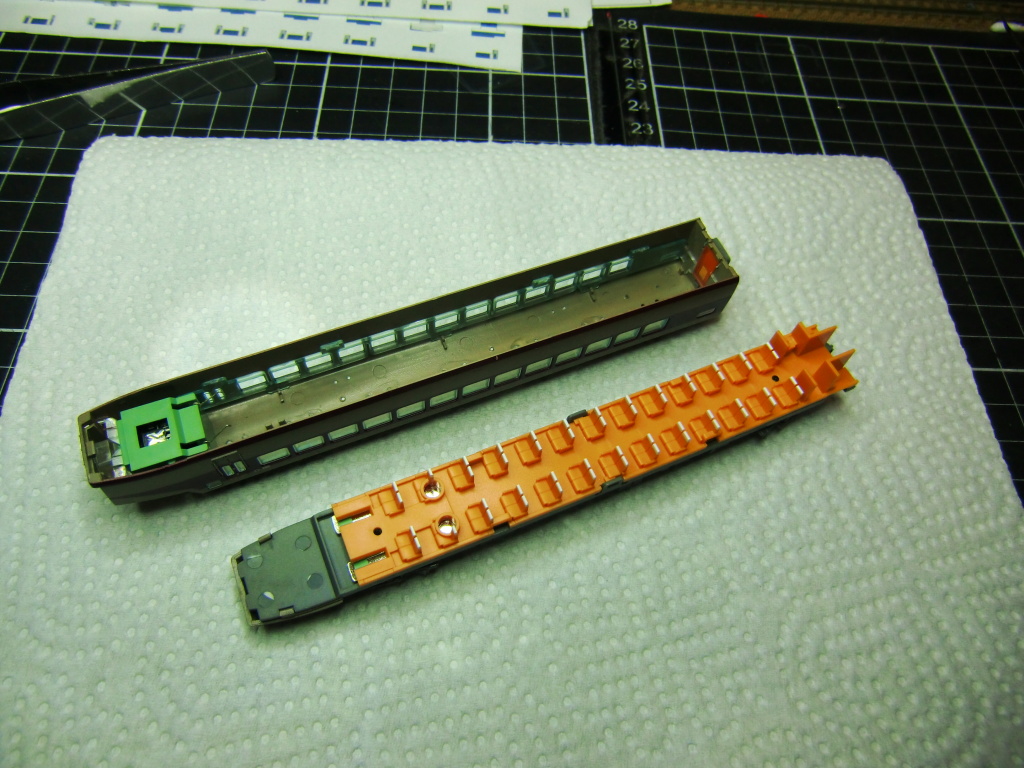
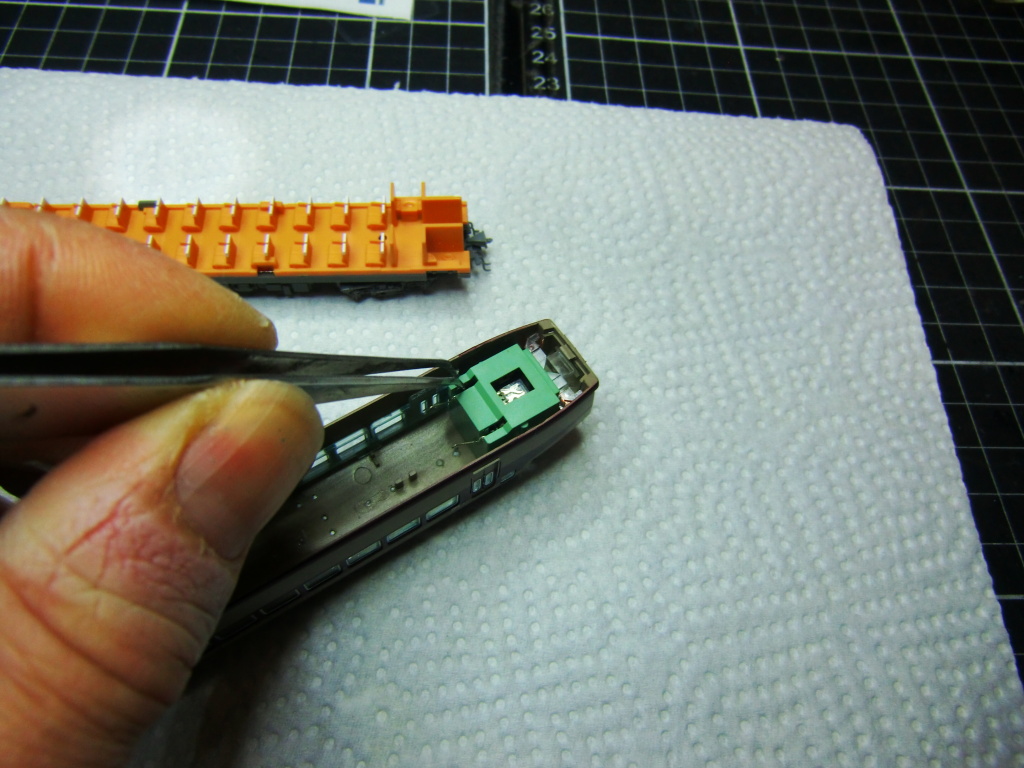

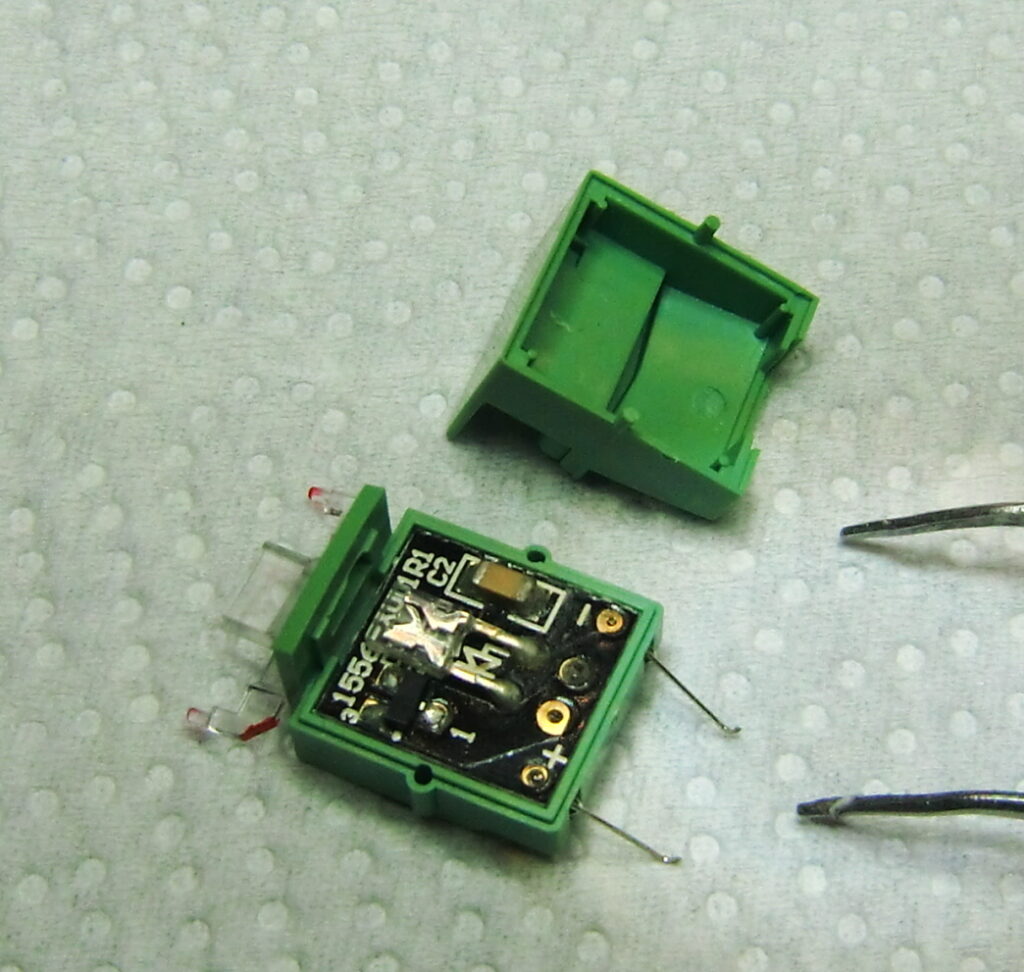
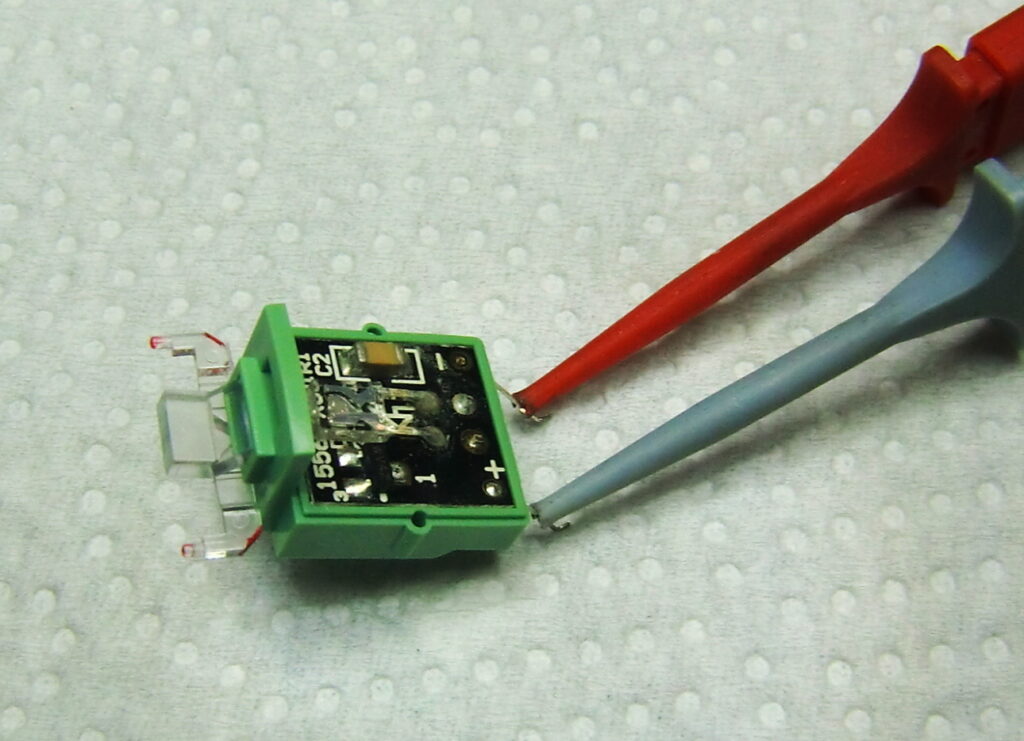
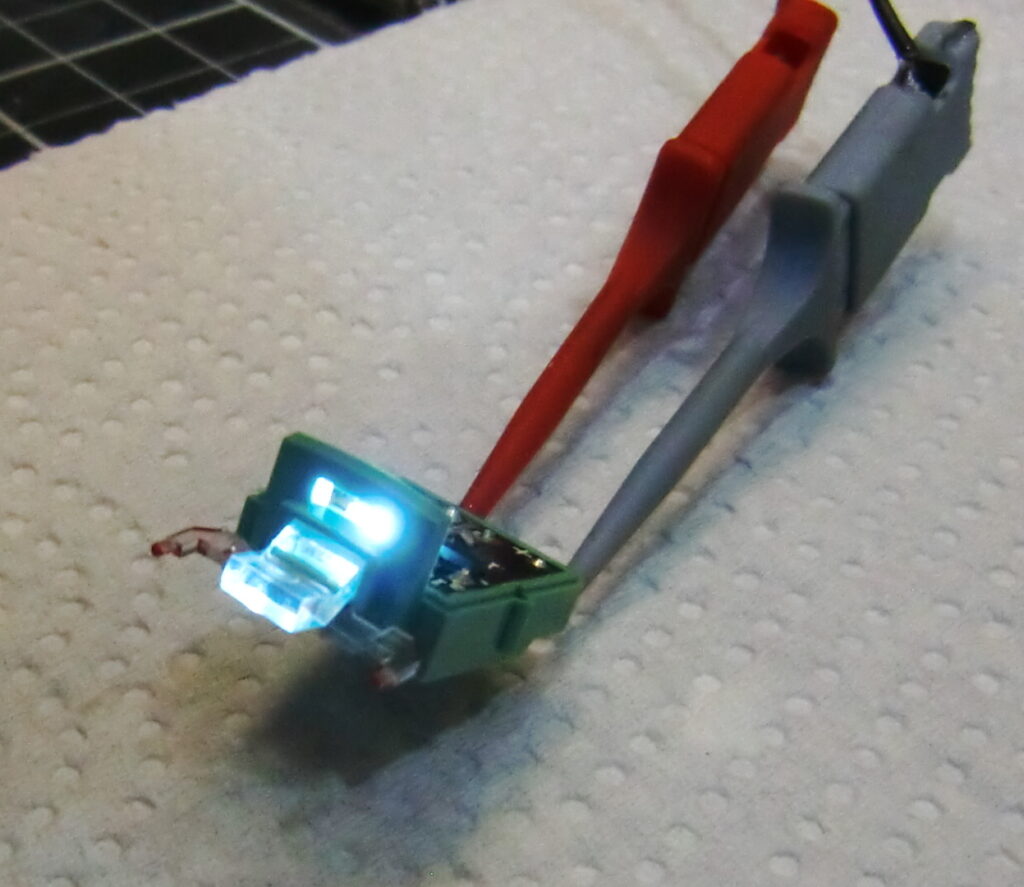
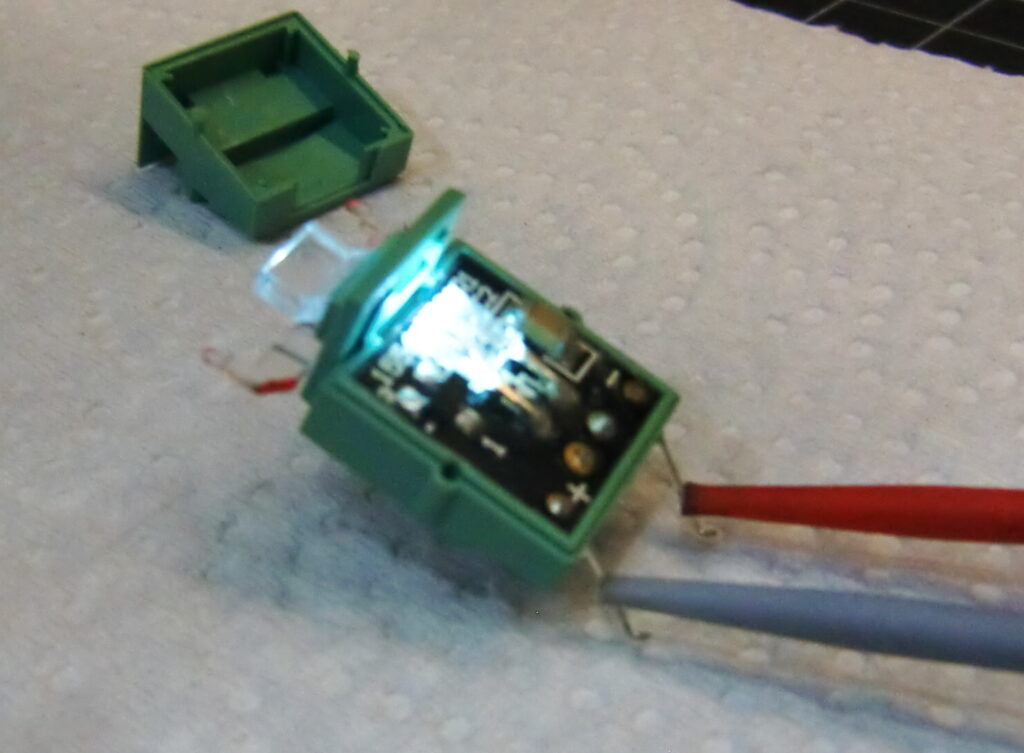
今回の作業では、一般加工で対応できそうです。また、抵抗値をやや下げて560オームとします。


良さそうです。


▼カプラー短縮化
ぴょん鉄カプラー短縮化パーツを組み込んでいます。

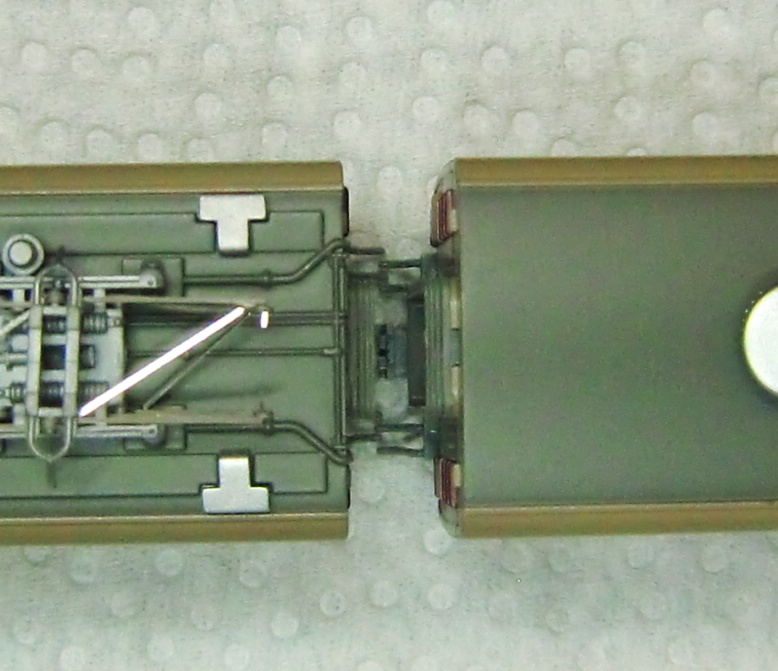

作業完了でございます。
現状では、速度がまったくでない状況でございます。


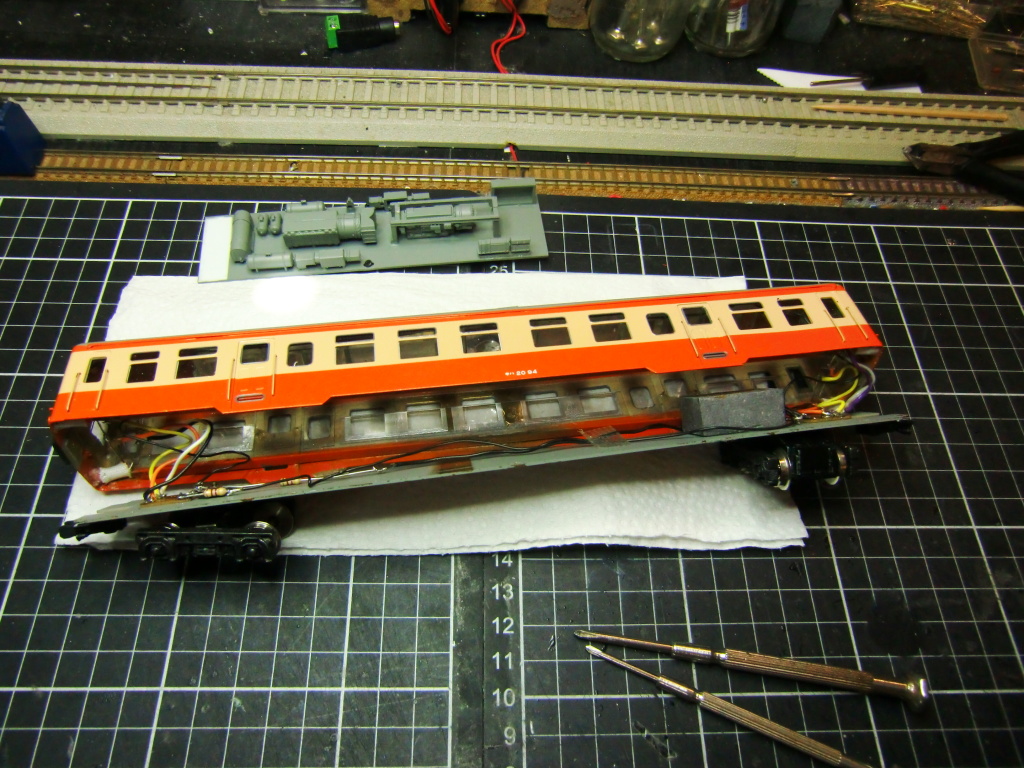
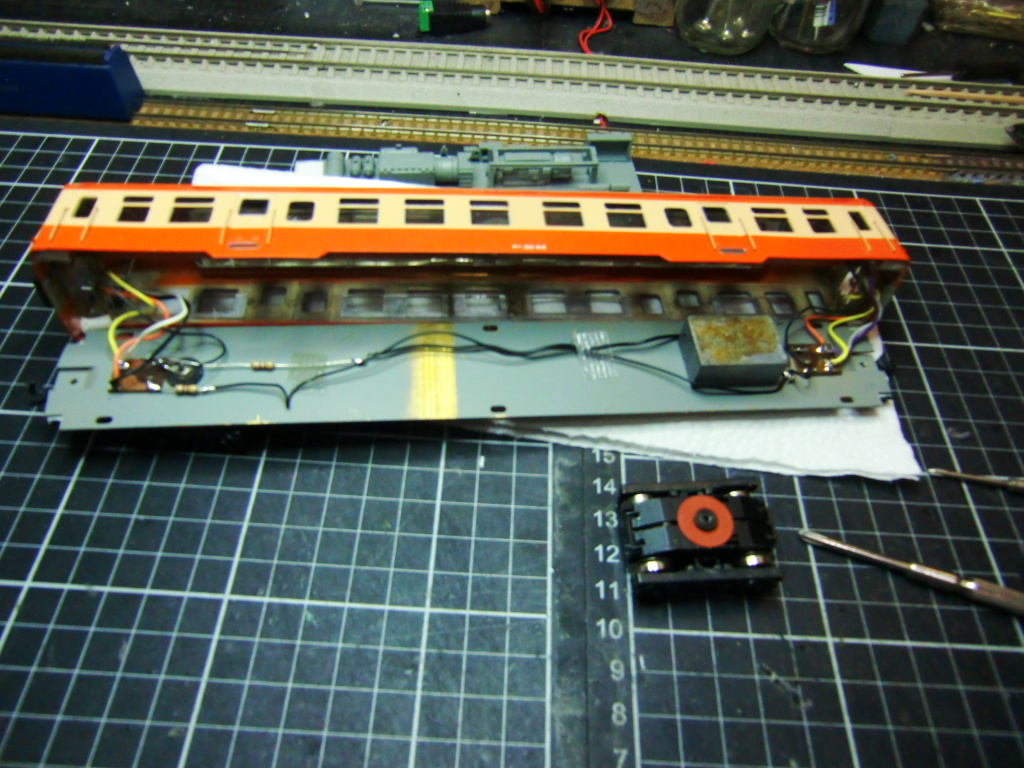
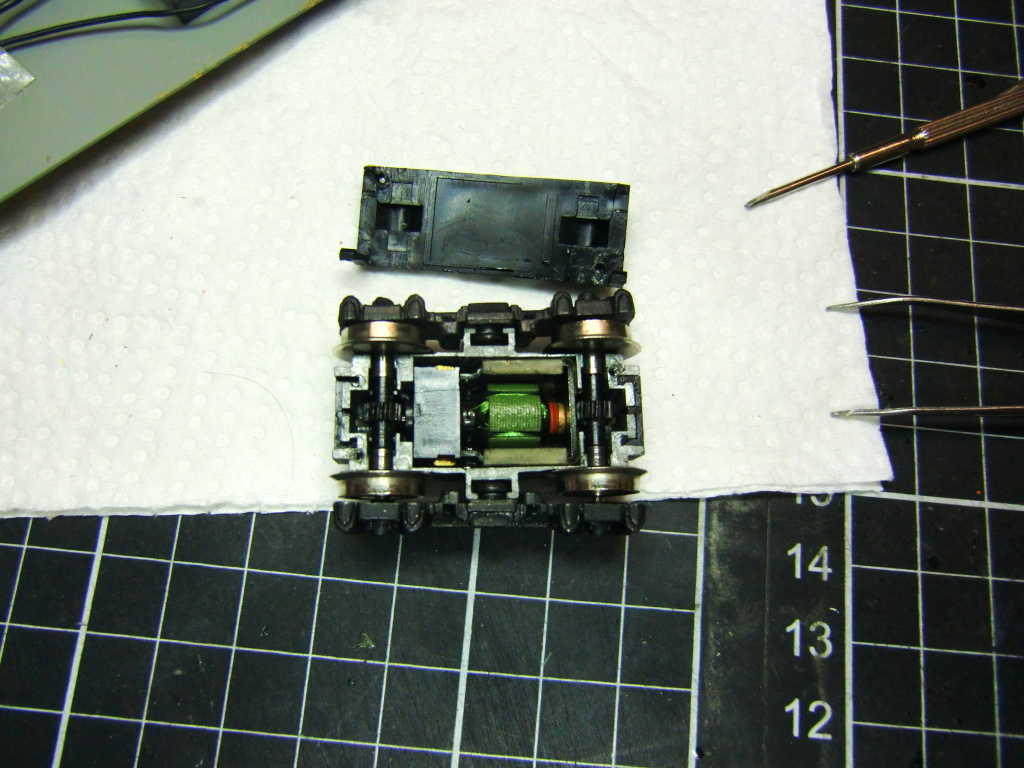
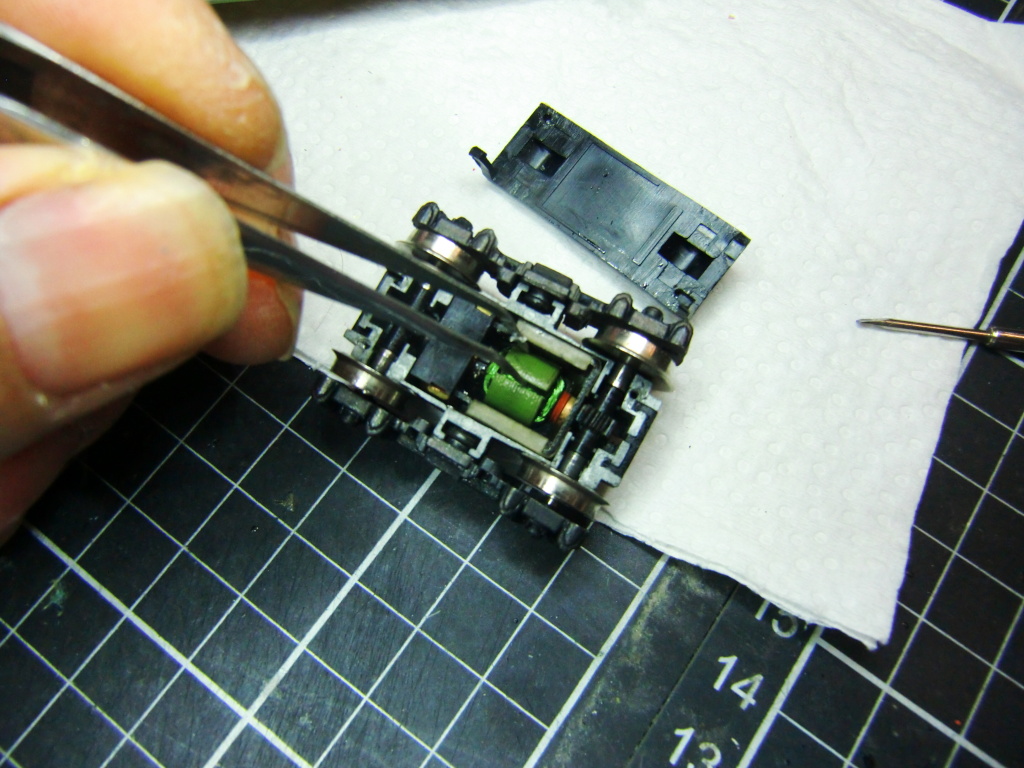
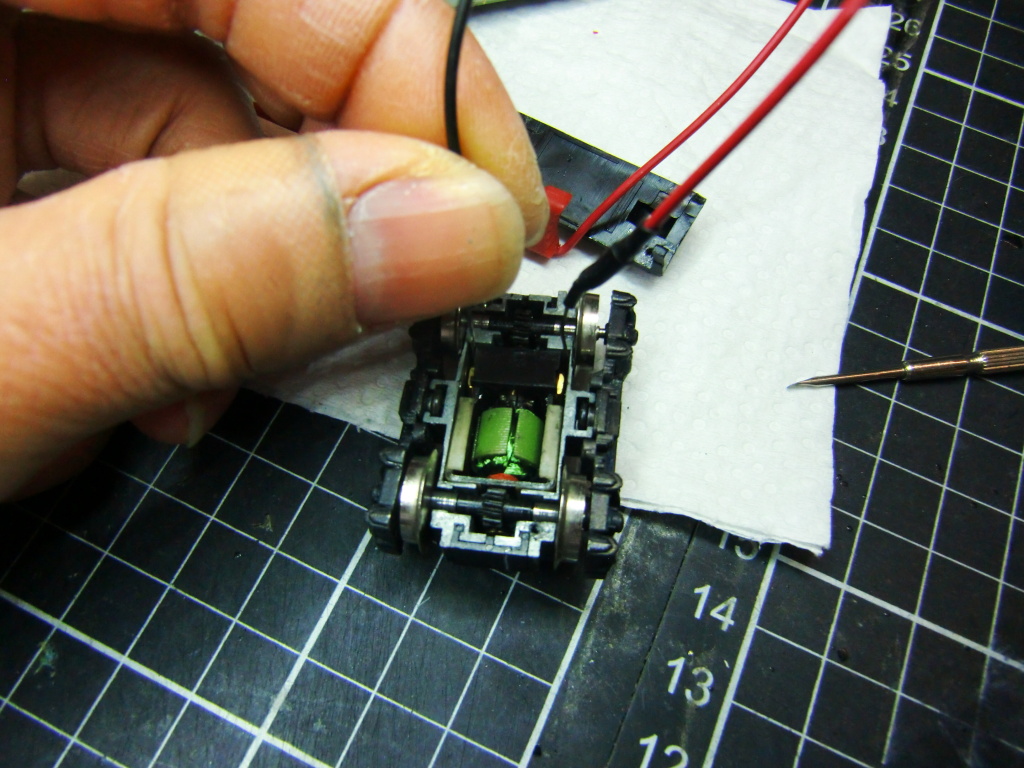
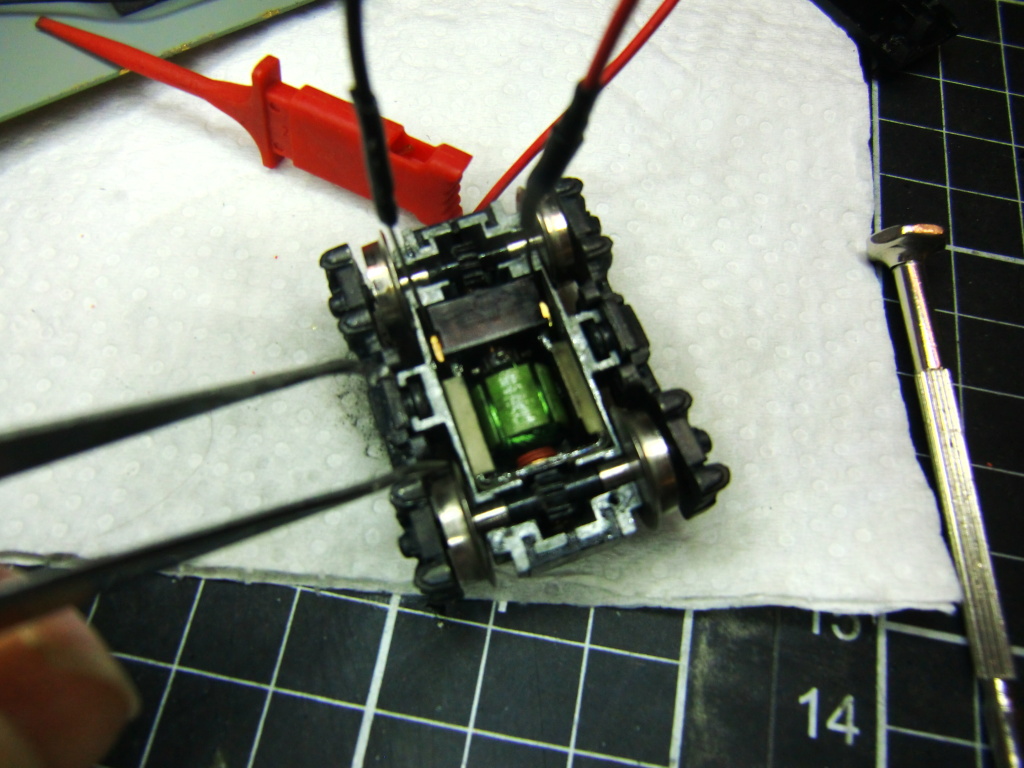
モーターの本来のパワーが全然出ません。
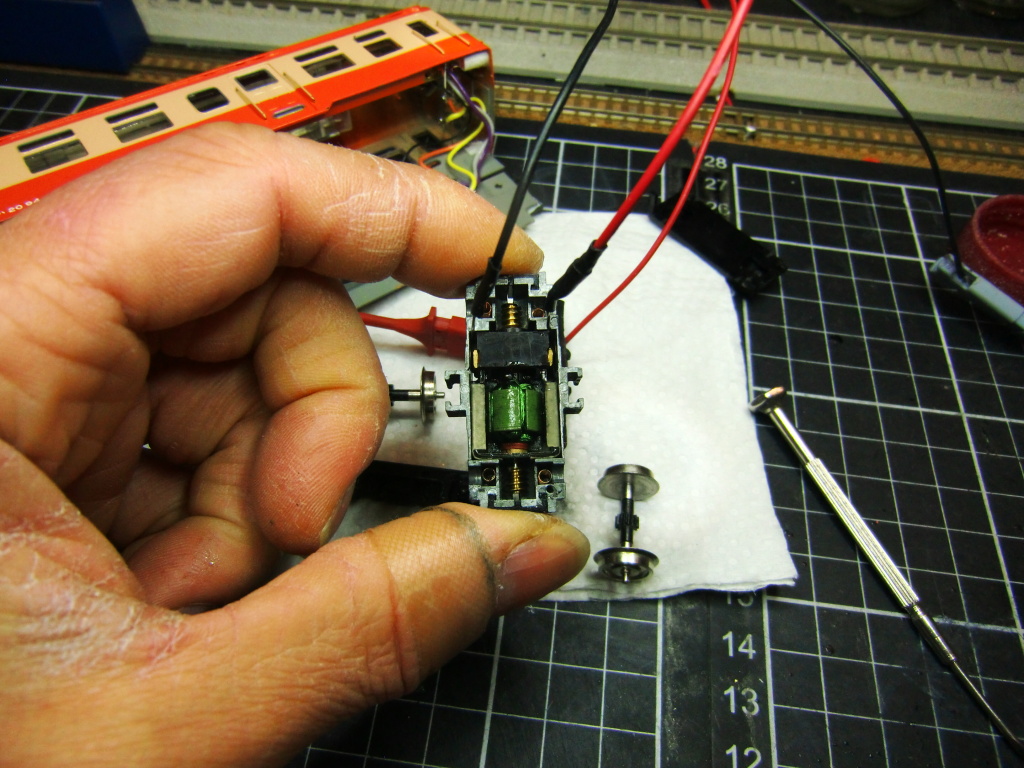
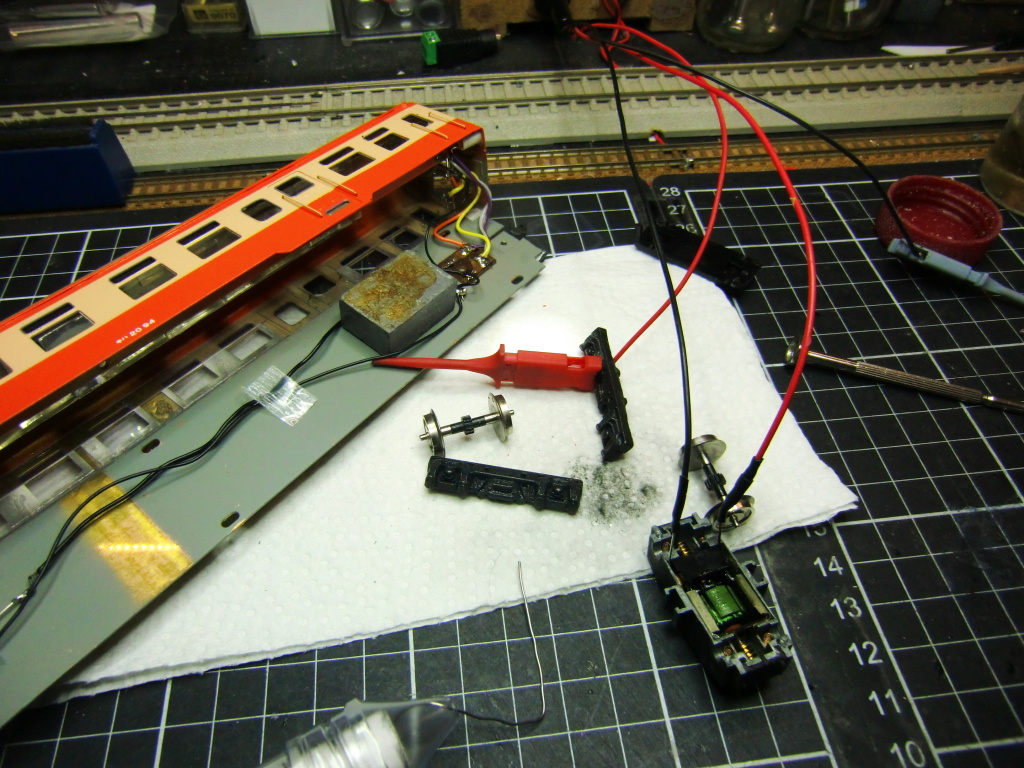
ローターコイルの線が焼き切れているようです。そのため、本来のパワーの半分以下のパワーしか出ていません。
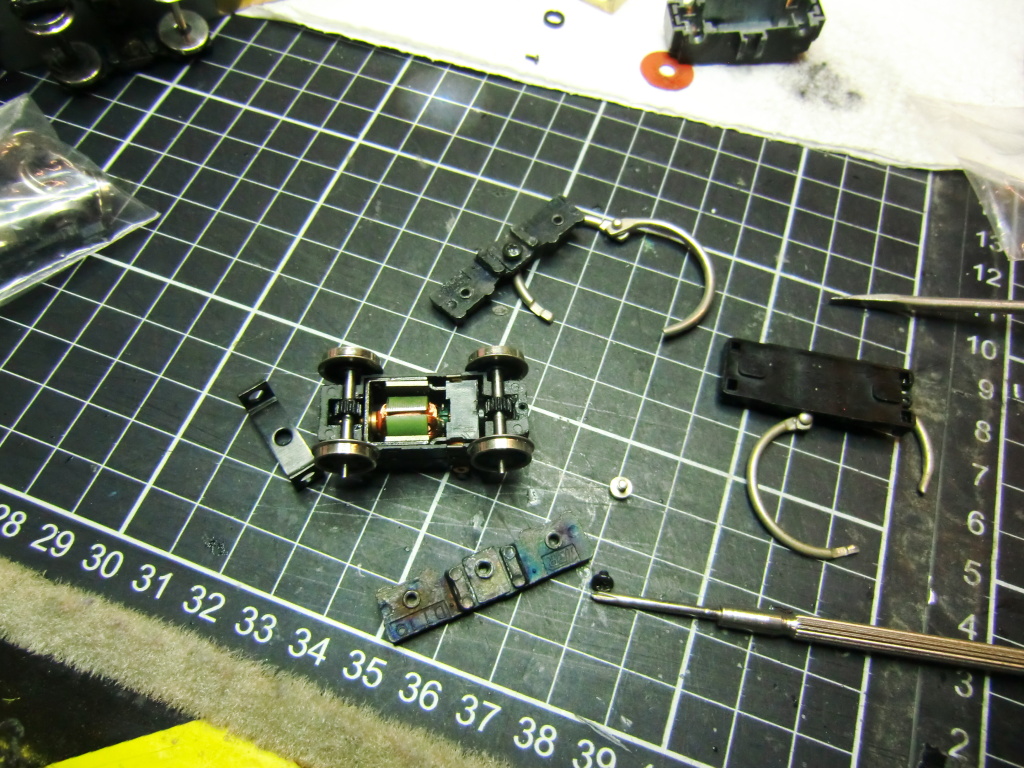
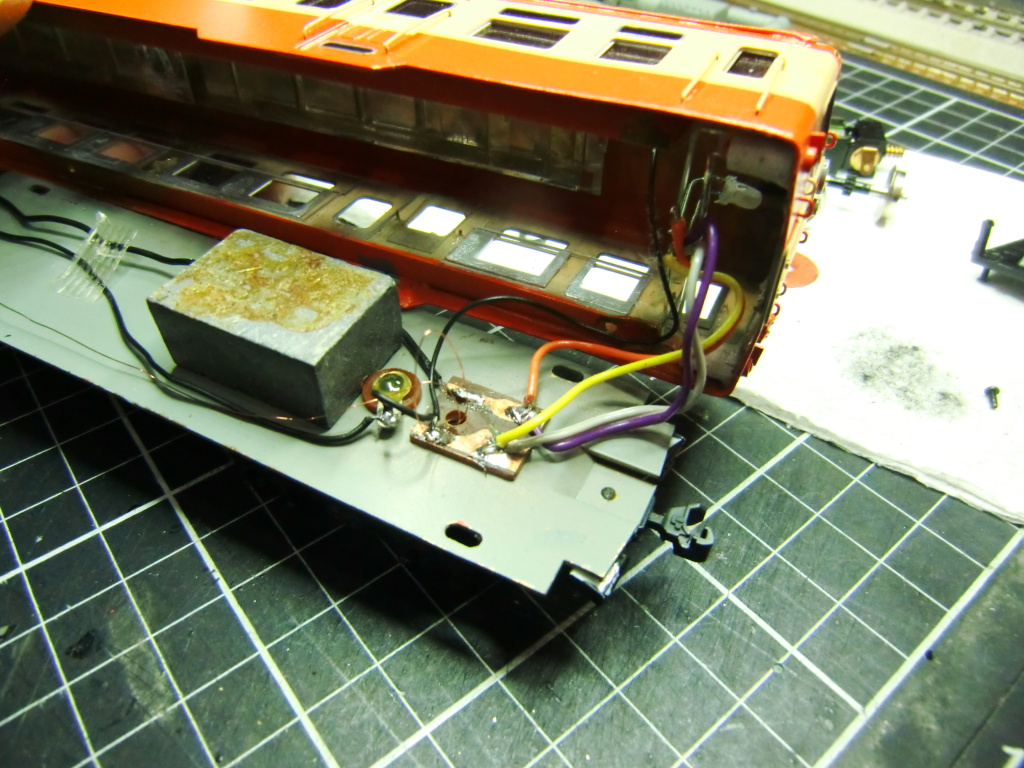
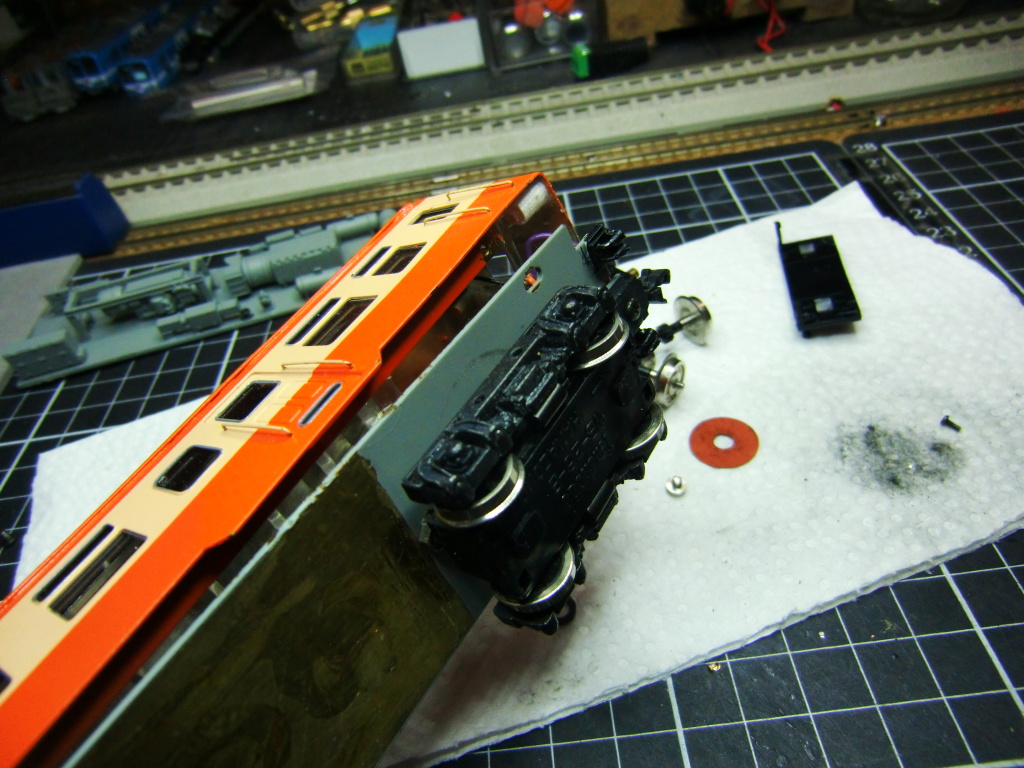
床下に3mm程度穴あけを行い、新たに取り付けたモーターを基盤に配線していきます。その後、各部のO/Hを行い調整していきます。また、台車の極性がかわらないように回転止めのパーツを床下に追加しておきます。
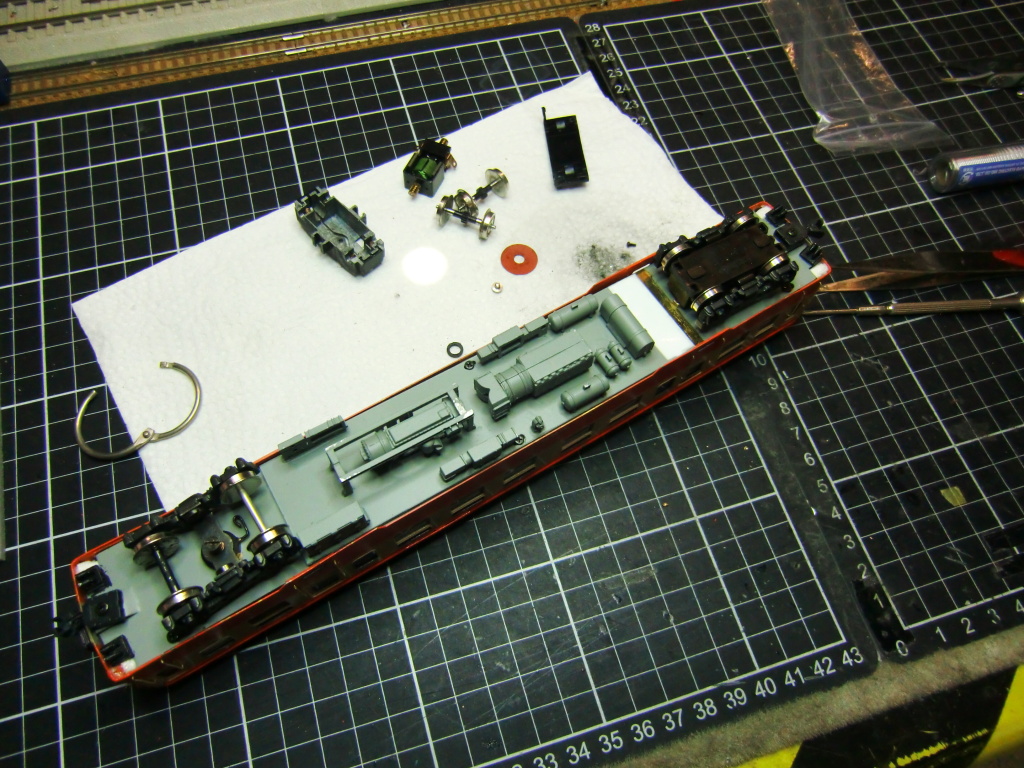
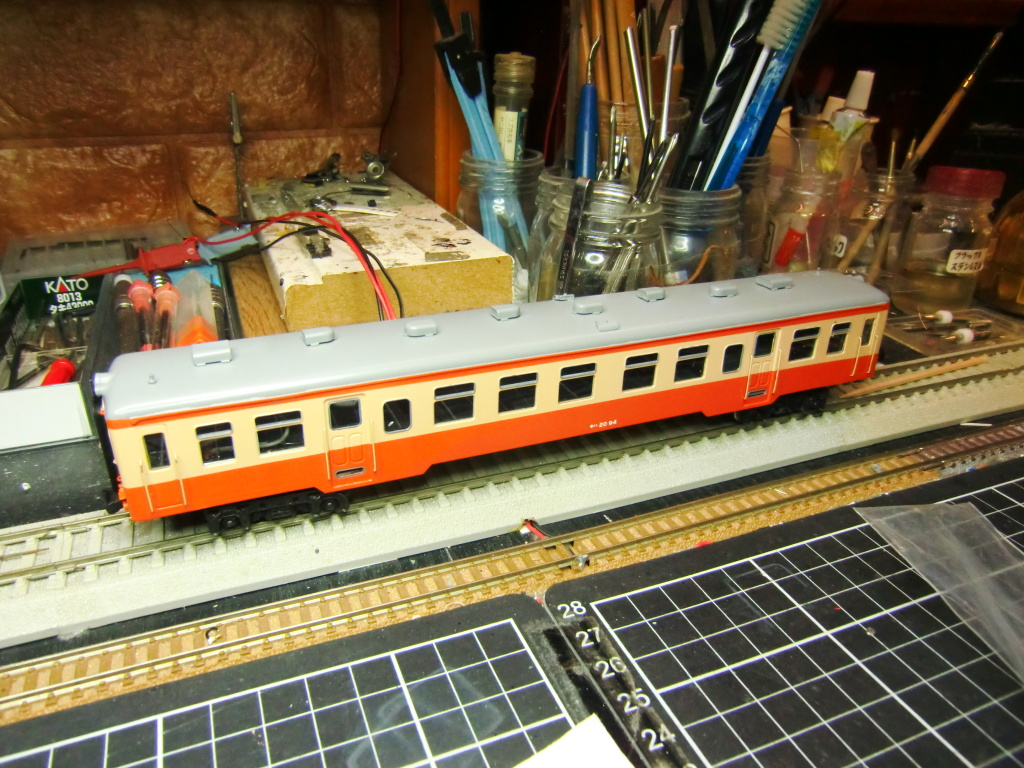



作業完了でございます。


加工前は上のような感じです。
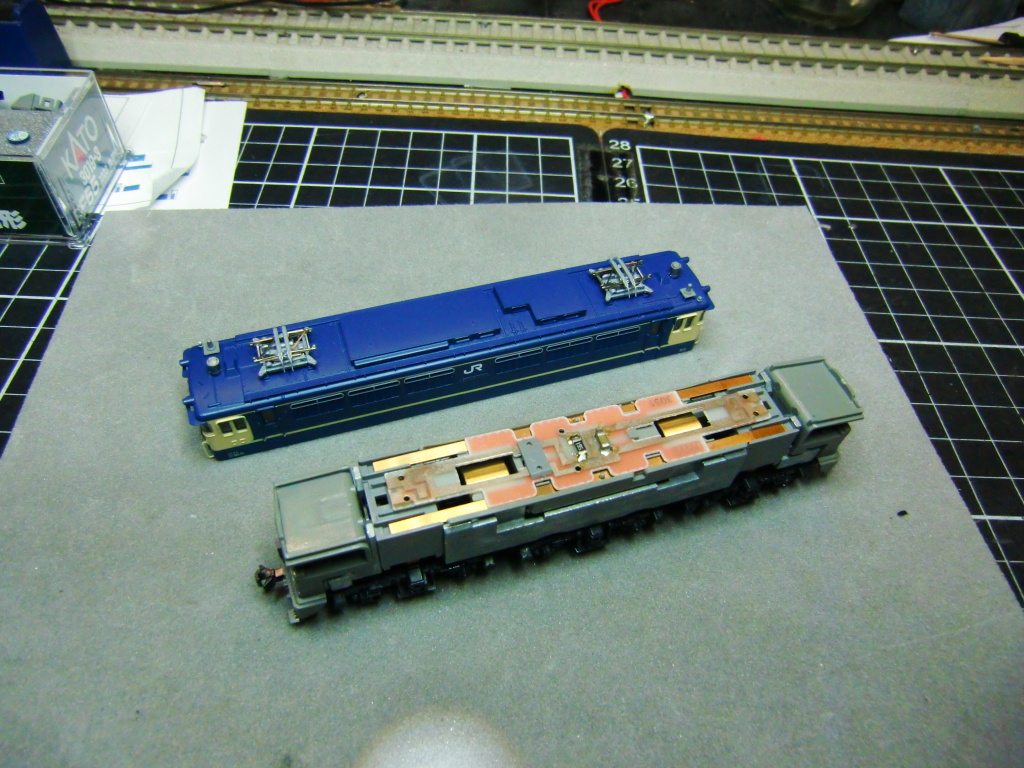
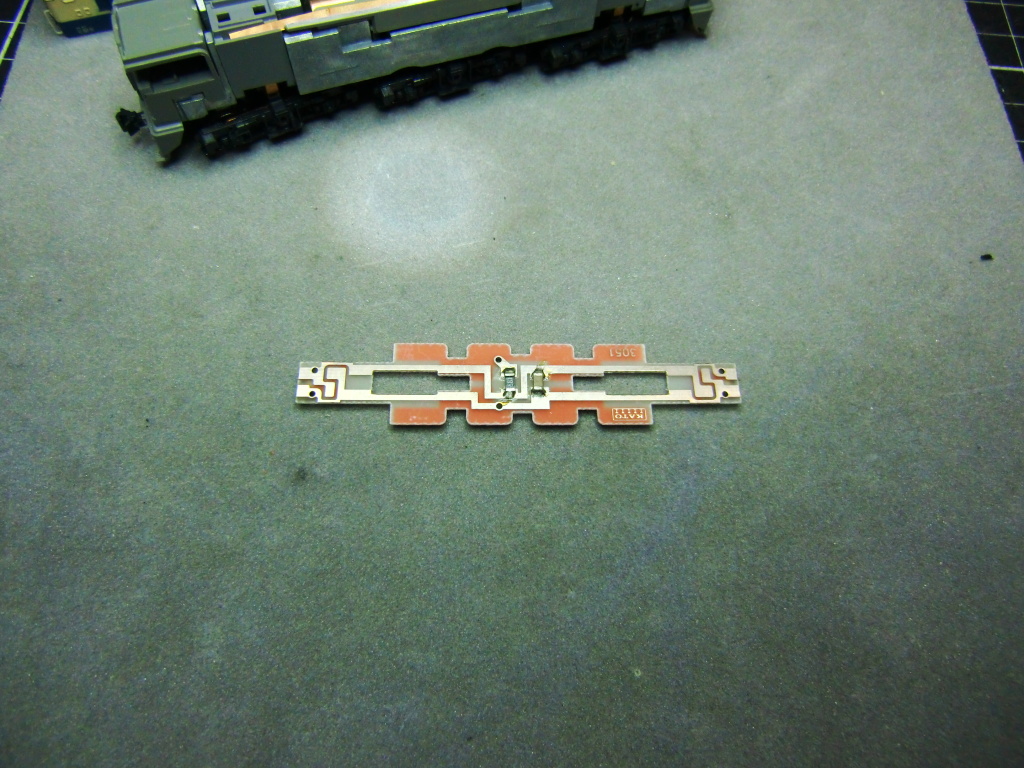

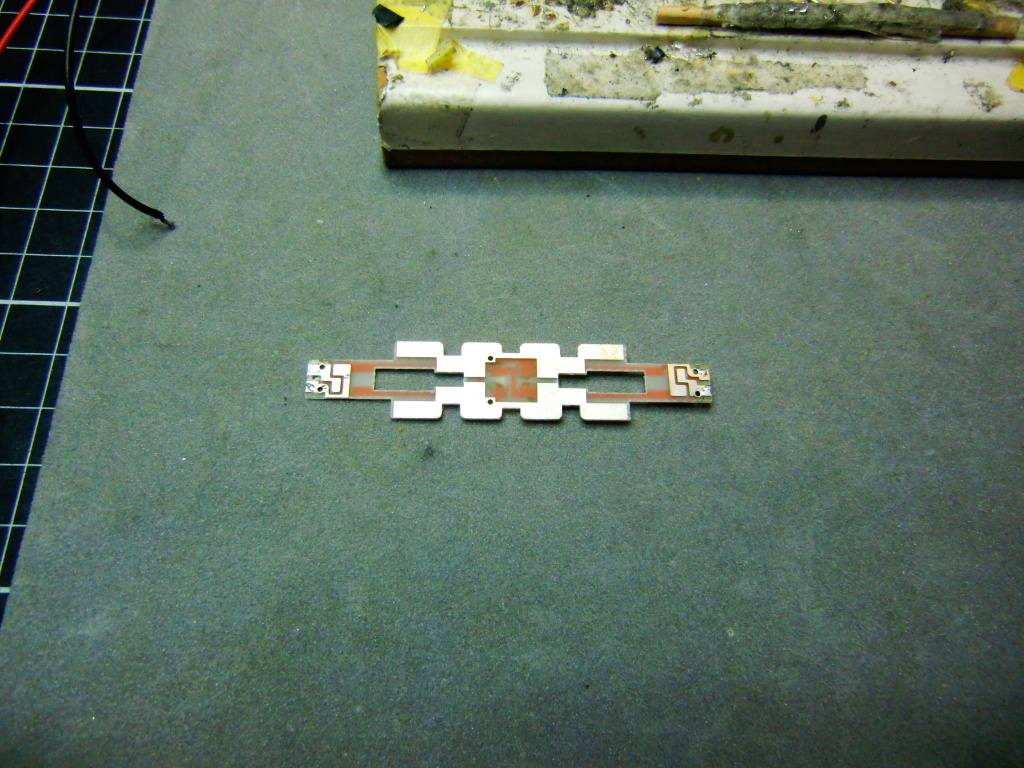
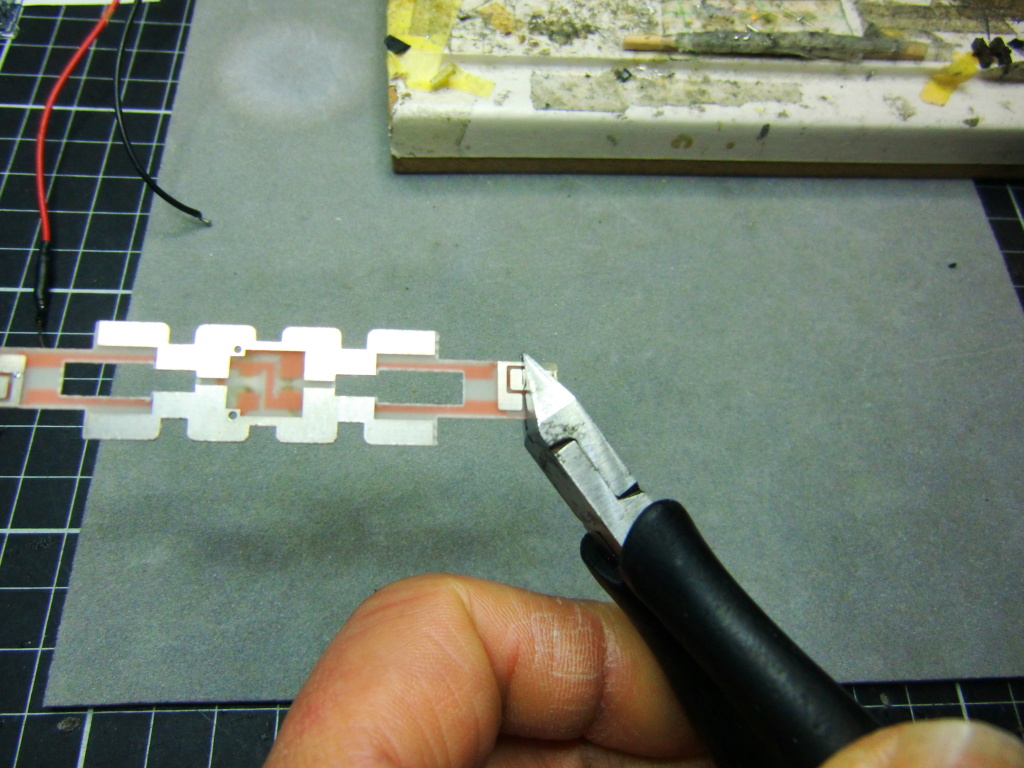
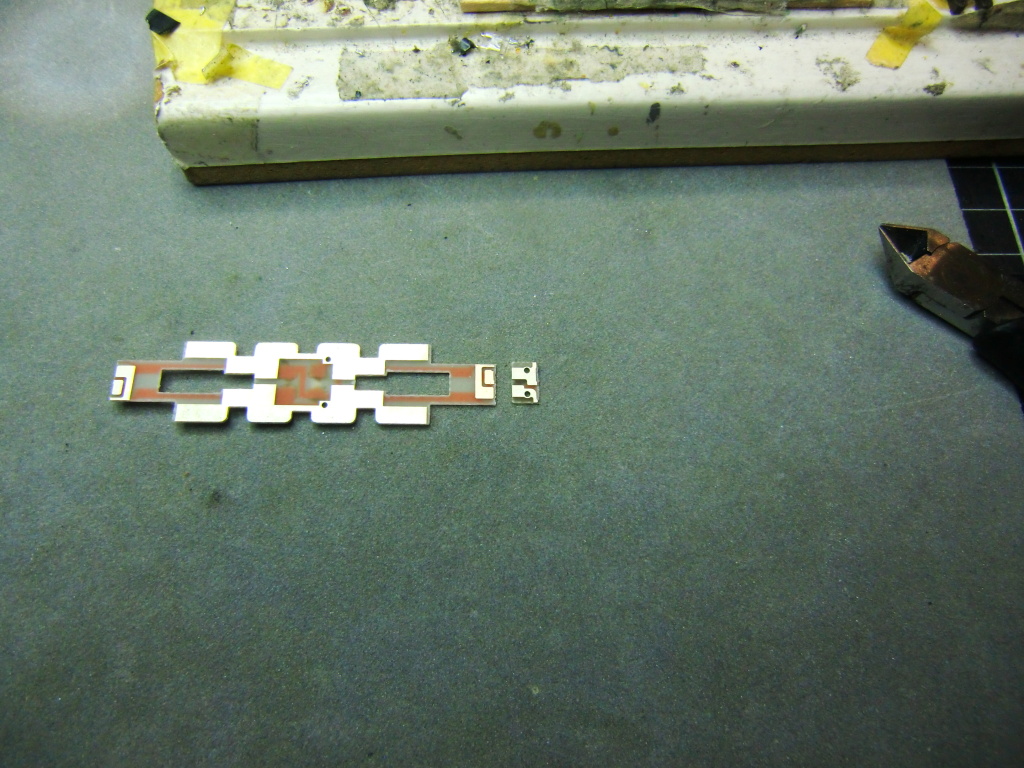
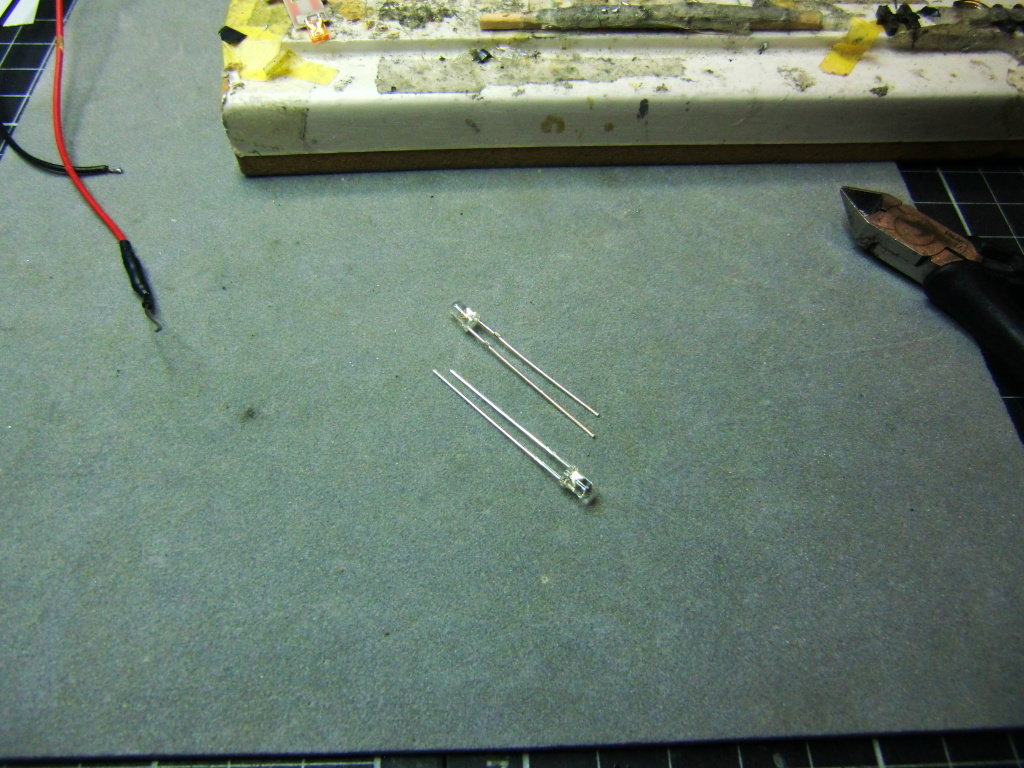
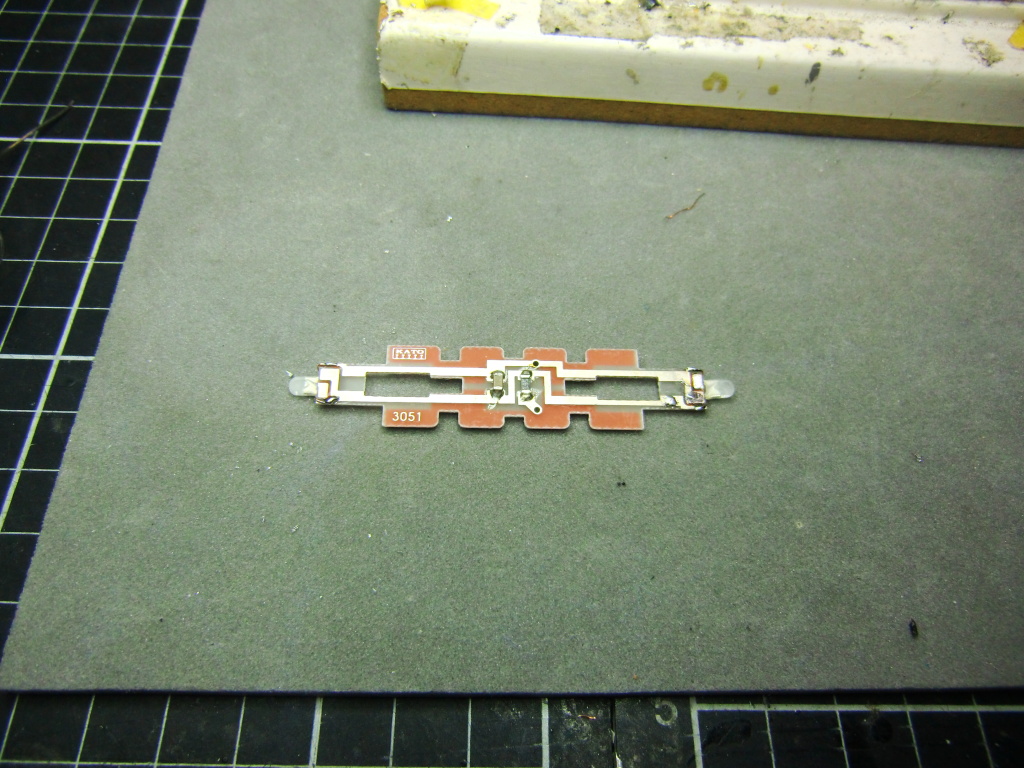




加工前は上のような感じです。
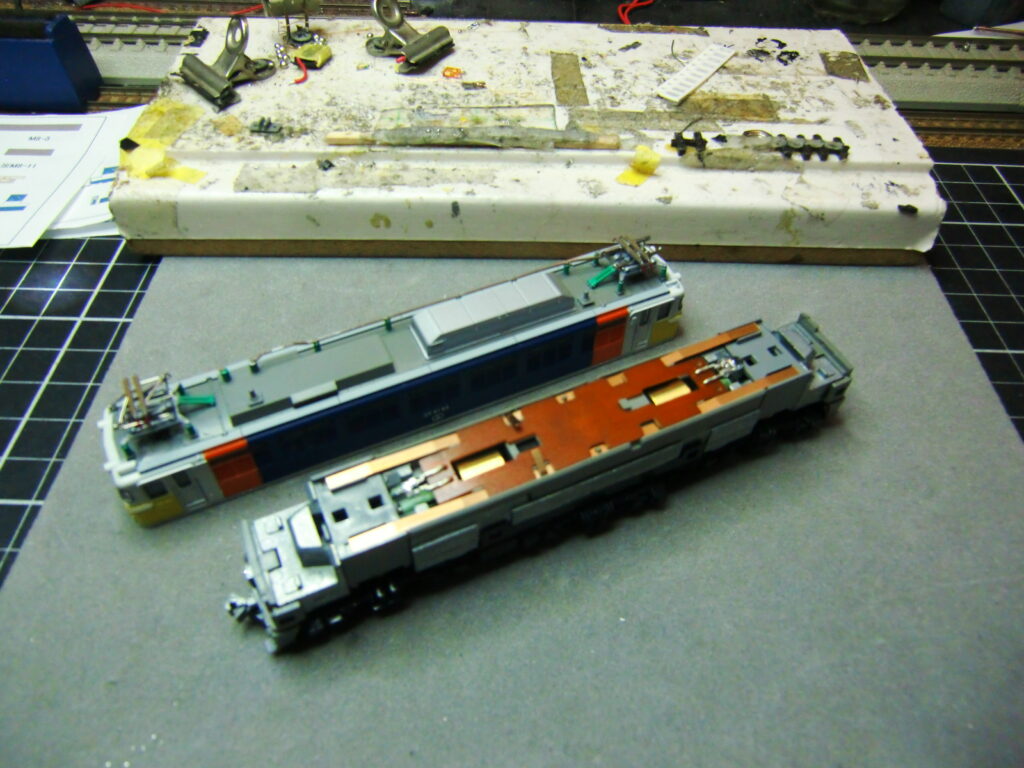
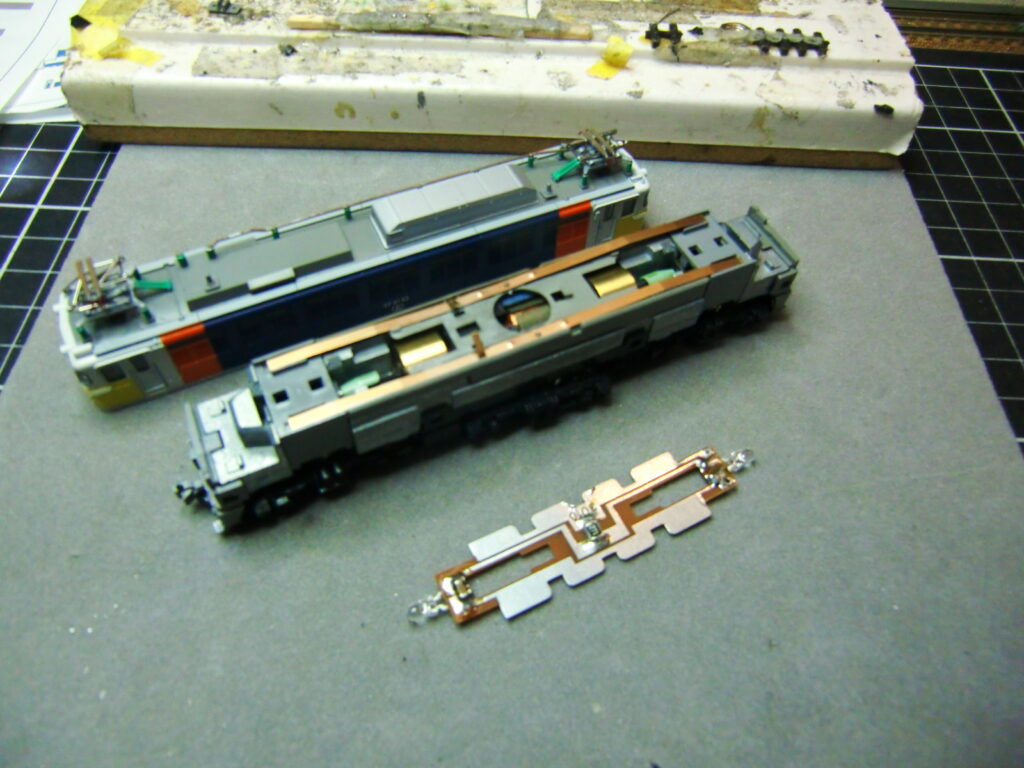
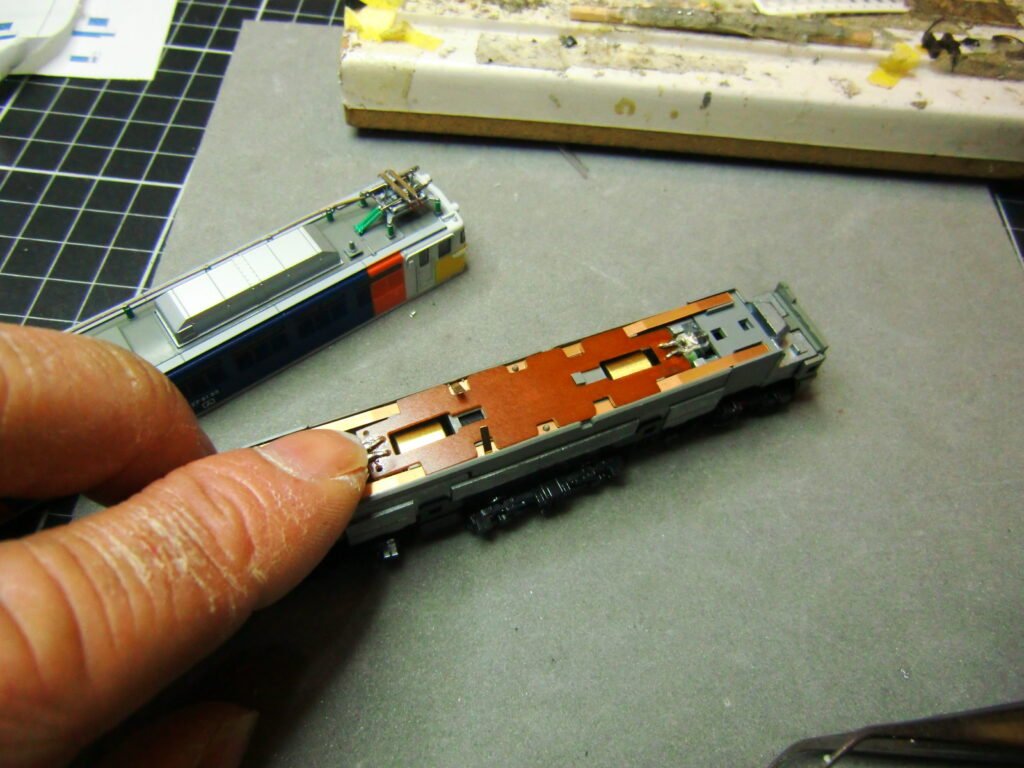


加工前は上のような感じです。
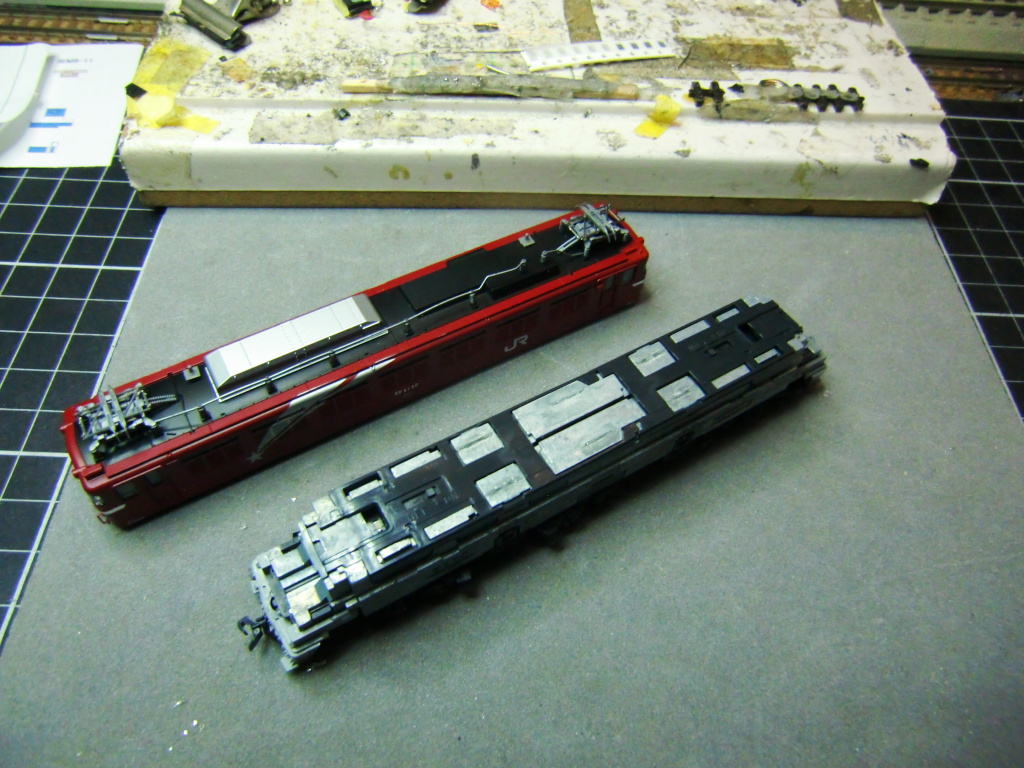

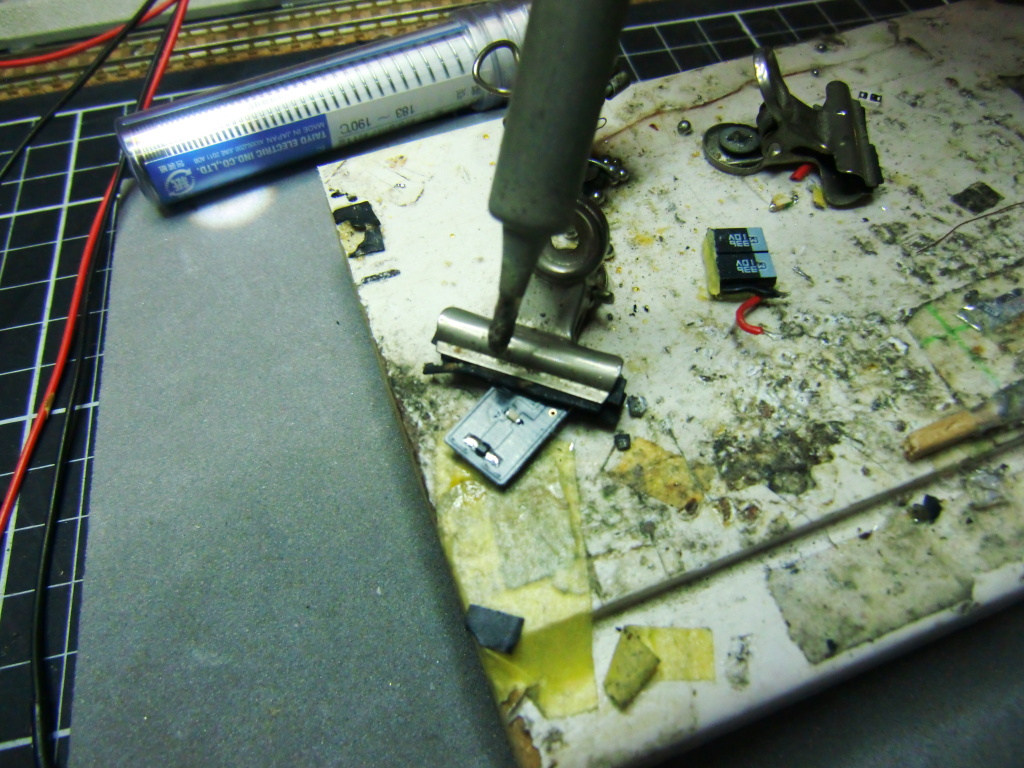
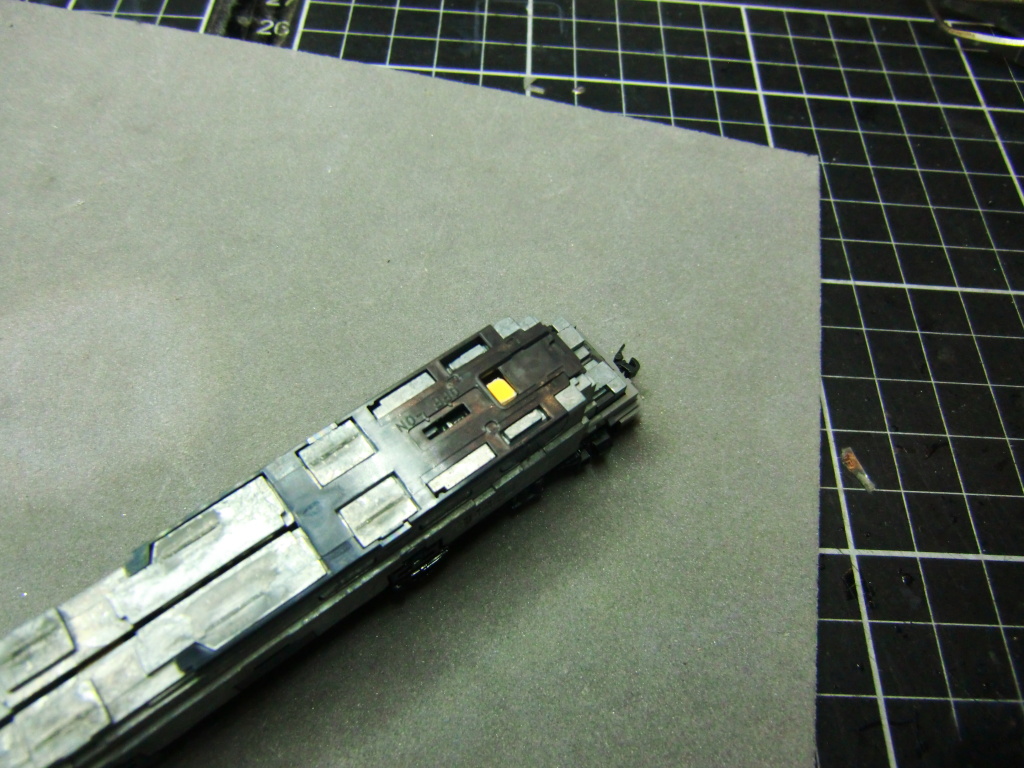
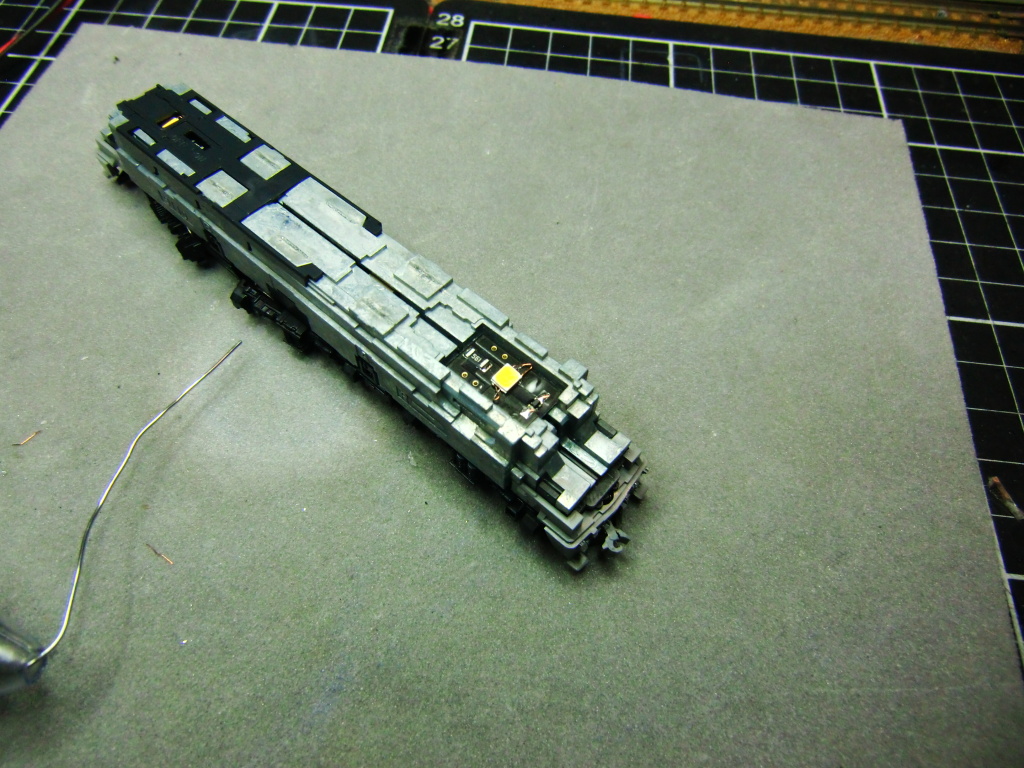


作業完了です。
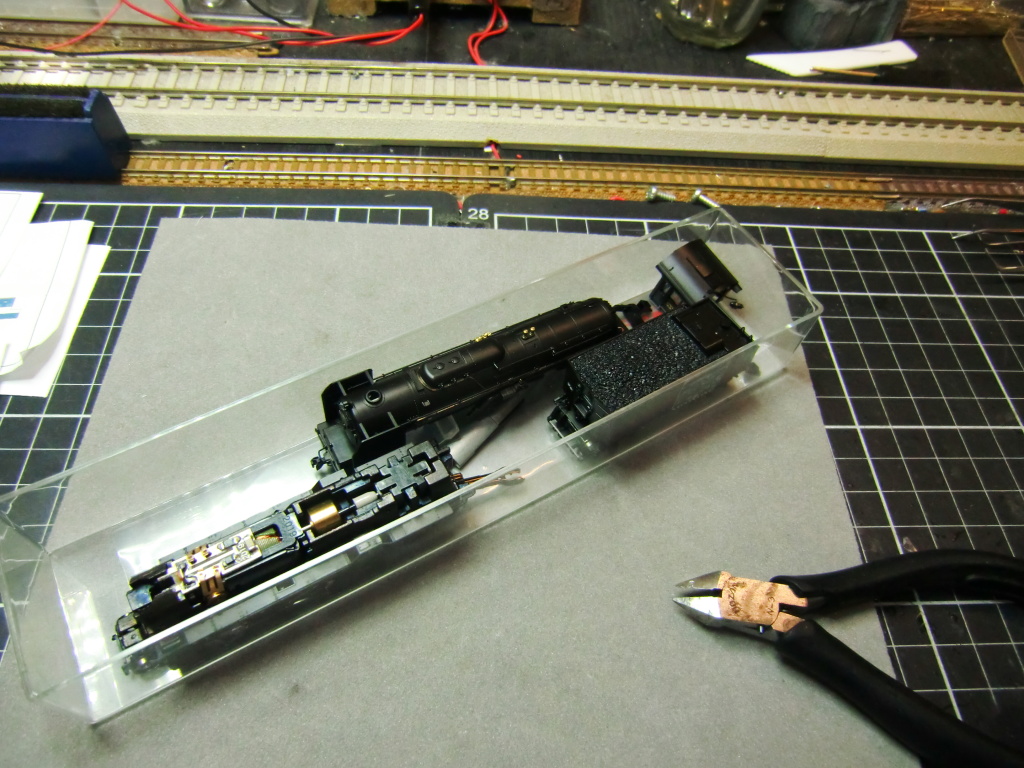
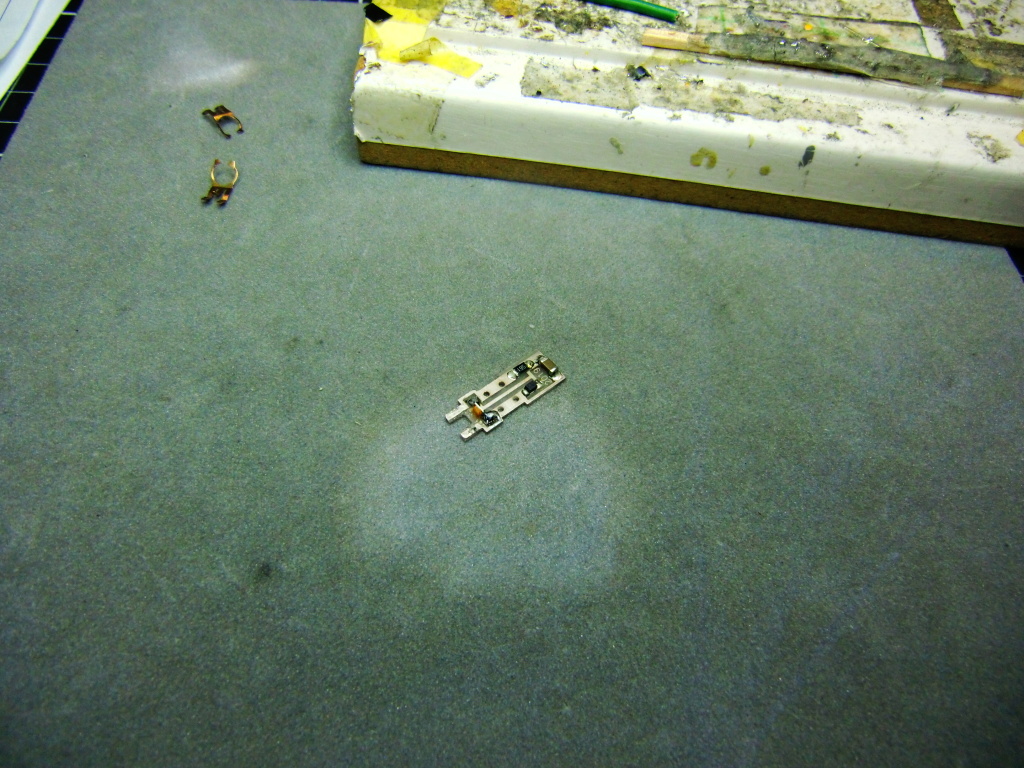

砲弾型LEDを内部に収まるようになるまで削っていきます。
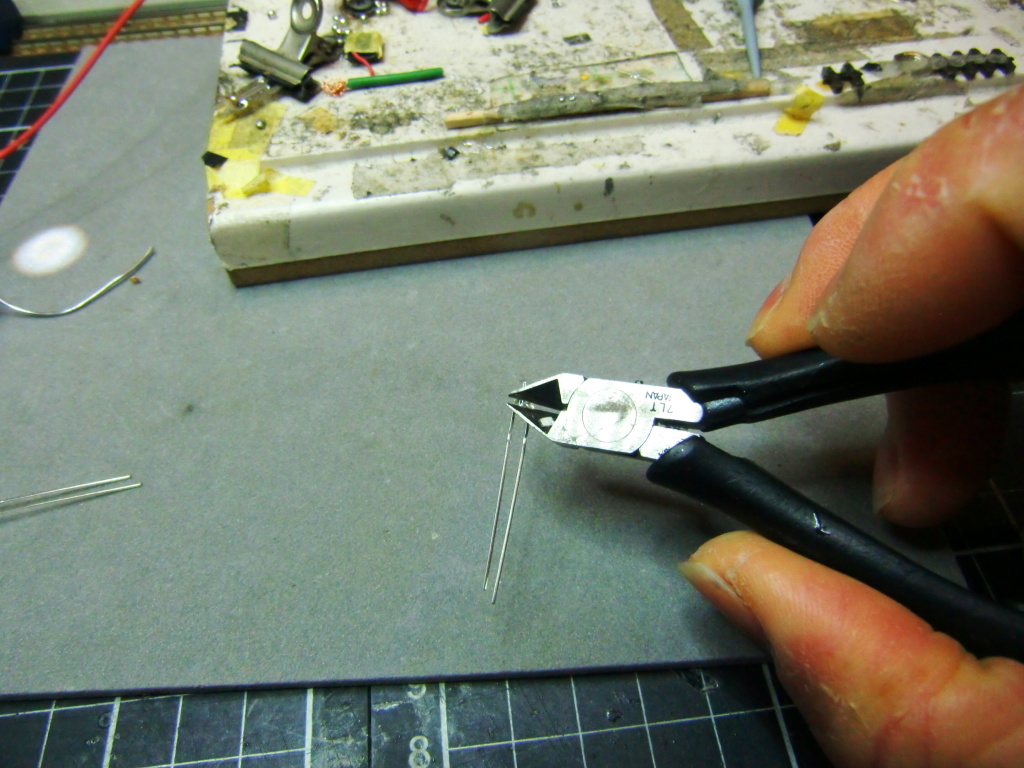
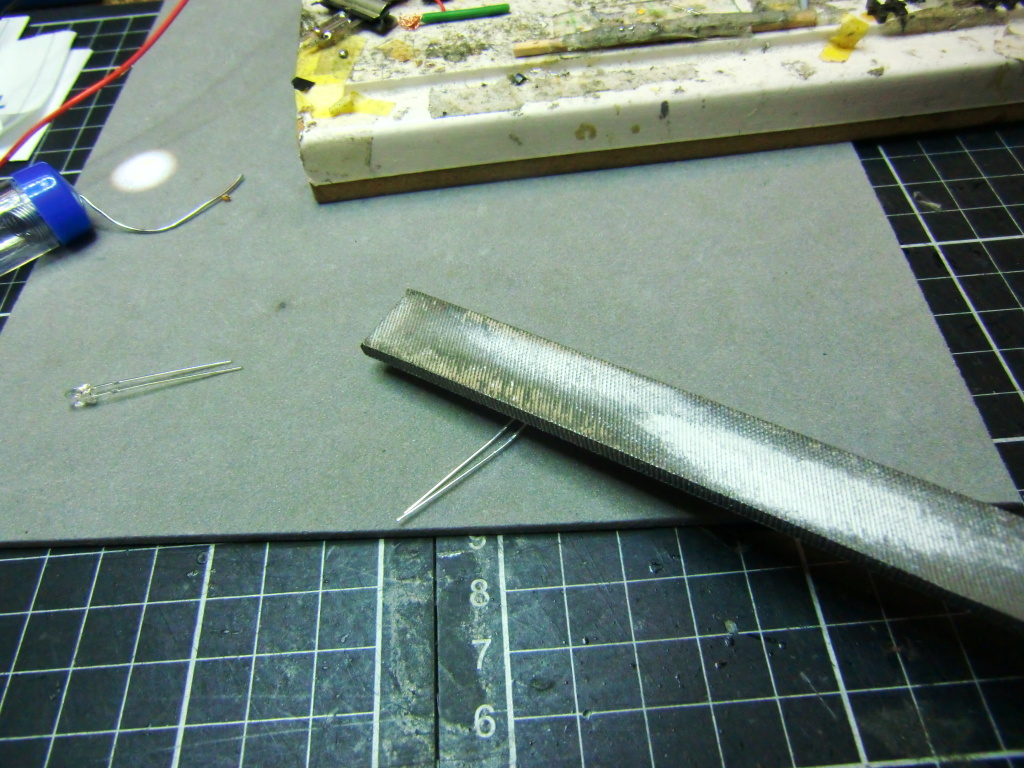

ここまで薄くなるまで削り込みます。
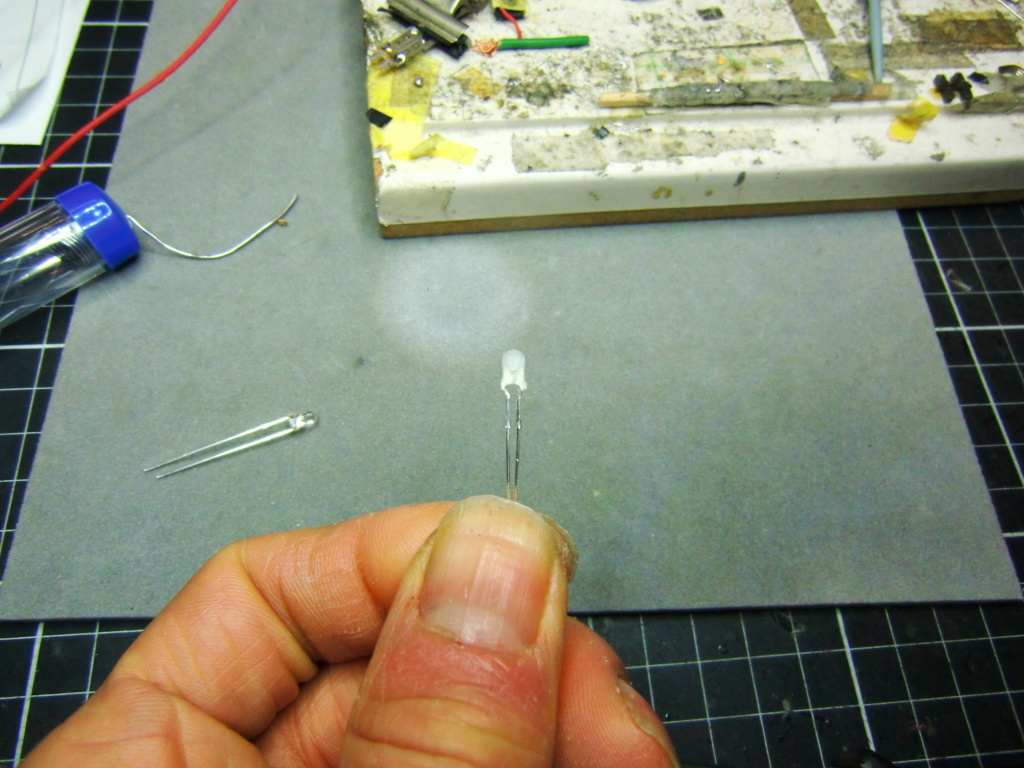
足を上記のように曲げておきます。
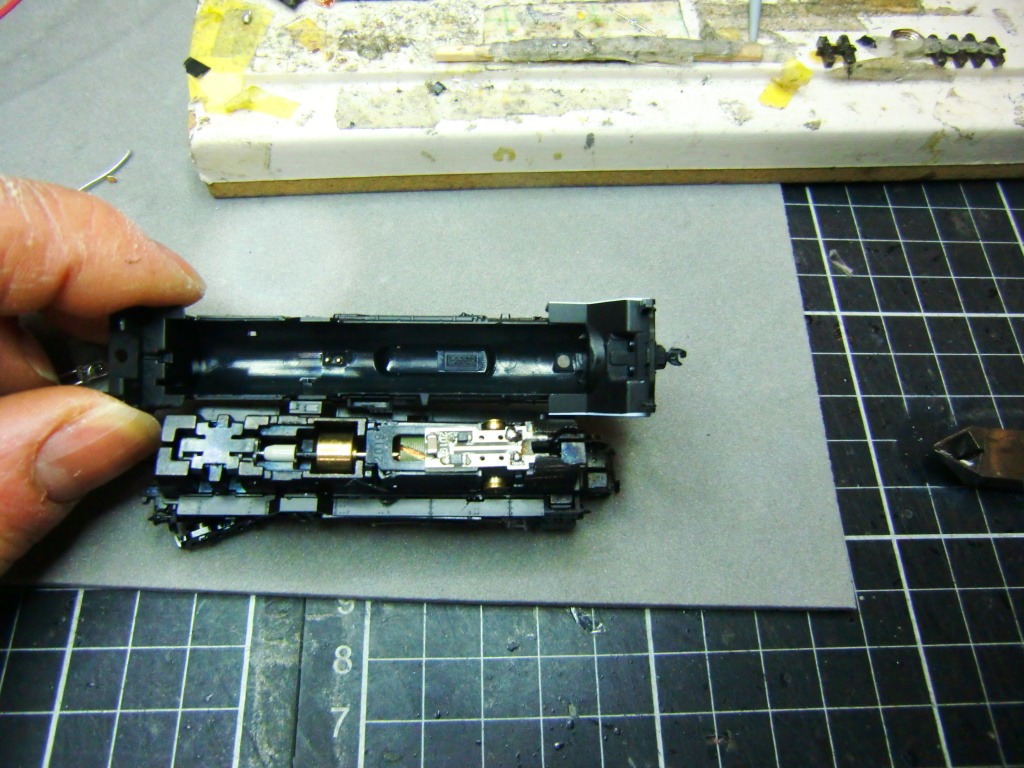
基盤との位置関係を確認しながら、さらに削って調整します。

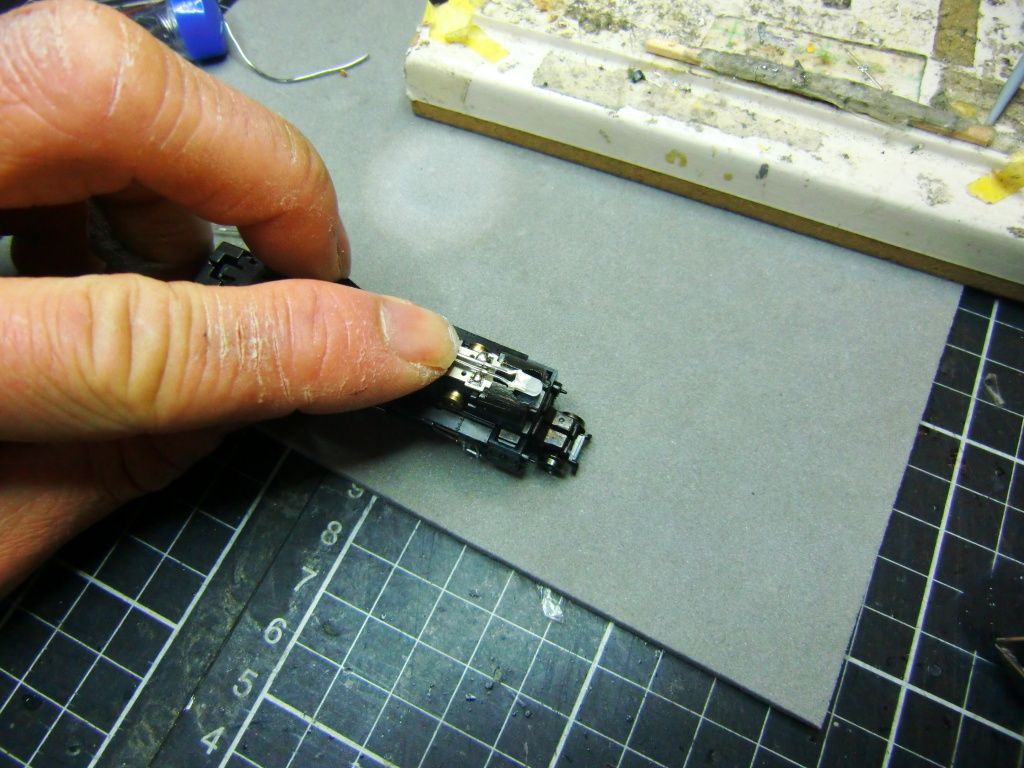
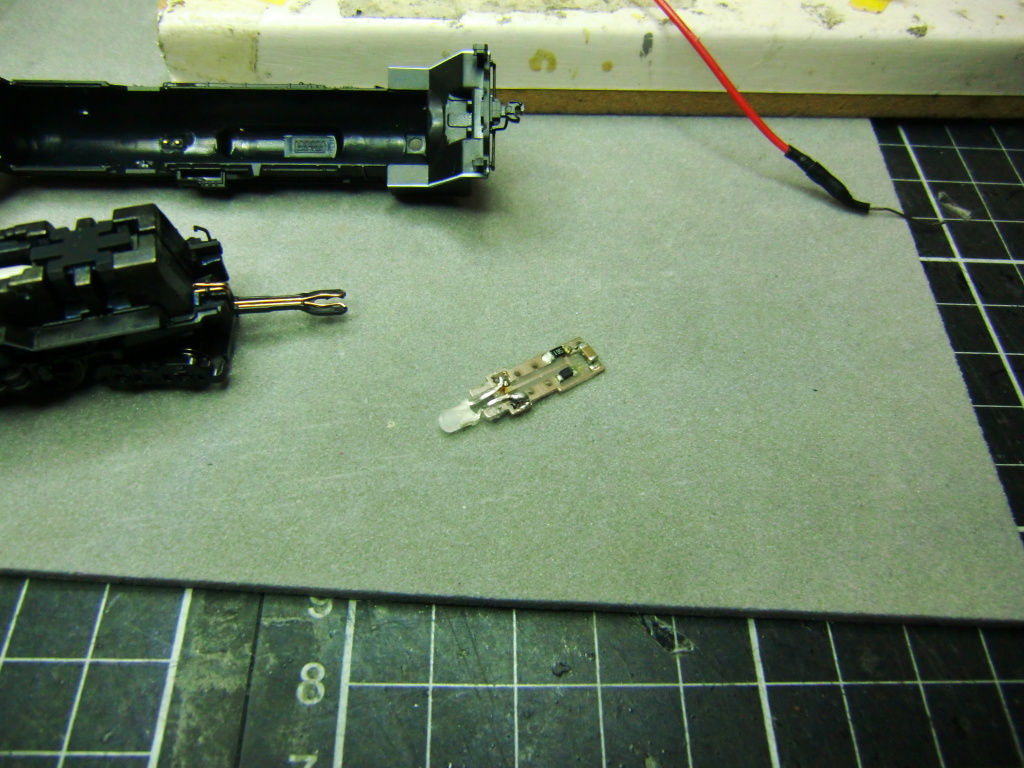
長さの微調整行い先端を切り落とします。その後、LEDを上向きに10度程度傾けておきます。
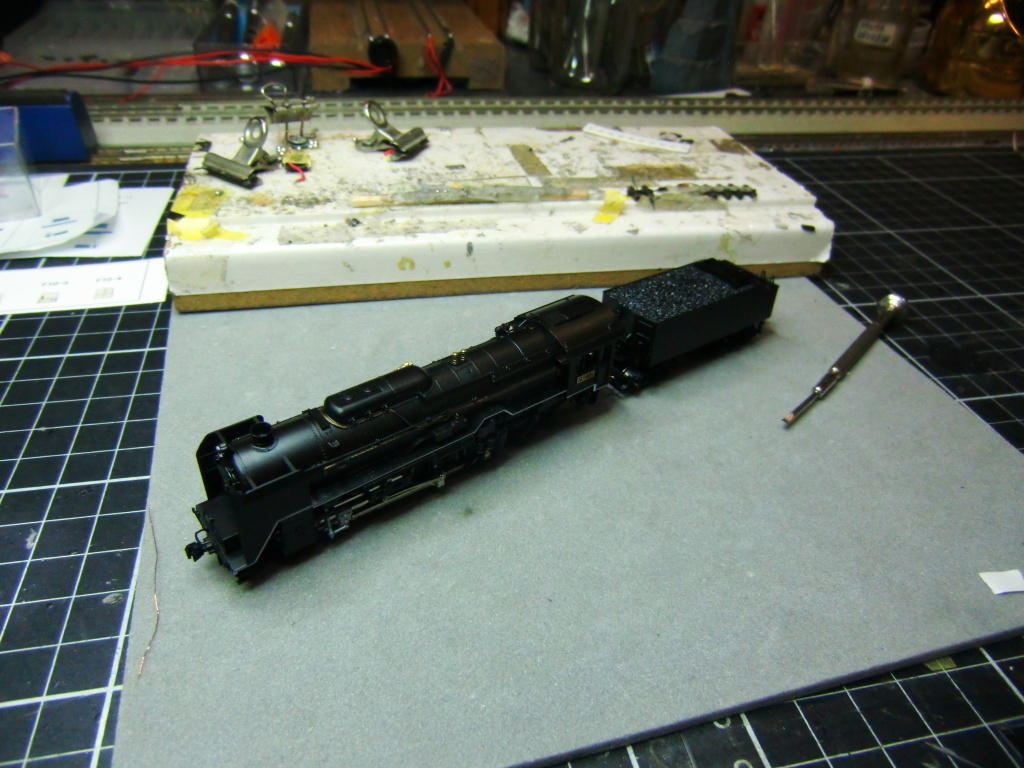

ボディーを被せてから前面を開けた状態でLEDの指向角の微調整を行います。


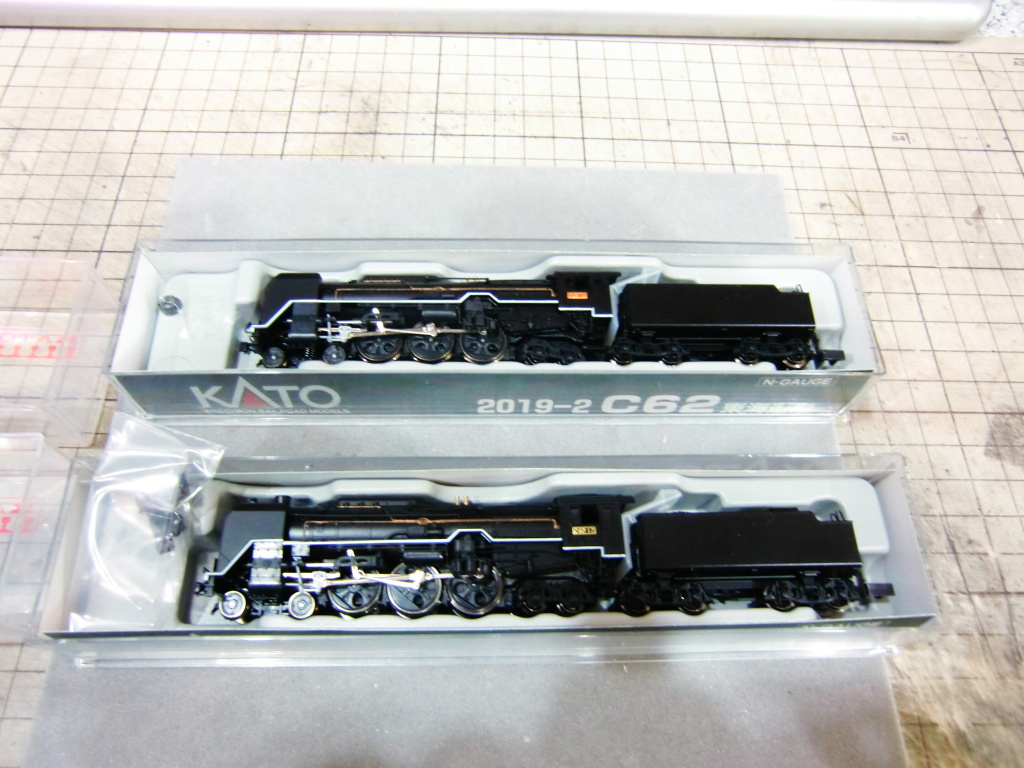
作業完了でございます。

トーマス君、体調不良でただいま入院中です。
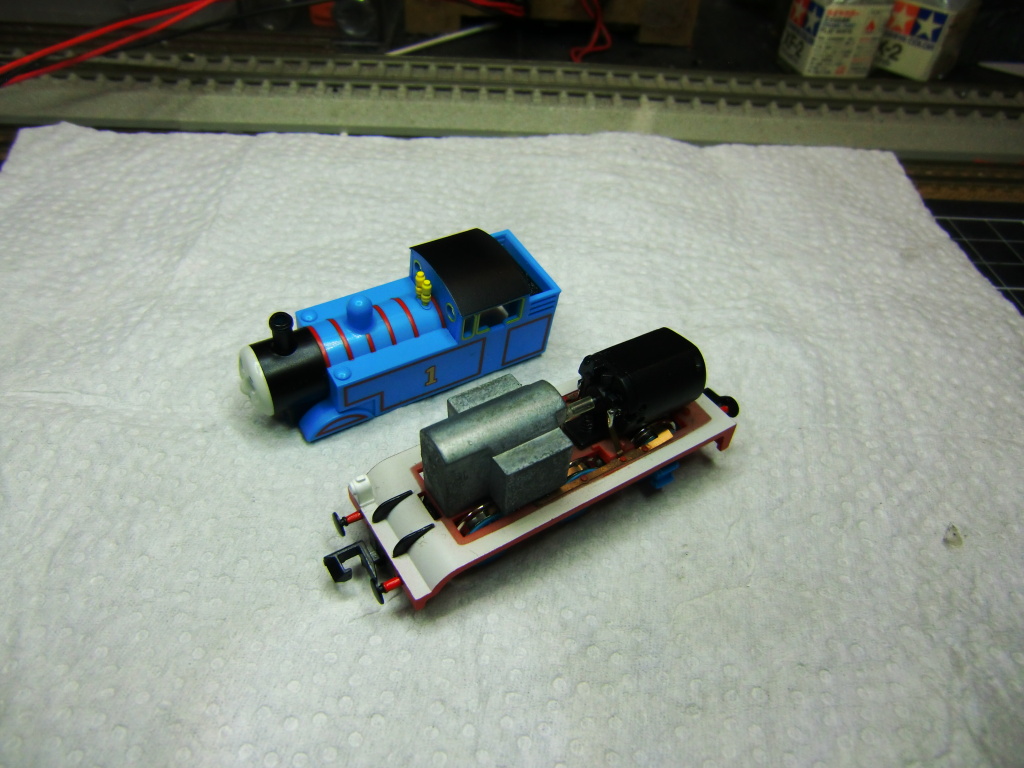
チューブが途中から切れています。まずはここから直していきます。
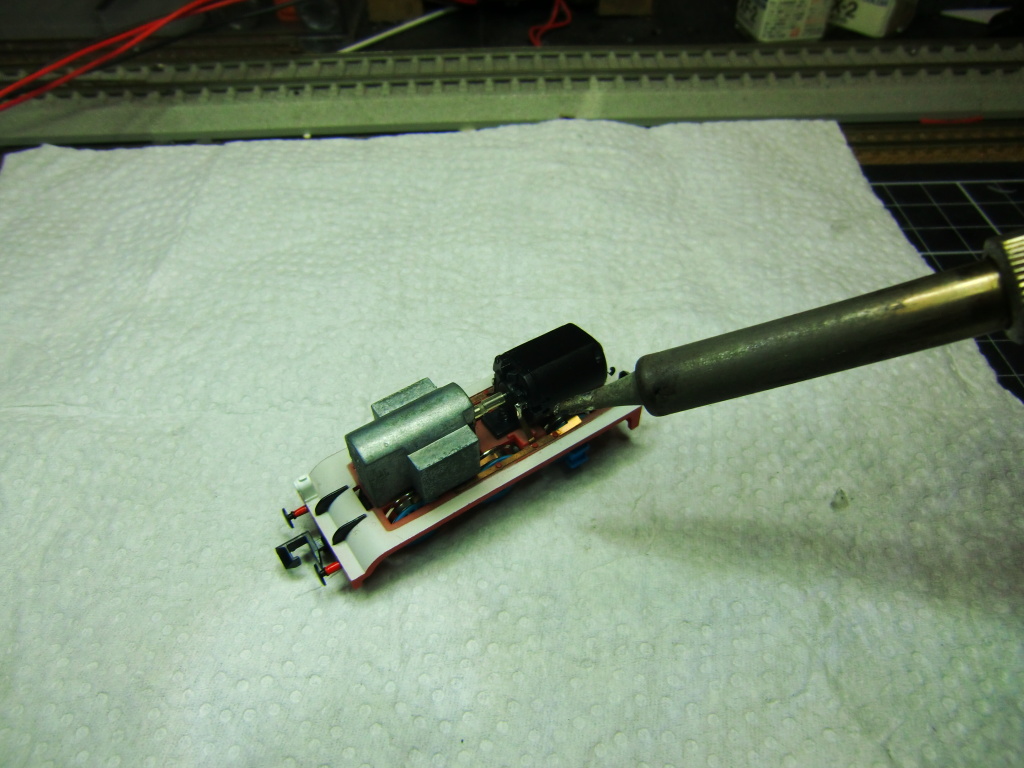
モーター端子と直接ハンダ付けされているので、それを外してモーターを取り出します。
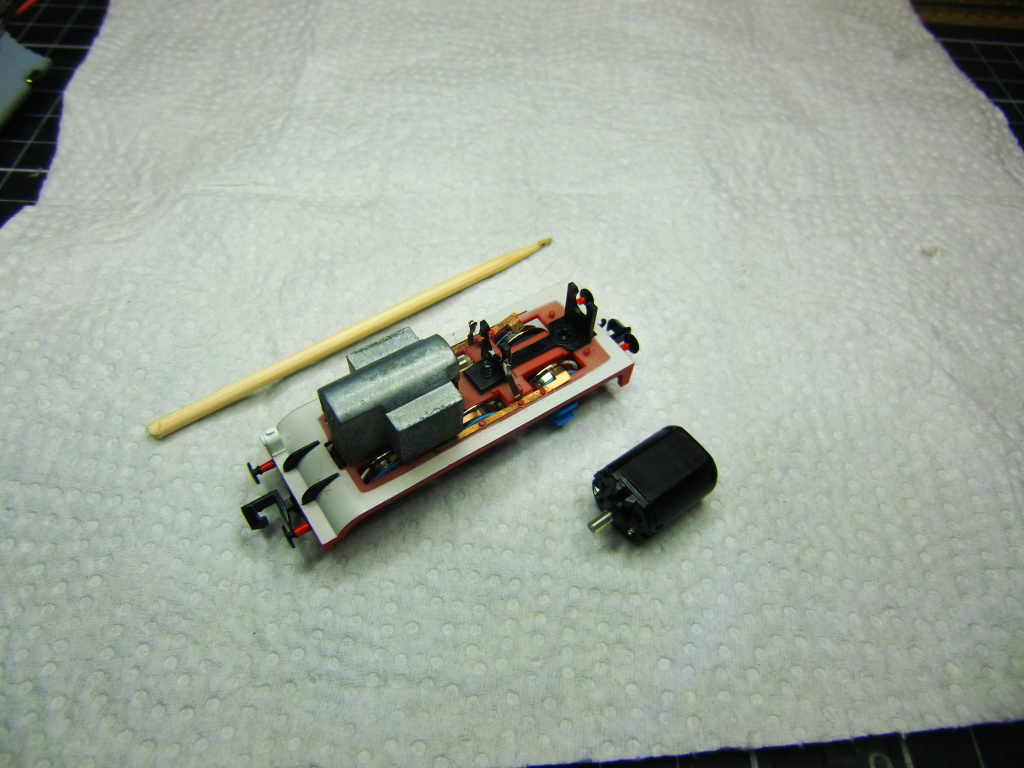
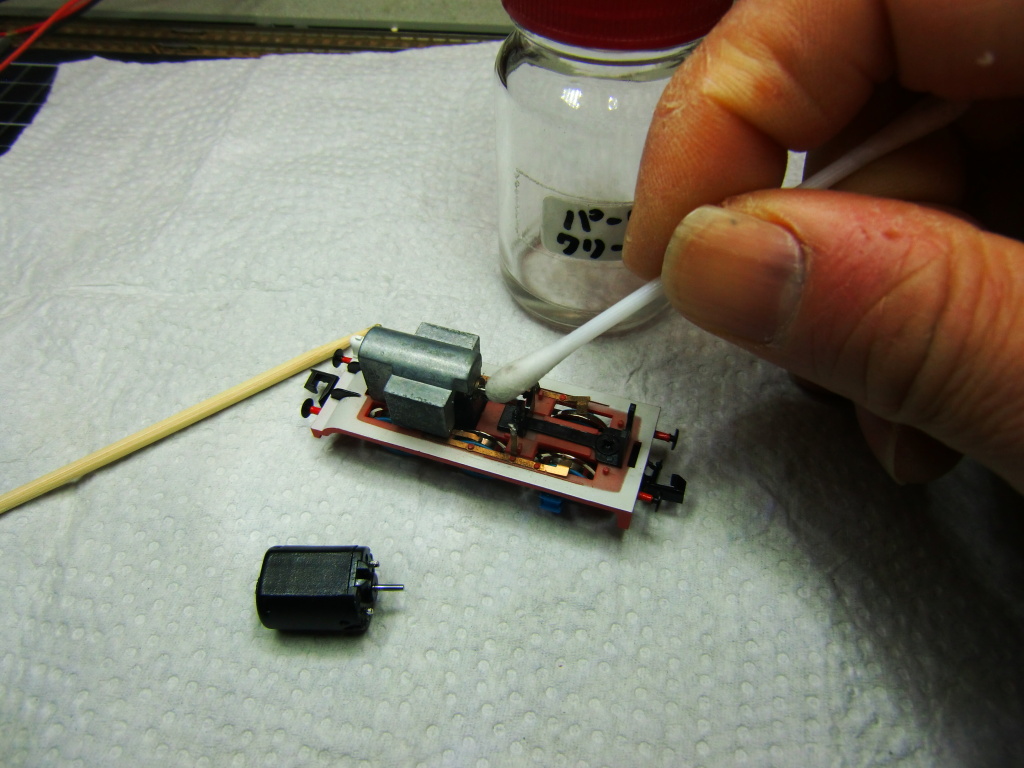
シャフト部分をしっかり洗浄してチューブが滑らないようにします。このあと、ゴムチューブを加工して伝達パーツを自作して組み込みます。
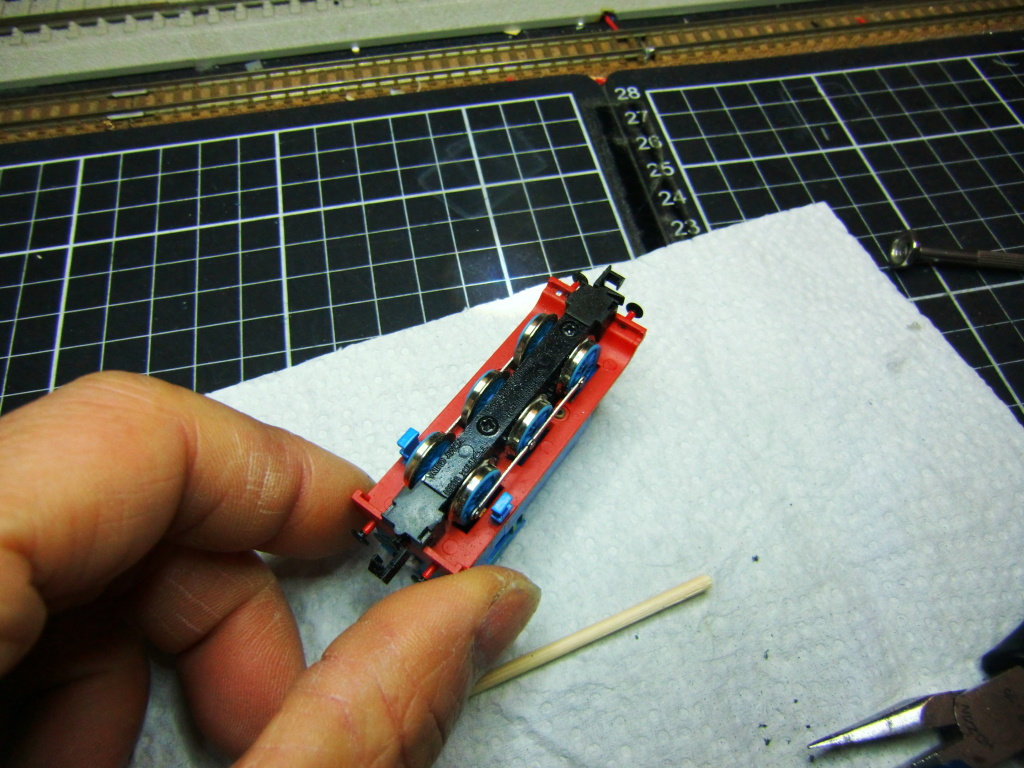
集電も不安定でしたので、各部調整を行いました。
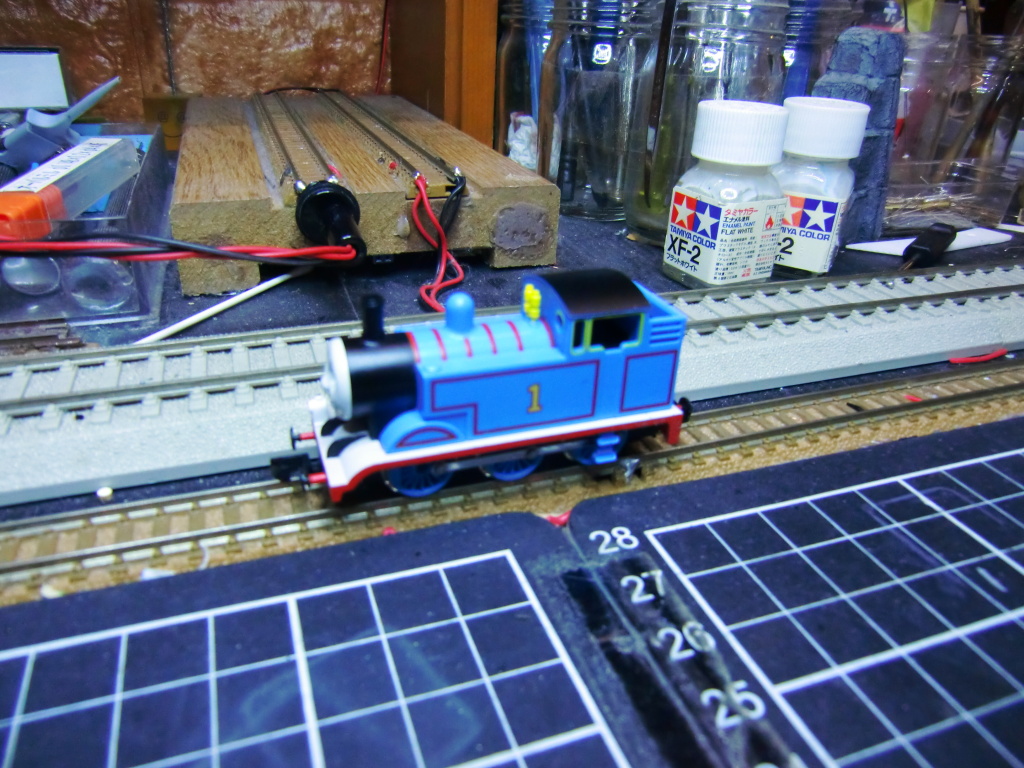

トーマス君、無事に退院しました。作業完了でございます。
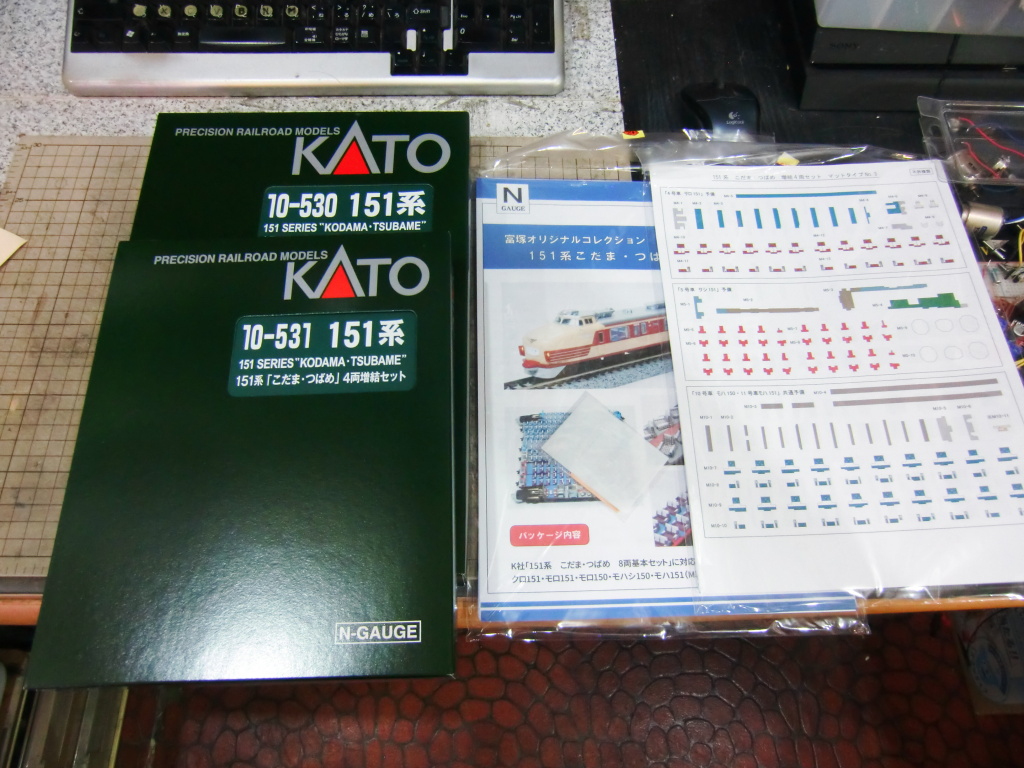
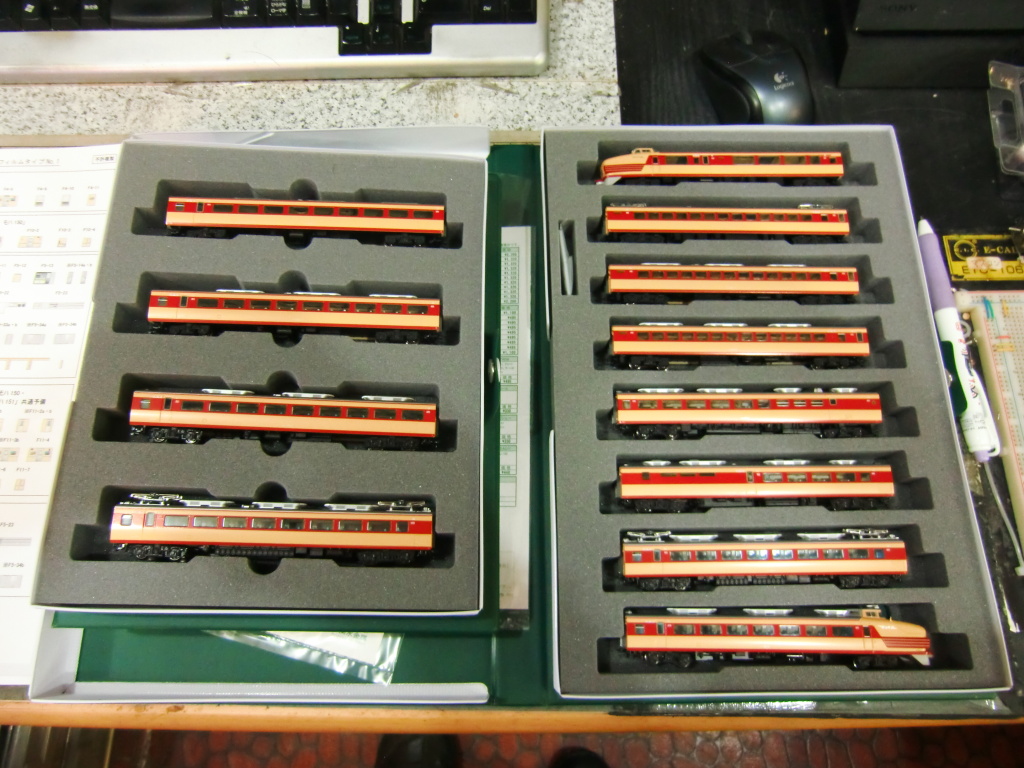
冨塚商会さんの内装シールの貼り付け作業でございます。かなりのボリュームがありますので、コツコツ作業を進めることにいたします。

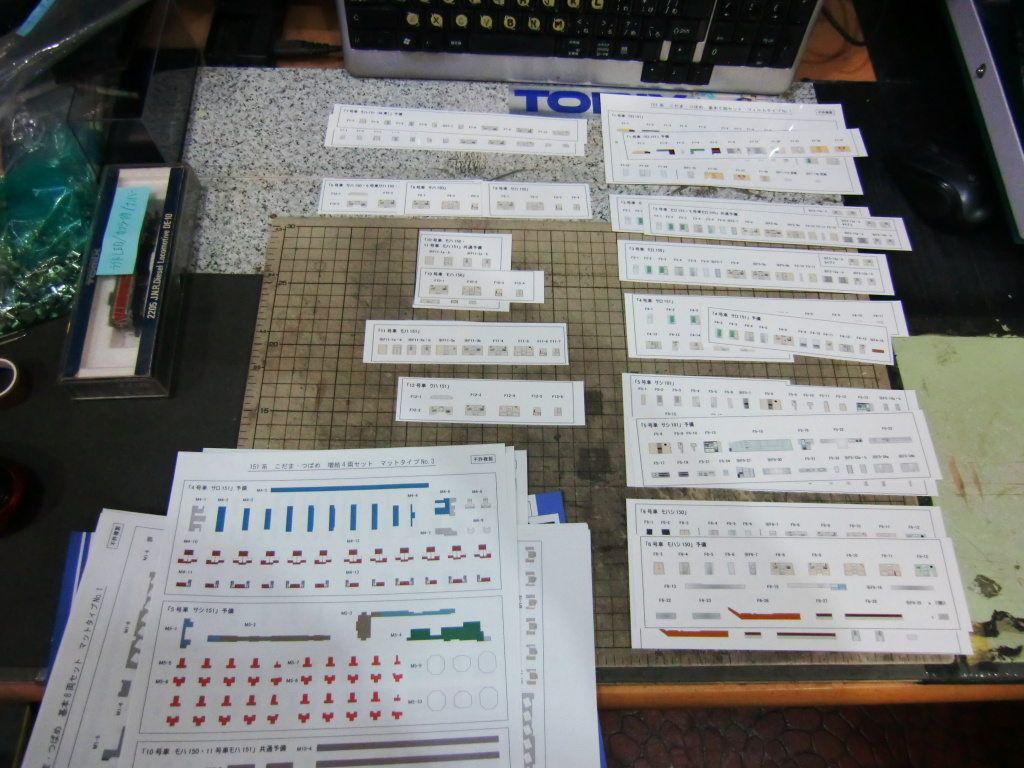
1~12号車のシール区分を先に行っておきます。
▼パーツ洗浄
まずは、パーツの洗浄作業ですが、シールの貼り付けにおいてこの作業は大変重要です。面倒だからといって、パーツについた油分と汚れを完全に落とさないまま貼ると、簡単に剥がれてきます。
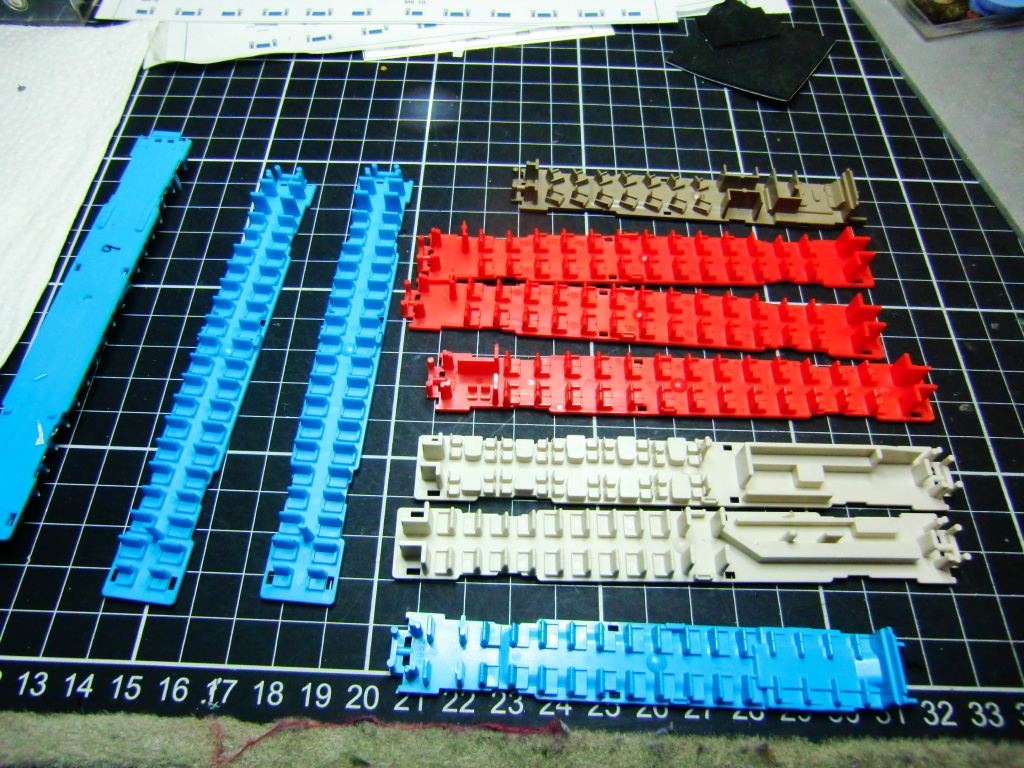

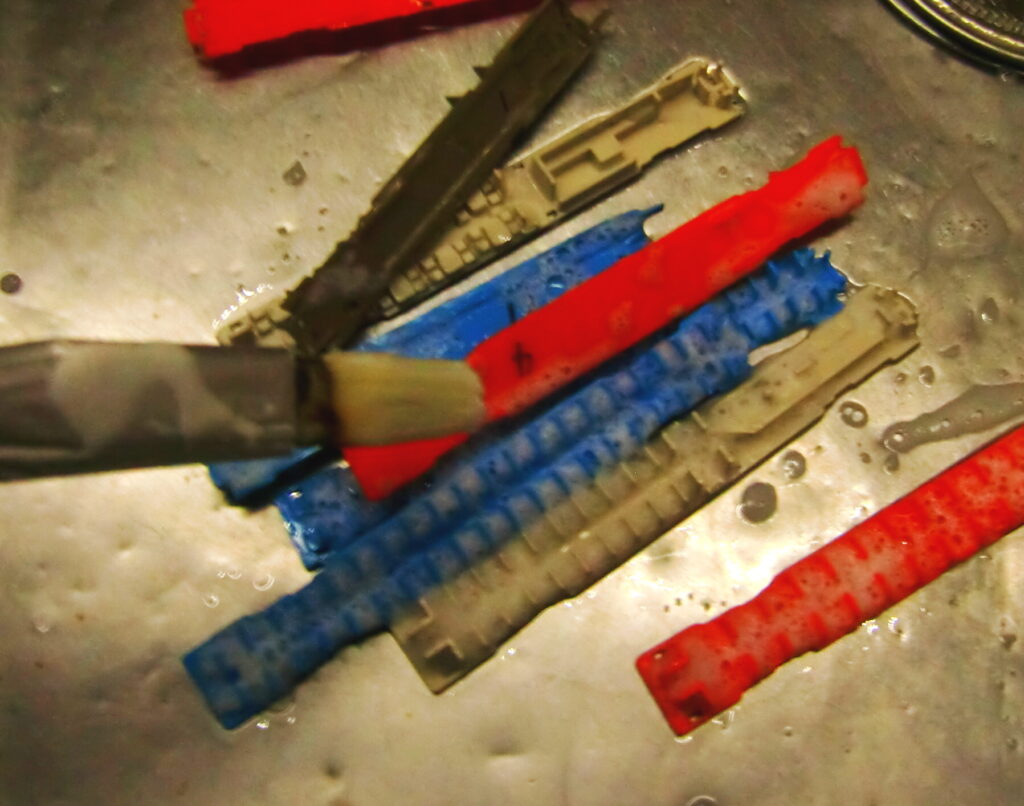
隅々まで念入りに油分と汚れを落とします。
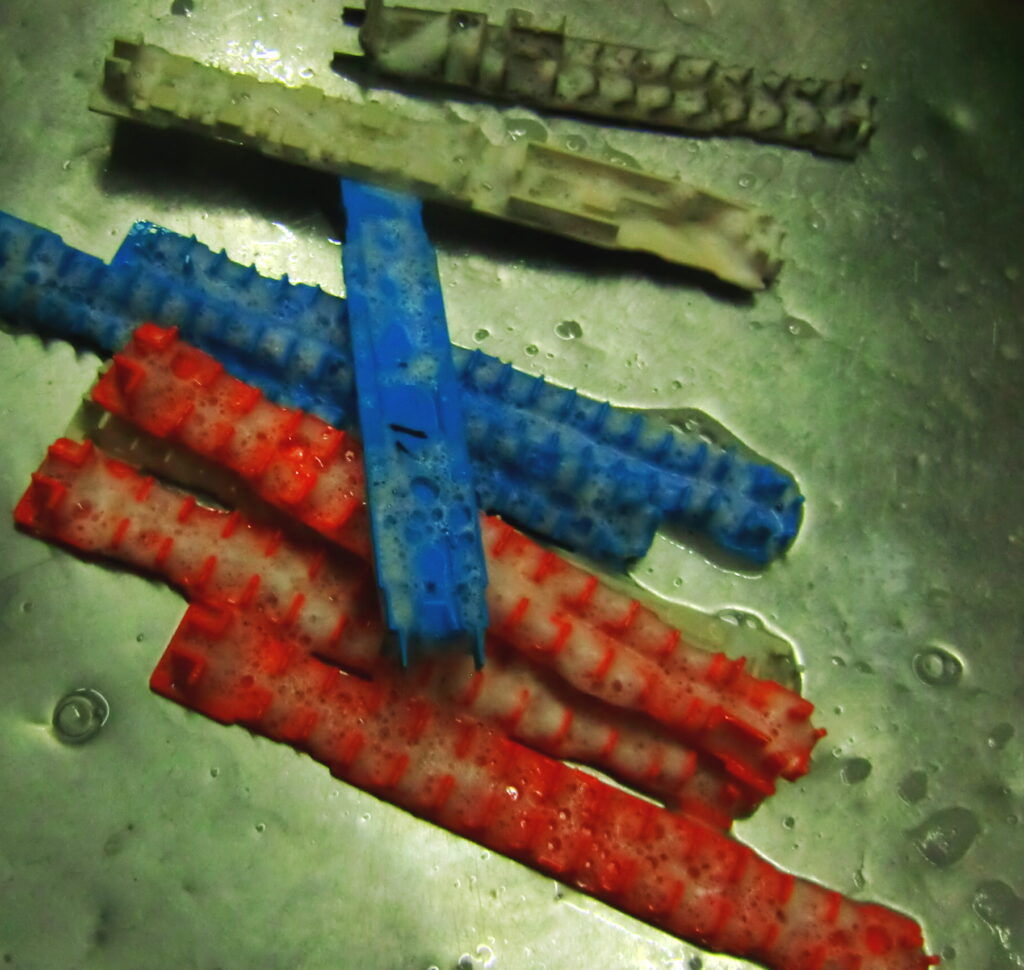

洗剤を残さないようにしっかりと流します。
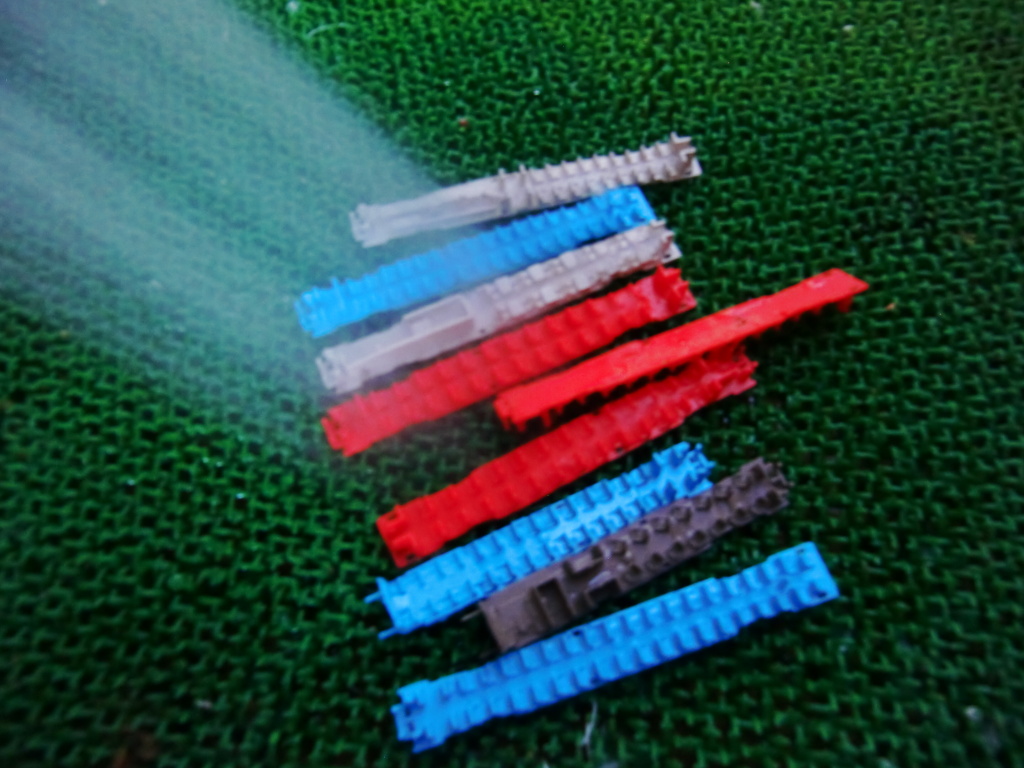
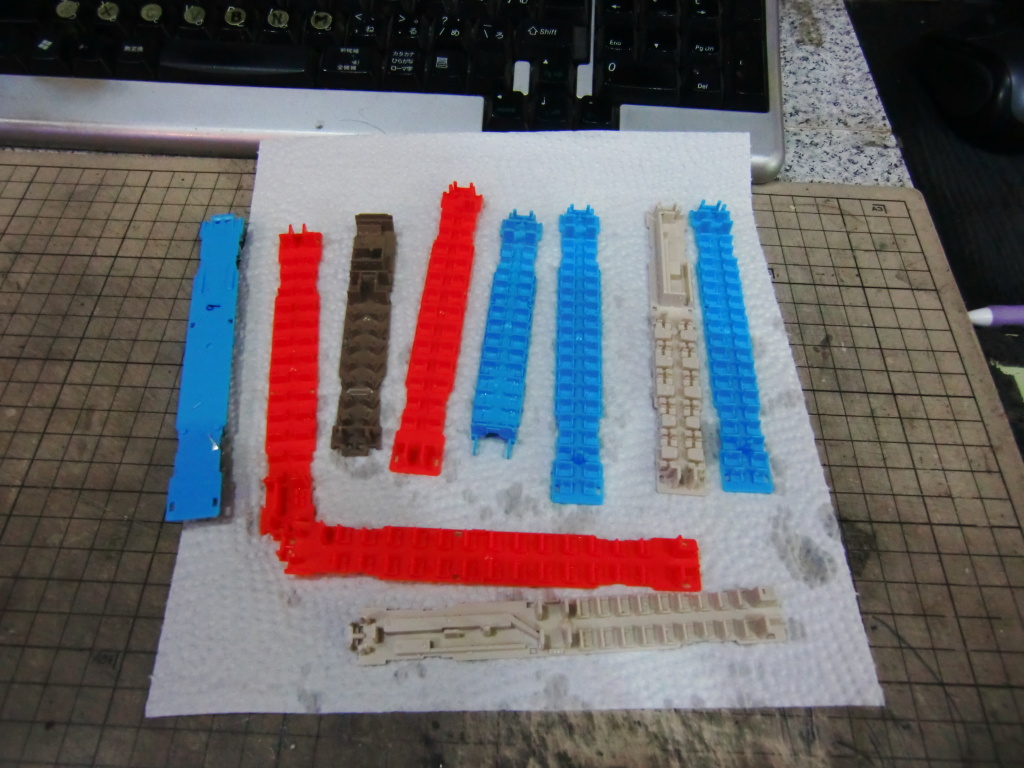
このあと、乾燥機で乾かします。
▼下塗り作業
上記の洗浄だけでは、基本的に不十分ですので、シールを貼る前に念のため下塗り剤を塗っておきます。特に曲面に貼る場合は、よほど粘着力の強いシール以外はこの作業は必修です。
▼貼り付け作業
実際にシール貼ってみましたが、粘着力が弱くイスなどの曲面への貼り付けには問題がありそうです。この粘着力では簡単に浮いて剥がれてしまいます。そこで、シールの台紙をいったん剥がしてから、裏に市販の両面テープを貼って粘着力を強化することにしました。ちなみに一部だけ貼ってあった座席のシールは膨らんで剥がれた状態となっておりました。貼った直後は付いているようにみえても、徐々に浮き上がって剥がれてしまいます。このような症状は、過去に何度も見てきていますので、下処理と曲面への貼り付けには注意が必要です。
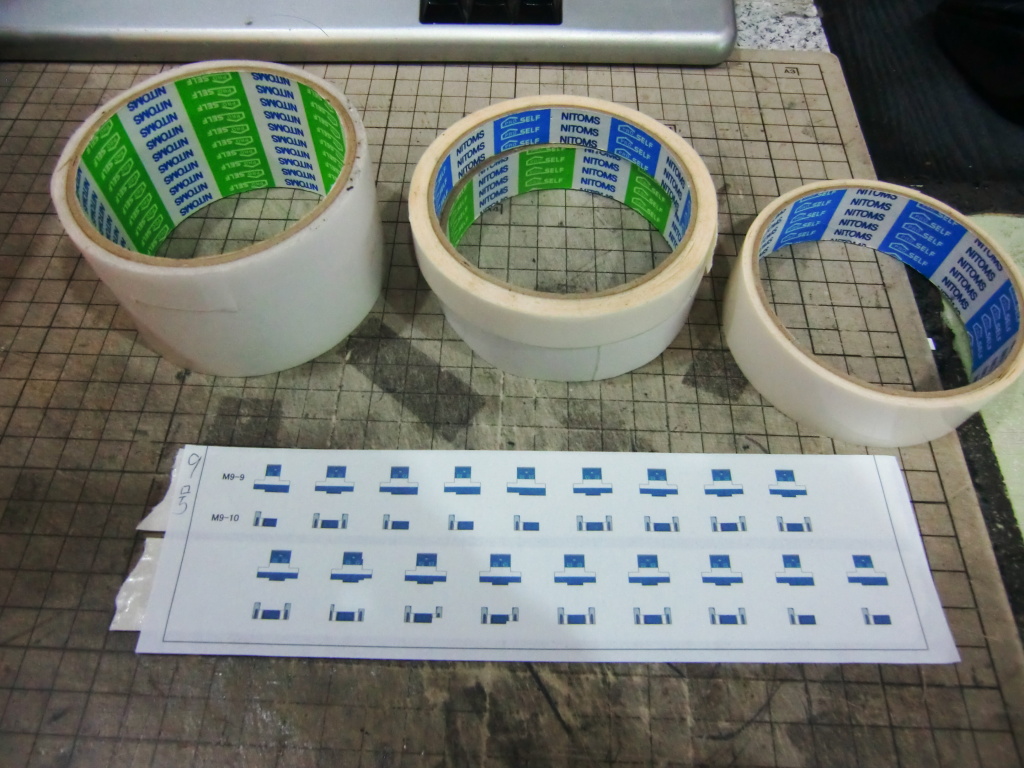
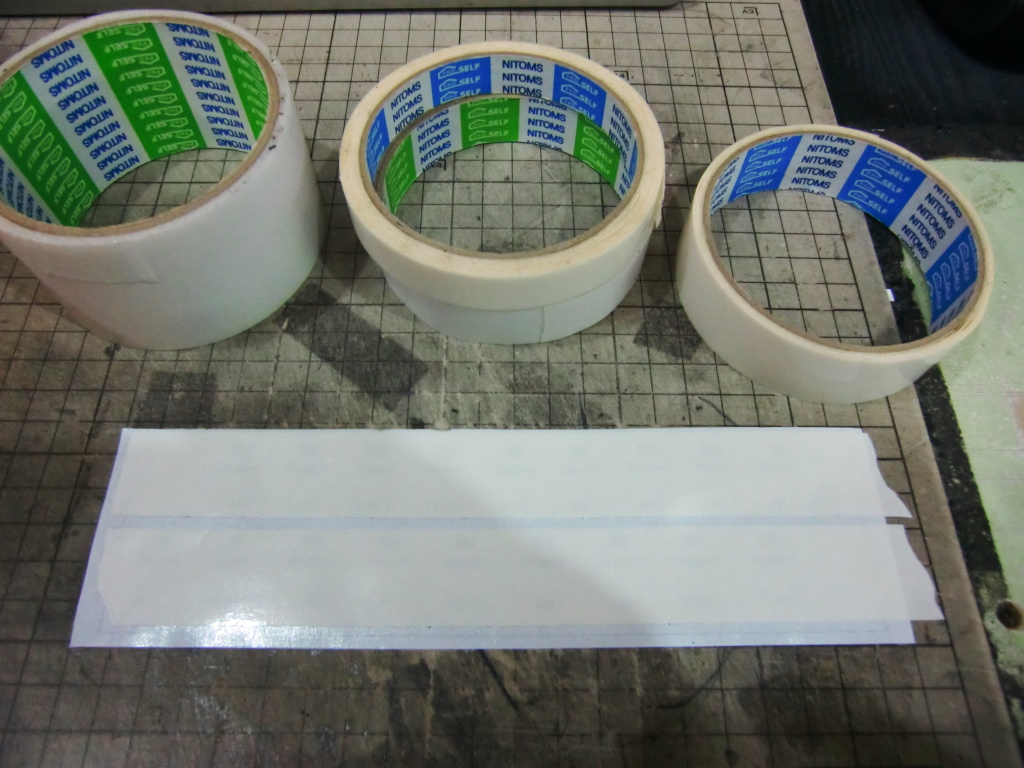
実際貼り付けを開始して、「これは結構大変な作業だ~」と思いました。1枚のシールを切り出すにも、何回も刃を入れる工程が必要になるなど、想定を超える作業となりそうである。
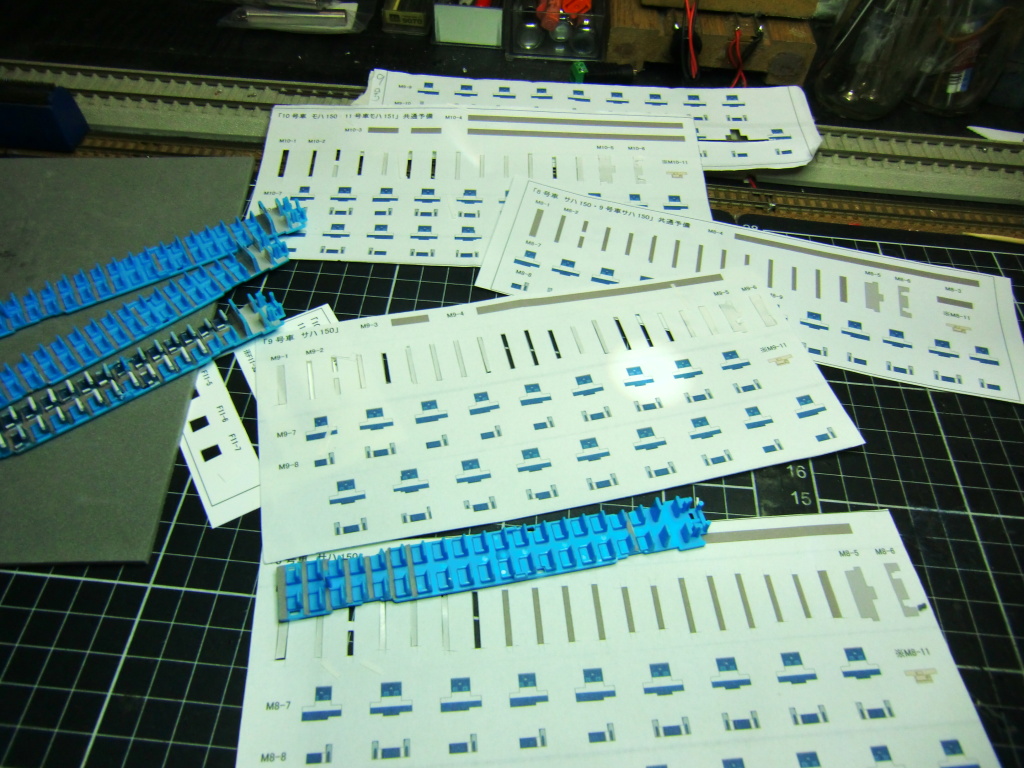
シールのボリュームがすごいです。プラバン板を加工して仕切りを作る必要があるなど単なるシールの貼り付け作業とはいかないようです。
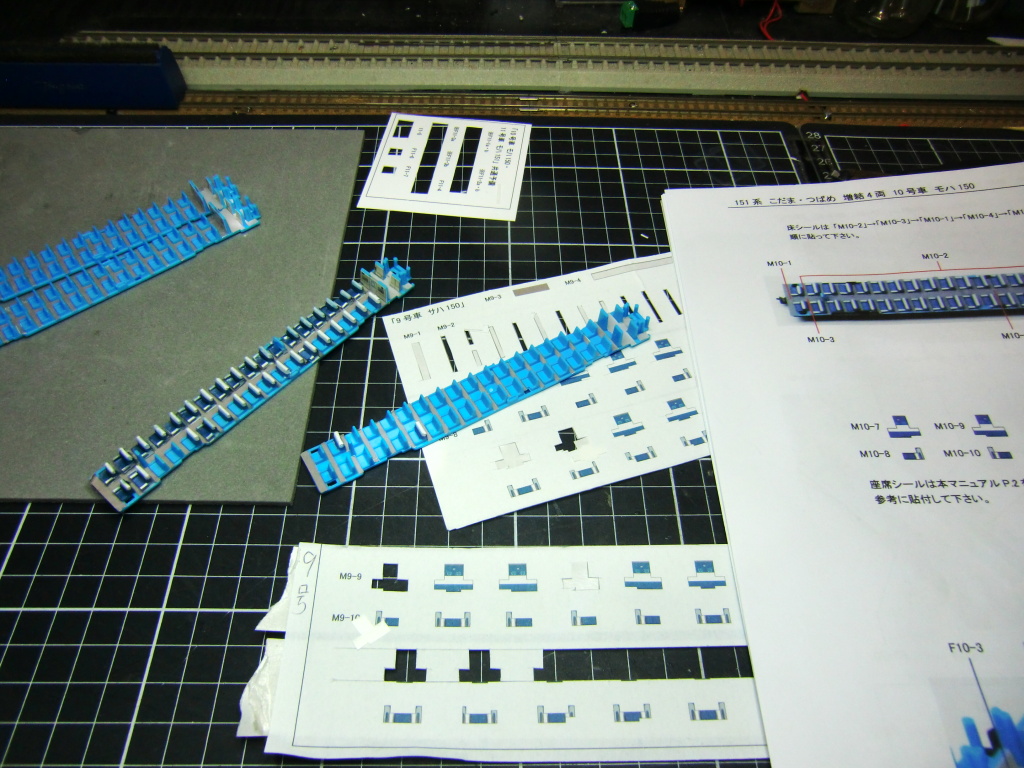
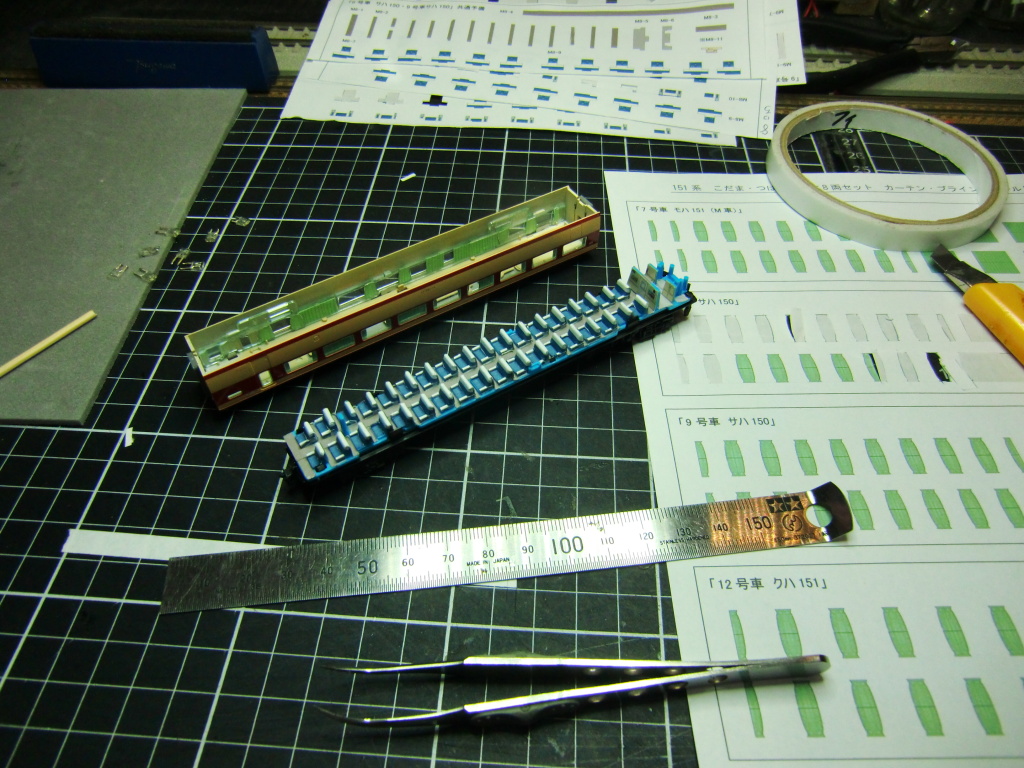
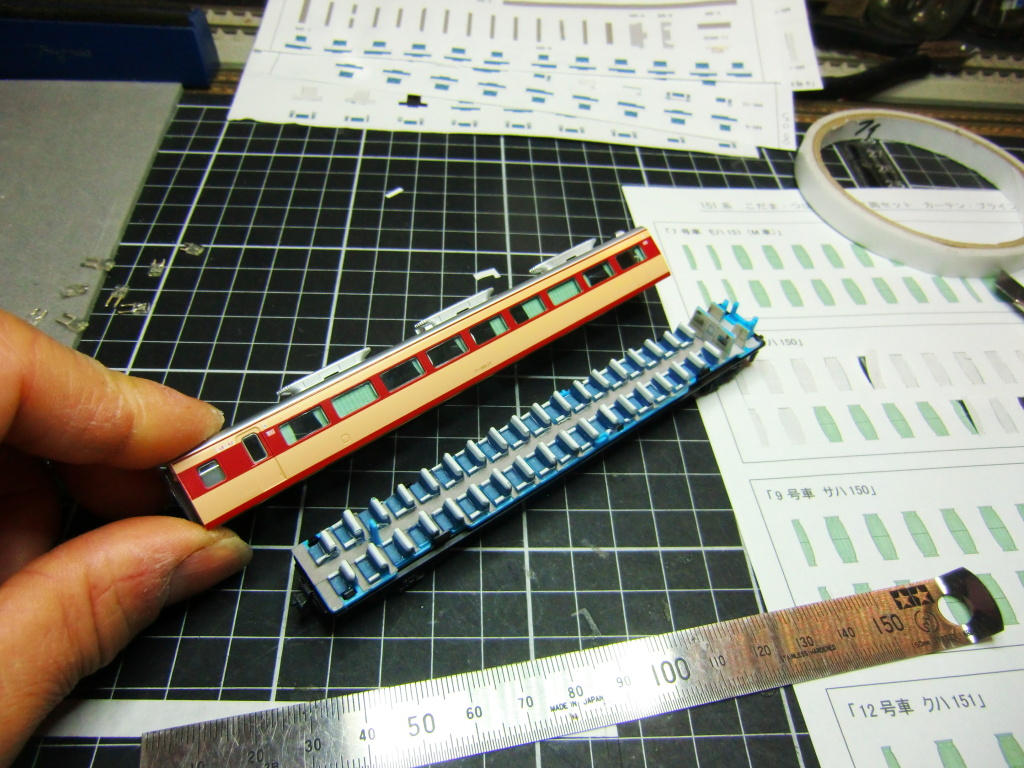
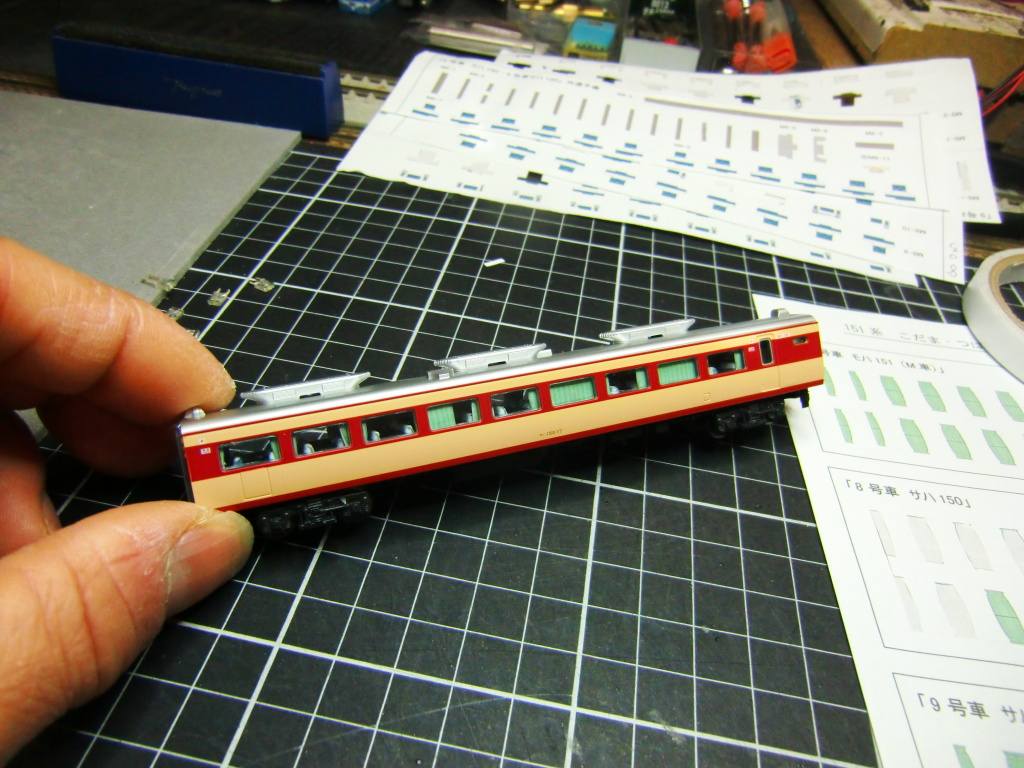
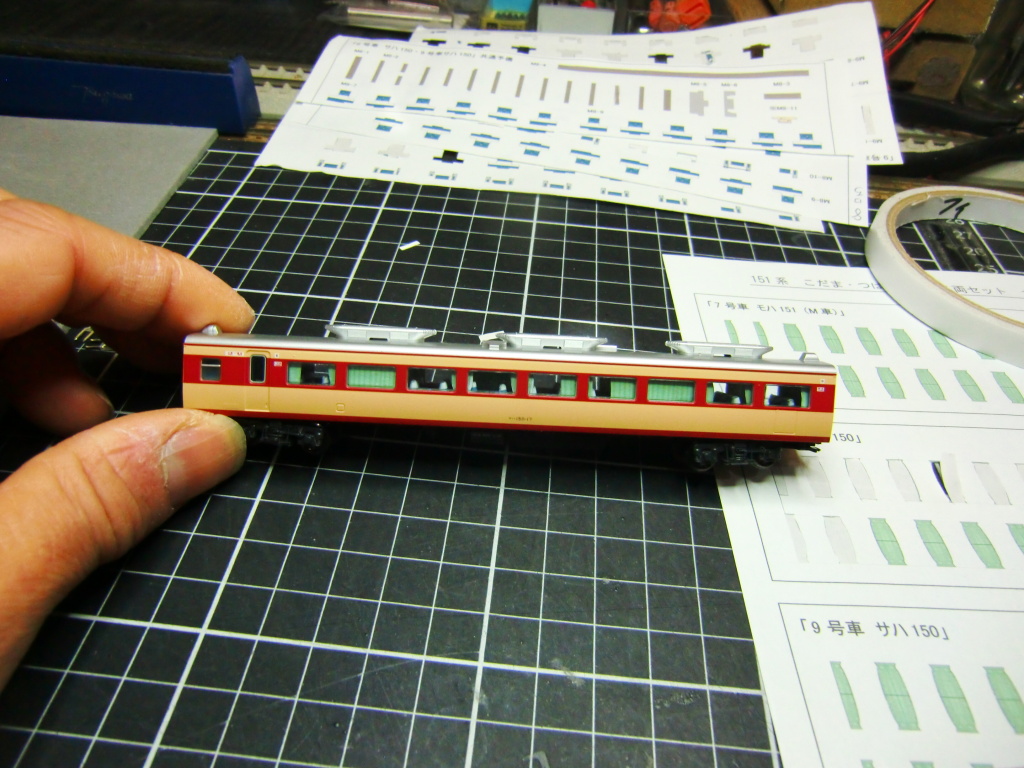

いままでご依頼を受けた中でも一番きつい作業かもしれません。相当な時間をかけているはずなのですが、なぜかあまり進んでいる気がしません。次回からこの手のご依頼はお受けするかどうか充分検討する必要がありそうです。
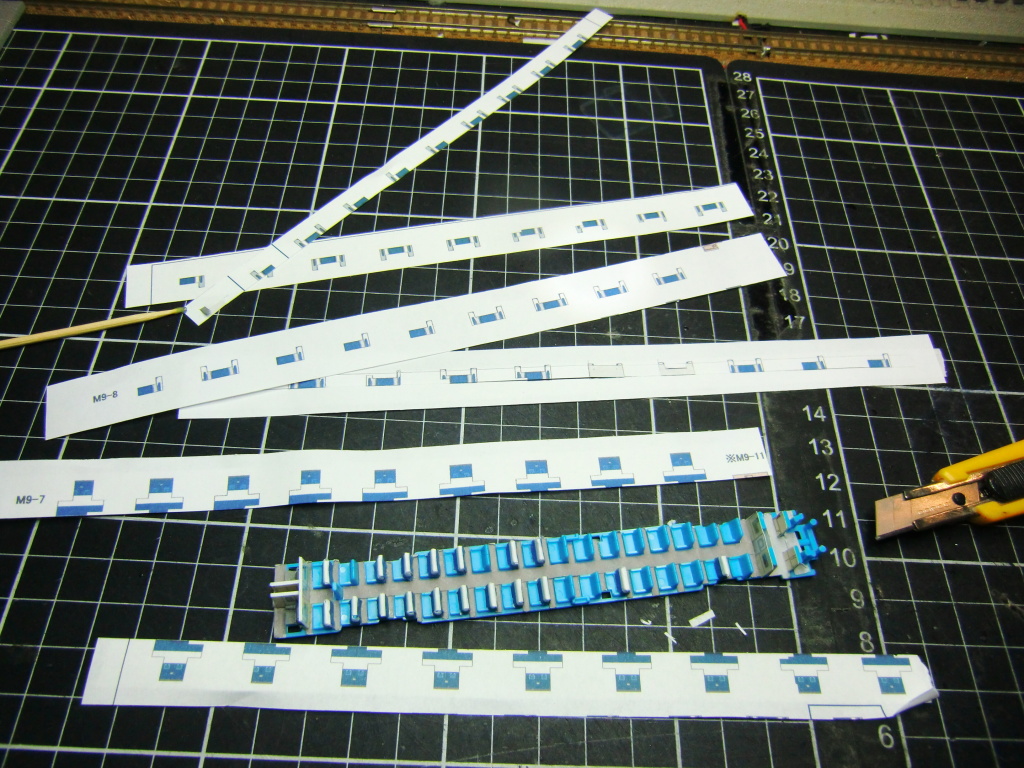
まだまだ先は長いです。
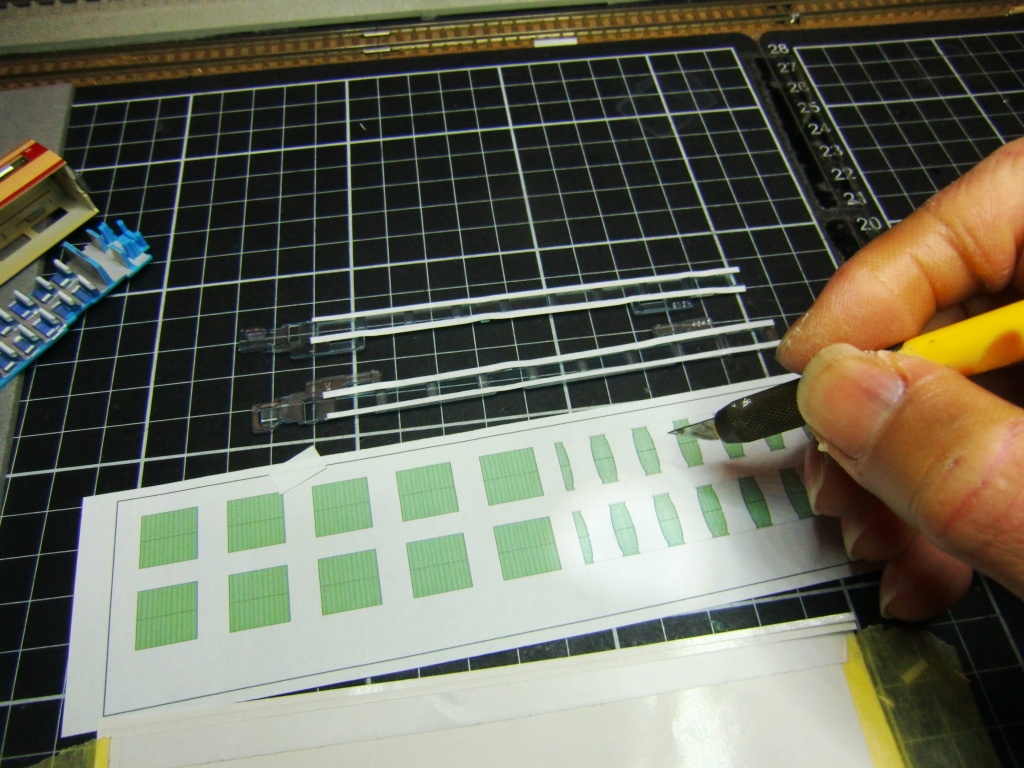
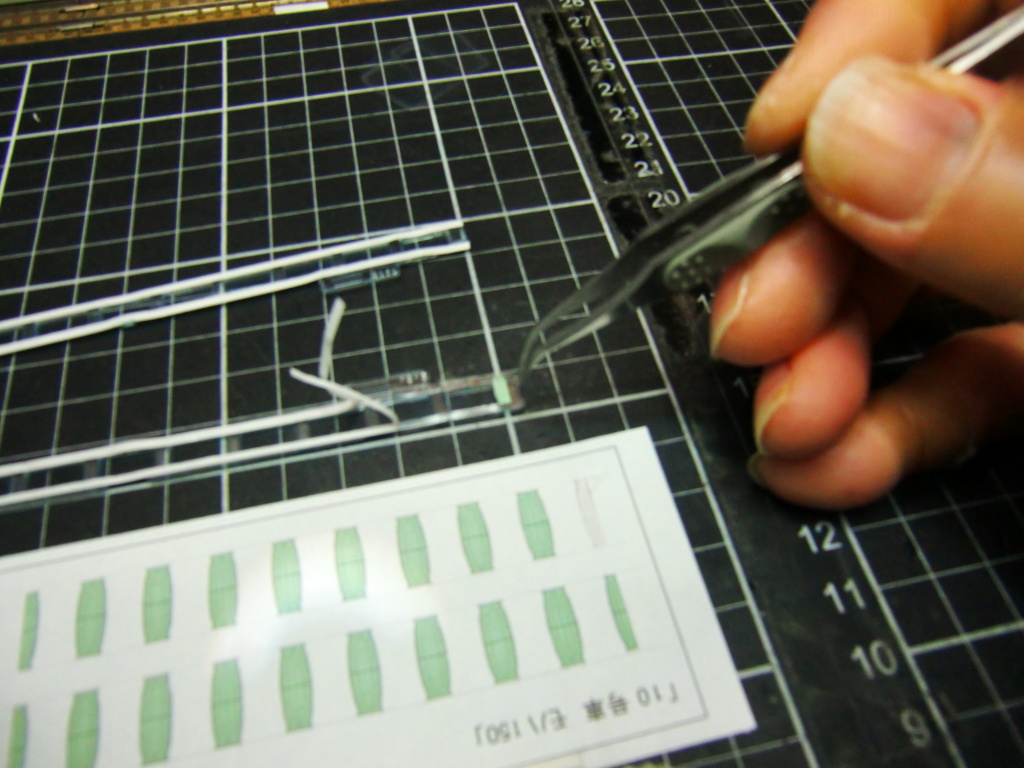
カーテンの貼り付けは、まず窓ガラスをクリーナーで洗浄してから、2mmにカットしたフィルムタイプの両面テープをガラスの裏面の上下にそれぞれ貼ります。次にカーテンを切り抜いてから2つ折りにして位置を確認しながら1枚ずつ貼りつけていきます。1枚のカーテンを貼るにも大変な時間と手間がかかる作業です。正直、かなりきついです。普段シールを貼りなれていない人にとってはかなり厳しい作業になると思われます。ここで1つ疑問に思ったのですが、シールにして2つ折りする必要があるのだろうか?といった点です。1枚の用紙を両面印刷することで、作業が大幅に軽減されるのでは?と思った次第です。
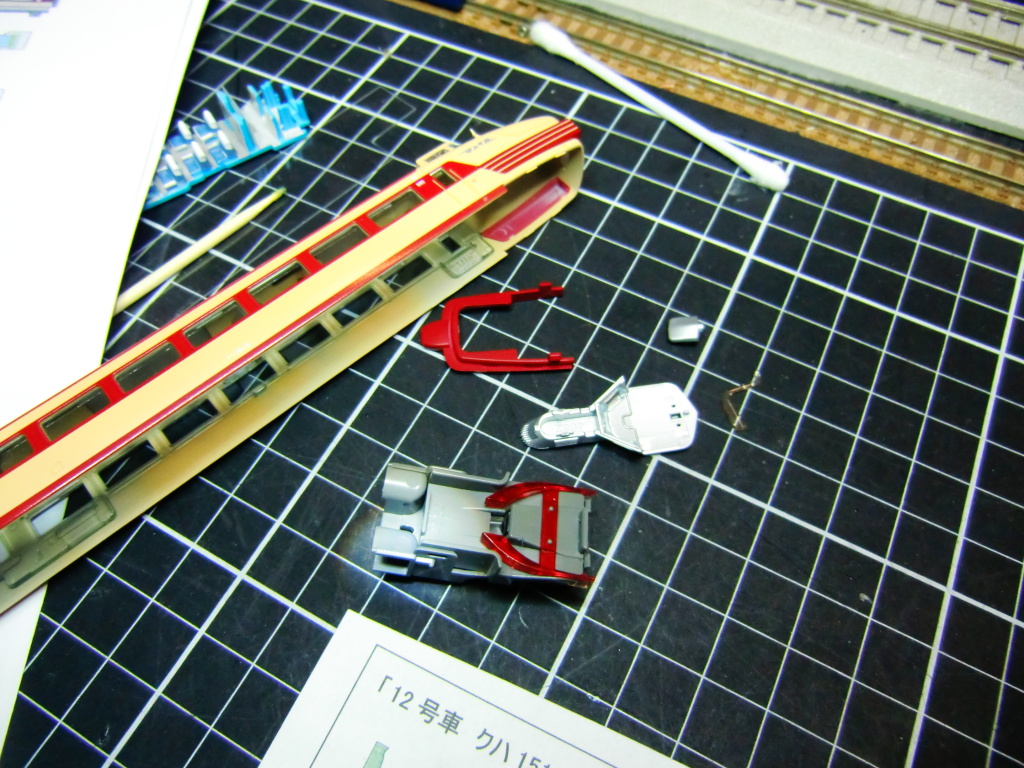
先頭車の窓ガラスを外すには、まずはライトユニットも全部外さなくてはならない。上の屋根を外し導光材を抜き、ユニットをプライヤーで引き抜きます。
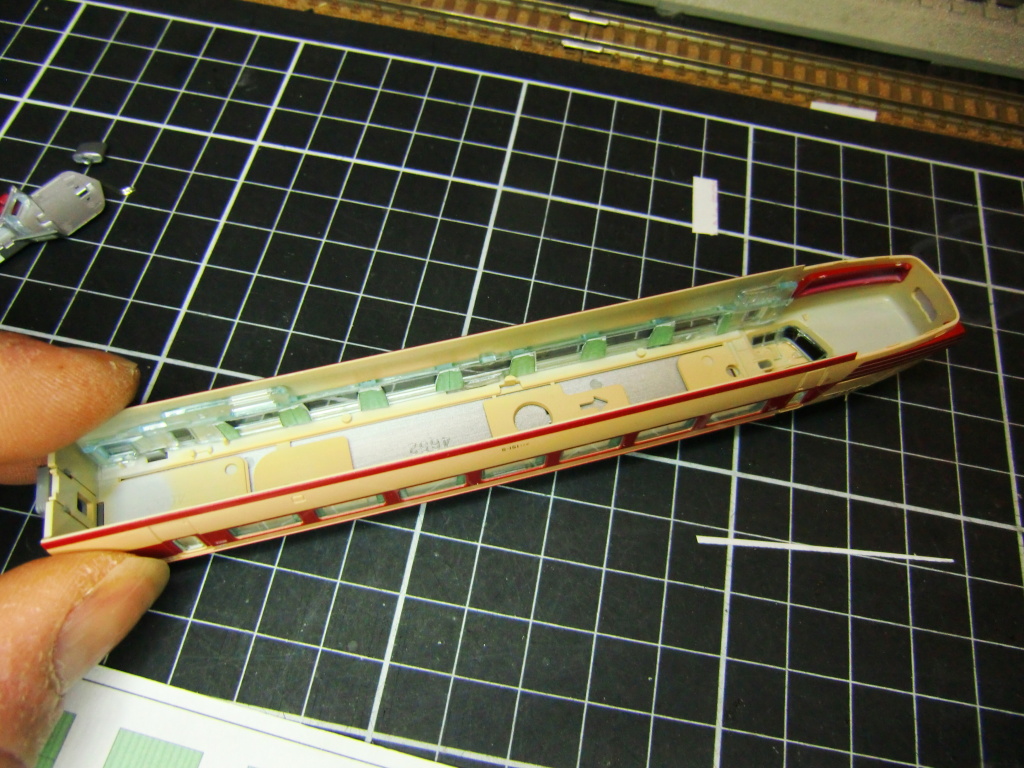


次に1号車ですが、「こんなにあるよ~」
だんだん頭が痛くなってきました。一般的な付属シール貼りのご依頼と違い、とにかく時間と手間を必要とします。
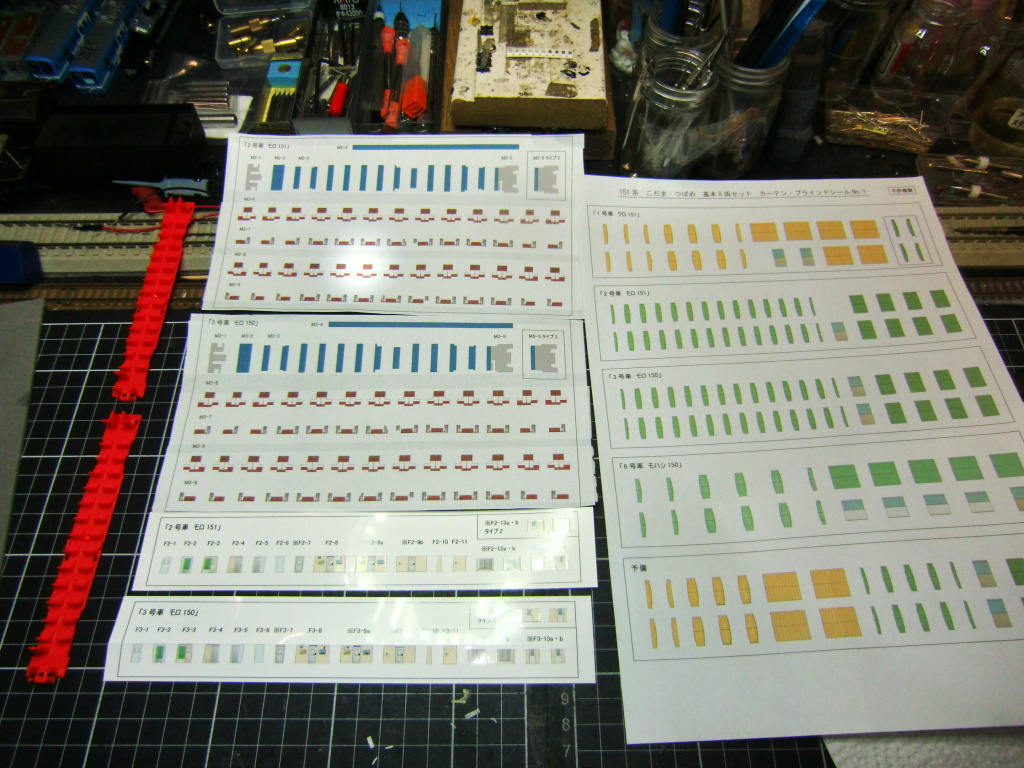
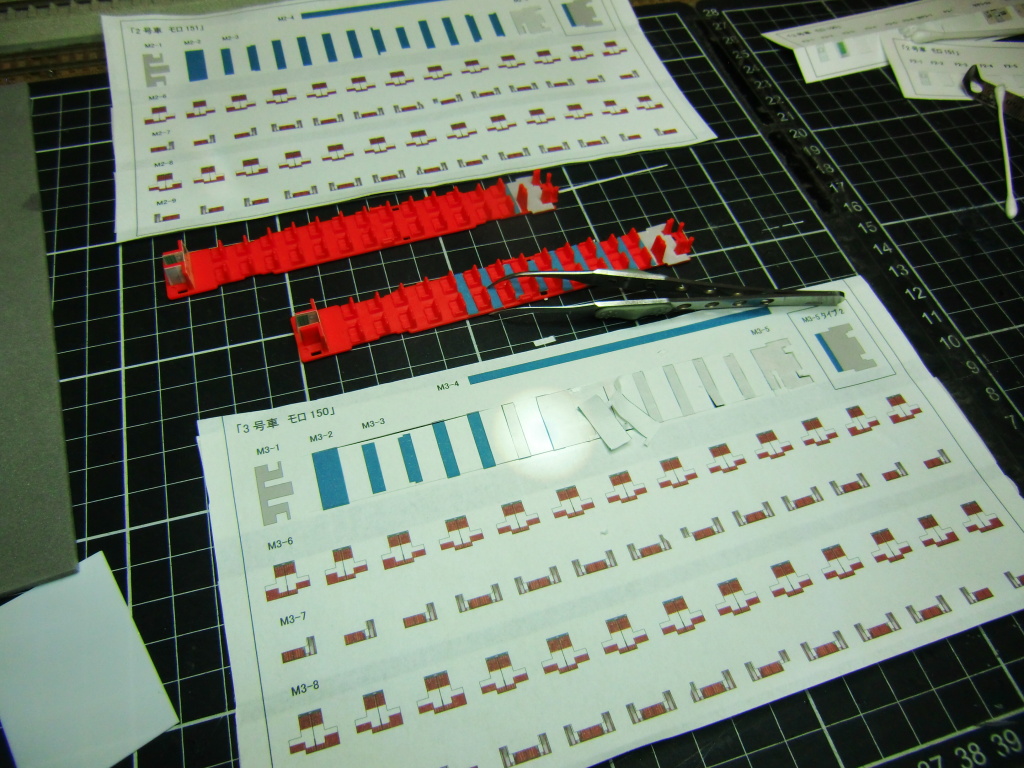
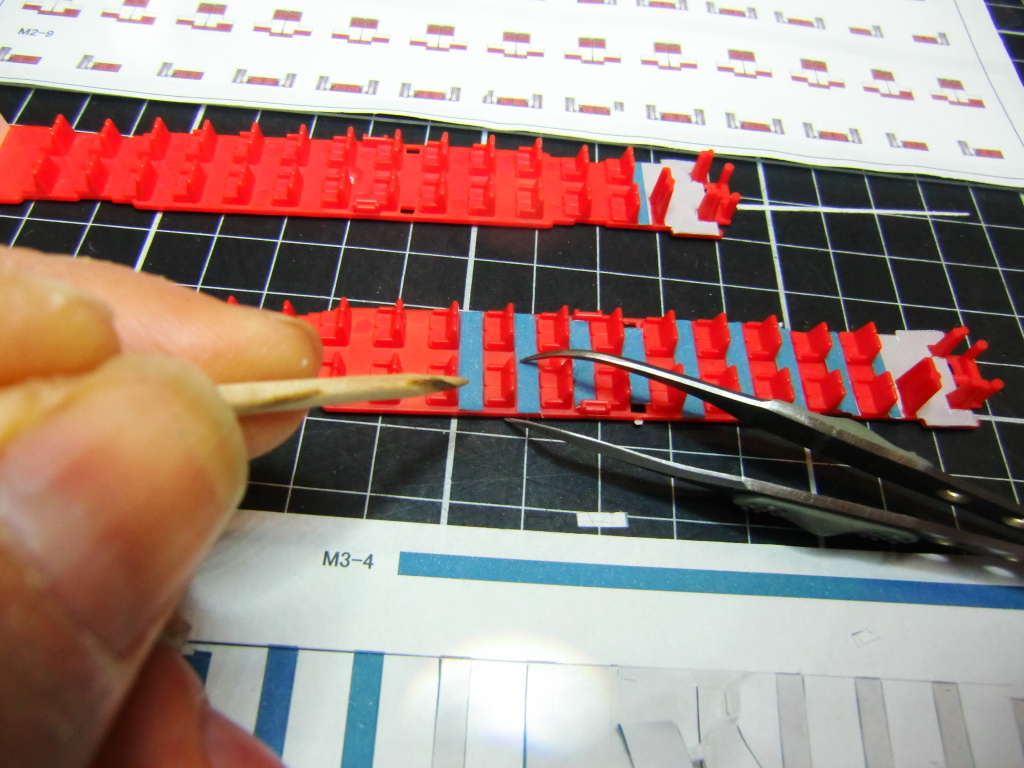
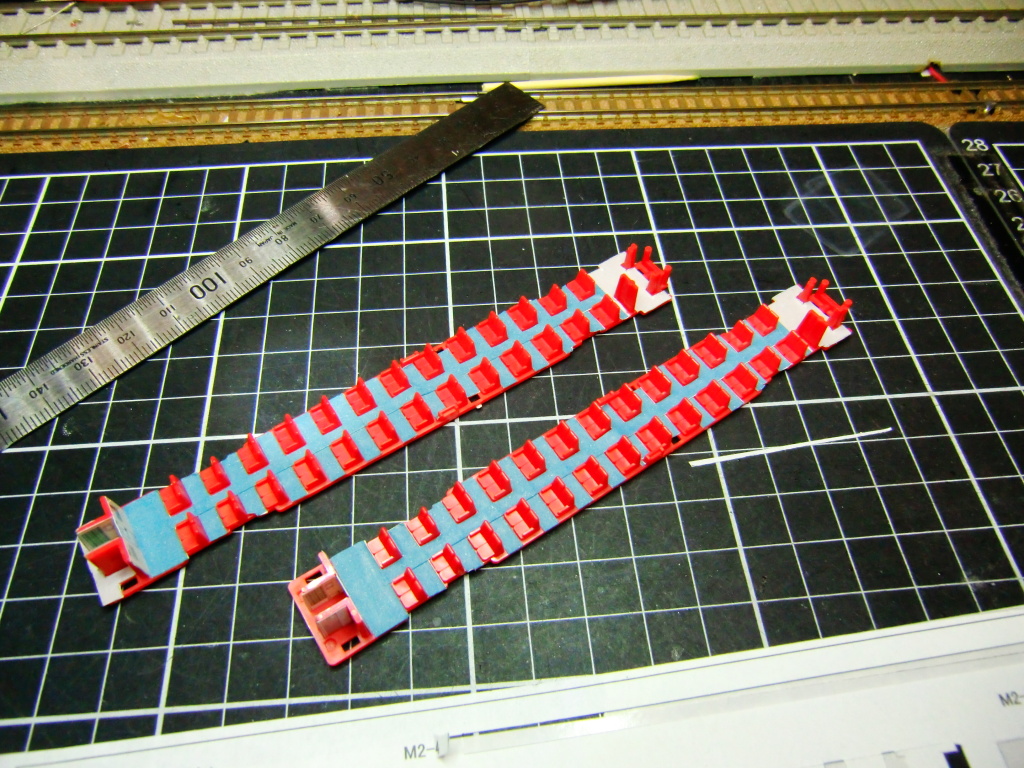
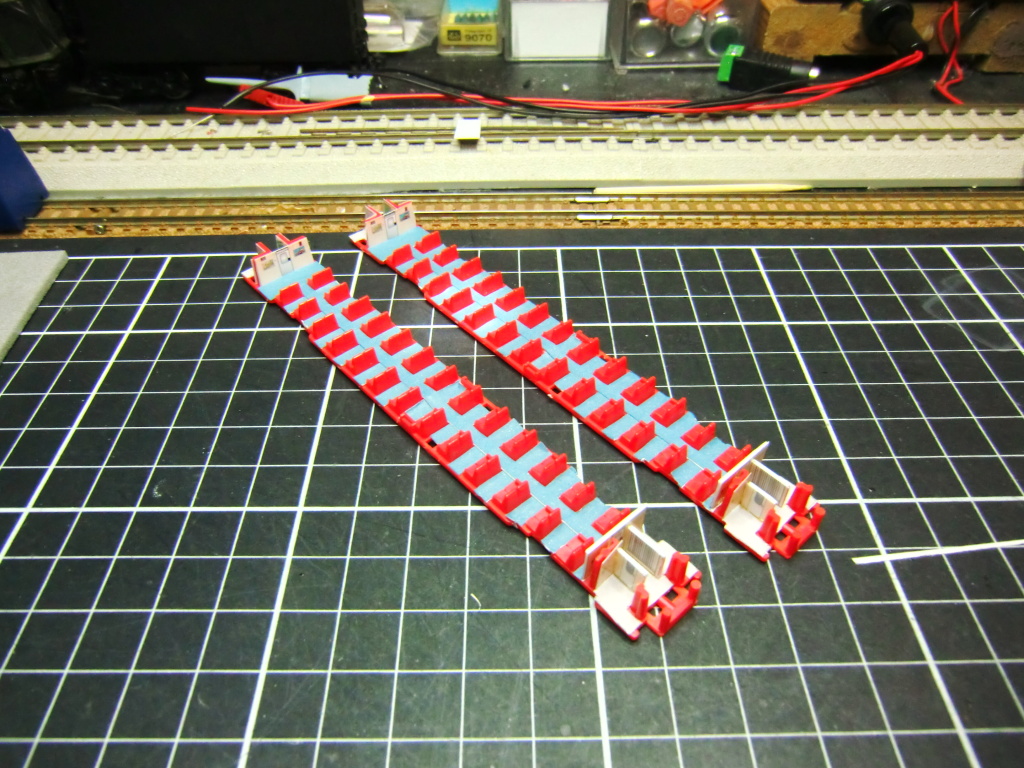
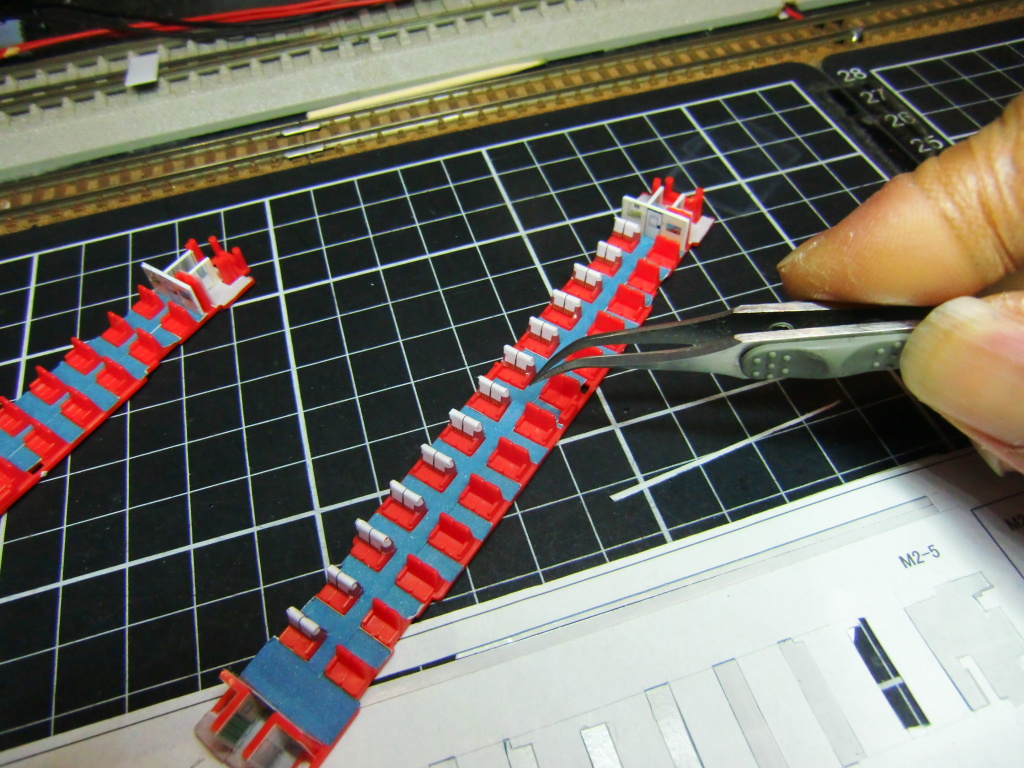
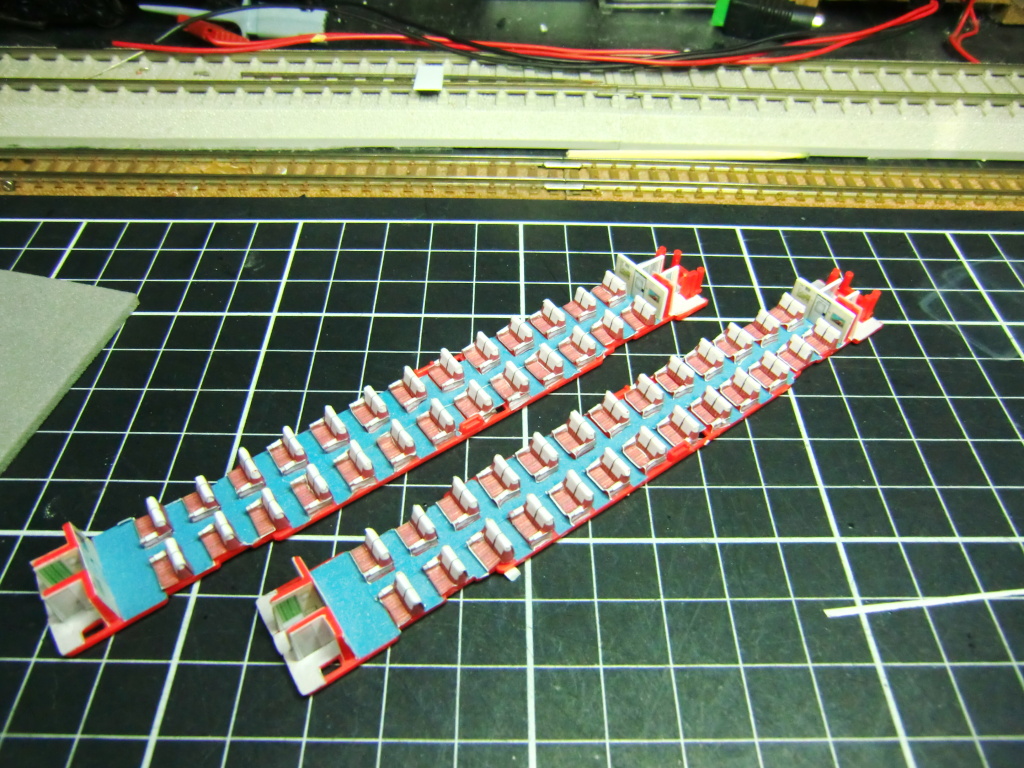
眼の疲労がひどくなってきました。残すは4両というところまできました。
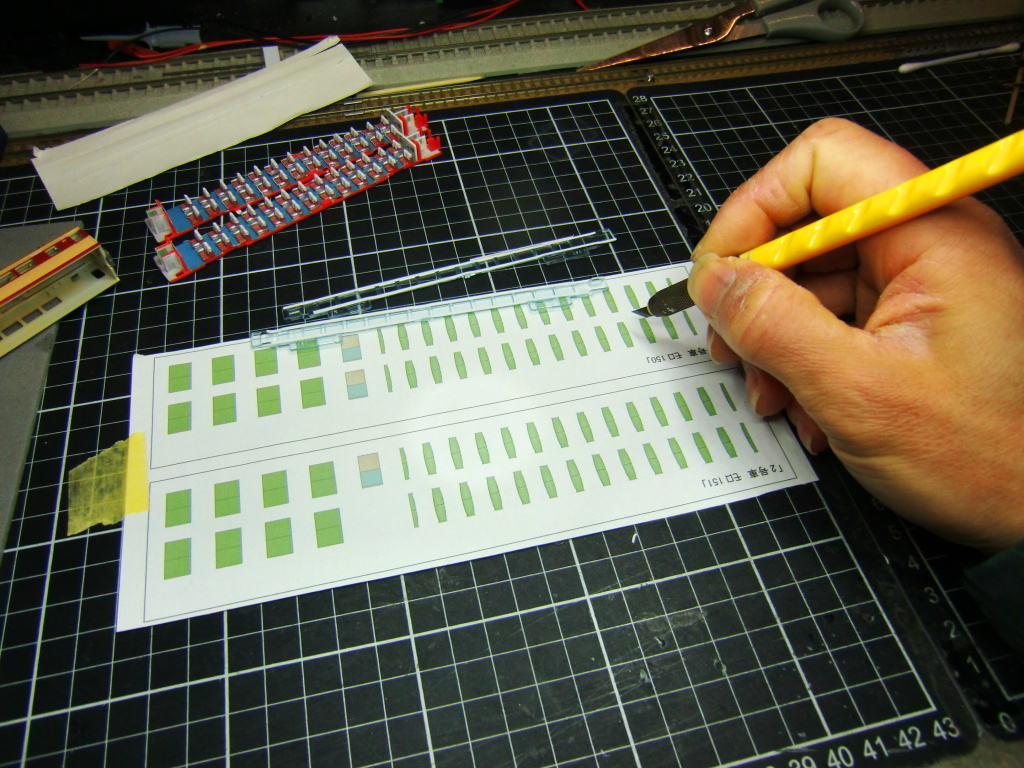

座席の貼り付けが終っても、カーテンの貼り付け作業も待ってます。
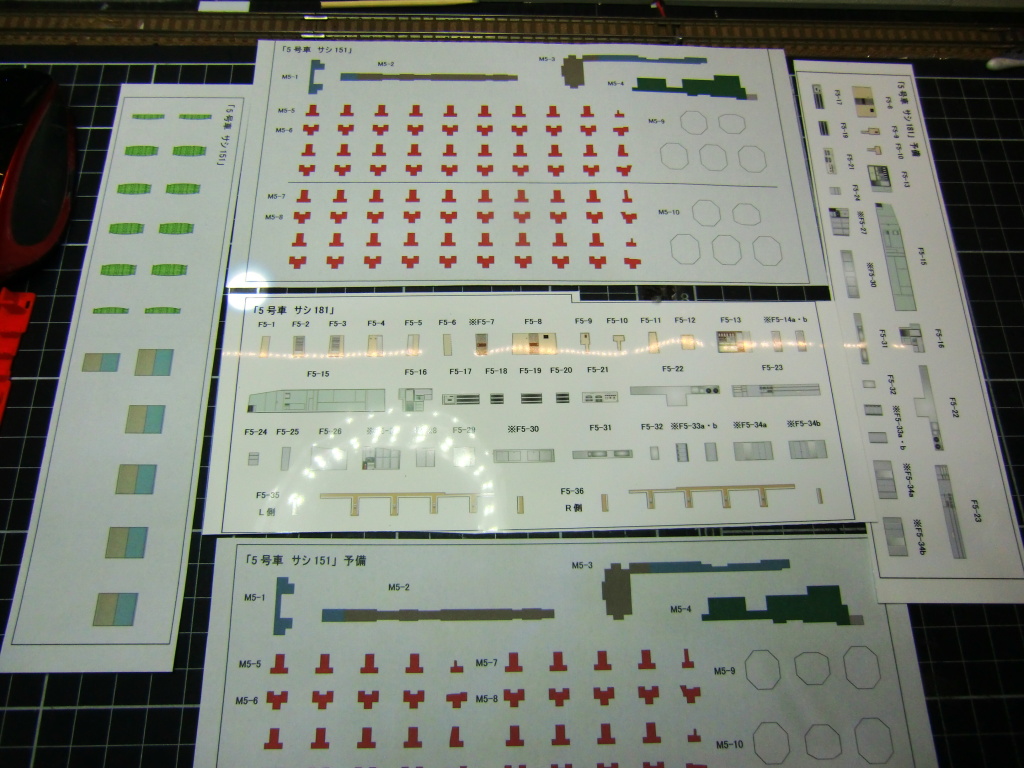
ここ何日もこのシール貼り作業の連続でしたから、この辺りでちょっとお休みです。さすがにちょっと気分が悪くなってきました。
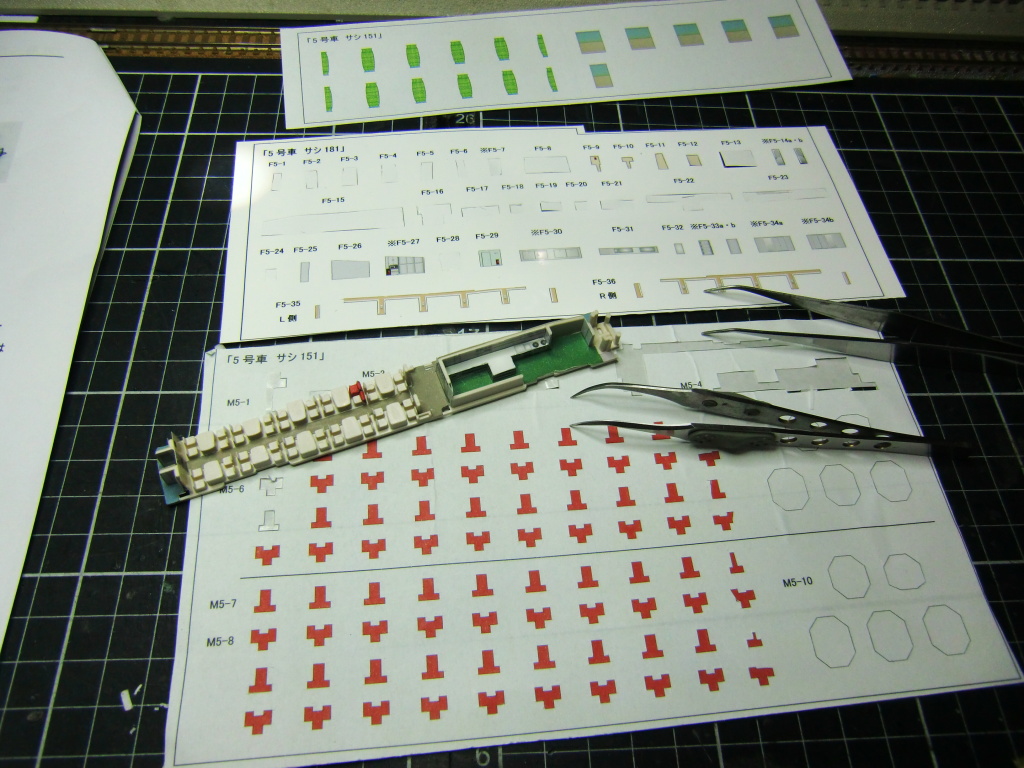
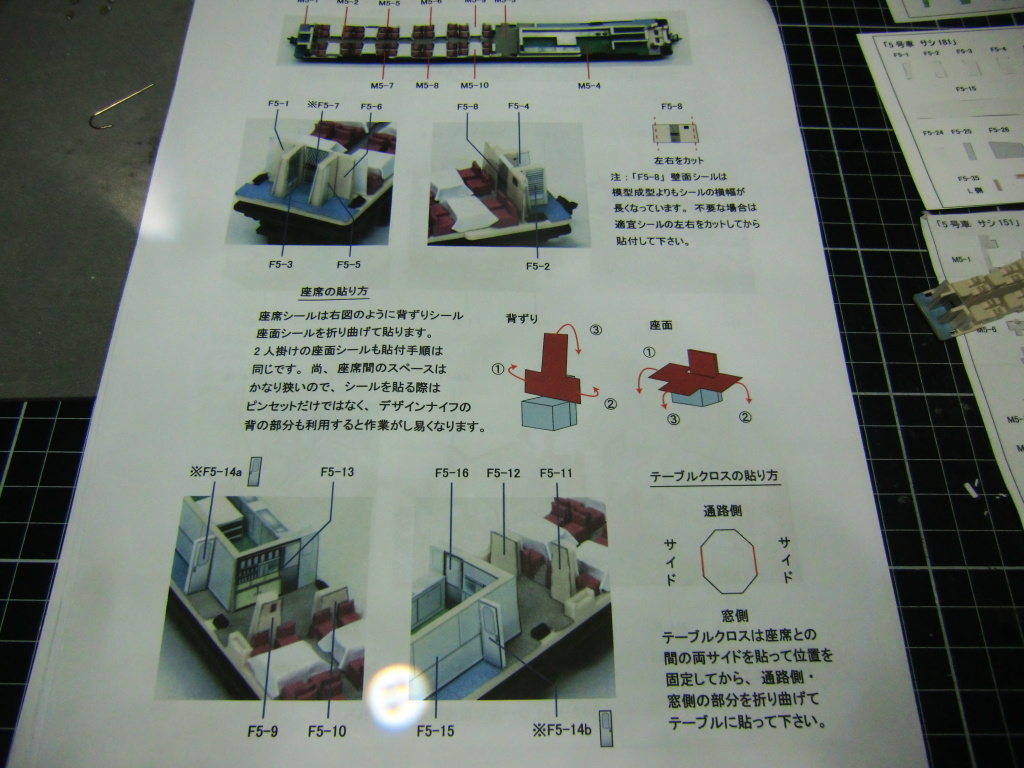
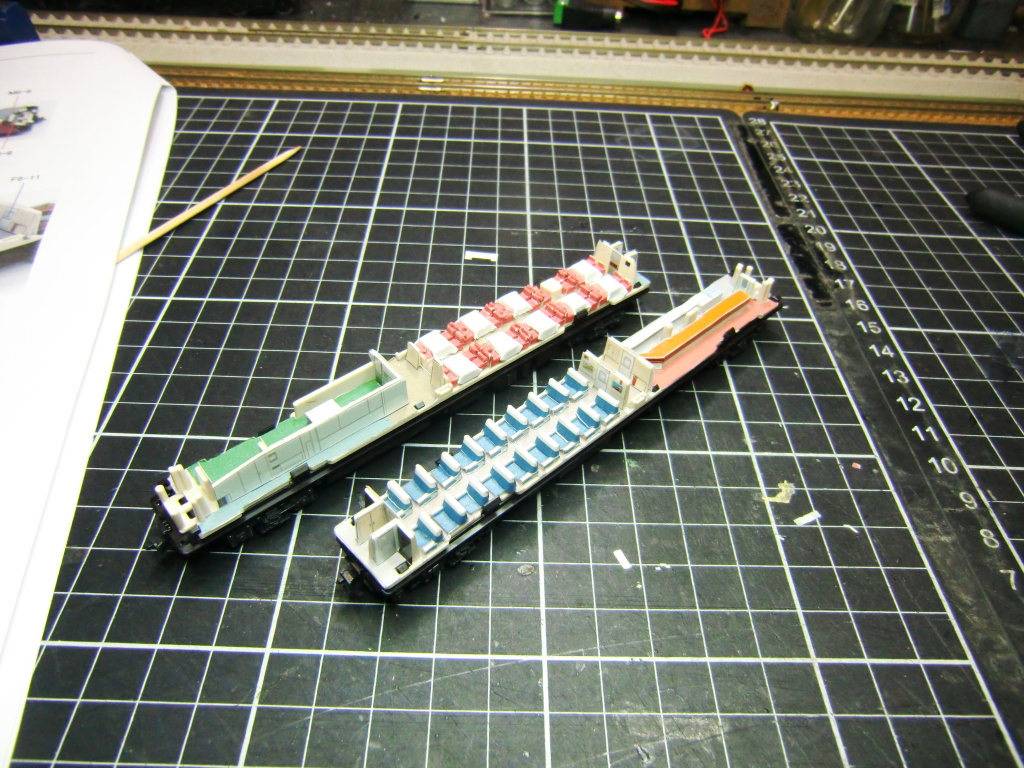
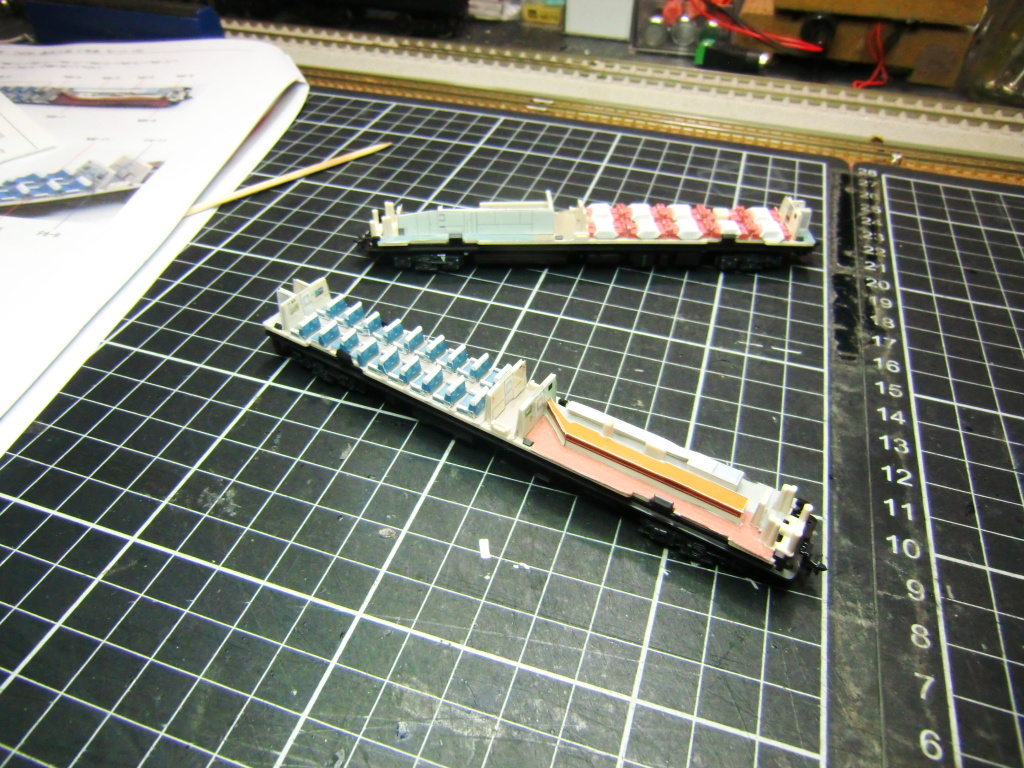
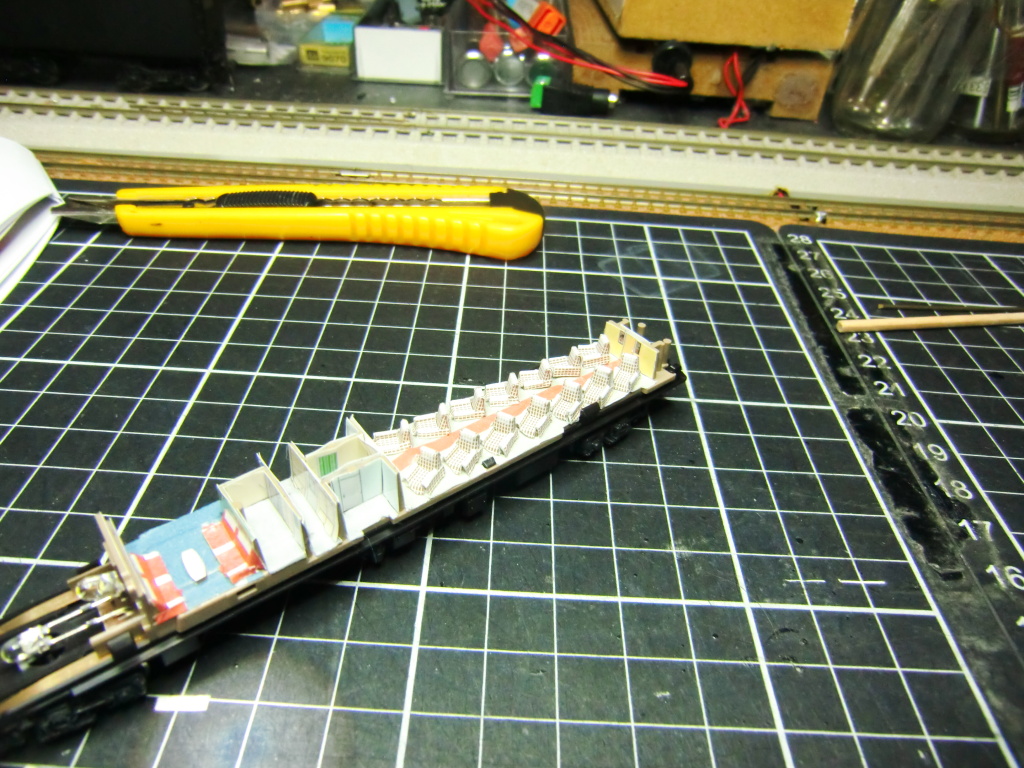
残りの1号車を仕上げます。
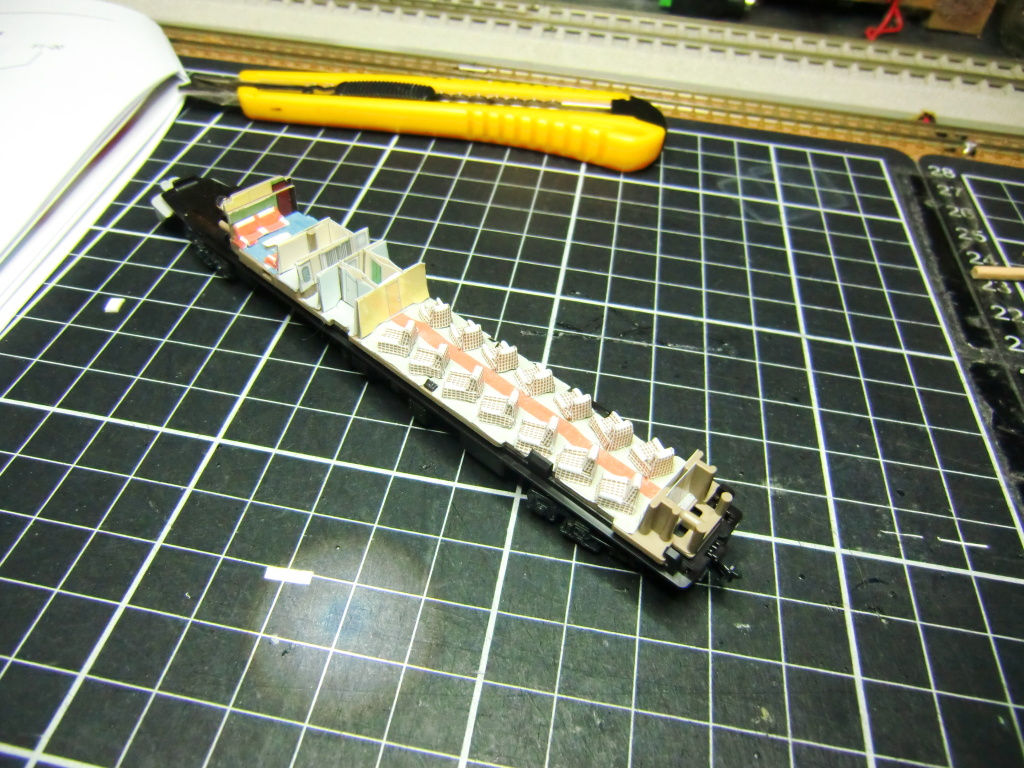

ようやく作業完了です。長かった~

▼C59 ロッド損傷/モーター不動/OH/ヘッド点灯化

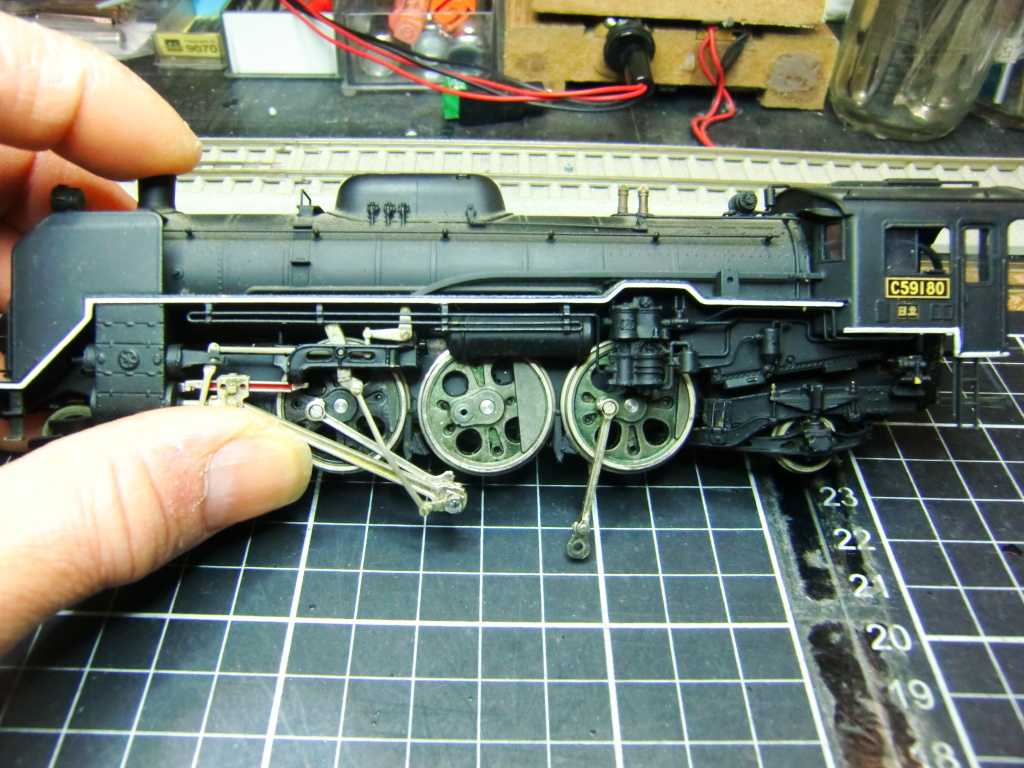
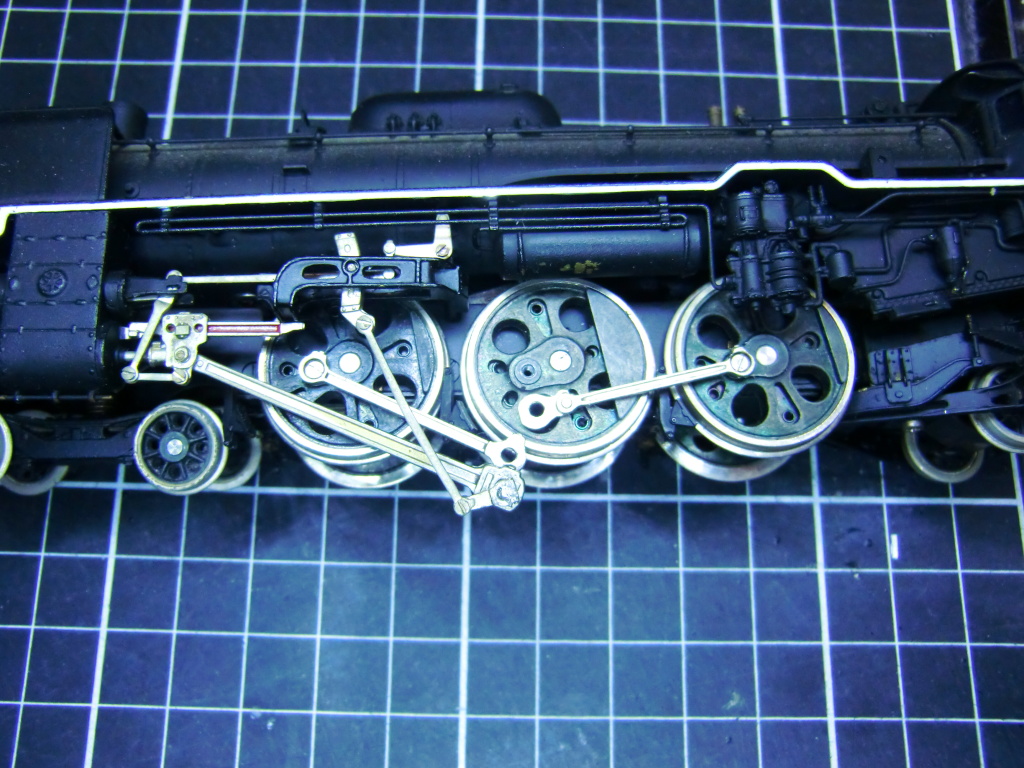
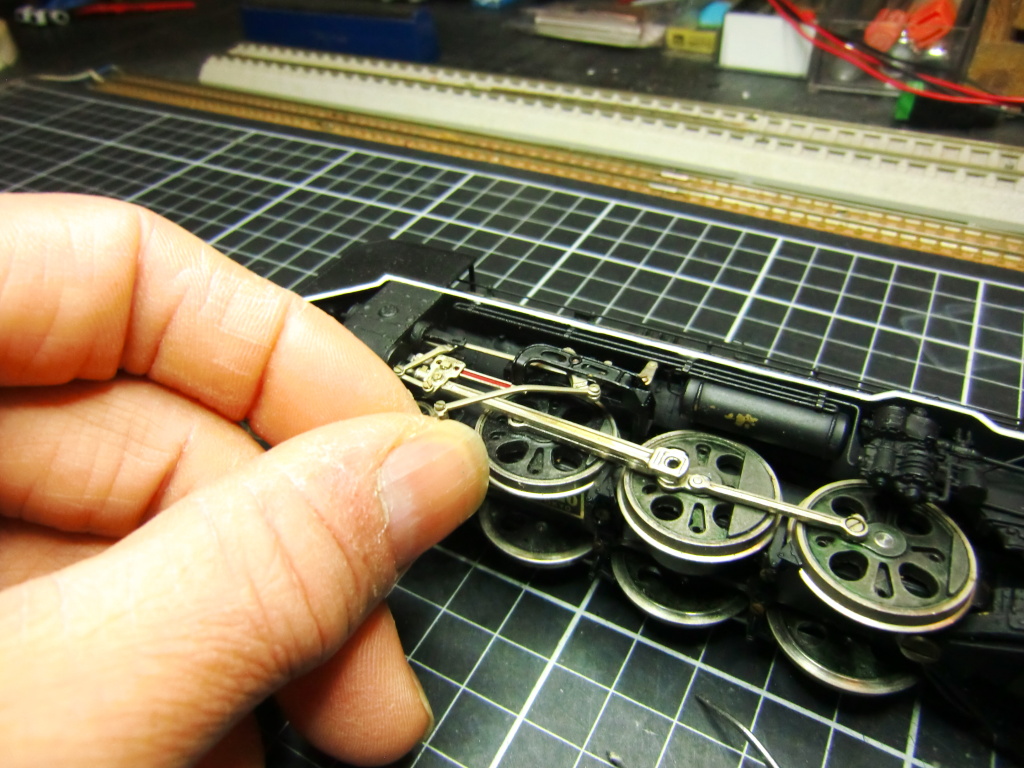
パーツが変形しています。プライヤーで戻します。
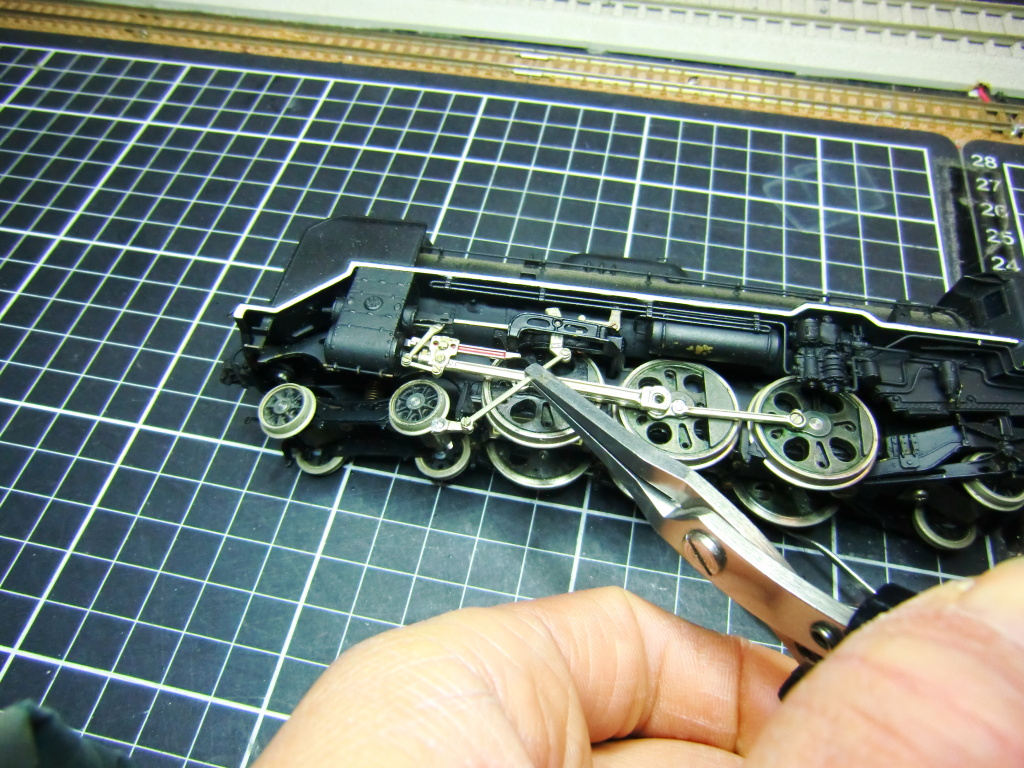
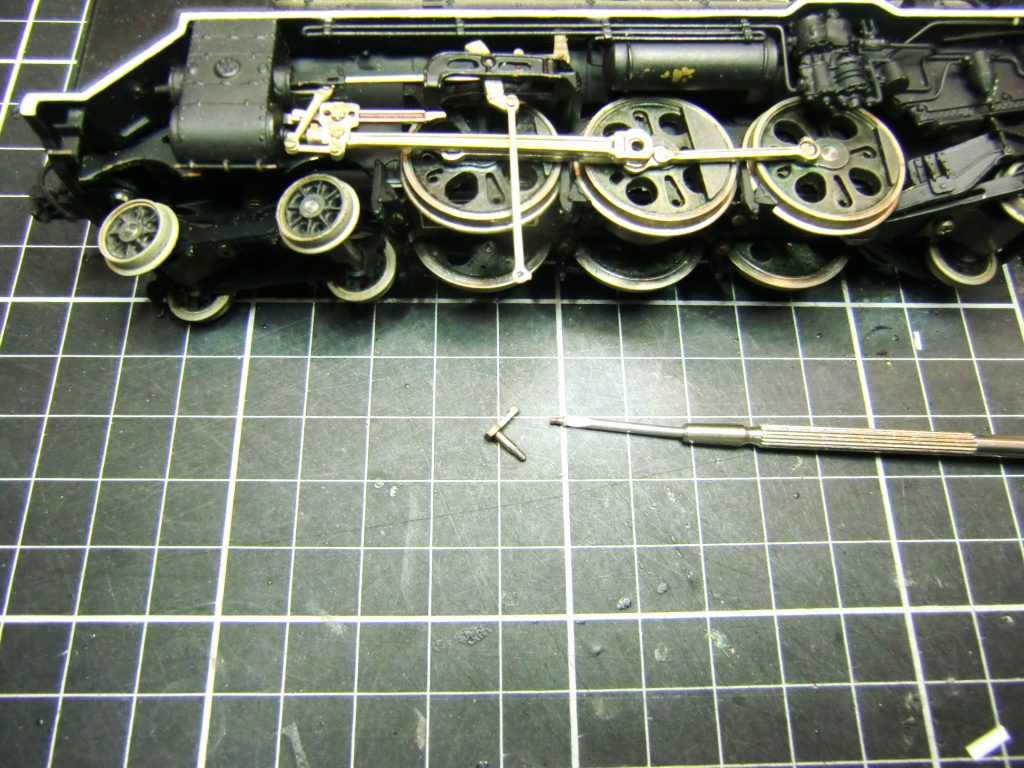
こちらも変形してしまっています。プライヤー2本を折れないように注意しながら少しずつ戻します。
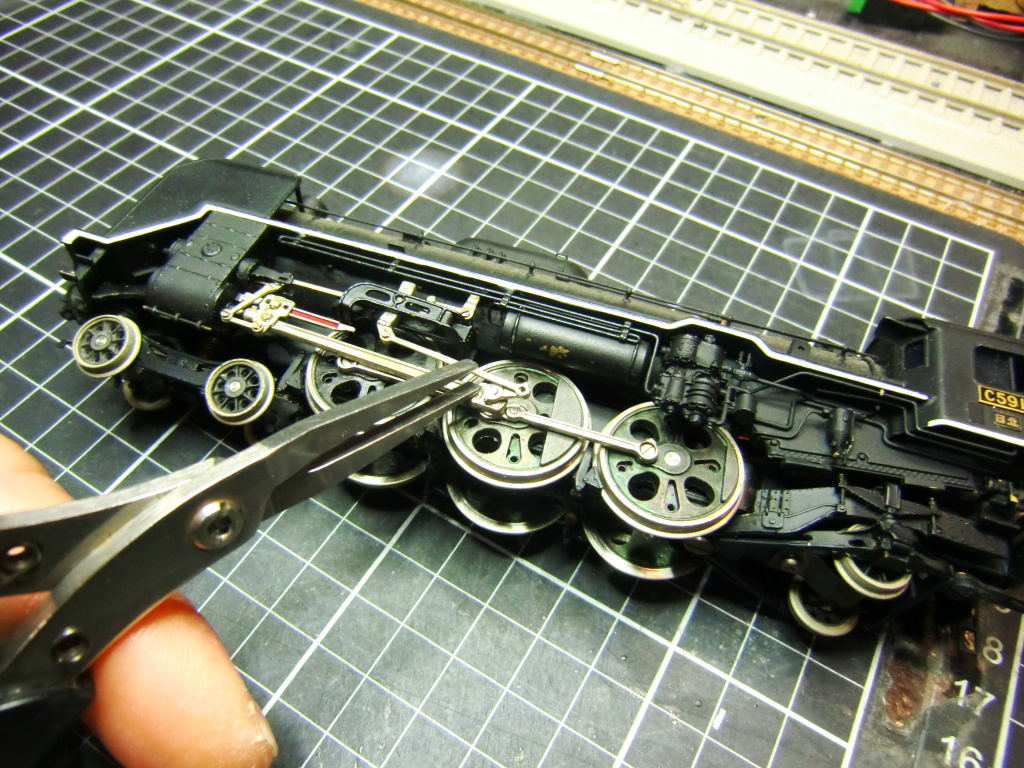
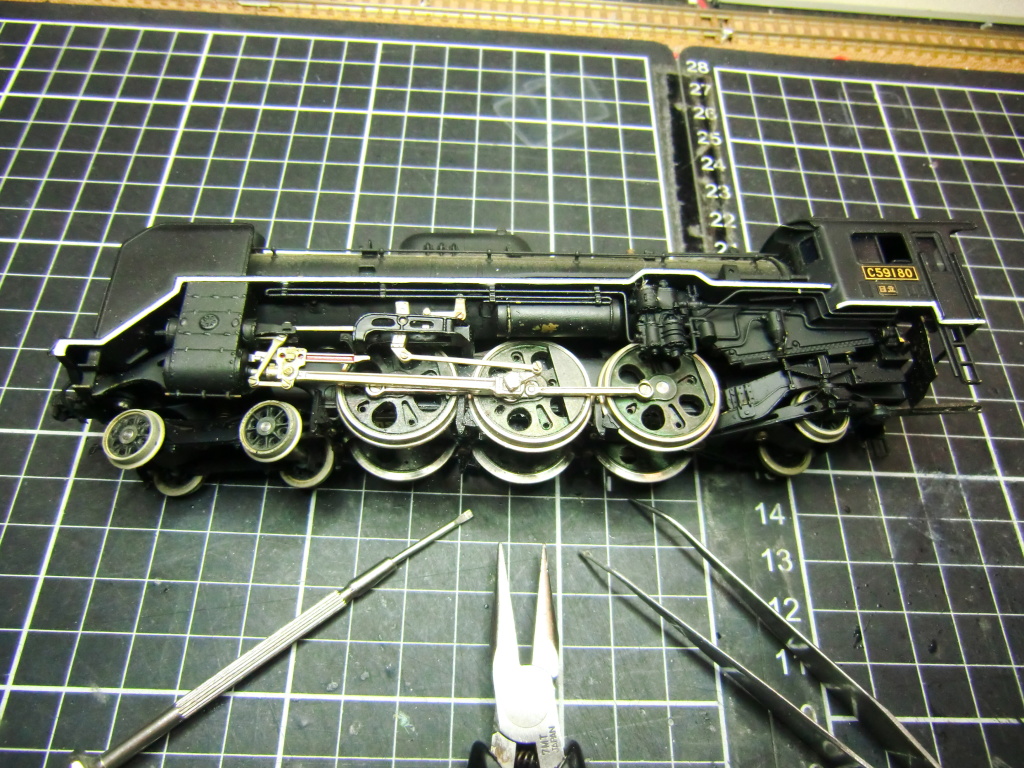
ピン中央がグラグラしているため、ハンダを流したのちルーターで削って平らにします。

左:車輪磨き出し後、右:磨き出し前
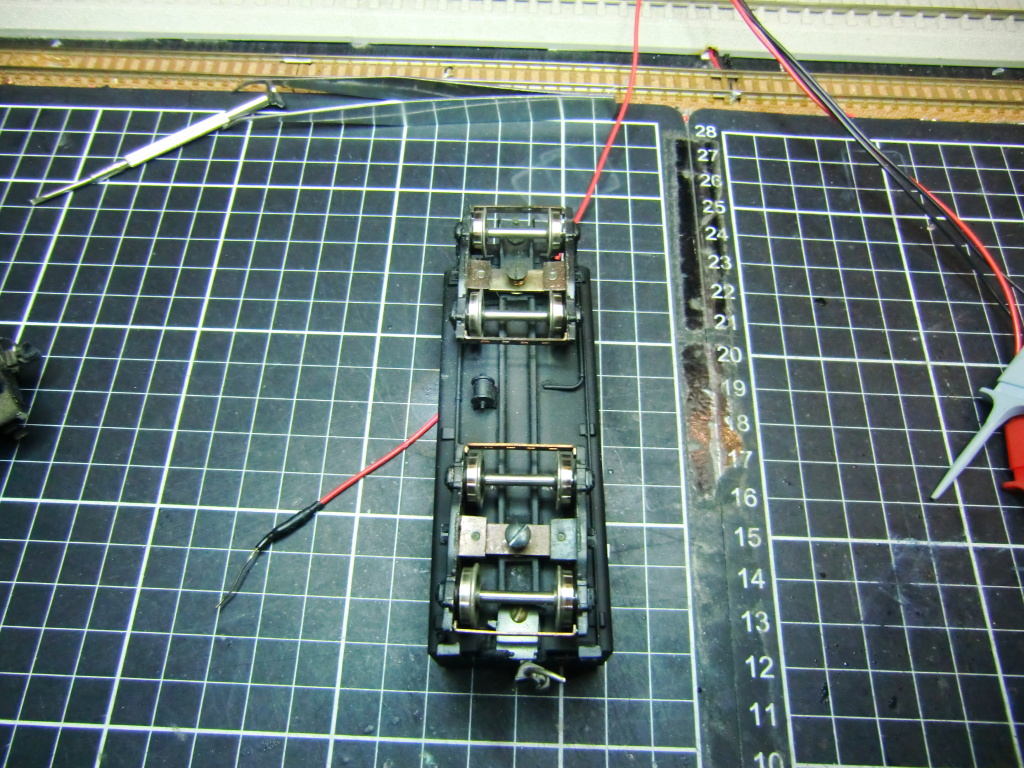
まずは、車輪をピカピカに磨きだします。

次に台車を分解して各部接点を磨き出して、1つ1つ集電状態を確認していきます。

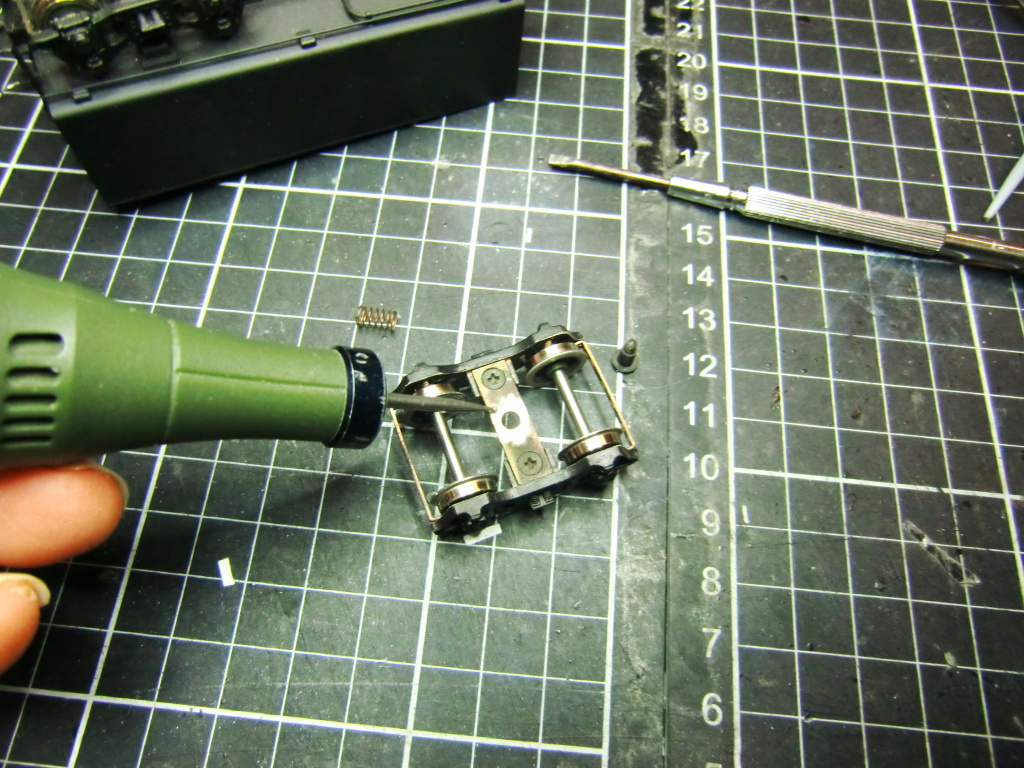
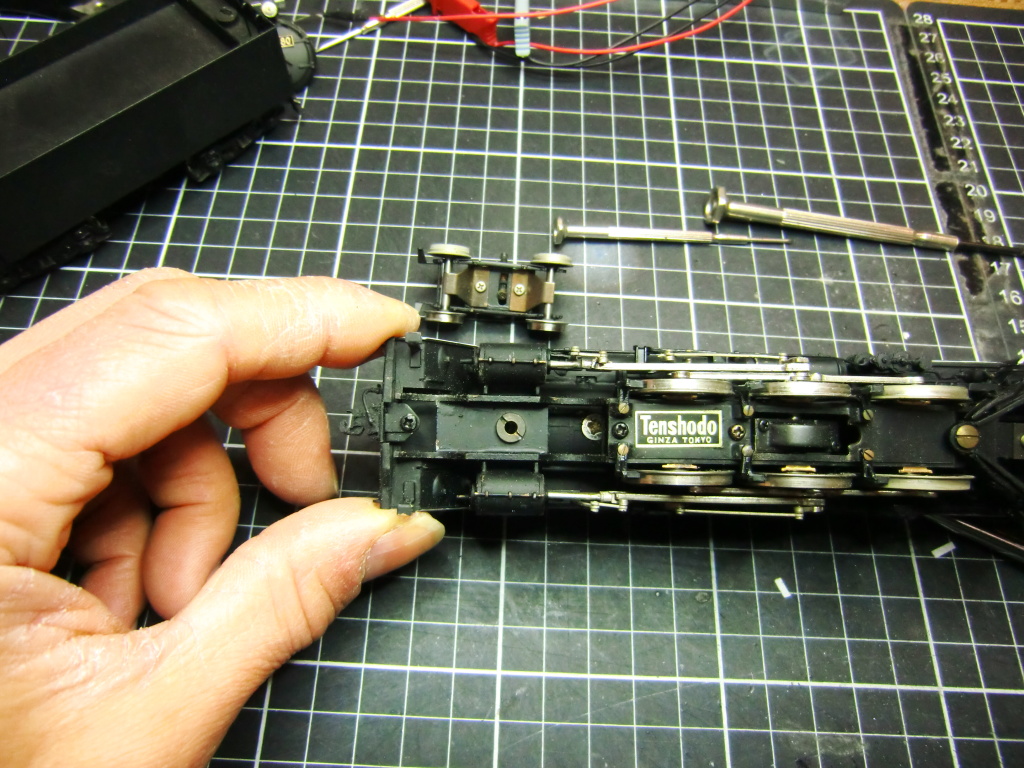
ここから機関車の本格的な修理作業です。
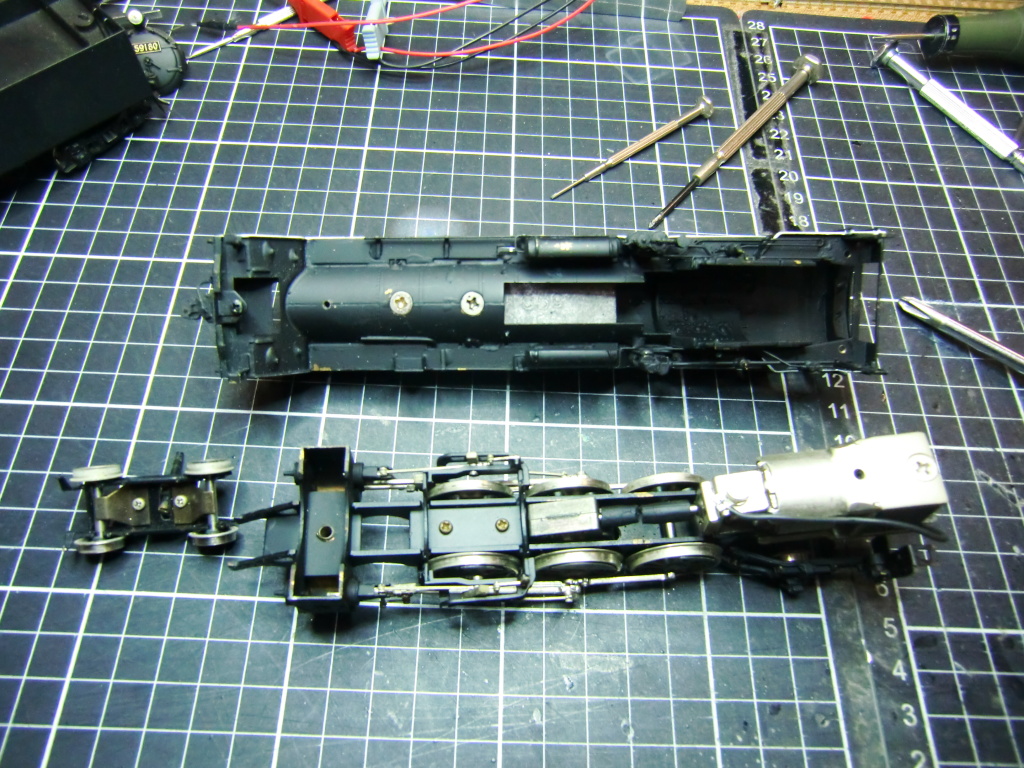
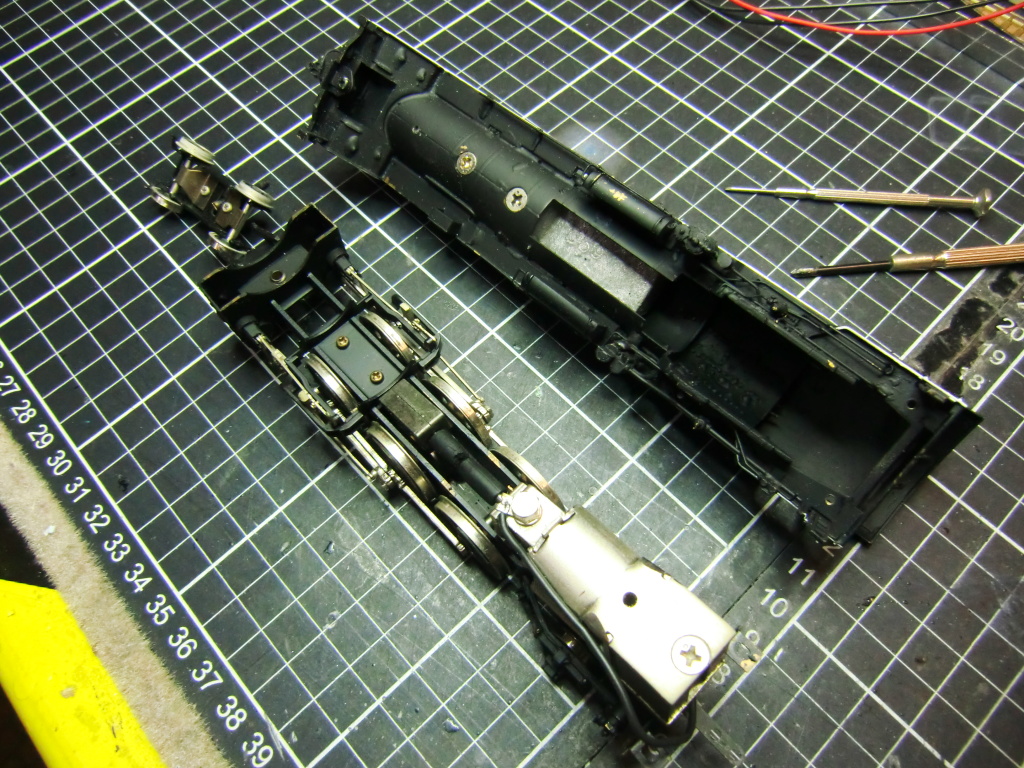
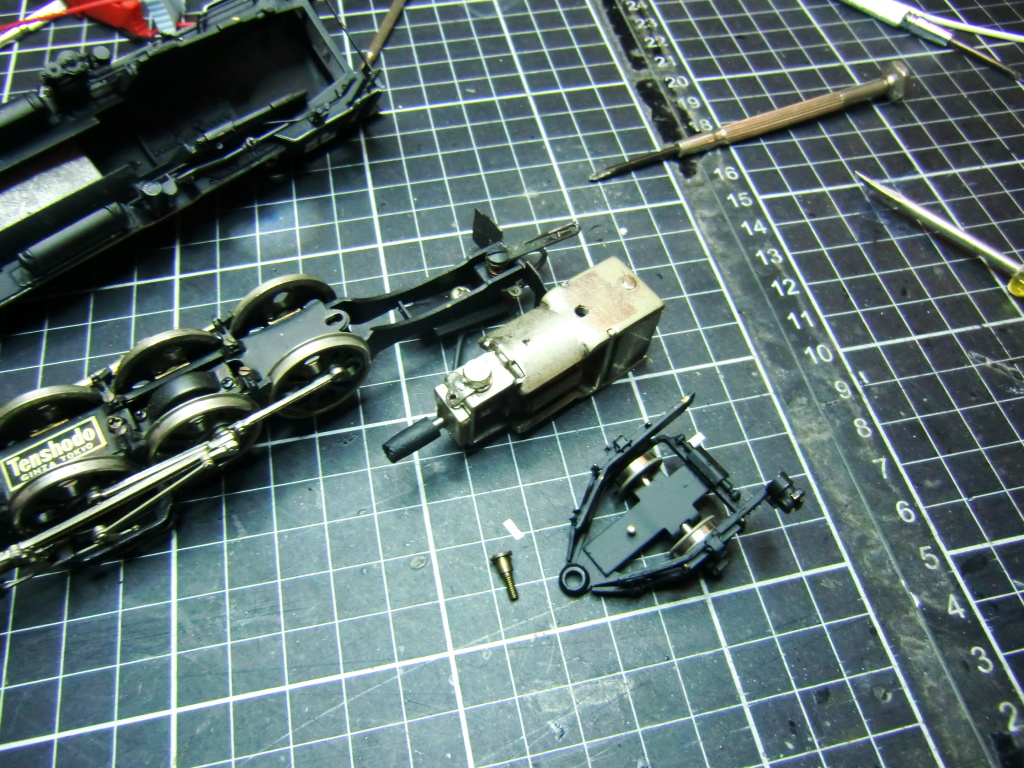
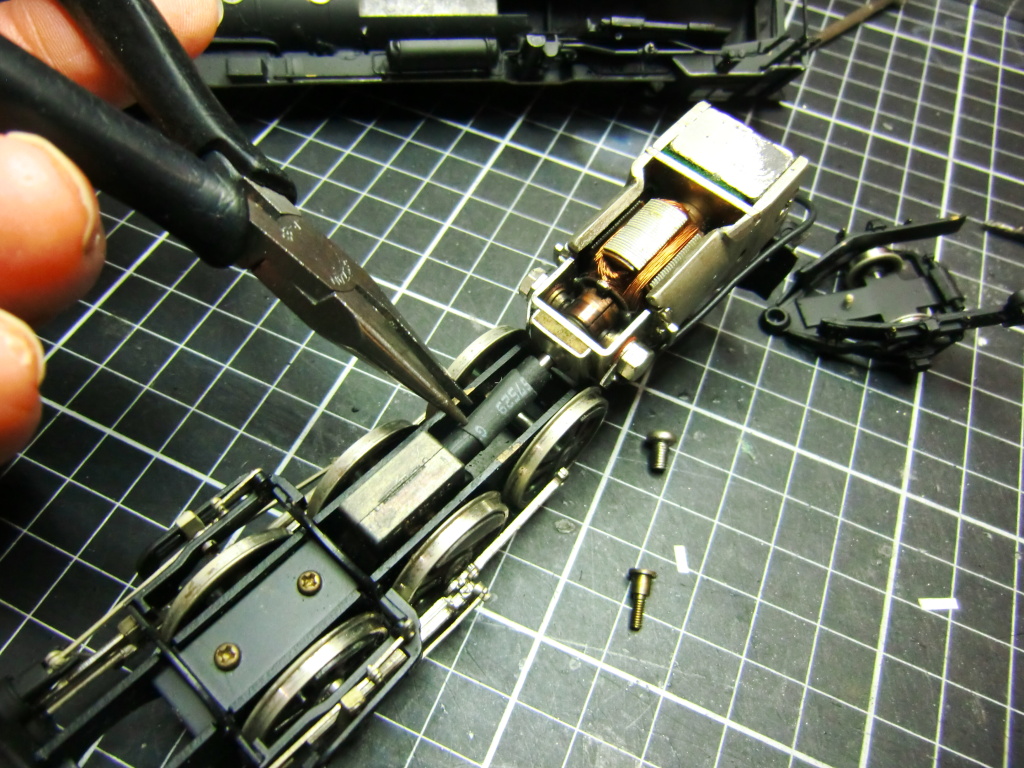
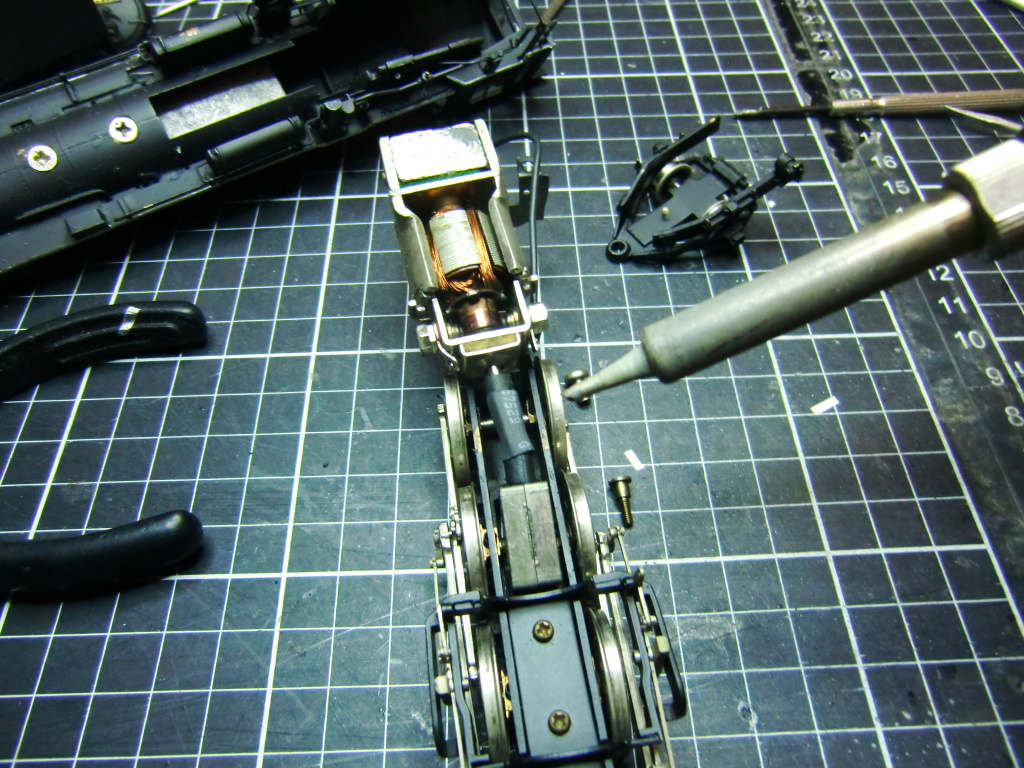
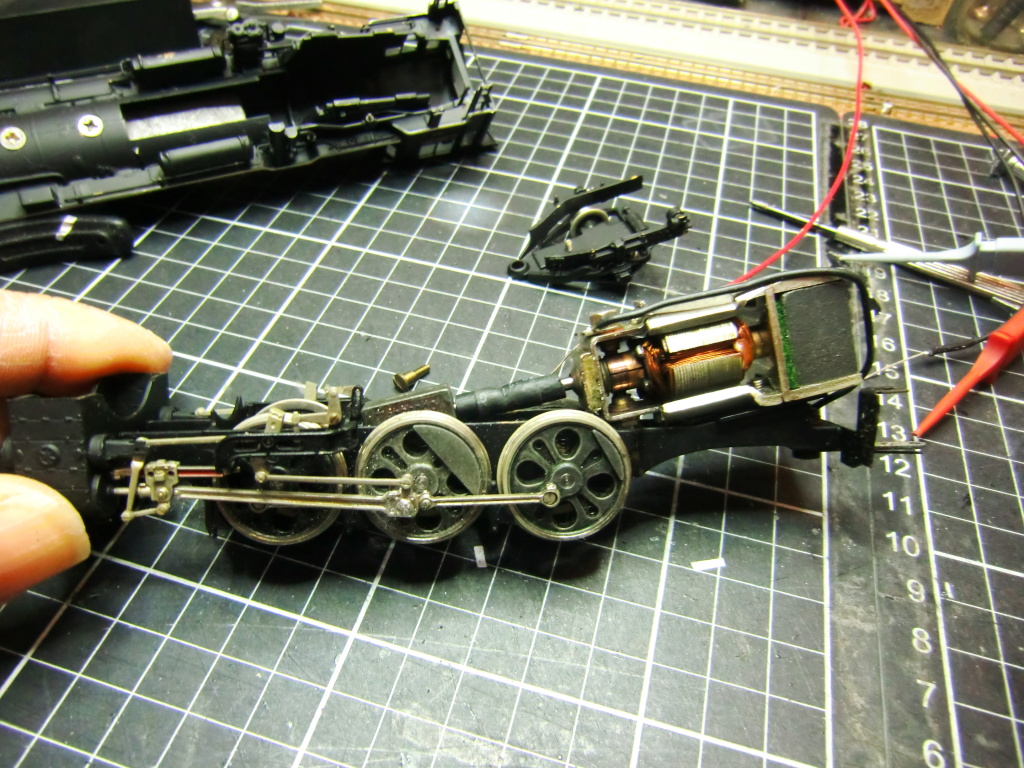
分解と調整、確認を繰り返してモーターがスムーズに回るまで行います。

最後に機関車側の車輪をすべて磨き出して集電を復活させます。
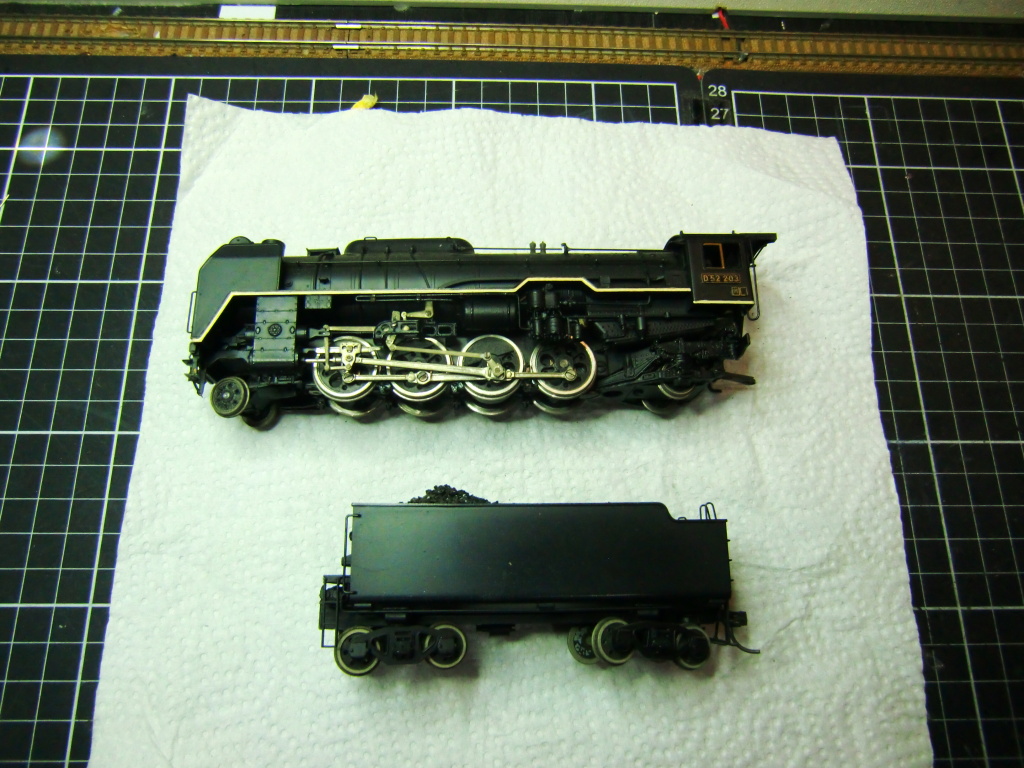

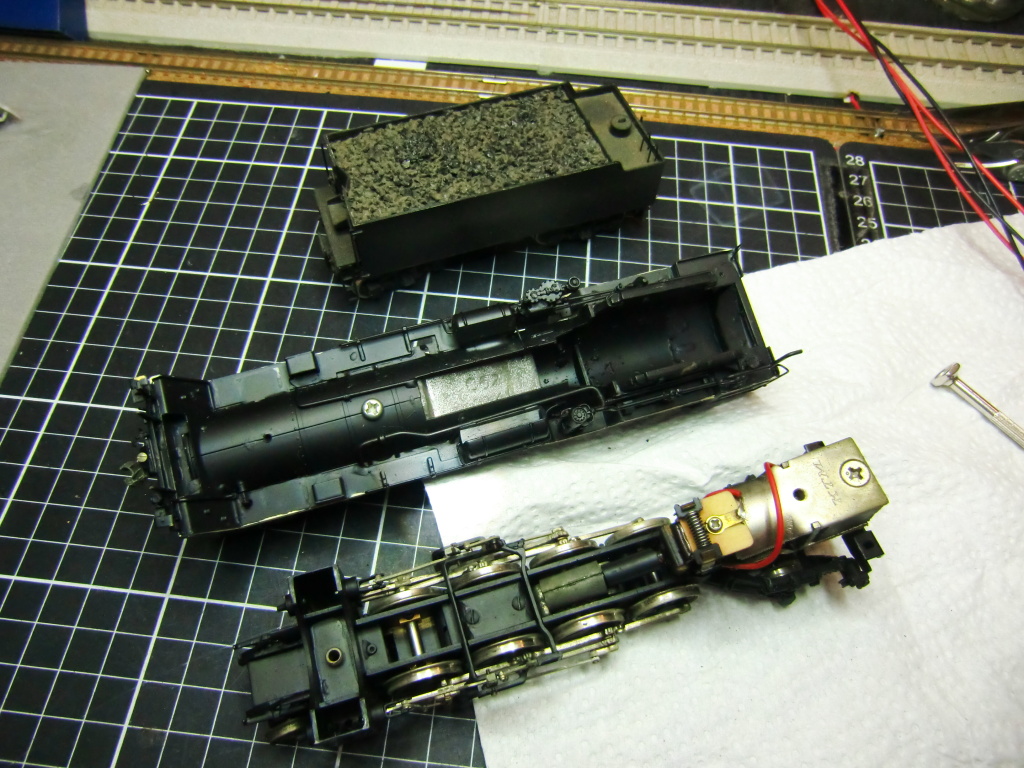
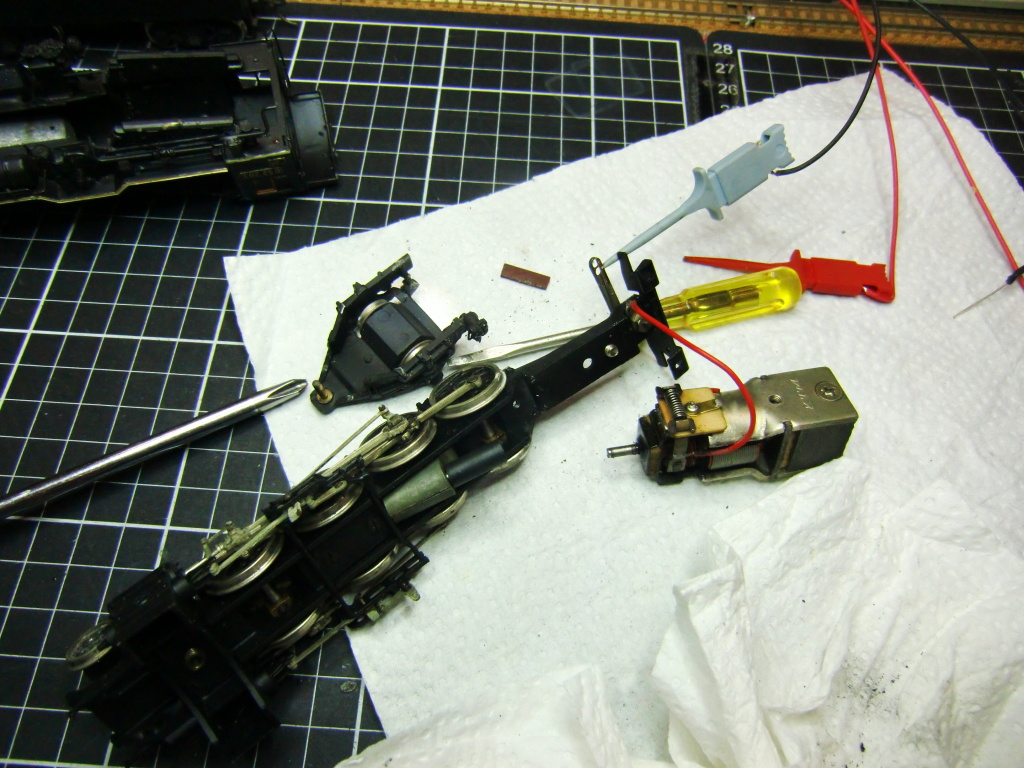
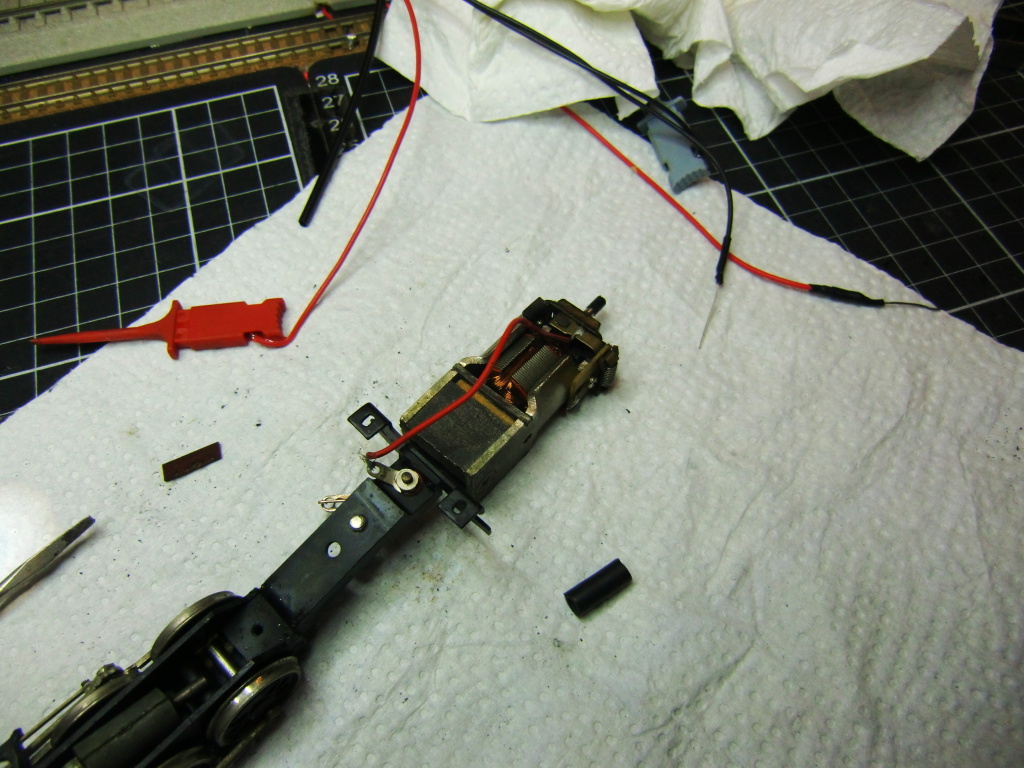
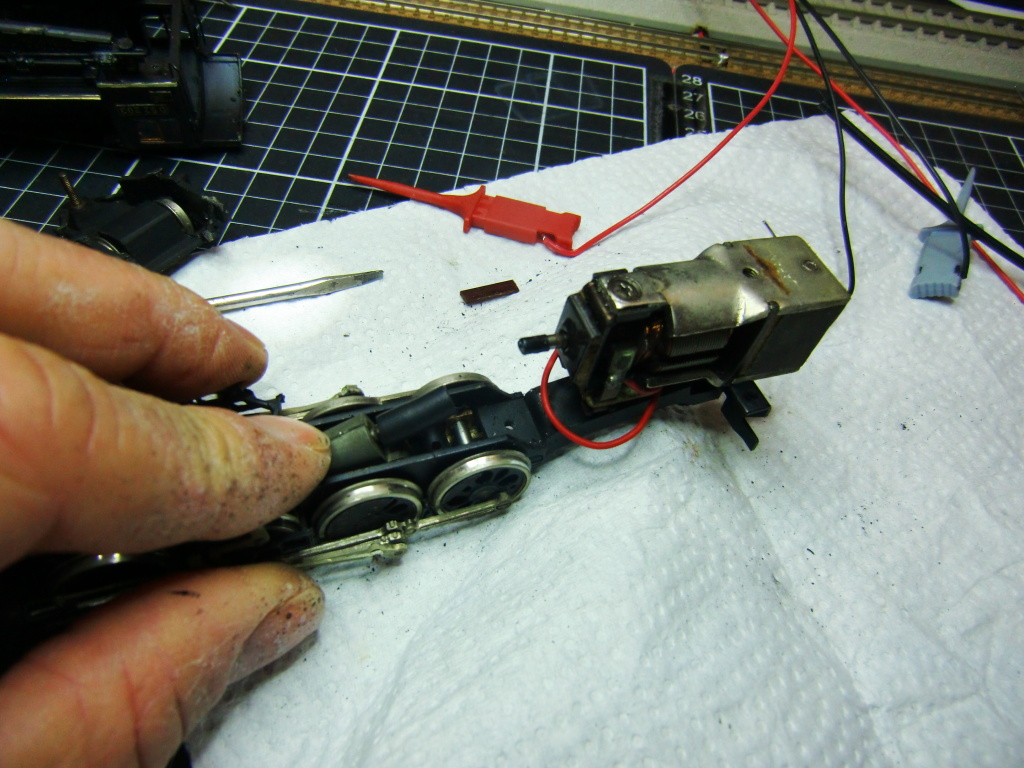
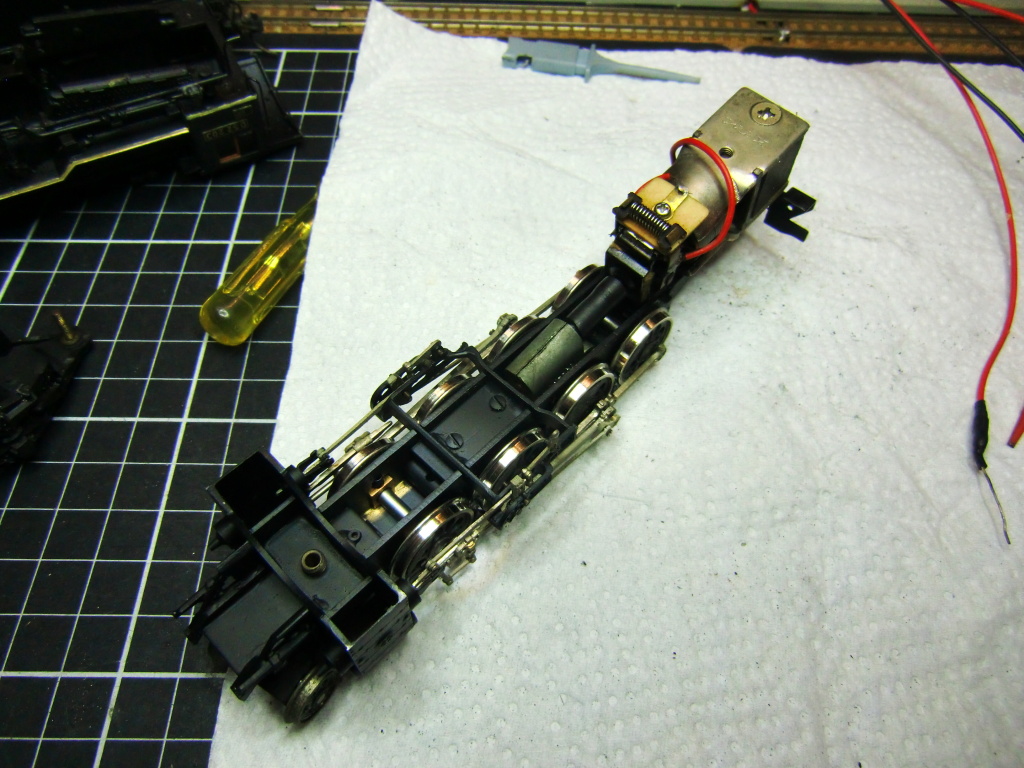
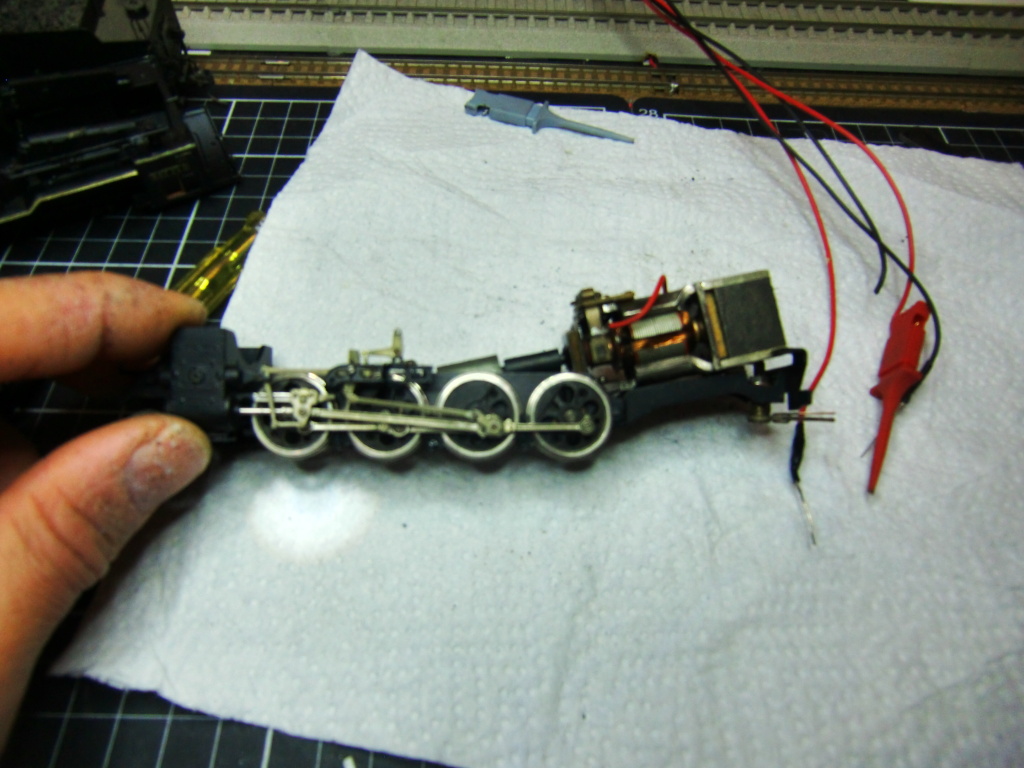
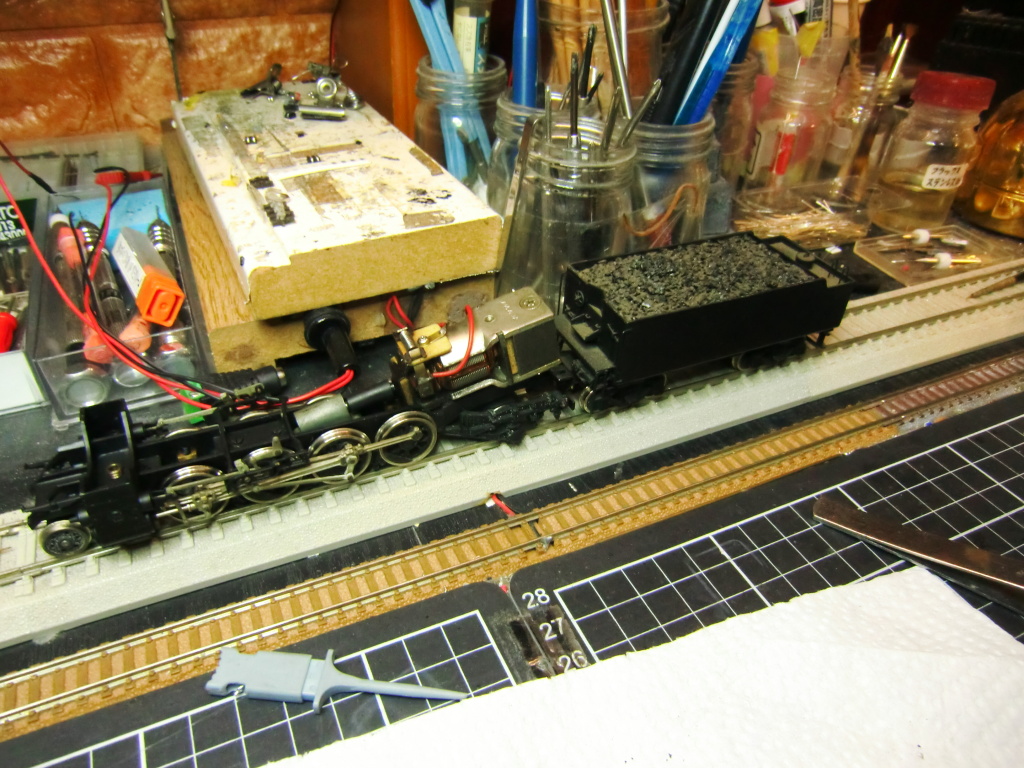
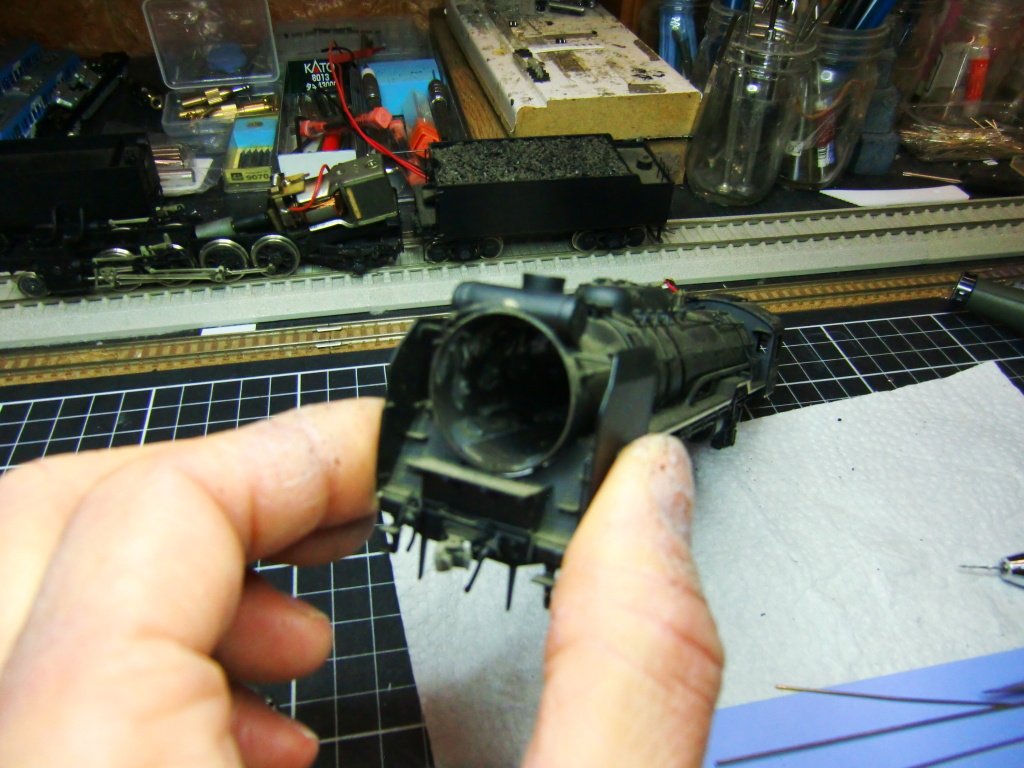



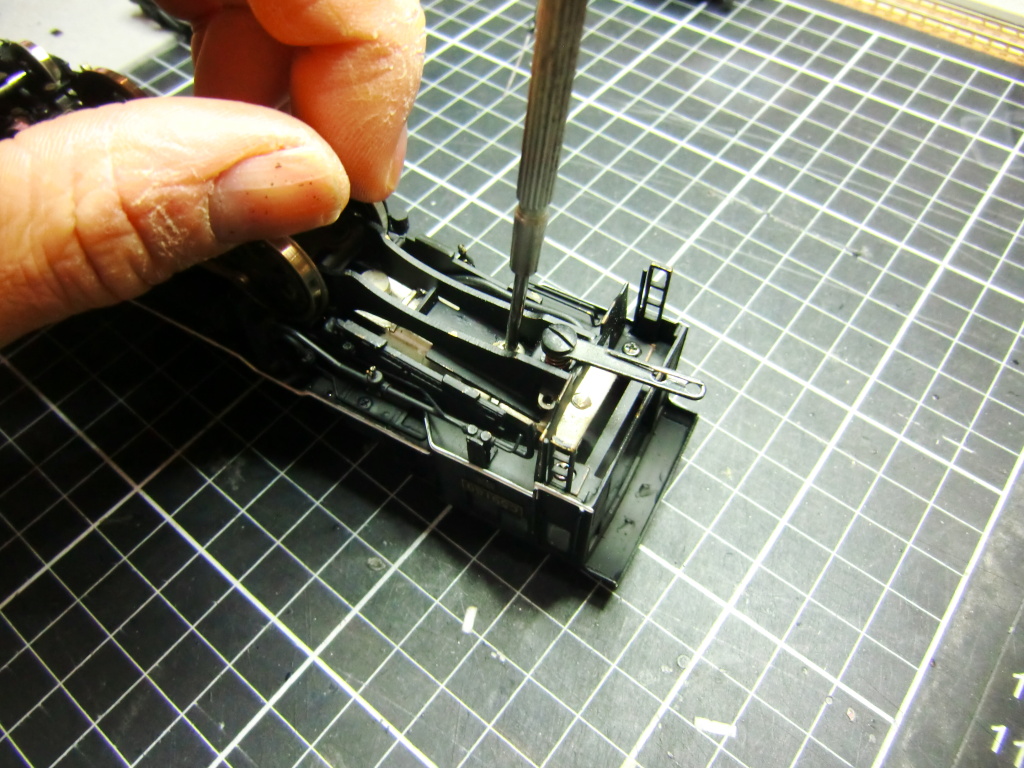


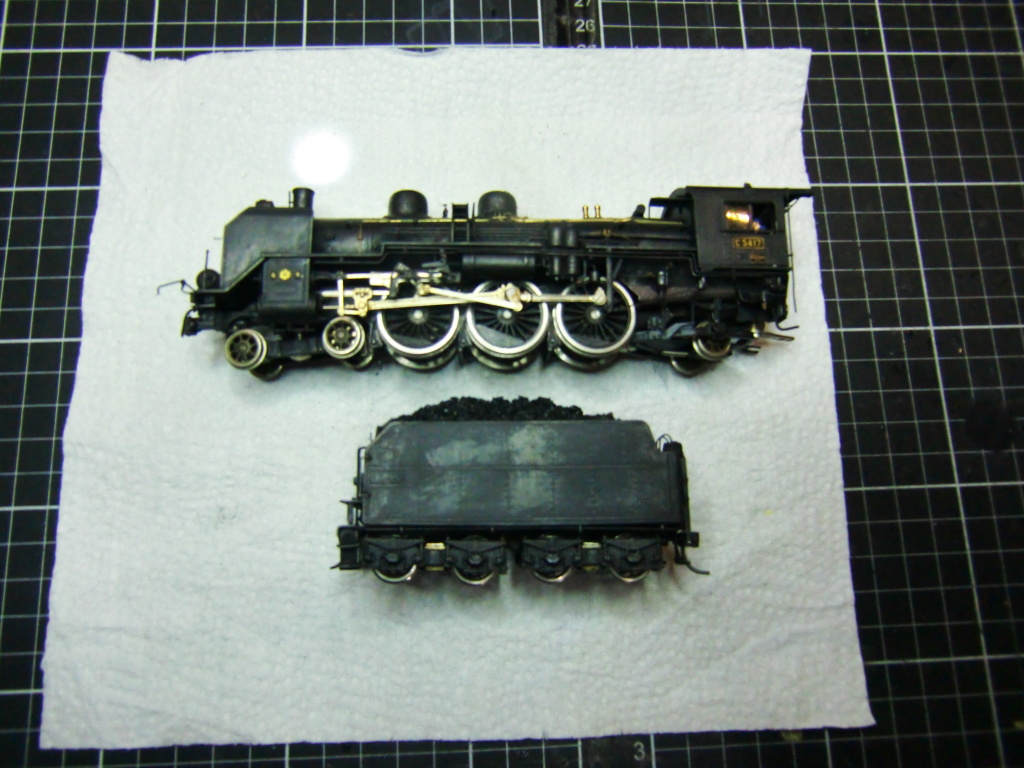

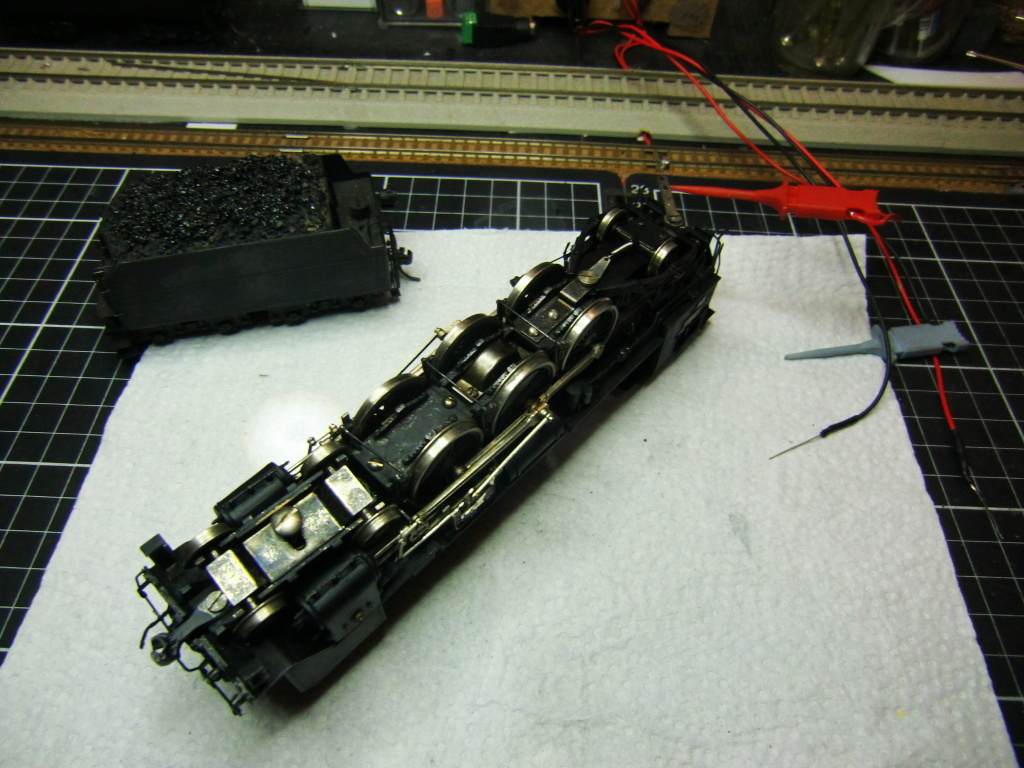
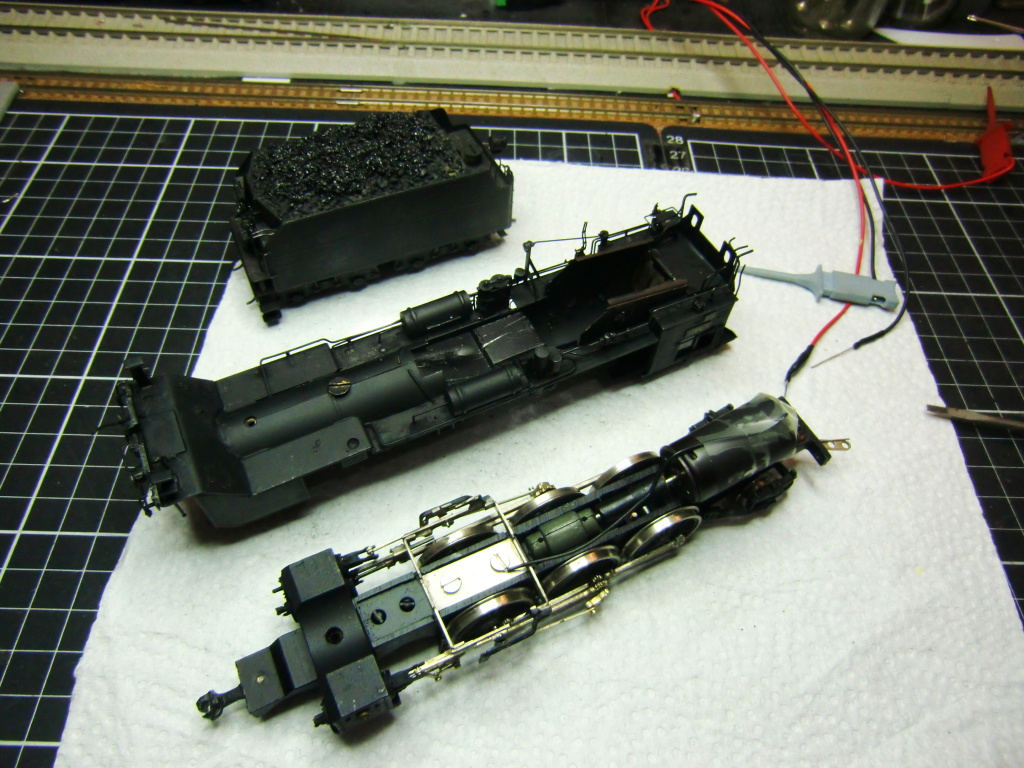
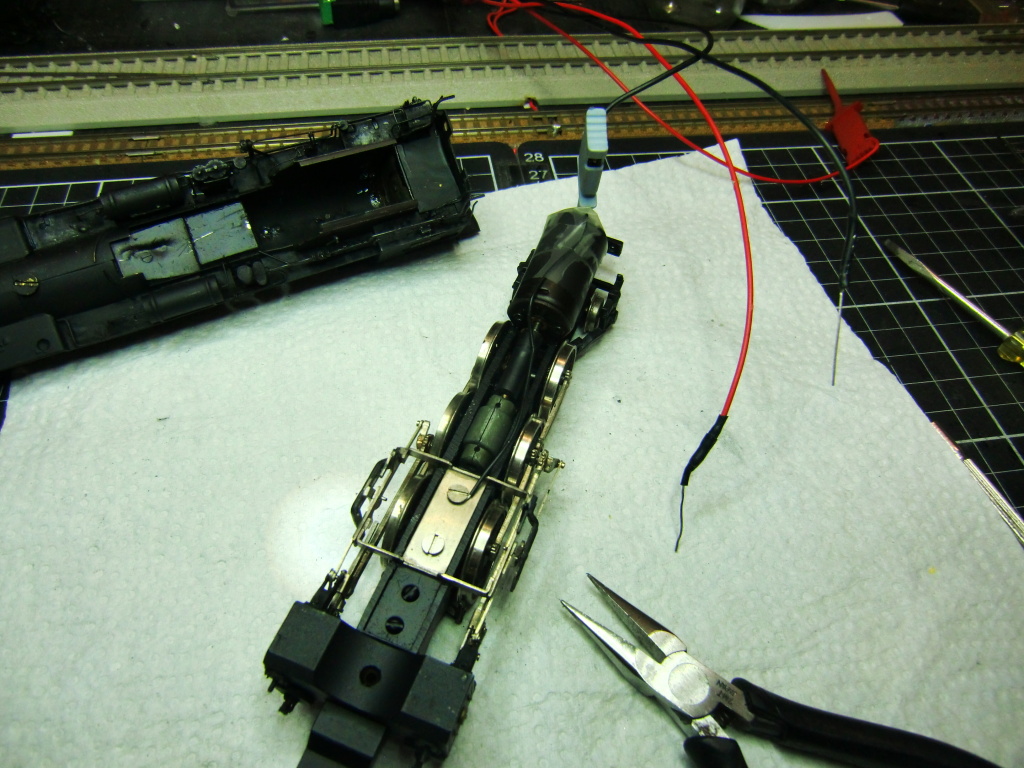
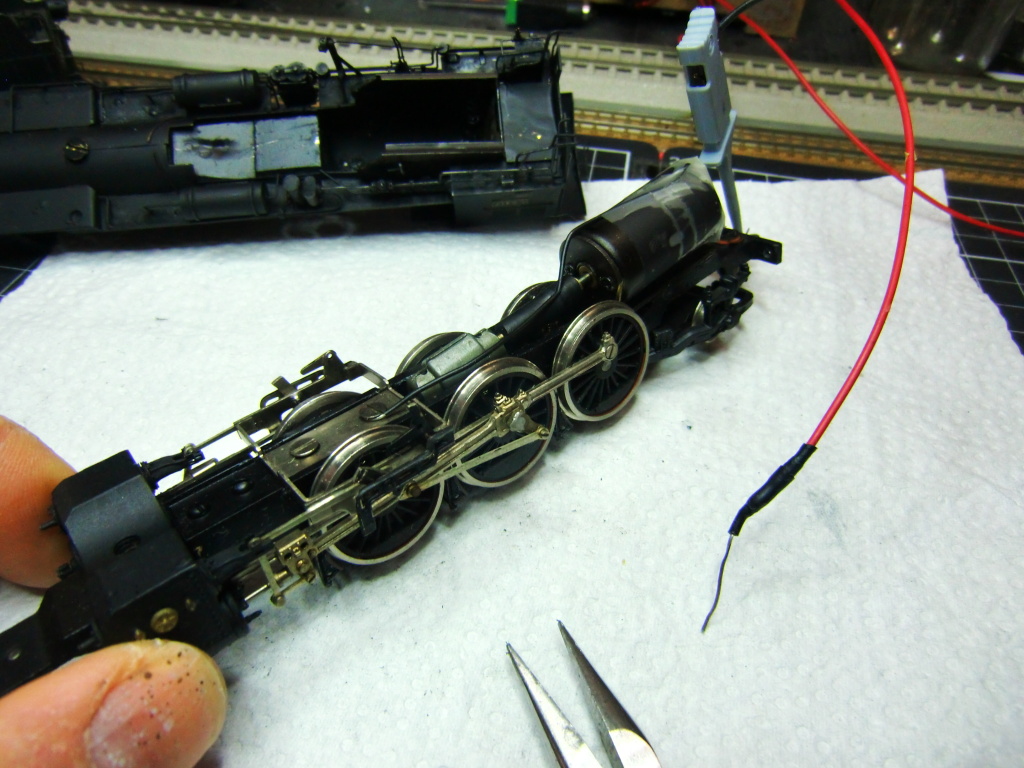
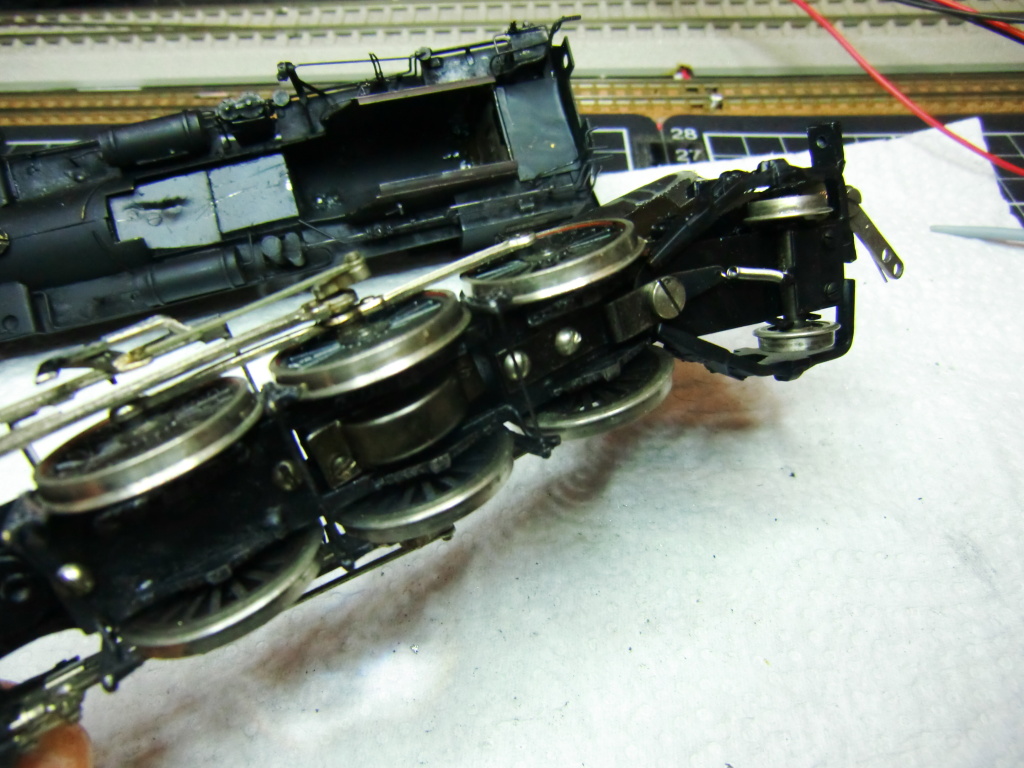
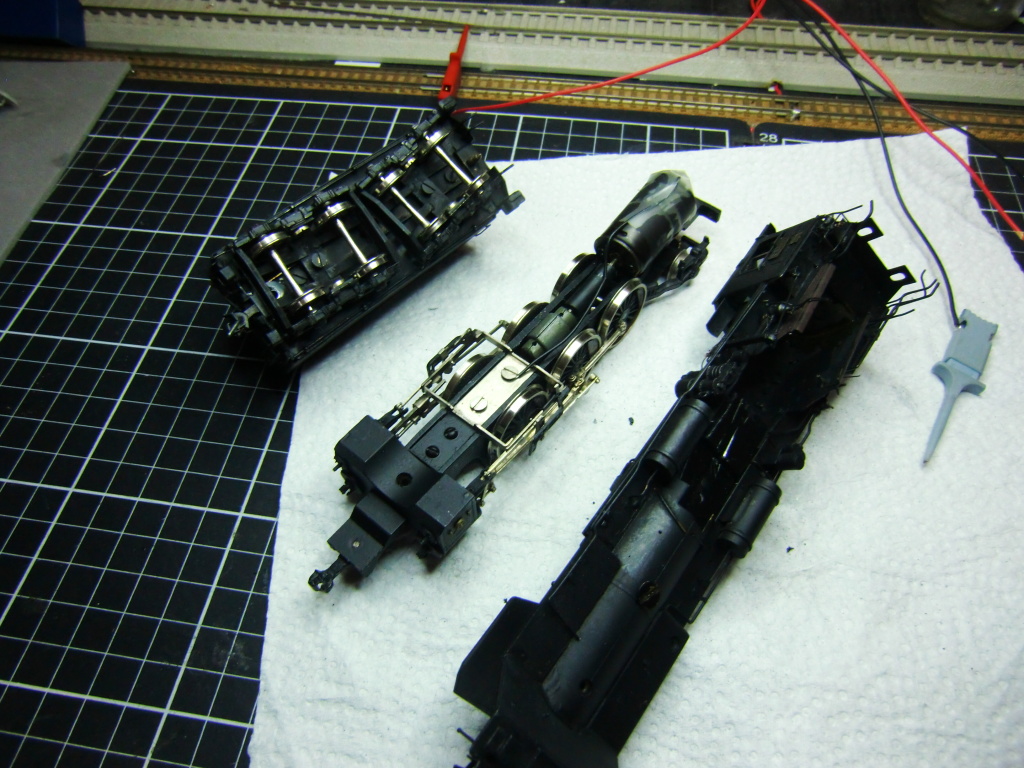
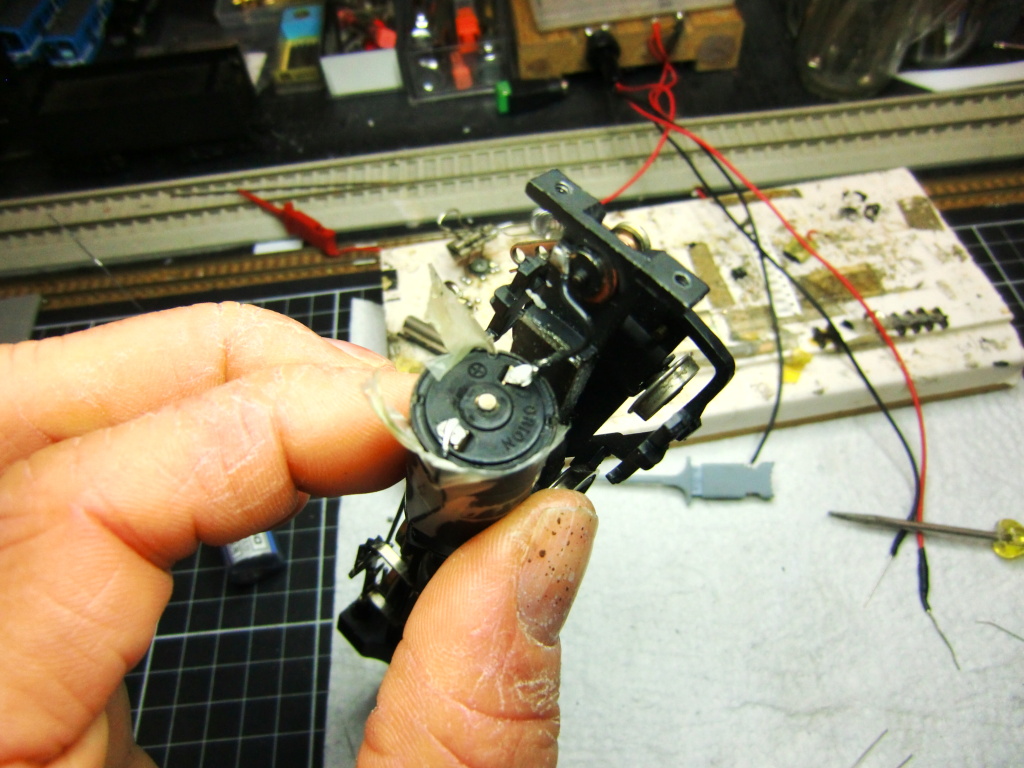
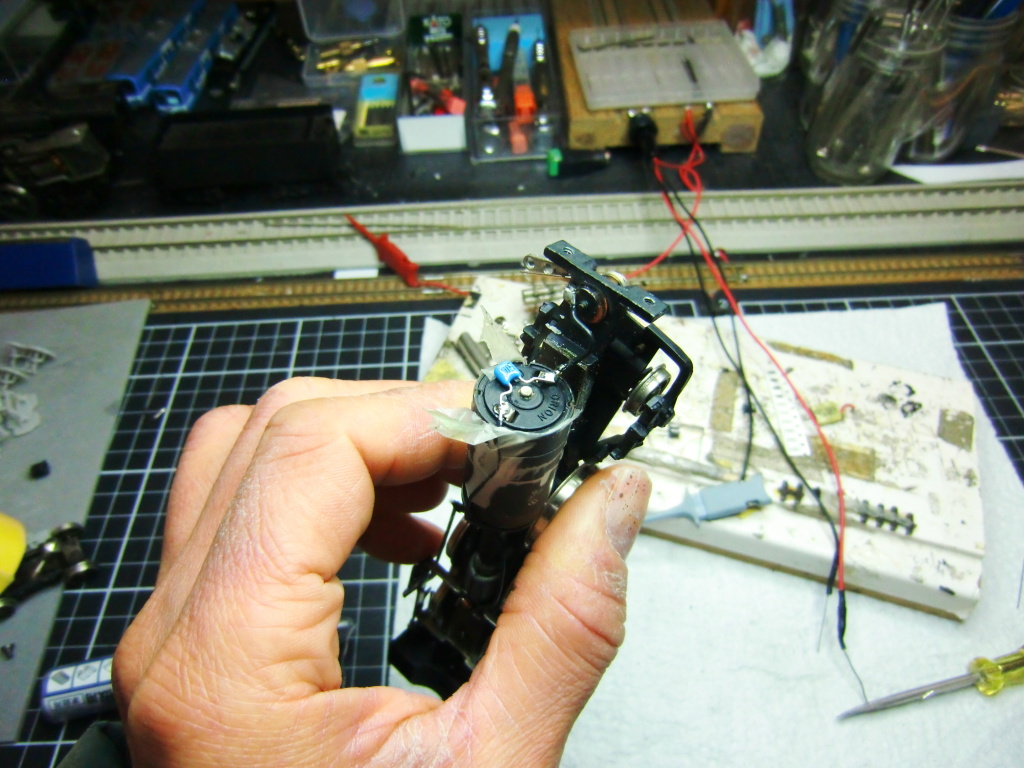

こちらの機関車では、かなり作業が難航しましたが、ようやくモーターのスムーズな回転が得られるようになりました。問題化箇所を特定するだけでもかなり時間がかかりました。
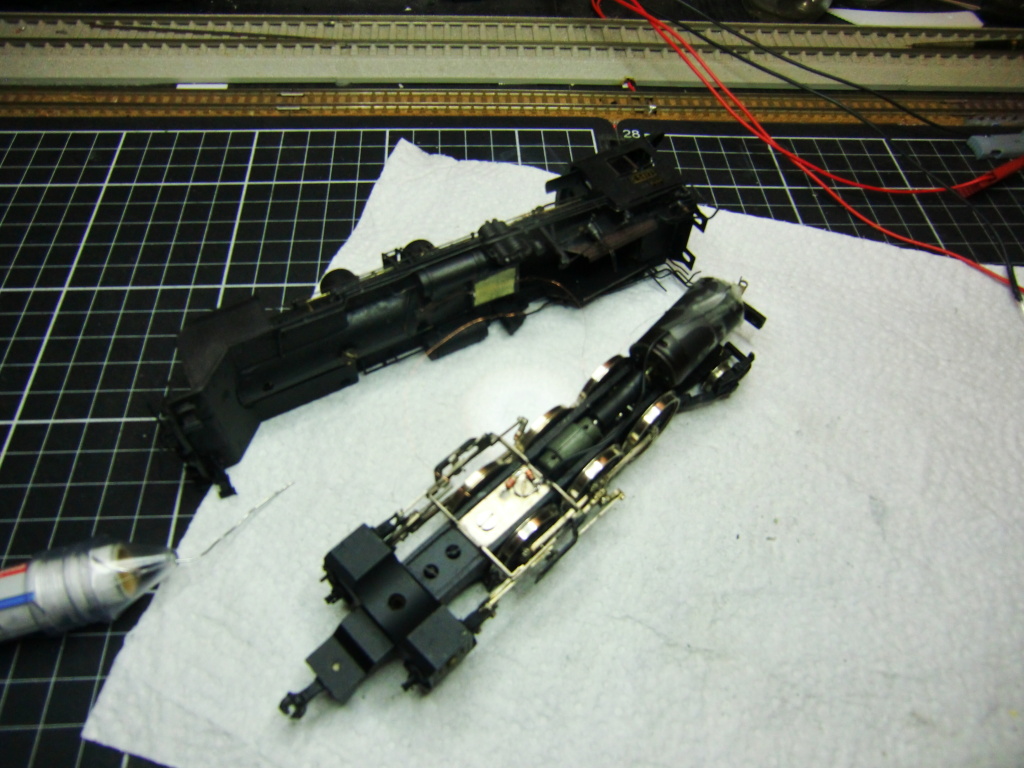
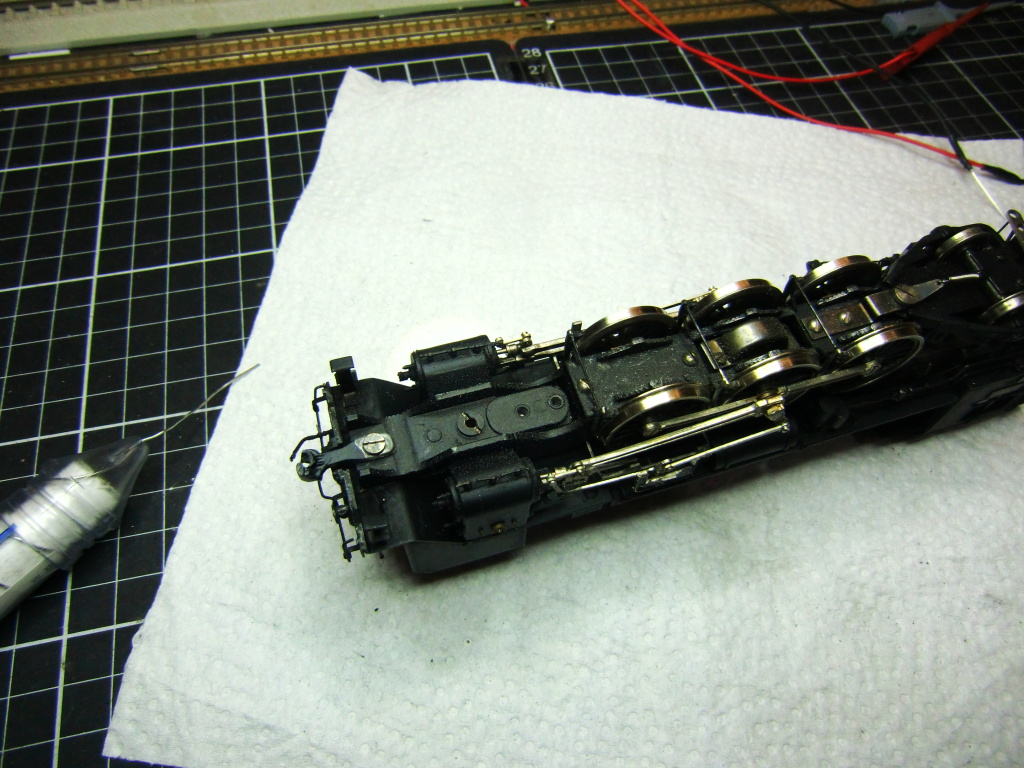
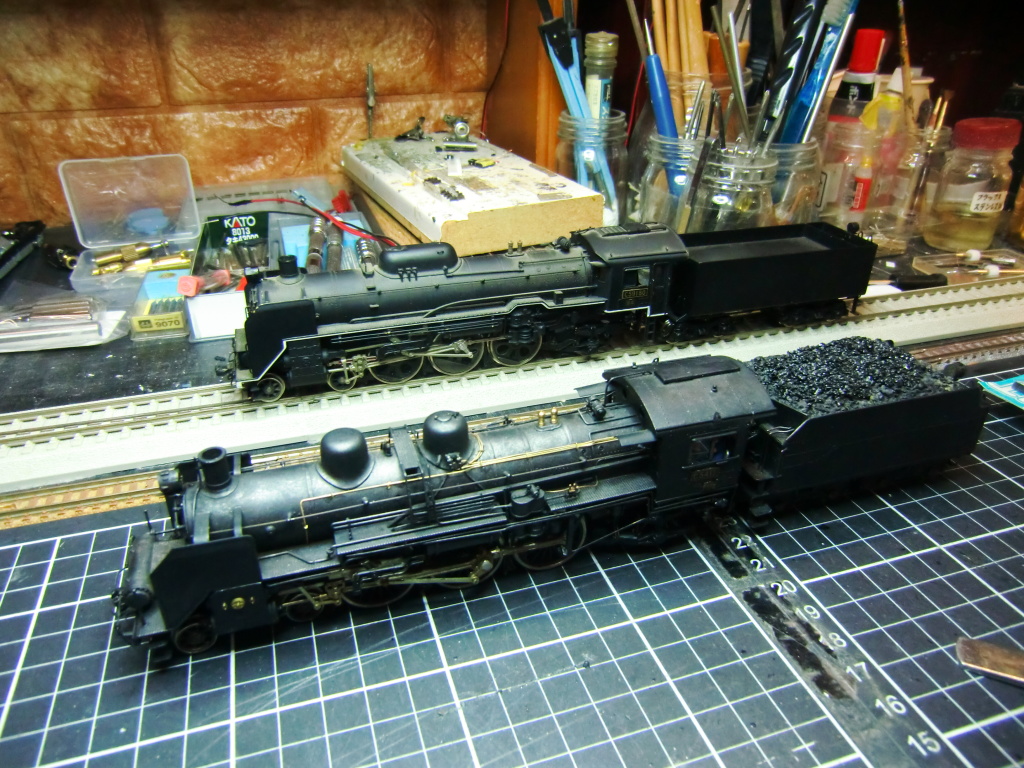
今回はちょっと難しかったですね。モーターの回転に抵抗となる箇所があり、その個所の特定と対策には苦労しましたが、ようやくすべての作業が完了いたしました。



加工前はこんな感じでオレンジ色っぽい色です。


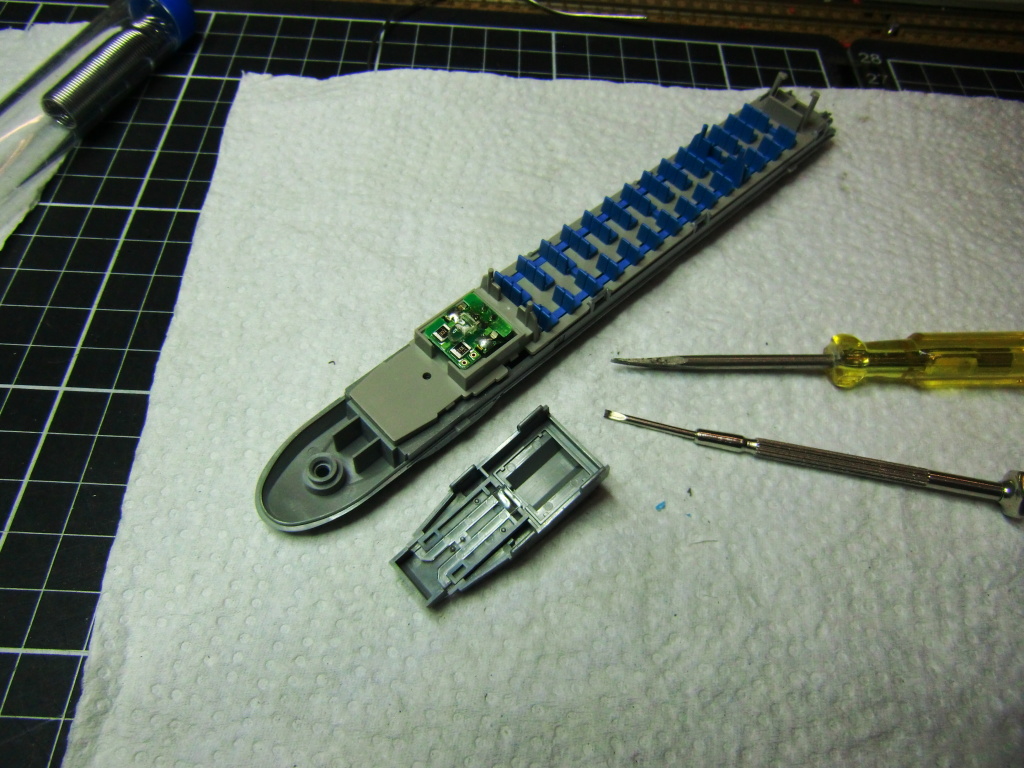
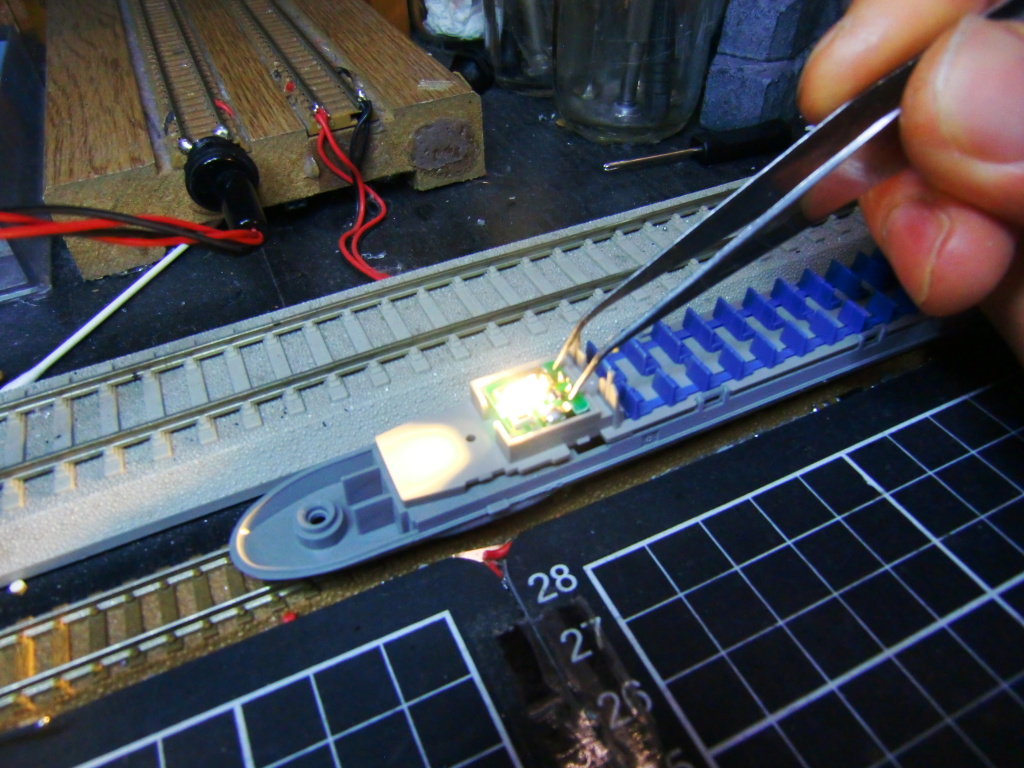
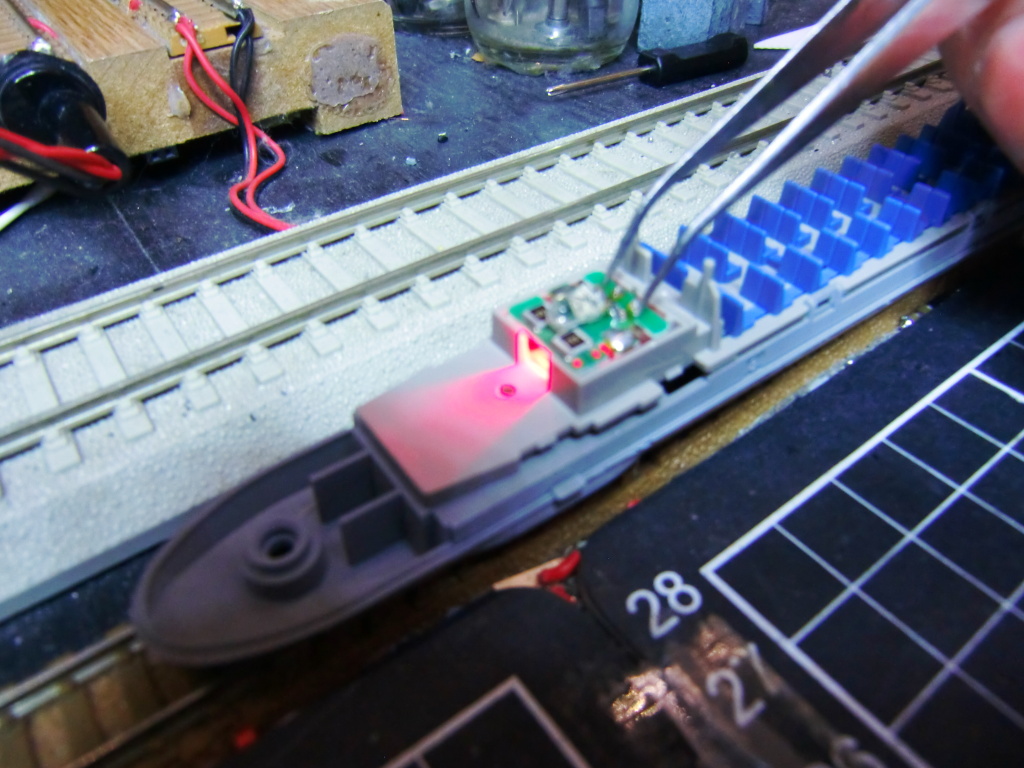
ヘッド&テールの高輝度化

ヘッドライトは、オレンジ色から明るい電球色へと変わりました。



作業完了でございます。


今回は、特殊加工にて対応してまいります。

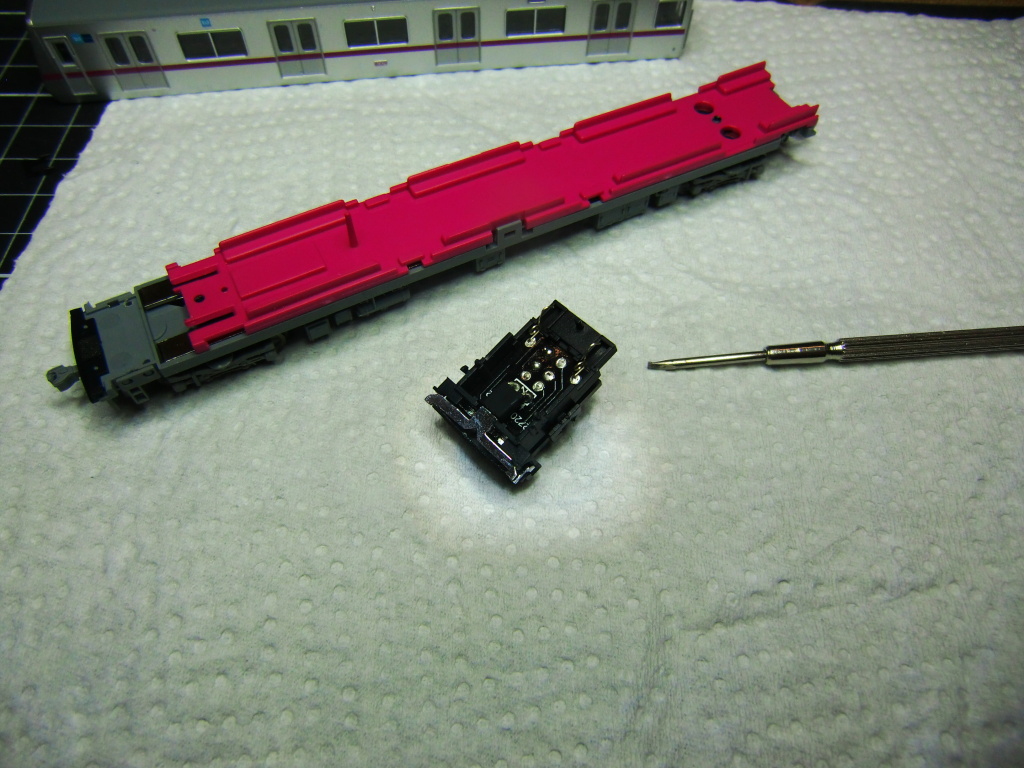
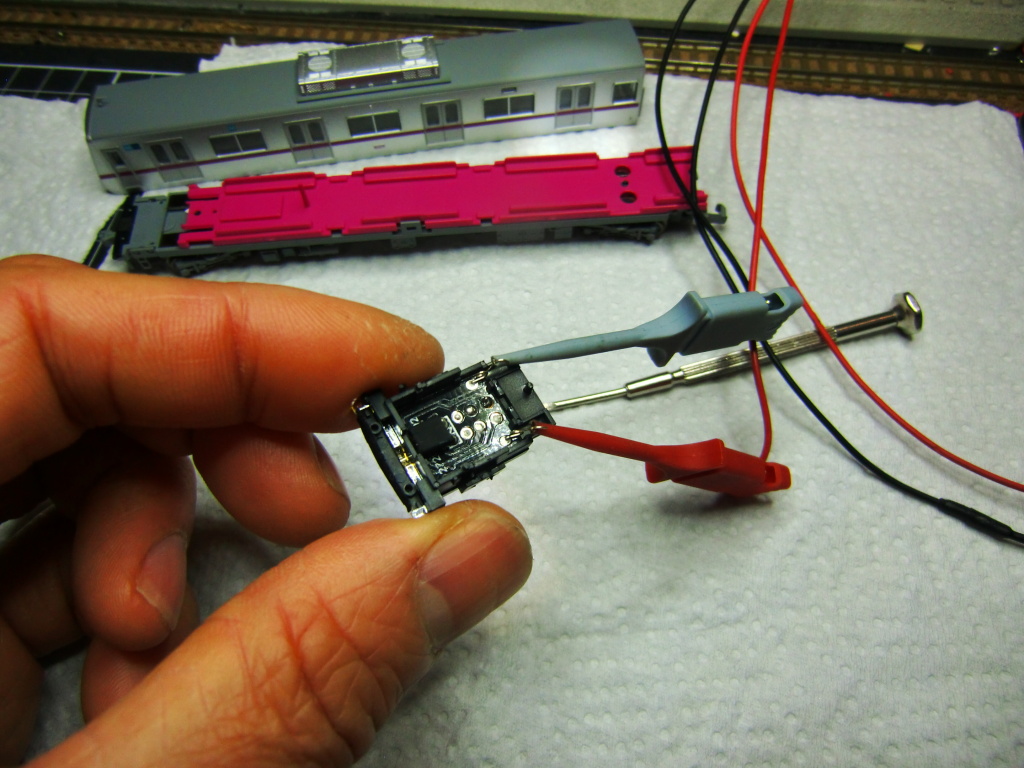
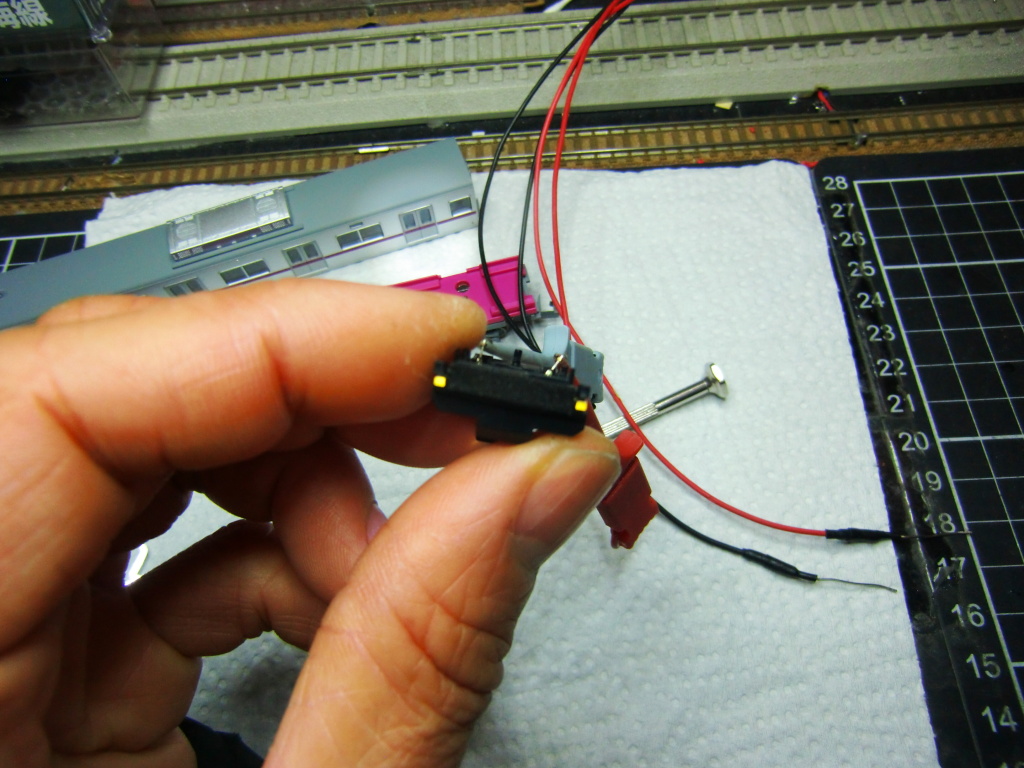
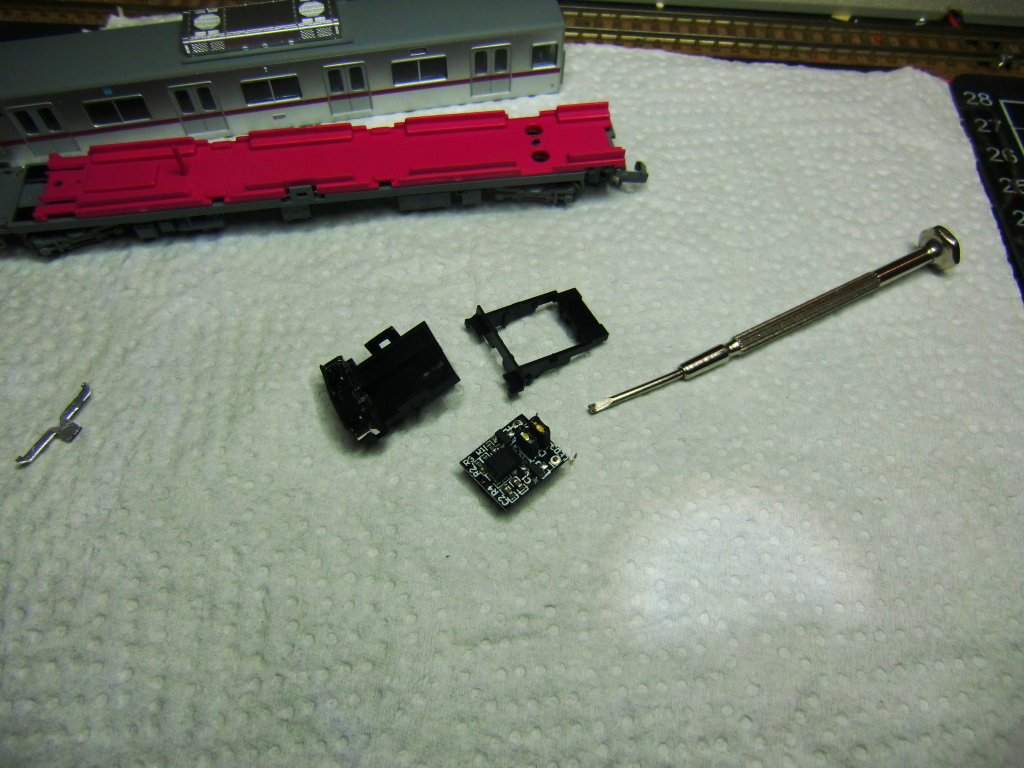
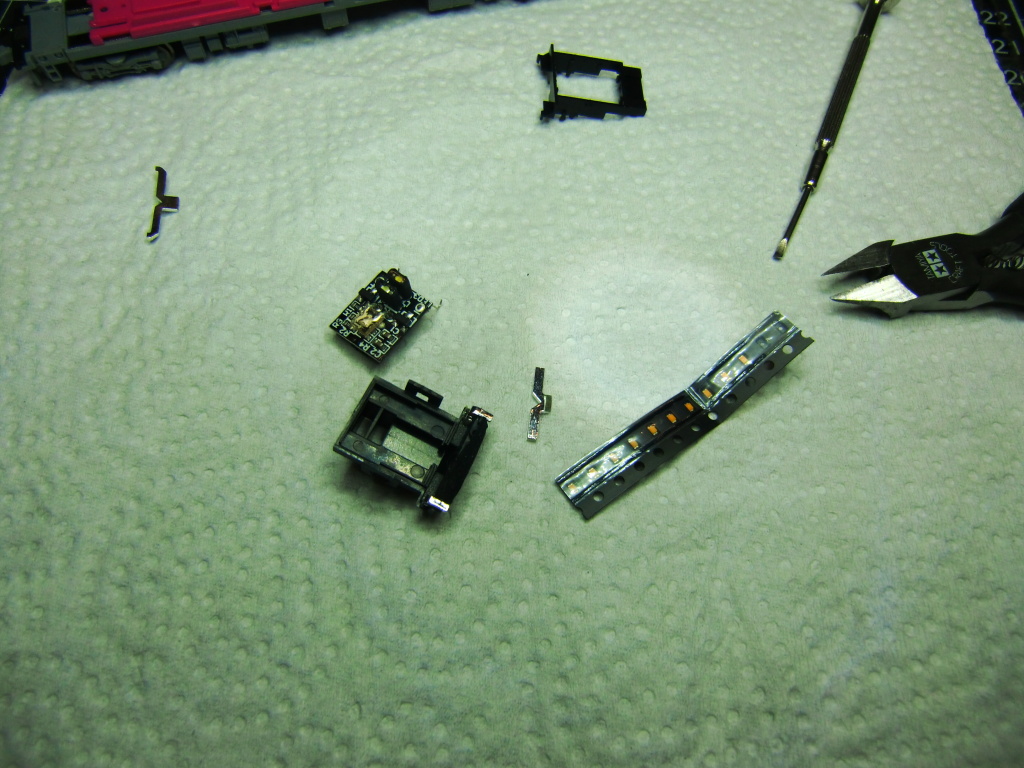
導光材を1/3の位置でカットして、真後ろにそれぞれチップLEDを配置します。

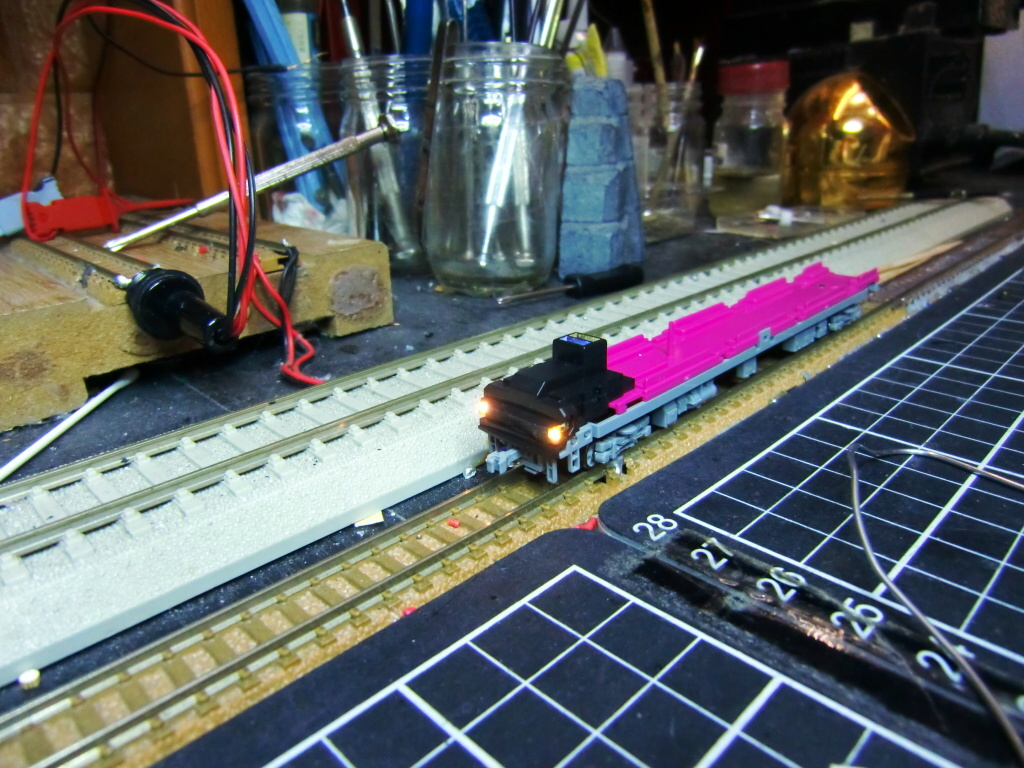

上の写真は、変更前のヘッドライト点灯で若干緑っぽい感じのする色合いです。下は加工完了後のヘッドライトです。


作業完了でございます。
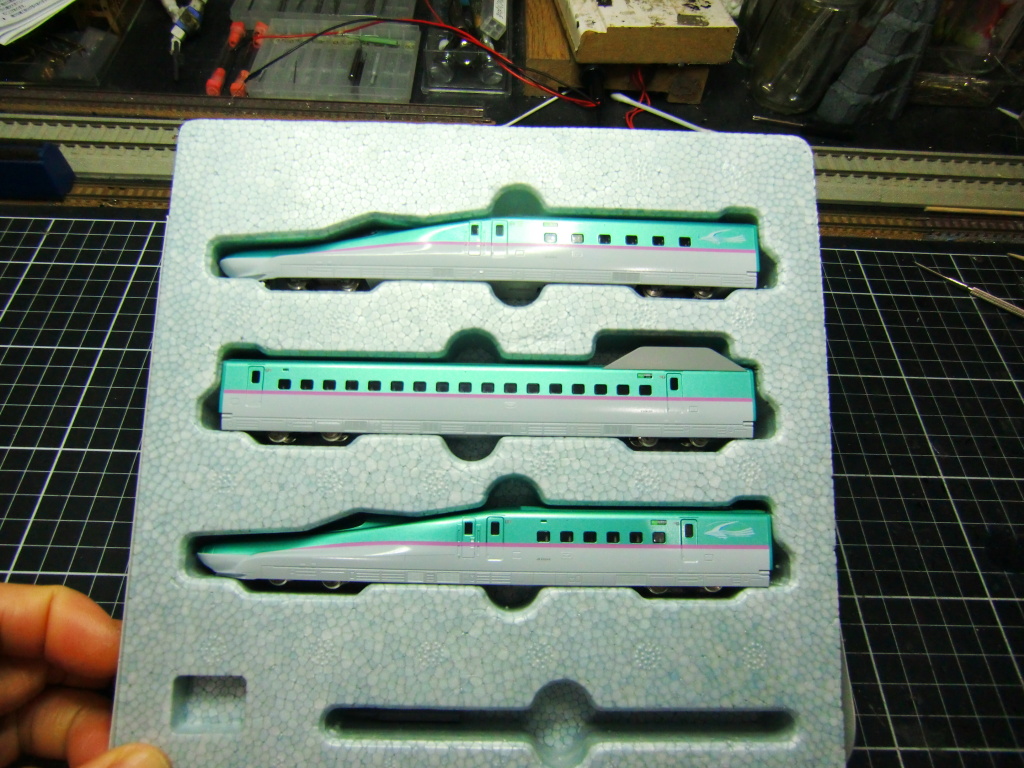
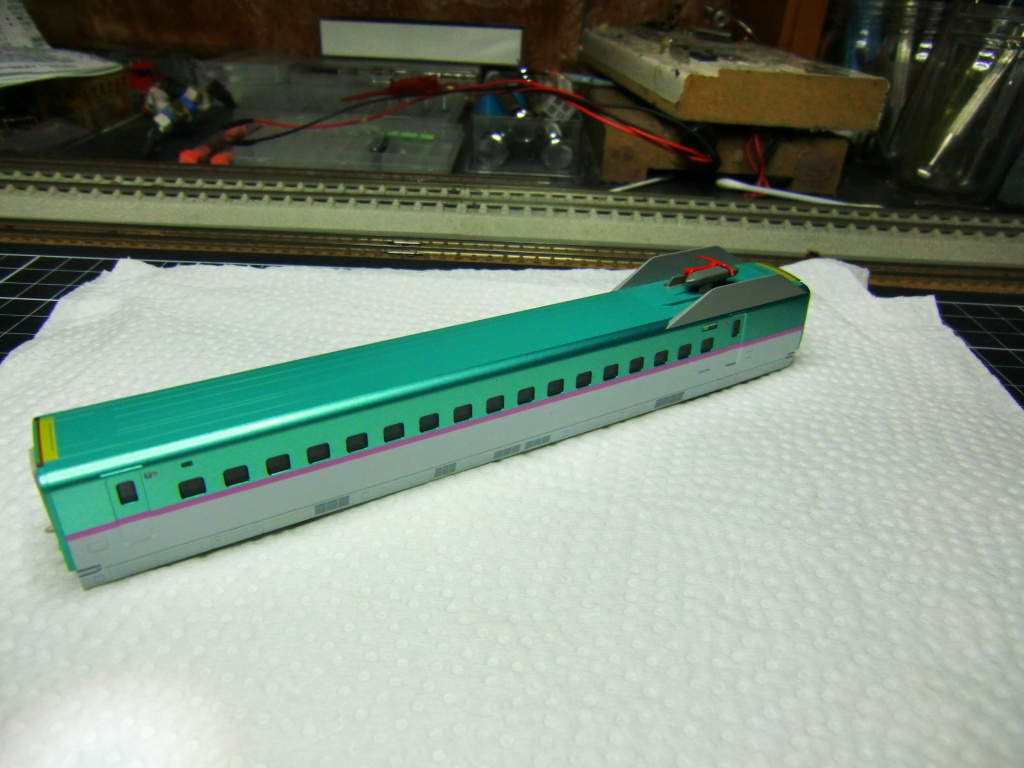
それでは分解していきます

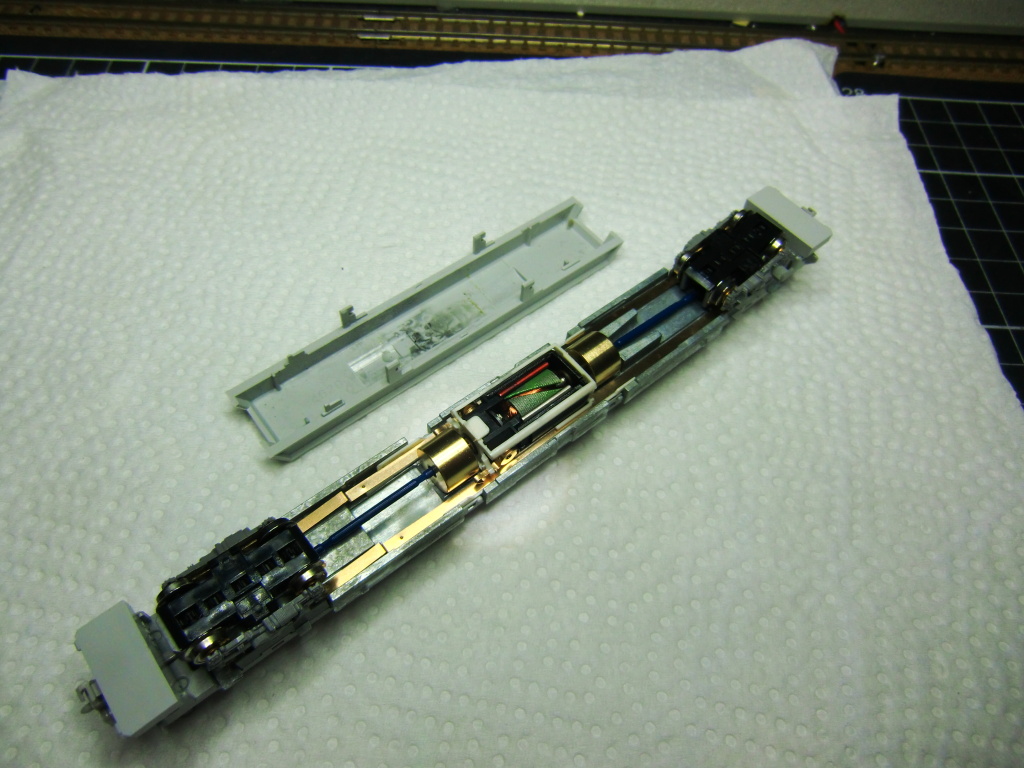
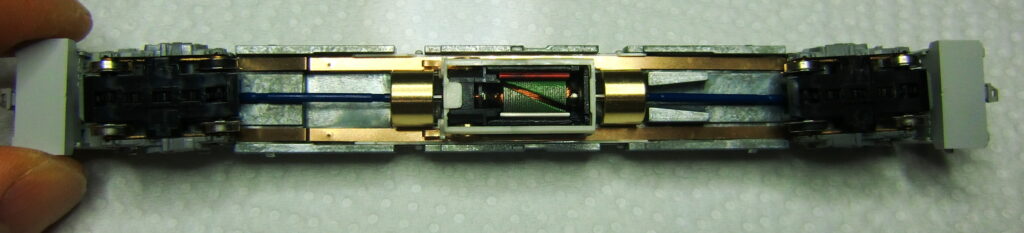
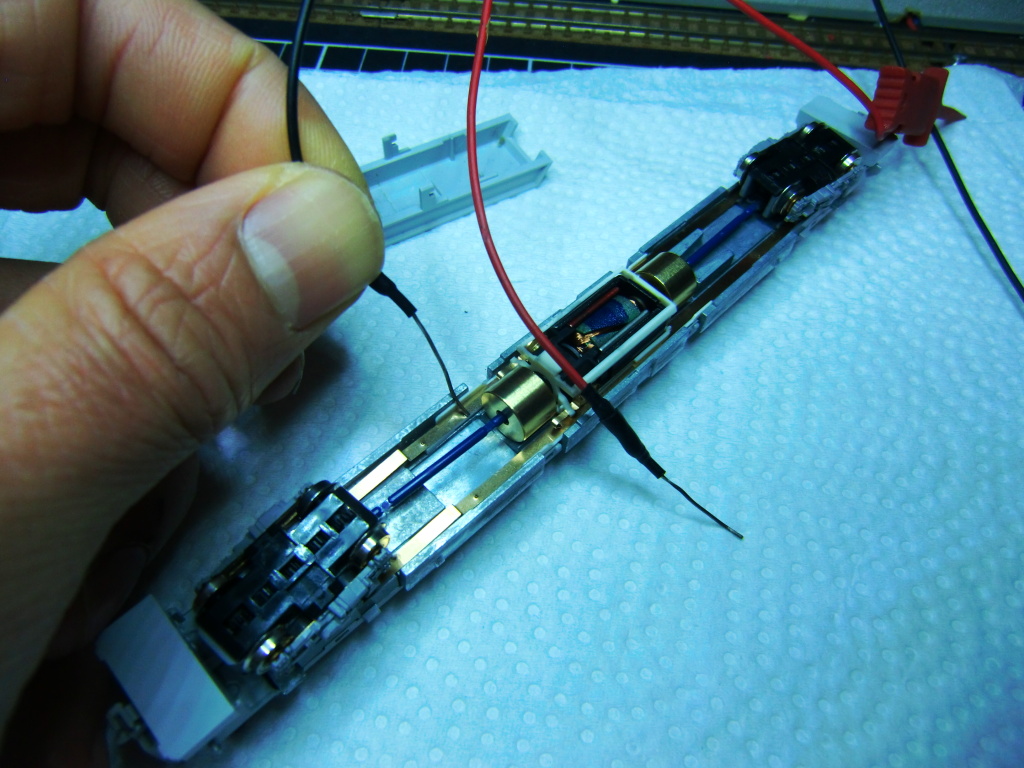
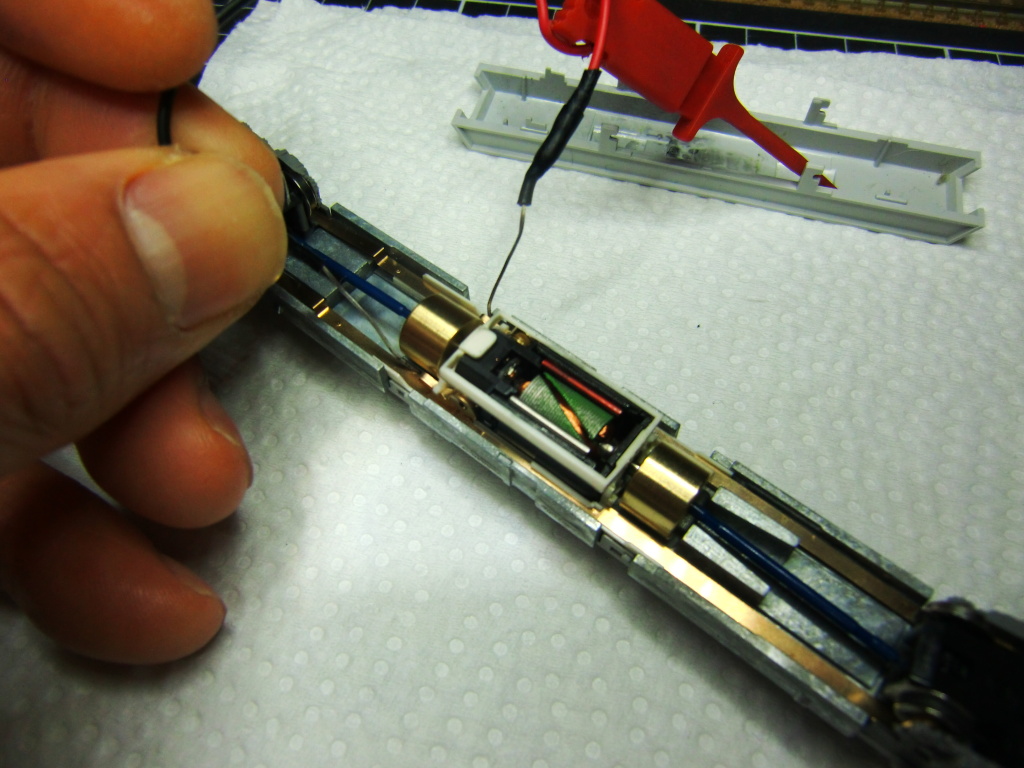
モーターの回転を細かく確認しながら問題個所を特定していきます。
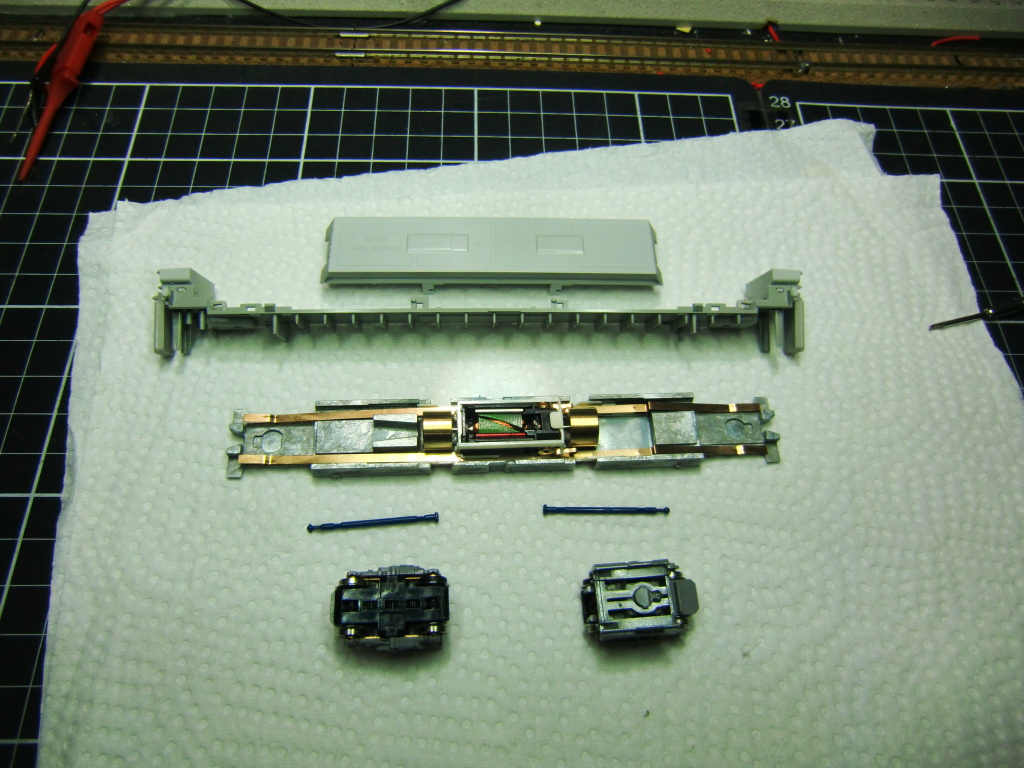

台車もすべて分解してメンテを行っていきます。

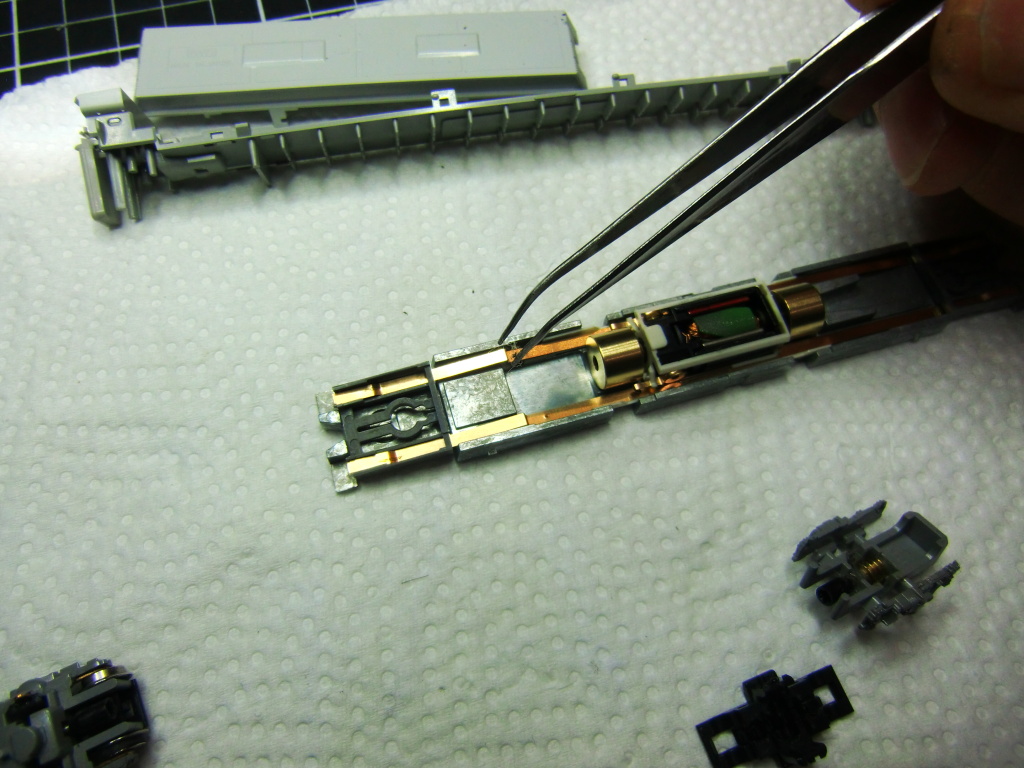
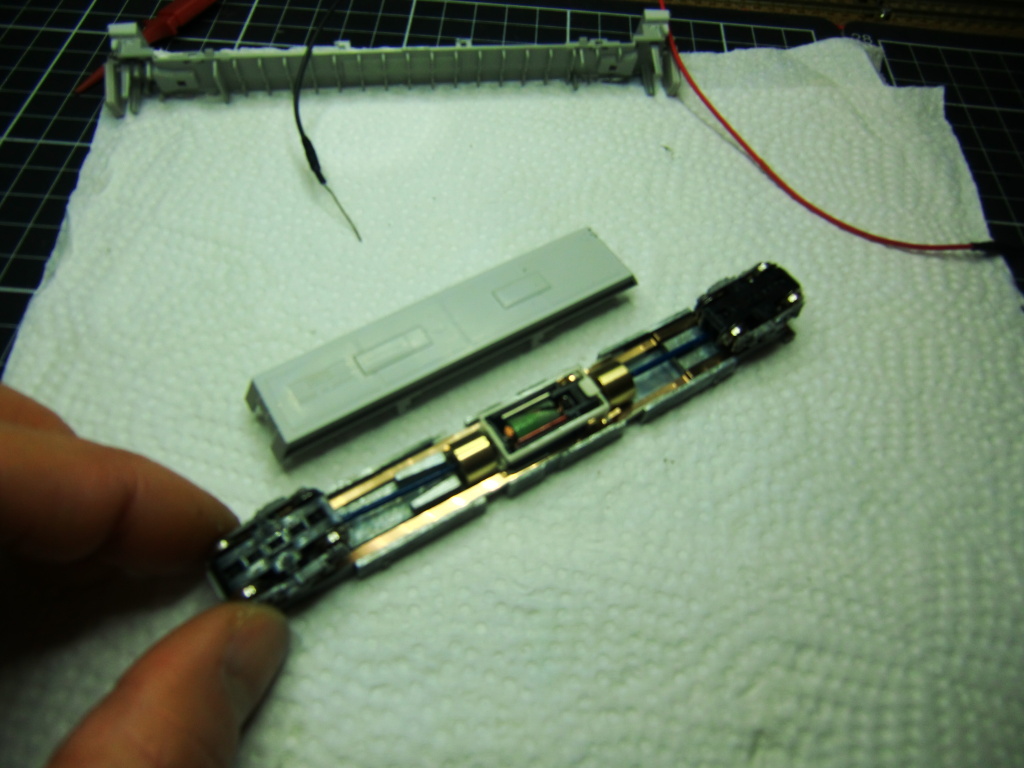
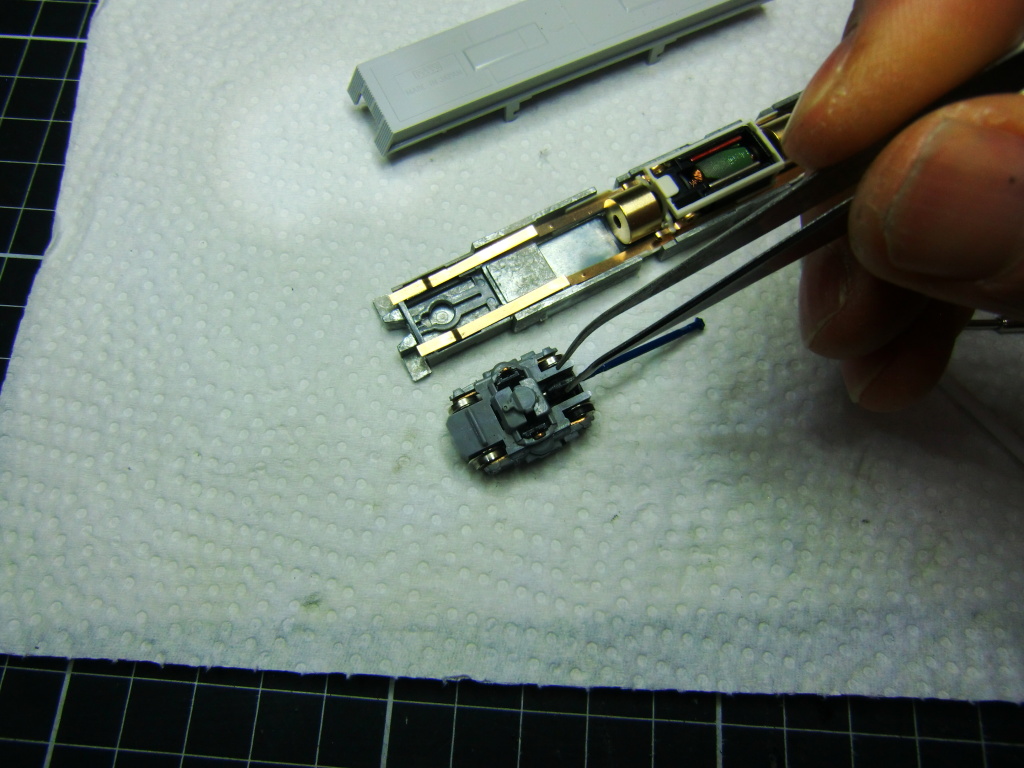
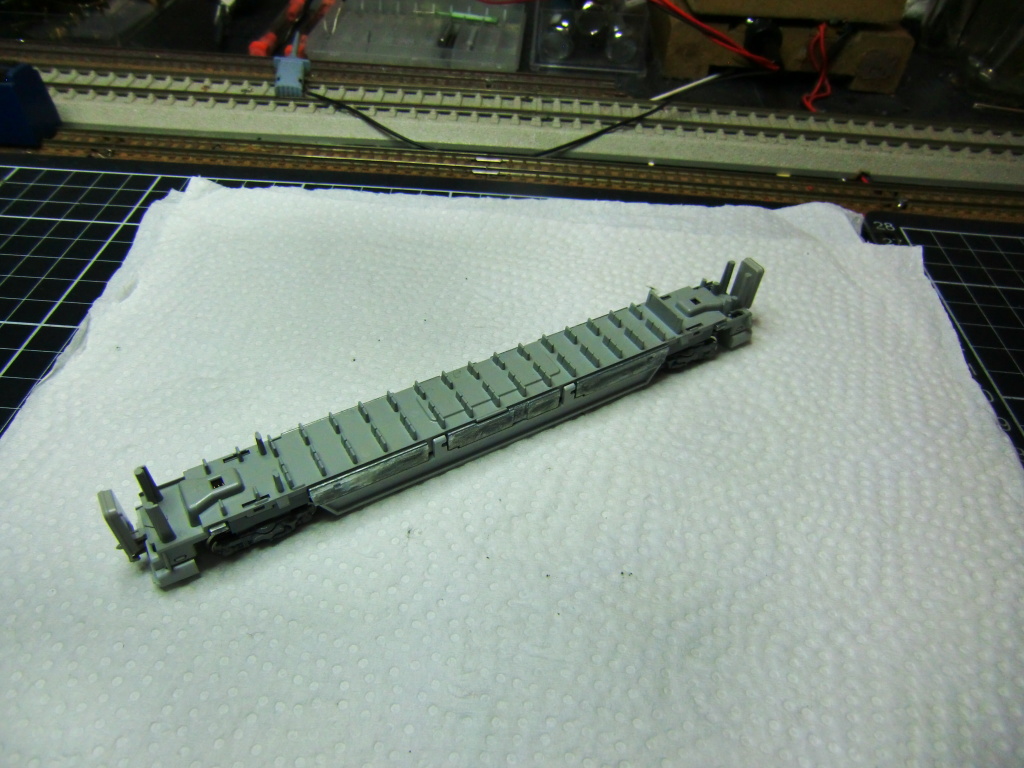
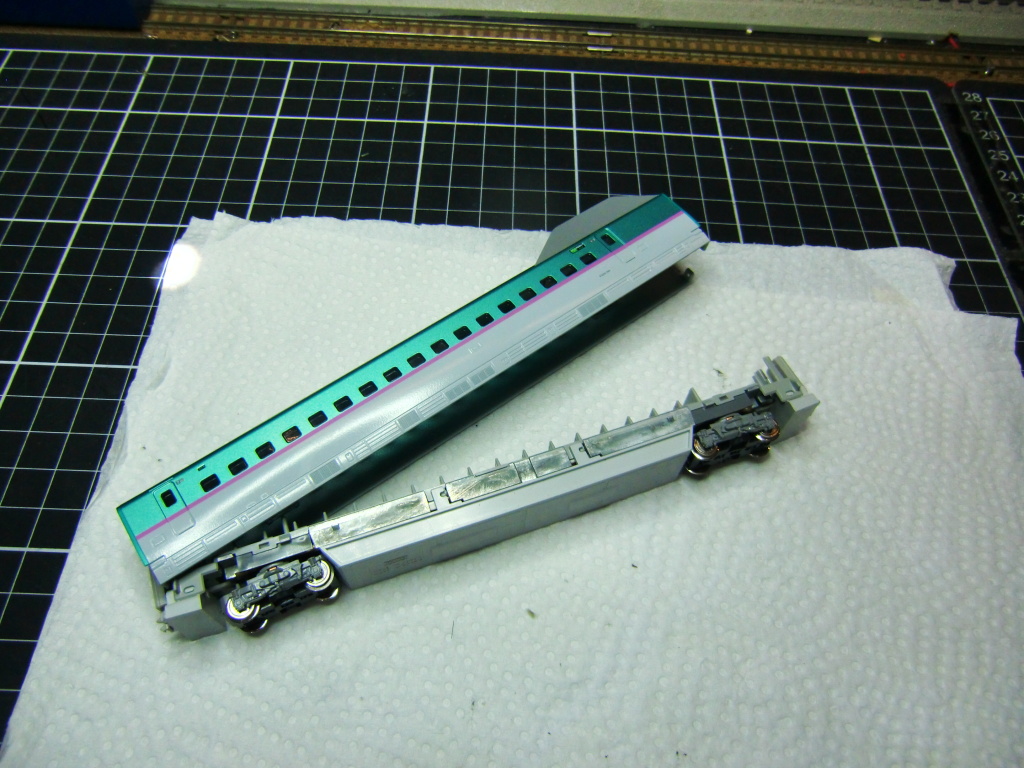
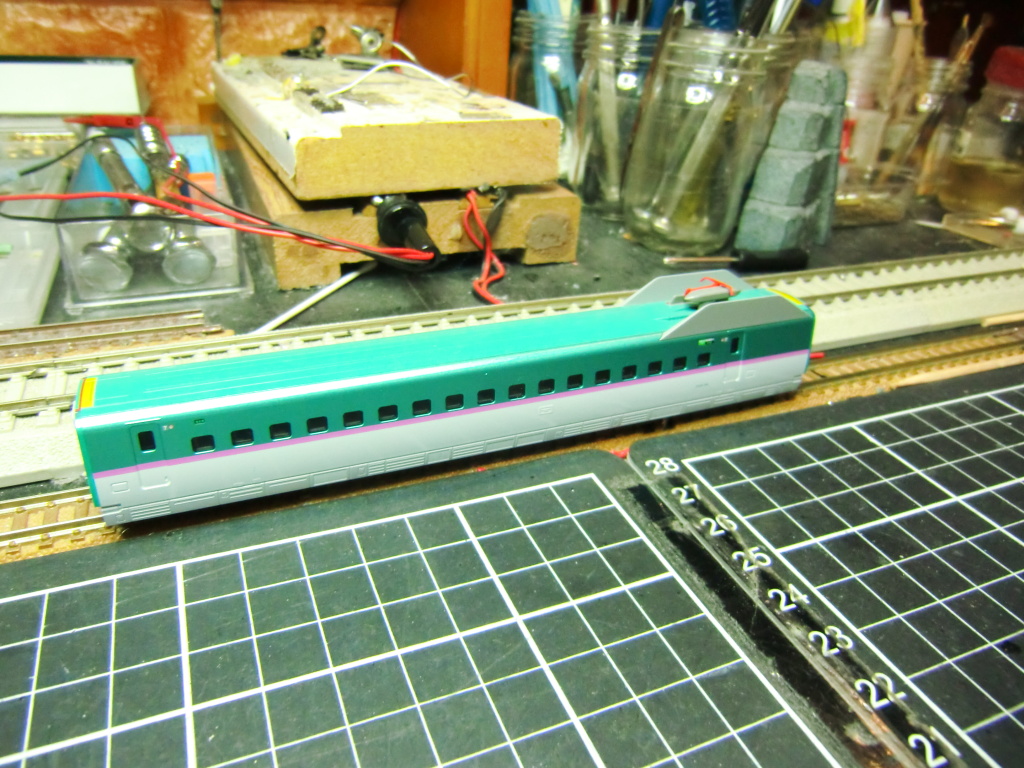
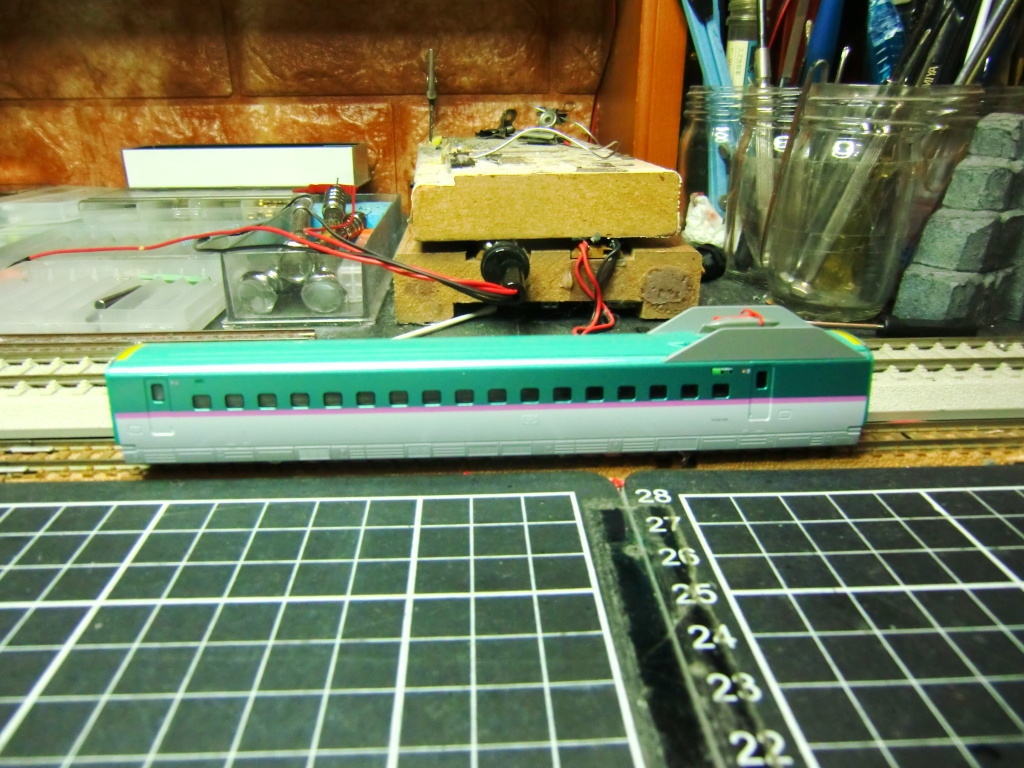
作業完了でございます。今回の不具合の原因は次の2点。軸受けの汚れによる集電不良とギアとシャフトに大量の糸くずが絡みつき振動と異音の原因になっておりました。
そのままではお取付けできませんので、カプラーおよび台車に加工を施していきます。


標準のカプラーはこのような感じです。

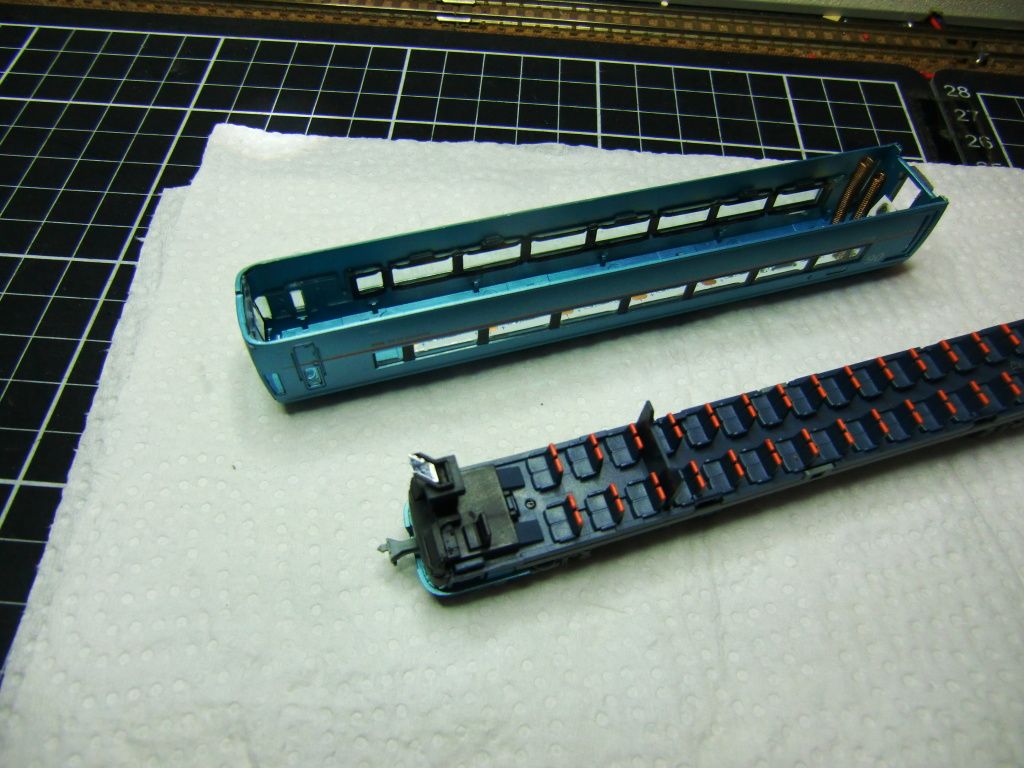
それでは加工作業を開始します。
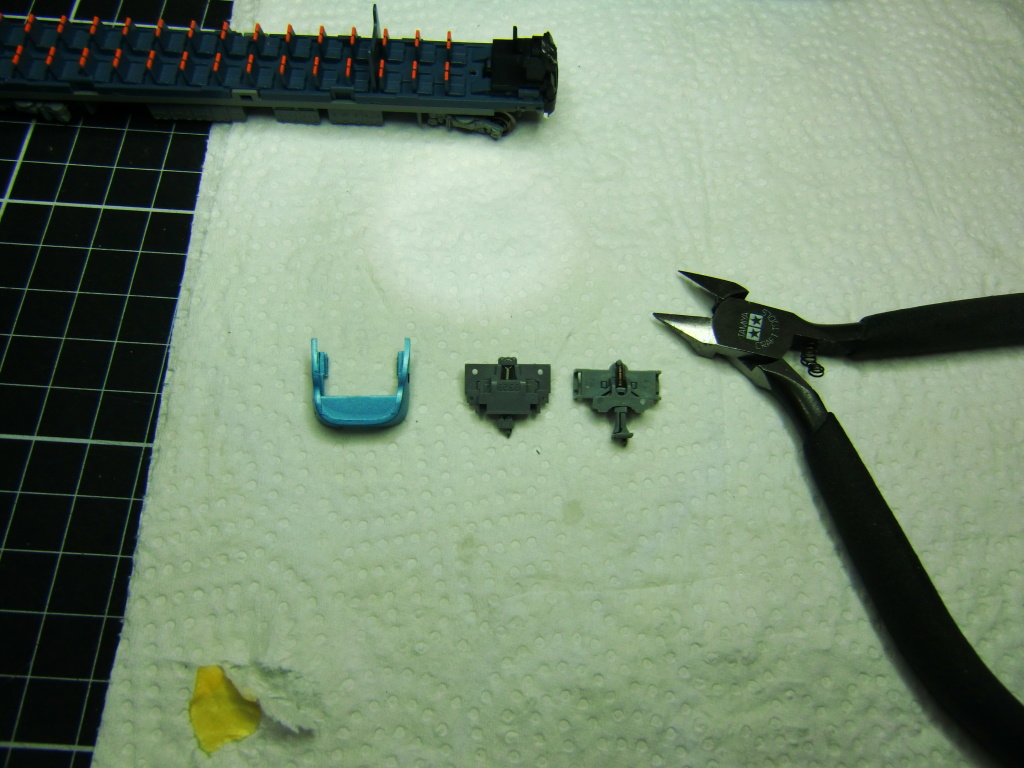

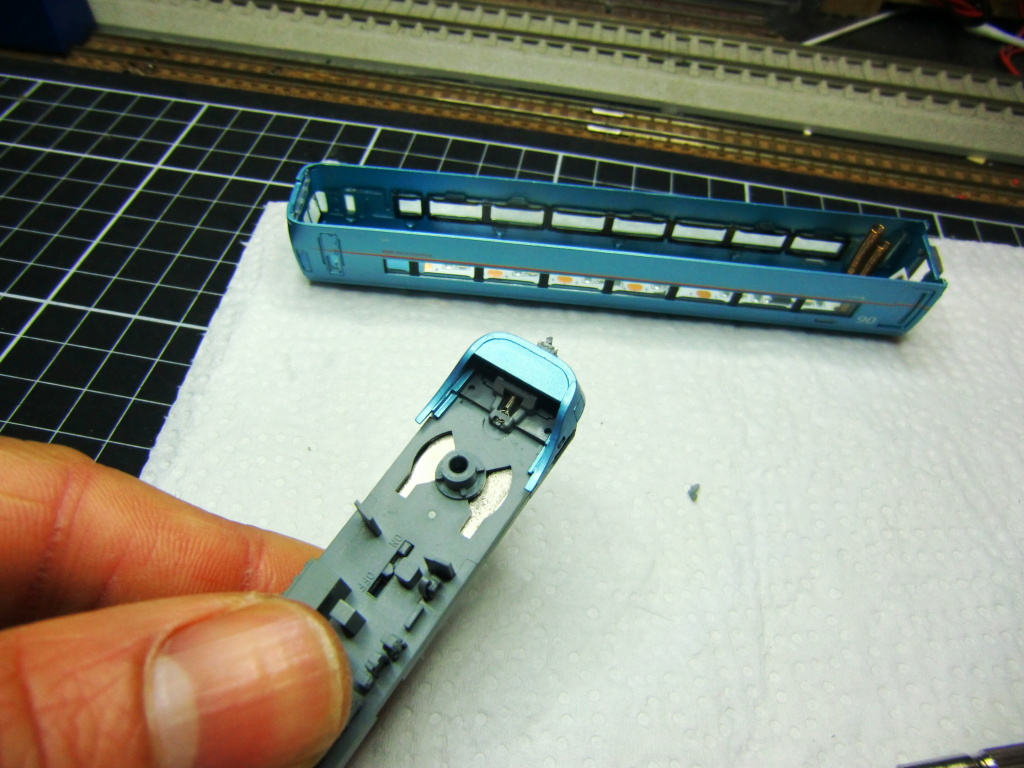
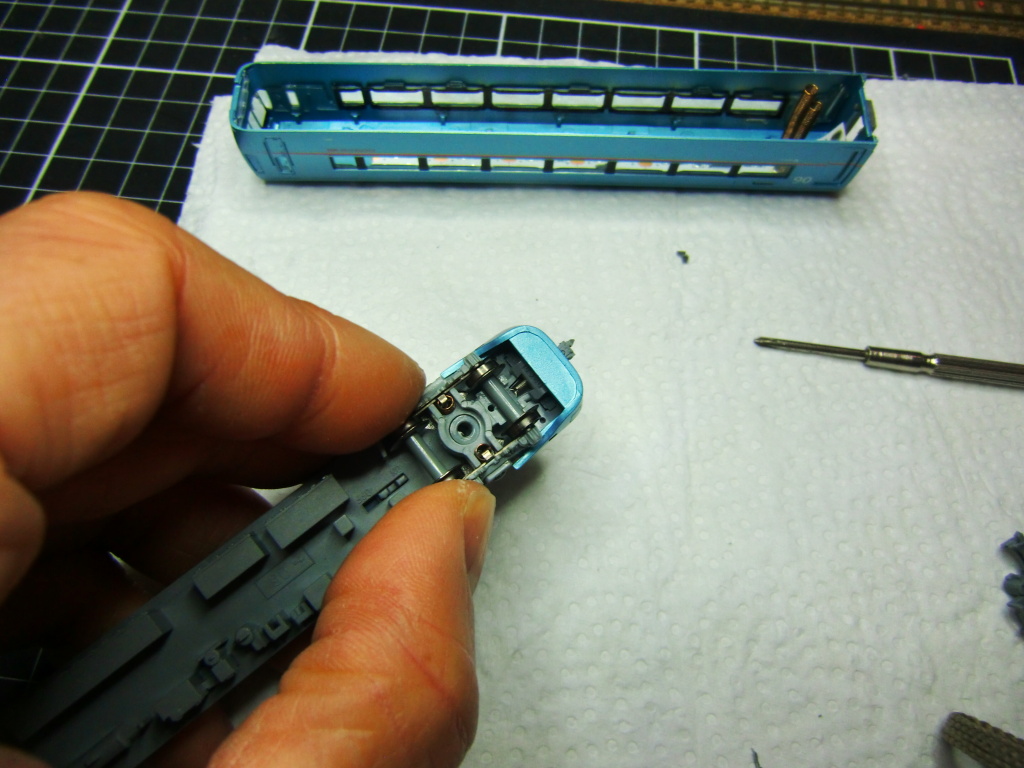






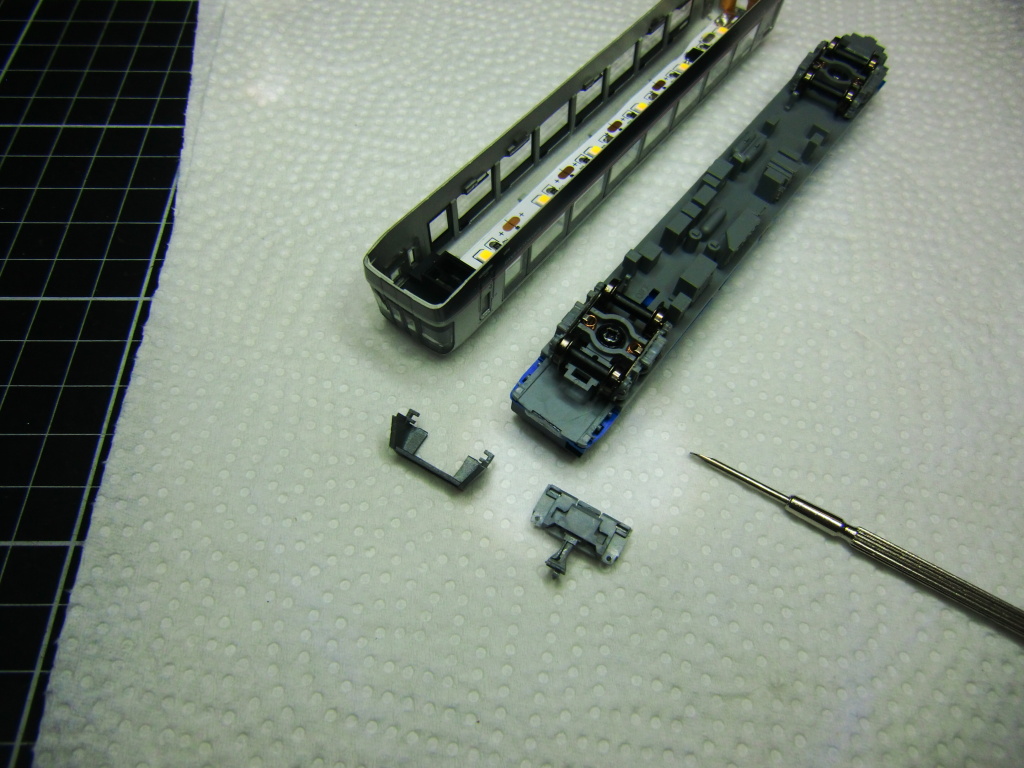
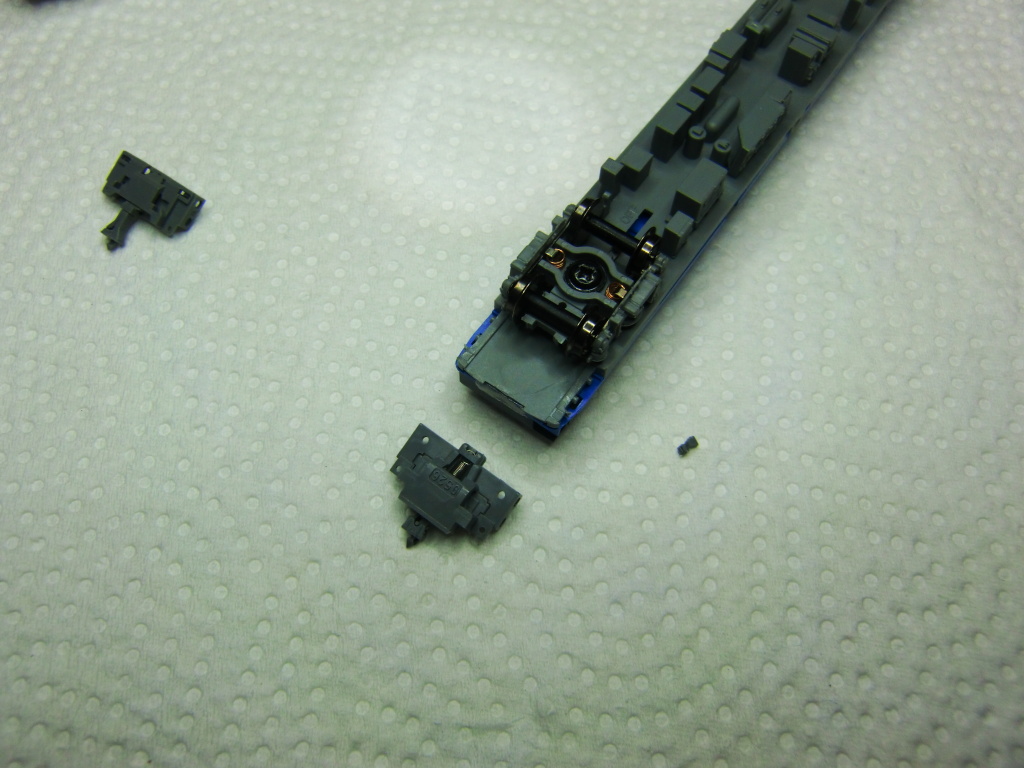
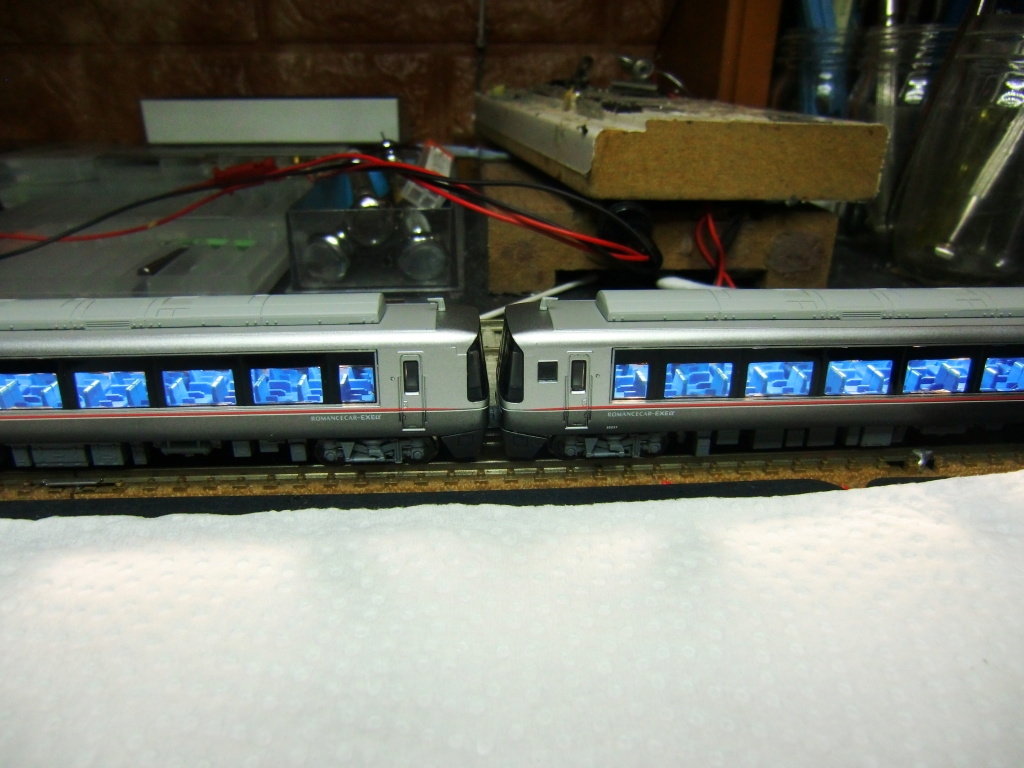
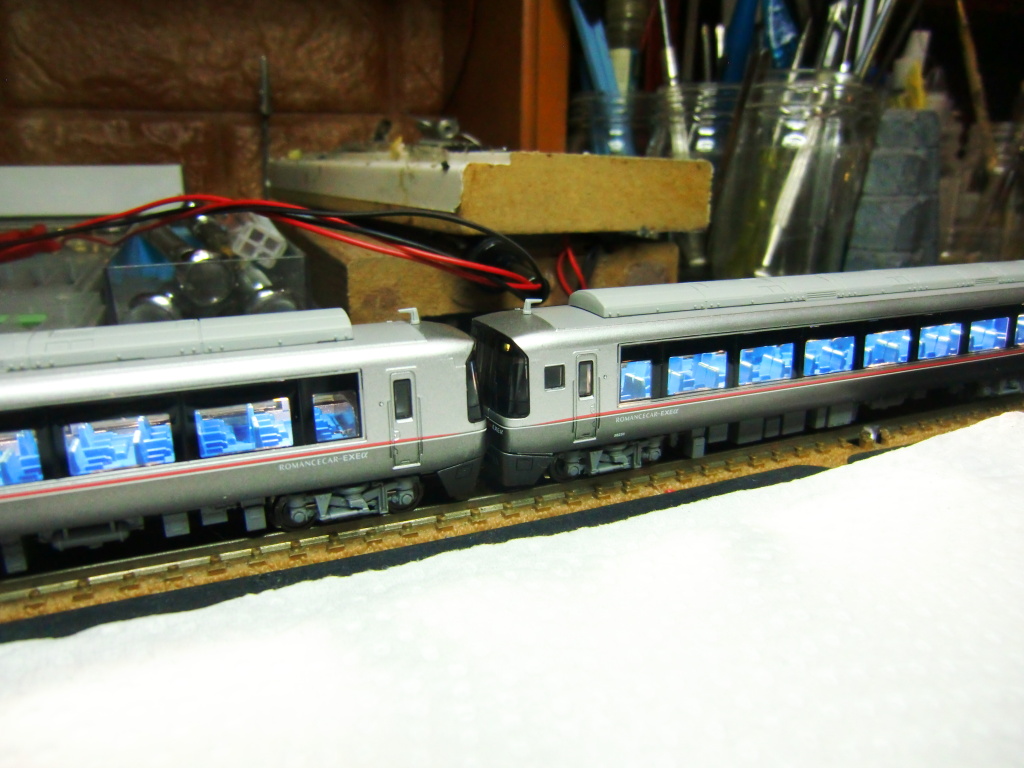


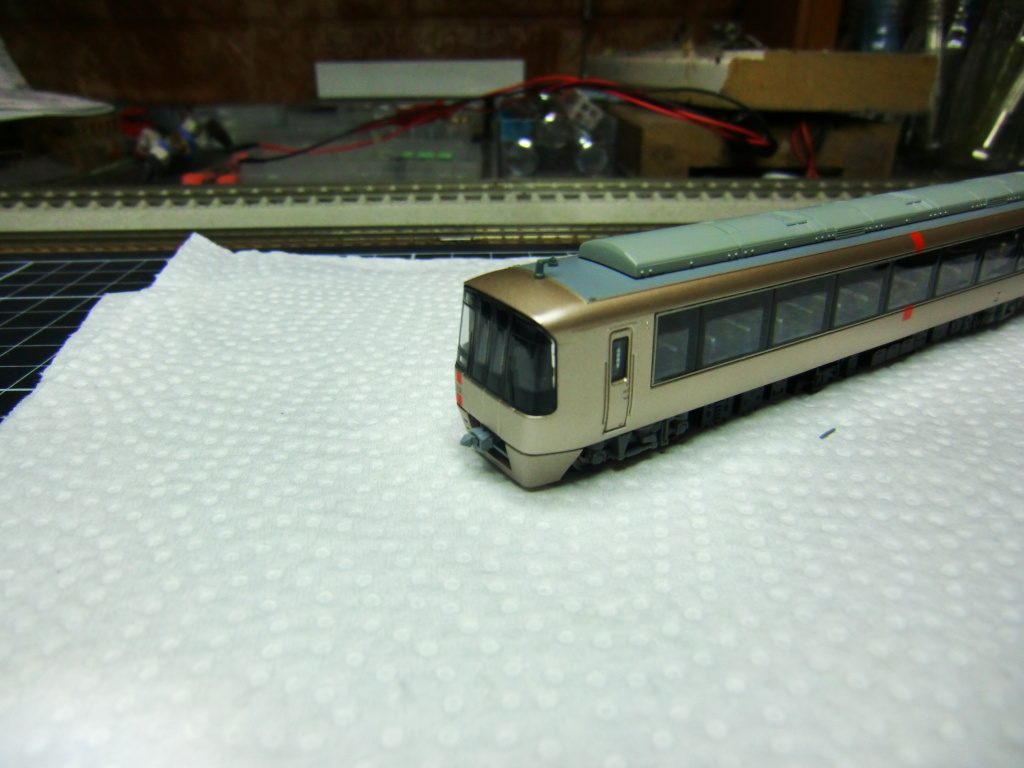

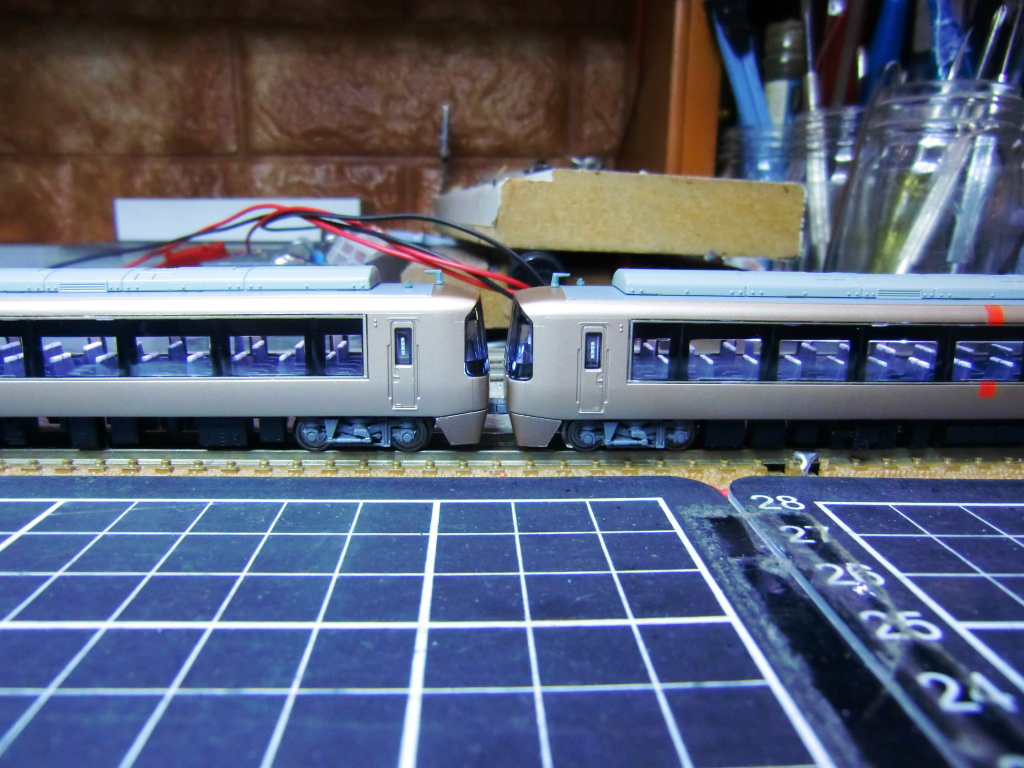
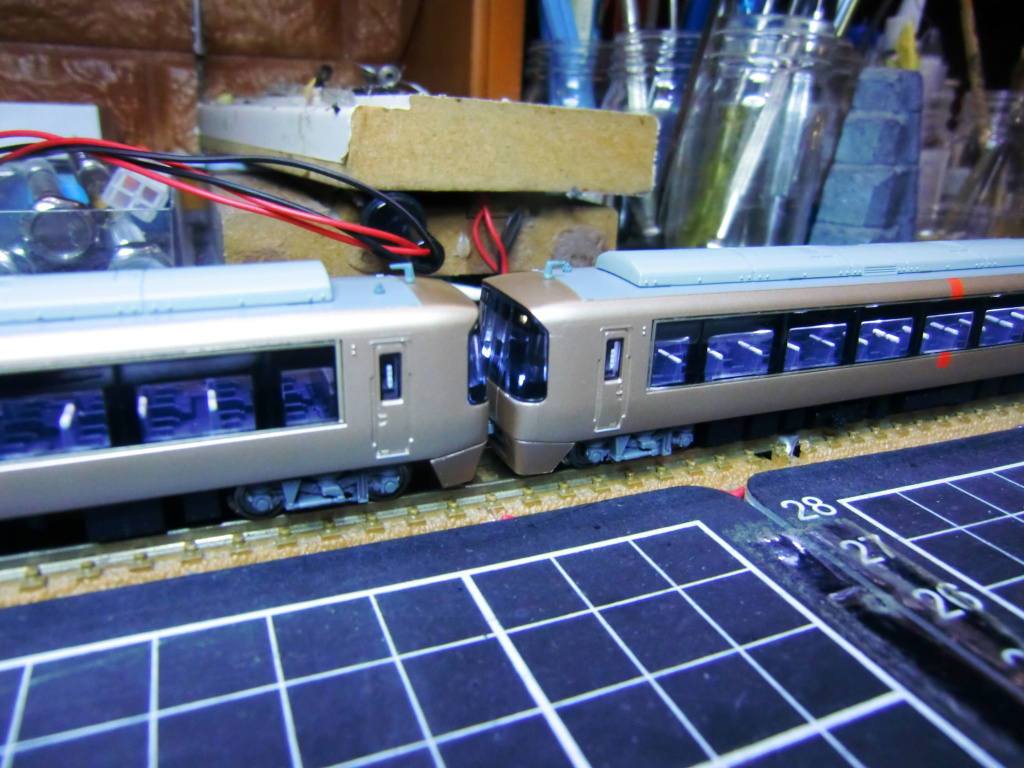

作業完了でございます。連結面が短縮化されたことで、見た目もだいぶ良くなったと思います。


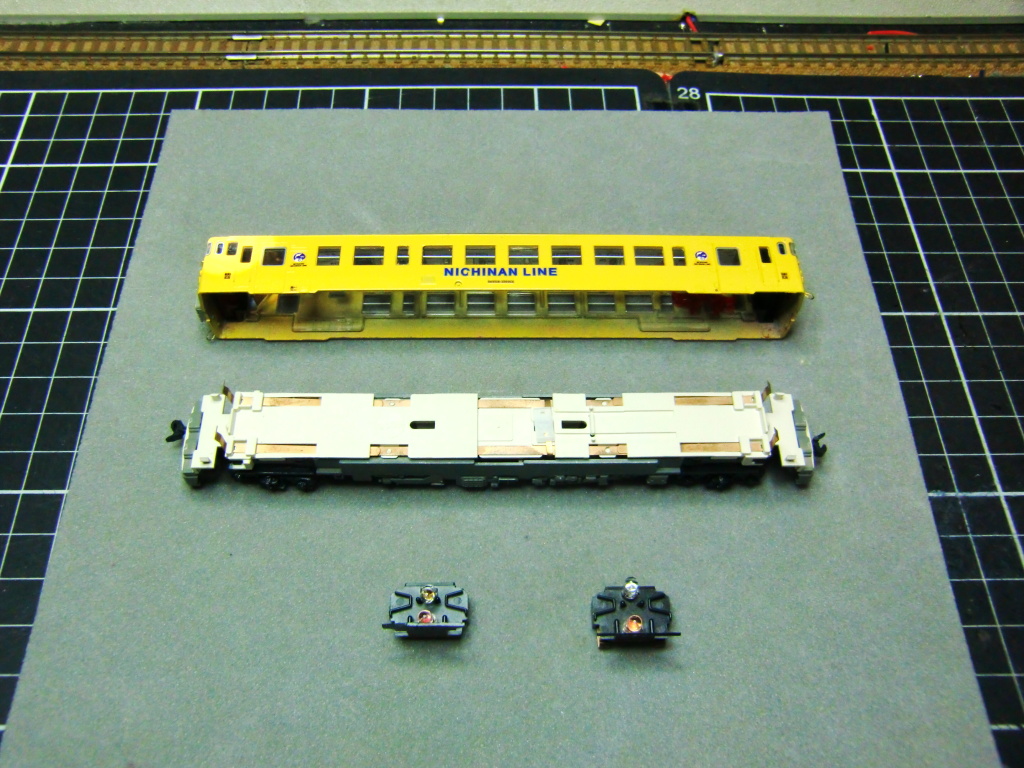
今回の作業では、既存LEDから高輝度LEDへの組み替え作業となります。
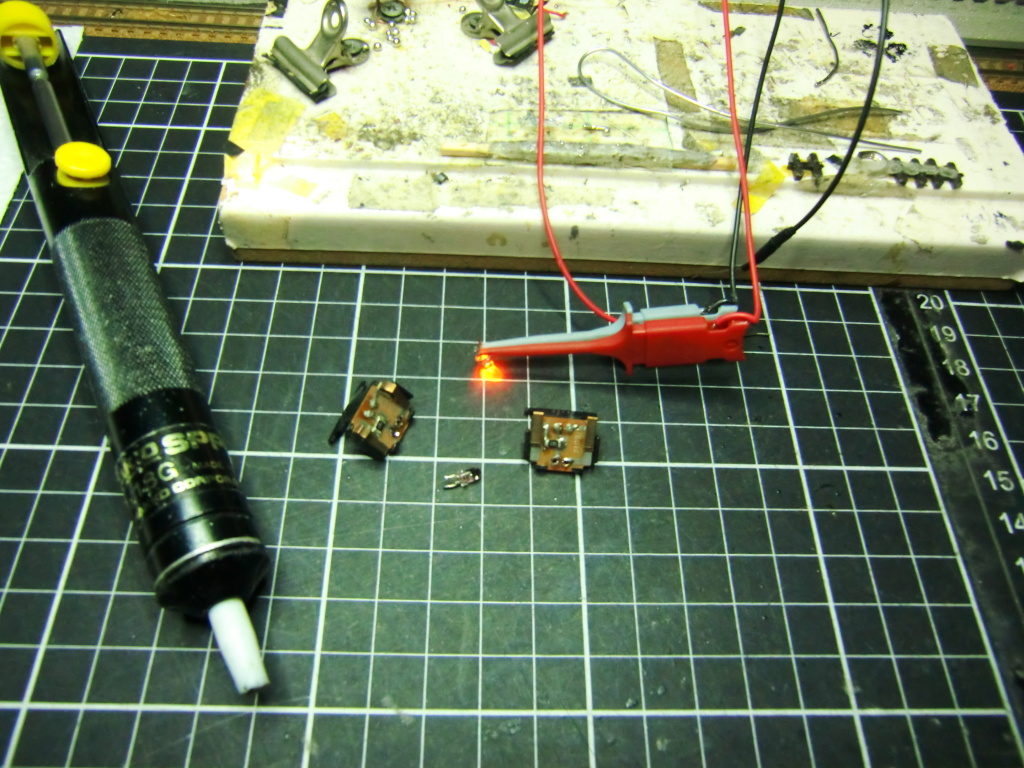
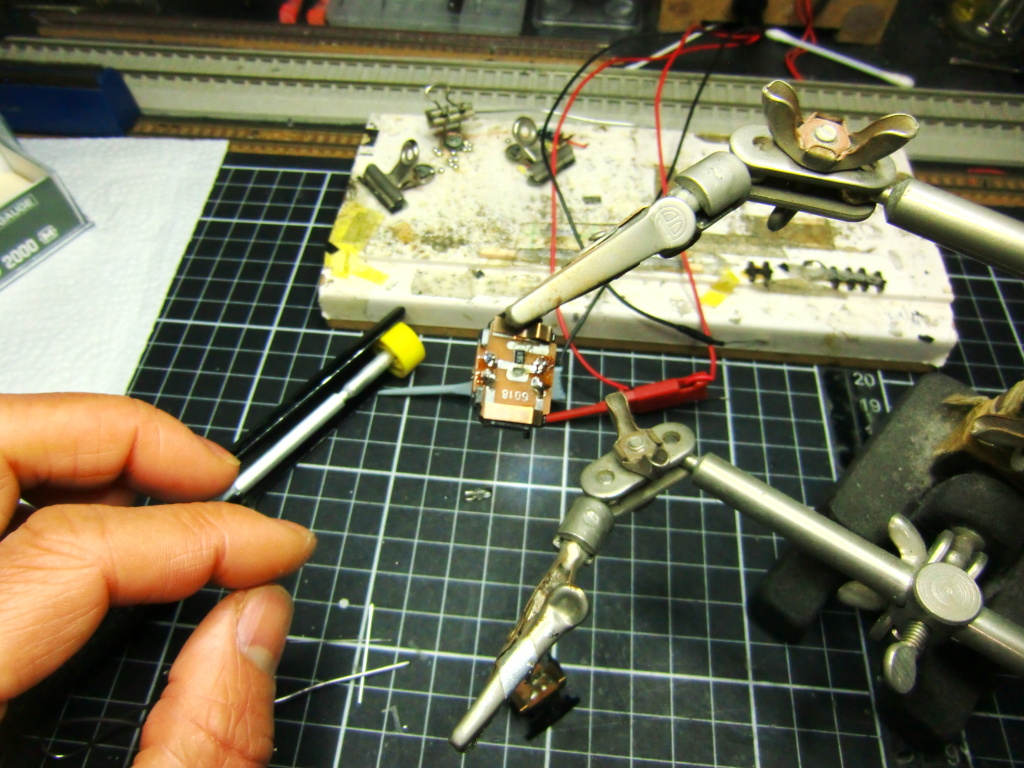
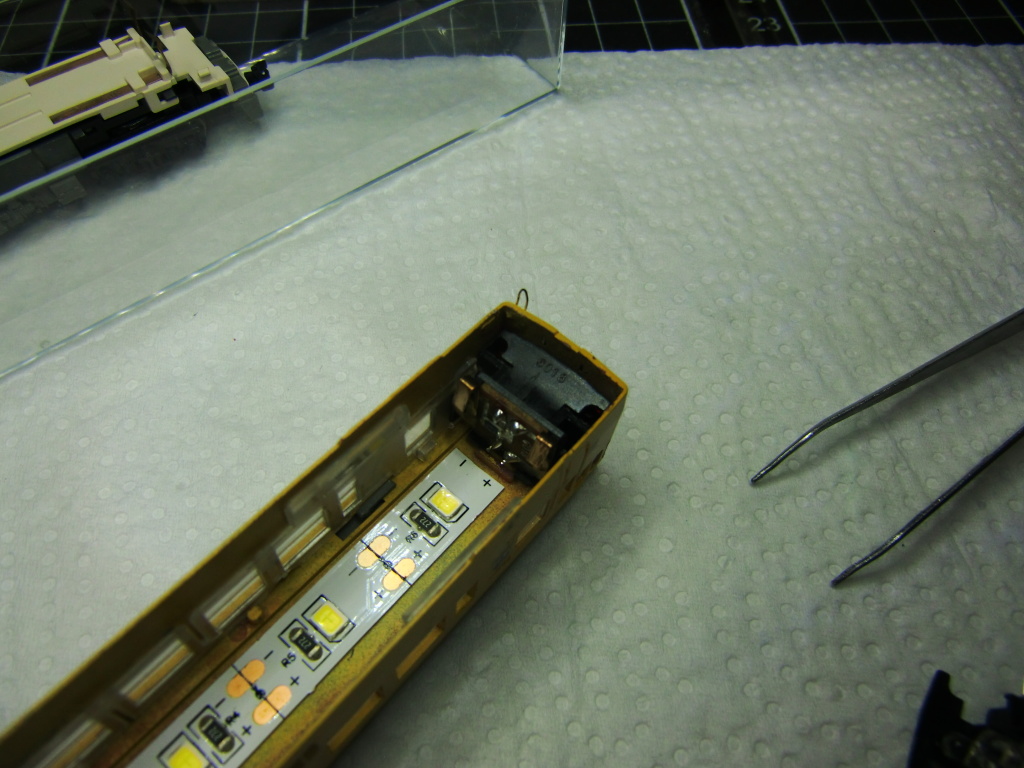
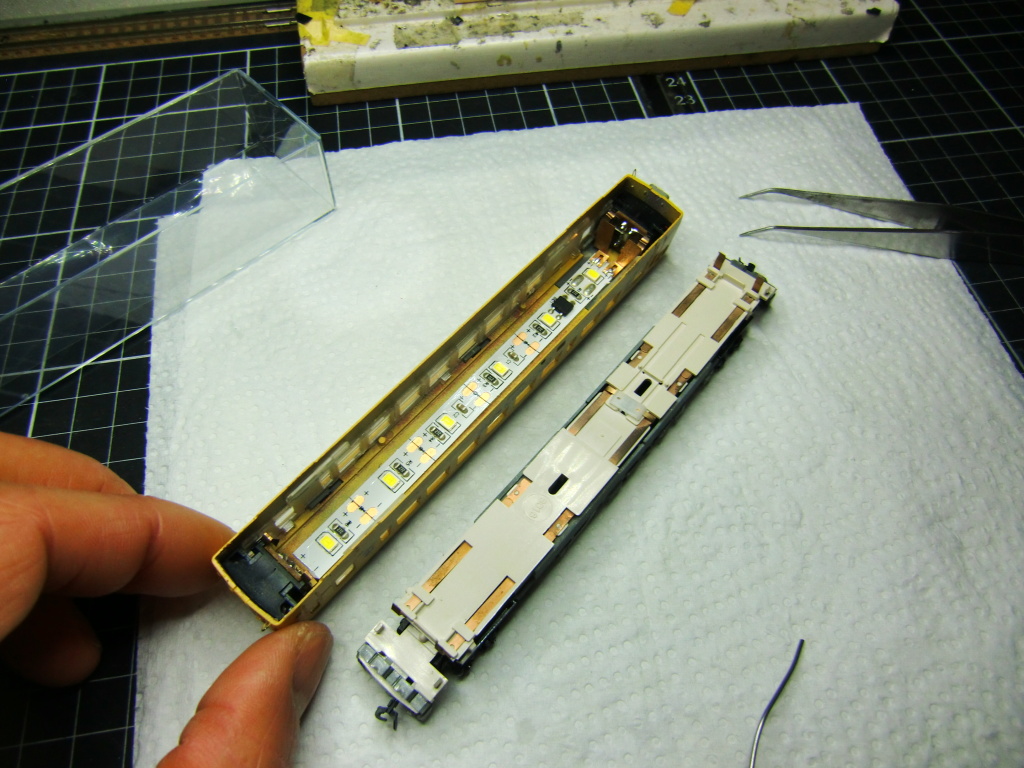
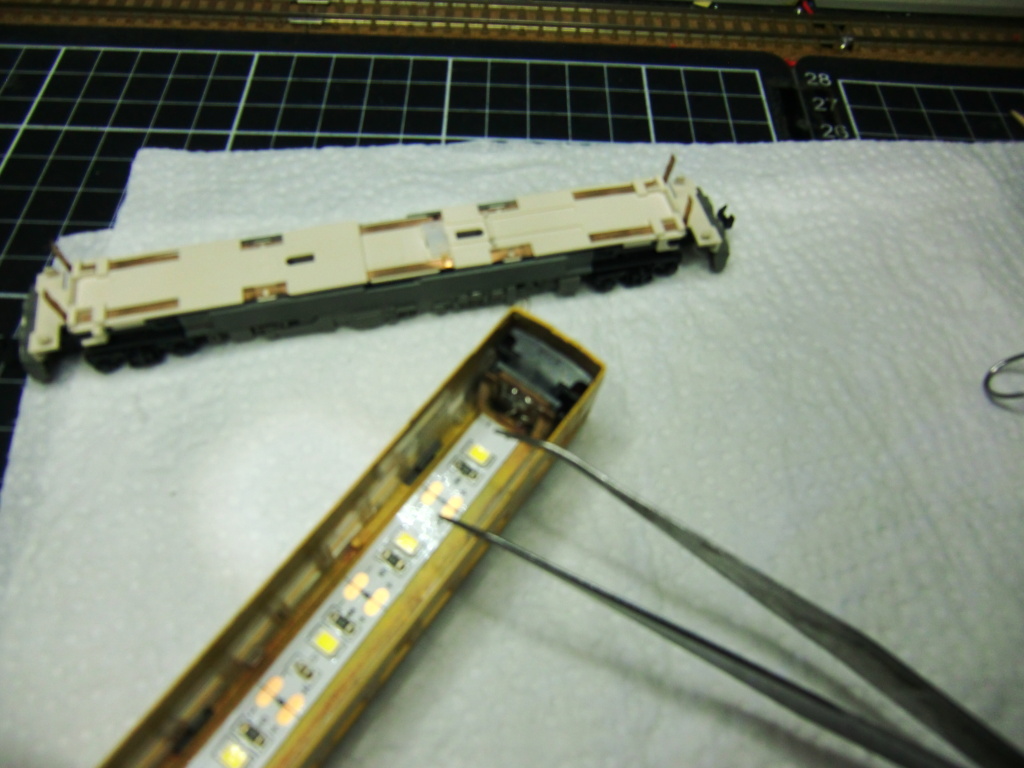
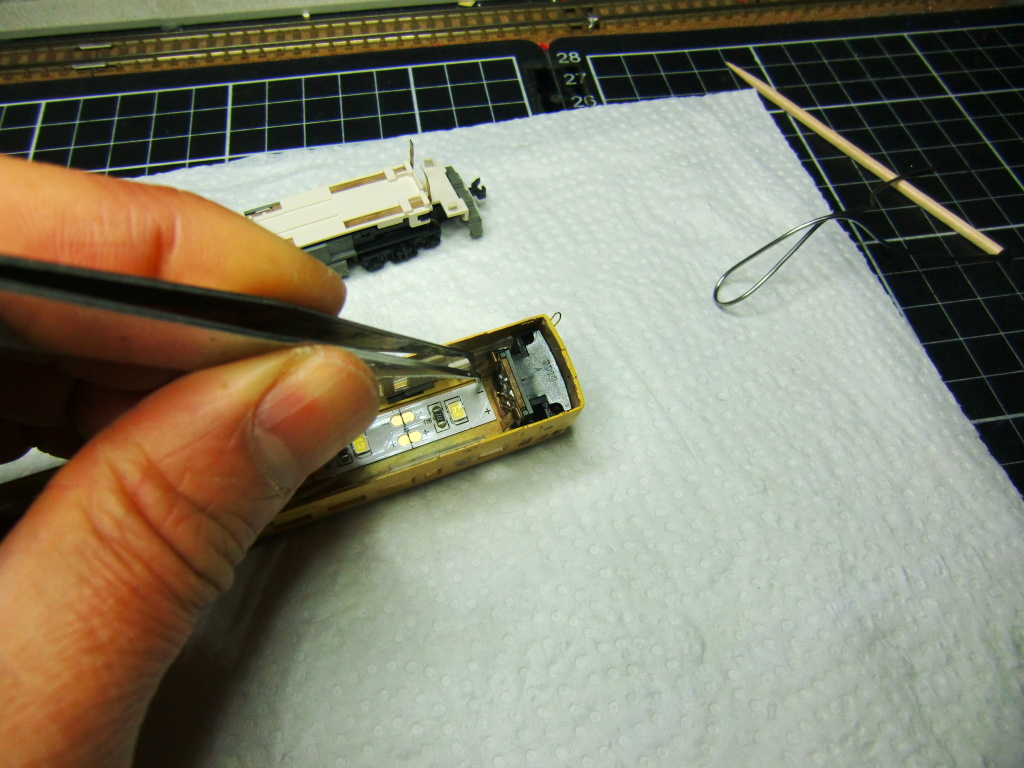


ヘッド・テールともに大変明るくなりました。作業完了でございます。

HOゲージにつきましては、取付けするパーツ数は意外とあります。作業途中の工程写真は省略します。

パーツおよびインレタを貼り終えた車体です。






作業が完了いたしました。
まとめてのご依頼となりますので、機関車と客車の2段階に分けて作業を進めていくことにいたします。それでは作業にとりかかります。

▼DD51オーバーホール

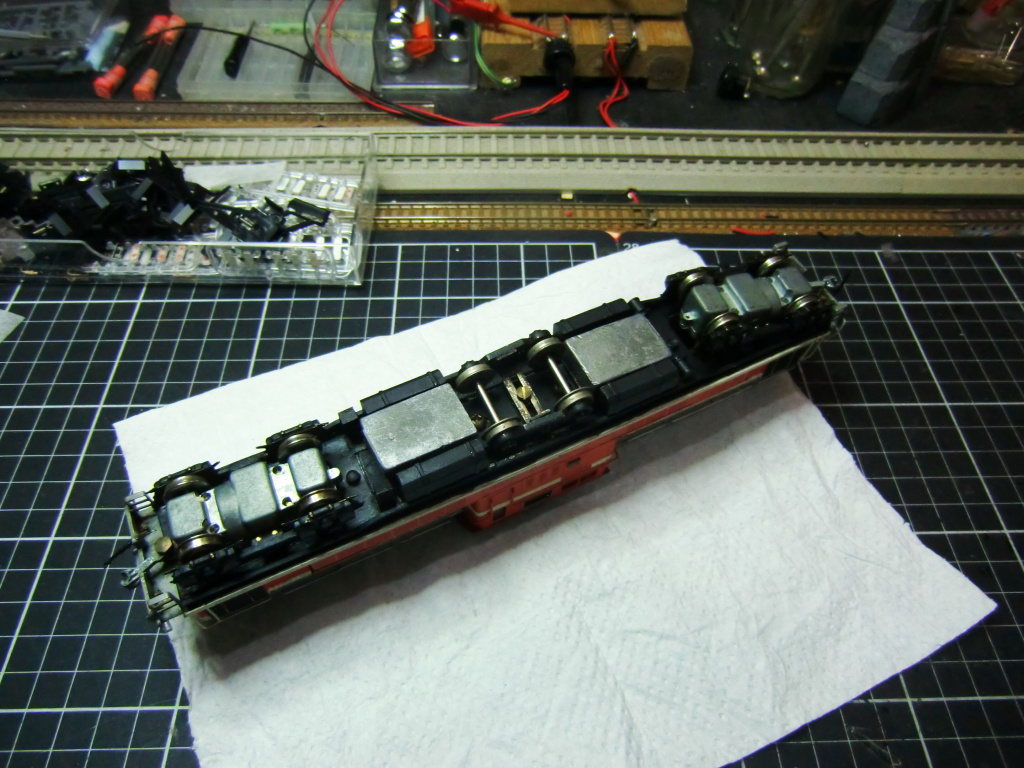
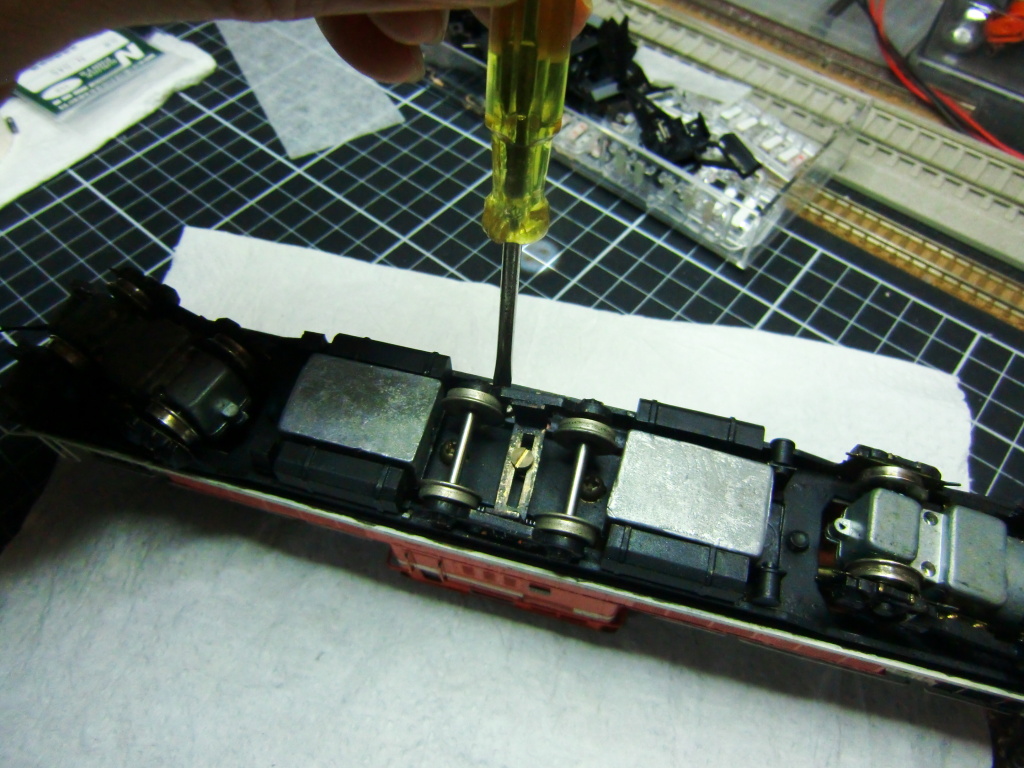
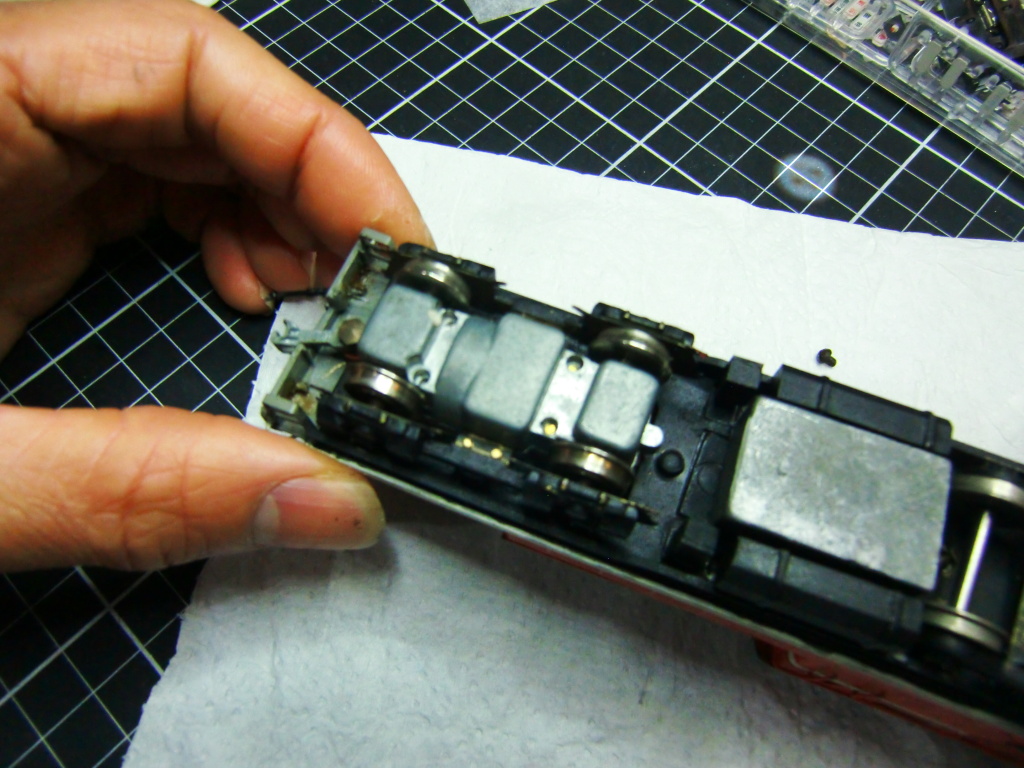

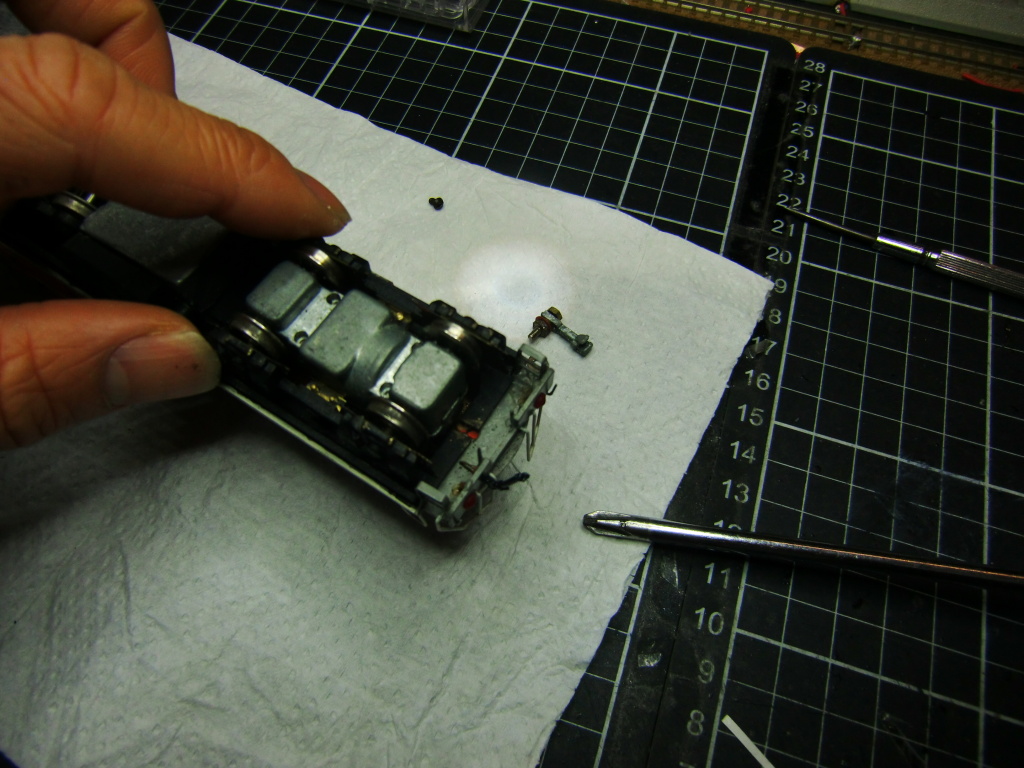
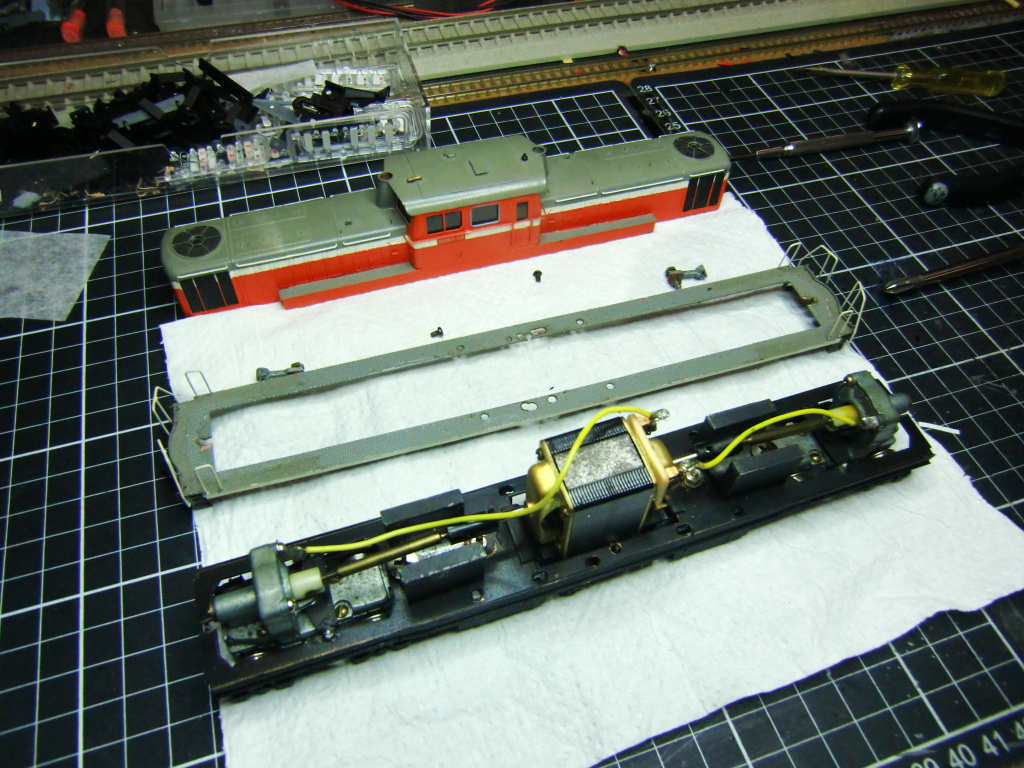

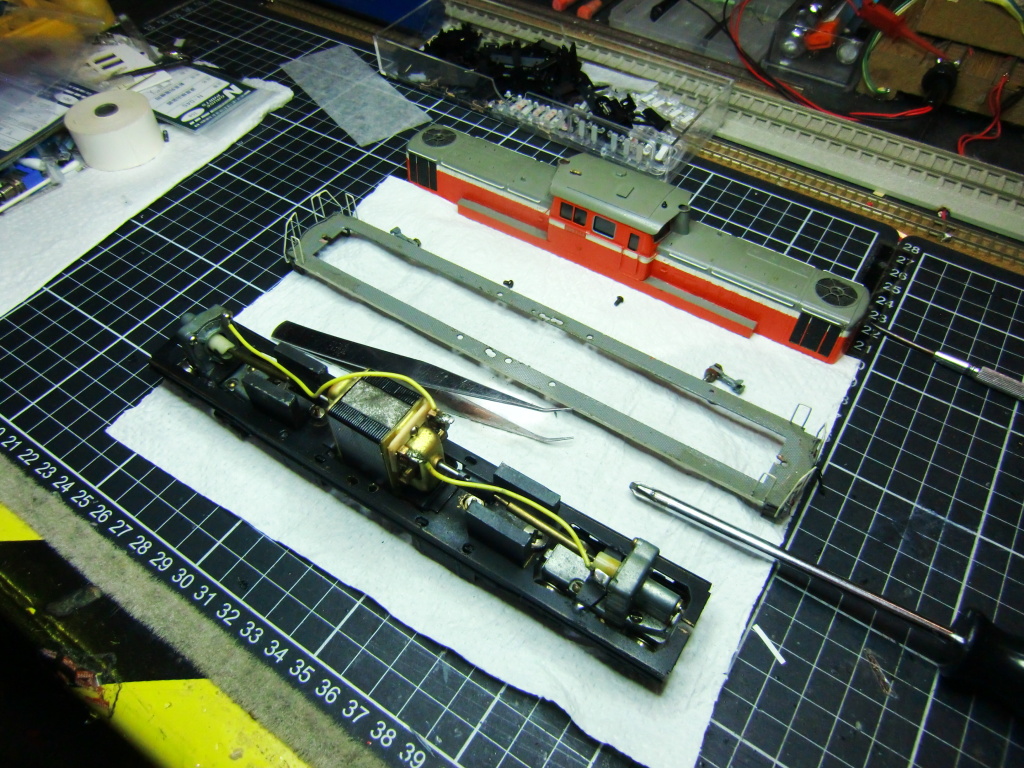
モーターもすべて取り外して分解していきます。
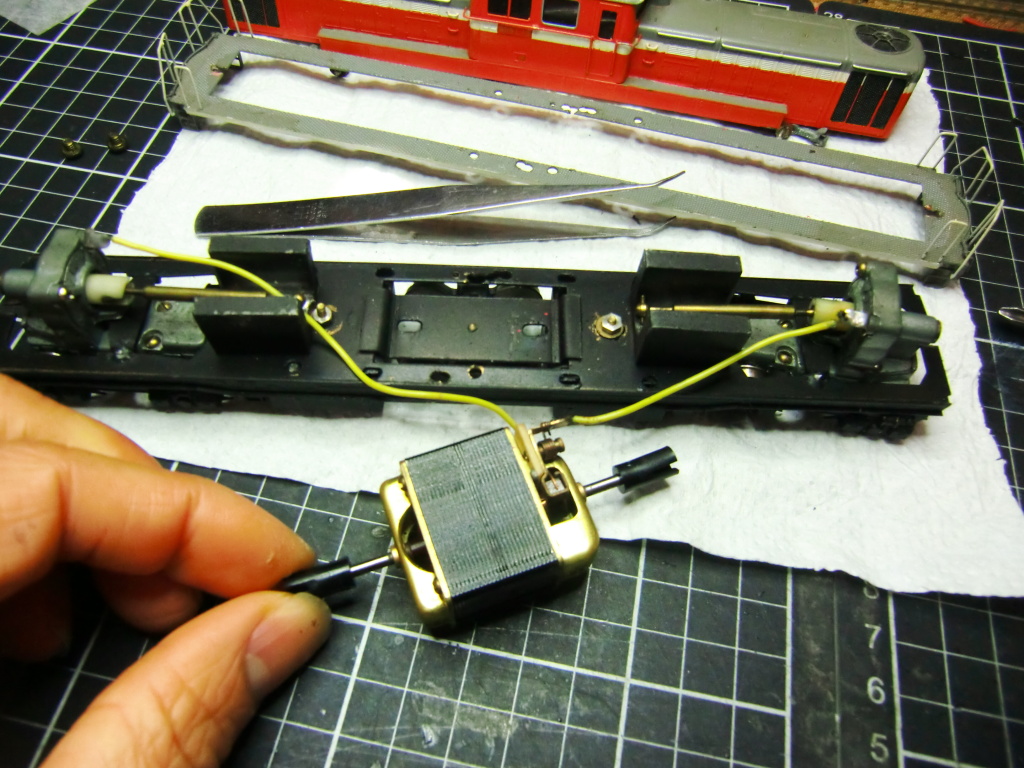
モーター内部もすべてメンテを行っていきます。
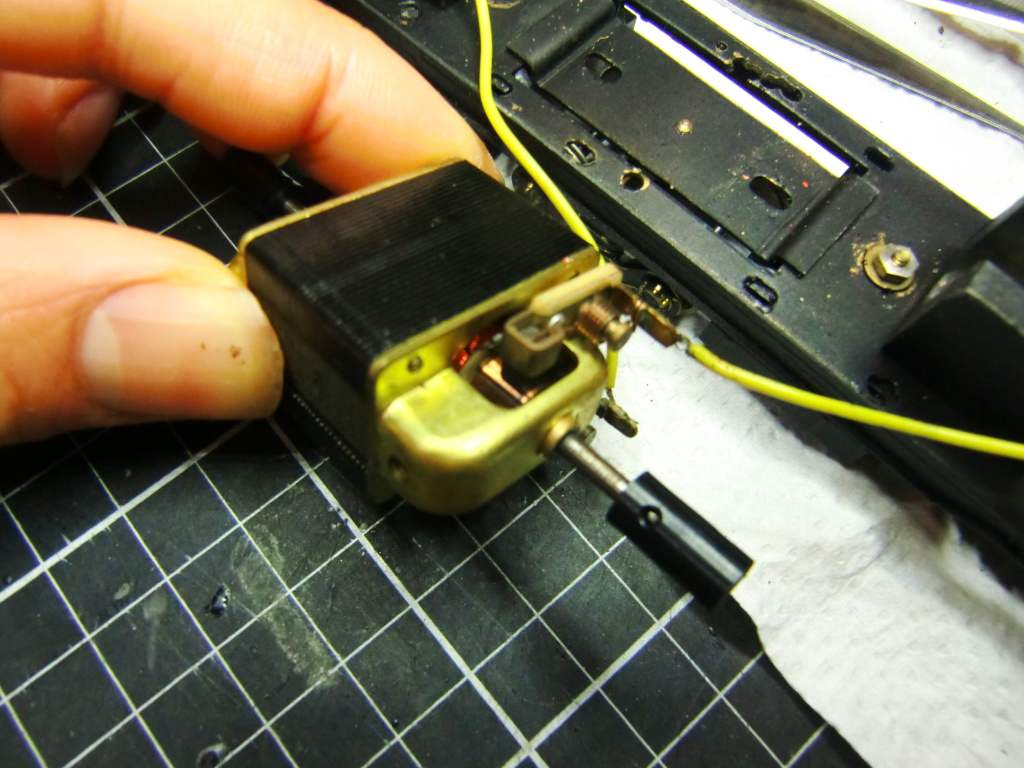
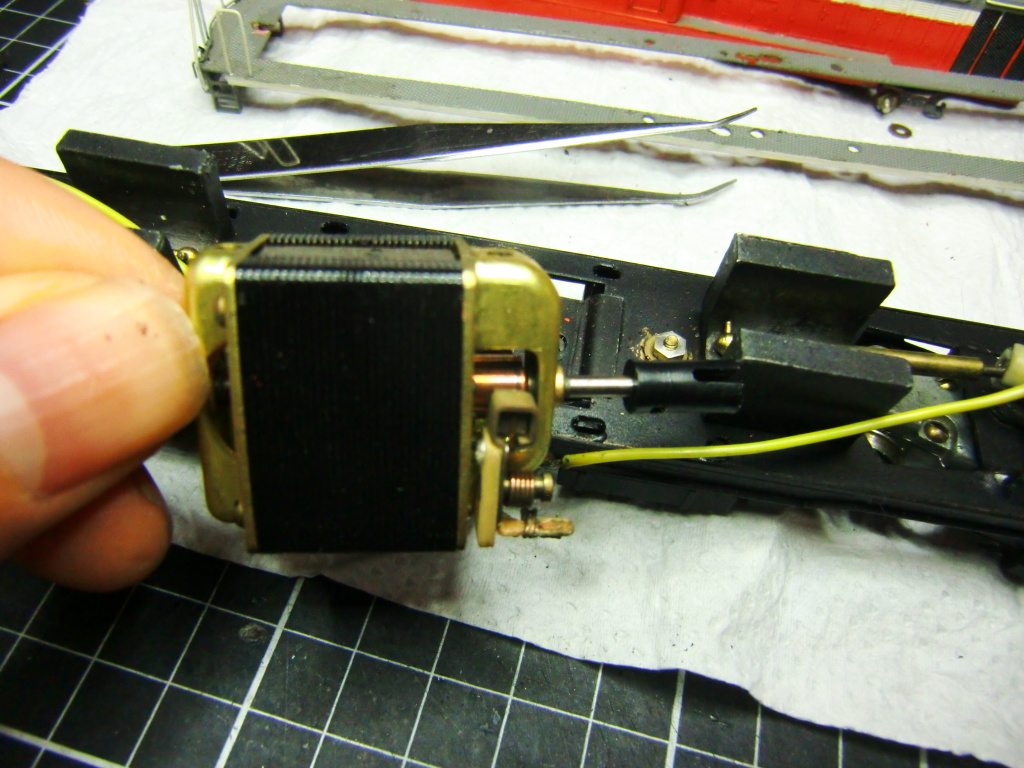

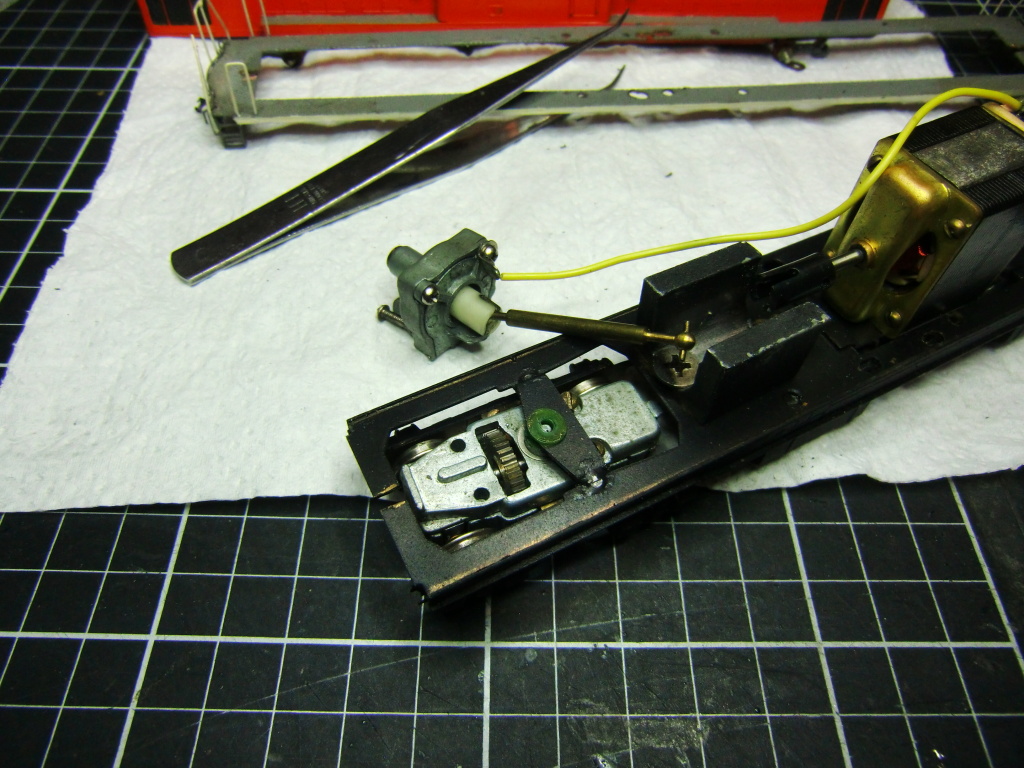
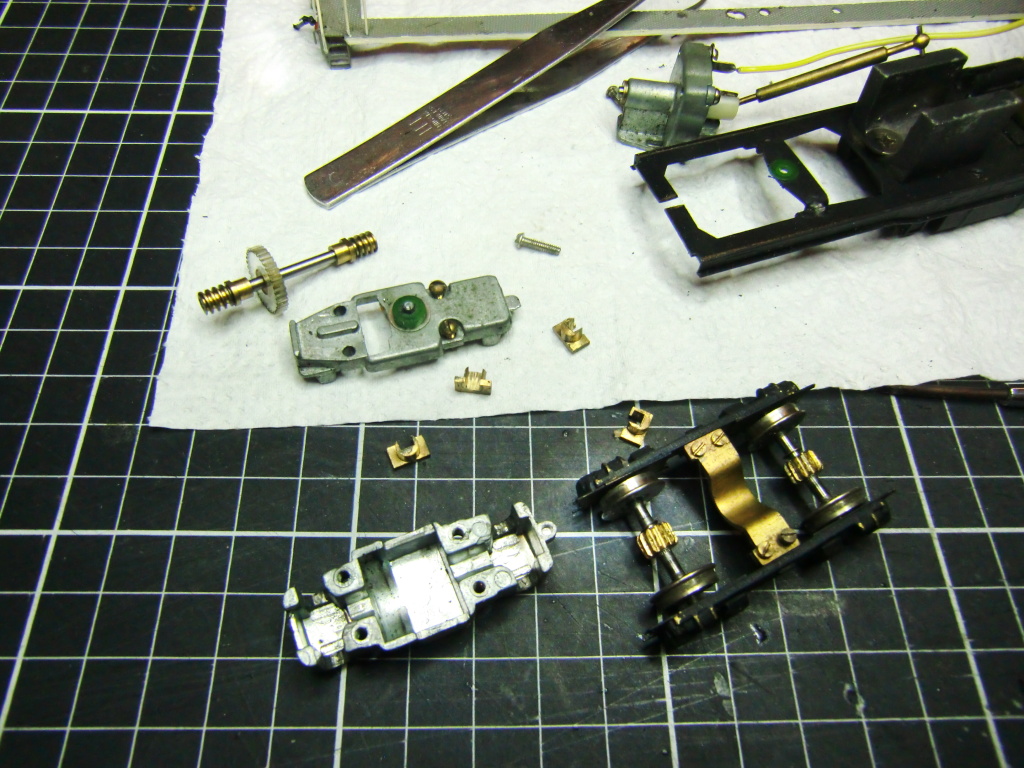
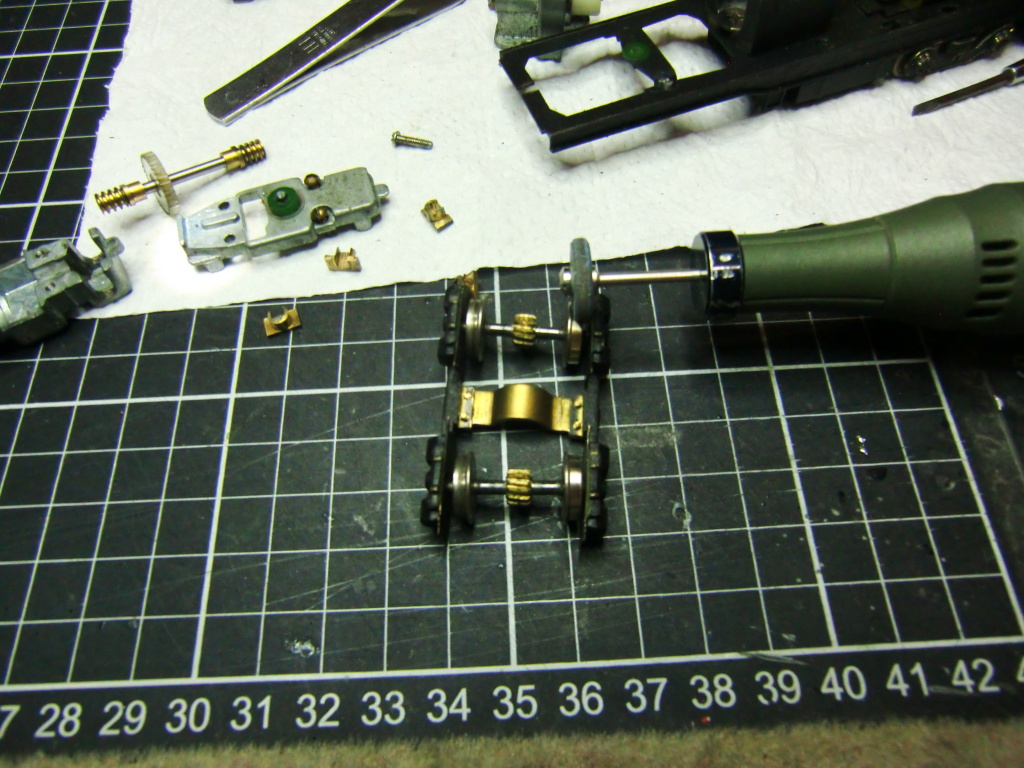
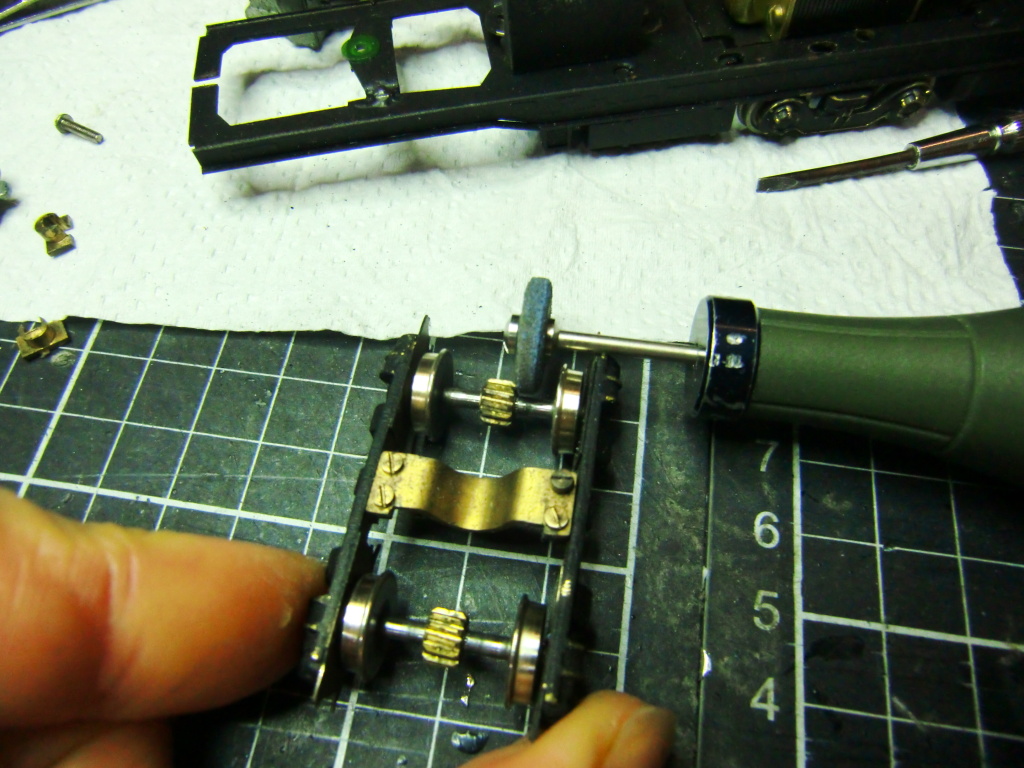




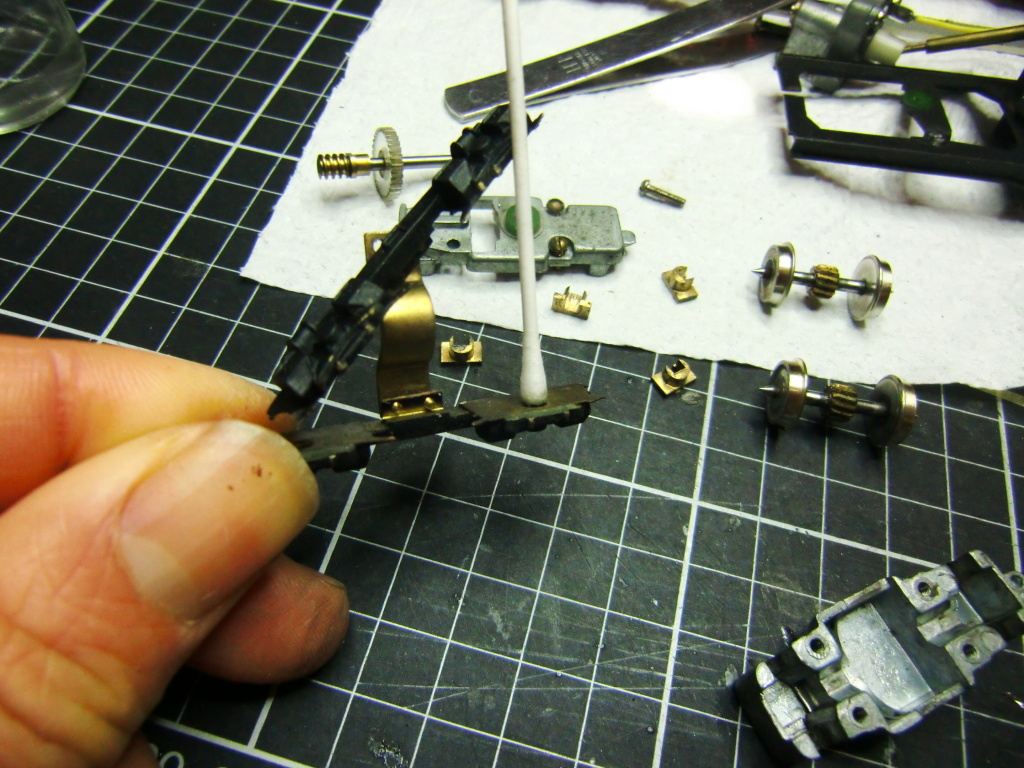

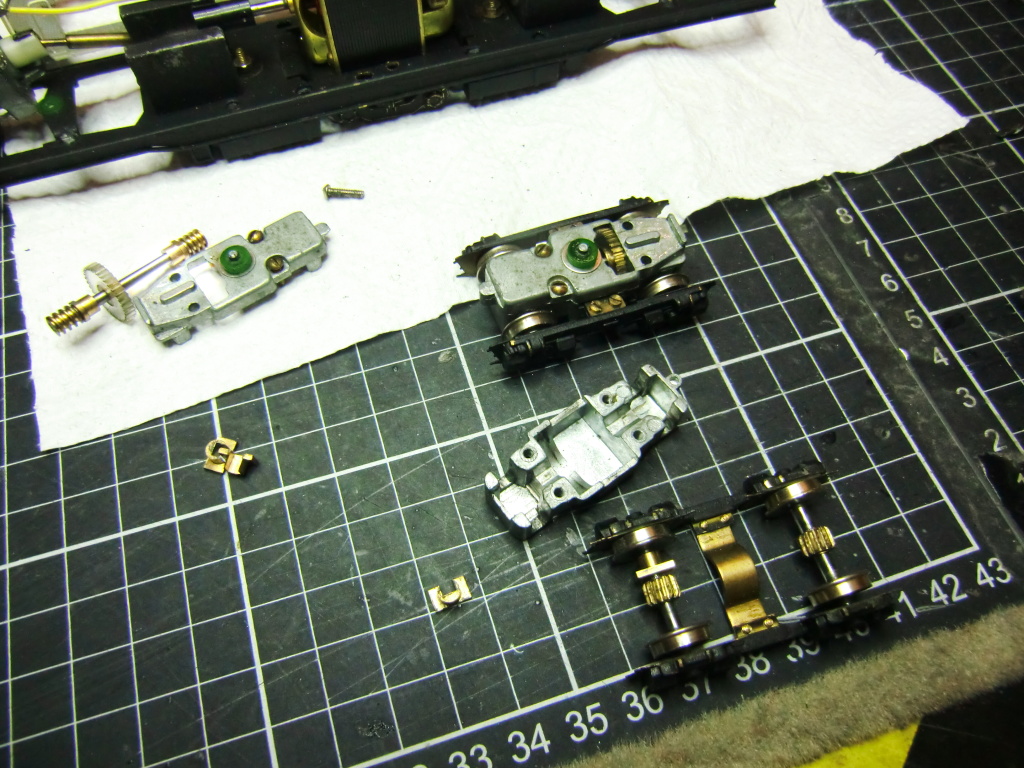
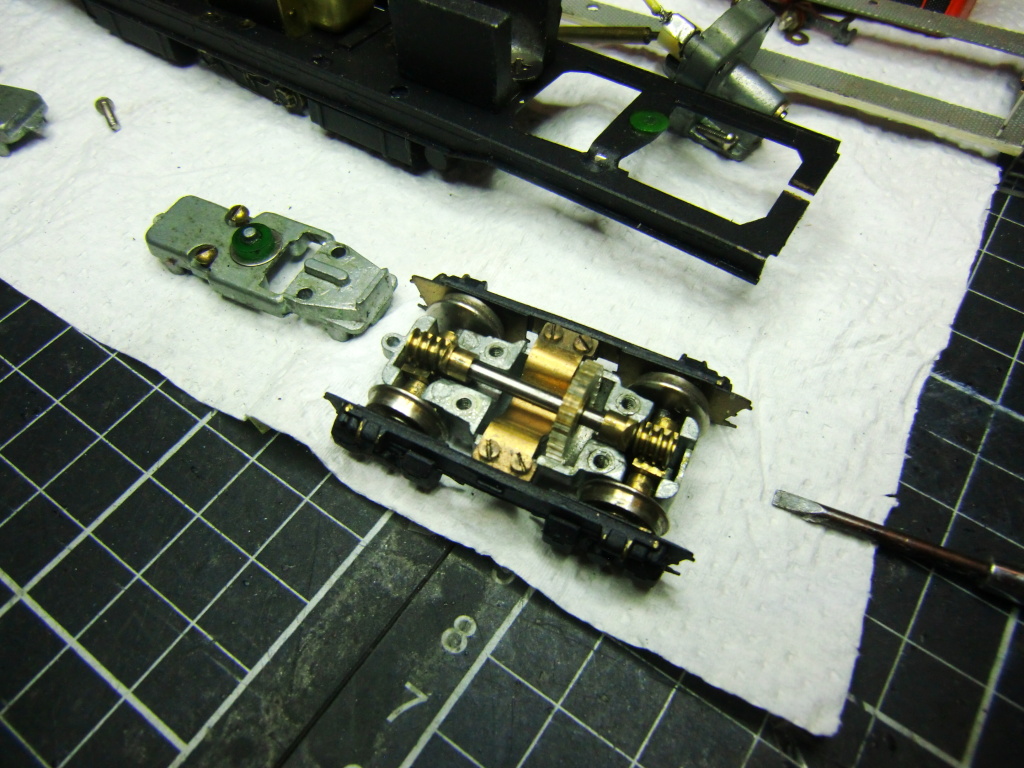

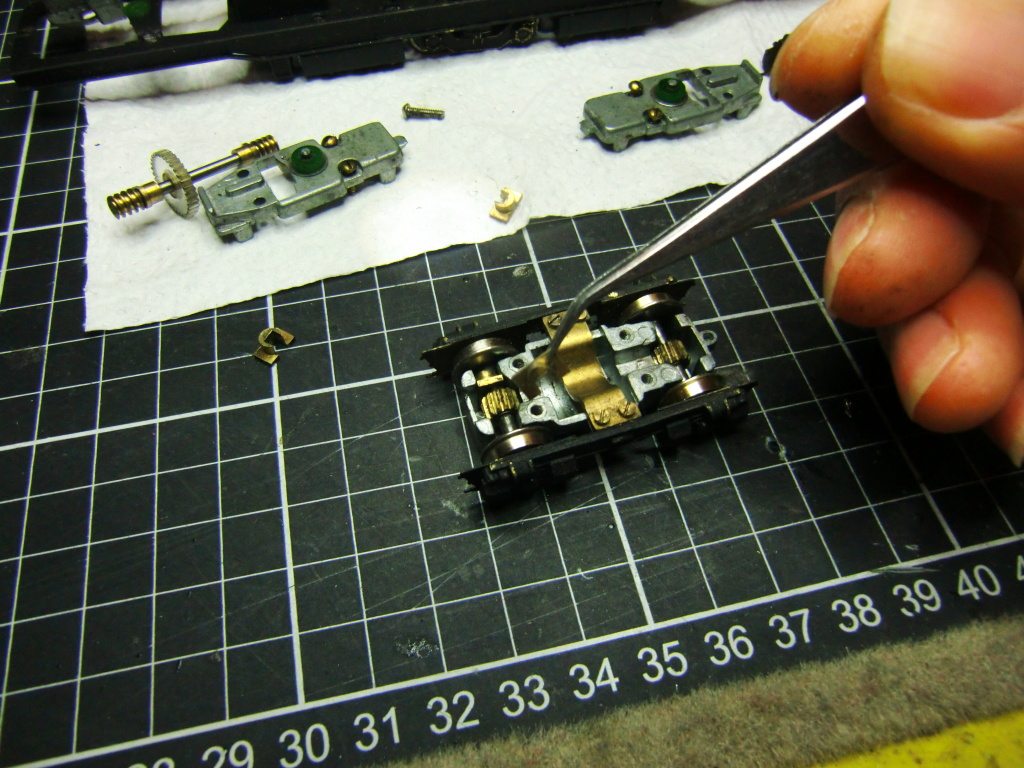


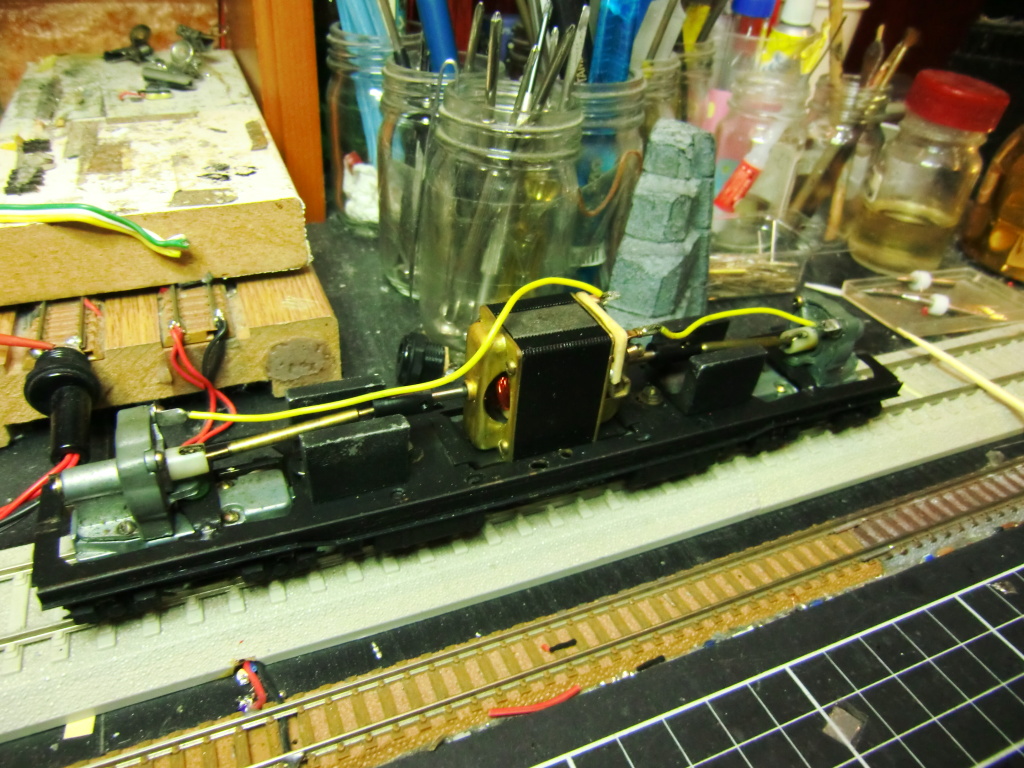
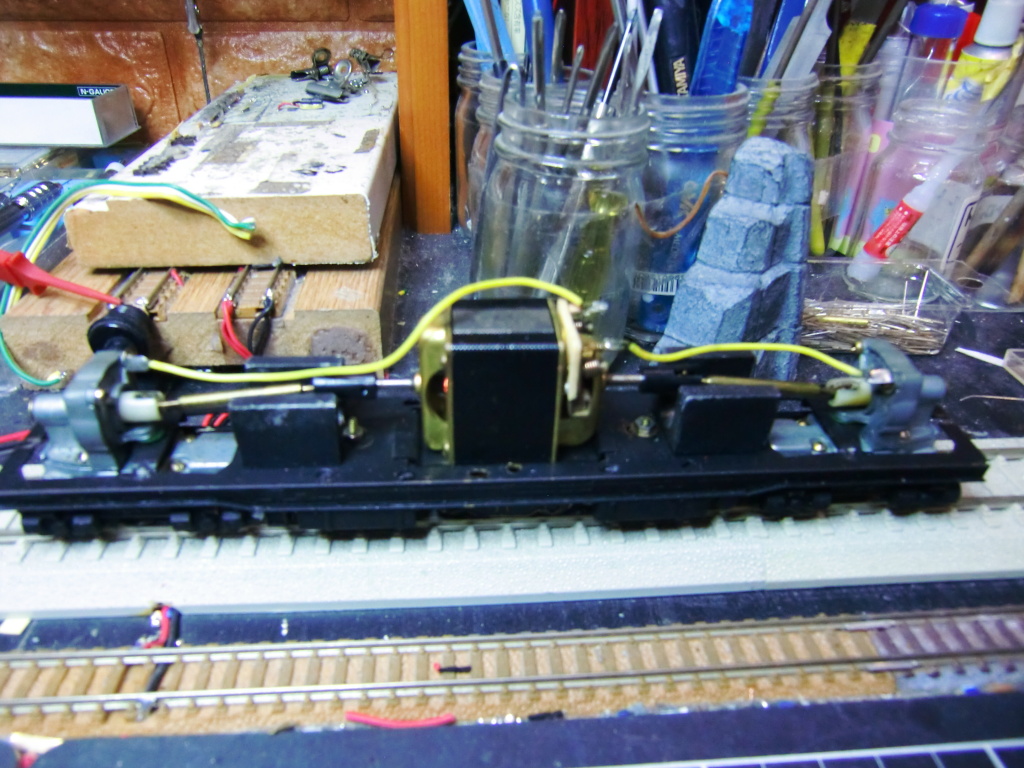
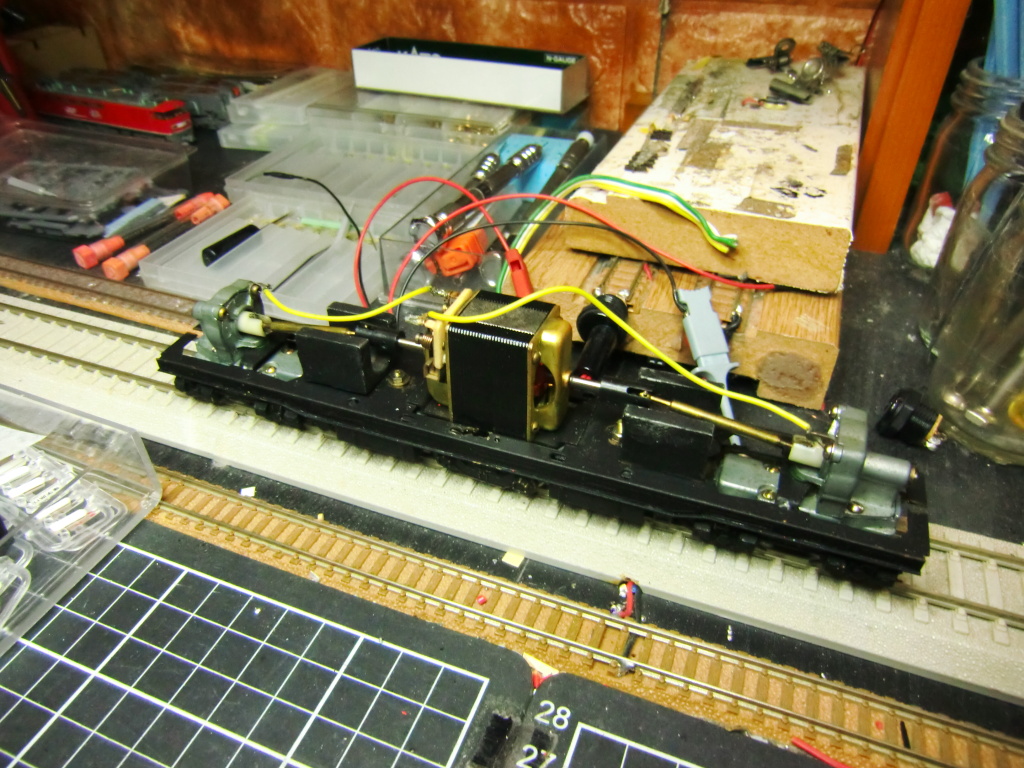
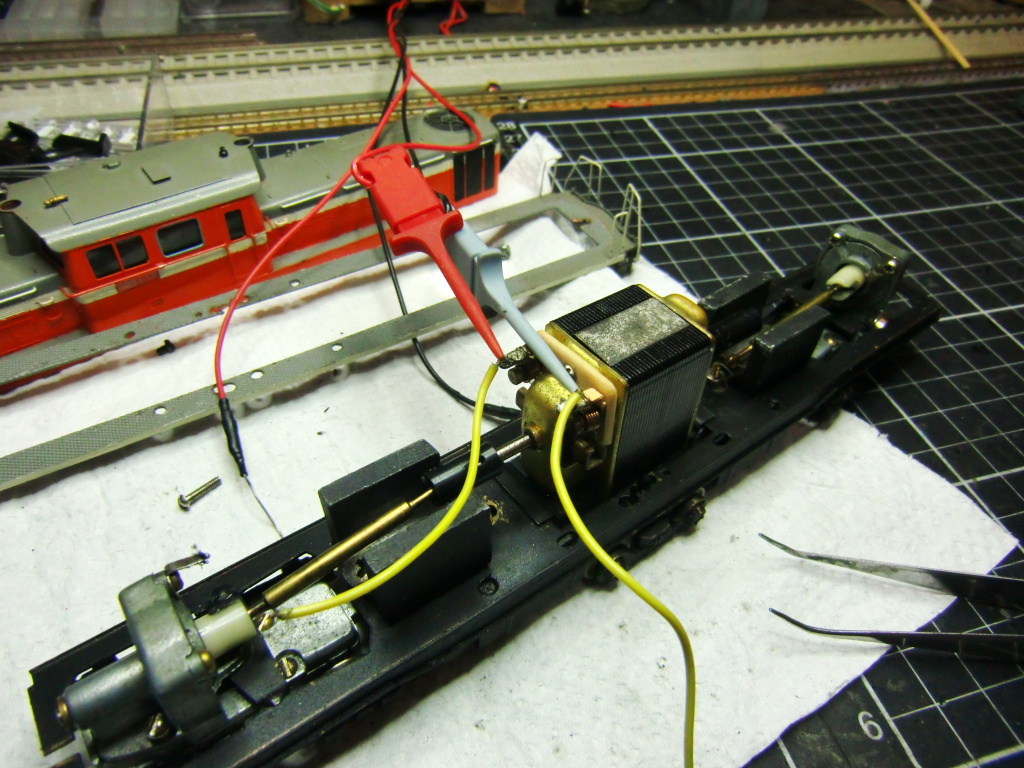
回転が重く台車内部で抵抗となっている箇所があるようです。何度か分解と調整を繰り返しながら問題個所を1つ1つ取り除いていきました。モーターからもかなり大きな異音が出ていましたが、だいぶ改善しました。

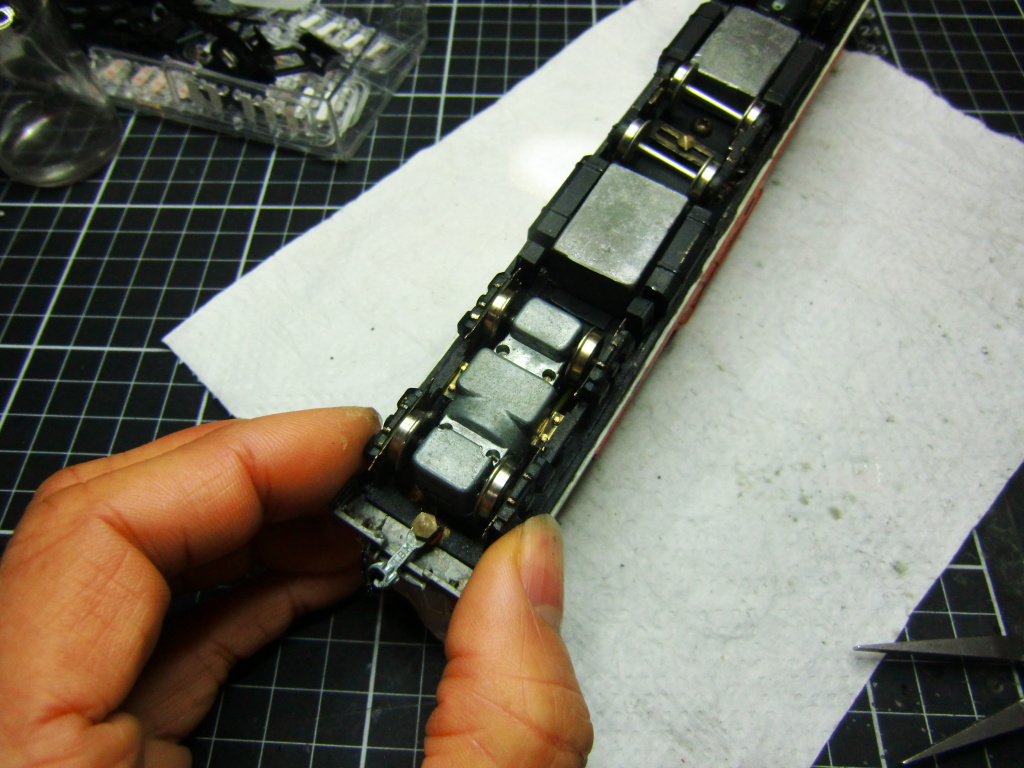



DD51復活です。車輪もすべてピカピカに
▼C51 修理+ライト点灯改造
DD51にやや手こずってしまいましたが、それでは次に行きましょう。ここからは、ライト点灯化改造と修理作業が続きます。

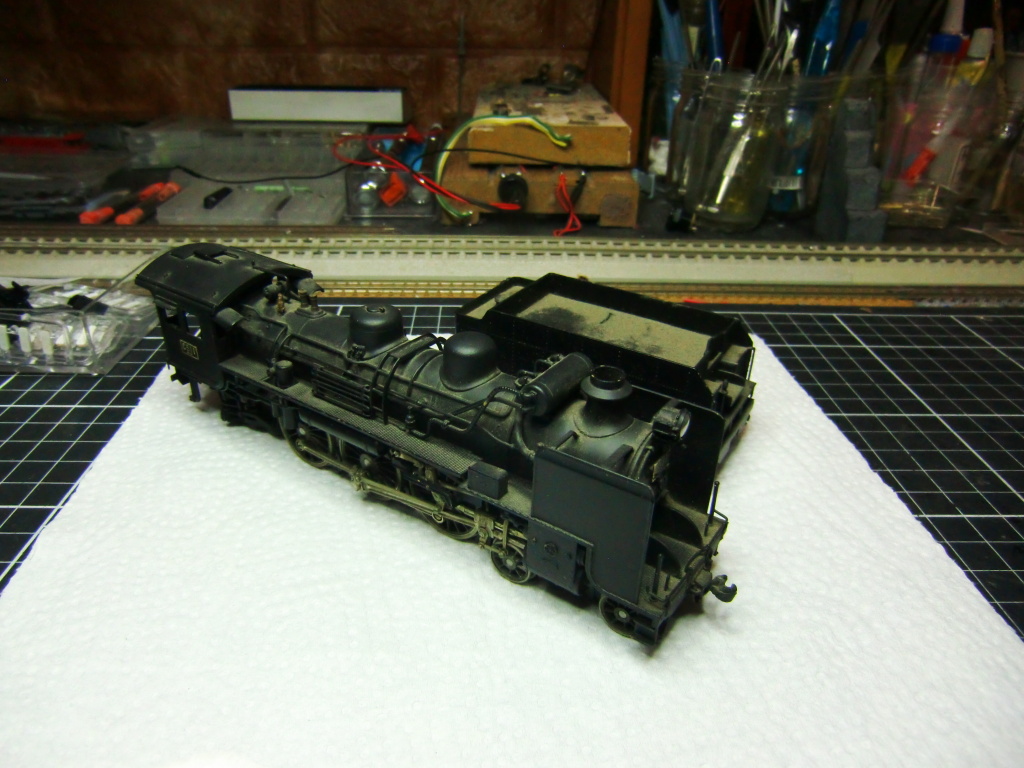

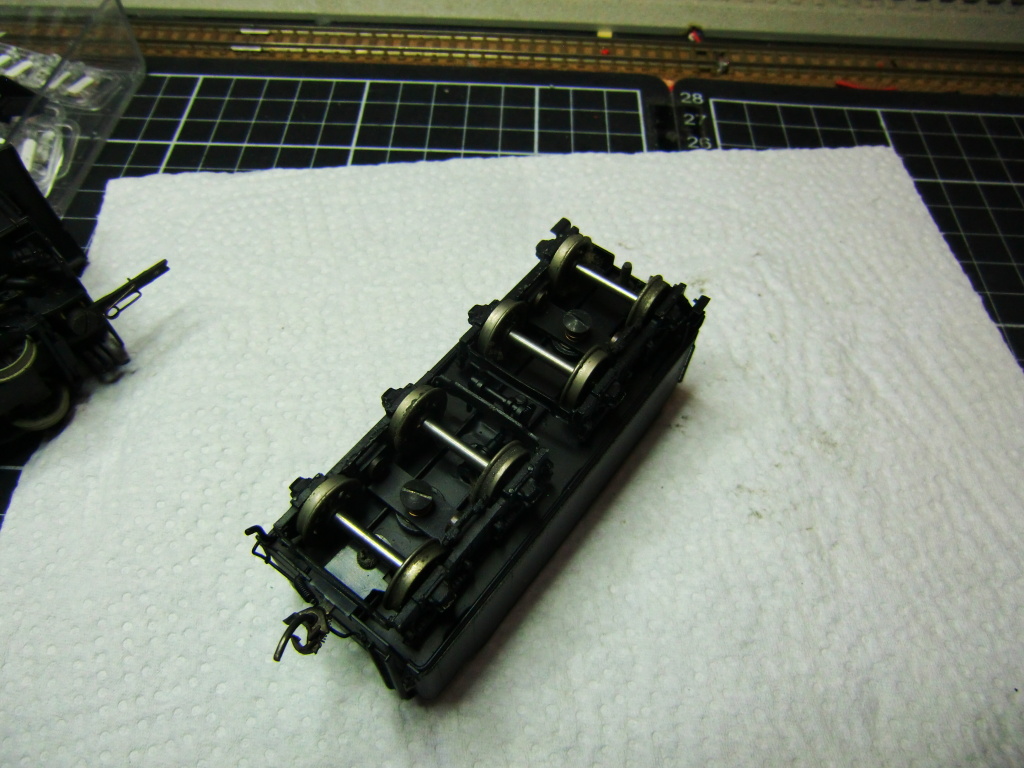

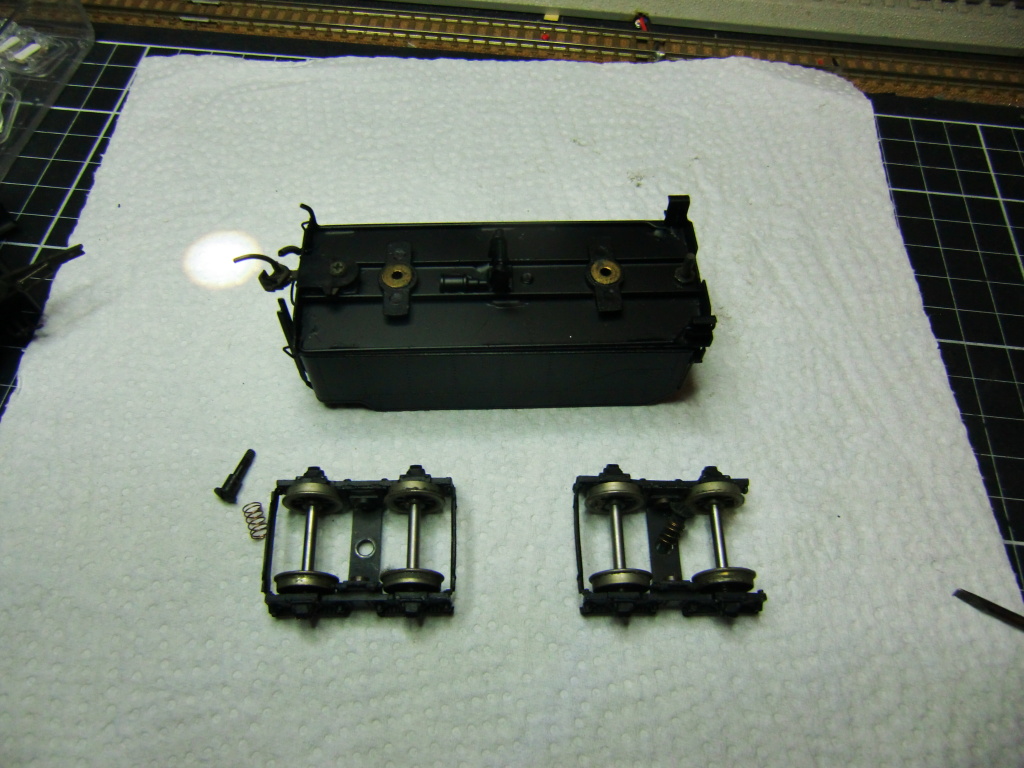
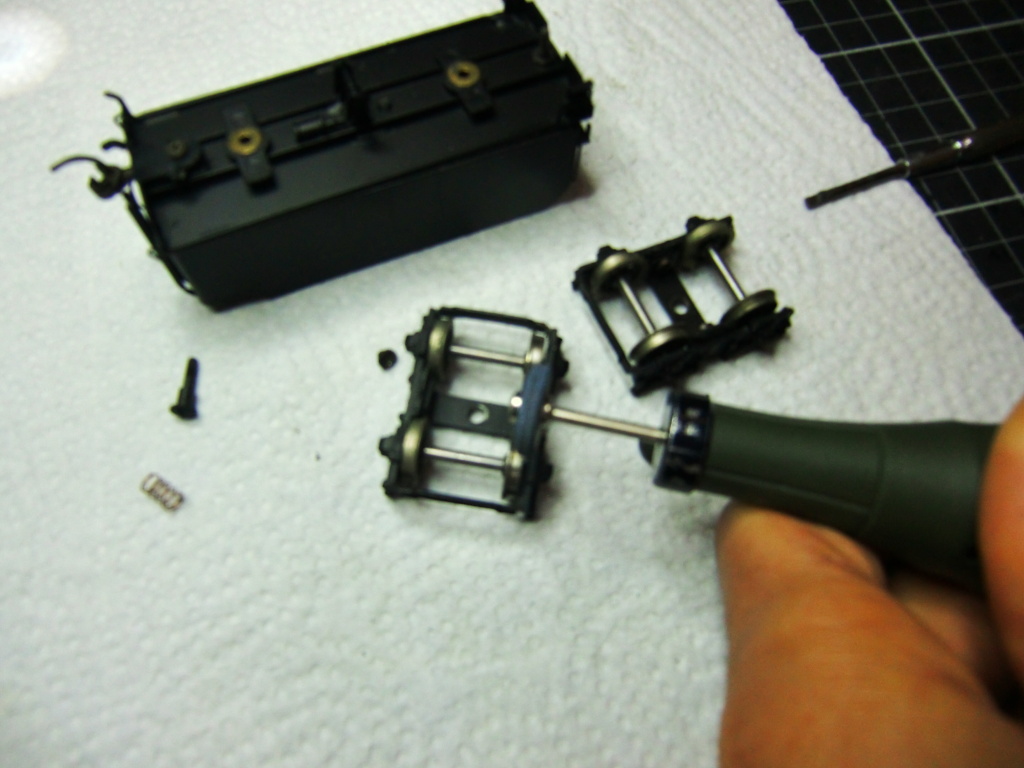

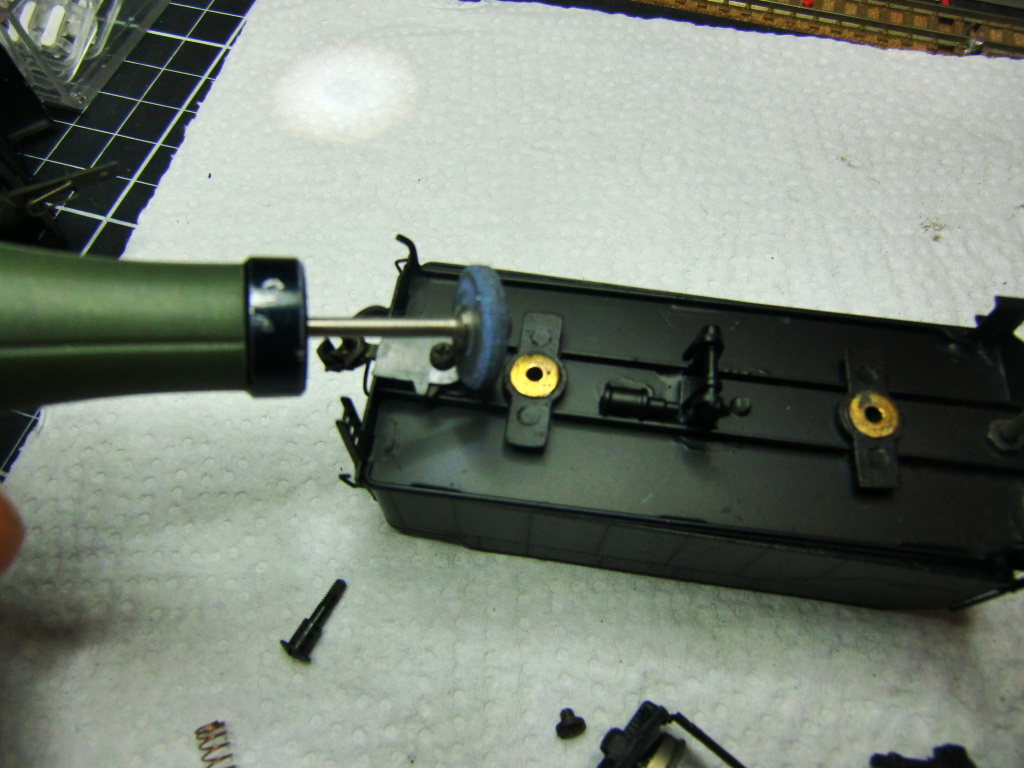
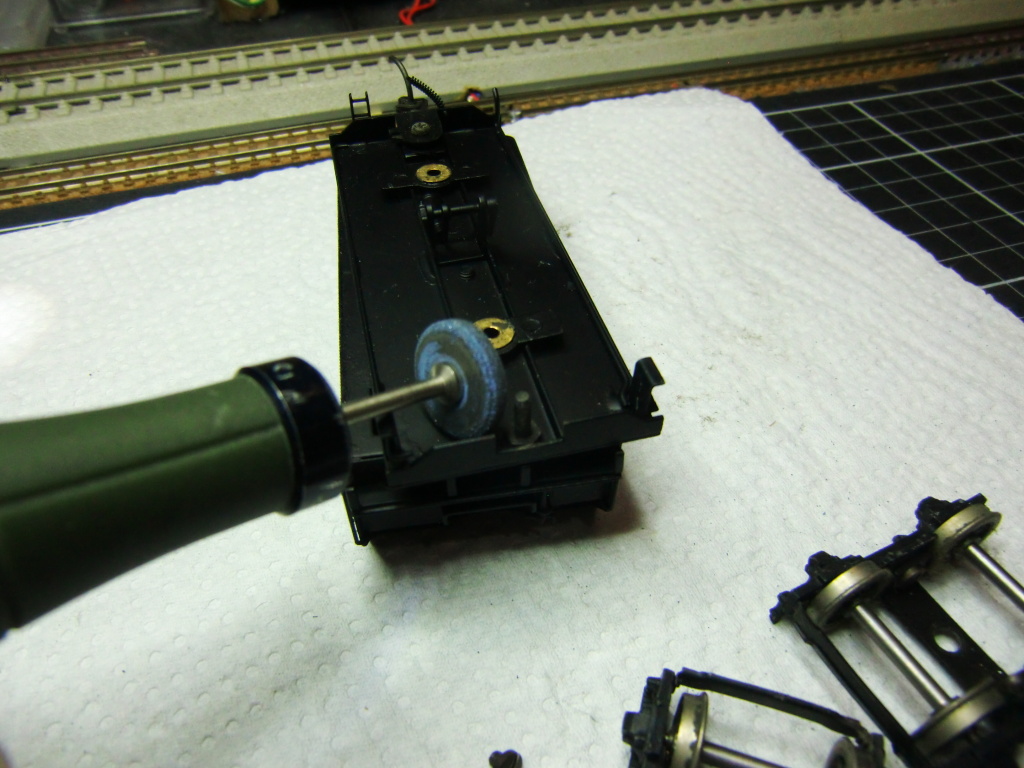

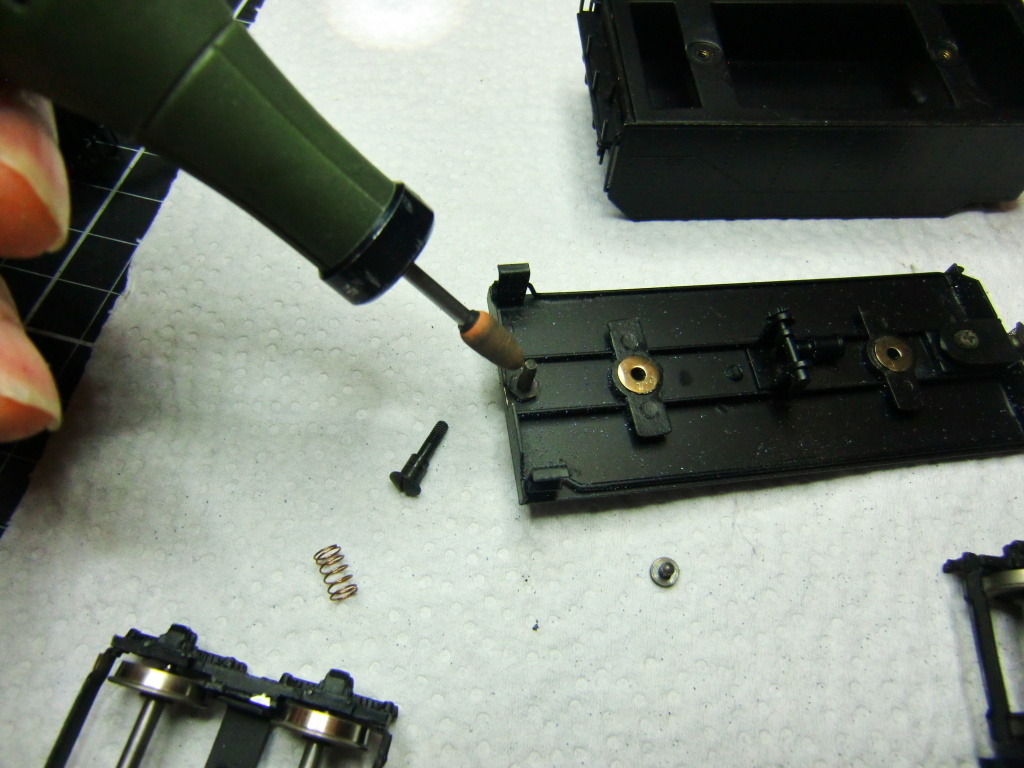
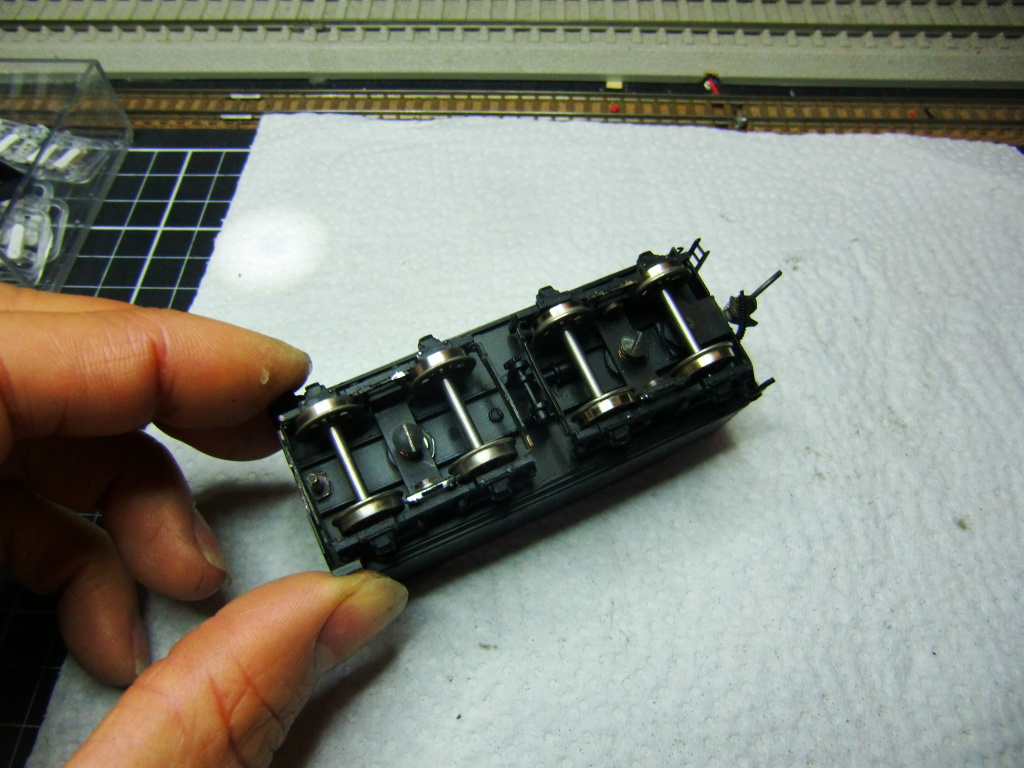
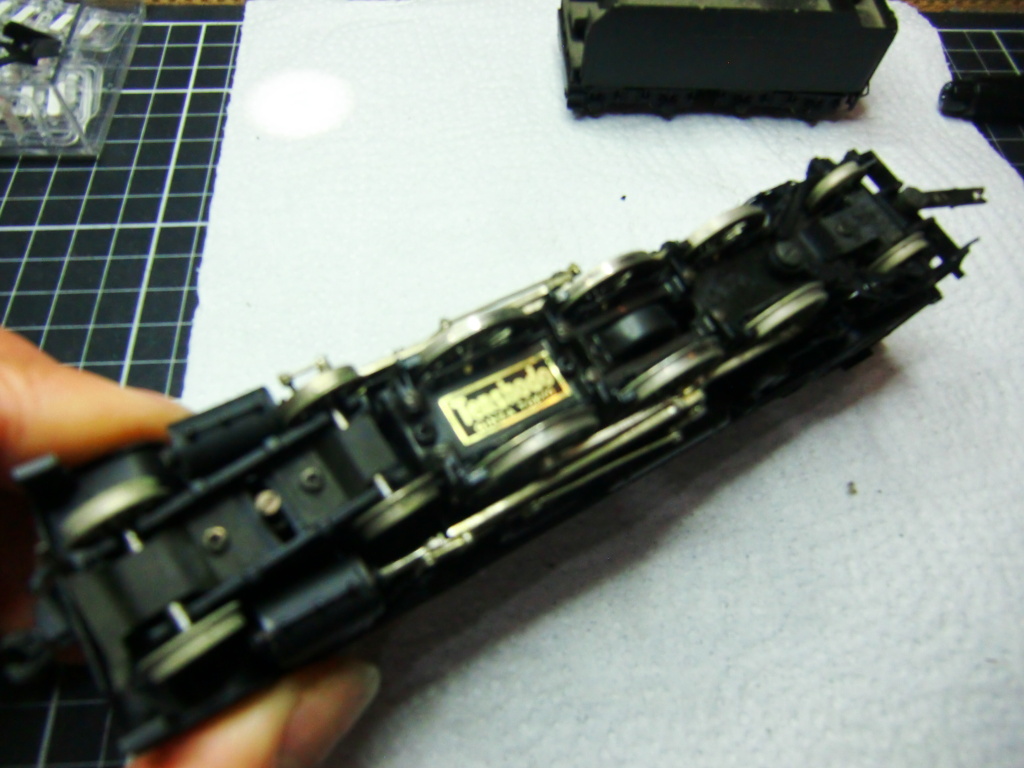
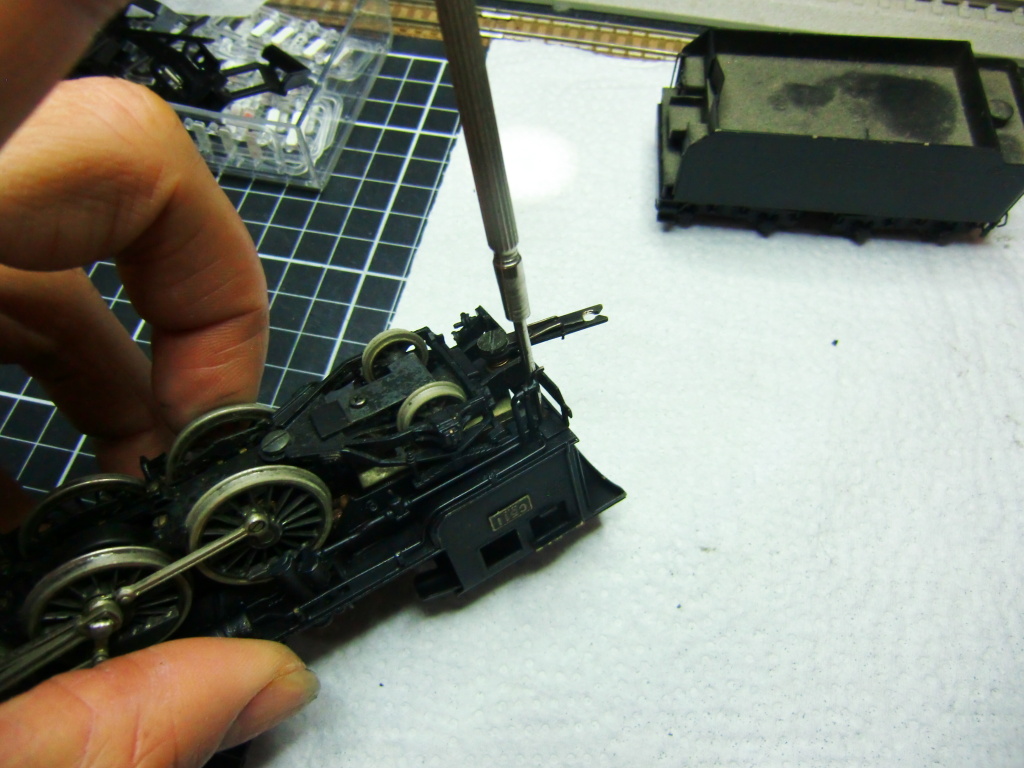
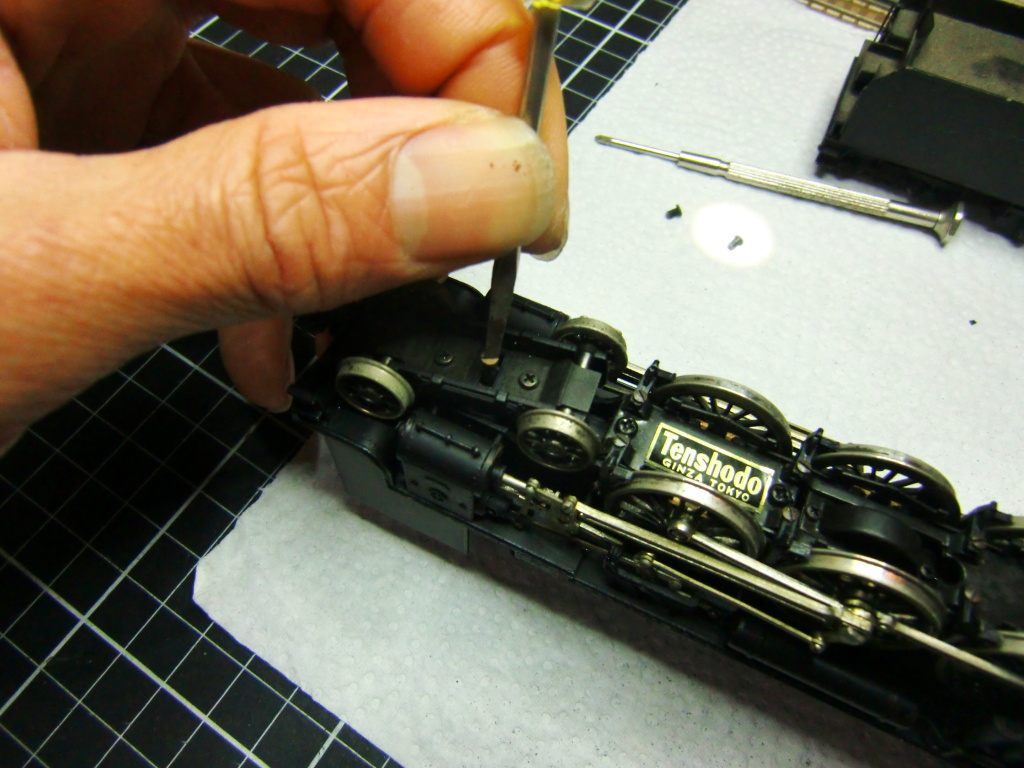
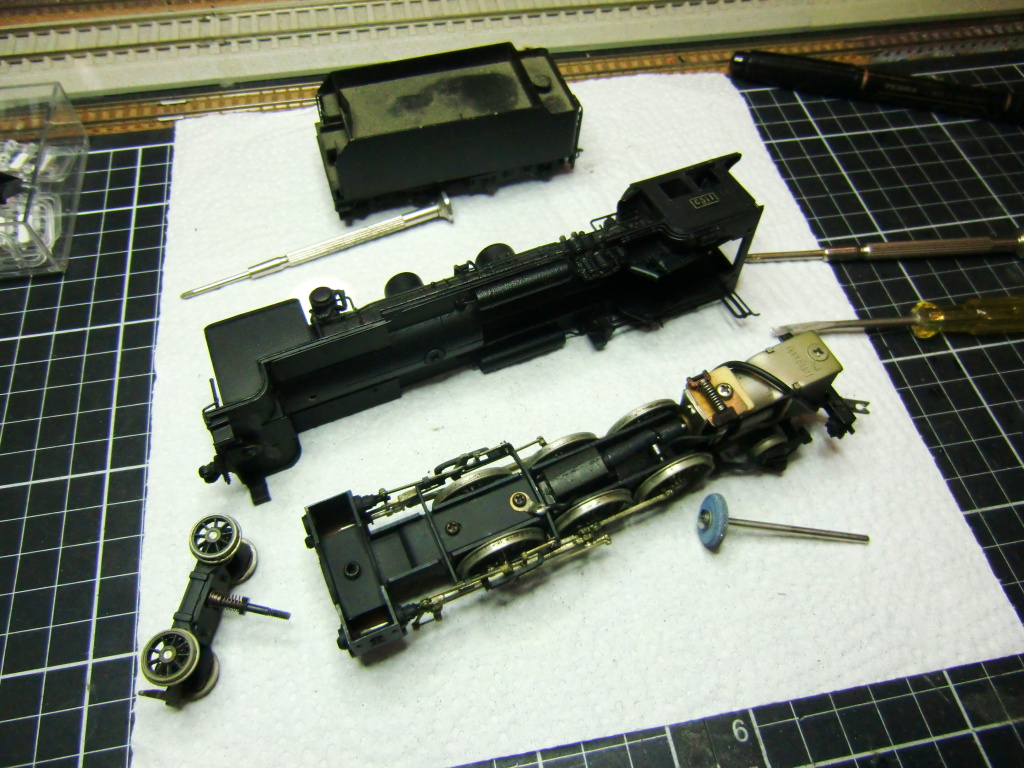
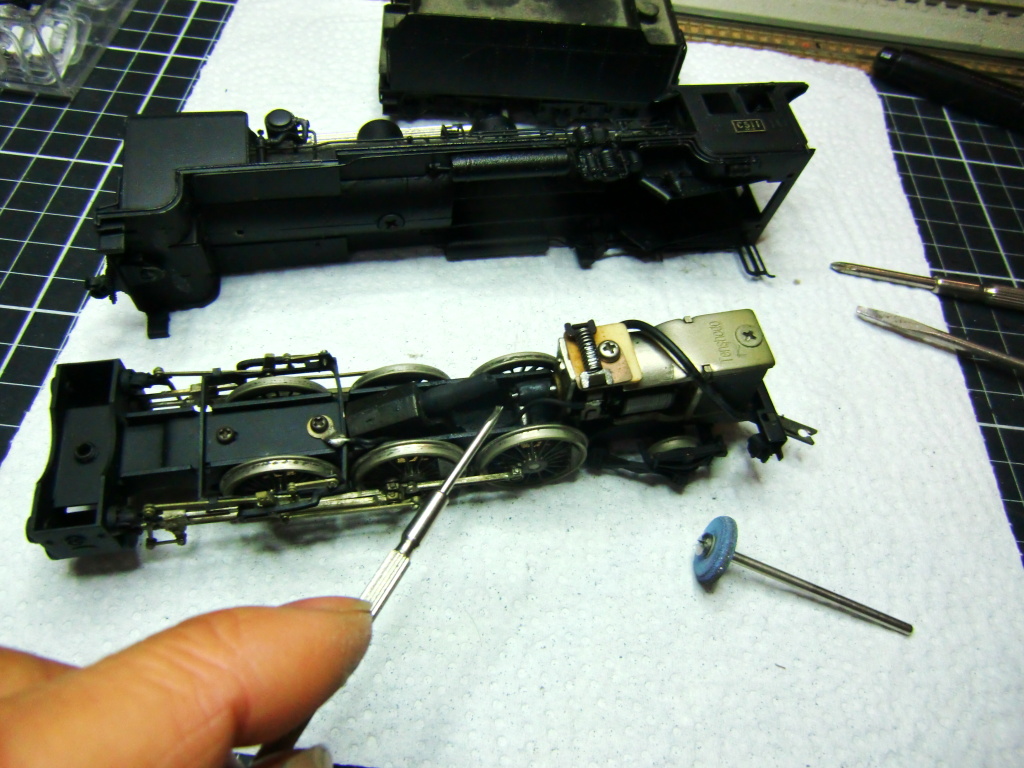
モーターの回転を車輪に伝達する部品が完全に破損しています。ここは作り直さなくてはなりません。
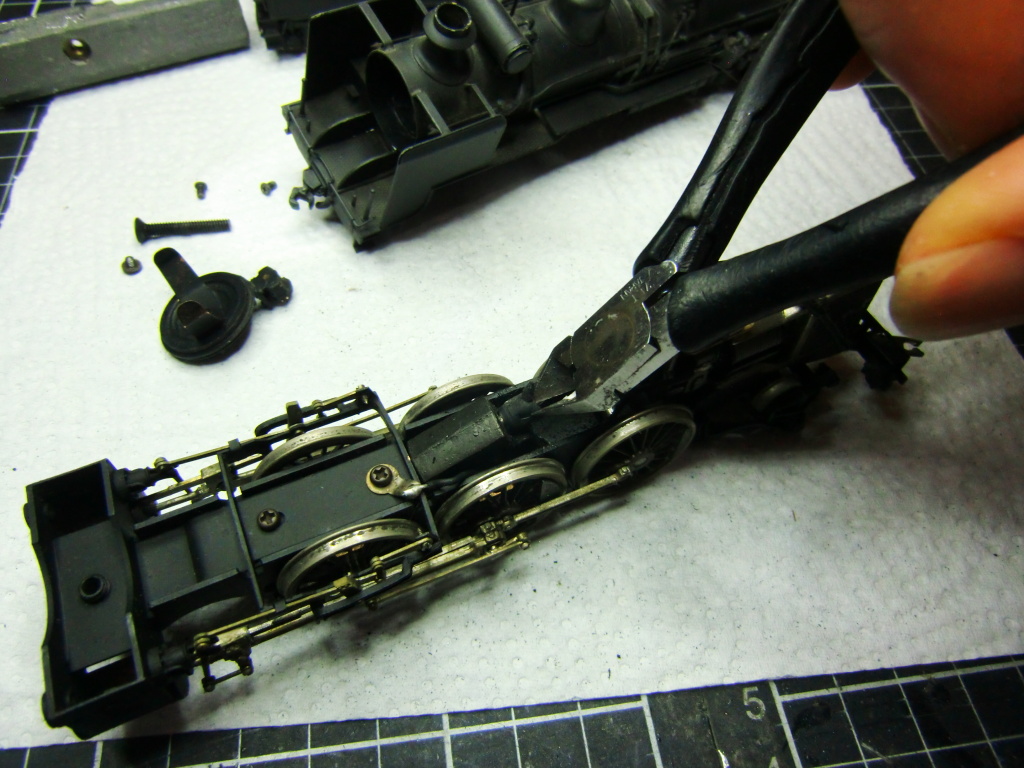



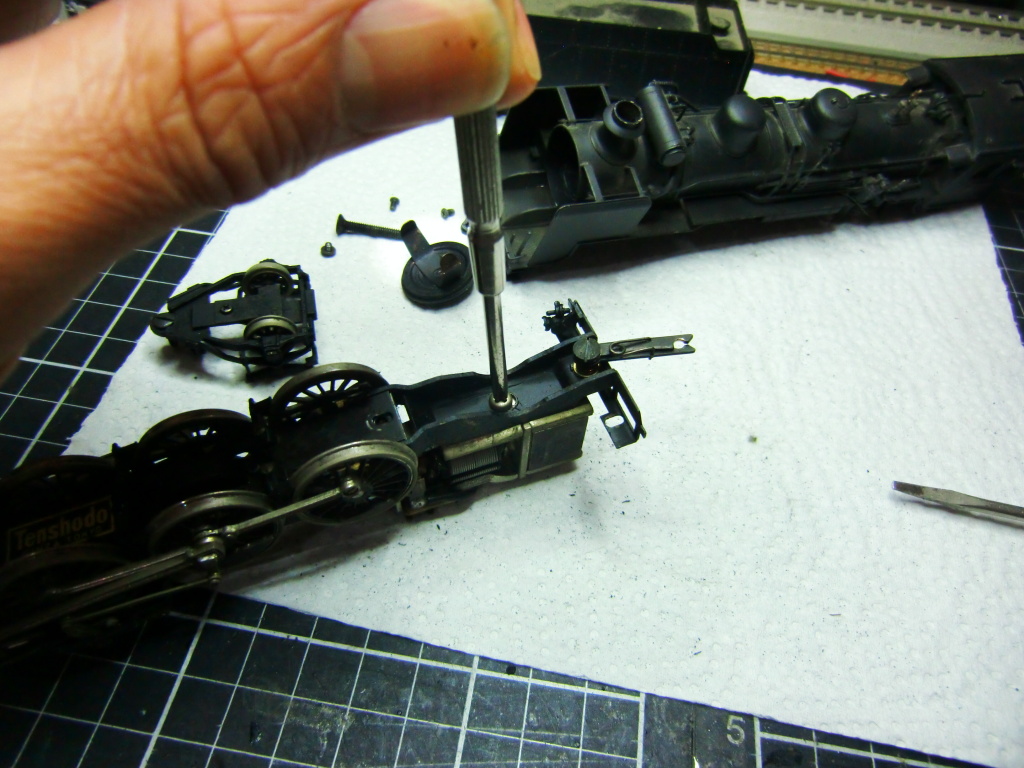
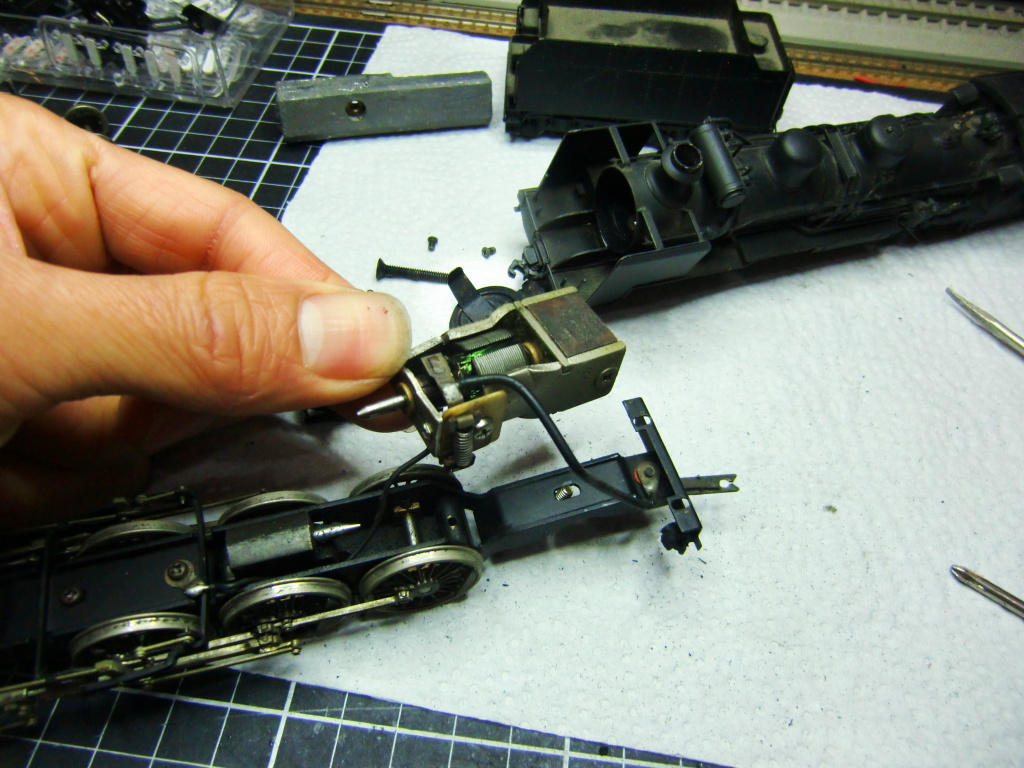
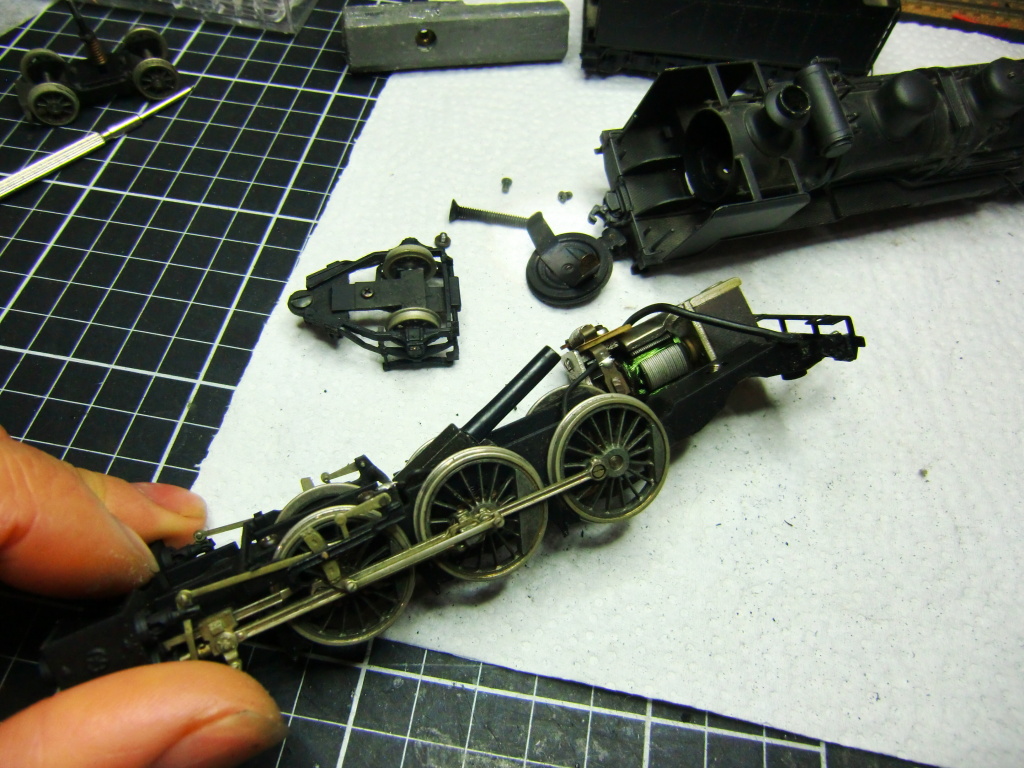
「う~ん」、問題個所が次々と出てきてしまい、泥沼にはまりそうな気がしてきました。

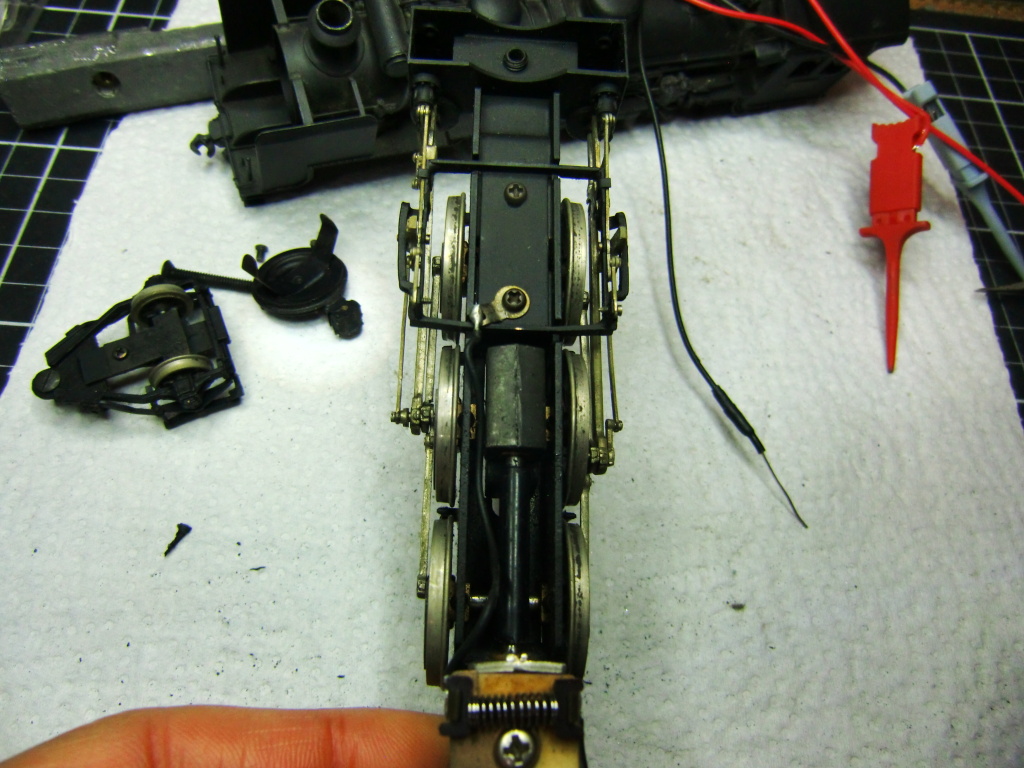
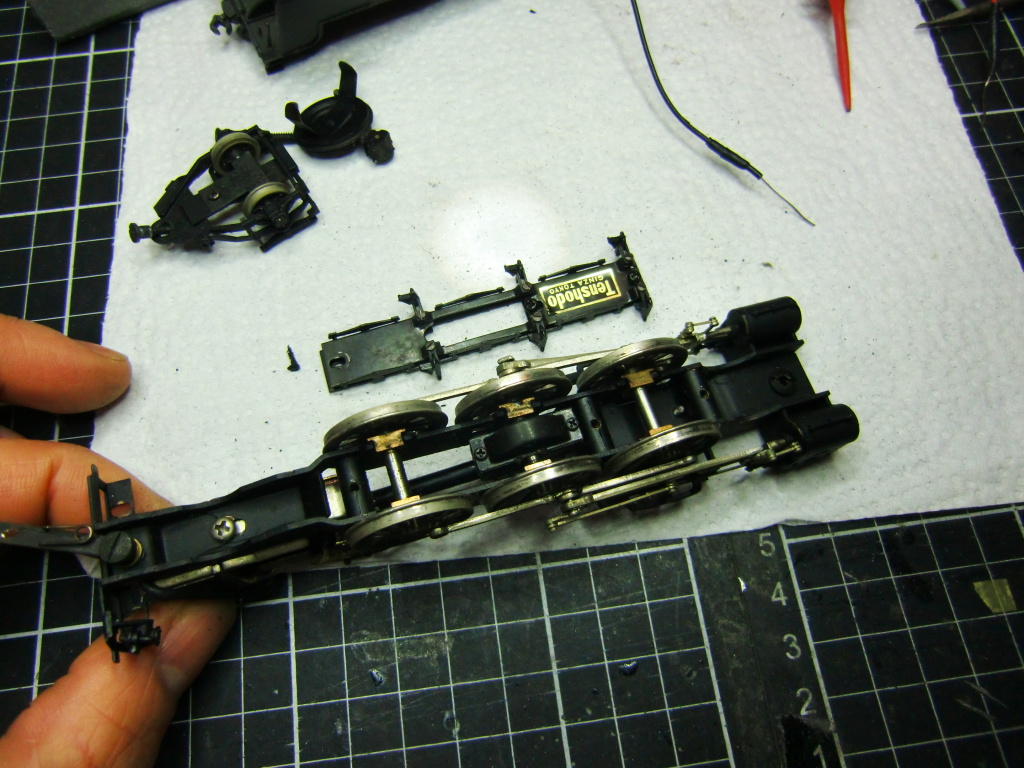
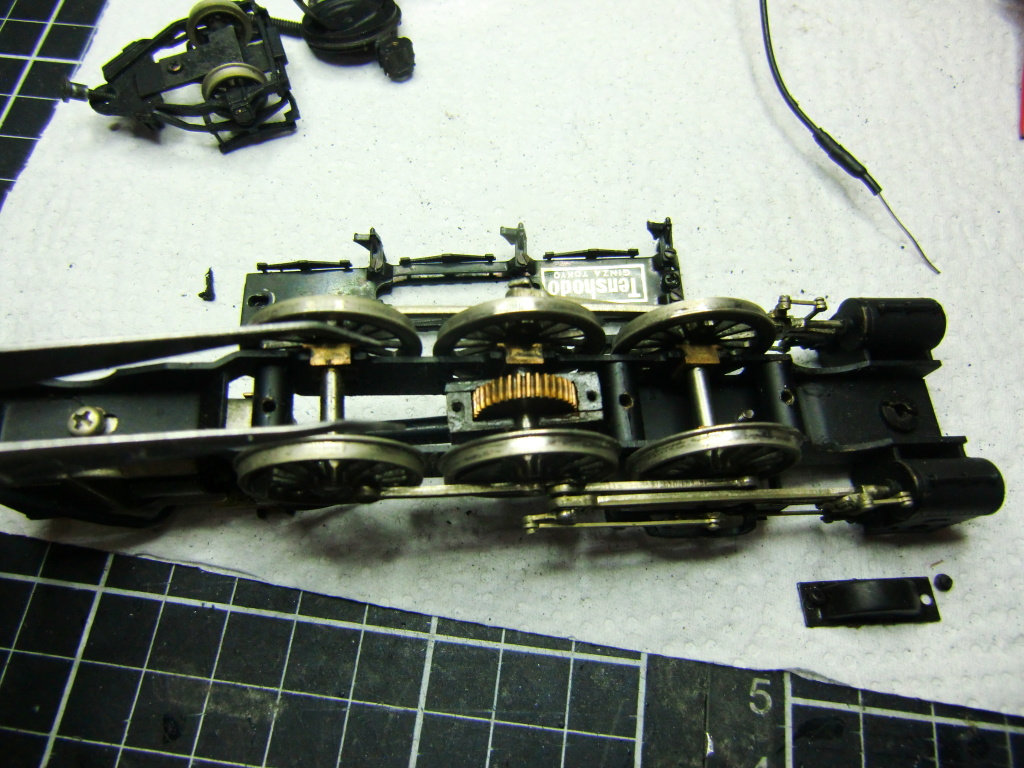
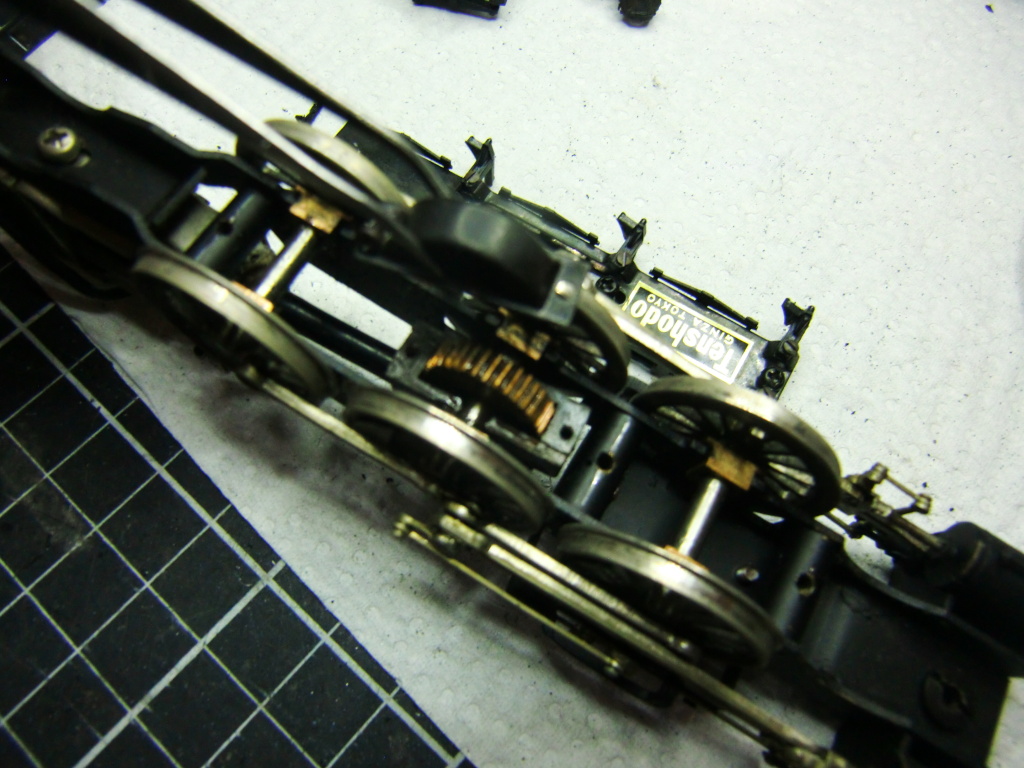
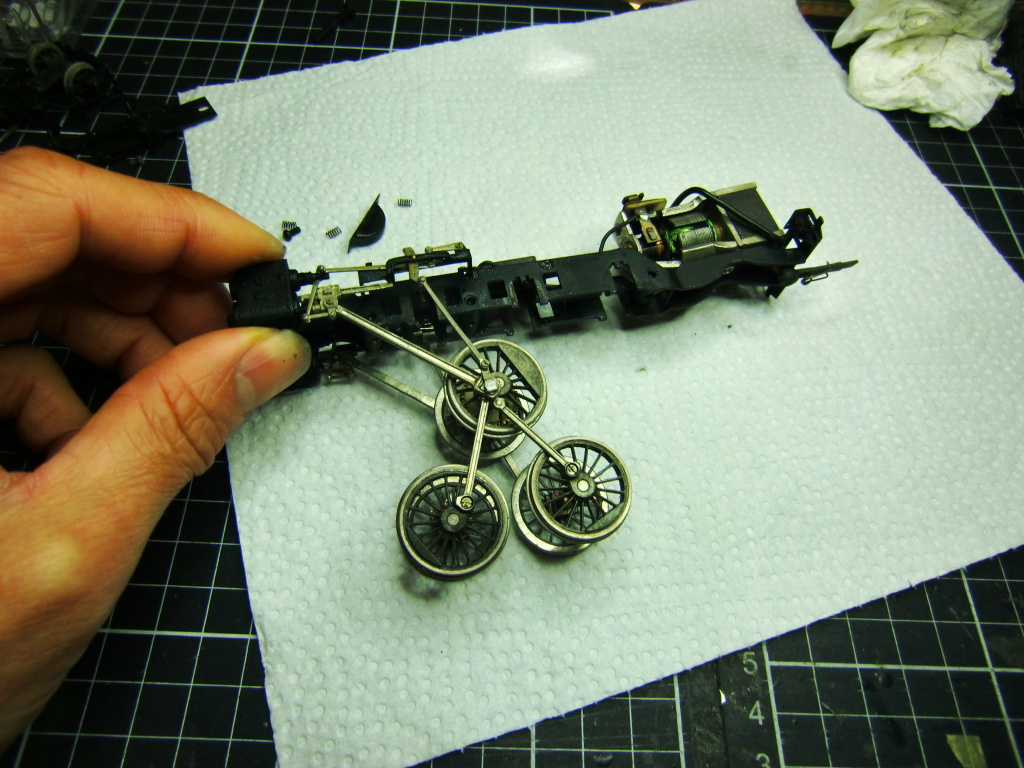




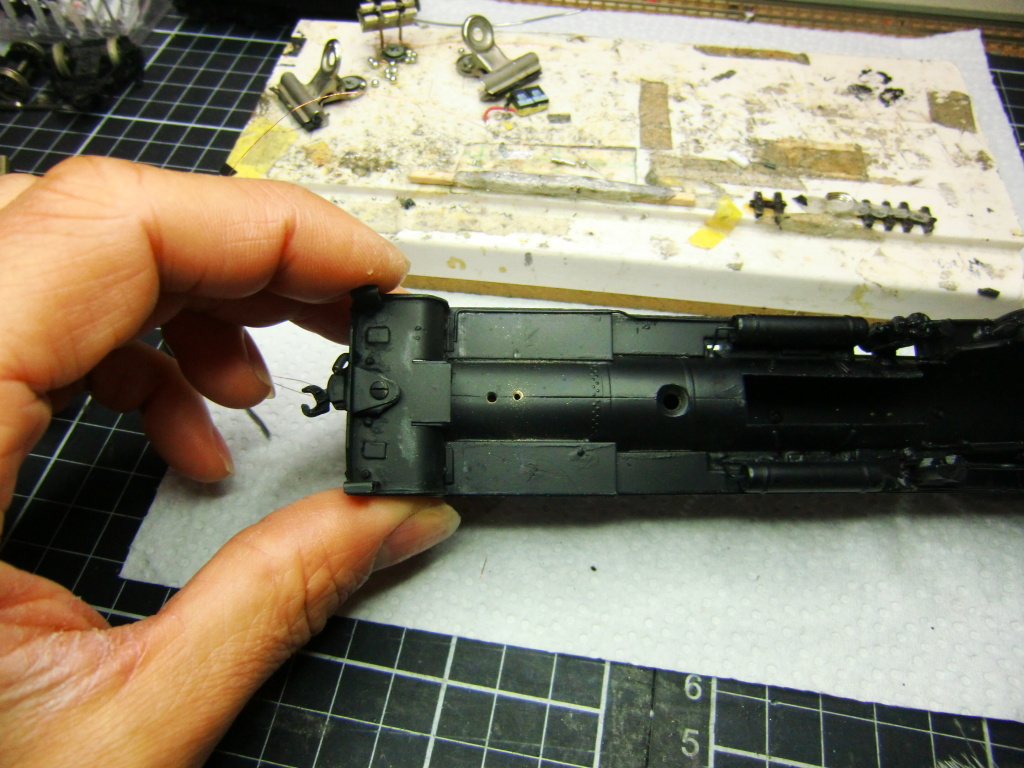



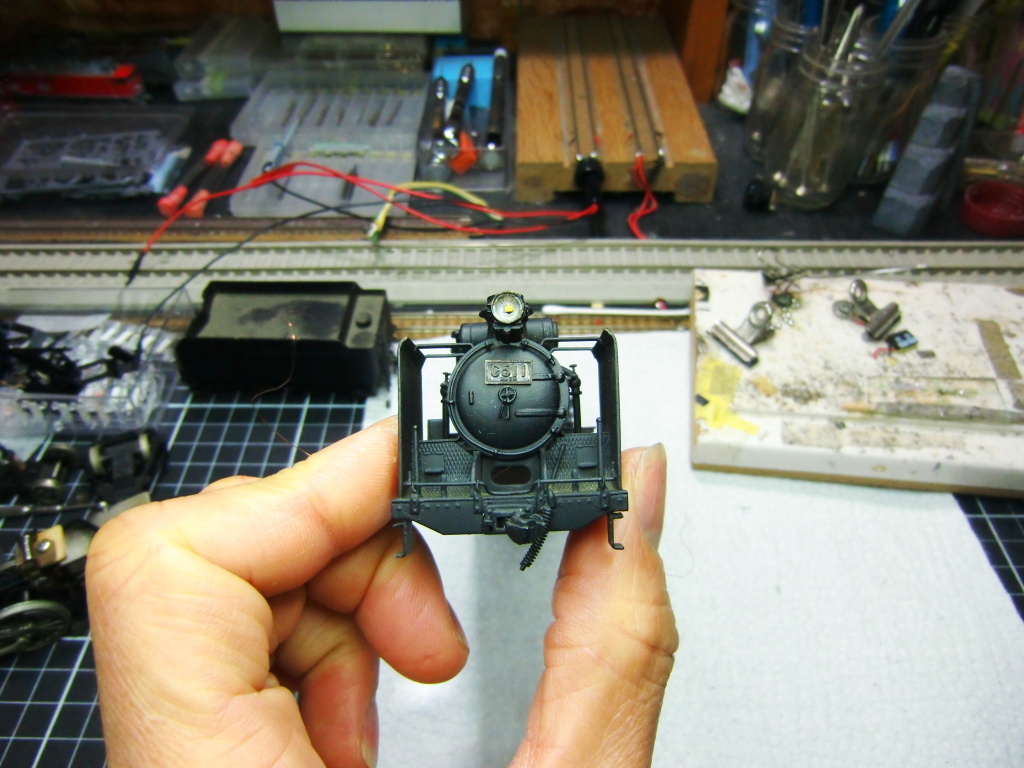
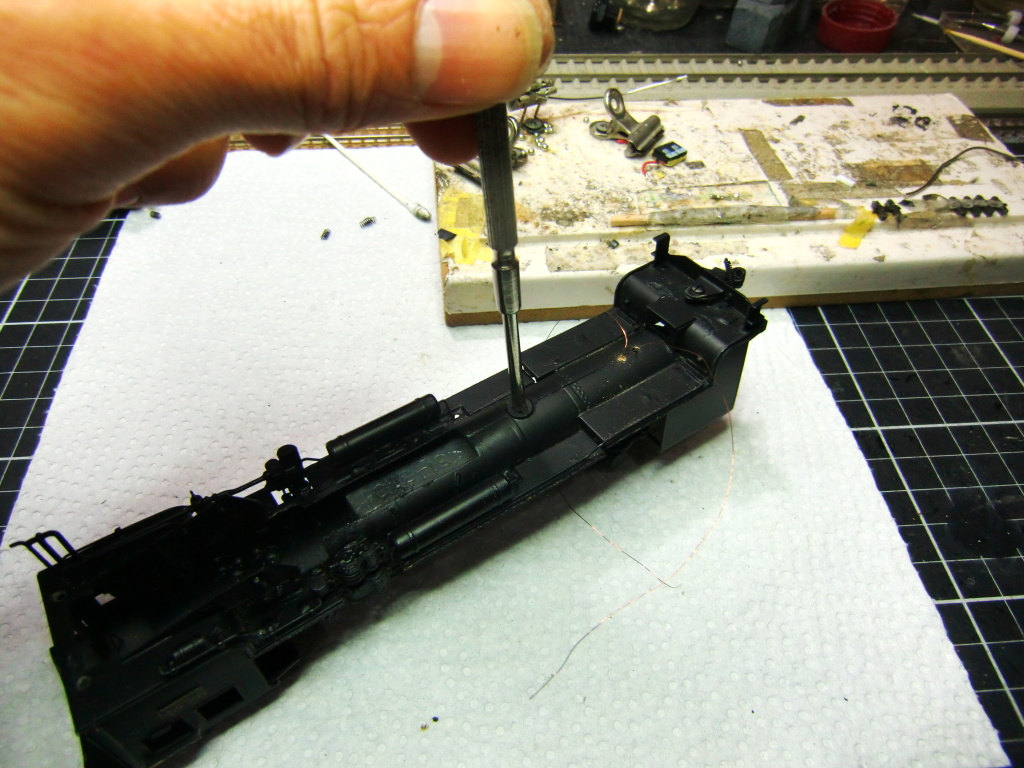

モータの両端にセラミックコンデンサーを取り付けます。


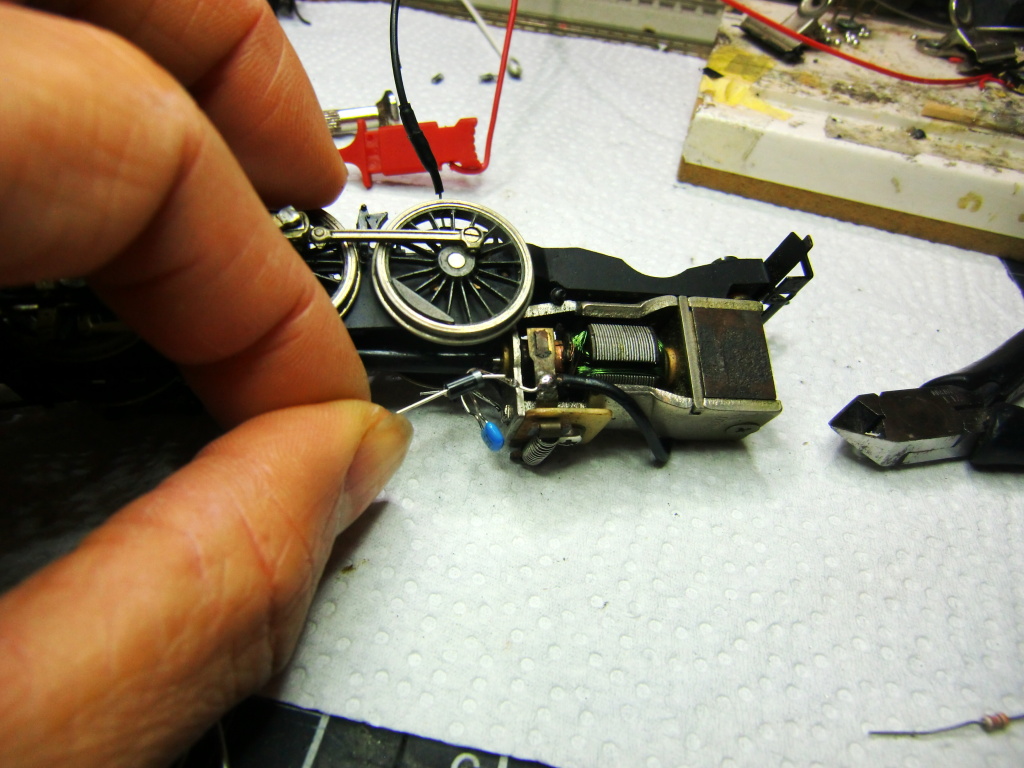
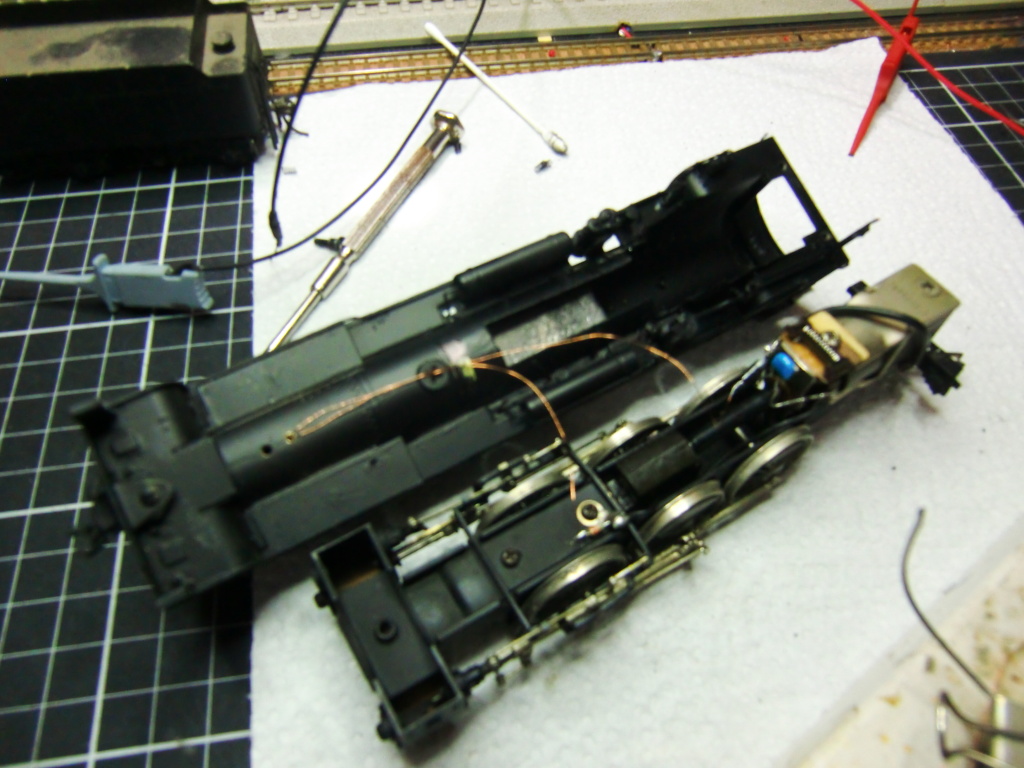
ヘッドライトからの配線を繋げます。
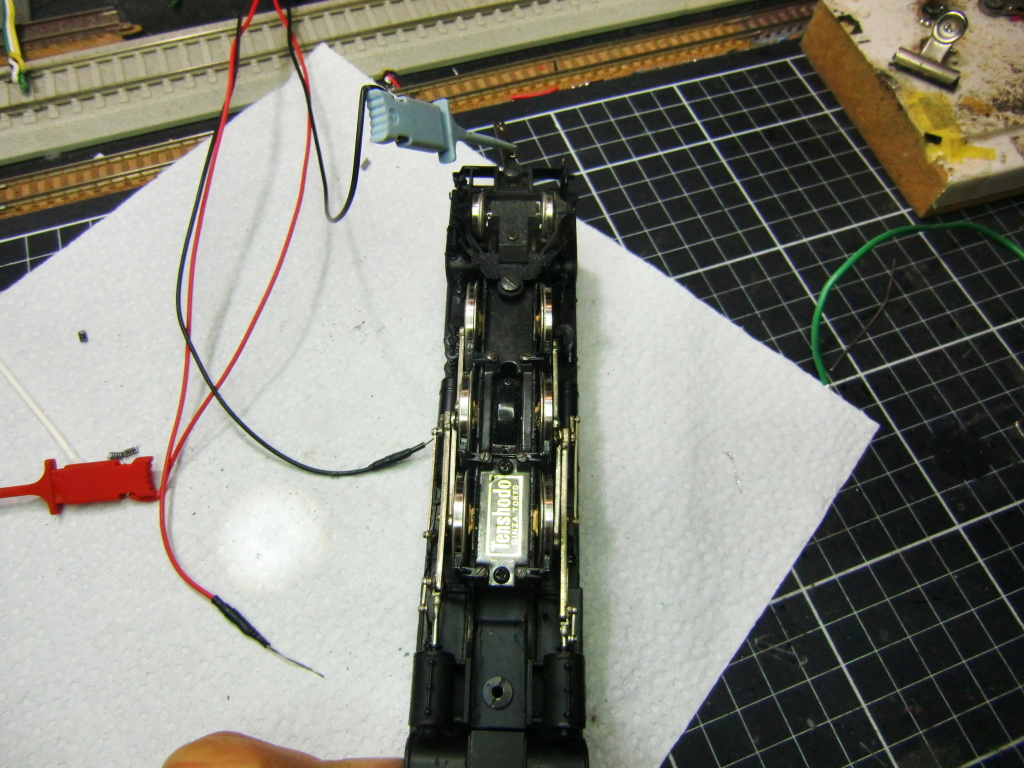
車輪はピカピカに磨きだしました。
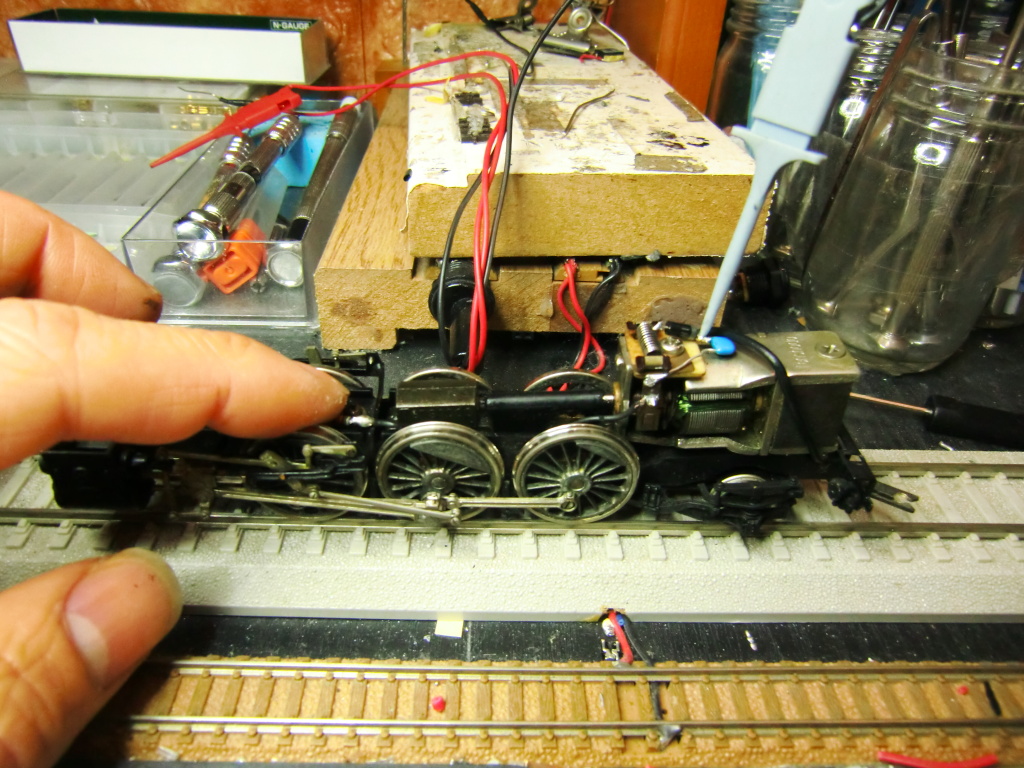
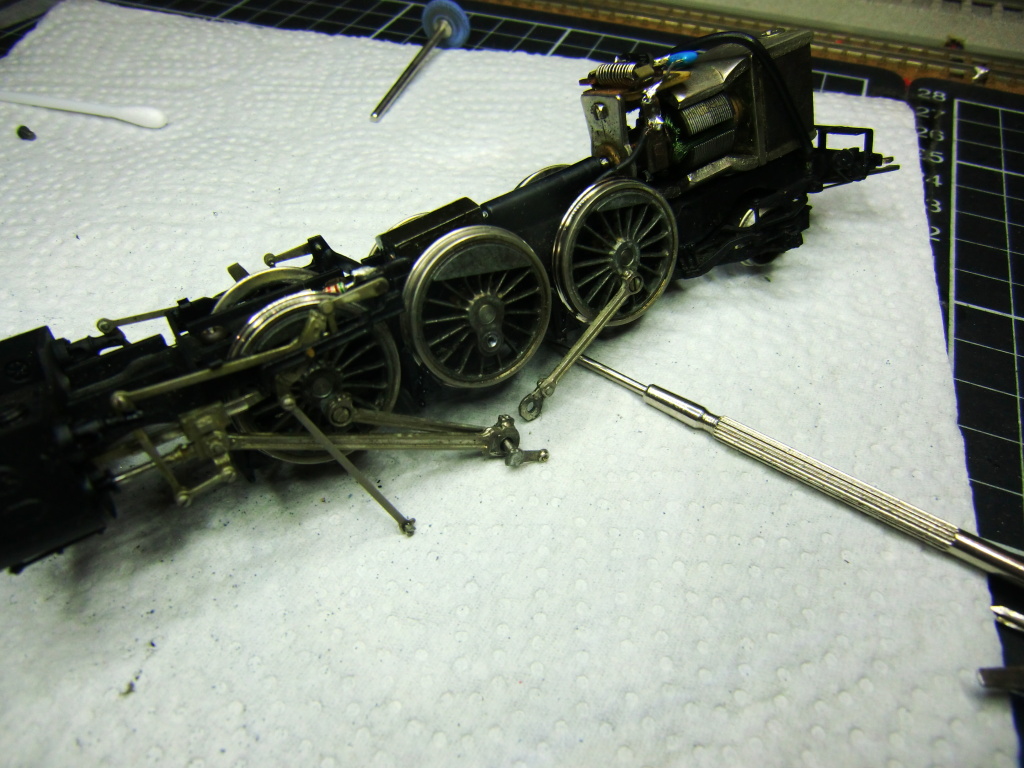
一旦機関車を組み戻してみましたが、何回かに1度車輪がロックする。原因を調べてみるとロッドピンがしっかり固定されずクルクル回ってしまいます。どうやらネジ山が完全に削れて車輪に固定されなくなっているようです。ロッドをすべて分解してネジ穴を復元してみるところから始めなくてはなりません。ようやくモーターが回転し、パワーを車輪に伝達できるところまではうまくいったが、今度は別の問題が出てきて作業は難航。

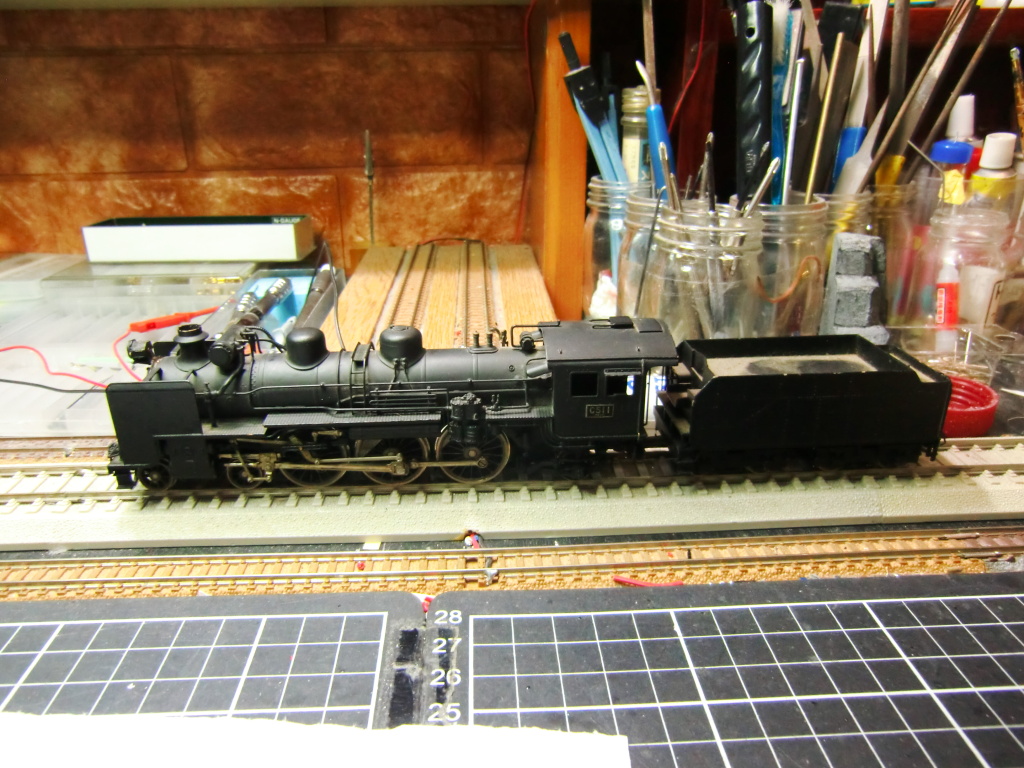
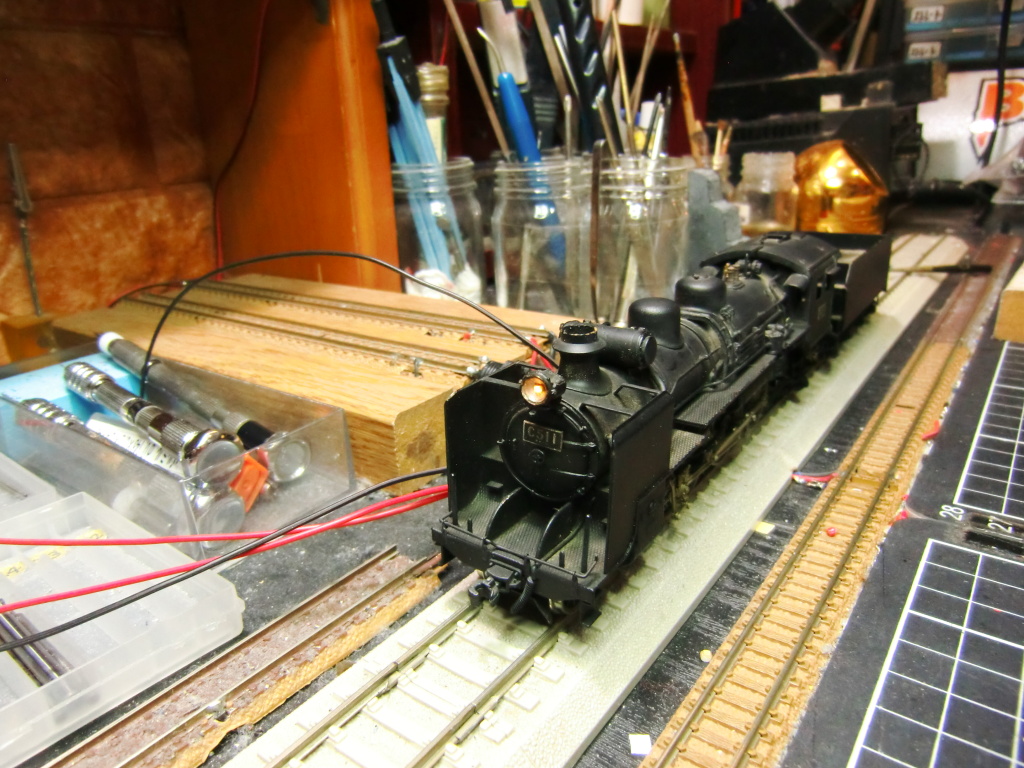

ようやく、C51様の修理完了。ヘッドライトも点灯化改造して上記のようになりました。
▼C59 修理+ライト点灯改造


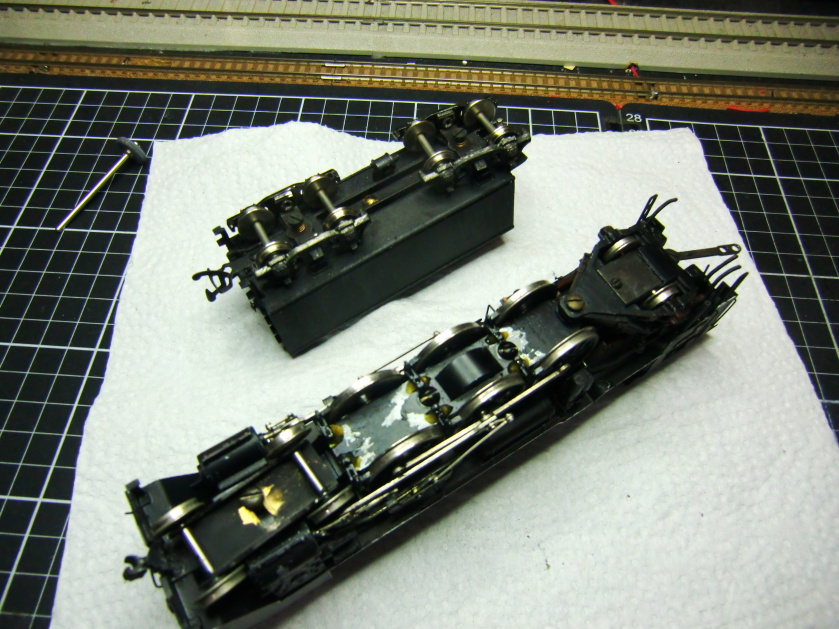
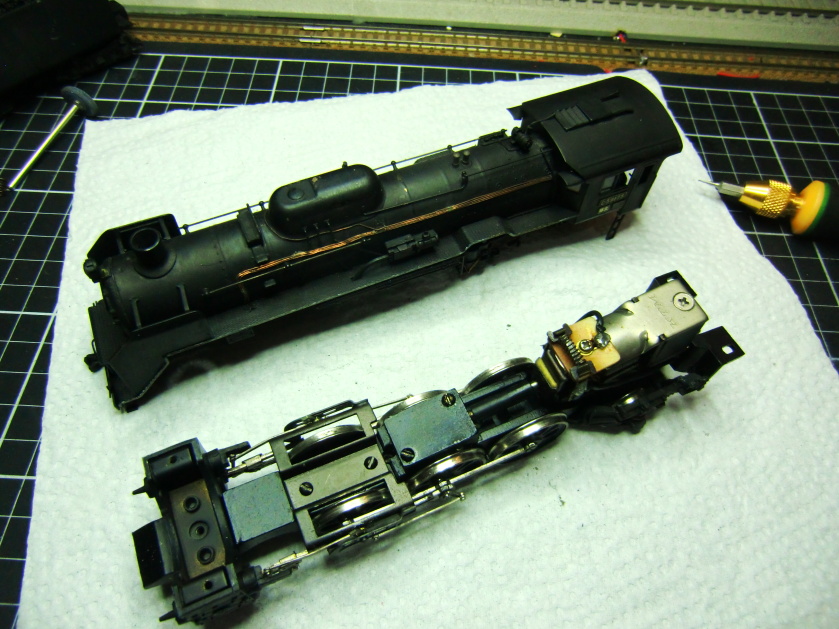

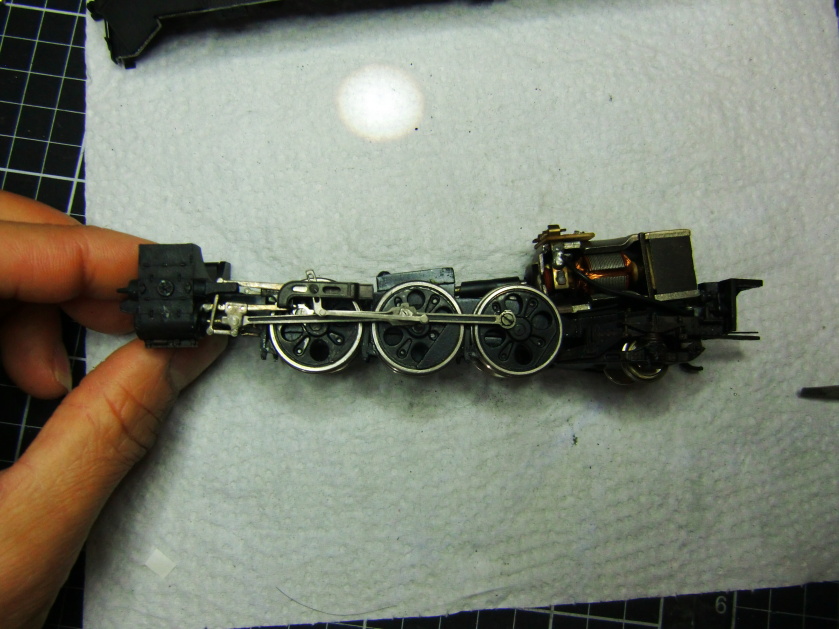
以下、基本的にC51と同様の作業内容となるため画像は省略いたします。
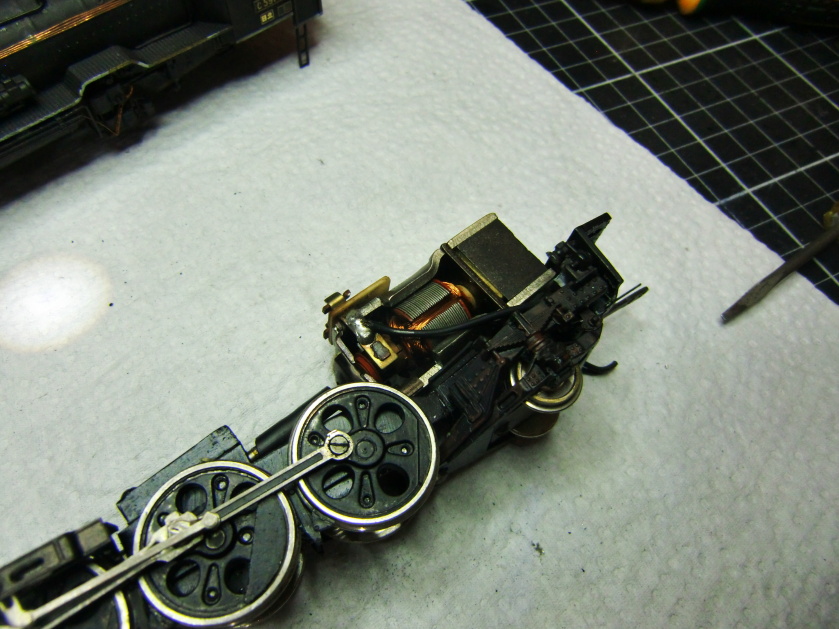

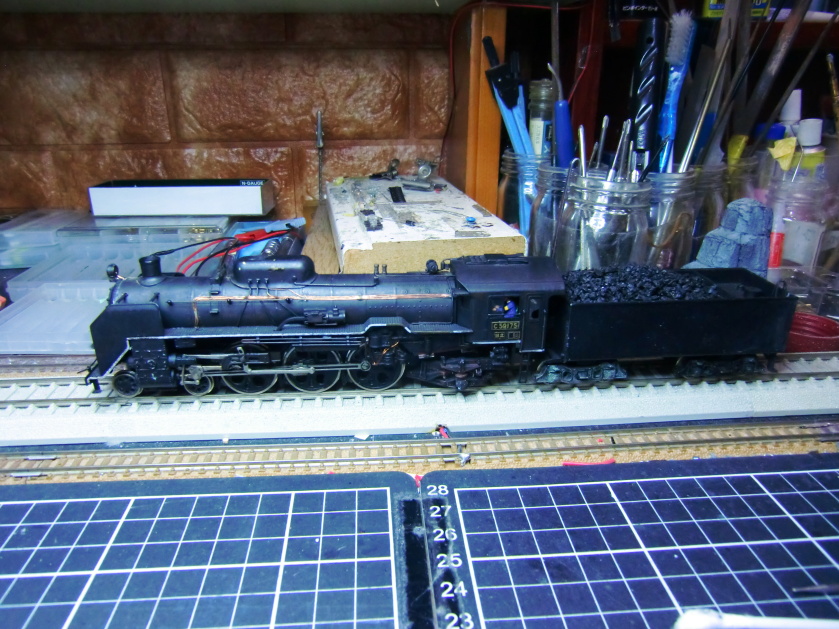

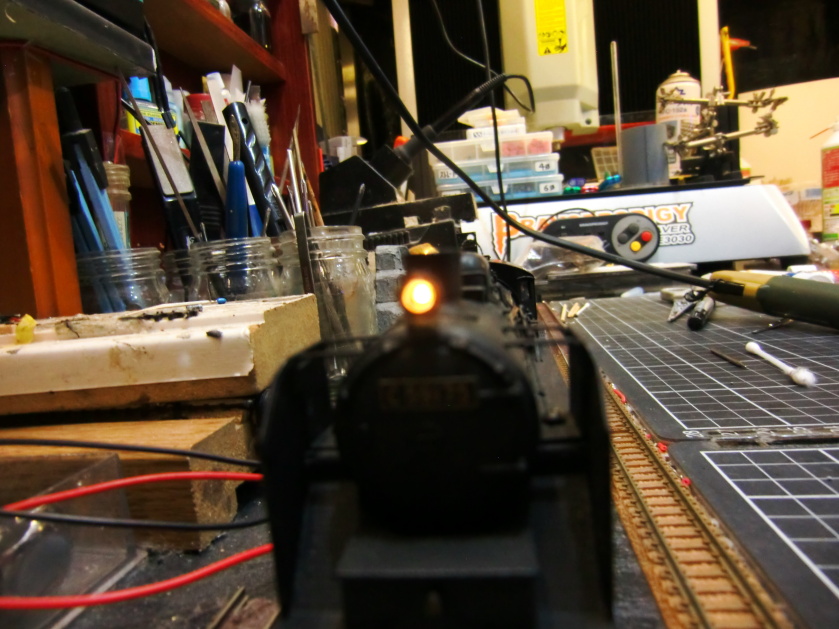
▼C51 修理+ライト点灯改造

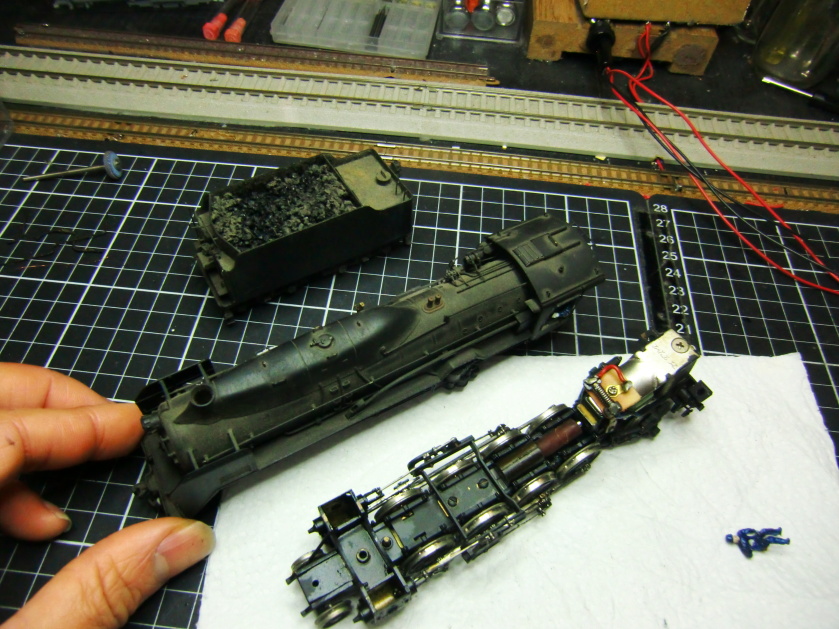

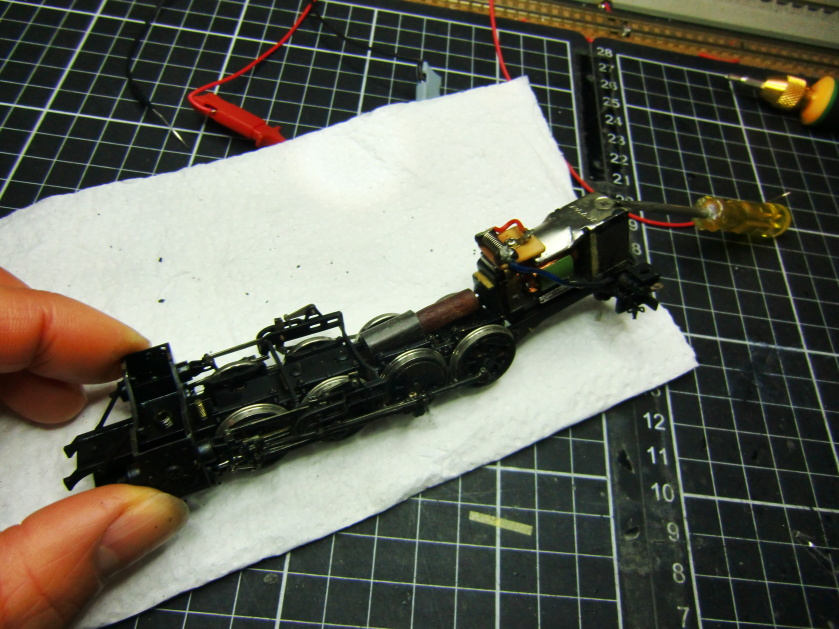
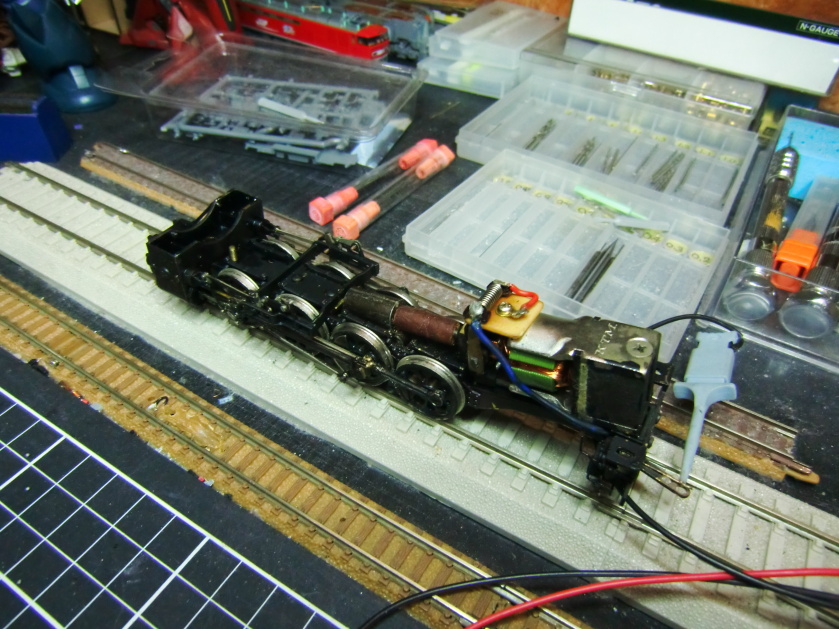
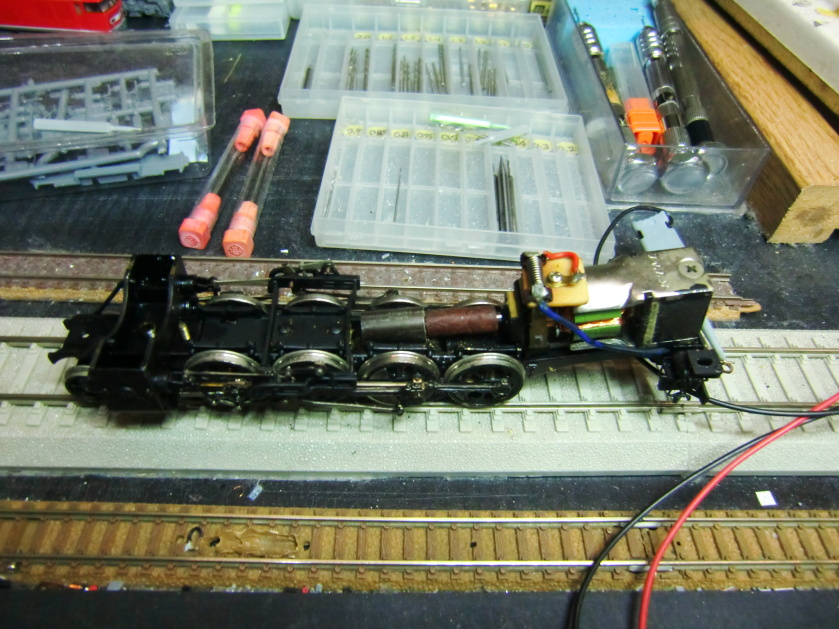
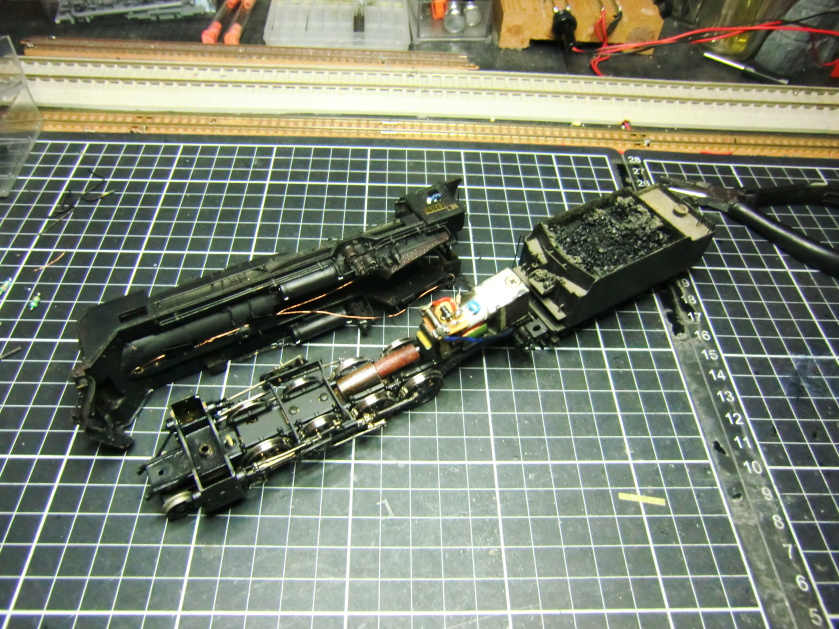
作業内容は基本的にC51と同様の作業となるため画像は省略いたします。



どうにか、すべての機関車が現状よりどうにか復活となりました。
客車の修理・加工作業については、少し時間を空けてから作業に入ります。
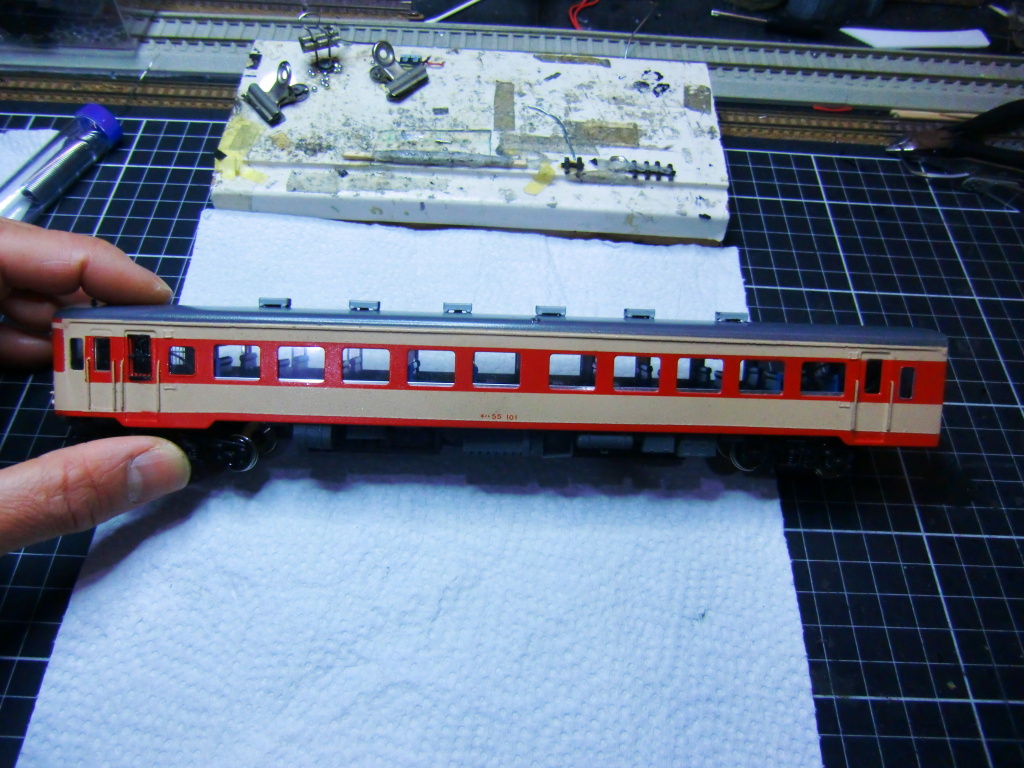


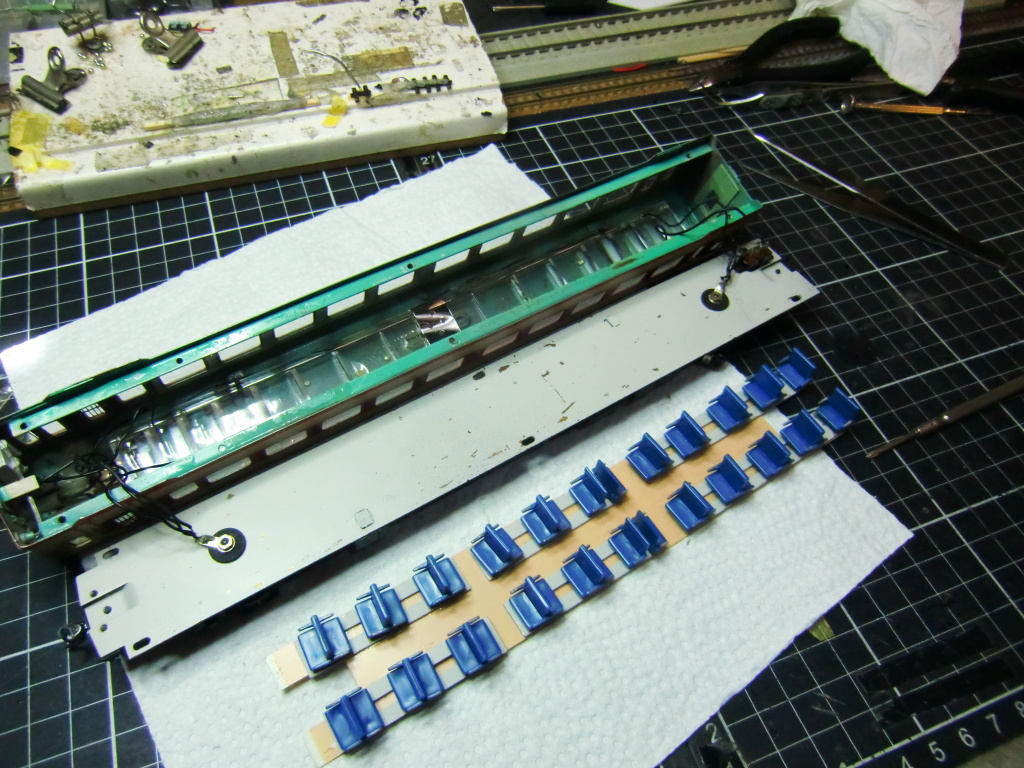
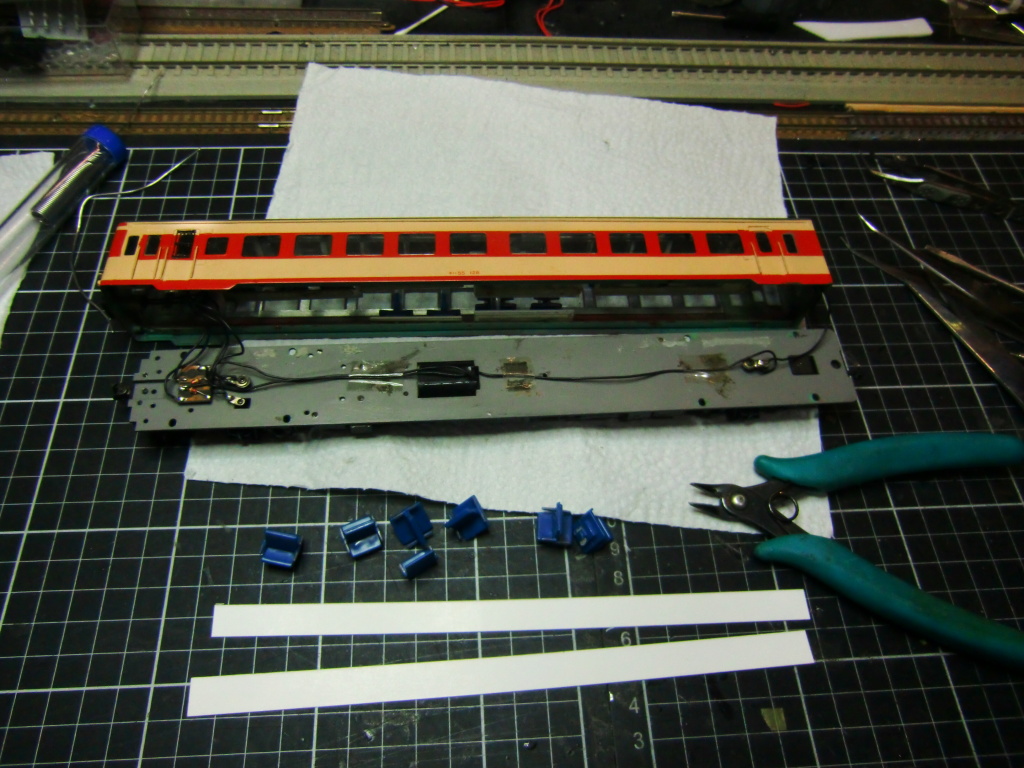
椅子を全部外してベースを作り直します。

裏面を1つ1つ削りなおして平らにします。
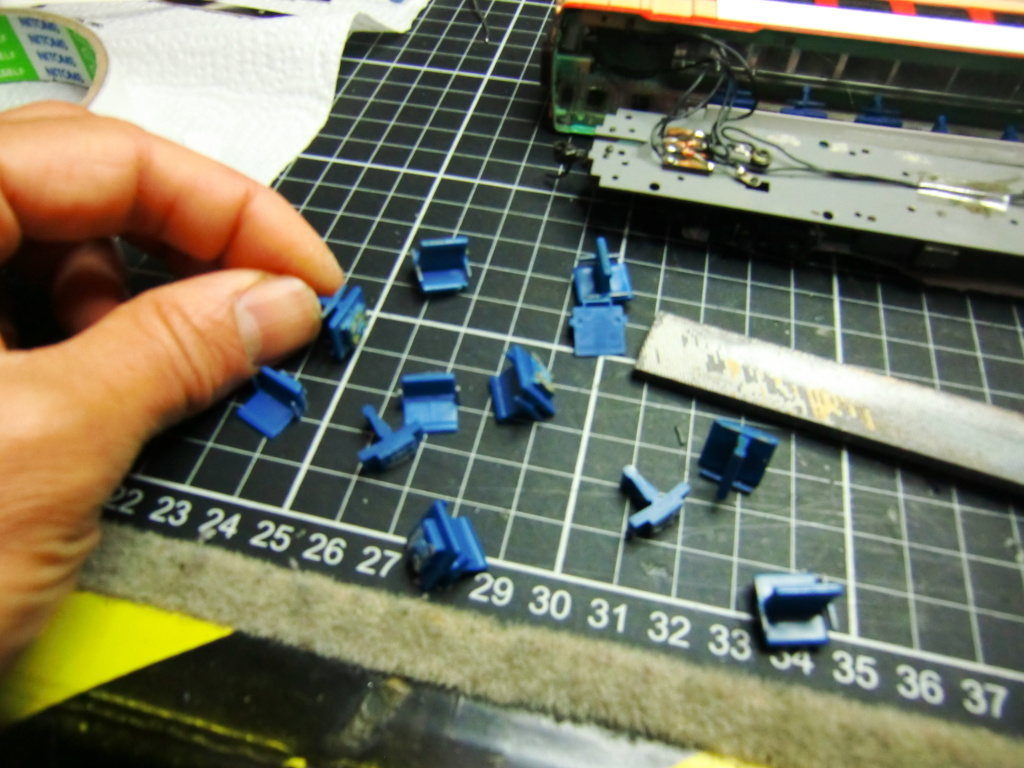
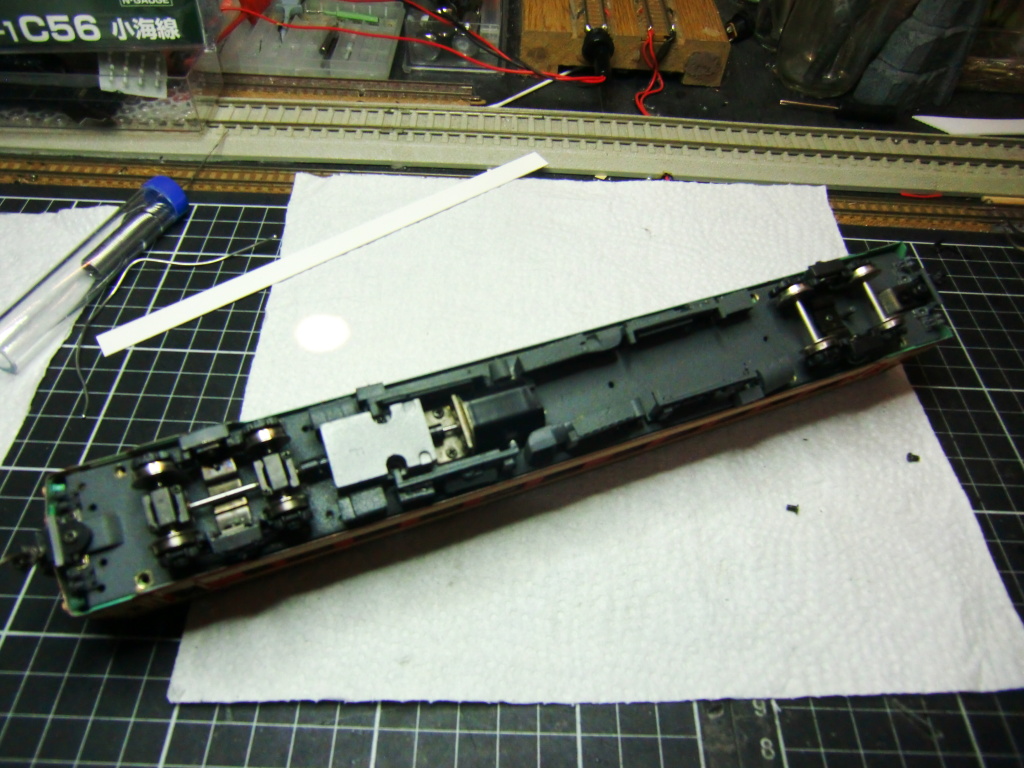
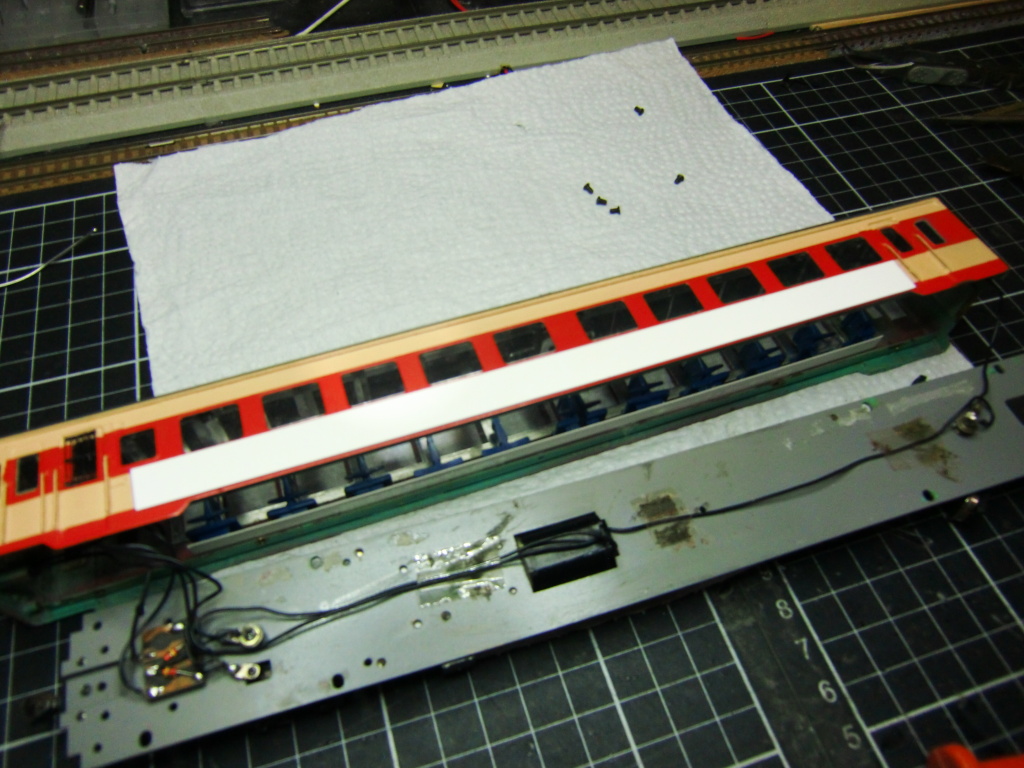
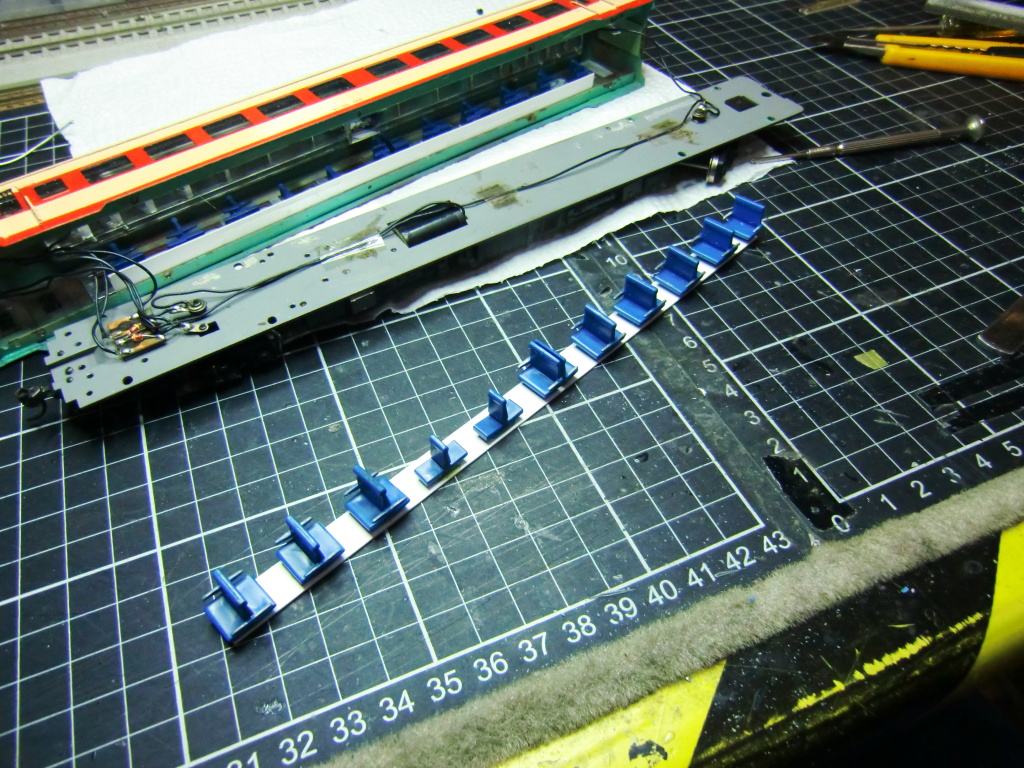


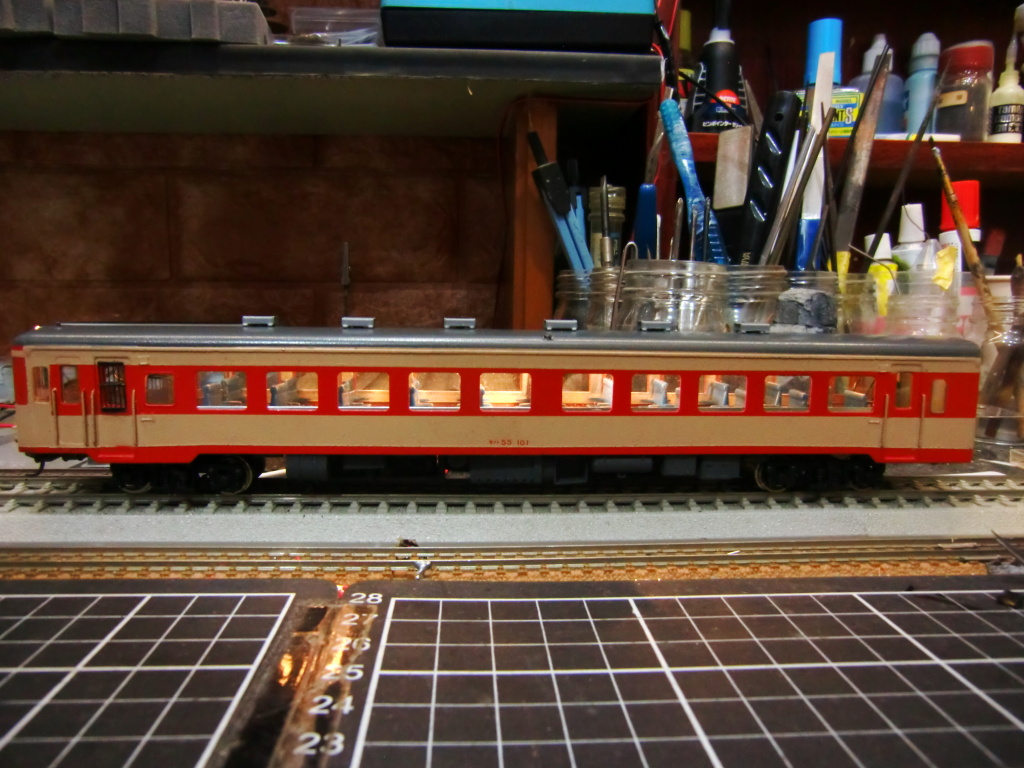



ライト不点灯修理+動力メンテ+座席直し
まずは、上記2両は作業完了です。残りの2両へ移ります。

こちらの車体には、OHはもちろんご依頼により「ヘッド/テール点灯化改造」による加工を施していきます。
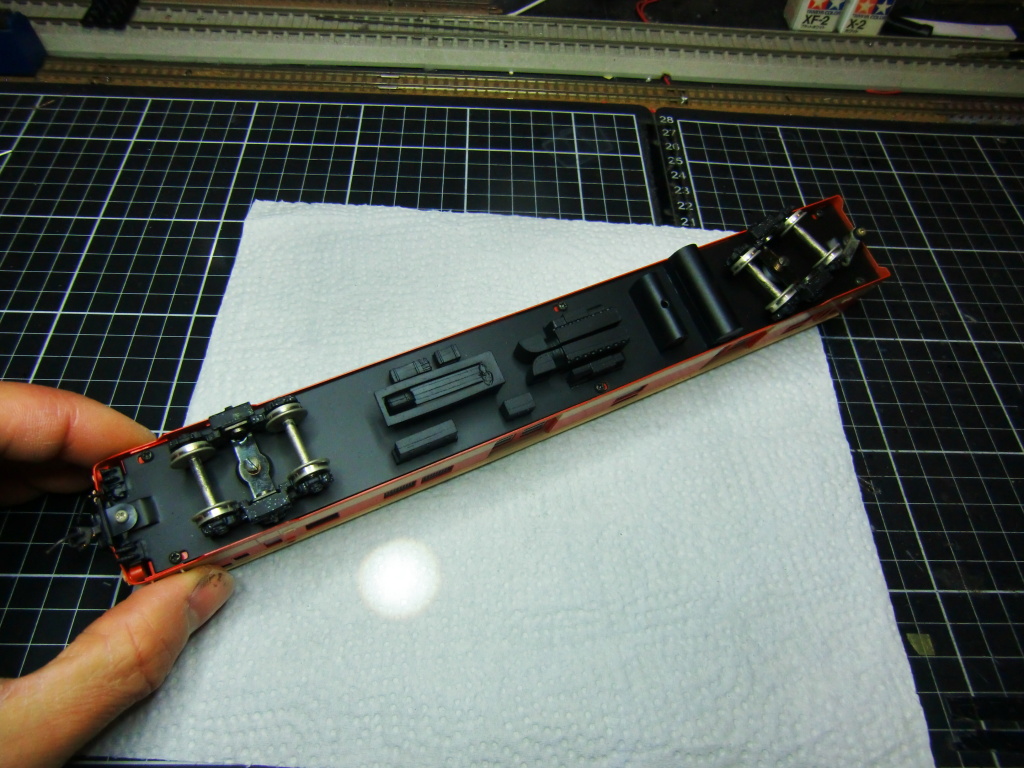

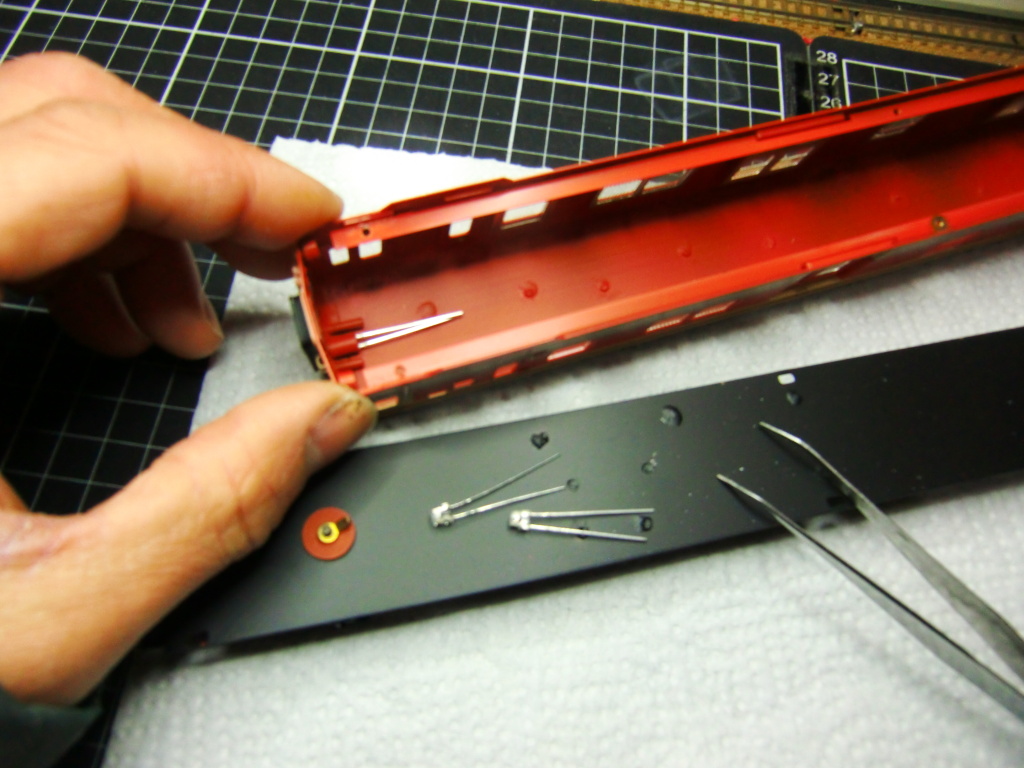
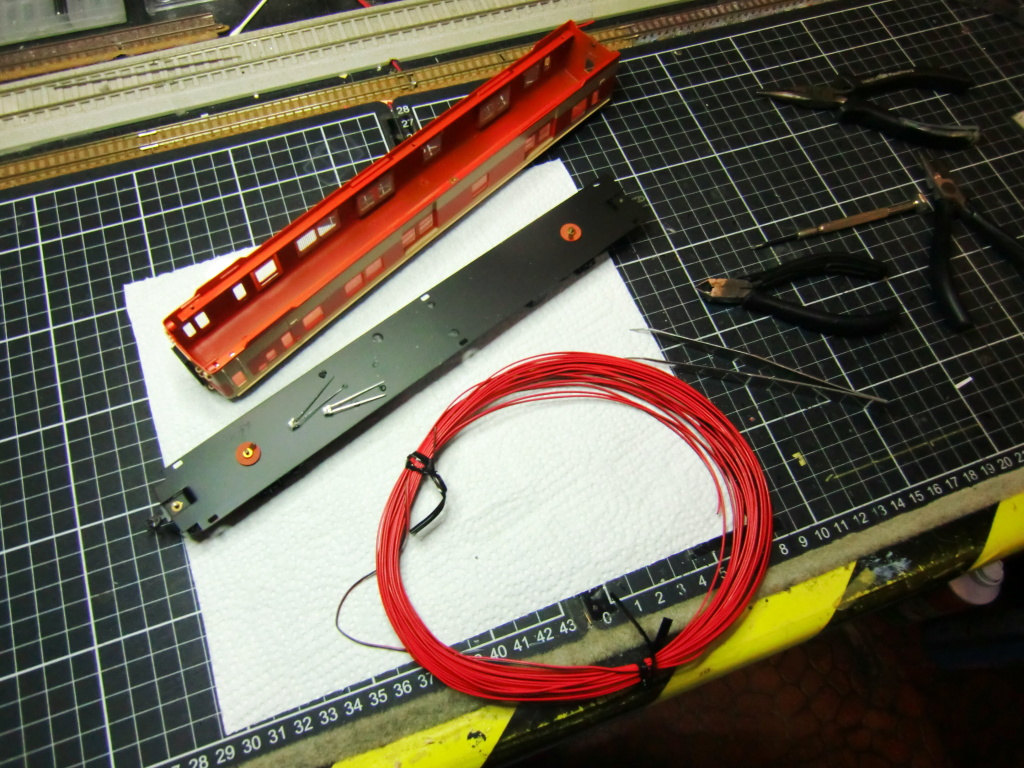
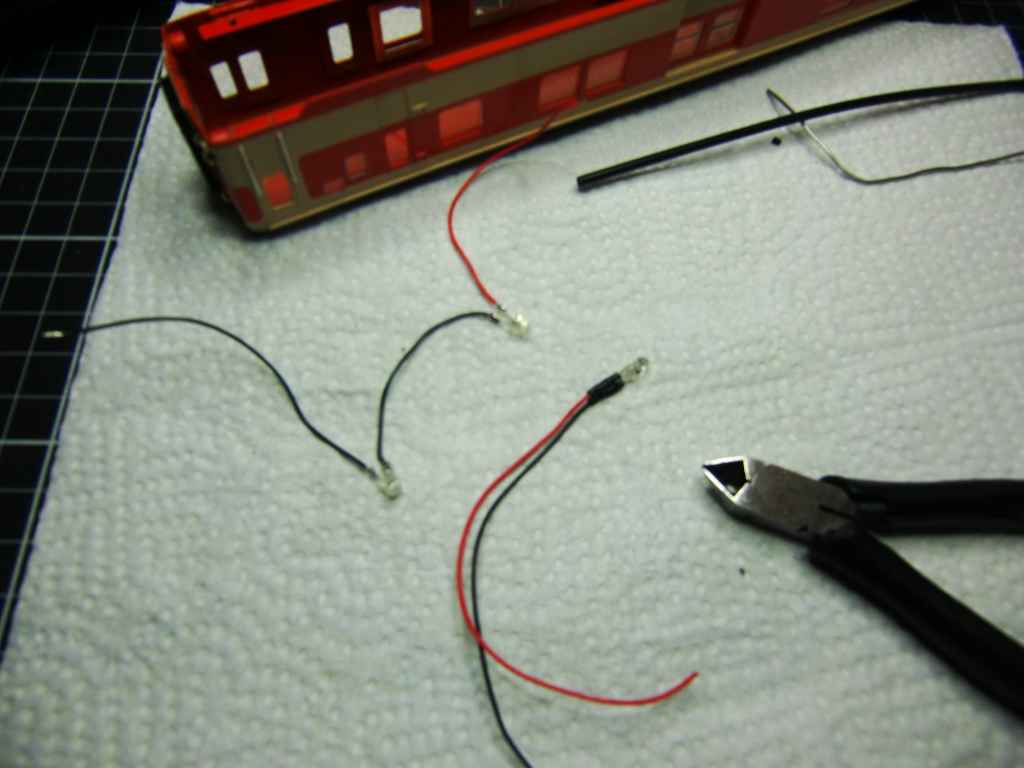
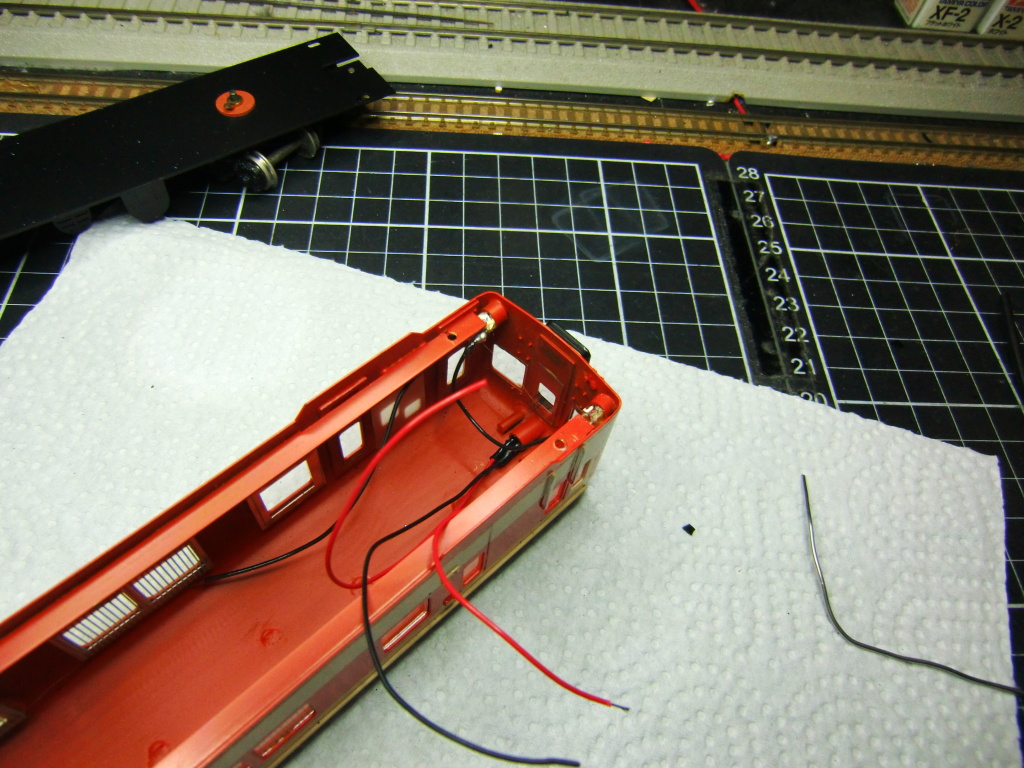


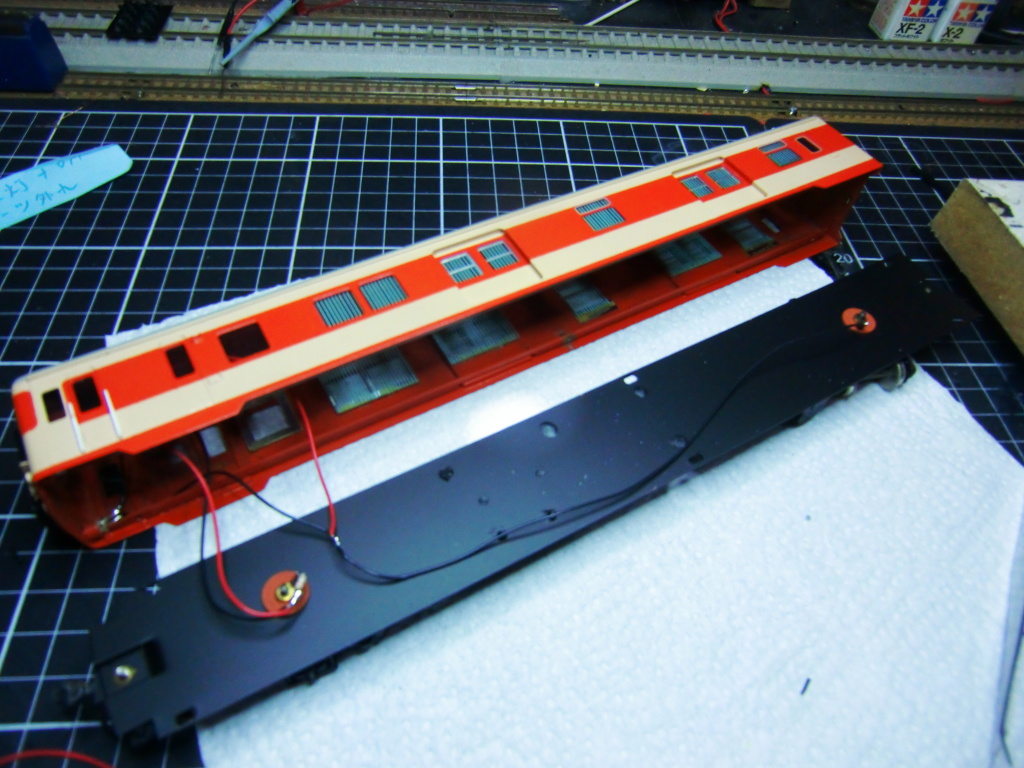


大変明るいライトに仕上がりました。

こちらも上記車両と同じ加工となります。こちらの車両では、ご依頼により座席を「設計・制作・塗装・配置」まで行う必要があります。
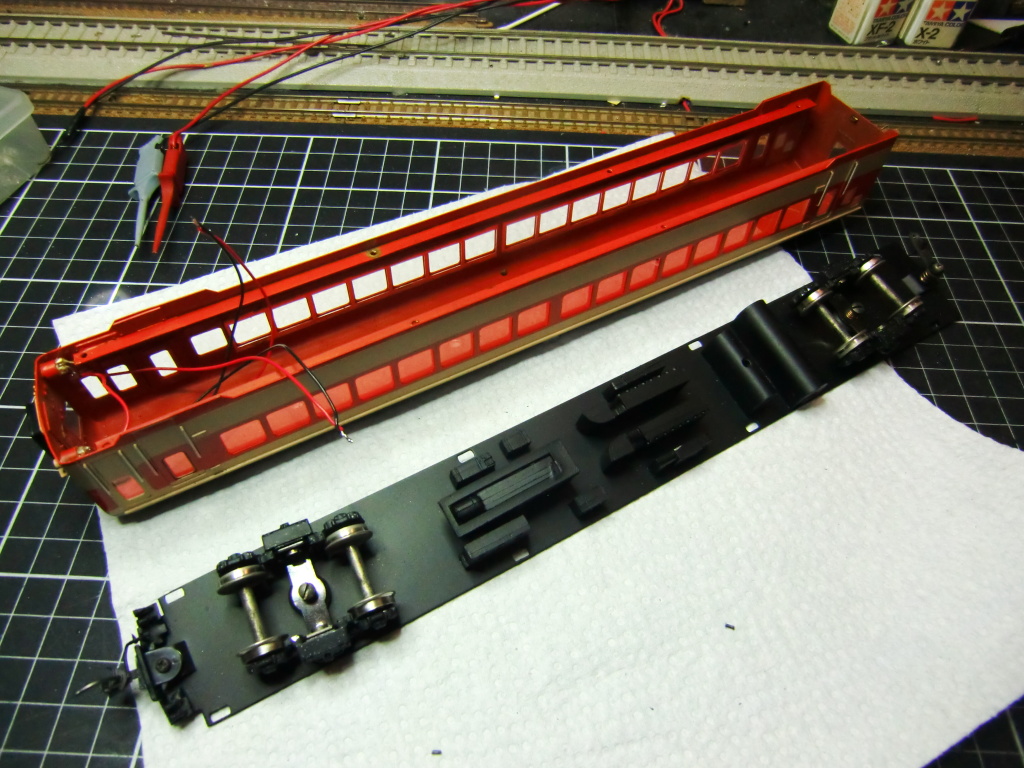

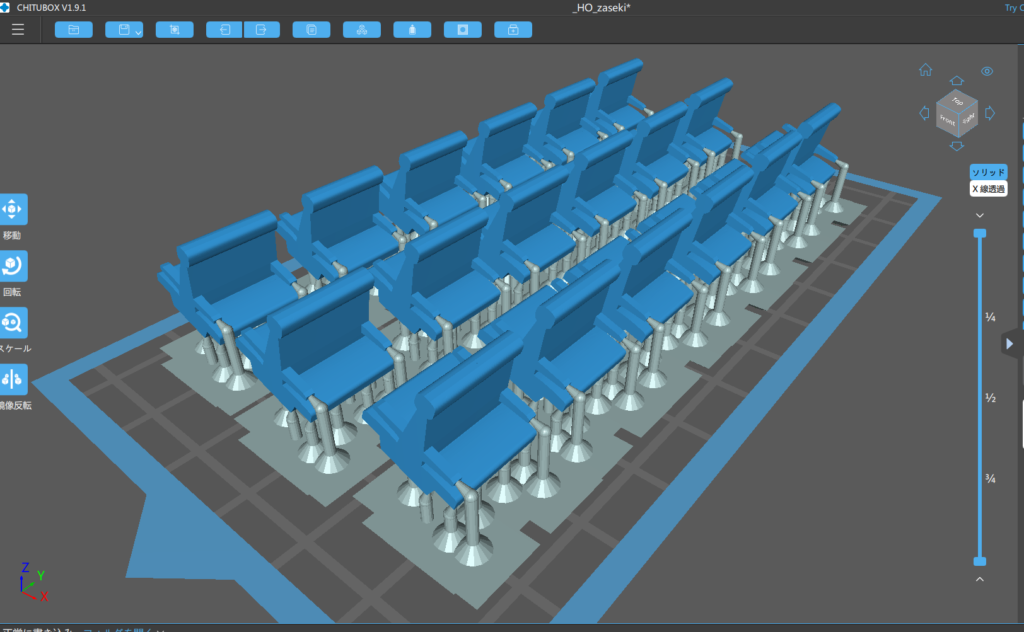
座席を設計していきます。出来上がったデータを3Dプリンターで出力します。
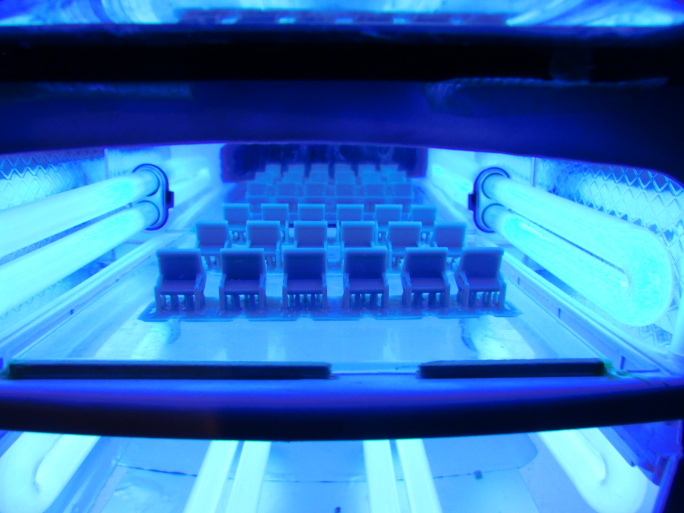
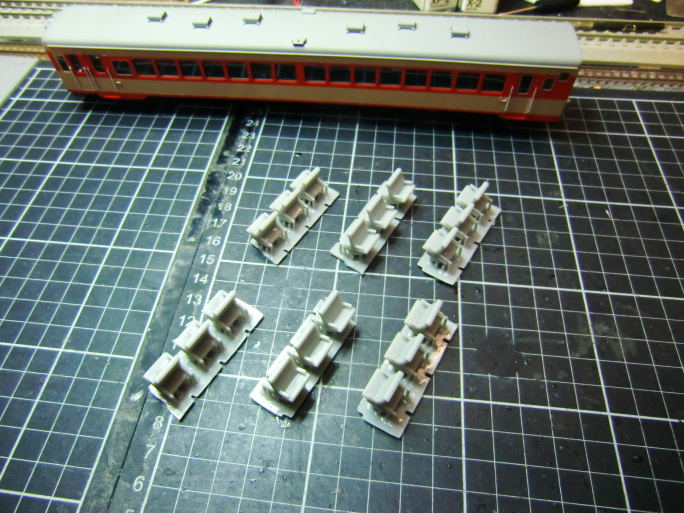


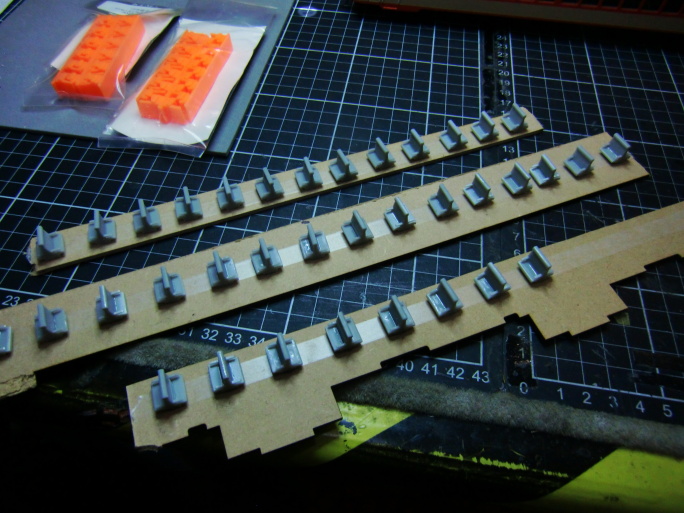



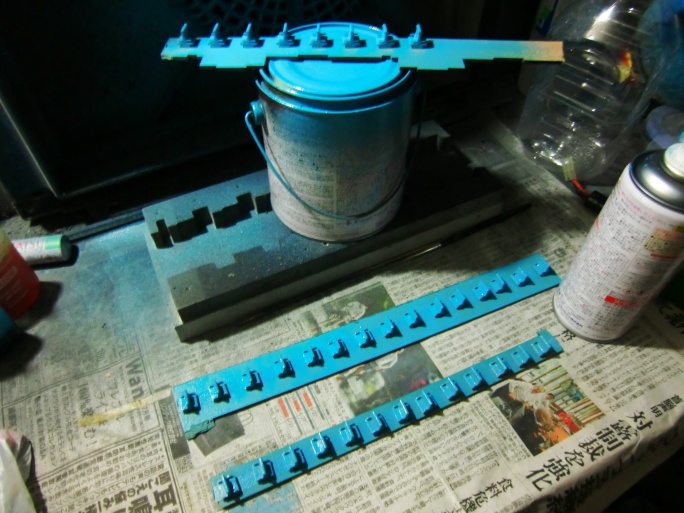

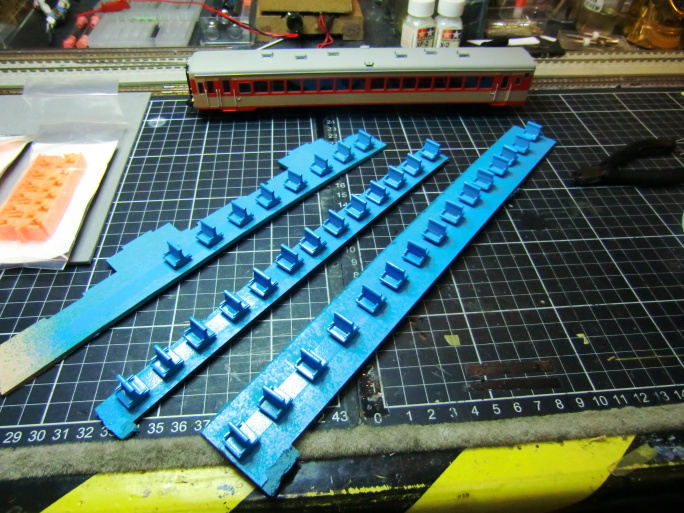
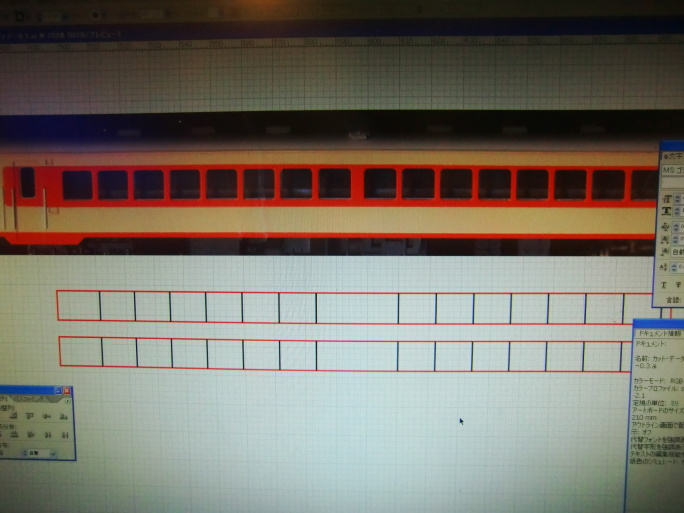
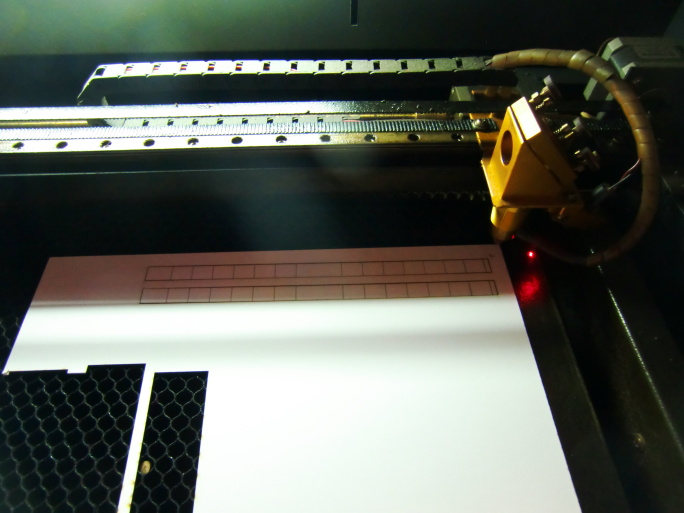


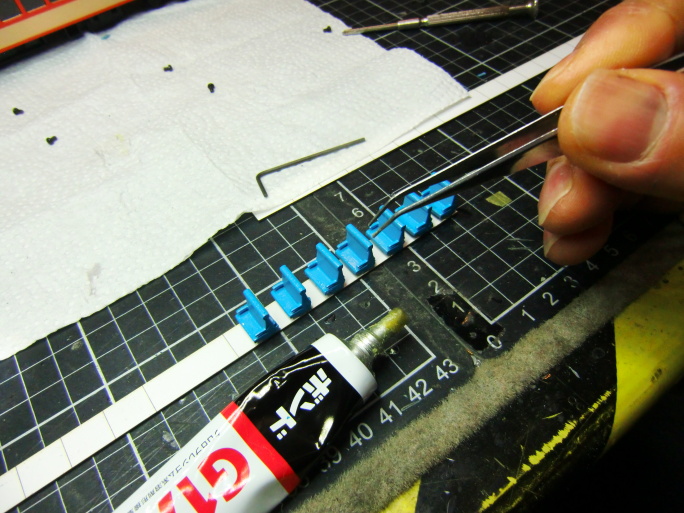
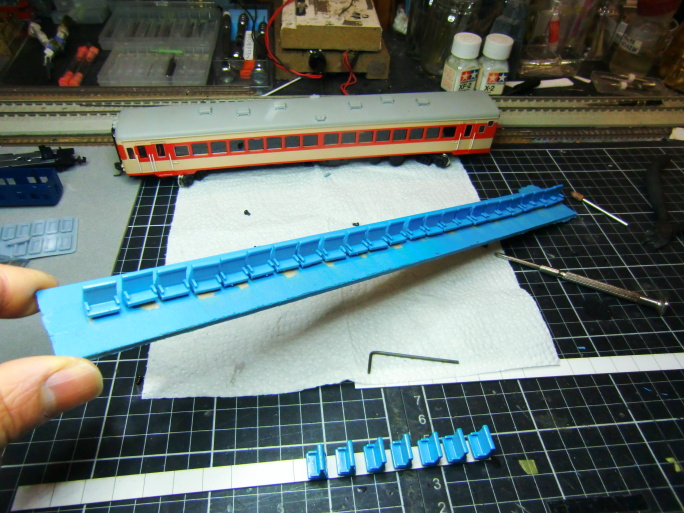
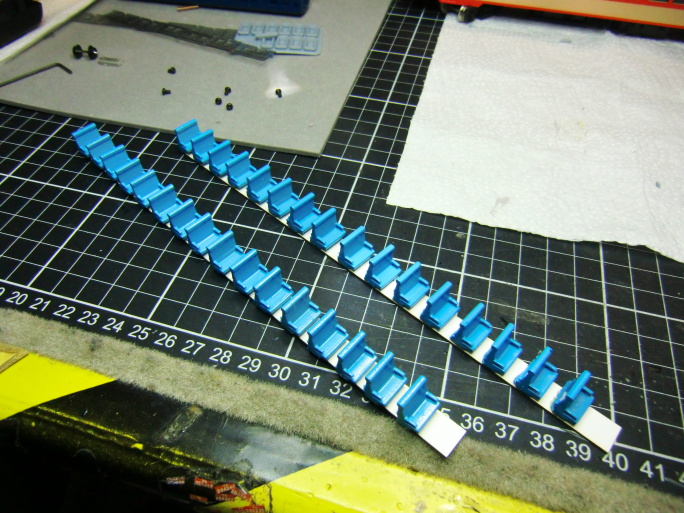




ヘッド・テールも点灯化構造を行い、作業はすべて完了しました。
▼タキ50000
まずはこちらから修理作業に入ります。


ハンダが盛り上がってしまってますので、まずはこれを取り除きます。



ある程度はんだを取り除いた段階で、ルーターで研ぎます。


塗装前に脱脂を行っておきます。

手すりをかける上中下面の各部が色剥げしていますので、タッチペイントで補修していきます。

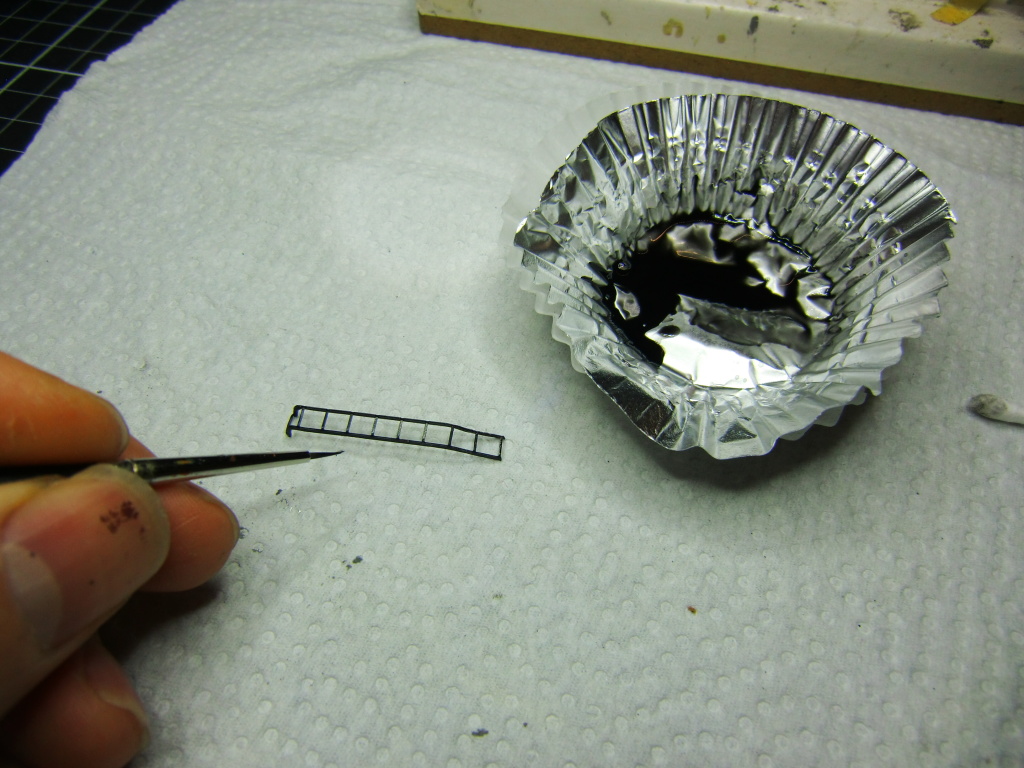




▼マイ3812 客車 修理・補修作業

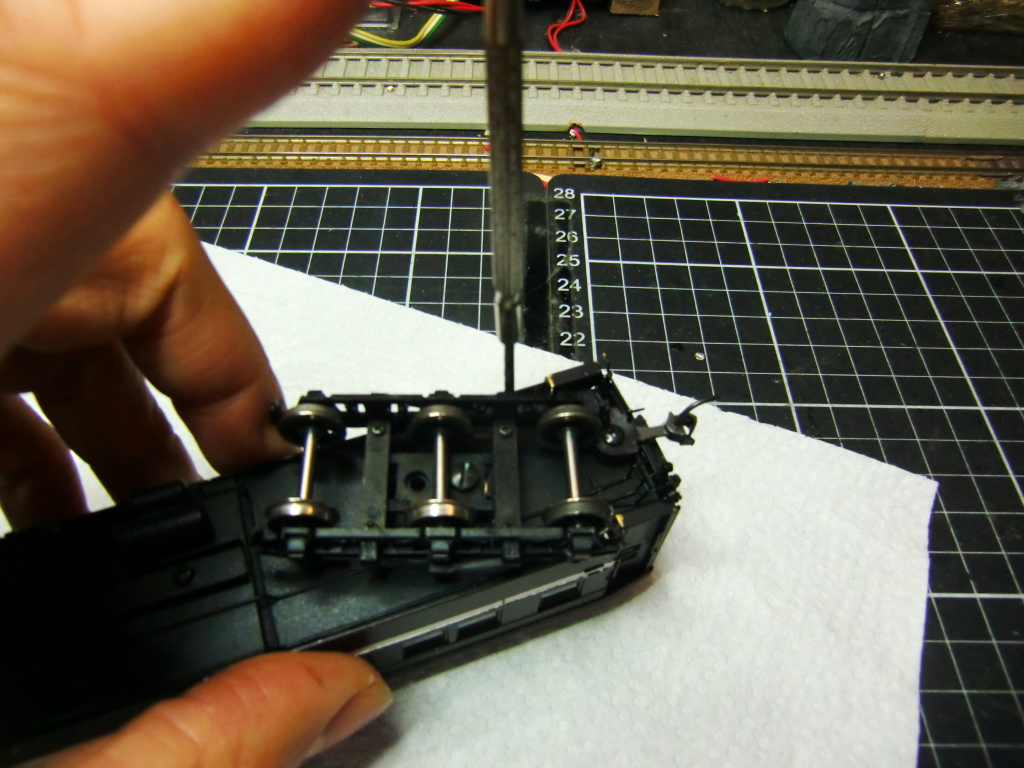
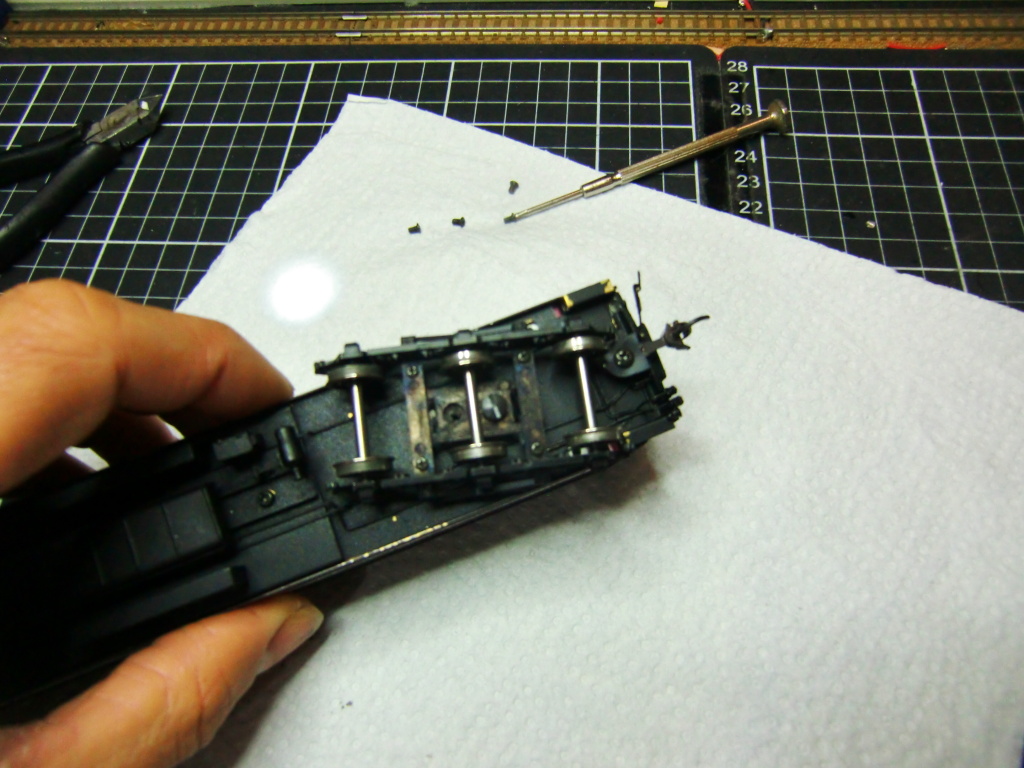

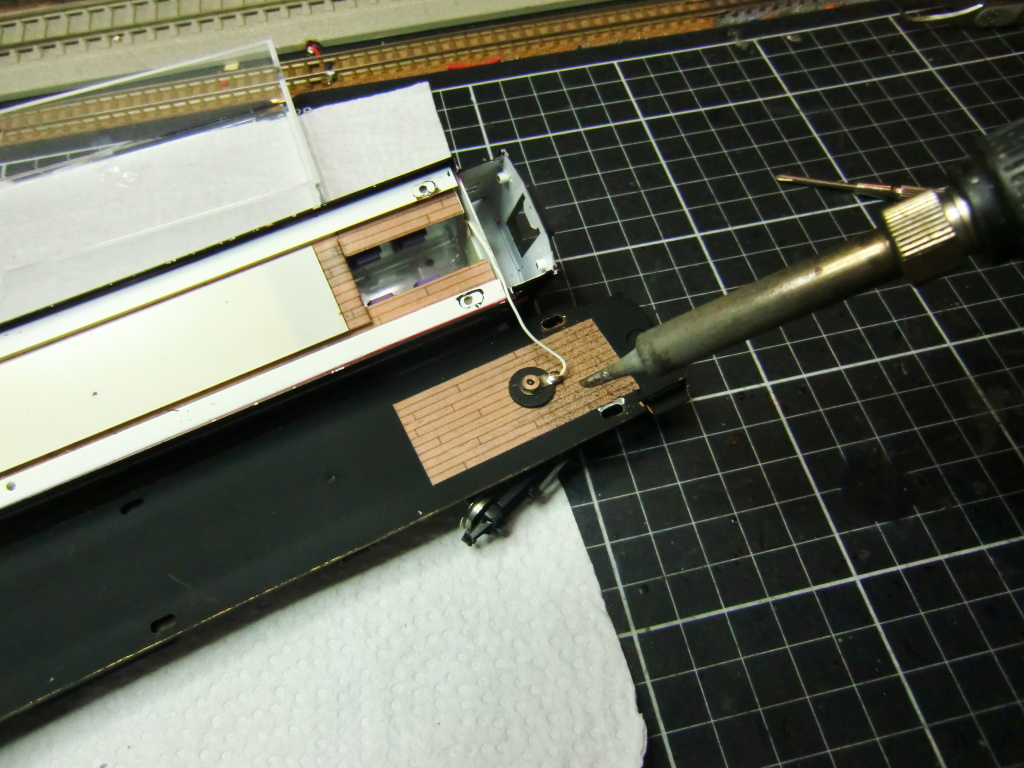
そのままでは作業しにくいので、配線を外していきます。
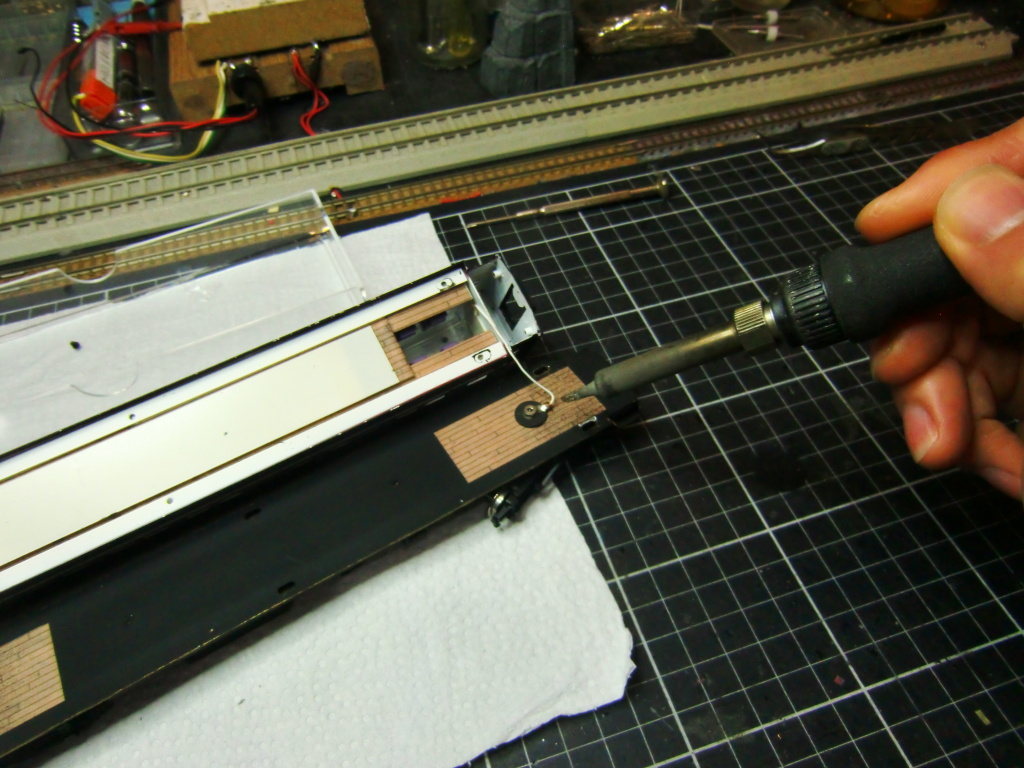
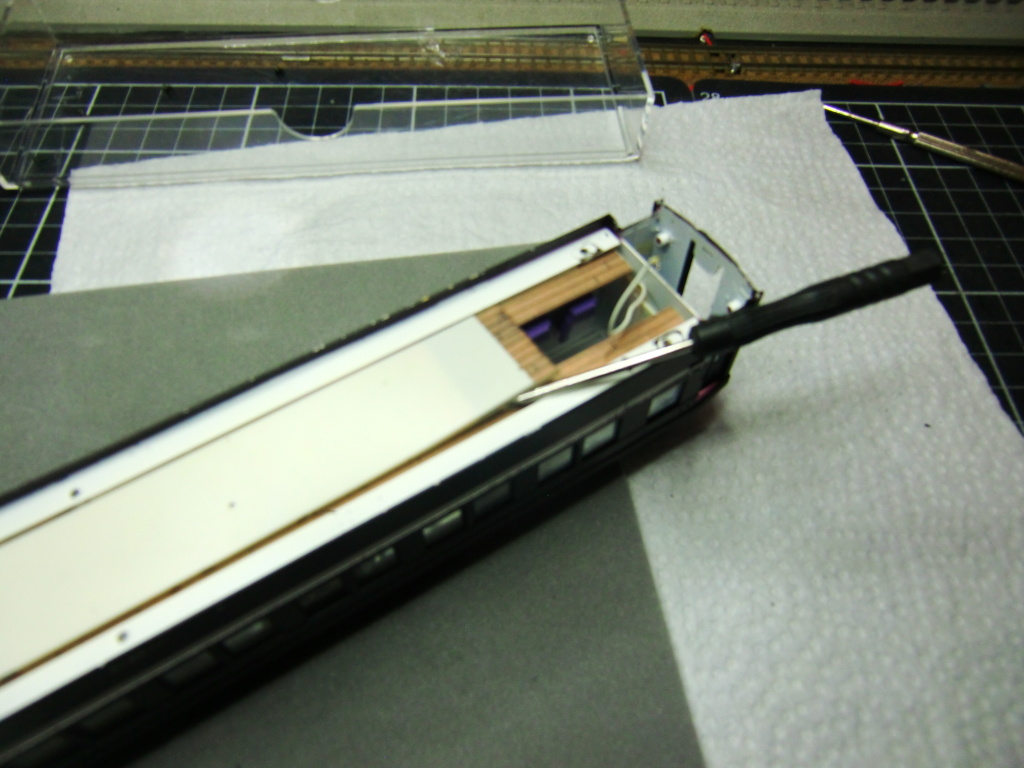
両面テープでしっかり固定されており分解できないようになっています。プラバンの上に印刷物を両面テープで貼って床板の模様を再現しているようです。

床面を強制的に剥がします。
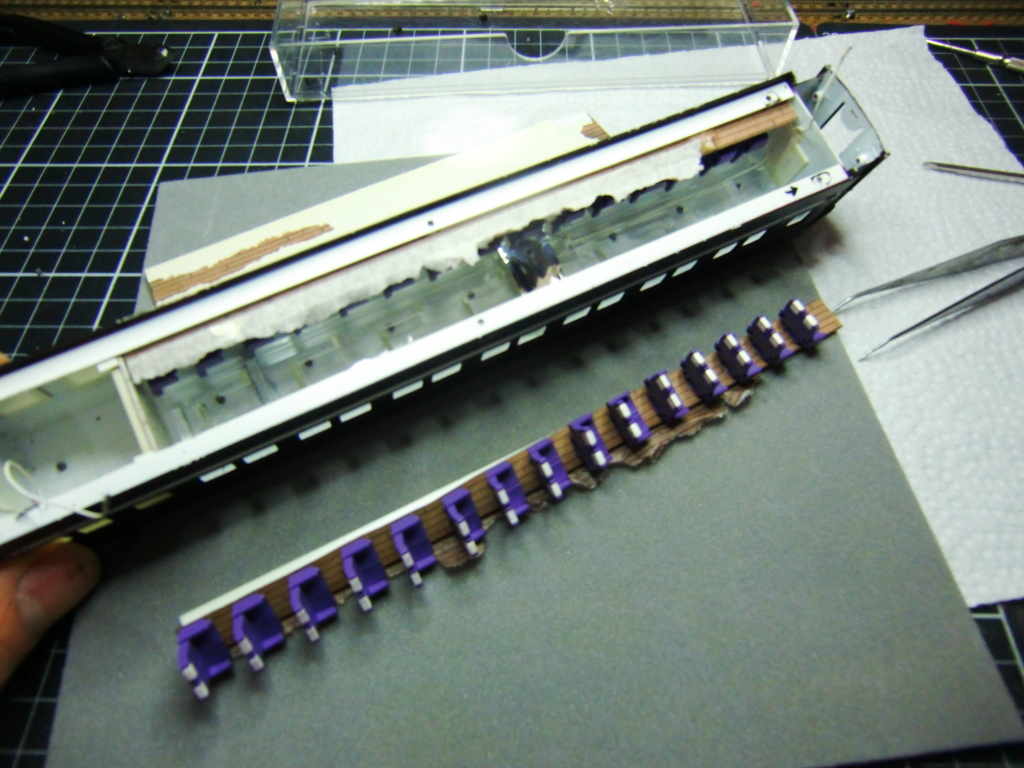
座席はゴム系接着剤で固定されてあり、取り出すのにちょっと苦戦しましたが、ようやく取り出せました。
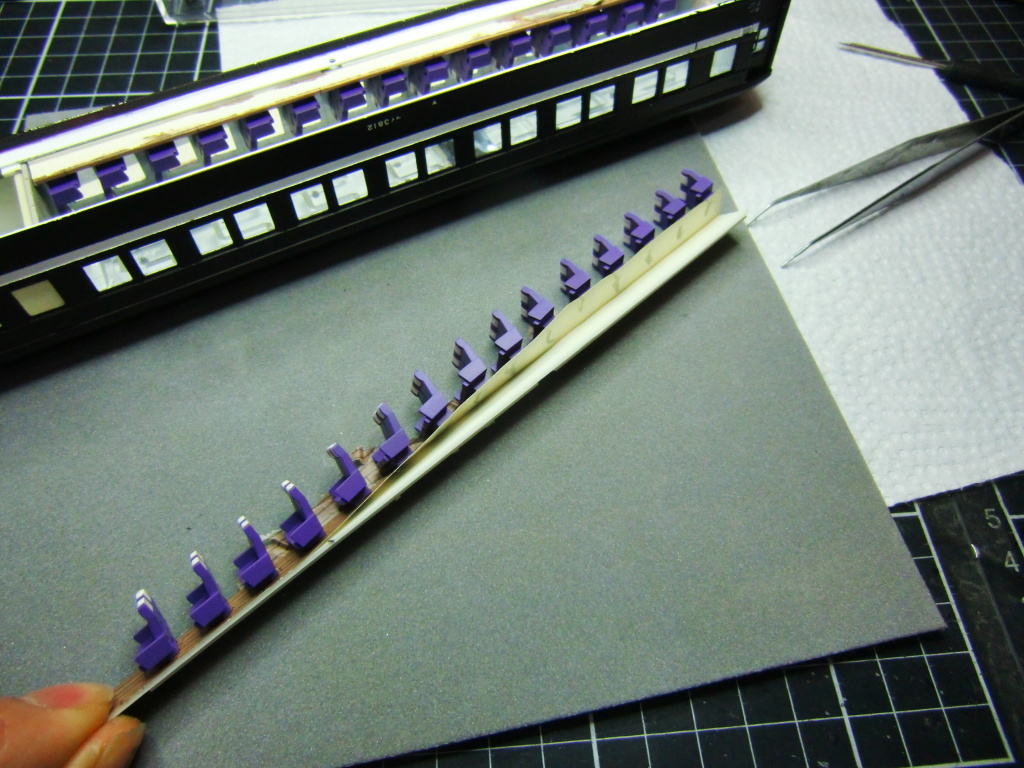
このように粘着性が失われて波打ってます。
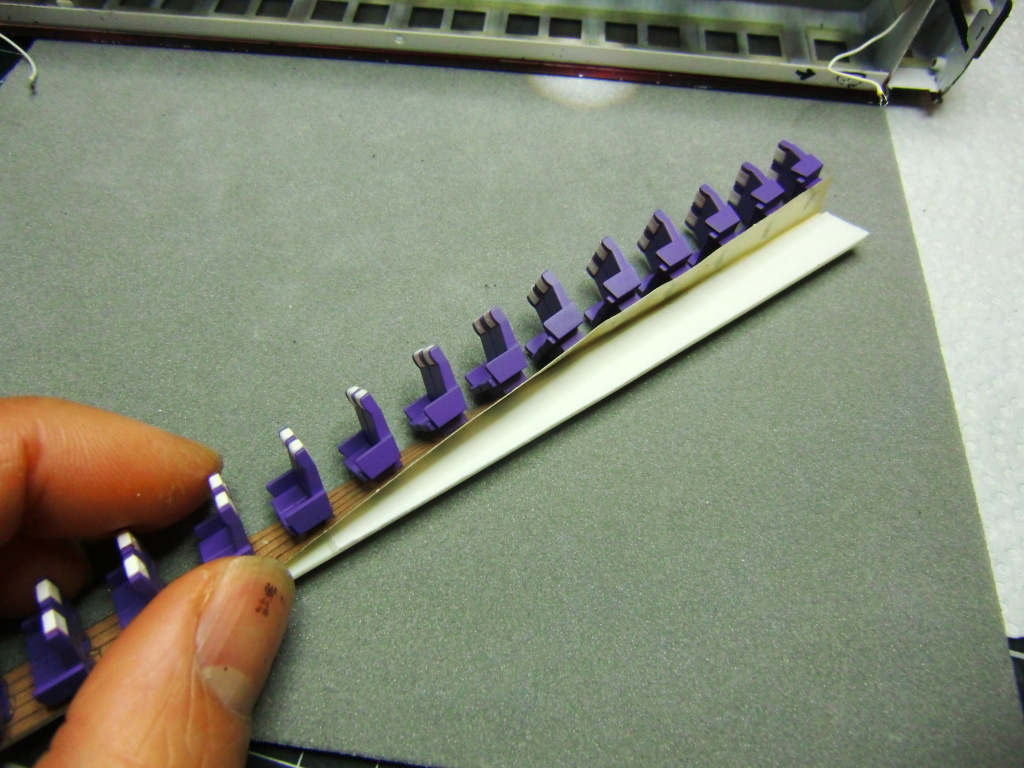
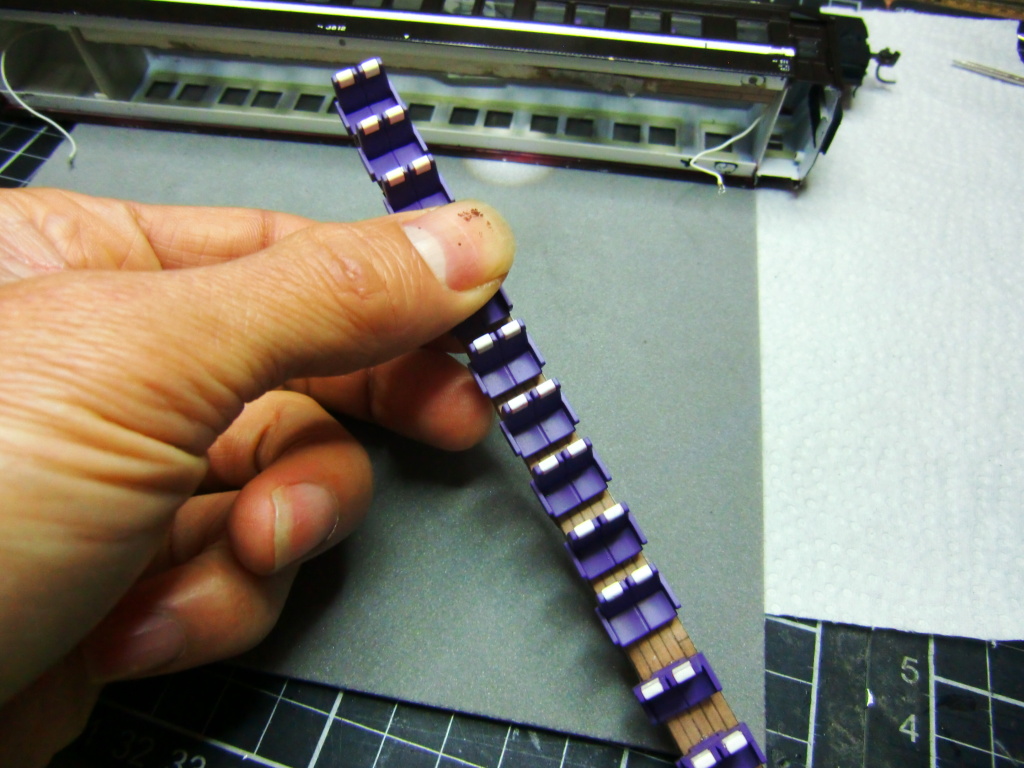

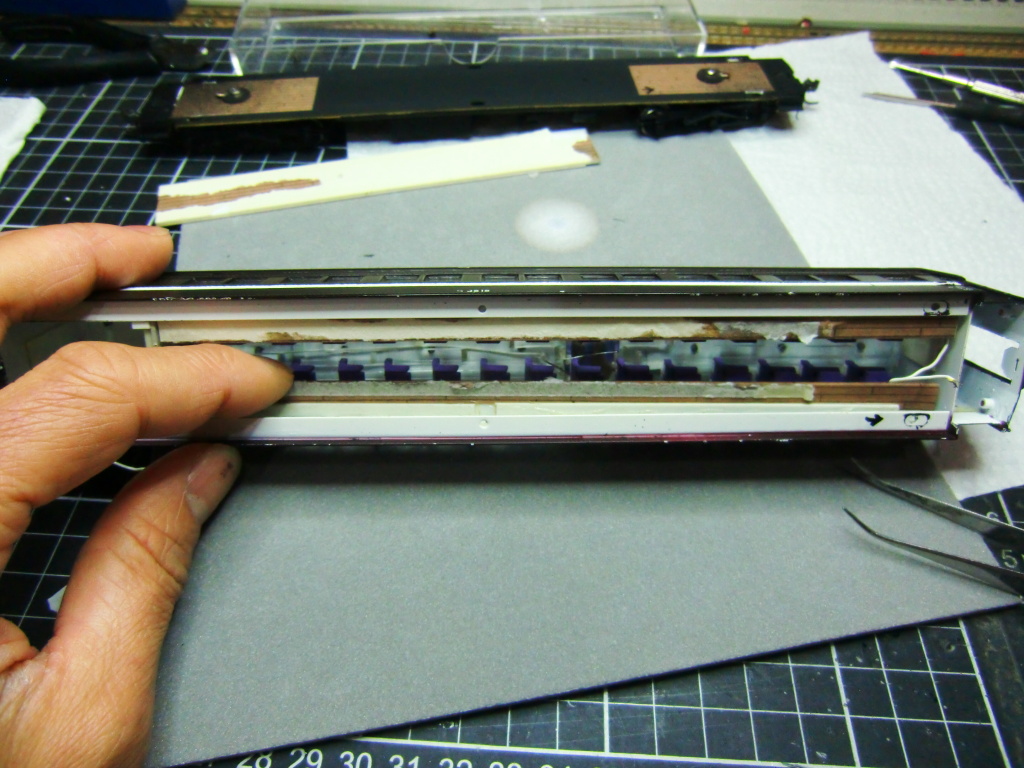
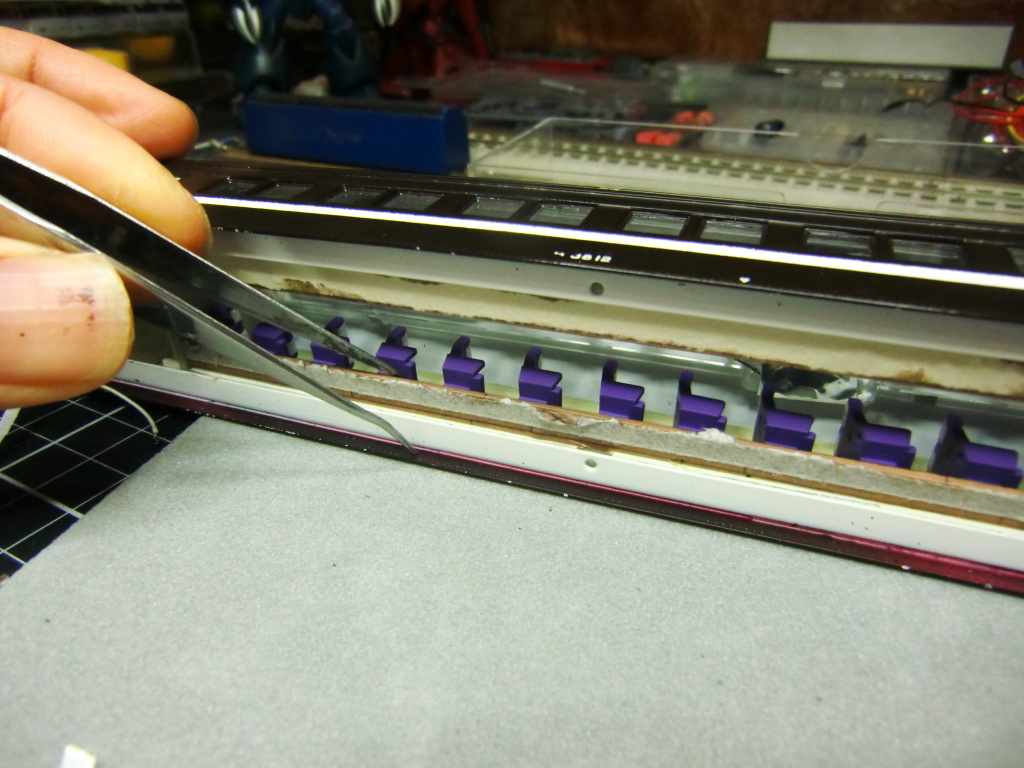


床の印刷データを作ります。

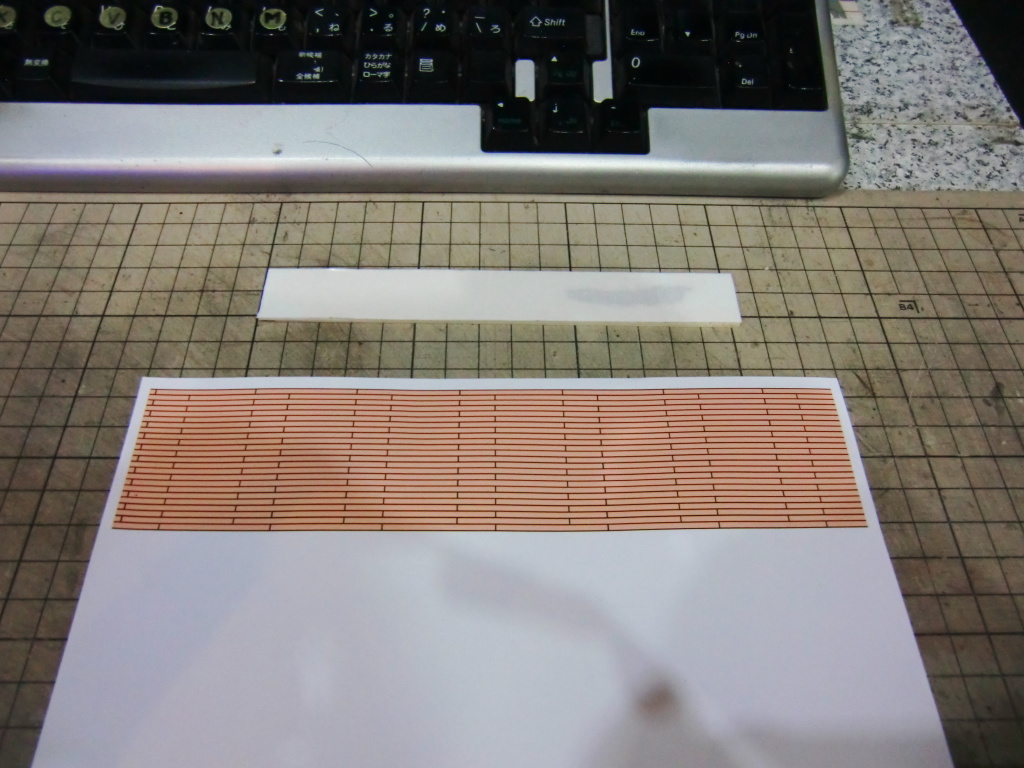
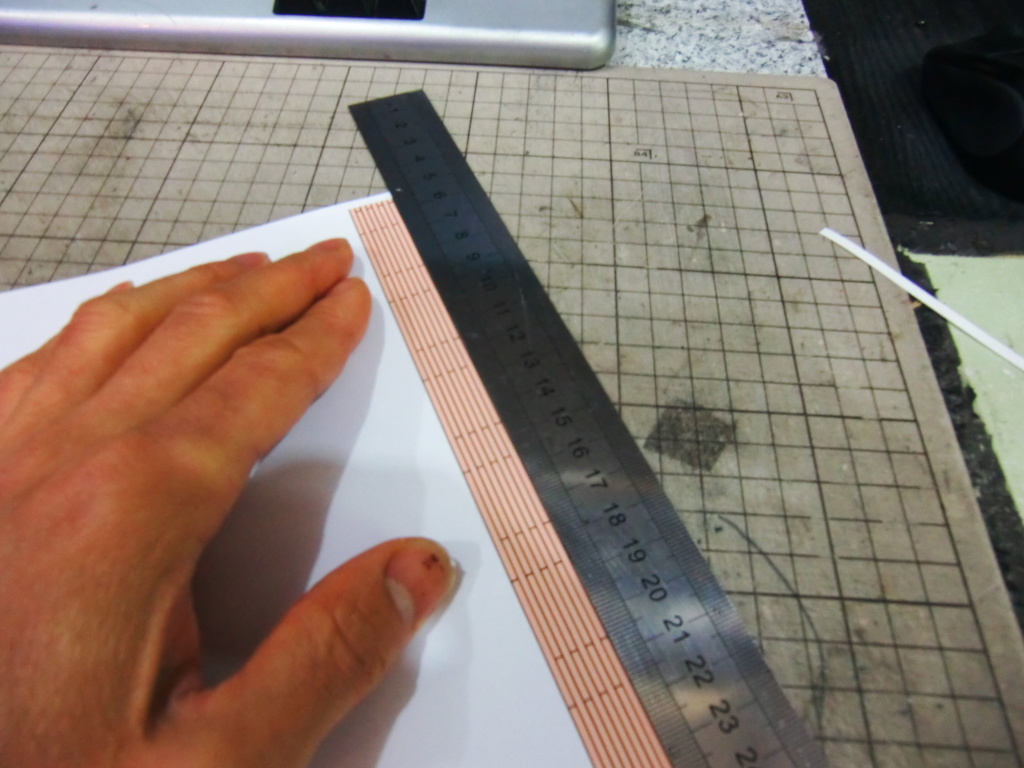
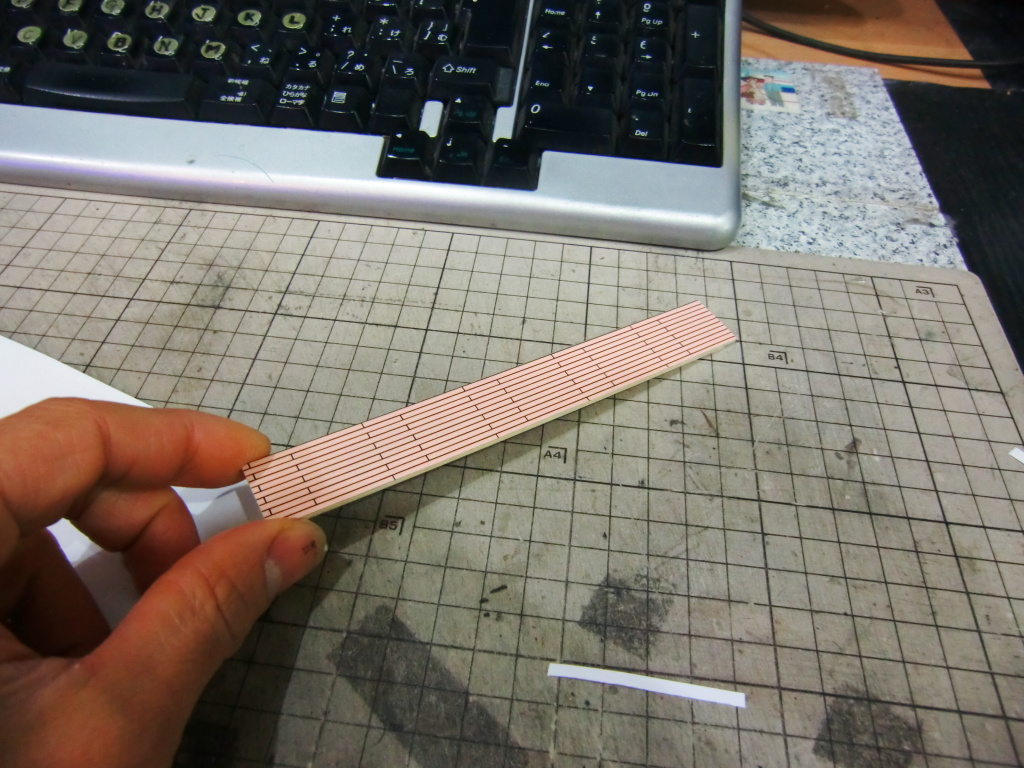
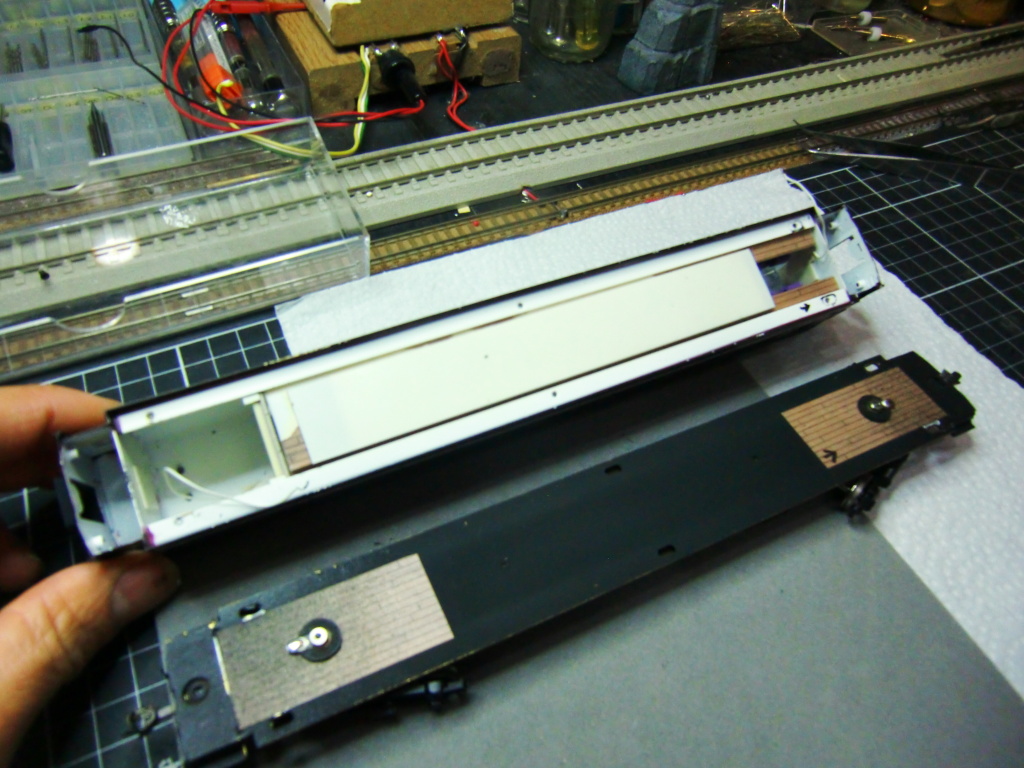

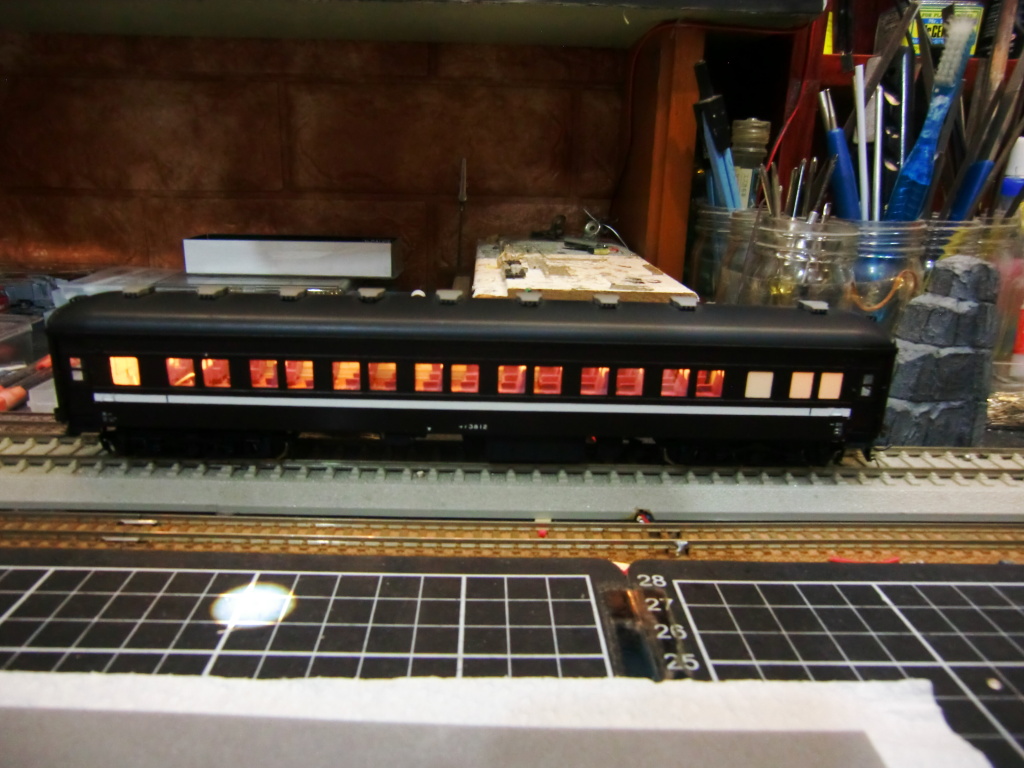

▼スイ6233客車 修理・補修作業
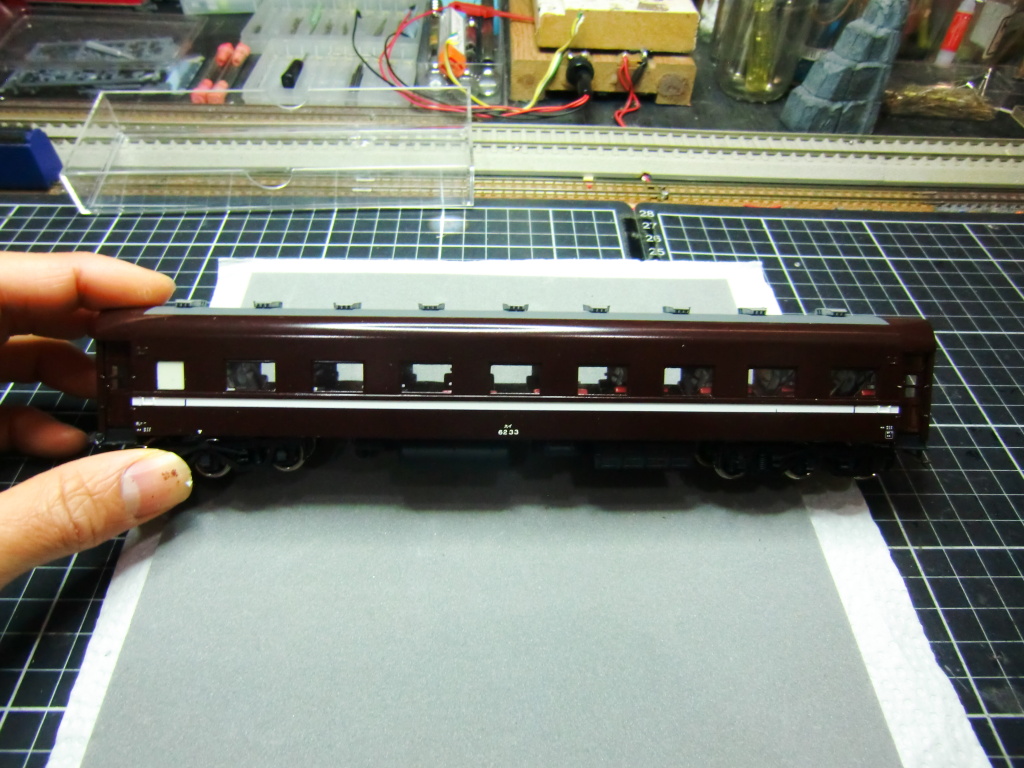
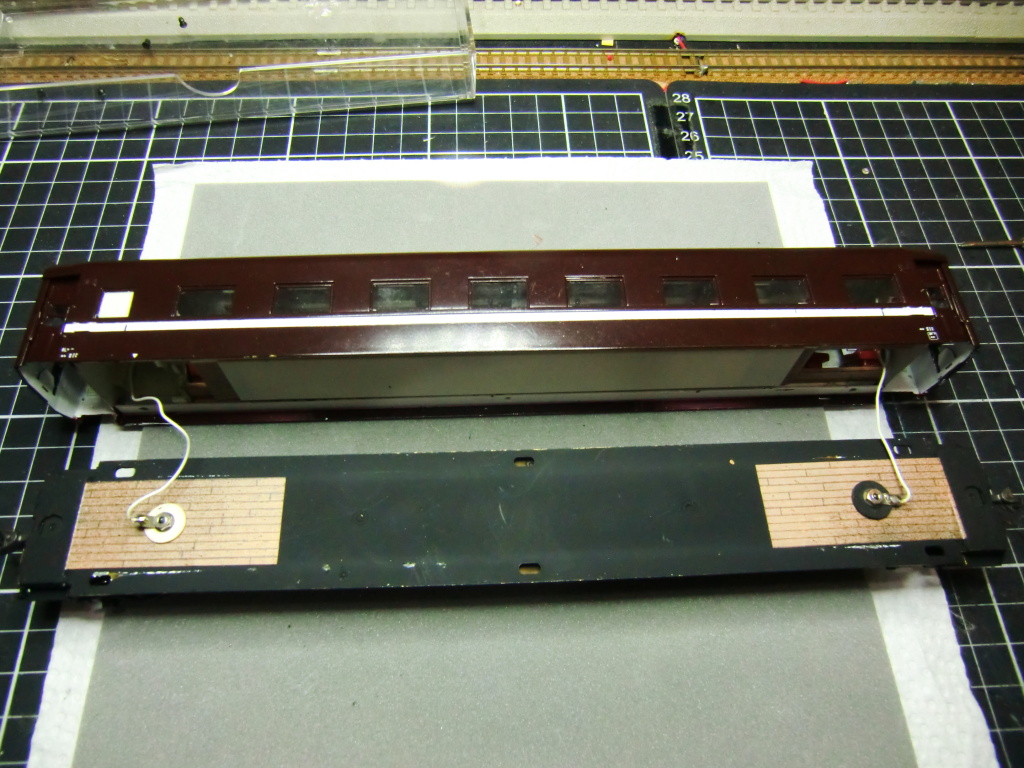
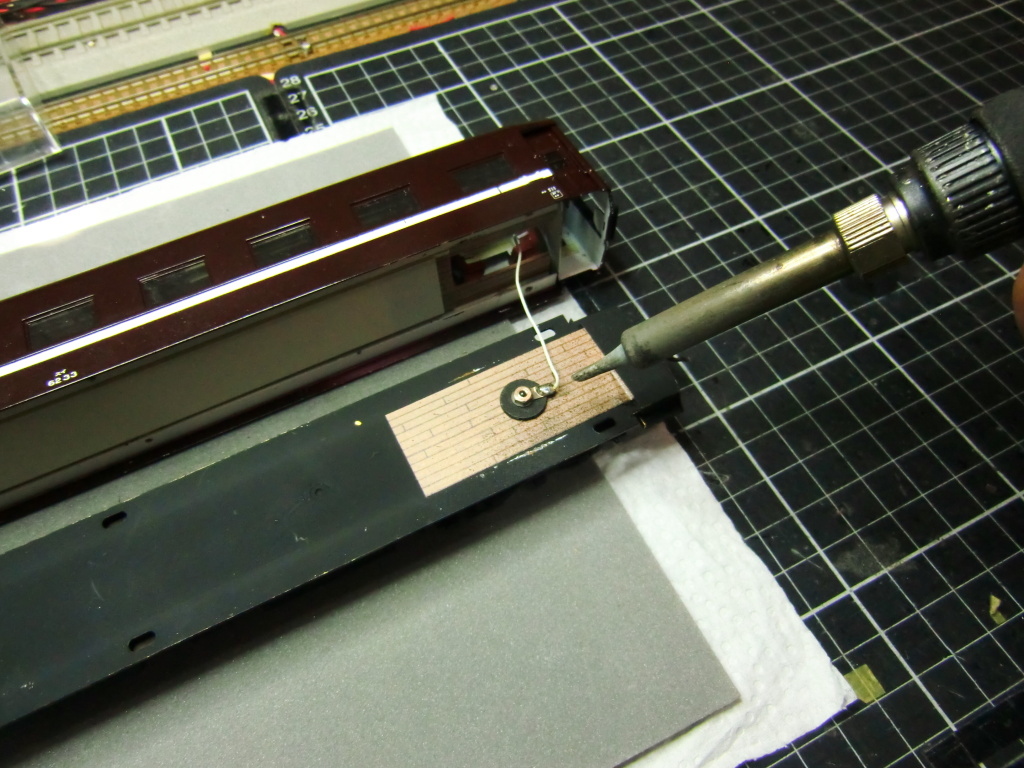
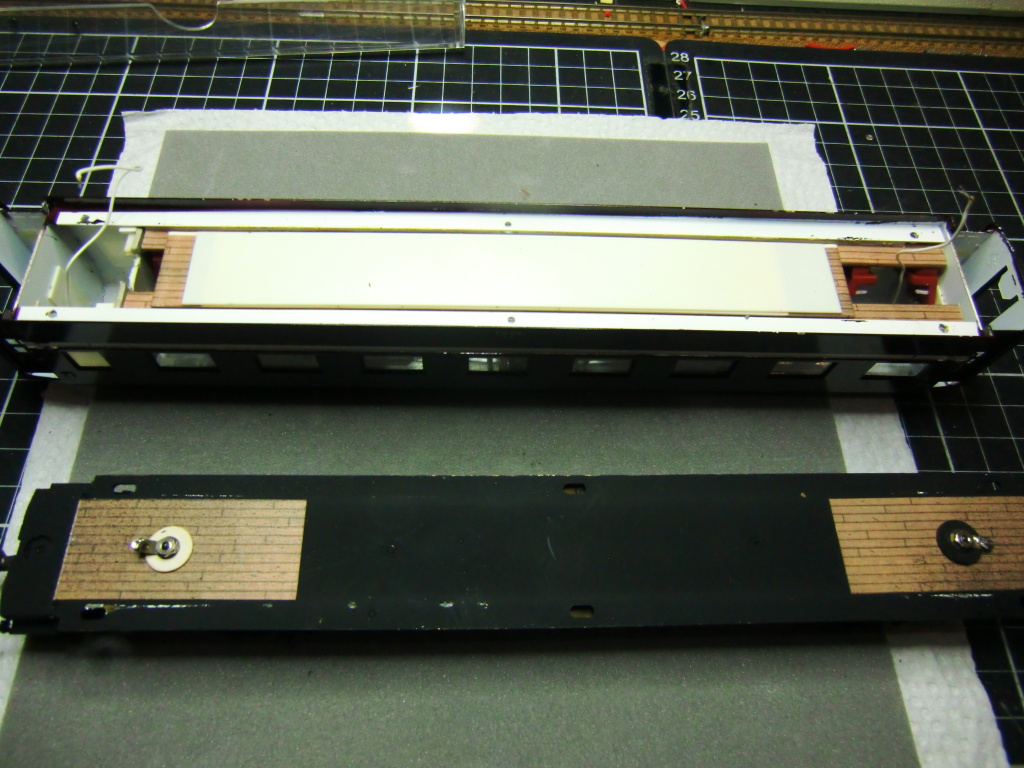
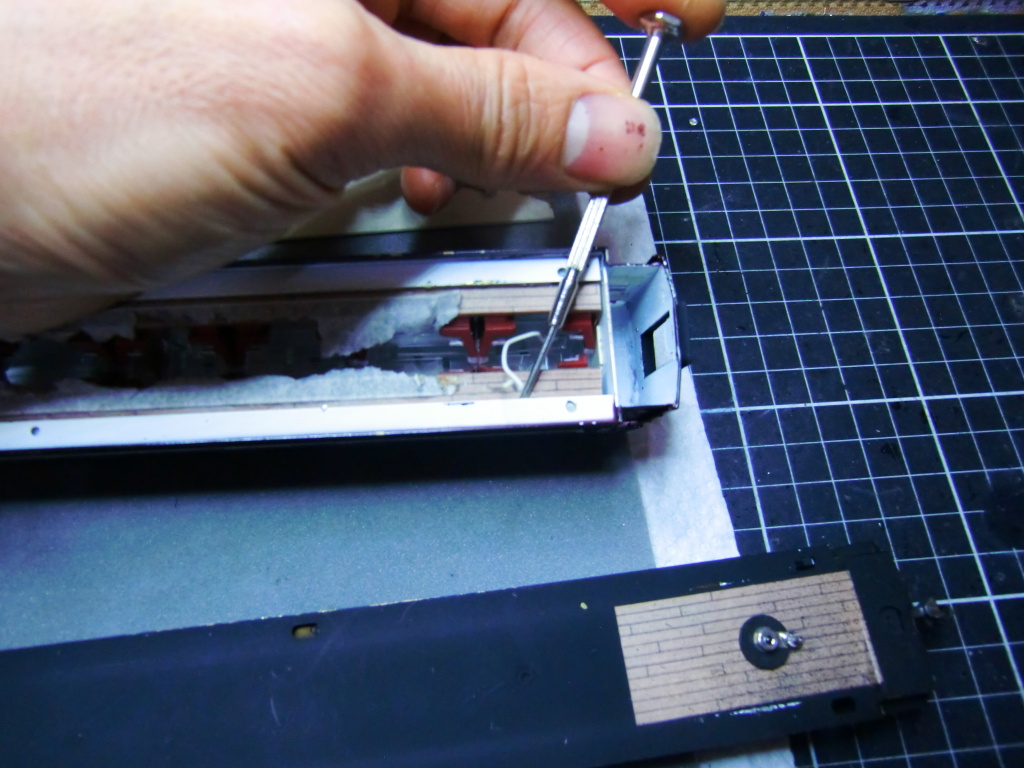
接着剤がべったりついていてなかなか外れません。隅から少しずつに持ち上げて時間をかけて剥がしていきます。
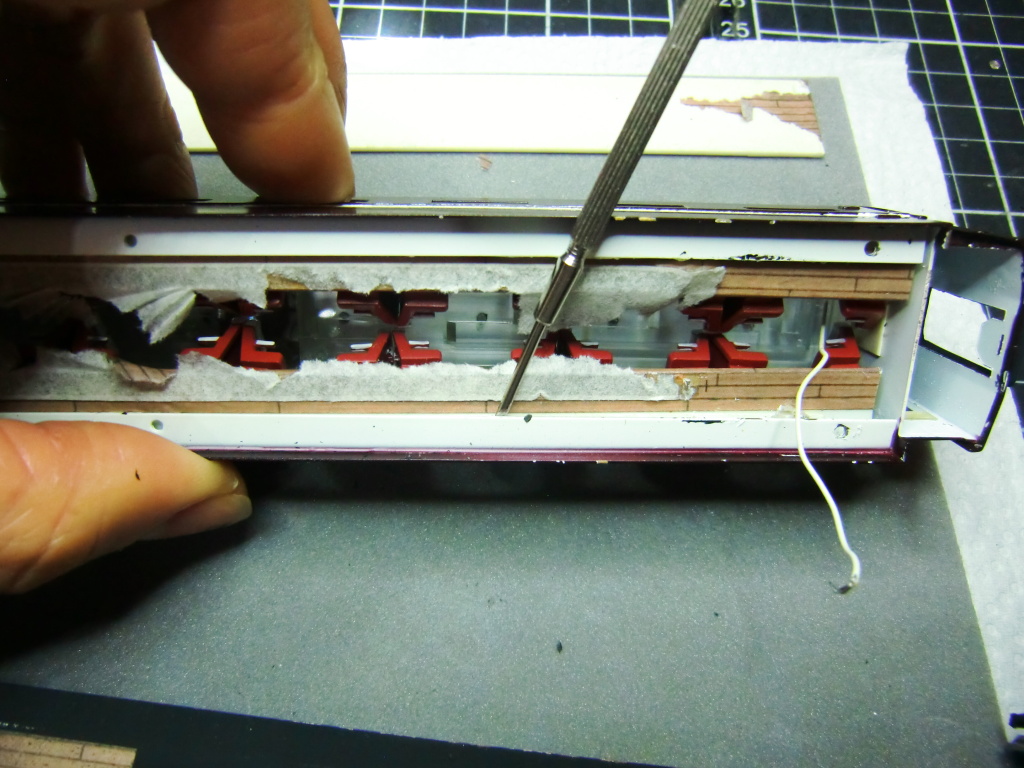
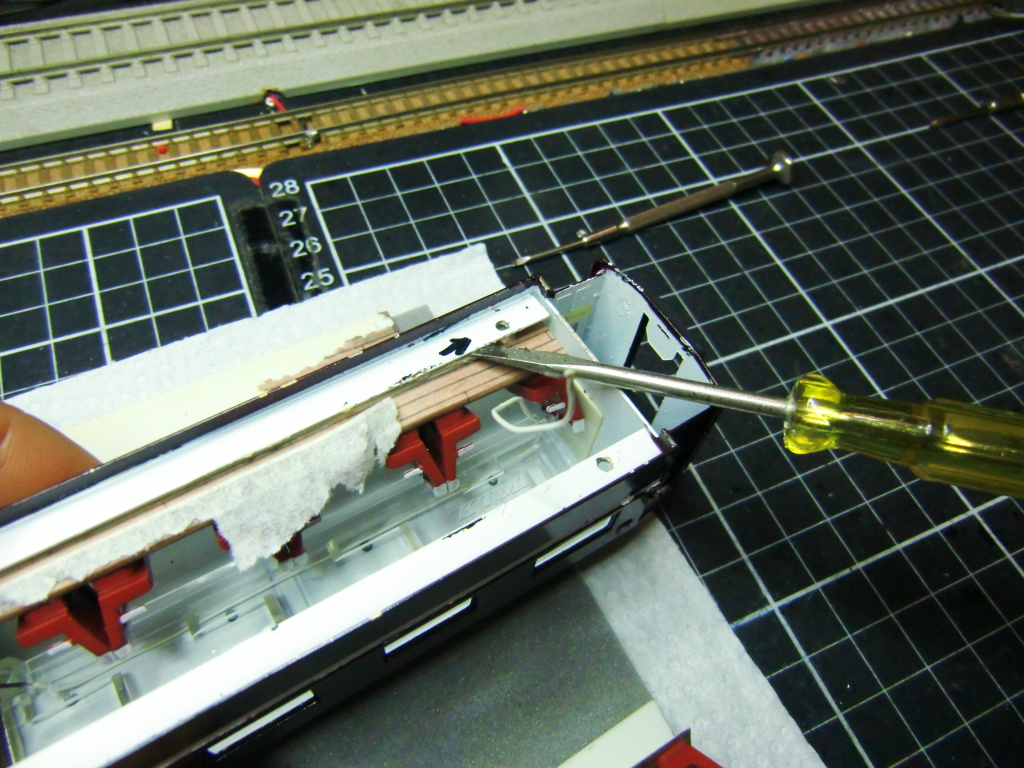
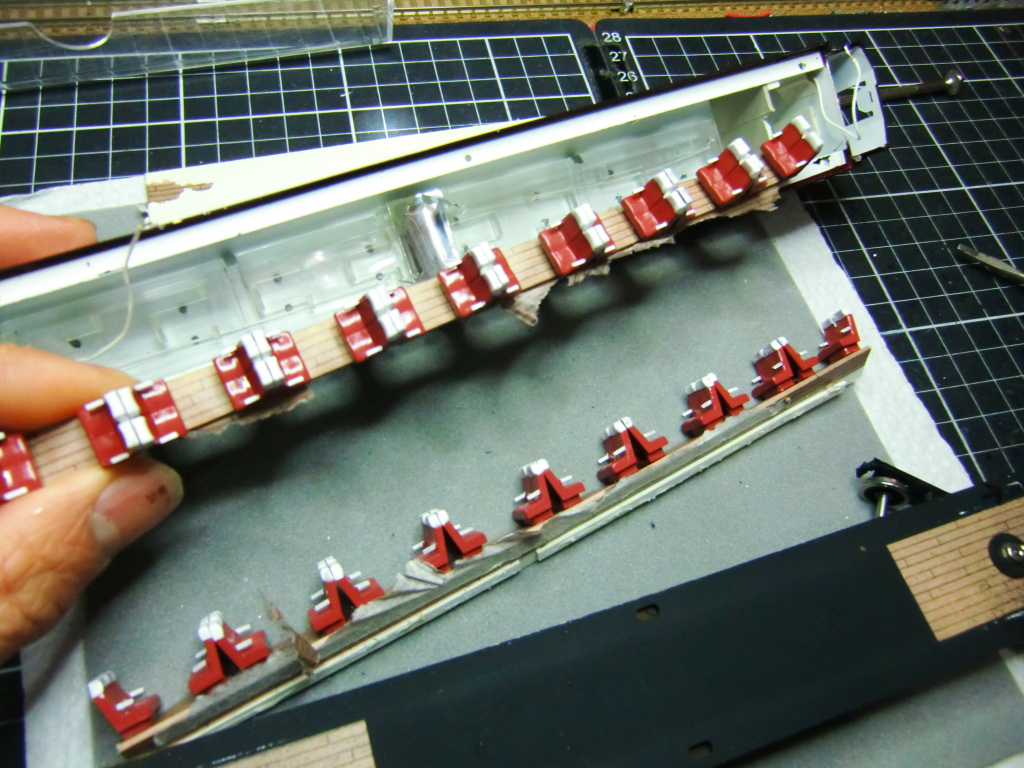
ようやく外れました。
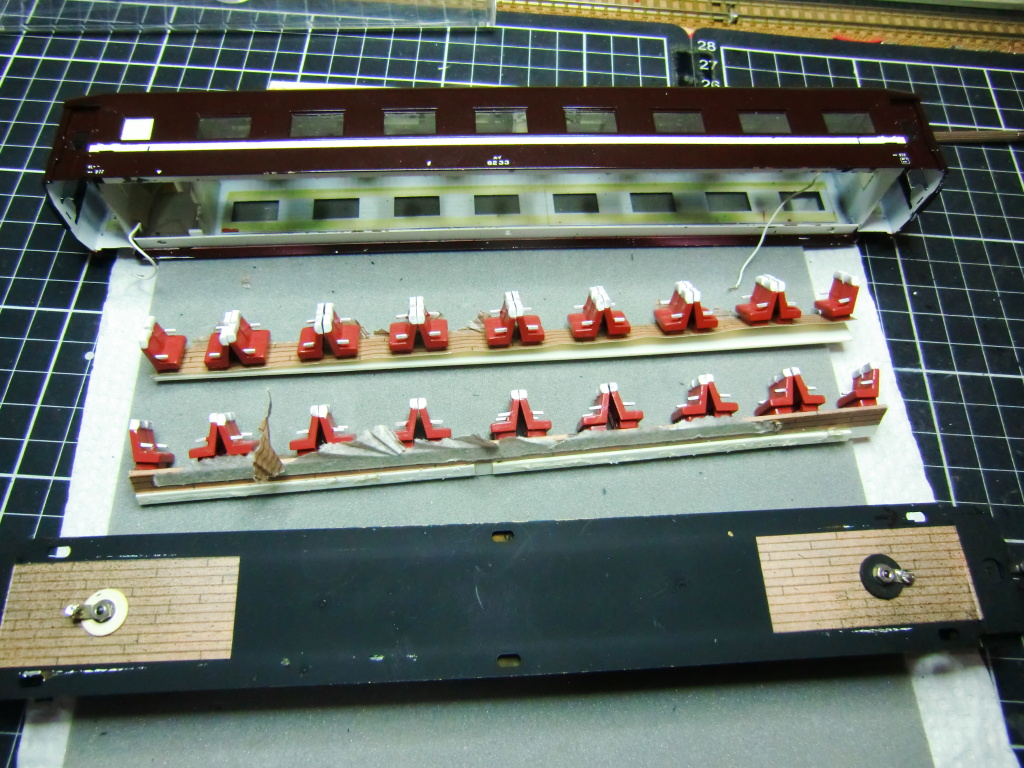
ここから1つ1つ直していきます。
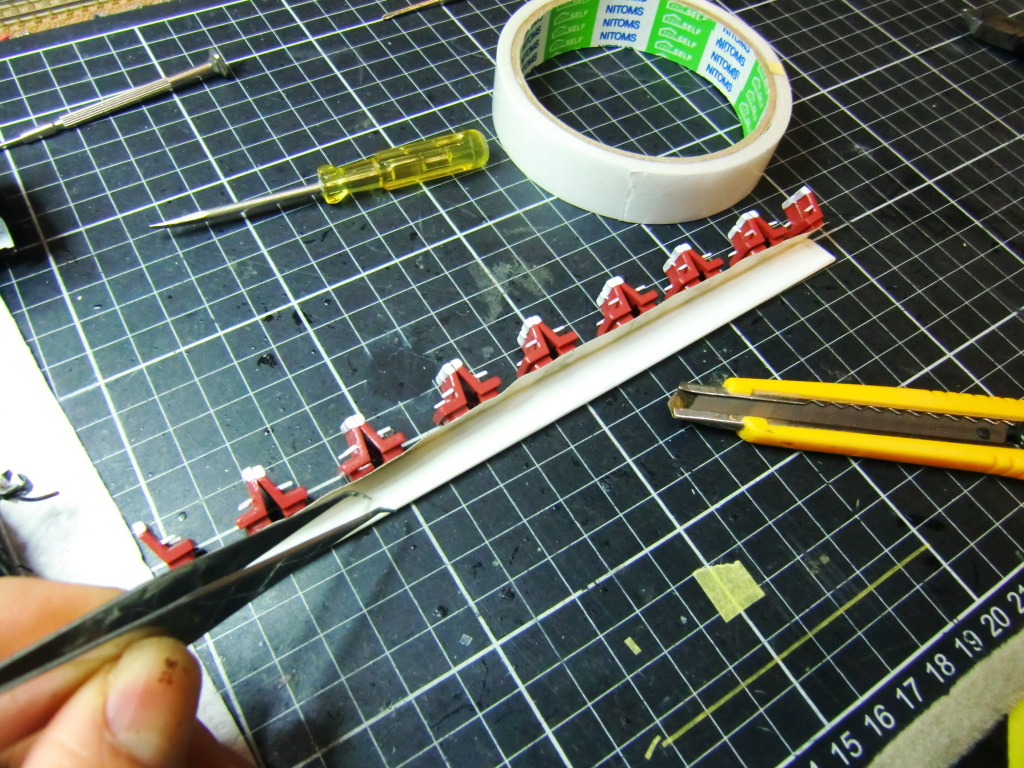
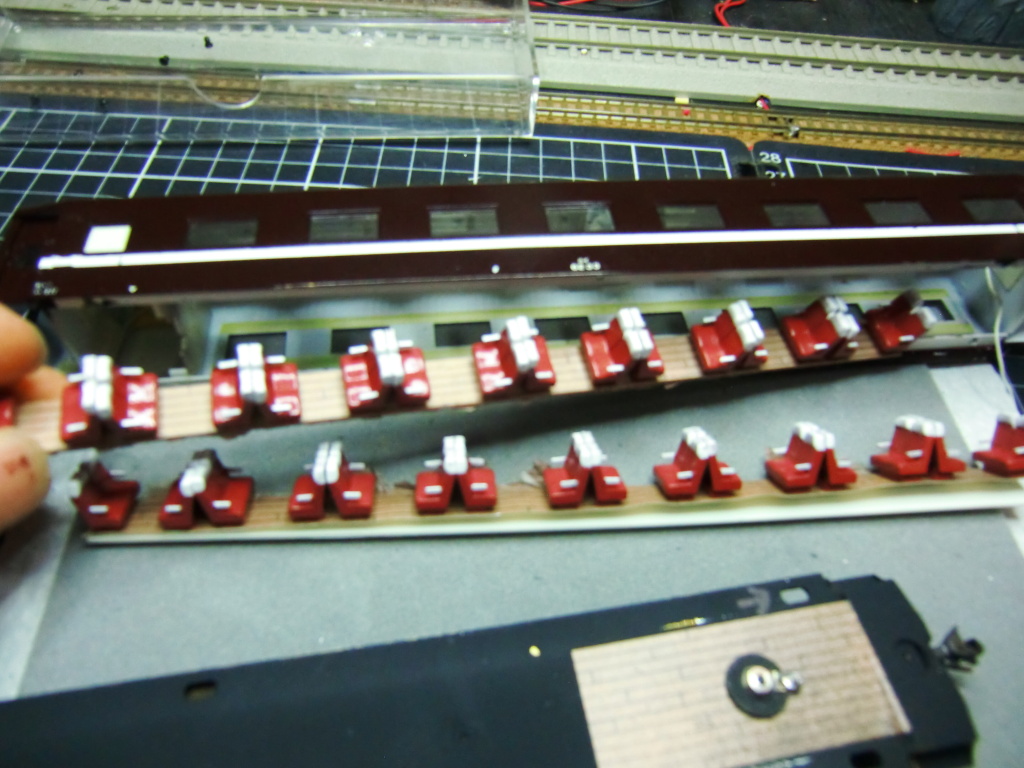
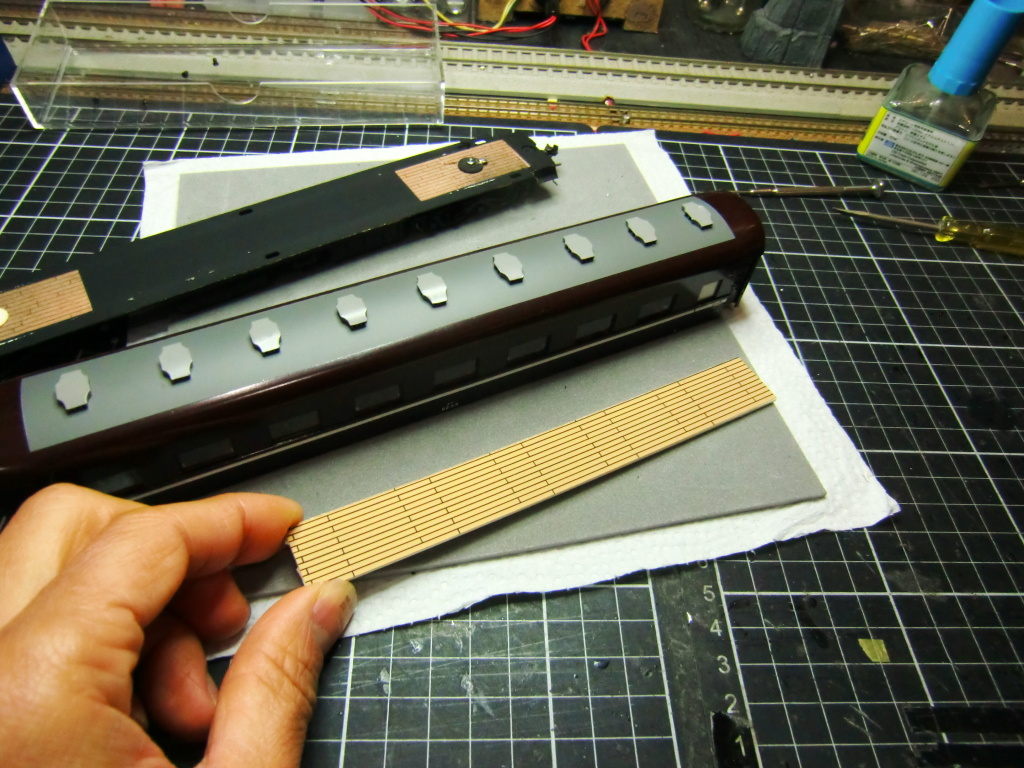
床も新しく作り替えました。
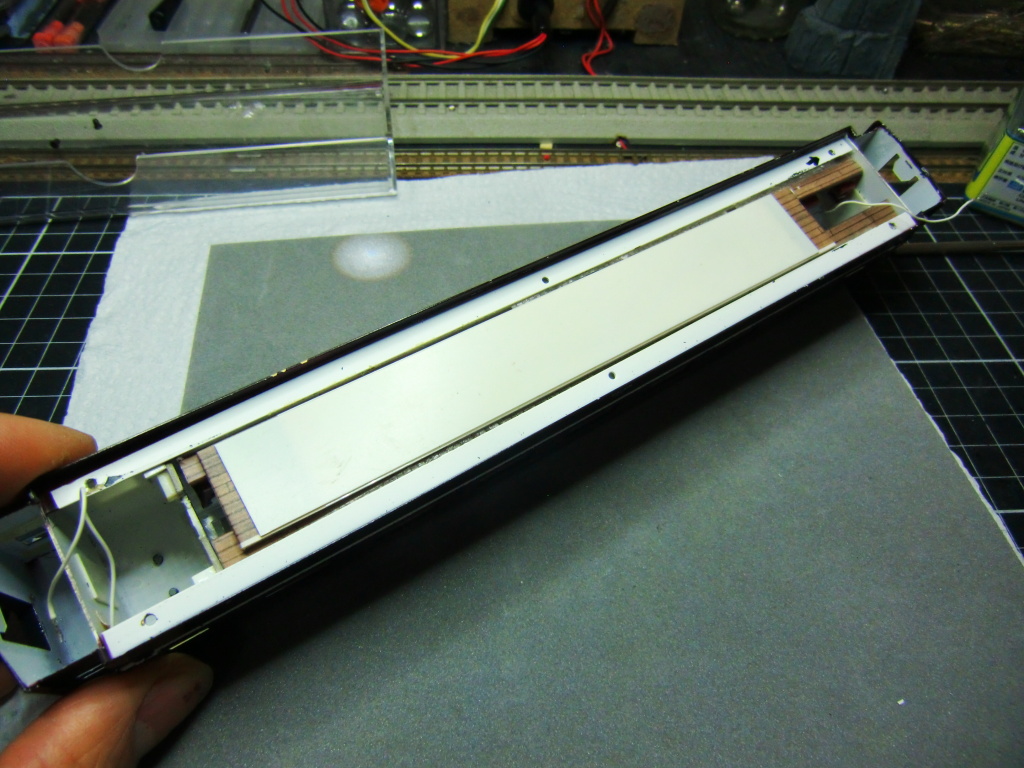
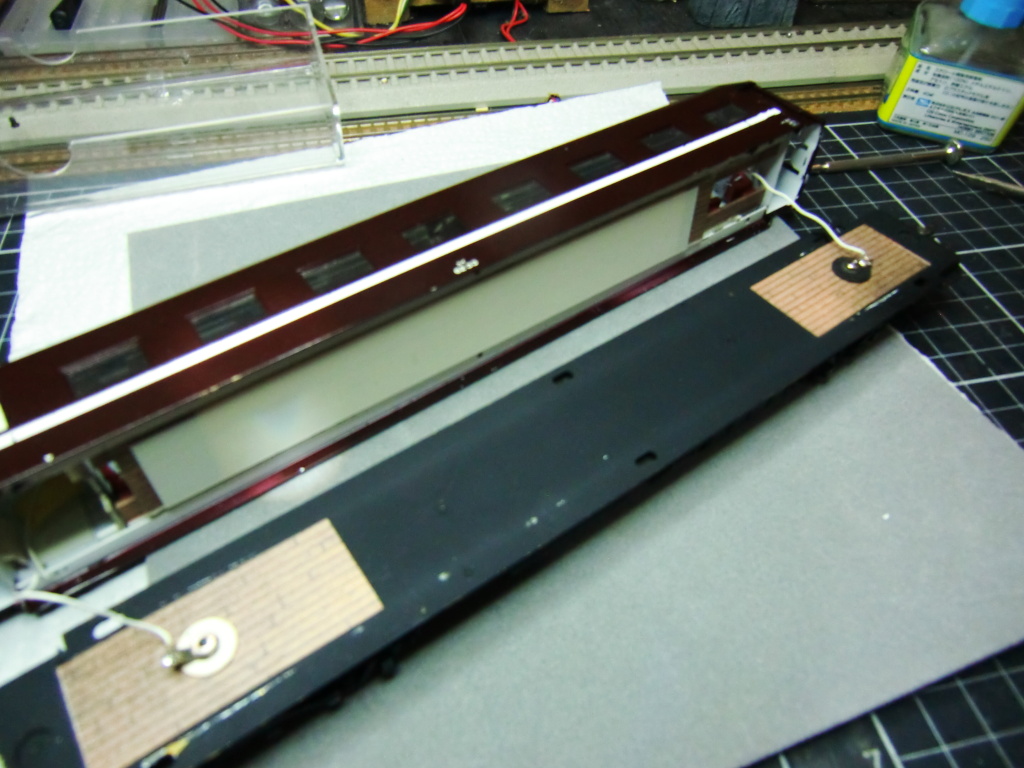
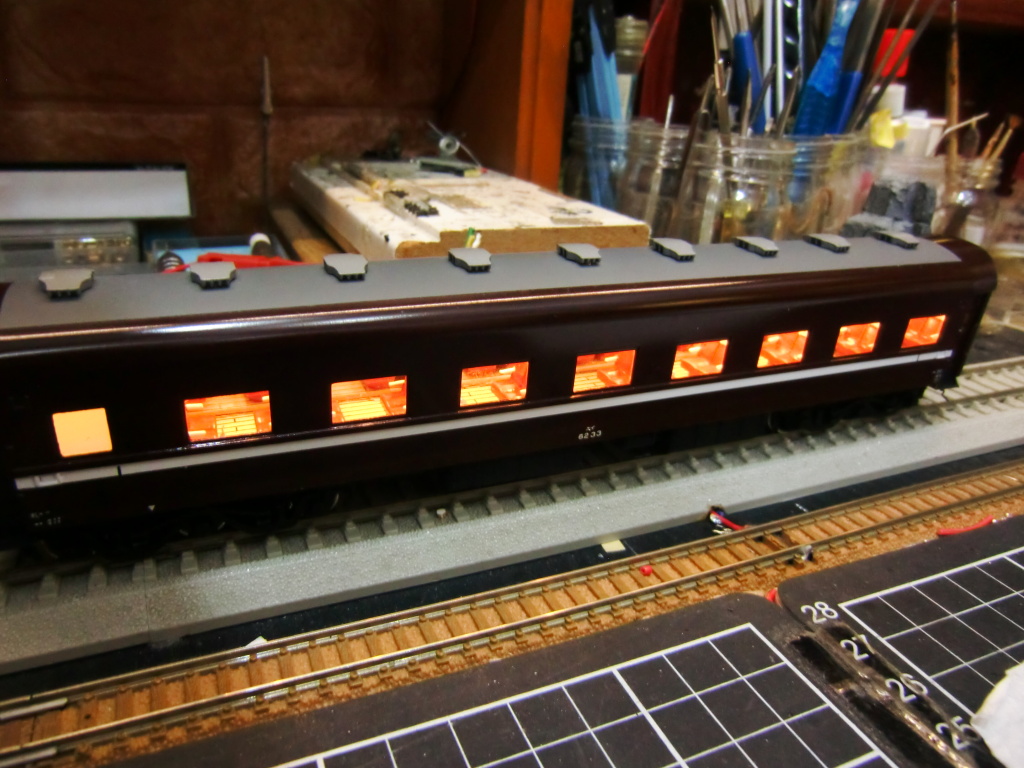

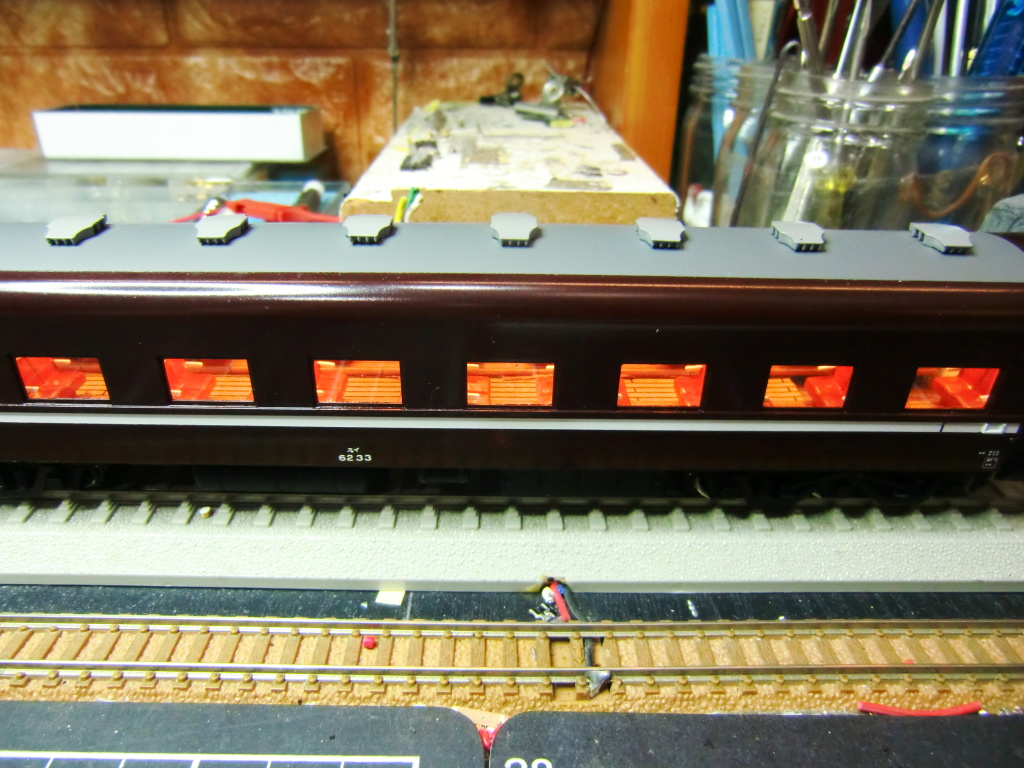

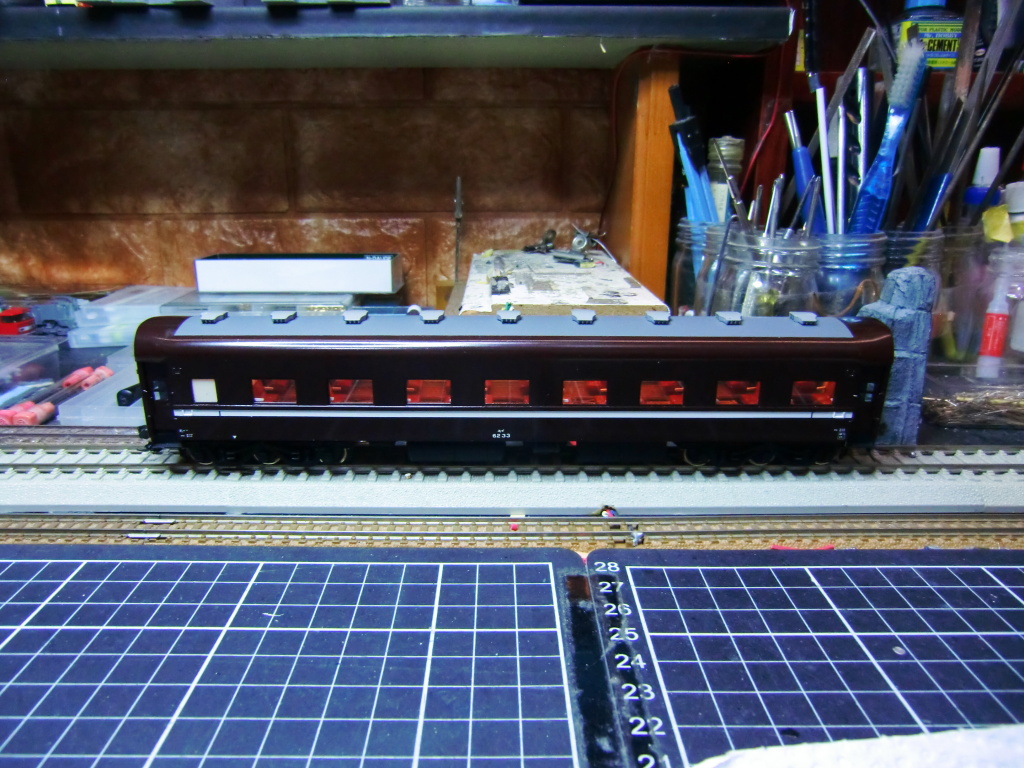
▼床下/側面の色剥げタッチアップ
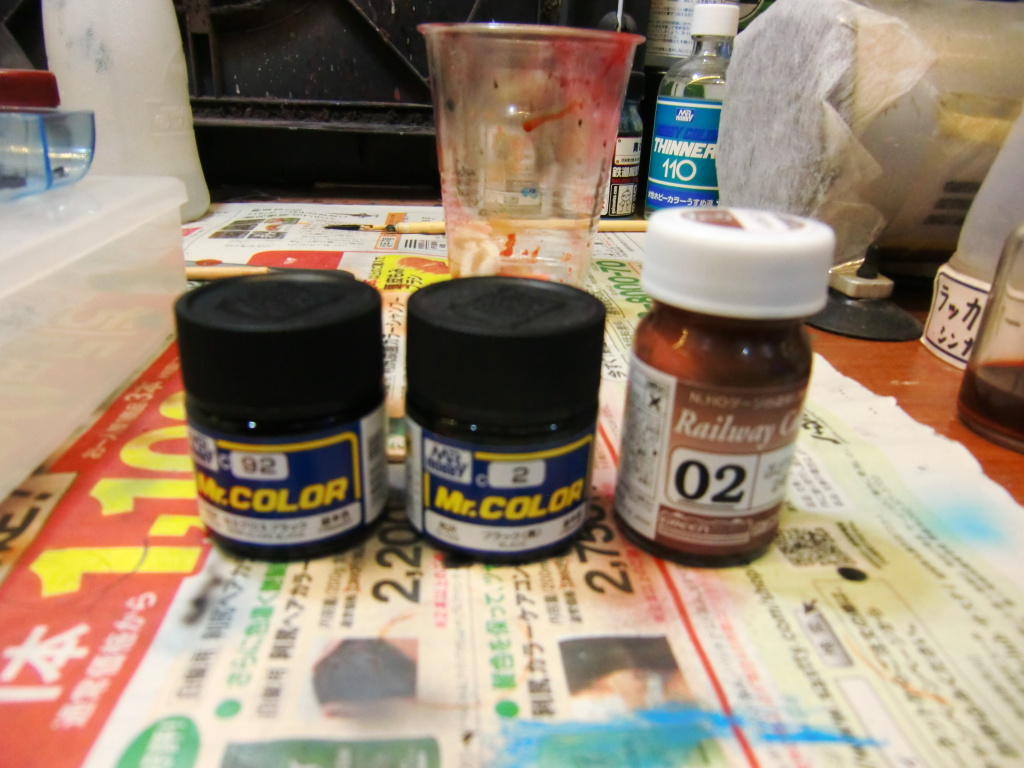

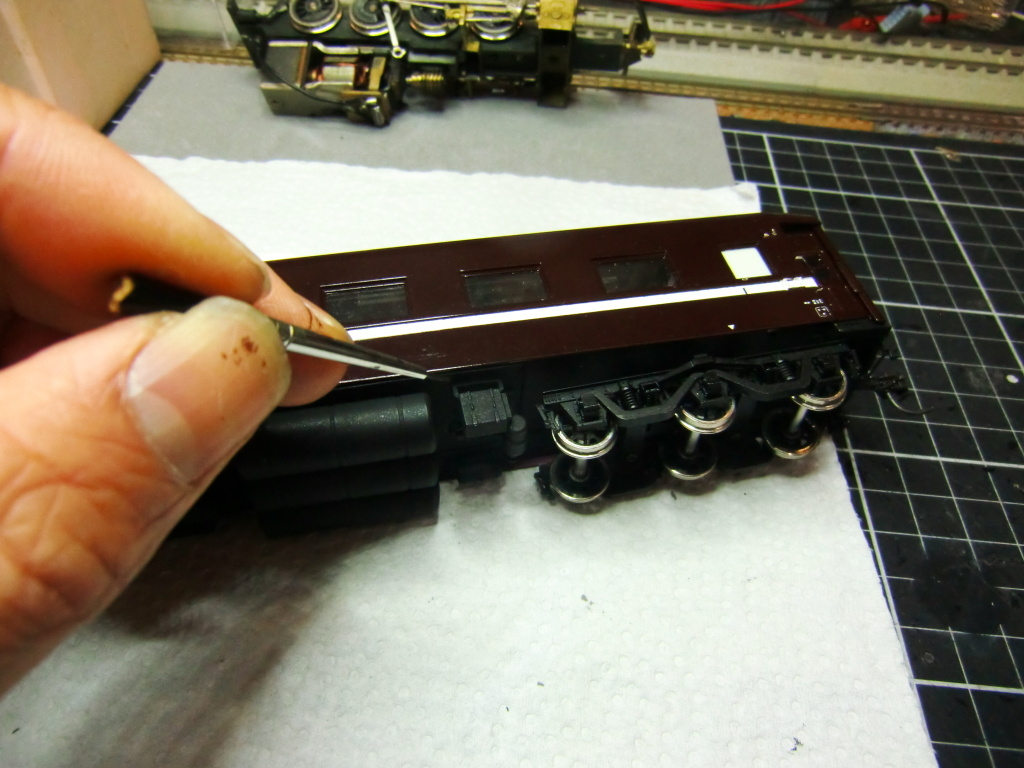


床下は「つや消し黒」で、側面は色を調合して近い色を作りタッチアップを行いました。
▼蒸気機関車79618
こちらは走行不良ということです。一番時間のかかりそうな作業を最後に持ってきました。




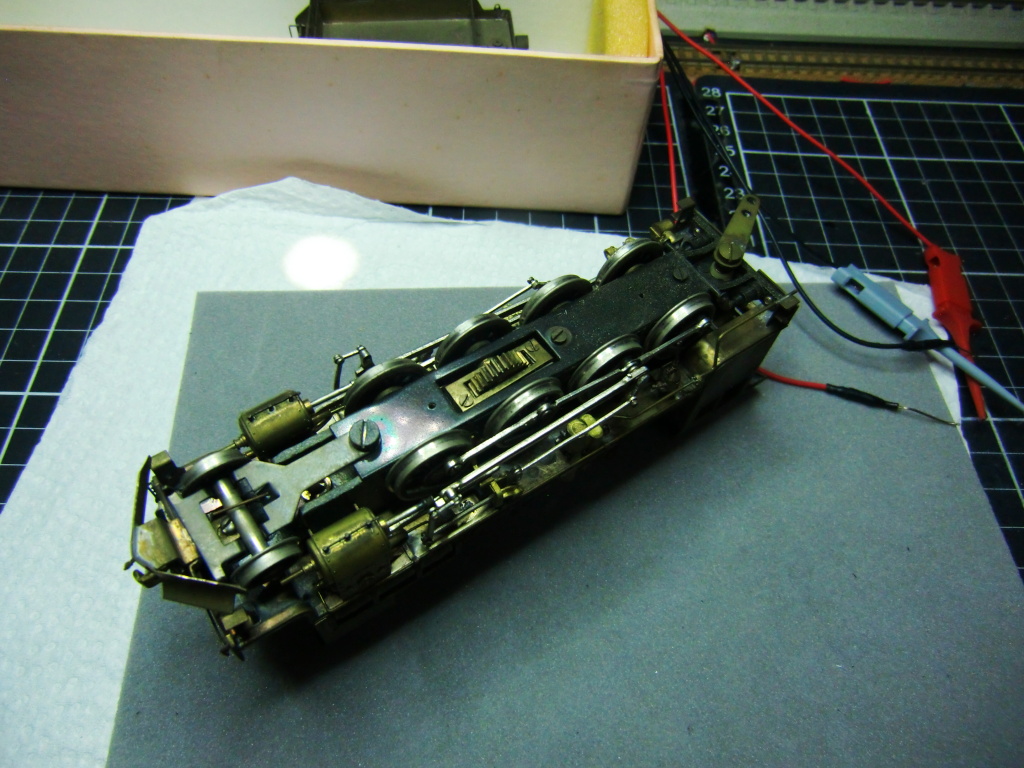
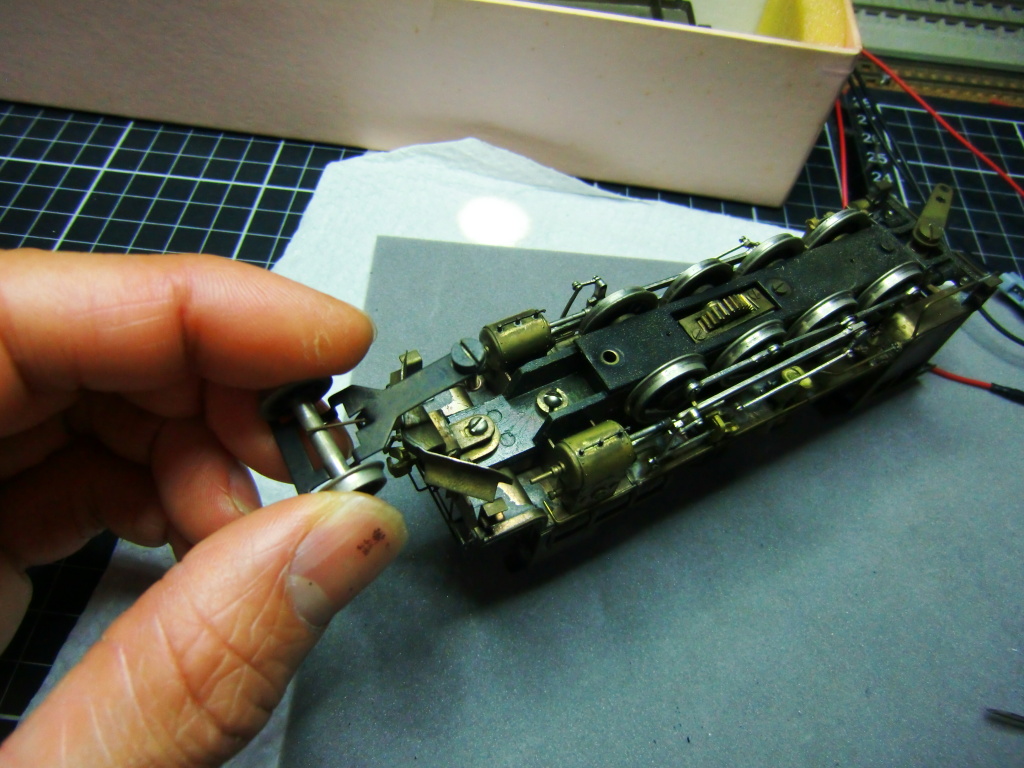
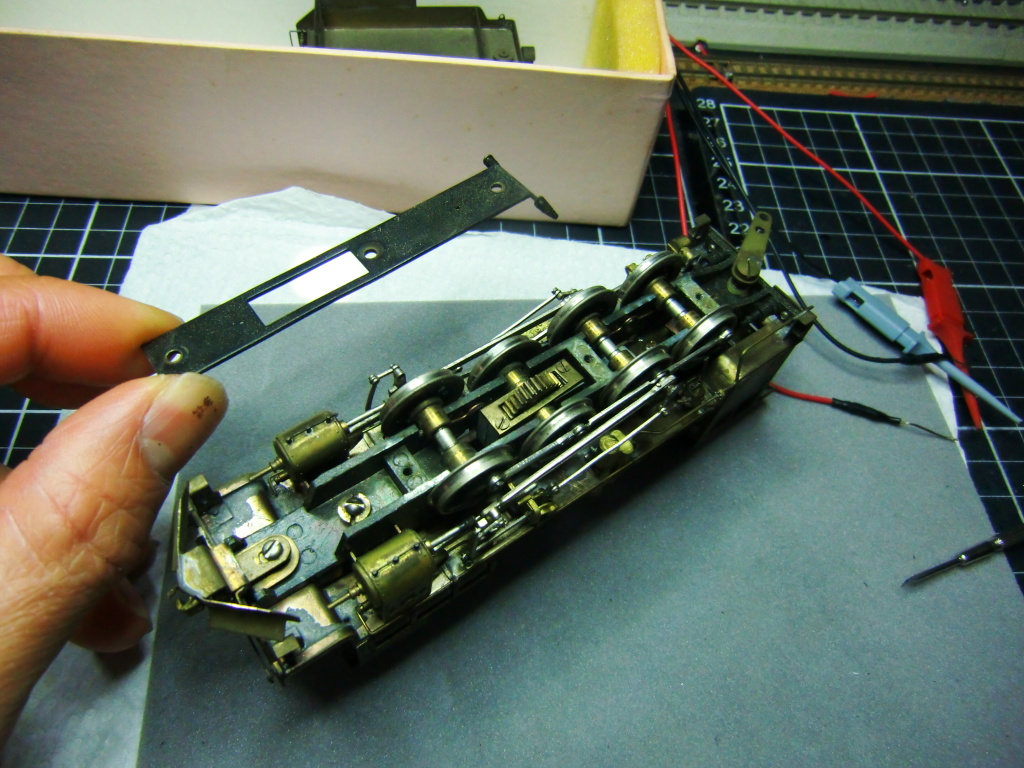
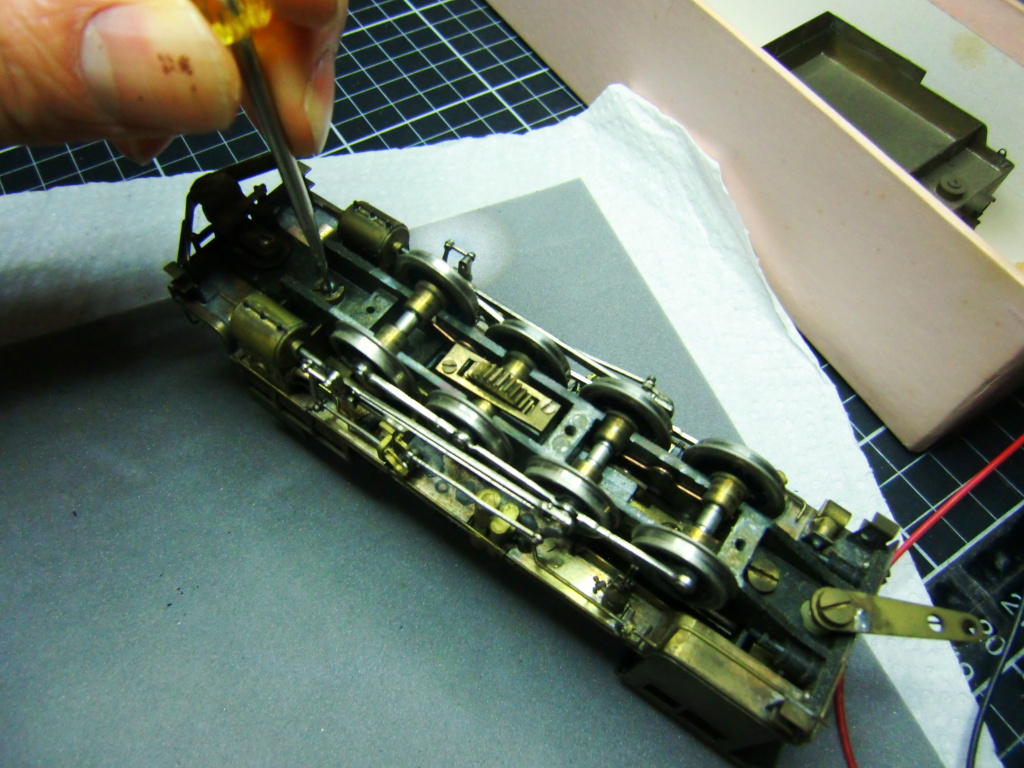
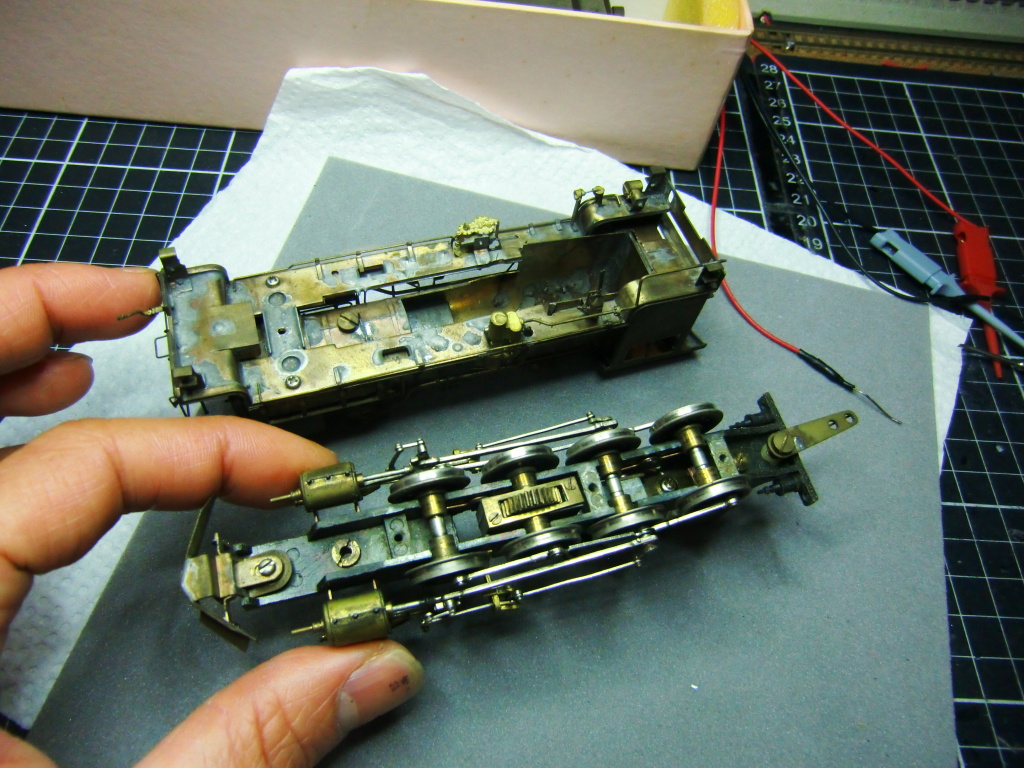
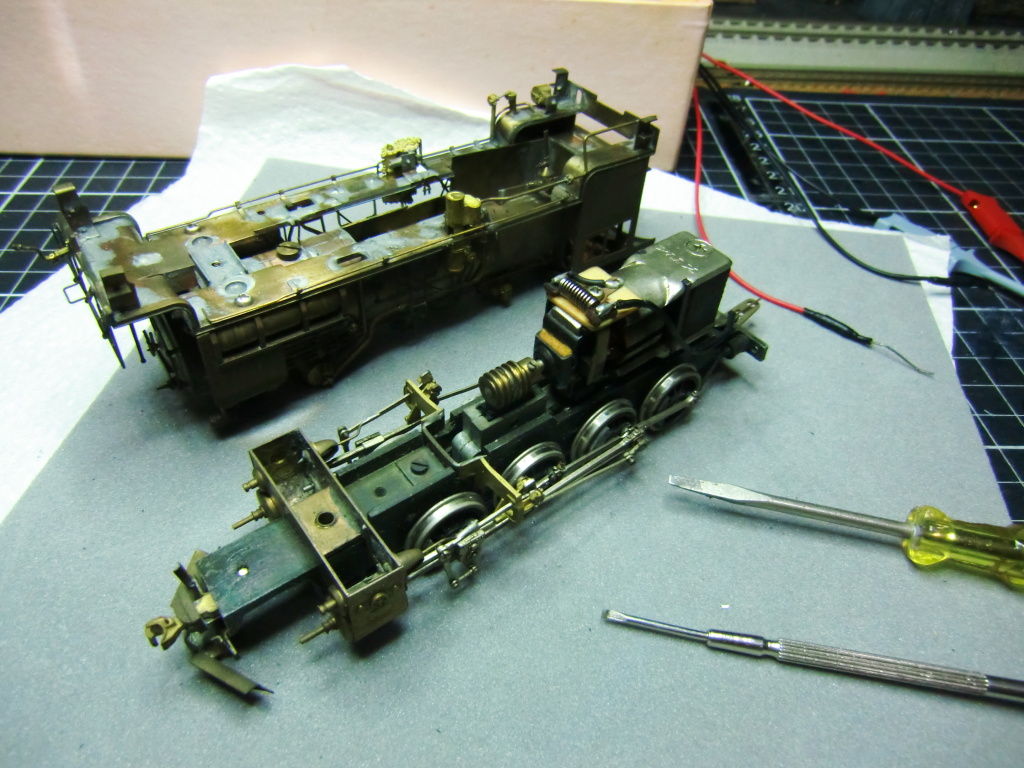
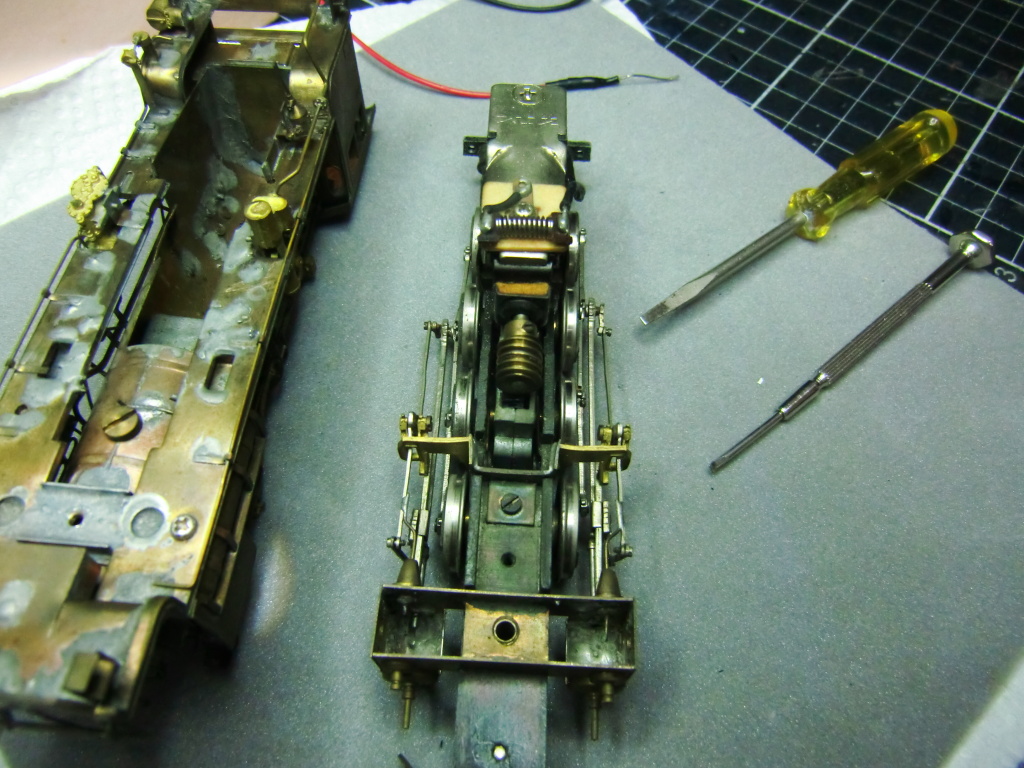
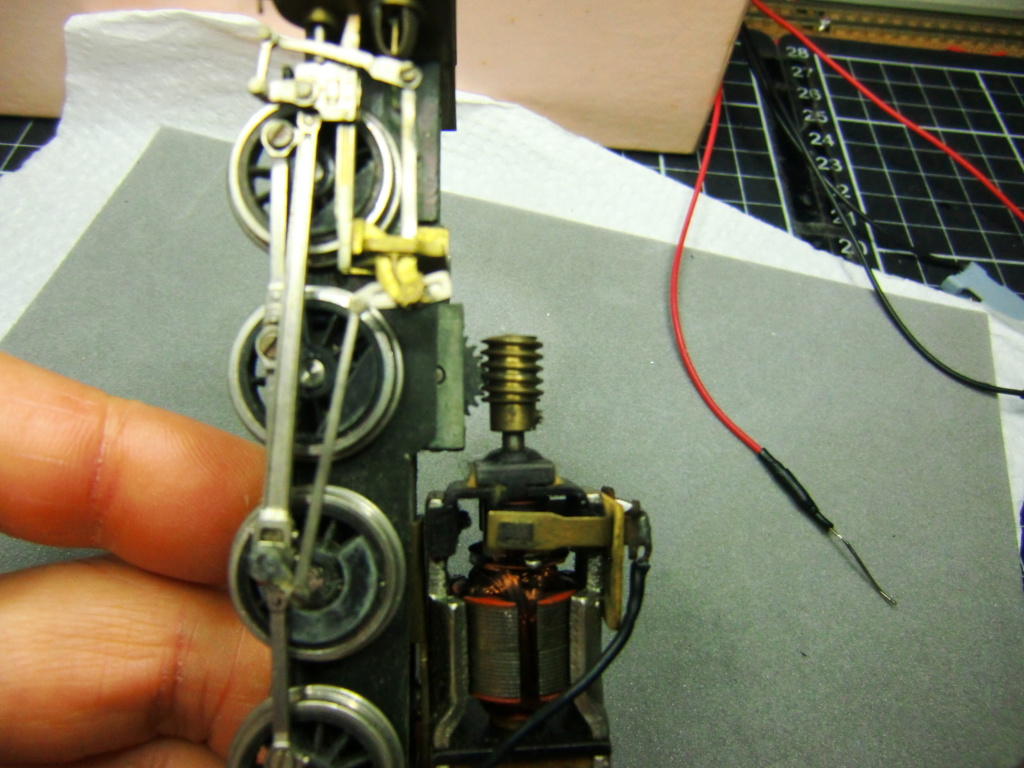
手で回転させながら空回りする原因を探っていきます。恐らくギア損傷によりピッチが異なる箇所がどこかにあると思われます。
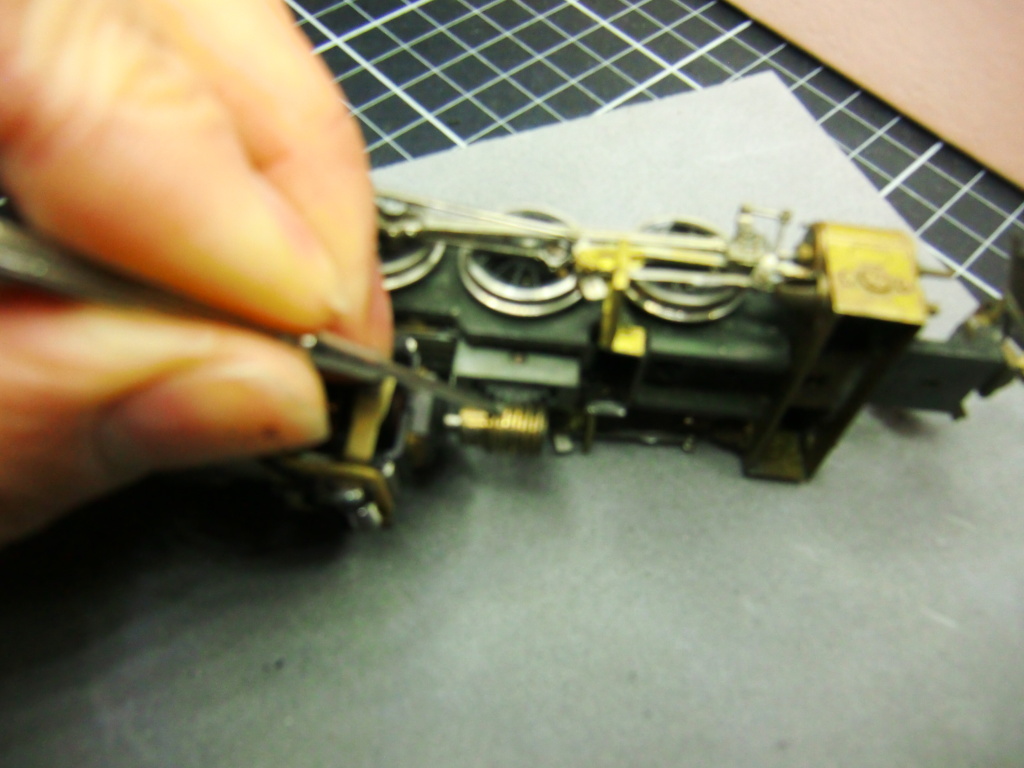
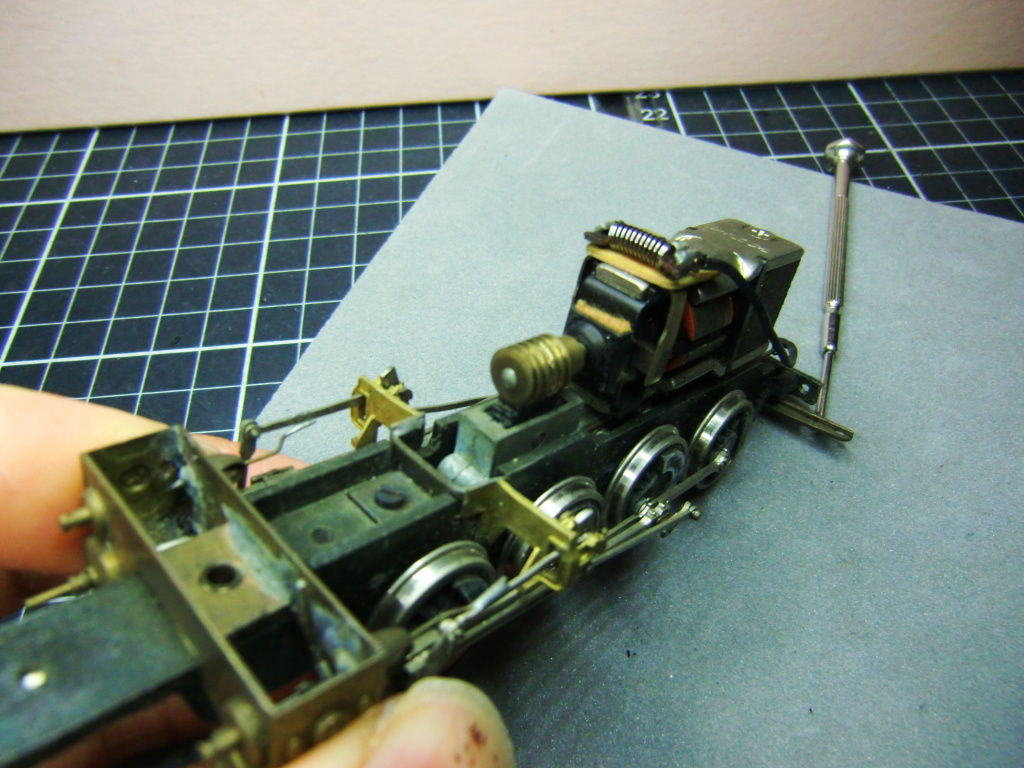
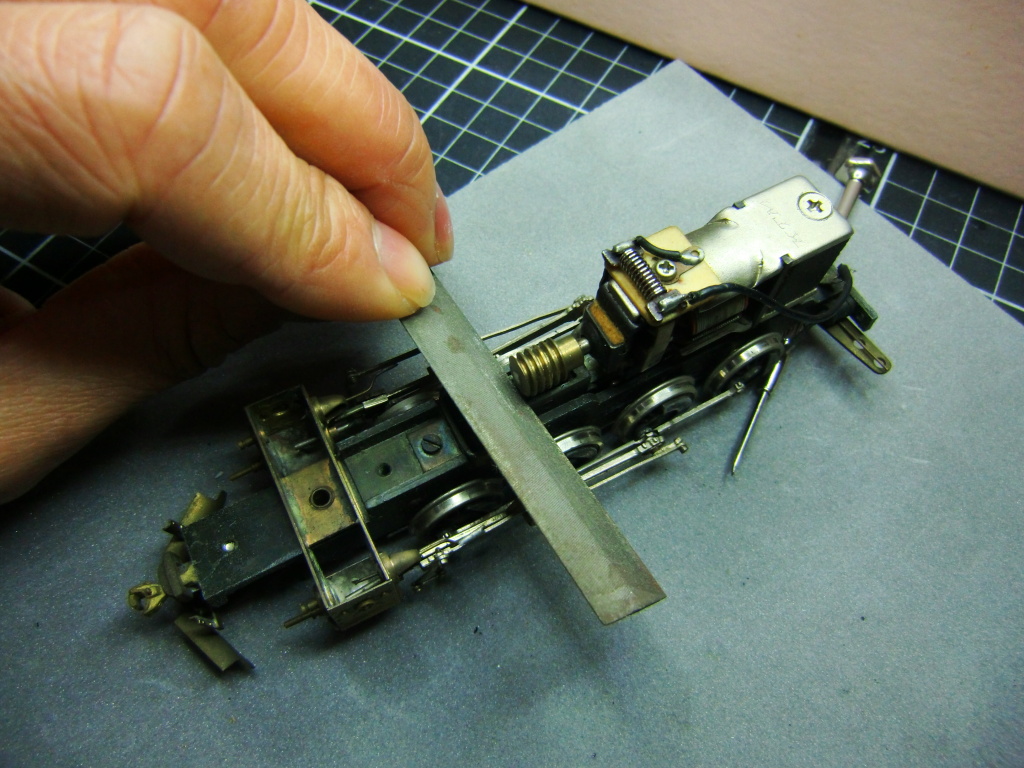
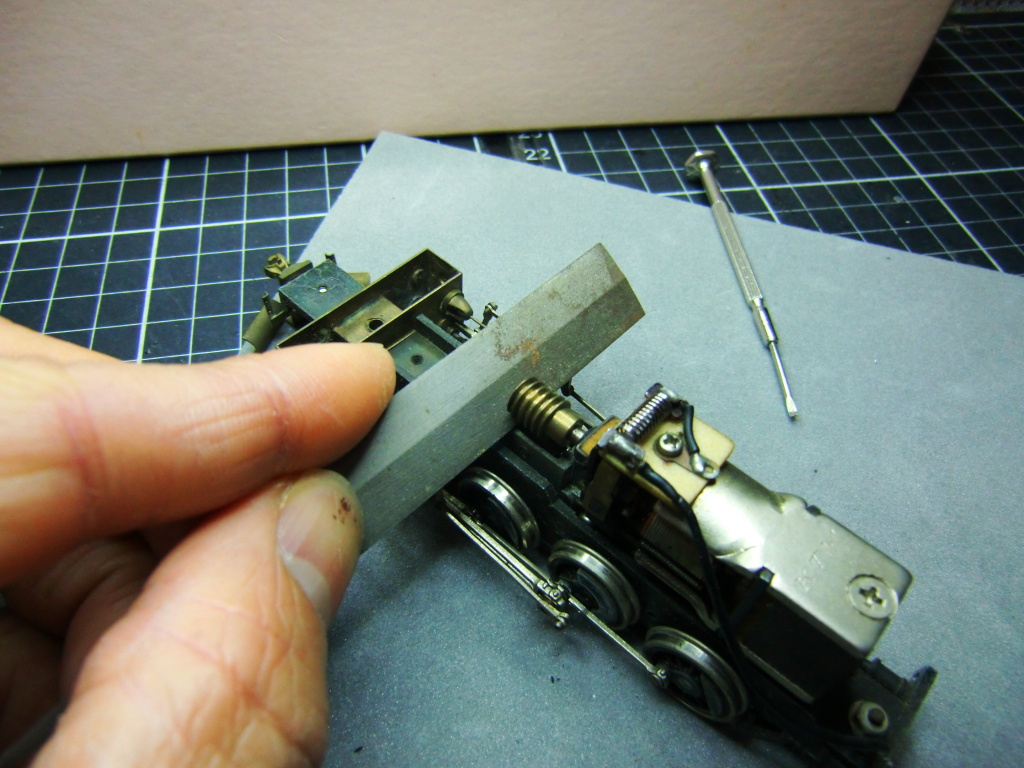
手作業で1つ1つピッチを整えていきます。
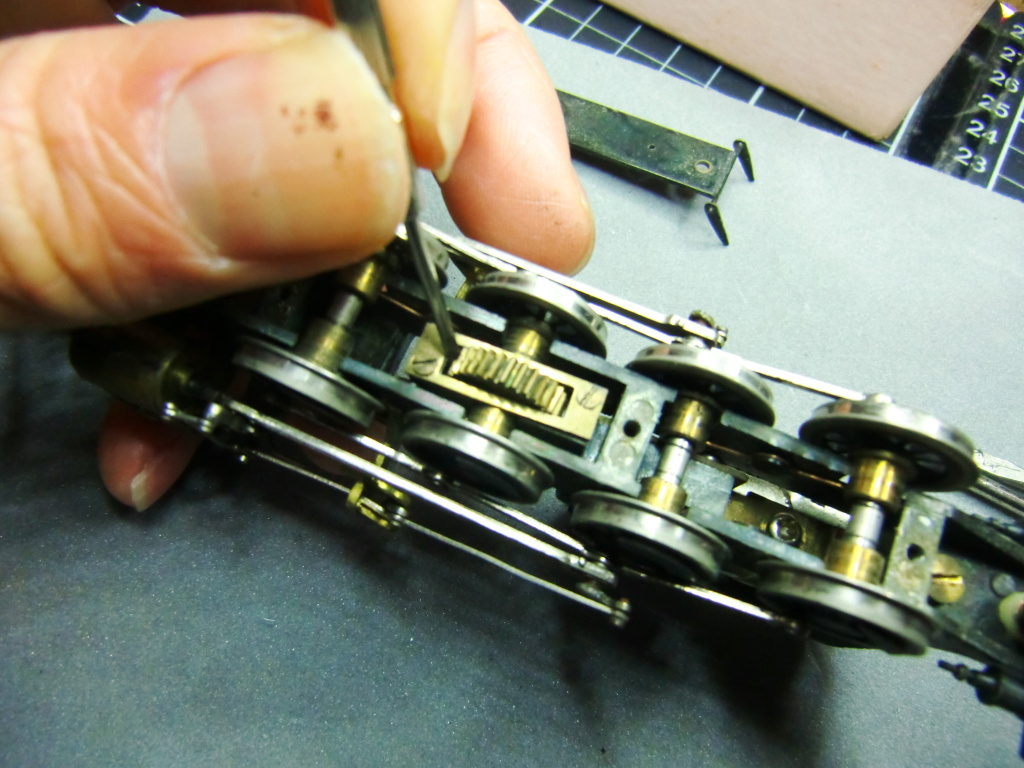
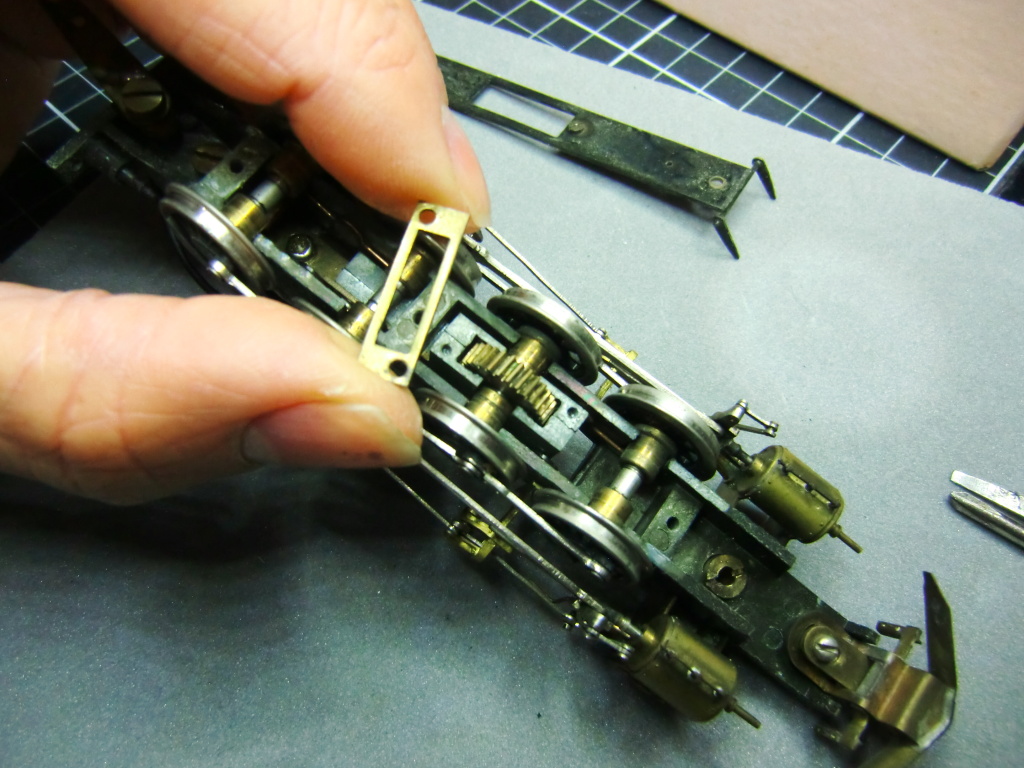
こちらのパーツの穴位置もずれてますので、穴あけしなおして位置を整えます。
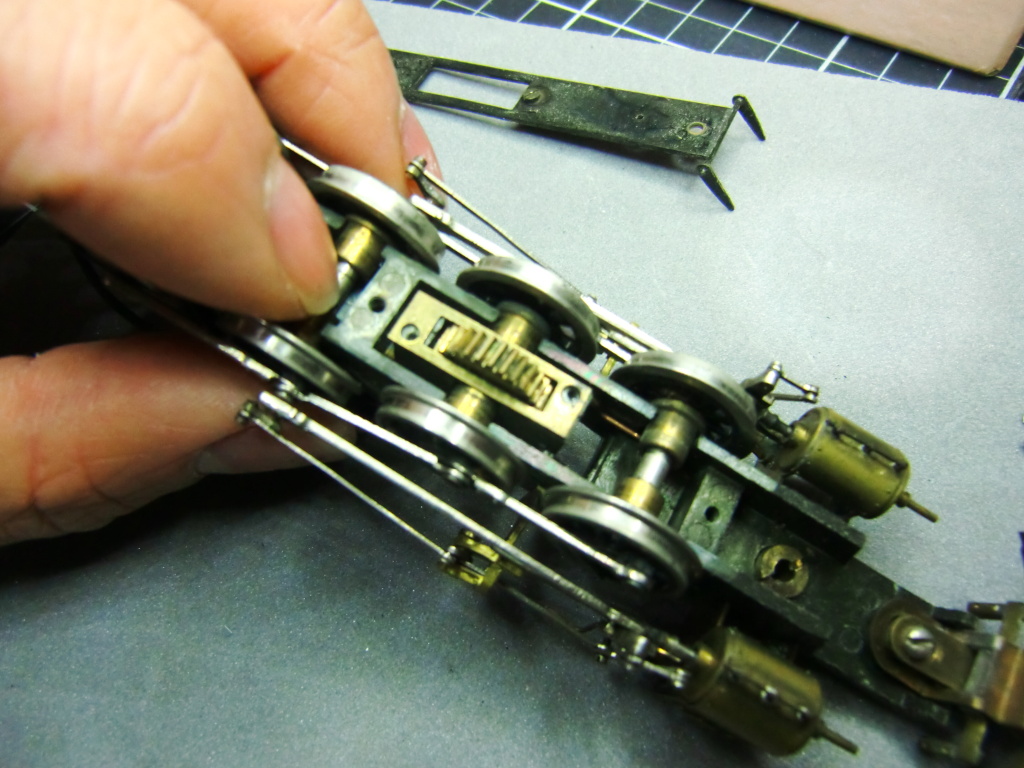
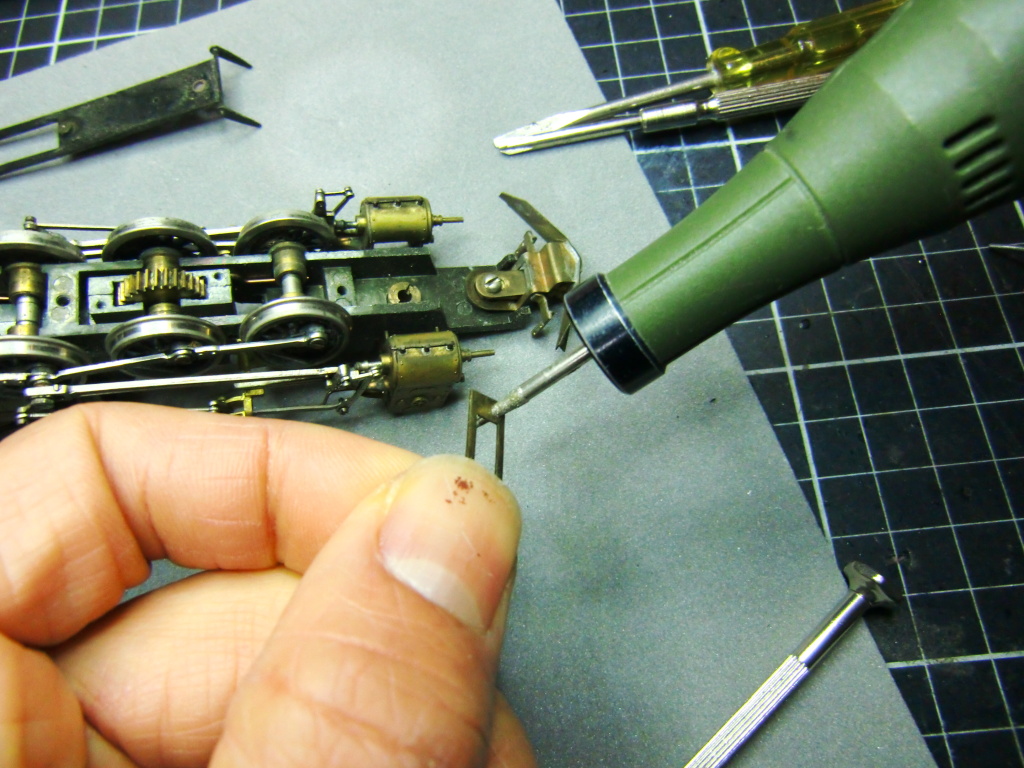
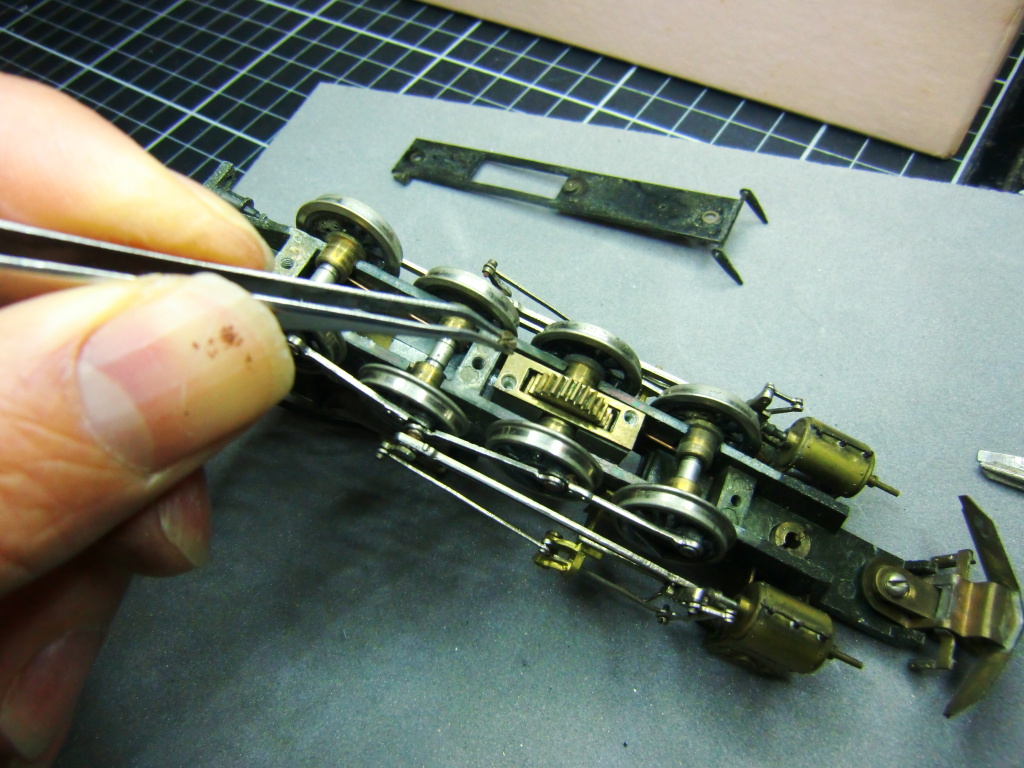
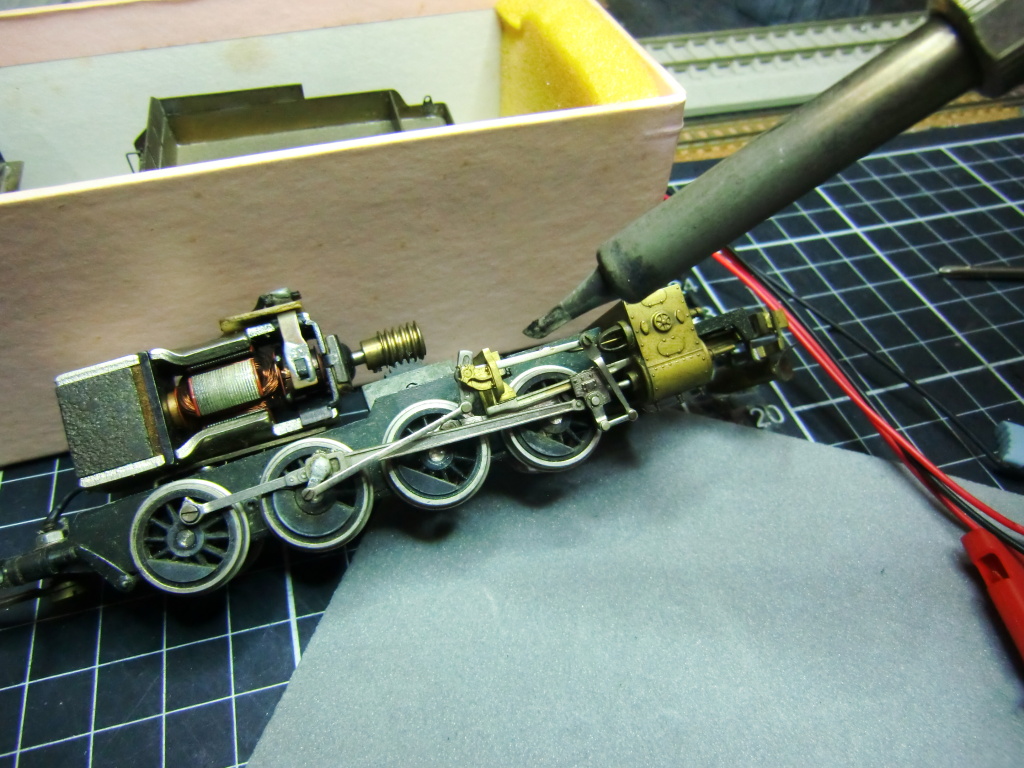
片側のピンのハンダが外れていますので、固定しなおします。
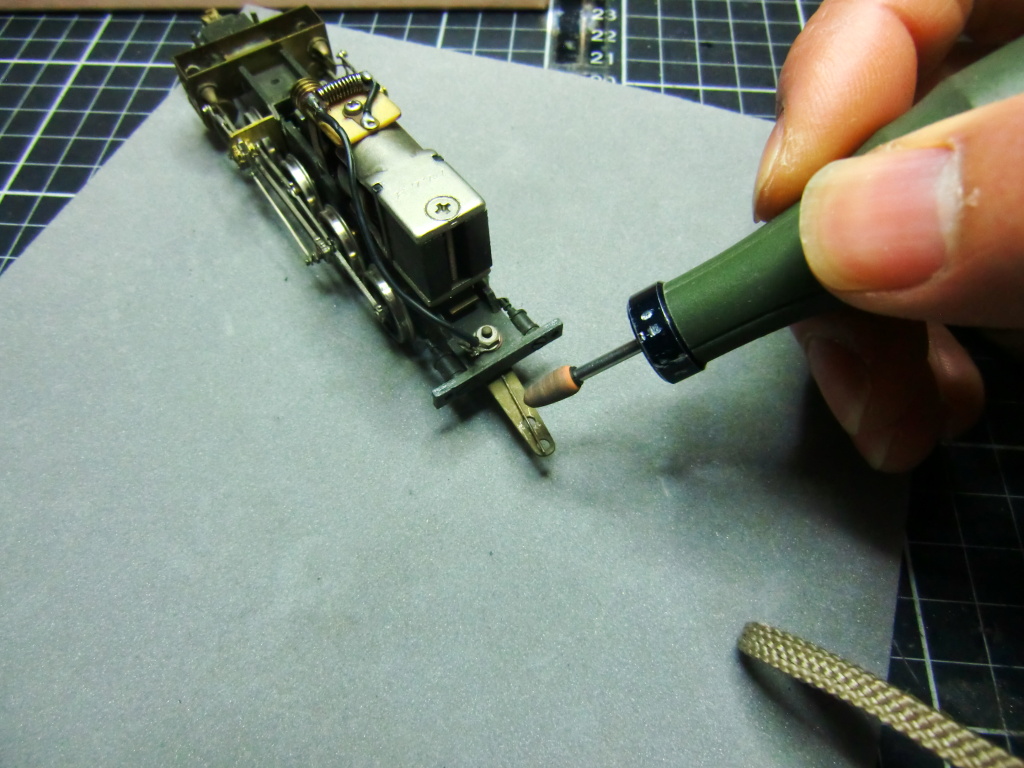
集電部分を磨き出していきます。
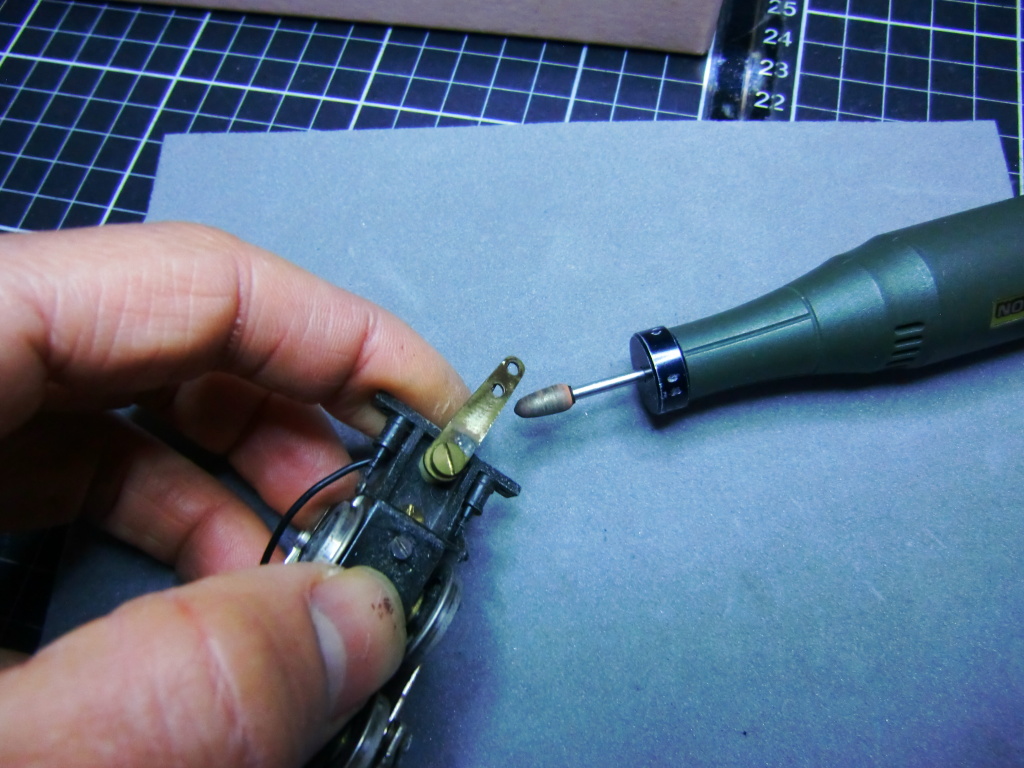
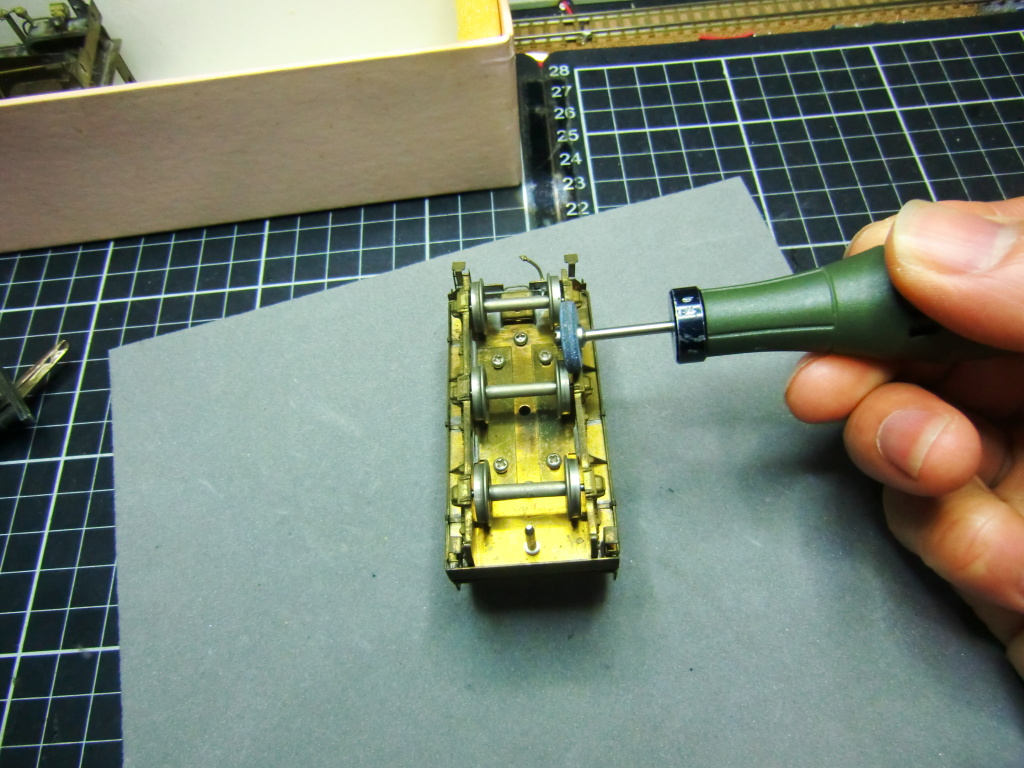
テンダーも車輪と集電棒を磨き出してピカピカにします。
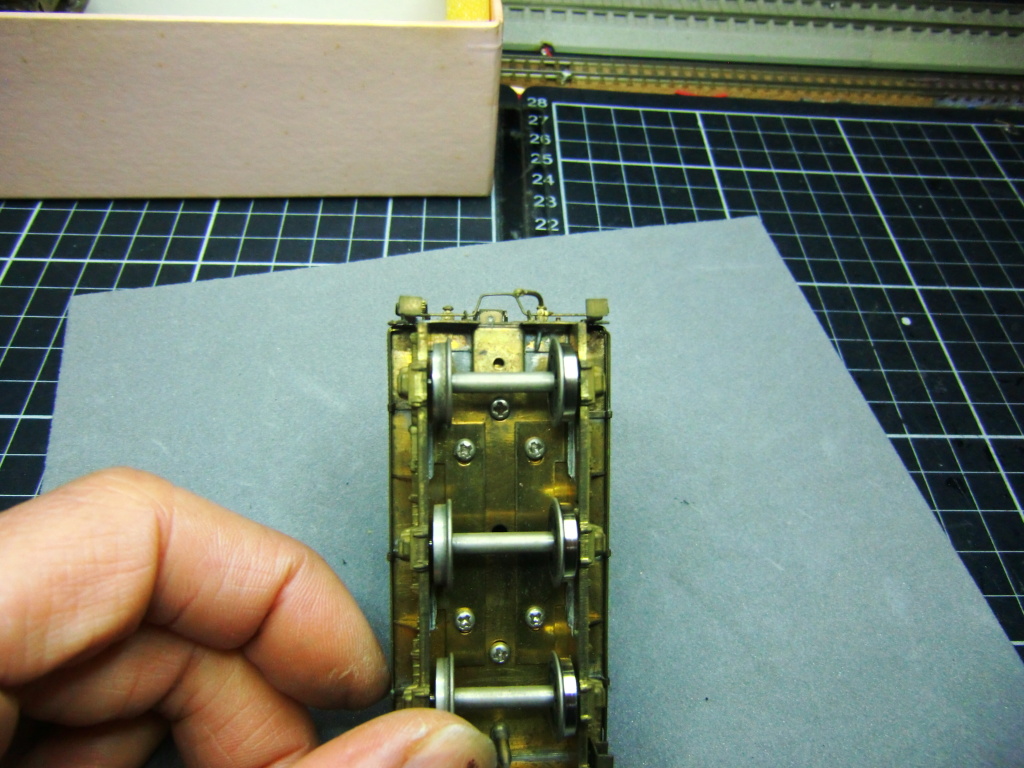
左が磨き出し前、右が磨き出し後です。
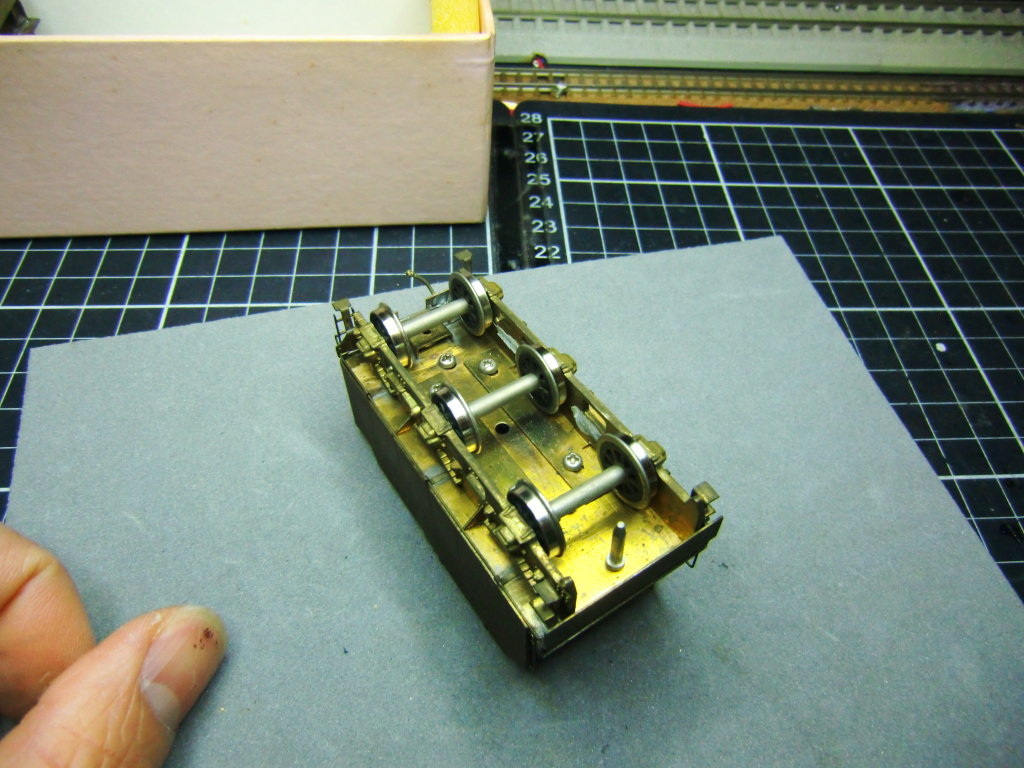
車輪本来の光沢を取り戻しました。
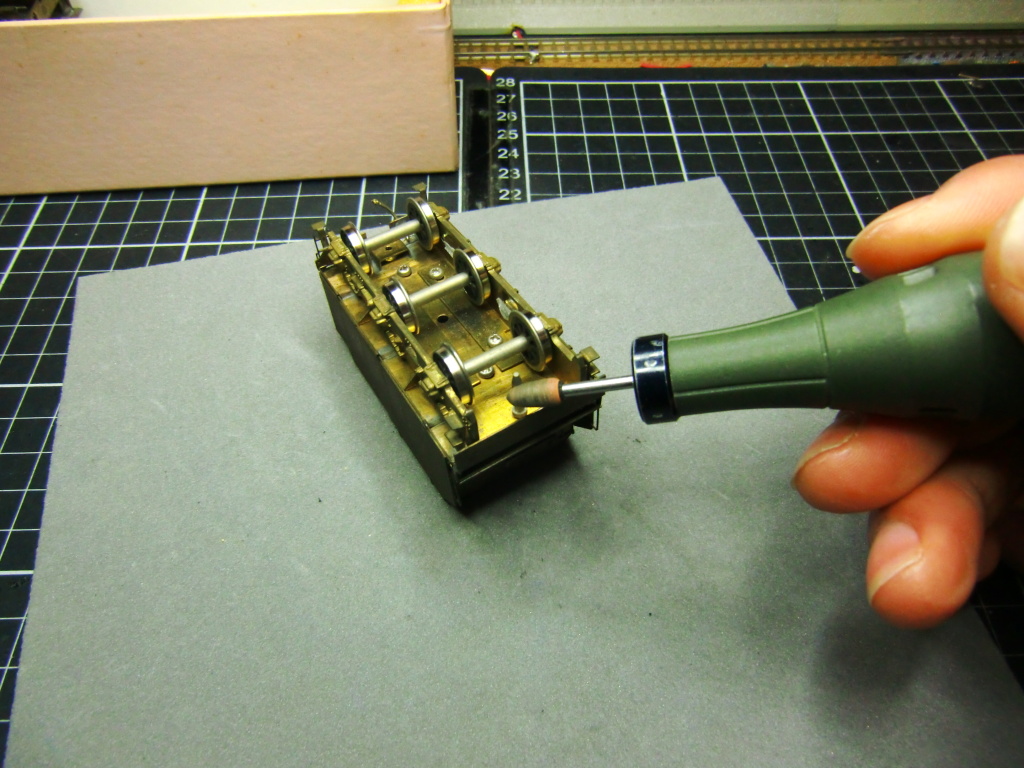
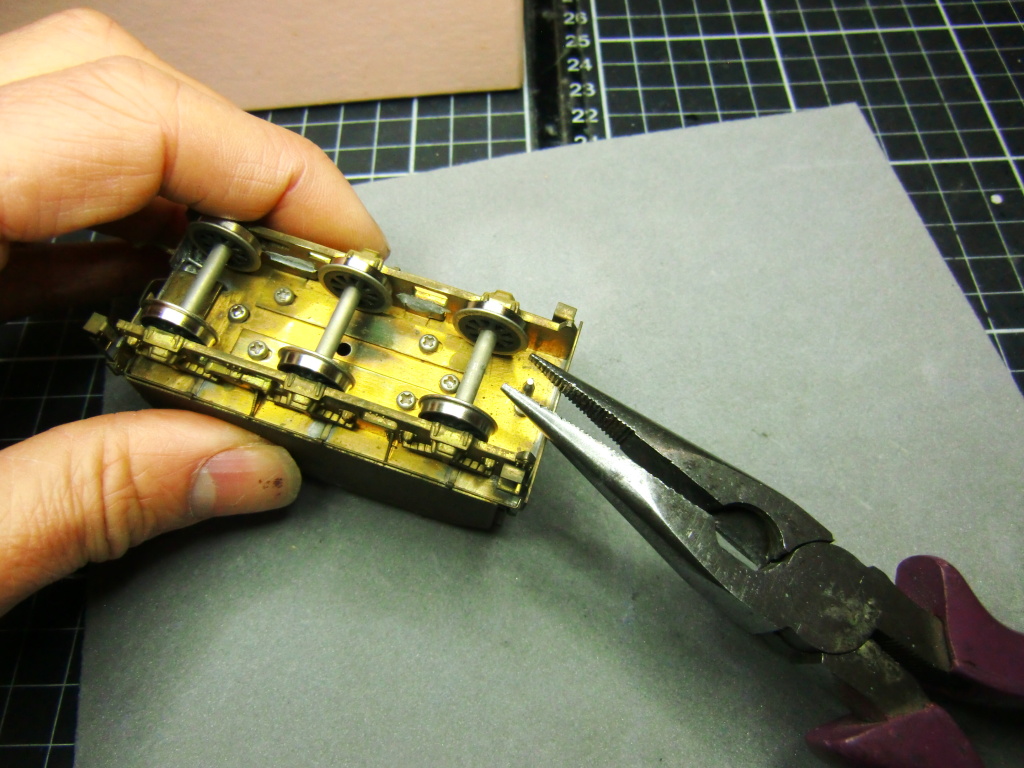
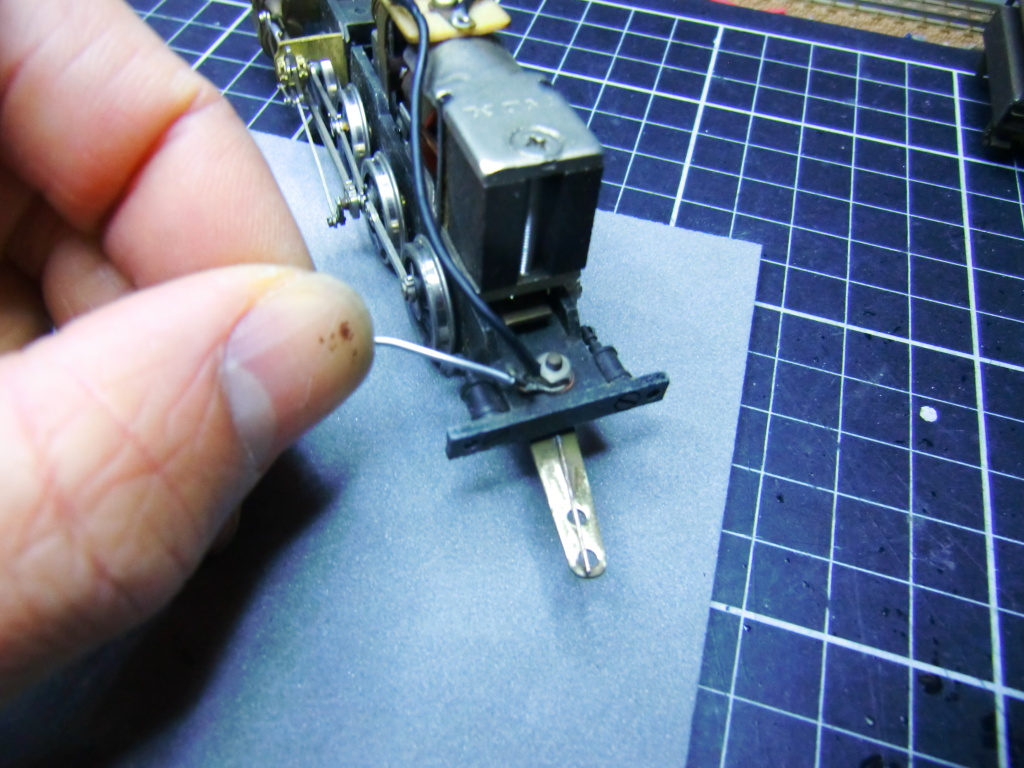
機関車側の配線もハンダしなおします。
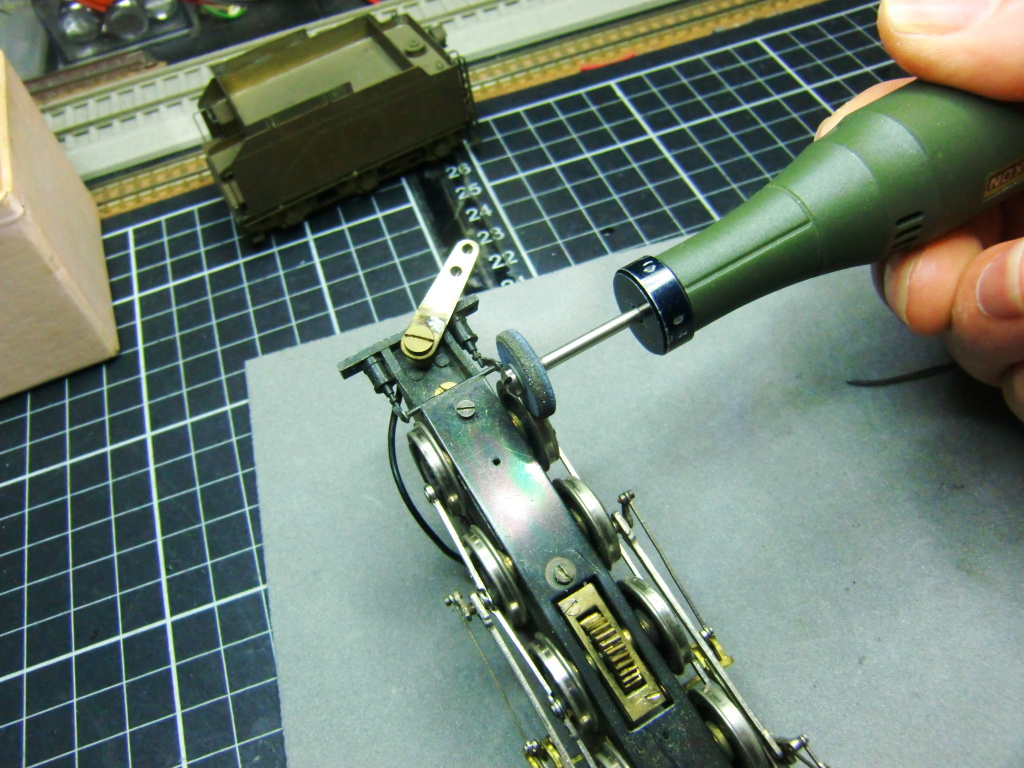
機関車も車輪を磨き出していきます。
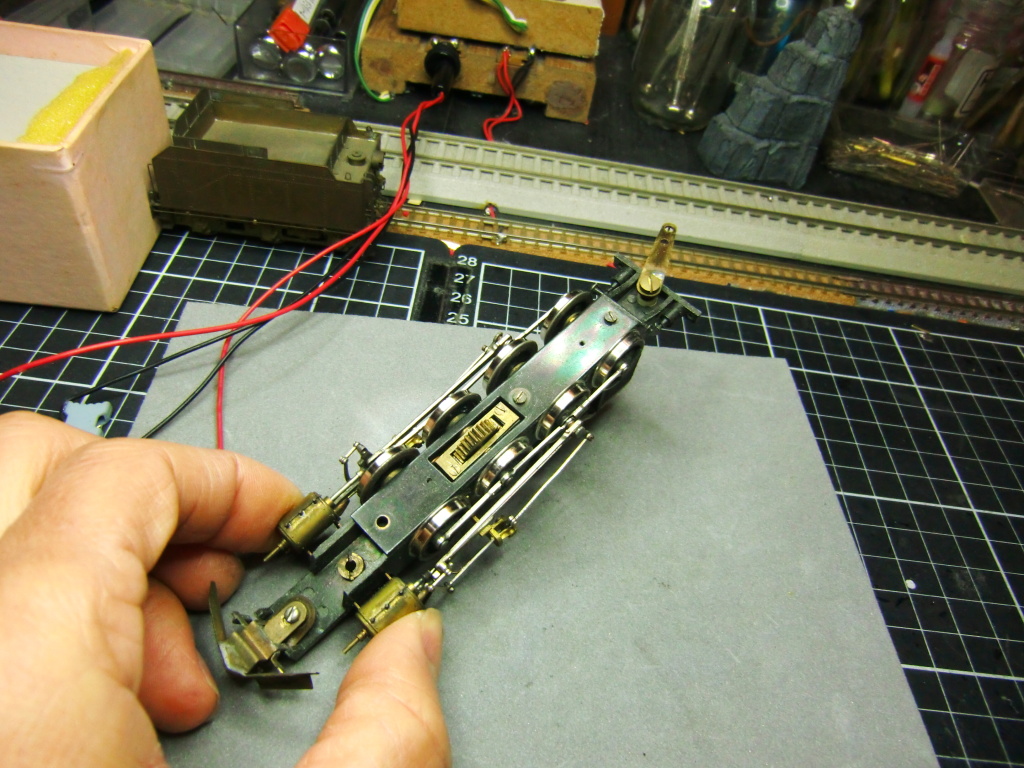
光沢感が蘇りました。
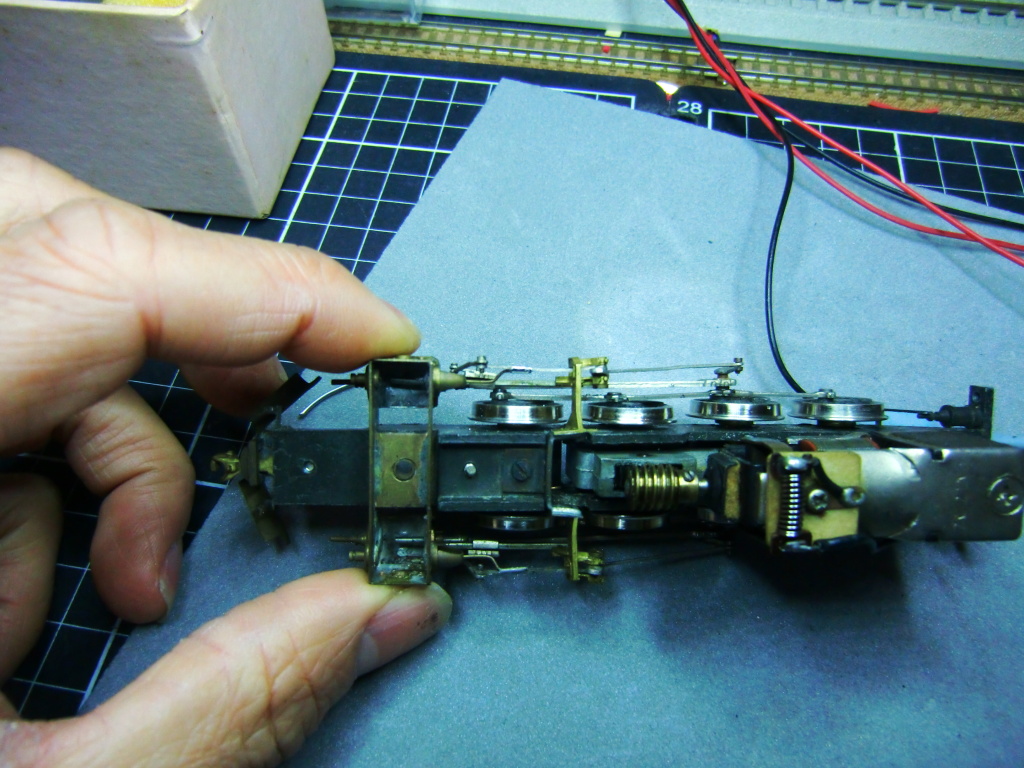
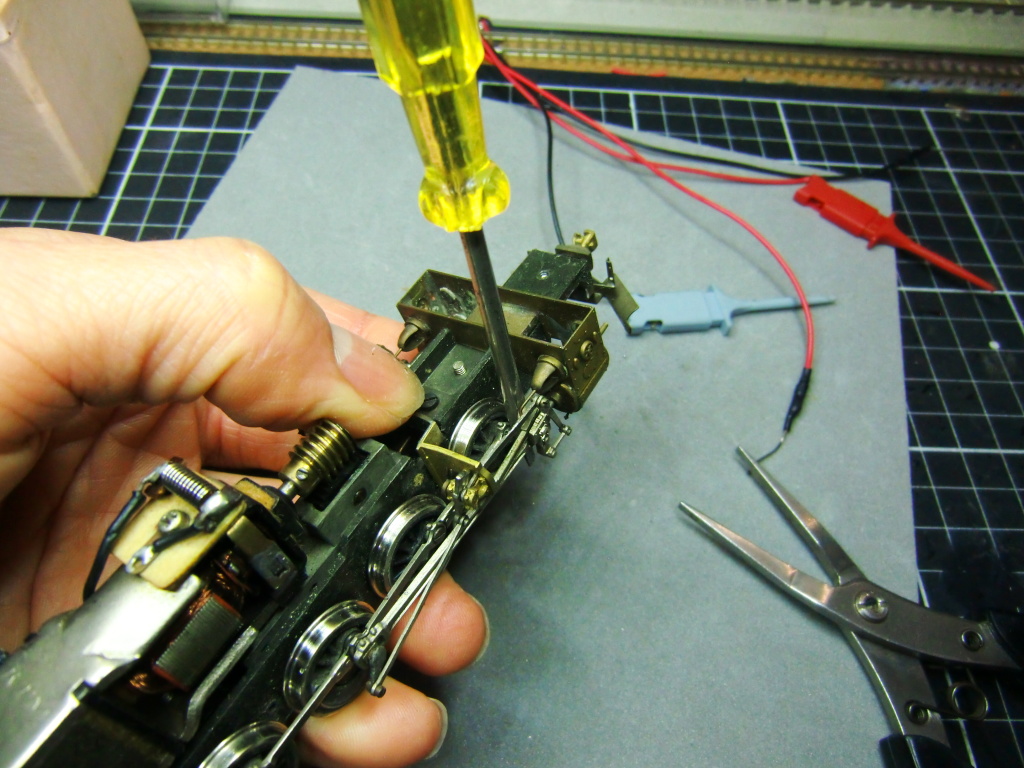
続いて歪んでいる部品を1つ1つ正常な位置に戻していきます。
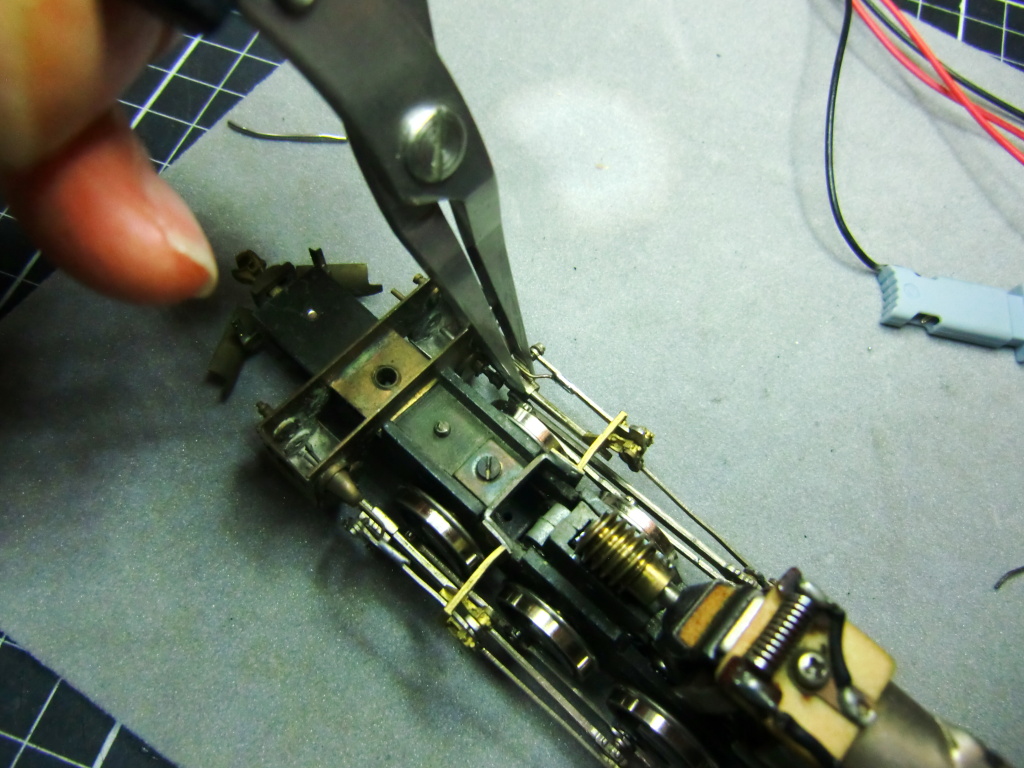
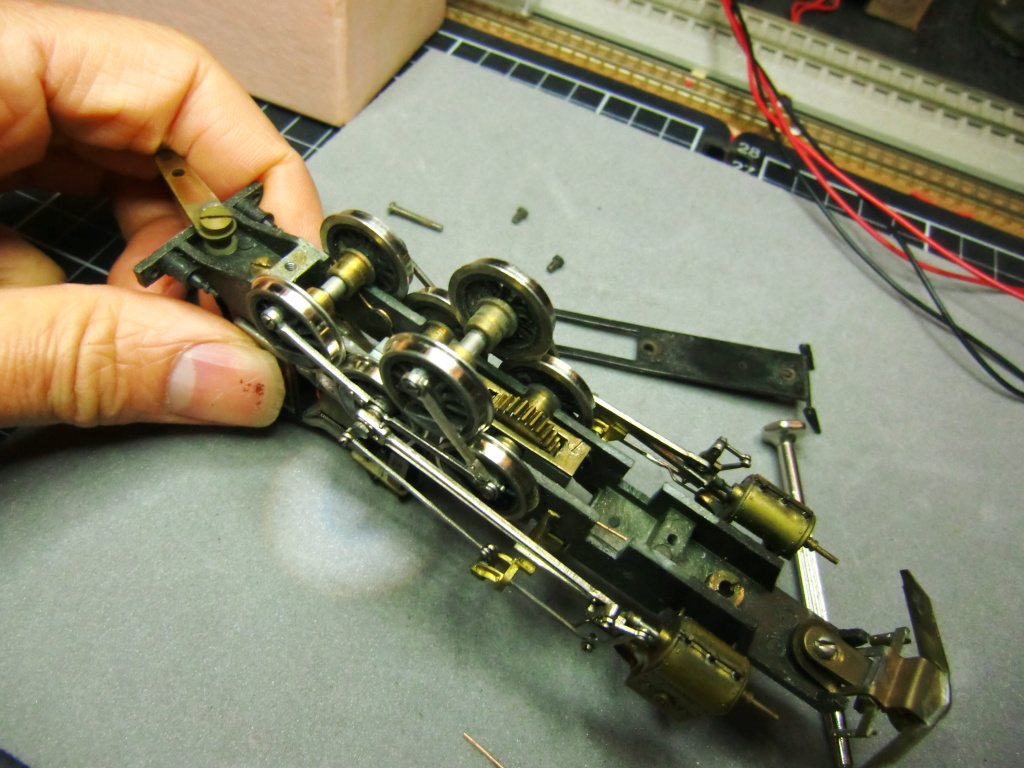
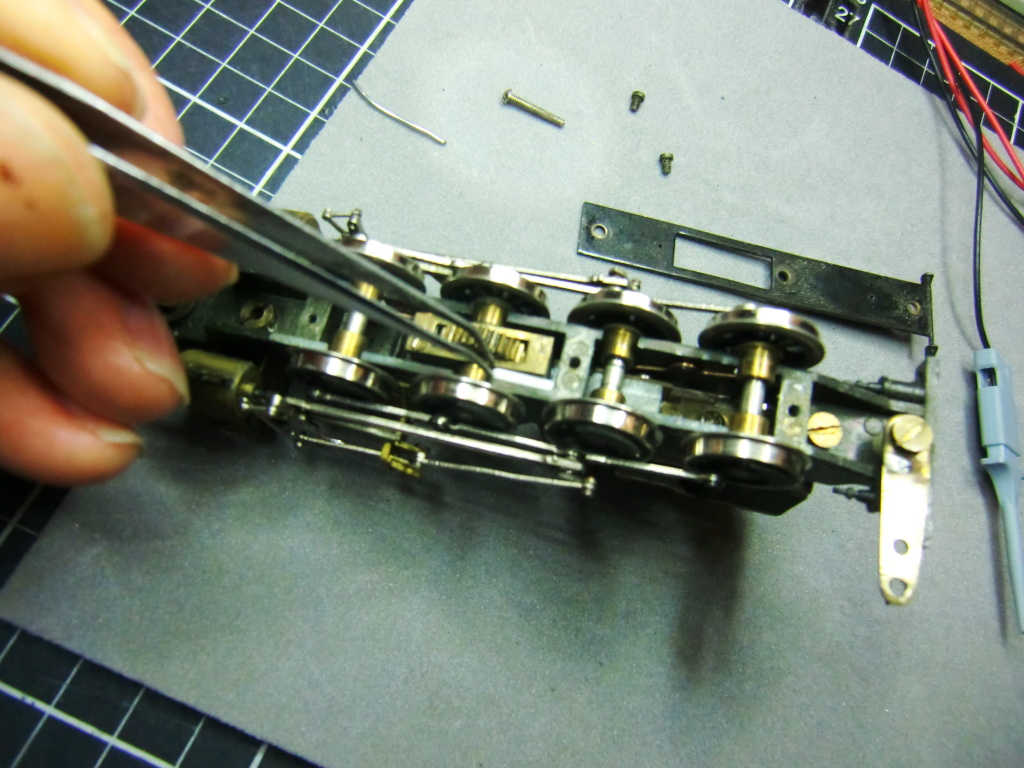
1.2mmのプラバンを加工して、ギアユニットの両サイドにそれぞれ埋め込みます。これによりぐらつきを押さえます。
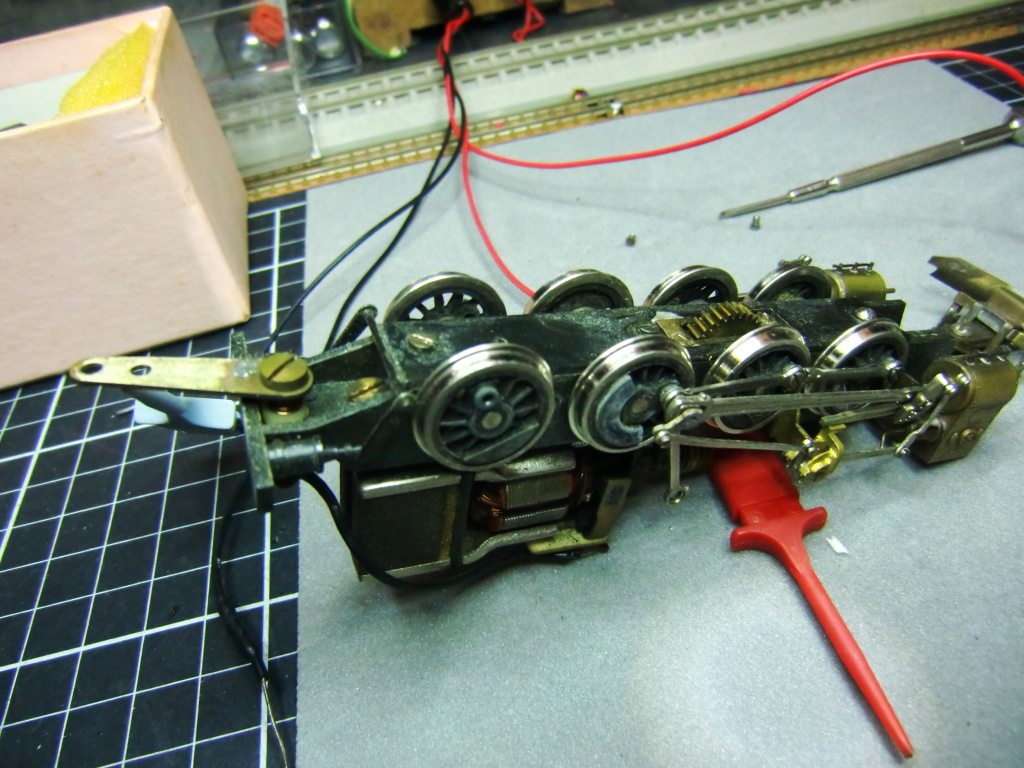
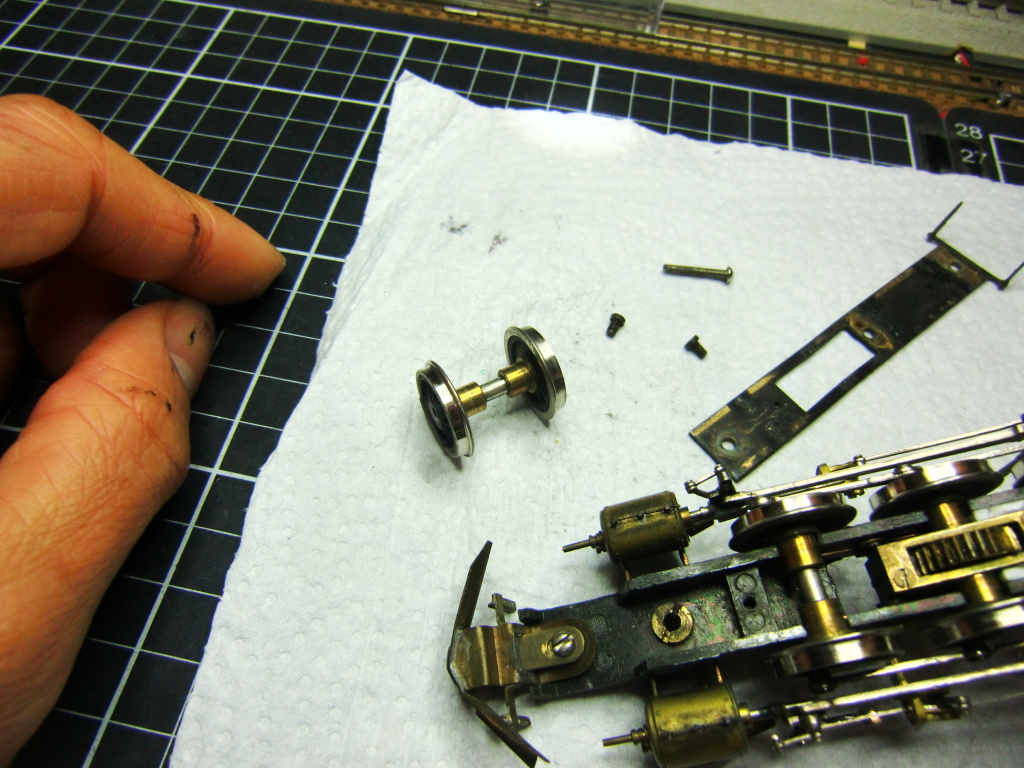
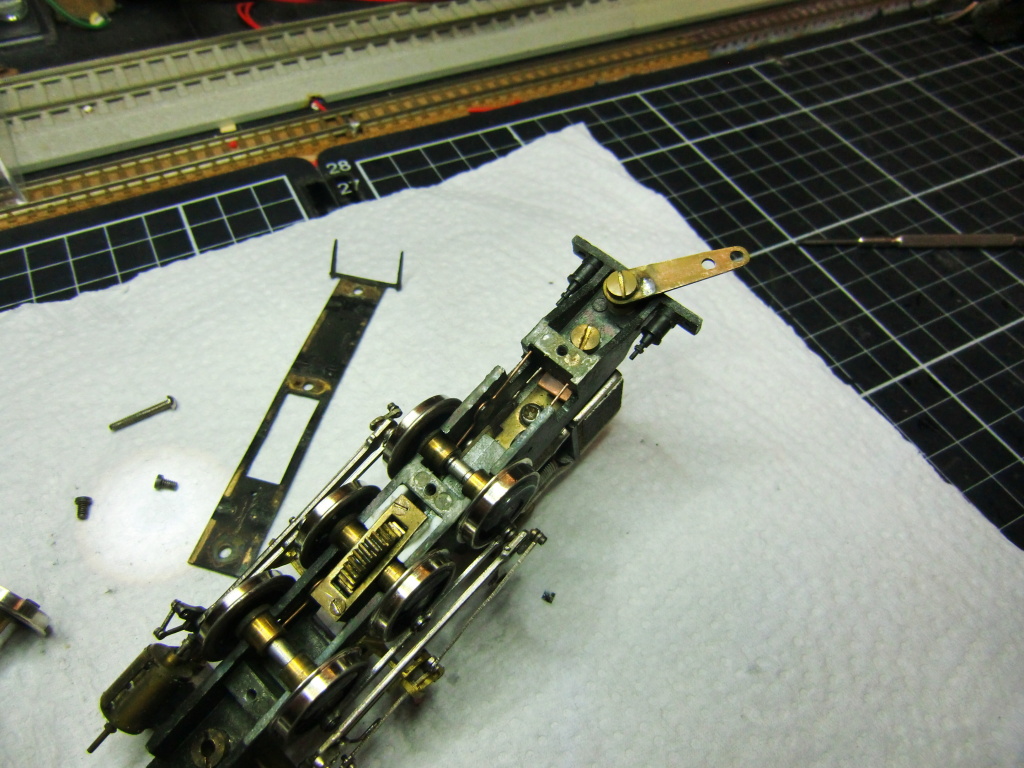
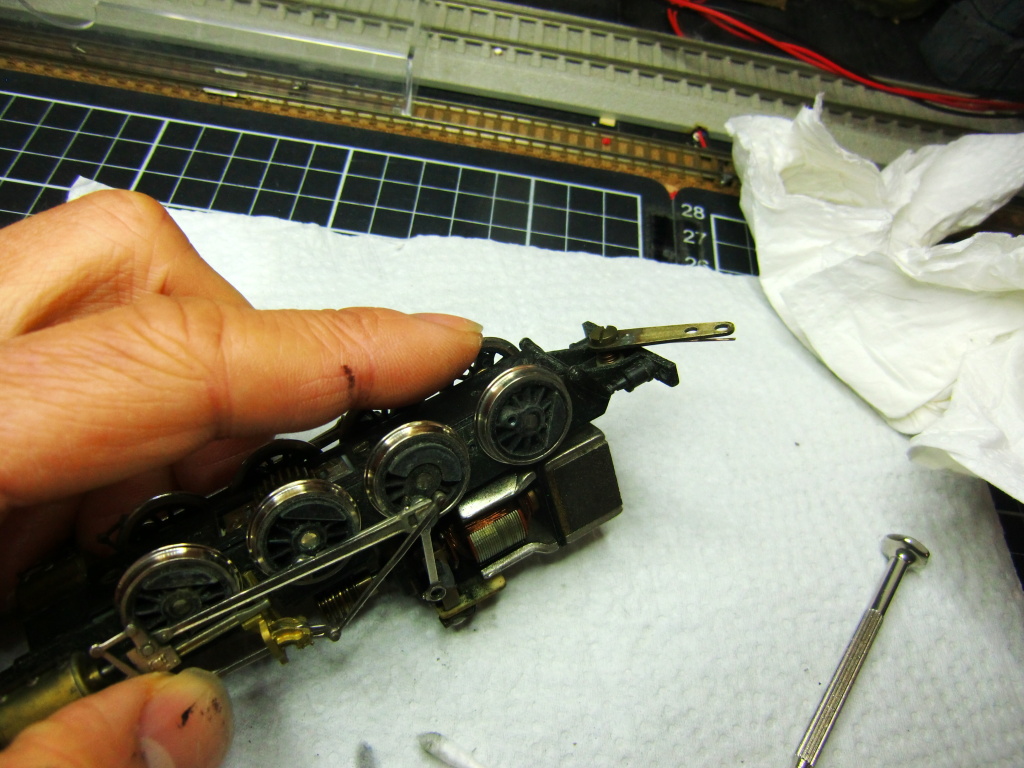
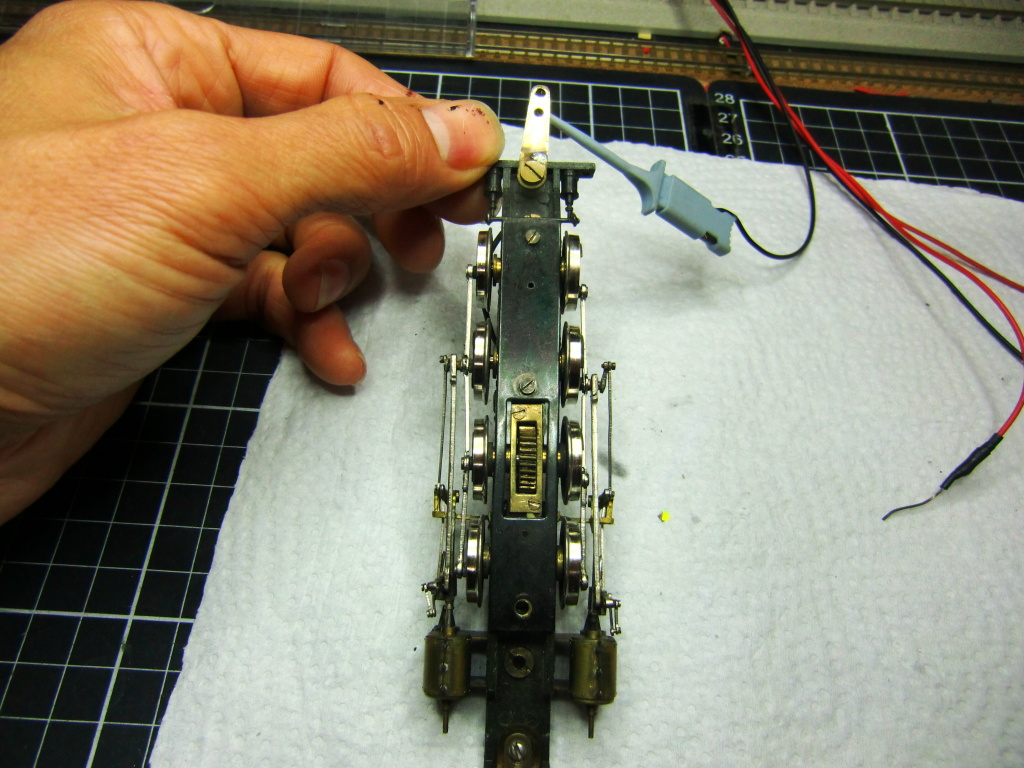
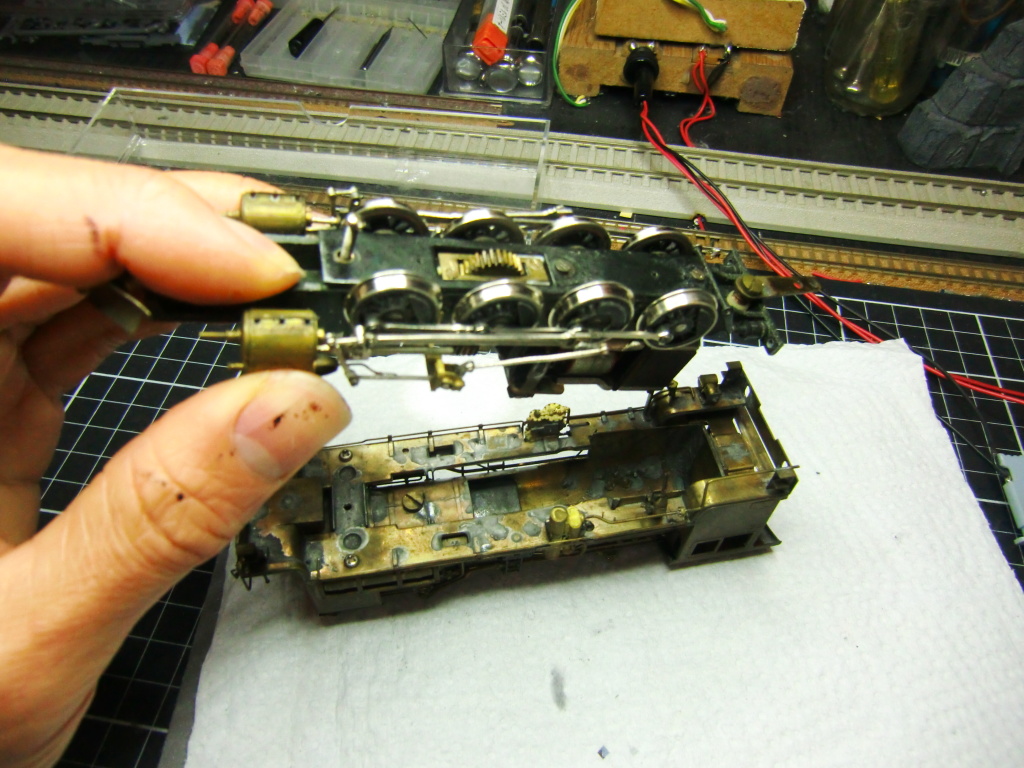
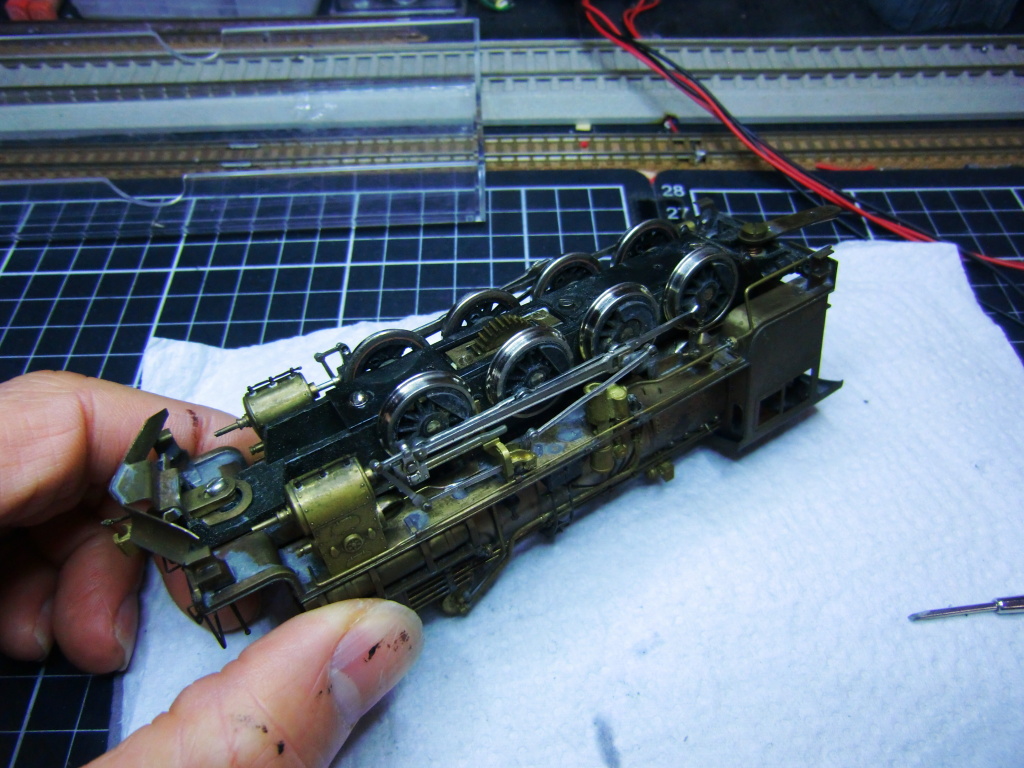
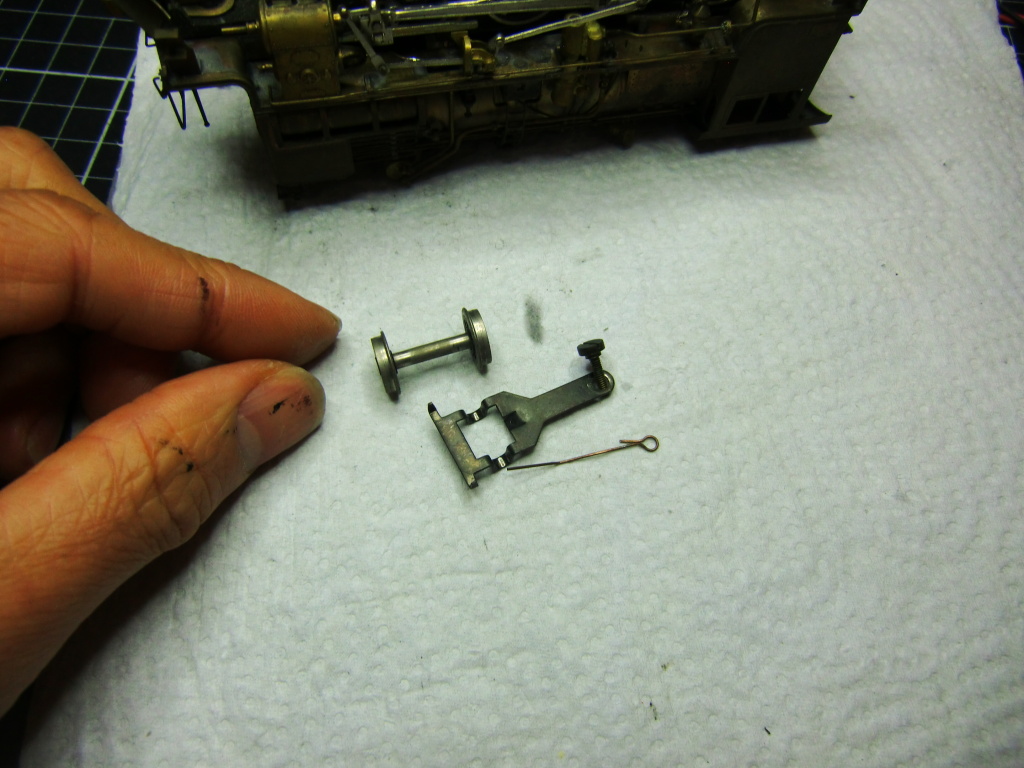

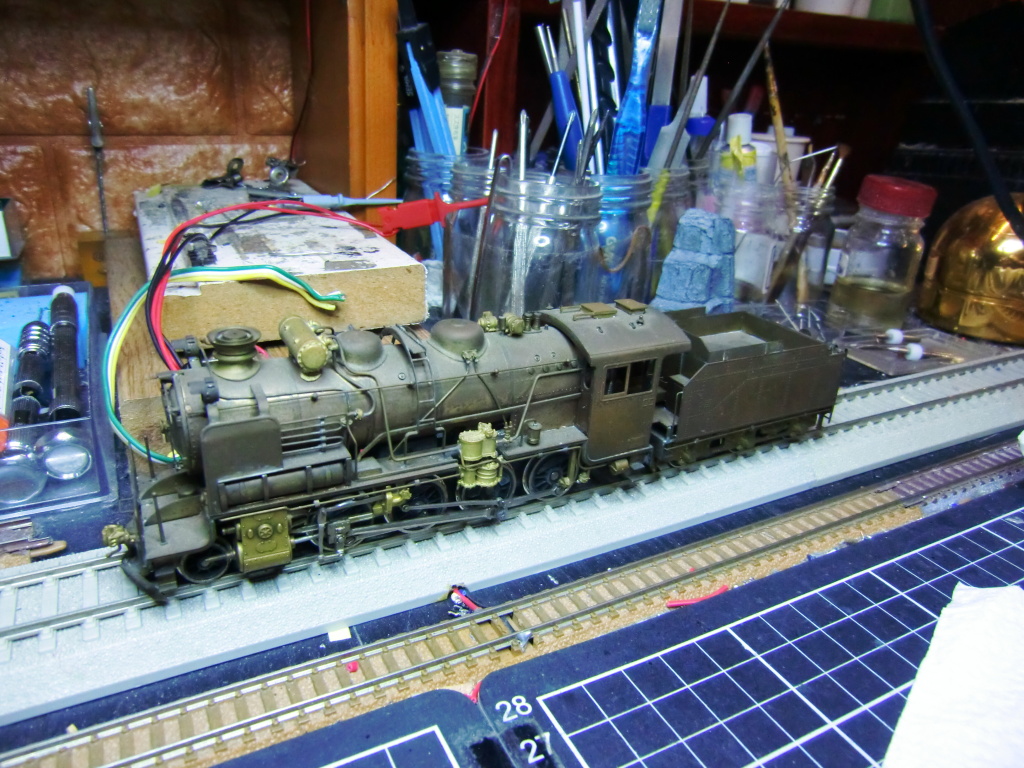

今回はちょっと難しかったですね。問題となる箇所が複数ありまして、確認と分解を繰り返し行ってようやく復活させることができました。今回の故障は次のような過程で引き起こされたのだと思われます。まず動輪が経年劣化と焼き付きで重くなったことでロッドによるリンクができなくなり、ある特定の位置に達すると著しく回転が重くなるポイントがありました。結果ギアユニットもぐらついていたことで、ギアがかみ合わなくなり空回りしてギア先端が損傷。無理に回したことでギア先端が熱で溶けてウォームギアの隙間に詰まってさらに状況は悪化。1つ1つ問題を解決しながら作業を進めていきました。正常に走行できるようになるまで作業は難航しましたが、ようやく低速でもスムーズに走行できるまで復活いたしました。作業はすべて完了いたしました。
今回は、ご依頼者様のご要望によりヘッドライトの明るさアップ以外に副灯点灯化も行うため、作業の難度がいっきに上がります。

▼ワフ室内点灯化


まずは、「ワフさん」から作業に入ります。
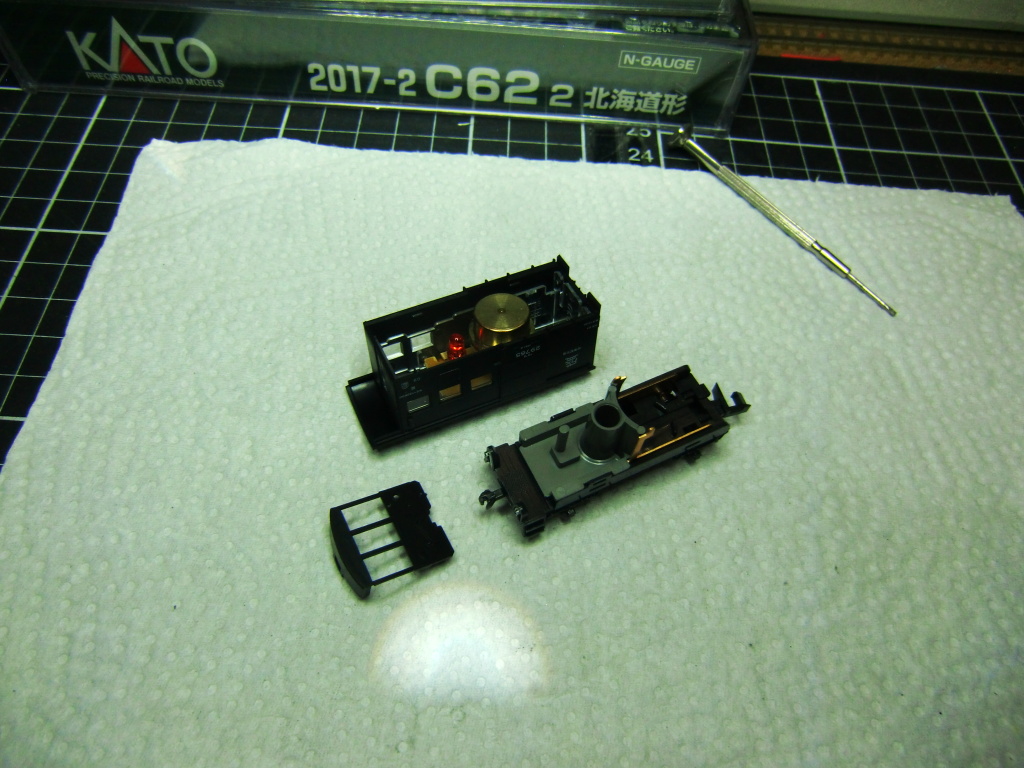

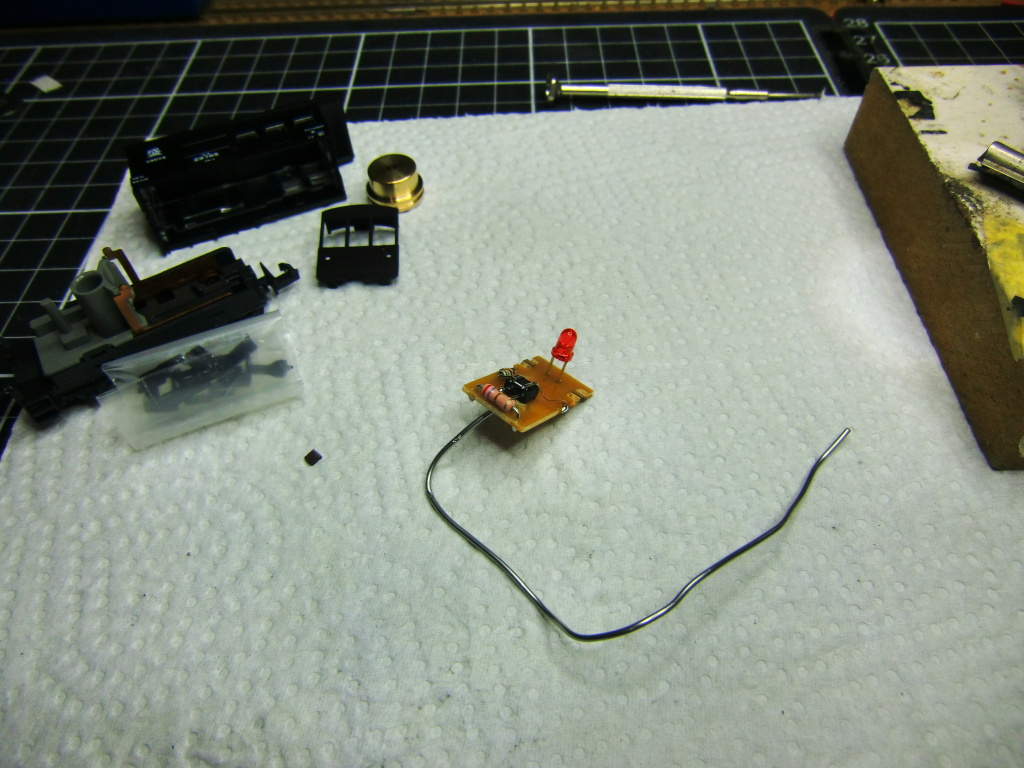
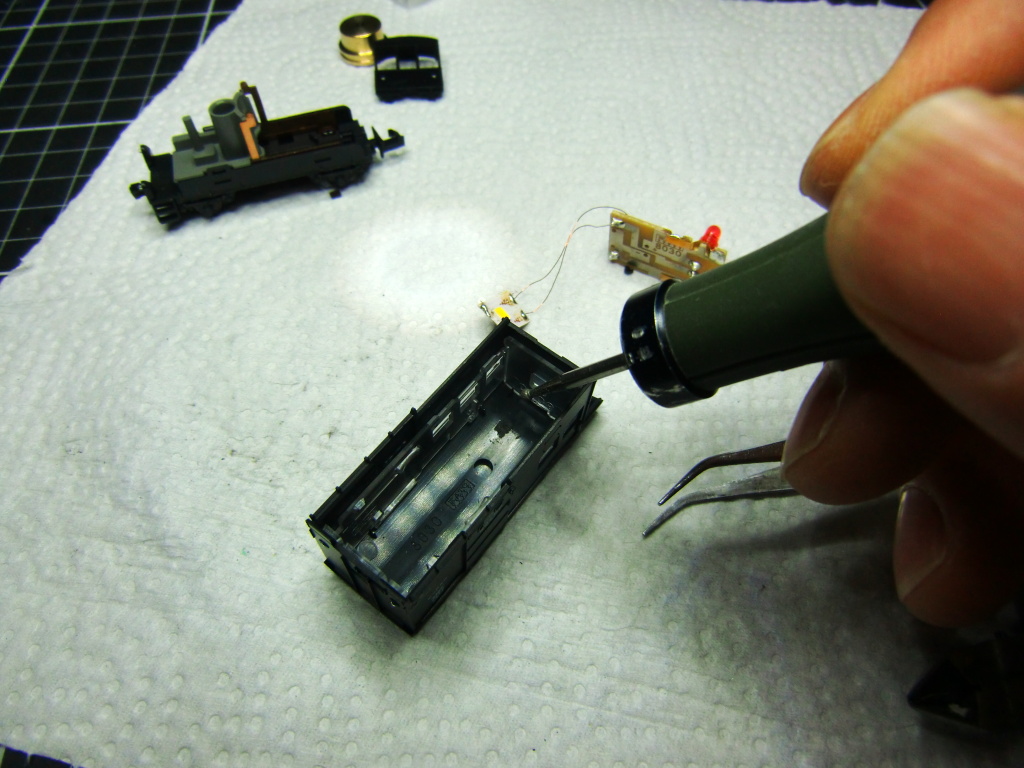
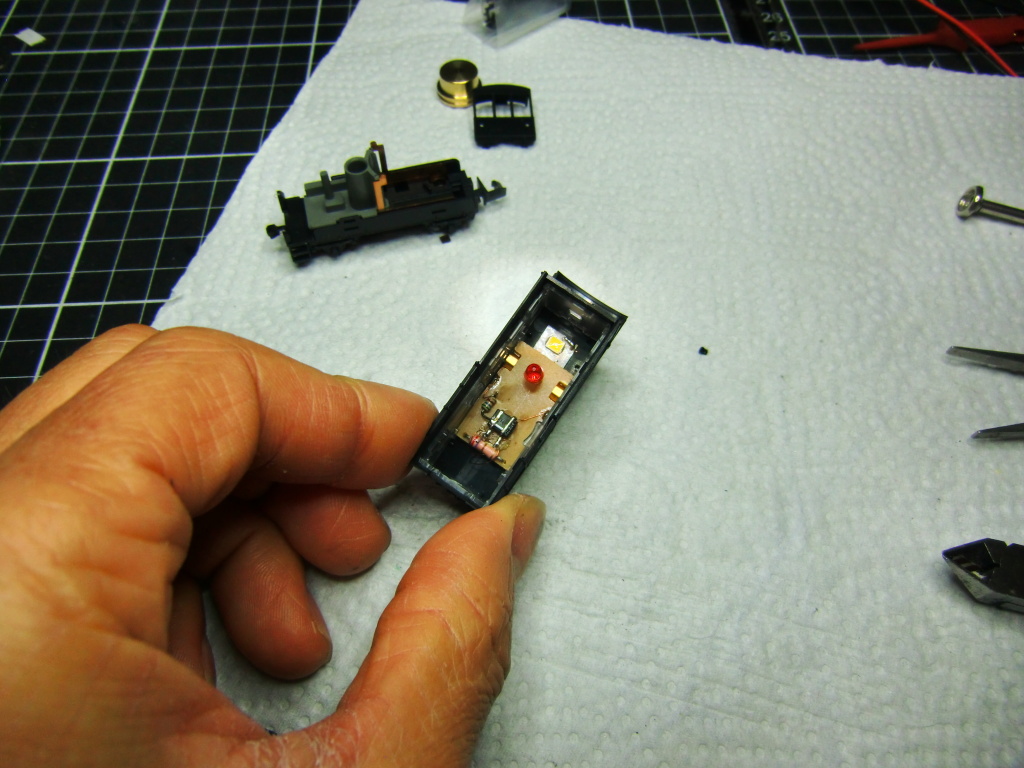
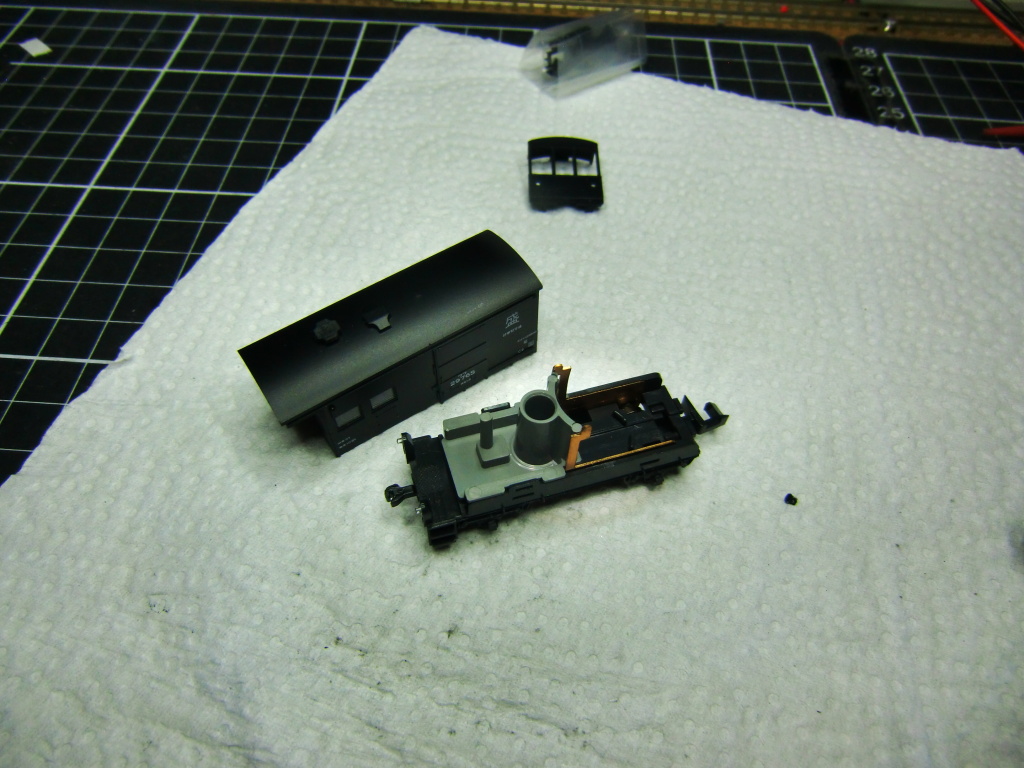
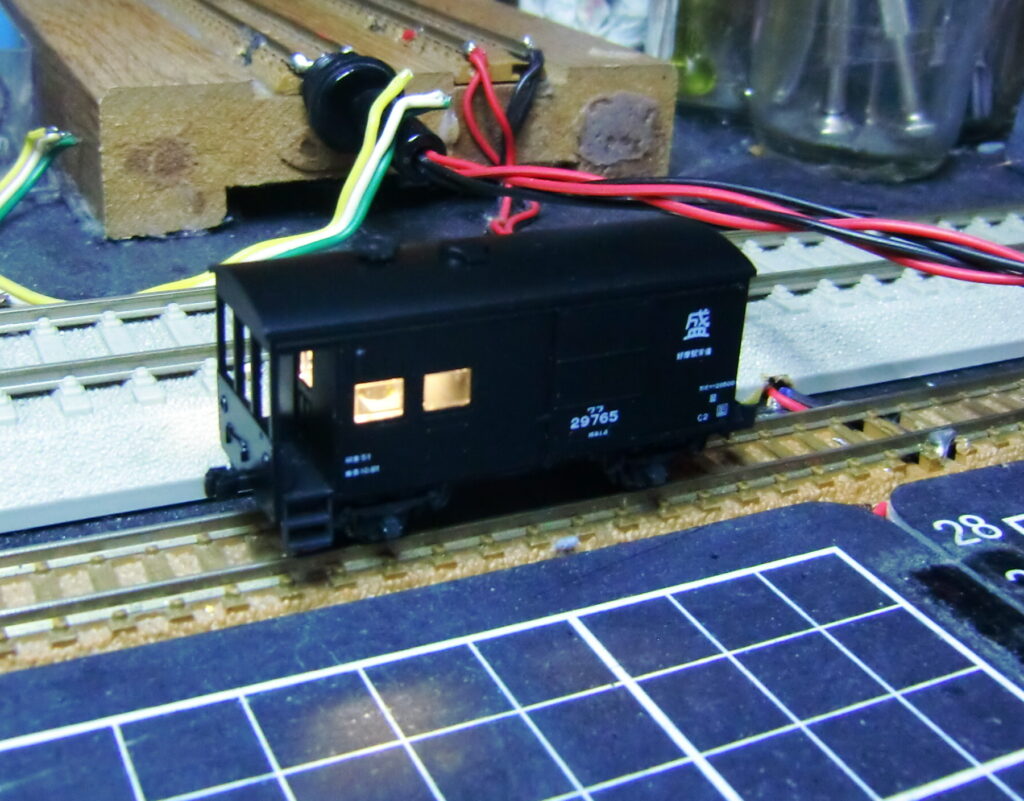

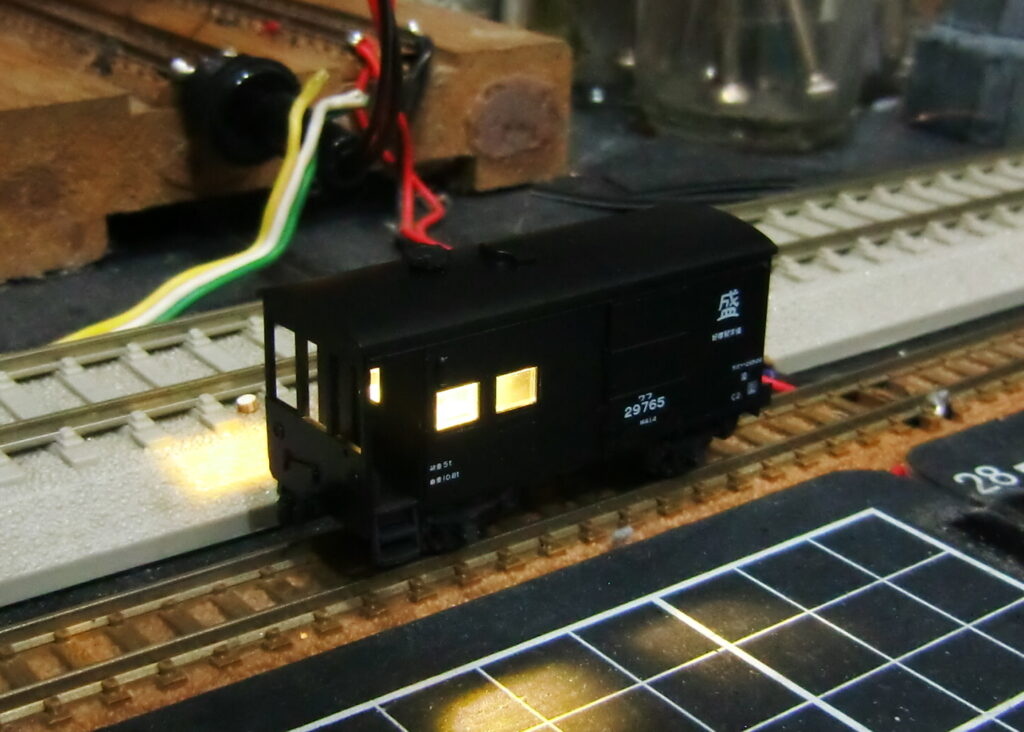
▼KATO C62ヘッドライト明るさアップ+副灯点灯改造

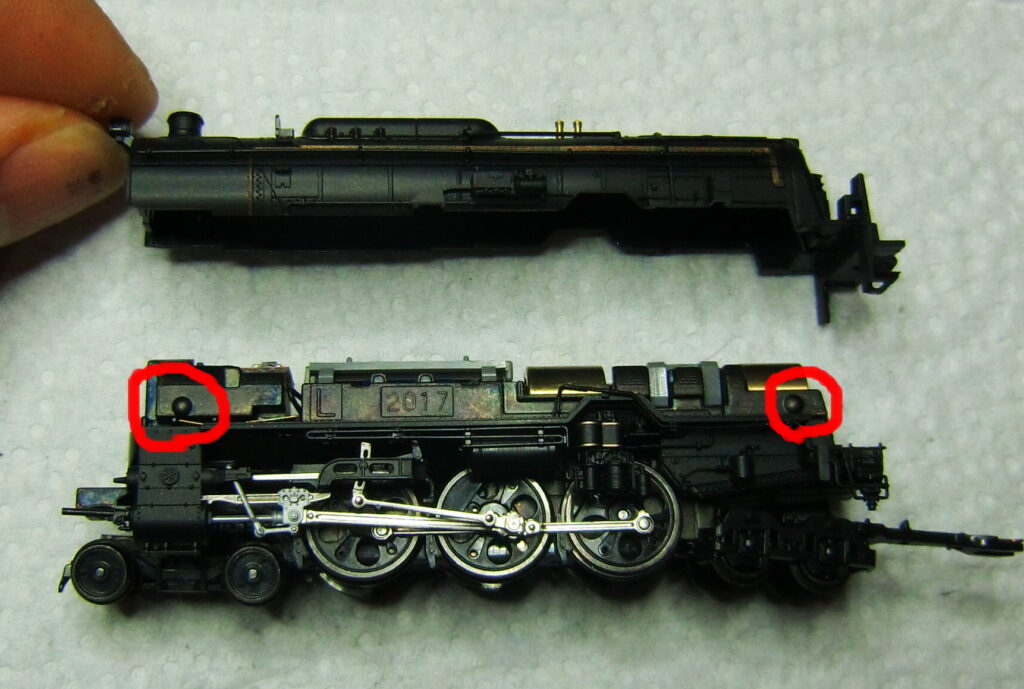
赤丸で囲った出っ張りが、上ボディーを固定しています。まずは後ろを持ち上げて、そのまま前方を持ち上げると比較的簡単に外れます。持つ場所を間違えたり、無理に上げると破損してしまう可能性がありますの注意が必要です。

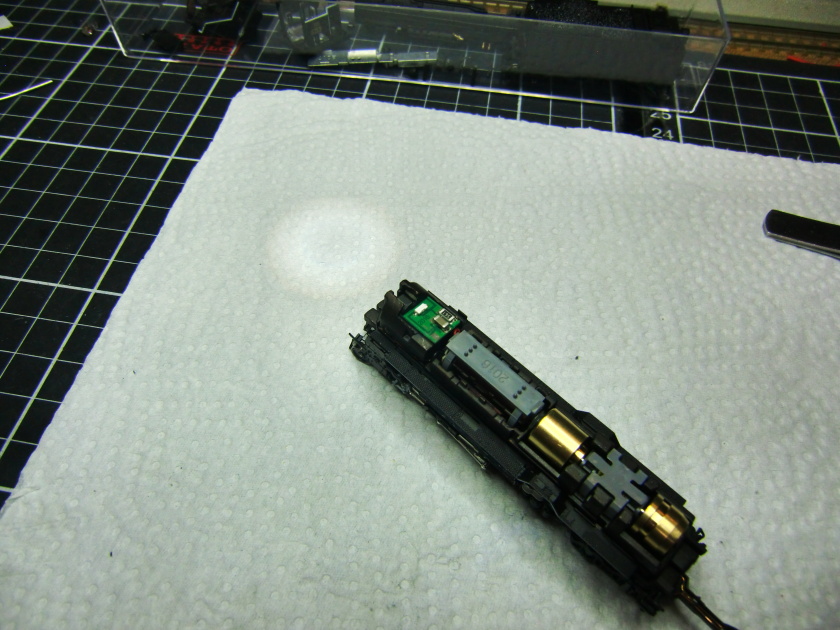

砲弾型LEDを収納できるサイズまで削り込んでいきます。

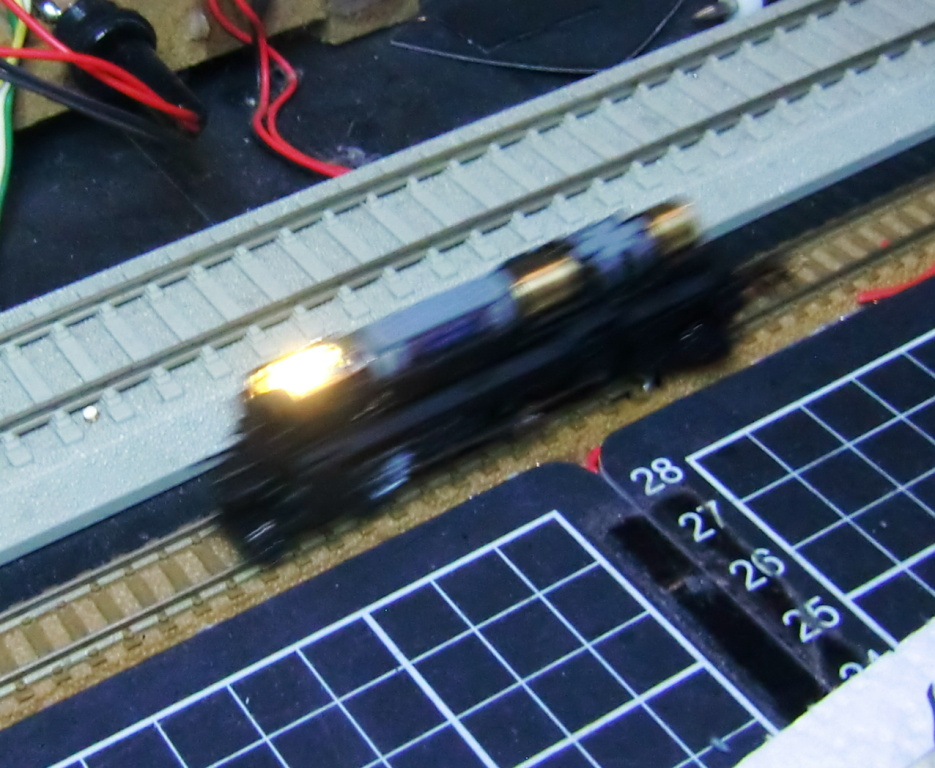
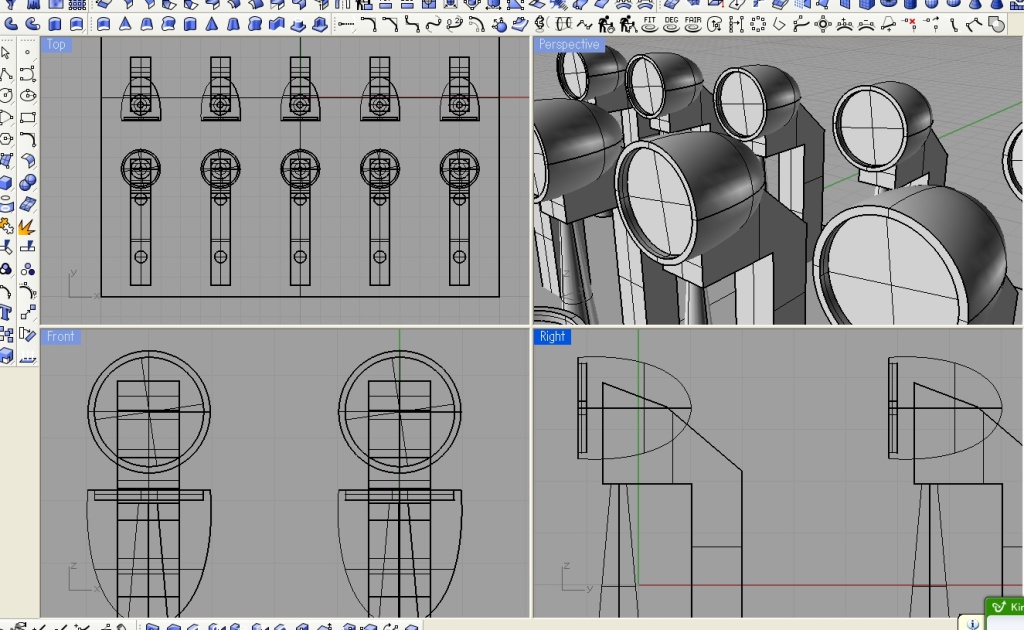
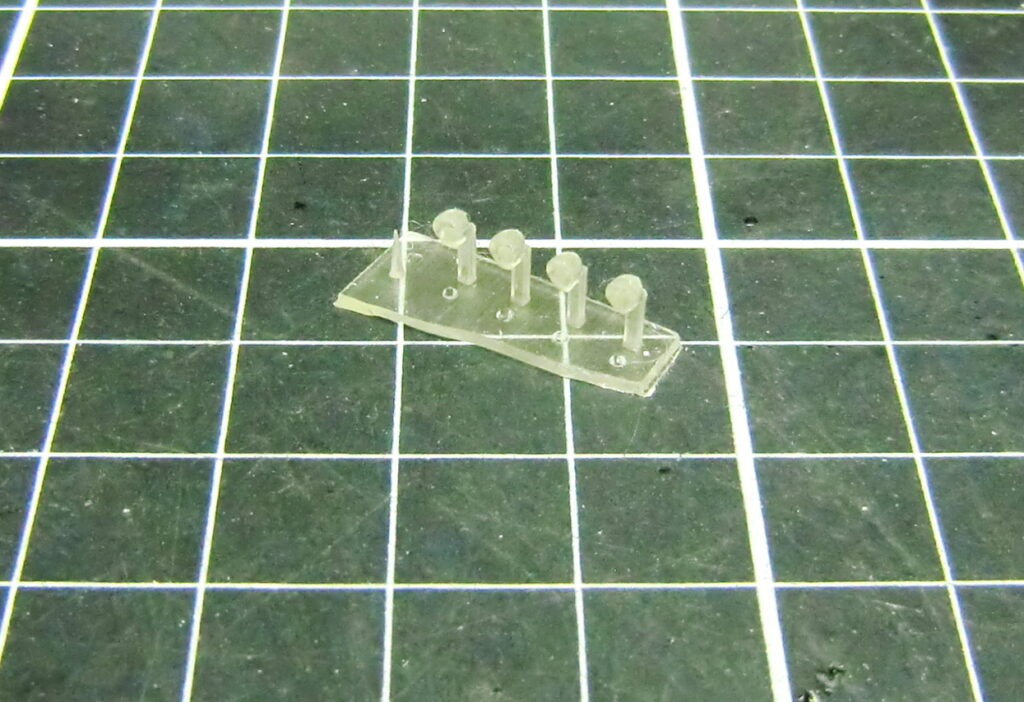
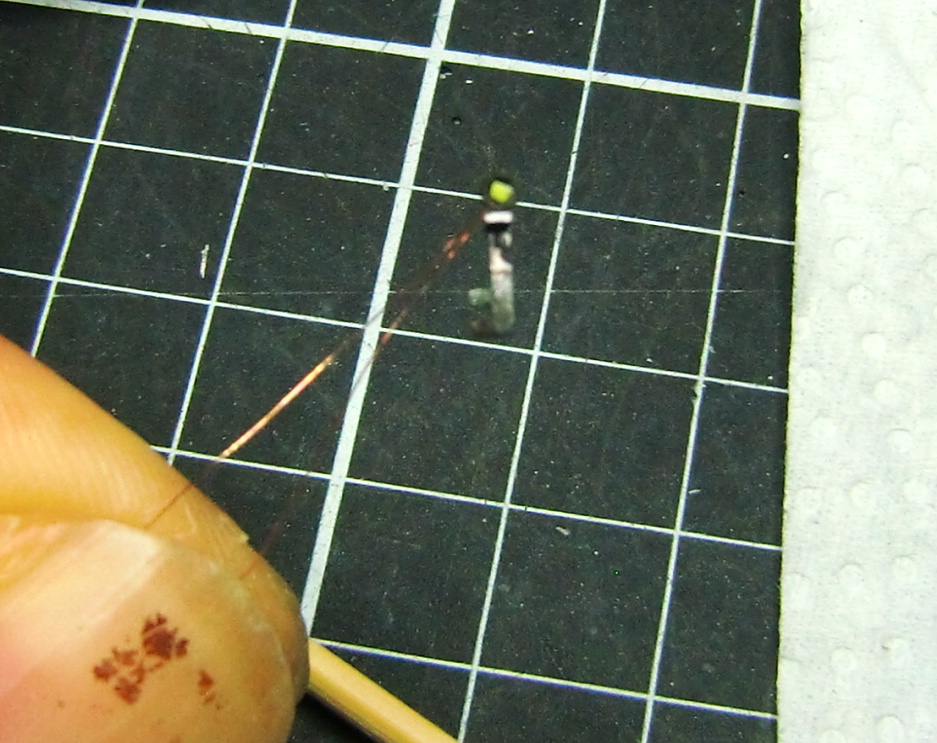


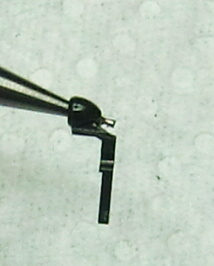

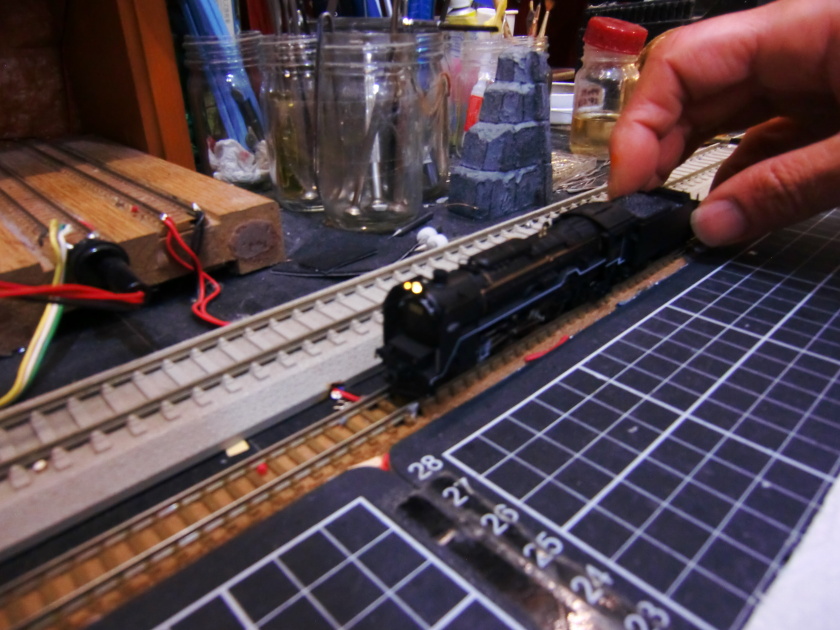

副灯の後方に0.2mmで穴をあけ、続いて前方から0.5mmで穴あけ。そのあと、LEDを埋め込むためのスペースを確保するため、ルータービットを径を広げます。LED断面をクリアーオレンジで着色後に0.1mmの配線を2本通して基盤に結合します。最後に制作したレンズをはめ込んで完成です。

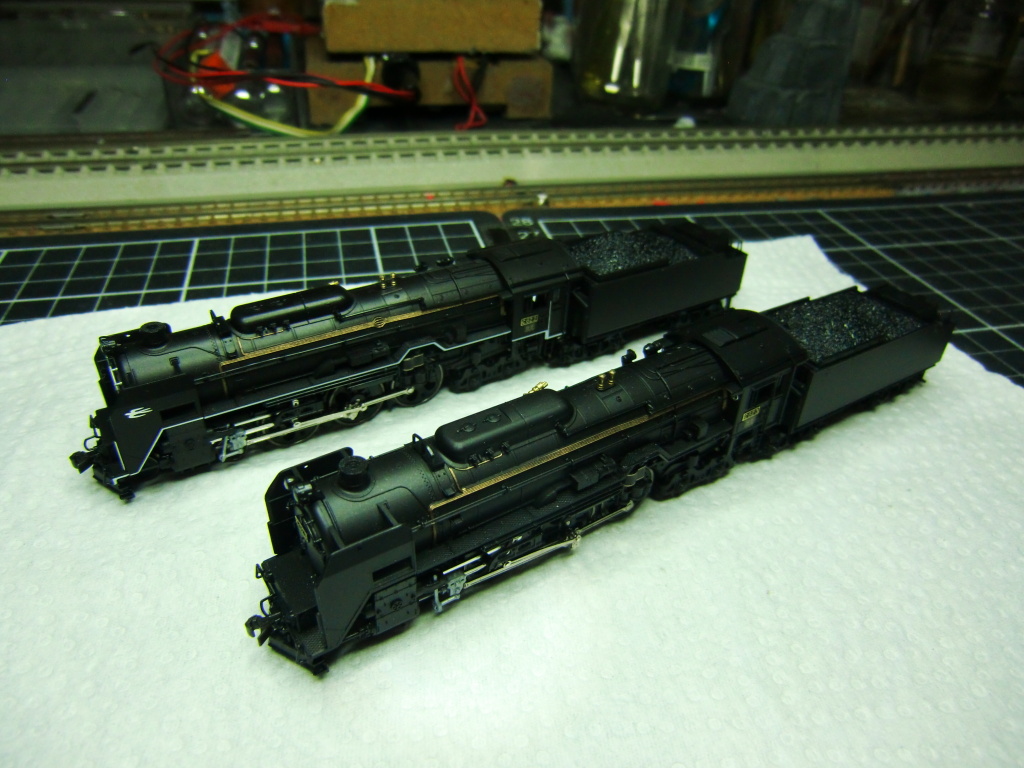
作業完了でございます。
続いてのご依頼は、白色LED化による点灯のご依頼でございます。導光材が色付けされてなければ良いのですが・・


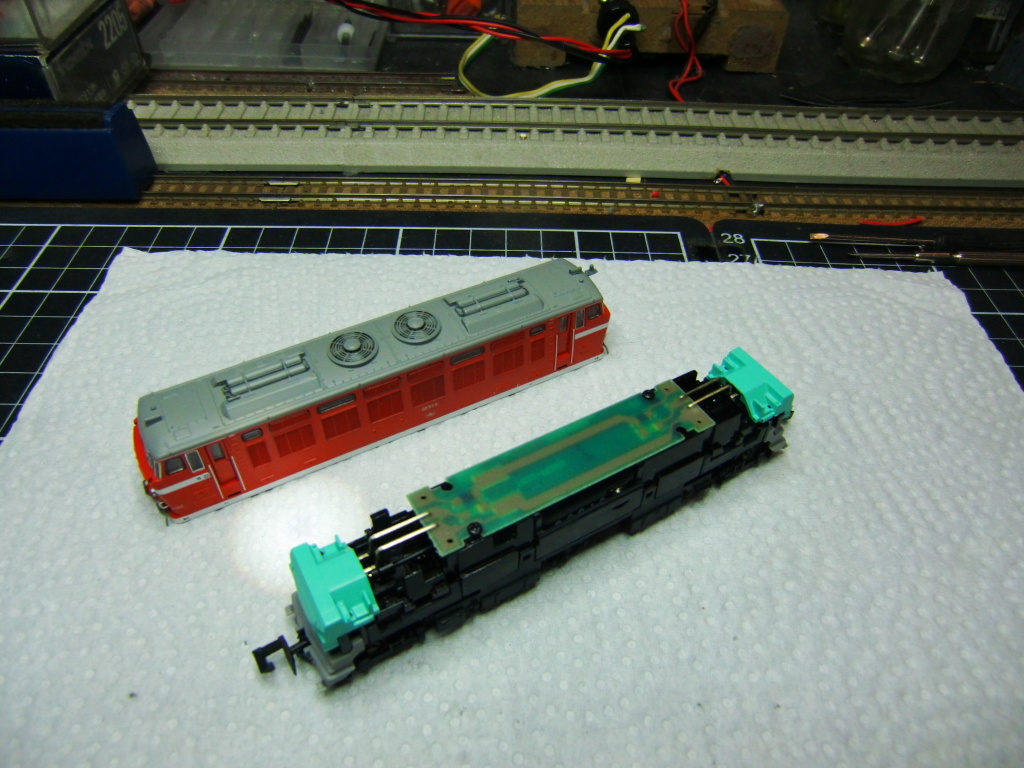
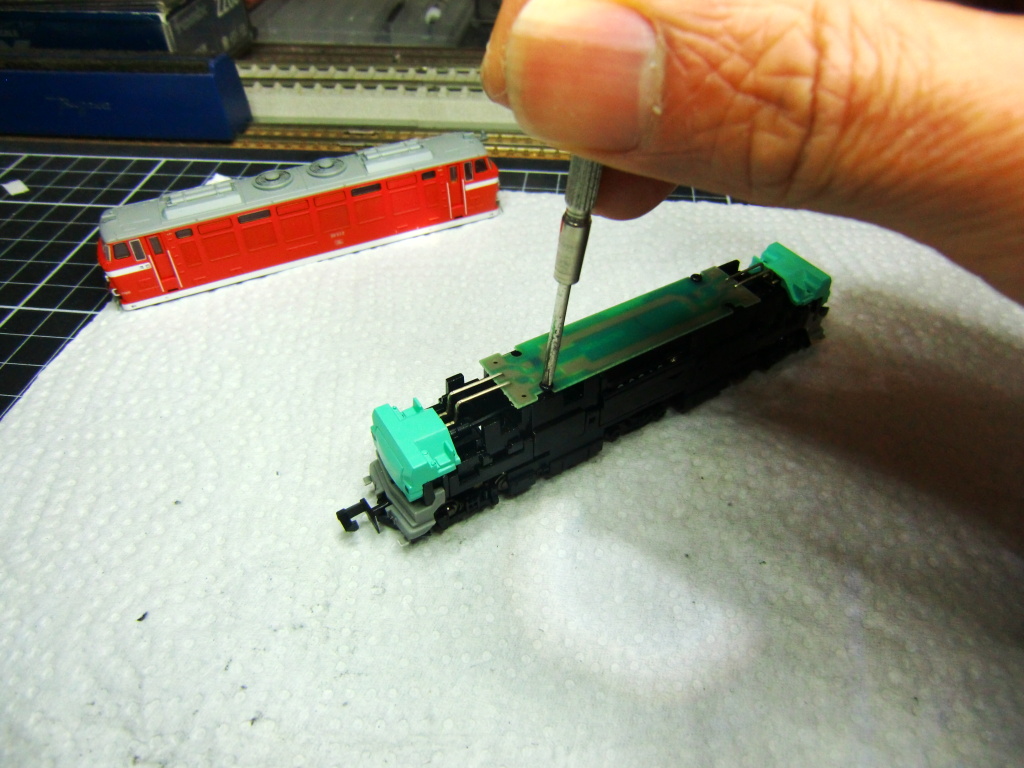
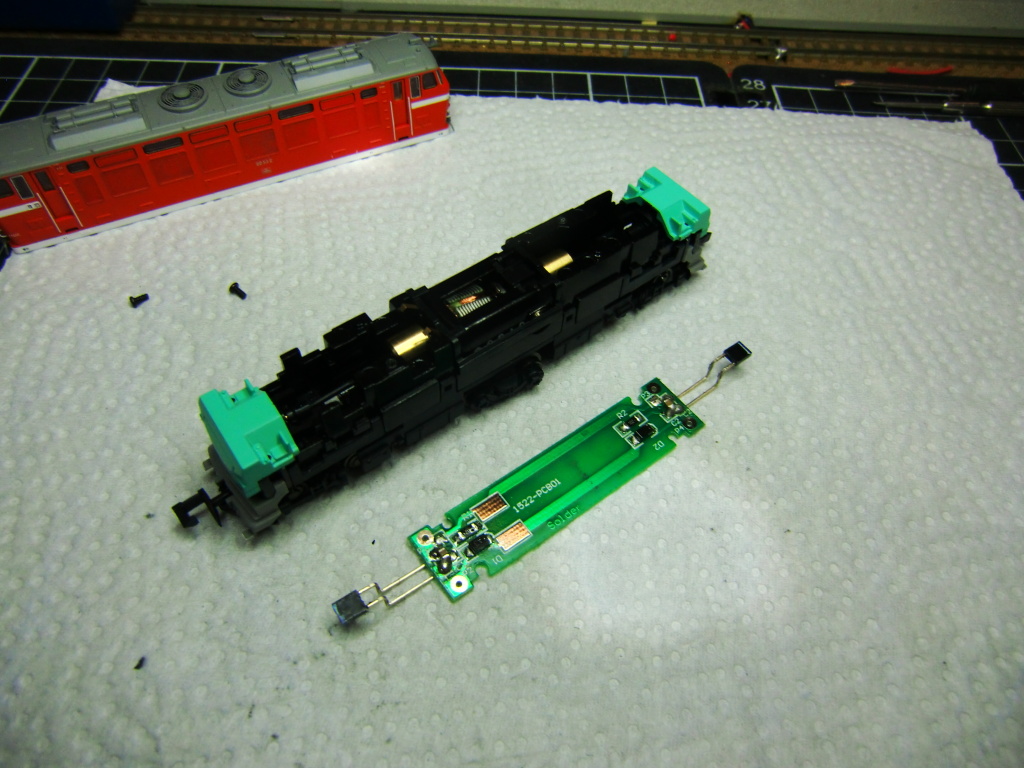
試験的にヘッドライトの導光材に直接白色LEDで点灯させてみました。どうやら導光材は無色透明のようです。よかった、よかった。
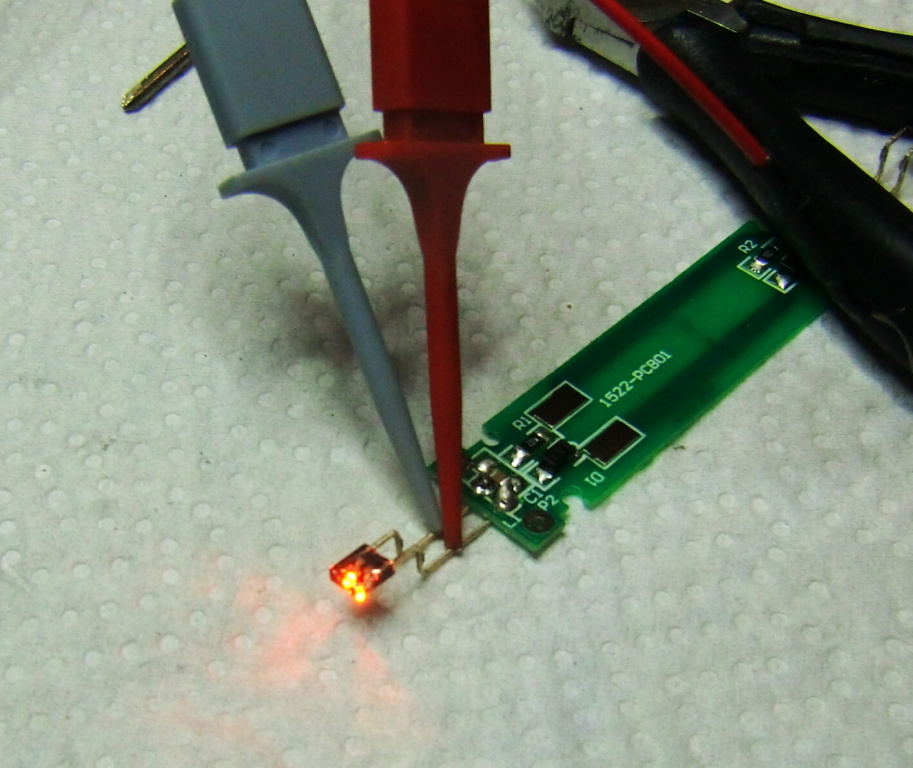
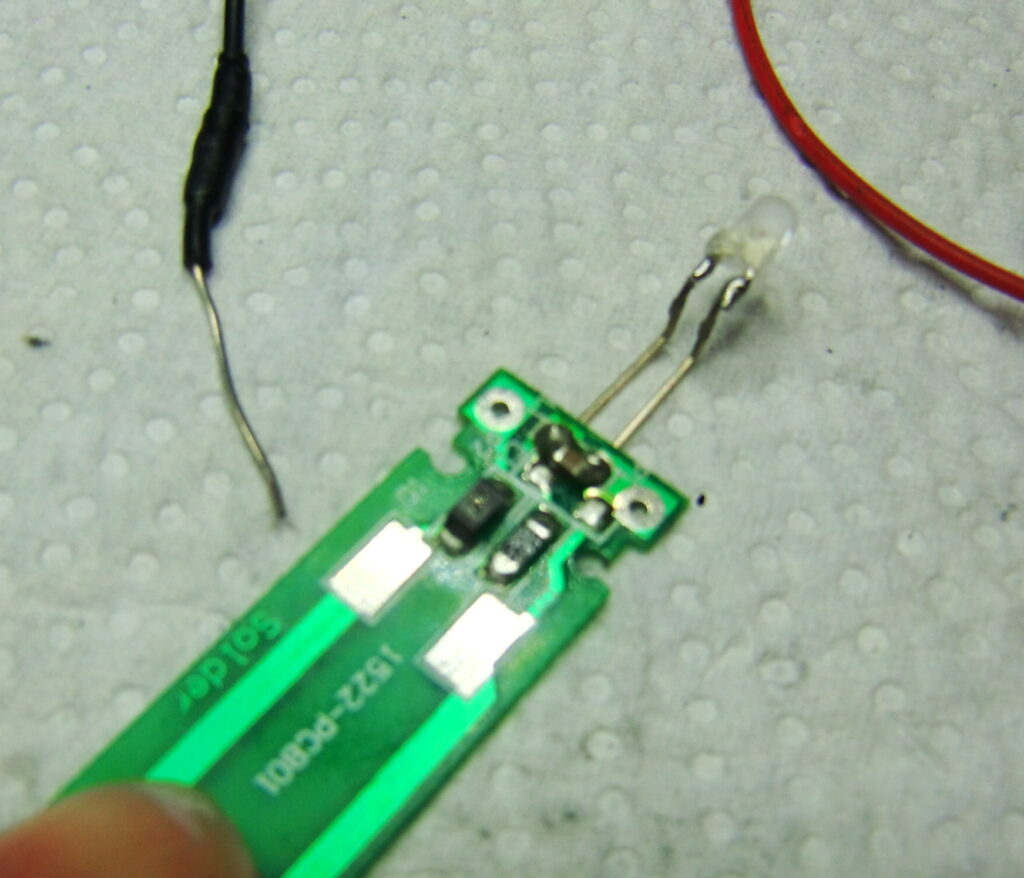
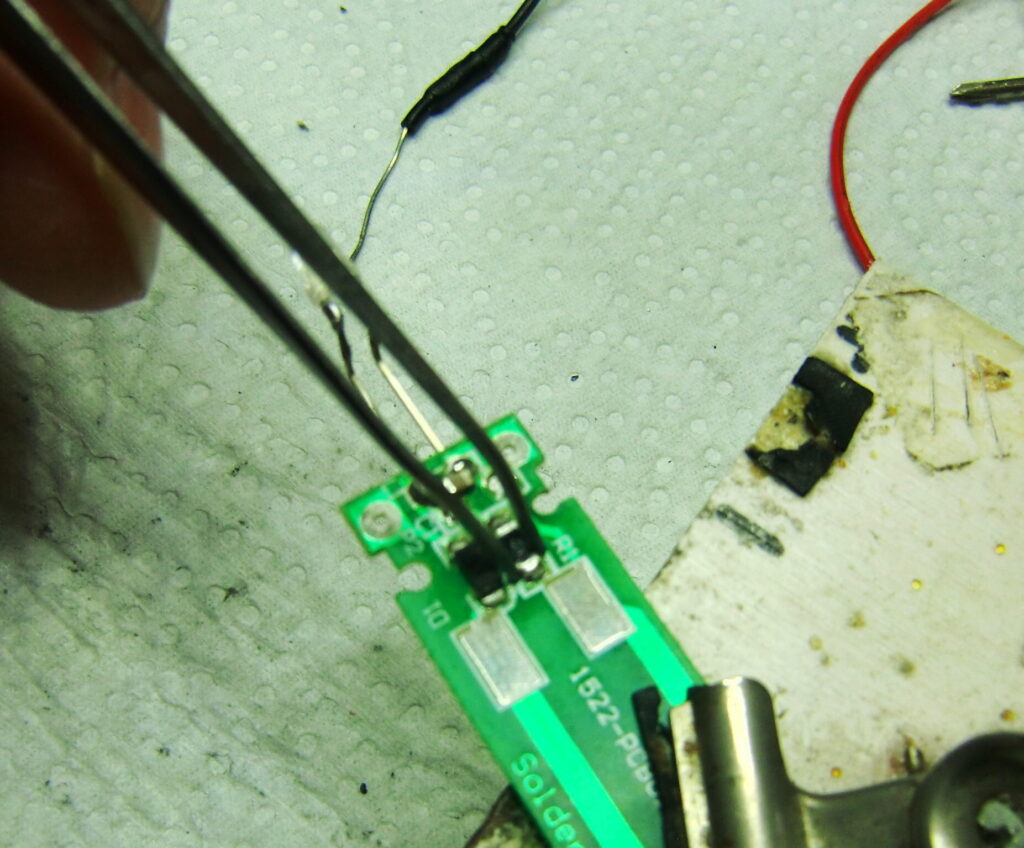
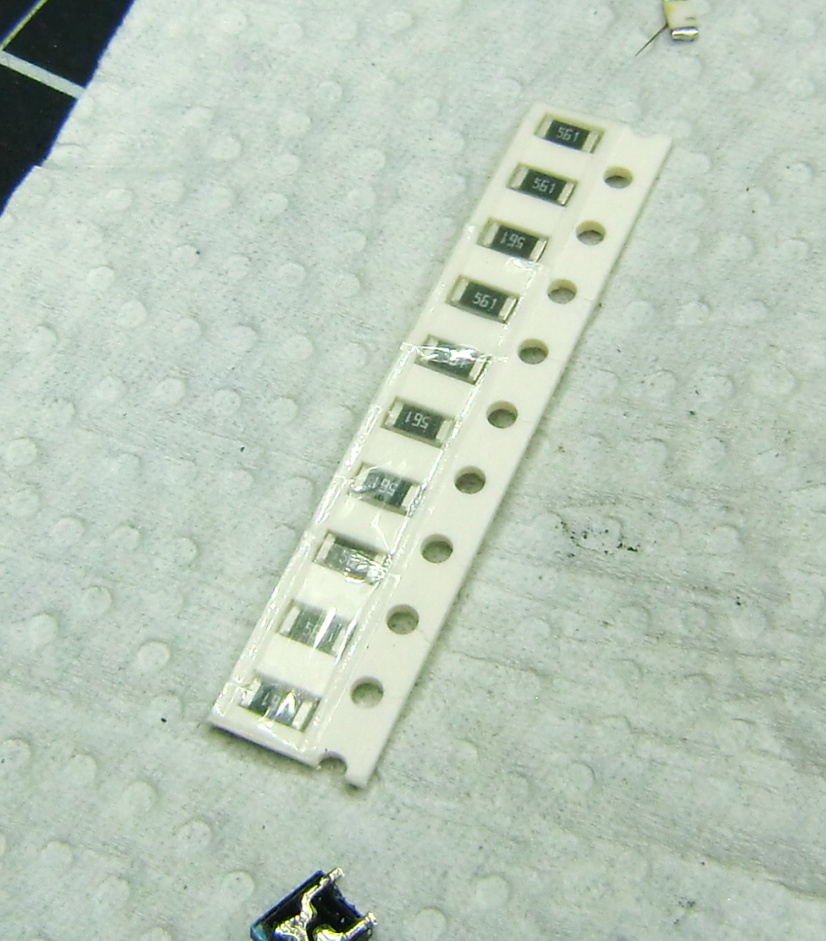
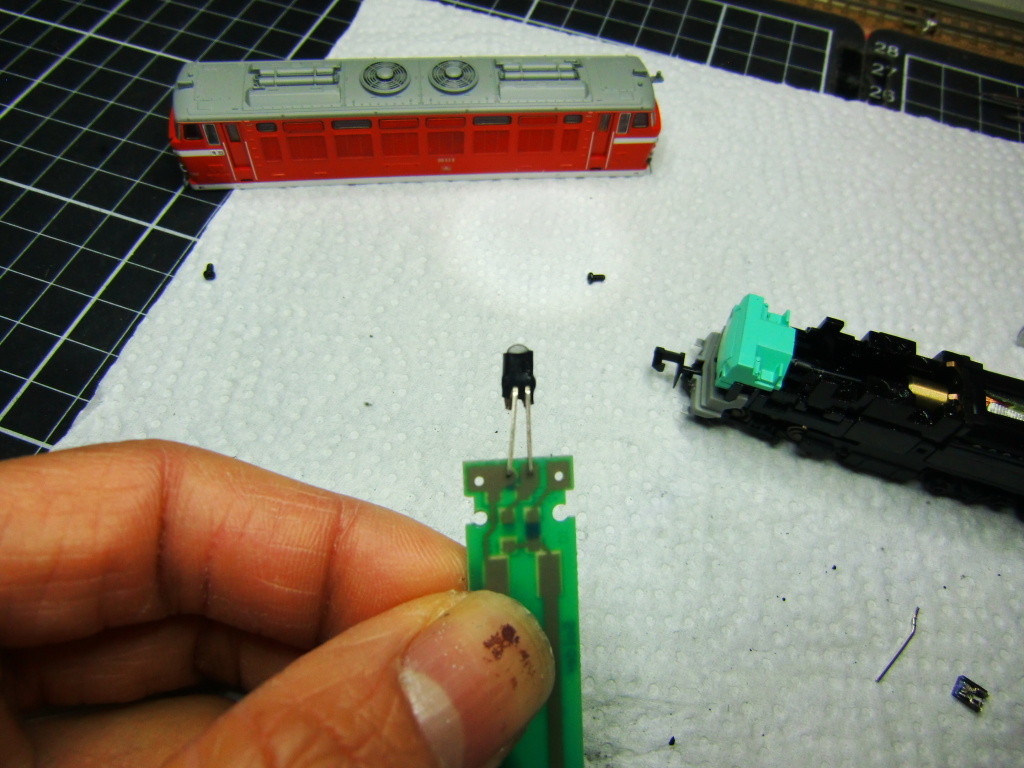
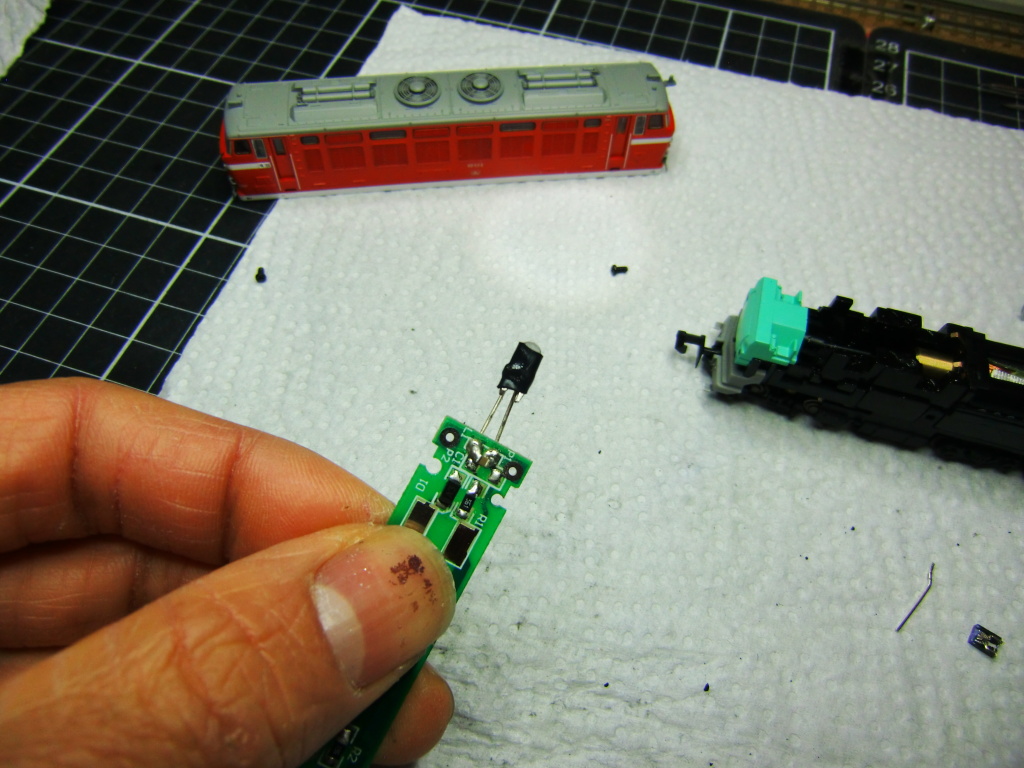

作業完了でございます。

それでは早速作業に入ります。まずは、トミックス製DD51からです。現状は、まったく動きません。

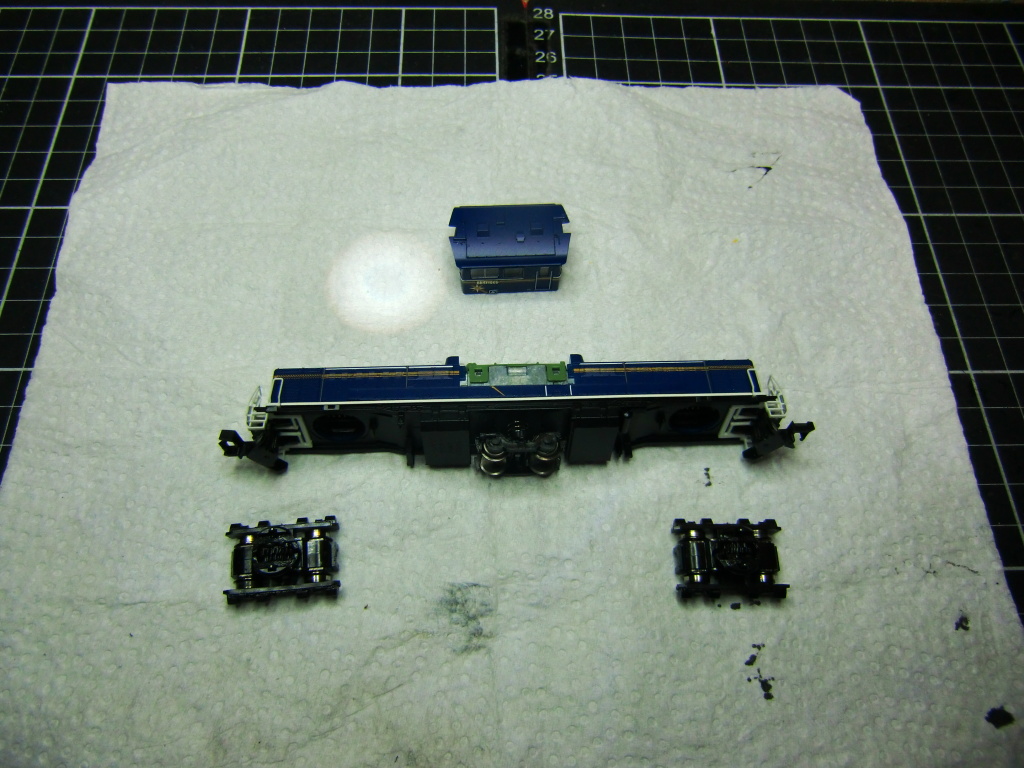
分解していきます。
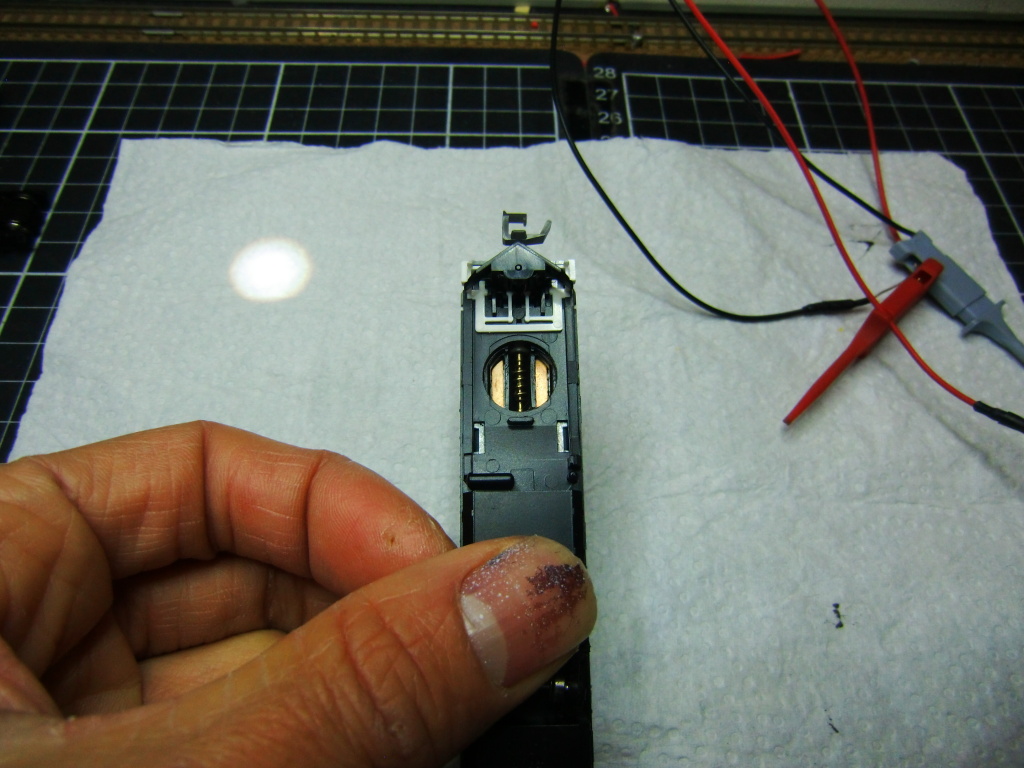
台車を返さず直接集電板に電気を流しても動きません。
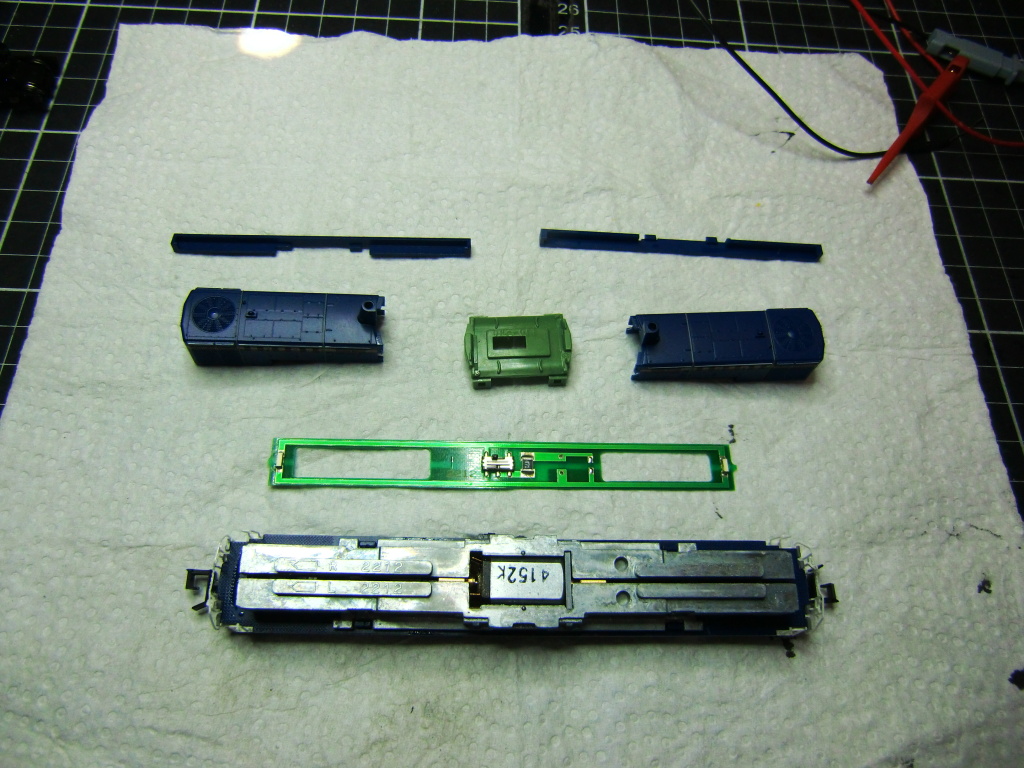
さらに分解します。
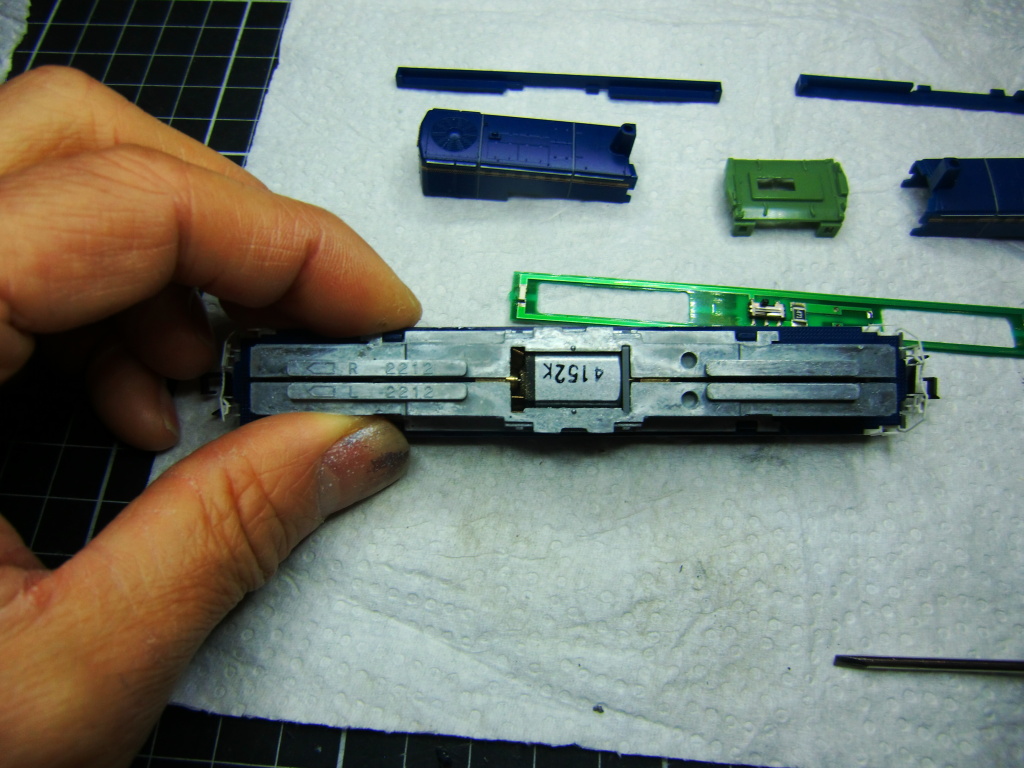
この状態でモーターとの接点を確認してみると周りに金属の削れたものが付着しており、集電板も正しい位置についておりません。

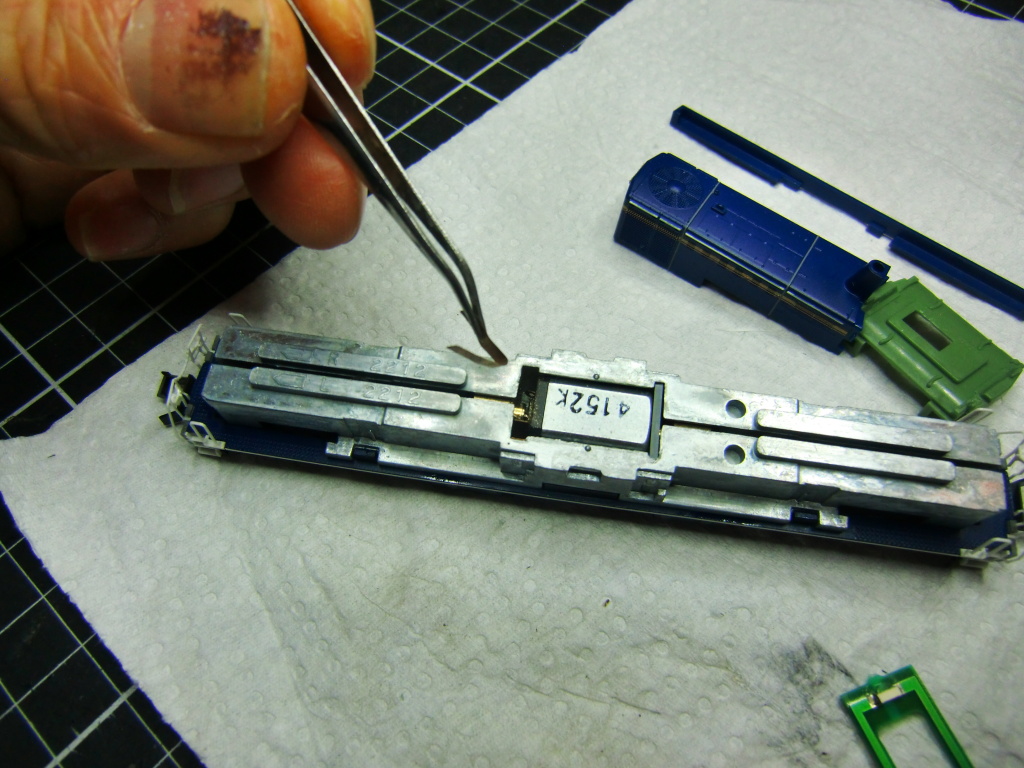
鉄粉を取り除いてから集電板を本来の形状に戻してから正しい位置に差込みます。
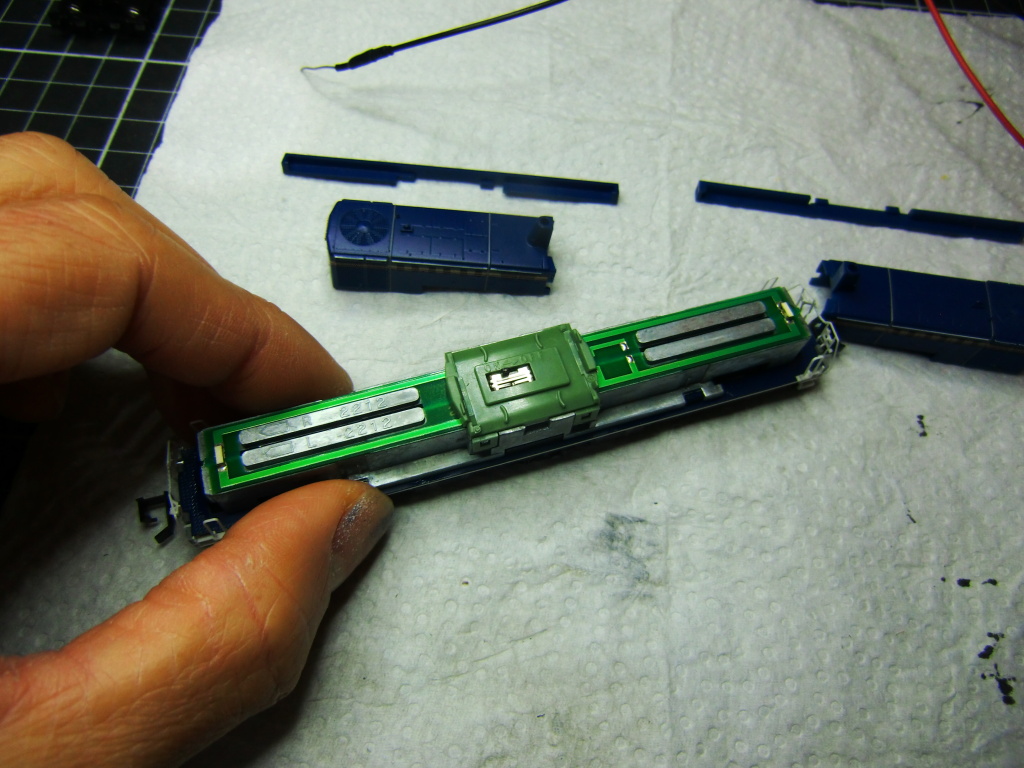
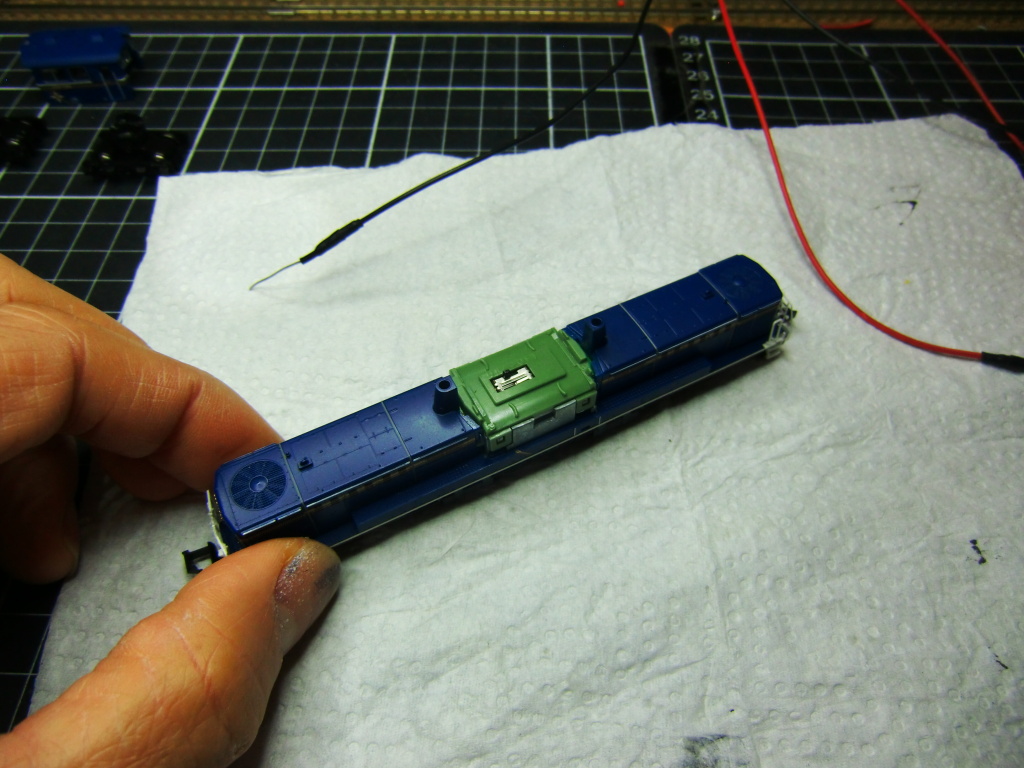

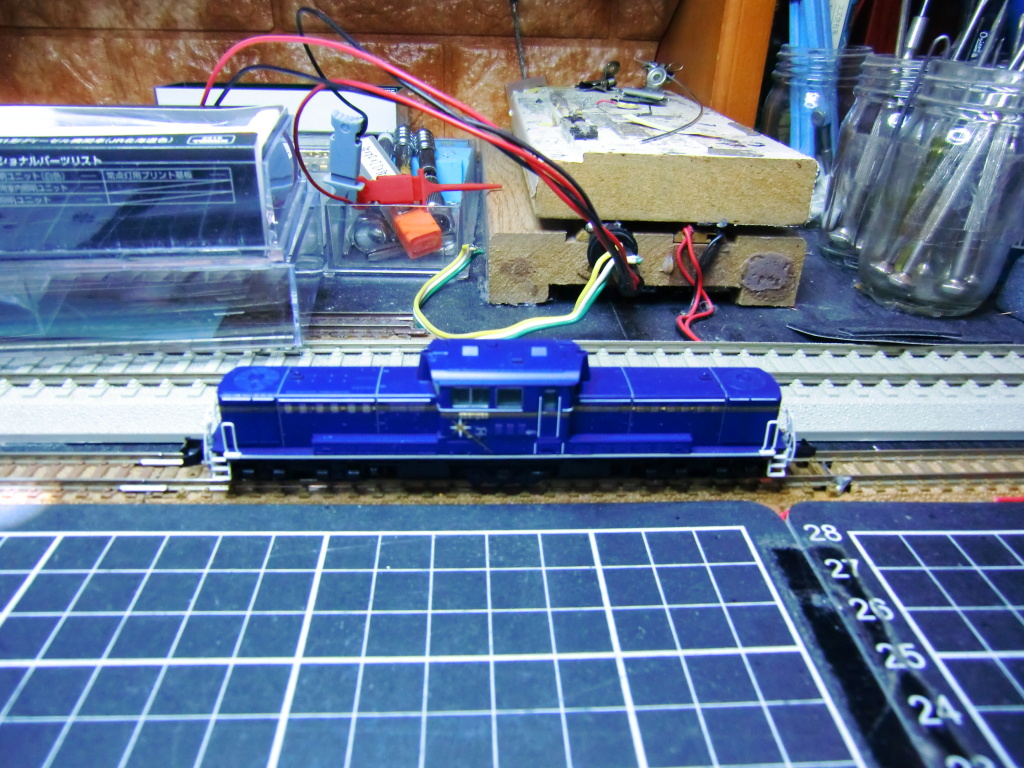
作業完了です。
▼DE10 カプラー修理/OH/ナンバー補修
さて、続いては旧製品のトミックス製DE10です。まずは折れてしまったカプラーを復元します。

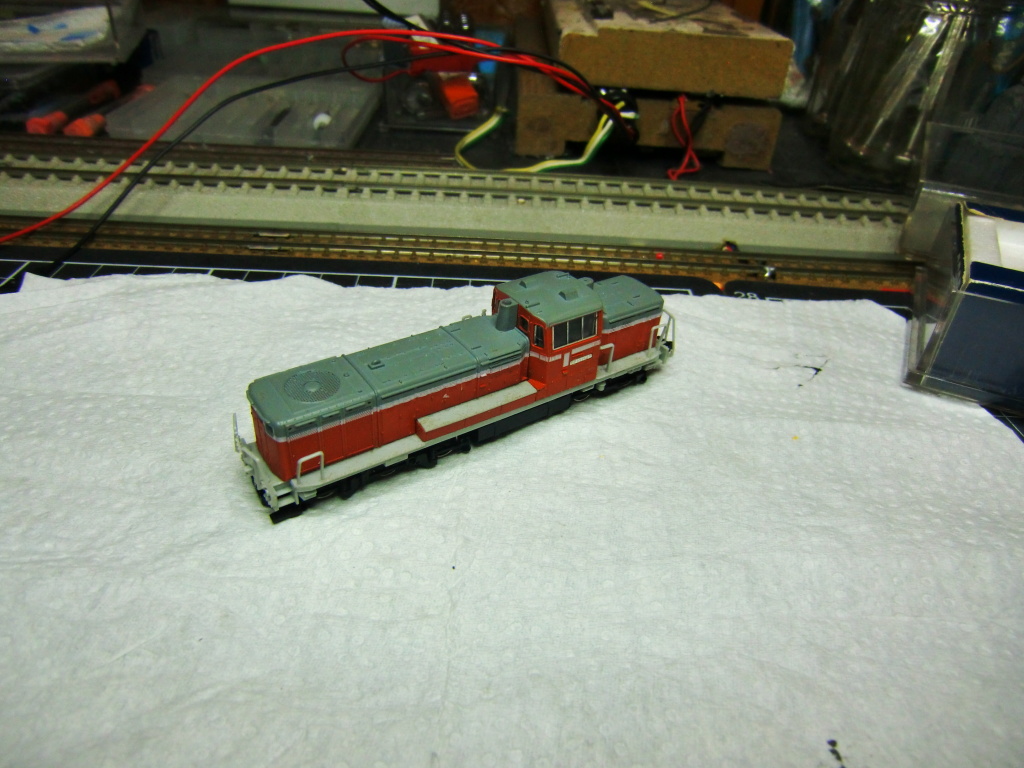
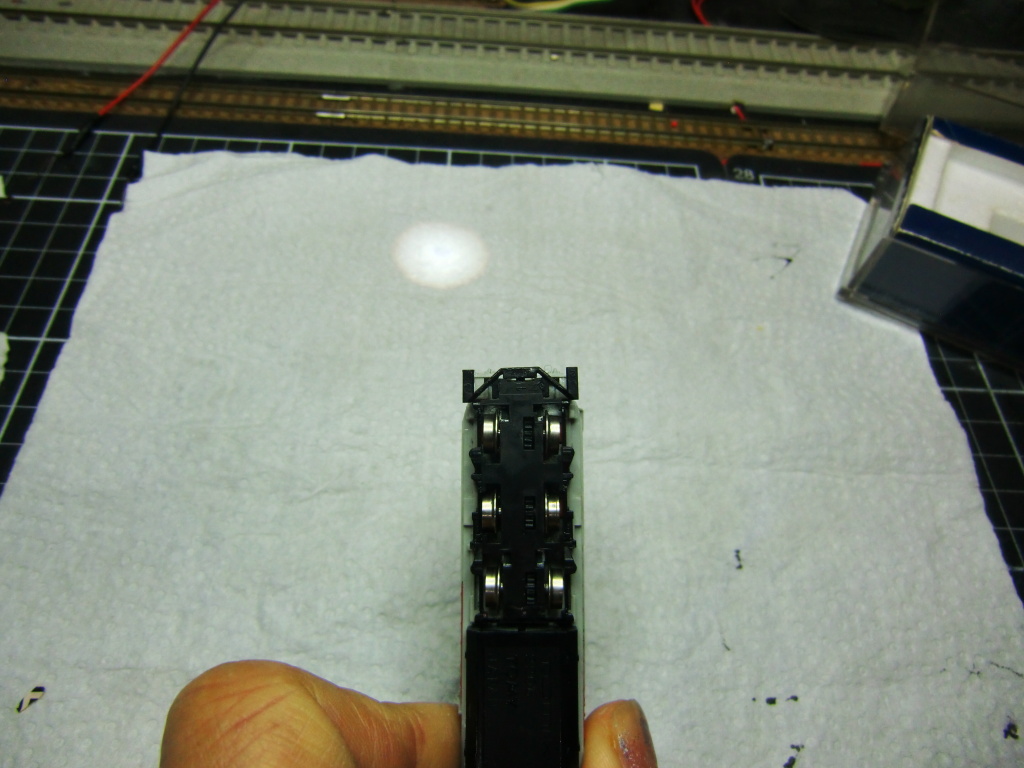
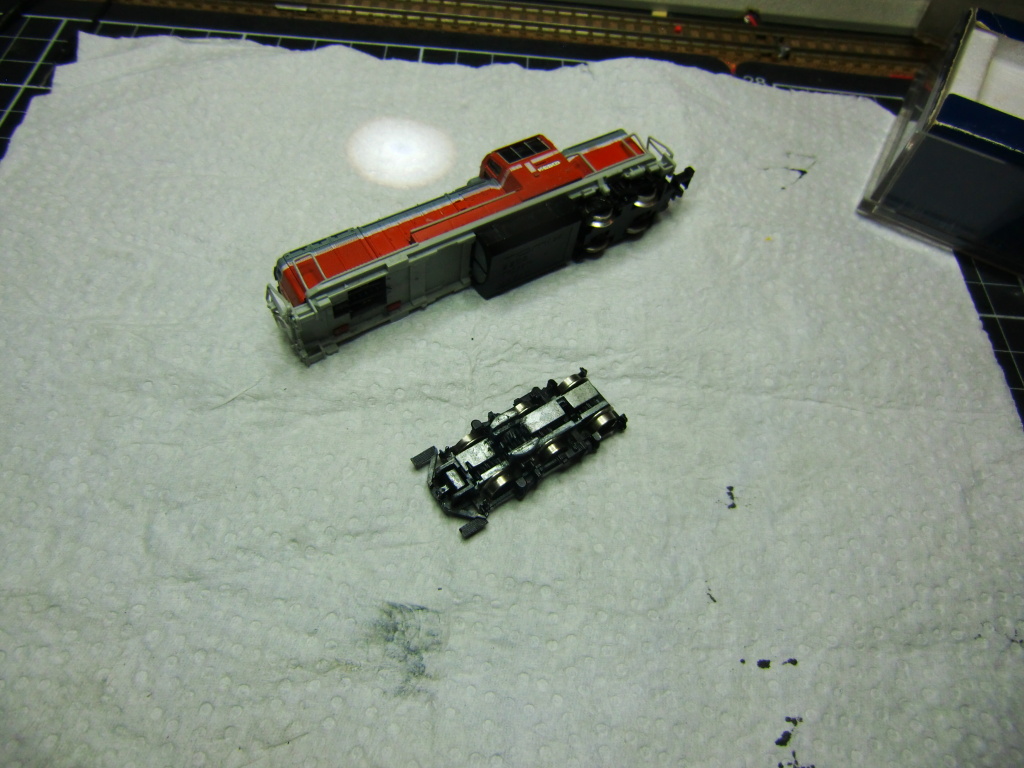
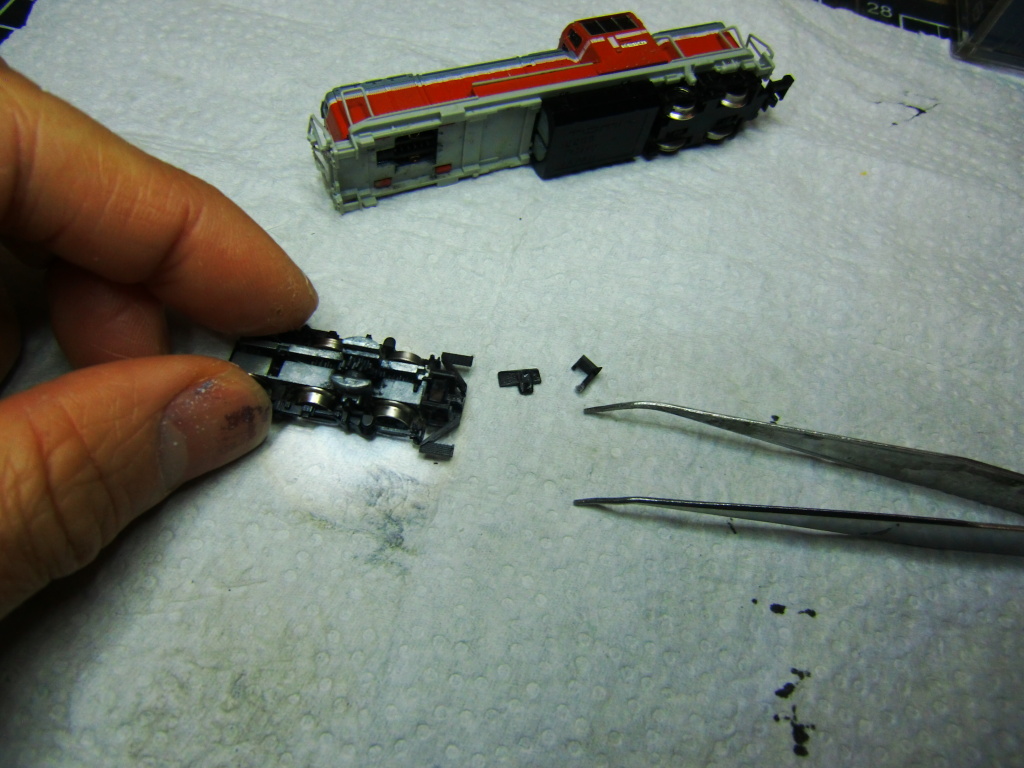
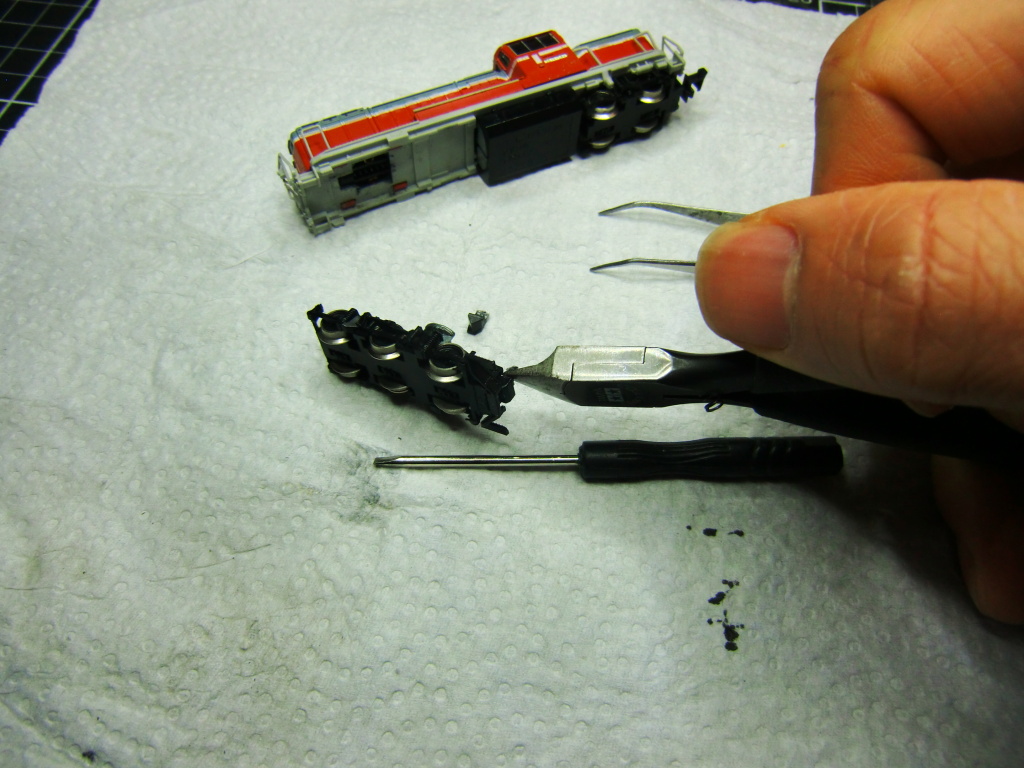
この時代のカプラーは、マグネットで連結器が解放するタイプです。解放機構を活かす形でカプラーを直します。
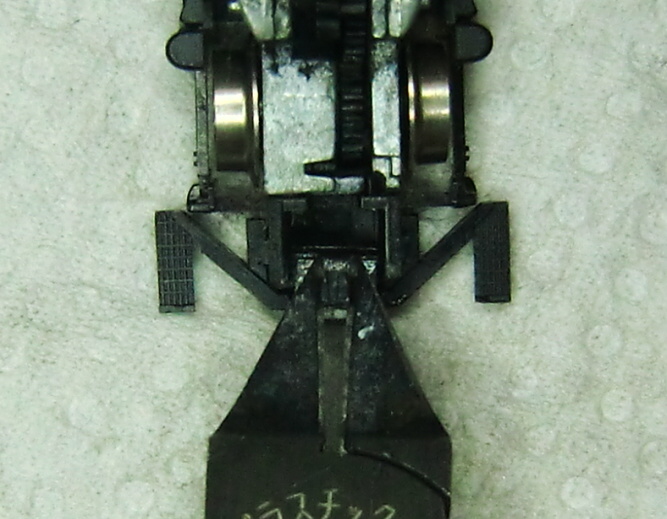

このように折れた個所をニッパーで切り取って、ルーターで削って平らにしておきます。カプラーが直ったところで走行機能の復活作業に入ります。
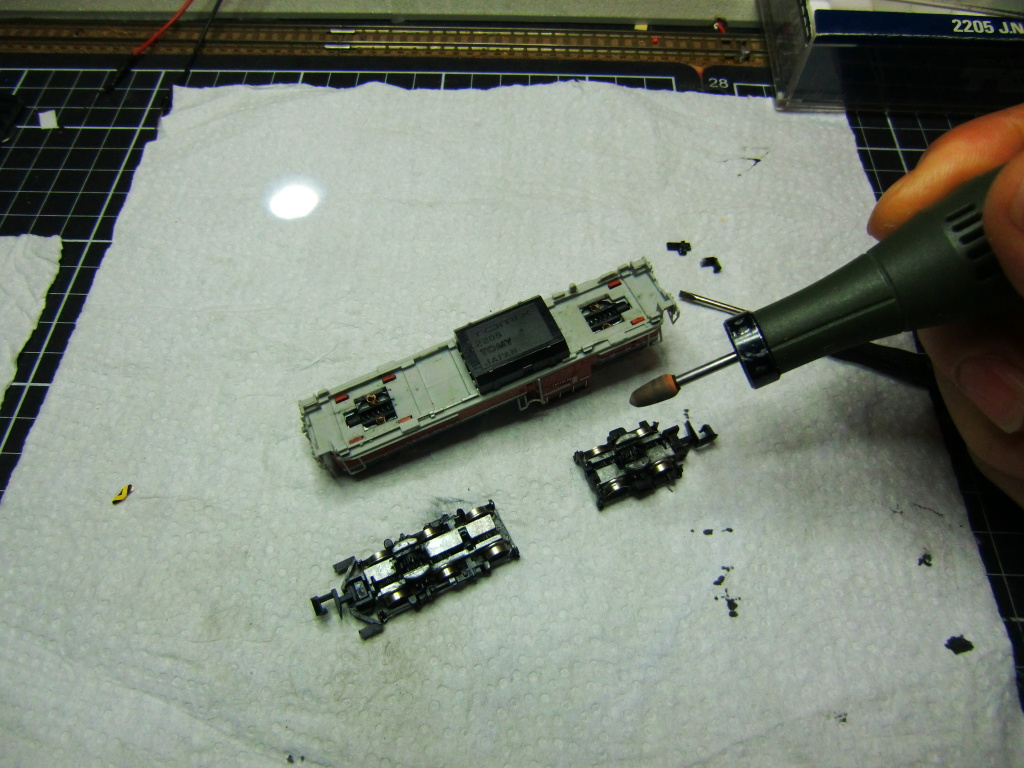
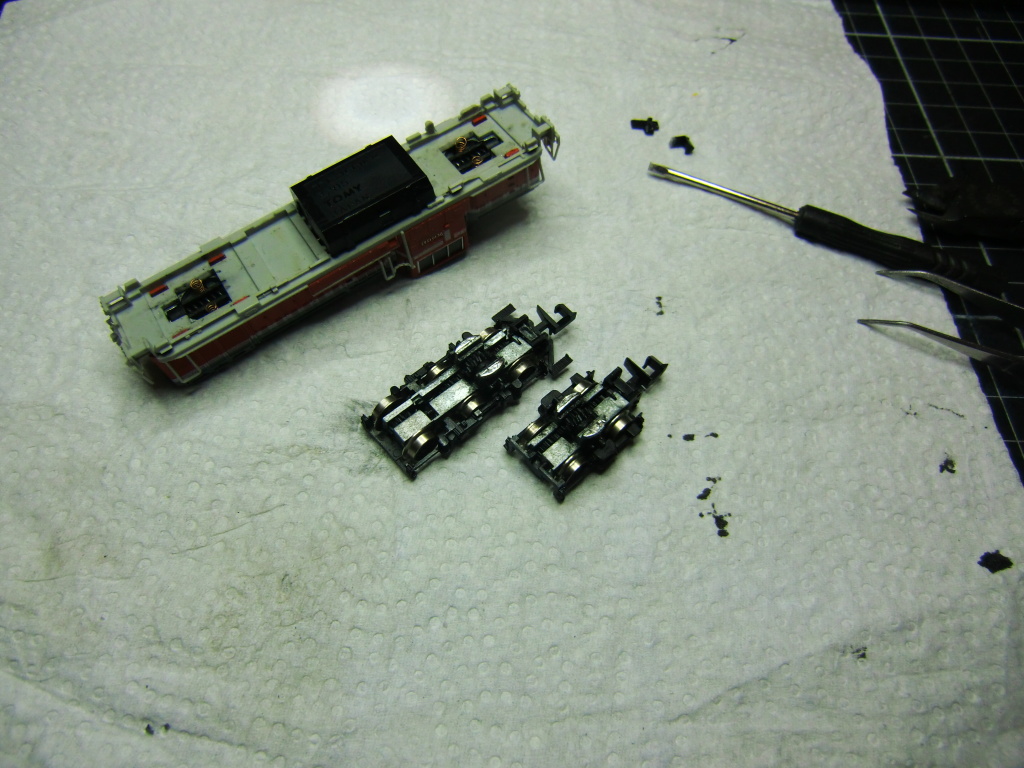
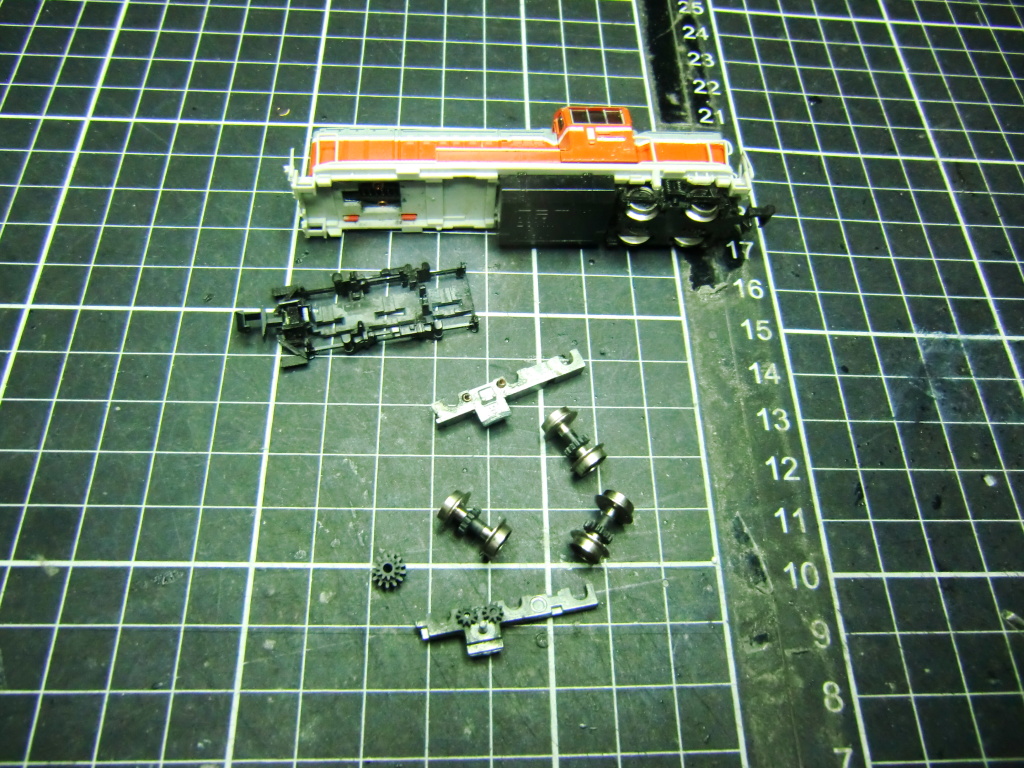
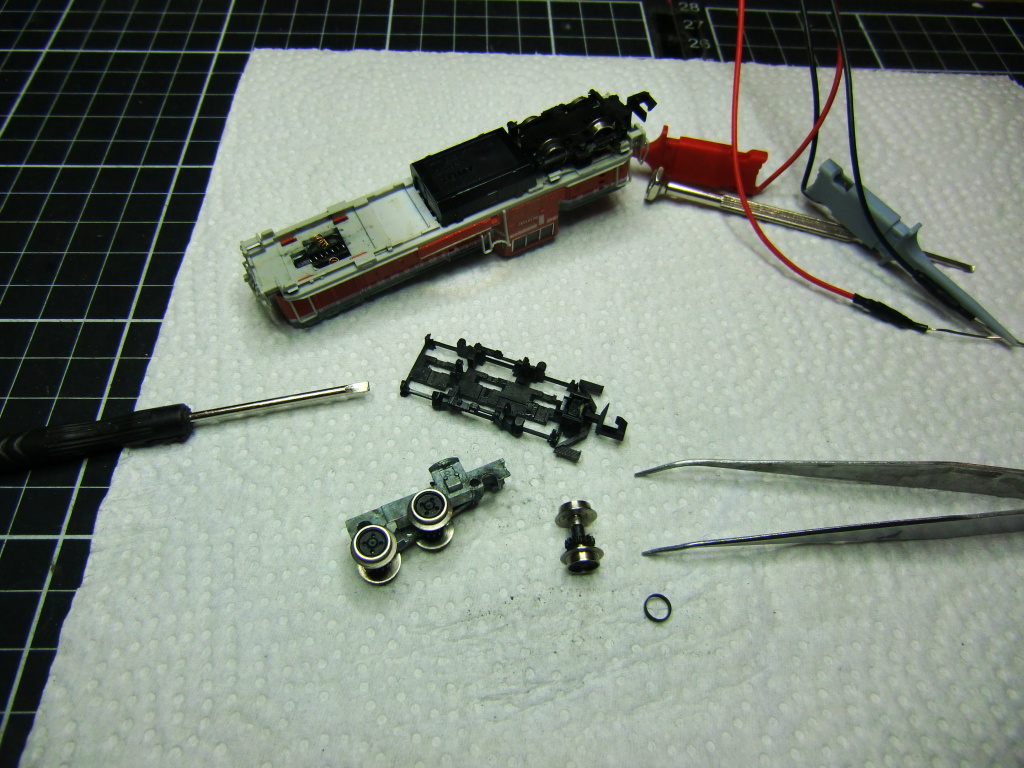
前後の車輪から集電バネまで1つ1つメンテを行って集電系を復活させます。また、前後のトラクションタイヤも共になくなっているので新しいものを取り付けます。
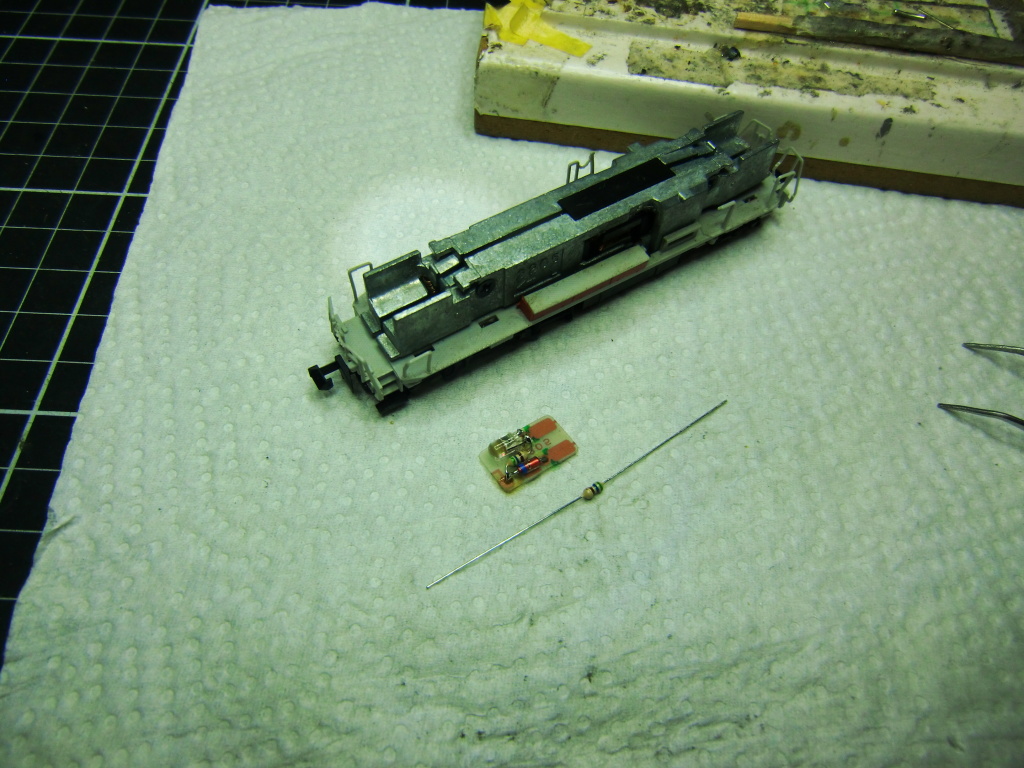
続いて、ご要望のヘッドライトをLED化いたします。
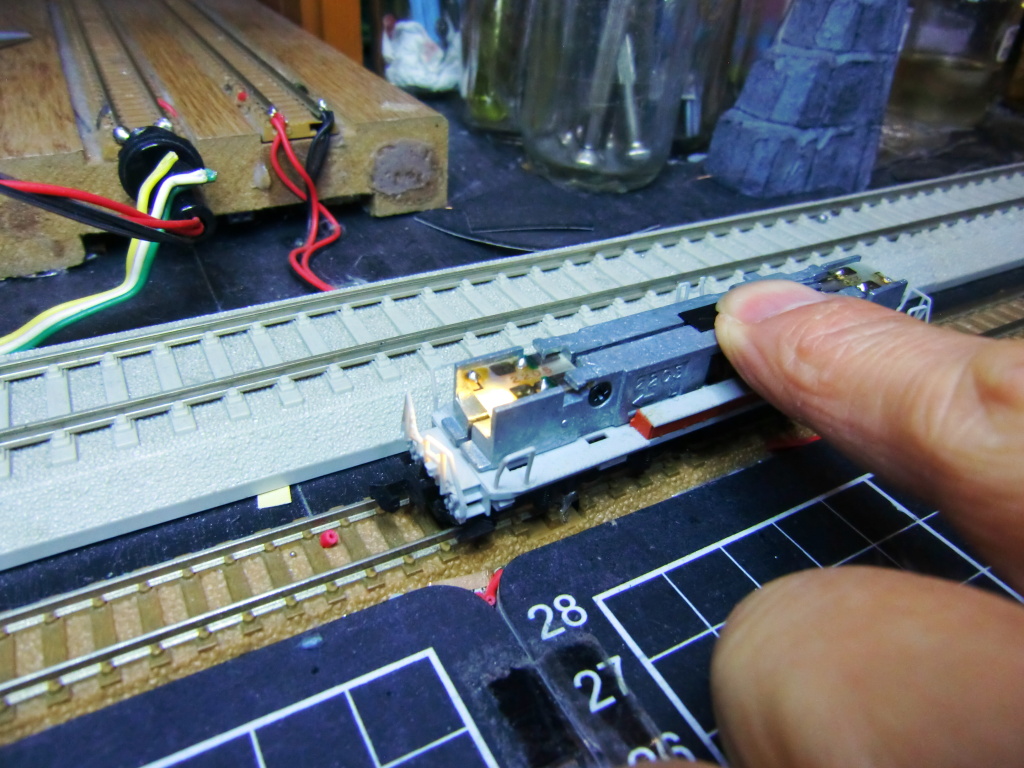

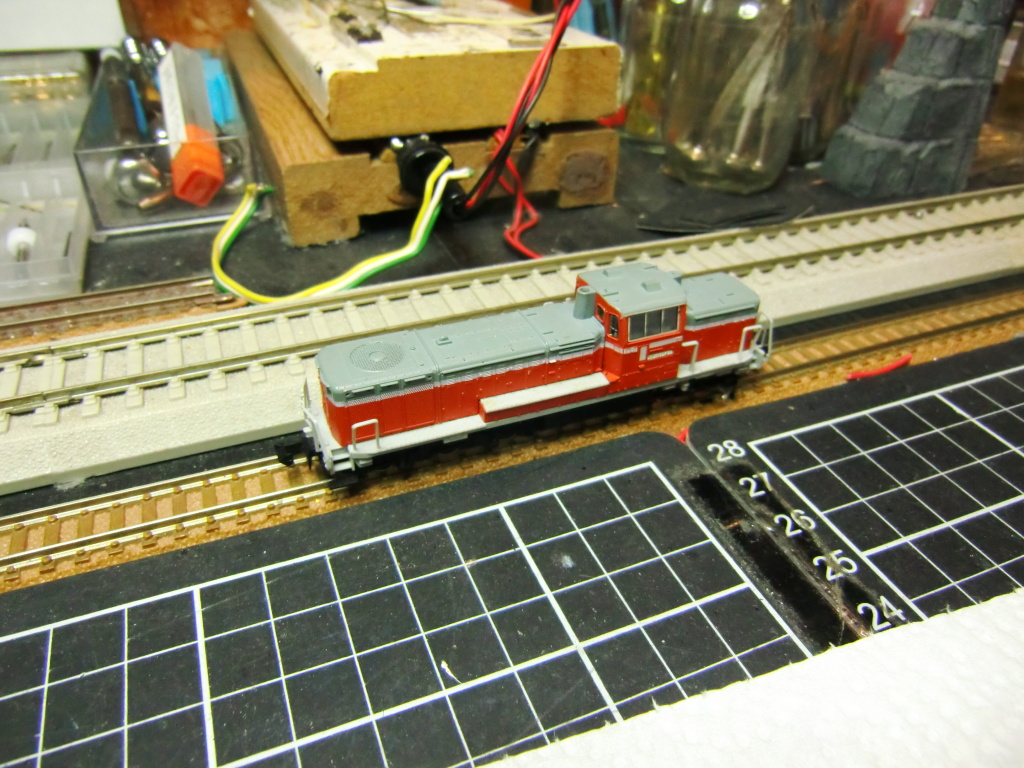
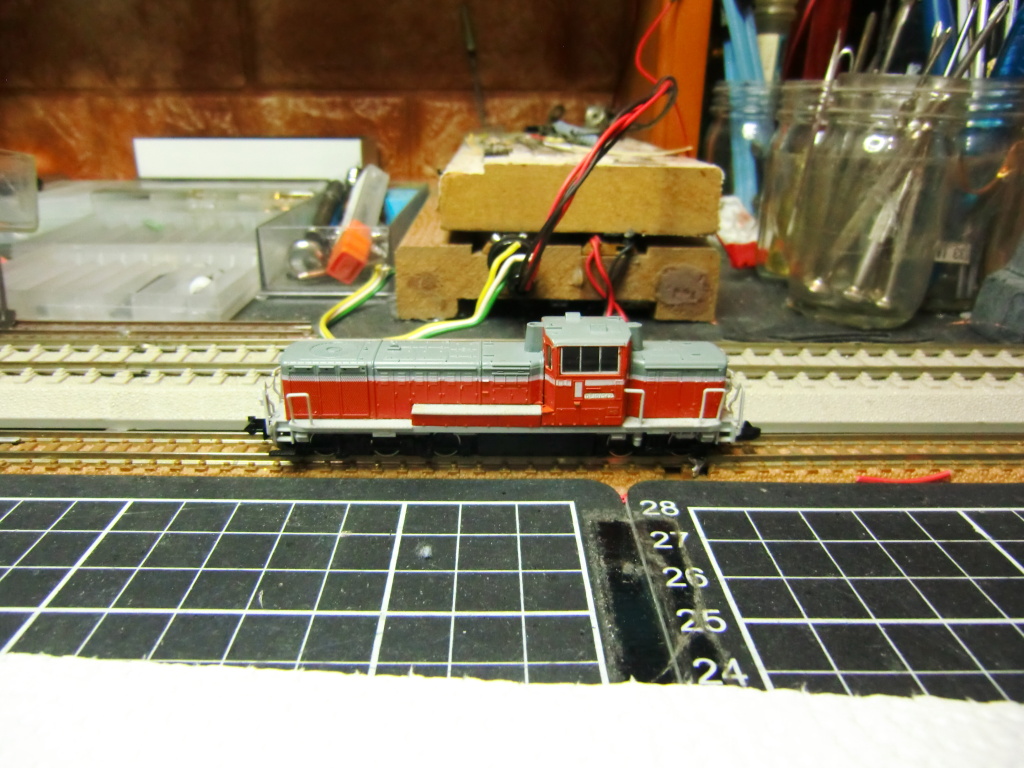
古い製品ということもあり、走りが多少ぎこちない感じもしますが、現状可能な限り対応させていただきました。
▼EF-15 パンタ修理/OH/ナンバー補修


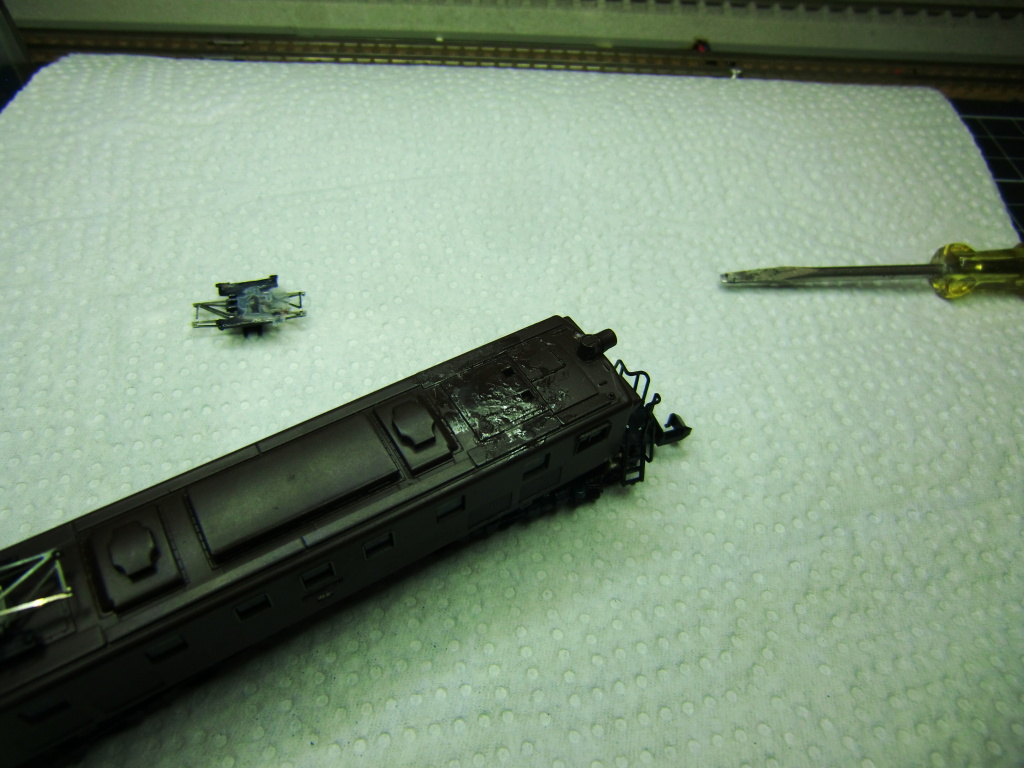
まずは、パンタグラフを外して接着剤を削りだして剥がしていきます。ある程度剥がせた段階で補修の塗装を行いました。



修理完了です。
▼C62逆転棒修理

▼50系屋根グレードアップパーツ

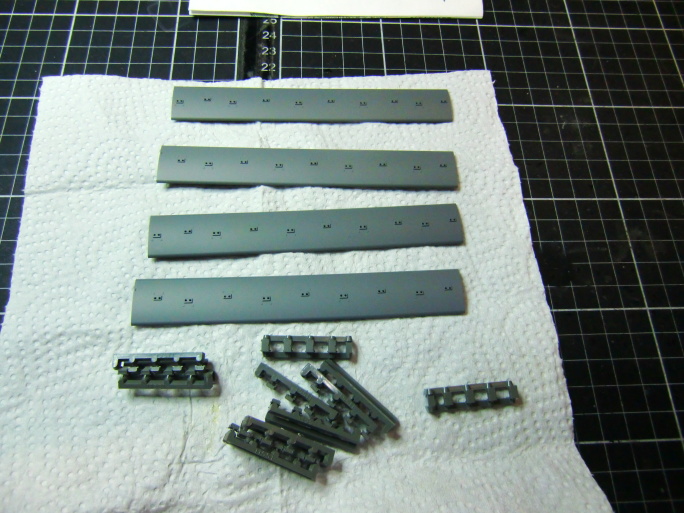
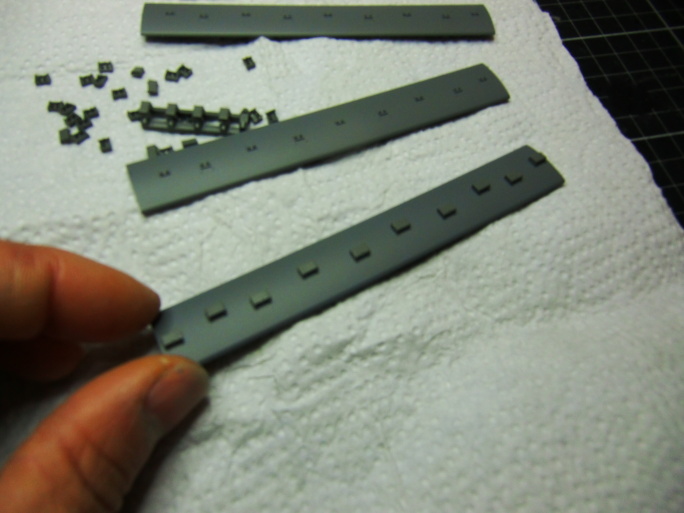
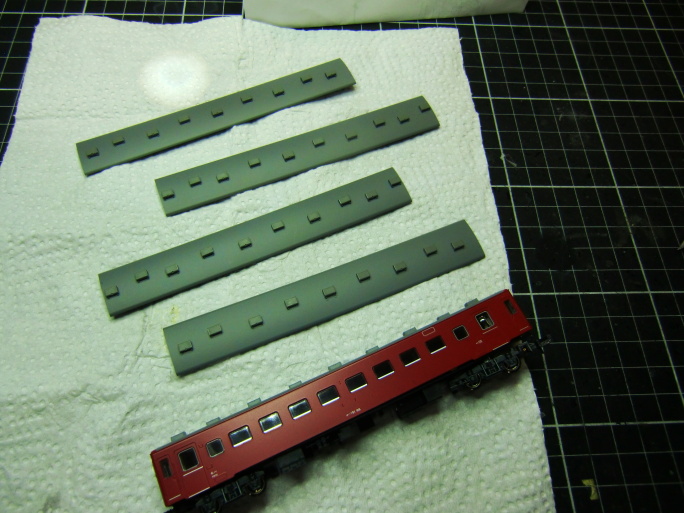


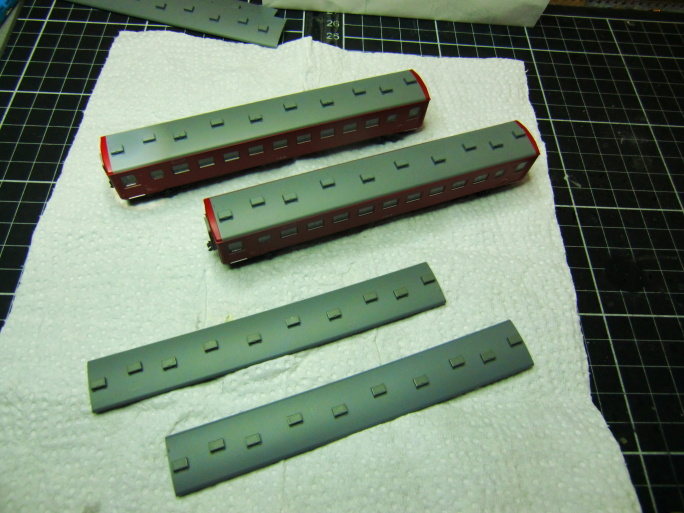
▼マニ50 テール両点灯/室内灯点灯/修理他


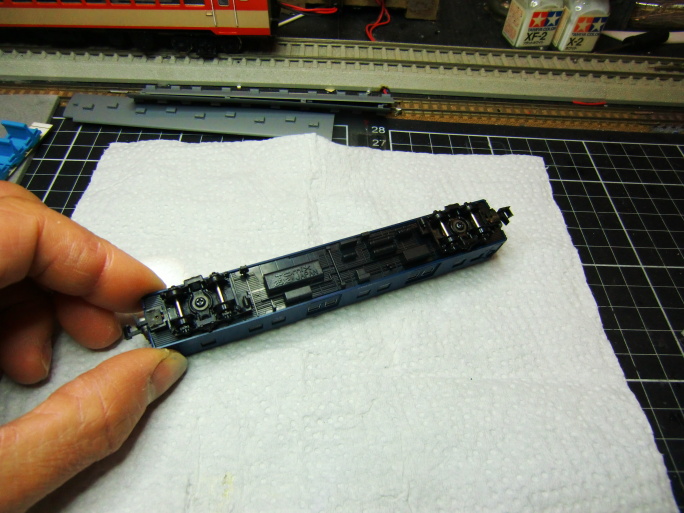


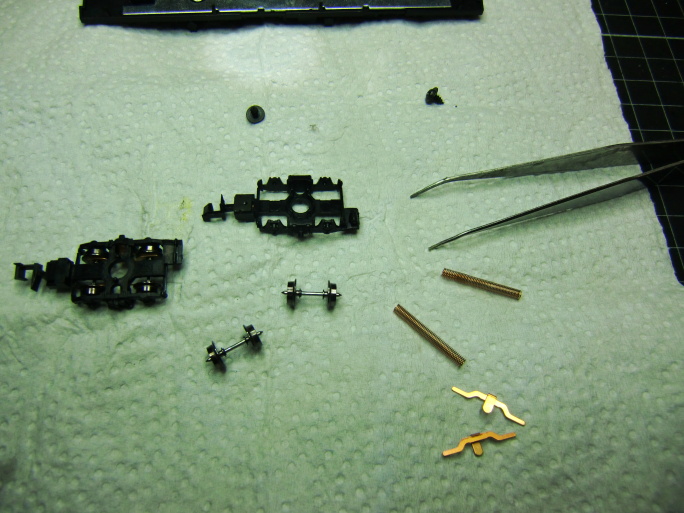
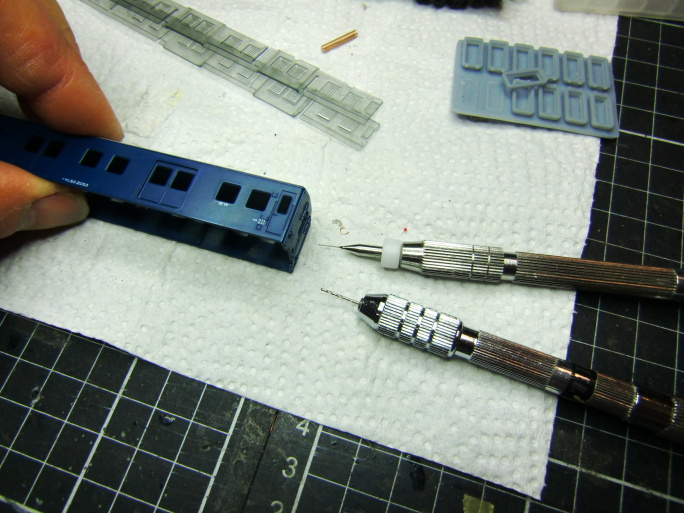
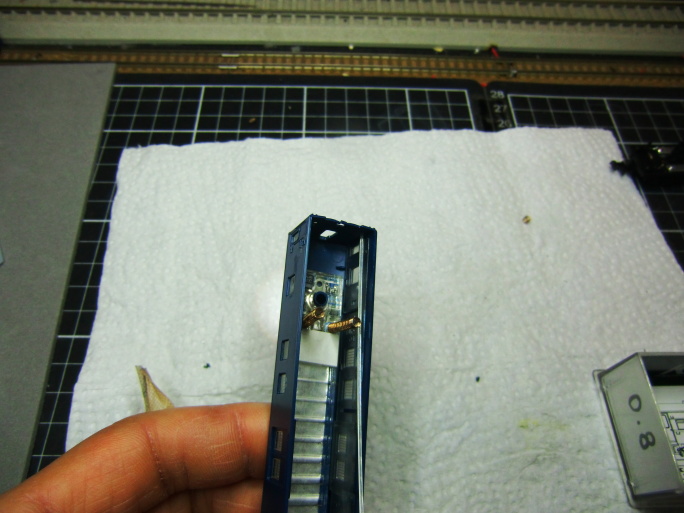
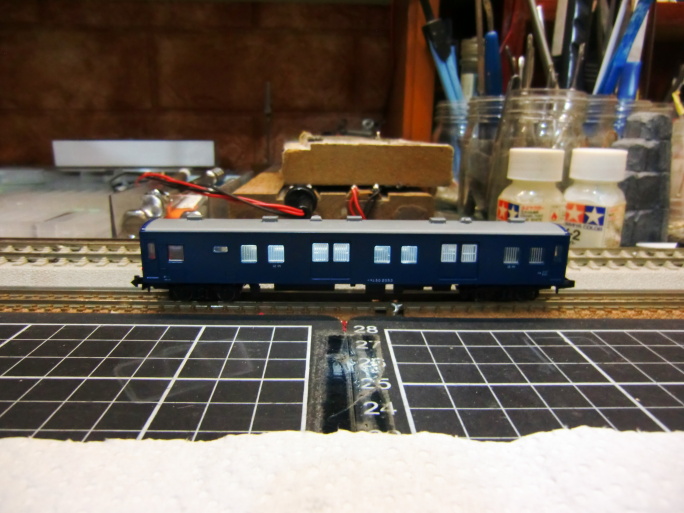


作業完了です。
今回のご依頼者さまのご要望は3つ。後進時の運転席点灯、ライト周りの黒塗装、そして全車内面の遮光処理です。


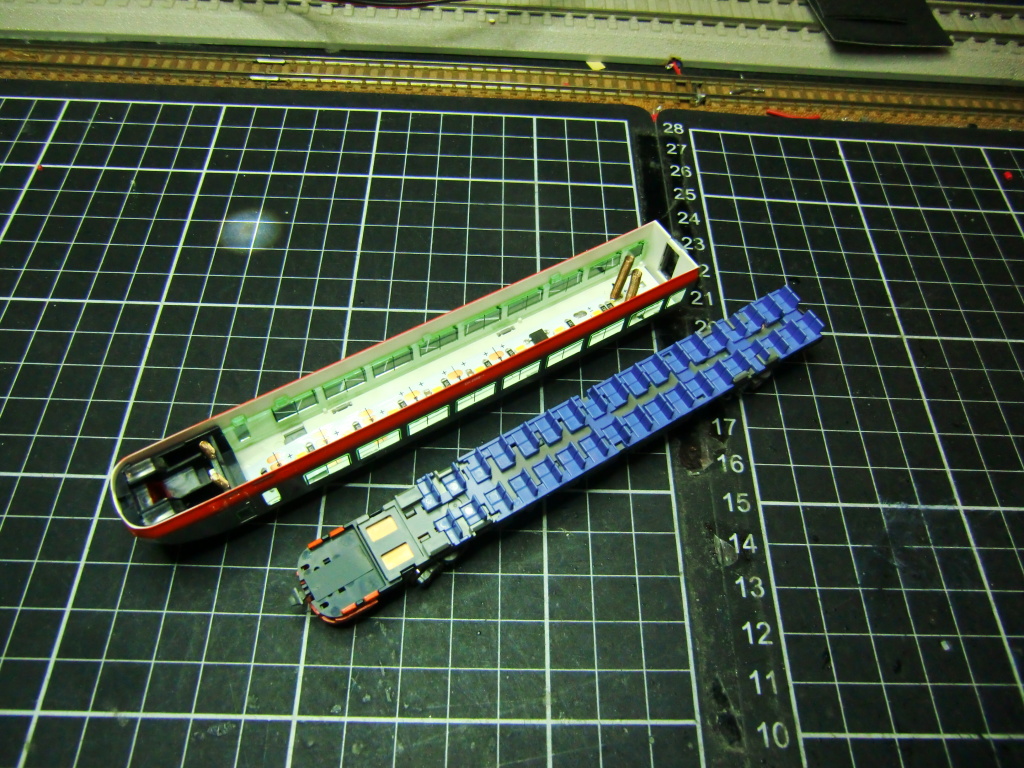
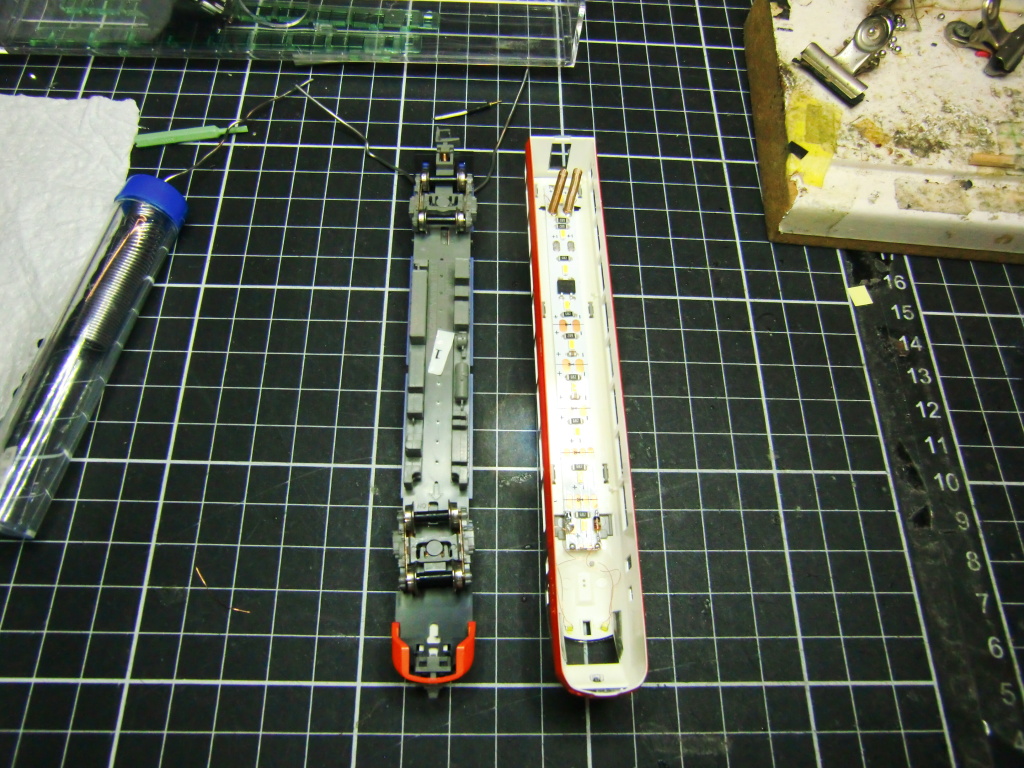
こちらの車体では、中央にユニットが大きく張り出しているため、左右それぞれに光源を設ける必要がありました。天井部に左右それぞれにチップLEDが設置されたのがわかると思います。
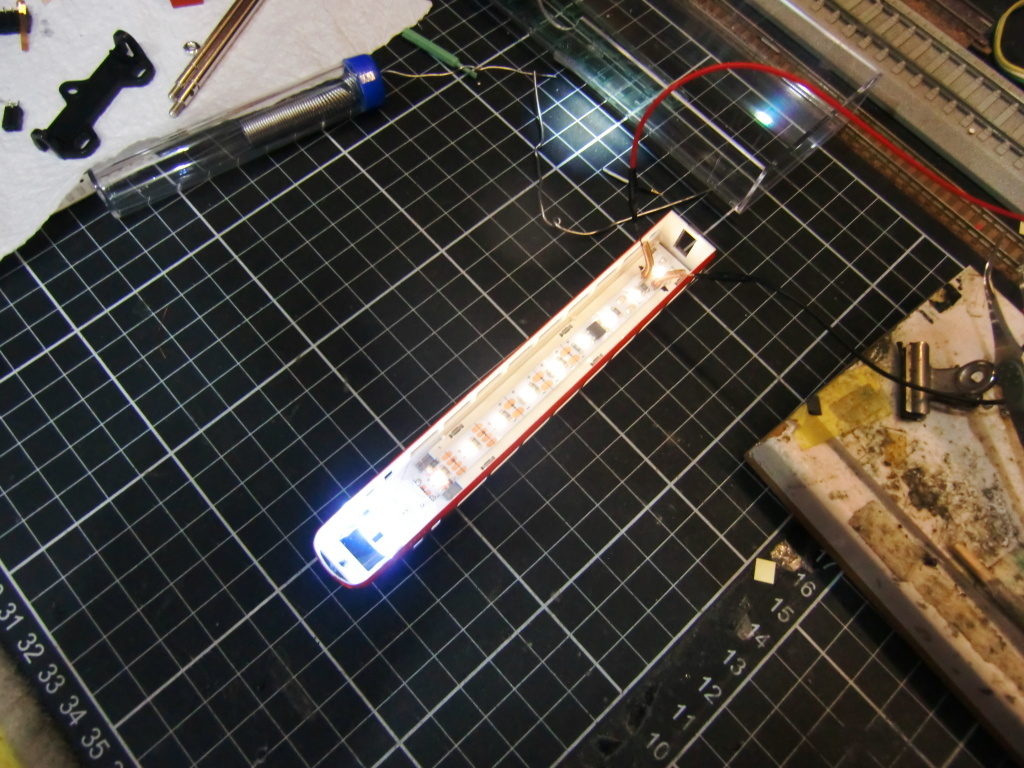
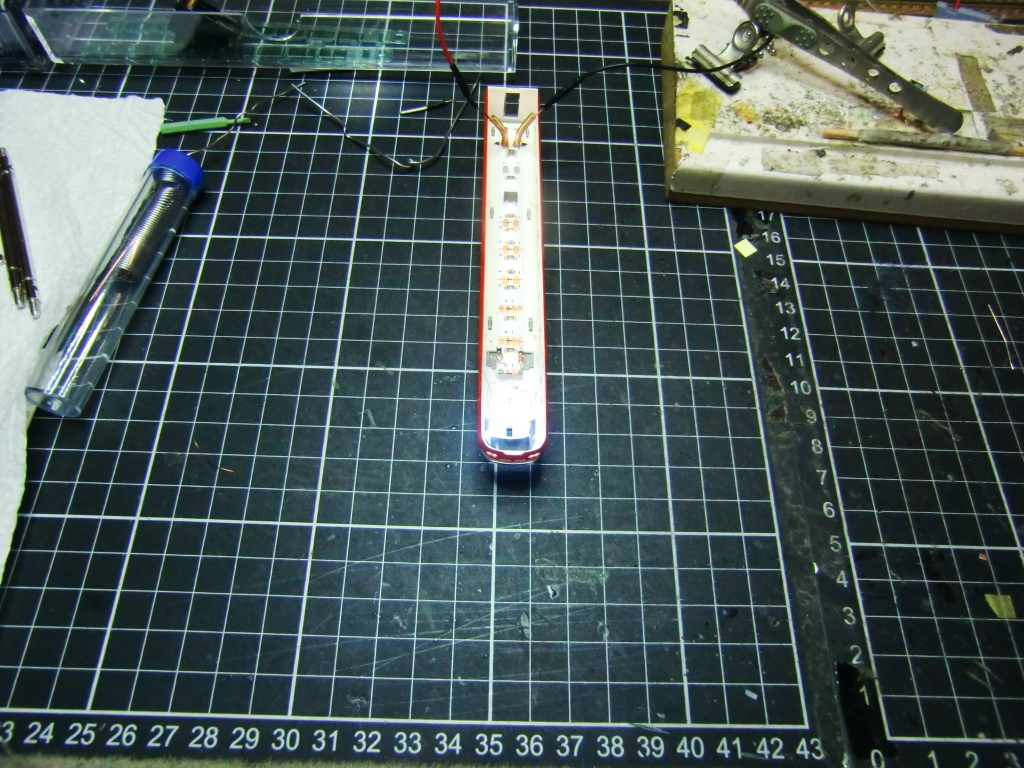
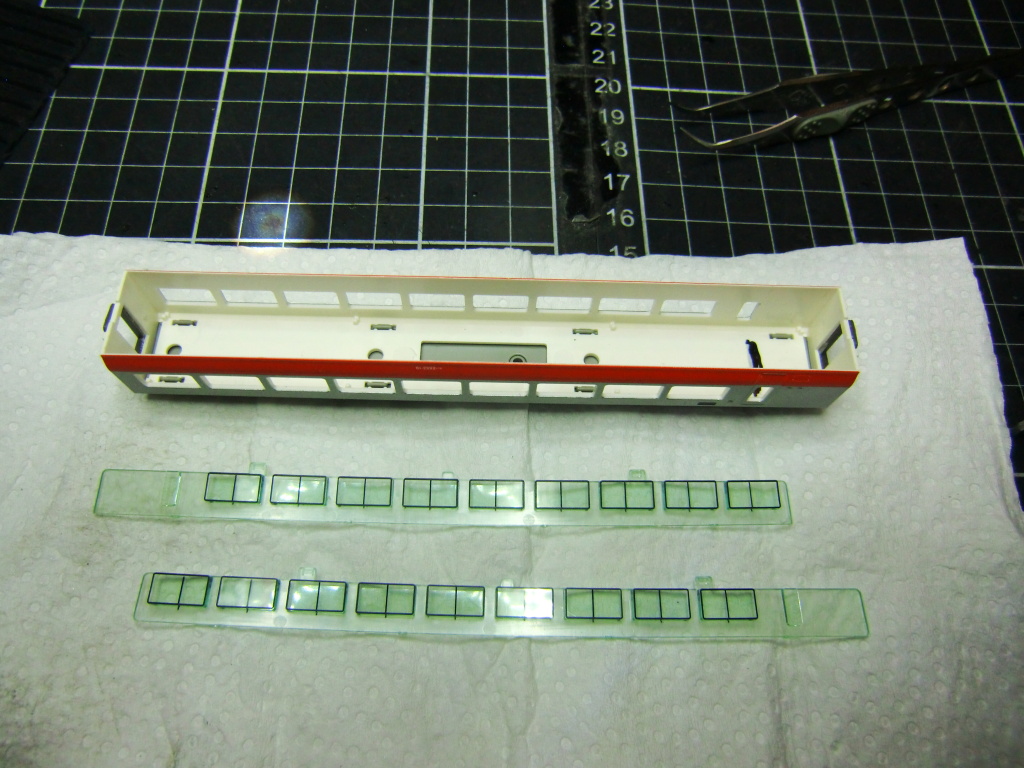
続いて遮光シートの制作ですが、まずは全車スキャンして素材を切り出します。
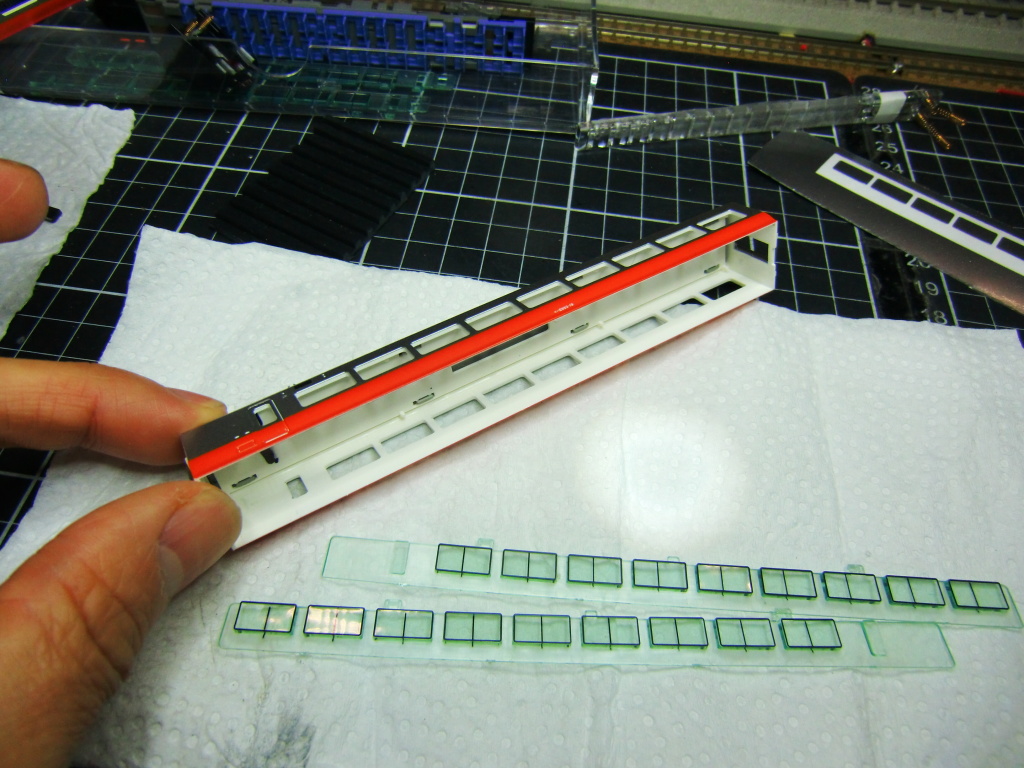
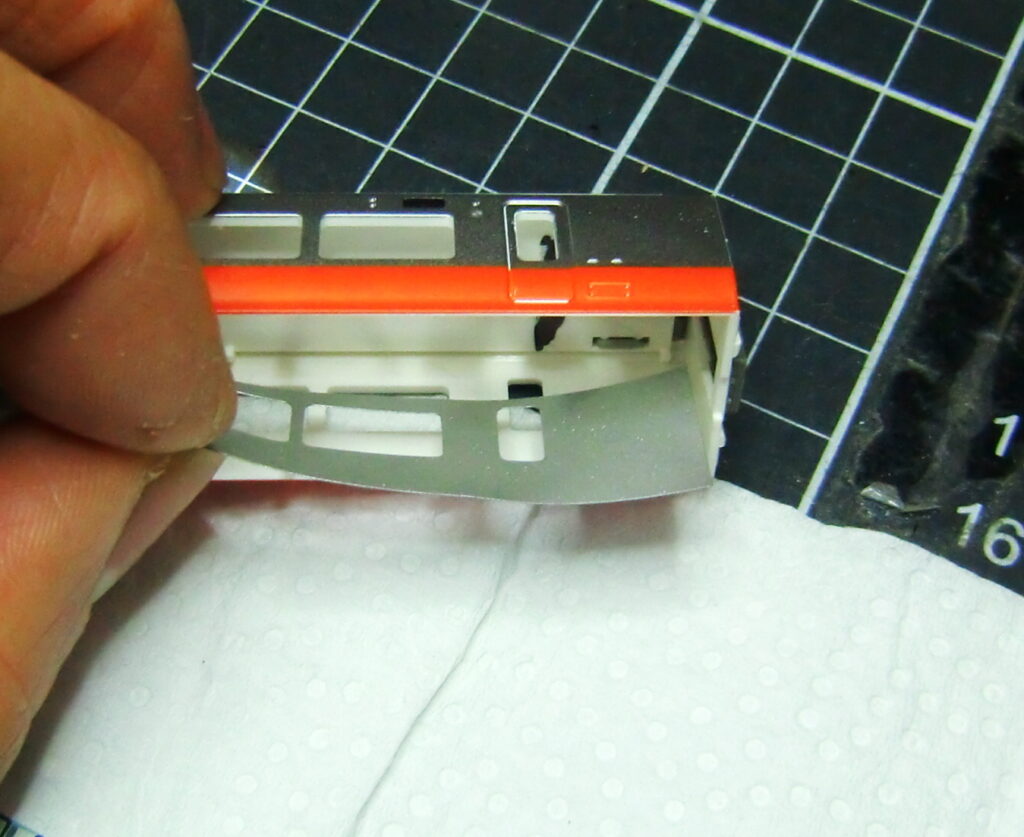
このように個別の遮光シートができましたので、内面から貼っていきます。
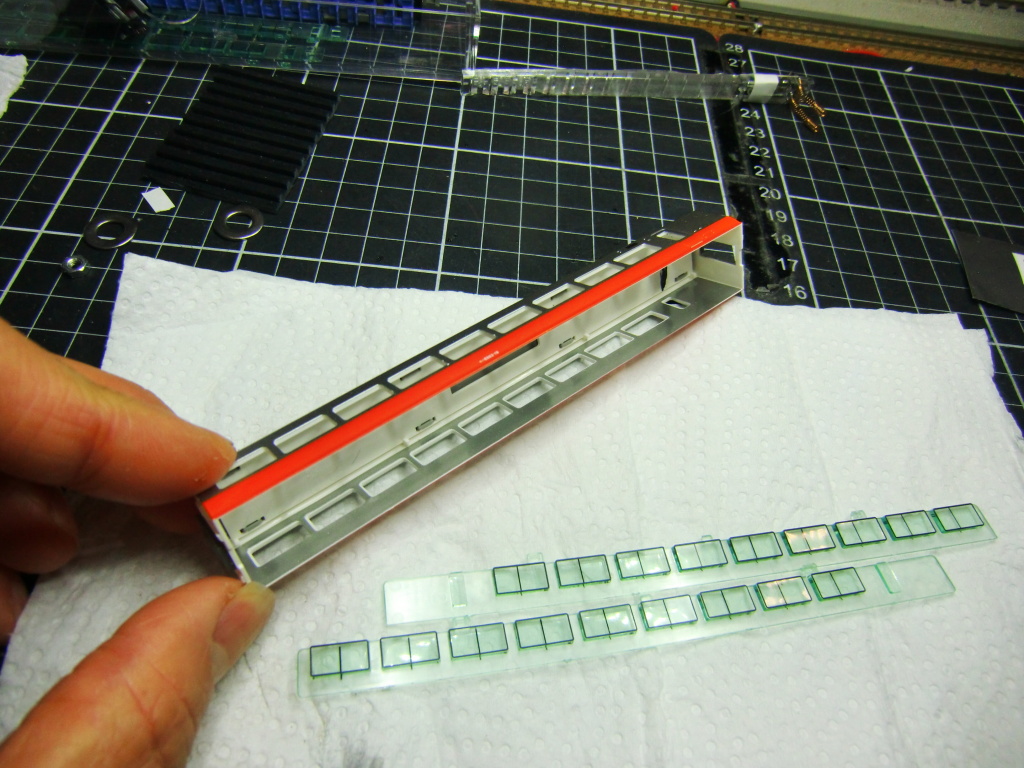
このようになります。これにより明るめの室内灯でも車体が透けることはありません。
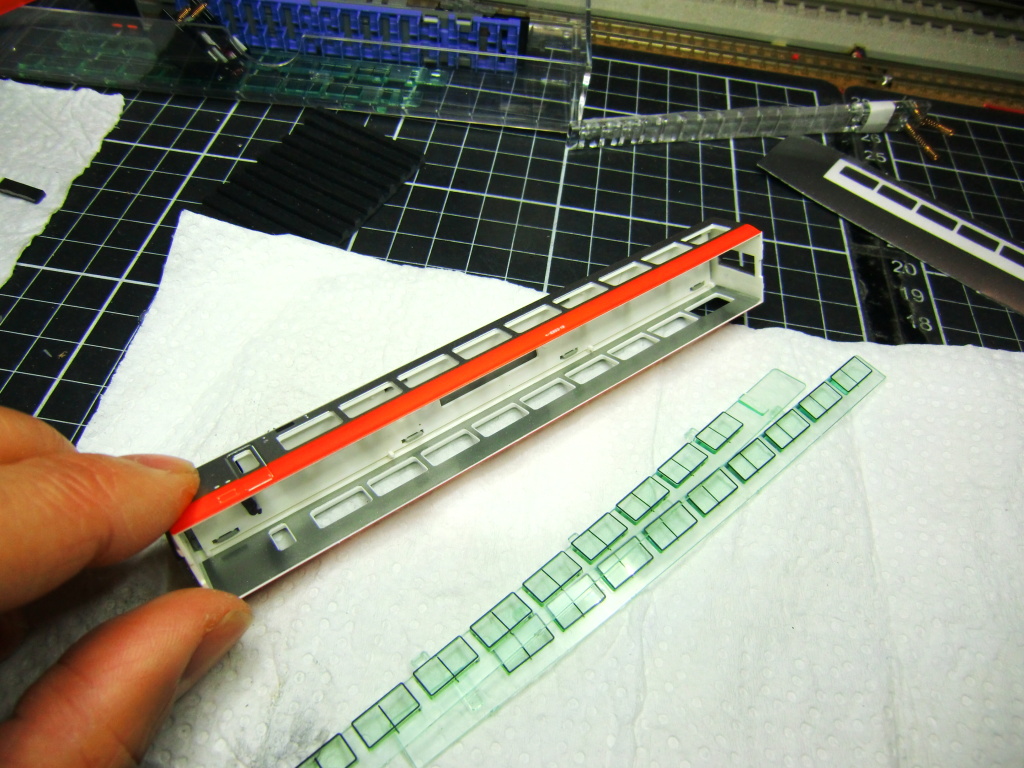
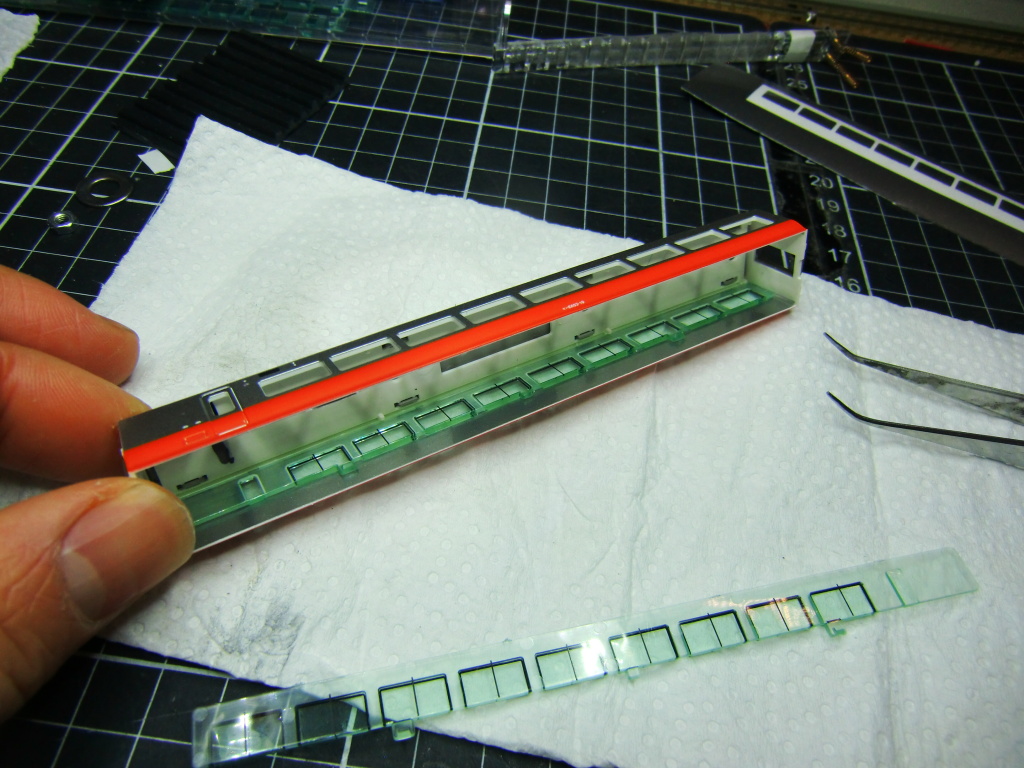
シートも薄くしっかりと車体に貼りつくため、窓ガラスをはめ込む際も、きつくて入らなくなることはありません。
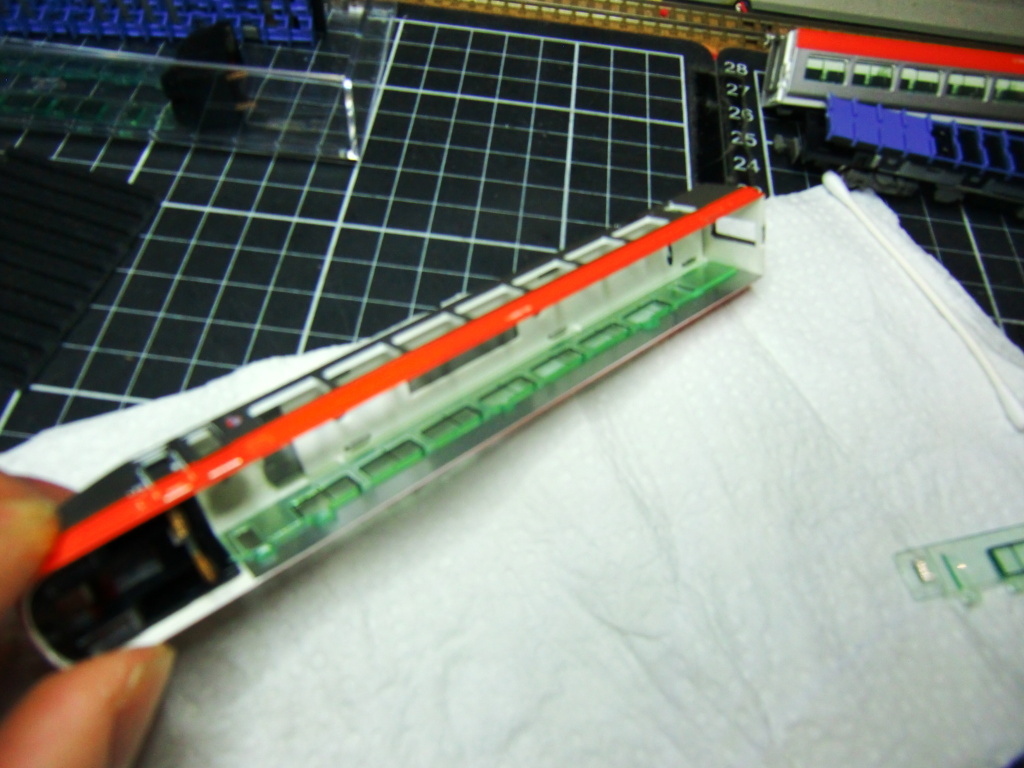
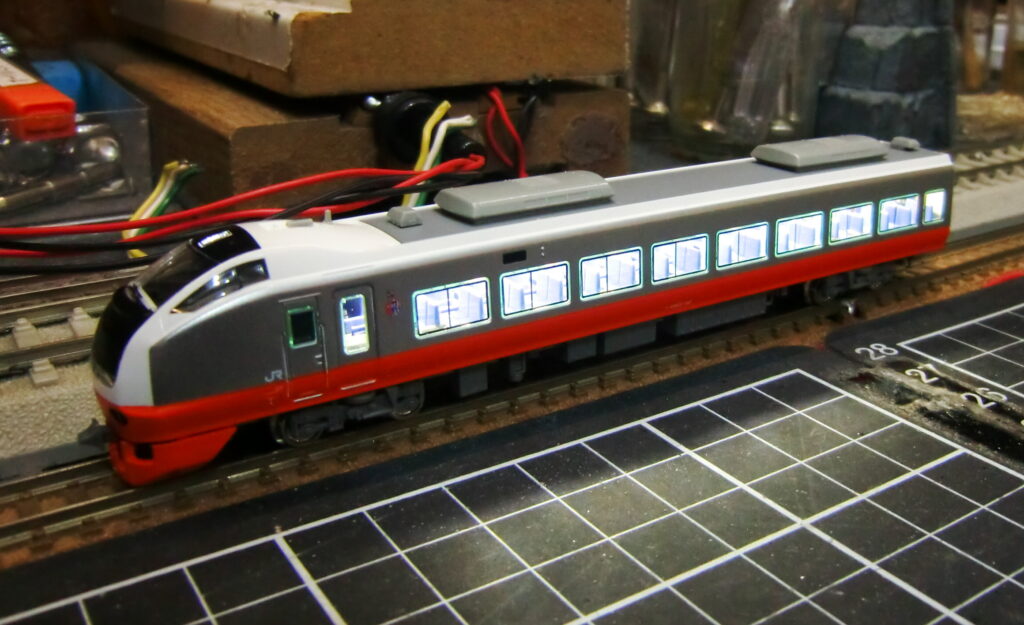





作業完了でございます。
今回の作業は、異なる製品のボディーと床板を被せられるように加工してもらいたいとのご依頼でございます。
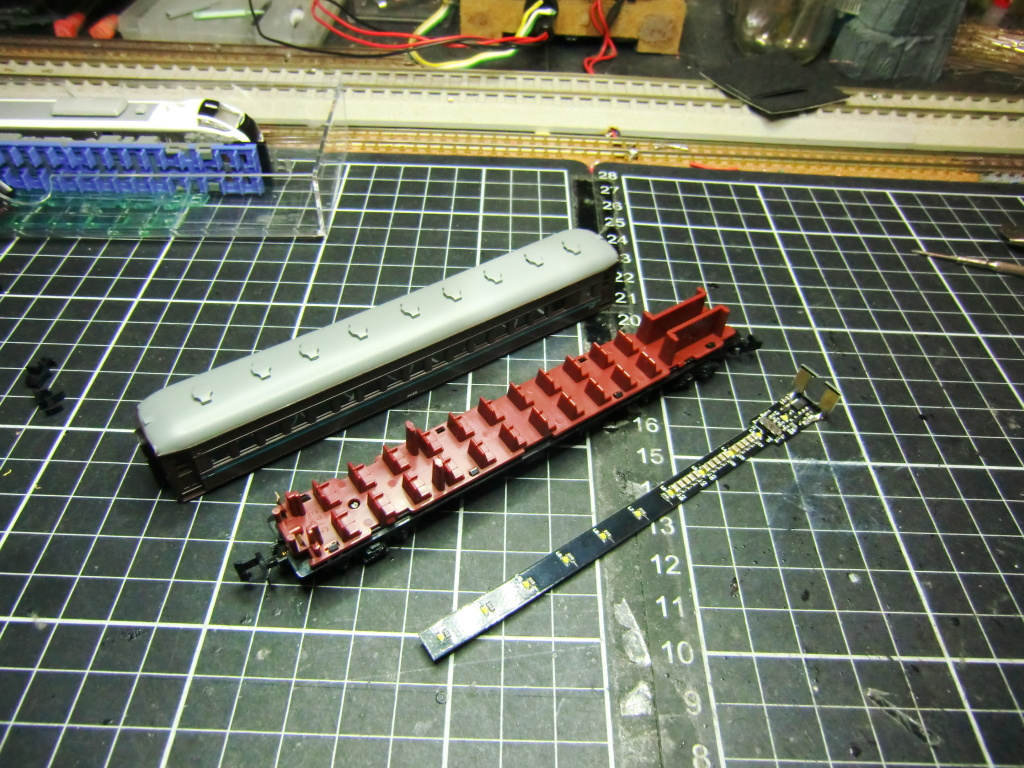

まず、そのままでは全然収まりません。かなり削り込む必要がありそうです。
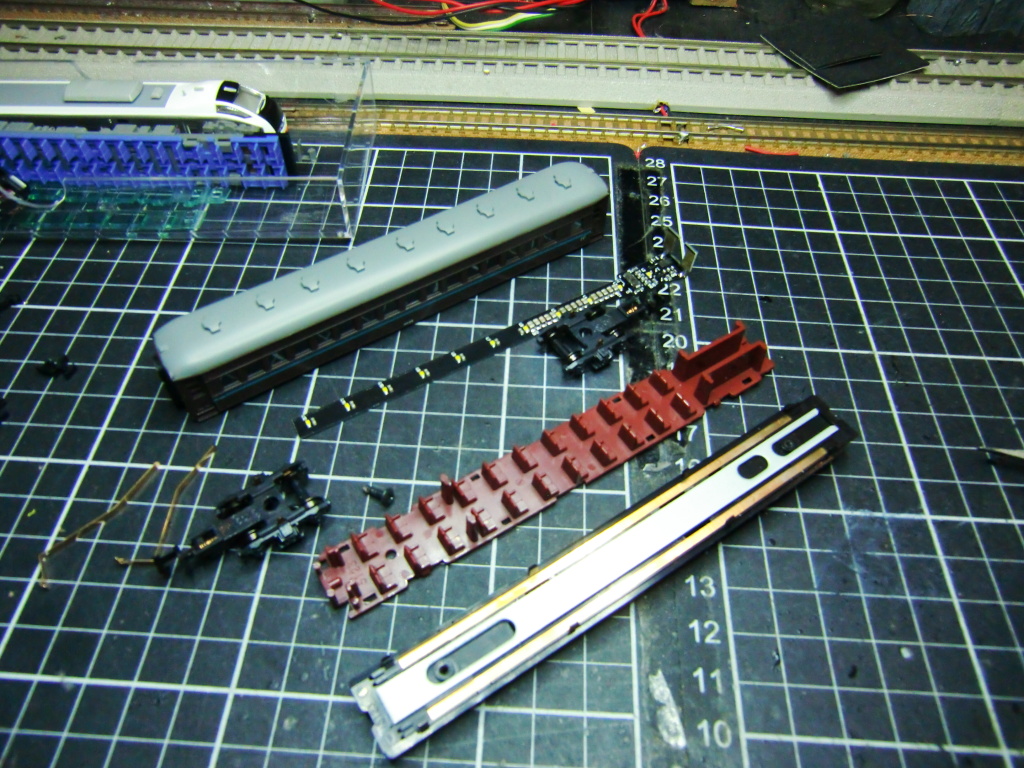
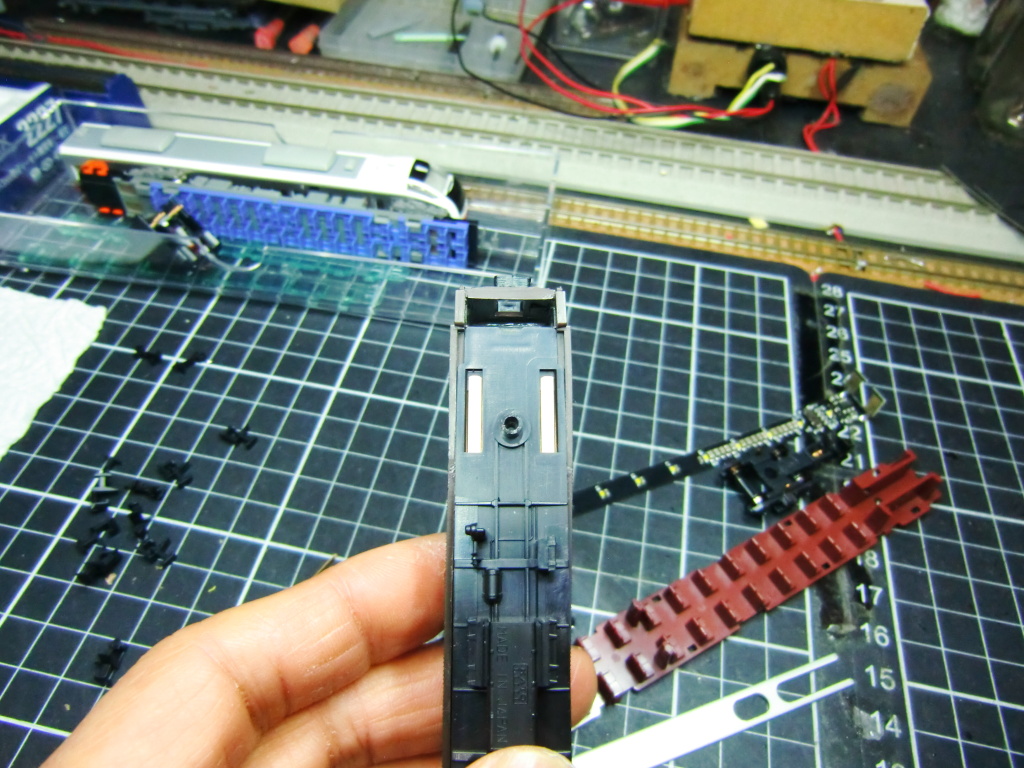



削って確認また削るを繰り返します。

反対側もニッパーで切れ込みを入れます。

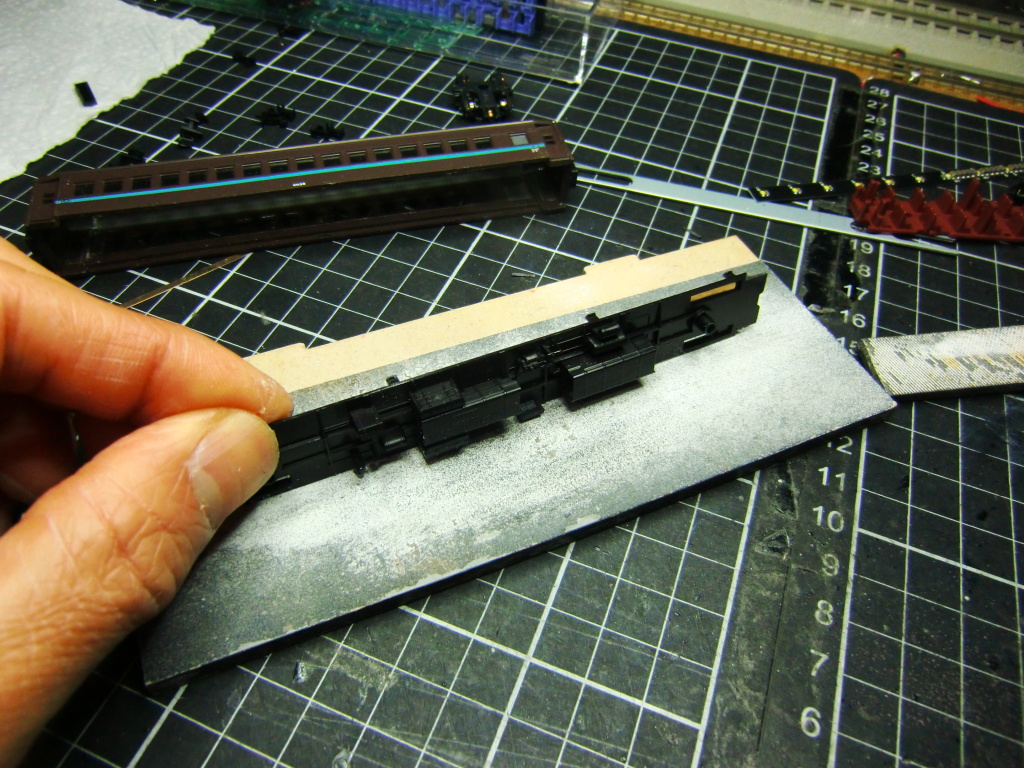
左右それぞれ1mmていど削ります。
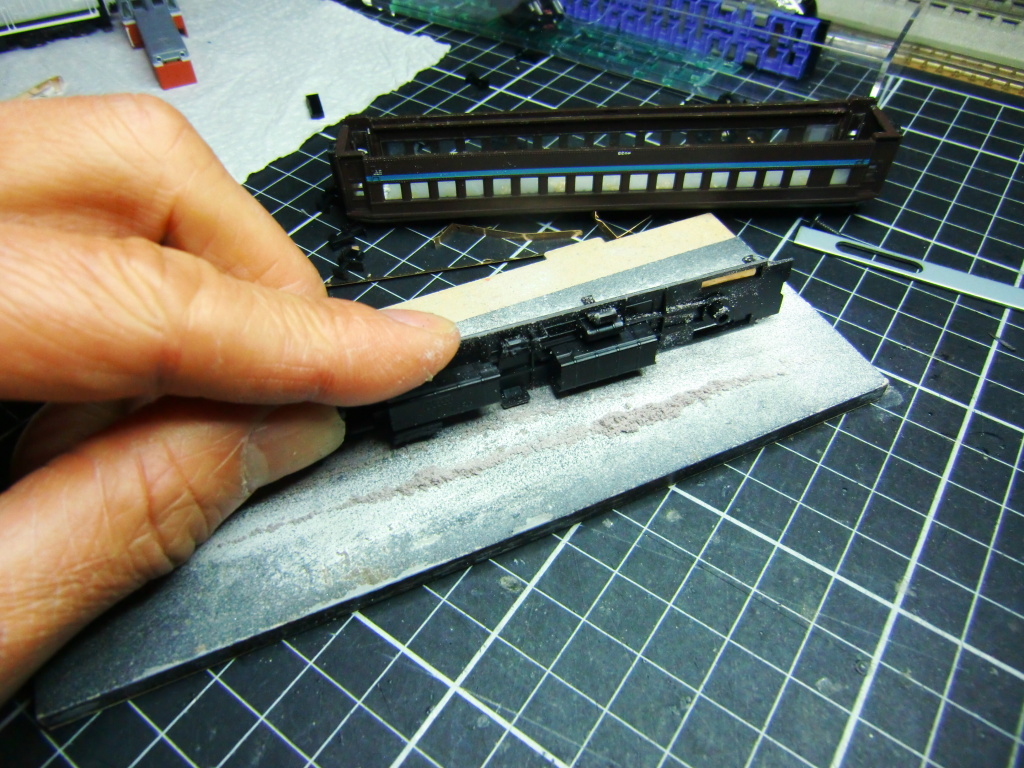
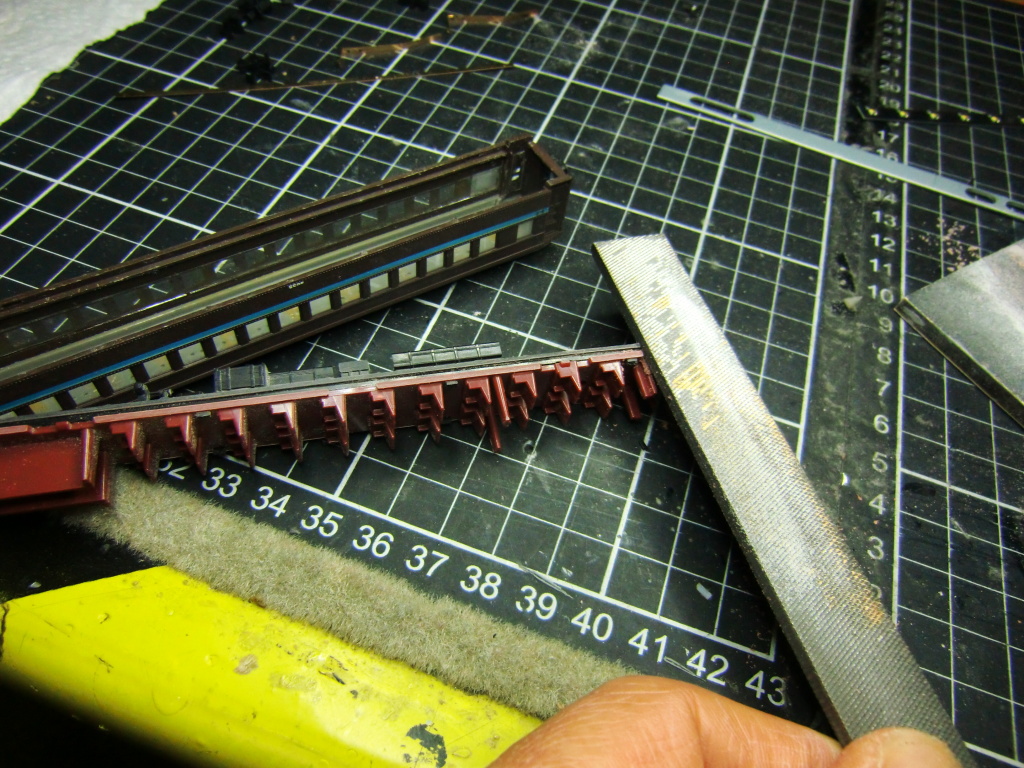

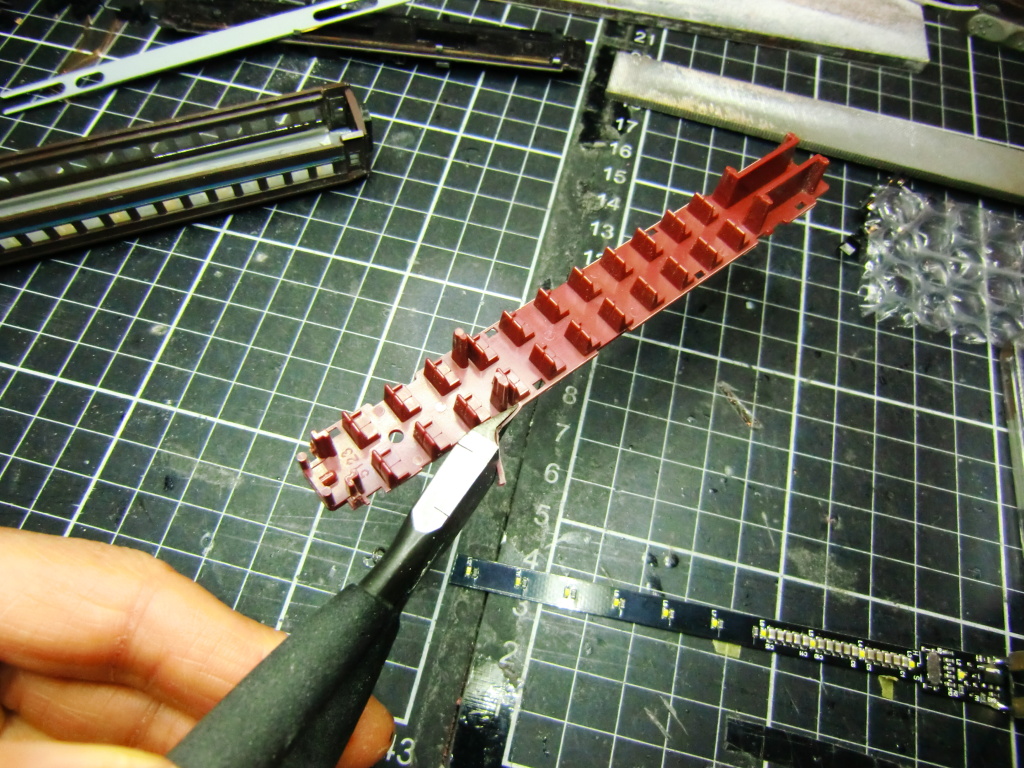
床上の出っ張りはすべて切り落とします。

切り取った面をきれいに成形します。
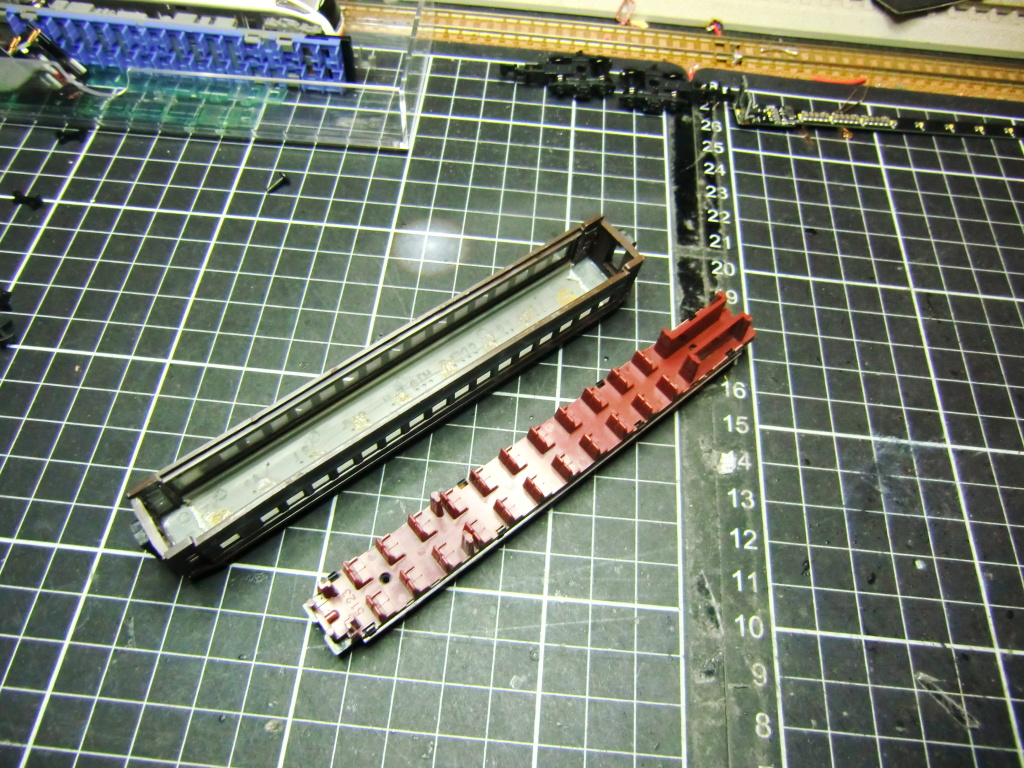
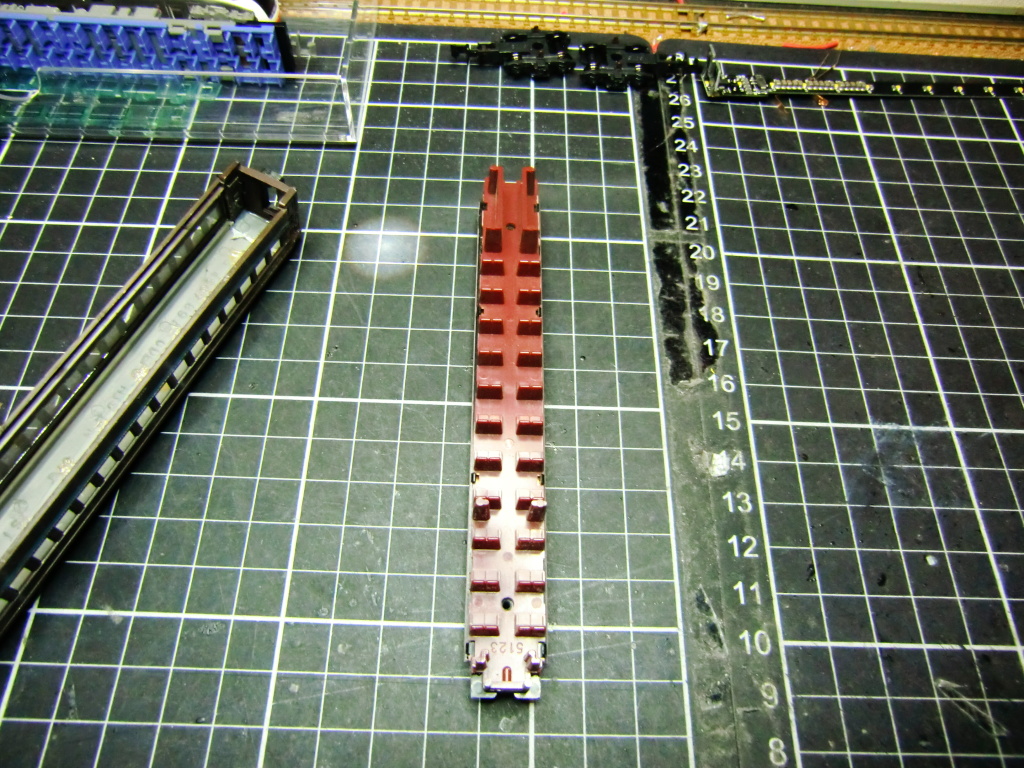
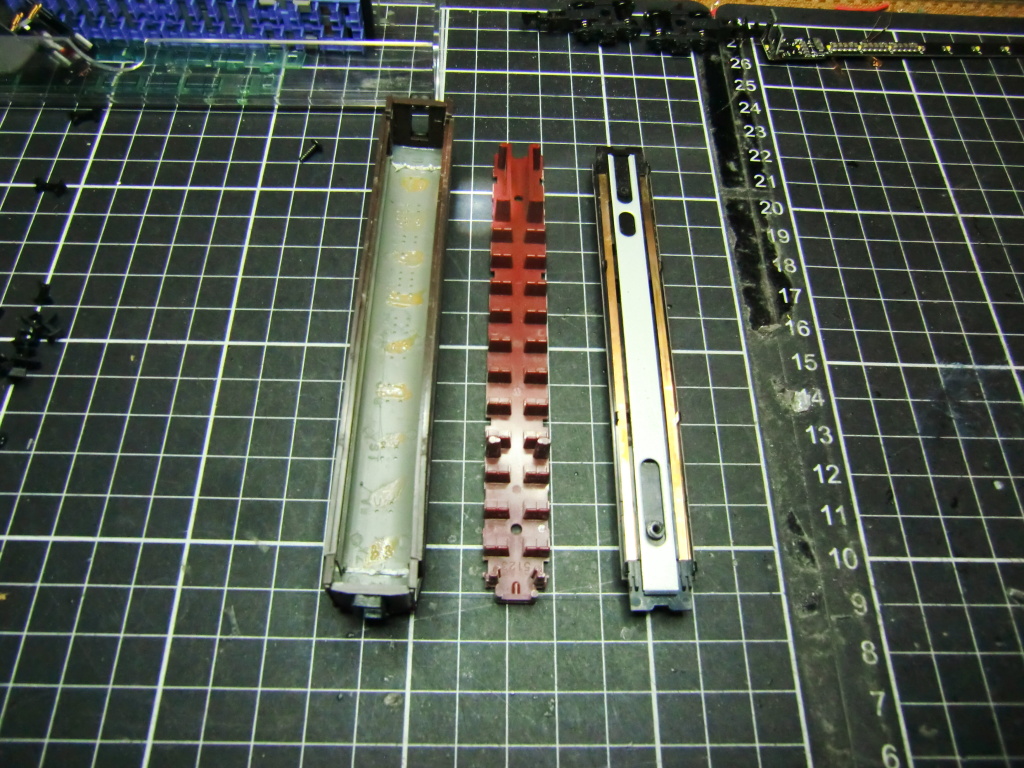
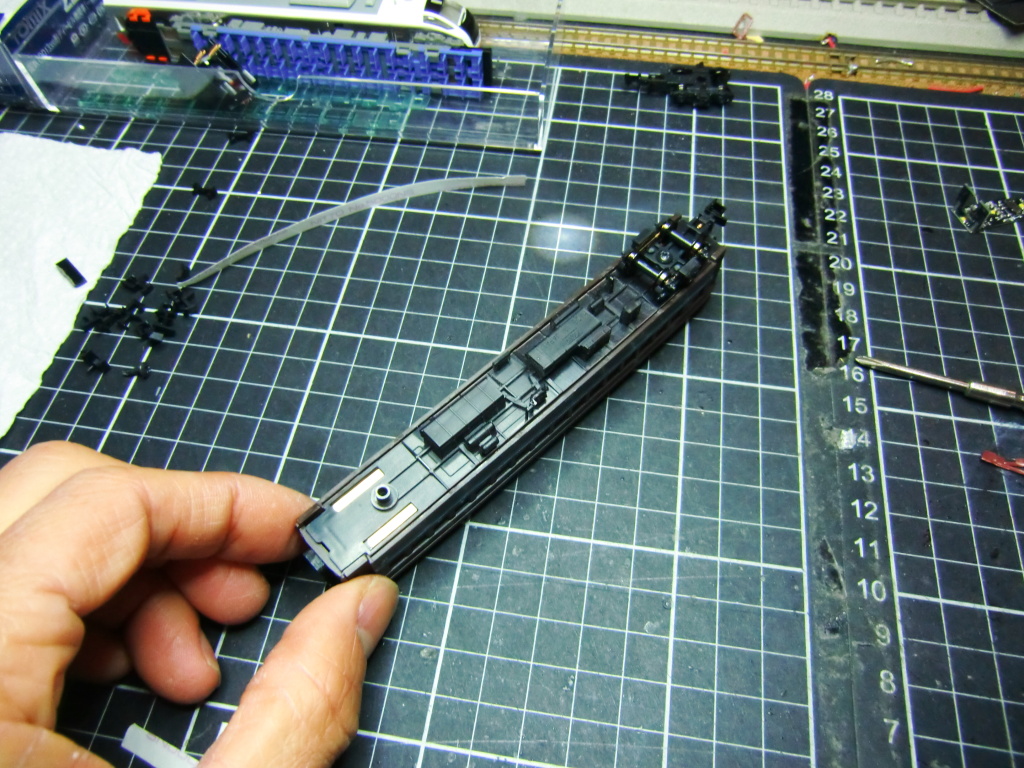
ぴったり収まりました。
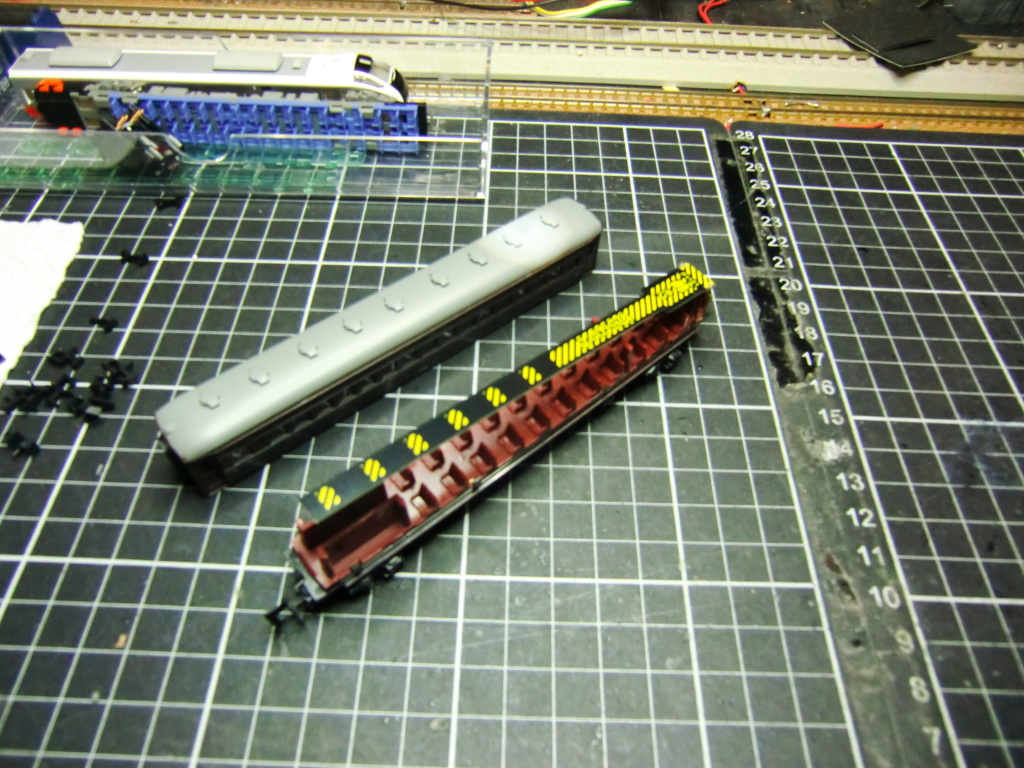
最後に室内灯ユニットを組み込んで完了となります。
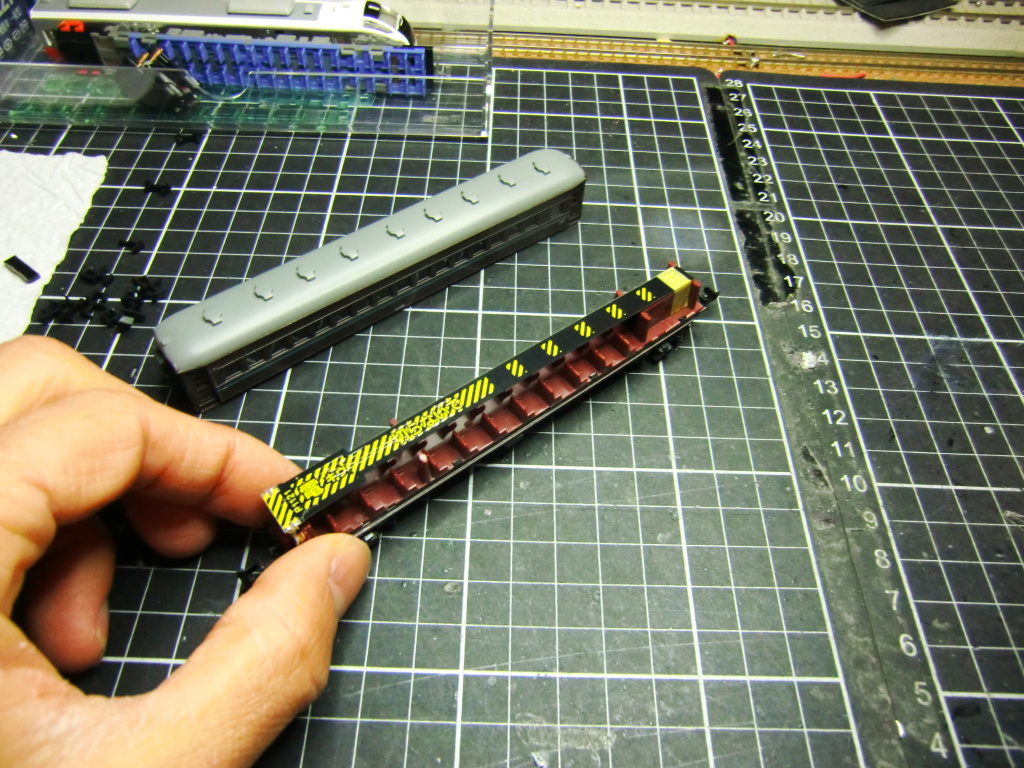
先っちょをマスキングテープで固定します。
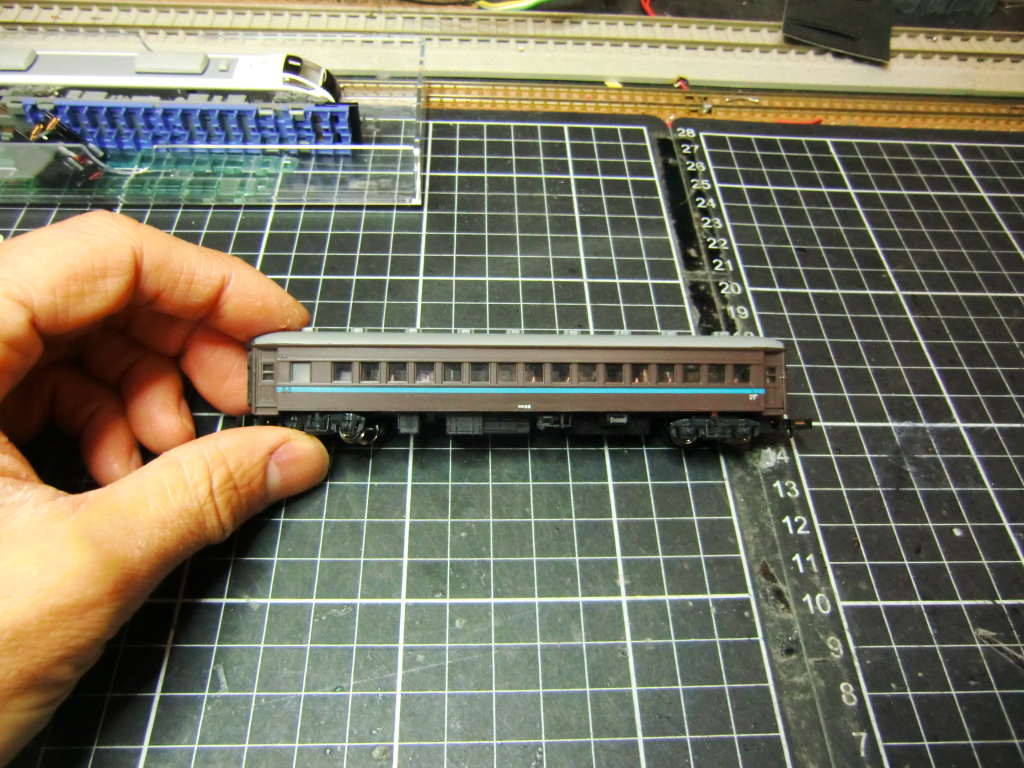
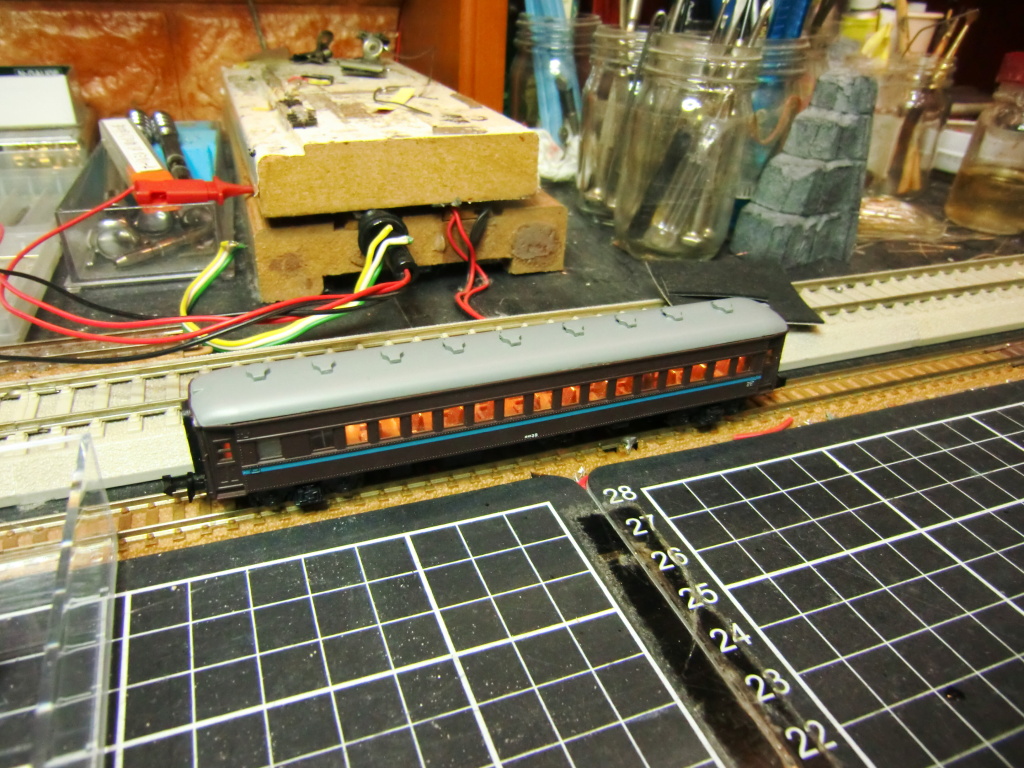

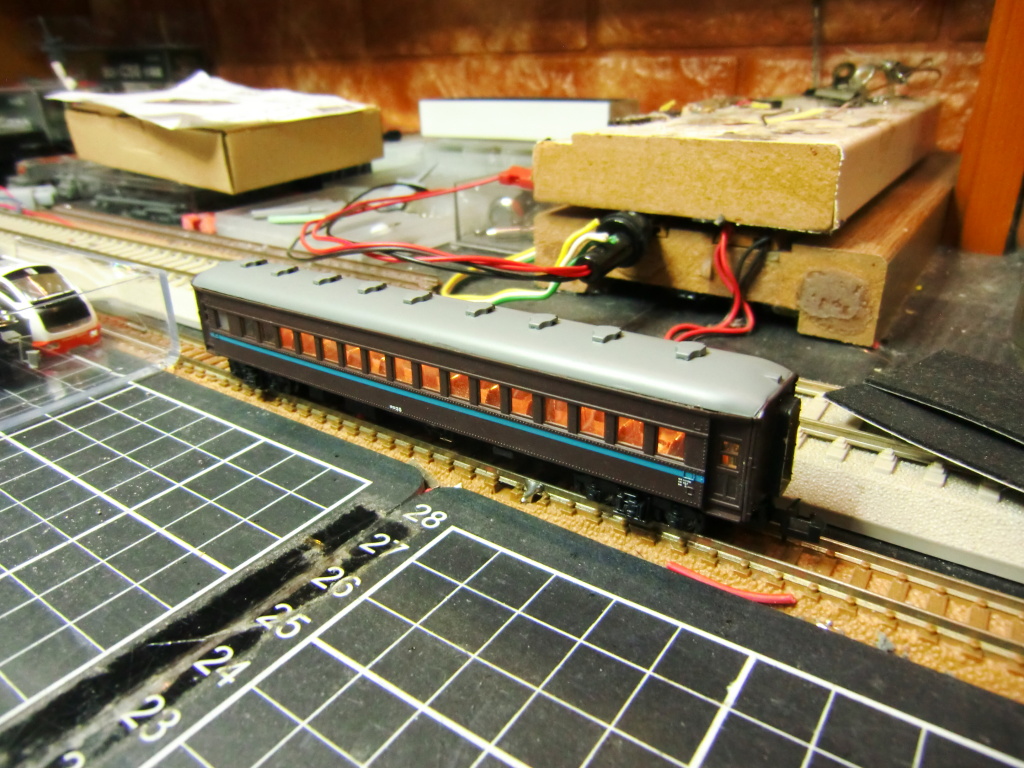
作業完了でございます。
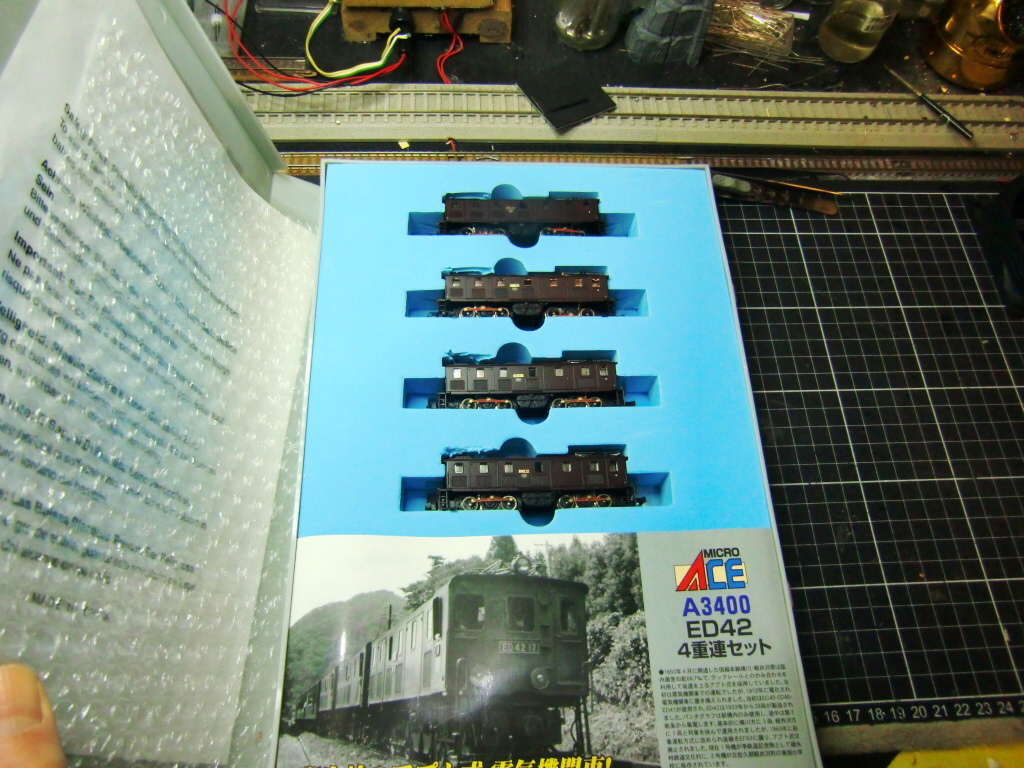
こちらのカプラー交換の作業も完了いたしました。
今回は、ご自身で車両加工される方向けのパーツ制作のご依頼でございます。
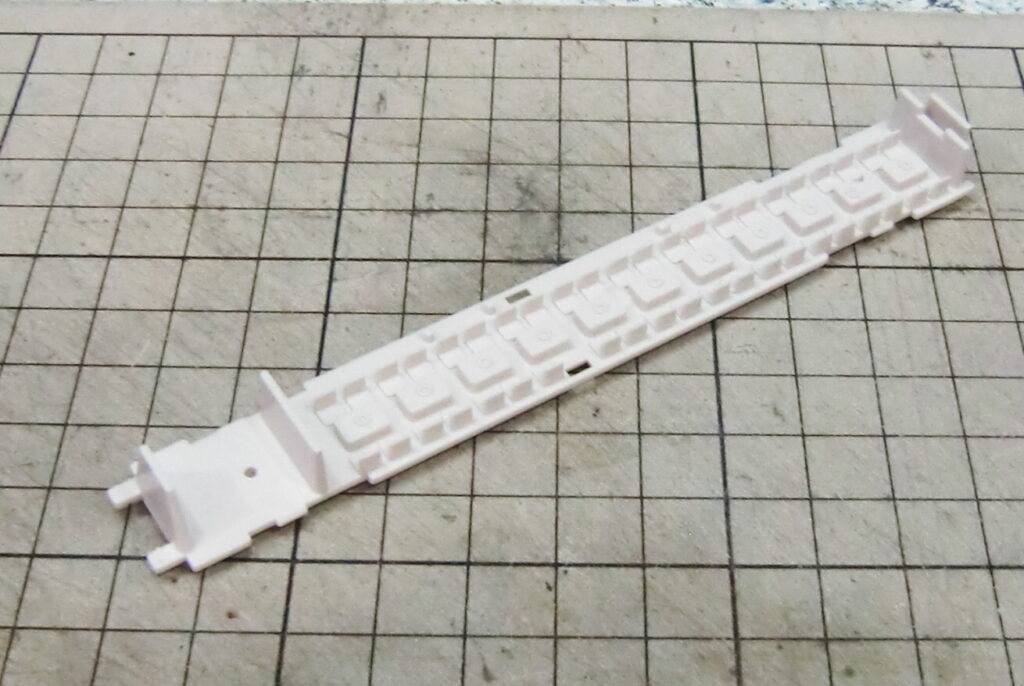

座席部分の寸法を測ります。
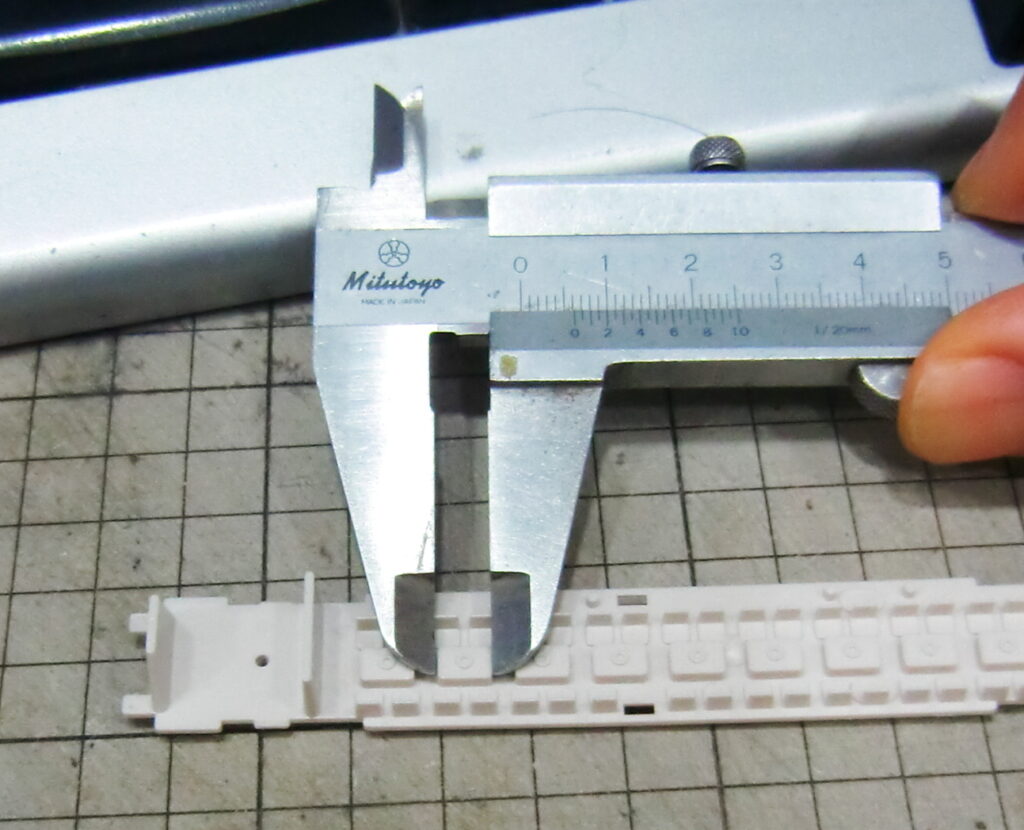
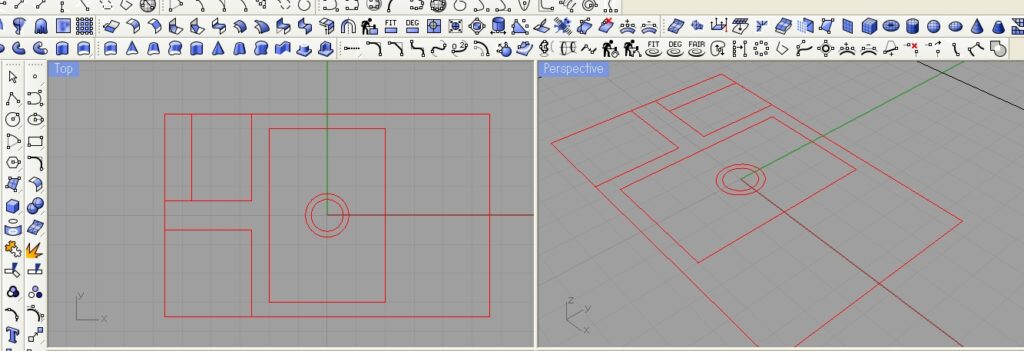
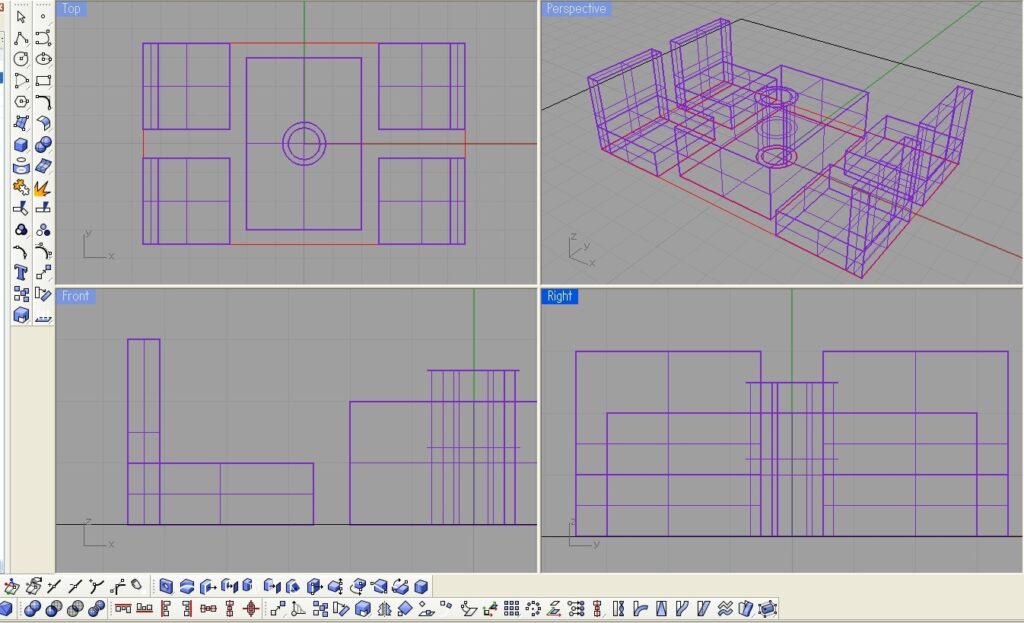
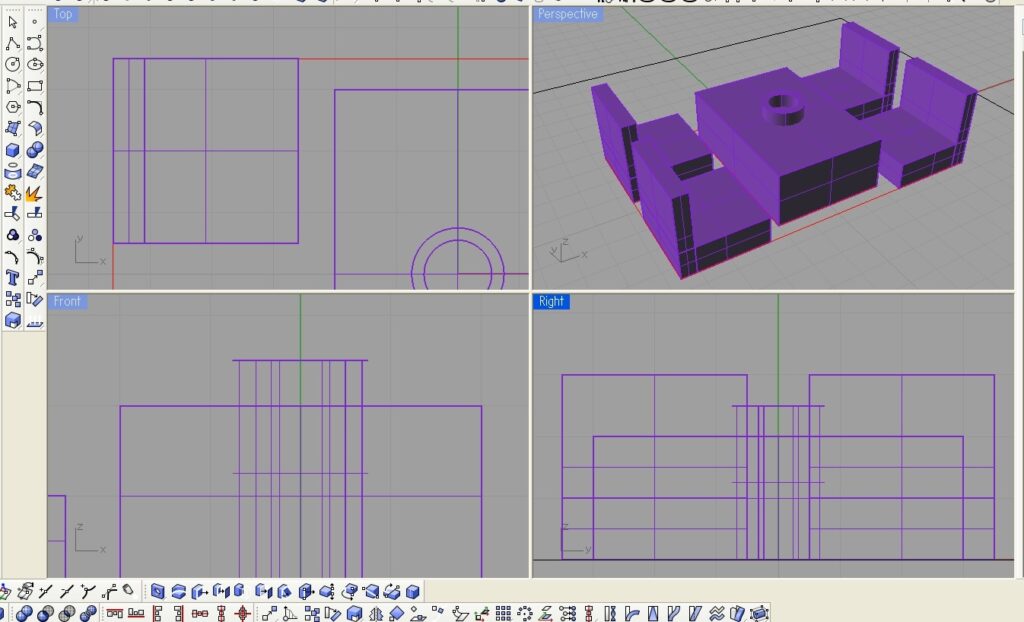
イスとテーブルをそれぞれ、0.25mm厚で連結して1つのユニットとします。
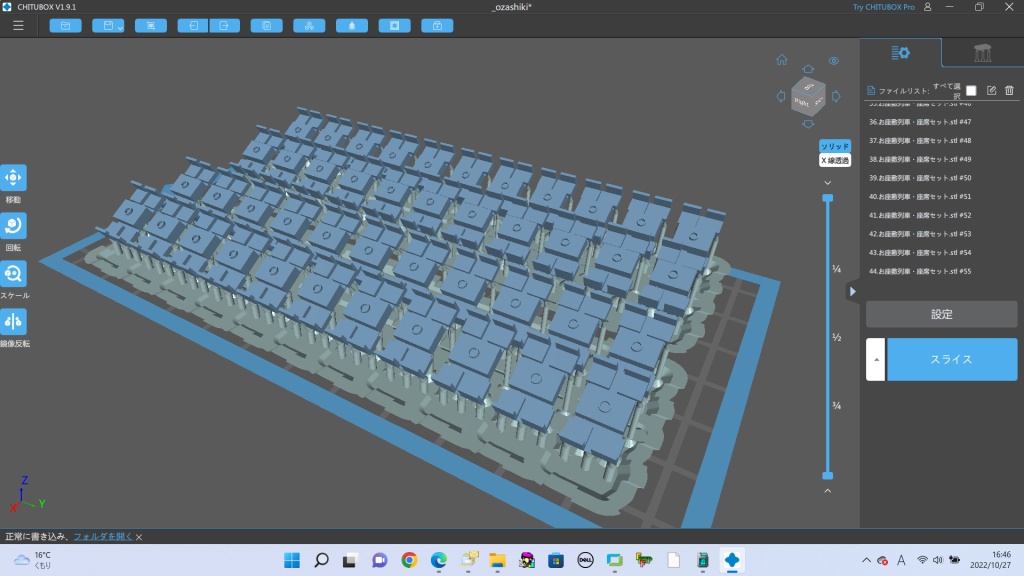
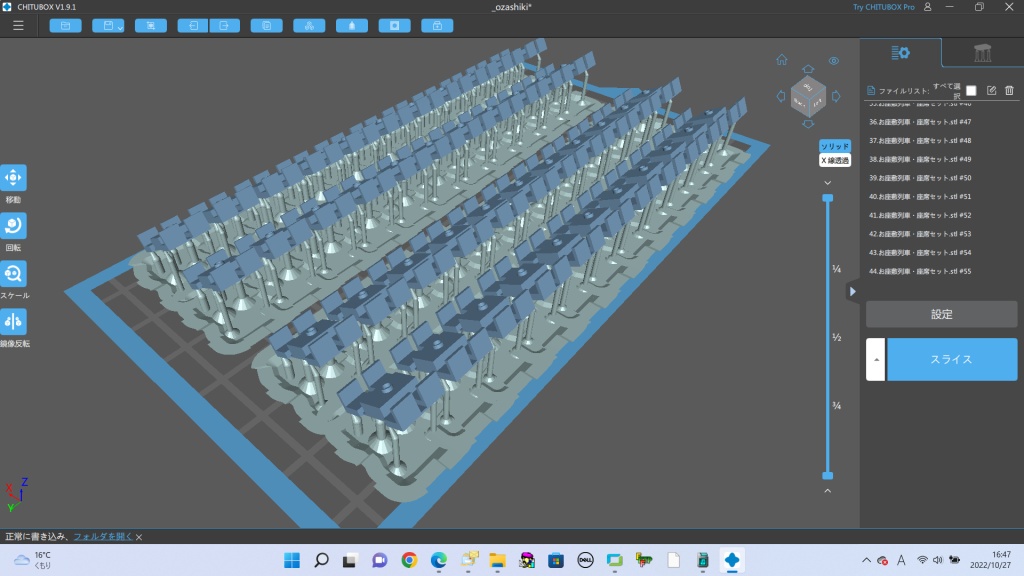
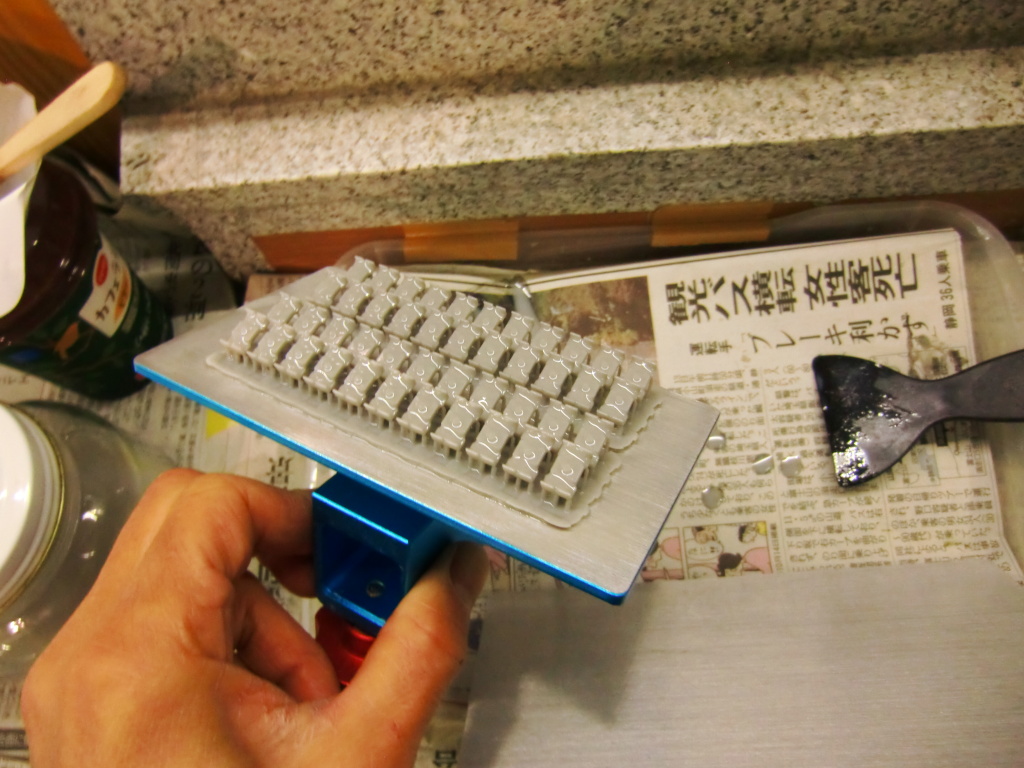
比較的小さな成形物となりますので「3Dプリンター Photon S」を使って出力を行いました。
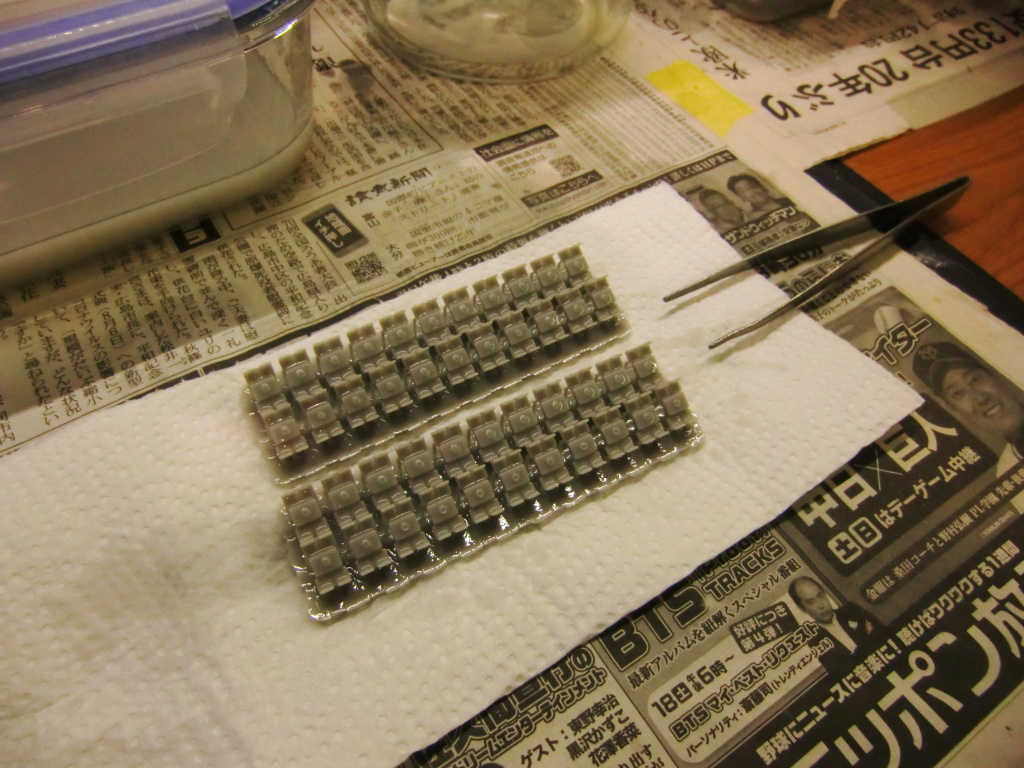
アルコール洗浄で余分なレジンをしっかりと洗い流します。

このあと2次硬化させて完成となります。
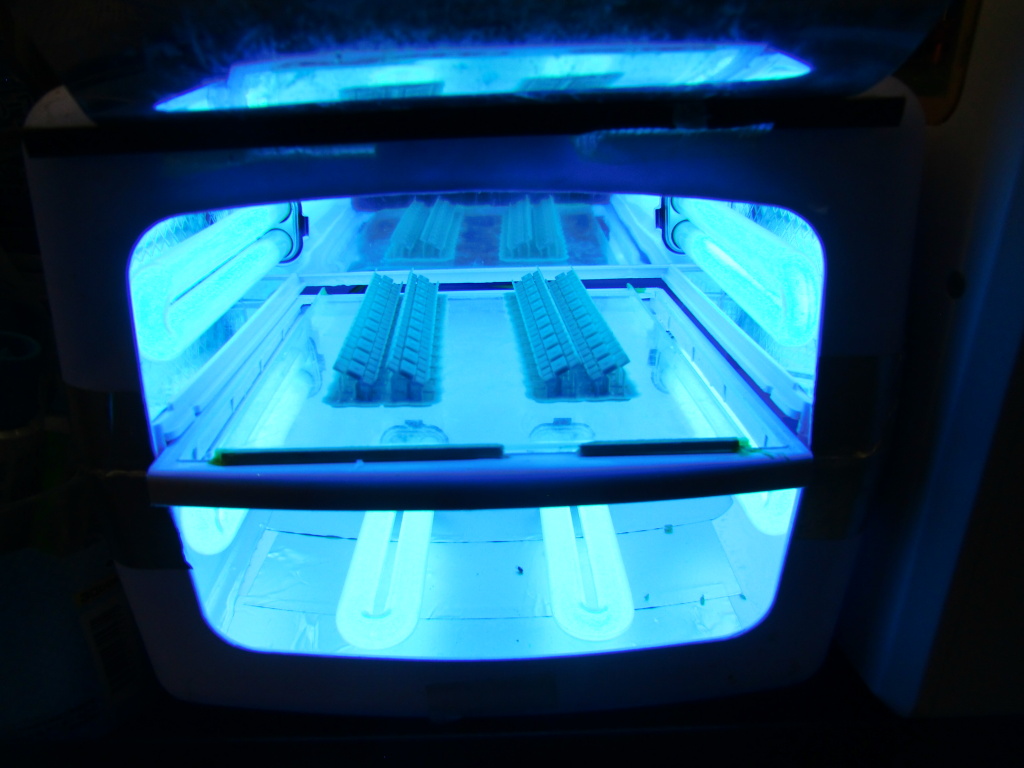
上下左右、向きを変えながら2~3回ほど露光して完全硬化させます。

じゃん。
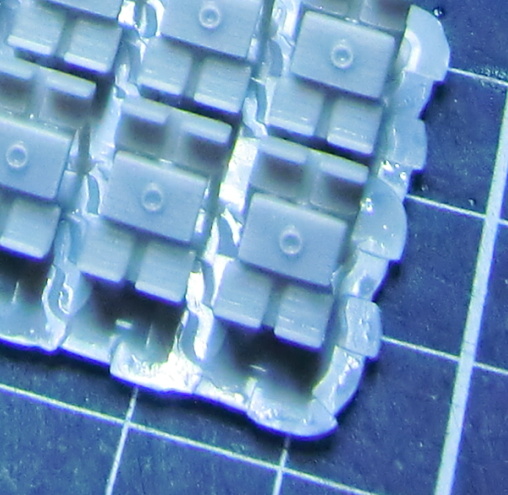
作業完了でございます。




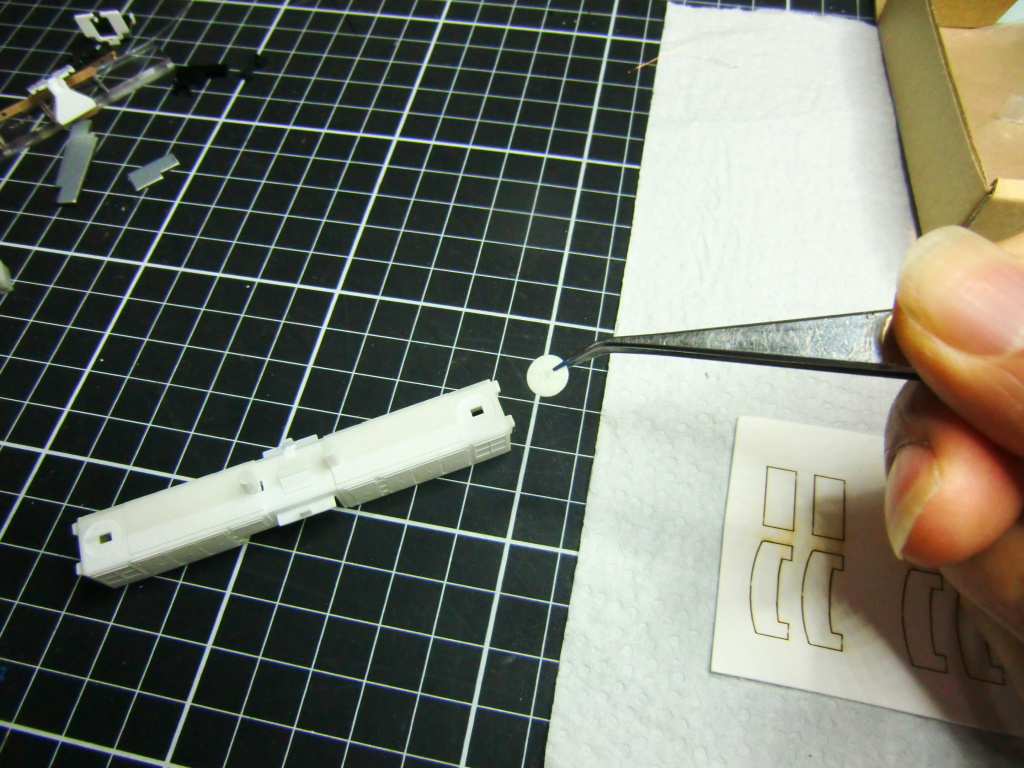

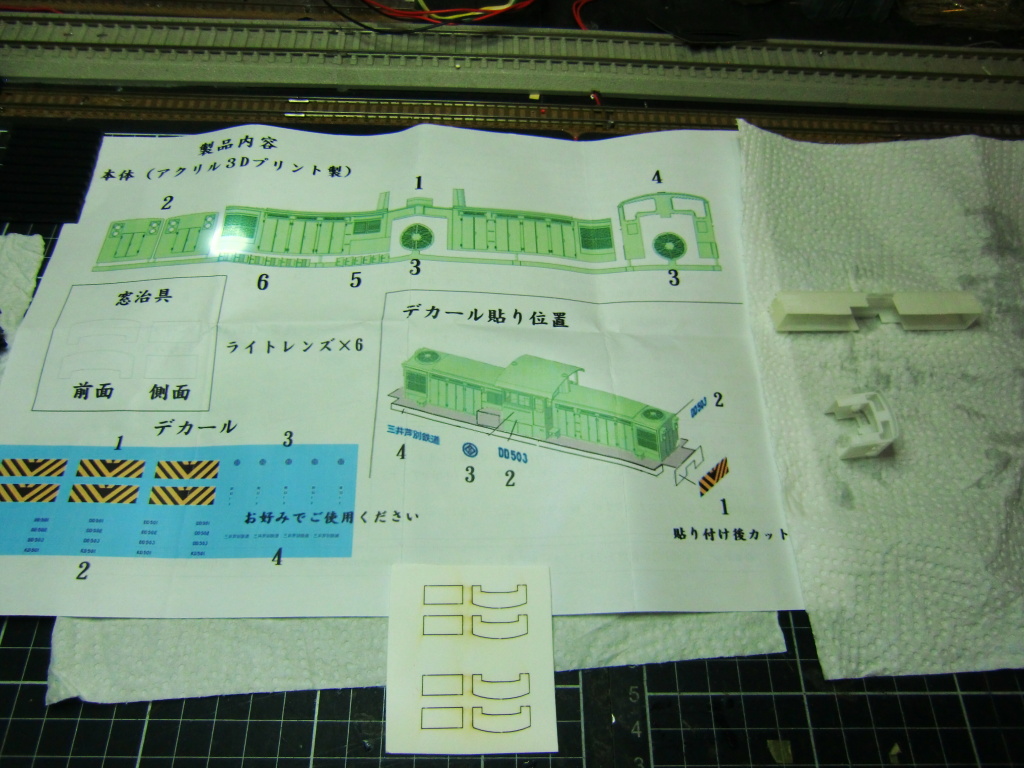

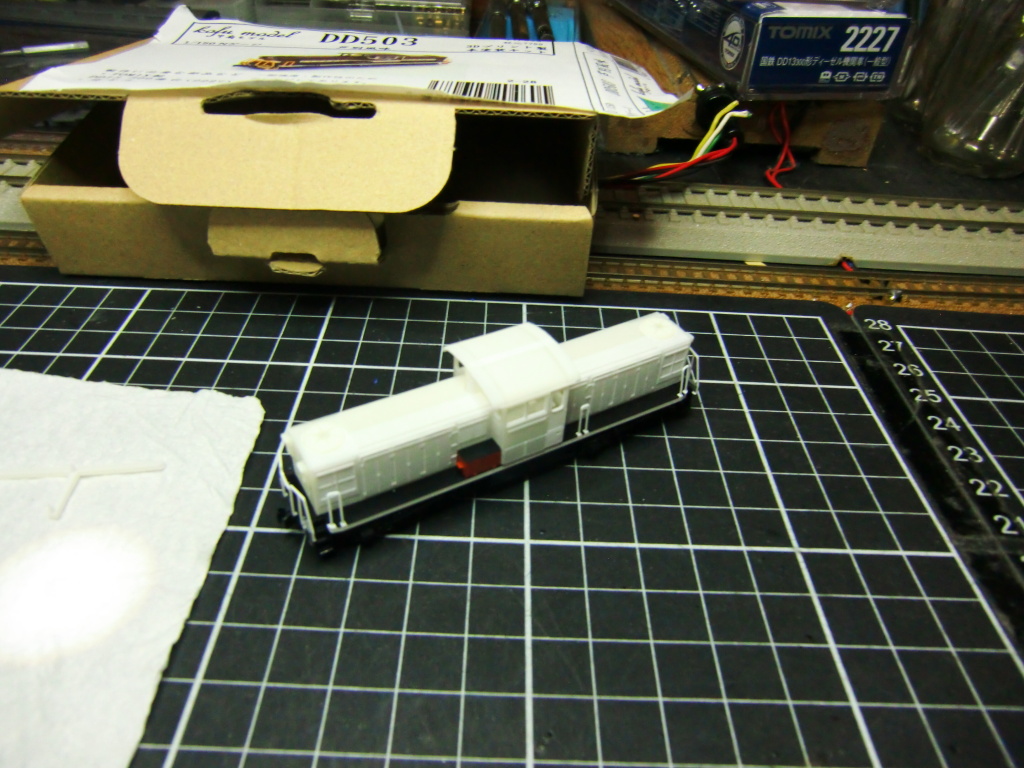
塗装に移る前に洗浄作業を行います。

続いて、内側を黒で塗っておきます。この作業をしないとライト点灯時にボディーが透けてしまいます。

さらにグレーのサーフェイサーを2~3回に分けて吹き付け下地と遮光効果を高めます。


このあと白で全体を塗装します。
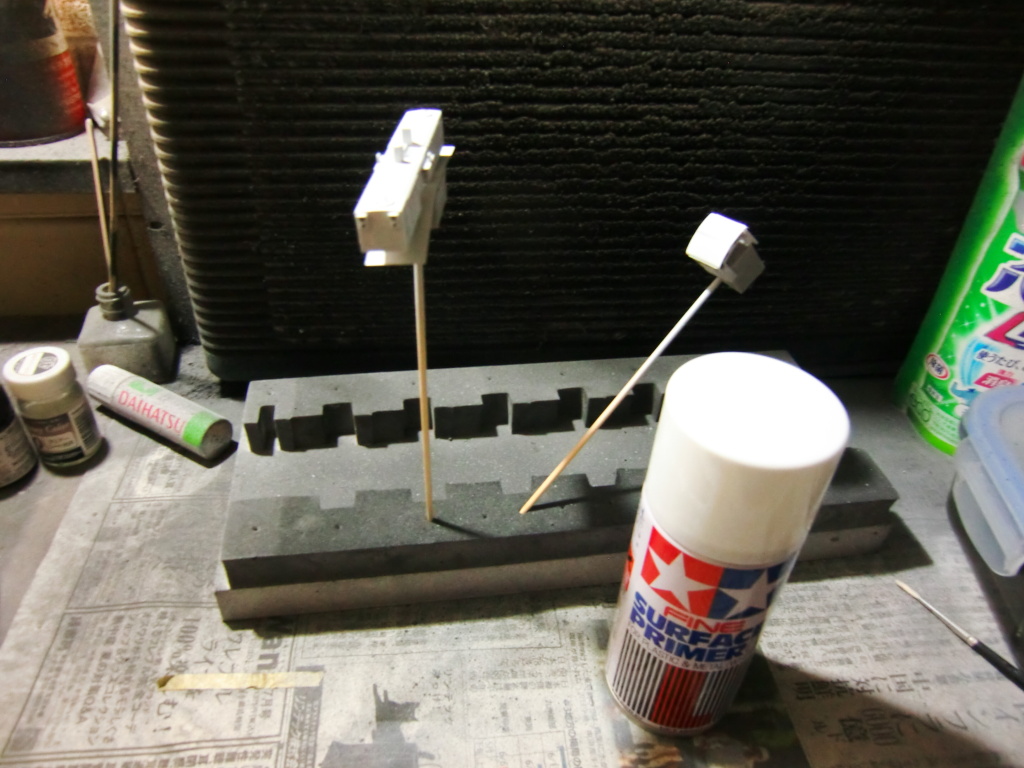
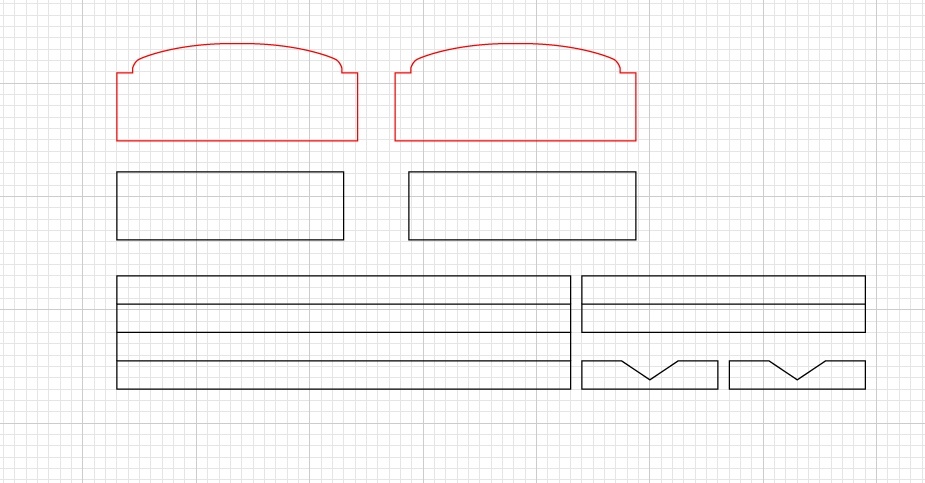
マスキング・データを作ります。
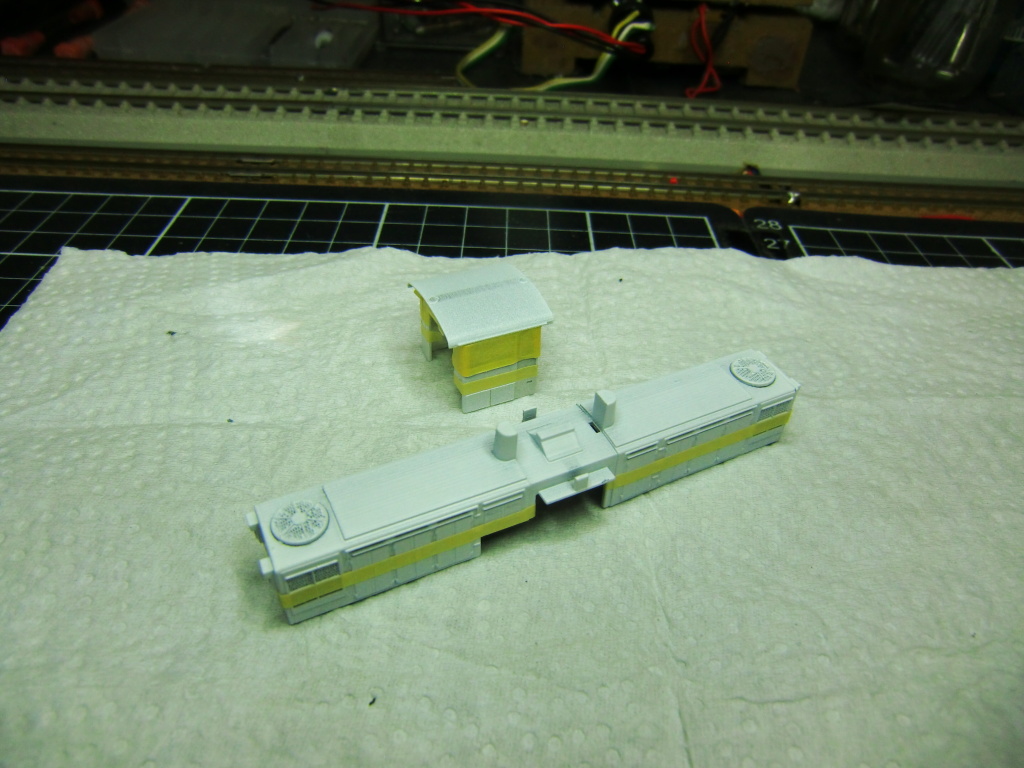
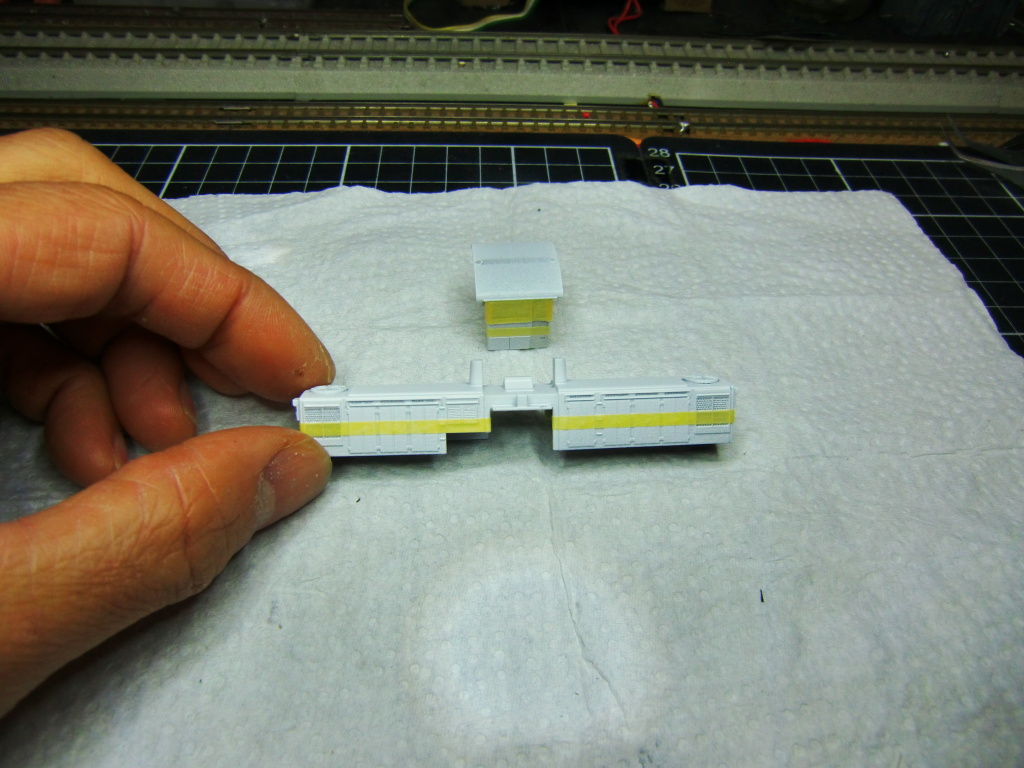






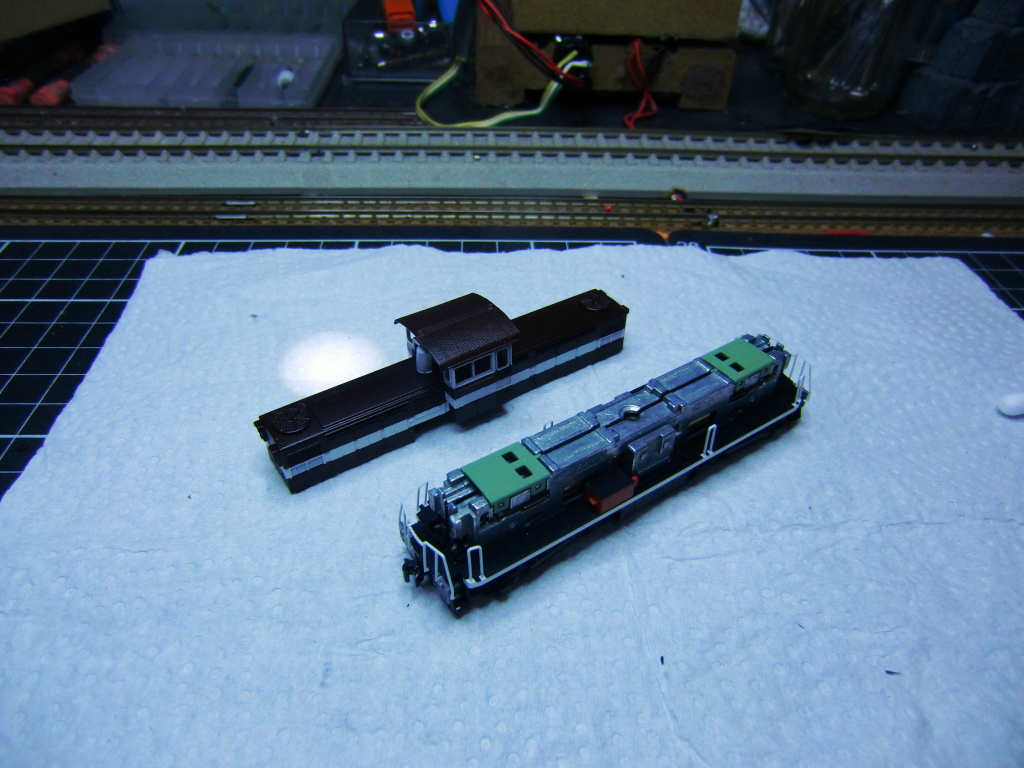
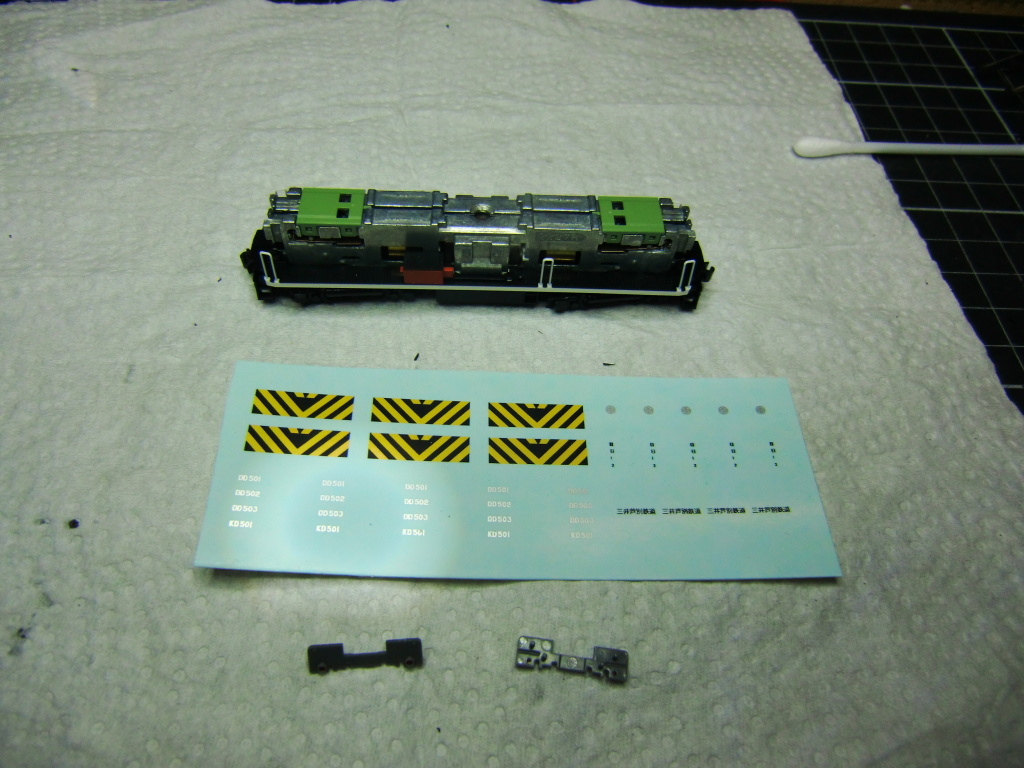



手すりへの塗装は、そのままでは剥がれやすくなるため「ミッチャクロン」を筆塗りで1つ1つ下塗りします。

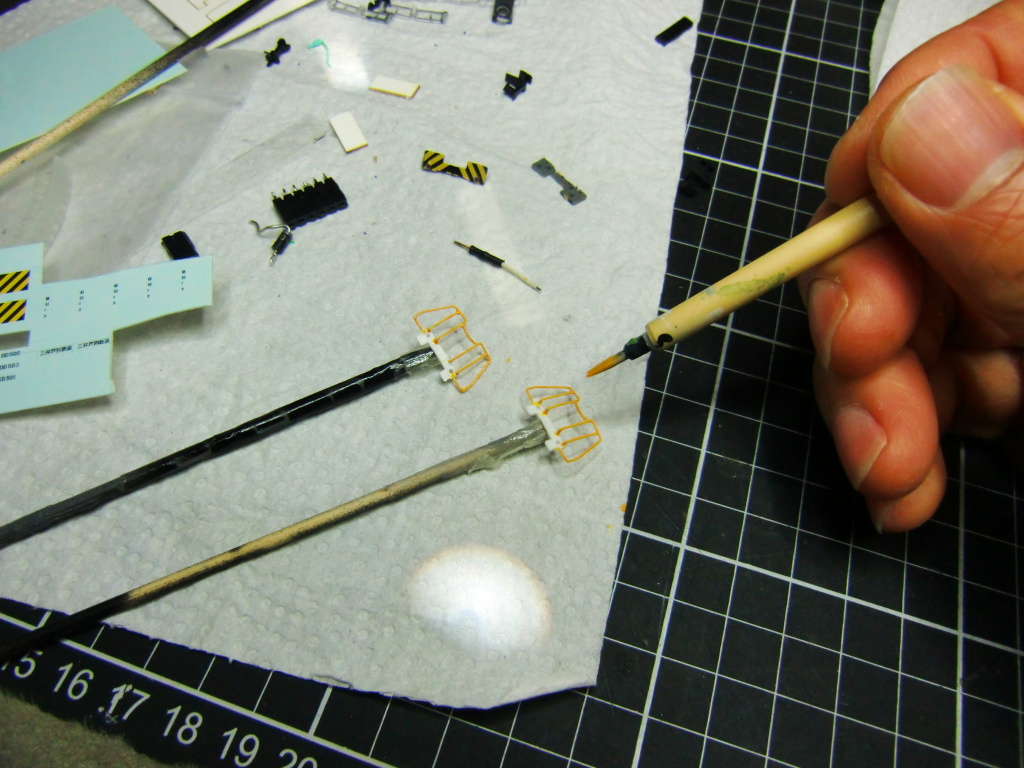

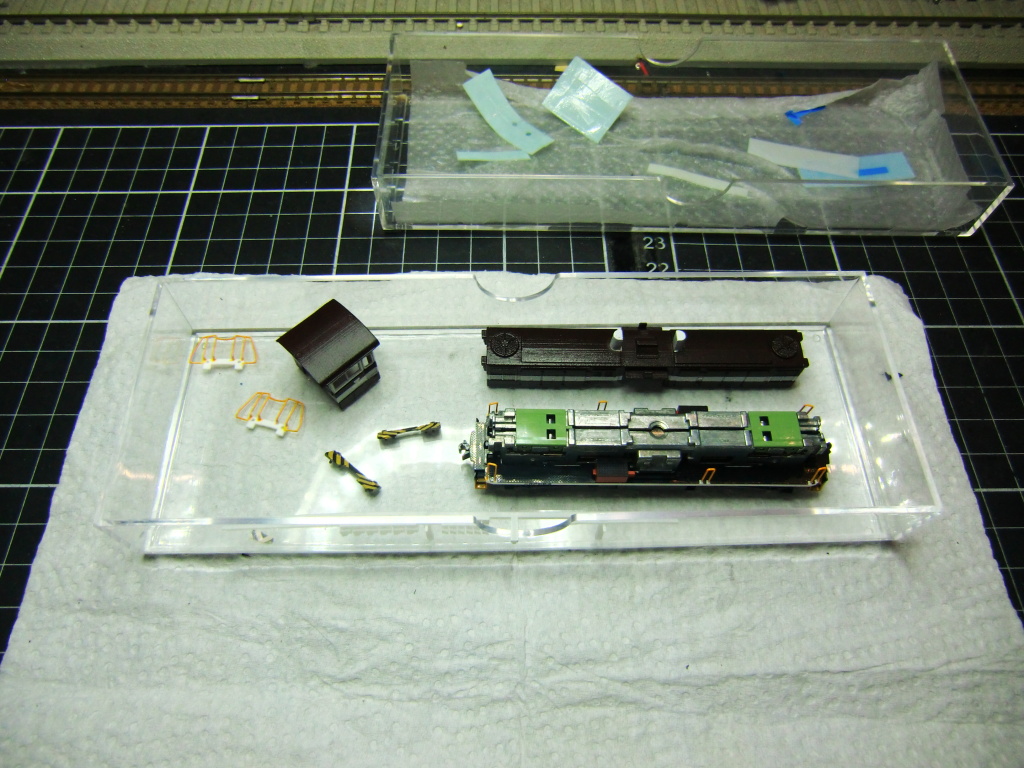


個々のパーツも塗装していきます。

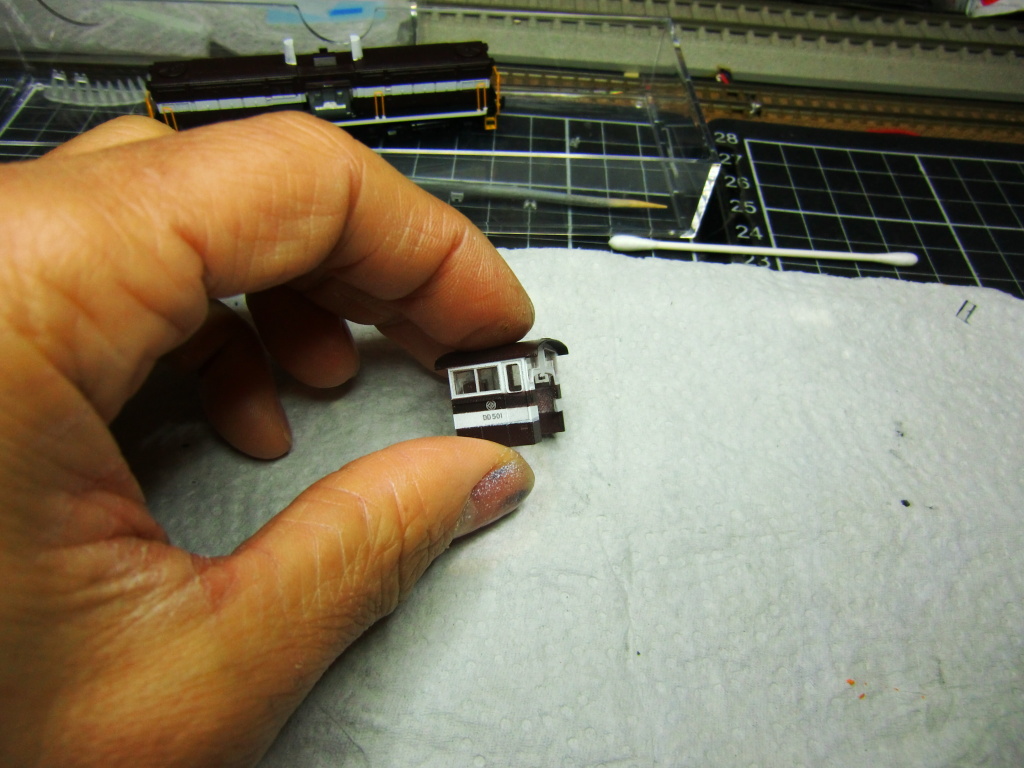
続いて、透明プラバン(厚0.2mm)を切り抜いて、裏から貼りつけます。完成まであと少しです。

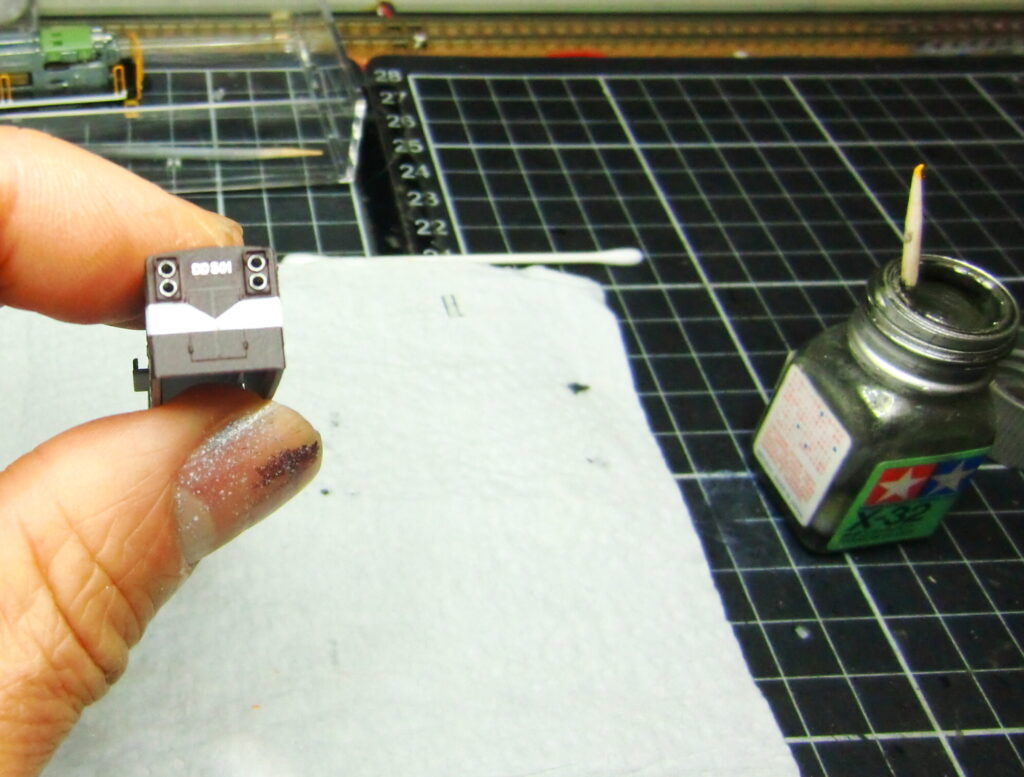
ライト周りをシルバーで色サシします。



作業完了でございます。

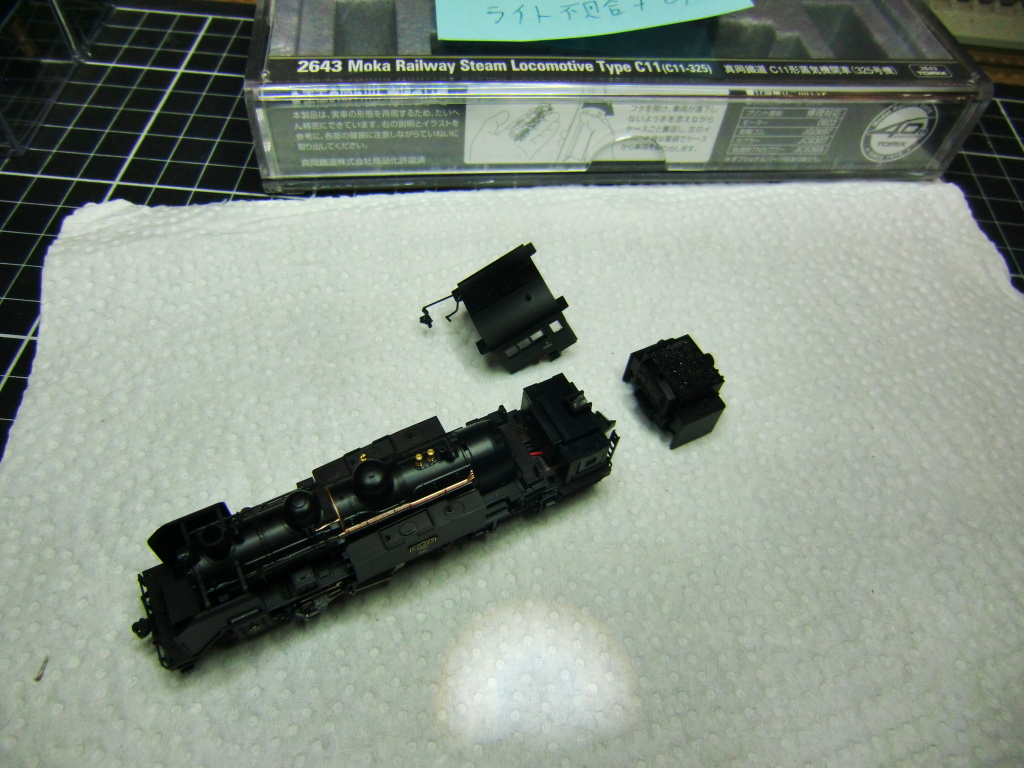
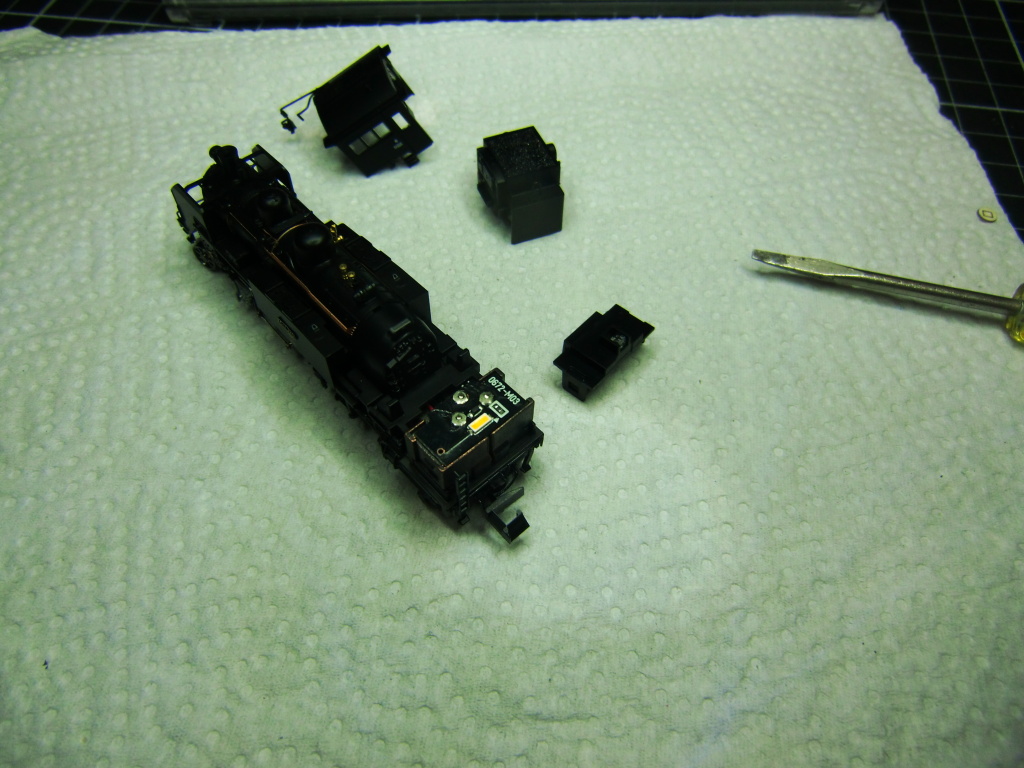


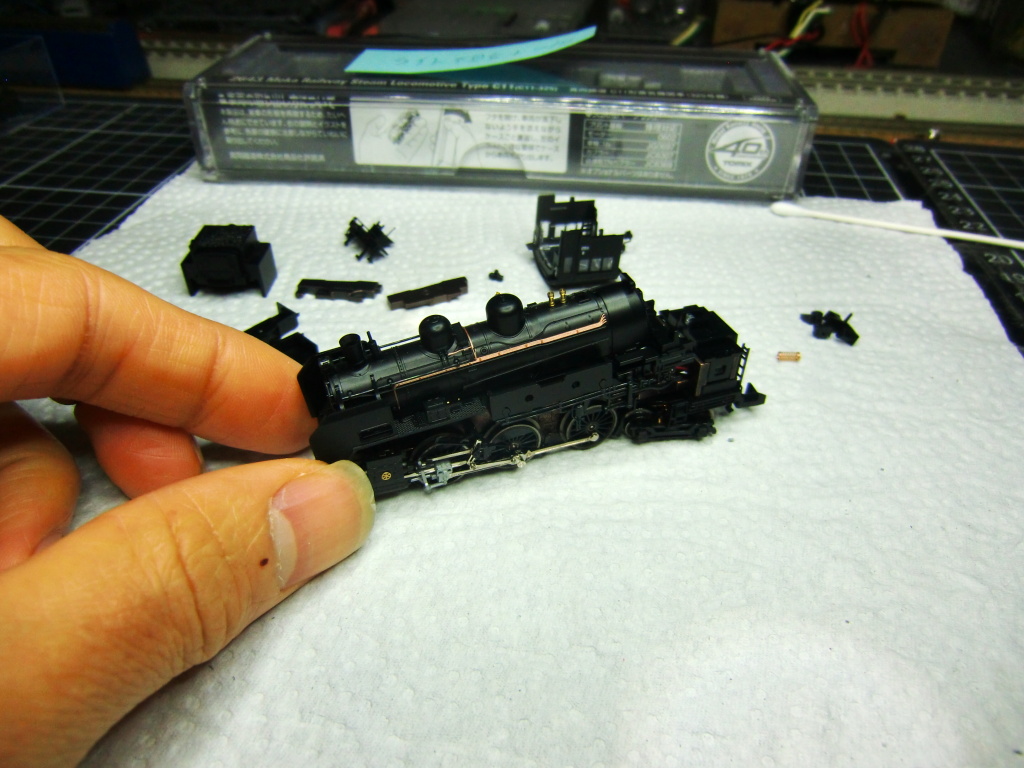
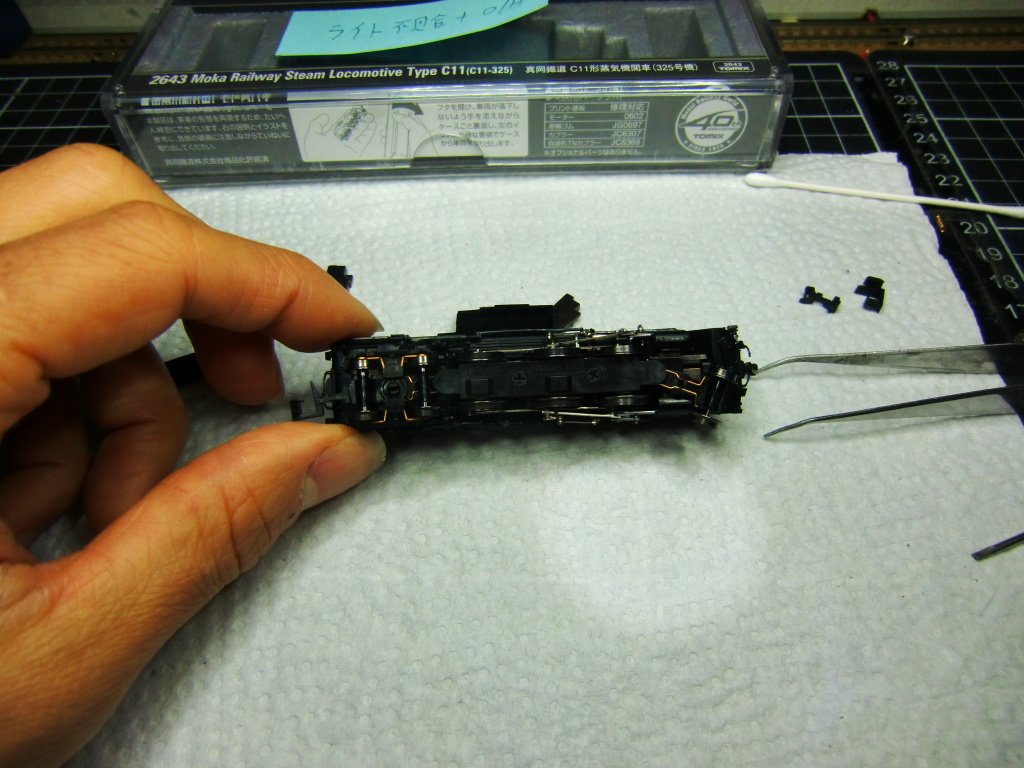
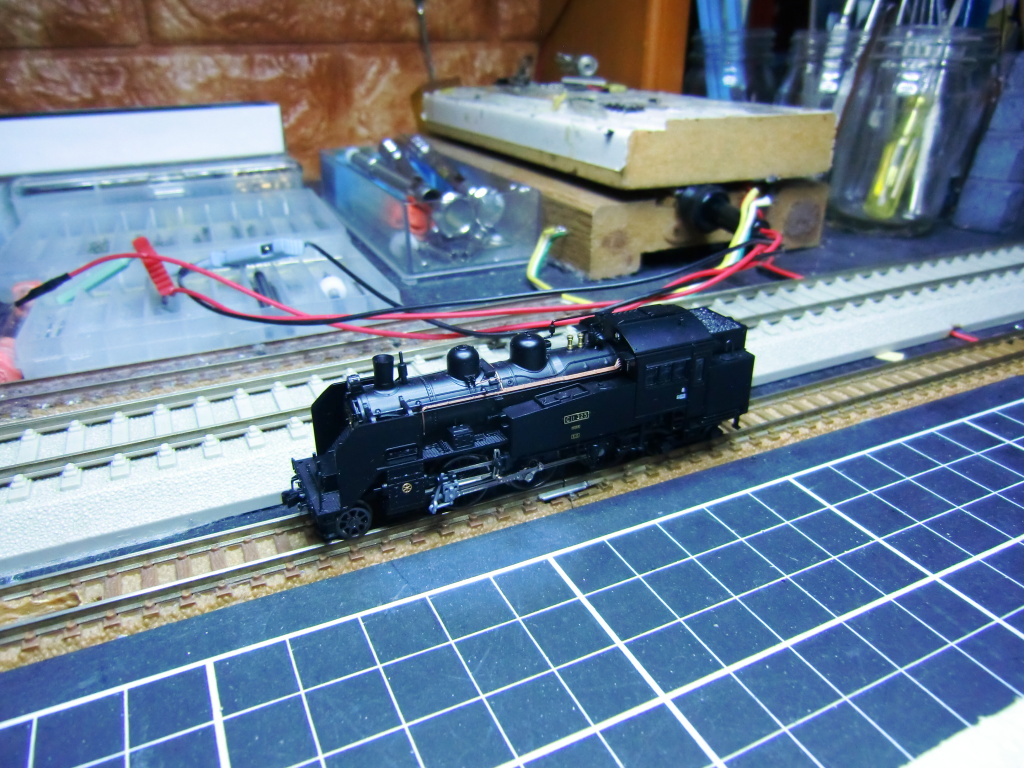
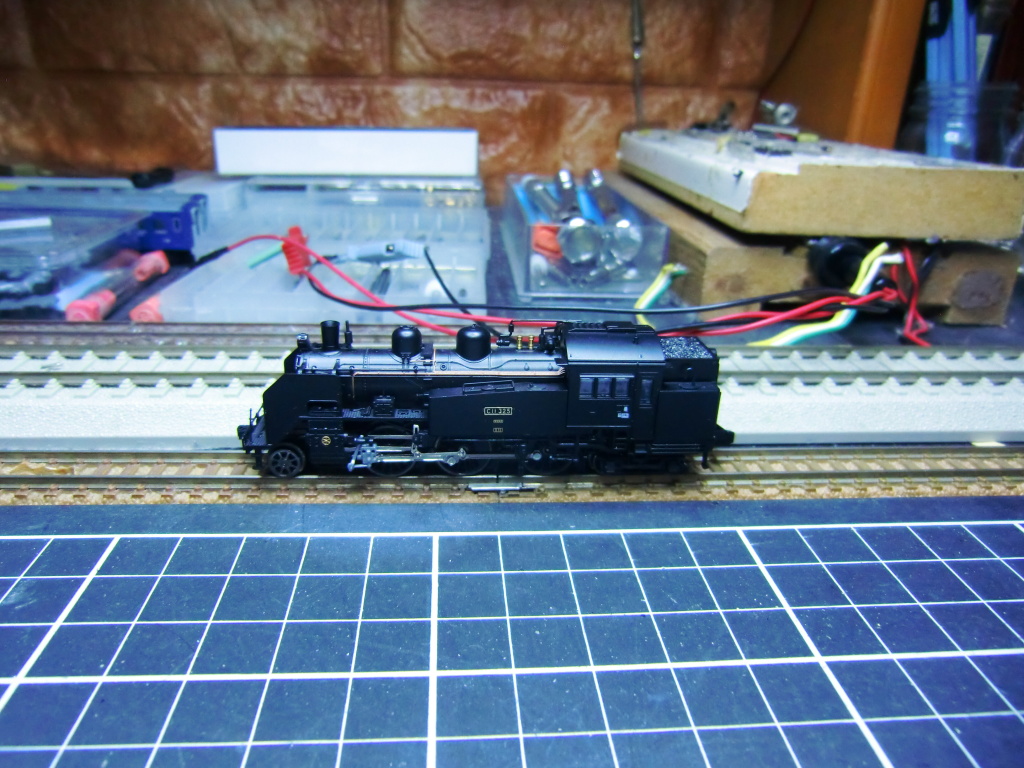

まずは、現状として回転がやや重いです。何か負荷がかかっているようです。


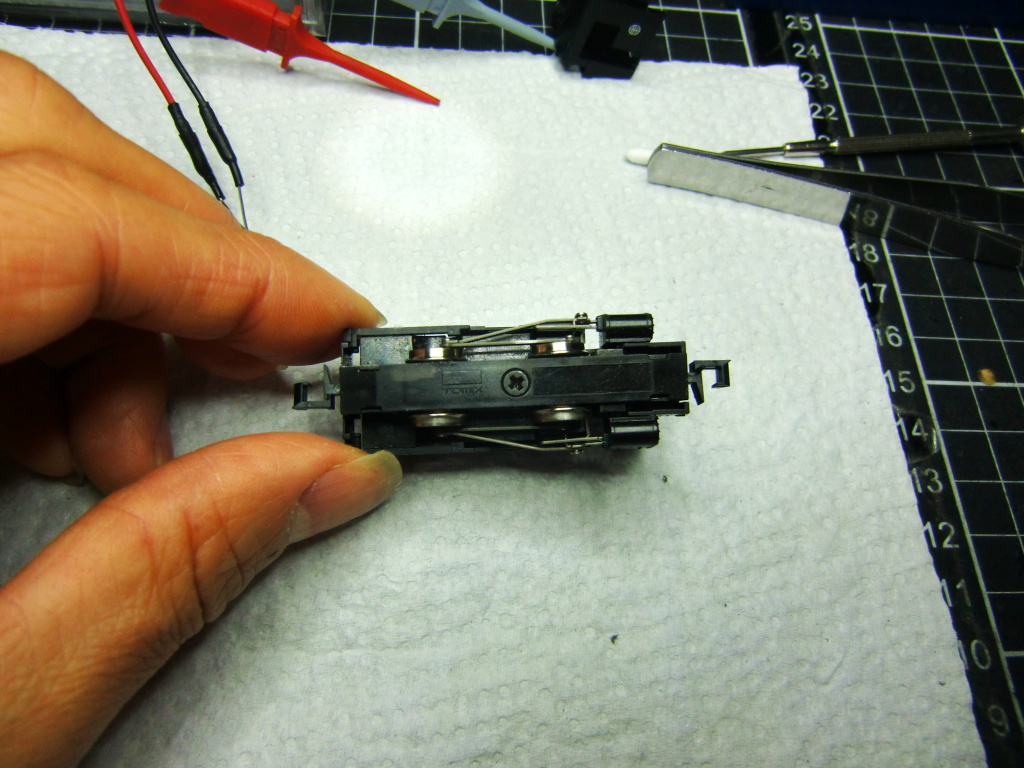
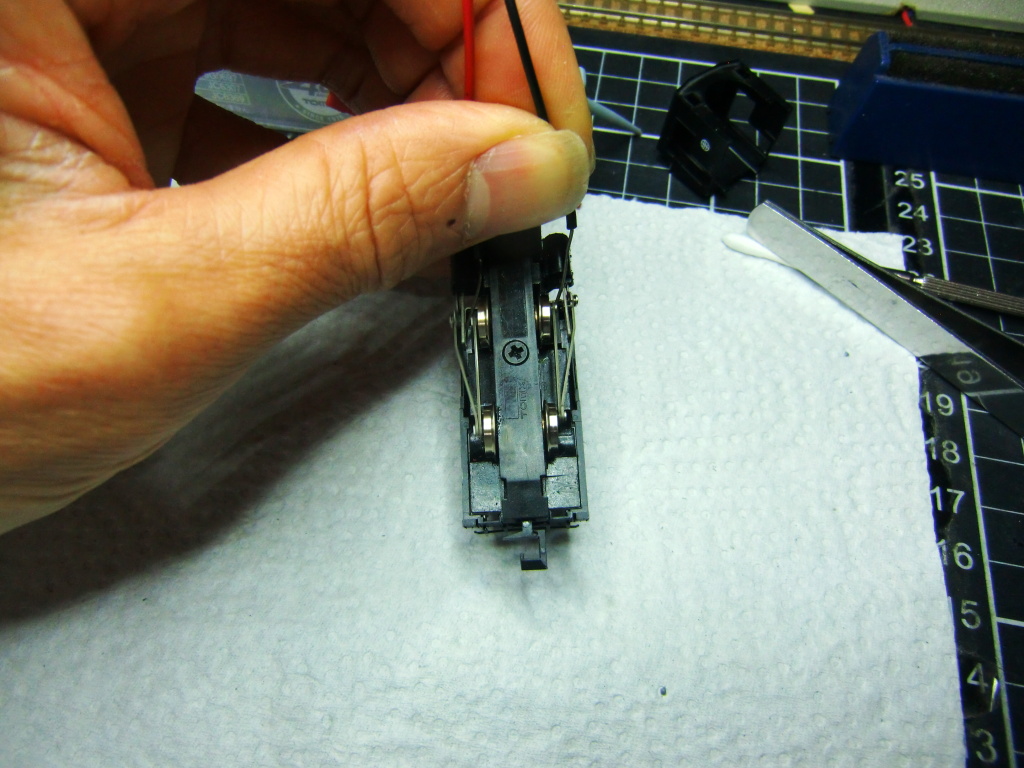

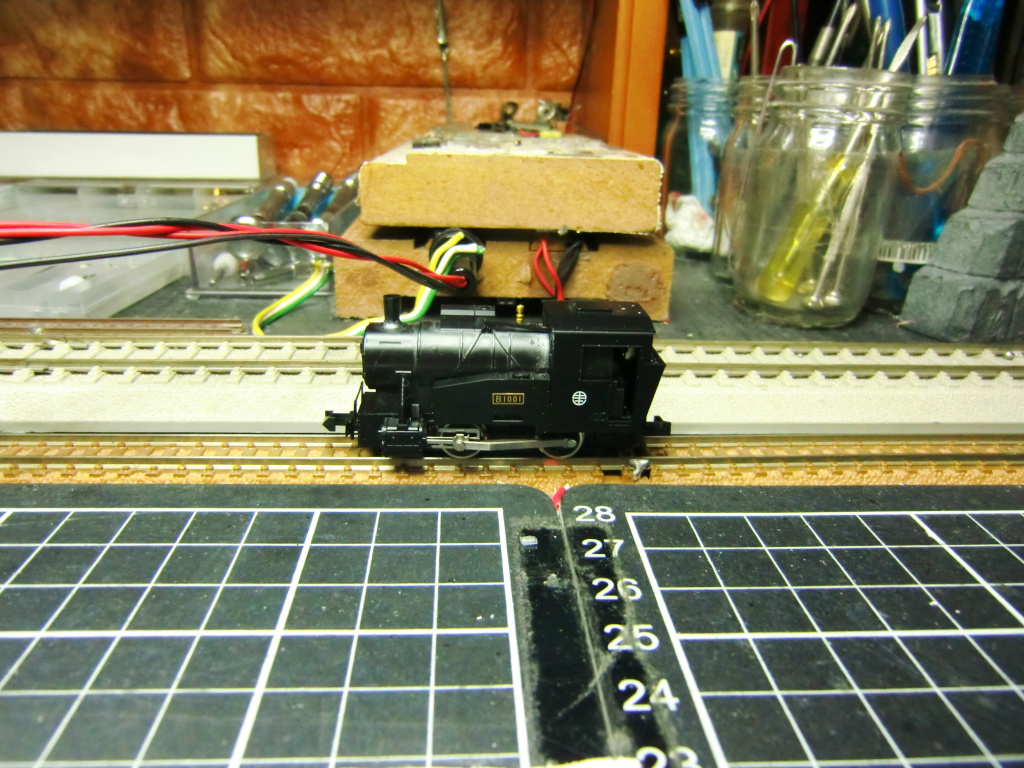



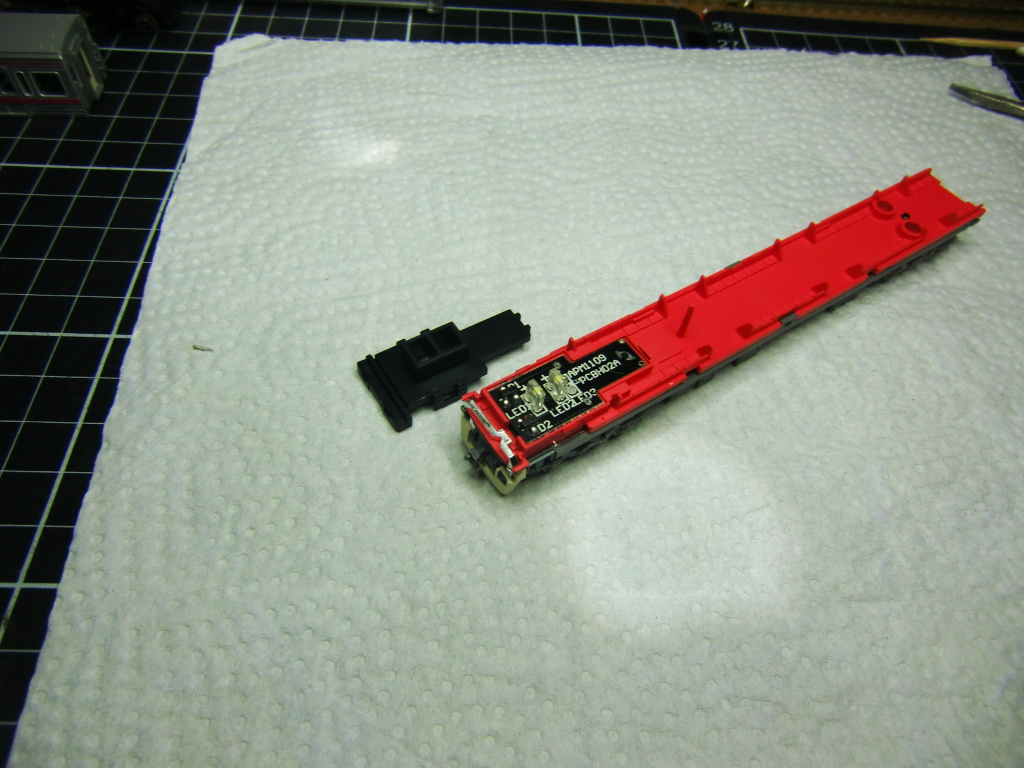
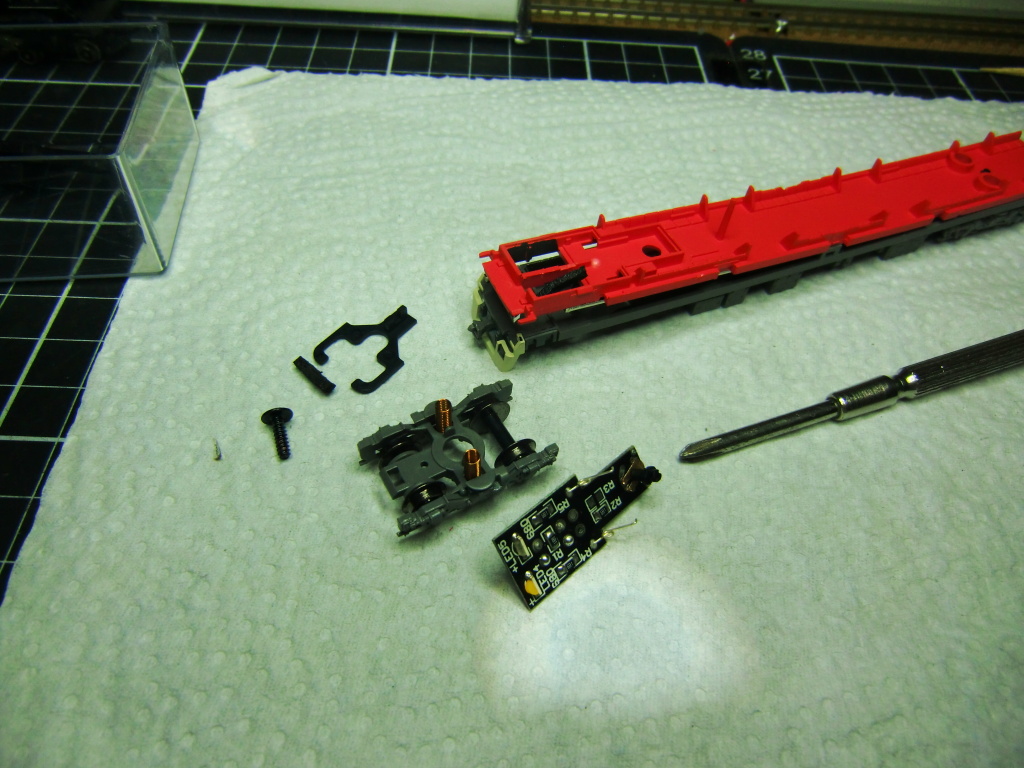
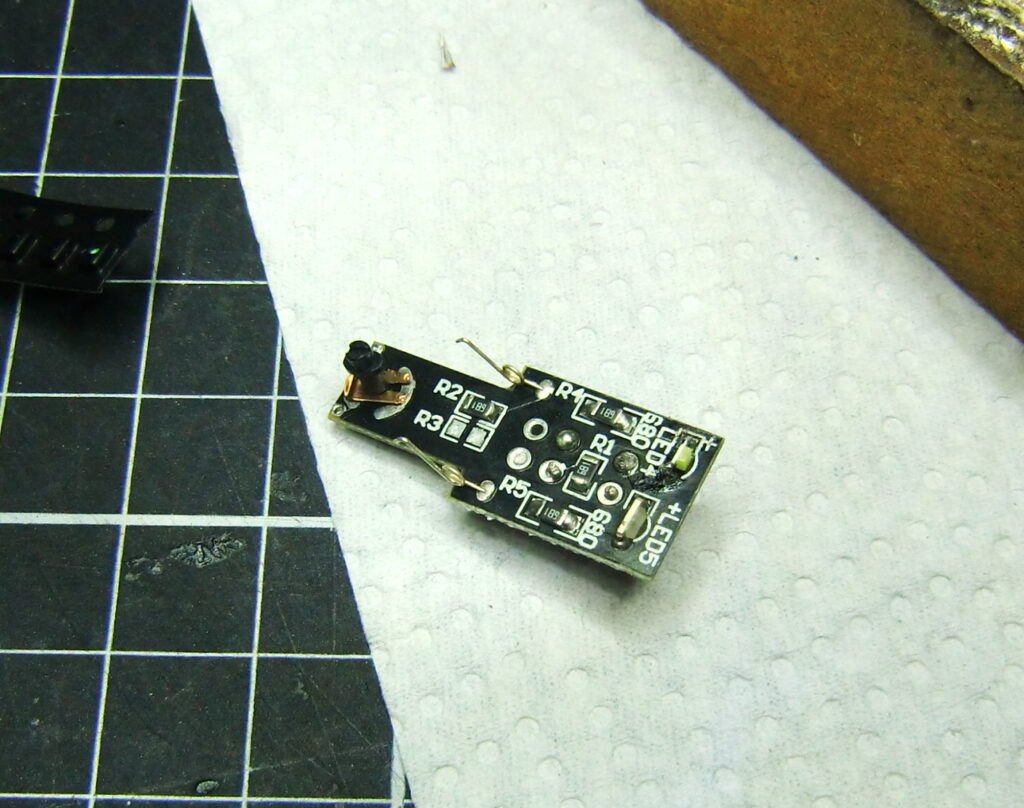


発光源を白色LEDにしましたが、どうもぱっとしません。マイクロ製のライト加工におきましては、導光材そのものが透明ではなく黄ばんだ感じになっているケースが少なくありません。今回もそうですし、透過率も低く暗いです。明るめの白色LEDを組み込んだとしても写真のように黄色っぽく暗いです。このような状態では、ご依頼者様もがっかりしてしまいます。今回は、一般加工から特殊加工へ切り替えて作業をすすめていきます。
一般加工に比べらべてやや費用はかかりますが、確実な明るさとご希望の発光色に仕上げることができます。
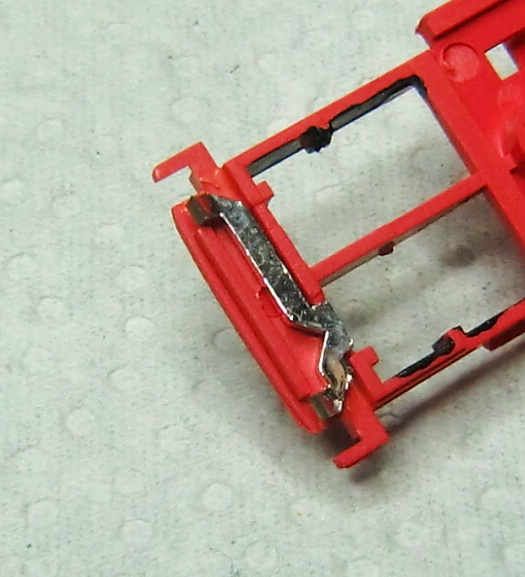
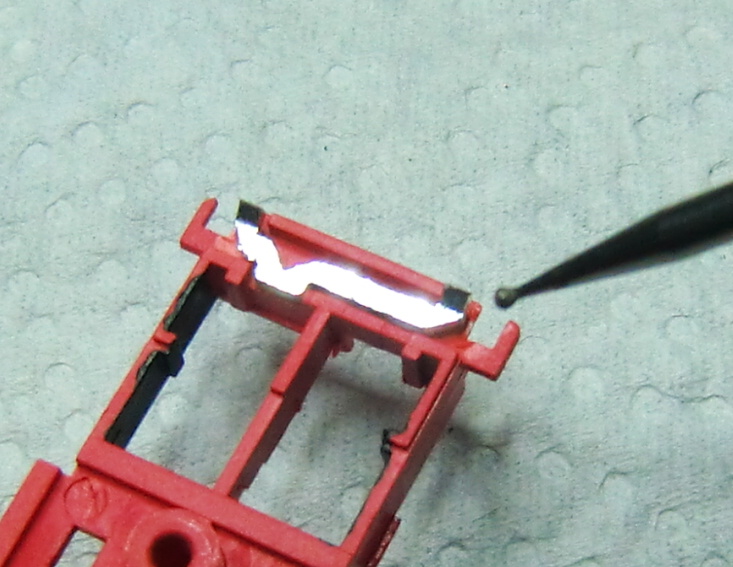
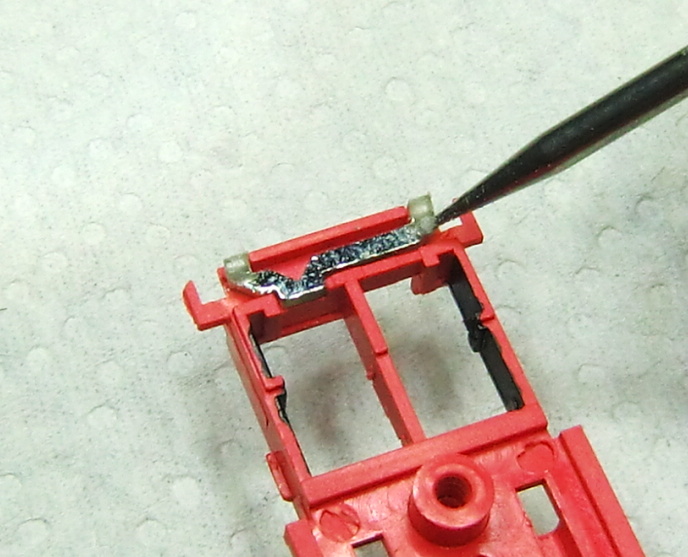
まずは、導光材の先端から近い位置の遮光をルーターで削って剥がします。写真中央が削る前で、右側が削ったあとになります。この位置に左右それぞれにチップLEDを配置します。
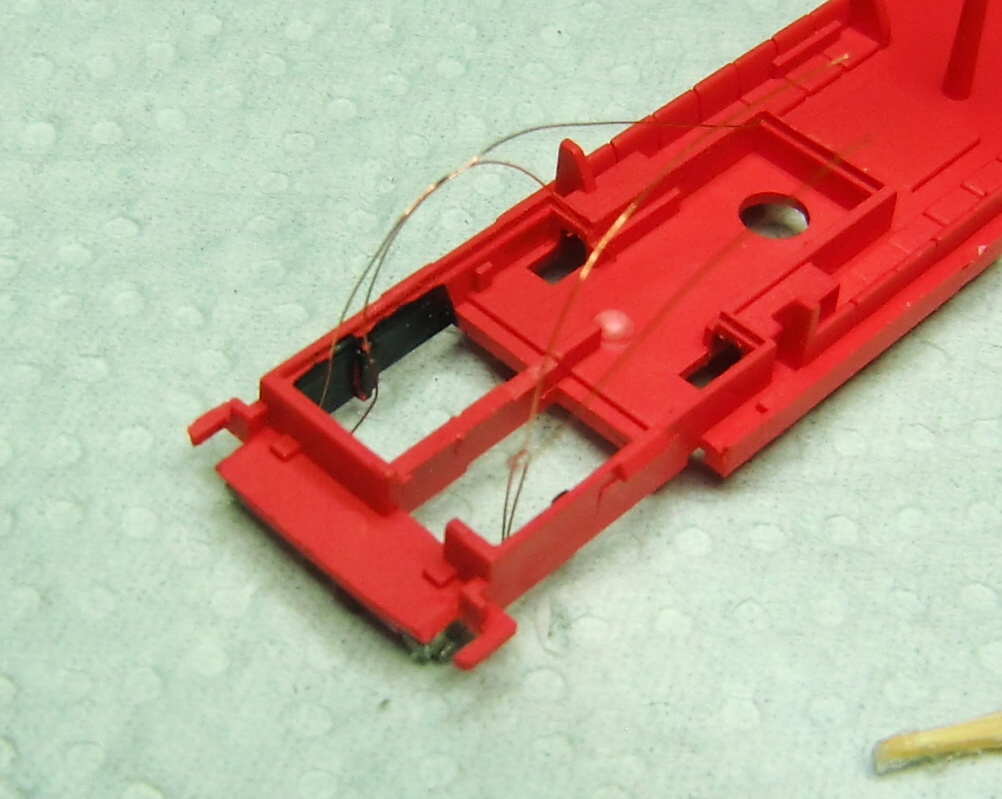
このあと配線を基盤へとつなぎます。
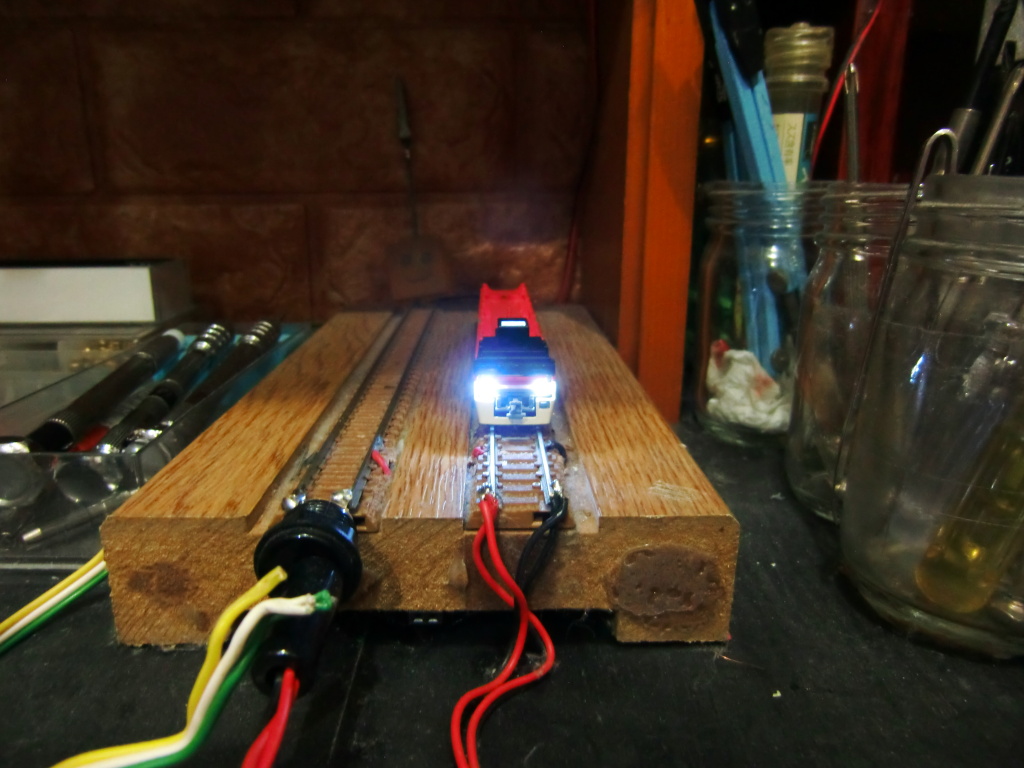
大変明るくご希望の発光色となりました。

ボディーを被せて光具合を確認と調整を行います。どうやら良さそうです。撮影の関係上、テール部分も一緒に光って見えますが、ヘッドライトのみ独立して発光しております。真正面から見るとかなり明るいです。
作業完了でございます。
今回は少々難しい作業となります。



まずは、車体を分解して加工の準備をします。
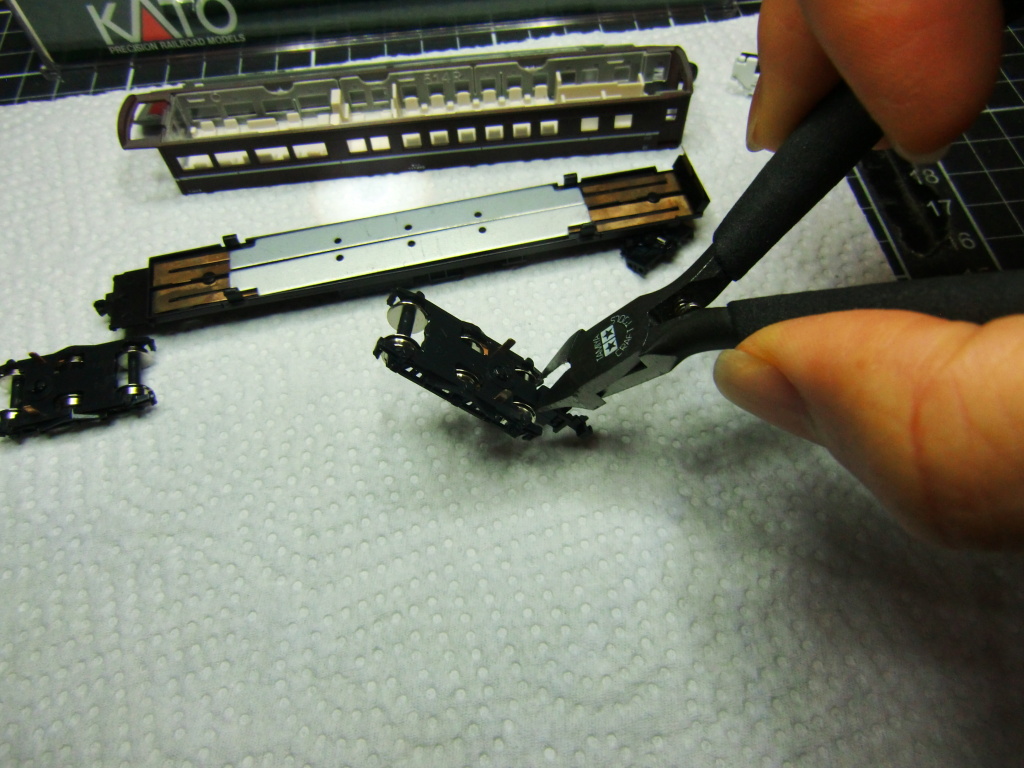
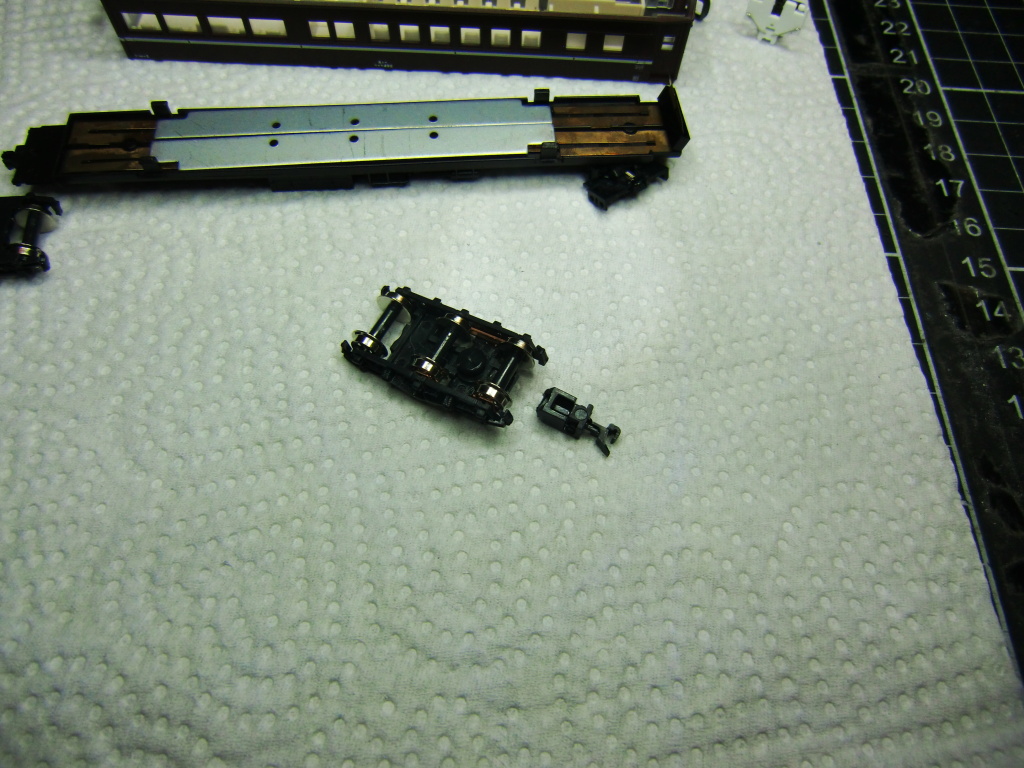
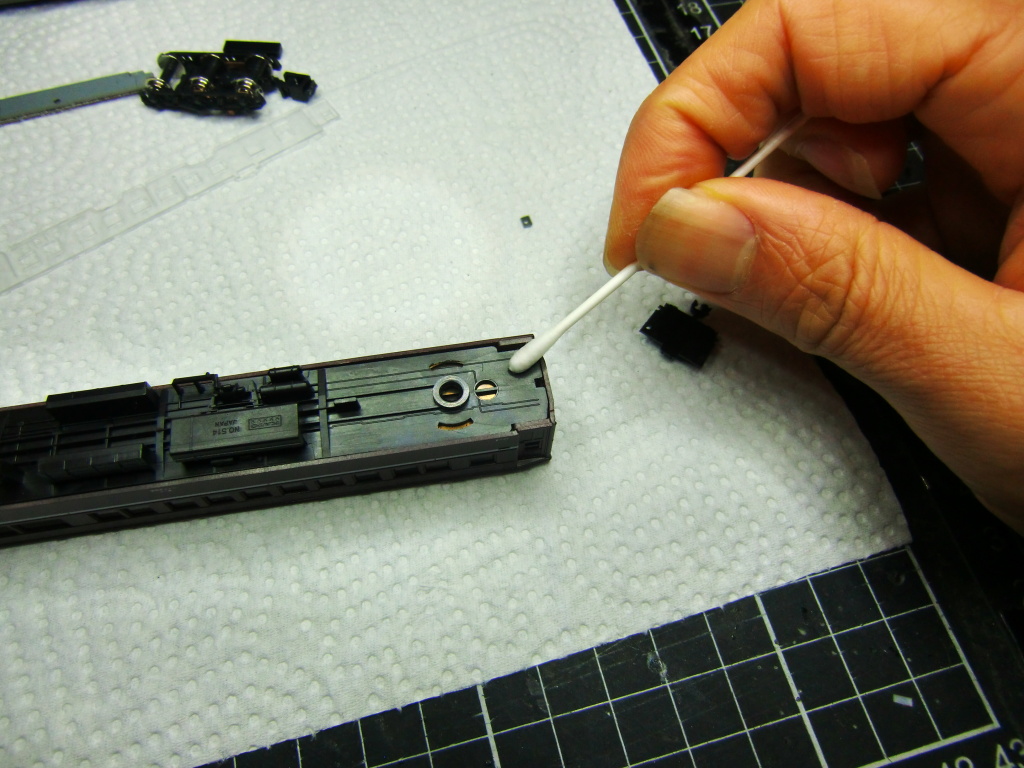
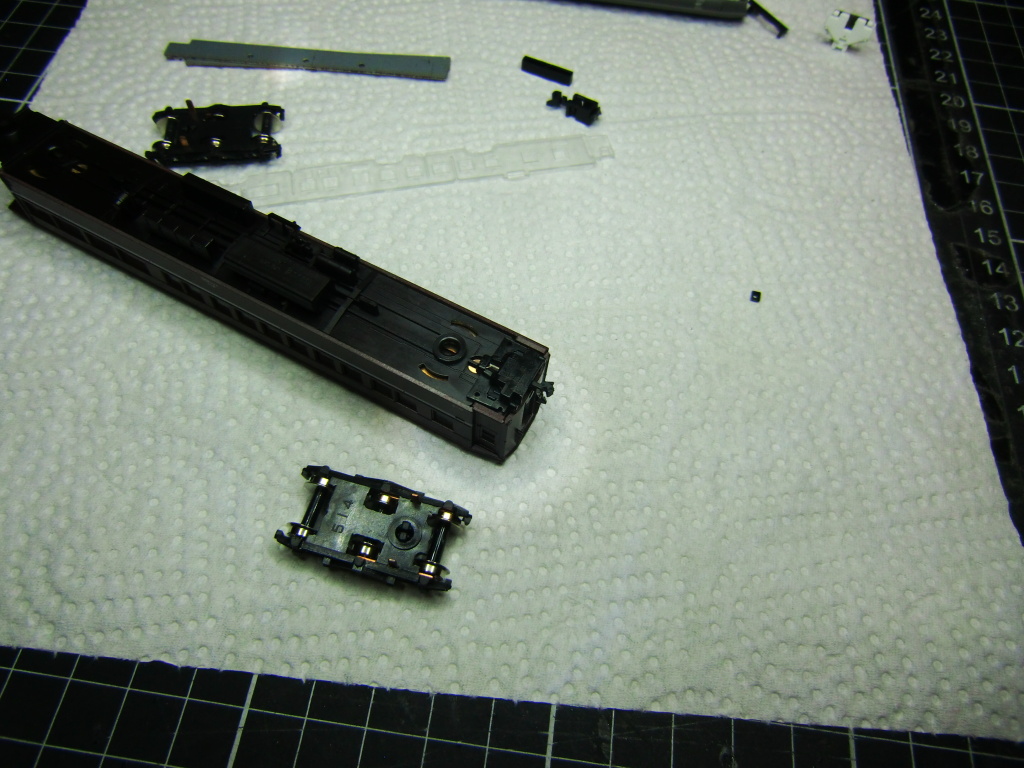
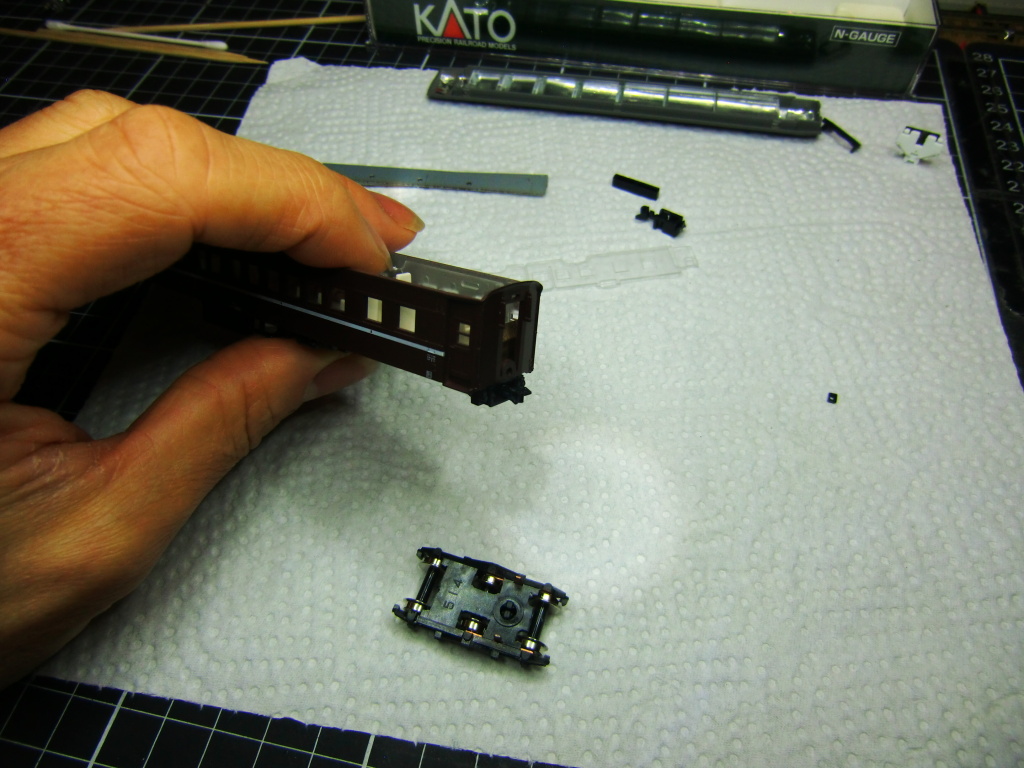
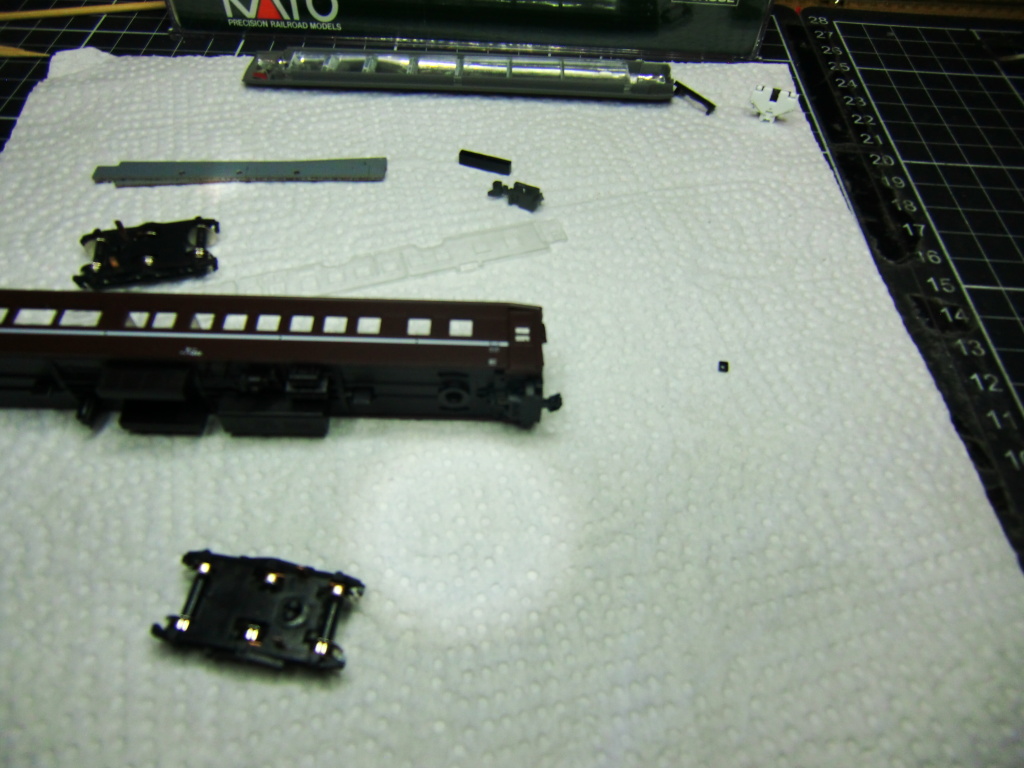
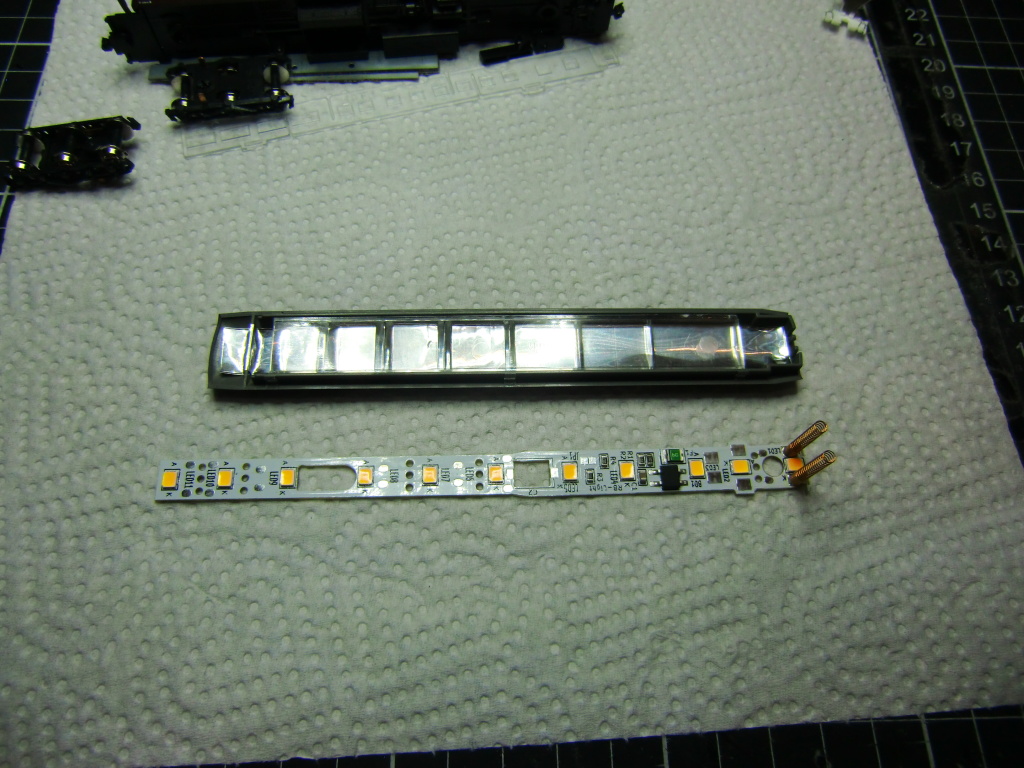
旧室内灯ユニットから現行のLED室内灯(バネ集電式)に組み替えます。取り付けにはちょっとしたコツが必要です。

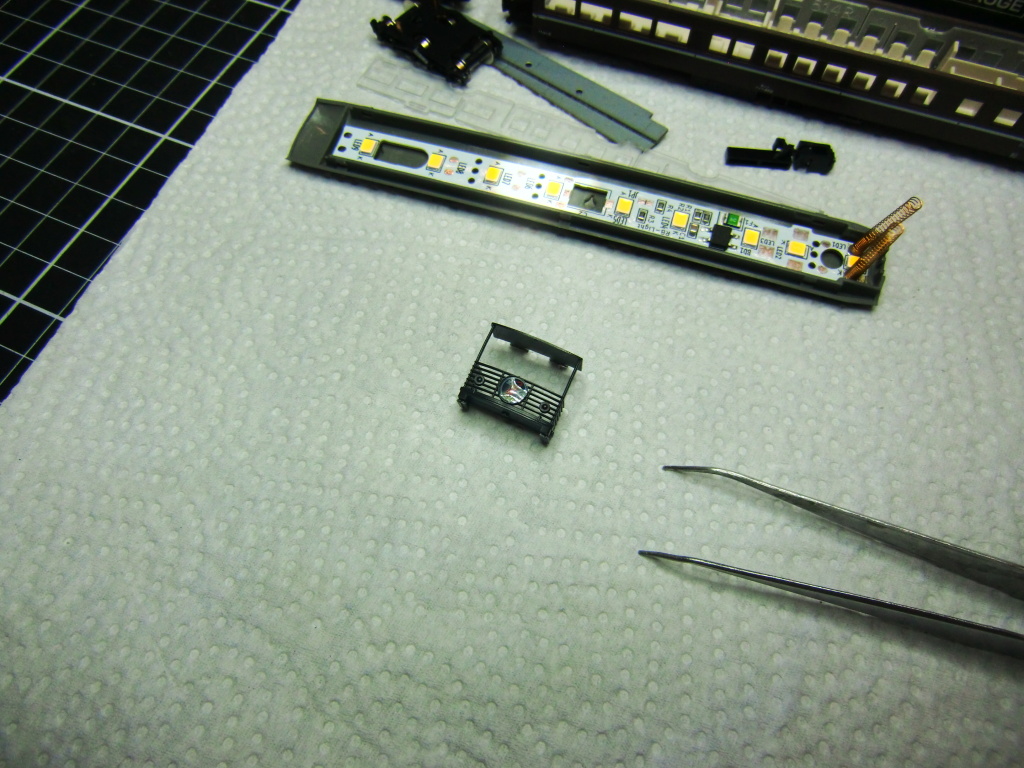
今回の作業の本命でもある、テールマークとテールライトの点灯化改造です。
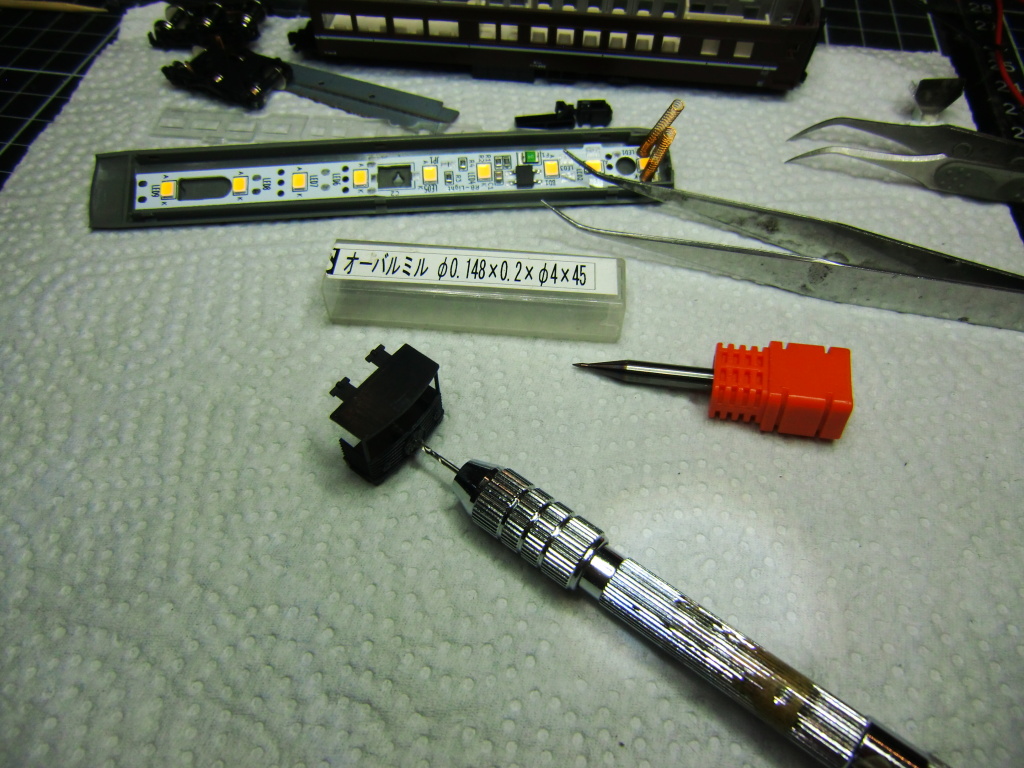
まずは、ピンバイスで中心に穴をあけます。
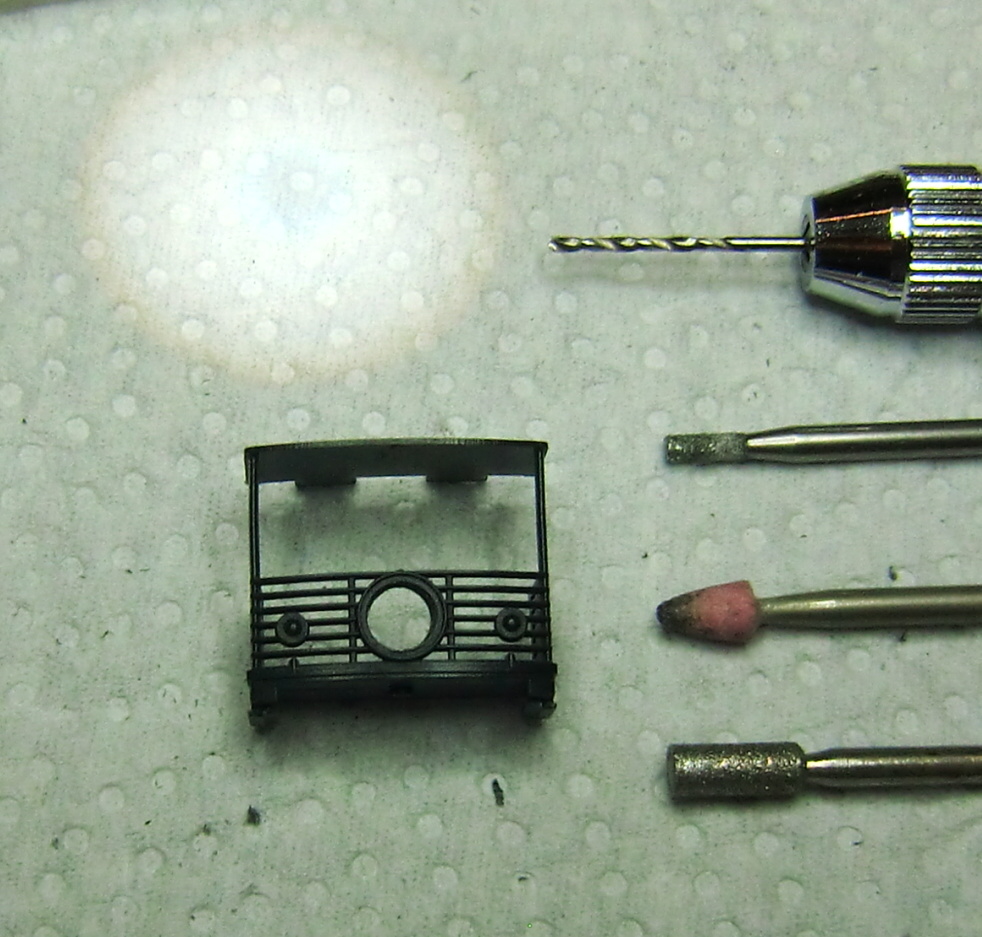
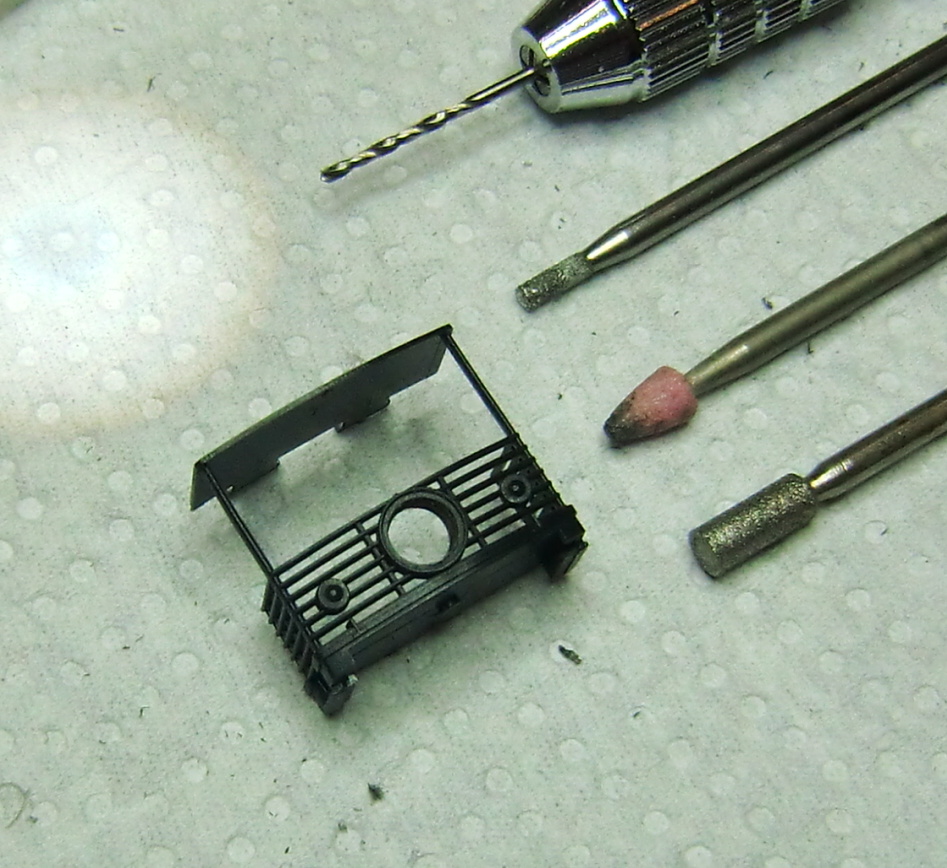
円の中心からずれてしまわないように慎重に作業をすすめていきます。あるていど穴が広がったところで、ルーターを使ってビットを使い分けながら枠ギリギリまで削り込みます。
マーク埋込用の穴が開いたところで、アクリルをレーザー加工機で切り抜きます。
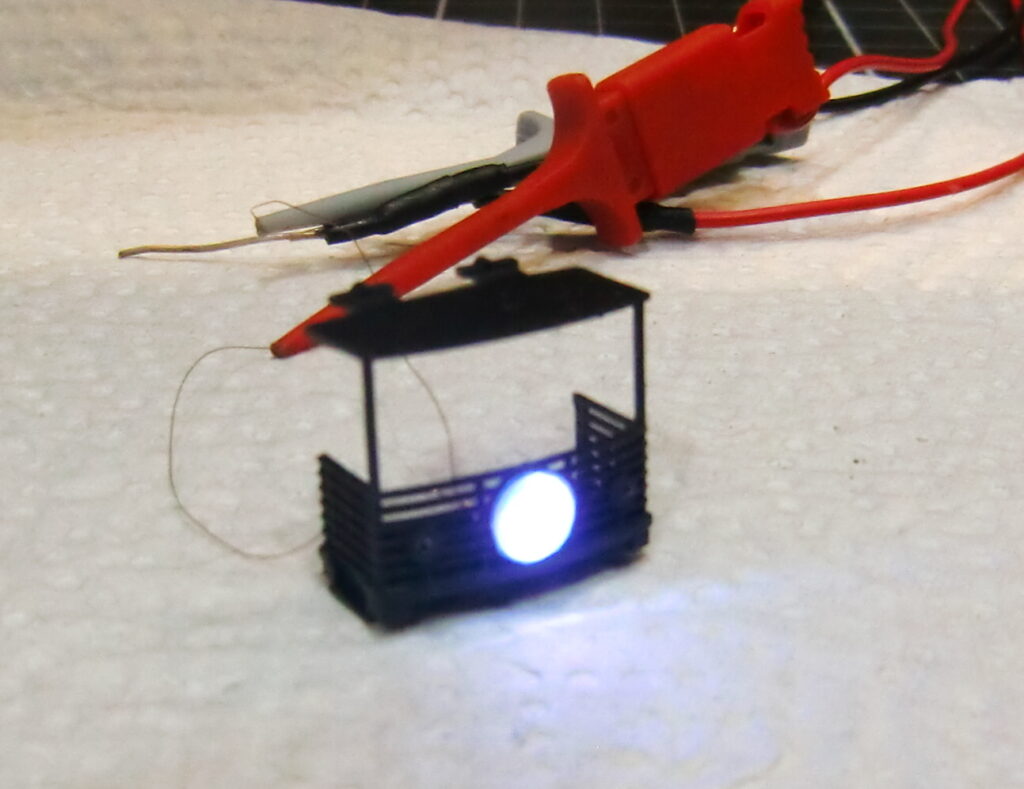
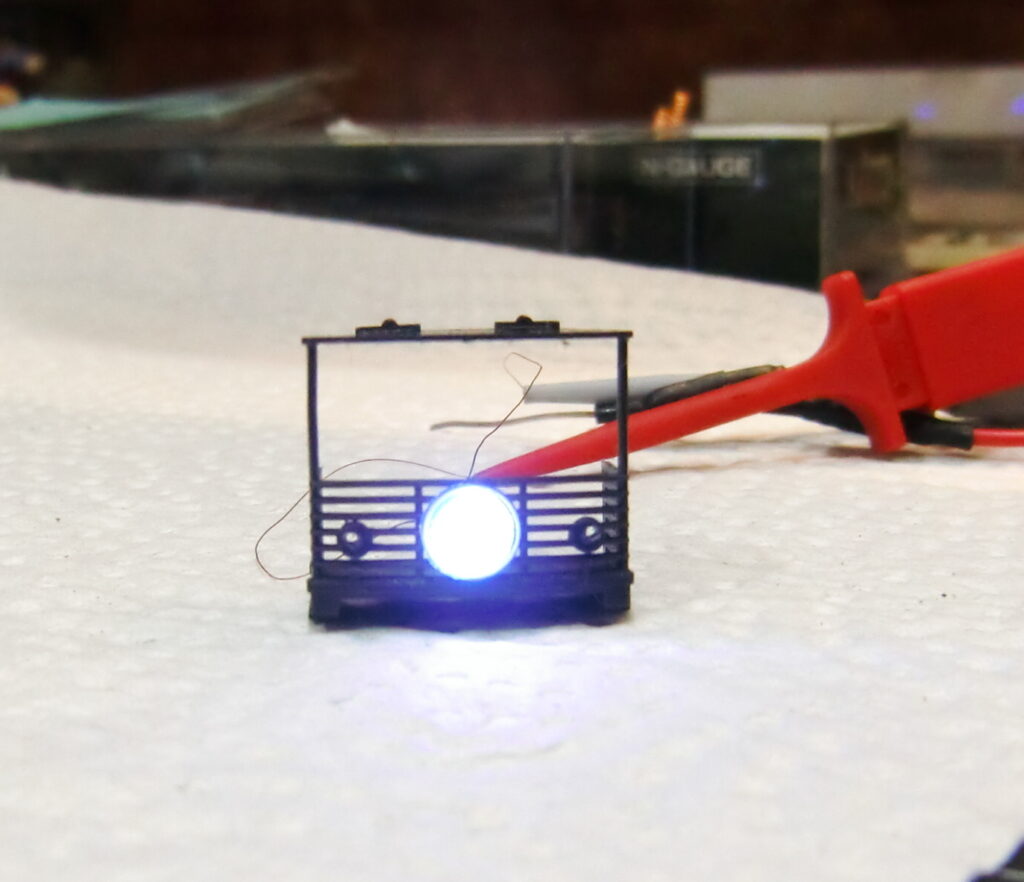
次に遮光パーツと発光源(チップLED)を合わせたパーツを作り、合体させます。こうして出来上がったパーツを裏側から固定して、発光させるとこのような感じとなります。厚さわずか1.5mmで実現できました。あとは制作したシールを貼れば完成です。
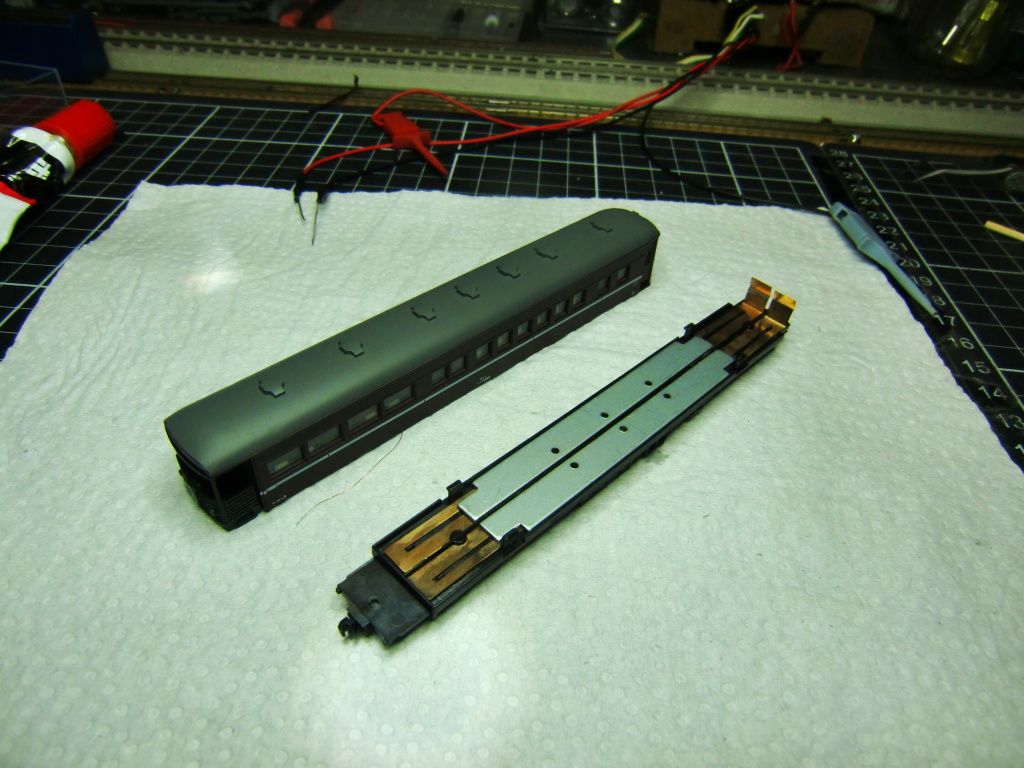



作業完了でございます。

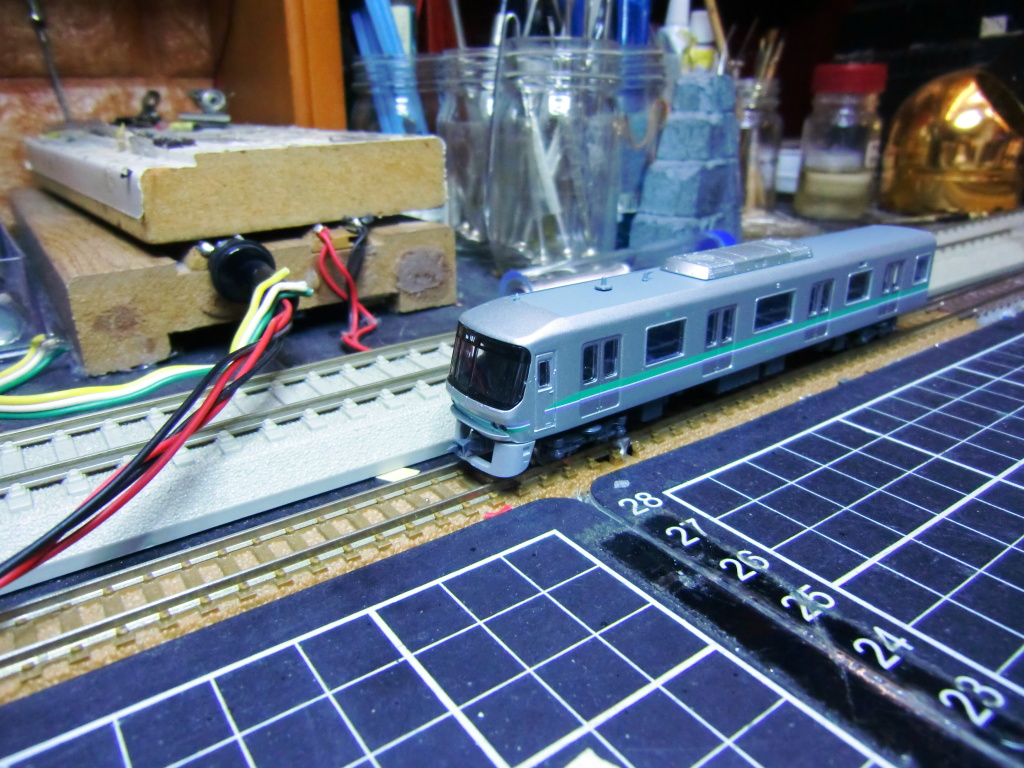
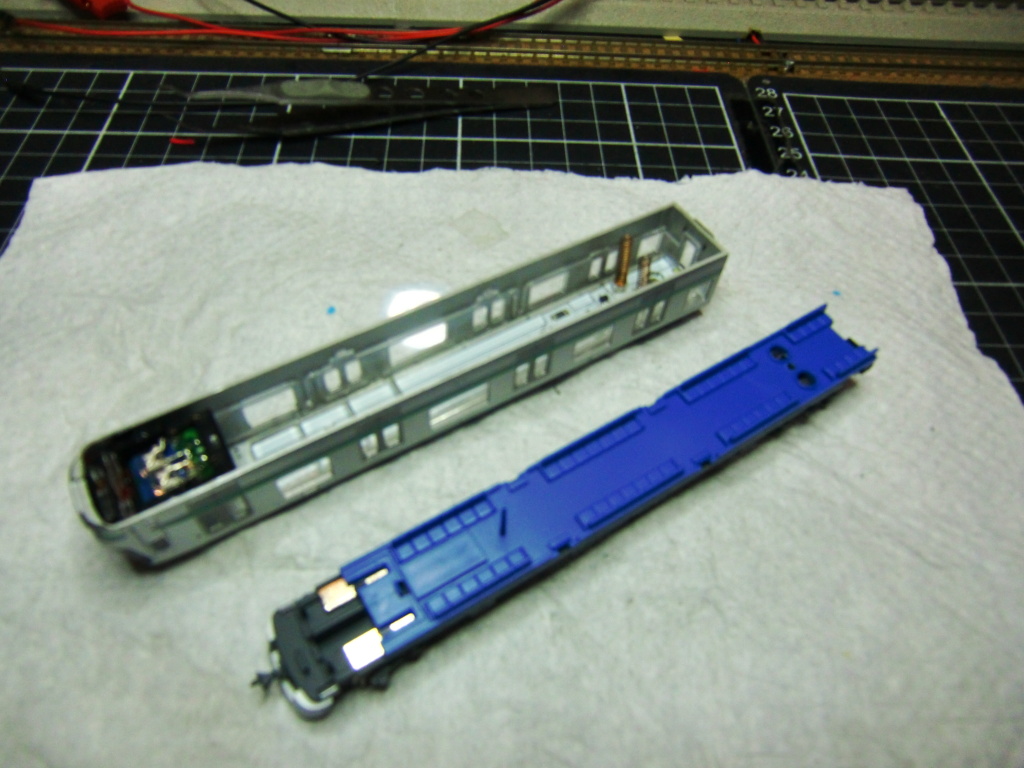
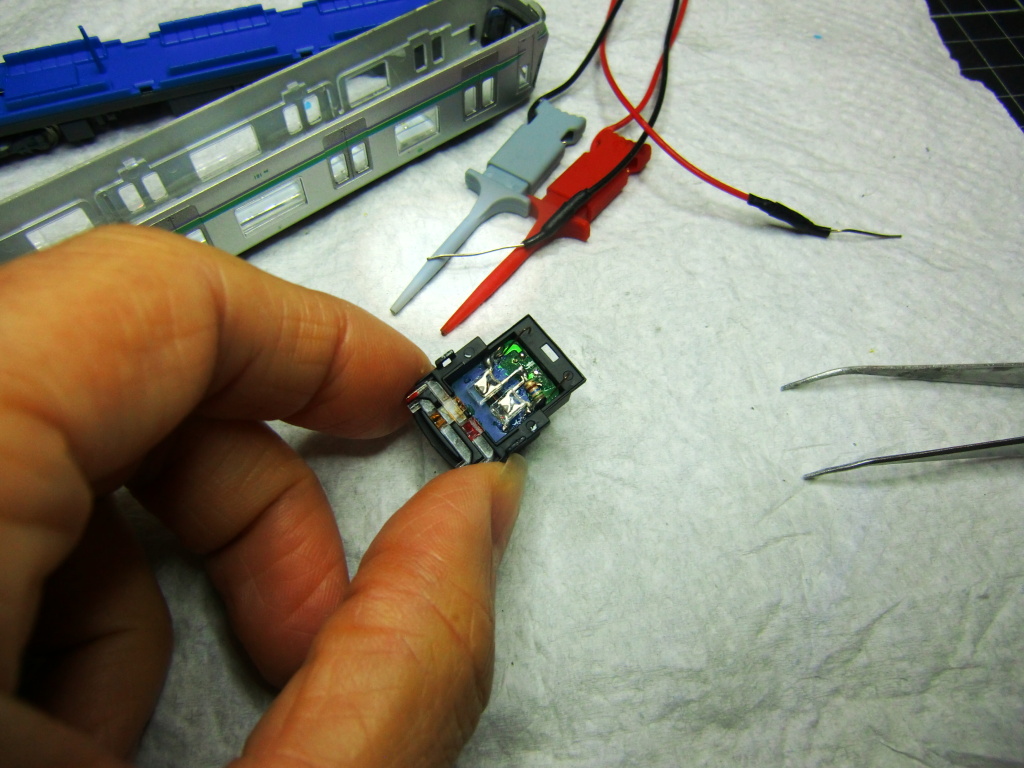
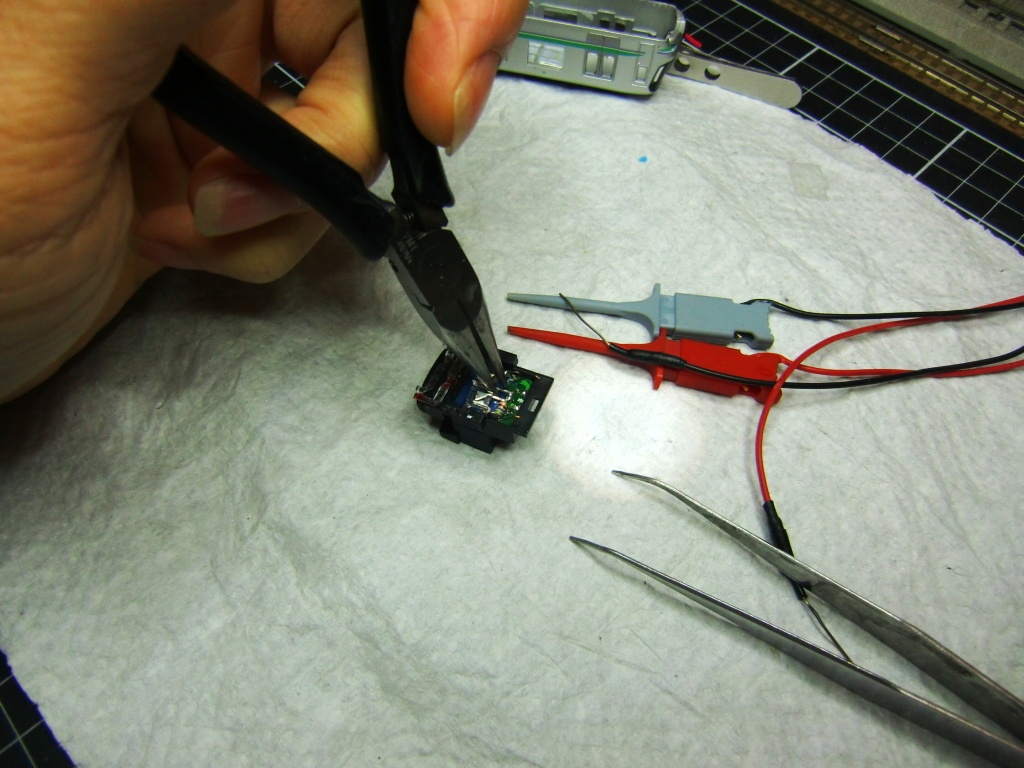
端子間に接点離れが生じないように加工していきます。
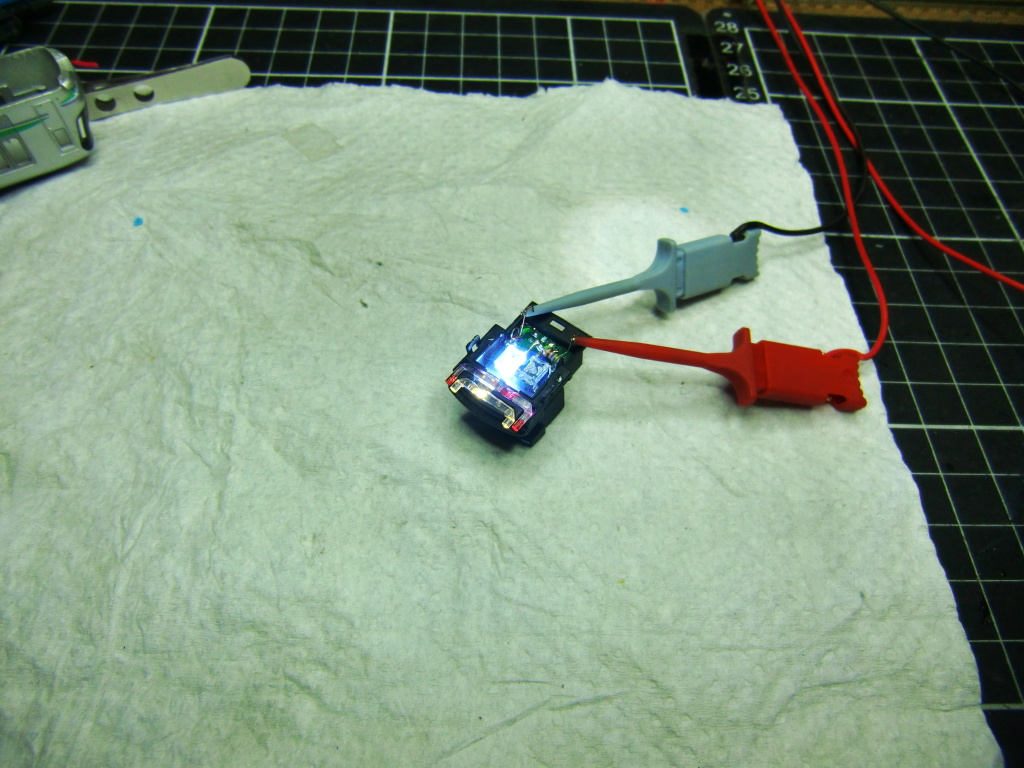


作業完了でございます。
今回は、ライト周りを黒くしたいとのご依頼でございます。

そのままでは、ライトレンズや周りに塗料がついてしまいますので、すべて分解して作業する必要があります。ライトユニットを外すには側面の窓ガラスを先に外す必要がありますが、それなりにコツが必要で簡単には外れません。
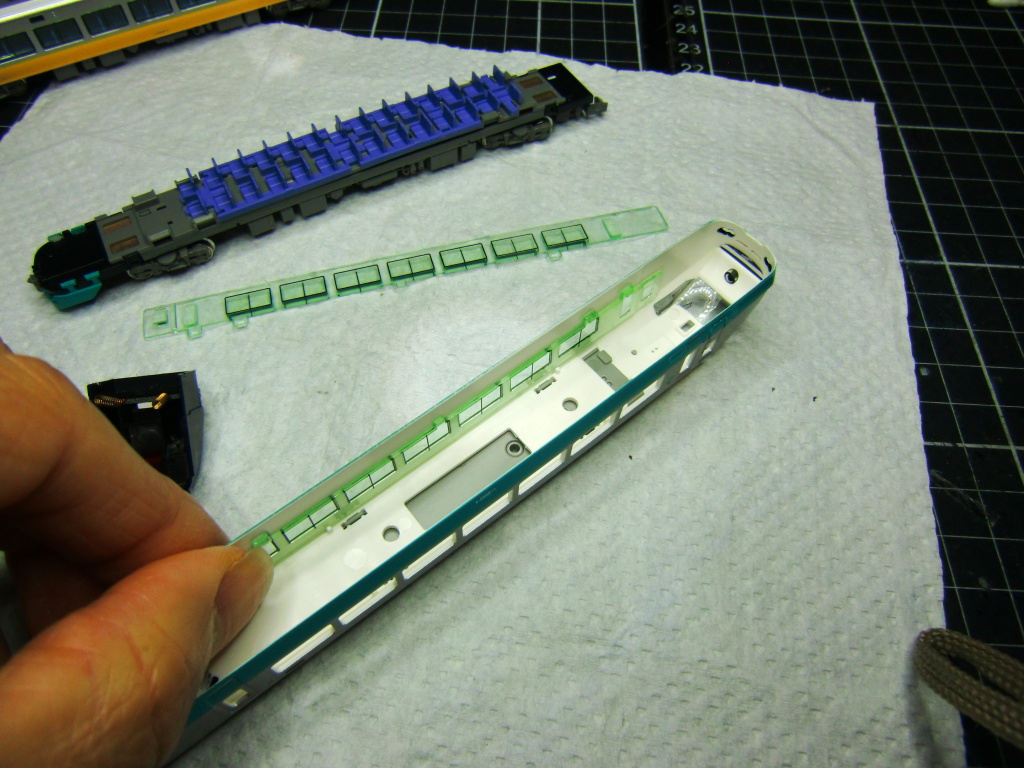
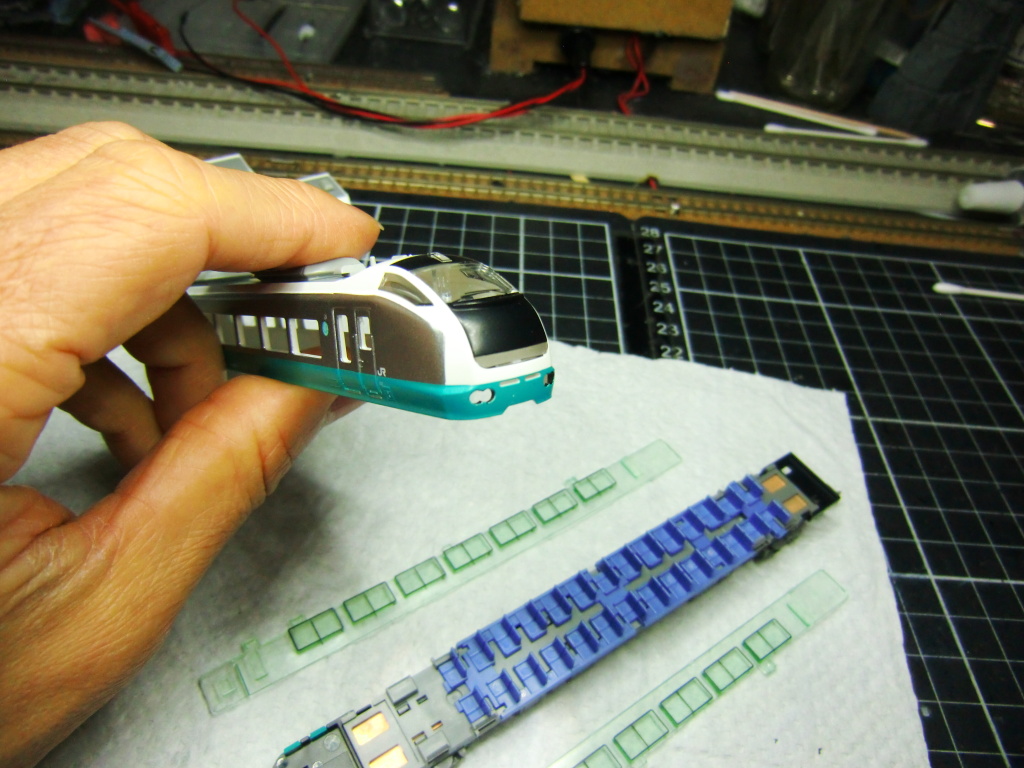
写真では少々見にくいかもしれませんが、奥部分のライト周りは白くなっています。
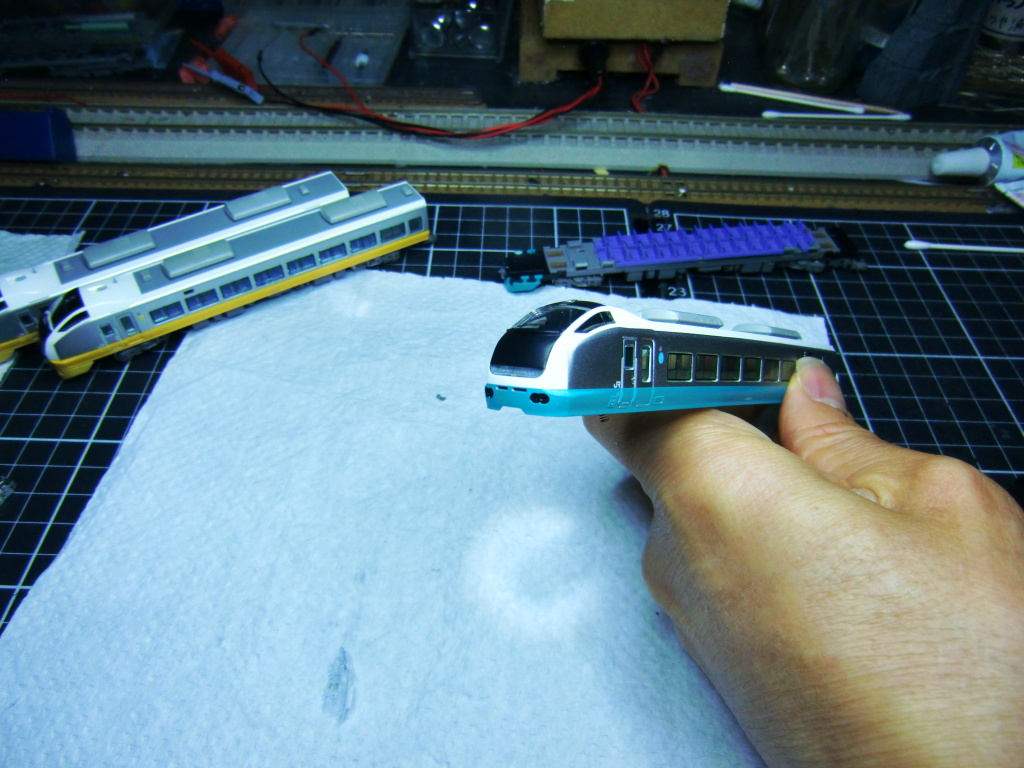
外にはみ出さないように慎重に「つや消し黒」で塗装していきます。「つやあり黒」にしないのは、そのほうが引き締まって見えると考えました。
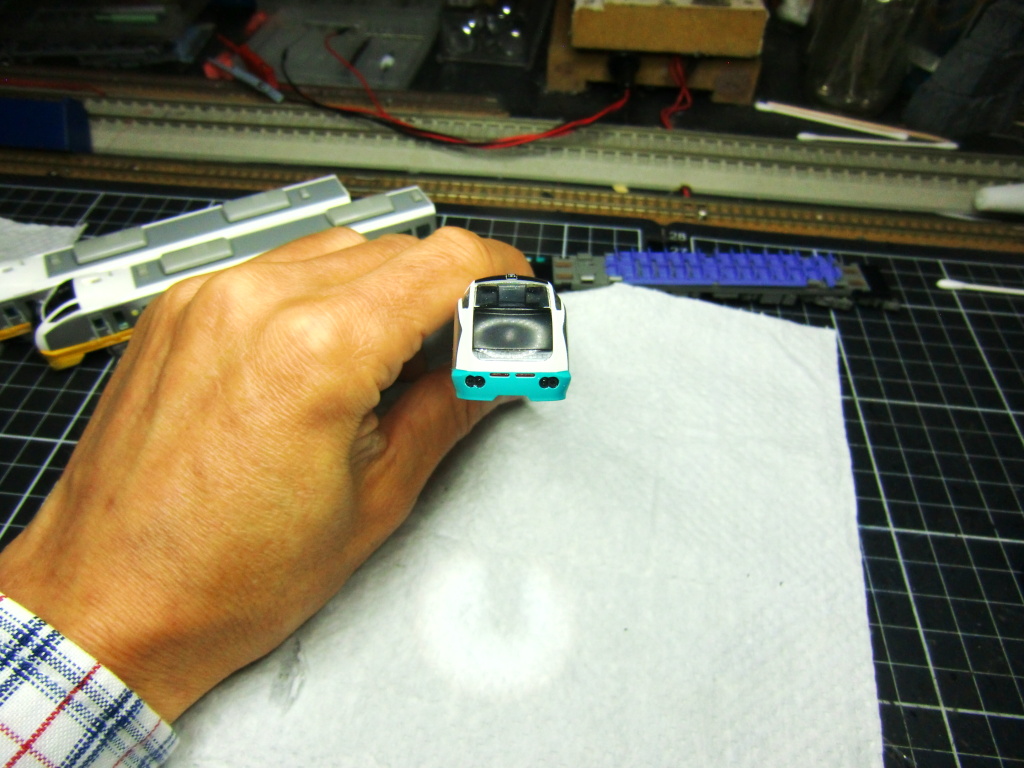

このようになります。つや消し黒の効果がしっかりと出てライト周りは引き締まって見えます。


以上で作業は完了いたしました。
まとめて修理のご依頼です。
▼トーマス君

まずは、こちらの「トーマス君」から作業に入ります。めったに修理のご依頼がない機関車だけに新鮮な感じがします。
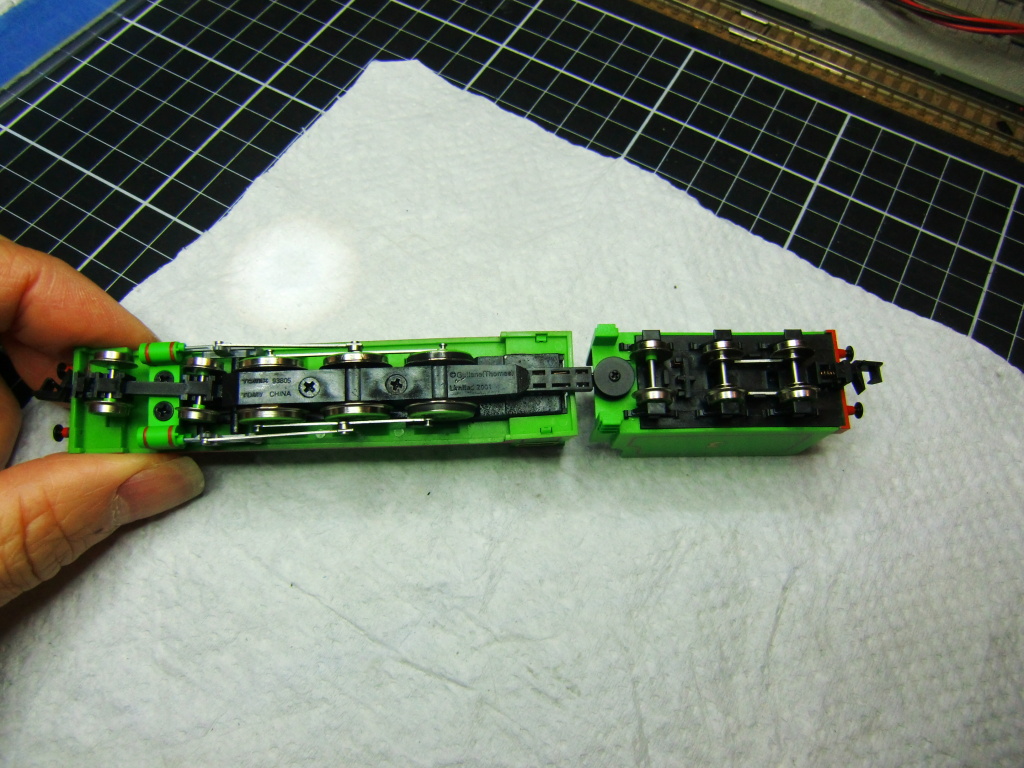
ふむふむ、下はこのようになっているのね。

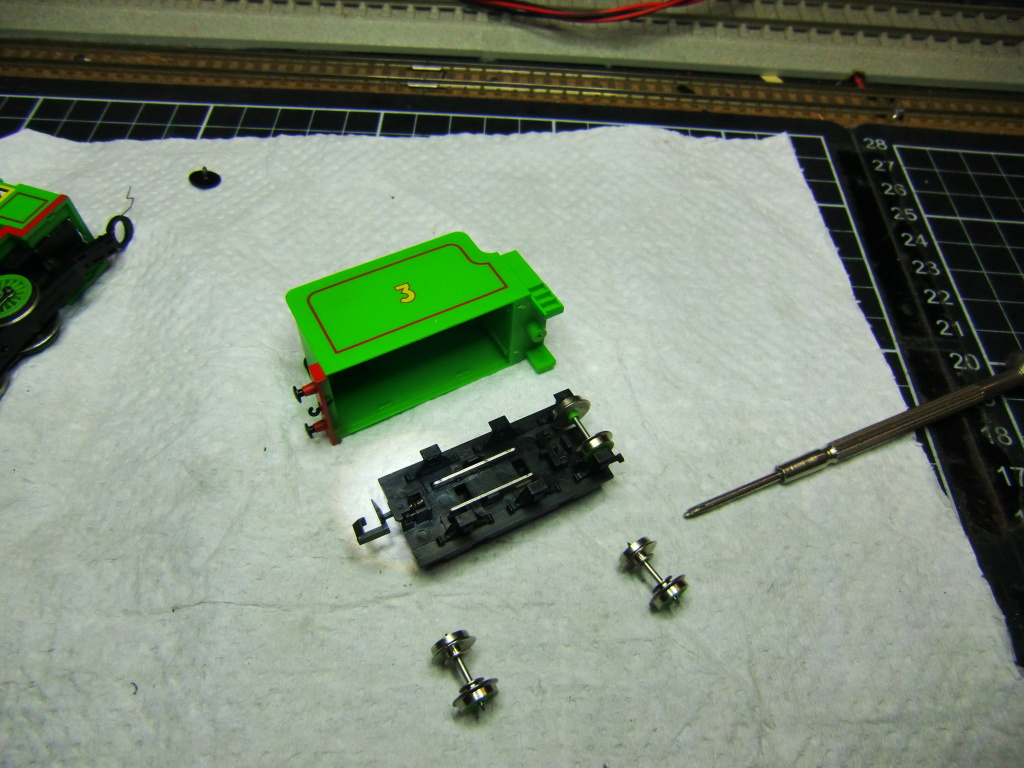

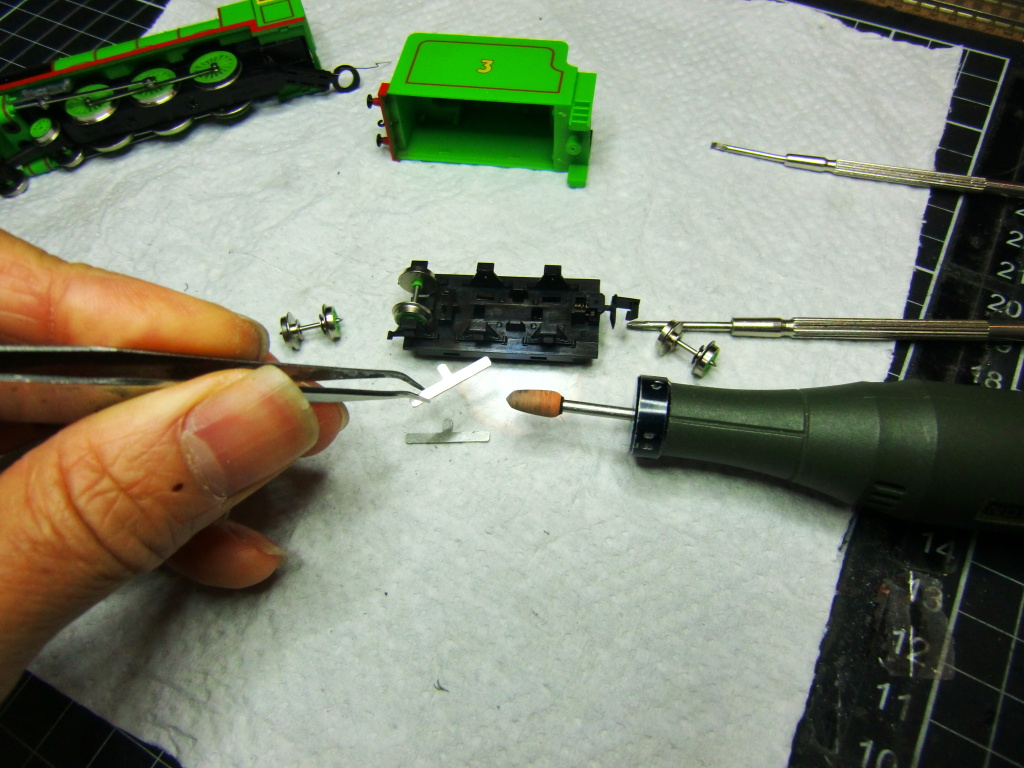
内部の集電パーツも徹底してメンテを行います。
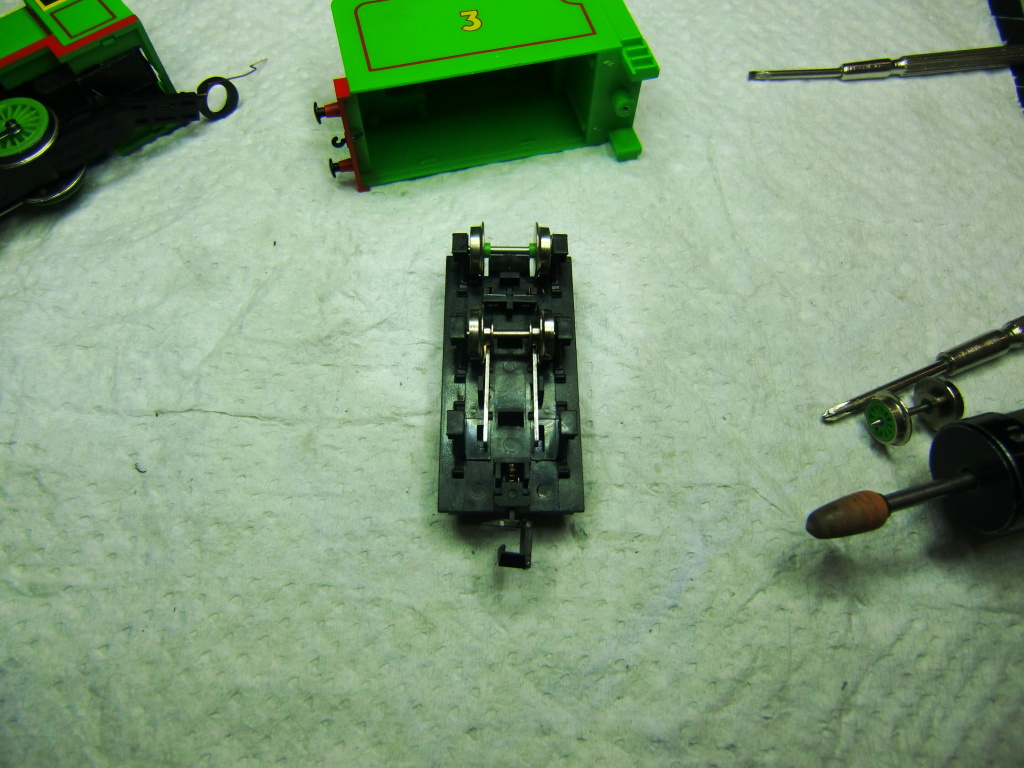
ピカピカになりました。
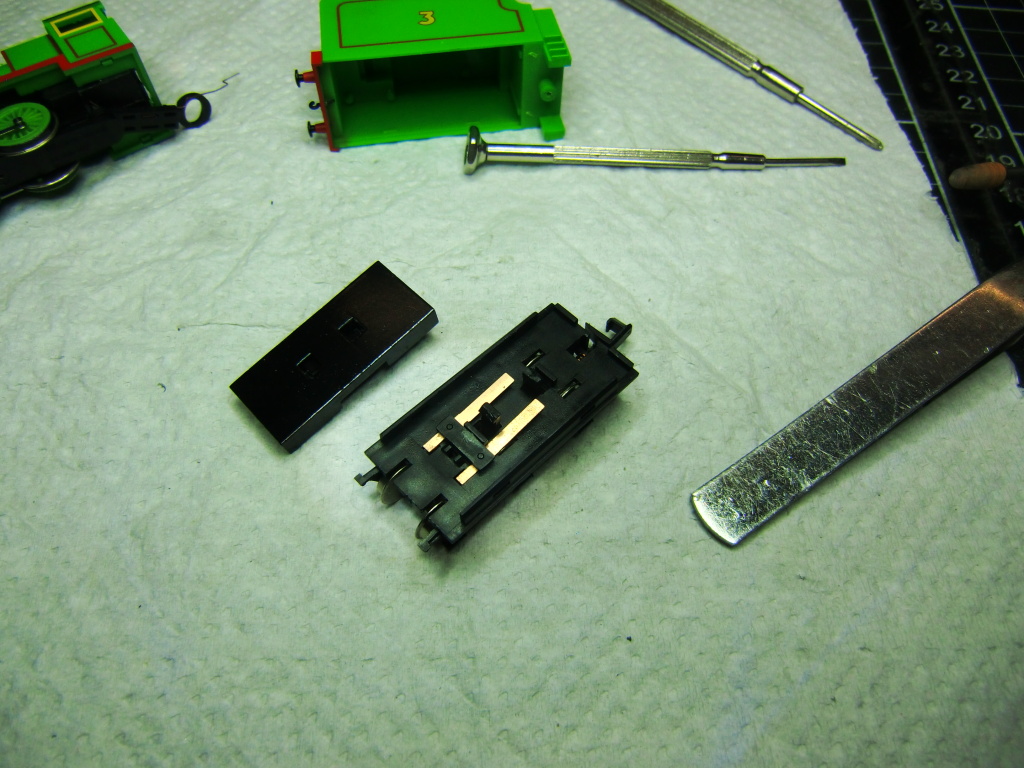

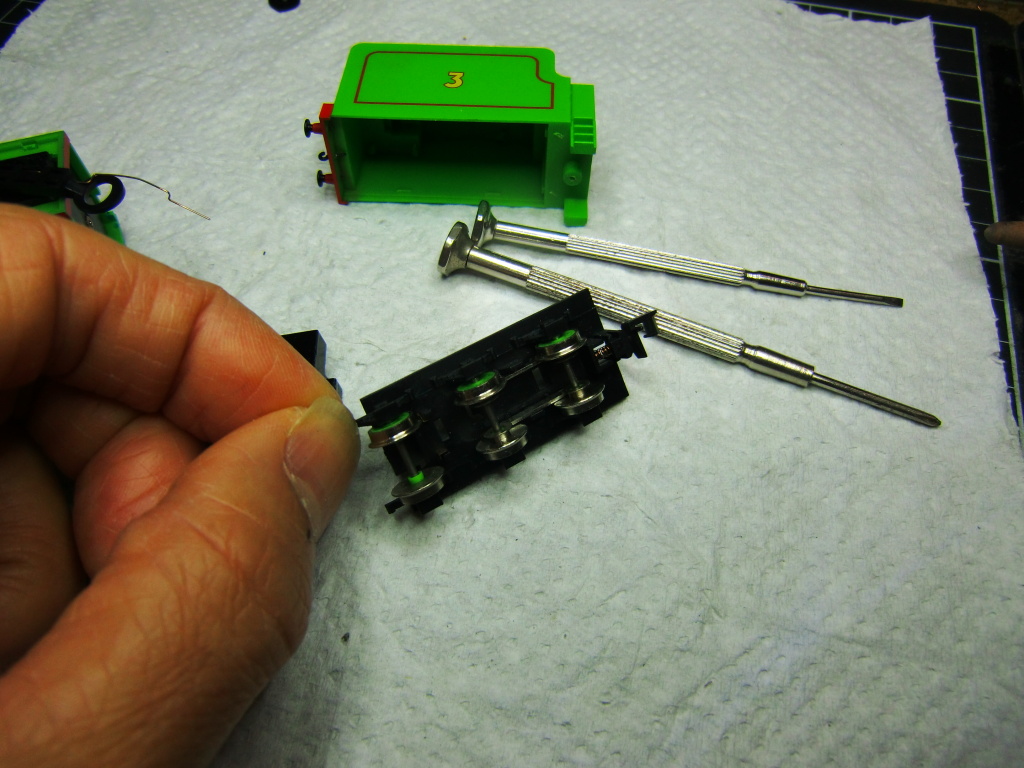
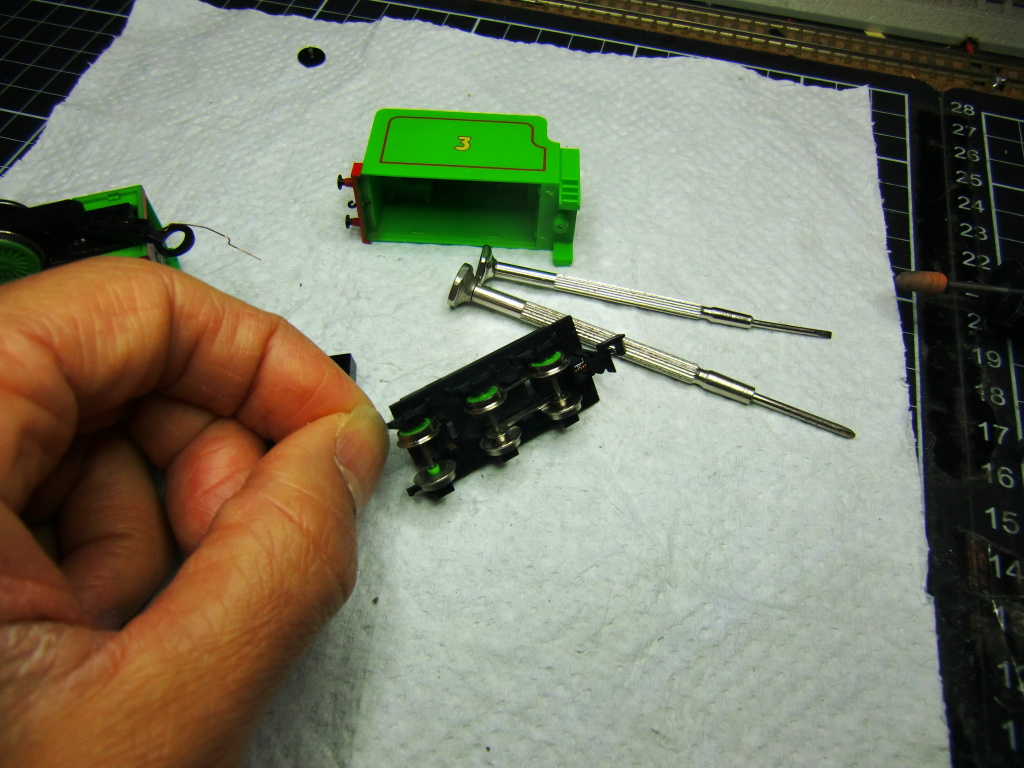
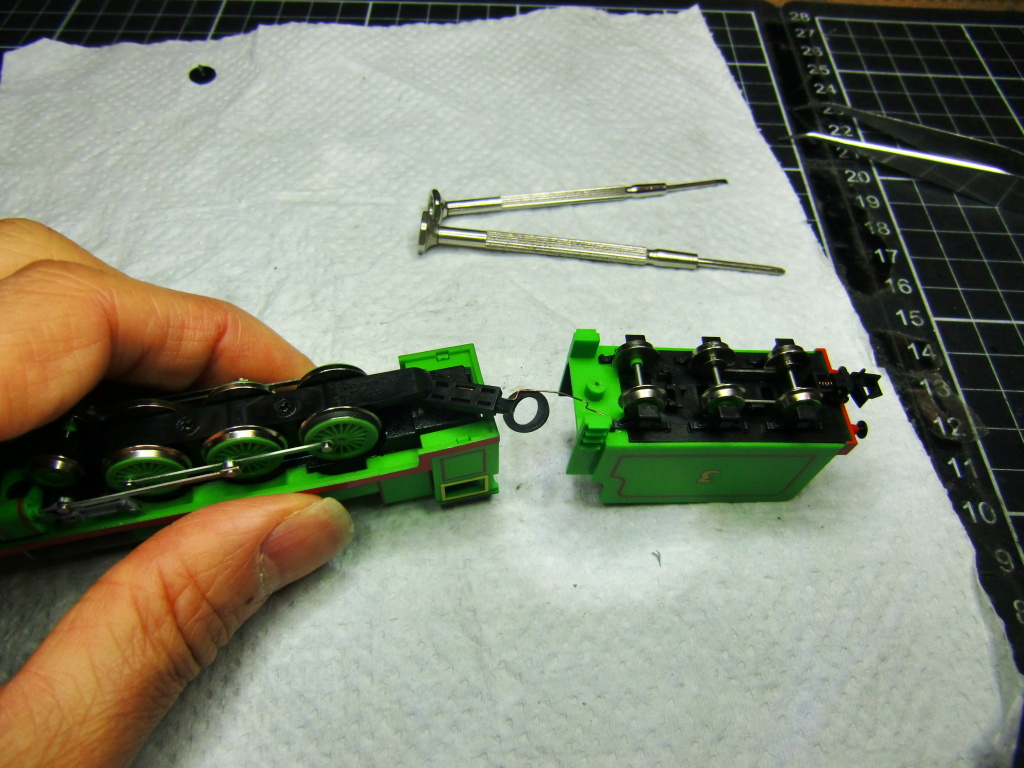
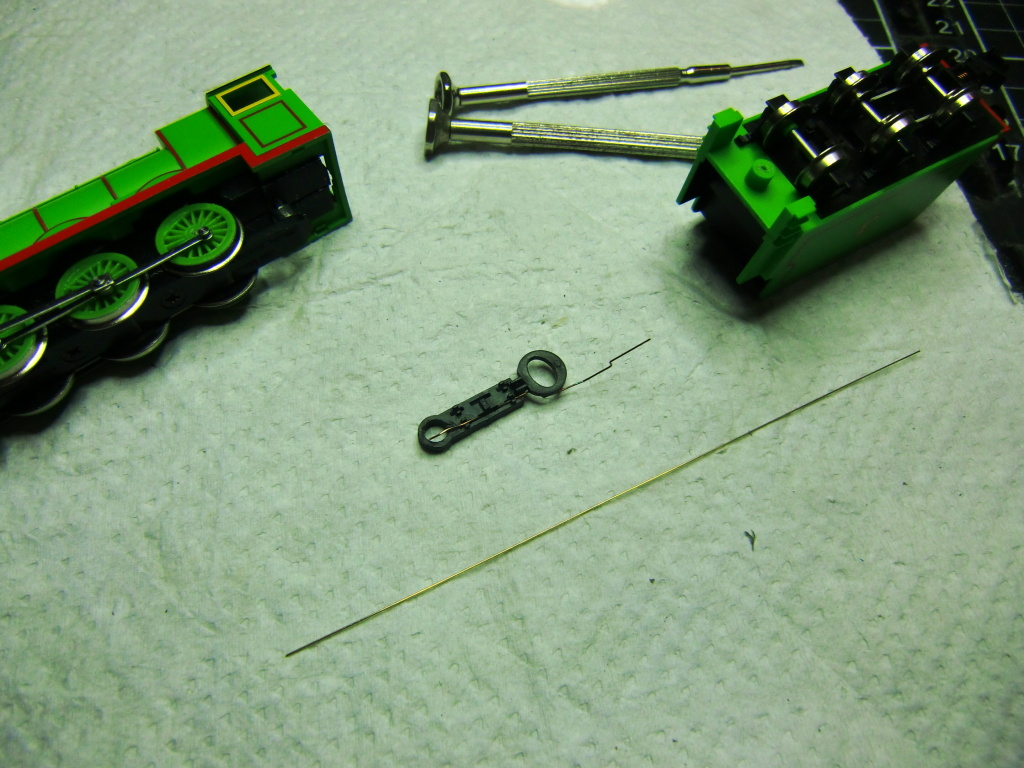
テンダーからの集電用のピンもありませんので、真鍮線(0.3φ)で自作して組み込むことにします。

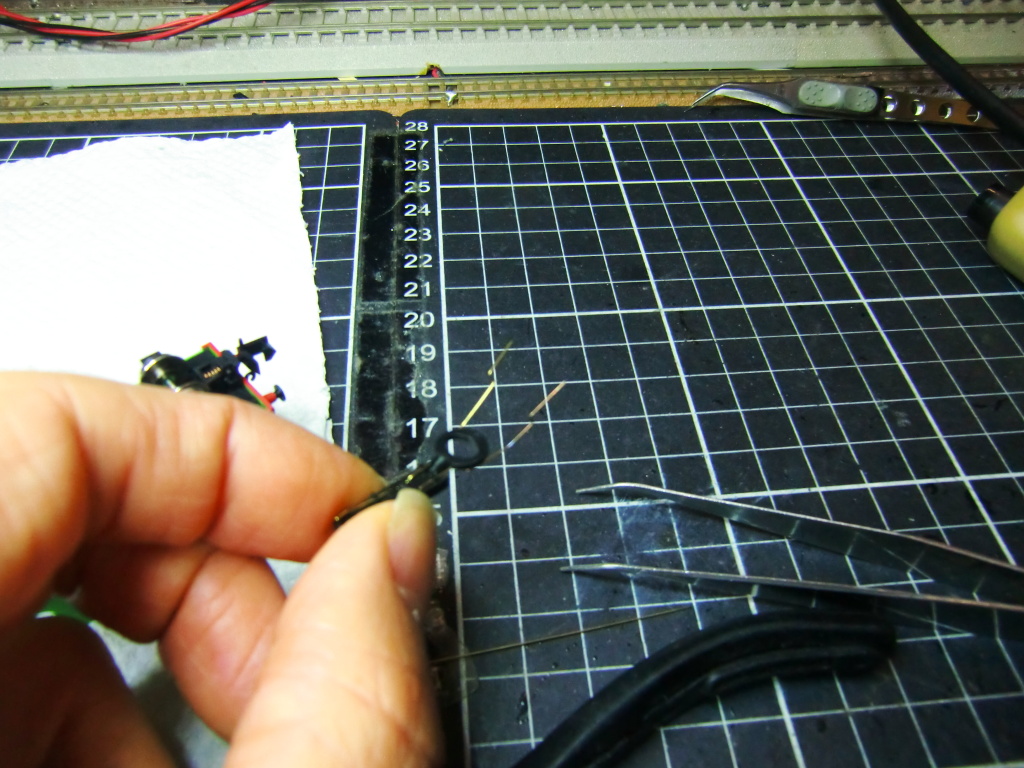
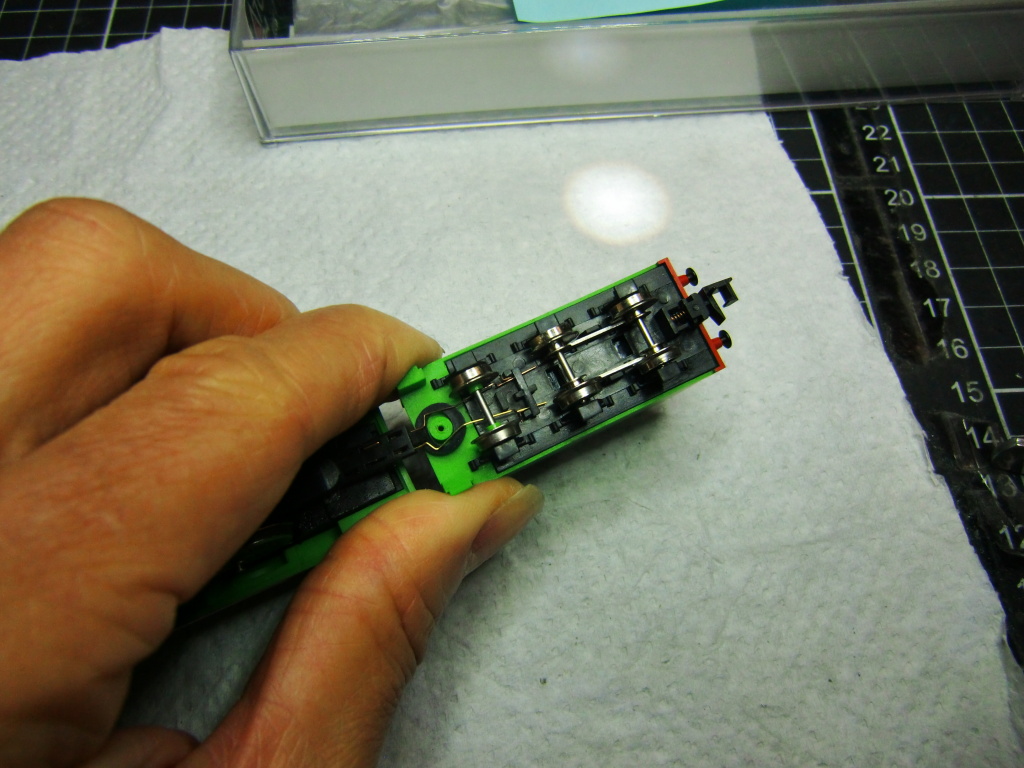
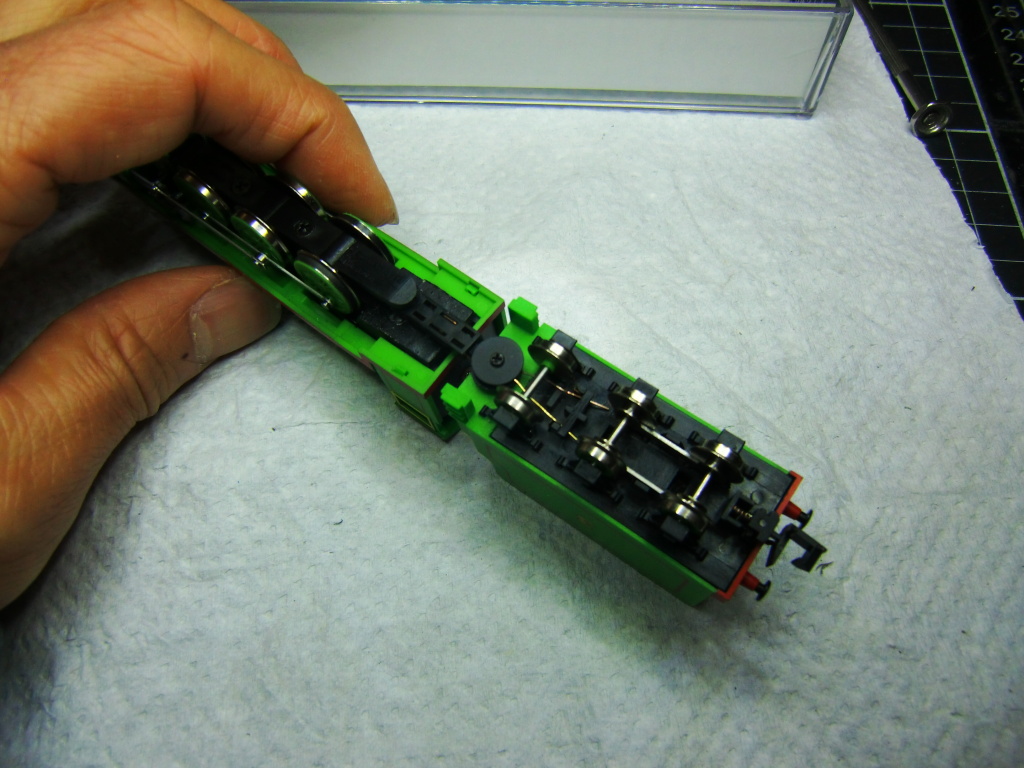
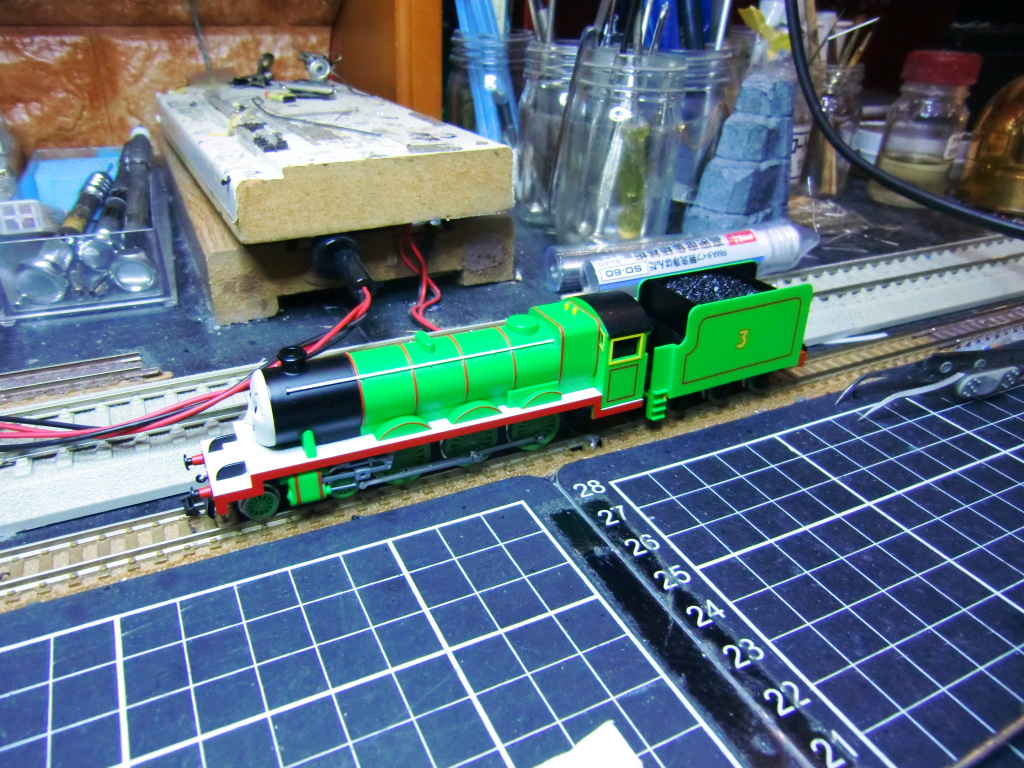

何度か分解と調整を繰り返して、ようやく安定集電も安定し問題なく走行できるようになりました。
▼ITALY 5629 蒸気機関車
さて、「トーマス君」が終ったところで、次の機関車へ移ります。

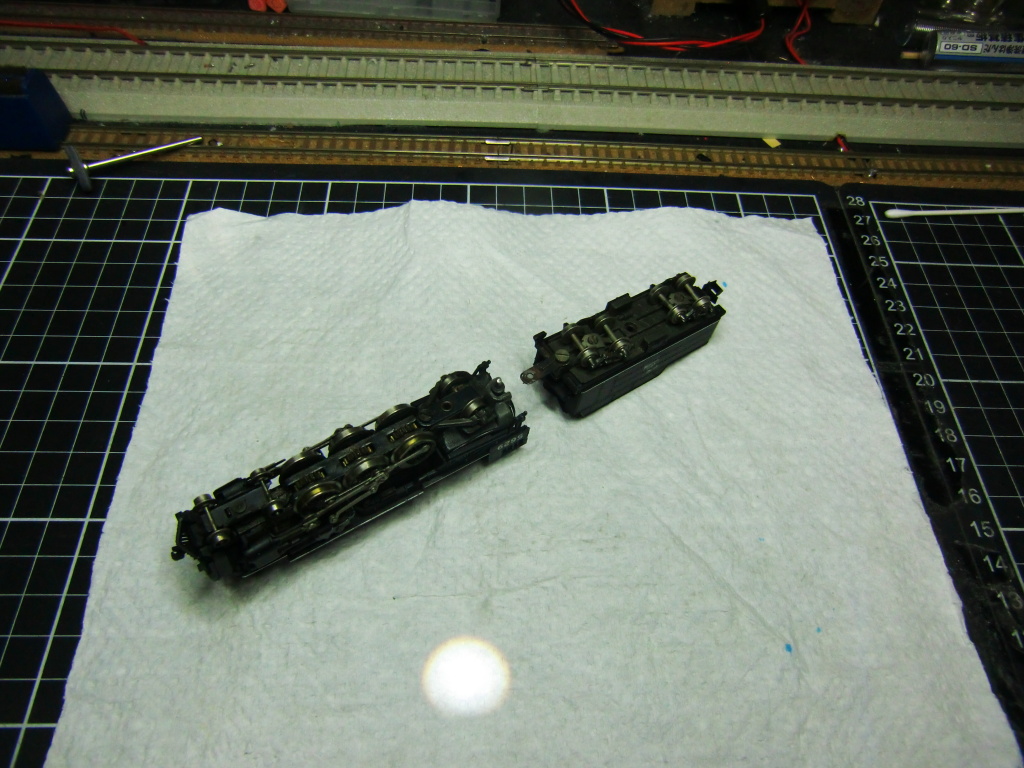
車輪および集電板他、所々錆が出ており白く劣化している状況で、まったく電気を通さない状態でした。台車枠も変形しており車輪が抜け落ちかかっている状況です。単純なメンテという訳にはいかず、直すところがいりいろありそうです。
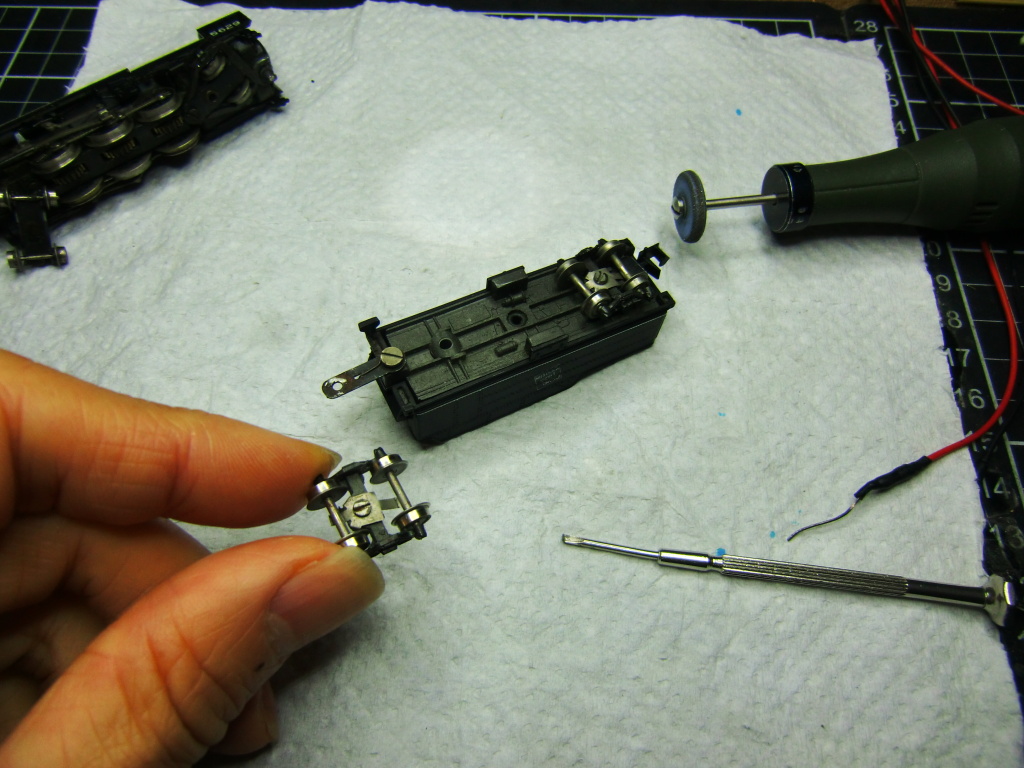
まずは車輪は磨き出していきます。
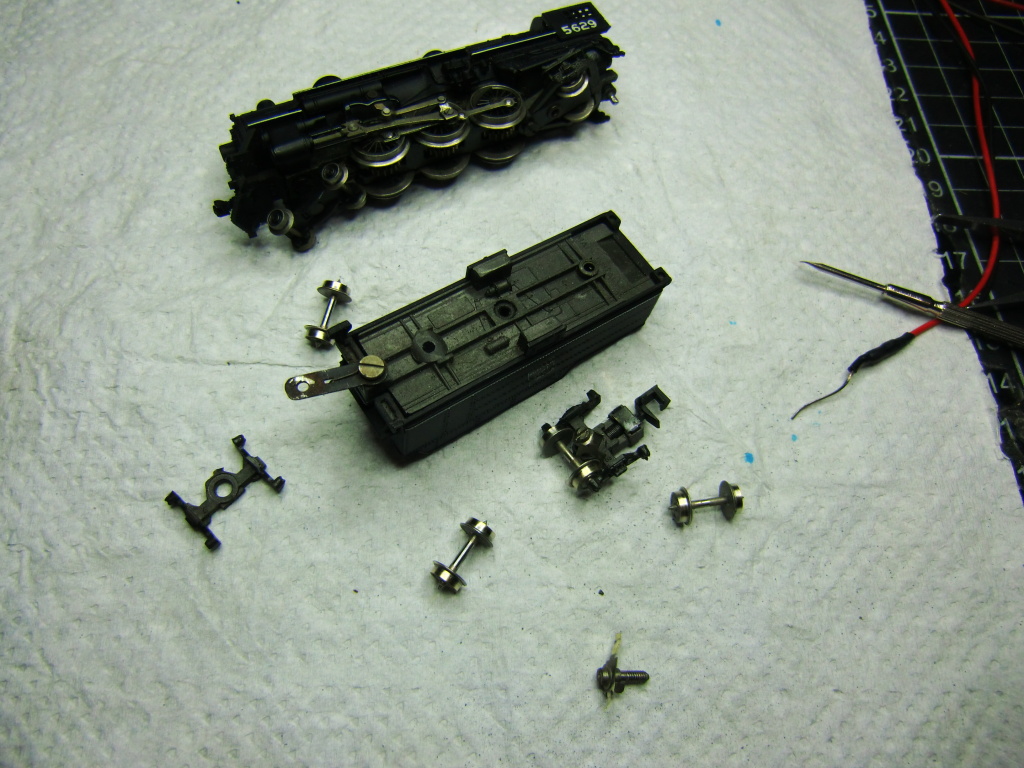
集電板他、いろいろ直さなくてはならい箇所があります。台枠も変形しています。機関車への集電ピンも錆により途中から折れてなくなっています。
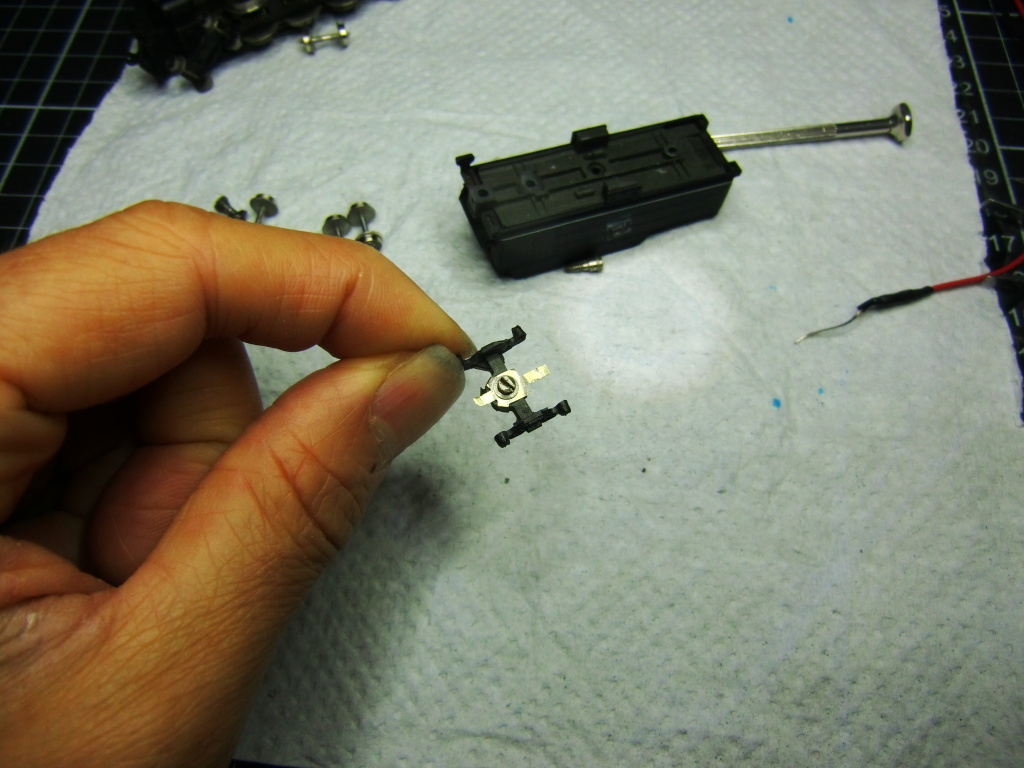
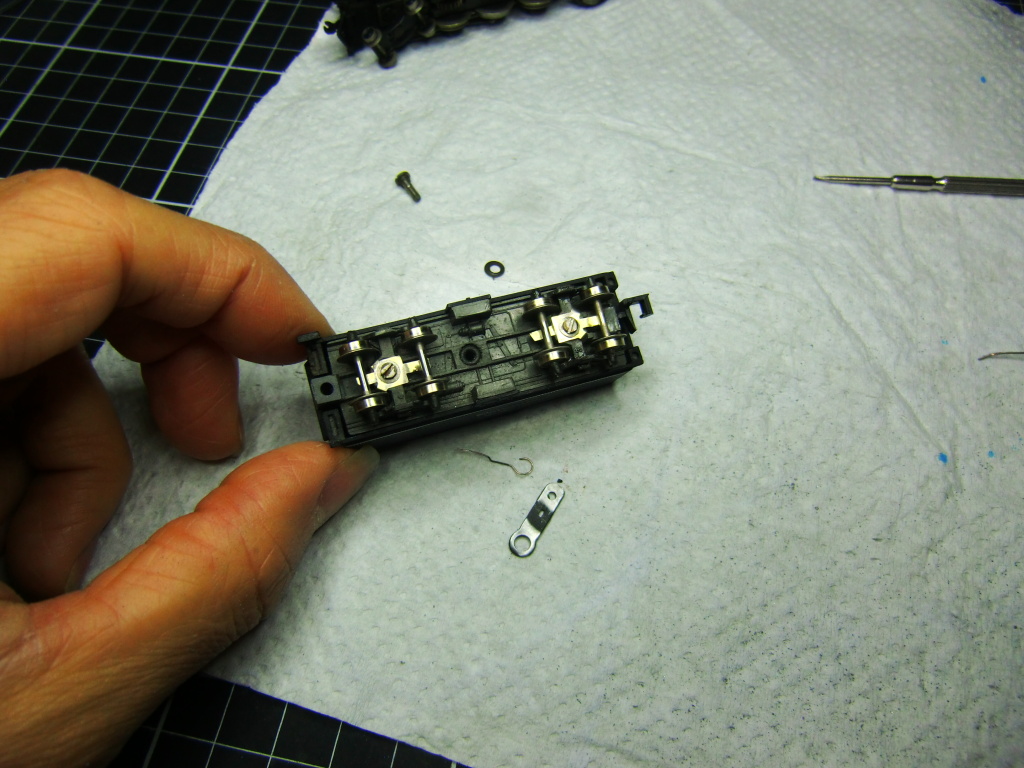
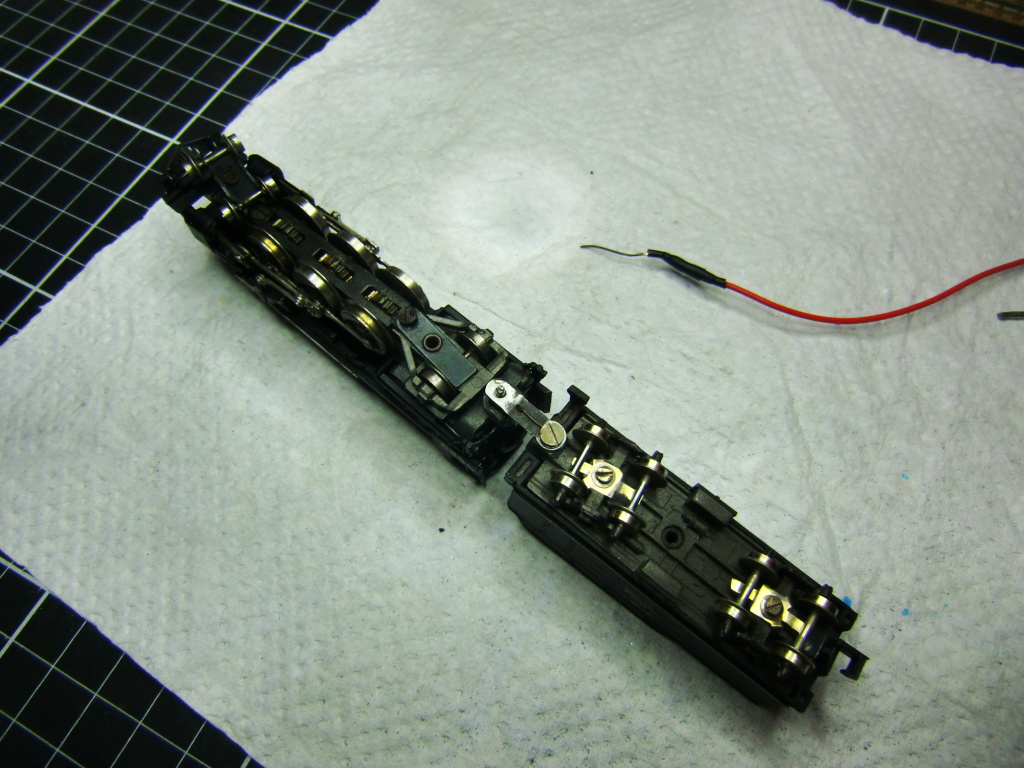
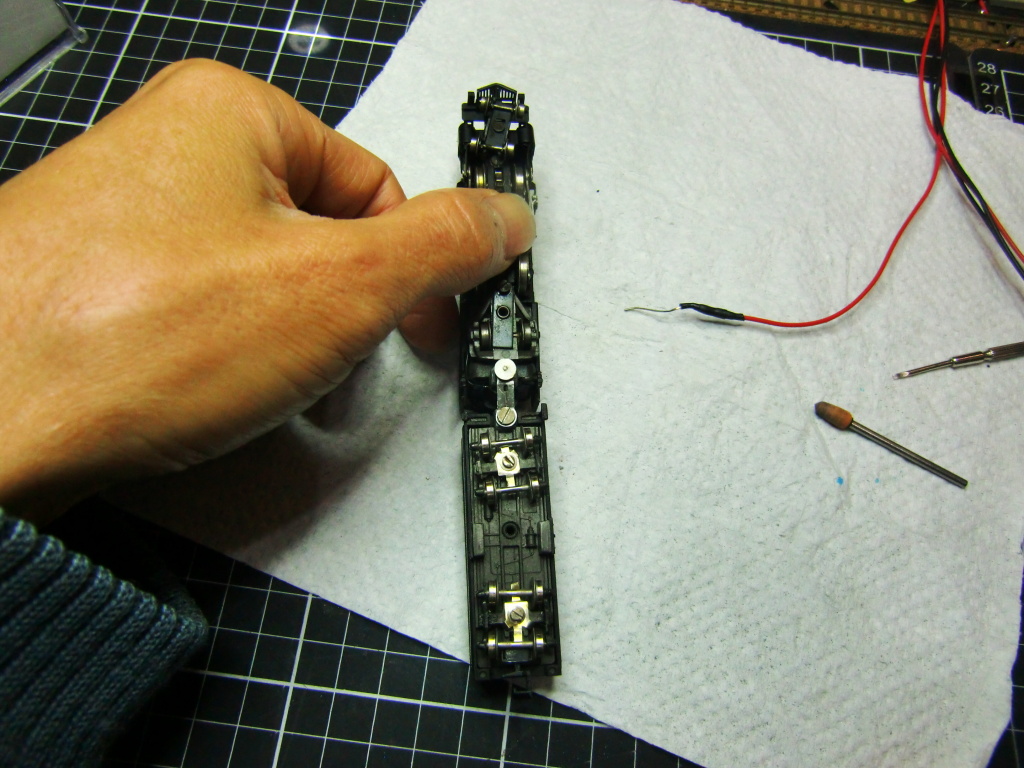
機関車とテンダーを固定するパーツもなくなっているようですので、こちらも制作して組み込みました。
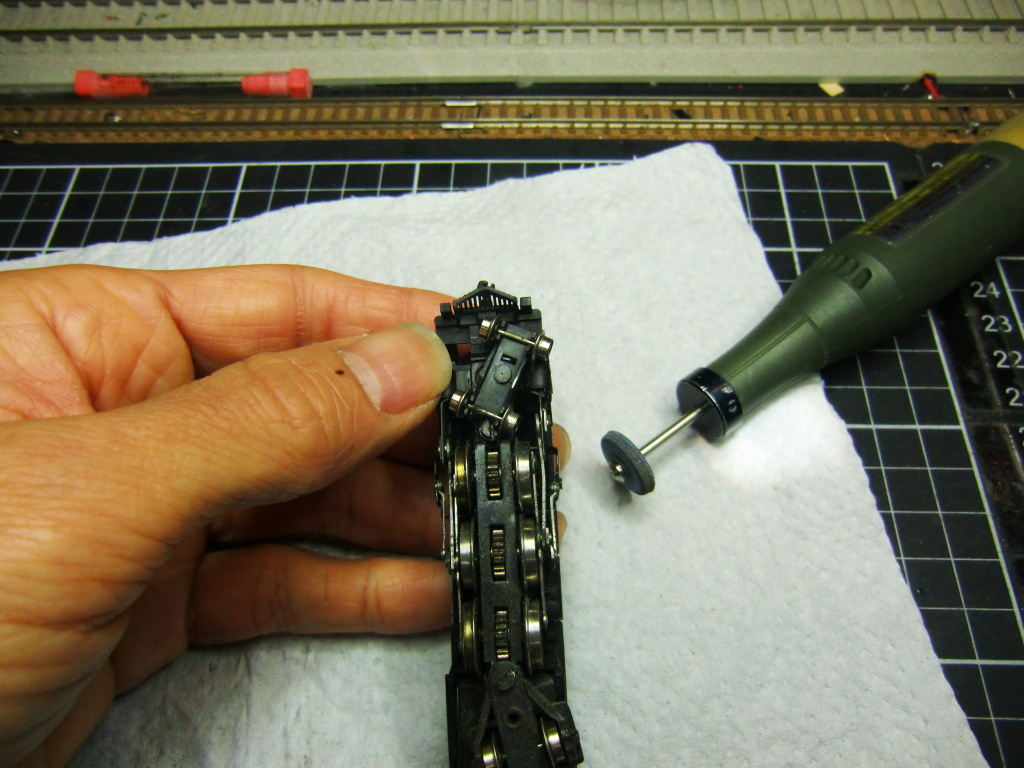

先台車および従輪も磨き出しておきます。車輪本来の輝きを取り戻しました。
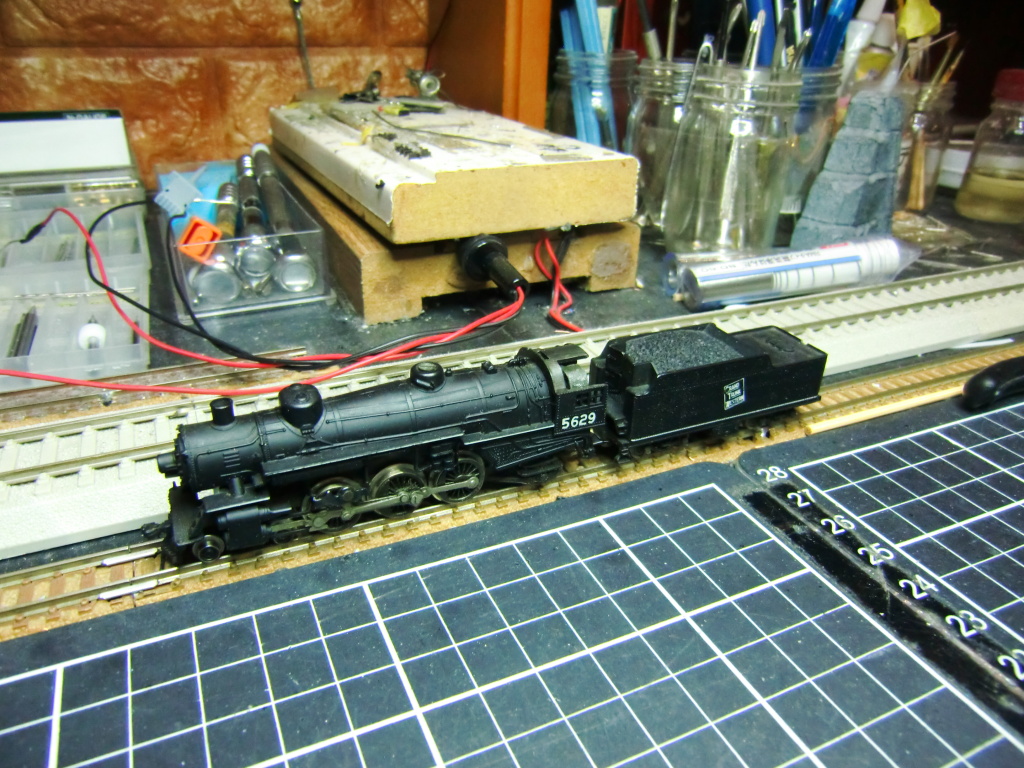

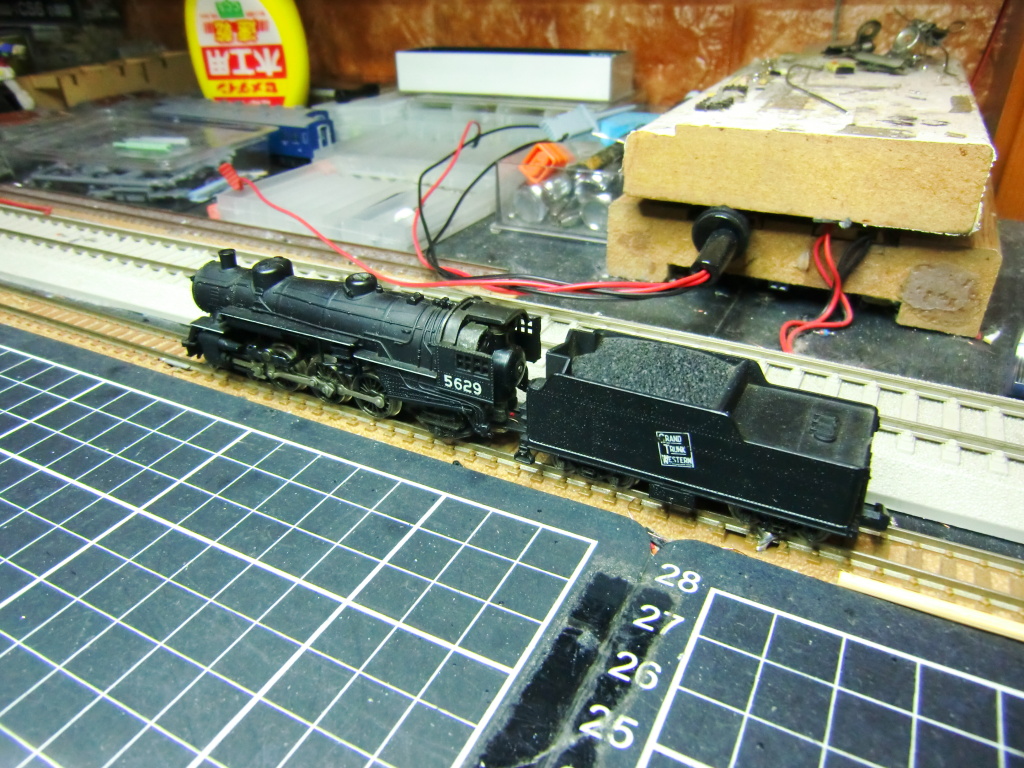
最後に走行テストを行って作業は完了です。
▼マイクロ EF67タイプ 修理(異音)
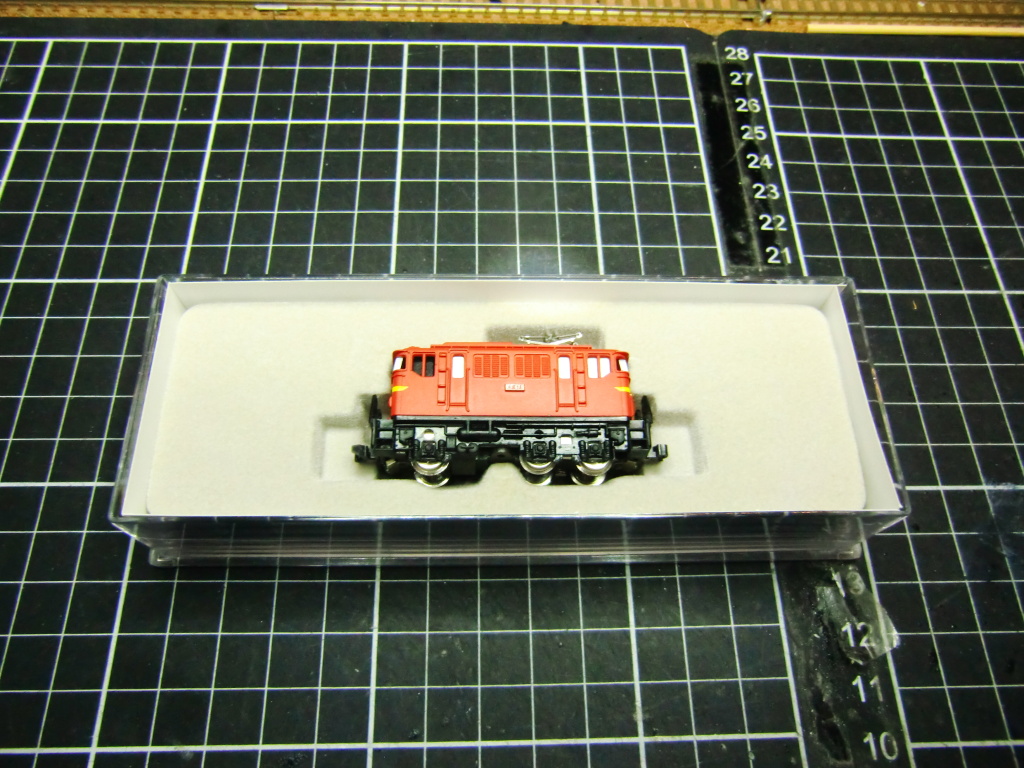

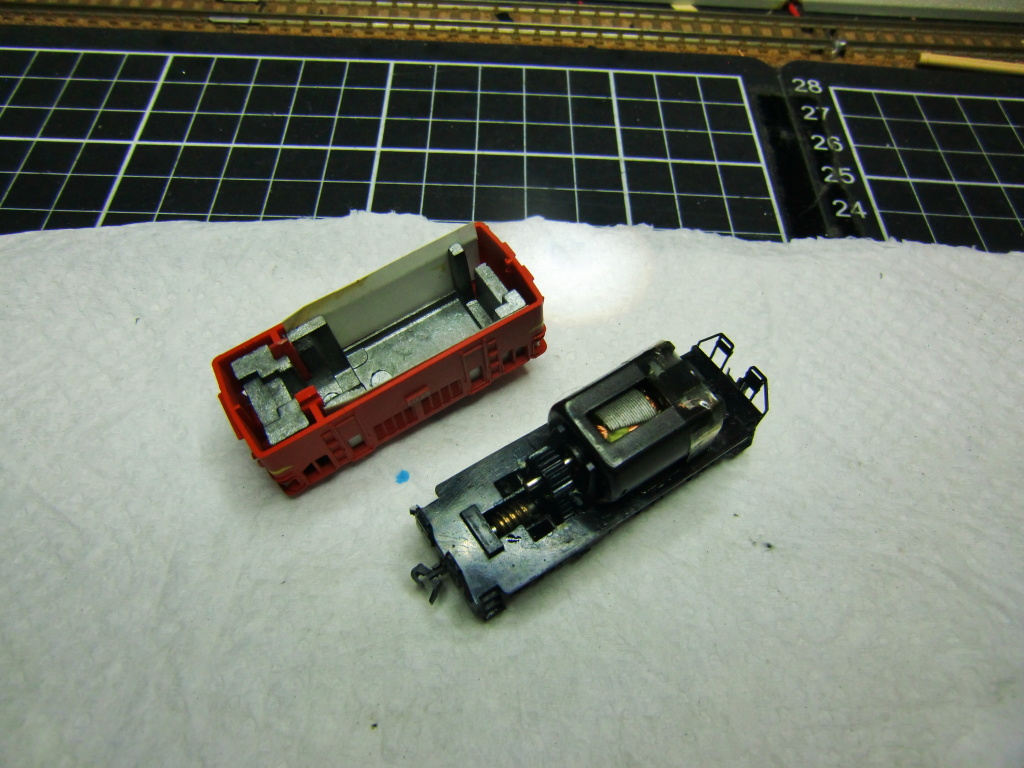
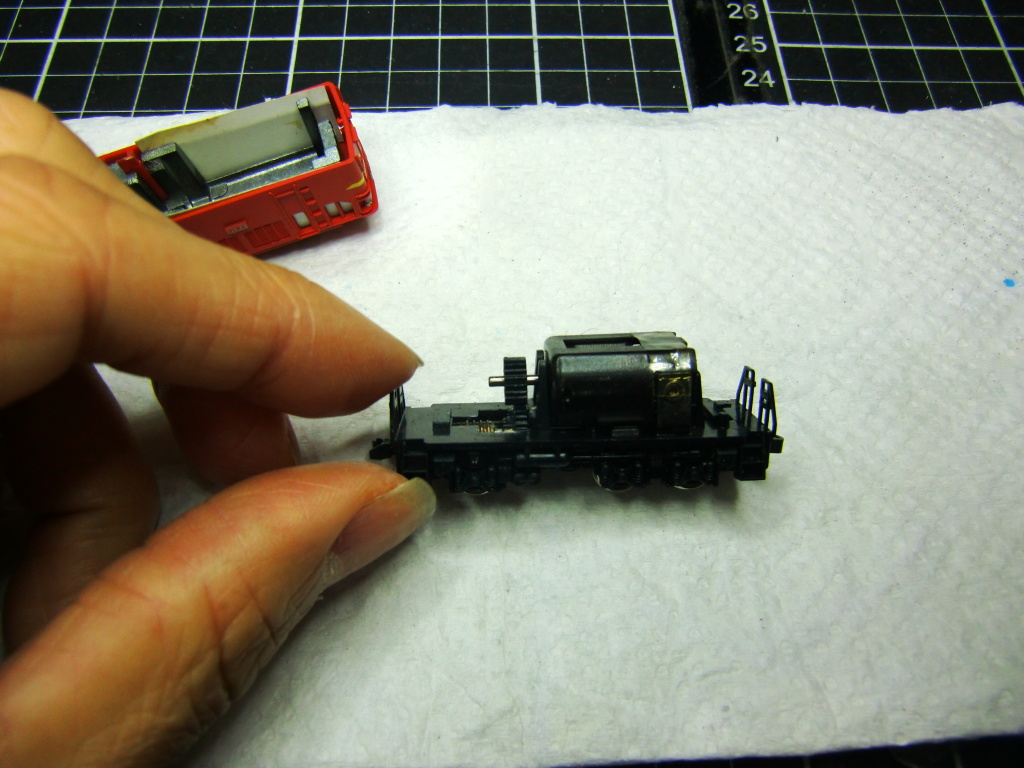
分解してギアの調整を行います。また、モーターとの接点も不安点でしたのでこちらも対処いたしました。
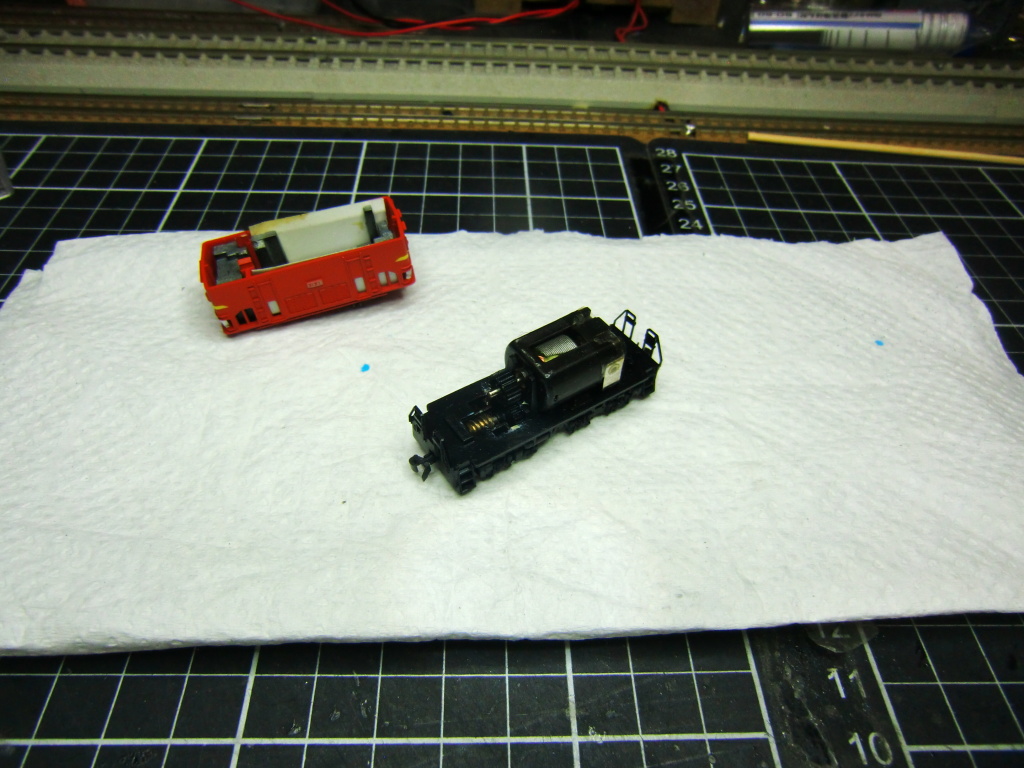
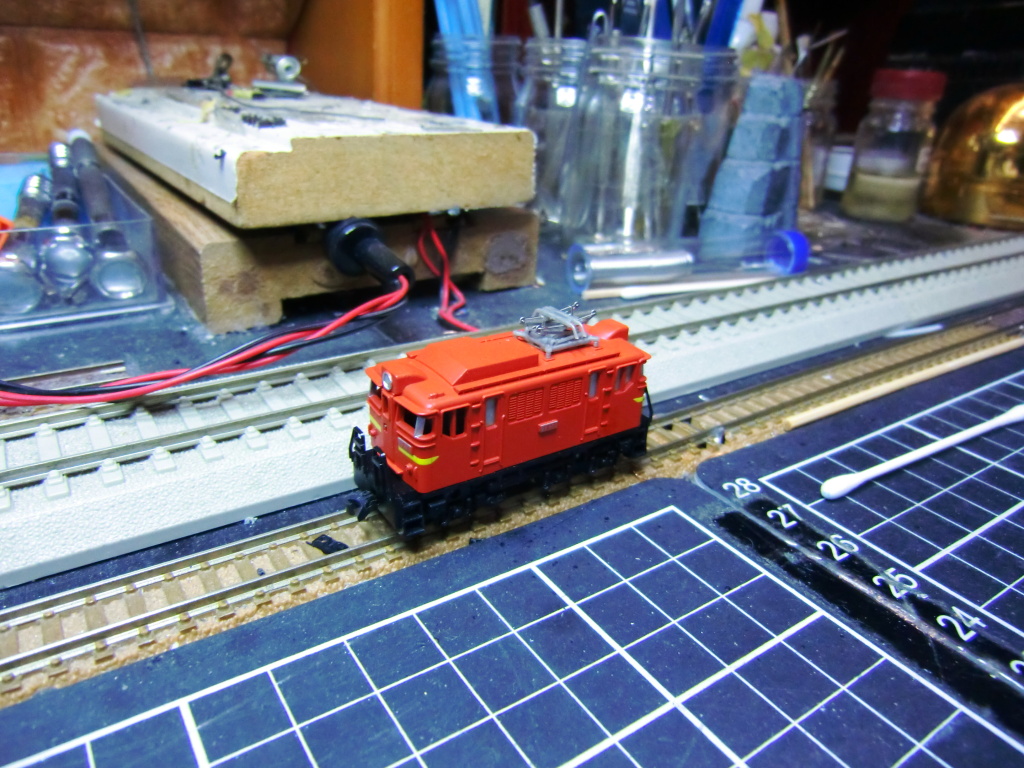

▼中村精密 国鉄C51蒸気機関車
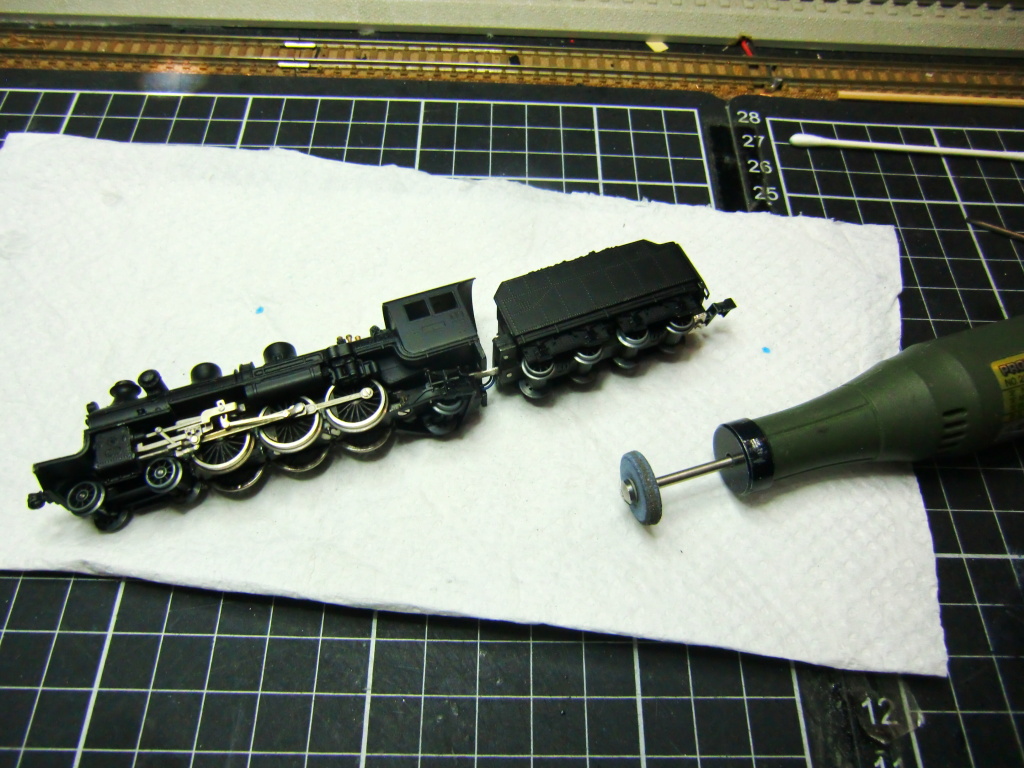
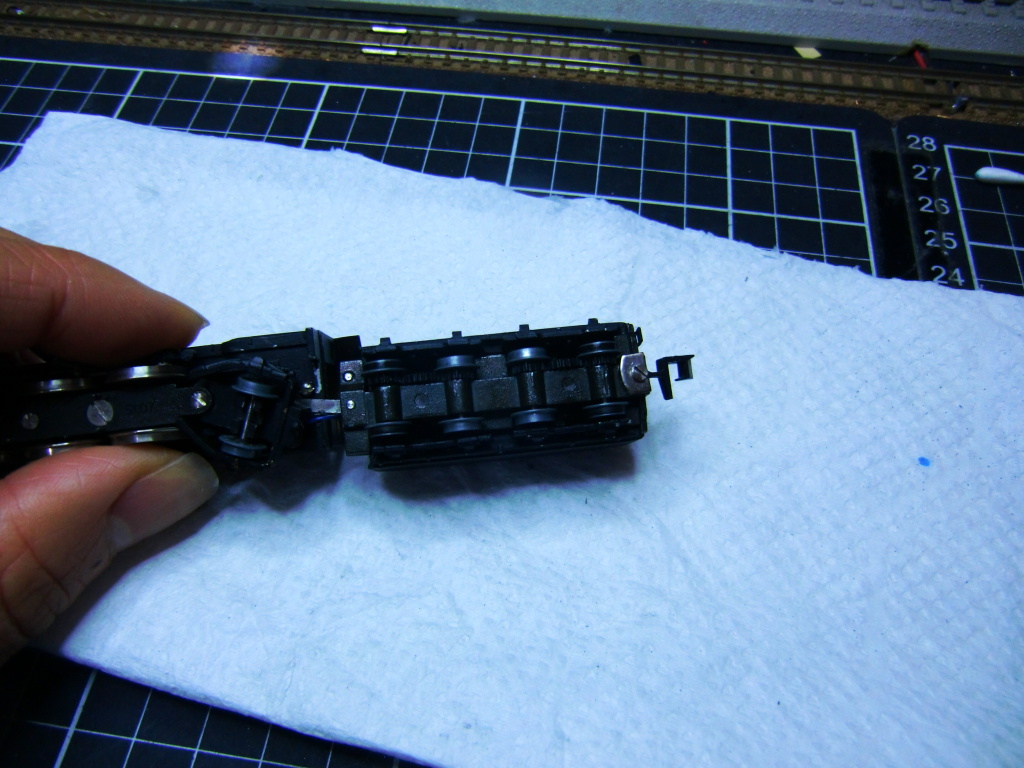
車輪は完全に光沢感がなくなっています。
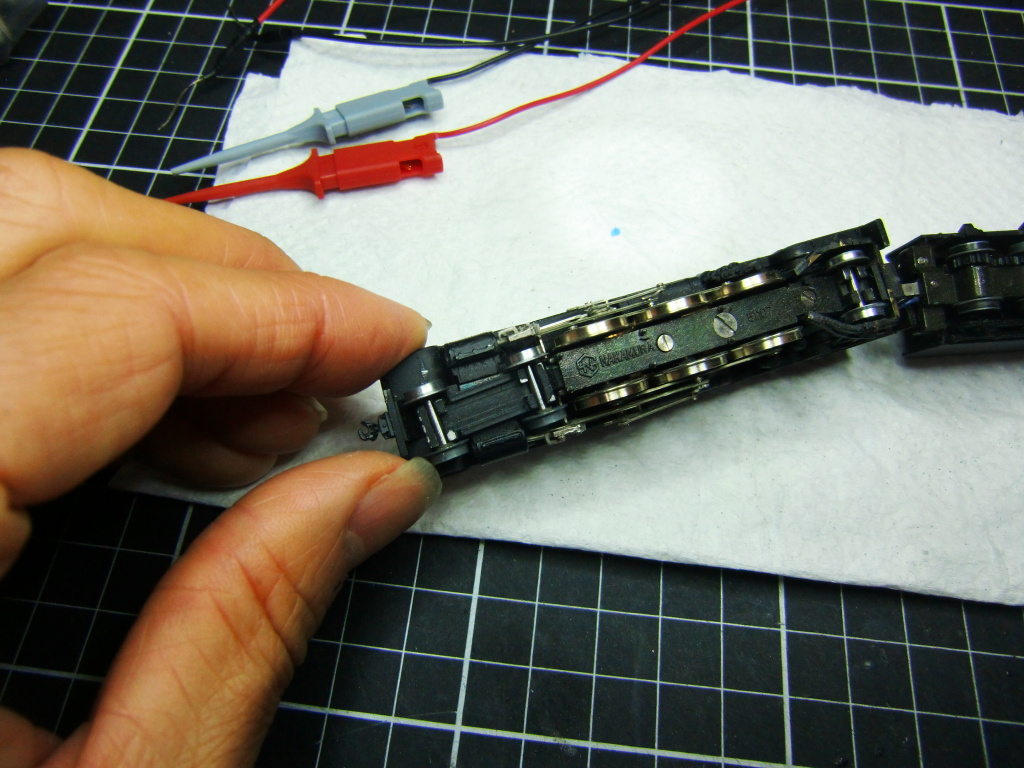
車輪を磨き出しました。違いがわかるように先台車の下(磨く前)、上(磨いた後)です。単純な汚れではないので拭いただけでは落ちませんので、磨き出しで行っております。
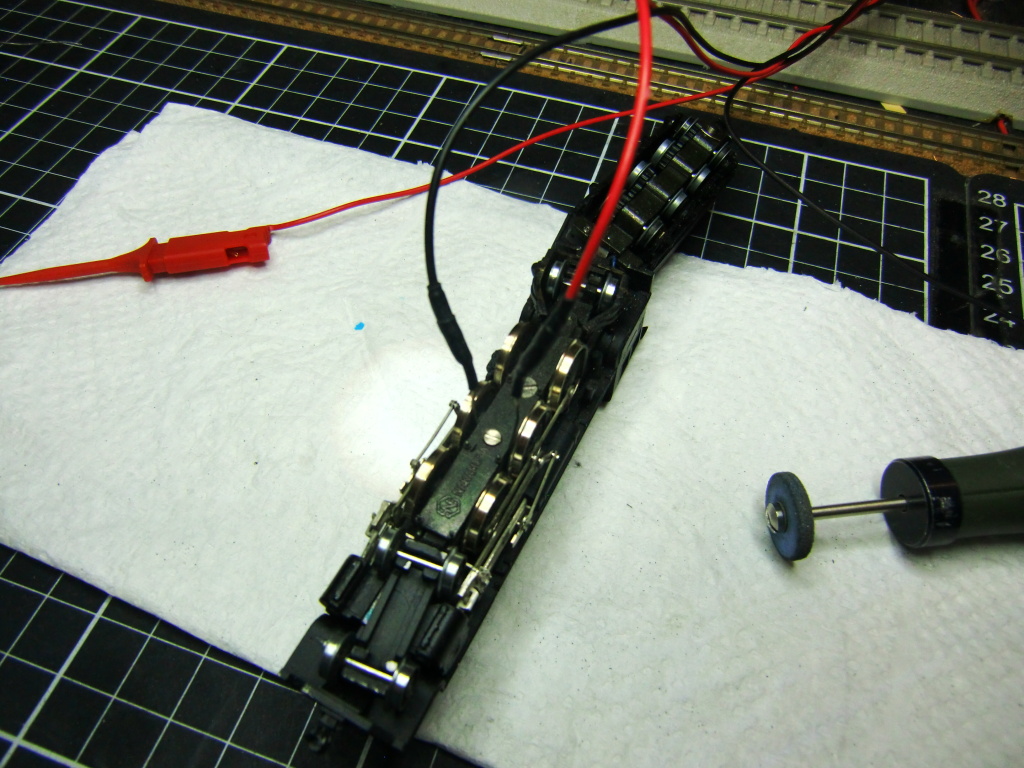
すべての車輪をピカピカに磨き出しました。
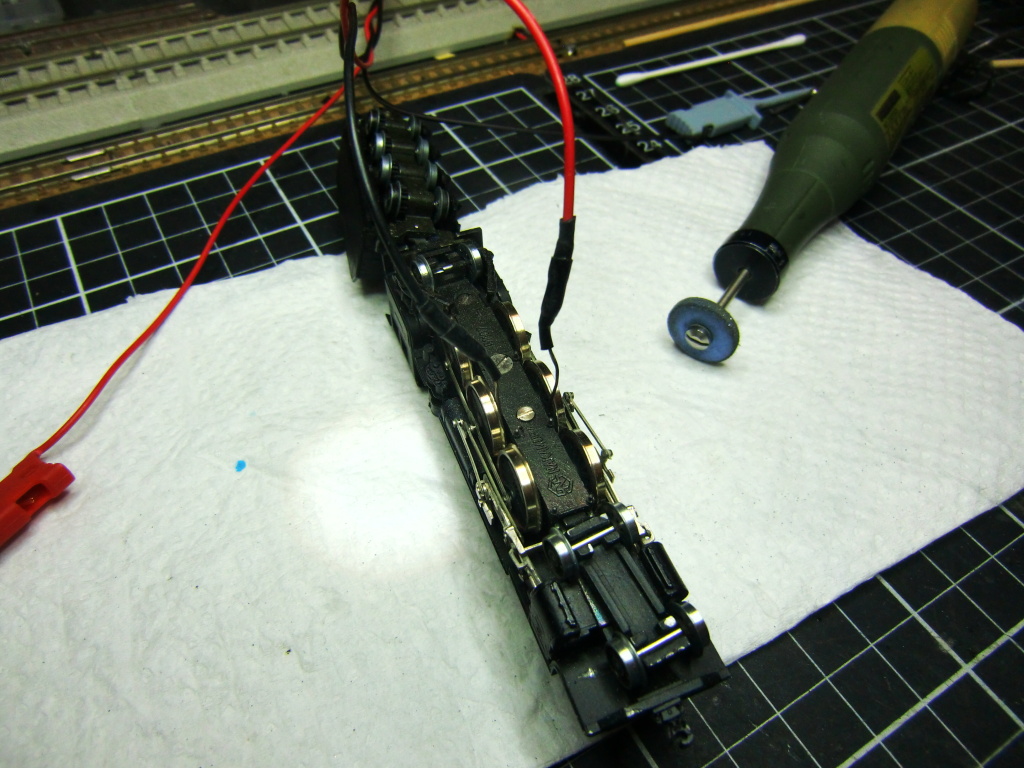
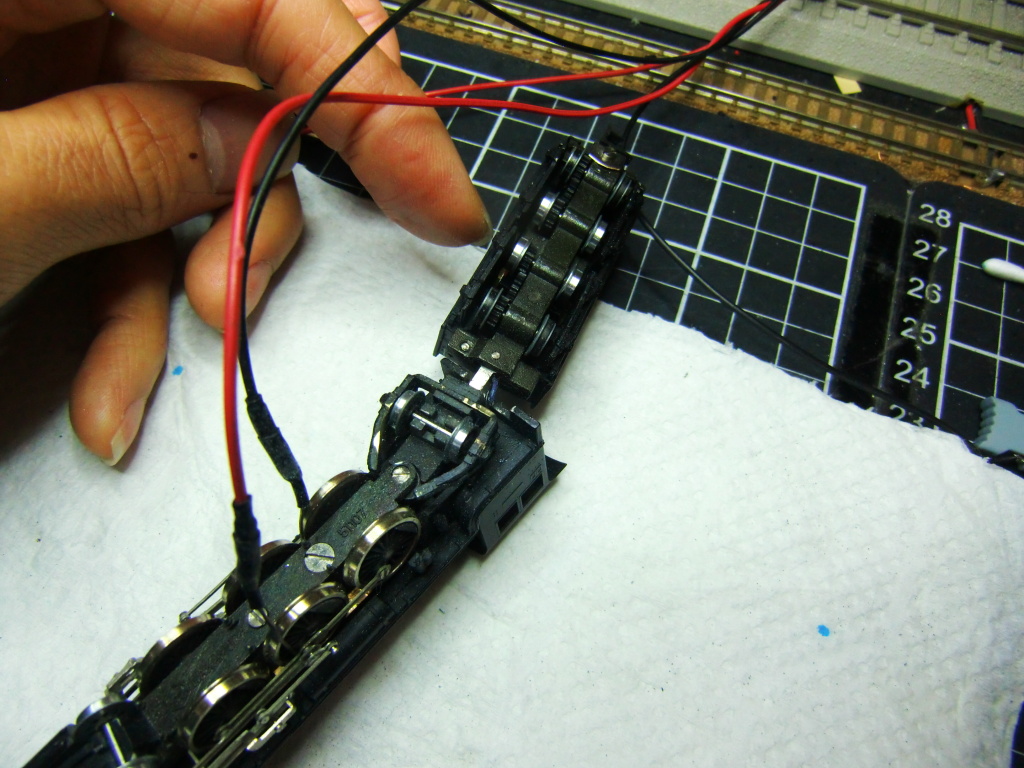

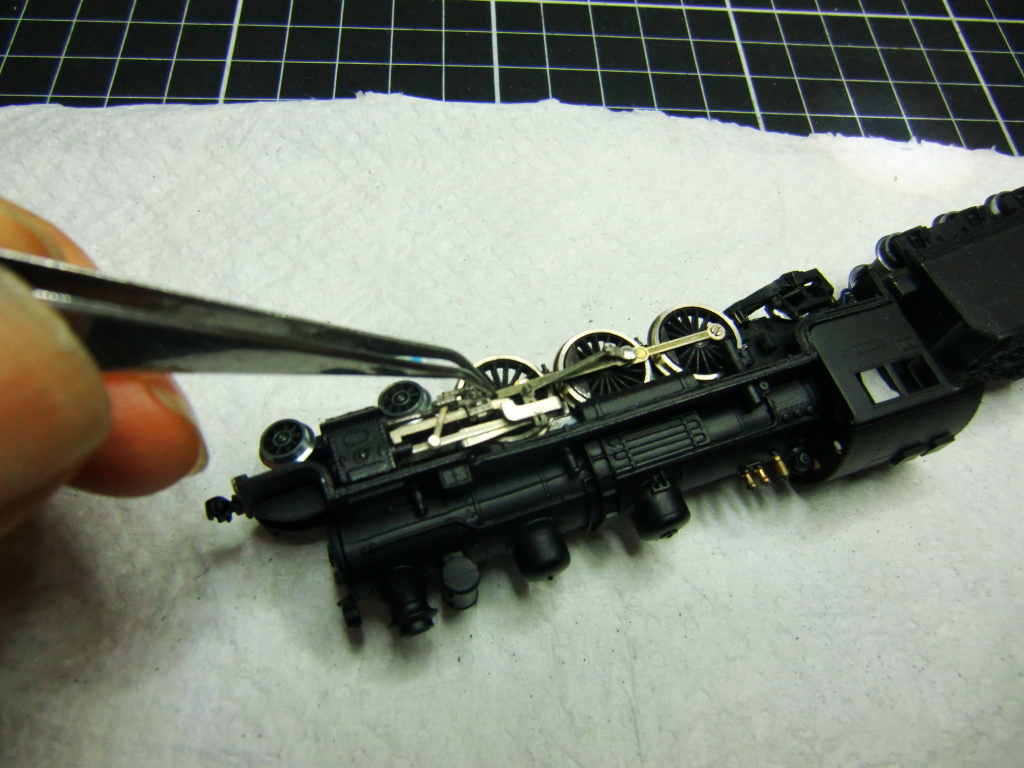
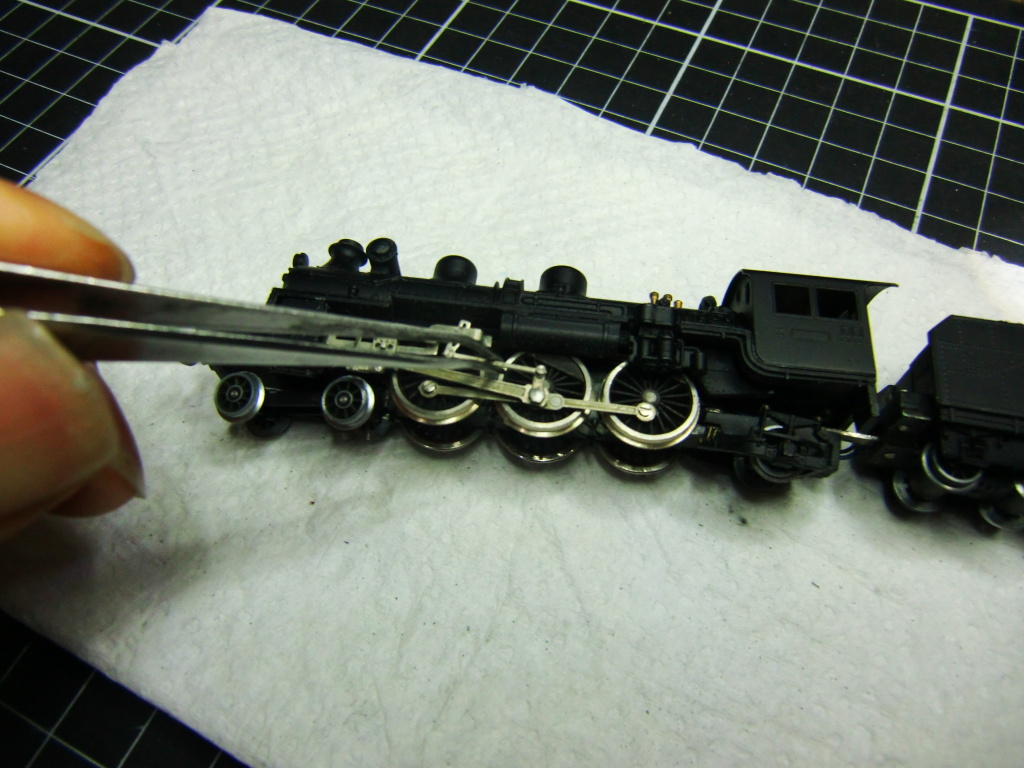
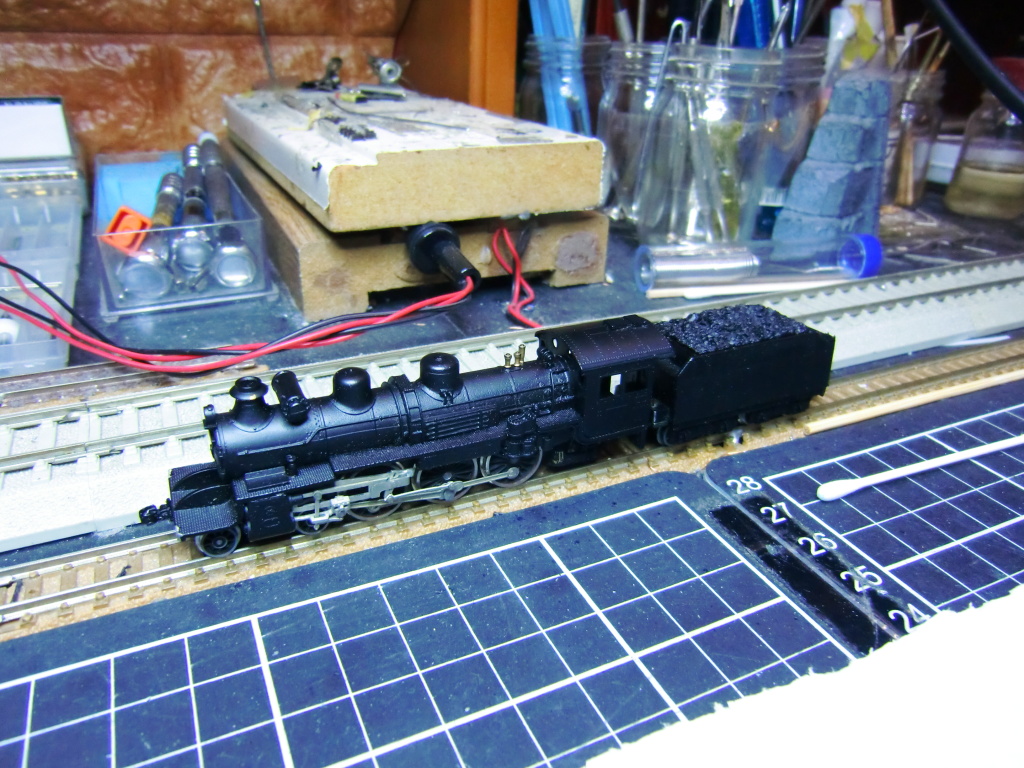
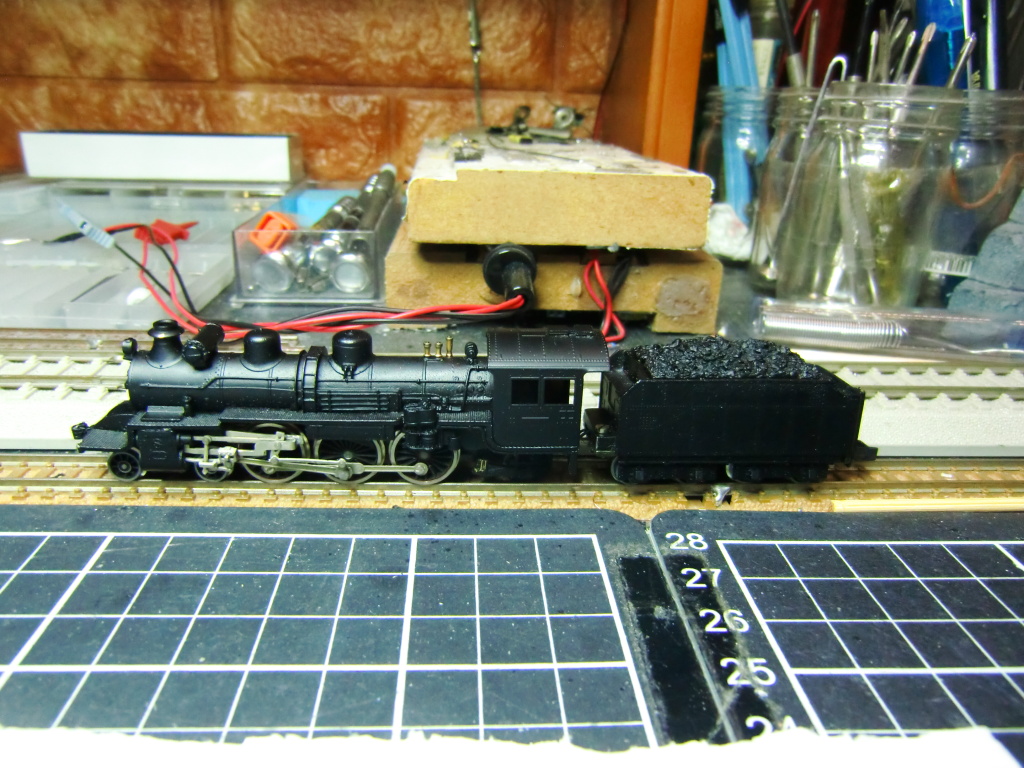
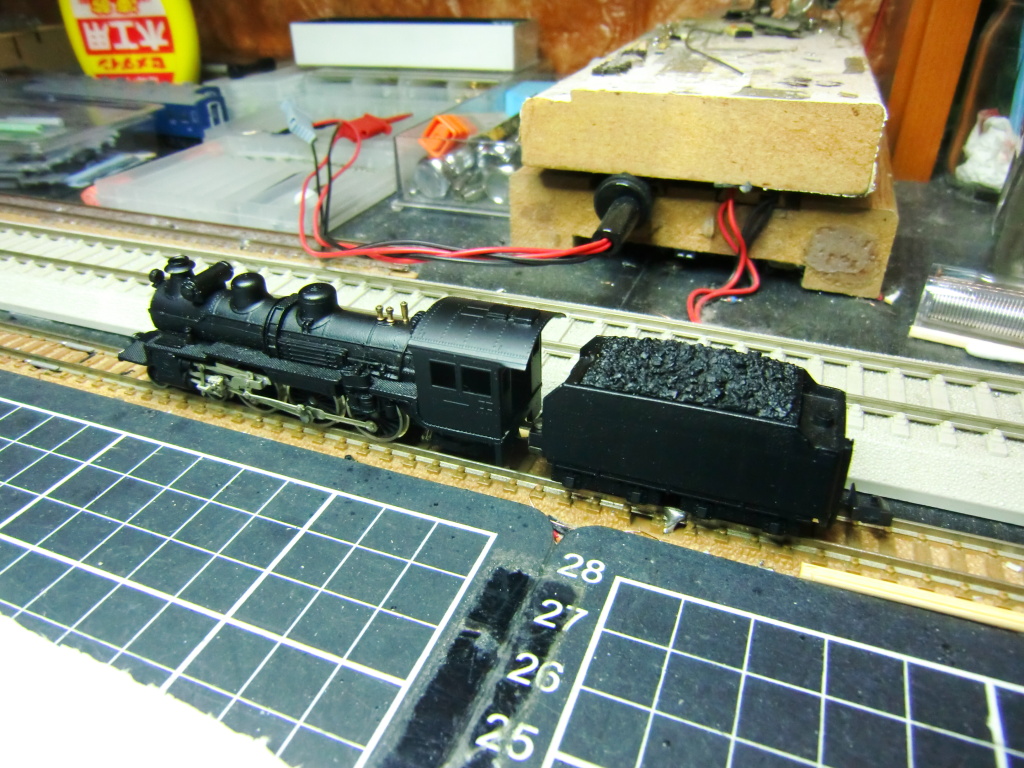
▼マイクロ 国鉄C11-91-61系客車テール点灯不具合




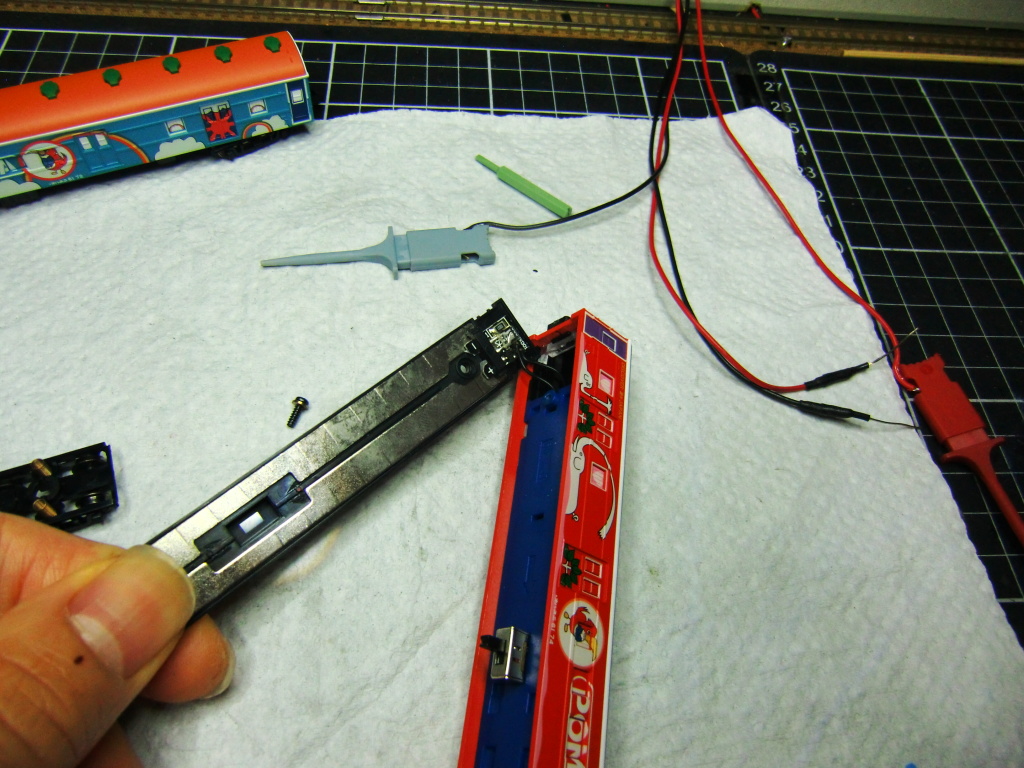
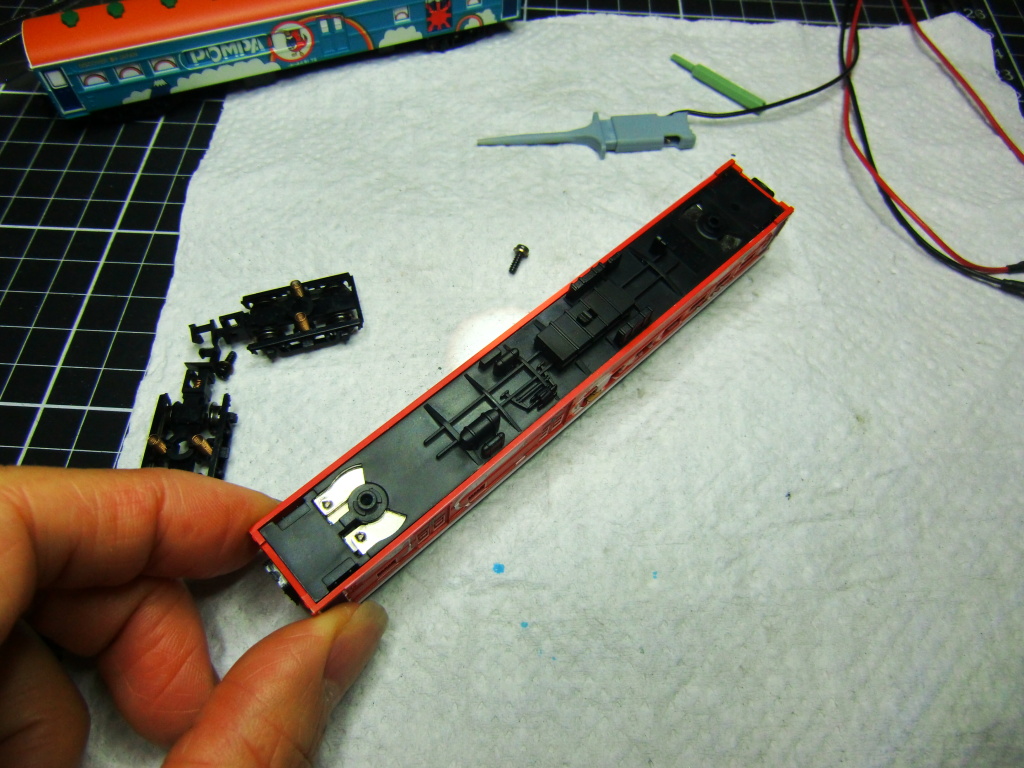
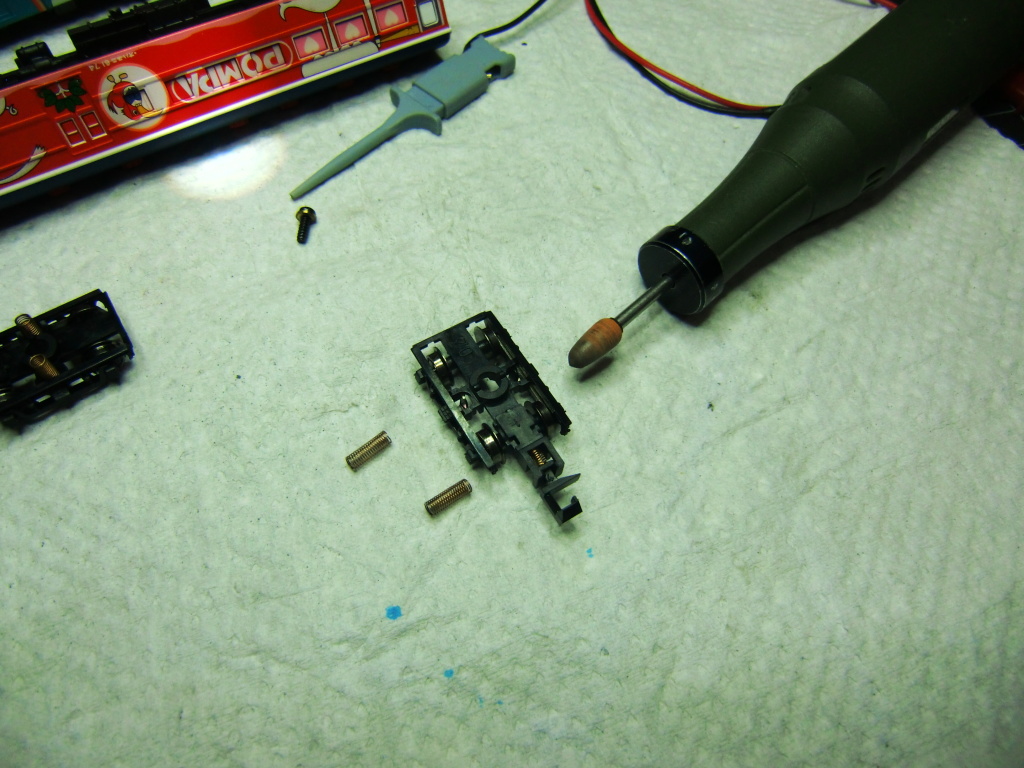



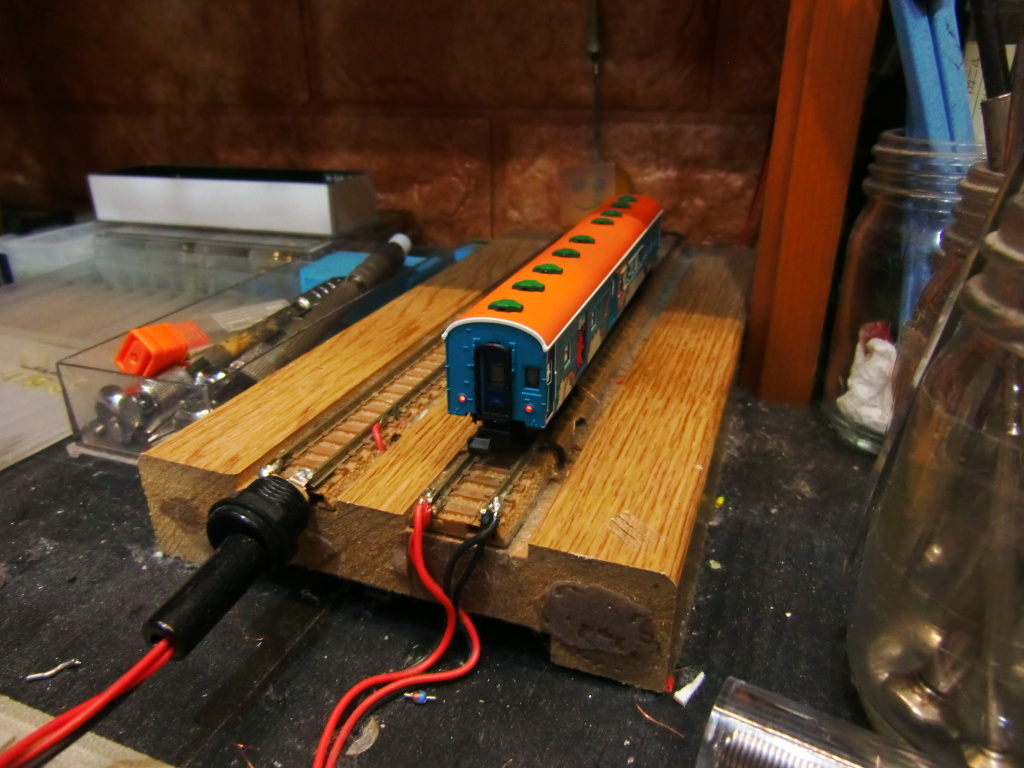
すべての作業が完了いたしました。
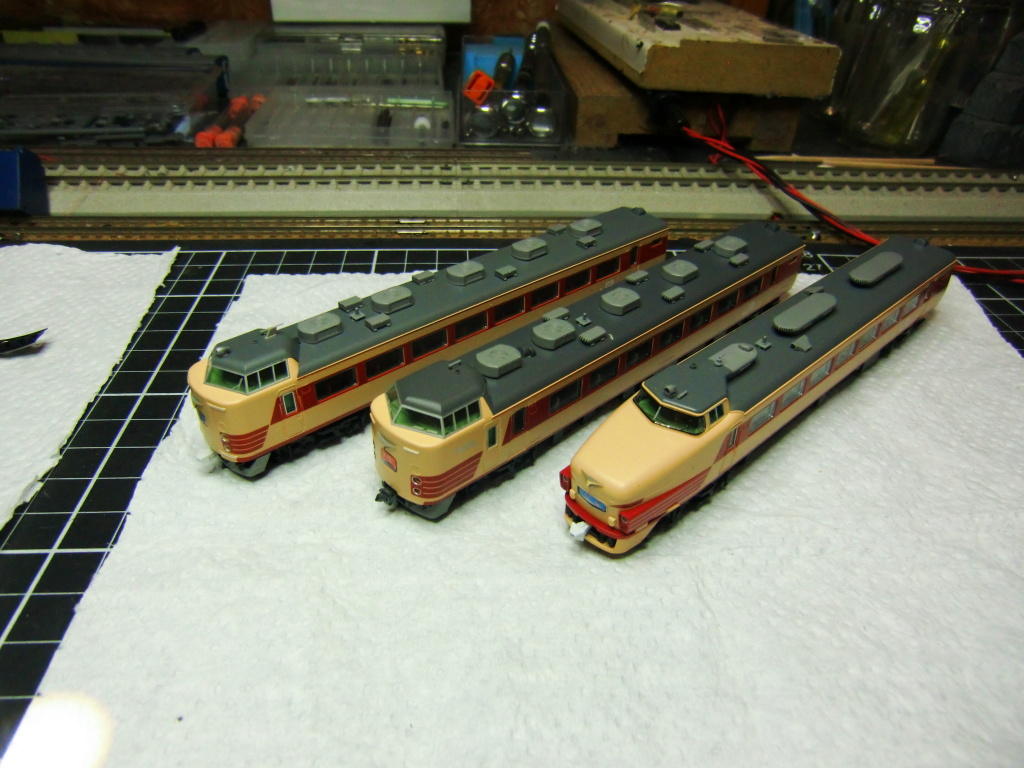
続いて「後進時に運転室が点灯するようにしたい」とのご依頼でございます。

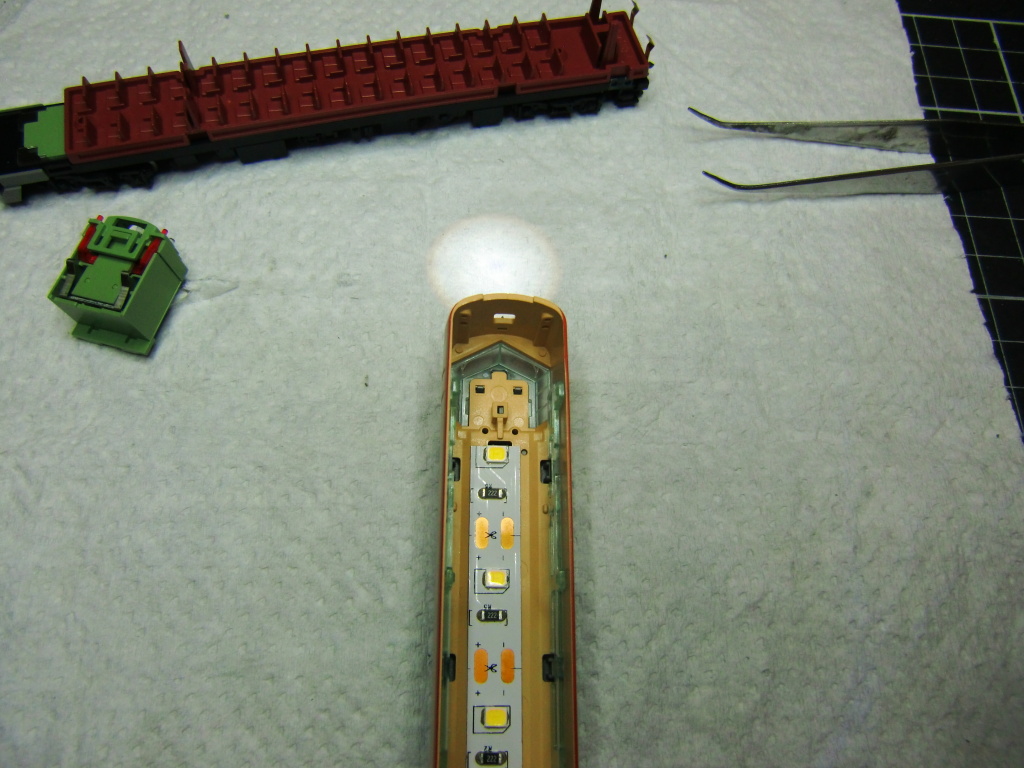
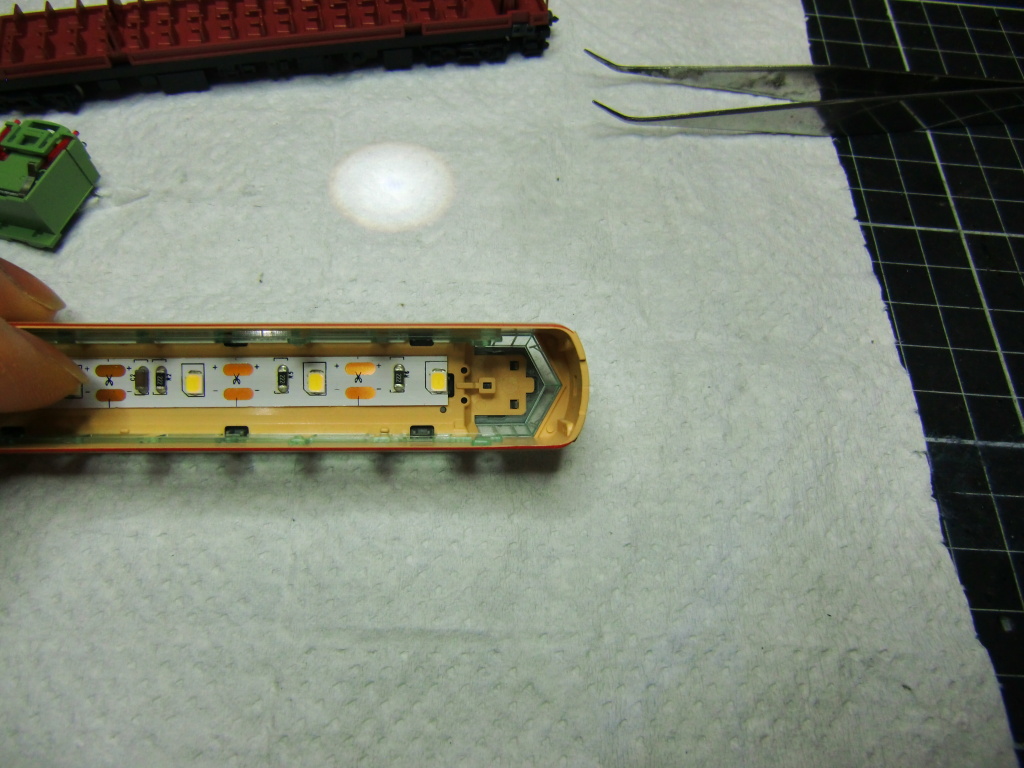

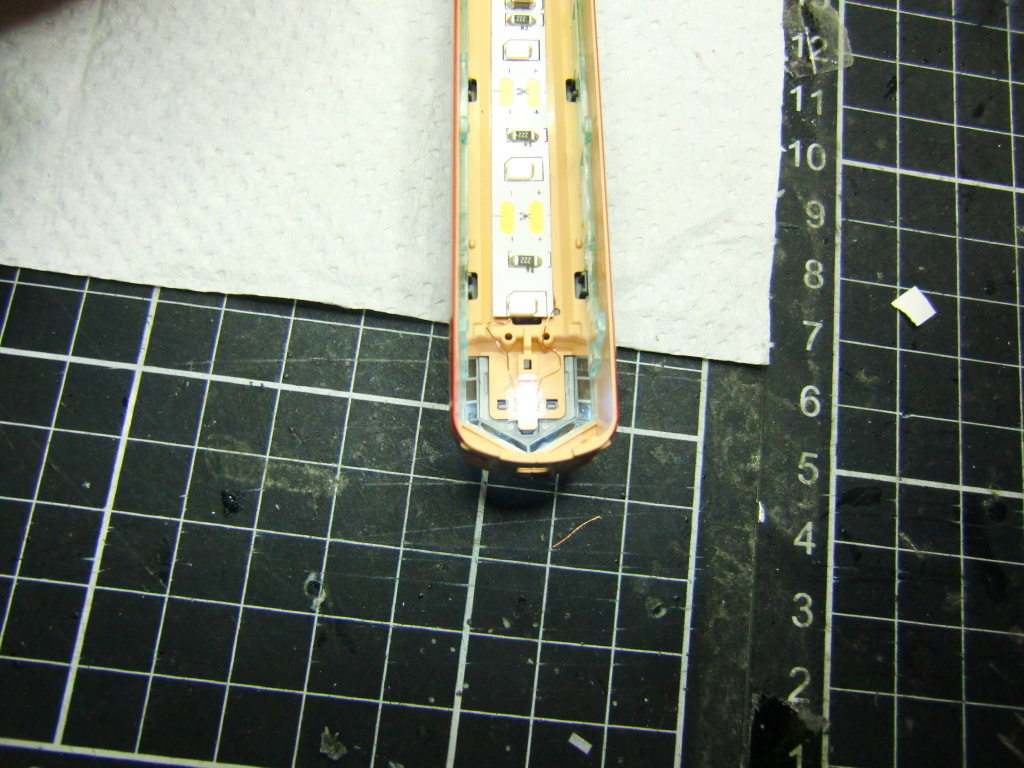


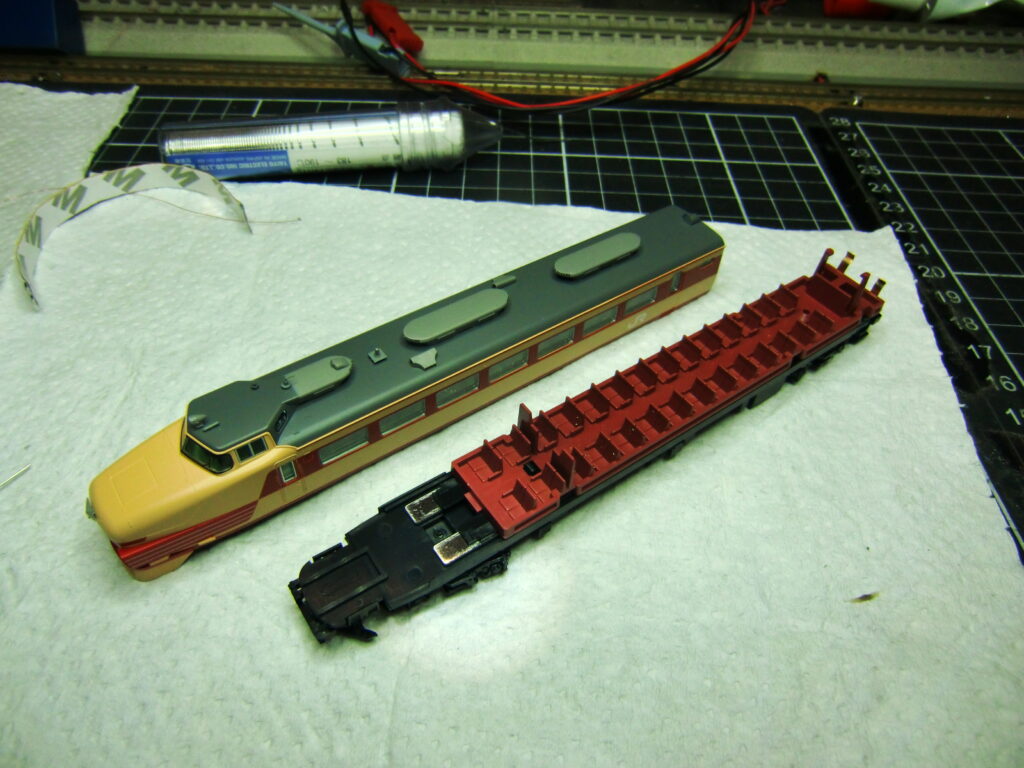
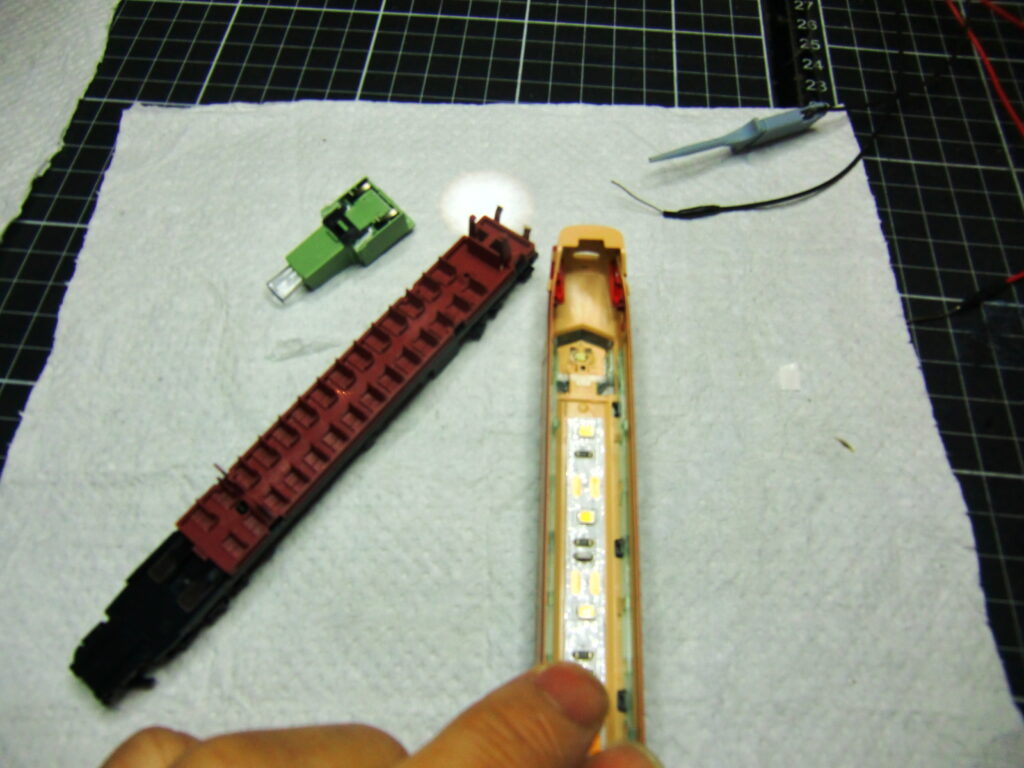





作業完了でございます。


今回は、こちらの車体「KATO マニ50 2187 」をベースにしたロイマニの制作でございます。以前制作いたしました「ロイマニ」にいくつかの改修を加えたものを2台制作していきます。
ヘッドライト白色LED輝度アップ
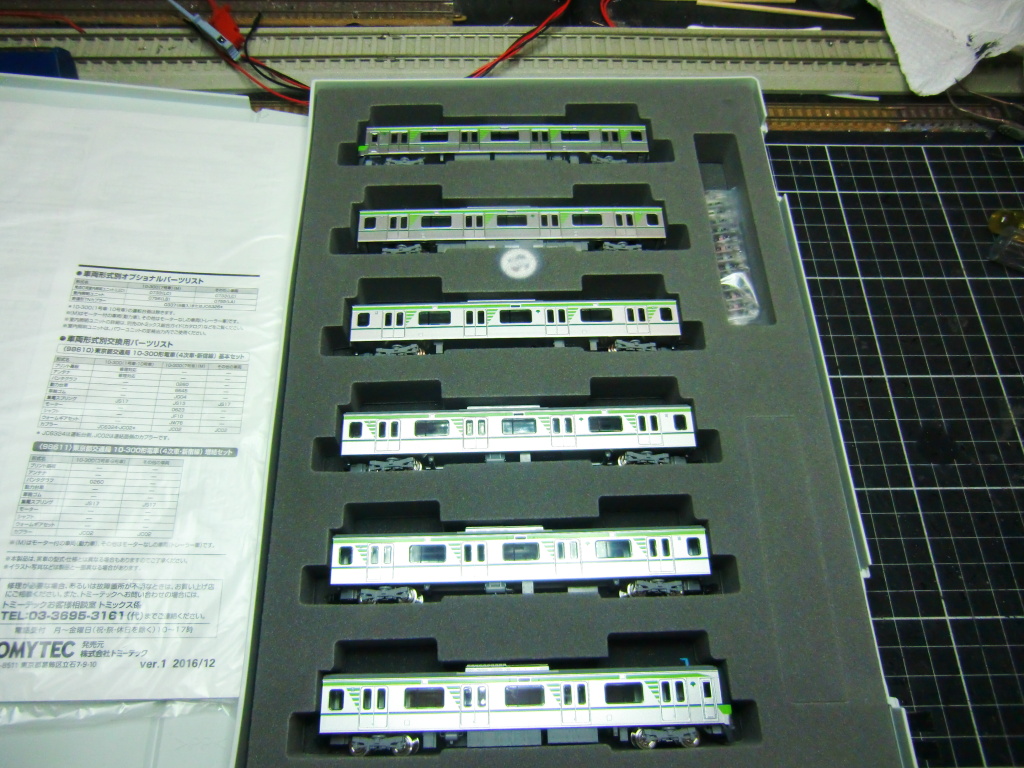



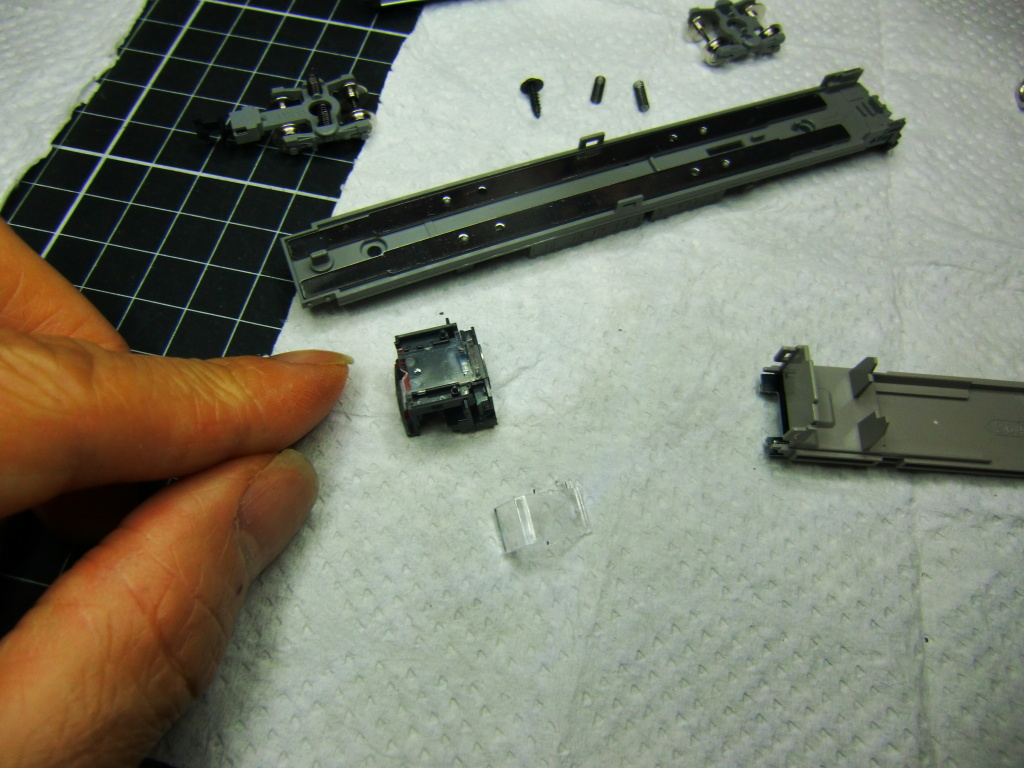
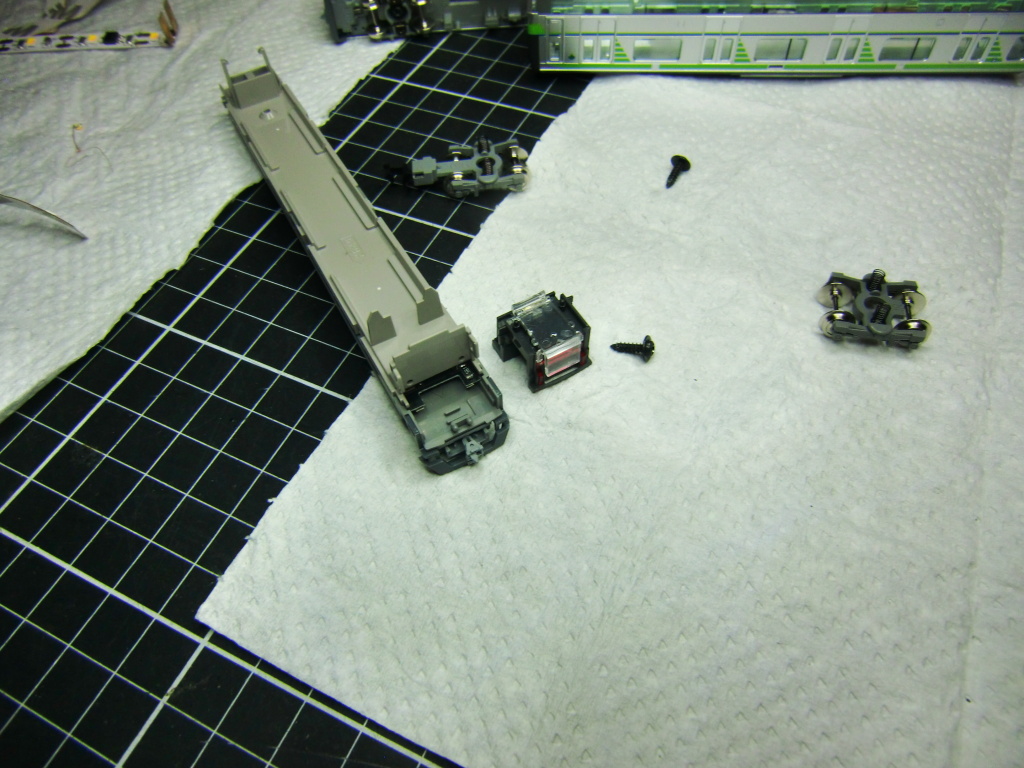
ヘッドライト用導光材の真後ろにチップ型白色LEDをダイレクトに置きます。
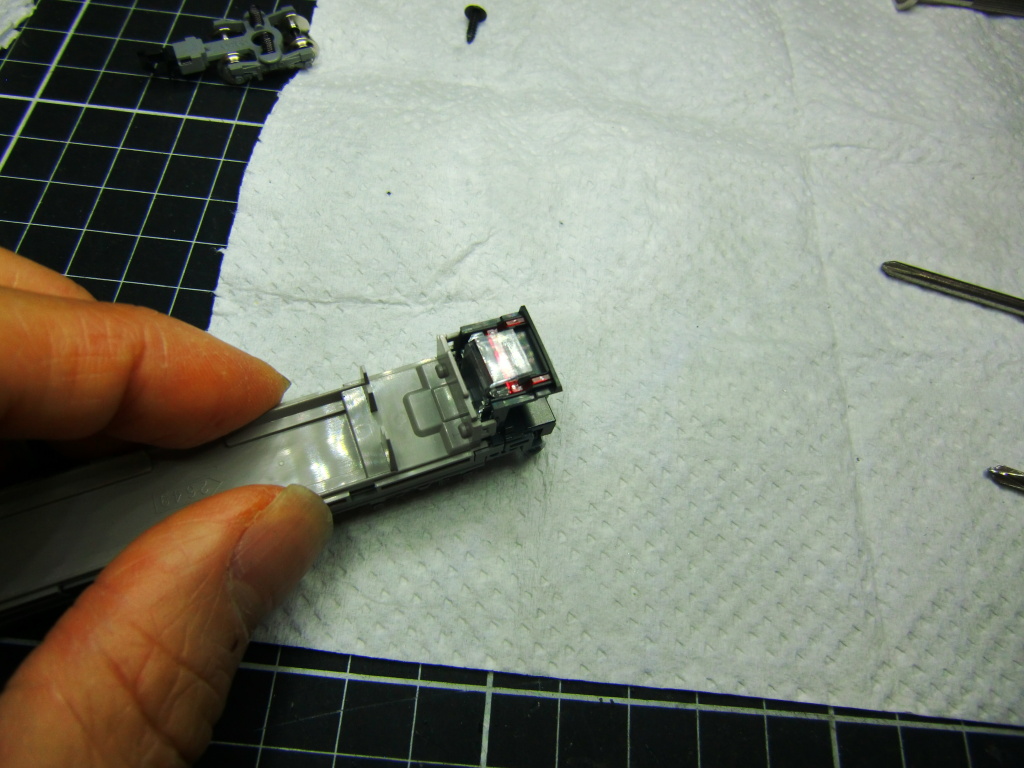




くっきり明るい白色ヘッドライト点灯になりました。
▼E231系TNカプラー化


まずは、もともと付いていたカプラーを取り外します。次に床板に一体化された突起部分をニッパーで根元からカットしたのち、ルーターで平らになりまで削ります。平らな面ができたら、TNカプラーをスペース内に収まるまで加工して現物合わせを行います。干渉する箇所があれば、加工して収まるようにします。

加工途中の過程は撮影し忘れておりましたので、今回は省略いたします。

このように取付けが出来ました。カプラーの前方への張り出し具合を確認して調整を行って完成となります。


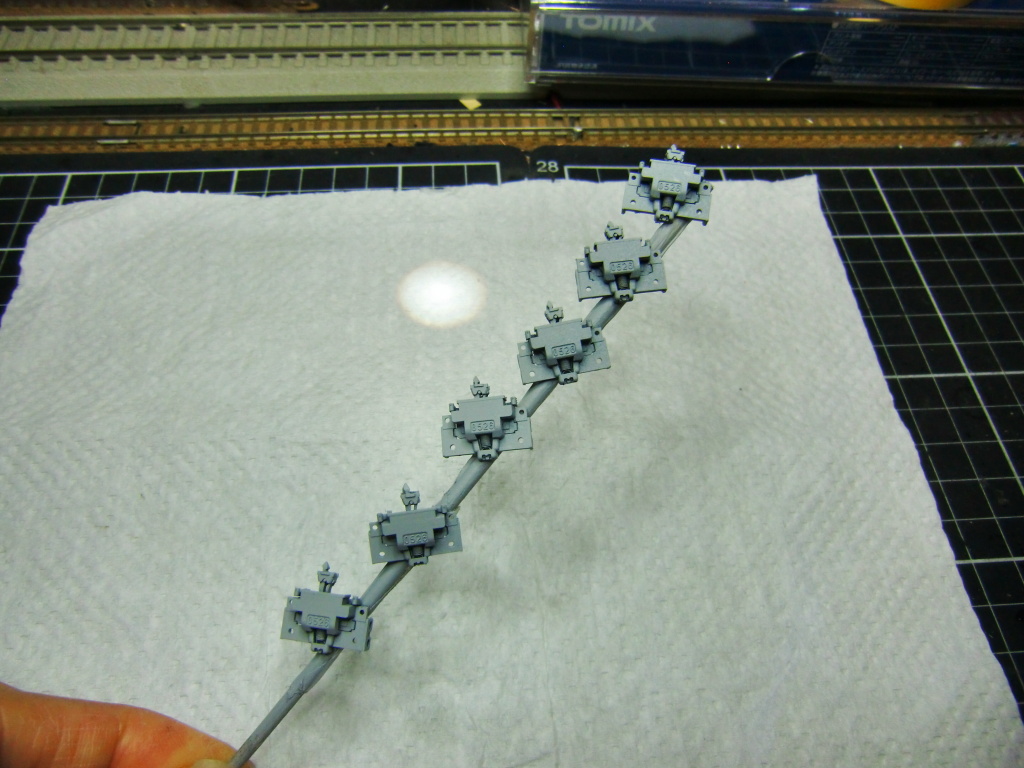
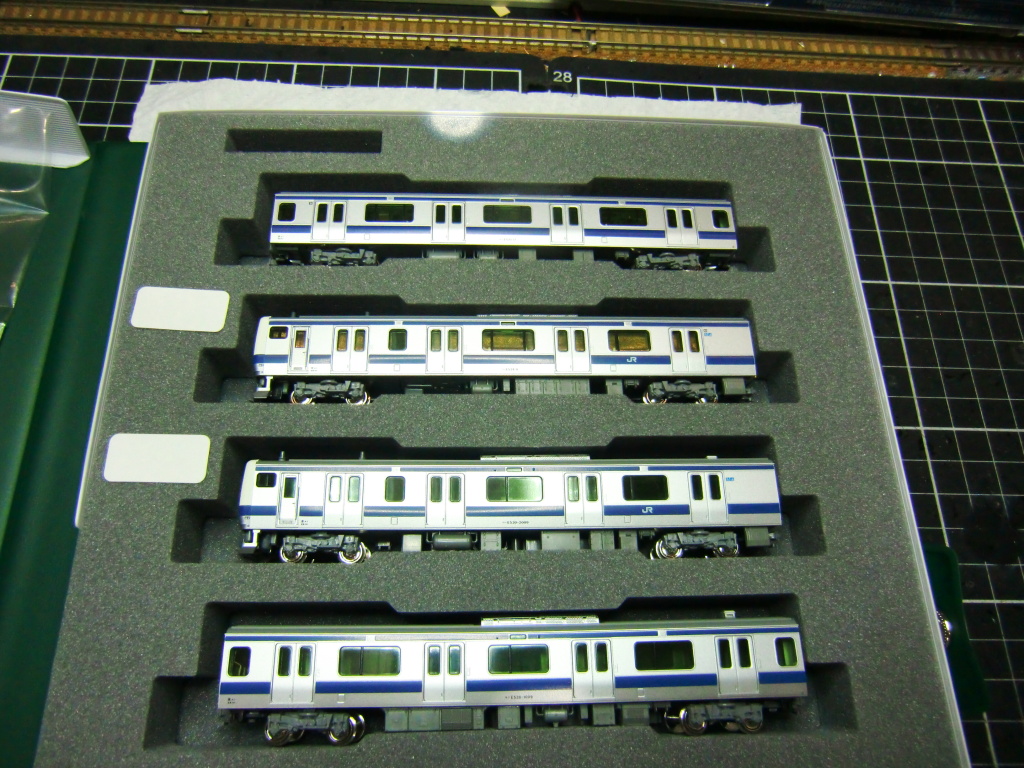
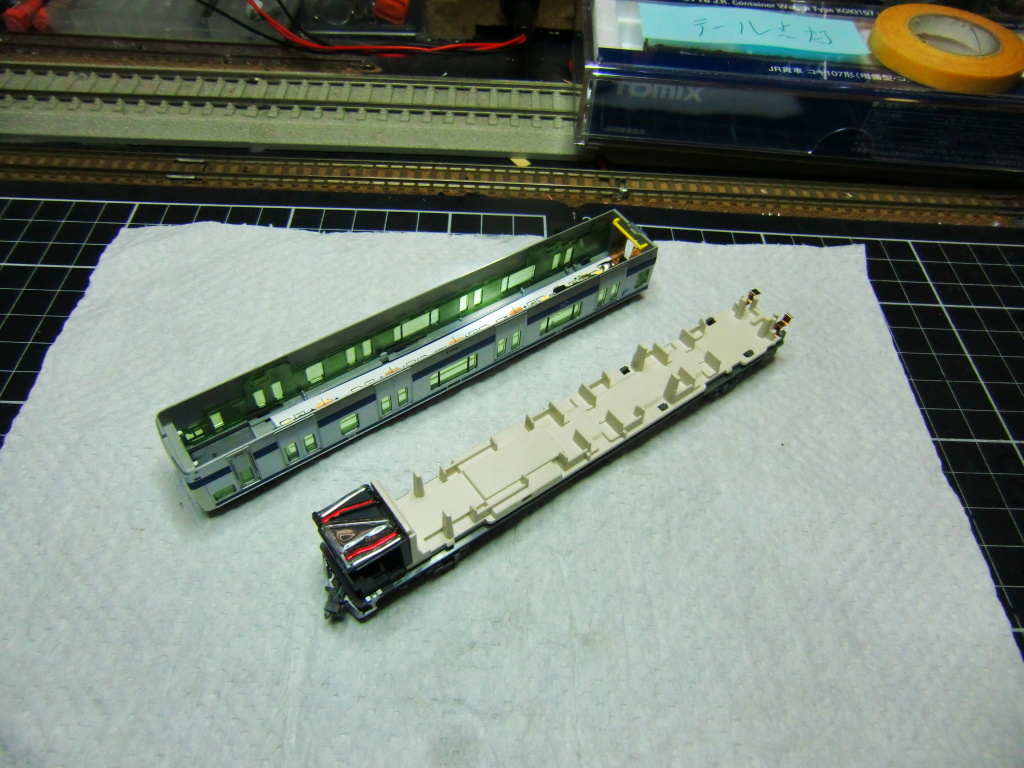

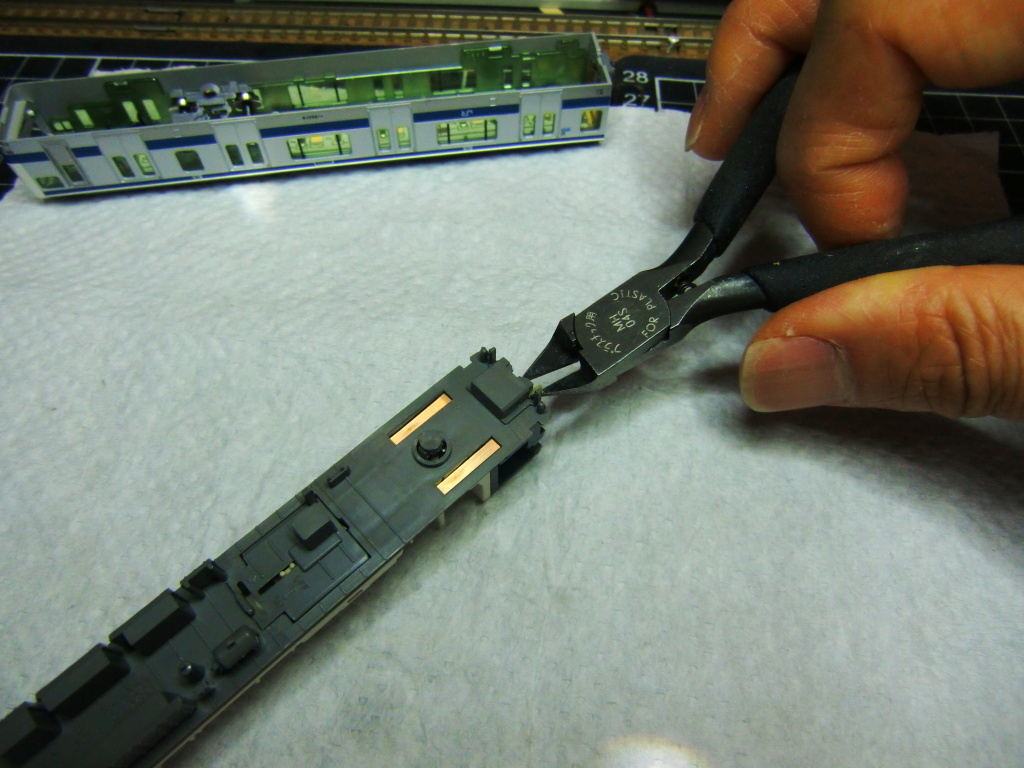

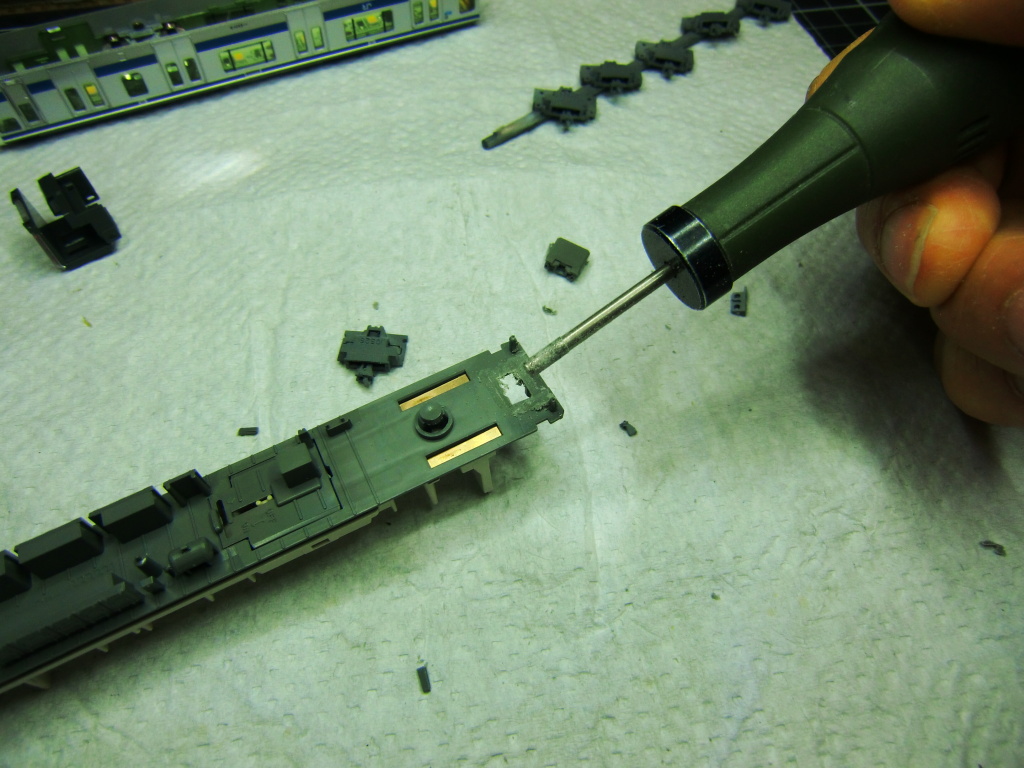
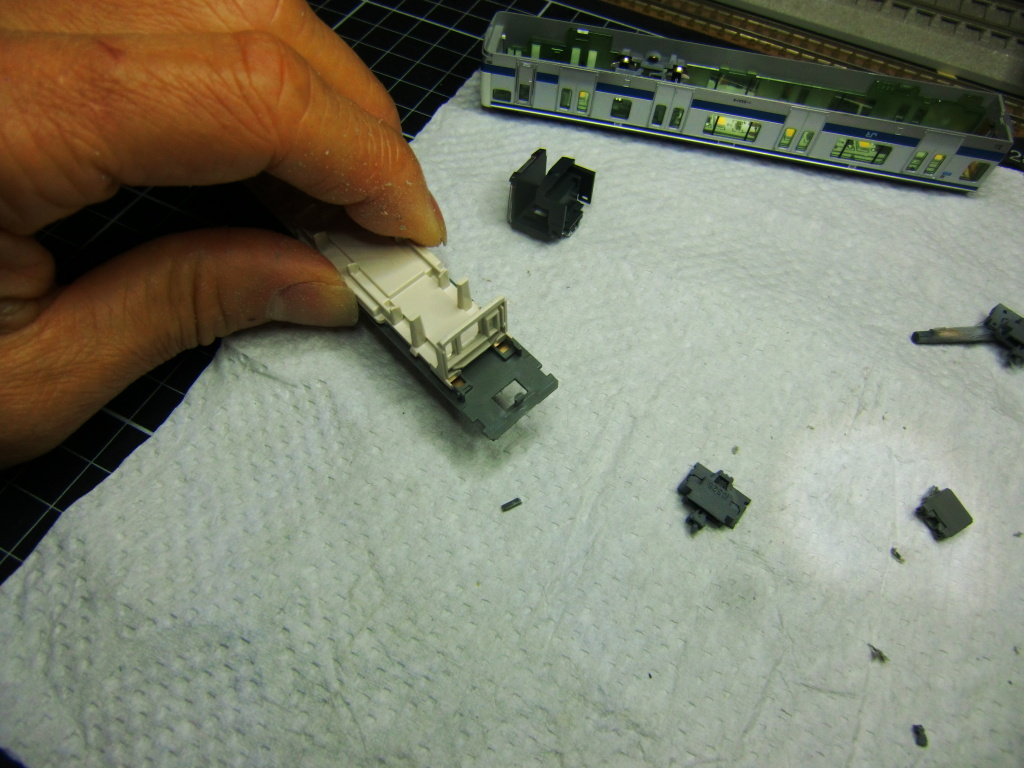
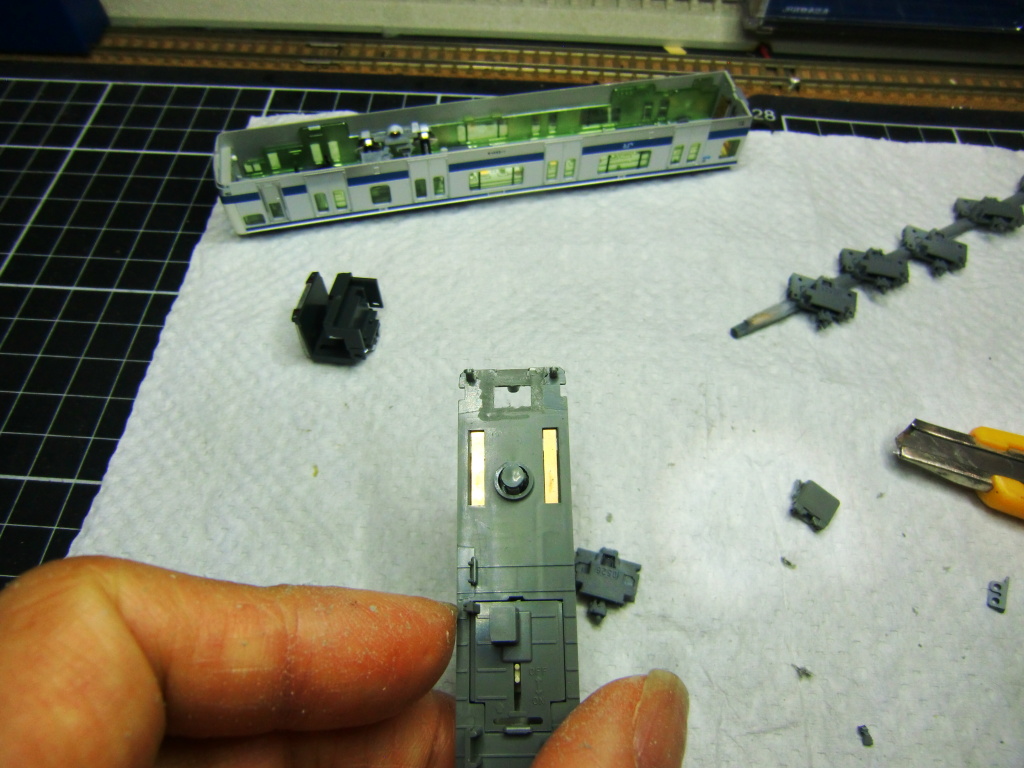

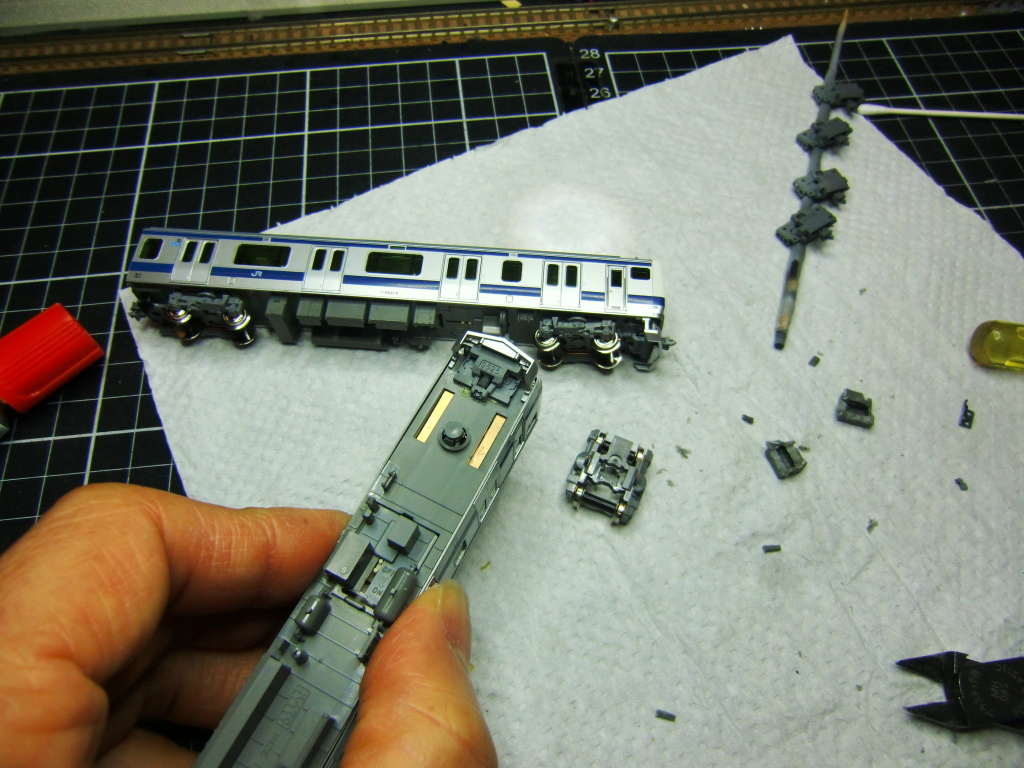



こちらの車両も上記と同様の作業工程。


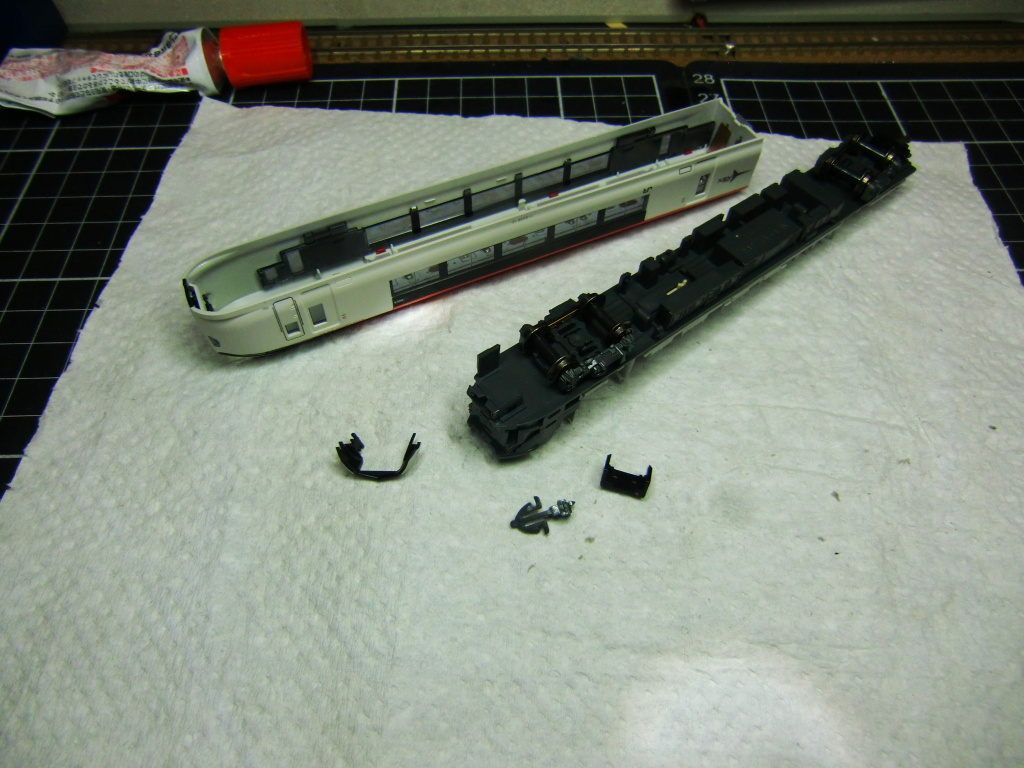
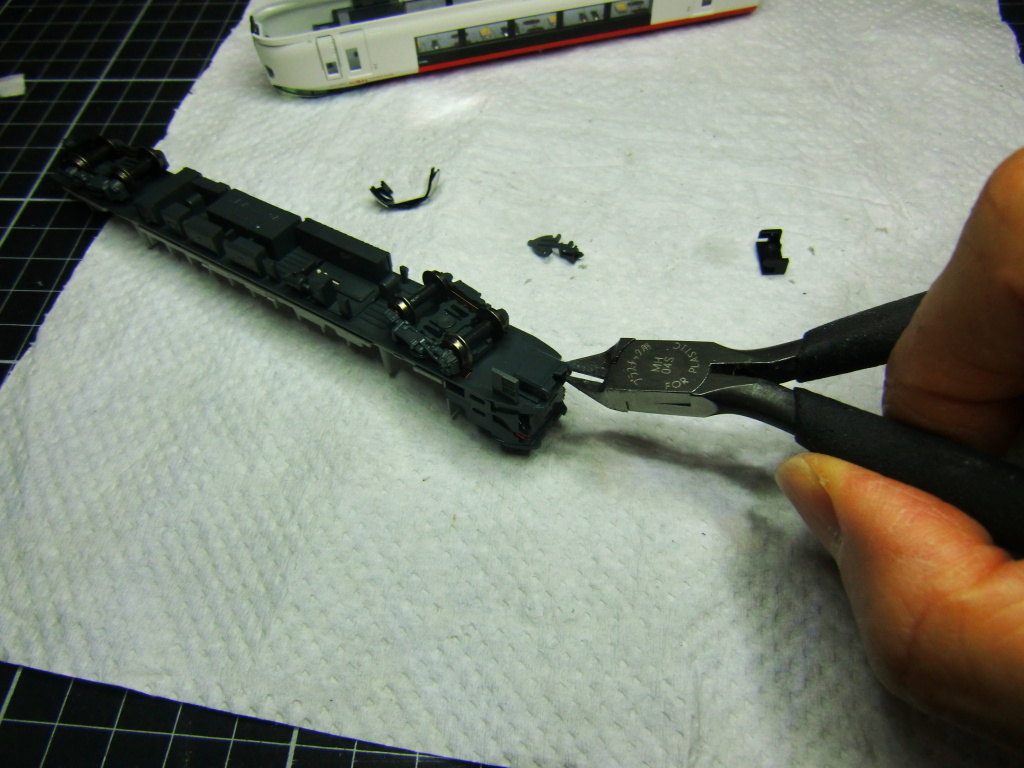



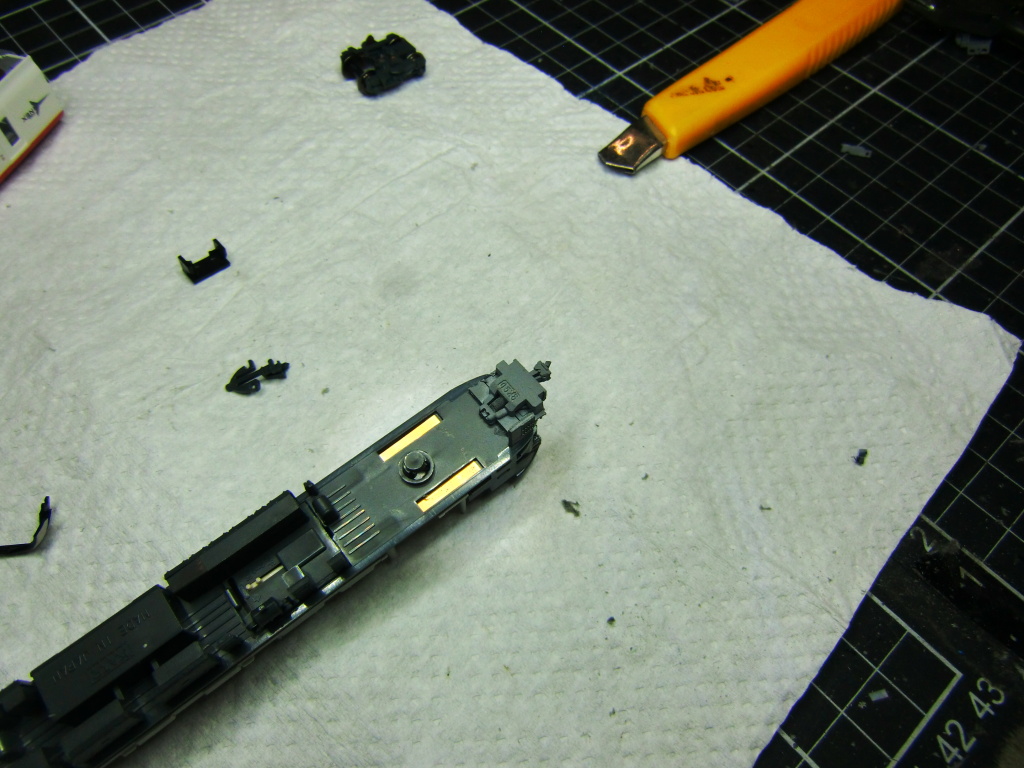

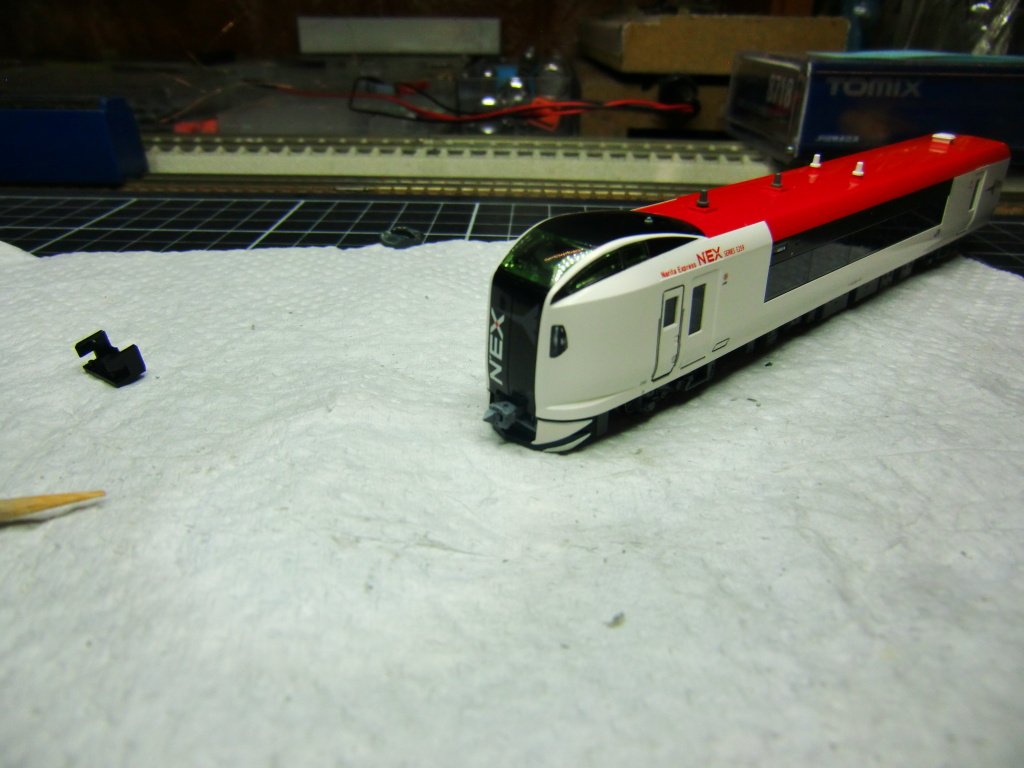
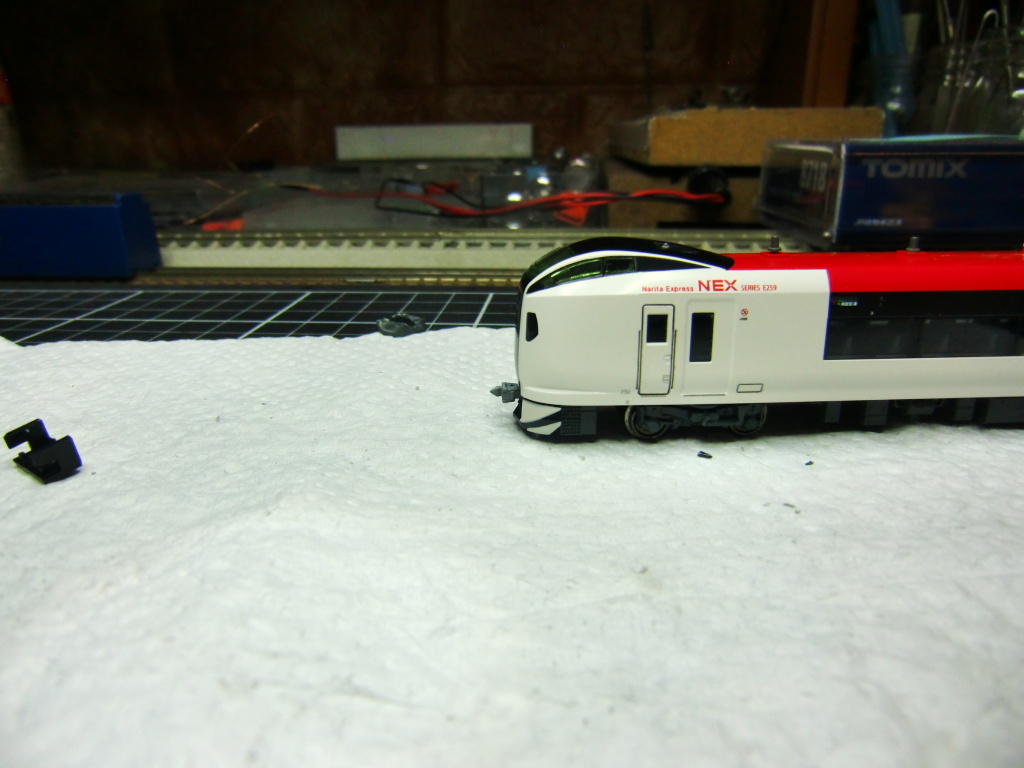


すべてのカプラー加工が完了しました。
今回のご依頼は、こちらのレールバスの修理でございます。現状は片側の車輪が完全にロックしており。


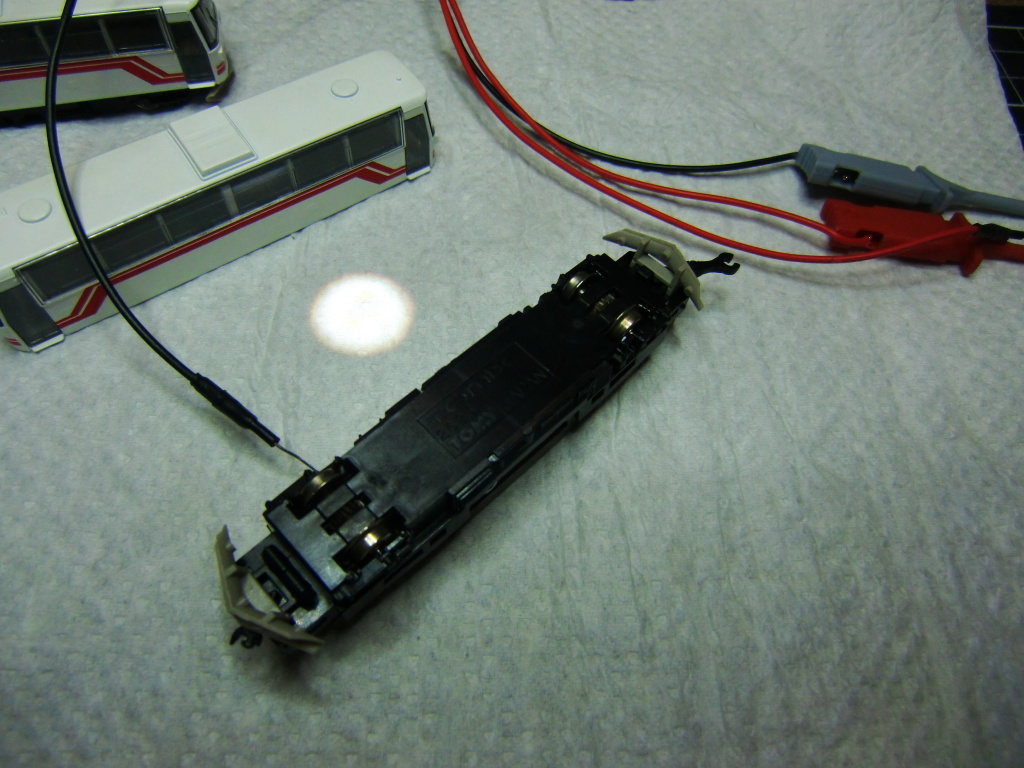
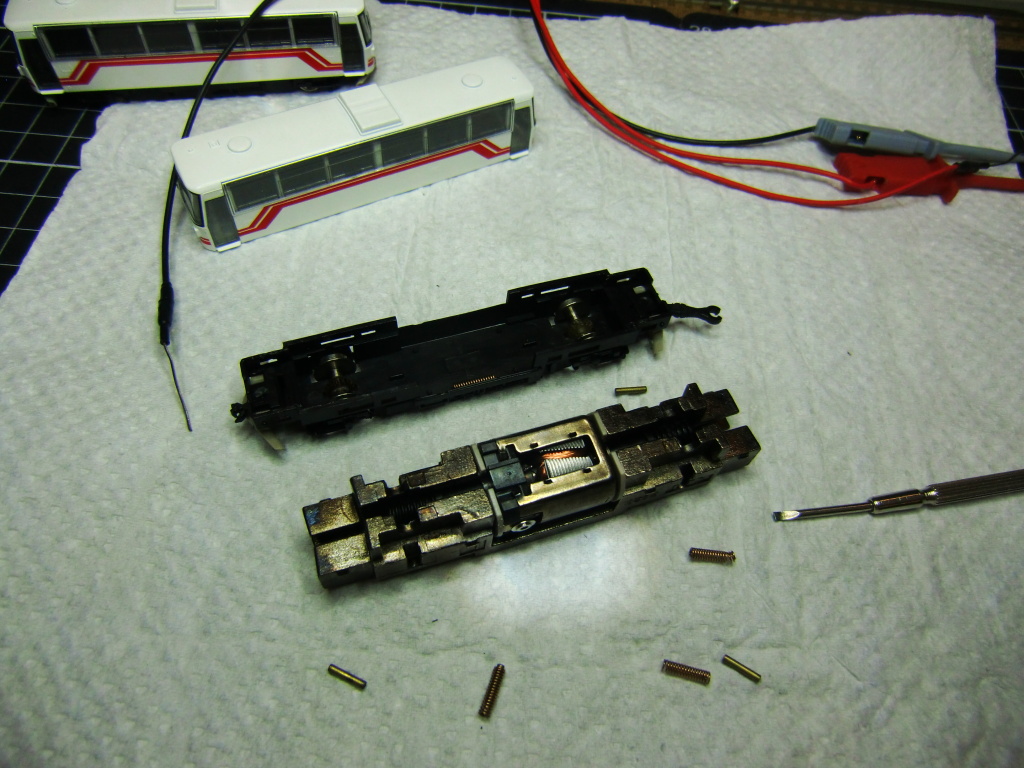
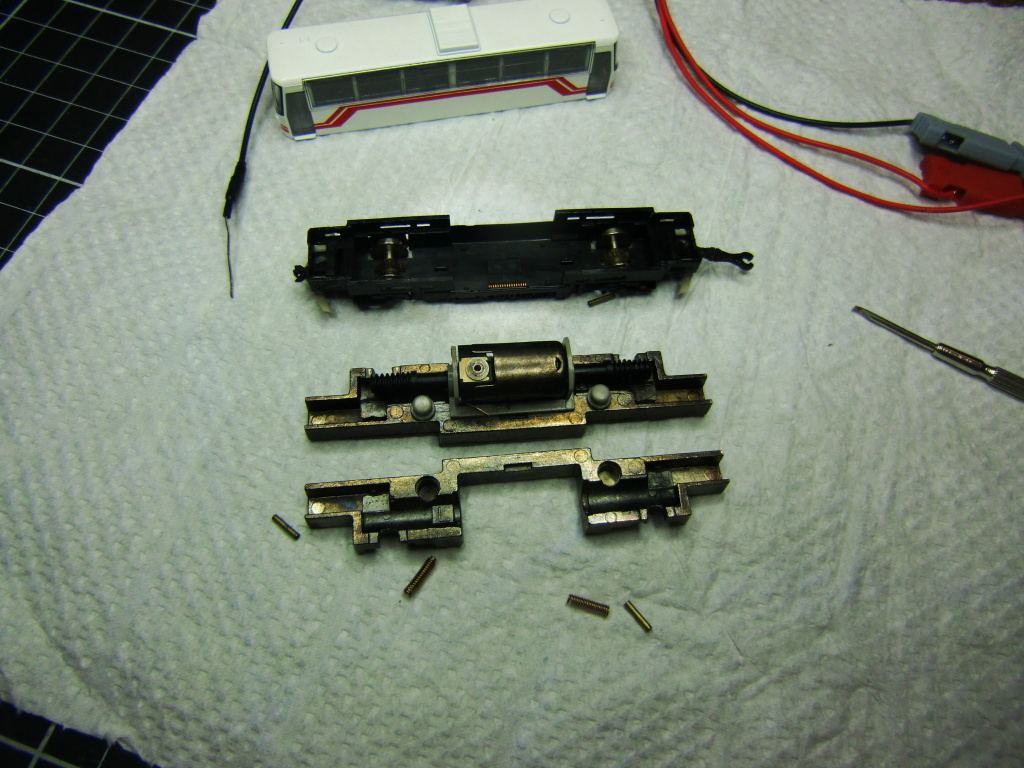

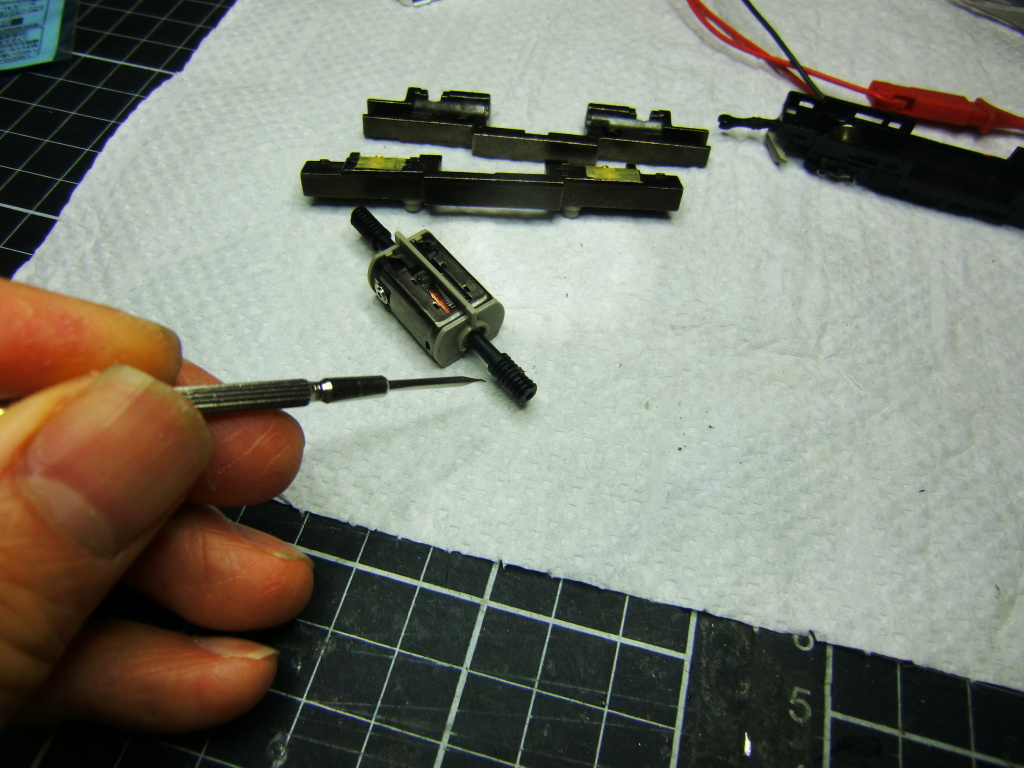
問題となった箇所を特定しましたが、修理の中でも少々難しい箇所です。ギアが損傷しています。
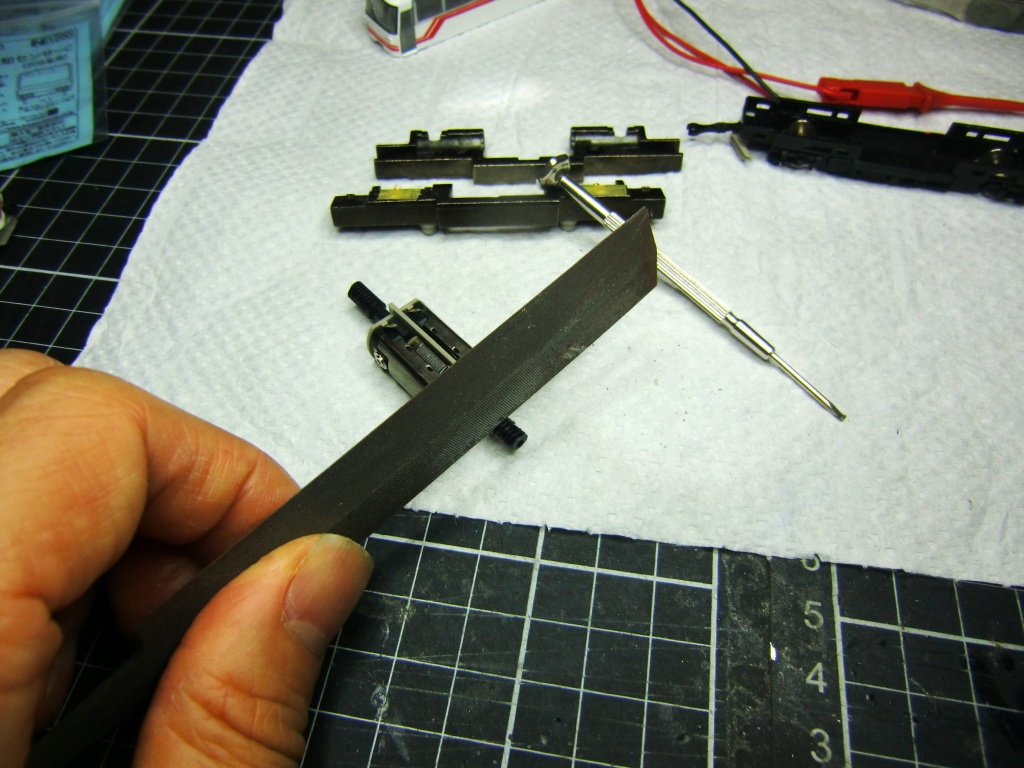
ウォームギアを金やすりを使って削りなおして復元します。「分解>組立て>確認>分解・・・」を5、6回ほど繰り返して、ようやく回るようにまりました。車輪が側にギアも損傷していたため、こちらも削りなおしてピッチを整えました。
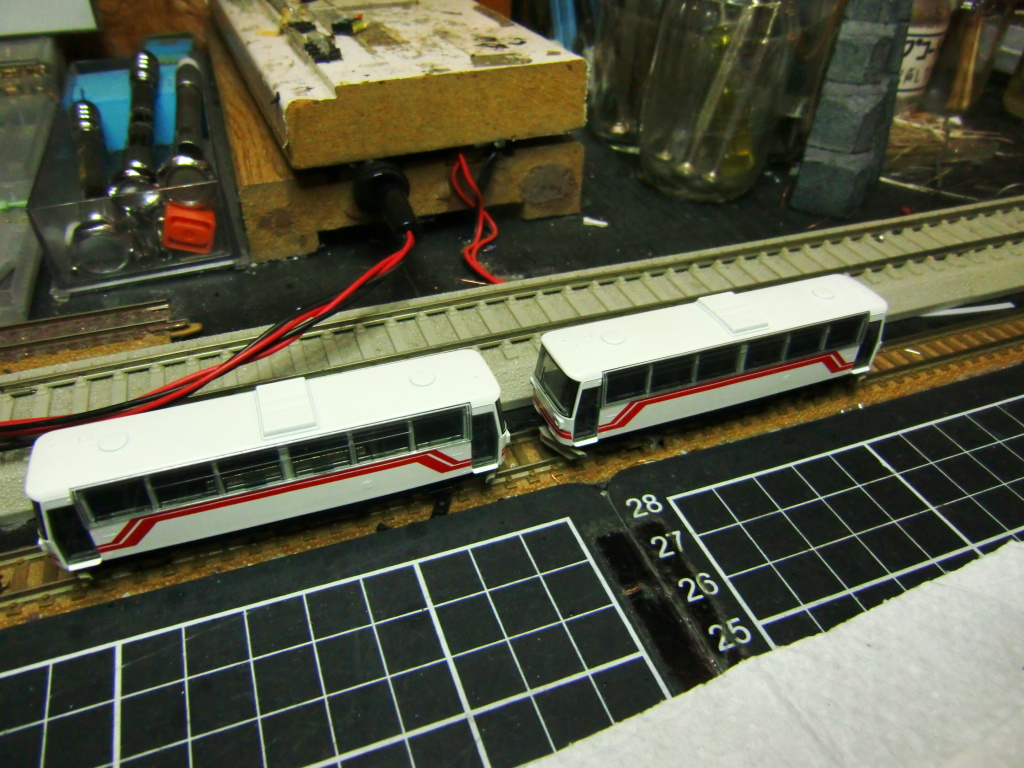
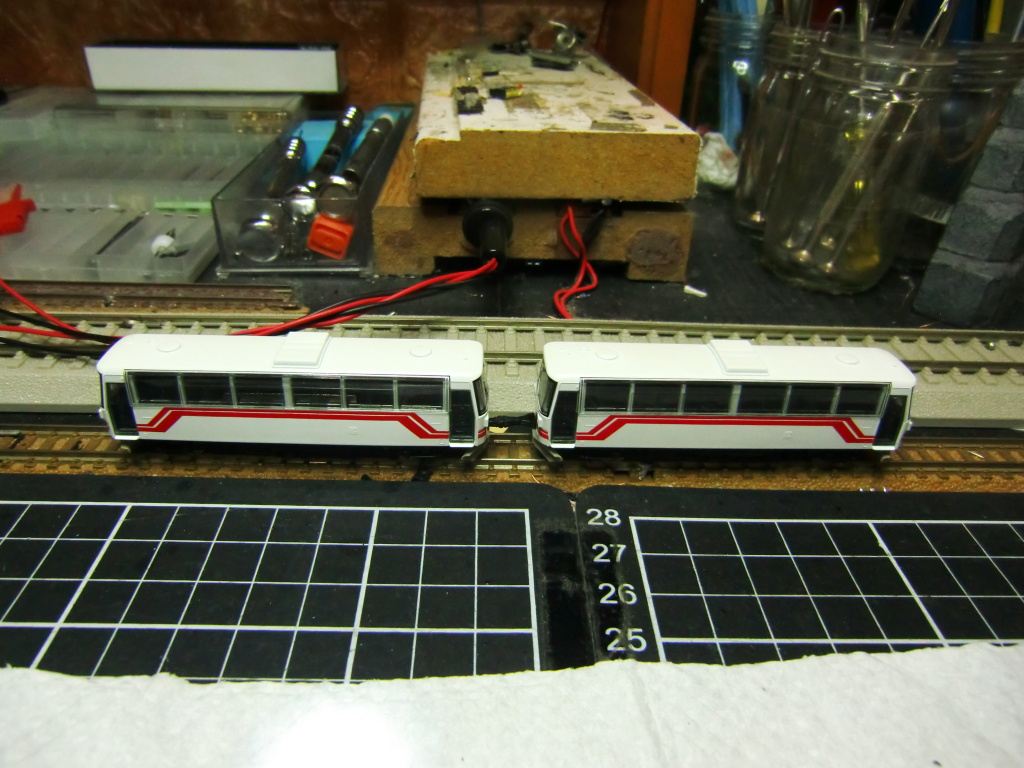
当初、簡単に終わると考えていましたが、思いのほか手間取りましたが、無事にお直し出来て良かったです。


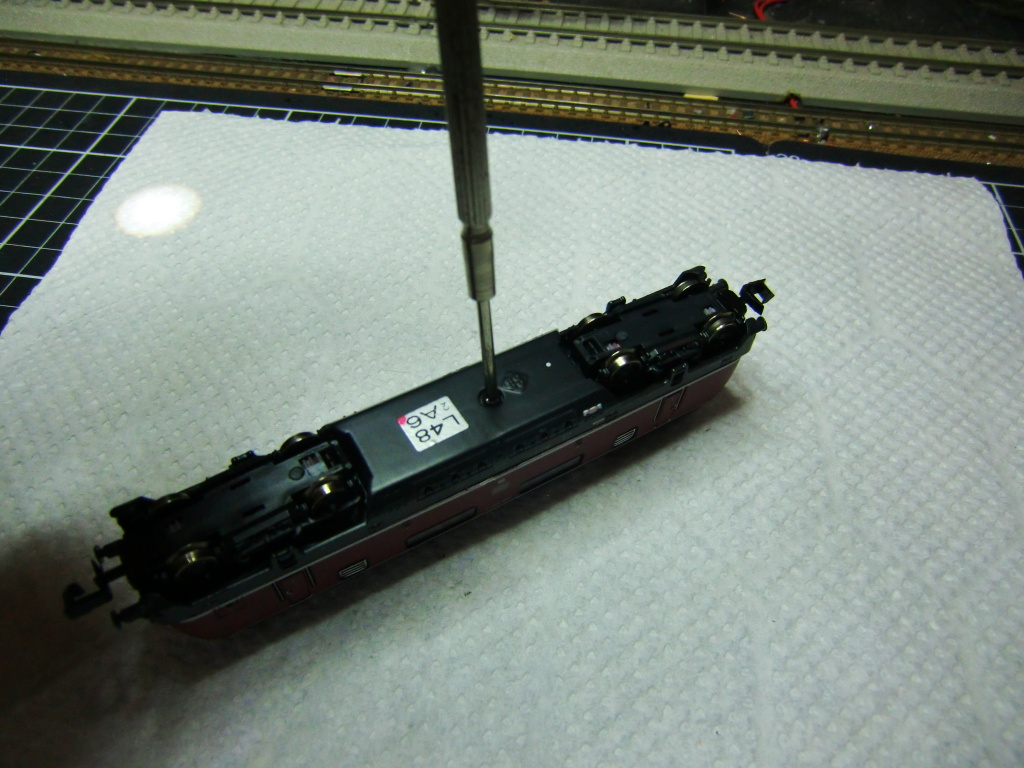
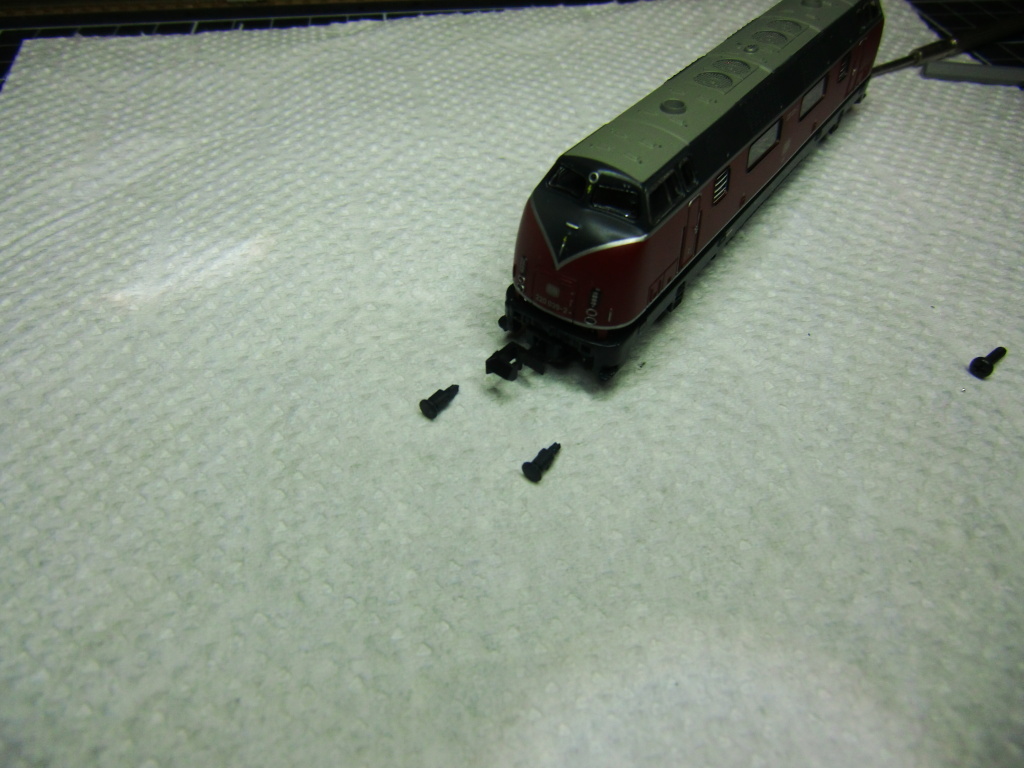
こちらの車体では、底面ネジ1本と正面パーツ(※写真参照)の4カ所をすべて外さないとボディーが外れません。これを知らずに無理にボディーを開けようとすると、本体を割ってしまいますので注意が必要です。

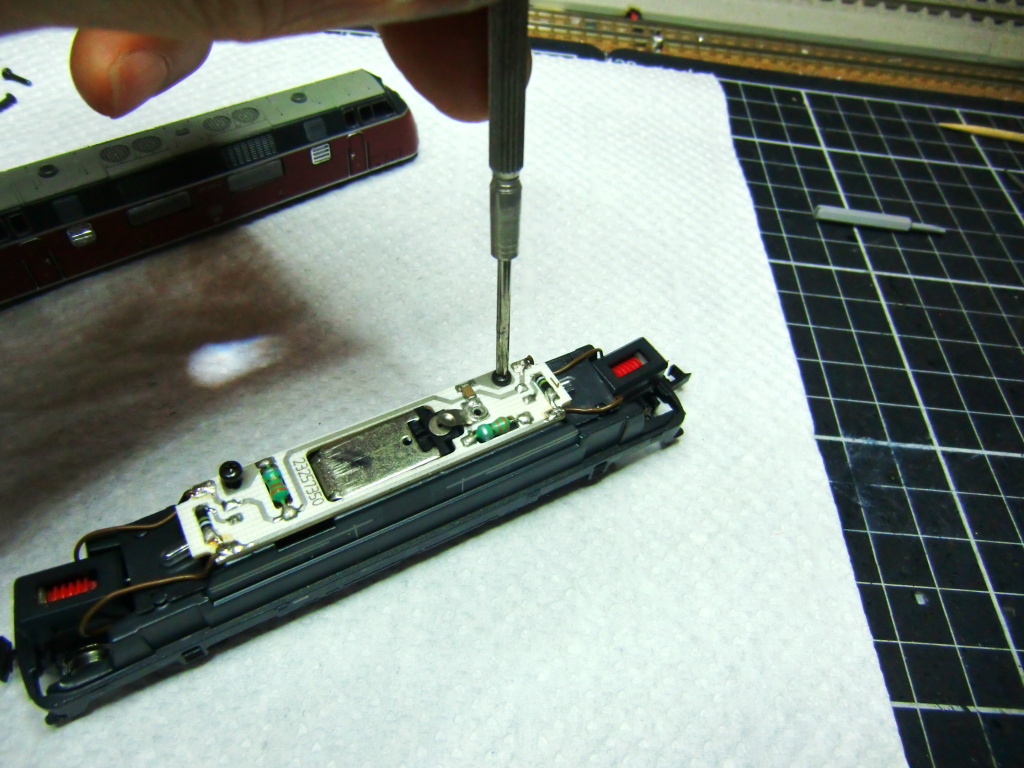
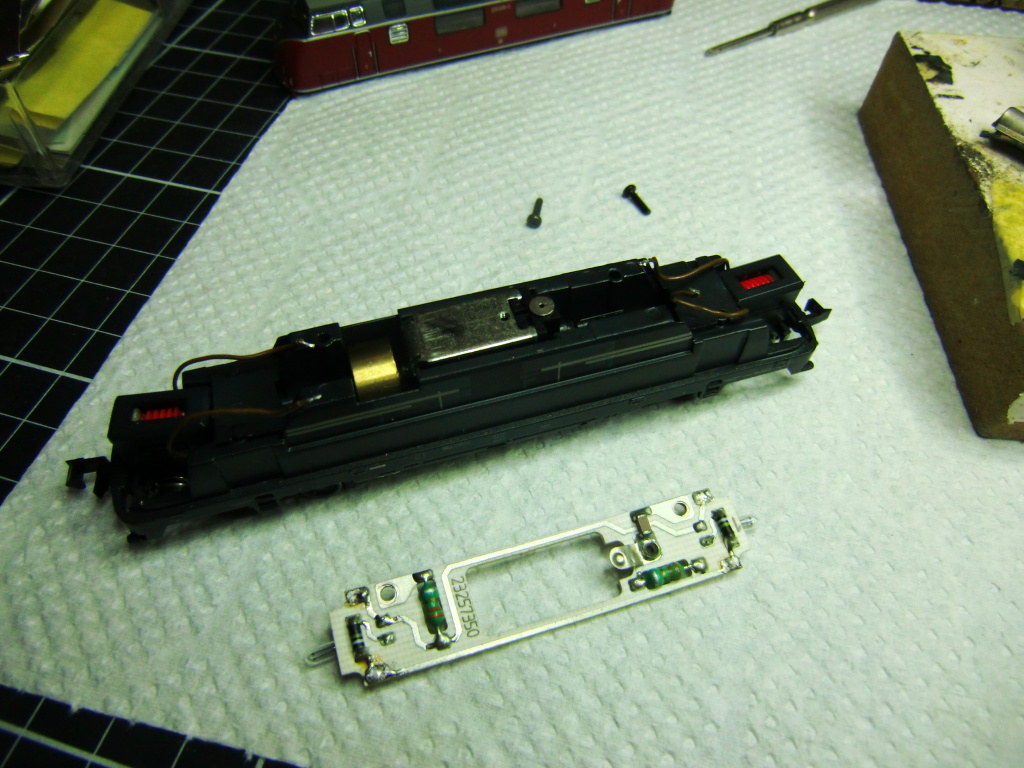

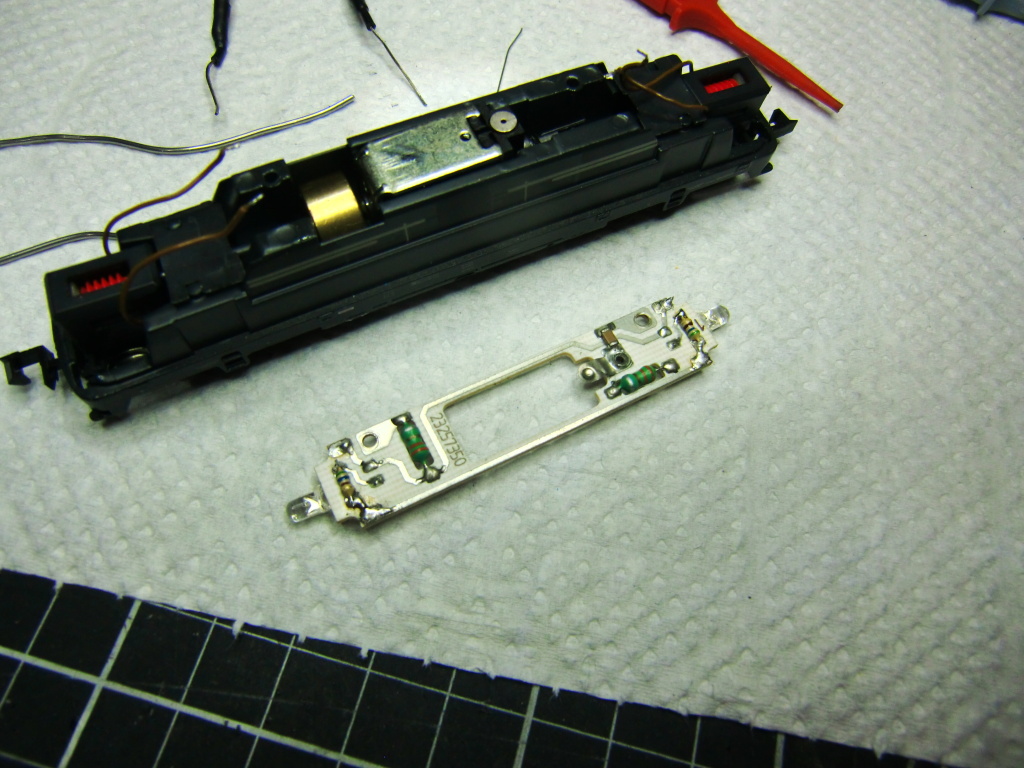
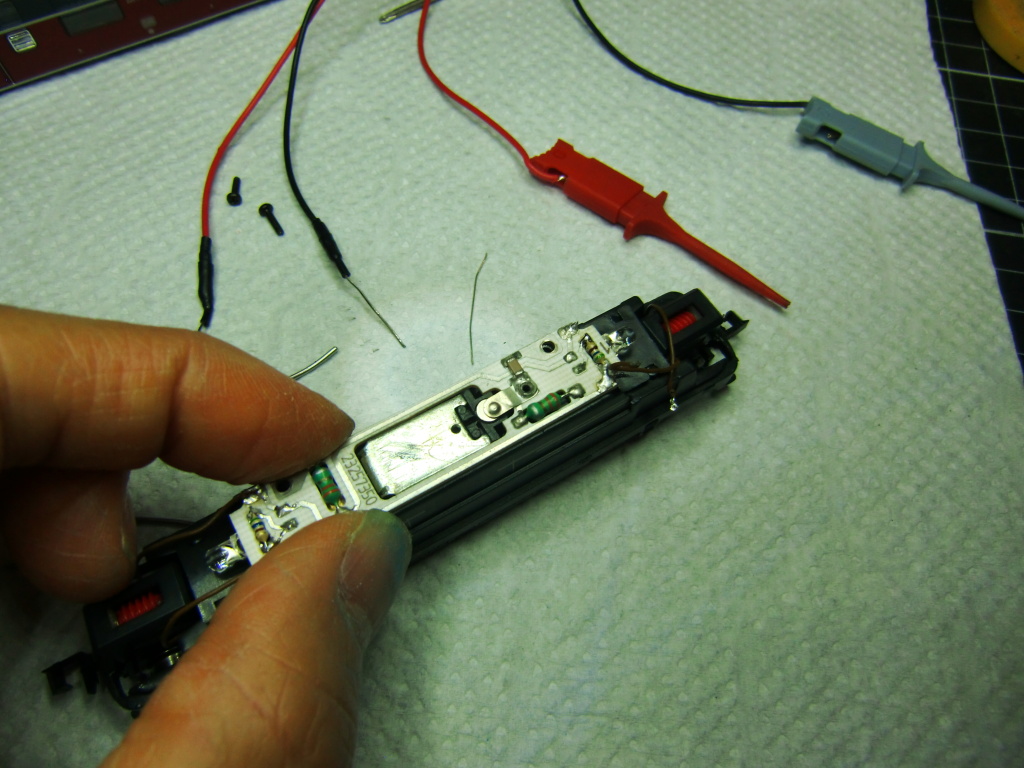
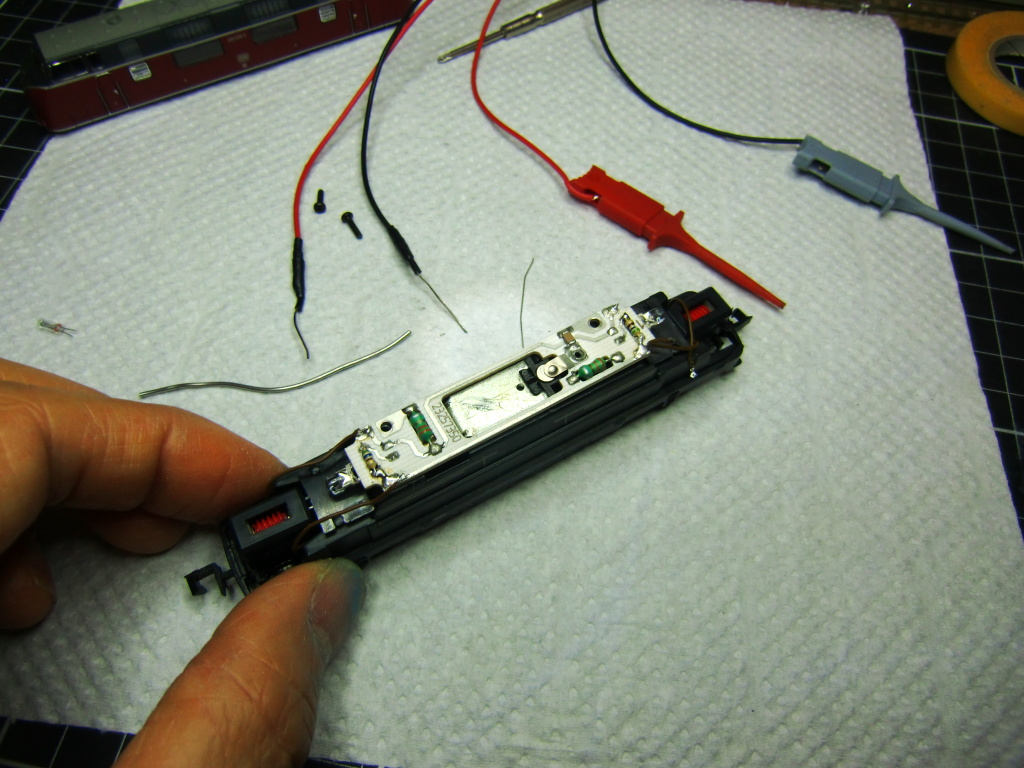
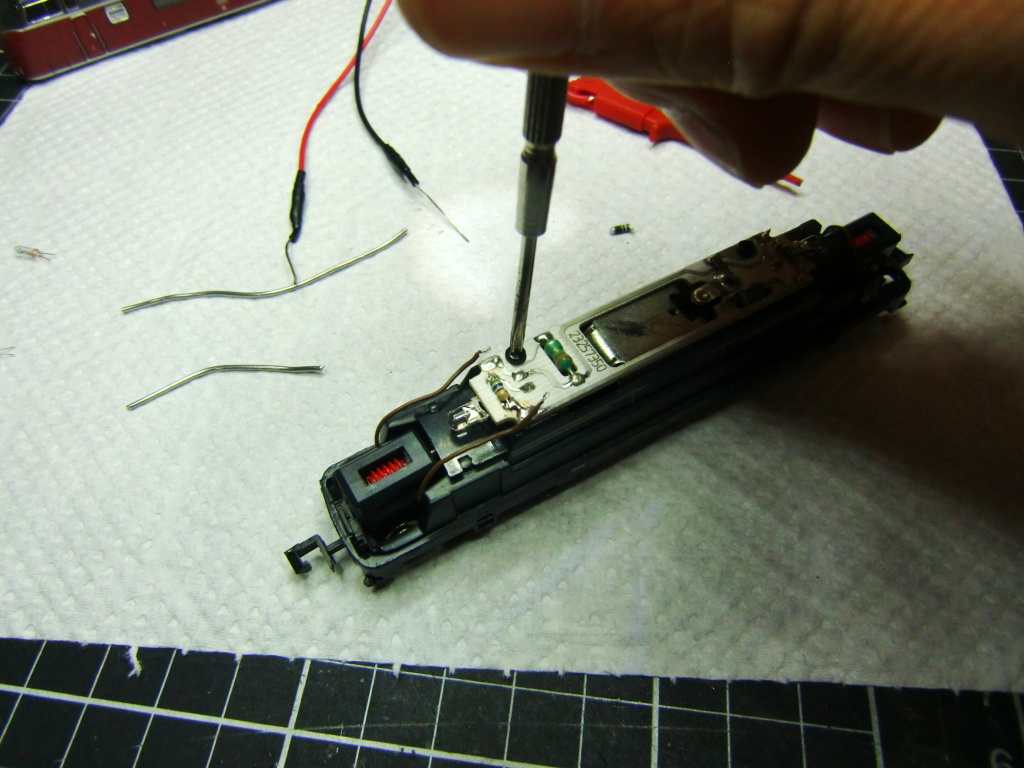
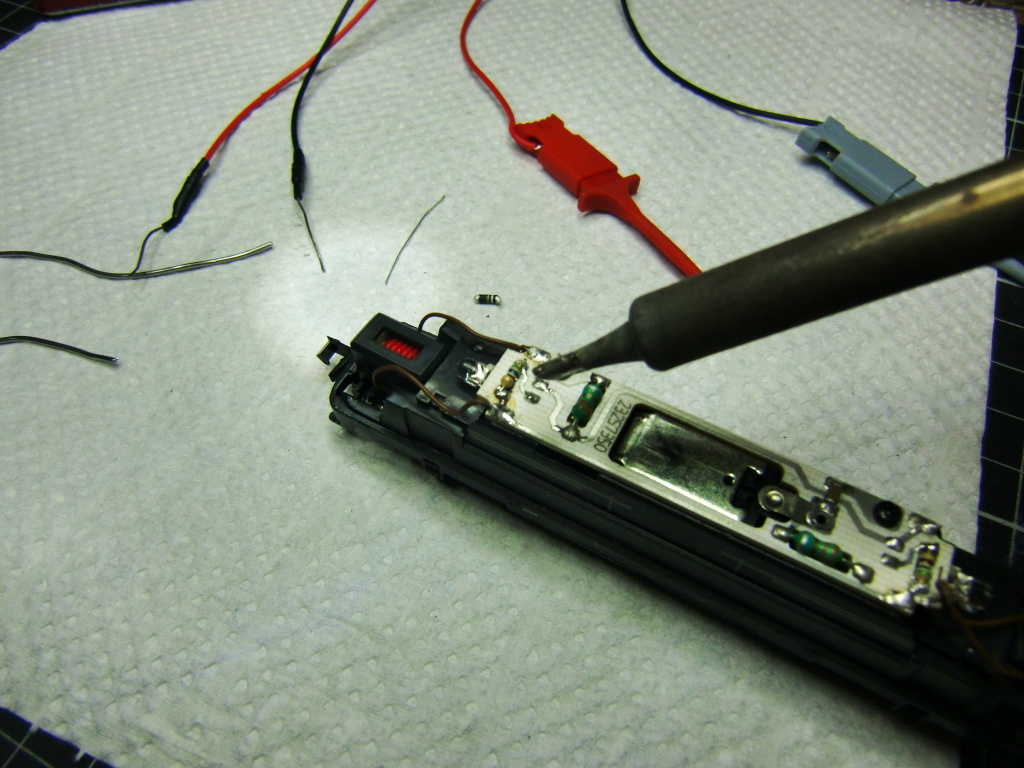
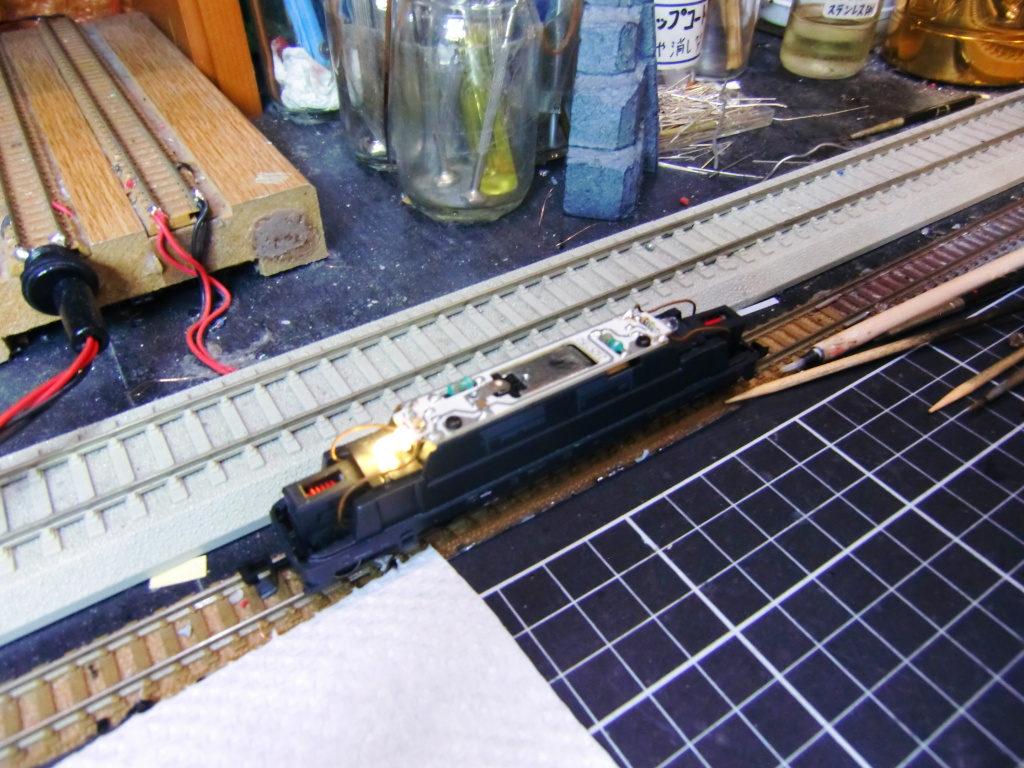
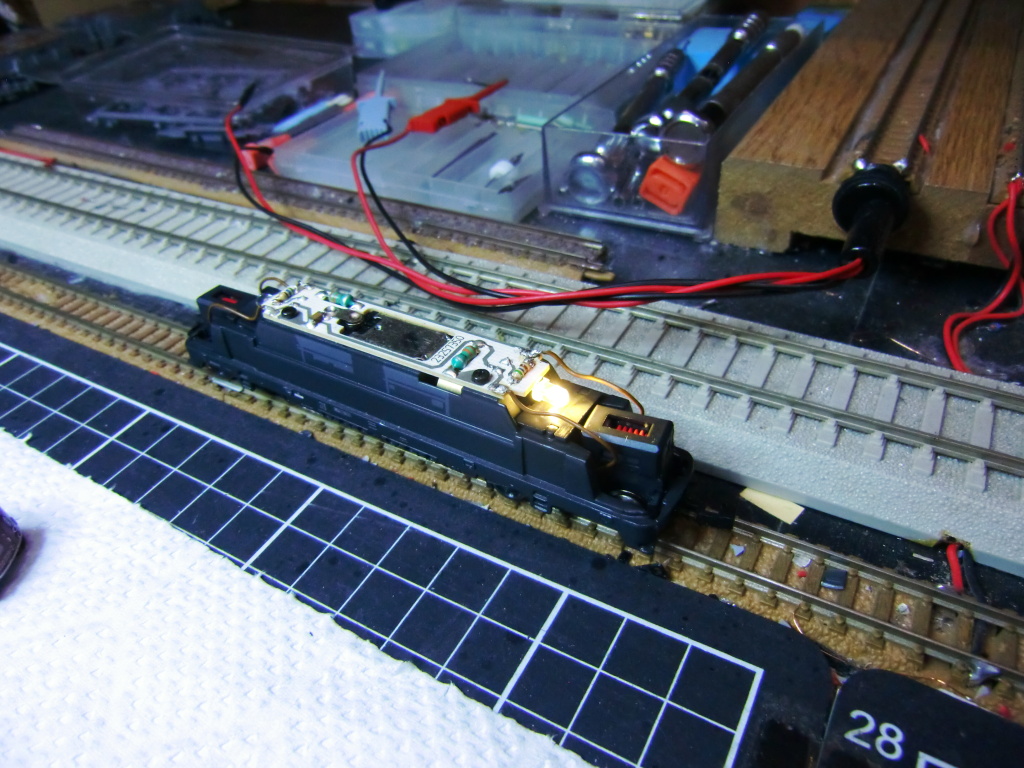

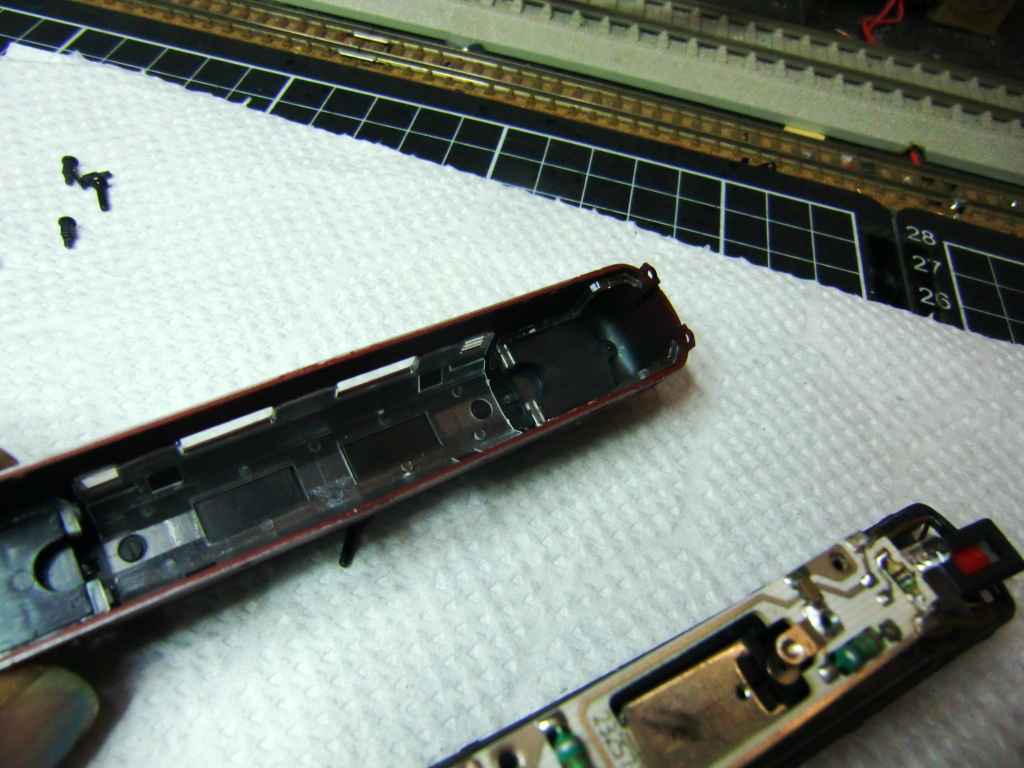
導光材の配置が電球に合わせた配置となっているため、そのままではダメそうです。対応策を考えますので、もう一度やり直します。
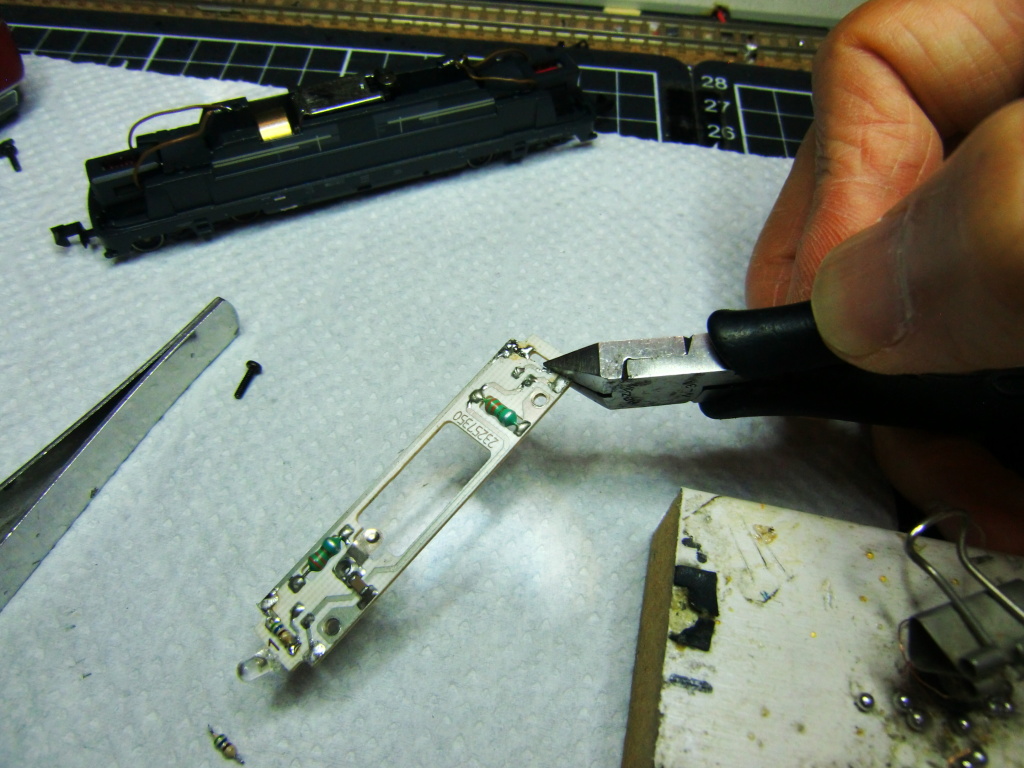
LEDをより後方へ配置できるように基盤を短縮加工します。それに合わせて各部のパーツも配置換えします。
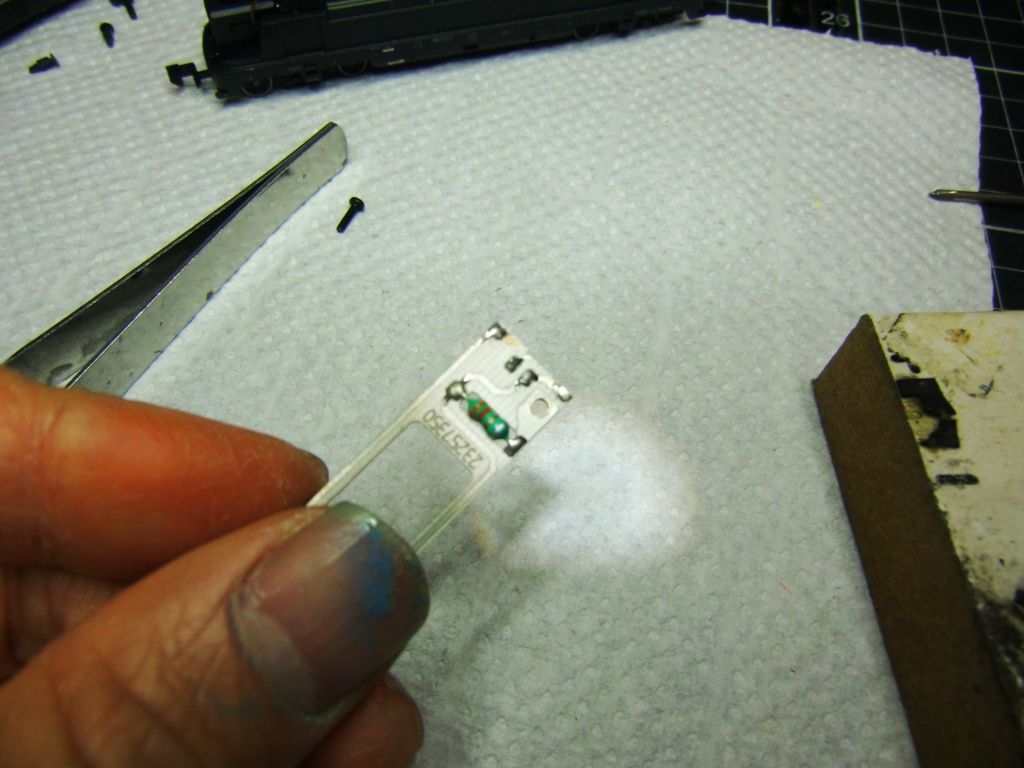

加工機板の完成です。最後にLED正面に反射板を置いて光を拡散させます。
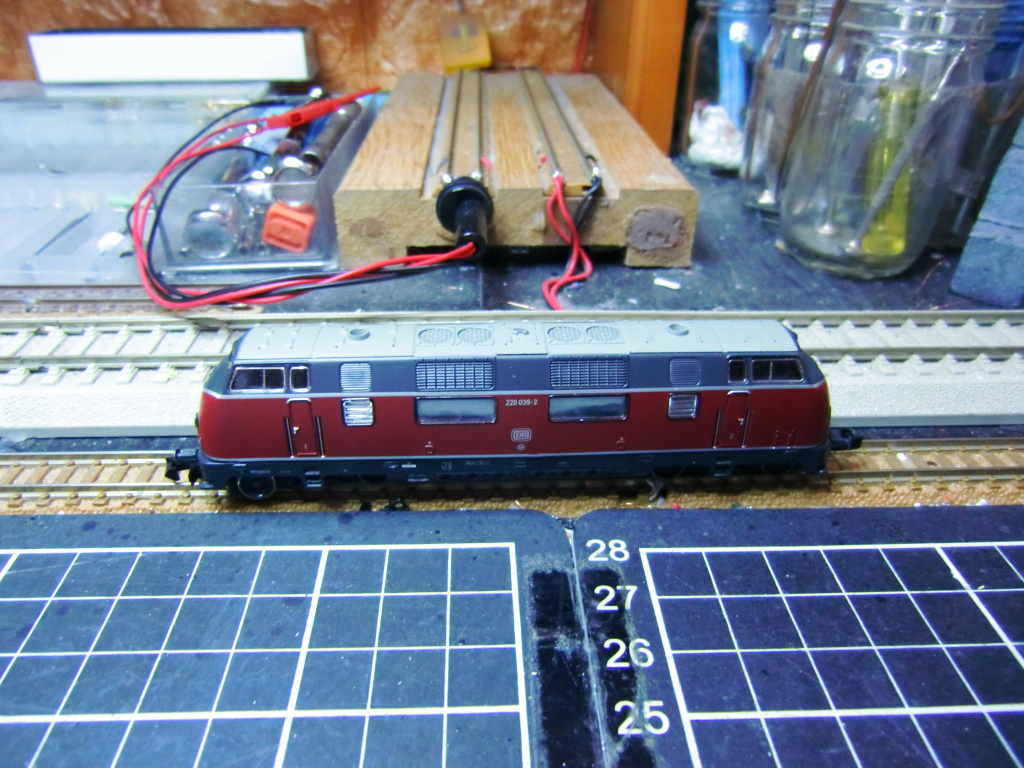



写真ではちょっと見ずらいですが、しっかりと光ってます。運転席横の窓が光ってますが、そういう製品なのだと思います。作業完了でございます。


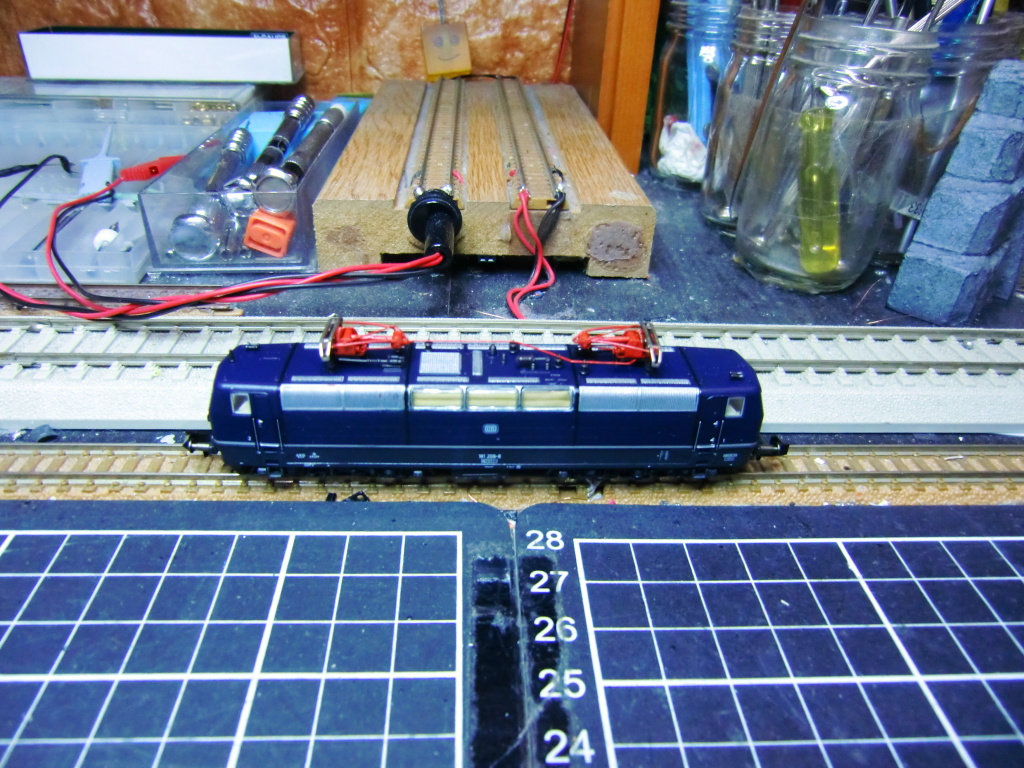
動きません。
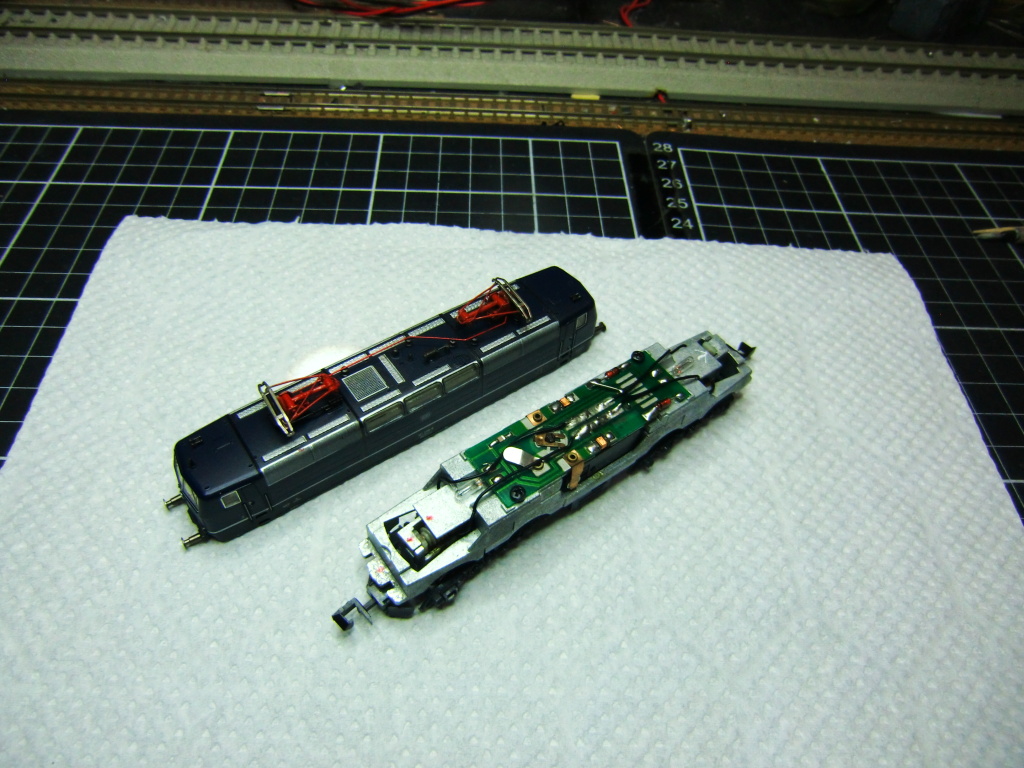
単なる台車の通電不良という訳ではなさそうです。
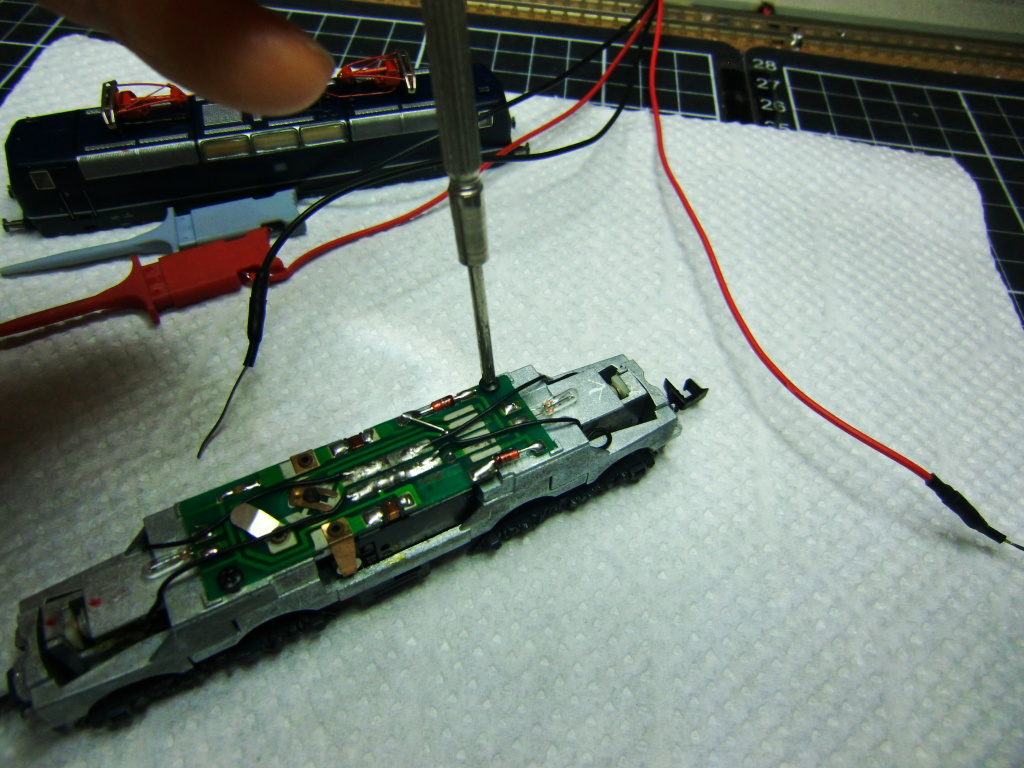
基盤を外します。
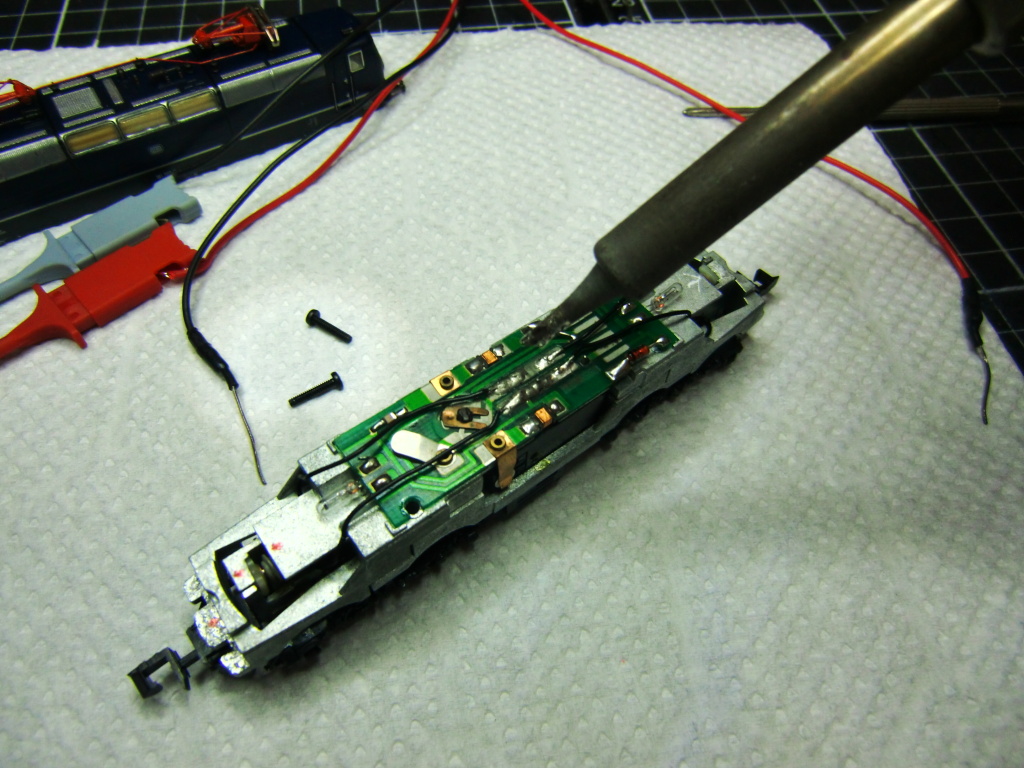
ハンダで配線を外していきます。
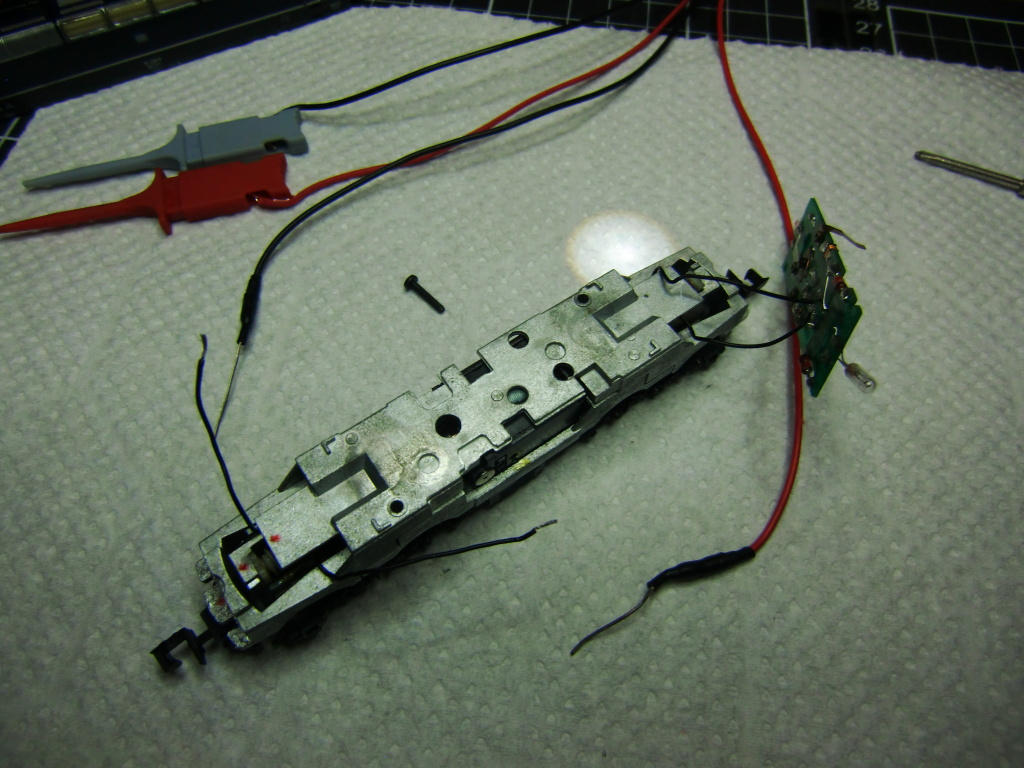
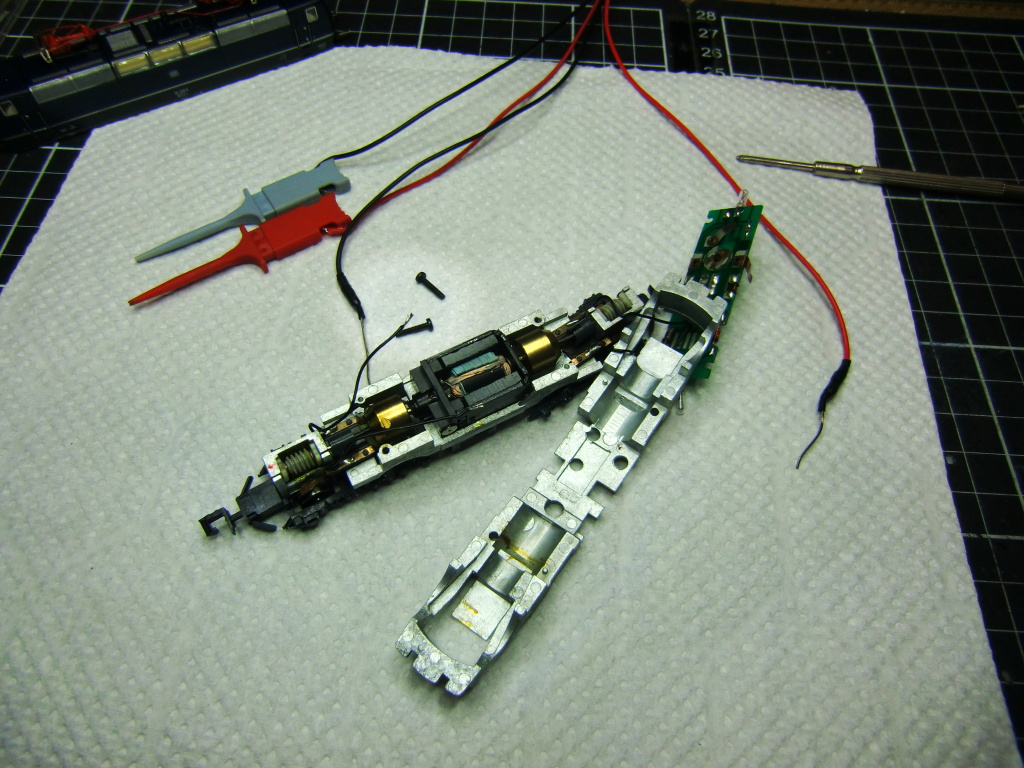
モーターが出てきました。
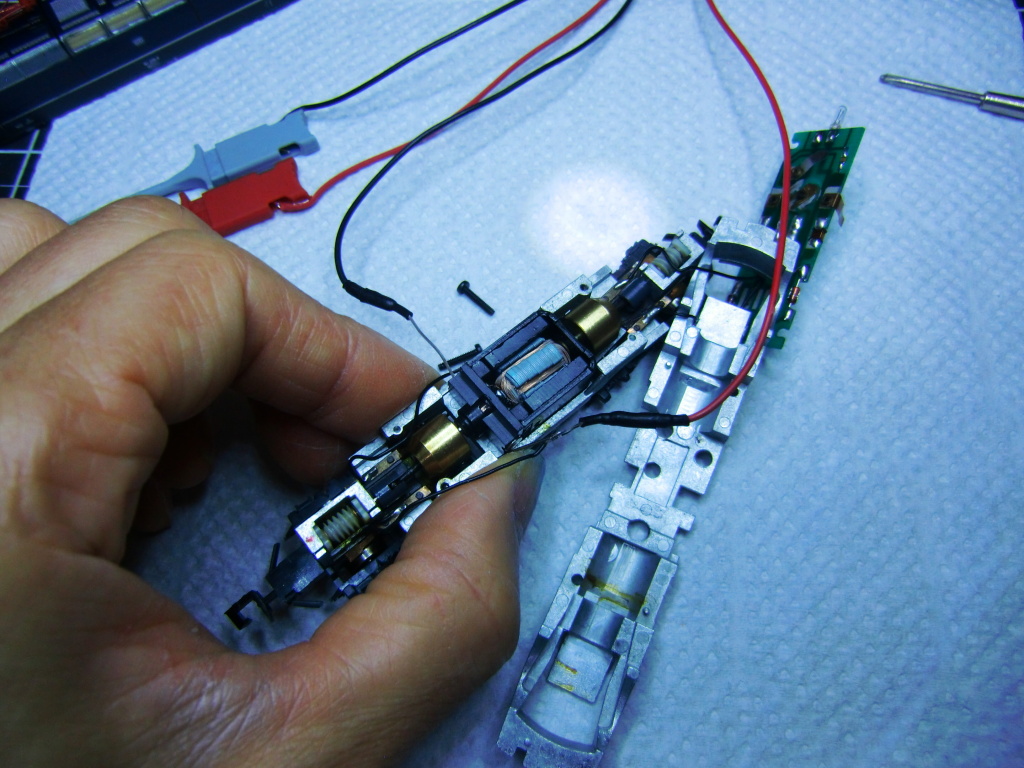
どうやらモーターそのものに問題があるようです。回りません。
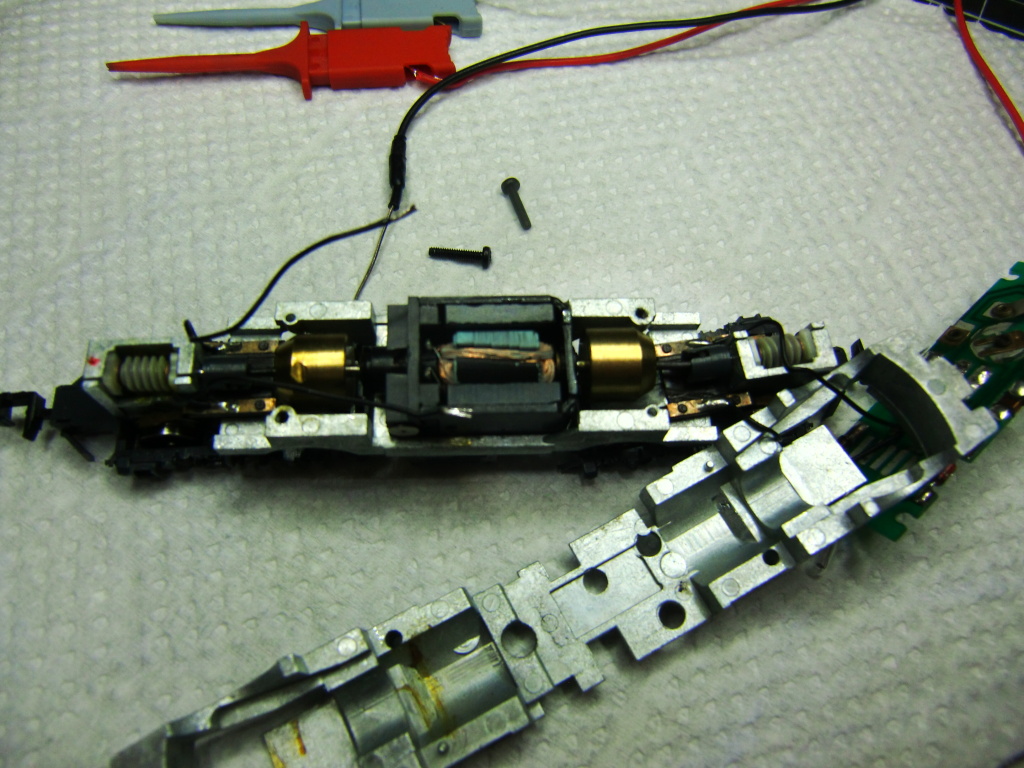
ブラシ、コミュ、コイル断線など1つ1つ確認して、モーター内部の問題個所を特定します。さまざまな要因でモータが回転しなくなります。原因をしっかり調べて対策を講じます。今回は幸いモーター全分解までには至らなかったので良かったです。フライホイールの付いたモーター分解は結構大変ですからね。
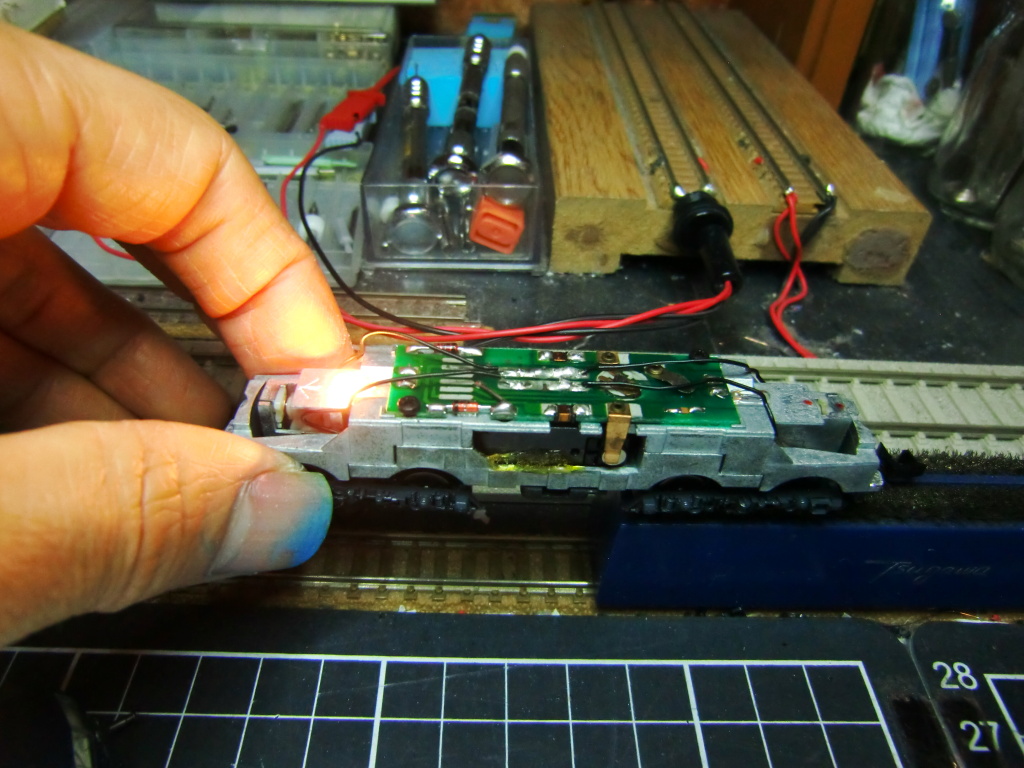
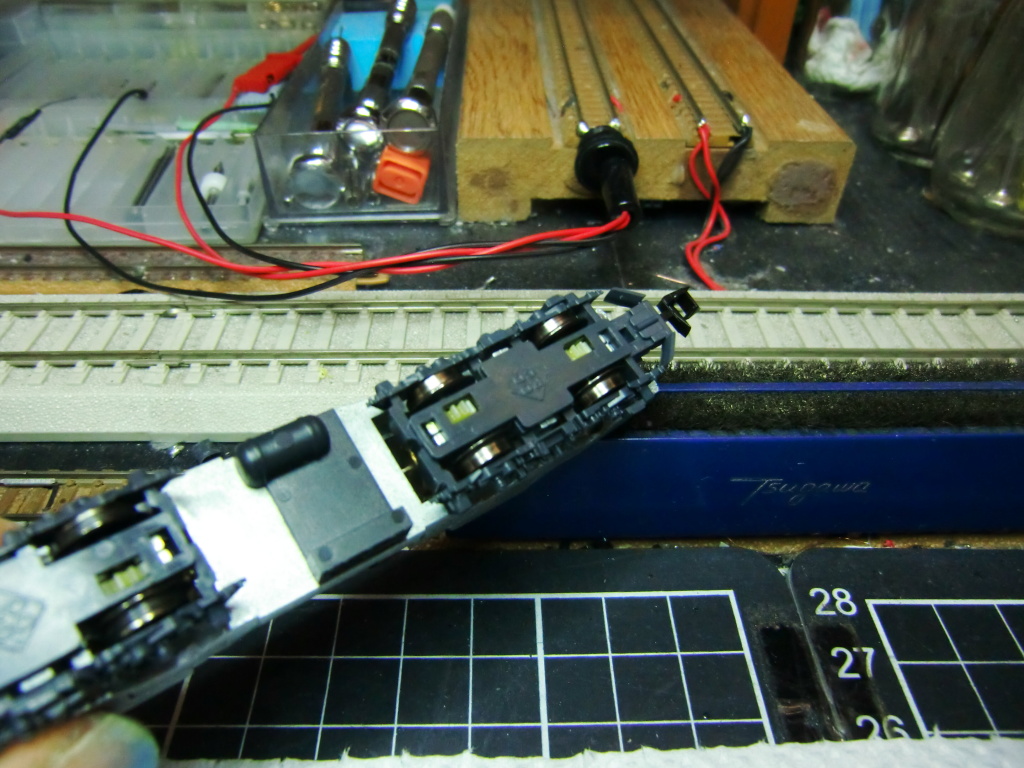
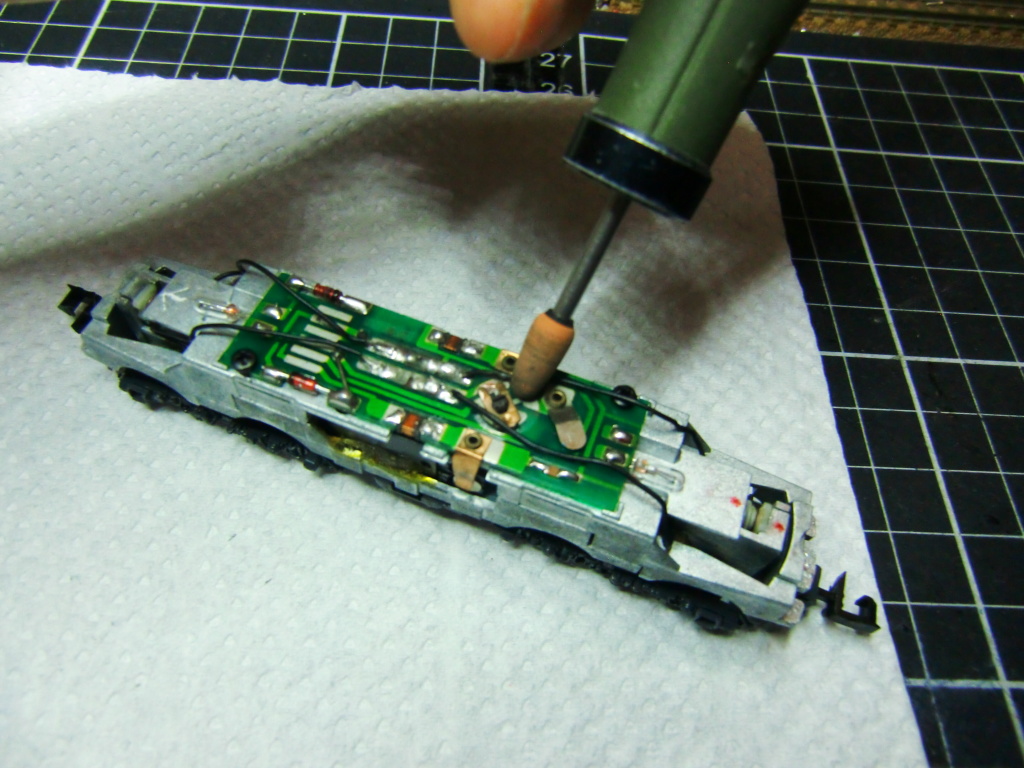
基盤のスイッチ箇所もだいぶ酸化して黒くなっていますので、せっかくですからこの辺りも磨き出しておきます。
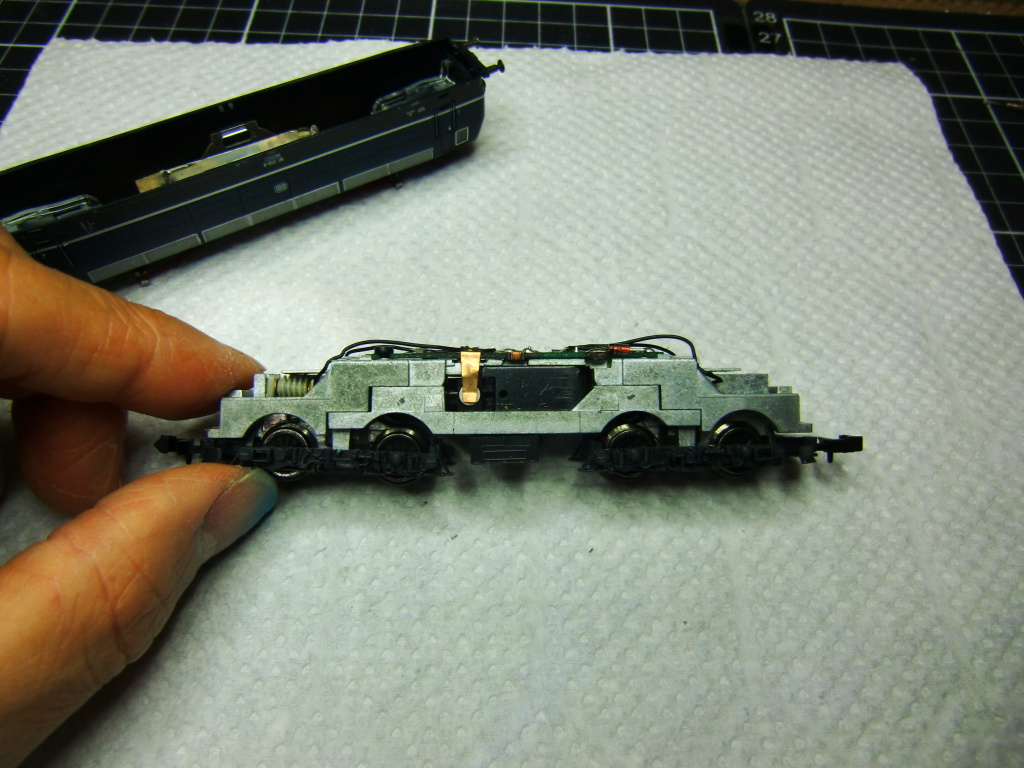
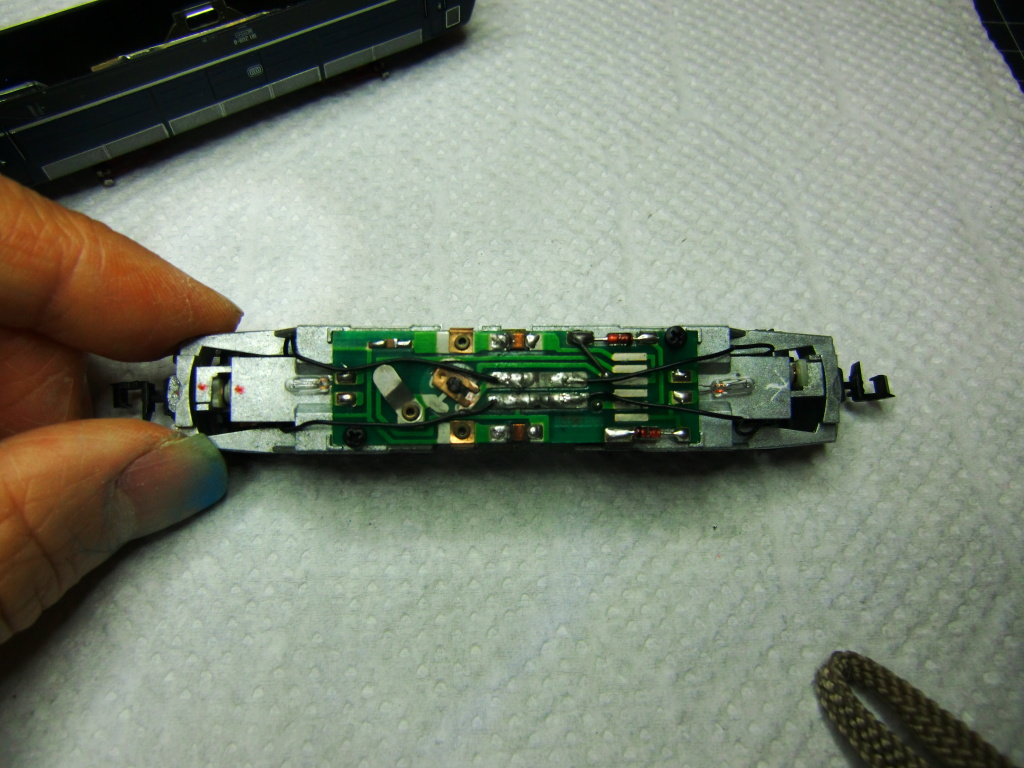
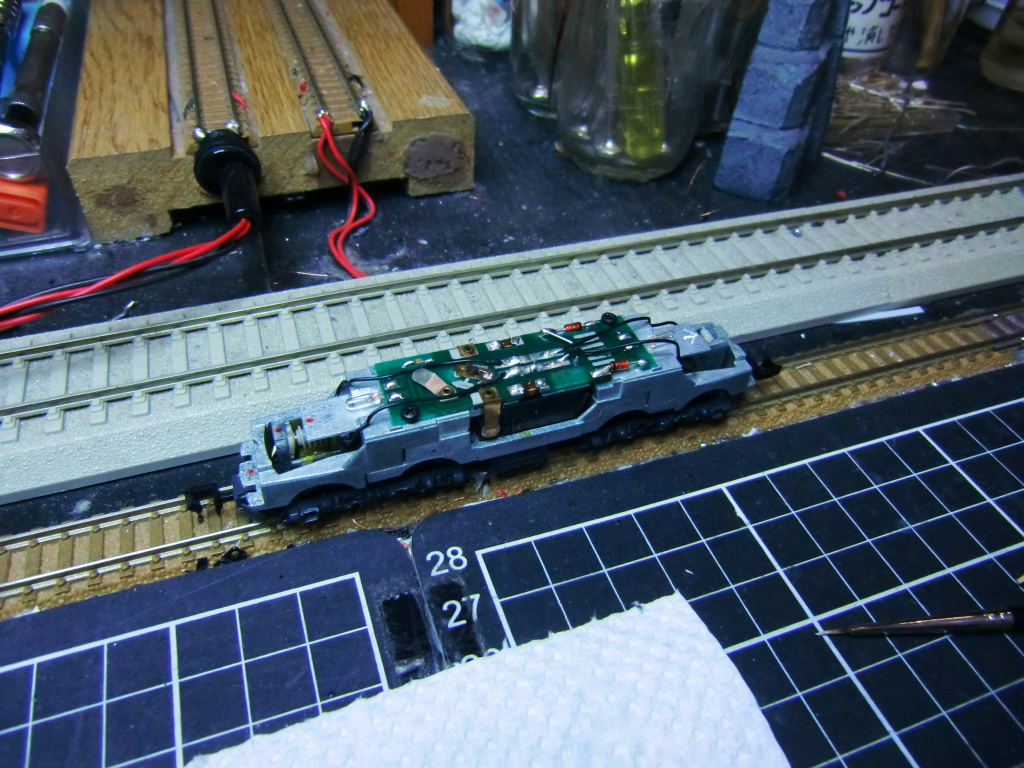
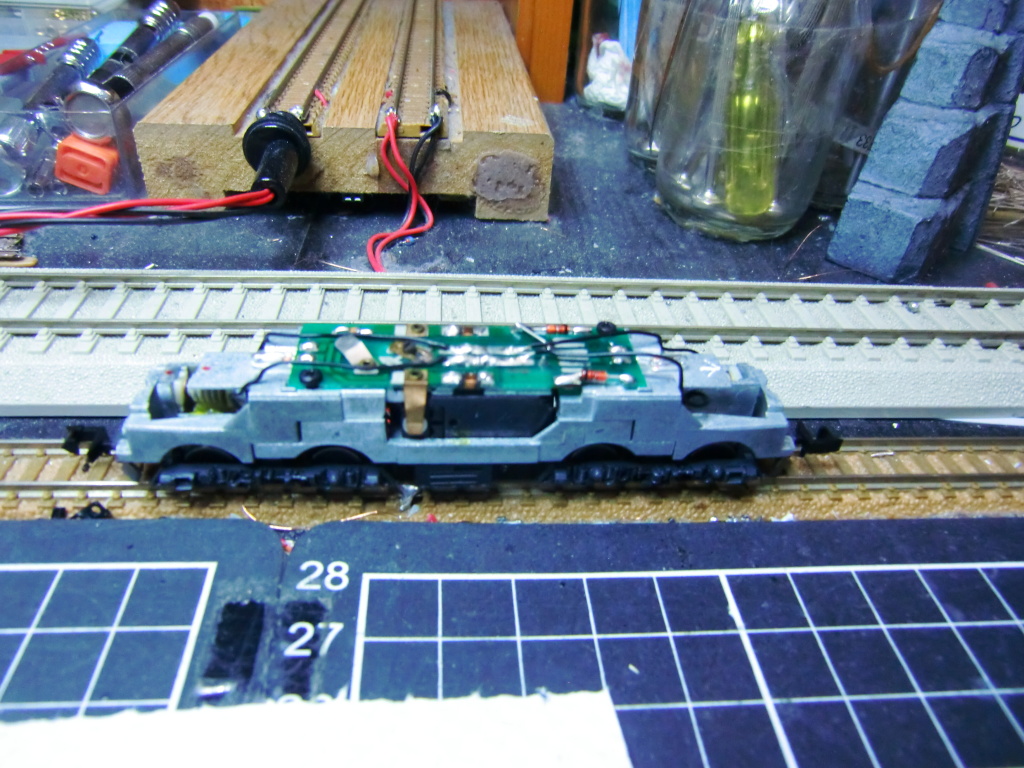
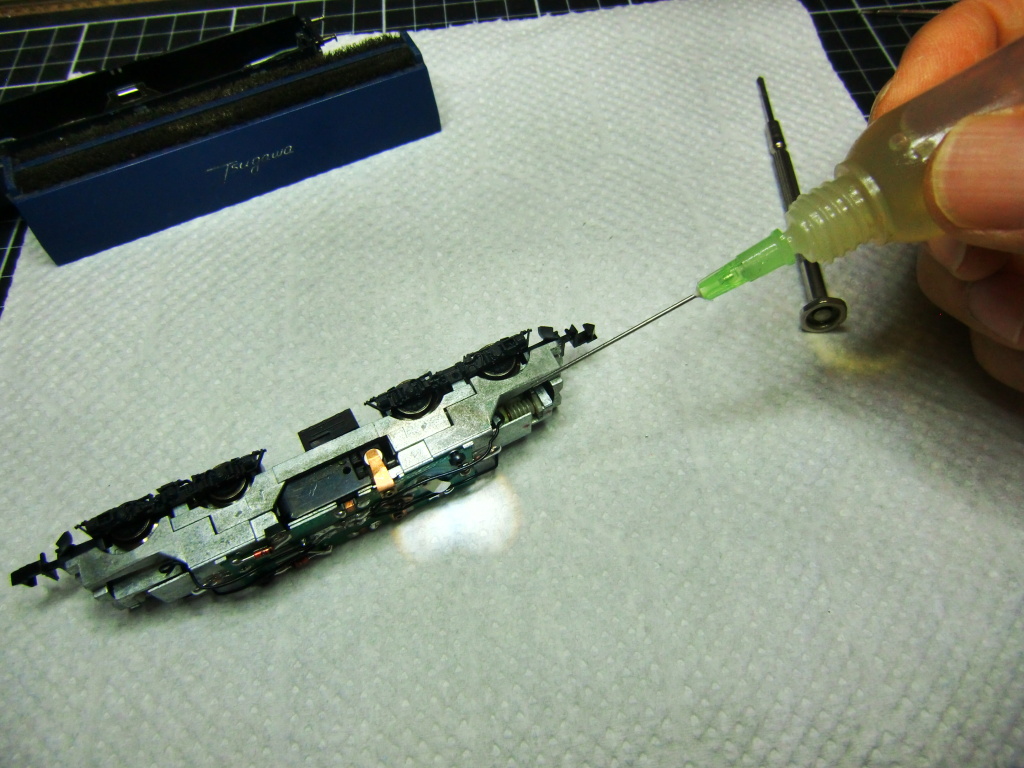
最後に各部に注油を行って作業は完了となります。
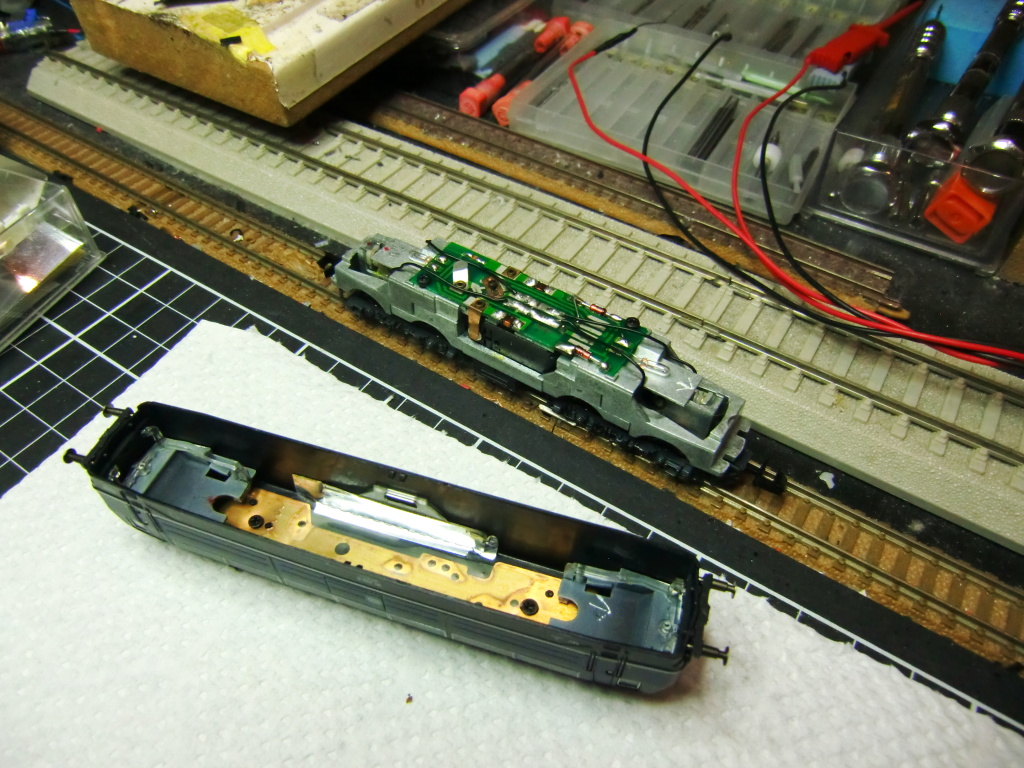
ギア全体に程よく油が回るまで往復運転します。
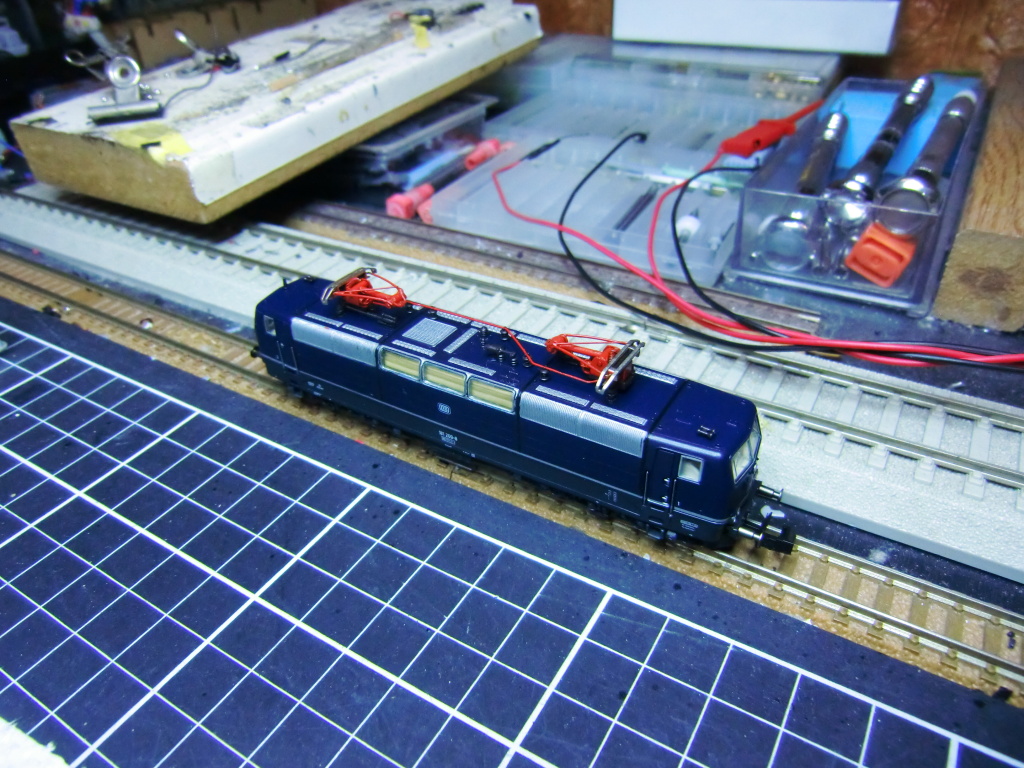
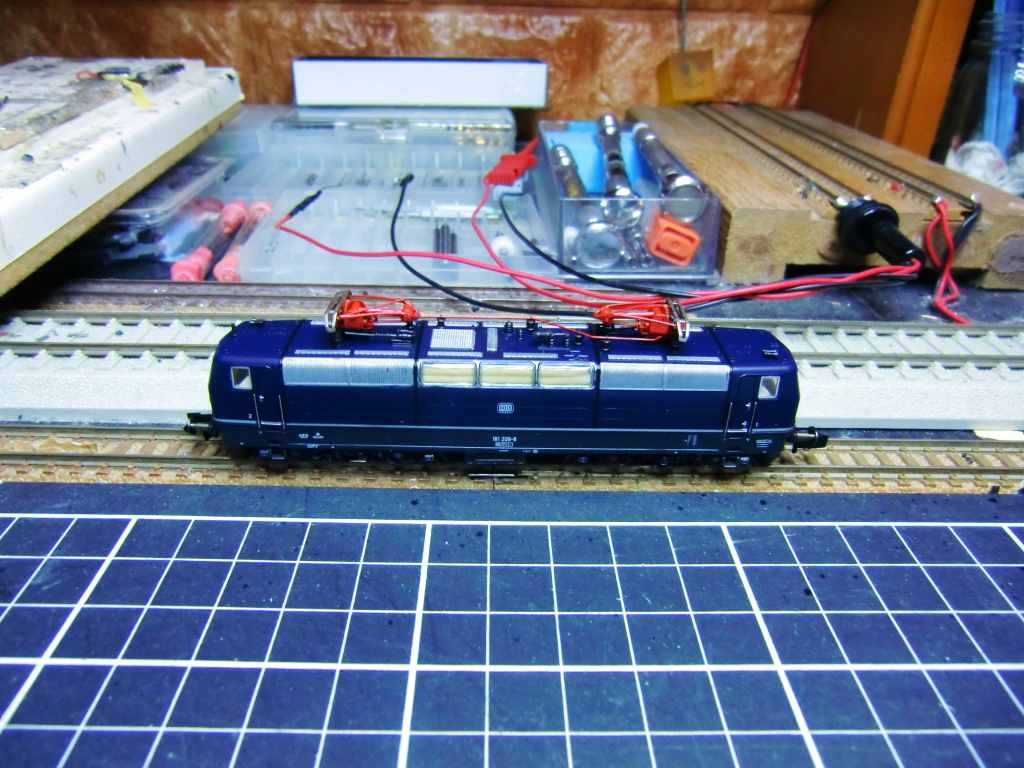
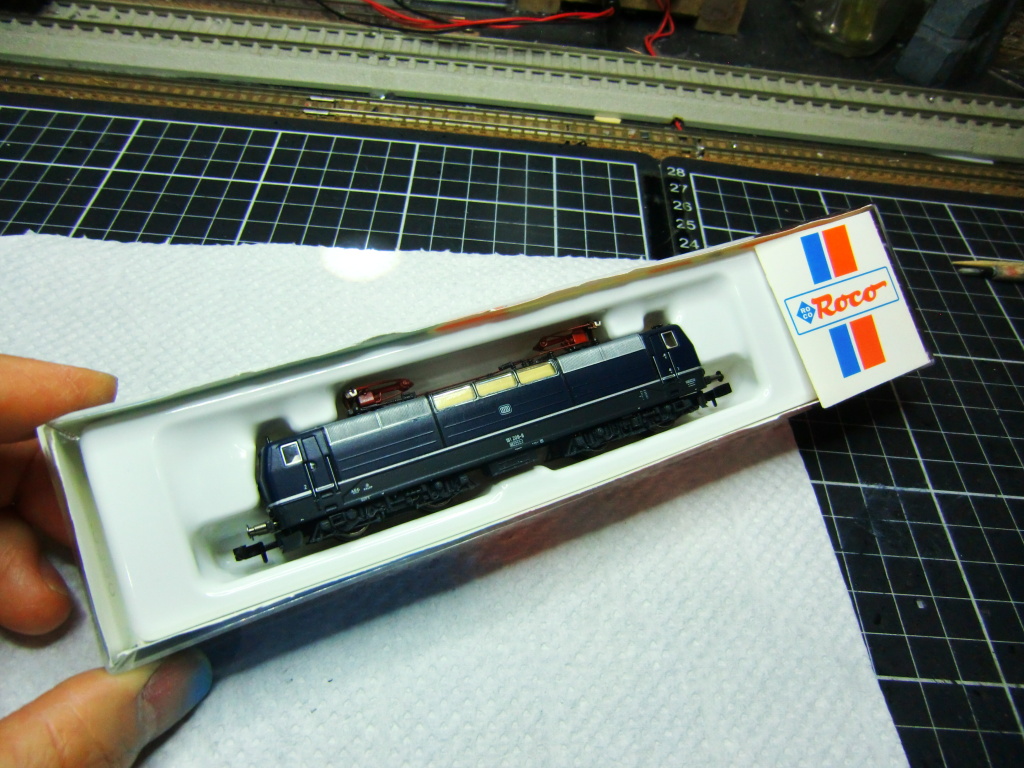
走行テストも終えて、修理完了です。


運転室のヘッドライト用の遮光が透けてしまってオレンジ色に発光しています。今回のご依頼は、この光漏れを何とかしたいとのご相談を受けました。
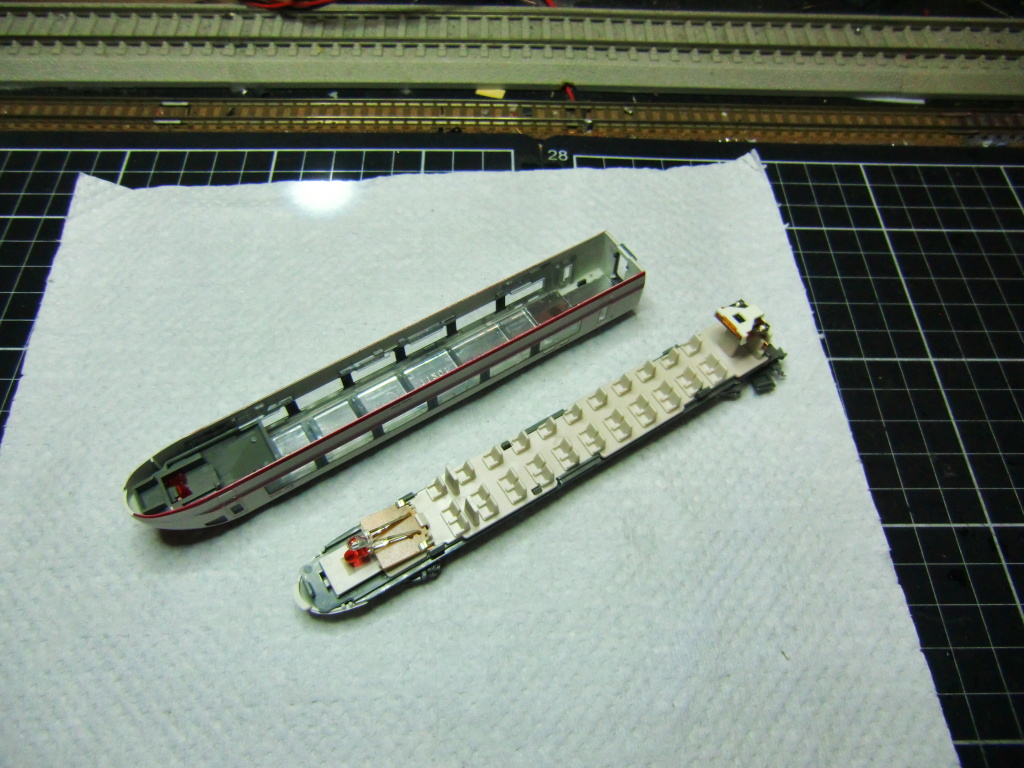
早速分解して構造を見てみます。
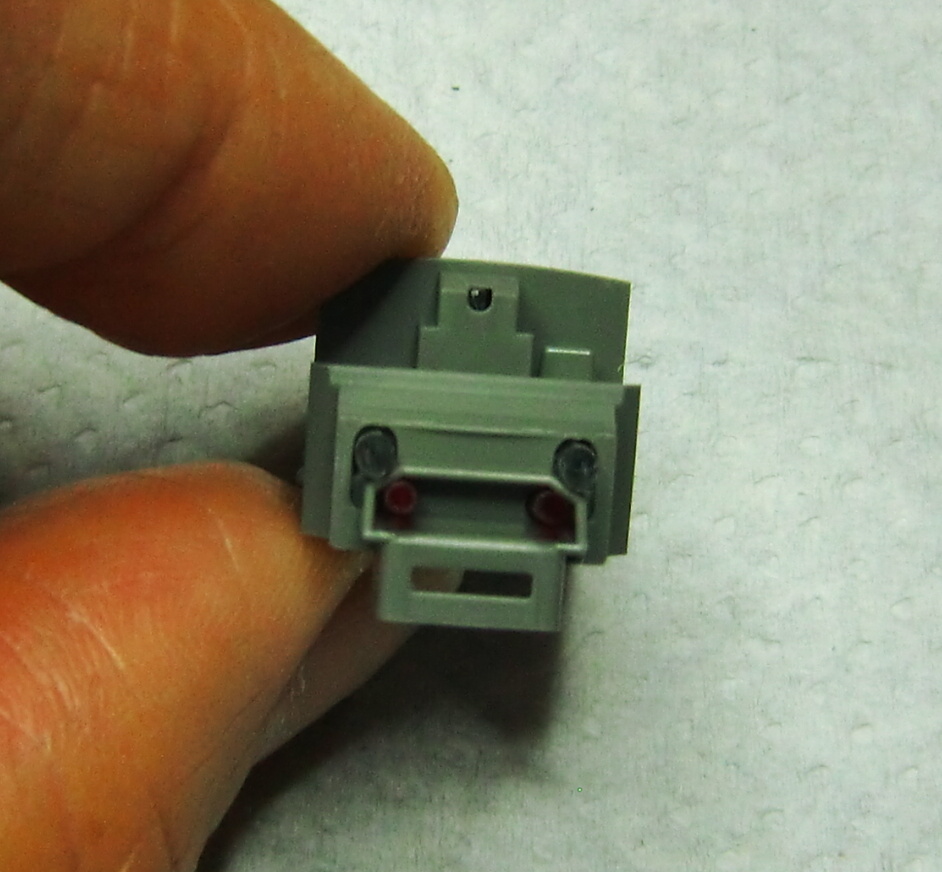
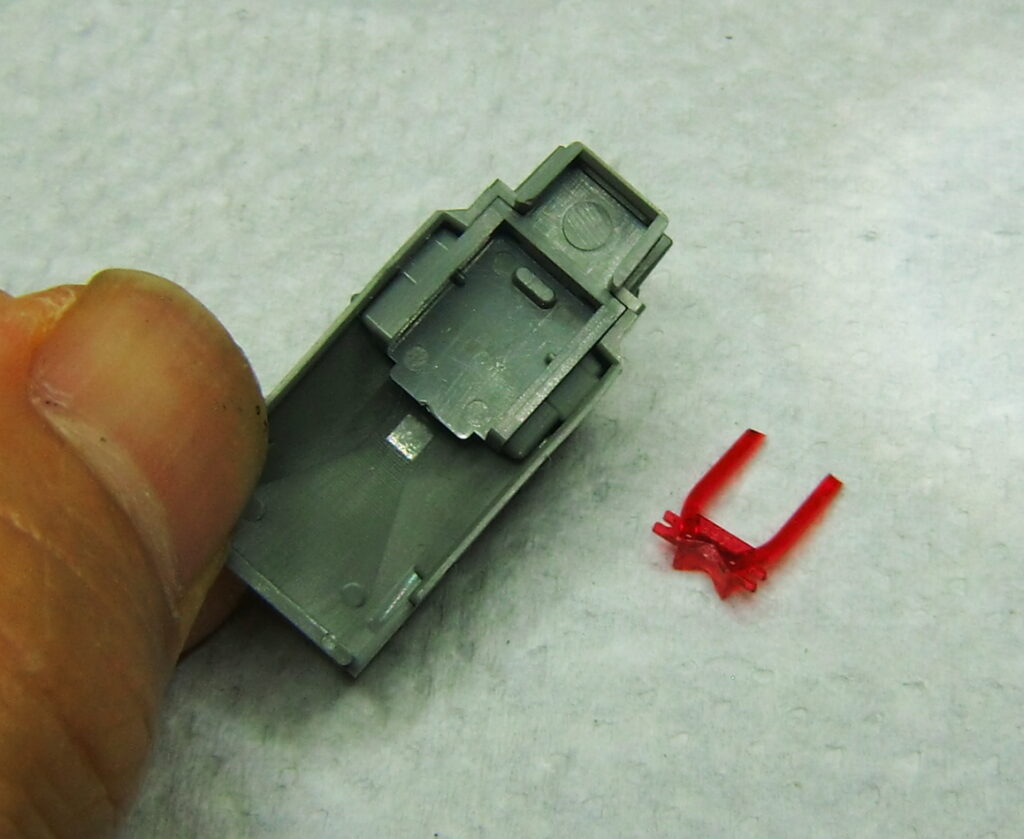

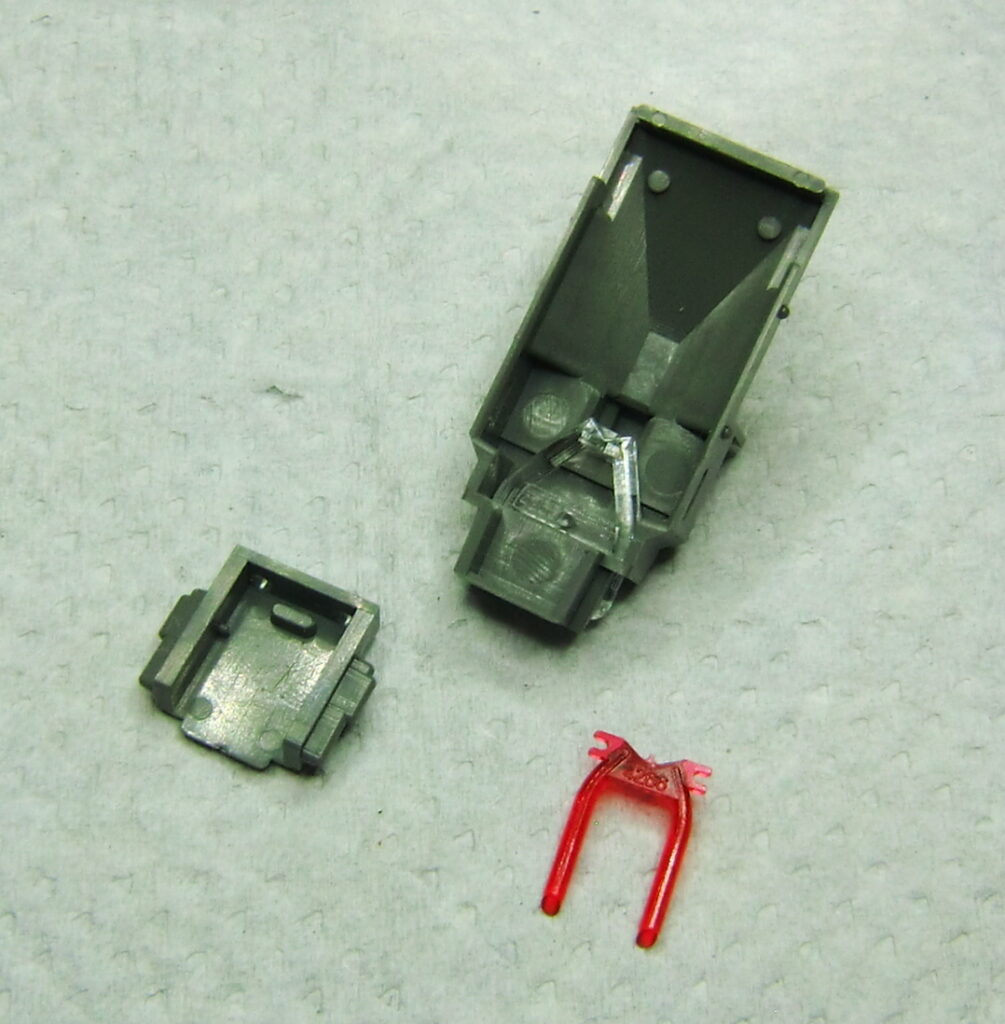
ユニットをすべて分解したあと、光が透けてしまわないように対策を施します。
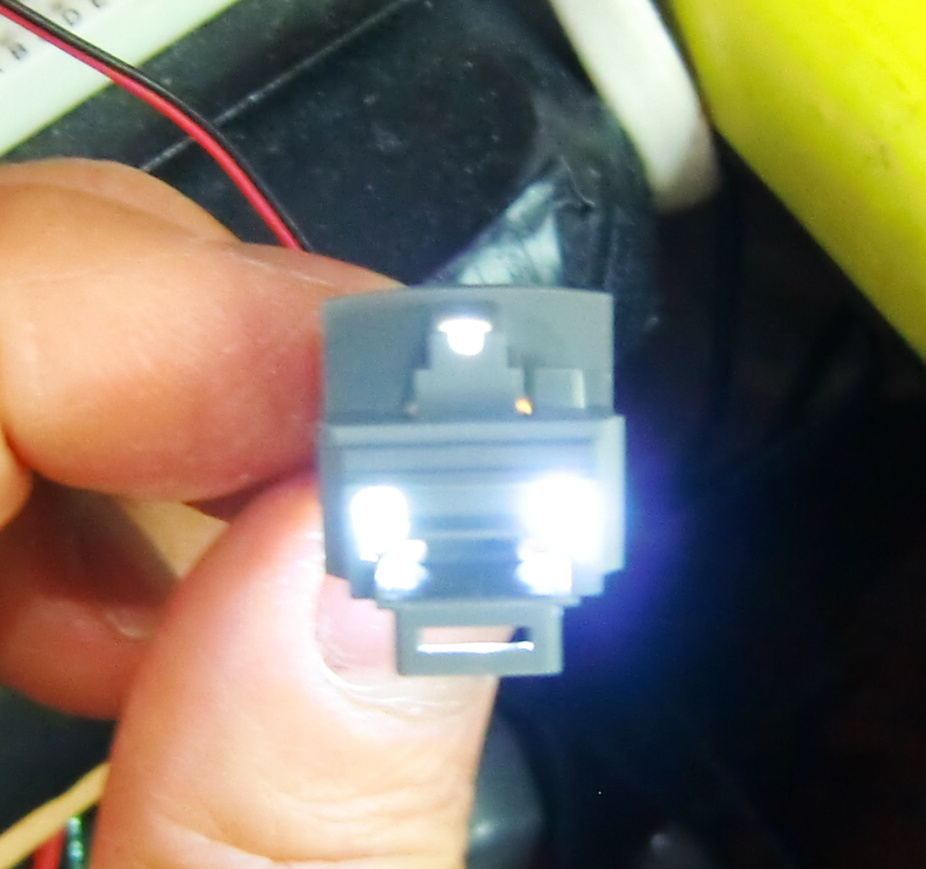
このように正面から見て光が透けることがなくなりました。


作業完了でございます。続いて貫通部分のドアの塗装です。

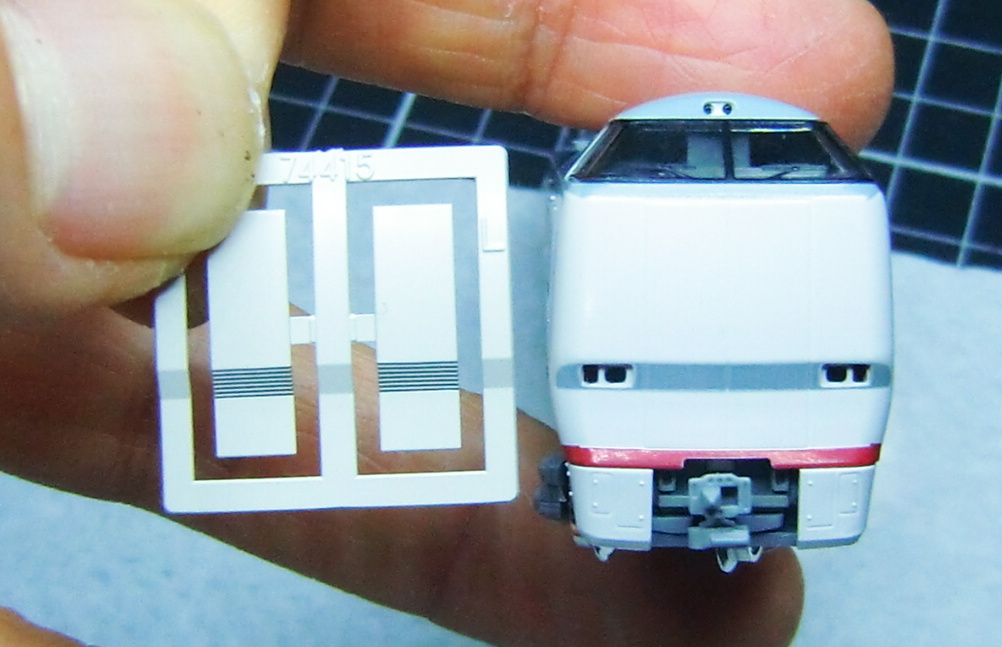
写真ではわかりづらいかもしれませんが、ドアパーツがやや黄色味を帯びています。

色を調合します。

色を薄く吹いていき現物合わせで色合いを近づけていきます。しかしながら車体色とまったく同じ色という訳にはいきません。

あまり色の調合にはまると泥沼に陥るので、とりあえずこのあたりで良しとします。塗装完了です。